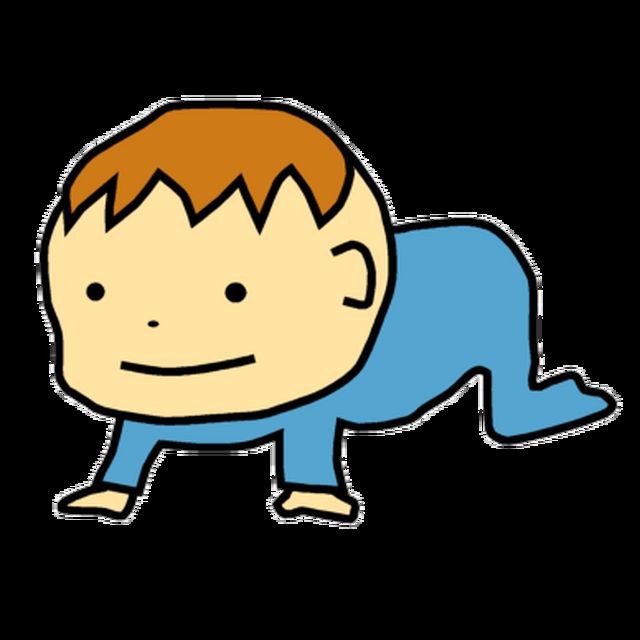第5話
文字数 2,738文字
ところで、僕は最近もせっせと裏門で松ぼっくりを拾ってきてはカゴに集めていた。そのうちに、なんと二匹目の目玉が生まれた。朝起きるとたまちゃんと同じく、カゴの中にいた。松ぼっくりと入れ替わるように。
その目玉はメガネみたいに目玉が横に2つつながっている。それ以外の体の構造はたまちゃんと同じだ。生態もたまちゃんと全く同じで、餌を食べ、ただ僕に着いてくるだけだ。これといったメリットはない。ちょっと安易だけど、二匹目なので「次郎」と名づけた。
そして次郎が生まれた翌日も学校の裏門の付近には松ぼっくりが落ちていた。たぶん近いうちに「三郎」も生まれるだろう。
さて、池田さんとお友達になってからというもの、僕らは一緒に過ごすことが多くなった。放課後は縄跳びをしたり、図書室で本を読んだり、休日には市民プールや町の書館にも足を運んだ。
池田さんはやはり、たいへんな読書家で、大人向けの作品でも難なく読む。でも彼女曰く、本が好きなのではなく、「やることがないから」本を読んでいるらしい。
彼女が特によく読んでいるのは幻想怪奇文学だ。その中でもおすすめはアンブローズ・ビアスという人だそう。僕も子供向けのふりがなが振ってあるものを読んでみたが、何が面白いのかさっぱり理解できなかった。しかも、だいたいの主人公が死んでしまうので非常に後味が悪い。僕はもう少しポジティブな物語がよみたいと思う。彼女曰く「子供にも女にも貧乏人にも勇敢な兵士にも容赦ないところが好き」なんだとか。他にも泉鏡花の現代語訳の外科室をおすすめされた。こちらは「ゾクゾクする」という。これについては物語の展開に全くついていけず、なんだかよく分からなかった。
5月のある土曜日のこと。その日僕らは午前授業の後、公園で縄跳びをしていた。この公園も川沿いの道のすぐ脇にある。池田さんが三毛猫に餌やりをしていた橋とは違うが、橋を渡ってすぐのところにある公園だ。
午後、そこで僕らは縄跳びの練習に少し疲れてきたから、ベンチで休んでいた。すると公園のフェンスのうえを虫取り網と麦わら帽子が横切った。すぐに麦わら帽子を被った少年が現れた。たぶん小学一二年生といったところだろう。青いTシャツにブカブカのズボンをゴムのベルトで止めている。頭は丸刈りで、肩に虫かごをかけ、片手に虫網を持っている。
虫取りに来たのだろう。公園を眺め回し、僕らの向かい側の樹木に向かった。少年は枝葉をつついたり幹を蹴飛ばしたりしている。いろいろ試してみたが、結果は伴わなかった。
今度はツツジの生け垣を回り始めた。それでも、なかなか何も見つからないようだ。5月の下旬なのでまだ虫は少ないのだ。
僕がふと公園の中央の低い草むらに目を向けるとアゲハチョウが飛び回っていた。
「おーい」僕は草むらを指差して少年に声をかける「そこの草むらに蝶々がいるよ!」
少年は真剣な表情でその草むらに駆け寄ると虫取り網を振り回した。それを何度か繰り返すと、どうやら蝶を捕まえたようで、虫かごに蝶を収めた。そして少年は誇らしげに僕らに虫かごを掲げてみせた。
「僕もあのくらいの頃はよく虫取りをしたな」
彼女は身を乗り出して言う。
「私もしたよ。私は生き物が好きなの。愛していると言っても過言ではないわ」
どうも本心から言ってるらしい。僕は彼女に問う。
「へー。僕は一時期、捕まえて持ち帰って、トカゲやカブトムシを飼っていたよ。君は?」
彼女は腕を組むと、遠くにいる少年を眺めながら答えた。
「私は脚や頭を千切ってどうなるのか観察していたわ。意外と虫ってどこを失っても死なないのよ」
「それは変わった愛し方だね。僕ならそんな愛され方はごめんだなあ。ははは」
目を細めて彼女が言う。
「私は二学期からは生き物係になろうと思ってる」
僕は肘を膝に置き、俯いて答える。
「そう。でも猫のように殺したら問題になると思うよ」
池田さんは横目で僕を見下した。
そのとき一滴、雨粒が僕の腕に落ちた。僕は空を見上げる。空は一面、灰色の雲に覆われていた。
すぐに辺りは細かい雨に包まれた。僕は折りたたみ傘を持っていたので、彼女との間に差し、とりあえず橋の下に行った。橋の下から公園を見ると、少年が公園の中央につっ立っていた。僕は走って、もう一度公園に向かった。そして公園の中央の少年に折りたたみ傘を手渡した。少年は
「ありがとう」
と言って公園の出口へ駆けていった。彼は出口で振り返ると虫網を脇に抱え、僕に向かって手を振り、その顔に気持ちのよい笑顔をつくった。少年を見送ると僕はまた走って橋の下へ戻った。橋の下に入ると彼女が言った。「お人好しね」
「まあね」
「早く雨が止むといいね」
「そうだね。きっと通り雨だよ。予報は雨ではなかったから」
しかし、雨はなかなか止まなかった。池田さんは橋脚に凭れ、気だるそうに片脚を揺らしている。大きくなってきた雨粒がノイズのような音を立てていた。川の流れも少しずつ増えていく。傘を指して疎らに行き交う人々や車を、たまちゃんたちが目で追っている。
彼女の顔が少しずつ不機嫌そうに変わっていく。
とうとう彼女が言う。
「あのガキの親がまともならさ、傘持ってくると思わない? クズね」
「でも親が家にいるとも限らないし」
「土曜日よ? いるでしょ。あなたこのまま雨が止まなかったらどうするつもり。わたし達はずぶ濡れで走って帰るの? そもそもあんなガキにいい顔して、なんの意味もないよ」
「まあそう言わないでくれよ。だって子供をあのまま公園においておいたら、心が痛むじゃないか」
「そうかしら。私は全然気にしないけど。ガキが濡れようと、猫が死のうと」
僕は目をそらし、雨粒で揺れる川面を眺める。彼女がため息をつく。
午後4時、雨はまだやまない。でも少しずつ小ぶりになっていた。池田さんは橋の下の段差に腰掛け、少し明るくなった雨空を眺めている。彼女がつぶやく。
「あなたがもし、明日死ぬとしたら、さっきみたいにあの子供に傘を渡すと思う?」
「うん。たぶん渡すと思うよ」
「そうかしらね。まあ、そこまでお人好しなら清々しいわね」
なんとなく、このとき僕は彼女のことを鬼のお面を通して見てみた。彼女の体の目玉は以前よりさらに少なくなっているように見えた。
彼女が僕に問う。
「将来子供ができたらなんて名前にしたい?」
「うーん、『ともひろ』かな」
「なんで?」
「友達をたくさん作ってほしいから」
彼女は軽く吹き出した。
「喧嘩をうってるの?」
「…」僕は話題を変える「縄跳びでもしようか」
僕らはそれぞれ自分の縄跳びをカバンから取り出し、練習をした。
縄が地面を叩く音が橋の下に響いた。
やがて、雨は上がった。その日はそれで池田さんと別れた。辺りはもう暗く、西の空だけが薄明るく白んでいた。
その目玉はメガネみたいに目玉が横に2つつながっている。それ以外の体の構造はたまちゃんと同じだ。生態もたまちゃんと全く同じで、餌を食べ、ただ僕に着いてくるだけだ。これといったメリットはない。ちょっと安易だけど、二匹目なので「次郎」と名づけた。
そして次郎が生まれた翌日も学校の裏門の付近には松ぼっくりが落ちていた。たぶん近いうちに「三郎」も生まれるだろう。
さて、池田さんとお友達になってからというもの、僕らは一緒に過ごすことが多くなった。放課後は縄跳びをしたり、図書室で本を読んだり、休日には市民プールや町の書館にも足を運んだ。
池田さんはやはり、たいへんな読書家で、大人向けの作品でも難なく読む。でも彼女曰く、本が好きなのではなく、「やることがないから」本を読んでいるらしい。
彼女が特によく読んでいるのは幻想怪奇文学だ。その中でもおすすめはアンブローズ・ビアスという人だそう。僕も子供向けのふりがなが振ってあるものを読んでみたが、何が面白いのかさっぱり理解できなかった。しかも、だいたいの主人公が死んでしまうので非常に後味が悪い。僕はもう少しポジティブな物語がよみたいと思う。彼女曰く「子供にも女にも貧乏人にも勇敢な兵士にも容赦ないところが好き」なんだとか。他にも泉鏡花の現代語訳の外科室をおすすめされた。こちらは「ゾクゾクする」という。これについては物語の展開に全くついていけず、なんだかよく分からなかった。
5月のある土曜日のこと。その日僕らは午前授業の後、公園で縄跳びをしていた。この公園も川沿いの道のすぐ脇にある。池田さんが三毛猫に餌やりをしていた橋とは違うが、橋を渡ってすぐのところにある公園だ。
午後、そこで僕らは縄跳びの練習に少し疲れてきたから、ベンチで休んでいた。すると公園のフェンスのうえを虫取り網と麦わら帽子が横切った。すぐに麦わら帽子を被った少年が現れた。たぶん小学一二年生といったところだろう。青いTシャツにブカブカのズボンをゴムのベルトで止めている。頭は丸刈りで、肩に虫かごをかけ、片手に虫網を持っている。
虫取りに来たのだろう。公園を眺め回し、僕らの向かい側の樹木に向かった。少年は枝葉をつついたり幹を蹴飛ばしたりしている。いろいろ試してみたが、結果は伴わなかった。
今度はツツジの生け垣を回り始めた。それでも、なかなか何も見つからないようだ。5月の下旬なのでまだ虫は少ないのだ。
僕がふと公園の中央の低い草むらに目を向けるとアゲハチョウが飛び回っていた。
「おーい」僕は草むらを指差して少年に声をかける「そこの草むらに蝶々がいるよ!」
少年は真剣な表情でその草むらに駆け寄ると虫取り網を振り回した。それを何度か繰り返すと、どうやら蝶を捕まえたようで、虫かごに蝶を収めた。そして少年は誇らしげに僕らに虫かごを掲げてみせた。
「僕もあのくらいの頃はよく虫取りをしたな」
彼女は身を乗り出して言う。
「私もしたよ。私は生き物が好きなの。愛していると言っても過言ではないわ」
どうも本心から言ってるらしい。僕は彼女に問う。
「へー。僕は一時期、捕まえて持ち帰って、トカゲやカブトムシを飼っていたよ。君は?」
彼女は腕を組むと、遠くにいる少年を眺めながら答えた。
「私は脚や頭を千切ってどうなるのか観察していたわ。意外と虫ってどこを失っても死なないのよ」
「それは変わった愛し方だね。僕ならそんな愛され方はごめんだなあ。ははは」
目を細めて彼女が言う。
「私は二学期からは生き物係になろうと思ってる」
僕は肘を膝に置き、俯いて答える。
「そう。でも猫のように殺したら問題になると思うよ」
池田さんは横目で僕を見下した。
そのとき一滴、雨粒が僕の腕に落ちた。僕は空を見上げる。空は一面、灰色の雲に覆われていた。
すぐに辺りは細かい雨に包まれた。僕は折りたたみ傘を持っていたので、彼女との間に差し、とりあえず橋の下に行った。橋の下から公園を見ると、少年が公園の中央につっ立っていた。僕は走って、もう一度公園に向かった。そして公園の中央の少年に折りたたみ傘を手渡した。少年は
「ありがとう」
と言って公園の出口へ駆けていった。彼は出口で振り返ると虫網を脇に抱え、僕に向かって手を振り、その顔に気持ちのよい笑顔をつくった。少年を見送ると僕はまた走って橋の下へ戻った。橋の下に入ると彼女が言った。「お人好しね」
「まあね」
「早く雨が止むといいね」
「そうだね。きっと通り雨だよ。予報は雨ではなかったから」
しかし、雨はなかなか止まなかった。池田さんは橋脚に凭れ、気だるそうに片脚を揺らしている。大きくなってきた雨粒がノイズのような音を立てていた。川の流れも少しずつ増えていく。傘を指して疎らに行き交う人々や車を、たまちゃんたちが目で追っている。
彼女の顔が少しずつ不機嫌そうに変わっていく。
とうとう彼女が言う。
「あのガキの親がまともならさ、傘持ってくると思わない? クズね」
「でも親が家にいるとも限らないし」
「土曜日よ? いるでしょ。あなたこのまま雨が止まなかったらどうするつもり。わたし達はずぶ濡れで走って帰るの? そもそもあんなガキにいい顔して、なんの意味もないよ」
「まあそう言わないでくれよ。だって子供をあのまま公園においておいたら、心が痛むじゃないか」
「そうかしら。私は全然気にしないけど。ガキが濡れようと、猫が死のうと」
僕は目をそらし、雨粒で揺れる川面を眺める。彼女がため息をつく。
午後4時、雨はまだやまない。でも少しずつ小ぶりになっていた。池田さんは橋の下の段差に腰掛け、少し明るくなった雨空を眺めている。彼女がつぶやく。
「あなたがもし、明日死ぬとしたら、さっきみたいにあの子供に傘を渡すと思う?」
「うん。たぶん渡すと思うよ」
「そうかしらね。まあ、そこまでお人好しなら清々しいわね」
なんとなく、このとき僕は彼女のことを鬼のお面を通して見てみた。彼女の体の目玉は以前よりさらに少なくなっているように見えた。
彼女が僕に問う。
「将来子供ができたらなんて名前にしたい?」
「うーん、『ともひろ』かな」
「なんで?」
「友達をたくさん作ってほしいから」
彼女は軽く吹き出した。
「喧嘩をうってるの?」
「…」僕は話題を変える「縄跳びでもしようか」
僕らはそれぞれ自分の縄跳びをカバンから取り出し、練習をした。
縄が地面を叩く音が橋の下に響いた。
やがて、雨は上がった。その日はそれで池田さんと別れた。辺りはもう暗く、西の空だけが薄明るく白んでいた。