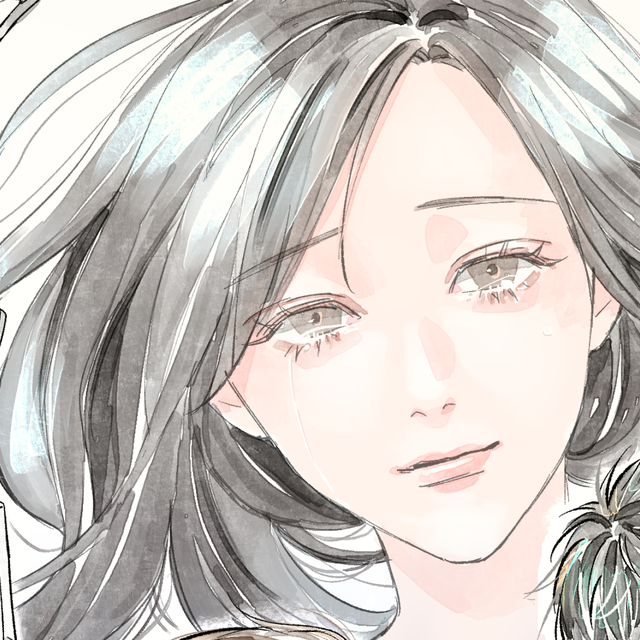第2話
文字数 8,290文字
黒のメルセデス後部座席に戻った将隆は、エンジンが掛かると同時に運転席間の仕切り窓を閉じ、声を上げて笑い出した。肩を震わせながら笑う姿を呆れ顔で見つめ、康則は溜め息を吐く。
「相馬刑事のこと、からかっているんですか?」
「そんなことはないよ。でも、あの顔は、面白かった」
言いながら、また、将隆は笑いを噛み殺す。
「失礼ですよ」
「礼は、表したつもりだけど? グローブも外したしね」
確かに、将隆が握手を求めるなど、滅多にないことだ。ただし、グローブは最初から付けていなかったのだが。
「堀川警視正に握手を求められたときは、無視されました」
「ああ、ビジネス関係の人間とは手を握らない主義なんだ。相馬刑事とは、友人になれそうだから握手したんだよ」
事件発生の一報が入って直ぐ、外出していた将隆に連絡した。屋敷近くにいたらしく数分で現れた将隆は、出動準備よりも先に、堀川警視正を呼び出せと命令したのだ。
その理由を聞き、康則は驚いた。
将隆が鬼龍家と警察の繋ぎ役として指名した人物が、相馬祐介だったからだ。
しかも「友人になれそうだ」とは……。
どこまで本気の言葉か、康則には計り知れない。
もしかして自分も、からかわれているのか? だとすれば、不愉快だった。
「不満そうな顔だな、康則。相馬刑事を指名した理由は、下っ端を取り次ぎ役にすることで上層部が動きにくくなると考えたのさ。警察に勝手な真似をされると、面倒だからな」
友人になれそうだと言いながら、下っ端扱いとは将隆らしい。少なからず、遊びで相馬を指名したわけではないようだ。
「ところで康則は、この状況を、どう考える?」
この状況とは言うまでもない、一般人の鬼化のことだ。
康則は頭の中で情報を整理し、言葉を選んで口を開く。
「二本以上の角を持つまでに成長した〈業苦の鬼〉は、鬼化の素因を持つ人間を嗅ぎ分けて操り、新たな鬼を生み出します。そこで先日の鬼狩り、高槻頼子と男の接点を調べましたが無関係でした。餌にされた女子学生と男の接点は不明ですが……実は、今の男も犠牲者かもしれません」
「俺も、そう思う。鬼化は本来、段階を得て進行する。だが今日、鬼化した男は変化に混乱して暴れ、知性を失った。頼子が兵隊にした鬼共と同じだ。強力な力を持つ鬼は、ターゲットにした相手の精気を枯れ果てる直前まで吸い取り、自らの一部を与える事で急激な変化を起こさせる。鬼化した男の近くに、真の敵がいたはずだ」
誰かが、いや、強い力を持つ〈業苦の鬼〉が意図的に一般人を鬼化している。
何のために?
将隆の口調も、表情も、いつもと同じく醒めていた。しかし、車中という狭い空間で近くにいると、そこに含まれた僅かな心象を感じることが出来た。
将隆は、「敵」と言った。怒っているのだ。
その怒りの矛先が、康則には解っていた。自らの欲望と罪を背負い、鬼になるのは業報だ。だが敵は、報いを受ける段階にない人間を利用し、多くの犠牲者を出している。
もはや、鬼龍家の体面は問題ではなかった。
将隆の怒りは、康則を奮わせた。一刻も早く敵の存在を、明らかにしなくてはならない。
「えっ……?」
その時、康則は自分の中に沸いた感情に戸惑い、思わず声をあげた。
主君に対する忠誠と、献身とは違う。純粋に、将隆を怒らせた敵が憎いと思ったからだ。
「なんだ? 心当たりがあるのか?」
怪訝そうに康則の顔を覗き込み、将隆が尋ねた。
「いえ……もう少し検証してからご報告するつもりでしたが、餌になった二人目の犠牲者は精気が枯れ果てていませんでした。鬼化に、失敗したとも考えられます。過去五十年ほどの統計から見ても、同じ地域で一般人の鬼化が連続発生した例はありません。鬼は、意図的に生み出されていると考えて、間違いないでしょう」
努めて平静に答えたが、胸にはまだ、不思議な感覚が残っていた。
顎に手を当て将隆は少し考え込んでいたが、顔を上げると運転席間の仕切り窓を開いた。
「車を、横浜にまわせ。今夜は帰らない」
「了解しました」
ハンドルを握る黒服隊員が無線を鬼龍家本部に繋ぎ、執事の鈴城に指示を仰ぐ。
「鬼化した男の身辺調査は、私がします。将隆さまは、屋敷に戻って下さい。確か今日は……」
将隆の母、館山の別邸に住んでいる鬼龍亜弥子が来訪しているはずだ。
「調査じゃない、屋敷は息が詰まるから外で遊んでくるだけだ。気が向いたら帰るよ」
館山まで会い行くことはあっても、父である将成の元で会うのは嫌なのだろう。その気持ちが理解できた康則は、それ以上、何も言わなかった。
「康則、おまえはどうする?」
「自分は残務処理と、男の身辺情報収集があるので帰ります」
「なんだ、つまらないヤツだな……」
必要とあれば、護衛も宿泊先も鈴城が用意する。一滴の返り血も浴びず、涼しい顔の将隆とは違って康則は、我が身に纏い付いた殺戮の臭いが気になった。
常時利用しているホテルは地下駐車場の直通エレベーターを使い、最上階にキープしてあるスイートまで誰にも会わずに行くことが出来る。それでも、その場所に存在する人々とは世界が違うのだと、思い知ることになるのだ。
相馬刑事の、異質な物を目にした人間特有の表情が、脳裏にこびり付いて離れない。
将隆が、ドア・ウィンドウを下げた。
心地よい夜風が、髪を掻き上げ頬を撫でた。この風が、血の臭いも拭い去ってくれればいいのにと思う。車窓の向こうに明滅する色とりどりの明かりに、平和な生活が垣間見えた。
世界の違い……。
康則は、広げた両手を見つめ、強く握りしめる。
〈業苦の鬼〉と鬼斬りの一族。相馬から見れば、どちらも化け物に思えるだろう。だが自分は、欲望に支配され殺戮に愉悦を覚える鬼とは違う。戦う理由があるのだ。
戦う理由? それは何だ? 主である、将隆のためだけか?
何度も繰り返される疑問の答えが、まだ見つからない。
「到着しました」
気が付くと車は、ホテルの地下駐車場に停まっていた。
部屋まで送ろうとした康則を断り将隆は、専用ケースに収めた〈鬼斬りの刀〉を携えて直通エレベーターのドア向こうに姿を消した。
再び走り出した車が、駐車場を出たときだった。普段使いの携帯電話が、メールの着信を知らせた。
『件名/お疲れ様
本文/今度、ゆっくり飯でも食おう』
相馬刑事からのメールに、康則は苦笑した。
◇
屋敷に帰り熱いシャワーを浴びた康則は、ようやく人心地がついた気がした。
将隆が不在の時は大抵、自室で食事を摂るのだが、迎えに出てきた万由里に遅い時間を希望しておいた。済ませたいことが、あったからだ。
まずは、将成の正室、鬼龍亜弥子に挨拶をしなくてはならない。
新しい学生服を手に取り、考えた。康則を実子の将隆と同じに扱う亜弥子は、堅苦しい挨拶を嫌う。礼を欠かない程度の私服に着替え、母屋に向かった。
おそらくは将成の住む別邸にいるであろう亜弥子に挨拶するタイミングを、執事の鈴城に聞こうと思ったのだ。
執務室の前を通りかかると、丁度ドアを開いて中に入るところだった鈴城が、康則に気付いた。相変わらず綺麗にプレスされた白シャツに海老茶のタイ、黒無地のスラックス姿。艶のある銀髪を普段よりきっちり後ろに撫でつけてあるのは、亜弥子が来訪しているからだ。
「これは……康則さま。お務め、お疲れ様でした。ところで此度の鬼ですが、切り落とされた右腕を発見するまで処理部隊が難儀したようです。しかし、先ほど無事に見つかったと報告がありましたので、ご安心下さい」
銀縁眼鏡の奥、少し咎めるような上目遣いで鈴城は康則を見た。右腕は確か、海中に没したはずだ。
いつもの務めと違い、今日は警察という招かれざる客がいた。
戦闘前、相馬に気付いた将隆が「派手なショーを観せてやろう」と言ったので、少し気負いすぎた。
悪いのは自分だ、責められても仕方がない。
「……申し訳ありませんでした。気をつけます」
殊勝顔で康則が詫びた時。
「鈴城、そのような言い方は私が許しません。康則さんは、命を懸けて大事なお務めをされているのですよ?」
背後から、凛とした女性の声が響いた。
木賊色の加賀小紋に黄檗の帯、朱の帯締め。襟元からすっと伸びた、細く白い項、ほつれ一つ無く結い上げられた髪。
鬼龍亜弥子が、初夏らしい和装の佇まいで居間から姿を現した。
「失礼いたしました、康則さま。他意はなかったのですが。では私は執務がありますので、これで」
鈴城は亜弥子に目礼した後、僅かに片眉を上げて康則に詫びてから執務室に入った。
「鈴城の難点は、職務に忠実すぎるところです。気に障る時がありましたら、わたくしに免じて許してあげて下さい」
居間から出てきた亜弥子は執務室に顔を向け、困ったように微笑んだ。弧を描く眉、細い鼻梁と顎。将隆は母親似だなと、改めて思った。
「あ、いえ、とんでもないです……今日の件は、自分に非がありますから。それで、あの、実は……」
言いにくそうにする康則を気遣い、亜弥子が遮る。
「将隆なら、気にしなくても良いのです。あの子は、わたくしと将成さまが一緒にいることを嫌います。ところで万由里から聞きましたが、まだ夕食を済ませていないそうですね。こちらに運ばせましょう。康則さんと少しお話しがしたいのですが、よろしいかしら?」
「承知、いたしました」
畏まる康則に、亜弥子が笑った。無邪気な少女のような笑顔だ。性格な年齢は知らないが、若々しい美しさは、高校生の息子を持つ女性には見えない。
「いらっしゃい、お茶を入れましょう」
居間に招かれた康則は、亜弥子にお茶を入れて貰い夕食を摂った。亜弥子は将成と一緒に夕食を済ませたと言って自分にもお茶を注ぎ、康則の話に耳を傾ける。
仕事の話は、敢えて聞いてこなかった。
康則が話したのは、学校のこと、友達のこと、授業で習っていることなどだ。亜弥子は季節の花や、館山の別邸で見たという鳥の話をしてくれた。
本当は、将隆の様子を話すべきなのだが、亜弥子を心配させる内容しか思いつかない。そう言えば今夜、将隆が横浜のどこで何をして遊ぶのかさえ知らなかった。亜弥子との会話で気が付き、康則は愕然とする。
学生の顔、鬼狩りの仕事をする顔、屋敷内で父親である将成に反発する顔。
職務に囚われすぎて自分は、将隆の本当の顔を見ていない?
「優希奈に、会ったそうですね」
食事の膳が下げられてから、熱いお茶を入れ直していた亜弥子が唐突に切り出した言葉で、康則は我に返った。
流れからして、優希奈の話があるだろうと内心覚悟していた。
亜弥子の別居、月に二度の来訪、将隆の不在。疑問の答えは、全て明らかになっていた。だが実際に、その名が出てくると平静な気持ちではいられない。
「はい」
会った、とは言えなかった。優希奈は、康則のことが解らないのだから。
亜弥子は目を伏せ、一口お茶を含んでから再び康則に顔を向けた。
「お務めと解っていても、心穏やかではいられません。辛さから逃れようとして、家を出たわたくしを、将隆は恨んでいるでしょうね」
「それは、無いと思います。むしろ将隆さまは……」
亜弥子を慰めようとして、つい、口が滑った。
「将隆が、将成さまを憎んでいることは知っています。時間は掛かるでしょうが将隆も、いずれ将成さまのお考えが解るはずです」
「では亜弥子さまは、将成さまを……」
許しているのか? それでは、あまりにも将隆が不憫だ。
亜弥子は何も言わずに、悲しそうな目をした。それが、口にすることが出来ない答えだった。
居たたまれずに、康則は席を立つ。部屋を出ようとした矢先、亜弥子の声が背に掛かった。
「欲望だけが、鬼化の原因でしょうか?」
振り向くと、射貫くような真摯な瞳が、康則を見つめていた。
「それは、どういう意味です?」
着物の裾も乱さす立ち上がった亜弥子は、滑らかに康則の傍らへ歩み寄る。ふわりと、甘い香りが鼻腔をくすぐった。
「高槻家御当主の依頼で、鬼となった長女の頼子さんを斬りに行かれたそうですね……。高槻家代々の〈業苦〉を背負ったとしても、女性である頼子さんが、お金や地位や名誉といった欲望で鬼になったと思いますか?」
「えっ?」
「頼子さんは家柄が違うという理由で、恋人を奪われました。その怨念が、彼女を鬼にしたのです。恋人は自ら鬼となって頼子さんと祝言を挙げ、一緒に斬られるつもりでした」
康則は、花嫁姿の頼子と黒羽二重の青年を思い出した。あの青年は、頼子と一緒に死ぬために、鬼になったというのか?
理解できない話だ。
「なぜ、亜弥子様はご存じなのですか?」
「高槻家とは……懇意にしていましたから」
高槻家の〈鬼狩り〉を依頼された時、調査した。当主の奥方は三年ほど前に病気で亡くなり、まだ大学生だった頼子を心配した亜弥子は、何かと相談に乗っていた。
まさか、頼子本人から打ち明けられたのか?
そして全ての事情を知った上で、将隆の初陣を見守るしかなかったとしたら……。
「申し訳ありませんが、亜弥子さまが言いたいことが解りません。自分は、自分に与えられた責務を果たすだけです。他に……何が出来ると言うんです?」
締め付けられたように苦しい胸から、やっと、声を絞り出した。
「人は、いつでも誰もが鬼になれる。鬼は、斬り捨てればいい。でも、それでは悲劇の連鎖は終わらない。〈業苦〉を断つのは、新たな悲劇を生むためではなく後に続く世代の幸せのためです。それだけは、忘れないで下さい。将隆を頼みます。あなただけが、あの子を守れるのですから」
そう言って亜弥子は、康則の右手を両掌で包み微笑んだ。とても、暖かな手だった。
不思議なことに、苛立ちや不安が霧散し、気力が蘇る。
亜弥子の言葉は、康則の心に一条の光をもたらした。
◇
務めがあった夜は、なかなか寝付くことが出来ないのだが、昨夜は久しぶりによく眠れた。
早朝に目覚め、すっきりとした頭で考えた。些細な疑問も問題も、一つずつ解決していけば必ず真実が見えてくるはずだ。自分が出来るのは、人脈を生かした地道な調査しかない。日曜日で時間がある今日は、情報を整理し考えをまとめてみよう。
身支度をしながら携帯を開いた。将隆との連絡用にはメールも着信もない。普段使いの携帯には、良昭の他に数人の友人からメールが入っていた。相馬からの追信は無く、康則は安堵の息を吐いた。
相馬は不確定要素が多すぎて、扱いあぐねる。
リビングのカーテンを開けると、気持ちの良い快晴だった。朝食までは、時間がある。庭を歩きながら、今日の段取りを決めることにした。
母屋の縁側から庭に出ると、スラックスの裾を朝露に濡らしながら執事の鈴城が若芽の剪定をしていた。
「おはようございます、鈴城さん」
「おはようございます、康則さま。お早いですね」
いつものスタイルに作業着を羽織った鈴城が、剪定ハサミの手を止め顔を向けた。
「鈴城さんこそ、こんなに早くから庭仕事までなさるんですか?」
「新緑が見苦しいほど伸びてきたので、庭師を頼まなくてはなりません。どう指示するか考えていたのですが、お屋敷から見える範囲だけでも朝のうちに整えておきます」
眉を寄せ、庭を見渡す鈴城に苦笑した。生真面目と言われる康則も、鈴城の完璧主義にはかなわない。
現在二名の見習い執事がいるが、財務管理から仕事の窓口、交渉代理、はては厨房事から庭の管理までこなす鈴城の後を継ぐのは難しそうだ。
「昨夜、将隆さまは戻られたのですか?」
康則の質問に、鈴城は少し首を傾げる。
「康則さまが存じ上げないのでしたら、わたくしは存じません」
将隆の世話は、康則の仕事だと言いたそうだ。将成の忠臣である鈴城とは、雑談一つするにも神経が磨り減る。ただし、話の内容が仕事に関する場合は別だ。
康則は気持ちを切り替え、業務だけを頼むことにした。
「蔵に保管されている古文書を調べたいので、鍵を貸して下さい」
「畏まりました。今すぐ、お持ちします」
鮮やかな手つきで腰に付けた革ケースに剪定ハサミを仕舞い、母屋に消えてから数分もしないうちに鈴城は、鍵束を持って戻ってきた。
「書庫は……三号蔵です。以前、亜弥子さまに頼まれて御用意した物がありますが、御利用になりますか?」
蔵番号を告げる時、少しだけ迷いがあった。優希奈の件が康則に知られた事を、万由里に聞いたのだろう。
隙に付け込むのは気が進まないが、これまでのやり方で事態の進展はない。亜弥子の信頼が、康則の強気を後押しした。
「ええ、お願いします。ところで鈴城さんは、優希奈さんが変化した原因を知っていますか?」
礼を述べてから、思い切って単刀直入に尋ねてみた。
「存じません」
鈴城の仮面に、変化はない。
「選任の露払い、鎧塚清愁氏は知っているはずですね?」
「……」
「彼は何故、鬼になったのでしょう?」
僅かな、動揺。
「清愁さまの件は、将成さまだけがご存じです。わたくしは朝の仕事がありますので、失礼しても宜しいでしょうか?」
「ええ、どうぞ。引き止めてしまって、すみませんでした」
この瞬間、康則に対する鈴城の認識が変わったようだ。何かを納得したように頷き、一礼してから母屋へ戻っていった。
収穫は、あった。
鈴城の反応から、清愁の死の真相に鍵がある気がした。
しかし、何故? どうすれば、突き止められる?
鈴城の動揺と、会得の頷きの意味は……?
「康則さまの立ち位置が、我々のお仕えすべき当主を決めるのです。あなた様が、いつまでも将成さまに伺いを立てていては誰が当主なのか分からない」
声がした方に身体を向けると、東門警備の久米が庭箒を手にして立っていた。
「立ち位置……?」
久米は先ほど鈴城が剪定していたツツジの植え込みの間を抜けて来ると、康則の傍らに立った。口元には、穏やかな笑みが浮かんでいる。
「〈露払い〉の任に就いた者は主君を守るだけではなく、その正道を見極めなくてはなりません。主君に意見できる唯一の存在であり、組織の参謀でもあります。お若い康則さまに言葉で説明するのは難しいので、将成さまや鈴城さんは、見守っておられた。しかし最近になって、康則さまは変わられました。鈴城さんも、気が付いたようですね」
「いきなり……何を言い出すんですか、久米さん」
不可解な言葉に、康則は狼狽えた。
「先んずれば人を制す……守りの体勢から、攻めの体勢になられた。上に立つには、必要な資質です」
久米の言葉には、普段の態度からは想像もつかない気迫が込められていた。康則に向けて、真の務めを説いているのだ。
「自分には、将隆さまのあるべき姿を見極める役目と、その資質がある……」
「そうです、あなた様の資質を見抜き、将隆さまの露払いに推したのは清愁さまです。しかし慎み深い康則さまは、なかなか本領を発揮して下さらないので内心では、もどかしく思っておりましたよ」
清愁が、自分を推した?
新たな事実を知り、康則は我を忘れた。
「久米さんは、清愁さまを御存知なのですね! 清愁さまが鬼になり、将成さまに斬られた話は本当なんですか? お願いです、詳しく教えて下さい!」
康則の質問を覚悟して、その名を出したに違いない。久米は迷わず、言い切った。
「私の本来の姓は鎧塚、久米は養子先の姓です。そして清愁は……私の弟でした。私は頭脳を買われて養子に出され、剣技の優れた弟が将成さまに請われ〈露払い〉の任に就きました」
絶句した。
言われてみれば、康則の記憶にある清愁と面影が重なる部分があった。茫然自失の康則に向かって久米は寂しげに微笑み、その肩に手を置く。
「事実は伝えられても、真実は伝えることは出来ません。真実は、将隆さまと力を合わせ自分の手で掴みなさい。そうしなければ、何も解決しないでしょう」
「自分の手で、真実を掴む……」
康則は顔を上げて空を仰ぎ、大きく息を吸い込んだ。
頭上には、雲一つ無い澄み切った青空が広がっていた。
「相馬刑事のこと、からかっているんですか?」
「そんなことはないよ。でも、あの顔は、面白かった」
言いながら、また、将隆は笑いを噛み殺す。
「失礼ですよ」
「礼は、表したつもりだけど? グローブも外したしね」
確かに、将隆が握手を求めるなど、滅多にないことだ。ただし、グローブは最初から付けていなかったのだが。
「堀川警視正に握手を求められたときは、無視されました」
「ああ、ビジネス関係の人間とは手を握らない主義なんだ。相馬刑事とは、友人になれそうだから握手したんだよ」
事件発生の一報が入って直ぐ、外出していた将隆に連絡した。屋敷近くにいたらしく数分で現れた将隆は、出動準備よりも先に、堀川警視正を呼び出せと命令したのだ。
その理由を聞き、康則は驚いた。
将隆が鬼龍家と警察の繋ぎ役として指名した人物が、相馬祐介だったからだ。
しかも「友人になれそうだ」とは……。
どこまで本気の言葉か、康則には計り知れない。
もしかして自分も、からかわれているのか? だとすれば、不愉快だった。
「不満そうな顔だな、康則。相馬刑事を指名した理由は、下っ端を取り次ぎ役にすることで上層部が動きにくくなると考えたのさ。警察に勝手な真似をされると、面倒だからな」
友人になれそうだと言いながら、下っ端扱いとは将隆らしい。少なからず、遊びで相馬を指名したわけではないようだ。
「ところで康則は、この状況を、どう考える?」
この状況とは言うまでもない、一般人の鬼化のことだ。
康則は頭の中で情報を整理し、言葉を選んで口を開く。
「二本以上の角を持つまでに成長した〈業苦の鬼〉は、鬼化の素因を持つ人間を嗅ぎ分けて操り、新たな鬼を生み出します。そこで先日の鬼狩り、高槻頼子と男の接点を調べましたが無関係でした。餌にされた女子学生と男の接点は不明ですが……実は、今の男も犠牲者かもしれません」
「俺も、そう思う。鬼化は本来、段階を得て進行する。だが今日、鬼化した男は変化に混乱して暴れ、知性を失った。頼子が兵隊にした鬼共と同じだ。強力な力を持つ鬼は、ターゲットにした相手の精気を枯れ果てる直前まで吸い取り、自らの一部を与える事で急激な変化を起こさせる。鬼化した男の近くに、真の敵がいたはずだ」
誰かが、いや、強い力を持つ〈業苦の鬼〉が意図的に一般人を鬼化している。
何のために?
将隆の口調も、表情も、いつもと同じく醒めていた。しかし、車中という狭い空間で近くにいると、そこに含まれた僅かな心象を感じることが出来た。
将隆は、「敵」と言った。怒っているのだ。
その怒りの矛先が、康則には解っていた。自らの欲望と罪を背負い、鬼になるのは業報だ。だが敵は、報いを受ける段階にない人間を利用し、多くの犠牲者を出している。
もはや、鬼龍家の体面は問題ではなかった。
将隆の怒りは、康則を奮わせた。一刻も早く敵の存在を、明らかにしなくてはならない。
「えっ……?」
その時、康則は自分の中に沸いた感情に戸惑い、思わず声をあげた。
主君に対する忠誠と、献身とは違う。純粋に、将隆を怒らせた敵が憎いと思ったからだ。
「なんだ? 心当たりがあるのか?」
怪訝そうに康則の顔を覗き込み、将隆が尋ねた。
「いえ……もう少し検証してからご報告するつもりでしたが、餌になった二人目の犠牲者は精気が枯れ果てていませんでした。鬼化に、失敗したとも考えられます。過去五十年ほどの統計から見ても、同じ地域で一般人の鬼化が連続発生した例はありません。鬼は、意図的に生み出されていると考えて、間違いないでしょう」
努めて平静に答えたが、胸にはまだ、不思議な感覚が残っていた。
顎に手を当て将隆は少し考え込んでいたが、顔を上げると運転席間の仕切り窓を開いた。
「車を、横浜にまわせ。今夜は帰らない」
「了解しました」
ハンドルを握る黒服隊員が無線を鬼龍家本部に繋ぎ、執事の鈴城に指示を仰ぐ。
「鬼化した男の身辺調査は、私がします。将隆さまは、屋敷に戻って下さい。確か今日は……」
将隆の母、館山の別邸に住んでいる鬼龍亜弥子が来訪しているはずだ。
「調査じゃない、屋敷は息が詰まるから外で遊んでくるだけだ。気が向いたら帰るよ」
館山まで会い行くことはあっても、父である将成の元で会うのは嫌なのだろう。その気持ちが理解できた康則は、それ以上、何も言わなかった。
「康則、おまえはどうする?」
「自分は残務処理と、男の身辺情報収集があるので帰ります」
「なんだ、つまらないヤツだな……」
必要とあれば、護衛も宿泊先も鈴城が用意する。一滴の返り血も浴びず、涼しい顔の将隆とは違って康則は、我が身に纏い付いた殺戮の臭いが気になった。
常時利用しているホテルは地下駐車場の直通エレベーターを使い、最上階にキープしてあるスイートまで誰にも会わずに行くことが出来る。それでも、その場所に存在する人々とは世界が違うのだと、思い知ることになるのだ。
相馬刑事の、異質な物を目にした人間特有の表情が、脳裏にこびり付いて離れない。
将隆が、ドア・ウィンドウを下げた。
心地よい夜風が、髪を掻き上げ頬を撫でた。この風が、血の臭いも拭い去ってくれればいいのにと思う。車窓の向こうに明滅する色とりどりの明かりに、平和な生活が垣間見えた。
世界の違い……。
康則は、広げた両手を見つめ、強く握りしめる。
〈業苦の鬼〉と鬼斬りの一族。相馬から見れば、どちらも化け物に思えるだろう。だが自分は、欲望に支配され殺戮に愉悦を覚える鬼とは違う。戦う理由があるのだ。
戦う理由? それは何だ? 主である、将隆のためだけか?
何度も繰り返される疑問の答えが、まだ見つからない。
「到着しました」
気が付くと車は、ホテルの地下駐車場に停まっていた。
部屋まで送ろうとした康則を断り将隆は、専用ケースに収めた〈鬼斬りの刀〉を携えて直通エレベーターのドア向こうに姿を消した。
再び走り出した車が、駐車場を出たときだった。普段使いの携帯電話が、メールの着信を知らせた。
『件名/お疲れ様
本文/今度、ゆっくり飯でも食おう』
相馬刑事からのメールに、康則は苦笑した。
◇
屋敷に帰り熱いシャワーを浴びた康則は、ようやく人心地がついた気がした。
将隆が不在の時は大抵、自室で食事を摂るのだが、迎えに出てきた万由里に遅い時間を希望しておいた。済ませたいことが、あったからだ。
まずは、将成の正室、鬼龍亜弥子に挨拶をしなくてはならない。
新しい学生服を手に取り、考えた。康則を実子の将隆と同じに扱う亜弥子は、堅苦しい挨拶を嫌う。礼を欠かない程度の私服に着替え、母屋に向かった。
おそらくは将成の住む別邸にいるであろう亜弥子に挨拶するタイミングを、執事の鈴城に聞こうと思ったのだ。
執務室の前を通りかかると、丁度ドアを開いて中に入るところだった鈴城が、康則に気付いた。相変わらず綺麗にプレスされた白シャツに海老茶のタイ、黒無地のスラックス姿。艶のある銀髪を普段よりきっちり後ろに撫でつけてあるのは、亜弥子が来訪しているからだ。
「これは……康則さま。お務め、お疲れ様でした。ところで此度の鬼ですが、切り落とされた右腕を発見するまで処理部隊が難儀したようです。しかし、先ほど無事に見つかったと報告がありましたので、ご安心下さい」
銀縁眼鏡の奥、少し咎めるような上目遣いで鈴城は康則を見た。右腕は確か、海中に没したはずだ。
いつもの務めと違い、今日は警察という招かれざる客がいた。
戦闘前、相馬に気付いた将隆が「派手なショーを観せてやろう」と言ったので、少し気負いすぎた。
悪いのは自分だ、責められても仕方がない。
「……申し訳ありませんでした。気をつけます」
殊勝顔で康則が詫びた時。
「鈴城、そのような言い方は私が許しません。康則さんは、命を懸けて大事なお務めをされているのですよ?」
背後から、凛とした女性の声が響いた。
木賊色の加賀小紋に黄檗の帯、朱の帯締め。襟元からすっと伸びた、細く白い項、ほつれ一つ無く結い上げられた髪。
鬼龍亜弥子が、初夏らしい和装の佇まいで居間から姿を現した。
「失礼いたしました、康則さま。他意はなかったのですが。では私は執務がありますので、これで」
鈴城は亜弥子に目礼した後、僅かに片眉を上げて康則に詫びてから執務室に入った。
「鈴城の難点は、職務に忠実すぎるところです。気に障る時がありましたら、わたくしに免じて許してあげて下さい」
居間から出てきた亜弥子は執務室に顔を向け、困ったように微笑んだ。弧を描く眉、細い鼻梁と顎。将隆は母親似だなと、改めて思った。
「あ、いえ、とんでもないです……今日の件は、自分に非がありますから。それで、あの、実は……」
言いにくそうにする康則を気遣い、亜弥子が遮る。
「将隆なら、気にしなくても良いのです。あの子は、わたくしと将成さまが一緒にいることを嫌います。ところで万由里から聞きましたが、まだ夕食を済ませていないそうですね。こちらに運ばせましょう。康則さんと少しお話しがしたいのですが、よろしいかしら?」
「承知、いたしました」
畏まる康則に、亜弥子が笑った。無邪気な少女のような笑顔だ。性格な年齢は知らないが、若々しい美しさは、高校生の息子を持つ女性には見えない。
「いらっしゃい、お茶を入れましょう」
居間に招かれた康則は、亜弥子にお茶を入れて貰い夕食を摂った。亜弥子は将成と一緒に夕食を済ませたと言って自分にもお茶を注ぎ、康則の話に耳を傾ける。
仕事の話は、敢えて聞いてこなかった。
康則が話したのは、学校のこと、友達のこと、授業で習っていることなどだ。亜弥子は季節の花や、館山の別邸で見たという鳥の話をしてくれた。
本当は、将隆の様子を話すべきなのだが、亜弥子を心配させる内容しか思いつかない。そう言えば今夜、将隆が横浜のどこで何をして遊ぶのかさえ知らなかった。亜弥子との会話で気が付き、康則は愕然とする。
学生の顔、鬼狩りの仕事をする顔、屋敷内で父親である将成に反発する顔。
職務に囚われすぎて自分は、将隆の本当の顔を見ていない?
「優希奈に、会ったそうですね」
食事の膳が下げられてから、熱いお茶を入れ直していた亜弥子が唐突に切り出した言葉で、康則は我に返った。
流れからして、優希奈の話があるだろうと内心覚悟していた。
亜弥子の別居、月に二度の来訪、将隆の不在。疑問の答えは、全て明らかになっていた。だが実際に、その名が出てくると平静な気持ちではいられない。
「はい」
会った、とは言えなかった。優希奈は、康則のことが解らないのだから。
亜弥子は目を伏せ、一口お茶を含んでから再び康則に顔を向けた。
「お務めと解っていても、心穏やかではいられません。辛さから逃れようとして、家を出たわたくしを、将隆は恨んでいるでしょうね」
「それは、無いと思います。むしろ将隆さまは……」
亜弥子を慰めようとして、つい、口が滑った。
「将隆が、将成さまを憎んでいることは知っています。時間は掛かるでしょうが将隆も、いずれ将成さまのお考えが解るはずです」
「では亜弥子さまは、将成さまを……」
許しているのか? それでは、あまりにも将隆が不憫だ。
亜弥子は何も言わずに、悲しそうな目をした。それが、口にすることが出来ない答えだった。
居たたまれずに、康則は席を立つ。部屋を出ようとした矢先、亜弥子の声が背に掛かった。
「欲望だけが、鬼化の原因でしょうか?」
振り向くと、射貫くような真摯な瞳が、康則を見つめていた。
「それは、どういう意味です?」
着物の裾も乱さす立ち上がった亜弥子は、滑らかに康則の傍らへ歩み寄る。ふわりと、甘い香りが鼻腔をくすぐった。
「高槻家御当主の依頼で、鬼となった長女の頼子さんを斬りに行かれたそうですね……。高槻家代々の〈業苦〉を背負ったとしても、女性である頼子さんが、お金や地位や名誉といった欲望で鬼になったと思いますか?」
「えっ?」
「頼子さんは家柄が違うという理由で、恋人を奪われました。その怨念が、彼女を鬼にしたのです。恋人は自ら鬼となって頼子さんと祝言を挙げ、一緒に斬られるつもりでした」
康則は、花嫁姿の頼子と黒羽二重の青年を思い出した。あの青年は、頼子と一緒に死ぬために、鬼になったというのか?
理解できない話だ。
「なぜ、亜弥子様はご存じなのですか?」
「高槻家とは……懇意にしていましたから」
高槻家の〈鬼狩り〉を依頼された時、調査した。当主の奥方は三年ほど前に病気で亡くなり、まだ大学生だった頼子を心配した亜弥子は、何かと相談に乗っていた。
まさか、頼子本人から打ち明けられたのか?
そして全ての事情を知った上で、将隆の初陣を見守るしかなかったとしたら……。
「申し訳ありませんが、亜弥子さまが言いたいことが解りません。自分は、自分に与えられた責務を果たすだけです。他に……何が出来ると言うんです?」
締め付けられたように苦しい胸から、やっと、声を絞り出した。
「人は、いつでも誰もが鬼になれる。鬼は、斬り捨てればいい。でも、それでは悲劇の連鎖は終わらない。〈業苦〉を断つのは、新たな悲劇を生むためではなく後に続く世代の幸せのためです。それだけは、忘れないで下さい。将隆を頼みます。あなただけが、あの子を守れるのですから」
そう言って亜弥子は、康則の右手を両掌で包み微笑んだ。とても、暖かな手だった。
不思議なことに、苛立ちや不安が霧散し、気力が蘇る。
亜弥子の言葉は、康則の心に一条の光をもたらした。
◇
務めがあった夜は、なかなか寝付くことが出来ないのだが、昨夜は久しぶりによく眠れた。
早朝に目覚め、すっきりとした頭で考えた。些細な疑問も問題も、一つずつ解決していけば必ず真実が見えてくるはずだ。自分が出来るのは、人脈を生かした地道な調査しかない。日曜日で時間がある今日は、情報を整理し考えをまとめてみよう。
身支度をしながら携帯を開いた。将隆との連絡用にはメールも着信もない。普段使いの携帯には、良昭の他に数人の友人からメールが入っていた。相馬からの追信は無く、康則は安堵の息を吐いた。
相馬は不確定要素が多すぎて、扱いあぐねる。
リビングのカーテンを開けると、気持ちの良い快晴だった。朝食までは、時間がある。庭を歩きながら、今日の段取りを決めることにした。
母屋の縁側から庭に出ると、スラックスの裾を朝露に濡らしながら執事の鈴城が若芽の剪定をしていた。
「おはようございます、鈴城さん」
「おはようございます、康則さま。お早いですね」
いつものスタイルに作業着を羽織った鈴城が、剪定ハサミの手を止め顔を向けた。
「鈴城さんこそ、こんなに早くから庭仕事までなさるんですか?」
「新緑が見苦しいほど伸びてきたので、庭師を頼まなくてはなりません。どう指示するか考えていたのですが、お屋敷から見える範囲だけでも朝のうちに整えておきます」
眉を寄せ、庭を見渡す鈴城に苦笑した。生真面目と言われる康則も、鈴城の完璧主義にはかなわない。
現在二名の見習い執事がいるが、財務管理から仕事の窓口、交渉代理、はては厨房事から庭の管理までこなす鈴城の後を継ぐのは難しそうだ。
「昨夜、将隆さまは戻られたのですか?」
康則の質問に、鈴城は少し首を傾げる。
「康則さまが存じ上げないのでしたら、わたくしは存じません」
将隆の世話は、康則の仕事だと言いたそうだ。将成の忠臣である鈴城とは、雑談一つするにも神経が磨り減る。ただし、話の内容が仕事に関する場合は別だ。
康則は気持ちを切り替え、業務だけを頼むことにした。
「蔵に保管されている古文書を調べたいので、鍵を貸して下さい」
「畏まりました。今すぐ、お持ちします」
鮮やかな手つきで腰に付けた革ケースに剪定ハサミを仕舞い、母屋に消えてから数分もしないうちに鈴城は、鍵束を持って戻ってきた。
「書庫は……三号蔵です。以前、亜弥子さまに頼まれて御用意した物がありますが、御利用になりますか?」
蔵番号を告げる時、少しだけ迷いがあった。優希奈の件が康則に知られた事を、万由里に聞いたのだろう。
隙に付け込むのは気が進まないが、これまでのやり方で事態の進展はない。亜弥子の信頼が、康則の強気を後押しした。
「ええ、お願いします。ところで鈴城さんは、優希奈さんが変化した原因を知っていますか?」
礼を述べてから、思い切って単刀直入に尋ねてみた。
「存じません」
鈴城の仮面に、変化はない。
「選任の露払い、鎧塚清愁氏は知っているはずですね?」
「……」
「彼は何故、鬼になったのでしょう?」
僅かな、動揺。
「清愁さまの件は、将成さまだけがご存じです。わたくしは朝の仕事がありますので、失礼しても宜しいでしょうか?」
「ええ、どうぞ。引き止めてしまって、すみませんでした」
この瞬間、康則に対する鈴城の認識が変わったようだ。何かを納得したように頷き、一礼してから母屋へ戻っていった。
収穫は、あった。
鈴城の反応から、清愁の死の真相に鍵がある気がした。
しかし、何故? どうすれば、突き止められる?
鈴城の動揺と、会得の頷きの意味は……?
「康則さまの立ち位置が、我々のお仕えすべき当主を決めるのです。あなた様が、いつまでも将成さまに伺いを立てていては誰が当主なのか分からない」
声がした方に身体を向けると、東門警備の久米が庭箒を手にして立っていた。
「立ち位置……?」
久米は先ほど鈴城が剪定していたツツジの植え込みの間を抜けて来ると、康則の傍らに立った。口元には、穏やかな笑みが浮かんでいる。
「〈露払い〉の任に就いた者は主君を守るだけではなく、その正道を見極めなくてはなりません。主君に意見できる唯一の存在であり、組織の参謀でもあります。お若い康則さまに言葉で説明するのは難しいので、将成さまや鈴城さんは、見守っておられた。しかし最近になって、康則さまは変わられました。鈴城さんも、気が付いたようですね」
「いきなり……何を言い出すんですか、久米さん」
不可解な言葉に、康則は狼狽えた。
「先んずれば人を制す……守りの体勢から、攻めの体勢になられた。上に立つには、必要な資質です」
久米の言葉には、普段の態度からは想像もつかない気迫が込められていた。康則に向けて、真の務めを説いているのだ。
「自分には、将隆さまのあるべき姿を見極める役目と、その資質がある……」
「そうです、あなた様の資質を見抜き、将隆さまの露払いに推したのは清愁さまです。しかし慎み深い康則さまは、なかなか本領を発揮して下さらないので内心では、もどかしく思っておりましたよ」
清愁が、自分を推した?
新たな事実を知り、康則は我を忘れた。
「久米さんは、清愁さまを御存知なのですね! 清愁さまが鬼になり、将成さまに斬られた話は本当なんですか? お願いです、詳しく教えて下さい!」
康則の質問を覚悟して、その名を出したに違いない。久米は迷わず、言い切った。
「私の本来の姓は鎧塚、久米は養子先の姓です。そして清愁は……私の弟でした。私は頭脳を買われて養子に出され、剣技の優れた弟が将成さまに請われ〈露払い〉の任に就きました」
絶句した。
言われてみれば、康則の記憶にある清愁と面影が重なる部分があった。茫然自失の康則に向かって久米は寂しげに微笑み、その肩に手を置く。
「事実は伝えられても、真実は伝えることは出来ません。真実は、将隆さまと力を合わせ自分の手で掴みなさい。そうしなければ、何も解決しないでしょう」
「自分の手で、真実を掴む……」
康則は顔を上げて空を仰ぎ、大きく息を吸い込んだ。
頭上には、雲一つ無い澄み切った青空が広がっていた。