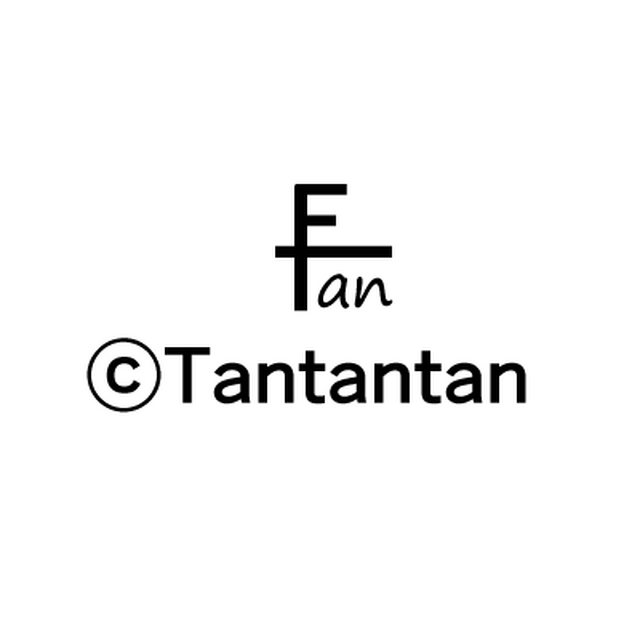五章 瑞木新七のアリバイ、そして三人目の死体
文字数 8,029文字
敷地内の瓦礫を外に出す作業も同時に行われていた。下屋敷にふたたび、踏み場がもどっていた。別府は書院のまえに立っていた。見張りの男を呼びよせた。
「所沢、おまえは書院のまえを見張っていてくれ。瑞木を外に出さないように、たのみたいのだ」
所沢は不満気に目を見開いた。
同心に気おくれせず、口をとがらせた。
「瑞木さんですか……。彼は下手人の犯行を目撃していました。同心様の助けを呼んだのも彼です。だから……」
「瑞木の犯行を疑うのはおかしいと云いたいのか?」
「ええ。わたしはふだんから彼と会話しています。瑞木さんの人柄もよく知っています。人殺しをするような人には思えません」
書院に目を向けた。瑞木は室内でざしていた。
「もちろん、一見、彼の犯行がむずかしいように思える。瑞木新七は、最初に佐々木の死体を発見した。死体の第一発見者だ。同心である、われわれを呼びこんだ。凶器ももっていなかった。それでも、下手人ではないと断定できない」
「なぜですか?」
「蛇崩池の氾濫は、下屋敷への侵入をとざしている。下手人は裏門以外からは侵入できなかった。だから、最初に鉢合わせになったのは佐々木だ。おそらく、佐々木は最初に殺されている」
「でしたら、その犯行を目撃した瑞木さんでは無理でしょう」
「いいや。犯行を終えたあとに、土間へともどってくることはできる。瑞木以外に目撃した者はいない。瑞木が下手人ならば、証言も信用できなくなる。疑いは完全には晴れない」
「つまり、瑞木さんは佐々木様を殺害し、そのあと、すぐ昌村様を殺した。なに食わぬ顔で土間へともどり、下手人を目撃したふりをしたということですか?」
「そのとおりだ。素早くふたりを殺害すれば、実行できる」
「……たいへんな犯行ですけど、たしかにありえますね」
「じっさい、下手人は密室の土倉で、どのように大村を殺したのか。蛇崩池の濁流が来るまでに、もどってくる時間はあったのか、慎重に確認しなくてはならない。ただ、ありえない話ではない以上、瑞木の監視が必要だ」
所沢は両目をゆっくりと開閉した。黒い瞳を縦にゆらした。
「わかりました。彼がおかしな行動をとらないように見ておきます」
所沢は口唇の両端をさげていた。への字になっていた。
気合いを入れ直したように見える。
別府は書院から離れるように、きびすをかえした。
背後には未堂棟が立っていた。気がつかなかった。別府は未堂棟と衝突した。未堂棟の両胸を押し出す形になった。未堂棟は依然として立ちどまっていた。未堂棟には確固たる意志があった。書院の屋根をじっと見ていた。書院とは書斎のことだ。
室内には本が所狭しとならべられている。経子が立ちいりを許されなかった場所だ。書院の外見は普通の家屋だ。ほかの屋敷よりも簡素な屋根だった。
四角い小屋に二面の屋根がのっている。典型的な切妻屋根だが、直上に瓦がない。化粧屋根のままだった。下地の板だけをのせて、真下に長い棒を釣りさげている。
竿だった。
「どうやら突き上げ窓になっているようだ。開閉できる屋根として使っている。珍しいな」
突き上げ窓は、茶室に設けられる形式だった。竿で押すと、一部の屋根をひらくことができた。屋根の大部分が突き上げ窓になっている造りは珍しかった。
「天日干しにした魚を保存する小屋などは、海辺で、たまに見かけるが」
蛇崩町は海沿いではない。しかし、川沿いではある。
川魚を捕ったとき、干す場所も必要になる。
いまは書院として使っているが、家屋そのものは下屋敷が建てられるまえからあったのかもしれない。別府はふと土倉に目を向けた。
脳裏をよぎるものがあったからだ。
しかし、すぐに肩をすくめた。苦笑いを浮かべた。
「もしかしたら、土倉の屋根も突きあげられるのかと思ったが、流石にそれはなさそうだ」
土倉は書院とは、あきらかに造りがことなっていた。土倉のほうは、全面に瓦がのせられている。四方は漆喰で塗り固められていた。遠目で見ても高い。屋根は二段になっていた。
「しかし、念には念をいれる必要がある。未堂棟、これから土倉の調査をする。異存はないか?」
未堂棟は名残惜しそうに書院を見ていた。
ゆっくりと別府のうしろを追ってきた。
土倉のまえは、ほぼ片づけられていた。太陽によって、泥水も蒸発をはじめている。
大村昌村の死体は土倉の端に出されていた。
身体を隠すように、わらがのせられていた。
別府はわらの前方をめくった。
「……最初に見たときは、水に浸かっていたからわからなかったが、少し痛んでいる。浸水の勢いに流されて、傷を負ったのかもしれない。皮膚は紫色だ。時間経過がうかがえる。ただし、虫は湧いていない」
泥水に浸かっていたから、とうぜんでもあるが、腐敗臭もない。
通常の夏過ぎの気温だと、一日、経っていると死体に変化が出る。
「やはり、蛇崩池の氾濫のあとに殺されたと考えるべきだ。そうなると、問題はどうやって、堅牢な土倉を突破したのかになる」
別府は立ちあがろうとした。ふたたび、腰をおろした。死体の横に引き戸があった。地面と隣接している。二の腕ほどの幅しかない。ひらいてみる。
わずかに空間が広がっていた。
奥行きはお盆ひとつ分だ。土間の真下を掘ったようだ。
「この引き戸から食事と水桶をいれていたのか。いまは流されてしまって、なにも置いていない。大村昌村は心臓を突かれていた。この隙間では、凶器を彼の左胸へと刺すことはできない。身体半分もはいらない」
密室殺人の打破にはならなかった。別府は正面にまわった。
門扉はすでに壊されていた。錠前も置いたままになっていた。
「蝶番に細工された形跡はない。錠前には傷ひとつない。まだ下屋敷にあった鍵は見つかっていないが、和錠はまともだ。無理に押しいったようには思えない」
別府は欅の門扉を叩いていった。共鳴音は一定だった。一部が腐っているということもない。蝶番は欅にふかく食いこんでいる。上下に動かした形跡もなかった。
「門扉を両脇からとり外して、殺害したあとにもどすといったことも考えたが、そういった細工が見つからない。下手人は、この出入り口を使っていないように思える」
別府は室内にはいった。一気に気温がさがった。肌寒く感じる。土倉は外の気温がとどきにくいようだ。室内には昌村のもちこんでいた私物が散乱していた。
ほとんどが壊れている。
殺しに関係しているものもあるかもしれない。別府は入念に見回した。読めなくなった瓦版。阿蘭陀の望遠鏡。長細いござ。木綿の布団。夏用の夜着。大きめの括り枕。めぼしい遺留品はない。下手人が利用できそうなものも、見当たらなかった。
別府は、もっともちかくにあった瓦版を拾いあげた。
「瓦版の日付だけは読める。さいきんだ。日食の予報も書いている。万屋にかよっていたのは、ほんとうのようだ」
つぎにござをつかんだ。ひっくりかえした。
「血痕がこびりついている。昌村は出血のほとんどをござのうえに出したようだ。真っ赤になっている。固まっている」
土倉の床は土だった。
「地面に高い場所から落下したような削り跡もあるが、生活の跡にも見える。少なくとも土倉の出入り口にはならないな」
別府は土倉の内壁を叩きながらまわった。
破損箇所がないかを調べた。
「だめだ。土倉の造りには、なんの問題もない。濁流も門扉の隙間からとおったものだ。穴はあけられていない」
打つ手がなくなっていた。だれが下手人でも、犯行はむずかしかった。
どうやって、密室内にいた大村昌村を殺したのか。
その方法を突き止めないと、なにもはじまらない。
「昌村が自分で心臓を突いたことも考えられるが、それならば、土倉のなかで凶器が発見されるはずだ。逃げ場はないのだからな。しかし、この場に、凶器のかわりになるものもない」
別府は苦悶の表情を浮かべた。
「……いったい下手人はどうやって昌村を殺害したのだ」
別府は背中を内壁に預けた。
ひんやりとした感触が背中に広がった。代案が出なかった。
しかし、絶望はしていなかった。別府は常々、感じていたことがある。
頭のなかが暗闇に染まったとき、あるいは否定的な状況が起きたとき、かならず光は差しこんでくる。そして、それは神様や仏様から差しこむのではない。昔からの友人が与えてくれる。
未堂棟は門扉の外に立っていた。
「――そもそも……」
別府は顔をあげた。未堂棟は頬に手をあて、首を横にかしげていた。
「――下手人はどうして敷地内に泥水がみたされるのを待ったのでしょうか? 佐々木さんさえ殺害すれば、出入りは自由だったはずです。蛇崩池を壊した必要性が感じられないのです」
「見張りを土倉にちかづかせないためではないか。静かな夜だと、昌村を殺すときの音で気づかれるかもしれない」
表門にはふたりの男が立っていた。土倉からは、さほど、とおくない。
「水音があれば、大村昌村のうめき声もきこえにくいものとなる。じっさいに彼らは見張り台のうえに避難していた。下手人が捕まらないようにするために、蛇崩池を壊し、氾濫させたのではないか?」
未堂棟はすぐに首を横にふった。
「――われわれは土嚢を周辺に置くことで敷地内を歩くことができたのです。それまでは大水にかこまれていました。はたして下手人は奔流のなかで、土倉のまわりを歩きまわれたのでしょうか?」
「……ううむ。それは無理だ。不可能だ。この土倉は中庭と面していている。遮蔽物がない。蛇崩池と土倉は直線上にある。当時も強い波に打たれていたにちがいない」
別府は錠前を壊れた門扉に引っかける。
「下手人に時間はなかったはずだ。濁流に足がとられるなかで、土倉の門扉を交換するといった方法も、とうぜん、とれなかった」
未堂棟は左目をひらきつづけている。
九回目だった。
「――そもそも蛇崩池を氾濫させた目的は、ほんとうに殺人のためなのでしょうか。破壊や陽動だけではない。ほんとうに、敷地内に水をいれる必要があったとは考えられませんか?」
「なるほど、氾濫の見方を変えるのか。下手人には水が必要だった……。地上を歩くことをできなくしていた……。このふたつが関係しているとしたら……いったいなにが……」
そのとき、脳裏に電撃が走った。
別府は首をうしろにさげていった。
「ありえるかもしれない」
発想の手掛かりは屋根の種類にあった。
「書院のほうは屋根が開閉式だったが、土倉のほうは瓦屋根だ。越屋根になっている。越屋根の特徴は二段屋根にある。採光と換気のために、二段屋根の上部に、出窓がつくられるのだ」

別府は両手をのばした。一段目の瓦屋根にはとどかない。
……濁流が弱い段階だったら、周囲に、なにか置いていたかもしれない。下手人の計画通りだったとすれば、あらかじめ、目をつけたものがあったはずだ。
別府は土倉の外壁を見ながら、周辺を歩きまわる。裏側の漆喰、その一部に汚れがあった。汚れをよく見ると、泥ではなかった。
こけだ。
周辺を見わたした。荷車が表門の壁によっていた。泥をかぶっている。濁流に押されて、運ばれたにちがいない。こけの高さは荷車より低い。もともと、荷車は土倉に隣接していたらしい。日の光がとどかなかったから、こけが生えたのだ。
別府は荷車を土倉まで引いた。濁流がはいるまえと同じ位置に置いた。荷車を足場にする。一段目の瓦屋根を見た。
さきほどとはことなり、両手でつかめる高さとなった。
別府は瓦屋根のうえにのぼった。
「思ったとおりだ。土倉のなかからは見えなかったが、越屋根には採光のための出窓がつくられている。顔が出るか出ないかのおおきさだが、刃物を押しこむだけなら可能だ」
出窓の木枠は外されていた。血痕が底にこびりついている。
漆喰が削り落とされるように長細い跡がふたつのこっていた。
「縄はしごをかけた跡だ。下手人は、ここから昌村を呼んだのだ」
大村昌村は下手人の云われるままに避難しようとした。顔を出窓に出した。下手人はその夜着をつかみあげる。別府は闇夜に凶器が光る姿を想像した。
彼の心臓は目のまえだ。
息の根をとめるのは、羽虫を潰すより簡単なものだったにちがいない。
……一日はやく面会できていたら、防げていたのかもしれない。
後悔がつのった。
別府は未堂棟の待つ土倉までおりていった。瓦屋根で見つけた血痕を報告した。
「未堂棟、わかったぞ。密室でどうやって昌村を殺したのかわかった。未堂棟の云うとおりだった。下手人は濁流によって、下屋敷を破壊することが目的ではなかったのだ」
別府はしゃがみこんだ。門扉にふれた。泥の汚れが指についた。腰の高さだ。蛇崩池の泥水はここまでとどいていたことになる。
「昌村は轟音と浸水で目がさめた。なにが起きているかわからず、混乱したはずだ。ひとりでは外に出られなかった。轟音で声もとどかない。みるみると泥水は侵入し、室内の水かさはましていった」
天井までの高さは大の男、四人分だ。
のぼることはできない。彼は仏を祈る思いだったにちがいない。
「そのときに下手人があらわれた。屋根から縄はしごをおろすので、避難してくるように云った。昌村は命じられたとおりに動くしかなかった。そして目のまえに来たとき、刃物で突き刺したのだ」
出窓の血痕がなによりの証拠だった。縄はしごは下手人が回収した。氾濫で混乱した下屋敷から脱出するのは簡単だ。
濁流によって、かがり火はすべて消えていたからだ。
内壁は大部分が損壊していた。のりこえるのもむずかしくない。なによりもきのうの夜は新月だった。もっとも暗い夜である。
未堂棟は左目をひらいていた。別府の推理に反応を示した。
十回目だった。おおきくは外れていないと確信した。
「――下手人は水門を壊せば、敷地内まで水がはいる確証があったのかもしれません。それを知りえたうえの仕掛けならば、過去になんらかの切っ掛けがあったはずです」
「……なるほど、瑞木ならば、かつての蛇崩池のことを知っているかもしれない」
別府は書院へと引きかえした。きのうの早朝とくらべると、葉月の暑さをとりもどしていた。泥水の蒸発もはやいにちがいない。屋敷側は町民によって、整理されている。崩れた屋根は、つぎつぎと外に運ばれていた。見張りの所沢は背筋をのばしている。入り口を凝視していた。瑞木の一挙一動を見逃さないようにしている。
別府は彼の肩を叩いた。ねぎらいのことばをかける。引き戸をそっとひらいた。
瑞木は片膝を立て、足下をじっと見ていた。吊りあげた眉からは表情がつかめない。本を読んでいるわけではない。ただ、床板を見ていた。別府は咳払いをする。
「ききたいことがあるのだが、構わないか?」
「……え、ええ」
瑞木は立ちあがった。着物の襟を正した。
「なにをおききしたいのでしょうか。佐々木さんが殺されたときのことは、すべてお話したのですが……」
「いいや。べつの話だ。おまえが知ってのとおり、蛇崩池の水門が破壊されてしまった。どうやら留め具の部分が燃やされていたらしい」
「そうですか……だったら、仕方ないのかもしれません」
「仕方ないだと?」
瑞木はうなずいた。
「過去にも同じように氾濫したことがあったのか?」
「ええ。下屋敷が建つまえのことですが、そのときは古くなった木材が腐ってしまい、水門がひらいてしまったのです」
「それでどうなった?」
「この台地に水が溜まってしまいました。町の区画まではとどかなかったのですが、水場を管理する者としては失態です。内々で処理したのをおぼえています」
蛇崩池の氾濫は、二度目だったのである。
「氾濫の過去を知っている者はだれがいる?」
「わたし、作間政信さん、上野左衛門さん。……亡くなった藤三郎さんを除けば、この三人です」
水屋の瑞木、農夫の作間、万屋の上野。別府は職種と関連付けながら反芻した。
ふと、名前の出ていない人物を思い出した。
「炊馬経子は? 大村家の女中だ。彼女は知らないのか?」
「当時、まだ幼かったので、その場にはいませんでした」
「じかに見ていないわけか」
「ええ。しかし、なにかの折に、藤三郎さんからきいていたかもしれません。彼女は水番人の仕事に興味があったようですので……」
「つまり、作間家につらなる者ならば、水門の一部を燃やして、いまの下屋敷まで濁流がとどくことを知っていたわけだ。経子がきいていたとしたら、四人が水門の秘密を知っていたことになる」
「そうなりますね。しかし、殺人と関係がある話なのですか?」
「いいや。まだ調査中だ」
瑞木は黙りこんだ。彼の喉から質問が出かかっているようだった。何度か口をひらこうとしてとめる。三回、つづけたあとに彼は云った。
「わたしはいつまで書院にいなければならないのですか?」
仕事にもどりたい。とうぜんの要求だった。
「大村家だけが取引先ではありません。つぎの仕事があります。もう飲み水を、とりに行かなければならないのですが……」
「すまない。もう少し待っていてくれ」
「……どのくらいかかりますか?」
「ほかの者の居所がわかるまでは動かないで欲しいのだ。わかっていると思うが、これは殺しだ。瑞木の安全のためでもある」
瑞木はしぶしぶ了承した。屋根の隙間から日が差しこんでいた。書物が痛むのではないかと心配になった。ただし、別府の憂慮は長くつづかなかった。風雲はまだ終わりではなかった。所沢の制止を振り切って、町役人のひとりが書院のなかにはいってきた。町役人は急を告げた。
「たいへんです。同心様、こちらに来てください!」
町役人たちは、さっきまで、町民といっしょに瓦礫を片づけていたはずだ。
あわてている様子だった。
「どうした。作間家の三人が見つかったのか?」
「ちがいます。そちらの件ではありません。下屋敷の話です。また死体が発見されたのです」
「なんだと。女中か、おともの侍か?」
「いいえ。どちらでもないのです。死体の身元も確認済みです。大村昌村様の甥です。菊太郎様の死体が見つかりました。北側の離れ座敷の瓦礫に埋まっていました。首を絞められた跡もあります」
「だったら……」
「殺人です。何者かに殺されたのです」
別府はこのときになって、ようやく未明の下屋敷で起きた惨劇の全貌を知った。瑞木はふたつの眼に鈍い影をつくっていた。未堂棟は書院の天井を見つめている。別府は謎ばかりふえる蛇崩村の殺人に立ちくらみをおぼえていた。
「……菊太郎は北側の離れ座敷で殺されていた」
目線を向けた。
「裏門のさきだ。瑞木の目撃から考えれば、下手人は最初に佐々木を殺した。これはまちがいない。下手人はそのあと、蛇崩池の氾濫を待った」
別府は書院を出た。役人の背中を追った。独り言のように話しつづける。
未堂棟は黙ってきいていた。
「濁流はもくろみどおりに外壁にとどいた。大穴をあけようとした。下手人は敷地内の浸水が本格的にはじまるまえに離れ座敷へと向かった。大村菊太郎を殺した」
土倉の二段屋根に目を向けた。
「菊太郎の殺害が終わったころに、敷地内へと濁流がはいりはじめる」
別府と未堂棟が下屋敷へと走っている刻限である。
「下手人が蛇崩池を氾濫させた目的は、土倉内の密室を打開するためだ。大水によって、昌村を上階へと誘き出すためだ。下手人は瓦屋根のうえから、昌村を助けるふりをして刺殺した。土倉内へと突き落とした。一人目、二人目、三人目の殺害だ。氾濫による混乱がつづくなか、どこかへと逃げ去った」
蛇崩池の氾濫は、災害では終わらなかった。
すべては計算された崩壊劇だった。
三人の連続殺人へと有機的に繋がっていたのである。