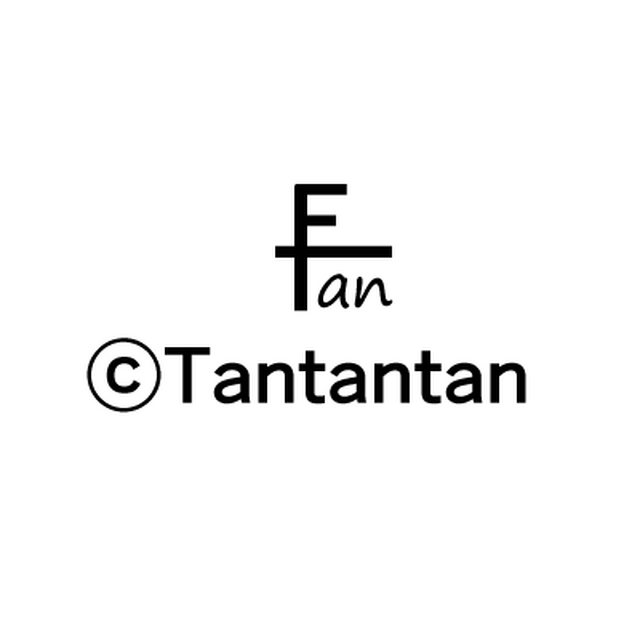六章 容疑者たちの鉄壁のアリバイ
文字数 11,742文字
別府は三つ目の死体を検分していた。全身が濡れているのはとうぜんだが、菊太郎の死体には、いくつもの木片が突き刺さっていた。ほかの死体は傷口が少なかったが、菊太郎の死体は全身に肉身が見え隠れしており、痛々しかった。
「もともと、建材が腐っていたのかもしれない。屋根から踏みつぶされたように倒れている」
別府は目のまえの瓦礫の山を見た。座敷の原型はなかった。濁流によって支柱が外され、すべてが押し潰されていた。
建材から鋭利な木片が飛び出していた。
菊太郎の傷口には二点、気になることがあった。
一つ目は血液の流れ出た跡が見つからないことであり、二つ目はかさぶたのように治癒した形跡がないことだ。濁流に血痕が流されたことも考えられた。
しかし、それにしては、傷口の断面が奇妙だった。
傷口の開き方そのものが、極端に狭かったのだ。
とじた傷口は、死後に切り裂かれた皮膚の特徴でもあった。別府は菊太郎の死亡要因が全身の傷口とは、関係がないと判断した。
「ほかのふたつの死体よりも、あきらかに状況が悪い。濁流に座敷が壊され、発見そのものがおくれたせいにちがいない。すでに彼の皮膚は蒼白だ。皮膚のさきに、黒い血液が透けている。足から背中まで斑点が広がっている」
この斑点は死斑と呼ばれるものだ。心臓が停止すると、血液の流れはとまる。
すると静脈に血液が溜まり、斑点模様が浮きあがるのだ。
検分を行ううえでの常識だった。別府は江戸時代の法医学書である無冤録述を読みこんでいた。現代の検死にも十分、つうじる内容だった。
死体の変化や季節、気候のちがいによる影響も記述されていた。
「葉月に見つかる死体ならば、一日目で全身が暗めの赤褐色に変色し、二日目以降からは全身がふくらみはじめる。しかし、菊太郎の死体にはどの前兆も見当たらない」
いまは夏過ぎだ。まだ、暑さを引きずっている。
そらも曇っているわけではなく、気温は高かった。別府の全身には汗が流れ落ちている。きのうの夜も同じくらい蒸し暑かった。
彼の死体からは刺激的なにおいは、漂っていない。
腐敗そのものは進行していなかった。冬場なら一日、二日の変化だ。
「葉月のいまごろならば、数刻にそうとうする変化だ。半日以上、経過していたら、腐敗は皮膚のうえにあらわれる。だが、菊太郎の死体には見当たらない」
別府は結論を出した。
「やはり、きのうの丑三つ時に殺害されたものにちがいない。距離的に裏口とちかい。佐々木のあとに殺されたのだ」
菊太郎の首には円状の線がはいっていた。縄目の跡も見えた。彼の口唇はめくられていた。鼻孔はひどく汚れていた。すべて、絞殺死体の特徴だった。
万力の力が首よりうえにかかった証拠だった。
「しかし、彼はいつから下屋敷にいたのだ。きのうは見なかった。われわれと行きちがいになったのか?」
別府の疑問に答えるかのように大村家の関係者があらわれた。町役人につれられていた。老婆だ。ひとりだった。彼女は下屋敷の敷地内にいた唯一の女中らしい。名前を千代と云った。
「彼女は南西のほうの離れ座敷に暮らしています。お年を召された女中は敷地内にある離れ座敷の女中部屋で寝泊まりしているようです。彼女は殺しのあった当日もいました」
「濁流のとどかなかった場所か。ほかの女中はどこにいる?」
「敷地内にはいません。蛇崩町の西区画で暮らしているようです。なんでも菊太郎様が身内以外の者に寝泊まりされることを嫌がったときいています」
「その理由は?」
「わかりません。さいきんは親しい人間以外の出入りを少なくしていたようですね」
……もしかしたら、大村昌村の蟄居から人払いをはじめたのかもしれない。昌村の姿を見られるのを恥と考えたのだ。武士としてはよくある話だった。
蟄居の待遇に耐えられなくて、憤死する者も多かった。見張りを立たせているわけだから、人払いしていたとしても、下屋敷を無防備にしていたわけでもない。蛇崩池の氾濫も人払いされていたから、被害が少なかったとも云える。
「千代と云ったか。貴方は彼とは親しかったのか?」
「……はい。乳母でもありました。幼いころから知っています。わたしの足腰が悪くなってからはお会いする機会はへりましたが、菊太郎様の話はわたしの耳に自然とはいってきます」
「きのうは彼と会ったか」
「いいえ。夜に出かけることも多く、かえっていたことも知りませんでした。ほかの者も知らなかったと云っていました」
「ふむ。そうか。……だったら、菊太郎を殺害する動機をもった者に心当たりはないか?」
「……そうですね。身内への密告のようになってしまいますが……」
「お願いする。菊太郎を殺した下手人を捕まえるためだ。少しでも情報が欲しいのだ」
「そうですね……ここさいきん、言い争いになっていた者は、大村家に仕えている佐々木五郎でしょうか」
被害者のひとりである。声が低くなった。
「佐々木と? どんな理由かわかるか?」
「いいえ。くわしくは知りません。ただ、ふたりが言い争っていたとき、ひとりの女性の姿もあったようです。炊事場で働いている女中でした」
「まさか、炊馬経子か?」
「よくご存じですね。彼女は佐々木と古くからの知り合いです。もともと、佐々木は落ちぶれた侍の長子でした。幼いころは蛇崩町の外れの長屋で暮らしていたそうです。炊馬経子とは、当時からの付き合いだときいています」
「知らなかった。佐々木と経子は、親しい間柄だったわけか」
「ほかの女中の噂ではそのようです。……それと菊太郎様は女癖が少々、悪いところがありまして……とくにお酒がはいると、人がかわるのです。ふだんは頭のまわるかたなのですが……」
「つまり、貴方は佐々木と経子がふかい間柄にあり、そこに菊太郎が手を出したことで、色恋沙汰の問題が起きていたと思っているわけか?」
「じかに見たわけではありません。そういう噂もあっただけです。……じっさいは菊太郎様だけではなく、佐々木も非業の死をとげたときいています。あまり関係ない話かもしれませんね」
「たしかにそうかもしれない。佐々木が死んでなければ、菊太郎を殺害する動機になったことも考えられる。しかし、両者が殺されている。ふたりとも手にかけているならば、色恋沙汰の線は薄いか」
しかし、痴情のもつれはなにが起こるかわからない。逆に、経子のほうが菊太郎に気があったとしたら、どうだろうか。佐々木ははやまって、菊太郎を殺害してしまった。
その事実を知った経子が佐々木を撲殺した。
三つの殺人、すべてがひとりの犯行とはかぎらない。
瑞木は土間から出ていく下手人しか見ていない。佐々木が菊太郎を殺し、逆上した経子が佐々木を殺したという順番も考えられる。どうせなら、復讐もしよう。そう思って、最後に大村昌村を殺害したのかもしれない。なんにせよ、経子が殺害現場に向かえたかどうかだ。彼女の犯行が可能だったならば、おおきく話はかわる。
「いまの話は案外に役立つかもしれない。少なくとも経子に話をきく必要ができた。ほかに被害者と問題を起こしていた者はいないか?」
「ほかですか?」
「ああ、水騒動のことでもかまわない。殺害におよんでもおかしくない。そう思える人物だ。心当たりはないか?」
「それならば、作間政信でしょうね。彼と菊太郎様は一悶着を起こしていました」
「いつの話だ?」
「だいぶ、まえでございます。作間藤三郎が殺された、つぎの日でした。彼は同心様が再調査するまえから、大村家に仕える一介の武士が義兄を殺したのではなく、昌村様が殺したと考えていました」
「……文句を云いにきたのか?」
「ええ。しかし、それだけではおさまらず、彼は大村家の者に乱暴を働こうとしました。そのときに菊太郎様は刀を抜いてしまったのです。薄皮一枚で、ことなきをえましたが……」
千代は一瞬、云い淀んだ。
「彼の憎しみのこめられた瞳は、いまでもおぼえています。それはそれは、恐ろしい色をしていました」
「どんなふうだったかおぼえているか?」
「政信は左肩から右脇腹の先まで斬られ、血を流していました。生血は握り拳のなかに流れこみ、赤い血溜まりをつくっていました。怒ると血がのぼると云います。はじめて、じかに見ました」
千代は下屋敷の表門に身体を向けた。
「彼はとおくに引き離されるまで菊太郎様をにらんでいました。まばたきをしない眼球は蛇の目のようでした。体外の血はしたに流れているのに、体内の血はうえに流れているようでした」
彼女の溜め息は、濁流のように淀んでいる。
「政信の目は赤く染まっていきました。ジャノメ傘を両目にはめこんでいる。そう錯覚するほどに、ふかい赤色をしていました。いまでも、その恨みは消えていないでしょう」
……赤い目で菊太郎をにらんでいた。
別府は息を呑んだ。ジャノメ傘とは蛇の目を真似た和傘のことである。美しい和傘の象徴でもあるが、人間の両目にたとえられると、もの恐ろしさを感じた。
「大村家にとっても危ないところだった。向こうから仕掛けてきたとしても、作間家の者を連日、ふたり、殺したとなれば、奉行所の心証が悪かったはずだ。どちらも助かった」
菊太郎はあまり理性的な男ではないようだ。
平気で刀を抜く男だ。政信も彼が短気なのは知っていたはずだ。
それでも自制できないほどに、菊太郎に恨みを抱いていた。
政信ならば、蛇崩池を氾濫させることも容易だったはずだ。
義兄の殺された恨みを晴らそうとしたとも考えられる。
「それでは瑞木新七はどうだ? 水屋の男だ」
「瑞木とはなにも問題は起きていませんよ。そもそも瑞木様に水を運んでくるように依頼したのは菊太郎様ですからね」
「そうなのか?」
「ええ、ですから双方、恨みをもっているとは思えません。佐々木ともうまくやっていたように見えました」
「たしかにきのうの正午に話していたときも、かわった様子はなかった。とくに動機はない……。だったら、万屋の上野はどうだ。彼を知っているか? 上野は菊太郎と問題を起こしていなかったか?」
「彼もありません。まず、ないと思います。菊太郎様と上野は朋友のようでした。水騒動が起きるまえからおふたりでよく会っていましたよ。ご主人様とも面識があったはずです」
「やはりか。大村昌村は蟄居があけると、彼の営んでいる万屋へ向かうときいた。水騒動のまえから親しかったならば、とうぜんだ。ふたりとも菊太郎に恨みがあったとは考えにくいか……」
上野にかんする証言は、気になる点が多かった。
大村家のふたりと上野は親密な間柄だった。それにもかかわらず、佐々木は上野と別段、親しくないという素振りを見せていた。隠し事があるのかもしれない。
別府は千代にお礼を云った。彼女はとぼとぼ引きかえしていった。千代は大村家に仕えている。事後処理が終わったら、ふたたび大村家のだれかが、この地を治めるにちがいない。
大村昌村にも兄弟がいるはずだ。彼らの都合が合うまで、宿屋で待つらしい。千代はとくに昌村と菊太郎に忠義を誓っているようではないようである。さきほどの証言も正直に答えてくれたはずだ。
別府は裏口の手前を見た。見慣れた役人の姿があった。
さすまたをもった男が立っていた。目明かしの九兵衛だった。
目明かしは外廻り同心の部下である。九兵衛は別府の姿を見ると、足を進めた。城下町の奉行所から来てくれたらしい。ようやく自由に調査できるようになった。別府は未堂棟をつれて、下屋敷の外を調査しようと考えた。
九兵衛と合流しよう。地面を強く蹴った。
しかし、もうひとりの足音がつづかなかった。
未堂棟は菊太郎の死体のまえで片膝をついている。動かない。
左目をひらいていた。十一回目だった。
「――どうして、下手人は菊太郎さんを絞殺したのでしょうか?」
未堂棟の云っている意味が理解できなかった。
「どういう意味だ?」
下手人は菊太郎を絞殺した。その行為に疑問などは浮かんでもいなかった。だが、未堂棟は別府とはことなる着眼点を有していた。
「――昨夜だけで三人の死体が発見されました。しかし、ひとつとして共通とした殺し方がないのです。下手人は三種類のことなる凶器を使いました。その理由がいまだにわからないのです」
未堂棟に云われて、はじめて疑問に思った。
「たしかにおかしい。三人とも殺した方がことなっている。佐々木は撲殺された。菊太郎は絞殺された。昌村は刺殺されている」
その意味することはなにか……。別府は云った。
「三人の被害者の状況に合わせて殺したからではないか?」
殺害の刻限は丑三つ時だ。起きている者のほうが少ない。
「菊太郎は寝ていた。佐々木のように木刀を凶器にしたら、逃げられるかもしれない。刺殺だと血痕が身体につきすぎるうえに、刃物はつぎの昌村の殺しでも使うことになる」
万が一にでも刃物が折れたら。計画は失敗だ。
「だから、叫び声をあげさせないために絞殺したのだ」
未堂棟はちいさくうなずいた。それが納得の仕草なのかはわからなかった。未堂棟は腰をおろしたままだ。右手を眉のうえにかかげている。
地面に鳥のような影がのびている。ただし、ほんらいの身長より長い。そのはずだ。
未堂棟は瓦礫をもっていた。瓦礫の影が加わっていたのだ。
家屋の支柱のようだった。菊太郎を押し潰していた家屋の残骸だった。濁流で掘り起こされたにちがいない。支柱には複数の傷がついていた。横線がはいっている。
未堂棟は確認を終えたのか、ゆっくりと立ちあがった。
別府のほうに身体を反転させた。暗闇で顔が見えない。
しかし、左目がひらいているのはわかった。
十三回目である。
「――新月の夜は真っ暗です。見知らぬ敷地内を自由に歩きまわるのはむずかしかったはずです。おのずと下手人は過去に下屋敷に出入りしたことがある人物になるでしょう」
別府も同意する。
「表門は見張りがふたりいた。裏門には佐々木しかいなかった。夜中に裏門から奇襲すれば、殺害は容易だと知っていたのだ。この点も下手人が下屋敷の事情にくわしかった者だと裏付けている」
別府は未堂棟を追いこした。
「下手人はそのあとにふたりを殺害した。わずかな時間で、三人も手にかけている。この事実は、離れ座敷と土倉、彼らの居場所を把握していたことを証明している」
別府は指折り数えていった。
「容疑者は四人だ。瑞木新七、炊馬経子、作間政信、上野左衛門……」
この四人は四人とも下屋敷に来たことがある。そのなかでもっとも土地勘があったのはだれか。女中の経子である。彼女はとくに怪しかった。
経子は佐々木とは昔なじみだった。菊太郎からは手を出されそうになっていた。作間藤三郎を殺された恨みもあった。すべての条件が三つの殺人とあてはまっていた。
別府は彼女がもっとも下手人にちかい人物だと捉えていた。
待ちきれず、九兵衛が足早に駆けよってきた。
彼には別府たちへの報告があったのだ。別府の知りたがっていた三人の居所が判明したのである。九兵衛は息切れしながら云った。
「万屋の上野左衛門は早朝に発見されました。しかも下屋敷から目と鼻のさきにいました。上野は蛇崩池の氾濫を見にきた野次馬のなかにいました。行人坂の中腹にいた十人のなかです」
「だったら、三人を殺害したあとに下屋敷を脱出し、行人坂の見物人として混ざったのかもしれない。そうすれば、犯行は可能だったわけだ」
「いいえ。それは無理なのです。じつはこの人垣の手前には木戸番があり、殺しが判明してから、すぐにとじていたのです」
「……どうして、それで無理になる」
「上野の服装と持ち物です。彼の夜着は綺麗なままでした」
別府は九兵衛の意図を理解した。
「……大村昌村を密室外から殺すためには、蛇崩池の濁流を利用しなくてはならない。濁流は泥の水だ。かならず衣服には汚れが付着する。汚れがない以上は下手人ではないか……」
「ええ。もしも北の番地内に捨てられた着衣が見つかれば、話はべつですが、いまのところ、報告がありません。万屋のなかにも衣服の着替えは置いていませんでした」
「とおくに衣服を捨ててからもどってきたのではないか。燃やすことだって、できる。瑞木が佐々木の殺しを目撃し、われわれが辿り着くまでに四半時はあった。そのあいだに衣服に付着した証拠ごと処分したのかもしれない」
「……いいえ。それでも、むずかしいでしょうね。卯吉さんは殺しを確認したあと、木戸番に警戒を強めるようにたのんだのですよね」
「ああ、まちがいない……」
「木戸番は蛇崩町の各番地に危険を知らせました。町内の木戸は暁七つから順次、とじられていきました。同時に夜警をしていた者も、現場の周囲に集まったのです」

別府は提灯を釣りさげた者が大通りの左右を探っている姿を想像した。
「しかも木戸番は近隣の者を五人呼び、人垣の前後に立たせていました」
江戸時代の常識である。五人組と呼ばれる監視体制だった。
「上野が下手人ならば、この二種類の包囲網をかいくぐったことになります。しかし、それは至難の業です。最初から行人坂の中腹にいたと考えるほうが無難でしょう」
「上野の犯行は不可能ということか?」
「ええ。彼がなんらかの手段を講じたのならば、わかりませんが……」
九兵衛は苦々しい顔を浮かべた。
いまはなにも見つかっていないということだ。
上野が下手人だという証拠が足りない。否定の材料のほうが優勢である。丑三つ時に蛇崩池の氾濫と殺人事件が行われ、その直後、暁七つには周囲を夜警が見張っていた。上野は下屋敷のちかくの野次馬のなかで発見された。殺人事件の直後にしか人垣に加わることはできない。
彼の着衣には犯行を印しづける汚れが見当たらなかった。
ゆえに、上野が下手人とは考えにくかった。
「それでは、ほかのふたりはどうだったのだ?」
「われわれが調査をつづけ、上野のつぎに居場所がわかったのは作間政信です。彼は賭博町にいました」
「賭博町? どこの賭博町だ?」
「湯島天神です。門前町の一角にあります」
湯島の門前町は蛇崩町と同じように幕臣の住地になっている。
当時は遊郭と賭博の町として知られていた。
「なるほど、義兄の藤三郎が殺されてから、酒と賭博に溺れているという話は、ほんとうだったのか」
「そのようですね。常連のようです」
「上野はちかい場所にいたが、作間はとおい場所にいた。ままならないものだ。彼はずっと賭け事に興じていたのか?」
「ええ。われわれが政信を見つけたときも、朝から闘鶏を見ている最中でした。下屋敷の状況を説明し、いままでなにをしていたかききました」
「ふむ。それで?」
「彼は暁八つまで丁半をしたあとに宿屋にかえり、明け六つに賭博仲間に起こされるまで寝ていたと答えています。湯島から蛇崩町までは、走り慣れた者でも、時の音ひとつはかかります」
九兵衛は町飛脚に移動時間をきいていた。距離と時間にまちがいはなかった。現代の時刻にあてはめると、別府たちは深夜の二時三十分から三時のあいだに、佐々木の死体を目撃している。時の鐘のひとつは、おおよそ二時間だ。往復で四時間になる。
政信は深夜の一時よりまえに宿屋へともどり、朝の五時よりまえに起こされている。
時間の猶予は四時間だ。移動時間ちょうどだ。
下屋敷で、殺人を行った時間を考慮すれば、六時間の猶予は必要になる。目撃証言から蛇崩町に向かっては間に合わない。賭博町にいたことで、彼の犯行は不可能となっていた。
「政信が寝るまえの目撃、起きたときの目撃はどういう状況だったかを調べているか?」
「ええ。寝るまえの半丁、起きたあとの闘鶏。どちらも確認をとっています。まちがいありません。複数人が証言しています」
「その目撃者たちは、政信の素顔を見ていたのか?」
「素顔とはどういうことですか?」
「怪我などの理由で包帯を巻いていなかったか? 賭博町で政信が他人と会話していたかどうかも確認したい。誤認の可能性がある」
九兵衛は別府の疑いを理解した。
「賭博町から抜け出すために、第三者に変装してもらったと思っているのですね。残念ですが、ありえないでしょう」
「どうしてだ?」
「彼は門前町でも有名な賭場にいました。いかさま師をいれないために紹介状がないと参加できないのです。つまり、その場には顔見知りしかいませんでした。とうぜん、顔を隠すのは無理です。賭場は全員が敵のようなものです。損得の発生する場所である以上、協力も見込めないでしょう」
身体の一部を隠す行為はいかさまを生む温床になる。政信は素顔であり、危険物ももっていなかった。そして、少なくとも六人以上の知り合い政信と会話していることが報告された。
つまり、目撃証言のほうを誤認させることは、かぎりなく不可能なのである。そうなると、のこりの容疑者はひとりだった。
九兵衛は神妙な面持ちで彼女のことを語りはじめた。
「じつは炊馬経子の犯行もむずかしいのです。彼女は西区画の弐番地の空き地にいました。ほかの女中と避難していました。彼女が目撃されたのは朝五つ、卯ノ刻をすぎたころでした」
午前七時である。殺人事件はおそくても午前三時である。
「だったら、時間的にだれよりも余裕があるではないか。午前四時には女中部屋にもどれる。証拠を処分したあと、何気ない顔で空き地に来た。彼女は唯一、犯行のできた人物になる」
九兵衛は両肩をちぢめた。背後に合図を送った。もうひとりの部下が風呂敷をもってきた。風呂敷の隙間から樫の木刀と赤く染まった小刀と上等な組紐が飛び出していた。
「佐々木を撲殺した木刀と大村昌村を刺殺した小刀、それに菊太郎の首を絞めた紐だな。どこにあったのだ?」
小刀は一尺、木刀は三尺三寸ほどの長さだ。両手でも絞殺が可能な菊太郎を除けば、ふたりの殺害には凶器が必要になる。下手人と直接的に繋がる証拠だった。
「部下が凶器を発見した場所は東区画の先です。ほぼ蛇崩町の外と云っていいでしょう。風呂敷には凶器が三つはいっており、木刀には手形がついていました」
「だれの手形か調べたか?」
「はい。佐々木の掌紋と一致しました。おそらく下手人と争っているときに木刀をつかみ、血の手形がついたのだと思われます」
「現場の状況とも合っているな。風呂敷のなかから下手人の特定に繋がる証拠は見つかったか?」
「いいえ。ただ、この風呂敷の発見そのものが問題なのです」
九兵衛は苦笑いを浮かべた。彼の話では、ちかくの行人坂にいた上野、遠方の賭博町にいた政信には影響が出ないのだが、町内の西区画にいた経子だと、犯行がむずかしくなるらしい。
「炊馬経子のいた西区画は凶器の発見された場所とは反対の位置です。下屋敷からも四半刻はかかります。ふたたび、もどってくるにしても、半刻はかかるでしょう」
つまり、経子が犯人ならば、深夜三時をすぎてから西区画の女中部屋にもどったことになる。しかし、同時刻よりまえには別府たちが死体を発見していた。
この時間差が問題になっていた。
「寅の刻をすぎた頃合いならば、わたしが木戸を封鎖する指示を出したあとになる。そうなると西区画にはもどれなくなる。そういうことか?」
「はい。木戸の閉鎖は一時的なものではなく、彼女の居場所が判明した朝五つまでつづいていました」
「凶器は彼女の居場所とは逆の場所で発見された。それを置きに行ったら、西区画にはもどれなくなる。だから、経子は下手人ではない」
「そのとおりです」
「すべての証拠が正しければ、三人とも犯行は無理になるな。わたしは殺しを調査するたびに感じるよ。わたしは蛙だ。下手人は常に蛇だ。じりじりと、うしろにさげられる」
「どういうことですか?」
「蛙は蛇に勝てない。どうあっても負けつづける。無理だ。不可能だ。わからない、どんどん未解決に追いこまれる」
「でしたら、未堂棟さんはなめくじですね。蛇はなめくじにはかなわない」
「それだといいな。ふたりで挑めば、かならず勝てる。わたしがさがっても、かわりに未堂棟がまえに出る」別府は冗談めかした。
「ははっ。まちがいないですよ。だって、殺しの調査とは反対に、青人様は卯吉さんに弱いですものね! いつも卯吉さんを追いかけて……」
九兵衛は、はっとうしろを見た。
左目をとじたままの未堂棟が立っている。なにも云わない。
沈黙の重圧が九兵衛を責めていた。
わざとらしく咳きこみ、話題をかえた。
「しかし、だれも犯行できないのならば、ちかくの野盗の仕業かもしれませんね」
「野盗?」
「ええ。城下町の外れとはいえ、下屋敷です。金目のものを狙ったとも考えられます。周辺に山賊の根城がないか、調べますか? 蛇崩町の調査はおくれますが……」
別府はやんわりと断る。
「未堂棟が蛇崩池を気にかけていた。わたしとしても、蛇崩池の氾濫がこんかいの殺しと関係していると考えている」
別府は蛇崩池を見上げた。
「千代の話から、経子と佐々木のあいだに問題が起きていたのもわかっている。そちらをたしかめるほうがさきだ」
別府は九兵衛に下屋敷の排水を、さらに進めるようにたのんだ。中庭を通過する。土間の裏口から蛇崩町へと出ようとした。
しかし、途中で足をとめた。書院のほうへときびすをかえした。
別府は見張りをしている所沢に声をかけた。
瑞木新七を解放してもいい。その許可を与えるためだった。
瑞木とは、ほかの三人の身柄を確保したら、解放すると約束していた。
「瑞木さんの疑いは解けたのですか?」
所沢はたずねた。
「ああ、完全ではないけどね。敷地内で大村菊太郎の死体が発見された。佐々木のつぎに殺されたと思われる。きのうの夜には、三つの殺人が行われていたわけだ」
「三つの殺人……」
「下手人は佐々木のあとに菊太郎と昌村を殺害した。凶器を蛇崩町の外まで運んだ。瑞木の犯行ならば、凶器を敷地外に置いたあと、下屋敷へともどり、目撃者のふりをしたことになる」
所沢は首を捻った。指を折り曲げている。刻限を数えているようだった。
「暁八つから暁七つのあいだに殺しがあった……。凶器が蛇崩町の外で発見される。同心様が来たのは丑三つ時よりあと。瑞木さんは土間にいた……それならば……」
「ああ。時間の辻褄があわなくなる。彼が殺したのならば、土間にはもどれない」
凶器を置いてから下屋敷にもどった場合、往復で三十分以上かかる。蛇崩池の氾濫は深夜の二時三十分をこえている。
大村昌村を誘き出してから殺したのならば、犯行はその時間のあいだになる。
どれだけ急いだとしても、深夜三時をまわるのだ。
瑞木よりさきに別府たちが土間にはやく着くことになる。
じっさいには暁七つ、三時をすぎた刻限に、彼は土間にすわりこんでいた。
「瑞木新七は下手人ではない。彼と約束したとおり、自由にしていい。おまえもしばらく休むといい」
所沢は緊張の糸を解いた。
額には脂汗が浮かんでいた。右手で顔をぬぐった。
体力を消耗しているのもとうぜんだ。
もしも書院のなかにいる男が下手人だったら、凶悪な殺しを続け様に行った人物になる。追いこまれた下手人が逃げようと企むかもしれない。
鉢合わせになるのは所沢だ。
最悪の状況も考えていたにちがいない。
別府は所沢の肩を叩いた。
別府は瑞木の様子を見ないまま、足早に下屋敷を出て行った。別府の疑いは、すでに経子へと移っていたのである。ふたりの下駄が小気味よく地面を鳴らしていった。
しかし、行人坂に出た途端、足音が消える。地面が泥濘みにかわっていたからだ。排水中の泥水と行人坂が交差している。背後では町民がおおきい板を使って、敷地外へと泥水を押し出していた。町民の足音、別府の足音、周辺には不快な音がびちゃびちゃと響きわたっていた。
その間隙を縫うように未堂棟の声がとおり抜けた。
「――無月の夜の殺人事件は、なにを発端として、起こされたのでしょうか?」
つづけられる。
「――そして、水騒動よりまえ、変死体がつぎつぎと見つかった事件は、こんかいの事件とどのように関係しているのでしょうか?」
未堂棟の声は水音に混じりあうように、かすみと消えた。
別府は必死にかすみの焦点を追った。
未堂棟がなにを見つけて、どうして、そう思ったのかを知るためだった。
未堂棟はひとつの方向をにらんでいた。
未堂棟の左目は、確実に事件の元凶を捉えていた。
しっかりとひらかれた両目のさきは蛇崩池だった。視線が順番にさげられていった。東水門、外壁、書院、下屋敷、表門、どれもまっすぐにつづき、ゆるやかにかたむいていた。
壊されなかった東水門には、まだ大水が溜まっていた。破壊されなかった書院、変死体の意味するもの、覆面の男の目撃、別府にはわからないことばかりだった。
しかし、未堂棟はちがっていたようだ。

壊されなかった水門のさきが書院に向いていることを見逃さなかった。
無傷で済んだ書院をにらんでいた。
もっとも重要となる場所を、けっして、見逃さなかったのである。