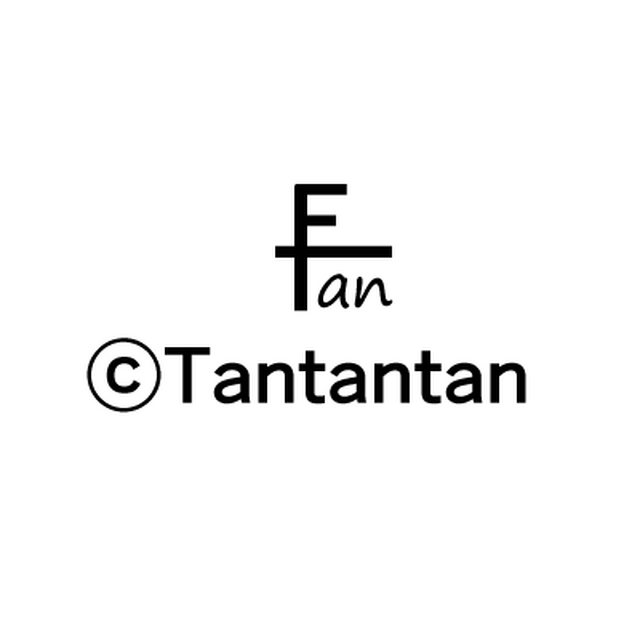八章 作間政信のアリバイ崩し
文字数 9,529文字
ひとつは宿駅だ。おおきな街道には宿駅に早馬が用意されているものだ。しかし、簡単に借りられるものでもなかった。武士身分の者が問屋場の役人に書類を提出し、身元を確認されたあとに借りられるのだ。
ふだんは馬が盗まれないように見張りが立っていた。
別府は馬泥棒が出なかったか、見張りのいない時間に馬を使われていないか、問屋場の者に確認をとった。答えは明快なものだった。
どんな者でも、盗みは無理というものだった。
問屋場は五人の役人が交代制で管理していた。夜から朝まで、人の目が途切れることがなかった。すべての馬は厩舎のなかにはいっており、心張り棒でとじられていた。厩舎のなかには、役人が常駐していた。
つまり、だれにも見られずに馬を盗むことは不可能だとわかったのだ。
もうひとつの探りは宿屋だ。主人に早馬を置いていないかきいた。主人はないと答えた。そもそも、この町には牛馬がいないと答えるのだった。
湯島天神では、牛馬が天神様の乗り物とされていた。
この門前町の敷地内で、牛馬を用いることは禁じられていた。

……牛馬は湯島の門前町にはいない。
別府はかくたる証拠をつかめないまま、作間政信と対面することになった。宿屋は一階から二階まで、大勢の人間で、ごったがえしになっていた。
見張りの役人はとうぜんだが、無関係の野次馬までも集まっていた。関係者ではなかった。遊郭や賭博を目当てに来た者たちだ。
彼らは大捕物が見られるかもしれないと集まっていた。
政信の賭博仲間もいるらしい。
政信は二階の部屋の奥にすわっていた。
「あんな野郎は死んで、とうぜんなんだよ」
彼は開口一番で大村家に悪態をついた。とくに菊太郎に対しては、そうとうの不満を抱えていたらしい。瑞木や経子とはことなり、上っ面を装う気はないようだった。
「だれがやったかは知らんが、いっぱいおごってやりてえくらいだ」
彼はあぐらをかいていた。右手で頬を支えていた。首を横にかたむけ、別府たちに目線を向けていた。右足首だけが股から離れている。右足は青白く、血色が悪かった。左足よりも右足の太股が薄い。菊太郎に袈裟斬りされた後遺症なのかもしれない。
下半身が不自由というのは、ほんとうのようだ。
「へへっ、あんたが殺したんじゃないのか。作間の旦那よ。さんざん、大村家の罵詈雑言はきいているぜ」
まわりの野次馬がおもしろおかしく、囃し立てた。
「そうだ、そうだ。さっさとお縄にしちまえばいいんだ」
「待て待て、こいつには金を貸しているんだ。捕まっちまうのは困る。有り金を全部、出しきってくれねえとな」
「有り金なんてあるのか。うん十年に一度の日食だって、水田の世話をして、仕事が終わったら、すぐに湯島に来たって云うぜ」
「へへっ。風情もありもしねえな」
彼らは両手を叩いて、大笑いした。
「心配すんな、どうせ捕まりやしねえよ。さっき、この同心たちが馬を探していたぜ。あんたは馬を使ったと怪しまれているんだ」
「はははっ。なんだそりゃ、湯島の門前町には牛馬がいねえと知らねえのか。さいきんの同心は湯島に遊女を買えねえくらい貧乏なのか、こりゃいい。はっはっは!」
別府はほかの役人に目配せする。
人払いの指示だったが、作間がさきに動いた。
「てめえら、だまっていろ!」
凄みのある声が宿屋に響いた。
「同心とはいえ、武士身分だと忘れたのか。斬られても知らねえぞ」
別府と未堂棟の役職である同心は、事件を足で調査する仕事だ。現代で云うところの刑事である。武士のなかでも身分の低い者がほとんどであり、平民から馬鹿にされることも多かった。
むろん、別府と未堂棟はただの同心ではない。特別な職を与えられ、下級身分ではない。与力からも一目置かれているが、それは野次馬の知る由ではなかった。
いまだに彼らは、けたたましく騒いでいた。
作間は帯をゆるめた。上半身をはだけさせた。野次馬は一瞬で息を呑んだ。
みなが彼の身体を見つめている。左肩から右脇腹まで大蛇がとおったような腫れがあった。股引までつづいていた。
「おれみたいな身体になりてえのか。ここで斬り殺されても、同心殿は、なんの罪にも問われねェんだぞ」
さきほどの喧噪がうそのように静まりかえった。
……菊太郎に斬られた傷にちがいない。
大村家の女中は菊太郎が作間の薄皮を斬ったと云っていた。
しかし、真相はことなっていたらしい。
薄皮どころか、致命傷にちかい傷口だ。
「それで馬を盗まれた形跡はあったのかい?」
作間は低い声できいてきた。
「……いいや。なかった。宿屋にも問屋場にもなかった」別府は語気を強める。
「しかし、あくまでも門前町のちかくでは、馬が手にはいらなかっただけだ」
「おもしれえことを云うじゃなえか。そりゃ、どういう意味で云っているんだい?」
「もちろん、政信、おまえへの疑いがあるという意味だ」
別府は眼光を鋭くする。
「下屋敷の殺人は計画的に行われていた。突発的に三つの殺しが起きたわけではない。もしも、おまえが下手人ならば、牛馬のいない門前町に意図的にいたと考えられる」
「信用ねえやつらかもしれねえが、おれが丁半を夜おそくまでしていたのを見ている。ひとり、ふたりじゃねえはずだ」
「ああ。きいている。会話もしていたらしいな。だから、当日の目撃は正しいにちがいない。問題はそのあとだ。おまえは寝るとうそぶいた。部屋にもどると、二階の屋根から外に出たのだ」
作間は意外にも反論しなかった。
「まァ、外に出ることはむずかしくないだろうな。湯島のまわりには酔っ払いがたくさんいる。ごろつきも多い。夜も眠らない町だ。こっそり外に出るのはむずかしくない。そういう男は、珍しくないからな。だれも興味を示さない」
別府は窓の外に目線を向けた。
「街道の向こうは山だ。あらかじめ用意した馬を隠しておくには都合がいい。おまえは馬で蛇崩町まで行った。三人を殺し、なに食わぬ顔で宿屋へともどった」
凶器のはいった風呂敷は町の外のそばに落ちていた。
ちかくに馬をとめていたと考えれば、辻褄が合った。
「無理な話だな。明け方までに馬では往復できねえ」
「……具体的に説明できるか?」
「馬は臆病な生き物でな。あかりがないと走れねえ。まァ、たいまつをかざしてやれば、だましだまし行けるかもしれねえが、時間的に無理なのはそれだけじゃねえ」
作間は音が割れるほどの大声で叫んだ。
「だれでもいい! 下目黒のほうの地図はもっていねえか?」
野次馬たちはお互いに顔を見合わせた。懐からとり出したのは役人のほうだった。
四つ折りの地図が広げられる。御場絵図と書かれていた。彼は地図を奪いとると、別府のまえに広げた。作間の人差し指が地図の南東をたどる。
「ここだ。よく見てくれや」
「等間隔に線が引いてあるみたいだが、なんの印だ?」
「高台だ。蛇崩町のまわりには五つの高台がそびえている。切りひらかれてもねえ。ほぼ山だ。湯島からだと、ふたつの山をこえなければならねえ。人の足でも苦労するが、馬なら余計にたいへんだ」
蛇崩町の直線上に、御殿山と八山のふたつが鎮座している。
「どんな馬でも傾斜の高い山は一気にのぼれねえ」
別府は山のあいだに抜け道がないか見た。
どう迂回しても、五つの山に差しかかるようだった。
……たしかに、むずかしい。
当時は現代とちがって、主要の街道以外は整備されていなかった。
細い道、飛び出た岩壁、ひとりでしかわたれない木橋。大概、山をこえるときは、馬をおりて、引っ張らなくてはならなかった。早馬で時間を短縮するのは、むずかしいどころか、不可能だ。
かならず山をとおるならば、馬を使ったとしても、徒歩と同じくらいに時間はかかることになる。御場絵図は彼の現場不在証明を裏付けていた。別府は口唇を噛んだ。
しかし、暗闇のなかには光が差しこむものである。この地図には別府の思いあたらなかった事実が書かれていた。御場絵図には、山のあいだに細い線が引かれていた。
薄く色付けされていた。ちいさく名称が書かれていた。
「……蛇崩川だ……」
湯島に来るまえ、蛇崩町の表通りで魚屋がアユを運んでいたところを目にしている。下屋敷の書院も干物をつくる小屋を改装したものだった。支流の川がちかいことを示している。それが蛇崩川である。
とうぜん、内陸に流れる川は、ほかの川へとつづいている。
問題は行き先だった。
「地図では蛇崩川が北につづいている。どこまで流れている……」
顔をあげた。
「だれか! 湯島界隈の地図をもっていないか?」
こんどは別府が地図を求めた。さきほどは役人が作間に地図をわたした。こんかいは野次馬のひとりが別府に地図をわたした。同心の仲間の役人が作間を手助けし、容疑者の賭博仲間が別府の手助けをする。公平な質疑応答となっていた。
まるで奉行所のお白州のように攻勢がいれかわっていた。
それは切り絵図と呼ばれる地図だった。別府は切り絵図を広げる。
湯島の門前町のちかくには江戸川が流れていた。
……やはりだ。わかった。
「作間よ、たしかに馬で山をのぼるのは無理だ」
にやりと笑みを浮かべる。
「ほかの方法なら、できると云いたそうだが?」
「ああ、もちろんだ。切り絵図には川の流れまで書いてあった。湯島からもっともちかいのは江戸川だ。すぐそばにある」
切り絵図によれば、江戸川は宿屋からまっすぐ進んださきにあるらしい。作間も認めるように顎を引いた。
「その江戸川を南下すると大川、江戸の内海、目黒川、そして、もっともとおくにあるのが蛇崩川だ。蛇崩川をおりたさきに蛇崩町がある。下屋敷にもちかい」
賭け仲間も役人もざわつきはじめる。
「つまり、湯島から下屋敷まで小舟にのって、最短で移動できるのだ」
「するってェと、おれが三人を殺すために四つの川を行き来したって云っているのかい?」
「じっさいにできるのではないか。そう疑っている段階だ。すでに下屋敷の氾濫は作間家の者ではないと、計画できなかったと判明している」
「……水門が壊せないからか、まァ、わかるが」
「もしも、おまえが移動時間を短縮できるのならば、作間家の四人のなかで唯一、殺害現場に向かえた者になる」
「おれはやっていなねえ、だけでは信じねェよな?」
「われわれの仕事は殺しのできた者を見つけ出すことだ。あとは自身番屋に来てもらい、ほんとうに実行できたのか調べられる。むろん、お白州に行ったあとでも罪に問われない場合だってある」
「……どうせ話なんて、きいちゃくれねェよ」
菊太郎に斬られたときの経験から察しているのかもしれない。
とおい目を窓の外に向けていた。
「知らねェ役人に命運をゆだねるってのは、分が悪い話だ」
「ならば、どうする?」
「ちっ……」作間は膝を立てた。
「だったら、賭けるしかねえわけか」
「賭けるだと?」
「ああ、あんたら、同心殿のほうが信用できそうに思える。後生だ。この場にいる役人にたのんで、四つの河川を調べに行ってくれ。じっさいに小舟の往来ができたかどうかの確認だ」
作間は畳のうえをこすった。
丁半のつぼふりのように右手を動かしていた。祈る思いのあらわれかもしれない。
「事件のあった日は晴天だった。日食のあった日だ。よくおぼえている。しばらく雨もなかった。だとしたら……」
「なるほど。河川の治水をしていたかもしれないか。ふむ。十分に考えられる。調べる価値はありそうだ」
江戸時代では、大雨がふるたびに、河川が氾濫し、堤防を造り直していた。
治水工事は簡単には終わらない。悪天候だと途中で未完成の堤が壊れることもある。よって、晴れの日に集中してつづけられる。夜通しの作業だ。
「治水工事によっては、川をせきとめる場合も多い。どこかの川で工事をしていれば、小舟がとおるのは不可能になる。そうすれば、政信、おまえの疑いは完全に晴れるわけだ」
当時の江戸川では棒出しと呼ばれる、川幅を狭くする堤がつくられていた。川のうえに足場つくるのだ。船の往来は制限された。別府も河川の段階工事を認識していた。
「おれが番所につれていかれたあとだと、時間が経っちまうかもしれねェ。いまなら、きのうの話だ。日食も起きていた。土手方にきけば、簡単に確認がとれるはずだ」
作間のことばには説得力があった。別府は役人を走らせることにした。往復まで一刻だ。部屋で待つことになった。
野次馬はおもしろおかしく話をするために、揚屋へと散っていった。宿屋の部屋には別府と未堂棟と作間の三人だけになった。
別府は殺人事件とはべつに、彼にききたいことがあった。
「作間、おまえは変死体が過去に見つかった事実を知っているか?」
「……そりゃ、こんかいの殺しと関係のある話なのかい?」
作間は顔色をかえた。
「……われわれはそう考えている。おまえの義理の兄、作間藤三郎は殺される直前、変死体について調べていたらしい。知っていたか?」
「あたりまえだ。いっしょに調べていた」
「どこまでわかったのだ? 知りたがっているやつがいてね。くわしく知りたいのだ」
作間はたばこ盆に手をのばした。懐を探った。キセルをとり出した。くわえる。たばこ盆のうえに炭火があった。キセルのがん首をちかづける。火をいれた。ゆっくりとふかした。
「同心殿はどこまで知っているんだ?」
キセル内の灰を落としながらきいてきた。
「炊馬経子からきいた話しか知らない。彼女は殺されるまえ、藤三郎から不審者に気をつけるように忠告されていたらしい」
「……そうか。だったら、会ったのは少しまえか。兄者はひとりの男を探っておった。そいつが金儲けのために、疫病をまいていると疑っていた」
「だれを疑っていたのだ?」
「上野だ」
「上野だと?」
「ああ。兄者は上野を怪しんでおった。あいつが変死体の騒動にかかわっていると踏んでいた」
別府は最後の容疑者の名前が出てきたことに、驚きを隠せなかった。
「上野がかかわっている根拠はあるのか?」
「あいつには、よくない噂があった。大陸に単身でわたり、町にかえってきてから万屋をはじめた。売っているのは見慣れないものばかりだった。見たことのない薬もあったらしい」
「藤三郎は毒薬だと疑っていたのか?」
「あたりとも云えるし、外れとも云える」
政信の顔に、緊張の色が浮かんだ。
「兄者は蛇崩川の上流に腐乱死体などが見つからなかったこと、町の通り沿いでも変死体が出たことから、変死体の騒動は、べつの企みによって引き起こされたと考えておった」
「べつの企みだと?」
「ああ、ちょうど、変死体が出るまえだった。万屋で上野がとある宣伝をしておった。蘭方医いらずの薬の源が手にはいったと、喧伝していたらしい。大陸産のものだ」
……蘭方医いらずの薬の源、未堂棟が反応した。
左目をひらいている。二十一回目だった。
「――大陸から手にいれたものを実験した結果、変死体がふえている。あるいは苦しむ者をふやしたあとに、薬で救済しようとしている。どちらかだと考えたのですね」
「ああ、そっちの同心殿の云うとおりだ。兄者は後者だと考えた。蛇崩町には薬屋はない。万屋がひとつだけだ」
未堂棟はまた左目をひらいている。
「――蛇崩町のなかで、体調の悪い者がふえれば、異国の薬、蘭方医いらずの薬をもっている万屋に客がふえる。そう企んだ上野さんの犯行だと思ったわけでしょう」
作間はキセルを縦にゆらした。
「だが、結果としては、兄者の予想はまちがっていた」
「どうしてだ?」
「おれたちは上野の万屋に行ったんだよ。大陸産の薬があるという噂をたしかめるためにな。店内もすみずみまで探した」
「違法なものは、ひとつもなかったのか?」
「ああ。まちがいねえ。どんな薬だろうと、町内の変死体が出た数からすれば、そうとうの量になるはずだ。しかし、万屋にあったのは大陸産の道具ばかりだった。珍しいものはたしかにあったが……」
「どんなものが置いていた?」
「いまもあるかはわからんが、蘇木の染料、阿蘭陀の望遠鏡、鹿皮の鉄鎧、西洋の絵画なんかをならべていたよ」
「阿蘭陀の望遠鏡は大村家の土倉内で見た。やはり、万屋で買ったものだったか」
「……ふん、お得意様なら、贔屓にしていることだろうよ」
作間はキセルを火鉢に投げた。
「その領主様にやられたんだ」
作間は憎しみを隠そうともしなかった。
「それで藤三郎が殺されたのは、変死体の調査をはじめてから、どのくらいあとだったんだ?」
「すぐあとだ。万屋に押しいった直後だった。五十日になるまえだったかな。忌々しい。兄者は殺された。おれもこの様だ」
作間は首のしたの傷口を叩いた。眉を吊りあげた。
「いまとなっては、変死体の騒動なんてなかったかのようにおさまっちまった。兄者は殺され、水番人も奪われた。おれにはもう丁半しかのこっちゃいねえ」
作間は別府に目を向けた。
そのうえ、身におぼえのない下手人にされてはたまらない。
彼の眼光がそう告げている。
「……われわれはまだ上野とは会っていない。そこで、ききたい。藤三郎が殺されて、上野左衛門は大村家に恨みをもつと思うか?」
「いいや、ないね。ありえない」作間は断言した。
「もしも、大村家を恨むことがあるとしたら、自分の仕事に損失が出るときだ」
「万屋の商売に問題が起きたときか?」
「ああ、蛇崩町には万屋は一軒しかない」作間はみずからの考えを述べる。
「いまどきは上級武士でも裏で商売しているからな。もしも大村家が上野に黙って、商売をはじめようとしたら……」
「しこりが生まれる?」
「上野はかなり憤慨するはずだ。それこそ、大村家の代替わりを起こさせるために、一族郎党を殺してもおかしくない」
「まさか」
別府は目を丸くした。
「万屋で商売をつづけるために三人を殺したというのか? 誇張していないか?」
「いいや。上野はそういう男だ。金のためならば、なんでもする。いまどきは珍しくないがな」
「だったら、経子はどうだ? 給金が少なく、生活も困窮していたときいた。大村家で女中をしているのは嫌々だと、愚痴をこぼしていたらしい」
「ははっ。だれからきいた?」
「宿屋の主人だ」
「じゃ、又聞きだな。本人がうそぶいている話だよ。経子は佐々木に惚れていた。佐々木といっしょにいるために女中になったくらいだ。身内を殺されている手前、おおっぴらな理由が必要だったんだろう」
「惚れた弱みか。だったら、瑞木はどうだ。水騒動のあとでも大村家に水を売りに行っている。金に困っているのではないか?」
「いいや。作間家の者でいちばんたくわえがあるのは瑞木だ。あいつは水売りだけをやっているわけではないからな」
「なに? ほかには、なにをしているのだ?」
「氷屋だ。まァ、水屋とたいしてかわらん。ただ、氷を売るのは、身分の高い相手だ。そうとう、儲けがいいらしいぜ」
「水のほかに氷も売るのか。冬場だけの仕事か?」
作間は目を丸くした。抱瓶を離した。
腹を抱えた。
笑い声が漏れている。
足を崩した。
不自由な下半身を抱えていた。大笑いをつづけている。
別府はむっと顔をしかめた。
「すまねえ」作間は膝を叩いた。
「役人と云っても、抱関撃柝じゃねえ。身分の高い武士様は、売り買いに関与しねえよな。あまりにも、ものを知らないんだと思ったら、おかしくなっちまった」
「……ご教授してもらえるだろうか?」
「氷屋は夏と秋に、氷を売るんだ。冬の寒い時期に東北の国から氷を運んでくる。そんで、溶けないように年中寒いところで保管する。山中の洞窟だな。それも地下だな。暑くなると、城下町へと運ぶんだ。懇意の旗本に売る。葉月に氷だ。かなりの値段になる」
「なるほど、大村家より潤沢な取り引き相手だ。瑞木は商売にも金にも困っていなかったようだ。懸想する相手もいなかった。おまえのように賭け事にも、溺れていない」
「云いやがる。おれは犬っころの泳ぎよりもはやく、両手を出しているんだぜ。丁半の決め札をもってな。賭け事にじょうじているときは、だれよりも上手に泳いでいる」
作間は軽口を叩いたあとに「まァ、瑞木は兄者とも親しかったわけでもねえ。三人も殺す理由が思いあたらないね。おれの目立てじゃ、上野が怪しいところだが……」と本音をつぶやいた。
彼がふたたび、キセルをとったとき、ふすまの奥から階段を踏みしめる音がきこえてきた。
引き戸があけられた。
土手方に向かわせた役人のひとりだった。
「はァはァ、報告です。江戸川は棒出しをつくっている途中でした。完全にせきとめてはいなかったものの、作業は夜中にも行われ、そのあいだにとおった小舟はないそうです」
さらに、べつの役人も到着した。
「目黒川と蛇崩川は開通していました。しかし、大川は駄目です。とおれません。きのうの昼に木橋が崩れ、きょうの昼間に直したようです。事件の夜はとおれませんでした」
「ふたつの川がとおれないか……」
別府は首を横にふった。
「賭けはおれの勝ちのようだ。おっと、勘ちがいするなよ。褒めているんだ。番所の役人なら、調べてもくれなかったはずだ。あんたらだからすぐに動いてくれた。おおあたりだった。感謝してるぜ」
別府はゆっくりと立ちあがった。朗らかな態度をとる作間に、にらみを利かせた。
「安心するのはまだはやい。あたらしい手掛かりが見つかり、作間の犯行を示すようならば、また来る。ことばじゃなくて、両手のあいだをかよわすことになる」
「へいへい」
「つぎに会うとき、自由に泳げる両手があると思うなよ」
作間は手首同士をかさねた。畳を叩き、「怖い怖い」と笑った。
門前町に出る。表門のほうに向かった。
すでに夕日が落ちようとしていた。
蛇崩町に着くころは夜五つだ。
「こんどの調べも外れだった。簡単には下手人が突きとめられないものだ」
別府は鼻にしわをよせた。
「密室殺人と凶器の発見によって、瑞木と経子の犯行はむずかしいことがわかった。作間が目撃されている門前町は、蛇崩町からとおく、犯行時刻までに到着することができない。作間も不可能だ。そうなると、のこりはひとりだ……」
「別府殿、忘れていました!」
ふり向いた。大川の報告に来た役人が追いかけてきた。
「か、火急の用です」
肩で息をしていた。
「きいてください」
「どうしたんだ?」
「九兵衛殿からです。下屋敷まで急ぎで来られるようにと、申しつけがありました」
「いまからもどるところだ。なんだ。なにかあったのか?」
「上野左衛門が捕まりました」
別府は耳を疑った。間髪入れずにききかえした。
「なんだと、どういうことだ?」
「敷地内の排水が終わったころです。見張りの目を盗んで、下屋敷へと侵入したのです」
「いったいなんのために?」
「わかりません。上野は書院から出てきたところを捕らえられたようです。行人坂のまえの番所につれていかれました」
未堂棟の左目がひらいた。
両目をぱちくりさせ、彼の行動に疑問の声をあげた。
二十三回目だった。
「――下手人が犯行の手掛かりを処分しようとすることは考えられる行動ですが、彼の捕まった場所は殺人と関係のない書院です。上野さんは、なにをしに書院へと出向いたのでしょうか?」
「……まさか、書院内に隠した犯行の証拠を隠滅するためか!」
別府は早口でまくし立てた。
「三つの殺人を可能にする証拠が書院にあった!」
未堂棟の左肩を抱いた。
「それを処分しようとしていたのかもしれない!」
別府は未堂棟を押しながら、走りつづける。
駕籠のなかに飛びこんだのである。