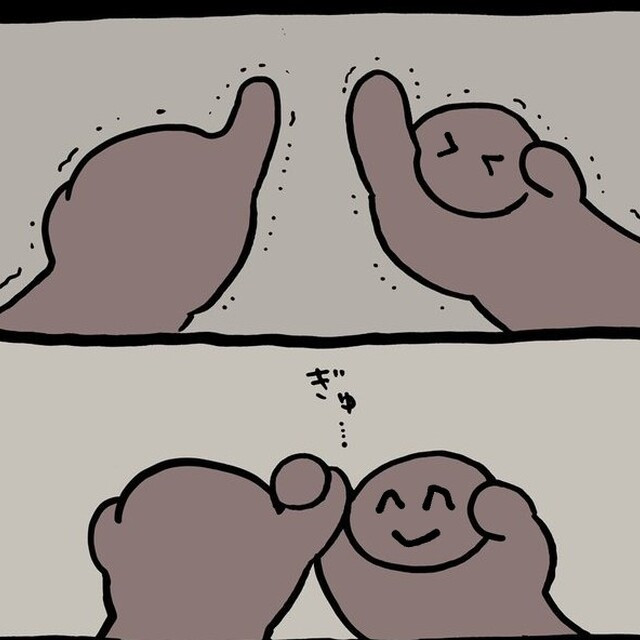#4 徒然なるままに
文字数 6,120文字
『かなたの庭に、大きなる柑子の木の、枝もたわわになりたるが、まはりをきびしく囲ひたりしこそ、少しことさめて、この木なからましかばと覚えしか』
◇
短期的なおれの日々は続いた。
さらに数年におよぶ時間を過ごしながら、おれはどこかの会社に属することもなく、社会に貢献することもなかった。
役に立たないというよりは、役に立てなくなっていた。
そりゃそうだ。
たった数日で跡形もなく消え去る人間にやれることはない。
短期的にしか存在できない以上、社会的な約束を果たすことも、仕事を継続することもできない。
社会も、そんな人間は求めていない。
チェンソーの事故に遭ってからしばらくの間、おれは金があるうちは活動的なことはなるべくしなくなっていた。
再び同じような目に遭うことは極力避けたい。
◇
そんなわけで、おれはここ数年、部屋に寝転び、ひたすらに庭の景色を眺めていた。
繰り返しのたびに、別の季節の景色を楽しめた。
元に戻されて目が覚めるたびに、吸い込む空気の質は変化していて、風雅な気分を味わうことができた。
朝起きると、湯を沸かし、お茶をいれる。
おれはもはや俗世を捨てた僧侶になったような心持ちで、毎日を満喫していた。
◇
転生をして、ひとつ分かったことがある。
それは、世の中の色んなことがどうでもよくなる、ということだ。
日々の繰り返しの影響も大いにあるだろう。
しかし、根源的な部分で、最初からおれの気持ちは変化していた。
◇
前世の記憶もあるせいか、おれの目には出来事のひとつひとつが相対的に見えていた。
おかげで、あまり物事にのめり込まなくなっていた。
主体性よりも、世界を見届ける傍観者としての性格のほうが強くなった、とも言える。
人間関係が希薄でも、思うところもなく、胸に手を当てて我が身を振り返ってみたところで、承認欲求らしいものもなくなっている。
おれは目の前の景色を承認していくだけだった。
◇
一度目の人生の人には伝わらないかもしれないが、なんというか正直、世の中に人間がいてくれるだけで、ありがたいような気持ちになる。
もちろん関わろうと思えば、関わることだってできる。
自分ひとりしか存在していない孤絶した世界に転生しなくて本当によかった、と心から思っている。
あくまで、おれの体感だが、転生をして同じ気持ちを抱く人も、少なくはないだろうと思っている。
世界にいられるだけで、少しうれしい。
◇
転生したからと言って、よりよい人生を求めて、あくせく動き回りたいとも思っていない。
前の人生は、前の人生。この人生は、この人生。まったくの別物だからだ。
前世と今では、過去に辿ってきた境遇も違う。
住んでいる世界そのものが違うのだから、前世の価値観に縛られる必要はまったくない。
無理に一緒のものとして考える必要もない。
単純にそう思うようになった。
◇
前世でやり残したことも、特に思い当たらない。
ひとつだけ挙げるとすれば、死にたいと思っていなかったときに死にたくはなかったな、という感想くらいだろう。
それもまあ、仕方ないと言えば、仕方ない気もする。
殺される落ち度は、結構おれにもあったような気もしている。
◇
前世の社会に出てからのおれは、ひたすらに働いていた。
それというのも、働き詰めになれば色んな事をいちいち考えなくてよくなるから、という理由からでしかなかった。
働いたことのない人には不思議に思われるかもしれないが、人は会社に行きっぱなしになると、社会との関係性が徐々に薄れていく。
なぜなら社会との接点は、会社という組織が肩代わりしてくれるからだ。
おれの場合、働いていたのがブラックな環境だったから、その効果はなおさら大きかった。
社会との関わりは断絶され、個人的にとても楽な状態ではあった。
◇
そこでは人と人が直接ぶつかり合うこともない。
必ず間には仕事が挟まってくれている。
むしろ、そこに個人的な自我のようなものを差し込もうとすると、たいてい精神的に病むか、思い通りにいかず、気力をなくして潰れていく。
仕事の中に自我にまつわるドラマを差し込もうとすると、決まって人格は傷つけられることになる。
勢い良く動いている機械に指を突っ込むようなものかもしれない。
それは仕事に限った話ではないだろう。
人の社会性は刃物のようにできている。
有効に使えば、多くの人間を生き延びさせることができるが、少し扱い方を間違えるだけで、いとも簡単に怪我をする。
そして刃物に罪がないように、社会性そのものにも罪はない。
扱い方と、扱う人間次第だ。
そして素晴らしいことに、世の中の人々は社会性そのものには無自覚のまま、やみくもにそれを振り回し合っている。
――人はひとりでは生きていけない!
そんなことを言い合いながら、鋭い刃先を振り回す。
そいつが正気かどうかは本人にしか分からない。
◇
さらに働き詰めでいてよかったことは、誰かに干渉されることがないこと、だろうか。
自分のプライベートの生活を誰かに咎められることもない。
おれの場合、実際には下請け企業の悪感情を買って殺されたわけだから、よくない部分は大いにあったわけだけれども……。
◇
前世のおれと、働くことのできない今のおれを比べても、たいした違いはない。
どちらも社会との関係は希薄だ。
働いていた前世のおれと、いまのおれのどちらが偉いかも、正直よく分からない。
ただ、前世で懸命に働いていた身として、ひとつだけ確実に言えることはある。
――働いているほうが偉いと思わなきゃ、やってられない。
単純にそれだけのことだ。
人は自分の苦労を、他の誰かと比較したがる。
きっと嫌々働いている人ほど、そう思えるだろう。
◇
いずれにせよ、数十年に及ぶ時間が過ぎながら、誰からの連絡もなく、自分から連絡をすることもなかった。
おれはこの繰り返しに飲み込まれてから、他人の時系列からバッサリと切り落とされてしまったのかもしれない。
そう考えると、おれと孤独な老人との間に大した違いはないだろう。
自分が過去にどんな人間関係を築きあげてきたのかも、すっかり忘れてしまっている。
◇
前世では頻繁に人に会っていたが、それもいまとなっては何の役にも立たない。
ちなみに、前世のおれの学生時代には、まるで恋人のように頻繁に会うことを求めてくる面倒くさい山岡という先輩がいた。
恋人でもなく、友人でもない先輩にその頻度で呼ばれると、さすがに途中から鬱陶しくは感じた。
何が先輩を駆り立てているのかは最後まで分からなかったが、暇を見つけては後輩を呼び出し、会うと長時間拘束し、そこから一切役に立つことのない世間話が続いた。
山岡先輩はいわゆる、うざ絡みをしてくるような人だった。
ラーメンチェーン店の『山岡家』のことを『オレん家』と呼ぶくらいアホな先輩だったが、時空の遥か遠くに行ってしまった今となっては、かつての終わりのみえない不毛な会話も、張りのない声も、どこか物悲しげで懐かしくすら感じる。
山岡先輩がどうなっているかは、もちろん分からない。文字通りの意味でおれと先輩は住む世界が変わってしまった。もちろん連絡先も知らない。
先輩は今も別の世界で、いつでも誰かを求めて、連絡しまくっているかもしれない。
◇
そういうわけで、人間関係は、なければないで気楽でいられる。
巷に耳を傾けてみると、たいてい良い人間関係の話よりも、好ましくない人間関係の話題のほうがスラスラと飛び出してくる。
無尽蔵に、と言ってもいいくらい。
なんといっても、人生の苦悩の大半は、人間関係に起因している。そう思う。
◇
しかし、繰り返しの最初の頃、心底うろたえたおれは、誰かの助けが必要だと本気で感じていた。
調べ物を進めているうちに、信仰の道に足を踏み入れようかとも考えた。
まともじゃない状況を受け入れてくれるのは、そういった環境しかないと思ったからだ。可愛そうな奴だとは思われたかもしれないが、少なくとも話くらいは聞いてくれそうだと考えていた。
しかし、すぐに思いとどまり、特定の団体に所属する前に足を止めた。
◇
そのときのおれには、一つのイメージが思い浮かんでいた。
それは、宗教施設の内部で古参の信者が、新参者に対して執拗に精神的マウントを取っている様子だった。
なんとなく、想像できるだろうか?
ちなみに、なにかの当てつけに無責任に思いついた情景ではない。
きちんと過去に苦い思い出がある。
◇
母親と2人で暮らしていた頃、母親の職場に、団体名は忘れたが何かの宗教に熱心なオバサンがいた。
おれたち親子のことを知り、おおいに不幸な存在だと認定されたのか、はたまた、勧誘してもこの人ならイケそうだ、と思われたのかは知らないが、母親はそのオバサンから執拗に集会への参加を持ちかけられていた。
職場が同じということで、逃げようもなく、話をするためにおれたちのアパートまで押しかけ、いつの間にか教義について長々と説明を始めるほどだった。
◇
その時ほど、母親が頑固で自分をしっかり持っている人間でよかったと思ったこともない。
「お気持ちは嬉しいのですが――」母親はそう前置きし、きちんと理由を説明したうえで、きっぱりと勧誘を断った。
それでもなかなか、オバサンは引き下がらなかった。母親の入信への消極的な言葉を耳にするたびに、かえって勧誘に対する熱意を燃え上がらせていたのかもしれない。
◇
あなたたちがいかに不幸な境遇であるか。救われる必要があるか。
そんな話を切々と続けていた。
おれは傍から見ていて、だんだんと、オバサンが何の為に母親を勧誘しているのか分からなくなっていた。そしてオバサン本人もそう感じてくれることを願った。
◇
その頃には母親は自分の気持ちを隠さず、堂々と眉間にシワを寄せ、迷惑を受けている人間の表情をしていた。露骨に不愉快そうな表情を出していたかもしれない。
オバサンはまったくそれを気にしていない様子だった。
◇
なんというか、オバサン本人が自分を善人だと思い込んでいるぶん、こちらの言い分が届きづらく、かえってタチが悪かった。
おれたち親子にとっては迷惑だったものの、オバサンからは悪意のようなものは微塵も感じられなかった。
悪意は感じられなかったが、母親に説明する態度が終始、偉そうには見えた。
その時のおれは疑問に思った。
創始者が偉いのは分かる。神さま仏さまが偉いのも、当然分かる。しかし、どうして組織の下っ端の下っ端であるこのオバサンまで偉そうなのかは、まるで分からない。
その疑問は、おれの頭の中に残り続けた。
◇
オバサンの話は続き、おれたち親子はそれを聞かされ続けた。
もしも、現世のプラスに転じなかったこんなお節介のせいで規定のポイントが足りず、オバサンが死後に望んだ世界に行けなかったとしたら、それこそ可哀想だ、とすら思えてきた。
しかし、おれたち親子にできることは、話を聞くことくらいだった。
◇
オバサンは自分の行為を正しいものだと信じて疑っていない様子だった。
そりゃそうだ。
正しいと思っている行為に対して、反省的になる人は少ない。
誰だって正しい行いに想像力を働かせる必要は感じない。
皮肉なことに根っからの悪人のほうが、相手が嫌がることを考慮する点で、むしろ想像力がある、とさえ言える。
しばらくおれたち親子は、毎日ため息をついて過ごすことになった。
◇
「ごめん、晩ごはん、今日もカップ麺でいい?」母親はおれに聞いた。
「それでいいよ。なんだったらスーパーでお惣菜でも買ってこようか?」おれは答えた。
◇
母親の願いは至極単純だった。
「わたしのことは放っておいてほしい」
それだけだ。
善悪の判断をつけるのは簡単だが、善人と悪人の判別は難しく、面倒でもある。
◇
なかなか立派な体験をしたおかげで、おれは信仰や宗教という言葉を聞くたびに、あのときのオバサンの姿を思い出すことになった。
◇
しかし、考えてみれば不思議なものだ。
例えばどこかの誰かが、人間関係による軋轢に疲れ果て、心の平穏を求めて宗教に頼ろうとする。
しかし、そこで大手を広げて待ち構えているのは、別の複雑な人間関係でしかない。
そこもまた集団である以上、秩序と関係性が重んじられる。
いつのまにか「教え」と「精神的マウント」がミルフィーユみたいに折り重なった代物を、紅茶と一緒に進められて、愛想笑いをしながら飲み込むハメになる。
帰り道には、いつものように重たい疲れを感じ、教団に関わる前と瓜二つのため息をついている。
いつでもどこでも、たとえ小さな価値を伝えるためだけであっても、集団は人間を囲い込みたがる。
◇
世の中の苦悩の根本は、集団を形成したがる人間性にあるのかもしれないが、それを乗り越える発想も手段も、集団それ自体は持ち合わせていない。
人間関係に疲れ果て、誰とも関わり合いたくなくなった人間を救える集団というものも存在しない。
集団内の論理は、ひとりで居たいという誰かの願いを、永遠に叶えてやることはできない。
集団は、人と関われなくなった人間を救うこともできない。
ちょうどいまのおれの状態のような人間を。
なんというか、人間社会が抱える、なかなか立派な矛盾だ。
◇
断っておくが、おれは何かを否定したいわけではない。
自分の経験を振り返っているだけだ。
和風な例えで言うなら、人間関係や集団というものに、どうしようもない生臭さを感じる(他の人は気にならないのだろうか?)。
洋風で言うなら、誰かから教えを厳しく説明されるたびに、心の中の十字架がへし折られるような気分になる。
もしも、世界中の様々な教義から「使役形」で書かれた言葉を消し去ったら、一体何が残るんだろうか。
おれは宗教について思う時、あの時の必死なオバサンの姿と一緒に、そんなことを考える。
善悪の判断や、死生観を人の信仰と呼ぶのなら、おれにも信仰はある。そして他人の信仰に干渉するつもりもない。
どこかのご隠居みたいに一人でぼんやりと考え事をしているだけだ。
◇
おれは、部屋に寝転び、静かに雪の降り積もる庭を眺めていた。
窓は開け放している。
顔と腹には外からの冷気、背中には暖房から届く温もりを感じている。
立派なご隠居になるために、色々とメモ帳に書き留めておこうと思ったが、面倒なので手つかずのままでいる。
いまのおれから言えることはそれくらいだ。