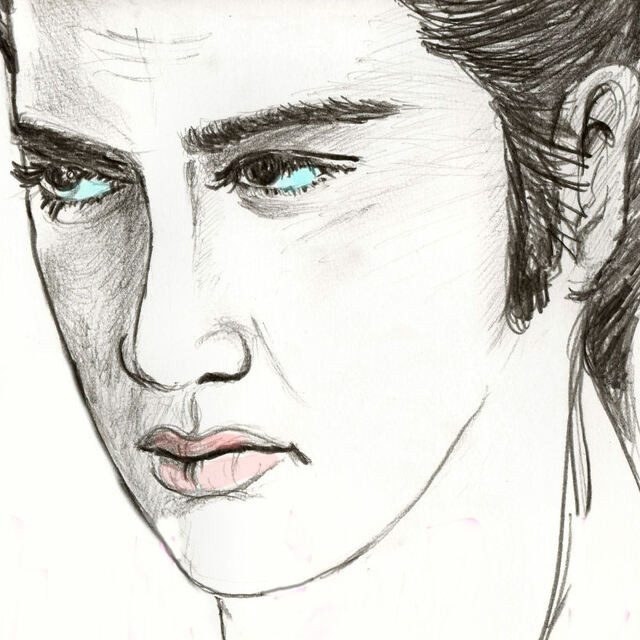第21話 二月二十六日の決行
文字数 2,682文字
昨夜から降り出した雪をものともせず、熱い思いを胸に秘めた大尉、中尉、少尉の将校達と、彼等が率いる軍人の総数のおよそ千五百人はそれぞれの襲撃場所に向かって足早に行進していました。
彼等は防寒・防雨のための軍隊用の外套 を着込んでおりましたが、昨日の夜から、久しぶりの大雪で積雪は四十センチほどになっていたのです。
その彼等は隊列を組みながら、未明から準備した武器を携えて、白い息を吐きながら黙々と足早に襲撃場所に向かっていたのです。
前夜から降りしきる雪はチラホラと舞いながら、彼等の軍帽を白くしていました。
その時刻は目立たないような午前の五時頃であり、寒い朝と言うことで彼等以外にはあまり人の気配がありません。
ときどき隊を組んで歩く彼等に気がついた犬もいたようですが、さすがにこれほどの多くの隊員の行進に、吠えるのを忘れたように怯えていたのです。
一行は黙々と歩き続けました。彼等は一様に腰にはベルトを締め、軍刀を付けている者もおりました、そして肩から掛けた鞄には何やら入っているのでしょう。中には、成功を祈願したお守りを懐深く忍ばせた者もおりました。
南郷様は、その中でも高橋是清蔵相邸を襲撃するグループに入っておりました。歩きながら、彼は思っていたのです。
(今日のこの日からは新しい日本の幕開けになるのだ。我々が信じてやってきたこの行動がこの世の中を代えていく、その第一歩としての行動なのだ)と。
本来、軍人は国を守るために武器を携え、外国からの侵入者を防ぎ、さらに国民を守るための逆賊を打つことと信じていました。その武器を、同じ同胞で或る日本人に向けることの後ろめたさを感じないわけではありません。
しかし、世の中を一握りの国賊達に牛耳られているこの世を守るためにやむを得ず、今、行動しているのだと、自らに奮い立たせていました。
南郷様は、貴美子様にこの計画を打ち明けることはできませんでしたが、その行動の趣旨をいつかは信じてもらえると思っておりました、その自信は確固たるものではありません。
国のため、天皇陛下の御為に……と思えばこその行動なのです。
その根本的な彼等の崇高なる思いが、後ほどに無残にも打ち砕かれようとは、彼等の誰が思うことでしょうか。まことに彼等の命運は危うい状態になっておりました。
この計画の首謀者である将校達はその目的を理解しているので良いのですが、それを知らされていない、いわゆる下部の軍人達の多くは、その目的さえ知らずに駆り出されたのです。
その中には、高橋蔵相を襲撃するグループとして赤坂に駐屯しております近衛兵第三連隊の第七中隊の隊員に非常の呼集が掛けられたのです。
呼集を掛けたのは隊長代理の中橋基明中尉でした。その時刻はまだ冷え冷えとした午前の四時よりも前でした。
近衛兵とは政府の直属の部隊で、各地区から選別された優秀な者達で編成されており、天皇をお守りする護衛兵のことです。
皇居に何かあればすぐに駆けつけて護衛することを目的としていたのです。
その朝、中橋中尉は呼集前に隊付きの将校である今泉義道少尉を起こしていました。
「今泉、起きてくれ!」
「どうしました? 中橋中尉殿」
早朝に急に起こされた今泉は怪訝な顔をして兵舎のベッドから身を起こしました。
「今泉、じつは、お国のためにそれを今日、実行することになった、急だが申し訳ない」
「それは……」
今泉はそれ以上の言葉が出ず唾を飲み込んだのです。あの勝ち気な中橋が自分に頭を下げたのですから。
(いよいよ、その時がやってきたのか……)
中橋は、決行の中心メンバーではない今泉には詳細は告げてはいません。その今泉は同じ部隊で行動する中橋を見ていたので、彼自身もそのことは何となくは感ずいていたようです。
「そうだ、今朝、これから『昭和維新断行』を実行させる、一緒に立ち上がってくれ、たのむ、今泉!」
今泉はしばらく考えておりましたが、中橋の熱意に動かされ同意したのです。
「わかりました、中尉殿」
「ありがとう、今泉……」
中橋は目の前にいる今泉の肩を抱き寄せていました。その目には中橋には珍しく涙が溢れていたのです。中橋の泣き忍ぶ姿に、今泉ももらい泣きしたのでした。
「私も中橋さんの思いは分かります、我が小隊も参加しましょう」
「ありがとう、今泉」
(この後々において、死を逃れられた人情に厚い今泉は、一生涯においてずっとこのことを忘れることはありませんでした)
すぐに隊員には呼集が発せられました。その中には萩原光太郎という初年兵の若者がおりました。昼間の訓練で疲れ切ってその兵舎の中でぐっすりと眠っていると、大きな怒号で目を覚ましたのです。その知らせは、ラッパの音ではありませんでした。
「非常呼集だ、みな起きろ、起きろ!」
怒号で起きたのは、同じ初年兵仲間の斉藤邦夫でした。
「おい、萩原、あの声を聞いただろう?」
「うん、非常呼集らしいな、いったいどうしたんだろう、まさか外国が攻めてきたわけじゃないだろう」
萩原と言われた若者は、眠そうな顔をして目を擦っておりました。
「冗談を言うな、でもとにかく急いで着替えて準備しよう、遅いと怒られるからな」
「うん」
「早く! 早く」
あちこちで軍服に着替えたり、装備品を身につけようと、慌ただしい光景が広がっていました。しかも、電気は付けられていないので、手探り状態なのです、その中を班長が見て回ります。
「とにかく急げ! 持って行くのは帯剣と銃だけでいいぞ、すぐ兵舎前に集まるんだ!」
こうして他の隊員達もすでに着替えが終わり、それぞれの武器を携えて兵舎前に集合し整列しておりました。誰もが、早朝の急な呼集に緊張をしております、昨夜からの雪のために地面は白く覆われておりました。
隊列に一人遅れてきた者がおりました。彼は川島国夫という初年兵の若者ですが、いつも動作が鈍く上等兵から叱られておりました。
その朝も足のすねに巻くゲートルや軍靴の紐がうまく結べず、何度もやり直したりしたため遅くなったようです。
最後の列に並んだ川島に、上等兵が近づき「遅いぞ、馬鹿者!」といって殴ったのです。川島は雪の下に倒れ、その頬は腫れあがっておりましたが、すぐに起き上がりました。
他の者が手を差し向けて助けることなどできません、そうすれば自分にも鉄拳がくだるのが分かっているからなのです。
隊員の一番前に立ち、じっと整列した彼等を見つめる第七中隊長の代理である中橋基明中尉の目は、これから世間を驚かすような大事件を前にして熱く燃え上がるようでした。
彼等は防寒・防雨のための軍隊用の
その彼等は隊列を組みながら、未明から準備した武器を携えて、白い息を吐きながら黙々と足早に襲撃場所に向かっていたのです。
前夜から降りしきる雪はチラホラと舞いながら、彼等の軍帽を白くしていました。
その時刻は目立たないような午前の五時頃であり、寒い朝と言うことで彼等以外にはあまり人の気配がありません。
ときどき隊を組んで歩く彼等に気がついた犬もいたようですが、さすがにこれほどの多くの隊員の行進に、吠えるのを忘れたように怯えていたのです。
一行は黙々と歩き続けました。彼等は一様に腰にはベルトを締め、軍刀を付けている者もおりました、そして肩から掛けた鞄には何やら入っているのでしょう。中には、成功を祈願したお守りを懐深く忍ばせた者もおりました。
南郷様は、その中でも高橋是清蔵相邸を襲撃するグループに入っておりました。歩きながら、彼は思っていたのです。
(今日のこの日からは新しい日本の幕開けになるのだ。我々が信じてやってきたこの行動がこの世の中を代えていく、その第一歩としての行動なのだ)と。
本来、軍人は国を守るために武器を携え、外国からの侵入者を防ぎ、さらに国民を守るための逆賊を打つことと信じていました。その武器を、同じ同胞で或る日本人に向けることの後ろめたさを感じないわけではありません。
しかし、世の中を一握りの国賊達に牛耳られているこの世を守るためにやむを得ず、今、行動しているのだと、自らに奮い立たせていました。
南郷様は、貴美子様にこの計画を打ち明けることはできませんでしたが、その行動の趣旨をいつかは信じてもらえると思っておりました、その自信は確固たるものではありません。
国のため、天皇陛下の御為に……と思えばこその行動なのです。
その根本的な彼等の崇高なる思いが、後ほどに無残にも打ち砕かれようとは、彼等の誰が思うことでしょうか。まことに彼等の命運は危うい状態になっておりました。
この計画の首謀者である将校達はその目的を理解しているので良いのですが、それを知らされていない、いわゆる下部の軍人達の多くは、その目的さえ知らずに駆り出されたのです。
その中には、高橋蔵相を襲撃するグループとして赤坂に駐屯しております近衛兵第三連隊の第七中隊の隊員に非常の呼集が掛けられたのです。
呼集を掛けたのは隊長代理の中橋基明中尉でした。その時刻はまだ冷え冷えとした午前の四時よりも前でした。
近衛兵とは政府の直属の部隊で、各地区から選別された優秀な者達で編成されており、天皇をお守りする護衛兵のことです。
皇居に何かあればすぐに駆けつけて護衛することを目的としていたのです。
その朝、中橋中尉は呼集前に隊付きの将校である今泉義道少尉を起こしていました。
「今泉、起きてくれ!」
「どうしました? 中橋中尉殿」
早朝に急に起こされた今泉は怪訝な顔をして兵舎のベッドから身を起こしました。
「今泉、じつは、お国のためにそれを今日、実行することになった、急だが申し訳ない」
「それは……」
今泉はそれ以上の言葉が出ず唾を飲み込んだのです。あの勝ち気な中橋が自分に頭を下げたのですから。
(いよいよ、その時がやってきたのか……)
中橋は、決行の中心メンバーではない今泉には詳細は告げてはいません。その今泉は同じ部隊で行動する中橋を見ていたので、彼自身もそのことは何となくは感ずいていたようです。
「そうだ、今朝、これから『昭和維新断行』を実行させる、一緒に立ち上がってくれ、たのむ、今泉!」
今泉はしばらく考えておりましたが、中橋の熱意に動かされ同意したのです。
「わかりました、中尉殿」
「ありがとう、今泉……」
中橋は目の前にいる今泉の肩を抱き寄せていました。その目には中橋には珍しく涙が溢れていたのです。中橋の泣き忍ぶ姿に、今泉ももらい泣きしたのでした。
「私も中橋さんの思いは分かります、我が小隊も参加しましょう」
「ありがとう、今泉」
(この後々において、死を逃れられた人情に厚い今泉は、一生涯においてずっとこのことを忘れることはありませんでした)
すぐに隊員には呼集が発せられました。その中には萩原光太郎という初年兵の若者がおりました。昼間の訓練で疲れ切ってその兵舎の中でぐっすりと眠っていると、大きな怒号で目を覚ましたのです。その知らせは、ラッパの音ではありませんでした。
「非常呼集だ、みな起きろ、起きろ!」
怒号で起きたのは、同じ初年兵仲間の斉藤邦夫でした。
「おい、萩原、あの声を聞いただろう?」
「うん、非常呼集らしいな、いったいどうしたんだろう、まさか外国が攻めてきたわけじゃないだろう」
萩原と言われた若者は、眠そうな顔をして目を擦っておりました。
「冗談を言うな、でもとにかく急いで着替えて準備しよう、遅いと怒られるからな」
「うん」
「早く! 早く」
あちこちで軍服に着替えたり、装備品を身につけようと、慌ただしい光景が広がっていました。しかも、電気は付けられていないので、手探り状態なのです、その中を班長が見て回ります。
「とにかく急げ! 持って行くのは帯剣と銃だけでいいぞ、すぐ兵舎前に集まるんだ!」
こうして他の隊員達もすでに着替えが終わり、それぞれの武器を携えて兵舎前に集合し整列しておりました。誰もが、早朝の急な呼集に緊張をしております、昨夜からの雪のために地面は白く覆われておりました。
隊列に一人遅れてきた者がおりました。彼は川島国夫という初年兵の若者ですが、いつも動作が鈍く上等兵から叱られておりました。
その朝も足のすねに巻くゲートルや軍靴の紐がうまく結べず、何度もやり直したりしたため遅くなったようです。
最後の列に並んだ川島に、上等兵が近づき「遅いぞ、馬鹿者!」といって殴ったのです。川島は雪の下に倒れ、その頬は腫れあがっておりましたが、すぐに起き上がりました。
他の者が手を差し向けて助けることなどできません、そうすれば自分にも鉄拳がくだるのが分かっているからなのです。
隊員の一番前に立ち、じっと整列した彼等を見つめる第七中隊長の代理である中橋基明中尉の目は、これから世間を驚かすような大事件を前にして熱く燃え上がるようでした。