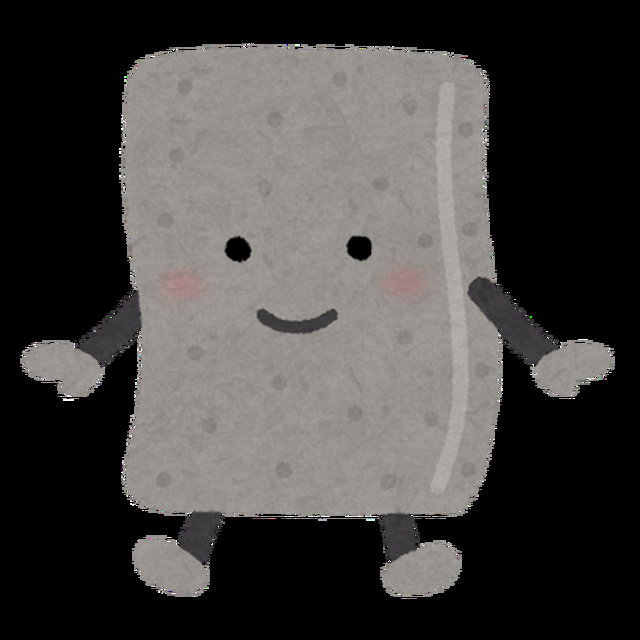第7話 異世界からの追手
文字数 5,240文字
「おい君たち! こんな時間に、こんなところで何してるんだ!」
幕張メッセの建物内を夜間巡回中の警備員が、建物の裏手でウロウロしていた怪しい二人組に声をかけた。
「あっ、いえ。決して怪しいものでは……知らないうちにここに紛れ込んでしまいまして……あの、出口はどちらに……?」
どう見ても五十歳は越えているであろう小柄な男が答えた。
「うーん。とりあえず一度、事務所に来てくれるかな。このあたり調べて何か問題があれば警察呼ばなきゃならん」警備員は警戒を解かない。小柄な男が連れの女性を前に押し出して言った。
「すんません! この娘とちょっとエッチな事をしようとして、どこかいい場所はと探してたら、いつのまにかここに入っちゃってて……」
「はいー? ……まったく、いい年してしょうがねえおっさんだな。ほら、出口はあっちだから、さっさと出た出た! まったくもう……」呆れた顔でそう言いながら、警備員は二人が通用口から外に出たことを確認して、その場を去った。
「いやー、危なかったですね。警察はまずいです」小柄な男が言う。
「なーにが、危なかっただにゃん! あたいはあんたとエッチしにゃいっての!」
連れの女の子が言い返す。
「あれ? 私の言葉、わかりました?」
「ふんっ、魔法院の語学学習術式は優秀なのにゃん!
それにしても……ここはどこにゃ?」
「うーん、私もこっちに帰って来たのは三十年以上ぶりくらいで……道端の看板を見る限りでは、千葉の幕張っぽいんですが……私、こっち来た事なくて……アホミンさん。
何かの魔法術式とかで手っ取り早く、姫様の居所判ったりしませんかね?」
「こらー、あたいはマホミン! 間違えるにゃバカハル! そんな術式あったら、あんたなんか連れて来てにゃいっちゅうの!」
「バカハルはひどいなー。私はマサハルです……。
それにしても、これからどうしましょうか。私の持ってる夏目漱石の千円札が、ここの自販機で使えないんですよ……」
「もう、お腹へったにゃー!」
そう、この二人、セシル姫を連れ戻すべく、カレイド王子が派遣した追手なのだ。
マサハルと言う男は、三十年以上前にあちらに転移した次元転生者であり、マホミンという娘は、魔法院で勇者召喚チームの助手をしていた猫型獣人だ。
二人の目的は、当然、セシル姫を探し出して連れ帰ること。
マサハルは、こちらの世界のガイド役としてマホミンに随伴させられているのだ。
しかし、自分の元いた世界に戻って来ては見たものの、どうやって姫を探したものか。
「あのー、ア……マホミンさん。とりあえず、あそこの牛丼屋で、この千円札が使えるか……聞いてみましょうかね?」
牛丼屋のオヤジがいい人で、二人は並牛丼にありつくことが出来たが、さて、今夜はどこで夜明かししようか。漱石の千円札はまだ数枚あるのだが、これで二人でホテルに入ったりしたら、めちゃくちゃ怪しいし……というより、このお金が当面、虎の子の軍資金でもあり、こちらでの活動方針が定まるまであまり無駄遣いはしたくないのが本音だ。
なにせ、アホミンが活動資金として王子から貰ってきた貴金属が、よく見たら、ただのアルミだったし…‥。
あてもなく、国道に沿って歩いていると、マホミンがぐずりだした。
「バカハルー、眠いにゃー。それに寒いにゃー」
「そうですね……結構冷え込みますね。さっきの牛丼屋のカレンダー、令和五年の二月になってました。平成は終わっちゃったんですね‥‥‥。
ですが、このまま寝たら間違いなく凍死です。マホミンさん。江戸川沿いに私の昔の知り合いが、もしかしたらまだいるかも知れません。まずは、そいつを頼ろうかと思うんですが……そこまで、いっしょに歩いていただけませんか?」
「えー、どんくらい?」
「まあ、普通に歩いて、朝までにはなんとか……」
「バカー、そんにゃに歩けるかー! にゃんとかしろー、おんぶしろー!」
「はいはい……もし動けなくなったら、さっき牛丼屋でもらったお釣りの小銭で、あったかい缶コーヒーくらいは買ってあげますから……機嫌直して下さいよ」
「ぶうーっ」
こうして二人は、市川・浦安と描かれている道路案内標識の矢印の方向に向かい、とぼとぼと歩を進めるのだった。
◇◇◇
すでに正午を回ったと思われる。マサハルとマホミンは、旧江戸川にかかる江戸川水閘門 のところにいた。幕張海岸から夜通し歩き続けて疲れ切ってしまったのか、マホミンは一言も口を利かない。というか陽だまりの中、ベンチで眠ってしまっているようだ。
「いやはや、この水閘門 はそのまんま……というかまあ修繕してるんですかね。それにしても街並みが変わりすぎです。自分が住んでたはずなのに、まったくわからん。
仕方ない、篠崎の駅の方にでも行って、馴染みの飲み屋が残ってたりしないか探しましょうか……。いい加減どこかに落ち着かないと、この子も可哀そうですしね」
マサハルは、マホミンの頬をぺちぺち叩いて起こし、グズる彼女をなだめながら、駅の方に向かった。
「いやー、ここも全然変わっちゃってるなー……でも、ああ、あの路地の奥とか、知ってる店がありましたよ! ちょっと話を聞いてみましょうね」
そう言いながらマサハルは、準備中の看板が出ている神田川という小さな居酒屋に入っていった。中では中年の男性が仕込みの最中だった。
「あのー、すいません。つかぬことをお伺いしますが……私、三十年位前に、ここの常連だったものなんですが、近くに来たら急に懐かしくなっちゃいまして、当時の大将とかお元気だったらご挨拶したいなーと……」
仕込み中の男が魚を捌く手を止めてマサハルの方を見て言った。
「お客さん。わざわざすいませんねー。ですが、その時代だと多分、俺のオヤジが店主なんですが、もう十年以上前にあの世に行っちまってまして……」
「そうですか……そうですよねー。すいません、御忙しいところ声かけちゃって。失礼しました」マサハルがそう言って店を出ようとした時、「もういや……もう動けにゃい……」とマホミンが突然、店の玄関先でヤンキー座りをして泣きだしてしまった。
その光景を目の当たりにして、店主も気の毒に思ったのか、マサハル達に声をかけた。
「あのー、お客さん。お連れさんかなりお疲れみたいですし、少し店ん中で休んでいかれます?」
「ああ、ありがとう……だが、私今持ち合わせがなくてね……」
「なーに、まだ開店前ですし、気楽に休んでって下さい…………。
というか、おっさん……もしかして……マサさん?」
「えっ? 確かに私はマサハルですけど……」
「ああっ、やっぱりそうか! この、人ん家の玄関先で女泣かせる犬畜生なヒモ男の感じ……そうじゃないかと思ったんだ! 覚えてません? 三十年位前だと俺まだ高校生だったんですけど、よく店手伝ってたんで……テツヤですよ!」
「テツヤ? んー……テツヤ、テツヤ。あー、小岩高校野球部の! あのテッちゃん?」
「そうそう! いやー、懐かしいな。おっさん、いっつもコハルさんの財布からお金くすねて、うちに飲みに来て、いっつもそこの玄関先でケンカしてたもんなー…………。
で、今はそのすっ飛んだ格好の娘のヒモやってるんだ!」
「いやいや、違う違う……誤解です。この子はそういうんじゃありません。ちょいとワケアリで、この子のボディーガードといったところなんですが……ああ、とにかく知ってる人に出会えてよかった……そんじゃ、テッちゃん。お言葉に甘えさせていただいて、少し休ませて下さいね」
テツヤが、おごりだといって二人分のジョッキと刺身の盛り合わせを出してくれた。
「これはなんにゃ? 魚みたいだけど……生なのにゃん?」マホミンが不思議そうにお造りを眺めている。うーん。確かにあっちの世界のやつら、刺身とか食ってるの見たことないなー。川魚しかいないからかな……などと考えながら、マサハルはジョッキをグイっとあけた。
「ほわーーーーーっ」三十余年ぶりの生ビールが臓腑に染みわたっていくのが分かった。
「ああ、ア……マホミンさん。これはこの皿にとった黒いやつを一寸つけてですね……ああ、あなたはその緑色のは無理だと思いますんで、そのままそのまま……そうそう」
マサハルに教えられながら、マホミンは生まれて初めてマグロの刺身を食べた。
「んんんんっ! なんにゃこれはー! これが魚にゃのか……こんなおいしいの食べたことないにゃ!」そういいながらマホミンは飛び上がる様に立ち上がった。
「ははは、そんなに喜んでもらえると、おごり甲斐があるなー。マホさんだっけ? そんじゃこれ、カレイの煮付けね! あっ、ビールもセルフでどんどん注いで飲んでね」
マホミンの大袈裟な反応がうれしかったのか、テツヤも上機嫌で次々料理を出してくれ
昨日の夜から牛丼一杯しか食べていなかった体が、急速に満たされていくのが分かった。
夕方を過ぎ、店にもお客が入り出したが、テツヤが遠慮しなくていいと言ってくれた。
そのうちバイトの店員さんも来て、手が空いたのかテツヤもマサハル達のテーブルに来て、一緒に飲み始めた。
「そんでね、このおやじ。ほんっとうに最低なの……コハルさんってのは、当時、小岩駅前のピンサロのNo1だったんだけど、こう、おしとやかできれいで上品で……高校生の俺でも惚れちゃいそうな感じの人でさ。それをこの男がさんざん泣かせるのよ……そんで俺は思ったね。絶対こんな大人にはならねえってさ! はははははは……マホさんもこのオヤジにはだまされないようにね……いや、もうだまされちゃったのかな?」
「だーいじょうーぶにゃー。あたいは、かしこいからー」
そう言うマホミンはすでにかなり出来上がっているように見える。
「テッちゃん、しゃべりすぎですよ。マホさんはそんな関係じゃないんだって……それでね、テッちゃん。酔ったついでで恐縮ながら相談があります。どっか二人で暮らせるようなところないですかね。いやいや、もちろん労働付きで結構なんですが……」
「……なんだー。やっぱ、昭和枯れススキなんだ……。三十年前に、突然行方不明になっちゃって、コハルさんもオヤジもそれなりに心配してたんだけどなー。
コハルさんは、その後、西の方へ行くって言ったきり見てないし……。
でも、マサさんは、お変わりなさそうで何より何より……。
そうだな……ああ、そうそう。小岩の連れ込み旅館の女将が、住み込みでもいいから、誰か遣り手いないかって言ってたなー。行ってみるかい?
多分、細かい詮索はしてこないと思うよ」
「そりゃ願ってもない……頼むよ。落ち着いたら礼は必ずするから」
「いやそれは、あんまり期待しないけど……この子、見た目はかなり変だけど、いい子みたいじゃないか。あんまり苦労させるなよ、おっさん」
もうほとんど寝落ちしかかっているマホミンの顔を見ながら、テツヤはその女将にその場で連絡を入れてくれ、マサハルはテツヤに何回も礼を述べながら店を出て、マホミンを抱えて小岩駅行のバスに乗り込んだ。
手持ちの漱石の千円札は、テツヤに無理言って、野口英世のに替えてもらった。
旅館の女将は、マサハルとそれほど年齢の差はなさそうだったが、他に飲み屋などを何軒も経営している実業家で、この連れ込み旅館は、手放すほどではないが、さほど収益も上がっていないので、手をかけず経営ごと丸投げしたい意向らしい。
ゼネラルマネージャーと言えば聞こえはいいが、要は、店番だけではなく、掃除、洗濯から仕入れ、帳簿まで全部やれという事だ。
一応地元の老舗、神田川の主人の紹介ということで、あまり深く詮索はされず、一ヵ月の試用ということになった。
とにかく、今は屋根付きの部屋と仕事が確保出来ただけでオンの字だ。
業績が悪くて一ヵ月後にクビになったとしても、それまでにいろいろやれるだろう。
旅館の帳場の奥に従業員用の六畳間があり、そこで寝起きしろとのことだったので、とりあえず今日のところはそこで寝ることにした。
「マサハルー……この布団、薄いし、すごくカビ臭いにゃ……」
「もう……文句言わないで下さい。明日、晴れてたら干しましょう。さすがに今日野宿してたら二人ともおしまいでしたので、それを思えばこのくらいは……」
「……寒い……くっついていい?」
「はい? あ、でも私……あっちに妻子いますし……」
「勘違いするにゃ! エッチはしないにゃ! 本当に寒いんにゃ!」
「あー、はは。猫ですもんねー」
「うるさい! バカハル……」
マホミンは、マサハルに背中をくっつけたかと思ったら、スースーと寝息をたて始めた。
「やっぱり、お疲れですよね…………でもそうか……やはりコハルは行方知れずですか」
もちろん、同じ所にコハルがいること自体、あり得ない話だと最初から分かっていたが……ちょっとがっかりしながら、マサハルも疲れがどっと出たのか、直ぐに深い眠りに
落ちた。
幕張メッセの建物内を夜間巡回中の警備員が、建物の裏手でウロウロしていた怪しい二人組に声をかけた。
「あっ、いえ。決して怪しいものでは……知らないうちにここに紛れ込んでしまいまして……あの、出口はどちらに……?」
どう見ても五十歳は越えているであろう小柄な男が答えた。
「うーん。とりあえず一度、事務所に来てくれるかな。このあたり調べて何か問題があれば警察呼ばなきゃならん」警備員は警戒を解かない。小柄な男が連れの女性を前に押し出して言った。
「すんません! この娘とちょっとエッチな事をしようとして、どこかいい場所はと探してたら、いつのまにかここに入っちゃってて……」
「はいー? ……まったく、いい年してしょうがねえおっさんだな。ほら、出口はあっちだから、さっさと出た出た! まったくもう……」呆れた顔でそう言いながら、警備員は二人が通用口から外に出たことを確認して、その場を去った。
「いやー、危なかったですね。警察はまずいです」小柄な男が言う。
「なーにが、危なかっただにゃん! あたいはあんたとエッチしにゃいっての!」
連れの女の子が言い返す。
「あれ? 私の言葉、わかりました?」
「ふんっ、魔法院の語学学習術式は優秀なのにゃん!
それにしても……ここはどこにゃ?」
「うーん、私もこっちに帰って来たのは三十年以上ぶりくらいで……道端の看板を見る限りでは、千葉の幕張っぽいんですが……私、こっち来た事なくて……アホミンさん。
何かの魔法術式とかで手っ取り早く、姫様の居所判ったりしませんかね?」
「こらー、あたいはマホミン! 間違えるにゃバカハル! そんな術式あったら、あんたなんか連れて来てにゃいっちゅうの!」
「バカハルはひどいなー。私はマサハルです……。
それにしても、これからどうしましょうか。私の持ってる夏目漱石の千円札が、ここの自販機で使えないんですよ……」
「もう、お腹へったにゃー!」
そう、この二人、セシル姫を連れ戻すべく、カレイド王子が派遣した追手なのだ。
マサハルと言う男は、三十年以上前にあちらに転移した次元転生者であり、マホミンという娘は、魔法院で勇者召喚チームの助手をしていた猫型獣人だ。
二人の目的は、当然、セシル姫を探し出して連れ帰ること。
マサハルは、こちらの世界のガイド役としてマホミンに随伴させられているのだ。
しかし、自分の元いた世界に戻って来ては見たものの、どうやって姫を探したものか。
「あのー、ア……マホミンさん。とりあえず、あそこの牛丼屋で、この千円札が使えるか……聞いてみましょうかね?」
牛丼屋のオヤジがいい人で、二人は並牛丼にありつくことが出来たが、さて、今夜はどこで夜明かししようか。漱石の千円札はまだ数枚あるのだが、これで二人でホテルに入ったりしたら、めちゃくちゃ怪しいし……というより、このお金が当面、虎の子の軍資金でもあり、こちらでの活動方針が定まるまであまり無駄遣いはしたくないのが本音だ。
なにせ、アホミンが活動資金として王子から貰ってきた貴金属が、よく見たら、ただのアルミだったし…‥。
あてもなく、国道に沿って歩いていると、マホミンがぐずりだした。
「バカハルー、眠いにゃー。それに寒いにゃー」
「そうですね……結構冷え込みますね。さっきの牛丼屋のカレンダー、令和五年の二月になってました。平成は終わっちゃったんですね‥‥‥。
ですが、このまま寝たら間違いなく凍死です。マホミンさん。江戸川沿いに私の昔の知り合いが、もしかしたらまだいるかも知れません。まずは、そいつを頼ろうかと思うんですが……そこまで、いっしょに歩いていただけませんか?」
「えー、どんくらい?」
「まあ、普通に歩いて、朝までにはなんとか……」
「バカー、そんにゃに歩けるかー! にゃんとかしろー、おんぶしろー!」
「はいはい……もし動けなくなったら、さっき牛丼屋でもらったお釣りの小銭で、あったかい缶コーヒーくらいは買ってあげますから……機嫌直して下さいよ」
「ぶうーっ」
こうして二人は、市川・浦安と描かれている道路案内標識の矢印の方向に向かい、とぼとぼと歩を進めるのだった。
◇◇◇
すでに正午を回ったと思われる。マサハルとマホミンは、旧江戸川にかかる江戸川
「いやはや、この
仕方ない、篠崎の駅の方にでも行って、馴染みの飲み屋が残ってたりしないか探しましょうか……。いい加減どこかに落ち着かないと、この子も可哀そうですしね」
マサハルは、マホミンの頬をぺちぺち叩いて起こし、グズる彼女をなだめながら、駅の方に向かった。
「いやー、ここも全然変わっちゃってるなー……でも、ああ、あの路地の奥とか、知ってる店がありましたよ! ちょっと話を聞いてみましょうね」
そう言いながらマサハルは、準備中の看板が出ている神田川という小さな居酒屋に入っていった。中では中年の男性が仕込みの最中だった。
「あのー、すいません。つかぬことをお伺いしますが……私、三十年位前に、ここの常連だったものなんですが、近くに来たら急に懐かしくなっちゃいまして、当時の大将とかお元気だったらご挨拶したいなーと……」
仕込み中の男が魚を捌く手を止めてマサハルの方を見て言った。
「お客さん。わざわざすいませんねー。ですが、その時代だと多分、俺のオヤジが店主なんですが、もう十年以上前にあの世に行っちまってまして……」
「そうですか……そうですよねー。すいません、御忙しいところ声かけちゃって。失礼しました」マサハルがそう言って店を出ようとした時、「もういや……もう動けにゃい……」とマホミンが突然、店の玄関先でヤンキー座りをして泣きだしてしまった。
その光景を目の当たりにして、店主も気の毒に思ったのか、マサハル達に声をかけた。
「あのー、お客さん。お連れさんかなりお疲れみたいですし、少し店ん中で休んでいかれます?」
「ああ、ありがとう……だが、私今持ち合わせがなくてね……」
「なーに、まだ開店前ですし、気楽に休んでって下さい…………。
というか、おっさん……もしかして……マサさん?」
「えっ? 確かに私はマサハルですけど……」
「ああっ、やっぱりそうか! この、人ん家の玄関先で女泣かせる犬畜生なヒモ男の感じ……そうじゃないかと思ったんだ! 覚えてません? 三十年位前だと俺まだ高校生だったんですけど、よく店手伝ってたんで……テツヤですよ!」
「テツヤ? んー……テツヤ、テツヤ。あー、小岩高校野球部の! あのテッちゃん?」
「そうそう! いやー、懐かしいな。おっさん、いっつもコハルさんの財布からお金くすねて、うちに飲みに来て、いっつもそこの玄関先でケンカしてたもんなー…………。
で、今はそのすっ飛んだ格好の娘のヒモやってるんだ!」
「いやいや、違う違う……誤解です。この子はそういうんじゃありません。ちょいとワケアリで、この子のボディーガードといったところなんですが……ああ、とにかく知ってる人に出会えてよかった……そんじゃ、テッちゃん。お言葉に甘えさせていただいて、少し休ませて下さいね」
テツヤが、おごりだといって二人分のジョッキと刺身の盛り合わせを出してくれた。
「これはなんにゃ? 魚みたいだけど……生なのにゃん?」マホミンが不思議そうにお造りを眺めている。うーん。確かにあっちの世界のやつら、刺身とか食ってるの見たことないなー。川魚しかいないからかな……などと考えながら、マサハルはジョッキをグイっとあけた。
「ほわーーーーーっ」三十余年ぶりの生ビールが臓腑に染みわたっていくのが分かった。
「ああ、ア……マホミンさん。これはこの皿にとった黒いやつを一寸つけてですね……ああ、あなたはその緑色のは無理だと思いますんで、そのままそのまま……そうそう」
マサハルに教えられながら、マホミンは生まれて初めてマグロの刺身を食べた。
「んんんんっ! なんにゃこれはー! これが魚にゃのか……こんなおいしいの食べたことないにゃ!」そういいながらマホミンは飛び上がる様に立ち上がった。
「ははは、そんなに喜んでもらえると、おごり甲斐があるなー。マホさんだっけ? そんじゃこれ、カレイの煮付けね! あっ、ビールもセルフでどんどん注いで飲んでね」
マホミンの大袈裟な反応がうれしかったのか、テツヤも上機嫌で次々料理を出してくれ
昨日の夜から牛丼一杯しか食べていなかった体が、急速に満たされていくのが分かった。
夕方を過ぎ、店にもお客が入り出したが、テツヤが遠慮しなくていいと言ってくれた。
そのうちバイトの店員さんも来て、手が空いたのかテツヤもマサハル達のテーブルに来て、一緒に飲み始めた。
「そんでね、このおやじ。ほんっとうに最低なの……コハルさんってのは、当時、小岩駅前のピンサロのNo1だったんだけど、こう、おしとやかできれいで上品で……高校生の俺でも惚れちゃいそうな感じの人でさ。それをこの男がさんざん泣かせるのよ……そんで俺は思ったね。絶対こんな大人にはならねえってさ! はははははは……マホさんもこのオヤジにはだまされないようにね……いや、もうだまされちゃったのかな?」
「だーいじょうーぶにゃー。あたいは、かしこいからー」
そう言うマホミンはすでにかなり出来上がっているように見える。
「テッちゃん、しゃべりすぎですよ。マホさんはそんな関係じゃないんだって……それでね、テッちゃん。酔ったついでで恐縮ながら相談があります。どっか二人で暮らせるようなところないですかね。いやいや、もちろん労働付きで結構なんですが……」
「……なんだー。やっぱ、昭和枯れススキなんだ……。三十年前に、突然行方不明になっちゃって、コハルさんもオヤジもそれなりに心配してたんだけどなー。
コハルさんは、その後、西の方へ行くって言ったきり見てないし……。
でも、マサさんは、お変わりなさそうで何より何より……。
そうだな……ああ、そうそう。小岩の連れ込み旅館の女将が、住み込みでもいいから、誰か遣り手いないかって言ってたなー。行ってみるかい?
多分、細かい詮索はしてこないと思うよ」
「そりゃ願ってもない……頼むよ。落ち着いたら礼は必ずするから」
「いやそれは、あんまり期待しないけど……この子、見た目はかなり変だけど、いい子みたいじゃないか。あんまり苦労させるなよ、おっさん」
もうほとんど寝落ちしかかっているマホミンの顔を見ながら、テツヤはその女将にその場で連絡を入れてくれ、マサハルはテツヤに何回も礼を述べながら店を出て、マホミンを抱えて小岩駅行のバスに乗り込んだ。
手持ちの漱石の千円札は、テツヤに無理言って、野口英世のに替えてもらった。
旅館の女将は、マサハルとそれほど年齢の差はなさそうだったが、他に飲み屋などを何軒も経営している実業家で、この連れ込み旅館は、手放すほどではないが、さほど収益も上がっていないので、手をかけず経営ごと丸投げしたい意向らしい。
ゼネラルマネージャーと言えば聞こえはいいが、要は、店番だけではなく、掃除、洗濯から仕入れ、帳簿まで全部やれという事だ。
一応地元の老舗、神田川の主人の紹介ということで、あまり深く詮索はされず、一ヵ月の試用ということになった。
とにかく、今は屋根付きの部屋と仕事が確保出来ただけでオンの字だ。
業績が悪くて一ヵ月後にクビになったとしても、それまでにいろいろやれるだろう。
旅館の帳場の奥に従業員用の六畳間があり、そこで寝起きしろとのことだったので、とりあえず今日のところはそこで寝ることにした。
「マサハルー……この布団、薄いし、すごくカビ臭いにゃ……」
「もう……文句言わないで下さい。明日、晴れてたら干しましょう。さすがに今日野宿してたら二人ともおしまいでしたので、それを思えばこのくらいは……」
「……寒い……くっついていい?」
「はい? あ、でも私……あっちに妻子いますし……」
「勘違いするにゃ! エッチはしないにゃ! 本当に寒いんにゃ!」
「あー、はは。猫ですもんねー」
「うるさい! バカハル……」
マホミンは、マサハルに背中をくっつけたかと思ったら、スースーと寝息をたて始めた。
「やっぱり、お疲れですよね…………でもそうか……やはりコハルは行方知れずですか」
もちろん、同じ所にコハルがいること自体、あり得ない話だと最初から分かっていたが……ちょっとがっかりしながら、マサハルも疲れがどっと出たのか、直ぐに深い眠りに
落ちた。