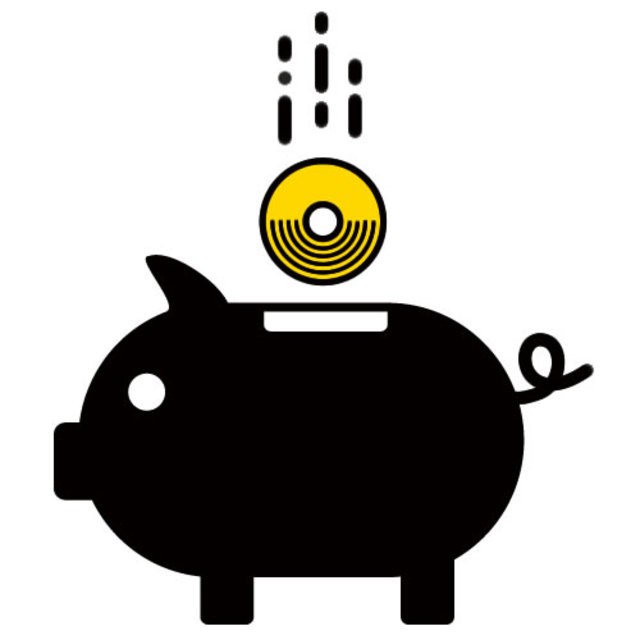魔術師 ガーゼル
文字数 7,229文字
激しい雨が大地を打っていた。川の流れは力強く、すべてのものを流そうとしてる。その濁流に下半身をさらして、少年が一人、岩の隙間にひっかかっていた。
ガーゼルは雨具代わりのフードを少し上げ、少年の方を見た。死んでいるのか、それとも気を失っているのか、少年はぴくりとも動かない。
足を一歩踏みだしかけてやめる。少年のところまでは少し距離があった。激流に阻まれそばまでいくのは困難だ。少年が流れていかないのが奇跡だった。
「こんな雨の日に見てしまったのも、何かの縁ですかね」
風が吹きフードが飛ばされ、二十代後半の青年の顔が現れた。後ろにまとめた長髪が風に揺れる。開いてるのかどうか判らない細い目を、ガーゼルはますます細めた。
「久々ですから、失敗してもうらまないでくださいよ」
聞こえるはずのない少年に向かってガーゼルは呟いた。
【我思う。汝は強き風なりや。全てを包み、決して離さず】
ガーゼルの口から特殊な発声による言葉が紡がれる。それに合わせたように少年の体が宙に浮いた。それはふらつきながらもガーゼルの足元へと降り立った。
ガーゼルがしゃがみこんで脈を調べた。脈はあった。息もなんとかしている。だが、体がすっかりと冷えていた。フードを被り直し、少年をかかえて歩き出す。
「…………」
うわごとで少年が呟いた。ガーゼルは立ち止まって耳を傾ける。少年に気がついた様子はなかった。再び口が開き誰かの名を呼んだ。
「エスティ、ですか……」
ガーゼルは空を見上げた。壁は遥か上まで続き、その先に雨雲が渦巻いていた。
★
始めは何も見えない暗闇だった。その中に光が灯った。その光は近づいて来ると、手足が生まれ人の形になった。発光している中に見覚えのある顔が浮かんだ。
「エスティ」
ルキフォは一歩光に近づいた。エスティの顔に両手を伸ばす。しかし、包み込もうとしたルキフォの手に、エスティの柔らかな頬の感触はなかった。触れることができないのだ。
呆然としているルキフォを、エスティは悲しそうに見つめた。その瞳には涙が浮かんでいる。そして、何かを伝えようと口を開いた。
「エスティ、聞こえないよ」
ルキフォにはエスティの声を聞き取ることができない。エスティの口に耳を寄せ、懸命に聞き取ろうとする。それでもルキフォには聞き取ることができなかった。
エスティを正面に見据え、その細い肩に触れようとした。それを阻むように、突如エスティの体は紅蓮の炎に包まれた。ルキフォの手が炎に焼かれ焦げていく。エスティは驚きの表情でルキフォを見つめた。
エスティを包む炎がさらに広がり、一つになって大きな顔を生み出した。燃え盛る赤髪の青年が、ルキフォの前に立ちふさがる。その顔は嗤っていた。炎が揺れて、嗤いも歪んだものとなる。
ルキフォの体から光が伸びた。光は炎を貫き、虚空に消えていく。貫かれた炎は、何事もなかったかのように燃え続けた。ルキフォは尽きることなく光の矢を撃ち続けた。そのたびに炎は削れ、そして元に戻っていく。
ルキフォの光がやんだ。
これ以上撃ってこないと判ると、炎は嘲笑うかのようにひときわ大きく燃えた。そして、エスティを包み込むと、闇の彼方へと去っていった。
「エスティ!」
連れ去られる光に向かって、ルキフォは叫んだ。
「きっと、助けに行くっ。今度こそ君を守るから!」
炎に抱かれたエスティが、その言葉に頷いた。闇の中、ルキフォとエスティは見えなくなるまで互いをずっと見つめていた。
ルキフォの視界が炎で埋め尽くされる。いつの間にかルキフォの全身は炎に焦がされていた。体中の水分が蒸発し、皮膚が爛れていく。肉が焦げ、骨を焼き、ルキフォの手足は体を離れていった。熱くはなかった。ただ、自分の体が崩れていく感覚だけが、ルキフォの精神を支配した。
そしてルキフォは──絶叫した。
「はあ、はあ……夢か」
気づくとルキフォはベッドにいた。上半身を起こし肩で息をしている。体中が汗ばんでいた。自分の両手を顔の前に出し、ちゃんとあることを確かめる。
「大丈夫ですか?」
男の声が、ルキフォの耳に飛び込んできた。部屋の扉から見慣れない青年が顔を覗かせている。開いているのか判断しかねる細い目で、じっとを見ていた。
「あの、ここは?」
ルキフォが訊いた。
「ああ。私の家です。谷底の川でひっかかっていたのを、私が見つけたんですよ」
青年が部屋に入ってきた。
「私はガーゼルといいます」
「あ、ルキフォです」
「では、ルキフォ君でいいかな? えっと、しばらくここで休むといいですよ」
「いえ。すぐにでも行かなと……」
ベッドを降りようとするルキフォをガーゼルが止めた。
「長い間流されていたのと雨に打たれていたせいで、君はずいぶんと体力を消耗してます。火霊宮に行くんでしたら、今のままじゃ絶対に無理ですよ。途中で倒れてしまいます」
「火霊宮?」
ルキフォが不思議そうに言った。
「あれ、精火門の人じゃなかったんですか? エスティって名前をうわごとで呟いてたんで、私はてっきり……。エスティって確か精火門門下、グレン・ネレードの妹さんでしたよね?」
「エステイを知っているんですか?」
ルキフォの今にも飛びかかりそうな勢いに、ガーゼルは一歩あとずさった。
「落ち着いてください。知ってるて言っても、名前ぐらいですよ。これでも元素術の人とは縁があるんで」
「すみません……」
ルキフォは素直に謝った。
「何か色々とあるみたいですね。そう言えばネレード家のお屋敷が半月ぐらい前に襲われたって噂でしたけど、それと関係あるんでしょうか?」
「え? ああ、えっと……」
「話したくないのなら、無理に話さなくて結構ですよ。それより、ルキフォ君は休まないといけないんですから」
「ガーゼルさん」
部屋を出ていこうとしたガーゼルを、ルキフォが止めた。
「元素術に詳しいんですか?」
「元素術の術法についてはそれほどでもないですけど、内情について、うわさ話程度なら」
「お願いです。精火門について俺に教えてください。エスティを助けたいんです。俺も、知っていることはすべて話しますから」
黙ったまま立っているガーゼルを、ルキフォは真剣な表情で見つめた。
「わけありですか……。判りました。協力できることは協力しますよ」
「ありがとうございます」
ルキフォはガーゼルに深々と頭を下げた。
「では、食事でもしながら話しを聞きましょう。今、ちょうどできたとこですから」
そう言い残すと、ガーゼルは部屋を出て行った。
★
大きなテーブルのある部屋で食事を終え、ルキフォは今までのことを包み隠さずガーゼルに話した。今のルキフォはエスティに関する情報が手に入るのなら、どんなことでもするつもりだった。
「あの谷の上から落ちて、よく大きな怪我もなく生きてましたね」
ガーゼルは感心と呆れとが半々に混じった口調で言った。
「何をしたのか、自分でもよく覚えていないんです」
ルキフォは自信なげに言った。リュードに落とされてるとこまでは覚えているのだが、その後のことは記憶になかった。
「ゴルド殿の弟子、ですか。懐かしいなぁ。療術だけでなく、ちゃんと〝魔法〟の方も伝承されてるんですね」
「師匠を知ってるんですか?」
ガーゼルの口振りに驚き、ルキフォは意外といった表情で尋ねた。〝魔法〟もそうだが、ゴルドのことを知ってるというのは、ルキフォにとって驚き以外のなにものでもない。
「ええ。昔……そうですね、ルキフォ君くらいの頃に何度かお会いしたことがあります。もうそんなになりますか。あのゴルド殿のお弟子さんですか」
少し遠い目をしながら、ガーゼルは微笑んだ。そして思いついたようにルキフォに焦点を合わせる。
「君の〝魔法〟見せてもらっていいですか?」
「え? はい」
あまりに自然なガーゼルの物言いにルキフォは思わず〝魔法〟を顕現させる。
一瞬の光と共に、銀色の毛並みの猫に似た小動物がルキフォの前に現れる。〝魔法〟は少しよたつきながらもガーゼルを見た。
ガーゼルは何の迷いもなくルキフォの〝魔法〟を両手で抱き寄せた。〝魔法〟もおとなしく従う。
「猫……いえ、虎ですか? いい〝魔法〟です。ルキフォ君が助かったのはこの子のおかげでしょう」
ガーゼルは自分の膝の上に置いて〝魔法〟の顎を撫でた。〝魔法〟は目を細め、気持ち押さそうに喉を鳴らず。
「え?」
「〝魔法〟そのものの魔力がかなり減っています。気を失った君を支える為に術者からの供給なしで魔力を使ったのでしょう」
ガーゼルの言葉に〝魔法〟が我が意を得たりとばかりに鳴いた。
「元にしたのはゴルド殿と同じく、セルゲの光の書ですか……おや、別の系統も混じってますね? 影? いや闇……ですか?」
〝魔法〟の金色と黒の瞳を覗き込んで、ガーゼルが言う。
「あ、はい。師匠にはまだ早いって怒られました」
「この子が最初の〝魔法〟なら、そうでしょうね。普通は一つの系統を元に〝魔法〟を育てますから。系統が増えるとそれだけで〝魔法〟が必要とする魔力も上がります。それにいきなり複数系統は危険ですしね。ゴルド殿はあれで、なかなか真面目ですから」
「そうなんです」
ルキフォが苦笑いをする。そしてすぐにハッとした表情になる。あまりに自然にガーゼルが話すものだから気にしなかったが、目の前の男は〝魔法〟に詳しすぎる。知識だけではなく、実践しないとここまで話せないだろう。
「ガーゼルさん、もしかして〝魔法〟使いなんですか?」
驚きと期待を込めて、ルキフォは訊いた。ゴルドと自分以外に〝魔法〟を扱う魔術師をルキフォはまだ見たことがない。居ることすらも分からなかった。
同じ魔術の系譜である魔導具師や療術師に比べて絶対数が少ないのだ。
「あ……ええ、まぁ」ガーゼルは決まり悪そうに言う。「元〝魔法〟使いですかね」
「元?」
「ええ、昔にね、ちょっと無茶が祟りまして、現在は封印中です」
「封印、ですか?」
ルキフォは不思議そう訊いた。〝魔法〟は術者の身に宿り、術者と意識レベルで繋がった存在だ。その存在を封印するということは、己の魔力を封印するに等しい。
「まあ、人には色々あるということですよ。それより、ルキフォ君の〝魔法〟は名付けをしてあるのですか?」
はぐらかすように、ガーゼルは話題を変えた。不思議に思ったが、ルキフォも特に追求しない。
「いえ、まだ《魔名》は貰っていません。師匠は、半人前が組んでよい〝魔法〟ではないって言われて……」
「私は嫌いじゃないですけどね、こういう型破りな組み方は。相反する系統ですが、光を操ることで闇へ転化もできますから相性は決して悪くない」
ガーゼルの言葉にルキフォは驚いた表情を浮かべる。自分の〝魔法〟の特性を見ただけで言い当てたのだ。
ルキフォもそして彼の〝魔法〟も、まだまだ半人前だ。ルキフォがいま自在に操れるのは光の系統のみ。〝魔法〟に組み込んである闇の系統はあくまで補助であり、バッシュとの戦いで見せた術法は光の系統を応用し闇の系統へと転化したものだ。
「ガーゼルさん、すごいです。術も見ないで俺の〝魔法〟の特性が分かるなんて」
「まぁ、年の功ですかね」どこか照れたようにガーゼルが言う。「あとは一つの系統に絞って複数の〝魔法〟を使うなんてのも面白いですよね」
そう言ったガーゼルの表情は何かを懐かしんでいるようにルキフォには見えた。
「そう言えば居ましたね。魔術が衰退を始め、〝魔法〟が作り出された最初のころに。八つの〝魔法〟を操った〝大魔法〟使いが。確か〝魔法〟一つにつき一系統しか組み込まなかったって」
〝魔法〟は存在するだけで魔力を必要とする。そして通常、必要な魔力は〝魔法〟を所有する魔術師から供給される。〝魔法〟が扱える系統を増やせば、その分〝魔法〟が必要とする魔力は増えていく。それは〝魔法〟の成長であり、所有する魔術師の成長の証でもあった。
しかし、系統の違う複数の〝魔法〟を持つことは、一つの〝魔法〟が複数の系統を持つこととは意味が異なる。複数系統を組み込むことよる必要魔力の増加よりも、〝魔法〟一体が存在するのに必要となる魔力の方が遙かに大きい。
そればかりか複数の〝魔法〟を受け入れられるだけの精神的な器の大きさも必要になるのだ。
「よく知ってますね。魔術師イグァシティェイルですね」
ガーゼルは嬉しそうに言った。
「そう、そのイグァシティ……痛っ」
その名前を繰り返そうとして、ルキフォは舌を噛んだ。
「昔の名前ですからねぇ。今の人には発音が難しいんでしょうね」
苦笑してガーゼルが言う。
「史実に現れた〝魔法〟使いはその人で最後でしたよね?」
舌の痛みに顔をしかめながらルキフォが言う。
「ええ。今では魔術そのものが学問になってしまいましたからね。魔術書に記された呪文を扱えるほどの魔力の持ち主は、なかなか現れなくなってしまいました。今、魔力を持った人間といえば、魔導機械を使って道具を造る魔導具師ぐらいでしょうね。
あ、もちろんルキフォ君やゴルド殿のようにひっそりと魔術の系譜を受け継ぐひとたちはいるでしょうが」
「ガーゼルさんも、そうですよね?」
「私のはまぁ、趣味みたいなものです。今は魔導具を作って生計をたててますし」
「魔導具も作っているんですか?」
「君たちと同じです。私は療術が得意ではないので、代わりに魔導具になります。本当は魔術書だけ読んで暮らして行きたいんですけどね」
照れ臭そうにガーゼルは言った。
「なら、俺を見つけたのは、魔導具を街に売りに行った帰りだったんですか」
「いえ。あれは散歩をしてたんです」
一瞬、ルキフォの動きが止まった。
「散歩って、雨が降ってたんでしょ?」
「ええ。晴れた日の散歩もいいですけど、雨の日の散歩もいいものですよ。嵐なんかが来るとわくわくしてきませんか?」
「はあ」
どう答えていいのか、ルキフォは迷った。
「えっと、そうそうルキフォ君は訊きたいことがあったんですよね」
気まずい沈黙にガーゼルは再び強引に話題を変えた。
ルキフォは最初の目的を思い出して、それに飛びつく。
「エスティがどこに連れ去られたのか、その場所が知りたいんです」
ルキフォの言葉にガーゼルは苦笑した。
「そればっかりは、調べないと判りませんよ。そうですね……ルキフォ君の話しを聞く限りだと火霊宮あたりが可能性が高いですかね」
「だったら、その火霊宮のある場所を教えてください」
「まあ、そうあせらないで」
場所を教えたら、今にでも飛び出して行きそうなルキフォを、ガーゼルはなだめる。
「調べて見ないと確実なことは言えませんよ。精火門は他の門派と違って、街の中に霊宮を構えていないんです。もともと精火門の人間は、街から離れて住んでいる場合が多い。だから、火霊宮にいないからって、すぐに心の当たりのある他の場所に行くなんてことはできないんですよ」
それを聞いてルキフォは落ち込んだようだった。
「まあ、二、三日もあれば調べてあげれると思いますよ。だからそれまで、しっかりと休んでおいてください。そのエスティって娘さんを助けるのに、ひと悶着ありそうですからね。体調は整えておかないといけませんよ」
ルキフォはしぶしぶ頷いた。
「でも、調べるってどうするんですか? 他の門派もエスティを狙ってるのに、そう簡単に居場所が判るとは思えないんですけど」
ガーゼルはルキフォの問に笑って、
「それは、私にも色々と伝 がありましてね。言ったでしょ? 元素術には縁があるって。なにを隠そう、私の魔導具の一番のお得意様は、精火門の方たちですから」
そう言って、ガーゼルは片方の頬を上げた。本人は片目をつむったつもりらしい。だが、開いているのかどか分からない細い目では判断がつかない。
「さて、私はこれから街にでも行って、情報を集めてきます。夜までには帰りますから、ルキフォ君はおとなしくしていてください。暇なら書斎にある本を読んでもいいですよ。魔術書しかないですけどね」
そう言って、ガーゼルはルキフォが寝かされていた部屋の隣の扉を指した。
「読んだら元のところに戻しておいて下さい。それでは、くれぐれも先走らないように」
ガーゼルは〝魔法〟をルキフォに手渡すと、外出の準備をするために自室へと向かった。
「ガーゼルさん」
呼び止めたルキフォの声に、ガーゼルが振り返る。
「なんで、見ず知らずの俺に協力してくれるんですか?」
「ゴルド殿の弟子なら、まったくの見ず知らずってわけでもないですし、それに……」
ばつが悪そうに、ガーゼルは頭を掻いた。
「こういうこと言うとルキフォ君は怒るかも知れませんが、その、おもしろいじゃないですか。わくわくしてきませんか? 少女を助けるために頑張る少年。青春ですよね」
無邪気にそう言われ、怒るのを通りこしてルキフォは呆れてしまった。目が開いているのかどうか判らないぐらい細いせいで、何もしなくてもどことなく笑顔に見える。それに輪をかけて無邪気に言われると、後はもう笑うしかなかった。
「あ、それじゃ」
ルキフォがそれ以上何も言わないことで気まずいと思ったのか、ガーゼルはそそくさと自室へ入って行ってしまった。後には少し不安になったルキフォが残っていた。
エスティに会ってからこれまでの緊張が、一気に抜けていくのをルキフォは感じた。そのまま椅子からずり落ちそうになったのは、なにも疲労のせいだけではなかった。
嵐の中を歩くのが好きなのといい、ルキフォに協力するのをおもしろがっているのといい、何か人とは違う。決して悪い人間ではないのだろうが……。
だが、初めて会ったはずのガーゼルに妙な親近感を覚えているのも確かだった。
「ああそうか。なんとなく師匠と似てるんだ」
ゴルドの所を飛び出して以来初めて、ルキフォは師匠のことを懐かしんだ。
ガーゼルは雨具代わりのフードを少し上げ、少年の方を見た。死んでいるのか、それとも気を失っているのか、少年はぴくりとも動かない。
足を一歩踏みだしかけてやめる。少年のところまでは少し距離があった。激流に阻まれそばまでいくのは困難だ。少年が流れていかないのが奇跡だった。
「こんな雨の日に見てしまったのも、何かの縁ですかね」
風が吹きフードが飛ばされ、二十代後半の青年の顔が現れた。後ろにまとめた長髪が風に揺れる。開いてるのかどうか判らない細い目を、ガーゼルはますます細めた。
「久々ですから、失敗してもうらまないでくださいよ」
聞こえるはずのない少年に向かってガーゼルは呟いた。
【我思う。汝は強き風なりや。全てを包み、決して離さず】
ガーゼルの口から特殊な発声による言葉が紡がれる。それに合わせたように少年の体が宙に浮いた。それはふらつきながらもガーゼルの足元へと降り立った。
ガーゼルがしゃがみこんで脈を調べた。脈はあった。息もなんとかしている。だが、体がすっかりと冷えていた。フードを被り直し、少年をかかえて歩き出す。
「…………」
うわごとで少年が呟いた。ガーゼルは立ち止まって耳を傾ける。少年に気がついた様子はなかった。再び口が開き誰かの名を呼んだ。
「エスティ、ですか……」
ガーゼルは空を見上げた。壁は遥か上まで続き、その先に雨雲が渦巻いていた。
★
始めは何も見えない暗闇だった。その中に光が灯った。その光は近づいて来ると、手足が生まれ人の形になった。発光している中に見覚えのある顔が浮かんだ。
「エスティ」
ルキフォは一歩光に近づいた。エスティの顔に両手を伸ばす。しかし、包み込もうとしたルキフォの手に、エスティの柔らかな頬の感触はなかった。触れることができないのだ。
呆然としているルキフォを、エスティは悲しそうに見つめた。その瞳には涙が浮かんでいる。そして、何かを伝えようと口を開いた。
「エスティ、聞こえないよ」
ルキフォにはエスティの声を聞き取ることができない。エスティの口に耳を寄せ、懸命に聞き取ろうとする。それでもルキフォには聞き取ることができなかった。
エスティを正面に見据え、その細い肩に触れようとした。それを阻むように、突如エスティの体は紅蓮の炎に包まれた。ルキフォの手が炎に焼かれ焦げていく。エスティは驚きの表情でルキフォを見つめた。
エスティを包む炎がさらに広がり、一つになって大きな顔を生み出した。燃え盛る赤髪の青年が、ルキフォの前に立ちふさがる。その顔は嗤っていた。炎が揺れて、嗤いも歪んだものとなる。
ルキフォの体から光が伸びた。光は炎を貫き、虚空に消えていく。貫かれた炎は、何事もなかったかのように燃え続けた。ルキフォは尽きることなく光の矢を撃ち続けた。そのたびに炎は削れ、そして元に戻っていく。
ルキフォの光がやんだ。
これ以上撃ってこないと判ると、炎は嘲笑うかのようにひときわ大きく燃えた。そして、エスティを包み込むと、闇の彼方へと去っていった。
「エスティ!」
連れ去られる光に向かって、ルキフォは叫んだ。
「きっと、助けに行くっ。今度こそ君を守るから!」
炎に抱かれたエスティが、その言葉に頷いた。闇の中、ルキフォとエスティは見えなくなるまで互いをずっと見つめていた。
ルキフォの視界が炎で埋め尽くされる。いつの間にかルキフォの全身は炎に焦がされていた。体中の水分が蒸発し、皮膚が爛れていく。肉が焦げ、骨を焼き、ルキフォの手足は体を離れていった。熱くはなかった。ただ、自分の体が崩れていく感覚だけが、ルキフォの精神を支配した。
そしてルキフォは──絶叫した。
「はあ、はあ……夢か」
気づくとルキフォはベッドにいた。上半身を起こし肩で息をしている。体中が汗ばんでいた。自分の両手を顔の前に出し、ちゃんとあることを確かめる。
「大丈夫ですか?」
男の声が、ルキフォの耳に飛び込んできた。部屋の扉から見慣れない青年が顔を覗かせている。開いているのか判断しかねる細い目で、じっとを見ていた。
「あの、ここは?」
ルキフォが訊いた。
「ああ。私の家です。谷底の川でひっかかっていたのを、私が見つけたんですよ」
青年が部屋に入ってきた。
「私はガーゼルといいます」
「あ、ルキフォです」
「では、ルキフォ君でいいかな? えっと、しばらくここで休むといいですよ」
「いえ。すぐにでも行かなと……」
ベッドを降りようとするルキフォをガーゼルが止めた。
「長い間流されていたのと雨に打たれていたせいで、君はずいぶんと体力を消耗してます。火霊宮に行くんでしたら、今のままじゃ絶対に無理ですよ。途中で倒れてしまいます」
「火霊宮?」
ルキフォが不思議そうに言った。
「あれ、精火門の人じゃなかったんですか? エスティって名前をうわごとで呟いてたんで、私はてっきり……。エスティって確か精火門門下、グレン・ネレードの妹さんでしたよね?」
「エステイを知っているんですか?」
ルキフォの今にも飛びかかりそうな勢いに、ガーゼルは一歩あとずさった。
「落ち着いてください。知ってるて言っても、名前ぐらいですよ。これでも元素術の人とは縁があるんで」
「すみません……」
ルキフォは素直に謝った。
「何か色々とあるみたいですね。そう言えばネレード家のお屋敷が半月ぐらい前に襲われたって噂でしたけど、それと関係あるんでしょうか?」
「え? ああ、えっと……」
「話したくないのなら、無理に話さなくて結構ですよ。それより、ルキフォ君は休まないといけないんですから」
「ガーゼルさん」
部屋を出ていこうとしたガーゼルを、ルキフォが止めた。
「元素術に詳しいんですか?」
「元素術の術法についてはそれほどでもないですけど、内情について、うわさ話程度なら」
「お願いです。精火門について俺に教えてください。エスティを助けたいんです。俺も、知っていることはすべて話しますから」
黙ったまま立っているガーゼルを、ルキフォは真剣な表情で見つめた。
「わけありですか……。判りました。協力できることは協力しますよ」
「ありがとうございます」
ルキフォはガーゼルに深々と頭を下げた。
「では、食事でもしながら話しを聞きましょう。今、ちょうどできたとこですから」
そう言い残すと、ガーゼルは部屋を出て行った。
★
大きなテーブルのある部屋で食事を終え、ルキフォは今までのことを包み隠さずガーゼルに話した。今のルキフォはエスティに関する情報が手に入るのなら、どんなことでもするつもりだった。
「あの谷の上から落ちて、よく大きな怪我もなく生きてましたね」
ガーゼルは感心と呆れとが半々に混じった口調で言った。
「何をしたのか、自分でもよく覚えていないんです」
ルキフォは自信なげに言った。リュードに落とされてるとこまでは覚えているのだが、その後のことは記憶になかった。
「ゴルド殿の弟子、ですか。懐かしいなぁ。療術だけでなく、ちゃんと〝魔法〟の方も伝承されてるんですね」
「師匠を知ってるんですか?」
ガーゼルの口振りに驚き、ルキフォは意外といった表情で尋ねた。〝魔法〟もそうだが、ゴルドのことを知ってるというのは、ルキフォにとって驚き以外のなにものでもない。
「ええ。昔……そうですね、ルキフォ君くらいの頃に何度かお会いしたことがあります。もうそんなになりますか。あのゴルド殿のお弟子さんですか」
少し遠い目をしながら、ガーゼルは微笑んだ。そして思いついたようにルキフォに焦点を合わせる。
「君の〝魔法〟見せてもらっていいですか?」
「え? はい」
あまりに自然なガーゼルの物言いにルキフォは思わず〝魔法〟を顕現させる。
一瞬の光と共に、銀色の毛並みの猫に似た小動物がルキフォの前に現れる。〝魔法〟は少しよたつきながらもガーゼルを見た。
ガーゼルは何の迷いもなくルキフォの〝魔法〟を両手で抱き寄せた。〝魔法〟もおとなしく従う。
「猫……いえ、虎ですか? いい〝魔法〟です。ルキフォ君が助かったのはこの子のおかげでしょう」
ガーゼルは自分の膝の上に置いて〝魔法〟の顎を撫でた。〝魔法〟は目を細め、気持ち押さそうに喉を鳴らず。
「え?」
「〝魔法〟そのものの魔力がかなり減っています。気を失った君を支える為に術者からの供給なしで魔力を使ったのでしょう」
ガーゼルの言葉に〝魔法〟が我が意を得たりとばかりに鳴いた。
「元にしたのはゴルド殿と同じく、セルゲの光の書ですか……おや、別の系統も混じってますね? 影? いや闇……ですか?」
〝魔法〟の金色と黒の瞳を覗き込んで、ガーゼルが言う。
「あ、はい。師匠にはまだ早いって怒られました」
「この子が最初の〝魔法〟なら、そうでしょうね。普通は一つの系統を元に〝魔法〟を育てますから。系統が増えるとそれだけで〝魔法〟が必要とする魔力も上がります。それにいきなり複数系統は危険ですしね。ゴルド殿はあれで、なかなか真面目ですから」
「そうなんです」
ルキフォが苦笑いをする。そしてすぐにハッとした表情になる。あまりに自然にガーゼルが話すものだから気にしなかったが、目の前の男は〝魔法〟に詳しすぎる。知識だけではなく、実践しないとここまで話せないだろう。
「ガーゼルさん、もしかして〝魔法〟使いなんですか?」
驚きと期待を込めて、ルキフォは訊いた。ゴルドと自分以外に〝魔法〟を扱う魔術師をルキフォはまだ見たことがない。居ることすらも分からなかった。
同じ魔術の系譜である魔導具師や療術師に比べて絶対数が少ないのだ。
「あ……ええ、まぁ」ガーゼルは決まり悪そうに言う。「元〝魔法〟使いですかね」
「元?」
「ええ、昔にね、ちょっと無茶が祟りまして、現在は封印中です」
「封印、ですか?」
ルキフォは不思議そう訊いた。〝魔法〟は術者の身に宿り、術者と意識レベルで繋がった存在だ。その存在を封印するということは、己の魔力を封印するに等しい。
「まあ、人には色々あるということですよ。それより、ルキフォ君の〝魔法〟は名付けをしてあるのですか?」
はぐらかすように、ガーゼルは話題を変えた。不思議に思ったが、ルキフォも特に追求しない。
「いえ、まだ《魔名》は貰っていません。師匠は、半人前が組んでよい〝魔法〟ではないって言われて……」
「私は嫌いじゃないですけどね、こういう型破りな組み方は。相反する系統ですが、光を操ることで闇へ転化もできますから相性は決して悪くない」
ガーゼルの言葉にルキフォは驚いた表情を浮かべる。自分の〝魔法〟の特性を見ただけで言い当てたのだ。
ルキフォもそして彼の〝魔法〟も、まだまだ半人前だ。ルキフォがいま自在に操れるのは光の系統のみ。〝魔法〟に組み込んである闇の系統はあくまで補助であり、バッシュとの戦いで見せた術法は光の系統を応用し闇の系統へと転化したものだ。
「ガーゼルさん、すごいです。術も見ないで俺の〝魔法〟の特性が分かるなんて」
「まぁ、年の功ですかね」どこか照れたようにガーゼルが言う。「あとは一つの系統に絞って複数の〝魔法〟を使うなんてのも面白いですよね」
そう言ったガーゼルの表情は何かを懐かしんでいるようにルキフォには見えた。
「そう言えば居ましたね。魔術が衰退を始め、〝魔法〟が作り出された最初のころに。八つの〝魔法〟を操った〝大魔法〟使いが。確か〝魔法〟一つにつき一系統しか組み込まなかったって」
〝魔法〟は存在するだけで魔力を必要とする。そして通常、必要な魔力は〝魔法〟を所有する魔術師から供給される。〝魔法〟が扱える系統を増やせば、その分〝魔法〟が必要とする魔力は増えていく。それは〝魔法〟の成長であり、所有する魔術師の成長の証でもあった。
しかし、系統の違う複数の〝魔法〟を持つことは、一つの〝魔法〟が複数の系統を持つこととは意味が異なる。複数系統を組み込むことよる必要魔力の増加よりも、〝魔法〟一体が存在するのに必要となる魔力の方が遙かに大きい。
そればかりか複数の〝魔法〟を受け入れられるだけの精神的な器の大きさも必要になるのだ。
「よく知ってますね。魔術師イグァシティェイルですね」
ガーゼルは嬉しそうに言った。
「そう、そのイグァシティ……痛っ」
その名前を繰り返そうとして、ルキフォは舌を噛んだ。
「昔の名前ですからねぇ。今の人には発音が難しいんでしょうね」
苦笑してガーゼルが言う。
「史実に現れた〝魔法〟使いはその人で最後でしたよね?」
舌の痛みに顔をしかめながらルキフォが言う。
「ええ。今では魔術そのものが学問になってしまいましたからね。魔術書に記された呪文を扱えるほどの魔力の持ち主は、なかなか現れなくなってしまいました。今、魔力を持った人間といえば、魔導機械を使って道具を造る魔導具師ぐらいでしょうね。
あ、もちろんルキフォ君やゴルド殿のようにひっそりと魔術の系譜を受け継ぐひとたちはいるでしょうが」
「ガーゼルさんも、そうですよね?」
「私のはまぁ、趣味みたいなものです。今は魔導具を作って生計をたててますし」
「魔導具も作っているんですか?」
「君たちと同じです。私は療術が得意ではないので、代わりに魔導具になります。本当は魔術書だけ読んで暮らして行きたいんですけどね」
照れ臭そうにガーゼルは言った。
「なら、俺を見つけたのは、魔導具を街に売りに行った帰りだったんですか」
「いえ。あれは散歩をしてたんです」
一瞬、ルキフォの動きが止まった。
「散歩って、雨が降ってたんでしょ?」
「ええ。晴れた日の散歩もいいですけど、雨の日の散歩もいいものですよ。嵐なんかが来るとわくわくしてきませんか?」
「はあ」
どう答えていいのか、ルキフォは迷った。
「えっと、そうそうルキフォ君は訊きたいことがあったんですよね」
気まずい沈黙にガーゼルは再び強引に話題を変えた。
ルキフォは最初の目的を思い出して、それに飛びつく。
「エスティがどこに連れ去られたのか、その場所が知りたいんです」
ルキフォの言葉にガーゼルは苦笑した。
「そればっかりは、調べないと判りませんよ。そうですね……ルキフォ君の話しを聞く限りだと火霊宮あたりが可能性が高いですかね」
「だったら、その火霊宮のある場所を教えてください」
「まあ、そうあせらないで」
場所を教えたら、今にでも飛び出して行きそうなルキフォを、ガーゼルはなだめる。
「調べて見ないと確実なことは言えませんよ。精火門は他の門派と違って、街の中に霊宮を構えていないんです。もともと精火門の人間は、街から離れて住んでいる場合が多い。だから、火霊宮にいないからって、すぐに心の当たりのある他の場所に行くなんてことはできないんですよ」
それを聞いてルキフォは落ち込んだようだった。
「まあ、二、三日もあれば調べてあげれると思いますよ。だからそれまで、しっかりと休んでおいてください。そのエスティって娘さんを助けるのに、ひと悶着ありそうですからね。体調は整えておかないといけませんよ」
ルキフォはしぶしぶ頷いた。
「でも、調べるってどうするんですか? 他の門派もエスティを狙ってるのに、そう簡単に居場所が判るとは思えないんですけど」
ガーゼルはルキフォの問に笑って、
「それは、私にも色々と
そう言って、ガーゼルは片方の頬を上げた。本人は片目をつむったつもりらしい。だが、開いているのかどか分からない細い目では判断がつかない。
「さて、私はこれから街にでも行って、情報を集めてきます。夜までには帰りますから、ルキフォ君はおとなしくしていてください。暇なら書斎にある本を読んでもいいですよ。魔術書しかないですけどね」
そう言って、ガーゼルはルキフォが寝かされていた部屋の隣の扉を指した。
「読んだら元のところに戻しておいて下さい。それでは、くれぐれも先走らないように」
ガーゼルは〝魔法〟をルキフォに手渡すと、外出の準備をするために自室へと向かった。
「ガーゼルさん」
呼び止めたルキフォの声に、ガーゼルが振り返る。
「なんで、見ず知らずの俺に協力してくれるんですか?」
「ゴルド殿の弟子なら、まったくの見ず知らずってわけでもないですし、それに……」
ばつが悪そうに、ガーゼルは頭を掻いた。
「こういうこと言うとルキフォ君は怒るかも知れませんが、その、おもしろいじゃないですか。わくわくしてきませんか? 少女を助けるために頑張る少年。青春ですよね」
無邪気にそう言われ、怒るのを通りこしてルキフォは呆れてしまった。目が開いているのかどうか判らないぐらい細いせいで、何もしなくてもどことなく笑顔に見える。それに輪をかけて無邪気に言われると、後はもう笑うしかなかった。
「あ、それじゃ」
ルキフォがそれ以上何も言わないことで気まずいと思ったのか、ガーゼルはそそくさと自室へ入って行ってしまった。後には少し不安になったルキフォが残っていた。
エスティに会ってからこれまでの緊張が、一気に抜けていくのをルキフォは感じた。そのまま椅子からずり落ちそうになったのは、なにも疲労のせいだけではなかった。
嵐の中を歩くのが好きなのといい、ルキフォに協力するのをおもしろがっているのといい、何か人とは違う。決して悪い人間ではないのだろうが……。
だが、初めて会ったはずのガーゼルに妙な親近感を覚えているのも確かだった。
「ああそうか。なんとなく師匠と似てるんだ」
ゴルドの所を飛び出して以来初めて、ルキフォは師匠のことを懐かしんだ。