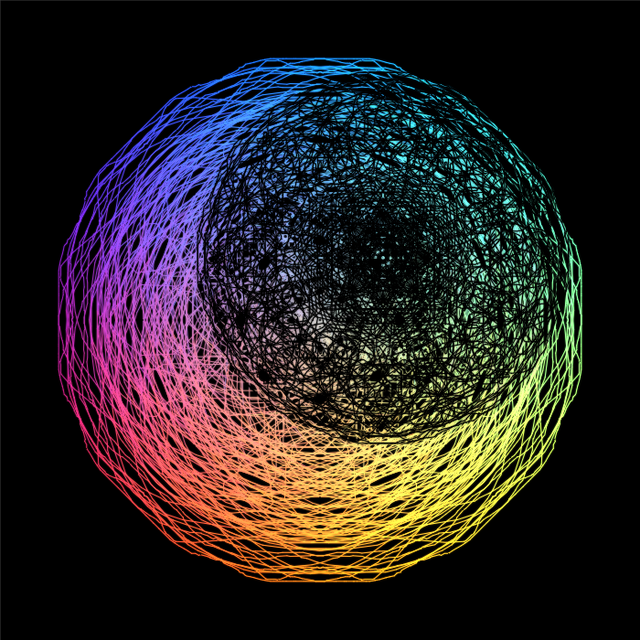Quiet Snow(百合、現代/約5000字)
文字数 4,911文字

文字数 :約5,000字
ジャンル :学園・青春
キーワード:百合/GL 恋愛 現代 高校生 受験 冬 雪
コメント :受験生百合です。主人公の母が毒親気味なので苦手な方はご注意ください。
◆◆◆◆◆◆
白が視界を閉ざす。
冷たさが身体に沁みいるようだ。
大の字になった私を覆ってしまおうと、雪花は後からあとから舞い落ちる。
奪われていく熱。
奪われていく気力。
奪われていく、わだかまり。
止まっていく。凍っていく。
ずっとこのまま――雪の中に閉じ込めてしまえたなら。
*
信号が変わると、人波が交差点にあふれ出す。
地方の町の駅前、チェーン店のドーナツ屋、そのカウンター席。私はフレンチクルーラーを行儀悪く指でつつきながらぼうっと外を眺めている。
町並みはくすんだ
色彩はいっとき入り交じったあと思い思いに歩み去り、車の列が流れる筆致でアスファルトを横切る。その滲んでは消える水彩に無表情が映っていた。
手つかずのドーナツは皿の上で心なしか萎びている。冷め切ったレモンティーで口を潤しても、食欲は湧いてこない。
『
八つ当たりで学校を飛び出してきたのも、その大元の原因も、悪いのは私なのに。
ごう、と大型トラックが駆け抜け、ガラスの外は金属質の灰色に染まる。
「メッセージ、送んないと。ゴメンって。そしたら……許してくれるんだろう、な」
溜め息が零れた。春花のそういう優しいのだか弱気なのだか分からないところが、たまに嫌いだ。理不尽にはもっと言い返せばいい。
スマホケースにじゃらじゃらぶら下げたキーホルダーの無秩序な可愛さに隠れて、小さなハートのチャームが揺れている。私は反発するように顔を上げて――瞬間、目の前を
「あ……」
それを合図に、街頭を舞う薄片は数を増していく。
肌を切る寒さをありありと想像させる、だからこそ綺麗な、無彩色。今シーズン初めての雪だった。
*
「ねえ、由紀。聞いてる?」
咎める口調の、厳しくなりきれない声で我に返った。
「ゴメン。ボーっとしちゃってた」
というより、窓の外を見ていた。静かに降り続ける雪を。付きっきりで数学を教えてくれていた春花は曖昧に笑って首を傾げる。
「ちょっと休憩しよっか。飲み物買ってくるよ、カフェオレでいいよね?」
疑問形だが答えは分かっているのだろう。くるりと外に向かう背に、ありがと、とだけ口にした。
市立図書館に併設された学習室には様々な制服の学生が隙間なく座っている。図書館とは違って教え合いやお菓子の持ち込みもOK。そんな好条件にも関わらずただの溜まり場にならないのは、ピリついた緊張感が漂っているからだ。
――共通テスト間近。冬の受験生はストレスを纏って生きている。
春花と喧嘩した、あの推薦の合格発表日から、十日少し経っていた。
よくある話だ。二人で同じ大学を目指し、受かったのは一人。推薦が駄目でも切り替えて一般で頑張れ、などと教師は言う。私だってそうしたかった。しかし春花の学力に合わせた地方都市の大学は私には高望みで、推薦に落ちたら一般は実力相応のところにする、そう親と約束していた。
「おまたせ!」
カフェオレとレモネードの紙カップを両手に、戻ってきた春香はちょこんと隣に座った。鼻の頭がほんのり赤らんでいる。自販機コーナーは半屋外にあり、外と変わらないほど寒い。
「さんきゅ」
百円玉を渡し、受け取ったカフェオレをすする。春花の財布についたハートのチャームが視界に入って、私は慌ててカップに目を伏せた。
春花にはまだ言っていなかった。一般入試で別の大学を受けるということを。
一足先に受験を終えた春花に、快く勉強を見てもらうため――では、ない。断じて。
「三角関数の文章題、かなり対応できてるね」
レモネードをはふはふ舐めている、そのカップを支える春花の華奢な右手。空いた反対の手が、机の下に垂れていた私の指をやわく握る。三本だけ絡められた指は縋るようだった。
「……春花の、おかげだよ」
私はきゅっと握り返してから、カフェオレを抱え込むふりをして、手を離した。
言えるはずがない。肩を並べて同じ大学に通うと、私の成績でも合格圏内に届くと、信じようとしている春花には。それすら受験者当人である私の不安を助長しないためなのだ。
ぎらつく夏の盛りには、二人でなら何だってできた。あでやかな秋には、ふとした瞬間に取り残される恐れを感じた。
今は冬。模試の結果に黒々としたDの字が印刷されている。
「次はどこやる? 三角関数をもうちょっとさらう?」
応えながら、私は春花でも過去問でもなく、まだ窓の外に魅かれていた。暖房の届かないモノクロームの世界。
例年にない豪雪は日ごとに深く町並みを
*
教室内の悲喜こもごもなさざめきを、窓に叩きつける雪がかき消している。
私はそのただ中で呼吸を忘れていた。両耳の奥、血管がばくばくと破裂しそうだ。
「B……」
一般入試前期、出願前の最後の模試返却。かすかに見えた光だった。
しかし希望など――所詮、風前の灯にすぎない。
吹雪に逆らって帰宅した私を、見飽きた仏頂面が待ち受けていた。母はダイニングテーブルに肘をついて、おかえり、と呟いた。
「お母さん。模試、A」
「ああ良かった。推薦で無茶するから心配してたのよ」
「それと、その……。推薦で受けたとこも駄目元で書いたら、そっちもBで」
「……はあ?」
言わんとすることを即座に察したのだろう。母はテレビの画面から、不機嫌そうに私に視線を移した。
声音は頭ごなしに叱る時のそれ。聞くだけで、こちらも不快感がこみ上げてくる。
――落ち着け私。今大事なのは志望校だ。
すうと息を吸い込む母の前で、奥歯を噛み、非難を受け流す準備をする。
「推薦も身の丈に合った学校にしたらってお母さん言ったよね。それを由紀が、一回だけチャレンジするって言い張って、やっぱり落ちたんじゃない。約束破るの? うちは私立の学費も浪人の塾代も出せないよ?」
小馬鹿にしたような、それでいて苛立った早口。つられて私まで感情的になってしまったら意味がない。
「浪人することになったら頑張ってバイトする。判定、ずっとDだったのがBになったんだよ。お願い、これも落ちたら後期はちゃんと……」
しかし、なるべく冷静に言い募る私を、母は鼻で笑った。
「はっ、バイトね! したこともないのに軽々しく言うわ。それにB判定が一回出ましたあーなんて、どう見てもマグレでしょ!」
「……マグレじゃないっ!!」
一際強くガラス戸が鳴った。
こういう物言いをされると、予想していたのに堪えられなかった。肺が熱を持ち、ひく、と引きつる。目頭の濡れた感触が零れないように、私は目を見開いた。
「知らないのに適当言わないで! 夏休みも、推薦の前も、落ちてからも。私ずっと勉強してた。推薦決まってからは、春花も私のために時間作って教えてくれてたんだよ。何も見てないくせに……!」
「は、……」
突然の剣幕に母はたじろいだようだった。肩を震わせ、口の端を一度ひくつかせ、そして表情を嘲りに歪める。
子供に気圧されたなどあってはならない誤りで、正すべきことである――、そういう顔をする。
「へえ、まだお友達に迷惑掛けてるのね。その子と一緒の大学行きたいんだっけ。で、進学してからも足を引っ張るつもり? だいたいそんな薄っぺらい理由で志望を変えようなんて、」
「……
――そして。ここが。我慢の限界だった。
こうも狭量で、蒙昧で、己のちんけなプライドばかり大事にする人間と意思疎通しようだなんて、はなから無駄だったのだ。
激しく舞う雪の中をがむしゃらに走る。怒りに煮え立った自分を、もう一人の私が白けた目で見下ろしている。
推薦に落ちた時と何も変わらない。衝動のままにその場を飛び出して、当てなく駆けるだけ。
こんな幼稚な手段しか、子供の私は持ち合わせていなかった。
それが嫌な一心で――受験に食らいついていたのに。
*
白が視界を閉ざす。冷たさが身体に沁みいるようだ。大の字になった私を覆ってしまおうと、雪花は後からあとから舞い落ちる。
奪われていく熱。奪われていく気力。奪われていく、わだかまり。
止まっていく。凍っていく。
「この冬を、今を……」
ずっとこのまま――雪の中に閉じ込めてしまえたなら。
スマホが寂しげに歌っている。
どこかヨーロッパの知らない言葉。受験漬けの耳は英語だと単語を拾おうとしてしまうから、耳休めに春花と二人でDLした曲だ。
報われない恋の歌なのだと、後で調べて知った。
さく。さくり。
雪を踏む音が近づいて、旋律がぴたりと止んだ。
「由紀」
明るい若草色のマフラーを吹雪にはためかせ、春花は私を見下ろす。
蒼白な顔の中の丸っこい目が潤んで揺れている。
「……っ、何考えてるの!? こんなメッセージ寄越して……!」
顔の真上に突き付けられたトーク履歴。『受験やめる ごめんね』という小さな吹き出しに、春花の混乱と心配がいくつも連なっていた。
なのに私は凍え切っていて、申し訳なさ以上の気持ちを抱けない。春花の激情を目の当たりにしてすら。
「ごめん。ほんとは、推薦落ちたら志望校のランク下げることになってたんだ。説得しようとしたけど、無理だった」
「だからって、受験やめるなんてどういうこと。……一緒に、家を出ようって言ってたじゃない」
「同じ大学じゃないと意味ないもん。離れるぐらいなら、そう春花も、ずっと今のままでいようよ」
「どうして!!」
――どうして?
この旧弊な町を離れたかった。人の目に怯えずに、春花と過ごしたかった。
それだけなら立地が近い別の大学でもいいはずだ。同じキャンパスで大学生活を送れない不満はあっても、受験ごと投げ捨てる理由にはならない。
ならどうして、私は。
風鳴りがごうごうと唸る。初めて気付いた不安を、私はぽつりと口にした。
「……変わっちゃうのが、怖い」
「それでも今よりマシでしょ。だから二人で遠くに行くって決めたんでしょ!」
仁王立ちの春花からホワイトノイズの夜空に目を移して、ほうと息を吐く。白く濁ったそれは風雪にまかれてかき消える。
「今の学校で、女の子が好きだって子、春花は私以外に知らないじゃん。でも大学に行ったらきっと新しい出会いがある。いつも一緒にいなきゃ、繋ぎとめておけない」
「……ばかぁっ!!!!」
腹に衝撃があって、私は胸倉を掴まれていた。馬乗りになった春花の、夜目にも紅潮した顔がすぐ真上にある。
ぽつ、と頬に熱いものが滴った。
「わたしは! 由紀に告られる前から、由紀もそうだって知る前から、由紀のこと好きだった! 学校が違うくらいで心変わりなんてしないよ!」
「そ……んなの、初めて聞いた……」
「約束したじゃない、ルームシェアしようって。お揃いのものを持つだけで我慢するのはやめて、二人で色んなところに行って色んなことをしようって……」
春花はもはやしがみつくようにして、私の上でしゃくりあげている。大粒の涙がぼたぼたと降ってくる。
雫は私の頬を丸く滑り落ち、耳の横の雪に触れる。その部分がじわりと融けるのを肌で感じた。
緩んでいく。消えていく。
あれほど冷たく美しかった雪が春花の温度に負けてしまう。私の目からも流れ出した涙が重なれば、もう雪解けを止めることなどできない。
「居る場所が変わっても、大事なものは変わらないでいられるかな」
震える声で囁く。
ここは寒い。もう少しだけ、温めてほしい。
「変えないよ」
涙とともに、春花の泣き笑いが降ってきて、唇に触れた。
桜色の微熱。
それは新しい、春の兆しだった。