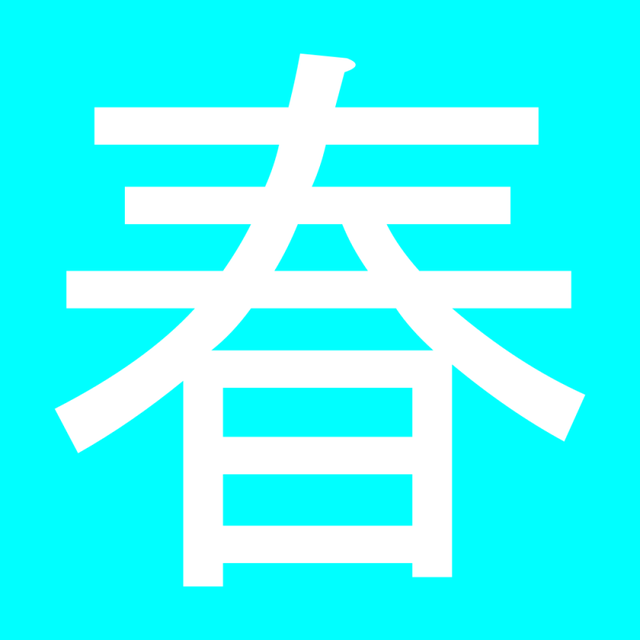第3章 孤立【2】
文字数 8,319文字
土日は職業訓練が休みだった。休みの日にコトブキが両親と一緒に朝食をとったのは数年ぶりのことだったかもしれない。八時半に着替えて家を出ようとすると、あら、きょうは休みよね? と母親が言った。庭仕事をしていた父親も同じことを言った。
図書館で勉強するんだ、
コトブキはそう言って車に乗った。
茂木楽器店・駐車場には土曜だというのに車は一台も停まっていなかった。エレベーターの数字の入っていないあのボタンを押しても動かない。二階のピアノ教室や三階のヨガ教室には行くことができた。しかし、何度数字のない四角いボタンを押してもエレベーターは動かなかった。
茂木楽器店に客は相変わらず一人もいなかった。
営業中ですか?
タトゥーだらけのあの店員にそう訊いてみた。この男に秘密クラブのことを尋ねる訳にはいかない。それとなく訊くしか方法がない。雑居ビル自体が謎だらけだった。
店員は、ああ、とだけ言った。
日曜は父親の庭仕事を手伝った。コトブキは去年まで人間は永遠に歳を取らないものだと思っていた。それが今年に入ってから急にしょんべんが近くなったり、寝ていると背中が痛くなったり、ちょっとからだをぶつけただけで痣になったりする。ばか女に腰を振ったときの膝の震えを思い出していた。一度もセックスをしないうちに動けなくなってしまうのではないか、そういった恐怖がコトブキに庭仕事を手伝わせていた。父親の背中が心なしか小さく見えた。この日、サイトには一度もアクセスしなかった。
翌朝、家を出ていく父親と母親は機嫌が良かった。朝食は普段よりウインナーが一本多かったし、父親は偶然テレビに映った鼻の大きい女優の名前をコトブキに訊いてきた。
コトブキは三年仕事が続いた試しがない。幾何学的に複雑な職歴の中で一番長く続いた仕事が工場だった。その工場は街はずれの高台にあって他にも二十棟ほどの工場があった。午前中は何に使うかわからない部品の、恐ろしく長い英字と数字で組み合わされた型番のようなものを用紙に記入する。午後はラインから流れてくる部品をひたすら梱包する。やっと仕事が終わって外に出ると真っ暗だ。作業場の中には窓がなかったからタイムスリップでもしたような感覚に襲われる。本当にこのまま老人になっていく気がした。高台のせいか夜はいつも奇妙な鳥の鳴き声が聞こえていた。
両親はおれが更生することを心から願っている。でも、それは両親の見当違いだ。おれは一度だってグレたことはない、そうコトブキは思っている。仕事を辞めても次に必ず探してくる。ただ、どうしても長続きさせることができない。根性がないとか、だらしないとか、大人になれないだとか、そういったものとは何か違うような気がする。もっと別な何か。世の中が自分にとってなぜこれほどまで生きづらくなったのかコトブキ自身わからなかった。
母親は家を出るときコトブキに一万円をくれた。もし、コトブキがグレたとしたなら、それはきょうという日だった。車はパソコン教室とは反対方向に走っていた。
『みんなの掲示板』
痴漢OK娘:
〉不倫なうとかもう死語ですか? スーパー
〉の多目的トイレで待ち合わせ。
10/30. 14:49
コトブキがこれを読んだのは家を出る直前だった。八時半はもうとっくに過ぎている。今から電話したんじゃ『先生』がうるさい、そう思った。無断欠席だった。
茂木楽器店・駐車場に車が一台も停まっていないのを見てコトブキは不安になったが、エレベーターは動いた。扉が開くと真っ暗闇の通路にあの WELCOME のネオン管が煌々と浮かび上がっていた。よし! と握りしめた手が汗ばんだ。MALE のネオン管を横切り、OPEN のスチールドアを開けた。レールの継ぎ目を通過する音を聞いているうちに鼓動が速くなり、電車の前に立ったコトブキは呼吸が苦しくなるほど喉が渇いた。
女のアナウンスが流れた。電車が減速していく。今のこの緊張が恐れなのか、それとも今度こそ宿願とも言える妄想のすべてを実行するんだという気の昂ぶりなのかコトブキは判別できなかった。指先が異常に冷たくて震えていることはわかった。
再びアナウンスが流れたあとで電車のドアが開いた。緊張のあまりコトブキは両開きのドアの入り口で躓いて、しかも無理に足を踏ん張ったせいで床に転んだ。何人かの女が慌てて座席から腰を浮かせ、だいじょうぶですか、と声をシンクロさせた。
顔を上げたコトブキは座席に並ぶ脚の多さに驚いた。コトブキが立ち上がっても先程声をかけたくれた女は心配そうだ。座席に浅く腰を掛けていて、いつでも立ち上がれるようにハンドバックを傍に置く者もいた。それを見て、コトブキの気持から気負いのようなものが少しずつ消えていった。扉が閉まるアナウンスが終わると、電車はじきに動きだした。
コトブキは前回と同じ場所に立ち吊革に摑まった。それとなく車両を眺めた。ばか女の姿はなかったが、あの日正面に坐っていた三人は乗っていた。コトブキがそれに気づくと、向こう三人は微笑んだ。コトブキは照れくさくて顔が赤くなってしまい、吊革を握り直した。
赤ん坊になれたらどれほど楽だろう、寝ぐせを撫でつけながらコトブキはそう思った。いつも疑問に思うのだが、母性をくすぐる男とだめな男の違いがわからない。母性を犯す夢は見たことがある。転んだ膝が痛みだした。痛みだしたところが心臓の鼓動に合わせて脈打っている。そのうちにレールの継ぎ目を通過する音ともシンクロしてきて、暖房はひどく暑いし、頭がぼーっとしてきた。だから、横にその女が立っていても声をかけられるまでコトブキは気がつかなかった。
「だいじょうぶですか」
ああ……転んだとき、いつでも立ち上がれるようにハンドバックを傍に置いていた女だとコトブキは思った。
女はその場にしゃがみ込み、コトブキの膝をさすってくれた。膝をさすりだすと心配そうだった女の表情が一変して真剣なものに変わっていった。看護師とか介護職の人なのだろうか、とコトブキは思った。手つきが慣れていて迷いがなかったからだ。
女は肩まである髪を後ろで結わえている。よく手入れされた髪からは金銭的な苦労をしているようには見えなかったし、蛍光灯の光を受けて天使の輪ができるほど漆黒の艶があった。
「痛みますか……」
まだ膝に違和感があるようだったら診察を受けることと、掛かり付けの医者はありますか、直接病院に行くより紹介状を書いて貰った方がスムーズに診察がいくことを女は言った。
襟ぐりの開いた服にブラジャーの刺繍が透けて見えた。ボインという死語がピタリときた。コトブキは頭の中でこの女に白衣を着せてみたがどこかリアリティがなかった。だが、介護職の、例えばピンク色のユニフォームを着せてやるとそれっぽく見えた。マッサージの動きに合わせてボインはゼリーのように揺れた。
スカートが上がってきても女は真剣そのものだった。コトブキが肌色のストッキングに見惚れているとスカートの奥が無防備に開いた。かしずく仕草のひとつひとつが優しかった。女の化粧には汗が光っていた。
もし童貞のまま年老いてからだが動かなくなったら……昨日そんなことを考えてコトブキは絶望していた。無性に女に甘えてみたくなった。もっと自分を解放する為にはどうすればいいのか。この女の前で自分の尊厳も社会性も過去も全部捨ててすべてを預けてみたい、そう思った。万歳するんだ、底尽きの人生でした、もう自分の力ではどうすることもできません、聖母マリアの前でおれは跪き、そして、おれはアナタを信じます、罪深き僕はアナタから受けた命を今ここでアナタの許へお還します、アーメン、さあ、アナタの御心のままに、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、おれは万歳だ、万歳したんだ、万歳……万歳……コトブキは両手で吊革に摑まった。
コトブキはふいに泣きそうになった。それでも涙で歪んだ唇を噛んで顔を上げた。見ればいい……ありのままを見ればいいさ、これがおれだ……無様だろう、だから何だ、そう思ったとき、背中の鈍痛が嘘のように消えた。眩い光が差し込んだように瞼の裏側がとても明るくなった。そして、勃起した。
女はそのことに気がついていない。働く女の顔だ。献身的なマッサージの前でコトブキの背徳感はより一段と募っていった。女の頭のちょうどうえで言い訳しようもないほどズボンがふくらんだ。もし女が少しでも顔を上げればすぐに気づくだろう。どんな顔をされても構わない。ただ、もう少しこのまま……恥かしい思いをしていたい気がする。コトブキはいま一度、アーメンと祈った。それでも我慢できずに今にも自供してしまいそうな舌を軽く噛んだ。
正面にいた女は皆探るような目をさせて二人を凝視していた。一応に顔を赤くさせて溜め息をつき、唾を呑むタイミングさえ一緒だった。ただし、『悪魔』の属性を持つコトブキと目を合わせる女は誰一人としていないし、まるで自分が恥かしいことでもしているかのように、これも同時に全員が下を向いた。
「興奮……しちゃいましたか」と女は下をむいたまま言った。
唐突にそう言われたのでコトブキは焦った。尻のあたりに力が入ってふくらませたズボンが返事でもしたかのように動いた。女は申し訳なさそうな顔をして笑った。アソコの先が痺れた。トクトクトクという脈打つ感じのあとでドッドッドという漲り方をした。中学の頃に授業が始まる直前に(それは一時間目が多かった)前触れもなく勃起してしまうあの感覚と似ていた。日直が号令をかけるまでの一秒を争って鎮めようとするのだけれど第二次性徴が始まったばかりのアソコは独立器官のようになっていてまるで言うことを聞いてくれないのだった。
服を着ているはずなのに裸にされたような気がした。女は、困ります、といったような顔をさせてコトブキの膝におでこをくっつけて笑った。
「まだ……痛みますか」
女の手つきが煽情的なものになった。
コトブキは痛いと思うところを突き出した。女は俯いたまま首を横に振った。コトブキの腰がおねだりをすると、女は吐息をあげた。女はもう一度コトブキの膝におでこをつけて瞳を閉じた。コトブキは女がそうやって瞳を閉じている間レールを通過する音をただジッとして聞いていた。
顔を上げた女が初めてズボンのふくらみを見た。化粧のうえからでも女の顔が赤くなるのがわかった。女の表情からしだいに笑みが消え、コトブキの中心にある漢に目を寄せた。それはソノ気になった女の顔だった。女は言いようのない眼つきをさせてコトブキを見上げてきた。
「元気に……なっちゃいましたね」
そう言った女は諸膝を床に揃えた。女と女の目の前にある異形のふくらみとの間には何か反発し合う磁極でもあるかのようだった。女は下から見上げたり、首を傾げてみたり、上から見下ろしてみたり、落ち着かない様子で眺め回した。女は物欲しそうに唇をすぼめたあと、両手でコトブキの中心に触れた。女は長い溜め息をついた。いいですか……と言うのがやっとだった。女はコトブキがうなずいたのを見て安堵したのか、もたれかかるようにしてアソコに頬を寄せた。そして、そっと睫毛を伏せた。
女は最初優しく頬ずりをしたあと、次に鼻や唇をアソコに擦りつけ、最後には顔全部を使って愛撫した。擦りつけられたズボンの布地は口紅やファンデーションで赤黒い月経のような染みができた。女が伏せていた睫毛を上げたとき、男の匂いに酔っ払ったような瞳は既に正体がなかった。透明なしずくが赤い口紅から垂れていった。
コトブキは吊革に摑まっているだけでよかった。女がコトブキのベルトをはずし終えるまでは。股下から中に手を入れられた。唐突だった。睾丸を握られた。
「お玉が張ってらっしゃる」
そう言って股下から抜いた手を女は自分の鼻先に近づけた。そして、溜め過ぎかしら、腐敗したザーメンの匂いがしますね、黄色く濁ってたりして、うふふ、可愛そう、と微笑んだ。
女はコトブキの足を両手で捧げ持つと片っぽずつ靴を脱がせた。ズボンを足首から抜き取ってしまうと、今度はパンツを一気に下げた。
「ウエルカムちんぽ!」と女は大声で言った。
コトブキは幼児にでもなった気分だった。吊革が身じろぎで軋んだ。女はコトブキに再び靴を履かせている間ずっと奇妙な笑い声を立てていて、いや、笑い声というよりは原生林に生息している小鳥のようなさえずりで、恐らくその小鳥というのは鮮やかなコバルトブルーで頭に羽毛が立っている、そんな鳥だとコトブキは思った。
女はその場に立ち上がった。横広がりの腰つき。太っているせいで肌に艶がある。太腿が発達しているせいで脚が短く見えた。女とは目が合っているのに女はどこか遠いところでも見ているような気がした。上着を脱がされ、Tシャツも脱がされて再び吊革に摑まったコトブキは靴下と靴、それ以外は一糸纏わぬ素っ裸にさせられた。女はもう一度その場に諸膝をついて脱がせた服を丁寧に畳んだ。
コトブキは裸に靴下と靴だけを履いていることが恥かしくてたまらなかった。女は三つ指をついてこう言った。
「セクシー」
コトブキは熱烈に下から見上げてくる女から視線を逸らした。そして、偶然目に留まった乗客の女から声にださずに、セクシー、と挽きたてのコーヒーの香りを味わうかのように微笑まれて思わず悶絶しそうになった。悪魔から聖母マリア様の僕、ついで幼児が大人の男根を付けた哀しい怪物となり果てた気がした。尻の弛んだ肉が羞恥に力んだ。コトブキの背後で、鼻で笑う気配がした。見世物小屋の小人はそうやって客に囃されるとおどけて見せるものだ。どこでそういったことを見聞きしたのか記憶が曖昧だったが、でも例えば、天皇を敬う気持を誰に教わったのかと尋ねられて答えられる日本人は全人口の一割にも満たないだろう。コトブキは尻たぶをぐいと寄せて宙に男根を突き上げた。自分のルーツを辿っていけば、もしかすると、どこかに一人くらい小人のじいさんがいるのかもしれないな、コトブキはそう思った。セクシー、とまた背後で声があがってコトブキは正面の座席にも喝采を求めた。
「セクシー! ウエルカムちんぽ!」と女は口々に言った。
いったん哀しい怪物になってしまえば、あとは随分気が楽になった。母乳をねだるように唇をめいいっぱい尖らせて甘える素振りだってできた。しかも、その顔を乗客や三つ指をついた女に見られても動じない傲慢さえ同時に身に付けていた。
吊革は今、身じろぎの為に軋むのではなくてコトブキの欲望の為に軋んでいた。ブランコに揺られるようにからだが前後した。とても素敵な気分だった。勃起しているせいで女の顔にしょんべんをかけてやれないのが残念なくらいだった。世の男はおれを見習うべきだ、そうだろ、と心の中で思ったことを途中から声にだして喋っていた。三つ指をついた女は快い返事をしたし他の乗客もそれに倣った。そして、セクシーの大合唱。この瞬間――
哀しい怪物コトブキアキラは聖母マリア様の僕でありながら異教を唱える教祖になった。教祖誕生を祝う僕らのうっとりとしたこの目を見よ、オオハナタカコやヒタチノゾミ、そして教室の女にそう語りかけるのだった。
三つ指をついた女は「検品の女」というハンドル名だった。コトブキは女の顔の前で手をかざし、女よ、ママンと名乗りなさい、そう言って洗礼を授けた。女はやはり快い返事をした。ママンという洗礼名の意味もよく理解しているようだった。女は、そう言われるのはずっと以前からわかっておりました、という笑みでコトブキに応えた。コトブキは目を細めてこれに満足した。
肉を与えよう、さあ食べるがよい、
ママンは赤黒い肉塊に目を寄せた。口に入るかどうか寸法を計るようにそれは熱心だった。大きいです、と言ったママンの溜め息が肉塊を震わせた。ママンは水中に潜るときのように息を止めてアーン、口を開いた。肉塊は赤い口紅を淫らがましく裂いていく。だが、潜っていったのは寧ろ肉塊の方で今度はコトブキが息を止める番だった。肉塊で感じたママンの口の中は熱かった。肉塊自身が小人だった。背丈ほどある強靭なベロが蔓のように絡まりついて面白可笑しくくすぐってくる。ベロの感触を通して小人には頭が二つあることがわかった。小人にはそのことがまた可笑しくて笑い出しそうになるとママンの唇でその頭を摑まれてしまうのであった。
ママンは片膝を立てた。スカートの空洞は影になっていて暗い。小人が鼻の下をのばしたママンの口の中で溺れている最中、女のからだは穴だらけだ、とコトブキは思った。しかし、スカートが捲れ上がっていくうちに暗がりにはもうひとつ理由があることがわかった。ストッキングは大事なところに小窓がついていた。黒い叢は毬藻のような形をして毛羽立っていた。ママンはノーパンだった。小人は慌てて、これ以上頭に血を上らせるな! とコトブキに直接テレパシーを飛ばしてきた。小人は粘膜という粘膜に上下左右、予告なしに小突き回された。ママンの涎はエイリアンの体液のようにベトベトしてて小人は自分のからだがママンの口の中の一部になった気がした。目が回る……ぐるぐるぐる。小人は全身を硬直させたまま泡を吹いた。小人が双頭を唇で引っ張られながら外に出て、ようやく解放されたのはそれから間もなくのことだった。
「すっごいハンサムちんぽ」
ママンはそう言って小人を褒めた。小人はレディからそうやって敬意を示されたのは初めてだったので口を引き締めていま一度やる気をだした。生まれつき奇形だが、生まれつき超合金のようなボディをしている、それが小人だ。そうやって強がってみせる小人を、セクシー、セクシー、と観客は言ってこの小さな巨人を励ました。ママンはやにわに小人を握りしめてビンタを強要した。頬の次は鼻っぱしを、鼻っぱしの次は濡れた唇を、唇のあとは氷柱のように涎の垂れた顎を、小人は風を切るように全身を撓らせた。
「ああ……若いっていいわ」
そう言ったママンは、でも足りない、もっともっと、とうわ言のように繰り返しベロのうえで小人をめちゃくちゃに振りたくった。小人は再び目を回して泡を吹いた。
ママンは服を脱ぎだした。
「子どもを産んでから……乳首が敏感なんです」
何人だ、
「四人です」
ほいど め、
「最近また大きくなってきて困ってます」
抱きかかえるようにして寄せあつめられた胸はママンの言う通り、出荷前のウォーターメロンのようで切り取られたヘタによく似た乳首が充血してふくらんでいた。
「検品……してください」
コトブキはしっかりしろ、と小人に言ってやったあと、威厳のある声で、うむ、とうなずいた。
小人はまだ泡を吹いていたがママンの胸で抱き寄せられた。実り過ぎとも思えるウォーターメロンの谷間は深くて小人の頭が丸ごと隠れるほどだった。なぜ左右対称の瘤が並ぶとこうもいやらしいのだろう、とコトブキは思った。おっぱいもお尻も小人の頭の後ろ側や小鼻も。小人の方は小人の方で、ゼリーみたいにプルンプルン、と叫んでいた。ママンは、やだ……からだが熱い、からだが熱い、と言っている。ママンの化粧からは到底想像ができないくらい神秘的なぬめ白い柔肌に包まれて、時折にょっきと顔をだす小人は肝臓を壊した中年のように日焼けした土色だった。
ママンがパンプスの先を八の字に向けた。両の太腿を水平に保って尻の重心を据えた。踵がパンプスから脱げて浮かび上がり、爪先立ちとなった姿にコトブキは愛を感じた。ママンのパイズリに一段と熱がこもった。
「ぼくちゃん……ぼくちゃん」
ママン……ママン、
小人は死体のようにからだを硬くした。ママンは如何にも妊娠しやすそうな段腹を揺らして上下した。
「ちんぽ……ちんぽ、ちんぽ……」
「ちんぽ! ちんぽ! ちんぽ!」と車内からシュプレヒコールがあがった。
女の感性はピカソ的だ……とコトブキは思った。的はここよん、と言わんばかりにママンがあんぐり大口を開いた。小人はむきむきむきむき、と唸った。その最後には、小人殺し! そう叫んで白玉を飛ばした。
「ビンゴ!」と誰かが大声をあげた。
コトブキはママンの口の中を見た。腐敗したザーメンが本当に黄色いかどうか確かめたかったからだ。幸いザーメンは白かった。その代わり、液体じゃなかった。
「固形のりみたいね」
舌先を遊ばせているママンにそう言われてコトブキは恥かしかった。
図書館で勉強するんだ、
コトブキはそう言って車に乗った。
茂木楽器店・駐車場には土曜だというのに車は一台も停まっていなかった。エレベーターの数字の入っていないあのボタンを押しても動かない。二階のピアノ教室や三階のヨガ教室には行くことができた。しかし、何度数字のない四角いボタンを押してもエレベーターは動かなかった。
茂木楽器店に客は相変わらず一人もいなかった。
営業中ですか?
タトゥーだらけのあの店員にそう訊いてみた。この男に秘密クラブのことを尋ねる訳にはいかない。それとなく訊くしか方法がない。雑居ビル自体が謎だらけだった。
店員は、ああ、とだけ言った。
日曜は父親の庭仕事を手伝った。コトブキは去年まで人間は永遠に歳を取らないものだと思っていた。それが今年に入ってから急にしょんべんが近くなったり、寝ていると背中が痛くなったり、ちょっとからだをぶつけただけで痣になったりする。ばか女に腰を振ったときの膝の震えを思い出していた。一度もセックスをしないうちに動けなくなってしまうのではないか、そういった恐怖がコトブキに庭仕事を手伝わせていた。父親の背中が心なしか小さく見えた。この日、サイトには一度もアクセスしなかった。
翌朝、家を出ていく父親と母親は機嫌が良かった。朝食は普段よりウインナーが一本多かったし、父親は偶然テレビに映った鼻の大きい女優の名前をコトブキに訊いてきた。
コトブキは三年仕事が続いた試しがない。幾何学的に複雑な職歴の中で一番長く続いた仕事が工場だった。その工場は街はずれの高台にあって他にも二十棟ほどの工場があった。午前中は何に使うかわからない部品の、恐ろしく長い英字と数字で組み合わされた型番のようなものを用紙に記入する。午後はラインから流れてくる部品をひたすら梱包する。やっと仕事が終わって外に出ると真っ暗だ。作業場の中には窓がなかったからタイムスリップでもしたような感覚に襲われる。本当にこのまま老人になっていく気がした。高台のせいか夜はいつも奇妙な鳥の鳴き声が聞こえていた。
両親はおれが更生することを心から願っている。でも、それは両親の見当違いだ。おれは一度だってグレたことはない、そうコトブキは思っている。仕事を辞めても次に必ず探してくる。ただ、どうしても長続きさせることができない。根性がないとか、だらしないとか、大人になれないだとか、そういったものとは何か違うような気がする。もっと別な何か。世の中が自分にとってなぜこれほどまで生きづらくなったのかコトブキ自身わからなかった。
母親は家を出るときコトブキに一万円をくれた。もし、コトブキがグレたとしたなら、それはきょうという日だった。車はパソコン教室とは反対方向に走っていた。
『みんなの掲示板』
痴漢OK娘:
〉不倫なうとかもう死語ですか? スーパー
〉の多目的トイレで待ち合わせ。
10/30. 14:49
コトブキがこれを読んだのは家を出る直前だった。八時半はもうとっくに過ぎている。今から電話したんじゃ『先生』がうるさい、そう思った。無断欠席だった。
茂木楽器店・駐車場に車が一台も停まっていないのを見てコトブキは不安になったが、エレベーターは動いた。扉が開くと真っ暗闇の通路にあの WELCOME のネオン管が煌々と浮かび上がっていた。よし! と握りしめた手が汗ばんだ。MALE のネオン管を横切り、OPEN のスチールドアを開けた。レールの継ぎ目を通過する音を聞いているうちに鼓動が速くなり、電車の前に立ったコトブキは呼吸が苦しくなるほど喉が渇いた。
女のアナウンスが流れた。電車が減速していく。今のこの緊張が恐れなのか、それとも今度こそ宿願とも言える妄想のすべてを実行するんだという気の昂ぶりなのかコトブキは判別できなかった。指先が異常に冷たくて震えていることはわかった。
再びアナウンスが流れたあとで電車のドアが開いた。緊張のあまりコトブキは両開きのドアの入り口で躓いて、しかも無理に足を踏ん張ったせいで床に転んだ。何人かの女が慌てて座席から腰を浮かせ、だいじょうぶですか、と声をシンクロさせた。
顔を上げたコトブキは座席に並ぶ脚の多さに驚いた。コトブキが立ち上がっても先程声をかけたくれた女は心配そうだ。座席に浅く腰を掛けていて、いつでも立ち上がれるようにハンドバックを傍に置く者もいた。それを見て、コトブキの気持から気負いのようなものが少しずつ消えていった。扉が閉まるアナウンスが終わると、電車はじきに動きだした。
コトブキは前回と同じ場所に立ち吊革に摑まった。それとなく車両を眺めた。ばか女の姿はなかったが、あの日正面に坐っていた三人は乗っていた。コトブキがそれに気づくと、向こう三人は微笑んだ。コトブキは照れくさくて顔が赤くなってしまい、吊革を握り直した。
赤ん坊になれたらどれほど楽だろう、寝ぐせを撫でつけながらコトブキはそう思った。いつも疑問に思うのだが、母性をくすぐる男とだめな男の違いがわからない。母性を犯す夢は見たことがある。転んだ膝が痛みだした。痛みだしたところが心臓の鼓動に合わせて脈打っている。そのうちにレールの継ぎ目を通過する音ともシンクロしてきて、暖房はひどく暑いし、頭がぼーっとしてきた。だから、横にその女が立っていても声をかけられるまでコトブキは気がつかなかった。
「だいじょうぶですか」
ああ……転んだとき、いつでも立ち上がれるようにハンドバックを傍に置いていた女だとコトブキは思った。
女はその場にしゃがみ込み、コトブキの膝をさすってくれた。膝をさすりだすと心配そうだった女の表情が一変して真剣なものに変わっていった。看護師とか介護職の人なのだろうか、とコトブキは思った。手つきが慣れていて迷いがなかったからだ。
女は肩まである髪を後ろで結わえている。よく手入れされた髪からは金銭的な苦労をしているようには見えなかったし、蛍光灯の光を受けて天使の輪ができるほど漆黒の艶があった。
「痛みますか……」
まだ膝に違和感があるようだったら診察を受けることと、掛かり付けの医者はありますか、直接病院に行くより紹介状を書いて貰った方がスムーズに診察がいくことを女は言った。
襟ぐりの開いた服にブラジャーの刺繍が透けて見えた。ボインという死語がピタリときた。コトブキは頭の中でこの女に白衣を着せてみたがどこかリアリティがなかった。だが、介護職の、例えばピンク色のユニフォームを着せてやるとそれっぽく見えた。マッサージの動きに合わせてボインはゼリーのように揺れた。
スカートが上がってきても女は真剣そのものだった。コトブキが肌色のストッキングに見惚れているとスカートの奥が無防備に開いた。かしずく仕草のひとつひとつが優しかった。女の化粧には汗が光っていた。
もし童貞のまま年老いてからだが動かなくなったら……昨日そんなことを考えてコトブキは絶望していた。無性に女に甘えてみたくなった。もっと自分を解放する為にはどうすればいいのか。この女の前で自分の尊厳も社会性も過去も全部捨ててすべてを預けてみたい、そう思った。万歳するんだ、底尽きの人生でした、もう自分の力ではどうすることもできません、聖母マリアの前でおれは跪き、そして、おれはアナタを信じます、罪深き僕はアナタから受けた命を今ここでアナタの許へお還します、アーメン、さあ、アナタの御心のままに、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、おれは万歳だ、万歳したんだ、万歳……万歳……コトブキは両手で吊革に摑まった。
コトブキはふいに泣きそうになった。それでも涙で歪んだ唇を噛んで顔を上げた。見ればいい……ありのままを見ればいいさ、これがおれだ……無様だろう、だから何だ、そう思ったとき、背中の鈍痛が嘘のように消えた。眩い光が差し込んだように瞼の裏側がとても明るくなった。そして、勃起した。
女はそのことに気がついていない。働く女の顔だ。献身的なマッサージの前でコトブキの背徳感はより一段と募っていった。女の頭のちょうどうえで言い訳しようもないほどズボンがふくらんだ。もし女が少しでも顔を上げればすぐに気づくだろう。どんな顔をされても構わない。ただ、もう少しこのまま……恥かしい思いをしていたい気がする。コトブキはいま一度、アーメンと祈った。それでも我慢できずに今にも自供してしまいそうな舌を軽く噛んだ。
正面にいた女は皆探るような目をさせて二人を凝視していた。一応に顔を赤くさせて溜め息をつき、唾を呑むタイミングさえ一緒だった。ただし、『悪魔』の属性を持つコトブキと目を合わせる女は誰一人としていないし、まるで自分が恥かしいことでもしているかのように、これも同時に全員が下を向いた。
「興奮……しちゃいましたか」と女は下をむいたまま言った。
唐突にそう言われたのでコトブキは焦った。尻のあたりに力が入ってふくらませたズボンが返事でもしたかのように動いた。女は申し訳なさそうな顔をして笑った。アソコの先が痺れた。トクトクトクという脈打つ感じのあとでドッドッドという漲り方をした。中学の頃に授業が始まる直前に(それは一時間目が多かった)前触れもなく勃起してしまうあの感覚と似ていた。日直が号令をかけるまでの一秒を争って鎮めようとするのだけれど第二次性徴が始まったばかりのアソコは独立器官のようになっていてまるで言うことを聞いてくれないのだった。
服を着ているはずなのに裸にされたような気がした。女は、困ります、といったような顔をさせてコトブキの膝におでこをくっつけて笑った。
「まだ……痛みますか」
女の手つきが煽情的なものになった。
コトブキは痛いと思うところを突き出した。女は俯いたまま首を横に振った。コトブキの腰がおねだりをすると、女は吐息をあげた。女はもう一度コトブキの膝におでこをつけて瞳を閉じた。コトブキは女がそうやって瞳を閉じている間レールを通過する音をただジッとして聞いていた。
顔を上げた女が初めてズボンのふくらみを見た。化粧のうえからでも女の顔が赤くなるのがわかった。女の表情からしだいに笑みが消え、コトブキの中心にある漢に目を寄せた。それはソノ気になった女の顔だった。女は言いようのない眼つきをさせてコトブキを見上げてきた。
「元気に……なっちゃいましたね」
そう言った女は諸膝を床に揃えた。女と女の目の前にある異形のふくらみとの間には何か反発し合う磁極でもあるかのようだった。女は下から見上げたり、首を傾げてみたり、上から見下ろしてみたり、落ち着かない様子で眺め回した。女は物欲しそうに唇をすぼめたあと、両手でコトブキの中心に触れた。女は長い溜め息をついた。いいですか……と言うのがやっとだった。女はコトブキがうなずいたのを見て安堵したのか、もたれかかるようにしてアソコに頬を寄せた。そして、そっと睫毛を伏せた。
女は最初優しく頬ずりをしたあと、次に鼻や唇をアソコに擦りつけ、最後には顔全部を使って愛撫した。擦りつけられたズボンの布地は口紅やファンデーションで赤黒い月経のような染みができた。女が伏せていた睫毛を上げたとき、男の匂いに酔っ払ったような瞳は既に正体がなかった。透明なしずくが赤い口紅から垂れていった。
コトブキは吊革に摑まっているだけでよかった。女がコトブキのベルトをはずし終えるまでは。股下から中に手を入れられた。唐突だった。睾丸を握られた。
「お玉が張ってらっしゃる」
そう言って股下から抜いた手を女は自分の鼻先に近づけた。そして、溜め過ぎかしら、腐敗したザーメンの匂いがしますね、黄色く濁ってたりして、うふふ、可愛そう、と微笑んだ。
女はコトブキの足を両手で捧げ持つと片っぽずつ靴を脱がせた。ズボンを足首から抜き取ってしまうと、今度はパンツを一気に下げた。
「ウエルカムちんぽ!」と女は大声で言った。
コトブキは幼児にでもなった気分だった。吊革が身じろぎで軋んだ。女はコトブキに再び靴を履かせている間ずっと奇妙な笑い声を立てていて、いや、笑い声というよりは原生林に生息している小鳥のようなさえずりで、恐らくその小鳥というのは鮮やかなコバルトブルーで頭に羽毛が立っている、そんな鳥だとコトブキは思った。
女はその場に立ち上がった。横広がりの腰つき。太っているせいで肌に艶がある。太腿が発達しているせいで脚が短く見えた。女とは目が合っているのに女はどこか遠いところでも見ているような気がした。上着を脱がされ、Tシャツも脱がされて再び吊革に摑まったコトブキは靴下と靴、それ以外は一糸纏わぬ素っ裸にさせられた。女はもう一度その場に諸膝をついて脱がせた服を丁寧に畳んだ。
コトブキは裸に靴下と靴だけを履いていることが恥かしくてたまらなかった。女は三つ指をついてこう言った。
「セクシー」
コトブキは熱烈に下から見上げてくる女から視線を逸らした。そして、偶然目に留まった乗客の女から声にださずに、セクシー、と挽きたてのコーヒーの香りを味わうかのように微笑まれて思わず悶絶しそうになった。悪魔から聖母マリア様の僕、ついで幼児が大人の男根を付けた哀しい怪物となり果てた気がした。尻の弛んだ肉が羞恥に力んだ。コトブキの背後で、鼻で笑う気配がした。見世物小屋の小人はそうやって客に囃されるとおどけて見せるものだ。どこでそういったことを見聞きしたのか記憶が曖昧だったが、でも例えば、天皇を敬う気持を誰に教わったのかと尋ねられて答えられる日本人は全人口の一割にも満たないだろう。コトブキは尻たぶをぐいと寄せて宙に男根を突き上げた。自分のルーツを辿っていけば、もしかすると、どこかに一人くらい小人のじいさんがいるのかもしれないな、コトブキはそう思った。セクシー、とまた背後で声があがってコトブキは正面の座席にも喝采を求めた。
「セクシー! ウエルカムちんぽ!」と女は口々に言った。
いったん哀しい怪物になってしまえば、あとは随分気が楽になった。母乳をねだるように唇をめいいっぱい尖らせて甘える素振りだってできた。しかも、その顔を乗客や三つ指をついた女に見られても動じない傲慢さえ同時に身に付けていた。
吊革は今、身じろぎの為に軋むのではなくてコトブキの欲望の為に軋んでいた。ブランコに揺られるようにからだが前後した。とても素敵な気分だった。勃起しているせいで女の顔にしょんべんをかけてやれないのが残念なくらいだった。世の男はおれを見習うべきだ、そうだろ、と心の中で思ったことを途中から声にだして喋っていた。三つ指をついた女は快い返事をしたし他の乗客もそれに倣った。そして、セクシーの大合唱。この瞬間――
哀しい怪物コトブキアキラは聖母マリア様の僕でありながら異教を唱える教祖になった。教祖誕生を祝う僕らのうっとりとしたこの目を見よ、オオハナタカコやヒタチノゾミ、そして教室の女にそう語りかけるのだった。
三つ指をついた女は「検品の女」というハンドル名だった。コトブキは女の顔の前で手をかざし、女よ、ママンと名乗りなさい、そう言って洗礼を授けた。女はやはり快い返事をした。ママンという洗礼名の意味もよく理解しているようだった。女は、そう言われるのはずっと以前からわかっておりました、という笑みでコトブキに応えた。コトブキは目を細めてこれに満足した。
肉を与えよう、さあ食べるがよい、
ママンは赤黒い肉塊に目を寄せた。口に入るかどうか寸法を計るようにそれは熱心だった。大きいです、と言ったママンの溜め息が肉塊を震わせた。ママンは水中に潜るときのように息を止めてアーン、口を開いた。肉塊は赤い口紅を淫らがましく裂いていく。だが、潜っていったのは寧ろ肉塊の方で今度はコトブキが息を止める番だった。肉塊で感じたママンの口の中は熱かった。肉塊自身が小人だった。背丈ほどある強靭なベロが蔓のように絡まりついて面白可笑しくくすぐってくる。ベロの感触を通して小人には頭が二つあることがわかった。小人にはそのことがまた可笑しくて笑い出しそうになるとママンの唇でその頭を摑まれてしまうのであった。
ママンは片膝を立てた。スカートの空洞は影になっていて暗い。小人が鼻の下をのばしたママンの口の中で溺れている最中、女のからだは穴だらけだ、とコトブキは思った。しかし、スカートが捲れ上がっていくうちに暗がりにはもうひとつ理由があることがわかった。ストッキングは大事なところに小窓がついていた。黒い叢は毬藻のような形をして毛羽立っていた。ママンはノーパンだった。小人は慌てて、これ以上頭に血を上らせるな! とコトブキに直接テレパシーを飛ばしてきた。小人は粘膜という粘膜に上下左右、予告なしに小突き回された。ママンの涎はエイリアンの体液のようにベトベトしてて小人は自分のからだがママンの口の中の一部になった気がした。目が回る……ぐるぐるぐる。小人は全身を硬直させたまま泡を吹いた。小人が双頭を唇で引っ張られながら外に出て、ようやく解放されたのはそれから間もなくのことだった。
「すっごいハンサムちんぽ」
ママンはそう言って小人を褒めた。小人はレディからそうやって敬意を示されたのは初めてだったので口を引き締めていま一度やる気をだした。生まれつき奇形だが、生まれつき超合金のようなボディをしている、それが小人だ。そうやって強がってみせる小人を、セクシー、セクシー、と観客は言ってこの小さな巨人を励ました。ママンはやにわに小人を握りしめてビンタを強要した。頬の次は鼻っぱしを、鼻っぱしの次は濡れた唇を、唇のあとは氷柱のように涎の垂れた顎を、小人は風を切るように全身を撓らせた。
「ああ……若いっていいわ」
そう言ったママンは、でも足りない、もっともっと、とうわ言のように繰り返しベロのうえで小人をめちゃくちゃに振りたくった。小人は再び目を回して泡を吹いた。
ママンは服を脱ぎだした。
「子どもを産んでから……乳首が敏感なんです」
何人だ、
「四人です」
「最近また大きくなってきて困ってます」
抱きかかえるようにして寄せあつめられた胸はママンの言う通り、出荷前のウォーターメロンのようで切り取られたヘタによく似た乳首が充血してふくらんでいた。
「検品……してください」
コトブキはしっかりしろ、と小人に言ってやったあと、威厳のある声で、うむ、とうなずいた。
小人はまだ泡を吹いていたがママンの胸で抱き寄せられた。実り過ぎとも思えるウォーターメロンの谷間は深くて小人の頭が丸ごと隠れるほどだった。なぜ左右対称の瘤が並ぶとこうもいやらしいのだろう、とコトブキは思った。おっぱいもお尻も小人の頭の後ろ側や小鼻も。小人の方は小人の方で、ゼリーみたいにプルンプルン、と叫んでいた。ママンは、やだ……からだが熱い、からだが熱い、と言っている。ママンの化粧からは到底想像ができないくらい神秘的なぬめ白い柔肌に包まれて、時折にょっきと顔をだす小人は肝臓を壊した中年のように日焼けした土色だった。
ママンがパンプスの先を八の字に向けた。両の太腿を水平に保って尻の重心を据えた。踵がパンプスから脱げて浮かび上がり、爪先立ちとなった姿にコトブキは愛を感じた。ママンのパイズリに一段と熱がこもった。
「ぼくちゃん……ぼくちゃん」
ママン……ママン、
小人は死体のようにからだを硬くした。ママンは如何にも妊娠しやすそうな段腹を揺らして上下した。
「ちんぽ……ちんぽ、ちんぽ……」
「ちんぽ! ちんぽ! ちんぽ!」と車内からシュプレヒコールがあがった。
女の感性はピカソ的だ……とコトブキは思った。的はここよん、と言わんばかりにママンがあんぐり大口を開いた。小人はむきむきむきむき、と唸った。その最後には、小人殺し! そう叫んで白玉を飛ばした。
「ビンゴ!」と誰かが大声をあげた。
コトブキはママンの口の中を見た。腐敗したザーメンが本当に黄色いかどうか確かめたかったからだ。幸いザーメンは白かった。その代わり、液体じゃなかった。
「固形のりみたいね」
舌先を遊ばせているママンにそう言われてコトブキは恥かしかった。