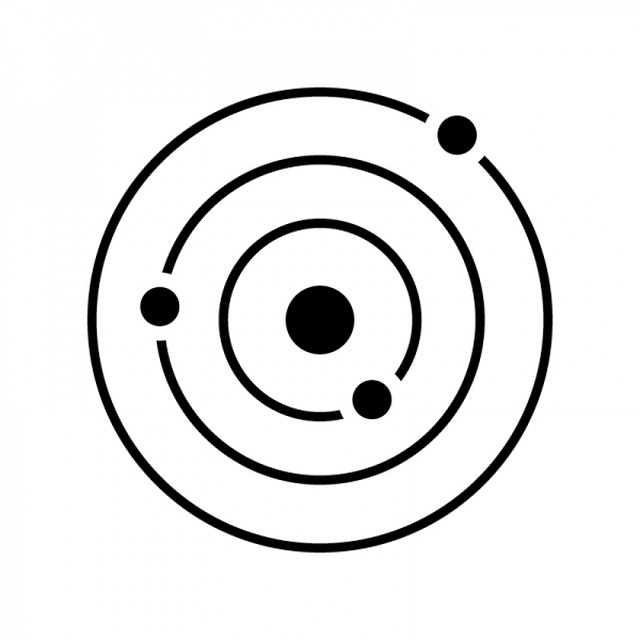66.煙
文字数 1,640文字
現実感のないまま、侑子は立ち上る細い煙を見つめていた。
真っ直ぐに線を描きながら、次第にぐにゃぐにゃと踊るように揺らめいて、終いには散るように消え去る。
――消えた煙は、どこに行ったんだろう
立ち上る煙の向こう、香立ての奥に、柔和な笑みを浮かべる玄一の写真が見える。
黒いフレームに縁取られた、それは遺影だった。
「侑子ちゃん。来てくれてありがとう」
そう声を掛けながら侑子の隣に膝をついたのは、喜久子だった。玄一の妻で、裕貴の祖母である。
ぼんやりと手を合わせたままだった侑子は、慌てて喜久子に向かい合う。
「この度は――」
「止めよう、そういう挨拶は」
言いかけた侑子を遮って、喜久子は笑った。
「聞き飽きちゃった。会う人会う人、同じ事言ってくるんだもん」
カラカラと明るく笑う彼女は、やはりいつ見ても若々しかった。玄一と同い年だというのだから、明らかに実年齢よりも数十歳は若く見える。言葉尻からも年齢を感じさせない、不思議な人だった。
「ゲンちゃんだって、侑子ちゃんからそんな湿っぽい挨拶聞くの、寂しいと思うから。ね」
むらなく薄茶に染めたロングヘアは艷やかだ。その髪を耳にかけながら、喜久子は遺影に微笑みかけている。
「侑子ちゃんからの手紙、嬉しそうに読んでたよ。この話、裕貴から聞いてる?」
「はい」
入学式の日、侑子が書いた手紙は、裕貴から玄一に手渡された。
その六時間後のことだった。
容態が急変して、そのまま静かに息を引き取ったのだ。
十日前のことだった。
「私ね、明日からまたライブハウスに戻るんだ」
喜久子の手が、蝋燭の炎を扇いで消した。指を彩る指輪が煌めいた。
「『早くない?』なんて言う人もいるけどさ。だっていつまでも喪に服して、手を合わせてるわけにいかないよ――――止まったら、嫌な方に引っ張られちゃうもん」
ふっと短く笑った喜久子の横顔が、一瞬だけ年相応に見えた気がして、侑子は目を瞠った。
「長く生きてるとね、その分身近な人との別れを経験するものなんだよ。当たり前だけど。祖父母でしょ、両親でしょ、恩師や、それから年長の兄弟とか、友達とか」
仏間の窓は開いていたが、線香の香りはいつまでも滞留している。侑子も喜久子も、鼻が慣れてしまっていたが。
「生きていればいるだけ、順当に死は身近になっていくものなんだ。若い頃には漠然としてて恐怖でしかなかったけど、身近になると、不思議とそうでもなくなるんだよね」
「そうなんですか?」
疑問符が自然と口から滑り出て、そんな侑子に喜久子は笑った。
「そりゃ、人によってはいつまでも死は恐いかも知れないけど。私はね、そうでもないタイプ」
はは、と笑って喜久子は再び夫の遺影に視線を戻した。
「身近な人があっち側に行く度に、自分もいつか同じ側に行くだけなんだなぁって思えるんだ。だから怖くないよ。けどさすがにさ、これだけいつも一緒だった人が、あっけなく逝ってしまうと……悲しみに身を任せてしまいたくなるでしょ。それは私にしてみたら、あまり良くない引っ張られ方なの。自分自身まで見失う気がして」
「……なるほど」
「今、なんだか嫌な世の中じゃない? 死が身近になりすぎてる。順番飛ばしが多すぎる。油断したら、すぐに気持ちが持っていかれちゃう」
「……」
「だから戻らなきゃ。“いつも”を整えなきゃ。私にとってそれは音楽。ゲンちゃんと私の間にも、いつも音楽があった。鳴らすのを止めたら、私達の時間も止まってしまうでしょ」
その言葉に、思い出す感情が侑子にはあった。
側村で追体験した、一組の夫婦の残した感情だった。
正彦とちえみが共に過ごした時間は、玄一と喜久子とが過ごした時間よりも、ずっと短いものだっただろう。しかし侑子が感じた彼らの“愛”の感情は、時間と比例しない濃度を持つものだったのだ。
「憧れます」
侑子の言葉に、喜久子は大きく笑った。
さあ、あっちで音楽でも聞こうと手を取られた。
侑子は座布団から立ち上がると、最後にもう一度遺影に目礼して、仏間を後にした。
真っ直ぐに線を描きながら、次第にぐにゃぐにゃと踊るように揺らめいて、終いには散るように消え去る。
――消えた煙は、どこに行ったんだろう
立ち上る煙の向こう、香立ての奥に、柔和な笑みを浮かべる玄一の写真が見える。
黒いフレームに縁取られた、それは遺影だった。
「侑子ちゃん。来てくれてありがとう」
そう声を掛けながら侑子の隣に膝をついたのは、喜久子だった。玄一の妻で、裕貴の祖母である。
ぼんやりと手を合わせたままだった侑子は、慌てて喜久子に向かい合う。
「この度は――」
「止めよう、そういう挨拶は」
言いかけた侑子を遮って、喜久子は笑った。
「聞き飽きちゃった。会う人会う人、同じ事言ってくるんだもん」
カラカラと明るく笑う彼女は、やはりいつ見ても若々しかった。玄一と同い年だというのだから、明らかに実年齢よりも数十歳は若く見える。言葉尻からも年齢を感じさせない、不思議な人だった。
「ゲンちゃんだって、侑子ちゃんからそんな湿っぽい挨拶聞くの、寂しいと思うから。ね」
むらなく薄茶に染めたロングヘアは艷やかだ。その髪を耳にかけながら、喜久子は遺影に微笑みかけている。
「侑子ちゃんからの手紙、嬉しそうに読んでたよ。この話、裕貴から聞いてる?」
「はい」
入学式の日、侑子が書いた手紙は、裕貴から玄一に手渡された。
その六時間後のことだった。
容態が急変して、そのまま静かに息を引き取ったのだ。
十日前のことだった。
「私ね、明日からまたライブハウスに戻るんだ」
喜久子の手が、蝋燭の炎を扇いで消した。指を彩る指輪が煌めいた。
「『早くない?』なんて言う人もいるけどさ。だっていつまでも喪に服して、手を合わせてるわけにいかないよ――――止まったら、嫌な方に引っ張られちゃうもん」
ふっと短く笑った喜久子の横顔が、一瞬だけ年相応に見えた気がして、侑子は目を瞠った。
「長く生きてるとね、その分身近な人との別れを経験するものなんだよ。当たり前だけど。祖父母でしょ、両親でしょ、恩師や、それから年長の兄弟とか、友達とか」
仏間の窓は開いていたが、線香の香りはいつまでも滞留している。侑子も喜久子も、鼻が慣れてしまっていたが。
「生きていればいるだけ、順当に死は身近になっていくものなんだ。若い頃には漠然としてて恐怖でしかなかったけど、身近になると、不思議とそうでもなくなるんだよね」
「そうなんですか?」
疑問符が自然と口から滑り出て、そんな侑子に喜久子は笑った。
「そりゃ、人によってはいつまでも死は恐いかも知れないけど。私はね、そうでもないタイプ」
はは、と笑って喜久子は再び夫の遺影に視線を戻した。
「身近な人があっち側に行く度に、自分もいつか同じ側に行くだけなんだなぁって思えるんだ。だから怖くないよ。けどさすがにさ、これだけいつも一緒だった人が、あっけなく逝ってしまうと……悲しみに身を任せてしまいたくなるでしょ。それは私にしてみたら、あまり良くない引っ張られ方なの。自分自身まで見失う気がして」
「……なるほど」
「今、なんだか嫌な世の中じゃない? 死が身近になりすぎてる。順番飛ばしが多すぎる。油断したら、すぐに気持ちが持っていかれちゃう」
「……」
「だから戻らなきゃ。“いつも”を整えなきゃ。私にとってそれは音楽。ゲンちゃんと私の間にも、いつも音楽があった。鳴らすのを止めたら、私達の時間も止まってしまうでしょ」
その言葉に、思い出す感情が侑子にはあった。
側村で追体験した、一組の夫婦の残した感情だった。
正彦とちえみが共に過ごした時間は、玄一と喜久子とが過ごした時間よりも、ずっと短いものだっただろう。しかし侑子が感じた彼らの“愛”の感情は、時間と比例しない濃度を持つものだったのだ。
「憧れます」
侑子の言葉に、喜久子は大きく笑った。
さあ、あっちで音楽でも聞こうと手を取られた。
侑子は座布団から立ち上がると、最後にもう一度遺影に目礼して、仏間を後にした。