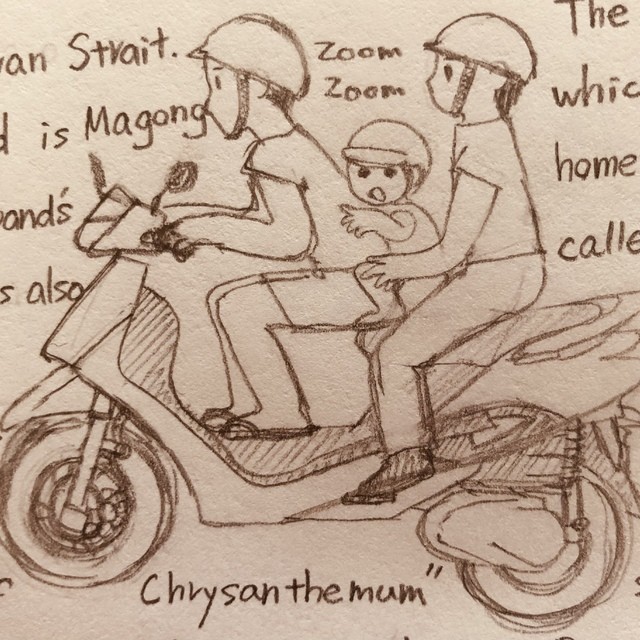十三、かげろう
文字数 3,277文字
隣を歩く若い修道士は青褪めて震えている。無理もない。既に多くの人で賑わう市場通りで馬の手綱を引き並んで歩くが、人相を隠した男たちが一人また一人と路地裏から姿を現して、ほとんど取り囲まれてしまっている。通行人に紛れ距離は置かれているので、直ぐに襲われることはないだろうが、河岸壁に出たら一気に取り押さえるつもりなのだろう。聖職者に扮したグリシナと神父は一足早く教会を出ており、そちらの状況は分からない。ラースは道案内を買って出てくれた教会の修道士に囁いた。
「このまま道なりに進めばよろしいのですよね」
「はい、もうすぐ広場に出ますので、そうしましたら時計塔の脇の道を」
「有り難うございます。もうお戻りになって下さい。これ以上ご迷惑は掛けられません」
「しかし、危のうございます」
ラースのブルガリア語は聞き齧りで覚えたものなので、二人の会話はほとんど身振り手振りなのだが、修道士は青くなりながらラースの身の上を心配して離れ難いらしい。丁度広場に出たところで、ラースは建物の壁の方に寄り、修道士の手を取って額に付ける礼をした。修道士もラースが言っていることが分かったようで、深く腰を屈めて返礼すると、踵を返して小走りに戻っていく。修道士の後を追う者がいないことを視界の外で確認し、ラースはゆっくりと時計塔へ向かって歩き出した。
道は緩やかに下っていく。屋根屋根の間から空が青く輝き、鳥たちが囀り舞い遊ぶ。追われてなければ歩を止めて暫く眺めていたいものだ、とラースは考える。老馬は穏やかで人懐っこく、ラースが撫ぜてやると目を細めて喜ぶようだった。男たちのにじり寄る気配がする。建物の並びが切れるのも目前だ。ラースは溜息を吐いて、一日限りの相棒に耳打ちした。
「すまないが、よろしく頼む」
跳び乗り、腹を蹴ると、老馬はぐん、と姿勢を伸ばし駆け出した。元は農耕馬なのかもしれない、太い脚は力強く大地を踏みつける。男たちも馬を引き連れた者は鞭を鳴らして追い掛けてくる。川風がびゅうびゅうと耳元を叩く。
「見えた!」
教えられた通りの紋章を掲げたルスチュク港の関所だが、おかしい、とラースは目を細めて睨め付ける。なんだあの人だかりは。港湾警備兵らしき制服の男たちに押し留められているのは神父だ。何かあれば『自分は何も知らなかった』『旅の者に騙された』と仰って下さい、と言い含めてあったはずだが、必死に抵抗し訴えている。
「グリシナ!!」
エクソラソンのフードを引き剥がされ、後ろ手に石畳へ押さえ付けられているのは、見慣れた癖の有る黒髪だった。殴られたのか顔に酷い擦過傷が浮き、唇が血で紅く濡れている。満月のような瞳が、怒りで爛々と燃えている。ラースは頭が沸騰しそうになった。手綱を離し、抜刀しようとする。すると追いついてきた男の一人に馬体ごと体当たりされ、ラースも地面に放り出された。受け身は取ったが息が詰まる。立ち上がった時には、蹴り殺されるに充分な距離まで囲まれていた。
「ラース、止めろ!」
グリシナは叫んだが、背中を押さえ付けられているせいでまともに声が出ない。神父とグリシナが関所で通関の手続きをしていると、港湾警備兵たちがやってきた。違法脱国者の取り締まりだとして、グリシナを連れ出そうとし、抵抗したためにその場で殴られたのである。関所の職員たちは遠巻きに見ているだけだったので、港湾警備兵たちの横暴はよくあることなのかもしれなかった。霞む視界に見えるのは、取り囲まれた麦穂色の髪の大男である。馬から落ちて泥だらけの外套に、転がったターバン、だが、どんな時もどこか物寂しく諦めた視線は、今激情に染まっていた。彼の剣技が実際のところいかほどのものなのか、グリシナは知らないし、知りたいと思ったこともない。何故なら、ラースが刀を厭っているからだ。ラースは人を傷付けるのが嫌いである。それなのに、こんな状況に彼を追い込んだ自分を、グリシナは呪わずにいられなかった。
「そこまで!」
晴天に高らかに、銃声が鳴り響いた。港湾警備兵も、ラースを取り囲んだ男たちも、驚愕して振り返る。煙を吹くマスケット銃を掲げた男が、港に停泊していた船の一艘から、甲板の縁に足を掛け身を乗り出してこちらを見ていた。
「…イティア・エフェンディ」
「久しぶりだな、グリシナ。元気だったか…とは言えなさそうだが」
朗らかな声音に、無精程度の顎髭、短く刈られた海松色の髪に、刺繍の入った異国の外套。イティア・エフェンディ。ラースは逆光になっているその姿を見上げた。すると別の道から帝国軍憲兵の制服が一騎駆け出し、グリシナと神父を押さえ付けていた港湾警備兵たちの前に立ちはだかった。一方、イティアが銃を構え直しこちらへ照準を合わせている様子をを見てとった男たちは、ラースを残して散り散りに退散していった。
「グリシナ!グリシナ、大丈夫ですか」
ラースは刀を放り出すと、グリシナに走り寄り助け起こす。港湾警備兵たちは、帝国憲兵にに杖で押さえ込まれている。いつの間にやらイティアが船を降りて隣りに立っていた。
「まだ大物捕りとはいかないのだがね」
言いつつ外套の下から蒲黄(蒲の穂粉)を練ったものをラースに差し出す。ラースは礼を言ってグリシナの頬に触れた。グリシナはそれでも痛みに潤んだ瞳で、イティアを睨み返した。
「エフェンディ、何故ルスチュクに?」
「いや、お前たち遅いから」
こっちから出向いた訳。からりと笑うイティアに、ラースは今更やっと気が付いて敬礼する。イティアは笑い皺の付いた目元を緩ませ、ラースの肩に手を伸ばすと、ぱたぱたと埃を払ってやりながら言う。
「君、背が高いなあ。何て呼べばいい?」
今まで知っている軍の士官たちとは大分様子が違う。ラースは途惑いつつ答えた。
「ラースタチカと申します。エフェンディ」
「藤に燕か。良いコンビだ」
藤に燕。ラースは傍らのグリシナを見た。捻られていた手首を摩り、憮然としていたグリシナは、傷のせいだけでなく、唇を震わせて上気したようだった。
「エフェンディは、通訳官よりタチが悪い」
そうか、グリシナの名前の意味は藤なのだ。ラースは理解して、改めてイティアを見詰めた。今まで誰でも、仕事の上では通訳官と交渉官の上下関係を、身分の上ではグリシナの血統を憚かるような態度だったが、イティアは何も気にしていない。
「全くです。人使いの荒い」
港湾警備兵たちを縛り上げ、帝国憲兵が近付いてきた。ターバンに陰って気が付かなかったが、市庁舎で面会したあの書記官である。イティアは肩を竦める。
「有り難う、助かったよ。アルダに伝えておく」
「私は退役したんです。アルダ・ムラズィム(少佐・大尉への称号)のお役には立ちたいですが」
イティアはラースとグリシナに振り向くと、やれやれと溜息を吐く書記官を指差した。失礼である。
「彼は元アルダ・ムラズィムの部下なんだ。退役して書記官やってるけど。勿体無い」
「軍人が皆、望んで軍人になったと思われているなら大きな間違いですよ、エフェンディ」
「分かってる。悪かった。俺も似たようなもんだ」
呆気に取られて側に立ち竦んでいたラースに、教会の老馬が寄り添ってきた。体当たりされてこちらも倒れ込み、怒号と銃声に驚いて逃げてしまったのかと思ったが、ラースを心配して戻ってきたらしい。首筋を撫ぜてやると、まだ若干怯えているようだが、温かい頬を擦り寄せてくる。
「…帰って傷の手当てをなさった方が良いでしょう」
神父も随分乱暴に扱われたはずだが、グリシナへ顔を拭くよう布を差し出して言う。ラースは手綱を取り、グリシナへ手を伸ばした。
「グリシナ、乗って下さい」
グリシナはまだどこか咲き綻んだ花のようにそれぞれを見渡していたが、ラースがもう一度名を呼ぶと、振り向いて笑った。腫れて血と青なじみだらけの酷い顔だ。自分も泥だらけで、刀もどこかに放りっぱなしである。だけれど、彼女が自分の通訳官で、自分が彼女の交渉官であることが、とても誇らしいように感じる、幸せそうな笑顔だった。
「このまま道なりに進めばよろしいのですよね」
「はい、もうすぐ広場に出ますので、そうしましたら時計塔の脇の道を」
「有り難うございます。もうお戻りになって下さい。これ以上ご迷惑は掛けられません」
「しかし、危のうございます」
ラースのブルガリア語は聞き齧りで覚えたものなので、二人の会話はほとんど身振り手振りなのだが、修道士は青くなりながらラースの身の上を心配して離れ難いらしい。丁度広場に出たところで、ラースは建物の壁の方に寄り、修道士の手を取って額に付ける礼をした。修道士もラースが言っていることが分かったようで、深く腰を屈めて返礼すると、踵を返して小走りに戻っていく。修道士の後を追う者がいないことを視界の外で確認し、ラースはゆっくりと時計塔へ向かって歩き出した。
道は緩やかに下っていく。屋根屋根の間から空が青く輝き、鳥たちが囀り舞い遊ぶ。追われてなければ歩を止めて暫く眺めていたいものだ、とラースは考える。老馬は穏やかで人懐っこく、ラースが撫ぜてやると目を細めて喜ぶようだった。男たちのにじり寄る気配がする。建物の並びが切れるのも目前だ。ラースは溜息を吐いて、一日限りの相棒に耳打ちした。
「すまないが、よろしく頼む」
跳び乗り、腹を蹴ると、老馬はぐん、と姿勢を伸ばし駆け出した。元は農耕馬なのかもしれない、太い脚は力強く大地を踏みつける。男たちも馬を引き連れた者は鞭を鳴らして追い掛けてくる。川風がびゅうびゅうと耳元を叩く。
「見えた!」
教えられた通りの紋章を掲げたルスチュク港の関所だが、おかしい、とラースは目を細めて睨め付ける。なんだあの人だかりは。港湾警備兵らしき制服の男たちに押し留められているのは神父だ。何かあれば『自分は何も知らなかった』『旅の者に騙された』と仰って下さい、と言い含めてあったはずだが、必死に抵抗し訴えている。
「グリシナ!!」
エクソラソンのフードを引き剥がされ、後ろ手に石畳へ押さえ付けられているのは、見慣れた癖の有る黒髪だった。殴られたのか顔に酷い擦過傷が浮き、唇が血で紅く濡れている。満月のような瞳が、怒りで爛々と燃えている。ラースは頭が沸騰しそうになった。手綱を離し、抜刀しようとする。すると追いついてきた男の一人に馬体ごと体当たりされ、ラースも地面に放り出された。受け身は取ったが息が詰まる。立ち上がった時には、蹴り殺されるに充分な距離まで囲まれていた。
「ラース、止めろ!」
グリシナは叫んだが、背中を押さえ付けられているせいでまともに声が出ない。神父とグリシナが関所で通関の手続きをしていると、港湾警備兵たちがやってきた。違法脱国者の取り締まりだとして、グリシナを連れ出そうとし、抵抗したためにその場で殴られたのである。関所の職員たちは遠巻きに見ているだけだったので、港湾警備兵たちの横暴はよくあることなのかもしれなかった。霞む視界に見えるのは、取り囲まれた麦穂色の髪の大男である。馬から落ちて泥だらけの外套に、転がったターバン、だが、どんな時もどこか物寂しく諦めた視線は、今激情に染まっていた。彼の剣技が実際のところいかほどのものなのか、グリシナは知らないし、知りたいと思ったこともない。何故なら、ラースが刀を厭っているからだ。ラースは人を傷付けるのが嫌いである。それなのに、こんな状況に彼を追い込んだ自分を、グリシナは呪わずにいられなかった。
「そこまで!」
晴天に高らかに、銃声が鳴り響いた。港湾警備兵も、ラースを取り囲んだ男たちも、驚愕して振り返る。煙を吹くマスケット銃を掲げた男が、港に停泊していた船の一艘から、甲板の縁に足を掛け身を乗り出してこちらを見ていた。
「…イティア・エフェンディ」
「久しぶりだな、グリシナ。元気だったか…とは言えなさそうだが」
朗らかな声音に、無精程度の顎髭、短く刈られた海松色の髪に、刺繍の入った異国の外套。イティア・エフェンディ。ラースは逆光になっているその姿を見上げた。すると別の道から帝国軍憲兵の制服が一騎駆け出し、グリシナと神父を押さえ付けていた港湾警備兵たちの前に立ちはだかった。一方、イティアが銃を構え直しこちらへ照準を合わせている様子をを見てとった男たちは、ラースを残して散り散りに退散していった。
「グリシナ!グリシナ、大丈夫ですか」
ラースは刀を放り出すと、グリシナに走り寄り助け起こす。港湾警備兵たちは、帝国憲兵にに杖で押さえ込まれている。いつの間にやらイティアが船を降りて隣りに立っていた。
「まだ大物捕りとはいかないのだがね」
言いつつ外套の下から蒲黄(蒲の穂粉)を練ったものをラースに差し出す。ラースは礼を言ってグリシナの頬に触れた。グリシナはそれでも痛みに潤んだ瞳で、イティアを睨み返した。
「エフェンディ、何故ルスチュクに?」
「いや、お前たち遅いから」
こっちから出向いた訳。からりと笑うイティアに、ラースは今更やっと気が付いて敬礼する。イティアは笑い皺の付いた目元を緩ませ、ラースの肩に手を伸ばすと、ぱたぱたと埃を払ってやりながら言う。
「君、背が高いなあ。何て呼べばいい?」
今まで知っている軍の士官たちとは大分様子が違う。ラースは途惑いつつ答えた。
「ラースタチカと申します。エフェンディ」
「藤に燕か。良いコンビだ」
藤に燕。ラースは傍らのグリシナを見た。捻られていた手首を摩り、憮然としていたグリシナは、傷のせいだけでなく、唇を震わせて上気したようだった。
「エフェンディは、通訳官よりタチが悪い」
そうか、グリシナの名前の意味は藤なのだ。ラースは理解して、改めてイティアを見詰めた。今まで誰でも、仕事の上では通訳官と交渉官の上下関係を、身分の上ではグリシナの血統を憚かるような態度だったが、イティアは何も気にしていない。
「全くです。人使いの荒い」
港湾警備兵たちを縛り上げ、帝国憲兵が近付いてきた。ターバンに陰って気が付かなかったが、市庁舎で面会したあの書記官である。イティアは肩を竦める。
「有り難う、助かったよ。アルダに伝えておく」
「私は退役したんです。アルダ・ムラズィム(少佐・大尉への称号)のお役には立ちたいですが」
イティアはラースとグリシナに振り向くと、やれやれと溜息を吐く書記官を指差した。失礼である。
「彼は元アルダ・ムラズィムの部下なんだ。退役して書記官やってるけど。勿体無い」
「軍人が皆、望んで軍人になったと思われているなら大きな間違いですよ、エフェンディ」
「分かってる。悪かった。俺も似たようなもんだ」
呆気に取られて側に立ち竦んでいたラースに、教会の老馬が寄り添ってきた。体当たりされてこちらも倒れ込み、怒号と銃声に驚いて逃げてしまったのかと思ったが、ラースを心配して戻ってきたらしい。首筋を撫ぜてやると、まだ若干怯えているようだが、温かい頬を擦り寄せてくる。
「…帰って傷の手当てをなさった方が良いでしょう」
神父も随分乱暴に扱われたはずだが、グリシナへ顔を拭くよう布を差し出して言う。ラースは手綱を取り、グリシナへ手を伸ばした。
「グリシナ、乗って下さい」
グリシナはまだどこか咲き綻んだ花のようにそれぞれを見渡していたが、ラースがもう一度名を呼ぶと、振り向いて笑った。腫れて血と青なじみだらけの酷い顔だ。自分も泥だらけで、刀もどこかに放りっぱなしである。だけれど、彼女が自分の通訳官で、自分が彼女の交渉官であることが、とても誇らしいように感じる、幸せそうな笑顔だった。