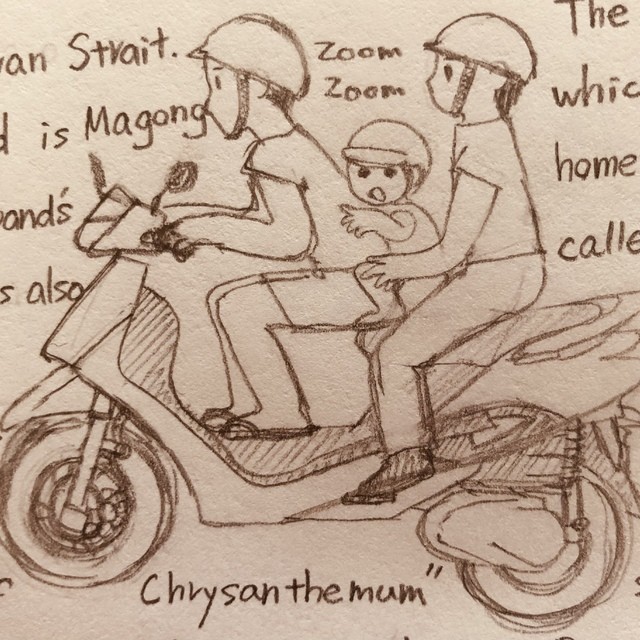一、邂逅
文字数 3,070文字
太陽が金角湾を黄金に染めて沈んでいく。東の空から藍色に煙り、雲は薔薇色に縮れて流れていく。ラースは足を止めて、天を仰いだ。静謐で美しい彼方に思いを馳せるが、通りにはまだ大勢の人々が行き交っている。ここはヨーロッパとアジアに跨る世界随一の都市、オスマン帝国の首都コンスタンティニエだ。ふと懐かしい言葉が耳に届いて、ラースは首を巡らせた。
埃っぽい服と髪の子供が、ストールの主人にしきりに話しかけている。言葉が通じず、主人は困り顔だ。ラースはこちら側の人通りを抜けて、ストールに近付いた。
「どうしたの」
屈んで視線を下ろし、ロシア語で子供に尋ねる。背後から突然現れた青年に子供は途惑ったようだったが、同じ言葉を話すらしい、と気が付いて大分低いところからラースを見上げてきた。
「弟に、何か食べさせてあげたいの。熱を出していて…」
そうか、とラースは頷くと、腰を上げてストールの主人に向いた。少女も主人も明らかに驚いたようだったが、慣れている。ストールの屋根に打つかりそうな長身に、麦穂色の髪、外套の下は帝国官吏の制服。そのクシャック(帯)の吊りから硬貨を取り出すと、唖然としているストールの主人に渡しながら尋ねる。
「蜂蜜とバターと粥用のオーツを」
「そりゃ有りますが、どこか悪いんですか、この子」
ラースが頼んだものを聞いて、主人は複雑な顔をした。うちにも小さな子がいるんでね、やってられませんよ、こう子供の物乞いが増えちゃ…
「弟が熱を出しているそうだ」
身なりからして、戦火で親とはぐれたか、一緒にいても養えきれなくなったのだろう。少女は痩せてちっぽけで、汚れた顔に窪んだ目を瞬かせている。だが、これ以上は何もできない。同じような境遇の子供たちは数え切れないほどいるのだ。ストールの主人もそれを分かっていて、やるせない表情で少女にオーツの袋を持たせてやる。おまけに、パンを一切れ入れてやっているのを、ラースは横目に見ていた。
「お粥の作り方は分かるかい?」
「うん、でもお鍋が無い」
「先ずは弟に蜂蜜とバターを溶いて飲ませてあげるといい。君も食べて、モスクか教会へお行き。彼らも手立てが無いかもしれないが、鍋と水を貸してくれるだろう」
今モスクも教会も戦争から逃れてきた人々で溢れかえっている。ラースは溜息を吐いた。
「有り難う、お役人様、お店のおじさん」
オーツの袋を大事そうに抱え、少女は礼を言うと、路地裏へ走り去っていった。ストールの主人は暫くその後ろ姿を見送って髭を撫ぜ、改めてラースを見る。
「どうにかならないんですかね、“お役人様“」
「いや、俺は官吏と言っても、」
ラースが答える前に、少女が戻っていった路地から小さな悲鳴が上がった。通りは今だ人々と馬車の騒音がひしめいており、耳に入っても野良猫の喧嘩くらいにしか思わないだろうその声に、しまった、とラースは駆け出す。そんな境遇の子供も大人もいくらでもいる。弱い者は奪われる。
「何をしている!」
二階建ての家々の隙間を畝る小道は、黄昏の光も途切れてもう薄暗い。男たちの影が、少女を壁際へ追い詰めていた。ラースの呼び掛けに少女は振り向くと、男の一人に体当たりして輪の中から逃れようとする。しかし、空腹で疲れ切った子供の力など高が知れている。男の大きな手が伸びて少女の頭髪を掴み上げ、口元を覆い、細い肩を締め付けた。声を出させないようにだろうが、窒息しようが構わないのだろう。恐慌に青褪めた少女の顔に、ラースは後ずさった。
「こいつあコソ泥さ。あんたにゃ関係ない」
テュルクでもないスラヴでもない、何を言っているのか分からない。だが下手に動くと少女が危ない。護身用の短刀は身に付けているが、使い方には全く自信が無い。躊躇した一瞬に他の男二人に突進され、鳩尾をしたたかに殴られる。よろけたところを一人の男に背後から羽交い締めにされ、二度三度と殴打される。口の中に鉄の味が広がり、舌が腫れて言葉が出ない。脱力したところを、男たちはラースの外套を剥いで金目のものを物色しだした。
「大したことねえな。宮廷も金が無いのかねえ」
「その通り」
朦朧とし出した意識が覚醒する。反対側へ抜ける道から、声が響いた。意味は分からない。だが濁った視覚を引き戻されたのは、鈍重な直弾音のせいだった。声の主は反響の中軽快に駆け寄ると、少女を捕まえていた男の顳顬を勢いのまま短剣の柄で凪ぎ叩く。耳を掠めた銃弾に半ば呆然としていたらしい男は、身構えもできず衝撃に仰反ると、そこへ憲兵が踏み込み、男たちを縛り上げた。銃声は、威嚇のためだったのだろう。
「あんた、このご時世丸腰ってどういうこと」
憲兵が男たちを引っ張っていった後も尻を着いたままだったラースは、声の主を見上げた。テュルクだ。緩く流れる黒髪を簡易ターバンで纏め、ジュッべを着流した背はすらりと伸びている。胡桃色の艶やかな肌に、青銅の大きな瞳が月のように光っている。片手に握った短刀には上品な装飾が施されており、主人の身分を物語っていた。我に返り、ラースは辺りを見回した。少女はまだ、震えて立ち尽くしていた。
「怪我は無い?すまない、気付くべきだった。送ろう」
身を起こすと吐き気が迫り上がるが、殴られたところを庇いつつ、ラースは少女に近付いた。大きく見開かれた目に涙が溜まっているが、オーツの袋をしっかり抱いたまま、歯を食いしばって耐えている。
「…君は勇敢だね。さあ、帰ろう」
無闇に女性に触れるべきではないが、それよりも優先されるべきこともある。ラースは少女の痩せた肩に軽く触れた。少女の強張っていた表情がじわりと緩んだが、唇は引き締めたまま小さく頷いた。ラースは振り返り、まだそこでラースたちの様子を眺めている黒髪の青年に礼をした。
「助けて戴き、有り難うございます」
腕を組み、考えごとをしていたらしい青年は、爛とした瞳で興味深そうにラースを見た。
「あんたも官吏だろう。こんな所で何してんだ」
「俺は通りすがりに巻き込まれただけです。貴方は軍の?」
は、と青年は鼻先で笑った。無花果を舐めたような紅い口内が夜気に浮かび上がる。
「私は通訳官(ドラゴマン)だ。“剣を用いず守るもの”」
そうか、とラースは納得した。先刻からあの男たちの言葉も、少女と自分のやりとりも全て理解できているらしいのは、彼が複数の言語を操る通訳官であるからだ。帝国は、多民族を支配下に置き、多くの国と交易・戦争をするため、通訳・翻訳を専門とする官職を設けている。使節団に随行し、軍の遠征に従い、属領に派遣される政務官たちを補佐する、彼らは通訳官(ドラゴマン)と呼ばれる。
「あんたの所属は?見たところ財務官か」
宮廷では役職によって制服が異なるため、知っている者から見れば、ラースが財務部の職員であることは直ぐに分かる。
「はい、財務官のラースタチカと言います…」
助けて貰った相手なので礼儀を通そうと思ったのだが、名乗ってから後悔した。相手が明らかに破顔したからである。そうだ、スラヴが分かるんだった、この人。
「ラースタチカ(燕)!その図体で!?」
身長が高いのはどうしようもない。駐屯地での雑役経験が長く、筋力は付いたが、戦闘にはさっぱり向いていなかった。それでも幼い頃はチビで愚図で引っ込み思案の農家の三男坊だったから、名前はラースタチカと適当なのだ。通訳官はにやにやと笑いながら、ラースににじり寄り、背中をばしりと叩いた。傷に響いて、ラースは息を詰める。
「よし、先ずは彼女を送っていこうか、ラース」
埃っぽい服と髪の子供が、ストールの主人にしきりに話しかけている。言葉が通じず、主人は困り顔だ。ラースはこちら側の人通りを抜けて、ストールに近付いた。
「どうしたの」
屈んで視線を下ろし、ロシア語で子供に尋ねる。背後から突然現れた青年に子供は途惑ったようだったが、同じ言葉を話すらしい、と気が付いて大分低いところからラースを見上げてきた。
「弟に、何か食べさせてあげたいの。熱を出していて…」
そうか、とラースは頷くと、腰を上げてストールの主人に向いた。少女も主人も明らかに驚いたようだったが、慣れている。ストールの屋根に打つかりそうな長身に、麦穂色の髪、外套の下は帝国官吏の制服。そのクシャック(帯)の吊りから硬貨を取り出すと、唖然としているストールの主人に渡しながら尋ねる。
「蜂蜜とバターと粥用のオーツを」
「そりゃ有りますが、どこか悪いんですか、この子」
ラースが頼んだものを聞いて、主人は複雑な顔をした。うちにも小さな子がいるんでね、やってられませんよ、こう子供の物乞いが増えちゃ…
「弟が熱を出しているそうだ」
身なりからして、戦火で親とはぐれたか、一緒にいても養えきれなくなったのだろう。少女は痩せてちっぽけで、汚れた顔に窪んだ目を瞬かせている。だが、これ以上は何もできない。同じような境遇の子供たちは数え切れないほどいるのだ。ストールの主人もそれを分かっていて、やるせない表情で少女にオーツの袋を持たせてやる。おまけに、パンを一切れ入れてやっているのを、ラースは横目に見ていた。
「お粥の作り方は分かるかい?」
「うん、でもお鍋が無い」
「先ずは弟に蜂蜜とバターを溶いて飲ませてあげるといい。君も食べて、モスクか教会へお行き。彼らも手立てが無いかもしれないが、鍋と水を貸してくれるだろう」
今モスクも教会も戦争から逃れてきた人々で溢れかえっている。ラースは溜息を吐いた。
「有り難う、お役人様、お店のおじさん」
オーツの袋を大事そうに抱え、少女は礼を言うと、路地裏へ走り去っていった。ストールの主人は暫くその後ろ姿を見送って髭を撫ぜ、改めてラースを見る。
「どうにかならないんですかね、“お役人様“」
「いや、俺は官吏と言っても、」
ラースが答える前に、少女が戻っていった路地から小さな悲鳴が上がった。通りは今だ人々と馬車の騒音がひしめいており、耳に入っても野良猫の喧嘩くらいにしか思わないだろうその声に、しまった、とラースは駆け出す。そんな境遇の子供も大人もいくらでもいる。弱い者は奪われる。
「何をしている!」
二階建ての家々の隙間を畝る小道は、黄昏の光も途切れてもう薄暗い。男たちの影が、少女を壁際へ追い詰めていた。ラースの呼び掛けに少女は振り向くと、男の一人に体当たりして輪の中から逃れようとする。しかし、空腹で疲れ切った子供の力など高が知れている。男の大きな手が伸びて少女の頭髪を掴み上げ、口元を覆い、細い肩を締め付けた。声を出させないようにだろうが、窒息しようが構わないのだろう。恐慌に青褪めた少女の顔に、ラースは後ずさった。
「こいつあコソ泥さ。あんたにゃ関係ない」
テュルクでもないスラヴでもない、何を言っているのか分からない。だが下手に動くと少女が危ない。護身用の短刀は身に付けているが、使い方には全く自信が無い。躊躇した一瞬に他の男二人に突進され、鳩尾をしたたかに殴られる。よろけたところを一人の男に背後から羽交い締めにされ、二度三度と殴打される。口の中に鉄の味が広がり、舌が腫れて言葉が出ない。脱力したところを、男たちはラースの外套を剥いで金目のものを物色しだした。
「大したことねえな。宮廷も金が無いのかねえ」
「その通り」
朦朧とし出した意識が覚醒する。反対側へ抜ける道から、声が響いた。意味は分からない。だが濁った視覚を引き戻されたのは、鈍重な直弾音のせいだった。声の主は反響の中軽快に駆け寄ると、少女を捕まえていた男の顳顬を勢いのまま短剣の柄で凪ぎ叩く。耳を掠めた銃弾に半ば呆然としていたらしい男は、身構えもできず衝撃に仰反ると、そこへ憲兵が踏み込み、男たちを縛り上げた。銃声は、威嚇のためだったのだろう。
「あんた、このご時世丸腰ってどういうこと」
憲兵が男たちを引っ張っていった後も尻を着いたままだったラースは、声の主を見上げた。テュルクだ。緩く流れる黒髪を簡易ターバンで纏め、ジュッべを着流した背はすらりと伸びている。胡桃色の艶やかな肌に、青銅の大きな瞳が月のように光っている。片手に握った短刀には上品な装飾が施されており、主人の身分を物語っていた。我に返り、ラースは辺りを見回した。少女はまだ、震えて立ち尽くしていた。
「怪我は無い?すまない、気付くべきだった。送ろう」
身を起こすと吐き気が迫り上がるが、殴られたところを庇いつつ、ラースは少女に近付いた。大きく見開かれた目に涙が溜まっているが、オーツの袋をしっかり抱いたまま、歯を食いしばって耐えている。
「…君は勇敢だね。さあ、帰ろう」
無闇に女性に触れるべきではないが、それよりも優先されるべきこともある。ラースは少女の痩せた肩に軽く触れた。少女の強張っていた表情がじわりと緩んだが、唇は引き締めたまま小さく頷いた。ラースは振り返り、まだそこでラースたちの様子を眺めている黒髪の青年に礼をした。
「助けて戴き、有り難うございます」
腕を組み、考えごとをしていたらしい青年は、爛とした瞳で興味深そうにラースを見た。
「あんたも官吏だろう。こんな所で何してんだ」
「俺は通りすがりに巻き込まれただけです。貴方は軍の?」
は、と青年は鼻先で笑った。無花果を舐めたような紅い口内が夜気に浮かび上がる。
「私は通訳官(ドラゴマン)だ。“剣を用いず守るもの”」
そうか、とラースは納得した。先刻からあの男たちの言葉も、少女と自分のやりとりも全て理解できているらしいのは、彼が複数の言語を操る通訳官であるからだ。帝国は、多民族を支配下に置き、多くの国と交易・戦争をするため、通訳・翻訳を専門とする官職を設けている。使節団に随行し、軍の遠征に従い、属領に派遣される政務官たちを補佐する、彼らは通訳官(ドラゴマン)と呼ばれる。
「あんたの所属は?見たところ財務官か」
宮廷では役職によって制服が異なるため、知っている者から見れば、ラースが財務部の職員であることは直ぐに分かる。
「はい、財務官のラースタチカと言います…」
助けて貰った相手なので礼儀を通そうと思ったのだが、名乗ってから後悔した。相手が明らかに破顔したからである。そうだ、スラヴが分かるんだった、この人。
「ラースタチカ(燕)!その図体で!?」
身長が高いのはどうしようもない。駐屯地での雑役経験が長く、筋力は付いたが、戦闘にはさっぱり向いていなかった。それでも幼い頃はチビで愚図で引っ込み思案の農家の三男坊だったから、名前はラースタチカと適当なのだ。通訳官はにやにやと笑いながら、ラースににじり寄り、背中をばしりと叩いた。傷に響いて、ラースは息を詰める。
「よし、先ずは彼女を送っていこうか、ラース」