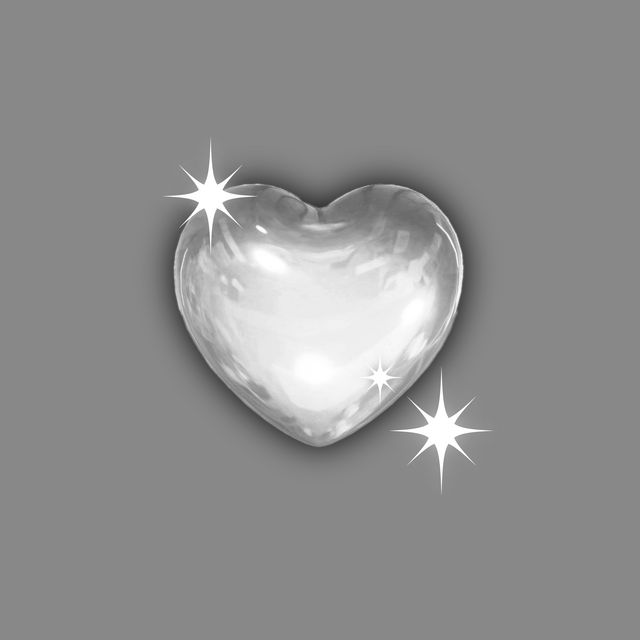5.結婚式と海
文字数 9,246文字
好きだよ。言葉にしてしまったことで自覚せざるを得なかった。僕はいつの間にか幽霊に恋をしている。触れられない、そんな甘い悪夢に閉じ込められるような霊感に溺れている。そして、出来るわけがないからこそ数々の行為を望んでいる。たとえば、手を繋ぐ。抱き合う。そしてキスやセックス。こんな欲求不満は大人になってからは久しぶりだった。初めて自分の唇に重なる他人の唇を想像したのは、確か、思春期よりもずっと前だ。好きな相手が自分を好きになり、そのまま結婚すると信じていた頃だ。相手が幽霊だろうが死んでいようが、出来るものならしたいと願う今の僕は、ピュアさの欠片もないただの物好きになってしまった。
──くだらないよな。
僕は鏡の中の自分を見ながらそんなことを考えていた。鏡の中の僕は目の下に薄い隈を浮かべながらも、唇の端を緩やかに上げていた。自分の笑顔が他人のものに見えた。僕の見る僕は皺ひとつないスーツに身を包み、いつもは締めないネクタイまで締めている。だけど今日は仕事ではない。素直にもっとおめでたい日だ。結婚式。僕のためのではない。真依の結婚式のために、僕はドレスコードをキメている。
元カノでありながらなんとなく身体を重ね続けている真依。彼女は今日、結婚式を挙げ、浮気の疑惑をいくつも巻き散らかしたままの結婚相手と、真依は人生を共に歩み始める。別に真依はそれでいいらしい。何も迷いはないらしい。彼女が彼女なりに定めた幸せはあまりにも潔く、僕には意味不明に眩しかった。真依はあろうことか僕を堂々と結婚式に招待した。いつものように僕の部屋へ転がり込んできた夜。長いキスの後で、自分を押し潰そうとする後ろめたいものが初めから何もないかのように、裸の彼女は言ったのだった。「ねぇ。拓ちゃん。呼んだら結婚式来てくれるよね?」「……いいけどなんで?」そう言った僕に、彼女は続けた。「ドレスなんて、お祝いしてくれる人たち皆に見せてあげたいもん」
「それって真依が可愛いから?」
「ふふ」
「すごいね。真依は」
「うん。私は幸せになるしかないから」
真依は言い切った。そして両腕を僕に絡め、抱き寄せた。僕は真依の強さに窒息しそうな気持ちになった。そして、誰かに攫われたいとも攫いたいとも思うことのないウェディングドレスの純白を思い、力無く笑い声を吐き出すことしか出来なかった。釣られるようにして真依も笑った。他の誰でもない、自分の未来のために、一日を目一杯着飾る彼女。人に流されっぱなしの僕は流されたままどこかに置いていかれるのだと思った。だったらせめて僕の今を気持ち良くしろよ。そう思いながら彼女を押し倒し、荒々しくキスをした。
**
「新郎新婦のご入場です」
女性の司会が言い、厳かな扉が開いた。Aラインのウェディングドレスに身を包んだ真依は、まるで知らない国のプリンセスのようで、僕の知らない新しい真依に見えた。新郎の男はなるほど、笑顔と白い歯がよく似合う爽やかさ200%の男だった。僕の周りで学生時代の同級生が「可愛いね、真依」「めっちゃ綺麗!」などと囁き合っていた。僕はウエディングドレスに包まれた彼女の身体を眺めた。真依のウエストは細く、いつか彼女が宿すのかもしれない子どもが、僕との子じゃないことになぜかほっとしていた。全部やるよ。幸福そうな新郎に心の中で告げ、僕は2人を祝福した。やるだなんて、別に初めから僕のものでもないのに。真依の首元には何連にも連なるアクセサリーが照明の光を受けて輝き、彼女の華奢さを際立てていた。僕は一度だけあの首を締めたのを思い出していた。結婚式の10日程前のことだ。彼女の独身生活を締めくくるであろうセックスを僕たちはした。正常位で見つめ合っている最中。挿れて少し経った頃に真依は潤んだ瞳で言った。「拓ちゃん」
「何」
「ねぇ。私の首、絞めてみてくれる?」
想像もしない言葉に、僕は思わず前後の動きを止めた。真依を真っ直ぐに見下ろしたまま、部屋を暖めるエアコンの音の中で聞き返した。
「そういうの好きだったんだ?」
僕の問いかけに真依は答えなかった。
「なんか、一回だけ苦しくなりたいの」
「なんで」
「私の馬鹿なとこだけ、死んで消えちゃえばいいなーって」
真依の軽い口調はかえって切実に聞こえた。僕は一瞬だけ躊躇したものの、僕は真依のか細い白い首を絞めた。折れそうだと思った。そして結局は燃えてしまった。「もっと強くして」と言われ、躊躇いながらも手に力を込め続け、息継ぎでさえキスで遮った。その瞬間、真依が可愛くて、一瞬だけ僕の手の中で死んでしまえばいいと本気で思った。大切な玩具に対する子どもの独占欲と大人の性欲の混じり合った暴力的な感情だった。真依が苦しむと、繋がった部分が連動するように締まった。ああ、気持ちいいなと思いながら僕は腰を打ちつけ真依を貪った。快楽の波に溺れ、すぐに出てしまった。精液は。快楽と共に余分な愛情めいたものが抜け、身も心も軽くなったように感じられた。真依の身体の上で呼吸を荒げながら、これなら手放せると漠然と思った。それなのに真依より苦しいのはきっと僕だった。
少しの気まずさを残した長い沈黙の中、僕は言った。
「ごめん。大丈夫だった? 痛かったよね」
真依は首を小さく横に振った。首はかすかに赤みを帯びていた。
「気持ち良かった。それに、してって言ったの私だもん」
「したのは僕だよ」
「いいよ。それよりさ」
「何?」
「多分、これが最後だったよね」
「だね」
どこか解放された表情で僕たちは見つめ合った。楽しかったし、気持ちよかった。僕の扱える愛情なんてそれしかない。そして、愛情のある・ないなんて枕詞は、本当にセックスによく似合う。ただの行為、快楽ひとつに振り回されている自分が滑稽に感じられる。今、どうしてこんなに寂しいのだろうと不思議にも思う。動物の雄だからだろうか。それとも結局、人間だからだろうか。
「真依、おめでとう」
「ありがとう」
拓ちゃん。絶え間なく真依は僕の髪を撫で、小さい子にするように僕をあやした。僕はそれが嫌で真依を抱き寄せた。真依は僕の腕の中で自由を失い、僕はようやく束の間の満足を手に入れた。きっと忘れないだろうと思ったのは「お幸せにね」と吹き込んだ先にある彼女の耳が、火照る身体に反して冷たかったということだけだ。
**
滞りなく披露宴は進んでいる。「本当にお似合いだね!」と、真依と僕、共通の女友達が無邪気にはしゃぎ、ケーキの入刀にも友人代表のスピーチにも、絶え間ない幸せが降り注いでいる。幸せを包み込む会場は、ナチュラルなグリーンと白を基調とした花々に彩られていた。僕の心の中でそれらは徐々に色を失い優しげなモノクロームに映った。指輪の交換の直後、僕と真依はっきりと視線を合わせた。僕たちは互いに微笑み合った。お色直しの度に、真依は可愛く、綺麗になっていくが、そのときの犯罪めいた微笑みが、振り返ればいちばんよかった。
僕と彼女の距離は開いていくようだった。だけどそれでいい。周りを見渡すと近くのテーブルで真依の両親は目を赤くして泣いているようだった。最後に投げられたブーケは、昔から真依とよくつるんでいた女の子の手に渡った。涙や笑い声といった澄み切ったもので溢れていた。いい式だったと皆が感想を抱くであろう、完璧な披露宴だったように思う。彼女にとても相応しい。
二次会は途中で抜けた。皆と学生時代の想い出話に花を咲かせるのは楽しかったが、一度外の空気を吸いに出たら、最後までいる気になれなかった。「ごめん。先に帰ったって言っておいてくれる?」僕は隣に座る同級生の女の子に耳打ちをした。「それから、真依に本当におめでとうって伝えて」僕はそう言い残し、重いコートを掴んだ。酒を飲めば飲むほど、言葉にならない自己嫌悪に耐え切れなくなっていくのがわかった。僕は、僕以上に幸せな真依を本当は見たくなかったのかもしれない。
店を出ると電車をいくつか乗り継ぎ、冬の空の下を気ままに歩いた。右、左、右、右、直進。道は無作為に選んだはずだった。だけど足取りは結局、自ずといつもの墓地へと向かっていた。忘れてはいない。一番好きなのは幽霊の彼女だ。存在するはずもないはずの世奈だ。今、眩しいものを浴びすぎてとても疲れている。だから僕は幽霊に会いたかった。彼女と接し続けている限り、生きている誰かに何かを傷つけられることはないような気がする。ある日偶然手に入れた霊感は、僕の現実逃避として完全に役に立っている。
白い息を吐き続け、お気に入りの静かな場所に辿り着いた。連なる墓石たちはミニチュアのビル群にも見え、僕はそびえ立つ何かだった。当然、今ここには誰もいない。だけど、寂しげに点滅する街灯の側で僕は夜の挨拶をする。「世奈」と祈るように小さく呟く。今日もどこか遠くで犬が吠えている、その声がわずかな現実感を僕に与えている。
「世奈。いるよね?」
「……うるさい」
少しの間をあけて彼女は闇の中から現れた。そして、口を開くなり今日も僕を睨んだ。墓の上に直立し腕を組んでいる幽霊。月の光は透ける身体を通り抜けて墓石を照らし、彼女が生きた存在ではないと僕に教えている。僕にとっての現実というファンタジー。その臨界点に世奈はいる。
「何それ」
「これ? 引き出物。今日、知り合いが結婚したんだよね。おめでたいでしょ」
「私には関係ないけど」
「全部あげるよ」
僕は別にいらないから。そう言うと、どこかのバームクーヘンと分けてもらった式場の花を、僕は無造作に墓に供えた。しゃがんだまま、紙袋から取り出したカタログギフトも軽く捲る。世奈の好きなものはなんだろうと一生懸命に考えながら。死んだ本人を目の前にした不思議な墓参りも、すっかり慣れた。「なんか欲しいの合ったら頼んどくけど」と言いながら高級ランク牛肉のページで指先は止まった。美味しそうな赤い肉だった。ふと見上げると、幽霊は僕の上で足を組んでいた。美味しいものを美味しいと言い仲良く味わうのは生きた者同士の特権で、僕たちには関係なさそうではあった。
「食べたくない? これ」
「いらない」
世奈はいつも通り興味なさげに一刀両断し、そうだよねと僕は笑った。僕はめげずにカタログのページを後ろの方まで進めた。バスグッズや美容家電といった生活雑貨のカテゴリを通り過ぎると、現れたのは体験型のギフトの数々だった。訪れたことのない土地の旅館、魅力的な一泊二日のプランがいくつも掲載されている。東北。北陸。九州。僕はさまざまな土地に想いを巡らせ、言った。
「世奈、旅行行こうよー」
「は?」
「一緒に蟹食べよ」
「無理」
「じゃあ肉は? なんか今すぐ生き返れない?」
「無理だって。骨ごと身体焼いたし。てかさ」
「うん」
「……成仏させてくれるんでしょ? 私、待ってるんだけど」
「あぁ。ごめんそうだったね」
「自分の言ったことに責任取れって。私より大人なんだから」
世奈は墓から降り、座り込んだ僕と目線の高さを合わせた。幽霊の冷えた空気が肌の表面を撫でた。凍てつくような呪いの視線を浴び、身体が奥から痺れる。それでも、死んだ女の子に説教をされるシチュエーションはどこか心地よく、僕は成仏を後回しにしたくなった。どうせ方法もわからない。
「そういえばお前、この間、私のこと好きって言ったよね」
「言ったね」
僕は無責任に放った自分の「好きだよ」をおもむろに思い出した。彼女にそう言ったのは前回のデート、神社の階段を降り切った頃だ。空気に流された結果の気もするけど、嘘を言ったわけではない。
「だけど、私は全然、お前のこと好きじゃないから。忘れないでね」
「そっか。それでいいよ。ありがとう」
「……」
「あー、楽しいね」
「お前今日なんかキモいよ。いつもよりヘラヘラしてない? 死ねばー」
そう言われ、僕は思わず零した。「そういえばさ、元カノが結婚したんだよね。今日」と。人に話してみると、感傷はびっくりするほど陳腐だった。ついでに「仕事もあんまり上手くいってないんだよね」とも打ち明けた。僕の日常なんてあまりにもありきたりで、出来事のほうが絶望に追いついていないのだとよくわかった。だから「ふーん」という世奈の反応ももっともだった。今から死ぬ。それは別に悪くない提案のように思えた。今死ねば世奈と仲良く幽霊になれるような気がした。
「別にどっか行ってもいいけど」
世奈は気付けばカタログギフトの誌面を覗き込んでいた。幽霊の透ける身体の奥で、バスタオルを巻いた女性が笑顔で温泉に浸かっていた。幽霊に取り憑かれながら旅行するのは面白そうだ。うっかり途中で死ぬのかもしれない。
「じゃあどこにする?」
「海」
「海?」
僕は間髪入れずに聞き返した。きらめく太陽に白い砂浜、ブルーオーシャンと弾ける笑顔を瞬時に思い浮かべ、無理だろと思った。幽霊に海は似合わない。そもそも、朝になれば幽霊は消えると世奈本人は語っていた。僕たちがアクセス可能なのは、せいぜい凍てつくような冬の夜の海だ。太陽には初めから負けている。
「行こ」
世奈はおもむろに月を見上げ、そう言った。
「え。今から?」
「夜なんて早くしないと終わるよ。朝が来る前に死んじゃうかもよ。お前も」
世奈は墓石を離れ、浮遊で移動を始めた。僕は慌ててその後ろ姿を追いかけた。足という足が無いからか、世奈の移動は速かった。だけどここから海なんて歩いていける距離じゃない。どうしよう。そこに都合よく通りかかった一台のタクシー。僕は手を挙げて捕まえると、開けられた後部ドアから座席に乗り込んだ。一緒に乗ってよと目で訴えかけると、世奈は僕に続いて乗り込んだ。生きている人間と死んでいる人間を乗せてタクシーのドアは閉まった。タクシーの運転手は「お客さん、どちらまで?」とあまり抑揚のない声で尋ねた。僕は「いちばん近い海まで」と言いかけては飲み込み、記憶を頼りに適当な地名を告げた。こんな季節と時間帯に海に行くなんて、うっかり自殺志願者と思われたら困る。犯罪を怪しまれても困る。僕たちのことは誰にも何も一切気にされたくはなかった。なんせひとりは幽霊なのだから。
安全運転で墓場からはみるみるうちに遠ざかる。当然、世奈の存在に運転手は気づかず「明日からまた冷えるらしいですね」だとか「今年は雪、降りますかね」といった世間話を僕に投げかけている。「そうですね」適当に相槌を打ちながら、僕は隣の幽霊を横目で眺める。「こうしたら事故るのかな」などと言い、運転手の目を両手で塞ぐ、悪質な半透明の姿を。
ラジオからは古いJ-POPが流れていた。子供の頃、親の車でよく聴いた曲だった。機嫌が良いのだろう、世奈は小さく口ずさんでいた。僕は風のような幽霊の歌に聞き入っていた。あんなに「死ね」と僕に言っているのに柔らかい歌声をしている。不思議なアンバランスだ。世奈は歌いながら外の景色に見入っている。一体、彼女はどんな表情をしているのだろう。タクシーがトンネルを通ったときに窓に目を凝らしたが、そこには僕の顔しか写っていなかった。だけど、確実に世奈はいる。少なくとも僕はそう信じ、シートに身を預ける。万が一の事故に備え、目も閉じたままでいる。
「お客さん」
うっかり寝落ちしそうになった頃、運転手に声をかけられた。辺りを見回すと、見覚えのあるようなないような景色が広がっていた。きっと目的地が近いのだとわかった。「この辺でいいです。降ろしてください」僕はそう伝え、少し怪訝な顔をした運転手にクレジットカードを渡し支払いを終えた。
タクシーが遠ざかり、深呼吸をすると鼻の奥まで潮の香りが突き抜けていった。導かれるようにして僕は少しの間、歩いた。海へは迷わず辿り着けた。文字が剥げかけ、淵の錆びた「立ち入り禁止」の看板を乗り越え、夜の砂浜に踏み込む。辺りに目を凝らす。現れた海という景色はとてつもなく暗い。というより黒い巨大な生き物のようだった。僕はひとりでこんな怖いところに来たのだろうかと、心細い気持ちになった。そういえば、世奈は。周りを見渡すとちゃんと世奈はいた。少し離れたところに浮かんでいた。世奈の姿はむしろ墓場にいるときよりもはっきりとした存在感があった。幽霊に海はよく似合っていた。きっと、より多くの死を孕んでいるからかも知れない。
「気持ちいいよね?」
「そうだね。僕は少し寒いけど」
世奈は僕を一瞥するとさらにふわふわと漂い始めた。辺りは完全に暗く、夜と海と闇の境は曖昧だった。僕たちは黙々と砂浜を歩いた。その辺に落ちている朽ちかけたゴミの正体を考えたり、砕け散る泡の白を僕は眺めた。波の打ち寄せる規則的な音に身を任せていると、現実的なものが削ぎ落とされ、次々と非現実的な考えが浮かんでいった。一体、どこへ向かっているのだろう。このまま歩き続けたら黄泉の世界に行けるんじゃないか。そうして、世奈は僕を殺そうとしているんじゃないか、と。そもそもどうして世奈は僕にキスをしたんだろう。僕は霊感を手に入れ、世奈と出会ってしまったのだろう。何もわからない。
──世奈は、僕をどう思っているんだろう。
そう思った途端、突然、目の前で世奈の浮遊は止まった。僕はうっかり世奈の身体を通り抜けてしまった。冷気に痺れたような感覚に襲われ、僕は砂浜につまずいた。そして歩く気が失せ、その場になんとなく座った。世奈は僕を見下ろし無言の圧をかけている。
「……私、死ぬ前に海に来たんだけど」
「そうなんだ」
「そう。明日、首吊って死ぬって決めたのが、海」
世奈は距離を縮め、僕の目の前にやってきた。理由を尋ねる代わりに、僕は塊のような唾を飲み込んだ。
「どうして私、今も消えられないんだろう」
そう呟く世奈の身体の奥には月が照らす海面があった。月も幽霊も、こんなにも掴めそうなのに掴めない。消えそうで消えられないもどかしさが彼女の苛立ちを作っているのだろうか。
「あんたといると結局、成仏なんて出来ない気がする」
「出来るよ」
「出来ないよ。この世からいなくなりたくてそうしたのに、拓人。あんたといると変になる。いなくなりたくなかった理由ばっかり膨らんでくから、嫌」
「どういうこと?」
返事より先に波の音がした。世奈は僕にさらに近づいた。背筋に冷や汗が伝い、目の前の存在が幽霊であると改めて僕は思い出していた。本当は見えてはいけない存在。
「……なんかもう、いくら呪っても足りない。これ以上、私に入り込まないでよ」
どうしてキスなんてしちゃったんだろう。世奈は両腕を伸ばし、僕の首を両手で絞めながら言った。僕は首をもたげ、されるがままにして身体を預けた。全部好きにすればいい。出会ったあの日から幽霊に抗おうとは思えない。取り憑かれたならそれでいい。初めから無駄に思えることはしたくない。広がる海の水をスプーンで掬って減らそうとしないように。というより本当は、誰と関わっても単に傷つきたくない。その本心に気づき僕は眉を顰めた。
幽霊とのキスで気を失ったことがあるのに、首を絞められるのは平気だった。代わりに心がわずかに痛んだ。そういえば真依はセックス中に「絞めて」と願った首。こんなときでさえ僕はここにいない他人を考えていた。
「成仏させてあげられなくて、ごめん」
多分、手に力を込めているであろう世奈に言った。世奈は僕を離さない。今、どれくらい僕を殺したいのだろう。もしかすると明日になれば海に僕という死体が転がっているのかもしれないと思った。
「あの夜どうして私を見つけたの? どうせ成仏出来ないなら誰にも気づかれたくなかった。そうしたら、孤独にいくらでもこの世界を呪っていられたのに。幽霊ってそういうものでしょ?」
「ごめん」
「……ねぇ。拓人」
好き。
死ねと言うのと同じトーンで世奈は言った。僕は思わず目を見開いた。今、幽霊と両想いであるとわかった。それなのに結ばれる未来はまったく見えない。なぜなら彼女は死んでいる。世奈は苦しそうだし、僕もどんな表情を浮かべていいのかよくわからない。頬を撫でる潮風がとても冷たい。視界の中で幽霊と波だけが白い。
「あんたへのこの想いのせいで私は上手く動けない」
「……」
「だから死んで。拓人」
「ごめん。世奈」
世奈は正しい。だけど僕は死ねない。形だけの謝罪をしながら僕は昼間の結婚式を思い出していた。真依。そして世奈。生きている女の子と死んでいる女の子、そのどちらにも属せず、なんとなく明るい場所を探してはふらふらと飛ぶ蛾のような自分を思った。僕も世奈が好きなのに、一体、何に謝っているのだろう。僕にとっては僕ではなく元カノの真依が、幽霊の世奈ばかりがいつも正しい。幸せの定義も存在の論理も何もかも。
「だけど成仏のやり方、絶対見つけるから」
僕がそう言うと世奈は不機嫌に言い放った。期待してない。
「お前に腹が立つ。イライラしても幽霊って泣けないから余計に腹立つ」
「いいよ。別に。そうだ」
「何」
「世奈が生まれ変わったら、また海に来よう。あったかいときに」
そう言うと、世奈はゆっくりと両腕を離した。僕は思わず深呼吸をした。やがてつまらなさそうに海を見つめ、世奈は言った。
「……私、泳げない」
「泳ぐとか泳がないとか、どっちでもいいよそんなの」
「そうだね」
「今は何も出来ないからこうしていようよ」
僕たちは砂浜に並んで腰掛け、波の音に耳を傾けた。世奈が死ぬと決めた日の寂しさを思い、その日に決して届かないぶん幽霊の世奈を抱きしめたいと願った。出来ないとわかっているから、冷えた砂浜に爪を立てるしかなかった。僕も世奈も墓に戻ろうとしなかった。僕たちは出会ってしまった奇跡を持て余し、後悔の中に立ちすくみ、結局はなんとなく離れがたい、それだけで動けない。恐ろしい金縛りなんてなくても。
空が明るみ出す頃まで、僕たちは寄り添い海にいた。砂の上に置かれた幽霊の手に僕は自分の手を重ねた。冷えた砂の感触を確かめながら、あるはずの世奈の手を想像した。そして見つめ合い、波の音と音の間にキスをした。僕の手も唇も、やはり世奈に触れられるものは何ひとつない。代わりに潮の匂いとわずかな冷気が確かな夜の証だった。僕は砂浜で目を閉じ、それらすべてを記憶しようとする。「……拓人」そう呼ぶ声が風ではないと僕はただ、信じたい。
静寂は死者とのキスで出来ているのかもしれない。
「世奈」
世奈が僕から離れた気配を感じると僕は薄く目を開けた。そしてまた、どちらからともなくキスをした。音のないキスはその繰り返しだった。何度目かに目を開けたとき、遠くの水平線に太陽があった。代わりに、隣にいるはずの世奈の姿はどこにもなかった。夜はいつの間にか終わり、僕たちはひとつの朝を迎えていた。そうして僕は、幽霊の消失を初めて見た。
──くだらないよな。
僕は鏡の中の自分を見ながらそんなことを考えていた。鏡の中の僕は目の下に薄い隈を浮かべながらも、唇の端を緩やかに上げていた。自分の笑顔が他人のものに見えた。僕の見る僕は皺ひとつないスーツに身を包み、いつもは締めないネクタイまで締めている。だけど今日は仕事ではない。素直にもっとおめでたい日だ。結婚式。僕のためのではない。真依の結婚式のために、僕はドレスコードをキメている。
元カノでありながらなんとなく身体を重ね続けている真依。彼女は今日、結婚式を挙げ、浮気の疑惑をいくつも巻き散らかしたままの結婚相手と、真依は人生を共に歩み始める。別に真依はそれでいいらしい。何も迷いはないらしい。彼女が彼女なりに定めた幸せはあまりにも潔く、僕には意味不明に眩しかった。真依はあろうことか僕を堂々と結婚式に招待した。いつものように僕の部屋へ転がり込んできた夜。長いキスの後で、自分を押し潰そうとする後ろめたいものが初めから何もないかのように、裸の彼女は言ったのだった。「ねぇ。拓ちゃん。呼んだら結婚式来てくれるよね?」「……いいけどなんで?」そう言った僕に、彼女は続けた。「ドレスなんて、お祝いしてくれる人たち皆に見せてあげたいもん」
「それって真依が可愛いから?」
「ふふ」
「すごいね。真依は」
「うん。私は幸せになるしかないから」
真依は言い切った。そして両腕を僕に絡め、抱き寄せた。僕は真依の強さに窒息しそうな気持ちになった。そして、誰かに攫われたいとも攫いたいとも思うことのないウェディングドレスの純白を思い、力無く笑い声を吐き出すことしか出来なかった。釣られるようにして真依も笑った。他の誰でもない、自分の未来のために、一日を目一杯着飾る彼女。人に流されっぱなしの僕は流されたままどこかに置いていかれるのだと思った。だったらせめて僕の今を気持ち良くしろよ。そう思いながら彼女を押し倒し、荒々しくキスをした。
**
「新郎新婦のご入場です」
女性の司会が言い、厳かな扉が開いた。Aラインのウェディングドレスに身を包んだ真依は、まるで知らない国のプリンセスのようで、僕の知らない新しい真依に見えた。新郎の男はなるほど、笑顔と白い歯がよく似合う爽やかさ200%の男だった。僕の周りで学生時代の同級生が「可愛いね、真依」「めっちゃ綺麗!」などと囁き合っていた。僕はウエディングドレスに包まれた彼女の身体を眺めた。真依のウエストは細く、いつか彼女が宿すのかもしれない子どもが、僕との子じゃないことになぜかほっとしていた。全部やるよ。幸福そうな新郎に心の中で告げ、僕は2人を祝福した。やるだなんて、別に初めから僕のものでもないのに。真依の首元には何連にも連なるアクセサリーが照明の光を受けて輝き、彼女の華奢さを際立てていた。僕は一度だけあの首を締めたのを思い出していた。結婚式の10日程前のことだ。彼女の独身生活を締めくくるであろうセックスを僕たちはした。正常位で見つめ合っている最中。挿れて少し経った頃に真依は潤んだ瞳で言った。「拓ちゃん」
「何」
「ねぇ。私の首、絞めてみてくれる?」
想像もしない言葉に、僕は思わず前後の動きを止めた。真依を真っ直ぐに見下ろしたまま、部屋を暖めるエアコンの音の中で聞き返した。
「そういうの好きだったんだ?」
僕の問いかけに真依は答えなかった。
「なんか、一回だけ苦しくなりたいの」
「なんで」
「私の馬鹿なとこだけ、死んで消えちゃえばいいなーって」
真依の軽い口調はかえって切実に聞こえた。僕は一瞬だけ躊躇したものの、僕は真依のか細い白い首を絞めた。折れそうだと思った。そして結局は燃えてしまった。「もっと強くして」と言われ、躊躇いながらも手に力を込め続け、息継ぎでさえキスで遮った。その瞬間、真依が可愛くて、一瞬だけ僕の手の中で死んでしまえばいいと本気で思った。大切な玩具に対する子どもの独占欲と大人の性欲の混じり合った暴力的な感情だった。真依が苦しむと、繋がった部分が連動するように締まった。ああ、気持ちいいなと思いながら僕は腰を打ちつけ真依を貪った。快楽の波に溺れ、すぐに出てしまった。精液は。快楽と共に余分な愛情めいたものが抜け、身も心も軽くなったように感じられた。真依の身体の上で呼吸を荒げながら、これなら手放せると漠然と思った。それなのに真依より苦しいのはきっと僕だった。
少しの気まずさを残した長い沈黙の中、僕は言った。
「ごめん。大丈夫だった? 痛かったよね」
真依は首を小さく横に振った。首はかすかに赤みを帯びていた。
「気持ち良かった。それに、してって言ったの私だもん」
「したのは僕だよ」
「いいよ。それよりさ」
「何?」
「多分、これが最後だったよね」
「だね」
どこか解放された表情で僕たちは見つめ合った。楽しかったし、気持ちよかった。僕の扱える愛情なんてそれしかない。そして、愛情のある・ないなんて枕詞は、本当にセックスによく似合う。ただの行為、快楽ひとつに振り回されている自分が滑稽に感じられる。今、どうしてこんなに寂しいのだろうと不思議にも思う。動物の雄だからだろうか。それとも結局、人間だからだろうか。
「真依、おめでとう」
「ありがとう」
拓ちゃん。絶え間なく真依は僕の髪を撫で、小さい子にするように僕をあやした。僕はそれが嫌で真依を抱き寄せた。真依は僕の腕の中で自由を失い、僕はようやく束の間の満足を手に入れた。きっと忘れないだろうと思ったのは「お幸せにね」と吹き込んだ先にある彼女の耳が、火照る身体に反して冷たかったということだけだ。
**
滞りなく披露宴は進んでいる。「本当にお似合いだね!」と、真依と僕、共通の女友達が無邪気にはしゃぎ、ケーキの入刀にも友人代表のスピーチにも、絶え間ない幸せが降り注いでいる。幸せを包み込む会場は、ナチュラルなグリーンと白を基調とした花々に彩られていた。僕の心の中でそれらは徐々に色を失い優しげなモノクロームに映った。指輪の交換の直後、僕と真依はっきりと視線を合わせた。僕たちは互いに微笑み合った。お色直しの度に、真依は可愛く、綺麗になっていくが、そのときの犯罪めいた微笑みが、振り返ればいちばんよかった。
僕と彼女の距離は開いていくようだった。だけどそれでいい。周りを見渡すと近くのテーブルで真依の両親は目を赤くして泣いているようだった。最後に投げられたブーケは、昔から真依とよくつるんでいた女の子の手に渡った。涙や笑い声といった澄み切ったもので溢れていた。いい式だったと皆が感想を抱くであろう、完璧な披露宴だったように思う。彼女にとても相応しい。
二次会は途中で抜けた。皆と学生時代の想い出話に花を咲かせるのは楽しかったが、一度外の空気を吸いに出たら、最後までいる気になれなかった。「ごめん。先に帰ったって言っておいてくれる?」僕は隣に座る同級生の女の子に耳打ちをした。「それから、真依に本当におめでとうって伝えて」僕はそう言い残し、重いコートを掴んだ。酒を飲めば飲むほど、言葉にならない自己嫌悪に耐え切れなくなっていくのがわかった。僕は、僕以上に幸せな真依を本当は見たくなかったのかもしれない。
店を出ると電車をいくつか乗り継ぎ、冬の空の下を気ままに歩いた。右、左、右、右、直進。道は無作為に選んだはずだった。だけど足取りは結局、自ずといつもの墓地へと向かっていた。忘れてはいない。一番好きなのは幽霊の彼女だ。存在するはずもないはずの世奈だ。今、眩しいものを浴びすぎてとても疲れている。だから僕は幽霊に会いたかった。彼女と接し続けている限り、生きている誰かに何かを傷つけられることはないような気がする。ある日偶然手に入れた霊感は、僕の現実逃避として完全に役に立っている。
白い息を吐き続け、お気に入りの静かな場所に辿り着いた。連なる墓石たちはミニチュアのビル群にも見え、僕はそびえ立つ何かだった。当然、今ここには誰もいない。だけど、寂しげに点滅する街灯の側で僕は夜の挨拶をする。「世奈」と祈るように小さく呟く。今日もどこか遠くで犬が吠えている、その声がわずかな現実感を僕に与えている。
「世奈。いるよね?」
「……うるさい」
少しの間をあけて彼女は闇の中から現れた。そして、口を開くなり今日も僕を睨んだ。墓の上に直立し腕を組んでいる幽霊。月の光は透ける身体を通り抜けて墓石を照らし、彼女が生きた存在ではないと僕に教えている。僕にとっての現実というファンタジー。その臨界点に世奈はいる。
「何それ」
「これ? 引き出物。今日、知り合いが結婚したんだよね。おめでたいでしょ」
「私には関係ないけど」
「全部あげるよ」
僕は別にいらないから。そう言うと、どこかのバームクーヘンと分けてもらった式場の花を、僕は無造作に墓に供えた。しゃがんだまま、紙袋から取り出したカタログギフトも軽く捲る。世奈の好きなものはなんだろうと一生懸命に考えながら。死んだ本人を目の前にした不思議な墓参りも、すっかり慣れた。「なんか欲しいの合ったら頼んどくけど」と言いながら高級ランク牛肉のページで指先は止まった。美味しそうな赤い肉だった。ふと見上げると、幽霊は僕の上で足を組んでいた。美味しいものを美味しいと言い仲良く味わうのは生きた者同士の特権で、僕たちには関係なさそうではあった。
「食べたくない? これ」
「いらない」
世奈はいつも通り興味なさげに一刀両断し、そうだよねと僕は笑った。僕はめげずにカタログのページを後ろの方まで進めた。バスグッズや美容家電といった生活雑貨のカテゴリを通り過ぎると、現れたのは体験型のギフトの数々だった。訪れたことのない土地の旅館、魅力的な一泊二日のプランがいくつも掲載されている。東北。北陸。九州。僕はさまざまな土地に想いを巡らせ、言った。
「世奈、旅行行こうよー」
「は?」
「一緒に蟹食べよ」
「無理」
「じゃあ肉は? なんか今すぐ生き返れない?」
「無理だって。骨ごと身体焼いたし。てかさ」
「うん」
「……成仏させてくれるんでしょ? 私、待ってるんだけど」
「あぁ。ごめんそうだったね」
「自分の言ったことに責任取れって。私より大人なんだから」
世奈は墓から降り、座り込んだ僕と目線の高さを合わせた。幽霊の冷えた空気が肌の表面を撫でた。凍てつくような呪いの視線を浴び、身体が奥から痺れる。それでも、死んだ女の子に説教をされるシチュエーションはどこか心地よく、僕は成仏を後回しにしたくなった。どうせ方法もわからない。
「そういえばお前、この間、私のこと好きって言ったよね」
「言ったね」
僕は無責任に放った自分の「好きだよ」をおもむろに思い出した。彼女にそう言ったのは前回のデート、神社の階段を降り切った頃だ。空気に流された結果の気もするけど、嘘を言ったわけではない。
「だけど、私は全然、お前のこと好きじゃないから。忘れないでね」
「そっか。それでいいよ。ありがとう」
「……」
「あー、楽しいね」
「お前今日なんかキモいよ。いつもよりヘラヘラしてない? 死ねばー」
そう言われ、僕は思わず零した。「そういえばさ、元カノが結婚したんだよね。今日」と。人に話してみると、感傷はびっくりするほど陳腐だった。ついでに「仕事もあんまり上手くいってないんだよね」とも打ち明けた。僕の日常なんてあまりにもありきたりで、出来事のほうが絶望に追いついていないのだとよくわかった。だから「ふーん」という世奈の反応ももっともだった。今から死ぬ。それは別に悪くない提案のように思えた。今死ねば世奈と仲良く幽霊になれるような気がした。
「別にどっか行ってもいいけど」
世奈は気付けばカタログギフトの誌面を覗き込んでいた。幽霊の透ける身体の奥で、バスタオルを巻いた女性が笑顔で温泉に浸かっていた。幽霊に取り憑かれながら旅行するのは面白そうだ。うっかり途中で死ぬのかもしれない。
「じゃあどこにする?」
「海」
「海?」
僕は間髪入れずに聞き返した。きらめく太陽に白い砂浜、ブルーオーシャンと弾ける笑顔を瞬時に思い浮かべ、無理だろと思った。幽霊に海は似合わない。そもそも、朝になれば幽霊は消えると世奈本人は語っていた。僕たちがアクセス可能なのは、せいぜい凍てつくような冬の夜の海だ。太陽には初めから負けている。
「行こ」
世奈はおもむろに月を見上げ、そう言った。
「え。今から?」
「夜なんて早くしないと終わるよ。朝が来る前に死んじゃうかもよ。お前も」
世奈は墓石を離れ、浮遊で移動を始めた。僕は慌ててその後ろ姿を追いかけた。足という足が無いからか、世奈の移動は速かった。だけどここから海なんて歩いていける距離じゃない。どうしよう。そこに都合よく通りかかった一台のタクシー。僕は手を挙げて捕まえると、開けられた後部ドアから座席に乗り込んだ。一緒に乗ってよと目で訴えかけると、世奈は僕に続いて乗り込んだ。生きている人間と死んでいる人間を乗せてタクシーのドアは閉まった。タクシーの運転手は「お客さん、どちらまで?」とあまり抑揚のない声で尋ねた。僕は「いちばん近い海まで」と言いかけては飲み込み、記憶を頼りに適当な地名を告げた。こんな季節と時間帯に海に行くなんて、うっかり自殺志願者と思われたら困る。犯罪を怪しまれても困る。僕たちのことは誰にも何も一切気にされたくはなかった。なんせひとりは幽霊なのだから。
安全運転で墓場からはみるみるうちに遠ざかる。当然、世奈の存在に運転手は気づかず「明日からまた冷えるらしいですね」だとか「今年は雪、降りますかね」といった世間話を僕に投げかけている。「そうですね」適当に相槌を打ちながら、僕は隣の幽霊を横目で眺める。「こうしたら事故るのかな」などと言い、運転手の目を両手で塞ぐ、悪質な半透明の姿を。
ラジオからは古いJ-POPが流れていた。子供の頃、親の車でよく聴いた曲だった。機嫌が良いのだろう、世奈は小さく口ずさんでいた。僕は風のような幽霊の歌に聞き入っていた。あんなに「死ね」と僕に言っているのに柔らかい歌声をしている。不思議なアンバランスだ。世奈は歌いながら外の景色に見入っている。一体、彼女はどんな表情をしているのだろう。タクシーがトンネルを通ったときに窓に目を凝らしたが、そこには僕の顔しか写っていなかった。だけど、確実に世奈はいる。少なくとも僕はそう信じ、シートに身を預ける。万が一の事故に備え、目も閉じたままでいる。
「お客さん」
うっかり寝落ちしそうになった頃、運転手に声をかけられた。辺りを見回すと、見覚えのあるようなないような景色が広がっていた。きっと目的地が近いのだとわかった。「この辺でいいです。降ろしてください」僕はそう伝え、少し怪訝な顔をした運転手にクレジットカードを渡し支払いを終えた。
タクシーが遠ざかり、深呼吸をすると鼻の奥まで潮の香りが突き抜けていった。導かれるようにして僕は少しの間、歩いた。海へは迷わず辿り着けた。文字が剥げかけ、淵の錆びた「立ち入り禁止」の看板を乗り越え、夜の砂浜に踏み込む。辺りに目を凝らす。現れた海という景色はとてつもなく暗い。というより黒い巨大な生き物のようだった。僕はひとりでこんな怖いところに来たのだろうかと、心細い気持ちになった。そういえば、世奈は。周りを見渡すとちゃんと世奈はいた。少し離れたところに浮かんでいた。世奈の姿はむしろ墓場にいるときよりもはっきりとした存在感があった。幽霊に海はよく似合っていた。きっと、より多くの死を孕んでいるからかも知れない。
「気持ちいいよね?」
「そうだね。僕は少し寒いけど」
世奈は僕を一瞥するとさらにふわふわと漂い始めた。辺りは完全に暗く、夜と海と闇の境は曖昧だった。僕たちは黙々と砂浜を歩いた。その辺に落ちている朽ちかけたゴミの正体を考えたり、砕け散る泡の白を僕は眺めた。波の打ち寄せる規則的な音に身を任せていると、現実的なものが削ぎ落とされ、次々と非現実的な考えが浮かんでいった。一体、どこへ向かっているのだろう。このまま歩き続けたら黄泉の世界に行けるんじゃないか。そうして、世奈は僕を殺そうとしているんじゃないか、と。そもそもどうして世奈は僕にキスをしたんだろう。僕は霊感を手に入れ、世奈と出会ってしまったのだろう。何もわからない。
──世奈は、僕をどう思っているんだろう。
そう思った途端、突然、目の前で世奈の浮遊は止まった。僕はうっかり世奈の身体を通り抜けてしまった。冷気に痺れたような感覚に襲われ、僕は砂浜につまずいた。そして歩く気が失せ、その場になんとなく座った。世奈は僕を見下ろし無言の圧をかけている。
「……私、死ぬ前に海に来たんだけど」
「そうなんだ」
「そう。明日、首吊って死ぬって決めたのが、海」
世奈は距離を縮め、僕の目の前にやってきた。理由を尋ねる代わりに、僕は塊のような唾を飲み込んだ。
「どうして私、今も消えられないんだろう」
そう呟く世奈の身体の奥には月が照らす海面があった。月も幽霊も、こんなにも掴めそうなのに掴めない。消えそうで消えられないもどかしさが彼女の苛立ちを作っているのだろうか。
「あんたといると結局、成仏なんて出来ない気がする」
「出来るよ」
「出来ないよ。この世からいなくなりたくてそうしたのに、拓人。あんたといると変になる。いなくなりたくなかった理由ばっかり膨らんでくから、嫌」
「どういうこと?」
返事より先に波の音がした。世奈は僕にさらに近づいた。背筋に冷や汗が伝い、目の前の存在が幽霊であると改めて僕は思い出していた。本当は見えてはいけない存在。
「……なんかもう、いくら呪っても足りない。これ以上、私に入り込まないでよ」
どうしてキスなんてしちゃったんだろう。世奈は両腕を伸ばし、僕の首を両手で絞めながら言った。僕は首をもたげ、されるがままにして身体を預けた。全部好きにすればいい。出会ったあの日から幽霊に抗おうとは思えない。取り憑かれたならそれでいい。初めから無駄に思えることはしたくない。広がる海の水をスプーンで掬って減らそうとしないように。というより本当は、誰と関わっても単に傷つきたくない。その本心に気づき僕は眉を顰めた。
幽霊とのキスで気を失ったことがあるのに、首を絞められるのは平気だった。代わりに心がわずかに痛んだ。そういえば真依はセックス中に「絞めて」と願った首。こんなときでさえ僕はここにいない他人を考えていた。
「成仏させてあげられなくて、ごめん」
多分、手に力を込めているであろう世奈に言った。世奈は僕を離さない。今、どれくらい僕を殺したいのだろう。もしかすると明日になれば海に僕という死体が転がっているのかもしれないと思った。
「あの夜どうして私を見つけたの? どうせ成仏出来ないなら誰にも気づかれたくなかった。そうしたら、孤独にいくらでもこの世界を呪っていられたのに。幽霊ってそういうものでしょ?」
「ごめん」
「……ねぇ。拓人」
好き。
死ねと言うのと同じトーンで世奈は言った。僕は思わず目を見開いた。今、幽霊と両想いであるとわかった。それなのに結ばれる未来はまったく見えない。なぜなら彼女は死んでいる。世奈は苦しそうだし、僕もどんな表情を浮かべていいのかよくわからない。頬を撫でる潮風がとても冷たい。視界の中で幽霊と波だけが白い。
「あんたへのこの想いのせいで私は上手く動けない」
「……」
「だから死んで。拓人」
「ごめん。世奈」
世奈は正しい。だけど僕は死ねない。形だけの謝罪をしながら僕は昼間の結婚式を思い出していた。真依。そして世奈。生きている女の子と死んでいる女の子、そのどちらにも属せず、なんとなく明るい場所を探してはふらふらと飛ぶ蛾のような自分を思った。僕も世奈が好きなのに、一体、何に謝っているのだろう。僕にとっては僕ではなく元カノの真依が、幽霊の世奈ばかりがいつも正しい。幸せの定義も存在の論理も何もかも。
「だけど成仏のやり方、絶対見つけるから」
僕がそう言うと世奈は不機嫌に言い放った。期待してない。
「お前に腹が立つ。イライラしても幽霊って泣けないから余計に腹立つ」
「いいよ。別に。そうだ」
「何」
「世奈が生まれ変わったら、また海に来よう。あったかいときに」
そう言うと、世奈はゆっくりと両腕を離した。僕は思わず深呼吸をした。やがてつまらなさそうに海を見つめ、世奈は言った。
「……私、泳げない」
「泳ぐとか泳がないとか、どっちでもいいよそんなの」
「そうだね」
「今は何も出来ないからこうしていようよ」
僕たちは砂浜に並んで腰掛け、波の音に耳を傾けた。世奈が死ぬと決めた日の寂しさを思い、その日に決して届かないぶん幽霊の世奈を抱きしめたいと願った。出来ないとわかっているから、冷えた砂浜に爪を立てるしかなかった。僕も世奈も墓に戻ろうとしなかった。僕たちは出会ってしまった奇跡を持て余し、後悔の中に立ちすくみ、結局はなんとなく離れがたい、それだけで動けない。恐ろしい金縛りなんてなくても。
空が明るみ出す頃まで、僕たちは寄り添い海にいた。砂の上に置かれた幽霊の手に僕は自分の手を重ねた。冷えた砂の感触を確かめながら、あるはずの世奈の手を想像した。そして見つめ合い、波の音と音の間にキスをした。僕の手も唇も、やはり世奈に触れられるものは何ひとつない。代わりに潮の匂いとわずかな冷気が確かな夜の証だった。僕は砂浜で目を閉じ、それらすべてを記憶しようとする。「……拓人」そう呼ぶ声が風ではないと僕はただ、信じたい。
静寂は死者とのキスで出来ているのかもしれない。
「世奈」
世奈が僕から離れた気配を感じると僕は薄く目を開けた。そしてまた、どちらからともなくキスをした。音のないキスはその繰り返しだった。何度目かに目を開けたとき、遠くの水平線に太陽があった。代わりに、隣にいるはずの世奈の姿はどこにもなかった。夜はいつの間にか終わり、僕たちはひとつの朝を迎えていた。そうして僕は、幽霊の消失を初めて見た。