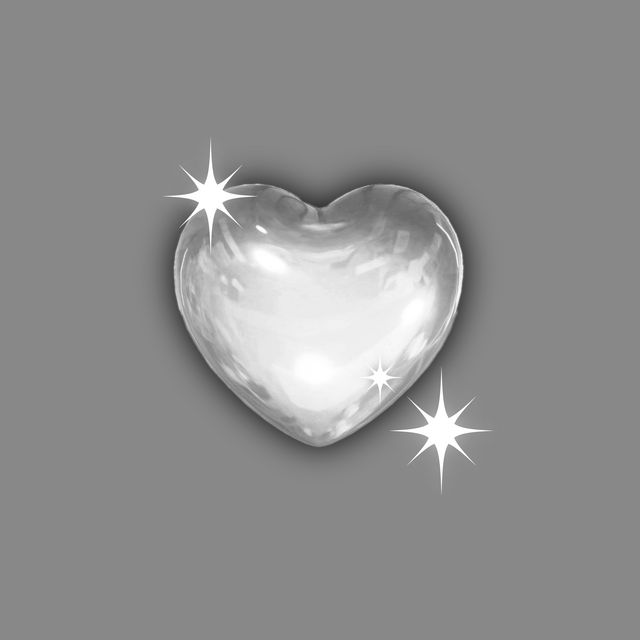1.僕を殺した冬のキス
文字数 5,871文字
僕は幽霊と恋に落ちたことがある。誰にも信じられないとわかっているから、一生、話さないと決めている。だったらいっそ忘れたい。そう思えば思うほど疼く、目には見えない甘い傷跡がひとつ、心の底に残されている。
僕は日々、あくまで記憶の紙切れ1枚として彼女を留めようとする。想い出なんて、風が吹けば飛んでいく程度の重さだ。彼女との時間は初めからなかったようなものだ。朝が来れば忘れるはずの夢を、今も身体が偶然覚えているだけだ、と。なのに、その恋の一枚をめくるのを止められない。書き記した痛みをいちいち手放せそうにない。理由は彼女に幾度となく投げかけられた「死ね」という言葉。そして何より、確かな想いを伝え合っておきながら、キスもセックスも叶わなかった身体の心残りのせいだろう。
短い間、僕と彼女は確かに想いを重ね合わせていた。求め合っていた。それなのに、本当に、一度たりともまともに触れ合えなかった。服を脱ぎ去った全身はもちろん、指先や前髪、頬やまつ毛といった末梢でさえも。生きているのにも関わらず、僕の身体は届けたい場所へと届かず、何の意味も持たずにそこにあるだけで終わった。五歳のとき、初恋相手のみどりちゃんとですら僕は手を繋いだのに。36.9℃。僕の平熱の高さは、目の前の誰かを喜ばせられるはずだった。あんなに寒い冬には特に。
触れ合えなかったのは当然だ。なぜなら、世奈という名の彼女は、出会った時点で死んでいた。彼女はいつまでも成仏出来ずに彷徨う、僕が知るただひとりの幽霊だった。そしてもう、二度と会えない。僕が殺した。
初めて彼女を見かけたのは、12月の金曜の夜、仕事の帰り道のことだった。冬を実感せざるを得ないほど、澄んだ夜空に浮かぶ星々が綺麗で、吐き出される息は白く霞んでいた。僕は一週間の疲労を抱えた重い身体を引きずるようにアパートへ向かっていたが、気付けば途中でコンビニに寄り、お気に入りの酒を数本買っていた。そして、適当に目についたベンチに、吸い込まれるようにして腰掛けた。家に辿り着く前にどこかで一息つきたくなるほど、それも人のいる居酒屋やバーを選べないほど、僕は心身共に疲れ果てていたのだった。
23:55。ふと目を止めたスマートウォッチの上で、日付が変わる直前だったのを覚えている。溜め息をつきながら缶チューハイのプルタブを開けた僕の目の前には、遊具の少ない公園、そして隣には古びた金網のフェンスに囲まれた小さな墓地があった。街灯は誰のためでもなく、とりあえずそこにいるという佇まいで青白く光っていた。辺りに人の気配はなく、手元から炭酸の音が聞こえるくらい静かな住宅街の中に僕はいた。
僕は墓地に目をやり、墓石を何気なく数えた。規則的に並べられた墓石はざっと三十。つまりここには少なくとも三十人ぶんの骨が眠っているのだと、疲れた頭の片隅で思った。でも、それが一体何だと言うのだろう。僕は冬の寒さに身震いをした。身体を内側からも痛めつけるように、冷えた度数9%のアルコールを一気に流し込んだ。炭酸で喉は心地良く灼け、作られたレモンの酸味が身体中に広がった。ロング缶の三分の一程度を空けた後、僕は目の前の墓地を再び眺めた。
墓地でひとり酒を飲むなんて趣味が悪いとわかっていた。それでも、自分以外の皆が死んでいるという覆しようもない事実に、僕は心地良く浸っていた。一切、怖さや不気味さなんてなかった。今日は仕事でミスをし、そのミスの小ささとは釣り合わないほど上司に執拗に詰められた。ついでに取引先の新人と話が上手く噛み合わず、疲れた。家に帰れば部屋が荒れている。何かしらの通知で常に忙しなくスマートフォンに呼ばれている。そもそも世の中は怖い事件で溢れている。そういう現実に比べれば、墓地の静けさなんてホラーどころかリラクゼーションに近い。ここに誰がいようが、僕は生きているし相手は死んでいる。つまり、墓石を挟んで、出会う前から互いに別れを告げている。生前の相性が、関わるだけ無駄だという最悪のものだろうが、来世でも結ばれたいと願うほど離れがたいものだろうが、死の静けさはすべてお構いなしだ。無関係を貫く安らぎは貴重だ。
僕はそんなことを考えていた。酒に強いとは言えない僕は、この時点でしっかりと酔い始めていたのかもしれない。右手の中で、気付けばロング缶が空になっていた。帰ろう。残りの1本はシャワーを浴びた後で飲もう。疲れた。腹減った。どうか、死んだ人たちは今夜も安らかに眠ってください。おやすみなさい。そう思い、ベンチから立ち上がった瞬間に間抜けな声が出た。
「え……?」
僕は目を疑った。並べられた墓石の内のひとつに、女の子が座っているのを見つけたのだった。一体いつからいたのかまるで見当もつかない。ついさっきまで、ここには誰もいないと思っていたはずだった。女の子は墓石の上に腰掛け、細い両脚を前後に揺らし、どこか遠い一点を見つめていた。思いっきりふて腐れているようにも、退屈を持て余しているようにも見えた。こんな時間に外にいるなんて、家出少女なのだろうか。しかも墓石で遊ぶなんて、どれほど常識のない奴なんだろう。声をかけることもためらわれ、僕は一旦、ぼんやりとした。女の子の斜め後ろには自販機があった。今は冬だから当然「あったかい」飲み物が多い。女の子の身体の中心の辺りで、ココアの売り切れを伝える赤い文字列が重なり、光っていた。売り切れ。そうだ。冬だからみんな飲むよな。僕は普通に納得しかけた後で目を見開いた。ココア。なぜ、女の子の身体に遮られる場所に位置するはずの自販機が見えるのだろう。そういえば女の子の全身はやけに白く、向こう側が透けている。奇しくもここは墓場。夜。
──何。もしかして幽霊?
そう思った瞬間、僕は背中の産毛が逆立つのを感じた。本能的な感覚だった。逃げるべきだという危険信号は激しい胸の鼓動となり、皮膚に嫌な汗を滲ませた。にもかかわらずしばらくの間、僕はそこから目を逸らせずにいた。かき集めた恐怖心よりも好奇心が勝っていた。なぜなら僕は金縛りにすら遭ったことがなかった。二十数年の人生の中で、霊感のような何かを覚えるのは初めてのことだったのだ。
やがて、幽霊のような何かと僕は目が合った。その物体はいきなり、吐き捨てるような低い声で告げた。
「じろじろ見てんじゃねーよ。死ね」
「え?」
僕は面食らった。たとえば「私が見えるの……?」などと消えそうなか細い声で言われれば、ボーイミーツガールに繋がる展開を期待しただろう。だが、思いもよらない態度に、僕の頭はかえって冷静になった。
「……見てねーよ」
「そんなの嘘。今だって私のこと見てるでしょ。不快なんだけど」
「……」
「つまんない嘘ついてたらお前の大切な人全員、呪い殺すよ」
「は? なんで」
「だって私、幽霊だから。多分そういうことできるよ。どうする?」
「どうするって言われても……」
僕はただ、目を逸らせない。足を動かせない。女の子の形をした正体不明の何かから発せられる声は、不思議とはっきりと響いた。彼女は、全身が薄く透けている以外は普通の女の子に見えた。十代後半からおそらく二十歳くらい。僕より歳下だろう。切り揃えられた前髪の下で大きな瞳が僕を睨んでいる。目が大きい。そう思った瞬間に夜風が吹き、伸びた僕の前髪は揺れ、視界はより一層、開けた。一方で、乳白色のもやの塊は、髪の毛一本ですら形が変わっていなかった。実体がないのを酔った頭で実感する。だけど、本当に幽霊を見ているのか? 僕は深呼吸をし、落ち着いて頭を冷やそうとする。
「……なんで、ここにいるの? まじで幽霊なの?」
自称・幽霊は溜め息をついてから、言った。
「本当に幽霊だよ。多分。てかお前、見えてるのに、見ててわかんないの?」
「なんかごめん。僕、酔ってるのかなって……」
「知らねーよ」
「ねぇ。ここで何してるの? 名前は?」
幽霊はそれには答えず、自分の座り込む墓石を投げやりな態度で指差した。僕はベンチから離れ、墓に近寄った。目を凝らすと、幽霊の指差す墓の表面には「谷口家ノ墓」と彫られているのがわかった。両サイドに供えられた仏花は、無惨に萎れていた。食べ物や飲み物といったお供物は特に見当たらない。誰にも気にかけてもらえていないのか、と思うと寂しい墓だった。
「このお墓が君の家?」
「家じゃない。帰るところなんてないもん」
「とりあえず……谷口さん、ていうんだね」
墓地を取り囲むフェンス越しに僕が声をかけると、幽霊はひときわ強い視線で僕を睨んだ。ゆらゆらと揺れる両脚を、音もなく墓石に貫通させながら。
僕は拓人だよ。そう言うと僕は幽霊の全身をまじまじと見た。やはり、儚いイメージも、おどろおどろしい雰囲気もどこにもない。透けているだけの女の子。なんだか頼りなく小さい。僕は次第に、未確認物体の目撃者の気持ちから、非行少女に声をかける補導員のような気持ちになっていった。
「君は、とっくに死んじゃってるんだよね?」
「そう」
「死んだのにどうしてここにいるの?」
「知らない。気付いたらいたんだもん」
「とりあえず墓に戻ったら?」
「なんで?」
「だって、お化けでしょ。通った人がびっくりしちゃうじゃん」
「どうでもいいよ。てか毎日ここにいるけど、お前しか私のこと見えてないよ。そもそも墓に戻るやり方わかんないし」
「そうなんだ」
「ほっといて」
「……この墓地では、君だけが成仏できてないの?」
「今は、そう」
「前は他にもいたんだ」
「太ったおっさんがいた。だけど急にいなくなった」
「どうして?」
「知るかよ。まじでどうでもいい」
「君にはやり残したこと、ないの? ていうかさ、死んだとき、お経とか読んでもらったんじゃないの? それでも成仏ってできないもん?」
いい加減にしろ、という類の舌打ちが聞こえたような気がした。
「うるさい! 死んだとき、私、人の話なんて全然聞いてなかったから」
僕は頭がくらくらした。今、一体、誰と話しているのだろう。目の前の光景が信じられなかった。それでも、眺めれば眺めるほど、この幽霊は確かに存在するのだと思えた。それほどまでに幽霊の声ははっきりと頭の内側に響いていた。生春巻きの皮みたいに白く透けている以外、女の子はただ女の子だった。一定の距離を保ったまま、今度は幽霊が品定めをする目で僕の全身を眺めた。
「まぁ、お前でいいか」
「何が」
「ねぇ。私と一緒にあの世に行かない? ていうか行こう。行け」
「どういうこと?」
「死ねってこと」
「え」
「試させて」
幽霊は墓石から飛び降りた。敷石の上に着地したわけではなく、その場に浮かんでいた。そしてフェンスを何の支障もなく通り抜け、僕の目の前へと距離を詰めた。かなり気怠い浮遊だった。僕たちは出逢うや否や、至近距離から見つめ合うこととなった。幽霊は怒っているようで、どこか寂しそうな表情を浮かべていた。沈黙の中、生死を超えて初めて何かを交わしあったその瞬間を僕は忘れない。流れる空気はスローモーションを極め、まるで時が止まっているようだった。幽霊の身体を通して夜空はトリミングされ、淡い白のフィルターがかけられていた。遠くに光るオリオン座を僕は見つけた。冬だなと冷静に思った。
「うわー、生きてる」
そう呟く幽霊は、浮かんでいるからか僕より少し高い位置にいた。やがて幽霊は腕を伸ばし、両手で僕の頬を包んだ。見えない何かに引っ張られるように、僕は自然と首をもたげた。僕は触れられる感覚がないまま、素直に唇まで開く。幽霊は僕の顔から手を離さない。人生で感じたことのない冷気を浴びながら、僕はなす術もなく立ち尽くしていた。思わず「……寒いんだけど」と呟き、幽霊はそれを完全に無視した。
「私はお前をこれから殺す」
「……うん」
肯定の言葉が自ずと引き出されるのを僕はぼんやりと聞いた。自分の言葉の意味なんて、息が真っ白なだけで何もわからなかった。
「ねぇ。もしかしたら今から死ぬんだよ。最後に言い残すことある?」
「別にない。……でも今から何するのかだけ教えてよ」
情けなく掠れた僕の声に噛み付くように幽霊は吐き捨てる。
「キス」
「え?」
「あぁ、したことなかったの? キス」
違ぇよ。そう言いたいはずの僕の右手から力が抜けた。酒の空き缶は転がり、その音はどこか乾いた効果音として夜の墓場を演出した。僕はなんとか、崩れずに立っている。幽霊は実体のない唇を歪め、初めて笑顔のようなものを見せている。邪悪かもしれないけど怖くはない、懐かしささえ感じる笑顔だった。本当に何をするんだろう。わからないまま僕はただ、寒さだけを受け入れていた。幽霊は、風でも吹けば消えてしまう幻の光景のようにも思えた。
「じゃあ、動かないで。黙ってて」
「……」
僕は何も言えずに目に焼き付けていた。返事の代わりに吐き出した熱い溜め息の終わり頃が、幽霊と同じ色になるのを。聞いていた。近くで、夜の散歩をしているであろう犬がけたたましく吠える声を。今夜、犬はもしかするとこの現場の唯一の目撃者なのかもしれない。だからと言って何も出来ないだろう。飼い主に「どうしたの、ココアちゃん!」と叱られる以外には。側から見た僕は今、墓の前のフェンスでひとり呆けたように立ち尽くしている二十代前半の男だ。実は幽霊に絡め取られている。
「そうだ。私は、世奈っていう名前で死んだの。世間の世と奈良県の奈。簡単でしょ」
「……」
「今さらそんなのどうでも良いか。……じゃ」
自己紹介を済ませるや否や、女の子はひそやかに距離を詰め、白い影の形で僕に襲い掛かる。やばい。僕は今になって全力で逃げようとした。だけど、意志に反して身体は少しも動かせなかった。金縛りにあう自分を意識しながら、僕は目の閉じ方さえ忘れていた。死ぬ間際には走馬灯のように人生が見えると聞いたことがあるが、僕が見ていたのはまったく別の光景だった。人を見下ろし、じりじりと、獲物を見つけたネコ科の生き物のように迫り来る、知らない女の子。それも若干、透けている。この夜に知った重大な事実がある。幽霊の唇の隙間は夜の闇だ。顔に当たる冷気の正体は、風なんかじゃない。幽霊の吐く息だ。そして、彼女の名前は世奈。指先が微かに痺れる感覚が、生の実感を僕に唯一、与えている。時刻は0時過ぎ。頭をそっと両腕で抱きかかえられた。空気が冷たい。幽霊のキスを受ける僕の酔いは、とっくに醒めている。
僕は日々、あくまで記憶の紙切れ1枚として彼女を留めようとする。想い出なんて、風が吹けば飛んでいく程度の重さだ。彼女との時間は初めからなかったようなものだ。朝が来れば忘れるはずの夢を、今も身体が偶然覚えているだけだ、と。なのに、その恋の一枚をめくるのを止められない。書き記した痛みをいちいち手放せそうにない。理由は彼女に幾度となく投げかけられた「死ね」という言葉。そして何より、確かな想いを伝え合っておきながら、キスもセックスも叶わなかった身体の心残りのせいだろう。
短い間、僕と彼女は確かに想いを重ね合わせていた。求め合っていた。それなのに、本当に、一度たりともまともに触れ合えなかった。服を脱ぎ去った全身はもちろん、指先や前髪、頬やまつ毛といった末梢でさえも。生きているのにも関わらず、僕の身体は届けたい場所へと届かず、何の意味も持たずにそこにあるだけで終わった。五歳のとき、初恋相手のみどりちゃんとですら僕は手を繋いだのに。36.9℃。僕の平熱の高さは、目の前の誰かを喜ばせられるはずだった。あんなに寒い冬には特に。
触れ合えなかったのは当然だ。なぜなら、世奈という名の彼女は、出会った時点で死んでいた。彼女はいつまでも成仏出来ずに彷徨う、僕が知るただひとりの幽霊だった。そしてもう、二度と会えない。僕が殺した。
初めて彼女を見かけたのは、12月の金曜の夜、仕事の帰り道のことだった。冬を実感せざるを得ないほど、澄んだ夜空に浮かぶ星々が綺麗で、吐き出される息は白く霞んでいた。僕は一週間の疲労を抱えた重い身体を引きずるようにアパートへ向かっていたが、気付けば途中でコンビニに寄り、お気に入りの酒を数本買っていた。そして、適当に目についたベンチに、吸い込まれるようにして腰掛けた。家に辿り着く前にどこかで一息つきたくなるほど、それも人のいる居酒屋やバーを選べないほど、僕は心身共に疲れ果てていたのだった。
23:55。ふと目を止めたスマートウォッチの上で、日付が変わる直前だったのを覚えている。溜め息をつきながら缶チューハイのプルタブを開けた僕の目の前には、遊具の少ない公園、そして隣には古びた金網のフェンスに囲まれた小さな墓地があった。街灯は誰のためでもなく、とりあえずそこにいるという佇まいで青白く光っていた。辺りに人の気配はなく、手元から炭酸の音が聞こえるくらい静かな住宅街の中に僕はいた。
僕は墓地に目をやり、墓石を何気なく数えた。規則的に並べられた墓石はざっと三十。つまりここには少なくとも三十人ぶんの骨が眠っているのだと、疲れた頭の片隅で思った。でも、それが一体何だと言うのだろう。僕は冬の寒さに身震いをした。身体を内側からも痛めつけるように、冷えた度数9%のアルコールを一気に流し込んだ。炭酸で喉は心地良く灼け、作られたレモンの酸味が身体中に広がった。ロング缶の三分の一程度を空けた後、僕は目の前の墓地を再び眺めた。
墓地でひとり酒を飲むなんて趣味が悪いとわかっていた。それでも、自分以外の皆が死んでいるという覆しようもない事実に、僕は心地良く浸っていた。一切、怖さや不気味さなんてなかった。今日は仕事でミスをし、そのミスの小ささとは釣り合わないほど上司に執拗に詰められた。ついでに取引先の新人と話が上手く噛み合わず、疲れた。家に帰れば部屋が荒れている。何かしらの通知で常に忙しなくスマートフォンに呼ばれている。そもそも世の中は怖い事件で溢れている。そういう現実に比べれば、墓地の静けさなんてホラーどころかリラクゼーションに近い。ここに誰がいようが、僕は生きているし相手は死んでいる。つまり、墓石を挟んで、出会う前から互いに別れを告げている。生前の相性が、関わるだけ無駄だという最悪のものだろうが、来世でも結ばれたいと願うほど離れがたいものだろうが、死の静けさはすべてお構いなしだ。無関係を貫く安らぎは貴重だ。
僕はそんなことを考えていた。酒に強いとは言えない僕は、この時点でしっかりと酔い始めていたのかもしれない。右手の中で、気付けばロング缶が空になっていた。帰ろう。残りの1本はシャワーを浴びた後で飲もう。疲れた。腹減った。どうか、死んだ人たちは今夜も安らかに眠ってください。おやすみなさい。そう思い、ベンチから立ち上がった瞬間に間抜けな声が出た。
「え……?」
僕は目を疑った。並べられた墓石の内のひとつに、女の子が座っているのを見つけたのだった。一体いつからいたのかまるで見当もつかない。ついさっきまで、ここには誰もいないと思っていたはずだった。女の子は墓石の上に腰掛け、細い両脚を前後に揺らし、どこか遠い一点を見つめていた。思いっきりふて腐れているようにも、退屈を持て余しているようにも見えた。こんな時間に外にいるなんて、家出少女なのだろうか。しかも墓石で遊ぶなんて、どれほど常識のない奴なんだろう。声をかけることもためらわれ、僕は一旦、ぼんやりとした。女の子の斜め後ろには自販機があった。今は冬だから当然「あったかい」飲み物が多い。女の子の身体の中心の辺りで、ココアの売り切れを伝える赤い文字列が重なり、光っていた。売り切れ。そうだ。冬だからみんな飲むよな。僕は普通に納得しかけた後で目を見開いた。ココア。なぜ、女の子の身体に遮られる場所に位置するはずの自販機が見えるのだろう。そういえば女の子の全身はやけに白く、向こう側が透けている。奇しくもここは墓場。夜。
──何。もしかして幽霊?
そう思った瞬間、僕は背中の産毛が逆立つのを感じた。本能的な感覚だった。逃げるべきだという危険信号は激しい胸の鼓動となり、皮膚に嫌な汗を滲ませた。にもかかわらずしばらくの間、僕はそこから目を逸らせずにいた。かき集めた恐怖心よりも好奇心が勝っていた。なぜなら僕は金縛りにすら遭ったことがなかった。二十数年の人生の中で、霊感のような何かを覚えるのは初めてのことだったのだ。
やがて、幽霊のような何かと僕は目が合った。その物体はいきなり、吐き捨てるような低い声で告げた。
「じろじろ見てんじゃねーよ。死ね」
「え?」
僕は面食らった。たとえば「私が見えるの……?」などと消えそうなか細い声で言われれば、ボーイミーツガールに繋がる展開を期待しただろう。だが、思いもよらない態度に、僕の頭はかえって冷静になった。
「……見てねーよ」
「そんなの嘘。今だって私のこと見てるでしょ。不快なんだけど」
「……」
「つまんない嘘ついてたらお前の大切な人全員、呪い殺すよ」
「は? なんで」
「だって私、幽霊だから。多分そういうことできるよ。どうする?」
「どうするって言われても……」
僕はただ、目を逸らせない。足を動かせない。女の子の形をした正体不明の何かから発せられる声は、不思議とはっきりと響いた。彼女は、全身が薄く透けている以外は普通の女の子に見えた。十代後半からおそらく二十歳くらい。僕より歳下だろう。切り揃えられた前髪の下で大きな瞳が僕を睨んでいる。目が大きい。そう思った瞬間に夜風が吹き、伸びた僕の前髪は揺れ、視界はより一層、開けた。一方で、乳白色のもやの塊は、髪の毛一本ですら形が変わっていなかった。実体がないのを酔った頭で実感する。だけど、本当に幽霊を見ているのか? 僕は深呼吸をし、落ち着いて頭を冷やそうとする。
「……なんで、ここにいるの? まじで幽霊なの?」
自称・幽霊は溜め息をついてから、言った。
「本当に幽霊だよ。多分。てかお前、見えてるのに、見ててわかんないの?」
「なんかごめん。僕、酔ってるのかなって……」
「知らねーよ」
「ねぇ。ここで何してるの? 名前は?」
幽霊はそれには答えず、自分の座り込む墓石を投げやりな態度で指差した。僕はベンチから離れ、墓に近寄った。目を凝らすと、幽霊の指差す墓の表面には「谷口家ノ墓」と彫られているのがわかった。両サイドに供えられた仏花は、無惨に萎れていた。食べ物や飲み物といったお供物は特に見当たらない。誰にも気にかけてもらえていないのか、と思うと寂しい墓だった。
「このお墓が君の家?」
「家じゃない。帰るところなんてないもん」
「とりあえず……谷口さん、ていうんだね」
墓地を取り囲むフェンス越しに僕が声をかけると、幽霊はひときわ強い視線で僕を睨んだ。ゆらゆらと揺れる両脚を、音もなく墓石に貫通させながら。
僕は拓人だよ。そう言うと僕は幽霊の全身をまじまじと見た。やはり、儚いイメージも、おどろおどろしい雰囲気もどこにもない。透けているだけの女の子。なんだか頼りなく小さい。僕は次第に、未確認物体の目撃者の気持ちから、非行少女に声をかける補導員のような気持ちになっていった。
「君は、とっくに死んじゃってるんだよね?」
「そう」
「死んだのにどうしてここにいるの?」
「知らない。気付いたらいたんだもん」
「とりあえず墓に戻ったら?」
「なんで?」
「だって、お化けでしょ。通った人がびっくりしちゃうじゃん」
「どうでもいいよ。てか毎日ここにいるけど、お前しか私のこと見えてないよ。そもそも墓に戻るやり方わかんないし」
「そうなんだ」
「ほっといて」
「……この墓地では、君だけが成仏できてないの?」
「今は、そう」
「前は他にもいたんだ」
「太ったおっさんがいた。だけど急にいなくなった」
「どうして?」
「知るかよ。まじでどうでもいい」
「君にはやり残したこと、ないの? ていうかさ、死んだとき、お経とか読んでもらったんじゃないの? それでも成仏ってできないもん?」
いい加減にしろ、という類の舌打ちが聞こえたような気がした。
「うるさい! 死んだとき、私、人の話なんて全然聞いてなかったから」
僕は頭がくらくらした。今、一体、誰と話しているのだろう。目の前の光景が信じられなかった。それでも、眺めれば眺めるほど、この幽霊は確かに存在するのだと思えた。それほどまでに幽霊の声ははっきりと頭の内側に響いていた。生春巻きの皮みたいに白く透けている以外、女の子はただ女の子だった。一定の距離を保ったまま、今度は幽霊が品定めをする目で僕の全身を眺めた。
「まぁ、お前でいいか」
「何が」
「ねぇ。私と一緒にあの世に行かない? ていうか行こう。行け」
「どういうこと?」
「死ねってこと」
「え」
「試させて」
幽霊は墓石から飛び降りた。敷石の上に着地したわけではなく、その場に浮かんでいた。そしてフェンスを何の支障もなく通り抜け、僕の目の前へと距離を詰めた。かなり気怠い浮遊だった。僕たちは出逢うや否や、至近距離から見つめ合うこととなった。幽霊は怒っているようで、どこか寂しそうな表情を浮かべていた。沈黙の中、生死を超えて初めて何かを交わしあったその瞬間を僕は忘れない。流れる空気はスローモーションを極め、まるで時が止まっているようだった。幽霊の身体を通して夜空はトリミングされ、淡い白のフィルターがかけられていた。遠くに光るオリオン座を僕は見つけた。冬だなと冷静に思った。
「うわー、生きてる」
そう呟く幽霊は、浮かんでいるからか僕より少し高い位置にいた。やがて幽霊は腕を伸ばし、両手で僕の頬を包んだ。見えない何かに引っ張られるように、僕は自然と首をもたげた。僕は触れられる感覚がないまま、素直に唇まで開く。幽霊は僕の顔から手を離さない。人生で感じたことのない冷気を浴びながら、僕はなす術もなく立ち尽くしていた。思わず「……寒いんだけど」と呟き、幽霊はそれを完全に無視した。
「私はお前をこれから殺す」
「……うん」
肯定の言葉が自ずと引き出されるのを僕はぼんやりと聞いた。自分の言葉の意味なんて、息が真っ白なだけで何もわからなかった。
「ねぇ。もしかしたら今から死ぬんだよ。最後に言い残すことある?」
「別にない。……でも今から何するのかだけ教えてよ」
情けなく掠れた僕の声に噛み付くように幽霊は吐き捨てる。
「キス」
「え?」
「あぁ、したことなかったの? キス」
違ぇよ。そう言いたいはずの僕の右手から力が抜けた。酒の空き缶は転がり、その音はどこか乾いた効果音として夜の墓場を演出した。僕はなんとか、崩れずに立っている。幽霊は実体のない唇を歪め、初めて笑顔のようなものを見せている。邪悪かもしれないけど怖くはない、懐かしささえ感じる笑顔だった。本当に何をするんだろう。わからないまま僕はただ、寒さだけを受け入れていた。幽霊は、風でも吹けば消えてしまう幻の光景のようにも思えた。
「じゃあ、動かないで。黙ってて」
「……」
僕は何も言えずに目に焼き付けていた。返事の代わりに吐き出した熱い溜め息の終わり頃が、幽霊と同じ色になるのを。聞いていた。近くで、夜の散歩をしているであろう犬がけたたましく吠える声を。今夜、犬はもしかするとこの現場の唯一の目撃者なのかもしれない。だからと言って何も出来ないだろう。飼い主に「どうしたの、ココアちゃん!」と叱られる以外には。側から見た僕は今、墓の前のフェンスでひとり呆けたように立ち尽くしている二十代前半の男だ。実は幽霊に絡め取られている。
「そうだ。私は、世奈っていう名前で死んだの。世間の世と奈良県の奈。簡単でしょ」
「……」
「今さらそんなのどうでも良いか。……じゃ」
自己紹介を済ませるや否や、女の子はひそやかに距離を詰め、白い影の形で僕に襲い掛かる。やばい。僕は今になって全力で逃げようとした。だけど、意志に反して身体は少しも動かせなかった。金縛りにあう自分を意識しながら、僕は目の閉じ方さえ忘れていた。死ぬ間際には走馬灯のように人生が見えると聞いたことがあるが、僕が見ていたのはまったく別の光景だった。人を見下ろし、じりじりと、獲物を見つけたネコ科の生き物のように迫り来る、知らない女の子。それも若干、透けている。この夜に知った重大な事実がある。幽霊の唇の隙間は夜の闇だ。顔に当たる冷気の正体は、風なんかじゃない。幽霊の吐く息だ。そして、彼女の名前は世奈。指先が微かに痺れる感覚が、生の実感を僕に唯一、与えている。時刻は0時過ぎ。頭をそっと両腕で抱きかかえられた。空気が冷たい。幽霊のキスを受ける僕の酔いは、とっくに醒めている。