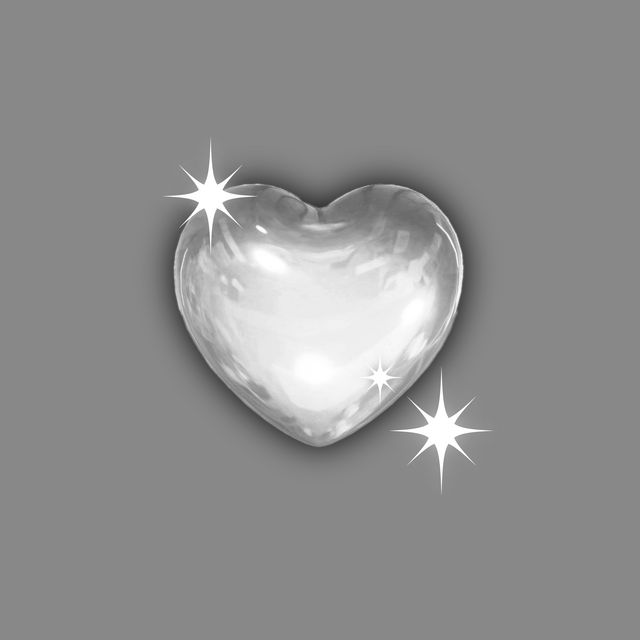6. 幽霊36.9℃
文字数 10,337文字
「ねぇ。夜だよ」
ある夜、突然現れた幽霊は僕の肩の辺りで囁いた。僕は一旦、足を止め、前を向いたまま言った。
「知ってるよ」
「……」
「何やってんの、世奈」
「何もしてない。別にいいでしょ?」
幽霊はそう言うと背後から抱きついてきた。僕は自分の身体に回されたこの世のものではない両腕を眺め「別にいいよ」と言った。そして寒さに身震いした後、再び歩き出した。2月。春は近づいているが、息はまだ白い。
近頃は夜が来ると気づけば幽霊は──世奈は側にいる。仕事帰りの丸まった僕の肩の上に、友達と遊んだ帰り道の途中に、世奈は突然、音もなく現れる。そして不機嫌に側に漂う。僕は密かに幽霊を連れながら、素知らぬ顔をして道路を歩いている。当然、誰も幽霊の存在には気づかない。たまに野良猫がいやに僕を見つめていたり、散歩中の犬が意味ありげに吠えたりはするけれど。
世奈は夜の海で僕に「好き」と言った。どうやらこの日を境に世奈は優しい悪霊と化したらしい。「生まれ変わったら海へ来よう」という約束が、重ねた手が、海で繰り返したキスが、ただの幽霊と人間という僕たちの関係を変えてしまったらしい。今までの彼女は、一応は墓場に納まる幽霊だった。僕が墓参りに行くのを、墓石で待つだけの存在だった。それが、彼女は僕の日常に自ら進んで入り込むようになった。
──完全に取り憑かれてる。
そう思い隣の幽霊を眺めると、彼女は死んだのも忘れたみたいに堂々とそこにいる。一体いつからだろう。側に幽霊がいる事実を当然のように思い始めたのは。最初に物陰から「おい。拓人」と言われたときは、飛び上がるような恐怖を僕は覚えた。だけど今はせいぜい軽く驚くだけだ。会えば世奈は「お疲れ」と優しい言葉をかけてくれる日もある。「死ぬほど仕事が疲れた」と言えば「そんなに怠いなら死んじゃえば」などと突き放す日もある。そして僕たちはそのまま墓に向かい、テンションの低い会話をしたり、キスを繰り返す。幽霊とのキスは不思議と心地良く、もはや気を失うこともない。もし誰かに見られたら? それは少しだけ奇妙な祈りのシルエットでしかないだろう。
夜は幽霊に利用され、幽霊は僕に利用され、日々は幽霊と同じ濃さのぶんフィルターをかけられているようだった。頭の中が夜と幽霊で満たされていくとき、不思議と現実の方が非現実なものにさえ感じられた。仕事で些細なミスを繰り返し、上司の竹内さんに「最近ほんと顔色悪いよ。病院行ったら?」と心配されても、自分が他人のように思えた。ここのところずっと寝不足で、パソコンのモニターに現れる数字に向かう自分が夢のようにも感じる。ゴミを捨て忘れたり、植物を枯らしたり、生活がおろそかにもなっている。それが心底どうでもいいとも思っている。
現実なんて本当に幻覚なのかもしれない。だからこの間、真依と結婚相手がスーパーで手を繋いで買い物するのを見かけても何も感じなかった。僕は僕を好きな幽霊に取り憑かれている、その優越感の前では。僕の理屈なんて終わってる。
きっと世奈は初めからただの迷子だ。そう思ったのは、何の変哲もないある夜のことだった。長い一週間をようやく終え、その日はとても疲れていた。だから僕は墓場に寄らずまっすぐ帰宅するつもりだった。片手に酒と菓子の入ったビニール袋を下げながら、僕は暗い路地を足早に進んでいた。そこを幽霊に襲われたのだった。世奈は電柱の影から浮かび上がり、帰宅途中の僕の前に立ちはだかった。また来たのか。もはや慣れてしまった僕は幽霊を通り抜けようとし、どこか物言いたげな世奈の様子に足を止めた。
「どうしたの。世奈」
「……」
世奈は僕を見ていた。自転車が近づき、幽霊の身体の中を通り抜けて行っても動かずに。そして僕も動けない。金縛りではなく、湧き上がった罪悪感で。成仏を約束したものの、幽霊との日々が刺激的で後回しにし、結局、方法もわからず探すのも面倒にもなっている。口先ばかりの約束に痺れを切らした幽霊は、とうとう僕を殺すのかもしれない。仕方がない。今さら何をされても怖くもない。僕は抗うくらいなら初めから降伏したい。
「好きにしていいよ」
僕はほとんど無意識に両手を上げた。闇によく馴染む世奈は、現れたままの姿で言った。
「今からどこか行きたいんだけど」
「……お墓に帰りたくなくなったの?」
「……そう。なのに、どこに行ったらいいか思いつかない」
世奈は困りきっていて小さな子どものようだった。思えば最初に出会った頃からずっとそうだった。僕はなんだか安堵して、少しだけ身体の力が抜けた。
「そういう日もあるよね。きっと」
「お前と一緒に海に行った日から、私、どこにも行けなくなった」
「え? 飛べるし、すり抜けられるのに?」
「今まで朝までひとりでも平気だったのに。だめになったのはお前のせいだ。本当、死ね」
「……ごめん」
「死んでる私を寂しくさせるなんて最悪。本当、お前も死んじゃえよ」
こんなにも切実な世奈を僕は初めて見た。全部きっと、僕のせいだった。気軽に好きになってごめん、と疲れた頭で考えた。恋に誘い込んではひとりになれない夜を教えてしまったのが僕なら、与えられた霊感の責任を負うべきだろう。僕と一緒にいたいと願う幽霊なら、なるべく僕は側にいてあげたかった。南無阿弥陀仏じゃない方法で心に触れたかった。僕は幽霊から「好き」という言葉を引き出して優位に立った気でいるのかもしれない。わかっている。世奈の言う「死ね」がどんどん「好き」という意味に近づいているのだと。そして今、ふたり仲良く成仏から遠ざかっている。
「でも、今日は出かけるのは無理。疲れてるんだよごめん」
そう言った後で僕は思いついた。だったら、出かけなければいい。
「僕の家、来る?」
幽霊を連れ込んで何をするのか、深く考えずに言った。
「別にどっちでもいい」
そして、世奈は結局、ついてきたのだった。
僕たちは恋人同士がそうするように、仲良く家に帰った。墓地ではなく、少し古びた僕のアパートへ。墓地が世奈の領域なら、ここから先は初めての僕の領域だった。アパートの外階段を登りながら「お前の家、壁、薄そうだね」と世奈は鼻で笑った。実際、壁は薄い。たまに誰かの電話する声や甲高い喘ぎ声が漏れ出している。今も僕ひとりの話し声が、建物のあちこちに聞こえていることだろう。
「ただいま」と誰もいない空間へ呟くと、隣の幽霊はぶっきらぼうに「お邪魔します」と言った。
靴を脱ぐや否や、いつも通りに電気のスイッチを押そうとして伸ばした腕を僕は下ろした。部屋の明るさに幽霊の身体が負ける気がしたからだ。辺りが暗くなければ幽霊はきっと上手く輪郭を持てない。僕は少しでも世奈が見えなくなるのが嫌だった。だから、細く開いたカーテンの隙間から射し込む街灯や月明かりが唯一の光だった。
「えっと……なんか飲む?」
世奈は部屋を一周、漂っていた。掃除しておけばよかったという僕の後悔を見透かすように、散らかった服の上を通り過ぎた後、幽霊は冷蔵庫の上に座った。
「私が何も飲めないの知ってるくせに」
「じゃあ映画でも見る? ホラー映画でもいいよ」
「……」
「めっちゃ怖いやつ、一昨日から配信されたらしいよ」
「気分じゃない。ていうかさ」
「うん」
「今さらだけど私のことが怖くないの? 怖いもの、ないの?」
世奈の問いに僕は思わず笑ってしまった。本当に今さらだ。僕たちは出会って、形にならないキスまでしたというのに。世奈には言わないが、僕はとても怖がりだ。真っ当に幽霊を怖がることすら出来ないほどに怖がりだ。現実から好きなだけ目を塞がせてくれる幽霊の存在なんて、もはやありがたさを感じている。
「全然、怖くないよ。だって世奈じゃん」
僕は冷たい空気のまとわりついたコートを脱ぎ、無造作に床に落とした。マフラーも外した。僕の身体は途端に軽くなった。喉の渇きをおぼえた僕は、冷蔵庫のペットボトルから緑茶を一気に飲んだ。飲み終えると世奈は目の前にいた。墓が近くになくても、世奈は幽霊だった。可愛い。幽霊の頭を撫でようとし、腕は当然のようにすり抜け、僕は立ち尽くした。途端にやることがなくなり、僕たちは真正面からただ見つめ合った。僕はおずおずと腕を広げた。その瞬間、待ちわびていたかのように幽霊は飛び込んできた。僕は薄く透ける白い塊に両腕を回した。触れられないとわかっていても、彼女を抱き締めたかった。
──僕は、世奈が好きだ。
あるはずのない身体に対してそう思う。今の感情は100%純粋なものではないのかもしれない。幽霊に対する僕の「好き」は「かわいそう」と「抱きたい」の半々だからだ。それでも世奈を離せず、僕は思いきり強く彼女を抱き締めた。身体と身体の間にあるはずの空気を押しつぶすように。これ以上は近づくことが出来ない距離と少しも離れることのない距離は等しい。その事実が希望にも絶望にも感じられた。今ここには、世奈という他人の身体があるはずだった。抱き合えるはずだった。彼女が生きてさえいればの話だ。僕の身体の上には今、誰もいないのだ。僕は僕だけを間抜けに抱き締め、まるで今までしてきた恋愛の答え合わせのようだった。
僕は、幽霊の耳元に向かって呟く。
「世奈。好きだよ」
死んでてもいいよ。そう続ける。世奈は、僕たちは何も間違っていないのだと信じるために。
「……」
「だから、生きてる僕のことも許して」
「別にいい」
「そっか。ありがと」
「拓人。私も拓人が好き」
「うん。知ってる。僕も」
世奈が好きだ。言えば言うほど白々しくも感じられる「好き」が本心だと、全力で信じては繰り返した。明日の僕については、明日の僕でさえわからないのかもしれない。だけど今の僕は世奈が好きだと心から信じられた。好き。魔法の言葉だ。今の自分が幸せだろうが不幸せだろうがすべてどうでも良くなる言葉だ。そして、こんな言葉を幽霊に言い続けたところで、結局また「お前も死ね」とか言われるのだろう。僕はそう思った。だけど、返ってきたのは意外な言葉だった。
「ねぇ、拓人。私の中に出してくれる?」
「え?」
僕は身体を離した。何を、とは聞けなかった。世奈は初めて会ったときと同じ表情を浮かべていた。死んでいるのに得意げで、僕を見下す幽霊。世奈はお構いなしに「セックスしてみようよ」と続けた。「どうせ出来ないんだもん。変なことしてみようよ」と。
僕は立ち尽くし、幽霊と見つめ合ったまま黙り、最終的には考えるより先に言葉が出てきた。
「いいよ」
僕は洗面所へ向かうと上半身のぶんだけ服を脱いだ。瞬時に寒さに身震いをし、足元のヒーターの電源を入れた。世奈はその間、僕に背後から抱きついては少しも離れない。それなのに鏡に目をやると見慣れた僕の身体だけが映っている。まるで初めから何も起こっていないように。
「そうだ」
少し楽しい気分になった僕はあることを思いついていた。今、スマホで自撮りをすれば愛すべき心霊写真が出来上がるのかもしれない。上手くツーショットを収められたら、画像は自分だけの宝物にしてもいいし、SNSでいいねの餌にしてもいい。
「写真撮っていい?」
僕はスマホを取り出し、返事を待たずにカメラを起動した。そして胸の高鳴りの中でシャッターを切った。すぐに画面を確認する。残念なことに、僕が写した僕の写真には幽霊の姿なんて一切どこにもなかった。幽霊との、今この瞬間を写した記念写真。高揚感に満ちた未来は、妄想の中でさえ砕け散ってしまったらしい。
「なんだ。せっかくだから写ってよ。世奈」
「気分じゃない。てかモデル料払えよ」
「えー高そうー」
世奈は鼻で笑うと「脱いでよ」とだるそうに続けた。僕は若干ためらいながらも残りの服を脱ぎ、下着一枚の姿になった。世奈は頭の先からつま先まで僕を眺めていた。突っ立っている時間が僕はなんだか気まずく、恥ずかしく、冷たい床に座り込み脚を伸ばした。思わず呟いた。
「いや、無理じゃね?」
冷静になればなるほど幽霊とセックスなんて出来るはずもない。本当はこうしているのが馬鹿みたいだとも思えた。それなのに世奈は僕を解放してはくれない。幽霊の顔が近づいた、と思ったら、耳の奥まで甘く低い囁き声が流れ込んできた。
「私の前で気持ちいいことしてみて」
「何それ……」
「やり方なんてわかるでしょ?」
僕は溜め息をついた。忘れてはいない。幽霊という現実と非現実の境目に、初めから降伏を決めたのは僕だ。正気なんてとっくに捨てている。だったら見られていればいい。見ていればいい。下着を下ろし、僕は性器を手のひらで包んだ。そして性器をしごき始めた。幽霊に見つめられながら。熱い吐息が漏れる。慣れた快楽はすぐに腰の奥まで伝わり、性器は硬くなり、素直で単純な生きている身体だった。僕は世奈の生前の身体を目の前の白い影に重ねようとし、想像力の限界を感じ、結局は何日か前に見たアダルト動画を思い浮かべ、その姿に興奮していた。同時に元カノの真依の乱れる姿も脳裏をよぎっていた。だけど、それらの裸では足りない。知りたい。僕は欲を吐き出したいし、だけどもっと切実に丁寧に触れたい。世奈は一体どんなふうに、誰とどんな声で喘いだのかを。
「世奈……」
「何」
──僕は何も知らない。
そして、世奈は教えてはくれないとわかっていた。死んでいる、その一点で繋がれない相手を前に、僕の手は絶えず規則的な速度で動く。気持ちよさに考えることを少しずつ放棄しながら。やがて幽霊は僕に跨った。生きていれば対面座位だった。僕はあったのかもしれないキスを、濡れた生身の舌を妄想する。欲しい。そう思うと同時に湧いた唾液を飲み込む。世奈は僕の首に両腕を絡めて抱きつき、耳元で囁いた。
「気持ちいい? 拓人」
その囁き声が微かな風となって僕に流れ込んだとき、出る、と思った。
「……っ」
ひとり絶頂を迎えた僕は手の中へ熱い精液を吐き出した。世奈の中に出したと信じた。普通に気持ち良かった。そのこと自体がすぐに空虚さへと変わった。今の自慰はすべての象徴だった。僕は僕を抱き締めるような恋愛、セックス、人生しか送ってこなかったのだと。僕は幽霊を気持ち良くさせる方法がわからない。出来るのはせいぜい、本当はあり得ないはずの見抜きだ。触れたいのに触れられたいこの行為がプラトニックと呼べるなら、あまりにも不純すぎる。それなのに幽霊は微笑んで尋ねている。
「今、幸せ?」
「……」
「答えて。拓人」
幸せでも不幸せでも別にどちらでもよかった。僕は自分の状態をいちいち定めたりしない。ただ、僕の中に確実にあったのは束の間の恍惚、そして今は情けなさだった。僕は逃げるように立ち上がり風呂場へと向かった。熱いシャワーを勢いよく頭上から浴びると、心の奥から何かが溶け出していくようだった。少しだけ元の自分を取り戻せた気がし、溜め息を漏らす。幽霊は今も僕を見ているのだろうか。近くを見回してみても、風呂場に立ち昇る湯気の濃さで世奈の色は薄れ、よくわからない。
「世奈、その辺にいるよね?」
返事はなく、しばらくの間、シャワーの音だけがした。少しずつ膨れ上がる心細さに比例するように、水音は虚しく響いた。僕はシャンプーとボディソープで全身を泡だらけにし一旦は生まれ変わろうとした。そして時間をかけて洗い終え、手持ち無沙汰になってしまった。どれほどの時が経ったのだろう。出しっぱなしのシャワーを止め「……世奈?」と呟くと、ようやく耳元で声だけがした。
「やっぱり、死ねば良いのにお前。気持ち悪」
僕からは思わず、はは、と乾いた笑いが漏れ出した。幽霊の姿形は見えなくても、まだ側にいてくれることに安堵していた。と同時に、気持ちいい行為をした後に自分自身が芯から気持ち悪くなる中学生のような感覚がどこか懐かしくもある。
「みっともないところ見せてくれて、ありがと」
「……何だよそれ」
どういたしまして、と言いかけてなぜか上手く笑えなかった。確かに僕は今みっともなくて恥ずかしい。だけどみっともなさを素直に曝け出せる相手なんて、どうでもいい相手か特別な相手かのどちらかだ。そして世奈は後者だ。たとえ既に死んでいる相手であっても、彼女は僕の思う以上に特別な誰かなんじゃないか。僕はそれを認めようとしてはまだ怖く、夢のような湯気の中に向かって問いかけた。
「……世奈はさ、本当にいるんだよね?」
「今さら、何? 私はいるよ」
風呂場には声が、声だけがこだましている。
「あんたが死んでようが生きてようが、私が見えようが見えなかろうが、ずっといるから」
幽霊の言葉は優しさのぶんだけ悲しく、寂しく響く。
「ねぇ、世奈は今も、成仏したい? 消えたいの?」
僕はそう言って強い後悔に襲われた。なぜなら、僕が投げかけたのは、返事が来るのを永遠に先延ばしにしたい。そんな問いかけだった。そして世奈は答えなかった。
「私たちは、初めから出会えなかったんだよ」
「そうだね」
わかっている。幽霊と僕を結びつけるのが死ならば、隔てるのも死だった。僕たちの出会い方は愛し合うには初めから間に合わない。風呂場の湯気の中で僕は何も出来ずに髪から水滴を落としていた。もしも神や仏がいるのなら尋ねてみたい。どうして性欲が過ぎ去った後の人間を、こんなに物悲しく真剣な生き物にさせたのか、と。
──どうでもいい。
今、幽霊に取り憑かれていることも、恋と呼べる感情を抱いていることも、それがあらかじめ叶わないからこそ心を引き寄せ合う甘い罠であることも。どうでもいい。全部、僕以外の誰かの好きにすればいい。いつもの考え方で僕は心を楽にさせようとする。僕はいつも自分を軽く見繕うことで物事をやり過ごす。それは、傲慢で自意識過剰かもしれないけど僕は僕を含めて誰のことも悲しませたり、傷つけたくないからだ。幽霊になりたいのは僕だ。きっと、幽霊本人以上に。
腕を伸ばし、風呂場の窓を少しだけ開けた。冷えた風が途端に入り込み、僕はくしゃみをした。この風でアパートの浴槽はすぐに冷え、冬の墓石のように冷えることだろう。僕は濡れた裸のままずるずると浴槽にもたれかかる。水滴の溜まった天井を見上げる。すると風呂場にいるはずの自分がいつもの墓場にいるように感じられた。記憶の中で音がする。光が点滅する。キスをしたときの波の音。信号の赤。幽霊の身体の中から見上げた冬の星々。
──私たちは、出会えなかったんだよ。
今も頭の中でリフレインするその言葉がすべてだと思った。僕たちは出会えたのに出会えなかった。だけどいつか振り返ればきっと、僕のした自慰行為は幽霊とのセックスに変わる。世奈への想いはティッシュのように使い捨てられるものではないからだ。そして、世奈はそこにいた。
ようやく立ち上がり、風呂場から出た。今すぐに風邪を引きそうなほど寒かった。服を着た後も、どこか泣き出したいような気持ちを抑えるために僕はバスタオルに頭を突っ込んでいた。「セックス出来たのかな」と世奈はどこかからくすくす笑い、僕はそれが心地良い。タオルから頭を出すと幽霊は、世奈は目の前にいた。
「だけど、不思議。死んでから初めてこんなに満たされた」
「僕がイくの見てただけじゃん」
「まぁ、そうだけど」
幽霊は無表情だった。何を考えているんだろう。そう思った瞬間、その表情のまま彼女は優しく僕にキスをした。殺意なんて微塵も感じさせない、短い触れ合いだった。このキスで死ねたらいい、と思わせるキスも幽霊は出来るらしい。
「私、なんでキスしたのか、ずっと考えてたの。……初めて会った夜」
「ノリじゃないの?」
「違う」
世奈は小さい子にするように、僕の頭に手のひらを置いた。そして続けた。もしかしたら私、きっと初めから知ってたんだと思う、と。
「拓人が、今ここに自分がいないことを後悔させる人だって。……だからどうしていいかわかんなかった。ごめん」
僕たちは狭い洗面所の中、同じ高さで見つめあっていた。世奈はどこか晴れやかな表情で、それは僕が見る、きっと最初で最後の幽霊の後悔だった。そして僕にとっての世奈は、自分が今ここにいることを後悔させる人だ。僕たちは似たもの同士だった。出会わされてしまった、それだけの幽霊と人間だ。
「だけど会えてよかった」
「だね」
「いつかまた会えたら海に行って、その後はそのときになったら考えよ?」
「うん。覚えてるよ。ずっと」
「生まれ変わる理由をありがとね」
「どういたしまして」
僕は寝る支度を整え、ベッドに横たわった。何をするにも幽霊は僕の側を離れなかった。寝ると決めて瞼を閉じると、いつの間にか涙が頬を一筋流れていた。「怖いの? それとも悲しいの?」そう尋ねられ僕は力なく首を横に振る。彼女は幽霊だ。だけど怖いのは幽霊ではなかった。愛することと、愛されることが僕には怖かった。そして、僕は世奈に恋をしてみたかったわけじゃない。僕はただ、自分が生きている事実に、ほんの少しだけ犯されてみたかっただけだ。
「さよなら。拓人。おやすみ」
僕の瞼の向こう側で、世奈は、成仏した。
**
「渡辺くん。最近、顔色いいね。一時はどうしたのかと思ったけど」
職場で上司の竹内さんが言った。僕はパソコンのキーボードを打つ手を止め、小さく頭を下げた。
「すみません。大丈夫です。前は少し寝不足だっただけです」
「へー。なんか、実は噂になってたりもしてたんだよ」
「噂?」
「渡辺くん、やばい女に惚れ込んだりしてるんじゃないか、それでやつれてるんじゃないかって」
何ですかそれ。僕は曖昧に微笑んでは誤魔化し、目の前の仕事に戻った。確かに僕は恋に溺れていたのかもしれない。そう思いながらブラックコーヒーの入ったペットボトルに唇を当てる。
あの夜を最後に幽霊は僕の側から消えた。夜が来ても幽霊の姿はどこにもなく、僕は自然と墓参りをやめてしまった。墓場の側の道を通ることでさえも。取り戻した現実世界はそれはそれで居心地がよかった。仕事中は余計なことを考えずに済む。夜はまっすぐ家に帰る。適度に晩酌をする。そして何気なく巡回したSNSで、友人や元カノの真依が幸せなのを見る。そんな感じで毎日よく眠れている。僕はほとんど誰にも心を乱されることなく日々を送っている。幽霊の世奈とは不確かな想い出であり、いつかの眠りで見た夢に近い。良くも悪くも僕は目が覚めたのだろう。
最後に墓参りに向かったのは、あの夜からひと月以上後のことだった。吐息から白さは消え、近くの桜の蕾が膨らみ始めた頃だった。僕は友人と遊びに行った帰りに偶然、墓場の側を通りかかった。そのとき身体が何かを思い出し、足が勝手に止まった。そして視線はある一点に落ち着いた。小さな墓地の隅の小さな墓。表面には谷口家之墓と刻まれている。
──世奈。
僕は懐かしさに吸い寄せられるように墓石の前まで歩みを進めた。そして、墓石を撫でながら呟いた。
「世奈」
淡い期待を抱きながら墓の上を見ても、誰の姿もなく、返事もなかった。世奈。一度名前を呼ぶと何かが崩壊したように止まらなかった。僕は飽き足らず墓石の表面にキスをした。夜だからか、唇の当たる部分は冷えていた。僕はそっと上から下へ唇を滑らせる。そしてさらに墓石に抱きついた。人目などは一切気にせずに。なぜならここには誰もいない。違う。世奈だけがいる。この世にいないことで救われている世奈が、いつかの再会を願ってどこかで僕を見守っている。僕の人生でもっとも愛おしい不在を教えてくれた、たったひとりの幽霊。
そのとき、僕は人の気配を感じ振り返った。そこには背筋の丸まった小柄なおじいさんがいた。もしかしてこいつも幽霊かよ。そう思ったが、おじいさんは透けても浮かんでもいなければ、地に足を付けていた。そして、墓に縋り付く僕をフェンス越しから不思議そうに見つめている。
「ちょっと、大丈夫?」
「はい……」
いいからさっさとどこかへ行ってくれよ。僕の無様さなんて僕と世奈以外の誰も見ないでくれよ。そう思い、立ち上がると視線で圧をかけた。ところが、おじいさんは僕から視線を逸らしてくれなかった。僕の想像する以上に僕は不審者で、今もしかすると通報3秒前なのかもしれない。
「あんた、何やってんの」
「えっと……ただの墓参りです」
「そう」
おじいさんは言葉を切ると、気の毒そうに僕を見た。
「冷えるから、また昼に来たら」
そうですね。そう言うと、おじいさんは踵を返し、それ以上何も言わずに立ち去って行った。しばらくの間、僕は初めて墓を知った人間のように立ち尽くしていた。本当は、湧き上がる涙で鼻の奥が痛み出すのに必死で耐えていた。そして、もう一度改めて墓石の前にしゃがんだ。両手を合わせる。目を閉じる。言葉を探す。世奈本人の前で繰り返してきた祈りというルーティンが、世にも切実な行為に変わったのを自覚しながら。そういえば幽霊と最後に言葉を交わした夜に言いそびれた言葉がある。僕はそれを思い出し、口を開いた。
「おやすみ。世奈」
僕は僧侶なんかじゃない。だからきっと「南無阿弥陀仏」より、単純なこの言葉が届けたい場所へ届く。するとどこかから「死ねば」という声が聞こえた気がした。僕は額を墓石につけながら心の中で語りかけた。まだ死なないよ。世奈。いつかまた恋をさせてくれるなら、愛させてくれるなら。出会えたときにしたいことがある。僕はこの世界で待っている。初めから冷えも痺れもしない、36度台の熱を帯びたキスを。
ある夜、突然現れた幽霊は僕の肩の辺りで囁いた。僕は一旦、足を止め、前を向いたまま言った。
「知ってるよ」
「……」
「何やってんの、世奈」
「何もしてない。別にいいでしょ?」
幽霊はそう言うと背後から抱きついてきた。僕は自分の身体に回されたこの世のものではない両腕を眺め「別にいいよ」と言った。そして寒さに身震いした後、再び歩き出した。2月。春は近づいているが、息はまだ白い。
近頃は夜が来ると気づけば幽霊は──世奈は側にいる。仕事帰りの丸まった僕の肩の上に、友達と遊んだ帰り道の途中に、世奈は突然、音もなく現れる。そして不機嫌に側に漂う。僕は密かに幽霊を連れながら、素知らぬ顔をして道路を歩いている。当然、誰も幽霊の存在には気づかない。たまに野良猫がいやに僕を見つめていたり、散歩中の犬が意味ありげに吠えたりはするけれど。
世奈は夜の海で僕に「好き」と言った。どうやらこの日を境に世奈は優しい悪霊と化したらしい。「生まれ変わったら海へ来よう」という約束が、重ねた手が、海で繰り返したキスが、ただの幽霊と人間という僕たちの関係を変えてしまったらしい。今までの彼女は、一応は墓場に納まる幽霊だった。僕が墓参りに行くのを、墓石で待つだけの存在だった。それが、彼女は僕の日常に自ら進んで入り込むようになった。
──完全に取り憑かれてる。
そう思い隣の幽霊を眺めると、彼女は死んだのも忘れたみたいに堂々とそこにいる。一体いつからだろう。側に幽霊がいる事実を当然のように思い始めたのは。最初に物陰から「おい。拓人」と言われたときは、飛び上がるような恐怖を僕は覚えた。だけど今はせいぜい軽く驚くだけだ。会えば世奈は「お疲れ」と優しい言葉をかけてくれる日もある。「死ぬほど仕事が疲れた」と言えば「そんなに怠いなら死んじゃえば」などと突き放す日もある。そして僕たちはそのまま墓に向かい、テンションの低い会話をしたり、キスを繰り返す。幽霊とのキスは不思議と心地良く、もはや気を失うこともない。もし誰かに見られたら? それは少しだけ奇妙な祈りのシルエットでしかないだろう。
夜は幽霊に利用され、幽霊は僕に利用され、日々は幽霊と同じ濃さのぶんフィルターをかけられているようだった。頭の中が夜と幽霊で満たされていくとき、不思議と現実の方が非現実なものにさえ感じられた。仕事で些細なミスを繰り返し、上司の竹内さんに「最近ほんと顔色悪いよ。病院行ったら?」と心配されても、自分が他人のように思えた。ここのところずっと寝不足で、パソコンのモニターに現れる数字に向かう自分が夢のようにも感じる。ゴミを捨て忘れたり、植物を枯らしたり、生活がおろそかにもなっている。それが心底どうでもいいとも思っている。
現実なんて本当に幻覚なのかもしれない。だからこの間、真依と結婚相手がスーパーで手を繋いで買い物するのを見かけても何も感じなかった。僕は僕を好きな幽霊に取り憑かれている、その優越感の前では。僕の理屈なんて終わってる。
きっと世奈は初めからただの迷子だ。そう思ったのは、何の変哲もないある夜のことだった。長い一週間をようやく終え、その日はとても疲れていた。だから僕は墓場に寄らずまっすぐ帰宅するつもりだった。片手に酒と菓子の入ったビニール袋を下げながら、僕は暗い路地を足早に進んでいた。そこを幽霊に襲われたのだった。世奈は電柱の影から浮かび上がり、帰宅途中の僕の前に立ちはだかった。また来たのか。もはや慣れてしまった僕は幽霊を通り抜けようとし、どこか物言いたげな世奈の様子に足を止めた。
「どうしたの。世奈」
「……」
世奈は僕を見ていた。自転車が近づき、幽霊の身体の中を通り抜けて行っても動かずに。そして僕も動けない。金縛りではなく、湧き上がった罪悪感で。成仏を約束したものの、幽霊との日々が刺激的で後回しにし、結局、方法もわからず探すのも面倒にもなっている。口先ばかりの約束に痺れを切らした幽霊は、とうとう僕を殺すのかもしれない。仕方がない。今さら何をされても怖くもない。僕は抗うくらいなら初めから降伏したい。
「好きにしていいよ」
僕はほとんど無意識に両手を上げた。闇によく馴染む世奈は、現れたままの姿で言った。
「今からどこか行きたいんだけど」
「……お墓に帰りたくなくなったの?」
「……そう。なのに、どこに行ったらいいか思いつかない」
世奈は困りきっていて小さな子どものようだった。思えば最初に出会った頃からずっとそうだった。僕はなんだか安堵して、少しだけ身体の力が抜けた。
「そういう日もあるよね。きっと」
「お前と一緒に海に行った日から、私、どこにも行けなくなった」
「え? 飛べるし、すり抜けられるのに?」
「今まで朝までひとりでも平気だったのに。だめになったのはお前のせいだ。本当、死ね」
「……ごめん」
「死んでる私を寂しくさせるなんて最悪。本当、お前も死んじゃえよ」
こんなにも切実な世奈を僕は初めて見た。全部きっと、僕のせいだった。気軽に好きになってごめん、と疲れた頭で考えた。恋に誘い込んではひとりになれない夜を教えてしまったのが僕なら、与えられた霊感の責任を負うべきだろう。僕と一緒にいたいと願う幽霊なら、なるべく僕は側にいてあげたかった。南無阿弥陀仏じゃない方法で心に触れたかった。僕は幽霊から「好き」という言葉を引き出して優位に立った気でいるのかもしれない。わかっている。世奈の言う「死ね」がどんどん「好き」という意味に近づいているのだと。そして今、ふたり仲良く成仏から遠ざかっている。
「でも、今日は出かけるのは無理。疲れてるんだよごめん」
そう言った後で僕は思いついた。だったら、出かけなければいい。
「僕の家、来る?」
幽霊を連れ込んで何をするのか、深く考えずに言った。
「別にどっちでもいい」
そして、世奈は結局、ついてきたのだった。
僕たちは恋人同士がそうするように、仲良く家に帰った。墓地ではなく、少し古びた僕のアパートへ。墓地が世奈の領域なら、ここから先は初めての僕の領域だった。アパートの外階段を登りながら「お前の家、壁、薄そうだね」と世奈は鼻で笑った。実際、壁は薄い。たまに誰かの電話する声や甲高い喘ぎ声が漏れ出している。今も僕ひとりの話し声が、建物のあちこちに聞こえていることだろう。
「ただいま」と誰もいない空間へ呟くと、隣の幽霊はぶっきらぼうに「お邪魔します」と言った。
靴を脱ぐや否や、いつも通りに電気のスイッチを押そうとして伸ばした腕を僕は下ろした。部屋の明るさに幽霊の身体が負ける気がしたからだ。辺りが暗くなければ幽霊はきっと上手く輪郭を持てない。僕は少しでも世奈が見えなくなるのが嫌だった。だから、細く開いたカーテンの隙間から射し込む街灯や月明かりが唯一の光だった。
「えっと……なんか飲む?」
世奈は部屋を一周、漂っていた。掃除しておけばよかったという僕の後悔を見透かすように、散らかった服の上を通り過ぎた後、幽霊は冷蔵庫の上に座った。
「私が何も飲めないの知ってるくせに」
「じゃあ映画でも見る? ホラー映画でもいいよ」
「……」
「めっちゃ怖いやつ、一昨日から配信されたらしいよ」
「気分じゃない。ていうかさ」
「うん」
「今さらだけど私のことが怖くないの? 怖いもの、ないの?」
世奈の問いに僕は思わず笑ってしまった。本当に今さらだ。僕たちは出会って、形にならないキスまでしたというのに。世奈には言わないが、僕はとても怖がりだ。真っ当に幽霊を怖がることすら出来ないほどに怖がりだ。現実から好きなだけ目を塞がせてくれる幽霊の存在なんて、もはやありがたさを感じている。
「全然、怖くないよ。だって世奈じゃん」
僕は冷たい空気のまとわりついたコートを脱ぎ、無造作に床に落とした。マフラーも外した。僕の身体は途端に軽くなった。喉の渇きをおぼえた僕は、冷蔵庫のペットボトルから緑茶を一気に飲んだ。飲み終えると世奈は目の前にいた。墓が近くになくても、世奈は幽霊だった。可愛い。幽霊の頭を撫でようとし、腕は当然のようにすり抜け、僕は立ち尽くした。途端にやることがなくなり、僕たちは真正面からただ見つめ合った。僕はおずおずと腕を広げた。その瞬間、待ちわびていたかのように幽霊は飛び込んできた。僕は薄く透ける白い塊に両腕を回した。触れられないとわかっていても、彼女を抱き締めたかった。
──僕は、世奈が好きだ。
あるはずのない身体に対してそう思う。今の感情は100%純粋なものではないのかもしれない。幽霊に対する僕の「好き」は「かわいそう」と「抱きたい」の半々だからだ。それでも世奈を離せず、僕は思いきり強く彼女を抱き締めた。身体と身体の間にあるはずの空気を押しつぶすように。これ以上は近づくことが出来ない距離と少しも離れることのない距離は等しい。その事実が希望にも絶望にも感じられた。今ここには、世奈という他人の身体があるはずだった。抱き合えるはずだった。彼女が生きてさえいればの話だ。僕の身体の上には今、誰もいないのだ。僕は僕だけを間抜けに抱き締め、まるで今までしてきた恋愛の答え合わせのようだった。
僕は、幽霊の耳元に向かって呟く。
「世奈。好きだよ」
死んでてもいいよ。そう続ける。世奈は、僕たちは何も間違っていないのだと信じるために。
「……」
「だから、生きてる僕のことも許して」
「別にいい」
「そっか。ありがと」
「拓人。私も拓人が好き」
「うん。知ってる。僕も」
世奈が好きだ。言えば言うほど白々しくも感じられる「好き」が本心だと、全力で信じては繰り返した。明日の僕については、明日の僕でさえわからないのかもしれない。だけど今の僕は世奈が好きだと心から信じられた。好き。魔法の言葉だ。今の自分が幸せだろうが不幸せだろうがすべてどうでも良くなる言葉だ。そして、こんな言葉を幽霊に言い続けたところで、結局また「お前も死ね」とか言われるのだろう。僕はそう思った。だけど、返ってきたのは意外な言葉だった。
「ねぇ、拓人。私の中に出してくれる?」
「え?」
僕は身体を離した。何を、とは聞けなかった。世奈は初めて会ったときと同じ表情を浮かべていた。死んでいるのに得意げで、僕を見下す幽霊。世奈はお構いなしに「セックスしてみようよ」と続けた。「どうせ出来ないんだもん。変なことしてみようよ」と。
僕は立ち尽くし、幽霊と見つめ合ったまま黙り、最終的には考えるより先に言葉が出てきた。
「いいよ」
僕は洗面所へ向かうと上半身のぶんだけ服を脱いだ。瞬時に寒さに身震いをし、足元のヒーターの電源を入れた。世奈はその間、僕に背後から抱きついては少しも離れない。それなのに鏡に目をやると見慣れた僕の身体だけが映っている。まるで初めから何も起こっていないように。
「そうだ」
少し楽しい気分になった僕はあることを思いついていた。今、スマホで自撮りをすれば愛すべき心霊写真が出来上がるのかもしれない。上手くツーショットを収められたら、画像は自分だけの宝物にしてもいいし、SNSでいいねの餌にしてもいい。
「写真撮っていい?」
僕はスマホを取り出し、返事を待たずにカメラを起動した。そして胸の高鳴りの中でシャッターを切った。すぐに画面を確認する。残念なことに、僕が写した僕の写真には幽霊の姿なんて一切どこにもなかった。幽霊との、今この瞬間を写した記念写真。高揚感に満ちた未来は、妄想の中でさえ砕け散ってしまったらしい。
「なんだ。せっかくだから写ってよ。世奈」
「気分じゃない。てかモデル料払えよ」
「えー高そうー」
世奈は鼻で笑うと「脱いでよ」とだるそうに続けた。僕は若干ためらいながらも残りの服を脱ぎ、下着一枚の姿になった。世奈は頭の先からつま先まで僕を眺めていた。突っ立っている時間が僕はなんだか気まずく、恥ずかしく、冷たい床に座り込み脚を伸ばした。思わず呟いた。
「いや、無理じゃね?」
冷静になればなるほど幽霊とセックスなんて出来るはずもない。本当はこうしているのが馬鹿みたいだとも思えた。それなのに世奈は僕を解放してはくれない。幽霊の顔が近づいた、と思ったら、耳の奥まで甘く低い囁き声が流れ込んできた。
「私の前で気持ちいいことしてみて」
「何それ……」
「やり方なんてわかるでしょ?」
僕は溜め息をついた。忘れてはいない。幽霊という現実と非現実の境目に、初めから降伏を決めたのは僕だ。正気なんてとっくに捨てている。だったら見られていればいい。見ていればいい。下着を下ろし、僕は性器を手のひらで包んだ。そして性器をしごき始めた。幽霊に見つめられながら。熱い吐息が漏れる。慣れた快楽はすぐに腰の奥まで伝わり、性器は硬くなり、素直で単純な生きている身体だった。僕は世奈の生前の身体を目の前の白い影に重ねようとし、想像力の限界を感じ、結局は何日か前に見たアダルト動画を思い浮かべ、その姿に興奮していた。同時に元カノの真依の乱れる姿も脳裏をよぎっていた。だけど、それらの裸では足りない。知りたい。僕は欲を吐き出したいし、だけどもっと切実に丁寧に触れたい。世奈は一体どんなふうに、誰とどんな声で喘いだのかを。
「世奈……」
「何」
──僕は何も知らない。
そして、世奈は教えてはくれないとわかっていた。死んでいる、その一点で繋がれない相手を前に、僕の手は絶えず規則的な速度で動く。気持ちよさに考えることを少しずつ放棄しながら。やがて幽霊は僕に跨った。生きていれば対面座位だった。僕はあったのかもしれないキスを、濡れた生身の舌を妄想する。欲しい。そう思うと同時に湧いた唾液を飲み込む。世奈は僕の首に両腕を絡めて抱きつき、耳元で囁いた。
「気持ちいい? 拓人」
その囁き声が微かな風となって僕に流れ込んだとき、出る、と思った。
「……っ」
ひとり絶頂を迎えた僕は手の中へ熱い精液を吐き出した。世奈の中に出したと信じた。普通に気持ち良かった。そのこと自体がすぐに空虚さへと変わった。今の自慰はすべての象徴だった。僕は僕を抱き締めるような恋愛、セックス、人生しか送ってこなかったのだと。僕は幽霊を気持ち良くさせる方法がわからない。出来るのはせいぜい、本当はあり得ないはずの見抜きだ。触れたいのに触れられたいこの行為がプラトニックと呼べるなら、あまりにも不純すぎる。それなのに幽霊は微笑んで尋ねている。
「今、幸せ?」
「……」
「答えて。拓人」
幸せでも不幸せでも別にどちらでもよかった。僕は自分の状態をいちいち定めたりしない。ただ、僕の中に確実にあったのは束の間の恍惚、そして今は情けなさだった。僕は逃げるように立ち上がり風呂場へと向かった。熱いシャワーを勢いよく頭上から浴びると、心の奥から何かが溶け出していくようだった。少しだけ元の自分を取り戻せた気がし、溜め息を漏らす。幽霊は今も僕を見ているのだろうか。近くを見回してみても、風呂場に立ち昇る湯気の濃さで世奈の色は薄れ、よくわからない。
「世奈、その辺にいるよね?」
返事はなく、しばらくの間、シャワーの音だけがした。少しずつ膨れ上がる心細さに比例するように、水音は虚しく響いた。僕はシャンプーとボディソープで全身を泡だらけにし一旦は生まれ変わろうとした。そして時間をかけて洗い終え、手持ち無沙汰になってしまった。どれほどの時が経ったのだろう。出しっぱなしのシャワーを止め「……世奈?」と呟くと、ようやく耳元で声だけがした。
「やっぱり、死ねば良いのにお前。気持ち悪」
僕からは思わず、はは、と乾いた笑いが漏れ出した。幽霊の姿形は見えなくても、まだ側にいてくれることに安堵していた。と同時に、気持ちいい行為をした後に自分自身が芯から気持ち悪くなる中学生のような感覚がどこか懐かしくもある。
「みっともないところ見せてくれて、ありがと」
「……何だよそれ」
どういたしまして、と言いかけてなぜか上手く笑えなかった。確かに僕は今みっともなくて恥ずかしい。だけどみっともなさを素直に曝け出せる相手なんて、どうでもいい相手か特別な相手かのどちらかだ。そして世奈は後者だ。たとえ既に死んでいる相手であっても、彼女は僕の思う以上に特別な誰かなんじゃないか。僕はそれを認めようとしてはまだ怖く、夢のような湯気の中に向かって問いかけた。
「……世奈はさ、本当にいるんだよね?」
「今さら、何? 私はいるよ」
風呂場には声が、声だけがこだましている。
「あんたが死んでようが生きてようが、私が見えようが見えなかろうが、ずっといるから」
幽霊の言葉は優しさのぶんだけ悲しく、寂しく響く。
「ねぇ、世奈は今も、成仏したい? 消えたいの?」
僕はそう言って強い後悔に襲われた。なぜなら、僕が投げかけたのは、返事が来るのを永遠に先延ばしにしたい。そんな問いかけだった。そして世奈は答えなかった。
「私たちは、初めから出会えなかったんだよ」
「そうだね」
わかっている。幽霊と僕を結びつけるのが死ならば、隔てるのも死だった。僕たちの出会い方は愛し合うには初めから間に合わない。風呂場の湯気の中で僕は何も出来ずに髪から水滴を落としていた。もしも神や仏がいるのなら尋ねてみたい。どうして性欲が過ぎ去った後の人間を、こんなに物悲しく真剣な生き物にさせたのか、と。
──どうでもいい。
今、幽霊に取り憑かれていることも、恋と呼べる感情を抱いていることも、それがあらかじめ叶わないからこそ心を引き寄せ合う甘い罠であることも。どうでもいい。全部、僕以外の誰かの好きにすればいい。いつもの考え方で僕は心を楽にさせようとする。僕はいつも自分を軽く見繕うことで物事をやり過ごす。それは、傲慢で自意識過剰かもしれないけど僕は僕を含めて誰のことも悲しませたり、傷つけたくないからだ。幽霊になりたいのは僕だ。きっと、幽霊本人以上に。
腕を伸ばし、風呂場の窓を少しだけ開けた。冷えた風が途端に入り込み、僕はくしゃみをした。この風でアパートの浴槽はすぐに冷え、冬の墓石のように冷えることだろう。僕は濡れた裸のままずるずると浴槽にもたれかかる。水滴の溜まった天井を見上げる。すると風呂場にいるはずの自分がいつもの墓場にいるように感じられた。記憶の中で音がする。光が点滅する。キスをしたときの波の音。信号の赤。幽霊の身体の中から見上げた冬の星々。
──私たちは、出会えなかったんだよ。
今も頭の中でリフレインするその言葉がすべてだと思った。僕たちは出会えたのに出会えなかった。だけどいつか振り返ればきっと、僕のした自慰行為は幽霊とのセックスに変わる。世奈への想いはティッシュのように使い捨てられるものではないからだ。そして、世奈はそこにいた。
ようやく立ち上がり、風呂場から出た。今すぐに風邪を引きそうなほど寒かった。服を着た後も、どこか泣き出したいような気持ちを抑えるために僕はバスタオルに頭を突っ込んでいた。「セックス出来たのかな」と世奈はどこかからくすくす笑い、僕はそれが心地良い。タオルから頭を出すと幽霊は、世奈は目の前にいた。
「だけど、不思議。死んでから初めてこんなに満たされた」
「僕がイくの見てただけじゃん」
「まぁ、そうだけど」
幽霊は無表情だった。何を考えているんだろう。そう思った瞬間、その表情のまま彼女は優しく僕にキスをした。殺意なんて微塵も感じさせない、短い触れ合いだった。このキスで死ねたらいい、と思わせるキスも幽霊は出来るらしい。
「私、なんでキスしたのか、ずっと考えてたの。……初めて会った夜」
「ノリじゃないの?」
「違う」
世奈は小さい子にするように、僕の頭に手のひらを置いた。そして続けた。もしかしたら私、きっと初めから知ってたんだと思う、と。
「拓人が、今ここに自分がいないことを後悔させる人だって。……だからどうしていいかわかんなかった。ごめん」
僕たちは狭い洗面所の中、同じ高さで見つめあっていた。世奈はどこか晴れやかな表情で、それは僕が見る、きっと最初で最後の幽霊の後悔だった。そして僕にとっての世奈は、自分が今ここにいることを後悔させる人だ。僕たちは似たもの同士だった。出会わされてしまった、それだけの幽霊と人間だ。
「だけど会えてよかった」
「だね」
「いつかまた会えたら海に行って、その後はそのときになったら考えよ?」
「うん。覚えてるよ。ずっと」
「生まれ変わる理由をありがとね」
「どういたしまして」
僕は寝る支度を整え、ベッドに横たわった。何をするにも幽霊は僕の側を離れなかった。寝ると決めて瞼を閉じると、いつの間にか涙が頬を一筋流れていた。「怖いの? それとも悲しいの?」そう尋ねられ僕は力なく首を横に振る。彼女は幽霊だ。だけど怖いのは幽霊ではなかった。愛することと、愛されることが僕には怖かった。そして、僕は世奈に恋をしてみたかったわけじゃない。僕はただ、自分が生きている事実に、ほんの少しだけ犯されてみたかっただけだ。
「さよなら。拓人。おやすみ」
僕の瞼の向こう側で、世奈は、成仏した。
**
「渡辺くん。最近、顔色いいね。一時はどうしたのかと思ったけど」
職場で上司の竹内さんが言った。僕はパソコンのキーボードを打つ手を止め、小さく頭を下げた。
「すみません。大丈夫です。前は少し寝不足だっただけです」
「へー。なんか、実は噂になってたりもしてたんだよ」
「噂?」
「渡辺くん、やばい女に惚れ込んだりしてるんじゃないか、それでやつれてるんじゃないかって」
何ですかそれ。僕は曖昧に微笑んでは誤魔化し、目の前の仕事に戻った。確かに僕は恋に溺れていたのかもしれない。そう思いながらブラックコーヒーの入ったペットボトルに唇を当てる。
あの夜を最後に幽霊は僕の側から消えた。夜が来ても幽霊の姿はどこにもなく、僕は自然と墓参りをやめてしまった。墓場の側の道を通ることでさえも。取り戻した現実世界はそれはそれで居心地がよかった。仕事中は余計なことを考えずに済む。夜はまっすぐ家に帰る。適度に晩酌をする。そして何気なく巡回したSNSで、友人や元カノの真依が幸せなのを見る。そんな感じで毎日よく眠れている。僕はほとんど誰にも心を乱されることなく日々を送っている。幽霊の世奈とは不確かな想い出であり、いつかの眠りで見た夢に近い。良くも悪くも僕は目が覚めたのだろう。
最後に墓参りに向かったのは、あの夜からひと月以上後のことだった。吐息から白さは消え、近くの桜の蕾が膨らみ始めた頃だった。僕は友人と遊びに行った帰りに偶然、墓場の側を通りかかった。そのとき身体が何かを思い出し、足が勝手に止まった。そして視線はある一点に落ち着いた。小さな墓地の隅の小さな墓。表面には谷口家之墓と刻まれている。
──世奈。
僕は懐かしさに吸い寄せられるように墓石の前まで歩みを進めた。そして、墓石を撫でながら呟いた。
「世奈」
淡い期待を抱きながら墓の上を見ても、誰の姿もなく、返事もなかった。世奈。一度名前を呼ぶと何かが崩壊したように止まらなかった。僕は飽き足らず墓石の表面にキスをした。夜だからか、唇の当たる部分は冷えていた。僕はそっと上から下へ唇を滑らせる。そしてさらに墓石に抱きついた。人目などは一切気にせずに。なぜならここには誰もいない。違う。世奈だけがいる。この世にいないことで救われている世奈が、いつかの再会を願ってどこかで僕を見守っている。僕の人生でもっとも愛おしい不在を教えてくれた、たったひとりの幽霊。
そのとき、僕は人の気配を感じ振り返った。そこには背筋の丸まった小柄なおじいさんがいた。もしかしてこいつも幽霊かよ。そう思ったが、おじいさんは透けても浮かんでもいなければ、地に足を付けていた。そして、墓に縋り付く僕をフェンス越しから不思議そうに見つめている。
「ちょっと、大丈夫?」
「はい……」
いいからさっさとどこかへ行ってくれよ。僕の無様さなんて僕と世奈以外の誰も見ないでくれよ。そう思い、立ち上がると視線で圧をかけた。ところが、おじいさんは僕から視線を逸らしてくれなかった。僕の想像する以上に僕は不審者で、今もしかすると通報3秒前なのかもしれない。
「あんた、何やってんの」
「えっと……ただの墓参りです」
「そう」
おじいさんは言葉を切ると、気の毒そうに僕を見た。
「冷えるから、また昼に来たら」
そうですね。そう言うと、おじいさんは踵を返し、それ以上何も言わずに立ち去って行った。しばらくの間、僕は初めて墓を知った人間のように立ち尽くしていた。本当は、湧き上がる涙で鼻の奥が痛み出すのに必死で耐えていた。そして、もう一度改めて墓石の前にしゃがんだ。両手を合わせる。目を閉じる。言葉を探す。世奈本人の前で繰り返してきた祈りというルーティンが、世にも切実な行為に変わったのを自覚しながら。そういえば幽霊と最後に言葉を交わした夜に言いそびれた言葉がある。僕はそれを思い出し、口を開いた。
「おやすみ。世奈」
僕は僧侶なんかじゃない。だからきっと「南無阿弥陀仏」より、単純なこの言葉が届けたい場所へ届く。するとどこかから「死ねば」という声が聞こえた気がした。僕は額を墓石につけながら心の中で語りかけた。まだ死なないよ。世奈。いつかまた恋をさせてくれるなら、愛させてくれるなら。出会えたときにしたいことがある。僕はこの世界で待っている。初めから冷えも痺れもしない、36度台の熱を帯びたキスを。