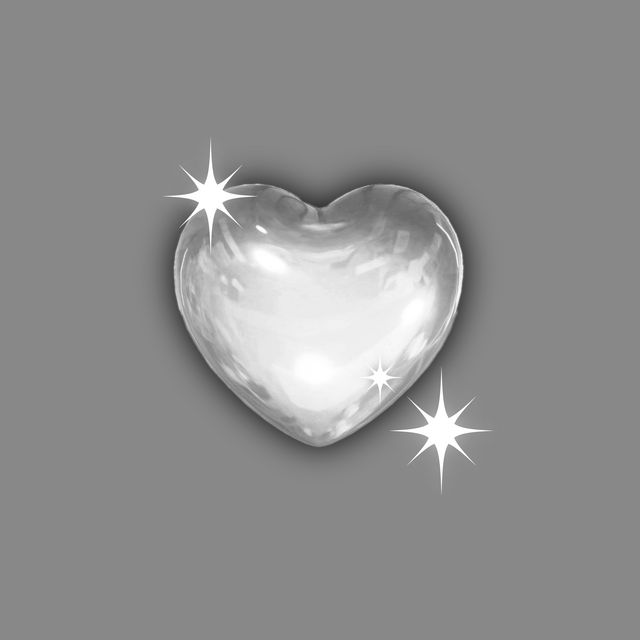4. 彼女と彼女の間
文字数 12,515文字
「幽霊の成仏って、どうやるか知ってる?」
ある日、僕は目の前の生きているひとりの女の子に尋ねた。唐突な僕の質問を、女の子は笑わず茶化さず、真剣に受け止めてくれた。
「えっと……。お坊さんにお願いする。供養してほしい人がいるんですけどって」
「じゃあさ、幽霊本人にそういうのやめてって言われたらさ、どうしたらいいんだろう」
「えー。わかんない。無理なんじゃない?」
「だよね?」
「うん」
女の子は困ったように笑いながら続けた。
「拓ちゃん、もしかして幽霊が見えるの?」
「見えないよ。全部妄想だよ」と僕は小さく笑う。
「そうだよね。霊感ないって、前に言ってたもんね」
そう言うと、僕の隣で気怠く寝転がっていた女の子はベッドから身体を起こした。週末。酒を飲んで映画を観てシャワーを浴び、セックスまでし終えた夜中2時頃のことだった。彼女がペットボトルの水を勢い良く飲み、満足げな溜め息をつく様子を僕は見守る。彼女にも霊感がないと知っているのは、彼女が元カノの真依だからだ。僕たちは数年前、2年程付き合っていた。その時間のおかげで、互いについてある程度は知り合っている。食べ物の好き嫌いや趣味。そしてキスの長さや、好きな身体の撫でられ方についても。
「あ、そうだ! あのね。私、来年結婚するの」
真依は僕のベッドの上で下着を身につけながら言った。明日は晴れだよ、というような調子だった。結婚という予期せぬ単語に、僕は一瞬、宇宙の真ん中に放り出されたような感覚を覚えて固まる。だけど心はすぐに地球に、アパートのベッドに戻されるた。言うべき言葉を思い浮かべるなんて、地上で息を吸うのと同じくらい自然な動作だった。
「おめでとう。お幸せにね」
「ありがと」
「てか彼氏いたんだ。元彼と会ってたら駄目じゃん?」
「そうだね。バレたらまずいよね」
「何。真依はマリッジブルーでこんなことしてんの?」
「そうかも。わかんないや」
中途半端に服を着た真依は、僕の腕の中に収まり、少しの間、僕の素肌に熱い吐息を当てていた。懐かしさを感じながら、僕は真依の肩甲骨の辺りに手のひらを当てる。彼女は付き合っていた頃から、裸で遠慮なく抱き着いては「こうしなきゃ寂しい」と言い「でも嫌だったら離れてね」と控えめに付け加えるのも忘れない、素直で甘え上手で可愛くて、優しい女の子だった。出会ったときから彼女はずっと、周囲の「あの子良いよね」を一箇所にかき集めたような、人に愛されるのが上手い子だった。なぜ取り立てて善人ではない僕と付き合っているのか謎のまま、大学卒業と同時に彼女との関係は終わった。そして、数ヶ月前にふたたび始まった。きっかけはSNSだ。いいねの形で姿を表した彼女は、僕のアップした野良猫の写真に「久しぶり!猫ちゃん可愛い♡」とコメントをつけ、さらにメッセージで「拓ちゃん、元気?」と一気に距離を縮めてきた。昔を懐かしんだ僕たちがリアルで会うのに、時間は掛からなかった。久しぶりに服を脱がせ合うのも。僕たちは以降、なんとなくのノリで会い続けている。
「拓ちゃん、お腹空かない?」
「んー、普通。真依、何食べたいの」
「駅前のカフェのモッツァレラ入ったオムライスかな。気分的にはね」
「夜中なのにだいぶヘビーだね。ていうかあの店潰れたよね?」
「ねー。一緒に何回も行ったのにね。残念」
こんなふうに僕たちは付き合っていた頃の想い出話を自然と繰り出す。だけど、想い出は想い出のままで、僕たちは今さら新しく何かを始める関係ではない。何かを牽制し合っている。そのことが空気から伝わる。確かな不確かさを受け止めることが大人になったということなのだろうか。僕は深く考えるのがただ面倒だった。真依とは、心に余計な重しのかけられないセックスで繋がっているだけだった。抱き慣れた身体、か細い肩甲骨にキスしながら吸う空気は美味い。
「ねぇ、暇なときまた遊びに来てもいい?」
真依は屈託なく笑った後に上目遣いで言った。僕は返事の代わりに真依のダークブラウンの柔らかい髪を撫でた。どっちでも良いよ。という言葉を込めた。
「拓ちゃんといると、一番落ち着くんだよね」
僕の耳元から聞き慣れた甘い声がする。
「なんか、拓ちゃんにはいろいろ、全部わかってもらえそうな気がする」
いつの間にか、真依の唇は僕の耳を辿っていた。ふふ、と照れたような吐息混じりの笑いが注ぎ込まれ、舌先で耳をくすぐられ、僕は思わず身体を離す。
「何それ。僕は何もわかんないよ」
「そんなことないよ。でも、拓ちゃんはそういうところが良いんだよ」
「どういうこと?」
「拓ちゃんは初めから、いろいろわかろうとすることを諦めてる人。だから、一緒にいてすごく楽なの」
「じゃあ、真依の婚約者は?」
「世の中とか……私のことを全然、何も疑わない人」
「へー。熱いね」
真依は照れたように頷いて言った。
「多分、私の人生に必要なのはそういう人」
「そっか。結婚おめでとう」
「だけど拓ちゃんのクールさも嫌いじゃないよ」
甘えて寄りかかる元カノの真依を僕は抱き止め、髪や肌から漂う優しい匂いに目を閉じる。真依に婚約者がいることにも、それを知りながら今もう一回セックスをしようか悩んでいることにも、とりあえず抱き寄せていることにも、一切の罪の意識は芽生えなかった。自分以外の誰かが作り上げるシーツの皺や、そこに残される熱の中でくつろぐ感覚に、ただ僕はいた。こうしていると、心の怪我が優しい動物に舐められるような気がする。僕の心は誰かに傷付けられたわけではなくても、勝手によく皮が剥けている。大したことない痛みだとは思う。
「ねぇ、そういえば何で私たち別れたんだっけ?」
真依はふと思い出したように言った。
「なんでだっけ。だけど別れようって言ったの、真依だよ」
「あぁ。そうだったよね」
僕は忘れない。付き合ってから二度目の春のことだった。デートやキスやセックス、会話。仲良く積み重ねる時間と共に彼女を好きになりかけている僕を、真依はある日突然「今までありがとう。別れよっか」と突き放した。「拓ちゃんとはもうたくさん付き合ったから」と、晴れやかな笑顔で。「わかった」僕はそう言った。理由を尋ねることで別れに抗うのは、別れを受け入れること以上に怖いことに感じられた。それほどに僕は空虚で怖がりな人間だった。
そして、今も同じだった。真依が結婚しようが、今の関係が続こうが、別にうれしくも悲しくもなかった。真依がどんな理由で僕の存在を利用しようと構わなかった。僕も真依を利用しているからだ。誰かに触れて安心したい、本能的な欲求のために。近頃は、今まで以上に身体に寄り添う毛布のような誰かを求めている。温められたいと願っている。そして僕は知っている。理由は冬だから、それだけじゃない。
──幽霊。
「ねぇ、拓ちゃん。顔色悪いよ。寒そう」
「別に寒くないよ」
「だけど……さっき幽霊がどうとか言ってたけど、拓ちゃんがお化けみたいだよ」
僕は「お化け」という、今は聞きたくない言葉を振り払うようにキスをした。真依の唇を借りながら、真依のことを考えないキスだった。互いの唇が示し合わせたように薄く開くとき、僕はいつか訪れる僕自身の成仏の成功を願わずにはいられなかった。この身体がきちんと灰になり、必要以上の痕跡を残さずに消えられますように、と。じゃないとどうなってしまうのか。舌を絡めながら脳裏をよぎるのは墓石の上の不貞腐れた幽霊。世奈。僕の目に映るもっとも寂しい存在といえば彼女だ。
僕の秘密の墓場通いは続いている。成仏させると誓ったあの日から、日々は幽霊に取り憑かれたと言っても過言ではない。僕は何かの偶然で手に入れた霊感を、それも1人の女の子相手限定の霊感を完全にものにしていた。陽が沈むことで始まる何かを常に待ち望んでいた。夜になれば幽霊に会える。退屈な昼はそのためにあるようなもので、近頃は太陽より月のほうが眩しい。ずっと。
僕は幽霊と形にならないキスをした。
かといって別に世奈とは甘い雰囲気を漂わせているわけではない。そもそも触れようとしても触れられないのだから、生きている者と死んでいる者以上の距離で近付こうともしない。僕のやることといえば結局は墓参り、それ以上でも以下でもなかった。供え物を置いてさっさと帰る平日もあれば、夜が終わるまで語り明かす週末もあった。話題は世奈の生前のバイト先の愚痴や、ふたりの共通の好きなゲームと世奈がプレイすることの叶わないその続編、お気に入りの線香の匂いといったありふれたものだ。世奈はド下手なのにゲームが、線香は甘ったるいムスクの香りが好きらしい。僕は少しずつ世奈を知っていくけれど、彼女は、死因や享年といった肝心なものについては相変わらず教えてくれない。聞くと「お前がいつか死んだら教えてやるよ」と鼻で笑う。「今じゃ駄目?」とでも言えば「裏の線路で死んでくれば」と返される。そしてキスは出会いの夜以来、一度もなかった。
幽霊だからか、彼女との夜は刺激的で楽しい。成仏という決められたゴールに最短距離で向かうのが惜しく感じられるほどに。僕は墓地で酒を飲み続け、明け方まで墓にいたこともある。その日はほとんど眠らずに仕事へ向かい、僕は職場の竹内さんに軽く怒られ、心配もされた。「最近、なんだか上の空じゃない? 大丈夫?」と。
僕は大丈夫だ。
僕はいつも僕自身にそう思う。だけどそれは合っているようで少し違う。本当は問題なら、ある。幽霊の成仏の方法がわからない、という点だ。
幽霊のふと零した「寂しい」の言葉に突き動かされ、成仏の手助けを決心したあの夜。つい最近も、手がかりを掴むために僕は直球で世奈に尋ねた。「生きてる間にやり残したこととか、思い出せない?」と。なのに「ありすぎて逆にない」と言われ、取りつく島もない。助けてあげたいという願いは紛れもない本心である一方、方法のわからない「成仏」という言葉が、僕の日常の宙に浮かんでいる。今も、真依の髪に指を通しながら。幽霊を寂しくさせないって、どういうことだろう。
「私、結婚するの」
真依は目と唇を小さく開き、夢を見るような声で言った。その声は僕をふたたび現実に引き戻した。
「うん。さっき聞いたよ」
「ふふ。拓ちゃん。私ね。もうすぐ夫になるあの人のこと、大好きなの」
「よかったじゃん。幸せになってよ」
「だけど……」
「何?」
言葉の途切れた真依を見下ろすと、髪の中で真依はバツが悪そうに笑っていた。
「なんか、殺しちゃいたいなって思うときもあるの」
「え?」
僕の背筋に冷たいものが一瞬、走る。「殺したい」それに似た言葉をかけられ、僕は幽霊にキスをされたことがある。真依は真顔の僕を宥めるように笑うと、微かに表情を曇らせた。
「浮気してるの。彼」
「そうなんだ」
「うん。ついこないだ、知らない女の人とハートまみれのメッセージしてるの、偶然見ちゃった。前にもあったんだけどね。私のじゃない髪の毛が助手席に落ちてたり、そういう古臭くてありきたりな浮気の証拠品が」
「……真依はそれで、いいの?」
「何が?」
「結婚前からそんな女関係ぐだぐだな相手と結婚するの」
真依はあっけらかんと言った。
「別に平気。悲しくなかったわけじゃないけど……。彼が隠そうとしてくれることを無理やりほじくり出すなんて、私には勇気が出ないし。めんどくさいもん」
彼、お金持ちでかっこいいんだよね。背も高いし、今までずっと優しかったし? 人当たりも良くて、うちの親も彼のこと大好きなの。真依は自分に言い聞かせるように彼の魅力を羅列する。言い終えると安心したのか口元は緩んでいる。僕はぼんやりと聞きながら思う。たとえば浮気癖。ただのひとつの欠点、あるいは、すべての良さを帳消しにする致命傷。ふたつの違いは一体何なんだろう。ひとつ言えるのは、僕には真依の結婚に口を挟む余地はなさそうだった。ただ、場の雰囲気に流されて彼女を抱く僕には。
「拓ちゃんとこうやって会ったりして、あの人に間接的にお仕置きしてるのかも。それでイーブン。すっきりする」
「そっか」
「ふふ。わかってるよ。馬鹿みたいでしょ?」
「そんなことないよ。真依が納得してるならそれで正しいよ」
「ありがとう。だから拓ちゃんのことが好き。ねぇ、拓ちゃんもうんと幸せになってね」
幸せ。真依が言うその言葉は正しく魔法をかけるための言葉のように思える。だけど、実際に僕が僕に「幸せになろう」と言い聞かせるとき、その言葉は鉄の鎖のように重く巻き付く何かに変わる。だから言葉はそのまま返したい。「真依が幸せになってよ」と。僕は心の重さから自由でいられればそれで十分だ。そのために、必要以上に、身体以上の手段で誰かと関わりたくなかった。
「真依はちゃんと幸せになれる?」
僕はそう言おうとし、思いとどまっては言葉を飲み込み、シーツの上に身体を置いた。そして「やっぱり眠いから、私も寝るね」と目を閉じる彼女を背後から抱き締めた。真依は可愛い。それできっと、正しい。そう思いながら、一旦死んだように昼前まで眠った。何の夢も見なかった。
**
翌日、陽が沈むや否や、僕はどこか待ちきれない想いで、いつもの墓地へと足を運んだ。無性に世奈に会いたくなっていた。墓地で不貞腐れる幽霊に「死ね」とでも言われれば、僕の今の気持ちがどんな名前のものだろうが、清々しく手放せるような気もした。それを望んでいた。だけど、世奈は「谷口家之墓」の上にはいなかった。代わりに見覚えのない新しい花が墓には供えてあり、僕は自分以外の誰かの存在を初めて思った。僕は墓前にしばらく立ち尽くした後、一旦は諦めて家に帰った。霊感のない夜もあるだろう。あるいは幽霊にも暇じゃない夜があるのだろう、と。翌々日の夜も諦めきれずに訪れたが、世奈はやはりいなかった。なぜかわずかに胸が痛み、僕はその理由を無視した。
幽霊の彼女とふたたび会えたのは、結局、3日目だった。22:07。細く柔らかな雨が降る夜。世奈は墓の上で微動だにせず頬杖をついていた。安堵にも苛立ちにも似た気持ちを抱きながら、僕は広げたネイビーの傘の中で「暇?」と言った。聞こえているのかいないのか、世奈は僕を無視した。ようやく発せられた言葉は「……邪魔」だったけど、僕はその言葉にほっとして溶けそうになった。恋にも夢にも似た霊感がまだ僕の手元にあることに。
「ごめん。はい。今日のお供え」
僕は傘の中でしゃがみ、懲りずに花を供えた。先に差されていた花の側に無理やり詰め込むように、淡い色の花々を差した。いつか世奈が成仏できますように。僕は手を合わせながら変わり映えのない内容を祈り、そんな祈りはさっさと終え、目を開けて語りかける。
「そういえばさ」
「……」
「たまに墓いないけど、どこ行ってんの? 幽霊は」
「……」
「昨日、墓にいなかったじゃん」
「出かけてただけ。だけど、別にどこでもいいでしょ」
「そっか。誰かに呪いでもかけに行ったん? 気になるから教えてよ」
「生きてる人には関係ない」
傘で区切られた視界の隅に、透ける世奈の両足が見える。その白い影の中を絶えず雨が通り過ぎている。墓は泣き続けているように濡れている。冬の雨の中、墓参りをするのは初めてで、夏よりもずっと静かなんじゃないかと僕は思った。やがて世奈は諦めたように呟いた。
「暇すぎたから、生きてたときの場所、いろいろ行ってただけ」
「へー。どこ?」
家。世奈はガムを吐き出すように言った。自分の仏壇、見に行ったの。あと、あんまり仲良くなかったけど、母親のことも一応。私、母親と2人で暮らしてたから。
「お母さん、元気だった? それとも元気じゃない方が良かった?」
僕の質問を無視し、世奈は続けた。
「うちの母親、メンヘラなんだよねー」
てかメンヘラっていうより男依存なんだよ。あの人、私が生きてるときから、私より男の人のほうが好きだった。家には全然知らない人がいたの。ベタベタしてたから母親の新しい彼氏だってすぐにわかった。信じらんないけど、娘の仏壇と壁一枚隔てた部屋で盛ってて本当に吐きそうだった。だけどすごく元気に生きてるって思った。
「そっか」
淡々と語られる世奈の言葉を、僕は真依のときと同じようにただ受け止める。
「渡辺」
「え、何」
世奈は墓の上から僕を見下しては突き放して、言った。
「あんたって悩みなさそうでいいね?」
「はは。ありがとう」
だけどまぁ、御愁傷さまっていうことで。僕は世奈と真依、そして僕自身、目の前で眠る、もう死んでしまったすべての人々に対して言い放った。生きていようが、死んでいようが、人には人の事情があるのだ。自分にさえ他人事を貫くのが上手く生きるコツのように思え、僕はなるべく僕自身ですら薄めて生きていきたいと願っている。僕は立ち上がり、辺りを眺め回した。僕の好きな静かなパワースポット。墓。その真ん中で、お構いなしといった様子で冬の雨に打たれている世奈。彼女に傘を傾けながら、僕は言った。
「暇だし、今からどっか行かない?」
「は? なんで」
「ここにいても埒が開かないから」
それは墓参りを超えた初めてのデートの誘いだった。言った後で僕は中学生のように胸が高鳴っていることに気がついた。気がついた後でわずかに頬が熱くなるのを感じた。セックスを約束させるようなキスよりも、まだ手すら繋いだことのない誰かとのデートはかえって緊張する。それでも、したい。きっと世奈はついてくるだろう、僕にはそんな勝算もあった。そして実際、踵を返した僕の肩に、白い影はついてきた。「お前と出かけても別に楽しくないんだけど」という悪口付きで。
「僕は、世奈と墓以外のところに行けたらうれしいよ」
「そう」
どんなに世奈が不機嫌だろうが、僕は楽しかった。墓地から出た途端、濡れた硬いアスファルトが雲の絨毯にも感じられた。目的地なんてどこでもいい。せっかくの霊感だ。今、傘を差しながら肩に幽霊を浮かべて街を歩くのは、僕くらいしかいないだろう。しかも、取り憑かれているようで取り憑かせている。こんな形のデートが存在するだなんて、この街の誰もが思いもしないだろう。そんな優越感があった。狂気でもよかった。
「濡れるよ。ちゃんと傘、入りなよ」
「濡れないよ。死んでるんだから」
世奈はおとなしく僕の差す傘の中に入り、その中で漂っていた。たまにふらふらとどこかへ飛んで行き、それでも僕の肩の辺りに戻ってきた。
僕たちはふたりで、人ひとりぶんの足音を立てて雨の夜を歩いた。途中、雨にもかかわらずランニングをする夫婦、犬の散歩をする中年の男、びしょ濡れの女子高生を乗せた自転車、酔っ払った大学生の集団とすれ違った。当然、その誰もが世奈に気が付かなかった。ひとりで喋り続ける男だと思われないように、僕は声を顰めて歩き、世奈と時々目を合わせた。なんだか仲良く小さな犯罪を犯している気分だった。視線を交わす何回目かで、世奈は初めて笑ってくれた。完全に僕を馬鹿にしたような笑顔だったが、それでもよかった。
明るい街灯の光に近づくと幽霊の姿はますます薄くなり、離れるとふたたび姿を取り戻す。世奈は幽霊でも律儀に信号を守る。僕もそれに従う。たまに何かに勘づいた犬が世奈に吠える。「うるせークソ犬くたばれ」と悪態をつく幽霊のそばで僕は「元気なワンちゃんですね」と飼い主に挨拶をする。コートのポケットでスマホが震える。「来週末、遊びに行ってもいい?」と真依からLINEが届いている。「いいよ」と僕は返事をする。世奈は耳元で「死ねば」と囁く。現実と非現実の間で頭がおかしくなりそうだ。だけどそんな散歩が楽しい。
やがて僕たちは寝静まった住宅街を通り抜け、駅前に辿り着いた。すっかり忘れていたが、今は金曜日の夜。立ち並ぶ飲食店の前でいくつもの傘が楽しげに広がっていた。傘からはみ出し、濡れながら酔っ払っている人もいた。僕は道の端で立ち尽くし、隣を見上げた。世奈の身体は今、大衆居酒屋の柔らかいオレンジ色の光を通して透けている。
「は? きっしょ、勝手に通んなよ」
世奈は図らずも自分の身体を貫通していった人の後ろ姿を睨んでいた。「なんか、今一瞬すげー寒かった!」その男は幽霊の存在など考えもしないような声で笑い、適当な店へ仲間と入っていった。どこもかしこも笑い声が溢れ返っている。飲んだくれる人々は漏れなくとても楽しそうだと僕は思った。世奈が生きていれば、ふたりでその輪に加わる未来もあったのかもしれない。
「この辺、懐かしい?」
僕はキャッチの男をかわした後で世奈に聞いた。
「別に。……ねぇ。私、高校出てから、あそこでバイトしてた。コンカフェ」
世奈の指差す先には雑居ビルが、ピンク色の文字の浮かぶ看板があった。僕たちは少しの間、その場に立ち止まったまま店を眺めていた。すると、店内から中年の男が「本当はまだ帰りたくないよー。リナちゃん!」とか言いながら、千鳥足で転がるように出てきた。「私あいつ知ってる」駅に向かって男が徐々に遠ざかる様子を、世奈は冷えた目で見送っていた。
「懐かしい。あいつ、店の常連なんだけどさ。本当、金やばいんじゃねってペースで店通ってた。結婚しようとか、金がないなら俺の金で大学に行かせてやるとか、なんか色々言ってたなー」
「へぇ。良い客じゃん」
「まぁ、金払いはね」
私、だいぶ推されてた。世奈は懐かしそうにぼやく。
「でもさ、私がいなきゃいないで、さっさと他の子に切り替えていくんだよねー。まぁ知ってたけど。それでいいけど」
「あのおっさんは世奈が死んだの、知ってんのかな」
「知らないんじゃない?」
「ハッピーな奴だね」
「そうだよ。いいんだよそれで。自分で好きになった人とかものに縛られちゃったら、なんか全然意味ないじゃん。愛ってさ、重めに見せかけて軽めなやつがいいんだよ。ちょうどいい重さってあるから」
「あー。そうかも」
僕はどこかの飲み屋に入ろうか少し悩んだが、世奈が死んでいることを思い出し、やめた。生きていたら一回くらいは、世奈と飲みたかったかもしれない。そう思いながらあてもなく辺りを歩き続けた。途中、コンビニで酒を買い、傘の中で僕は飲み始めた。僕たちの足は自然と駅前から離れ、人の数は次第に減っていった。歩いているうちに、そびえる小さな山に辿り着いた。そこには安産祈願で名の知れた、僕たちにあまり関係のない神社がある。黙ったまま仲良く、境内へと向かう長い階段を登った。結局、墓を抜け出そうが僕たちは静かな場所へ向かうのだと思うとおかしい。階段を登り切る頃、僕だけが疲れ、息切れを起こしていた。世奈はマイペースに隣で涼しげに浮かんでいるだけだった。
「幽霊の身体は楽そうでいいね」
「何。やっと死にたくなった?」
「ならねーよ」
僕は日頃の運動不足を感じながら、境内の中にある東屋へ入った。休憩がてら雨宿りがしたかった。ベンチに腰掛け、アルコールを帯びた白い息を吐き出す。東屋からは夜の街が一望できた。街の寝ている部分と起きている部分が、光の量で一目瞭然だった。視界の遠くを横切るように走り抜ける8両編成の電車。そろそろ終電の時間が近づいているはずだ。ベンチの向かい側から気怠く街を見ている世奈は今、どんな気持ちでいるのだろう。成仏できず自分の終わりさえ見えない彼女は。
「世奈。なんとなく来たけどさ、夜の神社って結構良いよね」
「神社って正月以外、用事なくない? おみくじと初詣以外何すんの」
「ご祈祷とかいろいろ。あとはこういうデートとかじゃない? 雰囲気あるじゃん。神社って」
「……」
「あ、幽霊って神社で体調悪くなる? 平気?」
「……平気。ねぇ。教会にいる悪魔みたいな扱いしないでくれる」
「ごめん。世奈、今、何考えてんの?」
「別に何も」
「そっか」
しばらくの間、僕は幽霊を墓から連れ出した非現実的な気分に浸った。陳腐な言葉だが、ありふれた光景がいつもと違って見えた。この街も人も生きているのだと、皮肉にも幽霊の姿が僕に伝えてくれている。人間の営みが愛しいとか、今、特別に幸せだとか、僕はそんなことは思わない。そもそも僕は別に世間に愛着を持っていない。だけど、この世界はかつて世奈が存在した世界で、時に世間体に疲れたりもしながら、一生、世界そのものは憎めないのかもしれない。世間よりも世界、世界よりも世奈が今の僕には身近だ。世の後についてくる一文字次第で僕は振り回されている。頭の中で「世」という漢字がゲシュタルト崩壊を起こし、隣にいる幽霊を僕は眺める。僕の頭をおかしくさせているのか、ぎりぎりの理性にとどめているのかわからない夜風を、幽霊で濾された夜風を、余すことなく僕は浴びる。今夜は線香じゃなく湿った樹々や葉の匂いがする。雨はいつの間にか止んでいる。冬。僕は寒さに何度目かの身震いをする。
「なんでお前、生きてんの?」
気がつくと世奈は僕のすぐ隣にいた。「知らない。何。哲学? それとも死ねってこと?」僕が聞き返すと世奈は黙った。そして数秒後、頭を僕に傾け、もたれかかってきた。おそらく、彼女なりに僕の肩に頭を乗せたのだとわかった。思いがけない甘い展開だった。僕も同様に頭を世奈に傾けようとし、襲いかかるかもしれない金縛りを思い出し、思わず眉を顰めた。なんせ相手は幽霊だ。近づくとまた痛い目に遭うかもしれない。だけど、僕の身体はいつものままで、幽霊を身体に絡み付かせながら人体の平常を保ったままでいられた。このとき、幽霊の冷気だけははっきりと感じられた。僕は一体、何を克服してしまったのだろう?
「世奈といると寒い」
「ふーん。なんでだろうね」
冬だから。そして、幽霊だからだ。僕と世奈は恋人のように身を委ねあっていた。お互いの重みを少しも感じられないまま。触れ合う実感は今夜もない。せめてもの思いで、僕は幽霊の存在を感じることに集中した。かつて世奈に存在したはずの体温をイメージした。すると世奈に触れたくなり、空いた腕で小さな頭を撫でようとした。だけど手のひらは冷たい空気を掴んだ。どうしようもなく溜め息が白い。何にも邪魔されず、いくらでも暖め合えるはずの冬という季節を持て余しているのだった。
「腕邪魔なんだけど」
そう言う幽霊を僕は薄目で見つめる。
「世奈は、誰かと抱き締め合うのがあったかいって、今も覚えてる?」
「うん」
「……そっか」
すべてがどうでも良くなった僕は諦めて目を閉じる。確実に触れられる、という意味で真依が少し恋しい。だけど生きている真依も死んでいる世奈も、どちらも等しく僕を満たさない。そして僕が僕である以上僕ですら僕を満たすことも出来ない。僕と世奈は、触れ合う以外ならきっと何だって出来る。それが自由なのか不自由なのかも、今はわからない。
「まじ、幸せって何なんだろうね」
ふとつぶやいた僕に、世奈は身体を離しながら言った。
「めんどくさいこと聞かないでくれる?」
「死んでる観点から教えてよ」
しつこく聞くと、世奈は薄笑いを浮かべた。
「知らない。私はそういうの全部、墓の下に半分埋めてきちゃったから」
気付くと世奈は東屋から離れ、僕に背を向けたまま宙に浮かんでいた。世奈の視線の先には光る街が広がっていた。
「だけど私は、死んで良かった。そう思いたいの」
「どうして? 本心?」
「全部、私が選んだから。私がそうしたかったから、死んだ」
その一言に、僕は踏み込むことをすべて諦めた。彼女はおそらく自分で死んだのだ。理由や手段はどうであっても。覆すことのないその事実がすべてだった。
「僕は生きてて良かったよ」
さらに言うと、世奈が生きていてくれたらもっと良かった。僕は言葉を飲み込み、握った拳に力を込める。今この瞬間、世奈の死を悔いてしまうことでさえ怖かった。出会ったときから幽霊で、死んでしまっていた世奈。後悔や無念さという、取り返しのつかない領域に踏み込む勇気なんて僕にはなかった。傷付くことへの警告がいつも僕に考えることを止めさせる。僕はアルミ缶に唇を押し当てた。買ったすべての酒を次々と喉に流し込み、心地よい眠気が全身を包む頃に尋ねた。
「このまま、朝までここにいる?」
半端に開いた唇はとても冷えていた。
「帰る。別にいる意味もないから」
気乗りしない世奈に「わかった」と言いながらも、僕は名残惜しかった。幽霊を連れ出した。そんな唯一の夜を終わらせることが。だから、立ちあがろうとせずに背中をベンチに預けたままでいた。彼女の苛立つ気配がすぐに伝わってきた。
「ねぇ、渡辺。帰ろう。……帰れ」
「少しだけ待ってよ」
「だってこれ以上いたら、私」
「何」
世奈は言葉を切っていた。いつの間にか目の前に移動した幽霊を僕は至近距離で見上げた。空洞の目。完全な人型ではあるけれどどこか曖昧な輪郭と白いシルエット。初めて出会い、キスをしたあの夜と何も変わらない姿をしていた。幽霊は、相手が世奈というだけでもはや怖くない。それどころか僕は、僕を襲う冷気の中に生前の世奈を見つけたような気がした。初めてのことだった。幽霊の姿に肌や爪や指や髪を想像の中から貼り付けていくのは。世奈は僕に取り憑く幽霊である以前に、抱き寄せられるはずのひとりの女の子だった。普通の可愛い女の子だった。想像の中で出来上がった彼女を、僕は抱き寄せ、キスをし、やっぱり抱きたいと思う。そしてその願望は叶うことのない望みの刃物だ。
──相手はもう死んでるのに、馬鹿かよ。
僕は奥歯を噛み締める。世奈は吸い寄せられるように僕に近づく。何を企んでいるのだろう。どうせ生きていても主体性なく漂っているだけの僕だ。今夜こそ殺されても構わない。僕は挑むように世奈と見つめ合う。世奈の顔はキスの距離にあった。しばらくの間、世奈は夜風と冷気を、僕は漏れ出す息をそれぞれ送った。
「……なんでもない」
沈黙の中で先に目を逸らしたのは、彼女だった。
「てか気分悪い」
「わかった。もう帰ろう。世奈」
なんだか馬鹿馬鹿しいなと思いながら立ち上がった。僕たちは神社を後にし、長い石段を降り、真夜中の街をふたたび歩き始めた。世奈は僕より高い位置で浮かんでいるのが常だった。だけどこのとき、世奈の頭は僕の肩の辺りにあった。僕たちは繋げるはずもない手を繋ぎ、指を絡め、歩調を完全に合わせあった。世奈の墓場へと一緒に帰るために。これ以上、ふたりが近づくことはないと知るために。
「お前のこと、絶対に好きになりたくない」
「うん」
「だから私は死んでてよかった」
ここへ来たときよりも確実に縮まった距離で世奈はつぶやいた。幽霊の彼女は朝が来れば消える。何かのピースを埋めれば永遠に消える。僕の目的は彼女の成仏。現世にとどまる幽霊を葬る優しいはずのその行為が、僕は初めて寂しいと思った。だから思わず言ってしまったのだった。南無阿弥陀仏とは真逆の言葉を。
「僕は、世奈が好きだよ」
ある日、僕は目の前の生きているひとりの女の子に尋ねた。唐突な僕の質問を、女の子は笑わず茶化さず、真剣に受け止めてくれた。
「えっと……。お坊さんにお願いする。供養してほしい人がいるんですけどって」
「じゃあさ、幽霊本人にそういうのやめてって言われたらさ、どうしたらいいんだろう」
「えー。わかんない。無理なんじゃない?」
「だよね?」
「うん」
女の子は困ったように笑いながら続けた。
「拓ちゃん、もしかして幽霊が見えるの?」
「見えないよ。全部妄想だよ」と僕は小さく笑う。
「そうだよね。霊感ないって、前に言ってたもんね」
そう言うと、僕の隣で気怠く寝転がっていた女の子はベッドから身体を起こした。週末。酒を飲んで映画を観てシャワーを浴び、セックスまでし終えた夜中2時頃のことだった。彼女がペットボトルの水を勢い良く飲み、満足げな溜め息をつく様子を僕は見守る。彼女にも霊感がないと知っているのは、彼女が元カノの真依だからだ。僕たちは数年前、2年程付き合っていた。その時間のおかげで、互いについてある程度は知り合っている。食べ物の好き嫌いや趣味。そしてキスの長さや、好きな身体の撫でられ方についても。
「あ、そうだ! あのね。私、来年結婚するの」
真依は僕のベッドの上で下着を身につけながら言った。明日は晴れだよ、というような調子だった。結婚という予期せぬ単語に、僕は一瞬、宇宙の真ん中に放り出されたような感覚を覚えて固まる。だけど心はすぐに地球に、アパートのベッドに戻されるた。言うべき言葉を思い浮かべるなんて、地上で息を吸うのと同じくらい自然な動作だった。
「おめでとう。お幸せにね」
「ありがと」
「てか彼氏いたんだ。元彼と会ってたら駄目じゃん?」
「そうだね。バレたらまずいよね」
「何。真依はマリッジブルーでこんなことしてんの?」
「そうかも。わかんないや」
中途半端に服を着た真依は、僕の腕の中に収まり、少しの間、僕の素肌に熱い吐息を当てていた。懐かしさを感じながら、僕は真依の肩甲骨の辺りに手のひらを当てる。彼女は付き合っていた頃から、裸で遠慮なく抱き着いては「こうしなきゃ寂しい」と言い「でも嫌だったら離れてね」と控えめに付け加えるのも忘れない、素直で甘え上手で可愛くて、優しい女の子だった。出会ったときから彼女はずっと、周囲の「あの子良いよね」を一箇所にかき集めたような、人に愛されるのが上手い子だった。なぜ取り立てて善人ではない僕と付き合っているのか謎のまま、大学卒業と同時に彼女との関係は終わった。そして、数ヶ月前にふたたび始まった。きっかけはSNSだ。いいねの形で姿を表した彼女は、僕のアップした野良猫の写真に「久しぶり!猫ちゃん可愛い♡」とコメントをつけ、さらにメッセージで「拓ちゃん、元気?」と一気に距離を縮めてきた。昔を懐かしんだ僕たちがリアルで会うのに、時間は掛からなかった。久しぶりに服を脱がせ合うのも。僕たちは以降、なんとなくのノリで会い続けている。
「拓ちゃん、お腹空かない?」
「んー、普通。真依、何食べたいの」
「駅前のカフェのモッツァレラ入ったオムライスかな。気分的にはね」
「夜中なのにだいぶヘビーだね。ていうかあの店潰れたよね?」
「ねー。一緒に何回も行ったのにね。残念」
こんなふうに僕たちは付き合っていた頃の想い出話を自然と繰り出す。だけど、想い出は想い出のままで、僕たちは今さら新しく何かを始める関係ではない。何かを牽制し合っている。そのことが空気から伝わる。確かな不確かさを受け止めることが大人になったということなのだろうか。僕は深く考えるのがただ面倒だった。真依とは、心に余計な重しのかけられないセックスで繋がっているだけだった。抱き慣れた身体、か細い肩甲骨にキスしながら吸う空気は美味い。
「ねぇ、暇なときまた遊びに来てもいい?」
真依は屈託なく笑った後に上目遣いで言った。僕は返事の代わりに真依のダークブラウンの柔らかい髪を撫でた。どっちでも良いよ。という言葉を込めた。
「拓ちゃんといると、一番落ち着くんだよね」
僕の耳元から聞き慣れた甘い声がする。
「なんか、拓ちゃんにはいろいろ、全部わかってもらえそうな気がする」
いつの間にか、真依の唇は僕の耳を辿っていた。ふふ、と照れたような吐息混じりの笑いが注ぎ込まれ、舌先で耳をくすぐられ、僕は思わず身体を離す。
「何それ。僕は何もわかんないよ」
「そんなことないよ。でも、拓ちゃんはそういうところが良いんだよ」
「どういうこと?」
「拓ちゃんは初めから、いろいろわかろうとすることを諦めてる人。だから、一緒にいてすごく楽なの」
「じゃあ、真依の婚約者は?」
「世の中とか……私のことを全然、何も疑わない人」
「へー。熱いね」
真依は照れたように頷いて言った。
「多分、私の人生に必要なのはそういう人」
「そっか。結婚おめでとう」
「だけど拓ちゃんのクールさも嫌いじゃないよ」
甘えて寄りかかる元カノの真依を僕は抱き止め、髪や肌から漂う優しい匂いに目を閉じる。真依に婚約者がいることにも、それを知りながら今もう一回セックスをしようか悩んでいることにも、とりあえず抱き寄せていることにも、一切の罪の意識は芽生えなかった。自分以外の誰かが作り上げるシーツの皺や、そこに残される熱の中でくつろぐ感覚に、ただ僕はいた。こうしていると、心の怪我が優しい動物に舐められるような気がする。僕の心は誰かに傷付けられたわけではなくても、勝手によく皮が剥けている。大したことない痛みだとは思う。
「ねぇ、そういえば何で私たち別れたんだっけ?」
真依はふと思い出したように言った。
「なんでだっけ。だけど別れようって言ったの、真依だよ」
「あぁ。そうだったよね」
僕は忘れない。付き合ってから二度目の春のことだった。デートやキスやセックス、会話。仲良く積み重ねる時間と共に彼女を好きになりかけている僕を、真依はある日突然「今までありがとう。別れよっか」と突き放した。「拓ちゃんとはもうたくさん付き合ったから」と、晴れやかな笑顔で。「わかった」僕はそう言った。理由を尋ねることで別れに抗うのは、別れを受け入れること以上に怖いことに感じられた。それほどに僕は空虚で怖がりな人間だった。
そして、今も同じだった。真依が結婚しようが、今の関係が続こうが、別にうれしくも悲しくもなかった。真依がどんな理由で僕の存在を利用しようと構わなかった。僕も真依を利用しているからだ。誰かに触れて安心したい、本能的な欲求のために。近頃は、今まで以上に身体に寄り添う毛布のような誰かを求めている。温められたいと願っている。そして僕は知っている。理由は冬だから、それだけじゃない。
──幽霊。
「ねぇ、拓ちゃん。顔色悪いよ。寒そう」
「別に寒くないよ」
「だけど……さっき幽霊がどうとか言ってたけど、拓ちゃんがお化けみたいだよ」
僕は「お化け」という、今は聞きたくない言葉を振り払うようにキスをした。真依の唇を借りながら、真依のことを考えないキスだった。互いの唇が示し合わせたように薄く開くとき、僕はいつか訪れる僕自身の成仏の成功を願わずにはいられなかった。この身体がきちんと灰になり、必要以上の痕跡を残さずに消えられますように、と。じゃないとどうなってしまうのか。舌を絡めながら脳裏をよぎるのは墓石の上の不貞腐れた幽霊。世奈。僕の目に映るもっとも寂しい存在といえば彼女だ。
僕の秘密の墓場通いは続いている。成仏させると誓ったあの日から、日々は幽霊に取り憑かれたと言っても過言ではない。僕は何かの偶然で手に入れた霊感を、それも1人の女の子相手限定の霊感を完全にものにしていた。陽が沈むことで始まる何かを常に待ち望んでいた。夜になれば幽霊に会える。退屈な昼はそのためにあるようなもので、近頃は太陽より月のほうが眩しい。ずっと。
僕は幽霊と形にならないキスをした。
かといって別に世奈とは甘い雰囲気を漂わせているわけではない。そもそも触れようとしても触れられないのだから、生きている者と死んでいる者以上の距離で近付こうともしない。僕のやることといえば結局は墓参り、それ以上でも以下でもなかった。供え物を置いてさっさと帰る平日もあれば、夜が終わるまで語り明かす週末もあった。話題は世奈の生前のバイト先の愚痴や、ふたりの共通の好きなゲームと世奈がプレイすることの叶わないその続編、お気に入りの線香の匂いといったありふれたものだ。世奈はド下手なのにゲームが、線香は甘ったるいムスクの香りが好きらしい。僕は少しずつ世奈を知っていくけれど、彼女は、死因や享年といった肝心なものについては相変わらず教えてくれない。聞くと「お前がいつか死んだら教えてやるよ」と鼻で笑う。「今じゃ駄目?」とでも言えば「裏の線路で死んでくれば」と返される。そしてキスは出会いの夜以来、一度もなかった。
幽霊だからか、彼女との夜は刺激的で楽しい。成仏という決められたゴールに最短距離で向かうのが惜しく感じられるほどに。僕は墓地で酒を飲み続け、明け方まで墓にいたこともある。その日はほとんど眠らずに仕事へ向かい、僕は職場の竹内さんに軽く怒られ、心配もされた。「最近、なんだか上の空じゃない? 大丈夫?」と。
僕は大丈夫だ。
僕はいつも僕自身にそう思う。だけどそれは合っているようで少し違う。本当は問題なら、ある。幽霊の成仏の方法がわからない、という点だ。
幽霊のふと零した「寂しい」の言葉に突き動かされ、成仏の手助けを決心したあの夜。つい最近も、手がかりを掴むために僕は直球で世奈に尋ねた。「生きてる間にやり残したこととか、思い出せない?」と。なのに「ありすぎて逆にない」と言われ、取りつく島もない。助けてあげたいという願いは紛れもない本心である一方、方法のわからない「成仏」という言葉が、僕の日常の宙に浮かんでいる。今も、真依の髪に指を通しながら。幽霊を寂しくさせないって、どういうことだろう。
「私、結婚するの」
真依は目と唇を小さく開き、夢を見るような声で言った。その声は僕をふたたび現実に引き戻した。
「うん。さっき聞いたよ」
「ふふ。拓ちゃん。私ね。もうすぐ夫になるあの人のこと、大好きなの」
「よかったじゃん。幸せになってよ」
「だけど……」
「何?」
言葉の途切れた真依を見下ろすと、髪の中で真依はバツが悪そうに笑っていた。
「なんか、殺しちゃいたいなって思うときもあるの」
「え?」
僕の背筋に冷たいものが一瞬、走る。「殺したい」それに似た言葉をかけられ、僕は幽霊にキスをされたことがある。真依は真顔の僕を宥めるように笑うと、微かに表情を曇らせた。
「浮気してるの。彼」
「そうなんだ」
「うん。ついこないだ、知らない女の人とハートまみれのメッセージしてるの、偶然見ちゃった。前にもあったんだけどね。私のじゃない髪の毛が助手席に落ちてたり、そういう古臭くてありきたりな浮気の証拠品が」
「……真依はそれで、いいの?」
「何が?」
「結婚前からそんな女関係ぐだぐだな相手と結婚するの」
真依はあっけらかんと言った。
「別に平気。悲しくなかったわけじゃないけど……。彼が隠そうとしてくれることを無理やりほじくり出すなんて、私には勇気が出ないし。めんどくさいもん」
彼、お金持ちでかっこいいんだよね。背も高いし、今までずっと優しかったし? 人当たりも良くて、うちの親も彼のこと大好きなの。真依は自分に言い聞かせるように彼の魅力を羅列する。言い終えると安心したのか口元は緩んでいる。僕はぼんやりと聞きながら思う。たとえば浮気癖。ただのひとつの欠点、あるいは、すべての良さを帳消しにする致命傷。ふたつの違いは一体何なんだろう。ひとつ言えるのは、僕には真依の結婚に口を挟む余地はなさそうだった。ただ、場の雰囲気に流されて彼女を抱く僕には。
「拓ちゃんとこうやって会ったりして、あの人に間接的にお仕置きしてるのかも。それでイーブン。すっきりする」
「そっか」
「ふふ。わかってるよ。馬鹿みたいでしょ?」
「そんなことないよ。真依が納得してるならそれで正しいよ」
「ありがとう。だから拓ちゃんのことが好き。ねぇ、拓ちゃんもうんと幸せになってね」
幸せ。真依が言うその言葉は正しく魔法をかけるための言葉のように思える。だけど、実際に僕が僕に「幸せになろう」と言い聞かせるとき、その言葉は鉄の鎖のように重く巻き付く何かに変わる。だから言葉はそのまま返したい。「真依が幸せになってよ」と。僕は心の重さから自由でいられればそれで十分だ。そのために、必要以上に、身体以上の手段で誰かと関わりたくなかった。
「真依はちゃんと幸せになれる?」
僕はそう言おうとし、思いとどまっては言葉を飲み込み、シーツの上に身体を置いた。そして「やっぱり眠いから、私も寝るね」と目を閉じる彼女を背後から抱き締めた。真依は可愛い。それできっと、正しい。そう思いながら、一旦死んだように昼前まで眠った。何の夢も見なかった。
**
翌日、陽が沈むや否や、僕はどこか待ちきれない想いで、いつもの墓地へと足を運んだ。無性に世奈に会いたくなっていた。墓地で不貞腐れる幽霊に「死ね」とでも言われれば、僕の今の気持ちがどんな名前のものだろうが、清々しく手放せるような気もした。それを望んでいた。だけど、世奈は「谷口家之墓」の上にはいなかった。代わりに見覚えのない新しい花が墓には供えてあり、僕は自分以外の誰かの存在を初めて思った。僕は墓前にしばらく立ち尽くした後、一旦は諦めて家に帰った。霊感のない夜もあるだろう。あるいは幽霊にも暇じゃない夜があるのだろう、と。翌々日の夜も諦めきれずに訪れたが、世奈はやはりいなかった。なぜかわずかに胸が痛み、僕はその理由を無視した。
幽霊の彼女とふたたび会えたのは、結局、3日目だった。22:07。細く柔らかな雨が降る夜。世奈は墓の上で微動だにせず頬杖をついていた。安堵にも苛立ちにも似た気持ちを抱きながら、僕は広げたネイビーの傘の中で「暇?」と言った。聞こえているのかいないのか、世奈は僕を無視した。ようやく発せられた言葉は「……邪魔」だったけど、僕はその言葉にほっとして溶けそうになった。恋にも夢にも似た霊感がまだ僕の手元にあることに。
「ごめん。はい。今日のお供え」
僕は傘の中でしゃがみ、懲りずに花を供えた。先に差されていた花の側に無理やり詰め込むように、淡い色の花々を差した。いつか世奈が成仏できますように。僕は手を合わせながら変わり映えのない内容を祈り、そんな祈りはさっさと終え、目を開けて語りかける。
「そういえばさ」
「……」
「たまに墓いないけど、どこ行ってんの? 幽霊は」
「……」
「昨日、墓にいなかったじゃん」
「出かけてただけ。だけど、別にどこでもいいでしょ」
「そっか。誰かに呪いでもかけに行ったん? 気になるから教えてよ」
「生きてる人には関係ない」
傘で区切られた視界の隅に、透ける世奈の両足が見える。その白い影の中を絶えず雨が通り過ぎている。墓は泣き続けているように濡れている。冬の雨の中、墓参りをするのは初めてで、夏よりもずっと静かなんじゃないかと僕は思った。やがて世奈は諦めたように呟いた。
「暇すぎたから、生きてたときの場所、いろいろ行ってただけ」
「へー。どこ?」
家。世奈はガムを吐き出すように言った。自分の仏壇、見に行ったの。あと、あんまり仲良くなかったけど、母親のことも一応。私、母親と2人で暮らしてたから。
「お母さん、元気だった? それとも元気じゃない方が良かった?」
僕の質問を無視し、世奈は続けた。
「うちの母親、メンヘラなんだよねー」
てかメンヘラっていうより男依存なんだよ。あの人、私が生きてるときから、私より男の人のほうが好きだった。家には全然知らない人がいたの。ベタベタしてたから母親の新しい彼氏だってすぐにわかった。信じらんないけど、娘の仏壇と壁一枚隔てた部屋で盛ってて本当に吐きそうだった。だけどすごく元気に生きてるって思った。
「そっか」
淡々と語られる世奈の言葉を、僕は真依のときと同じようにただ受け止める。
「渡辺」
「え、何」
世奈は墓の上から僕を見下しては突き放して、言った。
「あんたって悩みなさそうでいいね?」
「はは。ありがとう」
だけどまぁ、御愁傷さまっていうことで。僕は世奈と真依、そして僕自身、目の前で眠る、もう死んでしまったすべての人々に対して言い放った。生きていようが、死んでいようが、人には人の事情があるのだ。自分にさえ他人事を貫くのが上手く生きるコツのように思え、僕はなるべく僕自身ですら薄めて生きていきたいと願っている。僕は立ち上がり、辺りを眺め回した。僕の好きな静かなパワースポット。墓。その真ん中で、お構いなしといった様子で冬の雨に打たれている世奈。彼女に傘を傾けながら、僕は言った。
「暇だし、今からどっか行かない?」
「は? なんで」
「ここにいても埒が開かないから」
それは墓参りを超えた初めてのデートの誘いだった。言った後で僕は中学生のように胸が高鳴っていることに気がついた。気がついた後でわずかに頬が熱くなるのを感じた。セックスを約束させるようなキスよりも、まだ手すら繋いだことのない誰かとのデートはかえって緊張する。それでも、したい。きっと世奈はついてくるだろう、僕にはそんな勝算もあった。そして実際、踵を返した僕の肩に、白い影はついてきた。「お前と出かけても別に楽しくないんだけど」という悪口付きで。
「僕は、世奈と墓以外のところに行けたらうれしいよ」
「そう」
どんなに世奈が不機嫌だろうが、僕は楽しかった。墓地から出た途端、濡れた硬いアスファルトが雲の絨毯にも感じられた。目的地なんてどこでもいい。せっかくの霊感だ。今、傘を差しながら肩に幽霊を浮かべて街を歩くのは、僕くらいしかいないだろう。しかも、取り憑かれているようで取り憑かせている。こんな形のデートが存在するだなんて、この街の誰もが思いもしないだろう。そんな優越感があった。狂気でもよかった。
「濡れるよ。ちゃんと傘、入りなよ」
「濡れないよ。死んでるんだから」
世奈はおとなしく僕の差す傘の中に入り、その中で漂っていた。たまにふらふらとどこかへ飛んで行き、それでも僕の肩の辺りに戻ってきた。
僕たちはふたりで、人ひとりぶんの足音を立てて雨の夜を歩いた。途中、雨にもかかわらずランニングをする夫婦、犬の散歩をする中年の男、びしょ濡れの女子高生を乗せた自転車、酔っ払った大学生の集団とすれ違った。当然、その誰もが世奈に気が付かなかった。ひとりで喋り続ける男だと思われないように、僕は声を顰めて歩き、世奈と時々目を合わせた。なんだか仲良く小さな犯罪を犯している気分だった。視線を交わす何回目かで、世奈は初めて笑ってくれた。完全に僕を馬鹿にしたような笑顔だったが、それでもよかった。
明るい街灯の光に近づくと幽霊の姿はますます薄くなり、離れるとふたたび姿を取り戻す。世奈は幽霊でも律儀に信号を守る。僕もそれに従う。たまに何かに勘づいた犬が世奈に吠える。「うるせークソ犬くたばれ」と悪態をつく幽霊のそばで僕は「元気なワンちゃんですね」と飼い主に挨拶をする。コートのポケットでスマホが震える。「来週末、遊びに行ってもいい?」と真依からLINEが届いている。「いいよ」と僕は返事をする。世奈は耳元で「死ねば」と囁く。現実と非現実の間で頭がおかしくなりそうだ。だけどそんな散歩が楽しい。
やがて僕たちは寝静まった住宅街を通り抜け、駅前に辿り着いた。すっかり忘れていたが、今は金曜日の夜。立ち並ぶ飲食店の前でいくつもの傘が楽しげに広がっていた。傘からはみ出し、濡れながら酔っ払っている人もいた。僕は道の端で立ち尽くし、隣を見上げた。世奈の身体は今、大衆居酒屋の柔らかいオレンジ色の光を通して透けている。
「は? きっしょ、勝手に通んなよ」
世奈は図らずも自分の身体を貫通していった人の後ろ姿を睨んでいた。「なんか、今一瞬すげー寒かった!」その男は幽霊の存在など考えもしないような声で笑い、適当な店へ仲間と入っていった。どこもかしこも笑い声が溢れ返っている。飲んだくれる人々は漏れなくとても楽しそうだと僕は思った。世奈が生きていれば、ふたりでその輪に加わる未来もあったのかもしれない。
「この辺、懐かしい?」
僕はキャッチの男をかわした後で世奈に聞いた。
「別に。……ねぇ。私、高校出てから、あそこでバイトしてた。コンカフェ」
世奈の指差す先には雑居ビルが、ピンク色の文字の浮かぶ看板があった。僕たちは少しの間、その場に立ち止まったまま店を眺めていた。すると、店内から中年の男が「本当はまだ帰りたくないよー。リナちゃん!」とか言いながら、千鳥足で転がるように出てきた。「私あいつ知ってる」駅に向かって男が徐々に遠ざかる様子を、世奈は冷えた目で見送っていた。
「懐かしい。あいつ、店の常連なんだけどさ。本当、金やばいんじゃねってペースで店通ってた。結婚しようとか、金がないなら俺の金で大学に行かせてやるとか、なんか色々言ってたなー」
「へぇ。良い客じゃん」
「まぁ、金払いはね」
私、だいぶ推されてた。世奈は懐かしそうにぼやく。
「でもさ、私がいなきゃいないで、さっさと他の子に切り替えていくんだよねー。まぁ知ってたけど。それでいいけど」
「あのおっさんは世奈が死んだの、知ってんのかな」
「知らないんじゃない?」
「ハッピーな奴だね」
「そうだよ。いいんだよそれで。自分で好きになった人とかものに縛られちゃったら、なんか全然意味ないじゃん。愛ってさ、重めに見せかけて軽めなやつがいいんだよ。ちょうどいい重さってあるから」
「あー。そうかも」
僕はどこかの飲み屋に入ろうか少し悩んだが、世奈が死んでいることを思い出し、やめた。生きていたら一回くらいは、世奈と飲みたかったかもしれない。そう思いながらあてもなく辺りを歩き続けた。途中、コンビニで酒を買い、傘の中で僕は飲み始めた。僕たちの足は自然と駅前から離れ、人の数は次第に減っていった。歩いているうちに、そびえる小さな山に辿り着いた。そこには安産祈願で名の知れた、僕たちにあまり関係のない神社がある。黙ったまま仲良く、境内へと向かう長い階段を登った。結局、墓を抜け出そうが僕たちは静かな場所へ向かうのだと思うとおかしい。階段を登り切る頃、僕だけが疲れ、息切れを起こしていた。世奈はマイペースに隣で涼しげに浮かんでいるだけだった。
「幽霊の身体は楽そうでいいね」
「何。やっと死にたくなった?」
「ならねーよ」
僕は日頃の運動不足を感じながら、境内の中にある東屋へ入った。休憩がてら雨宿りがしたかった。ベンチに腰掛け、アルコールを帯びた白い息を吐き出す。東屋からは夜の街が一望できた。街の寝ている部分と起きている部分が、光の量で一目瞭然だった。視界の遠くを横切るように走り抜ける8両編成の電車。そろそろ終電の時間が近づいているはずだ。ベンチの向かい側から気怠く街を見ている世奈は今、どんな気持ちでいるのだろう。成仏できず自分の終わりさえ見えない彼女は。
「世奈。なんとなく来たけどさ、夜の神社って結構良いよね」
「神社って正月以外、用事なくない? おみくじと初詣以外何すんの」
「ご祈祷とかいろいろ。あとはこういうデートとかじゃない? 雰囲気あるじゃん。神社って」
「……」
「あ、幽霊って神社で体調悪くなる? 平気?」
「……平気。ねぇ。教会にいる悪魔みたいな扱いしないでくれる」
「ごめん。世奈、今、何考えてんの?」
「別に何も」
「そっか」
しばらくの間、僕は幽霊を墓から連れ出した非現実的な気分に浸った。陳腐な言葉だが、ありふれた光景がいつもと違って見えた。この街も人も生きているのだと、皮肉にも幽霊の姿が僕に伝えてくれている。人間の営みが愛しいとか、今、特別に幸せだとか、僕はそんなことは思わない。そもそも僕は別に世間に愛着を持っていない。だけど、この世界はかつて世奈が存在した世界で、時に世間体に疲れたりもしながら、一生、世界そのものは憎めないのかもしれない。世間よりも世界、世界よりも世奈が今の僕には身近だ。世の後についてくる一文字次第で僕は振り回されている。頭の中で「世」という漢字がゲシュタルト崩壊を起こし、隣にいる幽霊を僕は眺める。僕の頭をおかしくさせているのか、ぎりぎりの理性にとどめているのかわからない夜風を、幽霊で濾された夜風を、余すことなく僕は浴びる。今夜は線香じゃなく湿った樹々や葉の匂いがする。雨はいつの間にか止んでいる。冬。僕は寒さに何度目かの身震いをする。
「なんでお前、生きてんの?」
気がつくと世奈は僕のすぐ隣にいた。「知らない。何。哲学? それとも死ねってこと?」僕が聞き返すと世奈は黙った。そして数秒後、頭を僕に傾け、もたれかかってきた。おそらく、彼女なりに僕の肩に頭を乗せたのだとわかった。思いがけない甘い展開だった。僕も同様に頭を世奈に傾けようとし、襲いかかるかもしれない金縛りを思い出し、思わず眉を顰めた。なんせ相手は幽霊だ。近づくとまた痛い目に遭うかもしれない。だけど、僕の身体はいつものままで、幽霊を身体に絡み付かせながら人体の平常を保ったままでいられた。このとき、幽霊の冷気だけははっきりと感じられた。僕は一体、何を克服してしまったのだろう?
「世奈といると寒い」
「ふーん。なんでだろうね」
冬だから。そして、幽霊だからだ。僕と世奈は恋人のように身を委ねあっていた。お互いの重みを少しも感じられないまま。触れ合う実感は今夜もない。せめてもの思いで、僕は幽霊の存在を感じることに集中した。かつて世奈に存在したはずの体温をイメージした。すると世奈に触れたくなり、空いた腕で小さな頭を撫でようとした。だけど手のひらは冷たい空気を掴んだ。どうしようもなく溜め息が白い。何にも邪魔されず、いくらでも暖め合えるはずの冬という季節を持て余しているのだった。
「腕邪魔なんだけど」
そう言う幽霊を僕は薄目で見つめる。
「世奈は、誰かと抱き締め合うのがあったかいって、今も覚えてる?」
「うん」
「……そっか」
すべてがどうでも良くなった僕は諦めて目を閉じる。確実に触れられる、という意味で真依が少し恋しい。だけど生きている真依も死んでいる世奈も、どちらも等しく僕を満たさない。そして僕が僕である以上僕ですら僕を満たすことも出来ない。僕と世奈は、触れ合う以外ならきっと何だって出来る。それが自由なのか不自由なのかも、今はわからない。
「まじ、幸せって何なんだろうね」
ふとつぶやいた僕に、世奈は身体を離しながら言った。
「めんどくさいこと聞かないでくれる?」
「死んでる観点から教えてよ」
しつこく聞くと、世奈は薄笑いを浮かべた。
「知らない。私はそういうの全部、墓の下に半分埋めてきちゃったから」
気付くと世奈は東屋から離れ、僕に背を向けたまま宙に浮かんでいた。世奈の視線の先には光る街が広がっていた。
「だけど私は、死んで良かった。そう思いたいの」
「どうして? 本心?」
「全部、私が選んだから。私がそうしたかったから、死んだ」
その一言に、僕は踏み込むことをすべて諦めた。彼女はおそらく自分で死んだのだ。理由や手段はどうであっても。覆すことのないその事実がすべてだった。
「僕は生きてて良かったよ」
さらに言うと、世奈が生きていてくれたらもっと良かった。僕は言葉を飲み込み、握った拳に力を込める。今この瞬間、世奈の死を悔いてしまうことでさえ怖かった。出会ったときから幽霊で、死んでしまっていた世奈。後悔や無念さという、取り返しのつかない領域に踏み込む勇気なんて僕にはなかった。傷付くことへの警告がいつも僕に考えることを止めさせる。僕はアルミ缶に唇を押し当てた。買ったすべての酒を次々と喉に流し込み、心地よい眠気が全身を包む頃に尋ねた。
「このまま、朝までここにいる?」
半端に開いた唇はとても冷えていた。
「帰る。別にいる意味もないから」
気乗りしない世奈に「わかった」と言いながらも、僕は名残惜しかった。幽霊を連れ出した。そんな唯一の夜を終わらせることが。だから、立ちあがろうとせずに背中をベンチに預けたままでいた。彼女の苛立つ気配がすぐに伝わってきた。
「ねぇ、渡辺。帰ろう。……帰れ」
「少しだけ待ってよ」
「だってこれ以上いたら、私」
「何」
世奈は言葉を切っていた。いつの間にか目の前に移動した幽霊を僕は至近距離で見上げた。空洞の目。完全な人型ではあるけれどどこか曖昧な輪郭と白いシルエット。初めて出会い、キスをしたあの夜と何も変わらない姿をしていた。幽霊は、相手が世奈というだけでもはや怖くない。それどころか僕は、僕を襲う冷気の中に生前の世奈を見つけたような気がした。初めてのことだった。幽霊の姿に肌や爪や指や髪を想像の中から貼り付けていくのは。世奈は僕に取り憑く幽霊である以前に、抱き寄せられるはずのひとりの女の子だった。普通の可愛い女の子だった。想像の中で出来上がった彼女を、僕は抱き寄せ、キスをし、やっぱり抱きたいと思う。そしてその願望は叶うことのない望みの刃物だ。
──相手はもう死んでるのに、馬鹿かよ。
僕は奥歯を噛み締める。世奈は吸い寄せられるように僕に近づく。何を企んでいるのだろう。どうせ生きていても主体性なく漂っているだけの僕だ。今夜こそ殺されても構わない。僕は挑むように世奈と見つめ合う。世奈の顔はキスの距離にあった。しばらくの間、世奈は夜風と冷気を、僕は漏れ出す息をそれぞれ送った。
「……なんでもない」
沈黙の中で先に目を逸らしたのは、彼女だった。
「てか気分悪い」
「わかった。もう帰ろう。世奈」
なんだか馬鹿馬鹿しいなと思いながら立ち上がった。僕たちは神社を後にし、長い石段を降り、真夜中の街をふたたび歩き始めた。世奈は僕より高い位置で浮かんでいるのが常だった。だけどこのとき、世奈の頭は僕の肩の辺りにあった。僕たちは繋げるはずもない手を繋ぎ、指を絡め、歩調を完全に合わせあった。世奈の墓場へと一緒に帰るために。これ以上、ふたりが近づくことはないと知るために。
「お前のこと、絶対に好きになりたくない」
「うん」
「だから私は死んでてよかった」
ここへ来たときよりも確実に縮まった距離で世奈はつぶやいた。幽霊の彼女は朝が来れば消える。何かのピースを埋めれば永遠に消える。僕の目的は彼女の成仏。現世にとどまる幽霊を葬る優しいはずのその行為が、僕は初めて寂しいと思った。だから思わず言ってしまったのだった。南無阿弥陀仏とは真逆の言葉を。
「僕は、世奈が好きだよ」