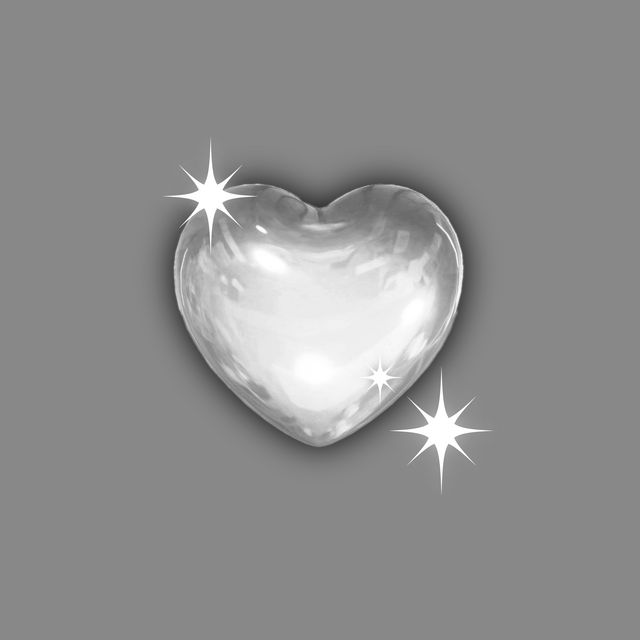2. 霊感なんて
文字数 5,510文字
「そうだ。幽霊って信じますか?」
ある日、僕の投げかけた問いに、鈴木さんは「いないんじゃない?」とあくびを噛み殺しながら答え、加藤さんは「俺も信じないねー」と投げやりに言った。加藤さんは「昔、廃トンネル巡りにハマってたときも余裕で何もなかったよ」と続けて笑い、近くを偶然通りかかった竹内さんが「え。私は見たことあるけど」と大真面目に口を挟んだ。すぐさま、その場の全員が目を丸くした。職場での話だ。僕はある日の休憩中、数人の親しい同僚や上司と、砕けたやり取りを珍しく楽しんでいた。そのとき、ふと訪れた会話と会話との空白に、思わず零してしまったのだ。そうだ、幽霊って信じますか、と。
竹内さんは胸の奥底から記憶を掬い出すように数回頷き、続けてくれた。子どもの頃ね、お祭りの帰り道に空に浮かぶ光を見つけたことがあるの。あれは絶対に火の玉だった。全然怖くなかったしすぐに消えちゃったけど。えー、UFOじゃないの? いや絶対火の玉。お墓の近くだったし、本で見たのと同じ形だったから。でもそれっきり。
「いないでしょ、幽霊は」
「どうだろうね。結局、子どものただの見間違いなのかなぁ」
目の前の人たちが楽しそうに盛り上がる様子を、僕は他人事のようにぼんやりと眺めていた。幽霊は良くて不確かな想い出程度であり、現在進行形でどこかにいる可能性を誰にも信じられていないようだった。夜が想像できないほど明るいオフィスの昼光色の下では当然なのかもしれない。ここでは現実以外に何も似合わない。幽霊のいない現実しか。
お茶をひと口飲み、竹内さんは口を開いた。
「渡辺くんは信じるの? 幽霊」
「僕は──」
慌てて口角を上げ直しながら、まずは心の中だけで返事をする。僕はどっちかって言うと信じてますねー。だって僕、先週末、幽霊と話してキスしたんですよ。殺すとか、そういう物騒な言葉付きですけど。そこまで言葉にしたところで、現実的、まともな人間からは外れているであろうファンタジックな発言を「ちょっと待て」「絶対に言うな」と理性がとどめる。幽霊と話したりキスなんて。他の誰でもない僕が僕自身を馬鹿にしている。ありえない。痛い妄想が過ぎる、と。だけど、本当に? いる。いない。僕は疑惑のメーターの針を左右に忙しなく動かしては心が子供のように落ち着かない。
目線を手元に落とし、アイスコーヒーの黒く静かな水面を見つめた。口からは小さな溜め息が零れた。他にも脳の労力を割くべきことがいくつもあるのに、こんなことを考え続けている自分がくだらなく感じられた。
「……僕も信じてないっすねー。幽霊とかそういうのは。いないんじゃないですか」
「そっかぁ。渡辺くんもか」
「はい」
結局、適当にはぐらかして賛同を得ると、実際にそうだとしか思えなかった。幽霊なんて、どこにもいないのだろう、と。僕はありふれた確かなものが好きだった。たとえば買えば当たったかもしれない宝くじより、部屋の片隅に落ちていた百円。浴びたのかもしれない幽霊のキスより、新しい事務の女の子と偶然触れ合った指先の熱。といった具合に。
「確かに、渡辺くんは霊とか全然信じてなさそう。でも、急にどうしたの? ホラー映画でも観た?」
「いや……」
楽しめる答えをまだ引き出し足りない、といった竹内さんに僕は苦笑いをする。
「実はこないだ初めて金縛りにあっちゃって。キツいっすね」
あながち嘘ではない証言を彼女は「大丈夫?」と心配してくれた。
「金縛りかぁ……。あれ寝不足になるよね」
竹内さんは口の中だけで小さく言葉を発している。幽霊ね。そして、間髪入れず切り替えた仕事の顔で知的に笑った。
「やっぱり私もそういうのは信じない。だけど、優秀な人材なら幽霊でも雇いたいのよ」
「まじすか」
「うん」
じゃあ、私14時から面接だから。お疲れ。そう言い残し、人事部の竹内さんは去って行った。鈴木さんも席を外した。加藤さんはいつの間にかスマホを耳に当て、取引先からかかってきたのであろう電話に意識が向いている。おしゃべりの輪は一旦、完全に分解され、僕を含めそれぞれが自分の仕事に戻っていった。普段通りの、何てことない一コマだった。
あの日、結局、僕は殺されなかった。
世奈と名乗る幽霊に出会った後、どのように家に帰ったのかは覚えていない。気付けば辺りは早朝で、ベンチに倒れ込むように僕は眠っていた。「お兄さん、ちょっと」身体を揺さぶられる衝撃で僕は目を覚ました。目の前にいたのは幽霊ではなく、人の良さそうな中年の警察だった。
「こんなとこで寝てたら風邪引くよ。下手したら死んじゃうからね。ダメだよー」
警察は軽い調子でそう言った。慌てて僕は辺りを見回したが、女の子の幽霊なんてどこにもいなかった。僕は貴重品の無事を確かめ、事務的な職務質問の後で解放され、ようやく辿り着いた家で大量に水を飲み、熱いシャワーを浴び、泥のようにもう一度眠った。目が覚めるとひどく頭が痛んだ。何も考えたくなかった。だが、警察の「死んじゃうからね」という言葉が、いつまでも嫌にこびりついていた。死ななかったからだ。
僕は普段通り、週末を引きこもって過ごした。出歩こうとは思ったものの、あの墓地に少しも近づく気にはなれなかった。夜に大して怖くなかったものが翌日の昼に怖くなってしまうなんて、僕の反応は少し遅かった。布団にくるまってスマホを眺め、各種SNSに高速スクロールをし、身体に埋め込まれたシステムのようにいいねのハートを連続で付けた。それに飽きるとオンラインゲームでひたすらに人を殺した。それにも飽きると部屋の掃除をした。観葉植物に水をやった。忙しさにかまけてここ最近は水やりをサボっていたが、相変わらず生命力溢れんばかりのパキラに日々癒されている。緑の葉にはきちんとした艶があった。半径何mかのリアルの世界で息をする、僕以外の唯一の生きた何か。生きている、そんな親しみを込めて葉脈を撫でた。
日曜の夕方には、アパートに1人の女の子がやって来た。学生時代に2年程付き合っていた元カノの真依だった。互いに就職してから完全に疎遠になり、SNS経由で再会し、リアルでも遊ぶようになってからこれで数度目だった。再会が一回限りで終わらなかった理由は何だっていいし、僕は真依の「久しぶり」や「会おうよ」に心地良く流され、幽霊に遭遇する数週間前には、付き合っていたとき振りのセックスをなし崩し的にしたところだった。
「拓ちゃん、どうしたの?」
「何が?」
「なんか今日、顔色良くないよ」
「んー」
会うなり真面目に心配してくれる真依をそっと抱き寄せ、僕はキスをした。一度は別れたけど真依は相変わらず優しくて可愛くて、そして唇が薄い。本人も「コンプレックスなんだよね」と昔から気にしている。だが、真依の唇にはきちんと実体がある。誰かと重ねたい僕の身体という実体を、薄い皮膚の境界から受け入れてくれる。そういう本物のキスが出来る。もちろん重ね合わせることで痺れたり、金縛りにあったりもしない。
「え、いきなりどうしたの?」慌てるふりをする真依を、僕は安心してその場に押し倒した。真依は温かった。僕だってそうだろう。なぜなら僕たちは、生きている。出会ったのかもしれない、いるのかもわからないあの女の子は、死んでいる。そんなことを思いながら僕は真依の肌にキスを繰り返し、身体は少しずつ興奮し、真依は両腕をそっと絡めてそれに応えた。気持ち良かった。
結局、次に墓地を通りかかったのは週明けの朝だった。学生、老人、社会人。僕は一日を始めるさまざまな人たちの波に乗るようにして、歩いて駅へと向かっていた。月曜日だという理由で、心を少し落ち込ませながら。その道の途中には公園と、あの日の墓地がある。降り注ぐ朝日を輝きで跳ね返す黒い墓石が並んでいる。僕は思わず横目で墓石を確認した。だけど、幽霊はいなかった。あの子。寝てるのか、消えていなくなったのかどっちだろう。太陽の下で元気いっぱいの幽霊のイメージは僕にはない。幽霊は夜と結びついているはずだから、今の時間にいないのは当然だと僕は判断した。だけど夜が来たからといって、世奈という幽霊にもう一度会える保証もどこにもなかった。そもそも会いたいのかどうかもわからない。そんなことを僕は思いながら通り過ぎようとした。
「おはようございます」
墓地の前の道路を、若い僧侶が竹箒で掃除していた。落ち葉を集めながら微笑む彼に僕は曖昧な笑顔を返し、足を止め、小さく頭を下げた。おたく、女の子ひとり成仏させられてないですよ。もしかして。胸の内でそう呟いた。そしてふたたび、人々がどこかへ向かうゆるやかな流れに乗った。一旦離れてしまうと、この場所を気にする理由がそもそもないような気がした。この道を通りさえしなければ、もう彼女と会うことはないのだろう。あったような気がする霊感なんて、初めからないも同然だろう。考えなければ振り回されなくて済む。見なければ思い出さずに済む。こうして、臆病にマイペースな僕の通勤は別のルートへ変わってしまった。
──やっぱり、ないよな。幽霊とキスとか。
主に職場で、日々、僕はそんなことばかり考えていた。たとえばオフィスチェアに腰を沈ませ、軋む音と同時に伸びをするときや、つまらない会議の内容が頭に入って来ないとき。午後の仕事を再開させるべく、PCのデスクトップを見つめても一切、集中出来ない。以前よりやる気が起きない。幽霊に襲われた週明けからずっとそうだった。飲み慣れたブラックコーヒーを喉、というより胃に流し込みながら思い浮かべるものは、作りかけのパワーポイントのデータなんかじゃない。編集不可能なあの日の夜のことだった。キスを迫る幽霊の白とオリオン座の明滅が重なる、初めての官能的な冬の光景。風に似た「さよなら」の囁き。さらには、他人によって苦痛なく死に向かわされる恍惚。すべては甘い罠のような、誘惑にも似た金縛りの中にあった。時間にして5分足らずの出来事だろう。それは生涯にわたって忘れることのない5分だろう。あのとき自分の命は一瞬、あまりにも軽かった。その軽さが心地良かった。あのまま死んでも別に良かったのかもしれない。そんな好奇心は今もなお消えない。不謹慎だから誰にも言えない。
霊感のれの字もない単調な平日が過ぎていった。初めから何もなかったかのように、職場と家を往復する元の日々に戻っただけだった。大して不満はないはずだった。なのに、なぜだろう。ふたたび訪れた金曜日の夜。僕はまた、吸い寄せられるようにしてあの墓地へと向かってしまったのだ。それも、もしもまた会えたなら──今度は酒の酔いで見た幻覚ではないと確かめるために、完全なる素面で。一度覚えた甘い金縛りは身体に染みついてしまったのかもしれない。僕はきっと待ちわびていたのだろう。起伏の少ない心がどこかの誰かに掻き乱されたり、つまらない日常が背後から犯されたりするのを。それも身体の痛みには至らない程度に優しく甘く。無意識にそうされたくて、見えない尻尾を誰かに振っていたのかもしれない。ずっと。
墓地の数百m以上手前から、僕の心臓は高鳴っていた。あの女の子。最後に世奈と名乗った幽霊。もしもふたたび会えたら、今度こそ殺されるのだろうか。そもそも会えるのだろうか。僕は何を期待しているのだろう。殺されること、それとも殺されかけることで生まれる楽しみだろうか。答えなどないまま、あの晩と同じく、吐き出される息だけが白かった。冬は以前よりも確実に世界を冷やしていた。明日の最低気温は2℃だと、天気予報で見たのを思い出していた。
歩む速度を落としながら、頼りない街灯の下を恐る恐る足を進める。現在時刻は午後22時30分過ぎ。野良猫が視界を横切った、たったそれだけのことで息を呑んでは思わず足を止める。そしてまた歩き出す。自分の鼓動が他人のものに感じられるほど、大きな音を立てていた。歩いていると、景色は勝手に墓へ差し掛かった。僕は足を止め、冷たい空気を吸う。意を決し、顔の向きを墓場へと向け、おそるおそる全体へ視線を彷徨わせる。だけどそこには誰もいない。
──やっぱり、夢だったのか。
夜の墓地は、静まり返ったただの墓地だった。人ひとりいないという当然の事実がそこにはあった。じわじわと時間をかけて身体の内側に広がる落胆を感じながら、僕はすぐに納得した。ありえないことはありえないんだ、と。もう二度と、僕の内側から霊感など呼び覚まされないような気がした。それで良いんだと、幻を幻で済ませられた自分に清々しい気持ちもなくはなかった。ふと視線を投げかけると、あのとき売り切れていた自販機のココアは補充されていた。別に良かった。ココアでも買って、適当に温まりながら帰れれば。
視線を下に落としながら足早に通り過ぎようとした。世奈とかいう霊の墓の位置がいちばん端だったのを思い出し、落ち着きそうな場所だと思った。なぜなら僕は学生の頃、席替えで窓際のいちばん後ろの席になると嬉しかった。思わず鼻で笑う。コミュ障には数十年後、墓場暮らしでさえ辛いのかもしれない。墓と墓の間はせいぜい50cmくらいしか空いていない、僕が考えていたのはそんなあるかもわからない死後のパーソナルスペースのことだった。
すると、聞き覚えのある声がすぐ側から聞こえた。
「なんで殺せなかったんだろう。お前のこと」
僕は足を止めた。勢い良く顔を上げ、横を向いた。目の前にいたのは白く浮かび上がるあの日の幽霊──世奈だった。
ある日、僕の投げかけた問いに、鈴木さんは「いないんじゃない?」とあくびを噛み殺しながら答え、加藤さんは「俺も信じないねー」と投げやりに言った。加藤さんは「昔、廃トンネル巡りにハマってたときも余裕で何もなかったよ」と続けて笑い、近くを偶然通りかかった竹内さんが「え。私は見たことあるけど」と大真面目に口を挟んだ。すぐさま、その場の全員が目を丸くした。職場での話だ。僕はある日の休憩中、数人の親しい同僚や上司と、砕けたやり取りを珍しく楽しんでいた。そのとき、ふと訪れた会話と会話との空白に、思わず零してしまったのだ。そうだ、幽霊って信じますか、と。
竹内さんは胸の奥底から記憶を掬い出すように数回頷き、続けてくれた。子どもの頃ね、お祭りの帰り道に空に浮かぶ光を見つけたことがあるの。あれは絶対に火の玉だった。全然怖くなかったしすぐに消えちゃったけど。えー、UFOじゃないの? いや絶対火の玉。お墓の近くだったし、本で見たのと同じ形だったから。でもそれっきり。
「いないでしょ、幽霊は」
「どうだろうね。結局、子どものただの見間違いなのかなぁ」
目の前の人たちが楽しそうに盛り上がる様子を、僕は他人事のようにぼんやりと眺めていた。幽霊は良くて不確かな想い出程度であり、現在進行形でどこかにいる可能性を誰にも信じられていないようだった。夜が想像できないほど明るいオフィスの昼光色の下では当然なのかもしれない。ここでは現実以外に何も似合わない。幽霊のいない現実しか。
お茶をひと口飲み、竹内さんは口を開いた。
「渡辺くんは信じるの? 幽霊」
「僕は──」
慌てて口角を上げ直しながら、まずは心の中だけで返事をする。僕はどっちかって言うと信じてますねー。だって僕、先週末、幽霊と話してキスしたんですよ。殺すとか、そういう物騒な言葉付きですけど。そこまで言葉にしたところで、現実的、まともな人間からは外れているであろうファンタジックな発言を「ちょっと待て」「絶対に言うな」と理性がとどめる。幽霊と話したりキスなんて。他の誰でもない僕が僕自身を馬鹿にしている。ありえない。痛い妄想が過ぎる、と。だけど、本当に? いる。いない。僕は疑惑のメーターの針を左右に忙しなく動かしては心が子供のように落ち着かない。
目線を手元に落とし、アイスコーヒーの黒く静かな水面を見つめた。口からは小さな溜め息が零れた。他にも脳の労力を割くべきことがいくつもあるのに、こんなことを考え続けている自分がくだらなく感じられた。
「……僕も信じてないっすねー。幽霊とかそういうのは。いないんじゃないですか」
「そっかぁ。渡辺くんもか」
「はい」
結局、適当にはぐらかして賛同を得ると、実際にそうだとしか思えなかった。幽霊なんて、どこにもいないのだろう、と。僕はありふれた確かなものが好きだった。たとえば買えば当たったかもしれない宝くじより、部屋の片隅に落ちていた百円。浴びたのかもしれない幽霊のキスより、新しい事務の女の子と偶然触れ合った指先の熱。といった具合に。
「確かに、渡辺くんは霊とか全然信じてなさそう。でも、急にどうしたの? ホラー映画でも観た?」
「いや……」
楽しめる答えをまだ引き出し足りない、といった竹内さんに僕は苦笑いをする。
「実はこないだ初めて金縛りにあっちゃって。キツいっすね」
あながち嘘ではない証言を彼女は「大丈夫?」と心配してくれた。
「金縛りかぁ……。あれ寝不足になるよね」
竹内さんは口の中だけで小さく言葉を発している。幽霊ね。そして、間髪入れず切り替えた仕事の顔で知的に笑った。
「やっぱり私もそういうのは信じない。だけど、優秀な人材なら幽霊でも雇いたいのよ」
「まじすか」
「うん」
じゃあ、私14時から面接だから。お疲れ。そう言い残し、人事部の竹内さんは去って行った。鈴木さんも席を外した。加藤さんはいつの間にかスマホを耳に当て、取引先からかかってきたのであろう電話に意識が向いている。おしゃべりの輪は一旦、完全に分解され、僕を含めそれぞれが自分の仕事に戻っていった。普段通りの、何てことない一コマだった。
あの日、結局、僕は殺されなかった。
世奈と名乗る幽霊に出会った後、どのように家に帰ったのかは覚えていない。気付けば辺りは早朝で、ベンチに倒れ込むように僕は眠っていた。「お兄さん、ちょっと」身体を揺さぶられる衝撃で僕は目を覚ました。目の前にいたのは幽霊ではなく、人の良さそうな中年の警察だった。
「こんなとこで寝てたら風邪引くよ。下手したら死んじゃうからね。ダメだよー」
警察は軽い調子でそう言った。慌てて僕は辺りを見回したが、女の子の幽霊なんてどこにもいなかった。僕は貴重品の無事を確かめ、事務的な職務質問の後で解放され、ようやく辿り着いた家で大量に水を飲み、熱いシャワーを浴び、泥のようにもう一度眠った。目が覚めるとひどく頭が痛んだ。何も考えたくなかった。だが、警察の「死んじゃうからね」という言葉が、いつまでも嫌にこびりついていた。死ななかったからだ。
僕は普段通り、週末を引きこもって過ごした。出歩こうとは思ったものの、あの墓地に少しも近づく気にはなれなかった。夜に大して怖くなかったものが翌日の昼に怖くなってしまうなんて、僕の反応は少し遅かった。布団にくるまってスマホを眺め、各種SNSに高速スクロールをし、身体に埋め込まれたシステムのようにいいねのハートを連続で付けた。それに飽きるとオンラインゲームでひたすらに人を殺した。それにも飽きると部屋の掃除をした。観葉植物に水をやった。忙しさにかまけてここ最近は水やりをサボっていたが、相変わらず生命力溢れんばかりのパキラに日々癒されている。緑の葉にはきちんとした艶があった。半径何mかのリアルの世界で息をする、僕以外の唯一の生きた何か。生きている、そんな親しみを込めて葉脈を撫でた。
日曜の夕方には、アパートに1人の女の子がやって来た。学生時代に2年程付き合っていた元カノの真依だった。互いに就職してから完全に疎遠になり、SNS経由で再会し、リアルでも遊ぶようになってからこれで数度目だった。再会が一回限りで終わらなかった理由は何だっていいし、僕は真依の「久しぶり」や「会おうよ」に心地良く流され、幽霊に遭遇する数週間前には、付き合っていたとき振りのセックスをなし崩し的にしたところだった。
「拓ちゃん、どうしたの?」
「何が?」
「なんか今日、顔色良くないよ」
「んー」
会うなり真面目に心配してくれる真依をそっと抱き寄せ、僕はキスをした。一度は別れたけど真依は相変わらず優しくて可愛くて、そして唇が薄い。本人も「コンプレックスなんだよね」と昔から気にしている。だが、真依の唇にはきちんと実体がある。誰かと重ねたい僕の身体という実体を、薄い皮膚の境界から受け入れてくれる。そういう本物のキスが出来る。もちろん重ね合わせることで痺れたり、金縛りにあったりもしない。
「え、いきなりどうしたの?」慌てるふりをする真依を、僕は安心してその場に押し倒した。真依は温かった。僕だってそうだろう。なぜなら僕たちは、生きている。出会ったのかもしれない、いるのかもわからないあの女の子は、死んでいる。そんなことを思いながら僕は真依の肌にキスを繰り返し、身体は少しずつ興奮し、真依は両腕をそっと絡めてそれに応えた。気持ち良かった。
結局、次に墓地を通りかかったのは週明けの朝だった。学生、老人、社会人。僕は一日を始めるさまざまな人たちの波に乗るようにして、歩いて駅へと向かっていた。月曜日だという理由で、心を少し落ち込ませながら。その道の途中には公園と、あの日の墓地がある。降り注ぐ朝日を輝きで跳ね返す黒い墓石が並んでいる。僕は思わず横目で墓石を確認した。だけど、幽霊はいなかった。あの子。寝てるのか、消えていなくなったのかどっちだろう。太陽の下で元気いっぱいの幽霊のイメージは僕にはない。幽霊は夜と結びついているはずだから、今の時間にいないのは当然だと僕は判断した。だけど夜が来たからといって、世奈という幽霊にもう一度会える保証もどこにもなかった。そもそも会いたいのかどうかもわからない。そんなことを僕は思いながら通り過ぎようとした。
「おはようございます」
墓地の前の道路を、若い僧侶が竹箒で掃除していた。落ち葉を集めながら微笑む彼に僕は曖昧な笑顔を返し、足を止め、小さく頭を下げた。おたく、女の子ひとり成仏させられてないですよ。もしかして。胸の内でそう呟いた。そしてふたたび、人々がどこかへ向かうゆるやかな流れに乗った。一旦離れてしまうと、この場所を気にする理由がそもそもないような気がした。この道を通りさえしなければ、もう彼女と会うことはないのだろう。あったような気がする霊感なんて、初めからないも同然だろう。考えなければ振り回されなくて済む。見なければ思い出さずに済む。こうして、臆病にマイペースな僕の通勤は別のルートへ変わってしまった。
──やっぱり、ないよな。幽霊とキスとか。
主に職場で、日々、僕はそんなことばかり考えていた。たとえばオフィスチェアに腰を沈ませ、軋む音と同時に伸びをするときや、つまらない会議の内容が頭に入って来ないとき。午後の仕事を再開させるべく、PCのデスクトップを見つめても一切、集中出来ない。以前よりやる気が起きない。幽霊に襲われた週明けからずっとそうだった。飲み慣れたブラックコーヒーを喉、というより胃に流し込みながら思い浮かべるものは、作りかけのパワーポイントのデータなんかじゃない。編集不可能なあの日の夜のことだった。キスを迫る幽霊の白とオリオン座の明滅が重なる、初めての官能的な冬の光景。風に似た「さよなら」の囁き。さらには、他人によって苦痛なく死に向かわされる恍惚。すべては甘い罠のような、誘惑にも似た金縛りの中にあった。時間にして5分足らずの出来事だろう。それは生涯にわたって忘れることのない5分だろう。あのとき自分の命は一瞬、あまりにも軽かった。その軽さが心地良かった。あのまま死んでも別に良かったのかもしれない。そんな好奇心は今もなお消えない。不謹慎だから誰にも言えない。
霊感のれの字もない単調な平日が過ぎていった。初めから何もなかったかのように、職場と家を往復する元の日々に戻っただけだった。大して不満はないはずだった。なのに、なぜだろう。ふたたび訪れた金曜日の夜。僕はまた、吸い寄せられるようにしてあの墓地へと向かってしまったのだ。それも、もしもまた会えたなら──今度は酒の酔いで見た幻覚ではないと確かめるために、完全なる素面で。一度覚えた甘い金縛りは身体に染みついてしまったのかもしれない。僕はきっと待ちわびていたのだろう。起伏の少ない心がどこかの誰かに掻き乱されたり、つまらない日常が背後から犯されたりするのを。それも身体の痛みには至らない程度に優しく甘く。無意識にそうされたくて、見えない尻尾を誰かに振っていたのかもしれない。ずっと。
墓地の数百m以上手前から、僕の心臓は高鳴っていた。あの女の子。最後に世奈と名乗った幽霊。もしもふたたび会えたら、今度こそ殺されるのだろうか。そもそも会えるのだろうか。僕は何を期待しているのだろう。殺されること、それとも殺されかけることで生まれる楽しみだろうか。答えなどないまま、あの晩と同じく、吐き出される息だけが白かった。冬は以前よりも確実に世界を冷やしていた。明日の最低気温は2℃だと、天気予報で見たのを思い出していた。
歩む速度を落としながら、頼りない街灯の下を恐る恐る足を進める。現在時刻は午後22時30分過ぎ。野良猫が視界を横切った、たったそれだけのことで息を呑んでは思わず足を止める。そしてまた歩き出す。自分の鼓動が他人のものに感じられるほど、大きな音を立てていた。歩いていると、景色は勝手に墓へ差し掛かった。僕は足を止め、冷たい空気を吸う。意を決し、顔の向きを墓場へと向け、おそるおそる全体へ視線を彷徨わせる。だけどそこには誰もいない。
──やっぱり、夢だったのか。
夜の墓地は、静まり返ったただの墓地だった。人ひとりいないという当然の事実がそこにはあった。じわじわと時間をかけて身体の内側に広がる落胆を感じながら、僕はすぐに納得した。ありえないことはありえないんだ、と。もう二度と、僕の内側から霊感など呼び覚まされないような気がした。それで良いんだと、幻を幻で済ませられた自分に清々しい気持ちもなくはなかった。ふと視線を投げかけると、あのとき売り切れていた自販機のココアは補充されていた。別に良かった。ココアでも買って、適当に温まりながら帰れれば。
視線を下に落としながら足早に通り過ぎようとした。世奈とかいう霊の墓の位置がいちばん端だったのを思い出し、落ち着きそうな場所だと思った。なぜなら僕は学生の頃、席替えで窓際のいちばん後ろの席になると嬉しかった。思わず鼻で笑う。コミュ障には数十年後、墓場暮らしでさえ辛いのかもしれない。墓と墓の間はせいぜい50cmくらいしか空いていない、僕が考えていたのはそんなあるかもわからない死後のパーソナルスペースのことだった。
すると、聞き覚えのある声がすぐ側から聞こえた。
「なんで殺せなかったんだろう。お前のこと」
僕は足を止めた。勢い良く顔を上げ、横を向いた。目の前にいたのは白く浮かび上がるあの日の幽霊──世奈だった。