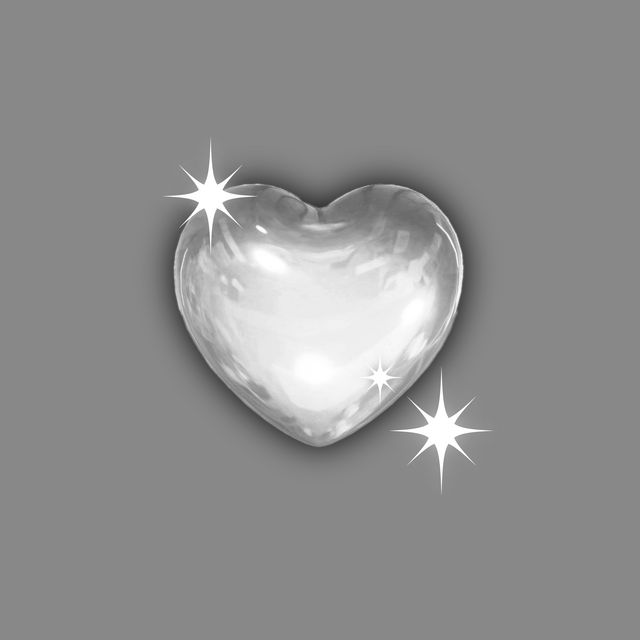3.正しい成仏
文字数 9,234文字
「……お前、何か言えば」
出会いのときと同様、フェンス越しに僕を睨み、墓石に座る真冬の幽霊。何か言えと言われても、言葉は何も思い浮かばなかった。目を合わせるのに必死だった。
「聞こえてるんでしょ?」
今日も透けている幽霊は、死んでいるうえにさらに死ぬほどめんどくさそうな態度でそう吐き捨てた。僕はもう一度出会えた喜び、いないと納得した後で現れた幽霊への困惑、衝撃、少しの恐怖、それらすべての入り混じった感情に足がすくんでいた。代わりに出てきたのはごく普通の言葉だった。
「元気?」
それから「あのさー、久しぶりだよね」となるべく明るく続けた。高校時代の友達に会うような感じを装って。死にそぐわない言葉だったのだろう。案の定、世奈は眉を顰めた。「は? 私死んでるんだけど」と告げる声は、はっきりとした怒気を孕んでいた。僕はお構いなしに墓地の中へと足を進めた。
「そうだ。確か世奈ちゃん、だよね。とりあえず、これあげる」
僕は自分が右手に持つビニール袋に何が入っているのか、唐突に思い出していた。安い花束だった。ここに来る途中、24時間営業のスーパーの花のコーナーで買った。値引きシールの付けられた惣菜のついでではあるけど、一応、たったひとりを想い、買った。新聞紙とガーリーなセロファンに包まれたごく小さな花束は、仏花ではなく、かすみ草と、名前のわからない淡いピンクの花が組み合わさったものだ。これから墓場に行くと決めていたのに、そっちのほうが良いと思った。菊や榊といったあらかじめ決められたものよりも。どうしてだろう。
「もらってよ」
僕は直接手渡そうとし、世奈は意外にも素直に受け取ろうとした。だけど透ける手は花束をすり抜け、僕は思わず唾を飲み込む。幽霊。
「私、死んでるから。ちゃんともらえない。てか触れない。だから、いらない」
「そうなんだ」
僕はめげずに空っぽの二つの花立てにそれを挿した。
「ここに置いとくね。どうせ何もないから良いじゃん?」
近くの蛇口で僕は花立てに水道水を注いだ。せっかくだから、誰かの杓子を借りて墓石にも水をかけてあげようと思ったが、墓石は今、世奈の座る大事な場所だから、止めた。代わりに僕は、花と花の間に小さな焼き菓子をふたつ並べた。職場の誰かに配られたお土産だった。食べ忘れてリュックの中に放置するよりずっと良いと思い、僕はそうした。一つひとつの行動を起こす間、呪い殺すかのような世奈の視線を感じた。僕がしていたのは、死んだ本人を目の前にした墓参りだった。本物の「恨めしい」を浴びながらの墓参りは、子どもの頃に初めて祖父の骨を拾ったのよりも遥かに緊張する行為だった。墓参りは、そこに幽霊がいるときに不思議なライブ感を持つのだと、今夜知った。
花と焼き菓子のおかげで、殺風景で可哀想だった墓が少しだけ華やいだような気がし、僕はひとりで勝手に気分が良い。でも、生前の世奈が甘いものが好きだったのかは知らない。そういえば彼女はさっきからずっと無言だ。
「ねぇ。生きてるとき、こういうの好きだった? 甘党? 辛党?」
「甘いものは太るから好きじゃない。」
「じゃあ辛党なんだ」
「てか食べるのにあんま興味なかった。お前うるさい。なんか生意気じゃない?」
「ごめん」
僕は笑った。死んでも大人しくなれない幽霊こそ生意気だと思う。だけど確かに、墓参りは残された者の自己満足かもしれない。「向こうで元気にやってる?」だとかそういう答えのない問いを投げかけ、返事のなさに癒されるための行為なのかもしれない。生意気だと世奈に言われ初めて手を合わせる。どうか、いつの日か彼女が天国とか極楽とか、僕の知らない温かい場所に行けますように。だけど今夜はまだここにいてください。なぜなら、この霊と話せることがとてもうれしく、楽しい。僕は本当にいつも僕のことばかり考えている。僕は目を開け、呟いた。「……あ」そういえば肝心の線香、買い忘れた。
「今度来るときはお線香、立てるから」
そう言うと世奈は「別にいらないよ。私には効かないから」と意味不明なことを言った。効くって何だよ? 訝しむように見上げると、僕の頭の上の方で、世奈は足を伸ばし座っている。透けるつま先が目の前で揺れている。隣の公園で遊具が夜風に軋んだ音を立てている。
「そうだ。この前、言ってたよね。どうして僕を殺したいの?」
僕は意を決し尋ねた。初めて出会ったあの夜から、いつまでも耳の底で繰り返される「お前を殺す」とかいう物騒な囁き。刃物のような言葉の鋭さとそれに矛盾する甘いキス。何もかもまだ上手く信じられず、だから好奇心にとどまっている。突然僕を襲った、人生最初で最後かもしれない霊感として。
欠けた月の方向を向いていた世奈だったが、やがてつま先を揺らすのを止め、僕を見た。
「どうしてだろうね」
どうでも良いよねという投げやりな音にもそれは聞こえた。
「本当に、手っ取り早く首でも絞めてみれば良かったよね。なのに、キスすればお前と一緒に死ねると思った。なんでだろう」
「何だよそれ。聞かれても困る」
「私だって困ってるよ。だって成仏したいじゃん。なんでさ、死んでるのにまだ死にたくならなきゃいけないわけ」
出会って二回目とは思えないほど気まずい沈黙が流れた。僕は返事に困っていた。何を言おうが、死んだ経験のない僕に説得力はないと思えたからだ。そして、黙っている間にも幽霊が消えてしまわないか念のため見張っていた。別に消えようが止められるわけがないし、この幽霊本人はどうやら消えるのを望んでいるのにもかかわらず。砂像のようにサイドから崩れ消失する幽霊をイメージし、見てみたいと僕は思った。
「あのさ……」世奈は急に諦めたように口を開いたから、僕は背筋を思わず伸ばす。
「私、確か5ヶ月くらい前に死んだんだよね」
「なんで死んだん?」
「さぁ」
「享年、っていくつだったの?」
「お前に話す必要なくない?」
「ごめん」
5ヶ月前。墓に彫られた「谷口家」の文字に視線を落としながら、5ヶ月前の僕は何をしていたのだろうと、過ぎ去った時に想いを巡らせる。三連休を使って旅行に行った。友達に誘われて乗ったヨットの上で酒を飲み、スナメリを見た後で海へ吐いた。吐瀉物と涙を浮かべて揺れる濃緑の海面を覚えている。それからクラゲの死骸。友達の明るい声。夏。毎日、もう少し金貯めなきゃなと思ったり、仕事辞めたいなと思ったり、かと思えば意識を突然高めては資格の勉強をしてみたり、どうでも良くなって投げ出したりもした。つまり、今と大して変化のない日々を送っていた。そのときどこかで死んでいたらしい、少女に近い年齢の女の子。たとえばブルーライトに日々流れるネットニュース、数々のショッキングな記事のどこかに世奈はいたのだろうか。
──知るわけ、ないよな。
僕は墓石の前に座り込んだ。初めから僕の人生に世奈が無関係であるのを思い出し、あらためてすべてを諦める。勝手に湧いた余計な感傷を捨てようとする。彼女はとっくに死んでいて、してあげられることなんて何もなかったんだ、と。今のところ、彼女の生に間に合わなかったという気持ちは寂しさとは結びつかず、ただの事実としてその辺りに転がっている。まるで墓地に敷かれた石みたいに。石の冷たさは腿の裏や尻の辺りに伝わり、僕は自分の座る場所を実感した。ここは墓場だ。すぐ真下には骨壷があり、中には世奈本人の骨の欠片が詰められているはずだ。そう思うと複雑な高揚感に鳥肌が立った。僕は今、幽霊を見ている。一生、会えないはずの人と会っている。その刺激。
世奈は何も言わず、捨てたばかりのゴミをゴミ箱の上から覗くような冷ややかな視線で僕を見下ろしていたが、僕はめげなかった。
「それで、世奈は死んで、それでどうなったの?」
「……。私これ死んだかもって思って、次に気付いたら夜でさー。なんか、ここに今と同じ格好で座ってたんだよね」
世奈は墓の上で、腕を伸ばし、自分の手のひらを月明かりに照らしながら言った。最初は──今もだけど、なんでここにいるのか意味不明だったの。別に墓なんて用事ないし。とりあえず家に帰ろうかなって思って、私、叫んだんだよね。だって身体透けてるんだもん。まじで大声で叫んだよ。だけど全っ然、誰も私に気づかなかった。すぐに私、思い出したの。そういえば私、死んだんだって。
「まじか……」
「うん」
「正直、死ぬほど焦ったよね。まぁ死んでるけど」
「……それでどうしたの?」
「別にどうもしないよ。後はずっとおとなしく死んでるだけー」
世奈は投げやりに言い放った。座る体勢を変え、伸ばした脚を隣の墓石に置いている。
「死んでも最初は良かったんだよ」
最初はね。限定された言葉の後で世奈は続けた。死んだもんはしょうがないじゃん? とりあえず幽霊やってみようかなって思ったんだよね。軽く飛んだら飛べたから、そこの電線でカラスと一緒に座ってた。そしたら、生きてるときに付き合ってた彼氏が私の友達と手繋いで目の前歩いてったんだよね。ウケる。もうヤったんだろうな。あいつら、幽霊に見られてるとか、全然、気付いてなかったけどね。
「でも、飛べるのは楽しそう」と僕は思わず言い、世奈は不機嫌につま先をゆらゆらと揺らしている。
「お前も死んで成仏出来なかったらやってみれば? てか今すぐその辺で死んでくれば?」
「ごめん。無理」
「……。まぁ確かに、初めは割と楽しかったかも。だから撮らなきゃって」
「何を?」
「自分に決まってるじゃん」
だけど、多分スマホなんて処分されたんだよね。ていうか私がちゃんと処分されたんだよね。そもそも骨とか肉がなかったらスマホになんて触れられないから。
「意味、わかる?」と世奈は言い放ち、僕は頷く。
「お疲れ」
「毎日最悪。ねぇ。どうしようもなくない?」
「そうかも……」
恨み言のような世奈のカミングアウトは続き、僕は生ぬるく同調しては先を促すくらいしかやることがなかった。「なんでみんなちゃんと死ねるんだろ?」という疑問に「なんでだろうね」と、「毎日つまんない」といった愚痴に「そっか。死んでるのも割とだるいんだね」といった具合に。今はまだ怨霊未満なら、僕は世奈に優しくしてあげたかった。彼女が透けているだけのただの女の子だったからだ。昔から僕は聞き上手だとよく言われる。主体性がないだけだけど。
世奈は「お前、カウンセラー気取りかよ」とせせら笑ったかと思うと、憤った。
「なんか久しぶりに会話したら、話すの止められないんだけど。最悪」
「別に良いよ。続けなよ」
「……。なんかさ、本当に飽きてるんだよね。死んでることに」
世奈は他人からさらに他人へと、川の中の飛石を移るようにいくつもの墓の上を歩いている。かと思えば「あーあ」というふて腐れた声でどこかの誰かの墓石に回し蹴りをしようとし、脚は見事に物体をすり抜ける。そんな風に闇に浮かんでいる。地面に足をつけられずに。
「忘れちゃったかも。生きてる身体がどんな感じだったか」
「別に、思い出すほどのものでもないかもよ」
僕はそう言いながらも同情せざるを得なかった。しばらくの間は、生前に抱いた幽霊のイメージそのままに動く身体を、テーマパークのアトラクション感覚で楽しむことが出来たらしい世奈。誰にも降ろしてもらえないアトラクションはもはやアトラクションではないのだと、僕は目の前の幽霊の身体を通して知らされていた。一生生きているのは一生死んでいるのとほぼ同義なのかもしれない。それでも好奇心は残酷で、僕が「死んでるってどんな気分なの?」と聞いた理由に別に深い意味はなかった。
「毎日腹とか、減る?」
「全然」
「感覚ってどう? 痛いとか、寒いとか」
「何もない。だけど……」
「うん」
「死んでから太陽、見てないんだよね」
世奈は墓2列ぶん離れた場所から月を睨んでいた。女の子の幽霊、月、墓。その三点の織りなす光景は、遠い過去に見た、実際にあるのかもわからない一枚の絵画のように僕の目に映った。
「なんで見てないの? 太陽」
「知らない。なんかさ、私、朝になると勝手に寝てるっぽい。昼間の意識がいっこもない」
「へー。幽霊って寝るんだ。普通に眠いの?」
「眠くない……。怠くても、それは生きててもそうだし」
「まぁ、そうだね」
「毎日毎日、気付いたら夜でここにいるんだよね」
とりあえず飽きたらこんな感じ。世奈はそう言うと自分の墓の上で小さく両膝を抱えた。頭を膝の上に乗せ、顔だけをこちらに向けていた。その姿はとても頼りなく、ストレートに哀れだと思った。空を見て風を浴びる以外何もない夜の長さを、スマホ1台で他人と繋がる僕には想像出来ない。夜は孤独で大きな檻で、もしかすると幽霊の身体は、魂は、何かに服役しているようなものなのかもしれない。
──誰にも気付いてもらえないなんて。
それは何かの罪なのだろうか。だけど僕だけは、突然の霊感でひとりぼっちの女の子に気が付いてあげられた。そう思うと、優越感がないと言えば嘘になる。その優越感が、今夜も僕をこの墓地にとどめていた。彼女を知りたい。それだけでまだ、全然帰る気になんてなれなかった。
「ちょっと待ってて」
僕はふと自分の喉の渇きと空腹に気が付き、立ち上がった。飲み物を買いに、道路を挟んだ向かい側にある自販機まで歩く。振り返ると世奈は墓石から姿を消していた。どこに行ったんだろう。と思うと同時に、いつの間にか世奈は僕の肩の辺りに浮かんでいて、思わず小さく叫んだ。
「こえーよ」
「ビビってんじゃねーよ」
意外なことに、世奈は僕のすぐ隣を不機嫌に漂ったまま離れずにいた。自販機で僕は温かいココアを選び、スマホで決済を済ませながら話しかける。
「今日、寒いね」
「別に私は寒くない」
「ここ、すごく静かだね」
「……当たり前でしょ。墓なんだから」
「うん。そうだ。誰かが死んでも世界は変わらないって言うよね。それって死んでる本人的にはどうなん?」
「……別に良いよ。私が死んで変わっちゃう世界なんてめちゃくちゃしょうもなさすぎるし」
「はは。まじか」
僕は取り繕いながらも内心、同意する。僕も僕が死んでどうにかなってしまう世界は恐ろしいし、自分は、世間に対してせいぜい血の通った消耗品程度であればいい。そんなことを考えながらココアを一口飲んだ。普段ブラックコーヒーばかり飲むせいだろう。こんな甘ったるい飲み物、久しぶりに飲んだなと思った。その瞬間「それクソ甘いよね。余計喉乾くやつ」と世奈に一刀両断された。僕が考えていたのとまったく同じことだった。どこか打ち解けた雰囲気を感じ、僕はうれしくなった。
「まぁ、そのうち成仏出来るよ」
そろそろ家に帰れよ、という軽いノリで僕は言う。そして、それが無理であるという前提に引き戻され、どうしたら良いのかを考え、思いついてはコートのポケットの中からスマホを出した。
「そうだ。人、呼んできてあげるよ」
「は? 誰」
「お祓い系の人。徳の高い坊さんとかでいい? もう一回ちゃんとお経読んでもらおうよ」
僕はスマホの画面に迷いなく指を滑らせ、チャットAI相手に「成仏の方法は?」と問いかける。人の生死にさえAIが入り込んだスマホは、この辺りでもっとも明るい光を放つ異質な物体にも思えた。少しの間を置き、次々と羅列される文字列を僕は心の中で読み上げる。①仏壇や神社でお祈りをする。②祓いを行う。③説得する。
「そういうの余計なお世話。いらないからー」
スマホを覗き込んだ後で世奈は低いテンションで言った。
「なんで? 成仏したいんでしょ。坊さんが嫌なら霊能者の手かざしとか、誰かの話とか、聞いてみたらいいじゃん」
「出来る気がしないんだもん。てか私、自分の読経もだるくてまともに聞けなかったんだよね……。だから成仏しなかったんだろうけど。国語苦手だし」
「生まれる前の赤ちゃんだって水子供養であの世行けるじゃん。国語関係ないって」
知らない。世奈はそう吐き捨てた。僕たちは暗黙の了解で、ふたたび墓地へ戻った。大人しく自分の墓石に座る世奈に僕は「おかえり」と声をかけ睨まれた。しばらくの沈黙の後で、彼女は呟いた。成仏とかよくわかんなくない?
「……なんかさ、知らない人の言葉なんかじゃ無理。もっとちゃんとしたのが欲しい」
「えー。金とか?」
銀行アプリに表示させた直近の預金残高を思い浮かべ、僕は一瞬、苦い気持ちになる。
「違う。……私が欲しいのは、多分もっと具体的な何かだから」
「何それ」
「少し前、ここに太った幽霊のおっさんがいたんだけど」
真剣に不機嫌な世奈は、二つ隣の墓石を指差していた。表面には「中田家之墓」と彫られ、足元には缶ビールとまだ新しい仏花が供えられている。世奈が言うようにおっさんの幽霊がいたとは思えないほど、静かでまっとうな墓らしい墓だった。
「中田とかいう人だったんだけど、おっさん、前科者でさ。生きてる間はずっと電車で痴漢やめられなかったんだって。で、何回目かでついに逮捕されて、家族にも捨てられて、それで出所したところ癌になってあっさり死んだ」
「……うん」
「誰にも墓参りに来てもらえなくて、寂しい寂しいってまじでうるさかったんだよね」
おっさんが寂しかったの、自業自得だと思う? 何かを試すように尋ねる世奈に僕は「人には人の事情があるよ」と当たり障りなく返事をする。
「それでその人、どうなったん?」
「急に、ひとりだけ……娘が会いに来たんだよ。それだけでおっさん、もう『俺には思い残すことない』とか言って消えてった」
「そうなんだ……」
「なんかすっきりして成仏したんだろうねー。良かったよねー」
他人事のように世奈は頬杖をついている。僕は立ち尽くしたまま、中田とかいうその人物の墓を二度見した。予想だにしないヒューマンドラマが付け加えられた後も墓は墓で、ただ静まり返っていた。すべての死には物語があると訴えかけるような静寂にも感じられた。もしかしたら今も僕の周りには幽霊がいるのかもしれない。だけど、僕に見えるのはたったひとり、世奈だけだ。
「多分、私は寂しいのかも」
小さな世奈の呟きで僕は我に返った。悪態ばかりついている幽霊から引き出された、素直で意外な言葉だった。
「じゃあ、寂しくなくなったら消えられそう?」
僕が尋ねると世奈は小さく頷いた。そして、今まででいちばん素直な態度で黙りこくっていた。困惑したまま、世奈と僕はふたたび見つめ合うこととなった。目の前で、世奈の身体を一匹の蛾が通り抜けていった。蛾はふらつきながらも上を目指して飛んでいった。本能的に。街灯という、辺りでもっともまばゆい光へと向かうために。道筋として蛾にさえ利用された幽霊の身体そのものが、僕にとってはとても寂しく、美しくも見えた。
「……そういえばお前、名前なんだっけ」
「僕は、拓人だよ。渡辺、拓人」
「へー。渡辺。普通だね」
しばらくの間、さらに沈黙が流れた。どこか身に覚えのある沈黙は、自ずとあるワンシーンを僕に思い出させた。人生の中でもトップクラスに強烈な印象を残したあの夜。迫り来る幽霊の白い影と、甘い囁き。身体を襲う金縛り。僕は、幽霊にキスをされたことがある。
「今日も殺そうとしてみても良いよ」
「……やるだけ無駄。気分じゃないし」
唇を真一文字に結ぶ今の世奈は、キスからは程遠い表情を浮かべていた。覚えたての手段で誰かを誘惑する女の子というよりは、欲しいものが目の前にあるのにわがままさえ上手く言えない子どものようだった。死んでも拗ねている。その姿を見て、僕は精いっぱいの優しい言葉をかけようとし、結果的に口説いてしまったのだった。
「成仏しようよ。僕がさせてあげるから」
「……どうやって?」
その瞬間、幽霊が初めて縋り付くような目をしたのを僕は見逃さなかった。もはや一切の疑う余地はなかった。幽霊は存在する。それも、救いを求めて彷徨える幽霊が。やり方もわからないのに、僕はなぜか不思議な使命感に燃え始めていた。神や仏のありがたい教えがひとつもない僕だから、俗な目線から救える魂もあるのではないか、と。そもそも僕たちはキスから始まった。「殺す」と囁かれた夜に、実際、僕の一部は殺されたのかもしれない。あのとき奪われた正体不明の何かは、たとえば、常識。倫理。幽霊がいないという一般論。
「そこにいて」
動かないで。僕は世奈へ手を伸ばし、寂しい幽霊の頭を撫でてみようとした。慰めるようでいて、単純に、もっとも心地良い方に自分の心と身体が引き寄せられる感覚を信じていた。呪いの目つきで世奈は僕を見ていたが、もはや怖くない。
「……いきなり近いんだけど」
「ごめん。でも、なんか遠くない?」
目の前に世奈はいるのに、僕は思わずそう言った。僕の手のひらは世奈の頭を通り抜けていた。近いのか、遠いのか。僕には幽霊と人間との、死と生の距離感なんてわからなかった。身体の輪郭はすぐそこにあるのに、あるのは痛いほど冷えた0℃付近の空気だけだった。世奈。ほとんど普通の女の子なのに透けている、不安定なシルエットを伝え続ける、質量でも形でもない第三の実体。一体何のためにいるのだろう。だけどそれは僕だって同じなのかもしれない。死んでいても生きていても、似た者同士なのかもしれない。僕は一旦、自分の手のひらを見つめた。不埒な胸の高鳴りに従い、世奈を抱き寄せようとした。すると僕の身体は突然、上手く動かなくなった。勝手に膝の力が抜け、その場に僕は崩れ落ちた。同時に音を立てて倒れる、今夜供え物を置いたばかりの花立て。スローに降り注ぐ花と水を僕は顔で受け止めた。身体は冷たく、痛く、そして動けない。
「……っ」
情けなく背を丸めた姿勢で、僕の身体は岩のようになっていた。僕を襲っているものの正体は金縛りだった。「いきなり、何?」という呆れた世奈の声を感じながら、これが幻聴なのか、そもそも今夜の出来事が現実なのか今になって疑う。他人に見られたらまずい、頭のおかしい行動をしている自覚は僕にはあった。だけど、妄想も現実も等しくひとつの脳内世界だと開き直ってもいた。少なくとも今は全身が痛いから夢ではなく、僕は、僕の感覚だけは信じられた。
ようやく口が動かせるようになった頃。仰向けの僕は掠れた声で尋ねた。
「……世奈。お前、悪霊?」
「わかんない。そうかも」
だって、今もお前のこと殺せたらいいなって思ってるよ。世奈はそう言いながら、あまりにも冷えた目で僕を見下ろしていた。幽霊に出会った二度目の夜。こうして僕はなんとなく、ひとりの女の子の成仏を目指し始めたのだった。透ける幽霊の身体の中には冬の夜空が広がっていた。僕の視界の隅、唯一の鮮やかな色彩と言ってもいい信号は、車も人も通らないのに、青、黄色、赤と色を変えていた。
出会いのときと同様、フェンス越しに僕を睨み、墓石に座る真冬の幽霊。何か言えと言われても、言葉は何も思い浮かばなかった。目を合わせるのに必死だった。
「聞こえてるんでしょ?」
今日も透けている幽霊は、死んでいるうえにさらに死ぬほどめんどくさそうな態度でそう吐き捨てた。僕はもう一度出会えた喜び、いないと納得した後で現れた幽霊への困惑、衝撃、少しの恐怖、それらすべての入り混じった感情に足がすくんでいた。代わりに出てきたのはごく普通の言葉だった。
「元気?」
それから「あのさー、久しぶりだよね」となるべく明るく続けた。高校時代の友達に会うような感じを装って。死にそぐわない言葉だったのだろう。案の定、世奈は眉を顰めた。「は? 私死んでるんだけど」と告げる声は、はっきりとした怒気を孕んでいた。僕はお構いなしに墓地の中へと足を進めた。
「そうだ。確か世奈ちゃん、だよね。とりあえず、これあげる」
僕は自分が右手に持つビニール袋に何が入っているのか、唐突に思い出していた。安い花束だった。ここに来る途中、24時間営業のスーパーの花のコーナーで買った。値引きシールの付けられた惣菜のついでではあるけど、一応、たったひとりを想い、買った。新聞紙とガーリーなセロファンに包まれたごく小さな花束は、仏花ではなく、かすみ草と、名前のわからない淡いピンクの花が組み合わさったものだ。これから墓場に行くと決めていたのに、そっちのほうが良いと思った。菊や榊といったあらかじめ決められたものよりも。どうしてだろう。
「もらってよ」
僕は直接手渡そうとし、世奈は意外にも素直に受け取ろうとした。だけど透ける手は花束をすり抜け、僕は思わず唾を飲み込む。幽霊。
「私、死んでるから。ちゃんともらえない。てか触れない。だから、いらない」
「そうなんだ」
僕はめげずに空っぽの二つの花立てにそれを挿した。
「ここに置いとくね。どうせ何もないから良いじゃん?」
近くの蛇口で僕は花立てに水道水を注いだ。せっかくだから、誰かの杓子を借りて墓石にも水をかけてあげようと思ったが、墓石は今、世奈の座る大事な場所だから、止めた。代わりに僕は、花と花の間に小さな焼き菓子をふたつ並べた。職場の誰かに配られたお土産だった。食べ忘れてリュックの中に放置するよりずっと良いと思い、僕はそうした。一つひとつの行動を起こす間、呪い殺すかのような世奈の視線を感じた。僕がしていたのは、死んだ本人を目の前にした墓参りだった。本物の「恨めしい」を浴びながらの墓参りは、子どもの頃に初めて祖父の骨を拾ったのよりも遥かに緊張する行為だった。墓参りは、そこに幽霊がいるときに不思議なライブ感を持つのだと、今夜知った。
花と焼き菓子のおかげで、殺風景で可哀想だった墓が少しだけ華やいだような気がし、僕はひとりで勝手に気分が良い。でも、生前の世奈が甘いものが好きだったのかは知らない。そういえば彼女はさっきからずっと無言だ。
「ねぇ。生きてるとき、こういうの好きだった? 甘党? 辛党?」
「甘いものは太るから好きじゃない。」
「じゃあ辛党なんだ」
「てか食べるのにあんま興味なかった。お前うるさい。なんか生意気じゃない?」
「ごめん」
僕は笑った。死んでも大人しくなれない幽霊こそ生意気だと思う。だけど確かに、墓参りは残された者の自己満足かもしれない。「向こうで元気にやってる?」だとかそういう答えのない問いを投げかけ、返事のなさに癒されるための行為なのかもしれない。生意気だと世奈に言われ初めて手を合わせる。どうか、いつの日か彼女が天国とか極楽とか、僕の知らない温かい場所に行けますように。だけど今夜はまだここにいてください。なぜなら、この霊と話せることがとてもうれしく、楽しい。僕は本当にいつも僕のことばかり考えている。僕は目を開け、呟いた。「……あ」そういえば肝心の線香、買い忘れた。
「今度来るときはお線香、立てるから」
そう言うと世奈は「別にいらないよ。私には効かないから」と意味不明なことを言った。効くって何だよ? 訝しむように見上げると、僕の頭の上の方で、世奈は足を伸ばし座っている。透けるつま先が目の前で揺れている。隣の公園で遊具が夜風に軋んだ音を立てている。
「そうだ。この前、言ってたよね。どうして僕を殺したいの?」
僕は意を決し尋ねた。初めて出会ったあの夜から、いつまでも耳の底で繰り返される「お前を殺す」とかいう物騒な囁き。刃物のような言葉の鋭さとそれに矛盾する甘いキス。何もかもまだ上手く信じられず、だから好奇心にとどまっている。突然僕を襲った、人生最初で最後かもしれない霊感として。
欠けた月の方向を向いていた世奈だったが、やがてつま先を揺らすのを止め、僕を見た。
「どうしてだろうね」
どうでも良いよねという投げやりな音にもそれは聞こえた。
「本当に、手っ取り早く首でも絞めてみれば良かったよね。なのに、キスすればお前と一緒に死ねると思った。なんでだろう」
「何だよそれ。聞かれても困る」
「私だって困ってるよ。だって成仏したいじゃん。なんでさ、死んでるのにまだ死にたくならなきゃいけないわけ」
出会って二回目とは思えないほど気まずい沈黙が流れた。僕は返事に困っていた。何を言おうが、死んだ経験のない僕に説得力はないと思えたからだ。そして、黙っている間にも幽霊が消えてしまわないか念のため見張っていた。別に消えようが止められるわけがないし、この幽霊本人はどうやら消えるのを望んでいるのにもかかわらず。砂像のようにサイドから崩れ消失する幽霊をイメージし、見てみたいと僕は思った。
「あのさ……」世奈は急に諦めたように口を開いたから、僕は背筋を思わず伸ばす。
「私、確か5ヶ月くらい前に死んだんだよね」
「なんで死んだん?」
「さぁ」
「享年、っていくつだったの?」
「お前に話す必要なくない?」
「ごめん」
5ヶ月前。墓に彫られた「谷口家」の文字に視線を落としながら、5ヶ月前の僕は何をしていたのだろうと、過ぎ去った時に想いを巡らせる。三連休を使って旅行に行った。友達に誘われて乗ったヨットの上で酒を飲み、スナメリを見た後で海へ吐いた。吐瀉物と涙を浮かべて揺れる濃緑の海面を覚えている。それからクラゲの死骸。友達の明るい声。夏。毎日、もう少し金貯めなきゃなと思ったり、仕事辞めたいなと思ったり、かと思えば意識を突然高めては資格の勉強をしてみたり、どうでも良くなって投げ出したりもした。つまり、今と大して変化のない日々を送っていた。そのときどこかで死んでいたらしい、少女に近い年齢の女の子。たとえばブルーライトに日々流れるネットニュース、数々のショッキングな記事のどこかに世奈はいたのだろうか。
──知るわけ、ないよな。
僕は墓石の前に座り込んだ。初めから僕の人生に世奈が無関係であるのを思い出し、あらためてすべてを諦める。勝手に湧いた余計な感傷を捨てようとする。彼女はとっくに死んでいて、してあげられることなんて何もなかったんだ、と。今のところ、彼女の生に間に合わなかったという気持ちは寂しさとは結びつかず、ただの事実としてその辺りに転がっている。まるで墓地に敷かれた石みたいに。石の冷たさは腿の裏や尻の辺りに伝わり、僕は自分の座る場所を実感した。ここは墓場だ。すぐ真下には骨壷があり、中には世奈本人の骨の欠片が詰められているはずだ。そう思うと複雑な高揚感に鳥肌が立った。僕は今、幽霊を見ている。一生、会えないはずの人と会っている。その刺激。
世奈は何も言わず、捨てたばかりのゴミをゴミ箱の上から覗くような冷ややかな視線で僕を見下ろしていたが、僕はめげなかった。
「それで、世奈は死んで、それでどうなったの?」
「……。私これ死んだかもって思って、次に気付いたら夜でさー。なんか、ここに今と同じ格好で座ってたんだよね」
世奈は墓の上で、腕を伸ばし、自分の手のひらを月明かりに照らしながら言った。最初は──今もだけど、なんでここにいるのか意味不明だったの。別に墓なんて用事ないし。とりあえず家に帰ろうかなって思って、私、叫んだんだよね。だって身体透けてるんだもん。まじで大声で叫んだよ。だけど全っ然、誰も私に気づかなかった。すぐに私、思い出したの。そういえば私、死んだんだって。
「まじか……」
「うん」
「正直、死ぬほど焦ったよね。まぁ死んでるけど」
「……それでどうしたの?」
「別にどうもしないよ。後はずっとおとなしく死んでるだけー」
世奈は投げやりに言い放った。座る体勢を変え、伸ばした脚を隣の墓石に置いている。
「死んでも最初は良かったんだよ」
最初はね。限定された言葉の後で世奈は続けた。死んだもんはしょうがないじゃん? とりあえず幽霊やってみようかなって思ったんだよね。軽く飛んだら飛べたから、そこの電線でカラスと一緒に座ってた。そしたら、生きてるときに付き合ってた彼氏が私の友達と手繋いで目の前歩いてったんだよね。ウケる。もうヤったんだろうな。あいつら、幽霊に見られてるとか、全然、気付いてなかったけどね。
「でも、飛べるのは楽しそう」と僕は思わず言い、世奈は不機嫌につま先をゆらゆらと揺らしている。
「お前も死んで成仏出来なかったらやってみれば? てか今すぐその辺で死んでくれば?」
「ごめん。無理」
「……。まぁ確かに、初めは割と楽しかったかも。だから撮らなきゃって」
「何を?」
「自分に決まってるじゃん」
だけど、多分スマホなんて処分されたんだよね。ていうか私がちゃんと処分されたんだよね。そもそも骨とか肉がなかったらスマホになんて触れられないから。
「意味、わかる?」と世奈は言い放ち、僕は頷く。
「お疲れ」
「毎日最悪。ねぇ。どうしようもなくない?」
「そうかも……」
恨み言のような世奈のカミングアウトは続き、僕は生ぬるく同調しては先を促すくらいしかやることがなかった。「なんでみんなちゃんと死ねるんだろ?」という疑問に「なんでだろうね」と、「毎日つまんない」といった愚痴に「そっか。死んでるのも割とだるいんだね」といった具合に。今はまだ怨霊未満なら、僕は世奈に優しくしてあげたかった。彼女が透けているだけのただの女の子だったからだ。昔から僕は聞き上手だとよく言われる。主体性がないだけだけど。
世奈は「お前、カウンセラー気取りかよ」とせせら笑ったかと思うと、憤った。
「なんか久しぶりに会話したら、話すの止められないんだけど。最悪」
「別に良いよ。続けなよ」
「……。なんかさ、本当に飽きてるんだよね。死んでることに」
世奈は他人からさらに他人へと、川の中の飛石を移るようにいくつもの墓の上を歩いている。かと思えば「あーあ」というふて腐れた声でどこかの誰かの墓石に回し蹴りをしようとし、脚は見事に物体をすり抜ける。そんな風に闇に浮かんでいる。地面に足をつけられずに。
「忘れちゃったかも。生きてる身体がどんな感じだったか」
「別に、思い出すほどのものでもないかもよ」
僕はそう言いながらも同情せざるを得なかった。しばらくの間は、生前に抱いた幽霊のイメージそのままに動く身体を、テーマパークのアトラクション感覚で楽しむことが出来たらしい世奈。誰にも降ろしてもらえないアトラクションはもはやアトラクションではないのだと、僕は目の前の幽霊の身体を通して知らされていた。一生生きているのは一生死んでいるのとほぼ同義なのかもしれない。それでも好奇心は残酷で、僕が「死んでるってどんな気分なの?」と聞いた理由に別に深い意味はなかった。
「毎日腹とか、減る?」
「全然」
「感覚ってどう? 痛いとか、寒いとか」
「何もない。だけど……」
「うん」
「死んでから太陽、見てないんだよね」
世奈は墓2列ぶん離れた場所から月を睨んでいた。女の子の幽霊、月、墓。その三点の織りなす光景は、遠い過去に見た、実際にあるのかもわからない一枚の絵画のように僕の目に映った。
「なんで見てないの? 太陽」
「知らない。なんかさ、私、朝になると勝手に寝てるっぽい。昼間の意識がいっこもない」
「へー。幽霊って寝るんだ。普通に眠いの?」
「眠くない……。怠くても、それは生きててもそうだし」
「まぁ、そうだね」
「毎日毎日、気付いたら夜でここにいるんだよね」
とりあえず飽きたらこんな感じ。世奈はそう言うと自分の墓の上で小さく両膝を抱えた。頭を膝の上に乗せ、顔だけをこちらに向けていた。その姿はとても頼りなく、ストレートに哀れだと思った。空を見て風を浴びる以外何もない夜の長さを、スマホ1台で他人と繋がる僕には想像出来ない。夜は孤独で大きな檻で、もしかすると幽霊の身体は、魂は、何かに服役しているようなものなのかもしれない。
──誰にも気付いてもらえないなんて。
それは何かの罪なのだろうか。だけど僕だけは、突然の霊感でひとりぼっちの女の子に気が付いてあげられた。そう思うと、優越感がないと言えば嘘になる。その優越感が、今夜も僕をこの墓地にとどめていた。彼女を知りたい。それだけでまだ、全然帰る気になんてなれなかった。
「ちょっと待ってて」
僕はふと自分の喉の渇きと空腹に気が付き、立ち上がった。飲み物を買いに、道路を挟んだ向かい側にある自販機まで歩く。振り返ると世奈は墓石から姿を消していた。どこに行ったんだろう。と思うと同時に、いつの間にか世奈は僕の肩の辺りに浮かんでいて、思わず小さく叫んだ。
「こえーよ」
「ビビってんじゃねーよ」
意外なことに、世奈は僕のすぐ隣を不機嫌に漂ったまま離れずにいた。自販機で僕は温かいココアを選び、スマホで決済を済ませながら話しかける。
「今日、寒いね」
「別に私は寒くない」
「ここ、すごく静かだね」
「……当たり前でしょ。墓なんだから」
「うん。そうだ。誰かが死んでも世界は変わらないって言うよね。それって死んでる本人的にはどうなん?」
「……別に良いよ。私が死んで変わっちゃう世界なんてめちゃくちゃしょうもなさすぎるし」
「はは。まじか」
僕は取り繕いながらも内心、同意する。僕も僕が死んでどうにかなってしまう世界は恐ろしいし、自分は、世間に対してせいぜい血の通った消耗品程度であればいい。そんなことを考えながらココアを一口飲んだ。普段ブラックコーヒーばかり飲むせいだろう。こんな甘ったるい飲み物、久しぶりに飲んだなと思った。その瞬間「それクソ甘いよね。余計喉乾くやつ」と世奈に一刀両断された。僕が考えていたのとまったく同じことだった。どこか打ち解けた雰囲気を感じ、僕はうれしくなった。
「まぁ、そのうち成仏出来るよ」
そろそろ家に帰れよ、という軽いノリで僕は言う。そして、それが無理であるという前提に引き戻され、どうしたら良いのかを考え、思いついてはコートのポケットの中からスマホを出した。
「そうだ。人、呼んできてあげるよ」
「は? 誰」
「お祓い系の人。徳の高い坊さんとかでいい? もう一回ちゃんとお経読んでもらおうよ」
僕はスマホの画面に迷いなく指を滑らせ、チャットAI相手に「成仏の方法は?」と問いかける。人の生死にさえAIが入り込んだスマホは、この辺りでもっとも明るい光を放つ異質な物体にも思えた。少しの間を置き、次々と羅列される文字列を僕は心の中で読み上げる。①仏壇や神社でお祈りをする。②祓いを行う。③説得する。
「そういうの余計なお世話。いらないからー」
スマホを覗き込んだ後で世奈は低いテンションで言った。
「なんで? 成仏したいんでしょ。坊さんが嫌なら霊能者の手かざしとか、誰かの話とか、聞いてみたらいいじゃん」
「出来る気がしないんだもん。てか私、自分の読経もだるくてまともに聞けなかったんだよね……。だから成仏しなかったんだろうけど。国語苦手だし」
「生まれる前の赤ちゃんだって水子供養であの世行けるじゃん。国語関係ないって」
知らない。世奈はそう吐き捨てた。僕たちは暗黙の了解で、ふたたび墓地へ戻った。大人しく自分の墓石に座る世奈に僕は「おかえり」と声をかけ睨まれた。しばらくの沈黙の後で、彼女は呟いた。成仏とかよくわかんなくない?
「……なんかさ、知らない人の言葉なんかじゃ無理。もっとちゃんとしたのが欲しい」
「えー。金とか?」
銀行アプリに表示させた直近の預金残高を思い浮かべ、僕は一瞬、苦い気持ちになる。
「違う。……私が欲しいのは、多分もっと具体的な何かだから」
「何それ」
「少し前、ここに太った幽霊のおっさんがいたんだけど」
真剣に不機嫌な世奈は、二つ隣の墓石を指差していた。表面には「中田家之墓」と彫られ、足元には缶ビールとまだ新しい仏花が供えられている。世奈が言うようにおっさんの幽霊がいたとは思えないほど、静かでまっとうな墓らしい墓だった。
「中田とかいう人だったんだけど、おっさん、前科者でさ。生きてる間はずっと電車で痴漢やめられなかったんだって。で、何回目かでついに逮捕されて、家族にも捨てられて、それで出所したところ癌になってあっさり死んだ」
「……うん」
「誰にも墓参りに来てもらえなくて、寂しい寂しいってまじでうるさかったんだよね」
おっさんが寂しかったの、自業自得だと思う? 何かを試すように尋ねる世奈に僕は「人には人の事情があるよ」と当たり障りなく返事をする。
「それでその人、どうなったん?」
「急に、ひとりだけ……娘が会いに来たんだよ。それだけでおっさん、もう『俺には思い残すことない』とか言って消えてった」
「そうなんだ……」
「なんかすっきりして成仏したんだろうねー。良かったよねー」
他人事のように世奈は頬杖をついている。僕は立ち尽くしたまま、中田とかいうその人物の墓を二度見した。予想だにしないヒューマンドラマが付け加えられた後も墓は墓で、ただ静まり返っていた。すべての死には物語があると訴えかけるような静寂にも感じられた。もしかしたら今も僕の周りには幽霊がいるのかもしれない。だけど、僕に見えるのはたったひとり、世奈だけだ。
「多分、私は寂しいのかも」
小さな世奈の呟きで僕は我に返った。悪態ばかりついている幽霊から引き出された、素直で意外な言葉だった。
「じゃあ、寂しくなくなったら消えられそう?」
僕が尋ねると世奈は小さく頷いた。そして、今まででいちばん素直な態度で黙りこくっていた。困惑したまま、世奈と僕はふたたび見つめ合うこととなった。目の前で、世奈の身体を一匹の蛾が通り抜けていった。蛾はふらつきながらも上を目指して飛んでいった。本能的に。街灯という、辺りでもっともまばゆい光へと向かうために。道筋として蛾にさえ利用された幽霊の身体そのものが、僕にとってはとても寂しく、美しくも見えた。
「……そういえばお前、名前なんだっけ」
「僕は、拓人だよ。渡辺、拓人」
「へー。渡辺。普通だね」
しばらくの間、さらに沈黙が流れた。どこか身に覚えのある沈黙は、自ずとあるワンシーンを僕に思い出させた。人生の中でもトップクラスに強烈な印象を残したあの夜。迫り来る幽霊の白い影と、甘い囁き。身体を襲う金縛り。僕は、幽霊にキスをされたことがある。
「今日も殺そうとしてみても良いよ」
「……やるだけ無駄。気分じゃないし」
唇を真一文字に結ぶ今の世奈は、キスからは程遠い表情を浮かべていた。覚えたての手段で誰かを誘惑する女の子というよりは、欲しいものが目の前にあるのにわがままさえ上手く言えない子どものようだった。死んでも拗ねている。その姿を見て、僕は精いっぱいの優しい言葉をかけようとし、結果的に口説いてしまったのだった。
「成仏しようよ。僕がさせてあげるから」
「……どうやって?」
その瞬間、幽霊が初めて縋り付くような目をしたのを僕は見逃さなかった。もはや一切の疑う余地はなかった。幽霊は存在する。それも、救いを求めて彷徨える幽霊が。やり方もわからないのに、僕はなぜか不思議な使命感に燃え始めていた。神や仏のありがたい教えがひとつもない僕だから、俗な目線から救える魂もあるのではないか、と。そもそも僕たちはキスから始まった。「殺す」と囁かれた夜に、実際、僕の一部は殺されたのかもしれない。あのとき奪われた正体不明の何かは、たとえば、常識。倫理。幽霊がいないという一般論。
「そこにいて」
動かないで。僕は世奈へ手を伸ばし、寂しい幽霊の頭を撫でてみようとした。慰めるようでいて、単純に、もっとも心地良い方に自分の心と身体が引き寄せられる感覚を信じていた。呪いの目つきで世奈は僕を見ていたが、もはや怖くない。
「……いきなり近いんだけど」
「ごめん。でも、なんか遠くない?」
目の前に世奈はいるのに、僕は思わずそう言った。僕の手のひらは世奈の頭を通り抜けていた。近いのか、遠いのか。僕には幽霊と人間との、死と生の距離感なんてわからなかった。身体の輪郭はすぐそこにあるのに、あるのは痛いほど冷えた0℃付近の空気だけだった。世奈。ほとんど普通の女の子なのに透けている、不安定なシルエットを伝え続ける、質量でも形でもない第三の実体。一体何のためにいるのだろう。だけどそれは僕だって同じなのかもしれない。死んでいても生きていても、似た者同士なのかもしれない。僕は一旦、自分の手のひらを見つめた。不埒な胸の高鳴りに従い、世奈を抱き寄せようとした。すると僕の身体は突然、上手く動かなくなった。勝手に膝の力が抜け、その場に僕は崩れ落ちた。同時に音を立てて倒れる、今夜供え物を置いたばかりの花立て。スローに降り注ぐ花と水を僕は顔で受け止めた。身体は冷たく、痛く、そして動けない。
「……っ」
情けなく背を丸めた姿勢で、僕の身体は岩のようになっていた。僕を襲っているものの正体は金縛りだった。「いきなり、何?」という呆れた世奈の声を感じながら、これが幻聴なのか、そもそも今夜の出来事が現実なのか今になって疑う。他人に見られたらまずい、頭のおかしい行動をしている自覚は僕にはあった。だけど、妄想も現実も等しくひとつの脳内世界だと開き直ってもいた。少なくとも今は全身が痛いから夢ではなく、僕は、僕の感覚だけは信じられた。
ようやく口が動かせるようになった頃。仰向けの僕は掠れた声で尋ねた。
「……世奈。お前、悪霊?」
「わかんない。そうかも」
だって、今もお前のこと殺せたらいいなって思ってるよ。世奈はそう言いながら、あまりにも冷えた目で僕を見下ろしていた。幽霊に出会った二度目の夜。こうして僕はなんとなく、ひとりの女の子の成仏を目指し始めたのだった。透ける幽霊の身体の中には冬の夜空が広がっていた。僕の視界の隅、唯一の鮮やかな色彩と言ってもいい信号は、車も人も通らないのに、青、黄色、赤と色を変えていた。