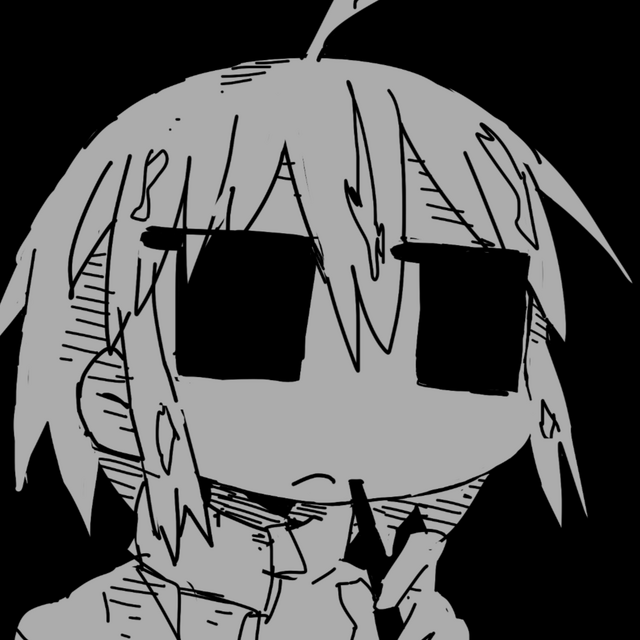第8話
文字数 2,982文字
他人様の家の、ステンレスの綺麗なシンクの前に立つ。
調理器具を確認して小鍋、ボウル、その他必要と思われるものは念の為、一度洗っておく。使われていなかったからだろう、基本的な調味料も一通り揃っている。使うものを一通り洗って白い布巾で丁寧に水気を取った。
そこから「よし始めるか」と料理が始めようとして。
だけど一体何を作ろうか、と考える。
今日のメインの材料は魚だ、御崎ちゃんにも作れる簡単なレシピにしないといけないことや出来れば他の料理にも通じるものがあるとより良い。初心者向けで何にでも使えること、それと出来ることなら「下ごしらえ」という面倒な工程が極力少ないものにしたい、そうじゃないと御崎ちゃんが料理から離れてしまいそうだ。
少し考えて、一つ思い浮かぶものがあった。
一人暮らしの時にお世話になった「あるもの」が。
「「万能ダレ」の作り方を教えるから」
「「万能ダレ」ですか?」
「何にでも使えるってこと、今から言うこと後でメモでもしておいてね。それと作り方もよく見ていて、何も難しくないことはないから。メモする時はまた同じこと教えるからとりあえず今はどんな感じで作るのかを見ておいて」
「分かりました、善処してみますね」
「小鍋に水、しょうゆ、みりん。昆布にかつお節」
「ギブアップしていいですか?」
「もうちょっと頑張ろうよ……これを煮立たせる」
「さて、出来上がったものがこちら」
「都合の良い料理番組じゃないからね? まあ言ってもすぐに沸騰するけど、この火力で小鍋だと。とか言っている間にふつふつと沸いてきた。沸騰したら大体30秒くらいで火を止める。これをコンロから離して粗熱をとって冷めたらざるでこす。これで完成なんだけど、最後にかつお節を絞る感じで旨みを保存容器に入れてね」
「家庭科の評価は「5」を上げます」
「いやいや、俺は小料理屋の店長って前にも伝えているよね?」
「学校にはそういうものを持ち込まないでください。なるほど……出来上がったらこれをご飯にかければいいんですね?」
「御崎ちゃん俺の話を全然聞いてないでしょ?」
なんておとぼけた会話の調子に正直ほっとした。
まだ多少は「生きる余力はありそうだな」と感じられたから。
「白米さえ炊いたならこの「万能ダレ」で煮たり焼いたり、和えたりしたものを乗せればそれだけで「丼物」の完成だから。丼物だと食器も丼だけだから洗う食器も少なくなるよ、まあ白米と分けて別の皿に乗せてもいいんだけどね」
「……チョロい」
「いや、作ったの俺だからね?」
小鍋の粗熱がとれる頃には白米も炊けているだろう。
「で、万能ダレの粗熱がとれるまでに魚をさばいていきます」
「私、多分教わっても出来ないですよ?」
「まあ、思ったよりは簡単だから見てて」
アジは鮮度も質も間違い無し、釣ったばかりの上物。
ゆっくり丁寧に説明しながらアジをさばいていくけれど、彼女の反応を見る限りだと魚をさばくことは難しそうか。そもそも自力でさばけそうなら、釣った魚を「持って行ってください」とも言わないだろう。
ともあれアジの方も綺麗にさばいた。
「あ、いけね、香味野菜が必要なんだわ、買ってくる」
アジは一旦冷蔵庫に入れて御崎ちゃんの家を出た。
車で駅前のスーパーへ。目的のものだけぱぱっと買ってしまうことに、会計を済ませてささっと車で戻ってくる。ほんの15分くらいのこと。
スーパーのビニール袋を持ってインターホンを押す。
「ただいま、香味野菜買ってきたよ」
インターホン越しに御崎ちゃんの声。
「鍵、開いてますよ」
「お邪魔します」と再度言ってから家の中、リビングに戻ってきた。
「お待たせ、もう出来上がるよ」
まず粗熱のとれた「万能ダレ」を保存用の容器に移す。その後で必要分の万能ダレでアジとみょうがと、買ってきたかいわれ菜、しそ、生姜を和えてちょうど炊き終わった白米の上に乗せれば「アジの香味野菜丼」の完成となる。テーブルの上を片付けて、倒れていた椅子も起こして二人で食事を食べることに。
「――いただきます」
御崎ちゃんは一口食べて恍惚そうな表情を浮かべる。
「うー、美味しい!」
そんな表情を見ると俺も嬉しくなる。
「それはどうも」
「まともなご飯食べたら涙が出てきた」
「おいおいおい」
「このクオリティーの料理に慣れちゃうと元の食事生活に戻れなくなりそうなので「万能ダレ」は、勿体無いですが封印しておきますね」
「おーい、おいおいおい、本末転倒すぎない?」
あっという間に「アジの香味野菜丼」を食べ終わる。
「――ご馳走様でした」
御崎ちゃんは食べ終えた食器を自分で洗った。その後で俺と彼女はごちゃごちゃしたリビングで少しまったりとしていた。御崎ちゃんも俺が料理人ということをようやく認識したようで少し興味があるようだった。
「小料理屋さんになるには何か特別なものが必要なんですか?」
「まあ、分かりやすくいうと「資格」が必要だね、調理師免許とかそういうの。それで一番分かりやすいのは「そういう学校」へ行って取るパターン。これがもう9割とかでそうじゃない例はほとんどないんだよね」
「そういうものなんですか?」
「そういうものだね。構造とかはきっと色々な理由があるんだろうけれど、まあ、俺はそこに疑問は持ったことはなかったよ。中学校に上がる頃には「専門学校へ行く」と思っていたからね、周りも「あいつは専門学校へ行く」と思っていた」
「料理の専門学校って、三浦市にもあるんですか?」
「いや、ない。だから高校卒業後は横浜の専門学校へ行って横浜で一人暮らし、それで生活費の足しにエオンでバイトしていたよ」
「やっぱり鮮魚とかだったりするんですか?」
「面接で「鮮魚へ行きたいです」って伝えたのに「気が弱そうだから」って理由でドラッグストアの品出しに回されたよ。鮮魚やりたかったのにさ」
「……ふふ、確かに気が弱そうですもんね」
思わず漏れた笑いに俺は苦笑い。
「笑うなって、今でも思い出すと地味にダメージあるんだから」
話していて当時のことを思い出した。
ドラッグストアの品出し、理不尽なことばかりだったな。
品出しなのに化粧品のこと聞かれて「説明出来ないってあなたプロでしょう?」とお客さんに説教されたり。他のヤンキーのバイトの姿が見えないと思っていたら、サボって煙草吸ってやがって。それで品出し終わらなくて、どういうわけか「なんでその場で怒って注意しないのか」と俺が現場に出てもいない上司に怒られた。
そんなこんなで二度とドラッグストアでバイトしない、と決めた「理不尽に耐える必要があるのなら自分のやりたいことをやろう」そう決心出来たという意味では、貴重な社会経験だったともいえる、二度とやりたくないけれど。
万能ダレのレシピを教えなおして、御崎ちゃんがメモを取り終えたことを確認してから「じゃあ帰るよ」と俺も家に帰ることにした。
「はい、ありがとうございました」
心配と言えば心配だけど俺にも俺の生活が、仕事がある。
そういうものを放棄して人を心配することは「良くないこと」だと俺は思っている、それは受け取る側の負担にもなってしまう。俺は俺に出来る範囲で人に親切にする、そこを崩したのなら人と本当に良い関係性は築くことは出来ない。
――言っていたのは俺の親父、受け売りというより受け継いた価値観だ。
調理器具を確認して小鍋、ボウル、その他必要と思われるものは念の為、一度洗っておく。使われていなかったからだろう、基本的な調味料も一通り揃っている。使うものを一通り洗って白い布巾で丁寧に水気を取った。
そこから「よし始めるか」と料理が始めようとして。
だけど一体何を作ろうか、と考える。
今日のメインの材料は魚だ、御崎ちゃんにも作れる簡単なレシピにしないといけないことや出来れば他の料理にも通じるものがあるとより良い。初心者向けで何にでも使えること、それと出来ることなら「下ごしらえ」という面倒な工程が極力少ないものにしたい、そうじゃないと御崎ちゃんが料理から離れてしまいそうだ。
少し考えて、一つ思い浮かぶものがあった。
一人暮らしの時にお世話になった「あるもの」が。
「「万能ダレ」の作り方を教えるから」
「「万能ダレ」ですか?」
「何にでも使えるってこと、今から言うこと後でメモでもしておいてね。それと作り方もよく見ていて、何も難しくないことはないから。メモする時はまた同じこと教えるからとりあえず今はどんな感じで作るのかを見ておいて」
「分かりました、善処してみますね」
「小鍋に水、しょうゆ、みりん。昆布にかつお節」
「ギブアップしていいですか?」
「もうちょっと頑張ろうよ……これを煮立たせる」
「さて、出来上がったものがこちら」
「都合の良い料理番組じゃないからね? まあ言ってもすぐに沸騰するけど、この火力で小鍋だと。とか言っている間にふつふつと沸いてきた。沸騰したら大体30秒くらいで火を止める。これをコンロから離して粗熱をとって冷めたらざるでこす。これで完成なんだけど、最後にかつお節を絞る感じで旨みを保存容器に入れてね」
「家庭科の評価は「5」を上げます」
「いやいや、俺は小料理屋の店長って前にも伝えているよね?」
「学校にはそういうものを持ち込まないでください。なるほど……出来上がったらこれをご飯にかければいいんですね?」
「御崎ちゃん俺の話を全然聞いてないでしょ?」
なんておとぼけた会話の調子に正直ほっとした。
まだ多少は「生きる余力はありそうだな」と感じられたから。
「白米さえ炊いたならこの「万能ダレ」で煮たり焼いたり、和えたりしたものを乗せればそれだけで「丼物」の完成だから。丼物だと食器も丼だけだから洗う食器も少なくなるよ、まあ白米と分けて別の皿に乗せてもいいんだけどね」
「……チョロい」
「いや、作ったの俺だからね?」
小鍋の粗熱がとれる頃には白米も炊けているだろう。
「で、万能ダレの粗熱がとれるまでに魚をさばいていきます」
「私、多分教わっても出来ないですよ?」
「まあ、思ったよりは簡単だから見てて」
アジは鮮度も質も間違い無し、釣ったばかりの上物。
ゆっくり丁寧に説明しながらアジをさばいていくけれど、彼女の反応を見る限りだと魚をさばくことは難しそうか。そもそも自力でさばけそうなら、釣った魚を「持って行ってください」とも言わないだろう。
ともあれアジの方も綺麗にさばいた。
「あ、いけね、香味野菜が必要なんだわ、買ってくる」
アジは一旦冷蔵庫に入れて御崎ちゃんの家を出た。
車で駅前のスーパーへ。目的のものだけぱぱっと買ってしまうことに、会計を済ませてささっと車で戻ってくる。ほんの15分くらいのこと。
スーパーのビニール袋を持ってインターホンを押す。
「ただいま、香味野菜買ってきたよ」
インターホン越しに御崎ちゃんの声。
「鍵、開いてますよ」
「お邪魔します」と再度言ってから家の中、リビングに戻ってきた。
「お待たせ、もう出来上がるよ」
まず粗熱のとれた「万能ダレ」を保存用の容器に移す。その後で必要分の万能ダレでアジとみょうがと、買ってきたかいわれ菜、しそ、生姜を和えてちょうど炊き終わった白米の上に乗せれば「アジの香味野菜丼」の完成となる。テーブルの上を片付けて、倒れていた椅子も起こして二人で食事を食べることに。
「――いただきます」
御崎ちゃんは一口食べて恍惚そうな表情を浮かべる。
「うー、美味しい!」
そんな表情を見ると俺も嬉しくなる。
「それはどうも」
「まともなご飯食べたら涙が出てきた」
「おいおいおい」
「このクオリティーの料理に慣れちゃうと元の食事生活に戻れなくなりそうなので「万能ダレ」は、勿体無いですが封印しておきますね」
「おーい、おいおいおい、本末転倒すぎない?」
あっという間に「アジの香味野菜丼」を食べ終わる。
「――ご馳走様でした」
御崎ちゃんは食べ終えた食器を自分で洗った。その後で俺と彼女はごちゃごちゃしたリビングで少しまったりとしていた。御崎ちゃんも俺が料理人ということをようやく認識したようで少し興味があるようだった。
「小料理屋さんになるには何か特別なものが必要なんですか?」
「まあ、分かりやすくいうと「資格」が必要だね、調理師免許とかそういうの。それで一番分かりやすいのは「そういう学校」へ行って取るパターン。これがもう9割とかでそうじゃない例はほとんどないんだよね」
「そういうものなんですか?」
「そういうものだね。構造とかはきっと色々な理由があるんだろうけれど、まあ、俺はそこに疑問は持ったことはなかったよ。中学校に上がる頃には「専門学校へ行く」と思っていたからね、周りも「あいつは専門学校へ行く」と思っていた」
「料理の専門学校って、三浦市にもあるんですか?」
「いや、ない。だから高校卒業後は横浜の専門学校へ行って横浜で一人暮らし、それで生活費の足しにエオンでバイトしていたよ」
「やっぱり鮮魚とかだったりするんですか?」
「面接で「鮮魚へ行きたいです」って伝えたのに「気が弱そうだから」って理由でドラッグストアの品出しに回されたよ。鮮魚やりたかったのにさ」
「……ふふ、確かに気が弱そうですもんね」
思わず漏れた笑いに俺は苦笑い。
「笑うなって、今でも思い出すと地味にダメージあるんだから」
話していて当時のことを思い出した。
ドラッグストアの品出し、理不尽なことばかりだったな。
品出しなのに化粧品のこと聞かれて「説明出来ないってあなたプロでしょう?」とお客さんに説教されたり。他のヤンキーのバイトの姿が見えないと思っていたら、サボって煙草吸ってやがって。それで品出し終わらなくて、どういうわけか「なんでその場で怒って注意しないのか」と俺が現場に出てもいない上司に怒られた。
そんなこんなで二度とドラッグストアでバイトしない、と決めた「理不尽に耐える必要があるのなら自分のやりたいことをやろう」そう決心出来たという意味では、貴重な社会経験だったともいえる、二度とやりたくないけれど。
万能ダレのレシピを教えなおして、御崎ちゃんがメモを取り終えたことを確認してから「じゃあ帰るよ」と俺も家に帰ることにした。
「はい、ありがとうございました」
心配と言えば心配だけど俺にも俺の生活が、仕事がある。
そういうものを放棄して人を心配することは「良くないこと」だと俺は思っている、それは受け取る側の負担にもなってしまう。俺は俺に出来る範囲で人に親切にする、そこを崩したのなら人と本当に良い関係性は築くことは出来ない。
――言っていたのは俺の親父、受け売りというより受け継いた価値観だ。