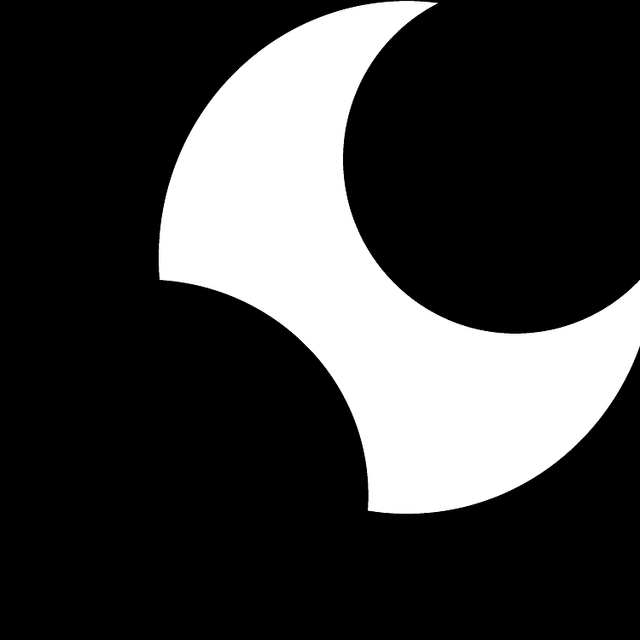【がらんどうの根は甘く】
文字数 79,567文字
【がらんどうの根は甘く】
「絶対に許さない」
彼女の目からは、私への破滅を望む炎が溢れていた。
つよい悪意をぶつけられ、そうして私は言葉を失った。初潮を迎える前のことだ。言葉だけでなく、人格そのものが消失したような空虚さに襲われ、それは立ち退くことなく私のなかに留まりつづけた。わだかまりつづけた、と言い換えても齟齬はなく、私は言葉を失い、底なしのがらんどうを手に入れた。
私がそうして言葉を失い、しゃべらなくなってから五年の月日が経った。私は小学生から中学生を越し、晴れて高校生となった。
しゃべれないのではなく、しゃべらないだけだと医師からのお墨付きをもらって以降、私はうるさくない女の子として、それなりに周りのコたちと仲良くやっていた。
大人たちも無理にしゃべらせようとはせず、それはなんだか女の子は静かで自己主張しないほうがよろしいよ、といった偏見のたまものでもあるように思えたけれど、すくなくとも私はそんな周囲の「臭くないなら蓋をせずともよしとするか」といった眼差しに支えられ、すこやかな日々を送っていた。
「いつからしゃべれないの」
ある程度の仲を深めた学友たちから、ときおりそのように話題を振られることはしばしばで、
なんとなく。
と、
いつも私は曖昧にノートに文字を書き、その場を切り抜けていた。
きっかけはあるのだ。
思いだしたくないきっかけが。
私は言葉を失くした人間で、けれど言葉に支えられた社会に生き、文字を介して意思を疎通する。
本来であれば、声を失くした、と形容すべきところではあるけれど、しゃべれないのではなくしゃべらないだけの私にしてみれば、それは正しくはないのだった。
「ええ、転校生の琉紗那(るさな)イユさんです」
夏期講習のプリントを配ったあとで先生は言った。「夏休み明けからこのクラスの一員になるので、名前と顔を憶えてあげてね」
転校生は女の子だった。線が細く、なんだか白くて背の高い花を連想した。
ぼーっと眺めていると目が合った。彼女はその前からきょろきょろと目を泳がせており、落ち着かないというよりもそれはどこか挙動不審で、すらりとした背格好に反して、なんだか小動物じみていた。
いちど目が合ったのを皮切りになぜだか、彼女の視線は微動だにせず、私に注がれつづけた。まるで私の内側に塞がることのないがらんどうが開いているのだと知っているかのように、彼女は私をまっすぐと、私だけを見ていた。
嫌な予感はすでにしていた。彼女の下の名前に聞き憶えがあったからだが、すくなくとも彼女の名字は初めて耳にするものだった。
だから、おそらく、油断した。
先生が転校生へと自己紹介をするようにと促すと、そのコは、ハイ、と子猫の、みゃー、と鳴くような声で返事をした。そして彼女は彼女自身の来歴をつらつらと述べた。
彼女の声を耳にしたとき、私は明瞭に、自身のがらんどうが大きく波打つのを感じた。
彼女は言った。以前、この街に住んでいたこと。両親の都合で引っ越したこと。名字が変わったこと。以前は世に有り触れた名字で、ひょっとしたらこのなかに小学校のころのオトモダチがいるかもしれないことを用意してきた祝辞のように述べた。
目が合う。
ヒッ。
私は私の声を、五年ぶりに耳にする。じぶんだけに聞こえた幻聴かとも思ったが、周りの生徒が振りかえり、私の身体は硬直した。
顔が熱くなってしかるべき状況をまえにして、私はじぶんの顔面が蒼白になっているのだと俯瞰の視点でみずからを想像する。現に四肢は震え、ひたすら寒かった。
だいじょうぶ?
教室の静寂を破ったのは、教壇のうえに立つ転校生だった。
ヒッ。幻聴のように私の五年ぶりの声が脳裡にこだまする。
内なるがらんどうの生みの親。
彼女は五年分の成長を経て、私の記憶のなかにある姿とは別物だったが、たしかにその片鱗を、面影を、彼女の夏の木陰のようなどこか心に染み入る声音に窺うことができた。
彼女はもういちど自身の名を、旧姓で名乗り、みなさんよろしくおねがいします、と折り目正しくお辞儀した。
私への破滅を願う炎が、私だけに視える蜃気楼のように、彼女の涼しげで、うるわしい姿に重なって視えている。
翌週から夏休みなのはさいわいと呼べた。転校生こと琉紗那イユは夏休み明けからの合流で、それまでは学校で顔を合わせる危険はない。
そうだ、これは明確に危機ではないか。
耳に染みこんだ、じぶんの「ヒッ」が、いくども、ことあるごとに反響する。
きっとあのコは気づいているはずだ。
考えすぎや思い過ごしを念頭におくよりも、そう考えたほうが私にとってはしぜんで、より安心できる懸念だった。
嫌な予感は留まることを知らず、サイレンのような耳障りなカタチを帯びて、私の脳内をチクチクと占領する。
嫌な予感ほど的中するのはなぜなのか。
科学の発展目覚ましい現代にあって、どうして誰もこの問いに答えてくれないのだろう。ひょっとしたら、認知バイアスの一言で片づけられてしまうかもしれないこの疑問に、私は「悪意」の関与を指摘したい。
嫌な予感とは、他者の悪意への防衛反応であると。
夏休み初日、私は陰鬱な気分を晴らそうと、街はずれの美術館に足を運んでいた。美術館とはいえど、一人の作家の記念館のようなもので、家屋もこじんまりとしていて骨董屋みたいだな、とくるたびに思う。
とくに好きな作家ではなかった。いつきても閑古鳥が鳴いているこの空間に身を置くのが私は好きだったのだ。
なのにこの日、私は初めて、私以外のお客さんがいるのを目にした。
ヒッ。
私はその場に踏みとどまる。
「あ、偶然」
彼女の物言いは白々しかった。近づいてくると、動けなくなったこちらを展覧物の一つであるかのようにぐるっとひと回りする。ひととおり、頭からひざの裏まで舐めるように目を走らせると彼女は、
「変わってないね」
眉根を寄せ、しみじみ言った。「すぐに判ったよ、ひと目で判った、学校で見て、びっくりしたけど、でもそう、いるかなって期待はしてたかな」
私は黙っていた。
しゃべろうにも、そもそも声を発しないのが私だからだ。
私から言葉を奪った女が目のまえにいる。
私の気質は、彼女だって教師から聞いているはずだ。私と同じクラスになるコたちはみなそうして私の性質を、私以外の言葉で受け取り、承知する。
「先生から聞いたよ」
私が銅像の真似事をやめられないでいるあいだも彼女は一方的に話しつづける。「しゃべれないんだってね。でも筆談ならだいじょうぶなんでしょ、何も問題ないじゃんね、いまどきしゃべるよりみんな電波飛ばしあって会話してるようなもんだしさ」
変わらないよね、と彼女は口にする。
むかしのあなたと変わらないし、あたしとあなたも変わらない。
彼女の言葉は言葉として耳に入るけれど、その背景に潜む彼女の意図を見抜けないでいる。
絶対に許さない。
むかし、私から言葉を奪った女の言葉は、いま目のまえにいる彼女と同じ口からつむがれたはずだった。五年の歳月が経過したいま、彼女の唇を構成する物質はもはや以前の彼女のものではなく、彼女に限らず、それは私も同じだった。
だから私たちは初対面であり、あのときとは別人なのだ、と捉えることもできないわけではないのだと、私は私に思いこませようと、理屈を捏ねては、内なる底なしのがらんどうを持て余す。
彼女、イユは私に言葉を浴びせつづけた。終始、ひなたぼっこをする猫に似た空気をまといながら、まるで私にがらんどうを植えつけたことなどなかったかのように、ひたすらむかし話を、それはおおむね、私との思い出話であるらしかったが、そんな話をされるまで私は彼女とそんなふうに関わっていたことすら忘れていたにも拘わらず、果実じみた唇を動かしつづけた。
私たちはかつてトモダチだったのだ。
かねてよりの、トモダチだったのだ。
かように記憶をねつ造され、刷りこまれるように、私は彼女の言葉にじっと耳の穴を向けていた。つまりがそっぽを向いていた。
気づくと私たちは美術館のそとにいた。ちかくの公園でベンチに座り、いつ買ったのかも覚束ないソフトクリームを舐めている。
「むかし、こうしてよく食べたよね」彼女は言うけれど、私にその記憶はなく、ひょっとすると努めて忘れようとしていた過去があるのかもしれなかった。「手話とか使うの? そうだ、連絡先教えてよ」
筆談、筆談。
言いながら彼女はメディア端末を取りだし、情報交換を促した。
私はたぶん、顔面蒼白になっていたはずだ。身振り手振りで、まずは遠慮したい旨を示したかったが、彼女をまえにするとどうしても身体がうまく動かない。
「どったの? 持ってるでしょ、だしなよ」
私がいつまでも地蔵の真似ごとをしているものだから、イユは眉を結び、ひょっとして、と自身の端末ごと手をひざのうえに置いた。「何か悩みとかあるの。聞くよ。なに。相談して」
顔を寄せてくる彼女からはほのかに甘い香りがした。
私は残ったソフトクリームを一口で頬張り、悩みなんてないない、と首を振り、だいじょうぶだと、チカラこぶをつくって、強調した。
「マッチョになりたいの? 痩せたいとか?」
うまく伝わらなかった。
「そうだ、部活とか入ってる? 運動部って感じじゃないよね。手芸部? あ、美術部とか? わかった、吹奏楽部でしょ」
部活動には入っていなかった。図書委員会に入っており、ふだんは放課後に図書室で本を読んでいる。
「そうそうあたし、まだ引っ越してきたばっかでしょ、服とか買いたいんだけど案内してよ」
彼女が私の腕をとる。
身体が硬直し、悪寒が背筋を駆け抜ける。あべこべに汗が噴きだし、手でひたいを拭うようにすると、
「うわー、びしょびしょじゃん」
彼女が離れたので、これさいわいと退避すべく、私帰るね、を伝えるためにメディア端末を取りだしたのが運の尽き、
「あ、持ってんじゃん。どれどれ」
彼女は私から端末を奪い取ると、そそくさと個人情報を抜き取った。
「これでいつでも話せるね」
まるで死刑宣告のように聞こえた。「そうだ、おばさん元気? 挨拶しなきゃだよね、家とか、うわー、めっちゃ久しぶりじゃんね」
ひょっとして、と思う間もなく彼女に引きずられるかたちで、私は彼女ごとじぶんの家までの道のりを歩いている。
頭のなかでハムスターが幾度も転げながら歯車を回す。逃げだすことはおろか一歩も進めないというのに。
なんと言って断ろうかと考えあぐねているあいだにも、彼女はいっぽうてきに捲し立てては、私のハムスターに鞭を打つ。
彼女の言動には脈絡がなく、家の話かと思えば、学校の話になり、お気に入りの音楽の話ときたらむかしの話に戻り、話題を振ってきたかと身構えると、我田引水にこちらの胸中を推し量っては、さらに舌鋒を鋭くした。
五年の月日を埋めんとするかの激しさに、私は内なるがらんどうの生みの親であることを抜きにして、彼女を心底苦手に思った。
「あたしがいないあいだとかさ」
声が上擦って聞こえたのでよこを窺うと、彼女は虚空を凝視しながら、まるでそこに私がいるみたいに、
「どうして過ごしてたの、しゃべれないんだよね、やっぱりそういうのってたいへんじゃんね、ほかに仲いい友達とかできたのかな、助けてもらったりしてたのかな、クラスにいるよねそういうコ、いるよね、そりゃね、でもさあたしのほうがさ」
身体がとたんに鉛を帯びた。
内なるがらんどうが鉄屑に成り代わったみたいだ。ずーん、と重くなる。
足取りまで鈍る。
彼女に腕をとられているからつんのめりながらもしかし、歩みは止まらない。首輪の食い込んだイヌのようになりながら、内なるがらんどうが身体のそとへと滲みでてくる様を連想する。或いはそれはあべこべで、私の周囲に、ブラックホールさながらのがらんどうが君臨しているのかもしれなかった。
なるほど、と私は思う。
身体から、がらんどうが抜けだしたから重くなったのか。風船の空気が抜けるみたいに。私の内は鉄屑のみが残る。
「でももうだいじょうぶだよ」
鉄屑でも?
問い返しそうになるも、元から私はしゃべらない人間だ。彼女、イユは私を置いてきぼりにして、引きずりながらも、しゃべりつづける。「だってあたしがいるし、もうだいじょうぶだよ。だいじょうぶ、だいじょうぶ。よかったね。あたしが戻ってきて」
そうでしょ。
虚空を見詰めたままの彼女の見開かれた目に、私は真夏だというのも忘れ、凍りついた。
それからさき、彼女が私の母に挨拶をし、親ぼくを深め、クラスが同じだと知るや否やかつてない待遇でもてなしはじめた母を手懐けていく彼女の手腕を私は、私の家で、私だけが世界の外側にいるかのような疎外感にくるまれながら、眺めた。
イユは母の運転する車に乗せられ、ようやく我が家から姿を消した。母は私がしゃべらないのをいいことに、イユから訊ねられるままに、私の過去をつらつらと漏らした。ひょっとしたら私がしゃべらないから、私の代わりに受け答えしていただけなのかもしれないが、いずれにせよ、イユはたった半日のあいだに、私の五年間を、母という記録媒体を通して、かっさらっていった。
じっさいに何かを奪われたわけではないのに、私にしてみたら、未来を奪われたような絶望感に襲われた。弱みを握られたようなものだ。爆弾を首にはめられたようなものだった。
私はもう、どうあっても彼女から距離を置くことも、拒むこともできないのだと知った。
そう悟らせるためにイユは家までついてきたのだとまで考えるのは、さすがに穿ちすぎではあるけれど、既成事実として私はそう悟ってしまったのだから、そう仕向けられたと見做して、何がおかしいだろう。彼女はきっと、まだ忘れていないのだ。
ぜったいに許さない、と言ったあのときの怒りを。感情を。
しかし、でも。
底なしのがらんどうが、私の内部にふたたび舞い戻りつつある。
私はそう、なぜ彼女が怒ったのかを、知らぬままでいる。
この五年間、ずっとだ。
夏休みのあいだ、イユは毎日のように私の家にやってきた。母のほうで誘っていた節がある。娘をよろしくね、とたびたび口にし、いつもありがとうね、とおもねる姿には、我が母親ながらというべきか、我が母親だからというべきか、見境のなさに吐き気を催す。
もし私がいなければ母はそんな真似をすることはなかったはずだ。なぜならそれは私のためであり、私のしゃべらない気質のせいだからで、回り回って、私から言葉を奪った元凶に媚びを売る姿は、手ひどく情けなく、可哀そうで、彼女の娘として罪悪感に押しつぶされそうになる。
彼女を母に近づかせないようにとのせめてもの策に、私は自ら進んでイユを遊びに誘った。二つ返事で乗り気のイユと、駅前で待ち合わせし、それから私は、彼女の喜びそうな場所を案内して歩いた。
彼女が周囲の環境に目を奪われれば奪われるほど、私への関心が薄れる。いっしょにいる時間は可能なかぎり、彼女を喜ばせることに心血をそそぎ、彼女が彼女自身で完結して夏休みを謳歌してもらうことが、私にとって最善の、最悪回避策と呼べた。
「ねぇねぇ、あしたはあそこ行こ、あそこ」
イユは好奇心旺盛だった。私がいくら刺激を提供しても満足する素振りをみせず、もっともっと、と欲しがった。雛鳥みたいだ。すこしでも気を抜き、手を抜いて、彼女に不満を抱く余地を持たせると、私のがらんどうはあべこべに養分を蓄え、深みを増す。
いくどかイユの家にも連れて行かれたが、彼女のほうの家族は私を歓迎しなかった。遊んでばかりいる娘に小言を言い、なるほどおまえが悪因か、と病原菌を見つけた医学博士のような目を向けられた。
「おっきなお人形だこと」
イユの母親は私を見ることなく、嘆いた。人形遊びはほどほどにね、と言わんばかりの溜息を残し、家をでていく。イユはこうなることを予期していたように、きょうも帰ってこなくていいからねー、と満面の笑みで手を振った。
こんな親子関係があったなんて。
世界観の違いにくらくらした。こんな身近に異国があったなんて、とふしぎの国のアリスになった心地がした。
イユの母親と会ったのはそのときが最後で、あとはもう、何度足を踏み入れても、イユの家に、イユ以外の人間の息遣いを感じることはなかった。
私の家とそれほど変わりのない内装なのに、ふしぎと足元にずらりと岩が詰まっているかのような窮屈感を覚えた。
牢獄の城のようだと思いながらイユの姿を目に入れると、途端に色褪せて見えた空間が、すこしだけ煌びやかな魔女の国のように思えてくる。
苦手な相手とはいえ、顔を合わせるたびに、私はすこしずつ警戒心をほどいていたのだろう。意図してほどいたのではなく、知らず知らずのうちに、過去の、私から言葉を奪い去ったあのイユと、目のまえのこのイユは別人なのではないか、と考えるよりさきに、身体のほうで判断している節がある。
彼女はすくなくとも、いまのところはまだ、はっきりと私を傷つけたりはしなかった。好きかってに振り回しはするけれど、それによって私が泣きたくなったとか、寝込んだとか、そういったことはないのだった。
「あしたはどこ行こっか。むかしいっしょに行ったとこはもう全部回っちゃったし、あしたからはじゃあ、新しい思い出づくりしよっか」
そうだ、そうだよ、それがいい。
はしゃぐイユに私はメディア端末の画面を差し向ける。
来週から学校だよ。
伝えると、イユの頭のうえに、しゅん、と垂れる耳が見えた。「そっか、そうだった」
宿題はやったの、と訊ねる。
「そりゃあね。まあね。いちおうはね」
転校初日だから緊張するね、と水を向けると、
「ぜんぜん」
彼女は唇をすぼめ、
「だってもう緊張する理由がなくなっちゃったから」
イユはくるくると回転しながら、公園のベンチに吸い寄せられていく。そのままストンと座ると、となりの席をぽんぽんと叩いた。「座って、座って。すこし話そ」
さっきからずっと喋りっぱなしではないか。
思ったけれども、わざわざ文字に打つまでもないと判じ、彼女のとなりに腰をおろす。イユはにこにことこちらを見詰める。子狐じみたその顔をまえにしても、以前のように、ヒッ、とはならない。
ひょっとしたら過去、私たちのあいだに因縁のようなものはなく、私は無駄に私の被害妄想を肥大化させて、自意識過剰に自虐しては、おのずから言葉を失くしてきただけなのではないか。
中学生のころに母から勧められ読んだ、アドラー心理学を思いだす。目的論と原因論の違いを論じたそれは、人は究極のところ「したいからしているのだ」という元も子もない主張を至極真面目に説いていた。原因があって結果があるのではなく、まずしたいことがあり、そのために言いわけを用意し、自身を鼓舞したり肯定したりしているだけなのだ、という理屈だった。そう言われればそんな気もしてくるし、違うような気もする。
だが、すくなくとも私の緘黙に関しては、私自身、ただしゃべるのが嫌で、そのための理由を、過去私のまえからいなくなったイユに押しつけていただけなのではないか、と問われて、違うと否定するだけの考えを私は私に示せないのだった。
イユを悪者にしていただけなのかもしれない。
彼女との再会は、邂逅というよりもどちらかと言えば遭遇と呼んだほうがちょうどよい塩梅だったはずが、こうして夏休みのあいだに振り回されていくうちに、段々と私の思い過ごしや、勘違いだった気がしてくるからふしぎだ。のど元過ぎればではないが、そもそも私は熱湯など呑みこんでおらず、煮込まれてもおらず、イユから憎まれた過去もないのかもしれなかった。
映画か何かの刺激のつよい場面を切って貼りつけて、記憶をねつ造していたとしてもふしぎではない。五年という歳月が流れているのだ。それこそ思春期以前のやわらかい時期の記憶だ。
罪悪感に似た感情が、イユと顔を合わせるたびに、私の内なるがらんどうに蓄積していく。埋められていく。埋まっていく私はもう、ただ単にしゃべるのすら面倒な横着者でしかない。
内心じぶんを責めていると、イユは両手のゆびを掻き合わせ、
「むかしさ、引っ越すとき、憶えてるかな」
もじゃもじゃ動かしながら、
「あたしひどいこと言ったじゃん?」
核心的な一言を口にした。私はその途端、埋まりかけていたがらんどうが広がりを帯び、耳の奥で、私の「ヒッ」がこだまするのを、幻聴だと判っていながらハッキリと知覚した。
「ずっと心残りで、引っかかってて、忘れてるならそれでいいんだけど、でもなんか気持ちわるいから謝らせてほしいっていうか、謝っておきたいというか」
もじゃもじゃとしきりにじぶんのゆびを気にしている彼女は、手元にしか視線を落としておらず、謝罪をしたいと言っておきながらとくにその後に、ごめんなさいだとか、許してくださいだとか、そういった言葉を口にすることはなかった。
私はしばらく呼吸を忘れていた。胸が苦しくて、なんだろうなんだろう、と思っていたら、そっか息をしていないのだ、と気づき、大きく息を吸うと、とたんに身体のなかが希薄になって、からっぽになってしまったような感覚に陥った。吸った息を吐くと、こんどは私からするするととめどなくがらんどうが大気へと馴染んでいき、私はいっとき世界と繋がった。しかし、私がどれほど世界と同化しても、そばにいるかつて私から言葉を奪い、私を希薄にし、こうして世界とまぜこぜにして私という輪郭をぼろぼろに打ち崩した転校生のことはまったくこれっぽっちも理解できないのだった。
私たちは水と油だ。
思うと同時に、水と油はそれでも接することはできるのだ、と何かが決定的に違うのだと思うと、私はもう、目のまえの、私のとなりに座る転校生のことをただの異物としてしか見做せないのだった。
「ずっとずっと心残りで」イユは繰りかえした。「こうしてまた会えたら、離れ離れになってた時間なんてなかったみたいに、それこそむかしみたいになれてうれしい。すごくすごくうれしい」
何を言っているのだろう、このコは。
私はもう彼女の言葉を言葉として咀嚼できなくなっていた。
「教室で、あっ、ってなったとき、本当はすっごい緊張してたんだ、心臓が口からでそうって本当に思った。憎まれてたらどうしよう、ひどいこと言ったあたしのこと嫌ってたらどうしようって、すごい不安だったんだよ」
だったんだよ、と彼女は言うが、私のほうが現在進行形で、なんですよ、と言いたい。あなたのことは苦手なんですよ、と。あなたの言葉はこうしていまなお私の内部を希薄にしつづけているというのに。
仕方がないのかもしれない。
私がこうまでも希薄だからこそ彼女は、私の苦悩も葛藤もなにもかもを察することができないのだ。
伝わることはないのだろう。
この口から言葉をつむげたとして、それで果たして彼女に何かこのがらんどうの片鱗でも届く可能性があるだろうか。私は今ならハッキリと断言できる。
届くわけがないのだ。
私の当惑を、懊悩を、そしてとびきりの諦観の念に気づくことなく、転校生は、ただただ位置座標的な意味合いでの私のとなりで、うっとりとじぶんの罪を告白し、かってに許しを得たつもりでこの空間を、私との夏休みを、再会を、美談にしようと夢中にむしゃぶりついている。しゃべり尽くしている。
私がしゃべれないのをいいことにして。
こんなふうに私が思っているだろうことにも思いを馳せようともせずに。
私は私に失望した。こんなに醜くゆがんだ感情を抱いていることにがっかりした。私は私が嫌いだ。でも嫌いになんてなりたくないのに、私は彼女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、姿を消し、そしてまた水族館のペンギンでも拝みにやってきたかのような顔つきで現れたこの異物をまえにするとどうしても私は私を嫌わずにはいられなくなる。
彼女を異物だなんて捉えるじぶんに反吐がでる。それと同じかそれ以上に、私は彼女のことを遠ざけたいと思っている。
私は醜い。どうしようもなく醜悪で、汚れていて、劣っていて、欠けている。
そしてそんな私をクズへと変貌させる女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、姿を消し、ふたたび天使のような姿で現れたこの異物は、私よりもうつくしく、きれいで、優れており、きっとどんな屈強をも自力で乗り越えられるくらいに強靭で、満たされている。
嫌だ、嫌だ。
私はもう、私であることをやめるか、彼女を私の世界からいっさいがっさい消し去ってしまうほかに、私は私の存在を許してあげることもできないのだ。
しかし、私がいくらこうして内なるがらんどうへと自虐を落とし、こだまさせたところで、がらんどうの空虚さを、その深さを、嫌というほど知るはめになるだけで、元凶たる当の本人、彼女、転校生は痛痒を感じることもなく、ハンバーグセットについてくるポテトみたいに、或いはコンビニで買い物をしたときのレジ袋みたいに、何も言わないうちから、何も言わないのをいいことに、こうしていつまでもまとわりつづける。
気づくと私は、私たちは、夕暮れの公園のベンチで手を繋ぎあっており、いつの間にか彼女はしゃべるのをやめ、私の肩にあたまを預けている。
「ずっとこうしてたいなぁ。帰りたくないね」
私はこのときほど、しゃべれなくてよかったと思ったことはない。
「ずっといっしょにいようね」
彼女はもう、私を手放す気はないのだと思い、そのことに絶望するよりさきに安堵してしまった。私の自意識はもう、とことん、がらんどうに蝕まれてしまったのだ。なんだか地に足がついたような、諦めのついた心地がした。
私は私を客観的に、俯瞰的に、幽体離脱みたいにして眺めている。上から、ときによこから、もしくは下から覗いたりして、ベンチの裏側はこんなに汚いのか、とまるで見てきたように想像しては、本当に汚いの? と気になったりして、そうすると途端に自意識と融合して、元通りで、私はまた諦めの心地のベンチで彼女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、いまなお肥大化させつづける少女にもたれかかれつつ、絡みつかれ、何か精気のようなものを吸われつづけていることを自覚する。
どこまで、いつまでも吸われつづけるものだから、ややもすると、とうなだれる。彼女は私に植え付けたがらんどうこそをご所望で、その苗床として私を選んでいるだけではなかろうか。
まるでエイリアンではないかと思い、まさに異界の者ではないかと腑に落ちる。
彼女からそそがれる熱く不快な何かを、私は口どころか胃が裂けても、好意と呼べそうにはない。好意的には見做せない。
ハリガネムシはけっしてカマキリのしあわせを望んでなどいない。それでも臓腑に巣食って、離れない。
彼女は私から言葉を奪い、がらんどうを植えつけ、肥大化していく私の空虚を吸いとっていく。私は希薄になればなるほど、彼女に身を委ね、破滅していく。
抵抗すべきなのだろう。
拒絶すべきなのだろう。
それができればこんなことにはなっていない。
どうしてだろう。
これほど冷静に現状を把握できていてなお、私は彼女を拒むことができないでいる。
なぜだろう。
私の何がそれを戸惑わせるのか。
私は傷つきたくないだけなのかもしれない。私が拒めば傷つくだろう無垢な侵略者に対して、私は傷をつけたくないのかもしれない。彼女が傷つくことで返ってくる、世にもおそろしい怨念を、因縁を、いまさらふたたび結びたくないだけなのかもしれない。
それはそうだと思うじぶんがいて、それはどうなの、と眉を結ぶ私もいる。
「あ、花火やってる」
いつの間にか辺りはすっかり陽が暮れていた。公園内では親子が闇夜に光の筋を描いている。
「そうだ、そうだよ。花火やってないじゃんね。やろうやろう」
立ちあがると財布の中身を確かめはじめるので、
え? いまから?
すっかり胸中のモヤモヤが霧散して、もう家に帰りたいよ、なんて言って断ろう、と打算的な考えを巡らせる。メディア端末を確認し、母からメッセージが届いていないかと期待したが、イユちゃんこんどいつくるか訊いといて、といった娘の安否を案じる気配のからっきしなテキストが届いているばかりだった。
かろうじて、お腹すいちゃった、と文字を打って、彼女に見せる。
「あ、そっか。そうだね。んー、コンビニじゃ味気ないしなぁ。この辺、ファミレスとかあったっけ」
帰ろうよ、帰ってお母さんのご飯を食べようよ。
もちろん母親との仲が暗雲垂れこめて晴れる気配のさっぱりな彼女にはかように訴える真似はできなかったけれど、うんざりなものはうんざりだ。出口の見えないマラソンを走らされているようで、いったいいつまで走ればいいのか、いつになったら解放されるのか、出口まであともうすこしと思っていたら、ぜんぜんまだ先があったと知って落胆するのに、それでもまだ走りつづけなくてはならない地獄のようで、そっかこれは地獄なのか、なるほどなー、なんて思いはじめて、私はもうもう、泣きたくなってしまった。
つかれちゃった。
私はなんの期待もこめず、ただ思ったことを文字に打った。誰に聞かせるでもなくつぶやくみたいに、溜息を吐くような感覚で、ただ打った。
すると彼女は、こちらが何かを伝えようとしていると勘違いしたようで、なになに、と画面を覗きこんでくる。その躊躇のない仕草からは、もはや私から拒まれることなどつゆほども想定していない傲慢さというか、強引さが感じられた。本来ならムっとすべき場面であったかもしれないが、私は彼女を拒むでもなく、懐に招き入れるように手元の画面を見せるようにした。
息を呑む音がはっきりと聞こえた。
「そっか、そうだよね、疲れちゃったよね」
彼女は早口で、わずかに頬を引くつかせながら、じゃ帰ろっか、とこちらが呆気にとられるほど簡単に前言を撤回した。足先を地面にこすりつけ、円を描きながら、
「どうする、一人で帰れる?」
私を見ずに、私の身を案じるようなことを言った。「送っていってもいい? だめ? やっぱりすこし疲れちゃったかな」
私はとりあえず一刻もはやくこの場を立ち去りたかったので、だいじょうぶだいじょうぶ、の意味合いを籠めながら、全力で、いいですいいです、けっこうです、と手をよこに振った。バイバイ、じゃあね、とそのまま駆けだしたいくらいだ。
そこからいかにして彼女と別れ、家まで帰ってきたのかを私はあまりよく憶えてはいない。家でシャワーを浴びていると、ふと、あれいま私家にいるな、と実感がふつふつと湧いてきて、きょう彼女と過ごした時間を断片的に思い返しながら、それはどちらかと言えば、かってに流れていく走馬灯じみていたけれど、この夏休みのことを思いだしている。
部屋のベッドに頭から潜りこむようにすると、なんだかじぶんの匂いにほっとした。私はきゅっと膝を抱え、ちいさくなる。
夏休みが終わる。
来週から学校がはじまる。
目を閉じて、窓の向こうに浮かぶ月を思い描く。きょうは満月だったらいいな。何ともなく思い、けれどそれを確かめようとは思えず、身体のほうはぬか底のナスみたいに、寝返り一つ打ちたくないのだと訴えているかのようだった。
土日に、家へ誰かが訪ねてくることはなかった。母はたびたび、イユちゃんはいつくるの、とぼやいた。料理サイトを眺めては、イユちゃんはこれ好きかな、これ食べるかな、と私に同意を求めるようにつぶやき、楽しげにしている。私では母にそんな顔をさせてあげられないから、このときばかりは私も、いささか素直に、母のぼやきに付き合った。もちろん、こんど会ったときに誘ってみるね、なんて約束は意地でもとりつけなかったけれど。要するに、しゃべれないじぶんの気質を最大限に活かして、なあなあで母のぼやきをいなしていただけだ。
本来ならば嫉妬の一つでも抱くべき状況なのかもしれないが、私は母の態度にモヤモヤするどころか、このひとはいともたやすく、人心を掌握されてしまうのだなぁ、と岡目八目ばりに、このひとだいじょうぶかな、の不安に駆られるのだった。よく生きてこられたなぁ、と。
学校へはいつもよりはやく向かった。ひょっとしたらあのコが家まで迎えにくるかもしれないと案じての早出だったけれど、学校に着いてみると彼女はすでに教室にいて、私はだからくるっと反転して、チャイムが鳴るギリギリまで花壇の花を眺めていた。
教室に入ると、先生はまだいなかった。あのコの周りにはほかの生徒たちが輪っかになって群がっている。花に、わーっとなっているミツバチを連想する。
なんの話題かは分からない。ものすごく盛りあがっているのだけは、ときおりあがる笑い声と、合戦さながらに飛び交う質問の嵐がハッキリと物語っていた。
自意識過剰かな。
私は私の小心翼々具合と幼稚な逃避が恥ずかしくなった。
この日、彼女、転校生こと私のがらんどうの生みの親は、クラスのみならず、学年全体の話題の的となった。みな内心、転校生と聞くと、どこか非日常のはじまりを期待するようで、そのじつやってきた転校生が、アイドル顔負けの美貌と親しみやすさを兼ね備えていると見るや否や、こぞって動物園のパンダでも物見にやってくるように、休み時間になるたびに、入れ代わり立ち代わり、廊下に人だかりを絶やさずにいた。
肩すかしだなぁ。
憂鬱の二文字が脳裡に浮かんでくるくらいには気を張っていた夏休み明け初日が、蓋を開けてみれば、一言も彼女と言葉を交わすことなく終わってしまった。
なんだかバスケットボールで、ゴール下で、ヘイヘイパスパス、と大声を張り上げたままなんの活躍も見せずに、なんならいちどもボールに触ることなく試合終了してしまったような空回り感がある。やはりというべきか、気恥ずかしい。
初日だもんな。
気を抜くにははやすぎる。
思いながら、嵐の前のしずけさでなければよいけれど、と学校生活の幕開けに波乱を感じずにはいられない。
翌日、翌々日、週末、土日。
あっという間に一週間が過ぎてみれば、どうであろう。けっきょく未だに学校で彼女につきまとわれるといった事態に直面することはなく、夏休みのような窮屈な思いをすることもなく、不安になるほどの平穏な日々が過ぎた。
彼女のほうからいくどか話しかけにこようとした素振りはあった。しかしことごとく邪魔が入り、これは私からすると渡りに船ではあるのだが、不発に終わり、彼女からしゃべりかけられることすらない日々で、ひょっとしたらこのままつつがなく、以前のような学校生活を送れるのではないか、とすら淡い希望を抱くまでに、私は転校生、かつて私にがらんどうを植えつけた張本人と距離を置いていられた。
そも、私にだって友人と呼べるクラスメイトはいるもので、もちろんほかのクラスにも仲の良い同級生、言い換えれば私が言葉を発さずとも、何不自由なく意思疎通の可能な、可能となるように心を配ってくれる学友たちがいる。
転校生につきまとわれて憂鬱になる理由の一つがそれだった。学友たちと過ごす時間がなくなるのは、私のこれまでの、この五年間の、がらんどうを植えつけられ、持て余し、けっきょくは慣れてしまった私の怠惰な、けれど懸命な日々を、丸ごとすっぱり捨ててしまうことと同義だった。
学友たちは私のがらんどうを埋めるだけの大きな、大きな、ふわふわを湛えている。私は彼女たちの輪のなかにいるあいだだけ、がらんどうを忘れ、質量を伴った肉体を感じられた。
杞憂だったかもしれない。
夏休みを遠い日のできごとのように思いはじめた三週間目にして、私は転校生との確執が単なる思い過ごしであったかもしれない可能性を考えはじめた。
たしかに思えば、五年も前、それこそ小学生のころに別れたきりの相手、しかも喧嘩別れしてほとほと絶縁していた相手と再会して、変に気分が高揚したとして不自然ではない。
押入れを掃除していたらむかし遊んでいたヌイグルミがでてきて、懐かしくてしばしのあいだ部屋に飾ったけれど、やっぱりかび臭いしどことなく不気味だからそのままゴミ箱にポイしてしまいたくなる気持ちは理解できる。
そうであったなら、さすがになんというか、あまり素直によろこべはしない。かってに他人にがらんどうを植えつけておいて、貴重な夏休みをじぶん色に染めあげておいて、終いにはやっぱりちょっとなかったことにしたいかも、なんていまさら他人のフリをしたがるなんて都合がよすぎる。
かといって私は彼女とどうなりたいのかと言えば、どうにもなりたくはないし、都合がよすぎるというのならば、まさにこうして距離の置けたいま、絶好の機会と見做して、よすぎる都合を受け入れてしまうほうが得策と言えば得策だ。
教室での座席も離れているため、授業で関わることはない。休み時間は未だに彼女は動物園のパンダのごとく人々に囲まれて、いよいよかぐや姫がごとく様相を漂わせはじめている。女王様ではなく姫なのは、周囲の学友たちを邪険にするでもなく、しかしそこはかとなく迷惑がっているのが、端から眺めていると判るからだ。
いいや、私だからこそ見抜いている彼女の本懐であるかも分からない。
見抜いている?
そこまで考えてから、おや、と眉間にちからがこもる。
彼女は周囲の人だかりを嫌がっていると私は考えているが、なぜそう考えるのかと言えば、彼女にはほかにやりたいことがあるからで、つまりそれは何なのかと想像すると、私はじぶんの顔が熱くなるのを止められないのだった。
ひょっとして、嫉妬してる?
まったくこれっぽっちもモヤモヤなどしていないつもりで、そのじつこうして彼女のクラスでの立ち位置や、心中をおもんぱかっては、あれやこれやと思考を費やしている。
やめやめ。
頬を両手で、ぱんぱん、としていると、
「何してん、ほっぺた腫れちゃうぞ」
アンパンマンやぞ。
言いながら隣のクラスのユウナが寄ってきた。中学生時代からの顔馴染みで、ときおりこうしてふらりとやってきては、さいきん読んだマンガの感想をいっぽうてきに話していく。私はもっぱら聞き役だが、この時間が嫌いじゃない。感性が似ているのか、ユウナのすすめるマンガはことごとく私の琴線を揺るがせる。
またぞろ、休み時間いっぱいいっぽうてきにしゃべり倒してユウナは、去っていった。どうやらこんどは一流の殺し屋を育てるゲームにはまっているらしい。メディアミックスもされていて、ようやく漫画が単行本として発売されたようだ。私がゲームをしないのを知っているからこれまで話さずにいたようで、堰を切ったようなと言えば端的で、鬱憤を晴らすがごとくの舌鋒で以って、しゃべり倒していった。倒された私のもとにはユウナの置いていった漫画本があり、封が切られていないところを見ると、彼女はもう電子書籍で読み終わっているのだと判る。
わざわざこうして紙の本で貸してくれるのは彼女の謎の拘りらしく、真新しい漫画本の水揚げ作業は半ば私の役割と化して久しいと呼べる。
遠慮するほうが失礼だと彼女の思いを汲めるくらいには彼女との付き合いは短くなく、かといってこうして漫画以外での話をするようなこともなく、また、学校のそとで遊んだことはいちどもない。
だから、これは本当に単なる日常の風景、生活のひとコマでしかないはずだったが、そう捉えない人物がそこにいた。
「ねぇ、それなに」
振り向くと、彼女、転校生、私にがらんどうを植えつけた張本人であるところの琉紗那イユが立っていた。呼吸が荒いのは、走ってきたからなのか、髪も乱れている。乱れてなおうつくしい。水のようだ。
こちらの視線に気づいたようで、手櫛で直すと、
「ねぇ、どうしたのそれ」
彼女はもういちど私の手にしている漫画本に視線を当てた。質問の意図がよく解からなくて、しばし固まる。夏休みが明けてから初めて投げかけられた言葉であることに遅れて気づき、さらに言葉に詰まる。元々しゃべらない気質なのだから、ことさら焦る必要もないのだけれど、どうしても思考のほうは何か答えなくては、と言葉を探す。
「誰から借りたの。休み時間にきてたの誰、どこのクラスのコ。なんでそれ借りたの。好きなの。新品みたいだけどなんで。もしかしてプレゼントか何か。誕生日まだだったよね」
矢継ぎ早にぶつけられ、私はたじたじだ。たぬきが地蔵さまに化けてコッチーンと左右に揺れる映像が頭のなかに流れる。
つぎは移動教室だ。みなすでに教室から脱していて、ちょうどゴングが鳴るみたいに、今、チャイムが鳴った。
これさいわい、とばかりに、はやく行かないと怒られちゃうよ、と身振り手振りで、遅刻の旨を告げてみせるも、彼女は暖簾に腕押しを地で描き、
「ねぇどうしてあたしにはそういうこと教えてくれないの」
眉間にしわを浮かべる。そのしわはどこか三途の川を彷彿とさせ、もちろん私は三途の川がどのようなカタチをしているのかなんて知らないのだけれども、何か押してはならぬスイッチを押してしまったような、インストールしてはならぬアプリをインストールしてしまったような、妙な緊張感に襲われた。その緊張感は、がうがう、とこちらに噛みつかんとするライオンの姿かたちをとっており、それでもどこかぬいぐるみを思わせる愛嬌もあり、私はそれをえいやと蹴飛ばす真似はおろか、拒絶することもできなかった。
「なんかさ、学校はじまってから避けられてるみたいだったし、ずっと待ってたのに、ぜんぜん話かけてくれなかったし」
そりゃ私はしゃべりませんからね。
言えるものなら言い返したかったが、もちろん彼女が訴えているのはそういうことではないことくらい、いくら私とて百も承知だ。
「学校じゃ恥ずかしいのかなって、あんまりベタベタされたくないのかなって、そう思ってたけど、なんかそういう感じじゃないんだね」
だね、と言われても、はいそうですが、としか答えようがない。学校にかぎらず、どこでだってベタベタされたくはない。
そもそも、と私は言いたかった。そっちこそ私なんかと仲が良いと思われたくなくて、避けていたのではないの。
お腹の底のほうで煮えたつグツグツを自覚し、はっとしてから、なぜ私がこんなことで苛立たなければならぬのか、とさらにグツグツの泡が大きく弾ける。まるでがらんどうという大鍋で、鬱憤や不満のシチューを煮ているかのようだ。
「なんでそんな怖い顔するの。怒ってるのはあたしのほうなのに」
彼女は手に持っていた教科書を机に叩きつける。大きな音が鳴り、いっしゅん学校全体が静寂に包まれたかのような錯覚に陥った。
間もなく、となりのクラスで授業をしていたらしい教員がひょっこり顔を覗かせ、何やってんの、と独特の訛りのある発音で、授業もうはじまってるよ、とこれは叱るというよりも、宥めるように言った。
私は微笑んでみせることで、なんでもないんですすみません、と暗に示し、彼女も彼女で、転校してきたばかりで、と言い訳がましく、移動教室の場所がわかんなくて、と続けた。もちろん彼女が転校してきてから幾度も移動教室はあったわけで、そんなのは教員のほうでも重々承知の助であったから、
「いいからはやく移動しちゃいなさい」
軽くあしらわれ、いちど引っ込んだ顔がもういちどひょっこり覗くと、ついでのように、
「喧嘩もほどほどにね。あ、もしかしてイジメのほうだった?」
などとかったるそうに言われてしまうと、まるで私たちのあいだにあったモヤモヤとグツグツは、オコチャマのおままごとのように感じられてしまって、端的に恥ずかしくなり、私は何度も素早くうなずいてから彼女、転校生、私にがらんどうを植えつけ、恥辱なる念まで上塗りしてくれた琉紗那イユの腕をとり、その場をあとにした。
廊下でいちど振りかえると、私に腕を引かれるがままの彼女はなぜか、うれしそうに顔をほころばせている。ゾっとしながらも、ふしぎとさきほまでグツグツと煮えていたがらんどうは鳴りをひそめ、ただいつものような空虚な闇を身体の奥底にひっそりと浮かべている。
***
ひと月もすると、休み時間に私たちのクラスにやってくる賑やかし、つまり転校生を拝みにくる集団は見かけなくなっていた。琉紗那イユの取り巻きたちも毎度お馴染みの顔ぶれに淘汰されている。顔馴染みというよりも、残った数人が狂信者となって、クラス内での立ち位置をより明確にすべく――それは琉紗那イユの立ち位置なのか、それともそれを利用してじぶんたちの立ち位置を高めんとする虎の威を借る狐なのかは定かではなかったものの――なにかと琉紗那イユの話題を振っては、教室内に飛び交う言葉の矢印を、一方向に整え、いつまでも転校生、才色兼備のアイドルの後光を煌びやかに保ちつづけていた。
あの日以降、彼女は私に遠慮なく話かけてくるようになった。あべこべに私は彼女以外との会話、意思疎通の場を失いかけている。
「ごめんね、きょうは委員会の手助け頼まれちゃって、いっしょに帰れないみたいで」
いいよいいよ、行ってきなよ。
私はあいまいに笑って、彼女を送りだす。
申しわけなさそうな、ともすれば雨に濡れた子犬にも見える彼女の背を見送りながら、久方ぶりの開放感を味わっていた。
「約束なんてしてないのになぁ、みたいな顔しとるねチミ」
びっくりして飛び退くと、箒の先端にあごを載せた格好で、ユウナがもごもごと口を動かしている。いつ見てもオカッパ頭の年中むすっとした顔つきをしているこの学友を目にすると、毎日のように髪型を変え、香りを変え、なんだったら下着のコーディネートまで変えてくる琉紗那イユの目の回りそうな後光の輝きを打ち消してくれる居心地のよさを覚える。お寺の鐘でボーンと煩悩を一蹴してくれるような頼もしさすら感じられるからふしぎだ。
「なんであんなんに付きまとわれとんの。疲れない?」
なんと応えたものか。私は眉を結び、それはむつかしい質問だ、と意思表示する。しゃべれない私にとって、イエスノーで答え切れない詰問には、沈黙で応じるにかぎる。
「なんだその顔。さてはチミ、うちが隣のクラスの同胞にこうしてわざわざ会いにくるのは、へそまがりのこんこんちきな性格のせいで同じクラスにしゃべる相手がいないからだ、なんて失礼なことを考えてはいないだろうな」
ぶんぶんと顔をよこに振る。
思ってない思ってない、とんでもない、の意思表示だ。
「でも間違ってるとも思ってないわけだろ」
そりゃあまあ、とこれは唇を尖らせ、目を逸らしておく。
「マンガの新刊、靴箱んなかに入れといたから」
やった、ありがとう、と手で拝んでから、なんでわざわざ靴箱に? 私の顔色を窺うことが特技というこの可哀そうな学友は、相も変わらず箒にもたれかかったままで、
「どっかのアイドルさまが妬いちゃうだろ。んでうちの宝物が焼かれちゃうだろ、そんなん適わんでキミ」
やいちゃってやかれちゃう、がうまく頭のなかで変換できずに手こずっていると、
「ホントなんであんなんに付きまとわれとんの。疲れない?」
ユウナは珍しく鼻のあたまにしわを浮かべた。子豚の姿が脳裡に浮かぶ。ぴぐぴぐかわいい。
彼女の掃除を手伝ったあとで、靴箱から漫画本を回収する。下校はせずに、また教室に戻り、そこでユウナとひとしきり漫画談議に花を咲かせた。
放課後の教室はがらんとしている。窓の向こうからは運動部の、わいわい、がやがや、が遠くかすかに届く。長閑だ。
語るべきことを語り終えたといった満足げな様で、しかし表情は相も変わらずムスっとしたまま、ユウナは、じゃ読んだら感想よろ、と言い残し、颯爽と一人で帰っていった。帰る方角が違うとはいえ、校門までいっしょに行けばいいのにと思うのだけれども、彼女のそういうマイペースな性格は嫌いではなかった。
帰ってもとくにすることはなく、ユウナから借りた漫画本はアコーディオンさながらのブロックと化しており、持ち帰るのには重すぎるので、ここで読んでしまおう、と姑息な考えを巡らせる。
改めて、
こんなによくぞ運んできてくれたものだね。
ユウナの布教精神に敬意を払う。いつもありがとうございます。
念じながら、ひとたび本を開くと、虚構の世界へと引きずりこまれる。物語の吸引力ときたら、と読み終わってからいつも思う。
ふぅ、と息を吐く。本を閉じ背伸びをすると、窓から差しこむ夕陽に目がくらんだ。教室の床に伸びる影は、ジャングルジムだ。
運動部の声がまだ聞こえている。完全な静寂でない静けさだ。そこはかとない微睡を引き連れる。それはどこか安堵にも似た心地よさを伴っている。
たぶん。
私は目を閉じる。
しあわせとは、こうしたふいに訪れる、暗がりと微睡の狭間そのものだ。
廊下に反響する足音がある。しだいに近づいてくるそれがやがて教室の戸を開けたところで、振りかえってみせると、そこには、びくんと身体をちいさく弾ませ、固まる転校生、もはやこの学年のアイドルとして不動の地位を獲得した琉紗那イユが立っていた。
彼女は挙動不審になりながら、言葉をどもらせつつ、どうしたの、と言った。その場から動こうともせず、なんだかモジモジしながら、
「なんでまだいるの、帰ったんじゃなかったの」
などとカバンを盛んに右に左に持ち替える。
漫画本を掲げ、これ読んでたんだよ、と示す。それから、もう帰るところだよ、とカバンを手にして立ちあがる。
教室後方の扉を彼女が塞いでいたので、教壇に近いほうの扉へ歩いていくと、
「待って待って、いっしょに帰ろうよ」
机に駆けより、荷物をカバンに詰めこむと、彼女は駆け足で私のとなりに並んだ。私はすっかり廊下にでていて、ほとんど歩きだしていたから、遅れまいと追いかけてくる彼女の必死さがすこしおかしかった。
私にがらんどうを植えつけた彼女が私にはおそろしく、そして疎んじていたはずなのに、なんだかいまだけ、彼女が生まれたてのカモかなにかのヒナのように思え、やはり胸の奥がくすぐったくなるのだった。
住んでいる区画がいっしょだから、ほとんど帰り道は同じだ。きのうまでは彼女のほうでいっぽうてきに話していたのに、きょうはおとなしく、その凪のようなおだやかさが不気味でもあり、嵐のまえのなんとやらでなければよいけれど、とイジワルな気持ちで考える。
「さっきのマンガ。おもしろいの? どんな話?」
メディア端末を操作し、少年漫画だよ、とまずは伝える。
読んでみる? 貸そっか?
なぜそのような提案をしたのかじぶんでも謎だったが、彼女は目を輝かせ、うんうんと食いついた。
私はそこでおぞましいことに、彼女のあごを撫でてあげたい衝動に駆られたのだ。
ひょっとしたらこれは優越感かもしれない。
なぜ私はそんなものを抱いているのか、とあたまのなかで腕を組み、そうしてしばし、内なるじぶんとにらめっこをしていると、沈黙を嫌ったのか、琉紗那イユは、
「又貸しはダメだよ」と言った。「あのコから借りたマンガをそのまま横流しとか、そういうのは、なんか危ないからよくないと思う」
危ない? なにが?
思いつつも、たしかにユウナに許可を得ようとしても渋い顔をされそうだ。ただでさえ仏頂面なのに。
私も持ってるからだいじょうぶだよ。
まずはそう文字を並べる。ホントは持っていなかったけれど、おもしろい本であったのは間違いなく、じぶんでも購入しようと思っていたので、そう文字を並べた。
「そっか、ならいいんだけど」
両足を揃え、ぴょんぴょん、と飛び跳ねる彼女がちいさなアマガエルのようで、雨がそんなに待ち遠しかったか、とほっこりしそうなところで、はたと我に返る。
ひょっとしたら。
頬が熱くなるのを感じる。私は学年のアイドルから慕われていると思いあがって、そのことにまんざらでもなく満足感を覚えてやいやしまいか。
嫌だ、嫌だ。
私は内心焦った。
ただでさえ人並み以下の人間の器しか持ち合わせていないのに、これ以上、人として落ちたくない。
ちょいと振り向いてみれば、彼女はどこか浮かない顔つきだ。
どうしたの、と訊ければよいのに、声をだせない私はそのまま歩く速度を落としてよこに並び、彼女の顔をこっそり覗きこむようにする。
私の影がないことに気づいたのか、そこで彼女は顔をあげ、あれっという顔をしてから、真横の私の存在に気づいた様子だ。
目を見開き、仰け反った。びっくりしたぁ、とかわいい歯を覗かせ、えへへ、と下唇をはむ。
あどけない。
そう感じた。
無防備なのだ。いまさらのように気づく。彼女は私のまえにいるときだけ、分厚い皮を脱ぎ去っている。学校やおとなたちに見せる着ぐるみではなく、かつて私に「絶対に許さない」とがらんどうを植えつけたときのように、彼女は彼女自身に巣食う感情のまま、機微のままを、隠すことなく、余すことなく、私にさらけ出している。
壊れているのか私は、そんな彼女の一挙一動、一言一句を漏らさず観察し、受け取っている。あたかも彼女に植えつけられたがらんどうが、彼女を受け入れるための器であるかのように。
深く考えこんでしまったのか、気づくと家のまえにいた。おかしなことにそばにはまだイユの姿があり、彼女は状況を呑みこめぬ私の代わりにインターホンを押した。
思わず、え、と声がでそうになった。
インターホンの向こうから母の声が、はいはーい、と聞こえ、あたしでーす、と快活に応じるイユの、まるで親戚の家に遊びにきた姪っ子のような馴れ馴れしさに、あれ、ここって私の家だよね、といっしゅんじぶんの身分を忘れそうになる。
玄関扉が勢いよく開く。裸足のままの母が、いらっしゃーい、と現れる。見たことのない笑みを引っさげている。
きょうはどうしたの、晩ご飯食べてく?
母は私を一顧だにせず、イユの腕をとって家のなかに招き入れる。私はその場にぽつんと取り残されたが、イユが腕を伸ばして、私の手を握った。
彼女は私の名を呼び、
「相談があってきちゃいました。急にお邪魔してごめんなさい、すぐに帰りますので」
おとなびたあいさつで断ると、母はとんでもないというように手を顔のまえで振り、
「どうせあしたお休みなんだから泊まってっちゃったら」
ね、あなたもそう思うでしょ。
まるで、うんと言え、と脅迫するかのように母は私を見た。私はあいまいに笑い、彼女たちを置いてひと足先に家に入る。
なんだか、何に腹を立てればよいのかが分からなくて、却って清々しい気持ちだ。
自室にあがる。部屋は二階にあって、黙ってあがってきてしまったから母から何か小言が飛んでくるかもと構えていたけれど、母は私よりも目のまえのお人形さんに夢中みたいだから、私はしばらく床のずっと奥のほう、まるで地獄の底から響いて聞こえるワルツを耳にするみたいに母の笑い声を、その残響を足の裏で聞いていた。
何をしても集中できない。いっそ寝てやろうと思い、そこでじぶんがまだ着替えもしていなかったことに気づき、いそいそと制服を脱いだ。
ちょうど下着姿になっているときに扉のノックする音が聞こえ、よもや開けやしないだろうな、と身体の動きが止まっている合間に、扉はちいさく隙間を開けた。
「ママさんがお菓子くれたよ、いっしょに食べよ」
イユがお盆を持って現れる。ジュースとコップとパンケーキが載っている。背中を丸め、金庫に忍び込むようなかっこうで部屋に侵入してきたイユはそこで、私の姿を目に留め、私の真似をするみたいに身体の動きを止めた。
私は何も言えず、イユも言葉を発しない。
目だけは私に釘付けだ。せめて顔を逸らすなり、何なりしたらどうなのか、と怒りがこみあげる。
しゃべれる人間ならこういうときは、出てって、と一言するどく言い放つ場面だろう。
思いながら、私はそのままいそいそと着替えを再開し、それからキッと睨みつけながら、私の着替えを余すことなく見届けたイユからお盆を受け取り、そのまま彼女を部屋のそとに押しやった。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
イユは冗談みたいに扉をドンドンやった。「わる気はなかったの、ホントに、ちょっと動揺しちゃっただけで、わる気はなかったの」
どうしたのー、と下の階から母の声が聞こえた。
あー、めんどうだ。
私は扉を開き、イユの腕をとって、引き入れる。あごをしゃくって階段の下を示し、母になんでもないと言って、と指示する。
うまく伝わらなかったのか彼女は、
「すみません、なんか着替え中に入っちゃったみたいで」
「そんなことで怒んないのー」
なぜか母は私を叱った。扉を閉め、イユから手を離し、ベッドに勢いよく座る。
癇癪を起こしそうだった。人間の怒りは六秒以上継続しない、という話を思いだし、ゆっくりと、一、二、三、と数えていく。
たしかに六をすぎたあたりで、落ち着きを取り戻してきた。物に当たり散らさなくてよかった、と思い、しゃべれないじぶんの気質にも、よかった、と思った。きっとしゃべれていたらひどいことを口走っていた。そしたらきっと未だに扉のまえでもじもじしているイユをこっぴどく傷つけていたはずだ。
ひょっとしたら怒らせてしまって、私のほうで何かしら傷を負っていたかもしれない。
それこそ五年前のように。
私はそこで、じぶんの内側が何かザラザラしていることに気づく。
がらんどう、なくないか?
かつてイユから植え付けられた底なしの虚無が消えかけていることに思い至る。
完全に失せてはいない。否、何かゴツゴツした岩肌じみた感触の合間を縫って、がらんどうはそこはかとない虚無を伴い、空いている。穴というより隙間であり、闇というより影だった。
息を吐く。喉の奥がきゅっと狭くなるような感覚があり、掠れた「あ」がちいさく、私にだけ聞こえた。
声、でちゃうかも。
しゃべれてしまうかもしれない予感が、私をひどく戸惑わせた。
そうだ、私はずっとしゃべりたくなかったのだ。
そのことに気づき、私は私自身の怠慢を知った。
「どうしたの、まだ怒ってる?」
イユが私のまえに立った。私はベッドに座ったままだ。彼女を見上げる。彼女の骨を思わせないなめらかな肢体を、腰を経由しながらゆっくりと下のほうへ、舐めるように視線を巡らせる。彼女の靴下は炭のように黒い。反して肌は雪原じみている。
何もかも完璧かよ。
無駄にイライラを募らせる。
私はかつてたしかに、目のまえの完璧な少女に傷つけられた。底なしのがらんどうを植えつけられ、声を失くし、いまこうしてふたたび相見えた彼女を目のまえにしている。
怒ってないよ。
私は私に言い聞かせるように、喉の奥に風を通した。
怒ってないよ。
怒る理由なんてないもの。
どうも思わない相手から何をされたところで、何を言われても、私は傷つきもせず、ゆえに怒りもしない。
だから私はどうしてもそれを言わなければならない衝動に駆られ、できそこないの口笛のように、怒ってないよ、と口にした。
舌のうえで転がったその声ともつかない掠れた音は、それでも目のまえの完璧な女の顔面を歪ませるには充分な呪文と化したようだ。
「しゃ、しゃ、しゃ」彼女のほうこそ言葉を失くしたように繰り返す。唾液を呑むようにしてから、しゃべれるの、と彼女は喉に詰まらせた飴玉さながらに吐きだした。
二の句は継げなかった。むかし中学生時代に卒業式の打ち上げでいったカラオケで、喉を枯らしていた同級生がいたけれど、あれと同じように私の声帯もまるでヤスリがけをしたようで、息がどこにも引っかかることなく、漏れるばかりだ。五年という歳月は私からしゃべる機能を奪っていた。
無理しなくていいよ。イユは言った。無理をしてしゃべらなくていいよ、とわざわざ言い換え、じんわりと目元に涙を湛えた。そのあまりのなみなみ具合に、表面張力、と私は意味もなく思い、あー垂れちゃう垂れちゃう、とふしぎともったいなく感じた。
私の身体は、彼女の目元に浮かぶシズクに釘付けになっている。棚から落ちる牡丹餅を手で受け止めるように目を離せない。
だから彼女が視界から、ふっと消え、つぎの瞬間には私の身体をなにか温かく、やわらかいものが包みこんでいると気づいたときには、嗅ぎ慣れたよい香り、それはどこか甘く、せつない匂いが私の身体の内側いっぱいに広がりつつあった。
よかったー、とイユは言った。鼓膜をくすぐる声はしかし、まるで歓喜とは程遠く、痛切な響きを伴っていた。
しきりに細かく揺れる彼女の肩越しに、鼻をすする音が聞こえている。こんなに間近に見つめても、彼女の髪の毛は隙間なく並べられたパスタのようにオウトツがない。
どうして泣いてるの?
こちらの疑問を見透かしたようにイユは、
「あたしのせいなんじゃないかって」
高熱にうなされるように、むせた。「ずっと思ってた。こわかった。ずっとこわかった。せっかく会えたのになんか素っ気なくて、そりゃ怒るよな、仕方ないなって、でもあたしのほうからそれで距離をおくのだけは嫌だったから、せめてきちんと突き放されるまではがまんしようって、がんばろうって、あたし」
うわーん。
虚構の世界でしかお目にかかれないオノマトペを彼女はしごくしぜんなさまで使いこなす。泣きじゃくる幼児だってもうすこし人間らしく泣きそうなものだ。
赤子であればもっと濁った、あーあーあー、を叫ぶのだろう。それに引き替え、いま私の身体にしがみつき、絡んで離れない女の子は、赤子と呼ぶよりも空腹に耐えかねて母親を呼ぶ動物の赤ちゃんのように、しきりに、うわーん、うわーん、と声をあげては、ひっくひっく、と身体をちいさく、それでいてちからづよく跳ねさせる。
どうどう。
背中を撫でてやりながら、生まれて初めて「あやす」なる行為をしているじぶんを俯瞰し、なんだこれ、と盛大なオママゴトをしている気分に陥る。舞台のうえから満員のマネキンに向け、おーロミオ、あなたはなぜロミオなの、と手を伸ばしたい気分だ。
おーイユよ、あなたはなぜ泣いているの!
泣きたいのはこちらのほうなのにと思ってみるものの、本当は何も哀しくはない。
なんだか首筋が湿っぽい。せめて涙であってほしい。しきりに鼻をすする音は、ジュルジュル、と途絶えることがない。
どうどう。
私はなおも彼女の背中をさすりつづける。
しばらくそうしていた。
彼女の鼓動、嗚咽、息遣い。
私の呼吸、デジタル時計の針の音、窓のそとから聞こえる鳥の声、遠くのサイレン、車の道路を舐める音。
風の音はそれ単体ではなく、窓を叩いたり、葉を揺らすことで聞こえるのだと、なにともなしに考える。
階段をあがってくる足音を耳にし、イユがはっと我に返ったように私から離れた。私は首筋をゆびで拭い、僅かなぬめり気に、ありゃりゃ、と思う。イユが怯えたように、ごめん、とつぶやく。
戸をノックする音が聞こえ、返事をする前に母が顔を覗かせる。
「イユちゃん、きょう夕飯いっしょに食べてくでしょ」
母はぎょっとして固まった。「どうしたの」
血相を変えた母がイユを覗きこむようにし、事情を聞きたそうに私を見る。その目に、私を非難する色は窺えず、どうあっても私に非がないことを確信している姿に、私は深く息を漏らす。
いじけていた私がばかみたいだ。
なんでもないから、のジェスチャーをし、母の背中を押す。私に任せて、とさらに身振りで伝え、部屋のそとに押しやった。
「ホントにだいじょうぶ?」これはイユへの言葉だろう。
「すみません、目にゴミが入っちゃって」
イユは言うが、ぐしゃぐしゃの顔はどう見てもそれ以上の感情の乱れを感じさせる。目の回りの滲んだ黒を見て、化粧をしていたのか、と気づけたほどだ。
「やっぱり心配」
母が足を踏ん張ってふたたびの侵入を試みてくるものだから、私はたまらず、ちゃぶ台のうえの手つかずのジュースとパンケーキの載った皿をお盆に載せ、
「いいから」
母にそれを押しつける。「下で待ってて」
でも、と食い下がろうとした母だったが、そこでふだんと異なる娘の変化に気づいた様子で、
「わお」
目を丸くして、固まった。私はバイバイと手を振って、戸を閉める。
戸に鍵はついていないが、母はそれ以上、踏みこんではこなかった。事情をなんとなしに呑みこめたのだろう。ひょっとしたら娘たちに見られたくない表情を浮かべている可能性すらある。
こんなことで泣いてくれるなよ。
思いながら、こんなことで泣かせてしまう親不孝者だったのだな、とかってに母を泣き虫認定しながら、新しいタオルを手に取り、イユに渡す。顔洗ってきなよ、のジェスチャーをする。二階にも洗面台はあり、一階におりた母とは顔を合わせずに済むはずだ。
イユはしぶったが、私が部屋の隅に立てかけてあった姿見にゆびを向けると、イユはそこに映るじぶんの顔を見て、ぱちくりと瞬きをした。すると即座に顔を伏せ、こちらの手からタオルを奪い、小声で礼を述べてから、私の顔をいっさい見ることなく部屋をでていく。尻尾を巻いたネズミみたいな姿に、
かわいい。
初めて彼女のことを純粋に愛くるしく思った。
この日、彼女は私の部屋に泊まった。夕飯はチラシ寿司だった。
顔を洗ってしまうと、彼女は化粧をしなおすことなく、すっぴんでいつづけた。母は気づいているのかいないのか、そのことには触れず、私は私で、彼女が生身の人間にちかづいたような親近感を覚えた。化粧は思っていた以上に人への印象を変えてしまう。
彼女の場合は美しく着飾るというよりもどちらかと言えば、素のやわらかい部分を隠す鎧にしていた節がある。こんなにもやわらかな雰囲気をまとっていたのだと私に気づかせたほどだ。
私はイユがお風呂に入っているあいだに、母と言葉を交わす。イユは化粧してもしなくてもかわいいね、うらやましいね。ふだんどおり、メディア端末を、ぱぱぽ、と打つ。
母は、あら、と唇を尖らせるが、私が喉をゆび差してみせると、まあ最初はね、と意図を汲んでくれた。退化した声帯はすぐに潤いを失くす。
「せっかくだし、いろいろ教えてもらいなさいな。イユちゃんとあなた、なんだか姉妹みたいよ」
私が姉?
文字を打つと、
「イユちゃんに何か一つでも教えられることがあるの」
真顔で訊き返され、私はイヤホンで耳を塞いだ。
夜、布団をふたつ敷いて、イユといっしょに寝そべりながら、ネットの動画を教え合った。私はかわいい動物の愛らしい仕草やおちゃめな挙動を集めた動画を提供し、イユからは化粧やファッションのチャンネルをご教授いただいた。
そのうち眠くなって、気づくとイユの寝息が聞こえた。明かりは消していて、私は、うすぼんやりとした暗がりの向こうの天井を眺める。
まるでがらんどうのなかにいるようだ。私のなかにあったがらんどうが、いまはこうして私の外側にある。
私のとなりにイユがいる。
がらんどうの生みの親、そのじつ私こそ彼女に拭えぬしこりを植えつけていたのかもしれない。
あー、あー、あー。
私はちいさく声をだす。
あ、い、う、え、お。
なんだか想像していたよりもずっと掠れていて、ずっと低い声だった。
女子も声変りするのかな。
そんなことを考えながら、学校でしゃべったら、クラスのみんなはどんな反応をするだろうか。思い描いてみるものの、きっとたいした話題にもならず、すんなり馴染んでしまいそうだ。なんだしゃべれたんだ、と。
それとも、このだみ声に触れていいのかどうかといらぬ気遣いをさせてしまうかもしれない。それは嫌だなぁ。
思うものの、やっぱり茶化されるのがいちばん怖くもあり、しかしそんな真似をするやつはクラスに一人もいないのだよなぁ。
おとなびた学友たちに私は、前以って感謝しておくのだった。
目をつむる。
おやすみなさい。
暗がりに漂う甘く、やさしい香りに、私はそっとつぶやくようにする。
***
翌週。家をでるとイユが待っていた。家の中からも見えていたので、アニメキャラみたいにパンを口に咥えたまま玄関をでた。
パンをひと口齧ってから私は、おはよう、と言った。ついでのように、こういうときは連絡してよ、と言う。寝坊したらどうするつもりだったのか、とつづけようとしたけれどうまく言葉がでてこなくて、メディア端末で文字を打った。
「寝坊してたらふつうに叩き起こしにいってたよ」
歩きだしたイユのあとを追う。「それにママさんには連絡しといたし」
なるほど。
母が私に持たせたなぞのサンドウィッチも、おそらく昼ごはんのための弁当ではない。案の定、イユがちらちらと私の手を覗いてくるので、はい、とサンドウィッチの入った紙袋を顔のまえに掲げる。
「わー、ありがとう」
さっそく取りだし、おいしそういただきまーす、と頬張りだすので、私もいっしょになってサンドウィッチの残りをハムハムした。
齧っても具がはみださない。ジューシーさが損なわれない。母のサンドウィッチは娘の贔屓目を抜いてもピカイチだ。
横目で窺うと、イユは、んー、と目を細めうっとりする。口のよこちょをゆびで拭って舐めとる。ゆびで丸をつくる。ばっちぐーのサインだ。
感想を挟む間もなく、もぐもぐとひと息にたいらげた。
「あー、おいしかった。こんなの食べちゃったらもうコンビニでサンドイッチは買えないね」
コンビニのはコンビニので私は好きだけどな。
思ったけれどまだ口にだしてしゃべれるほど慣れてはおらず、すこし迷ってから、これはでも言っておきたいな、と思ったので、ぱぱぽ、と文字を打った。
「やっさしー」
イユは両足を揃えて、ぴょんぴょんと跳ねた。
なんで跳ねる?
その浮かべてる笑みはなに?
やっさしーって、それは皮肉か何かかな?
しゃべれたらすぐに訊ねられるのに。
思うじぶんをすこし窮屈に感じる。先週までそんなふうには思わなかったのに、しゃべれるようになった、と自覚した途端、こうして欲張りになった。
伝えたいことや知りたいことがじぶんのなかにこんなにあるとは思わなかった。ひょっとしたら、元々私のなかには言葉がたくさん溢れていて、けれど私のなかに拡がっていたがらんどうがそれを奪い去ってしまっていたのかもしれない。
がらんどうを埋めたのはイユだろう。そして植えつけたのもまた彼女だ。
じぶんで問題の種を撒いて、回収するのを専門用語でなんてったっけ。
私は右斜めうえに視線を漂わせる。いい天気だ。しろい雲の合間から朝日が差している。雲のカタチが犬みたいで、かわいいな、なんて思う。
「なーに考えてんの」
イユがご機嫌に体当たりする。痛いのでやめてください。手で払うようにして意思表示し、それからさっきまで何を考えていたのかがすっかり抜け落ちていることに気づき、じぶんの記憶力のなさに、ありゃりゃとなる。
イユは叱られた子犬のように、しょぼんとしている。
たぶん彼女は、と考える。
しゃべれるようになった私と、これまで以上にコミュニケーションがとれると期待していたのではないか。それがどうだ。いざ蓋を開けてみれば、私は依然として口数すくなで、事情を知らないひとからすればただすげない態度をとっているのと変わらない。
そしてイユはイユで、私のこのふだんと変わらぬ態度を、すげない態度だと見做しつつある。いいや、とっくにそのように見做していたがこれまでは、それはきっとしゃべれないからだ、とする言いわけを自身に向けることができていた。
私が言葉を発するおとといまでは。
イユは私の胸中をかってに、都合のよいように我田引水、推し測っている。ひょっとしたら避けられているのではないか、嫌われているのではないか、拒まれているのではないかとの不安をそうして見て見ぬ振りをしてきたのだ。
それがどうだ。
いまはもうその魔法は通じない。
喉が痛くてとじぶんの喉を示してみせれば彼女のことだからそこから都合のよい解釈をしてくれると判っていながら私は、イユの不安を拭わぬままでいる。
凝らしめているのかもしれない。私は私の内心の声に耳を傾ける。私はまだ彼女を許してはおらず、気を緩めてもおらず、過去を水に流そうとなどは思っておらず、だからこうして、しゅん、と肩を落としてしまっている数分前まで上機嫌だった彼女をまえに、すんと澄ました顔で我関せずを貫いている。
学校に着くと、教室に入る前に、イユは彼女自身の信者に囲まれた。私はその瞬間、イユが私の知るのとは異なる人物になったような感覚につつまれる。不快ではない。清々もしない。我ながら釈然としない。
私はイユを異物どころか劇物に感じていたはずだ。いまではそこまでの脅威と見做してはいない。
罪悪感なのかもしれない。
何に対してかは私自身よくわかってはいない。
こうしてにべもない態度をとっていることに対してか、それとも私だけがこの数年間ずっと苦しんできたのだと思いこみ、私にがらんどうを植えつけた彼女のことを忘れよう、忘れようと延々してきたことに対してだろうか。ひょっとしたら私は、こう考えていることを彼女にだけは絶対に明かしたりはしないと制限をかけているじぶんに後ろめたさを覚えているのかもしれない。
イユは私に最初から正直に、素直に、何も隠さずに接しつづけてきた。教室で先生のよこに立ち自己紹介をしたとき、まっさきに私に気づいた。そのあとでも臆さず私に声をかけてきた。
彼女は私を忘れてなどいなかった。私を傷つけたかもしれない過去を抱えつづけてきた。
私はそこに、何かしら、救いのようなものを感じているようにも思え、なんだか私ばかりが葛藤し、悩み、もやもやしている気分になり、だから私は彼女に未だに冷たくあたっているのかもしれなかった。
彼女は何もかもが完璧だ。人形のように人々を魅了し、そのくせ当人は人間くささに溢れている。
苦手意識全開だった私ですら、いまでは彼女がとなりに座るのをどこかくすぐったく、好意的に捉えている。
慕われている。
慕ってくれている。
それが過去、私にがらんどうを植えつけ、私から声を奪った相手であっても、私はもう素直に怒りを、恨みを、屈託を、こねて、伸ばして、壁とすることができなくなってしまっている。
授業を受けているあいだ私は彼女を視界に入れずに済む。それでもときおり、落とした消しゴムを拾ったり、プリントをうしろの席の子に渡すときに、否応なく視界にイユの姿が入るのだ。毎回のように目が合うので、なんだかまえを向いているあいだも彼女が私の後頭部に視線をそそいでいるのではないかと考え、顔が熱くなる。
こんなにもじぶんの挙動を気にして過ごしたことはなかった。呼吸が意識下に置かれ、息を殺すような息の仕方をしているじぶんを歯がゆく思っては、自意識過剰!と諌めるじぶんの声が聞こえてくる。
日に日にその声は音量をあげ、しだいに夏の日の蝉の鳴き声のように、風物詩がごとく私の生活に馴染めはじめたころ、
「なんかさいきんオシャレだね。目覚めた?」
ユウナが教室のベランダの窓から顔をだした。私の座席のとなりの席を足場にして、よいしょ、と乗り越えてくる。
いくら休み時間でももうすこしマシな登場の仕方があってもよかろうに。
思い、教室の扉を見遣ると、イユがとなりのクラスの子に囲まれていた。トイレにいくにもああやってまとわりつかれてはさすがに嫌気も差すだろう。私に迷惑をかけまいと教室にいるあいだは話しかけてこない。私なんかと旧知だと思われたくないだけなのかな、と考えないわけではなかったけれども、彼女のためにわざわざ性格わるくなるのも癪なので、頭上にこもったモヤモヤを手で払って散らす。
もう一つの教室の扉は男子生徒が代わる代わる懸垂をしていて通せん坊をしている。お猿さんだな、なんてふだんのユウナならば毒づいているところだ。
しかし本日のユウナはおとなしかった。
というのも、登場したときから目についていたのだが、
どうしたの、それ。
問うつもりで、私は鼻のあたまをゆびでなぞる。
ユウナは鼻にティッシューを詰めていた。鼻血だろう。でもどうして?
「ぶつけた」
どこで、と首をかしげる。
「まあそれはそれとして」ユウナは強引に話を逸らした。「うちはさ。まあまあそれなりにあんさんとは親交を深めてきたつもりだよ、これでもね」
はあ。
私はあいまいにあごを引く。
「で、そんなあんさんはうちからの貢物をたらふくもらい受けておきながら――いや、それはうちが好きで布教してたわけだから恩を着せるつもりはないけどよ、それはそれとして、うちはあんさんの口から直接知りたかったなぁ」
それともうちとはききたくもないってか口を?
ああ、これは。
私は思った。ユウナはいま、怒っている。しずかに、しかしハッキリと私に失望の気色を示している。
「それともうちはただ誤解して、みんなの噂を真に受けて、あんさんにちゃっかりイチャモンをふっかけてるだけなんかな」
机にバンと手が置かれる。刑事の取り調べみたいだ。私はユウナの顔を見れずに、うつむいたままで、第一声が何がいいだろうか、と混乱する。
だからそのあいだに私の座席をぐるりと回って、わざわざユウナの真正面、窓側に回りこんだ人物に気づくのが遅れた。その人物はユウナの胸をドンと押し、彼女に尻もちをつかせる。大きな音が鳴ったのは、ユウナが机の脚に身体をぶつけたからだ。
「いってぇ、あにすんだドチクショー」ユウナはまくれたスカートを直そうともせず、尻を床につけた状態のまま目のまえに仁王立ちする転校生、私のがらんどうの生みの親の足首を蹴った。彼女は顔をしかめるだけで微動だにしなかった。
「だいじょうぶ?」
と、これはユウナではなく私にかけられた言葉だ。私は頷き、それから喧嘩はやめて、とアタフタする。じっさいに、やめて、と声にだす。私は椅子に座ったままだった。立ちあがったら、なにかこう、戦闘開始のゴングが鳴りそうで怖かった。
教室が騒然としている。それはそうだ。女子が二人、しかも違うクラスのコ同士で喧嘩をおっぱじめたのだから。どうしたどうした、とならないほうがおかしい。教員が飛んでくるのも時間の問題だ。
なんとかこの場をとりつくろわないと。
思うだけで、どうすればいいのかなんて解からない。
目頭が熱くなり、視界が滲む。
誰がわるいわけではないのに、考えてもみれば、きっかけの行き着く先にいるのは私だった。私は全然わるくないのに、私のせいで関係ない二人が接点を持ち、こうしてぶつかりあっている。
ばかじゃないか。
みんなばかだ。腹が立った。
私がしゃべれるようになったことを私の口から知らせなかっただけでヘソを曲げたユウナにも腹が立つし、白馬の王子さま気取りで私のたいせつな友人に暴力を働いたイユにも腹が立つ。
なにより、当のイユはいま、私の頭を両手で抱えこむようにし、よしよししているのがもっとも見逃しがたい怒髪天だ。沸点ここに極まれりだ。
だいじょうぶだいじょうぶ、こわかったね。
じゃないんだよ。
私は叫びそうだった。耐えられたのはひとえに、私の声帯がまだそこまで回復しておらず、私自身、しゃべることへの抵抗を拭えきれていないためだ。
まずはイユのうでをゆっくりていねいに引き剥がす。彼女の両手首を、それぞれ右手は右手、左手は左手で握り、必要なチカラ以上をこめて、彼女のへその位置にまとめて押しつける。
イユはそこに到ってようやく私の険のある表情に気づいた様子だ。怯えた表情で、でも、と言いわけぶった鳴き声をあげる。子犬が、きゅーんと耳を垂らすようだ。ふだんの私ならそこで、仕方ないなぁ、とため息の一つでも漏らしてあげたかもしれないが、きょうは違う。
私はわざとイユに目を向けず、イッテぇと言いながらひざに手を添え立ちあがるユウナを支えに寄った。
ごめんね。
まずはそれだけを口にした。きちんと言葉として聞き取れるように、はっきりと、一音、一音、舌で言葉の輪郭をなぞる。
ユウナはいっしゅん目を丸くした。それからお尻を手でさすり、口を一文字に結ぶ。ふだんと同じくムスっとした調子を崩さぬままに、許さん、とつぶやく。
教師がくるまえに私はユウナをつれて教室を離れた。イユはうしろから何かを言いたげに戸口のまえまでついてきたが、私たちが廊下にでてしまうと、結界のなかに入れないオバケみたいに教室のなかで立ち尽くした。私がいちども彼女を見なかったのが堪えたのかもしれない。
私ごときに無視されようと傷つくいわれはないはずだ。それでも彼女の、私を庇うような行動と、そのあとの慈しむようなここぞとばかりの演出を鑑みれば、いくら私でも、彼女の私への扱いが、同じクラスの一員以上であると推して知れる。
単なる旧知以上の何かが、私たちのあいだに、すくなくとも自身のなかにあるとイユはそう思いこんでいる。
私はそれをこのとき自覚した。
私の一挙一動が彼女を傷つけ得る。
かつて私がそうされたように。
私は彼女にがらんどうを植えつけることができるのだ。
保健室に逃げこんだのはとくに考えがあったわけではなかった。ちょうど予鈴が鳴ったから、遅刻の言いわけにいいかとしぜんと打算を働かせたのかもわからない。それはそれとして、ユウナは教室で盛大に尻もちをついたのだから、お尻が四つに割れていないかを診てもらったほうがいいかと心配したかと言えば、とくにそういうわけでもなかった。
「心配しろよー、そこはよー」
私が何も言わずに突っ立っていたからか、ユウナが膨れた。「うちの桃みたいなおちりが桃太郎みてぇにパッカーンっなっててもいいのか。よくねぇだろ」
「うるさいわねぇ、騒ぐんなら教室戻りなさい」
言いながら保健室の先生がユウナの臀部に制服のうえから触わり、痛いところあったら言って、と指示しながら、ここは、ここは、と痴漢の真似事を繰りひろげる。
「イタタ、イタタ、せんせい痛いってば」
「がまんなさい」
「つづけんのかよイタタ」
「仮病じゃないみたいね」
先生は舌打ちすると、しぶしぶといった様子を隠そうともせず、医療品の仕舞われた棚の鍵を開け、なかから湿布と包帯をとりだした。
「はい。短パン脱いで」
「えー」
「えーじゃない。それともじぶんでやる? 失敗しても代わりないからね」
「んー。でもせんせいはやだなぁ」
ユウナがこちらを見たので、私はきょとんとする。
「はいはい。さっさと貼って出てってちょうだい」先生は机に向かい、何かしらの紙面にペンを走らせる。治療したので書き記しておくべきことがあるのだろう。それともほかに仕事があったのかもしれない。それを、私たちが邪魔したものだから機嫌がわるいとも考えられたが、この先生はふだんからこれくらい生徒に媚びないので通常運転とも呼べる。
去年は男の先生だった。私たち生徒への慈しみがもうすこし感じられただけ、よい先生だったのだ。失われてからそのかけがえのなさに気づいたが、もう遅い。
それにしても、と思う。ユウナはなぜに私から目を逸らさず、いそいそとベッドのあるほうに移動しているのだろう。そしてなぜに手招きをするのだろう。
「ちょいちょい、はやくきてって。貼って貼って」
近寄ると、ユウナはカーテンを閉めた。「この辺。このあたり」
湿布をこちらに握らせると、じぶんでスカートを捲しあげる。短パンを履いているからといってそれはどうなの。はしたないと思うのは、私のほうがおかしいのだろうか。
「ぺろんってするけど笑わんでな」
言ってユウナは下着ごと短パンをめくった。私は噴きだした。陽気が溢れたのではなく突然のできごとに脳がパンクしたのだ。ぶは、のそれだ。
「やっと笑った」
ユウナはそれで満足したようだ。こちらの手から湿布を奪うと、いそいそと反対を向き、じぶんで臀部に貼りつける。
「やー、焦った。焦った。絶交されるかと思って身体張った甲斐があったわな」
怒ってたんじゃないの。
窓から乗りこんできてまでしてさあ。
眉を寄せて訴えてみせるも、ユウナには伝わらなかったようで、
「なんかさー。うちにとっては漫画の話できるのって一人しかいないからさー。そういうさー。なんていうかさー。じぶんだけ相手にしがみついてるのって惨めだなって」
え、なんの話?
あまりの突拍子のなさにまたまた噴きだしてしまった。唾が宙に舞う。ベッドの掛布団のうえに落ち、シミをつくる。それをなぜかユウナが手で払い、
「ごめん。暴走した。ゆるせ」
スカートを整え、ベッドのうえにあぐらを組むと、サムライのようにこうべを垂れた。
まだ喉の調子がよくないのを確かめてから私は、メディア端末を手に取って、
どうしよっかなぁ。
と打つ。
読ませると、んだよケチ、とユウナは唇をとんがらす。足を崩してあぐらをつくり、窮屈そうに頬杖をついた。「んー。ほら。散々、漫画読ませてやったじゃん」
恩着せがましいことを言う。
しかし、一理あるにはあるもので、私は不承不承、じゃあそれで手打ちに、と文字を打つ。
「しっしっし。恩は売っておくもんだ」
私たちは保健室をあとにし、それぞれの教室に戻った。いっそつぎの時間までサボってしまうおう、とユウナから誘われたが、いま戻れば先生から説教されなくて済むかもしれない授業中だし、と提案する。喧嘩があった旨は先生の耳にも入っているはずだ。ユウナはなるほどと手を打った。
ユウナはユウナの教室へ。
私は私の教室へ。
いざ戸を開け、足を踏み入れると、おー具合はどうだー、と歴史の先生がころころとした丸みのある笑みを、同じくらい丸い眼鏡の奥から向けてきた。
保健室の先生から持たされたメモを渡す。
「お、早退じゃないんだな」
座席に着くころには、平然と授業は滞りなく再開された。椅子に座るとき、教室のうしろのほうに座るイユの顔が視界に入った。彼女は窓のそとを眺めており、こちらを気にする素振りはなかった。
シカトか。
それはそれで新鮮でもあり、ほっとしつつも、何かもやもやと胃のなかがごろごろした。
授業が終わると、昼休みだ。食堂に行こうと思っていたら担任に呼び止められた。そのわきをイユがするると抜けていく。
担任が私の顔を覗きこみ、だいじょうぶか、と名簿代わりの端末で肩を叩きながら、もちろんこれはじぶんの肩を、という意味だけれど、言った。
「はい」私は声をだして言った。いっしゅん教室が静まったように感じた。気のせいだろう。自意識過剰になるんじゃない、とじぶんを叱咤する。
「具合わるかったら早退しろな。遠慮するなよ」
担任はそこでもういちどだけ、ホントにだいじょうぶか、と念を押した。私がうなずき、微笑んでみせるのを見届けると、そのまま、きょうは何食べよっかなー、とひとりごちながら教室の戸を潜っていった。
食堂にいくには、いま別れたばかりの先生のあとをついていかねばならず、そうでない経路でいくと遠回りだし、かといって時間をおいてからいくのもなんだか面倒になってしまって、私は、まあいっか、と思って、そのまま座席に戻った。
教室は徐々にがらんとしていき、いくつかの数人のグループが弁当をひろげたり、しゃべったりするだけとなった。このクラスにひとは集まらないのだなぁ。そんなことを思い、でもいつもはいっぱいいるのになぁ、とイユの姿が浮かんだ。
なるほど。
この教室にはいま女王蜂さまがいないのだ。
ふだんは食堂だったから知らなかったなぁ。
ささやかな発見に、ふん、と鼻息をみじかく漏らす。
メディア端末を操作し、本を読む。すこし読んでから、眠気が走ったので、マンガに切り替える。ユウナからおすすめしてもらった作品の最新刊だ。ユウナは紙派だけれど、私はどちらでも構わないので、じぶんで買う分には、いつでも読めるようにデータで購入している。同じシリーズでも、紙・データ・紙・データとちぐはぐに巻を揃えてしまうこともしばしばで、いっそのこと全部データにしようかと悩んでいる。
ただ、ユウナにそれを言うと、この反逆者め、と詰られるのでこちらからその旨を告げることはない。書店をこれ以上つぶすきか、と彼女は怒っているわけだが、私はそろそろ書店さんでもデータで本が売られはじめると睨んでいるので、まあまあ、と流している。
目のまえにペットボトルが現れる。顔をあげると、女王蜂さまことイユが立っていた。顔はこちらを見ておらず、教室の入り口のほうを眺めている。よこを向いても首にシワが寄らないんだ、すごいな、なんてじぶんのあごのしたを思わずつまみたくなる。イユなら上を向いただけで喉の皮が裂けてしまいそうだ。それくらい張りがあって、肌はどこも陶器じみている。
「食べないの、ごはん」
問われたので、うなずく。イユはうしろにまわしていた手をまえにもってきて、私の机に袋を置いた。中を覗くと、菓子パンが詰まっている。
「食べていいよ。いらないならほかのコにあげて。ほら、いるでしょ、仲いいコ」
清々しいほどわかりやすい態度に、ああ、と私は納得してしまった。何を考えているか分からないコだと思っていた。そのじつ、彼女は単に、見た目からは想像できないほど素直で、こどもじみている。賢い人間だと知っているがあまりに、何か複雑な駆け引きや、企みがあるのではないか、と穿ってしまっていただけで、私はもっと彼女のことを同じ人間として、対等な女の子として接するべきだったのだ。
いまさらながらに過ちに気づいた。
それを、誤解に、と言い換えてもいい。
ありがとう、と私は言った。喉が痛かった。でも声にださなければ伝わらないと感じた。いったい何が伝わらないのかはよく分からなかったが、伝えなければ、と思った。すくなくとも、伝えようとしているのだ、と示したかった。
だから私は、しゃがれた声で、とてもではないがひとに聞かせたいと思うような声ではない音で、どもることも厭わずに、ありがとう、と声帯を震わせた。
イユの顔は見れなかった。目を伏せたままで私はさっそく袋を開け、菓子パンを齧る。
ごっくんと呑みこんでから、これがメロンパンであることに気づく。とにかく食べなければ、と必死だった。パンの中にはホイップクリームが入っていた。美味しい。食堂で買ったことはなかった。彼女にこうして施されなければ、一生食べることはなかっただろう。
いや、大袈裟だ。
よしんば食堂のメニューすべてを食べずにいたからといってなんだと言うのか。購買の菓子パンを網羅しなかったからといってどんな損をするというのか。
それでも私は、彼女がこうして私のために、私が選ぶことのなかったけれど美味しい菓子パンを運んできてくれたことに、身体の裏側がもぞもぞとくすぐられたような心地を覚えた。
菓子パンを半分ほど食べ終えてから、教室に生徒たちがまだほとんど戻ってきていないことを思いだし、そういえば彼女はご飯を食べたのだろうか、と思い至って、菓子パンを半ぶんこにし、イユに差しだす。
イユはまだ私の席のまえに立っている。後ろ手に腕を組み、私の差しだした菓子パンに目を留めると、しばし身体を左右に揺らすように逡巡の間を置いてから、あたしも飲み物買ってくればよかった、とつぶやき、まえの席の椅子に座った。彼女の席ではないが、いまはそここそ彼女のおわすべき場所に思えた。
私たちは菓子パンを半ぶんこにし、つぎつぎに味比べをした。袋の中身はカラとなり、喉が渇いて仕方のなさそうなイユに私は、彼女からもらったペットボトル飲料を、それはすでに三分の一ほどなくなっていたけれど、手渡した。
「飲んじゃっていいの」
ぜんぶはダメ。
私はふだんどおり、メディア端末の画面に文字を打ち、彼女に見せる。イユは目じりを下げる。ペットボトルのキャップをとると彼女は先端にくちびるをつけ、なめらかな喉をこちらに見せつけるように、こくこくと赤子の鼓動にも似た音をたてた。
「はぁ、生きかえる」
飲みなよ、とペットボトルを返されたので、受け取りながらも、口をつけるのには抵抗があった。
視線を感じる。
ここで拒んだらなんだか空気がわるくなりそうだなぁ。
どうしよう。
思いながらも喉が渇いていたこともあり、考えすぎだとばかりに、えいや、とひと息にあおった。
「どう? おいしい?」
返事をするのがむつかしい。ここで美味しいと答えるのがしぜんな流れではあるものの、なんだかそれってほかの意味が含まれそうに思える反面、こう考え、悩むことそのものがすでに彼女の罠であるようにも感じられ、だからでもないが私は、わざわざ食べかけのパンを齧ってから、おいしいね、と文字を打つ。
イユは笑みをたやさぬままに、どこか不服そうに、よかった、と言った。
それから一週間もすると、つづけて声をだしても喉が痛くならなくなった。まだ長い文章は抵抗があるし、何度もつかえてしまうけれど、声帯の機能的にはほとんど問題ないように思えた。
ぐったりするような残暑を幾度か乗り越え、朝夕とヒグラシの声が涼しげに聞こえるようになってきたころには、私がかつてしゃべらない生徒だったことを憶えている者は稀になった。みんながどう思っているかなど私には分からないが、すくなくとも私がしゃべりだしても、あれ? という顔をされなくなったのは確かだ。どうしてしゃべらなかったのかとか、しゃべらないのってつらくなかったの、といった過去を蒸し返すような質問も、数えるほどにしか向けられず、それすらいまでは皆無と言ってよかった。
私は私を特別な存在だとは思っていないが、それ以上にみなにとって私は特別な存在ではなかったのだ。哀しむほうがしぜんなのかもしれないのに、私はそれを知れて、すこしほっとした。
「龍虎(りゅうこ)の仲だよね」
そんなセリフが私のクラスや、廊下をひそかに飛び交いはじめていたのを、私は衣替えをしたくらいのときに気がついた。私に向けられた言葉ではなかったので気に留めていなかったのだが、ふしぎと私に向けてその話題を振ってくる者がいないのに気づいて、これはひょっとするとひょっとするのか、と察し到った。
犬猿の仲を意味するようだ。それは判ったが、では、とそこで気になるのが道理というものだ。
誰が龍で、誰が虎なのか、と。
「イユちゃんは誰とでも仲よくていいね」私は放課後、帰宅途中にそう切りだした。文化祭の準備で放課後まで居残る日が増え、その分、委員会のあるイユと帰る時間帯が重なるようになった。朝は朝で、イユが家のまえで待っているのが習慣となっている。「アイドルみたいっていうか、まんまアイドルだよね。誰からも慕われて」
「まあね。あたし、もう誰のことも傷つけたくないから」
ならばどうしてユウナとは仲良くできないのか。
言い返したい衝動をぐっとこらえ私は、
「じゃあ仲直りできるよね」
カバンから一冊のマンガ本を取りだす。矢継ぎ早にイユに差しだすようにすると彼女は何を思ったのか歩行速度を緩め、私の背後に回った。こんどはさらに私の左側へとつきなおす。
私は右から左へとマンガ本を瞬間移動させる。彼女はもういちど私の背後を経由して最初の位置、私の右隣におさまった。
ん!
受け取ってよ、の意思をこめて私は懲りずにマンガ本を押しつける。彼女は頑としてそれを受け取ろうとしない。ほっぺたにぐいぐい押しつけても、そんなものは見えませんけれど?の顔で、涼しげに歩いている。
私はいよいよムっとして、彼女のカバンにマンガ本をねじこむと、
よーいドン。
一目散に駆けだした。
「あ、こら」
イユが追ってくる気配がある。
私は運動が得意でない。反してイユは完璧超人みたいだからフライングをしたカメを追い越すなんてわけないはずだ。
でも私は確信している。
彼女のようなオシャレ人間は、街中でスカートをはためかせながら、汗を掻くほどに全力疾走したりはしないのだ。
予想通り、角を曲がってひとしきり走ったところで振りかえってみても、そこにイユの姿はまだなかった。おおかたとっくに歩いているのだ。そもそも追いかけたりはしなかったのかもしれない。何事かと通行人がこぞってこちらを見ているので、さすがの私も呼吸を整え、なんでもないですけれど?の顔で、涼しげに歩きつづける。パン屋のまえを通ると焼きたてのパンの甘い香りが鼻をかすめた。
昼休み、私は食堂でうどんをすすっていた。一人だ。ここ数週間はとなりにイユがいるのが通例となっていた。交友関係の広い彼女であるから、食堂にいる時間が長ければ長いほど、私たちの座る区画には人が寄ってくる。まるで私などいないかのように人が押し寄せ、イユを取り囲むものだから、私としてはそそくさと退散するのが常であった。もうすこし言えば、さきにイユが席に座れば、そこに集まる小魚のような人々を避けて、私はほかのテーブルに座ることもしばしばだ。
だからこうして私が一人でうどんをすすっているのは正しい姿で、イユがいないほうがしぜんなのだが、私はなんだかすこしの不安と、嫌な予感、それはどこかしら火薬めいた匂いのする「火花よ散るな」といった懸念にちかかったが、イユの姿が食堂にないことを不気味に思った。
気持ちはやめに教室に戻ると、私の座席にイユが座っていた。まえの机にも座る者がある。そこからは凍てついた空気が立ち昇って見え、ともすればあべこべに灼熱の空気に怯えたように幾人かの生徒たちが教室を飛びだしていく。
私のすぐよこをすり抜けていくクラスメイトたちを尻目に、私は、やあやあ、と何気ない足取りで、自席に近づく。
イユはマンガ本を机に叩きつける。
「はいこれ、お返ししますね」
「雑にすんなや」ユウナが吠える。手本を示すような手つきでマンガ本を拾いあげると、「おまえ友達いねぇだろ。いたとしても同情しちゃうな。こんなふうに乱暴に扱われて。よっぽどやさしいお友達なんだろうなぁ」
愛想尽かれないように気をつけろよな。
吐き捨てながらユウナはこちらを見た。「うちはこれをあんたに貸したのであって、コイツに貸したわけじゃないからな」
断じて。
ユウナはマンガ本を両手で胸に抱く。着崩すことなく身にまとった制服の垢抜けなさに似つかわしくのない、野生じみた目でしばらく私の顔を睨み据えると彼女は一転、ひらりと背を向け、どすどす、と教室の床を踏み鳴らしながら去っていく。
追いかけるべきだろうか。追いかけるべきだろう。
だってあんなにも怒っているのだから。
でもそこまで怒られることをした覚えはなく、しかし心当たりが皆無かと言えばそれもまたノーであり、なんと謝ったものか、となんとなく釈然としない思いを胸に、待って、と声なき声で一歩を踏みだしたところで、
おえ。
うしろから上着の裾を引っ張られ、私の喉は悲鳴をあげた。カエルの断末魔じみている。
誰も聞いてないだろうなぁ。
思いつつ教室を見渡しがてら、私にそんな音をださせた張本人に抗議の目をそそぐ。
「ごめんなさい」イユはしょげた。「でも追いかけなくていいよ。友達なのはわかるよ。あたしがいなかった数年間に、あたしといっしょにいた時間よりも長く付き合っていたんだってのもなんとなく判るけど、なんかだってさ」彼女はまだ私の裾を握ったままだ。「ひとをわるく言うのは嫌だけど、付き合う相手は選んだほうがいいと思う」
えー。
私は内心絶叫した。それをあなたが言っちゃうんですかー。
というか、ユウナはユウナで同じことをあなたに対して言ってましたけど。
もし私の声帯が電動歯ブラシ並に流暢に振動できたならば反射的にそう口走っていたかもしれない。ただ、彼女たちの仲がよろしくないのは、人間関係においていつまでも母から心配されつづけている万年幼稚園児の私であっても察している。
似た者同士なのに。同族嫌悪かな。
仲良くしてほしいな。
思うけれど、これは私の一方的な願望であって、彼女たちが仲良くする道理は本当はないのかもしれない。無理に縁を繋ぎつづけるよりも、火傷をしない距離感を保ったまま、接点を持たずに生活していくのは一つの最善であるはずだ。
けれどできれば互いに嫌な面以外のところも知ってほしい。壁をつくるならそのあとでも遅くはないのではないかと思う反面、これ以上の軋轢を招く懸念も拭いきれず、けっきょく私にできることは、まあまあ、と彼女たちをなだめることに終始するし、終始すべきで、それ以上の干渉や強制を向けることではないのだろう。
考え私は、まあまあ、と目のまえのあらぶる女神に微笑みかけ、ちょっとお手洗いに、の仕草を残して、席を立つ。
「どこ行くの」
ちょっとあっちに。
先刻ユウナの立ち去った方向を示し、私は席を離れる。イユは息を呑んだような間を開けると、いったん椅子から立ちあがり、すこし迷った様子を見せてからまた座った。
私は一人で、教室をあとにする。ユウナの姿が廊下にないかと目を配り、となりのクラスを覗き、そこにも姿がないことを見届けると、食堂から戻ってくる生徒たちの川をさかのぼりながら保健室へと歩を向けている。
やはりユウナはそこにいた。
「ほら、相棒が迎えにきたよ」
保健室の先生は投げやりに言って、ちょっとお願いね、と意味ありげに私の肩に手を置くと、私と入れ違いで保健室を出ていった。
ベッドは三つある。うち一つの仕切りが下りており、私は泥棒になった気持ちで忍び寄る。カーテンにじぶんの影が映るところまでくると、その奥から、
「きょうはもうサボる」と声がした。「早退させてもらうことにしたから放っといて」
言われたところで、わかったじゃあね、とはいかぬのだ。
カーテンをくぐって中に入る。ユウナは掛布団のうえにじかによこになっている。膝を抱え丸まり、母体のなかの赤ちゃんのようだ。
ゆびをしゃぶっていたら百点満点だったのにな。
私はベッドに腰掛け、彼女の腰骨のうえに手を置く。
子守唄を歌えれば完璧だ。しかし私は歌えないので、ぽんぽん、と叩くだけにする。ユウナはさらに丸くなり、
「おせっかい」
つぶやいたきり、ぐおーぐおー、とおおげさにイビキを掻きだした。
彼女なりの照れ隠しかな。
私はメディア端末を取りだして、文字を打つ。
仲直りしてとは言わない。でもわざわざ衝突することないと思う。
ユウナに画面を向ける。彼女は目だけをちらりと寄こす。目玉が文字を追っているのが判る。彼女の唇がイソギンチャクみたいにきゅっとしぼまったので私は、
ユウちゃんのほうがおとなだと思ってるんだけどな。
続けて文字を打つ。ユウナは、うー、とうなり、そりゃそうだけど、とまんざらでもなさそうに、それでいて悶えるように言った。
ダメ押しとばかりに私がまた文字を打とうとすると、それを阻止するかのようにユウナはすばやく上半身を起こした。
「わかったってば。もういいよ」
宙を手で払う。それから彼女はいつものようにあぐらを組み、
「仲良くするのは無理そう。だって向こうにその気がないみたいだから」
私が目を細めると、
「こっちのほうでもないかもだけど」ユウナは言い直し、「でも、もう突っかかったりはしない。約束する」
突っかかったりしてたんだ、と唖然としてみせてもよかったが、いまは珍しくユウナが真面目ぶってくれているので、腰を折らずにおく。
マンガをだいじにしないのはよくないよね。
私はそういったことを文字にする。本を、それもひとから借りている本を粗末に扱うのは、たしかに怒ってもいいことかもしれない。
慰めるのも兼ねてユウナの肩を持つと、彼女は鼻の穴を膨らませ、
「ほんとそう」
語気を荒らげた。「本をだいじにしないやつは友達もだいじにできないやつだよ。むかしから言うよ。じっさいそうだよ。うちはなにもじぶんのことだけで怒ってるわけじゃないからな」ユウナは私の名を呼び、「アイツ転校してきてからやっぱり様子変だったし、あなたのお口チャックが解けたのだって無関係じゃないんだろ」
アイツと。
しもぶくれほっぺの合間から唇がちょこんと突きでている。いじけた幼児みたいだ。思わず頭をなでつけると、ますます膨れて赤くなる。「まじめに話してんの!」
私は立っていて、ユウナはベッドのうえであぐらを掻いている。だからだろうか、
こんなにちいさかったっけかな。
馴染みの友人の姿がやけにちいちゃく感じられた。不思議の国のアリスの気分を味わう。
ひょっとしたら、と思いつく。ふだん、身近に背の高い、すらっとしたひとを置いているせいかもしれない。
私がぼーっと視線を宙に彷徨わせたままでいたからか、
「分かった、もういい。もうマンガ貸してあげない」
同士でもなんでもない、とユウナはいじけた。私がびっくりしてしまうくらいに、私ですら誤解する余地のない拗ね具合だったもので、私はますます、おっきな赤ちゃん、と思って、にこにこした。
それがよくなかった。
おっきな赤ちゃんはもちろん赤ちゃんではないので、私の胸中を満たした慈愛の、どこか孫を見守る祖母じみた視線にちゃんと気づくこともできるし、立って歩くこともできる。
ベッドから飛びおりるとユウナは、靴を手で持った。履く時間ももったいないらしい、そのまま保健室をでていく。
私はあとを追う。彼女は廊下に放り投げた靴に、器用に足を引っかける。
ごめんごめん、とまずは両手で拝むようにして先回りし私は、ユウナの進路を塞ぐものの、彼女は、ふん、とまたしても分かりやすい返しをするので、私はもう、彼女がこんなにもひねくれるのがへたくそなのかと、無垢な者のせいいっぱいの反抗に胸の奥がくねくねした。
いっこうに歩行を緩めない彼女の背中に、えい、と抱きつく。それを、しがみつく、と言い換えてもよい。
彼女はいちど身体を硬直させたが、すぐさま足を踏ん張り、私ごと引きずった。私は無駄に分厚いマントの真似事をしながら、なんだか楽しくなってしまって、ふへへ、ふへへ、と即席のアトラクションを満悦する。
ユウナもユウナでじぶんの状況がおかしかったのか、やがて、やめてよもー、と言いながら肩を弾ませた。
廊下にほかの生徒の姿はない。ちょうどチャイムが鳴り、午後の授業がはじまる。廊下からほかの教室の様子を眺めながら、ガラスの向こうからいぶかしげな眼差しでこちらを見る教師たちに、具合がわるくて、の演技を披露しながら、私は相も変わらずユウナの背中にもたれかかっている。
ユウナはじぶんのクラスを通りすぎる。私を私の教室まで運んだ。
「数学だったからもすこしサボる」
あ、さいですか。
教室の扉を開けると誰もいなかった。体育だったのを忘れていた。
移動教室なん、と問われ、そう、とうなづく。
背中から降りようとすると、逃さんとばかりにユウナが私の腕に絡みつく。私たちはしばらく押しあいへしあい、笑い声を堪えながら、じゃれあった。
けっきょくつぎの授業がはじまるまで、私たちはがらんとした教室で終末の世界ごっこをつづけた。昼間なのに、明かりの消えた教室はひどく暗かった。秋風がひゅるると窓をぶつ。
やがて休み時間を知らせるチャイムが鳴り、五分ほどしてちらほらと生徒たちが戻ってくる。ユウナはじぶんのクラスから教師がいなくなるのを見計らって、ニンニン、などと立てたゆびを握りながら去っていった。
チャイムが鳴る寸前まで忍者が主人公のマンガの話をしていたので気持ちは分からないでもない。ふだんのムスっとした顔のままであるので、なおさらギャップが際立った。
おそらく私以外で、ユウナのそうしたお茶目な姿を知る者はそう多くはない。いいや、ひょっとしたらこの学校にはいないのかもしれない。
マンガをまた貸してくれるという。かってに机に置いておくから、と言っていた。いまから楽しみだ。
始業を知らせるチャイムが鳴る。本日最後の授業がはじまろうとする寸前にイユが教室に入ってきた。入口のところで先生が――この先生は担任だったけれども、具合はもういいのか、と話しかけている。イユは煮え切らない態度で、ええ、とか、まあ、と言って席に着く。
先生はこちらを見て私の名を呼んだ。
「――もいいのか? 体調わるかったら無理するなよ」
おおかた保険室の先生が担任に告げたのだろう。私はユウナの付き添いでしかなかったが、顔のまえで両手をぶんぶん振って、ぜんぜんだいじょうぶです、お気遣いなく、の意を示す。
先生はうなづき、授業を開始した。
私は授業中、うしろの子に消しゴムを借りるフリをして、それとなくイユの表情を窺った。彼女は上の空で、窓のそとを眺めていた。
私は考える。彼女は休み時間のあいだどこにいたのだろう。何より、先生はどうしてイユが具合を崩していると思ったのだろう。
私は、私たちが終末の世界ごっこをしていたときに、真面目に授業を受けていたコたちのことを思った。もし私たちの姿を目撃したら、彼ら彼女らの目にはどう映っただろう。
この日は放課後になってもイユからは近寄るなオーラがほとばしっていた。私にとっては瞭然のそれが視えない者もいるところにはいるもので、私が言うのもなんだけれど、もっと空気を読んであげて、と思いたくなるほどイユに話しかけては、けんもほろろに返事をもらい、たじたじになっている者たちを視界に入れつつ、私は久方ぶりに一人で帰路につく。
長期戦かな。
何ともなしに思う。とうぶんイユとは話すことはないだろう。それはそれで寂しいと健全に思えるじぶんにすこしほっとする。
翌朝、イユが家のまえで待っていた。ふだんと変わらぬ佇まいで、寝坊しないなんて偉いね、なんて飄々と笑窪を向けてくる。
あまりに変わり映えのない姿に、どちらかと言えば不穏なものを感じたが、学校に着くころにはそれも杞憂だと判断するまでに気をゆるめていた。
だからこの日、学校でいちどもユウナの姿を見かけなかったことに気を留めなかった。
「あしたはどうするの」イユが下駄箱から靴をとりだす。
あすは休日で、とくに予定はない。学校の昇降口をでるとイユはマフラーを掻き合わせ身震いする。「冬って苦手だなぁ」
同意、と思いながら私は肩をいからせる。
時期的にはまだ秋なのに例年よりも寒い気がした。木々は紅葉を終え、骨だけになっている。
期末試験や冬休みの予定など、やや気がはやい話題を振りながらイユは私に、お出かけの約束をとりつける。断る理由を探すよりも引き受けてしまったほうが楽なので、私は予定が合えばね、とこれは声にだして言った。
うわぁ、楽しみ。
無邪気のお手本のような笑みを向けられ、まんざらでもない。
私はもう、彼女をそばに置いても身体のなかがどんよりと重たくなったり、あべこべに希薄になったりすることはない。
そう思っていたのに。
あくる日、私はじぶんの部屋の姿見のまえでいつもよりすこしだけおめかししていた。イユに誘われ、午後にアウトレットモールに向かう予定だった。夕方から雨が降るそうで、水に濡れても構わないコーディネートを考えているうちに、家をでないといけない時刻になっていた。
待ち合わせ場所は駅前だ。どうせならうちにまで迎えに来てよ、と思ったが、私がそう訴える前にイユが、デート気分、とつぶやいたので、そういう趣向ですか、と納得した。家まで迎えにくるのはもはや日常であって、非日常感を味わうには待ち合わせが有効だ。その理屈は理解できた。
認めがたいことに私はふだんよりも気持ちがふわふわしていた。それはかつて私の内に巣食っていたがらんどうとは異なる、綿菓子めいた浮遊感だった。
居間でソファに座って、ぼーっとしている母の肩を叩き、行ってきます、のジェスチャーをする。母は片手をあげ、ひらひらと振った。「車と不審者には気をつけて」
玄関で靴を履き、そとにでると、アスファルトに人影が浮かんでいるのが見えた。
あれ、イユかな。
思いながら、ゆっくり段差を下りると、ブロックの陰からユウナが顔をだした。きょうもきょうとて仏頂面だ。
ど、ど、どうしたの。
私はゆびであっちを差したり、こっちを差したりしながら、戸惑いを示す。ユウナは、デニムパンツにダウンジャケットを羽織っていて、完全に冬の服装だった。リュックを背負っている。彼女はふだんよりいっそう深いむっつり顔で、どこ行くの、と言った。
アウトレットモール、と声にだそうとしたけれどいままで口にしたことのない語彙だったので、上手に発音できる気がしなかった。メディア端末に文字を打って、場所を伝える。
「ふうん。誰と」
一人で、と訊かれなかったことで、私がこれから誰とデートごっこをするかを彼女は知っているのだと思った。すくなくとも当て推量はついているはずだ。
隠す必要もなかったので、イユとだけど、と文字を打つ。
ユウナはまた、ふうん、と言った。
いっしょに行く、と誘ってもよかったけれど、私がよくともイユはもちろん、ユウナ本人だっていい顔をしないだろう。無言のまま数秒がすぎる。
顔を背けてからユウナは、
「疑ってるわけじゃないけど、そっちの口からちゃんと聞いておきたくて」
リュックを地面に置き、そこからマンガ本を一冊取りだした。
私は息を呑む。
その本はシワクチャで、表紙はぐちゃぐちゃに滲んでいた。
似た状態になった紙を見たことがある。服といっしょに洗濯した紙幣を乾かしたとき、そのマンガ本と同じような仕上がりになった。
どうしたのそれ。
ゆびさきを向けながら私は、女王蜂とそれを取り巻く複数の働き蜂のことを思った。
「知らん。うちはただ約束通りあんたにこれを貸そうとしただけ。あんたの席にこれを置いといただけ」
ボロボロのもう二度と読み物とは呼べないだろう漫画本をこちらに静かに差しだしながらユウナは、
「約束は果たしたかんな。うちはちゃんと貸した。でももう読めないよな。貸したって迷惑なだけだよな」
本を掴んだ私のゆびから彼女は半ば強引に本をひったくった。
私の名前を呼ぶと、わるくないのは知ってる、と続ける。「でももう無理だよ。いままでみたいにしてらんない」
言いたい旨は理解できた。そしてユウナが、本をダイナシにした人物の顔をはっきりと思い浮かべていることも窺い知れた。
証拠はあるの。
訊ねたい一心を押しとどめる。証拠なんてないはずだ。残すはずがないのだ。
思いながら私は、かつて私にがらんどうを植えつけた人物の顔を思い浮かべていることに失望した。
やり兼ねない。私はそう考え、そう結論していた。
ユウナがいそいそとリュックを背負い直したので、私はあわてて引き止める。
鋭利な眼差しを寄越され、ひるんでしまうが、本は弁償するから、とまずは伝える。声に出して言い、メディア端末にも文字を打った。
「なんで」
ユウナの疑問はもっともだ。私が本をダイナシにしたわけではない。ユウナからすれば私が犯人を庇っているように映ったはずだ。
そんなつもりはない、と告げる。きょうこのあとの予定もご破算にするし、なんなら新しい本をいまから買いに行こうと提案する。
「いいよ。わるいし」
それを言うなら私のほうがわるい。気分がわるい。気が済まない。巻き込んだようなものだ。責任がまったくないわけではない。私の机に置いたはずの本をイタズラされたのだ。私だって怒っているし、やっぱり責任を感じてしまう。
そういったことを声にだしながら、文字にも打って伝えた。
誤解されたくなかった。
これっきりになんてしてほしくなかった。
絶対に許さない。
私は言った。だいじな友達のだいじな本をこんなにした犯人のことは絶対に許さない。もし誰かに指示をしてそれをやらせた人物がいたら、そんなやつとは一生口をきかない。
そういったことをつれづれと口にしたらなぜかだみ声しかでず、おかしいなと思っていたら、ユウナがハンカチを取りだした。
「わかった、わかったから。もういいよ。なんかこっちこそごめん」
顔をごしごし擦られ、ようやくじぶんが泣いていることに気づいた。頭がぐわんぐわんする。
いったんユウナを家にあげ、落ち着いてからこの日はユウナと書店さん巡りをした。メディア端末の電源は切っていた。とうぶん起動をしないつもりだ。声はでるけど言葉が滑らかに出てくれないので、意思疎通のためのメモ帳を書店さんで購入した。ユウナには新しい漫画を二冊プレゼントした。彼女はズタボロの本を捨てようとはしなかった。
この日から一週間、私はいつもよりはやく登校し、学校でも時間があればつねにユウナのそばにいた。ユウナとは頻繁に手紙のやりとりをした。
しゃべるのは疲れる。
私がぼやくとユウナは、書くほうが疲れるべ、と言ってシャーペンを唇と鼻のあいだに挟んだ。
よい友を持った。
しみじみと思い、反面、ふたたび胸のうちにわだかまりはじめたがらんどうの空虚さを煩わしく思った。
この期間、私に話しかけてくる者は、ユウナ以外ではいなかった。
初雪を観測したその日、私はいつもよりも遅い時間帯に家をでた。母からはとくに何も聞いていなかった。私がはやく家をでた分、誰かが家のまえで待ちぼうけていたり、インターホンを鳴らして私の所在を問うた者はいなかったようだ。
だからもはや私がはやく家をでる意味はなく、安心してたっぷり布団のなかで丸まってから、ついでにいちどお風呂に浸かったりもして、丹念にぽかぽかを満タンにした身体で以って、学校に向かうべく、玄関を開けた。
あまりの寒さに、ぴゃ、と声がでた。
その声に驚いたように塀の陰から顔を覗かせる懐かしい顔、それはクラスでは馴染みの顔であるにも拘わらず、私の世界からはすっかり切り離されていた者の端正な横顔を目にして、私はその場から動けなくなった。
いったん家のなかに引き返し、立てこもろうかとも考えた。
ただ、私が引くのは違う気がした。私と彼女の問題ならそれでもよかった。でも今回ばかりは、私が引くわけにはいかないのだ。
私は怒っていた。
怒っていたのだと、いまさらのように思う。
短い階段を下りて、道路に足をつける。
無視はしない。
しっかりと目で彼女の顔を、姿を、一瞥する。タイツが温かそうで、それいいな、と思いながら歩を進めた。
彼女は私の名を呼んだ。呼び止めたと言っていいだろうそれを私は振り切った。
これは無視ではない。
いや、無視かもしれない。
ただ私のほうには彼女のそれに応じる道理がなかった。すくなくとも彼女には私よりさきに謝罪すべき相手がいるはずだ。
ひょっとしたら私の与り知らぬところでユウナと彼女とのあいだに何かしらの接触があったのかもしれない。ただ、それでも私はユウナから直接そのことを聞かなければ、私の独断で彼女との縁を結び直す真似はできない。
足音が追ってくる。小走りだ。
待ってよ、と肩を掴まれ、私は身体を揺すって振り払う。足は止めない。
彼女が何事かを言っている。声量はそれほど高くはないが、キンキンと肌を刺すような響きを伴っていた。
走ってしまおうか。
でも追いかけてきたら、さすがに可哀そうになって立ち止まってしまいそうだ。一顧だにせずこのまま進んだほうがよいのではないか。
思いながらすでに足は小走りになっている。追いかけてくる足音が徐々に遠のいていく。
パン屋のまえを通ると焼きたてのパンの甘い香りが鼻をかすめた。
そういえば、と思いだす。前にもこんなことがあったな。
あのときも彼女は私を追ってこなかった。
こんどもそうなのかと思った矢先に、遠くなりつつも未だに彼女の足音がするのに気づく。私の名を呼んでいる。待って、とか、話を、とか途切れ途切れに叫んでいる。しかしその声は確実に遠のき、かすれ、町の喧騒にかき消されつつあった。
足取りが重いのだ。
思い到ったときには、曲がり角に差し掛かっていた。いったん曲がってから歩を止める。彼女から私の姿は見えなくなったはずだ。それでも足音の律動は同じテンポを刻んで聞こえる。
足を引きずるようなバランスに欠けた音だ。
何かを持っている。それも、けっして軽くはない代物だ。
身体はさきを急ごうとしているのに、どうしても気になって、ああもう、と地団太を踏んでから私は、こっそり曲がり角の壁からいま来た道を覗き見た。
彼女は紙袋を両手で抱えて、よたよたとよろけていた。駆けるどころか、小走りですらなく、いまにもへたりこんでしまいそうな足取りだ。
千鳥足、死に体、満身創痍――とまでいくとさすがにいきすぎな気もするが、彼女はもはやまえを向いておらず、視界からはとっくに私の姿は消えていた様子だ。
それでも追うのをやめない姿に、罪悪感が喉元まで競りあがる。
話を聞くくらいはしてあげてもよいのではないか。
すくなくとも、ここで彼女を無視して置いてきぼりを味あわせるのは、私の信念に反する。信念と言うとなんだか大袈裟になってしまうが、要するに、これはイジメではないのか。私は私を嫌いになりそうで、そのことにひるんでいる。
それはそれで我が身可愛さの保身のようで気分のよいものではない。どうすればよいだろう、と顔を引っ込め、いまいちど考える。
考えながらも足は引き返すことなく、学校へと向いている。
歩きだすと、徐々に考えはまとまった。優先すべきはまずはユウナであり、背後でよろけている彼女ではない、との結論に結びつく。
すこしくらい痛い目に遭ったほうが彼女のためだ。
そうだ、そうだ。
これはけっして、かつて私にがらんどうを植えつけ、私から声を奪った彼女に復讐するための考えではない。そうつよく念じながら、すこしの清々しさと、やはり罪悪感を拭いきれずにいるのだった。
ひと足先に学校に着くと私は、朝の時間のチャイムが鳴るまでじぶんの席から動かずにいた。ユウナは隣のクラスだから、廊下にでれば、通学路に置き去りにしてきた例の彼女と鉢合わせしてしまい兼ねない。
危惧した割に、けっきょく件の彼女はチャイムが鳴るぎりぎりになって教室に入ってきた。今朝がた見かけた紙袋を持っておらず、どこかに置いてきたのだ、と思った。
どこにだろう、と考え、それから私はいくつかの候補、たとえば廊下のロッカーだったり、ほかのクラスの誰かへの贈り物だったりしたのだが、ともかく私は、つぎに彼女から話しかけられたら、こんどこそ応じようと心に決めた。
「聞いてよアイツ、こんなの持ってきやがった」
昼休みになってユウナが弁当を持ってやってきた。脇には見覚えのある紙袋を抱えている。
クラスの大半は食堂に出張り、いない。この時間帯の教室には私たちが二人きりだ。箱庭と言っても過言ではない。半ばクラスメイトたちがわざわざ席を外して、私とユウナをこの場に取り残すような作為を感じなくもなかったが、それはそれで配慮してくれているとも捉えられるし、さわらぬ神になんとやらを地で描いているだけだとしても、すなわち私たちが神のようなものだ、と解釈できなくもなく、端的に害はないので、甘んじてこの教室の孤島を味わう日々を送っている。
「朝きたらアイツがクラスで待ち受けててさ。うちの席に、椅子じゃなく机にケツつけて、何様だってんだ」ユウナは弁当のつつみをほどく。「弁償するってソレ押しつけてきやがって」あごをしゃくり、紙袋を示し、「本のことは誤解だけど、じぶんが元凶みたいなものだからって。言い訳がましくガガガガってしゃべってって、いっぽうてきに、うちなんかここにいないみたいにさ。謝罪する顔じゃねぇっての」
誤解ってどういうこと、とまずは訊いた。
「なんか、ほかのコが勝手にやったことだって。じぶんは何も言ってないって。信じられるわけねぇじゃんね」
じぶんの態度が周りに誤解を与えてしまったかもしれない。周りのコもよかれと思ってやってしまったことで、みないまはやりすぎたと反省している。元はじぶんとあなたの喧嘩が元だから、これはあたしたちで解決すべきことだ。だからまずは誠意を示すので、これで水に流してほしい。
まとめればそういうことを、つらつらとあのコはユウナに捲し立てたそうだ。
「知るかよ。んだよこれ。どうすんだよ、全部もう持ってるっつうの」
紙袋の中身は、私も以前にユウナから借りたことのあるマンガ本一式だった。買えばこの国でもっとも高い紙幣を二枚使っても、お釣りはじゃりじゃりと小銭だけとなる。
「アイツの席どこ。返すはこんなもん」ユウナが教室を見渡す。「ねぇ、どこってば」
私がなかなか反応を示さないからか、机のしたで脚を小突いてくる。私は、八つ当たりしないでよ、の抗議の眼差しをそそぐ。すこし悲しそうに唇をとがせてみせるのは、この半年に身に着けた私の処世術だ。
愛嬌を滲ませた甲斐があったのか、ごめん、とユウナは謝罪した。素直だ。
「でも、こんなんで許せないのはわかるでしょ。いまさら仲良しこよしなんて、たとえフリでもやなこった」
だってそうじゃん、とハンバーグを一切れ箸で挟んで、あーん、としてくるので、私はありがたくいただいくことにする。美味しい。
「食べたね」ユウナがにやりとしたので、咀嚼を中断する。逡巡しつつもごっくんの衝動に抗いきれずに、呑みこんだ。
目で、なに、と問う。
「食べたね。借りができたね。もううちを裏切れないからね、だってそうでしょ、そうだよね」
元々裏切るつもりなんてないし、そんな局面に立つ予定もない。
「前々から疑問だったんだよね。なんかべつに、うちらはただのマンガ同好会のよしみみたいなもので、こういう言い方するとなんだろ、束縛激しい恋人みたいでやなんだけどさ」
私は口を閉じたまま舌で歯のまわりを舐めとる。ユウナは続ける。
「どっちの味方なわけ」
ハンバーグはもうないのに私はまた、ごっくんと喉を鳴らす。
「まさか本にあんなことした相手のこと許そうだなんて考えてないよね。許してあげようよ、なんて言いだしたりしないよね。あっちはトコトンこっちのこと無視して、だって見てよこれ」
ユウナが腕を広げる。がらんとした教室に、静寂が浮きあがる。
「あのひと、じぶんじゃ何もしてない、命じてないとか言ってるけど、じゃあこれなんなん。アイツの影響ありまくりじゃん。それでいて何も動こうとしないで、はいコレってこれ見よがしな、誠意の感じられない贈り物されて、許せってほうがおかしいでしょ」
火に油、と文字が脳裡に浮かぶ。
動機はともあれ、あのコはユウナに謝罪をした。それはあのコにしてみれば屈辱にちかかっただろうことは私であっても推して知れる。それでもあのコはユウナとの仲をいまよりもマシな方向に修正しようと試みたのだ。
なぜかは詳らかではない。訊いたところで、当の本人がそれをはっきり言葉にできるのかも怪しいところだ。それでもあのコはユウナに謝罪をした。
だが、ユウナにとってそれは落とされた火ぶたに等しかった。宣戦布告も同然の侮辱に映った。
大炎上ではないか。
大爆発と言っていい。
それの火消しをどうして私がしなければならないのだろう。目のまえで私に当たり散らしているユウナにも腹が立つし、こんな事態を招いたあのコにも憤りが湧く。
かってにしなよ、巻き込まないで。
喉元までのぼった憤懣は、声になる前にまたハンバーグみたいにお腹の底に沈んだ。
私はユウナからたくさんの日々の癒しを受けてきた。それはときにマンガだったり、談話だったり、授業をサボるといった不良行為だったりする。でもこの関係は花に水をあげて、よちよち育んできたみたいに、一朝一夕で築かれる関係ではなかった。
それこそ、私のなかに巣食ったがらんどうに声を奪われていたあいだ、ユウナは私に水をそそぎつづけてくれていた。
私にがらんどうを植えつけたあのコと比べてどちらの関係がよりたいせつなのか、なんて考えるまでもなく、比較の対象になると考えるだけでもユウナへの裏切り、冒涜のように感じる。
いっぽうでは、ユウナは見境なしにあのコのことを毛嫌いしすぎだ。仲良くしなよ、とは言わないまでも、そこまで徹底して拒絶するのもどうなの、と思いはする。
今回の一件以外でも何かユウナにそうさせる拘泥のようなものがあるのではないか、と勘繰らずにはいられない。
だから手放しでユウナを肯定できないのだ。まるっと味方でいさせてくれればよいものを、そこらへん、人間関係って複雑、と気が重くなる。
「その顔は不満って顔だ。どこがダメ? うち、何かおかしいこと言ってる?」
さすがは長年私の友人をやっているだけのことはある。言葉がなくとも彼女をまえにすると私は雄弁になる。
「べつにいまさらあのひとと仲良くしたいわけじゃないんでしょ」
私がここで、仲良くしたいよ、と言えばおそらくユウナは食い下がったりはせず、ならそうしたら、と言うだろう。そして私から距離を置くのだろう。あのコにいまそうしているように。
仲良くはしたいよ、と私は言った。声にだし、言った。
そっか、とユウナが口にする前に私は、
「みんなと仲良くしたいよ」と補足する。「誰だからとかじゃなくて、みんなと仲良くしたい」
うまく言える気がしなくて、みんなと、を強調するよりない。
「うちはそうでもないけどね」
ユウナは言ったきり、お弁当をすっかりやっつけるまで、しゃべらなかった。
教室にクラスメイトたちが戻ってくる。あのコが戻ってくる前にユウナはじぶんのクラスに戻っていった。紙袋は私の席に置いたままだった。持っていって、とは言えなかった。
絶対に許さないつもりだった。マンガ本をダイナシにするなんて、それがじぶんの持ち物でなくとも腹が煮える。でも、わざとじゃなかった、と言われてしまったら、絶対に許さない気持ちから、「絶対」が抜け落ちもする。
これ、どうしよう。
ずっしりと腕にくるような紙袋をまえに、嘆息を吐く。マンガ本のレンガはロッカーにでも押しこめておこう。昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る前に、済ませてしまおう、と席を立ったところで、
「気に入らなかったんだ、それ」
うしろから声をかけられ、飛び跳ねる。びっくりしたぁ、と唇だけで唱えながら振り返ると、かつて私にがらんどうを植えつけ、いまは問題の種と化している女王蜂さまが立っていた。
私は彼女の存在よりも、こちらに浴びせるように視線を向けているほかのクラスメイトたちに鼻白む。
「謝りに行ったんだけど、あんまり受け入れてもらえなかったみたい」髪の毛をいじりながら彼女は、「それ、よかったらもらって。いらないなら捨ててもいいし」
もう片方の手で、しきりにスカートをにぎったり、離したりを繰りかえす。
捨てるなんてもったいない。ただ、私がもらうわけにもいかない。
かといってこのまま突き返しても彼女のことだから、自分の手で捨ててしまいそうだ。彼女の誠意を無駄にするのも何かが違うような気がした。
けっきょく私は考えあぐねた挙句、財布を取りだし、そこに仕舞ってあった紙幣をあるだけ彼女に握らせた。金額としては紙袋に詰まった本を買うにはもう半分くらい足りない。
「なにこれ、いいよ、もらえないよ」
それはこちらのセリフだ。
「それよりも」
と、口にした彼女の僅かに弾んだ声音に、とっさに耳を塞ぎたい衝動に駆られる。何か、そう、見てはいけないものを見てしまいそうな予感があり、それはどちらかというと私のための危機感というよりも、子どもがじぶんの誕生日ケーキを運ぶと言ってきかないときのような、覆水盆に返らずが脳裡をよぎるようなそういった嫌な感覚だった。
「もうこれで許してもらえたのかな。けっこうがんばったっていうか、つらかったんだよ、だって話しかけてもずっとそんな感じだったし、避けられたのもやっぱり、ほら、ね? あ、でもそうじゃなくて、べつに責めてるわけじゃなくって、だってわるいのはあたしのほうだし、だからこうして謝ったわけだし、でももう、こういうの終わりにしたいなって」
また前みたいに仲良くしよ。
差しだしてくる彼女の手を私は握り返すことができなかった。
彼女に透けて見える打算が、私に彼女への怒りを再燃させる。
椅子から勢いよく立ちあがり、じっくり彼女の手のひらに視線をそそいでから、何でもないようによこをすり抜ける。私の腕には紙袋が抱えられており、彼女の机まで移動すると、そのうえにわざとぞんざいにそれを置いた。
「え、なんで、わ、え、ありがとう?」
彼女が困惑している。座席まで荷物を運んでくれてありがとう? いやなんか違うな。そう戸惑っている様子がありありと伝わる。私はまたじぶんの机に戻り、こんどはまるでこの教室には私しかいないのだ、とじぶんに言い聞かせながら、ちょうどよく鳴った始業のチャイムを耳にする。
先生が入ってきて、さっさと席につけー、と声を張った。私のよこには未だに例のあのコが立っていたけれど、唾液を呑みこんだような音を残して、足取り重くじぶんの席へと戻っていった。
私の手渡した紙幣を彼女は握ったままだった。
返してほしいと思ったけれど、そのための行動をとるくらいならこのまま手切れ金と見做したほうが心の安寧は保たれそうだ。
「えー、泥棒じゃん」
放課後、ユウナにそのことを話した。私の怒りに共感してほしくて話したのに、いざユウナの髪が逆立つさまを目の当たりにすると、何かしてはいけないことをしてしまったような後味のわるさがこみあげた。だからなのかついつい、でもじぶんから謝ろうとしたのはよかったよね、と女王蜂さまを庇ってしまった。
「甘い。甘すぎる。どんだけ過保護だよ、ちょろ助だよ」
そうだよなぁ、としょげてしまう。もしかしたら、と思ってはいた。私はあのコに甘いのではないか、と。
どちらかと言えば、私から声を奪い、がらんどうを植えつけたという意味で、厳しめに接してきたつもりだ。ただ、そうした因縁から理不尽に彼女を傷つけてしまうのは私の好まぬところでもあり、差し引きゼロにしようと、いささか甘く接していたのかもしれない。
そっかぁ、そうだよなぁ。
ユウナから見てもそうなら、私はやはりあのコを特別視していたのだろう。本来ならばだいじなものを損なわれたユウナのほうに肩入れすべきなのに。
庇うべきなのに。
私が抱いている怒りの根源と同じことを、私はユウナにしてしまっていたのかもしれない。優先して考えるべきはユウナであり、私とあのコの縁ではないはずなのに、私はやはりあのコの肩を持とうとしていた。
「でもまあ、うれしいよ。ありがと。怒ってくれて」
ユウナはじぶんの下駄箱のほうに進路を曲げた。靴を履いた私たちは昇降口のさきで合流し、肩を並べて下校する。
振り返ったらあのコがこちらを見ていそうで、私は校門をでるまで足元の影を見詰めながら歩いた。ユウナはずっと一人でしゃべっていて、気づくとふだんどおりにマンガやアニメの話になっていた。ユウナはバス通学なので、ずっといっしょには歩かない。
ばいばい、とバスに乗りこむユウナに手を振り、彼女が座席に着く姿を見届けてから、遠ざかるバスとは反対方向へと私は一人で歩きだす。
いつも、このときに緊張しているじぶんがいるのには気づいていた。ひょっとしたらあのコがあとを追ってきていて、鉢合わせするのではないか、といった恐怖があった。それを期待といってもあながち間違ってはおらず、私はいつも期待が裏切られるたびに、安堵とすこしの寂しさを覚えるのだ。
いったい私は何をしているのだろう。
正しいことがしたいだけなのに。
本当はそんなことなど考えてはいないのに、正しさを指針にすることの気楽さには抗えない。
この日の帰路にも、つぎの日の朝にも、学校でも、放課後でも、あのコが私のそばに寄ってくることはなかった。
「諦めたんじゃない」
帰り道にユウナが言うけれど、愛想を尽かされただけだったりして、とおどけてみせる私は、無理に笑みを浮かべているのが、引きつる表情筋のお陰でよく判った。
「愛想なんかとっくに尽かしてるよ、こちとら、百億年前からな」
そっか、そうだよね。
私は声にだして、言った。ユウナとの会話ではもう、メディア端末を使うことはない。言い淀んでもユウナはちゃんと待ってくれるし、言い間違えも、ちゃんと指摘しながらに、何事もなく会話をつづけてくれる。母は私が素っ頓狂な言い間違えをすると、遠慮会釈なく笑う。私は笑われるまで、じぶんの言い間違えに気づかないから、そういうときはいっしょになって笑いながら、悔しい気持ちにもなった。
ユウナといっしょにいる時間では、そうした悔しい気持ちにならずに済んだ。
居心地がよい。
そのはずなのに、今この瞬間に胸に残留している感情はけっして上向きのふわふわではないのだった。
なぜだろう。
疑問しながらも、深く考えたくない気持ちそのものが、私に、私の意地汚さを突きつける。
後味がわるい。
もっとウキウキしたり、ワクワクしたり、たくさんお代わりしたいと思えるような美味しい気持ちになっていたい。マンガを読んでいるときや、新しい本を手に入れたときのあの感覚のように。
でも今は、本に目を落としていても、文章やキャラクターのセリフが、穴だらけのチーズみたいに不規則に欠落する。知らぬ間に私の意識はもっとほかのところに飛んでいて、それは虚構ですら届かない虚無の世界へと旅立っている。
がらんどうへと。
かつてそれは私のうちに根付き、広がっていたのに、いまではもう、私のそとに、手の届かないところに移ってしまった。
考えごとをしていたのがよくなかった。気づくと、右折するはずの道を通り過ぎていた。登校するときの道を辿っている。
要するに学校のまえまで戻ってきてしまっていて、何をしているんだか、と呆れるよりもさきに笑ってしまった。
誰かに見られていたら嫌だな。
思うものの、端から見たって帰り道を間違ってしまったなんて誰にも判りはしないのにと自意識の過剰さにうんざりする。
回れ道をする。校舎に背中を向けようとしたとき、昇降口からあのコが現れるのを目の端に捉えた。
気のせいかもしれない。
思うのに身体は振り返ろうとはせず、ふしぎなほど動悸を高鳴らせて、私に道をいそがせる。
大声がする。私の名を呼んでいる。
周囲の生徒たちがこぞって声のほうを向き、それから私のほうを見る。
声はまっすぐと私の背中にそそがれ、放たれている。
待って、お願い。
迫る足音に、私は化け物にでも襲われた羊みたいに駆けだしている。どうせまたすぐに諦める。ほらね。呼び声がやんでいることに気づき、足のちからを緩める。
けれど私はそこではたとして、また駆けだした。足音はさっきよりもずっと近くに響いて聞こえた。背後にまで迫っている。手を伸ばされたら捕まるのではないか、と焦るほどだ。うしろを見るのが怖い。ただ走るしかなかった。
息はあがり、身体はピンポン玉みたいに弾む。冬でよかった、と思う。汗を掻かない、それもある。スカートの下に短パンを着込んでいる。全力疾走するには都合がよい。
視界から生徒の姿が消えていく。このまま走りつづけると商店街にでる。朝とは異なり、夕方は買い物客でにぎわっている。さすがに衆目がありすぎるし、人通りの多い場所で全力疾走するなんて危ない真似は避けたかった。
路地を曲がり、住宅街へと進路を変える。
来たことのない道だ。
さすがに追ってはこないだろう。
ちいさな公園があり、そこを突っ切る。道路にいちどでてから、裏側のほうから回りこみ、もういちど公園に入る。ちょうどよく公衆トイレが目のまえにある。その陰に身をひそめた。
彼女は追ってきていた。
公園に入ってきて、ブランコのまえを横切る。道路にでるとひざに手をあて、肩で息をする。
あんなに髪を振り乱している彼女を見るのは初めてだ。風が吹くたびに髪の毛が空気の流れを浮き彫りにする。
彼女は迷った末にこちらから離れる方向に駆けていった。小走りではあったけれど、その姿からは惰性からは真逆の執念が見てとれた。
じぶんの息がまだ荒いことに気づく。休んでいるじぶんといまなお駆けつづけている彼女とを比べると、なんだかいたたまれない気持ちになる。
トイレの陰から抜けだす。ひと気が皆無なのを確認してから公園のベンチに腰かける。
疲れた。
声にだして言ったつもりなのに、うまく声にならなかった。
心で唱えるだけなら楽なのに。
しゃべることも、相手に想いを伝えるのも、どうしてこんなに面倒なのだろう。いっそのことすれ違うのが当たりまえの世のなかになってしまえばよいのに。そうすれば誰もが勘違いすることを前提に接しあうから、世のなかから勘違いや、すれ違いは減るのではないか。
意思を疎通できると思いこんでいるから人間関係がこじれてしまうのではないか。
端から人と人とは繋がりあえないのだとしておいたほうが好ましいのではないか。
糸は、互いに結びつこうとするからもつれるのだ。
思ういっぽうで、なぜじぶんはふたたびしゃべることを潔しとしてしまったのだろう、あのままずっと以前のように声を失くしたままでいればよかったのに。
そう思うじぶんがいる。
私のなかにはもう、がらんどうがぽっかりと空いてはいない。
私にそれを植えつけたあのコが、私からそれを奪ったから。
奪われてばかりだ。
そのじつがらんどうはそもそも彼女から植えつけられたものであり、そのおかげというのはすこしちがう気もするけれど、私はいま、ふたたびしゃべれるようになっている。
振り回されているだけではないか。
反面、彼女を振り回し、振りきり、こうして公園のベンチに腰かけているのは私なのだ。
このまま旅にでてしまいたい。見知らぬ土地で暮らしたい。たびたび胸に湧く衝動であるのに、私にはそれをする勇気も、行動力も、意思だってないのだった。
ふと足元に影が差す。
顔をあげる前に肩を掴まれた。
ブレザーのうえからでもその手のひらの体温が伝わった。
あごをあげる。視線のさきには誰もいない。
私はゆっくり顔をうしろに向ける。
彼女がそこに立っていた。
ベンチの背もたれを挟んだ、真後ろに。
かつて私にがらんどうを植えつけ、ふたたび奪い去り、そして私のそとにて、こうして虚ろな眼差しを以って、がらんどうはここにあるとでも誇示しているみたいに、彼女はそこに立っている。
「なんで逃げるの」
ホラー映画さながらのセリフを、彼女はだみ声で言った。母親に叱られ、もう知りません、と言われた子供が、どうして置いてくの、と母親に追い縋るような響きがあった。
私は首を振って、逃げてない、逃げてないよ、と無言の否定をしてみせるが、白々しいにもほどがある。案の定、
「なんでウソつくの」
却って彼女の情緒を不安定にさせた。「わるいことしたなって思ってるよ、ホントに、あたしがやったわけじゃないし、やれって言ったわけでもないけど、あたしのせいだって思ってるの」
両手をぶんぶんとマスカラでも振るみたいに上下すると彼女は一転、意気消沈した様子で、ベンチを迂回し、私のとなりに腰掛けた。
「許してほしいとかじゃなくて、でも誤解されたまんまなのはヤダ。あたしが嫌いになったらちゃんとそう」
言ってほしい、と続くだろうところで彼女は言葉を濁らせ、「言われたくはないけど、でも無視されるのはヤダよ。悲しいよ。避けられる人の気持ちがどんなか解かる? それでも追いかけて話を聞いてもらいたいって、必死なの。解かってよ」
それを言うなら、だいじなモノをダイナシにされた人の気持ちが解かるの、と問いたい。言ったところで、きっと彼女は、解かるよだから謝ってるでしょ、と頭ごなしにじぶんの意見を押しつけるだろう。本当にじぶんは解かっているのだろうか、と自問自答することなく、解かった気になって、こんどはじぶんが被害者のつもりで私たちのことを、私とユウナを責めるのだろう。
「また仲良くしたいよ。仲直りしてほしい。あたしがわるいのは解かってる。ごめんなさい。もうしない。誰にもあんなことさせないし、した人にも謝らせるから」
何様のつもりなの。
私はつぶやいた。こんどはちゃんと意識して声にだした。掠れた声だったけれど、それは言葉のカタチを伴った。
謝ってくれたのはうれしい。偉いと思う。私を慕ってくれるのも正直に言えば嫌な気はしないし、うれしいのかもしれない。でも、いくら謝られたって、傷ついた事実は消えないんだよ。ひどいことされた事実は消えないの。謝って済むことじゃないよ。すくなくとも私はそう思ってる。謝られたって、はいそうですか、なんて許せないよ。私のこと友達だと思ってて、すこしでもだいじにしてくれるつもりがあるのなら想像してみて。私のだいじなものを誰かに壊されて、すごく悲しくて、傷ついて、それでもあなたはその誰かを許してあげるの。謝ったからって、本当はそんなことしたいわけじゃなかったからって言いわけされて、はいそうですかって、許せるの。私のことだったら私は許すよ。でも今回はそうじゃない。私の友達が傷ついた。傷つけられたの。許せるはずもないでしょ。
ひと息にぜんぶをぶちまけたかったのに、私はためらった。
一瞬で巡ったそれら言葉が、すっかりじぶんに返ってきてしまうのが直感できたからだ。
私はいま、傷つける側に回っている。私は私が許せなくなる瀬戸際に立っている。
ただ、それを認めることは、とりもなおさず、私を追いかけ回し、私のよこに無断で座っている彼女が私にとってただのクラスメイトや他人ではないことを認めることでもあった。
もちろん彼女はただの他人ではない。かつて私にがらんどうを植えつけ、私からそのがらんどうを奪い去り、私にふたたびの声を、言葉を、与えた張本人だ。
端的に言って、腐れ縁と評すよりない。
比べっこをするのはおかしいかもしれないけれど、傷つけられたというならば私のほうが遥かに傷を受けている。ならばそれらの帳尻を合わせたってバチは当たらないはずだ。
すくなくともいま、彼女は反省しているとは言いがたい。彼女がどうしてそこまで私との縁が切れるのを嫌がるのかは知らないけれど、彼女がじぶんのしたことを心底悔いているようには思えない。
私がこのまま距離を置けば、また何かしら仕返しをするのではないか。彼女の言葉を信じれば、彼女自身はそもそも私たちを損なおうとしたつもりはなかったようだが、彼女が私たちを、すくなくともユウナのことをこころよく思っていなかったのは確かだろう。そしてその感情をあらわにし、ときには言葉にすらだしていたかもしれない。
それを聞いた取り巻きたちがどういう行動にでるかくらい、女王様にだって想像はついたはずだ。
たとえ想像がつかなかったのだとしても、ユウナの受けた傷をおもんぱかることはできたはずだ。ごめんなさい、で済むような話ではない。ましてや、ユウナから許されてもいないうちから、そちらをほっぽりだして私との仲を案じるなんて、そんなのは謝罪でもなんでもない。
反省などしていないのだ。
だからこんな真似ができるのだ。
私が避けるのも当然ではないか。
目のまえの彼女は、私が悪態を吐いたきり黙ってしまったからか、憮然としている。ひょっとしたら私のつむいだ、何様なの、が胸に突き刺さって動けなくなっているのかもしれない。
「絶対に許さない」
私は言った。声にだして言った。追い打ちをかけるように言った。トドメを刺すつもりで言った。
絶対に許さない。
かつて私が彼女から贈られたそれは言葉であり、私の内に根を張ったがらんどうの種と言ってよかった。
彼女の目が見開かれ、目玉だけがきょろきょろと虚空をさまよった。まるで掴むべき藁でも探しているかのような表情だ。
やがて彼女はうなだれた。魂が抜けたような姿は、妙に演技がかって見えた。
鼻につく。
そう思ったじぶんに失望する。
彼女のそばにいると私はどんどん嫌な奴になっていく。
それを彼女のせいにしようとしているじぶんに気づき、さらに胃が重くなる。
背を向け、私はその場をあとにした。足元を木の葉がカラカラと流れていく。
翌日、学校に着くと教室は騒然としていた。
私よりさきに登校し、教室でじぶんの席に座っていたあのコは髪をばっさりと切っていた。あれほどうつくしかった髪の毛を、耳が見えるほど短く、それこそうなじなどは、ゆびで撫でつければ順々に跳ねる毛先が見えるくらいに青々と。
クラスメイトたちは遠巻きに彼女を眺め、ときに話題にするためにわざわざ廊下にでてまで、彼女の噂をささめきあっている。
女王蜂から羽が失われたのだ。野次馬でなくとも関心をそそがずにはいられないのだろう。失恋、失恋、と単語が聞こえ、そんなんじゃないよ、と私のほうが反論しそうになる。
当の本人、転校生、私のがらんどうの生みの親はまるで聞こえていないようで、いいやそんなわけがないのだけれど、われ関せずを貫いている。
私はじぶんの席に着き、しばらくうしろを振り返らずに、ぼーっとした。
先生がやってきて、朝礼が終わって、授業がはじまって、休み時間、授業、休み時間、授業、昼休み、ごはん、授業、と淡々と時間が流れた。
放課後になるころにはもう誰も女王蜂からなぜ羽がなくなったのかを気にするひとはいなくなっていた。
慣れではない。
女王蜂は羽どころか毒針すら失くしていたのだ。着飾らずに言えば彼女、転校生、私のがらんどうの生みの親は、
「なんであいつしゃべらんの」
ユウナはバス停のベンチにどすんと腰を下ろした。「髪切って、しゃべらんくなって、うちのクラスまで、姫さまどうしたんだろって話で持ちきりだったわ」
どうしたんだろうね、と私は言う。ユウナがとなりの空いた席をぽんぽんと叩くのでそこにおさまる。
「うちはあの女がどうなろうと知ったこっちゃないけど、経験上まあ知っとるわけだ、あの女がどうにかなっちゃうときはたいがいそこにチミが関係しとるとね」
「あ、見て。鳥が飛んでる」
「チミ。話を逸らすのホント下手やね」
「うふふ」
笑ってみせるけれどユウナはそこで微笑みかえしてくれたりはしなかった。じっと見つめ返され、私は顔を伏せ、靴のさきで円を描きながら、
「追いかけられたから逃げただけだよ」と応じる。「許さないって言ったの。ぜったい許さないって」
「なんでまた」
「なんでって、だってユウちゃんだって許してないでしょ」
「そりゃうちはね」
「仲良くするなって前は言ってたのに」
「どっちの味方かって訊いただけだしょ」
「だしょ」
繰りかえすとユウナは、私の描いた円を足で消して、
「チミはすぐにそうやってあれやな」
「どれかな」
「ひとを茶化すのはやめい」
「やめい」
いちいちユウナの言い方がおかしくてついつい繰りかえしてしまう。太ももをつねられ、ごめんなさいをいそいで三回唱えた。
「なんかもう腹立つのもアホらしいわ」ユウナが立ちあがったので、バスが来たのだと判った。前かがみになって右側のほうの道を覗くと、遠くから四角い箱がやってくる。だんだんと大きく長方形になっていく。
扉が開く。むかしは扉が開くときに空気が漏れる音がしたんだってさ、とユウナがどうでもいいことを言って、はやく仲直りしろよな、といっぽうてきに吐き捨ててバスに乗りこみ、いなくなった。
苦笑する。その言い方には馴染みがあった。あまり琴線を揺るがせないマンガを読んだときに彼女はたびたびそうして登場人物たちの行動をさして、はやく何々しろよな、と言った。進展がなかったり、話の展開が遅かったり、つまらない問題にいつまでもまごついているとさっさとこうすればよいのに、と言いげに、結末を迫るのだ。
まどろっこしいのだろう。
しかしそれは読者たるユウナだからこそ見える結末であって、登場人物にとっては結果よりもその過程をどうすべきか、どれくらいていねいに歩んでいくのかのほうがだいじな気がする。
いまのじぶんがそうだからだ。
解かっているのだ。
怒りなんて抱えていてもじぶんにとっていいことはない。めいわくなひとのことでわざわざ思考をいっぱいにしてじぶんから不幸になりにいく筋合いはない。
さいわいと相手はもうこちらに絡んではこないのだ。ならばさっさとこのまま縁を切ってしまえば大団円、めでたしめでたしと終われるのではないか。
私とユウナとの吊りあいだけを求めればこんなに簡単なことはない。あのコとユウナとを天秤にかけて吊りあいを求めるからこんがらがるのだ。
要するに私はいまなおあのコをただの迷惑な他人だと割り切れていないだけの話なのだ。ユウナという友人の存在をよりどころにして私は、じぶんのためにあのコとの大団円、めでたしめでたしを迎えたいと欲している。
でもそう考えるじぶんを私はたぶん認めたくないのだ。
あのコの存在がじぶんにとって欠けては困る存在だと認めることになるから。
傍から見ているユウナからすれば、一目瞭然で、だからきっとああまでも呆れた顔で、さっさと仲直りしろ、などと口にしたのだ。
うちを言いわけに使ってんじゃねぇ、と叱られている気分だ。否、ユウナはきっとそう思っているに違いない。
見透かされている。
たぶん、私はあのコに痛い目をみてもらいたかっただけなのだ。当てつけだ。復讐だ。
八つ当たりではないだけで、私は単に、かつて私が植え付けられたがらんどうをあのコにそのまま返したかっただけなのだ。そうでなければ素直に私は彼女にこう進言して終わっておくべきだった、私に謝る前に許しを乞う相手がいるんじゃないの、と。
ただ謝れば済むって話じゃないと思うよ、と。
それなのに私は最善の助言を投げかけることなく不満だけを述べて、伝えて、突き放した。
過去、私が彼女にそうされたように、どうすれば許してもらえるのか、なぜそんなに怒っているのかすら説明しようとせず、敢えて理解させないようにすら言葉を濁して、気持ちに蓋をし、塗り固めた。
ただ、私にはそれをする権利がある気がするのもまた誤魔化しようがない事実で、同時にきっとそれすら私はじぶんに偽って、見て見ぬふりをしてきた。
夕焼けを目に留めて、じぶんが長いことベンチに座ったままなのだと知った。ユウナの乗りこんだバスのほかにも目のまえに何台かのバスが停まってはほかの生徒たちを吸いこんでいった様子が遅れて脳裡に蘇える。意識していなくとも目は映像を記憶しているのだなあ、と思ったけれど、そんなはずはない。無意識で映像をでっちあげて、記憶しているつもり、見たつもりになっているだけなのだ。
私はほとほとねつ造が得意なようだ。進路に困ったらねつ造屋さんにでもなろうかな、と想像して、なんじゃそりゃ、とあまりのでたらめ具合に、いよいよ頭がどうにかなってきた、とじぶんのゆがみ具合を自覚する。
いつの間にか自宅のそばにまできていた。もうあのコは朝に私を出迎えにはきてくれないのだろうな。思考が飛んで、また気づくとこんどはシャワーを浴びている。ちゃんと裸になっていて、どうやってここまできたのだっけ、と思いだそうとするときちんとここまでの道中、衣服を脱いで畳んだところまでを思いだせたが、それが正しい記憶かの自信はなかった。
ねつ造屋さん、と私はまた意味もなく唱える。
シャワーのお湯が肌を流れる。
目をつむる。心地よい滝に打たれる。
あのコはたしかに私にがらんどうを植えつけたけれど、それを後生大事に枯らさぬように、埋まらぬようにと手入れを欠かさなかったのは私ではなかったか。喉に異常がないにも拘わらずしゃべらずにいたのは私の勝手ではなかったか。
もちろん世のなかには精神的な傷によって声帯の異常とはまた別の因子でしゃべれなくなるひともいる。私もまたそれだとずっと思っていたし、私以外の周囲のおとなたち、学友、それこそあのユウナですらそう解釈していたに違いなかった。
でもそのじつ、私は本当にただ、しゃべらなかっただけなのだ。
一言でもしゃべってしまったら、私の内に根付いたがらんどうが、せっかく定着したがらんどうが、一瞬で埋もれてしまいそうだったから。
せっかくあのコが植えつけてくれたのに。
生みつけてくれたのに。
悪寒が首筋を伝った。頭からお湯を被っているのに腕の毛穴が閉じている。羽の毟られた鳥の皮みたいだ。なんとなくぽつぽつと雨の降るプールの水面を連想する。
浴室から上がる。自室ですこし勉強をしてから母に呼ばれて夕食を食べ、それからすこしマンガを読んで、そのままベッドに潜りこんで、ぐーすかふよふよと夢を見る。
私は犬と戯れている。本当は犬を飼っていた過去はないからこれは夢だと私は判る。とてもとてもたいせつにしていた子犬で、かわいくて、なついてくれて、私たちは互いに相手を必要としていた。なのにどうしてだかある日、子犬が私の手を噛んで、そのままどこかに消えてしまった。
私は傷ついた。
胸に走った亀裂をけれど私は癒したりしようとはせずに、それを塞がないように懸命にじぶんでこじ開けて、立派な立派ながらんどうに育てあげる。
目を覚ます。天井がぐるぐる回って見え、悪夢を見ていたのだとなんとなく思った。
窓のカーテンを開ける。日差しが眩しい。
肌寒くてストーブをつけて、またすこしのあいだ布団にくるまる。窓から眺めた道路には誰の姿もなかった。当然だ。ふしぎと気分は雨だった。
冬休みまで私はあのコと関わらなかった。機会がなかった。女王蜂の面影はなく、羽と毒針を失くした彼女は打って変わって存在感を失くした。彼女を崇拝していただろう学友たちも、何を投げかけても応じないのを認めると遠巻きになった。しだいに移ろうような変化ではなく、それは数日のあいだに完了した。
可哀そうに思うのがしぜんな状況のなかで、陰の一つでも滲ませればよいものを、あのコはいっそ清々しそうに恬淡としていた。
年末、年越しと過ぎていく。遠い国で物騒な事件があって、じぶんの手の届く範囲の悩み事がすこしだけちいさく感じられた。なんだか重力が増したのに呼吸だけはしやすくなったみたいなチグハグサにじぶんのさもしさを垣間見た。
いまさらな実感だ。
私はそもそも卑しくて、そういう人間だったのだ。
ユウナとは休みのあいだに三回だけ遊んだ。お互いに人混みが好きではないのでなんの変哲もない平日に、つまりクリスマスや元旦といった街が活気に満ちている日ではないときに、書店巡りやカフェ巡りをした。
ユウナはもう、あのコとどうなったかを口にしなかった。かってにしろ、と思っているに相違なかったけれど、それは怒っているのでも呆れているのでもなく、真実かってにしてほしいと思っているのだと私は知っている。ユウナにとってはもう終わったことで、あのコの存在はもうユウナにとっては遠い国の物騒な事件と同じ扱いなのだ。
新学期がはじまって、またすぐに春休みがきて、二年生になるとクラス替えがあって、もう私はあのコを学校で見かけることすらなくなった。ユウナとはまたとなりのクラス同士で、とくに接点は増えもせず減りもせず、それでいて春先の修学旅行だけは自由時間をいっしょに回った。
「休んだらしいよ」
いちどだけユウナが言った。空港からの帰りのバスのなかで、学友たちの大半がいねむりをしているなかで、車窓を眺めながらユウナは、
「ちょっと罪悪感」と口にした。
意図は汲めた。修学旅行中、あのコの姿を見掛けないどころか、到る箇所で一人分の欠けた席や余ったお弁当を目にしていた。
そうだね、と私は言った。チョコレートを一粒奪って、おいこら、とユウナに上品でない声をださせ、しんみりな空気を追い払う。
家のまえに母が立っている。出迎えてくれているのかと思い、ただいま、と近づくと、あらおかえりなさい、と母はいつまでもそとにいるので、どうしたの、ととなりに並ぶ。母はそらを仰いでおり、視線を辿ると屋根にツバメが巣をつくっていた。母が珍しそうにそれを眺め、来年もくるかな、と足元の白い糞の跡に目を落とす。迷惑がっているのか、それとも予想外のお客さんに気分をよくしているのかはその横顔からは窺い知れなかった。
月日はツバメが飛ぶように去っていく。気づくとツバメの巣からは雛の鳴き声が聞こえ、つぎに意識したときには親子共々いなくなっている。日が高くなり、蝉が鳴き、その亡骸がそらに足を向けてひっくり返って、赤とんぼが目のまえを横切る。通学路の街路樹が真っ赤に衣替えをし、落ち葉の絨毯が町を覆い、そしていつの間にか受験勉強に追われて、私の生活圏からはすっかり、がらんどうを愛でる習慣がなくなっていた。
受験があり、合格発表を迎え、私たちは卒業する。
「上京いいなぁ」ユウナがもらったばかりの卒業証書の入った円柱状の筒で肩を叩く。信号機が青になる。私たちは歩きだす。
「地元のほうがいいよ」私は街路樹の葉っぱをちぎり、捨てる。「家から通えるんでしょ、そっちのほうがよかった」
「じゃあ交換してくれ。独り暮らしをわしにくれ」
「遊びにきてよ」
「寂しくて死んじゃうってか」
「うん」
ユウナが歩を止めたので、どったの、と振り返る。「や、びっくりしたわ。きみそういうとこ素直やね」
「あなたがあまのじゃくなだけじゃない?」
「あ、クレープ食べてこうぜ」
すこし考え、あなただって素直でしょ、と思う。あまのじゃくからの連想で甘いものが食べたくなるだなんて玄関の開く音を耳にして駆け寄ってくる子犬じみている。
お互い、新しい生活の準備でいっぱいっぱいになる前に息抜きとして卒業旅行に出かけた。温泉巡りをして、美味しいものをたくさん食べた。カニと焼肉は素晴らしいと思ったけれど、予想外に食費がかかってしまい、予定よりも一日早く帰宅した。
「つぎはバイトしてお金溜めなあかんね」
「ユウちゃんさ」「はいな」「ときどき関西弁なのはなぜ?」
彼女はそこで眉をひそめ、いらんこと言うなや、と頬を赤く染めた。予想外の反応だったので、ごめんと謝罪したものの釈然とせず、彼女と別れたあと自室に戻ったさきで目にしたマンガ本、それはユウナからおすすめされた初期のマンガ本であったけれど、そう言えばこれにでてくるキャラも関西弁モドキだったな。
思いだして、
ああそういう。
私はユウナの意外な一面、というほどでもないけれど、案外にかわいいことするな、と長い付き合いの節目にてようやくというべきか、家族に向けるそれに似たほんわかを我が友に覚えた。
ユウナとはその後、引っ越しの手伝いをしにきてくれたのを機にしばらく会わずじまいとなった。
彼女が東京の私の住処に遊びにくることもけっきょくいちどもなかった。
近況報告すら半年もするとなくなった。
寂しい思いが湧いてしぜんなその境遇でなぜか私は何も感じなかった。大学に入ってからすぐにユウナに恋人ができたと聞いていたから、もう以前のようには付き合えないのだろうなとの予感があった。それを覚悟と言ってもよいのかもしれないけれど、どちらかと言えばすこしほっとした。
思っていた以上に私は薄情なのかもしれない。触れられる距離にいない相手と以前と同じような関係を結びつづけていく日々は案外に抵抗が大きく、率直に言って負担だった。
もちろんいまでもいちばんの友人はユウナだと胸を張って言えるし、爪の先ほども疑念はないけれど、それでもだからこそなのか、ユウナにはユウナの身近な人間関係を優先してほしいとの思いがつよく湧く。
何百キロもさきにいる私にわざわざマンガの話題を振らずとも、そばにいる誰かであっても同じようにユウナなら日々を楽しく過ごせるはずだ。そもそもを言えばわざわざ上京してきてまでマンガの話をするのは私のほうでもすこしと言わずして大いに不満だ。どうせならカフェ巡りでもしたい。
けっきょくのところ私たちの関係とはあの学校という極々狭い檻のなかで有効な絆だったのだ。
それをありていに楔や鎖と言い換えてもよい。
互いに縛りあって、寄りかかって、なんとか耐えていた均衡があったのだとあの環境から離れてみればしかと思う。
私とユウナ以外のほかのすべてが私たちを縛る縄であり、圧力だった。私たちは身を寄せ合い、くっつき合うほかに均衡を、輪郭を、自我を、保つ術がなかった。追いやられていたとまで言ってしまうとさすがにちょっと過去をとげとげしく形容しすぎで、あの学校はそこまで私たちを、すくなくとも私を損ないはしなかった。
けれども、やっぱり私はほかの誰とでもなくユウナでなければならなかったのだといまなら言える。私がユウナを頼っていたように、きっとユウナも私を頼って、触れたら脆く崩れてしまいそうな何かを互いに懸命に補強し合っていたのではないか、とどうしても省みてしまうのだ。
ほかにもきっと私たちみたいな分子がいて、互いにくっつき合うことでなんとかあの環境を漂っていられたコたちがいたはずだ。学校という場はそういうものであるとすら言えるかもしれない。原子のままでは漂えず、無数の分子によって場を保つものなのだ。
ふと私はそこで、たった一粒の、誰ともくっつき合うことのなかった原子の姿を無想した。
点となって存在するそれは、久しく忘れていたがらんどうの希薄さを私に思いださせた。
あのコはどうしているだろう。
いまになって私は気になった。誰ともくっつき合わずとも暮らせる環境にあって、私はすっかり意識の底に沈めて、なかったことにすらしていたかもしれないかつてのがらんどうの生みの親の顔を思い浮かべている。
それからというもの、たびたび私はあのコの顔を、姿を、ときには共に過ごした日々の記憶を振り返り、振り返り、回顧するようになった。舌のうえで飴玉を転がして味わうように、噛み砕きたいのにそうするのはもったいない気がしてもどかしい気持ちを楽しむように、むかしのじぶんの幼さを実感するたびにいまのじぶんの成熟さを知りたいがためにそうするかのように、私は日々のほんのすこしの何食わぬ時間、たとえばバスに乗っているあいだ、階段をのぼっているとき、書面に走らせる目が滑ってうまく文章が頭に入ってこないときなど、ことあるごとにあのコとの過去を、そして現在の有様を、思考の表層にとめどなく移ろわせた。
かといってあのコに会いたいとは思わない。連絡もとりようがない。メディア端末はとっくに新規にしていて、連絡先も失っている。
向こうから連絡がくれば応じるのもやぶさかではないけれど、そもそもあのコはもうおしゃべりではなくなっているのだと思い、その裏で、まさかまだしゃべらないままだなんてことはないよね、と不安じみた陽気が湧きあがる。
そんなわけがないのだ。まったくあり得ないとも思えなかった。馬のあたまから角が生えるくらいなら現実的にあり得そうで、だったらユニコーンだってこの世のどこかにはいるかもしれないと妄想を逞しくするのに似た他愛なさがある。
大学の長期休みはバイトをした。実家には戻らずに、ひとまず学生のあいだに社会人の年収くらいの金額を貯めたいなと考えていた。貯金が趣味というわけでもないのだが、かといってほかにやりたいこともなく、マンガや映画といった娯楽では、月にバイト代の半分を使い切るほうがむつかしいくらいで、いまの時代、たった一人で贅沢をするのも案外にむつかしい、と孤独な日々の豊かさをありがたく思う。
中学生、高校生のうちではまったく考えもしなかった考えをひまつぶしがてらに脳内で一人議論する。
知人と呼べるくらいの繋がりは大学でも結べた。反面、友人と呼ぶほどの濃ゆい関係、互いの私生活に干渉しあうほどの相手はおらず、下手をすれば誰も私の地元がどこかを知らない可能性すらあった。
私自身、ずいぶん長いこと地元の風景を思いだす暇がなく、いつの間にかどこに就職すべきかが私の思考野の大半を独占するようになっている。季節を感じた覚えがなく、駆け足で去っていったキャンパスライフを振り返る余裕もない。
勤勉だったのだ。それしかすることがなかった。みなはいったいどうやって時間をつぶしていたのだろう。日々を過ごしていたのだろう。大学生への憧れがあったかと問われたら首を傾げてしまうけれど、まったくなかったかと問われればこれもまた首を縦に振るのはむつかしい。
いざなってみたらこんな具合だ。高校生時代が懐かしい。
ことしの年末は実家に帰ろうと決意して、あとは勤勉に講義を消化して、テストを受け、単位を回収し、バイトを掛け持ちして打ち出の小づちに大判小判を蓄えた。
いまは魔法の小づちを振ればどこでも買い物ができる。便利な時代になったと思う反面、私たちは吹けば消えてしまう儚い何かをこの世の仕組みを動かす大きな大きな原動力にしてしまっているのではないか、と不安にもなる。
ひとからの評価の数がそのままそのひとの影響力として計上されるいまは社会だ。それだって必ずしも評価が可視化されたわけではないはずで、本当にたいせつな評価ほど可視化されにくいものなのではないか、とすら思うものの、あまりじぶんでも自信はない。
私は誰からもこれといって高く評価されていないし、された過去もない。
そう思い、ではあのコにとって私はどのように映っていたのだろう、といまさらながら気になった。いつだって私は私が彼女をどう思っているのかばかりに囚われていた。彼女が私にとってどういう存在であるのかがだいじで、彼女にとって私がどういう存在であるのかは二の次だった。
考えたことがなかったわけではない。
手帳を開き、ことしの正月は地元に帰ろう、と予定をそっと書きこんだ。
三年も経つと案外に街の外観は変わる。田舎ほど発展の余地があるからか、思っていた以上に駅前が小奇麗になっていて、駅の外装も近未来的な趣を醸している。
私はこの三年で何か変わっただろうか。
想像してみると案外に見えてくるのは、過去のじぶんを幼いと見做すだけの価値観の変容で、微笑ましいというよりもやはりどこか恥ずかしい。
過去のじぶんをじぶんと思えないと思うことすらあり、しかしそれを口にすることそのものが幼稚の塊のようにも思え、けっきょく私は私なのだ、と未だ熟しきれぬ我が身を歯がゆく思う。
おとなぶってみせるものの、玄関のピンポンを押さずにそのまま、ただいま、と家に入ったじぶんに気づき、三つ子の魂百まで、習性は成長よりもつよし、を感じずにはいられない。
母は白髪こそ増えたが変化はなく、父は一回り萎んで見えた。退職間際の引継ぎで忙しいのだろう。帰りが遅くてしょっちゅう飲んで帰ってくるの、と母は台所でぼやくでもなく言った。
「夜はどうするの」母がまな板を鳴らす。「予定とかあるんでしょ、お友達と会ったりとか」
「なくてすみませんね」
「あら。せっかくだから遊んでくればいいのに」
「家でゆっくりしてたいの」
「すっかり更けちゃって」
「せめて腑抜けたって言ってほしい」
「おばぁちゃん家には顔だせるんでしょ。年明けに行くから着いてきてね」
「お年玉まだもらえるかなぁ」
「ばか」
これをあっちに運んで、と皿を渡され、サラダを盛りつけてから食卓に運んだ。
思えば母はあれからいちども、あのコについて訊かなかった。つぎはいつ家にくるのかとあれほど楽しみにしていたというのに、卒業式までの期間、それからそのあと、いまに至ってもまるで私たちの縁がとっくに切れていることを見透かしているみたいにあのコの名を口にすることはなかった。
ひょっとした私が家を空けているあいだにあのコがここに顔をだして、母に事情を話している可能性もあったが、そこまでの行動力を羽と針を失くした女王蜂に幻視するのは酷に思えた。
あのコはしゃべれるようになっただろうか。
頭の片隅に張った蜘蛛の巣のようなその疑問は、たびたび私の視界に浮上して、かつて私の内側に根付いていたがらんどうがごとく、私からしばしの言葉を奪うのだ。
「ぼーっとしちゃってどうしたの」
「どうもしないけど」
「就職どうするの」
「えぇもうそういう話したくない」
「そんなわけにいかないでしょ。あんたあっちに戻ったらなかなか連絡くれないし。こういうときに話しといてくれないと」
あたかも、ふだんは自由にしてやってんだぞ、と釘を刺されたようでおもしろくない。とはいえ、正論ではあるのだ。
黙っているのも母にわるい気がして、しょうじきに打ち明ければ何も考えてはいなかったけれど、それでは納得してもらえないだろうと情勢を鑑みて、ひとまずゼミでいっしょのコが受けると言っていた企業の名前をつらつらと並べてみる。
思っていた以上に我が子が真剣に将来について考えていると勘違いしたのか何なのか、ひととおり企業名を唱え終えると、あらそう、と言ったきり母はエプロンを脱ぎ、食べましょ食べましょ、と食卓についた。
「お父さんは?」
「働かざる者食うべからず」母は箸を構え、いただきまーす、とグラタンの湖面に穴を開けた。
家に寄りつかなかったあいだに母と父の関係性にヒビが走ったのかと案じたが、二階から足音を立てて下りてきた父は居間に顔をだすと、しぜんなさまでじぶんでご飯とグラタンと取り皿を持ってきて、何でもないように席に着き、いただきますと唱えて、一口、二口、箸を進めたあとで、進路はどうするんだ、とうんざりする質問を投げかけてくるのだった。
年越しを家に引きこもって過ごした。正月は二日目になってから祖父母の家へと家族揃って出かけた。父が四日には仕事始めであるらしく、一泊して帰ってきた。
「お年玉もらっちゃった」
車のなかで父に報告すると、もらえるうちはもらっておけばいいさ、とお気楽な返答をいただき、母からは大きなため息をもらった。
駅前と違って住宅街はあまり景観が変わっておらず、なんだか懐かしさと安堵がいっしょくたになって車窓に流れる景色と共に流れては消えた。
スーパーに寄って今晩は焼肉にすると聞いて、こんなんだったら毎年帰省していればよかったな、と現金にも思い、声にだしてつぶやくと、母がまた大きなため息を吐いたので、なんじゃい、とすこし高めの焼き肉のタレをカゴのなかに投じた。我ながら家を離れて逞しく育ったと思う。
買い物を済ませまっすぐ家に戻るはずが、車はいつもの道をいかなかった。家に近づくにつれて鼓動が大きくなっていく。このままいくとあのコ、かつて私にがらんどうを植えつけた少女の家のまえを通ることになる。
そう気づいたとき、目のまえを空き地が素通りしていった。
あれ、と思い、釘付けになったまま後部座席で身体ごと振り返る。
「いつもの道が工事中でね。こっちのほうが近いんだ」
父は得意げに言ったが、私の脳内はそれどころではなかった。
あのコの家が消えていた。
引っ越したのだろうか。それはそうだろう、家がないのだから。
助手席の母を見たが、眠たげに欠伸をしている。思えば、あのコの家がどこにあるのかを母は知らないのだ。母のことだからきっとあのコにそれとなく、あなたのご両親にご挨拶をしたいのだけど、と申し入れたはずだ。そこであのコはおそらくそれをはぐらかしたに違いない。
想像し、そしてしばらくぶりに思いだす。あのコの家のことを。母親とあまりうまくいっていなかったあのコの私生活のことを。
大学に進学しただろうと想像するまでもなくかってに推し量っていたけれど、あのコはこの期間、どうやって過ごしていただろう。
何不自由なく進学した私は、のうのうと実家に帰ることもなく、それでいていざとなれば実家に泣きつけばどうにかなると高をくくって安全地帯に身を寄せている。
なんだか嫌な気分だ。
とてもとても、うんと気持ちがわるい。
腹の底がムカムカする、胸の奥がじゅくじゅくする。
「ほら着いたよ。荷物持ってきて」
父と母が車から下りる。買い物袋が丸ごと車内に置いたままにされていて、父が持とうとするのを母が諌めて、甘やかさないの、と聞こえがしに言う。
感傷的になっていただけに、こういうときに耳にする身内の声は、けっこう頭にくる。むしゃくしゃする。おもしろくない。
乱暴に荷物を持つと、卵入ってるからね、と母がすばやく釘を刺す。胸中を見透かされているようで余計に苛々した。大人げないので、この日は率先して母の手伝いをし、父におべっかを言って、親孝行、親孝行、とじぶんに言い聞かせながら、これだから実家は、とやきもきした。
予定では五日目にはアパートに帰る予定だったけれど、けっきょく五日目になっても私は家のコタツでぬくぬくしていた。都会に戻ってもとくにやることはなく、父は仕事で、母はパートをはじめていたり体操クラブに参加していたりと、家を留守にしている時間が多く、これだったらこっちにいたほうがお金も浮くし、ゆっくりできそうだと打算を働かせて、バイトがはじまる十日まではこっちにいることにした。
「子豚さんになっちゃうよ」
母に尻を踏まれながら、さすがに引きこもってばかりでは皮下脂肪さんがご成長あられるいっぽうなので散歩にでも出かけようと思い立ち、いそいそと着替えてそとにでた。
雪が積もらない冬は新鮮だ。これからはこっちがふつうになるのだろうな、と甚大な環境問題と引き換えにもたらされる雪掻きをしない気楽さを思う。
とりえず駅前まで歩いた。
通学路と同じ道だから懐かしさが込みあげる。細かなところで三年前と違っていて、それはたとえば電信柱が新しくなっていたり、あったはずの店がなくなっていたりと、生と死を彷彿とさせる栄枯のなせる業、といった塩梅で、この世の流れの無情さよ、のおとなびた嘆きを一つ、二つと、日差しの合間に息といっしょに吐きだしていく。
何歳になっても白くのぼる息はおもしろい。
駅ビルの地下で専門店をはしごした。コロッケを食べ、クレープを二個注文し、最後に餃子を買って、きょうの晩ご飯はこれにしようと決める。もちろん餃子は父と母の分も購入した。
クレープを二個仕入れたのは一個は家に持ち帰って食べようと思ったからで、ではなぜ一個をたいらげておきながら帰路を辿りつつすでにもう一個を頬張っているのか、については、思いのほか生クリームがアイスじみていて、手に持っているうちに融けだしてしまったからだ、とする言いわけを誰にともなく並べておく。
二個はさすがに欲張りすぎたかもと、もたれはじめた胃をなだめつつ、出掛けてまだ一時間も経っていない事実に、しぜんと脳裡に山間の小川の映像が流れた。ゆったりと流れるそれは、つぎの瞬間には、都会のナイアガラの滝さながらの濁流に様変わりをして、どっちもどっちだな、と両極端な流れの速さを天秤に載せているといつの間にかクレープは手元からなくなっていた。
帰路を辿っていたはずなのに、立っていたのは家に向かう道ではなかった。
身体が憶えていた。
休日になると私はよくこの道を歩いていた。
美術館がある。名もない芸術家の記念館じみているそれは、骨董屋みたいな造りだ。都会の街でいちど入った老舗のカメラ店にも内装がどこか似ている。
引き返すことなく私は美術館の入口に立ち、自動販売機で入場券を購入して、なかに入った。館長らしきひとをときおり見かけたことはあったけれどいつもはほとんど無人で、キセルをしようとすればいつでもできるな、と防犯意識の低さに心配するよりさきに、そんな人物など端から想定していない姿勢を好ましく感じていた。
いまにして思えばそもそも、キセルをしてまでなかに入りたい、この作家の作品を観たい、と思うような人物がいるならば、そちらのほうが芸術家にとってはうれしいのかもしれない、なんてお門違いに想像する。
漆黒の遮光カーテンをくぐると、そのさきが展示ルームだ。
私はいつもこの瞬間、別の世界にきたような気分になる。プラネタリウムを眺めているときのような微かな高揚感が、宇宙服さながらに身体を包みこむ。
包みこむのだ、とやっぱりいまになってそう思うのであって、当時はなぜじぶんがあんなにも足繁く通っていたのかは解かっていなかった。いまだってなぜじぶんがこんなにもこの美術館に吸い寄せられるのか、未だに胸の高鳴りをほんのりと覚えてしまうのかは判然としない。
展示ルームは薄暗い。天井からのライトはなく、ガラスケースから透ける展示棚の明かりが床に、柱やじぶんの影を伸ばす程度だ。
空気が澄んでいて、あれっと思う。
記憶にあるかぎり、ここは年中埃っぽさが抜けなかった。足元も木の目が浮きあがって見えるくらいにつややかで、埃が溜まっていない。
掃除をするようになったのかな。ひょっとしたら管理人さんが豆なひとに変わったのかもしれない。
妄想を逞しくしながら、かつての低位置、私がよく腰をかけていた長椅子のところまで歩く。
柱を一つ横切ったところで、はっと息を呑む。
誰かがすでに長椅子に腰掛けていた。
存在感がなく、初め人形か何かかとぎょっとした。
近づかずに、身体を傾けて、その横顔を覗き見る。暗いし、距離があるのでよく見えない。女の人だと判ってほっと息を吐く。
暗がりに異性とふたりきりはやはりすこし怖い。これも男女差別になるのかな。
引き返そうかとも思ったものの、それはそれで失礼に思え、しばらく展示物を見て回ることにした。当分またここにくる機会は巡ってこない。
改めてじっくり作品を眺めて歩くと、思っていた以上に新しい発見というか新鮮な驚きがあって、いったい私はあのころ何を見ていたのだろうね、とふしぎな心地になった。
ふんふん、とじぶんの思いがけない変化を如実に感じて私は気分をよくした。そのままぐるっと展示物を追いかけていくと、例のソファのまえにやってきていて、そのまま通り過ぎればよいものを、ぎくりとしたらうしろを意識してしまったが最後、気づかなかったフリをするのは無理があるし、かといって振り向いて挨拶をしたのでは最初から気づいていたと白状したようなもので、どうしたらよいだろう、と考えてしまったらもう、身動きがとれなくなってしまった。
ぎくしゃく、なる言葉のぴったり具合に感動してしまうな。
どうせきょう以外では足を運ぶことはないのだ。
気を使うのも愚かなり。
腹をくくって、私は愛想笑いってこれでよいのだっけ、とじぶんの不器用な頬の筋肉と会話しながら、背後をちらっと、しぜんなさまを意識して振り返る。
ソファの人物はとっくにこちらを見上げていて、座ったままの姿勢でありながらまえのめりになっていて、身体をななめにしてこちらの顔を覗きこもうとしていた。じっさいに覗きこまれていて、私たちは目を合わす。
会釈をした。
そうしようと思っていたから身体の所作を止められなかった。
相手はしかし私のそれに反応を返すことなく、目を見開いたまま、思考停止状態を地で描き、私に唾液を呑みこませるだけの猶予を与えた。
ごっくん。
大きな音が鳴り、というのも、それが大きな音に感じるほどにこの空間が静かなだけの話なのだけれど、私はしばし呆気にとられた。
薄暗いせいもあるのだろう、それにしてもどうしたことか、目のまえにいる女性はどうにも高校生だったころの私に似た髪型に、いでたちで、背格好もなんだかかつての私を見ているようで、鼓動が大きく高鳴った。
分身かと思った。
だがそんなわけがないもので、しかしそれにしてはむかし私が身にまとっていた服装に似ているなあ、と客観的に眺めたじぶんのファッションセンスを、それほどわるくないな、と思うくらいには冷静さを取り戻す。
ああどうも、と声にだして挨拶をしようとして、さらに私の鼓動は高鳴った。
目のまえの人物は、私が気づいたことに気づいた様子で目を伏せる。
ずいぶん変わったな、とまずは思った。
否、これは変わったわけではない。
この三年間、彼女は何一つ変わらずにいたのだ。
直感したそれが外れていてほしいとの祈りのようなものを胸に私はまず、あれ、と声にだし、久しぶりだねぇ、と過去のわだかまりなどとっくに忘れてしまった、そんなものは私たちのあいだにはなかったのだと暗に示そうとしたが、彼女にうまく伝わったかは判らない。正直に言えば自信はない。
彼女がここにいるのは偶然なのだろうか。街中で私を見かけて、先回りして待っていた、という可能性はあるのだろうか。
そう考えることがまず以って彼女への冒涜にあたると判っていながら、私はつぎからつぎに湧いてくる妄想を拭い去ることができなかった。
かつての私に似た髪型をし、服装まで真似て、いいやそれを偶然なのかもしれないと想像するだけの理性を私は働かせることができるものの、それにしたって二十歳を超えたおとながする格好にしてはいささか幼い。
とはいえ、かつての私はいまと同様に質素な格好を好んでいるから、言ってしまえば私だってあのころからたいして服飾の嗜好は変わっていない。質素ゆえに、却ってちょうどよい塩梅に落ち着いたと言えたかもしれない。
それこそ三年前の彼女がとっていたかっこうこそが、女子高生という初々しい時期のみに許される幼さがあったのかもしれず、たしかにそう考えてみるとあのころの彼女のかっこうをいまのじぶんがしたらコスプレもよいところだと想像し、すこしおかしくなって、はは、と声がでた。
彼女がこちらを怪訝そうに見上げる。
まずは、久しぶり、と声をかける。いまこっちに帰ってきてて、と続けてから、あっ憶えてるかな、と白々しくも言い添える。「ほら、むかしいっしょに遊んだりして」
彼女は頷いた。私がどこまでそれを本気で口にしているのかを推し量れていないような戸惑いがちな目のまま、ゆっくりと首を引く。
「懐かしいなって思ってきてみたらびっくりだよね。ここにはたまにくるの? ていうかまだこっちに住んでるんだね」
言ってから、何か地雷を踏んだ気がして、はっとする。彼女の家はすでにないのだ。空き地になっていた。
言葉を探すがうまくいかない。彼女がふたたび目を伏せた。恥辱の念を隠そうとする素振りからは、私が踏んでしまった地雷がまさしく地雷だったのだと判らせるのに充分であったし、私がこうしてあけてしまった沈黙の意味するところが彼女に伝わってしまったこともまた容易に私に伝わった。
「えっと、じゃあ、うん。元気そうでよかった」
会えてよかった、と言えればよかったものの、そう口にできない空気に逃げだしたくなり、そして私は逃げだした。
彼女が縋るようにこちらを見上げた。私が目を逸らすと、視界の端で彼女がうつむいたのが判った。
このまま出口に直行するのはあからさますぎるので、飽くまで展示物を見終わったから帰るのだと示すように、私は壁沿いに並ぶ展示ケースをなぞるように、つぎの壁にぶつかるまで歩を進めた。
右を向けば出入り口があり、もちろんそこには暗幕が下りているからそれをくぐらなきゃいけないわけだけれども、私はそこで首だけでソファのある場所を見て、そこにいる彼女に、じゃあね、と手を振ってみせる。
薄暗く、柱の陰にもなっているから、角度からして彼女の姿は見えず、彼女がこちらを向いているのか、声が届いたのかすら判らずに私は暗幕をくぐり、懐かしい異世界の空気とさよならをした。
美術館とは名ばかりの銭湯に似たつくりの玄関口を抜けると、ちょうど頭に鉢巻をしたご高齢の男性とすれ違った。
会釈をして通り過ぎたが、背後でそのひとが歩を止めた気配があったので振り返る。
そのひとは首を傾げ、こちらを見ていた。美術館の看板をゆびさし、
「お客さん?」と目を見開くようにした。
「あ、はい」
「ずいぶん珍しかったもんで」
「はあ」
「常連さん以外で初めて見た気がしますよ」
そこにきて、きっとこのひとが管理人さんなのだ、と閃いた。館長と呼ぶにはいささか和風に寄っていて、和尚さんといったイデタチだ。
「なかにお客さんが一人いらっしゃったんですけど」
それが常連さんなのか、と問うと管理人さんらしきひとは、そうそう、とうれしそうに、きょうも来てたんですねよっぽど好きなんでしょうねえ、と目じりのシワを深くした。
じつは私もむかしはよく足を運んでいたんですよ、と嫉妬ともつかぬ反発心から打ち明けようかとも思ったのに、管理人さんらしきひとは続けて、
「むかしからですよ。ずっと幼いころからここにいらっしゃっててね。まあ、高校生くらいになってずいぶんおしゃれになってしまって別人みたいに別嬪さんになって、まあそれでもこうして通ってくれているから掃除もサボるわけにいかなくてね」
愚痴ってわけじゃないですよ、とそのひとは微笑む。
「むかしからなんですか」
そんなはずはなかった。すくなくとも私が通っていた時期にはほかに客はなかった。ひょっとしたら私と勘違いしているのではないか、と当て推量だが考える。
「むかしからですよ。ここ数年でますます別嬪さんになられて」
外見の美しさを念を押されて強調されてしまっては、なるほどだからかつては手を抜いていた掃除をここ数年は念入りに行なうようになったのか、と管理人さんらしきひとの心中を推し量るのに躊躇はない。
まあ、解らないではない。
外見の差異で扱いを変えるのは褒められた所業ではないにしろ、私だってかつてあのコに懐かれてそれほどわるい気はしなかった。
そう、わるい気はしていなかったのだ。
友人としてただ慕ってくれていたのなら。
幼馴染としてしぜんに接してくれていたのなら。
「毎日来られてるんですか」
「ワタシですか?」
「いえ、常連さん」
「毎日ってこたあないでしょうがね。ワタシも休日のたまにしかこんでしょう。そういうときでもいらっしゃるんで、まあ、すくなくとも休日にはいらっしゃってるってことなんでしょうが。芸術家冥利につきますねえ。作家さんもさぞかし天国でよろこんでいらっしゃるでしょう」
その作家とあなたの関係は何なのか、と気になったが、それよりも私はなぜ彼女がこの数年間、高校を卒業してからいまに至るまでに足繁くこの美術館に通っていたのかを考えた。
何度思考を巡らせても結びつく像が一つある。
ここはそう。
私は美術館の屋根を見上げる。
私と彼女の再会の場所だった。
四年前、私はここで彼女と言葉を交わし、がらんどうの生みの親との邂逅を果たした。縁を結び直した。
高校を卒業して、別れの挨拶もなくチリヂリになった私たちのあいだには縁と呼べるものがまだ結びついているのだろうか。
私は踵を返し、入口に立つ。もういちど入場券の自動販売機にお金を投入しようとすると、管理人さんらしきひとに、あれいま観てきたんじゃないんですか、と驚かれたので、忘れ物をしてしまって、と言いわけする。
「ならそのまま入ってもらって構いませんよ。立場上こう言っちゃならんのでしょうけど、まあ、つぎも黙って入ってもらって構わんですよ。誰も怒りゃしませんのでね、それよりぜひまたきてやってください」
太っ腹なのかずぼらなのかの判断に困る。私は黙って会釈をして、ふたたび暗幕をくぐって、暗がりにくるまれる。
彼女はまだ同じ場所、ソファに座っていた。
足音で気づいているだろうに、彼女は顔を伏したままじっとしている。私がまえに立つとようやく垂れた前髪をそのままに、こちらを見た。
「それは当てつけ?」
彼女は黙っている。
「ひょっとしてあれからずっとしゃべってないの? 私の真似してたの? ずっと? この三年間? そんなわけないよね」
そんなわけないって言ってほしくて私は続ける。「怒ってるなら謝る。あのころ私たちちょっとどうかしてたと思う。私にも落ち度があったって思ってる。だからもうこういうの終わりにしよ。ね?」
彼女の目つきが険しくなったので私は気圧された。
彼女のぴったり貝みたいに閉じていた唇が開く。竹に走る避け目を連想する。戸惑いがちな呼吸が聞こえ、それから彼女は声を発することなく下唇を噛みしめた。喉の鳴る音が暗がりに反響し、彼女の足元にぴちょんとしずくが垂れる。彼女はひどく汗を掻いていた。
「怒ってて言葉を失くしちゃったの? それとも償いのつもりなの?」
どちらにしてもあまり意味のない問いかけだとじぶんでも判った。きっかけがどうであれ、いま彼女がこうしてしゃべらないでいるのは彼女の意思であり、そうありつづけてしまった彼女の問題だ。自己責任ではない。きっかけを辿ればそもそも彼女がかつて大昔、私にがらんどうを植えつけたりしなければこんなことにはならなかったのだ。
絶対に許さない。
彼女が私に言い放たなければ。
そして私が彼女に、言いかえさずにいてあげたら。
「私、もうなんとも思ってないよ。ホントだよ。もしかしたらあなたがここに通っていることも、私とこうしてしゃべってくれないことも、私とは関係のないことが原因かもしれないけど、念のために謝らせてね」
ごめんなさい。
口にしようとしたところで彼女の鋭い目つきが私の身体を貫いた。殺意ともとれるつよい怒りの波動が伝わった。
でもどうしてそんな顔をされるのかが判らなかった。
謝ってはいけないのだろうか。
それとも言い方がマズかったのか。
憐れんだのがいけなかったのか、それとも彼女がこの三年間に募らせていた私への想いと私が彼女にそそいでいた関心が吊りあわないことへの不満だろうか。
やっぱりじゃあ当てつけだったのか。
彼女は私を困らせたくて、傷つけたくて、罪悪感を植えつけたいがためにそんな同情を引くような自虐をつづけてきたのだろうか。
あのとき私が彼女よりもほかの友人を選んだから。優先したから。許さないなんて暴言を突きつけてしまったから。
彼女をとことん傷つけてしまったから。
傷つけてもよいと思ってしまったから。
だから彼女は私に復讐をしようとしているのだろうか。
だったらそれは失敗している。
私はもう、あなたにかけてあげられる情もやさしさもなくしてしまったから。
「まだ許してくれない? また『絶対に許さない』を私にぶつけるの? でも私はもうあなたに許されたいとも思わなくて。ただべつに嫌いじゃないよ。嘘じゃなくて。だから私のあのときの言葉――憶えてるか分からないけど、絶対に許さないって言ったこと、あれはわるかったと思う。許すよ。怒ってないよ。でもだからってあなたを傷つけたかもしれないこと、許されたいとは思わないから、好きなだけそうして恨んでくれてていいから」
それだけ。
ただそれだけ知っておいてほしかっただけ。
彼女の肩に、おっかなびっくり手を置いて、じゃあね元気でね、ばいばい、と私はふたたびのさよならを告げた。
正真正銘、こんどこそ本当のお別れだと思った。
彼女の肩まで届く髪の毛は私の記憶にあるものよりずっと色褪せていて、鏡を覗いている気分になった。
暗幕を手で押し退けると、背後から大きな音が鳴った。視線を向けると彼女が立ちあがっていて、ソファが柱の位置からズレていた。彼女が勢いよく立ちあがったせいかもしれないし、ひょっとしたら蹴ったのかもしれない。
肩を怒らせて文句を言いたげに顔面を歪ませて彼女はじっとこちらを睨みつけている。
罵詈の一つでも投げて寄越してくれればよいのに、それでも彼女は頑なに言葉を発しようとはしなかった。
このまま立ち去ってもよかったけれど、なんだか私は彼女のことがかつてないほど痛ましくて、可哀そうで、けっして触れあいたくはないし、縁を繋ぎ直したいとは思わないまでも、愛おしく感じられて、だからなのか、私のかってな幻想かも知れないけれど、彼女がかけられたがっている言葉がしぜんと、なぜかふと、口を衝いている。
「さっきのはぜんぶ嘘」
暗幕の裂け目からそとに出て、私は顔だけを中に入れ、
絶対に許さない。
けして覆らない決定事項だと突きつけるように、植えつけるように、そう告げた。
みずから育てた巨大ながらんどうのなかで、彼女はなぜか、ふっとほころびる。
【がらんどうの根は甘く】END
「絶対に許さない」
彼女の目からは、私への破滅を望む炎が溢れていた。
つよい悪意をぶつけられ、そうして私は言葉を失った。初潮を迎える前のことだ。言葉だけでなく、人格そのものが消失したような空虚さに襲われ、それは立ち退くことなく私のなかに留まりつづけた。わだかまりつづけた、と言い換えても齟齬はなく、私は言葉を失い、底なしのがらんどうを手に入れた。
私がそうして言葉を失い、しゃべらなくなってから五年の月日が経った。私は小学生から中学生を越し、晴れて高校生となった。
しゃべれないのではなく、しゃべらないだけだと医師からのお墨付きをもらって以降、私はうるさくない女の子として、それなりに周りのコたちと仲良くやっていた。
大人たちも無理にしゃべらせようとはせず、それはなんだか女の子は静かで自己主張しないほうがよろしいよ、といった偏見のたまものでもあるように思えたけれど、すくなくとも私はそんな周囲の「臭くないなら蓋をせずともよしとするか」といった眼差しに支えられ、すこやかな日々を送っていた。
「いつからしゃべれないの」
ある程度の仲を深めた学友たちから、ときおりそのように話題を振られることはしばしばで、
なんとなく。
と、
いつも私は曖昧にノートに文字を書き、その場を切り抜けていた。
きっかけはあるのだ。
思いだしたくないきっかけが。
私は言葉を失くした人間で、けれど言葉に支えられた社会に生き、文字を介して意思を疎通する。
本来であれば、声を失くした、と形容すべきところではあるけれど、しゃべれないのではなくしゃべらないだけの私にしてみれば、それは正しくはないのだった。
「ええ、転校生の琉紗那(るさな)イユさんです」
夏期講習のプリントを配ったあとで先生は言った。「夏休み明けからこのクラスの一員になるので、名前と顔を憶えてあげてね」
転校生は女の子だった。線が細く、なんだか白くて背の高い花を連想した。
ぼーっと眺めていると目が合った。彼女はその前からきょろきょろと目を泳がせており、落ち着かないというよりもそれはどこか挙動不審で、すらりとした背格好に反して、なんだか小動物じみていた。
いちど目が合ったのを皮切りになぜだか、彼女の視線は微動だにせず、私に注がれつづけた。まるで私の内側に塞がることのないがらんどうが開いているのだと知っているかのように、彼女は私をまっすぐと、私だけを見ていた。
嫌な予感はすでにしていた。彼女の下の名前に聞き憶えがあったからだが、すくなくとも彼女の名字は初めて耳にするものだった。
だから、おそらく、油断した。
先生が転校生へと自己紹介をするようにと促すと、そのコは、ハイ、と子猫の、みゃー、と鳴くような声で返事をした。そして彼女は彼女自身の来歴をつらつらと述べた。
彼女の声を耳にしたとき、私は明瞭に、自身のがらんどうが大きく波打つのを感じた。
彼女は言った。以前、この街に住んでいたこと。両親の都合で引っ越したこと。名字が変わったこと。以前は世に有り触れた名字で、ひょっとしたらこのなかに小学校のころのオトモダチがいるかもしれないことを用意してきた祝辞のように述べた。
目が合う。
ヒッ。
私は私の声を、五年ぶりに耳にする。じぶんだけに聞こえた幻聴かとも思ったが、周りの生徒が振りかえり、私の身体は硬直した。
顔が熱くなってしかるべき状況をまえにして、私はじぶんの顔面が蒼白になっているのだと俯瞰の視点でみずからを想像する。現に四肢は震え、ひたすら寒かった。
だいじょうぶ?
教室の静寂を破ったのは、教壇のうえに立つ転校生だった。
ヒッ。幻聴のように私の五年ぶりの声が脳裡にこだまする。
内なるがらんどうの生みの親。
彼女は五年分の成長を経て、私の記憶のなかにある姿とは別物だったが、たしかにその片鱗を、面影を、彼女の夏の木陰のようなどこか心に染み入る声音に窺うことができた。
彼女はもういちど自身の名を、旧姓で名乗り、みなさんよろしくおねがいします、と折り目正しくお辞儀した。
私への破滅を願う炎が、私だけに視える蜃気楼のように、彼女の涼しげで、うるわしい姿に重なって視えている。
翌週から夏休みなのはさいわいと呼べた。転校生こと琉紗那イユは夏休み明けからの合流で、それまでは学校で顔を合わせる危険はない。
そうだ、これは明確に危機ではないか。
耳に染みこんだ、じぶんの「ヒッ」が、いくども、ことあるごとに反響する。
きっとあのコは気づいているはずだ。
考えすぎや思い過ごしを念頭におくよりも、そう考えたほうが私にとってはしぜんで、より安心できる懸念だった。
嫌な予感は留まることを知らず、サイレンのような耳障りなカタチを帯びて、私の脳内をチクチクと占領する。
嫌な予感ほど的中するのはなぜなのか。
科学の発展目覚ましい現代にあって、どうして誰もこの問いに答えてくれないのだろう。ひょっとしたら、認知バイアスの一言で片づけられてしまうかもしれないこの疑問に、私は「悪意」の関与を指摘したい。
嫌な予感とは、他者の悪意への防衛反応であると。
夏休み初日、私は陰鬱な気分を晴らそうと、街はずれの美術館に足を運んでいた。美術館とはいえど、一人の作家の記念館のようなもので、家屋もこじんまりとしていて骨董屋みたいだな、とくるたびに思う。
とくに好きな作家ではなかった。いつきても閑古鳥が鳴いているこの空間に身を置くのが私は好きだったのだ。
なのにこの日、私は初めて、私以外のお客さんがいるのを目にした。
ヒッ。
私はその場に踏みとどまる。
「あ、偶然」
彼女の物言いは白々しかった。近づいてくると、動けなくなったこちらを展覧物の一つであるかのようにぐるっとひと回りする。ひととおり、頭からひざの裏まで舐めるように目を走らせると彼女は、
「変わってないね」
眉根を寄せ、しみじみ言った。「すぐに判ったよ、ひと目で判った、学校で見て、びっくりしたけど、でもそう、いるかなって期待はしてたかな」
私は黙っていた。
しゃべろうにも、そもそも声を発しないのが私だからだ。
私から言葉を奪った女が目のまえにいる。
私の気質は、彼女だって教師から聞いているはずだ。私と同じクラスになるコたちはみなそうして私の性質を、私以外の言葉で受け取り、承知する。
「先生から聞いたよ」
私が銅像の真似事をやめられないでいるあいだも彼女は一方的に話しつづける。「しゃべれないんだってね。でも筆談ならだいじょうぶなんでしょ、何も問題ないじゃんね、いまどきしゃべるよりみんな電波飛ばしあって会話してるようなもんだしさ」
変わらないよね、と彼女は口にする。
むかしのあなたと変わらないし、あたしとあなたも変わらない。
彼女の言葉は言葉として耳に入るけれど、その背景に潜む彼女の意図を見抜けないでいる。
絶対に許さない。
むかし、私から言葉を奪った女の言葉は、いま目のまえにいる彼女と同じ口からつむがれたはずだった。五年の歳月が経過したいま、彼女の唇を構成する物質はもはや以前の彼女のものではなく、彼女に限らず、それは私も同じだった。
だから私たちは初対面であり、あのときとは別人なのだ、と捉えることもできないわけではないのだと、私は私に思いこませようと、理屈を捏ねては、内なる底なしのがらんどうを持て余す。
彼女、イユは私に言葉を浴びせつづけた。終始、ひなたぼっこをする猫に似た空気をまといながら、まるで私にがらんどうを植えつけたことなどなかったかのように、ひたすらむかし話を、それはおおむね、私との思い出話であるらしかったが、そんな話をされるまで私は彼女とそんなふうに関わっていたことすら忘れていたにも拘わらず、果実じみた唇を動かしつづけた。
私たちはかつてトモダチだったのだ。
かねてよりの、トモダチだったのだ。
かように記憶をねつ造され、刷りこまれるように、私は彼女の言葉にじっと耳の穴を向けていた。つまりがそっぽを向いていた。
気づくと私たちは美術館のそとにいた。ちかくの公園でベンチに座り、いつ買ったのかも覚束ないソフトクリームを舐めている。
「むかし、こうしてよく食べたよね」彼女は言うけれど、私にその記憶はなく、ひょっとすると努めて忘れようとしていた過去があるのかもしれなかった。「手話とか使うの? そうだ、連絡先教えてよ」
筆談、筆談。
言いながら彼女はメディア端末を取りだし、情報交換を促した。
私はたぶん、顔面蒼白になっていたはずだ。身振り手振りで、まずは遠慮したい旨を示したかったが、彼女をまえにするとどうしても身体がうまく動かない。
「どったの? 持ってるでしょ、だしなよ」
私がいつまでも地蔵の真似ごとをしているものだから、イユは眉を結び、ひょっとして、と自身の端末ごと手をひざのうえに置いた。「何か悩みとかあるの。聞くよ。なに。相談して」
顔を寄せてくる彼女からはほのかに甘い香りがした。
私は残ったソフトクリームを一口で頬張り、悩みなんてないない、と首を振り、だいじょうぶだと、チカラこぶをつくって、強調した。
「マッチョになりたいの? 痩せたいとか?」
うまく伝わらなかった。
「そうだ、部活とか入ってる? 運動部って感じじゃないよね。手芸部? あ、美術部とか? わかった、吹奏楽部でしょ」
部活動には入っていなかった。図書委員会に入っており、ふだんは放課後に図書室で本を読んでいる。
「そうそうあたし、まだ引っ越してきたばっかでしょ、服とか買いたいんだけど案内してよ」
彼女が私の腕をとる。
身体が硬直し、悪寒が背筋を駆け抜ける。あべこべに汗が噴きだし、手でひたいを拭うようにすると、
「うわー、びしょびしょじゃん」
彼女が離れたので、これさいわいと退避すべく、私帰るね、を伝えるためにメディア端末を取りだしたのが運の尽き、
「あ、持ってんじゃん。どれどれ」
彼女は私から端末を奪い取ると、そそくさと個人情報を抜き取った。
「これでいつでも話せるね」
まるで死刑宣告のように聞こえた。「そうだ、おばさん元気? 挨拶しなきゃだよね、家とか、うわー、めっちゃ久しぶりじゃんね」
ひょっとして、と思う間もなく彼女に引きずられるかたちで、私は彼女ごとじぶんの家までの道のりを歩いている。
頭のなかでハムスターが幾度も転げながら歯車を回す。逃げだすことはおろか一歩も進めないというのに。
なんと言って断ろうかと考えあぐねているあいだにも、彼女はいっぽうてきに捲し立てては、私のハムスターに鞭を打つ。
彼女の言動には脈絡がなく、家の話かと思えば、学校の話になり、お気に入りの音楽の話ときたらむかしの話に戻り、話題を振ってきたかと身構えると、我田引水にこちらの胸中を推し量っては、さらに舌鋒を鋭くした。
五年の月日を埋めんとするかの激しさに、私は内なるがらんどうの生みの親であることを抜きにして、彼女を心底苦手に思った。
「あたしがいないあいだとかさ」
声が上擦って聞こえたのでよこを窺うと、彼女は虚空を凝視しながら、まるでそこに私がいるみたいに、
「どうして過ごしてたの、しゃべれないんだよね、やっぱりそういうのってたいへんじゃんね、ほかに仲いい友達とかできたのかな、助けてもらったりしてたのかな、クラスにいるよねそういうコ、いるよね、そりゃね、でもさあたしのほうがさ」
身体がとたんに鉛を帯びた。
内なるがらんどうが鉄屑に成り代わったみたいだ。ずーん、と重くなる。
足取りまで鈍る。
彼女に腕をとられているからつんのめりながらもしかし、歩みは止まらない。首輪の食い込んだイヌのようになりながら、内なるがらんどうが身体のそとへと滲みでてくる様を連想する。或いはそれはあべこべで、私の周囲に、ブラックホールさながらのがらんどうが君臨しているのかもしれなかった。
なるほど、と私は思う。
身体から、がらんどうが抜けだしたから重くなったのか。風船の空気が抜けるみたいに。私の内は鉄屑のみが残る。
「でももうだいじょうぶだよ」
鉄屑でも?
問い返しそうになるも、元から私はしゃべらない人間だ。彼女、イユは私を置いてきぼりにして、引きずりながらも、しゃべりつづける。「だってあたしがいるし、もうだいじょうぶだよ。だいじょうぶ、だいじょうぶ。よかったね。あたしが戻ってきて」
そうでしょ。
虚空を見詰めたままの彼女の見開かれた目に、私は真夏だというのも忘れ、凍りついた。
それからさき、彼女が私の母に挨拶をし、親ぼくを深め、クラスが同じだと知るや否やかつてない待遇でもてなしはじめた母を手懐けていく彼女の手腕を私は、私の家で、私だけが世界の外側にいるかのような疎外感にくるまれながら、眺めた。
イユは母の運転する車に乗せられ、ようやく我が家から姿を消した。母は私がしゃべらないのをいいことに、イユから訊ねられるままに、私の過去をつらつらと漏らした。ひょっとしたら私がしゃべらないから、私の代わりに受け答えしていただけなのかもしれないが、いずれにせよ、イユはたった半日のあいだに、私の五年間を、母という記録媒体を通して、かっさらっていった。
じっさいに何かを奪われたわけではないのに、私にしてみたら、未来を奪われたような絶望感に襲われた。弱みを握られたようなものだ。爆弾を首にはめられたようなものだった。
私はもう、どうあっても彼女から距離を置くことも、拒むこともできないのだと知った。
そう悟らせるためにイユは家までついてきたのだとまで考えるのは、さすがに穿ちすぎではあるけれど、既成事実として私はそう悟ってしまったのだから、そう仕向けられたと見做して、何がおかしいだろう。彼女はきっと、まだ忘れていないのだ。
ぜったいに許さない、と言ったあのときの怒りを。感情を。
しかし、でも。
底なしのがらんどうが、私の内部にふたたび舞い戻りつつある。
私はそう、なぜ彼女が怒ったのかを、知らぬままでいる。
この五年間、ずっとだ。
夏休みのあいだ、イユは毎日のように私の家にやってきた。母のほうで誘っていた節がある。娘をよろしくね、とたびたび口にし、いつもありがとうね、とおもねる姿には、我が母親ながらというべきか、我が母親だからというべきか、見境のなさに吐き気を催す。
もし私がいなければ母はそんな真似をすることはなかったはずだ。なぜならそれは私のためであり、私のしゃべらない気質のせいだからで、回り回って、私から言葉を奪った元凶に媚びを売る姿は、手ひどく情けなく、可哀そうで、彼女の娘として罪悪感に押しつぶされそうになる。
彼女を母に近づかせないようにとのせめてもの策に、私は自ら進んでイユを遊びに誘った。二つ返事で乗り気のイユと、駅前で待ち合わせし、それから私は、彼女の喜びそうな場所を案内して歩いた。
彼女が周囲の環境に目を奪われれば奪われるほど、私への関心が薄れる。いっしょにいる時間は可能なかぎり、彼女を喜ばせることに心血をそそぎ、彼女が彼女自身で完結して夏休みを謳歌してもらうことが、私にとって最善の、最悪回避策と呼べた。
「ねぇねぇ、あしたはあそこ行こ、あそこ」
イユは好奇心旺盛だった。私がいくら刺激を提供しても満足する素振りをみせず、もっともっと、と欲しがった。雛鳥みたいだ。すこしでも気を抜き、手を抜いて、彼女に不満を抱く余地を持たせると、私のがらんどうはあべこべに養分を蓄え、深みを増す。
いくどかイユの家にも連れて行かれたが、彼女のほうの家族は私を歓迎しなかった。遊んでばかりいる娘に小言を言い、なるほどおまえが悪因か、と病原菌を見つけた医学博士のような目を向けられた。
「おっきなお人形だこと」
イユの母親は私を見ることなく、嘆いた。人形遊びはほどほどにね、と言わんばかりの溜息を残し、家をでていく。イユはこうなることを予期していたように、きょうも帰ってこなくていいからねー、と満面の笑みで手を振った。
こんな親子関係があったなんて。
世界観の違いにくらくらした。こんな身近に異国があったなんて、とふしぎの国のアリスになった心地がした。
イユの母親と会ったのはそのときが最後で、あとはもう、何度足を踏み入れても、イユの家に、イユ以外の人間の息遣いを感じることはなかった。
私の家とそれほど変わりのない内装なのに、ふしぎと足元にずらりと岩が詰まっているかのような窮屈感を覚えた。
牢獄の城のようだと思いながらイユの姿を目に入れると、途端に色褪せて見えた空間が、すこしだけ煌びやかな魔女の国のように思えてくる。
苦手な相手とはいえ、顔を合わせるたびに、私はすこしずつ警戒心をほどいていたのだろう。意図してほどいたのではなく、知らず知らずのうちに、過去の、私から言葉を奪い去ったあのイユと、目のまえのこのイユは別人なのではないか、と考えるよりさきに、身体のほうで判断している節がある。
彼女はすくなくとも、いまのところはまだ、はっきりと私を傷つけたりはしなかった。好きかってに振り回しはするけれど、それによって私が泣きたくなったとか、寝込んだとか、そういったことはないのだった。
「あしたはどこ行こっか。むかしいっしょに行ったとこはもう全部回っちゃったし、あしたからはじゃあ、新しい思い出づくりしよっか」
そうだ、そうだよ、それがいい。
はしゃぐイユに私はメディア端末の画面を差し向ける。
来週から学校だよ。
伝えると、イユの頭のうえに、しゅん、と垂れる耳が見えた。「そっか、そうだった」
宿題はやったの、と訊ねる。
「そりゃあね。まあね。いちおうはね」
転校初日だから緊張するね、と水を向けると、
「ぜんぜん」
彼女は唇をすぼめ、
「だってもう緊張する理由がなくなっちゃったから」
イユはくるくると回転しながら、公園のベンチに吸い寄せられていく。そのままストンと座ると、となりの席をぽんぽんと叩いた。「座って、座って。すこし話そ」
さっきからずっと喋りっぱなしではないか。
思ったけれども、わざわざ文字に打つまでもないと判じ、彼女のとなりに腰をおろす。イユはにこにことこちらを見詰める。子狐じみたその顔をまえにしても、以前のように、ヒッ、とはならない。
ひょっとしたら過去、私たちのあいだに因縁のようなものはなく、私は無駄に私の被害妄想を肥大化させて、自意識過剰に自虐しては、おのずから言葉を失くしてきただけなのではないか。
中学生のころに母から勧められ読んだ、アドラー心理学を思いだす。目的論と原因論の違いを論じたそれは、人は究極のところ「したいからしているのだ」という元も子もない主張を至極真面目に説いていた。原因があって結果があるのではなく、まずしたいことがあり、そのために言いわけを用意し、自身を鼓舞したり肯定したりしているだけなのだ、という理屈だった。そう言われればそんな気もしてくるし、違うような気もする。
だが、すくなくとも私の緘黙に関しては、私自身、ただしゃべるのが嫌で、そのための理由を、過去私のまえからいなくなったイユに押しつけていただけなのではないか、と問われて、違うと否定するだけの考えを私は私に示せないのだった。
イユを悪者にしていただけなのかもしれない。
彼女との再会は、邂逅というよりもどちらかと言えば遭遇と呼んだほうがちょうどよい塩梅だったはずが、こうして夏休みのあいだに振り回されていくうちに、段々と私の思い過ごしや、勘違いだった気がしてくるからふしぎだ。のど元過ぎればではないが、そもそも私は熱湯など呑みこんでおらず、煮込まれてもおらず、イユから憎まれた過去もないのかもしれなかった。
映画か何かの刺激のつよい場面を切って貼りつけて、記憶をねつ造していたとしてもふしぎではない。五年という歳月が流れているのだ。それこそ思春期以前のやわらかい時期の記憶だ。
罪悪感に似た感情が、イユと顔を合わせるたびに、私の内なるがらんどうに蓄積していく。埋められていく。埋まっていく私はもう、ただ単にしゃべるのすら面倒な横着者でしかない。
内心じぶんを責めていると、イユは両手のゆびを掻き合わせ、
「むかしさ、引っ越すとき、憶えてるかな」
もじゃもじゃ動かしながら、
「あたしひどいこと言ったじゃん?」
核心的な一言を口にした。私はその途端、埋まりかけていたがらんどうが広がりを帯び、耳の奥で、私の「ヒッ」がこだまするのを、幻聴だと判っていながらハッキリと知覚した。
「ずっと心残りで、引っかかってて、忘れてるならそれでいいんだけど、でもなんか気持ちわるいから謝らせてほしいっていうか、謝っておきたいというか」
もじゃもじゃとしきりにじぶんのゆびを気にしている彼女は、手元にしか視線を落としておらず、謝罪をしたいと言っておきながらとくにその後に、ごめんなさいだとか、許してくださいだとか、そういった言葉を口にすることはなかった。
私はしばらく呼吸を忘れていた。胸が苦しくて、なんだろうなんだろう、と思っていたら、そっか息をしていないのだ、と気づき、大きく息を吸うと、とたんに身体のなかが希薄になって、からっぽになってしまったような感覚に陥った。吸った息を吐くと、こんどは私からするするととめどなくがらんどうが大気へと馴染んでいき、私はいっとき世界と繋がった。しかし、私がどれほど世界と同化しても、そばにいるかつて私から言葉を奪い、私を希薄にし、こうして世界とまぜこぜにして私という輪郭をぼろぼろに打ち崩した転校生のことはまったくこれっぽっちも理解できないのだった。
私たちは水と油だ。
思うと同時に、水と油はそれでも接することはできるのだ、と何かが決定的に違うのだと思うと、私はもう、目のまえの、私のとなりに座る転校生のことをただの異物としてしか見做せないのだった。
「ずっとずっと心残りで」イユは繰りかえした。「こうしてまた会えたら、離れ離れになってた時間なんてなかったみたいに、それこそむかしみたいになれてうれしい。すごくすごくうれしい」
何を言っているのだろう、このコは。
私はもう彼女の言葉を言葉として咀嚼できなくなっていた。
「教室で、あっ、ってなったとき、本当はすっごい緊張してたんだ、心臓が口からでそうって本当に思った。憎まれてたらどうしよう、ひどいこと言ったあたしのこと嫌ってたらどうしようって、すごい不安だったんだよ」
だったんだよ、と彼女は言うが、私のほうが現在進行形で、なんですよ、と言いたい。あなたのことは苦手なんですよ、と。あなたの言葉はこうしていまなお私の内部を希薄にしつづけているというのに。
仕方がないのかもしれない。
私がこうまでも希薄だからこそ彼女は、私の苦悩も葛藤もなにもかもを察することができないのだ。
伝わることはないのだろう。
この口から言葉をつむげたとして、それで果たして彼女に何かこのがらんどうの片鱗でも届く可能性があるだろうか。私は今ならハッキリと断言できる。
届くわけがないのだ。
私の当惑を、懊悩を、そしてとびきりの諦観の念に気づくことなく、転校生は、ただただ位置座標的な意味合いでの私のとなりで、うっとりとじぶんの罪を告白し、かってに許しを得たつもりでこの空間を、私との夏休みを、再会を、美談にしようと夢中にむしゃぶりついている。しゃべり尽くしている。
私がしゃべれないのをいいことにして。
こんなふうに私が思っているだろうことにも思いを馳せようともせずに。
私は私に失望した。こんなに醜くゆがんだ感情を抱いていることにがっかりした。私は私が嫌いだ。でも嫌いになんてなりたくないのに、私は彼女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、姿を消し、そしてまた水族館のペンギンでも拝みにやってきたかのような顔つきで現れたこの異物をまえにするとどうしても私は私を嫌わずにはいられなくなる。
彼女を異物だなんて捉えるじぶんに反吐がでる。それと同じかそれ以上に、私は彼女のことを遠ざけたいと思っている。
私は醜い。どうしようもなく醜悪で、汚れていて、劣っていて、欠けている。
そしてそんな私をクズへと変貌させる女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、姿を消し、ふたたび天使のような姿で現れたこの異物は、私よりもうつくしく、きれいで、優れており、きっとどんな屈強をも自力で乗り越えられるくらいに強靭で、満たされている。
嫌だ、嫌だ。
私はもう、私であることをやめるか、彼女を私の世界からいっさいがっさい消し去ってしまうほかに、私は私の存在を許してあげることもできないのだ。
しかし、私がいくらこうして内なるがらんどうへと自虐を落とし、こだまさせたところで、がらんどうの空虚さを、その深さを、嫌というほど知るはめになるだけで、元凶たる当の本人、彼女、転校生は痛痒を感じることもなく、ハンバーグセットについてくるポテトみたいに、或いはコンビニで買い物をしたときのレジ袋みたいに、何も言わないうちから、何も言わないのをいいことに、こうしていつまでもまとわりつづける。
気づくと私は、私たちは、夕暮れの公園のベンチで手を繋ぎあっており、いつの間にか彼女はしゃべるのをやめ、私の肩にあたまを預けている。
「ずっとこうしてたいなぁ。帰りたくないね」
私はこのときほど、しゃべれなくてよかったと思ったことはない。
「ずっといっしょにいようね」
彼女はもう、私を手放す気はないのだと思い、そのことに絶望するよりさきに安堵してしまった。私の自意識はもう、とことん、がらんどうに蝕まれてしまったのだ。なんだか地に足がついたような、諦めのついた心地がした。
私は私を客観的に、俯瞰的に、幽体離脱みたいにして眺めている。上から、ときによこから、もしくは下から覗いたりして、ベンチの裏側はこんなに汚いのか、とまるで見てきたように想像しては、本当に汚いの? と気になったりして、そうすると途端に自意識と融合して、元通りで、私はまた諦めの心地のベンチで彼女、転校生、かつて私にがらんどうを植えつけ、いまなお肥大化させつづける少女にもたれかかれつつ、絡みつかれ、何か精気のようなものを吸われつづけていることを自覚する。
どこまで、いつまでも吸われつづけるものだから、ややもすると、とうなだれる。彼女は私に植え付けたがらんどうこそをご所望で、その苗床として私を選んでいるだけではなかろうか。
まるでエイリアンではないかと思い、まさに異界の者ではないかと腑に落ちる。
彼女からそそがれる熱く不快な何かを、私は口どころか胃が裂けても、好意と呼べそうにはない。好意的には見做せない。
ハリガネムシはけっしてカマキリのしあわせを望んでなどいない。それでも臓腑に巣食って、離れない。
彼女は私から言葉を奪い、がらんどうを植えつけ、肥大化していく私の空虚を吸いとっていく。私は希薄になればなるほど、彼女に身を委ね、破滅していく。
抵抗すべきなのだろう。
拒絶すべきなのだろう。
それができればこんなことにはなっていない。
どうしてだろう。
これほど冷静に現状を把握できていてなお、私は彼女を拒むことができないでいる。
なぜだろう。
私の何がそれを戸惑わせるのか。
私は傷つきたくないだけなのかもしれない。私が拒めば傷つくだろう無垢な侵略者に対して、私は傷をつけたくないのかもしれない。彼女が傷つくことで返ってくる、世にもおそろしい怨念を、因縁を、いまさらふたたび結びたくないだけなのかもしれない。
それはそうだと思うじぶんがいて、それはどうなの、と眉を結ぶ私もいる。
「あ、花火やってる」
いつの間にか辺りはすっかり陽が暮れていた。公園内では親子が闇夜に光の筋を描いている。
「そうだ、そうだよ。花火やってないじゃんね。やろうやろう」
立ちあがると財布の中身を確かめはじめるので、
え? いまから?
すっかり胸中のモヤモヤが霧散して、もう家に帰りたいよ、なんて言って断ろう、と打算的な考えを巡らせる。メディア端末を確認し、母からメッセージが届いていないかと期待したが、イユちゃんこんどいつくるか訊いといて、といった娘の安否を案じる気配のからっきしなテキストが届いているばかりだった。
かろうじて、お腹すいちゃった、と文字を打って、彼女に見せる。
「あ、そっか。そうだね。んー、コンビニじゃ味気ないしなぁ。この辺、ファミレスとかあったっけ」
帰ろうよ、帰ってお母さんのご飯を食べようよ。
もちろん母親との仲が暗雲垂れこめて晴れる気配のさっぱりな彼女にはかように訴える真似はできなかったけれど、うんざりなものはうんざりだ。出口の見えないマラソンを走らされているようで、いったいいつまで走ればいいのか、いつになったら解放されるのか、出口まであともうすこしと思っていたら、ぜんぜんまだ先があったと知って落胆するのに、それでもまだ走りつづけなくてはならない地獄のようで、そっかこれは地獄なのか、なるほどなー、なんて思いはじめて、私はもうもう、泣きたくなってしまった。
つかれちゃった。
私はなんの期待もこめず、ただ思ったことを文字に打った。誰に聞かせるでもなくつぶやくみたいに、溜息を吐くような感覚で、ただ打った。
すると彼女は、こちらが何かを伝えようとしていると勘違いしたようで、なになに、と画面を覗きこんでくる。その躊躇のない仕草からは、もはや私から拒まれることなどつゆほども想定していない傲慢さというか、強引さが感じられた。本来ならムっとすべき場面であったかもしれないが、私は彼女を拒むでもなく、懐に招き入れるように手元の画面を見せるようにした。
息を呑む音がはっきりと聞こえた。
「そっか、そうだよね、疲れちゃったよね」
彼女は早口で、わずかに頬を引くつかせながら、じゃ帰ろっか、とこちらが呆気にとられるほど簡単に前言を撤回した。足先を地面にこすりつけ、円を描きながら、
「どうする、一人で帰れる?」
私を見ずに、私の身を案じるようなことを言った。「送っていってもいい? だめ? やっぱりすこし疲れちゃったかな」
私はとりあえず一刻もはやくこの場を立ち去りたかったので、だいじょうぶだいじょうぶ、の意味合いを籠めながら、全力で、いいですいいです、けっこうです、と手をよこに振った。バイバイ、じゃあね、とそのまま駆けだしたいくらいだ。
そこからいかにして彼女と別れ、家まで帰ってきたのかを私はあまりよく憶えてはいない。家でシャワーを浴びていると、ふと、あれいま私家にいるな、と実感がふつふつと湧いてきて、きょう彼女と過ごした時間を断片的に思い返しながら、それはどちらかと言えば、かってに流れていく走馬灯じみていたけれど、この夏休みのことを思いだしている。
部屋のベッドに頭から潜りこむようにすると、なんだかじぶんの匂いにほっとした。私はきゅっと膝を抱え、ちいさくなる。
夏休みが終わる。
来週から学校がはじまる。
目を閉じて、窓の向こうに浮かぶ月を思い描く。きょうは満月だったらいいな。何ともなく思い、けれどそれを確かめようとは思えず、身体のほうはぬか底のナスみたいに、寝返り一つ打ちたくないのだと訴えているかのようだった。
土日に、家へ誰かが訪ねてくることはなかった。母はたびたび、イユちゃんはいつくるの、とぼやいた。料理サイトを眺めては、イユちゃんはこれ好きかな、これ食べるかな、と私に同意を求めるようにつぶやき、楽しげにしている。私では母にそんな顔をさせてあげられないから、このときばかりは私も、いささか素直に、母のぼやきに付き合った。もちろん、こんど会ったときに誘ってみるね、なんて約束は意地でもとりつけなかったけれど。要するに、しゃべれないじぶんの気質を最大限に活かして、なあなあで母のぼやきをいなしていただけだ。
本来ならば嫉妬の一つでも抱くべき状況なのかもしれないが、私は母の態度にモヤモヤするどころか、このひとはいともたやすく、人心を掌握されてしまうのだなぁ、と岡目八目ばりに、このひとだいじょうぶかな、の不安に駆られるのだった。よく生きてこられたなぁ、と。
学校へはいつもよりはやく向かった。ひょっとしたらあのコが家まで迎えにくるかもしれないと案じての早出だったけれど、学校に着いてみると彼女はすでに教室にいて、私はだからくるっと反転して、チャイムが鳴るギリギリまで花壇の花を眺めていた。
教室に入ると、先生はまだいなかった。あのコの周りにはほかの生徒たちが輪っかになって群がっている。花に、わーっとなっているミツバチを連想する。
なんの話題かは分からない。ものすごく盛りあがっているのだけは、ときおりあがる笑い声と、合戦さながらに飛び交う質問の嵐がハッキリと物語っていた。
自意識過剰かな。
私は私の小心翼々具合と幼稚な逃避が恥ずかしくなった。
この日、彼女、転校生こと私のがらんどうの生みの親は、クラスのみならず、学年全体の話題の的となった。みな内心、転校生と聞くと、どこか非日常のはじまりを期待するようで、そのじつやってきた転校生が、アイドル顔負けの美貌と親しみやすさを兼ね備えていると見るや否や、こぞって動物園のパンダでも物見にやってくるように、休み時間になるたびに、入れ代わり立ち代わり、廊下に人だかりを絶やさずにいた。
肩すかしだなぁ。
憂鬱の二文字が脳裡に浮かんでくるくらいには気を張っていた夏休み明け初日が、蓋を開けてみれば、一言も彼女と言葉を交わすことなく終わってしまった。
なんだかバスケットボールで、ゴール下で、ヘイヘイパスパス、と大声を張り上げたままなんの活躍も見せずに、なんならいちどもボールに触ることなく試合終了してしまったような空回り感がある。やはりというべきか、気恥ずかしい。
初日だもんな。
気を抜くにははやすぎる。
思いながら、嵐の前のしずけさでなければよいけれど、と学校生活の幕開けに波乱を感じずにはいられない。
翌日、翌々日、週末、土日。
あっという間に一週間が過ぎてみれば、どうであろう。けっきょく未だに学校で彼女につきまとわれるといった事態に直面することはなく、夏休みのような窮屈な思いをすることもなく、不安になるほどの平穏な日々が過ぎた。
彼女のほうからいくどか話しかけにこようとした素振りはあった。しかしことごとく邪魔が入り、これは私からすると渡りに船ではあるのだが、不発に終わり、彼女からしゃべりかけられることすらない日々で、ひょっとしたらこのままつつがなく、以前のような学校生活を送れるのではないか、とすら淡い希望を抱くまでに、私は転校生、かつて私にがらんどうを植えつけた張本人と距離を置いていられた。
そも、私にだって友人と呼べるクラスメイトはいるもので、もちろんほかのクラスにも仲の良い同級生、言い換えれば私が言葉を発さずとも、何不自由なく意思疎通の可能な、可能となるように心を配ってくれる学友たちがいる。
転校生につきまとわれて憂鬱になる理由の一つがそれだった。学友たちと過ごす時間がなくなるのは、私のこれまでの、この五年間の、がらんどうを植えつけられ、持て余し、けっきょくは慣れてしまった私の怠惰な、けれど懸命な日々を、丸ごとすっぱり捨ててしまうことと同義だった。
学友たちは私のがらんどうを埋めるだけの大きな、大きな、ふわふわを湛えている。私は彼女たちの輪のなかにいるあいだだけ、がらんどうを忘れ、質量を伴った肉体を感じられた。
杞憂だったかもしれない。
夏休みを遠い日のできごとのように思いはじめた三週間目にして、私は転校生との確執が単なる思い過ごしであったかもしれない可能性を考えはじめた。
たしかに思えば、五年も前、それこそ小学生のころに別れたきりの相手、しかも喧嘩別れしてほとほと絶縁していた相手と再会して、変に気分が高揚したとして不自然ではない。
押入れを掃除していたらむかし遊んでいたヌイグルミがでてきて、懐かしくてしばしのあいだ部屋に飾ったけれど、やっぱりかび臭いしどことなく不気味だからそのままゴミ箱にポイしてしまいたくなる気持ちは理解できる。
そうであったなら、さすがになんというか、あまり素直によろこべはしない。かってに他人にがらんどうを植えつけておいて、貴重な夏休みをじぶん色に染めあげておいて、終いにはやっぱりちょっとなかったことにしたいかも、なんていまさら他人のフリをしたがるなんて都合がよすぎる。
かといって私は彼女とどうなりたいのかと言えば、どうにもなりたくはないし、都合がよすぎるというのならば、まさにこうして距離の置けたいま、絶好の機会と見做して、よすぎる都合を受け入れてしまうほうが得策と言えば得策だ。
教室での座席も離れているため、授業で関わることはない。休み時間は未だに彼女は動物園のパンダのごとく人々に囲まれて、いよいよかぐや姫がごとく様相を漂わせはじめている。女王様ではなく姫なのは、周囲の学友たちを邪険にするでもなく、しかしそこはかとなく迷惑がっているのが、端から眺めていると判るからだ。
いいや、私だからこそ見抜いている彼女の本懐であるかも分からない。
見抜いている?
そこまで考えてから、おや、と眉間にちからがこもる。
彼女は周囲の人だかりを嫌がっていると私は考えているが、なぜそう考えるのかと言えば、彼女にはほかにやりたいことがあるからで、つまりそれは何なのかと想像すると、私はじぶんの顔が熱くなるのを止められないのだった。
ひょっとして、嫉妬してる?
まったくこれっぽっちもモヤモヤなどしていないつもりで、そのじつこうして彼女のクラスでの立ち位置や、心中をおもんぱかっては、あれやこれやと思考を費やしている。
やめやめ。
頬を両手で、ぱんぱん、としていると、
「何してん、ほっぺた腫れちゃうぞ」
アンパンマンやぞ。
言いながら隣のクラスのユウナが寄ってきた。中学生時代からの顔馴染みで、ときおりこうしてふらりとやってきては、さいきん読んだマンガの感想をいっぽうてきに話していく。私はもっぱら聞き役だが、この時間が嫌いじゃない。感性が似ているのか、ユウナのすすめるマンガはことごとく私の琴線を揺るがせる。
またぞろ、休み時間いっぱいいっぽうてきにしゃべり倒してユウナは、去っていった。どうやらこんどは一流の殺し屋を育てるゲームにはまっているらしい。メディアミックスもされていて、ようやく漫画が単行本として発売されたようだ。私がゲームをしないのを知っているからこれまで話さずにいたようで、堰を切ったようなと言えば端的で、鬱憤を晴らすがごとくの舌鋒で以って、しゃべり倒していった。倒された私のもとにはユウナの置いていった漫画本があり、封が切られていないところを見ると、彼女はもう電子書籍で読み終わっているのだと判る。
わざわざこうして紙の本で貸してくれるのは彼女の謎の拘りらしく、真新しい漫画本の水揚げ作業は半ば私の役割と化して久しいと呼べる。
遠慮するほうが失礼だと彼女の思いを汲めるくらいには彼女との付き合いは短くなく、かといってこうして漫画以外での話をするようなこともなく、また、学校のそとで遊んだことはいちどもない。
だから、これは本当に単なる日常の風景、生活のひとコマでしかないはずだったが、そう捉えない人物がそこにいた。
「ねぇ、それなに」
振り向くと、彼女、転校生、私にがらんどうを植えつけた張本人であるところの琉紗那イユが立っていた。呼吸が荒いのは、走ってきたからなのか、髪も乱れている。乱れてなおうつくしい。水のようだ。
こちらの視線に気づいたようで、手櫛で直すと、
「ねぇ、どうしたのそれ」
彼女はもういちど私の手にしている漫画本に視線を当てた。質問の意図がよく解からなくて、しばし固まる。夏休みが明けてから初めて投げかけられた言葉であることに遅れて気づき、さらに言葉に詰まる。元々しゃべらない気質なのだから、ことさら焦る必要もないのだけれど、どうしても思考のほうは何か答えなくては、と言葉を探す。
「誰から借りたの。休み時間にきてたの誰、どこのクラスのコ。なんでそれ借りたの。好きなの。新品みたいだけどなんで。もしかしてプレゼントか何か。誕生日まだだったよね」
矢継ぎ早にぶつけられ、私はたじたじだ。たぬきが地蔵さまに化けてコッチーンと左右に揺れる映像が頭のなかに流れる。
つぎは移動教室だ。みなすでに教室から脱していて、ちょうどゴングが鳴るみたいに、今、チャイムが鳴った。
これさいわい、とばかりに、はやく行かないと怒られちゃうよ、と身振り手振りで、遅刻の旨を告げてみせるも、彼女は暖簾に腕押しを地で描き、
「ねぇどうしてあたしにはそういうこと教えてくれないの」
眉間にしわを浮かべる。そのしわはどこか三途の川を彷彿とさせ、もちろん私は三途の川がどのようなカタチをしているのかなんて知らないのだけれども、何か押してはならぬスイッチを押してしまったような、インストールしてはならぬアプリをインストールしてしまったような、妙な緊張感に襲われた。その緊張感は、がうがう、とこちらに噛みつかんとするライオンの姿かたちをとっており、それでもどこかぬいぐるみを思わせる愛嬌もあり、私はそれをえいやと蹴飛ばす真似はおろか、拒絶することもできなかった。
「なんかさ、学校はじまってから避けられてるみたいだったし、ずっと待ってたのに、ぜんぜん話かけてくれなかったし」
そりゃ私はしゃべりませんからね。
言えるものなら言い返したかったが、もちろん彼女が訴えているのはそういうことではないことくらい、いくら私とて百も承知だ。
「学校じゃ恥ずかしいのかなって、あんまりベタベタされたくないのかなって、そう思ってたけど、なんかそういう感じじゃないんだね」
だね、と言われても、はいそうですが、としか答えようがない。学校にかぎらず、どこでだってベタベタされたくはない。
そもそも、と私は言いたかった。そっちこそ私なんかと仲が良いと思われたくなくて、避けていたのではないの。
お腹の底のほうで煮えたつグツグツを自覚し、はっとしてから、なぜ私がこんなことで苛立たなければならぬのか、とさらにグツグツの泡が大きく弾ける。まるでがらんどうという大鍋で、鬱憤や不満のシチューを煮ているかのようだ。
「なんでそんな怖い顔するの。怒ってるのはあたしのほうなのに」
彼女は手に持っていた教科書を机に叩きつける。大きな音が鳴り、いっしゅん学校全体が静寂に包まれたかのような錯覚に陥った。
間もなく、となりのクラスで授業をしていたらしい教員がひょっこり顔を覗かせ、何やってんの、と独特の訛りのある発音で、授業もうはじまってるよ、とこれは叱るというよりも、宥めるように言った。
私は微笑んでみせることで、なんでもないんですすみません、と暗に示し、彼女も彼女で、転校してきたばかりで、と言い訳がましく、移動教室の場所がわかんなくて、と続けた。もちろん彼女が転校してきてから幾度も移動教室はあったわけで、そんなのは教員のほうでも重々承知の助であったから、
「いいからはやく移動しちゃいなさい」
軽くあしらわれ、いちど引っ込んだ顔がもういちどひょっこり覗くと、ついでのように、
「喧嘩もほどほどにね。あ、もしかしてイジメのほうだった?」
などとかったるそうに言われてしまうと、まるで私たちのあいだにあったモヤモヤとグツグツは、オコチャマのおままごとのように感じられてしまって、端的に恥ずかしくなり、私は何度も素早くうなずいてから彼女、転校生、私にがらんどうを植えつけ、恥辱なる念まで上塗りしてくれた琉紗那イユの腕をとり、その場をあとにした。
廊下でいちど振りかえると、私に腕を引かれるがままの彼女はなぜか、うれしそうに顔をほころばせている。ゾっとしながらも、ふしぎとさきほまでグツグツと煮えていたがらんどうは鳴りをひそめ、ただいつものような空虚な闇を身体の奥底にひっそりと浮かべている。
***
ひと月もすると、休み時間に私たちのクラスにやってくる賑やかし、つまり転校生を拝みにくる集団は見かけなくなっていた。琉紗那イユの取り巻きたちも毎度お馴染みの顔ぶれに淘汰されている。顔馴染みというよりも、残った数人が狂信者となって、クラス内での立ち位置をより明確にすべく――それは琉紗那イユの立ち位置なのか、それともそれを利用してじぶんたちの立ち位置を高めんとする虎の威を借る狐なのかは定かではなかったものの――なにかと琉紗那イユの話題を振っては、教室内に飛び交う言葉の矢印を、一方向に整え、いつまでも転校生、才色兼備のアイドルの後光を煌びやかに保ちつづけていた。
あの日以降、彼女は私に遠慮なく話かけてくるようになった。あべこべに私は彼女以外との会話、意思疎通の場を失いかけている。
「ごめんね、きょうは委員会の手助け頼まれちゃって、いっしょに帰れないみたいで」
いいよいいよ、行ってきなよ。
私はあいまいに笑って、彼女を送りだす。
申しわけなさそうな、ともすれば雨に濡れた子犬にも見える彼女の背を見送りながら、久方ぶりの開放感を味わっていた。
「約束なんてしてないのになぁ、みたいな顔しとるねチミ」
びっくりして飛び退くと、箒の先端にあごを載せた格好で、ユウナがもごもごと口を動かしている。いつ見てもオカッパ頭の年中むすっとした顔つきをしているこの学友を目にすると、毎日のように髪型を変え、香りを変え、なんだったら下着のコーディネートまで変えてくる琉紗那イユの目の回りそうな後光の輝きを打ち消してくれる居心地のよさを覚える。お寺の鐘でボーンと煩悩を一蹴してくれるような頼もしさすら感じられるからふしぎだ。
「なんであんなんに付きまとわれとんの。疲れない?」
なんと応えたものか。私は眉を結び、それはむつかしい質問だ、と意思表示する。しゃべれない私にとって、イエスノーで答え切れない詰問には、沈黙で応じるにかぎる。
「なんだその顔。さてはチミ、うちが隣のクラスの同胞にこうしてわざわざ会いにくるのは、へそまがりのこんこんちきな性格のせいで同じクラスにしゃべる相手がいないからだ、なんて失礼なことを考えてはいないだろうな」
ぶんぶんと顔をよこに振る。
思ってない思ってない、とんでもない、の意思表示だ。
「でも間違ってるとも思ってないわけだろ」
そりゃあまあ、とこれは唇を尖らせ、目を逸らしておく。
「マンガの新刊、靴箱んなかに入れといたから」
やった、ありがとう、と手で拝んでから、なんでわざわざ靴箱に? 私の顔色を窺うことが特技というこの可哀そうな学友は、相も変わらず箒にもたれかかったままで、
「どっかのアイドルさまが妬いちゃうだろ。んでうちの宝物が焼かれちゃうだろ、そんなん適わんでキミ」
やいちゃってやかれちゃう、がうまく頭のなかで変換できずに手こずっていると、
「ホントなんであんなんに付きまとわれとんの。疲れない?」
ユウナは珍しく鼻のあたまにしわを浮かべた。子豚の姿が脳裡に浮かぶ。ぴぐぴぐかわいい。
彼女の掃除を手伝ったあとで、靴箱から漫画本を回収する。下校はせずに、また教室に戻り、そこでユウナとひとしきり漫画談議に花を咲かせた。
放課後の教室はがらんとしている。窓の向こうからは運動部の、わいわい、がやがや、が遠くかすかに届く。長閑だ。
語るべきことを語り終えたといった満足げな様で、しかし表情は相も変わらずムスっとしたまま、ユウナは、じゃ読んだら感想よろ、と言い残し、颯爽と一人で帰っていった。帰る方角が違うとはいえ、校門までいっしょに行けばいいのにと思うのだけれども、彼女のそういうマイペースな性格は嫌いではなかった。
帰ってもとくにすることはなく、ユウナから借りた漫画本はアコーディオンさながらのブロックと化しており、持ち帰るのには重すぎるので、ここで読んでしまおう、と姑息な考えを巡らせる。
改めて、
こんなによくぞ運んできてくれたものだね。
ユウナの布教精神に敬意を払う。いつもありがとうございます。
念じながら、ひとたび本を開くと、虚構の世界へと引きずりこまれる。物語の吸引力ときたら、と読み終わってからいつも思う。
ふぅ、と息を吐く。本を閉じ背伸びをすると、窓から差しこむ夕陽に目がくらんだ。教室の床に伸びる影は、ジャングルジムだ。
運動部の声がまだ聞こえている。完全な静寂でない静けさだ。そこはかとない微睡を引き連れる。それはどこか安堵にも似た心地よさを伴っている。
たぶん。
私は目を閉じる。
しあわせとは、こうしたふいに訪れる、暗がりと微睡の狭間そのものだ。
廊下に反響する足音がある。しだいに近づいてくるそれがやがて教室の戸を開けたところで、振りかえってみせると、そこには、びくんと身体をちいさく弾ませ、固まる転校生、もはやこの学年のアイドルとして不動の地位を獲得した琉紗那イユが立っていた。
彼女は挙動不審になりながら、言葉をどもらせつつ、どうしたの、と言った。その場から動こうともせず、なんだかモジモジしながら、
「なんでまだいるの、帰ったんじゃなかったの」
などとカバンを盛んに右に左に持ち替える。
漫画本を掲げ、これ読んでたんだよ、と示す。それから、もう帰るところだよ、とカバンを手にして立ちあがる。
教室後方の扉を彼女が塞いでいたので、教壇に近いほうの扉へ歩いていくと、
「待って待って、いっしょに帰ろうよ」
机に駆けより、荷物をカバンに詰めこむと、彼女は駆け足で私のとなりに並んだ。私はすっかり廊下にでていて、ほとんど歩きだしていたから、遅れまいと追いかけてくる彼女の必死さがすこしおかしかった。
私にがらんどうを植えつけた彼女が私にはおそろしく、そして疎んじていたはずなのに、なんだかいまだけ、彼女が生まれたてのカモかなにかのヒナのように思え、やはり胸の奥がくすぐったくなるのだった。
住んでいる区画がいっしょだから、ほとんど帰り道は同じだ。きのうまでは彼女のほうでいっぽうてきに話していたのに、きょうはおとなしく、その凪のようなおだやかさが不気味でもあり、嵐のまえのなんとやらでなければよいけれど、とイジワルな気持ちで考える。
「さっきのマンガ。おもしろいの? どんな話?」
メディア端末を操作し、少年漫画だよ、とまずは伝える。
読んでみる? 貸そっか?
なぜそのような提案をしたのかじぶんでも謎だったが、彼女は目を輝かせ、うんうんと食いついた。
私はそこでおぞましいことに、彼女のあごを撫でてあげたい衝動に駆られたのだ。
ひょっとしたらこれは優越感かもしれない。
なぜ私はそんなものを抱いているのか、とあたまのなかで腕を組み、そうしてしばし、内なるじぶんとにらめっこをしていると、沈黙を嫌ったのか、琉紗那イユは、
「又貸しはダメだよ」と言った。「あのコから借りたマンガをそのまま横流しとか、そういうのは、なんか危ないからよくないと思う」
危ない? なにが?
思いつつも、たしかにユウナに許可を得ようとしても渋い顔をされそうだ。ただでさえ仏頂面なのに。
私も持ってるからだいじょうぶだよ。
まずはそう文字を並べる。ホントは持っていなかったけれど、おもしろい本であったのは間違いなく、じぶんでも購入しようと思っていたので、そう文字を並べた。
「そっか、ならいいんだけど」
両足を揃え、ぴょんぴょん、と飛び跳ねる彼女がちいさなアマガエルのようで、雨がそんなに待ち遠しかったか、とほっこりしそうなところで、はたと我に返る。
ひょっとしたら。
頬が熱くなるのを感じる。私は学年のアイドルから慕われていると思いあがって、そのことにまんざらでもなく満足感を覚えてやいやしまいか。
嫌だ、嫌だ。
私は内心焦った。
ただでさえ人並み以下の人間の器しか持ち合わせていないのに、これ以上、人として落ちたくない。
ちょいと振り向いてみれば、彼女はどこか浮かない顔つきだ。
どうしたの、と訊ければよいのに、声をだせない私はそのまま歩く速度を落としてよこに並び、彼女の顔をこっそり覗きこむようにする。
私の影がないことに気づいたのか、そこで彼女は顔をあげ、あれっという顔をしてから、真横の私の存在に気づいた様子だ。
目を見開き、仰け反った。びっくりしたぁ、とかわいい歯を覗かせ、えへへ、と下唇をはむ。
あどけない。
そう感じた。
無防備なのだ。いまさらのように気づく。彼女は私のまえにいるときだけ、分厚い皮を脱ぎ去っている。学校やおとなたちに見せる着ぐるみではなく、かつて私に「絶対に許さない」とがらんどうを植えつけたときのように、彼女は彼女自身に巣食う感情のまま、機微のままを、隠すことなく、余すことなく、私にさらけ出している。
壊れているのか私は、そんな彼女の一挙一動、一言一句を漏らさず観察し、受け取っている。あたかも彼女に植えつけられたがらんどうが、彼女を受け入れるための器であるかのように。
深く考えこんでしまったのか、気づくと家のまえにいた。おかしなことにそばにはまだイユの姿があり、彼女は状況を呑みこめぬ私の代わりにインターホンを押した。
思わず、え、と声がでそうになった。
インターホンの向こうから母の声が、はいはーい、と聞こえ、あたしでーす、と快活に応じるイユの、まるで親戚の家に遊びにきた姪っ子のような馴れ馴れしさに、あれ、ここって私の家だよね、といっしゅんじぶんの身分を忘れそうになる。
玄関扉が勢いよく開く。裸足のままの母が、いらっしゃーい、と現れる。見たことのない笑みを引っさげている。
きょうはどうしたの、晩ご飯食べてく?
母は私を一顧だにせず、イユの腕をとって家のなかに招き入れる。私はその場にぽつんと取り残されたが、イユが腕を伸ばして、私の手を握った。
彼女は私の名を呼び、
「相談があってきちゃいました。急にお邪魔してごめんなさい、すぐに帰りますので」
おとなびたあいさつで断ると、母はとんでもないというように手を顔のまえで振り、
「どうせあしたお休みなんだから泊まってっちゃったら」
ね、あなたもそう思うでしょ。
まるで、うんと言え、と脅迫するかのように母は私を見た。私はあいまいに笑い、彼女たちを置いてひと足先に家に入る。
なんだか、何に腹を立てればよいのかが分からなくて、却って清々しい気持ちだ。
自室にあがる。部屋は二階にあって、黙ってあがってきてしまったから母から何か小言が飛んでくるかもと構えていたけれど、母は私よりも目のまえのお人形さんに夢中みたいだから、私はしばらく床のずっと奥のほう、まるで地獄の底から響いて聞こえるワルツを耳にするみたいに母の笑い声を、その残響を足の裏で聞いていた。
何をしても集中できない。いっそ寝てやろうと思い、そこでじぶんがまだ着替えもしていなかったことに気づき、いそいそと制服を脱いだ。
ちょうど下着姿になっているときに扉のノックする音が聞こえ、よもや開けやしないだろうな、と身体の動きが止まっている合間に、扉はちいさく隙間を開けた。
「ママさんがお菓子くれたよ、いっしょに食べよ」
イユがお盆を持って現れる。ジュースとコップとパンケーキが載っている。背中を丸め、金庫に忍び込むようなかっこうで部屋に侵入してきたイユはそこで、私の姿を目に留め、私の真似をするみたいに身体の動きを止めた。
私は何も言えず、イユも言葉を発しない。
目だけは私に釘付けだ。せめて顔を逸らすなり、何なりしたらどうなのか、と怒りがこみあげる。
しゃべれる人間ならこういうときは、出てって、と一言するどく言い放つ場面だろう。
思いながら、私はそのままいそいそと着替えを再開し、それからキッと睨みつけながら、私の着替えを余すことなく見届けたイユからお盆を受け取り、そのまま彼女を部屋のそとに押しやった。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
イユは冗談みたいに扉をドンドンやった。「わる気はなかったの、ホントに、ちょっと動揺しちゃっただけで、わる気はなかったの」
どうしたのー、と下の階から母の声が聞こえた。
あー、めんどうだ。
私は扉を開き、イユの腕をとって、引き入れる。あごをしゃくって階段の下を示し、母になんでもないと言って、と指示する。
うまく伝わらなかったのか彼女は、
「すみません、なんか着替え中に入っちゃったみたいで」
「そんなことで怒んないのー」
なぜか母は私を叱った。扉を閉め、イユから手を離し、ベッドに勢いよく座る。
癇癪を起こしそうだった。人間の怒りは六秒以上継続しない、という話を思いだし、ゆっくりと、一、二、三、と数えていく。
たしかに六をすぎたあたりで、落ち着きを取り戻してきた。物に当たり散らさなくてよかった、と思い、しゃべれないじぶんの気質にも、よかった、と思った。きっとしゃべれていたらひどいことを口走っていた。そしたらきっと未だに扉のまえでもじもじしているイユをこっぴどく傷つけていたはずだ。
ひょっとしたら怒らせてしまって、私のほうで何かしら傷を負っていたかもしれない。
それこそ五年前のように。
私はそこで、じぶんの内側が何かザラザラしていることに気づく。
がらんどう、なくないか?
かつてイユから植え付けられた底なしの虚無が消えかけていることに思い至る。
完全に失せてはいない。否、何かゴツゴツした岩肌じみた感触の合間を縫って、がらんどうはそこはかとない虚無を伴い、空いている。穴というより隙間であり、闇というより影だった。
息を吐く。喉の奥がきゅっと狭くなるような感覚があり、掠れた「あ」がちいさく、私にだけ聞こえた。
声、でちゃうかも。
しゃべれてしまうかもしれない予感が、私をひどく戸惑わせた。
そうだ、私はずっとしゃべりたくなかったのだ。
そのことに気づき、私は私自身の怠慢を知った。
「どうしたの、まだ怒ってる?」
イユが私のまえに立った。私はベッドに座ったままだ。彼女を見上げる。彼女の骨を思わせないなめらかな肢体を、腰を経由しながらゆっくりと下のほうへ、舐めるように視線を巡らせる。彼女の靴下は炭のように黒い。反して肌は雪原じみている。
何もかも完璧かよ。
無駄にイライラを募らせる。
私はかつてたしかに、目のまえの完璧な少女に傷つけられた。底なしのがらんどうを植えつけられ、声を失くし、いまこうしてふたたび相見えた彼女を目のまえにしている。
怒ってないよ。
私は私に言い聞かせるように、喉の奥に風を通した。
怒ってないよ。
怒る理由なんてないもの。
どうも思わない相手から何をされたところで、何を言われても、私は傷つきもせず、ゆえに怒りもしない。
だから私はどうしてもそれを言わなければならない衝動に駆られ、できそこないの口笛のように、怒ってないよ、と口にした。
舌のうえで転がったその声ともつかない掠れた音は、それでも目のまえの完璧な女の顔面を歪ませるには充分な呪文と化したようだ。
「しゃ、しゃ、しゃ」彼女のほうこそ言葉を失くしたように繰り返す。唾液を呑むようにしてから、しゃべれるの、と彼女は喉に詰まらせた飴玉さながらに吐きだした。
二の句は継げなかった。むかし中学生時代に卒業式の打ち上げでいったカラオケで、喉を枯らしていた同級生がいたけれど、あれと同じように私の声帯もまるでヤスリがけをしたようで、息がどこにも引っかかることなく、漏れるばかりだ。五年という歳月は私からしゃべる機能を奪っていた。
無理しなくていいよ。イユは言った。無理をしてしゃべらなくていいよ、とわざわざ言い換え、じんわりと目元に涙を湛えた。そのあまりのなみなみ具合に、表面張力、と私は意味もなく思い、あー垂れちゃう垂れちゃう、とふしぎともったいなく感じた。
私の身体は、彼女の目元に浮かぶシズクに釘付けになっている。棚から落ちる牡丹餅を手で受け止めるように目を離せない。
だから彼女が視界から、ふっと消え、つぎの瞬間には私の身体をなにか温かく、やわらかいものが包みこんでいると気づいたときには、嗅ぎ慣れたよい香り、それはどこか甘く、せつない匂いが私の身体の内側いっぱいに広がりつつあった。
よかったー、とイユは言った。鼓膜をくすぐる声はしかし、まるで歓喜とは程遠く、痛切な響きを伴っていた。
しきりに細かく揺れる彼女の肩越しに、鼻をすする音が聞こえている。こんなに間近に見つめても、彼女の髪の毛は隙間なく並べられたパスタのようにオウトツがない。
どうして泣いてるの?
こちらの疑問を見透かしたようにイユは、
「あたしのせいなんじゃないかって」
高熱にうなされるように、むせた。「ずっと思ってた。こわかった。ずっとこわかった。せっかく会えたのになんか素っ気なくて、そりゃ怒るよな、仕方ないなって、でもあたしのほうからそれで距離をおくのだけは嫌だったから、せめてきちんと突き放されるまではがまんしようって、がんばろうって、あたし」
うわーん。
虚構の世界でしかお目にかかれないオノマトペを彼女はしごくしぜんなさまで使いこなす。泣きじゃくる幼児だってもうすこし人間らしく泣きそうなものだ。
赤子であればもっと濁った、あーあーあー、を叫ぶのだろう。それに引き替え、いま私の身体にしがみつき、絡んで離れない女の子は、赤子と呼ぶよりも空腹に耐えかねて母親を呼ぶ動物の赤ちゃんのように、しきりに、うわーん、うわーん、と声をあげては、ひっくひっく、と身体をちいさく、それでいてちからづよく跳ねさせる。
どうどう。
背中を撫でてやりながら、生まれて初めて「あやす」なる行為をしているじぶんを俯瞰し、なんだこれ、と盛大なオママゴトをしている気分に陥る。舞台のうえから満員のマネキンに向け、おーロミオ、あなたはなぜロミオなの、と手を伸ばしたい気分だ。
おーイユよ、あなたはなぜ泣いているの!
泣きたいのはこちらのほうなのにと思ってみるものの、本当は何も哀しくはない。
なんだか首筋が湿っぽい。せめて涙であってほしい。しきりに鼻をすする音は、ジュルジュル、と途絶えることがない。
どうどう。
私はなおも彼女の背中をさすりつづける。
しばらくそうしていた。
彼女の鼓動、嗚咽、息遣い。
私の呼吸、デジタル時計の針の音、窓のそとから聞こえる鳥の声、遠くのサイレン、車の道路を舐める音。
風の音はそれ単体ではなく、窓を叩いたり、葉を揺らすことで聞こえるのだと、なにともなしに考える。
階段をあがってくる足音を耳にし、イユがはっと我に返ったように私から離れた。私は首筋をゆびで拭い、僅かなぬめり気に、ありゃりゃ、と思う。イユが怯えたように、ごめん、とつぶやく。
戸をノックする音が聞こえ、返事をする前に母が顔を覗かせる。
「イユちゃん、きょう夕飯いっしょに食べてくでしょ」
母はぎょっとして固まった。「どうしたの」
血相を変えた母がイユを覗きこむようにし、事情を聞きたそうに私を見る。その目に、私を非難する色は窺えず、どうあっても私に非がないことを確信している姿に、私は深く息を漏らす。
いじけていた私がばかみたいだ。
なんでもないから、のジェスチャーをし、母の背中を押す。私に任せて、とさらに身振りで伝え、部屋のそとに押しやった。
「ホントにだいじょうぶ?」これはイユへの言葉だろう。
「すみません、目にゴミが入っちゃって」
イユは言うが、ぐしゃぐしゃの顔はどう見てもそれ以上の感情の乱れを感じさせる。目の回りの滲んだ黒を見て、化粧をしていたのか、と気づけたほどだ。
「やっぱり心配」
母が足を踏ん張ってふたたびの侵入を試みてくるものだから、私はたまらず、ちゃぶ台のうえの手つかずのジュースとパンケーキの載った皿をお盆に載せ、
「いいから」
母にそれを押しつける。「下で待ってて」
でも、と食い下がろうとした母だったが、そこでふだんと異なる娘の変化に気づいた様子で、
「わお」
目を丸くして、固まった。私はバイバイと手を振って、戸を閉める。
戸に鍵はついていないが、母はそれ以上、踏みこんではこなかった。事情をなんとなしに呑みこめたのだろう。ひょっとしたら娘たちに見られたくない表情を浮かべている可能性すらある。
こんなことで泣いてくれるなよ。
思いながら、こんなことで泣かせてしまう親不孝者だったのだな、とかってに母を泣き虫認定しながら、新しいタオルを手に取り、イユに渡す。顔洗ってきなよ、のジェスチャーをする。二階にも洗面台はあり、一階におりた母とは顔を合わせずに済むはずだ。
イユはしぶったが、私が部屋の隅に立てかけてあった姿見にゆびを向けると、イユはそこに映るじぶんの顔を見て、ぱちくりと瞬きをした。すると即座に顔を伏せ、こちらの手からタオルを奪い、小声で礼を述べてから、私の顔をいっさい見ることなく部屋をでていく。尻尾を巻いたネズミみたいな姿に、
かわいい。
初めて彼女のことを純粋に愛くるしく思った。
この日、彼女は私の部屋に泊まった。夕飯はチラシ寿司だった。
顔を洗ってしまうと、彼女は化粧をしなおすことなく、すっぴんでいつづけた。母は気づいているのかいないのか、そのことには触れず、私は私で、彼女が生身の人間にちかづいたような親近感を覚えた。化粧は思っていた以上に人への印象を変えてしまう。
彼女の場合は美しく着飾るというよりもどちらかと言えば、素のやわらかい部分を隠す鎧にしていた節がある。こんなにもやわらかな雰囲気をまとっていたのだと私に気づかせたほどだ。
私はイユがお風呂に入っているあいだに、母と言葉を交わす。イユは化粧してもしなくてもかわいいね、うらやましいね。ふだんどおり、メディア端末を、ぱぱぽ、と打つ。
母は、あら、と唇を尖らせるが、私が喉をゆび差してみせると、まあ最初はね、と意図を汲んでくれた。退化した声帯はすぐに潤いを失くす。
「せっかくだし、いろいろ教えてもらいなさいな。イユちゃんとあなた、なんだか姉妹みたいよ」
私が姉?
文字を打つと、
「イユちゃんに何か一つでも教えられることがあるの」
真顔で訊き返され、私はイヤホンで耳を塞いだ。
夜、布団をふたつ敷いて、イユといっしょに寝そべりながら、ネットの動画を教え合った。私はかわいい動物の愛らしい仕草やおちゃめな挙動を集めた動画を提供し、イユからは化粧やファッションのチャンネルをご教授いただいた。
そのうち眠くなって、気づくとイユの寝息が聞こえた。明かりは消していて、私は、うすぼんやりとした暗がりの向こうの天井を眺める。
まるでがらんどうのなかにいるようだ。私のなかにあったがらんどうが、いまはこうして私の外側にある。
私のとなりにイユがいる。
がらんどうの生みの親、そのじつ私こそ彼女に拭えぬしこりを植えつけていたのかもしれない。
あー、あー、あー。
私はちいさく声をだす。
あ、い、う、え、お。
なんだか想像していたよりもずっと掠れていて、ずっと低い声だった。
女子も声変りするのかな。
そんなことを考えながら、学校でしゃべったら、クラスのみんなはどんな反応をするだろうか。思い描いてみるものの、きっとたいした話題にもならず、すんなり馴染んでしまいそうだ。なんだしゃべれたんだ、と。
それとも、このだみ声に触れていいのかどうかといらぬ気遣いをさせてしまうかもしれない。それは嫌だなぁ。
思うものの、やっぱり茶化されるのがいちばん怖くもあり、しかしそんな真似をするやつはクラスに一人もいないのだよなぁ。
おとなびた学友たちに私は、前以って感謝しておくのだった。
目をつむる。
おやすみなさい。
暗がりに漂う甘く、やさしい香りに、私はそっとつぶやくようにする。
***
翌週。家をでるとイユが待っていた。家の中からも見えていたので、アニメキャラみたいにパンを口に咥えたまま玄関をでた。
パンをひと口齧ってから私は、おはよう、と言った。ついでのように、こういうときは連絡してよ、と言う。寝坊したらどうするつもりだったのか、とつづけようとしたけれどうまく言葉がでてこなくて、メディア端末で文字を打った。
「寝坊してたらふつうに叩き起こしにいってたよ」
歩きだしたイユのあとを追う。「それにママさんには連絡しといたし」
なるほど。
母が私に持たせたなぞのサンドウィッチも、おそらく昼ごはんのための弁当ではない。案の定、イユがちらちらと私の手を覗いてくるので、はい、とサンドウィッチの入った紙袋を顔のまえに掲げる。
「わー、ありがとう」
さっそく取りだし、おいしそういただきまーす、と頬張りだすので、私もいっしょになってサンドウィッチの残りをハムハムした。
齧っても具がはみださない。ジューシーさが損なわれない。母のサンドウィッチは娘の贔屓目を抜いてもピカイチだ。
横目で窺うと、イユは、んー、と目を細めうっとりする。口のよこちょをゆびで拭って舐めとる。ゆびで丸をつくる。ばっちぐーのサインだ。
感想を挟む間もなく、もぐもぐとひと息にたいらげた。
「あー、おいしかった。こんなの食べちゃったらもうコンビニでサンドイッチは買えないね」
コンビニのはコンビニので私は好きだけどな。
思ったけれどまだ口にだしてしゃべれるほど慣れてはおらず、すこし迷ってから、これはでも言っておきたいな、と思ったので、ぱぱぽ、と文字を打った。
「やっさしー」
イユは両足を揃えて、ぴょんぴょんと跳ねた。
なんで跳ねる?
その浮かべてる笑みはなに?
やっさしーって、それは皮肉か何かかな?
しゃべれたらすぐに訊ねられるのに。
思うじぶんをすこし窮屈に感じる。先週までそんなふうには思わなかったのに、しゃべれるようになった、と自覚した途端、こうして欲張りになった。
伝えたいことや知りたいことがじぶんのなかにこんなにあるとは思わなかった。ひょっとしたら、元々私のなかには言葉がたくさん溢れていて、けれど私のなかに拡がっていたがらんどうがそれを奪い去ってしまっていたのかもしれない。
がらんどうを埋めたのはイユだろう。そして植えつけたのもまた彼女だ。
じぶんで問題の種を撒いて、回収するのを専門用語でなんてったっけ。
私は右斜めうえに視線を漂わせる。いい天気だ。しろい雲の合間から朝日が差している。雲のカタチが犬みたいで、かわいいな、なんて思う。
「なーに考えてんの」
イユがご機嫌に体当たりする。痛いのでやめてください。手で払うようにして意思表示し、それからさっきまで何を考えていたのかがすっかり抜け落ちていることに気づき、じぶんの記憶力のなさに、ありゃりゃとなる。
イユは叱られた子犬のように、しょぼんとしている。
たぶん彼女は、と考える。
しゃべれるようになった私と、これまで以上にコミュニケーションがとれると期待していたのではないか。それがどうだ。いざ蓋を開けてみれば、私は依然として口数すくなで、事情を知らないひとからすればただすげない態度をとっているのと変わらない。
そしてイユはイユで、私のこのふだんと変わらぬ態度を、すげない態度だと見做しつつある。いいや、とっくにそのように見做していたがこれまでは、それはきっとしゃべれないからだ、とする言いわけを自身に向けることができていた。
私が言葉を発するおとといまでは。
イユは私の胸中をかってに、都合のよいように我田引水、推し測っている。ひょっとしたら避けられているのではないか、嫌われているのではないか、拒まれているのではないかとの不安をそうして見て見ぬ振りをしてきたのだ。
それがどうだ。
いまはもうその魔法は通じない。
喉が痛くてとじぶんの喉を示してみせれば彼女のことだからそこから都合のよい解釈をしてくれると判っていながら私は、イユの不安を拭わぬままでいる。
凝らしめているのかもしれない。私は私の内心の声に耳を傾ける。私はまだ彼女を許してはおらず、気を緩めてもおらず、過去を水に流そうとなどは思っておらず、だからこうして、しゅん、と肩を落としてしまっている数分前まで上機嫌だった彼女をまえに、すんと澄ました顔で我関せずを貫いている。
学校に着くと、教室に入る前に、イユは彼女自身の信者に囲まれた。私はその瞬間、イユが私の知るのとは異なる人物になったような感覚につつまれる。不快ではない。清々もしない。我ながら釈然としない。
私はイユを異物どころか劇物に感じていたはずだ。いまではそこまでの脅威と見做してはいない。
罪悪感なのかもしれない。
何に対してかは私自身よくわかってはいない。
こうしてにべもない態度をとっていることに対してか、それとも私だけがこの数年間ずっと苦しんできたのだと思いこみ、私にがらんどうを植えつけた彼女のことを忘れよう、忘れようと延々してきたことに対してだろうか。ひょっとしたら私は、こう考えていることを彼女にだけは絶対に明かしたりはしないと制限をかけているじぶんに後ろめたさを覚えているのかもしれない。
イユは私に最初から正直に、素直に、何も隠さずに接しつづけてきた。教室で先生のよこに立ち自己紹介をしたとき、まっさきに私に気づいた。そのあとでも臆さず私に声をかけてきた。
彼女は私を忘れてなどいなかった。私を傷つけたかもしれない過去を抱えつづけてきた。
私はそこに、何かしら、救いのようなものを感じているようにも思え、なんだか私ばかりが葛藤し、悩み、もやもやしている気分になり、だから私は彼女に未だに冷たくあたっているのかもしれなかった。
彼女は何もかもが完璧だ。人形のように人々を魅了し、そのくせ当人は人間くささに溢れている。
苦手意識全開だった私ですら、いまでは彼女がとなりに座るのをどこかくすぐったく、好意的に捉えている。
慕われている。
慕ってくれている。
それが過去、私にがらんどうを植えつけ、私から声を奪った相手であっても、私はもう素直に怒りを、恨みを、屈託を、こねて、伸ばして、壁とすることができなくなってしまっている。
授業を受けているあいだ私は彼女を視界に入れずに済む。それでもときおり、落とした消しゴムを拾ったり、プリントをうしろの席の子に渡すときに、否応なく視界にイユの姿が入るのだ。毎回のように目が合うので、なんだかまえを向いているあいだも彼女が私の後頭部に視線をそそいでいるのではないかと考え、顔が熱くなる。
こんなにもじぶんの挙動を気にして過ごしたことはなかった。呼吸が意識下に置かれ、息を殺すような息の仕方をしているじぶんを歯がゆく思っては、自意識過剰!と諌めるじぶんの声が聞こえてくる。
日に日にその声は音量をあげ、しだいに夏の日の蝉の鳴き声のように、風物詩がごとく私の生活に馴染めはじめたころ、
「なんかさいきんオシャレだね。目覚めた?」
ユウナが教室のベランダの窓から顔をだした。私の座席のとなりの席を足場にして、よいしょ、と乗り越えてくる。
いくら休み時間でももうすこしマシな登場の仕方があってもよかろうに。
思い、教室の扉を見遣ると、イユがとなりのクラスの子に囲まれていた。トイレにいくにもああやってまとわりつかれてはさすがに嫌気も差すだろう。私に迷惑をかけまいと教室にいるあいだは話しかけてこない。私なんかと旧知だと思われたくないだけなのかな、と考えないわけではなかったけれども、彼女のためにわざわざ性格わるくなるのも癪なので、頭上にこもったモヤモヤを手で払って散らす。
もう一つの教室の扉は男子生徒が代わる代わる懸垂をしていて通せん坊をしている。お猿さんだな、なんてふだんのユウナならば毒づいているところだ。
しかし本日のユウナはおとなしかった。
というのも、登場したときから目についていたのだが、
どうしたの、それ。
問うつもりで、私は鼻のあたまをゆびでなぞる。
ユウナは鼻にティッシューを詰めていた。鼻血だろう。でもどうして?
「ぶつけた」
どこで、と首をかしげる。
「まあそれはそれとして」ユウナは強引に話を逸らした。「うちはさ。まあまあそれなりにあんさんとは親交を深めてきたつもりだよ、これでもね」
はあ。
私はあいまいにあごを引く。
「で、そんなあんさんはうちからの貢物をたらふくもらい受けておきながら――いや、それはうちが好きで布教してたわけだから恩を着せるつもりはないけどよ、それはそれとして、うちはあんさんの口から直接知りたかったなぁ」
それともうちとはききたくもないってか口を?
ああ、これは。
私は思った。ユウナはいま、怒っている。しずかに、しかしハッキリと私に失望の気色を示している。
「それともうちはただ誤解して、みんなの噂を真に受けて、あんさんにちゃっかりイチャモンをふっかけてるだけなんかな」
机にバンと手が置かれる。刑事の取り調べみたいだ。私はユウナの顔を見れずに、うつむいたままで、第一声が何がいいだろうか、と混乱する。
だからそのあいだに私の座席をぐるりと回って、わざわざユウナの真正面、窓側に回りこんだ人物に気づくのが遅れた。その人物はユウナの胸をドンと押し、彼女に尻もちをつかせる。大きな音が鳴ったのは、ユウナが机の脚に身体をぶつけたからだ。
「いってぇ、あにすんだドチクショー」ユウナはまくれたスカートを直そうともせず、尻を床につけた状態のまま目のまえに仁王立ちする転校生、私のがらんどうの生みの親の足首を蹴った。彼女は顔をしかめるだけで微動だにしなかった。
「だいじょうぶ?」
と、これはユウナではなく私にかけられた言葉だ。私は頷き、それから喧嘩はやめて、とアタフタする。じっさいに、やめて、と声にだす。私は椅子に座ったままだった。立ちあがったら、なにかこう、戦闘開始のゴングが鳴りそうで怖かった。
教室が騒然としている。それはそうだ。女子が二人、しかも違うクラスのコ同士で喧嘩をおっぱじめたのだから。どうしたどうした、とならないほうがおかしい。教員が飛んでくるのも時間の問題だ。
なんとかこの場をとりつくろわないと。
思うだけで、どうすればいいのかなんて解からない。
目頭が熱くなり、視界が滲む。
誰がわるいわけではないのに、考えてもみれば、きっかけの行き着く先にいるのは私だった。私は全然わるくないのに、私のせいで関係ない二人が接点を持ち、こうしてぶつかりあっている。
ばかじゃないか。
みんなばかだ。腹が立った。
私がしゃべれるようになったことを私の口から知らせなかっただけでヘソを曲げたユウナにも腹が立つし、白馬の王子さま気取りで私のたいせつな友人に暴力を働いたイユにも腹が立つ。
なにより、当のイユはいま、私の頭を両手で抱えこむようにし、よしよししているのがもっとも見逃しがたい怒髪天だ。沸点ここに極まれりだ。
だいじょうぶだいじょうぶ、こわかったね。
じゃないんだよ。
私は叫びそうだった。耐えられたのはひとえに、私の声帯がまだそこまで回復しておらず、私自身、しゃべることへの抵抗を拭えきれていないためだ。
まずはイユのうでをゆっくりていねいに引き剥がす。彼女の両手首を、それぞれ右手は右手、左手は左手で握り、必要なチカラ以上をこめて、彼女のへその位置にまとめて押しつける。
イユはそこに到ってようやく私の険のある表情に気づいた様子だ。怯えた表情で、でも、と言いわけぶった鳴き声をあげる。子犬が、きゅーんと耳を垂らすようだ。ふだんの私ならそこで、仕方ないなぁ、とため息の一つでも漏らしてあげたかもしれないが、きょうは違う。
私はわざとイユに目を向けず、イッテぇと言いながらひざに手を添え立ちあがるユウナを支えに寄った。
ごめんね。
まずはそれだけを口にした。きちんと言葉として聞き取れるように、はっきりと、一音、一音、舌で言葉の輪郭をなぞる。
ユウナはいっしゅん目を丸くした。それからお尻を手でさすり、口を一文字に結ぶ。ふだんと同じくムスっとした調子を崩さぬままに、許さん、とつぶやく。
教師がくるまえに私はユウナをつれて教室を離れた。イユはうしろから何かを言いたげに戸口のまえまでついてきたが、私たちが廊下にでてしまうと、結界のなかに入れないオバケみたいに教室のなかで立ち尽くした。私がいちども彼女を見なかったのが堪えたのかもしれない。
私ごときに無視されようと傷つくいわれはないはずだ。それでも彼女の、私を庇うような行動と、そのあとの慈しむようなここぞとばかりの演出を鑑みれば、いくら私でも、彼女の私への扱いが、同じクラスの一員以上であると推して知れる。
単なる旧知以上の何かが、私たちのあいだに、すくなくとも自身のなかにあるとイユはそう思いこんでいる。
私はそれをこのとき自覚した。
私の一挙一動が彼女を傷つけ得る。
かつて私がそうされたように。
私は彼女にがらんどうを植えつけることができるのだ。
保健室に逃げこんだのはとくに考えがあったわけではなかった。ちょうど予鈴が鳴ったから、遅刻の言いわけにいいかとしぜんと打算を働かせたのかもわからない。それはそれとして、ユウナは教室で盛大に尻もちをついたのだから、お尻が四つに割れていないかを診てもらったほうがいいかと心配したかと言えば、とくにそういうわけでもなかった。
「心配しろよー、そこはよー」
私が何も言わずに突っ立っていたからか、ユウナが膨れた。「うちの桃みたいなおちりが桃太郎みてぇにパッカーンっなっててもいいのか。よくねぇだろ」
「うるさいわねぇ、騒ぐんなら教室戻りなさい」
言いながら保健室の先生がユウナの臀部に制服のうえから触わり、痛いところあったら言って、と指示しながら、ここは、ここは、と痴漢の真似事を繰りひろげる。
「イタタ、イタタ、せんせい痛いってば」
「がまんなさい」
「つづけんのかよイタタ」
「仮病じゃないみたいね」
先生は舌打ちすると、しぶしぶといった様子を隠そうともせず、医療品の仕舞われた棚の鍵を開け、なかから湿布と包帯をとりだした。
「はい。短パン脱いで」
「えー」
「えーじゃない。それともじぶんでやる? 失敗しても代わりないからね」
「んー。でもせんせいはやだなぁ」
ユウナがこちらを見たので、私はきょとんとする。
「はいはい。さっさと貼って出てってちょうだい」先生は机に向かい、何かしらの紙面にペンを走らせる。治療したので書き記しておくべきことがあるのだろう。それともほかに仕事があったのかもしれない。それを、私たちが邪魔したものだから機嫌がわるいとも考えられたが、この先生はふだんからこれくらい生徒に媚びないので通常運転とも呼べる。
去年は男の先生だった。私たち生徒への慈しみがもうすこし感じられただけ、よい先生だったのだ。失われてからそのかけがえのなさに気づいたが、もう遅い。
それにしても、と思う。ユウナはなぜに私から目を逸らさず、いそいそとベッドのあるほうに移動しているのだろう。そしてなぜに手招きをするのだろう。
「ちょいちょい、はやくきてって。貼って貼って」
近寄ると、ユウナはカーテンを閉めた。「この辺。このあたり」
湿布をこちらに握らせると、じぶんでスカートを捲しあげる。短パンを履いているからといってそれはどうなの。はしたないと思うのは、私のほうがおかしいのだろうか。
「ぺろんってするけど笑わんでな」
言ってユウナは下着ごと短パンをめくった。私は噴きだした。陽気が溢れたのではなく突然のできごとに脳がパンクしたのだ。ぶは、のそれだ。
「やっと笑った」
ユウナはそれで満足したようだ。こちらの手から湿布を奪うと、いそいそと反対を向き、じぶんで臀部に貼りつける。
「やー、焦った。焦った。絶交されるかと思って身体張った甲斐があったわな」
怒ってたんじゃないの。
窓から乗りこんできてまでしてさあ。
眉を寄せて訴えてみせるも、ユウナには伝わらなかったようで、
「なんかさー。うちにとっては漫画の話できるのって一人しかいないからさー。そういうさー。なんていうかさー。じぶんだけ相手にしがみついてるのって惨めだなって」
え、なんの話?
あまりの突拍子のなさにまたまた噴きだしてしまった。唾が宙に舞う。ベッドの掛布団のうえに落ち、シミをつくる。それをなぜかユウナが手で払い、
「ごめん。暴走した。ゆるせ」
スカートを整え、ベッドのうえにあぐらを組むと、サムライのようにこうべを垂れた。
まだ喉の調子がよくないのを確かめてから私は、メディア端末を手に取って、
どうしよっかなぁ。
と打つ。
読ませると、んだよケチ、とユウナは唇をとんがらす。足を崩してあぐらをつくり、窮屈そうに頬杖をついた。「んー。ほら。散々、漫画読ませてやったじゃん」
恩着せがましいことを言う。
しかし、一理あるにはあるもので、私は不承不承、じゃあそれで手打ちに、と文字を打つ。
「しっしっし。恩は売っておくもんだ」
私たちは保健室をあとにし、それぞれの教室に戻った。いっそつぎの時間までサボってしまうおう、とユウナから誘われたが、いま戻れば先生から説教されなくて済むかもしれない授業中だし、と提案する。喧嘩があった旨は先生の耳にも入っているはずだ。ユウナはなるほどと手を打った。
ユウナはユウナの教室へ。
私は私の教室へ。
いざ戸を開け、足を踏み入れると、おー具合はどうだー、と歴史の先生がころころとした丸みのある笑みを、同じくらい丸い眼鏡の奥から向けてきた。
保健室の先生から持たされたメモを渡す。
「お、早退じゃないんだな」
座席に着くころには、平然と授業は滞りなく再開された。椅子に座るとき、教室のうしろのほうに座るイユの顔が視界に入った。彼女は窓のそとを眺めており、こちらを気にする素振りはなかった。
シカトか。
それはそれで新鮮でもあり、ほっとしつつも、何かもやもやと胃のなかがごろごろした。
授業が終わると、昼休みだ。食堂に行こうと思っていたら担任に呼び止められた。そのわきをイユがするると抜けていく。
担任が私の顔を覗きこみ、だいじょうぶか、と名簿代わりの端末で肩を叩きながら、もちろんこれはじぶんの肩を、という意味だけれど、言った。
「はい」私は声をだして言った。いっしゅん教室が静まったように感じた。気のせいだろう。自意識過剰になるんじゃない、とじぶんを叱咤する。
「具合わるかったら早退しろな。遠慮するなよ」
担任はそこでもういちどだけ、ホントにだいじょうぶか、と念を押した。私がうなずき、微笑んでみせるのを見届けると、そのまま、きょうは何食べよっかなー、とひとりごちながら教室の戸を潜っていった。
食堂にいくには、いま別れたばかりの先生のあとをついていかねばならず、そうでない経路でいくと遠回りだし、かといって時間をおいてからいくのもなんだか面倒になってしまって、私は、まあいっか、と思って、そのまま座席に戻った。
教室は徐々にがらんとしていき、いくつかの数人のグループが弁当をひろげたり、しゃべったりするだけとなった。このクラスにひとは集まらないのだなぁ。そんなことを思い、でもいつもはいっぱいいるのになぁ、とイユの姿が浮かんだ。
なるほど。
この教室にはいま女王蜂さまがいないのだ。
ふだんは食堂だったから知らなかったなぁ。
ささやかな発見に、ふん、と鼻息をみじかく漏らす。
メディア端末を操作し、本を読む。すこし読んでから、眠気が走ったので、マンガに切り替える。ユウナからおすすめしてもらった作品の最新刊だ。ユウナは紙派だけれど、私はどちらでも構わないので、じぶんで買う分には、いつでも読めるようにデータで購入している。同じシリーズでも、紙・データ・紙・データとちぐはぐに巻を揃えてしまうこともしばしばで、いっそのこと全部データにしようかと悩んでいる。
ただ、ユウナにそれを言うと、この反逆者め、と詰られるのでこちらからその旨を告げることはない。書店をこれ以上つぶすきか、と彼女は怒っているわけだが、私はそろそろ書店さんでもデータで本が売られはじめると睨んでいるので、まあまあ、と流している。
目のまえにペットボトルが現れる。顔をあげると、女王蜂さまことイユが立っていた。顔はこちらを見ておらず、教室の入り口のほうを眺めている。よこを向いても首にシワが寄らないんだ、すごいな、なんてじぶんのあごのしたを思わずつまみたくなる。イユなら上を向いただけで喉の皮が裂けてしまいそうだ。それくらい張りがあって、肌はどこも陶器じみている。
「食べないの、ごはん」
問われたので、うなずく。イユはうしろにまわしていた手をまえにもってきて、私の机に袋を置いた。中を覗くと、菓子パンが詰まっている。
「食べていいよ。いらないならほかのコにあげて。ほら、いるでしょ、仲いいコ」
清々しいほどわかりやすい態度に、ああ、と私は納得してしまった。何を考えているか分からないコだと思っていた。そのじつ、彼女は単に、見た目からは想像できないほど素直で、こどもじみている。賢い人間だと知っているがあまりに、何か複雑な駆け引きや、企みがあるのではないか、と穿ってしまっていただけで、私はもっと彼女のことを同じ人間として、対等な女の子として接するべきだったのだ。
いまさらながらに過ちに気づいた。
それを、誤解に、と言い換えてもいい。
ありがとう、と私は言った。喉が痛かった。でも声にださなければ伝わらないと感じた。いったい何が伝わらないのかはよく分からなかったが、伝えなければ、と思った。すくなくとも、伝えようとしているのだ、と示したかった。
だから私は、しゃがれた声で、とてもではないがひとに聞かせたいと思うような声ではない音で、どもることも厭わずに、ありがとう、と声帯を震わせた。
イユの顔は見れなかった。目を伏せたままで私はさっそく袋を開け、菓子パンを齧る。
ごっくんと呑みこんでから、これがメロンパンであることに気づく。とにかく食べなければ、と必死だった。パンの中にはホイップクリームが入っていた。美味しい。食堂で買ったことはなかった。彼女にこうして施されなければ、一生食べることはなかっただろう。
いや、大袈裟だ。
よしんば食堂のメニューすべてを食べずにいたからといってなんだと言うのか。購買の菓子パンを網羅しなかったからといってどんな損をするというのか。
それでも私は、彼女がこうして私のために、私が選ぶことのなかったけれど美味しい菓子パンを運んできてくれたことに、身体の裏側がもぞもぞとくすぐられたような心地を覚えた。
菓子パンを半分ほど食べ終えてから、教室に生徒たちがまだほとんど戻ってきていないことを思いだし、そういえば彼女はご飯を食べたのだろうか、と思い至って、菓子パンを半ぶんこにし、イユに差しだす。
イユはまだ私の席のまえに立っている。後ろ手に腕を組み、私の差しだした菓子パンに目を留めると、しばし身体を左右に揺らすように逡巡の間を置いてから、あたしも飲み物買ってくればよかった、とつぶやき、まえの席の椅子に座った。彼女の席ではないが、いまはそここそ彼女のおわすべき場所に思えた。
私たちは菓子パンを半ぶんこにし、つぎつぎに味比べをした。袋の中身はカラとなり、喉が渇いて仕方のなさそうなイユに私は、彼女からもらったペットボトル飲料を、それはすでに三分の一ほどなくなっていたけれど、手渡した。
「飲んじゃっていいの」
ぜんぶはダメ。
私はふだんどおり、メディア端末の画面に文字を打ち、彼女に見せる。イユは目じりを下げる。ペットボトルのキャップをとると彼女は先端にくちびるをつけ、なめらかな喉をこちらに見せつけるように、こくこくと赤子の鼓動にも似た音をたてた。
「はぁ、生きかえる」
飲みなよ、とペットボトルを返されたので、受け取りながらも、口をつけるのには抵抗があった。
視線を感じる。
ここで拒んだらなんだか空気がわるくなりそうだなぁ。
どうしよう。
思いながらも喉が渇いていたこともあり、考えすぎだとばかりに、えいや、とひと息にあおった。
「どう? おいしい?」
返事をするのがむつかしい。ここで美味しいと答えるのがしぜんな流れではあるものの、なんだかそれってほかの意味が含まれそうに思える反面、こう考え、悩むことそのものがすでに彼女の罠であるようにも感じられ、だからでもないが私は、わざわざ食べかけのパンを齧ってから、おいしいね、と文字を打つ。
イユは笑みをたやさぬままに、どこか不服そうに、よかった、と言った。
それから一週間もすると、つづけて声をだしても喉が痛くならなくなった。まだ長い文章は抵抗があるし、何度もつかえてしまうけれど、声帯の機能的にはほとんど問題ないように思えた。
ぐったりするような残暑を幾度か乗り越え、朝夕とヒグラシの声が涼しげに聞こえるようになってきたころには、私がかつてしゃべらない生徒だったことを憶えている者は稀になった。みんながどう思っているかなど私には分からないが、すくなくとも私がしゃべりだしても、あれ? という顔をされなくなったのは確かだ。どうしてしゃべらなかったのかとか、しゃべらないのってつらくなかったの、といった過去を蒸し返すような質問も、数えるほどにしか向けられず、それすらいまでは皆無と言ってよかった。
私は私を特別な存在だとは思っていないが、それ以上にみなにとって私は特別な存在ではなかったのだ。哀しむほうがしぜんなのかもしれないのに、私はそれを知れて、すこしほっとした。
「龍虎(りゅうこ)の仲だよね」
そんなセリフが私のクラスや、廊下をひそかに飛び交いはじめていたのを、私は衣替えをしたくらいのときに気がついた。私に向けられた言葉ではなかったので気に留めていなかったのだが、ふしぎと私に向けてその話題を振ってくる者がいないのに気づいて、これはひょっとするとひょっとするのか、と察し到った。
犬猿の仲を意味するようだ。それは判ったが、では、とそこで気になるのが道理というものだ。
誰が龍で、誰が虎なのか、と。
「イユちゃんは誰とでも仲よくていいね」私は放課後、帰宅途中にそう切りだした。文化祭の準備で放課後まで居残る日が増え、その分、委員会のあるイユと帰る時間帯が重なるようになった。朝は朝で、イユが家のまえで待っているのが習慣となっている。「アイドルみたいっていうか、まんまアイドルだよね。誰からも慕われて」
「まあね。あたし、もう誰のことも傷つけたくないから」
ならばどうしてユウナとは仲良くできないのか。
言い返したい衝動をぐっとこらえ私は、
「じゃあ仲直りできるよね」
カバンから一冊のマンガ本を取りだす。矢継ぎ早にイユに差しだすようにすると彼女は何を思ったのか歩行速度を緩め、私の背後に回った。こんどはさらに私の左側へとつきなおす。
私は右から左へとマンガ本を瞬間移動させる。彼女はもういちど私の背後を経由して最初の位置、私の右隣におさまった。
ん!
受け取ってよ、の意思をこめて私は懲りずにマンガ本を押しつける。彼女は頑としてそれを受け取ろうとしない。ほっぺたにぐいぐい押しつけても、そんなものは見えませんけれど?の顔で、涼しげに歩いている。
私はいよいよムっとして、彼女のカバンにマンガ本をねじこむと、
よーいドン。
一目散に駆けだした。
「あ、こら」
イユが追ってくる気配がある。
私は運動が得意でない。反してイユは完璧超人みたいだからフライングをしたカメを追い越すなんてわけないはずだ。
でも私は確信している。
彼女のようなオシャレ人間は、街中でスカートをはためかせながら、汗を掻くほどに全力疾走したりはしないのだ。
予想通り、角を曲がってひとしきり走ったところで振りかえってみても、そこにイユの姿はまだなかった。おおかたとっくに歩いているのだ。そもそも追いかけたりはしなかったのかもしれない。何事かと通行人がこぞってこちらを見ているので、さすがの私も呼吸を整え、なんでもないですけれど?の顔で、涼しげに歩きつづける。パン屋のまえを通ると焼きたてのパンの甘い香りが鼻をかすめた。
昼休み、私は食堂でうどんをすすっていた。一人だ。ここ数週間はとなりにイユがいるのが通例となっていた。交友関係の広い彼女であるから、食堂にいる時間が長ければ長いほど、私たちの座る区画には人が寄ってくる。まるで私などいないかのように人が押し寄せ、イユを取り囲むものだから、私としてはそそくさと退散するのが常であった。もうすこし言えば、さきにイユが席に座れば、そこに集まる小魚のような人々を避けて、私はほかのテーブルに座ることもしばしばだ。
だからこうして私が一人でうどんをすすっているのは正しい姿で、イユがいないほうがしぜんなのだが、私はなんだかすこしの不安と、嫌な予感、それはどこかしら火薬めいた匂いのする「火花よ散るな」といった懸念にちかかったが、イユの姿が食堂にないことを不気味に思った。
気持ちはやめに教室に戻ると、私の座席にイユが座っていた。まえの机にも座る者がある。そこからは凍てついた空気が立ち昇って見え、ともすればあべこべに灼熱の空気に怯えたように幾人かの生徒たちが教室を飛びだしていく。
私のすぐよこをすり抜けていくクラスメイトたちを尻目に、私は、やあやあ、と何気ない足取りで、自席に近づく。
イユはマンガ本を机に叩きつける。
「はいこれ、お返ししますね」
「雑にすんなや」ユウナが吠える。手本を示すような手つきでマンガ本を拾いあげると、「おまえ友達いねぇだろ。いたとしても同情しちゃうな。こんなふうに乱暴に扱われて。よっぽどやさしいお友達なんだろうなぁ」
愛想尽かれないように気をつけろよな。
吐き捨てながらユウナはこちらを見た。「うちはこれをあんたに貸したのであって、コイツに貸したわけじゃないからな」
断じて。
ユウナはマンガ本を両手で胸に抱く。着崩すことなく身にまとった制服の垢抜けなさに似つかわしくのない、野生じみた目でしばらく私の顔を睨み据えると彼女は一転、ひらりと背を向け、どすどす、と教室の床を踏み鳴らしながら去っていく。
追いかけるべきだろうか。追いかけるべきだろう。
だってあんなにも怒っているのだから。
でもそこまで怒られることをした覚えはなく、しかし心当たりが皆無かと言えばそれもまたノーであり、なんと謝ったものか、となんとなく釈然としない思いを胸に、待って、と声なき声で一歩を踏みだしたところで、
おえ。
うしろから上着の裾を引っ張られ、私の喉は悲鳴をあげた。カエルの断末魔じみている。
誰も聞いてないだろうなぁ。
思いつつ教室を見渡しがてら、私にそんな音をださせた張本人に抗議の目をそそぐ。
「ごめんなさい」イユはしょげた。「でも追いかけなくていいよ。友達なのはわかるよ。あたしがいなかった数年間に、あたしといっしょにいた時間よりも長く付き合っていたんだってのもなんとなく判るけど、なんかだってさ」彼女はまだ私の裾を握ったままだ。「ひとをわるく言うのは嫌だけど、付き合う相手は選んだほうがいいと思う」
えー。
私は内心絶叫した。それをあなたが言っちゃうんですかー。
というか、ユウナはユウナで同じことをあなたに対して言ってましたけど。
もし私の声帯が電動歯ブラシ並に流暢に振動できたならば反射的にそう口走っていたかもしれない。ただ、彼女たちの仲がよろしくないのは、人間関係においていつまでも母から心配されつづけている万年幼稚園児の私であっても察している。
似た者同士なのに。同族嫌悪かな。
仲良くしてほしいな。
思うけれど、これは私の一方的な願望であって、彼女たちが仲良くする道理は本当はないのかもしれない。無理に縁を繋ぎつづけるよりも、火傷をしない距離感を保ったまま、接点を持たずに生活していくのは一つの最善であるはずだ。
けれどできれば互いに嫌な面以外のところも知ってほしい。壁をつくるならそのあとでも遅くはないのではないかと思う反面、これ以上の軋轢を招く懸念も拭いきれず、けっきょく私にできることは、まあまあ、と彼女たちをなだめることに終始するし、終始すべきで、それ以上の干渉や強制を向けることではないのだろう。
考え私は、まあまあ、と目のまえのあらぶる女神に微笑みかけ、ちょっとお手洗いに、の仕草を残して、席を立つ。
「どこ行くの」
ちょっとあっちに。
先刻ユウナの立ち去った方向を示し、私は席を離れる。イユは息を呑んだような間を開けると、いったん椅子から立ちあがり、すこし迷った様子を見せてからまた座った。
私は一人で、教室をあとにする。ユウナの姿が廊下にないかと目を配り、となりのクラスを覗き、そこにも姿がないことを見届けると、食堂から戻ってくる生徒たちの川をさかのぼりながら保健室へと歩を向けている。
やはりユウナはそこにいた。
「ほら、相棒が迎えにきたよ」
保健室の先生は投げやりに言って、ちょっとお願いね、と意味ありげに私の肩に手を置くと、私と入れ違いで保健室を出ていった。
ベッドは三つある。うち一つの仕切りが下りており、私は泥棒になった気持ちで忍び寄る。カーテンにじぶんの影が映るところまでくると、その奥から、
「きょうはもうサボる」と声がした。「早退させてもらうことにしたから放っといて」
言われたところで、わかったじゃあね、とはいかぬのだ。
カーテンをくぐって中に入る。ユウナは掛布団のうえにじかによこになっている。膝を抱え丸まり、母体のなかの赤ちゃんのようだ。
ゆびをしゃぶっていたら百点満点だったのにな。
私はベッドに腰掛け、彼女の腰骨のうえに手を置く。
子守唄を歌えれば完璧だ。しかし私は歌えないので、ぽんぽん、と叩くだけにする。ユウナはさらに丸くなり、
「おせっかい」
つぶやいたきり、ぐおーぐおー、とおおげさにイビキを掻きだした。
彼女なりの照れ隠しかな。
私はメディア端末を取りだして、文字を打つ。
仲直りしてとは言わない。でもわざわざ衝突することないと思う。
ユウナに画面を向ける。彼女は目だけをちらりと寄こす。目玉が文字を追っているのが判る。彼女の唇がイソギンチャクみたいにきゅっとしぼまったので私は、
ユウちゃんのほうがおとなだと思ってるんだけどな。
続けて文字を打つ。ユウナは、うー、とうなり、そりゃそうだけど、とまんざらでもなさそうに、それでいて悶えるように言った。
ダメ押しとばかりに私がまた文字を打とうとすると、それを阻止するかのようにユウナはすばやく上半身を起こした。
「わかったってば。もういいよ」
宙を手で払う。それから彼女はいつものようにあぐらを組み、
「仲良くするのは無理そう。だって向こうにその気がないみたいだから」
私が目を細めると、
「こっちのほうでもないかもだけど」ユウナは言い直し、「でも、もう突っかかったりはしない。約束する」
突っかかったりしてたんだ、と唖然としてみせてもよかったが、いまは珍しくユウナが真面目ぶってくれているので、腰を折らずにおく。
マンガをだいじにしないのはよくないよね。
私はそういったことを文字にする。本を、それもひとから借りている本を粗末に扱うのは、たしかに怒ってもいいことかもしれない。
慰めるのも兼ねてユウナの肩を持つと、彼女は鼻の穴を膨らませ、
「ほんとそう」
語気を荒らげた。「本をだいじにしないやつは友達もだいじにできないやつだよ。むかしから言うよ。じっさいそうだよ。うちはなにもじぶんのことだけで怒ってるわけじゃないからな」ユウナは私の名を呼び、「アイツ転校してきてからやっぱり様子変だったし、あなたのお口チャックが解けたのだって無関係じゃないんだろ」
アイツと。
しもぶくれほっぺの合間から唇がちょこんと突きでている。いじけた幼児みたいだ。思わず頭をなでつけると、ますます膨れて赤くなる。「まじめに話してんの!」
私は立っていて、ユウナはベッドのうえであぐらを掻いている。だからだろうか、
こんなにちいさかったっけかな。
馴染みの友人の姿がやけにちいちゃく感じられた。不思議の国のアリスの気分を味わう。
ひょっとしたら、と思いつく。ふだん、身近に背の高い、すらっとしたひとを置いているせいかもしれない。
私がぼーっと視線を宙に彷徨わせたままでいたからか、
「分かった、もういい。もうマンガ貸してあげない」
同士でもなんでもない、とユウナはいじけた。私がびっくりしてしまうくらいに、私ですら誤解する余地のない拗ね具合だったもので、私はますます、おっきな赤ちゃん、と思って、にこにこした。
それがよくなかった。
おっきな赤ちゃんはもちろん赤ちゃんではないので、私の胸中を満たした慈愛の、どこか孫を見守る祖母じみた視線にちゃんと気づくこともできるし、立って歩くこともできる。
ベッドから飛びおりるとユウナは、靴を手で持った。履く時間ももったいないらしい、そのまま保健室をでていく。
私はあとを追う。彼女は廊下に放り投げた靴に、器用に足を引っかける。
ごめんごめん、とまずは両手で拝むようにして先回りし私は、ユウナの進路を塞ぐものの、彼女は、ふん、とまたしても分かりやすい返しをするので、私はもう、彼女がこんなにもひねくれるのがへたくそなのかと、無垢な者のせいいっぱいの反抗に胸の奥がくねくねした。
いっこうに歩行を緩めない彼女の背中に、えい、と抱きつく。それを、しがみつく、と言い換えてもよい。
彼女はいちど身体を硬直させたが、すぐさま足を踏ん張り、私ごと引きずった。私は無駄に分厚いマントの真似事をしながら、なんだか楽しくなってしまって、ふへへ、ふへへ、と即席のアトラクションを満悦する。
ユウナもユウナでじぶんの状況がおかしかったのか、やがて、やめてよもー、と言いながら肩を弾ませた。
廊下にほかの生徒の姿はない。ちょうどチャイムが鳴り、午後の授業がはじまる。廊下からほかの教室の様子を眺めながら、ガラスの向こうからいぶかしげな眼差しでこちらを見る教師たちに、具合がわるくて、の演技を披露しながら、私は相も変わらずユウナの背中にもたれかかっている。
ユウナはじぶんのクラスを通りすぎる。私を私の教室まで運んだ。
「数学だったからもすこしサボる」
あ、さいですか。
教室の扉を開けると誰もいなかった。体育だったのを忘れていた。
移動教室なん、と問われ、そう、とうなづく。
背中から降りようとすると、逃さんとばかりにユウナが私の腕に絡みつく。私たちはしばらく押しあいへしあい、笑い声を堪えながら、じゃれあった。
けっきょくつぎの授業がはじまるまで、私たちはがらんとした教室で終末の世界ごっこをつづけた。昼間なのに、明かりの消えた教室はひどく暗かった。秋風がひゅるると窓をぶつ。
やがて休み時間を知らせるチャイムが鳴り、五分ほどしてちらほらと生徒たちが戻ってくる。ユウナはじぶんのクラスから教師がいなくなるのを見計らって、ニンニン、などと立てたゆびを握りながら去っていった。
チャイムが鳴る寸前まで忍者が主人公のマンガの話をしていたので気持ちは分からないでもない。ふだんのムスっとした顔のままであるので、なおさらギャップが際立った。
おそらく私以外で、ユウナのそうしたお茶目な姿を知る者はそう多くはない。いいや、ひょっとしたらこの学校にはいないのかもしれない。
マンガをまた貸してくれるという。かってに机に置いておくから、と言っていた。いまから楽しみだ。
始業を知らせるチャイムが鳴る。本日最後の授業がはじまろうとする寸前にイユが教室に入ってきた。入口のところで先生が――この先生は担任だったけれども、具合はもういいのか、と話しかけている。イユは煮え切らない態度で、ええ、とか、まあ、と言って席に着く。
先生はこちらを見て私の名を呼んだ。
「――もいいのか? 体調わるかったら無理するなよ」
おおかた保険室の先生が担任に告げたのだろう。私はユウナの付き添いでしかなかったが、顔のまえで両手をぶんぶん振って、ぜんぜんだいじょうぶです、お気遣いなく、の意を示す。
先生はうなづき、授業を開始した。
私は授業中、うしろの子に消しゴムを借りるフリをして、それとなくイユの表情を窺った。彼女は上の空で、窓のそとを眺めていた。
私は考える。彼女は休み時間のあいだどこにいたのだろう。何より、先生はどうしてイユが具合を崩していると思ったのだろう。
私は、私たちが終末の世界ごっこをしていたときに、真面目に授業を受けていたコたちのことを思った。もし私たちの姿を目撃したら、彼ら彼女らの目にはどう映っただろう。
この日は放課後になってもイユからは近寄るなオーラがほとばしっていた。私にとっては瞭然のそれが視えない者もいるところにはいるもので、私が言うのもなんだけれど、もっと空気を読んであげて、と思いたくなるほどイユに話しかけては、けんもほろろに返事をもらい、たじたじになっている者たちを視界に入れつつ、私は久方ぶりに一人で帰路につく。
長期戦かな。
何ともなしに思う。とうぶんイユとは話すことはないだろう。それはそれで寂しいと健全に思えるじぶんにすこしほっとする。
翌朝、イユが家のまえで待っていた。ふだんと変わらぬ佇まいで、寝坊しないなんて偉いね、なんて飄々と笑窪を向けてくる。
あまりに変わり映えのない姿に、どちらかと言えば不穏なものを感じたが、学校に着くころにはそれも杞憂だと判断するまでに気をゆるめていた。
だからこの日、学校でいちどもユウナの姿を見かけなかったことに気を留めなかった。
「あしたはどうするの」イユが下駄箱から靴をとりだす。
あすは休日で、とくに予定はない。学校の昇降口をでるとイユはマフラーを掻き合わせ身震いする。「冬って苦手だなぁ」
同意、と思いながら私は肩をいからせる。
時期的にはまだ秋なのに例年よりも寒い気がした。木々は紅葉を終え、骨だけになっている。
期末試験や冬休みの予定など、やや気がはやい話題を振りながらイユは私に、お出かけの約束をとりつける。断る理由を探すよりも引き受けてしまったほうが楽なので、私は予定が合えばね、とこれは声にだして言った。
うわぁ、楽しみ。
無邪気のお手本のような笑みを向けられ、まんざらでもない。
私はもう、彼女をそばに置いても身体のなかがどんよりと重たくなったり、あべこべに希薄になったりすることはない。
そう思っていたのに。
あくる日、私はじぶんの部屋の姿見のまえでいつもよりすこしだけおめかししていた。イユに誘われ、午後にアウトレットモールに向かう予定だった。夕方から雨が降るそうで、水に濡れても構わないコーディネートを考えているうちに、家をでないといけない時刻になっていた。
待ち合わせ場所は駅前だ。どうせならうちにまで迎えに来てよ、と思ったが、私がそう訴える前にイユが、デート気分、とつぶやいたので、そういう趣向ですか、と納得した。家まで迎えにくるのはもはや日常であって、非日常感を味わうには待ち合わせが有効だ。その理屈は理解できた。
認めがたいことに私はふだんよりも気持ちがふわふわしていた。それはかつて私の内に巣食っていたがらんどうとは異なる、綿菓子めいた浮遊感だった。
居間でソファに座って、ぼーっとしている母の肩を叩き、行ってきます、のジェスチャーをする。母は片手をあげ、ひらひらと振った。「車と不審者には気をつけて」
玄関で靴を履き、そとにでると、アスファルトに人影が浮かんでいるのが見えた。
あれ、イユかな。
思いながら、ゆっくり段差を下りると、ブロックの陰からユウナが顔をだした。きょうもきょうとて仏頂面だ。
ど、ど、どうしたの。
私はゆびであっちを差したり、こっちを差したりしながら、戸惑いを示す。ユウナは、デニムパンツにダウンジャケットを羽織っていて、完全に冬の服装だった。リュックを背負っている。彼女はふだんよりいっそう深いむっつり顔で、どこ行くの、と言った。
アウトレットモール、と声にだそうとしたけれどいままで口にしたことのない語彙だったので、上手に発音できる気がしなかった。メディア端末に文字を打って、場所を伝える。
「ふうん。誰と」
一人で、と訊かれなかったことで、私がこれから誰とデートごっこをするかを彼女は知っているのだと思った。すくなくとも当て推量はついているはずだ。
隠す必要もなかったので、イユとだけど、と文字を打つ。
ユウナはまた、ふうん、と言った。
いっしょに行く、と誘ってもよかったけれど、私がよくともイユはもちろん、ユウナ本人だっていい顔をしないだろう。無言のまま数秒がすぎる。
顔を背けてからユウナは、
「疑ってるわけじゃないけど、そっちの口からちゃんと聞いておきたくて」
リュックを地面に置き、そこからマンガ本を一冊取りだした。
私は息を呑む。
その本はシワクチャで、表紙はぐちゃぐちゃに滲んでいた。
似た状態になった紙を見たことがある。服といっしょに洗濯した紙幣を乾かしたとき、そのマンガ本と同じような仕上がりになった。
どうしたのそれ。
ゆびさきを向けながら私は、女王蜂とそれを取り巻く複数の働き蜂のことを思った。
「知らん。うちはただ約束通りあんたにこれを貸そうとしただけ。あんたの席にこれを置いといただけ」
ボロボロのもう二度と読み物とは呼べないだろう漫画本をこちらに静かに差しだしながらユウナは、
「約束は果たしたかんな。うちはちゃんと貸した。でももう読めないよな。貸したって迷惑なだけだよな」
本を掴んだ私のゆびから彼女は半ば強引に本をひったくった。
私の名前を呼ぶと、わるくないのは知ってる、と続ける。「でももう無理だよ。いままでみたいにしてらんない」
言いたい旨は理解できた。そしてユウナが、本をダイナシにした人物の顔をはっきりと思い浮かべていることも窺い知れた。
証拠はあるの。
訊ねたい一心を押しとどめる。証拠なんてないはずだ。残すはずがないのだ。
思いながら私は、かつて私にがらんどうを植えつけた人物の顔を思い浮かべていることに失望した。
やり兼ねない。私はそう考え、そう結論していた。
ユウナがいそいそとリュックを背負い直したので、私はあわてて引き止める。
鋭利な眼差しを寄越され、ひるんでしまうが、本は弁償するから、とまずは伝える。声に出して言い、メディア端末にも文字を打った。
「なんで」
ユウナの疑問はもっともだ。私が本をダイナシにしたわけではない。ユウナからすれば私が犯人を庇っているように映ったはずだ。
そんなつもりはない、と告げる。きょうこのあとの予定もご破算にするし、なんなら新しい本をいまから買いに行こうと提案する。
「いいよ。わるいし」
それを言うなら私のほうがわるい。気分がわるい。気が済まない。巻き込んだようなものだ。責任がまったくないわけではない。私の机に置いたはずの本をイタズラされたのだ。私だって怒っているし、やっぱり責任を感じてしまう。
そういったことを声にだしながら、文字にも打って伝えた。
誤解されたくなかった。
これっきりになんてしてほしくなかった。
絶対に許さない。
私は言った。だいじな友達のだいじな本をこんなにした犯人のことは絶対に許さない。もし誰かに指示をしてそれをやらせた人物がいたら、そんなやつとは一生口をきかない。
そういったことをつれづれと口にしたらなぜかだみ声しかでず、おかしいなと思っていたら、ユウナがハンカチを取りだした。
「わかった、わかったから。もういいよ。なんかこっちこそごめん」
顔をごしごし擦られ、ようやくじぶんが泣いていることに気づいた。頭がぐわんぐわんする。
いったんユウナを家にあげ、落ち着いてからこの日はユウナと書店さん巡りをした。メディア端末の電源は切っていた。とうぶん起動をしないつもりだ。声はでるけど言葉が滑らかに出てくれないので、意思疎通のためのメモ帳を書店さんで購入した。ユウナには新しい漫画を二冊プレゼントした。彼女はズタボロの本を捨てようとはしなかった。
この日から一週間、私はいつもよりはやく登校し、学校でも時間があればつねにユウナのそばにいた。ユウナとは頻繁に手紙のやりとりをした。
しゃべるのは疲れる。
私がぼやくとユウナは、書くほうが疲れるべ、と言ってシャーペンを唇と鼻のあいだに挟んだ。
よい友を持った。
しみじみと思い、反面、ふたたび胸のうちにわだかまりはじめたがらんどうの空虚さを煩わしく思った。
この期間、私に話しかけてくる者は、ユウナ以外ではいなかった。
初雪を観測したその日、私はいつもよりも遅い時間帯に家をでた。母からはとくに何も聞いていなかった。私がはやく家をでた分、誰かが家のまえで待ちぼうけていたり、インターホンを鳴らして私の所在を問うた者はいなかったようだ。
だからもはや私がはやく家をでる意味はなく、安心してたっぷり布団のなかで丸まってから、ついでにいちどお風呂に浸かったりもして、丹念にぽかぽかを満タンにした身体で以って、学校に向かうべく、玄関を開けた。
あまりの寒さに、ぴゃ、と声がでた。
その声に驚いたように塀の陰から顔を覗かせる懐かしい顔、それはクラスでは馴染みの顔であるにも拘わらず、私の世界からはすっかり切り離されていた者の端正な横顔を目にして、私はその場から動けなくなった。
いったん家のなかに引き返し、立てこもろうかとも考えた。
ただ、私が引くのは違う気がした。私と彼女の問題ならそれでもよかった。でも今回ばかりは、私が引くわけにはいかないのだ。
私は怒っていた。
怒っていたのだと、いまさらのように思う。
短い階段を下りて、道路に足をつける。
無視はしない。
しっかりと目で彼女の顔を、姿を、一瞥する。タイツが温かそうで、それいいな、と思いながら歩を進めた。
彼女は私の名を呼んだ。呼び止めたと言っていいだろうそれを私は振り切った。
これは無視ではない。
いや、無視かもしれない。
ただ私のほうには彼女のそれに応じる道理がなかった。すくなくとも彼女には私よりさきに謝罪すべき相手がいるはずだ。
ひょっとしたら私の与り知らぬところでユウナと彼女とのあいだに何かしらの接触があったのかもしれない。ただ、それでも私はユウナから直接そのことを聞かなければ、私の独断で彼女との縁を結び直す真似はできない。
足音が追ってくる。小走りだ。
待ってよ、と肩を掴まれ、私は身体を揺すって振り払う。足は止めない。
彼女が何事かを言っている。声量はそれほど高くはないが、キンキンと肌を刺すような響きを伴っていた。
走ってしまおうか。
でも追いかけてきたら、さすがに可哀そうになって立ち止まってしまいそうだ。一顧だにせずこのまま進んだほうがよいのではないか。
思いながらすでに足は小走りになっている。追いかけてくる足音が徐々に遠のいていく。
パン屋のまえを通ると焼きたてのパンの甘い香りが鼻をかすめた。
そういえば、と思いだす。前にもこんなことがあったな。
あのときも彼女は私を追ってこなかった。
こんどもそうなのかと思った矢先に、遠くなりつつも未だに彼女の足音がするのに気づく。私の名を呼んでいる。待って、とか、話を、とか途切れ途切れに叫んでいる。しかしその声は確実に遠のき、かすれ、町の喧騒にかき消されつつあった。
足取りが重いのだ。
思い到ったときには、曲がり角に差し掛かっていた。いったん曲がってから歩を止める。彼女から私の姿は見えなくなったはずだ。それでも足音の律動は同じテンポを刻んで聞こえる。
足を引きずるようなバランスに欠けた音だ。
何かを持っている。それも、けっして軽くはない代物だ。
身体はさきを急ごうとしているのに、どうしても気になって、ああもう、と地団太を踏んでから私は、こっそり曲がり角の壁からいま来た道を覗き見た。
彼女は紙袋を両手で抱えて、よたよたとよろけていた。駆けるどころか、小走りですらなく、いまにもへたりこんでしまいそうな足取りだ。
千鳥足、死に体、満身創痍――とまでいくとさすがにいきすぎな気もするが、彼女はもはやまえを向いておらず、視界からはとっくに私の姿は消えていた様子だ。
それでも追うのをやめない姿に、罪悪感が喉元まで競りあがる。
話を聞くくらいはしてあげてもよいのではないか。
すくなくとも、ここで彼女を無視して置いてきぼりを味あわせるのは、私の信念に反する。信念と言うとなんだか大袈裟になってしまうが、要するに、これはイジメではないのか。私は私を嫌いになりそうで、そのことにひるんでいる。
それはそれで我が身可愛さの保身のようで気分のよいものではない。どうすればよいだろう、と顔を引っ込め、いまいちど考える。
考えながらも足は引き返すことなく、学校へと向いている。
歩きだすと、徐々に考えはまとまった。優先すべきはまずはユウナであり、背後でよろけている彼女ではない、との結論に結びつく。
すこしくらい痛い目に遭ったほうが彼女のためだ。
そうだ、そうだ。
これはけっして、かつて私にがらんどうを植えつけ、私から声を奪った彼女に復讐するための考えではない。そうつよく念じながら、すこしの清々しさと、やはり罪悪感を拭いきれずにいるのだった。
ひと足先に学校に着くと私は、朝の時間のチャイムが鳴るまでじぶんの席から動かずにいた。ユウナは隣のクラスだから、廊下にでれば、通学路に置き去りにしてきた例の彼女と鉢合わせしてしまい兼ねない。
危惧した割に、けっきょく件の彼女はチャイムが鳴るぎりぎりになって教室に入ってきた。今朝がた見かけた紙袋を持っておらず、どこかに置いてきたのだ、と思った。
どこにだろう、と考え、それから私はいくつかの候補、たとえば廊下のロッカーだったり、ほかのクラスの誰かへの贈り物だったりしたのだが、ともかく私は、つぎに彼女から話しかけられたら、こんどこそ応じようと心に決めた。
「聞いてよアイツ、こんなの持ってきやがった」
昼休みになってユウナが弁当を持ってやってきた。脇には見覚えのある紙袋を抱えている。
クラスの大半は食堂に出張り、いない。この時間帯の教室には私たちが二人きりだ。箱庭と言っても過言ではない。半ばクラスメイトたちがわざわざ席を外して、私とユウナをこの場に取り残すような作為を感じなくもなかったが、それはそれで配慮してくれているとも捉えられるし、さわらぬ神になんとやらを地で描いているだけだとしても、すなわち私たちが神のようなものだ、と解釈できなくもなく、端的に害はないので、甘んじてこの教室の孤島を味わう日々を送っている。
「朝きたらアイツがクラスで待ち受けててさ。うちの席に、椅子じゃなく机にケツつけて、何様だってんだ」ユウナは弁当のつつみをほどく。「弁償するってソレ押しつけてきやがって」あごをしゃくり、紙袋を示し、「本のことは誤解だけど、じぶんが元凶みたいなものだからって。言い訳がましくガガガガってしゃべってって、いっぽうてきに、うちなんかここにいないみたいにさ。謝罪する顔じゃねぇっての」
誤解ってどういうこと、とまずは訊いた。
「なんか、ほかのコが勝手にやったことだって。じぶんは何も言ってないって。信じられるわけねぇじゃんね」
じぶんの態度が周りに誤解を与えてしまったかもしれない。周りのコもよかれと思ってやってしまったことで、みないまはやりすぎたと反省している。元はじぶんとあなたの喧嘩が元だから、これはあたしたちで解決すべきことだ。だからまずは誠意を示すので、これで水に流してほしい。
まとめればそういうことを、つらつらとあのコはユウナに捲し立てたそうだ。
「知るかよ。んだよこれ。どうすんだよ、全部もう持ってるっつうの」
紙袋の中身は、私も以前にユウナから借りたことのあるマンガ本一式だった。買えばこの国でもっとも高い紙幣を二枚使っても、お釣りはじゃりじゃりと小銭だけとなる。
「アイツの席どこ。返すはこんなもん」ユウナが教室を見渡す。「ねぇ、どこってば」
私がなかなか反応を示さないからか、机のしたで脚を小突いてくる。私は、八つ当たりしないでよ、の抗議の眼差しをそそぐ。すこし悲しそうに唇をとがせてみせるのは、この半年に身に着けた私の処世術だ。
愛嬌を滲ませた甲斐があったのか、ごめん、とユウナは謝罪した。素直だ。
「でも、こんなんで許せないのはわかるでしょ。いまさら仲良しこよしなんて、たとえフリでもやなこった」
だってそうじゃん、とハンバーグを一切れ箸で挟んで、あーん、としてくるので、私はありがたくいただいくことにする。美味しい。
「食べたね」ユウナがにやりとしたので、咀嚼を中断する。逡巡しつつもごっくんの衝動に抗いきれずに、呑みこんだ。
目で、なに、と問う。
「食べたね。借りができたね。もううちを裏切れないからね、だってそうでしょ、そうだよね」
元々裏切るつもりなんてないし、そんな局面に立つ予定もない。
「前々から疑問だったんだよね。なんかべつに、うちらはただのマンガ同好会のよしみみたいなもので、こういう言い方するとなんだろ、束縛激しい恋人みたいでやなんだけどさ」
私は口を閉じたまま舌で歯のまわりを舐めとる。ユウナは続ける。
「どっちの味方なわけ」
ハンバーグはもうないのに私はまた、ごっくんと喉を鳴らす。
「まさか本にあんなことした相手のこと許そうだなんて考えてないよね。許してあげようよ、なんて言いだしたりしないよね。あっちはトコトンこっちのこと無視して、だって見てよこれ」
ユウナが腕を広げる。がらんとした教室に、静寂が浮きあがる。
「あのひと、じぶんじゃ何もしてない、命じてないとか言ってるけど、じゃあこれなんなん。アイツの影響ありまくりじゃん。それでいて何も動こうとしないで、はいコレってこれ見よがしな、誠意の感じられない贈り物されて、許せってほうがおかしいでしょ」
火に油、と文字が脳裡に浮かぶ。
動機はともあれ、あのコはユウナに謝罪をした。それはあのコにしてみれば屈辱にちかかっただろうことは私であっても推して知れる。それでもあのコはユウナとの仲をいまよりもマシな方向に修正しようと試みたのだ。
なぜかは詳らかではない。訊いたところで、当の本人がそれをはっきり言葉にできるのかも怪しいところだ。それでもあのコはユウナに謝罪をした。
だが、ユウナにとってそれは落とされた火ぶたに等しかった。宣戦布告も同然の侮辱に映った。
大炎上ではないか。
大爆発と言っていい。
それの火消しをどうして私がしなければならないのだろう。目のまえで私に当たり散らしているユウナにも腹が立つし、こんな事態を招いたあのコにも憤りが湧く。
かってにしなよ、巻き込まないで。
喉元までのぼった憤懣は、声になる前にまたハンバーグみたいにお腹の底に沈んだ。
私はユウナからたくさんの日々の癒しを受けてきた。それはときにマンガだったり、談話だったり、授業をサボるといった不良行為だったりする。でもこの関係は花に水をあげて、よちよち育んできたみたいに、一朝一夕で築かれる関係ではなかった。
それこそ、私のなかに巣食ったがらんどうに声を奪われていたあいだ、ユウナは私に水をそそぎつづけてくれていた。
私にがらんどうを植えつけたあのコと比べてどちらの関係がよりたいせつなのか、なんて考えるまでもなく、比較の対象になると考えるだけでもユウナへの裏切り、冒涜のように感じる。
いっぽうでは、ユウナは見境なしにあのコのことを毛嫌いしすぎだ。仲良くしなよ、とは言わないまでも、そこまで徹底して拒絶するのもどうなの、と思いはする。
今回の一件以外でも何かユウナにそうさせる拘泥のようなものがあるのではないか、と勘繰らずにはいられない。
だから手放しでユウナを肯定できないのだ。まるっと味方でいさせてくれればよいものを、そこらへん、人間関係って複雑、と気が重くなる。
「その顔は不満って顔だ。どこがダメ? うち、何かおかしいこと言ってる?」
さすがは長年私の友人をやっているだけのことはある。言葉がなくとも彼女をまえにすると私は雄弁になる。
「べつにいまさらあのひとと仲良くしたいわけじゃないんでしょ」
私がここで、仲良くしたいよ、と言えばおそらくユウナは食い下がったりはせず、ならそうしたら、と言うだろう。そして私から距離を置くのだろう。あのコにいまそうしているように。
仲良くはしたいよ、と私は言った。声にだし、言った。
そっか、とユウナが口にする前に私は、
「みんなと仲良くしたいよ」と補足する。「誰だからとかじゃなくて、みんなと仲良くしたい」
うまく言える気がしなくて、みんなと、を強調するよりない。
「うちはそうでもないけどね」
ユウナは言ったきり、お弁当をすっかりやっつけるまで、しゃべらなかった。
教室にクラスメイトたちが戻ってくる。あのコが戻ってくる前にユウナはじぶんのクラスに戻っていった。紙袋は私の席に置いたままだった。持っていって、とは言えなかった。
絶対に許さないつもりだった。マンガ本をダイナシにするなんて、それがじぶんの持ち物でなくとも腹が煮える。でも、わざとじゃなかった、と言われてしまったら、絶対に許さない気持ちから、「絶対」が抜け落ちもする。
これ、どうしよう。
ずっしりと腕にくるような紙袋をまえに、嘆息を吐く。マンガ本のレンガはロッカーにでも押しこめておこう。昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る前に、済ませてしまおう、と席を立ったところで、
「気に入らなかったんだ、それ」
うしろから声をかけられ、飛び跳ねる。びっくりしたぁ、と唇だけで唱えながら振り返ると、かつて私にがらんどうを植えつけ、いまは問題の種と化している女王蜂さまが立っていた。
私は彼女の存在よりも、こちらに浴びせるように視線を向けているほかのクラスメイトたちに鼻白む。
「謝りに行ったんだけど、あんまり受け入れてもらえなかったみたい」髪の毛をいじりながら彼女は、「それ、よかったらもらって。いらないなら捨ててもいいし」
もう片方の手で、しきりにスカートをにぎったり、離したりを繰りかえす。
捨てるなんてもったいない。ただ、私がもらうわけにもいかない。
かといってこのまま突き返しても彼女のことだから、自分の手で捨ててしまいそうだ。彼女の誠意を無駄にするのも何かが違うような気がした。
けっきょく私は考えあぐねた挙句、財布を取りだし、そこに仕舞ってあった紙幣をあるだけ彼女に握らせた。金額としては紙袋に詰まった本を買うにはもう半分くらい足りない。
「なにこれ、いいよ、もらえないよ」
それはこちらのセリフだ。
「それよりも」
と、口にした彼女の僅かに弾んだ声音に、とっさに耳を塞ぎたい衝動に駆られる。何か、そう、見てはいけないものを見てしまいそうな予感があり、それはどちらかというと私のための危機感というよりも、子どもがじぶんの誕生日ケーキを運ぶと言ってきかないときのような、覆水盆に返らずが脳裡をよぎるようなそういった嫌な感覚だった。
「もうこれで許してもらえたのかな。けっこうがんばったっていうか、つらかったんだよ、だって話しかけてもずっとそんな感じだったし、避けられたのもやっぱり、ほら、ね? あ、でもそうじゃなくて、べつに責めてるわけじゃなくって、だってわるいのはあたしのほうだし、だからこうして謝ったわけだし、でももう、こういうの終わりにしたいなって」
また前みたいに仲良くしよ。
差しだしてくる彼女の手を私は握り返すことができなかった。
彼女に透けて見える打算が、私に彼女への怒りを再燃させる。
椅子から勢いよく立ちあがり、じっくり彼女の手のひらに視線をそそいでから、何でもないようによこをすり抜ける。私の腕には紙袋が抱えられており、彼女の机まで移動すると、そのうえにわざとぞんざいにそれを置いた。
「え、なんで、わ、え、ありがとう?」
彼女が困惑している。座席まで荷物を運んでくれてありがとう? いやなんか違うな。そう戸惑っている様子がありありと伝わる。私はまたじぶんの机に戻り、こんどはまるでこの教室には私しかいないのだ、とじぶんに言い聞かせながら、ちょうどよく鳴った始業のチャイムを耳にする。
先生が入ってきて、さっさと席につけー、と声を張った。私のよこには未だに例のあのコが立っていたけれど、唾液を呑みこんだような音を残して、足取り重くじぶんの席へと戻っていった。
私の手渡した紙幣を彼女は握ったままだった。
返してほしいと思ったけれど、そのための行動をとるくらいならこのまま手切れ金と見做したほうが心の安寧は保たれそうだ。
「えー、泥棒じゃん」
放課後、ユウナにそのことを話した。私の怒りに共感してほしくて話したのに、いざユウナの髪が逆立つさまを目の当たりにすると、何かしてはいけないことをしてしまったような後味のわるさがこみあげた。だからなのかついつい、でもじぶんから謝ろうとしたのはよかったよね、と女王蜂さまを庇ってしまった。
「甘い。甘すぎる。どんだけ過保護だよ、ちょろ助だよ」
そうだよなぁ、としょげてしまう。もしかしたら、と思ってはいた。私はあのコに甘いのではないか、と。
どちらかと言えば、私から声を奪い、がらんどうを植えつけたという意味で、厳しめに接してきたつもりだ。ただ、そうした因縁から理不尽に彼女を傷つけてしまうのは私の好まぬところでもあり、差し引きゼロにしようと、いささか甘く接していたのかもしれない。
そっかぁ、そうだよなぁ。
ユウナから見てもそうなら、私はやはりあのコを特別視していたのだろう。本来ならばだいじなものを損なわれたユウナのほうに肩入れすべきなのに。
庇うべきなのに。
私が抱いている怒りの根源と同じことを、私はユウナにしてしまっていたのかもしれない。優先して考えるべきはユウナであり、私とあのコの縁ではないはずなのに、私はやはりあのコの肩を持とうとしていた。
「でもまあ、うれしいよ。ありがと。怒ってくれて」
ユウナはじぶんの下駄箱のほうに進路を曲げた。靴を履いた私たちは昇降口のさきで合流し、肩を並べて下校する。
振り返ったらあのコがこちらを見ていそうで、私は校門をでるまで足元の影を見詰めながら歩いた。ユウナはずっと一人でしゃべっていて、気づくとふだんどおりにマンガやアニメの話になっていた。ユウナはバス通学なので、ずっといっしょには歩かない。
ばいばい、とバスに乗りこむユウナに手を振り、彼女が座席に着く姿を見届けてから、遠ざかるバスとは反対方向へと私は一人で歩きだす。
いつも、このときに緊張しているじぶんがいるのには気づいていた。ひょっとしたらあのコがあとを追ってきていて、鉢合わせするのではないか、といった恐怖があった。それを期待といってもあながち間違ってはおらず、私はいつも期待が裏切られるたびに、安堵とすこしの寂しさを覚えるのだ。
いったい私は何をしているのだろう。
正しいことがしたいだけなのに。
本当はそんなことなど考えてはいないのに、正しさを指針にすることの気楽さには抗えない。
この日の帰路にも、つぎの日の朝にも、学校でも、放課後でも、あのコが私のそばに寄ってくることはなかった。
「諦めたんじゃない」
帰り道にユウナが言うけれど、愛想を尽かされただけだったりして、とおどけてみせる私は、無理に笑みを浮かべているのが、引きつる表情筋のお陰でよく判った。
「愛想なんかとっくに尽かしてるよ、こちとら、百億年前からな」
そっか、そうだよね。
私は声にだして、言った。ユウナとの会話ではもう、メディア端末を使うことはない。言い淀んでもユウナはちゃんと待ってくれるし、言い間違えも、ちゃんと指摘しながらに、何事もなく会話をつづけてくれる。母は私が素っ頓狂な言い間違えをすると、遠慮会釈なく笑う。私は笑われるまで、じぶんの言い間違えに気づかないから、そういうときはいっしょになって笑いながら、悔しい気持ちにもなった。
ユウナといっしょにいる時間では、そうした悔しい気持ちにならずに済んだ。
居心地がよい。
そのはずなのに、今この瞬間に胸に残留している感情はけっして上向きのふわふわではないのだった。
なぜだろう。
疑問しながらも、深く考えたくない気持ちそのものが、私に、私の意地汚さを突きつける。
後味がわるい。
もっとウキウキしたり、ワクワクしたり、たくさんお代わりしたいと思えるような美味しい気持ちになっていたい。マンガを読んでいるときや、新しい本を手に入れたときのあの感覚のように。
でも今は、本に目を落としていても、文章やキャラクターのセリフが、穴だらけのチーズみたいに不規則に欠落する。知らぬ間に私の意識はもっとほかのところに飛んでいて、それは虚構ですら届かない虚無の世界へと旅立っている。
がらんどうへと。
かつてそれは私のうちに根付き、広がっていたのに、いまではもう、私のそとに、手の届かないところに移ってしまった。
考えごとをしていたのがよくなかった。気づくと、右折するはずの道を通り過ぎていた。登校するときの道を辿っている。
要するに学校のまえまで戻ってきてしまっていて、何をしているんだか、と呆れるよりもさきに笑ってしまった。
誰かに見られていたら嫌だな。
思うものの、端から見たって帰り道を間違ってしまったなんて誰にも判りはしないのにと自意識の過剰さにうんざりする。
回れ道をする。校舎に背中を向けようとしたとき、昇降口からあのコが現れるのを目の端に捉えた。
気のせいかもしれない。
思うのに身体は振り返ろうとはせず、ふしぎなほど動悸を高鳴らせて、私に道をいそがせる。
大声がする。私の名を呼んでいる。
周囲の生徒たちがこぞって声のほうを向き、それから私のほうを見る。
声はまっすぐと私の背中にそそがれ、放たれている。
待って、お願い。
迫る足音に、私は化け物にでも襲われた羊みたいに駆けだしている。どうせまたすぐに諦める。ほらね。呼び声がやんでいることに気づき、足のちからを緩める。
けれど私はそこではたとして、また駆けだした。足音はさっきよりもずっと近くに響いて聞こえた。背後にまで迫っている。手を伸ばされたら捕まるのではないか、と焦るほどだ。うしろを見るのが怖い。ただ走るしかなかった。
息はあがり、身体はピンポン玉みたいに弾む。冬でよかった、と思う。汗を掻かない、それもある。スカートの下に短パンを着込んでいる。全力疾走するには都合がよい。
視界から生徒の姿が消えていく。このまま走りつづけると商店街にでる。朝とは異なり、夕方は買い物客でにぎわっている。さすがに衆目がありすぎるし、人通りの多い場所で全力疾走するなんて危ない真似は避けたかった。
路地を曲がり、住宅街へと進路を変える。
来たことのない道だ。
さすがに追ってはこないだろう。
ちいさな公園があり、そこを突っ切る。道路にいちどでてから、裏側のほうから回りこみ、もういちど公園に入る。ちょうどよく公衆トイレが目のまえにある。その陰に身をひそめた。
彼女は追ってきていた。
公園に入ってきて、ブランコのまえを横切る。道路にでるとひざに手をあて、肩で息をする。
あんなに髪を振り乱している彼女を見るのは初めてだ。風が吹くたびに髪の毛が空気の流れを浮き彫りにする。
彼女は迷った末にこちらから離れる方向に駆けていった。小走りではあったけれど、その姿からは惰性からは真逆の執念が見てとれた。
じぶんの息がまだ荒いことに気づく。休んでいるじぶんといまなお駆けつづけている彼女とを比べると、なんだかいたたまれない気持ちになる。
トイレの陰から抜けだす。ひと気が皆無なのを確認してから公園のベンチに腰かける。
疲れた。
声にだして言ったつもりなのに、うまく声にならなかった。
心で唱えるだけなら楽なのに。
しゃべることも、相手に想いを伝えるのも、どうしてこんなに面倒なのだろう。いっそのことすれ違うのが当たりまえの世のなかになってしまえばよいのに。そうすれば誰もが勘違いすることを前提に接しあうから、世のなかから勘違いや、すれ違いは減るのではないか。
意思を疎通できると思いこんでいるから人間関係がこじれてしまうのではないか。
端から人と人とは繋がりあえないのだとしておいたほうが好ましいのではないか。
糸は、互いに結びつこうとするからもつれるのだ。
思ういっぽうで、なぜじぶんはふたたびしゃべることを潔しとしてしまったのだろう、あのままずっと以前のように声を失くしたままでいればよかったのに。
そう思うじぶんがいる。
私のなかにはもう、がらんどうがぽっかりと空いてはいない。
私にそれを植えつけたあのコが、私からそれを奪ったから。
奪われてばかりだ。
そのじつがらんどうはそもそも彼女から植えつけられたものであり、そのおかげというのはすこしちがう気もするけれど、私はいま、ふたたびしゃべれるようになっている。
振り回されているだけではないか。
反面、彼女を振り回し、振りきり、こうして公園のベンチに腰かけているのは私なのだ。
このまま旅にでてしまいたい。見知らぬ土地で暮らしたい。たびたび胸に湧く衝動であるのに、私にはそれをする勇気も、行動力も、意思だってないのだった。
ふと足元に影が差す。
顔をあげる前に肩を掴まれた。
ブレザーのうえからでもその手のひらの体温が伝わった。
あごをあげる。視線のさきには誰もいない。
私はゆっくり顔をうしろに向ける。
彼女がそこに立っていた。
ベンチの背もたれを挟んだ、真後ろに。
かつて私にがらんどうを植えつけ、ふたたび奪い去り、そして私のそとにて、こうして虚ろな眼差しを以って、がらんどうはここにあるとでも誇示しているみたいに、彼女はそこに立っている。
「なんで逃げるの」
ホラー映画さながらのセリフを、彼女はだみ声で言った。母親に叱られ、もう知りません、と言われた子供が、どうして置いてくの、と母親に追い縋るような響きがあった。
私は首を振って、逃げてない、逃げてないよ、と無言の否定をしてみせるが、白々しいにもほどがある。案の定、
「なんでウソつくの」
却って彼女の情緒を不安定にさせた。「わるいことしたなって思ってるよ、ホントに、あたしがやったわけじゃないし、やれって言ったわけでもないけど、あたしのせいだって思ってるの」
両手をぶんぶんとマスカラでも振るみたいに上下すると彼女は一転、意気消沈した様子で、ベンチを迂回し、私のとなりに腰掛けた。
「許してほしいとかじゃなくて、でも誤解されたまんまなのはヤダ。あたしが嫌いになったらちゃんとそう」
言ってほしい、と続くだろうところで彼女は言葉を濁らせ、「言われたくはないけど、でも無視されるのはヤダよ。悲しいよ。避けられる人の気持ちがどんなか解かる? それでも追いかけて話を聞いてもらいたいって、必死なの。解かってよ」
それを言うなら、だいじなモノをダイナシにされた人の気持ちが解かるの、と問いたい。言ったところで、きっと彼女は、解かるよだから謝ってるでしょ、と頭ごなしにじぶんの意見を押しつけるだろう。本当にじぶんは解かっているのだろうか、と自問自答することなく、解かった気になって、こんどはじぶんが被害者のつもりで私たちのことを、私とユウナを責めるのだろう。
「また仲良くしたいよ。仲直りしてほしい。あたしがわるいのは解かってる。ごめんなさい。もうしない。誰にもあんなことさせないし、した人にも謝らせるから」
何様のつもりなの。
私はつぶやいた。こんどはちゃんと意識して声にだした。掠れた声だったけれど、それは言葉のカタチを伴った。
謝ってくれたのはうれしい。偉いと思う。私を慕ってくれるのも正直に言えば嫌な気はしないし、うれしいのかもしれない。でも、いくら謝られたって、傷ついた事実は消えないんだよ。ひどいことされた事実は消えないの。謝って済むことじゃないよ。すくなくとも私はそう思ってる。謝られたって、はいそうですか、なんて許せないよ。私のこと友達だと思ってて、すこしでもだいじにしてくれるつもりがあるのなら想像してみて。私のだいじなものを誰かに壊されて、すごく悲しくて、傷ついて、それでもあなたはその誰かを許してあげるの。謝ったからって、本当はそんなことしたいわけじゃなかったからって言いわけされて、はいそうですかって、許せるの。私のことだったら私は許すよ。でも今回はそうじゃない。私の友達が傷ついた。傷つけられたの。許せるはずもないでしょ。
ひと息にぜんぶをぶちまけたかったのに、私はためらった。
一瞬で巡ったそれら言葉が、すっかりじぶんに返ってきてしまうのが直感できたからだ。
私はいま、傷つける側に回っている。私は私が許せなくなる瀬戸際に立っている。
ただ、それを認めることは、とりもなおさず、私を追いかけ回し、私のよこに無断で座っている彼女が私にとってただのクラスメイトや他人ではないことを認めることでもあった。
もちろん彼女はただの他人ではない。かつて私にがらんどうを植えつけ、私からそのがらんどうを奪い去り、私にふたたびの声を、言葉を、与えた張本人だ。
端的に言って、腐れ縁と評すよりない。
比べっこをするのはおかしいかもしれないけれど、傷つけられたというならば私のほうが遥かに傷を受けている。ならばそれらの帳尻を合わせたってバチは当たらないはずだ。
すくなくともいま、彼女は反省しているとは言いがたい。彼女がどうしてそこまで私との縁が切れるのを嫌がるのかは知らないけれど、彼女がじぶんのしたことを心底悔いているようには思えない。
私がこのまま距離を置けば、また何かしら仕返しをするのではないか。彼女の言葉を信じれば、彼女自身はそもそも私たちを損なおうとしたつもりはなかったようだが、彼女が私たちを、すくなくともユウナのことをこころよく思っていなかったのは確かだろう。そしてその感情をあらわにし、ときには言葉にすらだしていたかもしれない。
それを聞いた取り巻きたちがどういう行動にでるかくらい、女王様にだって想像はついたはずだ。
たとえ想像がつかなかったのだとしても、ユウナの受けた傷をおもんぱかることはできたはずだ。ごめんなさい、で済むような話ではない。ましてや、ユウナから許されてもいないうちから、そちらをほっぽりだして私との仲を案じるなんて、そんなのは謝罪でもなんでもない。
反省などしていないのだ。
だからこんな真似ができるのだ。
私が避けるのも当然ではないか。
目のまえの彼女は、私が悪態を吐いたきり黙ってしまったからか、憮然としている。ひょっとしたら私のつむいだ、何様なの、が胸に突き刺さって動けなくなっているのかもしれない。
「絶対に許さない」
私は言った。声にだして言った。追い打ちをかけるように言った。トドメを刺すつもりで言った。
絶対に許さない。
かつて私が彼女から贈られたそれは言葉であり、私の内に根を張ったがらんどうの種と言ってよかった。
彼女の目が見開かれ、目玉だけがきょろきょろと虚空をさまよった。まるで掴むべき藁でも探しているかのような表情だ。
やがて彼女はうなだれた。魂が抜けたような姿は、妙に演技がかって見えた。
鼻につく。
そう思ったじぶんに失望する。
彼女のそばにいると私はどんどん嫌な奴になっていく。
それを彼女のせいにしようとしているじぶんに気づき、さらに胃が重くなる。
背を向け、私はその場をあとにした。足元を木の葉がカラカラと流れていく。
翌日、学校に着くと教室は騒然としていた。
私よりさきに登校し、教室でじぶんの席に座っていたあのコは髪をばっさりと切っていた。あれほどうつくしかった髪の毛を、耳が見えるほど短く、それこそうなじなどは、ゆびで撫でつければ順々に跳ねる毛先が見えるくらいに青々と。
クラスメイトたちは遠巻きに彼女を眺め、ときに話題にするためにわざわざ廊下にでてまで、彼女の噂をささめきあっている。
女王蜂から羽が失われたのだ。野次馬でなくとも関心をそそがずにはいられないのだろう。失恋、失恋、と単語が聞こえ、そんなんじゃないよ、と私のほうが反論しそうになる。
当の本人、転校生、私のがらんどうの生みの親はまるで聞こえていないようで、いいやそんなわけがないのだけれど、われ関せずを貫いている。
私はじぶんの席に着き、しばらくうしろを振り返らずに、ぼーっとした。
先生がやってきて、朝礼が終わって、授業がはじまって、休み時間、授業、休み時間、授業、昼休み、ごはん、授業、と淡々と時間が流れた。
放課後になるころにはもう誰も女王蜂からなぜ羽がなくなったのかを気にするひとはいなくなっていた。
慣れではない。
女王蜂は羽どころか毒針すら失くしていたのだ。着飾らずに言えば彼女、転校生、私のがらんどうの生みの親は、
「なんであいつしゃべらんの」
ユウナはバス停のベンチにどすんと腰を下ろした。「髪切って、しゃべらんくなって、うちのクラスまで、姫さまどうしたんだろって話で持ちきりだったわ」
どうしたんだろうね、と私は言う。ユウナがとなりの空いた席をぽんぽんと叩くのでそこにおさまる。
「うちはあの女がどうなろうと知ったこっちゃないけど、経験上まあ知っとるわけだ、あの女がどうにかなっちゃうときはたいがいそこにチミが関係しとるとね」
「あ、見て。鳥が飛んでる」
「チミ。話を逸らすのホント下手やね」
「うふふ」
笑ってみせるけれどユウナはそこで微笑みかえしてくれたりはしなかった。じっと見つめ返され、私は顔を伏せ、靴のさきで円を描きながら、
「追いかけられたから逃げただけだよ」と応じる。「許さないって言ったの。ぜったい許さないって」
「なんでまた」
「なんでって、だってユウちゃんだって許してないでしょ」
「そりゃうちはね」
「仲良くするなって前は言ってたのに」
「どっちの味方かって訊いただけだしょ」
「だしょ」
繰りかえすとユウナは、私の描いた円を足で消して、
「チミはすぐにそうやってあれやな」
「どれかな」
「ひとを茶化すのはやめい」
「やめい」
いちいちユウナの言い方がおかしくてついつい繰りかえしてしまう。太ももをつねられ、ごめんなさいをいそいで三回唱えた。
「なんかもう腹立つのもアホらしいわ」ユウナが立ちあがったので、バスが来たのだと判った。前かがみになって右側のほうの道を覗くと、遠くから四角い箱がやってくる。だんだんと大きく長方形になっていく。
扉が開く。むかしは扉が開くときに空気が漏れる音がしたんだってさ、とユウナがどうでもいいことを言って、はやく仲直りしろよな、といっぽうてきに吐き捨ててバスに乗りこみ、いなくなった。
苦笑する。その言い方には馴染みがあった。あまり琴線を揺るがせないマンガを読んだときに彼女はたびたびそうして登場人物たちの行動をさして、はやく何々しろよな、と言った。進展がなかったり、話の展開が遅かったり、つまらない問題にいつまでもまごついているとさっさとこうすればよいのに、と言いげに、結末を迫るのだ。
まどろっこしいのだろう。
しかしそれは読者たるユウナだからこそ見える結末であって、登場人物にとっては結果よりもその過程をどうすべきか、どれくらいていねいに歩んでいくのかのほうがだいじな気がする。
いまのじぶんがそうだからだ。
解かっているのだ。
怒りなんて抱えていてもじぶんにとっていいことはない。めいわくなひとのことでわざわざ思考をいっぱいにしてじぶんから不幸になりにいく筋合いはない。
さいわいと相手はもうこちらに絡んではこないのだ。ならばさっさとこのまま縁を切ってしまえば大団円、めでたしめでたしと終われるのではないか。
私とユウナとの吊りあいだけを求めればこんなに簡単なことはない。あのコとユウナとを天秤にかけて吊りあいを求めるからこんがらがるのだ。
要するに私はいまなおあのコをただの迷惑な他人だと割り切れていないだけの話なのだ。ユウナという友人の存在をよりどころにして私は、じぶんのためにあのコとの大団円、めでたしめでたしを迎えたいと欲している。
でもそう考えるじぶんを私はたぶん認めたくないのだ。
あのコの存在がじぶんにとって欠けては困る存在だと認めることになるから。
傍から見ているユウナからすれば、一目瞭然で、だからきっとああまでも呆れた顔で、さっさと仲直りしろ、などと口にしたのだ。
うちを言いわけに使ってんじゃねぇ、と叱られている気分だ。否、ユウナはきっとそう思っているに違いない。
見透かされている。
たぶん、私はあのコに痛い目をみてもらいたかっただけなのだ。当てつけだ。復讐だ。
八つ当たりではないだけで、私は単に、かつて私が植え付けられたがらんどうをあのコにそのまま返したかっただけなのだ。そうでなければ素直に私は彼女にこう進言して終わっておくべきだった、私に謝る前に許しを乞う相手がいるんじゃないの、と。
ただ謝れば済むって話じゃないと思うよ、と。
それなのに私は最善の助言を投げかけることなく不満だけを述べて、伝えて、突き放した。
過去、私が彼女にそうされたように、どうすれば許してもらえるのか、なぜそんなに怒っているのかすら説明しようとせず、敢えて理解させないようにすら言葉を濁して、気持ちに蓋をし、塗り固めた。
ただ、私にはそれをする権利がある気がするのもまた誤魔化しようがない事実で、同時にきっとそれすら私はじぶんに偽って、見て見ぬふりをしてきた。
夕焼けを目に留めて、じぶんが長いことベンチに座ったままなのだと知った。ユウナの乗りこんだバスのほかにも目のまえに何台かのバスが停まってはほかの生徒たちを吸いこんでいった様子が遅れて脳裡に蘇える。意識していなくとも目は映像を記憶しているのだなあ、と思ったけれど、そんなはずはない。無意識で映像をでっちあげて、記憶しているつもり、見たつもりになっているだけなのだ。
私はほとほとねつ造が得意なようだ。進路に困ったらねつ造屋さんにでもなろうかな、と想像して、なんじゃそりゃ、とあまりのでたらめ具合に、いよいよ頭がどうにかなってきた、とじぶんのゆがみ具合を自覚する。
いつの間にか自宅のそばにまできていた。もうあのコは朝に私を出迎えにはきてくれないのだろうな。思考が飛んで、また気づくとこんどはシャワーを浴びている。ちゃんと裸になっていて、どうやってここまできたのだっけ、と思いだそうとするときちんとここまでの道中、衣服を脱いで畳んだところまでを思いだせたが、それが正しい記憶かの自信はなかった。
ねつ造屋さん、と私はまた意味もなく唱える。
シャワーのお湯が肌を流れる。
目をつむる。心地よい滝に打たれる。
あのコはたしかに私にがらんどうを植えつけたけれど、それを後生大事に枯らさぬように、埋まらぬようにと手入れを欠かさなかったのは私ではなかったか。喉に異常がないにも拘わらずしゃべらずにいたのは私の勝手ではなかったか。
もちろん世のなかには精神的な傷によって声帯の異常とはまた別の因子でしゃべれなくなるひともいる。私もまたそれだとずっと思っていたし、私以外の周囲のおとなたち、学友、それこそあのユウナですらそう解釈していたに違いなかった。
でもそのじつ、私は本当にただ、しゃべらなかっただけなのだ。
一言でもしゃべってしまったら、私の内に根付いたがらんどうが、せっかく定着したがらんどうが、一瞬で埋もれてしまいそうだったから。
せっかくあのコが植えつけてくれたのに。
生みつけてくれたのに。
悪寒が首筋を伝った。頭からお湯を被っているのに腕の毛穴が閉じている。羽の毟られた鳥の皮みたいだ。なんとなくぽつぽつと雨の降るプールの水面を連想する。
浴室から上がる。自室ですこし勉強をしてから母に呼ばれて夕食を食べ、それからすこしマンガを読んで、そのままベッドに潜りこんで、ぐーすかふよふよと夢を見る。
私は犬と戯れている。本当は犬を飼っていた過去はないからこれは夢だと私は判る。とてもとてもたいせつにしていた子犬で、かわいくて、なついてくれて、私たちは互いに相手を必要としていた。なのにどうしてだかある日、子犬が私の手を噛んで、そのままどこかに消えてしまった。
私は傷ついた。
胸に走った亀裂をけれど私は癒したりしようとはせずに、それを塞がないように懸命にじぶんでこじ開けて、立派な立派ながらんどうに育てあげる。
目を覚ます。天井がぐるぐる回って見え、悪夢を見ていたのだとなんとなく思った。
窓のカーテンを開ける。日差しが眩しい。
肌寒くてストーブをつけて、またすこしのあいだ布団にくるまる。窓から眺めた道路には誰の姿もなかった。当然だ。ふしぎと気分は雨だった。
冬休みまで私はあのコと関わらなかった。機会がなかった。女王蜂の面影はなく、羽と毒針を失くした彼女は打って変わって存在感を失くした。彼女を崇拝していただろう学友たちも、何を投げかけても応じないのを認めると遠巻きになった。しだいに移ろうような変化ではなく、それは数日のあいだに完了した。
可哀そうに思うのがしぜんな状況のなかで、陰の一つでも滲ませればよいものを、あのコはいっそ清々しそうに恬淡としていた。
年末、年越しと過ぎていく。遠い国で物騒な事件があって、じぶんの手の届く範囲の悩み事がすこしだけちいさく感じられた。なんだか重力が増したのに呼吸だけはしやすくなったみたいなチグハグサにじぶんのさもしさを垣間見た。
いまさらな実感だ。
私はそもそも卑しくて、そういう人間だったのだ。
ユウナとは休みのあいだに三回だけ遊んだ。お互いに人混みが好きではないのでなんの変哲もない平日に、つまりクリスマスや元旦といった街が活気に満ちている日ではないときに、書店巡りやカフェ巡りをした。
ユウナはもう、あのコとどうなったかを口にしなかった。かってにしろ、と思っているに相違なかったけれど、それは怒っているのでも呆れているのでもなく、真実かってにしてほしいと思っているのだと私は知っている。ユウナにとってはもう終わったことで、あのコの存在はもうユウナにとっては遠い国の物騒な事件と同じ扱いなのだ。
新学期がはじまって、またすぐに春休みがきて、二年生になるとクラス替えがあって、もう私はあのコを学校で見かけることすらなくなった。ユウナとはまたとなりのクラス同士で、とくに接点は増えもせず減りもせず、それでいて春先の修学旅行だけは自由時間をいっしょに回った。
「休んだらしいよ」
いちどだけユウナが言った。空港からの帰りのバスのなかで、学友たちの大半がいねむりをしているなかで、車窓を眺めながらユウナは、
「ちょっと罪悪感」と口にした。
意図は汲めた。修学旅行中、あのコの姿を見掛けないどころか、到る箇所で一人分の欠けた席や余ったお弁当を目にしていた。
そうだね、と私は言った。チョコレートを一粒奪って、おいこら、とユウナに上品でない声をださせ、しんみりな空気を追い払う。
家のまえに母が立っている。出迎えてくれているのかと思い、ただいま、と近づくと、あらおかえりなさい、と母はいつまでもそとにいるので、どうしたの、ととなりに並ぶ。母はそらを仰いでおり、視線を辿ると屋根にツバメが巣をつくっていた。母が珍しそうにそれを眺め、来年もくるかな、と足元の白い糞の跡に目を落とす。迷惑がっているのか、それとも予想外のお客さんに気分をよくしているのかはその横顔からは窺い知れなかった。
月日はツバメが飛ぶように去っていく。気づくとツバメの巣からは雛の鳴き声が聞こえ、つぎに意識したときには親子共々いなくなっている。日が高くなり、蝉が鳴き、その亡骸がそらに足を向けてひっくり返って、赤とんぼが目のまえを横切る。通学路の街路樹が真っ赤に衣替えをし、落ち葉の絨毯が町を覆い、そしていつの間にか受験勉強に追われて、私の生活圏からはすっかり、がらんどうを愛でる習慣がなくなっていた。
受験があり、合格発表を迎え、私たちは卒業する。
「上京いいなぁ」ユウナがもらったばかりの卒業証書の入った円柱状の筒で肩を叩く。信号機が青になる。私たちは歩きだす。
「地元のほうがいいよ」私は街路樹の葉っぱをちぎり、捨てる。「家から通えるんでしょ、そっちのほうがよかった」
「じゃあ交換してくれ。独り暮らしをわしにくれ」
「遊びにきてよ」
「寂しくて死んじゃうってか」
「うん」
ユウナが歩を止めたので、どったの、と振り返る。「や、びっくりしたわ。きみそういうとこ素直やね」
「あなたがあまのじゃくなだけじゃない?」
「あ、クレープ食べてこうぜ」
すこし考え、あなただって素直でしょ、と思う。あまのじゃくからの連想で甘いものが食べたくなるだなんて玄関の開く音を耳にして駆け寄ってくる子犬じみている。
お互い、新しい生活の準備でいっぱいっぱいになる前に息抜きとして卒業旅行に出かけた。温泉巡りをして、美味しいものをたくさん食べた。カニと焼肉は素晴らしいと思ったけれど、予想外に食費がかかってしまい、予定よりも一日早く帰宅した。
「つぎはバイトしてお金溜めなあかんね」
「ユウちゃんさ」「はいな」「ときどき関西弁なのはなぜ?」
彼女はそこで眉をひそめ、いらんこと言うなや、と頬を赤く染めた。予想外の反応だったので、ごめんと謝罪したものの釈然とせず、彼女と別れたあと自室に戻ったさきで目にしたマンガ本、それはユウナからおすすめされた初期のマンガ本であったけれど、そう言えばこれにでてくるキャラも関西弁モドキだったな。
思いだして、
ああそういう。
私はユウナの意外な一面、というほどでもないけれど、案外にかわいいことするな、と長い付き合いの節目にてようやくというべきか、家族に向けるそれに似たほんわかを我が友に覚えた。
ユウナとはその後、引っ越しの手伝いをしにきてくれたのを機にしばらく会わずじまいとなった。
彼女が東京の私の住処に遊びにくることもけっきょくいちどもなかった。
近況報告すら半年もするとなくなった。
寂しい思いが湧いてしぜんなその境遇でなぜか私は何も感じなかった。大学に入ってからすぐにユウナに恋人ができたと聞いていたから、もう以前のようには付き合えないのだろうなとの予感があった。それを覚悟と言ってもよいのかもしれないけれど、どちらかと言えばすこしほっとした。
思っていた以上に私は薄情なのかもしれない。触れられる距離にいない相手と以前と同じような関係を結びつづけていく日々は案外に抵抗が大きく、率直に言って負担だった。
もちろんいまでもいちばんの友人はユウナだと胸を張って言えるし、爪の先ほども疑念はないけれど、それでもだからこそなのか、ユウナにはユウナの身近な人間関係を優先してほしいとの思いがつよく湧く。
何百キロもさきにいる私にわざわざマンガの話題を振らずとも、そばにいる誰かであっても同じようにユウナなら日々を楽しく過ごせるはずだ。そもそもを言えばわざわざ上京してきてまでマンガの話をするのは私のほうでもすこしと言わずして大いに不満だ。どうせならカフェ巡りでもしたい。
けっきょくのところ私たちの関係とはあの学校という極々狭い檻のなかで有効な絆だったのだ。
それをありていに楔や鎖と言い換えてもよい。
互いに縛りあって、寄りかかって、なんとか耐えていた均衡があったのだとあの環境から離れてみればしかと思う。
私とユウナ以外のほかのすべてが私たちを縛る縄であり、圧力だった。私たちは身を寄せ合い、くっつき合うほかに均衡を、輪郭を、自我を、保つ術がなかった。追いやられていたとまで言ってしまうとさすがにちょっと過去をとげとげしく形容しすぎで、あの学校はそこまで私たちを、すくなくとも私を損ないはしなかった。
けれども、やっぱり私はほかの誰とでもなくユウナでなければならなかったのだといまなら言える。私がユウナを頼っていたように、きっとユウナも私を頼って、触れたら脆く崩れてしまいそうな何かを互いに懸命に補強し合っていたのではないか、とどうしても省みてしまうのだ。
ほかにもきっと私たちみたいな分子がいて、互いにくっつき合うことでなんとかあの環境を漂っていられたコたちがいたはずだ。学校という場はそういうものであるとすら言えるかもしれない。原子のままでは漂えず、無数の分子によって場を保つものなのだ。
ふと私はそこで、たった一粒の、誰ともくっつき合うことのなかった原子の姿を無想した。
点となって存在するそれは、久しく忘れていたがらんどうの希薄さを私に思いださせた。
あのコはどうしているだろう。
いまになって私は気になった。誰ともくっつき合わずとも暮らせる環境にあって、私はすっかり意識の底に沈めて、なかったことにすらしていたかもしれないかつてのがらんどうの生みの親の顔を思い浮かべている。
それからというもの、たびたび私はあのコの顔を、姿を、ときには共に過ごした日々の記憶を振り返り、振り返り、回顧するようになった。舌のうえで飴玉を転がして味わうように、噛み砕きたいのにそうするのはもったいない気がしてもどかしい気持ちを楽しむように、むかしのじぶんの幼さを実感するたびにいまのじぶんの成熟さを知りたいがためにそうするかのように、私は日々のほんのすこしの何食わぬ時間、たとえばバスに乗っているあいだ、階段をのぼっているとき、書面に走らせる目が滑ってうまく文章が頭に入ってこないときなど、ことあるごとにあのコとの過去を、そして現在の有様を、思考の表層にとめどなく移ろわせた。
かといってあのコに会いたいとは思わない。連絡もとりようがない。メディア端末はとっくに新規にしていて、連絡先も失っている。
向こうから連絡がくれば応じるのもやぶさかではないけれど、そもそもあのコはもうおしゃべりではなくなっているのだと思い、その裏で、まさかまだしゃべらないままだなんてことはないよね、と不安じみた陽気が湧きあがる。
そんなわけがないのだ。まったくあり得ないとも思えなかった。馬のあたまから角が生えるくらいなら現実的にあり得そうで、だったらユニコーンだってこの世のどこかにはいるかもしれないと妄想を逞しくするのに似た他愛なさがある。
大学の長期休みはバイトをした。実家には戻らずに、ひとまず学生のあいだに社会人の年収くらいの金額を貯めたいなと考えていた。貯金が趣味というわけでもないのだが、かといってほかにやりたいこともなく、マンガや映画といった娯楽では、月にバイト代の半分を使い切るほうがむつかしいくらいで、いまの時代、たった一人で贅沢をするのも案外にむつかしい、と孤独な日々の豊かさをありがたく思う。
中学生、高校生のうちではまったく考えもしなかった考えをひまつぶしがてらに脳内で一人議論する。
知人と呼べるくらいの繋がりは大学でも結べた。反面、友人と呼ぶほどの濃ゆい関係、互いの私生活に干渉しあうほどの相手はおらず、下手をすれば誰も私の地元がどこかを知らない可能性すらあった。
私自身、ずいぶん長いこと地元の風景を思いだす暇がなく、いつの間にかどこに就職すべきかが私の思考野の大半を独占するようになっている。季節を感じた覚えがなく、駆け足で去っていったキャンパスライフを振り返る余裕もない。
勤勉だったのだ。それしかすることがなかった。みなはいったいどうやって時間をつぶしていたのだろう。日々を過ごしていたのだろう。大学生への憧れがあったかと問われたら首を傾げてしまうけれど、まったくなかったかと問われればこれもまた首を縦に振るのはむつかしい。
いざなってみたらこんな具合だ。高校生時代が懐かしい。
ことしの年末は実家に帰ろうと決意して、あとは勤勉に講義を消化して、テストを受け、単位を回収し、バイトを掛け持ちして打ち出の小づちに大判小判を蓄えた。
いまは魔法の小づちを振ればどこでも買い物ができる。便利な時代になったと思う反面、私たちは吹けば消えてしまう儚い何かをこの世の仕組みを動かす大きな大きな原動力にしてしまっているのではないか、と不安にもなる。
ひとからの評価の数がそのままそのひとの影響力として計上されるいまは社会だ。それだって必ずしも評価が可視化されたわけではないはずで、本当にたいせつな評価ほど可視化されにくいものなのではないか、とすら思うものの、あまりじぶんでも自信はない。
私は誰からもこれといって高く評価されていないし、された過去もない。
そう思い、ではあのコにとって私はどのように映っていたのだろう、といまさらながら気になった。いつだって私は私が彼女をどう思っているのかばかりに囚われていた。彼女が私にとってどういう存在であるのかがだいじで、彼女にとって私がどういう存在であるのかは二の次だった。
考えたことがなかったわけではない。
手帳を開き、ことしの正月は地元に帰ろう、と予定をそっと書きこんだ。
三年も経つと案外に街の外観は変わる。田舎ほど発展の余地があるからか、思っていた以上に駅前が小奇麗になっていて、駅の外装も近未来的な趣を醸している。
私はこの三年で何か変わっただろうか。
想像してみると案外に見えてくるのは、過去のじぶんを幼いと見做すだけの価値観の変容で、微笑ましいというよりもやはりどこか恥ずかしい。
過去のじぶんをじぶんと思えないと思うことすらあり、しかしそれを口にすることそのものが幼稚の塊のようにも思え、けっきょく私は私なのだ、と未だ熟しきれぬ我が身を歯がゆく思う。
おとなぶってみせるものの、玄関のピンポンを押さずにそのまま、ただいま、と家に入ったじぶんに気づき、三つ子の魂百まで、習性は成長よりもつよし、を感じずにはいられない。
母は白髪こそ増えたが変化はなく、父は一回り萎んで見えた。退職間際の引継ぎで忙しいのだろう。帰りが遅くてしょっちゅう飲んで帰ってくるの、と母は台所でぼやくでもなく言った。
「夜はどうするの」母がまな板を鳴らす。「予定とかあるんでしょ、お友達と会ったりとか」
「なくてすみませんね」
「あら。せっかくだから遊んでくればいいのに」
「家でゆっくりしてたいの」
「すっかり更けちゃって」
「せめて腑抜けたって言ってほしい」
「おばぁちゃん家には顔だせるんでしょ。年明けに行くから着いてきてね」
「お年玉まだもらえるかなぁ」
「ばか」
これをあっちに運んで、と皿を渡され、サラダを盛りつけてから食卓に運んだ。
思えば母はあれからいちども、あのコについて訊かなかった。つぎはいつ家にくるのかとあれほど楽しみにしていたというのに、卒業式までの期間、それからそのあと、いまに至ってもまるで私たちの縁がとっくに切れていることを見透かしているみたいにあのコの名を口にすることはなかった。
ひょっとした私が家を空けているあいだにあのコがここに顔をだして、母に事情を話している可能性もあったが、そこまでの行動力を羽と針を失くした女王蜂に幻視するのは酷に思えた。
あのコはしゃべれるようになっただろうか。
頭の片隅に張った蜘蛛の巣のようなその疑問は、たびたび私の視界に浮上して、かつて私の内側に根付いていたがらんどうがごとく、私からしばしの言葉を奪うのだ。
「ぼーっとしちゃってどうしたの」
「どうもしないけど」
「就職どうするの」
「えぇもうそういう話したくない」
「そんなわけにいかないでしょ。あんたあっちに戻ったらなかなか連絡くれないし。こういうときに話しといてくれないと」
あたかも、ふだんは自由にしてやってんだぞ、と釘を刺されたようでおもしろくない。とはいえ、正論ではあるのだ。
黙っているのも母にわるい気がして、しょうじきに打ち明ければ何も考えてはいなかったけれど、それでは納得してもらえないだろうと情勢を鑑みて、ひとまずゼミでいっしょのコが受けると言っていた企業の名前をつらつらと並べてみる。
思っていた以上に我が子が真剣に将来について考えていると勘違いしたのか何なのか、ひととおり企業名を唱え終えると、あらそう、と言ったきり母はエプロンを脱ぎ、食べましょ食べましょ、と食卓についた。
「お父さんは?」
「働かざる者食うべからず」母は箸を構え、いただきまーす、とグラタンの湖面に穴を開けた。
家に寄りつかなかったあいだに母と父の関係性にヒビが走ったのかと案じたが、二階から足音を立てて下りてきた父は居間に顔をだすと、しぜんなさまでじぶんでご飯とグラタンと取り皿を持ってきて、何でもないように席に着き、いただきますと唱えて、一口、二口、箸を進めたあとで、進路はどうするんだ、とうんざりする質問を投げかけてくるのだった。
年越しを家に引きこもって過ごした。正月は二日目になってから祖父母の家へと家族揃って出かけた。父が四日には仕事始めであるらしく、一泊して帰ってきた。
「お年玉もらっちゃった」
車のなかで父に報告すると、もらえるうちはもらっておけばいいさ、とお気楽な返答をいただき、母からは大きなため息をもらった。
駅前と違って住宅街はあまり景観が変わっておらず、なんだか懐かしさと安堵がいっしょくたになって車窓に流れる景色と共に流れては消えた。
スーパーに寄って今晩は焼肉にすると聞いて、こんなんだったら毎年帰省していればよかったな、と現金にも思い、声にだしてつぶやくと、母がまた大きなため息を吐いたので、なんじゃい、とすこし高めの焼き肉のタレをカゴのなかに投じた。我ながら家を離れて逞しく育ったと思う。
買い物を済ませまっすぐ家に戻るはずが、車はいつもの道をいかなかった。家に近づくにつれて鼓動が大きくなっていく。このままいくとあのコ、かつて私にがらんどうを植えつけた少女の家のまえを通ることになる。
そう気づいたとき、目のまえを空き地が素通りしていった。
あれ、と思い、釘付けになったまま後部座席で身体ごと振り返る。
「いつもの道が工事中でね。こっちのほうが近いんだ」
父は得意げに言ったが、私の脳内はそれどころではなかった。
あのコの家が消えていた。
引っ越したのだろうか。それはそうだろう、家がないのだから。
助手席の母を見たが、眠たげに欠伸をしている。思えば、あのコの家がどこにあるのかを母は知らないのだ。母のことだからきっとあのコにそれとなく、あなたのご両親にご挨拶をしたいのだけど、と申し入れたはずだ。そこであのコはおそらくそれをはぐらかしたに違いない。
想像し、そしてしばらくぶりに思いだす。あのコの家のことを。母親とあまりうまくいっていなかったあのコの私生活のことを。
大学に進学しただろうと想像するまでもなくかってに推し量っていたけれど、あのコはこの期間、どうやって過ごしていただろう。
何不自由なく進学した私は、のうのうと実家に帰ることもなく、それでいていざとなれば実家に泣きつけばどうにかなると高をくくって安全地帯に身を寄せている。
なんだか嫌な気分だ。
とてもとても、うんと気持ちがわるい。
腹の底がムカムカする、胸の奥がじゅくじゅくする。
「ほら着いたよ。荷物持ってきて」
父と母が車から下りる。買い物袋が丸ごと車内に置いたままにされていて、父が持とうとするのを母が諌めて、甘やかさないの、と聞こえがしに言う。
感傷的になっていただけに、こういうときに耳にする身内の声は、けっこう頭にくる。むしゃくしゃする。おもしろくない。
乱暴に荷物を持つと、卵入ってるからね、と母がすばやく釘を刺す。胸中を見透かされているようで余計に苛々した。大人げないので、この日は率先して母の手伝いをし、父におべっかを言って、親孝行、親孝行、とじぶんに言い聞かせながら、これだから実家は、とやきもきした。
予定では五日目にはアパートに帰る予定だったけれど、けっきょく五日目になっても私は家のコタツでぬくぬくしていた。都会に戻ってもとくにやることはなく、父は仕事で、母はパートをはじめていたり体操クラブに参加していたりと、家を留守にしている時間が多く、これだったらこっちにいたほうがお金も浮くし、ゆっくりできそうだと打算を働かせて、バイトがはじまる十日まではこっちにいることにした。
「子豚さんになっちゃうよ」
母に尻を踏まれながら、さすがに引きこもってばかりでは皮下脂肪さんがご成長あられるいっぽうなので散歩にでも出かけようと思い立ち、いそいそと着替えてそとにでた。
雪が積もらない冬は新鮮だ。これからはこっちがふつうになるのだろうな、と甚大な環境問題と引き換えにもたらされる雪掻きをしない気楽さを思う。
とりえず駅前まで歩いた。
通学路と同じ道だから懐かしさが込みあげる。細かなところで三年前と違っていて、それはたとえば電信柱が新しくなっていたり、あったはずの店がなくなっていたりと、生と死を彷彿とさせる栄枯のなせる業、といった塩梅で、この世の流れの無情さよ、のおとなびた嘆きを一つ、二つと、日差しの合間に息といっしょに吐きだしていく。
何歳になっても白くのぼる息はおもしろい。
駅ビルの地下で専門店をはしごした。コロッケを食べ、クレープを二個注文し、最後に餃子を買って、きょうの晩ご飯はこれにしようと決める。もちろん餃子は父と母の分も購入した。
クレープを二個仕入れたのは一個は家に持ち帰って食べようと思ったからで、ではなぜ一個をたいらげておきながら帰路を辿りつつすでにもう一個を頬張っているのか、については、思いのほか生クリームがアイスじみていて、手に持っているうちに融けだしてしまったからだ、とする言いわけを誰にともなく並べておく。
二個はさすがに欲張りすぎたかもと、もたれはじめた胃をなだめつつ、出掛けてまだ一時間も経っていない事実に、しぜんと脳裡に山間の小川の映像が流れた。ゆったりと流れるそれは、つぎの瞬間には、都会のナイアガラの滝さながらの濁流に様変わりをして、どっちもどっちだな、と両極端な流れの速さを天秤に載せているといつの間にかクレープは手元からなくなっていた。
帰路を辿っていたはずなのに、立っていたのは家に向かう道ではなかった。
身体が憶えていた。
休日になると私はよくこの道を歩いていた。
美術館がある。名もない芸術家の記念館じみているそれは、骨董屋みたいな造りだ。都会の街でいちど入った老舗のカメラ店にも内装がどこか似ている。
引き返すことなく私は美術館の入口に立ち、自動販売機で入場券を購入して、なかに入った。館長らしきひとをときおり見かけたことはあったけれどいつもはほとんど無人で、キセルをしようとすればいつでもできるな、と防犯意識の低さに心配するよりさきに、そんな人物など端から想定していない姿勢を好ましく感じていた。
いまにして思えばそもそも、キセルをしてまでなかに入りたい、この作家の作品を観たい、と思うような人物がいるならば、そちらのほうが芸術家にとってはうれしいのかもしれない、なんてお門違いに想像する。
漆黒の遮光カーテンをくぐると、そのさきが展示ルームだ。
私はいつもこの瞬間、別の世界にきたような気分になる。プラネタリウムを眺めているときのような微かな高揚感が、宇宙服さながらに身体を包みこむ。
包みこむのだ、とやっぱりいまになってそう思うのであって、当時はなぜじぶんがあんなにも足繁く通っていたのかは解かっていなかった。いまだってなぜじぶんがこんなにもこの美術館に吸い寄せられるのか、未だに胸の高鳴りをほんのりと覚えてしまうのかは判然としない。
展示ルームは薄暗い。天井からのライトはなく、ガラスケースから透ける展示棚の明かりが床に、柱やじぶんの影を伸ばす程度だ。
空気が澄んでいて、あれっと思う。
記憶にあるかぎり、ここは年中埃っぽさが抜けなかった。足元も木の目が浮きあがって見えるくらいにつややかで、埃が溜まっていない。
掃除をするようになったのかな。ひょっとしたら管理人さんが豆なひとに変わったのかもしれない。
妄想を逞しくしながら、かつての低位置、私がよく腰をかけていた長椅子のところまで歩く。
柱を一つ横切ったところで、はっと息を呑む。
誰かがすでに長椅子に腰掛けていた。
存在感がなく、初め人形か何かかとぎょっとした。
近づかずに、身体を傾けて、その横顔を覗き見る。暗いし、距離があるのでよく見えない。女の人だと判ってほっと息を吐く。
暗がりに異性とふたりきりはやはりすこし怖い。これも男女差別になるのかな。
引き返そうかとも思ったものの、それはそれで失礼に思え、しばらく展示物を見て回ることにした。当分またここにくる機会は巡ってこない。
改めてじっくり作品を眺めて歩くと、思っていた以上に新しい発見というか新鮮な驚きがあって、いったい私はあのころ何を見ていたのだろうね、とふしぎな心地になった。
ふんふん、とじぶんの思いがけない変化を如実に感じて私は気分をよくした。そのままぐるっと展示物を追いかけていくと、例のソファのまえにやってきていて、そのまま通り過ぎればよいものを、ぎくりとしたらうしろを意識してしまったが最後、気づかなかったフリをするのは無理があるし、かといって振り向いて挨拶をしたのでは最初から気づいていたと白状したようなもので、どうしたらよいだろう、と考えてしまったらもう、身動きがとれなくなってしまった。
ぎくしゃく、なる言葉のぴったり具合に感動してしまうな。
どうせきょう以外では足を運ぶことはないのだ。
気を使うのも愚かなり。
腹をくくって、私は愛想笑いってこれでよいのだっけ、とじぶんの不器用な頬の筋肉と会話しながら、背後をちらっと、しぜんなさまを意識して振り返る。
ソファの人物はとっくにこちらを見上げていて、座ったままの姿勢でありながらまえのめりになっていて、身体をななめにしてこちらの顔を覗きこもうとしていた。じっさいに覗きこまれていて、私たちは目を合わす。
会釈をした。
そうしようと思っていたから身体の所作を止められなかった。
相手はしかし私のそれに反応を返すことなく、目を見開いたまま、思考停止状態を地で描き、私に唾液を呑みこませるだけの猶予を与えた。
ごっくん。
大きな音が鳴り、というのも、それが大きな音に感じるほどにこの空間が静かなだけの話なのだけれど、私はしばし呆気にとられた。
薄暗いせいもあるのだろう、それにしてもどうしたことか、目のまえにいる女性はどうにも高校生だったころの私に似た髪型に、いでたちで、背格好もなんだかかつての私を見ているようで、鼓動が大きく高鳴った。
分身かと思った。
だがそんなわけがないもので、しかしそれにしてはむかし私が身にまとっていた服装に似ているなあ、と客観的に眺めたじぶんのファッションセンスを、それほどわるくないな、と思うくらいには冷静さを取り戻す。
ああどうも、と声にだして挨拶をしようとして、さらに私の鼓動は高鳴った。
目のまえの人物は、私が気づいたことに気づいた様子で目を伏せる。
ずいぶん変わったな、とまずは思った。
否、これは変わったわけではない。
この三年間、彼女は何一つ変わらずにいたのだ。
直感したそれが外れていてほしいとの祈りのようなものを胸に私はまず、あれ、と声にだし、久しぶりだねぇ、と過去のわだかまりなどとっくに忘れてしまった、そんなものは私たちのあいだにはなかったのだと暗に示そうとしたが、彼女にうまく伝わったかは判らない。正直に言えば自信はない。
彼女がここにいるのは偶然なのだろうか。街中で私を見かけて、先回りして待っていた、という可能性はあるのだろうか。
そう考えることがまず以って彼女への冒涜にあたると判っていながら、私はつぎからつぎに湧いてくる妄想を拭い去ることができなかった。
かつての私に似た髪型をし、服装まで真似て、いいやそれを偶然なのかもしれないと想像するだけの理性を私は働かせることができるものの、それにしたって二十歳を超えたおとながする格好にしてはいささか幼い。
とはいえ、かつての私はいまと同様に質素な格好を好んでいるから、言ってしまえば私だってあのころからたいして服飾の嗜好は変わっていない。質素ゆえに、却ってちょうどよい塩梅に落ち着いたと言えたかもしれない。
それこそ三年前の彼女がとっていたかっこうこそが、女子高生という初々しい時期のみに許される幼さがあったのかもしれず、たしかにそう考えてみるとあのころの彼女のかっこうをいまのじぶんがしたらコスプレもよいところだと想像し、すこしおかしくなって、はは、と声がでた。
彼女がこちらを怪訝そうに見上げる。
まずは、久しぶり、と声をかける。いまこっちに帰ってきてて、と続けてから、あっ憶えてるかな、と白々しくも言い添える。「ほら、むかしいっしょに遊んだりして」
彼女は頷いた。私がどこまでそれを本気で口にしているのかを推し量れていないような戸惑いがちな目のまま、ゆっくりと首を引く。
「懐かしいなって思ってきてみたらびっくりだよね。ここにはたまにくるの? ていうかまだこっちに住んでるんだね」
言ってから、何か地雷を踏んだ気がして、はっとする。彼女の家はすでにないのだ。空き地になっていた。
言葉を探すがうまくいかない。彼女がふたたび目を伏せた。恥辱の念を隠そうとする素振りからは、私が踏んでしまった地雷がまさしく地雷だったのだと判らせるのに充分であったし、私がこうしてあけてしまった沈黙の意味するところが彼女に伝わってしまったこともまた容易に私に伝わった。
「えっと、じゃあ、うん。元気そうでよかった」
会えてよかった、と言えればよかったものの、そう口にできない空気に逃げだしたくなり、そして私は逃げだした。
彼女が縋るようにこちらを見上げた。私が目を逸らすと、視界の端で彼女がうつむいたのが判った。
このまま出口に直行するのはあからさますぎるので、飽くまで展示物を見終わったから帰るのだと示すように、私は壁沿いに並ぶ展示ケースをなぞるように、つぎの壁にぶつかるまで歩を進めた。
右を向けば出入り口があり、もちろんそこには暗幕が下りているからそれをくぐらなきゃいけないわけだけれども、私はそこで首だけでソファのある場所を見て、そこにいる彼女に、じゃあね、と手を振ってみせる。
薄暗く、柱の陰にもなっているから、角度からして彼女の姿は見えず、彼女がこちらを向いているのか、声が届いたのかすら判らずに私は暗幕をくぐり、懐かしい異世界の空気とさよならをした。
美術館とは名ばかりの銭湯に似たつくりの玄関口を抜けると、ちょうど頭に鉢巻をしたご高齢の男性とすれ違った。
会釈をして通り過ぎたが、背後でそのひとが歩を止めた気配があったので振り返る。
そのひとは首を傾げ、こちらを見ていた。美術館の看板をゆびさし、
「お客さん?」と目を見開くようにした。
「あ、はい」
「ずいぶん珍しかったもんで」
「はあ」
「常連さん以外で初めて見た気がしますよ」
そこにきて、きっとこのひとが管理人さんなのだ、と閃いた。館長と呼ぶにはいささか和風に寄っていて、和尚さんといったイデタチだ。
「なかにお客さんが一人いらっしゃったんですけど」
それが常連さんなのか、と問うと管理人さんらしきひとは、そうそう、とうれしそうに、きょうも来てたんですねよっぽど好きなんでしょうねえ、と目じりのシワを深くした。
じつは私もむかしはよく足を運んでいたんですよ、と嫉妬ともつかぬ反発心から打ち明けようかとも思ったのに、管理人さんらしきひとは続けて、
「むかしからですよ。ずっと幼いころからここにいらっしゃっててね。まあ、高校生くらいになってずいぶんおしゃれになってしまって別人みたいに別嬪さんになって、まあそれでもこうして通ってくれているから掃除もサボるわけにいかなくてね」
愚痴ってわけじゃないですよ、とそのひとは微笑む。
「むかしからなんですか」
そんなはずはなかった。すくなくとも私が通っていた時期にはほかに客はなかった。ひょっとしたら私と勘違いしているのではないか、と当て推量だが考える。
「むかしからですよ。ここ数年でますます別嬪さんになられて」
外見の美しさを念を押されて強調されてしまっては、なるほどだからかつては手を抜いていた掃除をここ数年は念入りに行なうようになったのか、と管理人さんらしきひとの心中を推し量るのに躊躇はない。
まあ、解らないではない。
外見の差異で扱いを変えるのは褒められた所業ではないにしろ、私だってかつてあのコに懐かれてそれほどわるい気はしなかった。
そう、わるい気はしていなかったのだ。
友人としてただ慕ってくれていたのなら。
幼馴染としてしぜんに接してくれていたのなら。
「毎日来られてるんですか」
「ワタシですか?」
「いえ、常連さん」
「毎日ってこたあないでしょうがね。ワタシも休日のたまにしかこんでしょう。そういうときでもいらっしゃるんで、まあ、すくなくとも休日にはいらっしゃってるってことなんでしょうが。芸術家冥利につきますねえ。作家さんもさぞかし天国でよろこんでいらっしゃるでしょう」
その作家とあなたの関係は何なのか、と気になったが、それよりも私はなぜ彼女がこの数年間、高校を卒業してからいまに至るまでに足繁くこの美術館に通っていたのかを考えた。
何度思考を巡らせても結びつく像が一つある。
ここはそう。
私は美術館の屋根を見上げる。
私と彼女の再会の場所だった。
四年前、私はここで彼女と言葉を交わし、がらんどうの生みの親との邂逅を果たした。縁を結び直した。
高校を卒業して、別れの挨拶もなくチリヂリになった私たちのあいだには縁と呼べるものがまだ結びついているのだろうか。
私は踵を返し、入口に立つ。もういちど入場券の自動販売機にお金を投入しようとすると、管理人さんらしきひとに、あれいま観てきたんじゃないんですか、と驚かれたので、忘れ物をしてしまって、と言いわけする。
「ならそのまま入ってもらって構いませんよ。立場上こう言っちゃならんのでしょうけど、まあ、つぎも黙って入ってもらって構わんですよ。誰も怒りゃしませんのでね、それよりぜひまたきてやってください」
太っ腹なのかずぼらなのかの判断に困る。私は黙って会釈をして、ふたたび暗幕をくぐって、暗がりにくるまれる。
彼女はまだ同じ場所、ソファに座っていた。
足音で気づいているだろうに、彼女は顔を伏したままじっとしている。私がまえに立つとようやく垂れた前髪をそのままに、こちらを見た。
「それは当てつけ?」
彼女は黙っている。
「ひょっとしてあれからずっとしゃべってないの? 私の真似してたの? ずっと? この三年間? そんなわけないよね」
そんなわけないって言ってほしくて私は続ける。「怒ってるなら謝る。あのころ私たちちょっとどうかしてたと思う。私にも落ち度があったって思ってる。だからもうこういうの終わりにしよ。ね?」
彼女の目つきが険しくなったので私は気圧された。
彼女のぴったり貝みたいに閉じていた唇が開く。竹に走る避け目を連想する。戸惑いがちな呼吸が聞こえ、それから彼女は声を発することなく下唇を噛みしめた。喉の鳴る音が暗がりに反響し、彼女の足元にぴちょんとしずくが垂れる。彼女はひどく汗を掻いていた。
「怒ってて言葉を失くしちゃったの? それとも償いのつもりなの?」
どちらにしてもあまり意味のない問いかけだとじぶんでも判った。きっかけがどうであれ、いま彼女がこうしてしゃべらないでいるのは彼女の意思であり、そうありつづけてしまった彼女の問題だ。自己責任ではない。きっかけを辿ればそもそも彼女がかつて大昔、私にがらんどうを植えつけたりしなければこんなことにはならなかったのだ。
絶対に許さない。
彼女が私に言い放たなければ。
そして私が彼女に、言いかえさずにいてあげたら。
「私、もうなんとも思ってないよ。ホントだよ。もしかしたらあなたがここに通っていることも、私とこうしてしゃべってくれないことも、私とは関係のないことが原因かもしれないけど、念のために謝らせてね」
ごめんなさい。
口にしようとしたところで彼女の鋭い目つきが私の身体を貫いた。殺意ともとれるつよい怒りの波動が伝わった。
でもどうしてそんな顔をされるのかが判らなかった。
謝ってはいけないのだろうか。
それとも言い方がマズかったのか。
憐れんだのがいけなかったのか、それとも彼女がこの三年間に募らせていた私への想いと私が彼女にそそいでいた関心が吊りあわないことへの不満だろうか。
やっぱりじゃあ当てつけだったのか。
彼女は私を困らせたくて、傷つけたくて、罪悪感を植えつけたいがためにそんな同情を引くような自虐をつづけてきたのだろうか。
あのとき私が彼女よりもほかの友人を選んだから。優先したから。許さないなんて暴言を突きつけてしまったから。
彼女をとことん傷つけてしまったから。
傷つけてもよいと思ってしまったから。
だから彼女は私に復讐をしようとしているのだろうか。
だったらそれは失敗している。
私はもう、あなたにかけてあげられる情もやさしさもなくしてしまったから。
「まだ許してくれない? また『絶対に許さない』を私にぶつけるの? でも私はもうあなたに許されたいとも思わなくて。ただべつに嫌いじゃないよ。嘘じゃなくて。だから私のあのときの言葉――憶えてるか分からないけど、絶対に許さないって言ったこと、あれはわるかったと思う。許すよ。怒ってないよ。でもだからってあなたを傷つけたかもしれないこと、許されたいとは思わないから、好きなだけそうして恨んでくれてていいから」
それだけ。
ただそれだけ知っておいてほしかっただけ。
彼女の肩に、おっかなびっくり手を置いて、じゃあね元気でね、ばいばい、と私はふたたびのさよならを告げた。
正真正銘、こんどこそ本当のお別れだと思った。
彼女の肩まで届く髪の毛は私の記憶にあるものよりずっと色褪せていて、鏡を覗いている気分になった。
暗幕を手で押し退けると、背後から大きな音が鳴った。視線を向けると彼女が立ちあがっていて、ソファが柱の位置からズレていた。彼女が勢いよく立ちあがったせいかもしれないし、ひょっとしたら蹴ったのかもしれない。
肩を怒らせて文句を言いたげに顔面を歪ませて彼女はじっとこちらを睨みつけている。
罵詈の一つでも投げて寄越してくれればよいのに、それでも彼女は頑なに言葉を発しようとはしなかった。
このまま立ち去ってもよかったけれど、なんだか私は彼女のことがかつてないほど痛ましくて、可哀そうで、けっして触れあいたくはないし、縁を繋ぎ直したいとは思わないまでも、愛おしく感じられて、だからなのか、私のかってな幻想かも知れないけれど、彼女がかけられたがっている言葉がしぜんと、なぜかふと、口を衝いている。
「さっきのはぜんぶ嘘」
暗幕の裂け目からそとに出て、私は顔だけを中に入れ、
絶対に許さない。
けして覆らない決定事項だと突きつけるように、植えつけるように、そう告げた。
みずから育てた巨大ながらんどうのなかで、彼女はなぜか、ふっとほころびる。
【がらんどうの根は甘く】END