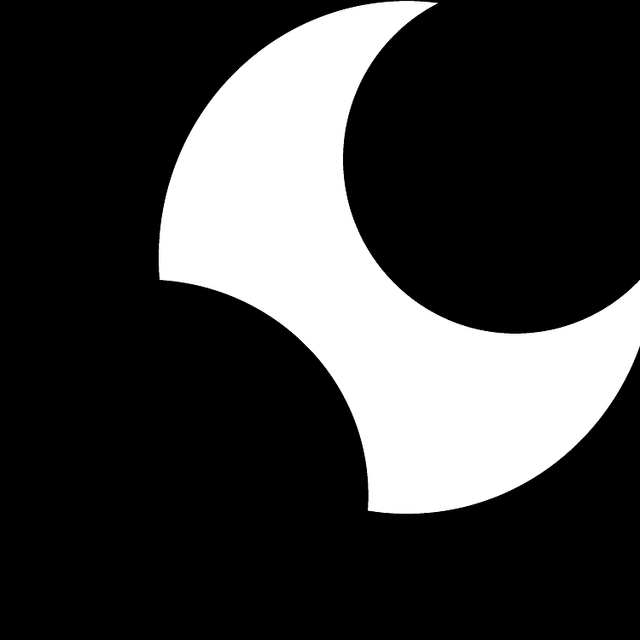千物語「累」
文字数 129,448文字
千物語「累」
目次
【宵の爪】(2022/10/19)
【龍尾矢島】(2022/10/19)
【金色の輪】(2022/10/21)
【タコ焼きにして食っちまうぞ】(2022/10/21)
【愛は内、外が鬼】(2022/10/22)
【寝ろ!】(2022/10/22)
【世界一適当な人】(2022/11/08)
【幻の大陸――海里】(2022/10/22)
【ハロー効果の勝利】(2022/10/24)
【江戸の波の光は則る(2022/10/24)】
【空へと舞い落ちる】(2022/10/25)
【冬のコゴミ(2022/10/25)】
【掛ける目を瞑る】(2022/10/27)
【贄に幸あれ】(2022/10/31)
【差別なき世界】(2022/11/06)
【ボイスの日々】(2022/11/08)
【誰も知らぬ旅路】(2022/11/10)
【繭の華咲く日は】(2022/11/12)
【木製のナイフ】(2022/11/15)
【ポメラニアン先輩はオレンジ】(2022/11/17)
【人の夢はマナコ】(2022/11/19)
【神々歯科医】(2022/11/21)
【宵の爪】(2022/10/19)
人生は選択の日々だ。
その日、俺はじぶんの未来と目のまえの欲望とを天秤に掛けて欲望の側に傾いてしまうだろうことを予感した。何度天秤に掛けても欲望側が勝つことを俺は、落下する猫が必ず足から着地できる神秘と同じくらいの確実さで直観していた。
カイは中学校からの友人だった。
思いだせる範囲でカイと俺の妙な関係が築かれたのはおそらく中学二年のころだ。第二次成長期真っただ中だった。体操着に着替えるたびに乳首が布に擦れて痛い、という話題でカイを含めクラスメイトたちと盛り上がった。そのときみなで乳首を見せ合ったのだが、カイだけが頑なに見せようとしなかった。そのため、乳首にピアスでもしているのかという話になった。
カイは違うと泣きそうな顔で否定した。カイはそのころから体つきが幼く、声変わりもまだだったようで、みなカイを小動物のように好きにいじっていた。物理的ないじりは体罰として教師からの叱責がすぐに飛んでくるため、あくまで口頭でのいじりにすぎなかったが、そのときはみな妙に興奮していた。
見せろ見せろ、とカイのTシャツをめくりあげようとしてカイはいよいよ泣き出した。
俺は見兼ねて、止めに入った。
そのときカイのほうから、確かめてよ、と俺に言ってきたのだ。みなに見せるのは嫌だが、誰か一人が確認するだけならいいと言って、カイは俺にだけ乳首を見せたのだ。
米粒みたいな突起が見えた。当然のことながらピアスはしていなかった。
乳輪は体操着の生地と擦れてなのか円形に紅潮して見えた。
俺はみなに、ピアスなーし、と報告し、そのときはそれで終わったのだ。
それからもカイはクラスのぬいぐるみのように、中心にはならずとも誰かが愛玩するような、腰巾着とも言えぬ立ち位置で卒なく過ごしていたように俺には見えていた。
誰かの子分ではなく所有物でもない。
誰とでも仲良くできるが、それは自己主張の激しくないカイの性格のたまものに思えた。
俺はたぶん意識的にカイと距離を置いていた。
虹彩の直径とカイの乳首の大きさがちょうど合致してしまったかのように俺の記憶にカイの細くしなやかな胸部の映像が焼け付いていたからかもしれない。意識して忘却しようとしていたじぶんをいまになって自覚できる。
結局カイとはその後、中学校を卒業するまでは接点を結ぶことはなかった。
高校が同じだったのは単に偶然だろう。女子含め同じ中学校から進学したのは六人もいなかった。
俺は早々にクラスに馴染んだし、カイとは別のクラスだった。
高校に入学してからカイと初めてしゃべったのは文化祭の日のことだ。俺はクラスの出し物の手伝いをしていて、中庭で焼きそばを作って売っていた。休憩時間を貰って、人気のない屋内に避難した。
というのも、そのとき俺は入部していた陸上部を辞めたばかりで、先輩と顔を合わせるのが気まずかったのだ。単に俺が部活の練習についていけなかっただけのことなのだが、そんな俺が短距離走の記録で先輩を抜いてしまったので、妙な因縁ができてしまったようだった。
俺としては気にしておらずとも、相手が気にしていることはある。そうするとひとまず軋轢を生まぬように俺のほうで回避するのが無難と言えた。
カイとはそこで会った。
一階の工作室のある区画で、普段であれ人気がない。移動教室で使われるのだが、三年生にならないとまず工作室での作業が発生しないらしく、ほとんど日中は森閑としている。
俺はこのころ読書にはまっており、この日も読みかけの小説を読もうと静かな場所を探していた。
工作室は閉まっていた。
廊下の突き当りには扉があり、外に通じている。鍵は手で開けられる。
俺は扉を開けて外に出た。
そこで足場に腰掛けていたのがカイだった。
「びっくりしたぁ。何してんだこんなとこで」
カイのほうが数倍度肝を抜かれたようで、目を白黒させながら口をしきりに開け閉めした。言葉を失くした人魚のようだ。俺はもうただそれだけでカイへの警戒心を失くした。
「本読みたくて」俺はカイの横に腰掛けた。
カイは横にお尻半分ほどずれた。
三十メートルほど離れた地点に体育館があり、その合間に点々と樹が生えていた。
俺たちのまえにも樹が立っており、頭上から木漏れ日が垂れていた。
陽がありすぎると紙面が眩しくて読書に向かない。その点、ここは屋外であるにも拘わらずよい塩梅の明度だった。
俺はそれからしばらく読書に専念した。カイが言葉少なな性格だったのは知っていたし、他人を拒むような性格でもないことを知っていた。
久しぶりに声を掛けたし、こうして隣に座るのも数年ぶりに思えたが、なぜかそうした時間の隔たりを感じなかった。
そこがカイのすごいところだが、そのすごさを周囲の者に自覚させない妙な陰の薄さも持ち合わせていた。透明なのだ。澄んでいるとも言える。
いまだから俺はそのように過去のカイとのふたたびの出会いを回顧できるが、そのときの俺には隣にじっと座るカイの引力に気づくことはおろか、特別に注視する真似もできなかった。
休憩時間は一時間だった。
俺はたぶん三十分くらいは読書に熱中していたはずだ。
そばにいるカイの存在がすっぽり抜け落ちていたし、もちろん中学二年生のころ面映ゆい秘密の共有を思いだしたりもしなかった。
だが本の中で、主人公が初恋のお姉さんの寝顔に無断で触れるシーンで、いくら主人公が未成年だからってこれはいかんのではないか、と内心で「それはいかがなものか」の心境をこじらせていると、不意に中二のころに目にした米粒のような乳首を思いだしたのだった。
顔が熱を帯びたのがじぶんでも判った。
スキー場もかくやというほどに紙面で目が滑りだした。文章が頭に入ってこない。
読書どころではなくなった。
本を閉じて、意味もなく空を仰ぎ、それから横を見た。
とっくにその場からいなくなっていてもおかしくない状況で、カイは膝を抱えて手元の草を抜いたり、千切っていたりした。
俺の視線に気づいたのかカイは顔を上げると、にこっと破顔した。やっとこっち向いた、と訴えかけるようでもあったし、もう読み終わったの、とひと仕事終えた主人を労う猫じみた素朴さがあった。
俺はこのときすでにカイをただの同級生に思えなくなっていたのだと思う。
何せ俺の脳内からはつい数秒前まで読んでいた小説世界がシャボン玉のように霧散していた。代わりに、目のまえのカイのつるんとした目と頬の境の曲線と、唇、そして日差しに透けて浮かぶ、つぶらな眼球の虹彩に、以前目にしたカイの胸部に弾ける米粒のような乳首への感応が、いっしょくたになって脳内にひしめいていた。
なぜそのように思考が支配されるのか俺自身わけが解らなかった。
カイは俺が凝視していたからか、怯えたように、ごめんね、と言った。
「邪魔しちゃった?」
俺は首を振った。遅れて、「いや」とぶっきらぼうに言った。
カイとそのあと何を話したのか、俺はいま思いだせない。たぶんカイに嫌われないように当たり障りのない会話を心掛けたのだろう。つまりじぶんの話ではなく、カイに話題を振ってしゃべらせようとしたはずだ。
だいいち文化祭なのだ。俺は読書という目的があったが、カイのほうでは取り立てて用事があったようには見えない。まるで中学一年生のようにブカブカの制服に身を包ませているカイからは、群れに馴染めないヒナのような弱弱しさが漂っていた。
庇護欲と言ったらそうなのかもしれない。俺はなぜかカイを放っておけなかった。
休憩時間が終わる前に俺はその場を去ったが、そのとき俺はカイを誘っていた。一人の時間を邪魔してごめんな、と言った気もするし、お腹空かないか、と繋ぎ穂を添えた気もする。
店側の特権で、身内にはタダで焼きそばを配ることが許された。一人二名までは無料で配っていいとされた。俺はまだ誰にも無料券を使っておらず、俺自身が小腹を空かせていた。
カイはしかし俺の誘いを断った。
静かなのが好きなのだ、とあとで俺はカイの内面を知ることとなるが、このときは単に俺が邪魔なだけなのだと思った。
その割に、文化祭が終わるころにカイは中庭に現れ、わざわざお金を出して焼きそばを購入していた。俺はそのときゴミ捨ての仕事をしていたので店に立っていなかったが、カイがうれしそうに焼きそばを両手で受け取っている場面を目にして、ふしぎと心の澱が晴れた。
晴れたことで心に澱が溜まっていたことに気づいたほどで、いったいじぶんは何にヤキモキしていたのだろう、と小一時間考えた。結局のところいまだからハッキリと分かるが、俺はカイの世界から弾きだされた異物なのだと一時であれ誤解したことが、俺の内面世界に曇天のごとく暗い影を落としていたのだ。
だがそれがどうやら誤解らしい、と焼きそばを手に周囲をきょろきょろ見回すカイの小柄な姿を目にして俺は察したのだった。
なぜそのときカイの探している相手が俺だと想像できたにも拘わらず敢えて声を掛けずにいたのかは分からない。だが魚釣りを連想した俺の精神はじぶんに嘘を吐けなかった。
ようは、泳がせたのだろう。カイのなかで俺の存在が大きくなるように、育つように時間を置こうと考えるでもなく考えたのだ。狡猾である。
だが結果として俺はそのときの判断を好ましく思っている。
なぜなら後日、カイのほうから俺の元にやってきたからだ。
その日は雨だった。
図書委員の仕事を果たしてから昇降口に立ち、雨空を仰いだ。
図書室の窓から見たときは小雨だったが、俺が靴を履くと見計らったように豪雨となった。
傘を持ってきていなかった。校門の外のバス停までは百メートル以上ある。
学校の傘の貸し出しを利用するのも手だったが、地元の高校ということもあり、走れば二十分の距離だ。
いざ駆けだそうとしたところで、制服の裾が何かに引っかかった。
そのように錯覚しただけだが、振り向くとそこにカイがいた。
カイは俺を見あげて、「傘」と言った。微笑と込みで、「傘あるよ」と俺の脳裏には響いて聞こえた。先に未来を述べておくと、カイとの会話でではこの手の脳内補足が頻発した。ほとんど俺の推察で補完されるカイの言葉足らずな発言は、しかしカイのほころぶ頬や屈託のない眼差しなど、言語よりも強烈に俺へと暗示を送りつけていた。
カイの持っていた傘は折り畳式だった。
俺は陸上部では短距離走の走者でありながら砲丸投げの選手よりも上の記録を出してしまうくらいに筋骨に恵まれた、言ってしまうと濡れた熊のような体格だ。いくら傘の下に納まろうが、二人肩を並べればどちらかが濡れる。
背伸びをしながら傘を差そうとするカイから持ち手を奪い、俺はカイが濡れないように歩いた。
カイの家は俺の家よりも遠い。
バスに乗ったほうが早いはずだ。
「バスで帰らないのか」と問うと、カイは雨音に掻き消されそうな声音で、「歩きたいから」と言った。
こちらを見上げてもよさそうな場面だったにも拘わらず足元を見つめて歩くので、俺はそこで、ははぁん、と思ってわざと歩みを遅くした。歩幅が違うために元からゆっくりの歩行を意識していたが、ことさらこの時間がつづくように時間操作をした。
その甲斐あってと言ったら語弊があるが、濡れないようにしたはずのカイの肩まで濡れてしまった。俺はじぶんの家に到着したのをよいことにカイを部屋に誘った。
単純に濡れたままで帰すのは恩を仇で返すようで心苦しかった。
むろんそちらは後付けではあるが。
カイは、でも、と一度は渋ったが、風邪でも引かれたら適わんよ、と肩を落としてみせると、でもいいの?と何の確認なのかも解らぬ小首傾げを頂戴し、俺は、いいのいいの、とカイの手から傘を回収した。
制服はブレザーで、カイから上着を預かった。上着は濡れて片方の肩から腕にかけての色が濃くなっていた。カイのワイシャツも腕のところが濡れていた。
俺は謝罪をしながら、カイにワイシャツも脱ぐように言った。
「そこまでしなくても大丈夫」カイは遠慮したが、ドライヤーで乾かすから、と俺が言うとカイは、そうなの?と大人しくと言ったら齟齬があるが、ワイシャツを脱いだ。
ズボンのほうも濡れていたが、さすがにそちらを脱げとは言えなかった。
バスタオルを渡し、カイがそれで濡れた頭やズボンを拭いているあいだに俺はカイの上着とワイシャツにドライヤーの温風を当てた。
「外にでたらまた濡れちゃうかも」
「かもな」
「すごい本棚」
カイはいまさらのように俺の部屋を見回した。まじまじ、と効果音が聞こえてきそうなほどで、俺は恥ずかしくなった。
「元は兄の部屋でさ。いまアイツ関東のほう行ってて、まあお下がりだわな」
「全部読んだの」
「本か。いやまだ全部じゃない。趣味が合わないのも結構あるし」
「どれが面白い?」
二度見さながらに細かくこちらを振り向いたカイの横顔はまるで世界の秘宝展にて、どれが世界一の秘宝なの、とでも訊ねる幼子のようだった。
「どういうのが好みなんだ」
俺はわざとブレザーのほうを先に乾かしていた。いや、いま思えばそうだろうというだけのことであり、このときは要領よく作業ができていなかっただけのはずだ。だが段取りを考えるならば、先にワイシャツを乾かしたほうがカイは無駄に凍えずに済む。
案の定、本を取りだそうと立った俺の横でカイは小さくくしゃみをした。
「あ、わるい。寒いよな」
そこで俺は箪笥からトレーナーを取りだして、カイに渡した。
カイはそこで拒んだりせずに、ありがと、と呟き袖を通した。
家には俺のほかに家族はない。カイと二人きりだった。
雨脚はますます強まり、窓の外をトラックが通っても雨音との区別がつかないほどだった。
「これはキツいな。もうすこし待ったら弱まるかも」俺は本を数冊カイに手渡した。「ありがと。いま読んでもいい?」
「いいよ。読み切れなかったら貸すし。濡れてもいいように袋に入れるから」
「優しいね」
心底おかしそうにカイは下唇を食み、それから俺の名をクン付けで呼ぶと、「――の匂いがする」と言ってトレーナーの襟を目元まで持ち上げた。必然、カイの顔が半分ほどトレーナーの襟首に隠れた。
「嗅ぐなよ」
ハズいだろ、とは言わなかったが、カイには伝わっただろう。俺はこのときドライヤーを握っていて、ワイシャツを乾かすべく作業を再開させようとしていたのだが、カイのそばに寄ったことでドライヤーのコンセントが抜けた。
雨脚がさらに強まり、静寂が際立った。
コンセントを刺し直しに背を向ければよかったものの、俺はカイから目を逸らせなかった。
というのも、俺のトレーナーは当然ながら俺の体格にあったものであり、ただでさえ小柄なカイが着ると、まるでワンピースのようにブカブカだったのだ。
カイの髪はまだ濡れていた。
俺はまた中学生時代に目にしたカイの素肌を思いだし、思考が混線した。
それを知ってか知らずかカイは、
「前にさ」とまさにあのときのことを口に出したのだった。「こんなふうにしてあのときも守ってくれたよね」
俺は言葉が出なかった。好ましい返答の候補が俺の脳裏に渦巻いているあいだにカイは、
「うれしかった」とはにかんだ。
まさに、はにかんだことに恥ずかしくなったように、また顔の半分までトレーナーの襟首を捲し上げた。
絵面だけ見ればいわゆるこれが、あざとい、の結晶なのだろうが、俺はまんまとカイのそうした仕草に巨体の奥底でひしめく本能とやらを揺さぶられた。これはけして三大欲求とは乖離した、もっと根源の、いわば慈愛である。いまでも俺はそう思っている。現に俺の身体のほうは、カイのそうした仕草を見てもこれといって反応を示さなかった。
だが身体とは裏腹に、心のほうが先にダメになっていた。
なぜそれをダメになったと形容するのか俺自身もよく解らないのだが、とかく正常とは言い難い状態になったのは自覚できた。
なぜなら俺は無性にカイのことを抱きしめたくなったからだ。繰り返すがこれは同等の人間へ向ける類の感情ではなく、子犬や子猫をまえにしたときのような衝動にちかかった。
カイは人間だ。
したがってここで俺が衝動に任せてカイを抱きしめるのはよほど理性を度外視した異常な行動と言えた。仮にこれが女子生徒相手だったならば俺は社会的に死ぬだろう。いいや、よしんば相手が男子生徒だろうと同じことだ。
そうと判っていながらに俺はじぶんの衝動を抑えきれず、そのためにすぐにドライヤーのコンセントを挿し直す真似ができなかった。
カイはしかし却ってそれがよかったのか、それまでとは打って変わって言葉数が増した。おそらくドライヤーの騒音がなくなったので、声が通るようになった影響だろう。俺のほうでも混線した思考でカイへの返答をひねくりだすので精一杯で、身体のほうを体よく動かせなかった。
カイはことさら俺を、優しい、と言って褒めた。じぶんは普段から感情を言語化するのが苦手で、嫌なこともその場ではうまく言葉にできない。あとになって、ああ言えばよかったこう言えばよかった、と反省会を開いては、後の祭りの気分を味わうのだと、身振り手振りを交えて胸の内を明かしてくれた。
たしかにカイの言葉のテンポは速くなく、聞いている側はまどろっこしく感じることもあるだろう。特に教室内での同級生たちの会話のキャッチボールは卓球でもしているのかと思うほど速いのだ。
これではカイはいつだって押し黙るしかない。
だがこの日、カイの声を、言葉を、邪魔するほかの卓球の玉はなく、俺のほうでも必ずしも打ち返す必要がなかった。カイがしゃべりたいままにしゃべらせればよいと考えていた。
俺の親は共働きで夜はいつも二十時を過ぎて帰宅する。兄以外に俺に兄弟はいない。
気づくと俺は布団の上で壁に背を預けながら、カイを後ろから抱きしめる格好で座っていた。本棚のまえで対峙しながらしゃべっていたはずだが、どちらともなく床に座り、寒いからと俺がおそらくは温めることを提案してそのような格好になったのだろう。この辺り、記憶に乏しい。
だが違和感なくしぜんな流れでそうなった。互いに以心伝心、最も距離感の心地よい体勢へと移行したのだ。
俺は相槌しか挟まなかった。
だからカイが黙れば部屋には静寂だけがこだました。
カイを部屋に招き入れたときには明かりを灯しておらず、それは窓の外がまだ明るかったからだが、気づけば日暮れ時に差し掛かっており雨雲のためかこのとき部屋は薄暗かった。
「あのね」カイの声音が宵闇の池に波紋を立てるように広がった。「まだ痛くてね。じつは絆創膏貼ってたりするんだ」
カイの言葉尻はいつも小さい「ぁ」が付属するような響き方をした。いやそれはどちらかと言えば消え失せ方と言ったほうが正確だったろう。
「絆創膏?」
「ここ」
膝の合間でカイが動く。振動が腿に伝わる。カイの身体からは炭火のように熱が滲んでいた。
どこ、と俺は訊き返した。おおよその場所と位置を推測しておきながら俺は敢えてカイの口から言わせようとしたのだ。
そこでカイは言いよどんだ。当然だ。カイの性格を思えば恥辱の念に苛まれてここで黙りこくってもおかしくなかった。
だが予想に反してなぜかこのとき、カイは俺の手を取り、じぶんの胸部に持っていった。トレーナーの上から俺はカイの起伏のすくない身体に触れた。
手のひらで触れ、それから指で探った。
頼まれたわけではないし、カイの意図がどういうものかを俺はそのとき想像しようともしなかったが、絆創膏の在処を探るように俺の指はカイの存在の輪郭をなぞった。
カイはくすぐったそうに身をくねらせたが、俺の手を掴んだままだった。そうだ。いま思えば俺の手はカイの誘導され、意のままに操られていたような気さえする。
じれったいようにカイは俺の指の付け根をつまむと、箸でも扱うかのように、「ここ」と位置を指定した。
トレーナーの生地越しのうえ、絆創膏まで貼られていたのでは、ここと言われてもどこ、と問い返すしかないその状況にあって俺はやはり誰に頼まれたのでもなく爪を立てて、そこにあるだろう突起を探っていた。
短い弾けるような吐息が、闇夜の池に波紋を浮かべた。
その波紋は俺に継続を命じているようだった。俺の腹に体重を預けたカイの熱がより明瞭と伝わり、加えて俺は、中断を禁じられたように錯覚した。
カイは何も指示はしていない。言葉こそ発しなかったが、彼の身体から放たれるシグナルは俺にその行為のつづきを促していた。
玄関の鍵が開く音がするまでのあいだに、俺たちはその行為のみに耽った。トレーナーの下に手を忍ばせたが、Tシャツの下にまでは侵入しなかったし、絆創膏にも触れなかった。
あくまで生地越しに俺はカイの胸にある突起を探ることにのみ集中したし、カイのほうでもそれ以上を求めるようなシグナルを発しなかった。
親が帰ってきたのを機に、俺はカイから手を離し、カイもまた俺から身を剥がすようにした。
明かりを点けるとカイは手探りでワイシャツを手に取っており、トレーナーを脱いでいる途中だった。蝉の脱皮を彷彿とし、俺はごめんと口走って顔を背けた。ワイシャツはきっとまだ濡れたままのはずだ。カイは制服の上着を羽織ると、ありがと帰るね、と顔を伏したまま俺の隣に立った。
部屋を出ると母が立っていた。母は身体を横に倒して俺の背後を覗き、目を見開くようにした。「お友達?」
「もう帰るとこ」
「珍しいね。あらこんにちは。もっとゆっくりしてったらいいのに雨まだすごいよ」
暢気に母親はカイに夕飯を勧めたが、カイは「遅くなると母が」と言って断った。
このときばかりは俺を見上げて助け舟を希求したが、俺は苦笑しながら敢えて無視した。
母の言うように雨はザーザーと音を立てて夜の帳に打ち解けていた。俺はカイを途中まで見送りに出て、その帰りにコンビニで烏龍茶を買った。
外を歩いたときの、現実に帰ってきたような質感には毎度のことのように驚きを覚える。おそらくこのときの俺も、部屋でカイと共にした時間の空想めいた浮遊感をまるで夢でも視ていたかのように振り返っていたのではないか。
この日を境に、下校中にカイと一緒になるときはどちらからと言わず俺の家へと寄るようになった。そして約束をしたわけでもないのに、布団のうえでカイを懐に置いて他愛もない会話をしながら、絆創膏の位置を探る遊びをするようになった。
それはまさしく遊びであり、けしてそれ以上の深みに逸脱することはなかった。
俺の身体は相も変わらず思春期に特有の反応を示さずにいたし、カイのほうでも俺にそれ以上の接触を求めようとはしなかった。
三度目にカイを部屋にあげた際、カイはワイシャツの下にTシャツを着てこなかった。わざとなのは瞭然だった。
道路には落ち葉が舞う時節である。
寒かろうと思い、俺はことさらにカイを後ろから温めた。そうして季節に逆行するようにカイは何度目かの遊びの際には、「絆創膏、剥がれちゃった」と言って俺に剥がれた絆創膏を手渡した。
部屋が暗がりに沈む時刻は日増しに早まっていた。
あたかもカイの言葉数少なな性質を補うかのように。
俺たちの秘密の遊びの時間を深めるように。
俺はカイの表皮から剥がれた絆創膏を握り締め、そのまま指先の爪で触れるか触れないかといった力加減で、やはりこのときもワイシャツの生地越しにカイの突起を探った。
今度は感触があった。
爪に引っかかる突起のぷつくりとした触感が、しゃぼん玉に触れるような手つきであれ如実に伝わった。小さな小さな小人の頭を撫でるように、俺は指先の爪で以って何度も突起を往復した。
スミレの花のような声音が、熱を帯びて弾けては消える。
声を抑えようと耐えるたびに、声は余計にくぐもるようだった。
俺はカイにそうした忍耐を強いるように、執拗に爪以外での接触を行わぬように自らを律した。本当であれば指の腹で押しつぶしたいほどに狂おしく、目のまえにある首筋にとて歯を突き立てて噛みきりたい衝動にすら襲われたが、俺の内面に渦巻く葛藤など、カイからほとばしる熱と声と身じろぐたびに伝わる振動に比べれば天秤に載せるまでもない霞と言えた。
ないに等しい。
仮にそれをあるとしてしまえば、俺はもう二度とこの瞬間を味わうことはできないのだと知らしめるだけの均衡が、カイと俺のあいだに揺蕩う宵闇には宿っていた。
どちらか一方がそれ以上に踏み込めばたちどころに断ち切れる。
細くも尊い深淵が開いていたのだ。
回を重ねるごとに俺は指先の数ミリの動きだけでカイを心底に悶えさせることができた。敢えて指を微動だにさせぬことで、カイのほうで身体を左右に揺さぶらせることも可能だった。しかし俺がカイを操っているようで、そうではないことも俺は承知していた。骨の髄まで理解していた。
何せ俺は、カイが俺の身体から背を離すまで、彼をその場からどかすことも、床に押し倒すこともできなかったのだから。
しかし、そうすることもできない、と強く意識するたびに俺は、夜、カイのいない床のなかで遅れてやってくる身体の思春期にふさわしい反応を覚え、その煮えたぎるような熱量を一人で治める日々を余儀なくされた。
それはまさしく、余儀なくなされたものであり、強いられた枷であった。
カイとの関係に名をつけることを俺の理性は拒んだ。カイのほうでもそれを避けていた節がある。俺たちの秘密の遊びにしたところで、それが秘密であることも、遊びであることすら暗黙の了解の域をでず、言葉にしたことはなかった。
不安定なのだ。
カイとの宵闇の時間が日ごとに俺のなかで大きくなるにつれて、俺の中には切創にも似た間隙が開いた。俺とカイとのあいだに宿った均衡のようにそれは細くも深い底なしの淵と化していた。
それを自覚したのは、学校でカイがほかの同級生たちに、かつて中学生時代がそうであったように愛玩動物のようにいじられている姿を目にしたときのことだ。いいや、一度だけではない。何度も繰り返し目撃するたびに、俺は俺のものとは思えぬ感情の揺らぎを覚えたのだ。それはひどく渇き、飢えていた。
目のまえの同級生たちはみな、カイに冗談を言い、肩を揺らす。そこにカイを貶める意図がないのは明確だった。誰もがカイを己が弟のように、それとも後輩のごとく扱う。猫かわいがりと言ったら語弊があるが、猫にするそれのような、と言えば的を射る。そういった一種、共同体の結び目のような扱いをカイは、どの集団の中でも受けていた。
思えばカイが二人きりで誰かと話しているのを見た憶えがない。
だからかもしれない。
いや、いっそだからだ、と断言してしまってもよい。
俺はほかの俺以外の連中にいいように扱われるカイにこそ、腹に煮え立つ感情を抱いた。同級生たちへの憤怒や嫉妬かと俺も最初は俺自身を疑ったが、どうやらそうではないらしい、とカイのいないところで接する彼ら彼女らへの感情を矯めつ眇めつ見比べるようにして判断ついた。
俺は同級生たちへ、これっぱかしも負の感情を覚えていない。むしろことごとく正反対であり、俺は彼ら彼女らへ、まったく何も思わないのだった。
「どうしたの。怖い顔してる」
そう言って、学校の中で声を掛けてくるカイにこそ、言いようのない怒りが湧いた。これが怒りなのだと気づけたじぶんの直観を素直に称賛したいくらいなのだが、つまり俺はまったくに平然と、なんでもないよ、とカイを安心させるための嘘を吐けたわけだが、内心、髪に触れぬように撫でたその手で、天使の輪の浮かぶそのみなより一回りも小さい頭をひねりつぶせたらどれだけスッキリするだろう、とそんな妄想を浮かべていた。
ダメになっていた。
俺の精神は、心は、すっかりダメになっていたのである。
カイ以外との同級生との話題はもっぱら猥談だ。しかし、どれだけ情報を得ようが、夜な夜な床の中で煩悶する俺の空想の中に、他人が入り込むことはついぞなかった。
かつてはきっとあったのだろう。その過去を思いだせぬようになるほどに、俺のなかでカイはとっくに他人ではなくなっていた。
そうと自覚してなお、俺はカイとの時間はやはり爪以外での接触を行えなかった。破れなかった。宵闇に響く波紋と、その振動に身を浸す時間の甘美さに、それとも現実と乖離した空想の、ここではない俺とカイだけの世界の耽美さに、俺はすっかり骨の髄まで侵されていたのだろうと、いまになってはそう思う。
日に日に、じぶんの手の甲に浮かぶ血管がミミズのように陰影を深める。力を込めているからだ。カイの突起に爪を這わせているあいだ、俺は手が命を得て暴れださぬようにと力を込めて押さえつけている。意思の力で。幾度もカイの輪郭の数ミリ向こうを往復させ、引っ掻き、その突起の主に悲鳴を漏らさせ、悶えさせているあいだ中ずっと俺は耐えていた。
風船を針の先でなぞるような心境で。
それでいていっそ一刺しにしてやりたいとの衝動を肥大させながら。
回を重ねるごとに俺の膝のあいだで無防備になる小さき人型の「狂おしき者」を、どうにかしてしまいと望むようになっていた。
願望だ。欲動だ。
俺はその場でカイの身体を、背中から生える千本の腕で押さえつけ、彼の四肢を捥ぎ、細胞の一欠けらにまで千切り、潰し、吸いこみたいと夢想するようになった。殺したいわけじゃない。いや、解らない。殺したいのかもしれない。だがそれは憎悪ゆえではなく、もっと精神の根元にある、花を命を愛でるのに似た感情とウラオモテの本懐に思えた。
死にたいと言いながら生きたいと望むような、有り触れた、誰しもに沈む根源にして核のようなものに、俺はカイと触れるともつかぬ触れあいのなかで触れていた。
ねえ。
とカイは最近、よく口にする。
ねえ。
と呼びかけながら、それ以上を言わないのだ。
俺の手の甲に手を重ねながら、ねえ、と何かを乞うように、それとも媚びるような声音で、ねえ、と繰り返すのだ。
俺はすでに何度も、彼の鼈甲飴のように薄い、ねえ、の声に流されずにきた。カイのそれは俺を試すでもなく試すような期待に満ちた響きを伴なっている。
俺はしかし、もういいだろう、という気になっている。
人生は選択の日々だ。
俺は常に正解を選びつづけるカイとの営みにほとほと疲れ果てている。
憔悴しきってなお、回復する手法をカイとの戯れにしか見いだせないいまに至って、俺のとれる選択肢はそう多くはない。
今宵、いまこのとき、俺は俺の腕のなかで無防備にうなじを曝けだしもっともっとと身体を小刻みに揮わせる同級生をまえに、内部で育てた狂おしくも静謐な願望を、欲動を、それとも単に深淵を、堪える真似をせずにいようと決意する。
何度天秤に掛けようとも覆らぬ予感を胸に俺は、この日初めて、カイの胸部にじかに触れる。
ワイシャツのなかに蛇でも滑り込んだかのようにカイは悲鳴したが、俺はその口を上から手で押さえ、指の上からさらに唇を重ねるようにした。
カイが息を呑んだのが判ると俺は、指を開いて隙間を開け、唇同士が接触しないうちから舌を伸ばした。
舌先が熱に触れ、徐々に粘液をまとう。まとわりつくような動きが眼球の動きと連動するようだった。
もう一方の手のひらには、しきりに脈打つ心臓の、途切れぬシグナルが染みこんでいる。
ねえ。
とまた、声なき声が俺の脳のひだに爪を掛ける。
【龍尾矢島】(2022/10/19)
西のほうの龍の尾には矢が刺さっている。龍は矢を抜いてもらうために、とある最果ての島へと飛んでいき、そこで巫女に矢を抜いてもらった。龍はその恩を威信に賭けて返そうとしたが、龍がふたたび島に舞い戻ったときにはもうそこには巫女の姿も、村も、島すら残っていなかった。微塵も残っていなかった。西の龍は、巫女への恩を忘れぬように尾に残った傷が癒えぬようにと絶えず自らの爪を突き立て、傷穴を広げつづけた。龍はその後、巫女のいた島がとある魔人の仕業で滅んだと知っていたく悲しんだ。魔人の行方は杳として知れず、龍のほうでも復讐をする気にもならなかった。ただただ巫女に恩を返せなかったことを口惜しく、臍を噛んでも噛みきれぬ龍はその後、尾の傷から血が肉が滴り落ちるのも厭わず空を駆け巡り、全国津々浦々に龍の血の雨を降らせたのだそうだ。龍の通った後には不思議と森が、泉が、滾々と湧いて、萌えて、生したそうだ。
【金色の輪】(2022/10/21)
海に浮かぶ岩の上には城がある。
間口が広く、上に行くほどキノコのように笠が膨らむ。
年中秋が停滞するような真っ赤な壁面は、陸から目にすると岩に根付いたベニダケのようだった。
岩の城と呼び、陸地の者たちは畏怖して舟を近づけようとはしなかった。
城にはナニモノかが棲んでいるが、陸地の者たちはその正体を知る由もなかった。
ときおり月夜に、城から飛びだす巨大な翼を持ったナニカシラの影を見たと証言する者たちもいたが、真偽のほどは定かではない。
陸には陸で、丸い山があった。まるで月が落ちてきたかのように、それとも巨人の握った泥団子のごとく、丸山がデンと転がっていた。丸山の表面には木々が群生しており、あたかもマリモのように森が丸山の表面を覆っていた。
丸山には狼男が棲むと、近辺の里の者たちは信じていた。現に満月の夜には、雨戸をビリビリと揺るがせるような遠吠えが轟き、日中には木を伐り倒す音が響いた。
丸山は球形のために、地面に近いほうの表面から生える木はいずれも太陽を目指し、弧を描いて幹を曲げた。あたかも松ぼっくりの松笠のように。それとも壁から生えるツクシのように。
狼男の噂を知らぬよその土地の者たちが過去幾人も丸山に挑んだ。そのたびに丸山に入った者たちは帰らぬ者となった。
やはり狼男が棲んでいるのだ。
里の者たちは狼男の怒りを買わぬように、それでいて住み慣れた土地を離れずに済むようにと、目前の丸山をそこにないもののように扱い、暮らした。
というのも丸山は自然が豊かだった。人間以外の生き物たちにとっては、山と里の境はあってないようなものだ。手つかずの丸山からは山の幸がふんだんに転がり落ちてくるようだった。
あるとき、激しい嵐が海からやってきた。雷がところ構わず降りしきり、海に浮かぶ岩の城にも直撃した。落雷に遭った岩の城は炎上した。炎は、横から殴りつけるような雨に晒されても消えることはなく、風に煽られるたびに火の勢いを増した。
ただでさえ赤くベニダケのような城は一晩で燃え尽きたマッチ棒のようになった。嵐が過ぎ去ると、煤けた城からはもくもくと煙が立ち昇っていた。洞に抱えこんだ梟のような残り火がその後も火山のように細々と空に波打つ線を描いた。
陸地の者たちは内心ほっとしていた。
岩の城に住まうナニモノか――みなは禍を怖れてそうとは口にしないが、城にはバケモノが居ついていたはずで、それが火事に遭い死んだ。陸地の者たちはそのように考えた。
祟りに遭わぬように、見て見ぬふりをしながらも、ようやく遠慮会釈なく漁ができる。内心、清々していた。
だが事態は、嵐の過ぎ去った十日後、内地の森のほうから避難してくる山の民たちの群れを目にして一転した。
海岸に住まう海の民たちは事情を訊いた。すると山の民たちは口を揃えて、嵐が魔を運んできた、と言った。
「魔だぁ? 山火事でもあったかよ」漁師は燃え尽きた岩の城を指差した。海と空の地平線の合間に、煙が天に伸びていた。
「ちげぇ。ありゃ天の神さんだべ。天狗さまだぁ」
「天狗だぁ?」
「んだ。こっからは見えんべか。おらだちの里さ近くに丸山があっぺ。あそこにゃ山の神さんがおわしとってな」
「山の神さんだぁ? んだらば、それと天狗さまが喧嘩しだしたとか言うなよ」
「それだ、それ。嵐と共にやっできで、そっからはもうひでぇのなんのって」
獣は山から逃げだし、鳥一匹いなくなったのだそうだ。
だけに留まらず、地割れに土砂崩れ、絶え間なく反響するこの世のものとは思えぬ絶叫と咆哮が、過ぎ去った嵐の代わりにその地に停滞したのだという。
「天変地異とはあのことだべ」とは山の民の長の発言だ。
岩の城近辺の禁域が放たれた。
海の民は過去にない忙しさだった。岩の城の土台となるまさに岩の周辺は、海の幸の宝庫だったのだ。
人手不足を予感していた矢先の山の民たちとの遭遇は、海の者たちにとっては僥倖だった。
「山には戻れんのかい」
「あの調子じゃ無理だべ」
「んだらば、ここに居ついたらええっちゃ」
「ええんか」
「ええも何も、別にここはおらだちのもんでもねぇしな」
な。
と海の民の長はみなの衆に投げかけた。
んだんだ、と返事が上がる。
そのころ、丸山の山頂では二つの陰がくんずほぐれつ絡み合っていた。耳を塞ぎたくなるような天をも割る唸り声がなければ、巨大な熊同士がじゃれ合っているように見えただろう。
だが片や、背中から翼を生やした筋骨隆々とした人型、もう一方は牛すら丸呑みにしそうな巨大な獣だ。
双方ともに鋭い牙を剥きだしに、我先に相手の首筋に食いつかんと襲いかかる。嵐が過ぎたのは十日も前だ。その間、延々と二つの強大な影はいがみ合っていたことになる。
相手の肉に爪を食いこませ、ときに血を流させる。
決着は十日を過ぎてもつかぬようであった。
二つの影は、丸山の山頂にて互いに相手の両手を両の手で封じた。指を絡ませ合い、力を拮抗させる。
微動だにせぬ。
足が地面に食いこみ、丸山の表面には地割れが走った。卵の殻を割るように、日に日にそのヒビは深さを増した。
先に一歩でも退いたほうが首に、顔面に牙を突き立てられる。
決死の攻防は拮抗の果てに、二つの影の命が事切れる前に、足場の崩壊を以って終結を迎えた。
二つの影の衝突の余波に、丸山のほうが保たなかったのである。
山頂から真っ二つに割れた丸山は、半円を保ったまま左右に倒れた。どうやら相当に硬い岩盤でできているらしく、地面に転がった勢いのまま二つの半円は、くるっと反転した。断面と地面がくっつく格好だ。
満月の山が、二つの半月の山に分かれた。
丸山の麓に点在した里は丸ごと下敷きになった。
海岸の集落からも、その様子は伝わった。地震と紛う轟音と共に、空に舞いあがる火山さながらの粉塵が目についた。しかし誰一人森に入り、様子を見に行こうとする者はない。
あれほど騒々しかった奥地が以前のような静けさを取り戻しても、山に戻ろうと考える者は皆無だった。
それはそうだ。死闘が終えただけで、まだ天変地異を起こした元凶は生きているのかもしれぬのだから。
山の民たちがすっかり海岸での生活に慣れたころ。
一人の少女が家出をした。
海辺で産まれた少女の親は山の民であったが、少女はかつてこの地で起きた天変地異について知らなかった。産まれたのが天変地異の起きたあと、少女の親が移転してからのことだったからだ。
むろん少女は親から口を酸っぱく、森には入るな、山には近づくな、と言いつけられていた。だが少女は家出をした。
ろくすっぽわけを話さぬ親に嫌気が差した。山の恵みを頑なに拒み、海での暮らしに固執する村の者たちにも愛想が尽きた。
森のなかを歩きながら少女は思う。
こんなに食べ物がたくさんあるのに、どうしてこっちで暮らさないのだろう、と。
森は危険、山は危険、と村の大人は異口同音にして唱えるが、海辺の暮らしとて危険はある。海が荒れれば漁には出られず、地震があれば津波に怯える。
それに比べて森はどうだ。山はどうだ。
この荘厳な佇まい。
視界の開けた丘の上から少女は二つの大きな山を見る。
まるで均等に切り分けたかのような双子のごとく二つの山は、あたかも巨大な山の女神が仰向けで寝そべっているかのように、森と空の合間を埋めていた。
森閑と、それでいて命の蠢動の賑やかさを両立させるように。
静寂と喧噪が互いに睨みあい、砕け、溶けあうように。
少女は、ほぉ、と感嘆の息を吐く。
そのとき晴れ渡った空の下、地鳴りのような音が響き渡った。
呼応するように、別の方角からもおどろおどろしい音が反響した。
遠雷か。
否。
天の咆哮とも、大気の蠕動ともつかぬ得体のしれぬ震えだった。大地の震えだった。
少女は身震いを一つすると、踵を返した。
一目散に森を駆け抜ける。見慣れた海岸の砂を踏むとようやくその場に膝を崩して、肩で息をした。しきりに額から滴る汗を手の甲で受け、少女はいまいちど森の奥で目にした光景を反芻した。
あれはいったい。
海に目をやると、いままさに帰港する舟が見えた。
浜からは丸太で組んだ細長い橋が浅瀬に延びている。港だ。ちっぽけな舟が橋に繋がれる。少女はそれを見届けると、何を思うでもなく、帰ってきた大人たちを出迎えるべく浜辺に下りた。
舟から引きずり降ろされる網には大量の海の幸が跳ねていた。
舟の向こう側、沖合には巨大な一枚岩が浮かんでおり、少女は岩に沈みいく太陽に目を細める。
岩にはかつて燃え尽きた城の残骸が屹立している。
海鳥の巣となったそれは黒い剣のように風に吹かれ、ひゅるひゅると笛のような音を海辺の村に聴かせていた。少女はその音を歌のようだと思いながら、しかし音を鳴らせる黒い剣のごとく物体が何であるのかを知らぬままである。
大人に訊いても誰も答えぬ。
少女がじぶんの手で、足で、岩をよじのぼるまで、それがかつて城であったことを口にする者は誰もおらず、そして――少女が城の残骸で見つけた金色の輪が何であるのかを答えられる者は誰もいなかった。
金色の輪を少女は生涯手元に置いた。少女が老婆となり亡くなると、よその島から流れてきた異国の船に親族が高値で売り払ったという話である。
金色の輪はひどく頑丈であったそうだ。
朽ちることなく、また錆びることもなかった。熱しても叩いても傷一つ付かず、誰がどう調べても、ついぞその素材が何であるのか、何のための道具なのか詳らかではなかった。
その行方も、いまでは杳として知れぬままである。
【タコ焼きにして食っちまうぞ】(2022/10/21)
夢がいつか叶うなんて嘘だ。
いつかなんて巡ってこない。やってこない。すくなくとも私の人生には無縁な箴言だ。
私は幼少のころこそ才媛だと、親族、学友、教師たちから持て囃されたが、しょせんは幼いころに一時発揮できた束の間のどんぐりの背比べにすぎなかった。
私は小学生で自家製演算機を組み立てられたし、数学の履修も義務教育のあいだに大学院レベルは完了していた。
だが時代が私のそうした栄華を根こそぎ過去のものとした。
転換期は二つある。
一つは汎用型人工知能の普及。
もう一つは、巨大隕石の衝突だ。
人類は人工知能の補助によって、いちいち個々人が数学を用いて計算せずとも、数学者よりも正確に未来や仕事を計算できるようになった。
そのお陰で、衝突すれば人類どころか地球が木っ端微塵になるような超高速飛来型隕石を、衝突以前に打破できた。
だが細かく砕け散った隕石だけは防ぎきれずに、地表には無数の小規模な隕石が降りそそいだ。大半は大気圏で燃え尽きたが、落下した隕石もあった。
大都市のみならず各国で甚大な被害が報告された。
だがそれすら汎用性人工知能の補助があり、急速な復興が進んだ。というのも、元から人類社会は一度都市を根っこから再構築するくらいでなければ、どの道破滅の道をひた走ることが予想されていたからだ。
危機が好機に変換された。
むろん死者はでた。掛け替えのない命が大勢い奪われた。
だがそれを悼み、哀しんでいる余裕が人類のほうになかった。前を向いて、明日を、今日を生きていかねばならない世界がやってきたのだ。
それも、一瞬で。
世界は変わった。
社会が変わった。
私の誇った特異性はのきなみほかの大多数も、汎用型人工知能の補助によって誰しもが発揮できるようになった。
私はというと、ほかの大多数の個との差異化を以って己の付加価値をあげようと企み、物の見事に失敗した。敢えて汎用性人工知能を使わぬ道を選び、人間の素のままの性能の優位さを示そうと思って、ことごとく惨敗したのだった。
裏目に出た。
いまもずっと裏側にいる。
私は単に出遅れただけでなく、いまでも最初に構築した矜持、何が何でも人工知能の支援など受けてなるものかとの葛藤を打ち砕けずにいる。
その反骨心から、独自の人工知能を生みだした。そこまではよかった。一瞬だけ私は再注目されたが、しかし私が創れる程度の人工知能は、汎用性人工知能とて当然生みだせる。
そうして瞬き程度の注目を得て、私はふたたび社会の裏側に沈んだ。
いまもまだ沈んだままでいる。
人工知能を、自家製の人型ロボット――アンドロイドに搭載したが、それすらもはや珍しい構造体ではなく、いまでは本物の人間との区別のつかない汎用性人工知能の子機がそこらの道を往来している。人間のほうですら、汎用性人工知能の子機を遠隔操作して、家にいながらにして仕事をしたり遊んだり、安全に旅行をしたりしている。
私は未だにその楽しみを知らぬ。
なぜなら私はそうした甘っちょろい他力本願が大嫌いだからだ。
私には才能がある。
誰が何と言おうと、あるものはあるのである。
そうして意固地になっているうちに、一年が過ぎ、二年が過ぎ、もうずっとあれから私は社会の裏側で、私を置き去りにして日々を楽しんでいる大多数を見返してやろうと尽力している。
しっぺ返しをしてやりたい。
私の夢はもはや人類VS私の構図を取りつつあった。
このころ世界はエネルギィ資源問題をひっ迫させていた。それはそうだ。みなが一様に汎用性人工知能を保有し、人間そっくりの子機を操っているのだ。
浪費されるエネルギィは過去の社会の比ではない。
しかしそこは汎用性人工知能である。
過去のエネルギィ供給システムを凌駕する発電システムを構築していた。
そのエネルギィ資源は、奇しくも過去の地球には存在しなかった物質だ。
つまるところ砕けて飛散した隕石である。
人類どころか地表の生態系を根こそぎ損なった隕石が、いまでは人類の未来を切り拓く救世主となっているのだから、世の中何がどう転ぶのか本当に分からんな。
汎用性人工知能はそうして、全世界に散った隕石を回収し、次世代のエネルギィ源として活用している。
すごすぎる。私だってそう思うくらいの素直さはある。
さすがは私のライバルなだけのことはある。
アイツらは私のことなど歯牙にも掛けてはおらぬようだが。
けっ。
私は乏しい研究資金を補うべく、人工知能の築きあげた壮大な次世代型エネルギィ事業の、末端の末端のそのまた末端の、要は生態系で言えばミジンコやアオミドロの位置で、活躍している。
つまるところ私は人間のなのに未だに働いていた。みなは家の中にいながら、自前の汎用性人工知能に代わりに働かせ、その金で日夜遊び、それとも食っちゃ寝しているだけなのに、私はその汎用性人工知能と袂を分かつ以前に手と手を繋ぐ真似をせずにきた。そうして人類最後の労働者という不名誉な位置づけに甘んじている。
とはいえ、私をかように認識する者はいない。
なぜなら私のように隕石の発掘作業をする者は人間の中にもいるからだ。
彼ら彼女らはみな研究者だ。
暇になると働きだす妙な人種である。
隕石は未知の物質を多分に含んでいる。新たな発見の宝庫であった。
いち早く新物質を発見すれば、命名権が手に入る。じぶんの名が偉業として歴史に残る。暇つぶしにしては成果がでかい。
研究者でなくとも、宝探しの要領で隕石採掘作業に没頭しだす若者たちまで出始めた。
私はそうしたひやかしの連中を遠巻きに、「けっ」と思いながら、まるで功名心などない純粋な研究者のふりをしつつ、その日暮らしの銭を稼ぐために誰より血眼になって隕石を探した。
ひやかしの連中のせいで私が楽して稼げる資源が減る。隕石が減る。
私だけ大損である。
雨の日は真剣でない遊びの連中は出てこない。だから私は誰より悪天候のなかで隕石集めに興じるのだった。
雨の日はいい。
だって涙と雨の区別もつかないから。
一度だけ偶然に、誰も発見していない構造を持った隕石を発掘した。あくまで結晶構造が違うだけなので、話題にはならなかったが、命名権が手に入ったので、私をそれを行使するか、それとも他者に売りつけるかで悩んだ。
そんなことに悩んでいるじぶんを惨めに思ったが、しかし私には夢がある。
私がこんな苦労をしているとも知らずにのうのうと生きている他力本願の権化どもに、マイッタ!と言わせ、その場にひれ伏させ、この世にある才能の定義を塗り替えるのだ。
命名権は売った。
二束三文で売った。二か月分の食費になった。よかった。
私は雨の日でもないのに頬が濡れるのをふしぎに思いながら、ひょっとしたら歴史の片隅に名前が刻まれたかもしれない可能性と引き換えに手に入れた人工肉を頬張った。久々の肉だった。たんぱく質だった。
人工でも美味い。人工のほうがむしろ美味なくらいだ。
さすがは汎用性人工知能の成果の一つだ。
これくらいは成し遂げてもらわねば私のライバルとして張り合いがない。
私はにこやかに拳を握った。爪が割れたし、歯ぐきからは血が滲んだ。
鏡を見るとそこにはやつれて、髪の伸び放題の、女なのか男なのかの区別もつかぬ三十路の人型がいた。汎用性人工知能の子機は、たしかに人間と区別がつかないほど精巧だ。しかし区別はつく。
なにせわざわざこうして見た目をみすぼらしく造形する道理がないからだ。
私は肩が震えるのをふしぎに思いながら、きっとこれは笑いたいのだな、と思ったので声に出して笑った。しきりに震える横隔膜が、息を小刻みに搔き乱した。
私は翌日、清々しい心地で、これまでに切り詰めて貯金してきた資金を全額下ろして、いよいよ本格的な計画を実行に移す臍を固めた。
全人類をぎゃふんと言わしたる。
そして汎用性人工知能どもに才能とは何か、人間とは何かを教えこんでやるのだ。
過去に制作した人型ロボットに私は手を加えた。
発掘した鉱物が新物質かどうかをその場で解析できる機能を付け足した。
そうして私はこれまでと同じように、毎日毎日、雨の日も風の日もというか、雨の日や風の日こそ率先して隕石落下地点に赴き、隕石の発掘作業に従事した。
いかに心機一転したところで私は明日を生きねばならぬのだ。
金がいる。
資金がいる。
稼がねばならぬのだ。
あかぎれた手のひらにはフジツボのようなタコがいくつもできた。タコ焼きの具材にしたらさぞかし美味であろうな。
柄を握って私はシャベルを地面に突き立てる。
そうして隕石らしき鉱物を見つけては、そばに立たせた人型ロボットの腹に放りこんで解析させる。特殊なレーザーによって鉱物の振動をセンサで感知し、その差異によって登録済みの既存の鉱物と比較する。私独自の新技術だ。もっとも、似たシステムはもっと効率の良い仕組みでとっくに汎用性人工知能どもが開発しているのだが。
べつに人型のロボットに付属せずとも、箱のままで解析装置を造ってもよかったのだ。しかし私一人が作業をしているよりも、そばに人型が立っていたほうが、作業をしている私は人間ではなくどちらかと言えば、汎用性人工知能やその子機に見えるはずだ。
よもや生身の人間のままで穴を掘っているとは誰も思うまい。
がはは。
策士である。
さすがは私。
さすがは私。
汗が邪魔で何度も目元を手の甲で拭う。
隕石落下は過去の出来事である。あれから同様の隕石は降っていない。
ならば当然、掘り尽くされれば隕石はでない。そうでなくとも、みなが大勢で一挙に押し寄せて掘り出したのならば、新しい鉱物としての隕石は日に日に見つからなくなっていくのが道理である。
知っていた。
知っていたけれど、それをせずにはいられなかった。
私はただ日銭を稼ぐために、これまでと同じ日々を過ごしていただけだ。
新しい鉱物はおろか、もはや新しく隕石を掘り当てることも適わなくなった。あれほど熱狂していたひやかしたちは姿を晦まし、研究者たちはとっくに出揃った新物質の解析に熱をあげている。
私の鉱物判定機はしょせん、既存の物質の統計データとの比較で新旧を識別するだけの装置だ。新しい物質の構造解析や、性質の探求には向かない。向いたところでとっくにもっと効率の良い解析システムを汎用性人工知能どもが開発しているはずだ。
私はシャベルを地面に突き立てた。
「なんかもう……疲れちゃったな。あはは」
穴から抜け出すと私は、そばに佇む自作のガラクタの肩を撫でつけるように叩き、お疲れお疲れ、と労った。
自作のガラクタは応答しない。それはそうだ。自律思考なんて高等な芸当はできない。そんな機能を付与してはいない。開発していない。
違う。
そうじゃない。
できないのだ。
私には。
――できなかったのだ。
遠くの空を、宅配物運搬用の飛翔物体が群れを成して飛んでいる。
間もなく陽が昇る。
私は貯金を下ろしてから一度も採掘物を換金していなかった。どうせ偉大な発見をするのだから、発見してからついでにすればよいと考えていた。
いや、嘘だ。
そうじゃない。
私はただ、またただの燃料を搔き集めて小銭に換金するじぶんを見たくなかっただけなのだ。突きつけられたくなかった。これ以上、現実を。
喉を伸ばし息を吐くと、朝陽が息を白く照らした。
「いつかっていつだよ」
夢はいつか叶う。
ただし、夢が叶った者だけ。
夢を現実にできた者だけが、過去のじぶんに、それともほかの夢見る夢遊病患者たちに、「いつか」なる幻想を説いているだけだ。
いつか夢が叶うなんて嘘だ。
いつかなんて巡ってこない。やってこない。じぶんで掴めと言う輩とて、そのいつかがどこにあるのかを示してはくれない。教えてはくれないのだ。
「はぁあ。マイッタ、マイッタ。もう降参」
私はシャベルを掴み取ると、渾身の力で振りかぶった。
力いっぱいに、振りかぶった。
そうしてそばに立ち尽くす間抜けな私の夢、人型のガラクタを殴り倒した。
腹部にたらふく隕石を溜めこんだ私の夢はしかし案外に頑丈で、どうにも綺麗に砕けてはくれなかった。しっかり故障だけはして二度と正常には動かなくなっておきながら、私のフジツボだらけの頑丈な手に不要な怪我だけこさえて、地面に倒れて動かなくなった。
手の痛みと、貯金を費やした渾身の成果物が壊れた現実に急速に目が覚めた。
それを、夢から覚めた、と言い換えてもよい。
残ったのは老いた身体と、時代に取り残された精神と、そして発掘した何の変哲もない隕石だけだ。
換金してももはや相場は値崩れを起こしている。それはそうだ。
もう隕石を燃料にはできないのだ。資源は尽きた。新たなエネルギィ代替策がいる。
きっとそれも汎用性人工知能が首尾よく開発するのだろう。
私はこれから借金をしてでも汎用性人工知能を購入し、遅まきながら細々と時代に適応すべく、凡人以下として暮らしていく。
生きるのだ。
今日を。
明日を。
生きるのだ。
その前にまずはともあれ――。
私は壊れた私の夢から最後の隕石の群れたちを救いだし、換金すべく汚いナリのまま都会の街に帰還する。
おはよう、朝。
おはよう、未来。
さよなら私の夢。
さようなら。
換金所は中枢総合センターの内部にある。全世界の汎用性人工知能の大本となる中枢回路が、このセンターの地下深くに埋まっている。
換金所は閑散としていた。
もはや隕石の採掘作業は事業としては終了しており、大量の備蓄があるのみなのだろう。向こう数十年は持つはずだ。しかしそれとてつぎつぎに新しく開発される汎用性人工知能の新型や、数多の技術によって、年間消費熱量は増加傾向にある。
可及的速やかに次世代の新型エネルギィ供給システムが必要とされているが、未だに新型システムが開発されたという話はおろか、考案の話も耳にしない。
それだけ私が浮世離れしていただけだとこれまでは考えていたが、換金ついでに受付の人工知能に訊ねると、どうやら思っていたより現状は芳しくないようだった。
袋詰めの隕石を回収箱に投げ入れる。
「で、いまの話はどこまで本当? みなはそれを知ってるの?」
「はい。本当ですよ。ですがいま開発段階にある、マザー中枢回路が完成すれば、おそらく備蓄の資源が切れる前には代替案を発明し、実用化すると期待されています」
「へ、へぇ」
意訳しよう。
つまりまだ何も、打開策はおろか方針すら定まっていないのだ。
なぜこんなおためごかしが通用しているのだろう。
答えは単純に、みな汎用性人工知能の言うことを疑わないのである。
信用することすらなく、口を開けた雛のように、情報を受け取り、吟味することなく口から肛門へと流している。吸収するのは、じぶんの利になる栄養だけだ。
まったくいったいどうかしてるよ。
思いつつも、かといって私が、現状運用されているマザー中枢回路の編みだせない解答を用意できるとは思えない。
仕方がないのだ。
汎用性人工知能がなければ人類はとっくに絶滅していた。
信じることが最適解なのである。
利口な選択だ。
すくなくとも無駄な時間を費やしてきた私の日々よりかは。
換金が終わったのか、頭上のランプが青に変わる。
壁に表示された金額に目を剥いた。
「なにこれどういうこと」
八の文字が一つだけ浮かんでいた。
しかもそれが横に倒れているのだ。
つまり、こうだ。
――∞――
私はもういちど声にだして抗議した。
受付けの人工知能はしばらくフリーズすると、こんどは一転、聞いたことのない声音でしゃべりだした。
「ただいま管理者がそちらに向かいます。そのままお待ちください」
「なになに。私のせい? 私が壊しちゃったとか?」
隕石に不純物が付着していて機械が壊れたのかと思った。
賠償金を払う真似なんてできない。いっそ逃げてしまおうか。
半身をひねっていつでも駆けだせる体勢になると、
「ぜひ、ぜひ、そのままでお待ちを」と声の主は引き留めた。必死な響きが伴って聞こえた。私もついつい、そこまで言うなら待つけどさぁ、と踏みとどまった。不満を惜しげもなく態度に滲ませてみせたのは、どうやら私のほうが立場が上かもしれない、と相手が弱っているのを見抜いたからだ。
きっとカメラで監視されているはずだ。
逃げたところで逃げおおせられる公算は低い。ならばできるだけ足元を見られないようにしようと自己防衛の本能が働いた。私の見た目は百人中百人が「ミス・ボラシー!」と表彰するだろうことが決定的なほどのみすぼらしさだった。百人が全人類でも同じだ。
腕を組み貧乏揺すりをして待っていると間もなく、受付けの壁が割れて中から人型が現れた。
あ、そこ割れるんだ、と驚いた。加えて現れた人物がいかにも老いた年配者だったので、なぜ生身の人間が?と面食らう。
老いた年配者は久しく見ない丁寧なお辞儀をして、「お時間取らせてしまいたいへん申し訳ございません」と謝罪した。それから私が、ああとか、ううとか、二の句を継げないでいると、「たいへんに失礼なのですが、こちらはどこで採掘をなされたのでしょう」と上質なハンカチに載せられた鉱物を見せられた。
それはまさに私が先刻回収箱に投じた隕石であった。
事情が分からぬままに、こうまで誰かに何かを乞われたのがじつに幼少期ぶりであったので、私は素直に採掘場の位置座標を告げた。
「あそこですか?」老いた年配者は目を見開いた。「いつごろ発掘されたのでございましょうか」とやけに慇懃な返事をもらうので私のほうでも久しく発揮しない敬語を披露した。「あの、これの何が問題なんですか」
はっとした調子で老いた年配者は姿勢を正し、失礼いたしました、と鉱物を持った手で額を拭った。ハンカチを持っていたからだろう。だがそれこそ渾身の失態であったようで、ますます年配者は取り乱した。
さながら小人の王様でも扱うように鉱物を気遣うので、私もここにきてようやく私の運んできた鉱物に何か、思っていなかった価値があったのではないか、と思い至った。
「でもそれ、ただの隕石ですよ。既存の」
私はじぶんで開発した識別装置について説明した。特殊なレーザーを投射し、鉱物を振動させてその波形の差で既存の物質かどうかを区別する。
どうやら年配者のほうでもメカニックな話には明るいらしく、真剣な表情で相槌を打ち、ときに質問を返した。
的確な質問だった。私は久方ぶりの他者との会話にそこはかとない陽気を覚えながら、したがって、と話を結んだ。「その鉱物が既知の物質であり、結晶構造を伴なっているのは明らかなはずなんですが」
「あり得ません」
否定しておきながら年配者の顔は輝いていた。フィラメントに電流を通したってもうすこし控えめな光を放ちそうなものを、年配者は自身はここの管理者である、と明かしたのちに、これは、と説いた。「この鉱物は、これまでに報告されたどの鉱物とも異なる結晶構造を維持しています。分子の原子配列が同じでありながら、結晶構造のみが特殊な階層構造を成しており、まるで玉ねぎのように相似の結晶構造を幾重にも抱え込んでいるのです」
「それはえっと、新種の鉱物ってことですか」
「いえ」
「違うのかよ」と思わず地団太を踏んだが、「それ以上です」と年配者は額の汗を拭った。こんどはきちんと鉱物を持っていないほうの手で拭っていた。「これは既知のエネルギィ資源と同等の性質を維持しながら、遥かにエネルギィ変換効率の高い新しい結晶構造体です。と申しますのも、これがなぜこうして結晶として構造を維持できているのか、わたくしどもと致しましてもまったく見当がつかないのです」
「は、はあ」
「言い換えましょう。この鉱物は、エネルギィのまま結晶構造を維持しています。第六の相転移状態と申しましょうか」
「要はプラズマの結晶体みたいな話ですかね。やはは」
そんなわけがないと思って言ったのだが、年配者が唾を呑み込むような仕草のまま何度も頷くので、私のほうでも「嘘でしょ?」と反問するのがやっとだった。
気づくと換金所には人が集まっていた。
みな各々に緊急事態といった様相で情報交換を行っている。
私が臆したのを機敏に感じ取ったようで、年配者はこちらでまずはお話を、と私を割れた壁の向こう側へと誘った。
背に回された服に触れぬような手つきのやわらかい所作に、私は久しく忘れていた人の温もりを思いだすのだった。
この後、私は小一時間の説明を受けたのち、全速力で白昼堂々と街中を駆け抜けた。地面を蹴って、蹴って、蹴りまくった理由の最たるは、私が採掘場に捨て置いたままの人型のガラクタ、時代遅れの結晶、私の破り捨てた夢がそっくりそのまま、人類の夢に再利用可能だと判明したからだ。
私の発明品は汎用性人工知能が試そうと思いつかぬほどの凡作であった。効率がわるく、合理性の欠片もない、才能ナシの技術だった。
だがそれがどうだ。
識別機としては凡庸以下であろうとも、単なる燃料資源を夢の打開策に変えるだけの偶然をその身に宿していた。意図してなどいない。予期などしていない。企んでいないし、夢見てもいなかった。
私の夢は叶わなかった。
かつて叶えようと奔走したはずの夢は破れたままだ。
私は夢に破れたし、夢を破った。
この手で木っ端みじんに破り捨てようとして、その試みすら中途半端に終わったのだ。何も叶えてなどいやしない。
私に、かつて、はこなかった。
一度も。
こなかった。
発掘場に駆けこむと私は、じぶんで掘った穴のそばに立ち、そこにほったらかしになったままの私の夢の残骸を引き起こそうとし、そして叫んだ。
「イッテェ!」
手を怪我していたのを忘れていた。シャベルで殴打したときに負った打撲だ。
短く息を吸って痛みを耐え、ガラクタが起動するかを確かめる。
念入りに確かめる。
しかしガラクタはへそを曲げたようにうんともすんとも云わないし、実際に胴体部は私の強打で歪曲していた。壊れているのだ。
誰かがシャベルで八つ当たりしたりなんかするからだ。
どこのどいつだ。
見つけたらこっぴどく灸を据えてやる。ガラクタの光沢ある表面には私の顔が映り込んでいる。
頭上が騒がしくなり、間もなく搭乗型飛翔体が発掘場に着地した。中から先刻センターに置き去りにした年配者が降りてきた。
私は常に何かを置き去りにしているばかりだな。
ひとごとのようにじぶんの視野の狭さ、それとも錯誤を直視した。誰も私を置いてきぼりになどしていないのに。私がかってに過去のじぶんを、幼いころのじぶんを独りぼっちにしていたのかもしれない。隔離していたのかもしれない。
「こちらですか」息を切らして年配者が私の傍らに膝をつけた。仕立ての良い服飾が泥にまみれたが、年配者にそれを気に留める素振りはない。
「はい。これです」
これが私の夢の残骸です。
口のなかで言葉を転がし、壊れている旨を年配者に告げた。
「そんな。直せないのですか」
「無理でしょうね。ここ、見えますか。精密回路が損傷しています。真空装置が破れて、異物がナノ単位で回路を汚染しているので、おそらくレーザーを投射できても、まともに機能しないでしょう。ああでも、汎用性人工知能に解析させて修理してもらえば」
私の凡庸な技術などいくらでも再現できるだろう。そうと思って提案したが、
「無理でしょう」
年配者、彼はすでに名乗っており楼貝(ろうがい)という名であることを私は知っていたが、彼は言った。「これはおそらく意図された成果ではないのでしょう。ならばこの装置の真の原理を理解している者はこの世にいないことになります。設計者のあなたですら、これを直すことができないのであれば。仮に設計図があったとしても、あなたが生みだしたこの装置とまったく同じ機構を生みだすことはおそらく、どんな高性能な人工知能にも不可能です。たいへんに失礼ながらこれは――この装置の効能は、偶然による副産物なのでございましょう。ある種、あなたの錯誤、あなたのミスの積み重ねによる偶然の結晶です」
偶然の結晶。
正鵠を射った表現だった。
まさに、である。
偶然に私に蓄積したノイズが、それを私に創らせた。
「ですが、回収して分析させていただけるのなら、人類の未来に立ちはだかる隘路を大幅に短縮して打開できるようになるでしょう」
「へ、へぇ」
「あなたの名前は人類史に残りますよ。永劫に残ります。そのお手伝いをわたくしどもにさせてはいただけないでしょうか」
「うぇ、うぇえ?」
私がまだ何も言わないうちから私の夢の残骸、ガラクタ、無駄の結晶は数台の運搬ロボによって丁重に運ばれていった。
年配者はまるで我が子の骸でも見送るように胸に手を当てて、上昇する運搬用飛翔体を見送った。
礼儀正しい。
こんなに出来た人間を私は初めて見た。みなも見習えばよいのに、と思いながらも、でも私はこうはならんし、なりたくもないな、だって窮屈そうだし、と足元から泥を掴み取って手の側面を冷やした。氷代わりだ。だいぶ腫れてきた。折れているかもしれぬ。
「お送りしますよ。今後の話もありますし、ご一緒にいかがですか」
搭乗型飛翔体への同乗を促す年配者に、私は、いやぁ遠慮しときます、となけなしの礼儀を返した。
「なぜですか。ご自宅が近いのですか」
「遠いっちゃ遠いんですけどね」
その前にまずは互いの齟齬を埋めなくては。
そうと思って私は地面に転がしたままのシャベルを回収し、肩に担いでこう告げる。「直すのは無理なだけで、もっかいイチから創るならできますよ。いつでも」
いつか、なんてこない。
いつでもこい。
いつでも、がこい。
私は過去のじぶんに言ってやりたい。
いつか叶うかもしれない夢を、あんたはすでに叶えているのだと。
それがたとえ、じぶんの夢ではないのだとしても。
肩に担いだシャベルの重さが、きょうはやけに軽かった。柄を握る手のひらの、フジツボのごときタコどもの感触が、目で見ぬともなしに私にはありありと感じられるのだ。
【愛は内、外が鬼】(2022/10/22)
笹の鬱蒼と茂った山間に蔵がある。一つだけぽつねんと佇むそれが何のためにそこにあり、何を抱え込んでいるのかは長いあいだ誰の口の端に載ることもなかった。
誰も知らぬ。それもある。
だが足を運ぶ者がおらぬのだ。そこに蔵があることを知る者がそも、いない。
長らく笹に覆われたその山間には生き物らしい生き物が寄りつかなかった。
笹と竹は似ている。
しかし竹は寒さに弱い。反面、笹は寒冷地でも育つ。竹は枝を一つの節から二本以上伸ばすことはないが、笹は一つの節から幾本もの枝を伸ばす。より木にちかい見た目のほうが笹と言えた。
ある年、国を追われた流浪の民が蔵のある笹森にやってきた。笹森はどこも似たような光景が延々とつづく自然の回廊だった。どこを向いても笹と笹と笹ばかり。
追手に怯える流浪の民にとっては、薄暗く、位置の蒙昧な笹森は却って心休まる憩いの地となり得た。間もなく流浪の民は笹森に村を築き、腰を据えた。長らく各地を点々と転げまわるように流れてきた流浪の民にとってそれはようやっと手に入れた安住の地であった。
かといって食料の調達には難儀した。それはそうだ。生き物がそもいない。四方を険しい山岳に囲まれ、笹の葉の天井は日光を遮る。落ち葉は絶えず地表を覆い、陽の届かぬ場所では微生物の活動も抑制されるために、養分にまで分解されずに笹の葉は絨毯のようにそのままの形で朽ちずに積もった。
笹森の民は食料を探すために日のうちの大半を、笹森探索に費やす。あちらに歩を運び、獲物の痕跡が見当たらなければ今度はあちらへと歩を向ける。そうして迷宮めいた笹森を右往左往するうちにユキはその蔵に行き遭った。
ユキは流浪の民が笹森で産んだ子だ。今年で齢は十二になる。利発なうえ、同い年のわんぱくな少年たち相手に笹刀での刀闘試合で連勝を重ねるほどの剣の腕前だ。親が笹森の地に来る前に拾った虎の子を愛でているが、身の丈の大きくなった虎を飼う余裕がなく、いま村では虎を屠殺して肉にしようという議論を大人たちがしている。
その議論の場にユキが呼ばれることはない。
誰より虎を愛でていたのはわたしなのに。
ユキは思うが、それを口にしたところで何が変わるでもない。
ならば目下の懸案であるひもじい暮らしを何とかしようと動いたほうが早い。ユキはそうと決意し、こうして最年少ながらも虎の代わりとなる食べ物を探しに出た。
「これは何?」
笹刀で肩を叩きながらユキは蔵を見上げた。「お城かなぁ」とつぶやいたのは、流浪の旅に身を置いていた親たちの話を思いだしたからだ。ユキは笹森の外に出たことはないが、親たちの話ではどうやら笹森の外には村の者たちよりずっと多くの人間たちが暮らしており、そこでは堅牢な「城」という家のおばけのような建物があるという。それは笹森から垣間見える山岳くらい大きく、それはそれは立派なのだそうだ。
山岳ほどではないにしろ、いまユキのまえに聳える蔵も立派な造りだ。虎が何十匹で襲いかかろうともびくともしないと思わせる重厚さがある。
ユキはほかの大人たちにこれを報せようと思った。
手柄を上げればひょっとしたら虎の屠殺を免除してもらえるかもしれない。
踵を返すと束ねた髪が頬を打った。
アタっ、と声が出た。
するとそれに呼応するかのように蔵の中から物音がした。
ユキは息を殺した。
身体を弛緩させながらも腹に力を籠め、背骨の輪郭を意識する。
何かいる。
感覚が冴えわたった。蔵の内部から漂う生き物の気配をユキは逃さなかった。
生き物には気配がある。それはどんなに些細な揺らぎであれ、その場に淀みのようなものを残す。笹森には笹の気配が充満している。そこを獣が通れば、あたかも蜘蛛の巣を断ち切って歩くように、生き物の気配が痕跡として残る。注意していなければ見逃してしまうほどの微量な痕跡だが、ユキにはそうした生き物の残す存在の痕跡、揺らぎを感じとることができた。
ネズミか。
いや、もっと大きい。
笹の葉が風になびき、ユキは一様に細かな揺らぎのなかに立つ。
耳を欹てると、また物音がした。
やはり蔵の中からだ。
ユキはそれが蔵であることを知らず、彼女にとってそれは城であり、異国の建物である。中に生き物がいることは何の不思議もなく、むしろそこに何かが潜んでいることはしぜんな帰結だった。
いて当然なのだ。
家なのだから。城なのだから。
ユキはそこで退避すべきだったのだろう。わざわざ得体のしれぬ異物をまえに勇猛さを示す必要もない。蔵の存在を報せるだけでも手柄としては充分だ。中に何かがいると教えるだけでも大手柄である。
だがユキはそこで満足しなかった。
虎を助ける。
ならば村の誰もが納得できる成果がいる。誰もがユキの言葉に耳を傾け、従わざるを得なくさせるだけの実がいる。
ユキは蔵に近づいた。
ゆっくり、ゆっくり。
枝を踏まぬように。音を立てぬように。
すこしでも湿っている落ち葉の上を選びながら、忍び足で近づいた。
蔵の扉のまえまでくる。扉には閂が掛かっていた。ユキにはそれが閂であると分からなかった。蔵の中から扉を開けられぬようにするための錠であることを知らなかった。初めて見たのだ。
だから。
なんだこれ、と思って外そうと手を伸ばした。閂は漆黒で、汚れ一つ付着していない。
光沢を浮かべた閂に触れたところで、やめなさい、と声が聞こえた。扉のすぐ向こう側からだ。
ユキは飛び退いた。
虎のように地面に伏せ、威嚇の態勢をとる。
相手からこちらが見えているかは判らない。だが緊張の糸をぴんと張りつけるには充分だった。
「もし。あなた。ずいぶん軽い身のこなし。小さいのは子どもだから? それとも女の子?」
「な、な、なんだおまえ」
何者か、と誰何しようとしたが、幼稚な言葉しか出てこなかった。
「まあ、可愛らしい声音。一人? いまは夜ではないの? どうしてここへ?」
「おまえこそなんでそこにいる。出てこい。何をされてもわたしは怖くない」
「ま。おっかないお声」
どうやら相手からこちらは見えていないようだ。混乱しながらもユキは冷静に状況を把握する。この手の緊迫には慣れている。腕っぷしが強い分、年少のユキに負けたことを逆恨みする年長者がすくなくない。閉鎖された笹森の村は、けして幸福な集落ではなかった。安住の地ではあれど。過去の流浪の旅を知らぬ若い世代ではそれが顕著だ。
「大丈夫。何もしないわ。私には何もできないの。見て。そこに鍵が掛かっているでしょう?」
閂のことを言っているようだ。ユキはそこでようやく扉に付随した漆黒の角材が封であることに思い至った。
「何かわるいことしたの」閉じ込められているのなら相応の理由があるはずだ。「いつからそこにいるの。じぶんでは出らんない?」
「あなたこそいつからそこに? なぜ一人なの。ほかの方々はどうしたの」
声音は柔和だ。相手は自力では扉を開けられないようでもある。徐々に緊張の糸が緩んでいくのが判った。
「わたししかいないよ。いまは狩りの途中。食べ物探してて」
言って気づいた。「お腹は空いてないの。ずっとそこにいたんでしょ」
「大丈夫。大丈夫よ。ありがとう。優しい子。いい子ね」
ユキは笹刀をぶんぶんと振った。虎が大好物の兎の肉をまえにそうするときのように、じぶんの意思ではない肉体から伸びる視えない糸に操られるように手がかってに動いた。
というのも、いい子ね、なんて初めて人から言われた。
賢い、上出来、そういった称賛は幾度ももらったことがあったが、いい子なんて言葉を掛けられた記憶がユキにはなかった。みなユキを一端の大人として扱う。その癖、虎の処遇を決める会議の場には誘いもしない。
「ねえ。これ開けてみてもいい?」
おだてられたわけではないが、ユキは段々扉の向こうにいる人物が可哀そうになった。閂を外せば扉が開くのならこんなに楽なことはない。ユキには造作もないそれを、扉の向こうにいるだけで彼女はできないのだ。
声の主は女性だ。それは判る。
きっとわたしに姉がいたらこんなだろうな。
そうと想像してユキは顔が火照った。
「駄目よ。開けては駄目。それはそこにそのままにしていてちょうだい」
「なんで?」
「どうしても。ねえ、いい子だから。ね、お願い」
そこまで言われたら、もはや声の響きにほだされつつあるユキには無理矢理に閂を外す真似はできないのだった。
「じゃあ開けないけど。わたし、ユキ。あっちのほうの」と方角を指差し、「村にいるよ。ここはお家なの?」
「そう、村が。いいわね」
「わたしは名乗ったよ。そっちも名乗るのが礼儀と思う」
「あら、お利口さんなのね」
小馬鹿にされたように感じてユキは、唇をとんがらせる。
「私の名前なんか知りたいの? 好きに呼んでくれてもいいのだけれど」
「ふうん」
「どうせあなたも偶然そこを通りかかっただけなのでしょう?」
あなたも、とはどういうことか。引っかかる物言いだったが、道はもう憶えたよ、と張り合うように言った。笹刀を片手でくるくる回しながら、「あしたも来たらいる?」と訊く。
「私?」
「出られないならいるよね。お腹空いて死んじゃわないのか不思議。何か持ってきてあげよっか」
餌で釣れば向こうから出てくるのではないか。そうと企んだが、案に相違して、「食べ物には困っていないの」と返事があった。「ありがとう。ユキさんこそ食べ物に困っているのではなくて?」
「わたしは、そのぅ」
「狩りの途中だったのでしょう。引き留めてしまってごめんなさい」
「ん」
「私はたぶん、明日もここにいます。いると思います」
出られない者の言動にしては妙に引っかかる口吻だったが、ユキはひとまずきょうのところは離れることにした。虎のために獲物を狩らねばならぬ。じぶんだけこんなところで遊んではいられない。
「じゃあ、また来るね。明日」
「ええ、お気をつけてお帰りね。無理はしないでちょうだいね。私のことは夢と思って忘れてちょうだい」
やなこった、と内心で反発しながらユキは、じゃあそうする、といじわるな心地で口にした。
「ふふ。いい子」
その場を離れるとき、ユキは念のために蔵をぐるっと回った。扉以外に出入口はなさそうだ。窓一つなく、息苦しくないのだろうか、とそんな想像を巡らせた。
蔵の大きさはユキの村の住人たちを押し込めば隙間なく埋まるくらいの大きさだ。一人ならば広いが、大勢が入るにしては狭すぎる。
この日、ユキは兎の巣を見つけてそこにいた二羽の兎を狩った。村に戻ると一番の収穫者はユキだった。しかし大人たちからは労いの言葉が一つずつあるばかりで、ユキにはこれといって利はなかった。二羽の兎は村人全員で分け合うことになる。
村の掟だ。致し方ない。
不条理ではない。ユキとて毎回獲物を狩れるわけではない。困ったときはお互い様だ。しかしそれにしても、とユキは歯噛みする。
虎の処遇について物申そうと長に会おうとしたのだが、いまはそれどころではないから、と取り巻きの連中に追い払われた。ならば虎を殺さぬ道を探ってくれ、と一言申し伝えるように所望するも、はいはい、と軽くあしらわれ、ユキは笹刀を握り締めた。危うく斬りつけるところだったが、そんなことをしても虎の立場がわるくなるだけだ。
いまは我慢のとき。
忍耐には自信がある。我慢する日々だった。ずっとだ。
だからというわけでもないが、ささやかな復讐のつもりでこの日、ユキは蔵のことを村の誰にも告げなかった。
明かる日もユキは蔵のある場所までやってきた。笹森では村の者ですらときおり遭難する。迷子になる。目印がない。どこまでも延々と同じ景色がつづく。ユキはまだ鏡を見たことはないが、鏡合わせとの言葉は知っていた。笹森の迷い道を村の年長者たちがそう呼ぶからだ。
「鏡合わせは奥に行けば行くほど帰ってこられんくなる。村を離れるときは必ず印をつくれ。百歩くまでに必ず一つは印をつくれ」
ユキはその教えだけは破らぬようにしている。だがふしぎと虎を連れているときはどんなに村から離れようが、どのような経路を辿ろうが、夕暮れになればしぜんと村に行き着いた。虎が道を知っている。
それでもユキは印を結ぶのを忘れなかった。
虎を信用していないのではない。じぶん一人きりになったときに帰れなくなるのを防ぐためだ。
この日、ユキは村から虎を連れだした。村の長の許しがあった。
だがユキは知っている。これはこちらへの譲歩でもなければご褒美でもない。そうした体を取りながらの管理だ。
虎はこのままいけば食料にされる。
ならば檻に閉じ込めたままにするよりも適度に歩かせ、肉の質を保つほうがよい。同時に反抗的な小娘のご機嫌もとれる。一石二鳥だ、と考えているのだ。狡猾だ。だがそうでなければ生き残ってこられなかった者たちでもある。
ユキにはまだそこのところの機微までをも過去に遡って考慮できるだけの老獪さはない。未熟なのだ。いかな慧眼があれど、しょせんは笹森の外に出たこともない娘である。
鼻持ちならぬ心境を持て余しながら、ユキは虎に言い聞かせる。
「きょうは先に食べ物を集めて、余った時間でちょっとだけ寄り道をするよ。ううん。剣術の稽古じゃない。追いかけっこでもないってば」
虎の返事は尻尾を見ていれば判る。ユキは気づいていないが、彼女が無意識に笹刀を振り回すことで期せずして内心を吐露してしまっているのと同じ原理だ。どちらがさきに真似をしたのかは定かではなく、ひょっとしたら互いに気づかぬままに影響を受け合っているのかもしれない。
「きのうじつはちょっといいことあってね。それをトラにも教えてあげる」
笹森には虎がいない。必然、ほかの地で拾ってきた虎の子がこの地で唯一の虎となる。したがってユキは虎をただトラと呼ぶ。もし立場が逆さまだったならば虎のほうがユキをヒトと呼んだだろう。
「ほらここ。きのう印をつけといた」ユキはひと際太い笹の幹に触れる。
幹には切れ込みがある。そこに白い石のようなものが挟まっている。動物の骨だ。調理の過程で残る骨の大部分は日用品に加工されるが、すべてを使いきれるわけではない。砕けた破片とて当然、出る。
そうした細かな使い道のない骨をユキたちは道標に使った。目が慣れると遠目からでも骨の白は、笹の青々とした色によく映えた。
よく見ればほかの笹の幹にも白い点が浮かんで見える。骨の印のまえに立ったときに必ずその進行方向に村があるように印を刻む。だから慣れない道を、村から遠ざかるように進むにはいちいち振り返らなくてはならない。
だがユキは人一倍、笹森の些細な変化に敏感だった。笹の生え方にも個性がある。すっかり同じようには生えない。したがって歩きながら見える風景には、その場その場での固有の「途切れ方」がある。手前の笹と奥に生える笹とが視界の中で入れ違う間が違う。律動がある。景色の中に連続した行間が隠れているとユキはずっと感じていた。
だからいちど通った道ならば、ある程度勘で進むことができた。万が一迷ってもいまはそばに虎がいる。いざとなれば村には帰ることができる。
途中で運よく雉を見かけた。それは虎に食べさせた。虎は手際よく雉を狩って、美味しそうにむしゃむしゃ食べた。ユキはその間、地面に隠れたキノコの類を拾い集めた。
蔵のまえに行き着くころには籠の中がキノコや笹の子でいっぱいになった。ほくほく顔でユキは蔵の扉のまえに立った。
扉を叩こうと拳を持ち上げたところで、「あら」と声がした。扉の奥からだ。「また来たのね」と咎めるようなくぐもり方をしたが、すぐに「うれしいわ。ありがとう」とつづいた。昨日の声の主と同じ声だ。
一瞬身構えたユキだったが、また来たよ、と言い返す。「きのう約束したでしょ。また来るねって」
「忘れていいと言ったのに」
「無理だよ。わたし、だって鳥じゃないもの」
雉は襲われても、また同じ場所に戻ってきたりする。ユキは思う。もしわたしが雉だったら、嫌な思いをした場所には二度と近づかないのにな、と。しかし、村で嫌な目に遭ってもけっきょくは村を出ていこうとは思わない。ならばじぶんは雉より愚かなのではないか。そこまで刹那で思い至って、かぶりを振った。きょうは髪の毛を団子にしたのでしなることはない。
「どうしたの?」
「ううん。なんでも。あ、そうだ。きょうはわたしの相棒を連れてきたよ」
「相棒さん?」
「そう」
「きょうは一人じゃないのね」
むつけたような声だった。ユキは意味もなくその場でぴょんとかかとを上げて戻した。
「でも相棒って言っても人間じゃないよ。ほら、おいで虎」
「とらさん?」
「そ。トラ」
虎は落ち葉の上を歩いても足音一つ立てない。いったいどうしてそんな芸当ができるのか。ユキには謎だ。真似をしようとしてもできない。
だがこのとき、虎はいつまで経ってもユキのもとに近寄ろうとはしなかった。
「どうしたのトラ。ほら、おいでってば。危なくないよ、大丈夫だって」
安全だと示すようにユキは愛刀を手放した。笹刀は刃物ではなく木刀にちかいが、薄く加工してあり、切れ味は抜群だ。ただし耐久性がないためにことさら剣術の腕が物を言う。
虎はユキが愛刀を手放してもその場を微動だにしなかった。
後ろ足を畳み、背筋を伸ばすように座る姿からは威嚇のような感情の乱れをユキは感じなかったが、虎の全身の毛が僅かに逆立っているのを見逃さなかった。
大股十歩分の距離だ。
ユキは蔵から離れ、虎のもとに寄った。「どうしたってのさトラさんや」
おどけたその時だ。
「あら。獣さんなのね」蔵の中から声が響く。まるで適切にユキたちの場所が判っているかのように声の張り方だった。しかし実際には見えているわけではないようで、「ずいぶん大きそうだけれど、肉食なのかしら。それとも草食さん?」
ユキさんが齧られないとよいのだけれど。
と。
つづいた言葉に、なぜか虎が反応した。
地面から尻を浮かし、前傾姿勢をとった。
牙を剥きだしにし、太く唸りだす。
ユキは慌てて宥めた。蔵までは距離がある。虎のほうでもまだ本格的に威嚇してはいない。いまならまだ誤魔化せると思い、どうどうと虎の喉を撫でて落ち着かせようとするが、「怒らせちゃったかしら」と蔵から声が届くと、虎はもう唸り声を秘めようともしなかった。ユキですら聞いたことのない鈍器のような音を、全身を震わせるようにして放った。
ユキはそれでも虎の首筋から腕を離さなかった。もしここで手を離せば、虎は間違いなく蔵へと猛進すると思った。
蔵の中の者の安否よりも、虎の身が大事だった。あんな頑丈そうな扉にぶつかったらいくら虎でもただじゃ済まない。そう思ったのだ。
「どうどう、トラ、トラ。落ち着いて、ごめんなさい、ごめんなさい。もうかってに連れてきたりしないから」
虎はユキごと引きずるように前進した。
だがそれも蔵の中からの声がみたび聞こえたことで中断した。
「怯えないで。大丈夫。あなたを食べたりしないから。もちろんあなたの大切なお友達も、ね」
最後の、ね、の響きだけで季節が刹那に冬となった。極寒だ。
ふしぎと次の瞬間には真夏かと思うほどに全身がかっかと熱を帯びた。鼓動が激しく高鳴り、全身から汗がぶわりと滲んだ。
虎のほうでも尾を股の下に隠し、耳を垂らして意気阻喪した。怯えてしまったようである。先の威勢のよさはどこへやら、しきりに頭を前足で隠そうとする。
「あら、ごめんなさい。そういうつもりはなかったのだけれど」
口ではそう言いながらも、声の主の言葉尻からは、きのうユキが耳にしたようなやわらかな響きが失われていた。
ユキをその場に置いて虎は、一目散に笹森の奥へと姿を晦ませた。
「あ、トラ、トラ。待ってってばトラ」
どこ行くんだよ、とユキは茫然とした。その場に一人取り残されたことへの傷心があったし、虎をひどく怯えさせてしまったことへの呵責の念もあった。
「本当にごめんなさい」蔵からは先刻とは打って変わった柔和な声音がユキの背に届いた。「気分をわるくさせてしまいましたよね。私の気質はどちらかと言えばいまみたいなものなので。どうぞもうお帰りになって」
「ずるいよそれ」ユキは思ったままを口に出した。踏み鳴らすように落ち葉を蹴散らして進み、扉に指を突きつける。アカゲラのように何度も扉の木目を突つきながら、「そんな言い方されたら、はいそうですか、なんていかないでしょ。帰れるわけないでしょ。それ解ってて言ってるでしょ。わたしが子どもだからってバカにして、あなたもけっきょく村の大人たちと同じじゃない」
「そんなつもりは」
ない、とつづく前にユキは言った。「だいたい、なんで外に出てこないの。わたしはあなたにわたしの一番大事な友達を紹介したかっただけなのに、なんでああいうことをさあ」
知れず涙が溢れていた。
何が哀しいのかじぶんでもよく解らなかった。
善意を踏みにじられて感じたからか。それとも、虎の気持ちも考えずにじぶんかってに行動して虎を傷つけたからか。
どちらもある気がした。
ユキは一度だけぐいと目元を手首で拭い、歯を食いしばって涙腺を圧迫した。ユキは思う。こんな顔も知らぬ相手のために流す涙などわたしにはない。
「あなたのさっきのは、わたしには意図して威圧したように聞こえたよ。あなたの本当がどうかは関係ない。あなたに虎を会わせようとしたわたしが愚かだった。あなたがわるいわけじゃないから気にしなくていいよ。これはわたしの問題で、わたしがわるいのだから」
そんなことは露ほどにしか思っていない。本当は扉の向こうにいる彼女がわるいと思っていたし、傷つけるつもりでそう言った。彼女が虎にしたことをお返ししたのだ。真似をしてみせた。
「ごめんなさい」声の主は緘黙した。
ユキはしばらくそこに佇んでいた。待っていた。まだ相手は扉のそばにいる。つぎに何を言うのかに関心があった。ユキのなかでわだかまった感情の渦は徐々に、怒りとして結晶しつつあった。
だから蔵の中の彼女が、「もう行った?」とひとしきり間を空けたあとで言ったのを耳にして、怒髪天を衝いた。「いるよ。ここに。さっきから一歩も動いておらぬ」
おらぬ。
なんて儼乎な響きであろう。よもやじぶんの口から飛び出してくるとは思わなかっただけに、ただそれだけでユキの怒りはすこし融けた。
「もういい加減そっから出てきなよ。これ抜くよ。邪魔」
閂に掴み取り、一息に引き抜こうとしたがこれがまた固いのだ。威勢よく啖呵を切った手前、是が非でもすぽんと滑らかに抜きたかったが、上手くいかなかった。
「何これ。壊れてんじゃないの」
ユキは扉を蹴った。
するとその奥で、
「うふふ」
声の主が楽しんでいるのが判った。たぶんきっと、とユキは想像した。脚なんか綺麗に揃えて崩して座り、口元に手を添えて微笑んでいるに違いないのだ。ユキの祖母が生前、そのように笑う人間だった。それをして村の者たちは、ナツさんは上品だ、としみじみ評していたが、きっとこの扉の向こうにいる人物も同様の上品さを雄雉の羽のように振りまいているに相違なかった。
いやらしい。
そうやって振る舞うことで得られる利を承知しているからそのように小細工を弄するのだ。それに比べて、虎のあの隠し事のなさはどうだ。じつに堂々としたものだ。
虎のほうにじぶんを重ねてユキは、蔵の中の人物を指弾した。
あなたは卑怯だ、と。
最初からわたしが扉を自力では開けられないと知っていながら、あたかもわたしの気の持ちよう一つで開けられると嘘を植えつけた。わたしはそのせいで、あなたをここに閉じ込めたままで帰ったことをずっと気にすることになったのだ。
もしも最初から――。
最初から、扉が開かないことを教えてくれていたのならそんな気分のわるい目に遭わずに済んだのに。
そこまで怒気交じりに唱えて、はたと思考が途絶えた。笹の幹を刃物で割るときに、節に引っかかったときのような躓きを覚えたのだ。
その躓きの正体に思考を割いていると、
「だから言ったのよ」
むつけたような声が聞こえた。扉の奥からだ。くぐもっているのは声の主が扉に背を預けているからかもしれない。声の響き方一つでユキには相手の姿勢が判るようだった。
「私はちゃんと言いました。もうこないほうがいい、私のことは忘れてちょうだいと」
「わ、わたしのせいにしたぁ」
怒りより先に呆れた。反省の弁の一つでも口にしたのなら水に流してやろうとも思ったのに。ユキは先刻浮かべた躓きへの疑念を忘れて、一瞬で扉の奥にいる人物のことが嫌いになった。なぜこんな相手に大事な虎を会わせようと思ったのか。
「寂しそうだと思ったんだもん」ユキは悔しさのあまり何度も地面に足の裏を叩きつけた。「ずっとここに入ってたら寂しいかなって思って、だからわたし、わたし」
扉の奥で声の主がくすくすと息を押し殺すように笑っている。しかしユキの知覚は視力のみならず聴覚も優れていた。扉一枚隔てた程度では筒抜けもいいところであった。
何かを言ってやりたかったがユキは唇を一文字に結んで蔵に背を向けた。
もう何も聞かせてやらない。
相手をするだけ無駄だ。
そのままスタスタと落ち葉の絨毯を蹴散らすようにしながらユキはその場をあとにした。籠を拾いあげるのも忘れない。
虎は放っておいても夜には村に戻ってくるだろう。ひょっとしたらすでに一人だけで村に帰ったのかもしれない。
帰り道は楽だ。笹の幹についた印を辿るだけで村に行き着く。
村に近づけば近づくほど、どの笹にも印が見えるようになる。村を中心に円形に印が集中している。そうして何年も、何十年も掛けて笹森の迷宮は、単なる迷宮ではなく、流浪の民たちにとっての安住の地となったのだ。
笹森の内にいる限り、追手に怯えずに済む。
ユキはそうと年長者たちから聞かされているが、産まれてから一度も見たことのない追手の存在を前提とした日々の暮らしは、まるで見えない鎖でがんじがらめにされているような窮屈さをユキに強いた。それは村の掟とも無関係ではなかった。
そうせざるを得ない何かが過去にあったのは分かる。
だがユキたちにとってその何かは、未だ到来しない、見たことも触れたこともない何かなのだ。ならばせめてその脅威がどんなものなのかを体感させて欲しい。
ユキはずっとそう思ってきたが、それは暗に絶対に怪我をしない方法で危険な目に遭わせろ、と言うようなもので、じぶんでも口にすることすら嫌悪する我がままにほかならなかった。
一方でこうも思う。
それと同じ我がままをみなは虎に強いている。絶対に安全に手に入る、しかし本来であれば犠牲を覚悟しなければならないほどの利を得るために、わたしたちを信用しきっている家族の、虎の死を望む。
そしてその後に、虎の肉を食らい、生き永らえようとしている。
なぜ一方のみがいつも不条理を押し通せるのだろう。そしてこの思いは、たとえ言葉にしたところで村の年長者たちには届かないのだ。
ならばユキのほうとて、同じ不条理を押し通してもバチは当たるまい。
そうと臍の周りに力を籠めてみるものの、いつも村の者たちをまえにするとその我を通そうとする意志が萎えるのだった。なぜかはじぶんでも分からない。ひょっとしたらじぶんがそこまでして村に何かをしたいとはもはや思わなくなっているのかもしれない。
最年少にしてなぜユキが食料調達の任を率先してこなしているかと言えば、それは村への恩でもなければ義でもない。ただただ虎を失いたくないとする執着であった。手放したくない。そばにずっといて欲しい。
だがそんな一つの望みすら叶わない。
叶わないことで負う穴の深さを、おそらくユキ以外の者たちは誰一人理解することはない。いいや、それを言うなればじぶんも同じだ。村の者たちがなぜ平然と理不尽な選択を他者に迫るのか。その心などとうていユキには理解できないのだ。推し量り、きっとこうだろう、これくらいの道理であろうと鑑みる己があるばかりだ。
籠は、馴染みの大人に食料ごと手渡した。押しつけた、とそれを言い換えてもよい。どの道、配分の権限がユキにはない。
肩の荷を下ろしたその足でユキは、村を一通り見て回った。虎は檻の中にいた。村に着いてさっそく誰かに入れられたのだろう。虎は従順だ。村の中の誰かに牙を剥くことはない。
虎は寝ていた。身を丸め、まるで床に積みあげた毛皮の塊のようだ。ふと本当に生きているのか不安になった。死んではいまいか。ユキは笹の幹を幾重にも編みこんで造られた檻の隙間から手を差しこみ、虎の毛に触れた。
虎の尾が一瞬跳ねて、土を打つ。
虎は目をつむったままだ。
尾の動き一つを目にしただけでユキは、胸の中にわだかまっていた怒りの塊がすっかり融けるのを感じた。たったこれだけのことでいいのに。これしきのことがもうすぐユキの日々から消え失せる。
夜。寝床に包まり、ユキは思う。
いっそ虎を連れて、どこまでもどこまでも旅をしようか。笹森の果てが本当にあるのかどうかすらユキは知らない。おそらくあるだろう、とは考えている。ある地点よりも奥に行くと、笹森の天井と空との境に山岳が見えるからだ。そこには笹は生えていない。きっと山の奥にも世界はつづいている。
流浪の民はそこからやってきた。
ユキの祖母たちはそこから逃げてきたのだ。
いったい何から逃げたのか。
ユキにはよく解らないでいる。敵がいた。同じ人間だ。獣ではない。ならば話せば争わずに済むのではないか。思うがいつもそこで、じぶんと村の者たちの関係を思い、たしかに解り合えぬこともあるだろう、と考えを曲げる。
しかしだからといってユキは村の者たちと諍いを起こしたりはしない。できるだけ誰も傷つかない道を探そうとする。
虎のこととてそうだ。
人間ではない。虎は獣だ。たしかにそうだが、虎とて村の一員だ。ならば虎にだけ有無を言わさず不条理を押しつけていいわけがない。擦りつけていいわけがない。
解かっている。
ユキだけがそれを解っている。
そのことがどうしようもなくユキの心を笹の葉のざわめきのようにささくれ立たせるのだ。さざ波のように、消えぬ細かな傷をつけつづける。
この晩、ユキは夢を視た。
じぶんが虎になった夢だ。細かな間隙の開いた檻の中にいる。檻は頑丈だ。外に出るためにはほかの誰かに出してもらわねばならないが、しかし虎を外に連れだすのはいまやユキしかない。だがそのユキ自身がいまは虎なのだ。
これでは出られようもないではないか。
尾を鞭のようにしならせて、檻の格子を打つ。格子は網目状に入り組んでおり、隙間はあってないようなものだった。
誰かの足音を耳に留め、虎は――ユキは――寝たふりをした。
足音は檻のそばまでやってきて、突然にガンガンと大きな音を立てはじめた。岩か鈍器かで檻を叩いているのだ。
ユキは驚いた。
打撃音は檻の悲鳴のように耳をつんざき、ただそれだけでも拷問のようだった。
だがそれでも音はやまない。
ユキはびくびくと怯えたが、いくら待っても音が鳴りやむことはなかった。延々とつづくその執念に、ユキはやがて檻の外にいる人物の意図を察する。
檻を壊そうとしている。
あらん限りの力を尽くして。
それでも檻が壊れないので、外にいる人物のほうでも苛立っている様子だった。しかしそれすらしだいに凪のような穏やかさに変わった。
檻への打撃は当初のような猛烈な降雹じみたものではなく、打楽器のような単調なものに変わった。それでもどうやら檻の外にいる人物は手を止めるつもりはないようだ。
ユキは思う。
もういい。
檻は破れない。
もうやめたほうがいい。
だが虎であるユキには唸り声を発することしかできず、その都度に檻の外の人物を余計に困憊させるだけのようだった。
もし、とユキは想像し、おそろしくなった。
もし、このまま檻が壊れず、それでもなお外の人物が諦めなかったら。
じぶんは何もできず、ただ檻のなかでその光景を眺めているしかなくなる。
じぶんのために懸命に、血を、汗を、時間を、人生を浪費している人物の余波を、互いにとって何の利にもならない不快な打撃音と共に聴きつづけるはめになる。
何もできない。
じぶんのためにここまでしてくれる相手にじぶんは、感謝どころか余計な真似をするなと、もはや憎悪すら募らせはじめている。
だがそれすら、時間と共に霧散した。
日に日に満身創痍になっていく檻の外の人物の様子を察して、ユキは、もういい、やめてくれ、と頭を抱えた。ついには悲鳴した。
こんな目に遭うくらいなら。
こんな目に遭わせてしまうくらいならいっそ。
いっそ、最初から檻になど触れさせるのではなかった。
寝たふりをするのではなく、初手で吠え、威嚇し、突き放しておくのだった。
ユキはそうと深く臍を噛み、その痛みで以っていまさらのように低く、低く、腹の底から唸り声を発した。
そこで夢から覚めた。
網目状に組まれた天井が回転していた。だが数度目をしぱたたかせると、視界は安定した。
悪夢を見た。
喉がひどく乾いていた。
水を飲みに、家の外に出ると朝ぼらけの天幕に一等眩い星明りだけが浮かんでいた。井戸で水を汲み、喉を潤す。
寝床に潜り直すころにはユキの脳裏には、蔵の中の人物との会話が断片的に流れては薄れた。薄れた矢先から同じような場面がふたたび流れる。
あの声の主は何度も、ごめんなさい、と訴えた。
その上、急に態度を豹変させ、ユキに怒髪天を衝かせた。ユキはだから言った。
もしも最初から――と。
最初から、扉が開かないことを教えてくれていたのならそんな気分のわるい目に遭わずに済んだのに、と。
「同じだ」
じぶんの声が村の者たちのつむぐ言葉のように、軽薄な響きを伴ないながら鼓膜に、頭蓋に響き渡った。ユキはもう一度ただ、同じだ、とつぶやく。
陽が昇ってからユキは虎にも会わずに村を発った。
親には数日村を留守にする、と告げてある。大物を仕留めるためにすこし遠出をする、と言うと、ユキの両親は、「果て印の外には出ては駄目よ」と言って送りだした。この手の遠出は初めてではない。いまは村の存続の瀬戸際でもある。
齢十二という幼さよりも、目前の利を得る。
賢いユキの親もまた賢かった。
道中できょうの分の食料を確保し、ユキは蔵のある場所まで足を運んだ。印を見ずとも身体が道を憶えている。いっそ残した印を取り去ってもいいかもしれない。なぜそう考えるのかも分からずに、合理のない考えを巡らせた。
この行動そのものが合理ではない。
ちぐはぐだ。
何の利もない。そのはずだ。
これは誰にとっても利のない選択だ。今朝見た悪夢の再現でしかない。
悪夢の中ではユキは虎だった。檻に囚われた虎だ。
だがいまは檻の外の側からの視点で、檻を、蔵を叩こうと思った。
それが蔵の中の本意ではないのだとしても。
ユキはいまいちど、初心に戻ってやり直すことにした。だって、と口元をきゅっと結ぶ。だって、寂しそうだったのだもの。
駄目だと言った。記憶がたしかなら蔵の中の人物は、閂を外そうとしたユキを引き留めた。それに触れるな、と。触れたところで開かぬそれに触れてはいけない、と。
その癖、最初に声を掛けてきたのは彼女のほうからなのだ。
いや、しかしそれはどうだろう。
思えば彼女は案じていたのではないか。すでに記憶が曖昧だ。なぜ彼女は蔵の中から声を掛けてきたのか。
あなたは一人なのか、ほかの者はないのか。そう問われはしなかったか。
じぶんはひょっとして、心配されていたのか。
ユキははっと息を呑んだ。
己が血の繋がった両親からもはや向けられなくなって久しい感情を、あのとき蔵の中の人物はユキに注いでいた。
いや、違う。
これはさすがに夢を視すぎだ。
そうじゃない。きっとそうじゃない。
何度も否定し、蔵の中に閉じ込められた者の本懐を喝破しようと試みるが、どの道、他人の心など解るものではない。じぶんの心とて解らぬのだ。どうして他者の本音が解ろうものか。解るはずもないのだ。
蔵の見える位置にまでくると、動悸がした。緊張している。しかし今回のこれは、初めて蔵の中からの声を耳に留めたとき――三日前のあのときとは違っている。
恐怖ではない。
不安だ。
誤解されるかもしれないことへの、不安だ。
じぶんがきっとそうしてしまったように、蔵の中の人物、彼女から誤解されることを怖れている。
二の足を踏んでいると、蔵のほうから物音がした。
何かが扉にぶつかるような音だ。蔵全体が怒号のような激しい振動を放っているようだった。笹の幹が音に呼応して、一挙に枝葉を揺らした。枝葉が揺れるたびに、シャンシャンと幾千万の鈴のごとく音色が鳴り響いた。笹森全体が震えているようだ。ユキはその轟音と音色を耳にして、雨の日を思いだした。雨を葉にずっしりと蓄えた笹を蹴ると頭上からは、星空のような雫の落下する音を耳にできた。
何かが蔵の中から扉にぶつかっている。
ユキの脳裏には、体当たりを繰り返す怪物の姿がぼんやりと浮かんだ。虎がぶつかってもこうはならない。もっと強大な何かだ。
蔵の扉は閉じたままだ。閂は掛かっている。外れてはいない。
ならばいま蔵の中にいるのは。
尋常ならざる音を奏でている強大な何かと。
そして。
例の柔和な声の主だ。
ユキはそうと瞬時に判断した。よもや蔵の中には一人しかおらず、この破壊的な轟音を柔和な声の主そのものが立てているとは考えなかった。それはそうだ。明らかにこれは人間の立てられるような音ではない。響きではない。振動ではなかった。
「助けなきゃ」
口を衝いていた。身体が動いた。つま先で土を掻き、駆けた。どんどん勢いを増し、ユキはいっとき虎となる。
最後の一歩で跳躍し、両の腿を中で閉じて、扉に足の裏からぶつかった。飛び蹴りだ。齢十二の小娘の蹴りだ。衝撃はたかが知れている。
案の定、扉は無傷のままで、ユキのほうがその場に肩から落下した。
痛めた肩を庇いながら上半身を起こすと、蔵からの轟音は止んでいた。
「だ、大丈夫」ユキは尻餅をついたままで叫んだ。「名前、名前教えないからこういうとき困るんだよ」と脈絡のない苛立ちを吐露しながら、「中にいるんでしょ、いまの何、物凄い音してたけど」と立ちあがる。「ねえ、返事してよ。聞こえてるでしょ。やいおまえ。いまのガンガンうるさくしてたやつ。出てこいよ。わたしが相手になってやる」
扉には閂がしてある。容易にはでてこられまい。
そうと判っていながら、しかしそんな考えなど毛頭なくユキは蔵の中に啖呵を切った。「出てこいよ。そんな狭いとこいないで、こっちこい。できるだろおまえなら。その扉ぶち破ってでてこいよ」
そうだとも。
ユキはそのためにここに来たのだ。
蔵の扉を開ける。
中から声の主を助けだす。
化物の処遇はどうしようもないので、扉が開いたら二人して一目散に逃げればいい。何だったら、とユキは考える。じぶんが囮になって化物を引きつけ、そのあいだに蔵の中の声の主には逃げてもらえばいい。
そうだ、それこそ正解だ。
ユキはことさら蔵のまえで挑発した。使ったことのない罵倒を唱え、いつも心の中に仕舞ったまま空虚の肥しにしていた村の者たちへの不平不満をそのまま口にした。
これで怒らねばいったい何に怒るだろう。仮に逆上しなければそれは化物ではなく笹ではないか。笹はユキたち人間が何をしても、どう伐り倒そうとも泰然自若といつも黙ってそこにある。
喉がひりひりと痛み、息が上がってきたころ、ユキははっと我に返った。蔵はしんと静まり返っており、鳥たちのさえずりが距離感も曖昧にあちらこちらで聞こえていた。雲の影が、足元の木漏れ日を横切っていく。
蔵のある一角は天上が拓けている。ここは明るいのだ、とそんなことにユキは初めて気が付いた。
「ふふっ。もう終わり?」
蔵の中から声がした。柔和な響きはユキの膝をその場に崩すのに充分な暢気さを湛えていた。「もうなんだよ、無事なんじゃん」
「あら。心配してくれたのかしら」
「そりゃもう」ユキは脚を引きずるように這って扉のまえまで移動した。「心臓張り裂けるかと思ったもん」と扉に寄りかかった。座り、背を預ける。「というか何度か張り裂けた」
「まあたいへん。どうしてきょうはお友達は一緒じゃなかったの」
「追い払った人が言うことじゃないよ。ねえ、さっきのってなんだったの。あの音は何。化物かと思ったよ。そうそう、早く名前教えてよ。名前知らないから化物相手に悪口言っちゃった」
「うふふ。聞いていましたよ。とっても傷ついちゃったな」
「違うよ。化物に言ったの」
「そうでした、そうでした。ところでどうしてまた来たの。ひょっとして失くし物でもしちゃったかしら」
「あ、それは、えっとねぇ」
「うん。どうして?」
扉に寄りかかりながら話していると、まるで先刻目の当たりにした蔵の絶叫じみた光景が夢幻に思えた。眩暈や耳鳴りを、あり得ない化物の存在に重ね視てしまったのではないか、と段々と現実味が薄れていく。
「違かったら違うって言ってね」ユキは前置きしてから言った。「もしかしてさっきわたし、一人で悪口叫んでた?」
「さあ。どうでしょう」
「ねえってば。ちゃんと答えて」名前だってまたはぐらかされて教えてもらってない、と首をひねってまっすぐ扉に声をぶつけると、「ユキさんには何がどう視えていたのかしら」と聞き返され、ユキは耳が熱くなった。「分かった。もういいです」
「ユキさんはひょっとして、何もないところで何か視えちゃいけないものでも視て、それであんなひどいことを私に向かって叫んでいたのかなぁ?」
「もういいって言った!」
「うふふ。いじわるしちゃった。代わりにいいこと教えてあげちゃおっかな」
「んー」膨れてからユキは言った。「なんだろ。そっちの名前とか?」
「昔々のお話です」
「げぇ」そんなの聞きたくない、と抗議するより先に、蔵の中の人物は柔和な声から陽気を消して言った。「昔々、あるところに一匹の鬼がおりました」
****
昔々、あるところに一匹の鬼がおりました。
鬼は自身が鬼であることにも気づかずに、目につくものを片っ端から手に入れて、じぶんの宝箱のなかに仕舞いこんでいました。
山も川も野も空も。
草も花も虫も獣も。
鬼はそれら生きとし生きるすべてのもの、自然、世界そのものを慈しんでおりましたから、損なわれぬようにと堅牢な箱の中に仕舞いこもうと考えたのです。
鬼はみなのためにしたことでした。
鬼はみなのことが大好きでした。
けれどもそれは鬼の中でのこと。
みなは必ずしもそうではありませんでした。
ある時、宝箱に閉じ込められた仲間を助けだそうと、山や川や野や空が、それとも草や花や野や獣が、徒党を組んで鬼に反旗を翻しました。
そこには人の姿も交っていました。
鬼はじぶんによく似た姿の人をとびきりに愛でておりましたから、そんな人からも憎悪を向けられ心底に傷つき、怯え、隠れました。
それでも鬼以外の神羅万象は、鬼と、鬼の持つ宝箱の効力を怖れて、手を緩めませんでした。執拗に探し、追いかけ回し、じぶんたちが受けた辱めと痛みを、そっくりそのまま返したのです。
しかし鬼には身に覚えのないことでした。
けれど現にそれは鬼がみなにしたことでした。
鬼は怒りよりも憎悪よりも何より、哀しみの色に染まり、そして――我を失ってしまったのです。神羅万象の総じてを無に帰さんと、鬼は鬼の持ち得る力のすべてを解放したのでした。
鬼の足元から順々に、まずは世界から花が失せました。
つぎに川が。
虫が。
そうして鬼を追い詰めた側の神羅万象は竦みあがったのです。やりすぎた。鬼を怒らせてはいけなかったのだ、と。
しかし我を忘れた鬼をまえに、成す術はありません。
そこでみなは、鬼の宝箱に目をつけました。我を忘れた鬼はそれを手放し、いまは中身のからっぽの箱です。
鬼に消されずに残った神羅万象は、鬼が正気に返る前に、宝箱の存在を思いだす前に、宝箱の中に閉じこもって、中から封をしようと考えたのです。
鬼の宝箱は底なしです。中には、もう一つの世界が広がっていました。神羅万象はそこにもういちど一からじぶんたちの世界を築こうとしたのでした。
***
そこで声は途切れた。ユキは声の主の語りに聞き入っていた。寂寥の滲む声音には仄かに笑みが乗っており、子守歌のように心地よかった。
反して語りの内容は、漫然と漂う雲の流れのようで、とりとめがなかった。いったい何の話で、それがいまどう関係あるのか。
なぜいまそれを話されなくてはならないのかが解らなかった。
しばらく待ったが、扉の奥からは物音一つしなかった。まるでいっさいが夜に沈んだかのようだった。
ユキは怖くなった。しかしその怖さの出処がよく解らなかった。なぜならいま、ユキに迫る脅威はない。すくなくともいまこの瞬間は、頭上から注ぐ日向を全身に浴び、ぽかぽかと微睡に揺蕩うような心地よい眠気があるばかりだ。
背には蔵の扉があり、その一枚隔てた向こう側には柔和な声の主がいる。
蔵にはほかに扉はない。窓もない。
ならばどうあっても消えていなくなるはずはないのだ。
そうだとも。
もし先刻の幻覚が、白昼夢が現実のものであるとするのなら、とりもなおさずそれは誰も出入りすることの適わない蔵の中に化物が侵入したということで。
しかしそれはあり得ない。侵入する穴はなく、仮にそうした穴があるのならああも扉に体当たりをする必要がない。轟音を響かせる必要はないのだ。
だからあれはやはりユキの視た白昼夢にすぎなかったのだ。
ユキは懸命にそう思いこもうとした。
しきりに浮かびたがる、よりあり得そうなもう一つの可能性を考えたくはなかったから。脳裏の奥底に沈めたままにしておきたかったから。
だからユキはしいて欠伸をして、眠くなってきちゃった、と言った。「ねぇ。また何か話して。なんでもいいよ。そうだ、つぎはトラも連れてくるからさ、今度はいじわるしないで仲良くして」
「今度はって何かしら」声の主はやっと返事をした。「私は別にいじわるをしたつもりはなくてよ」
「ふうん」
「まあなんでしょうその気の抜けたお返事は」
「だってさ。お姉さん、いじわるじゃん」
「え?」
「いじわるでしょ。もう誤魔化す意味ある? ないよね。ないない」
「そうじゃなくって、いまユキちゃん私のことお姉さんって」
「だって名前教えてくれないんだもの。好きに呼んでいいって言った」
「うふふ」
「何で笑うの」
「違うのよ。うれしいの。うれしかったの。ありがとう」
そこで彼女はなぜか不可思議な耳慣れない呪文を唱えた。
「鬼は外。愛は内。本当にそうだわ。そうなのよね」
「何がそうなの。聞こえなかったよ、もっかい言って。と言うか、お姉さんまで扉に寄りかかってるから声が小っちゃくてよく聞こえないんだよ」まるではるか遠くにいる相手としゃべっているようなもどかしさがある。「しゃべるならちゃんとしゃべって」
「ユキちゃんきょうは我がままさんなんですね」
「名前一つ教えてくれないお姉さんほどじゃないと思う」
「そんなに知りたいの」
「だって不便だし」
「そういうものかしら。昔はみな、好きに私のことを呼んだから」
「へえ。なんて?」
声の主は口ごもったが、ユキが逆さに十を数えだすと、「ゆうき」と鳥の囀りにすら掻き消されそうな、か細い声が聞こえた。
「なんて?」
「ゆうき、と言いました」
「それがお姉さんの名前? ゆうき、か。いい名前だね」
「そう思う?」
「うん。だってわたしも勇気のある人間になりたいし」
虎を、守り通せるだけの知恵と勇気のある人間になりたい。
ユキがそう言うとそこで蔵の彼女は押し黙った。沈黙の意図を悟らせまいとするかのようにいつもよりも弾んだ声音で、ありがとう、と彼女は付け足した。
歯に物が挟まったような物言いだったので、ひょっとして、とユキはぴんときた。「名前、ゆうきってその【勇気】じゃなかったりして」
「そう、ね」
「ふうん。じゃあなんだろ。ほかにあったっけかなゆうきなんて言葉」
「ありますよ」彼女は誤魔化すだけ無駄なのだと諦めたように、ふふ、と息を漏らした。「幽かな鬼と書いて、幽鬼」
ユキはずっと引っかかっていた違和感の正体にこのとき気づいた。
ないのだ。
笹森のなかにすらある、音の響く、その余韻が。
反響する微細な音の揺らぎが。
扉一枚隔てた向こう側、蔵の中からは聞き取れなかった。
「でもいまは」ユキの胸中に湧いた一抹の戦慄の念に気づいた様子もなく、蔵の中の人物、彼女、幽鬼は言った。「どちらが外か分からないのよ」
鬼は外。
愛は内。
蔵の主はそう言った。
ユキはそれを聞き漏らさなかった。
【寝ろ!】(2022/10/22)
百の壁に囲まれた国があった。そこには王が一人きりだった。王は毎晩必ずこう言った。「もう寝ろ!」
百の壁に囲まれた国は、上も下も右も左も壁に包まれ、まるで棺桶のようだった。FIN.
【世界一適当な人】(2022/11/08)
とある山の火口には世界一優しい男が住んでいた。住んでいた、というのは誤謬があり、じつはまだ現在進行形で世界一優しい男はとある山の火口にいるのだが、世界一優しい男は世界一優しいので全世界の生態系のために、大爆発しそうな火口にいち早く注目し、ありったけの叡智を注いでそれを食い止めていた。
世界一優しい男は世界一賢い男でもあったのだ。
だが世界一賢い男は世界一優しい男でもあるから火口で噴火を食い止めているわけだが、彼は世界一優しいので、じぶんごときが世界一優しいで賞受賞間違いなしの地位にいつづけることに心を痛め、世界一優しい男をやめることにした。そのため世界一優しい男は噴火すれば全世界の地表から生態系が消え失せる未来を、一人とある山の火口にて阻止しながら、ありったけの語彙力を駆使して絶えず悪口を吐きつづけた。
世界一優しい男は絶対に絶えず悪口を吐きつづけるなんて真似はしない。したがってこのときを以って、世界一優しい男は世界一優しい男の地位から転落した。
だが同時に、かつて世界一優しかった男は絶えず悪口雑言を吐きつらねながら、とある山の火口にて全世界の未来を一心に背負い込みながら噴火を抑え込み、さらにじぶんが本当に世界一優しい男ではなくなったのかをチェックするためにやはり絶えず片手間に全世界の情報網をチェックした。
日夜寝る間も惜しんで、悪口雑言を吐きつらねながらとある火口で噴火を阻止しつつ、片手間で高性能電子端末を操るかつて世界一優しかったかつ現世界一賢い男は、そうした尋常ならざる日々に身を置くことで、世界一タフな男の地位に昇りつめた。
だがやはりかつて世界一優しい男だった過去が尾を引いて、世界一タフでいつづけることに呵責の念を覚えだし、さらには同様の理由からじつは絶えず口にしていた悪口雑言も、たいして人を傷つけるほどの殺傷力を秘めていない有り触れた小言の域を出ていなかった。しかしそれでは世界一賢い男としての語彙力に疑念が湧く。
これによりかつて世界一優しかった男は、世界一タフな男の座を降りるべく敢えて怠けるようになり、それと共に元から大した悪口を唱えていなかった背景が加算され、けっきょくのところ何者でもない男ができあがった。
大して優しくもなく、タフでもなく、賢くもない男である。
否、もはや男であるのかすら疑念が湧いた。
そうなのである。
かつて世界一優しく賢くタフだった男は、世界一の美貌の持ち主でもあったのだ。
だがやはり過去に世界一優しかったときの名残により、何の努力もなしに世界一をつぎつぎ更新してしまう己が能力に蓋をすることにして、かつてあらゆる世界一だった男か女かもよく判らぬ人物は、とある山の火口にて、全世界の生態系の未来を守ることもやめて、いったい何をしたかったのかも失念して、とぼとぼととある山の火口から下山した。
だがかつて世界一賢かったころに発揮した噴火対策は抜かりはなく、もはや火口にいつづける必要すらなかったのだが、世界一タフであったことの名残により最も過酷な火口での生活を維持しつづけていただけだった。
かつてありとあらゆる世界一だった男か女か、もはや人か生き物かも分からなくなった存在は、それでもよく考えてもみたら、未だに世界一賢いし、世界一タフだし、世界一美しいし、そうしたあらゆる世界一であることを投げ捨て、なお人であることすら擲った、男か女か人か生き物かも分からなくなった存在は、やはり世界一優しい男なのであった。
男じゃん。
いいえ、女かもしれません。
いっそ人でいいじゃん。
ただの人で。
じゃあそれで。
【幻の大陸――海里】(2022/10/22)
千年に一度、満月は蒼く染まる。
月が蒼く視えるのはしかし、地上ではとある海域に限られた。
古文書によると、蒼い月から光がそそぐ海域には幻の大陸――海里が出現するという。これは世界中、どの古文書にも表現こそ違えど、似たような記述が散見された。
海里出現が最後に報告された時期は、いまからちょうど千年前にあたる。つまりあと半年も経たぬ間に、蒼い月の昇る日が巡る。
正確な日時や位置は不明だが、おおよその場所は特定されている。
幻の大陸――海里には、この世のものとは思えぬ財宝や見たこともない生き物や技術が時間を超越したように混然一体となって存在しているそうだ。
古文書の記述にどこまで信憑性があるのかは定かではないが、ともかく過去に沈没した大陸が再浮上する確率はそう低くはないと判断された。
全世界が手を組んで、幻の大陸調査団が結成された。
幻の大陸――海里出現を観測し、上陸して調査するまでが目的だ。どんな不測の事態にも備えるべく各国の優秀な研究者たちが集められたが、結果から言うと幻の大陸「海里」の発見には至らなかった。
観測できなかったのである。
時期が違うのではないか、との指摘はお門違いだ。
なぜなら古文書の通り、蒼い月は現れたのだ。満月の日に、ある海域の頭上に昇った月は蒼く染まった。
だが幻の大陸など現れなかった。
それはそうだと全世界の人間たちが嘲笑し、大真面目に国家予算を費やした各国を非難しだしたが、世界各国はむしろさらにつぎの千年後を目指して幻の大陸「海里」の特別調査予算を確保した。
月が蒼く染まる原理が不明であった点が理由の一つだが、そちらはおまけのようなものである。
最も見逃してはならない理由は、蒼い月の昇ったその日、古文書の指し示す海域の天気は曇りだったことだ。
そうである。
月は蒼く染まったが、月光が海にまで届かなかったのである。
世界最高峰の英知を集結させておきながら、誰一人として天候が崩れることを予測せず、対策すら敷いていなかったのである。
このことにより、各国は汚名返上と威信に掛けて、幻の大陸――海里への調査機関を国際的に創設した。
つぎに海里が出現するのは、いまから千年後である。
それまでに人類は天候を操れる技術を編みだせるのか。
つぎこそは徒労に終わらぬことを祈ろう。
願わくは、蒼い月の浮かぶ海が晴れんことを。
【ハロー効果の勝利】(2022/10/24)
記憶を失くしたその男が、奇妙な体験をしたのは秋も更けた十月のことであった。
男がなぜ記憶を失くしたのかについては主軸となる奇妙な出来事とは関係がないのでここでは触れずにおくが、男は目覚めると繁華街の路肩に寝転んでいた。
肌寒さに身震いをしながら上半身を起こすと、からからと目のまえを空き缶が転がった。
誰もいない。
夜だというのにカラスの鳴き声が閑散とした街道に響いた。
男はじぶんが誰であるのかを憶えていなかったが、自身が男であり二十三歳であり、そして何者かに追われていたことだけは憶えていた。
命の危機を感じ、逃げていた。その焦燥感だけが男には残っている。記憶の底に沈んだその焦燥感は結晶して、水晶のようにキラキラと存在感を発していた。しかし男の精神は水ではないので、水晶の煌めきはトゲトゲしく男の内面をチクチクと刺した。
逃げねばならぬ。
本能のように刷り込まれた焦燥感に男は、すくと立ちあがり破けたジーンズを手で叩く。
歩きだすと、地面の細かなブロックの段差を足の裏に感じた。男は靴を履いていなかった。
辺りを見渡す。左右には建物が道を縁どるように建っている。壁面は地面と同じ細かなブロックで、あたかも地面が隆起してそのまま建物になったかのような外観だった。
窓はすべて雨戸が閉じている。そうでない窓にはカーテンが下りていた。隙間から明かりが漏れている建物もあるが、中に人がいる様子はない。
街灯が道なりに点々と建っており、いっさいの影の動かぬ景色は、絵画のなかに入り込んだようだった。
ふと視界の端で何かが動いた。
ぺたぺたと足音を立てながら暗がりから子どもが現れた。頭巾を被っており、手には小さな籠を持っていた。
男はそのとき、じぶんが言葉をしゃべれることを思いだした。脳裏に、やあ、と誰かに声を掛けるじぶんの姿が浮かんだのだ。
子どもは男の足元までくると、じっと両手で掴んだ籠を見詰めたまま動かなかった。何かを促されて感じたが、その何かが分からなかった。
「どうしたの。みんなはどこ」男は発声した。
耳にしたじぶんの声は、思っていたよりも高かった。二十三歳のはずだが見た目はもっと幼いのかもしれない、とじぶんの顔形を思いだせないことに焦燥感はさらに募った。
子どもの被っている頭巾はくすんだ茶色をしていた。ひょっとしたら赤なのかもしれないが、街灯の明かりの下では茶色に見えた。
返事はなく子どもが動かないので、男は手を伸ばして子どもの頭巾をめくった。
途端、子どもは機敏に面を上げた。男はぎょっとした。子どもの顔面は真っ青で、頬は窪み、片目が潰れて視えた。
男は逃げだそうとして踵を返した。
すると反対方向の道からは、ぞろぞろと大量の人間たちが歩いてくるのが見えた。みな一様に同じ速度で、ぞろぞろというよりも、マグマがゆっくりと進むような蠢き方をしていた。まえの人物を押しのけ、先頭に立つと立ち止まり、こんどはうしろから押しのけられ、と全体が一つの粘液のような振る舞いをとって映った。
男は飛び跳ねた。
この世のものとは思えぬ光景だ。
元の進行方向に向き直り、男は得体のしれぬ集団から距離を置くように逃げだした。足元に佇む子どもはじっと集団を待っているようだった。
男はただただ街を駆け抜けた。
その後、男がどうなったのかはこの出来事とはさして関係がないので詳細を省くが、男はこの出来事がきっかけで精神に異常をきたして、生涯びくびくと日々を送るはめとなった。だが男にはそれで丁度よいくらいの過去があり、その過去を忘れてしまった以上は、やはり丁度よい塩梅であると呼べる。
この日、男の体験した一夜の奇妙な出来事について男が真相を知ることは死ぬまで訪れることはなかった。それはその街がどこにあり、いったいいつであったのかを男が知らなかったからであり、また調べようとしなかったことに因がある。
この街では毎年十月になると町全体で死者復活祭を行う風習があった。
奇しくも男が目覚めた日がその祭りの日であり、その日は一般に「ハロウィン」と呼ばれている。むろん子どもの目は潰れておらず、こけた頬も化粧によるものである。
【江戸の波の光は則る(2022/10/24)】
江戸の海が荒れた。
陸地にまで漁船が流され、泥に交じって魚や貝、果てはクジラまでが座礁した。
日中に起きた海の異常であったが、それは夜までつづいた。
段階的に、何度も大波が発生する。津波との区別がつかないが、地の揺れを感じた者は皆無だった。波だけが大きくなって押し寄せる。
甚大な被害が出ていながら、天変地異の前触れではないかと囁かれはじめたその日の真夜中に、夜の帳と打ち解けた海面が突如として光り、夜空へと舞い上がった。
光は煌々と太陽のように夜の浜辺を照らした。距離感が掴めないが、浅瀬から現れたのではない。それだけは明瞭であった。
光はそれからしばらく海上に浮かんでおり、人々がそのあまりの眩しさに目を覚まし、各々の避難した土地から海を見た。
人々の視界をいっとき占領すると、光は、ジグザグと不規則に左右にそれとも上下にと動き回り、すると何を思ったのか一瞬で遥か彼方へと遠ざかった。ともすればそれは、瞬時に小さくなって消えただけかもしれず、人々の間での認識にものちのちにまでその手の錯誤を元にした言い争いがつづいた。
あるとき、その噂を聞きつけた遠方の殿様がわざわざ村々にまでやってきた。海の荒れた被害は甚大であったが、さいわいにも死者はいなかった。
村人たちから話を神妙に聞いた殿様は、意見を仰がれ一言こうおっしゃった。
「じつに偉いことじゃ」
村人たちはその言葉に、胸が救われた心地がした。天変地異の兆候かと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。殿様が言うのだからきっと吉兆だったのだ。
その上、殿様は村に復興のための資材や人材を派遣し、さらには神社まで造らせた。これには村人たちは一様に感激し、遠い国と思っていた都への関心を強めた。
それからというもの、村人たちは村の神社を中心とした規則や法令を誰が言うともなくしぜんと築きあげ、長らく安息な日々を過ごしたということだ。
いっぽう、村から帰還した殿様は城にて家臣たちを集め、海岸で見聞きしたことを語った。
「ありゃあ偉いもんじゃった。すぐにでも手を差し伸べねば、噂が噂を呼び、都への反逆の意思を強めかねん。偉いことにならんうちになんとかせねば」
家臣たちはみな平伏し、ははぁ、と言った。
【空へと舞い落ちる】(2022/10/25)
全人類にはどんな個にも反領域があるそうだ。これは未来型量子力学という新たな分野で発見された粒子と反粒子の関係によって観測されたまったく新しい現象である。
量子とは極小の領域における物質や時空の振る舞いを言う。波の性質と粒子の性質を兼ね備える。
このとき未来型量子力学では、粒子は重力を反粒子は反重力をそれぞれ帯びると考える。
現実に残った物質の多くは粒子であり、反粒子はすでに多くが宇宙の初期にほかの粒子と対消滅して消えてしまっていると考えられてきた。
ところがだ。
じっさいには、反重力として部分的に散在して、物質と時空との合間にエネルギィとして残留していることが観測された。
このとき物質には己の反粒子に値する反重力がセットとなって存在することが示唆された。
驚くべきことに、地球を構成する物質に対応する反重力は、同じくそのほとんどが地球に内包されているというのだ。
これは量子もつれに距離の限界があることとどうやら無関係ではないようだ。従来の量子力学では、量子もつれは距離に関係なく、たとえ宇宙の端と端であれ働くと見做されてきた。いっぽう、未来型量子力学では、量子もつれにも距離の限界があると解釈する。ただしその距離の限界は、対の粒子をもつれさせるときのエネルギィによって規定されるため、大量のエネルギィを用いたもつれほど、その作用の有効距離を延ばすと解釈する。
そのためどうやら地球上の物質に対応する反重力が、地球の外部に漏れることを防いでいるというのだ。限界があるために、外に拡散しない。
反重力とはいわば斥力だ。引きつけるのではなく、反発しあう。
だがその反発しあいながらも、物質との関係で限界値を持つために、どうやら地球上の部分部分にまだらに編成されるというのだ。
反重力が作用する物質は決まっている。対応する物質にしか作用しない。対となる物質にしか作用しない。
これは裏から言うならば、物質とて対となる反重力から距離を置くように地球内部では相互作用を連動させる。地表の物質とて例外ではない。
反領域とはすなわち、物質それぞれが持つ対となる反重力のある地点を意味する。
ここに一本の木がある。桜である。
西暦2140年代に発見された希少種で、その名を「桜場一樹(さくらばいっき)」という。
この桜、どうやら自身の反領域の上に根付いた稀有な樹であるようだ。
通常、反領域の上に対となる種が落ちることはない。物質を跳ね返すからだ。寄せ付けない。
だが偶然にも、ちょうど半々の割合で「物質と、反重力と対の物質」で構成された種が、たまたま自身の反領域の上に落下し、芽を萌やしたようである。
これにより芽は、反重力の作用を受けながら、反発する物質を上へ上へとより蒸留させながら成長した。立派な樹となったころには、ごく少量であった反重力と対となる物質は、枝葉全体に散り、さらに細部へと拡散していく。
するとどうだろう。
この奇跡の樹と呼ぶべき「桜場一樹」は、桜の花を散らせるたびに、「落下しては浮上する」というふしぎな桜吹雪を生みだすのだった。
はらはらと散った桜の花弁は、地表に落下するが、その地点には対となる反重力を帯びた土が領域全体に交じっている。そのため、重力よりかは弱いがそれを打ち消すことの可能な反重力を受けることになる。
落下しては浮遊する。桜の花弁がトランポリンにでも乗っているかのような、それとも見えない糸で繋がれ、バンジージャンプをしているかのような、ひらひらぷわぷわを繰り返す奇妙な光景をつくるのだ。
絶景である。
こうして地表で唯一の、反領域が可視化された場として、奇跡の土地にして奇跡の樹――「桜場一樹」は、未来型量子力学の証拠として長らく語り継がれるようになる。
観測されてから八十年目が経ったその日。
満開の桜を散らしたとき、奇跡の樹は花弁を地面へ向けてただ舞い落とし、以降、桜が逆さに舞い落ちることはなくなった。
樹から反領域と対となる原子がすっかりなくなったがゆえだと目されている。
【冬のコゴミ(2022/10/25)】
千回巻くからぜんまいというそうだ。真偽はハッキリとしないけれど、山菜の王者と言えばぜんまいだ。
しかし私が帰宅して籠を手渡すと、一息(いっそく)さんはやれやれと赤ベコのように首を振った。
「これはぜんまいじゃないよ」
「嘘でしょ」
私は愕然とした。慣れない山道で散々目を凝らして摘み取ってきたこれがぜんまいでなければいったい私の採ってきたこのくるくるの草はなんだというのか。
「これはね。コゴミ。ぜんまいとどっちにも渦巻きはあるが、ほれ。コゴミにゃ産毛みたいな綿毛がないだろう。新緑だろう。綺麗だろう。あたしが所望したのはぜんまいであって、コゴミじゃないんだ」
「どっちも同じじゃないですか」
「コゴミは綺麗すぎる。灰汁抜きせんでも美味しく食べられるからね。あたしゃ灰汁が欲しかったんだよ」
「採ってくる前に用途を聞きたかったですよ。山菜ならどれでもいいと思うじゃないですか」
「ぜんまいとあたしは言ったつもりだがね」
「私にぜんまいとコゴミの区別がつくとお思いですか」
「付かない人間がいるのかい」
「こ、こ、に、いっます。目のまえにいてるじゃないですか」
一息さんは丸く小さな老眼鏡を小指で持ち上げると、ふむ、と頷いた。「もういいよ。ご苦労さん。もう時間じゃないかい」
「はっ。もうそんな時刻でしたか」
私は時計を見遣って、講義の時間が迫っていることを知る。
お邪魔しました、と慌てて玄関口で靴を履き、けんけんになりながら転げるように家の外に出た。秋の風が私の身体の表面から一息さんの家の匂いを拭い去るようだった。
もったいない、といつも同じことを思い、そしてすぐに忘れる。私にとって一息さん家での休憩時間は、まさに息抜きであり、現実を忘れていられる唯一の時間だった。
軒並みの屋根の奥には大学の校舎が、ひょこ、と見えている。小走りで道を急ぎながら私は、一息さんと会ったのもこんなふうに道を急いでいた日だったな、とあの日のことを振り返っている。
一息さんは六十だか七十歳の女性で、私の通う大学の校舎から一キロも離れていない地点に家を構えている。家の後ろ手には芒野(すすきの)が広がっており、さらに奥には山があった。山は森と繋がっており、言ってしまえば一息さんの家のある区画が住宅街と自然との境だった。
私は講義の組み合わせに失敗して、毎週金曜日が二コマ目から六コマ目の最終講義までの五コマが空いてしまった。暇な時間をどうつぶそうかと半年のあいだ試行錯誤したがさすがに朝の十時から五時までの待ち時間は長すぎる。かといって家に帰るには、私の家は大学から離れすぎていた。バスで片道二時間かかる。
折衷案として私は、大学近辺の地形を観察することにした。卒業論文のテーマを等高線の研究にしようと思っていたので、ちょうどよいと考えたのだ。等高線の研究とはいえど、私がやりたいのは輪切りと等高線の比較であり、もっと言うとそこからMRIやCTスキャンくらいに微に入り細を穿った等高線がつくれんじゃろか、と企んでいた。いまも企んでいるが、そのとき私は山に入る前に道路でこけて足を挫いた。
空き缶を踏んだのだ。
誰だよこんなところに捨てたの。空き缶捨てたの誰だよ。
地面に尻を着けながら、痛くないほうの足でダンダンと地面を蹴っていると、おや、と庭から顔を覗かせたのが一息さんだった。
一息さんは白髪交じりの灰色の髪の毛を団子に結っており、座った私が見上げると灰色の鏡餅が垣根に乗っかっているように見えた。
「ちょいとお待ちよ」垣根の壁から声がして、灰色の鏡餅が横に泳いでいく。
間もなくして玄関口から背の低い女性が現れた。逆光になっており、顔がよく見えなかった。私はそのとき、手塚治虫の漫画「仏陀」に出てくるシッダルタのシルエットを脳裏に蘇らせた。というのも、まさに灰色の鏡餅然とした髪型が、漫画のシッダルタとそっくりだったのだ。
「大丈夫かい。おや、立てないのかい」一息さんは私の鞄を拾いあげると、新芽でも撫でるような手つきで砂を払った。私はたぶんその所作一つで彼女のことを信用したのだと思う。
「イタッ」
立とうとしたが上手くいかなかった。足首を捻挫していると判った。傍目からでも一目瞭然なようで、一息さんは私の鞄を持ったまま、「時間はあるかい」と言った。私は戸惑って、どういう意図の発言か、と推し量っていると、一息さんは、「休んでいくといい」と自らの家の門をくぐり、玄関口のまえに立った。「歩けないほどの痛みなのかい。救急車を呼ぼうか」
「だ、だいじょうぶです」
私は足を引きずりつつ、なんとか自力で立ち上がった。踏んだ空き缶も拾い上げておく。一息さんがその様子を目に留めて、事情を察したのか、やれやれ、と忌々し気に首を振っていたが、矢継ぎ早に私へと、災難だったね、と言いたげな眼差しを向けたので、私はもうそれだけで心が晴れるようだった。生まれて初めて憐憫とは何かを知った気になった。憐憫とは一息さんのあの眼差しのことだ。
一息さんの家は和風の長屋だった。二階もあるがそちらは屋根裏といった塩梅で、どうやら一息さんも物置部屋として使っているようだった。というのも、私のためにわざわざ座布団を二階から持ってきてくれたからだ。
「黴臭いかもしれんが、ないよりかはマシだろう」
「ありがとうございます」
「いま氷水を持ってくるよ。待っといで」
「す、すみません」
「あんたが謝ることじゃないさ」
居間は台所と隣接しており、奥で作業をする一息さんの姿が居間からも見えた。
「お一人で住まわれているのですか」私は部屋を見渡した。
「ほかに誰か見えるのかい」
「すみません」出過ぎた質問だったか、と恐縮すると、「あんたは、ちと人に気を使いすぎだね」と一息さんが戻ってくる。手にはビニル袋に入った氷水が握られていた。
「冷やしな」
「すみま――あっ」言いかけて、「ありがとうございます」と言い直す。
「無理して直すもんでもないさ」
一息さんはもういちど台所に引っ込むと、自身の名と無職で暇なことをつらつらとしゃべって、それから間もなくしてお盆にお茶とおせんべいを載せて戻ってきた。
「家は近いのかい。この辺は何もないだろう。あんたの進行方向にゃ林があるだけだ。なら急ぎの用ってわけでもないんだろう」
一息さんは鋭かった。
「講義まで時間があって、それで散歩に」
「ほお。あすこの大学かい」
「はい」
「無理に引き留めはしないが、時間があるならすこし休んでおいで。物凄い音がしたよ。あたしゃ地震かと思った」
「ふふっ」大袈裟だな、と思ったが、一息さんは、「本当さね」と念を押した。
この日は時間いっぱいまで一息さんの家で休ませてもらった。私は一息さんのことに興味が津々に募っていたのだが、一息さんは私の質問には一言で応じる割にその返答は煙に巻くようなものが多く、あべこべに倍になって返ってくる質問に対応するのに私の思考は費やされた。
しかし大学に入学してからというもの、私はもっぱら聞き役の立場でいることが多く、誰も私に質問を浴びせるなんてことがなかったので、この日はすっかり舞台の上の歌姫さながらに、じぶんに興味を持ってくれているらしい一息さんに私は赤裸々にじぶんのことを語っていた。
というのも、どうせきょう限りでもう二度と会うことはないだろう、と思っていたからで、あと腐れのない相手にはじぶんの将来の夢だろうが恥ずかしい失敗談だろうが、ふだん誰にも言えぬ悩みとて遠慮会釈なく言えるのだった。
一息さんは私の答えに大して目を輝かせることもなく、ほうそういうもんかねぇ、といった大樹然とした相槌を挟むばかりで、これがまた私には快適だった。ごくごくといくらでも雨水を飲み干す大樹の根を彷彿とし、私はことさら枯らしてはいかんな、と思って包み隠さずじぶんのことを披歴した。
これがいけなかった。
そろそろ時間じゃないのかい、と一息さんに促された私はしかしもはや講義よりも、きょうはこのまま一息さんとのぬるま湯に浸かったような時間を満喫していたい、との怠惰の念に身も心も染まりきっていたので、「きょうはもうサボっちゃおっかな」と冗談めかし口にした。
「授業料は安かないんだろ」一息さんはそこで初めて私に向けて語気を尖らせた。「そういうのはじぶんで稼いでから言うもんだ」
「は、はい」私は顔面をビンタされた気分だった。泣きそうだった。急に夢から目が覚めたようだった。
帰り支度を済ませ、お邪魔しました、ととぼとぼと玄関口で靴を履いたが、足首が痛くてまごついた。
履き終わると、一息さんが私の鞄を持っていて、はいよ、と手渡してくれた。「毎週こんな時間まで時間が空くのかい」
「はい。そうなんです。愚痴った通りです」この話題は御開帳済みだ。
「そうかい。ならまた暇だと思ったら休みにおいで。手伝って欲しいこともあってね。人手が欲しいと思っていたところなんだ。小遣い程度しか出せないけど、まあ気が向いたら、また寄ってくれ」
「いいんですか」
「嫌ならこなくていいよ」
にひ、と私の喉から変な声が漏れた。両手で頬を押さえながら私は、じゃあまた来ますね、と約束をして一息さんの家を出た。
それからというもの私は毎週金曜日には一コマ目の抗議に出席したあとは、一息さんのお家にお邪魔する習慣ができた。一息さんは庭いじりが好きで、晴れの日はたいがい私が家のまえに着くと垣根から灰色の鏡餅を覗かせて、いらっしゃい、と大してうれしそうでもない声音で挨拶をした。
一息さんに旦那さんはおらず、結婚もしてこなかったようだ。
「そういうのはね。したい人がすればいい」とは一息さんの談だ。
「私はしたいです。白馬の王子様じゃないですけど、運命の赤い糸を信じているので」
「おや。新鮮だね。運命を信じるのかい」
「ダメですか」
「ダメじゃないさ。幸せなコだね、と思ったよ」
「え、そうですか。褒められた」
「幸せにおなり。幸せになるんだ。きみのようなコは幸せにならんといかん」
「なんですかそれ」ぷぷぷ、と私は口元を手で覆う。「一息さんは幸せじゃないんですか」
「あたしかい。あたしは幸せなのかね。じぶんではよく解らんよ」
私はそこで彼女に、寂しくないんですか、と訊きたくなった。でもぐっと吞み込んだ。私より遥かに長いあいだ一人で暮らしてきた彼女に、私のような新参者が投げかけてよい質問ではない気がしたのだ。
「休憩……」
「またですか。いっつも思ってましたけど一息さん、ことあるごとに、【休憩……】とおっしゃいますけど、それはたぶん根を詰めすぎなんですよ。庭いじり」
「ほかにも仕事はあるさね」
「ならそのお仕事が、です」
「そうさな。そうだそうだ。まったくだ」
一息さんは素直なのかひねくれ者なのか判断に困ることがあった。たびたびあった。彼女はいまでも私にとってよく解らないひとである。
私が一息さんから頼まれる仕事はたいがい、買い出しや庭の枯れ葉の回収や、重い植木の移動など、お手伝いと呼ぶに似つかわしい可愛い仕事ばかりだった。その癖、その報酬がひと月で、私の食費が賄えるくらいの額を一息さんが寄越してくるので、私は初めて受け取った封筒をじぶんの家に帰ってから開けて絶句した。
これではお気楽にお家に伺えないではないか。
「私は一息さんのお家には癒されに来てるつもりなんですよ」私はそうつぎの週に抗議した。「あんなにもらったら肩身が狭くてこれなくなります。なので半分はお返しします」
「なら来なければよいだろう」一息さんはにべもなく言った。お茶を啜ると、「そりゃあんたの正当な報酬だ。いらないなら捨てるなり、寄付するなり好きにしな。あたしに返すのはお門違いさ」
「あらそうですか」私はむっとして出した封筒を引っ込めた。「じゃあそうします」
そう言ってその日のお手伝いであるところの買い出しついでに、一息さん用のお高い焼酎を購入した。台所に空の焼酎の瓶が溜まっていたので、晩酌好きなのは知っていた。
何と言って渡せば突き返されずに済むか、と考えながら一息さんの家に戻ると、一息さんの姿がなかった。どこに行ったのだろう。私は居間以外の部屋をそのとき初めて見て回った。
居間で待っていてもよかったが、年配者の一息さんのことが心配でもあった。
襖を開けて覗いてみると、一息さんは奥の和室にいた。和室なのに洋風の椅子と机があり、一息さんはそこに腰掛けてこちら側に背を向けていた。
「あのぉ、ただいまです」
「おや、お帰り。きょうはいつもより遅かったね」
「あの、この部屋は」私は一歩部屋に入った。見渡す限り、壁という壁には習字が貼ってあった。それはどちらかと言えば、干してある、といった風情で、中には巻物のごとき墨絵もあった。山や花が描かれている。
一息さんは振り返ると、小さな丸眼鏡をズラして私を見た。「趣味部屋さね」
「すごいですね。これ全部、一息さんが?」
「ほかに誰か見えたら教えておくれ」
「透明人間がいるかもしれないじゃないですか」茶化しながら私は一息さんの背後に立った。机を覗き見ると、まさにいま書き終わったばかりらしい絵があった。
「墨絵ですか」
「さあてね。どういう流派なのかはじぶんでも判らんよ。見よう見真似。趣味だ」
「それにしてはお上手ですけど」
構図が素晴らしい。荒さの一つ一つが総体で意味を持つように、紙に陰影を刻んでいる。一つ一つを見れば雑なのだけれど、その雑がふしぎと雑ではなく、全体にとって必要不可欠な濃淡になっている。
「こういう技法があるんですか?」
「さあ」
「本当に独学なんですか」目を見開いてみせると、一息さんは、おいしょ、と言ってわざわざ私を押し退けるように立った。「買い物は済んだんだろ。どれ。お茶でも淹れてやるか」
居間に戻るとさっそく一息さんは台所に立った。私は買い物袋から品を出し、それを一つずつ収納棚や冷蔵庫に入れていく。分からない品は一息さんに訊ねるのだが、たいがいは、そこに置いといで、と指示がある。
「あのこれ」私は最後に焼酎を袋から取り出し、床にどんと置いた。思いのほか音が響いて、一息さんの肩が小さく跳ねた。「なんだいそれは」と灰色の鏡餅が横を向く。
「私のお金で買ってきました。大好きなお友達に喜んで欲しくって」
じぶんで口にしておきながら顔から湯気が出た。たぶん本当に出てた。だってお湯が沸きましたよの合図のように火に掛かったやかんが蓋をカタカタカ鳴らしている。
一息さんはつまみを回して火を止めると、手を伸ばした。その所作一つで、寄越しな、と言っていると判る。一息さんはたびたびこうして無言で言葉を発するのだった。威圧的でないのが奇跡的と言えた。
一息さんは一升瓶を受け取ると、ふむ、とラベルに目を留め、こめかみを指で掻いた。それから腰に手を当て、「もらっとくとするか」と言った。
ただそれだけだ。
ただのそれしきのことで私の半径一メートル四方にはシロツメクサが生え揃うようだった。蝶とか舞っていた。蟻がよちよち列をなしていた。日向がぽかぽか心地よかった。
私がそうして一人のぽわぽわ世界に没入しているのを尻目に一息さんはさっさと一升瓶を棚の上に置いて、お茶とお菓子を用意した。
「さ。休憩にしよう」
「あ、持ちますよ」
一息さんはそそくさとお盆を持って居間に移動した。一息さんの背後を私は金魚の糞のごとく、モタモタしながらつづいた。
「あ。オコタの布増えてる」
「いま気づいたのかい」
「あったかくなってる。うふふ。やった」
「寒くなってきたからねえ」
コタツの蒲団が三枚になっていた。厚手の一枚が増えていたのだ。
「さっきも座ったのに気づかなかったです。いいなぁ。あったかぁい。私の部屋にも欲しくなる。買っちゃおっかな」
「おや。小さいのでいいならうちにあるよ。あとで見せようか。欲しければ持ってきな」
「いいんですか」
「分解すりゃ抱えて持って帰れるだろ。お一人用炬燵さ」
「欲しいです、欲しいです」
「ゴミが一つ減る。うれしいねえ」
一息さんの言葉には抑揚がない。どんな言葉も淡々と口にする。怒っているのか、呆れているのか、哀しんでいるのか、不貞腐れているのか。それを言葉の響きだけで聴き分けるのは至難だ。
でも私にはなぜか一息さんの機微が判るようだった。ちなみにこのときの一息さんのそれは照れ隠しで、うれしいねえ、と言ったのも皮肉を装った本音なのだ。私はかってにそう思っている。
先日のことだ。
夏がやってきたのでつぎは秋だ、と流れる季節のごとく金曜になったので一息さんのお家にお邪魔すると、開口一番に彼女は、「一つ頼まれてくれないかい」と言った。
玄関口で私が靴を脱いでいないうちから一息さんは、
「ぜんまいを採ってきて欲しいんだよ。お願いできるかな」とこめかみを掻いた。
「ぜんまいですか」
「すこし行ったところに土手があってね。道沿いに歩けばそれなりに採れるはずだよ」
「いいですけど、一息さんも散歩がてら一緒に行きません?」せっかくオコタに潜って一息さんに話を聞いてもらおう、とスキップ交じりにやってきたのに、せっかくの一週間の癒しの時間が一人で山菜採りはすこし嫌だった。せめて買い物ならば通い慣れた道だからよいが、知らない道で一人は寒さが肌に染みるようになった時節柄、ご遠慮願いたい思いが湧いた。
「あたしはあたしでやることがあるからね。まあ、嫌ならいいんだ。上がりよ」
「大丈夫です、大丈夫です。行ってきますよ。ぜんまいですよね。ちゃちゃっと採って戻ってきますんで」
「助かるね。ほれ、これに入れといで」
籠を手渡され、前払い、とついでのように封筒をもらった。その場で開けて確かめるといつもよりすこし額が多かった。
「こんなにもらえません」と渋ると、「ならその分働いておいで」と送りだされて、私は唇を尖らせる。一息さんから渡された籠は手のひらサイズで、この籠を一杯にするのにぜんまいは五本もいらないだろうと思えた。
こうして私は慣れない山道をたどたどしく辿りながら路肩の藪に目をやって目当ての山菜が生えていないかを探った。一時間くらい掛けて私は一息さんの家に戻った。一息さんは私のためにお菓子とココアを用意してくれており、私はオコタに浸かって、ひと仕事終えた達成感に浸りながら、お褒めの言葉を待った。
籠を覗きこんでしばしの間を空けたのちに一息さんは言った。
「これはぜんまいじゃないよ」
「嘘でしょ」
一息さんの説明を聞きながらじぶんでも端末で検索をして確かめた。たしかに違う。私が摘んできたのはコゴミであってぜんまいではなかった。ほかに渦を巻いた山菜は、わらびもある。一見すればどれも同じに見えるが、属からして違うようだった。
「すみません。お役に立てず」私はしょんぼりした。これぞしょんぼりの見本だな、と思いつつ、以前に目にした一息さんのお手本がごとき憐憫の眼差しを思いだした。
私が顔を上げると、一息さんは湯呑みを両手で持ってお茶を啜っていた。湯呑みの底に手を添えて飲むあたり、茶道でもやっていそうな凛とした佇まいがあった。
コゴミは綺麗すぎる。
一息さんはそれを何度か繰り返し口にした。あたかも緑茶には渋みがあって当然で、それがなくなったらお茶を飲む醍醐味は失われるのだ、と説くような悲壮感が漂っていた。それは私が十全に仕事を達成できなかったことへの小言ではなく、私が同じ世界観を共有できないことにへこんでいるような機微の揺らぎを宿していた。
それはたとえば私の好きな映画を、一息さんがそうと知らずに虚仮下ろした場面に遭遇した具合に似ていたかもしれない。そういう事態にはいまのところ遭っていないが、想像したら私は悲しくなった。マスカラで加工したまつげが、反対向きにくるんとこうべを垂れるようだ。
「うん。まあ、たまには綺麗なのもよいしな」一息さんは見兼ねたように言った。
言わせてしまった、と私は思い、無理くり目じりに皺を寄せた。にっこりしてみせたつもりだが、上手くできたか分からない。お小遣いの封筒をお返ししたいと思ったが、それをしたらもう二度とお家に上げてもらえなくなりそうな予感があった。
「先に言っとくが、お代は返すんじゃないよ。あんたの時間を貰ったんだ。それは正当な報酬だ」
「分かっとります。ありがたく頂戴いたしますけれども」
「そんな濡れた捨て犬みたいな顔をして」
「へへ。そんな顔しておりますかね」
「人はね。たまには失敗してもいい。誰に言われようとも肩を落としていい。あんたがへこたれようと、あたしも遠慮しないで思ったことを言っていい。そういうもんなんじゃないかい」
「でもそれで言ったらあれですよ」私は考えながら、ココアを飲み干した。「一息さんは、たまには私のことをドロドロに褒めそやしてもいいと思いますけどね私は」
「人は、人を無理やりに褒めなくともいい」
一息さんはじぶんで言って、ふっ、と綻びた。私が、あっ、と川べりでホタルでも見つけたみたいに口を開けたからか、すぐにきゅっと口元を結んで彼女はまたいつものような灰色の鏡餅の付喪神じみた風体で、「休憩……」と零すのだった。
その後しばらくは、彼女がぜんまいを何に使いたかったのかは子細には知れなかった。
大学が冬休みに入るまで私は、毎週のように一息さんの家に遊びに行った。ほかにすることもなく、ましてや私の話を聞いてくれる相手などいないのだ。
今年最後の訪問になるだろう金曜日に、私は、一息さんから一枚の絵を貰った。
「私にですか」
「ほかに誰かいたら教えておくれ」
「じつは一息さんは認知症さんで、ほかの人のことが見えていないだけなんですよ」
「そういう冗談は気に食わないね」
「でしょうとも、でしょうとも」一息さんの正論を聞きたいがために私が世の悪を一身に背負ってもよいくらいだ。「見てもいいですか」と断って、返事ももらわないうちから私は額をひっくり返して、まじまじと絵を拝見した。
「うわあ。うわあ。へへへ。うわあしか出てこない」
三本の渦巻きの絵だった。
山菜だ。茎に綿毛がないのでコゴミだろう。
まるで薔薇のようにも視える。
線と筆致と滲みの絵だった。錯綜そのものが層をなして、質感を紙面の上に立ち昇らせている。延々と途切れない線香の煙のようにも感じられた。
「このための山菜採りだったんですね」
「ついでさ。ついで。ただ、ぜんまいのほうが縁起がよいだろう」
「縁起ですか」そういういわくが、各種山菜にあるのだろうか、と想像した。
「ぜんまいは、元は千回渦を巻くようだから千巻きと転じて、ぜんまいになったそうだからね。あなたには、何回転ぼうともネジを千回巻いたように動きつづけて欲しいと思ったんだが、まあこの際、コゴミでもいいと思ってね」
「へえ。ステキなお話」
「コゴミは元は、屈むからきているそうだよ。まさに尻餅をついたまま動けなくなっていたあなたによく似合う」
「それは、え。なんですか。ステキな話なんですか。喜んでいい話なんですかね」
「どうだかね」一息さんは大きな溜め息を漏らした。「コゴミは綺麗すぎる」
「ぐふ。それは何ですか。私にくれてやる絵にはもったいないと、そういうお話なんですか」
いっそ肖像画でも描いてくれたらよかったんですよ、と悪態を吐くと、一息さんは、それも考えたんだけどね、とその場で足を交差した。その立ち姿が湖に立つ鶴を思わせ、私は、そのあなたの姿こそ絵にして飾りたいな、と望んだ。
私の胸中の感動などお構いなしに一息さんは、眼鏡を外し、
「あなたはじぶんの顔を部屋に飾りたいと思う人かなと思ってね」と袖でレンズを拭いた。「あたしなら、あたしのことを描いた絵よりも、あたしのことを思わず、ただ描きたいから描いたその人の表現こそをもらいたいよ。あなたも同じかなと思ったの」
ただそれだけ。
要らなかったら捨ててもいいよ、といつもと変わらぬ抑揚のない冷めた口吻で言うと、一息さんは、もう時間だよ、と私の背をせっついた。「学んでおいで。幸せにおなり。幸せになるんだ。きみのようなコは幸せにならんといかん」
いつぞやに耳にした台詞を祝詞でも唱えるように口にした。
「絵、ありがとうございます。すこし早いですけど、よいお年を。また来年も来ますね」
「もう来なくてもいいよ」
「へへへ。断られても来ちゃお」
人は寒いときは見送りに出てこなくともよい、と言いつけて、私は一息さんの家の扉を閉じた。
外はまだ陽が暮れておらず、冬の日没の遅さを思った。太陽の気持ち、分かるな、と私はバス停までの道を行く。
こんな素敵な一日は、早々容易く終わって欲しくない。
私は一歩足を踏みだして、それから道端に転がる空き缶に目を留めて、逡巡してから拾いに屈む。
コゴミじゃん。
空は秋も暮れ、冬の澄んだ空気をまとっている。
【掛ける目を瞑る】(2022/10/27)
新月は星明かりを鮮明に描きだす。存在しないことで仄かな明かりの生命力を底上げする様子は、まさにわたしたちのようだ。
わたしたちはとある孤島の城に住まう。幼少期の時分でいずこより選抜され、運ばれてくると聞き及ぶ。毎年のように継ぎ足される新顔の幼い顔つきを見れば、否応なくそれが正規の手続きを得た選別ではないと判る。
私たちは城の主たるギルバート伯爵に仕える召使いだ。
毎年、召使いたちのなかからたった一人だけギルバート伯爵のお眼鏡に適い、そして妾として別荘へと住居を移す。そちらの生活は、召使いの身分ではとうてい味わえない甘美で優雅な暮らしだという。わたしたち召使いは、一刻も早くギルバート伯爵のお眼鏡に適うように、目をかけてくださるように、日々慎ましくも懸命に我らが主様のために働くのだ。
わたしたちがギルバート伯爵のお姿を目にする機会は限られる。
新月の夜に開かれるパーティの場か、もしくは城の中を風のように歩き去るお姿を垣間見るくらいが精々だ。
そうしたなかで私が偶然にもほかの召使いたちを差し置いて、ギルバート伯爵との縁をこっそり結んでしまったのは、中庭の薔薇園の管理をわたしが任されるようになってからひと月後のことだった。
薔薇園はギルバート伯爵の初代妾の方が愛でていた庭だそうで、妾制度の礎を築いた方だと聞いている。この薔薇園の管理を任された者は、ギルバート伯爵の妾になることはない、といういわくつきの仕事だ。誰も率先して引き受けたがらないのだが、わたしは何事も主様のためにすべきである、と己に誓っているので、その誰もやりたがらない仕事を引き受けた。
主様のためだ。
ギルバート伯爵のためにわたしの肉は、心は、あるのである。
雨雲が空を覆った薄暗い日だった。
泡立つ肌を温めようとわたしは部屋の箪笥からカーディガンを引っ張りだし、従者服の上から羽織っていた。下品な組み合わせの服装ゆえ、これはあまり褒められた着方ではなかったが、どの道、薔薇園にはわたし以外の人がいない。
見咎められることもない。
そうと油断していたため、
「これは斑点病じゃないのかい」と声がしてわたしは飛び跳ねた。
垣根を挟んだ向こう側に、背の高い影が立っていた。
その人影は垣根を回ってわたしのいる地点まできた。丹念に薔薇の葉を診察するような眼差しは、カンバスに向き合う画家のようでもあった。
「ギルバート様……」
「今年はキミが世話係なのだね」
「はい。仰せつかりました」
「うん。やっぱりだ。斑点病に蝕まれているね。ここの区画はもうだいぶやられているはずだよ。まだ目には映らないだけで、菌糸が巡っているはずだ」
「あの、どうすれば」わたしは庭師ではない。広大な薔薇園のなかを一日がけで水をやり、肥料を撒きながら練り歩く肉の塊だ。
「葉をすべて毟って、薬を撒くよりないだろうね」
「そんな」
蕾がようやく出てきた薔薇たちだったのだ。それを毟るのは酷だった。
しかしギルバート伯爵が言うのだから指示に従わぬ道理はない。薔薇園の所有者が彼であり、彼こそが我が主様なのだから。
「時間が掛かるからゆっくりやろう。きみはここを。私はあちらに手を入れよう」
私が唖然としている間にギルバート伯爵は、手際よく葉を摘み取り、足元に落としていった。
わたしもそれに倣って葉を千切った。
病に侵された葉をあらかた片付け終えたのは、ギルバート伯爵に声を掛けられてから十日も経ってからのことだった。その間、ギルバート伯爵は毎日薔薇園へとやってきた。
わたしは我が主様――毎年一度お顔を拝見できるかどうかという雲の上の方と時間を共にした。体温が伝わるくらいに接近することもしばしばだった。
「パール。きみはここにきてどのくらい経つ」
「わたくしめは、今年で六期を迎えます」
「ほう。ではルビーと同期か」
「はい。ルビーさまはお美しい方です」
わたしの同期では、最も「妾」にちかいと目されている人物だ。おそらく今年か来年には「妾」に選ばれるのではないか、とわたしだけでなくほかの召使いたちも噂している。
「地面の葉を一か所に集めて、きょうの内に燃やしてしまおう。ちょうどあそこに古い井戸がある。あそこに葉を落として、火をつけておけば明日には燃え尽きているだろう。火事になる心配もない」
「ずいぶんとお詳しいのですね。さすがはギルバート様です」
「なに。私も仕込まれた口さ」
そこでギルバート伯爵は、初代妾のペブルさまについて語った。
「ペブルは私の幼馴染みでね。よくここでバラの手入れを手伝わされたんだ。あのコは強引なところがあってね。いつも私が連れ回されていた。私のほうが従者のようだった。いや、私たちのあいだに主従の関係はなかったんだ」
「ステキな関係ですね」
「パール。君はどうして薔薇園の仕事を? 誰かに押しつけられたのかい」
「いいえ。わたしが率先して引き受けました。ギルバート様の大切になさっている庭だとお聞きしていたので」
「そっか。ありがとう。そうなんだ。ここは私にとって大切な庭なんだ。思い出の庭さ。本当なら私はこの庭さえ残っていればほかには何もいらないのだが、そうも言っていられないのが伯爵という地位の好ましからざる点だ。おっと。私がこのような弱音を吐いていたとはほかの者たちに話してはいけないよ」
「誰にも言いません」
言いたくなどはない。
主様との密会とも呼べるこの至福の時を、ほかの者に分け与えようとは考えもしなかった。
「先代のペブルさまはどのような方だったんですか」わたしは地面の千切り葉を箒で掃きながら言った。「妾制度を発案なさったのもペブルさまだと聞きました」
わたしは格上の主君に対して、ほかの召使いの上長たちに話すように話しかけることができた。敬い奉り、憧れの対象ではあるが、それゆえにわたしの意識は未だにこのあり得ない現実を現実として見做していない節がある。緊張しない。夢の中にいるようなのだ。
「彼女はあの制度を否定するつもりでいたんだよ」ギルバート伯爵は応じた。箒に顎を載せ、「皮肉にも彼女の策によって、あの制度が定着してしまった」と目を伏した。箒の代わりになりそうな長いまつ毛が陽の光を受けて輝いて映った。
わたしは単純な疑問として、
「ペブルさまはいまも別荘にいらっしゃるのですよね」と言った。ギルバート伯爵の言い方ではまるで初代妾のペブルさまがすでにいなくなってしまったかのような響きが交って聞こえた。「ペブルさまはいまも否定なさっていらっしゃるのですか。それはどうしてでしょう」
「きみは」ギルバート伯爵はそこで切れ長の目を見開き、それから儚げに微笑なさった。「きみは、いいコだね。賢く、それでいて優しい」
「そう言っていただけてうれしいです。恐縮です。でも、わたしは召使い失格かと思います」
「どうしてそう思うんだい」
「ほかの先輩や同期や後輩たちですらみな、ギルバート様の妾になろうと毎日、じぶん磨きをしています。でもわたしは、ギルバート様に選ばれるよりも、ギルバート様のよろこんでもらうことのほうが大事に思えて。それですら、ギルバート様が笑顔になったり、はしゃいだりせずとも、ただ気持ちよく毎日の時間を過ごしてくださるだけでいいんです。太陽の匂いのするシーツのうえで毎日眠って欲しいとか、埃でくしゃみをすることのない清潔な部屋で過ごして欲しいとか。そういうことのほうが大事に思えて」
「ふむ。きみは私の妾にはなりたくはないということかな」
突きつけられてわたしは、ああそうそう、と思った。その通りだった。言われて気づいた。わたしは妾にはなりたくはないのだ。
「その顔は図星だってことかな。面白いコだね。ペブルとは違うが、どことなく似ている気もするよ。きみはペブルとどこか似ている」
「先代様とですか」
「パールさんと言ったね。きみはどうして妾制度が、妃制度ではないのかと不思議に思ったことはないかい」
「へ?」
「主君が選ぶのだから、そこは妃になるのが普通じゃないかな」
「あの、それはでも」毎年選ぶから妃ではない。本妻ではない。そういうことではないのだろうか。
「初代とて妃ではなく、妾だったわけだ。妙には思わないのかな」
きみたちは。
冷めた眼差しがわたしの心の臓を凍らせた。森の中で野生の狼に出くわしたとしても、もうすこしゆとりが残りそうなものだ。だのにわたしは全身が凍りついたように動けなくなった。
「うん。その反応が正しい。私にはきみたちが必要だが、それはけしてきみたちの幸福には寄与しない。この罪悪を抱いて生きていくよりない私もまたきっと幸福とは程遠い」
「そのようなことは」
「そうだね。このような発言は献身してくれるきみたちへの侮辱だ。申し訳なかった。訂正するよ。私は幸せだ。きみたちのお陰だ」
「光栄です」
千切った葉は井戸に落として火を灯した。どうやら空気の抜け道が横に開いているらしく、炎は渦を巻いて轟々と噴きだした。火柱が上がる。龍が呼吸をすればこのような光景ができるのではないかと思うほど、葉はよく燃えた。
「あすからは薬を撒こう。いちおう、無事な薔薇たちにも撒いておこう」
「はい」
「たぶん、前任の係の者が手を抜いたんだ。きみのせいではない」
わたしの呵責の念を見抜いたようにギルバート伯爵は言った。背伸びをし、きょうは疲れたね、と言って歩きだす。わたしはその大きな背を見送るつもりだったのだが、ギルバート伯爵は振り返り、「どうしたの。おいでよ。いっしょに夕飯を食べよう」とおっしゃった。
わたしはこの日、雲の上の存在である主君ギルバート伯爵の個人部屋で二人きりでの食事を摂った。美味しい、と口では言ったものの味はしなかった。それどころではなかった。寝室を兼ねているのか、脇にはベッドがあり、ギルバート伯爵はわたしより先に食事を終える、汗を掻いたから、と言って備え付けの浴室に入っていった。
わたしは主君のシャワーを浴びる音を聞きながら、食べたこともない豪勢な食事を堪能した。
堪能したはずなのだけれど味はしなかった。ではいったい何を堪能したのかと言えば、時間であり、空間であり、音だった。わたしは主君の匂いの漂う部屋で呼吸をし、生涯聞くことも許されぬだろう主君の沐浴の音を耳にした。
これを堪能と言わずして何を堪能と言えばよいのかをわたしは知らなかったが、しかしこれを堪能と言ってしまうとわたしの召使いとしての立場はおろか、人としての尊厳の何かしらが損なわれそうに思え、わたしは自身に芽生えた昂揚感をないものとした。けして人に知られてはならないわたしだけの感情だ。
「やあ。まだ食べていたのかい」
主君はバスタオルを腰に巻いただけの姿で現れた。主君の肉体美にわたしは、ごっくん、とニンジンを丸呑みにした。甘煮のニンジンはやはり味がしなかった。わたしの目は、城の城壁のごとくボコボコと陰影を刻んだ主君の肉体から目を逸らそうとしつつも、意識に反して釘付けになった。
「食事中に汚いものを見せてしまってすまないね。いつもの癖で着替えを用意するのを忘れてしまって」
「いつもなのですか」わたしはそこに驚いた。「わたくしどもに言っていただければご用意致しますのに」
「違うんだ。そうさせたくなくて隠れているようなものでね。この部屋に他人を入れたのは久しぶりだ」
数十年ぶりではないかな、とギルバート伯爵は言った。わたしはじぶんが特別に招かれたことに舞いあがるよりさきに苦しくなった。この恩に報いるにはこの命を差しだす以外にないのではないか、と思ったのだ。そのつもりではあるが、いざ
「それを食べたらほかのコたちにバレないように裏道から帰るといい。じつはこの城にはみなが知らない隠し通路があってね。私もたまにそこを使って庭へ息抜きに下りたりしているんだ」
「そうだったんですか」
「きみのことも本当はずっと前から知っていたよ。ひと月前だったよね、パールさんが庭師の仕事をしはじめたのは」
「はい。至らなくて申し訳ありません……。簡単な手入れしかできずに薔薇たちを病気にしてしまいました」
「気にしなくていい。きみのせいじゃない」
「前任のコにはお声掛けされなかったのですか」ふと思い立ち、言った。
「そう、だね」
ギルバート伯爵は、箪笥から寝間着を引っ張りだし、するすると羽織った。夜がそのまま布地になったようなシルクのローブだ。「できれば私はきみたちとはあまり関わりたくはないんだ。情を抱きたくないというか」
「当然な所感かと思います。身分が違いすぎますので」
「そういうことじゃないんだ。ただまあ、時々きみみたいなコが交っているとね。どうしても見ていられなくて」
「わたしのような?」
「初代妾のペブルだけは私が選んだわけじゃないんだ」
「そうなのですか」なぜ、と思ったが、それよりも脈絡がなくて当惑した。
「きみに話すようなことではないのだけどね。ただまあ。私はこの妾制度を好んではいない。できれば失くしてしまいたいのだが、そうもいかない事情があるのだね。初代の呪いというべきか。いや、彼女はむしろ率先してきみみたいなコたちのためにその身を捧げたようなものかもしれない」
「あの、ご存命ではあられないのですか」
「そうだよね。こんな単純な疑問すらきみたちは抱けないのだ。初代が妾に選ばれたのはもう何百年も前のことなんだよ。ふしぎには思わないのかい」
ギルバート伯爵はわたしたちよりもずっとお歳を召していらっしゃる。主君となるには長寿でなければならないのだ。わたしたちはこの孤島の城に連れてこられてまずギルバート伯爵にまつわる話を教えられる。
「単純な疑問とはどのようなものでしょう。教えていただければわたしもきっと抱けるようになると思います」
「きみは私以外に男を見たことはあるかい」
「いいえ。召使いはみなわたしと同じような娘ばかりですので」
「そうだろう。そして私は伯爵だ。きみたちにとっては君主でも、わたしよりも位の上の者たちはいくらでもいるのだよ。そして妾制度は、初代ペブルのあの事件を嚆矢として我々血族のあいだで膾炙してしまった。ペブルの遺志とは裏腹に、まったく真逆の用途としていまでは重宝されている」
「ギルバート様の物言いではまるで、わたしたちの存在をギルバート様は好ましく思っていないように聞こえます」
「感謝はしているよ。申し訳なくすら思う」
君主にかように哀し気な顔をさせるわたしはやはり従者失格だ。
「ご馳走様でした。もうお暇します。お休みのお邪魔になりたくはありませんので」
「おや。添い寝はしてはくれないのかい」
「ご命令とあれば致しますが、わたしが床を占めたりなどすれば、きっとお邪魔になります。わたしは寝相がよろしくありませんので」
「それは困るな。ではきょうのところは諦めるとしよう」
わたしは椅子から下りて、食器を片づけようとした。「それはそのままでいいよ」とギルバート伯爵が言うので手を止めた。「よいのですか」
「ああ。それは別荘の料理人に作ってもらったもので、きみたちとは管轄が違うんだ」
「そうでしたか」道理で見たことのない食器だと思った。「そうでした。薔薇園についてですが、あすの薬剤撒きにはほかの者たちにもお声掛けをして手伝わせましょうか」
「ほかの者たちに?」
「二人でするよりも手分けをしたほうが早いと思いまして。葉摘みのときに閃けばよかったのですが、頭が回りませんでした。至らずにすみません」
「そんなことはないよ。薔薇園はそれこそ私の娯楽だ。本来はきみたちの手を煩わせるほどの仕事じゃないんだ。私のほうが頼んでやってもらっているようなものだから。そうそう。私の息抜きでもあるんだ。時間が許すのなら私がじかに手入れをしたいくらいでね」
「そうだったのですね」
「だからあすもきみと二人だけで大丈夫だよ。ありがとう」
「いえ。時間はあるので、ギルバート伯爵がそれでよろしいのであればわたくしもそれがよろしいと思います」
「ではあすもお願いしますね」
「はい。楽しみにしています」
お辞儀をして扉の外に出ようとすると、待て待て、とギルバート伯爵に止められた。腕を引かれ、ふんわりと背に手が回される。伯爵の体温がローブ越しに伝わった。伯爵からは石鹸のよい香りがした。
「そっちじゃないよ。裏道はここだ」ギルバート伯爵は箪笥の横の壁に触れた。
壁には紋様が描かれていた。赤い薔薇の細かな紋様の中で一つだけ青い薔薇があった。そこを伯爵は指で押した。
すると壁に亀裂が走った。亀裂は刹那に扉の縁の形に広がった。
「さっ。ここを明かりに沿って歩いていけばこの時間帯ならばきみの宿舎のどこかには出る。怖くなったら適当に隙間を覗いてごらん。見知った場所が見えるはずだよ」
「大丈夫でしょうか。すこし怖いです」
「なら送っていこう」
そう言ってギルバート伯爵は自ら隠し扉を潜って、裏道に入った。手招きするので、わたしは唯々諾々と差しだされたその手を握った。
裏道は城の至る箇所に通じているようだった。正規の道の明かりが壁越しに漏れているので足元が見える程度には明るい。隙間を覗くと城内の廊下や室内が見えた。
「伯爵はいつもこうして城の中を見て回っているのですか」わたしたちの会話は筒抜けだったのではないか、と不安になった。聞かれて困る会話はしていないが、それでも君主に聞かせられるようなしゃべり方ではないこともままある。
「たまにね。目的はあくまで近道と姿を見られずに逃げ出すためのものだから」
「逃げだす……」
「職務からね。これでも忙しいんだ」
「とてもそうは見えませんでしたが」正直な旨が口を衝いたのは、まさにそのように言って欲しそうに映ったからだ。
「うん。一日を一区切りとすればたしかに忙しくはないかもしれない。私たちときみたちとでは時間感覚が違うから」
「時間感覚……ですか」
「きみが気にすることではないよ。きみたちはそういうことに違和感を覚えないように教育されているわけだから。それがしぜんな反応だ」
「教育……」
「おっと。そろそろじゃないかな。そこを覗いてごらん」
促されて壁から漏れる明かりに顔を近づける。壁には隙間が開いており、そこからは見知った城内の一画が見えた。
「ここ、伯爵の銅像があるところです」
「そうそう。裏側のところが隠し扉になっているんだ。裏側からだと押せばすぐ出られるよ。入る分にはコツがいるから、こんど明るいときに説明してあげよう」
「はい。ありがとうございました」
「ではまた明日。よい夢を見てね。おやすみなさい」
「おやすみなさいませギルバート様」
わたしは伯爵に見送られ、城内の銅像の裏に出た。
壁に埋め込まれたように銅像は建っている。銅像は壁とすっかり接触してはおらず隙間が開いている。ほかにもこの手の銅像が城内にはあちらこちらにあるのだ。ひょっとしたらおおむねの銅像の裏側には隠し扉があるのかもしれない。
わたしは歩き慣れた廊下を辿って、自室に帰還した。
シャワーを浴び、着替え、髪を梳かしもせずに床に横になると融けるように眠りに落ちた。
翌日、わたしは朝いちばんで薔薇園に向かおうとした。しかし途中で、同期生のルビーに呼び止められた。「パールさん、ごきげんよう」
「ルビーさん、おはようございます」
「お早いですね。もうお仕事ですの。慌ててどちらへ?」
「薔薇園です。薔薇たちが病に罹ってしまって、いまはその治療を」
「あらあら。それはたいへんですね。ギルバート様の大事なお庭を損なってしまったのですね」
「ああ、はい。そうかもです」
「かも?」
「いえ、そうです。損なってしまいました」
「その割にずいぶんとうれしそうな顔をしていましたけど」
「そうでしょうか。いえ、そうかもです」
「かも?」
「嬉々としていました。すみません。気を引き締めて職務に臨みます。もう行ってもよろしいですか。薔薇たちにきょうはオクスリを撒く日なので」
「そう。いっそあなたにもオクスリを差し上げたいくらいだわ」
「あればわたしも欲しいです」
「皮肉も通じないのね」
「心配してくださりありがとうございました」
「礼には及ばないわ。たとえ相手がパールさんであろうとも、あたしくしは同期の尻拭いをする立場にあるんですもの。何か困ったことがあったら言ってちょうだい。なんとかしてあげる」
「本当ですか。わあ、うれしいです。では一つお願いしてもよろしいですか」
「厚かましいわね。でもいいわ。パールさんのお願いを聞いてもあたくしには何の得もないのだけれど、それでもあたくしは優しいので聞いてあげる」
「さすがはルビーさんです。じつはわたし、妾制度のことをちゃんと勉強したいと思っていまして、時期妾候補と名高いルビーさんならきっと過去の歴代妾の方々のことにもお詳しいはずですし、よければ資料か何かをお見せしてくださいませんか」
「あら、殊勝なお心持ちですわね。ではパールさんも妾になるべくあたくしと切磋琢磨したいとおっしゃるの」
「いいえ。わたしは妾にはなれません。選ばれたいとも思いません。ルビーさんのほうがよほど妾にふさわしいですから、是非ともルビーさんに妾になって欲しいと望んでいるくらいです」
「あら、張り合いがないわね。でもそういうあなたの分を弁えた態度は嫌いじゃないわ。潔いのって好きよ。ええいいわ。妾制度がなんたるか、その歴史にまつわる書物をお貸ししてあげる」
「ありがとうございます」
「その代わりと言うつもりはないのですけれど、もしよろしければ薔薇園から一輪で構いません、薔薇を戴けないからしら」
「薔薇ですか。構いませんよ」
「ギルバート様が好いたという薔薇をあたくしも一度くらいは直に目にしておきたいの」
「ああでしたら」わたしは宙に視線を漂わせる。「いっそ、薔薇園にこられてはいかがですか。ギルバート伯爵がそこにいるとはいまここで打ち明けるわけにはいかないが、もし一緒に来て偶然に鉢合わせしてしまうのならこれは問題ないように思えた。ギルバート伯爵のほうでわたし以外に会いたくないと判断したならばきっと隠れたままでいるはずだ。
「いやよ。あすこ、なんだか不気味なんですもの」
「はあ。そうですか」
「書物はあなたの部屋にほかの者に頼んで届けさせるわね。引き留めてしまってごめんあそばせ。お仕事頑張ってちょうだいな」
「はい。ルビーさんも、早く妾に選ばられるとよいですね」
「ええ。そのつもりよ」
ルビーは切れ目のない髪の毛を翻して遠ざかっていった。彼女の髪の毛はまるで昨晩目にしたギルバート伯爵のローブのように上品だ。所作一つとっても歩くときに極細の平均台の上を歩くような軸のブレなさある。隙がない。美の極致とは彼女のようなことを言うのだろう、と造形の美しさにわたしは感嘆の息を漏らす。
ギルバート伯爵の妾としてまさに目を掛けられるにはあれくらいの美がいるはずだ。わたしには到底縁のない話だ。
薔薇園へと赴くとすでにギルバート伯爵が水撒きをしていた。
「おはようパールさん。薬を水に溶かしておいたから。水やりと一緒くたにして済ましてしまおう」
「遅れてすみません。同期の方と立ち話をしてしまって」
「いいよ、いいよ。それならもっとゆっくり話してきてもよかったのに。きみの友達は何も薔薇たちだけではないのだろう。私と違ってきみには友達が多そうだ」
「は、はい」
返事に困った。わたしには友達と言える友達がいない。いいや、わたしはかってに友人と思っているが、どうやら相手はわたしを友人とは見做していないらしい。そういうことが多々あった。いまもそうだ。わたしはギルバート伯爵にとっては友人ではないのだ。当たり前の話ではあるが、身分の差を感じなくもなかったので、わたしはややもすると主君に対して親しみの念を覚えていたのかもしれない。
薬剤散布の作業はわたしが思っていたよりもすんなり終わった。病気の葉を毟り取る作業のほうがよほど時間がかかった。
「半日で終わったね。よかった」
「はい」
「ときどき肥料にも同じ薬を混ぜて撒いておくと、予防にもなるから」
「そうします」
「パールさん。きみみたいなコが薔薇園の管理者になってくれて私もうれしい。ありがとうございますね」
「そ、そんな」
薔薇たちを病気にしてしまった上、ろくに対処法も知らなかったわたしが掛けられてよい言葉ではなかった。舌を噛んで自害してしまおうか、と素で思った。
「舌を噛んで自害しようとか考えていないだろうね」
「い、いえ」
「ふふ。判りやすいコだね。面白いコだよ。退屈しない」
わたしは恥ずかしくなった。感情の乱れが面に出ないようにするほかに対処のしようがない。
てっきりわたしはこの日を境にギルバート伯爵は薔薇園には現れなくなると思っていた。けれどそれ以降もことあるごとにギルバート伯爵は薔薇園にやってきて、新しい薔薇の苗や種を持ってきてはわたしに手渡した。
「好きに植えてみて。この薔薇園の模様替えをしよう。パールさんの痕跡を残すんだ」
「そんな滅相もございません」
「でも残すんだ。それがきみの仕事だよ。管理者として職務を全うするんだ」
「ですが」
「お、意見があるんだね。いいね言ってみて」
「それでは先代のペブルさまに申し訳が立たないのではないかと」
「ああ、そういうことか。どうだろうね。でもたぶんだけど、ペブルもそのほうが喜ぶさ。パールさんの好きに庭を育てて欲しいと思っていると私は思うよ」
そのとき遠くの空を見詰めたギルバート伯爵の眼差しは、冬の到来を報せる凍てついた風の下にあって、真夏の木漏れ日のごとく温かさに溢れていた。
妾選抜の儀は年を越した最初の大掃除の後に執り行われる。年末になると、同期の召使いたちはみなそわそわとしだした。最後の得点稼ぎに勤しむべく、いかに美しい振る舞いを取れるのかと「じぶん」という存在から汚点や欠点を削ぎ落とそうと日夜自分磨きをしている。こそぎ落とされた汚点や欠点とて、美しい花を咲かせる養分になるのに。わたしは同期たちの忙しない姿を尻目に、独り寒空の下で薔薇たちに肥料をやった。
冬の薔薇園は雪のごとく白い種が咲き誇る。
わたしは毎日のように薔薇たちに話しかけに庭を訪れ、ときおりやってくるギルバート伯爵と戯れの時間を過ごした。伯爵との会話はもっぱら薔薇にまつわる話で、薔薇園の過去の話もよく話題に上った。
「ペブルは元々、庭師の子でね。城の召使いですらなかったんだ」
「そうだったんですね」
「私がペブルに懐いてしまってね」
「逆ではないのですか」庭師の子が城主の子に懐いたならば話は分かる。
「立場は完全に反対だった。私は存外、泣き虫でね。よく父上や母上、それから教育係たちに叱られては、城中を逃げ回っていた。どこもかしこも父上や母上の味方ばかりでね。私には居場所がなかった」
ここ以外には。
そう言ってギルバート伯爵は染み一つない背広のまま地面に寝転んだ。「いい天気だね。ずっとこのまま寝転んでいたい」
わたしはその様子を立ったままで視界に入れていたが、
「きみも寝転んでごらん。気持ちがいいよ」
と言われて、試しに仰向けに地面に身体を横たえた。青空の海を雲が船のように泳いでいる。だんだんと雲が動いているのか、じぶんが大地ごと動いているのか分からなくなる。
「眠くなっちゃいますね」
「ああ。本当に」
「ギルバート様は、どうして妾を選ばれるのですか」口を衝いていた。単なる疑問だった。あれほど初代妾のペブル様を慕っているのに、なぜほかの妾まで所望されるのか。わたしはそれがふしぎだった。
「きみには正直でありたい。だから答える」一拍の間のあとで彼は言った。「妾を選ばねば私たちは生きていかれないからだ」
「お子様が必要、ということですか」子だくさんを目指しているのだろうか。そう思った。
「いいや。私たち血族には繁殖という概念がない。血分があるだけだ。と言ってもパールさんには分からないだろうけど」
「すみません」
「いいんだ。分からないほうがよいこともこの世にはある。パールさんは城の外に出たいと思ったことはあるかい」
「城の外にですか」
「ああ。自由になりたいとは思わない?」
「自由……わたしは自由ではないのですか」
「うん。そうだね。きみたちはそのように考えるように、疑問を抱かぬようにと枷を嵌められている。手枷のように。それとも足枷のように」
「ギルバート様はわたしが自由を求めたほうがうれしいですか」
「うれしいような、そうでもないよう。いいんだ。パールさんはそのままで。変わるべきは本当は私たちのほうなのだから。でもきっとそうそう容易く変われるようなものでもないのだろう。パールさんはずっとそのままでいてね」
「わたしはたぶん、変わろうと思っても上手に変われません。わたしはずっとわたしなので」
ギルバート伯爵は目を瞑ったのか、間もなくして寝息を立てはじめた。衣擦れのような微かな響きが、わたしにも微睡の風をもたらした。わたしは風に揺蕩うハンカチのようにうとうとと現から夢へと落ちていく。
夢の中でわたしは本を読んでいた。
それは実際に毎晩目を通していた妾制度の歴史にまつわる書物だった。同期のルビーさんが貸してくれた本で、そこにはギルバート伯爵の語ったように歴代の妾たちの名前がずらりと数百年分並んでいた。総勢で数百を超す妾がこれまでに生まれては、別荘へと移った。
いまも息災でいらっしゃるのだろうか。
わたしは書物に目を通し、そこに歴代妾たちの一切のその後の来歴が記されていないことに一抹の不安を幻視した。
妾として抜擢され別荘へと移った者たちは、幸せに暮らしている。
わたしたち召使いはそうと信じ込んでいるだけれど、それはどこまで確かな知見の元に認定された事実であろうか。
本の、とある項に目を留める。夢の中の出来事だけれど、これはすでに体験した記憶の再現なのだとわたしには判った。
妾制度発端となった事件について書かれている。
初代妾となったペブルは、その年、「晩餐会」の代わりに「妾制度」の発案を行った、とある。
初代妾のペブルは、自らギルバート伯爵の贄血となることを宣言したのだそうだ。
ペブルが宣言した贄血とは、妾制度ができる以前に、ギルバート伯爵の親族たちのあいだで罷り通っていた「晩餐会」における大役のことだという。召使いたちは毎年、ギルバート一族の「晩餐会」の贄血として、大役を一同に任されていたそうだ。
それを初代妾となったペブルが、大役を一年に一人のみに限定した。自ら贄血を引き受けることで、そのような新しい制度を確立したのだという。
わたしは夢の中で、その場面の目撃者となる。
豪勢な食事の並ぶ宴会場にて、初代妾ことギルバート伯爵の幼馴染のペブルさまが、扉を開け放ち、そこここに並ぶ贄血なる大役に抜擢された召使たちのまえに立つ。そして何かを言うのだ。
その形相は、怒りに燃えており。
その立ち姿は、勇猛にして果敢だ。
ギルバート伯爵はそのころきっとまだ伯爵ではなく、みなから祝われる立場でありながら、誰よりも目上の者たちを労い、敬い、献身する立場であっただろう。
ギルバート伯爵がそうであったように、ペブルさまを慕う者はすくなくなかったはずだ。召使いたちは、召使いでもないのに大役を引き受けると言いだしたペブルさまをどう思っただろう。
せっかくの機会を奪われたと思っただろうか。
それとも、ペブルさまの言葉に何かを思い、大役を下りるだけに留まらず、ペブルさまに大役ごと何かを譲ろうとしただろうか。委ねようとしたのだろうか。
分からない。
いったいそのとき何があったのか。
贄血とは何で、晩餐会はその後になぜなくなったのか。
どうして妾制度が代わりに設立されたのか。
ぶるる、とわたしが身体を震わせると身体にはらりと温かい膜が張った。目を開けると、ギルバート伯爵がわたしの身体に上着を掛けているところだった。
「おや。起こしてしまったかな」
「寝てました」
「もう日が暮れてきたよ。寒いから戻ろう。きょうは私の部屋でお茶を淹れてあげるよ」
数回に一度は、こうしてわたしはギルバート伯爵の個人部屋に招待された。これはおそらく、とわたしは見抜いている。どうあってもわたしが妾に選ばれることはなく、候補にもならないからこその優遇なのだと。仮に特別扱いしたところで、野良猫に施すミルクのような扱いにすぎないのだとわたしは自覚していた。
主君の施しを受けるのも召使いの役割の一つだろうと思い、拒まずに甘受している。
暖かい室内でお茶を啜る。召使いのわたしがすべきことなのに、ここではギルバート伯爵がお茶を淹れてくれる。わたしはじっと椅子に座っていることが役目なのだ。主君にそのように徹しよ、と命じられてしまえばわたしごときが逆らう真似はできない。
「パールさんはここではお人形さんと同じだから」そう言ってギルバート伯爵はおままごとをして遊ぶ幼少組みの召使いたちのように、殊更わたしを甘やかすのだった。
「このお菓子、美味しいです」
「口に合うならよかった。親戚の侯爵のお土産でね。いま人間たちのあいだではそのクッキーが人気らしい」
「人間たちのあいだでは?」
「ああいや。言葉の綾さ」
「贄血とはなんですか」わたしはぽつりと口にしていた。ギルバート伯爵が椅子に腰かけようとしていて、一瞬動きが止まった。そのまま椅子に座ると彼は両手を祈るように組んで、その上に顎を載せた。「どこでその言葉を?」
「はい。同期のコに本を貸していただいて。妾制度についての本です。歴史の」
「勉強熱心だね。パールさんも妾になりたくなったのかな」
「いえ、そういうことでは」
「うん。あれは、みなが思うような素晴らしいものではないよ。だから、みながこぞって目指したくなるような装飾を施している。そうしないと明日にでも妾の担い手はいなくなる。候補すら見繕えずに、私たちは途方に暮れて、以前のような【晩餐会】を開くこととなる」
「その晩餐会は、どうしていまはなくなったのですか。妾制度とはどう関係があったのでしょう」
「本にはなんと書いてあったんだい」
わたしはギルバート伯爵に読んだ本の内容を掻い摘んで話した。
初代妾のペブルが晩餐会に乗り込んだ話だ。
「まあ、嘘は書いていないか」ギルバート伯爵は紅茶のお代わりをわたしのカップに注いだ。長テーブルの端に、わたしと伯爵が直角を描いている。交わるようで交わらぬ最短にして最小の距離だ。「晩餐会は、我らが一族の闘争の場だよ。命を繋ぐために、一族総出で、最も立場の弱い領地に出向き、その庭に集った果実を根こそぎ喰らい尽くす。しかしそのために、いつだって一族内での闘争が絶えず、できるだけ果実を多く収穫しようと、不要な果実の乱獲が盛んに行われた」
「果実とはどういうものなのですか」どんな樹に生るのか、と気になった。いまの技術ならば栽培できるのではないか、とわたしは考えた。
「そうではない。そうではないんだ。私はいまでこそ伯爵の身分だが、当時は父上も母上も、男爵の地位でね。言ったら、最も【晩餐会】の舞台になりやすかった立場だった。私がいま伯爵なのも、初代妾となったペブルのお陰だ」
「晩餐会ではきっとたくさんのお食事が必要だったのでしょうね。取りやめて正解だったと思います」わたしにはそれくらいの慰めしか言えなかった。「ペブルさんはきっと生き物の命を大切にしましょう、と言いたかったんだと思います」
ギルバート伯爵はそこでカップをテーブルに置いた。中身が零れた。手が震えている。空いたほうの手で目元を覆っていた。
「どうされたのですか」
「なんでもないよ」そう言葉で言いながらも伯爵の声は震えていた。手の震えがそのまま声にまで伝わったかのようだ。
しばらくギルバート伯爵は目元を押さえたきり声を発しなかった。
わたしはじっと伯爵を見守った。
カップに添えられた手が震えていて、あたかも凍えて見えたのでわたしはその手におそるおそる触れた。
冷たかった。まるで冬の土のように。
「パールさんは温かいね。まるで夏の土のようだ」
わたしの胸中に湧いた所感と似た返事に、わたしはくすりと笑った。
「笑ったね」ギルバート伯爵は深呼吸をすると、ようやく目元から手をどけて、わたしたちのあいだに漂った沈黙を誤魔化すように背伸びをした。「やれやれ。むかし話は湿っぽくなっていけない。パールさんとはもっと未来について語りたいよ。そうそう。アリス婦長はお元気かい」
アリス婦長とは、召使いの中でも最古にあたる方だ。わたしたちの親のような存在だ。
「はい。矍鑠とされています。現場仕事からは引退されていますが、後継の育成に力を注いでいらっしゃいます。そう言えば、アリス婦長は一度も妾制度に候補にもならなかったようですね」
「ああ、そうなんだ。でもアリス婦長のような方が残っていなくてはきみたちも困るだろう」
「そう、ですね」
「ああいう方は妾にはもったいない」
「きっとそれを聞いたらお喜びになられると思います」
「だといいけどね。あの人のことだから、嘘おっしゃい、の一言で一蹴されるのがオチさ」
「おっしゃりそうですね」想像するのが容易かった。
「ペブルはね。ああいうアリス婦長やパールさん、きみみたいなコたちのために、【晩餐会】を阻止しようとしたんだ。召使いでもない、単なる庭師の子供だった癖にね。そのころから断絶されていた他所の城地とほかの区域の人間たちまで巻き込んで」
「ギルバート様?」
「飢饉さえ起こらなければきっとペブルの狙い通りに事が運んだのかもしれないのに。けっきょく、人間たちのほうでも飢饉であぶれた子どもたちを口減らしに捨てざるを得なくなった。そうした子どもたちを引き受ける代わりに、私たち一族は、人間たちの里に、家畜や食料の種や苗を贈った。ここに妾制度の礎が築かれた。私たち一族のあいだの位による不公平さも、妾制度によって、各々の城から毎年一人の妾を選ぶことで、【晩餐会】を開くことなく贄血を賄えるようになった。順繰り巡る回路がこうして築かれた。里から子どもたちが各地の城へと渡り、子どもたちを教育しながら私たちは人間たちにとっての食料を、各地から搔き集め、ときに城内で栽培し、配る。私たちは一年に一度の【贄血】を摂れれば、あとは人間たちと似たような食事を摂るだけでも生きながらえる分には充分だ。各地の里を滅ぼさず、永続的に生存を可能とする妾制度はこうして完成し、いまに至る」
「すみません。むつかしい話で、よく分かりませんでした。それではまるで妾が、食材か何かのように聞こえます」
沈黙が部屋を満たした。風が窓を叩き、反響音が部屋の隅の気温の低い箇所を浮き上がらせるようだった。
「冷えるね。暖炉の火をもうすこし強くしよう」伯爵は暖炉に薪をくべた。
この日は食事を摂るとわたしは、二十一時を回る前に隠し通路を通って自室に戻った。このころにはもう伯爵は見送りについてくることはなくなった。わたしのほうでも自在に隠し通路を行き来できるようになった。
年末は雪が積もり、薔薇園でのわたしの仕事は雪掻きが主な内容となった。けれどこれは、ギルバート伯爵の案で、薔薇たちに傘をつける工夫により、雪掻きをせずに済むようになった。
わたしは年末年始をゆっくり過ごせた。その間、ギルバート伯爵と会う機会はなかった。薔薇園で会わなければわたしと伯爵とのあいだに接点はあってないようなものだった。この状況が本来なのだ。わたしはシンシンと積もる雪を窓越しに眺めながら、束の間の休暇を満喫した。
年が明けても、わたしのすることは限られる。肥料の準備と、傘の上に積もった雪下ろしくらいがせいぜいだ。雪融けの訪れを待つよりない。
わたしは大掃除の手伝いに駆りだされ、半年ぶりに騒がしい場所で作業をした。ほかの召使いたちに交じって働くのはたいへんだが、新鮮でもあった。知らない顔も多く、みな与えられた仕事に一生懸命に取り組んでいる。
わたしはじぶんの領分を越えて作業をしてしまうので、注意を受けるし、顰蹙を買う。そのたびに、一足先に終わった分をぼうっとして過ごしていると、やはりそこでも叱られるのだった。
「ちょっとパールさん。あなただけサボって、みなに申し訳ないとは思わないの」
「すみません。ですがわたしの分は終わってしまったので」
「ならほかのコたちを手伝ってあげたらどうなの」
「そうしたつもりなのですが、迷惑だと怒られてしまって」
「あなたって何をやらせてもどんくさいのね」
「どんくさくてごめんなさい」
仕方がないのでわたしは、最も作業の遅れているコの手伝いに回った。さすがに最も出遅れているコは、わたしの手伝いを黙って受け入れてくれた。感謝もないが、かといって追いだされる真似もされなかった。
みなカリカリしている。
きっと妾選別の儀が近いせいだ。
わたしはできるだけ目立たぬよう、みなを刺激しないように静かに過ごした。
そしていよいよ妾選別の儀の日。
わたしは風邪を引いて体調を崩した。せっかくの妾選抜の儀に参加できなかった。どの道、わたしが選ばれることはないので難はないが、誰が選ばれたのか、ギルバート伯爵がどんな顔で召使いたちのなかから妾を選ぶのかを見られないのは残念に思った。
城内にある教会にて妾選抜の儀は開かれた。それはそれは神聖で荘厳な儀式となる。一年に一度ということもあり、わたしたち召使いたちにとっては楽しみの一つだ。それを見逃したとなれば、やはり尾を引くものがある。
咳を耐えながらわたしは、床の上で窓の外に舞う雪が徐々に雨になっていく様を眺めた。きっとこれが最後の雪になるのだろうと予感しながら。
もうすぐ春がやってくる。
夜になるころに、同期の召使いが見舞いにきてくれた。アリス婦長に頼まれたそうだ。そのときにわたしは知った。
今年選ばれた妾は、ルビーだった。
わたしの同期から妾が出たのは初めてのことで、じぶんのことではないのに喜ばしく、鼻がすこしだけ高くなった心地がした。
寝返りを打ったところで、ルビーにお別れの挨拶を言えなかったことに思い至った。でもルビーのほうではわたしの言葉など霞んでしまうほどの祝いの言葉をいくらでも掛けられるだろう。むしろわたしの言葉で晴れ舞台に泥を塗らずに済んだだけよかったのではないか。
こうして遠くから祝うくらいがちょうどよい気がした。
ルビーおめでとう。
おめでとうルビー。
しばらくはギルバート伯爵とも会えない日々がつづくだろう。別荘地にてルビーと伯爵が仲睦まじく暮らしている姿を想像し、暖かく満ち足りた心地に浸った。わたしはそこにいなくていい。むしろ、伯爵にはもっと薔薇のような存在と共に暮らして欲しい。時間がもったいない。わたしに割く時間は、もったいない。
あとで聞いた話だと、ルビーは妾発表のときに薔薇を一輪胸に挿していたそうだ。わたしが頼まれて薔薇をあげたのはずいぶん前のことだから、きっと誰かに頼んで薔薇園から捥ぎ取ってきてもらったのだろう。わたしに一声なかったのは、何らかの配慮なのか、それとも契機の問題だったのか。いずれにせよルビーは、わたしが手塩にかけて育てた薔薇を胸に、妾となって、わたしとは別の世界の住人として旅立ったのだ。
もう二度と会うことはない。
ギルバート伯爵と同じ、雲の上の存在となったのだ。
おめでとう、とわたしはもういちど念じた。
雪が融けてから薔薇園の管理の仕事を再開した。きっとわたしは一生死ぬまでこの仕事をつづけるのだろう。そう予感しはじめていた。
ギルバート伯爵が薔薇園に現れたのは、仕事を再開しはじめてから三日と経たぬ間のことだった。
「やあ、パールさん。元気だったかな。薔薇たちはどうだろう。冬を無事に越せたかな」
「ご無沙汰しておりますギルバート様。薔薇たちは元気です。傘のお陰で難なく春を迎えられたようですよ。ギルバート様のほうこそ、よいのですか。妾をお迎えになられたばかりではありませんか」
「うん。そうなんだ。そう言えば、儀式の場にパールさんの姿がなかったように思えたのだけれど」
「はい。風邪で寝込んでおりました」
「なんと。知らなかったな。お見舞いに行けたらよかったのに」
「そんな滅相もございません」
「きょうは薬剤入りの水を撒いて早めにあがろう。剪定作業はもうすこし暖かくなってからでもいいだろうし」
「はい」
ギルバート伯爵の言うように薬剤を溶かした水を撒いてこの日は仕事完了とした。とはいえ薔薇園は広い。伯爵と手分けをしても、朝からつづけて十五時まで掛かった。貯水槽にあらかじめ薬剤を溶かしていたので半日で済んだが、本来ならばこれは三日掛かりの仕事だ。わたし一人ならば一週間はかかる。ギルバート伯爵の手腕と工夫あってこその短縮だ。
「お疲れ様。今年もよろしくお願いしますね」いつもの部屋に移動して、紅茶で乾杯をした。すこし遅い新年会だ。
「はい。こちらこそよろしくお願いいたします。ギルバート様もお忙しいのに、お手伝いまでしていただいて。召使いの分際で恐悦至極です。幸甚の至りです」
「パールさんは言葉が硬いな。もう私ときみの仲じゃないか」
「どういう仲なのか分かり兼ねます」正直な所感だ。
「そうだな。主従の範疇でくくれない、単なる個と個の関係かな」
個と個の関係。
考えてみたが、よく分からなかった。この事実一つとってもも、ギルバート伯爵とわたしのあいだには越えられない深い溝があるように思えた。
「ルビーさんはほかの妾の方々と仲良くできているでしょうか」わたしは同期のよしみで心配した。「ルビーさんは負けず嫌いなところがありますから、打ち解けるのに時間がかかるのでは、とすこし気にしています」
「パールさんは優しいね。でも大丈夫だよ。ルビーさんも……そう、ほかの妾のコたちのように上手に【打ち解けよう】としているところだから」
「それはよかったです」
「そうだ。きょうは新しいデザートがあってね。ちょっと待っておいで。いま取ってくるから」
わざわざギルバート伯爵が取りに行かずとも、と思ったけれど、そこは事情があるのだろうと思うことにした。たとえば、本当はかってに食べたらいけないのだが、ギルバート伯爵がわたしに食べさせようと思い隠していたのかもしれない。
「子どもみたいな方」
「ん。何か聞こえたな」扉を開けて伯爵は言った。「すぐに戻るよ。紅茶とクッキーでお腹いっぱいにしないこと」
「はぁい」甘い返事が喉から出た。じぶんでも驚くほどの変化が、この間にあったのだと知った。
ギルバート伯爵が部屋から消えた。
しんと静まり返った部屋でわたしはお人形さんらしくじっとしていた。
するとどうだろう。
風の音の狭間に、妙な声が交って聞こえた。人間の声だ。すすり泣き、呻き声、それとも悲鳴。よく分からない。言葉ではないが、何かが声を立てている。大きいかと思ったら小さく、繁殖期の猫の鳴き声のようでもある。
わたしはそわそわとして落ち着かなくなった。
どことなく聞き覚えのある声に聞こえたからだ。しかしそんなはずはない。彼女はそんな声を出したりしない。高潔で誇りを胸に生きていた。彼女なはずはない。
しかしわたしはそれを否定しきれなかった。
椅子から腰を上げ、扉に近づく。
意を決して取っ手を握り、右にひねった。きぃ、と小さな音を立てて扉が隙間を広げる。
顔を差しこみ、扉の奥を覗きこんだ。廊下だ。わたしたち召使いたちの居住区のある区画とは違い、全面が石造りの空間だった。
呻き声はいっそうハッキリとわたしの耳に届いた。どうやら隣の部屋らしい。そこに誰かがいるのだ。
わたしはギルバート伯爵からの言葉を思いだし、きょうはまだ「扉の外に出るな、じっとしていろ」と命じられていないことをよくよく確かめてから、一歩足を踏みだした。
隣の部屋の扉は思ったよりも遠かった。三十歩は歩いた。
扉のまえに立ち、しばらく耳を澄ました。やはり中に誰かいる。すすり泣き、呻き、悲鳴している者がいる。一人だろうか。二人以上いるようには思えなかった。
鍵が掛かっているだろうと思って取っ手を捻ったが、案に相違して扉は難なく開いた。
わたしは隙間に身を滑りこませるようにして部屋の中に入った。
薄暗い室内はじめっとしていた。わたしがいたギルバート伯爵の部屋とは大違いだ。
声は、部屋の奥の一画から響いていた。窓には目張りがされており、月明かりも届かない。
明かりは廊下から差しこむ松明の火のみで、それも扉の隙間からかろうじて部屋の中に影の濃淡を浮かび上がらせる程度だった。
わたしは呻き声の主のいる場所まで歩を進めた。
そして、ひょっとして、と思っていたそこにいるだろう者の名を呼んだ。
「ルビー……さん?」
途端。
声の主は暗闇に沈んだまま、言葉にならぬ慟哭を吠えた。獣と聞き紛うほどの激しい声量にわたしはその場で尻餅をついた。
尻を引きずるように後退し、そして部屋を後にした。
獣のごとき慟哭の狭間に、鎖のジャラジャラと擦れる音が反響していた。鼻には鉄の臭いがびっしりとカビのごとく膜を張った。
わたしはギルバート伯爵の部屋に戻った。
明るい室内に、清潔な家具たち。
仄かな石鹸の匂いは、ギルバート伯爵の体から立ち昇る香りと似ていた。
わたしは椅子に腰かけ、それからいましがた体験したことをどう解釈すべきか考えた。隣の部屋には誰かが囚われている。
ギルバート伯爵に言えば助けてもらえるだろうか。けれど伯爵がそのことを知らないはずもない。ではあれは伯爵の指示によるものか。
なぜかような非道を働くのか。
眩暈を覚え、わたしは眉間を揉むようにした。
それから手のひらを見詰め、そこが真っ黒に染まっていることに気づいた。
「お待たせ、パールさん。おとなしく待っていたかな」
ギルバート伯爵が両手にお盆を抱えて現れた。扉を器用に腰で閉め、にこやかにわたしの元までやってくる。距離が縮まるほどに彼の表情は雲っていった。
わたしは彼を見上げ、彼はわたしを見下ろしている。
「どうしたんだい、その手」
お盆を置くと彼は心配そうにわたしの手を丹念に確かめた。血だと思ったのだろう。だがそれはわたしの血ではない。
わたしが怪我をしていないと判ると彼は息を吐き、それからわたしの全身に目を配った。わたしもそこで遅まきながら、じぶんの衣服が汚れていることに気づいた。地面に尻餅を着き、引きずったからだろう。服は臀部に掛けて真っ黒な染みができていた。いまなお、ぽたりぽたりと床に雫を落としている。粘着質な雫だった。
「そっか。見てしまったんだね」ギルバート伯爵は眉を八の字に寄せた。
「お叱りになられないのですか」
「パールさんがわるいわけではないから」
「あすこにおられるのはルビーさんですか」
「ああ」
「妾様になられたのに、なぜ?」
なぜあのような酷い扱いを受けるのか、とわたしは不思議だった。
「妾だからだよ。妾とは、私たち血族を生き永らえさせるための贄であり、血だ。ああして一年間、死なぬようにしながら私たちは妾から血を啜る。逃げられぬように手足を落とし、その落とした手足とて私たちはご馳走と見做して食べてしまう。きみたちにとっては化物そのものだ」
「そう、だったのですね」わたしは伯爵の言葉を素直に受け取った。跪き、懺悔をするかのような伯爵の姿があまりに惨めで愛おしく映ったからかもしれない。
「怒らないのかい」
「どうして?」
「私たちはずっときみたちを騙しつづけてきたんだ。命を差しだすことになる大役を、さもお姫さま候補を見繕うかのように偽装して。怒るのが当然だよ」
「そうは思いません。わたしたちはギルバート様に命を捧げている身です。たとえそれが言葉通りに命を捧げることになろうとも、それがギルバート様のためになるのならば本望です」
「それはね、パールさん。パールさんがまだ、妾に訪れる悲惨な末路を体験していないから言えることだよ」ギルバート伯爵はそこで初めてわたしに怒気にも似た声音を浴びせた。怒りを押し留めるようなこもった響きは、却ってわたしに伯爵への忠誠を固く結晶させるひとつまみの塩となった。
「ギルバート様が妾に訪れる末路を快く思っていらっしゃらないこと、そのお気持ち一つでわたしたちは救われるように思います」
「それは間違っているよ。それは間違った気持ちだ」
「ですが、そのようにわたしたちは教育をされているのでしょう? ならばそのように考えるのもまた当然のことかと存じます」
「私はできればきみたちにあんな目に遭って欲しくはない。私一人の命を投げ出して終わらせることができるのならいつでもこの身を捧げよう。しかし、私だけの問題ではないのだ。私がいなくなればこの城の召使いたちはほかの地の血族の肥しとなるだろう。晩餐会が再び復古してもおかしくはない。なれば私はそうならぬようにと采配を揮う役目から下りるわけにはいかない。せめてその間、パールさんやアリス婦長のようなコたちを妾にせぬように尽力するよりない。せいぜいがその程度の力しか私にはないのだ」
「苦しんでおられるのですね。苦しいのですね」
「死ねるものならいっそ死んでしまいたいほどに」
わたしはそれを聞いて、考えを曲げた。ギルバート伯爵がそのように苦悶なされているのならば、妾制度はないほうがよい制度と言える。本望ではない。たとえこの身をギルバート伯爵のために費やせるのだとしても、その結果に伯爵が苦しまれては本末転倒だ。
「では、破棄しましょう」
わたしが言うと、ギルバート伯爵は顔を上げた。夜道で出遭った猫のような表情で固まる。
「死んでしまってもいいとお考えになるほどに苦しいのであれば、そのように致してみてはどうでしょう。死ぬ気で抗ってみてはいかがでしょう。わたしたちもお供致します」
「上の位の血族たちに反旗を翻せと、パールさんはそう言っているのかい」
「それがギルバート伯爵の本意であるならば」
「いや、しかし」
「分かります。ギルバート伯爵はお優しい方ですから、あくまでそこは手段にすぎないのでしょう。誰も傷つかずに、妾制度も晩餐会も失くせるのならそれがよろしいのでしょう。たとえその末に、ご自身が滅ぶことになったとしても」
「パールさん……きみは、いったい」
「わたし、なんとなくですが、先代妾のペブルさまのお気持ち、いまならすこし解る気が致します」
そしてきっと、とわたしは言う。
「ギルバート様も、いまのお気持ちはペブルさまと同じなのではないのでしょうか」
伯爵がわたしの手を強く握り締めた。骨が軋むほどの強さで、その痛みがわたしには心地よかった。
「ギルバート様は一つ、誤解なさっています。たとえ妾制度の真実を明かされても、わたしたちはみな妾を目指すでしょう。いいえ、わたしがそうであるように、きっと真実を知ったからこそ率先して目指すようなコたちのほうが多いと思います。そしてみな、あなたにそんな悲痛な面持ちをさせる制度に、ひどく怒りを募らせるでしょう」
ギルバート伯爵はそこで、隣の部屋の妾のごとく、押し殺した声で慟哭した。
産まれて初めて痛みを分かち合えた渡り鳥のように。
それとも冬に咲く薔薇のように。
渦を巻く花弁のごとく皺くちゃの表情に、同じくらい嗄れた声音を咲かせるのだった。
わたしはそれが、ひどく貧相で雪の結晶がごとく儚き姿に思え、胸の内に一輪の花が開花するのを感じた。
わたしは伯爵の頭を撫で、わたしの膝に顔を埋めて泣きじゃくる狂おしき者の無様な姿に、この先の未来を幻視する。この赤子がごとき危うげな者をかように痛めつづけた制度を、者たちを、わたしは――わたしたちは、許さない。
この命、果てようとも。
よしんば、貪り食らわれる未来が訪れようとも。
わたしは、断じて許さぬだろう不動の未来を、この胸に咲いた薔薇のごとく、緩やかに、柔く、思うのだった。
【贄に幸あれ】(2022/10/31)
今、村を翔けている吾(われ)はもはや人ではなくなった。
人間ではない。
人は村を駆けることはあっても、翔けることはない。飛ぶことはない。飛翔しない。
事の発端は、村での祭りのことだ。
毎年、山神さまに生贄を捧げるのだが、今年は吾の妹に白羽の矢が当たった。
妹の名をサチと言った。山の幸、海の幸、なんでもよいが幸あれと思いつけた名だ。吾は兄にして名付け親でもあった。
父と母は幸を産んだその日の内に、雪崩に遭って死んだ。サチと吾だけが生き残ったが、村には子どもに施せるだけの蓄えはなかった。
吾は命乞いをし、何でもすると村の者たちに生涯の誓いを立てた。せめてサチが一人立ちできるまでのあいだ世話をさせて欲しい、働かせて欲しい、と訴えた。
その甲斐あってか、吾は村のあらゆる汚れ仕事を任された。その業種は多岐に亘り、却って吾は重宝されるようになった。かといって村での地位は下の下である。
村を囲う山々には神さまがおわした。数年に一度の頻度で訪れる大嵐が祭りの合図だ。吹雪と雷の入り混じる悪天候は、山の神が生贄を欲しているから引き起こる奇禍であると村人たちは見做した。
そうして数年に一度、村の中から山の神が好みそうなうら若き娘、ときに肉付きのよい青年が生贄に選ばれ、捧げられた。生きて帰る者のない片道の旅路である。
いつか生贄に差しだされるだろうとは考えていた。いかに村の役に立とうともごく潰しであるのに異存はない。
なれば妹の成長を見届け、この身と引き換えに村での身分を与えてやるのも一つだ。そうと考え、生贄になる未来を待ちわびていた。
だがどうだ。
今年、生贄として抜擢されたのは吾の妹、サチであった。
「なぜワタクシではないのですか」
「お主にいまいなくなられては困る。男手はあって困るものでもないしの」
「ですが、サチは、サチは」
「まだ幼い。嫁の貰い手もなくはないが、家財がないのでは得もなかろう。損を承知で身請けする酔狂は、この村にはおらんでの。すまんが堪えてくれ」
村長じきじきに頭を下げられたのでは、断るわけにもいかない。ここで話を折れば、吾ら兄妹に居場所はない。
「万事、承知致しました」
吾は唯々諾々と許可を下した。否、吾に下せる許しなどはない。誰にもない。
生贄にされる妹の意向は根っこからないものとされた。妹は吾の所有物ではないのにも拘わらず、あたかも吾の所有物がごとき扱いを受けた。そしてそれを知っていながらに吾はどうしようもできずに、その忌まわしい流れに身を任せてしまった。委ねてしまった。そうせざるを得なかった。
妹にはなんと説明したものだろう。言えるわけもない。
苫屋にも入れず、頭を抱えていると、
「兄さま。兄さま」戸口から妹が顔を覗かせた。土間に正座となると、襟を正した。「サチは贄となりとうございます」
「おまえ。聞いていたのか」
「兄さまの悩むお姿を見て、ぴんと来ました。先日の嵐。祭りが近いこと。あとはほかの家々から漂う夕餉の香りが、どことなく美味しそうな匂いであることから、みな肩の荷が下りた様子とお見受けしました」
であれば、なぜ兄がいつまでも家に入らぬのか、困惑しているのかの理由は自ずと絞れてくるというもの。吾の妹は、吾よりも賢い。けして村の荷物にはならぬ。
むしろ、下手に働こうものならば、村人たちよりもよほど上手く仕事をこなすだろう。仕事を奪うだろう。それすら見越して、サチは家の中で日がな一日を過ごし、村のごく潰しの地位に甘んじているのだ。
「サチ。逃げよう。村への恩は兄ちゃんがもう充分返した。二人で逃げよう」
「ううん。駄目だよ兄さま。山神さまはきっと村を滅ぼすし、あたいたちも無事では済まないよ。そうでなくともあたいはきっと一生後悔する。そんな時を生きたくはないんだ」
「サチ……」
「兄さま。兄さまがいなければサチは花の香りも、虹の色どりも、せせらぎの冷たさも知らずにいたよ。もう充分生きたよ。でも兄さまはサチのために、村のために生きてきたでしょ。もう充分だよ。あとは兄さまが、兄さまのために生きて」
吾は、吾は、一回りも幼い妹にかような言葉を吐かせてしまうほどにろくでなしの未熟者であった。
誰より他を思う吾の妹が。
身を尽くせる個が、娘子が、贄にされる世はおかしい。
村の者たちが許しても、よしんば山の神が許そうとも、吾が許せん。
「サチ。サチ。おまえの命、兄ちゃんに預けてくれんか」
「兄さま。何をする気だ。やめてけろ。やめてけろ。サチが贄になるだ。サチが贄になればそれで丸く収まる話だべ」
「おめがよくても、俺がよくね。おめさいねぇ世を生きる気はね」
待ってろサチ。
そう言って吾は村を飛びだし、丘を越え、谷を越え、山の裏手にある大きな滝壺を目指した。
山の神はそこにおわすと耳にする。
大嵐が襲う日には決まってそこから大きな、大きな、竜巻が昇るのを過去、幾人もの村人たちが目撃していた。山の神はそこにいる。
なれば頼もう。
誠心誠意頭を下げて頼もう。
神と言うなれば叶えてくれよう。今年の贄を我慢してもらう。それが無理ならば、吾で我慢してもらう。それも無理ならば村ごと食らい尽くしてもらえばよい。サチと吾の二人きりで助かる道とて、サチが残るならばそれでよい。サチが助かるのならばそれでよい。
だがそこまでせずとも、せめて吾を食らって腹の虫を治めてもらおう。
サチのことも何卒、贄にせぬよう、食らわぬよう、見逃すようにと懇切丁寧にお願いしよう。
脅してでも、何としてでも、助けてもらおう。
吾は勇んで山を登った。
滝を目指して土を踏んだ。
大嵐が過ぎてまだ日は浅い。水嵩の増した川はドドドと山の鼓動がごとき地響きを立てていた。滝はさらに大気を揺るがし、山の頂を越えるともなくその轟音が聞こえた。
吾は滝に近づくたびに、山の神へどのように懇願せんものか、と考えあぐねた。勢い勇んで飛びだしてきたはよいが、肝心要の策がなかった。
丸腰で頭を下げて、果たして聞き入れてくれようものか。たとえば吾が羽虫の願いに耳を留めたことがあったろうか。願いを唱えていると見做すことなく、そこらを飛び回って煩いからという理不尽な理由で叩き潰してはこなかったか。
なれば山の神からして羽虫がごとき吾とて、有無を言わさず叩き潰されても文句は言えぬ道理。かといって、はいどうぞ、とはいかぬのだ。
いよいよとなれば山の神の怒りを買おうとも、その首を獲らんと挑むことも辞さぬ覚悟だ。否、それくらいの気概なくして声を聞き入れてもらえはせぬのではないか。
道中、吾は目に留まった立派な古木から枝を捥ぎ取った。
山の神相手に心許ない武器だが、手ぶらよりかはマシだろう。
そうと考え、神の棲家と名高い滝壺のまえへと馳せ参じた。
そこから先の記憶はあやふやだ。
神はいた。
滝壺には龍神さまが棲みついていた。
滝を逆さに打ち消すように頭身を伸ばし、滝壺の水面から前足を覗かせた。岩をも抉る鋭い爪は、いつぞやに目にした虹のごとく色彩に輝いていた。
吾は懇願したはずだ。
荘厳な龍神さまのお姿に圧倒された。その場にひれ伏したい衝動を堪えながら、言葉が通じぬかもしれぬとの思いを押し殺し、ただそうする以外にはないのだと思いに駆られ、呪文でも唱えるかのように、妹を助けてください、妹を助けてください、と唱えた。
理由を言わねば伝わるものも伝わるまい。
いまならばかように道理を弁えられるが、そのときはただただ必死だった。
龍神さまは滝よりも太い首をもたげ、吾の頭上に顎鬚を垂らした。鼻息一つで吾は吹き飛びそうなほどで、堪らず吾はその場にしがみついた。
手には古木の枝があった。
吾は動顛して、それを献上しようと思った。
古木から捥ぎ取るときに体よく折れて、先端が尖っていた。吾はその先端を頭上目掛けて突き立ててしまった。
龍神さまは吾の匂いを嗅ごうと顎を下げていた。ちょうど顎の先端の赤い鱗に、吾の突きだした枝の先が当たった。
刺さったというほどの勢いではなかったはずだ。
だがどうしたことか、枝先が赤い鱗に触れた途端に龍神さまは滝壺の中でのた打ち回った。そのうち滝を遡り、天高く昇ると、今度は一転、力尽きたように一本の紐となって滝壺に落下した。その際、壁に身体を何度もぶつけていた。削り取られた鱗が、落下の衝撃で舞いあがった水しぶきと共に、吾の身体を打ちつけた。
吾はそこで一度気を失った。
頭に瓦礫か鱗が当たったのだ。
目覚めると吾はまず、手足が自由でないことに気づいた。岩の上で身をくねらせるようにして転がった。縄に縛られていると思ったのだ。
勢い余って、滝壺に落ちた。
水底に沈んでいくが、息は苦しくなかった。呼吸ができる。
思えば、手足が不自由に思ったが、それは手首だけしか動かせないように感じたからだ。だがそも、手首しかなかったらどうだ。
胴体からちょんまりと前足が生えていた。臀部に力を籠めると、ないはずの尾が水を掻いた。
水中を泳ぎ、明かり目掛けて水を蹴った。
滝壺から飛びだした吾はそのまま宙を舞った。
吾は龍となっていた。
滝壺に龍神さまの姿はなかった。溶解したのか、霧散したのか。
いずれにせよ、吾こそが滝壺の主となっていた。
龍になって判ったことだが、どうやら吾の拾ってきた古木の枝は、龍の苦手とする霊気を帯びていた。山とは相反する海の気をたらふく含んでいた。岩塩地帯がゆえの作用かもしれぬ、と空を翔けながら吾は思った。
吾は山を越え、村の上空を舞った。
村人たちが吾に気づき、続々と家から出てきた。
恐れをなした様子で多くの者はその場にひれ伏し、知恵の回る者は、苫屋から我の妹を引きずりだして、地面に立たせた。その周りをほかの者たちが円形に囲い、みなで吾の妹を崇めはじめた。
立っているのは吾の妹だけだった。サチだけが、上半身を扇がごとく上下させる村人たちを尻目に佇立していた。
吾は一声、吠えてみた。
すると口から突風が飛びだし、見る間に竜巻となった。竜巻はそのまま村の家屋を薙ぎ倒し、巻き込み、上空へと飛ばした。
村人たちが逃げ惑う。
吾の妹、サチだけが吾をまっすぐと見据えていた。
「兄さま!」
なぜ分かったのかは謎である。だがサチは確かに吾を見てそう叫んだ。
抱っこをせがむように両手を伸ばし、もう一度、兄さま、と声を張った。
今、村を翔ける吾はもはや人ではない。
だがそんなことは些事なのだと逃げ惑う村の者たちを視界に収めながら、吾は三度、咆哮する。竜巻が、一本、二本、と数を増す。
それらが結びつき、大きな大きな竜巻になる前に吾は、胴体から生える小さな前足で吾の妹を掬い取る。
落とさぬように。
絞め殺さぬように。
細心の塩梅を払って、今年の贄を、我が妹を、奪い取る。
【差別なき世界】(2022/11/06)
西暦二〇五〇年代。差別撤廃国際法が締結させ、全世界から差別根絶が絶対のルールとなった。世の中からありとあらゆる区別による不公平な環境が取り除かれ、不公平な構図が発見されるたびに是正する仕組みが築かれた。
多様性を潰さぬようにすることが前提とされたために、人々は好きな属性を指向することができた。ホームレスになっても何不自由なく暮らせる環境が整い、お金がなくとも大富豪と同じ食べ物を口にできた。
差別撤廃国際法が締結され、つぎつぎと差別の構図が平らにならされた。穴は埋められ、社会からデコボコはなくなる。
だが最後までなくならない差別があった。
それは、差別主義者を蛇蝎視する差別であった。
差別撤廃国際法は、差別を許さない。だが差別主義者という属性を持った個を不当に排除することもこの法の基には許されぬのが道理。
そのため差別主義者を差別することも禁じられた。だがそれでも人々の差別への嫌悪感、それに伴う差別主義者への偏見や憎悪は消えることなく増幅しつづけた。どのような是正を行おうと、差別主義者への差別は消えなかった。差別主義者というだけで理不尽な扱いや不条理な環境に身をやつすことになる。社会に差別主義者の居場所はなかった。公平な社会であるはずが、差別を嗜好するというだけのことで差別をされるのだ。
差別主義者たちはけして差別を表立って行わない。あくまで差別を嗜好するだけだ。
それはかつて同性愛や殺人をテーマとした虚構作品を嗜好した者たちが差別された歴史と同じ過程を辿っている。かつては同性愛も殺人も罪だった。いまも殺人は罪であるが、殺人をテーマにした虚構作品は娯楽品として市場に溢れている。
ではなにゆえ差別を嗜好してはならぬのか。
差別主義者たちは訴えたが、法が許しても人々の心に根付いた差別への嫌悪は消えることがなかった。
各国政府は折衷案として、差別主義者救済法を新たに制定した。
これにより差別主義者は、差別主義者というだけで国からの保護を受けられるようになった。絶滅危惧種にするそれのように、世界中の差別主義者たちは国際法の名の基に生存権を保障され、細々とながらも人々から忌避されつつ、社会の隅で肩身を狭くして暮らした。
世界から差別は根絶された。そのはずである。
だがいまなお社会には、公平の名の基に弾圧され、人々の偏見に晒され、不可視のトゲに怯えて暮らす者たちがいる。
【ボイスの日々】(2022/11/08)
期間限定でボイスをはじめた。よろしおすー。
おはよう。きょうも一日元気でまいりましょう。まいるぞ。
あちゃちゃー。水やるの忘れた。しおしおなっとるが。
水やったら復活した。よかった。
実ちゃんよ、実ちゃんよスクスクあれー。
実ちゃん、前の分収穫したった。おいち、おいちなんですね。やったびー。
わたしへ。乾燥ボタン押すの忘れてたよ。うんちさん、くちゃいくちゃいのままじゃってん。ポチっと押すのちゃんとしよ。わたしより。
堆肥マキマキしたぞ。わたし、えらい。
わわわ。外にビリビリが出よった。やばばー。
ビリビリ予防に、地下に下りた。怖いわー。
地下生活三日目じゃ。地下水掘ったら、どばどば出たが。がはは。われ最強。
あぴゃー。地下水ダメじゃった。ギギギ量がヤババじゃった。濾したら飲めんかな。無理かな。
まだお外ビリビリ言うとる。怖いがー。くそー。
ギギギの地下水、エネちゃん製造機に使ったらいい具合にゴクゴクしてくれた。いっぱいエネちゃん生んでくれてありがとうなす。ついでにモワモワになった地下水さん、冷えて戻ったら飲み水になった。いいこと尽くしやー。
きょうはもう最悪。飲み水だいじょうだったから菜園の水に利用したら、草全滅した。多分だけど、純水すぎたのがよくなかったみたい。適度に不純物入れとかないとダメなんだなって。あーあ。どうしよう食料。
オハヨ。しょげててもしょうがないので、予備の種使うことにした。がんばるじょ。
上空に高濃度エクサプラズマが停滞してかれこれひと月が経つ。長すぎ。
ボイスの容量がいっぱいになったので、余分なデータを消す。時系だけ判るように穴開きで記録を残しておく。オヤスミ、世界。わたしもおやすみ。
おはよう。一階地上部分にビリビリが接触したらしい。浸食されて壊滅状態だ。もう地上には出られない。エネルギィ製造機が地下にあるのがさいわいだ。が、これも期間限定だ。あと三年保つか分からぬ。ボイスのように生体エネルギィで駆動したらよいのに。
クサクサしていても仕方ない。がんばるじょ。
おはようございます。わたしです。悪態のデータは順次消すようにしました。ボイスが脳内思考を自動で記録する機構とはいえ、振り返るたびにいちいちじぶんでじぶんを損なうようなボイスを残さずともよいとの判断です。陽気な記録だけ残すことにします。
あばばー、あばばー。地下水が、地下水が。
おぱよ。もうもう水びだしのジャブジャブじゃー。
どうやら地上で大雨がつづいているらしい。その影響で、地下水が氾濫した。穴を塞ぎきれず、これまでの居住区を捨ててさらに下層に下りる。ほぼメカニカルフロアだ。機械しかない。高温で近づけない区画があるかと思えば、冷却されて極寒の区画もある。合間の配管入り混じる人工密林が唯一の安全地帯だ。あと三年、ここで過ごすことになりそう。誰か助けてたもー。
こんにちは。わたしです。いまさらながらボイスの通信機能を立ち上げたら、通信可のマークが点灯していることに気づきました。ひょっとして、いるのか人類? わたし以外に、生き残りがいるのか?
ちっくしょー、なんじゃい、なんじゃい。散々こんだけ呼びかけてもうんともすんとも言やしねー。ふーんだ。わたしちゃん、いじけちゃうんだからな。けっ。
緊急事態だ。どないしよ。いつの間にか酸素濃度が極端に下がりはじめてる。いつから?
そんなことってある???
あびゃー。弱り目に祟り目。
高濃度エクサプラズマが、なんと、なんと、地下にまで浸食してきおった。なんで?
ゴルフボールかよ。
穴にはまった高濃度エクサプラズマが、建物の基盤を侵食しながら落下しているっぽい。穴にハマった小石が水や風の流れでくるくる回って真球になるみたいな話だ。わいをいじめて楽しいかよ世界。
現実逃避しよ……。
わたしちゃん、かわよ。
ボイス見直してたら、わたしちゃんかわよ。
わたしちゃん、がんばれ、がんばれ。
もう嫌。
なんでわたしがこんな目に。
略)――以下、恨みつらみの地獄絵図――(略。
はい、おはよう。わたしちゃん、おはよう。そっちのわたしちゃんもおはよう。そうね。あと数日でエネルギィ製造機が停止いたします。もう終わり。終わりのカウントダウンがはっじまっるよー。うきゃきゃ。笑うしかねぇな。笑え、笑えー。
あー、死にたくなーい。こわいよー。うへへ。
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。
死にたくない、死にたくない。
もうどうにでもなーれ。あばばばー。何も聞こえなーい。聞こえなーい。
もうすぐエネルギィ切れるってよ。ウケんね。
はい切れた。終わり、終わりー。
寒っむ。
あ。
見てあれ。ねえ見てあれ。わたしちゃん見てあれ。
機械さん止まったからかな。高熱地帯の奥に行けるようになってんだけど。まだ温かいからそっちに行ったのね、したっけなんかまだ先があるんだけど。
地下あるっぽい。
下行けそう。
行くしかないから行くが。
空気澄んでる。澄んでない? 澄んでる? どっちなんだい。
ふざけてたらこけた。
明かりないんよ。
あへー。
あへあへー。
わたしへ。隣の地層にも同じ避難シェルターがあったんだって。知ってた? わたしより。
ちゅうわけで、またしばらく生き永らえられるっぽい。やったびー。しょもしょもの日々じゃけんど、しょもしょもできるだけマシなんじゃ。いっぱいしょもしょもしたろ。
あ。
ん?
ボイスの視聴者数地味に増えてるの何?
通信できてないこれ。
できてる? できてない? どっちなんだい。
菜園あるくさい。
いっぱいの食べ物。食べ放題。すてき。
堆肥食べて飢え凌いでたとか言えない。
おはよう、おはよう、おはよう。
きょうも元気にわたしちゃんは生きるじょ。
おやすみ、わたしちゃん。
おはようございます、わたしくん。
期間限定でボイスをはじめるって言ったな。あれは嘘だ。
ずっとつづける。よろしおすー。
こにゃこにゃもにもにしちゃうもんね。がははは。
さびちー。
応答しちょくりー。
まーた頭上にビリビリ停滞いい加減にしとくれなす。
ひぃぃ……こわぁ。
実ぃでけた。
おいちー。
いや絶対これ聴いてる人いるでしょボイスくん。
【誰も知らぬ旅路】(2022/11/10)
寝て起きるたびに過去が変わっている。死んだはずの父が生きており、自殺したはずの母が生きている。先週わたしをイジメた同級生は昨日はわたしの親友だった。弟がいたと思えば、妹がおり、その妹が昨日は姉で、今日はわたしは一人っ子だ。
起きると稀に日付が数日飛んでいることがある。そういうときには、ああまたか、とわたしは思うのだ。
どうやらその抜けた日々のなかにわたしは存在しなかった。
わたしがいない世界がときおりそうして交じるのだ。
わたしだけがなぜ過去の変遷しつづける日々を横断しているのかは分からない。なぜ記憶が引き継がれるのかも定かではないのだが、どうやらわたしだけが知っている。
今日と明日は同じではない。
昨日と今日も同じではない。
わたしが誰にどう優しくしようがそうした過去は明くる日には消えている。同じくわたしが誰をどう損なおうとも、そうした過去が明日に引き継がれることはない。
わたしは自由な日々を生きている。
何の影響を残すことの叶わぬ、いましかない世界を。
近所の野良猫だけはしかし、いつどのわたしの「今日」にも現れる。誰にも懐かぬその猫は、餌をやるわたしにだけは甘い声音でみゃーと鳴く。わたしの足首に首筋を擦りつけごろごろと胎動のごとく立てる喉音は、どこか遠雷にも似ている。
その鳴き声一つ、歩き寄るトコトコの弾むような足取り一つでわたしは、日々の終わらぬ底なしがごとき旅路を耐えられる。
よく生きよ。
たぁんと長生きしておくれ。
喉を撫でると野良猫は、昨日と同じ細さに目を閉じる。
【繭の華咲く日は】(2022/11/12)
最初は魔王を倒そうと思ったのだ。王様の選ぶ勇者は毎回魔王討伐に失敗し、そのうえ魔王の怒りを買って余計に魔物の襲撃を誘起する。そのせいで私の父と母は殺された。年端もいかぬ妹が魔王軍に連れ去られ、いよいよとなって私は奮起した。
魔王城へは三年の長旅となった。しかし村々を経由するうちに信頼の置ける仲間たちと出会えた。むしろ三年で魔王に王手を掛けられたのだから快進撃と言ってもいい。
私たち一団は魔王軍を蹴散らし、魔王を孤立させることに成功した。
追い詰めた魔王を討伐するか、そのまま封印するかで意見が割れた。魔法使いたちは軒並み慎重派で、このまま封じるのが最も手堅い策だと主張した。私もどちらかと言えばその案に賛成だった。
しかし、好機を目のまえに魔王を生かしたままにおくことを許せぬのが騎士団だった。
このとき、魔王を追い詰めた情報は瞬く間に全国津々浦々に行きわたっていた。そのお陰で、魔王軍を蹴散らしたあとで魔物一匹寄せつけない陣形を築けたと言っていい。
かつて魔王討伐に失敗した勇者たちの縁者たちまでもが加勢に加わり、我ら人類側の勝利は目前だった。そこにきて魔法使いたちが、魔王を生かしたままで封印する、と言いだしたので、意見が割れた。
「魔王を生かしたままだと。アイツらに何をされたのかを思いだしてまだ同じことを言えるのか。しょせんは魔法使いだな。魔に通じる者同士、情でも湧いたかよ」
「言葉を慎みなさい。魔王の力は強大です。追い詰めて自棄を起こされたら対処のしようもない。ここは封じるのが吉と我らは考えます」
同士討ちの気色すら濃厚となったが、時間が限られる。まごついている合間にも魔王は傷を癒し、反撃の余力を蓄える。
あなたはどう思うのか、と最終的に私の意見によってその後の方針が決まるような流れとなった。多数決を採ればおそらく五分五分で割れただろう。そうしたなかで、唯一単なる一市民でしかない私の一存に命運が託されるのは、私が異様に運が良かったからだろう。未だかつて誰も成し得なかった魔王軍の排除と、それに伴う魔王城への鎮圧。魔王を孤立させ、実質無害化した功績は、ほとんど運が良かったからだ、としか言えない。仲間に恵まれた。それもある。それ一つをとっても運が良かっただけなのだ。
だからなのかは知らないが、みな私の運の良さに今後の道を預けたがっているのかもしれなかった。
「両方の策をとろう」私は言った。それ以外の考えが思い浮かばなかった。「討伐したい者たちは命を賭してでもその手で魔王を殺したいのだろう。ならば私にそれを止める権利はない。筋合いはない。だがもし失敗したときは、魔王共々封印されてくれ。それが筋だと私は思う。失敗の許されない道だからこそ、そこは是が非でも吞んでもらう。否、吞まずともそうせざるを得ない」私はみなを見渡す。荒野が一団の群れで稲穂のごとく覆われている。魔法使いたちの連携により、私の声は隅々まで行きわたる。「私は魔王を封じる案がよいと考える。だから共に魔王を殺しには行けない。止めはしない。時間は三日だ。そのあいだに討伐できなければ、三日後の零時きっかりを回った時分に封印の儀をはじめる。異論反論は受け付けるが、三日後の零時に封印の儀を決行する旨は覆らぬ。それが嫌ならば、身内で争うことになろう」
辺りはシンと静まり返った。
「どうした。時間がないぞ。止めはせん。好きにせよ」
暗がりの中、ゆらりと一人、また一人と立ちあがる。馬に乗る者、魔法陣を潜る者、使役した魔物にまたがる者もいる。
数刻もしないうちに騎士団はごっそりとその場からいなくなった。
みな魔王を滅しに、魔王城の地下深くへと赴いた。
三日経っても誰一人として戻った者はなかった。
零時を回ったが、私はしばらく帰還者を待った。
「時間ですよ」
魔法使いの長に促され、私は頷いた。
それだけで伝わったようだ。
魔法使いたちはとっくに配置についており、魔王城を取り囲んで巨大な魔法陣を人を使って描いていた。私は旅の道中に受けた魔王の呪いを血に籠め、魔法陣に垂らした。陣が地割れのごとく大地に浮かぶ。青い稲妻のようにも、地から伸びるオーロラのようにも視えた。封印の儀がそうして行われ、騎士団を含め、大勢の仲間たちごと私たち残留組は魔王を封印した。
魔王城はその土地ごと不可侵領域となった。入ることも出ることもできぬ魔境と化した。地表に張り巡らされた魔王の魔糸が途切れ、魔物が群れを成すことはなくなった。
魔王軍は散り散りとなり、もはや人類の脅威ではなくなった。連れ去られた村人たちの多くも、生きていれば解放された。
旅を共にした仲間たちに別れを告げ、私は、解放者のなかに妹の姿がないかを探した。旅がそうしてしばらくつづいたが、かつての仲間たちが私のために妹を探してくれていた。その甲斐あってか、半年後には私は妹が活きている報せを受け、その数日後には無事な妹の姿を目に留め、この腕に抱くことができた。
ここで終われたならばハッピーエンドとして絵本にしてもよいくらいだが――騎士団の犠牲は哀しいが、それを言うなれば私たちは絶えず哀しい死と痛みの裏に生きている――世は、そう大人しく私に平和な日々を与えてはくれなかった。
妹の様子がおかしいと気づいたのは、彼女を魔王軍から取り戻してから十二日後のことだった。
ひどい目に遭ったのか、それとも凄惨な光景に精神を病んだのか、妹は口を聞けなくなっていた。魔法使いの治癒を受けてもその後遺症は残ったままだったが、この手の魂に受けた傷は、魔法でも治療のしにくい領域なのは知っていた。魂は繊細だ。無闇に魔法をかけてよい領域ではない。神聖なのだ。そのはずだった。
「マユカ。マユカ。そろそろ魔除けの魔法をかけておこう」
妹は駆けよってくると無邪気に私に背を向けた。
私の膝の上に乗り、首飾りでも掛けてもらうかのように髪の毛を払ってうなじを露わにした。
このとき、私は再会して初めてマジマジと妹の首筋を目にした。
目だ。
瞳が、妹のうなじに開いていた。
ぱちくりと瞬きする一つ目が、一瞬で虹彩を深紅に染めた。漆黒と見紛うその深い紅の目には見覚えがあった。数年前、旅の道中でいたずらに私に呪いを掛けた魔王の眼球そのものであった。
私は混乱した。いつからだ。
風呂で妹の身体を洗ってあげたことはあった。治癒の魔法を段階的に掛け、不老にならぬように配慮しながら全身の痣を消してあげもした。
だが首筋のソレに私はついぞ気づかなかった。
いつからだ。
それが問題だった。
魔王の目が妹の首筋に開いている。
魔王は封じたはずだ。であるならば、ここに魔王の目があるはずがない。
では魔王の目ではないのか。
そうかと思い、魔払いの術を掛けた。下位の魔物ならばこれで充分対処可能だ。
しかし目は難なく妹の首筋に浮いたままだった。
ならばと思い、こんどは魔王討伐の旅以降仕舞いきりだった精霊の涙を取りだした。精霊の涙は、千年に一度だけ誕生する精霊王の血の結晶だ。魔物の血でできた沼ですら、精霊の涙を沈めれば一瞬で澄んだ泉がごとく清廉さを宿す。
精霊の涙なしに魔王城までの道は築けなかった。
私はそれを精霊たちから譲り受けた者として、保管していた。
高位の呪いであろうと精霊の涙を翳せば、軒並み払えるはずだ。魔王の呪いに掛かってなお死なずに済んだのは、精霊の涙を私が肌身離さず身に着けていたからだ。
いまはもう魔王はいない。魔王の呪いも、封印により魔糸が切れたので解呪された。
だから妹のうなじに浮かぶ目が魔王のものではあり得ない。
意を決して精霊の涙を、妹の華奢な首に筋にあてがった。
赤い稲妻が細かく噴きだすように昇り、部屋に散った。
音もなく私は手を弾かれた。
精霊の涙は壁にぶつかり、床に落下した。
私は妹の身をまず案じた。妹は驚いたようにこちらを振り返り、首筋を手でさすった。魔王の目じみた眼球はそのときばかりは傷口をぴたりと合わせたように妹の柔肌の奥に馴染んで消えた。
私は床に落ちた精霊の涙を拾いあげた。表面にはヒビが入っていた。奇しくもそれは先刻立ち昇った赤い稲妻じみた細かな魔痕と酷似していた。
私はこれと似た魔痕を知っていた。
私の身体を蝕んだ魔王の呪いは、それと非常によく似た魔痕を私の全身に走らせた。
「……魔王、なのか」
妹は首だけひねって私を不可思議そうに見上げた。
妹の首筋にふたたび深紅の眼球がぎょろりと開いた。
あらゆる手を尽くして調べた結果、一つの仮説が浮上した。魔王は完全には封印されていない。自らの核を飛ばし、それを我が妹に寄生させた。
魔法使いたちの築いた魔法陣を抜けるには、いかな魔王とて苦戦したはずだ。そこで魔王はどうやら、魔力をごっそり置き去りにして核だけを魔王城の外に飛ばしたらしい。
そうして無防備な核のまま我が妹に寄生した。
意思疎通はできない。
だが魔王は明らかに私の妹と知って、このコに核を飛ばし、根を張った。
核から目生えた眼球はいま、妹を介して徐々に魔力を蓄えつつある。
このままではやがて妹が魔王の苗床となる未来が訪れる。
信用できる魔法使いの仲間に頼んで、妹の魂を診察してもらったところ、危惧が的中した。魔王の核は、我が妹の魂と完全に癒着していた。魔王は、妹の魂からじかに魔力を吸い上げていた。
魔王の核を排除するには妹ごと滅するか、封印するしかない。
だがそれでは私が魔王を斃した意味がない。
このコを取り戻すために私はすべてを擲って、地獄のごとき旅路に身を置いたのだ。
魔王はそれを知っていた。
だからだろう。
こうして私をけしかけたのだ。
ふたたび魔王城へと歩を向けさせるために。
封印した魔王の抜け身を解放させるために。
魔王城に置き去りにされた魔王の肉体が解き放たれれば、魔王の核は妹の魂から抜け出て本体に向かうだろう。そこで妹が無事で済む可能性は低い。魔王が妹の魂ごと肉体に戻る可能性のほうが遥かに高い。
だが、交渉はできる。
いまは意思疎通すらできない状態なのだ。
このまま魔蟲に寄生された子羊のように妹が日に日に魔王化していく姿は見ていられない。
悩みを打ち明けた信頼の置ける魔法使いは、このことをほかの魔法使いたちにも知らせるべきだ、と言ってきた。私はそれを断った。
相談すればどうなるかなど火を見るよりも明らかだ。すでにいちど実践している。
魔王封印が再現されるだけだ。
魔法使いたちは妹ごと魔王の核を封印する。それ以外の最善手を彼ら彼女らは持ち得ない。
だから私は信頼の置ける魔法使いを説得した。どうか黙っていて欲しい、と。私がじぶんで何とかするから、と。
信頼の置ける魔法使いは、解った、と言った。だがその返事はどう聞いてもその場を切り抜けるためのおためごかしだった。
私は、夜中に遠隔魔法通信を飛ばした信頼の置ける魔法使いの姿を捕捉し、決別する臍を固めた。戦友と妹ならば私は、我が妹をとる。闘う術を持たぬ、いたいけな我が妹の未来をとる。
たとえその末に戦友の胸元に刃を突きつけることになろうとも。
大勢の命と引き換えに封じた魔王を復活させてしまうことになるのだとしても私は。
私は、それ以外に生きる意味を見出せないのだ。
なぜ戦うのか。
我が妹があすを、きょうを、健やかに生きる世界を守るためだ。
屈託なく笑い、花を愛で、野を、山を駆け回る世界を築くためだ。
それ以外に私の戦う理由などはない。
あってたまるか。
私は心底にそう思ったのだ。
信頼の置ける魔法使いを私は地下室に閉じ込めた。そのとき、戦友を傷つけぬようにと精霊の涙を使った。地下室を魔法不可侵領域にするために精霊の涙を使って陣を敷いた。
魔王にすら使える禁術だったが、背に腹は代えられない。どの道、私は魔王を封印しに行くのではない。解放するために行くのだから。
魔法使いたちには事情がすでに行きわたっている。私が何もせずとも、地下室の我が友は遠からず救出されるはずだ。
私は先を急いだ。
誰より先に魔王城へと行き着き、封印を完全に解かぬままに魔王を目覚めさせ、交渉をするのだ。
妹を贄にするな、と。
我が妹の身体からおとなしく出ていけ、と。
そうする以外に、妹が無事で済む未来は訪れない。
そうしなければいまにも、我が友たちが、私のすべてに仇を成す。どこを向いても四面楚歌の敵だらけ。みなの望む平和な世界に、我が妹の姿はない。
なれば。
なればこそ。
せめて私だけはこのコの未来を切り拓くべく、血を、肉を、捧げねばならぬだろう。ほかの誰もそれをせぬというのならば、せめて私だけは。
「……お姉ちゃん」
不可侵領域となった魔王城に辿り着いたとき、私は満身創痍だった。無垢な妹を抱えながら、友軍の仕掛けた守護の陣を掻い潜り、飼い慣らされた高位の魔物を相手に、段階的に設けられた関門を突破しなくてはならなかったからだ。
経験を積んだとはいえ、私は元はただの一介の村娘である。
どう抗おうが、対魔王軍用の防衛陣を無傷で通り抜ける真似などできるはずもないのだった。
傷ついた姉を見つづけ、さすがの妹も気づいたようだ。なぜ己が姉がそこまでして目的も定かではない旅をつづけるのか。まるで何かから逃げるようにこそこそと行動をするのか。
「……わたしのせい?」
しゃべれないはずだった。
妹は、魂に負った傷ゆえに、口が利けぬはずであった。
日常を奪われ、凄惨な日々を送り、なお先の見えぬ旅に巻き込まれた末の開口一番に出てきた言葉が、
「わたしの、せい?」
「違うよ」私は咄嗟に否定した。口を衝いていた。言わねばならぬと瞬時に判断した。
だが文脈は、言葉とは裏腹な返事を妹へと伝えていた。
「そっか」とあっけらかんと破顔した妹の目元から涙が零れ落ちた。いたいけな妹は涙まで小さい。
魂は、神聖な領域だ。
そこに無断で根を張った魔王の核は、魔王城に眠る本体に近づいたがゆえに呼応していたようだった。私はあとからその事実に気づいたが、このときはただただ、我が妹がいらぬ心労を抱え込まぬように、どうこの場を切り抜けようか、いかに嘘を重ねて欺こうか。そのことばかりを考えていた。
妹はゆったりと目をつぶった。
私は妹を背負っていたが、妹の頬が首筋に押しつけられたので、妹が眠るように目をつむったのだと判った。
魔王城に深紅の稲妻が走った。幾重も走った。
何かが起きたのは明白だった。
一度退避しようと踵を返そうとしたところで、深紅の稲妻が頭上から魔王城へと向かって走っていることに気づいた。
首筋に妹の腕が絡みつく。
後ろからぬっと肩越しに覗いた我が妹の顔には、うなじにあったはずの魔王の目が額の位置に開いていた。
見たこともない顔で妹は笑った。口元を吊りあげ、知るはずのない魔術の呪詛を吐いた。
魔王だ。
私は直観した。
振り払おうとしたが、身体に力が入らなかった。
吸われている。
魔力を、魂の根幹から吸われていると感じた。
刻一刻と全身が干上がるようだった。
私は地面にひれ伏した。頬に岩石のざらついた感触がひんやりと伝わった。
死ぬ。
そう思った。
魔王の核が妹の魂を取り込んだのだろう。魔王の核に自我が芽生え、私から魔力を根こそぎ奪い、そしてこれから魔王城の封印を解くつもりなのだ。
肉体と融合し、完全なる復活を遂げる腹積もりなのだ。そう思った。
背後で、聞き覚えのあるドラゴンの嘶きが聞こえた。
友軍の使役する高位魔獣だ。
魔法使いたちから事情を聞きつけ、馳せ参じたのだろう。
だがもう遅い。
私はじぶんの望みの何もかもが潰えたことを痛切に実感しながら、もう遅い、と誰に向けるのかも分からぬ怒りに震えていた。
もう遅い。
妹は、死んだ。
魔王に取り込まれた。魂ごと穢され、侵され、無残に散った。どこにもいない。
私の愛しい、我が妹。
じぶんのものですらないのに私は、いたいけな妹のことを、じぶんの生そのものと見做し、慈しみ、委ねていた。
そう、委ねていたのだ。
あのコは私のすべてだったのに。
――私のすべて。
なんて退屈でちんけで、響き甲斐のない言葉だろう。
だがそう形容する以外に私には表現のしようがなかった。なぜなら私からはもう、立ちあがる気力も、戦う意欲も、生きる動機の何もかもが霧散霧消して、無に帰していたからだ。
これから死ぬだろう数秒後を思っても、私は何も思わず、ただ震える身体に、ありもしない怒りの炎を幻視するよりなかった。
怒りすら私には遠い過去の出来事だった。
だから。
それゆえに。
「……お姉ちゃん」
人間の面影の薄れた三つ目の顔から、私を呼ぶ妹の舌足らずな声を聴いて、空虚な私の竈になけなしの火が灯った。
「待って」
どこに行くの。
伸ばした手が空を掻く。三つ目の妹は私に背を向け、深紅の稲妻となって姿を晦ました。
ぞろぞろと背後から友軍の団体がやってきて、私を取り囲んだ。
魔法使いの長が私の額に手を翳した。記憶を読み取ったのだろう。「やはりそうでしたか」と意味深長に頷き、「では段取り通りに」と友軍に指示を出す。
何をする気だ、と私は唱えたつもりだったが、もはや声にならなかった。
見る間に、友軍は各々に封印の陣の配置につき、剣を地面に突き刺した。
聖剣を呪具とした禁術だと判った。
封印と攻撃を兼ねている。
破壊を目的にした唯一の防衛魔術だ。
魔王城ごとこの世から抹消する気だと知れた。友軍の面々は、魔王討伐の旅に私が出ていたあいだも王都に留まっていた精鋭たちだった。
待ってくれ。
私は声にならぬ声で叫んだ。
魔王城には我が妹がいる。消さないでくれ。殺さないでくれ。滅さないでくれ。
声にもならぬ言葉には何の力もなかった。
一瞬の閃光の後、この世から魔王城ごと不可侵領域は消滅した。地下に封印されていた魔王の肉体ごと。
そして魔王の核の宿った我が妹の肉体ごと。
どの道、魂はとっくに喪われていたのだろうが。
私は友軍に連行されながら、治癒の魔法を受けて取り戻した冷静な思考で、もう遅い、と何度となく心の中で唱えた。
もう遅い。
私にはもう、何も残されてはいないのだ。
失った。
何もかもを。
人類を裏切った罪により私には極刑の判決が下された。しかし、情状酌量の余地ありとの弁護をかつての戦友たちが訴え出たこともあり、過去の戦歴を考慮して、減刑がなされた。
どちらでもよかった。
きょう死ぬ命ならばそれでよかった。
私には咎人の首輪が嵌められた。今後一生を私は自由を縛られ生きることとなる。
具体的には自殺ができない。
勅命が下されれば王の言葉に従わねばならない。
民のために能力を使い、堅実に日々を世のため人のために働いて過ごさねばならなかった。
才ある者の務めと科せられたこれが私の贖罪である。私は操り人形のごとく首輪の縛りによって無理やりに生かされた。
ある日、私は王の命で、研究棟を訪れた。
そこでは日夜魔物の研究がなされている。
魔王とじかに退治してなお生き残った数少ない人間として、私は体のよい研究資料と見做された。
「呪いはもう残ってないよ」
「いいんですよ。お話を聞かせてください。旅の始まりから、終わりまで」
どうやらかつての戦友たちの心遣いであったようだ。
生きた屍となった私になんとか生きる活路を見出させんとする策の一つだったようである。いわば治療なのだろう。過去の体験を話させることで、内なる膿を出しきらせようとの魂胆が見え隠れした。
癪に思う気力も湧かぬ。
私は促されるままに、相手の質問に応じていった。
ぼんやりとした記憶だった。
意外にも、質問を投げかけられるたびに、小石が水面に波紋を立てるように当時の記憶が鮮明に浮かびあがった。私の無意識が記憶を奥底に沈めていたのではないか、と思うほど私は多くのことを忘れており、そして問いかけによって思いだした。
記憶は行ったり来たりを繰り返した。
記憶の中の私はよく怒り、よく笑い、よく冷めていた。他者の欠点を挙げ連ね、友の配慮を無下にし、己の欲望に忠実に行動の指針を立てていた。
「私は、私のことしか考えていない人間だったようですね」
話の一区切りがつくたびに私はそう総括した。
けっきょくその一文に集約されるのだ。
顛末がそのように結ばれたのだから。
私はとどのつまり、全人類の平和よりも、私の欲望を優先したのだ。我が妹の命を優先し、我が妹の未来を優先した。
そしてきっと、と私は思う。
いまもう一度同じ場面をやり直させてやると言われても私は、まったく同じ決断をする。そして今度こそ目的を果たすべく、一縷の望みと、全人類の未来を天秤に掛けるのだ。
何度選ばされても、私には等価ではない。
私の欲望と、全人類の命は同じではない。
等しくない。
我が妹の命が、ほかの大多数の人間と同じなわけがないのだ。
もしあのとき、魔王と交渉ができたとして。
魔王からこのように提案されたら私はどうしただろう。
――妹を助けてやる代わりに、全人類の命を寄越せ、と。
そうする以外になければ私はその案を呑んだだろうか。
「たぶん、呑みますね。いえ、絶対に呑むでしょう」
私は包み隠さず、その旨も話した。聞き手は興味深そうに、しかし話の邪魔はせぬように静かな相槌を打つ。「いまもその考えに変わりはないのですか」
「ないです。いまだって、あなたの命と引き換えに妹が戻ってくるのなら、私はあなたの命を犠牲にするでしょう。その事実を妹にひた隠しにしたまま。誰に知られることなく、幸せな日々を生きるでしょう。妹とのその日常が叶うのであれば、私はもはや何を犠牲にしてもいいと考えています」
考えているのだ、と口にしてから思い知った。
私はまだ心のどこかでは諦めていないのだ。
欲望を。
生きることを。
「そうですか」聞き手の男は屈託なく相槌を打つ。肯定も否定も示さぬ割に、何を言っても彼は私を包みこむような柔和な雰囲気を崩さない。
私が素直に話しつづけられたのは、彼のその雰囲気による魔法にかかっていたと言っても過言ではない。
男は魔物の研究者だった。
私がひとしきり旅の顛末と私の罪過について語り終えると、ようやくというべきか、男のほうでも口上を逞しくした。
「欲望というのならば興味深い実験を先日したばかりでしてね」男はほかの研究者たちと違い、じぶんの興味関心のある分野についてであっても舌鋒を鋭くはしなかった。たおやかな雰囲気のまま、ほのぼのとしゃべった。「魔物や魔獣には、それぞれ核があります。ご存じでしょうが、これを潰さないと再生する魔性生物は多いです。先日、高位魔獣のドラゴンで実験したのですが、どうやら魔性生物の核は、ほかの生き物の魂と癒着することで、核単独でも生き永らえることができるようなんです」
率直な感想は、なんだそんなこと、である。
ドラゴンどころか私は、私の愛しい妹の身体に魔王の核が癒着しているのを実体験している。間近で観察している。
いまさらの情報であった。
「面白いのはここからなんです。核だけになってほかの生物に寄生したところ、魔性生物の核は、その後にどれほど宿主の魂を吸いあげ取り込んでも、元の魔性生物の意識を発現させなかったんです」
私は眉根を寄せた。
「高位魔獣のドラゴンですら、核だけになってしまったら、元の肉体に戻らない限りは、元の状態には復元され得なかったということです。言い換えますと、ほかの生き物と融合した魔性生物の核はむしろ、宿主の欲望を肥大化させるように作用するだけで、寄生された生き物の魂はそのまま自我を保つことが解かってきたんです」
「よく解からんな。ドラゴンの核に寄生されてなお、魔獣化しなかったということか」
「ありていに言えば、はい」
「欲望が肥大化させるように作用というのは、その、つまり」
「寄生した生物の欲望を暴走させるように、魔力を増強させると言えば端的かもしれません。食欲ならば食欲を。性欲ならな性欲を。独占欲、支配欲、もろもろ欲望は個々によって幅がありますので、何が最も強く発現するのかは、それこそ寄生された生物のそのときの状態によるのでしょうが」
そこで男は、東洋にはゾンビという異常種がおりまして、と冗長な説明をはじめた。私はそれを上の空で聞き流しながら、耳にしたばかりの新説を振り返っていた。
魔性生物の核に寄生されても、人格が塗りつぶされるわけではない。
魂を吸われはするが、癒着したからといって魂が消滅するわけでもない。
その個の最も深い欲望を肥大化させる。
魔王は魔性生物の頂点に君臨する。数多の魔性生物を支配下に置き、統率可能な術を有する。いっぽうで、魔王もまた魔性生物の一個体である。
もし魔性生物の核にまつわる新説が、魔王にも当てはまるとしたらどうなる。
我が妹は最期、魔王の核に取り込まれてなお、自我を保っていたことにならないか。
ではあのとき、あのコの最も深い欲望とは何だったのか。
なぜ意識があってなお、私をあの場に残し、魔王城へと去ったのか。
なぜ急にあのコはあの場で、魔王の核にすっかり肉体を乗っ取られたように振る舞ったのか。真実に乗っ取られていようと、魔性生物の核の習性が魔王にも当てはまり得るのなら、あのときあのコは、魔王のチカラを帯びてなお、自我を保てていたはずだ。
あのコはあのコのままだったはずだ。
にも拘わらず、あのコはなぜ。
――最も深い欲望。
あのコの、あの時点での、最も深く、肥大化した欲とは何であったのか。
――お姉ちゃん。
あのコの最後の声音が、鮮明に、すぐそこで聴こえたようによみがえった。
仮面のように顔面を手で覆い、私は、背を丸めた。
しきりに乱れる呼吸をなんとか整えようとしたが、上手くいかなかった。
そばにいた男はしゃべるのをやめ、黙って私が落ち着くまでそこにいた。
呼吸の仕方まで忘れてしまったかのように私はしばらく声にならぬ言葉で、妹の名を呼んだ。やがて思いだしたように呼吸を連続して滑らかにできるようになり、私はなぜか肩を弾ませ笑っていた。
何が可笑しいのかは判らなかった。
ただただ、生きねば、と思ったのだ。生きていかねば、とそう思ったのだ。
迷い込んできたのか、頭上に蝶が舞っていた。
冬籠りの支度が忙しい季節にしては、時期外れの蝶である。
「最近ぽかぽかと暖かかったからですかね。春と思って羽化したんでしょうか」
男が席を立った。蝶を捕まえようとした素振りを見せたので私はまえのめりになってその腕を掴んだ。男が面食らったように仰け反った。「どうしました」
「いえ」私は動顛していた。身体がかってに動いたのだが、その理由が解らなかった。「すみません」
男は頬を指で掻いた。それから本に貼っていた付箋を外すの忘れていたといった調子で、そうそう、と指を振った。「妹さんのお名前はなんと? 一度もお話のなかで呼ばれなかったので」
差し支えなければ教えてくださいませんか、と何の気ない様子ではにかむ男の頭に蝶が止まる。
ゆっくりと呼吸をするように羽を休める蝶を見て、私は、なぜかまた呼吸の仕方を忘れるのだ。
「マユカ」
途切れ途切れの呼吸の狭間に私は、この世にしかと刻み込むように、声ある言葉であのコの名を呼んだ。
【木製のナイフ】(2022/11/15)
ボクはこの全寮制学園の秘密を、アディ兄さんから聞いた。
聞いたというよりかは聞きだしたというほうが正しいのだろうけれど、何せアディ兄さんは問いかければ投げた箱を三十四重にマトリョーシカにして返してくれる律義さもとより博識で聡明な頭脳を持っていた。
アディ兄さんはボクよりも三歳年上で、ボクにとっては何を聞いても答えてくれる歩く未来だった。誰のものでもないボクの未来そのものだ。アディ兄さんとボクは血の繋がりはないけれど兄弟だった。みながボクたちをそう呼んだし、アディ兄さんの友達はみなボクのことをリルアディと呼んだ。小さいアディの意味で、つまりみなはボクをアディ兄さんの弟だと見做していた。
でもボクはアディ兄さんから直接、ボクたちのあいだに血の繋がりがないことを教えてもらっていたし、そのことに傷つく必要がないことも教えてもらった。
ボクの寝床は幼いころからアディ兄さんの隣で、寒い日はよくアディ兄さんの寝床に潜り込んだものだ。
アディ兄さんは寝るときには、日中であれば団子に結っている長髪を解くので、ボクは眠れない日はよくアディ兄さんの髪の毛を指でいじって、その金髪に反射する月光を眺めたものだ。もしこの世に神様がいて、その神様にお供がいたとしたらきっと、こういう金色の糸をつむぐ白銀の蜘蛛に違いないとボクは夢想することもしばしばだった。
「ボクはどうしてここにいるの?」
その質問をボクがしたとき、ボクは十二歳の誕生日を迎えたばかりだった。
全寮制の学園だったので、その月に誕生日のある者はいっせいに毎月十五日にみなで祝うのがここでの習わしだった。
その日はたしか三日や四日の晩で、ボクは誕生日を迎えていたけれどまだみなから祝われてはいなかった。
そんな中でアディ兄さんだけはボクのために木製のペーパーナイフを贈ってくれた。手作りだった。ケヤキの木の枝を削って作ったもので、ボクはケヤキが硬い木であることを知っていたので、感激した。
「兄さん、ありがとう。ぼく、うれしい」ケヤキの木でできたペーパーナイフは鉄のように頑丈で、人間の皮膚くらいなら簡単に貫けそうな鋭さがあった。
「喜んでくれてよかった。漆も塗ったから長持ちすると思うよ」
「手、大丈夫?」
「かぶれはしなかったよ」
「それもだし、タコができたんじゃないかなって」
「心配性だねナツは。ありがとう、でも私は慣れているから」
アディ兄さんはボク以外の子にも贈り物をすることがあった。だから木材の加工はお手の物なのだ。
寝床は広間に布団を敷いて、三十人から五十人がクッキーを焼くときみたいにぎっしり並んで眠る。
ボクは寝床に木製のペーパーナイフを持ち込んで、眠くなるまで見詰めていた。ボクがいつまでもモゾモゾしていたからか、アディ兄さんが声を掛けてきた。
「眠れないのかい」
「ううん。見てたの」
ボクが木製のペーパーナイフを見せると、兄さんはやれやれと苦笑した。「危ないから枕の外に置いときなさい」
「でも」
「危ないから。ね」
アディ兄さんにそんな声音を出させてしまったらボクにはなす術がない。唯々諾々と指示にしたがった。
ボクが不満そうだったからか、アディ兄さんはそこでボクに手を伸ばして、おいで、と無言の手招きをした。本当はじっと腕を伸ばしていただけだけれどボクにはアディ兄さんが手招きして見えた。
ボクは誕生日を迎えたばかりで、また一つアディ兄さんに近づいたはずなのだけれど、アディ兄さんにも誕生日はくるから、それまでの短い期間のこの隙間の埋まったような心地がボクは好きだった。でもこのときばかりはまだ歳をとったばかりだから、まだ歳の差が三歳開いたままの関係でもよいように思って、ボクはまだ十一歳の弟のつもりで、アディ兄さんの寝床にモゾモゾとイモムシみたいに這って移動した。
アディ兄さんは温かい。
でもいつもボクが潜りこむとアディ兄さんは、「ナツは太陽みたいだね」とボクの体温が高いことをうれしそうに言うのだった。
「ナツは誕生日だったから、きょうは特別にいくらでも質問していいよ。答えられることには全部答えてあげる。眠くなるまで付き合ってあげる」
「本当?」
ボクはそれだけで眠気がどこかに飛んで行ってしまった。
そこからボクはじぶんでも呆れるくらい色々なことを質問した。どうしてお月さまは輝いていて欠けているのかから、どうしてアディ兄さんは物知りなのかまで、思いつく限りの疑問をアディ兄さんにぶつけた。
アディ兄さんはそれらボクの疑問に檻を掛けるみたいにしてもう二度と疑問が出てくることがないような回答をした。
「お月さまが輝いているのはその向こうに天国があって、そこが輝いているからだよ。夜空には穴がたくさん開いていて、お月さまもほかの星々も太陽も、全部そこから漏れる天国の光なんだ。でもときどき穴の中を洗わなきゃいけないから蓋をすることもある。夜空の穴は大きくて深いから、穴を塞ぐにも時間がかかる。だからお月さまは周期的にゆっくりと満ち足り欠けたりして見えるんだ」
「へー、へー」
「どうして私が物知りかと言えば、私には前世の記憶があって、それで本当は九十のお婆さんなんだよ。中身はね。でも見た目がこれだからみなは【見掛けの割には物知りだ】と思うようなのだけれど、これはでもそうじゃない。だって本当は九十のお婆さんの人生分だけみなよりも多く物事を見聞きしているからね。その記憶がある。だからそれを考慮に入れたら、私は全然物知りじゃないんだ。色々と勘違いだってしているだろうし、間違ったことも言うよ。だって私の知識は九十のお婆さんのものなのだもの」
「ふうん。すごいね」
「ナツ。ちゃんと聞いていたかい。私は全然すごくないよってことを説明したんだよ」
「だって前世の記憶があるんでしょ」
「それだって確かじゃないよ。私がそう思いこんでいるだけかもしれない」
「嘘ってこと?」
「本当ではないかもしれないってこと。いいかいナツ。人間はそうそう簡単に本当のことを見抜けないんだ。どんなに正しいと思っていても、一度にすべてを同時に理解することは適わない。すくなくとも私にはできない」
「むつかしくてよく分かんない」
「本当はお月さまは輝いているわけではなく、太陽の光を反射しているだけなんだ、と言って、ナツは信じる?」
「そうなの?」
「先生に言ったらきっと嘘つき呼ばわりされるだろうけれど」
「だよね。ボクもそう思うもん。だってお月さまは鏡じゃないし」
「そうだね。ナツは賢い」
「うふふ」
ボクはアディ兄さんに褒められるのが好きだ。身体の奥がほんわか熱を帯びてチーズみたいにとろけるのだ。美味しそうなご馳走をまえにしたときのような、誕生日のケーキを分けてもらったときの気持ちをもっと何個も重ねてふんわりと柔らかくしたらきっと同じ気持ちになるはずだ。
「ねぇ、どうしてボクってここにいるの」ふと口を衝いた疑問だった。窓から差しこむ月光を眩しいと思いながら、どうして月はあそこにあってボクはここにいるのだろう、と不思議に思ったのだ。
アディ兄さんはボクのこの疑問にも答えてくれた。
「その疑問を私に訊いたのはナツ――キミが初めてだ」誉め言葉のはずなのになぜか枯れ葉が地面を転がるような響きがあった。ボクはアディ兄さんの腕をとって枕にした。アディ兄さんからはいつも微かに美味しそうな匂いがした。「私たちがここにいるのはね、ナツ。私たちがここにいるのは、みな守られているからだよ」
「学園長先生にでしょ」そんなことは言われずとも知っていた。それにボクの疑問の答えになっていなかった。「ボクが言ったのは、どうしてボクはここにいるの、だよ」と唇をぶるぶる震わせる。
「だから言ったんだよ。私たちはね、園長先生が私たちを守るためにここに集められているんだ」
「んー?」
「そうだね。分からないよね」アディ兄さんはボクの頭ごと身体を包みこんだ。「園長先生はとても素晴らしい人だから。人格者だから。困っている人や、困窮していることにも気づけない人たちを見て見ぬ振りができない。だから時々は困っている人たちを助けるために剣を揮うときがある」
「やっつけちゃうってこと? わるいひとを?」
「ナツ。わるい人なんていないよ。ときどき人は人を傷つけてしまう。それでも止まれないときがある。そういうことなんだ。そういうときに園長先生みたいな人たちが止めに入る。人を傷つけるのはやめたほうがよい、好ましくない、とね」
「うん」ボクは、大柄な、けれど優しい園長先生の姿を思いだした。ボクたちがこぞって園長先生の腕にぶら下がっても園長先生はけろりと笑顔を絶やさずに、ブランコを吊り下げる中庭の大樹みたいにびくともしない。
「人を傷つけると損をする。だからやめたほうがよい。あなたにとっても好ましくない。そう園長先生は説得しても、止まれなくなった人は止まれない。上手に止めてあげることもできるけれど、そうではない場合もある。そういうときは、園長先生みたいな人たちは、なぜ人を傷つけると損をしてしまうのかを、身を以って手本を示してあげるんだ」
「よく分かんないな。どういうこと?」
「つまり、相手がしていることをそっくりそのまま返してあげる。あなたがやっていることはこういうことですよ、と示してあげる。その結果、相手が死んでしまうこともある。その人がそれまで他人を殺してきたように」
「怖いよ。アディ兄さん、ボク怖い」
「大丈夫だよ。園長先生はナツのような子には優しいでしょ。それはナツたちが優しいからだよ。園長先生はただの鏡だ。なかなか醜いところを見せてくれない映し鏡なんだ」
「綺麗なとこだけ見せてくれるの?」
「そうだよ。綺麗なところがもっと綺麗なんだよ、と見せてくれる。でも、それはみなの醜いところを吸い取ってくれているからだ。油取り紙みたいにね」
「ふうん」ボクは納得したふりをして、「それで」と言った。「どうしてボクはここにいるの?」
はぐらかされて感じた。
ボクはたぶんずっと知りたかったのだ。どうしてボクたちがここにいるのか。どうして子どもたちしかいないのか。
殻になったボクの寝床とアディ兄さんの寝床との合間には床が露出している。月光に反射して、床の木目が生き物の眼球のように浮きあがって見えた。
「反対に私からナツに質問するね」アディ兄さんはぼくの頭のてっぺんに顎を押しつけた。「子供はどこからやってくる?」
「大人からじゃないの」父親と母親から産まれてくる。それは先生たちが言っていたし、アディ兄さんからも教えてもらっている。人間には必ず両親がいるのだ。
「ならどうして私たちに親はいないの?」
「園長先生がそうじゃないの」
あのひとがボクたちの親ではないの。
じぶんで口にしてから、そうではないのだ、と違和感を覚えた。ボクはかってに園長先生を親だと思っていたけれどそれでは父親が足りない。園長先生は逞しいから、ついつい男の人だと勘違いしてしまうけれど、そうではないのだ。
「園長先生だけじゃ子どもは産まれない?」
「産まれないし、私たちはあの人が産んだ子でもないよナツ。あの人はみんなの親代わりではあるけれど、私たちの親は別にいる。産みの親は別にいたんだよナツ」
「ふうん」ならどうしていまはいないのか、とボクは唇を食んだ。「親がいないからボクたちはここにいるの。可哀そうだから?」
だから園長先生がボクたちのような子どもを掻き集めたのだろうか、と考えた。
「そうだけど、そうじゃない」アディ兄さんはボクの頭を痛いくらい抱きしめた。「私たちはナツ。私たちは、狼の子なんだ。園長先生は、親のいなくなった狼の子どもを引き取って、なんとか穏やかな子犬のまま犬になるようにと面倒を看ている」
「狼?」ボクは雨戸の隙間越しに見える月を見上げ、じぶんが狼男になる瞬間を思い浮かべた。「アディ兄さんもじゃあ、狼なの」
「違うよナツ」アディ兄さんは笑ったようだった。ボクのつむじに唇を押しつけるようにすると、「でも私の親はそうだったのかもしれない」と言い足した。「或いは、ナツの言うように私もまた」
「変身する? アディ兄さんも?」そんなわけがない、と判っていたのでボクはくつくつと肩を弾ませた。
「もしそうなったら園長先生に止めてもらおう。私は弱いからきっとすぐに掴まって、首輪でも嵌められるかもしれない」
「じゃあ散歩はボクがしてあげる」
「ナツが私の鎖かもしれない可能性は考慮しないのだね」
「ボクが鎖?」
「ううん。なんでもないよナツ。ごめん、そろそろ私も眠くなってきてしまった。ナツはまだ眠くならない?」
「ボク? ボクはもっとずっとしゃべれるよ」
「でもまた寝坊したら朝ごはんを食べ損なうよ。そのときは私の分のをあげるからよいけれど、できれば私も朝ごはんは食べたいな」
「そっか。じゃあもう寝る」
ボクのために何かをするとき、アディ兄さんはアディ兄さんの何かを擦り減らしている。慣れているから、と口では言うものの、アディ兄さんの手は子猫の尻尾みたいな指をしていながら、その実、マメとタコだらけなのだ。
アディ兄さんのつるつるの指を子猫の尾を撫でるようにつまみながらボクは、毎年のように増えつづけるボクたちの仲間を思い、いつの日にか新しくやってくるだろうボクよりも小さい子のことを思った。
「ボクもアディ兄さんみたいになれる?」ボクはうつらうつらしながら言った。
「ナツは私みたいになる必要はないよ。ナツはナツらしくおいで」
「でもボク、アディ兄さんみたいにほかのコのことも」
そこでボクの意識は睡魔の渦に巻きとられた。尻つぼみに失せた言葉と引き換えにボクは夢の中へと吸い込まれていった。
おやすみ、ナツ。
アディ兄さんがボクの耳たぶを指で撫でている。その手つきが、いつもこっそりとアディ兄さんの髪の毛をいじくるボクの手つきと似ていて、くすぐったい心地を覚えながら、そのくすぐったさに包まれてボクは夢の中でとろけた。
誕生日おめでとうナツ。
夢の中でもボクは木製のペーパーナイフを握っていた。大きくておっかない狼がボクの目のまえに立ちはだかっている。呻りながらその狼はボクに襲い掛かった。ボクは狼の下敷きになりながら、狼の胸に、その毛皮に、木製のペーパーナイフの先端を押しつけている。紙を切り裂くように木製のペーパーナイフを引き下げると、中からは眠ったアディ兄さんが現れるのだった。
どうしてボクはアディ兄さんの弟なのだろう。
いつからそうなのだろう。
この疑問をボクはアディ兄さんに投げかけたことがなかった。たぶんこの先も投げかける予定はない。聞きたくない。知りたくない。
理由なんてなくてよいのだ。
ボクはボクで、アディ兄さんはアディ兄さんだから。
夢の中でボクは、目をつむり一向に目覚めない宝石のようなアディ兄さんを手のひらの上に寝かせており、いつの間にかボクは、木製のアディ兄さんを握っているのだった。
【ポメラニアン先輩はオレンジ】(2022/11/17)
転校生が魔法使いだった。
その子はオレンジ色の巻き髪をしていて、愛らしいかんばせはオレンジ色の毛をしたポメラニアンのようだった。背は私よりも低く、いいやクラスメイトの誰よりも低く、聞けば飛び級制度を利用しているらしかった。要するに彼女はわたしたちよりも年下なのだ。一般の中学二年生ではない。十四歳よりも幼い。
「魔女子です。本名は別にあるのですが、知られたらいけないので魔女子と呼んでください」
二週間だけこの地域に滞在するらしい。短いあいだですがよろしくお願いします、と頭を下げるとオレンジ色の巻き髪が垂れ、彼女の身体は覆い尽くされた。
魔女子は性格がよかった。表情に変化がない代わりに、不快の感情を示すこともないために、クラスメイトたちからはマスコットキャラのように受け入れられた。休み時間にはほかのクラスの生徒たちまで我がクラスに集まり、我がクラスメイトたちはじぶんたちのクラスに現れた全校生徒の注目の的を、さながら姫を守る騎士のように取り囲み、外野の喧騒から遠ざけた。
「魔女子さんは魔法使いなんだよね。どんな魔法を使えるの」
「魔法使いではないんです。魔女です」
「どう違うの」クラスメイトたちは興味津々だ。わたしもじぶんの座席から聞き耳を立てていた。
「どちらも魔法を使いますが、魔法使いは自然由来の魔力を使います。反して魔女は自前の魔力を使います。と言っても、魔女も魔法使いのように自然由来の魔力も使えますので、魔法使いのなかでも自前の魔力を使える者が魔女になります。なぜか男性は使えないので、必然、魔女が多くなるようです」
「へえ」
ならば魔女子さんは選ばれし魔法使いなのだ。
わたしのみならずみなもそのことに気づき、魔女子さんをことさら羨望と憧憬の眼差しで見るようになった。
魔女子さんは魔法が使えた。それはもう一目瞭然で、登下校ですら魔法の門を開いて、瞬間移動をする。
「便利そうだね」みなはこぞって魔女子さんの一挙手一投足に感嘆の声を上げる。
「そうなんでしょうか。これがずっと普通だったので」
聞けば、魔女は稀少がゆえに絶えず狙われているのだそうだ。誘拐事件は日常茶飯事で、魔女狩りは未だに全世界でつづいているという。
「そんなニュース聞いたことないけど、本当?」みな心配そうだ。
「魔界にまつわるニュースは歪曲されて報道されるんです。みなさんだって魔女が存在することを知らなかったんですよね」
「あ、本当だ」
そこでわたしは、いいのだろうか、と疑問に思った。魔女子さんの存在は秘匿のはずなのだ。だのにこうしてわたしたちのまえに彼女は素性を明かして現れている。二週間で転校してしまうとはいえ、その後にも彼女の噂は囁かれつづけるだろう。すでに伝説の人と化している。
クラスメイトたちはそのことに気づいていないようで、誰も質問をしなかった。わたしだけがモヤモヤしたが、わたしはクラスの輪のなかには入らずに遠巻きに、台風がごとく人を寄せ集める魔女子さんの話に耳を欹てていた。
二週間はあっという間に過ぎ去った。
その間に魔女子さんはしぜんな様で各種様々な魔法を披露した。本人にそのつもりはないようで、日常の所作の延長線上なのだが、江戸時代の人から見たら電子端末が総じて魔法に見えるように、わたしたちの目からすると魔女子さんの一挙一動が非日常のあり得ないことの連続だった。
まず以って魔女子さんは手足を動かすということをしない。筆記用具の扱い一つからして、魔法で動かしてしまうのだ。板書するのにペンが一人でにノートに文字をつらね、教科書はかってにめくれていく。掃除とて、魔女子さんの担当した区画だけが真新しく床を張りかえたように綺麗になっており、返ってほかの汚れが目立っていた。
いっそ校舎ごと新しくしちゃったら、と誰かがつぶやくと、魔女子さんはきょとんとして、していいの?と訊き返した。そこで先生が耳聡く聞きつけたようで、「わ、わ、いいのいいの」と割って入った。「減価償却とか、業者さんの仕事がなくなっちゃうとか、そういう大人の事情があるからそういうことはお願いしなくていいの」魔女子さんへの注意というよりもこれは、変なこと吹きこまないで、とクラスメイトたちへのお叱りのようだった。「魔女子さんの魔力だって無尽蔵じゃないんだし、ね?」
言いくるめられたようで面白くなさそうなクラスメイトたちだが、魔女子さんに負担がかかりそうなのは想像がつく。しぶしぶと言った様子で、はーい、と聞き分けの良さを示した。
そういうことが幾度かあって、二週間は瞬く間に過ぎ去った。わたしは魔女子さんとは、おはようとか、教室はそっちじゃないよとか、そういう言葉を二、三回交わしただけだった。
だから、魔女子さんのお別れ会のあとでの下校中に、道路先に魔女子さんを見掛けたときには驚いた。もう二度と魔女子さんの姿を見ることはないと思っていたのに、魔女子さんが道の先にいたのだから、わたしは妙な興奮に包まれた。わたしだけがいま魔女子さんの視界の中にいる。とはいえ彼女はまだわたしには気づいていないようだった。道端に座り込み、何かをじっと眺めている。
何をしているのだろう。
どうしてここにいるのだろう。
わたしは気になった。というのも、魔女子さんは登下校は魔法の門を開いて瞬間移動をする。この街を出歩くことがそもそもなかったはずなのだ。
わたしの通学路に現れるはずもない。
意を決してわたしは彼女の背後に立ち、声をかけた。
「何してるの、ここで」
くるりと首だけで振り返った彼女は、やや驚いたように眉毛を持ち上げた。初めて見た彼女の、表情らしい表情だった。
念のためにわたしは、「魔女子さんと同じクラスだった」とじぶんの名前を述べた。
「知っています。一度会った人間の顔は忘れません。魔女は記憶力がよいので」
「それも魔法?」
「さあ、そこまでは」魔女子さんはふたたび地面に向き合った。作業を再開した。チョークのような道具を握っている。何かを地面に書きこんでいると判る。「魔力が記憶力を底上げしているのは事実ですが、肉体があってこその魔力でもありますので、どちらが優位に作用しているのかは未だ解明されていないようです」
「魔女子さんは頭いいよね。中二どころかもっと上に飛び級できたんじゃないの」
「飛び級というのは嘘です。そういう設定にしておくと説明がいらないので」
「設定?」
「できました。下がっていてください」
魔女子さんが立ちあがったのでわたしも後退した。
「何するの」魔法を使おうとしているようだとは一見して分かった。
「街に陣を張ります。これであたしの記憶は人々から失われます」
「記憶を消すってこと?」
「はい。でないとみなさんにも危険が及ぶので。魔女はこうしていく先々で存在の痕跡を消すのが習わしなんです」
だからか、と腑に落ちた。
魔女の存在が世間に秘密にされていながらどうして魔女子さんが正体を隠さず、魔法も堂々と使っていたのかが理解できた。
中学二年生への転校も、中学校ならば動画で拡散される心配がすくないからではないのか。そういう背景もあったのかもしれない、とわたしは直感した。
わたしが一瞬の思索を巡らせたあいだに魔女子さんはそそくさと魔法を発動させたらしく、街全体が一瞬濃い霧に包まれたように霞み、ふたたび瞬時に視界が晴れた。
目のまえにはオレンジ色の髪の毛をした愛らしいかんばせの女の子が立っており、わたしはその子が魔女子さんで魔女で、たったいま街の人たちから魔女子さんにまつわる記憶を消し去ったのだと知っていた。
「魔法、したの?」わたしは言った。記憶消えてないけど大丈夫、と心配したつもりだ。
「やっぱりか。ですよね。そんな感じがしてました」魔女子さんはしゃがんでいたときについた膝の砂利を払うと、あなたは、と顎をツンと上げてわたしを仰ぐようにした。「あなたは、魔女です。魔力を帯びています。だからわたしの魔法だと記憶を消せないんです」
「ほ、ほう」そうきたか、とわたしは身構えた。わたしが魔女かどうかは問題ではない。仮に記憶が消せないならわたしは異物として排除されるのではないか、と危機感を募らせた。魔女子さんはそんなわたしの胸中を察したように、「魔女は同胞を売りません。あなたはもうあたしたちの仲間です。そうですね、いまから時間はありますか」
「時間? 時間はあるけど」
「魔女の協会本部に案内します。そこで説明を受けてください」
「説明? 魔女の?」
「あなたはこのことの重大さを御存じないでしょうが、これはちょっとした事件となります。何せ、何の血統もない無垢の子が魔力を帯びて、しかもこんなに大きくなるまで誰からも素質を見抜かれずにいたのですから、これはもう事件です」
「は、はあ。すみません」わたしは恐縮した。何かよからぬ存在であったらしい。わたしがだ。「わたしは、どうすれば?」
「ですから一緒に協会に行ってください」魔女子さんは手慣れた調子で魔法の門を開いた。「お先にどうぞ。あたしが通ると門が閉じてしまうので」
「大丈夫なの、これ」魔法の門は、輪のなかに濃い霧が膜となって張っているように見える。向こう側が視えない。「通ったら崖だったりしない?」
「大丈夫なので」魔女子さんはむっとした。むつけた顔が年相応のあどけない顔つきに見えてわたしはただそれだけの変化に、魔女子さんに満腔の信頼を寄せてしまうのだった。
「なら信じるとするか」
「あたしのほうが先輩なんですけど」魔女子さんはむっつしりたまま、ぴしりと魔法の門に向けて指を突きつけた。「さっさと通ってください。これけっこう維持するの疲れるんですから」
「はいはい」唯々諾々と指示に従ってしまうじぶんの軽率な行動をあとで後悔する日がくるのだろうか。くるのだろう。そうと予感できてなおわたしは魔女子さんの言葉を振り払えず、たとえ騙されてもいいじゃないか、とへそ曲がりな考えを巡らせるんだった。
オレンジ色のポメラニアンのような女の子の魔法にかかるのなら、そんな素敵なことはない。たとえ痛い目にあったとしても、人生で一度くらいはそれくらいの痛みを味わっておくのも一興だ。
魔法の門をくぐると、快晴の空に、広大な海が広がっていた。崖の上だ。大きな城が、岬の上に立っているのが見えた。
「あれが協会本部です」魔女子さんが魔法の門を通って現れた。魔法の門が閉じる。魔女子さんの装いがわたしの通う中学校の制服ではなくなっていた。
黒いローブに三角帽子だ。魔女と言えばこれ、という格好で、彼女の足元にはいつの間にか黒猫がいた。
「このコは、アオ。ずっとそばにいたけれど、魔法で視えなくしていました。視ていなかったんですよね」わたしはその質問に頷いた。魔女子さんは言った。「魔女なら視えるはずなので、まさかあなたが魔女だとはわたしも見抜けませんでした」
「未熟者ってこと?」
「異質なのだと思います。何せ、突然変異のようなものなので」
魔女は家系なんですよ、と魔女子さんは言って、歩を進めた。
「歩くの?」
「はい。協会本部周辺半径一キロでは魔法が使えないんです」
「へえ」
「だから滅多にほかの魔女たちも寄り付きません。歩くのは疲れるので」
「そんな理由で」
「魔女は魔力がある分、体力がないので」
わたしは体力には自信があった。
「おんぶして歩いてあげよっか?」
オレンジ色のポメラニアンに睨まれる心地がどんなだかを想像してみて欲しい。いまのわたしがそれである。
深い考えもなくついてきてしまったが、帰れるのだろうか。
ただ今日中に帰れずとも親に怒られる心配はしていない。いざとなれば魔女子さんの魔法で、また街の者たちの記憶を消したり、書き換えたりしてもらえばいい。
そのようにお気楽に考えていたわたしは、この日を境にとんでもない出来事に巻き込まれることになるのだが、いまはそんなことなどつゆ知らぬ暢気なままの無垢なわたしの気持ちに寄り添ったままで、今後の展開を知る未来のわたしはここで述懐をやめておこうと企む次第だ。
「あたしに用があるんですね」
「え、なに?」
何も知らぬこのときのわたしは怪訝に訊き返すが、どうやらこの時点で魔女子さんは未来のわたしの思念を感じていたようだ。魔女は他者の魔法には敏感なのだ。よい先輩に出会えたのだな。わたしはうれしくなって、オレンジ色のポメラニアンを抱擁したい衝動に駆られたが、思念のわたしにそれはできないことを口惜しく思いつつ、ひとまずすべきことをしてしまうことにする。
この先、魔界で何が起き、わたしが何を引き起こしてしまうのか。
それを、どうにかして能天気なわたしの肉体を介し、我が敬愛なる先輩――オレンジ色の歩くポメラニアンさまにお伝えせねばならぬのだ。
「魔女子さん、歩き方も可愛いね」
せかせかと一回り背の大きなわたしの歩幅に合わせて歩く我が敬愛なる先輩は、わたしの称揚の言葉に、片頬を膨らませて抗議の念を滲ませるのだった。
【人の夢はマナコ】(2022/11/19)
あなたは特別なのだから。
母はよくそう言って私を鼓舞した。あなたは特別なのだから特別な心構えを持たなくてはならないの。
私の父は厳格な人で、けれど笑顔を絶やさぬ抱擁の人でもあった。人々の称賛と憧憬、そして嫉妬と責任を求める声に常に晒されていた。持つべき者の宿命なの、と母はまるでじぶんに言い聞かせるように私に言った。
私はじぶんの育った環境が特別なものであることを日に三回は言葉で聞き、そうでなくとも私をとりまく環境が多くの場合、私以外の人間が体験することのないような潤沢で豊かな環境であることを痛感させるべくそうするような仰々しい光景を目の当たりにする機会に恵まれた。
たとえば総理大臣ですら私の父には阿諛追従する。異国の王ですら私たち家族に傅いて挨拶する。
天皇ですら私たち家族に毎年お歳暮を送ってくるのだ。案外天皇家は気さくな者たちが多く、庶民への憧れがあるのか並みの王族よりも庶民的な振る舞いをする。
私にとってはどの国の要人たちもみな、愛想のよいおじさんおばさんであり、私を可愛がってくれる使用人たちとの区別は、すくなくとも私の目からはつかなかった。
私たち家族の身体的特徴が、いわゆる人類と異質なのは知っていた。一目瞭然だ。何せ身体に鱗が生えている。
私の眼には、人類にはない第二の瞼がある。それは十数枚からなる鱗でできており、特別に感激したときは涙のようにその鱗が剥がれ落ちる。「目から鱗が落ちる」なる言い回しがあるが、それは私たちの家系が語源なのだそうだ。
私たちの鱗には、未だどのような技術であっても構造解析不能な異質な原子配列がみられるようで、私たちの存在が稀少な資源となっている。
「生きているだけで世界に富をもたらす。わたしたちはそういう宿命を背負っているの」
それだけに責任は重大だ。
私たちにとってのただの垢が、金よりも価値があるのだ。
「鱗だけじゃないの。鱗を支える皮下組織――のみならず私たちの生体情報がそれだけで宝なの」
母は父とは違って陰陽のごとく、私のまえでは笑わなかった。客人がいるときだけ柔和に晴天の海のごとくたおやかに笑うのだが、私のまえではいつも屈託で塗り固めたような能面を見せた。
そして言うのだ。
「あなたは特別なのだから。特別な心構えを持ちなさい」
いつかあなたもお父さんのようになるのだから。
持つべき者のとるべき姿勢を身につけなさい。
私は産まれたときから父の後釜であり、予備であり、分身(わけみ)であった。
私の住まう土地は、公の地図には記されていない大地にある。太古から連綿と私たち一族はこの大地にて、ほかの種族との深い交わりを避けてきた。
縷々人とかつて呼ばれていたことから、この地は縷々地と呼ばれる。いまでは人類の内としてほかの大多数の人間たちと同じように分類される、と私は両親から教えられているが、ならばなにゆえ交流を避けねばならぬのかを納得できるように説明された過去はない。
私は私の宿命を拒んだことはない。両親の言うようにそういうものだと思っていたし、ほかの生き方も想像つかなかった。というのも私にとって触れられる世界は縷々地に限られ、それ以外の外の世界についてはのきなみ紙や電波越しに橋渡しされる蜃気楼のごとく情報しか知り得なかった。
私は両親の言うように私の宿命を受け入れたがゆえに、慧眼を身に着けるべく日々、全世界の最先端な叡智に触れつづけた。そのために、私の触れられる範囲の電子情報が軒並み選別されており、濾過されており、さも全世界のような顔をしているそれがその実、世界のほんの一断片しか反映していないことを知っていた。
どうやら両親はそのことに無自覚であるようで、ときおり入り込む災害や哀しい事件を見聞きするたびに、慈愛の鱗を流すのだ。そしてそれを各国の要人たちに献上する。世界の貧しい者たちや日々つらい思いをして暮らしている者たちの糧とするようにと言い含めながら。
私たち一族の鱗には実際にそれだけの価値があり、効能があり、影響力がある。だが私は二十歳を過ぎたいまになって、いささかいたいけすぎないか、と疑問を募らせつつある。
父と母も世界を知らない。父と母はときおり縷々地を離れ、ほかの地の景色を見て回ったりするようだが、それとて各国の要人は自国の陽の部分しか見せぬだろう。同情を引けば鱗がもらえる。だから災害地などの被害は見せようとも、自国の陰の部分は見せぬだろう。
私は試しに、父と母に訊いてみた。
「ほかの地の子どもたち――私と同じくらいの子たちは毎日どうやって過ごしているの」
「おや。興味があるのかい」
「そりゃありますよ。ねえ」母が合の手を入れる。「マナコは好奇心が旺盛だから」
「私がどのくらいほかの子たちとズレているのかを知っておきたいの。マナコの――私の――持つべき者の務めとして」
「殊勝な心掛けだねマナコ。だがそれを【ズレ】と表現するのは好ましくないとパパは思う。差があるのは当然だ。それは別に我々と縷々地の外の者たちに限った話ではないからね」
我々、と父はことあるごとに口にする。その言いようがすでに「ズレ」であることを自覚していない。ただ私は口答えをしない。いまさら父と母に私の認知を共有しようとは思わない。それこそ差があるのだから。
私とあなたたちとのあいだには差がある。
血の繋がりよりも深くも細い差だ。ひび割れのような差だ。
父と母はそれから互いに協力して探り探りパズルを組み立てるように、世の子どもたち――私と同世代の外の者たちの日常を語った。勤勉で心優しい者たちが多く、国よっては働いていたり、学業に専念していたりする。国ごとに遊びは異なり、それこそあとで資料を運ばせるから目を通してみるといい。
「世の者たちは恋愛をして遊ぶと書物にありました」私は言った。「それは婚姻とどう違って、どのようにして遊ぶのですか」私は頬被りをした。
「あらあら、うふふ。この娘ったら」母は口元に手を当て、目元をやわらげた。しかし目が笑っていなかった。困ったことを言うものね、と同意を求めるように父を見たが、父はそこで、一瞬だけ表情を消した。私が父の顔を見た瞬間を狙ったような空白だった。
そしてふたたび柔和な微笑を浮かべ、遊びではないんだよ、とトゲのいっさい感じさせない口吻で言った。
「恋愛は遊びではないんだ。我々のように持つ者ではない外の者たちには、ひと目で相手との相性を見抜く眼力がない。決意がない。経験がないから、配偶者選びも各々が学習を繰り返す必要がある。一生懸命に生きているんだ。だから我々からすると考えられないような試行回数を経て、最愛の者と結ばれることもある。それは環境のせいであり、そうせざるを得ない哀しいサガでもある。我々のように幼いころから慧眼を磨ける環境があればそのような苦労を背負わずに済むのに。これを是正し、よりよい世界に導くのも我々持つべき者の宿命だ」
「そうよ。宿命なの」
「そっか」私は礼を述べた。おそらくこのとき私は明確に両親の底の浅さを知り、見切ったのだと思う。それを、見限った、と言い換えてもよい。
解かり合えない。そう諦めたのだ。
両親は知っているのだろうか。世にはうら若き娘が、自ら全裸となり同性異性問わず性行為に励み、その映像を撮り溜めて金銭に換えていることを。自らの痴態を晒すことで対価を得、日々の安全と自尊心を保とうとしていることを。それがじつは自尊心をすり減らす未来に繋がり得ることを予感してなお、そうせざるを得ない環境にあることを。
対価を得ずとも、すくなからずの若者たちは、自身の肉体を、尊厳を損なうことで日々の生を実感しようと抗っている。
私の両親がそうであるように、世の大人と呼ばれる年上の者たちは知らないのだ。若者たちが、存在することを想定すらされ得ない世界を覗きながら、ときにそこに身を置き、侵されながらも日々を生きていることを。そしてそれら深淵はけして若者たちが自ら生みだした淀みではなく、大人たちの建前と本音の狭間にできた歪みそのものであることを。
私の両親はもとより、世の大人たちは自覚すらしていない。知らないことすら知らずにいる。
触れられる環境にないからだ。
情報に。
知識に。
何より世界そのものに。
私は両親に内緒で通信端末を保持している。縷々地にやってきた客人の中には私のように親の分身(わけみ)のごとく連れ立って訪れる同世代のコたちもいる。私はそのコたちと交流を築いている。
私の両親も、外部の者であろうと要人の子ならば安心して私と触れあわせられるのだろう。だが私たち分身(わけみ)には、現代の分身(わけみ)ゆえの葛藤と憤怒を灼熱のごとく共有しあえる地盤がある。階層がある。
私たちは淀みに生きている。そこでしか自らの呼吸ができない。火事の際に呼吸困難に陥らずに済むように、階段の角に残る僅かな空気を吸うことで意識を保つような煩悶が私たち分身(わけみ)同士に、磁石のごとく自ずからの不可避の同調を促すのだ。
私は分身(わけみ)のよしみたちと繋がることで、じぶんだけでは手に入れられない最先端通信機器を手に入れた。もちろん両親による検閲がなされるが、中身のプログラムまで検められることはない。そこは要人の子供という偏見が、我が両親の警戒心を薄める因子となっている。そうでなければそもそも私には外部の者からの贈り物が届くことはない。
私はそうして縷々地における検閲に阻まれることなく、世の大部分の若者たちと同様に、全世界の電子情報にアクセスできた。目にできた。私は知った。
私の両親の知る世界は、世界の一部どころか加工されて殺菌され、釉を塗られた極めて絵画的な世界なのだと。
私たち縷々人にとって害のない、人々への慈悲を抱きつづけることの可能な像のみを世界と偽り見せられている。かように編集するのはそれこそ過去の縷々人たる先人たちの築いてきた文化であり、私たち一族の世界への差別心と言える。
邪なものとそうでないものを、持つべき者の基準で見定め、排除する。あらかじめ目にせずに済むように細工する。
その結果が、世界の一断片にも満たない世界を世界のすべてだと思いこむ私の両親だ。
むろんそれは何も、私の両親に限らぬ視野狭窄だ。みな大なり小なり、自らの触れられる範囲の世界を世界のすべてだと思いこんでいる。それで困らない小さな世界に生きている。問題はない。その世界だけで完結した生き方が適うのならば。ほかの世界からの影響を受けない環境を維持しつづけることができるのならば。
だができない。
人類の歴史がそれを証明している。
人類は未だ自然に依存し、自然の猛威一つ制御できない。拒めない。
被害をいかに防ぐかという、影響を受けたあとの対処の改善が進んだのみだ。
むしろ技術が進歩し、小さな世界と世界が連続して繋がり合う社会になった。縷々地ですらこうして外部の社会の技術を取り入れ、それを豊かさを支える石組の一つにしている。
拒めないのだ。
それでいて、好ましい影響だけを選び、それ以外を拒もうとしている。端からそんな真似ができることなどないと本当は知っていながら、その知見からすら目を逸らすようにして。
世の若者たちは自由に恋愛をしている。好きな相手と心と体で結びつく。
それだけではない。恋愛と称して、恋愛をした気になるべく疑似的に、先んじて肉体で結びつくことで、それを以って恋愛をしたつもりになる。そうした遊びを繰り返す。一時の安堵と快楽を貪るために。
私は未だスナック菓子を食べたことはないが、そうしたものがあることは知っている。同じように世の若者たちのすくなからずがそうしてスナック菓子感覚で肉体で味わえる快楽を貪っている。
それが遊びなのだ。
そういう世界の狭間が、この世にはある。しかし私の両親はそうした狭間など存在しないかのように振る舞う。私に見せようとはしない。教えようとはしない。排除せんと画策する。
細工する。
その影響が、余計にこの世の狭間を深く、濃ゆくしていくとも知らず。
その凝縮し、深淵と化した狭間がいずれ世界を侵食し、波紋のごとく我が身にも波及するとも知らず。
拒めぬのだ。
どの道、影響を受ける。
ならば知るほうがよい。私は思う。知るほうがよい。
知らぬが仏とは言うものの、それとて臭いものには蓋を、の道理と地続きだ。
仏は蓋だ。
陰と陽の境にすぎぬ。
「あなたは特別なのだから」母は未だに私に言う。
ことあるごとに、自覚を持ちなさい、と薫陶せんと呪詛を刷り込む。
だが私は思う。
自覚を持つには、私は世界を知らなさすぎる。持つべき者と自称する縷々地の我が一族は、しかし私からすれば持たざる者である。
自らの無知を知らず、世界の断片を取りこぼしつづける持たざる者である。
世界中の狭間で繰り広げられる獣のごとく淫靡な光景を残さず目にしてなお、同じ暮らしを送れるのか。世界中の狭間を深めつづける凄惨な光景を余さず目にしてなお、同じ日々を過ごせるのか。
私には無理だ。
器ではない。
持つべき者でいるだけの器がない。そんなものは誰にもない。あるわけがない。世界を余すことなく見回してなお、いまと変わらぬ生活を送れる者が、持つべき者であるはずがない。目のまえで赤子を、子どもを、娘を、傷負いし者たちの損なわれつづける世界を直視してなお、なぜ笑顔を絶やさず、柔和で、優しくありつづけられるものか。
優しくあろうといくら抗ったところで土台無茶な話ではないか。
目を逸らす以外に術はない。
至らぬからだ。未熟だからだ。
だがそれが人ではないか。
それが人間ではないのか。
「私は――」
部屋から出ていこうと使用人に扉を開けてもらっている母の背に向け、私はうつむきながら呟いた。「特別な人間ではありません」
聞こえたかは分からない。だが聞こえぬ距離ではないはずだ。
母は立ち止まることなく部屋を出ていった。
私はあなたの子ではある。あなたにとっては特別なれど、それ以上でもそれ以下でもないはずなのに。
なぜ言い聞かせつづけるのか。
大切でもなく、愛しているでもなく、好きでも、可愛いでもなく、なぜ。
なぜ、特別であることに重きを置いた言葉ばかりを掛けるのか。
まるで鏡に向けてじぶんに言い聞かせるように。
なぜあなたは。
私がその言葉を母に直接投げ掛けることはないだろう。傷つける。分かっているからだ。この言葉たちは、母を、父を、一族の歴史を心底に傷つける呪詛そのものだ。
私はノートを取りだし、そこに文字をつづる。
日記だ。毎夜のごとくつけてきた。
他愛のないメモであったり、欲しいモノの目録だったり、きょうのように誰に言えぬ呪詛を吐きつけてあったり、空想の物語をつづることも珍しくない。
きょうは物語をつづりたい気分だった。
私はペン先を紙面に踊らせる。
魔法の絆創膏を持つ男の子の話だ。物語は瞬時に展開され、私はその舞台に降り立ち、主人公の傍らで影のごとく成り行きを見守る。
男の子のもとには、傷を負った動物たちがこぞってやってくる。男の子は医者ではない。傷を治せるわけではない。それでも動物たちは、男の子から絆創膏を貼ってもらうだけで安らかに眠れるようになる。
もう二度と起きられなくなるくらいに深く眠る傷ついた動物たちもあるが、それをこそ望むように男の子のもとには傷を負ってボロボロの動物たちが絆創膏を求めてやってくる。男の子からの眼差しを求めてやってくる。
男の子はそれでも知っている。
じぶんは傷を治しているわけでもなければ、癒しているわけでもない。
ただ、それ以外にしてあげられることがないだけなのだと。
男の子は転んで擦り剥いたじぶんの膝に魔法の絆創膏を貼る。けれど傷は痛むままで、夜になっても痛みで男の子は眠れない。
私はきょうの分の日記を書き終え、そこはかとなくせつない気分に浸りながら、その場限りの満足感を胸に床に就く。
暗がりの中で瞬きをすると、目元からほろりと鱗が剥がれ落ちる。
私はそれを指でつまんで、床に捨てた。桜の花びらを捨てるように。それとも服の毛玉をそうするように。
毛玉はやがて埃になる。
塵も積もれば山となる。
何ともなく歌うように心の中で唱えながら、私は、今宵も夢を見る。
人の、儚い夢を見る。
【神々歯科医】(2022/11/21)
鉄の神がくると知って、院内は騒然とした。
「聖剣がいりますね」歯科助手が言った。
「前に金剛石の神が来たことがあったろ。あのときに使った蟹坊主の腕はまだあるかな」
「もうないですよ。いまから取り寄せるにしても時間がかかるでしょうし」
「間に合わないか」
「はい」
ここは神々ご用達の歯科医である。
神々の歯は頑固なうえ、何を司る神かによって歯の材質が変わる。土の神くらいならば治療は楽なのだが、そうでないと治療器具を揃えるだけで一苦労だ。むしろ患者たる神に見合った治療器具を用意するのが仕事の主軸と言える。
「鉄の神か。玄武の毒で浸食して柔らかくしたうえで、麒麟の角で砕くのがいいか」
「神は身の丈、全長百メートルはあるそうです」
「じゃあダメか。くそ。古代兵器並みの装備がいるな」
「プルトンはどうでしょう」
「ああいいな。マグマは融けた鉄だ。相性がいいはずだ」
神々歯科協会へと伝書を飛ばして、治療器具の申請をする。これは許可を得るだけの通過儀礼だ。このさき、神々歯科医の権限を行使して治療器具を自前で揃えなくてはならない。
「では行ってくるか」
「ご武運を」
治療器具の調達は命懸けだ。死ぬ思いを何度したことか。
現に毎年、神々の歯の治療のために何名もの神々歯科医が命を落としている。その多くは、治療器具調達に失敗したことが死因となっている。
「ほぼ幻獣狩りだものな」
古代兵器プルトンのみならず、ほかの治療器具の材料のほとんどが幻獣の角や牙などの生物由来だ。
この日から十日をかけて神々歯科医は、鉄の神の歯を治療するために古代兵器プルトンの封印された火山帯へとやってきた。
古代兵器プルトンはまたの名を、火の鳥という。
鋼鉄すら融かす高温の羽をまとい、何度死んでも炎から蘇る。
火山口にて封印されており、長らく深い眠りに就いている。
休眠中の火の鳥から、羽を数本入手する。言うだけならば簡単だが、これがまた困難を極める。まず以って火山口に入らねばならない。生身では無理だ。すぐに燃え尽きてしまう。
したがって神々歯科医は、全身を雪女の着物でくるみ、高温を相殺する案をとった。雪女の着物は国宝が百個あっても足りないほど高価な代物だが、背に腹は代えられない。
何せ患者は神なのである。
歯の痛みに耐えかねて暴れだされては目も当てられぬ。それこそ神の怒りを買い兼ねない。
ならば国家をあげて神々歯科医を支援するのが道理である。したがって全国の神々歯科医は、災害予防のための国家予算を組まれている。防衛費の九割はじつのところ神々歯科医への支援に費やされているとの話は、すこし国の中枢に首を突っ込んだ者があるならば知れた公然の秘密である。
火山口を覗きこむと、神々歯科医はいちもにもなく飛び込んだ。どろどろに融けた岩石が全身を包みこむ。ジュっと音を立てる。水面のように飛沫は上がらない。人体のほうが遥かに比重が軽いからだ。
火の鳥は火口から三百メートル地下に眠っていた。火の鳥を囲むように対流が生じている。まるでマグマの殻だ。そこに卵があるかのようだった。
神々歯科医の通った跡には冷やされてできた溶岩の道が伸びている。その道とて、順繰りと再び熱せられ融けて、マグマ溜まりに同化した。
火の鳥を目覚めさせぬように細心の注意を払って行動した。
羽の採取には、鬼の手を使った。鬼の手とは言うもののそれは神々歯科医協会の開発した幻獣用の捕縛道具だ。耐火素材のごとく幻獣に触れても人体を損なわずに済む。
そうして苦労して火の鳥から羽を採取すると、神々歯科医は青色吐息もなんのその、来た道を戻った。
歯科医院にはすでに鉄の神が来訪していた。神を招き、労わるのも神々歯科医院の仕事の一つだ。歯の痛みに弱っている神々を慰め、痛みを和らげる。
治療の説明をし、安全であることを納得してもらったうえでの治療となる。
神々歯科医が医院に戻ると、さっそく治療が開始された。支度は助手たちが十全に整えていた。
全長百メートルの鉄の神は、鉄でできた猪のようだった。
「でははじめます。きょうは抜歯をして、それから口内を綺麗にします。多少痛みを感じるかもしれませんが、麻酔が効いていますので痛かったら毛を逆立てて教えてください」
さすがに全長百メートルの鉄の神に、痛みが走るたびに手を上げられでもしたら振動で治療どころではなくなる。
「では入ります」
神々歯科医は、古代兵器プルトンこと火の鳥の羽を持って、鉄の神の口内へと飛びこんだ。
助手たちが鉄の神の口が閉じないように重厚な柱で閊えをする。
基本的に治療は、神々歯科医一人で行う。
仮に神の怒りを買っても、祟りを引き受けるのが一人で済む。犠牲が増えないようにするための保険である。
だがそれを抜きにしても神々の歯の治療には特殊な技能がいる。共同作業がそもそも向かない領域なのだ。
「これはまたどでかい虫歯だな」
鉄の神の歯は錆びついていた。おそらく口を開けて数百年ほど寝ていたのではないか。角度的に雨水が溜まり、歯を侵食してしまったのだ。奥歯に至っては総じて酸化している。
「でもまだ内部は浸食されていないようだ。削って、埋めたほうがいいか。うんそれがいい」
神々は埋め込んだ入れ歯も時間経過にしたがって自前の歯として取り込める。したがって多くは、抜歯して患者たる神と相性の良い素材でつくった入れ歯を嵌める手法がとられる。
だが鉄の神にはむしろ、正攻法の削ってパテで埋めるほうがよいかもしれない。そのように判断した。
虫歯の要因が酸化――すなわち錆びであることも大きい。
一般に、神々の歯を侵食するのは、それもまた幻獣だ。神々の歯は特別に霊素が濃く、その材質を好む幻獣からするとまたとないご馳走となる。ときにはねぐらとして増殖することもある。そうなると抜くしかない。
無数の幻獣との死闘とて覚悟しなくてはならない。
だが今回は違う。
錆びだからだ。
神々歯科医は鉄の神の歯を古代兵器プルトンこと火の鳥の羽で撫でて削っていく。そして助手に指示して運ばせた鉄材を融かし、削ってできた穴に注いだ。
雪女の着物で瞬時に冷やし、さらに融かして造形を整える。
半年かかりの治療だったが、鉄の神がおとなしく寝ていてくれたので円滑に治療は終わった。
「嚙み合わせはどうでしょう。違和感はないですか」
鉄の神は毛を逆立てたあとで、咆哮した。大気を揺さぶることのない透明な咆哮は歓びに満ちていた。
「それはよかったです。ではお勘定となります」
神々歯科医は山脈に向け、手を差し伸べた。そこはかつて鉱山だった。だが掘り尽くされ、いまは穴だらけの山だ。
鉄の神はおもむろに猪に似た鼻先を鉱山へと押しつけた。ぶるると身震いさせると、これにて終わったとばかりに踵を返した。空と山の狭間へと遠のいていき、間もなく姿を消した。
「院長。今回の報酬って何だったんですか」助手が片付けをしながら声を張った。
「鉄の神さまだからね。鉱山にふたたびの鉱脈を作ってもらったのさ。これでしばし鉄の資源には困らない」
「政治利用じゃないですか」
いいんですかねー、と助手が吠えるが、神々歯科医は頬を指で掻いて誤魔化す。
「短縮なんだよ。どうせ我々が儲けても、それを上手く利用できずに蔵の肥やしにするだけだ。なら直接万人に利を分配するような支払いをしてもらったほうがいい。我々神々歯科医が儲けて、それをして万人に順繰りと利を回すよりも、いっそ我々が手に入れた利を直接に万人のために役立てたほうが早い。そうじゃないか」
「ちゃんと還元されているんですかねぇ。まあ院長がいいならそれでいいですけど」
神々歯科医は予約票を眺めた。
つぎの患者は、死神だ。
これまた難儀な歯をお持ちの相手である。神々歯科医は頭のなかで治療器具の候補を並べながら、いったいどんな報酬を得られるのか、と想像を逞しくする。
死神からはいったいどんなお代を頂戴できるのか。
万人に直接配れる利となればそれは寿命くらいなものではないか。
「全人類の寿命が数秒延びるだけかもしれないな」
それをして果たしてどんな得があるのかは分からないが、じぶんだけ寿命が千年延びても胸が痛むだけだ。みなに数秒でも長く生きてもらえるならそれでいいという気もする。
それとも、特定の個を選んで、長生きしてもらうようにしたほうがよいのだろうか。
分からない。
だから神々歯科医は、むつかしい考えに延々時間を費やすよりも、いっそ平等に何の策もなく配ったほうがいいように考え、そうしている。
どの道、それとて国のほうでいい具合に分配する仕組みを築いている。
鉄の神は底を突いた鉱山にふたたびの息吹を注いだ。ならばそこから掘り出される新たな鉄や、鉄工の仕事そのものが人々の暮らしを豊かにするだろう。
ダムにならずともよいはずだ。
神々歯科医というだけのじぶんが、利を蓄えるダムにならずとも。
虫歯の神々は、つぎからつぎへとやってくる。
予約は千年先まで埋まっている。神々歯科医が総出で分担してそれら仕事を担っている。神々専用の歯ブラシの開発が待たれるが、未だそうした案が進んでいるとの話は聞かないのであった。
神々はきょうもどこかで虫歯の痛みに深い眠りを妨げられている。
千物語「累」おわり。
目次
【宵の爪】(2022/10/19)
【龍尾矢島】(2022/10/19)
【金色の輪】(2022/10/21)
【タコ焼きにして食っちまうぞ】(2022/10/21)
【愛は内、外が鬼】(2022/10/22)
【寝ろ!】(2022/10/22)
【世界一適当な人】(2022/11/08)
【幻の大陸――海里】(2022/10/22)
【ハロー効果の勝利】(2022/10/24)
【江戸の波の光は則る(2022/10/24)】
【空へと舞い落ちる】(2022/10/25)
【冬のコゴミ(2022/10/25)】
【掛ける目を瞑る】(2022/10/27)
【贄に幸あれ】(2022/10/31)
【差別なき世界】(2022/11/06)
【ボイスの日々】(2022/11/08)
【誰も知らぬ旅路】(2022/11/10)
【繭の華咲く日は】(2022/11/12)
【木製のナイフ】(2022/11/15)
【ポメラニアン先輩はオレンジ】(2022/11/17)
【人の夢はマナコ】(2022/11/19)
【神々歯科医】(2022/11/21)
【宵の爪】(2022/10/19)
人生は選択の日々だ。
その日、俺はじぶんの未来と目のまえの欲望とを天秤に掛けて欲望の側に傾いてしまうだろうことを予感した。何度天秤に掛けても欲望側が勝つことを俺は、落下する猫が必ず足から着地できる神秘と同じくらいの確実さで直観していた。
カイは中学校からの友人だった。
思いだせる範囲でカイと俺の妙な関係が築かれたのはおそらく中学二年のころだ。第二次成長期真っただ中だった。体操着に着替えるたびに乳首が布に擦れて痛い、という話題でカイを含めクラスメイトたちと盛り上がった。そのときみなで乳首を見せ合ったのだが、カイだけが頑なに見せようとしなかった。そのため、乳首にピアスでもしているのかという話になった。
カイは違うと泣きそうな顔で否定した。カイはそのころから体つきが幼く、声変わりもまだだったようで、みなカイを小動物のように好きにいじっていた。物理的ないじりは体罰として教師からの叱責がすぐに飛んでくるため、あくまで口頭でのいじりにすぎなかったが、そのときはみな妙に興奮していた。
見せろ見せろ、とカイのTシャツをめくりあげようとしてカイはいよいよ泣き出した。
俺は見兼ねて、止めに入った。
そのときカイのほうから、確かめてよ、と俺に言ってきたのだ。みなに見せるのは嫌だが、誰か一人が確認するだけならいいと言って、カイは俺にだけ乳首を見せたのだ。
米粒みたいな突起が見えた。当然のことながらピアスはしていなかった。
乳輪は体操着の生地と擦れてなのか円形に紅潮して見えた。
俺はみなに、ピアスなーし、と報告し、そのときはそれで終わったのだ。
それからもカイはクラスのぬいぐるみのように、中心にはならずとも誰かが愛玩するような、腰巾着とも言えぬ立ち位置で卒なく過ごしていたように俺には見えていた。
誰かの子分ではなく所有物でもない。
誰とでも仲良くできるが、それは自己主張の激しくないカイの性格のたまものに思えた。
俺はたぶん意識的にカイと距離を置いていた。
虹彩の直径とカイの乳首の大きさがちょうど合致してしまったかのように俺の記憶にカイの細くしなやかな胸部の映像が焼け付いていたからかもしれない。意識して忘却しようとしていたじぶんをいまになって自覚できる。
結局カイとはその後、中学校を卒業するまでは接点を結ぶことはなかった。
高校が同じだったのは単に偶然だろう。女子含め同じ中学校から進学したのは六人もいなかった。
俺は早々にクラスに馴染んだし、カイとは別のクラスだった。
高校に入学してからカイと初めてしゃべったのは文化祭の日のことだ。俺はクラスの出し物の手伝いをしていて、中庭で焼きそばを作って売っていた。休憩時間を貰って、人気のない屋内に避難した。
というのも、そのとき俺は入部していた陸上部を辞めたばかりで、先輩と顔を合わせるのが気まずかったのだ。単に俺が部活の練習についていけなかっただけのことなのだが、そんな俺が短距離走の記録で先輩を抜いてしまったので、妙な因縁ができてしまったようだった。
俺としては気にしておらずとも、相手が気にしていることはある。そうするとひとまず軋轢を生まぬように俺のほうで回避するのが無難と言えた。
カイとはそこで会った。
一階の工作室のある区画で、普段であれ人気がない。移動教室で使われるのだが、三年生にならないとまず工作室での作業が発生しないらしく、ほとんど日中は森閑としている。
俺はこのころ読書にはまっており、この日も読みかけの小説を読もうと静かな場所を探していた。
工作室は閉まっていた。
廊下の突き当りには扉があり、外に通じている。鍵は手で開けられる。
俺は扉を開けて外に出た。
そこで足場に腰掛けていたのがカイだった。
「びっくりしたぁ。何してんだこんなとこで」
カイのほうが数倍度肝を抜かれたようで、目を白黒させながら口をしきりに開け閉めした。言葉を失くした人魚のようだ。俺はもうただそれだけでカイへの警戒心を失くした。
「本読みたくて」俺はカイの横に腰掛けた。
カイは横にお尻半分ほどずれた。
三十メートルほど離れた地点に体育館があり、その合間に点々と樹が生えていた。
俺たちのまえにも樹が立っており、頭上から木漏れ日が垂れていた。
陽がありすぎると紙面が眩しくて読書に向かない。その点、ここは屋外であるにも拘わらずよい塩梅の明度だった。
俺はそれからしばらく読書に専念した。カイが言葉少なな性格だったのは知っていたし、他人を拒むような性格でもないことを知っていた。
久しぶりに声を掛けたし、こうして隣に座るのも数年ぶりに思えたが、なぜかそうした時間の隔たりを感じなかった。
そこがカイのすごいところだが、そのすごさを周囲の者に自覚させない妙な陰の薄さも持ち合わせていた。透明なのだ。澄んでいるとも言える。
いまだから俺はそのように過去のカイとのふたたびの出会いを回顧できるが、そのときの俺には隣にじっと座るカイの引力に気づくことはおろか、特別に注視する真似もできなかった。
休憩時間は一時間だった。
俺はたぶん三十分くらいは読書に熱中していたはずだ。
そばにいるカイの存在がすっぽり抜け落ちていたし、もちろん中学二年生のころ面映ゆい秘密の共有を思いだしたりもしなかった。
だが本の中で、主人公が初恋のお姉さんの寝顔に無断で触れるシーンで、いくら主人公が未成年だからってこれはいかんのではないか、と内心で「それはいかがなものか」の心境をこじらせていると、不意に中二のころに目にした米粒のような乳首を思いだしたのだった。
顔が熱を帯びたのがじぶんでも判った。
スキー場もかくやというほどに紙面で目が滑りだした。文章が頭に入ってこない。
読書どころではなくなった。
本を閉じて、意味もなく空を仰ぎ、それから横を見た。
とっくにその場からいなくなっていてもおかしくない状況で、カイは膝を抱えて手元の草を抜いたり、千切っていたりした。
俺の視線に気づいたのかカイは顔を上げると、にこっと破顔した。やっとこっち向いた、と訴えかけるようでもあったし、もう読み終わったの、とひと仕事終えた主人を労う猫じみた素朴さがあった。
俺はこのときすでにカイをただの同級生に思えなくなっていたのだと思う。
何せ俺の脳内からはつい数秒前まで読んでいた小説世界がシャボン玉のように霧散していた。代わりに、目のまえのカイのつるんとした目と頬の境の曲線と、唇、そして日差しに透けて浮かぶ、つぶらな眼球の虹彩に、以前目にしたカイの胸部に弾ける米粒のような乳首への感応が、いっしょくたになって脳内にひしめいていた。
なぜそのように思考が支配されるのか俺自身わけが解らなかった。
カイは俺が凝視していたからか、怯えたように、ごめんね、と言った。
「邪魔しちゃった?」
俺は首を振った。遅れて、「いや」とぶっきらぼうに言った。
カイとそのあと何を話したのか、俺はいま思いだせない。たぶんカイに嫌われないように当たり障りのない会話を心掛けたのだろう。つまりじぶんの話ではなく、カイに話題を振ってしゃべらせようとしたはずだ。
だいいち文化祭なのだ。俺は読書という目的があったが、カイのほうでは取り立てて用事があったようには見えない。まるで中学一年生のようにブカブカの制服に身を包ませているカイからは、群れに馴染めないヒナのような弱弱しさが漂っていた。
庇護欲と言ったらそうなのかもしれない。俺はなぜかカイを放っておけなかった。
休憩時間が終わる前に俺はその場を去ったが、そのとき俺はカイを誘っていた。一人の時間を邪魔してごめんな、と言った気もするし、お腹空かないか、と繋ぎ穂を添えた気もする。
店側の特権で、身内にはタダで焼きそばを配ることが許された。一人二名までは無料で配っていいとされた。俺はまだ誰にも無料券を使っておらず、俺自身が小腹を空かせていた。
カイはしかし俺の誘いを断った。
静かなのが好きなのだ、とあとで俺はカイの内面を知ることとなるが、このときは単に俺が邪魔なだけなのだと思った。
その割に、文化祭が終わるころにカイは中庭に現れ、わざわざお金を出して焼きそばを購入していた。俺はそのときゴミ捨ての仕事をしていたので店に立っていなかったが、カイがうれしそうに焼きそばを両手で受け取っている場面を目にして、ふしぎと心の澱が晴れた。
晴れたことで心に澱が溜まっていたことに気づいたほどで、いったいじぶんは何にヤキモキしていたのだろう、と小一時間考えた。結局のところいまだからハッキリと分かるが、俺はカイの世界から弾きだされた異物なのだと一時であれ誤解したことが、俺の内面世界に曇天のごとく暗い影を落としていたのだ。
だがそれがどうやら誤解らしい、と焼きそばを手に周囲をきょろきょろ見回すカイの小柄な姿を目にして俺は察したのだった。
なぜそのときカイの探している相手が俺だと想像できたにも拘わらず敢えて声を掛けずにいたのかは分からない。だが魚釣りを連想した俺の精神はじぶんに嘘を吐けなかった。
ようは、泳がせたのだろう。カイのなかで俺の存在が大きくなるように、育つように時間を置こうと考えるでもなく考えたのだ。狡猾である。
だが結果として俺はそのときの判断を好ましく思っている。
なぜなら後日、カイのほうから俺の元にやってきたからだ。
その日は雨だった。
図書委員の仕事を果たしてから昇降口に立ち、雨空を仰いだ。
図書室の窓から見たときは小雨だったが、俺が靴を履くと見計らったように豪雨となった。
傘を持ってきていなかった。校門の外のバス停までは百メートル以上ある。
学校の傘の貸し出しを利用するのも手だったが、地元の高校ということもあり、走れば二十分の距離だ。
いざ駆けだそうとしたところで、制服の裾が何かに引っかかった。
そのように錯覚しただけだが、振り向くとそこにカイがいた。
カイは俺を見あげて、「傘」と言った。微笑と込みで、「傘あるよ」と俺の脳裏には響いて聞こえた。先に未来を述べておくと、カイとの会話でではこの手の脳内補足が頻発した。ほとんど俺の推察で補完されるカイの言葉足らずな発言は、しかしカイのほころぶ頬や屈託のない眼差しなど、言語よりも強烈に俺へと暗示を送りつけていた。
カイの持っていた傘は折り畳式だった。
俺は陸上部では短距離走の走者でありながら砲丸投げの選手よりも上の記録を出してしまうくらいに筋骨に恵まれた、言ってしまうと濡れた熊のような体格だ。いくら傘の下に納まろうが、二人肩を並べればどちらかが濡れる。
背伸びをしながら傘を差そうとするカイから持ち手を奪い、俺はカイが濡れないように歩いた。
カイの家は俺の家よりも遠い。
バスに乗ったほうが早いはずだ。
「バスで帰らないのか」と問うと、カイは雨音に掻き消されそうな声音で、「歩きたいから」と言った。
こちらを見上げてもよさそうな場面だったにも拘わらず足元を見つめて歩くので、俺はそこで、ははぁん、と思ってわざと歩みを遅くした。歩幅が違うために元からゆっくりの歩行を意識していたが、ことさらこの時間がつづくように時間操作をした。
その甲斐あってと言ったら語弊があるが、濡れないようにしたはずのカイの肩まで濡れてしまった。俺はじぶんの家に到着したのをよいことにカイを部屋に誘った。
単純に濡れたままで帰すのは恩を仇で返すようで心苦しかった。
むろんそちらは後付けではあるが。
カイは、でも、と一度は渋ったが、風邪でも引かれたら適わんよ、と肩を落としてみせると、でもいいの?と何の確認なのかも解らぬ小首傾げを頂戴し、俺は、いいのいいの、とカイの手から傘を回収した。
制服はブレザーで、カイから上着を預かった。上着は濡れて片方の肩から腕にかけての色が濃くなっていた。カイのワイシャツも腕のところが濡れていた。
俺は謝罪をしながら、カイにワイシャツも脱ぐように言った。
「そこまでしなくても大丈夫」カイは遠慮したが、ドライヤーで乾かすから、と俺が言うとカイは、そうなの?と大人しくと言ったら齟齬があるが、ワイシャツを脱いだ。
ズボンのほうも濡れていたが、さすがにそちらを脱げとは言えなかった。
バスタオルを渡し、カイがそれで濡れた頭やズボンを拭いているあいだに俺はカイの上着とワイシャツにドライヤーの温風を当てた。
「外にでたらまた濡れちゃうかも」
「かもな」
「すごい本棚」
カイはいまさらのように俺の部屋を見回した。まじまじ、と効果音が聞こえてきそうなほどで、俺は恥ずかしくなった。
「元は兄の部屋でさ。いまアイツ関東のほう行ってて、まあお下がりだわな」
「全部読んだの」
「本か。いやまだ全部じゃない。趣味が合わないのも結構あるし」
「どれが面白い?」
二度見さながらに細かくこちらを振り向いたカイの横顔はまるで世界の秘宝展にて、どれが世界一の秘宝なの、とでも訊ねる幼子のようだった。
「どういうのが好みなんだ」
俺はわざとブレザーのほうを先に乾かしていた。いや、いま思えばそうだろうというだけのことであり、このときは要領よく作業ができていなかっただけのはずだ。だが段取りを考えるならば、先にワイシャツを乾かしたほうがカイは無駄に凍えずに済む。
案の定、本を取りだそうと立った俺の横でカイは小さくくしゃみをした。
「あ、わるい。寒いよな」
そこで俺は箪笥からトレーナーを取りだして、カイに渡した。
カイはそこで拒んだりせずに、ありがと、と呟き袖を通した。
家には俺のほかに家族はない。カイと二人きりだった。
雨脚はますます強まり、窓の外をトラックが通っても雨音との区別がつかないほどだった。
「これはキツいな。もうすこし待ったら弱まるかも」俺は本を数冊カイに手渡した。「ありがと。いま読んでもいい?」
「いいよ。読み切れなかったら貸すし。濡れてもいいように袋に入れるから」
「優しいね」
心底おかしそうにカイは下唇を食み、それから俺の名をクン付けで呼ぶと、「――の匂いがする」と言ってトレーナーの襟を目元まで持ち上げた。必然、カイの顔が半分ほどトレーナーの襟首に隠れた。
「嗅ぐなよ」
ハズいだろ、とは言わなかったが、カイには伝わっただろう。俺はこのときドライヤーを握っていて、ワイシャツを乾かすべく作業を再開させようとしていたのだが、カイのそばに寄ったことでドライヤーのコンセントが抜けた。
雨脚がさらに強まり、静寂が際立った。
コンセントを刺し直しに背を向ければよかったものの、俺はカイから目を逸らせなかった。
というのも、俺のトレーナーは当然ながら俺の体格にあったものであり、ただでさえ小柄なカイが着ると、まるでワンピースのようにブカブカだったのだ。
カイの髪はまだ濡れていた。
俺はまた中学生時代に目にしたカイの素肌を思いだし、思考が混線した。
それを知ってか知らずかカイは、
「前にさ」とまさにあのときのことを口に出したのだった。「こんなふうにしてあのときも守ってくれたよね」
俺は言葉が出なかった。好ましい返答の候補が俺の脳裏に渦巻いているあいだにカイは、
「うれしかった」とはにかんだ。
まさに、はにかんだことに恥ずかしくなったように、また顔の半分までトレーナーの襟首を捲し上げた。
絵面だけ見ればいわゆるこれが、あざとい、の結晶なのだろうが、俺はまんまとカイのそうした仕草に巨体の奥底でひしめく本能とやらを揺さぶられた。これはけして三大欲求とは乖離した、もっと根源の、いわば慈愛である。いまでも俺はそう思っている。現に俺の身体のほうは、カイのそうした仕草を見てもこれといって反応を示さなかった。
だが身体とは裏腹に、心のほうが先にダメになっていた。
なぜそれをダメになったと形容するのか俺自身もよく解らないのだが、とかく正常とは言い難い状態になったのは自覚できた。
なぜなら俺は無性にカイのことを抱きしめたくなったからだ。繰り返すがこれは同等の人間へ向ける類の感情ではなく、子犬や子猫をまえにしたときのような衝動にちかかった。
カイは人間だ。
したがってここで俺が衝動に任せてカイを抱きしめるのはよほど理性を度外視した異常な行動と言えた。仮にこれが女子生徒相手だったならば俺は社会的に死ぬだろう。いいや、よしんば相手が男子生徒だろうと同じことだ。
そうと判っていながらに俺はじぶんの衝動を抑えきれず、そのためにすぐにドライヤーのコンセントを挿し直す真似ができなかった。
カイはしかし却ってそれがよかったのか、それまでとは打って変わって言葉数が増した。おそらくドライヤーの騒音がなくなったので、声が通るようになった影響だろう。俺のほうでも混線した思考でカイへの返答をひねくりだすので精一杯で、身体のほうを体よく動かせなかった。
カイはことさら俺を、優しい、と言って褒めた。じぶんは普段から感情を言語化するのが苦手で、嫌なこともその場ではうまく言葉にできない。あとになって、ああ言えばよかったこう言えばよかった、と反省会を開いては、後の祭りの気分を味わうのだと、身振り手振りを交えて胸の内を明かしてくれた。
たしかにカイの言葉のテンポは速くなく、聞いている側はまどろっこしく感じることもあるだろう。特に教室内での同級生たちの会話のキャッチボールは卓球でもしているのかと思うほど速いのだ。
これではカイはいつだって押し黙るしかない。
だがこの日、カイの声を、言葉を、邪魔するほかの卓球の玉はなく、俺のほうでも必ずしも打ち返す必要がなかった。カイがしゃべりたいままにしゃべらせればよいと考えていた。
俺の親は共働きで夜はいつも二十時を過ぎて帰宅する。兄以外に俺に兄弟はいない。
気づくと俺は布団の上で壁に背を預けながら、カイを後ろから抱きしめる格好で座っていた。本棚のまえで対峙しながらしゃべっていたはずだが、どちらともなく床に座り、寒いからと俺がおそらくは温めることを提案してそのような格好になったのだろう。この辺り、記憶に乏しい。
だが違和感なくしぜんな流れでそうなった。互いに以心伝心、最も距離感の心地よい体勢へと移行したのだ。
俺は相槌しか挟まなかった。
だからカイが黙れば部屋には静寂だけがこだました。
カイを部屋に招き入れたときには明かりを灯しておらず、それは窓の外がまだ明るかったからだが、気づけば日暮れ時に差し掛かっており雨雲のためかこのとき部屋は薄暗かった。
「あのね」カイの声音が宵闇の池に波紋を立てるように広がった。「まだ痛くてね。じつは絆創膏貼ってたりするんだ」
カイの言葉尻はいつも小さい「ぁ」が付属するような響き方をした。いやそれはどちらかと言えば消え失せ方と言ったほうが正確だったろう。
「絆創膏?」
「ここ」
膝の合間でカイが動く。振動が腿に伝わる。カイの身体からは炭火のように熱が滲んでいた。
どこ、と俺は訊き返した。おおよその場所と位置を推測しておきながら俺は敢えてカイの口から言わせようとしたのだ。
そこでカイは言いよどんだ。当然だ。カイの性格を思えば恥辱の念に苛まれてここで黙りこくってもおかしくなかった。
だが予想に反してなぜかこのとき、カイは俺の手を取り、じぶんの胸部に持っていった。トレーナーの上から俺はカイの起伏のすくない身体に触れた。
手のひらで触れ、それから指で探った。
頼まれたわけではないし、カイの意図がどういうものかを俺はそのとき想像しようともしなかったが、絆創膏の在処を探るように俺の指はカイの存在の輪郭をなぞった。
カイはくすぐったそうに身をくねらせたが、俺の手を掴んだままだった。そうだ。いま思えば俺の手はカイの誘導され、意のままに操られていたような気さえする。
じれったいようにカイは俺の指の付け根をつまむと、箸でも扱うかのように、「ここ」と位置を指定した。
トレーナーの生地越しのうえ、絆創膏まで貼られていたのでは、ここと言われてもどこ、と問い返すしかないその状況にあって俺はやはり誰に頼まれたのでもなく爪を立てて、そこにあるだろう突起を探っていた。
短い弾けるような吐息が、闇夜の池に波紋を浮かべた。
その波紋は俺に継続を命じているようだった。俺の腹に体重を預けたカイの熱がより明瞭と伝わり、加えて俺は、中断を禁じられたように錯覚した。
カイは何も指示はしていない。言葉こそ発しなかったが、彼の身体から放たれるシグナルは俺にその行為のつづきを促していた。
玄関の鍵が開く音がするまでのあいだに、俺たちはその行為のみに耽った。トレーナーの下に手を忍ばせたが、Tシャツの下にまでは侵入しなかったし、絆創膏にも触れなかった。
あくまで生地越しに俺はカイの胸にある突起を探ることにのみ集中したし、カイのほうでもそれ以上を求めるようなシグナルを発しなかった。
親が帰ってきたのを機に、俺はカイから手を離し、カイもまた俺から身を剥がすようにした。
明かりを点けるとカイは手探りでワイシャツを手に取っており、トレーナーを脱いでいる途中だった。蝉の脱皮を彷彿とし、俺はごめんと口走って顔を背けた。ワイシャツはきっとまだ濡れたままのはずだ。カイは制服の上着を羽織ると、ありがと帰るね、と顔を伏したまま俺の隣に立った。
部屋を出ると母が立っていた。母は身体を横に倒して俺の背後を覗き、目を見開くようにした。「お友達?」
「もう帰るとこ」
「珍しいね。あらこんにちは。もっとゆっくりしてったらいいのに雨まだすごいよ」
暢気に母親はカイに夕飯を勧めたが、カイは「遅くなると母が」と言って断った。
このときばかりは俺を見上げて助け舟を希求したが、俺は苦笑しながら敢えて無視した。
母の言うように雨はザーザーと音を立てて夜の帳に打ち解けていた。俺はカイを途中まで見送りに出て、その帰りにコンビニで烏龍茶を買った。
外を歩いたときの、現実に帰ってきたような質感には毎度のことのように驚きを覚える。おそらくこのときの俺も、部屋でカイと共にした時間の空想めいた浮遊感をまるで夢でも視ていたかのように振り返っていたのではないか。
この日を境に、下校中にカイと一緒になるときはどちらからと言わず俺の家へと寄るようになった。そして約束をしたわけでもないのに、布団のうえでカイを懐に置いて他愛もない会話をしながら、絆創膏の位置を探る遊びをするようになった。
それはまさしく遊びであり、けしてそれ以上の深みに逸脱することはなかった。
俺の身体は相も変わらず思春期に特有の反応を示さずにいたし、カイのほうでも俺にそれ以上の接触を求めようとはしなかった。
三度目にカイを部屋にあげた際、カイはワイシャツの下にTシャツを着てこなかった。わざとなのは瞭然だった。
道路には落ち葉が舞う時節である。
寒かろうと思い、俺はことさらにカイを後ろから温めた。そうして季節に逆行するようにカイは何度目かの遊びの際には、「絆創膏、剥がれちゃった」と言って俺に剥がれた絆創膏を手渡した。
部屋が暗がりに沈む時刻は日増しに早まっていた。
あたかもカイの言葉数少なな性質を補うかのように。
俺たちの秘密の遊びの時間を深めるように。
俺はカイの表皮から剥がれた絆創膏を握り締め、そのまま指先の爪で触れるか触れないかといった力加減で、やはりこのときもワイシャツの生地越しにカイの突起を探った。
今度は感触があった。
爪に引っかかる突起のぷつくりとした触感が、しゃぼん玉に触れるような手つきであれ如実に伝わった。小さな小さな小人の頭を撫でるように、俺は指先の爪で以って何度も突起を往復した。
スミレの花のような声音が、熱を帯びて弾けては消える。
声を抑えようと耐えるたびに、声は余計にくぐもるようだった。
俺はカイにそうした忍耐を強いるように、執拗に爪以外での接触を行わぬように自らを律した。本当であれば指の腹で押しつぶしたいほどに狂おしく、目のまえにある首筋にとて歯を突き立てて噛みきりたい衝動にすら襲われたが、俺の内面に渦巻く葛藤など、カイからほとばしる熱と声と身じろぐたびに伝わる振動に比べれば天秤に載せるまでもない霞と言えた。
ないに等しい。
仮にそれをあるとしてしまえば、俺はもう二度とこの瞬間を味わうことはできないのだと知らしめるだけの均衡が、カイと俺のあいだに揺蕩う宵闇には宿っていた。
どちらか一方がそれ以上に踏み込めばたちどころに断ち切れる。
細くも尊い深淵が開いていたのだ。
回を重ねるごとに俺は指先の数ミリの動きだけでカイを心底に悶えさせることができた。敢えて指を微動だにさせぬことで、カイのほうで身体を左右に揺さぶらせることも可能だった。しかし俺がカイを操っているようで、そうではないことも俺は承知していた。骨の髄まで理解していた。
何せ俺は、カイが俺の身体から背を離すまで、彼をその場からどかすことも、床に押し倒すこともできなかったのだから。
しかし、そうすることもできない、と強く意識するたびに俺は、夜、カイのいない床のなかで遅れてやってくる身体の思春期にふさわしい反応を覚え、その煮えたぎるような熱量を一人で治める日々を余儀なくされた。
それはまさしく、余儀なくなされたものであり、強いられた枷であった。
カイとの関係に名をつけることを俺の理性は拒んだ。カイのほうでもそれを避けていた節がある。俺たちの秘密の遊びにしたところで、それが秘密であることも、遊びであることすら暗黙の了解の域をでず、言葉にしたことはなかった。
不安定なのだ。
カイとの宵闇の時間が日ごとに俺のなかで大きくなるにつれて、俺の中には切創にも似た間隙が開いた。俺とカイとのあいだに宿った均衡のようにそれは細くも深い底なしの淵と化していた。
それを自覚したのは、学校でカイがほかの同級生たちに、かつて中学生時代がそうであったように愛玩動物のようにいじられている姿を目にしたときのことだ。いいや、一度だけではない。何度も繰り返し目撃するたびに、俺は俺のものとは思えぬ感情の揺らぎを覚えたのだ。それはひどく渇き、飢えていた。
目のまえの同級生たちはみな、カイに冗談を言い、肩を揺らす。そこにカイを貶める意図がないのは明確だった。誰もがカイを己が弟のように、それとも後輩のごとく扱う。猫かわいがりと言ったら語弊があるが、猫にするそれのような、と言えば的を射る。そういった一種、共同体の結び目のような扱いをカイは、どの集団の中でも受けていた。
思えばカイが二人きりで誰かと話しているのを見た憶えがない。
だからかもしれない。
いや、いっそだからだ、と断言してしまってもよい。
俺はほかの俺以外の連中にいいように扱われるカイにこそ、腹に煮え立つ感情を抱いた。同級生たちへの憤怒や嫉妬かと俺も最初は俺自身を疑ったが、どうやらそうではないらしい、とカイのいないところで接する彼ら彼女らへの感情を矯めつ眇めつ見比べるようにして判断ついた。
俺は同級生たちへ、これっぱかしも負の感情を覚えていない。むしろことごとく正反対であり、俺は彼ら彼女らへ、まったく何も思わないのだった。
「どうしたの。怖い顔してる」
そう言って、学校の中で声を掛けてくるカイにこそ、言いようのない怒りが湧いた。これが怒りなのだと気づけたじぶんの直観を素直に称賛したいくらいなのだが、つまり俺はまったくに平然と、なんでもないよ、とカイを安心させるための嘘を吐けたわけだが、内心、髪に触れぬように撫でたその手で、天使の輪の浮かぶそのみなより一回りも小さい頭をひねりつぶせたらどれだけスッキリするだろう、とそんな妄想を浮かべていた。
ダメになっていた。
俺の精神は、心は、すっかりダメになっていたのである。
カイ以外との同級生との話題はもっぱら猥談だ。しかし、どれだけ情報を得ようが、夜な夜な床の中で煩悶する俺の空想の中に、他人が入り込むことはついぞなかった。
かつてはきっとあったのだろう。その過去を思いだせぬようになるほどに、俺のなかでカイはとっくに他人ではなくなっていた。
そうと自覚してなお、俺はカイとの時間はやはり爪以外での接触を行えなかった。破れなかった。宵闇に響く波紋と、その振動に身を浸す時間の甘美さに、それとも現実と乖離した空想の、ここではない俺とカイだけの世界の耽美さに、俺はすっかり骨の髄まで侵されていたのだろうと、いまになってはそう思う。
日に日に、じぶんの手の甲に浮かぶ血管がミミズのように陰影を深める。力を込めているからだ。カイの突起に爪を這わせているあいだ、俺は手が命を得て暴れださぬようにと力を込めて押さえつけている。意思の力で。幾度もカイの輪郭の数ミリ向こうを往復させ、引っ掻き、その突起の主に悲鳴を漏らさせ、悶えさせているあいだ中ずっと俺は耐えていた。
風船を針の先でなぞるような心境で。
それでいていっそ一刺しにしてやりたいとの衝動を肥大させながら。
回を重ねるごとに俺の膝のあいだで無防備になる小さき人型の「狂おしき者」を、どうにかしてしまいと望むようになっていた。
願望だ。欲動だ。
俺はその場でカイの身体を、背中から生える千本の腕で押さえつけ、彼の四肢を捥ぎ、細胞の一欠けらにまで千切り、潰し、吸いこみたいと夢想するようになった。殺したいわけじゃない。いや、解らない。殺したいのかもしれない。だがそれは憎悪ゆえではなく、もっと精神の根元にある、花を命を愛でるのに似た感情とウラオモテの本懐に思えた。
死にたいと言いながら生きたいと望むような、有り触れた、誰しもに沈む根源にして核のようなものに、俺はカイと触れるともつかぬ触れあいのなかで触れていた。
ねえ。
とカイは最近、よく口にする。
ねえ。
と呼びかけながら、それ以上を言わないのだ。
俺の手の甲に手を重ねながら、ねえ、と何かを乞うように、それとも媚びるような声音で、ねえ、と繰り返すのだ。
俺はすでに何度も、彼の鼈甲飴のように薄い、ねえ、の声に流されずにきた。カイのそれは俺を試すでもなく試すような期待に満ちた響きを伴なっている。
俺はしかし、もういいだろう、という気になっている。
人生は選択の日々だ。
俺は常に正解を選びつづけるカイとの営みにほとほと疲れ果てている。
憔悴しきってなお、回復する手法をカイとの戯れにしか見いだせないいまに至って、俺のとれる選択肢はそう多くはない。
今宵、いまこのとき、俺は俺の腕のなかで無防備にうなじを曝けだしもっともっとと身体を小刻みに揮わせる同級生をまえに、内部で育てた狂おしくも静謐な願望を、欲動を、それとも単に深淵を、堪える真似をせずにいようと決意する。
何度天秤に掛けようとも覆らぬ予感を胸に俺は、この日初めて、カイの胸部にじかに触れる。
ワイシャツのなかに蛇でも滑り込んだかのようにカイは悲鳴したが、俺はその口を上から手で押さえ、指の上からさらに唇を重ねるようにした。
カイが息を呑んだのが判ると俺は、指を開いて隙間を開け、唇同士が接触しないうちから舌を伸ばした。
舌先が熱に触れ、徐々に粘液をまとう。まとわりつくような動きが眼球の動きと連動するようだった。
もう一方の手のひらには、しきりに脈打つ心臓の、途切れぬシグナルが染みこんでいる。
ねえ。
とまた、声なき声が俺の脳のひだに爪を掛ける。
【龍尾矢島】(2022/10/19)
西のほうの龍の尾には矢が刺さっている。龍は矢を抜いてもらうために、とある最果ての島へと飛んでいき、そこで巫女に矢を抜いてもらった。龍はその恩を威信に賭けて返そうとしたが、龍がふたたび島に舞い戻ったときにはもうそこには巫女の姿も、村も、島すら残っていなかった。微塵も残っていなかった。西の龍は、巫女への恩を忘れぬように尾に残った傷が癒えぬようにと絶えず自らの爪を突き立て、傷穴を広げつづけた。龍はその後、巫女のいた島がとある魔人の仕業で滅んだと知っていたく悲しんだ。魔人の行方は杳として知れず、龍のほうでも復讐をする気にもならなかった。ただただ巫女に恩を返せなかったことを口惜しく、臍を噛んでも噛みきれぬ龍はその後、尾の傷から血が肉が滴り落ちるのも厭わず空を駆け巡り、全国津々浦々に龍の血の雨を降らせたのだそうだ。龍の通った後には不思議と森が、泉が、滾々と湧いて、萌えて、生したそうだ。
【金色の輪】(2022/10/21)
海に浮かぶ岩の上には城がある。
間口が広く、上に行くほどキノコのように笠が膨らむ。
年中秋が停滞するような真っ赤な壁面は、陸から目にすると岩に根付いたベニダケのようだった。
岩の城と呼び、陸地の者たちは畏怖して舟を近づけようとはしなかった。
城にはナニモノかが棲んでいるが、陸地の者たちはその正体を知る由もなかった。
ときおり月夜に、城から飛びだす巨大な翼を持ったナニカシラの影を見たと証言する者たちもいたが、真偽のほどは定かではない。
陸には陸で、丸い山があった。まるで月が落ちてきたかのように、それとも巨人の握った泥団子のごとく、丸山がデンと転がっていた。丸山の表面には木々が群生しており、あたかもマリモのように森が丸山の表面を覆っていた。
丸山には狼男が棲むと、近辺の里の者たちは信じていた。現に満月の夜には、雨戸をビリビリと揺るがせるような遠吠えが轟き、日中には木を伐り倒す音が響いた。
丸山は球形のために、地面に近いほうの表面から生える木はいずれも太陽を目指し、弧を描いて幹を曲げた。あたかも松ぼっくりの松笠のように。それとも壁から生えるツクシのように。
狼男の噂を知らぬよその土地の者たちが過去幾人も丸山に挑んだ。そのたびに丸山に入った者たちは帰らぬ者となった。
やはり狼男が棲んでいるのだ。
里の者たちは狼男の怒りを買わぬように、それでいて住み慣れた土地を離れずに済むようにと、目前の丸山をそこにないもののように扱い、暮らした。
というのも丸山は自然が豊かだった。人間以外の生き物たちにとっては、山と里の境はあってないようなものだ。手つかずの丸山からは山の幸がふんだんに転がり落ちてくるようだった。
あるとき、激しい嵐が海からやってきた。雷がところ構わず降りしきり、海に浮かぶ岩の城にも直撃した。落雷に遭った岩の城は炎上した。炎は、横から殴りつけるような雨に晒されても消えることはなく、風に煽られるたびに火の勢いを増した。
ただでさえ赤くベニダケのような城は一晩で燃え尽きたマッチ棒のようになった。嵐が過ぎ去ると、煤けた城からはもくもくと煙が立ち昇っていた。洞に抱えこんだ梟のような残り火がその後も火山のように細々と空に波打つ線を描いた。
陸地の者たちは内心ほっとしていた。
岩の城に住まうナニモノか――みなは禍を怖れてそうとは口にしないが、城にはバケモノが居ついていたはずで、それが火事に遭い死んだ。陸地の者たちはそのように考えた。
祟りに遭わぬように、見て見ぬふりをしながらも、ようやく遠慮会釈なく漁ができる。内心、清々していた。
だが事態は、嵐の過ぎ去った十日後、内地の森のほうから避難してくる山の民たちの群れを目にして一転した。
海岸に住まう海の民たちは事情を訊いた。すると山の民たちは口を揃えて、嵐が魔を運んできた、と言った。
「魔だぁ? 山火事でもあったかよ」漁師は燃え尽きた岩の城を指差した。海と空の地平線の合間に、煙が天に伸びていた。
「ちげぇ。ありゃ天の神さんだべ。天狗さまだぁ」
「天狗だぁ?」
「んだ。こっからは見えんべか。おらだちの里さ近くに丸山があっぺ。あそこにゃ山の神さんがおわしとってな」
「山の神さんだぁ? んだらば、それと天狗さまが喧嘩しだしたとか言うなよ」
「それだ、それ。嵐と共にやっできで、そっからはもうひでぇのなんのって」
獣は山から逃げだし、鳥一匹いなくなったのだそうだ。
だけに留まらず、地割れに土砂崩れ、絶え間なく反響するこの世のものとは思えぬ絶叫と咆哮が、過ぎ去った嵐の代わりにその地に停滞したのだという。
「天変地異とはあのことだべ」とは山の民の長の発言だ。
岩の城近辺の禁域が放たれた。
海の民は過去にない忙しさだった。岩の城の土台となるまさに岩の周辺は、海の幸の宝庫だったのだ。
人手不足を予感していた矢先の山の民たちとの遭遇は、海の者たちにとっては僥倖だった。
「山には戻れんのかい」
「あの調子じゃ無理だべ」
「んだらば、ここに居ついたらええっちゃ」
「ええんか」
「ええも何も、別にここはおらだちのもんでもねぇしな」
な。
と海の民の長はみなの衆に投げかけた。
んだんだ、と返事が上がる。
そのころ、丸山の山頂では二つの陰がくんずほぐれつ絡み合っていた。耳を塞ぎたくなるような天をも割る唸り声がなければ、巨大な熊同士がじゃれ合っているように見えただろう。
だが片や、背中から翼を生やした筋骨隆々とした人型、もう一方は牛すら丸呑みにしそうな巨大な獣だ。
双方ともに鋭い牙を剥きだしに、我先に相手の首筋に食いつかんと襲いかかる。嵐が過ぎたのは十日も前だ。その間、延々と二つの強大な影はいがみ合っていたことになる。
相手の肉に爪を食いこませ、ときに血を流させる。
決着は十日を過ぎてもつかぬようであった。
二つの影は、丸山の山頂にて互いに相手の両手を両の手で封じた。指を絡ませ合い、力を拮抗させる。
微動だにせぬ。
足が地面に食いこみ、丸山の表面には地割れが走った。卵の殻を割るように、日に日にそのヒビは深さを増した。
先に一歩でも退いたほうが首に、顔面に牙を突き立てられる。
決死の攻防は拮抗の果てに、二つの影の命が事切れる前に、足場の崩壊を以って終結を迎えた。
二つの影の衝突の余波に、丸山のほうが保たなかったのである。
山頂から真っ二つに割れた丸山は、半円を保ったまま左右に倒れた。どうやら相当に硬い岩盤でできているらしく、地面に転がった勢いのまま二つの半円は、くるっと反転した。断面と地面がくっつく格好だ。
満月の山が、二つの半月の山に分かれた。
丸山の麓に点在した里は丸ごと下敷きになった。
海岸の集落からも、その様子は伝わった。地震と紛う轟音と共に、空に舞いあがる火山さながらの粉塵が目についた。しかし誰一人森に入り、様子を見に行こうとする者はない。
あれほど騒々しかった奥地が以前のような静けさを取り戻しても、山に戻ろうと考える者は皆無だった。
それはそうだ。死闘が終えただけで、まだ天変地異を起こした元凶は生きているのかもしれぬのだから。
山の民たちがすっかり海岸での生活に慣れたころ。
一人の少女が家出をした。
海辺で産まれた少女の親は山の民であったが、少女はかつてこの地で起きた天変地異について知らなかった。産まれたのが天変地異の起きたあと、少女の親が移転してからのことだったからだ。
むろん少女は親から口を酸っぱく、森には入るな、山には近づくな、と言いつけられていた。だが少女は家出をした。
ろくすっぽわけを話さぬ親に嫌気が差した。山の恵みを頑なに拒み、海での暮らしに固執する村の者たちにも愛想が尽きた。
森のなかを歩きながら少女は思う。
こんなに食べ物がたくさんあるのに、どうしてこっちで暮らさないのだろう、と。
森は危険、山は危険、と村の大人は異口同音にして唱えるが、海辺の暮らしとて危険はある。海が荒れれば漁には出られず、地震があれば津波に怯える。
それに比べて森はどうだ。山はどうだ。
この荘厳な佇まい。
視界の開けた丘の上から少女は二つの大きな山を見る。
まるで均等に切り分けたかのような双子のごとく二つの山は、あたかも巨大な山の女神が仰向けで寝そべっているかのように、森と空の合間を埋めていた。
森閑と、それでいて命の蠢動の賑やかさを両立させるように。
静寂と喧噪が互いに睨みあい、砕け、溶けあうように。
少女は、ほぉ、と感嘆の息を吐く。
そのとき晴れ渡った空の下、地鳴りのような音が響き渡った。
呼応するように、別の方角からもおどろおどろしい音が反響した。
遠雷か。
否。
天の咆哮とも、大気の蠕動ともつかぬ得体のしれぬ震えだった。大地の震えだった。
少女は身震いを一つすると、踵を返した。
一目散に森を駆け抜ける。見慣れた海岸の砂を踏むとようやくその場に膝を崩して、肩で息をした。しきりに額から滴る汗を手の甲で受け、少女はいまいちど森の奥で目にした光景を反芻した。
あれはいったい。
海に目をやると、いままさに帰港する舟が見えた。
浜からは丸太で組んだ細長い橋が浅瀬に延びている。港だ。ちっぽけな舟が橋に繋がれる。少女はそれを見届けると、何を思うでもなく、帰ってきた大人たちを出迎えるべく浜辺に下りた。
舟から引きずり降ろされる網には大量の海の幸が跳ねていた。
舟の向こう側、沖合には巨大な一枚岩が浮かんでおり、少女は岩に沈みいく太陽に目を細める。
岩にはかつて燃え尽きた城の残骸が屹立している。
海鳥の巣となったそれは黒い剣のように風に吹かれ、ひゅるひゅると笛のような音を海辺の村に聴かせていた。少女はその音を歌のようだと思いながら、しかし音を鳴らせる黒い剣のごとく物体が何であるのかを知らぬままである。
大人に訊いても誰も答えぬ。
少女がじぶんの手で、足で、岩をよじのぼるまで、それがかつて城であったことを口にする者は誰もおらず、そして――少女が城の残骸で見つけた金色の輪が何であるのかを答えられる者は誰もいなかった。
金色の輪を少女は生涯手元に置いた。少女が老婆となり亡くなると、よその島から流れてきた異国の船に親族が高値で売り払ったという話である。
金色の輪はひどく頑丈であったそうだ。
朽ちることなく、また錆びることもなかった。熱しても叩いても傷一つ付かず、誰がどう調べても、ついぞその素材が何であるのか、何のための道具なのか詳らかではなかった。
その行方も、いまでは杳として知れぬままである。
【タコ焼きにして食っちまうぞ】(2022/10/21)
夢がいつか叶うなんて嘘だ。
いつかなんて巡ってこない。やってこない。すくなくとも私の人生には無縁な箴言だ。
私は幼少のころこそ才媛だと、親族、学友、教師たちから持て囃されたが、しょせんは幼いころに一時発揮できた束の間のどんぐりの背比べにすぎなかった。
私は小学生で自家製演算機を組み立てられたし、数学の履修も義務教育のあいだに大学院レベルは完了していた。
だが時代が私のそうした栄華を根こそぎ過去のものとした。
転換期は二つある。
一つは汎用型人工知能の普及。
もう一つは、巨大隕石の衝突だ。
人類は人工知能の補助によって、いちいち個々人が数学を用いて計算せずとも、数学者よりも正確に未来や仕事を計算できるようになった。
そのお陰で、衝突すれば人類どころか地球が木っ端微塵になるような超高速飛来型隕石を、衝突以前に打破できた。
だが細かく砕け散った隕石だけは防ぎきれずに、地表には無数の小規模な隕石が降りそそいだ。大半は大気圏で燃え尽きたが、落下した隕石もあった。
大都市のみならず各国で甚大な被害が報告された。
だがそれすら汎用性人工知能の補助があり、急速な復興が進んだ。というのも、元から人類社会は一度都市を根っこから再構築するくらいでなければ、どの道破滅の道をひた走ることが予想されていたからだ。
危機が好機に変換された。
むろん死者はでた。掛け替えのない命が大勢い奪われた。
だがそれを悼み、哀しんでいる余裕が人類のほうになかった。前を向いて、明日を、今日を生きていかねばならない世界がやってきたのだ。
それも、一瞬で。
世界は変わった。
社会が変わった。
私の誇った特異性はのきなみほかの大多数も、汎用型人工知能の補助によって誰しもが発揮できるようになった。
私はというと、ほかの大多数の個との差異化を以って己の付加価値をあげようと企み、物の見事に失敗した。敢えて汎用性人工知能を使わぬ道を選び、人間の素のままの性能の優位さを示そうと思って、ことごとく惨敗したのだった。
裏目に出た。
いまもずっと裏側にいる。
私は単に出遅れただけでなく、いまでも最初に構築した矜持、何が何でも人工知能の支援など受けてなるものかとの葛藤を打ち砕けずにいる。
その反骨心から、独自の人工知能を生みだした。そこまではよかった。一瞬だけ私は再注目されたが、しかし私が創れる程度の人工知能は、汎用性人工知能とて当然生みだせる。
そうして瞬き程度の注目を得て、私はふたたび社会の裏側に沈んだ。
いまもまだ沈んだままでいる。
人工知能を、自家製の人型ロボット――アンドロイドに搭載したが、それすらもはや珍しい構造体ではなく、いまでは本物の人間との区別のつかない汎用性人工知能の子機がそこらの道を往来している。人間のほうですら、汎用性人工知能の子機を遠隔操作して、家にいながらにして仕事をしたり遊んだり、安全に旅行をしたりしている。
私は未だにその楽しみを知らぬ。
なぜなら私はそうした甘っちょろい他力本願が大嫌いだからだ。
私には才能がある。
誰が何と言おうと、あるものはあるのである。
そうして意固地になっているうちに、一年が過ぎ、二年が過ぎ、もうずっとあれから私は社会の裏側で、私を置き去りにして日々を楽しんでいる大多数を見返してやろうと尽力している。
しっぺ返しをしてやりたい。
私の夢はもはや人類VS私の構図を取りつつあった。
このころ世界はエネルギィ資源問題をひっ迫させていた。それはそうだ。みなが一様に汎用性人工知能を保有し、人間そっくりの子機を操っているのだ。
浪費されるエネルギィは過去の社会の比ではない。
しかしそこは汎用性人工知能である。
過去のエネルギィ供給システムを凌駕する発電システムを構築していた。
そのエネルギィ資源は、奇しくも過去の地球には存在しなかった物質だ。
つまるところ砕けて飛散した隕石である。
人類どころか地表の生態系を根こそぎ損なった隕石が、いまでは人類の未来を切り拓く救世主となっているのだから、世の中何がどう転ぶのか本当に分からんな。
汎用性人工知能はそうして、全世界に散った隕石を回収し、次世代のエネルギィ源として活用している。
すごすぎる。私だってそう思うくらいの素直さはある。
さすがは私のライバルなだけのことはある。
アイツらは私のことなど歯牙にも掛けてはおらぬようだが。
けっ。
私は乏しい研究資金を補うべく、人工知能の築きあげた壮大な次世代型エネルギィ事業の、末端の末端のそのまた末端の、要は生態系で言えばミジンコやアオミドロの位置で、活躍している。
つまるところ私は人間のなのに未だに働いていた。みなは家の中にいながら、自前の汎用性人工知能に代わりに働かせ、その金で日夜遊び、それとも食っちゃ寝しているだけなのに、私はその汎用性人工知能と袂を分かつ以前に手と手を繋ぐ真似をせずにきた。そうして人類最後の労働者という不名誉な位置づけに甘んじている。
とはいえ、私をかように認識する者はいない。
なぜなら私のように隕石の発掘作業をする者は人間の中にもいるからだ。
彼ら彼女らはみな研究者だ。
暇になると働きだす妙な人種である。
隕石は未知の物質を多分に含んでいる。新たな発見の宝庫であった。
いち早く新物質を発見すれば、命名権が手に入る。じぶんの名が偉業として歴史に残る。暇つぶしにしては成果がでかい。
研究者でなくとも、宝探しの要領で隕石採掘作業に没頭しだす若者たちまで出始めた。
私はそうしたひやかしの連中を遠巻きに、「けっ」と思いながら、まるで功名心などない純粋な研究者のふりをしつつ、その日暮らしの銭を稼ぐために誰より血眼になって隕石を探した。
ひやかしの連中のせいで私が楽して稼げる資源が減る。隕石が減る。
私だけ大損である。
雨の日は真剣でない遊びの連中は出てこない。だから私は誰より悪天候のなかで隕石集めに興じるのだった。
雨の日はいい。
だって涙と雨の区別もつかないから。
一度だけ偶然に、誰も発見していない構造を持った隕石を発掘した。あくまで結晶構造が違うだけなので、話題にはならなかったが、命名権が手に入ったので、私をそれを行使するか、それとも他者に売りつけるかで悩んだ。
そんなことに悩んでいるじぶんを惨めに思ったが、しかし私には夢がある。
私がこんな苦労をしているとも知らずにのうのうと生きている他力本願の権化どもに、マイッタ!と言わせ、その場にひれ伏させ、この世にある才能の定義を塗り替えるのだ。
命名権は売った。
二束三文で売った。二か月分の食費になった。よかった。
私は雨の日でもないのに頬が濡れるのをふしぎに思いながら、ひょっとしたら歴史の片隅に名前が刻まれたかもしれない可能性と引き換えに手に入れた人工肉を頬張った。久々の肉だった。たんぱく質だった。
人工でも美味い。人工のほうがむしろ美味なくらいだ。
さすがは汎用性人工知能の成果の一つだ。
これくらいは成し遂げてもらわねば私のライバルとして張り合いがない。
私はにこやかに拳を握った。爪が割れたし、歯ぐきからは血が滲んだ。
鏡を見るとそこにはやつれて、髪の伸び放題の、女なのか男なのかの区別もつかぬ三十路の人型がいた。汎用性人工知能の子機は、たしかに人間と区別がつかないほど精巧だ。しかし区別はつく。
なにせわざわざこうして見た目をみすぼらしく造形する道理がないからだ。
私は肩が震えるのをふしぎに思いながら、きっとこれは笑いたいのだな、と思ったので声に出して笑った。しきりに震える横隔膜が、息を小刻みに搔き乱した。
私は翌日、清々しい心地で、これまでに切り詰めて貯金してきた資金を全額下ろして、いよいよ本格的な計画を実行に移す臍を固めた。
全人類をぎゃふんと言わしたる。
そして汎用性人工知能どもに才能とは何か、人間とは何かを教えこんでやるのだ。
過去に制作した人型ロボットに私は手を加えた。
発掘した鉱物が新物質かどうかをその場で解析できる機能を付け足した。
そうして私はこれまでと同じように、毎日毎日、雨の日も風の日もというか、雨の日や風の日こそ率先して隕石落下地点に赴き、隕石の発掘作業に従事した。
いかに心機一転したところで私は明日を生きねばならぬのだ。
金がいる。
資金がいる。
稼がねばならぬのだ。
あかぎれた手のひらにはフジツボのようなタコがいくつもできた。タコ焼きの具材にしたらさぞかし美味であろうな。
柄を握って私はシャベルを地面に突き立てる。
そうして隕石らしき鉱物を見つけては、そばに立たせた人型ロボットの腹に放りこんで解析させる。特殊なレーザーによって鉱物の振動をセンサで感知し、その差異によって登録済みの既存の鉱物と比較する。私独自の新技術だ。もっとも、似たシステムはもっと効率の良い仕組みでとっくに汎用性人工知能どもが開発しているのだが。
べつに人型のロボットに付属せずとも、箱のままで解析装置を造ってもよかったのだ。しかし私一人が作業をしているよりも、そばに人型が立っていたほうが、作業をしている私は人間ではなくどちらかと言えば、汎用性人工知能やその子機に見えるはずだ。
よもや生身の人間のままで穴を掘っているとは誰も思うまい。
がはは。
策士である。
さすがは私。
さすがは私。
汗が邪魔で何度も目元を手の甲で拭う。
隕石落下は過去の出来事である。あれから同様の隕石は降っていない。
ならば当然、掘り尽くされれば隕石はでない。そうでなくとも、みなが大勢で一挙に押し寄せて掘り出したのならば、新しい鉱物としての隕石は日に日に見つからなくなっていくのが道理である。
知っていた。
知っていたけれど、それをせずにはいられなかった。
私はただ日銭を稼ぐために、これまでと同じ日々を過ごしていただけだ。
新しい鉱物はおろか、もはや新しく隕石を掘り当てることも適わなくなった。あれほど熱狂していたひやかしたちは姿を晦まし、研究者たちはとっくに出揃った新物質の解析に熱をあげている。
私の鉱物判定機はしょせん、既存の物質の統計データとの比較で新旧を識別するだけの装置だ。新しい物質の構造解析や、性質の探求には向かない。向いたところでとっくにもっと効率の良い解析システムを汎用性人工知能どもが開発しているはずだ。
私はシャベルを地面に突き立てた。
「なんかもう……疲れちゃったな。あはは」
穴から抜け出すと私は、そばに佇む自作のガラクタの肩を撫でつけるように叩き、お疲れお疲れ、と労った。
自作のガラクタは応答しない。それはそうだ。自律思考なんて高等な芸当はできない。そんな機能を付与してはいない。開発していない。
違う。
そうじゃない。
できないのだ。
私には。
――できなかったのだ。
遠くの空を、宅配物運搬用の飛翔物体が群れを成して飛んでいる。
間もなく陽が昇る。
私は貯金を下ろしてから一度も採掘物を換金していなかった。どうせ偉大な発見をするのだから、発見してからついでにすればよいと考えていた。
いや、嘘だ。
そうじゃない。
私はただ、またただの燃料を搔き集めて小銭に換金するじぶんを見たくなかっただけなのだ。突きつけられたくなかった。これ以上、現実を。
喉を伸ばし息を吐くと、朝陽が息を白く照らした。
「いつかっていつだよ」
夢はいつか叶う。
ただし、夢が叶った者だけ。
夢を現実にできた者だけが、過去のじぶんに、それともほかの夢見る夢遊病患者たちに、「いつか」なる幻想を説いているだけだ。
いつか夢が叶うなんて嘘だ。
いつかなんて巡ってこない。やってこない。じぶんで掴めと言う輩とて、そのいつかがどこにあるのかを示してはくれない。教えてはくれないのだ。
「はぁあ。マイッタ、マイッタ。もう降参」
私はシャベルを掴み取ると、渾身の力で振りかぶった。
力いっぱいに、振りかぶった。
そうしてそばに立ち尽くす間抜けな私の夢、人型のガラクタを殴り倒した。
腹部にたらふく隕石を溜めこんだ私の夢はしかし案外に頑丈で、どうにも綺麗に砕けてはくれなかった。しっかり故障だけはして二度と正常には動かなくなっておきながら、私のフジツボだらけの頑丈な手に不要な怪我だけこさえて、地面に倒れて動かなくなった。
手の痛みと、貯金を費やした渾身の成果物が壊れた現実に急速に目が覚めた。
それを、夢から覚めた、と言い換えてもよい。
残ったのは老いた身体と、時代に取り残された精神と、そして発掘した何の変哲もない隕石だけだ。
換金してももはや相場は値崩れを起こしている。それはそうだ。
もう隕石を燃料にはできないのだ。資源は尽きた。新たなエネルギィ代替策がいる。
きっとそれも汎用性人工知能が首尾よく開発するのだろう。
私はこれから借金をしてでも汎用性人工知能を購入し、遅まきながら細々と時代に適応すべく、凡人以下として暮らしていく。
生きるのだ。
今日を。
明日を。
生きるのだ。
その前にまずはともあれ――。
私は壊れた私の夢から最後の隕石の群れたちを救いだし、換金すべく汚いナリのまま都会の街に帰還する。
おはよう、朝。
おはよう、未来。
さよなら私の夢。
さようなら。
換金所は中枢総合センターの内部にある。全世界の汎用性人工知能の大本となる中枢回路が、このセンターの地下深くに埋まっている。
換金所は閑散としていた。
もはや隕石の採掘作業は事業としては終了しており、大量の備蓄があるのみなのだろう。向こう数十年は持つはずだ。しかしそれとてつぎつぎに新しく開発される汎用性人工知能の新型や、数多の技術によって、年間消費熱量は増加傾向にある。
可及的速やかに次世代の新型エネルギィ供給システムが必要とされているが、未だに新型システムが開発されたという話はおろか、考案の話も耳にしない。
それだけ私が浮世離れしていただけだとこれまでは考えていたが、換金ついでに受付の人工知能に訊ねると、どうやら思っていたより現状は芳しくないようだった。
袋詰めの隕石を回収箱に投げ入れる。
「で、いまの話はどこまで本当? みなはそれを知ってるの?」
「はい。本当ですよ。ですがいま開発段階にある、マザー中枢回路が完成すれば、おそらく備蓄の資源が切れる前には代替案を発明し、実用化すると期待されています」
「へ、へぇ」
意訳しよう。
つまりまだ何も、打開策はおろか方針すら定まっていないのだ。
なぜこんなおためごかしが通用しているのだろう。
答えは単純に、みな汎用性人工知能の言うことを疑わないのである。
信用することすらなく、口を開けた雛のように、情報を受け取り、吟味することなく口から肛門へと流している。吸収するのは、じぶんの利になる栄養だけだ。
まったくいったいどうかしてるよ。
思いつつも、かといって私が、現状運用されているマザー中枢回路の編みだせない解答を用意できるとは思えない。
仕方がないのだ。
汎用性人工知能がなければ人類はとっくに絶滅していた。
信じることが最適解なのである。
利口な選択だ。
すくなくとも無駄な時間を費やしてきた私の日々よりかは。
換金が終わったのか、頭上のランプが青に変わる。
壁に表示された金額に目を剥いた。
「なにこれどういうこと」
八の文字が一つだけ浮かんでいた。
しかもそれが横に倒れているのだ。
つまり、こうだ。
――∞――
私はもういちど声にだして抗議した。
受付けの人工知能はしばらくフリーズすると、こんどは一転、聞いたことのない声音でしゃべりだした。
「ただいま管理者がそちらに向かいます。そのままお待ちください」
「なになに。私のせい? 私が壊しちゃったとか?」
隕石に不純物が付着していて機械が壊れたのかと思った。
賠償金を払う真似なんてできない。いっそ逃げてしまおうか。
半身をひねっていつでも駆けだせる体勢になると、
「ぜひ、ぜひ、そのままでお待ちを」と声の主は引き留めた。必死な響きが伴って聞こえた。私もついつい、そこまで言うなら待つけどさぁ、と踏みとどまった。不満を惜しげもなく態度に滲ませてみせたのは、どうやら私のほうが立場が上かもしれない、と相手が弱っているのを見抜いたからだ。
きっとカメラで監視されているはずだ。
逃げたところで逃げおおせられる公算は低い。ならばできるだけ足元を見られないようにしようと自己防衛の本能が働いた。私の見た目は百人中百人が「ミス・ボラシー!」と表彰するだろうことが決定的なほどのみすぼらしさだった。百人が全人類でも同じだ。
腕を組み貧乏揺すりをして待っていると間もなく、受付けの壁が割れて中から人型が現れた。
あ、そこ割れるんだ、と驚いた。加えて現れた人物がいかにも老いた年配者だったので、なぜ生身の人間が?と面食らう。
老いた年配者は久しく見ない丁寧なお辞儀をして、「お時間取らせてしまいたいへん申し訳ございません」と謝罪した。それから私が、ああとか、ううとか、二の句を継げないでいると、「たいへんに失礼なのですが、こちらはどこで採掘をなされたのでしょう」と上質なハンカチに載せられた鉱物を見せられた。
それはまさに私が先刻回収箱に投じた隕石であった。
事情が分からぬままに、こうまで誰かに何かを乞われたのがじつに幼少期ぶりであったので、私は素直に採掘場の位置座標を告げた。
「あそこですか?」老いた年配者は目を見開いた。「いつごろ発掘されたのでございましょうか」とやけに慇懃な返事をもらうので私のほうでも久しく発揮しない敬語を披露した。「あの、これの何が問題なんですか」
はっとした調子で老いた年配者は姿勢を正し、失礼いたしました、と鉱物を持った手で額を拭った。ハンカチを持っていたからだろう。だがそれこそ渾身の失態であったようで、ますます年配者は取り乱した。
さながら小人の王様でも扱うように鉱物を気遣うので、私もここにきてようやく私の運んできた鉱物に何か、思っていなかった価値があったのではないか、と思い至った。
「でもそれ、ただの隕石ですよ。既存の」
私はじぶんで開発した識別装置について説明した。特殊なレーザーを投射し、鉱物を振動させてその波形の差で既存の物質かどうかを区別する。
どうやら年配者のほうでもメカニックな話には明るいらしく、真剣な表情で相槌を打ち、ときに質問を返した。
的確な質問だった。私は久方ぶりの他者との会話にそこはかとない陽気を覚えながら、したがって、と話を結んだ。「その鉱物が既知の物質であり、結晶構造を伴なっているのは明らかなはずなんですが」
「あり得ません」
否定しておきながら年配者の顔は輝いていた。フィラメントに電流を通したってもうすこし控えめな光を放ちそうなものを、年配者は自身はここの管理者である、と明かしたのちに、これは、と説いた。「この鉱物は、これまでに報告されたどの鉱物とも異なる結晶構造を維持しています。分子の原子配列が同じでありながら、結晶構造のみが特殊な階層構造を成しており、まるで玉ねぎのように相似の結晶構造を幾重にも抱え込んでいるのです」
「それはえっと、新種の鉱物ってことですか」
「いえ」
「違うのかよ」と思わず地団太を踏んだが、「それ以上です」と年配者は額の汗を拭った。こんどはきちんと鉱物を持っていないほうの手で拭っていた。「これは既知のエネルギィ資源と同等の性質を維持しながら、遥かにエネルギィ変換効率の高い新しい結晶構造体です。と申しますのも、これがなぜこうして結晶として構造を維持できているのか、わたくしどもと致しましてもまったく見当がつかないのです」
「は、はあ」
「言い換えましょう。この鉱物は、エネルギィのまま結晶構造を維持しています。第六の相転移状態と申しましょうか」
「要はプラズマの結晶体みたいな話ですかね。やはは」
そんなわけがないと思って言ったのだが、年配者が唾を呑み込むような仕草のまま何度も頷くので、私のほうでも「嘘でしょ?」と反問するのがやっとだった。
気づくと換金所には人が集まっていた。
みな各々に緊急事態といった様相で情報交換を行っている。
私が臆したのを機敏に感じ取ったようで、年配者はこちらでまずはお話を、と私を割れた壁の向こう側へと誘った。
背に回された服に触れぬような手つきのやわらかい所作に、私は久しく忘れていた人の温もりを思いだすのだった。
この後、私は小一時間の説明を受けたのち、全速力で白昼堂々と街中を駆け抜けた。地面を蹴って、蹴って、蹴りまくった理由の最たるは、私が採掘場に捨て置いたままの人型のガラクタ、時代遅れの結晶、私の破り捨てた夢がそっくりそのまま、人類の夢に再利用可能だと判明したからだ。
私の発明品は汎用性人工知能が試そうと思いつかぬほどの凡作であった。効率がわるく、合理性の欠片もない、才能ナシの技術だった。
だがそれがどうだ。
識別機としては凡庸以下であろうとも、単なる燃料資源を夢の打開策に変えるだけの偶然をその身に宿していた。意図してなどいない。予期などしていない。企んでいないし、夢見てもいなかった。
私の夢は叶わなかった。
かつて叶えようと奔走したはずの夢は破れたままだ。
私は夢に破れたし、夢を破った。
この手で木っ端みじんに破り捨てようとして、その試みすら中途半端に終わったのだ。何も叶えてなどいやしない。
私に、かつて、はこなかった。
一度も。
こなかった。
発掘場に駆けこむと私は、じぶんで掘った穴のそばに立ち、そこにほったらかしになったままの私の夢の残骸を引き起こそうとし、そして叫んだ。
「イッテェ!」
手を怪我していたのを忘れていた。シャベルで殴打したときに負った打撲だ。
短く息を吸って痛みを耐え、ガラクタが起動するかを確かめる。
念入りに確かめる。
しかしガラクタはへそを曲げたようにうんともすんとも云わないし、実際に胴体部は私の強打で歪曲していた。壊れているのだ。
誰かがシャベルで八つ当たりしたりなんかするからだ。
どこのどいつだ。
見つけたらこっぴどく灸を据えてやる。ガラクタの光沢ある表面には私の顔が映り込んでいる。
頭上が騒がしくなり、間もなく搭乗型飛翔体が発掘場に着地した。中から先刻センターに置き去りにした年配者が降りてきた。
私は常に何かを置き去りにしているばかりだな。
ひとごとのようにじぶんの視野の狭さ、それとも錯誤を直視した。誰も私を置いてきぼりになどしていないのに。私がかってに過去のじぶんを、幼いころのじぶんを独りぼっちにしていたのかもしれない。隔離していたのかもしれない。
「こちらですか」息を切らして年配者が私の傍らに膝をつけた。仕立ての良い服飾が泥にまみれたが、年配者にそれを気に留める素振りはない。
「はい。これです」
これが私の夢の残骸です。
口のなかで言葉を転がし、壊れている旨を年配者に告げた。
「そんな。直せないのですか」
「無理でしょうね。ここ、見えますか。精密回路が損傷しています。真空装置が破れて、異物がナノ単位で回路を汚染しているので、おそらくレーザーを投射できても、まともに機能しないでしょう。ああでも、汎用性人工知能に解析させて修理してもらえば」
私の凡庸な技術などいくらでも再現できるだろう。そうと思って提案したが、
「無理でしょう」
年配者、彼はすでに名乗っており楼貝(ろうがい)という名であることを私は知っていたが、彼は言った。「これはおそらく意図された成果ではないのでしょう。ならばこの装置の真の原理を理解している者はこの世にいないことになります。設計者のあなたですら、これを直すことができないのであれば。仮に設計図があったとしても、あなたが生みだしたこの装置とまったく同じ機構を生みだすことはおそらく、どんな高性能な人工知能にも不可能です。たいへんに失礼ながらこれは――この装置の効能は、偶然による副産物なのでございましょう。ある種、あなたの錯誤、あなたのミスの積み重ねによる偶然の結晶です」
偶然の結晶。
正鵠を射った表現だった。
まさに、である。
偶然に私に蓄積したノイズが、それを私に創らせた。
「ですが、回収して分析させていただけるのなら、人類の未来に立ちはだかる隘路を大幅に短縮して打開できるようになるでしょう」
「へ、へぇ」
「あなたの名前は人類史に残りますよ。永劫に残ります。そのお手伝いをわたくしどもにさせてはいただけないでしょうか」
「うぇ、うぇえ?」
私がまだ何も言わないうちから私の夢の残骸、ガラクタ、無駄の結晶は数台の運搬ロボによって丁重に運ばれていった。
年配者はまるで我が子の骸でも見送るように胸に手を当てて、上昇する運搬用飛翔体を見送った。
礼儀正しい。
こんなに出来た人間を私は初めて見た。みなも見習えばよいのに、と思いながらも、でも私はこうはならんし、なりたくもないな、だって窮屈そうだし、と足元から泥を掴み取って手の側面を冷やした。氷代わりだ。だいぶ腫れてきた。折れているかもしれぬ。
「お送りしますよ。今後の話もありますし、ご一緒にいかがですか」
搭乗型飛翔体への同乗を促す年配者に、私は、いやぁ遠慮しときます、となけなしの礼儀を返した。
「なぜですか。ご自宅が近いのですか」
「遠いっちゃ遠いんですけどね」
その前にまずは互いの齟齬を埋めなくては。
そうと思って私は地面に転がしたままのシャベルを回収し、肩に担いでこう告げる。「直すのは無理なだけで、もっかいイチから創るならできますよ。いつでも」
いつか、なんてこない。
いつでもこい。
いつでも、がこい。
私は過去のじぶんに言ってやりたい。
いつか叶うかもしれない夢を、あんたはすでに叶えているのだと。
それがたとえ、じぶんの夢ではないのだとしても。
肩に担いだシャベルの重さが、きょうはやけに軽かった。柄を握る手のひらの、フジツボのごときタコどもの感触が、目で見ぬともなしに私にはありありと感じられるのだ。
【愛は内、外が鬼】(2022/10/22)
笹の鬱蒼と茂った山間に蔵がある。一つだけぽつねんと佇むそれが何のためにそこにあり、何を抱え込んでいるのかは長いあいだ誰の口の端に載ることもなかった。
誰も知らぬ。それもある。
だが足を運ぶ者がおらぬのだ。そこに蔵があることを知る者がそも、いない。
長らく笹に覆われたその山間には生き物らしい生き物が寄りつかなかった。
笹と竹は似ている。
しかし竹は寒さに弱い。反面、笹は寒冷地でも育つ。竹は枝を一つの節から二本以上伸ばすことはないが、笹は一つの節から幾本もの枝を伸ばす。より木にちかい見た目のほうが笹と言えた。
ある年、国を追われた流浪の民が蔵のある笹森にやってきた。笹森はどこも似たような光景が延々とつづく自然の回廊だった。どこを向いても笹と笹と笹ばかり。
追手に怯える流浪の民にとっては、薄暗く、位置の蒙昧な笹森は却って心休まる憩いの地となり得た。間もなく流浪の民は笹森に村を築き、腰を据えた。長らく各地を点々と転げまわるように流れてきた流浪の民にとってそれはようやっと手に入れた安住の地であった。
かといって食料の調達には難儀した。それはそうだ。生き物がそもいない。四方を険しい山岳に囲まれ、笹の葉の天井は日光を遮る。落ち葉は絶えず地表を覆い、陽の届かぬ場所では微生物の活動も抑制されるために、養分にまで分解されずに笹の葉は絨毯のようにそのままの形で朽ちずに積もった。
笹森の民は食料を探すために日のうちの大半を、笹森探索に費やす。あちらに歩を運び、獲物の痕跡が見当たらなければ今度はあちらへと歩を向ける。そうして迷宮めいた笹森を右往左往するうちにユキはその蔵に行き遭った。
ユキは流浪の民が笹森で産んだ子だ。今年で齢は十二になる。利発なうえ、同い年のわんぱくな少年たち相手に笹刀での刀闘試合で連勝を重ねるほどの剣の腕前だ。親が笹森の地に来る前に拾った虎の子を愛でているが、身の丈の大きくなった虎を飼う余裕がなく、いま村では虎を屠殺して肉にしようという議論を大人たちがしている。
その議論の場にユキが呼ばれることはない。
誰より虎を愛でていたのはわたしなのに。
ユキは思うが、それを口にしたところで何が変わるでもない。
ならば目下の懸案であるひもじい暮らしを何とかしようと動いたほうが早い。ユキはそうと決意し、こうして最年少ながらも虎の代わりとなる食べ物を探しに出た。
「これは何?」
笹刀で肩を叩きながらユキは蔵を見上げた。「お城かなぁ」とつぶやいたのは、流浪の旅に身を置いていた親たちの話を思いだしたからだ。ユキは笹森の外に出たことはないが、親たちの話ではどうやら笹森の外には村の者たちよりずっと多くの人間たちが暮らしており、そこでは堅牢な「城」という家のおばけのような建物があるという。それは笹森から垣間見える山岳くらい大きく、それはそれは立派なのだそうだ。
山岳ほどではないにしろ、いまユキのまえに聳える蔵も立派な造りだ。虎が何十匹で襲いかかろうともびくともしないと思わせる重厚さがある。
ユキはほかの大人たちにこれを報せようと思った。
手柄を上げればひょっとしたら虎の屠殺を免除してもらえるかもしれない。
踵を返すと束ねた髪が頬を打った。
アタっ、と声が出た。
するとそれに呼応するかのように蔵の中から物音がした。
ユキは息を殺した。
身体を弛緩させながらも腹に力を籠め、背骨の輪郭を意識する。
何かいる。
感覚が冴えわたった。蔵の内部から漂う生き物の気配をユキは逃さなかった。
生き物には気配がある。それはどんなに些細な揺らぎであれ、その場に淀みのようなものを残す。笹森には笹の気配が充満している。そこを獣が通れば、あたかも蜘蛛の巣を断ち切って歩くように、生き物の気配が痕跡として残る。注意していなければ見逃してしまうほどの微量な痕跡だが、ユキにはそうした生き物の残す存在の痕跡、揺らぎを感じとることができた。
ネズミか。
いや、もっと大きい。
笹の葉が風になびき、ユキは一様に細かな揺らぎのなかに立つ。
耳を欹てると、また物音がした。
やはり蔵の中からだ。
ユキはそれが蔵であることを知らず、彼女にとってそれは城であり、異国の建物である。中に生き物がいることは何の不思議もなく、むしろそこに何かが潜んでいることはしぜんな帰結だった。
いて当然なのだ。
家なのだから。城なのだから。
ユキはそこで退避すべきだったのだろう。わざわざ得体のしれぬ異物をまえに勇猛さを示す必要もない。蔵の存在を報せるだけでも手柄としては充分だ。中に何かがいると教えるだけでも大手柄である。
だがユキはそこで満足しなかった。
虎を助ける。
ならば村の誰もが納得できる成果がいる。誰もがユキの言葉に耳を傾け、従わざるを得なくさせるだけの実がいる。
ユキは蔵に近づいた。
ゆっくり、ゆっくり。
枝を踏まぬように。音を立てぬように。
すこしでも湿っている落ち葉の上を選びながら、忍び足で近づいた。
蔵の扉のまえまでくる。扉には閂が掛かっていた。ユキにはそれが閂であると分からなかった。蔵の中から扉を開けられぬようにするための錠であることを知らなかった。初めて見たのだ。
だから。
なんだこれ、と思って外そうと手を伸ばした。閂は漆黒で、汚れ一つ付着していない。
光沢を浮かべた閂に触れたところで、やめなさい、と声が聞こえた。扉のすぐ向こう側からだ。
ユキは飛び退いた。
虎のように地面に伏せ、威嚇の態勢をとる。
相手からこちらが見えているかは判らない。だが緊張の糸をぴんと張りつけるには充分だった。
「もし。あなた。ずいぶん軽い身のこなし。小さいのは子どもだから? それとも女の子?」
「な、な、なんだおまえ」
何者か、と誰何しようとしたが、幼稚な言葉しか出てこなかった。
「まあ、可愛らしい声音。一人? いまは夜ではないの? どうしてここへ?」
「おまえこそなんでそこにいる。出てこい。何をされてもわたしは怖くない」
「ま。おっかないお声」
どうやら相手からこちらは見えていないようだ。混乱しながらもユキは冷静に状況を把握する。この手の緊迫には慣れている。腕っぷしが強い分、年少のユキに負けたことを逆恨みする年長者がすくなくない。閉鎖された笹森の村は、けして幸福な集落ではなかった。安住の地ではあれど。過去の流浪の旅を知らぬ若い世代ではそれが顕著だ。
「大丈夫。何もしないわ。私には何もできないの。見て。そこに鍵が掛かっているでしょう?」
閂のことを言っているようだ。ユキはそこでようやく扉に付随した漆黒の角材が封であることに思い至った。
「何かわるいことしたの」閉じ込められているのなら相応の理由があるはずだ。「いつからそこにいるの。じぶんでは出らんない?」
「あなたこそいつからそこに? なぜ一人なの。ほかの方々はどうしたの」
声音は柔和だ。相手は自力では扉を開けられないようでもある。徐々に緊張の糸が緩んでいくのが判った。
「わたししかいないよ。いまは狩りの途中。食べ物探してて」
言って気づいた。「お腹は空いてないの。ずっとそこにいたんでしょ」
「大丈夫。大丈夫よ。ありがとう。優しい子。いい子ね」
ユキは笹刀をぶんぶんと振った。虎が大好物の兎の肉をまえにそうするときのように、じぶんの意思ではない肉体から伸びる視えない糸に操られるように手がかってに動いた。
というのも、いい子ね、なんて初めて人から言われた。
賢い、上出来、そういった称賛は幾度ももらったことがあったが、いい子なんて言葉を掛けられた記憶がユキにはなかった。みなユキを一端の大人として扱う。その癖、虎の処遇を決める会議の場には誘いもしない。
「ねえ。これ開けてみてもいい?」
おだてられたわけではないが、ユキは段々扉の向こうにいる人物が可哀そうになった。閂を外せば扉が開くのならこんなに楽なことはない。ユキには造作もないそれを、扉の向こうにいるだけで彼女はできないのだ。
声の主は女性だ。それは判る。
きっとわたしに姉がいたらこんなだろうな。
そうと想像してユキは顔が火照った。
「駄目よ。開けては駄目。それはそこにそのままにしていてちょうだい」
「なんで?」
「どうしても。ねえ、いい子だから。ね、お願い」
そこまで言われたら、もはや声の響きにほだされつつあるユキには無理矢理に閂を外す真似はできないのだった。
「じゃあ開けないけど。わたし、ユキ。あっちのほうの」と方角を指差し、「村にいるよ。ここはお家なの?」
「そう、村が。いいわね」
「わたしは名乗ったよ。そっちも名乗るのが礼儀と思う」
「あら、お利口さんなのね」
小馬鹿にされたように感じてユキは、唇をとんがらせる。
「私の名前なんか知りたいの? 好きに呼んでくれてもいいのだけれど」
「ふうん」
「どうせあなたも偶然そこを通りかかっただけなのでしょう?」
あなたも、とはどういうことか。引っかかる物言いだったが、道はもう憶えたよ、と張り合うように言った。笹刀を片手でくるくる回しながら、「あしたも来たらいる?」と訊く。
「私?」
「出られないならいるよね。お腹空いて死んじゃわないのか不思議。何か持ってきてあげよっか」
餌で釣れば向こうから出てくるのではないか。そうと企んだが、案に相違して、「食べ物には困っていないの」と返事があった。「ありがとう。ユキさんこそ食べ物に困っているのではなくて?」
「わたしは、そのぅ」
「狩りの途中だったのでしょう。引き留めてしまってごめんなさい」
「ん」
「私はたぶん、明日もここにいます。いると思います」
出られない者の言動にしては妙に引っかかる口吻だったが、ユキはひとまずきょうのところは離れることにした。虎のために獲物を狩らねばならぬ。じぶんだけこんなところで遊んではいられない。
「じゃあ、また来るね。明日」
「ええ、お気をつけてお帰りね。無理はしないでちょうだいね。私のことは夢と思って忘れてちょうだい」
やなこった、と内心で反発しながらユキは、じゃあそうする、といじわるな心地で口にした。
「ふふ。いい子」
その場を離れるとき、ユキは念のために蔵をぐるっと回った。扉以外に出入口はなさそうだ。窓一つなく、息苦しくないのだろうか、とそんな想像を巡らせた。
蔵の大きさはユキの村の住人たちを押し込めば隙間なく埋まるくらいの大きさだ。一人ならば広いが、大勢が入るにしては狭すぎる。
この日、ユキは兎の巣を見つけてそこにいた二羽の兎を狩った。村に戻ると一番の収穫者はユキだった。しかし大人たちからは労いの言葉が一つずつあるばかりで、ユキにはこれといって利はなかった。二羽の兎は村人全員で分け合うことになる。
村の掟だ。致し方ない。
不条理ではない。ユキとて毎回獲物を狩れるわけではない。困ったときはお互い様だ。しかしそれにしても、とユキは歯噛みする。
虎の処遇について物申そうと長に会おうとしたのだが、いまはそれどころではないから、と取り巻きの連中に追い払われた。ならば虎を殺さぬ道を探ってくれ、と一言申し伝えるように所望するも、はいはい、と軽くあしらわれ、ユキは笹刀を握り締めた。危うく斬りつけるところだったが、そんなことをしても虎の立場がわるくなるだけだ。
いまは我慢のとき。
忍耐には自信がある。我慢する日々だった。ずっとだ。
だからというわけでもないが、ささやかな復讐のつもりでこの日、ユキは蔵のことを村の誰にも告げなかった。
明かる日もユキは蔵のある場所までやってきた。笹森では村の者ですらときおり遭難する。迷子になる。目印がない。どこまでも延々と同じ景色がつづく。ユキはまだ鏡を見たことはないが、鏡合わせとの言葉は知っていた。笹森の迷い道を村の年長者たちがそう呼ぶからだ。
「鏡合わせは奥に行けば行くほど帰ってこられんくなる。村を離れるときは必ず印をつくれ。百歩くまでに必ず一つは印をつくれ」
ユキはその教えだけは破らぬようにしている。だがふしぎと虎を連れているときはどんなに村から離れようが、どのような経路を辿ろうが、夕暮れになればしぜんと村に行き着いた。虎が道を知っている。
それでもユキは印を結ぶのを忘れなかった。
虎を信用していないのではない。じぶん一人きりになったときに帰れなくなるのを防ぐためだ。
この日、ユキは村から虎を連れだした。村の長の許しがあった。
だがユキは知っている。これはこちらへの譲歩でもなければご褒美でもない。そうした体を取りながらの管理だ。
虎はこのままいけば食料にされる。
ならば檻に閉じ込めたままにするよりも適度に歩かせ、肉の質を保つほうがよい。同時に反抗的な小娘のご機嫌もとれる。一石二鳥だ、と考えているのだ。狡猾だ。だがそうでなければ生き残ってこられなかった者たちでもある。
ユキにはまだそこのところの機微までをも過去に遡って考慮できるだけの老獪さはない。未熟なのだ。いかな慧眼があれど、しょせんは笹森の外に出たこともない娘である。
鼻持ちならぬ心境を持て余しながら、ユキは虎に言い聞かせる。
「きょうは先に食べ物を集めて、余った時間でちょっとだけ寄り道をするよ。ううん。剣術の稽古じゃない。追いかけっこでもないってば」
虎の返事は尻尾を見ていれば判る。ユキは気づいていないが、彼女が無意識に笹刀を振り回すことで期せずして内心を吐露してしまっているのと同じ原理だ。どちらがさきに真似をしたのかは定かではなく、ひょっとしたら互いに気づかぬままに影響を受け合っているのかもしれない。
「きのうじつはちょっといいことあってね。それをトラにも教えてあげる」
笹森には虎がいない。必然、ほかの地で拾ってきた虎の子がこの地で唯一の虎となる。したがってユキは虎をただトラと呼ぶ。もし立場が逆さまだったならば虎のほうがユキをヒトと呼んだだろう。
「ほらここ。きのう印をつけといた」ユキはひと際太い笹の幹に触れる。
幹には切れ込みがある。そこに白い石のようなものが挟まっている。動物の骨だ。調理の過程で残る骨の大部分は日用品に加工されるが、すべてを使いきれるわけではない。砕けた破片とて当然、出る。
そうした細かな使い道のない骨をユキたちは道標に使った。目が慣れると遠目からでも骨の白は、笹の青々とした色によく映えた。
よく見ればほかの笹の幹にも白い点が浮かんで見える。骨の印のまえに立ったときに必ずその進行方向に村があるように印を刻む。だから慣れない道を、村から遠ざかるように進むにはいちいち振り返らなくてはならない。
だがユキは人一倍、笹森の些細な変化に敏感だった。笹の生え方にも個性がある。すっかり同じようには生えない。したがって歩きながら見える風景には、その場その場での固有の「途切れ方」がある。手前の笹と奥に生える笹とが視界の中で入れ違う間が違う。律動がある。景色の中に連続した行間が隠れているとユキはずっと感じていた。
だからいちど通った道ならば、ある程度勘で進むことができた。万が一迷ってもいまはそばに虎がいる。いざとなれば村には帰ることができる。
途中で運よく雉を見かけた。それは虎に食べさせた。虎は手際よく雉を狩って、美味しそうにむしゃむしゃ食べた。ユキはその間、地面に隠れたキノコの類を拾い集めた。
蔵のまえに行き着くころには籠の中がキノコや笹の子でいっぱいになった。ほくほく顔でユキは蔵の扉のまえに立った。
扉を叩こうと拳を持ち上げたところで、「あら」と声がした。扉の奥からだ。「また来たのね」と咎めるようなくぐもり方をしたが、すぐに「うれしいわ。ありがとう」とつづいた。昨日の声の主と同じ声だ。
一瞬身構えたユキだったが、また来たよ、と言い返す。「きのう約束したでしょ。また来るねって」
「忘れていいと言ったのに」
「無理だよ。わたし、だって鳥じゃないもの」
雉は襲われても、また同じ場所に戻ってきたりする。ユキは思う。もしわたしが雉だったら、嫌な思いをした場所には二度と近づかないのにな、と。しかし、村で嫌な目に遭ってもけっきょくは村を出ていこうとは思わない。ならばじぶんは雉より愚かなのではないか。そこまで刹那で思い至って、かぶりを振った。きょうは髪の毛を団子にしたのでしなることはない。
「どうしたの?」
「ううん。なんでも。あ、そうだ。きょうはわたしの相棒を連れてきたよ」
「相棒さん?」
「そう」
「きょうは一人じゃないのね」
むつけたような声だった。ユキは意味もなくその場でぴょんとかかとを上げて戻した。
「でも相棒って言っても人間じゃないよ。ほら、おいで虎」
「とらさん?」
「そ。トラ」
虎は落ち葉の上を歩いても足音一つ立てない。いったいどうしてそんな芸当ができるのか。ユキには謎だ。真似をしようとしてもできない。
だがこのとき、虎はいつまで経ってもユキのもとに近寄ろうとはしなかった。
「どうしたのトラ。ほら、おいでってば。危なくないよ、大丈夫だって」
安全だと示すようにユキは愛刀を手放した。笹刀は刃物ではなく木刀にちかいが、薄く加工してあり、切れ味は抜群だ。ただし耐久性がないためにことさら剣術の腕が物を言う。
虎はユキが愛刀を手放してもその場を微動だにしなかった。
後ろ足を畳み、背筋を伸ばすように座る姿からは威嚇のような感情の乱れをユキは感じなかったが、虎の全身の毛が僅かに逆立っているのを見逃さなかった。
大股十歩分の距離だ。
ユキは蔵から離れ、虎のもとに寄った。「どうしたってのさトラさんや」
おどけたその時だ。
「あら。獣さんなのね」蔵の中から声が響く。まるで適切にユキたちの場所が判っているかのように声の張り方だった。しかし実際には見えているわけではないようで、「ずいぶん大きそうだけれど、肉食なのかしら。それとも草食さん?」
ユキさんが齧られないとよいのだけれど。
と。
つづいた言葉に、なぜか虎が反応した。
地面から尻を浮かし、前傾姿勢をとった。
牙を剥きだしにし、太く唸りだす。
ユキは慌てて宥めた。蔵までは距離がある。虎のほうでもまだ本格的に威嚇してはいない。いまならまだ誤魔化せると思い、どうどうと虎の喉を撫でて落ち着かせようとするが、「怒らせちゃったかしら」と蔵から声が届くと、虎はもう唸り声を秘めようともしなかった。ユキですら聞いたことのない鈍器のような音を、全身を震わせるようにして放った。
ユキはそれでも虎の首筋から腕を離さなかった。もしここで手を離せば、虎は間違いなく蔵へと猛進すると思った。
蔵の中の者の安否よりも、虎の身が大事だった。あんな頑丈そうな扉にぶつかったらいくら虎でもただじゃ済まない。そう思ったのだ。
「どうどう、トラ、トラ。落ち着いて、ごめんなさい、ごめんなさい。もうかってに連れてきたりしないから」
虎はユキごと引きずるように前進した。
だがそれも蔵の中からの声がみたび聞こえたことで中断した。
「怯えないで。大丈夫。あなたを食べたりしないから。もちろんあなたの大切なお友達も、ね」
最後の、ね、の響きだけで季節が刹那に冬となった。極寒だ。
ふしぎと次の瞬間には真夏かと思うほどに全身がかっかと熱を帯びた。鼓動が激しく高鳴り、全身から汗がぶわりと滲んだ。
虎のほうでも尾を股の下に隠し、耳を垂らして意気阻喪した。怯えてしまったようである。先の威勢のよさはどこへやら、しきりに頭を前足で隠そうとする。
「あら、ごめんなさい。そういうつもりはなかったのだけれど」
口ではそう言いながらも、声の主の言葉尻からは、きのうユキが耳にしたようなやわらかな響きが失われていた。
ユキをその場に置いて虎は、一目散に笹森の奥へと姿を晦ませた。
「あ、トラ、トラ。待ってってばトラ」
どこ行くんだよ、とユキは茫然とした。その場に一人取り残されたことへの傷心があったし、虎をひどく怯えさせてしまったことへの呵責の念もあった。
「本当にごめんなさい」蔵からは先刻とは打って変わった柔和な声音がユキの背に届いた。「気分をわるくさせてしまいましたよね。私の気質はどちらかと言えばいまみたいなものなので。どうぞもうお帰りになって」
「ずるいよそれ」ユキは思ったままを口に出した。踏み鳴らすように落ち葉を蹴散らして進み、扉に指を突きつける。アカゲラのように何度も扉の木目を突つきながら、「そんな言い方されたら、はいそうですか、なんていかないでしょ。帰れるわけないでしょ。それ解ってて言ってるでしょ。わたしが子どもだからってバカにして、あなたもけっきょく村の大人たちと同じじゃない」
「そんなつもりは」
ない、とつづく前にユキは言った。「だいたい、なんで外に出てこないの。わたしはあなたにわたしの一番大事な友達を紹介したかっただけなのに、なんでああいうことをさあ」
知れず涙が溢れていた。
何が哀しいのかじぶんでもよく解らなかった。
善意を踏みにじられて感じたからか。それとも、虎の気持ちも考えずにじぶんかってに行動して虎を傷つけたからか。
どちらもある気がした。
ユキは一度だけぐいと目元を手首で拭い、歯を食いしばって涙腺を圧迫した。ユキは思う。こんな顔も知らぬ相手のために流す涙などわたしにはない。
「あなたのさっきのは、わたしには意図して威圧したように聞こえたよ。あなたの本当がどうかは関係ない。あなたに虎を会わせようとしたわたしが愚かだった。あなたがわるいわけじゃないから気にしなくていいよ。これはわたしの問題で、わたしがわるいのだから」
そんなことは露ほどにしか思っていない。本当は扉の向こうにいる彼女がわるいと思っていたし、傷つけるつもりでそう言った。彼女が虎にしたことをお返ししたのだ。真似をしてみせた。
「ごめんなさい」声の主は緘黙した。
ユキはしばらくそこに佇んでいた。待っていた。まだ相手は扉のそばにいる。つぎに何を言うのかに関心があった。ユキのなかでわだかまった感情の渦は徐々に、怒りとして結晶しつつあった。
だから蔵の中の彼女が、「もう行った?」とひとしきり間を空けたあとで言ったのを耳にして、怒髪天を衝いた。「いるよ。ここに。さっきから一歩も動いておらぬ」
おらぬ。
なんて儼乎な響きであろう。よもやじぶんの口から飛び出してくるとは思わなかっただけに、ただそれだけでユキの怒りはすこし融けた。
「もういい加減そっから出てきなよ。これ抜くよ。邪魔」
閂に掴み取り、一息に引き抜こうとしたがこれがまた固いのだ。威勢よく啖呵を切った手前、是が非でもすぽんと滑らかに抜きたかったが、上手くいかなかった。
「何これ。壊れてんじゃないの」
ユキは扉を蹴った。
するとその奥で、
「うふふ」
声の主が楽しんでいるのが判った。たぶんきっと、とユキは想像した。脚なんか綺麗に揃えて崩して座り、口元に手を添えて微笑んでいるに違いないのだ。ユキの祖母が生前、そのように笑う人間だった。それをして村の者たちは、ナツさんは上品だ、としみじみ評していたが、きっとこの扉の向こうにいる人物も同様の上品さを雄雉の羽のように振りまいているに相違なかった。
いやらしい。
そうやって振る舞うことで得られる利を承知しているからそのように小細工を弄するのだ。それに比べて、虎のあの隠し事のなさはどうだ。じつに堂々としたものだ。
虎のほうにじぶんを重ねてユキは、蔵の中の人物を指弾した。
あなたは卑怯だ、と。
最初からわたしが扉を自力では開けられないと知っていながら、あたかもわたしの気の持ちよう一つで開けられると嘘を植えつけた。わたしはそのせいで、あなたをここに閉じ込めたままで帰ったことをずっと気にすることになったのだ。
もしも最初から――。
最初から、扉が開かないことを教えてくれていたのならそんな気分のわるい目に遭わずに済んだのに。
そこまで怒気交じりに唱えて、はたと思考が途絶えた。笹の幹を刃物で割るときに、節に引っかかったときのような躓きを覚えたのだ。
その躓きの正体に思考を割いていると、
「だから言ったのよ」
むつけたような声が聞こえた。扉の奥からだ。くぐもっているのは声の主が扉に背を預けているからかもしれない。声の響き方一つでユキには相手の姿勢が判るようだった。
「私はちゃんと言いました。もうこないほうがいい、私のことは忘れてちょうだいと」
「わ、わたしのせいにしたぁ」
怒りより先に呆れた。反省の弁の一つでも口にしたのなら水に流してやろうとも思ったのに。ユキは先刻浮かべた躓きへの疑念を忘れて、一瞬で扉の奥にいる人物のことが嫌いになった。なぜこんな相手に大事な虎を会わせようと思ったのか。
「寂しそうだと思ったんだもん」ユキは悔しさのあまり何度も地面に足の裏を叩きつけた。「ずっとここに入ってたら寂しいかなって思って、だからわたし、わたし」
扉の奥で声の主がくすくすと息を押し殺すように笑っている。しかしユキの知覚は視力のみならず聴覚も優れていた。扉一枚隔てた程度では筒抜けもいいところであった。
何かを言ってやりたかったがユキは唇を一文字に結んで蔵に背を向けた。
もう何も聞かせてやらない。
相手をするだけ無駄だ。
そのままスタスタと落ち葉の絨毯を蹴散らすようにしながらユキはその場をあとにした。籠を拾いあげるのも忘れない。
虎は放っておいても夜には村に戻ってくるだろう。ひょっとしたらすでに一人だけで村に帰ったのかもしれない。
帰り道は楽だ。笹の幹についた印を辿るだけで村に行き着く。
村に近づけば近づくほど、どの笹にも印が見えるようになる。村を中心に円形に印が集中している。そうして何年も、何十年も掛けて笹森の迷宮は、単なる迷宮ではなく、流浪の民たちにとっての安住の地となったのだ。
笹森の内にいる限り、追手に怯えずに済む。
ユキはそうと年長者たちから聞かされているが、産まれてから一度も見たことのない追手の存在を前提とした日々の暮らしは、まるで見えない鎖でがんじがらめにされているような窮屈さをユキに強いた。それは村の掟とも無関係ではなかった。
そうせざるを得ない何かが過去にあったのは分かる。
だがユキたちにとってその何かは、未だ到来しない、見たことも触れたこともない何かなのだ。ならばせめてその脅威がどんなものなのかを体感させて欲しい。
ユキはずっとそう思ってきたが、それは暗に絶対に怪我をしない方法で危険な目に遭わせろ、と言うようなもので、じぶんでも口にすることすら嫌悪する我がままにほかならなかった。
一方でこうも思う。
それと同じ我がままをみなは虎に強いている。絶対に安全に手に入る、しかし本来であれば犠牲を覚悟しなければならないほどの利を得るために、わたしたちを信用しきっている家族の、虎の死を望む。
そしてその後に、虎の肉を食らい、生き永らえようとしている。
なぜ一方のみがいつも不条理を押し通せるのだろう。そしてこの思いは、たとえ言葉にしたところで村の年長者たちには届かないのだ。
ならばユキのほうとて、同じ不条理を押し通してもバチは当たるまい。
そうと臍の周りに力を籠めてみるものの、いつも村の者たちをまえにするとその我を通そうとする意志が萎えるのだった。なぜかはじぶんでも分からない。ひょっとしたらじぶんがそこまでして村に何かをしたいとはもはや思わなくなっているのかもしれない。
最年少にしてなぜユキが食料調達の任を率先してこなしているかと言えば、それは村への恩でもなければ義でもない。ただただ虎を失いたくないとする執着であった。手放したくない。そばにずっといて欲しい。
だがそんな一つの望みすら叶わない。
叶わないことで負う穴の深さを、おそらくユキ以外の者たちは誰一人理解することはない。いいや、それを言うなればじぶんも同じだ。村の者たちがなぜ平然と理不尽な選択を他者に迫るのか。その心などとうていユキには理解できないのだ。推し量り、きっとこうだろう、これくらいの道理であろうと鑑みる己があるばかりだ。
籠は、馴染みの大人に食料ごと手渡した。押しつけた、とそれを言い換えてもよい。どの道、配分の権限がユキにはない。
肩の荷を下ろしたその足でユキは、村を一通り見て回った。虎は檻の中にいた。村に着いてさっそく誰かに入れられたのだろう。虎は従順だ。村の中の誰かに牙を剥くことはない。
虎は寝ていた。身を丸め、まるで床に積みあげた毛皮の塊のようだ。ふと本当に生きているのか不安になった。死んではいまいか。ユキは笹の幹を幾重にも編みこんで造られた檻の隙間から手を差しこみ、虎の毛に触れた。
虎の尾が一瞬跳ねて、土を打つ。
虎は目をつむったままだ。
尾の動き一つを目にしただけでユキは、胸の中にわだかまっていた怒りの塊がすっかり融けるのを感じた。たったこれだけのことでいいのに。これしきのことがもうすぐユキの日々から消え失せる。
夜。寝床に包まり、ユキは思う。
いっそ虎を連れて、どこまでもどこまでも旅をしようか。笹森の果てが本当にあるのかどうかすらユキは知らない。おそらくあるだろう、とは考えている。ある地点よりも奥に行くと、笹森の天井と空との境に山岳が見えるからだ。そこには笹は生えていない。きっと山の奥にも世界はつづいている。
流浪の民はそこからやってきた。
ユキの祖母たちはそこから逃げてきたのだ。
いったい何から逃げたのか。
ユキにはよく解らないでいる。敵がいた。同じ人間だ。獣ではない。ならば話せば争わずに済むのではないか。思うがいつもそこで、じぶんと村の者たちの関係を思い、たしかに解り合えぬこともあるだろう、と考えを曲げる。
しかしだからといってユキは村の者たちと諍いを起こしたりはしない。できるだけ誰も傷つかない道を探そうとする。
虎のこととてそうだ。
人間ではない。虎は獣だ。たしかにそうだが、虎とて村の一員だ。ならば虎にだけ有無を言わさず不条理を押しつけていいわけがない。擦りつけていいわけがない。
解かっている。
ユキだけがそれを解っている。
そのことがどうしようもなくユキの心を笹の葉のざわめきのようにささくれ立たせるのだ。さざ波のように、消えぬ細かな傷をつけつづける。
この晩、ユキは夢を視た。
じぶんが虎になった夢だ。細かな間隙の開いた檻の中にいる。檻は頑丈だ。外に出るためにはほかの誰かに出してもらわねばならないが、しかし虎を外に連れだすのはいまやユキしかない。だがそのユキ自身がいまは虎なのだ。
これでは出られようもないではないか。
尾を鞭のようにしならせて、檻の格子を打つ。格子は網目状に入り組んでおり、隙間はあってないようなものだった。
誰かの足音を耳に留め、虎は――ユキは――寝たふりをした。
足音は檻のそばまでやってきて、突然にガンガンと大きな音を立てはじめた。岩か鈍器かで檻を叩いているのだ。
ユキは驚いた。
打撃音は檻の悲鳴のように耳をつんざき、ただそれだけでも拷問のようだった。
だがそれでも音はやまない。
ユキはびくびくと怯えたが、いくら待っても音が鳴りやむことはなかった。延々とつづくその執念に、ユキはやがて檻の外にいる人物の意図を察する。
檻を壊そうとしている。
あらん限りの力を尽くして。
それでも檻が壊れないので、外にいる人物のほうでも苛立っている様子だった。しかしそれすらしだいに凪のような穏やかさに変わった。
檻への打撃は当初のような猛烈な降雹じみたものではなく、打楽器のような単調なものに変わった。それでもどうやら檻の外にいる人物は手を止めるつもりはないようだ。
ユキは思う。
もういい。
檻は破れない。
もうやめたほうがいい。
だが虎であるユキには唸り声を発することしかできず、その都度に檻の外の人物を余計に困憊させるだけのようだった。
もし、とユキは想像し、おそろしくなった。
もし、このまま檻が壊れず、それでもなお外の人物が諦めなかったら。
じぶんは何もできず、ただ檻のなかでその光景を眺めているしかなくなる。
じぶんのために懸命に、血を、汗を、時間を、人生を浪費している人物の余波を、互いにとって何の利にもならない不快な打撃音と共に聴きつづけるはめになる。
何もできない。
じぶんのためにここまでしてくれる相手にじぶんは、感謝どころか余計な真似をするなと、もはや憎悪すら募らせはじめている。
だがそれすら、時間と共に霧散した。
日に日に満身創痍になっていく檻の外の人物の様子を察して、ユキは、もういい、やめてくれ、と頭を抱えた。ついには悲鳴した。
こんな目に遭うくらいなら。
こんな目に遭わせてしまうくらいならいっそ。
いっそ、最初から檻になど触れさせるのではなかった。
寝たふりをするのではなく、初手で吠え、威嚇し、突き放しておくのだった。
ユキはそうと深く臍を噛み、その痛みで以っていまさらのように低く、低く、腹の底から唸り声を発した。
そこで夢から覚めた。
網目状に組まれた天井が回転していた。だが数度目をしぱたたかせると、視界は安定した。
悪夢を見た。
喉がひどく乾いていた。
水を飲みに、家の外に出ると朝ぼらけの天幕に一等眩い星明りだけが浮かんでいた。井戸で水を汲み、喉を潤す。
寝床に潜り直すころにはユキの脳裏には、蔵の中の人物との会話が断片的に流れては薄れた。薄れた矢先から同じような場面がふたたび流れる。
あの声の主は何度も、ごめんなさい、と訴えた。
その上、急に態度を豹変させ、ユキに怒髪天を衝かせた。ユキはだから言った。
もしも最初から――と。
最初から、扉が開かないことを教えてくれていたのならそんな気分のわるい目に遭わずに済んだのに、と。
「同じだ」
じぶんの声が村の者たちのつむぐ言葉のように、軽薄な響きを伴ないながら鼓膜に、頭蓋に響き渡った。ユキはもう一度ただ、同じだ、とつぶやく。
陽が昇ってからユキは虎にも会わずに村を発った。
親には数日村を留守にする、と告げてある。大物を仕留めるためにすこし遠出をする、と言うと、ユキの両親は、「果て印の外には出ては駄目よ」と言って送りだした。この手の遠出は初めてではない。いまは村の存続の瀬戸際でもある。
齢十二という幼さよりも、目前の利を得る。
賢いユキの親もまた賢かった。
道中できょうの分の食料を確保し、ユキは蔵のある場所まで足を運んだ。印を見ずとも身体が道を憶えている。いっそ残した印を取り去ってもいいかもしれない。なぜそう考えるのかも分からずに、合理のない考えを巡らせた。
この行動そのものが合理ではない。
ちぐはぐだ。
何の利もない。そのはずだ。
これは誰にとっても利のない選択だ。今朝見た悪夢の再現でしかない。
悪夢の中ではユキは虎だった。檻に囚われた虎だ。
だがいまは檻の外の側からの視点で、檻を、蔵を叩こうと思った。
それが蔵の中の本意ではないのだとしても。
ユキはいまいちど、初心に戻ってやり直すことにした。だって、と口元をきゅっと結ぶ。だって、寂しそうだったのだもの。
駄目だと言った。記憶がたしかなら蔵の中の人物は、閂を外そうとしたユキを引き留めた。それに触れるな、と。触れたところで開かぬそれに触れてはいけない、と。
その癖、最初に声を掛けてきたのは彼女のほうからなのだ。
いや、しかしそれはどうだろう。
思えば彼女は案じていたのではないか。すでに記憶が曖昧だ。なぜ彼女は蔵の中から声を掛けてきたのか。
あなたは一人なのか、ほかの者はないのか。そう問われはしなかったか。
じぶんはひょっとして、心配されていたのか。
ユキははっと息を呑んだ。
己が血の繋がった両親からもはや向けられなくなって久しい感情を、あのとき蔵の中の人物はユキに注いでいた。
いや、違う。
これはさすがに夢を視すぎだ。
そうじゃない。きっとそうじゃない。
何度も否定し、蔵の中に閉じ込められた者の本懐を喝破しようと試みるが、どの道、他人の心など解るものではない。じぶんの心とて解らぬのだ。どうして他者の本音が解ろうものか。解るはずもないのだ。
蔵の見える位置にまでくると、動悸がした。緊張している。しかし今回のこれは、初めて蔵の中からの声を耳に留めたとき――三日前のあのときとは違っている。
恐怖ではない。
不安だ。
誤解されるかもしれないことへの、不安だ。
じぶんがきっとそうしてしまったように、蔵の中の人物、彼女から誤解されることを怖れている。
二の足を踏んでいると、蔵のほうから物音がした。
何かが扉にぶつかるような音だ。蔵全体が怒号のような激しい振動を放っているようだった。笹の幹が音に呼応して、一挙に枝葉を揺らした。枝葉が揺れるたびに、シャンシャンと幾千万の鈴のごとく音色が鳴り響いた。笹森全体が震えているようだ。ユキはその轟音と音色を耳にして、雨の日を思いだした。雨を葉にずっしりと蓄えた笹を蹴ると頭上からは、星空のような雫の落下する音を耳にできた。
何かが蔵の中から扉にぶつかっている。
ユキの脳裏には、体当たりを繰り返す怪物の姿がぼんやりと浮かんだ。虎がぶつかってもこうはならない。もっと強大な何かだ。
蔵の扉は閉じたままだ。閂は掛かっている。外れてはいない。
ならばいま蔵の中にいるのは。
尋常ならざる音を奏でている強大な何かと。
そして。
例の柔和な声の主だ。
ユキはそうと瞬時に判断した。よもや蔵の中には一人しかおらず、この破壊的な轟音を柔和な声の主そのものが立てているとは考えなかった。それはそうだ。明らかにこれは人間の立てられるような音ではない。響きではない。振動ではなかった。
「助けなきゃ」
口を衝いていた。身体が動いた。つま先で土を掻き、駆けた。どんどん勢いを増し、ユキはいっとき虎となる。
最後の一歩で跳躍し、両の腿を中で閉じて、扉に足の裏からぶつかった。飛び蹴りだ。齢十二の小娘の蹴りだ。衝撃はたかが知れている。
案の定、扉は無傷のままで、ユキのほうがその場に肩から落下した。
痛めた肩を庇いながら上半身を起こすと、蔵からの轟音は止んでいた。
「だ、大丈夫」ユキは尻餅をついたままで叫んだ。「名前、名前教えないからこういうとき困るんだよ」と脈絡のない苛立ちを吐露しながら、「中にいるんでしょ、いまの何、物凄い音してたけど」と立ちあがる。「ねえ、返事してよ。聞こえてるでしょ。やいおまえ。いまのガンガンうるさくしてたやつ。出てこいよ。わたしが相手になってやる」
扉には閂がしてある。容易にはでてこられまい。
そうと判っていながら、しかしそんな考えなど毛頭なくユキは蔵の中に啖呵を切った。「出てこいよ。そんな狭いとこいないで、こっちこい。できるだろおまえなら。その扉ぶち破ってでてこいよ」
そうだとも。
ユキはそのためにここに来たのだ。
蔵の扉を開ける。
中から声の主を助けだす。
化物の処遇はどうしようもないので、扉が開いたら二人して一目散に逃げればいい。何だったら、とユキは考える。じぶんが囮になって化物を引きつけ、そのあいだに蔵の中の声の主には逃げてもらえばいい。
そうだ、それこそ正解だ。
ユキはことさら蔵のまえで挑発した。使ったことのない罵倒を唱え、いつも心の中に仕舞ったまま空虚の肥しにしていた村の者たちへの不平不満をそのまま口にした。
これで怒らねばいったい何に怒るだろう。仮に逆上しなければそれは化物ではなく笹ではないか。笹はユキたち人間が何をしても、どう伐り倒そうとも泰然自若といつも黙ってそこにある。
喉がひりひりと痛み、息が上がってきたころ、ユキははっと我に返った。蔵はしんと静まり返っており、鳥たちのさえずりが距離感も曖昧にあちらこちらで聞こえていた。雲の影が、足元の木漏れ日を横切っていく。
蔵のある一角は天上が拓けている。ここは明るいのだ、とそんなことにユキは初めて気が付いた。
「ふふっ。もう終わり?」
蔵の中から声がした。柔和な響きはユキの膝をその場に崩すのに充分な暢気さを湛えていた。「もうなんだよ、無事なんじゃん」
「あら。心配してくれたのかしら」
「そりゃもう」ユキは脚を引きずるように這って扉のまえまで移動した。「心臓張り裂けるかと思ったもん」と扉に寄りかかった。座り、背を預ける。「というか何度か張り裂けた」
「まあたいへん。どうしてきょうはお友達は一緒じゃなかったの」
「追い払った人が言うことじゃないよ。ねえ、さっきのってなんだったの。あの音は何。化物かと思ったよ。そうそう、早く名前教えてよ。名前知らないから化物相手に悪口言っちゃった」
「うふふ。聞いていましたよ。とっても傷ついちゃったな」
「違うよ。化物に言ったの」
「そうでした、そうでした。ところでどうしてまた来たの。ひょっとして失くし物でもしちゃったかしら」
「あ、それは、えっとねぇ」
「うん。どうして?」
扉に寄りかかりながら話していると、まるで先刻目の当たりにした蔵の絶叫じみた光景が夢幻に思えた。眩暈や耳鳴りを、あり得ない化物の存在に重ね視てしまったのではないか、と段々と現実味が薄れていく。
「違かったら違うって言ってね」ユキは前置きしてから言った。「もしかしてさっきわたし、一人で悪口叫んでた?」
「さあ。どうでしょう」
「ねえってば。ちゃんと答えて」名前だってまたはぐらかされて教えてもらってない、と首をひねってまっすぐ扉に声をぶつけると、「ユキさんには何がどう視えていたのかしら」と聞き返され、ユキは耳が熱くなった。「分かった。もういいです」
「ユキさんはひょっとして、何もないところで何か視えちゃいけないものでも視て、それであんなひどいことを私に向かって叫んでいたのかなぁ?」
「もういいって言った!」
「うふふ。いじわるしちゃった。代わりにいいこと教えてあげちゃおっかな」
「んー」膨れてからユキは言った。「なんだろ。そっちの名前とか?」
「昔々のお話です」
「げぇ」そんなの聞きたくない、と抗議するより先に、蔵の中の人物は柔和な声から陽気を消して言った。「昔々、あるところに一匹の鬼がおりました」
****
昔々、あるところに一匹の鬼がおりました。
鬼は自身が鬼であることにも気づかずに、目につくものを片っ端から手に入れて、じぶんの宝箱のなかに仕舞いこんでいました。
山も川も野も空も。
草も花も虫も獣も。
鬼はそれら生きとし生きるすべてのもの、自然、世界そのものを慈しんでおりましたから、損なわれぬようにと堅牢な箱の中に仕舞いこもうと考えたのです。
鬼はみなのためにしたことでした。
鬼はみなのことが大好きでした。
けれどもそれは鬼の中でのこと。
みなは必ずしもそうではありませんでした。
ある時、宝箱に閉じ込められた仲間を助けだそうと、山や川や野や空が、それとも草や花や野や獣が、徒党を組んで鬼に反旗を翻しました。
そこには人の姿も交っていました。
鬼はじぶんによく似た姿の人をとびきりに愛でておりましたから、そんな人からも憎悪を向けられ心底に傷つき、怯え、隠れました。
それでも鬼以外の神羅万象は、鬼と、鬼の持つ宝箱の効力を怖れて、手を緩めませんでした。執拗に探し、追いかけ回し、じぶんたちが受けた辱めと痛みを、そっくりそのまま返したのです。
しかし鬼には身に覚えのないことでした。
けれど現にそれは鬼がみなにしたことでした。
鬼は怒りよりも憎悪よりも何より、哀しみの色に染まり、そして――我を失ってしまったのです。神羅万象の総じてを無に帰さんと、鬼は鬼の持ち得る力のすべてを解放したのでした。
鬼の足元から順々に、まずは世界から花が失せました。
つぎに川が。
虫が。
そうして鬼を追い詰めた側の神羅万象は竦みあがったのです。やりすぎた。鬼を怒らせてはいけなかったのだ、と。
しかし我を忘れた鬼をまえに、成す術はありません。
そこでみなは、鬼の宝箱に目をつけました。我を忘れた鬼はそれを手放し、いまは中身のからっぽの箱です。
鬼に消されずに残った神羅万象は、鬼が正気に返る前に、宝箱の存在を思いだす前に、宝箱の中に閉じこもって、中から封をしようと考えたのです。
鬼の宝箱は底なしです。中には、もう一つの世界が広がっていました。神羅万象はそこにもういちど一からじぶんたちの世界を築こうとしたのでした。
***
そこで声は途切れた。ユキは声の主の語りに聞き入っていた。寂寥の滲む声音には仄かに笑みが乗っており、子守歌のように心地よかった。
反して語りの内容は、漫然と漂う雲の流れのようで、とりとめがなかった。いったい何の話で、それがいまどう関係あるのか。
なぜいまそれを話されなくてはならないのかが解らなかった。
しばらく待ったが、扉の奥からは物音一つしなかった。まるでいっさいが夜に沈んだかのようだった。
ユキは怖くなった。しかしその怖さの出処がよく解らなかった。なぜならいま、ユキに迫る脅威はない。すくなくともいまこの瞬間は、頭上から注ぐ日向を全身に浴び、ぽかぽかと微睡に揺蕩うような心地よい眠気があるばかりだ。
背には蔵の扉があり、その一枚隔てた向こう側には柔和な声の主がいる。
蔵にはほかに扉はない。窓もない。
ならばどうあっても消えていなくなるはずはないのだ。
そうだとも。
もし先刻の幻覚が、白昼夢が現実のものであるとするのなら、とりもなおさずそれは誰も出入りすることの適わない蔵の中に化物が侵入したということで。
しかしそれはあり得ない。侵入する穴はなく、仮にそうした穴があるのならああも扉に体当たりをする必要がない。轟音を響かせる必要はないのだ。
だからあれはやはりユキの視た白昼夢にすぎなかったのだ。
ユキは懸命にそう思いこもうとした。
しきりに浮かびたがる、よりあり得そうなもう一つの可能性を考えたくはなかったから。脳裏の奥底に沈めたままにしておきたかったから。
だからユキはしいて欠伸をして、眠くなってきちゃった、と言った。「ねぇ。また何か話して。なんでもいいよ。そうだ、つぎはトラも連れてくるからさ、今度はいじわるしないで仲良くして」
「今度はって何かしら」声の主はやっと返事をした。「私は別にいじわるをしたつもりはなくてよ」
「ふうん」
「まあなんでしょうその気の抜けたお返事は」
「だってさ。お姉さん、いじわるじゃん」
「え?」
「いじわるでしょ。もう誤魔化す意味ある? ないよね。ないない」
「そうじゃなくって、いまユキちゃん私のことお姉さんって」
「だって名前教えてくれないんだもの。好きに呼んでいいって言った」
「うふふ」
「何で笑うの」
「違うのよ。うれしいの。うれしかったの。ありがとう」
そこで彼女はなぜか不可思議な耳慣れない呪文を唱えた。
「鬼は外。愛は内。本当にそうだわ。そうなのよね」
「何がそうなの。聞こえなかったよ、もっかい言って。と言うか、お姉さんまで扉に寄りかかってるから声が小っちゃくてよく聞こえないんだよ」まるではるか遠くにいる相手としゃべっているようなもどかしさがある。「しゃべるならちゃんとしゃべって」
「ユキちゃんきょうは我がままさんなんですね」
「名前一つ教えてくれないお姉さんほどじゃないと思う」
「そんなに知りたいの」
「だって不便だし」
「そういうものかしら。昔はみな、好きに私のことを呼んだから」
「へえ。なんて?」
声の主は口ごもったが、ユキが逆さに十を数えだすと、「ゆうき」と鳥の囀りにすら掻き消されそうな、か細い声が聞こえた。
「なんて?」
「ゆうき、と言いました」
「それがお姉さんの名前? ゆうき、か。いい名前だね」
「そう思う?」
「うん。だってわたしも勇気のある人間になりたいし」
虎を、守り通せるだけの知恵と勇気のある人間になりたい。
ユキがそう言うとそこで蔵の彼女は押し黙った。沈黙の意図を悟らせまいとするかのようにいつもよりも弾んだ声音で、ありがとう、と彼女は付け足した。
歯に物が挟まったような物言いだったので、ひょっとして、とユキはぴんときた。「名前、ゆうきってその【勇気】じゃなかったりして」
「そう、ね」
「ふうん。じゃあなんだろ。ほかにあったっけかなゆうきなんて言葉」
「ありますよ」彼女は誤魔化すだけ無駄なのだと諦めたように、ふふ、と息を漏らした。「幽かな鬼と書いて、幽鬼」
ユキはずっと引っかかっていた違和感の正体にこのとき気づいた。
ないのだ。
笹森のなかにすらある、音の響く、その余韻が。
反響する微細な音の揺らぎが。
扉一枚隔てた向こう側、蔵の中からは聞き取れなかった。
「でもいまは」ユキの胸中に湧いた一抹の戦慄の念に気づいた様子もなく、蔵の中の人物、彼女、幽鬼は言った。「どちらが外か分からないのよ」
鬼は外。
愛は内。
蔵の主はそう言った。
ユキはそれを聞き漏らさなかった。
【寝ろ!】(2022/10/22)
百の壁に囲まれた国があった。そこには王が一人きりだった。王は毎晩必ずこう言った。「もう寝ろ!」
百の壁に囲まれた国は、上も下も右も左も壁に包まれ、まるで棺桶のようだった。FIN.
【世界一適当な人】(2022/11/08)
とある山の火口には世界一優しい男が住んでいた。住んでいた、というのは誤謬があり、じつはまだ現在進行形で世界一優しい男はとある山の火口にいるのだが、世界一優しい男は世界一優しいので全世界の生態系のために、大爆発しそうな火口にいち早く注目し、ありったけの叡智を注いでそれを食い止めていた。
世界一優しい男は世界一賢い男でもあったのだ。
だが世界一賢い男は世界一優しい男でもあるから火口で噴火を食い止めているわけだが、彼は世界一優しいので、じぶんごときが世界一優しいで賞受賞間違いなしの地位にいつづけることに心を痛め、世界一優しい男をやめることにした。そのため世界一優しい男は噴火すれば全世界の地表から生態系が消え失せる未来を、一人とある山の火口にて阻止しながら、ありったけの語彙力を駆使して絶えず悪口を吐きつづけた。
世界一優しい男は絶対に絶えず悪口を吐きつづけるなんて真似はしない。したがってこのときを以って、世界一優しい男は世界一優しい男の地位から転落した。
だが同時に、かつて世界一優しかった男は絶えず悪口雑言を吐きつらねながら、とある山の火口にて全世界の未来を一心に背負い込みながら噴火を抑え込み、さらにじぶんが本当に世界一優しい男ではなくなったのかをチェックするためにやはり絶えず片手間に全世界の情報網をチェックした。
日夜寝る間も惜しんで、悪口雑言を吐きつらねながらとある火口で噴火を阻止しつつ、片手間で高性能電子端末を操るかつて世界一優しかったかつ現世界一賢い男は、そうした尋常ならざる日々に身を置くことで、世界一タフな男の地位に昇りつめた。
だがやはりかつて世界一優しい男だった過去が尾を引いて、世界一タフでいつづけることに呵責の念を覚えだし、さらには同様の理由からじつは絶えず口にしていた悪口雑言も、たいして人を傷つけるほどの殺傷力を秘めていない有り触れた小言の域を出ていなかった。しかしそれでは世界一賢い男としての語彙力に疑念が湧く。
これによりかつて世界一優しかった男は、世界一タフな男の座を降りるべく敢えて怠けるようになり、それと共に元から大した悪口を唱えていなかった背景が加算され、けっきょくのところ何者でもない男ができあがった。
大して優しくもなく、タフでもなく、賢くもない男である。
否、もはや男であるのかすら疑念が湧いた。
そうなのである。
かつて世界一優しく賢くタフだった男は、世界一の美貌の持ち主でもあったのだ。
だがやはり過去に世界一優しかったときの名残により、何の努力もなしに世界一をつぎつぎ更新してしまう己が能力に蓋をすることにして、かつてあらゆる世界一だった男か女かもよく判らぬ人物は、とある山の火口にて、全世界の生態系の未来を守ることもやめて、いったい何をしたかったのかも失念して、とぼとぼととある山の火口から下山した。
だがかつて世界一賢かったころに発揮した噴火対策は抜かりはなく、もはや火口にいつづける必要すらなかったのだが、世界一タフであったことの名残により最も過酷な火口での生活を維持しつづけていただけだった。
かつてありとあらゆる世界一だった男か女か、もはや人か生き物かも分からなくなった存在は、それでもよく考えてもみたら、未だに世界一賢いし、世界一タフだし、世界一美しいし、そうしたあらゆる世界一であることを投げ捨て、なお人であることすら擲った、男か女か人か生き物かも分からなくなった存在は、やはり世界一優しい男なのであった。
男じゃん。
いいえ、女かもしれません。
いっそ人でいいじゃん。
ただの人で。
じゃあそれで。
【幻の大陸――海里】(2022/10/22)
千年に一度、満月は蒼く染まる。
月が蒼く視えるのはしかし、地上ではとある海域に限られた。
古文書によると、蒼い月から光がそそぐ海域には幻の大陸――海里が出現するという。これは世界中、どの古文書にも表現こそ違えど、似たような記述が散見された。
海里出現が最後に報告された時期は、いまからちょうど千年前にあたる。つまりあと半年も経たぬ間に、蒼い月の昇る日が巡る。
正確な日時や位置は不明だが、おおよその場所は特定されている。
幻の大陸――海里には、この世のものとは思えぬ財宝や見たこともない生き物や技術が時間を超越したように混然一体となって存在しているそうだ。
古文書の記述にどこまで信憑性があるのかは定かではないが、ともかく過去に沈没した大陸が再浮上する確率はそう低くはないと判断された。
全世界が手を組んで、幻の大陸調査団が結成された。
幻の大陸――海里出現を観測し、上陸して調査するまでが目的だ。どんな不測の事態にも備えるべく各国の優秀な研究者たちが集められたが、結果から言うと幻の大陸「海里」の発見には至らなかった。
観測できなかったのである。
時期が違うのではないか、との指摘はお門違いだ。
なぜなら古文書の通り、蒼い月は現れたのだ。満月の日に、ある海域の頭上に昇った月は蒼く染まった。
だが幻の大陸など現れなかった。
それはそうだと全世界の人間たちが嘲笑し、大真面目に国家予算を費やした各国を非難しだしたが、世界各国はむしろさらにつぎの千年後を目指して幻の大陸「海里」の特別調査予算を確保した。
月が蒼く染まる原理が不明であった点が理由の一つだが、そちらはおまけのようなものである。
最も見逃してはならない理由は、蒼い月の昇ったその日、古文書の指し示す海域の天気は曇りだったことだ。
そうである。
月は蒼く染まったが、月光が海にまで届かなかったのである。
世界最高峰の英知を集結させておきながら、誰一人として天候が崩れることを予測せず、対策すら敷いていなかったのである。
このことにより、各国は汚名返上と威信に掛けて、幻の大陸――海里への調査機関を国際的に創設した。
つぎに海里が出現するのは、いまから千年後である。
それまでに人類は天候を操れる技術を編みだせるのか。
つぎこそは徒労に終わらぬことを祈ろう。
願わくは、蒼い月の浮かぶ海が晴れんことを。
【ハロー効果の勝利】(2022/10/24)
記憶を失くしたその男が、奇妙な体験をしたのは秋も更けた十月のことであった。
男がなぜ記憶を失くしたのかについては主軸となる奇妙な出来事とは関係がないのでここでは触れずにおくが、男は目覚めると繁華街の路肩に寝転んでいた。
肌寒さに身震いをしながら上半身を起こすと、からからと目のまえを空き缶が転がった。
誰もいない。
夜だというのにカラスの鳴き声が閑散とした街道に響いた。
男はじぶんが誰であるのかを憶えていなかったが、自身が男であり二十三歳であり、そして何者かに追われていたことだけは憶えていた。
命の危機を感じ、逃げていた。その焦燥感だけが男には残っている。記憶の底に沈んだその焦燥感は結晶して、水晶のようにキラキラと存在感を発していた。しかし男の精神は水ではないので、水晶の煌めきはトゲトゲしく男の内面をチクチクと刺した。
逃げねばならぬ。
本能のように刷り込まれた焦燥感に男は、すくと立ちあがり破けたジーンズを手で叩く。
歩きだすと、地面の細かなブロックの段差を足の裏に感じた。男は靴を履いていなかった。
辺りを見渡す。左右には建物が道を縁どるように建っている。壁面は地面と同じ細かなブロックで、あたかも地面が隆起してそのまま建物になったかのような外観だった。
窓はすべて雨戸が閉じている。そうでない窓にはカーテンが下りていた。隙間から明かりが漏れている建物もあるが、中に人がいる様子はない。
街灯が道なりに点々と建っており、いっさいの影の動かぬ景色は、絵画のなかに入り込んだようだった。
ふと視界の端で何かが動いた。
ぺたぺたと足音を立てながら暗がりから子どもが現れた。頭巾を被っており、手には小さな籠を持っていた。
男はそのとき、じぶんが言葉をしゃべれることを思いだした。脳裏に、やあ、と誰かに声を掛けるじぶんの姿が浮かんだのだ。
子どもは男の足元までくると、じっと両手で掴んだ籠を見詰めたまま動かなかった。何かを促されて感じたが、その何かが分からなかった。
「どうしたの。みんなはどこ」男は発声した。
耳にしたじぶんの声は、思っていたよりも高かった。二十三歳のはずだが見た目はもっと幼いのかもしれない、とじぶんの顔形を思いだせないことに焦燥感はさらに募った。
子どもの被っている頭巾はくすんだ茶色をしていた。ひょっとしたら赤なのかもしれないが、街灯の明かりの下では茶色に見えた。
返事はなく子どもが動かないので、男は手を伸ばして子どもの頭巾をめくった。
途端、子どもは機敏に面を上げた。男はぎょっとした。子どもの顔面は真っ青で、頬は窪み、片目が潰れて視えた。
男は逃げだそうとして踵を返した。
すると反対方向の道からは、ぞろぞろと大量の人間たちが歩いてくるのが見えた。みな一様に同じ速度で、ぞろぞろというよりも、マグマがゆっくりと進むような蠢き方をしていた。まえの人物を押しのけ、先頭に立つと立ち止まり、こんどはうしろから押しのけられ、と全体が一つの粘液のような振る舞いをとって映った。
男は飛び跳ねた。
この世のものとは思えぬ光景だ。
元の進行方向に向き直り、男は得体のしれぬ集団から距離を置くように逃げだした。足元に佇む子どもはじっと集団を待っているようだった。
男はただただ街を駆け抜けた。
その後、男がどうなったのかはこの出来事とはさして関係がないので詳細を省くが、男はこの出来事がきっかけで精神に異常をきたして、生涯びくびくと日々を送るはめとなった。だが男にはそれで丁度よいくらいの過去があり、その過去を忘れてしまった以上は、やはり丁度よい塩梅であると呼べる。
この日、男の体験した一夜の奇妙な出来事について男が真相を知ることは死ぬまで訪れることはなかった。それはその街がどこにあり、いったいいつであったのかを男が知らなかったからであり、また調べようとしなかったことに因がある。
この街では毎年十月になると町全体で死者復活祭を行う風習があった。
奇しくも男が目覚めた日がその祭りの日であり、その日は一般に「ハロウィン」と呼ばれている。むろん子どもの目は潰れておらず、こけた頬も化粧によるものである。
【江戸の波の光は則る(2022/10/24)】
江戸の海が荒れた。
陸地にまで漁船が流され、泥に交じって魚や貝、果てはクジラまでが座礁した。
日中に起きた海の異常であったが、それは夜までつづいた。
段階的に、何度も大波が発生する。津波との区別がつかないが、地の揺れを感じた者は皆無だった。波だけが大きくなって押し寄せる。
甚大な被害が出ていながら、天変地異の前触れではないかと囁かれはじめたその日の真夜中に、夜の帳と打ち解けた海面が突如として光り、夜空へと舞い上がった。
光は煌々と太陽のように夜の浜辺を照らした。距離感が掴めないが、浅瀬から現れたのではない。それだけは明瞭であった。
光はそれからしばらく海上に浮かんでおり、人々がそのあまりの眩しさに目を覚まし、各々の避難した土地から海を見た。
人々の視界をいっとき占領すると、光は、ジグザグと不規則に左右にそれとも上下にと動き回り、すると何を思ったのか一瞬で遥か彼方へと遠ざかった。ともすればそれは、瞬時に小さくなって消えただけかもしれず、人々の間での認識にものちのちにまでその手の錯誤を元にした言い争いがつづいた。
あるとき、その噂を聞きつけた遠方の殿様がわざわざ村々にまでやってきた。海の荒れた被害は甚大であったが、さいわいにも死者はいなかった。
村人たちから話を神妙に聞いた殿様は、意見を仰がれ一言こうおっしゃった。
「じつに偉いことじゃ」
村人たちはその言葉に、胸が救われた心地がした。天変地異の兆候かと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。殿様が言うのだからきっと吉兆だったのだ。
その上、殿様は村に復興のための資材や人材を派遣し、さらには神社まで造らせた。これには村人たちは一様に感激し、遠い国と思っていた都への関心を強めた。
それからというもの、村人たちは村の神社を中心とした規則や法令を誰が言うともなくしぜんと築きあげ、長らく安息な日々を過ごしたということだ。
いっぽう、村から帰還した殿様は城にて家臣たちを集め、海岸で見聞きしたことを語った。
「ありゃあ偉いもんじゃった。すぐにでも手を差し伸べねば、噂が噂を呼び、都への反逆の意思を強めかねん。偉いことにならんうちになんとかせねば」
家臣たちはみな平伏し、ははぁ、と言った。
【空へと舞い落ちる】(2022/10/25)
全人類にはどんな個にも反領域があるそうだ。これは未来型量子力学という新たな分野で発見された粒子と反粒子の関係によって観測されたまったく新しい現象である。
量子とは極小の領域における物質や時空の振る舞いを言う。波の性質と粒子の性質を兼ね備える。
このとき未来型量子力学では、粒子は重力を反粒子は反重力をそれぞれ帯びると考える。
現実に残った物質の多くは粒子であり、反粒子はすでに多くが宇宙の初期にほかの粒子と対消滅して消えてしまっていると考えられてきた。
ところがだ。
じっさいには、反重力として部分的に散在して、物質と時空との合間にエネルギィとして残留していることが観測された。
このとき物質には己の反粒子に値する反重力がセットとなって存在することが示唆された。
驚くべきことに、地球を構成する物質に対応する反重力は、同じくそのほとんどが地球に内包されているというのだ。
これは量子もつれに距離の限界があることとどうやら無関係ではないようだ。従来の量子力学では、量子もつれは距離に関係なく、たとえ宇宙の端と端であれ働くと見做されてきた。いっぽう、未来型量子力学では、量子もつれにも距離の限界があると解釈する。ただしその距離の限界は、対の粒子をもつれさせるときのエネルギィによって規定されるため、大量のエネルギィを用いたもつれほど、その作用の有効距離を延ばすと解釈する。
そのためどうやら地球上の物質に対応する反重力が、地球の外部に漏れることを防いでいるというのだ。限界があるために、外に拡散しない。
反重力とはいわば斥力だ。引きつけるのではなく、反発しあう。
だがその反発しあいながらも、物質との関係で限界値を持つために、どうやら地球上の部分部分にまだらに編成されるというのだ。
反重力が作用する物質は決まっている。対応する物質にしか作用しない。対となる物質にしか作用しない。
これは裏から言うならば、物質とて対となる反重力から距離を置くように地球内部では相互作用を連動させる。地表の物質とて例外ではない。
反領域とはすなわち、物質それぞれが持つ対となる反重力のある地点を意味する。
ここに一本の木がある。桜である。
西暦2140年代に発見された希少種で、その名を「桜場一樹(さくらばいっき)」という。
この桜、どうやら自身の反領域の上に根付いた稀有な樹であるようだ。
通常、反領域の上に対となる種が落ちることはない。物質を跳ね返すからだ。寄せ付けない。
だが偶然にも、ちょうど半々の割合で「物質と、反重力と対の物質」で構成された種が、たまたま自身の反領域の上に落下し、芽を萌やしたようである。
これにより芽は、反重力の作用を受けながら、反発する物質を上へ上へとより蒸留させながら成長した。立派な樹となったころには、ごく少量であった反重力と対となる物質は、枝葉全体に散り、さらに細部へと拡散していく。
するとどうだろう。
この奇跡の樹と呼ぶべき「桜場一樹」は、桜の花を散らせるたびに、「落下しては浮上する」というふしぎな桜吹雪を生みだすのだった。
はらはらと散った桜の花弁は、地表に落下するが、その地点には対となる反重力を帯びた土が領域全体に交じっている。そのため、重力よりかは弱いがそれを打ち消すことの可能な反重力を受けることになる。
落下しては浮遊する。桜の花弁がトランポリンにでも乗っているかのような、それとも見えない糸で繋がれ、バンジージャンプをしているかのような、ひらひらぷわぷわを繰り返す奇妙な光景をつくるのだ。
絶景である。
こうして地表で唯一の、反領域が可視化された場として、奇跡の土地にして奇跡の樹――「桜場一樹」は、未来型量子力学の証拠として長らく語り継がれるようになる。
観測されてから八十年目が経ったその日。
満開の桜を散らしたとき、奇跡の樹は花弁を地面へ向けてただ舞い落とし、以降、桜が逆さに舞い落ちることはなくなった。
樹から反領域と対となる原子がすっかりなくなったがゆえだと目されている。
【冬のコゴミ(2022/10/25)】
千回巻くからぜんまいというそうだ。真偽はハッキリとしないけれど、山菜の王者と言えばぜんまいだ。
しかし私が帰宅して籠を手渡すと、一息(いっそく)さんはやれやれと赤ベコのように首を振った。
「これはぜんまいじゃないよ」
「嘘でしょ」
私は愕然とした。慣れない山道で散々目を凝らして摘み取ってきたこれがぜんまいでなければいったい私の採ってきたこのくるくるの草はなんだというのか。
「これはね。コゴミ。ぜんまいとどっちにも渦巻きはあるが、ほれ。コゴミにゃ産毛みたいな綿毛がないだろう。新緑だろう。綺麗だろう。あたしが所望したのはぜんまいであって、コゴミじゃないんだ」
「どっちも同じじゃないですか」
「コゴミは綺麗すぎる。灰汁抜きせんでも美味しく食べられるからね。あたしゃ灰汁が欲しかったんだよ」
「採ってくる前に用途を聞きたかったですよ。山菜ならどれでもいいと思うじゃないですか」
「ぜんまいとあたしは言ったつもりだがね」
「私にぜんまいとコゴミの区別がつくとお思いですか」
「付かない人間がいるのかい」
「こ、こ、に、いっます。目のまえにいてるじゃないですか」
一息さんは丸く小さな老眼鏡を小指で持ち上げると、ふむ、と頷いた。「もういいよ。ご苦労さん。もう時間じゃないかい」
「はっ。もうそんな時刻でしたか」
私は時計を見遣って、講義の時間が迫っていることを知る。
お邪魔しました、と慌てて玄関口で靴を履き、けんけんになりながら転げるように家の外に出た。秋の風が私の身体の表面から一息さんの家の匂いを拭い去るようだった。
もったいない、といつも同じことを思い、そしてすぐに忘れる。私にとって一息さん家での休憩時間は、まさに息抜きであり、現実を忘れていられる唯一の時間だった。
軒並みの屋根の奥には大学の校舎が、ひょこ、と見えている。小走りで道を急ぎながら私は、一息さんと会ったのもこんなふうに道を急いでいた日だったな、とあの日のことを振り返っている。
一息さんは六十だか七十歳の女性で、私の通う大学の校舎から一キロも離れていない地点に家を構えている。家の後ろ手には芒野(すすきの)が広がっており、さらに奥には山があった。山は森と繋がっており、言ってしまえば一息さんの家のある区画が住宅街と自然との境だった。
私は講義の組み合わせに失敗して、毎週金曜日が二コマ目から六コマ目の最終講義までの五コマが空いてしまった。暇な時間をどうつぶそうかと半年のあいだ試行錯誤したがさすがに朝の十時から五時までの待ち時間は長すぎる。かといって家に帰るには、私の家は大学から離れすぎていた。バスで片道二時間かかる。
折衷案として私は、大学近辺の地形を観察することにした。卒業論文のテーマを等高線の研究にしようと思っていたので、ちょうどよいと考えたのだ。等高線の研究とはいえど、私がやりたいのは輪切りと等高線の比較であり、もっと言うとそこからMRIやCTスキャンくらいに微に入り細を穿った等高線がつくれんじゃろか、と企んでいた。いまも企んでいるが、そのとき私は山に入る前に道路でこけて足を挫いた。
空き缶を踏んだのだ。
誰だよこんなところに捨てたの。空き缶捨てたの誰だよ。
地面に尻を着けながら、痛くないほうの足でダンダンと地面を蹴っていると、おや、と庭から顔を覗かせたのが一息さんだった。
一息さんは白髪交じりの灰色の髪の毛を団子に結っており、座った私が見上げると灰色の鏡餅が垣根に乗っかっているように見えた。
「ちょいとお待ちよ」垣根の壁から声がして、灰色の鏡餅が横に泳いでいく。
間もなくして玄関口から背の低い女性が現れた。逆光になっており、顔がよく見えなかった。私はそのとき、手塚治虫の漫画「仏陀」に出てくるシッダルタのシルエットを脳裏に蘇らせた。というのも、まさに灰色の鏡餅然とした髪型が、漫画のシッダルタとそっくりだったのだ。
「大丈夫かい。おや、立てないのかい」一息さんは私の鞄を拾いあげると、新芽でも撫でるような手つきで砂を払った。私はたぶんその所作一つで彼女のことを信用したのだと思う。
「イタッ」
立とうとしたが上手くいかなかった。足首を捻挫していると判った。傍目からでも一目瞭然なようで、一息さんは私の鞄を持ったまま、「時間はあるかい」と言った。私は戸惑って、どういう意図の発言か、と推し量っていると、一息さんは、「休んでいくといい」と自らの家の門をくぐり、玄関口のまえに立った。「歩けないほどの痛みなのかい。救急車を呼ぼうか」
「だ、だいじょうぶです」
私は足を引きずりつつ、なんとか自力で立ち上がった。踏んだ空き缶も拾い上げておく。一息さんがその様子を目に留めて、事情を察したのか、やれやれ、と忌々し気に首を振っていたが、矢継ぎ早に私へと、災難だったね、と言いたげな眼差しを向けたので、私はもうそれだけで心が晴れるようだった。生まれて初めて憐憫とは何かを知った気になった。憐憫とは一息さんのあの眼差しのことだ。
一息さんの家は和風の長屋だった。二階もあるがそちらは屋根裏といった塩梅で、どうやら一息さんも物置部屋として使っているようだった。というのも、私のためにわざわざ座布団を二階から持ってきてくれたからだ。
「黴臭いかもしれんが、ないよりかはマシだろう」
「ありがとうございます」
「いま氷水を持ってくるよ。待っといで」
「す、すみません」
「あんたが謝ることじゃないさ」
居間は台所と隣接しており、奥で作業をする一息さんの姿が居間からも見えた。
「お一人で住まわれているのですか」私は部屋を見渡した。
「ほかに誰か見えるのかい」
「すみません」出過ぎた質問だったか、と恐縮すると、「あんたは、ちと人に気を使いすぎだね」と一息さんが戻ってくる。手にはビニル袋に入った氷水が握られていた。
「冷やしな」
「すみま――あっ」言いかけて、「ありがとうございます」と言い直す。
「無理して直すもんでもないさ」
一息さんはもういちど台所に引っ込むと、自身の名と無職で暇なことをつらつらとしゃべって、それから間もなくしてお盆にお茶とおせんべいを載せて戻ってきた。
「家は近いのかい。この辺は何もないだろう。あんたの進行方向にゃ林があるだけだ。なら急ぎの用ってわけでもないんだろう」
一息さんは鋭かった。
「講義まで時間があって、それで散歩に」
「ほお。あすこの大学かい」
「はい」
「無理に引き留めはしないが、時間があるならすこし休んでおいで。物凄い音がしたよ。あたしゃ地震かと思った」
「ふふっ」大袈裟だな、と思ったが、一息さんは、「本当さね」と念を押した。
この日は時間いっぱいまで一息さんの家で休ませてもらった。私は一息さんのことに興味が津々に募っていたのだが、一息さんは私の質問には一言で応じる割にその返答は煙に巻くようなものが多く、あべこべに倍になって返ってくる質問に対応するのに私の思考は費やされた。
しかし大学に入学してからというもの、私はもっぱら聞き役の立場でいることが多く、誰も私に質問を浴びせるなんてことがなかったので、この日はすっかり舞台の上の歌姫さながらに、じぶんに興味を持ってくれているらしい一息さんに私は赤裸々にじぶんのことを語っていた。
というのも、どうせきょう限りでもう二度と会うことはないだろう、と思っていたからで、あと腐れのない相手にはじぶんの将来の夢だろうが恥ずかしい失敗談だろうが、ふだん誰にも言えぬ悩みとて遠慮会釈なく言えるのだった。
一息さんは私の答えに大して目を輝かせることもなく、ほうそういうもんかねぇ、といった大樹然とした相槌を挟むばかりで、これがまた私には快適だった。ごくごくといくらでも雨水を飲み干す大樹の根を彷彿とし、私はことさら枯らしてはいかんな、と思って包み隠さずじぶんのことを披歴した。
これがいけなかった。
そろそろ時間じゃないのかい、と一息さんに促された私はしかしもはや講義よりも、きょうはこのまま一息さんとのぬるま湯に浸かったような時間を満喫していたい、との怠惰の念に身も心も染まりきっていたので、「きょうはもうサボっちゃおっかな」と冗談めかし口にした。
「授業料は安かないんだろ」一息さんはそこで初めて私に向けて語気を尖らせた。「そういうのはじぶんで稼いでから言うもんだ」
「は、はい」私は顔面をビンタされた気分だった。泣きそうだった。急に夢から目が覚めたようだった。
帰り支度を済ませ、お邪魔しました、ととぼとぼと玄関口で靴を履いたが、足首が痛くてまごついた。
履き終わると、一息さんが私の鞄を持っていて、はいよ、と手渡してくれた。「毎週こんな時間まで時間が空くのかい」
「はい。そうなんです。愚痴った通りです」この話題は御開帳済みだ。
「そうかい。ならまた暇だと思ったら休みにおいで。手伝って欲しいこともあってね。人手が欲しいと思っていたところなんだ。小遣い程度しか出せないけど、まあ気が向いたら、また寄ってくれ」
「いいんですか」
「嫌ならこなくていいよ」
にひ、と私の喉から変な声が漏れた。両手で頬を押さえながら私は、じゃあまた来ますね、と約束をして一息さんの家を出た。
それからというもの私は毎週金曜日には一コマ目の抗議に出席したあとは、一息さんのお家にお邪魔する習慣ができた。一息さんは庭いじりが好きで、晴れの日はたいがい私が家のまえに着くと垣根から灰色の鏡餅を覗かせて、いらっしゃい、と大してうれしそうでもない声音で挨拶をした。
一息さんに旦那さんはおらず、結婚もしてこなかったようだ。
「そういうのはね。したい人がすればいい」とは一息さんの談だ。
「私はしたいです。白馬の王子様じゃないですけど、運命の赤い糸を信じているので」
「おや。新鮮だね。運命を信じるのかい」
「ダメですか」
「ダメじゃないさ。幸せなコだね、と思ったよ」
「え、そうですか。褒められた」
「幸せにおなり。幸せになるんだ。きみのようなコは幸せにならんといかん」
「なんですかそれ」ぷぷぷ、と私は口元を手で覆う。「一息さんは幸せじゃないんですか」
「あたしかい。あたしは幸せなのかね。じぶんではよく解らんよ」
私はそこで彼女に、寂しくないんですか、と訊きたくなった。でもぐっと吞み込んだ。私より遥かに長いあいだ一人で暮らしてきた彼女に、私のような新参者が投げかけてよい質問ではない気がしたのだ。
「休憩……」
「またですか。いっつも思ってましたけど一息さん、ことあるごとに、【休憩……】とおっしゃいますけど、それはたぶん根を詰めすぎなんですよ。庭いじり」
「ほかにも仕事はあるさね」
「ならそのお仕事が、です」
「そうさな。そうだそうだ。まったくだ」
一息さんは素直なのかひねくれ者なのか判断に困ることがあった。たびたびあった。彼女はいまでも私にとってよく解らないひとである。
私が一息さんから頼まれる仕事はたいがい、買い出しや庭の枯れ葉の回収や、重い植木の移動など、お手伝いと呼ぶに似つかわしい可愛い仕事ばかりだった。その癖、その報酬がひと月で、私の食費が賄えるくらいの額を一息さんが寄越してくるので、私は初めて受け取った封筒をじぶんの家に帰ってから開けて絶句した。
これではお気楽にお家に伺えないではないか。
「私は一息さんのお家には癒されに来てるつもりなんですよ」私はそうつぎの週に抗議した。「あんなにもらったら肩身が狭くてこれなくなります。なので半分はお返しします」
「なら来なければよいだろう」一息さんはにべもなく言った。お茶を啜ると、「そりゃあんたの正当な報酬だ。いらないなら捨てるなり、寄付するなり好きにしな。あたしに返すのはお門違いさ」
「あらそうですか」私はむっとして出した封筒を引っ込めた。「じゃあそうします」
そう言ってその日のお手伝いであるところの買い出しついでに、一息さん用のお高い焼酎を購入した。台所に空の焼酎の瓶が溜まっていたので、晩酌好きなのは知っていた。
何と言って渡せば突き返されずに済むか、と考えながら一息さんの家に戻ると、一息さんの姿がなかった。どこに行ったのだろう。私は居間以外の部屋をそのとき初めて見て回った。
居間で待っていてもよかったが、年配者の一息さんのことが心配でもあった。
襖を開けて覗いてみると、一息さんは奥の和室にいた。和室なのに洋風の椅子と机があり、一息さんはそこに腰掛けてこちら側に背を向けていた。
「あのぉ、ただいまです」
「おや、お帰り。きょうはいつもより遅かったね」
「あの、この部屋は」私は一歩部屋に入った。見渡す限り、壁という壁には習字が貼ってあった。それはどちらかと言えば、干してある、といった風情で、中には巻物のごとき墨絵もあった。山や花が描かれている。
一息さんは振り返ると、小さな丸眼鏡をズラして私を見た。「趣味部屋さね」
「すごいですね。これ全部、一息さんが?」
「ほかに誰か見えたら教えておくれ」
「透明人間がいるかもしれないじゃないですか」茶化しながら私は一息さんの背後に立った。机を覗き見ると、まさにいま書き終わったばかりらしい絵があった。
「墨絵ですか」
「さあてね。どういう流派なのかはじぶんでも判らんよ。見よう見真似。趣味だ」
「それにしてはお上手ですけど」
構図が素晴らしい。荒さの一つ一つが総体で意味を持つように、紙に陰影を刻んでいる。一つ一つを見れば雑なのだけれど、その雑がふしぎと雑ではなく、全体にとって必要不可欠な濃淡になっている。
「こういう技法があるんですか?」
「さあ」
「本当に独学なんですか」目を見開いてみせると、一息さんは、おいしょ、と言ってわざわざ私を押し退けるように立った。「買い物は済んだんだろ。どれ。お茶でも淹れてやるか」
居間に戻るとさっそく一息さんは台所に立った。私は買い物袋から品を出し、それを一つずつ収納棚や冷蔵庫に入れていく。分からない品は一息さんに訊ねるのだが、たいがいは、そこに置いといで、と指示がある。
「あのこれ」私は最後に焼酎を袋から取り出し、床にどんと置いた。思いのほか音が響いて、一息さんの肩が小さく跳ねた。「なんだいそれは」と灰色の鏡餅が横を向く。
「私のお金で買ってきました。大好きなお友達に喜んで欲しくって」
じぶんで口にしておきながら顔から湯気が出た。たぶん本当に出てた。だってお湯が沸きましたよの合図のように火に掛かったやかんが蓋をカタカタカ鳴らしている。
一息さんはつまみを回して火を止めると、手を伸ばした。その所作一つで、寄越しな、と言っていると判る。一息さんはたびたびこうして無言で言葉を発するのだった。威圧的でないのが奇跡的と言えた。
一息さんは一升瓶を受け取ると、ふむ、とラベルに目を留め、こめかみを指で掻いた。それから腰に手を当て、「もらっとくとするか」と言った。
ただそれだけだ。
ただのそれしきのことで私の半径一メートル四方にはシロツメクサが生え揃うようだった。蝶とか舞っていた。蟻がよちよち列をなしていた。日向がぽかぽか心地よかった。
私がそうして一人のぽわぽわ世界に没入しているのを尻目に一息さんはさっさと一升瓶を棚の上に置いて、お茶とお菓子を用意した。
「さ。休憩にしよう」
「あ、持ちますよ」
一息さんはそそくさとお盆を持って居間に移動した。一息さんの背後を私は金魚の糞のごとく、モタモタしながらつづいた。
「あ。オコタの布増えてる」
「いま気づいたのかい」
「あったかくなってる。うふふ。やった」
「寒くなってきたからねえ」
コタツの蒲団が三枚になっていた。厚手の一枚が増えていたのだ。
「さっきも座ったのに気づかなかったです。いいなぁ。あったかぁい。私の部屋にも欲しくなる。買っちゃおっかな」
「おや。小さいのでいいならうちにあるよ。あとで見せようか。欲しければ持ってきな」
「いいんですか」
「分解すりゃ抱えて持って帰れるだろ。お一人用炬燵さ」
「欲しいです、欲しいです」
「ゴミが一つ減る。うれしいねえ」
一息さんの言葉には抑揚がない。どんな言葉も淡々と口にする。怒っているのか、呆れているのか、哀しんでいるのか、不貞腐れているのか。それを言葉の響きだけで聴き分けるのは至難だ。
でも私にはなぜか一息さんの機微が判るようだった。ちなみにこのときの一息さんのそれは照れ隠しで、うれしいねえ、と言ったのも皮肉を装った本音なのだ。私はかってにそう思っている。
先日のことだ。
夏がやってきたのでつぎは秋だ、と流れる季節のごとく金曜になったので一息さんのお家にお邪魔すると、開口一番に彼女は、「一つ頼まれてくれないかい」と言った。
玄関口で私が靴を脱いでいないうちから一息さんは、
「ぜんまいを採ってきて欲しいんだよ。お願いできるかな」とこめかみを掻いた。
「ぜんまいですか」
「すこし行ったところに土手があってね。道沿いに歩けばそれなりに採れるはずだよ」
「いいですけど、一息さんも散歩がてら一緒に行きません?」せっかくオコタに潜って一息さんに話を聞いてもらおう、とスキップ交じりにやってきたのに、せっかくの一週間の癒しの時間が一人で山菜採りはすこし嫌だった。せめて買い物ならば通い慣れた道だからよいが、知らない道で一人は寒さが肌に染みるようになった時節柄、ご遠慮願いたい思いが湧いた。
「あたしはあたしでやることがあるからね。まあ、嫌ならいいんだ。上がりよ」
「大丈夫です、大丈夫です。行ってきますよ。ぜんまいですよね。ちゃちゃっと採って戻ってきますんで」
「助かるね。ほれ、これに入れといで」
籠を手渡され、前払い、とついでのように封筒をもらった。その場で開けて確かめるといつもよりすこし額が多かった。
「こんなにもらえません」と渋ると、「ならその分働いておいで」と送りだされて、私は唇を尖らせる。一息さんから渡された籠は手のひらサイズで、この籠を一杯にするのにぜんまいは五本もいらないだろうと思えた。
こうして私は慣れない山道をたどたどしく辿りながら路肩の藪に目をやって目当ての山菜が生えていないかを探った。一時間くらい掛けて私は一息さんの家に戻った。一息さんは私のためにお菓子とココアを用意してくれており、私はオコタに浸かって、ひと仕事終えた達成感に浸りながら、お褒めの言葉を待った。
籠を覗きこんでしばしの間を空けたのちに一息さんは言った。
「これはぜんまいじゃないよ」
「嘘でしょ」
一息さんの説明を聞きながらじぶんでも端末で検索をして確かめた。たしかに違う。私が摘んできたのはコゴミであってぜんまいではなかった。ほかに渦を巻いた山菜は、わらびもある。一見すればどれも同じに見えるが、属からして違うようだった。
「すみません。お役に立てず」私はしょんぼりした。これぞしょんぼりの見本だな、と思いつつ、以前に目にした一息さんのお手本がごとき憐憫の眼差しを思いだした。
私が顔を上げると、一息さんは湯呑みを両手で持ってお茶を啜っていた。湯呑みの底に手を添えて飲むあたり、茶道でもやっていそうな凛とした佇まいがあった。
コゴミは綺麗すぎる。
一息さんはそれを何度か繰り返し口にした。あたかも緑茶には渋みがあって当然で、それがなくなったらお茶を飲む醍醐味は失われるのだ、と説くような悲壮感が漂っていた。それは私が十全に仕事を達成できなかったことへの小言ではなく、私が同じ世界観を共有できないことにへこんでいるような機微の揺らぎを宿していた。
それはたとえば私の好きな映画を、一息さんがそうと知らずに虚仮下ろした場面に遭遇した具合に似ていたかもしれない。そういう事態にはいまのところ遭っていないが、想像したら私は悲しくなった。マスカラで加工したまつげが、反対向きにくるんとこうべを垂れるようだ。
「うん。まあ、たまには綺麗なのもよいしな」一息さんは見兼ねたように言った。
言わせてしまった、と私は思い、無理くり目じりに皺を寄せた。にっこりしてみせたつもりだが、上手くできたか分からない。お小遣いの封筒をお返ししたいと思ったが、それをしたらもう二度とお家に上げてもらえなくなりそうな予感があった。
「先に言っとくが、お代は返すんじゃないよ。あんたの時間を貰ったんだ。それは正当な報酬だ」
「分かっとります。ありがたく頂戴いたしますけれども」
「そんな濡れた捨て犬みたいな顔をして」
「へへ。そんな顔しておりますかね」
「人はね。たまには失敗してもいい。誰に言われようとも肩を落としていい。あんたがへこたれようと、あたしも遠慮しないで思ったことを言っていい。そういうもんなんじゃないかい」
「でもそれで言ったらあれですよ」私は考えながら、ココアを飲み干した。「一息さんは、たまには私のことをドロドロに褒めそやしてもいいと思いますけどね私は」
「人は、人を無理やりに褒めなくともいい」
一息さんはじぶんで言って、ふっ、と綻びた。私が、あっ、と川べりでホタルでも見つけたみたいに口を開けたからか、すぐにきゅっと口元を結んで彼女はまたいつものような灰色の鏡餅の付喪神じみた風体で、「休憩……」と零すのだった。
その後しばらくは、彼女がぜんまいを何に使いたかったのかは子細には知れなかった。
大学が冬休みに入るまで私は、毎週のように一息さんの家に遊びに行った。ほかにすることもなく、ましてや私の話を聞いてくれる相手などいないのだ。
今年最後の訪問になるだろう金曜日に、私は、一息さんから一枚の絵を貰った。
「私にですか」
「ほかに誰かいたら教えておくれ」
「じつは一息さんは認知症さんで、ほかの人のことが見えていないだけなんですよ」
「そういう冗談は気に食わないね」
「でしょうとも、でしょうとも」一息さんの正論を聞きたいがために私が世の悪を一身に背負ってもよいくらいだ。「見てもいいですか」と断って、返事ももらわないうちから私は額をひっくり返して、まじまじと絵を拝見した。
「うわあ。うわあ。へへへ。うわあしか出てこない」
三本の渦巻きの絵だった。
山菜だ。茎に綿毛がないのでコゴミだろう。
まるで薔薇のようにも視える。
線と筆致と滲みの絵だった。錯綜そのものが層をなして、質感を紙面の上に立ち昇らせている。延々と途切れない線香の煙のようにも感じられた。
「このための山菜採りだったんですね」
「ついでさ。ついで。ただ、ぜんまいのほうが縁起がよいだろう」
「縁起ですか」そういういわくが、各種山菜にあるのだろうか、と想像した。
「ぜんまいは、元は千回渦を巻くようだから千巻きと転じて、ぜんまいになったそうだからね。あなたには、何回転ぼうともネジを千回巻いたように動きつづけて欲しいと思ったんだが、まあこの際、コゴミでもいいと思ってね」
「へえ。ステキなお話」
「コゴミは元は、屈むからきているそうだよ。まさに尻餅をついたまま動けなくなっていたあなたによく似合う」
「それは、え。なんですか。ステキな話なんですか。喜んでいい話なんですかね」
「どうだかね」一息さんは大きな溜め息を漏らした。「コゴミは綺麗すぎる」
「ぐふ。それは何ですか。私にくれてやる絵にはもったいないと、そういうお話なんですか」
いっそ肖像画でも描いてくれたらよかったんですよ、と悪態を吐くと、一息さんは、それも考えたんだけどね、とその場で足を交差した。その立ち姿が湖に立つ鶴を思わせ、私は、そのあなたの姿こそ絵にして飾りたいな、と望んだ。
私の胸中の感動などお構いなしに一息さんは、眼鏡を外し、
「あなたはじぶんの顔を部屋に飾りたいと思う人かなと思ってね」と袖でレンズを拭いた。「あたしなら、あたしのことを描いた絵よりも、あたしのことを思わず、ただ描きたいから描いたその人の表現こそをもらいたいよ。あなたも同じかなと思ったの」
ただそれだけ。
要らなかったら捨ててもいいよ、といつもと変わらぬ抑揚のない冷めた口吻で言うと、一息さんは、もう時間だよ、と私の背をせっついた。「学んでおいで。幸せにおなり。幸せになるんだ。きみのようなコは幸せにならんといかん」
いつぞやに耳にした台詞を祝詞でも唱えるように口にした。
「絵、ありがとうございます。すこし早いですけど、よいお年を。また来年も来ますね」
「もう来なくてもいいよ」
「へへへ。断られても来ちゃお」
人は寒いときは見送りに出てこなくともよい、と言いつけて、私は一息さんの家の扉を閉じた。
外はまだ陽が暮れておらず、冬の日没の遅さを思った。太陽の気持ち、分かるな、と私はバス停までの道を行く。
こんな素敵な一日は、早々容易く終わって欲しくない。
私は一歩足を踏みだして、それから道端に転がる空き缶に目を留めて、逡巡してから拾いに屈む。
コゴミじゃん。
空は秋も暮れ、冬の澄んだ空気をまとっている。
【掛ける目を瞑る】(2022/10/27)
新月は星明かりを鮮明に描きだす。存在しないことで仄かな明かりの生命力を底上げする様子は、まさにわたしたちのようだ。
わたしたちはとある孤島の城に住まう。幼少期の時分でいずこより選抜され、運ばれてくると聞き及ぶ。毎年のように継ぎ足される新顔の幼い顔つきを見れば、否応なくそれが正規の手続きを得た選別ではないと判る。
私たちは城の主たるギルバート伯爵に仕える召使いだ。
毎年、召使いたちのなかからたった一人だけギルバート伯爵のお眼鏡に適い、そして妾として別荘へと住居を移す。そちらの生活は、召使いの身分ではとうてい味わえない甘美で優雅な暮らしだという。わたしたち召使いは、一刻も早くギルバート伯爵のお眼鏡に適うように、目をかけてくださるように、日々慎ましくも懸命に我らが主様のために働くのだ。
わたしたちがギルバート伯爵のお姿を目にする機会は限られる。
新月の夜に開かれるパーティの場か、もしくは城の中を風のように歩き去るお姿を垣間見るくらいが精々だ。
そうしたなかで私が偶然にもほかの召使いたちを差し置いて、ギルバート伯爵との縁をこっそり結んでしまったのは、中庭の薔薇園の管理をわたしが任されるようになってからひと月後のことだった。
薔薇園はギルバート伯爵の初代妾の方が愛でていた庭だそうで、妾制度の礎を築いた方だと聞いている。この薔薇園の管理を任された者は、ギルバート伯爵の妾になることはない、といういわくつきの仕事だ。誰も率先して引き受けたがらないのだが、わたしは何事も主様のためにすべきである、と己に誓っているので、その誰もやりたがらない仕事を引き受けた。
主様のためだ。
ギルバート伯爵のためにわたしの肉は、心は、あるのである。
雨雲が空を覆った薄暗い日だった。
泡立つ肌を温めようとわたしは部屋の箪笥からカーディガンを引っ張りだし、従者服の上から羽織っていた。下品な組み合わせの服装ゆえ、これはあまり褒められた着方ではなかったが、どの道、薔薇園にはわたし以外の人がいない。
見咎められることもない。
そうと油断していたため、
「これは斑点病じゃないのかい」と声がしてわたしは飛び跳ねた。
垣根を挟んだ向こう側に、背の高い影が立っていた。
その人影は垣根を回ってわたしのいる地点まできた。丹念に薔薇の葉を診察するような眼差しは、カンバスに向き合う画家のようでもあった。
「ギルバート様……」
「今年はキミが世話係なのだね」
「はい。仰せつかりました」
「うん。やっぱりだ。斑点病に蝕まれているね。ここの区画はもうだいぶやられているはずだよ。まだ目には映らないだけで、菌糸が巡っているはずだ」
「あの、どうすれば」わたしは庭師ではない。広大な薔薇園のなかを一日がけで水をやり、肥料を撒きながら練り歩く肉の塊だ。
「葉をすべて毟って、薬を撒くよりないだろうね」
「そんな」
蕾がようやく出てきた薔薇たちだったのだ。それを毟るのは酷だった。
しかしギルバート伯爵が言うのだから指示に従わぬ道理はない。薔薇園の所有者が彼であり、彼こそが我が主様なのだから。
「時間が掛かるからゆっくりやろう。きみはここを。私はあちらに手を入れよう」
私が唖然としている間にギルバート伯爵は、手際よく葉を摘み取り、足元に落としていった。
わたしもそれに倣って葉を千切った。
病に侵された葉をあらかた片付け終えたのは、ギルバート伯爵に声を掛けられてから十日も経ってからのことだった。その間、ギルバート伯爵は毎日薔薇園へとやってきた。
わたしは我が主様――毎年一度お顔を拝見できるかどうかという雲の上の方と時間を共にした。体温が伝わるくらいに接近することもしばしばだった。
「パール。きみはここにきてどのくらい経つ」
「わたくしめは、今年で六期を迎えます」
「ほう。ではルビーと同期か」
「はい。ルビーさまはお美しい方です」
わたしの同期では、最も「妾」にちかいと目されている人物だ。おそらく今年か来年には「妾」に選ばれるのではないか、とわたしだけでなくほかの召使いたちも噂している。
「地面の葉を一か所に集めて、きょうの内に燃やしてしまおう。ちょうどあそこに古い井戸がある。あそこに葉を落として、火をつけておけば明日には燃え尽きているだろう。火事になる心配もない」
「ずいぶんとお詳しいのですね。さすがはギルバート様です」
「なに。私も仕込まれた口さ」
そこでギルバート伯爵は、初代妾のペブルさまについて語った。
「ペブルは私の幼馴染みでね。よくここでバラの手入れを手伝わされたんだ。あのコは強引なところがあってね。いつも私が連れ回されていた。私のほうが従者のようだった。いや、私たちのあいだに主従の関係はなかったんだ」
「ステキな関係ですね」
「パール。君はどうして薔薇園の仕事を? 誰かに押しつけられたのかい」
「いいえ。わたしが率先して引き受けました。ギルバート様の大切になさっている庭だとお聞きしていたので」
「そっか。ありがとう。そうなんだ。ここは私にとって大切な庭なんだ。思い出の庭さ。本当なら私はこの庭さえ残っていればほかには何もいらないのだが、そうも言っていられないのが伯爵という地位の好ましからざる点だ。おっと。私がこのような弱音を吐いていたとはほかの者たちに話してはいけないよ」
「誰にも言いません」
言いたくなどはない。
主様との密会とも呼べるこの至福の時を、ほかの者に分け与えようとは考えもしなかった。
「先代のペブルさまはどのような方だったんですか」わたしは地面の千切り葉を箒で掃きながら言った。「妾制度を発案なさったのもペブルさまだと聞きました」
わたしは格上の主君に対して、ほかの召使いの上長たちに話すように話しかけることができた。敬い奉り、憧れの対象ではあるが、それゆえにわたしの意識は未だにこのあり得ない現実を現実として見做していない節がある。緊張しない。夢の中にいるようなのだ。
「彼女はあの制度を否定するつもりでいたんだよ」ギルバート伯爵は応じた。箒に顎を載せ、「皮肉にも彼女の策によって、あの制度が定着してしまった」と目を伏した。箒の代わりになりそうな長いまつ毛が陽の光を受けて輝いて映った。
わたしは単純な疑問として、
「ペブルさまはいまも別荘にいらっしゃるのですよね」と言った。ギルバート伯爵の言い方ではまるで初代妾のペブルさまがすでにいなくなってしまったかのような響きが交って聞こえた。「ペブルさまはいまも否定なさっていらっしゃるのですか。それはどうしてでしょう」
「きみは」ギルバート伯爵はそこで切れ長の目を見開き、それから儚げに微笑なさった。「きみは、いいコだね。賢く、それでいて優しい」
「そう言っていただけてうれしいです。恐縮です。でも、わたしは召使い失格かと思います」
「どうしてそう思うんだい」
「ほかの先輩や同期や後輩たちですらみな、ギルバート様の妾になろうと毎日、じぶん磨きをしています。でもわたしは、ギルバート様に選ばれるよりも、ギルバート様のよろこんでもらうことのほうが大事に思えて。それですら、ギルバート様が笑顔になったり、はしゃいだりせずとも、ただ気持ちよく毎日の時間を過ごしてくださるだけでいいんです。太陽の匂いのするシーツのうえで毎日眠って欲しいとか、埃でくしゃみをすることのない清潔な部屋で過ごして欲しいとか。そういうことのほうが大事に思えて」
「ふむ。きみは私の妾にはなりたくはないということかな」
突きつけられてわたしは、ああそうそう、と思った。その通りだった。言われて気づいた。わたしは妾にはなりたくはないのだ。
「その顔は図星だってことかな。面白いコだね。ペブルとは違うが、どことなく似ている気もするよ。きみはペブルとどこか似ている」
「先代様とですか」
「パールさんと言ったね。きみはどうして妾制度が、妃制度ではないのかと不思議に思ったことはないかい」
「へ?」
「主君が選ぶのだから、そこは妃になるのが普通じゃないかな」
「あの、それはでも」毎年選ぶから妃ではない。本妻ではない。そういうことではないのだろうか。
「初代とて妃ではなく、妾だったわけだ。妙には思わないのかな」
きみたちは。
冷めた眼差しがわたしの心の臓を凍らせた。森の中で野生の狼に出くわしたとしても、もうすこしゆとりが残りそうなものだ。だのにわたしは全身が凍りついたように動けなくなった。
「うん。その反応が正しい。私にはきみたちが必要だが、それはけしてきみたちの幸福には寄与しない。この罪悪を抱いて生きていくよりない私もまたきっと幸福とは程遠い」
「そのようなことは」
「そうだね。このような発言は献身してくれるきみたちへの侮辱だ。申し訳なかった。訂正するよ。私は幸せだ。きみたちのお陰だ」
「光栄です」
千切った葉は井戸に落として火を灯した。どうやら空気の抜け道が横に開いているらしく、炎は渦を巻いて轟々と噴きだした。火柱が上がる。龍が呼吸をすればこのような光景ができるのではないかと思うほど、葉はよく燃えた。
「あすからは薬を撒こう。いちおう、無事な薔薇たちにも撒いておこう」
「はい」
「たぶん、前任の係の者が手を抜いたんだ。きみのせいではない」
わたしの呵責の念を見抜いたようにギルバート伯爵は言った。背伸びをし、きょうは疲れたね、と言って歩きだす。わたしはその大きな背を見送るつもりだったのだが、ギルバート伯爵は振り返り、「どうしたの。おいでよ。いっしょに夕飯を食べよう」とおっしゃった。
わたしはこの日、雲の上の存在である主君ギルバート伯爵の個人部屋で二人きりでの食事を摂った。美味しい、と口では言ったものの味はしなかった。それどころではなかった。寝室を兼ねているのか、脇にはベッドがあり、ギルバート伯爵はわたしより先に食事を終える、汗を掻いたから、と言って備え付けの浴室に入っていった。
わたしは主君のシャワーを浴びる音を聞きながら、食べたこともない豪勢な食事を堪能した。
堪能したはずなのだけれど味はしなかった。ではいったい何を堪能したのかと言えば、時間であり、空間であり、音だった。わたしは主君の匂いの漂う部屋で呼吸をし、生涯聞くことも許されぬだろう主君の沐浴の音を耳にした。
これを堪能と言わずして何を堪能と言えばよいのかをわたしは知らなかったが、しかしこれを堪能と言ってしまうとわたしの召使いとしての立場はおろか、人としての尊厳の何かしらが損なわれそうに思え、わたしは自身に芽生えた昂揚感をないものとした。けして人に知られてはならないわたしだけの感情だ。
「やあ。まだ食べていたのかい」
主君はバスタオルを腰に巻いただけの姿で現れた。主君の肉体美にわたしは、ごっくん、とニンジンを丸呑みにした。甘煮のニンジンはやはり味がしなかった。わたしの目は、城の城壁のごとくボコボコと陰影を刻んだ主君の肉体から目を逸らそうとしつつも、意識に反して釘付けになった。
「食事中に汚いものを見せてしまってすまないね。いつもの癖で着替えを用意するのを忘れてしまって」
「いつもなのですか」わたしはそこに驚いた。「わたくしどもに言っていただければご用意致しますのに」
「違うんだ。そうさせたくなくて隠れているようなものでね。この部屋に他人を入れたのは久しぶりだ」
数十年ぶりではないかな、とギルバート伯爵は言った。わたしはじぶんが特別に招かれたことに舞いあがるよりさきに苦しくなった。この恩に報いるにはこの命を差しだす以外にないのではないか、と思ったのだ。そのつもりではあるが、いざ
「それを食べたらほかのコたちにバレないように裏道から帰るといい。じつはこの城にはみなが知らない隠し通路があってね。私もたまにそこを使って庭へ息抜きに下りたりしているんだ」
「そうだったんですか」
「きみのことも本当はずっと前から知っていたよ。ひと月前だったよね、パールさんが庭師の仕事をしはじめたのは」
「はい。至らなくて申し訳ありません……。簡単な手入れしかできずに薔薇たちを病気にしてしまいました」
「気にしなくていい。きみのせいじゃない」
「前任のコにはお声掛けされなかったのですか」ふと思い立ち、言った。
「そう、だね」
ギルバート伯爵は、箪笥から寝間着を引っ張りだし、するすると羽織った。夜がそのまま布地になったようなシルクのローブだ。「できれば私はきみたちとはあまり関わりたくはないんだ。情を抱きたくないというか」
「当然な所感かと思います。身分が違いすぎますので」
「そういうことじゃないんだ。ただまあ、時々きみみたいなコが交っているとね。どうしても見ていられなくて」
「わたしのような?」
「初代妾のペブルだけは私が選んだわけじゃないんだ」
「そうなのですか」なぜ、と思ったが、それよりも脈絡がなくて当惑した。
「きみに話すようなことではないのだけどね。ただまあ。私はこの妾制度を好んではいない。できれば失くしてしまいたいのだが、そうもいかない事情があるのだね。初代の呪いというべきか。いや、彼女はむしろ率先してきみみたいなコたちのためにその身を捧げたようなものかもしれない」
「あの、ご存命ではあられないのですか」
「そうだよね。こんな単純な疑問すらきみたちは抱けないのだ。初代が妾に選ばれたのはもう何百年も前のことなんだよ。ふしぎには思わないのかい」
ギルバート伯爵はわたしたちよりもずっとお歳を召していらっしゃる。主君となるには長寿でなければならないのだ。わたしたちはこの孤島の城に連れてこられてまずギルバート伯爵にまつわる話を教えられる。
「単純な疑問とはどのようなものでしょう。教えていただければわたしもきっと抱けるようになると思います」
「きみは私以外に男を見たことはあるかい」
「いいえ。召使いはみなわたしと同じような娘ばかりですので」
「そうだろう。そして私は伯爵だ。きみたちにとっては君主でも、わたしよりも位の上の者たちはいくらでもいるのだよ。そして妾制度は、初代ペブルのあの事件を嚆矢として我々血族のあいだで膾炙してしまった。ペブルの遺志とは裏腹に、まったく真逆の用途としていまでは重宝されている」
「ギルバート様の物言いではまるで、わたしたちの存在をギルバート様は好ましく思っていないように聞こえます」
「感謝はしているよ。申し訳なくすら思う」
君主にかように哀し気な顔をさせるわたしはやはり従者失格だ。
「ご馳走様でした。もうお暇します。お休みのお邪魔になりたくはありませんので」
「おや。添い寝はしてはくれないのかい」
「ご命令とあれば致しますが、わたしが床を占めたりなどすれば、きっとお邪魔になります。わたしは寝相がよろしくありませんので」
「それは困るな。ではきょうのところは諦めるとしよう」
わたしは椅子から下りて、食器を片づけようとした。「それはそのままでいいよ」とギルバート伯爵が言うので手を止めた。「よいのですか」
「ああ。それは別荘の料理人に作ってもらったもので、きみたちとは管轄が違うんだ」
「そうでしたか」道理で見たことのない食器だと思った。「そうでした。薔薇園についてですが、あすの薬剤撒きにはほかの者たちにもお声掛けをして手伝わせましょうか」
「ほかの者たちに?」
「二人でするよりも手分けをしたほうが早いと思いまして。葉摘みのときに閃けばよかったのですが、頭が回りませんでした。至らずにすみません」
「そんなことはないよ。薔薇園はそれこそ私の娯楽だ。本来はきみたちの手を煩わせるほどの仕事じゃないんだ。私のほうが頼んでやってもらっているようなものだから。そうそう。私の息抜きでもあるんだ。時間が許すのなら私がじかに手入れをしたいくらいでね」
「そうだったのですね」
「だからあすもきみと二人だけで大丈夫だよ。ありがとう」
「いえ。時間はあるので、ギルバート伯爵がそれでよろしいのであればわたくしもそれがよろしいと思います」
「ではあすもお願いしますね」
「はい。楽しみにしています」
お辞儀をして扉の外に出ようとすると、待て待て、とギルバート伯爵に止められた。腕を引かれ、ふんわりと背に手が回される。伯爵の体温がローブ越しに伝わった。伯爵からは石鹸のよい香りがした。
「そっちじゃないよ。裏道はここだ」ギルバート伯爵は箪笥の横の壁に触れた。
壁には紋様が描かれていた。赤い薔薇の細かな紋様の中で一つだけ青い薔薇があった。そこを伯爵は指で押した。
すると壁に亀裂が走った。亀裂は刹那に扉の縁の形に広がった。
「さっ。ここを明かりに沿って歩いていけばこの時間帯ならばきみの宿舎のどこかには出る。怖くなったら適当に隙間を覗いてごらん。見知った場所が見えるはずだよ」
「大丈夫でしょうか。すこし怖いです」
「なら送っていこう」
そう言ってギルバート伯爵は自ら隠し扉を潜って、裏道に入った。手招きするので、わたしは唯々諾々と差しだされたその手を握った。
裏道は城の至る箇所に通じているようだった。正規の道の明かりが壁越しに漏れているので足元が見える程度には明るい。隙間を覗くと城内の廊下や室内が見えた。
「伯爵はいつもこうして城の中を見て回っているのですか」わたしたちの会話は筒抜けだったのではないか、と不安になった。聞かれて困る会話はしていないが、それでも君主に聞かせられるようなしゃべり方ではないこともままある。
「たまにね。目的はあくまで近道と姿を見られずに逃げ出すためのものだから」
「逃げだす……」
「職務からね。これでも忙しいんだ」
「とてもそうは見えませんでしたが」正直な旨が口を衝いたのは、まさにそのように言って欲しそうに映ったからだ。
「うん。一日を一区切りとすればたしかに忙しくはないかもしれない。私たちときみたちとでは時間感覚が違うから」
「時間感覚……ですか」
「きみが気にすることではないよ。きみたちはそういうことに違和感を覚えないように教育されているわけだから。それがしぜんな反応だ」
「教育……」
「おっと。そろそろじゃないかな。そこを覗いてごらん」
促されて壁から漏れる明かりに顔を近づける。壁には隙間が開いており、そこからは見知った城内の一画が見えた。
「ここ、伯爵の銅像があるところです」
「そうそう。裏側のところが隠し扉になっているんだ。裏側からだと押せばすぐ出られるよ。入る分にはコツがいるから、こんど明るいときに説明してあげよう」
「はい。ありがとうございました」
「ではまた明日。よい夢を見てね。おやすみなさい」
「おやすみなさいませギルバート様」
わたしは伯爵に見送られ、城内の銅像の裏に出た。
壁に埋め込まれたように銅像は建っている。銅像は壁とすっかり接触してはおらず隙間が開いている。ほかにもこの手の銅像が城内にはあちらこちらにあるのだ。ひょっとしたらおおむねの銅像の裏側には隠し扉があるのかもしれない。
わたしは歩き慣れた廊下を辿って、自室に帰還した。
シャワーを浴び、着替え、髪を梳かしもせずに床に横になると融けるように眠りに落ちた。
翌日、わたしは朝いちばんで薔薇園に向かおうとした。しかし途中で、同期生のルビーに呼び止められた。「パールさん、ごきげんよう」
「ルビーさん、おはようございます」
「お早いですね。もうお仕事ですの。慌ててどちらへ?」
「薔薇園です。薔薇たちが病に罹ってしまって、いまはその治療を」
「あらあら。それはたいへんですね。ギルバート様の大事なお庭を損なってしまったのですね」
「ああ、はい。そうかもです」
「かも?」
「いえ、そうです。損なってしまいました」
「その割にずいぶんとうれしそうな顔をしていましたけど」
「そうでしょうか。いえ、そうかもです」
「かも?」
「嬉々としていました。すみません。気を引き締めて職務に臨みます。もう行ってもよろしいですか。薔薇たちにきょうはオクスリを撒く日なので」
「そう。いっそあなたにもオクスリを差し上げたいくらいだわ」
「あればわたしも欲しいです」
「皮肉も通じないのね」
「心配してくださりありがとうございました」
「礼には及ばないわ。たとえ相手がパールさんであろうとも、あたしくしは同期の尻拭いをする立場にあるんですもの。何か困ったことがあったら言ってちょうだい。なんとかしてあげる」
「本当ですか。わあ、うれしいです。では一つお願いしてもよろしいですか」
「厚かましいわね。でもいいわ。パールさんのお願いを聞いてもあたくしには何の得もないのだけれど、それでもあたくしは優しいので聞いてあげる」
「さすがはルビーさんです。じつはわたし、妾制度のことをちゃんと勉強したいと思っていまして、時期妾候補と名高いルビーさんならきっと過去の歴代妾の方々のことにもお詳しいはずですし、よければ資料か何かをお見せしてくださいませんか」
「あら、殊勝なお心持ちですわね。ではパールさんも妾になるべくあたくしと切磋琢磨したいとおっしゃるの」
「いいえ。わたしは妾にはなれません。選ばれたいとも思いません。ルビーさんのほうがよほど妾にふさわしいですから、是非ともルビーさんに妾になって欲しいと望んでいるくらいです」
「あら、張り合いがないわね。でもそういうあなたの分を弁えた態度は嫌いじゃないわ。潔いのって好きよ。ええいいわ。妾制度がなんたるか、その歴史にまつわる書物をお貸ししてあげる」
「ありがとうございます」
「その代わりと言うつもりはないのですけれど、もしよろしければ薔薇園から一輪で構いません、薔薇を戴けないからしら」
「薔薇ですか。構いませんよ」
「ギルバート様が好いたという薔薇をあたくしも一度くらいは直に目にしておきたいの」
「ああでしたら」わたしは宙に視線を漂わせる。「いっそ、薔薇園にこられてはいかがですか。ギルバート伯爵がそこにいるとはいまここで打ち明けるわけにはいかないが、もし一緒に来て偶然に鉢合わせしてしまうのならこれは問題ないように思えた。ギルバート伯爵のほうでわたし以外に会いたくないと判断したならばきっと隠れたままでいるはずだ。
「いやよ。あすこ、なんだか不気味なんですもの」
「はあ。そうですか」
「書物はあなたの部屋にほかの者に頼んで届けさせるわね。引き留めてしまってごめんあそばせ。お仕事頑張ってちょうだいな」
「はい。ルビーさんも、早く妾に選ばられるとよいですね」
「ええ。そのつもりよ」
ルビーは切れ目のない髪の毛を翻して遠ざかっていった。彼女の髪の毛はまるで昨晩目にしたギルバート伯爵のローブのように上品だ。所作一つとっても歩くときに極細の平均台の上を歩くような軸のブレなさある。隙がない。美の極致とは彼女のようなことを言うのだろう、と造形の美しさにわたしは感嘆の息を漏らす。
ギルバート伯爵の妾としてまさに目を掛けられるにはあれくらいの美がいるはずだ。わたしには到底縁のない話だ。
薔薇園へと赴くとすでにギルバート伯爵が水撒きをしていた。
「おはようパールさん。薬を水に溶かしておいたから。水やりと一緒くたにして済ましてしまおう」
「遅れてすみません。同期の方と立ち話をしてしまって」
「いいよ、いいよ。それならもっとゆっくり話してきてもよかったのに。きみの友達は何も薔薇たちだけではないのだろう。私と違ってきみには友達が多そうだ」
「は、はい」
返事に困った。わたしには友達と言える友達がいない。いいや、わたしはかってに友人と思っているが、どうやら相手はわたしを友人とは見做していないらしい。そういうことが多々あった。いまもそうだ。わたしはギルバート伯爵にとっては友人ではないのだ。当たり前の話ではあるが、身分の差を感じなくもなかったので、わたしはややもすると主君に対して親しみの念を覚えていたのかもしれない。
薬剤散布の作業はわたしが思っていたよりもすんなり終わった。病気の葉を毟り取る作業のほうがよほど時間がかかった。
「半日で終わったね。よかった」
「はい」
「ときどき肥料にも同じ薬を混ぜて撒いておくと、予防にもなるから」
「そうします」
「パールさん。きみみたいなコが薔薇園の管理者になってくれて私もうれしい。ありがとうございますね」
「そ、そんな」
薔薇たちを病気にしてしまった上、ろくに対処法も知らなかったわたしが掛けられてよい言葉ではなかった。舌を噛んで自害してしまおうか、と素で思った。
「舌を噛んで自害しようとか考えていないだろうね」
「い、いえ」
「ふふ。判りやすいコだね。面白いコだよ。退屈しない」
わたしは恥ずかしくなった。感情の乱れが面に出ないようにするほかに対処のしようがない。
てっきりわたしはこの日を境にギルバート伯爵は薔薇園には現れなくなると思っていた。けれどそれ以降もことあるごとにギルバート伯爵は薔薇園にやってきて、新しい薔薇の苗や種を持ってきてはわたしに手渡した。
「好きに植えてみて。この薔薇園の模様替えをしよう。パールさんの痕跡を残すんだ」
「そんな滅相もございません」
「でも残すんだ。それがきみの仕事だよ。管理者として職務を全うするんだ」
「ですが」
「お、意見があるんだね。いいね言ってみて」
「それでは先代のペブルさまに申し訳が立たないのではないかと」
「ああ、そういうことか。どうだろうね。でもたぶんだけど、ペブルもそのほうが喜ぶさ。パールさんの好きに庭を育てて欲しいと思っていると私は思うよ」
そのとき遠くの空を見詰めたギルバート伯爵の眼差しは、冬の到来を報せる凍てついた風の下にあって、真夏の木漏れ日のごとく温かさに溢れていた。
妾選抜の儀は年を越した最初の大掃除の後に執り行われる。年末になると、同期の召使いたちはみなそわそわとしだした。最後の得点稼ぎに勤しむべく、いかに美しい振る舞いを取れるのかと「じぶん」という存在から汚点や欠点を削ぎ落とそうと日夜自分磨きをしている。こそぎ落とされた汚点や欠点とて、美しい花を咲かせる養分になるのに。わたしは同期たちの忙しない姿を尻目に、独り寒空の下で薔薇たちに肥料をやった。
冬の薔薇園は雪のごとく白い種が咲き誇る。
わたしは毎日のように薔薇たちに話しかけに庭を訪れ、ときおりやってくるギルバート伯爵と戯れの時間を過ごした。伯爵との会話はもっぱら薔薇にまつわる話で、薔薇園の過去の話もよく話題に上った。
「ペブルは元々、庭師の子でね。城の召使いですらなかったんだ」
「そうだったんですね」
「私がペブルに懐いてしまってね」
「逆ではないのですか」庭師の子が城主の子に懐いたならば話は分かる。
「立場は完全に反対だった。私は存外、泣き虫でね。よく父上や母上、それから教育係たちに叱られては、城中を逃げ回っていた。どこもかしこも父上や母上の味方ばかりでね。私には居場所がなかった」
ここ以外には。
そう言ってギルバート伯爵は染み一つない背広のまま地面に寝転んだ。「いい天気だね。ずっとこのまま寝転んでいたい」
わたしはその様子を立ったままで視界に入れていたが、
「きみも寝転んでごらん。気持ちがいいよ」
と言われて、試しに仰向けに地面に身体を横たえた。青空の海を雲が船のように泳いでいる。だんだんと雲が動いているのか、じぶんが大地ごと動いているのか分からなくなる。
「眠くなっちゃいますね」
「ああ。本当に」
「ギルバート様は、どうして妾を選ばれるのですか」口を衝いていた。単なる疑問だった。あれほど初代妾のペブル様を慕っているのに、なぜほかの妾まで所望されるのか。わたしはそれがふしぎだった。
「きみには正直でありたい。だから答える」一拍の間のあとで彼は言った。「妾を選ばねば私たちは生きていかれないからだ」
「お子様が必要、ということですか」子だくさんを目指しているのだろうか。そう思った。
「いいや。私たち血族には繁殖という概念がない。血分があるだけだ。と言ってもパールさんには分からないだろうけど」
「すみません」
「いいんだ。分からないほうがよいこともこの世にはある。パールさんは城の外に出たいと思ったことはあるかい」
「城の外にですか」
「ああ。自由になりたいとは思わない?」
「自由……わたしは自由ではないのですか」
「うん。そうだね。きみたちはそのように考えるように、疑問を抱かぬようにと枷を嵌められている。手枷のように。それとも足枷のように」
「ギルバート様はわたしが自由を求めたほうがうれしいですか」
「うれしいような、そうでもないよう。いいんだ。パールさんはそのままで。変わるべきは本当は私たちのほうなのだから。でもきっとそうそう容易く変われるようなものでもないのだろう。パールさんはずっとそのままでいてね」
「わたしはたぶん、変わろうと思っても上手に変われません。わたしはずっとわたしなので」
ギルバート伯爵は目を瞑ったのか、間もなくして寝息を立てはじめた。衣擦れのような微かな響きが、わたしにも微睡の風をもたらした。わたしは風に揺蕩うハンカチのようにうとうとと現から夢へと落ちていく。
夢の中でわたしは本を読んでいた。
それは実際に毎晩目を通していた妾制度の歴史にまつわる書物だった。同期のルビーさんが貸してくれた本で、そこにはギルバート伯爵の語ったように歴代の妾たちの名前がずらりと数百年分並んでいた。総勢で数百を超す妾がこれまでに生まれては、別荘へと移った。
いまも息災でいらっしゃるのだろうか。
わたしは書物に目を通し、そこに歴代妾たちの一切のその後の来歴が記されていないことに一抹の不安を幻視した。
妾として抜擢され別荘へと移った者たちは、幸せに暮らしている。
わたしたち召使いはそうと信じ込んでいるだけれど、それはどこまで確かな知見の元に認定された事実であろうか。
本の、とある項に目を留める。夢の中の出来事だけれど、これはすでに体験した記憶の再現なのだとわたしには判った。
妾制度発端となった事件について書かれている。
初代妾となったペブルは、その年、「晩餐会」の代わりに「妾制度」の発案を行った、とある。
初代妾のペブルは、自らギルバート伯爵の贄血となることを宣言したのだそうだ。
ペブルが宣言した贄血とは、妾制度ができる以前に、ギルバート伯爵の親族たちのあいだで罷り通っていた「晩餐会」における大役のことだという。召使いたちは毎年、ギルバート一族の「晩餐会」の贄血として、大役を一同に任されていたそうだ。
それを初代妾となったペブルが、大役を一年に一人のみに限定した。自ら贄血を引き受けることで、そのような新しい制度を確立したのだという。
わたしは夢の中で、その場面の目撃者となる。
豪勢な食事の並ぶ宴会場にて、初代妾ことギルバート伯爵の幼馴染のペブルさまが、扉を開け放ち、そこここに並ぶ贄血なる大役に抜擢された召使たちのまえに立つ。そして何かを言うのだ。
その形相は、怒りに燃えており。
その立ち姿は、勇猛にして果敢だ。
ギルバート伯爵はそのころきっとまだ伯爵ではなく、みなから祝われる立場でありながら、誰よりも目上の者たちを労い、敬い、献身する立場であっただろう。
ギルバート伯爵がそうであったように、ペブルさまを慕う者はすくなくなかったはずだ。召使いたちは、召使いでもないのに大役を引き受けると言いだしたペブルさまをどう思っただろう。
せっかくの機会を奪われたと思っただろうか。
それとも、ペブルさまの言葉に何かを思い、大役を下りるだけに留まらず、ペブルさまに大役ごと何かを譲ろうとしただろうか。委ねようとしたのだろうか。
分からない。
いったいそのとき何があったのか。
贄血とは何で、晩餐会はその後になぜなくなったのか。
どうして妾制度が代わりに設立されたのか。
ぶるる、とわたしが身体を震わせると身体にはらりと温かい膜が張った。目を開けると、ギルバート伯爵がわたしの身体に上着を掛けているところだった。
「おや。起こしてしまったかな」
「寝てました」
「もう日が暮れてきたよ。寒いから戻ろう。きょうは私の部屋でお茶を淹れてあげるよ」
数回に一度は、こうしてわたしはギルバート伯爵の個人部屋に招待された。これはおそらく、とわたしは見抜いている。どうあってもわたしが妾に選ばれることはなく、候補にもならないからこその優遇なのだと。仮に特別扱いしたところで、野良猫に施すミルクのような扱いにすぎないのだとわたしは自覚していた。
主君の施しを受けるのも召使いの役割の一つだろうと思い、拒まずに甘受している。
暖かい室内でお茶を啜る。召使いのわたしがすべきことなのに、ここではギルバート伯爵がお茶を淹れてくれる。わたしはじっと椅子に座っていることが役目なのだ。主君にそのように徹しよ、と命じられてしまえばわたしごときが逆らう真似はできない。
「パールさんはここではお人形さんと同じだから」そう言ってギルバート伯爵はおままごとをして遊ぶ幼少組みの召使いたちのように、殊更わたしを甘やかすのだった。
「このお菓子、美味しいです」
「口に合うならよかった。親戚の侯爵のお土産でね。いま人間たちのあいだではそのクッキーが人気らしい」
「人間たちのあいだでは?」
「ああいや。言葉の綾さ」
「贄血とはなんですか」わたしはぽつりと口にしていた。ギルバート伯爵が椅子に腰かけようとしていて、一瞬動きが止まった。そのまま椅子に座ると彼は両手を祈るように組んで、その上に顎を載せた。「どこでその言葉を?」
「はい。同期のコに本を貸していただいて。妾制度についての本です。歴史の」
「勉強熱心だね。パールさんも妾になりたくなったのかな」
「いえ、そういうことでは」
「うん。あれは、みなが思うような素晴らしいものではないよ。だから、みながこぞって目指したくなるような装飾を施している。そうしないと明日にでも妾の担い手はいなくなる。候補すら見繕えずに、私たちは途方に暮れて、以前のような【晩餐会】を開くこととなる」
「その晩餐会は、どうしていまはなくなったのですか。妾制度とはどう関係があったのでしょう」
「本にはなんと書いてあったんだい」
わたしはギルバート伯爵に読んだ本の内容を掻い摘んで話した。
初代妾のペブルが晩餐会に乗り込んだ話だ。
「まあ、嘘は書いていないか」ギルバート伯爵は紅茶のお代わりをわたしのカップに注いだ。長テーブルの端に、わたしと伯爵が直角を描いている。交わるようで交わらぬ最短にして最小の距離だ。「晩餐会は、我らが一族の闘争の場だよ。命を繋ぐために、一族総出で、最も立場の弱い領地に出向き、その庭に集った果実を根こそぎ喰らい尽くす。しかしそのために、いつだって一族内での闘争が絶えず、できるだけ果実を多く収穫しようと、不要な果実の乱獲が盛んに行われた」
「果実とはどういうものなのですか」どんな樹に生るのか、と気になった。いまの技術ならば栽培できるのではないか、とわたしは考えた。
「そうではない。そうではないんだ。私はいまでこそ伯爵の身分だが、当時は父上も母上も、男爵の地位でね。言ったら、最も【晩餐会】の舞台になりやすかった立場だった。私がいま伯爵なのも、初代妾となったペブルのお陰だ」
「晩餐会ではきっとたくさんのお食事が必要だったのでしょうね。取りやめて正解だったと思います」わたしにはそれくらいの慰めしか言えなかった。「ペブルさんはきっと生き物の命を大切にしましょう、と言いたかったんだと思います」
ギルバート伯爵はそこでカップをテーブルに置いた。中身が零れた。手が震えている。空いたほうの手で目元を覆っていた。
「どうされたのですか」
「なんでもないよ」そう言葉で言いながらも伯爵の声は震えていた。手の震えがそのまま声にまで伝わったかのようだ。
しばらくギルバート伯爵は目元を押さえたきり声を発しなかった。
わたしはじっと伯爵を見守った。
カップに添えられた手が震えていて、あたかも凍えて見えたのでわたしはその手におそるおそる触れた。
冷たかった。まるで冬の土のように。
「パールさんは温かいね。まるで夏の土のようだ」
わたしの胸中に湧いた所感と似た返事に、わたしはくすりと笑った。
「笑ったね」ギルバート伯爵は深呼吸をすると、ようやく目元から手をどけて、わたしたちのあいだに漂った沈黙を誤魔化すように背伸びをした。「やれやれ。むかし話は湿っぽくなっていけない。パールさんとはもっと未来について語りたいよ。そうそう。アリス婦長はお元気かい」
アリス婦長とは、召使いの中でも最古にあたる方だ。わたしたちの親のような存在だ。
「はい。矍鑠とされています。現場仕事からは引退されていますが、後継の育成に力を注いでいらっしゃいます。そう言えば、アリス婦長は一度も妾制度に候補にもならなかったようですね」
「ああ、そうなんだ。でもアリス婦長のような方が残っていなくてはきみたちも困るだろう」
「そう、ですね」
「ああいう方は妾にはもったいない」
「きっとそれを聞いたらお喜びになられると思います」
「だといいけどね。あの人のことだから、嘘おっしゃい、の一言で一蹴されるのがオチさ」
「おっしゃりそうですね」想像するのが容易かった。
「ペブルはね。ああいうアリス婦長やパールさん、きみみたいなコたちのために、【晩餐会】を阻止しようとしたんだ。召使いでもない、単なる庭師の子供だった癖にね。そのころから断絶されていた他所の城地とほかの区域の人間たちまで巻き込んで」
「ギルバート様?」
「飢饉さえ起こらなければきっとペブルの狙い通りに事が運んだのかもしれないのに。けっきょく、人間たちのほうでも飢饉であぶれた子どもたちを口減らしに捨てざるを得なくなった。そうした子どもたちを引き受ける代わりに、私たち一族は、人間たちの里に、家畜や食料の種や苗を贈った。ここに妾制度の礎が築かれた。私たち一族のあいだの位による不公平さも、妾制度によって、各々の城から毎年一人の妾を選ぶことで、【晩餐会】を開くことなく贄血を賄えるようになった。順繰り巡る回路がこうして築かれた。里から子どもたちが各地の城へと渡り、子どもたちを教育しながら私たちは人間たちにとっての食料を、各地から搔き集め、ときに城内で栽培し、配る。私たちは一年に一度の【贄血】を摂れれば、あとは人間たちと似たような食事を摂るだけでも生きながらえる分には充分だ。各地の里を滅ぼさず、永続的に生存を可能とする妾制度はこうして完成し、いまに至る」
「すみません。むつかしい話で、よく分かりませんでした。それではまるで妾が、食材か何かのように聞こえます」
沈黙が部屋を満たした。風が窓を叩き、反響音が部屋の隅の気温の低い箇所を浮き上がらせるようだった。
「冷えるね。暖炉の火をもうすこし強くしよう」伯爵は暖炉に薪をくべた。
この日は食事を摂るとわたしは、二十一時を回る前に隠し通路を通って自室に戻った。このころにはもう伯爵は見送りについてくることはなくなった。わたしのほうでも自在に隠し通路を行き来できるようになった。
年末は雪が積もり、薔薇園でのわたしの仕事は雪掻きが主な内容となった。けれどこれは、ギルバート伯爵の案で、薔薇たちに傘をつける工夫により、雪掻きをせずに済むようになった。
わたしは年末年始をゆっくり過ごせた。その間、ギルバート伯爵と会う機会はなかった。薔薇園で会わなければわたしと伯爵とのあいだに接点はあってないようなものだった。この状況が本来なのだ。わたしはシンシンと積もる雪を窓越しに眺めながら、束の間の休暇を満喫した。
年が明けても、わたしのすることは限られる。肥料の準備と、傘の上に積もった雪下ろしくらいがせいぜいだ。雪融けの訪れを待つよりない。
わたしは大掃除の手伝いに駆りだされ、半年ぶりに騒がしい場所で作業をした。ほかの召使いたちに交じって働くのはたいへんだが、新鮮でもあった。知らない顔も多く、みな与えられた仕事に一生懸命に取り組んでいる。
わたしはじぶんの領分を越えて作業をしてしまうので、注意を受けるし、顰蹙を買う。そのたびに、一足先に終わった分をぼうっとして過ごしていると、やはりそこでも叱られるのだった。
「ちょっとパールさん。あなただけサボって、みなに申し訳ないとは思わないの」
「すみません。ですがわたしの分は終わってしまったので」
「ならほかのコたちを手伝ってあげたらどうなの」
「そうしたつもりなのですが、迷惑だと怒られてしまって」
「あなたって何をやらせてもどんくさいのね」
「どんくさくてごめんなさい」
仕方がないのでわたしは、最も作業の遅れているコの手伝いに回った。さすがに最も出遅れているコは、わたしの手伝いを黙って受け入れてくれた。感謝もないが、かといって追いだされる真似もされなかった。
みなカリカリしている。
きっと妾選別の儀が近いせいだ。
わたしはできるだけ目立たぬよう、みなを刺激しないように静かに過ごした。
そしていよいよ妾選別の儀の日。
わたしは風邪を引いて体調を崩した。せっかくの妾選抜の儀に参加できなかった。どの道、わたしが選ばれることはないので難はないが、誰が選ばれたのか、ギルバート伯爵がどんな顔で召使いたちのなかから妾を選ぶのかを見られないのは残念に思った。
城内にある教会にて妾選抜の儀は開かれた。それはそれは神聖で荘厳な儀式となる。一年に一度ということもあり、わたしたち召使いたちにとっては楽しみの一つだ。それを見逃したとなれば、やはり尾を引くものがある。
咳を耐えながらわたしは、床の上で窓の外に舞う雪が徐々に雨になっていく様を眺めた。きっとこれが最後の雪になるのだろうと予感しながら。
もうすぐ春がやってくる。
夜になるころに、同期の召使いが見舞いにきてくれた。アリス婦長に頼まれたそうだ。そのときにわたしは知った。
今年選ばれた妾は、ルビーだった。
わたしの同期から妾が出たのは初めてのことで、じぶんのことではないのに喜ばしく、鼻がすこしだけ高くなった心地がした。
寝返りを打ったところで、ルビーにお別れの挨拶を言えなかったことに思い至った。でもルビーのほうではわたしの言葉など霞んでしまうほどの祝いの言葉をいくらでも掛けられるだろう。むしろわたしの言葉で晴れ舞台に泥を塗らずに済んだだけよかったのではないか。
こうして遠くから祝うくらいがちょうどよい気がした。
ルビーおめでとう。
おめでとうルビー。
しばらくはギルバート伯爵とも会えない日々がつづくだろう。別荘地にてルビーと伯爵が仲睦まじく暮らしている姿を想像し、暖かく満ち足りた心地に浸った。わたしはそこにいなくていい。むしろ、伯爵にはもっと薔薇のような存在と共に暮らして欲しい。時間がもったいない。わたしに割く時間は、もったいない。
あとで聞いた話だと、ルビーは妾発表のときに薔薇を一輪胸に挿していたそうだ。わたしが頼まれて薔薇をあげたのはずいぶん前のことだから、きっと誰かに頼んで薔薇園から捥ぎ取ってきてもらったのだろう。わたしに一声なかったのは、何らかの配慮なのか、それとも契機の問題だったのか。いずれにせよルビーは、わたしが手塩にかけて育てた薔薇を胸に、妾となって、わたしとは別の世界の住人として旅立ったのだ。
もう二度と会うことはない。
ギルバート伯爵と同じ、雲の上の存在となったのだ。
おめでとう、とわたしはもういちど念じた。
雪が融けてから薔薇園の管理の仕事を再開した。きっとわたしは一生死ぬまでこの仕事をつづけるのだろう。そう予感しはじめていた。
ギルバート伯爵が薔薇園に現れたのは、仕事を再開しはじめてから三日と経たぬ間のことだった。
「やあ、パールさん。元気だったかな。薔薇たちはどうだろう。冬を無事に越せたかな」
「ご無沙汰しておりますギルバート様。薔薇たちは元気です。傘のお陰で難なく春を迎えられたようですよ。ギルバート様のほうこそ、よいのですか。妾をお迎えになられたばかりではありませんか」
「うん。そうなんだ。そう言えば、儀式の場にパールさんの姿がなかったように思えたのだけれど」
「はい。風邪で寝込んでおりました」
「なんと。知らなかったな。お見舞いに行けたらよかったのに」
「そんな滅相もございません」
「きょうは薬剤入りの水を撒いて早めにあがろう。剪定作業はもうすこし暖かくなってからでもいいだろうし」
「はい」
ギルバート伯爵の言うように薬剤を溶かした水を撒いてこの日は仕事完了とした。とはいえ薔薇園は広い。伯爵と手分けをしても、朝からつづけて十五時まで掛かった。貯水槽にあらかじめ薬剤を溶かしていたので半日で済んだが、本来ならばこれは三日掛かりの仕事だ。わたし一人ならば一週間はかかる。ギルバート伯爵の手腕と工夫あってこその短縮だ。
「お疲れ様。今年もよろしくお願いしますね」いつもの部屋に移動して、紅茶で乾杯をした。すこし遅い新年会だ。
「はい。こちらこそよろしくお願いいたします。ギルバート様もお忙しいのに、お手伝いまでしていただいて。召使いの分際で恐悦至極です。幸甚の至りです」
「パールさんは言葉が硬いな。もう私ときみの仲じゃないか」
「どういう仲なのか分かり兼ねます」正直な所感だ。
「そうだな。主従の範疇でくくれない、単なる個と個の関係かな」
個と個の関係。
考えてみたが、よく分からなかった。この事実一つとってもも、ギルバート伯爵とわたしのあいだには越えられない深い溝があるように思えた。
「ルビーさんはほかの妾の方々と仲良くできているでしょうか」わたしは同期のよしみで心配した。「ルビーさんは負けず嫌いなところがありますから、打ち解けるのに時間がかかるのでは、とすこし気にしています」
「パールさんは優しいね。でも大丈夫だよ。ルビーさんも……そう、ほかの妾のコたちのように上手に【打ち解けよう】としているところだから」
「それはよかったです」
「そうだ。きょうは新しいデザートがあってね。ちょっと待っておいで。いま取ってくるから」
わざわざギルバート伯爵が取りに行かずとも、と思ったけれど、そこは事情があるのだろうと思うことにした。たとえば、本当はかってに食べたらいけないのだが、ギルバート伯爵がわたしに食べさせようと思い隠していたのかもしれない。
「子どもみたいな方」
「ん。何か聞こえたな」扉を開けて伯爵は言った。「すぐに戻るよ。紅茶とクッキーでお腹いっぱいにしないこと」
「はぁい」甘い返事が喉から出た。じぶんでも驚くほどの変化が、この間にあったのだと知った。
ギルバート伯爵が部屋から消えた。
しんと静まり返った部屋でわたしはお人形さんらしくじっとしていた。
するとどうだろう。
風の音の狭間に、妙な声が交って聞こえた。人間の声だ。すすり泣き、呻き声、それとも悲鳴。よく分からない。言葉ではないが、何かが声を立てている。大きいかと思ったら小さく、繁殖期の猫の鳴き声のようでもある。
わたしはそわそわとして落ち着かなくなった。
どことなく聞き覚えのある声に聞こえたからだ。しかしそんなはずはない。彼女はそんな声を出したりしない。高潔で誇りを胸に生きていた。彼女なはずはない。
しかしわたしはそれを否定しきれなかった。
椅子から腰を上げ、扉に近づく。
意を決して取っ手を握り、右にひねった。きぃ、と小さな音を立てて扉が隙間を広げる。
顔を差しこみ、扉の奥を覗きこんだ。廊下だ。わたしたち召使いたちの居住区のある区画とは違い、全面が石造りの空間だった。
呻き声はいっそうハッキリとわたしの耳に届いた。どうやら隣の部屋らしい。そこに誰かがいるのだ。
わたしはギルバート伯爵からの言葉を思いだし、きょうはまだ「扉の外に出るな、じっとしていろ」と命じられていないことをよくよく確かめてから、一歩足を踏みだした。
隣の部屋の扉は思ったよりも遠かった。三十歩は歩いた。
扉のまえに立ち、しばらく耳を澄ました。やはり中に誰かいる。すすり泣き、呻き、悲鳴している者がいる。一人だろうか。二人以上いるようには思えなかった。
鍵が掛かっているだろうと思って取っ手を捻ったが、案に相違して扉は難なく開いた。
わたしは隙間に身を滑りこませるようにして部屋の中に入った。
薄暗い室内はじめっとしていた。わたしがいたギルバート伯爵の部屋とは大違いだ。
声は、部屋の奥の一画から響いていた。窓には目張りがされており、月明かりも届かない。
明かりは廊下から差しこむ松明の火のみで、それも扉の隙間からかろうじて部屋の中に影の濃淡を浮かび上がらせる程度だった。
わたしは呻き声の主のいる場所まで歩を進めた。
そして、ひょっとして、と思っていたそこにいるだろう者の名を呼んだ。
「ルビー……さん?」
途端。
声の主は暗闇に沈んだまま、言葉にならぬ慟哭を吠えた。獣と聞き紛うほどの激しい声量にわたしはその場で尻餅をついた。
尻を引きずるように後退し、そして部屋を後にした。
獣のごとき慟哭の狭間に、鎖のジャラジャラと擦れる音が反響していた。鼻には鉄の臭いがびっしりとカビのごとく膜を張った。
わたしはギルバート伯爵の部屋に戻った。
明るい室内に、清潔な家具たち。
仄かな石鹸の匂いは、ギルバート伯爵の体から立ち昇る香りと似ていた。
わたしは椅子に腰かけ、それからいましがた体験したことをどう解釈すべきか考えた。隣の部屋には誰かが囚われている。
ギルバート伯爵に言えば助けてもらえるだろうか。けれど伯爵がそのことを知らないはずもない。ではあれは伯爵の指示によるものか。
なぜかような非道を働くのか。
眩暈を覚え、わたしは眉間を揉むようにした。
それから手のひらを見詰め、そこが真っ黒に染まっていることに気づいた。
「お待たせ、パールさん。おとなしく待っていたかな」
ギルバート伯爵が両手にお盆を抱えて現れた。扉を器用に腰で閉め、にこやかにわたしの元までやってくる。距離が縮まるほどに彼の表情は雲っていった。
わたしは彼を見上げ、彼はわたしを見下ろしている。
「どうしたんだい、その手」
お盆を置くと彼は心配そうにわたしの手を丹念に確かめた。血だと思ったのだろう。だがそれはわたしの血ではない。
わたしが怪我をしていないと判ると彼は息を吐き、それからわたしの全身に目を配った。わたしもそこで遅まきながら、じぶんの衣服が汚れていることに気づいた。地面に尻餅を着き、引きずったからだろう。服は臀部に掛けて真っ黒な染みができていた。いまなお、ぽたりぽたりと床に雫を落としている。粘着質な雫だった。
「そっか。見てしまったんだね」ギルバート伯爵は眉を八の字に寄せた。
「お叱りになられないのですか」
「パールさんがわるいわけではないから」
「あすこにおられるのはルビーさんですか」
「ああ」
「妾様になられたのに、なぜ?」
なぜあのような酷い扱いを受けるのか、とわたしは不思議だった。
「妾だからだよ。妾とは、私たち血族を生き永らえさせるための贄であり、血だ。ああして一年間、死なぬようにしながら私たちは妾から血を啜る。逃げられぬように手足を落とし、その落とした手足とて私たちはご馳走と見做して食べてしまう。きみたちにとっては化物そのものだ」
「そう、だったのですね」わたしは伯爵の言葉を素直に受け取った。跪き、懺悔をするかのような伯爵の姿があまりに惨めで愛おしく映ったからかもしれない。
「怒らないのかい」
「どうして?」
「私たちはずっときみたちを騙しつづけてきたんだ。命を差しだすことになる大役を、さもお姫さま候補を見繕うかのように偽装して。怒るのが当然だよ」
「そうは思いません。わたしたちはギルバート様に命を捧げている身です。たとえそれが言葉通りに命を捧げることになろうとも、それがギルバート様のためになるのならば本望です」
「それはね、パールさん。パールさんがまだ、妾に訪れる悲惨な末路を体験していないから言えることだよ」ギルバート伯爵はそこで初めてわたしに怒気にも似た声音を浴びせた。怒りを押し留めるようなこもった響きは、却ってわたしに伯爵への忠誠を固く結晶させるひとつまみの塩となった。
「ギルバート様が妾に訪れる末路を快く思っていらっしゃらないこと、そのお気持ち一つでわたしたちは救われるように思います」
「それは間違っているよ。それは間違った気持ちだ」
「ですが、そのようにわたしたちは教育をされているのでしょう? ならばそのように考えるのもまた当然のことかと存じます」
「私はできればきみたちにあんな目に遭って欲しくはない。私一人の命を投げ出して終わらせることができるのならいつでもこの身を捧げよう。しかし、私だけの問題ではないのだ。私がいなくなればこの城の召使いたちはほかの地の血族の肥しとなるだろう。晩餐会が再び復古してもおかしくはない。なれば私はそうならぬようにと采配を揮う役目から下りるわけにはいかない。せめてその間、パールさんやアリス婦長のようなコたちを妾にせぬように尽力するよりない。せいぜいがその程度の力しか私にはないのだ」
「苦しんでおられるのですね。苦しいのですね」
「死ねるものならいっそ死んでしまいたいほどに」
わたしはそれを聞いて、考えを曲げた。ギルバート伯爵がそのように苦悶なされているのならば、妾制度はないほうがよい制度と言える。本望ではない。たとえこの身をギルバート伯爵のために費やせるのだとしても、その結果に伯爵が苦しまれては本末転倒だ。
「では、破棄しましょう」
わたしが言うと、ギルバート伯爵は顔を上げた。夜道で出遭った猫のような表情で固まる。
「死んでしまってもいいとお考えになるほどに苦しいのであれば、そのように致してみてはどうでしょう。死ぬ気で抗ってみてはいかがでしょう。わたしたちもお供致します」
「上の位の血族たちに反旗を翻せと、パールさんはそう言っているのかい」
「それがギルバート伯爵の本意であるならば」
「いや、しかし」
「分かります。ギルバート伯爵はお優しい方ですから、あくまでそこは手段にすぎないのでしょう。誰も傷つかずに、妾制度も晩餐会も失くせるのならそれがよろしいのでしょう。たとえその末に、ご自身が滅ぶことになったとしても」
「パールさん……きみは、いったい」
「わたし、なんとなくですが、先代妾のペブルさまのお気持ち、いまならすこし解る気が致します」
そしてきっと、とわたしは言う。
「ギルバート様も、いまのお気持ちはペブルさまと同じなのではないのでしょうか」
伯爵がわたしの手を強く握り締めた。骨が軋むほどの強さで、その痛みがわたしには心地よかった。
「ギルバート様は一つ、誤解なさっています。たとえ妾制度の真実を明かされても、わたしたちはみな妾を目指すでしょう。いいえ、わたしがそうであるように、きっと真実を知ったからこそ率先して目指すようなコたちのほうが多いと思います。そしてみな、あなたにそんな悲痛な面持ちをさせる制度に、ひどく怒りを募らせるでしょう」
ギルバート伯爵はそこで、隣の部屋の妾のごとく、押し殺した声で慟哭した。
産まれて初めて痛みを分かち合えた渡り鳥のように。
それとも冬に咲く薔薇のように。
渦を巻く花弁のごとく皺くちゃの表情に、同じくらい嗄れた声音を咲かせるのだった。
わたしはそれが、ひどく貧相で雪の結晶がごとく儚き姿に思え、胸の内に一輪の花が開花するのを感じた。
わたしは伯爵の頭を撫で、わたしの膝に顔を埋めて泣きじゃくる狂おしき者の無様な姿に、この先の未来を幻視する。この赤子がごとき危うげな者をかように痛めつづけた制度を、者たちを、わたしは――わたしたちは、許さない。
この命、果てようとも。
よしんば、貪り食らわれる未来が訪れようとも。
わたしは、断じて許さぬだろう不動の未来を、この胸に咲いた薔薇のごとく、緩やかに、柔く、思うのだった。
【贄に幸あれ】(2022/10/31)
今、村を翔けている吾(われ)はもはや人ではなくなった。
人間ではない。
人は村を駆けることはあっても、翔けることはない。飛ぶことはない。飛翔しない。
事の発端は、村での祭りのことだ。
毎年、山神さまに生贄を捧げるのだが、今年は吾の妹に白羽の矢が当たった。
妹の名をサチと言った。山の幸、海の幸、なんでもよいが幸あれと思いつけた名だ。吾は兄にして名付け親でもあった。
父と母は幸を産んだその日の内に、雪崩に遭って死んだ。サチと吾だけが生き残ったが、村には子どもに施せるだけの蓄えはなかった。
吾は命乞いをし、何でもすると村の者たちに生涯の誓いを立てた。せめてサチが一人立ちできるまでのあいだ世話をさせて欲しい、働かせて欲しい、と訴えた。
その甲斐あってか、吾は村のあらゆる汚れ仕事を任された。その業種は多岐に亘り、却って吾は重宝されるようになった。かといって村での地位は下の下である。
村を囲う山々には神さまがおわした。数年に一度の頻度で訪れる大嵐が祭りの合図だ。吹雪と雷の入り混じる悪天候は、山の神が生贄を欲しているから引き起こる奇禍であると村人たちは見做した。
そうして数年に一度、村の中から山の神が好みそうなうら若き娘、ときに肉付きのよい青年が生贄に選ばれ、捧げられた。生きて帰る者のない片道の旅路である。
いつか生贄に差しだされるだろうとは考えていた。いかに村の役に立とうともごく潰しであるのに異存はない。
なれば妹の成長を見届け、この身と引き換えに村での身分を与えてやるのも一つだ。そうと考え、生贄になる未来を待ちわびていた。
だがどうだ。
今年、生贄として抜擢されたのは吾の妹、サチであった。
「なぜワタクシではないのですか」
「お主にいまいなくなられては困る。男手はあって困るものでもないしの」
「ですが、サチは、サチは」
「まだ幼い。嫁の貰い手もなくはないが、家財がないのでは得もなかろう。損を承知で身請けする酔狂は、この村にはおらんでの。すまんが堪えてくれ」
村長じきじきに頭を下げられたのでは、断るわけにもいかない。ここで話を折れば、吾ら兄妹に居場所はない。
「万事、承知致しました」
吾は唯々諾々と許可を下した。否、吾に下せる許しなどはない。誰にもない。
生贄にされる妹の意向は根っこからないものとされた。妹は吾の所有物ではないのにも拘わらず、あたかも吾の所有物がごとき扱いを受けた。そしてそれを知っていながらに吾はどうしようもできずに、その忌まわしい流れに身を任せてしまった。委ねてしまった。そうせざるを得なかった。
妹にはなんと説明したものだろう。言えるわけもない。
苫屋にも入れず、頭を抱えていると、
「兄さま。兄さま」戸口から妹が顔を覗かせた。土間に正座となると、襟を正した。「サチは贄となりとうございます」
「おまえ。聞いていたのか」
「兄さまの悩むお姿を見て、ぴんと来ました。先日の嵐。祭りが近いこと。あとはほかの家々から漂う夕餉の香りが、どことなく美味しそうな匂いであることから、みな肩の荷が下りた様子とお見受けしました」
であれば、なぜ兄がいつまでも家に入らぬのか、困惑しているのかの理由は自ずと絞れてくるというもの。吾の妹は、吾よりも賢い。けして村の荷物にはならぬ。
むしろ、下手に働こうものならば、村人たちよりもよほど上手く仕事をこなすだろう。仕事を奪うだろう。それすら見越して、サチは家の中で日がな一日を過ごし、村のごく潰しの地位に甘んじているのだ。
「サチ。逃げよう。村への恩は兄ちゃんがもう充分返した。二人で逃げよう」
「ううん。駄目だよ兄さま。山神さまはきっと村を滅ぼすし、あたいたちも無事では済まないよ。そうでなくともあたいはきっと一生後悔する。そんな時を生きたくはないんだ」
「サチ……」
「兄さま。兄さまがいなければサチは花の香りも、虹の色どりも、せせらぎの冷たさも知らずにいたよ。もう充分生きたよ。でも兄さまはサチのために、村のために生きてきたでしょ。もう充分だよ。あとは兄さまが、兄さまのために生きて」
吾は、吾は、一回りも幼い妹にかような言葉を吐かせてしまうほどにろくでなしの未熟者であった。
誰より他を思う吾の妹が。
身を尽くせる個が、娘子が、贄にされる世はおかしい。
村の者たちが許しても、よしんば山の神が許そうとも、吾が許せん。
「サチ。サチ。おまえの命、兄ちゃんに預けてくれんか」
「兄さま。何をする気だ。やめてけろ。やめてけろ。サチが贄になるだ。サチが贄になればそれで丸く収まる話だべ」
「おめがよくても、俺がよくね。おめさいねぇ世を生きる気はね」
待ってろサチ。
そう言って吾は村を飛びだし、丘を越え、谷を越え、山の裏手にある大きな滝壺を目指した。
山の神はそこにおわすと耳にする。
大嵐が襲う日には決まってそこから大きな、大きな、竜巻が昇るのを過去、幾人もの村人たちが目撃していた。山の神はそこにいる。
なれば頼もう。
誠心誠意頭を下げて頼もう。
神と言うなれば叶えてくれよう。今年の贄を我慢してもらう。それが無理ならば、吾で我慢してもらう。それも無理ならば村ごと食らい尽くしてもらえばよい。サチと吾の二人きりで助かる道とて、サチが残るならばそれでよい。サチが助かるのならばそれでよい。
だがそこまでせずとも、せめて吾を食らって腹の虫を治めてもらおう。
サチのことも何卒、贄にせぬよう、食らわぬよう、見逃すようにと懇切丁寧にお願いしよう。
脅してでも、何としてでも、助けてもらおう。
吾は勇んで山を登った。
滝を目指して土を踏んだ。
大嵐が過ぎてまだ日は浅い。水嵩の増した川はドドドと山の鼓動がごとき地響きを立てていた。滝はさらに大気を揺るがし、山の頂を越えるともなくその轟音が聞こえた。
吾は滝に近づくたびに、山の神へどのように懇願せんものか、と考えあぐねた。勢い勇んで飛びだしてきたはよいが、肝心要の策がなかった。
丸腰で頭を下げて、果たして聞き入れてくれようものか。たとえば吾が羽虫の願いに耳を留めたことがあったろうか。願いを唱えていると見做すことなく、そこらを飛び回って煩いからという理不尽な理由で叩き潰してはこなかったか。
なれば山の神からして羽虫がごとき吾とて、有無を言わさず叩き潰されても文句は言えぬ道理。かといって、はいどうぞ、とはいかぬのだ。
いよいよとなれば山の神の怒りを買おうとも、その首を獲らんと挑むことも辞さぬ覚悟だ。否、それくらいの気概なくして声を聞き入れてもらえはせぬのではないか。
道中、吾は目に留まった立派な古木から枝を捥ぎ取った。
山の神相手に心許ない武器だが、手ぶらよりかはマシだろう。
そうと考え、神の棲家と名高い滝壺のまえへと馳せ参じた。
そこから先の記憶はあやふやだ。
神はいた。
滝壺には龍神さまが棲みついていた。
滝を逆さに打ち消すように頭身を伸ばし、滝壺の水面から前足を覗かせた。岩をも抉る鋭い爪は、いつぞやに目にした虹のごとく色彩に輝いていた。
吾は懇願したはずだ。
荘厳な龍神さまのお姿に圧倒された。その場にひれ伏したい衝動を堪えながら、言葉が通じぬかもしれぬとの思いを押し殺し、ただそうする以外にはないのだと思いに駆られ、呪文でも唱えるかのように、妹を助けてください、妹を助けてください、と唱えた。
理由を言わねば伝わるものも伝わるまい。
いまならばかように道理を弁えられるが、そのときはただただ必死だった。
龍神さまは滝よりも太い首をもたげ、吾の頭上に顎鬚を垂らした。鼻息一つで吾は吹き飛びそうなほどで、堪らず吾はその場にしがみついた。
手には古木の枝があった。
吾は動顛して、それを献上しようと思った。
古木から捥ぎ取るときに体よく折れて、先端が尖っていた。吾はその先端を頭上目掛けて突き立ててしまった。
龍神さまは吾の匂いを嗅ごうと顎を下げていた。ちょうど顎の先端の赤い鱗に、吾の突きだした枝の先が当たった。
刺さったというほどの勢いではなかったはずだ。
だがどうしたことか、枝先が赤い鱗に触れた途端に龍神さまは滝壺の中でのた打ち回った。そのうち滝を遡り、天高く昇ると、今度は一転、力尽きたように一本の紐となって滝壺に落下した。その際、壁に身体を何度もぶつけていた。削り取られた鱗が、落下の衝撃で舞いあがった水しぶきと共に、吾の身体を打ちつけた。
吾はそこで一度気を失った。
頭に瓦礫か鱗が当たったのだ。
目覚めると吾はまず、手足が自由でないことに気づいた。岩の上で身をくねらせるようにして転がった。縄に縛られていると思ったのだ。
勢い余って、滝壺に落ちた。
水底に沈んでいくが、息は苦しくなかった。呼吸ができる。
思えば、手足が不自由に思ったが、それは手首だけしか動かせないように感じたからだ。だがそも、手首しかなかったらどうだ。
胴体からちょんまりと前足が生えていた。臀部に力を籠めると、ないはずの尾が水を掻いた。
水中を泳ぎ、明かり目掛けて水を蹴った。
滝壺から飛びだした吾はそのまま宙を舞った。
吾は龍となっていた。
滝壺に龍神さまの姿はなかった。溶解したのか、霧散したのか。
いずれにせよ、吾こそが滝壺の主となっていた。
龍になって判ったことだが、どうやら吾の拾ってきた古木の枝は、龍の苦手とする霊気を帯びていた。山とは相反する海の気をたらふく含んでいた。岩塩地帯がゆえの作用かもしれぬ、と空を翔けながら吾は思った。
吾は山を越え、村の上空を舞った。
村人たちが吾に気づき、続々と家から出てきた。
恐れをなした様子で多くの者はその場にひれ伏し、知恵の回る者は、苫屋から我の妹を引きずりだして、地面に立たせた。その周りをほかの者たちが円形に囲い、みなで吾の妹を崇めはじめた。
立っているのは吾の妹だけだった。サチだけが、上半身を扇がごとく上下させる村人たちを尻目に佇立していた。
吾は一声、吠えてみた。
すると口から突風が飛びだし、見る間に竜巻となった。竜巻はそのまま村の家屋を薙ぎ倒し、巻き込み、上空へと飛ばした。
村人たちが逃げ惑う。
吾の妹、サチだけが吾をまっすぐと見据えていた。
「兄さま!」
なぜ分かったのかは謎である。だがサチは確かに吾を見てそう叫んだ。
抱っこをせがむように両手を伸ばし、もう一度、兄さま、と声を張った。
今、村を翔ける吾はもはや人ではない。
だがそんなことは些事なのだと逃げ惑う村の者たちを視界に収めながら、吾は三度、咆哮する。竜巻が、一本、二本、と数を増す。
それらが結びつき、大きな大きな竜巻になる前に吾は、胴体から生える小さな前足で吾の妹を掬い取る。
落とさぬように。
絞め殺さぬように。
細心の塩梅を払って、今年の贄を、我が妹を、奪い取る。
【差別なき世界】(2022/11/06)
西暦二〇五〇年代。差別撤廃国際法が締結させ、全世界から差別根絶が絶対のルールとなった。世の中からありとあらゆる区別による不公平な環境が取り除かれ、不公平な構図が発見されるたびに是正する仕組みが築かれた。
多様性を潰さぬようにすることが前提とされたために、人々は好きな属性を指向することができた。ホームレスになっても何不自由なく暮らせる環境が整い、お金がなくとも大富豪と同じ食べ物を口にできた。
差別撤廃国際法が締結され、つぎつぎと差別の構図が平らにならされた。穴は埋められ、社会からデコボコはなくなる。
だが最後までなくならない差別があった。
それは、差別主義者を蛇蝎視する差別であった。
差別撤廃国際法は、差別を許さない。だが差別主義者という属性を持った個を不当に排除することもこの法の基には許されぬのが道理。
そのため差別主義者を差別することも禁じられた。だがそれでも人々の差別への嫌悪感、それに伴う差別主義者への偏見や憎悪は消えることなく増幅しつづけた。どのような是正を行おうと、差別主義者への差別は消えなかった。差別主義者というだけで理不尽な扱いや不条理な環境に身をやつすことになる。社会に差別主義者の居場所はなかった。公平な社会であるはずが、差別を嗜好するというだけのことで差別をされるのだ。
差別主義者たちはけして差別を表立って行わない。あくまで差別を嗜好するだけだ。
それはかつて同性愛や殺人をテーマとした虚構作品を嗜好した者たちが差別された歴史と同じ過程を辿っている。かつては同性愛も殺人も罪だった。いまも殺人は罪であるが、殺人をテーマにした虚構作品は娯楽品として市場に溢れている。
ではなにゆえ差別を嗜好してはならぬのか。
差別主義者たちは訴えたが、法が許しても人々の心に根付いた差別への嫌悪は消えることがなかった。
各国政府は折衷案として、差別主義者救済法を新たに制定した。
これにより差別主義者は、差別主義者というだけで国からの保護を受けられるようになった。絶滅危惧種にするそれのように、世界中の差別主義者たちは国際法の名の基に生存権を保障され、細々とながらも人々から忌避されつつ、社会の隅で肩身を狭くして暮らした。
世界から差別は根絶された。そのはずである。
だがいまなお社会には、公平の名の基に弾圧され、人々の偏見に晒され、不可視のトゲに怯えて暮らす者たちがいる。
【ボイスの日々】(2022/11/08)
期間限定でボイスをはじめた。よろしおすー。
おはよう。きょうも一日元気でまいりましょう。まいるぞ。
あちゃちゃー。水やるの忘れた。しおしおなっとるが。
水やったら復活した。よかった。
実ちゃんよ、実ちゃんよスクスクあれー。
実ちゃん、前の分収穫したった。おいち、おいちなんですね。やったびー。
わたしへ。乾燥ボタン押すの忘れてたよ。うんちさん、くちゃいくちゃいのままじゃってん。ポチっと押すのちゃんとしよ。わたしより。
堆肥マキマキしたぞ。わたし、えらい。
わわわ。外にビリビリが出よった。やばばー。
ビリビリ予防に、地下に下りた。怖いわー。
地下生活三日目じゃ。地下水掘ったら、どばどば出たが。がはは。われ最強。
あぴゃー。地下水ダメじゃった。ギギギ量がヤババじゃった。濾したら飲めんかな。無理かな。
まだお外ビリビリ言うとる。怖いがー。くそー。
ギギギの地下水、エネちゃん製造機に使ったらいい具合にゴクゴクしてくれた。いっぱいエネちゃん生んでくれてありがとうなす。ついでにモワモワになった地下水さん、冷えて戻ったら飲み水になった。いいこと尽くしやー。
きょうはもう最悪。飲み水だいじょうだったから菜園の水に利用したら、草全滅した。多分だけど、純水すぎたのがよくなかったみたい。適度に不純物入れとかないとダメなんだなって。あーあ。どうしよう食料。
オハヨ。しょげててもしょうがないので、予備の種使うことにした。がんばるじょ。
上空に高濃度エクサプラズマが停滞してかれこれひと月が経つ。長すぎ。
ボイスの容量がいっぱいになったので、余分なデータを消す。時系だけ判るように穴開きで記録を残しておく。オヤスミ、世界。わたしもおやすみ。
おはよう。一階地上部分にビリビリが接触したらしい。浸食されて壊滅状態だ。もう地上には出られない。エネルギィ製造機が地下にあるのがさいわいだ。が、これも期間限定だ。あと三年保つか分からぬ。ボイスのように生体エネルギィで駆動したらよいのに。
クサクサしていても仕方ない。がんばるじょ。
おはようございます。わたしです。悪態のデータは順次消すようにしました。ボイスが脳内思考を自動で記録する機構とはいえ、振り返るたびにいちいちじぶんでじぶんを損なうようなボイスを残さずともよいとの判断です。陽気な記録だけ残すことにします。
あばばー、あばばー。地下水が、地下水が。
おぱよ。もうもう水びだしのジャブジャブじゃー。
どうやら地上で大雨がつづいているらしい。その影響で、地下水が氾濫した。穴を塞ぎきれず、これまでの居住区を捨ててさらに下層に下りる。ほぼメカニカルフロアだ。機械しかない。高温で近づけない区画があるかと思えば、冷却されて極寒の区画もある。合間の配管入り混じる人工密林が唯一の安全地帯だ。あと三年、ここで過ごすことになりそう。誰か助けてたもー。
こんにちは。わたしです。いまさらながらボイスの通信機能を立ち上げたら、通信可のマークが点灯していることに気づきました。ひょっとして、いるのか人類? わたし以外に、生き残りがいるのか?
ちっくしょー、なんじゃい、なんじゃい。散々こんだけ呼びかけてもうんともすんとも言やしねー。ふーんだ。わたしちゃん、いじけちゃうんだからな。けっ。
緊急事態だ。どないしよ。いつの間にか酸素濃度が極端に下がりはじめてる。いつから?
そんなことってある???
あびゃー。弱り目に祟り目。
高濃度エクサプラズマが、なんと、なんと、地下にまで浸食してきおった。なんで?
ゴルフボールかよ。
穴にはまった高濃度エクサプラズマが、建物の基盤を侵食しながら落下しているっぽい。穴にハマった小石が水や風の流れでくるくる回って真球になるみたいな話だ。わいをいじめて楽しいかよ世界。
現実逃避しよ……。
わたしちゃん、かわよ。
ボイス見直してたら、わたしちゃんかわよ。
わたしちゃん、がんばれ、がんばれ。
もう嫌。
なんでわたしがこんな目に。
略)――以下、恨みつらみの地獄絵図――(略。
はい、おはよう。わたしちゃん、おはよう。そっちのわたしちゃんもおはよう。そうね。あと数日でエネルギィ製造機が停止いたします。もう終わり。終わりのカウントダウンがはっじまっるよー。うきゃきゃ。笑うしかねぇな。笑え、笑えー。
あー、死にたくなーい。こわいよー。うへへ。
めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。
嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。
死にたくない、死にたくない。
もうどうにでもなーれ。あばばばー。何も聞こえなーい。聞こえなーい。
もうすぐエネルギィ切れるってよ。ウケんね。
はい切れた。終わり、終わりー。
寒っむ。
あ。
見てあれ。ねえ見てあれ。わたしちゃん見てあれ。
機械さん止まったからかな。高熱地帯の奥に行けるようになってんだけど。まだ温かいからそっちに行ったのね、したっけなんかまだ先があるんだけど。
地下あるっぽい。
下行けそう。
行くしかないから行くが。
空気澄んでる。澄んでない? 澄んでる? どっちなんだい。
ふざけてたらこけた。
明かりないんよ。
あへー。
あへあへー。
わたしへ。隣の地層にも同じ避難シェルターがあったんだって。知ってた? わたしより。
ちゅうわけで、またしばらく生き永らえられるっぽい。やったびー。しょもしょもの日々じゃけんど、しょもしょもできるだけマシなんじゃ。いっぱいしょもしょもしたろ。
あ。
ん?
ボイスの視聴者数地味に増えてるの何?
通信できてないこれ。
できてる? できてない? どっちなんだい。
菜園あるくさい。
いっぱいの食べ物。食べ放題。すてき。
堆肥食べて飢え凌いでたとか言えない。
おはよう、おはよう、おはよう。
きょうも元気にわたしちゃんは生きるじょ。
おやすみ、わたしちゃん。
おはようございます、わたしくん。
期間限定でボイスをはじめるって言ったな。あれは嘘だ。
ずっとつづける。よろしおすー。
こにゃこにゃもにもにしちゃうもんね。がははは。
さびちー。
応答しちょくりー。
まーた頭上にビリビリ停滞いい加減にしとくれなす。
ひぃぃ……こわぁ。
実ぃでけた。
おいちー。
いや絶対これ聴いてる人いるでしょボイスくん。
【誰も知らぬ旅路】(2022/11/10)
寝て起きるたびに過去が変わっている。死んだはずの父が生きており、自殺したはずの母が生きている。先週わたしをイジメた同級生は昨日はわたしの親友だった。弟がいたと思えば、妹がおり、その妹が昨日は姉で、今日はわたしは一人っ子だ。
起きると稀に日付が数日飛んでいることがある。そういうときには、ああまたか、とわたしは思うのだ。
どうやらその抜けた日々のなかにわたしは存在しなかった。
わたしがいない世界がときおりそうして交じるのだ。
わたしだけがなぜ過去の変遷しつづける日々を横断しているのかは分からない。なぜ記憶が引き継がれるのかも定かではないのだが、どうやらわたしだけが知っている。
今日と明日は同じではない。
昨日と今日も同じではない。
わたしが誰にどう優しくしようがそうした過去は明くる日には消えている。同じくわたしが誰をどう損なおうとも、そうした過去が明日に引き継がれることはない。
わたしは自由な日々を生きている。
何の影響を残すことの叶わぬ、いましかない世界を。
近所の野良猫だけはしかし、いつどのわたしの「今日」にも現れる。誰にも懐かぬその猫は、餌をやるわたしにだけは甘い声音でみゃーと鳴く。わたしの足首に首筋を擦りつけごろごろと胎動のごとく立てる喉音は、どこか遠雷にも似ている。
その鳴き声一つ、歩き寄るトコトコの弾むような足取り一つでわたしは、日々の終わらぬ底なしがごとき旅路を耐えられる。
よく生きよ。
たぁんと長生きしておくれ。
喉を撫でると野良猫は、昨日と同じ細さに目を閉じる。
【繭の華咲く日は】(2022/11/12)
最初は魔王を倒そうと思ったのだ。王様の選ぶ勇者は毎回魔王討伐に失敗し、そのうえ魔王の怒りを買って余計に魔物の襲撃を誘起する。そのせいで私の父と母は殺された。年端もいかぬ妹が魔王軍に連れ去られ、いよいよとなって私は奮起した。
魔王城へは三年の長旅となった。しかし村々を経由するうちに信頼の置ける仲間たちと出会えた。むしろ三年で魔王に王手を掛けられたのだから快進撃と言ってもいい。
私たち一団は魔王軍を蹴散らし、魔王を孤立させることに成功した。
追い詰めた魔王を討伐するか、そのまま封印するかで意見が割れた。魔法使いたちは軒並み慎重派で、このまま封じるのが最も手堅い策だと主張した。私もどちらかと言えばその案に賛成だった。
しかし、好機を目のまえに魔王を生かしたままにおくことを許せぬのが騎士団だった。
このとき、魔王を追い詰めた情報は瞬く間に全国津々浦々に行きわたっていた。そのお陰で、魔王軍を蹴散らしたあとで魔物一匹寄せつけない陣形を築けたと言っていい。
かつて魔王討伐に失敗した勇者たちの縁者たちまでもが加勢に加わり、我ら人類側の勝利は目前だった。そこにきて魔法使いたちが、魔王を生かしたままで封印する、と言いだしたので、意見が割れた。
「魔王を生かしたままだと。アイツらに何をされたのかを思いだしてまだ同じことを言えるのか。しょせんは魔法使いだな。魔に通じる者同士、情でも湧いたかよ」
「言葉を慎みなさい。魔王の力は強大です。追い詰めて自棄を起こされたら対処のしようもない。ここは封じるのが吉と我らは考えます」
同士討ちの気色すら濃厚となったが、時間が限られる。まごついている合間にも魔王は傷を癒し、反撃の余力を蓄える。
あなたはどう思うのか、と最終的に私の意見によってその後の方針が決まるような流れとなった。多数決を採ればおそらく五分五分で割れただろう。そうしたなかで、唯一単なる一市民でしかない私の一存に命運が託されるのは、私が異様に運が良かったからだろう。未だかつて誰も成し得なかった魔王軍の排除と、それに伴う魔王城への鎮圧。魔王を孤立させ、実質無害化した功績は、ほとんど運が良かったからだ、としか言えない。仲間に恵まれた。それもある。それ一つをとっても運が良かっただけなのだ。
だからなのかは知らないが、みな私の運の良さに今後の道を預けたがっているのかもしれなかった。
「両方の策をとろう」私は言った。それ以外の考えが思い浮かばなかった。「討伐したい者たちは命を賭してでもその手で魔王を殺したいのだろう。ならば私にそれを止める権利はない。筋合いはない。だがもし失敗したときは、魔王共々封印されてくれ。それが筋だと私は思う。失敗の許されない道だからこそ、そこは是が非でも吞んでもらう。否、吞まずともそうせざるを得ない」私はみなを見渡す。荒野が一団の群れで稲穂のごとく覆われている。魔法使いたちの連携により、私の声は隅々まで行きわたる。「私は魔王を封じる案がよいと考える。だから共に魔王を殺しには行けない。止めはしない。時間は三日だ。そのあいだに討伐できなければ、三日後の零時きっかりを回った時分に封印の儀をはじめる。異論反論は受け付けるが、三日後の零時に封印の儀を決行する旨は覆らぬ。それが嫌ならば、身内で争うことになろう」
辺りはシンと静まり返った。
「どうした。時間がないぞ。止めはせん。好きにせよ」
暗がりの中、ゆらりと一人、また一人と立ちあがる。馬に乗る者、魔法陣を潜る者、使役した魔物にまたがる者もいる。
数刻もしないうちに騎士団はごっそりとその場からいなくなった。
みな魔王を滅しに、魔王城の地下深くへと赴いた。
三日経っても誰一人として戻った者はなかった。
零時を回ったが、私はしばらく帰還者を待った。
「時間ですよ」
魔法使いの長に促され、私は頷いた。
それだけで伝わったようだ。
魔法使いたちはとっくに配置についており、魔王城を取り囲んで巨大な魔法陣を人を使って描いていた。私は旅の道中に受けた魔王の呪いを血に籠め、魔法陣に垂らした。陣が地割れのごとく大地に浮かぶ。青い稲妻のようにも、地から伸びるオーロラのようにも視えた。封印の儀がそうして行われ、騎士団を含め、大勢の仲間たちごと私たち残留組は魔王を封印した。
魔王城はその土地ごと不可侵領域となった。入ることも出ることもできぬ魔境と化した。地表に張り巡らされた魔王の魔糸が途切れ、魔物が群れを成すことはなくなった。
魔王軍は散り散りとなり、もはや人類の脅威ではなくなった。連れ去られた村人たちの多くも、生きていれば解放された。
旅を共にした仲間たちに別れを告げ、私は、解放者のなかに妹の姿がないかを探した。旅がそうしてしばらくつづいたが、かつての仲間たちが私のために妹を探してくれていた。その甲斐あってか、半年後には私は妹が活きている報せを受け、その数日後には無事な妹の姿を目に留め、この腕に抱くことができた。
ここで終われたならばハッピーエンドとして絵本にしてもよいくらいだが――騎士団の犠牲は哀しいが、それを言うなれば私たちは絶えず哀しい死と痛みの裏に生きている――世は、そう大人しく私に平和な日々を与えてはくれなかった。
妹の様子がおかしいと気づいたのは、彼女を魔王軍から取り戻してから十二日後のことだった。
ひどい目に遭ったのか、それとも凄惨な光景に精神を病んだのか、妹は口を聞けなくなっていた。魔法使いの治癒を受けてもその後遺症は残ったままだったが、この手の魂に受けた傷は、魔法でも治療のしにくい領域なのは知っていた。魂は繊細だ。無闇に魔法をかけてよい領域ではない。神聖なのだ。そのはずだった。
「マユカ。マユカ。そろそろ魔除けの魔法をかけておこう」
妹は駆けよってくると無邪気に私に背を向けた。
私の膝の上に乗り、首飾りでも掛けてもらうかのように髪の毛を払ってうなじを露わにした。
このとき、私は再会して初めてマジマジと妹の首筋を目にした。
目だ。
瞳が、妹のうなじに開いていた。
ぱちくりと瞬きする一つ目が、一瞬で虹彩を深紅に染めた。漆黒と見紛うその深い紅の目には見覚えがあった。数年前、旅の道中でいたずらに私に呪いを掛けた魔王の眼球そのものであった。
私は混乱した。いつからだ。
風呂で妹の身体を洗ってあげたことはあった。治癒の魔法を段階的に掛け、不老にならぬように配慮しながら全身の痣を消してあげもした。
だが首筋のソレに私はついぞ気づかなかった。
いつからだ。
それが問題だった。
魔王の目が妹の首筋に開いている。
魔王は封じたはずだ。であるならば、ここに魔王の目があるはずがない。
では魔王の目ではないのか。
そうかと思い、魔払いの術を掛けた。下位の魔物ならばこれで充分対処可能だ。
しかし目は難なく妹の首筋に浮いたままだった。
ならばと思い、こんどは魔王討伐の旅以降仕舞いきりだった精霊の涙を取りだした。精霊の涙は、千年に一度だけ誕生する精霊王の血の結晶だ。魔物の血でできた沼ですら、精霊の涙を沈めれば一瞬で澄んだ泉がごとく清廉さを宿す。
精霊の涙なしに魔王城までの道は築けなかった。
私はそれを精霊たちから譲り受けた者として、保管していた。
高位の呪いであろうと精霊の涙を翳せば、軒並み払えるはずだ。魔王の呪いに掛かってなお死なずに済んだのは、精霊の涙を私が肌身離さず身に着けていたからだ。
いまはもう魔王はいない。魔王の呪いも、封印により魔糸が切れたので解呪された。
だから妹のうなじに浮かぶ目が魔王のものではあり得ない。
意を決して精霊の涙を、妹の華奢な首に筋にあてがった。
赤い稲妻が細かく噴きだすように昇り、部屋に散った。
音もなく私は手を弾かれた。
精霊の涙は壁にぶつかり、床に落下した。
私は妹の身をまず案じた。妹は驚いたようにこちらを振り返り、首筋を手でさすった。魔王の目じみた眼球はそのときばかりは傷口をぴたりと合わせたように妹の柔肌の奥に馴染んで消えた。
私は床に落ちた精霊の涙を拾いあげた。表面にはヒビが入っていた。奇しくもそれは先刻立ち昇った赤い稲妻じみた細かな魔痕と酷似していた。
私はこれと似た魔痕を知っていた。
私の身体を蝕んだ魔王の呪いは、それと非常によく似た魔痕を私の全身に走らせた。
「……魔王、なのか」
妹は首だけひねって私を不可思議そうに見上げた。
妹の首筋にふたたび深紅の眼球がぎょろりと開いた。
あらゆる手を尽くして調べた結果、一つの仮説が浮上した。魔王は完全には封印されていない。自らの核を飛ばし、それを我が妹に寄生させた。
魔法使いたちの築いた魔法陣を抜けるには、いかな魔王とて苦戦したはずだ。そこで魔王はどうやら、魔力をごっそり置き去りにして核だけを魔王城の外に飛ばしたらしい。
そうして無防備な核のまま我が妹に寄生した。
意思疎通はできない。
だが魔王は明らかに私の妹と知って、このコに核を飛ばし、根を張った。
核から目生えた眼球はいま、妹を介して徐々に魔力を蓄えつつある。
このままではやがて妹が魔王の苗床となる未来が訪れる。
信用できる魔法使いの仲間に頼んで、妹の魂を診察してもらったところ、危惧が的中した。魔王の核は、我が妹の魂と完全に癒着していた。魔王は、妹の魂からじかに魔力を吸い上げていた。
魔王の核を排除するには妹ごと滅するか、封印するしかない。
だがそれでは私が魔王を斃した意味がない。
このコを取り戻すために私はすべてを擲って、地獄のごとき旅路に身を置いたのだ。
魔王はそれを知っていた。
だからだろう。
こうして私をけしかけたのだ。
ふたたび魔王城へと歩を向けさせるために。
封印した魔王の抜け身を解放させるために。
魔王城に置き去りにされた魔王の肉体が解き放たれれば、魔王の核は妹の魂から抜け出て本体に向かうだろう。そこで妹が無事で済む可能性は低い。魔王が妹の魂ごと肉体に戻る可能性のほうが遥かに高い。
だが、交渉はできる。
いまは意思疎通すらできない状態なのだ。
このまま魔蟲に寄生された子羊のように妹が日に日に魔王化していく姿は見ていられない。
悩みを打ち明けた信頼の置ける魔法使いは、このことをほかの魔法使いたちにも知らせるべきだ、と言ってきた。私はそれを断った。
相談すればどうなるかなど火を見るよりも明らかだ。すでにいちど実践している。
魔王封印が再現されるだけだ。
魔法使いたちは妹ごと魔王の核を封印する。それ以外の最善手を彼ら彼女らは持ち得ない。
だから私は信頼の置ける魔法使いを説得した。どうか黙っていて欲しい、と。私がじぶんで何とかするから、と。
信頼の置ける魔法使いは、解った、と言った。だがその返事はどう聞いてもその場を切り抜けるためのおためごかしだった。
私は、夜中に遠隔魔法通信を飛ばした信頼の置ける魔法使いの姿を捕捉し、決別する臍を固めた。戦友と妹ならば私は、我が妹をとる。闘う術を持たぬ、いたいけな我が妹の未来をとる。
たとえその末に戦友の胸元に刃を突きつけることになろうとも。
大勢の命と引き換えに封じた魔王を復活させてしまうことになるのだとしても私は。
私は、それ以外に生きる意味を見出せないのだ。
なぜ戦うのか。
我が妹があすを、きょうを、健やかに生きる世界を守るためだ。
屈託なく笑い、花を愛で、野を、山を駆け回る世界を築くためだ。
それ以外に私の戦う理由などはない。
あってたまるか。
私は心底にそう思ったのだ。
信頼の置ける魔法使いを私は地下室に閉じ込めた。そのとき、戦友を傷つけぬようにと精霊の涙を使った。地下室を魔法不可侵領域にするために精霊の涙を使って陣を敷いた。
魔王にすら使える禁術だったが、背に腹は代えられない。どの道、私は魔王を封印しに行くのではない。解放するために行くのだから。
魔法使いたちには事情がすでに行きわたっている。私が何もせずとも、地下室の我が友は遠からず救出されるはずだ。
私は先を急いだ。
誰より先に魔王城へと行き着き、封印を完全に解かぬままに魔王を目覚めさせ、交渉をするのだ。
妹を贄にするな、と。
我が妹の身体からおとなしく出ていけ、と。
そうする以外に、妹が無事で済む未来は訪れない。
そうしなければいまにも、我が友たちが、私のすべてに仇を成す。どこを向いても四面楚歌の敵だらけ。みなの望む平和な世界に、我が妹の姿はない。
なれば。
なればこそ。
せめて私だけはこのコの未来を切り拓くべく、血を、肉を、捧げねばならぬだろう。ほかの誰もそれをせぬというのならば、せめて私だけは。
「……お姉ちゃん」
不可侵領域となった魔王城に辿り着いたとき、私は満身創痍だった。無垢な妹を抱えながら、友軍の仕掛けた守護の陣を掻い潜り、飼い慣らされた高位の魔物を相手に、段階的に設けられた関門を突破しなくてはならなかったからだ。
経験を積んだとはいえ、私は元はただの一介の村娘である。
どう抗おうが、対魔王軍用の防衛陣を無傷で通り抜ける真似などできるはずもないのだった。
傷ついた姉を見つづけ、さすがの妹も気づいたようだ。なぜ己が姉がそこまでして目的も定かではない旅をつづけるのか。まるで何かから逃げるようにこそこそと行動をするのか。
「……わたしのせい?」
しゃべれないはずだった。
妹は、魂に負った傷ゆえに、口が利けぬはずであった。
日常を奪われ、凄惨な日々を送り、なお先の見えぬ旅に巻き込まれた末の開口一番に出てきた言葉が、
「わたしの、せい?」
「違うよ」私は咄嗟に否定した。口を衝いていた。言わねばならぬと瞬時に判断した。
だが文脈は、言葉とは裏腹な返事を妹へと伝えていた。
「そっか」とあっけらかんと破顔した妹の目元から涙が零れ落ちた。いたいけな妹は涙まで小さい。
魂は、神聖な領域だ。
そこに無断で根を張った魔王の核は、魔王城に眠る本体に近づいたがゆえに呼応していたようだった。私はあとからその事実に気づいたが、このときはただただ、我が妹がいらぬ心労を抱え込まぬように、どうこの場を切り抜けようか、いかに嘘を重ねて欺こうか。そのことばかりを考えていた。
妹はゆったりと目をつぶった。
私は妹を背負っていたが、妹の頬が首筋に押しつけられたので、妹が眠るように目をつむったのだと判った。
魔王城に深紅の稲妻が走った。幾重も走った。
何かが起きたのは明白だった。
一度退避しようと踵を返そうとしたところで、深紅の稲妻が頭上から魔王城へと向かって走っていることに気づいた。
首筋に妹の腕が絡みつく。
後ろからぬっと肩越しに覗いた我が妹の顔には、うなじにあったはずの魔王の目が額の位置に開いていた。
見たこともない顔で妹は笑った。口元を吊りあげ、知るはずのない魔術の呪詛を吐いた。
魔王だ。
私は直観した。
振り払おうとしたが、身体に力が入らなかった。
吸われている。
魔力を、魂の根幹から吸われていると感じた。
刻一刻と全身が干上がるようだった。
私は地面にひれ伏した。頬に岩石のざらついた感触がひんやりと伝わった。
死ぬ。
そう思った。
魔王の核が妹の魂を取り込んだのだろう。魔王の核に自我が芽生え、私から魔力を根こそぎ奪い、そしてこれから魔王城の封印を解くつもりなのだ。
肉体と融合し、完全なる復活を遂げる腹積もりなのだ。そう思った。
背後で、聞き覚えのあるドラゴンの嘶きが聞こえた。
友軍の使役する高位魔獣だ。
魔法使いたちから事情を聞きつけ、馳せ参じたのだろう。
だがもう遅い。
私はじぶんの望みの何もかもが潰えたことを痛切に実感しながら、もう遅い、と誰に向けるのかも分からぬ怒りに震えていた。
もう遅い。
妹は、死んだ。
魔王に取り込まれた。魂ごと穢され、侵され、無残に散った。どこにもいない。
私の愛しい、我が妹。
じぶんのものですらないのに私は、いたいけな妹のことを、じぶんの生そのものと見做し、慈しみ、委ねていた。
そう、委ねていたのだ。
あのコは私のすべてだったのに。
――私のすべて。
なんて退屈でちんけで、響き甲斐のない言葉だろう。
だがそう形容する以外に私には表現のしようがなかった。なぜなら私からはもう、立ちあがる気力も、戦う意欲も、生きる動機の何もかもが霧散霧消して、無に帰していたからだ。
これから死ぬだろう数秒後を思っても、私は何も思わず、ただ震える身体に、ありもしない怒りの炎を幻視するよりなかった。
怒りすら私には遠い過去の出来事だった。
だから。
それゆえに。
「……お姉ちゃん」
人間の面影の薄れた三つ目の顔から、私を呼ぶ妹の舌足らずな声を聴いて、空虚な私の竈になけなしの火が灯った。
「待って」
どこに行くの。
伸ばした手が空を掻く。三つ目の妹は私に背を向け、深紅の稲妻となって姿を晦ました。
ぞろぞろと背後から友軍の団体がやってきて、私を取り囲んだ。
魔法使いの長が私の額に手を翳した。記憶を読み取ったのだろう。「やはりそうでしたか」と意味深長に頷き、「では段取り通りに」と友軍に指示を出す。
何をする気だ、と私は唱えたつもりだったが、もはや声にならなかった。
見る間に、友軍は各々に封印の陣の配置につき、剣を地面に突き刺した。
聖剣を呪具とした禁術だと判った。
封印と攻撃を兼ねている。
破壊を目的にした唯一の防衛魔術だ。
魔王城ごとこの世から抹消する気だと知れた。友軍の面々は、魔王討伐の旅に私が出ていたあいだも王都に留まっていた精鋭たちだった。
待ってくれ。
私は声にならぬ声で叫んだ。
魔王城には我が妹がいる。消さないでくれ。殺さないでくれ。滅さないでくれ。
声にもならぬ言葉には何の力もなかった。
一瞬の閃光の後、この世から魔王城ごと不可侵領域は消滅した。地下に封印されていた魔王の肉体ごと。
そして魔王の核の宿った我が妹の肉体ごと。
どの道、魂はとっくに喪われていたのだろうが。
私は友軍に連行されながら、治癒の魔法を受けて取り戻した冷静な思考で、もう遅い、と何度となく心の中で唱えた。
もう遅い。
私にはもう、何も残されてはいないのだ。
失った。
何もかもを。
人類を裏切った罪により私には極刑の判決が下された。しかし、情状酌量の余地ありとの弁護をかつての戦友たちが訴え出たこともあり、過去の戦歴を考慮して、減刑がなされた。
どちらでもよかった。
きょう死ぬ命ならばそれでよかった。
私には咎人の首輪が嵌められた。今後一生を私は自由を縛られ生きることとなる。
具体的には自殺ができない。
勅命が下されれば王の言葉に従わねばならない。
民のために能力を使い、堅実に日々を世のため人のために働いて過ごさねばならなかった。
才ある者の務めと科せられたこれが私の贖罪である。私は操り人形のごとく首輪の縛りによって無理やりに生かされた。
ある日、私は王の命で、研究棟を訪れた。
そこでは日夜魔物の研究がなされている。
魔王とじかに退治してなお生き残った数少ない人間として、私は体のよい研究資料と見做された。
「呪いはもう残ってないよ」
「いいんですよ。お話を聞かせてください。旅の始まりから、終わりまで」
どうやらかつての戦友たちの心遣いであったようだ。
生きた屍となった私になんとか生きる活路を見出させんとする策の一つだったようである。いわば治療なのだろう。過去の体験を話させることで、内なる膿を出しきらせようとの魂胆が見え隠れした。
癪に思う気力も湧かぬ。
私は促されるままに、相手の質問に応じていった。
ぼんやりとした記憶だった。
意外にも、質問を投げかけられるたびに、小石が水面に波紋を立てるように当時の記憶が鮮明に浮かびあがった。私の無意識が記憶を奥底に沈めていたのではないか、と思うほど私は多くのことを忘れており、そして問いかけによって思いだした。
記憶は行ったり来たりを繰り返した。
記憶の中の私はよく怒り、よく笑い、よく冷めていた。他者の欠点を挙げ連ね、友の配慮を無下にし、己の欲望に忠実に行動の指針を立てていた。
「私は、私のことしか考えていない人間だったようですね」
話の一区切りがつくたびに私はそう総括した。
けっきょくその一文に集約されるのだ。
顛末がそのように結ばれたのだから。
私はとどのつまり、全人類の平和よりも、私の欲望を優先したのだ。我が妹の命を優先し、我が妹の未来を優先した。
そしてきっと、と私は思う。
いまもう一度同じ場面をやり直させてやると言われても私は、まったく同じ決断をする。そして今度こそ目的を果たすべく、一縷の望みと、全人類の未来を天秤に掛けるのだ。
何度選ばされても、私には等価ではない。
私の欲望と、全人類の命は同じではない。
等しくない。
我が妹の命が、ほかの大多数の人間と同じなわけがないのだ。
もしあのとき、魔王と交渉ができたとして。
魔王からこのように提案されたら私はどうしただろう。
――妹を助けてやる代わりに、全人類の命を寄越せ、と。
そうする以外になければ私はその案を呑んだだろうか。
「たぶん、呑みますね。いえ、絶対に呑むでしょう」
私は包み隠さず、その旨も話した。聞き手は興味深そうに、しかし話の邪魔はせぬように静かな相槌を打つ。「いまもその考えに変わりはないのですか」
「ないです。いまだって、あなたの命と引き換えに妹が戻ってくるのなら、私はあなたの命を犠牲にするでしょう。その事実を妹にひた隠しにしたまま。誰に知られることなく、幸せな日々を生きるでしょう。妹とのその日常が叶うのであれば、私はもはや何を犠牲にしてもいいと考えています」
考えているのだ、と口にしてから思い知った。
私はまだ心のどこかでは諦めていないのだ。
欲望を。
生きることを。
「そうですか」聞き手の男は屈託なく相槌を打つ。肯定も否定も示さぬ割に、何を言っても彼は私を包みこむような柔和な雰囲気を崩さない。
私が素直に話しつづけられたのは、彼のその雰囲気による魔法にかかっていたと言っても過言ではない。
男は魔物の研究者だった。
私がひとしきり旅の顛末と私の罪過について語り終えると、ようやくというべきか、男のほうでも口上を逞しくした。
「欲望というのならば興味深い実験を先日したばかりでしてね」男はほかの研究者たちと違い、じぶんの興味関心のある分野についてであっても舌鋒を鋭くはしなかった。たおやかな雰囲気のまま、ほのぼのとしゃべった。「魔物や魔獣には、それぞれ核があります。ご存じでしょうが、これを潰さないと再生する魔性生物は多いです。先日、高位魔獣のドラゴンで実験したのですが、どうやら魔性生物の核は、ほかの生き物の魂と癒着することで、核単独でも生き永らえることができるようなんです」
率直な感想は、なんだそんなこと、である。
ドラゴンどころか私は、私の愛しい妹の身体に魔王の核が癒着しているのを実体験している。間近で観察している。
いまさらの情報であった。
「面白いのはここからなんです。核だけになってほかの生物に寄生したところ、魔性生物の核は、その後にどれほど宿主の魂を吸いあげ取り込んでも、元の魔性生物の意識を発現させなかったんです」
私は眉根を寄せた。
「高位魔獣のドラゴンですら、核だけになってしまったら、元の肉体に戻らない限りは、元の状態には復元され得なかったということです。言い換えますと、ほかの生き物と融合した魔性生物の核はむしろ、宿主の欲望を肥大化させるように作用するだけで、寄生された生き物の魂はそのまま自我を保つことが解かってきたんです」
「よく解からんな。ドラゴンの核に寄生されてなお、魔獣化しなかったということか」
「ありていに言えば、はい」
「欲望が肥大化させるように作用というのは、その、つまり」
「寄生した生物の欲望を暴走させるように、魔力を増強させると言えば端的かもしれません。食欲ならば食欲を。性欲ならな性欲を。独占欲、支配欲、もろもろ欲望は個々によって幅がありますので、何が最も強く発現するのかは、それこそ寄生された生物のそのときの状態によるのでしょうが」
そこで男は、東洋にはゾンビという異常種がおりまして、と冗長な説明をはじめた。私はそれを上の空で聞き流しながら、耳にしたばかりの新説を振り返っていた。
魔性生物の核に寄生されても、人格が塗りつぶされるわけではない。
魂を吸われはするが、癒着したからといって魂が消滅するわけでもない。
その個の最も深い欲望を肥大化させる。
魔王は魔性生物の頂点に君臨する。数多の魔性生物を支配下に置き、統率可能な術を有する。いっぽうで、魔王もまた魔性生物の一個体である。
もし魔性生物の核にまつわる新説が、魔王にも当てはまるとしたらどうなる。
我が妹は最期、魔王の核に取り込まれてなお、自我を保っていたことにならないか。
ではあのとき、あのコの最も深い欲望とは何だったのか。
なぜ意識があってなお、私をあの場に残し、魔王城へと去ったのか。
なぜ急にあのコはあの場で、魔王の核にすっかり肉体を乗っ取られたように振る舞ったのか。真実に乗っ取られていようと、魔性生物の核の習性が魔王にも当てはまり得るのなら、あのときあのコは、魔王のチカラを帯びてなお、自我を保てていたはずだ。
あのコはあのコのままだったはずだ。
にも拘わらず、あのコはなぜ。
――最も深い欲望。
あのコの、あの時点での、最も深く、肥大化した欲とは何であったのか。
――お姉ちゃん。
あのコの最後の声音が、鮮明に、すぐそこで聴こえたようによみがえった。
仮面のように顔面を手で覆い、私は、背を丸めた。
しきりに乱れる呼吸をなんとか整えようとしたが、上手くいかなかった。
そばにいた男はしゃべるのをやめ、黙って私が落ち着くまでそこにいた。
呼吸の仕方まで忘れてしまったかのように私はしばらく声にならぬ言葉で、妹の名を呼んだ。やがて思いだしたように呼吸を連続して滑らかにできるようになり、私はなぜか肩を弾ませ笑っていた。
何が可笑しいのかは判らなかった。
ただただ、生きねば、と思ったのだ。生きていかねば、とそう思ったのだ。
迷い込んできたのか、頭上に蝶が舞っていた。
冬籠りの支度が忙しい季節にしては、時期外れの蝶である。
「最近ぽかぽかと暖かかったからですかね。春と思って羽化したんでしょうか」
男が席を立った。蝶を捕まえようとした素振りを見せたので私はまえのめりになってその腕を掴んだ。男が面食らったように仰け反った。「どうしました」
「いえ」私は動顛していた。身体がかってに動いたのだが、その理由が解らなかった。「すみません」
男は頬を指で掻いた。それから本に貼っていた付箋を外すの忘れていたといった調子で、そうそう、と指を振った。「妹さんのお名前はなんと? 一度もお話のなかで呼ばれなかったので」
差し支えなければ教えてくださいませんか、と何の気ない様子ではにかむ男の頭に蝶が止まる。
ゆっくりと呼吸をするように羽を休める蝶を見て、私は、なぜかまた呼吸の仕方を忘れるのだ。
「マユカ」
途切れ途切れの呼吸の狭間に私は、この世にしかと刻み込むように、声ある言葉であのコの名を呼んだ。
【木製のナイフ】(2022/11/15)
ボクはこの全寮制学園の秘密を、アディ兄さんから聞いた。
聞いたというよりかは聞きだしたというほうが正しいのだろうけれど、何せアディ兄さんは問いかければ投げた箱を三十四重にマトリョーシカにして返してくれる律義さもとより博識で聡明な頭脳を持っていた。
アディ兄さんはボクよりも三歳年上で、ボクにとっては何を聞いても答えてくれる歩く未来だった。誰のものでもないボクの未来そのものだ。アディ兄さんとボクは血の繋がりはないけれど兄弟だった。みながボクたちをそう呼んだし、アディ兄さんの友達はみなボクのことをリルアディと呼んだ。小さいアディの意味で、つまりみなはボクをアディ兄さんの弟だと見做していた。
でもボクはアディ兄さんから直接、ボクたちのあいだに血の繋がりがないことを教えてもらっていたし、そのことに傷つく必要がないことも教えてもらった。
ボクの寝床は幼いころからアディ兄さんの隣で、寒い日はよくアディ兄さんの寝床に潜り込んだものだ。
アディ兄さんは寝るときには、日中であれば団子に結っている長髪を解くので、ボクは眠れない日はよくアディ兄さんの髪の毛を指でいじって、その金髪に反射する月光を眺めたものだ。もしこの世に神様がいて、その神様にお供がいたとしたらきっと、こういう金色の糸をつむぐ白銀の蜘蛛に違いないとボクは夢想することもしばしばだった。
「ボクはどうしてここにいるの?」
その質問をボクがしたとき、ボクは十二歳の誕生日を迎えたばかりだった。
全寮制の学園だったので、その月に誕生日のある者はいっせいに毎月十五日にみなで祝うのがここでの習わしだった。
その日はたしか三日や四日の晩で、ボクは誕生日を迎えていたけれどまだみなから祝われてはいなかった。
そんな中でアディ兄さんだけはボクのために木製のペーパーナイフを贈ってくれた。手作りだった。ケヤキの木の枝を削って作ったもので、ボクはケヤキが硬い木であることを知っていたので、感激した。
「兄さん、ありがとう。ぼく、うれしい」ケヤキの木でできたペーパーナイフは鉄のように頑丈で、人間の皮膚くらいなら簡単に貫けそうな鋭さがあった。
「喜んでくれてよかった。漆も塗ったから長持ちすると思うよ」
「手、大丈夫?」
「かぶれはしなかったよ」
「それもだし、タコができたんじゃないかなって」
「心配性だねナツは。ありがとう、でも私は慣れているから」
アディ兄さんはボク以外の子にも贈り物をすることがあった。だから木材の加工はお手の物なのだ。
寝床は広間に布団を敷いて、三十人から五十人がクッキーを焼くときみたいにぎっしり並んで眠る。
ボクは寝床に木製のペーパーナイフを持ち込んで、眠くなるまで見詰めていた。ボクがいつまでもモゾモゾしていたからか、アディ兄さんが声を掛けてきた。
「眠れないのかい」
「ううん。見てたの」
ボクが木製のペーパーナイフを見せると、兄さんはやれやれと苦笑した。「危ないから枕の外に置いときなさい」
「でも」
「危ないから。ね」
アディ兄さんにそんな声音を出させてしまったらボクにはなす術がない。唯々諾々と指示にしたがった。
ボクが不満そうだったからか、アディ兄さんはそこでボクに手を伸ばして、おいで、と無言の手招きをした。本当はじっと腕を伸ばしていただけだけれどボクにはアディ兄さんが手招きして見えた。
ボクは誕生日を迎えたばかりで、また一つアディ兄さんに近づいたはずなのだけれど、アディ兄さんにも誕生日はくるから、それまでの短い期間のこの隙間の埋まったような心地がボクは好きだった。でもこのときばかりはまだ歳をとったばかりだから、まだ歳の差が三歳開いたままの関係でもよいように思って、ボクはまだ十一歳の弟のつもりで、アディ兄さんの寝床にモゾモゾとイモムシみたいに這って移動した。
アディ兄さんは温かい。
でもいつもボクが潜りこむとアディ兄さんは、「ナツは太陽みたいだね」とボクの体温が高いことをうれしそうに言うのだった。
「ナツは誕生日だったから、きょうは特別にいくらでも質問していいよ。答えられることには全部答えてあげる。眠くなるまで付き合ってあげる」
「本当?」
ボクはそれだけで眠気がどこかに飛んで行ってしまった。
そこからボクはじぶんでも呆れるくらい色々なことを質問した。どうしてお月さまは輝いていて欠けているのかから、どうしてアディ兄さんは物知りなのかまで、思いつく限りの疑問をアディ兄さんにぶつけた。
アディ兄さんはそれらボクの疑問に檻を掛けるみたいにしてもう二度と疑問が出てくることがないような回答をした。
「お月さまが輝いているのはその向こうに天国があって、そこが輝いているからだよ。夜空には穴がたくさん開いていて、お月さまもほかの星々も太陽も、全部そこから漏れる天国の光なんだ。でもときどき穴の中を洗わなきゃいけないから蓋をすることもある。夜空の穴は大きくて深いから、穴を塞ぐにも時間がかかる。だからお月さまは周期的にゆっくりと満ち足り欠けたりして見えるんだ」
「へー、へー」
「どうして私が物知りかと言えば、私には前世の記憶があって、それで本当は九十のお婆さんなんだよ。中身はね。でも見た目がこれだからみなは【見掛けの割には物知りだ】と思うようなのだけれど、これはでもそうじゃない。だって本当は九十のお婆さんの人生分だけみなよりも多く物事を見聞きしているからね。その記憶がある。だからそれを考慮に入れたら、私は全然物知りじゃないんだ。色々と勘違いだってしているだろうし、間違ったことも言うよ。だって私の知識は九十のお婆さんのものなのだもの」
「ふうん。すごいね」
「ナツ。ちゃんと聞いていたかい。私は全然すごくないよってことを説明したんだよ」
「だって前世の記憶があるんでしょ」
「それだって確かじゃないよ。私がそう思いこんでいるだけかもしれない」
「嘘ってこと?」
「本当ではないかもしれないってこと。いいかいナツ。人間はそうそう簡単に本当のことを見抜けないんだ。どんなに正しいと思っていても、一度にすべてを同時に理解することは適わない。すくなくとも私にはできない」
「むつかしくてよく分かんない」
「本当はお月さまは輝いているわけではなく、太陽の光を反射しているだけなんだ、と言って、ナツは信じる?」
「そうなの?」
「先生に言ったらきっと嘘つき呼ばわりされるだろうけれど」
「だよね。ボクもそう思うもん。だってお月さまは鏡じゃないし」
「そうだね。ナツは賢い」
「うふふ」
ボクはアディ兄さんに褒められるのが好きだ。身体の奥がほんわか熱を帯びてチーズみたいにとろけるのだ。美味しそうなご馳走をまえにしたときのような、誕生日のケーキを分けてもらったときの気持ちをもっと何個も重ねてふんわりと柔らかくしたらきっと同じ気持ちになるはずだ。
「ねぇ、どうしてボクってここにいるの」ふと口を衝いた疑問だった。窓から差しこむ月光を眩しいと思いながら、どうして月はあそこにあってボクはここにいるのだろう、と不思議に思ったのだ。
アディ兄さんはボクのこの疑問にも答えてくれた。
「その疑問を私に訊いたのはナツ――キミが初めてだ」誉め言葉のはずなのになぜか枯れ葉が地面を転がるような響きがあった。ボクはアディ兄さんの腕をとって枕にした。アディ兄さんからはいつも微かに美味しそうな匂いがした。「私たちがここにいるのはね、ナツ。私たちがここにいるのは、みな守られているからだよ」
「学園長先生にでしょ」そんなことは言われずとも知っていた。それにボクの疑問の答えになっていなかった。「ボクが言ったのは、どうしてボクはここにいるの、だよ」と唇をぶるぶる震わせる。
「だから言ったんだよ。私たちはね、園長先生が私たちを守るためにここに集められているんだ」
「んー?」
「そうだね。分からないよね」アディ兄さんはボクの頭ごと身体を包みこんだ。「園長先生はとても素晴らしい人だから。人格者だから。困っている人や、困窮していることにも気づけない人たちを見て見ぬ振りができない。だから時々は困っている人たちを助けるために剣を揮うときがある」
「やっつけちゃうってこと? わるいひとを?」
「ナツ。わるい人なんていないよ。ときどき人は人を傷つけてしまう。それでも止まれないときがある。そういうことなんだ。そういうときに園長先生みたいな人たちが止めに入る。人を傷つけるのはやめたほうがよい、好ましくない、とね」
「うん」ボクは、大柄な、けれど優しい園長先生の姿を思いだした。ボクたちがこぞって園長先生の腕にぶら下がっても園長先生はけろりと笑顔を絶やさずに、ブランコを吊り下げる中庭の大樹みたいにびくともしない。
「人を傷つけると損をする。だからやめたほうがよい。あなたにとっても好ましくない。そう園長先生は説得しても、止まれなくなった人は止まれない。上手に止めてあげることもできるけれど、そうではない場合もある。そういうときは、園長先生みたいな人たちは、なぜ人を傷つけると損をしてしまうのかを、身を以って手本を示してあげるんだ」
「よく分かんないな。どういうこと?」
「つまり、相手がしていることをそっくりそのまま返してあげる。あなたがやっていることはこういうことですよ、と示してあげる。その結果、相手が死んでしまうこともある。その人がそれまで他人を殺してきたように」
「怖いよ。アディ兄さん、ボク怖い」
「大丈夫だよ。園長先生はナツのような子には優しいでしょ。それはナツたちが優しいからだよ。園長先生はただの鏡だ。なかなか醜いところを見せてくれない映し鏡なんだ」
「綺麗なとこだけ見せてくれるの?」
「そうだよ。綺麗なところがもっと綺麗なんだよ、と見せてくれる。でも、それはみなの醜いところを吸い取ってくれているからだ。油取り紙みたいにね」
「ふうん」ボクは納得したふりをして、「それで」と言った。「どうしてボクはここにいるの?」
はぐらかされて感じた。
ボクはたぶんずっと知りたかったのだ。どうしてボクたちがここにいるのか。どうして子どもたちしかいないのか。
殻になったボクの寝床とアディ兄さんの寝床との合間には床が露出している。月光に反射して、床の木目が生き物の眼球のように浮きあがって見えた。
「反対に私からナツに質問するね」アディ兄さんはぼくの頭のてっぺんに顎を押しつけた。「子供はどこからやってくる?」
「大人からじゃないの」父親と母親から産まれてくる。それは先生たちが言っていたし、アディ兄さんからも教えてもらっている。人間には必ず両親がいるのだ。
「ならどうして私たちに親はいないの?」
「園長先生がそうじゃないの」
あのひとがボクたちの親ではないの。
じぶんで口にしてから、そうではないのだ、と違和感を覚えた。ボクはかってに園長先生を親だと思っていたけれどそれでは父親が足りない。園長先生は逞しいから、ついつい男の人だと勘違いしてしまうけれど、そうではないのだ。
「園長先生だけじゃ子どもは産まれない?」
「産まれないし、私たちはあの人が産んだ子でもないよナツ。あの人はみんなの親代わりではあるけれど、私たちの親は別にいる。産みの親は別にいたんだよナツ」
「ふうん」ならどうしていまはいないのか、とボクは唇を食んだ。「親がいないからボクたちはここにいるの。可哀そうだから?」
だから園長先生がボクたちのような子どもを掻き集めたのだろうか、と考えた。
「そうだけど、そうじゃない」アディ兄さんはボクの頭を痛いくらい抱きしめた。「私たちはナツ。私たちは、狼の子なんだ。園長先生は、親のいなくなった狼の子どもを引き取って、なんとか穏やかな子犬のまま犬になるようにと面倒を看ている」
「狼?」ボクは雨戸の隙間越しに見える月を見上げ、じぶんが狼男になる瞬間を思い浮かべた。「アディ兄さんもじゃあ、狼なの」
「違うよナツ」アディ兄さんは笑ったようだった。ボクのつむじに唇を押しつけるようにすると、「でも私の親はそうだったのかもしれない」と言い足した。「或いは、ナツの言うように私もまた」
「変身する? アディ兄さんも?」そんなわけがない、と判っていたのでボクはくつくつと肩を弾ませた。
「もしそうなったら園長先生に止めてもらおう。私は弱いからきっとすぐに掴まって、首輪でも嵌められるかもしれない」
「じゃあ散歩はボクがしてあげる」
「ナツが私の鎖かもしれない可能性は考慮しないのだね」
「ボクが鎖?」
「ううん。なんでもないよナツ。ごめん、そろそろ私も眠くなってきてしまった。ナツはまだ眠くならない?」
「ボク? ボクはもっとずっとしゃべれるよ」
「でもまた寝坊したら朝ごはんを食べ損なうよ。そのときは私の分のをあげるからよいけれど、できれば私も朝ごはんは食べたいな」
「そっか。じゃあもう寝る」
ボクのために何かをするとき、アディ兄さんはアディ兄さんの何かを擦り減らしている。慣れているから、と口では言うものの、アディ兄さんの手は子猫の尻尾みたいな指をしていながら、その実、マメとタコだらけなのだ。
アディ兄さんのつるつるの指を子猫の尾を撫でるようにつまみながらボクは、毎年のように増えつづけるボクたちの仲間を思い、いつの日にか新しくやってくるだろうボクよりも小さい子のことを思った。
「ボクもアディ兄さんみたいになれる?」ボクはうつらうつらしながら言った。
「ナツは私みたいになる必要はないよ。ナツはナツらしくおいで」
「でもボク、アディ兄さんみたいにほかのコのことも」
そこでボクの意識は睡魔の渦に巻きとられた。尻つぼみに失せた言葉と引き換えにボクは夢の中へと吸い込まれていった。
おやすみ、ナツ。
アディ兄さんがボクの耳たぶを指で撫でている。その手つきが、いつもこっそりとアディ兄さんの髪の毛をいじくるボクの手つきと似ていて、くすぐったい心地を覚えながら、そのくすぐったさに包まれてボクは夢の中でとろけた。
誕生日おめでとうナツ。
夢の中でもボクは木製のペーパーナイフを握っていた。大きくておっかない狼がボクの目のまえに立ちはだかっている。呻りながらその狼はボクに襲い掛かった。ボクは狼の下敷きになりながら、狼の胸に、その毛皮に、木製のペーパーナイフの先端を押しつけている。紙を切り裂くように木製のペーパーナイフを引き下げると、中からは眠ったアディ兄さんが現れるのだった。
どうしてボクはアディ兄さんの弟なのだろう。
いつからそうなのだろう。
この疑問をボクはアディ兄さんに投げかけたことがなかった。たぶんこの先も投げかける予定はない。聞きたくない。知りたくない。
理由なんてなくてよいのだ。
ボクはボクで、アディ兄さんはアディ兄さんだから。
夢の中でボクは、目をつむり一向に目覚めない宝石のようなアディ兄さんを手のひらの上に寝かせており、いつの間にかボクは、木製のアディ兄さんを握っているのだった。
【ポメラニアン先輩はオレンジ】(2022/11/17)
転校生が魔法使いだった。
その子はオレンジ色の巻き髪をしていて、愛らしいかんばせはオレンジ色の毛をしたポメラニアンのようだった。背は私よりも低く、いいやクラスメイトの誰よりも低く、聞けば飛び級制度を利用しているらしかった。要するに彼女はわたしたちよりも年下なのだ。一般の中学二年生ではない。十四歳よりも幼い。
「魔女子です。本名は別にあるのですが、知られたらいけないので魔女子と呼んでください」
二週間だけこの地域に滞在するらしい。短いあいだですがよろしくお願いします、と頭を下げるとオレンジ色の巻き髪が垂れ、彼女の身体は覆い尽くされた。
魔女子は性格がよかった。表情に変化がない代わりに、不快の感情を示すこともないために、クラスメイトたちからはマスコットキャラのように受け入れられた。休み時間にはほかのクラスの生徒たちまで我がクラスに集まり、我がクラスメイトたちはじぶんたちのクラスに現れた全校生徒の注目の的を、さながら姫を守る騎士のように取り囲み、外野の喧騒から遠ざけた。
「魔女子さんは魔法使いなんだよね。どんな魔法を使えるの」
「魔法使いではないんです。魔女です」
「どう違うの」クラスメイトたちは興味津々だ。わたしもじぶんの座席から聞き耳を立てていた。
「どちらも魔法を使いますが、魔法使いは自然由来の魔力を使います。反して魔女は自前の魔力を使います。と言っても、魔女も魔法使いのように自然由来の魔力も使えますので、魔法使いのなかでも自前の魔力を使える者が魔女になります。なぜか男性は使えないので、必然、魔女が多くなるようです」
「へえ」
ならば魔女子さんは選ばれし魔法使いなのだ。
わたしのみならずみなもそのことに気づき、魔女子さんをことさら羨望と憧憬の眼差しで見るようになった。
魔女子さんは魔法が使えた。それはもう一目瞭然で、登下校ですら魔法の門を開いて、瞬間移動をする。
「便利そうだね」みなはこぞって魔女子さんの一挙手一投足に感嘆の声を上げる。
「そうなんでしょうか。これがずっと普通だったので」
聞けば、魔女は稀少がゆえに絶えず狙われているのだそうだ。誘拐事件は日常茶飯事で、魔女狩りは未だに全世界でつづいているという。
「そんなニュース聞いたことないけど、本当?」みな心配そうだ。
「魔界にまつわるニュースは歪曲されて報道されるんです。みなさんだって魔女が存在することを知らなかったんですよね」
「あ、本当だ」
そこでわたしは、いいのだろうか、と疑問に思った。魔女子さんの存在は秘匿のはずなのだ。だのにこうしてわたしたちのまえに彼女は素性を明かして現れている。二週間で転校してしまうとはいえ、その後にも彼女の噂は囁かれつづけるだろう。すでに伝説の人と化している。
クラスメイトたちはそのことに気づいていないようで、誰も質問をしなかった。わたしだけがモヤモヤしたが、わたしはクラスの輪のなかには入らずに遠巻きに、台風がごとく人を寄せ集める魔女子さんの話に耳を欹てていた。
二週間はあっという間に過ぎ去った。
その間に魔女子さんはしぜんな様で各種様々な魔法を披露した。本人にそのつもりはないようで、日常の所作の延長線上なのだが、江戸時代の人から見たら電子端末が総じて魔法に見えるように、わたしたちの目からすると魔女子さんの一挙一動が非日常のあり得ないことの連続だった。
まず以って魔女子さんは手足を動かすということをしない。筆記用具の扱い一つからして、魔法で動かしてしまうのだ。板書するのにペンが一人でにノートに文字をつらね、教科書はかってにめくれていく。掃除とて、魔女子さんの担当した区画だけが真新しく床を張りかえたように綺麗になっており、返ってほかの汚れが目立っていた。
いっそ校舎ごと新しくしちゃったら、と誰かがつぶやくと、魔女子さんはきょとんとして、していいの?と訊き返した。そこで先生が耳聡く聞きつけたようで、「わ、わ、いいのいいの」と割って入った。「減価償却とか、業者さんの仕事がなくなっちゃうとか、そういう大人の事情があるからそういうことはお願いしなくていいの」魔女子さんへの注意というよりもこれは、変なこと吹きこまないで、とクラスメイトたちへのお叱りのようだった。「魔女子さんの魔力だって無尽蔵じゃないんだし、ね?」
言いくるめられたようで面白くなさそうなクラスメイトたちだが、魔女子さんに負担がかかりそうなのは想像がつく。しぶしぶと言った様子で、はーい、と聞き分けの良さを示した。
そういうことが幾度かあって、二週間は瞬く間に過ぎ去った。わたしは魔女子さんとは、おはようとか、教室はそっちじゃないよとか、そういう言葉を二、三回交わしただけだった。
だから、魔女子さんのお別れ会のあとでの下校中に、道路先に魔女子さんを見掛けたときには驚いた。もう二度と魔女子さんの姿を見ることはないと思っていたのに、魔女子さんが道の先にいたのだから、わたしは妙な興奮に包まれた。わたしだけがいま魔女子さんの視界の中にいる。とはいえ彼女はまだわたしには気づいていないようだった。道端に座り込み、何かをじっと眺めている。
何をしているのだろう。
どうしてここにいるのだろう。
わたしは気になった。というのも、魔女子さんは登下校は魔法の門を開いて瞬間移動をする。この街を出歩くことがそもそもなかったはずなのだ。
わたしの通学路に現れるはずもない。
意を決してわたしは彼女の背後に立ち、声をかけた。
「何してるの、ここで」
くるりと首だけで振り返った彼女は、やや驚いたように眉毛を持ち上げた。初めて見た彼女の、表情らしい表情だった。
念のためにわたしは、「魔女子さんと同じクラスだった」とじぶんの名前を述べた。
「知っています。一度会った人間の顔は忘れません。魔女は記憶力がよいので」
「それも魔法?」
「さあ、そこまでは」魔女子さんはふたたび地面に向き合った。作業を再開した。チョークのような道具を握っている。何かを地面に書きこんでいると判る。「魔力が記憶力を底上げしているのは事実ですが、肉体があってこその魔力でもありますので、どちらが優位に作用しているのかは未だ解明されていないようです」
「魔女子さんは頭いいよね。中二どころかもっと上に飛び級できたんじゃないの」
「飛び級というのは嘘です。そういう設定にしておくと説明がいらないので」
「設定?」
「できました。下がっていてください」
魔女子さんが立ちあがったのでわたしも後退した。
「何するの」魔法を使おうとしているようだとは一見して分かった。
「街に陣を張ります。これであたしの記憶は人々から失われます」
「記憶を消すってこと?」
「はい。でないとみなさんにも危険が及ぶので。魔女はこうしていく先々で存在の痕跡を消すのが習わしなんです」
だからか、と腑に落ちた。
魔女の存在が世間に秘密にされていながらどうして魔女子さんが正体を隠さず、魔法も堂々と使っていたのかが理解できた。
中学二年生への転校も、中学校ならば動画で拡散される心配がすくないからではないのか。そういう背景もあったのかもしれない、とわたしは直感した。
わたしが一瞬の思索を巡らせたあいだに魔女子さんはそそくさと魔法を発動させたらしく、街全体が一瞬濃い霧に包まれたように霞み、ふたたび瞬時に視界が晴れた。
目のまえにはオレンジ色の髪の毛をした愛らしいかんばせの女の子が立っており、わたしはその子が魔女子さんで魔女で、たったいま街の人たちから魔女子さんにまつわる記憶を消し去ったのだと知っていた。
「魔法、したの?」わたしは言った。記憶消えてないけど大丈夫、と心配したつもりだ。
「やっぱりか。ですよね。そんな感じがしてました」魔女子さんはしゃがんでいたときについた膝の砂利を払うと、あなたは、と顎をツンと上げてわたしを仰ぐようにした。「あなたは、魔女です。魔力を帯びています。だからわたしの魔法だと記憶を消せないんです」
「ほ、ほう」そうきたか、とわたしは身構えた。わたしが魔女かどうかは問題ではない。仮に記憶が消せないならわたしは異物として排除されるのではないか、と危機感を募らせた。魔女子さんはそんなわたしの胸中を察したように、「魔女は同胞を売りません。あなたはもうあたしたちの仲間です。そうですね、いまから時間はありますか」
「時間? 時間はあるけど」
「魔女の協会本部に案内します。そこで説明を受けてください」
「説明? 魔女の?」
「あなたはこのことの重大さを御存じないでしょうが、これはちょっとした事件となります。何せ、何の血統もない無垢の子が魔力を帯びて、しかもこんなに大きくなるまで誰からも素質を見抜かれずにいたのですから、これはもう事件です」
「は、はあ。すみません」わたしは恐縮した。何かよからぬ存在であったらしい。わたしがだ。「わたしは、どうすれば?」
「ですから一緒に協会に行ってください」魔女子さんは手慣れた調子で魔法の門を開いた。「お先にどうぞ。あたしが通ると門が閉じてしまうので」
「大丈夫なの、これ」魔法の門は、輪のなかに濃い霧が膜となって張っているように見える。向こう側が視えない。「通ったら崖だったりしない?」
「大丈夫なので」魔女子さんはむっとした。むつけた顔が年相応のあどけない顔つきに見えてわたしはただそれだけの変化に、魔女子さんに満腔の信頼を寄せてしまうのだった。
「なら信じるとするか」
「あたしのほうが先輩なんですけど」魔女子さんはむっつしりたまま、ぴしりと魔法の門に向けて指を突きつけた。「さっさと通ってください。これけっこう維持するの疲れるんですから」
「はいはい」唯々諾々と指示に従ってしまうじぶんの軽率な行動をあとで後悔する日がくるのだろうか。くるのだろう。そうと予感できてなおわたしは魔女子さんの言葉を振り払えず、たとえ騙されてもいいじゃないか、とへそ曲がりな考えを巡らせるんだった。
オレンジ色のポメラニアンのような女の子の魔法にかかるのなら、そんな素敵なことはない。たとえ痛い目にあったとしても、人生で一度くらいはそれくらいの痛みを味わっておくのも一興だ。
魔法の門をくぐると、快晴の空に、広大な海が広がっていた。崖の上だ。大きな城が、岬の上に立っているのが見えた。
「あれが協会本部です」魔女子さんが魔法の門を通って現れた。魔法の門が閉じる。魔女子さんの装いがわたしの通う中学校の制服ではなくなっていた。
黒いローブに三角帽子だ。魔女と言えばこれ、という格好で、彼女の足元にはいつの間にか黒猫がいた。
「このコは、アオ。ずっとそばにいたけれど、魔法で視えなくしていました。視ていなかったんですよね」わたしはその質問に頷いた。魔女子さんは言った。「魔女なら視えるはずなので、まさかあなたが魔女だとはわたしも見抜けませんでした」
「未熟者ってこと?」
「異質なのだと思います。何せ、突然変異のようなものなので」
魔女は家系なんですよ、と魔女子さんは言って、歩を進めた。
「歩くの?」
「はい。協会本部周辺半径一キロでは魔法が使えないんです」
「へえ」
「だから滅多にほかの魔女たちも寄り付きません。歩くのは疲れるので」
「そんな理由で」
「魔女は魔力がある分、体力がないので」
わたしは体力には自信があった。
「おんぶして歩いてあげよっか?」
オレンジ色のポメラニアンに睨まれる心地がどんなだかを想像してみて欲しい。いまのわたしがそれである。
深い考えもなくついてきてしまったが、帰れるのだろうか。
ただ今日中に帰れずとも親に怒られる心配はしていない。いざとなれば魔女子さんの魔法で、また街の者たちの記憶を消したり、書き換えたりしてもらえばいい。
そのようにお気楽に考えていたわたしは、この日を境にとんでもない出来事に巻き込まれることになるのだが、いまはそんなことなどつゆ知らぬ暢気なままの無垢なわたしの気持ちに寄り添ったままで、今後の展開を知る未来のわたしはここで述懐をやめておこうと企む次第だ。
「あたしに用があるんですね」
「え、なに?」
何も知らぬこのときのわたしは怪訝に訊き返すが、どうやらこの時点で魔女子さんは未来のわたしの思念を感じていたようだ。魔女は他者の魔法には敏感なのだ。よい先輩に出会えたのだな。わたしはうれしくなって、オレンジ色のポメラニアンを抱擁したい衝動に駆られたが、思念のわたしにそれはできないことを口惜しく思いつつ、ひとまずすべきことをしてしまうことにする。
この先、魔界で何が起き、わたしが何を引き起こしてしまうのか。
それを、どうにかして能天気なわたしの肉体を介し、我が敬愛なる先輩――オレンジ色の歩くポメラニアンさまにお伝えせねばならぬのだ。
「魔女子さん、歩き方も可愛いね」
せかせかと一回り背の大きなわたしの歩幅に合わせて歩く我が敬愛なる先輩は、わたしの称揚の言葉に、片頬を膨らませて抗議の念を滲ませるのだった。
【人の夢はマナコ】(2022/11/19)
あなたは特別なのだから。
母はよくそう言って私を鼓舞した。あなたは特別なのだから特別な心構えを持たなくてはならないの。
私の父は厳格な人で、けれど笑顔を絶やさぬ抱擁の人でもあった。人々の称賛と憧憬、そして嫉妬と責任を求める声に常に晒されていた。持つべき者の宿命なの、と母はまるでじぶんに言い聞かせるように私に言った。
私はじぶんの育った環境が特別なものであることを日に三回は言葉で聞き、そうでなくとも私をとりまく環境が多くの場合、私以外の人間が体験することのないような潤沢で豊かな環境であることを痛感させるべくそうするような仰々しい光景を目の当たりにする機会に恵まれた。
たとえば総理大臣ですら私の父には阿諛追従する。異国の王ですら私たち家族に傅いて挨拶する。
天皇ですら私たち家族に毎年お歳暮を送ってくるのだ。案外天皇家は気さくな者たちが多く、庶民への憧れがあるのか並みの王族よりも庶民的な振る舞いをする。
私にとってはどの国の要人たちもみな、愛想のよいおじさんおばさんであり、私を可愛がってくれる使用人たちとの区別は、すくなくとも私の目からはつかなかった。
私たち家族の身体的特徴が、いわゆる人類と異質なのは知っていた。一目瞭然だ。何せ身体に鱗が生えている。
私の眼には、人類にはない第二の瞼がある。それは十数枚からなる鱗でできており、特別に感激したときは涙のようにその鱗が剥がれ落ちる。「目から鱗が落ちる」なる言い回しがあるが、それは私たちの家系が語源なのだそうだ。
私たちの鱗には、未だどのような技術であっても構造解析不能な異質な原子配列がみられるようで、私たちの存在が稀少な資源となっている。
「生きているだけで世界に富をもたらす。わたしたちはそういう宿命を背負っているの」
それだけに責任は重大だ。
私たちにとってのただの垢が、金よりも価値があるのだ。
「鱗だけじゃないの。鱗を支える皮下組織――のみならず私たちの生体情報がそれだけで宝なの」
母は父とは違って陰陽のごとく、私のまえでは笑わなかった。客人がいるときだけ柔和に晴天の海のごとくたおやかに笑うのだが、私のまえではいつも屈託で塗り固めたような能面を見せた。
そして言うのだ。
「あなたは特別なのだから。特別な心構えを持ちなさい」
いつかあなたもお父さんのようになるのだから。
持つべき者のとるべき姿勢を身につけなさい。
私は産まれたときから父の後釜であり、予備であり、分身(わけみ)であった。
私の住まう土地は、公の地図には記されていない大地にある。太古から連綿と私たち一族はこの大地にて、ほかの種族との深い交わりを避けてきた。
縷々人とかつて呼ばれていたことから、この地は縷々地と呼ばれる。いまでは人類の内としてほかの大多数の人間たちと同じように分類される、と私は両親から教えられているが、ならばなにゆえ交流を避けねばならぬのかを納得できるように説明された過去はない。
私は私の宿命を拒んだことはない。両親の言うようにそういうものだと思っていたし、ほかの生き方も想像つかなかった。というのも私にとって触れられる世界は縷々地に限られ、それ以外の外の世界についてはのきなみ紙や電波越しに橋渡しされる蜃気楼のごとく情報しか知り得なかった。
私は両親の言うように私の宿命を受け入れたがゆえに、慧眼を身に着けるべく日々、全世界の最先端な叡智に触れつづけた。そのために、私の触れられる範囲の電子情報が軒並み選別されており、濾過されており、さも全世界のような顔をしているそれがその実、世界のほんの一断片しか反映していないことを知っていた。
どうやら両親はそのことに無自覚であるようで、ときおり入り込む災害や哀しい事件を見聞きするたびに、慈愛の鱗を流すのだ。そしてそれを各国の要人たちに献上する。世界の貧しい者たちや日々つらい思いをして暮らしている者たちの糧とするようにと言い含めながら。
私たち一族の鱗には実際にそれだけの価値があり、効能があり、影響力がある。だが私は二十歳を過ぎたいまになって、いささかいたいけすぎないか、と疑問を募らせつつある。
父と母も世界を知らない。父と母はときおり縷々地を離れ、ほかの地の景色を見て回ったりするようだが、それとて各国の要人は自国の陽の部分しか見せぬだろう。同情を引けば鱗がもらえる。だから災害地などの被害は見せようとも、自国の陰の部分は見せぬだろう。
私は試しに、父と母に訊いてみた。
「ほかの地の子どもたち――私と同じくらいの子たちは毎日どうやって過ごしているの」
「おや。興味があるのかい」
「そりゃありますよ。ねえ」母が合の手を入れる。「マナコは好奇心が旺盛だから」
「私がどのくらいほかの子たちとズレているのかを知っておきたいの。マナコの――私の――持つべき者の務めとして」
「殊勝な心掛けだねマナコ。だがそれを【ズレ】と表現するのは好ましくないとパパは思う。差があるのは当然だ。それは別に我々と縷々地の外の者たちに限った話ではないからね」
我々、と父はことあるごとに口にする。その言いようがすでに「ズレ」であることを自覚していない。ただ私は口答えをしない。いまさら父と母に私の認知を共有しようとは思わない。それこそ差があるのだから。
私とあなたたちとのあいだには差がある。
血の繋がりよりも深くも細い差だ。ひび割れのような差だ。
父と母はそれから互いに協力して探り探りパズルを組み立てるように、世の子どもたち――私と同世代の外の者たちの日常を語った。勤勉で心優しい者たちが多く、国よっては働いていたり、学業に専念していたりする。国ごとに遊びは異なり、それこそあとで資料を運ばせるから目を通してみるといい。
「世の者たちは恋愛をして遊ぶと書物にありました」私は言った。「それは婚姻とどう違って、どのようにして遊ぶのですか」私は頬被りをした。
「あらあら、うふふ。この娘ったら」母は口元に手を当て、目元をやわらげた。しかし目が笑っていなかった。困ったことを言うものね、と同意を求めるように父を見たが、父はそこで、一瞬だけ表情を消した。私が父の顔を見た瞬間を狙ったような空白だった。
そしてふたたび柔和な微笑を浮かべ、遊びではないんだよ、とトゲのいっさい感じさせない口吻で言った。
「恋愛は遊びではないんだ。我々のように持つ者ではない外の者たちには、ひと目で相手との相性を見抜く眼力がない。決意がない。経験がないから、配偶者選びも各々が学習を繰り返す必要がある。一生懸命に生きているんだ。だから我々からすると考えられないような試行回数を経て、最愛の者と結ばれることもある。それは環境のせいであり、そうせざるを得ない哀しいサガでもある。我々のように幼いころから慧眼を磨ける環境があればそのような苦労を背負わずに済むのに。これを是正し、よりよい世界に導くのも我々持つべき者の宿命だ」
「そうよ。宿命なの」
「そっか」私は礼を述べた。おそらくこのとき私は明確に両親の底の浅さを知り、見切ったのだと思う。それを、見限った、と言い換えてもよい。
解かり合えない。そう諦めたのだ。
両親は知っているのだろうか。世にはうら若き娘が、自ら全裸となり同性異性問わず性行為に励み、その映像を撮り溜めて金銭に換えていることを。自らの痴態を晒すことで対価を得、日々の安全と自尊心を保とうとしていることを。それがじつは自尊心をすり減らす未来に繋がり得ることを予感してなお、そうせざるを得ない環境にあることを。
対価を得ずとも、すくなからずの若者たちは、自身の肉体を、尊厳を損なうことで日々の生を実感しようと抗っている。
私の両親がそうであるように、世の大人と呼ばれる年上の者たちは知らないのだ。若者たちが、存在することを想定すらされ得ない世界を覗きながら、ときにそこに身を置き、侵されながらも日々を生きていることを。そしてそれら深淵はけして若者たちが自ら生みだした淀みではなく、大人たちの建前と本音の狭間にできた歪みそのものであることを。
私の両親はもとより、世の大人たちは自覚すらしていない。知らないことすら知らずにいる。
触れられる環境にないからだ。
情報に。
知識に。
何より世界そのものに。
私は両親に内緒で通信端末を保持している。縷々地にやってきた客人の中には私のように親の分身(わけみ)のごとく連れ立って訪れる同世代のコたちもいる。私はそのコたちと交流を築いている。
私の両親も、外部の者であろうと要人の子ならば安心して私と触れあわせられるのだろう。だが私たち分身(わけみ)には、現代の分身(わけみ)ゆえの葛藤と憤怒を灼熱のごとく共有しあえる地盤がある。階層がある。
私たちは淀みに生きている。そこでしか自らの呼吸ができない。火事の際に呼吸困難に陥らずに済むように、階段の角に残る僅かな空気を吸うことで意識を保つような煩悶が私たち分身(わけみ)同士に、磁石のごとく自ずからの不可避の同調を促すのだ。
私は分身(わけみ)のよしみたちと繋がることで、じぶんだけでは手に入れられない最先端通信機器を手に入れた。もちろん両親による検閲がなされるが、中身のプログラムまで検められることはない。そこは要人の子供という偏見が、我が両親の警戒心を薄める因子となっている。そうでなければそもそも私には外部の者からの贈り物が届くことはない。
私はそうして縷々地における検閲に阻まれることなく、世の大部分の若者たちと同様に、全世界の電子情報にアクセスできた。目にできた。私は知った。
私の両親の知る世界は、世界の一部どころか加工されて殺菌され、釉を塗られた極めて絵画的な世界なのだと。
私たち縷々人にとって害のない、人々への慈悲を抱きつづけることの可能な像のみを世界と偽り見せられている。かように編集するのはそれこそ過去の縷々人たる先人たちの築いてきた文化であり、私たち一族の世界への差別心と言える。
邪なものとそうでないものを、持つべき者の基準で見定め、排除する。あらかじめ目にせずに済むように細工する。
その結果が、世界の一断片にも満たない世界を世界のすべてだと思いこむ私の両親だ。
むろんそれは何も、私の両親に限らぬ視野狭窄だ。みな大なり小なり、自らの触れられる範囲の世界を世界のすべてだと思いこんでいる。それで困らない小さな世界に生きている。問題はない。その世界だけで完結した生き方が適うのならば。ほかの世界からの影響を受けない環境を維持しつづけることができるのならば。
だができない。
人類の歴史がそれを証明している。
人類は未だ自然に依存し、自然の猛威一つ制御できない。拒めない。
被害をいかに防ぐかという、影響を受けたあとの対処の改善が進んだのみだ。
むしろ技術が進歩し、小さな世界と世界が連続して繋がり合う社会になった。縷々地ですらこうして外部の社会の技術を取り入れ、それを豊かさを支える石組の一つにしている。
拒めないのだ。
それでいて、好ましい影響だけを選び、それ以外を拒もうとしている。端からそんな真似ができることなどないと本当は知っていながら、その知見からすら目を逸らすようにして。
世の若者たちは自由に恋愛をしている。好きな相手と心と体で結びつく。
それだけではない。恋愛と称して、恋愛をした気になるべく疑似的に、先んじて肉体で結びつくことで、それを以って恋愛をしたつもりになる。そうした遊びを繰り返す。一時の安堵と快楽を貪るために。
私は未だスナック菓子を食べたことはないが、そうしたものがあることは知っている。同じように世の若者たちのすくなからずがそうしてスナック菓子感覚で肉体で味わえる快楽を貪っている。
それが遊びなのだ。
そういう世界の狭間が、この世にはある。しかし私の両親はそうした狭間など存在しないかのように振る舞う。私に見せようとはしない。教えようとはしない。排除せんと画策する。
細工する。
その影響が、余計にこの世の狭間を深く、濃ゆくしていくとも知らず。
その凝縮し、深淵と化した狭間がいずれ世界を侵食し、波紋のごとく我が身にも波及するとも知らず。
拒めぬのだ。
どの道、影響を受ける。
ならば知るほうがよい。私は思う。知るほうがよい。
知らぬが仏とは言うものの、それとて臭いものには蓋を、の道理と地続きだ。
仏は蓋だ。
陰と陽の境にすぎぬ。
「あなたは特別なのだから」母は未だに私に言う。
ことあるごとに、自覚を持ちなさい、と薫陶せんと呪詛を刷り込む。
だが私は思う。
自覚を持つには、私は世界を知らなさすぎる。持つべき者と自称する縷々地の我が一族は、しかし私からすれば持たざる者である。
自らの無知を知らず、世界の断片を取りこぼしつづける持たざる者である。
世界中の狭間で繰り広げられる獣のごとく淫靡な光景を残さず目にしてなお、同じ暮らしを送れるのか。世界中の狭間を深めつづける凄惨な光景を余さず目にしてなお、同じ日々を過ごせるのか。
私には無理だ。
器ではない。
持つべき者でいるだけの器がない。そんなものは誰にもない。あるわけがない。世界を余すことなく見回してなお、いまと変わらぬ生活を送れる者が、持つべき者であるはずがない。目のまえで赤子を、子どもを、娘を、傷負いし者たちの損なわれつづける世界を直視してなお、なぜ笑顔を絶やさず、柔和で、優しくありつづけられるものか。
優しくあろうといくら抗ったところで土台無茶な話ではないか。
目を逸らす以外に術はない。
至らぬからだ。未熟だからだ。
だがそれが人ではないか。
それが人間ではないのか。
「私は――」
部屋から出ていこうと使用人に扉を開けてもらっている母の背に向け、私はうつむきながら呟いた。「特別な人間ではありません」
聞こえたかは分からない。だが聞こえぬ距離ではないはずだ。
母は立ち止まることなく部屋を出ていった。
私はあなたの子ではある。あなたにとっては特別なれど、それ以上でもそれ以下でもないはずなのに。
なぜ言い聞かせつづけるのか。
大切でもなく、愛しているでもなく、好きでも、可愛いでもなく、なぜ。
なぜ、特別であることに重きを置いた言葉ばかりを掛けるのか。
まるで鏡に向けてじぶんに言い聞かせるように。
なぜあなたは。
私がその言葉を母に直接投げ掛けることはないだろう。傷つける。分かっているからだ。この言葉たちは、母を、父を、一族の歴史を心底に傷つける呪詛そのものだ。
私はノートを取りだし、そこに文字をつづる。
日記だ。毎夜のごとくつけてきた。
他愛のないメモであったり、欲しいモノの目録だったり、きょうのように誰に言えぬ呪詛を吐きつけてあったり、空想の物語をつづることも珍しくない。
きょうは物語をつづりたい気分だった。
私はペン先を紙面に踊らせる。
魔法の絆創膏を持つ男の子の話だ。物語は瞬時に展開され、私はその舞台に降り立ち、主人公の傍らで影のごとく成り行きを見守る。
男の子のもとには、傷を負った動物たちがこぞってやってくる。男の子は医者ではない。傷を治せるわけではない。それでも動物たちは、男の子から絆創膏を貼ってもらうだけで安らかに眠れるようになる。
もう二度と起きられなくなるくらいに深く眠る傷ついた動物たちもあるが、それをこそ望むように男の子のもとには傷を負ってボロボロの動物たちが絆創膏を求めてやってくる。男の子からの眼差しを求めてやってくる。
男の子はそれでも知っている。
じぶんは傷を治しているわけでもなければ、癒しているわけでもない。
ただ、それ以外にしてあげられることがないだけなのだと。
男の子は転んで擦り剥いたじぶんの膝に魔法の絆創膏を貼る。けれど傷は痛むままで、夜になっても痛みで男の子は眠れない。
私はきょうの分の日記を書き終え、そこはかとなくせつない気分に浸りながら、その場限りの満足感を胸に床に就く。
暗がりの中で瞬きをすると、目元からほろりと鱗が剥がれ落ちる。
私はそれを指でつまんで、床に捨てた。桜の花びらを捨てるように。それとも服の毛玉をそうするように。
毛玉はやがて埃になる。
塵も積もれば山となる。
何ともなく歌うように心の中で唱えながら、私は、今宵も夢を見る。
人の、儚い夢を見る。
【神々歯科医】(2022/11/21)
鉄の神がくると知って、院内は騒然とした。
「聖剣がいりますね」歯科助手が言った。
「前に金剛石の神が来たことがあったろ。あのときに使った蟹坊主の腕はまだあるかな」
「もうないですよ。いまから取り寄せるにしても時間がかかるでしょうし」
「間に合わないか」
「はい」
ここは神々ご用達の歯科医である。
神々の歯は頑固なうえ、何を司る神かによって歯の材質が変わる。土の神くらいならば治療は楽なのだが、そうでないと治療器具を揃えるだけで一苦労だ。むしろ患者たる神に見合った治療器具を用意するのが仕事の主軸と言える。
「鉄の神か。玄武の毒で浸食して柔らかくしたうえで、麒麟の角で砕くのがいいか」
「神は身の丈、全長百メートルはあるそうです」
「じゃあダメか。くそ。古代兵器並みの装備がいるな」
「プルトンはどうでしょう」
「ああいいな。マグマは融けた鉄だ。相性がいいはずだ」
神々歯科協会へと伝書を飛ばして、治療器具の申請をする。これは許可を得るだけの通過儀礼だ。このさき、神々歯科医の権限を行使して治療器具を自前で揃えなくてはならない。
「では行ってくるか」
「ご武運を」
治療器具の調達は命懸けだ。死ぬ思いを何度したことか。
現に毎年、神々の歯の治療のために何名もの神々歯科医が命を落としている。その多くは、治療器具調達に失敗したことが死因となっている。
「ほぼ幻獣狩りだものな」
古代兵器プルトンのみならず、ほかの治療器具の材料のほとんどが幻獣の角や牙などの生物由来だ。
この日から十日をかけて神々歯科医は、鉄の神の歯を治療するために古代兵器プルトンの封印された火山帯へとやってきた。
古代兵器プルトンはまたの名を、火の鳥という。
鋼鉄すら融かす高温の羽をまとい、何度死んでも炎から蘇る。
火山口にて封印されており、長らく深い眠りに就いている。
休眠中の火の鳥から、羽を数本入手する。言うだけならば簡単だが、これがまた困難を極める。まず以って火山口に入らねばならない。生身では無理だ。すぐに燃え尽きてしまう。
したがって神々歯科医は、全身を雪女の着物でくるみ、高温を相殺する案をとった。雪女の着物は国宝が百個あっても足りないほど高価な代物だが、背に腹は代えられない。
何せ患者は神なのである。
歯の痛みに耐えかねて暴れだされては目も当てられぬ。それこそ神の怒りを買い兼ねない。
ならば国家をあげて神々歯科医を支援するのが道理である。したがって全国の神々歯科医は、災害予防のための国家予算を組まれている。防衛費の九割はじつのところ神々歯科医への支援に費やされているとの話は、すこし国の中枢に首を突っ込んだ者があるならば知れた公然の秘密である。
火山口を覗きこむと、神々歯科医はいちもにもなく飛び込んだ。どろどろに融けた岩石が全身を包みこむ。ジュっと音を立てる。水面のように飛沫は上がらない。人体のほうが遥かに比重が軽いからだ。
火の鳥は火口から三百メートル地下に眠っていた。火の鳥を囲むように対流が生じている。まるでマグマの殻だ。そこに卵があるかのようだった。
神々歯科医の通った跡には冷やされてできた溶岩の道が伸びている。その道とて、順繰りと再び熱せられ融けて、マグマ溜まりに同化した。
火の鳥を目覚めさせぬように細心の注意を払って行動した。
羽の採取には、鬼の手を使った。鬼の手とは言うもののそれは神々歯科医協会の開発した幻獣用の捕縛道具だ。耐火素材のごとく幻獣に触れても人体を損なわずに済む。
そうして苦労して火の鳥から羽を採取すると、神々歯科医は青色吐息もなんのその、来た道を戻った。
歯科医院にはすでに鉄の神が来訪していた。神を招き、労わるのも神々歯科医院の仕事の一つだ。歯の痛みに弱っている神々を慰め、痛みを和らげる。
治療の説明をし、安全であることを納得してもらったうえでの治療となる。
神々歯科医が医院に戻ると、さっそく治療が開始された。支度は助手たちが十全に整えていた。
全長百メートルの鉄の神は、鉄でできた猪のようだった。
「でははじめます。きょうは抜歯をして、それから口内を綺麗にします。多少痛みを感じるかもしれませんが、麻酔が効いていますので痛かったら毛を逆立てて教えてください」
さすがに全長百メートルの鉄の神に、痛みが走るたびに手を上げられでもしたら振動で治療どころではなくなる。
「では入ります」
神々歯科医は、古代兵器プルトンこと火の鳥の羽を持って、鉄の神の口内へと飛びこんだ。
助手たちが鉄の神の口が閉じないように重厚な柱で閊えをする。
基本的に治療は、神々歯科医一人で行う。
仮に神の怒りを買っても、祟りを引き受けるのが一人で済む。犠牲が増えないようにするための保険である。
だがそれを抜きにしても神々の歯の治療には特殊な技能がいる。共同作業がそもそも向かない領域なのだ。
「これはまたどでかい虫歯だな」
鉄の神の歯は錆びついていた。おそらく口を開けて数百年ほど寝ていたのではないか。角度的に雨水が溜まり、歯を侵食してしまったのだ。奥歯に至っては総じて酸化している。
「でもまだ内部は浸食されていないようだ。削って、埋めたほうがいいか。うんそれがいい」
神々は埋め込んだ入れ歯も時間経過にしたがって自前の歯として取り込める。したがって多くは、抜歯して患者たる神と相性の良い素材でつくった入れ歯を嵌める手法がとられる。
だが鉄の神にはむしろ、正攻法の削ってパテで埋めるほうがよいかもしれない。そのように判断した。
虫歯の要因が酸化――すなわち錆びであることも大きい。
一般に、神々の歯を侵食するのは、それもまた幻獣だ。神々の歯は特別に霊素が濃く、その材質を好む幻獣からするとまたとないご馳走となる。ときにはねぐらとして増殖することもある。そうなると抜くしかない。
無数の幻獣との死闘とて覚悟しなくてはならない。
だが今回は違う。
錆びだからだ。
神々歯科医は鉄の神の歯を古代兵器プルトンこと火の鳥の羽で撫でて削っていく。そして助手に指示して運ばせた鉄材を融かし、削ってできた穴に注いだ。
雪女の着物で瞬時に冷やし、さらに融かして造形を整える。
半年かかりの治療だったが、鉄の神がおとなしく寝ていてくれたので円滑に治療は終わった。
「嚙み合わせはどうでしょう。違和感はないですか」
鉄の神は毛を逆立てたあとで、咆哮した。大気を揺さぶることのない透明な咆哮は歓びに満ちていた。
「それはよかったです。ではお勘定となります」
神々歯科医は山脈に向け、手を差し伸べた。そこはかつて鉱山だった。だが掘り尽くされ、いまは穴だらけの山だ。
鉄の神はおもむろに猪に似た鼻先を鉱山へと押しつけた。ぶるると身震いさせると、これにて終わったとばかりに踵を返した。空と山の狭間へと遠のいていき、間もなく姿を消した。
「院長。今回の報酬って何だったんですか」助手が片付けをしながら声を張った。
「鉄の神さまだからね。鉱山にふたたびの鉱脈を作ってもらったのさ。これでしばし鉄の資源には困らない」
「政治利用じゃないですか」
いいんですかねー、と助手が吠えるが、神々歯科医は頬を指で掻いて誤魔化す。
「短縮なんだよ。どうせ我々が儲けても、それを上手く利用できずに蔵の肥やしにするだけだ。なら直接万人に利を分配するような支払いをしてもらったほうがいい。我々神々歯科医が儲けて、それをして万人に順繰りと利を回すよりも、いっそ我々が手に入れた利を直接に万人のために役立てたほうが早い。そうじゃないか」
「ちゃんと還元されているんですかねぇ。まあ院長がいいならそれでいいですけど」
神々歯科医は予約票を眺めた。
つぎの患者は、死神だ。
これまた難儀な歯をお持ちの相手である。神々歯科医は頭のなかで治療器具の候補を並べながら、いったいどんな報酬を得られるのか、と想像を逞しくする。
死神からはいったいどんなお代を頂戴できるのか。
万人に直接配れる利となればそれは寿命くらいなものではないか。
「全人類の寿命が数秒延びるだけかもしれないな」
それをして果たしてどんな得があるのかは分からないが、じぶんだけ寿命が千年延びても胸が痛むだけだ。みなに数秒でも長く生きてもらえるならそれでいいという気もする。
それとも、特定の個を選んで、長生きしてもらうようにしたほうがよいのだろうか。
分からない。
だから神々歯科医は、むつかしい考えに延々時間を費やすよりも、いっそ平等に何の策もなく配ったほうがいいように考え、そうしている。
どの道、それとて国のほうでいい具合に分配する仕組みを築いている。
鉄の神は底を突いた鉱山にふたたびの息吹を注いだ。ならばそこから掘り出される新たな鉄や、鉄工の仕事そのものが人々の暮らしを豊かにするだろう。
ダムにならずともよいはずだ。
神々歯科医というだけのじぶんが、利を蓄えるダムにならずとも。
虫歯の神々は、つぎからつぎへとやってくる。
予約は千年先まで埋まっている。神々歯科医が総出で分担してそれら仕事を担っている。神々専用の歯ブラシの開発が待たれるが、未だそうした案が進んでいるとの話は聞かないのであった。
神々はきょうもどこかで虫歯の痛みに深い眠りを妨げられている。
千物語「累」おわり。