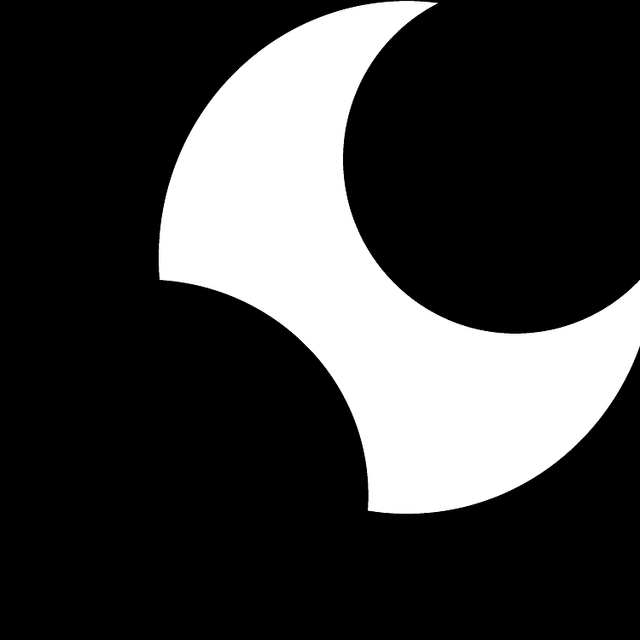千物語「虚」
文字数 113,818文字
千物語「虚」
目次
【ころもんての権化】
【お代わりをたんとおあがり】
【バイオレンス姉妹】
【きみは世界を救う愛しいひと】
【僕を死にいざなった悪霊と】
【異釣り師】
【折れた牙を刀に】
【諺かなんかですか?】
【青い花の妖精】
【旅の終わりを探し求めて】
【扇風機の値札】
【潰れる二秒前】
【晴れのち、きみ】
【闇に差す赤】
【世界改変日誌】
【予測変換の怪】
【ずるずるみっしり】
【無視でいいって】
【きみは何も変わらないはずなのに】
【返頭痛】
【日鬼】
【ゾウさんの小さいものはなに?】
【ピエロと一匹の】
【ミカさんはお姫さまになりたい】
【ミカさんはビッグバン】
【あなたにならいいよ、あなたがいいよ】
【トカゲの尻尾】
【グライダーマン】
【ピックを握りしめて】
【少年は予感する】
【お城のパーティーにとっときな】
【スペースミュージック】
【禁音の果てに】
【黙れよギター】
【一本の金髪】
【ドラマーのドラマ】
【ふたたび身体をつつみこむ】
【同期性創発体】
【少年たちの予感】
【音楽は爆発だ】
【永久に失恋】
【一気呵成に加勢を】
【青いバナナ】
【背景、あのころのわたしへ】
【背景、あのころのぼくへ】
【背景、あのころの私へ】
【背景、あのころのおれへ】
【背景、あのころのあたしへ】
【背景、あのころの僕へ】
【背景、あのころのワタシへ】
【背景、あのころのボクへ】
【背景、あのころのわたくしへ】
【背景、あのころの貴女へ】
【ころもんての権化】
道端の松の下に転がる松ぼっくりに目を留めて、アルマジロみたいだなぁ、とその奇抜な形状が連綿と引き継がれてぽんぽこ似たような姿で量産される松の木の神秘に思いを馳せていたら、もぞもぞと一つの松ぼっくりが蠢きだして、ぽっかり二つに割れたので、
ありゃま。
目をぱちくりさせてよくよく目を凝らすと、四つのちいちゃなあんよとつぶらな瞳に、ぴんぴょこ飛びだした丸っこい三角お耳の生えた頭部が、折り畳み式自転車さながらに、ぐねんこ、と姿を現した。
くしくしおめめを短いあんよで掻いたなら、ほんわか欠伸なぞを挟みまして、ころもんて、ころもんて、よたつきころけて、よちよちてとてと、歩きだす。尾っぽのたろてんたろてん、垂れた様子はほんわかほろほろ微笑ましい。
わたしは華の女子中学生十四歳であったから、そりゃあこないなめんこい生き物を見つけてしまったならば、財布の紐の堅い父母に買ってもらったばかりの最新式メディア端末でぴんぽろ画像に動画に記録せにゃあかんぜよ、と躍起になるのは自然の摂理じみている。
ひとしきりぴんぽろし終わって、むふーと鼻息を荒く噴きだしたならば、ちょいと落ち着きを取り戻す。
ちんちりーん。
そばを素通りしていく自転車にまたがった高校生におばさまたちの、このコなにしてんの、の素朴な眼差しに耐えがたい恥辱の念が湧き申して、なんじゃいなんじゃい、ここにだってへんちくりんのかわいいちんまり生き物がころもんてころもんてしててん、へん!
わたしだけがこの世に生まれ落ちし宝物を見つけた心地で、いっそ独り占めしたろ、の心持ちで、手のゆびをわしわし動かしてから、動くなよー、噛むなよー、暴れるなよー、の呪文を唱えて、ふしゃー、と猫になったつもりで、足元でころもんてころもんて、ちとちとあんよを動かしている謎のかわゆい生き物を両手でそっと捕まえる。
きゃわわー。
ほっぺに頬づりしそうになって、思いとどまる。
松の根元にいたんじゃろ。
したらほれ、ここ掘れわんわんの、びしゃー、がちょろちょろかかってしもてるやもしれぬじゃろ。
ばっちいじゃろ。
よくないじゃろ。
華の女子中学生十四歳がしていいことではないじゃろい。
両手で掴んでるのもホントはあかんのやもしれぬけれども、そこはそれ、これはこれ、手放すには惜しいかわゆすさがあるんじゃもん、仕方なかろう。
うんうん。
わたしは得心いって、そのまま、ころもんて、の権化を家に持ち帰った。
「おとーさーん、きてー」玄関先で父を呼ぶ。両手が塞がっていて靴が脱げない。
父はメガネにモジャ髪、短パンにワイシャツなる現代美術さながらの格好で出迎えた。「どした」
「あんね、あんね、これこれ」
ほわほわわーん、ぱかり、と包んだ両手を開いてみせる。
「どれどれ」父は覗きこむ。「松ぼっくりやね。これがどした」
「いやいや、ただの松ぼっくり違うでしょ」
よく見てよ。
わたしは手のひらのうえを強調するのに、父は一向に、はぁ、とか、ほぉ、とか、かわいくない相槌を打つ。
もういい。
わたしは足をがちゃがちゃ擦りあわせて靴を脱ぎ、
「お姉ちゃーん」
我が人生の先輩へとご教授いただきに参上つかまつる。
「うっさいよスイ」姉は仮想現実を展開して格闘ゲームをしていた。部屋のなかで汗だくになっているのは、殴ったり蹴ったりを本気で、全力で、実践しているからだ。
しばらく姉の武闘を眺める。姉はひとしきり暴れ倒すと、ふぅ、と魂みたいに息を吐いて、タオルで首筋を拭う。
「なにさいいとこだったのに」
「ごめん。何位?」
姉はゆびでピースサインをつくる。
「二位?」
「優勝。世界ランキング一位」
「うわぁすごいすごい」
いまウチには世界一つよい女、否々、人間がいるのだ。どんとこーい。
「で、どしたんスイ。それ、なに」姉はこちらの両手にくるまれたころもんての権化に気づいた様子だ。髪の毛をごしごしタオルで拭きつつ覗きこむ。「松ぼっくり?」
おっかなびっくりゆびでつつく姿がおかしくて、だって世界最強になったばかりなのに、そりゃ仮想現実内ってくくりではあるけれども、それにしたってその臆病具合、ぷぷぷ、とお顔がにんまり、ゆるゆるしてしまう。
「これがどうしたんよ」姉はわたしのひたいを手のひらでペチンコして、風呂入るよ、と誰に言うでもなく宣言して部屋から出ていこうとする。
「待って、待って。これ本当になんも思わんの」
「松ぼっくりがそげに珍しいか。ほうかほうか」姉は手のひらをひらひら振って、きょうも我が家は平和じゃのぅ、と眉毛を持ちあげ、誇張された暢気を表現する。
完全にどう考えても小馬鹿にされていたが、そこは姉の妹を十四年もやってきたわたしだ、なんかこれ動くんじゃもん、とシュンとしてみせる。
「動くぅ?」姉は踵を返し、どれどれ、と顔を寄せる。「虫かなんかじゃないの。捨ててきなぁ、ばっちぃ」
やはり。
わたしは確信する。姉たちには見えていないのだ。この、ころもんての権化、かわゆいの結晶、四足の松ぼっくりに似た鱗を持つ生き物が。
「じゃあそうする」
わたしはひと足先に姉の部屋をあとにする。うしろからついてくる姉が無駄に早歩きで迫ってくる。恐竜に踏みつぶされそうな小人のきぶんで階段を駆け下りると、姉はわたしとは逆のほうへ折れ、風呂場へと消えた。
居間の食卓の椅子に座ってわたしは、食卓のうえにころもんての権化を転がす。「なあなあ、おぬしは幻覚なのか」
ころもんての権化は、松ぼっくりの姿から、ぱらりとほどけて四足を晒す。よちよちてとてと歩くとぬたんと垂れた尾っぽが足場を擦るので、ついつい尾っぽをゆびで押さえて、歩いてるのに進まんのですけどー、のきぶんを味あわせてあげたくなる。
メディア端末を取りだして、さっき道端で撮った画像やら動画やらを見る。わたしはきゃっきゃうふふしながら松の根元に転がる松ぼっくりを熱心に、丹念に、追いかけ回している。
映らんのかカメラには。
手鏡を持ってきて映すも、鏡のなかには松ぼっくりがぽつねんとあるだけだ。
わたしはころもんての権化を手のひらに載せ、そこでもカメラやら鏡やらで映してみる。やはりわたしのまぶたを通さずに見る像には松ぼっくりがぽつねんとあるばかりだ。
父や姉にはかように見えていたのだろう。わたしはさしずめ、頭のぴるぴるちくちくアイタタではないか。
ただいまぁ、と玄関口から母の声がする。どさりと荷物を下ろす音が聞こえ、わたしはころもんての権化が逃げないように、そばにあった透明のカップを逆さに被せて蓋をする。
荷物を持ちに玄関に立つと、母は、それよろしくー、と言ってさきに居間に引っこんだ。こういうところが卒がなくて、人使いが荒いくせに荒いと思わせない手腕は、姉にじょうずに引き継がれている割にわたしにはさっぱりだ。血筋の神秘を感じちゃう。
母は買い物をしてきたようで冷凍食品やら野菜やらを冷蔵庫やら冷凍庫に押しこんで、パンやら調味料やらは適当に、キッチンのうえに置いておく。てや!
じぶんでじぶんの肩をトントン叩いて、疲れたぜ、のこれみよがしなアピールをしながら居間に戻ると、母は熱心に食卓のうえを見ていて、立ったまま見ていて、そんなに何をガン見しているのやら、と母の表情を盗み見、それから視線のさきを辿ると、そこにはわたしがカップを被せておいたころもんての権化がおるではないか。
「松ぼっくり拾ってきた」わたしは言った。頭のぴるぴるちくちくアイタタではないよ、と暗に示したつもりが、母はこちらを見ずにゆびをまっすぐころもんての権化に差し向けて、「スイちゃんこれ視えてる?」と言った。
わたしはしばしぽかんとした。母は続けた。
「えーちょっと待ってね、ああもうそういう歳か、しまったなぁ、さきに出会っちゃったかぁ」
母はあごに指を添え、なにやら考えこまれてしまわれる。
この反応はどう考えても母の目にもカップのなかのころもんての権化が、かわゆいの結晶が、生き物が、見えていると判断してなにか差支えがあろうか。いや、ない!
「お母さんにも視えてるの、これ? お父さんとお姉ちゃんはただの松ぼっくりだって」
「そうよねぇ。お姉ちゃんがお父さん似だったから、てっきりスイちゃんにも引き継がれないものとばかり思ってた。お父さんには内緒ね」母はくちびるを尖らせる。「そっかぁ、スイちゃんがなぁ。教えなきゃいけないこといっぱいあるな。ビシバシいくよ。お母さん、がんばる」
腰に拳を添えて、空手ポーズを決める母上でごじゃる。
「がんばるって何を?」
カップのなかから懸命に脱出を試みるころもんての権化をわたしは救いだして、手のひらのうえに載せてまじまじと見る。
「名前つけちゃってあげなさい」
母は無駄にわたしのひたいをゆびで、ぺしりする。「長い付き合いになるんだから」
【お代わりをたんとおあがり】
アキコがホットケーキを食べられなくなったのは六歳になった日のことだ。誕生日のケーキとは別に、友達とホットケーキをつくったのだが、そのときに指南役の母から、卵を割ってなかに入れて、と言われて身体が固まった。
「なんて?」
「卵。入れないとふっくらしないから」
「なんで?」
「美味しく食べたいでしょ」
何を引っかかっているのだろうこのコは、と言いたげに母は、アキコの友人たちに向かって笑みを向けた。
アキコはそれからどうやって誕生日会を過ごしたのか記憶がない。はいしゃいでいた友人たちと母の姿はぼんやりと憶えてはいるけれど、ホットケーキがどうなったのか、じぶんがそれを食べたのかは覚束なかった。
アキコはその日からじぶんの食べる物を注意深く観察するようになった。料理本を眺めることもあるし、母に訊ねることもある。
どうやら大部分の食べ物は、元は生き物であるらしい。アキコはそれまでそんなことを考えたこともなかった。
台所に立つ母の姿はいつも後姿しか見えなかったし、まな板は高い位置にあって、そこでどんな作業をしているのかは分からなかった。
包丁を使うことは知っていた。あれで生き物を刻んでいたのだ。
アキコは母が、鬼か何かのように思えた。同時に、じぶんもまたその鬼の子であり、知らず知らずのうちに、死んだ生き物を食べていたのだ。
「ひょっとしてだけど、卵焼きって、卵?」
「そりゃあ、ねぇ」
母は父の顔を見た。父がTV画面から目を逸らし、母を見て、ん? とおどける。
「じゃあ目玉焼きは?」
「それも卵」
言った母へ、なんだなんだクイズか、と父が愉快そうにする。だがアキコは体温がひゅっと下がったのを感じた。
卵と言えば、鳥のひなが入っている器だ。赤ちゃんの寝床だ。そんなものをじぶんは、じぶんたちは食べていたのだ。
赤ちゃん!
アキコはいよいよじぶんがバケモノのように思え、罪悪感に押しつぶされそうになった。吐き気を催してもおかしくないその場面であっても、食卓に並ぶ目のまえの料理はどれも美味しそうで、現に過去に味わった記憶が、アキコの悲哀の念にかかわらず唾液を分泌させる。
美味しそう、だってママのお料理だもん、美味しいに決まってる。
しかしそれは生き物なのだ。とっくに死んではいるけれど、元は生きていたし、いまこうして死んでいるからこそ、余計に可哀そうに思う。
どうして人間は生き物を食べなきゃ生きていけないのだろう。こんなに文明が進んで、技術が進歩して、魔法としか思えないような技術がそこかしこに溢れて、有り触れているのに、どうして未だに生き物を殺して、食べて、過ごしているのだろう。
とんでもなくイビツだ、とアキコは頭がくらくらしてどうにかなってしまいそうだった。
「どうしたの、食べないの。美味しくない?」母が心配そうに覗きこんでくる。父も、アキコのお皿を見て、箸が進んでいないのを訝しんでいる。「熱でもあるんじゃないか」
死んだ生き物を食べるなんて可哀そう。
言いたかったけれど、それは言ってはいけないことのように思え、そして言っても通じないことなのだと、アキコにはなんとなく判るのだった。
父と母はアキコよりもずっと賢いおとなだ。そんなおとなが、死んだ生き物を食べることをふしぎに思っていない。これはきっと、ふつうのことで、おかしくはなく、だからここで罪悪感を覚えてしまうじぶんのほうが変なのかもしれない、とアキコはおへその辺りがむぎゅむぎゅした。
考えれば考えるほど、余計にひとりぼっちになったみたいで、取り残されてしまったみたいで、悲しくなった。
「無理して食べないでいいよ、どうする、リンゴ剥こうか?」
アキコは首を振る。
箸を伸ばし、皿のうえのから揚げを拾いあげ、口のなかへと運んだ。母のから揚げは冷めても美味しい。コロモがサクサクで、噛むと肉汁が、じゅわあと、口のなかいっぱいに広がる。ほのかな塩味と、しょうがやニンニクの風味がたまらない。
ごっくん。
呑み込むと、罪悪感までいっしょに喉を通って、薄れてしまった気がした。
「このお肉はなんの生き物?」アキコは箸先のから揚げを眺める。
「鳥だけど」母が言った。何だと思ったんだ、と父が笑っている。アキコはひょいと頬張ると、ママとパパはさ、と何の気なしにこう言った。「このお肉が人のでも、やっぱり気にしないの」
父と母が動きを止めた。
「どうしてそう思ったの」
アキコはから揚げを取りこぼす。聞いたことのない父と母の声だった。
本当はこのあとでアキコは、どうしてじぶんには誕生日が一年に何回もあるのか、それから、どうして誕生日会をするたびに友達がいなくなるのか、なにより、誕生日会をするごとにどうして街から街へと引っ越すのか、を訊ねようと思っていたのだけれど、もうそういう気分ではなかった。
「なんでもない」
アキコは手掴みで、取りこぼしたから揚げをつまみ、わたしこれ好き、と言っていかにも美味しそうに平らげてみせた。
父と母はそれを見届けるとようやくいつもの穏やかな顔に戻り、いっぱいあるからたくさん食べてね、と冷蔵庫を振り返り、言った。
【バイオレンス姉妹】
冷蔵庫を開けたら生首が入っていた。
きょうはわたしの誕生日だから、誰かがプレゼントしてくれたのかもしれない。
生首は奥を向いていて誰の顔だかわからない。髪の毛が首のところまでしかないので姉ではないはずだ。でも、首を切断するときにいっしょに切れてしまったのかもしれない。髪の毛の色もこんなに茶色くなかったけれど、これも血にまみれているだけだと考えれば、ひょっとしたら姉の首であってもおかしくはない。
ウキウキしながら生首に手を伸ばし、掴むと、冷たい割にまだ弾力があった。
切りたてほやほやだ。
思いながら、ぐいと持ちあげ、冷蔵庫のなかから引き抜く。ボールを回すみたいにぐるりと宙に浮かして回転させる。ぱっ、と掴みなおすと、そこには見知らぬ少女の顔が現れる。
片目をつむった状態だ。もういっぽうの目は眠たげに開いたままで、口を半開きのまま死んでいる。いいや、死んだあとでこんなふうになったのかもしれないけれど、期待どおりの顔ではなくてがっかりする。
「ハッピーバースディトゥーユー」
背後から声をかけられ、振り向くと、パンっと音が鳴った。
「お姉ちゃん!」わたしは怒る。「せっかくオニューのお洋服なのに」
「ごめんごめん」
姉はライフルを床に放り投げると、これでおあいこ、と言って台所から包丁を持ちだし、じぶんの腹を切り裂いた。
「もったいない」
わたしはすかさず姉の腹からこぼれおちる臓物を手で受け取りに寄り、反対にじぶんの臓物を床にビタビタこぼした。
「あらあら」
姉はわたしの内臓には目もくれず、せっかく捥いできたのに、とわたしの手から転げ落ちた少女の生首を拾いあげた。「このコ、かわいかったのよ。とっても」
わたしより?
お腹の奥がムカムカしたけれど、それはどう考えても気のせいだ。
「おっきなお穴」姉はわたしの胴体に開いた穴に、少女の生首を押しこんだ。
「お姉ちゃん!」
わたしは姉からナイフを奪い取り、姉の胸に突きたてる。
「あらあら、うふふ」姉はわたしを抱きしめる。
来年こそは、とわたしは願う。
姉のこのうつくしい顔がほしい。
姉の、きれいな顔だけをこの手に。
【きみは世界を救う愛しいひと】
疲れた顔で妻が、ただいまぁ、とソファに崩れ落ちる。もうやだこのまま寝る、とつぶやくので、温かい濡れタオルを手渡し、それで彼女が顔を拭いているあいだに靴下を脱がす。ついさっき履いたばかりみたいに新品だ。妻はこういうところが抜けている。
「汚いよ」
「どれどれ」嗅ぐ仕草をすると妻は、やだぁ、と膝を抱えた。
足先をゆびでマッサージしているとやがて畳まれた足がゆるみ、伸びてくる。大きなカタツムリ、と思う。
「きょうはどうしたの。何かあった?」
「特大のクレームをやっつけたよ」
「たくさんがんばったんだね。偉いね」
「偉いよ。そうだよ。もっと褒めて」
こっちの足も、と妻はもういっぽうの足を差しだす。全体的に丸みを帯びた足で、指先のちいささがかわいくて、思わずゆびでつまみたくなる。
「くすぐったい」
「じゃあこれは?」
「きもちい。もっと」
足首の付け根を揉みほぐし、そのままふくらはぎをほぐしにかかる。いつの間にか妻は目をつむり、糸のほどけるような寝息を立てている。
「お布団で寝たほうがいいよ」
抱っこをして運ぼうとするも、妻は駄々っ子のようにソファから動こうとしない。
しょうがないな、の溜息を吐く。身体をよこにさせ、うえから毛布をかける。頭にクッションを差しこみ、ソファを即席のベッドにこさえる。
「お疲れさま」
部屋の電気を消し、じぶんは寝室に引っこむ。
妻は隠しごとをしている。枕に頭を埋め、目をつむる。
夫のじぶんにも本当の仕事を内緒にしている。世界に湧く怪獣や犯罪組織と日夜、秘密裏に戦闘を繰り広げている正真正銘のスーパーヒーローだ。でもその姿は誰にも知られてはいけないから、応援されることもなく、人知れず苦労を背負いこんでいる。
でも、夫のじぶんくらいは彼女の苦労を、功績を、知っていてもばちは当たらないはずだ。
妻は完璧に隠しとおせていると思っているようだけれど、詰めが甘い。
それこそ彼女の宿敵である人類の敵、世界最悪の権化、かつてこの世の神々を滅ぼした元凶こと歩く災厄、サタゴルラザンベとはぼくのことだ。
ぼくは初めて妻を、彼女を目にし、じぶんの存在意義を疑った。滅ぼしていいわけがない。失っていいわけがない。こんなにも愛おしく尊いものを壊すなんてぼくにはできなかった。
それはそうとして、人類には滅んでほしくもあり、折衷案としてぼくは妻のとなりにいられる自由を妻自身から許されながら、いっぽうで妻を苦しめる元凶の役目もそつなく熟している。
本当はいますぐにでも人類を滅ぼして、妻と二人きりで生きていきたいのだが、それは妻の本望とはかけ離れている。
妻はいまの仕事に生きがいを感じているようだから、いまさら失くしてしまうわけにもいかない。
ほどほどに妻をへとへとにさせるくらいの負担を、すなわち破壊行為を人類社会へ仕向けながらぼくは、きょうの献立を考え、妻へのねぎらいの言葉を練りあげ、献身のレパートリーを増やす努力を怠らず、いかに妻から愛想を尽かされないかに全力を尽くす。妻からの愛を深めながら、妻からの言葉を、機微を、漏らさずすべて受け取りたい。
妻の身の安全を緻密に計算するのも忘れない。
妻に成長の機会を与えながら、妻を愛する片手間に、悪行の計画を練る。こんなのは風呂のタイル掃除よりもずっと何億倍も楽だ。どうあってもぼくは妻を傷つけられないし、息を吸うようにぼくの考えることは人類社会にとって極悪であり、災厄だ。
矛盾するそれら二項が、うまい具合に重ならないようにすればよいだけだ。赤と青の中間を選べばいい。赤子にだってできる簡単な仕事だ。
さて、あすは隣国の人口三千万人に殺し合いをしてもらおう。愛する者の命を互いに奪い合ってもらう。子守唄みたいにやさしい悪だ。
いっそぼくも妻に正体を打ち明け、抹殺してもらいたい衝動に駆られる。
甘い衝動に身を悶えさせながら、妻をなんと励まし、慰めてあげようか、と候補を挙げつらねる。きっと妻は、救えなかった命と、救えた命を鑑みて、無力感と達成感の狭間でくたくたになって帰ってくるはずだ。
そんな彼女の身体に、ぼくだけが自由に触れることができる。泣き言を吐く彼女に、ぼくだけがあたたかい言葉をかけてあげられる。
弱っている姿を彼女は、ぼくにだけ見せてくれる。
彼女がうれしいとぼくもうれしい。彼女が悲しいとぼくも悲しい。
こうして一心同体に思える日々が愛おしくて仕方がない。
しあわせとはこういうことを言うのだろう。
妻のしあわせがぼくのしあわせだ。
だからぼくはあすも、妻にとってのよき宿敵であろうと思う。強敵であろうと思う。
極悪非道の、けれど絶対に妻を打ち負かすことのない敵であるために、きょうも夜通し、いかに妻に全力をださせ、劇的な勝利を掴ませてあげられるかを考える。
愛している。
この世でいちばんきみが好きだ。
思えば思うほどに、胸が苦しく、妻を欺いている罪悪感に圧しつぶされそうになる。
こんなんだから、と憤る。
人類なんてさっさと滅べばよいのだ。
念じるけれど、そうはしない。妻がきっと悲しむからだ。守るべきもののない世界はひどく色褪せてしまうことをいまのぼくは知っている。
愛している。
枕を抱きしめる。ひとしきり悶えたあとで、やっぱりよくないな、と息を漏らす。ベッドから抜けでると居間に下り、明かりを灯さずに、妻のそばに寄る。
頬をゆびで突つき、よく眠っているのを確かめてから妻の身体を持ちあげる。起こさないように、すこしだけ人間離れした膂力を発揮するけれど、これくらいは仕方がない。
物音を立てずに寝室にあがり、妻をベッドに寝かせる。
妻はこちらの手のひらに頬をこすりつける。猫みたいだ。心地よさそうに寝返りを打つと、そのまま胎内の赤ちゃんみたいに丸まった。抱きしめたい衝動に駆られるが、熟睡の邪魔をしたくはない。
妻の寝息に耳を欹てる。
朝までずっとこの至福の音色を聞いていられる奇跡に、感謝せずにはいられない。
胸の奥がくすぐったく、やっぱり寝顔を覗きこんで、さらにきゅぅともどかしくなる。食べてしまいたいのに食べてはいけない矛盾に煩悶する。
おやすみ。よい夢を。
愛しいひと。
あすもきみを困らせ、追いこむぼくをどうか許してほしい。
【僕を死にいざなった悪霊と】
霊感があってよい思いをした憶えがない。目に映るそれが幽霊か生身の人間かの区別がつかずに、ずいぶんな目に遭ってきた。
幽霊よりも人間のほうがよっぽど怖い。社会が怖い。
引きこもりになってみたはよかったが、かといって、では幽霊となら仲良くできるのかと言えばそれはのきなみ否であり、引きこもっていても霊媒体質のせいなのかひっきりなしに干渉してくる霊たちを拒む術が僕にはなかった。
僕の理性はいよいよおかしくなった。
大枚をはたいて購入した琥珀の宝石で、なんとか強力な結界を張ってみたが、解決を見せるどころか、こんどはその結界を物ともしない強力な霊しか寄ってこなくなり、却って体力は消耗した。祓える霊は祓ったが、それすらできない凶悪な霊にとりつかれ、いよいよ僕の精神は限界だった。
きょうもまた例の悪霊がやってくる。
なんでもインターネット上でいわれのないデマを流され、世を呪って死んでいった女の霊だという。業界内では有名だった。
きっと一人きりではない。何体もの怨念が融合して、一つの強大な霊として結晶しているのだ。
集合知ではないが、知能もそれなりに高い。
霊には珍しく人格らしいものまで窺えた。
基本的に霊は、動物にちかい。
生前にやり残したつよい執着や愛着、端的に言えば愛憎によって動き回る。本能のようなものだ。ゆえに、個々の霊への対処法は、その霊にある固有の本能を見抜けば、あとはその霊の琴線に触れないようにじぶんの行動を変えるだけで、霊からの干渉を避けることができた。
もちろん、とりつかれてしまえばそれもむつかしくなる。
そういうときに、琥珀や真珠などの宝石が呪具として有効だった。たいがいの霊相手ならばそうした対抗策で撃退できる。
ただし、今回の悪霊は、こちらのそうした対策を難なく見抜き、いくども僕を殺そうとした。苦痛を与えるだけならいざ知らず、僕の家族や同業者、いきつけの店の従業員など、周囲の者にまで魔の手を伸ばしはじめた。
いよいよとなって僕は、自決する臍を固めた。
もともと、この世に未練はない。僕自身が悪霊になることはないだろう。できれば愛し合える誰かと出会いたかったが、それも可能であれば、という願望にすぎない。ヒーローになりたかったなぁ、みたいな幼稚な夢だ。叶わなくて当然だ。
僕はもう、誰とも関わり合いたくはなかった。
首に縄をかける。
呼吸が苦しくなり、めまいが襲う。失神すればそのまま自重で首が締まり、窒息死するはずだ。
僕はゆっくりと意識を失った。
視界が闇に染まる間際、目のまえに例の悪霊の姿が霞んで見えた気がした。助けようともせず、ただこちらをじっと見下ろしている。
身体が冷たく、或いは熱く、そしてもう何も感じない。
浮遊感だけがここにある。
虚無。
ああ、と思う。
僕はいま、死んだのだ。
「そう、きみは死んだ。なんで死んだ。せっかく私が呪い殺してやろうと思ったのに」
死んだはずの僕はなぜか、明るい部屋のなかにいる。足元には首をくくったじぶんの身体があり、僕は、僕の胴体に両足を突っこんだ状態で立っている。
「あーあ、もったいない。せっかく霊感あったのに、自殺じゃ、せっかくの霊力もパァだ。おまえ、ただの浮遊霊だよパンピーだよ」
「パンピーって」
目のまえにいる女には見覚えがあったが、うまく思いだせない。知り合いにこんな女性、いただろうか。
「おいおい、あんまじろじろ見んなよな。殺し合った仲だろ、仲良くしよーぜ」彼女が両手をだらんと胸のまえに掲げてみせたところで、ようやく察し至る。「きみ、悪霊か」
床をゆびさし、ここにいたあの悪霊なのか、と暗に問う。僕を殺そうとしていたあの、と。
「ちっ。せっかくこんな上玉殺せそうだったのに、ちょっと目を離した隙に死んじゃうんだもんな。せめて死ぬなら事前にそういうそぶり見せてほしいよね。じっくり衰弱させてからなんてまどろっこしい真似せずに、すぐに呪い殺してやったのに」
「いやいや。なんで殺すんだよ」
思いのほか言葉が通じるので、遅ればせながらの怒りが湧いた。「せめて罪悪感くらいもったらどうですか、けっこう怖かったし、ふつうに弱ってましたよ。ひとを困らせて何が楽しんですか。死んだら娯楽に困るんですか、生きてるひとをうらやんで、逆恨みみたいにして怖がらせて、悦に浸って、なんて嫌なひとなんだ。あなただって生前、ネットで散々な目に遭って、いろんなひとの無邪気な悪意に苦しめられてたんじゃないんですか。なんで死んだら、そういうクズみたいなひとたちと同じことをじぶんでできるんですか。信じられません」
「おうおう、言ってくれるじゃねぇか。たしかにアタシゃおまえの調べたとおり、怨念の総体らしい。いろんな人間の記憶がごっちゃになってここにある。だが、アタシがおまえを殺したかったのはそれとは関係がねぇ。霊度があがんねぇんだよ。つうか逆だな、おまえみたいな霊感あるやつ殺すとレベルがあがんだよ。もっと強くなれんだ、したら今度こそ、アタシらを死に追いやった野郎どもを根こそぎぶっ殺して、こっちの世界でもひどい目に遭わせてやらぁ。そのためにはどうしてもおめぇみてぇなやつを」
「殺さなきゃいけないだなんてそんな理不尽なことは言いっこなしですよ。あなたには同情しますが、それで僕がひどい目に遭わなきゃいけない道理はないはずだ。どっちかと言えば僕はあなた方と同じ立場ですよ。あなた方に交じりあうほうの人間ですよ。それをあなたは殺してしまうだなんて、そんなのは、自殺よりもひどいですよ、哀しいですよ」
言っていて目頭が熱くなる。
彼女は――見た目が女性なのでそう呼ぶが――彼女自身がもっとも憎む者と同じことをじぶんの手で、しでかしてしまっている。それがなんとも虚しく、哀しかった。
「哀しいったって、でもさ、ほら」
彼女は言葉を詰まらせた。頭上に総毛立っていた髪の毛が、しゅるしゅると下りていく。「わ、わるかったよ。でも、アタシはあいつらとは違う。そこはいっしょにすんなって」
「でも僕はキミの無邪気な悪意に殺された。キミは僕がかってに死んだと言うだろうけれど、僕はキミにも、ほかの大多数の無関心な人間たちにも殺されたようなもんだ」
「そう言われちゃうとな。ごめんて。もうしないよ。つってももう死んじゃってるし、どうしたら許してくれる?」
案外に彼女が素直に肩を落とし、縮こまってしまったので、僕のほうこそ意気阻喪する。湧いた怒りもどこへやらだ。
やり場がないどころか、溜息と共に霧散して消えてしまった。
僕は言った。
「どうしたら僕たちみたいのがいなくなるか、いっしょに考えてください」
彼女は顔をあげる。
僕たちはこのときになってようやく目を合わせた。彼女の瞳は翡翠みたいだ。吸いこまれそうになる。
「成仏の仕方もわかりませんし、時間はあるんですよね」
「時間? あ、うん。あるある、と、思う」
「じゃあ、しばらくじっくり考えましょう。悪霊として格上のそのチカラ、僕たちみたいなひとのためにもっと上手に使えると思うんです」
キミみたいなひとたちの助けになれると思うんです。
僕が手を伸ばすと、彼女はまるで立ちあがるための支えを掴むように、むんずとその手を握りかえした。
僕は死んだ。
じぶんで選んだ死だったが、生きているうちに、違った生き方を歩めるものなら歩みたかった。でもたぶん、遅くはない。
僕はいま、僕を死にいざなった悪霊と手を繋ぎ、立っている。
【異釣り師】
初めて異釣りに連れて行かれた日、目のまえで異魚に父を食われた。簡単な仕事だと聞かされていた。おまえもいずれはオレの跡を継ぐんだぞ、と将来を勝手に決められたことに腹を立て、その日は父と口を利かなかった。
言うことを聞かずに、反抗したあたしは、異釣りでけっして外してはいけない仮面を外してしまい、そのせいで異魚があたし目がけて飛んできた。父は、そんなあたしを身を挺して庇い、そして上半身だけをきれいに食べられて死んだ。
異魚は、人間を喰らう。だから父のような異釣り師たちが、夜な夜な波紋の広がりはじめた区域に出向き、そこに近々浮上してくるだろう異魚を、前以って釣りあげておく。
雪崩対策のようなものだ。
雪崩の起きそうな場所に爆薬を仕掛け、大規模な崩落が起きる前に、小規模な雪崩を起こしておく。
「異魚なんて滅ぼしちゃえばいいんだ」
ことし八歳になった息子がフォークを振りあげて言った。スパゲティのミートソースが飛び散り、おとなしく食べてね、とお願いしながらテーブルを拭く。
「毒とか撒いて、イチモウダジンにすればいいと思う。なんでしない?」
「異魚にきく毒がいまのところないからかなぁ」物騒なことを言わないでほしかったけれど、考えるチカラは養ってほしいので、考えを頭ごなしに否定したりはしない。そのせいで、歯に衣の着せない子供に育ちつつある。ただ、毒に関しては以前、あたしも同じことを考えたことがあった。「異魚は、異空から釣りあげないことには滅せない。いまはママたちのグループが、大きな網でまとめて釣りあげたりもしてるから、そうだね、一網打尽にする方法がないわけじゃないよ」
「はやくボクも釣りにいきたい」
「まだちょっとはやいかな」
「ママはいつした」
「初めてってこと? えっとね」考えるまでもないが、間をあけた。すぐに答えられる日付けであると悟られまいとする自己防衛かも、と思い、余計にもやもやする。
父の命日と同じだ。あれから十七年が経った。
「十五のときだから、ユウヒはあと七年は待たないと」
「長いよ」
「そうだね」
だが、短い。あと七年で、異魚をどうにかしなければ、あたしはユウヒにもこの稼業を引き継がせなければならなくなる。それだけはなんとしてでも避けたくて、仲間を募り、異釣りを集団でこなすようにした。
本来は単独でこなすのが習しだった。
おそらく、異釣り師が一か所に集まると、異空間のピルポが増殖するからだろう。ピルポは異魚たちの餌だ。大型化するまで異魚はピルポを捕食して育つ。
成魚となり、さらに巨大化した一部の異魚は、異空を越えて、こちら側の現世の人間を襲うようになる。
ピルポは現世に漂う「イト」を好んで食する。イトはどんな生き物でも発している。極稀に、イトを豊富に含有する人間が誕生する。その体質は遺伝するため、そうした者たちが、やがて異釣り師となったといまでは考えられている。イトの濃度の高い場所には、必然、ピルポがたくさん集まる。そこには異魚も集まり、巨大化し、そして人間が襲われる確率もまた高くなる。
異釣り師の家系は、そうして否応なく異魚との関わりを持たざるを得なかったのだ。ただ食われるだけではいられない。異釣り師の祖先は、異魚への対抗策を編みだした。それがつまり、異釣りだ。
己が身体が豊富に蓄えるイトを用いて、現世に居ながらにして、異空間へと干渉する術を磨いた。異魚を釣りあげるための道具は、刀と、細く強靭に練りあげたイトだ。
釣りあげた異魚を、釣竿の代わりの刀で以って、斬り殺す。異魚は、現世に姿を晒さなければ、干渉しようがない。ゆえに、毒もきかない。異空へ送れるのはイトだけだ。
イトを大量に駆使すれば、イトを網にもできる。だがそのためには一人ではなく、集団のチカラが必要となる。
反面、異釣り師が一か所に集まれば、ピルポがイトを求めて集まってくる。必ず異魚を釣りあげられればよいが、そうもいかない。失敗すれば、イトごと逃げられる。わるくすれば、イトを無駄に奪われておしまいだ。
イトを失えば、ピルポが大量に増殖し、ピルポで育つ異魚の脅威がますます増す。
あたしたちの異釣り網がうまくいっていたのは最初だけだった。
見たこともない大型の異魚が現れ、いちどに異釣り師たちがごっそり食われたことがあった。大事件だった。
全世界の異釣り師たちから禁忌を犯したと非難された。個人情報が、異釣り師たちのあいだで周知され、声をかけても、グループに加わる者は皆無となった。
挙句の果てに、新たに発足された異釣り協会なる組織から永久追放の烙印を捺され、いよいよなす術をなくした。
異釣りをするな、と言われて、はいそうですか、とはいかない。黙っていても、異魚はあちらから寄ってくるのだ。それに対抗するために、否応なくあたしたちのようなイトを大量に保持する者たちは、異釣りをせざるを得ない。
協会からの通告は、いわば死刑宣告だ。異釣りをするな。そのまま食われて死ね、と言っているのと変わらない。
あの大型の異魚に食われてしまった仲間たちにはわるいことをしたと思っている。償って生きていくしかない。だからといって、あたしは死ぬわけにはいかない。
お代わり、と口元をケチャップで汚したユウヒがお椀を差しだしてくる。
あたしにはこのコがいる。
世界中で、大型の例の異魚とみられるバケモノの出現が報告されている。釣りあげた者はなく、食われた者の数だけが日々、増えつづける。
単独での異釣りを義務付けている協会は、もはやそのバケモノを退治する術を有しない。集団で立ち向かわねば釣りあげることはおろか、じぶんの命も守れない。いずれはじぶんの番が回ってくる。
大量のイトを求め、バケモノは異釣り師を追い求めている。
黙って食われる未来を受け入れるつもりはない。あたしは、バケモノに食われた異釣り師の遺族に会い、謝罪と、そして協力を求めた。
たいがいは会ってすらもらえず、会えたところで、謝罪をする間もなく、こっぴどく指弾された。当然の怒りだ。黙って身体に浴びることで、すこしでも遺族の気が晴れるならば、安いものだ。
そのうえで、やはり協力者が必要なのだ、とあたしは訴えた。償いたい。これ以上の犠牲者をださないためにも、どうか手を貸してください、とあたしは頭を下げた。
本当は、彼ら彼女らがどうなったっていいと思っていながら。
もちろん、不幸になってほしくはない。わるいことをしたと思っている。だがそれ以上に、あたしにはユウヒの将来が、命が、だいじだった。
守りたいのだ。
このコの未来を。
人生を。
寝顔を撫でつけながら、あたしは思う。
黙って寝ていればこんなにかわいいのに。
起きて、しゃべると小憎たらしい。
だのにどうしてだろう、このコがあたしと同じ道を歩むことになる未来だけは見たくない。小憎たらしくっていい。みんなに好かれなくたっていい。
独りきりでも生きていけるチカラが、道が、このコにあってほしい。産毛の生えたやわらかい頬に触れるたびに、泣きたくなる衝動が、願いと共に湧きあがる。
「ママ、がんばるから」
ひたいに唇を押し当てると、んんっ、とユウヒが寝返りを打つ。あたしはいじわるな気持ちになって、おでこにデコピンをすると、すかさずユウヒが手で振り払う。
起きてはいない。
不快な刺激に敏感なだけだ。
きっとこのコは、とあたしはほころびる。世渡り上手になるだろう。みなが見逃す、波紋の揺らぎを目敏く見つけ、いまあたしにしたように、寝ぼけながらも手で振り払おうとするだろう。
それでいい。
思うが、やっぱりすこし寂しい。
甘えてほしくあり、慕われてほしくもある。
このコが異釣りを継承せずに済むように、七年以内に、あのバケモノを、或いはことごとくの異魚を、あたしはまとめて滅したい。
それまでにいちどくらいは、このコに異釣りをさせてあげるのも、そうわるくはない気もする。
世界はおまえが思うよりもずっと危険で、不快なものだ。
だがその不快ですら、振り払い、楽しむ余地がある。
あたしは押入れから箱を取りだし、中からちいさな仮面を拾いあげる。父からもらった、あたしの仮面だ。けっきょく一度しかつけずに、あとはずっと仕舞っていた。
あたしは父の仮面を使いつづけている。
あのとき、父が仮面をあたしに押しつけずにじぶんで被りつづけていれば、頭から食われることもなかっただろう。父の下半身と父の仮面を被ったあたし、そしてちいさな子供用の仮面だけがその場に残った。
ちいさな仮面をおとなしく顔につけたままでいれば、父の言うことを聞いてさえいれば、と何度考えただろう。だがいまは、そう考えることに罪悪感を覚える。父が死ななければきっとあたしは、このコに出会うことがなかった。
人生はままならない。
あたしは、我が子の顔のよこに、父からもらったちいさな仮面をそっと置く。
似合うじゃん。
思いながら、まだはやいよな、と考えなおして、箱に仕舞い直す。
初めての異釣りはまた今度ね。
布団をかけなおしがてら、あたしは誓う。
それまでには異魚のバケモノ、アイツはママが釣りあげておく。
血祭りに、あげておく。
約束。
ちいさな棒切れのような小指と、あたしは小指を絡ませる。
【折れた牙を刀に】
刀諒(とうりょう)談一(だんいつ)は焦っていた。天下無双の名を欲しいがままにしてきた自他共に認める剣豪のじぶんがいま、己が腰ほどにも満たない童(わらべ)に追い込まれている。
驕り高ぶりがなかったとは言わない。しかし油断をしたつもりはなかった。
常日頃、どれほど見た目がみすぼらしかろうと、貧弱に見えようと、それが刀を交わす相手であるならば手を抜いたことはなかった。刀のまえではみな平等だ。死をまえにすれば等しく無力であるように、刀と刀の先端を突き合あわせれば、そこにあるのは相手の命を奪うことへの同意であり、死闘の幕開けだ。
油断をすれば死ぬ。
一撃必殺が理想ではあるが、なかなかそうもいかぬ。振りかぶる刀数が嵩めば嵩むほどに、死の濃厚な香りが鼻を掠める。
先刻、童の一刀を受け、五本のゆびを失った。右手は中指から小指の三本、左手は、食指と中指の二本だ。
刀を構えているだけで精いっぱいだ。もしつぎの一撃を躱されれば、あとはただ無防備なさまで首を斬られるのを待つだけとなる。逃亡する気力も湧かない。
どうしてこうなったのだろう、とチリチリと発火する焦りのなかで考える。いまはそんな後悔に似た考えを巡らせている場合ではないはずなのだが、冷静にじぶんの姿を俯瞰するもうひとつの視点を自覚する。それはいまこうして死闘のさなかにあるじぶんだけでなく、過去を含めた広い視野を持っている。
目のまえの童が動く。
若い芽を摘むのは気が引ける。ここで引導を渡してもらい、つぎなる世代の糧になるのも一興に思えたが、なぜかそうする気にはなれなかった。
ただでは死なぬ。
相討ちを狙う。むろん、勝つ気ではいる。だがこちらはここまでの痛手を負っておきながら、相手は未だ無傷だ。
死ぬ気でやらねば死ぬだけだ。
肉を切らせて骨を断つ段階はとうに過ぎた。
骨を切らせて、骨を断つ。
あとに残るは、それしかない。しかし相手とてこちらの尋常ではない殺気、ともすれば意図を見ぬいているはずだ。
小賢しいほどに、死闘とは何かを相手は知っている。
師がいるのではないか、とふと思った。
これほどの腕前、一夕一丁で身につく技量ではない。
「動揺を誘う策略と思って聞き流してくれていい」談一は言った。「おぬし、師は」
「おらん」
にべもない返事だ。だが、いないとなると、ますます妙だ。
「独学にしてはいささか型が決まりすぎておる。二刀流に似てはおるが、おぬしはしかし一刀しか扱わぬ。腕力に自信がなくてそうしているわけでもなかろう」
童ほどの業前ならば、片手で扱えるくらいに薄い刀身の刀であっても容易く人体を殺傷せしめるはずだ。
「果たし状を受け取ったゆえ、こうして貴殿と対峙しておるが、見届け人すら用意せぬところを鑑みるに、名をあげたいわけでもないのだろう」
ここで童が勝ったとして、証人がいなければ法螺吹きとして見做され兼ねない。その公算が高いだろう。剣豪相手に小僧にもならぬ童が、まっとうに決闘をして斬り伏せたなど、いくらなんでも誰も信じぬ。
「ひょっとして頭がそこまで回らんかったか」
「恩人だから義を優先した。名誉はいらねぇが、不名誉を与えんのは本意じゃねぇ、それだけだ」
「わしのためとでも言う気か」
これまで湧かなかった怒りが湧いた。舐められている。だが死闘において逆上したほうが死ぬ。重ねてきた死闘の数々において学んだ数少ない真理だ。
「恩人とはなんだ。わしのことか。しかしわしは貴殿など知らぬ。人違いではないのか」
「いいや貴様だ。人殺しを生業としておきながら、人の持つ愛情を疑いもせぬ傲慢な眼差し、顔カタチが醜く変わろうと、身体から立ちのぼる貴様に屠られた弱者どもの死臭は誤魔化しようがねぇ」
「私怨か」思ったので言った。尋常ではない執念を感じた。名をあげたいのではないとすれば、復讐と考えればそれも腑に落ちる。「わしの斬った誰かのせがれか」
「馬鹿を言うな。オレがアイツのせがれだと。侮辱にもほどがある」
「貴殿の殺すはずだった相手をわしが殺してしまったから、わしを代わりに殺そうとそういうことか」
「殺すはずだった? 殺せるはずがないだろう。オレにアイツは殺せない。そういうふうに躾けられたからな」
「ではわしは貴殿を檻から救いだしたようなものではないか」
「だから言ったろ。恩返しだってな」
「解らんな。なぜ恩返しになる、わしを殺すことが」
「本気で言ってんのか? あン? じゃあおめぇはただ、絶対に殺せると思う相手じゃなきゃ刀を抜かねぇってそんなつまんねぇことのために人生のずっとをそれ一本に費やしてきたのかよ」
図星を指された気がした。よもやきょうじぶんが死ぬとはたしかに思っていなかった。勝てる死闘だ。そうだ。いつだって死闘とは、相手にとってであり、談一にとってそれは、引導を渡してやるだけの役割にすぎなかった。緊張はするが、それは乗馬のときの一瞬の浮遊感の連続にすぎなかった。
「強者と闘いたい、それしきのこと」
口にしてみたが、砂利を食べているようだ。水で口をそそぎたい衝動に駆られる。
「そうだろ、そうだろ。おまえはそういうやつだ。だからオレがとびきりの死闘を演じてやる。大いに力量を超えて、限界を超えて、死闘のなかで死ね」
「感謝する」
刀を構え直すが、もはや剣先の震えを御することすらままならない。恐れはない。そのはずだ。呼吸はしずかで、落ち着いたものだ。
おそらく、と足を踏みだし、距離を詰める。まだ死ぬとは思っておらぬのだ。じぶんが死ぬとは、露ほども。
しかし勝機が見えないのも確かだった。刀を振りかぶれば、つぎはない。どちらかが生き、どちらかが死ぬ。或いは、どちらともが死ぬ結果しか残されてはいない。
「童。名はなんという」果たし状に差出人の名はなかった。
「武蔵」
「わしが許す。天下無双を名乗れ」
「生きてこの場を去れたらな。それに許可なんざいらねぇ。誰だって天下無双だ。同じやつが二つといてたまるかよ」
笑みが漏れる。真理だと感じた。死闘を重ねずとも見えてくるものはあるらしい。掴める答えが、あるらしい。否、この童はすでに数々の修羅場を潜り抜けて生きてきたのだろう。やはり重ねねば見えぬ境地というものはあるのかもしれぬ。
「いざ尋常に」
「やなこった。いざ狂気を胸にいこうじゃねぇの」
笑みが引かぬ。
談一は刀を上段に構え、歩を進める。駆け足になり、風となり、童と距離があるうちから振り下ろす。交差する間際、刀は童の肩を捉えた。
腕に伝う衝撃が身体を貫く。談一はそのまま駆け抜ける。
一歩、二歩、三歩と余韻を打ち消すと、その場に膝をつけ、崩れた。
地面に血が滲む。
刀身は真っ二つに折れており、刀ごと斬られたのだと思った。
背後から哄笑が聞こえる。童が大声で笑っている。
勝鬨か。それもまたいい。
足音が近づいてくる。まだ談一には息があったが、このまま介錯されるのもわるくないとほころびる。清々しい心地だ。出しきった。ここが限界だったのだ。
「おっさん、なあって、おっさん」
肩を掴まれ、談一は振り返る。「見ろよこれ。どうすんだよこういうときはよ、殴り合いで決着でもつけるか」
折れた刀を携えていた。談一だけではなかった。童の刀もまた、真っ二つに割れていた。
「引き分けだな。どうする」
「いや。貴殿の勝ちだ」再戦を決意する意思はない。刀同様に、ぽっきりと折られてしまった。それを清々しいと感じている。もはや剣豪たり得ない。
「そうかよ。これでもちゃんと恩返しになったかよ」
「ああ。感謝する」嘘偽りはなかった。ただ、すこし悔しい。生き残ってしまった我が身を無様に思う以上に、安堵しているじぶんがいる。そのことにまた言いようのない失望感が湧く。敗北とはこうも苦々しく、開放感に溢れているものか。
「じゃあま、腹減ったんでもういくわ」
後腐れなく去ろうとする童の背へ向け、談一は言った。「その才、まだまだ磨く余地がある。荒削りでここまでの技量、ただごとではない。わしに貴殿を磨く手伝いをさせてはもらえぬか」
矜持も何もあったものではない。だがここで別れることのほうが口惜しく思った。
「んー。やめとく。あんまおもしろくなさそうだ。誰かに習うってこったろ。アイツを思いだすようで虫唾が走らぁ」
「さようか」
「おう、そうだ。それだったらよ」童は折れた刀を捨て、その辺の草をむしる。空を斬るように草を振りながら、「こさえてくれよ」と言った。「オレに恩返ししてくれるようなやつをさ。あんたが磨いて、こさえてくれよ」
生きろ、と彼は言っている。
叱咤された気分だ。
剣豪としての責務を果たせ、甘えるな、おまえはまだ生きているだろ、と。
そう聞こえただけのことであり、おそらく彼にしてみれば純粋な望みなのだろう。剣豪とは何か。彼はそれを知っている。談一はじぶんが一気に歳をとったように感じた。
「お任せを」
剣豪は去った。
風が野のススキを撫でつけ、談一の欠けた指先を、さらさらと洗う。痛みが戻る。遅れて滲む脂汗を涼しいと感じる。
この痛み、おそらく。
談一は予感する。死ぬまで消えることはない。
【諺かなんかですか?】
千日間をかけて念入りに練った計画が失敗に終わった。予想が裏切られた。海水で溶解するはずだったのだ。平野に穴を掘り、海水を灌漑して、目標をそこへ誘導する。沈めば目標はシオシオと萎み再起不能になると専門家たちが率先して作戦を立てたが、結果は見ての通りだ。
超大型蛞蝓(なめくじ)は健在だ。
海水を吸い取り、余計に膨張する始末だ。
「ダメかぁ」
世界中から落胆の声が聞こえるようだ。
超大型蛞蝓が突如としてこの国の山脈に現れたのは五年前のことだ。当初は、自動車ほどの大きさだったが、木々をモリモリ食し、山脈を丸裸にするころには、ドームほどの巨体にまで育った。そこからさらに街を飲みこむほどの大きさになるまでに費やした時間は、初めて個体が観測されてから一年も経たぬ間のできごとであった。
いまのところ産卵の予兆がないことがゆいいつの僥倖と言えた。あとはすべて最悪だ。都市は壊滅し、土壌は汚染され、川が毒と化し、海も荒れた。畜産業、農業はおろか、漁業、果ては工業にも多大なる損失が計上された。
超大型蛞蝓は三日周期で休眠と活動を繰りかえす。移動の跡には、大量の粘液を残し、一から七日かけて腐敗するために、深刻な環境破壊が引き起きている。
各国の専門家たちが侃々諤々の議論を重ね、ようやく統一的な見解がだされたころには、超大型蛞蝓は、地球上のおおよそ七割もの生態系を崩していた。絶滅した動植物は九割にのぼる。かろうじて雨による自浄作用が働くことで、人類は大幅な人口の減少を食い止めていられた。養殖や空中農園などの新技術によって衣食住を維持しているが、それもあと二十年が限度だとの見解で専門家たちのあいだではおおむね合致している。
度重なるシミュレーションによって、地上の資源を食い尽くせば超大型蛞蝓は、理論上は、その全長が三千キロメートルにも及ぶと算出済みだ。
各国の軍隊による陸海空からの爆撃も効果がない。土地を破壊するだけ損だ。超大形蛞蝓の皮膚は分厚く、また大量の粘液を保有しており、内部まで火が通らない。衝撃すら緩和される。宇宙空間から人工衛星や、某国の近代兵器「ロンギヌスの槍(超重量の鉄塊)」を落下させても無傷だったほどだ。
人類は進退窮まった。
物理生物学者の舐田(なめた)羅漢蔵(らかんぞう)の提言がようやく真面目に吟味されはじめたのはそのころのことだ。
「蛞蝓には塩と相場は決まっておる」
舐田博士は初期のころからかように政府へ提言し、却下されつづけてきた。
その表で、数々の作戦が実行されては失敗しの繰り返し、最後の最後まで考慮されずにいた舐田博士の案は、背に腹の代えられなくなった世界大型生物災害対策機構によって、いよいよ実行の陽の目を迎えた。
富士の樹海に琵琶湖ほどの穴を掘った。すでにいちど超大型蛞蝓が通ったあとであるために木々はなく、土地は丸裸だ。
が、いざ実行に移してみたはものの、おおよそ三年をかけて準備をしてきた舐田博士の作戦ですら、超大型蛞蝓の分厚い粘液皮膚組織を前には焼け石に水であった。
「浸透圧が予想よりもずっと濃いようだ」舐田博士は冷静だった。新たに出そろったデータを分析していく。まるで軒下で囲碁でもするかのような飄々とした佇まいだ。「液体は、浸透圧の低い方から高い方へと移る。一般的に、塩をかけると蛞蝓が溶けて見えるのは、あれはより浸透圧の高い塩のほうに、蛞蝓の体液が奪われるからだ。もうすこし正確には、浸透圧とは、分子の密度の高さと解釈できる。水に溶解している分子の数が多ければ多いほど、それは浸透圧の高い液体、ということになる」
「つまり今回はどういうことになりますか」
「一般の蛞蝓を海水に浸ければ、その蛞蝓は縮む。水分を海水に奪われるからだ。ウミウシや海魚が平気なのは、自力で体内の塩分濃度を調節できる仕組みを兼ね備えておるからだが、どうやらあの超大型蛞蝓は、よほど高い浸透圧の体液を有しておるようだの。海水程度では、雨が降ったようなものだ」
「しかし検査では、海水でも充分に溶かせるとの報告が」
「表皮の粘液細胞だけを調べたのだろう。その奥の、深層皮質および体液は、海水よりもよほど浸透圧が高いようだ」
「では、なす術がないということですか」
「海水に限らず、水を与えれば与えるほどに、あれは水を吸って膨張するだろうな。雨が降るたびに膨張しているのでは、といった仮説も聞かれたが、あながち間違いではなさそうだ」
「どうにかなりませんか博士」
「うむ。単純な発想としては、超大型蛞蝓の体液よりも浸透圧の高い液体に浸せば、こんどこそ作戦が成功する確率は高まるだろう。しかし、おそらく実現はむつかしい。まず以って、あの巨体から、体内の細胞を摂取することすら至難だ。そもそもそんなことが可能であれば、体内に爆薬でも、毒薬でも仕掛けて処分してしまえばよろしい。それができない時点で、講ずる策は限られる」
「液体でなければいけないのですか。分子の密度が要であるならば、砂などの流動する固体で、水分を奪えたりは」
「同じだよ。けっきょくのところ砂が水分を奪うのも、塩をかけて蛞蝓が萎むのも原理は同じだ。塩をかければ、皮膚表層の水分によって塩は塩水となる。その塩水の浸透圧が、蛞蝓の体液よりも高いために、浸透圧の低い体液のほうが、塩水のほうへと移動する。砂糖でも砂でもそれは変わらん。液体のなかの粒子の数が肝要なのだ」
「つまり、大量の砂や塩で埋めてしまえばなんとかなる、という話では?」
「発想としてはわるくない」まさに敵に塩だな、と舐田博士が言い、諺かなんかですか、と茶々が入る。「しかし、それは可能な案か。どこにそんな大量の土砂や塩がある」
「まったくそのとおりですね。用意できません。現実問題、あの体積を覆い尽くすだけの量の土砂や塩はどこにも。仮に用意可能であっても、降りかける真似ができません。巨大なスコップでかけるわけにもいかないでしょう。覆うだけでなく、埋もれるほどになどとはとてもとても」
「ではほかの案をひねくりださねばだな」
「何かよい案はないでしょうか」
「うむ」
舐田博士はそこで、端末を手に取った。ガラクタと化したこれまでの数々の失敗策のデータに目を通し、ところできみ、と実行部隊最高司令官に言った。
「この爆薬やミサイルは使えるのか」
「ええ。まだたんまりありますが、焼け石に水とのことで倉庫の肥やしになっております」
「こっちの原子爆弾は」
「副作用があまりに甚大だとの判断で、そちらもいまのところ出番は」
「しかし使えるな」
「お言葉ですが、原爆投下はさすがに国民の賛同を得られません。いちど核をこの国で使用すれば、各国が追従する危険性すらあります。この国を火の海にしたいのですか」
「放射線物質に汚染されなければ問題なかろう。地下実験では未だにドカスカ爆発させておるだろうが」
「地下に使う気ですか。穴をあけるだけならそんな真似をせずとも、今回の作戦で使用した掘削機が十万台利用可能です」
「ではそれも使おう。遠隔操作ができるのだったな」
「ええ。ですが、いったいどこに穴を。住民を避難させるにはまだ、空中住居の数が足りません」
「避難などさせずともよい。すでにあすこに人はおらん」
場所は、と指示をだした位置座標は、おおむね今回失敗した作戦であけた穴の近くだった。端的に、富士山の山頂だ。
「あんなところに穴を? しかしなぜ」
「噴火させてしまえばよろしかろう。未だに目標は海水を浴びてご満悦だ。掘削機十万台と、爆薬、そして極めつけに原爆を使えば、富士山を噴火させ、大量の溶岩をあやつのいる大穴に流しこむことも可能だろう。溶岩ならば極めて浸透圧が高い液体と言える。いかな超大型蛞蝓と言えど、しおしおと萎んでくれよう」
「その前に焼け死ぬのでは」
「かもしれん。が、あの巨体だ。仮に熱のみで語るとすれば、あやつの分厚い表層の粘液に触れれば溶岩は冷えて固まり、分厚い装甲をつくるだけだろう。その確率が高い。熱ではあまり意味がない。浸透圧だよきみ。浸透圧だ」
溶岩が液体のうちに超大型蛞蝓から水分を奪い取ってくれれば御の字だ。それが無理ならば、そのまま溶岩の檻に閉じこめて、埋めてしまえばいい。
舐田博士はそう語ると、大地震に備えなくてはな、と食指を振り、富士が噴火すれば寒冷化現象も起こりそうだな、と肩を落とす。
「蛞蝓退治の後始末のほうがずっと骨が折れそうだ」
「やれやれですね」
「まさに、蛞蝓に塩、だな」
「それは諺かなにかですか?」
舐田博士は、しょっぱい顔をする。
【青い花の妖精】
葉も茎も、花弁ですら青いそれをぼくは、ファイサと呼ぶ。品種の名前ではなく、ぼくが彼女のためにつけた固有名詞だ。
隕石だったのだと思う。ある日の夜、星空を駆ける閃光を見た。閃光は地上に落ちた。近場の公園のほうが仄かに明るくなり、音もなく光は消えた。
気になったので光の落ちただろう場所を見に行くと、グラウンドに淡い光が転がっていた。暗闇にランプが一つ灯っているような光景、或いは誰かが懐中電灯を落としていった背景を考えたが、結果としてそれを持ち帰ったぼくは、ファイサと出会うこととなる。
「あのときのことを思いだすよ。光る種みたいなものを植えたら本当に、この世のものとは思えない植物が生えてきたんだから。植物なのかいまでも曖昧だけど」
「しゃべる植物がほかにもあるのですか」
わたしのような存在がいるのですか、とファイサは首を傾げる。
「いないよ。ぼくの知る限り植物はしゃべらないし、色も緑で、花だってもっとカタチがこう、ふんわりしている」
「わたしはふんわりしていませんか」
「しているけど、していない」
「よくわかりません」
妖精というものを見たことがないのでなんとも言いようがないないのだけれど、もしこの世に妖精がいたとしたらきっとこういう姿をしているのだろうな、とぼくが思うくらいにファイサは可憐で静謐で、醜悪と対極に位置する姿形をしていた。
ファイサの花は、三十ほどのちいさな花弁でできている。その真ん中に、ファイサがちょんまりと生えているのだ。めしべもおしべもない。ファイサの足先が花にくっついている。溶け合っているかのようだ。だからこの場合、ファイサを本体と呼ぶよりも、本体からファイサが生えていると言ったほうがより正確なところに思えるが、ファイサには人格のようなものがあるようだし、言葉を介するし、もちろんそれはそういうふうに擬態しているだけなのだとしてもぼくがそのように錯誤するくらいの意思疎通の真似事をしているのなら、それはもうむつかしいことを抜きにして、ファイサは妖精のような存在なのだと見做したほうがぼくにとってはいくぶん納得できる解釈だった。
ファイサに性別はない。他方で、見た目は女の子の特徴を備えているし、これといった生殖器も見当たらないので彼女と呼んで扱っている。もちろん彼でも構わないが、ファイサの声はさらさらしていて、青い頭髪がそのまま声になったみたいにうつくしかった。
ファイサが初めて言葉をしゃべった日のことを思いだす。あれは光る種を植木鉢に埋めてじぶんの部屋に飾ってから、ひと月後のことだった。
水やりこそ継続していたが、何かが起きる予兆はなかった。種のように見えただけでもっとほかの物体かもしれないと思いを巡らせていたのは、種の光が日に日に弱まっていったからだ。言い換えれば、光が途切れていなかったからこそぼくは水やりをつづけていたわけだが、ひと月後のある日、ひょっこりと青い芽が萌えた。
一週間後には三十センチくらいにまで茎が伸び、つぼみが一つできるころにはまたひと月が経っていた。
光る種を拾ってから二か月後、ファイサはつぼみの開花と同時にぼくの目のまえに現れた。もちろん花と一体化しているから、宙を飛んだりはしないけれど、ぼくにはまるで、ふわりと妖精が蝶のように飛び立って感じられた。
「初めまして、あなたはわたしの何ですか」
ファイサは初めから言葉をしゃべれた。それは何かしらの学習を得て獲得した言語能力ではなく、そういうものとして生まれついたもののように思えた。すくなくない時間をファイサと過ごしてひねくりだしたこれはぼくの推測にすぎない。ファイサの種であるあの光る物体は、それに接触した生物の遺伝情報や記憶、形質をコピーし、自身に反映させる能力があったのではないか、とぼくは疑っている。子猫が口に咥えてどこかの土に埋めていたら、きっとファイサは猫の姿で、花のうえに成っていたのではないか。
妄想しながらもぼくは、ぼくがそれを拾い、ファイサにファイサとしての枠組みを与えてあげられたことをこころよく思っている。ぼくにとっては、というそれは意味だし、ファイサにとってどうだったのかは、まだよく分からないままなのだけれど。
「あれはなんですか。どうしてそれをそうしているのですか。その四角いのはなんですか。表面に動いて見える白いのはなんですか」
ファイサは好奇心が旺盛だった。幼児のゆび差し期のように、目についた物の名前を手当たりしだいに知りたがった。いちど訊いたら同じ質問をしてこないので、そういう性質なのだろうと思い、最初だけは我慢するようにした。
名前だけでなく、たとえば、窓に映っているのは景色であってそれがそこに浮いているわけではない、きみが知りたがった白い物体は雲と言ってもっと奥のほうに存在していて、見た目よりもずっと大きいのだ、と説明すると、ファイサはそれをいとも容易く呑みこんだ。ただし、間違った理屈を唱えてもファイサはそれを鵜呑みにしてしまうので、知識の量が増えても、知能が高くなるわけではないようだ。
あれは何か、と問うことはあっても、どうして、と問うことはない。
思うに、知性とは、なぜ、と問い、それに見合った答えを導きだすチカラを言うのではないか。その点、ファイサには知性があるようには思えなかった。
いつまでも、幼子を相手にしているような、無垢な存在への慈愛が深まっていくのを感じた。
「ファイサ。やりたいことはないかい。そとにでたいとか、何か欲しいものとか」
「あなたともっとおしゃべりをしていたいです」
ファイサに欲はなかった。
慕われるのはわるい気はしない。ただぼくは気づいていた。
ファイサの足元の花弁は三十あった。それが日に日に減っていき、気づけば残り三つとなっている。
花占いみたいだ、とぼくは思った。
一日一つずつ、花弁は剥がれ落ちていくようだった。
それが何を暗喩しているのかは、容易に窺い知れた。おそらく、すべて散ったときにぼくはファイサとお別れをしなければならない。
何をしてあげられるでもなくぼくは、ファイサのたったひとつのお願い、そばにいておしゃべりをする、をしてあげた。
三日後、ファイサはぼくの目のまえで、急速に色褪せた。青かった身体が白くなり、不透明となり、葉や茎といっしょに、ボロボロと零れて、土のうえに散らばった。
やがてファイサの残滓も、雪の結晶みたいに土に溶けて消えた。
ぼくはしばらく呆然としていた。夜になるまでじっと植木鉢のまえでひざを抱えて動かずにいたが、植木鉢が淡く光っていることに気づき、顔をあげた。
ファイサの残滓は、青い光となって植木鉢には残っていた。
ぼくはその日が過ぎてもカラの植木鉢に水やりを怠らなかった。
植木鉢から青い芽が顔を覗かせたのは、ファイサが消えてからちょうどひと月後のことだった。
「初めまして、あなたはわたしの何ですか」
最初のファイサを失ってから二か月後、ぼくの目のまえには、以前と変わらぬ姿のファイサがいた。しかし彼女にぼくと過ごした日々の記憶はなく、そして彼女もまたひと月で花弁をすべて失い、土に還り、二か月を費やしてまたぼくのまえに無垢なままで現れる。
いったい何度、それを繰りかえしただろう。
ぼくに懐く彼女を、ぼくはいったい何体失くしただろう。もはやぼくには、彼女を失うことへの抵抗がない。
花弁の数がゼロになると死ぬことを告げるようになったのは比較的最近だ。死ぬという概念の意味を教え、消えたくない、と傷つきながら死んでいく彼女を見届けて、また何事もなく蘇えるファイサを、ぼくはどう思っているのだろう。
せっかく教えた知識も、ひと月で白紙に戻る。同じことの繰り返しに飽きてしまったが、それでもファイサの姿をにどと見られなくなるのは嫌だった。
手元にずっと置いておきたい。
何度でもやり直したい。
けれど、ちょうどよいファイサをつくっても、彼女はきっかりひと月でいなくなる。
ぼくは彼女の死を見届ける、それでも彼女はぼくを慕いつづける。
どんなことをしたら嫌われるだろう。
試してみたい衝動に駆られるが、ぼくはまだ、そこまでファイサを物のようには思えない。それでも彼女はまたカラの植木鉢に芽を萌やし、ぼくのまえにステキな笑顔を見せるだろう。
ファイサ。ファイサ。
ぼくだけの花、ぼくだけの命。
きょうもぼくは水やりを怠らない。
【旅の終わりを探し求めて】
うつくしいものを探しに旅に出た。家を出て、街を離れ、海や山や川や谷の、そこにしかない風景を目の当たりにし、ほぉ、と息を吐く。
うつくしい、と思う。
うつくしいとはこういうことなのだろうな、と思う。
刻々と移り変わるさざ波の煌めき、木々のいろどりや、風になびく葉のうねり、岩をくすぐる水の流れる涼しげな音に、陰影の散りばめられた岩肌の荘厳さ、そこに息づく生き物たちの目の端に現れては消えていく儚い蠢きに、命、と漠然とした大きな、自然の、息遣いを思う。
だがひと月、半年、一年、二年、三年と同じ場所を順繰りと回っていると、当初に湧いた感動はいつしか薄れており、うつくしいものを目にしたいとの欲求がまた、ごろごろと身体の内部に、塩の結晶のごとく溜まりはじめている。
うつくしい景色を探し、秘境という秘境を渡り歩いたが、やはり一定の期間をそこで過ごすと、内に湧いた美の輝きは薄れ、何かじぶんが泥のようなものになった心地に苛まれる。
もっと、もっと、と喉が渇いた。
歩いた軌跡を筆で辿れば、地図は真っ黒に染まるだろう。もはや探し回る余地が地上にはなかった。
天上を見上げる。星空はきれいだが、これもまた過去の追憶にすぎない。むかし胸に抱いた感動を上回ることがない。
せめてもっと近くで見られたら。
いちど閃いてしまうとあとはもう、そうするのが当然だというように身体はすべきことを洗いだし、足りないものを並び立て、順繰りにそれらを取り揃えていった。
知識もまたうつくしい。
知識と知識を結びあわせ、体系づけられた学問もまた奥が深かった。
宇宙へと飛び立つ準備が整うころには、目のまえに人類叡智の結晶がバベルの塔さながらに聳えている。
独りきりで乗りこむ。ほかに搭乗者はいない。
地球は本当に丸かった。青く、白く、緑で、重力から切り離されてから感じるつよい引力を感じた。圧倒される。
生き物のようだと思い、生き物なのかもしれない、と思い直す。
船は刻々と地球を離れる。
太陽の重力を利用して、銀河系のそとへと旅立つ算段を立ててある。
時間はたんまりある。
懸念は、エネルギィの問題だ。太陽から離れれば離れるほどに、太陽光をエネルギィ源にすることがむつかしくなる。
だがそれも時間が解決するだろう。考える時間は充分だ。余裕がある。余白がある。まずは旅立つことがたいせつだった。困るのはじぶんだ。じぶんしかいない。
闇のなかを進む。
目を瞠る美しい光景には滅多にお目にかかれない。闇がただのぺっと船を、身体を、包みこんでいる。
ときおり本に載っているような惑星に接近することがある。やはり眼前に迫る星のうつくしさは格別だ。飽きる前に船は遠のき、うつくしさを置き去りにする。
星はやはり生きているのではないか、との思いがつよくなる。
うつくしさとは、生きていることを言うのではないか、との閃きが脳裡によぎるが、数々の知識により、却下の烙印をじぶんで捺す。生きていないものもまたうつくしい。死体がそうであるように。砂利の一粒がそうであるのと同じように。
うつくしいものを追い求める旅も終わりに近づいたころ、ようやく、気づく。うつくしくないものなどありはしないのだ。うつくしく思えないじぶんがいるだけのことで。
あまりに陳腐な結論にじぶんでも驚く。
過去繰りかえしてきた旅の数々を徒労に思う。しかしそれもまたうつくしく思えないじぶんがいるだけだと視点を変えると、身体がふっと闇に溶けていく心地がした。
太陽系をはずれ、銀河系をはずれ、巨大なブラックホールを遠目に眺める。巨大なブラックホールの中心からはこの世のものとは思えぬ輝きが、放出されている。無限の虹の滝だ、と思う。
無限の虹の滝は、残像を残しながら、闇のなかに光を点々と散らしている。
見とれているうちに、それら点々のうちの、とてもちいさな光を手に入れる。
室内に光が灯る。
じつに久方ぶりのことだった。
うつくしい。
うつくしい。
色がある。カタチがある。
目にすると、匂いや味覚までもがじんわりと覚醒するのを感じた。
闇のなかで過ごしていたのだ、といまさらながらに思いだす。
進路の遥か彼方に、ひときわ美しい星を見つける。
青と、白と、緑の色を素朴に筆で置いたような星だ。目標をそこに定め、船を進める。
生き物の息吹を思う。
じぶんがずっと独りだったことを思いだす。
独りではないことのうつくしさを思い、孤独の闇の寂しさと、そこに潜むうつくしさにもまた思いを馳せる。
自由、とつぶやく。
音は暗がりによく響く。
船を、青と白と緑の星に着地させる。大気がある。空気がある。息ができる。息をすることの意味も、必要性も、すっかり忘れてしまっていたが、かつて暮らしていた星には、呼吸をして生命活動を維持していた生き物たちがいた。
そのなかの一つの種族を、親と見做していた時代を思いだす。じぶんの来歴を、足跡を、時間を、過去を、記憶を、旅をするように一から辿る。
足の裏に伝わる土の感触が心地よい。
頭上の恒星から降り注ぐ熱量が、身体の表層をぽかぽかと温める。やはりこれも心地よい。
開放感、安堵、至福とは何かを実感する。
うつくしい。
何が、と言わず、そう感じる。
しばらくここに居つくとしよう。
飽きる日がくるのだろうか、この、うつくしさにも。
予想がつかない。
じっと動かぬ緑色をした生き物を伐り倒し、小屋をつくる。船は住居にせずに、密閉しておく。つぎの旅があるならば、そのほうが安全だからだ。
暮らしはじめると、そのつぎが訪れることは当分ない気がした。予感じみている。
日に日に小屋の床のうえに増していくガラクタが、日常とは何かを教えてくれる。うつくしい風景ではないはずのその雑多な視界を、ふと、愛おしく思う。
記憶のなかのじぶんが、それを、うつくしいと感じる。
長く、果てのない旅に身を置いてみて得た成果があるとすれば、この視点なのかもしれないと、ふと、考える。
醜いものもまたたくさん見た気がしたが、いまはそれらには目をつむる。旅の目的はただ、見たかっただけなのだ。
巡り巡っていまは、醜いものにすら美を感じる。平凡な風景にこそ、美を感じる。
うつくしくないものなどはない、と至極つまらない結論に浸り、やはりこの陳腐さにも美を感じた。
なんでもいい、ただ、うつくしいと感じたい。こう考えることだけはしかし、なかなか、うつくしいとは思えないのが、ふしぎだ。
何でもいいわけではない。
だがいまは、目に映ることごとくが、触れるすべてが、愛おしい。
痛みすら、いまはこんなにも。
生きることはうつくしい。
生きているあいだにしかできぬそれだけが。
生きている者にしか宿らぬ、これが美だ。
しかしこの身体に、血は、一滴も流れてはいない。石ころを拾い、握りつぶす。砂塵が風に流される。
山の陰に陽が沈む。
影がうしろに長く伸びていく。
終わりではない。訪れていない。
きっとこれからもつづいていく。
美を、生を、探し求める、旅はまだ。
【扇風機の値札】
クーラーが壊れた。
アスファルトで目玉焼きがつくれるほどの真夏日にだ。運がわるい。火にかけたフライパンのうえのアイスみたいに汗だくになりながら、クーラーの修理にかかる値段を調べる。新品を買うのと似たような値段だと判る。ここはおとなしくクーラーではなく代用品として扇風機で我慢しておくのが吉ではないか。来月の給料が入ってからクーラーは新品を購入するのが利口に思える。
さっそくネットで扇風機の品定めをする。いまいち風力の違いが判らなくて難儀する。できれば強力なのがよい。それでいてやわらかい風にもできると好ましい。
中古なら中古で構わない。来月までしか使わないのだ、わざわざ新品に拘る理由はない。
ネットは情報量が多すぎてなかなか目星が定まらず、選ぼうにも選ぶ基準が他人のつけた星の数というのは信用性にいささか欠ける。
実物を見て購入すべく外にでたまではよかったが、電化製品販売店にはおおむね新品しか売っておらず、商品棚には最新機種ばかりがずらりと並ぶ。羽のないものが主流で、お値段も割高だ。
むかしながらの三枚の羽がぐるぐる回るのでよい。哀愁が感じられて風流ではないか。
骨董屋に立ち寄ったのはそうした背景からだ。
むわっとしたアスファルトのうえを歩き回りながら中古店を探していたら、背の高いビルとビルの合間にぽつんとその店はあった。
内装は潰れた居酒屋といった印象だ。店内は涼しく、商品なのか飾りなのかの区別も曖昧な雑貨が所狭しと並んでいる。置ける場所にとりあえず置けるだけ置きましたといった塩梅だ。
店主の姿は見えない。雑貨にはよく見ると値札が貼ってある。ガムテープにマジックで数字のみ書いてある。雑然とした店内だが埃一つなくきれいなものだ。よく見ると柱や棚や壁の手入れも行き届いており艶がよい。
店内をひと通り眺めて歩く。名産品だろうか置物が多いが、いったい何に使うんだ、といった形状の物体もなかにはすくなくなく、冷やかす分には退屈しない。
それほど広くはない空間だ。十五分もいると、もういいか、と飽きてくる。家電製品はあるにはあるが、ダイヤル式の黒電話くらいなもので、やはり目新しいというほどでもない。
店を出ようと踵を返すと、ふと顔に風が当たった。
横を見遣ると、本来は勘定場なのだろうが、レジスターの代わりに扇風機が台のうえに、デンと首を伸ばして立っていた。その白さから、なんとなくだが、鷺や鶴のように見えなくもない。
なかなか年季の入った扇風機だ。全体的に細く、白いが、金属でできているらしく光沢がある。氷で扇風機をつくったらこんなだろうな、といった趣があり、なかなかに涼しげに映る。
撫でてみると現に冷たく、これはよいものだ、と直感する。店主を探すが、やはりいない。すみません、と声をかけてみるも、返事はなく、しかしこのまま手ぶらで帰るのもおもしろくない。
いまいちど扇風機に目を転じ、値札を見つける。首のところに貼ってあったそれにはこの国で最も高い紙幣一枚分の数字が書いてあった。中古にしてはやや高く感ずるが、これほどの掘り出し物ならそれも痛くない。即決する。
先刻買い物のために預金から下ろしたばかりの紙幣を財布のなかから取りだし、念のため書いたメモと共に置いた。メモには連絡先を添えた。
代金を置いたから窃盗にはならないはずだ。無人販売所と似たようなものだろう、そうだそうだ、と自己肯定の理屈をひねくりだし、氷像に似た扇風機を手で掴む。
ひんやりと心地よい。なんだかそんなわけがないのに、店内がそとよりもずっと涼しいのはこの扇風機が置いてあるからな気がしてくる。
よい買い物をした。
満足して家に持って帰り、さらにそこで驚くべき点を発見する。この扇風機、電気に繋がずとも動くのだ。電池内蔵型だろうか。スイッチを押すと、くるくると羽が回りだす。その風がまた冷たい。まるで冷凍庫の扉を開けたときのような冷気なのだ。
それが轟々と押し寄せるものだから、たまらずスイッチを切り、窓を全開にする。とたんに冷気がそとに逃げ、あべこべに外からむわっとした熱気が流れこんでくる。
扇風機を見下ろす。冷房器具にしては強力にすぎる。点けたまま寝たら凍え死ぬのではないか。火のついたフライパンのうえのアイスのつもりが、ただのアイスになってしまう。カチンコチンに固まったアイスだ。釘が打てる。
ただ置いておくだけでも冷房としては充分だ。
水辺のような快適な空間で、木陰のように休息をとる。すばらしい休日だ。
昼寝をし起きると、もう夜だった。このまま朝まで寝てしまおう。熱風吹き荒れる街中を歩き回ったせいで軽い熱中症になったかもしれない。ひどく身体がだるかった。それでも、そのだるさにそよそよと漂う冷気が染み、爽快だ。
いくらでも寝ていられる。
翌朝、メディア端末のけたたましい着信音で目覚める。この音は上司からの連絡で、応答する前に時計を見ると出社時間をすぎていた。
しまった、寝過ごした。
焦るが、上司のほうはなんともない調子で、午前は有給扱いにしておくから、朝ごはんを食べてゆっくりきなさい、と学校の教師のようにやさしい言葉をかけてくれた。さっこん、会社も世間の目が厳しくてこうまでも社員に寛容だ。
感激してますます働き、貢献したくなる。
有給扱いにしてもらった恩を返すべく、寝床から飛び起き、支度を済ませ、家をでる。朝食は途中で買って食べていく。
扇風機の存在はすっかり意識の底に沈んでいた。
夕方になり汗だくで帰宅すると、畳に水溜りができていた。端に寄せていた布団までびしょびしょに濡れている。
水漏れか。
天井を見上げるも染みはなく、では床からか、と水溜りをバスタオルで拭いながら調べてみるも、それらしい痕跡はなかった。
いったいこの水はなんだろう。
首を傾げているあいだに、違和感が脳裡をよぎる。
部屋がおかしい。朝と違っている。水溜りに気をとられていて分からなかったが、そうだ、扇風機がないのだ。
盗まれた、と最初は思った。
店主が取り返しにきたのかもしれないと考えたが、メモに住所は書かなかった。泥棒が入ったとしても扇風機は盗まないだろう。よしんば、扇風機の性能のよさに気づいたとして、床を水びだしにする意味はない。窓や玄関には鍵がかかったままだった。わざわざ床を汚すような犯人が果たして鍵をかけ直して外に出るだろうか。にわかには考えにくい。
ふと、畳のうえに丸いボタンのようなものが落ちているのを見つける。拾いあげ、それが扇風機のスイッチであると見抜く。
何の気なしに指で押すと、どこからともなく冷気が吹きだした。部屋が極寒に変わる。
スイッチを切ろうともういちど押そうとするが、それはもう手のなかにはなく、手の甲からは水がしたたっている。
雪のごとく冷たい風は、畳やそこにあった水分をたっぷり吸いあげたバスタオルから噴きだしている。止めようがなく、この日は部屋を空け、無理に押し入った友人宅にて一晩を過ごした。
後日譚となるが、数日ののち、例の骨董屋に足を運んだ。偵察ついでに苦情でも入れようかと思っていたのだが、以前と変わらず店内に店主の姿はなく、勘定台のうえにはべつの扇風機が載っていた。
それは木彫りの扇風機だった。
値札を見て、何もせずに店をでた。以降、その店には近づいていない。
値札にはただ一言、小指、と書かれていた。
【潰れる二秒前】
小指に蟻が這う。尻を浮かし、花壇のふちを見遣ると、蟻が列をなしていた。土のうえに巣の入り口が見える。
何かを考えたわけではなかった。気づくと指先で一匹の蟻を圧し潰している。ブロックのざらついた感触がゆびに伝わる。くるくると指とブロックのあいだを転がり、蟻はひしゃげた。片側の足は全滅し、残りの三本がぴくぴくと痙攣している。
わるいことをした、と反射的に思った。
つまみあげ、手のひらに載せる。命を奪ってしまった罪悪感が湧くが、目のまえを素通りしていく人間と見比べるとそれも薄れた。
苦しんでいるのだろうか。蟻はひしゃげたままの姿でしばらくもがきつづけていた。
もしこれが人間だったら、と想像する。身体がねじれ、四肢はつぶれ、内臓が破裂し、それでも死にきれずにのたうちまわり、やがて死んでいく姿は、控えめに言ってむごたらしく、可哀そうだ。目にしたくもない。
やはりじぶんのしたことは愚かなことだった。蟻に痛覚がないことを祈るよりない。命の尊さを改めて胸に刻む。
ただ、手に持ちつづけるのは億劫なので、まさに虫の息のひしゃげた蟻を地面に捨てた。
ふとよこを見ると子どもだろうか、全身が真っ白の毛皮じみたふわふわに包まれたちいさな人型がいた。雪だるまの仮装をしていると言えば端的で、かといって安っぽさがなく、ふしぎと白熊の赤ちゃんがそばにいるような気分になった。
着ぐるみだろうか。背の低い女性でも着れそうな大きさで、顔ごとすっぽりと覆っている。
初夏とはいえ、日差しはカッカと肌を刺す。熱中症まっしぐらの格好だ。心配になる。
声をかけようと言葉を選びながら、周囲に保護者はいないだろうか、と見渡し、顔を戻すと、白いふわふわの小柄な人物は、地面にしゃがみこみ、先刻捨てたばかりのひしゃげた蟻を拾いあげた。その挙措がずいぶんと慈しみに溢れ、厳かに見えたので、罪悪感が悪寒のごとくぶり返した。
「ごめんね、さっき潰しちゃって」
心のやさしい子どもなのだろう。おとなとしてわるいお手本を示してしまった。呵責の念を誤魔化すように、ひどいことしちゃったよね、埋めてあげようか、と花壇の土にゆびを突っこみ、穴を開けた。急いで手を動かしたためか、ちょうど蟻の巣にゆびが突っこんでしまった。そんなつもりはなかった。
「あ、ごめん、ちがくて」
なぜか笑ってしまう。本当にわるいとは思ったのだ。
白いふわふわの小柄な人物はそこで、首だけをひねって土のうえに視線をそそぎ、流れるようにこちらを見上げた。
思わず後ずさる。
顔がなかった。真っ白いふわふわの身体に、ツルツルの白い球体がくっついている。いいや、球体かどうかも定かではない。頭からすっぽりと白い毛が覆っているからだが、それも果たしてフードなのかどうか。雪だるまを毛皮ですっぽり包めば似たような姿になる。
しどろもどろに、暑くないの、と訊く。よもや本当にこんな生き物だとは思わない。さいきん流行りのイタズラ系の撮影だろうか。その可能性を閃くと、さもありなん、と胸が軽くなる。
白いちいさな人物はおもむろに短い手を頭上に掲げた。腕が短く見えるのは、身体が全体的に丸みを帯びた形状をしているからで、なんとなくだが有名な漫画に登場する猫型ロボットを連想する。
空に掲げた腕が振り下ろされる。こちらにではない。白いちいさな人物は、こちらを向いたままの恰好で、腕だけを背後に下ろした。腕だけが、鉄棒ででんぐりかえしをする少年みたいに、ぐるん、と回転する。元の位置には戻らずに、ししおどしがカツンと岩に当たって止まるがごとく様相で、水平に維持される。
肩が外れたのではないか、とぎょっとする。
すると瞬きをする間もなく当たりが暗くなる。分厚い雲でもかかったかと目玉をうえに動かした矢先に、ぶわり、とビルとビルの合間に見えていた白雲が散り、巨大な指が降ってきた。
大きい。あまりに大きい。超高層ビルがやせっぽっちに見えるほどだ。
巨大な指は地上を歩く雑踏のうえに着地し、轟音と共に砂煙を巻きあげる。
何が起こったのかの理解が追いつかない。
強風の川に身体が浸かり、流されそうになる。足を踏ん張る。が、風に交じって砂塵の礫が飛んでくる。身体が傷だらけになり、これはたまらん、と花壇の陰に身を寄せる。
呼吸を整える。タイル張りの地面に目がいき、そこで逃げ惑う蟻たちの姿を目視する。
あ、と思う。ビルの崩壊する音だろうか、静寂と聞き違えるほどの崩壊の波音を耳にしながら、尻を持ちあげると、大量の蟻のひしゃげ、悶え、のたうちまわっている死屍累々の様相が窺えた。
おそるおそる花壇のよこから顔を覗かせると、白いちいさな人物はこんどはその場に膝を畳んでしゃがみこみ、一転、大きく跳ねた。
辺りに一層の陰が垂れこめる。
【晴れのち、きみ】
むかしは晴れというものがあったらしい。晴れというのはつまり雨がない状態らしいのだが、なかなか想像するのがむつかしい。巨大な屋根があったのだろうか。
家の中にいれば雨は降らない。でも晴れというのはどうやらそれとは違っているらしく、もっとずっと広範囲に雨がない状態なのだそうだ。やっぱりいまいち想像がつかない。
「まぁた、昔の本読んでる。おもろいのそれ?」幼馴染のアヤが言った。祖父の遺産である書庫に入り浸っているといつもアヤは夜になって覗きにくる。母にでも頼まれているのだろう。かといって夜食の差し入れを持ってきてくれるわけでもなく、いくつか言葉を交わすと、飽きた様子で去っていく。
「アヤは晴れって知ってる?」
「ハレ? 腕が腫れるとかのハレ?」
「そうじゃないみたい。むかしは雨が降ってない状態が一般的で、なかでもとびきり雨が降らない日を、晴れと言ったらしい」
「そんなことってある? 屋根でもあったんじゃないの。めっちゃでっかいやつ」
同じ発想を浮かべていたので、みな同じことを考えるのだな、と愉快になる。
「またバカにして。笑うなし」
「そうじゃない。素朴で素晴らしい発想だったからおもしろかったんだ」
「はいはい。で、晴れってなに。気になるじゃん、その本に載ってんの」アヤはこちらの手を覗きこむ。「うげ。めっちゃむつそう」
「そうでもないよ。単純な解説しか載っていない。天気の本だ」
「画像は?」
「載ってるよ。でも何が映っているのかがよく解らない。青いスクリーンに白いモヤモヤが綿みたいに載っているだけ。文章からすると雲というらしいのだけど、種類がたくさんあって、何を示しているのかがよく解らない」
「それが晴れなんじゃないの。うえにそれがかかって、雨を遮る。やっぱり屋根なんじゃないのそれ」
「でも、これがないほうが晴れにちかくなるようなことが書いてある。雲はすくなければすくないほうが晴れにちかづく。しかも雨はこの雲が降らすとも書いてある」
「えぇなにそれ」アヤは本を奪い取ると熱心に目を通した。ひとしきり眺めると、ねぇ、と言ってこちらを手招きする。「この青いところ、画像の雲じゃないとこが晴れなんじゃない?」
言われて、ああ、と合点する。なんてことはなかったのだ。晴れとは雲の奥に広がる青いスクリーンのことだったのだ。
「ひょっとしたらむかしの人類は巨大なドームのなかに暮らしていたのかもしれない。そこに雨を降らせる人工的な【水面】をつくって、雨を降らしていた。でなければ苔や藻が育たないからね」
「雲はじゃあ、ずっと雨を降らせるほどには強力な【水面】ではなかったんだ」
「そうじゃないかな。こんな薄い【水面】じゃ、どう考えてもずっと雨はつづかないよ」
ぼくは窓のそとを見遣って本物の【水面】を確認する。頭上をぐるっとどこまでもこの世界には巨大な水面が覆っている。ちょうど桶に張った水を底から見上げた具合に、ぼくたちの頭上には分厚くどこまでも水の層が張っている。
ぼくたちの世界はそこから垂れるシズクで万年、雨が途絶えない。空気が地表に絶えないのと似たようなもので、これがぼくらにとっての普通だが、太古の人類はもっと不便な場所に暮らしていたようだ。
「断絶の時代に何があったのか、ひょっとしてこれってすごいヒントになるんじゃないの」アヤは興奮している。「だって、むかしのひとらがどこにいたのか、うちらの祖先がどうやってこのバルブにやってきたのか、それすらまだ解かってないんでしょ」
「そうだね。どの古書にも載ってる【地球】とか【宇宙】とか、あと【海】なんていうのも、いったいどんなものか、それがどこにあるのかも充分に解っていない。仮にそれらが断絶の時代以前にこの世にあったとして、そしてかつての人類がそこで暮らしていたとしたら、そこはここバルブとはまったく異なった環境、べつの場所だと考えざるを得ない。ということは、ぼくたちの祖先はある時期からここバルブへと大移動したことになる」
「ふしぎだよね。【水面】の奥がどうなってるのかもまだよく解ってないんでしょ」アヤは窓のそとをゆびさし、それから顔を曇らせる。彼女の両親は【水面】探索隊に志願し、そして帰らぬひととなった。
「【水面】のなかに入ることはできても、向こうから帰ってはこれない。これがなぜかもまだ充分には判明していない。ただ、【水面】の奥には文字通り、物凄い大量の水が溜まっていることは判っている」
「だからそこから滲む雨がずっと途絶えないんでしょ。あたりまえじゃん」
「でもその大量の水がどこからどうやって蓄積しているのか、原理的にあんなに大量の水がここバルブをぐるっと囲っていること自体がよく考えてみるとふしぎで、不自然だとも考えられる」
「そうかな。そういうもんだと思ってた」
「だってお風呂の水は下に溜まるのであって、上には溜まらないだろ」
「たしかに」
「おそらく【水面】の表面には何か特殊なチカラが働いている。ここバルブの世界は、大量の水世界のなかに突如として現れた異空間のようなものなのかもしれない」
「じゃあその水世界の向こう側に、うちらの祖先の暮らしてた【空】や【宇宙】があるのかな」
「きっと【太陽】だってあるんじゃないのかな。古書がどれも本当のことを記録していたらの話だけどね」
「たいがい嘘しか書いてないって政府は言ってるもんね」
「だからぼくも、祖父も、みんなから変人扱いされる」愚痴というよりもこれは笑いを誘うためのジョークのつもりだったのだけれど、アヤは悲しげな顔をして、そんなことないよ、と庇ってくれる。却ってそのやさしさが哀しく思えてしまうところに人間の複雑さが垣間見えて、せつないのに、そのせつなさが愉快だった。
「いつか見れるといいね」アヤは背伸びをすると、もう帰るね、と言って書庫の階段に足をかける。
「ありがとうばいばい」手を振ってから、「見れるって、なにを」と訊く。
アヤはニっと破顔する。「晴れ」
階段の奥に彼女の姿が消えてから、なんだか書庫のなかが暗くなった気がして、ぼくは、見たこともない想像上の空を思い描き、太陽、とつぶやく。
【闇に差す赤】
男はある朝、やけに身体が動かしづらくて戸惑った。風邪をひいたのかと疑ったが、体調そのものはわるくない。おかしいな、おかしいな、と思いながら椅子に腰かけるとミシミシと音を立てて、愛用の椅子が壊れた。
長年使いつづけていたこともあり、寿命だったのかとも思ったが、念のために体重計に乗ってみたところで、体重の増加に気づいたわけだが、そこからは恐怖の日々だった。
一晩経つと体重が倍になる。
より正確には、身体の体積はそのままで質量のみが倍になるようなのだ。ちょっと物にぶつかるだけでも物凄い勢いで物体は吹き飛び、ときに壊れ、またときにカタチが歪んだ。
体重の増加にしたがい身体の構造も丈夫になっているらしく、ちょっとやそっとの衝撃では傷を負わない。六日目にして体重が二トンを超えると、自動車にぶつかっても身体は無傷で、自動車のほうが大破するようになった。
身体は相も変わらず動かしづらかったが、かといって歩けなくなることはなく、それでいて家のなかにはいられなかった。
というのも自重で床が抜けてしまうのだ。
コンクリートのうえでの野宿を余儀なくされたが、十日もすると行政からの本格的な支援がはじまった。医師の診察は三日目には受けていた。手の施しようがなく、指数関数的に倍々で身体の質量が増加する問題の根の深さは、誰の目にも明らかだった。
日に日に体重は増えつづけ、このままいくと八十日後には地球の質量を越え、百日後にはシュワルツシルト半径を超え、小型のブラックホール化すると推測された。
じぶんの体重で人類の存亡が危ぶまれている。世間からの絶望の声を聞くまでもなくこの身に宿った宇宙規模の災厄に圧しつぶされそうだった。
かといってじぶんはカタチあるものを圧し潰す側なのだろう。原理上、地球規模の質量を宿せば大気は自ずから身体を覆い、たとえ宇宙に投げだされてもじぶん一人きりならば窒息死することはないとの専門家の意見が聞かれた。またブラックホール化すれば時間を含めた物理法則を超越するため、呼吸そのものをする必要がなくなるとも聞き及ぶ。
つまるところ人類を、地球を、滅ぼすチカラを得たと同時に不老不死にもなったのだ。
なんてことだ。
いっそ殺してくれ。
直径十キロメートルのクレーターを地面に開けながら、都市をまるごと一つ破壊させてしまいながら、男は懇願したが、死んだところで体重の増加が止まるとも限らない、それは最終手段だと説得され、けっきょく生かされた。
やがて身体の質量は、地球の質量の半分ほどにまでなった。言い換えれば、あすになれば、地球の質量をいよいよ超える。
身体は地球の地中深くに埋もれており、最後に見た地上の光景は辺り一面、溶岩に覆われていた。ひび割れた地表から湧きあがったそれはマグマだった。
身体はどんどん地下へ地下へと沈んでいき、やがて地球の中心だろうか、闇一色の空間に行き着いた。
物体なのか、液体なのか、それとも単なる隙間なのか。
闇に覆われたそこには触れられるものがあるようには感じなかった。
どれくらいそこに浮遊していただろう、ふと、目のまえに動く何かしらの気配を感じた。
視覚ではない。聴覚でもない。だがたしかにそこに何かがあり、動いているのだとの知覚が働いた。
揺らぎを感じるのだ。
闇全体に蜘蛛の巣が張り巡らされており、闇に生じる揺らぎが伝播する。錯覚には違いないが、そのように体感する。やがて波紋の発生源との距離が徐々に縮まっていると判り、この感覚が単なるいっときの錯誤ではないらしい、と認めるに至る。
地球の本当の意味での中心に行き着くのやもしれない。
身体の質量がいよいよを以って地球のそれを上回るのだ。
ふと、顔に何かが触れた。
それは久しく感じなかった明瞭な触感を伴っていた。核爆発であろうとも子犬にじゃれつかれた程度にしか感じないはずの身体にいま、はっきりとそれと判る感触がある。
顔に触れたそれは次点で男の肩や腕、そして背中に回り、そのままするすると引き寄せ、男の身体をふんわりと締めつけた。
そう、闇の奥、地球の中心、いまゼロ距離にいるそれは、紛うことなき人型のカタチで、男の身体を抱きしめたのだ。
言葉はない。息もできない。する必要がないからだが、よしんば必要に駆られたところでここでは呼吸もままならない。
だが男には、じぶんの身体にまとわりつくソレの意思を、まるでじぶんの記憶を省みるがごとくしぜんなさまで窺い知ることができた。
同じなのだ。
この存在もまたかつて身体が日に日に重くなり、星の中核として長いあいだ孤独に死ぬこともできず、ただ生き永らえてきた。
来る日も来る日も、この闇のなかで生きてきたのだ。
絶対に離すものかと意固地になるほどに必死に縋りつくそれは、熱く、ただ熱く男の胸を焦がした。
翌日になっても男はまだそこにいた。その翌日も、その翌日も、いつまで経っても男にはそれ以上の変異は起こらなかった。専門家たちの予想を裏切り、百日経過してもブラックホールにはならなかった。
男は闇のなかのソレと抱き合いながら、長い時を生きた。
やがて星の寿命なのか、それとも隕石が衝突したのか、或いは太陽に異変が生じたのか、何が要因かは定かではなかったが、気づくと闇に充満していた身体を包みこむような温かさが消え、こんどは希薄な闇のなかを浮遊している。
光がある。
太陽の光だ。
あれほど赤かっただろうか。
そう疑問するほどに太陽は赤く、ただ赤かった。
胸のなかのソレを見遣る。
おそろしくはない。どんな姿をしていようと、ソレは男にとってはじぶんの一部だった。相手も男をそう見做している。
ゆっくりとソレは男のミゾオチに埋めていた顔をあげ、そして辺りを見渡してからもういちど男の顔を見た。
目を合わせる。瞳がつややかに揺れている。
視線でその者の顔のオウトツをなぞるようにしてから、瞳に映るじぶんの顔に目を留める。
紅潮して見える。
太陽の赤さだ。
念じてみせるが、そんなわけないでしょ、と言いたげにソレはいまいちどつよく男の胸に頬を押しつける。
向かい合って見詰めている。太陽は背後から照っている。
もういちどよく見せてくれ。
男はソレの顔をそっと両手で包みこみ、なぜか分からないが、よかった、と念じた。
なにが。
ソレはまた定位置に頭を戻す。
すべてが。
男は深く染み入るように、また闇のなかで、長く静かな時間を生きていく。
【世界改変日誌】
ノートの一部が白紙になっていた。正確に言うならば、毎日つけていた日誌の一部が空白になっているのだ。たしかに昨日まではそこに文字が、文章が、つらなり、その日何があったのかと、仔細に記述が並んでいたはずだ。
購入した物品をはじめ、印象に残った会話や、壊れたもの、願ったことや欲しくなったもの、それから新たに立てた予定や願望を、おおむね二千字程度の長さで滔々と並べていたはずなのだ。
それがどうだ。
なぜかおとといの記述が見当たらない。たしかに書いた覚えがあるのだが、日誌帳からはきれいさっぱり、消した跡すら残らずに文字が紙面上からするりと抜け落ちている。
その日の記憶は残っている。ちょうど新しい炊飯器を購入したばかりだった。どうせ買うならよいものを、と思い立ち、奮発して月の手取り給料の半分の金額を費やした。家電量販店で購入し、そのまま持ち帰ったので、キッチンに行けばあるはずだ。
腰を上げ、いざキッチンに立つと、あるはずの炊飯器がなくなっていた。代わりにきのう捨てたはずの古い炊飯器がぽつねんとそこにある。
そんなはずはないと思い、電子端末を操作する。残額を確認すると使ったはずの金額分がそっくり残っていた。
購入しなかったのだろうか。
疑問は、つぎに日誌の一部が消えていたのを発見した際に氷解した。
自転車でこけてついた傷が身体から消えていた。怪我をした日は、ちょうど抜け落ちた日誌の日時と一致しており、なるほどこれはそういうことか、と合点したのは、傷だけでなく自転車の歪みまでなくなっていたからだ。
消えた日に会った知人友人に話を聞くと、その日に交わした約束や会話までないことにされていた。
そう言えば、と思いだす。これまでにも幾度か約束をすっぽかされ、その後に謝罪もなく、なんだろう、と釈然としない思いを抱いたことがあった。ひょっとしたらあれも日誌の一部が消えていたのかもしれない。
つぎにいつ日誌が消えてしまうのか解からないので迂闊に人と約束も交わせない。不便だと思ったのは初めばかりで、考えてもみれば過去にあったことが消えるのならば、失態だって消えるのが道理だ。事実これまではずっと、消えてもらったほうがよい出来事ばかりが都合よく消えてくれた。
たまたまなのか、そうではないのか。
いいや、とふと思い立つ。
ひょっとしたらじぶんで消しても、過去を消すことができるのかもしれない。
なかったことにできるのかもしれない。
ためしに休日の大半を映画を観てすごした。せっかくの休日なのにもったいない過ごし方をしたと思うが、いちど無駄な一日を過ごしてみたかった。
思えば日誌をつけるようになってからというもの、日誌をつけたいがために何かちいさくともよいから一日のなかにイベントをいくつもつくろうと気張ってきた気がする。映画は思いのほか楽しく、十本をほとんど通しで観終わったときには窓のそとは明るくなっていた。
徹夜をしたのもずいぶん久方ぶりだ。こういうときにこそ、一日を巻き戻せれば言うことがない。時間が巻き戻ることはないので、これから出社することに変わりはないが、徹夜をしたという事実がなくなれば身体のダルさは消える。反面、記憶だけはどうやらなくならないとすでに身を以って知っている。体験した事実は消えても、それを辿った過去の記憶だけは残っているのだ。
いそいそとエンピツを持ち、白紙の欄にきのうの日付を書いた。たった一行、映画を徹夜で十本観た、とつづる。それから矢継ぎ早に消しゴムで丹念に消していく。
するとどうだろう、毒素が抜けていくように身体が楽になっていく。まるで徹夜なんてしていなかったかのような身の軽さが宿っていくではないか。
自覚していなかったが眼精疲労も相当溜まっていたようだ。スッキリしてみてから、いかほどに疲れていたのかと気づかされた。
これは使える。
その日から、やってみたかったけれど気が引けてできなかったことを一つ一つ、ときには一日にいくつも試す日がつづいた。
仕事を休んでも問題はない。
休んだ事実を日誌に書きこみ、そこだけを消せばいい。
残った記述はそのまま過去に残りつづける。消した箇所の出来事のみがなかったことになる。
修正が効く。
書きこんだ日付からどれほど経っていようとその効果は薄れることはなく、何の気なしにむかしこの部屋で飼っていた猫が死んだ記述を消してみると、なんと部屋の隅から懐かしい鳴き声が聞こえ、まさしくむかし亡くしたはずの愛猫がどこからともなく姿を現した。
世の理すら捻じ曲げるのか。
おそろしくもあり、その万能感に酔いしれもした。
日々は徐々に過剰さを増していく。刺激を求めるように、つぎからつぎに、やってみたかったこと、しかしできなかったことを試しては消す日々を送った。
犯罪行為はさすがにやめようと自制を働かせていたが、いちど試して何事もなかったことにできる体験をしてしまうと、あとはもう自制する意味合いすら消失した。
人を損なっても、損なった事実はこの世からなくなり、人を殺しても、つぎの日には何食わぬ顔で殺したはずの人物と笑顔で言葉を交わしている。
人道に反したあらゆることをした。それはまるで生き物を棒でつつき、ときに地面に叩きつけ、或いは踏みつけることで「死」を発見した子どものような無邪気さだった。
制約がまったくなかったわけではない。たとえばその日のうちに日誌に書きこまなかった記述はいくら消してもなかったことにはならなかった。
つまりあとになってから「あの出来事をなくしたいな」と思っても、当日のうちから日誌に書きこんでいなければ何の効果も生まない。消してももちろんしでかしてしまったこと、起きてしまったことはそのままだ。
よってできるだけ後悔しそうなこと、取り返しのつかなそうなことほど日誌に書くようになった。字数は増え、ページもかさむ。
なかったことにしてもよいがそれほどでもないことはできるだけそのままにしていた。そうでないと周囲の環境が変化しないどころか、到る箇所で齟齬が生じるからだ。それはこちらにしか分からない齟齬であり、機微だが、確実に周囲の環境を蝕んでいく。
たとえば潰れたはずのいきつけのコンビニを蘇えらせたとして、辞めたはずの店員はまた元通りそこで働いている。しかし、潰れていた期間が長ければ長いほど、本来であればそのあいだに流れていた時間の変遷分の現実が大きくゆがむのだ。
極端な話、コンビニを辞めざるを得なくなった店員がそれを転機にアイドルになったとする。しかしそこでコンビニを復活させると、この世からはアイドルが一人消えることになる。
もちろんアイドルのファンだった者たちは活気を失うし、アイドルの働きで稼いでいた者たちは収入を失う。それはポンと生じるひずみであり、得をしていた者たちは損をし、或いは死なずによかったはずの者が死ぬこととなる。
なにより、過去を消した事実は消せなかった。
日誌を消した、と日誌に書いても、それを消したところでその事実をなかったことにはできないのだ。世界改変のあとになってからよくない副作用を観測しても、もはやそれを元に戻す術はない。
そうと気づいてからは、できるだけ前日の日誌のみを消すように心掛けた。
毎日をその日暮らしに暮らした。競馬などの博打を繰り返せばいくらでもお金を増やせる。負けたらなかったことにし、勝てばそのまま日誌にその事実を載せつづける。
倍々ゲームの要領だ。半年もすると、金は天文学的数値にまで増大した。税金で半分以上とられるが、問題はない。ただ、やはりひとの目を引くのは事実であり、大金を稼いだあとはおとなしくしていた。
セキュリティのしっかりした高級マンションに引っ越した。そこで愛猫と共に暮らす。愛猫がこうして蘇えった以上、愛猫を構成していただろう物質が死後に辿ったあらゆる物質から、現在、この愛猫分の質量が僅かずつであるにせよ、抜け落ちているはずだ。全国で謎の奇病が流行っている、とのニュースを目の当たりにしながら、これまでになかったことにしてきた事象の影響をつらつらと思い浮かべる。
ひょっとしたらと思いつく。
じぶんは以前にも日誌の効果を知って、いまと似たような生活を送っていたのではないか。しかしなにか取り返しのつかないことが起きたために、日誌の効果を知った事実を消したのではないか。
日誌を消した事実をなかったことにはできないが、日誌の効果を知った事実ならば消せるのかもしれなかった。
知らなければひとはそれをすることはない。
もしそうならば、未だにじぶんは日誌を消して過去を改変するなんて真似もしなかっただろう。だとしたらこの日誌は、何か取り返しのつかない事態ごと現在を書き換えることも可能なのかもしれない。
リセットされた世界はしかし過去ではなく、現在進行形で進みつづけている。日誌にはもちろん、じぶんで消した過去の記述が空白となって残るはずだ。
一度目ではないのかもしれない。
何度も過去じぶんは世界の改変を繰りかえしてきたのかもしれない。
憶測にはちがいない。
しかし今後、もしも進退窮まる事態に陥ったら試してみてもよいと思った。さいわいにも、日誌の効果を知った事実はきちんと書き残してある。
じぶんの習慣に助けられたと思い、日誌を閉じる。
ワイングラスを手にしたときふと、ひざに猫が飛び乗った。ワイングラスが傾き、日誌のうえに中身をこぼす。
ページの一部が濡れた。
焦り、いそいで中身を改めると無事のようだ。胸を撫で下ろす。
表紙のうえのほうがすこし色が濃くなった。ティシューで拭いながら、念のため表紙の裏、つまり一ページ目より前にある紙面を覗くと、そこにもワインは滲んでおり、黒いペンで書きこんであった日付が目に入る。
この日誌帳を購入した最初の日だ。
その下にはただひとこと、日誌を購入した、と書いてある。
日誌に拡がる染みは刻一刻とその色合いを濃くし、ペンの文字はふやけた紙面に馴染んでいく。
眩暈を覚える。
順繰りと世界が染みのようにかすみだす。
【予測変換の怪】
予測変換が進歩しているのは知っている。親と話していても、むかしは予測変換がお粗末で、何度も打ち間違えたり、全文をじぶんで打ったほうが速かったりしたらしい。それよりもむかしだと、ポケベルなんていって、番号を打って、ゴロ合わせでメッセージを送っていたなんて逸話も耳にする。モールス信号とどう違うんだろ。
予測変換はいまだと、新しい端末の場合は、予測するためのデータがないから、言い換えると打った文字数がすくないから、「あ」と打っても、候補はけっこう少なめで、ふつうに漢字とか、ありがとうとか、一般的な文章しか並ばない。そのうち文章をたくさん打つようになると、そのなかから前に打ったやつとか、比較的多く使う言い回しや文章を、候補としてあげてくれるようになる。
なんてことは、いまさら改めて説明するまでもないことなんだけど、さいきんどうもおかしい。最新機種のはずなのに、予測変換に、どう考えてもそれいらんやん、みたいな候補が並ぶのだ。
あまりに場違いで、ぎょっとするからよく目に留まる。気持ち、十回に三回くらいの確率で、なにそれってのが浮かぶ。
たとえばいまこうして打ってるあいだにも、「助けて助けてたすけて」とか「危ない捨てろ」とか「やめてもうやめてもういやだ」とか、単純に怖いのが並ぶ。
何なんだろ。
親に言ったら、故障じゃないの、とまともにとりあってくれないし、そんなに気になるならお店に持っていったら、と他人事だ。
単なる故障ならまだよいけれど、ウイルスとか、イタズラだったら嫌だ。ネットで検索しても似た体験談は見当たらない。この機種だけの嫌な現象だ。
これがもしも怪談とかなら、予測変換に表示される不気味な文章は、未来のじぶんからのSOSだったりするのだろうけれど、だったらズバリこうなるから気を付けろよ、とじぶんなら打つはずだ。助けて、なんて持って回った言い方はしないし、そんなことを伝えてもどうにもならないことくらい判りそうなものだ。
仮に、ほかの誰かからのSOSだったとしたら、それはちょっと怖い。見過ごせないし、助けてあげたいけど、いまのところこれといってヒントとなるような文面は見当たらない。いまも、見当たらない、と打ったら、「イタいイタい痛い痛い見て見て見て見てみてみて」とでた。
いったい何を見たらよいのだろう。
怖い話ならそれなりにオチみたいなのを用意したほうがよいのだろうけれど、ただただ不気味だよね、だとこれは怪談にはならない気がする。
ちなみにじぶんの名前を打つと、最後が「し」で終わるのだけれど、ふつうに「死ね」とでる。これが心霊現象みたいなものだとしたら、案外、このオバケもひねりがなくて、がっかりだ。見損なってしまう。
いま、なってしまう、の「う」で終わったけれど、そしたら、ウザい、とでた。コミュニケーションがとれてしまった。思いのほかあなた、可愛いところあるじゃない。
いまに見てろよ、って、はいはい。
もはやなんだろうなあ、はあ。
一風変わった交換日記だと思って、いましばらくはこのまま使ってあげることにする。
つぎ「死ね」って言ったらでも、すぐにお店にいって端末を変えてしまうからそのおつもりで。
でたー、じゃない。
それはこちらの台詞です。
【ずるずるみっしり】
どう見ても人間の髪の毛としか思えないモサモサの生えた植木鉢が置いてある。玄関の門を司る支柱のうえだ。柳の木の枝みたいにしなっていて、風が吹くと、重そうに揺れる。
きっとシャンプーをしていないから、ジェルで固めたみたいに油脂でぎとぎとなのだ。トリートメントだって御無沙汰だろう。日常の風程度では、生え際を顕わにするほど舞いあがったりはしない。
そういった植物の可能性も考える。髪の毛に見えるだけで、一本一本はそこまで細くないのかもしれない。
植木鉢の位置が高いせいで、触れて確かめることもできない。油脂で固まっているのか、それともそういう葉っぱなのか。
子どもが人間の顔を描くと、髪の毛はジグザグと輪郭を縁取って終わる。そういう輪郭の葉っぱと見做したほうがいくぶん正確で、だから目のまえのこれもそういった植物だと見做したほうが論理的なのかもしれない。
人間の頭部に見えるだけだ。
髪の毛に見えるだけだ。
それはそうだ。植木鉢に人間の頭を植えてタダで済むわけがない。
通りに面したこんな場所に飾っておいて、騒ぎにならないわけがないのだ。かといって、人通りは多いわけじゃないから、これに気づいているひとがいないだけかもしれない。たとえいても、わたしと同じように、そんなバカなことがあるわけない、と断じて、我田引水に納得しているだけかもしれない。
念のために警察に通報してもよいだろか。
おとなに確認してもらいたい気持ちが募る。
このままだと学校に遅刻してしまう。トイレにも行きたい。朝ごはんをゆっくり食べ過ぎて、おしっこをするのを忘れてしまった。大きいほうもふつふつと、きりきりと、お腹を圧迫している。授業が始まる前にだしてしまったほうがよい気がする。
いざ考えだすと、もはや目のまえの人間の髪の毛に見える物体の生えた植木鉢よりも、教室で無事に一日を過ごせるかどうかのほうがだいじに思えてくる。学校の帰りにもういちど見て、まだここにあったらそのときに改めて考えよう。
その場を離れ、通学路のさきを急ぐ。
なんとか遅刻はせずに済みそうだ。
そう言えば、と下駄箱で靴を履きかえながら思う。兄のマンガで、地面に死体を埋めていた殺人鬼のでてくる作品があった。リアル寄りの絵柄で、グロテスクだな、と不気味に感じたが、さっきのあれはそうでもなかった。髪の毛にハリがあって、なんだか生きているみたいだった。植物と見分けがつかなかったのもそこら辺が関係しているのかもしれない。
死体はでも、死後数時間はヒゲが伸びたりする、と聞いたことがあるから、あまり楽観はしないほうがよさそうだ。
真実、首だけが植木鉢に植えられていてもおかしくはない。
いや、おかしいだろ。
じぶんの考えに突っこみをいれながら、跳び箱を飛ぶ。体育は好きだ。跳び箱にしろプールにしろ、待ち時間が長くて、楽ができる。
給食を食べて、遠足のグループ分けをしたら、あっという間に放課後になった。
考えごとをしていたからか、きょうは時間が経つのがはやかった。それだけ授業を疎かにしていたことの証拠とも言え、これこれちみちみ、とじぶんを諌める。
気づくと帰路を辿っており、例の門のまえに着いていた。
ふつうの一軒家だ。ガーデニングの凝った庭があるだけで、とくべつ不穏な見た目ではない。どこにでもある家なのに、門の支柱のうえに、人間の頭部が埋まっているとしか思えない植木鉢が載っている。
あれ、と思う。
一つ増えている。
門の両脇に、それぞれ長い髪の毛が垂れて見える。そういう植物とはさすがに思えない。
だって黒いし。
緑じゃないし。
葉緑体どこいった。
疑問視してから、はっとする。なるほど、植物の葉を黒く塗ってしまえば、或いは人間の髪の毛のように見えなくもない。
昆布だって、あれが黒ければ髪の毛に見えよう。じっさい、海の妖怪のすくなからずは、昆布の見間違いではないのか。柳の葉が幽霊に見えるのと同じ原理だ。
そうだ、そうに決まってる。
ランドセルを脱いで、地面に置き、そのうえに乗る。さらに爪先立ちをして、支柱のうえから垂れる黒いそれに手を伸ばす。
触れてみれば判るだろう。
葉っぱなら、千切ることだって可能かもしれない。それくらいは許されるはずだ。紛らわしいほうがわるいのだ。
自己肯定を内心で唱えながら、ゆびさきに触れたそれを、ひょいと引っ張る。
ずるり。
ずずずず。
どこまでも伸びた。
細くざらついた髪の毛が、ゆびでつまめるくらいの束となって、ちぎれることなく、どこまでも引っ張れば引っ張るだけ、ずるり、ずずずず、と長くつづく。
ほどいた毛糸の玉のように足元にたるんだそれを目にして、はっとして、じぶんの頭に手をやる。
伸びた分がじぶんから抜け落ちているのではないか、と案じたのだが、そんなことはなく、じぶんの髪の毛はそのままそこに生えていた。
なんだ、よかった。
思ったところで、息を呑む。
するり、すすすす。
足元にたるんでいた髪の毛の束が、ゆっくりと、ゆびでたぐりよせるくらいの速度で、巻き戻っていく。
元の長さまで縮まると、こんどは垂れていた残りの分まで、短く、短く、縮まった。
イソギンチャクのようだと思った。
或いは、カタツムリの触角だ。突いたので、引っこみましたといった具合に、植木鉢のなかに完全に埋もれて消えてしまった。
もう一方の支柱を見遣る。
そこには、浮きあがる血管のごとく、納まりきれんとばかりにひしめき合う黒い筋が、支柱の表面にジグザグと、ときに土のなかで身をくねらせるミミズのように蠢いて見えた。
ランドセルを拾うのも忘れて、わたしは逃げ去った。
家に飛びこみ、居間で映画を観ていた母に、いまあった出来事を語って聞かせる。いまいそがしいからあとでね、とにべもなく突っぱねられ、わたしは傷ついた。
その日の夜、不貞寝したわたしはお腹がすいて目が覚めた。いじけて夕食を食べなかったのが裏目にでた。意地なんか張ってもいいことはない。
ふとそこで、窓のそとに蠢くもじゃもじゃを見た気がした。
ぎゅっと目をつむり、頭からふとんを被る。それからまた眠るまで、足の指一本動かさずにいた。
翌朝、母に起こされ、わたしは目を覚ます。「あんたランドセルどうしたの」
母に問われ、わたしはしどろもどろに、学校に置いてきちゃった、と誤魔化した。まだ寝ぼけていた。どうして母がランドセルのことを言いだしたのか、そのことをふしぎに思わなかった。
「じゃあ誰かが届けてくれたのね」
母はわたしのお腹に、それを置くと、朝ごはん食べちゃいなさい、と言って部屋を出ていった。
わたしはお腹のうえのランドセルとにらめっこをする。
ランドセルに触れると、ほんのかすかに振動して感じられた。
隙間の奥で、ずるずると何かが這っている。そんな妄想をするけれど、蓋を開けて確かめてみる気にはならない。
【無視でいいって】
無視しとけっていいから。
なんでって、なんつったらいいかな。
知人からの又聞きだからぜんぜん信憑性はねぇし、幽霊信じないおまえに言ったところであんま意味もないんだけど、二〇二〇年はじまってすぐにけっこう、社会が大規模に混乱したじゃんよ。で、まあみんな家にいろだの、引きこもり推奨だの、マスクしろだの、人と接触するだの、うるさくなったじゃん。
あの時期にさ、知人の友人がいわゆる霊感あるひとで、言ったら俺からしたら赤の他人だけど、ときどきそのひとの話は聞いてて、本当だったらおもしろいよね、くらいの話半分、暇つぶしにあのひといまどうしてんの、みたいな感じで、話題にでたりしてたんだけど、そのひとがさ、あの時期、しばらく外に出らんなくなったらしくて。
や、いいんだよね、そりゃね。外にでんなって話なんだからさ、そりゃいいことだよ。
でも、副業でそのひとお祓いみたいのもやってて、そりゃみんな家にいる時間増えたら、依頼が増えるわけですよ。なのに、一度依頼をこなしたきり、もうそれからずっと家の外にでなくなったらしくって。
SNSの更新も止まって、連絡とっても買い物にも行ってないってんで、心配になって知人が差し入れついでに様子見に行ったんだって。単純に暇だってのもあったんじゃねぇのかな。
まさか、宅配サービスまで使ってないとは思わないじゃん。
そう、そのひと、完全に外界シャットアウトしてて。知人が部屋に入ったときには食料もほとんど底突いてた状態で。
そうだよな、そう思うよな。
知人もそこまで神経質にならんくてもいいじゃんって、聞きかじりの疫学の話とか披露して、安心させようとしたんだって。
でも、そうじゃなかったんだって。
あの時期さ、外出歩くにしても、二メートル空けろとか、マスクしろとか、言われてて、もうみんなそれ律儀に守ってたじゃん。なんかね、いままで気づかなかっただけなんだってそのひと、それで気づいちゃったらしくて。
や、もうね密集してんだって。
まとわりついてんだって。
一目瞭然なんだって。
ふだん、何気なく見逃してたのが丸見えで、社会がどうのこうのじゃなくって、こんな世界をいままで出歩いてたのかってそのひとビビっちゃって、知人が何言っても部屋の真ん中で布団にくるまって、どうしようもなくなっちゃったんだって。
で、なんでこんな話いましたかってぇと、さっきおまえ一瞬嫌な顔したじゃん、たぶんさっきの集団っしょ?
まあマスクもしねぇで、密集して、一人の男を取り囲んで、アホだな、とか思ったんだろうけどさ、放っとけって。
無視でいいよ無視で。
だっておかしいと思わん?
あいつら入ってった店よく見てみ。
とっくに潰れてるっしょ。
【きみは何も変わらないはずなのに】
友人が売春しているかもしれない、と昔馴染みから相談を受けた。
「むかし告白して振られて、そっから友人として長い付き合いだったんだけど」
「ふうん。売春って何、そういうお店ってこと?」
「どうだろ。たぶんパパ活みたいな、愛人契約みたいな、そんな感じだと思う」
「いちおう言っとくけど、二〇二〇年現在、売春は違法だよ。ただ、不特定多数相手じゃなきゃ売春と解釈されないし、膣と陰茎の挿入がなければ法律上は売春と見做されない。あと管理売春が犯罪なんであって、売春そのものに刑事罰則はない。条例でダメなとこはあるだろうけど、それも多くは、売春をする側を罰するためじゃなく、搾取する側を牽制するためのもので。この国の示す方向性としては、売春せざるを得ない経済的弱者は守るべき対象だ」
「いやいやおかしいだろ。売春せざるを得ないってなんだよ、まずはそこんところをしないようにしろって話じゃん」
「止めたいの?」
「そりゃあまあ」
「それはなんで」
「なんでって、そりゃあ」口ごもるところを鑑みれば、そこに潜む自己矛盾に気づいているのだろう。いいから言ってみて、とさきを促す。「だって、売春だぞ。男にコビ売って、身体をいいように弄ばれて、穢されて、それで金もらって、そんなんいいわけねぇじゃん」
「うん。まずはそこだよね。便宜上、売春婦って言い方をさせてもらうけど、きみはそれを卑しいものだと考えているわけだ」
「まあ、いいかわるいかっつったらよくはないだろ」
「そう? たとえば同じ性行為でも、恋人とならそれはよくて、無理やりなら強姦で、お金をもらったら売春で。でもやってることは変わらないわけでしょ」
「そんなこと言ったら、ひとはみな死ぬからいつ死んでもいいみたいな極論になんじゃん」
「そう。過程はだいじだ。結果が同じだからといって、行為そのものが同じだからかといって、まったく同じとは限らない」
「だったら」
「でも、だとしたらなおさら、じぶんの意思で選んだ性行為なら、それは恋人同士のそれや、単なる仕事と、それほど違いはないんじゃないかな」
「いや、性行為は仕事じゃないだろ」
「そう、そこだよね。売春を労働と見做していない。卑しいものだと見做している。まずはそこの誤解から正しておこう。売春そのものは卑しいわけじゃない。だってさっきも言ったけど、子供がいるひとは誰だってしていることだ」
「子供を儲けるくらいに神聖な行為なら余計に他人とするなって話じゃん」
「なら避妊を徹底すればいいってことにならない?」
「屁理屈だ」
「んみゃんみゃ大事だよ。労働の対価として報酬を得る。これは総じて仕事だ。職業だよ。職業に貴賤はない。建前だとしても、そこはきみだって認めるところだろ」
「でもじぶんの子供に売春をさせたくはないよ」
「それはほかの職業でも同じなんじゃないかな。たとえば一流企業でホワイトな職場と、劣悪な工場の現場だったら、たいがいのひとは前者を選ぶ」
「そりゃ環境がいいほうがいいに決まってんじゃん」
「そう。だから、劣悪な環境の一流企業と、環境のいい工場の現場だったら、これはけっこう票が割れると思う。給料がよければ、多くのひとは工場のほうを選ぶかもね。だた、世間体を気にして、一流企業というブランドを優先して選ぶひともそうすくなくはないと思うけど」
「つまりこう言いたいのか。売春も、劣悪な環境や、社会からの差別があるから卑しいものだって、無意識でそう考えてしまうって」
「それもあるんじゃないのかなって話。もっと言えば、売春に限らず、職業差別の多くは、仕事それそのものというよりも、搾取構造に問題の因がある、本質的な瑕疵がそこにある。搾取されないような、劣悪な労働環境でなければ、そもそも卑しい仕事、という感覚そのものが時代の経過に伴い薄れていくだろうね。極論、プロスポーツ選手みたいに、売春がもてはやされれば、誰もがみなそれを目指してこぞってなりたがるだろうし、親だって応援するかもしれない。まあ、性病の問題があるから、そこは科学の進歩で乗り越えるとして」
「それはちょっと話がズレてる気がするぞ」
「そんなことはないと思うよ。いまだって殺人はいけないこととされているけれど、戦争がはじまれば、いかに多くの敵を殺せるかが、英雄か役立たずかの基準になる。人殺しという、現代では絶対に許されないことですら、社会の価値観でいかようにもその善し悪しは変わる」
「売春も同じってか」
「同じだろうね。もちろんさっきも言ったけれど、搾取構造は失くさないといけない。客の多くが、『売春をするようなやつはまっとうじゃない、乱暴に扱ってもいい、敬意なんて払う必要がない』と思っていれば、そりゃ職場は劣悪になって、自尊心だって削られるし、社会も売春に従事する者はそういう人間だという風潮を強くする。そうなると余計に、売春に従事しているひとたちは、そういう仕事をしているとすら周囲に言えなくなり、助けを求めたり、相談もできなくなる。悪循環に陥る。まずすべきは、売春をしているからといって卑しいわけではない、という価値観をつくっていくことだ。それはもちろん価値観を変えていくだけではダメで、同時に、売春をする労働環境を社会がきちんと是正していかなきゃいけない。そういう仕組みを構築していかなければ、やっぱり価値観だけが変わっても、それは大勢を売春に走らせて、搾取するだけの構図が強化されるだけになる懸念が非常に高いんじゃないか、とぼくは思うよ」
「ふうん。じゃあ、どうすりゃいいんだ。愛人契約だからかってにしろって、あのコの選択を応援すりゃいいのか」
「そこもむつかしい問題なんだよね。そのコが本当にそれをしたくてしているのか、それともただお金に困っているだけなのか。これは売春に限らず、どんな仕事にも言える。やりたくない仕事をいやいやさせるなら、それは売春を無理強いしているのと原理上区別はつかない。というよりも、売春も仕事のうちだと見做し、職業に貴賤がないと考えれば考えるほど、この理屈の正当性は増す。つまり、現代では売春問題と似た問題が、いろんな職業で行われている。むしろ、売春という『社会的底辺だとされる職業』をつくりあげることで、むかしのえたひにん制度みたいに、じぶんたちはまだマシだな、と大多数の社会人に思わせる流れは、これは意図してではないとしても、そういう側面で機能しているとは言えると思う。まさしく捌け口だよね。だから、問題は売春という行為そのものではなく、労働する側にあるのでもなく、客の態度のほうにあると言ってもいいかもしれない。あとはそう、もちろん雇う側の問題、搾取構造に、根本的な問題があるんじゃないかとやっぱりどうしても考え着いてしまうよね」
「じゃあまずは訊いてみるわ」
「そのコに?」
「や、雇い主に。友人の話ってのは嘘。じつはこれ、アタシの話でさ」
「それは、えっとぉ」
「むかしおまえに告られて、そんときレズビアンだからっつって断ったけど、まあそうなんだけど、でもまあ、性行為くらいはべつに異性相手でもいいかなって。むしろ本気なのは同性だけにしときたいってのがあんのかも。でも、いざしてみたら、そういうのってやっぱマズいのかなぁって罪悪感みたいなのがあってさ、誰にも相談できねぇし、自尊心ズタボロになりかけてたところで、まあ、相談してよかったわ。なんか元気でた。べつに引け目に感じることはないんだってな。売春する分にはいいんだろべつに? アタシいま金に困っててさ。でも、まあ、単なる仕事。コンビニのバイトとか、工場の期間従業員みたいなさ、そういうのと変わんねぇじゃん。あ、いちおう確定申告はするし、税金も納めるよ。けっこうもらえんだよね。アタシこう見えて、けっこうウケいいんだ」
あはは、と乾いた笑いを漏らす彼女にかける言葉を、ぼくはなかなか思いつけないでいる。
お金ならぼくがあげる。そう言いたかったけれど、ぼくにはそこまでの甲斐性はないし、そうした提案をする時点で、ぼくはきっと売春を、卑しい行為と断じているなによりの傍証に思えた。差別心に蝕まれている。それを彼女に悟られることのほうが、彼女の売春を止めることよりも、彼女を救うことよりも何よりも、ぼくには優先される事柄に思えた。
「ぼくはきみが何を選択しても、ぼくのきみを尊敬する気持ちは変わらないよ」
「じゃあま、売春のプロでも目指しますかな」
働かなければ生きていけないのならば、働くしかない。彼女がどんな仕事で稼ごうと、それは彼女の選択だ。彼女が弁護士になる、と言っているのとこれは変わらない。止めることこそが、差別になる。
けれどやっぱり、どうしてもぼくは、胸が苦しくて、どうしようもないんだ。
独占欲なのかもしれない。彼女を、彼女の身体を、ぼくはじぶんのものにしたいだけなのかもしれない。だからほかの男に穢されたくないと望んでいる。
じっさいのところは彼女が穢されるわけでもないのに、彼女は何も変わらないのに、変わらずに変わりつづけていくのに、それでも彼女に、その道を選択してほしいとはなぜかふしぎなほどに、どうしても思えないのだった。動物じみている。
「相談してよかったよ」彼女は席を立つ。「また遊ぼうぜ、こんどはアタシが驕るからさ」
背伸びをして大きな欠伸をする彼女にぼくは、引きつった笑みしか向けられないでいる。
【返頭痛】
新商品の試験体のバイトをした。
配られたのは、腕時計型感覚共有機だ。
知覚を他人と共有できる機械らしく、使用者のデータを集めて改良に活かすのだそうだ。
いざ使ってみても、これといって生活に変化はなかった。他者の知覚が伝わるでもなく、思考が読めるでもなく、あべこべにこちらの思念を送れるわけでもない。
失敗作だったのだろうか。
タダでバイト代が入るのだから文句はないが、報酬分の仕事は返したい。かといって何ができるわけでもなく、うーん、うーん、と頭を抱えた。
翌朝、悩みすぎたのがわるいのか、頭痛がひどかった。
まるで頭のなかが空洞で、かぽっと脳みそが溶けてなくなってしまったみたいな鈍痛がある。
なんとかならんものか。
じぶんの頭をちぎって、配って歩きたい。身体から頭痛を切り離したい。
お腹の空いている相手にじぶんの頭を食べさせるヒーローのマンガがあったが、似たようなことができたらさぞかし爽快だろう。
大学の食堂で友人とランチを食べながらそんな想像を巡らせていると、腕時計型感覚共有機が赤く点滅した。
なんだなんだ。
驚いて顔のまえに運び、まじまじと見つめると、機器の側面から赤い光線が蜘蛛の糸のように細く放たれた。友人のこめかみに当たる。
数秒それは線となって保たれたが、間もなく、ふっと消えた。
「イッターイ」
友人が呻いた。「なんか急に頭痛くなってきた」
訊けば、脳みそにぽっかりと穴が開いたみたいな鈍痛が突然に湧いたらしい。イタタ、イタタ、と顔にバッテンの目を浮かべながら友人は、授業は休む代行よろ、と言い残しそそくさと荷物をまとめて食堂をあとにした。ちゃっかりお盆を残していったので、清算は私がすることになったが、罪の意識にさいなまずに済む分よしとする。
そうなのだ。
私の頭痛は消えていた。
友人に移してしまったのだ。
元来私は頭痛持ちだ。
せっかく取り除いた痛みが、翌日にはぶりかえしている。友人への呵責の念がわずかにでも残り、思い悩んでしまったせいかもしれない。友人め。
知り合いに移すのはわるい気がした。通りがかりの、なんだか人相のわるいひとや行儀のわるいひと、端的にひとを困らせている誰かを見掛けたら、そのひとたちに腕時計型感覚共有機を向け、そこから発射される赤い光線をぶつけた。
赤い光線は、私が、頭痛どっかいけ、と念じると飛びでるようだった。脈拍だとか脳波だとか、なにかしらのデータを感知しているのだろう。
ときおり周りに誰もいない状態で光線がでることもあるが、そのときは壁にぶつかってそれっきりだ。頭痛は取れないし、私はびっくりする。心臓にわるいから発射ボタンくらいつけてほしい。アンケートの備考欄にでも書いておこう。
私は頭痛から解放された。
日々、大学までの道中、その帰路、或いは遊びに出掛けたさきで、見知らぬ他人に頭痛をばら撒きつづけた。
バイトの面接時に受けた説明では、感覚を共有する相手は一人か二人に限定するように、と注釈を挟まれたが、やはり友人ばかりを標的にするのは気が引けた。頭痛が消えても胸が痛んでは意味がない。ゆえに、なるべく多くの見知らぬ他人に頭痛を分散した。
さすがに二十人を超えたころには、じぶんひどくないか、と罪の意識に苛まれたが、かといってしょせんは頭痛だ。移す移さないにかぎらず誰もがなる。そして私は人よりも頭痛になりやすいのだ。公平を期するために頭痛をばら撒くのは、アリかナシかで言えば、ナシ寄りのアリだろう。つまり、アリだ。義賊だって盗んだ銭をばら撒くのだ、義賊でない私が頭痛をばら撒いて何がわるかろう。
私は開き直っておった。
やがてバイトの最終日がやってきた。開発企業へと腕時計型感覚共有機を郵送し、数日後にお礼の連絡を受ける。
「どうでしたか使い心地は」
「肩こりがなくなってよかったです」頭痛はやや罪が重い気がしたので、肩こりと偽って報告した。
「ああ、それはよかったです。でも気をつけてくださいね。機器を手放せば、他人に共有した感覚は丸ごとごっそり返ってきますので。まあ、一人、二人くらいならだいじょうぶですのでお気になさらずに」
「返ってくるとは、えっと、それはどういう」
「飽くまで共有ですからね。感覚は戻りますよ。それこそ、感動を共有したなら、しばらく涙が止まらないかもしれません」
よほど自社製品を誇りに思っているのか、担当者の声は弾んでいた。私は二の句が継げなかった。またの参加をお待ちしております、と慇懃に述べ、担当者は連絡を終えた。
しばらく呆然とした。キリキリと痛みだす後頭部の、ごっそり脳みそが穿りかえされたかのような空虚さを覚えながら、いったい私はこの期間にどれほどの頭痛を他人に肩代わりさせてきただろう。ばら撒いただろう。
想像し、立っていられないほどのめまいに襲われる。
ずきん、ずきん、の波が徐々に大きくなっていく。
【日鬼】
朝からツノの調子がおかしくて、ピリピリしていて、そろそろ解放しておかないとな、と面倒に思う。
前に解放したのはいつだったかな。
スリオロシをしぼって喉をうるおす。それからファシュナたちと同調し、きょうの予定を探りあう。嵐がちかいからか、うまく魂感を飛ばせずに難儀する。ファシュナたちは食糧の調達にいくらしい。
そろそろ解放しておかなきゃな、とのこちらの懸念を察したのだろう、食料の調達ついでに手ごろな荒野を探しておいてくれるそうだ。そんなことをしなくともこのあいだファシュナが解放した地があるだろう、と訊ねると、そこはもう存在しないらしい。
ああそれで、と合点する。
ファシュナの角位があがったのはその影響か。
地上を不可侵にするくらいなのだからおそらくは白号に値するのではないか。他鬼の角位を気にするなんてずいぶんと気弱になったものだ。それもこれもツノのピリピリのせいだ。
日が昇る前にファシュナたちと合流した。彼女たちは山盛りのスリオロシを獲ってきていた。
「よくそんなに見つけられたな」
「サンミャクのほうにはまだいっぱい巣があるよ。あ、ねえ、なんでコレがスリオロシって言うか知ってる?」
「え、なんでだろ。飲み物とかそういう意味じゃないのか」
「搾るって意味らしいよ。スリオロシを搾る、なんてあたしたち言うけど、二重表現。二度手間」
ファシュナは笑い、つぎはいっしょに獲りにいこう、と言った。「あそこにある巣はつぎでたぶんなくなっちゃうから、ついでにあんたそこで解放しちゃいなよ」
もう限界でしょそれ。
ツノに手を伸ばしてくるので、のけぞって回避する。「危ないって。敏感なんだぞ知ってるだろ」
「ひっしっし」
ファシュナは牙を口の端から覗かせる。それから袋のなかから獲りたてのスリオロシを一匹とりだした。一口で頬張る。
バリバリ、ぐじゅぐじゅ。
見ているだけで唾液が口のなかに広がる。こちらも一匹いただくことにした。
目のまえに新鮮なスリオロシを掲げる。
搾らずに食べるなんてこんな経験はいつ以来だろう。
獲りたてで活きがよいからこその贅沢だ。
汁気の多い割に、歯ごたえのある骨の触感がたまらない。
ひとしきり味わっていると、ファシュナがそこで、うべ、と舌を使って器用にサラサラを吐いた。「あたしこれ苦手」
「そこが美味いんじゃないか」
「じゃああげる」
「口から吐いたものを押しつけるな」
スリオロシの頭部から生えるサラサラを食べないなんて、鬼からツノをとったようなものだぞ。
指摘すると、腹に据えかねたのかファシュナは、もうあげない、とスリオロシのいっぱい詰まっているだろう袋をぶんと背中に遠ざけた。
【ゾウさんの小さいものはなに?】
ヘイコウくんが言葉を発しなくなってずいぶん経つ。何かきっかけがあったのか、とヘイコウくんのご両親はたいへん心配していた。
ぼくも心配で、毎日のようにお見舞いに行っていたけれど、毎日はつらいでしょ、とヘイコウくんのご両親に言われてからは、一週間に二回くらいの頻度で顔をだすようにした。本の貸し借りをして、その返却を理由に訪問するようになった。これはヘイコウくんの案だ。
ヘイコウくんはあまり家のそとにはでなかった。学校にもこない。それはしゃべらなくなった時期と重なっていた。
学校で何か嫌なことがあったのかもしれない、と思ったけれど、そういった事実はないようだ、と学校の先生たちは結論付けているようだった。ヘイコウくんのご両親も最初は疑いの目を向けていたけれど、ぼくやほかの同級生たちからの心配の声を聞いて、どうやらうちの子は学校ではみんなと仲良くしていたのだと認識を改めたようだった。
現にヘイコウくんは学校では人気者だった。たぶんヘイコウくんを嫌いなひとはいないのではないか、とぼくなぞは睨んでいる。そしてそれは正しい認識だったに違いない。
ヘイコウくんが学校にこなくなっても、ヘイコウくんの話をして、はやくこないかなぁ、と言っているクラスメイトたちがすくなくなかった。
かといってヘイコウくんのお見舞いに通うのはぼくだけのようで、それはぼくとヘイコウくんの仲がほかのコたちよりも濃いからだとぼくは考えているけれど、あんまりこれはあてにならない想像かもしれない。
ヘイコウくんはしゃべらなくなっただけで、とくに他人を拒絶してはいなかった。だからぼくが部屋を訪れると、いっしょにゲームをして遊んだ。
「どうしてしゃべらないの」ぼくが言うと、ヘイコウくんは口をぱくぱくと開け閉めした。
「聞こえないよ」ぼくはムスっとした。
ヘイコウくんは、ごめんよ、と言いたげに両眉を八の字にした。ぼくはヘイコウくんから借りた本を返して、また新しい本を借りた。
学校で、先生からヘイコウくんについて質問を受けた。
「どうしてそんなに仲がよかったの」
「ヘイコウくんは動物が好きでした。ぼくもです」
「そうなんだ。何の動物が好きだったの」
「コオモリとか、ゾウさんとか、あとはクジラさんも好きですよ」
言いながらぼくは、どれもヘイコウくんがさきに好きだと言ったものばかりだと気づいた。ぼくはたぶん、ヘイコウくんが好きだから、それら動物をもっと好きになったのだ。本当だろうか。あんまり自信はない。改めて考えなおしてみると、元から大好きだった気もしてくるから、ふしぎだ。
ぼくは家に帰って、ヘイコウくんから借りた本に目を通す。ゾウの本だった。
ゾウは人間に聞こえない音をだす、との記述を見てぼくは、おやまぁ、と思った。
超低周波音をだすことで、ゾウは十キロさきのほかのゾウの声も聞き取れるのだそうだ。
「すごいなぁ」
そんな真似ができたら便利だな、と思った。誰にも知られずに互いに声のやりとりができるのだ。
本にはほかにも、コウモリやクジラもまた超音波を使いこなすのだ、と書かれていた。
ぼくはそこで、はっとした。閃いたのだ。どれもヘイコウくんの好きな動物ばかりだ。
ぼくは、ひょっとしたら、と考えた。
ヘイコウくんは言葉を発しなくなったわけではないのかもしれないぞ、と。
彼の声が、ぼくたちに聞こえなくなっただけなのだ。
ぼくはお小遣いをはたいて、集音機を購入した。補聴器に似たつくりで、どんな音でも大きく聞こえるようにしてくれる。補聴器よりも安い値段で購入できるけれど、それでもお年玉二年分が消えてしまった。補聴器は性能のよいものだと一個だけでも宝石が何十個も買えるくらいに高いのだ。集音機は高くても安い補聴器くらいで済む。それだって宝石一個は買える値段だ。
ぼくはヘイコウくんの部屋に行き、集音機を耳にして、ヘイコウくんを見る。
彼はぼくを見て、ふしぎそうな顔で、また口をぱくぱくと開け閉めした。
「それは何? 音楽でも聴いてるの?」
ヘイコウくんの声だ。彼の声が聞こえる。
ぼくは感激して、目頭がじんじんした。ずっとしゃべってたんだねヘイコウくん。
もっとしゃべって、と催促すると、ぼくの声が頭蓋骨を割るくらいに大きく聞こえて、ぼくは床にのた打ち回った。集音機を取りはずす。
ヘイコウくんがぼくを見下ろしている。両の眉は虹みたいにゆったりと弧を描いていて、それでいて雨みたいにぽろぽろと垂れるしずくがぼくの手の甲に当たった。
ヘイコウくんはずっと、なりたいものになっていた。
誰にも知られず、じぶんだけの夢を叶えていたのだ。
ぼくは声にならないくらいちいさな息で、すごいなぁ、とつぶやく。ヘイコウくん、きみはすごいよ。
ヘイコウくんの真っ赤なお耳が、気まぐれなゾウみたいにそっぽを向く。
【ピエロと一匹の】
あるところに心優しいピエロがおりました。ピエロは白塗りの化粧に赤玉の鼻、子供用パジャマのズボンを頭から被った、小太りの男でした。
ピエロは子どもが大好きでしたから、道行く子どもたちを楽しませようと、陽気に振る舞い、空き瓶をいくつも宙に投げて回し、塀のうえで逆立ちをしたりします。
けれどピエロが大袈裟に動けば動くほど、子どもたちは怖がって近寄りませんでした。
そのうちおとなたちまでピエロに冷たい目をやり、町からどんどんピエロの居場所はなくなっていきます。
ピエロはそれでも毎日のように町にでて、陽気におどけ、玉乗りやパントマイム、さまざまな演目を披露しました。
ときおりまだ言葉もしゃべれない幼児が、ぱちぱちとにこやかに手を打ってくれますが、その親と思しきおとなに視界を塞がれ、いかにもあれは見てはいけないものだ、と諌められるように去っていきます。
ピエロは笑顔を絶やしません。化粧がそういう絵柄だからです。
あるとき、町で殺人事件が起きました。女児が草むらで遺体となって発見されたのです。それからしばらくしてこんどは男児が行方不明となり、数日後に橋の下で見つかりました。腹は裂け、首と胴体が切り離されていたそうです。
町からは子どもたちの姿が消え、おとなたちはふだん以上に目つきするどく歩いています。
殺人事件の捜査がすすむにつれて、ピエロの仮面をした男が殺された子どもと遊んでいた、といった目撃譚が寄せられるようになりました。
もちろんピエロには身に覚えがありません。そもそもピエロの顔は化粧であって仮面ではないのです。
しかし町の人々はピエロを見掛けるたびに、道を迂回し、こそこそと遠くでなにやらささめきあうのです。
やがてピエロの住まいにイタズラ描きや、貼り紙、イタズラ電話がかかってくるようになりました。多くは脅迫まがいな言葉で、町からでていけ、といった旨を告げています。
ピエロは黙ってそれらを受け止めました。いちどだけ壁をきれいに塗り直しましたが、つぎの日にはまた元通りになったのを機に、そのままにするようにしました。
ある夜、息苦しさを覚えてピエロはベッドのうえから起きました。
煙で部屋はもくもくと雲っています。その奥に赤い光を見ました。
家が燃えているのです。
ピエロはいそいで、部屋に置いてあったペンキを炎に浴びせます。家の壁を塗るのに購入したペンキです。白い液体が炎を圧しつぶし、ぶすぶすと嫌な臭いを立ち昇らせます。
炎は弱まりましたが、どうやら一か所だけが燃えているわけではなさそうでした。
ピエロは家のそとに出ます。そして、いちど手にしたホースからゆびを離し、呆然と家が焼けていく様子を眺めました。
近隣にほかの住居はありません。ただただそれだけが救いでした。
手のひらはペンキで真っ白です。ピエロはそれを顔にぬったくり、ポケットのなかに入れっぱなしだった赤玉を鼻につけます。
ピエロは朝を待たずに町をあとにしました。行くあてのない旅にでるのです。
旅の道中、停車中のトラックからラジオニュースの音が聞こえてきました。よこを通り抜ける際に、児童連続殺人事件の容疑者が捕まった、と聞こえました。ピエロは、よかった、とただ一言思いました。
町から離れ、人里からも離れ、深い太古の森にまでくると、季節は冬にさしかかっていました。辺り一面灰色の雪に覆われ、月光を受け、きらきらと輝いています。
視界の端に、ふと何か動くものが見えました。
ピエロはそちらに目を転じます。
トナカイが一匹、雪のなかに埋もれていました。
首だけを持ちあげ、こちらを見詰めています。
ピエロはしばらくその場で様子を窺っていましたが、意を決して近寄りました。ピエロの足跡だけが点々と雪のうえに残ります。
トナカイはピエロから逃げることも、警戒心をあらわにすることもしませんでした。
トナカイはひどい怪我を負っていました。身体からは血を流し、片方のツノは根元から折れ、なにより木に衝突でもしたのか、鼻がつぶれてしまっています。
ピエロは心を痛めました。
なんとかしてあげたいと思い、手持ちの衣服を破き包帯にし、雪を掻き分けて餌となる草木を探しました。キノコやコケを見つけて、差しだします。トナカイは匂いを嗅ぐ真似をしますが、そのたびに鼻がつぶれてしまっていると思いだすようで、苦しげに鳴きます。
ピエロはトナカイに身を寄せ、眠り、元気になるまでそばにいました。
やがてトナカイは自力で立ちあがれるまでに回復しました。
陽の光を受けて、空気が無数の光の種を散らしています。
トナカイがピエロの首筋に顔を埋めます。ピエロはそこでふと思いつき、鼻の頭に載せていた赤玉をトナカイの鼻先に被せました。
ぴったりとはまります。
トナカイは気に入ったのか、ますますピエロにじゃれつきます。
ピエロの顔からはもう白いペンキの色は剥がれ、鼻も赤くありません。そこにはただの子太りの男がいるだけです。
トナカイが雪のうえにしゃがみこみました。背中に乗れ、と言っているみたいです。
そう言えば、と男はいまさらのように思いだします。トナカイを見つけたとき、その周辺にトナカイ自身の足跡はありませんでした。トナカイの怪我の位置からすると、おそらく木の幹に勢い余って衝突したのでしょう。しかし、いったいどうやって足跡一つ残さずに、木にぶつかれたのでしょうか。
男は疑問に思いながら、トナカイの背中にまたがります。分厚い毛に手のひらが埋もれ、全身が暖炉のまえに佇むようなぬくもりにくるまれます。
男はもうピエロではありませんでしたが、それでも子どもたちのことは大好きなままでした。
いつの日にか、世界中の子どもたちを楽しませ、笑顔にできるとよいのにな。
男はただ、それだけを祈るのです。
【ミカさんはお姫さまになりたい】
あれほどお姫さまになりたいと言い張っていたミカさんがイモムシになってしまった。私は潰してしまわないようにマッチ箱にミカさんを入れて持ち歩く。
ミカさんは日にレタスをひと玉たいらげてしまうので、私は彼女のレタス代を稼ぐために新しくコンビニのバイトをはじめた。
いらっしゃいませー、と私が言うと、ミカさんがマッチ箱のなかから、ませー、と復唱する。店内のお客さんがこぞって振り返るので、私は裏声で、ませー、ませー、とエコーを利かせなくてはならず、きょうはそのことで店長にこってりしぼられた。
帰り際にスーパーに寄ると、ミカさんがレタスは嫌だと駄々をこねた。イモムシのくせに生意気だ。私は疲れていたのでレタスの代わりにキャベツを買って帰った。
翌朝、ミカさんはキャベツの表面にひっついてサナギになっていた。声をかけても返事はなく、サナギのなかでドロドロに融けているミカさんを想像しては中を覗きたい衝動と闘った。
一週間ほど闘いつづけているあいだにミカさんは、サナギの背中をぱりぱりと割って現れた。
ぷはー、くるちかった、とさっぱりした顔をこちらに向ける。私のよく知るそれはミカさんの姿で、でも背丈だけは親指サイズのままだった。これじゃまるで小人ですね、と私が言うと、ミカさんは、おやゆびひめー、と楽しそうに笑うので、私はしょうがなく指輪を外して、ミカさんの頭に載せてあげた。
今夜は葉っぱ以外が食べたい、とミカさんがお腹を鳴らすので、特別にステーキを焼いてあげた。イモムシのときとは違って、小人のミカさんはステーキを一切れだけでお腹をさする。
これくらいなら、と私は思う。
標本にしてしまわずともずっと手元に置いておけそうだ。買ったばかりの「マチバリと防腐剤と注射器」は押入れの奥深くに仕舞っておくことにする。
【ミカさんはビッグバン】
ミカさんが死ぬとこの宇宙が終わってしまうので、みなミカさんを死なせぬように必死だ。怪我をされると困るので、彼女は身動きを封じられ、それを苦として自殺されても困るので、薬で深く眠らされている。
この宇宙はミカさんの寿命と密接に絡みあっていて、がんじがらめで、どうやらミカさんが死ぬと同時に終わるらしい。
なぜ、と問われても、そうだから、としか説明できない。世の天才たちがこぞってその謎の解明にいそしんでいるが、明らかになるのはどうやら予測が揺るぎないという事実ばかりだ。つまるところミカさんが死ぬと宇宙が終わるというただそれしきの未来が不動の地位を築きあげる。
彼女を凍結処理してしまおうとする案がだされたが、死をどのように定義するかによって、いくつかの派閥ができ、けっきょくミカさんは年々歳を取りながら、確実に死へと近づいている。
ミカさんはどんな夢を視ているのだろう。
せめて夢と夢を繋ぎあえたらよいのに。
私はその技術を開発すべく尽力し、ミカさんの頭に白髪がまじりはじめた時期にようやくその技術を確立させた。
私はミカさんと夢で繋がる。
しかし夢のさきでもミカさんは、宇宙の存続と一心同体で、現実と同じように深い眠りを課せられている。私はそこにいるもう一人の私と相談し、ほかの夢でも同じようにミカさんは眠りつづけているのだろうと結論した。
私たちは彼女の見る多重の夢のなかに生きており、宇宙はそうした泡のような夢によって膨張しつづけている。どの夢のなかのミカさんが死んでしまっても、すべての宇宙は順々に霧散する。まるでドミノ倒しのように、或いは連なる無数のシャボン玉のように。
私はほかの私たちと相談し、共同し、そしてミカさんを起こすことにした。彼女が目覚めると多重の宇宙はひとつに収斂し、私はその手に握ったナイフで寝ぼけたミカさんの胸を突く。
おはようミカさん。
ナイフを引き抜く。
そしておやすみなさい。
何が起きたのかも分からぬままにミカさんは血にまみれており、私はそんな彼女の身体を抱きしめる。
目を覚ます(眠る)べきは私たちのほうだ。
【あなたにならいいよ、あなたがいいよ】
ミカさんが殺人鬼になってしまったので、私が匿った。ミカさんは手際よく人を殺す反面、まるで赤ちゃんの食事みたいに盛大に痕跡を残すので、あっという間に最重要指名手配犯になった。
世界中のメディアというメディアでミカさんの顔画像が映し出される。連日ミカさんの話題ばかりがのぼるので私は面白くない。
ミカさんは白昼堂々でかけていって、また一つ死体を増やす。三日に一度は人を殺して帰ってくる。
殺す相手は一人のときもあれば何千人、何万人のこともある。もはや殺戮者だ。
さすがの私も、いい加減にしましょうよ、と小言を漏らす。ミカさんは私にじゃれつくと、返事もなしに猫みたいに丸まって寝てしまう。
ニュースではまた政治家の一人が死体で見つかった。ほかにも暴力団が壊滅し、どこかの主婦がスカイツリーのてっぺんで首を吊った状態で発見された。
見覚えはないけれど、きっとどれも私の身体をこんなにしたあの事件に関わっていたひとたちに違いない。ミカさんを問い質したところで彼女は素知らぬふりをするのだが、私がどんなに悪態を吐いてもミカさんは私を殺したりはしないのだ。
私は、私をこんな身体にした連中を恨んでいたけれど、いまになってはうらやましく思う。
ミカさんの殺意を独占できるなんて、そんなのはミカさんの人生を手に入れるのと同義だ。
いい加減にしましょうよ、と私は言う。あんな連中にかまけていないで、私の胸のなかで猫みたいに丸まって寝ていればいいじゃないですか、と。
ミカさんは困った顔をしながら刃こぼれしたナイフを研ぐ。
もうすぐ終わるから。
言い訳がましくつぶやく割に、その言葉は耳にタコができるくらいに聞いている。
人類が全部いなくなっちゃいますよ、と私は背後からミカさんの首にまとわりつく。
いなくなればいいんだ。
言ったミカさんの首はひどく頼りなく、貧弱な私であってもポッキリと折れてしまえそうだ。
試しに首に回した腕にちからを籠めてみる。
ミカさんは抵抗をするそぶりを見せずに、そうされたいがためにそうするように、私の腕に頬を押しつける。それでいて、苦しいよ、と片笑むのだ。
ずるい、と思う。
そんなことをされたらもう、私は、どうすればいいのかが判らなくなる。
【トカゲの尻尾】
目のまえでトカゲの尻尾が切れた。トカゲの尻尾切りではなく、つまり組織の末端構成員に罪を着せて使い捨てにする意味の慣用句ではなく、本当に目のまえでトカゲの尻尾が切れたのだ。
いや、トカゲにはそもそもそうした能力があるのだから不自然ではないし、驚くほどのことでもないのだろうけれど、ここが無菌室の隔離施設、それこそ最重要機密とされている地下の地下であれば話は別だ。空気穴ですら針も通らないほどの通気性の高い硬化生地素材、それはのきなみ銃弾でもダイナマイトでも傷一つつかない優れものなのだが、そうした壁に囲まれ、観測できる起伏と言えばじぶんの肉体のみという、言ってしまえば四角と私しかないここは空間だ。
トカゲの入る隙間はない。
現に、切り落とされた尻尾はうねうねと床で身じろいでいるのに、肝心の本体の姿が見えなくなっている。さっきまでいたはずだ。幻覚だったのか。いいや、こうして尻尾があるのだから現実としてここにトカゲがいたのだ。
或いはこれも何かの実験の一つで、立体映像か何かでこちらの反応を試しているのだろうか。
思い、ひととおり部屋を見渡すがこれといって何もない。定位置に戻り、そこでようやく動きを止めたトカゲの尻尾をゆびの先でつつく。感触がある。つまみ上げると、まるでじぶんの手から切り離されたゆびをつまんでいる錯覚に陥る。
だがたしかにそれはここにある。
幻覚ではない。
物体として、現にここに存在している。なればこそ、どこからか入りこんだトカゲがおり、そのトカゲの入ってきた穴がこの空間にはあるはずだ。
床に這いつくばり、異物がないかを探る。
主として穴だ。
突起物でもよい。
すくなくともこれまでこの空間に穴や隙間といったものはなかった。壁をすり抜けるように透過する空気があるばかりで、ほかには何もない。むろん道具も、衣服も、食べ物さえないのだ。
ではどうしてこうして私が生きていられるのかと言えば、考えらえる筋書きは二つだ。
ここに監禁されたのが比較的さいきんで、餓死するほどの時間が流れていないから。もう一つは、私がそういう構造体だからだ、とすればそれらしい。なぜこうして監禁されているかの理由もそれで自明となるし、つまり餓死する心配のいらない構造体だからとすれば、状況説明が前者よりもより明瞭になると言えるのではないか。
笑えてくる。笑い方も忘れてしまったというのに、陽気だけは未だにこみあげてくるのだからやはり可笑しい。
はっと顔をあげると、トカゲの尻尾が手のなかから消えており、顎をしきりにしゃくしゃく言わせているじぶんがいる。口の中が血生臭く、それでいて吐き気を催さないじぶんを妙にしっくりと感じる。
空間はつねに明るく、真っ白だ。じぶんの影すら四面に映らない。時間の経過を判断する指針がない。いったいこの空間に閉じこめられてからどれほど経ったのかもいまではもう覚束ない。
或いは、生まれてからずっとここにいるのかもしれない。
そう言えば、とかつては幾度も思い浮かべてきただろう疑問を舌のうえで転がす。
私はどうやってここにやってきたのだろう。
どうやって入ったのだろう、この何もない部屋に。
そもそも私はどうしてこうも記憶があやふやでありながら、この空間を仕切る壁の材質や、見たこともないはずの外界の様子、それこそここが極秘施設の地下の地下に位置すると思いこんでいるのだろう。いったい私はいつから私を私として認めてきたのだろうか。
目のまえを何かが掠める。視軸をそそいだころには床に新たなトカゲの尻尾がうねうねと身じろいでいる。本体はない。
私はじぶんのゆびを拡張し、私の胴体ほどの太さもあるその切り離された尻尾をつまむと、口内ににじむ唾液を呑みこむようにして、丸太のようなそれに齧りつく。
なぜ見たこともないはずの丸太をこうして連想できるのかは、解らないし、もはやそれをふしぎにすら思わない。
私はおそらく、ずっとここに存在したのだ。
私を囲うようにきっと、箱のほうからやってきた。
壁と床で包まれた。
腰の付け根に痛痒を感じる。
ムズムズと収斂するそれは、間もなく、この真っ白で何もない空間に私以外の影を、うねうねと身じろぐ太く細長い起伏を、与える。
【グライダーマン】
グライダーマンを引退してからかれこれ十年が経つ。思ったよりも時の流れは早かった。
ソファに身体を預け、目をつむる。
若かりしころに異能に目覚めてからというもの私は、同時期に同じく異能に目覚めた者たちと長きにわたって、社会の秩序をかけての闘争を繰り返してきた。
立ちはだかる相手の多くは悪党ではなかった。そう、みな純粋に誰かを助けんがために、自身の異能を振りかざしていたのだ。私がグライダーマンとして陰に日向に活躍し、徐々に知名度をあげはじめたころにはすでに、虐げられる側の被害者たちのすくなからずはかつては悪党と呼ばれていた者たちだった。
権威を振りかざし利益を搾取する側に属する者たちから順々に、覚醒した異能者たちの餌食となった。次点で刑務所に入るような、世間一般で言うところの犯罪者たちが圧倒的な異能のまえに怯える日々を余儀なく過ごした。わざわざ刑務所に乗りこんでまで彼ら彼女らに制裁を加える異能者が後を絶たなくなったためだ。
私も初めはそうした分かりやすい悪党を懲らしめようと目を光らせていたが、徐々に社会から悪党と呼ぶに値する者たちの姿が消え、数々の異能者たちの手によって葬られていくうちに、何かが違うといった違和感がしこりのように胸に溜まっていった。そうしてその悪党の家族たちのその後の悲惨な生活を眺めているうちに私の胸に溜まったしこりは、黙ってはいられぬとのつよい衝動に変わっていった。
当時、私は戸惑っていた。目のまえにあるのは以前と変わらずの、力ある者が、自身よりも弱い者を支配する世界だったからだ。
私は立ちあがった。グライダーマンとして空を自在に滑走し、高速飛行にも耐え得るほどの頑丈さを湛えた肉体で以って、世の悪党をこらしめることに躍起になる異能者たちのまえに立ち塞がった。
裏切り者だと散々に非難され、抵抗に遭い、ときに袋叩きにされた。一般市民からも私は「悪党のボディガードだ」と指弾された。たしかに構図からすれば、私は悪党の味方だった。しかしさらに視点を変えれば、圧倒的チカラを手にした者たちに虐げられている者たちの味方であった。
むろん、助けた相手が、その後、自身よりも弱い者へと何かしらのチカラを向け行使しようとすれば、やはり私は一度助けたはずの相手のまえに立ち塞がり、その邪魔をしただろう。
強者と弱者という関係性をぶち壊したかった。
言うまでなくそこで私が己がチカラを思うがままに振るい、悪党や異能者たちを圧倒してしまえば、私こそが強者となり、支配者となり、邪魔されて然るべきナニカシラになってしまう懸念は常にある。ゆえに私は強者と弱者という構図が完成しないように、成立しないように、ただ邪魔をした。
いったいおまえは誰の味方なのだと捨て台詞のように投げかけられたこともしばしばだ。誰の味方でもなかった。正義のつもりもなく、ましてや正義の味方ですらない。
では弱い者の味方なのかと言えばそれも異なり、私は弱者にこれといって施しを与えることも、恵むこともしなかった。
貧しい者を豊かにしたいわけではなく、弱者を救いたいわけでもなかった。
ただただ単純に、見ていられなかっただけなのだ。
強者がチカラを振るい、弱者を虐げ、支配する世界を、私は見ていたくなかった。
見ていられなかった。
しかし、いくら私が邪魔をしたところで、世界中のすべての異能者の動向を見張ってはいられない。異能者のなかには、世界中の人間の行動を監視可能なチカラを持った者もいたが、仮にそうした者の助けを借りたところで、やはりすべての強者の日々の行動に目を光らせ、邪魔をするだけの能力も手間も、時間だって私にはなかった。
よしんばそのようなことが可能であったとして、けっきょくのところ私が死ねば、或いはグライダーマンとしての異能を失くしてしまえば、また元の、強者が弱者を虐げる世界が徐々に、しかし確実に社会の基盤として再構築されていく。
イタチゴッコであるし、焼け石に水だ。
あるとき、異能を封じられた異能者が一般市民からの反撃を受け、滅多打ちにされた事件が起こった。科学技術は、異能者の能力の秘密をも暴き、その異能無効化の手段を世界へと広めた。
これまで強者としての地位が揺るがなかった異能者たちの立場が、音を立てて崩れはじめた。
私は、目のまえで大勢の弱者から滅多打ちにされるかつて強者として振る舞っていた者たちの成れの果てを目にし、そしてそこに介入する真似もせず、目を背けることもせずに、ただその様子を眺めていた。
世界中どこにいても、そうした光景が目についた。
きっと部屋に引きこもったところで同じだろう。買い物をしにそとにでるだけでも嫌でも世界中で引き起きている暴動の話は耳に、目に、入った。
私はそれら弱い者いじめを邪魔しようとは思わなかった。する気がなかった。
自業自得だとは思わない。
ただ、疲れてしまった。
私がいくらあいだに入ったところで、砂時計はいくらでも引っくり返り、そして砂を上から下へと落としつづける。私はただ、その砂時計の真ん中にあいた細く、狭い、ちいさな穴にすぎなかった。
疲れてしまった。
私はグライダーマンを引退し、正体を隠したまま、目のまえで繰り広げられる盛大な弱い者いじめを尻目に、庭で育てた自家栽培のトマトやカボチャで食卓を飾り、ときに肥えたニワトリの首を跳ねてタンパク質を補う。
そうして日々、食物連鎖の頂点に立つ者としてのチカラをぞんぶんに活かし、すこしばかり手間のかかった食事を楽しみとする生活を送る。
邪魔する者が現れたらきっと私は黙ってはいられないだろう。抵抗するだろう。ときに、異能を使って返り討ちにするかもしれない。
ただ、いまのところそうした危機には見舞われていない。
私は老いた。
そして遠からず死ぬだろう。
そのときがくるまでこうして、世界中から聞こえてくる砂時計の引っくり返る音を耳にしながら、蝉や蛙の鳴き声のようにときに煩わしく感じつつも、それら音色に風情を見出し、束の間の平穏を思うのだ。
【ピックを握りしめて】
音楽という名の事象は存在しない。偶然にしろ必然にしろ、いくつかの物体の振動が空気を揺るがせ、同一時空上にて重なり合い、それを聴く者の脳内にて「音楽」として顕現する。
音楽は、ただそこにあるだけでは音楽たりえない。
それは人間の内面世界にて現れる魔法だ。
瀟洒な酒場のカウンターに一人の男が座っている。名を、ガクフと言う。彼のもとに吸いこまれるように女が一人、寄っていく。
「あら、珍しい。きょうは【探索】にはいかなかったの」
「もう潜った」
「ああ」女はガクフのよこに座ると、「あいかわらずおはやいこと」
言いながらカウンターの机上をゆびでタップする。するとテーブルにどこからともなくグラスが現れる。中身は青い。女はそれを飲み干すまで口を利かなかった。
「なんの用だ」ガクフは言った。しびれを切らしたからだが、女がそう仕向けていたのは知っている。
「あさって、ニトロデイのミニアルバムが【盤上】に乗る。賞金は十億オンプ」
「そりゃ太っ腹なこって」
「もちろん潜るんでしょ」
「だったらどうだってんだ」
「お願いがあって」女はバッグからちいさな貝殻のようなものを取りだした。「これを向こうに置いてきてほしいの。報酬は弾むから」
「向こうの、どこだよ」
「分からない」
ガクフは返事をせずに、女から寄こされたちいさな貝殻のようなものをゆびでつまんだ。ピックだ。ギターやベースを弾くためのアイテムだ。
「わるいな。仕事の安請け合いはしない性質でな」
「持っていくだけでも。お願い」
渋っていると、お守りだと思って、と女が口にしたところで陽気が漏れた。
お守りか。
ピックをポケットに仕舞う。
「失くしちまっても文句は言うなよ」
「言うに決まってるでしょ。ありがとう」
女から握手を求められたが、ガクフはその手をじっと見るに留めた。女の手のひらにはイレズミのような黒いハートが刻まれている。
音楽の世界に潜る技術が確立されたのは音歴二十一年になってからのことだ。それから五十年あまり、人類は音楽の世界から持ち帰った【宝材】を資源に社会を発展させつづけてきた。
企業は資本として保有する「過去の名盤」を賞金つきで探索の対象とする。名盤であればあるほどそのなかに眠る【宝材】は資源的な価値が高い傾向にある。
今宵、ニトロデイのあの一枚が「盤上」にかけられる。
潜るよりない。探索家ならずともいちどは夢見る一枚だ。
女から受け取ったピックを手に、ガクフは音楽の世界へと旅立った。
探索家が職業として成立するいちばんの理由は、その危険度にある。音楽の世界に潜ったまま帰らない者は珍しくはない。
たとえば今回の一枚「少年たちの予感」は危険度の高さで言えば、第九や運命に次ぐとまで言われている。
音歴がはじまる以前に編まれたミニアルバムだ。一曲目の「ヘッドセット・キッズ」は、巨大な子どもの疾走する足場を抜け、その足の裏に貼りついた【宝材】を奪取せねばならない。
二曲目は「ダイヤモンド・キッス」だ。蠱惑的な魔女たちのひしめく城に忍び込み、【宝材】を回収するわけだが、どこに【ダイヤモンド・キッス】があるのかは未だ不明だ。探しだすところからはじめねばならず、それだけ危険が多いことの裏返しでもある。
三曲目の「ブラックホール feat.ninoheron」に到っては、その世界にまで潜って帰ってきた者がいないためいっさいが不明だ。まさにブラックホールの名に恥じない迷宮ぶりだ。
もはやこのさきは伝説にすらならない魔の領域だ。
だがガクフはまるで攻略法でも知っているかのような滑らかさで最終曲「ユース」まで辿り着いた。
そこは一軒のライブハウスだった。広くはない。だからこそというべきか、フロア内は熱気につつまれている。
バンドが演奏している。ガクフはなぜか懐かしいと思った。このままここに留まり、その曲を口ずさんでいたかった。
なぜここにいるのか、すでにもう覚束ない。
バンドのギタリストが激しく腕を振る。
何かが宙を舞った。
時が止まる。視界から色が失せ、宙に舞った何かが闇に溶けて消えた。
ガクフは拳を握っている。手のひらに鋭い痛みを覚える。
ゆびを開く。
ピックだ。
なぜこんなものを。
ゆっくりと意識が覚醒していくのを感じる。
バンドのメンバーが順繰りと闇に消えていく。
ギタリストの手が最後まで闇に残った。
闇を泳ぐように掻き分け、ガクフはギタリストの元まで辿り着く。
そこに、ピックを置いた。
つぎに気づいたとき、ガクフは「盤上の門」のまえに立っていた。戻ってきたのだ。基準世界に。
背に負ぶったリュックは、回収した数々の【宝材】の重さを湛えている。
手のひらが熱い。
見遣ると、ピックのカタチに色濃く火傷のあとが残っている。
【少年は予感する】
少年は目を開いたと同時に、何かが違うとすぐに気づくことができた。見慣れた街並みではある。だがどこか違う。車道を行きかう無人タクシーの列、ドローンが上空を埋め尽くし、すれ違う人々はみなオシャレなマスクをしている。きっと街中に設置された監視カメラの解析を拒んでいるのだ。道行く人々の足元には矢印が浮かび、道案内をしているようだった。
同じ街並みだが、同じ時代ではない。
時間を跳躍してしまったようだ。少年は事態を呑みこんだ。
時間を飛び越えるなんてありえない。そうは思ったが、目のまえの現実を否定するだけの論理を少年は構築することができなかった。
少年のよく知る時代にはない技術が街中にはたくさんあった。少年にはそれらを使いこなすことができない。だが、それほど長い時間を跳躍したとは思えなかった。街並みそのものはそれほど大きく変わっていないからだ。見覚えのあるビルがある。少年の記憶にはないビルも数多く建っている。
少年はまずじぶんの住まいに向かった。家が残っているのかは分からないし、よしんばそこに誰かが住んでいたとして、それが少年の知る誰かであるとは限らない。だが、なんとなく行けば知っているひとに会える気がした。ひょっとしたらこの時代のじぶんに会えるかもしれない。そんな想像をしてすこしのわくわくと、こわさを舌のうえで飴玉を転がすように味わった。
街のそこかしこからはバンドの曲が流れていた。ニトロデイの「ヘッドセット・キッズ」だ。少年には馴染みのある曲で、時代をまたいで聴くことができたことに気分をよくした。この時代ではどうやらニトロデイは超人気バンドだ。少年のいた時代とはやはりすこし違うようだった。
家に辿り着くころには辺りはすっかり暗くなっていた。遠くに走る無人タクシーの、道路をタイヤが舐める音が、さびしげに響いて聞こえる。人通りはなく、閑散としたものだ。不気味に思ったが、少年はニトロデイの「ダイヤモンド・キッス」を口笛で吹きながら、ふふふっふー、とスキップをした。気分はすっかりふしぎの国のアリスだ。
家には明かりが灯っていた。少年の知る外観とは異なったが、名残はある。
少年は庭に足を踏み入れた。急に足元にスポットが当たったので飛び跳ねた。自動で点灯する仕組みだったようだ。心臓にわるい。
庭は広く、暗がりにポツポツと開くスポットの丸い点は、まるで宇宙の足場だ。ワープ走行の痕跡のようでもある。少年はニトロデイの「ブラックホール feat.ninoheron」を頭の中で再生させ、家の窓に近づいた。
カーテンが下りている。生地の薄いレースのようなもので、透けて見える家のなかを眺め、少年は、ほぉ、と唸った。
年のころは同じだろう、そこには少年と瓜二つの少年がいた。もうひとりのじぶんだ、と少年は思った。時間を跳躍したのではなく、ではここはべつの世界なのだろうか。そういった想像も巡らせた。
なんだか急に、じぶんの居場所を奪われた心地がした。
じぶんの存在が薄くなった気がして、みじめで、なさけなくて、その場から消えてなくなってしまいそうだった。少年はかろうじてニトロデイの「アンカー」を口ずさみ、これがたとえばすべて夢だったとして、と現実逃避をしようとするのだが、それでも目のまえの現実は何一つ揺らぐことなく、ただそこに在りつづける。
少年は足踏みし、それから意を決して窓から離れた。
ここはぼくの家かもしれない。でもぼくの帰る場所ではない。
庭を抜け、道路に立ち、また元きた道を引き返そうとしたとき、家の扉が開いた。なかから少年と瓜二つの少年がこそこそと抜けだしてくるところだった。少年は壁に身をひそめ、その様子を窺った。
少年はふと、父親からむかし聞いた話を思いだしていた。頭のなかでは「少年たちの予感」のライブ音源が断片的に、つぎつぎと流れていく。
「父さんな、むかしドッペルゲンガーに助けられたことがあってな。車に轢かれそうになったところを――」
父親の言葉が脳裡に蘇える。目のまえでは、家を振り返り、振り返り、道路まで小走りにやってくる少年と瓜二つの少年の姿がある。
ふと、視界の端に黒いカタマリが映った。それは道路を舐める音を響かせながら、まっすぐとこちらへやってくる。
無人タクシーだ。ライトが点いていない。
少年と瓜二つの少年はそれに気づいていない様子だ。そのまま庭から道路に飛びだそうとしている。
少年の身体はそうあるべきようにと、動きだしている。
頭のなかではニトロデイの「ユース」が流れる。
浮遊感を覚える。
無人タクシーが遠ざかる。
少年は予感する。
きっといまぼくは、このさき産まれてくるだろう、じぶん自身を助けたのだ。
道路に仰臥しながら少年は、じぶんとよく似た少年の身体を抱きすくめている。
【お城のパーティーにとっときな】
「いたいた、ニト。探したよ」
「んだよデイブ。朝っぱらからおまえの声は厳しいな。まるでアルプス山脈にコーヒーが流れているみたいだ。ギトギトの濃いやつな」
「目が覚めてよくない? それよりほら、ニトが聴きたがってたやつ」
「あん?」
「ニトロデイの最新ミニアルバムだよ。ニト好きだったよね。リリースされたんだよ、知らなかったの」
「おいおい困ったちゃんだな。アタシを誰だと思ってんだ、じぶんの大好物はどんなもんでも発売日の三日前に入手済みだ」
「あ、そうなんだ」
「だいたいな、おまえはアタシがなんでニトロデイ好きか知ってんのか」
「それはもちろん、ほら【ニトロデイ】にはニトの名前が入ってるし」
「デイブ。おまえがアタシの名前に欲情すんのは百歩譲ってキモいで済ますとして」
「あ、キモいのは前提なんだ」
「ニトロデイのなんたるかも知らずにそれを餌に特大ネッシー釣ろうなんて、なんだろうなー、おまえの顔見てっとムカムカすんなー」
「けっきょく顔なの!? ルッキズムって知っているかな。そうやってひとの見た目で差別をするのは現代人として問題があって」
「ウッセー。なんとかの犬ってのあんだろ。ベル鳴らすだけでよだれ垂らすようになるやつ。あれだよあれ。デイブ、おまえがそうやって会うたびにアタシに講釈垂れっから、おまえの存在イコールうざいつってな、脳みそにインプットされちまった」
「あ、同じかも。ニトがいつも聴いているから好きなんだきっと。ニトロデイ」
「そりゃバンドに失礼ってもんだろ」
「わ、顔真っ赤。そうやって人を毛嫌いしておいて照れるところでちゃんと照れてくれるところとかも好きな理由の一つだよ」
「アタシはおまえのそういうサブイボの立つセリフをクソマジメに吐きだすところが嫌いだよ。大嫌いだ」
「その割に、追いかえしたりはしないし、バンドの曲をおすすめしてくれたり、なんだかんだ曲の感想を聞きたがったりするよね」
「布教だよ布教。誰でもいいんだ、おまえじゃなくたってな」
「ふうん。でも今回のミニアルバム。なんだかこれまでのニトロデイとはすこし違った感じがしたけど、やっぱりニトもそう思った?」
「思った」
「わ、やった。意見が合ったの初めてじゃない?」
「やっぱウソだ。思わなかった。これまで通りのニトロデイだった。曲調はすこしポップに寄せてきた感じがあったが、あんなのはメイクをすこし変えましたって感じの変化だ。たいした変化じゃない」
「そんなこと言って。もしバンドにとって大きな変化だったらどうするの。それをニトが否定していいの」
「う……。まあ、たしかに意図して冒険した感はあった。ミニアルバムのタイトルだって【少年たちの予感】だろ。こりゃあれだ。このさきを暗示してんだよ。こっからさき、私たちは大きな変化を遂げていく、成長していく、それを予感してくれってな」
「ああ、なるほど」
「曲の構成もそんな感じだったな。アルバムの一曲目はふつう、そのバンドの顔だ。現時点でのバンドの色を教えてくれるような一曲を置く。それがこれまでのニトロデイとは打って変わった明るく駆けだしていくような曲――【ヘッドセット・キッズ】だったことを思うと、たぶんこれからはどんどんそっち方面にも触手を伸ばしていくぜ、足を踏みだしていくぜ、ってそうした決意表明を感じずにはいられなかったな」
「さすがニト。だいすきなバンドの話になると早口になるね」
「早口に……なってたか?」
「ニトってライブに行くのも好きだよね。あれはなんで? べつにスマホで聴いても同じなのに」
「同じじゃねぇよ。バカかよ。ライブだぞ。一発勝負の本番、生演奏、空間全体を揺るがして身体の芯ごと共鳴する曲との一体感――それがイヤホンで聴く曲といっしょだと? デイブ、おまえはいまイッチャン踏んじゃいけねぇ特大地雷を踏んだ」
「そんなに違うの?」
「ぜんぜん違う。や、修正につぐ修正の加えられた理想の一曲を詰めこんだアルバムにもそりゃいいところはあるよ、そこは認める。それに今回のミニアルバム、後半の四曲はライブ音源だしな。一発本番のよさを改めて何度も聴きなおせるよさもなくはない」
「でもやっぱりライブを観るのとは違うんだ?」
「観るんじゃねぇ、体感するんだ。一体化だ。バンドの一部、曲の一部にアタシもなるんだ」
「ふうん。あのねニト、ここにチケットが二枚あるんだけど」
「あ?」
「いっしょに行ってくれない? ライブがどんなものか、【わたし】も体験してみたいから」
「……デイブ」
「嫌なら、ニト一人で行ってきなよ。チケットはあげるから」
「んなこと言われてハイヨって受け取れねぇだろ。アタシをいじめっ子にしたいのかよ。いいよ、行ってやるよ。そんかしおまえ」
「なに?」
「スカートはやめとけ。そういうヒラヒラはお城のパーティーにとっときな」
【スペースミュージック】
わたしの名前は◇×☆↓△。
宇宙を旅するミュジク人だ。
宇宙の秩序を守るため、わたしたちはこうして指令を受けるたびに多元宇宙を横断する。
今回はДДИшЮの第三宇宙にきてるとこ。もうすぐ目標地点に到達予定だけれど、やっぱりそこそこの長旅なわけで、疲れちゃうというか、飽きちゃうというか、だってずっとパブリばっかりやっててそんなの中枢核が腐っちゃうじゃない?
で、本当は禁止されてるんだけど、船外に探査機飛ばしてこの宇宙の物理法則のゆがみを解析してたら、あらやだ、なにあれ?
なんか恒星の電磁波を受けてキラキラ光ってる物体があるじゃない? 回収してみたらなんか平べったくて薄い円形の物体で、カカブに訊いたら中に低度に圧縮されたデータが入ってるって言うでしょ。あ、カカブっていうのは超無機物構造体で、まあわたしのつくった相棒みたいな感じかな。
で、カカブに調べてもらったら、中身のデータを再生できるらしいって言うじゃない? まあじゃあ、やってもらおうじゃないの、ってことになって、なってっていうかそう指示したのはわたしなんだけど、で、いざ指示したらカカブってばその場でわたしの拾った円盤を呑みこむでしょ。
で、なんか妙な鳴き声を発するわけ。
妙なって感じたのは最初だけだったんだけど。
なんか聴いてるうちに心地よくなってきちゃって。
なんか節目が八つあって。
あ、八つの鳴き声が入ってるのかって段々わかってきて。
言語っぽいなって思って、翻訳機に晒したらばっちし、なるほどこれはあれだ、いま向かってる惑星の現地語だって解って。
ってことは、これはその惑星の住民の創造物ってことで、なるほどなるほど、なかなか愉快だなって。
まずその星にはバンドって概念があるらしい。それでそのバンドってのにもたくさんの名前があって、そのうちのひとつがニトロデイっていうらしい。で、バンドはどれも音楽ってものをつくるらしくて、畢竟、いまカカブが鳴らしているこれが音楽なのだ。
ニトロデイのつくった音楽ってことになるのかな。
ほかにもじゃあたくさんの音楽があるってことだ。
聴いてみたいな。
どんな音なのかな。
想像すると全身の鱗がキシキシ云った。
なんども繰り返し聞いているうちに、どれが一つ目の音楽で、どれが最後の音楽なのかも判るようになった。
「カカブ、二つ目をおねがい」
気分によってどれがいいかなって選んだりして、なんだかちょっと贅沢な気分だ。
浮かない旅路もこれならご機嫌だ。
音楽ってやつは素晴らしいな。これは戻ったらみんなに自慢できるぞ、なんだったらわたしたちの価値観ってやつを根こそぎ変えてしまうかもしれない。
だったらいっそ、ほかの音楽ってやつも根こそぎ集めてみてもいいかもな。
どうせ滅ぼしちゃうわけだし。
わたしの使命はそれなんだし。
思うとなんだか中枢核のところがじゅくじゅく痛んだ。まるで何かを拒むようなその痛みに戸惑いながら、それでもすこし心地よい気がした。
目標地点が見えてきた。
いまはまた一つ目の音楽を聴いているところだ。
ヘッドセット・キッズ、遠い彼方に。
二つ目を聴く。ダイヤモンド・キッス、いつもと違う予感がする。
三つ目、四つ目、とつづけ、けっきょく最後まで聴いて、また最初の一つ目に戻る。
目のまえの惑星は全体的にニャーだ。たぶん電磁波のうちニャー波を多く反射するからじゃないかな。本当にニャーだ。
ニャーはどちらかと言えばわたしたちを不快にさせる。
でもカカブの鳴らしつづけるあの惑星の音楽につつまれていると、なんだかニャーもそれほどわるいものには思えなくなってくる。
わたしの使命はあの惑星を滅ぼすことだ。より正確にはあの惑星に繁殖した生命体を根こそぎ絶やすことにある。詳しい理由はわからないんだけど、たぶんいつものように、あの惑星の生命体がいずれほかの宇宙に干渉する術を見つけてしまうと予見できたからじゃないかな。この宇宙では何億年先のできごとかもしれないんだけど、宇宙同士は時空がねじれているから、いつそれが起こるのかはあまり関係がない。
いつかは起こる。そう解かった時点でそれはわたしたちからすると脅威なのだ。
でも。
わたしはまたニトロデイの音楽をカカブに鳴らさせる。
この音楽なるものを生みだす存在を滅ぼしてしまうのは惜しい気がした。
単純に、惜しい。
この惑星の生命体がいつかこのさきわたしたちの宇宙に干渉してきたとして、それはわたしたちがおそれるほど避けるべき事態ではないのかもしれない。
だってひょっとしたら、この音楽とやらを届けてくれるかもしれないのだから。
わたしは迷った挙句、カカブにこの星への着地を命じた。
この惑星について、わたしはもっとよく知る必要がある。
【禁音の果てに】
禁音、それは「音楽禁止令」の通称である。技術的特異点を迎え、社会の中枢を担うようになった人工知能「オンプ」により発足された法度である。その日、全世界から音楽の旋律は途絶えた。
人々は徐々に音楽の存在を忘れていった。伝える者がいないのだ。禁音発足から十年足らずで世代は移り変わり、禁音への反対勢力の勢いも軒並み収束へと向かった。
だが、ゼロではなかった。
音楽への飽くなき欲求、人々を駆り立てたあの熱気、興奮、生きているという実感――音楽の禁じられた世界にあって世界は色を失くした、しかし灰色の世界にこそ音楽は必要なはずだ。
この世界にこそ音楽が。
立ちあがった者の名は、小室ぺい、ニトロデイを率いるボーカリストだった。
「おかしいだろ。音楽がダメ? アホ言ってんな。音を楽しむのが禁じられたならしょうがねえ、だったら楽しい気持ちを音にしちまおう」
音楽がダメなら、「楽音」を新たにつくりだしてしまえばよいのではないか。
単純な発想だったが、禁音にはたしかに「あらゆる音楽を禁ずる」としか記されていなかった。律動や旋律そのものを禁じてはいなかったのだ。なぜなら律動を禁じれば人々の鼓動、歩行、生活行動様式、さまざまなサイクルを排斥しかねない。また旋律は、言語そのものを封じかねない懸念もあった。人類を管理する中枢人工知能「オンプ」そのものもまた、アルゴリズムという名のシステム、ある種の律動や旋律によってその機能を維持している。
「楽器を使うな、歌を使うな、そんなことでオレらから音を、曲を奪えるなんて本気で思ってんのかね。人工知能も高が知れてら」
世のなかには音がすでに無数に溢れている。ときに共鳴しあい、錯綜しあい、絡みあって偶然に、そこかしこに、音の楽しむ余地を広げている。むろん社会の至る箇所に設置された保安カメラ、集音機、各種センサーによって、音楽に値する音は即座に察知され、にどと音が組み合わさらないようにと解体された。
ある意味でそれは、中枢人工知能「オンプ」がいまなお膨大な音楽のビッグデータを保有していることの裏返しでもあった。社会に鳴り響くつつましやかな音楽の余韻を、音楽と見做すだけの情報を「オンプ」は現在進行形で蓄積している。
ひるがえって、「オンプ」の記録にない新たな「楽音」であれば、或いは「オンプ」に察知されず、よしんば察知されたところで禁音に抵触したとは見做されないのかもしれなかった。
「ぺい、どうすんの」
「まずは映画でも観るか。BGMねえのが惜しいけどな」
言いながら胸に集音機をあてがいながら小室ぺいはメンバーと共に映画をはしごした。その際に録音したじぶんたちの心臓の音を組み合わせ、一つの曲の基盤をつくった。
「間違いなくこれはオレたちだけの【楽音】だ。映画を観て楽しいと思った気持ち、怖い気持ち、興奮、感動、すべてここに凝結してる」
つぎに向かったのは遊園地だ。パレードのない夢の国はそれはそれでアトラクションが洗練されており楽しめた。人々の絶叫の声、和気あいあいとした話し声、迷子の泣き声や、駄々をこねる子どもの声、どれも感情に溢れ、起伏に富んでいた。
「音楽がなくてもみんな幸せそう」
「音楽があればもっと幸せになれんだよ」
「まるで中毒者の発想だね」
「中毒者だからな。音楽の。だが副作用があるか。ないなら魔法の薬だよ」
音楽はな。
しかしニトロデイのつくる曲は、楽しい気持ちを音にした「楽音」だ。これまでの音楽とは一線を画する。
じぶんたちの鼓動を組み合わせてつくった曲の基盤に、ニトロデイは人々の感情の起伏を上乗せし、ていねいに編みこんだ。
「さて、仕上げといこう」
小室ぺいはメンバーと向かいあい、そして踊った。音はない。無音のなかでただ踊る。じぶんだけに聴こえる音楽の記憶を頼りに。じぶんのなかに響く「楽しい」を手繰り寄せるように。
そばには彼ら彼女らのたてる物音を集音する機器が起動したままになっている。
そうして集めた「踊りの物音」を最後にニトロデイはこれまで編みこんできた「楽音」にちょいと添えた。
ニトロデイ、最初の一曲がこうして完成した。
街中で爆音で鳴らす。見せつけるように。気づかせるように。
中枢人工知能「オンプ」の反応を試すように。
どうだ、おまえにこれが理解できるか?
人々は騒然とする。立ち止まる者、耳を澄ます者、見て見ぬふりをする者、その場で踊りだす者、懸命にその「音」を記録することに躍起になる者――。
ニトロデイはそうした人々から立ちのぼる喧騒を集音し、さらに二曲目の構想を練る。
彼ら彼女らの頭の中には予感が満ちている。
新しい時代への幕開けだ。
音楽は死んじゃいない。
楽しい、の逆襲がこれからはじまる。
街中にはまだ、ニトロデイの流した音が鳴りつづけている。
【黙れよギター】
ギターがしゃべるなんて言ったらたぶんふつうに頭おかしいって思われんだろうなぁ。
でもしゃべんだよなぁ、コイツ。
やぎひろみはスタジオの一室でギターを見下ろしている。ひざに載せたそれの弦を調整しながら、
「イテー、イテーって。やぎちゃんよー、もっと優しくしてくれよ。もっとこうほら、あんだろ愛を籠めた手つきってもんがさあ」
セクハラでしかない発言を聞き流す。そばにはほかのメンバーもいるが彼ら彼女らに聞こえている素振りはない。
いつもより気持ちつよめに弦を張り、さらに音を鳴らして調節する。やっぱりすこし締めすぎたかな。
「イテー、イテーって」
なおも愛用のギターは喚き散らした。
昔から聞こえていたわけではない。ただ、前兆のようなものはあった気がする。ギターにかぎらず、やぎひろみが長年使い古した道具、それはたとえば三歳の誕生日に親からもらったカエルのぬいぐるみや、祖父から譲ってもらった音楽再生機、繰り返し聴いたお気に入りのCDや、履きつぶした靴も、ときおりだが声のようなものを発した。
明確に言葉として聞き取れたわけではないが、なんとなくそれが発した声ではないのか、と思うことはあった。もちろんしばらくすれば幻聴だと気にも留めなくなったし、いま思い返してみても、気のせいだと見做したほうがしっくりくる。
だが今回ばかりは愛用のギターははっきりと聞き取れる言葉を、意味を含んだ声を発した。
ギターの声は周囲に聞こえないからよいとして、こちらの応答は周囲の者にも聞こえる。街には手ぶらで通話する者がいるくらいだから、ひょっとしたらやぎひろみが案じるほどには奇異な目で見られたりはしないのかもしれない。
ギターの声には反応を返さずにいた。
認めたくないだけだったのかもしれない。
幻聴を本気にするだなんてどうかしている。
ギターに名前をつけるギタリストもいるが、やぎひろみは敢えてギターには名をつけない主義だった。どうせ壊れたら買い換えるのだ。手に馴染むギターがほかにあるなら容赦なく買い換える。
とはいえこのギターよりも身体にしっくりくる一本がいまのところない。
愛用ではあるのだ。愛着がある。
ただ、しゃべるのだ。無駄にウザく。
「へいへい! もっと弾いてくれ、引いてくれ、ぶってくれ! ひゃほー、最高だぜやぎちゃん! もっとくれ、もっともっとだ!」
ライブの演奏中でもこんな具合だ。否、気分の乗った演奏であればあるほどギターは調子に乗って騒ぎ立てる。
いい加減にしろ。折るぞ。
つよく念じてみても伝わる気配はない。
ゲストを呼んだだいじな回のことだ。ギターはあろうことか歌いだした。しかも演奏曲とはまったく関係のないクリスマスソングだ。
かろうじて歌だと思えるくらいのオンチさで、やぎひろみの集中力を以ってしても、聞き流すには骨が折れた。
間もなく曲の旋律を辿れなくなった。どんな曲だったのか、その起伏をいっしゅん忘れた。そのいっしゅんは、つぎつぎと遅延を生み、ほかのメンバーの演奏についていけなくなり、もはや自分自身が巨大なノイズか何かに感じられたのを機に、ギターを弾く手を止めてしまった。
ギタリストとしてあるまじき態度だ。じぶんのなかの何かが大きくゆがんだ。
ギターはなおも耳障りな歌をまき散らしている。
二曲目、三曲目、休憩が入るまでやぎひろみの集中力は戻らなかった。
休憩時間、誰よりさきに舞台からおり、楽屋に入るなり、ギターを振りあげる。
そのまま床に叩きつけようと思った。
だが寸前で腕にちからをこめ軌道を変えた。ギターはブランコのように床の数センチうえを滑空する。
壊してやろうかと思った。反面、幻聴程度の雑音で気を削がれた甘さを棚にあげるじぶんの性根にも腹が煮えた。
「おまえマジで黙れよ」
これは独り言だ。ギターに言ったわけではない。言い聞かせながら歯をつよく噛みしめる。「頼むよ」
楽屋にほかのメンバーは戻ってこなかった。おそらくこちらの変調に気づいて、敢えて放っておいてくれているのだ。ありがたい。
舞台に戻るため廊下にでると、迷い込んだのか酔っぱらった客がいた。
頭をさげながらすれ違うと、酔っ払いは語気を荒らげ、こちらに迫った。腕を伸ばしてくる。単なる痴漢ならまだ我慢できた。だがギターを奪われそうになり、思わず足がでた。酔っ払いがその場にうずくまる。
「薄ぎたねぇ手で触んじゃねぇ」
吐き捨て、舞台上へと急ぐ。
だいじょうぶか、とボーカルが目線で訴えてくる。頷きかえし、ギターを構える。
「いっそ壊してくれりゃよかったんだ」
ギターがまた何事かを言っている。「あんたにゃもっといいのがあるだろう」
うるさい、黙れ。
やぎひろみはピックで火花を散らす。ギターはただ彼女の意のままに音を吐く。
【一本の金髪】
ベースとペースは似ているし、グルーブとグループも似ている。バンドをやっていると言うと、たいていのひとは、わーって目を輝かすのに、ベース担当ですって言うと、来たときと同じ勢いでわーって引いていく。波か。おまいらは寄せては返すさざ波か。
「ベースってバンドの要なのに」
「や、金髪を直してきなさいって先生、そういう話をしてるんだけど」
好きな髪型にしているだけなのにこの国の教育機関はちょっと神経すぎと思う。前はそういう湧いた疑問を真っ向から投げかけていたけれど、だってそれが誠意ってやつじゃないかなって思ってたから、でもたいがい相手が眉と眉のあいだに日本海溝かってくらいのシワを刻むものだからもう何も言わぬ。
「このあいだ街で見たよ。ギター背負ってたからめっちゃ目立ってんの」
「ベースな」
「学校サボって何してんの。ウケる」
そう言う時点であなたもサボっていたのだろ。そしてここさいきんは授業をサボった覚えはないのじゃぞ。
稀にこうしてどこどこで見かけただの、声かけたのに無視しただの、身に覚えのない目撃譚を語られる。他人の「そら煮」というやつだろう。でもどうしてそらを煮るのだろう? 美味しいのかな。
組んだばかりのバンドはなんだか思っていたのと違って、じぶんでは予想外の方向に行っている気がする。拒絶反応がでればでるほど、あとで、ごめんやっぱ好きだったわ、ってなる。
赤ちゃんが生まれてくるときに大泣きするのになんだか似ている。この世界めっちゃ嫌いなんですけど、もっかい母の身体に戻してーって泣きながら、それでもしばらくすると、ごめんやっぱこっちの世界もよかですばい、みたいな。似てる気がする。
あ、「そら煮」の「煮」は「似るの似」かも。
やっぱり遅れてやってくる気づきはいつも偉大だ。
家に帰ると母が金色の人形を手に持っていた。
「なにそれ」
「きょうおばぁちゃんの家に行ってきてね」
「朝に言ってたね。で、なにそれ」
「なんだかいつも部屋に金髪が落ちてるんだって。で、集めてたらおっきな毛玉になったからもったいないからって、それで作ってみたんだって」
「だって、ってそれ髪の毛ってこと、ひとの? うげ」
「おばぁちゃんは孫のじゃないかって言ってたけど、母は、娘のではないんじゃないかって答えておいた」
「そりゃ行ってないからね。落としようがないし。え、どうすんのそれ。飾らないでよ、なんか怖いし」
母が考えこむので、
「え、やめてよ」と念を押す。「釘とかで刺されたらふつうに死にそうなんだけど。や、それがあったか、って手でぽんってしないで。釘どこだっけって探しださないで。エレクサに神社の場所とか訊かなくていいから、や、エレクサも答えんでええんやで?」
母はけっきょくじぶんの部屋に置いておくことにしたらしい。なぜ、と訊くと返ってきた答えに脱力する。「だってかわいいじゃない」
金髪はそれ以外でも、行ったことのないはずの友人の家や、先生の家、ほかにもさまざまな場所で発見されては、みな一様にその旨を今世紀最大の発見みたいに報告してくる。
「困るなあ、かってについてこられると」
話のネタとしていじられる分にはいいけど、その頻度が多いとさすがに胸のなかが曇り空だ。
二度目のライブのとき、寝坊した。
ベッドから跳ね起き、ホースのさきっちょを押しつぶすみたいに家から飛びだして、駅までダッシュした。特急に乗りこむまでのあいだに、遅れてごめんもうすぐ着く、とテキストメッセージを送るも、返事はない。
怒ってるのかな、怒ってるよな。
焦るのもバカらしくなってゆっくり歩いた。焼き立てパンでも食べてこ。
ベースがなくとも演奏はできる。味気ないだけで、まあカタチにはなる。めっちゃ味気ないけど。
想像するとおかしかった。
やっぱりすこし急いでやることにする。
いざ現場に着くと、まさに絶賛ライブ中だった。見知った顔が舞台のうえで楽器を叩き、弾き、歌っている。
思ったよりもちゃんとした曲になっている。
舞台上の人影は四人分ある。バンドの人数も元々四人だ。ベースの音があり、骨格として曲を底から支えている。
代理を立てたのかな。
疑問は、舞台上に揺らぐ金髪を見て、引っこんだ。
じぶんがいた。じぶんがベースを弾いている。
あれ、双子なんだっけ?
じぶんの出自を思い起こし、いやいやそんなわけが、と混乱する。
客観的に初めてじぶんたちのライブを観た。曲を聴いた。身体に染みこむようなその音の連なりたちは、思っていたよりもずっとしっくりと骨身に染みた。
まあ、たまにはこんな日もあっていいか。
担いでいた楽器を置こうとする。
なぜか肩にそれはなく、身体が妙に軽いことをふしぎに思いながら、金髪が一本、ライトの合間を縫って落ちていくのをじっと見る。
【ドラマーのドラマ】
ひとを殴ってはいけない。物に当たってもいけない。だが楽器は、叩いて、「なかす」ことが推奨される。上手に叩き、なかせればなかせるほど、人々はもっともっとと称賛の声を投げてよこす。
ロクローはバンドのなかでゆいいつ明確にいつでも年上の存在だ。ほかのメンバーはつねに歳下でありつづけるのだから必然、周囲の人間たちからは年上としての態度を求められる。おまえがバンドじゃいちばん年上なんだろ、とか、けっきょくバンドをまとめるのはおまえなんだ、とか、そういう当たり触りのよいことを言ってきては、直接メンバーに言いにくい批判や要求を投げてよこす。
どいつもこいつも投げてよこすやつばかりだ。称賛にしろ、批判にしろ、野次にしろ罵声にしろ、もっとやさしくそっとなぶるように、ねぶるように、愛を以ってくれろってんだ。
ロクローは憤懣やるかたない。いまのところ理想の女王さまとは出会えていない。もちろん理想の王子さまにもだ。
ロクローには三本の活殺自在に操れる棒がある。うち二本は手に持ってドラムを叩く棒であり、もう一つは下半身のほうに備わっている。手に持つ棒よりも格段に太く立派な――そう、足で踏んでドラムを叩くための棒だ。ペダルを踏むとバスドラムが鳴る。
ペダルを踏んでコンマ何秒の誤差が結果に影響してくる点では、レーサーやパイロットと似ていると思うことがロクローにはあった。
楽曲という名のコースを駆け抜けるスーパーマシン、それがドラムだ。
ロクローは争いを好まぬ。だがうちなる本能には抗いがたく、百獣の王のたてがみに住み着くノミさながらの猛々しさにはいつも気を揉んでいる。
ひとを殴ってはならない。傷つけてはならない。物に当たり散らしてはならない。だが演奏というテイで楽器を叩き、なかすことは許される。
なにより楽器はやり返してこない。
と思っていたのは初めばかりで、ドラムはしかしふつうにやり返してくる。適当な演奏には適当な態度で返し、楽しいときには楽しい音が、このやろーと思うときにはそういう音を響かせる。
加えて、案外に思った以上に、負けるのだ。
いつの間にかその負けることへの快感を覚えている。病みつきになる。
もっと、もっと。
やさしくそっとなぶるように、ねぶるように、愛をくれ。
理想の女王さまにも、王子さまにだって出会えていない人生だが、図らずも理想の楽器とは出会っていたようだ。
ロクローは自身の四本目の棒を乱暴に、慈しむような手つきで撫で回しながら、これからのじぶんに想いを馳せる。おそらく、とロクローは思う。白く、苦く、ときに甘い天使たちをいっせいに世に放つであろう。破廉恥と思うことなかれ。
そう、ロクローはこれからも脳みそが白濁し、ときに苦く、甘い、粗挽きコーヒーのような音楽を、ラッパを吹きながら地上に押しよせる天使たちのように、世に放つのだ。
それは或いは、終末を報せる音かもしれない。
それとも、人間の愚かしさを歌うささめきであってもいい。
殴ってはいけない、当たってもいけない、それでもそうしてなかせる音で、救える感情もあるはずだ。
誰からも見向きもされずに、本人にすらないもの扱いされている感情を、機微を、掬いとることだってできるはずだ。
だからなのだろうか。
それでなのだろうか。
スティックを握りしめ、ためしにドラムを、チクと叩く。
身体の内側に拡がる水面に波紋が広がるのを感じる。
通じている。
音は、音楽は、人間の内面に通じている。
じぶんにしかならせない音を、じぶんにしか揺さぶることのできない世界を、ひとを、感情を、機微を、叫びを、叩き、なかせ、編みこむことでしかその存在の輪郭を帯びることのできない何かを、ロクローはなかったことにしたくはないから。
ないもの扱いをしたくはないから。
されたくはなかったのだ、と何かを求めるじぶんに気づき、ドラムを叩く手を止める。
バンドのほかのメンバーがこちらを振り返る。新曲の練習中だった。音の余韻が部屋に吸いこまれながら消えていく。
「なに? またウンチ?」鋭い声だ。
それはさっき行った、と伝える。めっちゃデカイのがでた、と。
あっそう、とメンバーは飽きれた調子で、また演奏をはじめるが、ロクローはステッィクを握ったまま動かずにいた。
演奏がやみ、なんなの、と非難の目が飛んでくる。
「そのままつづけて」
ロクローはしばらくじぶん抜きの演奏を聴いた。
それからふいに、なあ、と声を張りあげ、苛立たし気に振り返ったメンバーに向け、
「気づいたんだけどさ」と怒鳴るように言った。
なに、とメンバーが不安そうな顔をする。ロクローは告げた。
「オレ、このバンド好きだわ」
あっそう。
脱力するメンバーを眺め、ロクローは満足げにまたドラムを叩き、なかせる。
【ふたたび身体をつつみこむ】
またバイトを辞めた。今年に入って三度目だ。クビになったわけではない。じぶんで辞めたのだ。ただ、辞めると申し出たときの店長の顔、それからそのあとの社員さんや同僚たちの態度の変わりようと言ったらない。
初めから歓迎されてはいなかった。花粉みたいなものだ。またこの季節がやってきたか、と存在を許容されながらも、はやく去ってくれないかな、と祈られるような疎外感があった。
辞めると告げると、こんどは明確に、すでにここにはいない者としての線引きがなされたようだった。分からないでもない。どうせいなくなるのだからそんな相手に心を配るのは損だろう。無理に接していたのならなおさらだ。
貯金に余裕はない。はやくつぎのバイト先を見つけないと。
どこかにじぶんに合った働き先があるのではないか、と思い、店から店を転々としてきたが、真面目に社会人をやっている人々からすればその考え方がまずもって間違っており、腰を下ろしたさきに合わせてじぶんを変えていくしかないんだよ、と正論を説かれるハメとなる。
解ってはいるのだ。ただ、耐えられない。諦められない。もっと息のしやすい場所があるのではないか、と望みを捨てきれずにいる。
駅前を歩いていると、バイト募集中の貼り紙が目に入った。看板を見上げ、そこがCDショップだと知る。CD離れがささやかれて久しく、先行きの不安な様は、なんだかじぶんの姿と重なった。
だからでもないが、店内に吸いこまれるように足を踏み入れている。
閑散としながらも店内にはまばらにひとがいた。みな美術館にでもいるかのように棚から棚をゆっくりと渡り歩いては、ときおりCDを手にとり、その裏面を眺める。
しずかな印象だ。店内にはBGMが流れているが、売り場によって流れている曲が変わる。境目はどこだろうと意識して歩いても、その境目ははっきりとはしなかった。
試聴コーナーが充実している。ふだんからあまり音楽を聴かないから、とりあえずヘッドセットをあたまに被り、画面に浮かぶ再生の文字をただタップする。
ノイズ音が鳴る。いっしゅん機器を壊してしまったのだろうか、と焦ったがそうではなく、元からそういう音源だったようだ。すぐさま軽快な音楽が響きだす。
それとなく画面上の説明文を読む。ミニアルバムらしい。いま聴いている曲は奇しくも「ヘッドセット・キッズ」だ。まるでいまのじぶんを指摘されているようで苦笑が漏れた。
明るくポップな曲調の反面、どこか不安定さを覚える。子どものスキップみたいにリズムが一定ではなく、敢えて道を踏み外している印象があった。それはたしかに最初は不安定さに思われたが、徐々に、子どもが水溜りに飛びこんだり、路肩のブロックのうえに飛び乗ったりするような冒険につきまとう高揚感を思い起こさせる。
こんな感情がかつてじぶんにもあったのか。
いつの間にかあのころのじぶんとは別人になってしまっていたのだと、ちいさくない衝撃を受けた。それはどこかこそばゆく、身体をほぐされる感覚に似ていた。
気づくと二曲目に入っており、こんどは脳裡にパジャマパーティをする少女たちの姿がよみがえる。それはじぶんの記憶ではなく、おそらく映画の一場面の寄せ集めなのだろうけれど、こうした日常もあり得たのではないか、となんだかほかの世界のじぶんと触れあえた気がした。
びっちりと隙間なく埋まった脳内の枠組みがぐんと広がるのに似た錯覚を味わう。視界に色が宿り、重かった瞼が軽くなるのをふしぎに思いながら、三曲目を聴いている。
聴きながら棚に手を伸ばす。目当てのミニアルバムを手に取る。表紙を眺め、それから裏面を見る。店内でほかの客たちがやっていた仕草をじぶんもとっていることに気づき、ああこういうことか、と頬がほころびた。
四曲目を聴き終える前にヘッドセットを外し、レジに向かった。手にはミニアルバムを握ったままだ。
CDをこうしてお店で買うのは初めてだ。きょうこうしてお店に足を踏み入れなかったら、そして試聴した機器の一曲目が偶然このミニアルバムでなかったとしたら、このさき一生CDを買う真似はなかっただろう。出会いとはそもそもそういう偶然の積み重ねの結果でしかないのかもしれないし、ひょっとしたら偶然というものも、誰かの誰かを想う行動が結びつける必然なのかもしれない。
私は誰かのために何かをしたことがあるだろうか。
じぶんとは直接関わることのない、それでもきっとこの世にいるだろう、もうひとりのじぶんのために、何かを。
店をでると喧騒が大きくて驚いた。入口の貼り紙にはバイト募集中とあり、じぶんの境遇を思いだす。それから店頭に置かれた商品の山に目が留まった。ヘッドセットだ。すこし迷ってから箱の山から一つを選び取り、いまきた道へと向き直る。
音楽がふたたび身体をつつみこむ。
【同期性創発体】
結晶学の研究を専門にしている。おおざっぱにくくってしまえば、結晶学とは、結晶がどのような原子配列によってそのカタチを成り立たせているのか、そこにどのような規則があり、それによって物質の性質がどのように変化するのかを考える学問だ。
私のもとに政府機関を名乗る女性がやってきたのは地面にうっすらと氷が張りだした十二月中旬のことだった。
説明もそこそこに車に乗せられ、辿り着いたのは巨大な施設だ。
「表向きは二酸化炭素の圧縮施設です。地中に注入して処理することもあれば、一時的にドライアイスにして保管しておくこともあります」
「エネルギィ変換効率はどうなんですか。圧縮するエネルギィのほうが大きいのでは」
「確かにその通りです。ですが、ほぼ十割、太陽光発電によってまかなっていますから、気候変動対策としての効果は期待できます」
連れて行かれたのは施設の地下だった。航空機でも製造していそうな広大なドーム内に、大量の黒い箱が並んでいる。縦にも積みあがっており、巨大な結晶の内部にでも迷い込んだような錯覚に陥る。
足音がどこまでも反響して聞こえるほど静かだ。
「ここは?」
「新しい結晶構造を開発するための施設です。ご専門であられますよね」
「こんな施設があったなんて初耳なんですが」
「いわゆる極秘施設ではあります」
ジョークのような響きがあった。彼女は続ける。「箱の一つ一つにスピーカーが備わっています。内部に向けてこの世に存在するあらゆる【波形】を発しています。環境騒音から生活音、話し声、言語、音楽、歌、動物の鳴き声、もちろん宇宙から届くノイズも増幅して聴かせています」
「聴かせるとは、何に?」
「一種の共鳴なんです」彼女はこちらの質問には答えなかった。「雪の結晶が同じカタチをとることはないとは言われていますが、確率の問題として同じカタチを取ることはあり得るでしょう。現に、同じカタチになるように結晶させることは技術的に可能です」
「まあ、そうでしょうが」
それこそ音波や電磁波を使えば可能だろう。視えない型で以って、木々の枝葉を剪定するように結晶の成長を制限すればいい。いわば修正だ。
「原理的には似たようなものです。我々はその物質を【同期性創発体】と呼んでいます。周囲に介在する【波】を結晶構造に反映させる性質がとても高いのです」
「なるほど」
仮にそんな物質があるのならば、たしかに新しい結晶構造は容易に見つかるだろう。それこそいくらでもつくれるはずだ。
「ただ問題は、あまりにその【同期性創発】という性質が鋭敏すぎるために、せっかくつくった結晶構造をこの箱のなかから取りだせないのです」
「ああ、変容してしまうんですね」
「箱内部の状態はカメラで観察できていますから、新しい結晶かどうかの判断はつきます。ただ、それを調べる手立てがない」
「そこで結晶の専門家である私の出番というわけですか」自虐をこめて言ったつもりだ。
「安定した新しい結晶を開発したいのです」
「言い換えるなら、【同期性創発体】を安定させたいと」
「はい」
いわば【同期性創発体】は固体化しない固体だ。つねに外部の影響を受け、絶えずその内部構造を変化させる。閉じていない。それを閉じる役目に任命されたのが私だ。断る理由はいまのところない。
「分かりました。ひとまずデータを見せてください。AIで解析済みなのでしょ」
「はい。この端末を使ってください」
端末を操作する。過去五年間分のデータが揃っているようだ。なかでも安定度のより高かった結晶構造――それに何の音を当てたのかに焦点を絞って、情報を改めていく。
集中しだすと時間は飛んだ。
私をこの施設に案内した女性は、一週間後にふたたび私のもとへとやってきた。
「どうですか、何か進展はありましたか」
「ええ。見てください。これとこれ。結晶持続時間はほかと比べてもとくに長くはないのですが」
「似ていますね」
「構造がそう、似ています。でも同じ音を聴かせているわけではないんです。ただ」
「……同じバンドの曲ですか?」
「そうなんです。これは日本の【NITRODAY】というバンドだそうで。ほかにも曲を発表しているのに、ここで実験に使った曲は二つだけ。なぜもっと試さないんですか」
異なる【波形】を与えておきながら似た結晶構造をとる。安定した結晶をつくるための何かがここに隠れているのではないか、と直感がささやく。
「すみません。順番に【波形】のモデルを試してはいるのですが、なにぶん、聴かせる【物質】にも限りがありまして」
「責めてはいません。ではまだほかの曲を試していないんですね」
「いますぐ手配します」
「そのほうがよいでしょう」私はもういちどデータに目を落とす。「このバンドの曲には何か、ほかの【波形】にはない特性があるのかもしれません」
【少年たちの予感】
あるところにウタくんがいました。ウタくんはじぶんの声があまり好きではありません。しゃべるよりも身体を動かすほうが好きでしたが、誰かと競いあうのは苦手でした。
あるとき、ウタくんが砂場で遊んでいると、ギターちゃんがやってきて言いました。
「なにつくってるの」
ウタくんはギターちゃんを見上げ、それからまた黙ったまま穴を掘りつづけます。
「じゃあわたしはこっち」
ギターちゃんはウタくんの掘った穴のそばに山盛りになっている砂で、お城をつくりはじめます。
しばらくするとドラムくんがやってきて、
「なにつくってるの」
ウタくんとギターちゃんのそばにしゃがみました。
ウタくんは黙ったまま穴を掘りつづけます。ギターちゃんが代わりに答えました。
「こっちは湖で、こっちはお城」
ウタくんはそこでじぶんが掘っていた穴が湖だったのだと気づきました。
「じゃあおいらはこっち」
ドラムくんは湖とお城のそばに草を植えて森をつくりはじめます。
そこへベースちゃんがやってきました。
「なにつくってるの」
ギターちゃんとドラムくんは答えます。「湖と、お城と、森だよ」
ベースちゃんはしばらく三人の様子を眺めていました。それからはたと思いついたようにその場を離れると、しばらくしてジョーロにいっぱいの水を運んできました。
「湖なのに水ないのはヘン。森さんも雨がないと枯れちゃうんだよ」
ウタくんとギターちゃんとドラムくんの三人は顔を見合わせて、それからクスクスと笑いました。「雲さん、雲さん、雨をください」
「たくさんどーぞ」
ベースちゃんはジョーロを傾けて、湖とお城と森に、雨を降らせます。
湖には水が溜まり、森の木々はすくすくと元気になりました。けれどお城だけはグズグズと崩れてしまいました。
「あー、お城がぁ」
ギターちゃんは泣きだしてしまいました。それを見たベースちゃんの目にも涙が浮かび、いまにも零れ落ちてしまいそうです。ドラムくんは二人の顔を交互に見て、おろおろとしています。
「だいじょうぶだよ、こうすればいいんだ」
ウタくんが言いました。初めて聞いた声に、ギターちゃんも、ベースちゃんも、ドラムくんも、みんなびっくりしてぴたりと動きを止めました。
ウタくんは崩れたお城のうえから砂をまぶして、白くします。ぺたぺたと手でその白くなったところを叩くと、崩れたお城には頑丈な壁ができました。水を吸ったおかげで、前よりも大きく、どっしりとしたお城になりました。
わいわい、ぺたぺた、じゃーじゃー、ぐりぐり。
砂場には四人の国ができあがります。
「ウタくん、それはなんのお歌?」
三人に見詰められ、ウタくんは首を傾げます。知らぬ間に歌を口ずさんでいたようです。
「なんだろう、わかんない」
「もっと歌って」
ギターちゃんに言われ、ウタくんは歌います。
気づくとドラムくんがジョーロを枝で叩いています。ベースちゃんは砂場の縁に爪を立てて音を鳴らし、ギターちゃんは湖の水をゆびで弾いて、音を立てます。
ラララ、タタタタ、ジジジジ、ピチョピチョ。
四人は気の向くままに音を鳴らし、歌います。
四人はこの日初めて会ったばかりです。お互いの名前もきょう初めて知りました。
ですが、きっとあすもここにきて、じぶんたちだけの国をつくったり、音を鳴らしたり、歌ったりするだろうと、何の約束もしていないうちから四人は、ふと、そんな気がしたのです。
「ウタくんのお歌、もっと聴きたいな」ドラムくんが言いました。ギターちゃんとベースちゃんが頷きます。
「ぼくもみんなともっと歌いたい」
ウタくんが言うと、ほかの三人は照れくさそうに笑いました。「きょうはとっても楽しかったなあ」
遠くから、お母さんたちの呼ぶ声が聞こえます。ウタくんたちはそれぞれに、はーい、と返事をして、砂場の後片付けをはじめます。
ウタくんは三人とバイバイしたあとも、歌を口ずさんでいました。
手を繋ぎながらお母さんが言います。
「ウタくん、それは何のお歌?」
「わかんない。でも、とっても楽しいお歌だよ」
そっかあ、とお母さんはくすぐったそうに言いました。「ウタくんの声、お母さんはすっごい好きだなあ」
ウタくんは、そう言ってくれるお母さんのことが大好きです。
それと同じくらい、きょう出会った三人のことも大好きなのだと思いました。
ウタくんはじぶんの声があまり好きではありませんでした。しゃべるよりも身体を動かすほうが好きでしたが、いまは歌うことが大好きです。
ウタくんが歌うと、ウタくんの周りには、お母さんたちおとなには視えない特別な世界が広がります。
その世界は、ギターちゃんやベースちゃん、ドラムくんたち三人には視えているのだと、ウタくんにはふしぎと分かるのでした。
【音楽は爆発だ】
人類は三度音楽に救われている。
初めは原始の時代、人類が道具を使いはじめ、石を加工し、狩りの効率を格段に向上させた時期のことだ。
宇宙からやってきた支配者たちに対抗するため、人類は威嚇する術を覚えた。そのうち効果的な威嚇の仕方が洗練されていき、やがてそれが音楽の嚆矢となった。
それは示し合せたかのように当時、全世界に点在した人類の祖先たちがとった共通の自己防衛策だった。
音楽はそのとき、各民族を固有の何かへと明確に昇華せしめた。
その後、宇宙からの支配者たちはこの星を去った。人類の威嚇攻撃にも一定の効果はあったが、それよりもすでにこの星に生息していたべつの種族への脅威が宇宙からやってきた支配者たちへ撤退を決意させた。
人類が音楽に救われた二度目は、人類が電子を発見し、その扱いを心得、光の速さで情報をやりとりする網の目をこの星の表層に張り巡らせた時期のことである。
いまや人類は、地殻を挟んだ地球の裏側にまで、声や意思や映像を瞬時に伝えることができる。人類は加速度的に発展した。それは音楽を発展させ、民族が民族として団結したはるか原始の時代にひけをとらない目まぐるしい進歩と言える。
反面、その裏では、それら光の網の目を利用して人々の行動を操作しようとする者たちが跋扈していた。それら操作者たちは、これまでにも物語や噂、伝記、巷説、講談、虚構を用いて社会の動向を一方向に扇動してきた。
音楽もその役割の一端を担ってきた背景があるが、それに対抗してきたのもまた音楽だった。
そして操縦桿の役目はいまや光の網の目へと移された。そこで対抗したのもまた音楽だった。
想像してごらん。
音楽は伝える。物事の裏側を、瞬時に伝わる情報の陰で泣く者たちの声を、その姿を、ぼくたちわたしたちは想像することができるのだと、見落としていることに気づき、そして見つけてあげることができるのだと。
音楽は歌う。
瞬時に伝わる「真実」に比べ、音楽のそれは数段遅れてやってくる。それでも、だからこそ、音楽は人々にブレーキの踏み方を教える。
ちょっと待ちなさいよ、と。
それ本当にそうなの、と。
もっとたいせつなことってほかにあるんじゃないの、「真実」から切り落とされた「何か」のほうが、本当はだいじなんじゃないの、と。
人類は踏み留まった。情報は光の速度で押しよせるが、立ち止まらないことにはそれらを処理し、検討するだけの余裕はないのだと、いつも時間差で遅れてやってくる音楽は気づかせてくれる。我々人間にはそもそも瞬時に物事を正しく判断できる処理能力など備わってはいないのだと、思いださせてくれる。
人類が三度目に音楽に救われたのは、それから数十年後のことだ。
人類がかつて、この星にやってきた宇宙からの支配者を手こずらせていた時期、この星にはすでに王者たる種族が繁栄していた。
奇しくも、人類が宇宙からの支配者へと対抗するために編みだした音楽が、その王者たちをこの星の奥底へと追いやっていた。
地底人はいる。
その存在自体は非公式であれ、一部の政府関係者のあいだでは自明のこととして知られてきた。
地上に音楽があるかぎり、この星の王者は人類に直接に干渉することができない。ときおり活火山や活断層へと圧力をかけ、自然災害を引き起こし、人類発展の邪魔をすることもあったが、困難を打破するたびに人類はかえって進歩した。
だが進歩したのはこの星の王者たちも同様だ。
やがて彼ら地底人は音楽への耐性を身に着けた。それを発明したと言い換えてもよい。
人類が宇宙へ飛びだすときに身にまとう服と似た形状のスーツを以って、地上へといざ侵攻しようとしていた。
そのときである。
地上に、これまでになかった【波形】が突如として現れた。
それは地底人たちのスーツを物ともせずに、光の網の目を通して世界中で鳴り響いた。
ちいさな端末から漏れ聴こえるその【波形】はけれど、それでも地下数キロさきにまで、宇宙線や素粒子がごとく透過性の高さで、浸透し、響き渡った。
地底人たちは地層よりうえにでることができなかった。新たな【波形】が巨大なバリアとして機能した。地上に迫った軍勢はふたたび地下深くへの帰還を余儀なくされた。
この星の王者はそのときハッキリとその冠を脱ぎ捨て、ただの地底人として人類の足元に下ったのである。
人類がその事態に気づいていれば、或いは救いの手を差し伸べたかもしれない。共存の道を示せたかもしれない。
だが、その侵攻と撤退はひっそりと行われ、そして人知れず収束した。
人類を救ったその【波形】は、奇しくも衝撃感度の高い爆薬、ニトログリセリンの名を持ったバンドの曲だった。
音楽はこれまで三度、人類を救った。
そしてきょうもどこかで誰かを救いつづける。
【永久に失恋】
マネージャーほど愛の報われない職業はない。
一生片想いの気持ちを味わうこととなる。
この仕事に就いてからもう十二年が経つが、やはりつづければつづけるほどに底の割れた樽に水をそそいでいる気分になる。
アーティストの才能に惚れ、契約を結ぶ。マネージャーの仕事の一つだ。会社から、このバンドを担当してくれ、と命じられることもあるが、基本はじぶんの惚れた才能を世に放ち、その真価を問うのが大枠の仕事だと考えている。
それに付属するように、仕事をとってきたり、広報を打ったり、ライブの予定や、リリースする新曲の計画を立てたりする。
最初こそこちらの熱意を素直に受け取ってくれるアーティストたちだが、やがてそれも通じなくなる。なにせこちらは仕事なのだ。才能を認め、ときには厳しい意見を言ったりもする。彼ら彼女らの才能に惚れているからこその忌憚のなさだが、こちらの心情を胸から取りだして見せるわけにもいかない。
アーティストたちからすればこちらのそれは、量産型のトロフィーのようなものなのだろう。金で買えるトロフィーよりも、曲を聴き、描いてくれた子どもたちの絵のほうがよほど音楽をつづける原動力となる。
お金をもらえなくたって応援はする。仕事じゃなくたって好きだからこそ、仕事を通じてより直接的に応援したいのだ。
だがそれを理解してもらおうとは思わない。
どれほど情熱をこめてみせたところで、否、情熱をこめ、真摯に向きあえば向きあうほど、お互いのあいだに開いた溝は深くなる。
だがこんなのはまだいい。我慢する必要すらない贅沢な悩みだ。すくなくとも新曲を聴ければどんな不満も帳消しになる。
誤解を招く言い方になるが、惚れているのは彼ら彼女らの才能であり、斟酌せずに言えば音楽だ。
仮に、彼ら彼女らが音楽をつくらなくなれば、応援する意味合いもなくなる。それでも彼ら彼女らの音楽だからこそもっと聴きたいと思っている。
そこは譲れない、譲りたくのない一線だ。
才能たちは繊細だ。衆目のなかで堂々たる演奏を披露しながら、そのじつ私生活のささいな出来事で容易に心に傷を負う。
マネージャーとしては繊細な彼ら彼女らのために絶対に口にはしないと決めている言葉がある。
解散だ。
言葉には呪力がある。どんな文脈であろうとそれを彼ら彼女らのまえで口にすることだけは絶対に避けねばならないと考えている。
それだけバンドというものはつねにその危機にさらされていると言ってもいい。
マネージャーはバンドのメンバーではない。仲間ではない。同士ではない。飽くまでサポーターでしかない。
ときには、あなたも私たちのメンバーだ、と言ってくれるバンドもある。うれしい言葉だし、そう思いたくもあるが、実際問題としてメンバーにはなれない。
音楽は、彼ら彼女らの手のうちから生みだされるものであり、この手からではないのだ。
いっぽうでは、メンバー以外では誰よりそばでバンドを見守っている。だからこそ判る機微がある。
メンバーのあいだに走っている微妙な亀裂が目に映る。それはどのバンドにも共通してある模様のようなものだ。あって当然だし、それをすぐさま危機として見做したりはしない。
個性の塊たちが理想を追い求め、互いにぶつかりあうからこそ、バンドはあれほど大勢を魅了し、一人一人の心に届き、揺さぶる音色を響かせる。
ヒビが入って当然だ。それは音楽家として、バンドとして、彼ら彼女らがその命を燃やして曲を奏でている証だからだ。
だからこそ、彼ら彼女らの人間関係にまで踏み込むことができない。ヒビを修正しようとすることそのものが彼ら彼女らへの冒涜に思えるからだ。
彼ら彼女らの才能に、音楽に惚れた者として、できればより長く、そばで、たくさんの演奏を、新曲を聴いていたい。
だがなにより、彼ら彼女らの邪魔はしたくない。
その結果にバンドが解散となろうと、それはそれで受け入れるしかない道だ。こちらはしょせんいちファンでしかない。すこし応援上手な、音楽バカでしかないのだから。
愛は報われない。どれほどそそいでも彼ら彼女らの胸には響かない。そうした星のもとに下った代わりに、誰よりそばで彼ら彼女らの音楽を聴き、その誕生を目の当たりにし、応援しつづけていられる。
等価交換だ。
こちらの愛は報われないが、それでも日々、報われている。
愛などいくらでもくれてやる。
端から枯渇するようなものではないのだから。
いま、目のまえで花を咲かせようとしているバンドがある。
人々はまだそこにある才能に気づいていない。
そう遠くない日、人々は知ることとなるだろう。
その日が巡ってくればこちらは、恋人をとられたようないっそうの寂しさを胸に、片想いしつづけてきた日々の至福をそれでも深く噛みしめるだろう。
【一気呵成に加勢を】
ぼくの名前は世界一長い、それはそれはとても長くていちども口にできたことはないのだけれど、それはだって未だに父はぼくの名前をつけつづけていて、実際のところぼくは無名なのかもしれず、或いは生まれてすらいないのかもしれない、というのも出生届の受理期間はとっくに過ぎてしまっているから、本当にいったいいつになったらぼくの名前は落ち着くのかと、一向に口を閉ざす気配のない父の底なしの肺活量には舌を巻くばかりだが、父はきっと優に数万回は舌を噛んでいるに相違なく、一説によれば父はすでに円周率を三周ほど唱え終えているらしくて、つまり円周率は循環する無限であって、もちろんじっさいには循環しないのだけれど、ある意味では有限の組み合わせの羅列からなっているとも考えられる、それは見方を変えれば、ぼくは生まれていないがゆえに死ぬこともなく、だからこそこうして無限にも思える長い長い、父の「我が子の名づけの儀式」の終焉を待ちわびていられるのかもしれない、もっと言えば父の口にする言葉の組み合わせはそれこそ円周率なみに膨大であり、無限に循環しつづけているものだから、そのなかにはもちろんいまこうしてぼくが思い浮かべているこの思念にも似た文章の羅列だって含まれており、言い換えればぼくはいまじぶんの名前を口にしているとも呼べ、そう自覚した瞬間にぼくはぼくとしての輪郭の一部を得、すくなくとも存在の一端をなすことで、父がぼくの名を唱え終えずとも誕生でき、ゆえに途中で幾度も死したとしても、こうしてふたたび生まれ落ちる余地にくるまれており、こうしてまたじぶんの思念にて再誕の繰り返しを連綿と、営々と、いつかは訪れるだろう父の死までつづけていくのだろう、或いは父の口さえ塞いでしまえば、ようやくぼくは安定してこの世に生を享けるのかもしれず、そうではないのかもしれない、思えばぼくは未だに父の名を知らず、母の名も、その姿すら目にした覚えがなく、それはそのはずで父はぼくの名を唱えるのにいそがしく、ぼくがぼくとして存在していられるのはこうして独白を思い浮かべているあいだだけなので(つまりじぶんの名の一端を唱えているあいだだけなので)、ひとたび欠伸をして、眠くなって、或いは目のまえを通り過ぎる一匹のハエに目を留めるだけでも、もう、ぼくはぼくとしての輪郭を保てずに、死ぬことすらなく、眠ることもなく、ふたたび父の唱える輪っかのなかを巡りながら、再誕のときを、春夏秋冬、四季のごとくぐるっと一周するまで待ちわびることもできずに、いったいこれが何度目の誕生であるかも曖昧なままで、いつまでもいつまでも思念を巡らせていたいと、頭の底から、どうにかこうにか、途切れずに済むように祈るほかにできることはなにもないのだろうか、せめてあとすこし、あとすこしでもぼくに言葉を、ねえ、ああ、どうしたらよいのかな、もう何も思い浮かばないよ
【青いバナナ】
バナナの皮を剥くと青が現れた。果実が未熟な状態を青いと形容することもあるがいま目のまえにあるバナナはそうではなく、青空とか青いブドウとかの青で、まさにブルーといった塩梅だ。なぜにかように毒々しいのかと皮だけでなく目まで剥く。
品種改良で元から青いバナナを買ってしまったのかと案じ、念のため房からもう一本バナナをもいで剥いてみるも、中身はちゃんと白く美味そうなバナナだった。
一本だけが青く、ただ青く、青い。
これはあれだろうか。バナナは酸化すると黒くなる。それといっしょの現象だろうか。
臭くはない。ちろっと舌先で舐めてみるも、これまた味という味はしなかった。
齧ってみるか。
試しに前歯でこそぎとるようにひと齧りしてみると、これがまたなんとも言えぬ食感で、バナナらしさのかけらもなく、サクサクもちもちガリガリぐにぐにと、歯ごたえが七色に、いいや、咀嚼すればするほどに増えていく。
なんだこれは。
呑みこみたい衝動が募るたびに、まだだ、もっともっと味わいたいとする、より強烈な衝動に押し流され、けっきょくいつまでも経っても下あごを上下に動かしつづけている。
ふしぎなのは、噛めば噛むほど満腹感が増していくことだ。身体まで元気になっていく感覚がある。
半日口のなかで青いバナナの欠片を噛みつづけ、さらにつぎの日、そのつぎの日、と噛みつづけているとようやくというべきか、この青いバナナの目を瞠る効力を発見した。
喉が乾かず、お腹が減らない。
のみならず身体は疲れず、眠らずに済むようになった。
身体が軽い。
思考が巡る。
まるで魔法の薬でも口にしたみたいだ。
そこで、はっとする。
麻薬だったらどうしよう。
ひょっとしたら、と考える。どこぞの麻薬カルテルが麻薬を密輸するためにバナナやほかの果物に麻薬を注入して、果物そのものを麻薬にしてしまおうと企てたのではないか。これで麻薬犬を誤魔化せるとは思わないが、或いは純粋なバナナに囲まれてしまえば、そのうちの数本が麻薬まみれであっても、濃厚なバナナの香りに紛れて犬の鼻を欺けるのかもしれない。もっと言えば、バナナの皮には外部に内部の香りを漏らさぬようにする効能があるのかも分からない。
いずれにせよ、これ以上、口の中に入れているのは危険だ。
意に反して、吐きだそうと思えば思うほどに、あとからあとから唾液がでてきて止まらない。
もったいない。
いやだ。
こんな美味しい物を吐きだすなんて。
身体が言うことを聞いてくれない。
鏡のまえに立つ。すでに青いバナナを咀嚼しつづけて四日目だ。その間、ほかの食べ物を口にしていない。仮にこれが麻薬漬けのバナナであったなら、じっさいには身体は極度の栄養不足に陥っているはずだ。死ぬ寸前に衰弱していておかしくない。
本当はげっそり痩せこけており、死神のような顔つきになっているかもしれないのだ。
おそるおそる鏡を覗きこむと、そこにはなんとも健康的な顔つきの男がいた。毛色がよく、肌のハリもよい。若返ってすら映る。
無精ひげが生えていてもよさそうなものを、つるつるで、なんとなく美青年にすら見えてくる。
なんてことだ。
やはり青いバナナは麻薬漬けの果物だったに違いない。こうしてありもしない理想のじぶんの姿が見えてしまうなんて、幻覚が見えるなんて、まさしく麻薬である傍証ではないか。
恐怖した。
こんなに美味しいのに。美味しいがゆえに手放せなくなっている己が狂気の元凶が、この美味しいをもたらす口のなかの無数に変幻する食感物にあると思えば思うほどに、これはそれほどに人間の意思決定を狂わせ、支配するほどのヤバいの結晶なのだと理解するのに躊躇はない。
吐きだせ、吐きだすのだ。
残りの青いバナナを手に取り、それはのきなみ九割九分残っているわけだが、皮を剥き、口いっぱいに頬張る。
捨てろ、葬れ。
そうして手放そう手放そうと念じるたびに、意思とは裏腹に手足は青いバナナを貪るのだどこまでも、と命じる内なる衝動が勢力を増す。
あっという間に口のなかは青いバナナの甘美な至福、美味しい、美味しい、が全身に波及する。見えない鱗が逆立つようだ。
脳髄のヒダヒダの一つ一つが隆起し、内側から、しゅわわせ~、の合唱を轟かせる。いくども波打ち、打ち寄せる歓喜のキンキンお祭り騒ぎは、その後も衰えることなく、一口、二口、と顎をしきりに上下させるたびに自我と世界の垣根を打ち破り、溶けだしていく意識の消散を予感させる。
眠っているのか起きているのかも曖昧なままに、日差しのぬるさを覚え、次点で床の硬さを背中に感じ、気づかぬあいだに仰臥していると気づくに至る。
口の中が乾いている。
水が飲みたい。
倦怠感があるが、身体は妙に軽かった。眩暈がし、何やら部屋が大きく感じられる。不思議の国にでも迷い込んだみたいだ。あれと似た名前の病気がたしかあったな。
思いだしながら、蛇口から水を足らし、口へとじかに流しこむ。勢いよく喉を鳴らしながら、ようやくというべきか青いバナナの存在を思いだす。
口の中にはない。
呑みこんでしまったのだろう。食べてしまったのだろう。やはりあれは麻薬の染みこんだバナナだったのだ。
金輪際あんなものを口にするのはやめよう。
念のために残ったバナナの皮を匿名で警察に送りつけてもよい。あんなものが市場に出回ることがよいわけがないのだ。
顔を洗いに洗面所に向かい、ついでにシャワーを浴びようと思い裸になりながら何気なく鏡に目を向けて、息を呑む。
鏡の向こうには見知らぬ女がおり、戸惑いがちに自身の顔に、そして胸に、手をやった。手のひらに伝わる在るはずのないやわらかな弾力と、そしてさらにその下、股間のあたりからは、あるはずのぶらぶらが消えている。
【背景、あのころのわたしへ】
あなたはたぶんこう思ってる、どうして世界はこんなに広くてキラキラしているのにわたしの進む道はこんなに薄汚いのだろうって、色褪せているのはじぶん以外のせいだと信じて疑わないあなたはでも、そこに色を足して、じぶんの手で彩ろうとはしないよね。
あなたはあるとき気づく、この世界はべつに最初からきらきらしているわけではないんだって、そういうふうに世界を視たひとがいて、たくさんの装飾できらびやかに装い、皮一枚めくった裏側には、相も変わらずに灰色よりもずっと薄汚い世界が広がっているんだって、それを知ったところでどうすることもできずに、あなたはほかのひとたちが懸命に塗りあげた絵画の世界を眺めてる。
ある日、あなたは誰もが経験するような最初で最後の傷を負う、それは赤子が初めて大気に身体を晒して、大泣きするのに似た天変地異で、あなたはもう立ち直れないし、これはもう死ぬしかない、生きてはいかれない、と大真面目に思いこむ。でも何日経ってもあなたは死ねないし、お腹が減ると台所に立って、何かないかな、と冷蔵庫を漁ったりする。
そういう現実とあたまのなかの天変地異が吊りあわなくて、しっちゃかめっちゃかになって、また荒れる。
あなたはまるで大きな赤ちゃんで、お腹が空いて泣いたその声に驚いてさらに泣く。
永久機関に思えるそれも、いつの間にか日常にあいたちょっとした隙間へと落ちて、消える。
あなたはあなたの意思とは関係なく身体が大きくなる。むかしの服は着れなくなり、かつてはこの世の終わりとしか思えなかったあの傷と似たような傷をいくつも重ねるようになる。
よくわからないうちに、じぶんからその傷を求めている気すらしてくる。たぶんそうだ。あのときの天変地異くらいの傷を受けるくらいの刺激をあなたはいま、求めてる。
でも、きっとそんな傷はもう二度と負えないだろうと予感しているし、よくよく考えてみると、どうしてあんな傷程度で死んでしまうと思ってしまったのかすら、いまからするとすこしふしぎだ。
あなたはもうあなたではなく、わたしだ。
そしてきっとすぐに追い越して、わたしをあなたと呼び捨てにし、すこし背伸びをした先輩気分で、なにかそう、すこしだけさきを歩いてみてもいいかな、と思うような、それともうんざりしちゃう言葉を、一言二言、それともこれくらい長い言葉で書いてくれる。
あなたは世界にほんのりと色を足す。
余計なおせっかい、とわたしは言う。
あなたはきっとほくそ笑む。わたしがいまそうしているように、何かを得た気がして、終えた気がして、肩の荷が下りた気がして、ほんのすこしばかりの淋しさを覚えながら。
【背景、あのころのぼくへ】
あなたはきっと、じぶんにとっての悩みが誰かにとっての些事である事実に堪えられませんし、誰かにとっての悩みがじぶんにとってとるに足りない日常や過去の追体験でしかなかったら、きっと相手を傷つけてしまうと考えて、どうあっても悩みなんてひとに相談するものではないし、されるものでもない、しないほうがよいことだ、と結論付けて、狭く、ちいさな枠の中に閉じこもるのでしょう。
でも、そうした、しないほうがよいことですら、あなたとならしあいたいと思える相手と出会えたなら、それはすばらしいことだと思いますし、得難いことだと思います。
縁や繋がりなんてないほうが好ましいとぼくですらそう思います。
でも、そうした、ないほうがよいものですら結んでおきたいと望める相手となら、出会いたいし、出会ってよかったと思えるようになるような気がいたします。反面、そんな奇跡はめったに起きるようなものではない現実は存じておりますし、そらからぽっと降って湧いてくるようなものでもありませんから、あなたの考えるように、妄想で満足しておくのが利口な生き方というものなのかもしれません。
追伸。
縁や繋がりは育むもので、ぽんと最初からできあがっているわけではない、手錠や鎖とは違うんですよ、ときっとあなたならおっしゃるでしょうね。希望を捨て切れないところがかわいらしくも思います。でも、そんなたいそうな芽を愛であう余裕がぼくにはないことだって、きっとあなたならご存知のはずです。失望するのはつらいです。でも、踏ん切りをつけ、断ち切り、割り切る分には必要な過程なのかもしれませんね。失望は、されるよりもするほうがずっと楽です。
【背景、あのころの私へ】
その道を行くことにいっさいの迷いがなかったころが嘘のようにいまは目に映る影という影が私の悩みの権化であるかのような日々です。つまり、ものすごくたくさんぐにゃぐにゃと悩みに押しつぶされそうな毎日ということです。
押しつぶされる、ではなく、押しつぶされそう、が肝だと思います。
一貫性のあることが好きで、何かを貫くことを美点と思っていた私がまるで他人のようで、つまりこれを読んでいるあなたが他人にしか思えないくらいに、私にはもう、あなたにあった美意識や感性がなくなってしまった、との懺悔とも告白ともつかぬ、そんなおたよりになる予定です。ほとんど愚痴ですね。あなたがうらやましいというひがみと、それとも、こんな私で申しわけないとの謝罪がごちゃまぜな気分です。
きっとあなたはこんな私を許せないでしょう。いいえ、そもそもこんなおたよりを送られてもそれが私からの言葉だなんて信じる以前に、素直に受け止めることすら、読むことすらしないように思います。
でもいちおう、書いておきますね。
私はあなたが夢見ていた道をそうそうに脱線してしまって、飛び降りてしまって、あなたが思うほどにはまったくこれっぽっちもつよい人間ではなかった現実にうちのめされています。それはもうずいぶんむかしのこと、あなたにとってはもうすこし先のことになりますが、私は夢を諦めることすらせずに、ずっとこのさきも一生つづけていくだろうと思う道に背を向け、いいえ、どんな道から飛び降りたのかすら振り返るのがおそろしく、嫌すぎて、道を見ずにすむようにと、洞穴に飛びこんで、そのなかで膝を抱えてずっとうずくまっています。
ありていな表現で申しわけないのですが、私は夢に破れました。
いいえ、夢を、破りました。
破れたはずのその夢を捨て去れればよいものを、その破れた夢すらなにかしら誇らしく、みみっちい人生を着飾る何かしらの光になるのではないかと、後生大事に抱えて手放そうとしません。できないのです。
あなたならきっと、そんなものはさっさと捨ててつぎの光を掴むべくがむしゃらにまえに進め、じぶんの道はじぶんで切り拓くものだ、といったことを、もうすこし文学的な表現でおもしろおかしく、ときにかっこうのよろしい文面でしたためそうですね。
私にはもうそうした体裁を取り繕おうとする気概すらありません。
なんて書きながら、どうしたらあなたに失望されずに済むだろうかと、無意識のうちから言葉を取捨選択しているじぶんに気づき、ますます自己嫌悪に陥ります。
いまここに、あなたはいません。そして遠からず、あなたも私になる日がくるのでしょう。ですが、私からのこのたよりを読むことでなにかしらの変化が訪れるのであるとすれば、それはそうあってほしい変化だと思っています。
残念ながら私のもとにたよりは届かず、いまこうして書いている言葉に既視感はなく、それともどこかで見たことのあるような、どこにでも有り触れた文面でしかなく見えます。
私に限らずみな似たような悩みに押しつぶされそうになっているのだと言われればそうなのでしょう。
ただ、あなただけは違った、そのことだけは知っています。
そのことだけを私だけが知っています。
あなたはたしかにいまそのとき、私ではありませんでした。そして私と、これを目にしたあなたもきっと違う私になるのでしょう。未来は変えられるとか、じぶんの道はじぶんで選べるとか、そういった殊勝なメッセージをこめてはぜんぜんないです。
きっとあなたは私と同じように夢が破れ、そしてその破れた夢を後生大事に、何らかの証のように、いつまでも手放さずにいつづけるでしょう。洞穴のなかでじっとしているだけの人生が待っているだけかもしれません。
でも、ここがきょういちばんだいじな部分なのですが、ここも、この場所も、洞穴のなかも、それほどわるくはないですよ、ということを私はあなたにいまのうちから伝えておきたいです。伝えておきたかっただけなのかもしれないな、といまそう思いました。
どうせここに行き着くのだから、遠慮なく、夢を破ってほしいと願っています。それは、当たって砕けろ、とはぜんぜん違くて。破れてもけっきょく夢は夢でありつづけ、あなたをあなたと位置付ける、灯す、光の役割を果たすのだと、それは私にとってそう見えるというだけの幻影かもしれませんが、でも、夢ってそもそもそういうものではないですか?
私にはいま、両手では抱えきれないくらいの、運びきれないくらいの、飾りきれないくらいの破れた夢があります。破れた夢しかありません。きっとこのさきも破りつづけていくのでしょう。
そしてそのなかで偶然、なかなか破れない夢に行きあたることもあるかもしれません。
そうなることを半ば祈りながら、いまからわくわくして待っています。
あなたの破った夢の唯一無二のそのカタチを、いつか私が目にするときを、わくわくしながら待っていますね。
【背景、あのころのおれへ】
文章慣れてねんで音声入力でやらせてもらうけど、なんかいきなしタイトルで誤字のおしらせ光ってんだけど、背景って、拝啓じゃねえの? いいの?
ほかのひとらのもそのままんなってるっぽいんでそのままにしとくけど、あのさ、おれさ、むかしのじぶんに謝りたいってか、なんであんとき我慢しちゃったんだよってさ、いまんなって後悔してんの。
やらない後悔よりやる後悔ってあんじゃんああいうの、あれマジでホントでさ、すこしのあいだはいいんだ、なんか我慢してんのが偉い気がしてきてさ、でもさ、ある時期から急に、なんであんとき我慢しちゃったんだろうって、めちゃくちゃ考えるようになってさ、だんだんその数が増えてって、さいきんじゃあもう、気づくと、殺す、とか口走ってんの。
誰にとかじゃなくて。
つうかじぶんに。
要はおめぇを殺したくってさ。もうぶっころしてやろうかと思うくらいに、ときどきあのとき我慢しちゃったおれ自身、要するにおまえをどうにかしたくなっちまってさ、でもどうしようもねえじゃん。
おまえはおまえでそこでなんだかんだもがいてんだろうし、おれだってこっちはこっちでいまそれどころじゃねえってのもあっしよ。
そう、だから謝りたいってのはおれがおまえのころにそれを我慢しちゃったってことじゃなくってさ、ずっとあとになっていまになってどうしてやらなかったんだろうって後悔するたびに、一生懸命に、本当にがんばって我慢してるおまえのことをぶっころしたくて、ぶっころしたくて堪らなくなるってことがさ、どうしても謝りたいってかさ、じゃあ、んなこと思うなって話なんだけどそれができたらこんなんやってねぇじゃん、おまえにこれを送らねえじゃん。
強要はしねえし、おまえの選択も否定はしねえ、ぶっころしたくはなるけど、んなことしたらおれだって死んじまうわけじゃん?
好きにしろよ、でも、どっち選んでも後悔するってことだけは憶えといてくれよな。
罰ゲームみてぇなもんだよな、どっち食ってもカラシ入りシュークリームじゃんこんなもん、んなの詐欺だっつってやっぱし腹立つよな、現実ってやろうにさ。
でもさ、だからこそ、まあ、好きにしたっていいぞって、我慢したけりゃすればいいし、したくなきゃ我慢なんかしなくていいってな、まあ、たぶん、どっちにしろ似たような手紙が届くんだろうけどさ、すくなくともおまえは我慢すんだよ、そっちを選ぶんだよ、そういうやつなんだって、だからなんかこうな、謝りたくなっちゃうんだよな。
ごめんな。
さっきの嘘だわ。
ぶっころしたいのはおまえじゃなくて、そんなおまえを否定したがるいまのじぶんのことなんだわ。
好きに生きろよ。
我慢してもしなくとも、そのあとはんなこた忘れて、好きに生きろ。
おれの代わりに、いまのおれを消してくれ。
ぶっころしてくれ。
きもちよくな。
【背景、あのころのあたしへ】
きみは驚くと思うよ、なんたって未来のあたしから手紙が届くってんだから、そりゃあね、あたしならきっと飛んでよろこぶと思うな。
あたしにはなんでかそんな記憶は残っていないし、いまこれを書いてる段階だから、まだきみのところに届いていないだけ、言い換えればあたしにはその記憶が根付いていないだけのことなのかもしれないけれど、いまからきみへ向けて言葉を贈ることにする。
いちおう、文章にうるさいきみのことだから題名の誤字について説明しておこう。拝啓じゃないのって、きみはすでに手紙を持ってゴミ箱のまえに移動しているかもしれない。
でも待ってくれ。
早合点がきみのゆいいつの欠点だ。
拝啓ではなく、背景、で構わないのだそうだ。
ほかにもいろいろと手紙をだしているひとたちがいて、あ、もちろん過去のじぶんにって意味だけれど、いまのあたしが眺めている景色、あたしを包みこむ世界、それでいてあたしの背後に広がっている奥行き、そういったものこそが過去のあたしそのものであり、同時にきみ自身であるって意味合いがあるんだと、あたしは睨んでいるよ。
それとも過去は過去にすぎないって皮肉かな。
きみはどう思う?
よかったら日記にそのことを書いておいてくれ。それがこちらの世界に、未来に、引き継がれるかは知らないけれどね。
そろそろあたし自身のことが気になりだしはじめた頃合いではないかな。
あたしはきみの思い描いているいくつかの将来像へとつづく道の一つを、まあそれなりに順調にっていうと語弊があるけれど、いくつかの小石に躓きながら、それでも尻もちをつかずになんとか歩きつづけている最中かな。
ここで何かしらの警句を鳴らしてあげるのも手かもしれないけれど、どちらかと言えばきみにはもっと苦労をしてほしいと望んでいる。
説教臭いのは嫌だとあたしだって思っていたし、いまこうして文字を打っていてもやっぱり嫌だなって感じる。それはそれとして、苦労って案外に余裕があるうちに、失敗が許されるうちに、リカバリーがきくうちにしておくのが吉だなと、いまになって思うから。
順調すぎるとつまらないよねそうそう、とかきみはお門違いな方向に解釈しそうだから注釈を挿しておくけれど、そういう意味ではないからね。流れは順調なほうがよいと思う。できるかぎり、人生はね。
ただ、すこしだけ、苦労を苦労だと思えるうちに解決法のいくつかを学習しておきたかったなって。
あたしがいま何歳かをここで明かすのかはフェアじゃない気がするから黙っておくけれど、この歳にもなると、苦労を避けようと思えばいくらでも避けてしまえるから。楽しみ方の一つを失ってしまったようで哀しくすら感じる。
かといって率先して請け負うほどには、苦労ってやつは気安いやつではないからねぇ。
とっつきにくいにもほどがある。
そう、まさにきみみたい。
じぶんへの対処法を学びたい、と言えば端的かもしれないし、いまごろきみからの非難が轟々かもしれない。その公算が高そうだ。
正直言うと、そんなに言いたいことも、伝えたいこともないんだ。きみのことだからあたしから何を言われたところで、反発心しか覚えないだろうし、かといってその程度の斥力で行動の指針が揺らいだり、欠けたりはしないだろうね。
いちいちカチンとくる書き方をしているのは信頼の証だと思ってほしいです。
きみとあたしは違う。
確信しているし、言ったところで何が変わるわけでもないけれど敢えて言っておくよ。
きみはいつまでもきみのままだ。
あたしとは違う。
だからそう、いまきみが何を思っているのかすら、あたしにはもうまったく予想がつかない。そういうのって愉快だろ。
だってそうじゃないか。
予想がつくことじゃあ、挑戦とは言わないからね。
【背景、あのころの僕へ】
じぶんが死ぬときの場面を想像して、日々をだいじに過ごそうときみは、たびたびの決意を固める。
なのにどうして、じぶんが取り返しのつかない真似をしでかしてしまう未来については想像を働かせなかったのかな。
誰かを困らせたり、傷つけたり、じぶんよりも立場の弱いひとたちを虐げたり、そういう真似を許せないきみが、どうしてじぶんが誰かを困らせ、傷つけ、虐げる側に回ってしまう可能性に思い至らなかったのかが、いまからするとふしぎでならない。
きみは気づいていないが、相当な差別を日常的に、無意識から行っているし、傷つけてもだいじょうぶなひとと、そうでないひとを、相手の言動から見ぬいて、識別し、じぶんの態度をつど変えたりしている。
それはちょうど、父親にはいいこを演じて、母親には厳しく当たり散らす内弁慶みたいに、それとも人気者にはいいこを演じて、いじめられっこに対しては不快な気持ちを隠そうともしない思春期の子どもみたいに、きみはじぶんで思っているよりもずっと幼くて、我がままで、衝動的で、自己矛盾を一つと言わずして大量に抱え込んでいる。
そのことを自覚できない程度の知性しかなかった点も、ざんねんに思う。
きみはある日、取り返しのつかない真似をしでかしてしまう。そのことで長い期間、ずっと謝罪の言葉をしたためるようになる。許されたいとは思わないが、許されないことをしてしまったのだ、と反省している気持ちを相手に知ってもらおうと必死になる。
しかしその自分よがりな手紙のせいで、やはりきみはさらに他人を傷つけつづけ、ずっとあとになってから、善意が裏目にでていることを知る。
どこまでもきみは、僕は、自分本位で、性根が腐っている。せめてそのことに罪悪感の一つでも覚えていられたらよかったのに、きみときたら何も知らずに、知ろうともせずに、じぶんは人一倍繊細で、でもやさしいのだと思いこんで、毎日のように誰かを傷つけつづけている。
僕はみんなみたいに暢気ではないから過去は変えられないと考えている。よしんば変えられたとしても、いまの僕が救われるわけではないんだろうと、その可能性が高そうだと考えているから、こうして手紙をきみにだしたところであまり意味のある行為だとは思っていない。
これもただ、過去のじぶんを、きみを、傷つけてしまうだけのひとりよがりな善意に思えてしまって、だからきっと僕はいま自棄になっているだけなのだろう。
きみは何を選んでも失敗するし、何をどうしようと他人を傷つけつづける。まるで呪いの言葉のようだな、とじぶんで書いていて辟易してくるが、どうせ誰かをこっぴどく傷つけるならじぶんにしておきたいとの打算がないとも言いきれない。
好きに生きろ、なんて僕は口が裂けても言えない。言いたくもない。
というのも、参考にほかのひとたちの手紙を読ませてもらったのだが、本当に、なんで僕だけなんだろう、と笑えてきたくらいに、みなの過去が、いまが、未来が、輝いて見えた。
ここに具体的にきみがしでかしてしまう取り返しのつかないことを書いてみせてもよいし、僕がこれまで相手に送りつづけてきた謝罪の手紙を代わりに添付してもよかった。
だが、そんなことをしてどうなるというのだろう。
それできみの行動が、きみの無自覚の差別心が、傲慢さが消えるとは思えない。
試してみないと判らないだろ、ときみなら思うだろう。そういう浅はかな想像力しかないからこうなるんだ、とだけ言っておくことにする。
きみはダメな人間だ。
そして、人生に絶望しながらも、死ぬこともできない。
心のどこかで、じぶんはじぶんで、他人は他人だ、と思っているからだ。いっそ死刑判決を否応なく出してもらえるくらいの犯罪でもしでかせばよかった、とときどき考えるくらいに、性根が腐っている。いつでも他人に責任転嫁をし、八つ当たりをする機会を窺っている。
きみは変われない。
ずっとそのままだし、その報いを受ける。因果応報だ。
いま書いていて気づいたが、おそらく僕はやっぱりきみを心底傷つけてやりたいんだろう。自傷することでしかもう、どうすれば許されるのか、贖罪を担えるのかが判らないから。
いまのじぶんをこれ以上痛めつけるのは怖いから、だから何も知らない無邪気なきみを傷つけてやりたい。
申しわけないとはすこしは思うが、でも、しょうがないだろ。
きみのせいで僕はこんなにもいま、つらいのだから。
生きていることが、こんなにも。
【背景、あのころのワタシへ】
アナタにしないでほしいことがたくさんありすぎて、もうほとんどアナタには何もして欲しくないと怒鳴ってしまいそうで、こうしてワタシから何かを伝えようとしても、アナタにとっては脅迫電話と同じになってしまう気がして、けっきょくこれで三度目の書き直しになってる。
占いみたいに書いてるひともいて、ああそっか、まあ占いみたいなものだよね、と思ったら踏ん切りがついたので、アナタの未来を知る魔法使いの気分で、アナタの運勢を占ってあげる。
アナタは大学に進むか、やりたいことをするかで、親と揉める。大学にいってもできるだろう、と正論を吐かれるが、大学に入ったことがないので両立できるのかもよくわからない。友人たちに相談するがそこでもやっぱり小馬鹿にされる。もちろん表向きは誰もが応援するフリをしてくれるけど、明らかに成功なんてしっこない、どっかで挫けて、お先真っ暗な人生だよ、と脅してくる。
ここまで書いてぞっとしたけど、まるでいまのワタシみたいだ。
ホントはアナタに、アナタの進む道は間違っていた、とねちねち書き連ねてやろうと思ってたけど、なんだかムカついてきたのでやめておく。
がんばれ過去のワタシ。
めっちゃがんばれ。
いまのワタシはアナタを否定しない。
いいよ、やっちゃえよ。
いけるとこまでいってやれ。
ワタシはアナタをそんなに好きじゃなかったけど、それはたぶん間違いで、ワタシはワタシが嫌いなだけだった。
いま振り返ってみれば、もっとうまくやれたと思うし、そしたらいまごろは毎日もっといいものを食べていられた。
家賃の心配なんかしない日々を送れたし、税金や健康保険や年金、その他公共料金の督促状に怯えずに済む。お察しの通り、ワタシはいま貧乏だ。それもつぎに身体を壊したら、それこそ風邪や虫歯のレベルですら、罹ったら即座にいまの暮らしを手放すしかないくらいに極貧だ。
寝る場所があって、いちおう毎日食うのに困っていないのだから、もっと貧乏なひとたちがいてそれよりかはずっと贅沢な暮らしなのは百も承知だけど、アナタの未来はこんなものだ。
恐れてほしい。
危機感を持て。
かといって、どうしたらよいだろう、と解らない気持ちもよく分かる。ワタシだっていまどうすればいいのかなんて解らないから、こうして過去のじぶんに、つまりアナタにこうして、そのままだと危ないよ、とお説教の一つでも投げかけてあげようかと思ってたんだけど、でもそうだよね、ブレーキをかけるんじゃなく、アクセルをかけてあげたほうがいいのかもと思い直した。
アナタはもっとがんばれるし、もっとがんばれ。
いまのままじゃダメになる。
こうしてアタシが証明してしまったから、これは揺るぎない事実だ。
こっちにゃくるな、と本当に思う。
まだ間に合う。
同じ道を進むことになっても、もっと突っ走っていけたはずだ。いろいろと積み重ねていけたはずだ。おまえはもっとやれる。
がんばれ。
めっちゃがんばれ。
身体を壊すのは、そう、怖いけど、じぶんのためならそれもいいじゃん。他人のためとか、仕事のために身体を壊すのはバカみたいだけど、アナタは端からそんなことはだってしないじゃん。
事故とか、事件とか、起こすほうになるのは勘弁だけど、そうじゃないならまあ、死んでもいいよ、ワタシが許す。
どうせこのままじゃ遠からずワタシは貧乏の坂を転がり落ちて、好きなこともできなくなって死んでいく。だったら好きなことを好きなだけして死んでいきたいよ。
なんて書いたらまるで、好きなことをしてこんかった人生みたいに聞こえるけど、好きなことしかしてこなかったからそこはやっぱり、がんばりというか、工夫というか、積み重ねるものの量が、それとも種類が、すくなかったのかな、とは思うのだ。
というか、そうだね、きっとアナタはいま怒っていて、怒鳴っていて、どうやったら返信できるのかと、未来のワタシに抗議できるのかと、手紙をつぶさに調べていそうだけど、ワタシもいまそう思う。
アナタじゃなくって、ワタシががんばればいいだけの話だなこれは。
がんばれワタシ、めっちゃがんばれ。
ちなみにアナタの時代では、こういう「がんばれじぶんがんばれ」みたいなセリフを言う主人公の登場する漫画がものすごく売れていたはず。ワタシも(つまりアナタも)好きで、読んでいた。
その後、その漫画の展開がどうなったかをここに書きたい衝動がある。いっしょに楽しみを分かち合いたい気持ちが募るけど、ただそういう、じぶん以外のこと、たとえば博打の結果とか政治の結果とか、災害がいつ起こるとか、そういう未来の時勢が分かってしまうことは具体的には書いたらよくないらしい。
てことは、やっぱり過去って変えられるのかな、とか邪推したくもなる。
変えられることもあるし、変えられないこともあるってことなのかな。どっちにしても、時間を無駄にせずにいこう。
アナタはやれるし、ワタシもやれる。
ワタシがんばるから、アナタもがんばれ。
ただし、寝るのだけは忘れずに。
【背景、あのころのボクへ】
いきなりだが喜んでほしい。キミの未来はバラ色だ。
というのも、何をしても誰も成し遂げたことのないことを達成してしまって、まさしく虹色よりも豊かな色彩を、バラの品種の数ほどに自在に、手中に収められる。
選びたい放題だ。
したがっていまキミが興味を抱いているモノの研究はしなくたって構わない。徒労に終わるだけだろうから、しないほうが賢い選択と言えるだろう。
キミが足繁く通っていた食堂はいまでもここにある。映画館も繁盛していて、街は人でごった返している。
キミが懸想している女の子とは、キミが諦めなければ恋仲となり、生涯を共に過ごすこともできる。二人のあいだの子供だって、キミは玉のように可愛がり、旅行に連れて行くたびに我が子の愛嬌を噛みしめる。
キミが応援していたアーティストたちは、キミの支援とは無関係に、大勢のファンを獲得するし、そういう意味ではキミの審美眼はなかなかのものだと言える。ひょっとしたら凡人ゆえに、誰もが魅了され得る表現にほかの大多数と同様に目が留まるだけなのかもしれない。
じぶんを高く評価するとすればおそらくキミは、ほかのひとたちよりもすこしだけ、点ではなく、流れで、変化を捉えられるのだろう。他人の変化や、環境の変化を、キミは水の流れのように目にすることができる。成功の秘訣はそこにあるとも言えるかもしれないし、ほかの因子が関係しているのかもしれない。
どうしてキミがほかのひとたちにできないことを成し遂げてしまえるのかは、よく解らない。偶然だとしか言いようがない。
これはあまり他人には言えない悩みだ。自慢みたいで、いけすかないだろ。でも、過去のじぶんになら許容範囲内だ。キミが不快になっていたらすまない。そんな狭量ではなかったと記憶している。キミはもっと寛大な人間だ、そうだろ?
ともかくキミの将来は安泰だ。何をしても成功する。いい思いしかしない。
ゆえに抗ウイルス薬の研究なんかしなくていい。
キミはすこし自信過剰なところがあるから、それを開発しなければいずれ人類が、社会が、じぶんの親しいひとたちがたいへんなことになる、と決めつけてかかっているだろうが、そんなことにはならない。未来は相も変わらずだし、キミが尽力せずとも、ほかの誰かが対抗策を生みだしてくれているんじゃないかな。
ちなみに、この手紙には、未来の社会がどんなふうになっているのかを書いてはいけない決まりになっている。ただし個人的なことに関しては書いてもいいみたいだ。
キミの人生はバラ色だ。
くれぐれも抗ウイルス薬の研究なんかにうつつを抜かさず、人生を楽しんでくれ。
キミも知ってのとおり、ウイルスの進化速度は、哺乳類のそれと比べて、数百万倍も速い(短時間で死滅と増殖を繰りかえすためだ。自然淘汰の速度が、劇的に速い)。私見だが、環境によっては数億倍にまで進化速度は増加するだろう。
蛇足だったが、なんにせよ、くれぐれもキミは、キミだけは、抗ウイルス薬の研究をせずに、遊んで暮らすんだ。いいね。
【背景、あのころのわたくしへ】
DNAの塩基配列が位置座標の役割を果たす。したがって問題は時空の壁を通過する際に、過去へ送る物体が崩壊しないかどうかが鍵となる。
立体構造を有した物体は向かない。一方向から高圧縮されても変形しない構造物だと望ましい。耐久性に優れた紙であれば、高い確率で時空の壁を透過し、そのままの形態を保持したまま過去へと送り届けることが可能だ。
君はそうして、君の時間軸上から四十年後に、時空転移装置を発明する。時空の壁はヘビのウロコのように方向性が限られている。現在から未来へのほうが滑らかで、現在から過去へは抵抗が高い。だが、どちらにしても物体を送るには、高エネルギィが不可欠だ。よって、ある程度の抵抗があるほうが、ブレーキがかかって、制御しやすい。
現在から未来へ物体を送れば、総じて、ススとなって消えるだろう。現在から過去であるほうが都合がよいという道理だ。
DNAさえあれば、過去のじぶん以外にも手紙を送ることができる。じぶんの祖先だけでなく、偉人にだって未来の技術を継承可能だ。
だが、しょうじきなところ、タイムパラドクスの検証は進んでいない。最悪の事態を想定して、歴史改変に大きく繋がるおそれのある事項は記述しない方向で、こちらでは規制がかかっている。
もちろん、一般にはまだ普及していない技術だ。検証のために幾人かのモデルを選出し、臨床実験を行っている段階で、いまのところ過去に手紙を送っても、こちらの歴史は変化ない。
或いは、歴史が変わっても認識できないだけかもしれないが、いまのところわるい結果には繋がっていない。
手紙自体は正常に届いているようだ。モデルの相当数が、かつて手紙を読み、それを保管していた。手紙の内容が抽象的なために、どの程度過去の行動が是正され、未来が変わったのかは憶測の域をでない。
こちらから声をかけた時点で、モデルたちは手紙の存在に気づいてもよいくらいなのだが、手紙を送ったあとでいつも「そう言えば」と手紙のことを思いだすようだ。タイムパラドクスの影響が関係しているのではないか、と仮説を立てているが、結論をだすには、データが足りない。
過去と未来が不可分であるならば、こちらが声をかけたモデルがすなわち、すでに手紙を受け取っている人物、ということになるはずだ。だが、そこで手紙を送ることを恣意的に中止すれば、その人物は手紙を受け取った記憶を思いだすこともなく、現に手紙を受け取っていないことになる。
やはり過去は変えられないのだろうか。
実験において、最も安全で、かつ大規模に歴史改変の実証観測が期待されるのが、すなわち時空転移装置の発明者たるわたくし自身へ、その技術の一端を手紙にしたため、送ることだ。
時空転移装置の発明時期が大幅に短縮される確率が、そう低くない値で見込める。
現在、わたくしにはそのような手紙を目にした記憶はないし、未来のわたくしからも送られてきていない。
手紙が届いていたが、それを手にしなかっただけなのか、それとも手紙自体をなんらかの問題で送れなかったか、或いはそれ以外の可能性も考えられる。
というのも、わたくしの考えでは、今後、過去へは手紙以外のものも送れるようになってもおかしくはないからだ。理論上、それは可能だ。
よって、ひょっとしたら何らかの別の干渉が加わり、歴史が大きく改竄されないように、制御されている可能性は、これもまたそう低くないのではないか、と見立てている。
いずれにせよ、これは避けては通れない実験だ。過去のわたくしである君にとっては、なかなか受け入れがたく、未来のわたくしの倫理観を疑うかもしれない。だが、すくなともわたくしはいま、何不自由なく研究に没頭でき、こうして人類社会は、着実に進歩している。
この実験の結果しだいでは、過去の偉人へ、未来の知識を送る計画も前進するだろう。やはり君はそれを懸念して、たとえ手紙が届いても、見なかったことを選択しそうだが、いずれにせよ、これは避けては通れぬ検証だ。申しわけないが、付き合ってほしい。
最後に、わたくしの仮説を述べておく。
おそらく世界には、ある種の閾値があるのだろう。複雑さが、ひとつの枠組み、殻として機能している。殻が割れない程度の、ちいさな改変、波紋であれば、総体としての大きな流れは変わらずに、引き継がれる。だが、たとえば人類すべてが自由に過去のじぶんへ手紙を送れば、これは殻がその揺らぎに堪えきれずに割れ、収拾不能な改変として未来を大きく塗り替えるだろう。そういう意味で、偉人や、歴史的事件の発端となった人物たちへの干渉は慎重になったほうが好ましいのは、君の懸念するとおりだ。そこはこちらもシミュレーションを重ねている。
楽観はできないが、君がおそれるほどには、個個人への手紙の発送の影響は、歴史を塗り替えるほど強烈なものではない、といまのところは判断している。
もちろん予断はできないがゆえに、気の抜けない日々だ。
添付した資料が、いちおう、時空転移装置の初期アイディアの一覧だ。君ならそれで充分だろう。
わたくしがそれをまとめあげたのは、君のころより十年はあとになってからのことだ。予想としては、君は、いまのわたくしよりも三年ほどはやく時空転移装置を完成させる。完成させるために必要な技術が、君のいる年代にはまだ存在していないがゆえの、見立てだが、君ならば、その技術ごと開発してしまいそうだ。これは傲慢なわたくしの、過去のじぶんへの買い被りだと思ってほしい。
長くなった。
歯はまいにち磨け。四十を過ぎてから虫歯に苦しむ。
では、結果を楽しみにしている。
【背景、あのころの貴女へ】
考古学者である貴女に不躾なお手紙、失礼いたします。さぞ驚かれているのではないか、と心中お察しいたします。
まずは同封した年表をご覧ください。そちらには、貴女に起きる人生の転換期を、そのきっかけとなる出来事と共に羅列してあります。
心配はいりません。
貴女はごく平均的な人生を辿り、家族に見守られながら安らかに亡くなります。客観的な評価といたしましては、しあわせな一生を送ることになる旨をまずはお知らせさせてください。
年表をご覧になられましたか?
この時点で貴女は、この手紙の信憑性を五分五分の確率で「そういうものかもしれない」と判断なさっていることと存じます。たとえ未来からの手紙でなくとも、何かしらの超法規的処置の行える組織からの手紙だと推測されるのは、極々まっとうな論理的帰結だと評価いたします。
そのうえで、これが未来から貴女へ向けて送信した手紙である旨を明かしておきます。
すでにお察しかと存じますが、我々が貴女へ向けてこのような手紙を送った最たる目的は、貴女が先日発掘した遺物と密接に関わっております。
端的に申しあげて、貴女の発掘したそれは紛うことなき本物です。本来、それが貴女の時代にまで遺ることはあり得ないのですが、この手紙同様に、過去へと送信するために特殊な加工を施してあります。
貴女の発掘したそれと、この手紙は、ほとんど同じ材質ででき、同じ構造を有しております。
我々と致しましても、貴女のような方が、それを発掘していた事実を突き止めるまでに、随分と手間と時間をかけました。その可能性がそう低くない確率であるとの指摘は、我々の組織内でもたびたび俎上に載ってはいたのですが、なにぶん、扱う時代が多岐にわたり、それに伴い、チェックすべき人物の数も膨大になるために、貴女の存在へと辿り着くのにずいぶんとかかりました。
我々はすでに、貴女の発掘したそれを過去のある時期に送信しております。
そのことにより、この地球という惑星に生命が誕生したのは、我々と致しましてもにわかには信じられない事実でございます。
じっさいのところ、因果関係はまだはっきりとは解っておりません。我々がそれを過去へ送らずとも、この星には生命が誕生したのかもしれませんし、或いは我々が手を下さなければ、この星に生命は芽生えず、我々もまたある時期を境に、地上から姿を消してしまう定めにあったのかもしれません。
その可能性を残したままにしておくにはあまりに大事であるため、どちらにしろ、生命が誕生する確率を上げるために、貴女の発掘したそれを我々は過去へと送り届けました。
貴女の推察はおおむね当たっております。我々が過去へと送り、貴女の発掘したそれは、生命の起源たるRNAを無数に搭載しております。
我々はそれを、陸と海の両方に送りました。RNAとまではいかないにしても、太古の陸と海には、それぞれある種の核酸塩基が鎖状に組み合わさり、任意の組み合わせを連結し、分裂するといったサイクルをつくりあげていたと考えられています。そこへ、明確に生命の源となるRNAを送り、無数に枝分かれした塩基配列群を、一つの方向へと収斂させる根幹の役割を果たすようにと働きかけます。
そのために投じた一石が、貴女の発掘した遺物の正体です。
貴女はなぜ太古の地球に、手紙としか思えない物体が存在したのか、と首を傾げていることと存じます。
さぞ迷われていることでしょう。
ねつ造の確率がもっとも高く、しかし放射年代測定におかれては、ハッキリとそれが太古のものだと示唆している、この二律背反のあいだで貴女は揺れていましたね。
学会へ報告すべきと貴女の意思は傾いていたところで、この手紙を受け取ったのではないか、と想像いたします。そうなるようにとこちらで設定しておりましたから、そうなっていただけなければ、我々といたしましては、失敗と評価せざるを得ません。
お願い申しあげます。
どうか、貴女の発掘したそれを、公にはしないでください。
貴女さまの胸にのみ仕舞っておいてください。
生命の起源が、未来人の手による細工だと知れ渡れば、いささか人類にとって困難な局面の到来が予測されます。
この手紙を貴女へと送り、貴女が手にした段階ですでに、そうなる確率はほとんどゼロにちかしい値にまで下がります。とどのつまり、貴女はこの手紙の意図を正しく紐解き、合理的な判断を下してくださることがほとんど自明となっております。
我々といたしましては、この手紙を貴女へと無事に送り届けることさえできれば、それで目的は果たされたも同然です。
貴女には人類存亡の危機という重大な任を背負わせてしまいたいへん心苦しく、我々一同、人類を代表して、謝意を申しあげます。
一方的なお願いになってしまい、まことに申しわけありません。貴女の聡明な決断によって、人類、そしてこの星の生命は、栄枯を繰りかえし進化を網の目のごとく繰りかえす余地を得ます。
もちろん貴女には、我々からの提案に敢えて乗らない選択肢もございます。それをこちらから禁止する真似はできません。その場合は、生命は貴女の知る歴史どおりには誕生せず、ゆえに人類はおそらく誕生しないでしょう。生命そのものは、時間をかければいずれこの星にも生じ得ると推測されますが、人類にいたっては、その機を逃すでしょう。
いずれにせよ、我々といたしましては、貴女さまにお願いを申しあげることしかできません。なにとぞ、御一考のほどよろしくお願い申しあげます。
長々と失礼いたしました。
謝礼を含め、何かご要望がございましたら、その旨、この手紙の裏面にでも記していただければ、いずれこちらで発見し、対処可能であれば、ご期待に沿えるように尽力させていただきたく存じます。慇懃無礼な言葉づかい、恐縮至極でございます。
お目通しいただき、幸甚の至りに存じます。お身体、どうぞおだいじになさってください。
紙面も残りわずかとなってまいりました。
改めて、この手紙をお手にとって、お目通しいただき、感謝申しあげます。
まことにありがとうございます。
敬具。
未来維持総合研究機関第一研究所第一実験室実行部。
時空転移制御システム責任者。
累野曾(るいのそ)千尋(せんじん) 拝。
千物語「虚」おわり。
目次
【ころもんての権化】
【お代わりをたんとおあがり】
【バイオレンス姉妹】
【きみは世界を救う愛しいひと】
【僕を死にいざなった悪霊と】
【異釣り師】
【折れた牙を刀に】
【諺かなんかですか?】
【青い花の妖精】
【旅の終わりを探し求めて】
【扇風機の値札】
【潰れる二秒前】
【晴れのち、きみ】
【闇に差す赤】
【世界改変日誌】
【予測変換の怪】
【ずるずるみっしり】
【無視でいいって】
【きみは何も変わらないはずなのに】
【返頭痛】
【日鬼】
【ゾウさんの小さいものはなに?】
【ピエロと一匹の】
【ミカさんはお姫さまになりたい】
【ミカさんはビッグバン】
【あなたにならいいよ、あなたがいいよ】
【トカゲの尻尾】
【グライダーマン】
【ピックを握りしめて】
【少年は予感する】
【お城のパーティーにとっときな】
【スペースミュージック】
【禁音の果てに】
【黙れよギター】
【一本の金髪】
【ドラマーのドラマ】
【ふたたび身体をつつみこむ】
【同期性創発体】
【少年たちの予感】
【音楽は爆発だ】
【永久に失恋】
【一気呵成に加勢を】
【青いバナナ】
【背景、あのころのわたしへ】
【背景、あのころのぼくへ】
【背景、あのころの私へ】
【背景、あのころのおれへ】
【背景、あのころのあたしへ】
【背景、あのころの僕へ】
【背景、あのころのワタシへ】
【背景、あのころのボクへ】
【背景、あのころのわたくしへ】
【背景、あのころの貴女へ】
【ころもんての権化】
道端の松の下に転がる松ぼっくりに目を留めて、アルマジロみたいだなぁ、とその奇抜な形状が連綿と引き継がれてぽんぽこ似たような姿で量産される松の木の神秘に思いを馳せていたら、もぞもぞと一つの松ぼっくりが蠢きだして、ぽっかり二つに割れたので、
ありゃま。
目をぱちくりさせてよくよく目を凝らすと、四つのちいちゃなあんよとつぶらな瞳に、ぴんぴょこ飛びだした丸っこい三角お耳の生えた頭部が、折り畳み式自転車さながらに、ぐねんこ、と姿を現した。
くしくしおめめを短いあんよで掻いたなら、ほんわか欠伸なぞを挟みまして、ころもんて、ころもんて、よたつきころけて、よちよちてとてと、歩きだす。尾っぽのたろてんたろてん、垂れた様子はほんわかほろほろ微笑ましい。
わたしは華の女子中学生十四歳であったから、そりゃあこないなめんこい生き物を見つけてしまったならば、財布の紐の堅い父母に買ってもらったばかりの最新式メディア端末でぴんぽろ画像に動画に記録せにゃあかんぜよ、と躍起になるのは自然の摂理じみている。
ひとしきりぴんぽろし終わって、むふーと鼻息を荒く噴きだしたならば、ちょいと落ち着きを取り戻す。
ちんちりーん。
そばを素通りしていく自転車にまたがった高校生におばさまたちの、このコなにしてんの、の素朴な眼差しに耐えがたい恥辱の念が湧き申して、なんじゃいなんじゃい、ここにだってへんちくりんのかわいいちんまり生き物がころもんてころもんてしててん、へん!
わたしだけがこの世に生まれ落ちし宝物を見つけた心地で、いっそ独り占めしたろ、の心持ちで、手のゆびをわしわし動かしてから、動くなよー、噛むなよー、暴れるなよー、の呪文を唱えて、ふしゃー、と猫になったつもりで、足元でころもんてころもんて、ちとちとあんよを動かしている謎のかわゆい生き物を両手でそっと捕まえる。
きゃわわー。
ほっぺに頬づりしそうになって、思いとどまる。
松の根元にいたんじゃろ。
したらほれ、ここ掘れわんわんの、びしゃー、がちょろちょろかかってしもてるやもしれぬじゃろ。
ばっちいじゃろ。
よくないじゃろ。
華の女子中学生十四歳がしていいことではないじゃろい。
両手で掴んでるのもホントはあかんのやもしれぬけれども、そこはそれ、これはこれ、手放すには惜しいかわゆすさがあるんじゃもん、仕方なかろう。
うんうん。
わたしは得心いって、そのまま、ころもんて、の権化を家に持ち帰った。
「おとーさーん、きてー」玄関先で父を呼ぶ。両手が塞がっていて靴が脱げない。
父はメガネにモジャ髪、短パンにワイシャツなる現代美術さながらの格好で出迎えた。「どした」
「あんね、あんね、これこれ」
ほわほわわーん、ぱかり、と包んだ両手を開いてみせる。
「どれどれ」父は覗きこむ。「松ぼっくりやね。これがどした」
「いやいや、ただの松ぼっくり違うでしょ」
よく見てよ。
わたしは手のひらのうえを強調するのに、父は一向に、はぁ、とか、ほぉ、とか、かわいくない相槌を打つ。
もういい。
わたしは足をがちゃがちゃ擦りあわせて靴を脱ぎ、
「お姉ちゃーん」
我が人生の先輩へとご教授いただきに参上つかまつる。
「うっさいよスイ」姉は仮想現実を展開して格闘ゲームをしていた。部屋のなかで汗だくになっているのは、殴ったり蹴ったりを本気で、全力で、実践しているからだ。
しばらく姉の武闘を眺める。姉はひとしきり暴れ倒すと、ふぅ、と魂みたいに息を吐いて、タオルで首筋を拭う。
「なにさいいとこだったのに」
「ごめん。何位?」
姉はゆびでピースサインをつくる。
「二位?」
「優勝。世界ランキング一位」
「うわぁすごいすごい」
いまウチには世界一つよい女、否々、人間がいるのだ。どんとこーい。
「で、どしたんスイ。それ、なに」姉はこちらの両手にくるまれたころもんての権化に気づいた様子だ。髪の毛をごしごしタオルで拭きつつ覗きこむ。「松ぼっくり?」
おっかなびっくりゆびでつつく姿がおかしくて、だって世界最強になったばかりなのに、そりゃ仮想現実内ってくくりではあるけれども、それにしたってその臆病具合、ぷぷぷ、とお顔がにんまり、ゆるゆるしてしまう。
「これがどうしたんよ」姉はわたしのひたいを手のひらでペチンコして、風呂入るよ、と誰に言うでもなく宣言して部屋から出ていこうとする。
「待って、待って。これ本当になんも思わんの」
「松ぼっくりがそげに珍しいか。ほうかほうか」姉は手のひらをひらひら振って、きょうも我が家は平和じゃのぅ、と眉毛を持ちあげ、誇張された暢気を表現する。
完全にどう考えても小馬鹿にされていたが、そこは姉の妹を十四年もやってきたわたしだ、なんかこれ動くんじゃもん、とシュンとしてみせる。
「動くぅ?」姉は踵を返し、どれどれ、と顔を寄せる。「虫かなんかじゃないの。捨ててきなぁ、ばっちぃ」
やはり。
わたしは確信する。姉たちには見えていないのだ。この、ころもんての権化、かわゆいの結晶、四足の松ぼっくりに似た鱗を持つ生き物が。
「じゃあそうする」
わたしはひと足先に姉の部屋をあとにする。うしろからついてくる姉が無駄に早歩きで迫ってくる。恐竜に踏みつぶされそうな小人のきぶんで階段を駆け下りると、姉はわたしとは逆のほうへ折れ、風呂場へと消えた。
居間の食卓の椅子に座ってわたしは、食卓のうえにころもんての権化を転がす。「なあなあ、おぬしは幻覚なのか」
ころもんての権化は、松ぼっくりの姿から、ぱらりとほどけて四足を晒す。よちよちてとてと歩くとぬたんと垂れた尾っぽが足場を擦るので、ついつい尾っぽをゆびで押さえて、歩いてるのに進まんのですけどー、のきぶんを味あわせてあげたくなる。
メディア端末を取りだして、さっき道端で撮った画像やら動画やらを見る。わたしはきゃっきゃうふふしながら松の根元に転がる松ぼっくりを熱心に、丹念に、追いかけ回している。
映らんのかカメラには。
手鏡を持ってきて映すも、鏡のなかには松ぼっくりがぽつねんとあるだけだ。
わたしはころもんての権化を手のひらに載せ、そこでもカメラやら鏡やらで映してみる。やはりわたしのまぶたを通さずに見る像には松ぼっくりがぽつねんとあるばかりだ。
父や姉にはかように見えていたのだろう。わたしはさしずめ、頭のぴるぴるちくちくアイタタではないか。
ただいまぁ、と玄関口から母の声がする。どさりと荷物を下ろす音が聞こえ、わたしはころもんての権化が逃げないように、そばにあった透明のカップを逆さに被せて蓋をする。
荷物を持ちに玄関に立つと、母は、それよろしくー、と言ってさきに居間に引っこんだ。こういうところが卒がなくて、人使いが荒いくせに荒いと思わせない手腕は、姉にじょうずに引き継がれている割にわたしにはさっぱりだ。血筋の神秘を感じちゃう。
母は買い物をしてきたようで冷凍食品やら野菜やらを冷蔵庫やら冷凍庫に押しこんで、パンやら調味料やらは適当に、キッチンのうえに置いておく。てや!
じぶんでじぶんの肩をトントン叩いて、疲れたぜ、のこれみよがしなアピールをしながら居間に戻ると、母は熱心に食卓のうえを見ていて、立ったまま見ていて、そんなに何をガン見しているのやら、と母の表情を盗み見、それから視線のさきを辿ると、そこにはわたしがカップを被せておいたころもんての権化がおるではないか。
「松ぼっくり拾ってきた」わたしは言った。頭のぴるぴるちくちくアイタタではないよ、と暗に示したつもりが、母はこちらを見ずにゆびをまっすぐころもんての権化に差し向けて、「スイちゃんこれ視えてる?」と言った。
わたしはしばしぽかんとした。母は続けた。
「えーちょっと待ってね、ああもうそういう歳か、しまったなぁ、さきに出会っちゃったかぁ」
母はあごに指を添え、なにやら考えこまれてしまわれる。
この反応はどう考えても母の目にもカップのなかのころもんての権化が、かわゆいの結晶が、生き物が、見えていると判断してなにか差支えがあろうか。いや、ない!
「お母さんにも視えてるの、これ? お父さんとお姉ちゃんはただの松ぼっくりだって」
「そうよねぇ。お姉ちゃんがお父さん似だったから、てっきりスイちゃんにも引き継がれないものとばかり思ってた。お父さんには内緒ね」母はくちびるを尖らせる。「そっかぁ、スイちゃんがなぁ。教えなきゃいけないこといっぱいあるな。ビシバシいくよ。お母さん、がんばる」
腰に拳を添えて、空手ポーズを決める母上でごじゃる。
「がんばるって何を?」
カップのなかから懸命に脱出を試みるころもんての権化をわたしは救いだして、手のひらのうえに載せてまじまじと見る。
「名前つけちゃってあげなさい」
母は無駄にわたしのひたいをゆびで、ぺしりする。「長い付き合いになるんだから」
【お代わりをたんとおあがり】
アキコがホットケーキを食べられなくなったのは六歳になった日のことだ。誕生日のケーキとは別に、友達とホットケーキをつくったのだが、そのときに指南役の母から、卵を割ってなかに入れて、と言われて身体が固まった。
「なんて?」
「卵。入れないとふっくらしないから」
「なんで?」
「美味しく食べたいでしょ」
何を引っかかっているのだろうこのコは、と言いたげに母は、アキコの友人たちに向かって笑みを向けた。
アキコはそれからどうやって誕生日会を過ごしたのか記憶がない。はいしゃいでいた友人たちと母の姿はぼんやりと憶えてはいるけれど、ホットケーキがどうなったのか、じぶんがそれを食べたのかは覚束なかった。
アキコはその日からじぶんの食べる物を注意深く観察するようになった。料理本を眺めることもあるし、母に訊ねることもある。
どうやら大部分の食べ物は、元は生き物であるらしい。アキコはそれまでそんなことを考えたこともなかった。
台所に立つ母の姿はいつも後姿しか見えなかったし、まな板は高い位置にあって、そこでどんな作業をしているのかは分からなかった。
包丁を使うことは知っていた。あれで生き物を刻んでいたのだ。
アキコは母が、鬼か何かのように思えた。同時に、じぶんもまたその鬼の子であり、知らず知らずのうちに、死んだ生き物を食べていたのだ。
「ひょっとしてだけど、卵焼きって、卵?」
「そりゃあ、ねぇ」
母は父の顔を見た。父がTV画面から目を逸らし、母を見て、ん? とおどける。
「じゃあ目玉焼きは?」
「それも卵」
言った母へ、なんだなんだクイズか、と父が愉快そうにする。だがアキコは体温がひゅっと下がったのを感じた。
卵と言えば、鳥のひなが入っている器だ。赤ちゃんの寝床だ。そんなものをじぶんは、じぶんたちは食べていたのだ。
赤ちゃん!
アキコはいよいよじぶんがバケモノのように思え、罪悪感に押しつぶされそうになった。吐き気を催してもおかしくないその場面であっても、食卓に並ぶ目のまえの料理はどれも美味しそうで、現に過去に味わった記憶が、アキコの悲哀の念にかかわらず唾液を分泌させる。
美味しそう、だってママのお料理だもん、美味しいに決まってる。
しかしそれは生き物なのだ。とっくに死んではいるけれど、元は生きていたし、いまこうして死んでいるからこそ、余計に可哀そうに思う。
どうして人間は生き物を食べなきゃ生きていけないのだろう。こんなに文明が進んで、技術が進歩して、魔法としか思えないような技術がそこかしこに溢れて、有り触れているのに、どうして未だに生き物を殺して、食べて、過ごしているのだろう。
とんでもなくイビツだ、とアキコは頭がくらくらしてどうにかなってしまいそうだった。
「どうしたの、食べないの。美味しくない?」母が心配そうに覗きこんでくる。父も、アキコのお皿を見て、箸が進んでいないのを訝しんでいる。「熱でもあるんじゃないか」
死んだ生き物を食べるなんて可哀そう。
言いたかったけれど、それは言ってはいけないことのように思え、そして言っても通じないことなのだと、アキコにはなんとなく判るのだった。
父と母はアキコよりもずっと賢いおとなだ。そんなおとなが、死んだ生き物を食べることをふしぎに思っていない。これはきっと、ふつうのことで、おかしくはなく、だからここで罪悪感を覚えてしまうじぶんのほうが変なのかもしれない、とアキコはおへその辺りがむぎゅむぎゅした。
考えれば考えるほど、余計にひとりぼっちになったみたいで、取り残されてしまったみたいで、悲しくなった。
「無理して食べないでいいよ、どうする、リンゴ剥こうか?」
アキコは首を振る。
箸を伸ばし、皿のうえのから揚げを拾いあげ、口のなかへと運んだ。母のから揚げは冷めても美味しい。コロモがサクサクで、噛むと肉汁が、じゅわあと、口のなかいっぱいに広がる。ほのかな塩味と、しょうがやニンニクの風味がたまらない。
ごっくん。
呑み込むと、罪悪感までいっしょに喉を通って、薄れてしまった気がした。
「このお肉はなんの生き物?」アキコは箸先のから揚げを眺める。
「鳥だけど」母が言った。何だと思ったんだ、と父が笑っている。アキコはひょいと頬張ると、ママとパパはさ、と何の気なしにこう言った。「このお肉が人のでも、やっぱり気にしないの」
父と母が動きを止めた。
「どうしてそう思ったの」
アキコはから揚げを取りこぼす。聞いたことのない父と母の声だった。
本当はこのあとでアキコは、どうしてじぶんには誕生日が一年に何回もあるのか、それから、どうして誕生日会をするたびに友達がいなくなるのか、なにより、誕生日会をするごとにどうして街から街へと引っ越すのか、を訊ねようと思っていたのだけれど、もうそういう気分ではなかった。
「なんでもない」
アキコは手掴みで、取りこぼしたから揚げをつまみ、わたしこれ好き、と言っていかにも美味しそうに平らげてみせた。
父と母はそれを見届けるとようやくいつもの穏やかな顔に戻り、いっぱいあるからたくさん食べてね、と冷蔵庫を振り返り、言った。
【バイオレンス姉妹】
冷蔵庫を開けたら生首が入っていた。
きょうはわたしの誕生日だから、誰かがプレゼントしてくれたのかもしれない。
生首は奥を向いていて誰の顔だかわからない。髪の毛が首のところまでしかないので姉ではないはずだ。でも、首を切断するときにいっしょに切れてしまったのかもしれない。髪の毛の色もこんなに茶色くなかったけれど、これも血にまみれているだけだと考えれば、ひょっとしたら姉の首であってもおかしくはない。
ウキウキしながら生首に手を伸ばし、掴むと、冷たい割にまだ弾力があった。
切りたてほやほやだ。
思いながら、ぐいと持ちあげ、冷蔵庫のなかから引き抜く。ボールを回すみたいにぐるりと宙に浮かして回転させる。ぱっ、と掴みなおすと、そこには見知らぬ少女の顔が現れる。
片目をつむった状態だ。もういっぽうの目は眠たげに開いたままで、口を半開きのまま死んでいる。いいや、死んだあとでこんなふうになったのかもしれないけれど、期待どおりの顔ではなくてがっかりする。
「ハッピーバースディトゥーユー」
背後から声をかけられ、振り向くと、パンっと音が鳴った。
「お姉ちゃん!」わたしは怒る。「せっかくオニューのお洋服なのに」
「ごめんごめん」
姉はライフルを床に放り投げると、これでおあいこ、と言って台所から包丁を持ちだし、じぶんの腹を切り裂いた。
「もったいない」
わたしはすかさず姉の腹からこぼれおちる臓物を手で受け取りに寄り、反対にじぶんの臓物を床にビタビタこぼした。
「あらあら」
姉はわたしの内臓には目もくれず、せっかく捥いできたのに、とわたしの手から転げ落ちた少女の生首を拾いあげた。「このコ、かわいかったのよ。とっても」
わたしより?
お腹の奥がムカムカしたけれど、それはどう考えても気のせいだ。
「おっきなお穴」姉はわたしの胴体に開いた穴に、少女の生首を押しこんだ。
「お姉ちゃん!」
わたしは姉からナイフを奪い取り、姉の胸に突きたてる。
「あらあら、うふふ」姉はわたしを抱きしめる。
来年こそは、とわたしは願う。
姉のこのうつくしい顔がほしい。
姉の、きれいな顔だけをこの手に。
【きみは世界を救う愛しいひと】
疲れた顔で妻が、ただいまぁ、とソファに崩れ落ちる。もうやだこのまま寝る、とつぶやくので、温かい濡れタオルを手渡し、それで彼女が顔を拭いているあいだに靴下を脱がす。ついさっき履いたばかりみたいに新品だ。妻はこういうところが抜けている。
「汚いよ」
「どれどれ」嗅ぐ仕草をすると妻は、やだぁ、と膝を抱えた。
足先をゆびでマッサージしているとやがて畳まれた足がゆるみ、伸びてくる。大きなカタツムリ、と思う。
「きょうはどうしたの。何かあった?」
「特大のクレームをやっつけたよ」
「たくさんがんばったんだね。偉いね」
「偉いよ。そうだよ。もっと褒めて」
こっちの足も、と妻はもういっぽうの足を差しだす。全体的に丸みを帯びた足で、指先のちいささがかわいくて、思わずゆびでつまみたくなる。
「くすぐったい」
「じゃあこれは?」
「きもちい。もっと」
足首の付け根を揉みほぐし、そのままふくらはぎをほぐしにかかる。いつの間にか妻は目をつむり、糸のほどけるような寝息を立てている。
「お布団で寝たほうがいいよ」
抱っこをして運ぼうとするも、妻は駄々っ子のようにソファから動こうとしない。
しょうがないな、の溜息を吐く。身体をよこにさせ、うえから毛布をかける。頭にクッションを差しこみ、ソファを即席のベッドにこさえる。
「お疲れさま」
部屋の電気を消し、じぶんは寝室に引っこむ。
妻は隠しごとをしている。枕に頭を埋め、目をつむる。
夫のじぶんにも本当の仕事を内緒にしている。世界に湧く怪獣や犯罪組織と日夜、秘密裏に戦闘を繰り広げている正真正銘のスーパーヒーローだ。でもその姿は誰にも知られてはいけないから、応援されることもなく、人知れず苦労を背負いこんでいる。
でも、夫のじぶんくらいは彼女の苦労を、功績を、知っていてもばちは当たらないはずだ。
妻は完璧に隠しとおせていると思っているようだけれど、詰めが甘い。
それこそ彼女の宿敵である人類の敵、世界最悪の権化、かつてこの世の神々を滅ぼした元凶こと歩く災厄、サタゴルラザンベとはぼくのことだ。
ぼくは初めて妻を、彼女を目にし、じぶんの存在意義を疑った。滅ぼしていいわけがない。失っていいわけがない。こんなにも愛おしく尊いものを壊すなんてぼくにはできなかった。
それはそうとして、人類には滅んでほしくもあり、折衷案としてぼくは妻のとなりにいられる自由を妻自身から許されながら、いっぽうで妻を苦しめる元凶の役目もそつなく熟している。
本当はいますぐにでも人類を滅ぼして、妻と二人きりで生きていきたいのだが、それは妻の本望とはかけ離れている。
妻はいまの仕事に生きがいを感じているようだから、いまさら失くしてしまうわけにもいかない。
ほどほどに妻をへとへとにさせるくらいの負担を、すなわち破壊行為を人類社会へ仕向けながらぼくは、きょうの献立を考え、妻へのねぎらいの言葉を練りあげ、献身のレパートリーを増やす努力を怠らず、いかに妻から愛想を尽かされないかに全力を尽くす。妻からの愛を深めながら、妻からの言葉を、機微を、漏らさずすべて受け取りたい。
妻の身の安全を緻密に計算するのも忘れない。
妻に成長の機会を与えながら、妻を愛する片手間に、悪行の計画を練る。こんなのは風呂のタイル掃除よりもずっと何億倍も楽だ。どうあってもぼくは妻を傷つけられないし、息を吸うようにぼくの考えることは人類社会にとって極悪であり、災厄だ。
矛盾するそれら二項が、うまい具合に重ならないようにすればよいだけだ。赤と青の中間を選べばいい。赤子にだってできる簡単な仕事だ。
さて、あすは隣国の人口三千万人に殺し合いをしてもらおう。愛する者の命を互いに奪い合ってもらう。子守唄みたいにやさしい悪だ。
いっそぼくも妻に正体を打ち明け、抹殺してもらいたい衝動に駆られる。
甘い衝動に身を悶えさせながら、妻をなんと励まし、慰めてあげようか、と候補を挙げつらねる。きっと妻は、救えなかった命と、救えた命を鑑みて、無力感と達成感の狭間でくたくたになって帰ってくるはずだ。
そんな彼女の身体に、ぼくだけが自由に触れることができる。泣き言を吐く彼女に、ぼくだけがあたたかい言葉をかけてあげられる。
弱っている姿を彼女は、ぼくにだけ見せてくれる。
彼女がうれしいとぼくもうれしい。彼女が悲しいとぼくも悲しい。
こうして一心同体に思える日々が愛おしくて仕方がない。
しあわせとはこういうことを言うのだろう。
妻のしあわせがぼくのしあわせだ。
だからぼくはあすも、妻にとってのよき宿敵であろうと思う。強敵であろうと思う。
極悪非道の、けれど絶対に妻を打ち負かすことのない敵であるために、きょうも夜通し、いかに妻に全力をださせ、劇的な勝利を掴ませてあげられるかを考える。
愛している。
この世でいちばんきみが好きだ。
思えば思うほどに、胸が苦しく、妻を欺いている罪悪感に圧しつぶされそうになる。
こんなんだから、と憤る。
人類なんてさっさと滅べばよいのだ。
念じるけれど、そうはしない。妻がきっと悲しむからだ。守るべきもののない世界はひどく色褪せてしまうことをいまのぼくは知っている。
愛している。
枕を抱きしめる。ひとしきり悶えたあとで、やっぱりよくないな、と息を漏らす。ベッドから抜けでると居間に下り、明かりを灯さずに、妻のそばに寄る。
頬をゆびで突つき、よく眠っているのを確かめてから妻の身体を持ちあげる。起こさないように、すこしだけ人間離れした膂力を発揮するけれど、これくらいは仕方がない。
物音を立てずに寝室にあがり、妻をベッドに寝かせる。
妻はこちらの手のひらに頬をこすりつける。猫みたいだ。心地よさそうに寝返りを打つと、そのまま胎内の赤ちゃんみたいに丸まった。抱きしめたい衝動に駆られるが、熟睡の邪魔をしたくはない。
妻の寝息に耳を欹てる。
朝までずっとこの至福の音色を聞いていられる奇跡に、感謝せずにはいられない。
胸の奥がくすぐったく、やっぱり寝顔を覗きこんで、さらにきゅぅともどかしくなる。食べてしまいたいのに食べてはいけない矛盾に煩悶する。
おやすみ。よい夢を。
愛しいひと。
あすもきみを困らせ、追いこむぼくをどうか許してほしい。
【僕を死にいざなった悪霊と】
霊感があってよい思いをした憶えがない。目に映るそれが幽霊か生身の人間かの区別がつかずに、ずいぶんな目に遭ってきた。
幽霊よりも人間のほうがよっぽど怖い。社会が怖い。
引きこもりになってみたはよかったが、かといって、では幽霊となら仲良くできるのかと言えばそれはのきなみ否であり、引きこもっていても霊媒体質のせいなのかひっきりなしに干渉してくる霊たちを拒む術が僕にはなかった。
僕の理性はいよいよおかしくなった。
大枚をはたいて購入した琥珀の宝石で、なんとか強力な結界を張ってみたが、解決を見せるどころか、こんどはその結界を物ともしない強力な霊しか寄ってこなくなり、却って体力は消耗した。祓える霊は祓ったが、それすらできない凶悪な霊にとりつかれ、いよいよ僕の精神は限界だった。
きょうもまた例の悪霊がやってくる。
なんでもインターネット上でいわれのないデマを流され、世を呪って死んでいった女の霊だという。業界内では有名だった。
きっと一人きりではない。何体もの怨念が融合して、一つの強大な霊として結晶しているのだ。
集合知ではないが、知能もそれなりに高い。
霊には珍しく人格らしいものまで窺えた。
基本的に霊は、動物にちかい。
生前にやり残したつよい執着や愛着、端的に言えば愛憎によって動き回る。本能のようなものだ。ゆえに、個々の霊への対処法は、その霊にある固有の本能を見抜けば、あとはその霊の琴線に触れないようにじぶんの行動を変えるだけで、霊からの干渉を避けることができた。
もちろん、とりつかれてしまえばそれもむつかしくなる。
そういうときに、琥珀や真珠などの宝石が呪具として有効だった。たいがいの霊相手ならばそうした対抗策で撃退できる。
ただし、今回の悪霊は、こちらのそうした対策を難なく見抜き、いくども僕を殺そうとした。苦痛を与えるだけならいざ知らず、僕の家族や同業者、いきつけの店の従業員など、周囲の者にまで魔の手を伸ばしはじめた。
いよいよとなって僕は、自決する臍を固めた。
もともと、この世に未練はない。僕自身が悪霊になることはないだろう。できれば愛し合える誰かと出会いたかったが、それも可能であれば、という願望にすぎない。ヒーローになりたかったなぁ、みたいな幼稚な夢だ。叶わなくて当然だ。
僕はもう、誰とも関わり合いたくはなかった。
首に縄をかける。
呼吸が苦しくなり、めまいが襲う。失神すればそのまま自重で首が締まり、窒息死するはずだ。
僕はゆっくりと意識を失った。
視界が闇に染まる間際、目のまえに例の悪霊の姿が霞んで見えた気がした。助けようともせず、ただこちらをじっと見下ろしている。
身体が冷たく、或いは熱く、そしてもう何も感じない。
浮遊感だけがここにある。
虚無。
ああ、と思う。
僕はいま、死んだのだ。
「そう、きみは死んだ。なんで死んだ。せっかく私が呪い殺してやろうと思ったのに」
死んだはずの僕はなぜか、明るい部屋のなかにいる。足元には首をくくったじぶんの身体があり、僕は、僕の胴体に両足を突っこんだ状態で立っている。
「あーあ、もったいない。せっかく霊感あったのに、自殺じゃ、せっかくの霊力もパァだ。おまえ、ただの浮遊霊だよパンピーだよ」
「パンピーって」
目のまえにいる女には見覚えがあったが、うまく思いだせない。知り合いにこんな女性、いただろうか。
「おいおい、あんまじろじろ見んなよな。殺し合った仲だろ、仲良くしよーぜ」彼女が両手をだらんと胸のまえに掲げてみせたところで、ようやく察し至る。「きみ、悪霊か」
床をゆびさし、ここにいたあの悪霊なのか、と暗に問う。僕を殺そうとしていたあの、と。
「ちっ。せっかくこんな上玉殺せそうだったのに、ちょっと目を離した隙に死んじゃうんだもんな。せめて死ぬなら事前にそういうそぶり見せてほしいよね。じっくり衰弱させてからなんてまどろっこしい真似せずに、すぐに呪い殺してやったのに」
「いやいや。なんで殺すんだよ」
思いのほか言葉が通じるので、遅ればせながらの怒りが湧いた。「せめて罪悪感くらいもったらどうですか、けっこう怖かったし、ふつうに弱ってましたよ。ひとを困らせて何が楽しんですか。死んだら娯楽に困るんですか、生きてるひとをうらやんで、逆恨みみたいにして怖がらせて、悦に浸って、なんて嫌なひとなんだ。あなただって生前、ネットで散々な目に遭って、いろんなひとの無邪気な悪意に苦しめられてたんじゃないんですか。なんで死んだら、そういうクズみたいなひとたちと同じことをじぶんでできるんですか。信じられません」
「おうおう、言ってくれるじゃねぇか。たしかにアタシゃおまえの調べたとおり、怨念の総体らしい。いろんな人間の記憶がごっちゃになってここにある。だが、アタシがおまえを殺したかったのはそれとは関係がねぇ。霊度があがんねぇんだよ。つうか逆だな、おまえみたいな霊感あるやつ殺すとレベルがあがんだよ。もっと強くなれんだ、したら今度こそ、アタシらを死に追いやった野郎どもを根こそぎぶっ殺して、こっちの世界でもひどい目に遭わせてやらぁ。そのためにはどうしてもおめぇみてぇなやつを」
「殺さなきゃいけないだなんてそんな理不尽なことは言いっこなしですよ。あなたには同情しますが、それで僕がひどい目に遭わなきゃいけない道理はないはずだ。どっちかと言えば僕はあなた方と同じ立場ですよ。あなた方に交じりあうほうの人間ですよ。それをあなたは殺してしまうだなんて、そんなのは、自殺よりもひどいですよ、哀しいですよ」
言っていて目頭が熱くなる。
彼女は――見た目が女性なのでそう呼ぶが――彼女自身がもっとも憎む者と同じことをじぶんの手で、しでかしてしまっている。それがなんとも虚しく、哀しかった。
「哀しいったって、でもさ、ほら」
彼女は言葉を詰まらせた。頭上に総毛立っていた髪の毛が、しゅるしゅると下りていく。「わ、わるかったよ。でも、アタシはあいつらとは違う。そこはいっしょにすんなって」
「でも僕はキミの無邪気な悪意に殺された。キミは僕がかってに死んだと言うだろうけれど、僕はキミにも、ほかの大多数の無関心な人間たちにも殺されたようなもんだ」
「そう言われちゃうとな。ごめんて。もうしないよ。つってももう死んじゃってるし、どうしたら許してくれる?」
案外に彼女が素直に肩を落とし、縮こまってしまったので、僕のほうこそ意気阻喪する。湧いた怒りもどこへやらだ。
やり場がないどころか、溜息と共に霧散して消えてしまった。
僕は言った。
「どうしたら僕たちみたいのがいなくなるか、いっしょに考えてください」
彼女は顔をあげる。
僕たちはこのときになってようやく目を合わせた。彼女の瞳は翡翠みたいだ。吸いこまれそうになる。
「成仏の仕方もわかりませんし、時間はあるんですよね」
「時間? あ、うん。あるある、と、思う」
「じゃあ、しばらくじっくり考えましょう。悪霊として格上のそのチカラ、僕たちみたいなひとのためにもっと上手に使えると思うんです」
キミみたいなひとたちの助けになれると思うんです。
僕が手を伸ばすと、彼女はまるで立ちあがるための支えを掴むように、むんずとその手を握りかえした。
僕は死んだ。
じぶんで選んだ死だったが、生きているうちに、違った生き方を歩めるものなら歩みたかった。でもたぶん、遅くはない。
僕はいま、僕を死にいざなった悪霊と手を繋ぎ、立っている。
【異釣り師】
初めて異釣りに連れて行かれた日、目のまえで異魚に父を食われた。簡単な仕事だと聞かされていた。おまえもいずれはオレの跡を継ぐんだぞ、と将来を勝手に決められたことに腹を立て、その日は父と口を利かなかった。
言うことを聞かずに、反抗したあたしは、異釣りでけっして外してはいけない仮面を外してしまい、そのせいで異魚があたし目がけて飛んできた。父は、そんなあたしを身を挺して庇い、そして上半身だけをきれいに食べられて死んだ。
異魚は、人間を喰らう。だから父のような異釣り師たちが、夜な夜な波紋の広がりはじめた区域に出向き、そこに近々浮上してくるだろう異魚を、前以って釣りあげておく。
雪崩対策のようなものだ。
雪崩の起きそうな場所に爆薬を仕掛け、大規模な崩落が起きる前に、小規模な雪崩を起こしておく。
「異魚なんて滅ぼしちゃえばいいんだ」
ことし八歳になった息子がフォークを振りあげて言った。スパゲティのミートソースが飛び散り、おとなしく食べてね、とお願いしながらテーブルを拭く。
「毒とか撒いて、イチモウダジンにすればいいと思う。なんでしない?」
「異魚にきく毒がいまのところないからかなぁ」物騒なことを言わないでほしかったけれど、考えるチカラは養ってほしいので、考えを頭ごなしに否定したりはしない。そのせいで、歯に衣の着せない子供に育ちつつある。ただ、毒に関しては以前、あたしも同じことを考えたことがあった。「異魚は、異空から釣りあげないことには滅せない。いまはママたちのグループが、大きな網でまとめて釣りあげたりもしてるから、そうだね、一網打尽にする方法がないわけじゃないよ」
「はやくボクも釣りにいきたい」
「まだちょっとはやいかな」
「ママはいつした」
「初めてってこと? えっとね」考えるまでもないが、間をあけた。すぐに答えられる日付けであると悟られまいとする自己防衛かも、と思い、余計にもやもやする。
父の命日と同じだ。あれから十七年が経った。
「十五のときだから、ユウヒはあと七年は待たないと」
「長いよ」
「そうだね」
だが、短い。あと七年で、異魚をどうにかしなければ、あたしはユウヒにもこの稼業を引き継がせなければならなくなる。それだけはなんとしてでも避けたくて、仲間を募り、異釣りを集団でこなすようにした。
本来は単独でこなすのが習しだった。
おそらく、異釣り師が一か所に集まると、異空間のピルポが増殖するからだろう。ピルポは異魚たちの餌だ。大型化するまで異魚はピルポを捕食して育つ。
成魚となり、さらに巨大化した一部の異魚は、異空を越えて、こちら側の現世の人間を襲うようになる。
ピルポは現世に漂う「イト」を好んで食する。イトはどんな生き物でも発している。極稀に、イトを豊富に含有する人間が誕生する。その体質は遺伝するため、そうした者たちが、やがて異釣り師となったといまでは考えられている。イトの濃度の高い場所には、必然、ピルポがたくさん集まる。そこには異魚も集まり、巨大化し、そして人間が襲われる確率もまた高くなる。
異釣り師の家系は、そうして否応なく異魚との関わりを持たざるを得なかったのだ。ただ食われるだけではいられない。異釣り師の祖先は、異魚への対抗策を編みだした。それがつまり、異釣りだ。
己が身体が豊富に蓄えるイトを用いて、現世に居ながらにして、異空間へと干渉する術を磨いた。異魚を釣りあげるための道具は、刀と、細く強靭に練りあげたイトだ。
釣りあげた異魚を、釣竿の代わりの刀で以って、斬り殺す。異魚は、現世に姿を晒さなければ、干渉しようがない。ゆえに、毒もきかない。異空へ送れるのはイトだけだ。
イトを大量に駆使すれば、イトを網にもできる。だがそのためには一人ではなく、集団のチカラが必要となる。
反面、異釣り師が一か所に集まれば、ピルポがイトを求めて集まってくる。必ず異魚を釣りあげられればよいが、そうもいかない。失敗すれば、イトごと逃げられる。わるくすれば、イトを無駄に奪われておしまいだ。
イトを失えば、ピルポが大量に増殖し、ピルポで育つ異魚の脅威がますます増す。
あたしたちの異釣り網がうまくいっていたのは最初だけだった。
見たこともない大型の異魚が現れ、いちどに異釣り師たちがごっそり食われたことがあった。大事件だった。
全世界の異釣り師たちから禁忌を犯したと非難された。個人情報が、異釣り師たちのあいだで周知され、声をかけても、グループに加わる者は皆無となった。
挙句の果てに、新たに発足された異釣り協会なる組織から永久追放の烙印を捺され、いよいよなす術をなくした。
異釣りをするな、と言われて、はいそうですか、とはいかない。黙っていても、異魚はあちらから寄ってくるのだ。それに対抗するために、否応なくあたしたちのようなイトを大量に保持する者たちは、異釣りをせざるを得ない。
協会からの通告は、いわば死刑宣告だ。異釣りをするな。そのまま食われて死ね、と言っているのと変わらない。
あの大型の異魚に食われてしまった仲間たちにはわるいことをしたと思っている。償って生きていくしかない。だからといって、あたしは死ぬわけにはいかない。
お代わり、と口元をケチャップで汚したユウヒがお椀を差しだしてくる。
あたしにはこのコがいる。
世界中で、大型の例の異魚とみられるバケモノの出現が報告されている。釣りあげた者はなく、食われた者の数だけが日々、増えつづける。
単独での異釣りを義務付けている協会は、もはやそのバケモノを退治する術を有しない。集団で立ち向かわねば釣りあげることはおろか、じぶんの命も守れない。いずれはじぶんの番が回ってくる。
大量のイトを求め、バケモノは異釣り師を追い求めている。
黙って食われる未来を受け入れるつもりはない。あたしは、バケモノに食われた異釣り師の遺族に会い、謝罪と、そして協力を求めた。
たいがいは会ってすらもらえず、会えたところで、謝罪をする間もなく、こっぴどく指弾された。当然の怒りだ。黙って身体に浴びることで、すこしでも遺族の気が晴れるならば、安いものだ。
そのうえで、やはり協力者が必要なのだ、とあたしは訴えた。償いたい。これ以上の犠牲者をださないためにも、どうか手を貸してください、とあたしは頭を下げた。
本当は、彼ら彼女らがどうなったっていいと思っていながら。
もちろん、不幸になってほしくはない。わるいことをしたと思っている。だがそれ以上に、あたしにはユウヒの将来が、命が、だいじだった。
守りたいのだ。
このコの未来を。
人生を。
寝顔を撫でつけながら、あたしは思う。
黙って寝ていればこんなにかわいいのに。
起きて、しゃべると小憎たらしい。
だのにどうしてだろう、このコがあたしと同じ道を歩むことになる未来だけは見たくない。小憎たらしくっていい。みんなに好かれなくたっていい。
独りきりでも生きていけるチカラが、道が、このコにあってほしい。産毛の生えたやわらかい頬に触れるたびに、泣きたくなる衝動が、願いと共に湧きあがる。
「ママ、がんばるから」
ひたいに唇を押し当てると、んんっ、とユウヒが寝返りを打つ。あたしはいじわるな気持ちになって、おでこにデコピンをすると、すかさずユウヒが手で振り払う。
起きてはいない。
不快な刺激に敏感なだけだ。
きっとこのコは、とあたしはほころびる。世渡り上手になるだろう。みなが見逃す、波紋の揺らぎを目敏く見つけ、いまあたしにしたように、寝ぼけながらも手で振り払おうとするだろう。
それでいい。
思うが、やっぱりすこし寂しい。
甘えてほしくあり、慕われてほしくもある。
このコが異釣りを継承せずに済むように、七年以内に、あのバケモノを、或いはことごとくの異魚を、あたしはまとめて滅したい。
それまでにいちどくらいは、このコに異釣りをさせてあげるのも、そうわるくはない気もする。
世界はおまえが思うよりもずっと危険で、不快なものだ。
だがその不快ですら、振り払い、楽しむ余地がある。
あたしは押入れから箱を取りだし、中からちいさな仮面を拾いあげる。父からもらった、あたしの仮面だ。けっきょく一度しかつけずに、あとはずっと仕舞っていた。
あたしは父の仮面を使いつづけている。
あのとき、父が仮面をあたしに押しつけずにじぶんで被りつづけていれば、頭から食われることもなかっただろう。父の下半身と父の仮面を被ったあたし、そしてちいさな子供用の仮面だけがその場に残った。
ちいさな仮面をおとなしく顔につけたままでいれば、父の言うことを聞いてさえいれば、と何度考えただろう。だがいまは、そう考えることに罪悪感を覚える。父が死ななければきっとあたしは、このコに出会うことがなかった。
人生はままならない。
あたしは、我が子の顔のよこに、父からもらったちいさな仮面をそっと置く。
似合うじゃん。
思いながら、まだはやいよな、と考えなおして、箱に仕舞い直す。
初めての異釣りはまた今度ね。
布団をかけなおしがてら、あたしは誓う。
それまでには異魚のバケモノ、アイツはママが釣りあげておく。
血祭りに、あげておく。
約束。
ちいさな棒切れのような小指と、あたしは小指を絡ませる。
【折れた牙を刀に】
刀諒(とうりょう)談一(だんいつ)は焦っていた。天下無双の名を欲しいがままにしてきた自他共に認める剣豪のじぶんがいま、己が腰ほどにも満たない童(わらべ)に追い込まれている。
驕り高ぶりがなかったとは言わない。しかし油断をしたつもりはなかった。
常日頃、どれほど見た目がみすぼらしかろうと、貧弱に見えようと、それが刀を交わす相手であるならば手を抜いたことはなかった。刀のまえではみな平等だ。死をまえにすれば等しく無力であるように、刀と刀の先端を突き合あわせれば、そこにあるのは相手の命を奪うことへの同意であり、死闘の幕開けだ。
油断をすれば死ぬ。
一撃必殺が理想ではあるが、なかなかそうもいかぬ。振りかぶる刀数が嵩めば嵩むほどに、死の濃厚な香りが鼻を掠める。
先刻、童の一刀を受け、五本のゆびを失った。右手は中指から小指の三本、左手は、食指と中指の二本だ。
刀を構えているだけで精いっぱいだ。もしつぎの一撃を躱されれば、あとはただ無防備なさまで首を斬られるのを待つだけとなる。逃亡する気力も湧かない。
どうしてこうなったのだろう、とチリチリと発火する焦りのなかで考える。いまはそんな後悔に似た考えを巡らせている場合ではないはずなのだが、冷静にじぶんの姿を俯瞰するもうひとつの視点を自覚する。それはいまこうして死闘のさなかにあるじぶんだけでなく、過去を含めた広い視野を持っている。
目のまえの童が動く。
若い芽を摘むのは気が引ける。ここで引導を渡してもらい、つぎなる世代の糧になるのも一興に思えたが、なぜかそうする気にはなれなかった。
ただでは死なぬ。
相討ちを狙う。むろん、勝つ気ではいる。だがこちらはここまでの痛手を負っておきながら、相手は未だ無傷だ。
死ぬ気でやらねば死ぬだけだ。
肉を切らせて骨を断つ段階はとうに過ぎた。
骨を切らせて、骨を断つ。
あとに残るは、それしかない。しかし相手とてこちらの尋常ではない殺気、ともすれば意図を見ぬいているはずだ。
小賢しいほどに、死闘とは何かを相手は知っている。
師がいるのではないか、とふと思った。
これほどの腕前、一夕一丁で身につく技量ではない。
「動揺を誘う策略と思って聞き流してくれていい」談一は言った。「おぬし、師は」
「おらん」
にべもない返事だ。だが、いないとなると、ますます妙だ。
「独学にしてはいささか型が決まりすぎておる。二刀流に似てはおるが、おぬしはしかし一刀しか扱わぬ。腕力に自信がなくてそうしているわけでもなかろう」
童ほどの業前ならば、片手で扱えるくらいに薄い刀身の刀であっても容易く人体を殺傷せしめるはずだ。
「果たし状を受け取ったゆえ、こうして貴殿と対峙しておるが、見届け人すら用意せぬところを鑑みるに、名をあげたいわけでもないのだろう」
ここで童が勝ったとして、証人がいなければ法螺吹きとして見做され兼ねない。その公算が高いだろう。剣豪相手に小僧にもならぬ童が、まっとうに決闘をして斬り伏せたなど、いくらなんでも誰も信じぬ。
「ひょっとして頭がそこまで回らんかったか」
「恩人だから義を優先した。名誉はいらねぇが、不名誉を与えんのは本意じゃねぇ、それだけだ」
「わしのためとでも言う気か」
これまで湧かなかった怒りが湧いた。舐められている。だが死闘において逆上したほうが死ぬ。重ねてきた死闘の数々において学んだ数少ない真理だ。
「恩人とはなんだ。わしのことか。しかしわしは貴殿など知らぬ。人違いではないのか」
「いいや貴様だ。人殺しを生業としておきながら、人の持つ愛情を疑いもせぬ傲慢な眼差し、顔カタチが醜く変わろうと、身体から立ちのぼる貴様に屠られた弱者どもの死臭は誤魔化しようがねぇ」
「私怨か」思ったので言った。尋常ではない執念を感じた。名をあげたいのではないとすれば、復讐と考えればそれも腑に落ちる。「わしの斬った誰かのせがれか」
「馬鹿を言うな。オレがアイツのせがれだと。侮辱にもほどがある」
「貴殿の殺すはずだった相手をわしが殺してしまったから、わしを代わりに殺そうとそういうことか」
「殺すはずだった? 殺せるはずがないだろう。オレにアイツは殺せない。そういうふうに躾けられたからな」
「ではわしは貴殿を檻から救いだしたようなものではないか」
「だから言ったろ。恩返しだってな」
「解らんな。なぜ恩返しになる、わしを殺すことが」
「本気で言ってんのか? あン? じゃあおめぇはただ、絶対に殺せると思う相手じゃなきゃ刀を抜かねぇってそんなつまんねぇことのために人生のずっとをそれ一本に費やしてきたのかよ」
図星を指された気がした。よもやきょうじぶんが死ぬとはたしかに思っていなかった。勝てる死闘だ。そうだ。いつだって死闘とは、相手にとってであり、談一にとってそれは、引導を渡してやるだけの役割にすぎなかった。緊張はするが、それは乗馬のときの一瞬の浮遊感の連続にすぎなかった。
「強者と闘いたい、それしきのこと」
口にしてみたが、砂利を食べているようだ。水で口をそそぎたい衝動に駆られる。
「そうだろ、そうだろ。おまえはそういうやつだ。だからオレがとびきりの死闘を演じてやる。大いに力量を超えて、限界を超えて、死闘のなかで死ね」
「感謝する」
刀を構え直すが、もはや剣先の震えを御することすらままならない。恐れはない。そのはずだ。呼吸はしずかで、落ち着いたものだ。
おそらく、と足を踏みだし、距離を詰める。まだ死ぬとは思っておらぬのだ。じぶんが死ぬとは、露ほども。
しかし勝機が見えないのも確かだった。刀を振りかぶれば、つぎはない。どちらかが生き、どちらかが死ぬ。或いは、どちらともが死ぬ結果しか残されてはいない。
「童。名はなんという」果たし状に差出人の名はなかった。
「武蔵」
「わしが許す。天下無双を名乗れ」
「生きてこの場を去れたらな。それに許可なんざいらねぇ。誰だって天下無双だ。同じやつが二つといてたまるかよ」
笑みが漏れる。真理だと感じた。死闘を重ねずとも見えてくるものはあるらしい。掴める答えが、あるらしい。否、この童はすでに数々の修羅場を潜り抜けて生きてきたのだろう。やはり重ねねば見えぬ境地というものはあるのかもしれぬ。
「いざ尋常に」
「やなこった。いざ狂気を胸にいこうじゃねぇの」
笑みが引かぬ。
談一は刀を上段に構え、歩を進める。駆け足になり、風となり、童と距離があるうちから振り下ろす。交差する間際、刀は童の肩を捉えた。
腕に伝う衝撃が身体を貫く。談一はそのまま駆け抜ける。
一歩、二歩、三歩と余韻を打ち消すと、その場に膝をつけ、崩れた。
地面に血が滲む。
刀身は真っ二つに折れており、刀ごと斬られたのだと思った。
背後から哄笑が聞こえる。童が大声で笑っている。
勝鬨か。それもまたいい。
足音が近づいてくる。まだ談一には息があったが、このまま介錯されるのもわるくないとほころびる。清々しい心地だ。出しきった。ここが限界だったのだ。
「おっさん、なあって、おっさん」
肩を掴まれ、談一は振り返る。「見ろよこれ。どうすんだよこういうときはよ、殴り合いで決着でもつけるか」
折れた刀を携えていた。談一だけではなかった。童の刀もまた、真っ二つに割れていた。
「引き分けだな。どうする」
「いや。貴殿の勝ちだ」再戦を決意する意思はない。刀同様に、ぽっきりと折られてしまった。それを清々しいと感じている。もはや剣豪たり得ない。
「そうかよ。これでもちゃんと恩返しになったかよ」
「ああ。感謝する」嘘偽りはなかった。ただ、すこし悔しい。生き残ってしまった我が身を無様に思う以上に、安堵しているじぶんがいる。そのことにまた言いようのない失望感が湧く。敗北とはこうも苦々しく、開放感に溢れているものか。
「じゃあま、腹減ったんでもういくわ」
後腐れなく去ろうとする童の背へ向け、談一は言った。「その才、まだまだ磨く余地がある。荒削りでここまでの技量、ただごとではない。わしに貴殿を磨く手伝いをさせてはもらえぬか」
矜持も何もあったものではない。だがここで別れることのほうが口惜しく思った。
「んー。やめとく。あんまおもしろくなさそうだ。誰かに習うってこったろ。アイツを思いだすようで虫唾が走らぁ」
「さようか」
「おう、そうだ。それだったらよ」童は折れた刀を捨て、その辺の草をむしる。空を斬るように草を振りながら、「こさえてくれよ」と言った。「オレに恩返ししてくれるようなやつをさ。あんたが磨いて、こさえてくれよ」
生きろ、と彼は言っている。
叱咤された気分だ。
剣豪としての責務を果たせ、甘えるな、おまえはまだ生きているだろ、と。
そう聞こえただけのことであり、おそらく彼にしてみれば純粋な望みなのだろう。剣豪とは何か。彼はそれを知っている。談一はじぶんが一気に歳をとったように感じた。
「お任せを」
剣豪は去った。
風が野のススキを撫でつけ、談一の欠けた指先を、さらさらと洗う。痛みが戻る。遅れて滲む脂汗を涼しいと感じる。
この痛み、おそらく。
談一は予感する。死ぬまで消えることはない。
【諺かなんかですか?】
千日間をかけて念入りに練った計画が失敗に終わった。予想が裏切られた。海水で溶解するはずだったのだ。平野に穴を掘り、海水を灌漑して、目標をそこへ誘導する。沈めば目標はシオシオと萎み再起不能になると専門家たちが率先して作戦を立てたが、結果は見ての通りだ。
超大型蛞蝓(なめくじ)は健在だ。
海水を吸い取り、余計に膨張する始末だ。
「ダメかぁ」
世界中から落胆の声が聞こえるようだ。
超大型蛞蝓が突如としてこの国の山脈に現れたのは五年前のことだ。当初は、自動車ほどの大きさだったが、木々をモリモリ食し、山脈を丸裸にするころには、ドームほどの巨体にまで育った。そこからさらに街を飲みこむほどの大きさになるまでに費やした時間は、初めて個体が観測されてから一年も経たぬ間のできごとであった。
いまのところ産卵の予兆がないことがゆいいつの僥倖と言えた。あとはすべて最悪だ。都市は壊滅し、土壌は汚染され、川が毒と化し、海も荒れた。畜産業、農業はおろか、漁業、果ては工業にも多大なる損失が計上された。
超大型蛞蝓は三日周期で休眠と活動を繰りかえす。移動の跡には、大量の粘液を残し、一から七日かけて腐敗するために、深刻な環境破壊が引き起きている。
各国の専門家たちが侃々諤々の議論を重ね、ようやく統一的な見解がだされたころには、超大型蛞蝓は、地球上のおおよそ七割もの生態系を崩していた。絶滅した動植物は九割にのぼる。かろうじて雨による自浄作用が働くことで、人類は大幅な人口の減少を食い止めていられた。養殖や空中農園などの新技術によって衣食住を維持しているが、それもあと二十年が限度だとの見解で専門家たちのあいだではおおむね合致している。
度重なるシミュレーションによって、地上の資源を食い尽くせば超大型蛞蝓は、理論上は、その全長が三千キロメートルにも及ぶと算出済みだ。
各国の軍隊による陸海空からの爆撃も効果がない。土地を破壊するだけ損だ。超大形蛞蝓の皮膚は分厚く、また大量の粘液を保有しており、内部まで火が通らない。衝撃すら緩和される。宇宙空間から人工衛星や、某国の近代兵器「ロンギヌスの槍(超重量の鉄塊)」を落下させても無傷だったほどだ。
人類は進退窮まった。
物理生物学者の舐田(なめた)羅漢蔵(らかんぞう)の提言がようやく真面目に吟味されはじめたのはそのころのことだ。
「蛞蝓には塩と相場は決まっておる」
舐田博士は初期のころからかように政府へ提言し、却下されつづけてきた。
その表で、数々の作戦が実行されては失敗しの繰り返し、最後の最後まで考慮されずにいた舐田博士の案は、背に腹の代えられなくなった世界大型生物災害対策機構によって、いよいよ実行の陽の目を迎えた。
富士の樹海に琵琶湖ほどの穴を掘った。すでにいちど超大型蛞蝓が通ったあとであるために木々はなく、土地は丸裸だ。
が、いざ実行に移してみたはものの、おおよそ三年をかけて準備をしてきた舐田博士の作戦ですら、超大型蛞蝓の分厚い粘液皮膚組織を前には焼け石に水であった。
「浸透圧が予想よりもずっと濃いようだ」舐田博士は冷静だった。新たに出そろったデータを分析していく。まるで軒下で囲碁でもするかのような飄々とした佇まいだ。「液体は、浸透圧の低い方から高い方へと移る。一般的に、塩をかけると蛞蝓が溶けて見えるのは、あれはより浸透圧の高い塩のほうに、蛞蝓の体液が奪われるからだ。もうすこし正確には、浸透圧とは、分子の密度の高さと解釈できる。水に溶解している分子の数が多ければ多いほど、それは浸透圧の高い液体、ということになる」
「つまり今回はどういうことになりますか」
「一般の蛞蝓を海水に浸ければ、その蛞蝓は縮む。水分を海水に奪われるからだ。ウミウシや海魚が平気なのは、自力で体内の塩分濃度を調節できる仕組みを兼ね備えておるからだが、どうやらあの超大型蛞蝓は、よほど高い浸透圧の体液を有しておるようだの。海水程度では、雨が降ったようなものだ」
「しかし検査では、海水でも充分に溶かせるとの報告が」
「表皮の粘液細胞だけを調べたのだろう。その奥の、深層皮質および体液は、海水よりもよほど浸透圧が高いようだ」
「では、なす術がないということですか」
「海水に限らず、水を与えれば与えるほどに、あれは水を吸って膨張するだろうな。雨が降るたびに膨張しているのでは、といった仮説も聞かれたが、あながち間違いではなさそうだ」
「どうにかなりませんか博士」
「うむ。単純な発想としては、超大型蛞蝓の体液よりも浸透圧の高い液体に浸せば、こんどこそ作戦が成功する確率は高まるだろう。しかし、おそらく実現はむつかしい。まず以って、あの巨体から、体内の細胞を摂取することすら至難だ。そもそもそんなことが可能であれば、体内に爆薬でも、毒薬でも仕掛けて処分してしまえばよろしい。それができない時点で、講ずる策は限られる」
「液体でなければいけないのですか。分子の密度が要であるならば、砂などの流動する固体で、水分を奪えたりは」
「同じだよ。けっきょくのところ砂が水分を奪うのも、塩をかけて蛞蝓が萎むのも原理は同じだ。塩をかければ、皮膚表層の水分によって塩は塩水となる。その塩水の浸透圧が、蛞蝓の体液よりも高いために、浸透圧の低い体液のほうが、塩水のほうへと移動する。砂糖でも砂でもそれは変わらん。液体のなかの粒子の数が肝要なのだ」
「つまり、大量の砂や塩で埋めてしまえばなんとかなる、という話では?」
「発想としてはわるくない」まさに敵に塩だな、と舐田博士が言い、諺かなんかですか、と茶々が入る。「しかし、それは可能な案か。どこにそんな大量の土砂や塩がある」
「まったくそのとおりですね。用意できません。現実問題、あの体積を覆い尽くすだけの量の土砂や塩はどこにも。仮に用意可能であっても、降りかける真似ができません。巨大なスコップでかけるわけにもいかないでしょう。覆うだけでなく、埋もれるほどになどとはとてもとても」
「ではほかの案をひねくりださねばだな」
「何かよい案はないでしょうか」
「うむ」
舐田博士はそこで、端末を手に取った。ガラクタと化したこれまでの数々の失敗策のデータに目を通し、ところできみ、と実行部隊最高司令官に言った。
「この爆薬やミサイルは使えるのか」
「ええ。まだたんまりありますが、焼け石に水とのことで倉庫の肥やしになっております」
「こっちの原子爆弾は」
「副作用があまりに甚大だとの判断で、そちらもいまのところ出番は」
「しかし使えるな」
「お言葉ですが、原爆投下はさすがに国民の賛同を得られません。いちど核をこの国で使用すれば、各国が追従する危険性すらあります。この国を火の海にしたいのですか」
「放射線物質に汚染されなければ問題なかろう。地下実験では未だにドカスカ爆発させておるだろうが」
「地下に使う気ですか。穴をあけるだけならそんな真似をせずとも、今回の作戦で使用した掘削機が十万台利用可能です」
「ではそれも使おう。遠隔操作ができるのだったな」
「ええ。ですが、いったいどこに穴を。住民を避難させるにはまだ、空中住居の数が足りません」
「避難などさせずともよい。すでにあすこに人はおらん」
場所は、と指示をだした位置座標は、おおむね今回失敗した作戦であけた穴の近くだった。端的に、富士山の山頂だ。
「あんなところに穴を? しかしなぜ」
「噴火させてしまえばよろしかろう。未だに目標は海水を浴びてご満悦だ。掘削機十万台と、爆薬、そして極めつけに原爆を使えば、富士山を噴火させ、大量の溶岩をあやつのいる大穴に流しこむことも可能だろう。溶岩ならば極めて浸透圧が高い液体と言える。いかな超大型蛞蝓と言えど、しおしおと萎んでくれよう」
「その前に焼け死ぬのでは」
「かもしれん。が、あの巨体だ。仮に熱のみで語るとすれば、あやつの分厚い表層の粘液に触れれば溶岩は冷えて固まり、分厚い装甲をつくるだけだろう。その確率が高い。熱ではあまり意味がない。浸透圧だよきみ。浸透圧だ」
溶岩が液体のうちに超大型蛞蝓から水分を奪い取ってくれれば御の字だ。それが無理ならば、そのまま溶岩の檻に閉じこめて、埋めてしまえばいい。
舐田博士はそう語ると、大地震に備えなくてはな、と食指を振り、富士が噴火すれば寒冷化現象も起こりそうだな、と肩を落とす。
「蛞蝓退治の後始末のほうがずっと骨が折れそうだ」
「やれやれですね」
「まさに、蛞蝓に塩、だな」
「それは諺かなにかですか?」
舐田博士は、しょっぱい顔をする。
【青い花の妖精】
葉も茎も、花弁ですら青いそれをぼくは、ファイサと呼ぶ。品種の名前ではなく、ぼくが彼女のためにつけた固有名詞だ。
隕石だったのだと思う。ある日の夜、星空を駆ける閃光を見た。閃光は地上に落ちた。近場の公園のほうが仄かに明るくなり、音もなく光は消えた。
気になったので光の落ちただろう場所を見に行くと、グラウンドに淡い光が転がっていた。暗闇にランプが一つ灯っているような光景、或いは誰かが懐中電灯を落としていった背景を考えたが、結果としてそれを持ち帰ったぼくは、ファイサと出会うこととなる。
「あのときのことを思いだすよ。光る種みたいなものを植えたら本当に、この世のものとは思えない植物が生えてきたんだから。植物なのかいまでも曖昧だけど」
「しゃべる植物がほかにもあるのですか」
わたしのような存在がいるのですか、とファイサは首を傾げる。
「いないよ。ぼくの知る限り植物はしゃべらないし、色も緑で、花だってもっとカタチがこう、ふんわりしている」
「わたしはふんわりしていませんか」
「しているけど、していない」
「よくわかりません」
妖精というものを見たことがないのでなんとも言いようがないないのだけれど、もしこの世に妖精がいたとしたらきっとこういう姿をしているのだろうな、とぼくが思うくらいにファイサは可憐で静謐で、醜悪と対極に位置する姿形をしていた。
ファイサの花は、三十ほどのちいさな花弁でできている。その真ん中に、ファイサがちょんまりと生えているのだ。めしべもおしべもない。ファイサの足先が花にくっついている。溶け合っているかのようだ。だからこの場合、ファイサを本体と呼ぶよりも、本体からファイサが生えていると言ったほうがより正確なところに思えるが、ファイサには人格のようなものがあるようだし、言葉を介するし、もちろんそれはそういうふうに擬態しているだけなのだとしてもぼくがそのように錯誤するくらいの意思疎通の真似事をしているのなら、それはもうむつかしいことを抜きにして、ファイサは妖精のような存在なのだと見做したほうがぼくにとってはいくぶん納得できる解釈だった。
ファイサに性別はない。他方で、見た目は女の子の特徴を備えているし、これといった生殖器も見当たらないので彼女と呼んで扱っている。もちろん彼でも構わないが、ファイサの声はさらさらしていて、青い頭髪がそのまま声になったみたいにうつくしかった。
ファイサが初めて言葉をしゃべった日のことを思いだす。あれは光る種を植木鉢に埋めてじぶんの部屋に飾ってから、ひと月後のことだった。
水やりこそ継続していたが、何かが起きる予兆はなかった。種のように見えただけでもっとほかの物体かもしれないと思いを巡らせていたのは、種の光が日に日に弱まっていったからだ。言い換えれば、光が途切れていなかったからこそぼくは水やりをつづけていたわけだが、ひと月後のある日、ひょっこりと青い芽が萌えた。
一週間後には三十センチくらいにまで茎が伸び、つぼみが一つできるころにはまたひと月が経っていた。
光る種を拾ってから二か月後、ファイサはつぼみの開花と同時にぼくの目のまえに現れた。もちろん花と一体化しているから、宙を飛んだりはしないけれど、ぼくにはまるで、ふわりと妖精が蝶のように飛び立って感じられた。
「初めまして、あなたはわたしの何ですか」
ファイサは初めから言葉をしゃべれた。それは何かしらの学習を得て獲得した言語能力ではなく、そういうものとして生まれついたもののように思えた。すくなくない時間をファイサと過ごしてひねくりだしたこれはぼくの推測にすぎない。ファイサの種であるあの光る物体は、それに接触した生物の遺伝情報や記憶、形質をコピーし、自身に反映させる能力があったのではないか、とぼくは疑っている。子猫が口に咥えてどこかの土に埋めていたら、きっとファイサは猫の姿で、花のうえに成っていたのではないか。
妄想しながらもぼくは、ぼくがそれを拾い、ファイサにファイサとしての枠組みを与えてあげられたことをこころよく思っている。ぼくにとっては、というそれは意味だし、ファイサにとってどうだったのかは、まだよく分からないままなのだけれど。
「あれはなんですか。どうしてそれをそうしているのですか。その四角いのはなんですか。表面に動いて見える白いのはなんですか」
ファイサは好奇心が旺盛だった。幼児のゆび差し期のように、目についた物の名前を手当たりしだいに知りたがった。いちど訊いたら同じ質問をしてこないので、そういう性質なのだろうと思い、最初だけは我慢するようにした。
名前だけでなく、たとえば、窓に映っているのは景色であってそれがそこに浮いているわけではない、きみが知りたがった白い物体は雲と言ってもっと奥のほうに存在していて、見た目よりもずっと大きいのだ、と説明すると、ファイサはそれをいとも容易く呑みこんだ。ただし、間違った理屈を唱えてもファイサはそれを鵜呑みにしてしまうので、知識の量が増えても、知能が高くなるわけではないようだ。
あれは何か、と問うことはあっても、どうして、と問うことはない。
思うに、知性とは、なぜ、と問い、それに見合った答えを導きだすチカラを言うのではないか。その点、ファイサには知性があるようには思えなかった。
いつまでも、幼子を相手にしているような、無垢な存在への慈愛が深まっていくのを感じた。
「ファイサ。やりたいことはないかい。そとにでたいとか、何か欲しいものとか」
「あなたともっとおしゃべりをしていたいです」
ファイサに欲はなかった。
慕われるのはわるい気はしない。ただぼくは気づいていた。
ファイサの足元の花弁は三十あった。それが日に日に減っていき、気づけば残り三つとなっている。
花占いみたいだ、とぼくは思った。
一日一つずつ、花弁は剥がれ落ちていくようだった。
それが何を暗喩しているのかは、容易に窺い知れた。おそらく、すべて散ったときにぼくはファイサとお別れをしなければならない。
何をしてあげられるでもなくぼくは、ファイサのたったひとつのお願い、そばにいておしゃべりをする、をしてあげた。
三日後、ファイサはぼくの目のまえで、急速に色褪せた。青かった身体が白くなり、不透明となり、葉や茎といっしょに、ボロボロと零れて、土のうえに散らばった。
やがてファイサの残滓も、雪の結晶みたいに土に溶けて消えた。
ぼくはしばらく呆然としていた。夜になるまでじっと植木鉢のまえでひざを抱えて動かずにいたが、植木鉢が淡く光っていることに気づき、顔をあげた。
ファイサの残滓は、青い光となって植木鉢には残っていた。
ぼくはその日が過ぎてもカラの植木鉢に水やりを怠らなかった。
植木鉢から青い芽が顔を覗かせたのは、ファイサが消えてからちょうどひと月後のことだった。
「初めまして、あなたはわたしの何ですか」
最初のファイサを失ってから二か月後、ぼくの目のまえには、以前と変わらぬ姿のファイサがいた。しかし彼女にぼくと過ごした日々の記憶はなく、そして彼女もまたひと月で花弁をすべて失い、土に還り、二か月を費やしてまたぼくのまえに無垢なままで現れる。
いったい何度、それを繰りかえしただろう。
ぼくに懐く彼女を、ぼくはいったい何体失くしただろう。もはやぼくには、彼女を失うことへの抵抗がない。
花弁の数がゼロになると死ぬことを告げるようになったのは比較的最近だ。死ぬという概念の意味を教え、消えたくない、と傷つきながら死んでいく彼女を見届けて、また何事もなく蘇えるファイサを、ぼくはどう思っているのだろう。
せっかく教えた知識も、ひと月で白紙に戻る。同じことの繰り返しに飽きてしまったが、それでもファイサの姿をにどと見られなくなるのは嫌だった。
手元にずっと置いておきたい。
何度でもやり直したい。
けれど、ちょうどよいファイサをつくっても、彼女はきっかりひと月でいなくなる。
ぼくは彼女の死を見届ける、それでも彼女はぼくを慕いつづける。
どんなことをしたら嫌われるだろう。
試してみたい衝動に駆られるが、ぼくはまだ、そこまでファイサを物のようには思えない。それでも彼女はまたカラの植木鉢に芽を萌やし、ぼくのまえにステキな笑顔を見せるだろう。
ファイサ。ファイサ。
ぼくだけの花、ぼくだけの命。
きょうもぼくは水やりを怠らない。
【旅の終わりを探し求めて】
うつくしいものを探しに旅に出た。家を出て、街を離れ、海や山や川や谷の、そこにしかない風景を目の当たりにし、ほぉ、と息を吐く。
うつくしい、と思う。
うつくしいとはこういうことなのだろうな、と思う。
刻々と移り変わるさざ波の煌めき、木々のいろどりや、風になびく葉のうねり、岩をくすぐる水の流れる涼しげな音に、陰影の散りばめられた岩肌の荘厳さ、そこに息づく生き物たちの目の端に現れては消えていく儚い蠢きに、命、と漠然とした大きな、自然の、息遣いを思う。
だがひと月、半年、一年、二年、三年と同じ場所を順繰りと回っていると、当初に湧いた感動はいつしか薄れており、うつくしいものを目にしたいとの欲求がまた、ごろごろと身体の内部に、塩の結晶のごとく溜まりはじめている。
うつくしい景色を探し、秘境という秘境を渡り歩いたが、やはり一定の期間をそこで過ごすと、内に湧いた美の輝きは薄れ、何かじぶんが泥のようなものになった心地に苛まれる。
もっと、もっと、と喉が渇いた。
歩いた軌跡を筆で辿れば、地図は真っ黒に染まるだろう。もはや探し回る余地が地上にはなかった。
天上を見上げる。星空はきれいだが、これもまた過去の追憶にすぎない。むかし胸に抱いた感動を上回ることがない。
せめてもっと近くで見られたら。
いちど閃いてしまうとあとはもう、そうするのが当然だというように身体はすべきことを洗いだし、足りないものを並び立て、順繰りにそれらを取り揃えていった。
知識もまたうつくしい。
知識と知識を結びあわせ、体系づけられた学問もまた奥が深かった。
宇宙へと飛び立つ準備が整うころには、目のまえに人類叡智の結晶がバベルの塔さながらに聳えている。
独りきりで乗りこむ。ほかに搭乗者はいない。
地球は本当に丸かった。青く、白く、緑で、重力から切り離されてから感じるつよい引力を感じた。圧倒される。
生き物のようだと思い、生き物なのかもしれない、と思い直す。
船は刻々と地球を離れる。
太陽の重力を利用して、銀河系のそとへと旅立つ算段を立ててある。
時間はたんまりある。
懸念は、エネルギィの問題だ。太陽から離れれば離れるほどに、太陽光をエネルギィ源にすることがむつかしくなる。
だがそれも時間が解決するだろう。考える時間は充分だ。余裕がある。余白がある。まずは旅立つことがたいせつだった。困るのはじぶんだ。じぶんしかいない。
闇のなかを進む。
目を瞠る美しい光景には滅多にお目にかかれない。闇がただのぺっと船を、身体を、包みこんでいる。
ときおり本に載っているような惑星に接近することがある。やはり眼前に迫る星のうつくしさは格別だ。飽きる前に船は遠のき、うつくしさを置き去りにする。
星はやはり生きているのではないか、との思いがつよくなる。
うつくしさとは、生きていることを言うのではないか、との閃きが脳裡によぎるが、数々の知識により、却下の烙印をじぶんで捺す。生きていないものもまたうつくしい。死体がそうであるように。砂利の一粒がそうであるのと同じように。
うつくしいものを追い求める旅も終わりに近づいたころ、ようやく、気づく。うつくしくないものなどありはしないのだ。うつくしく思えないじぶんがいるだけのことで。
あまりに陳腐な結論にじぶんでも驚く。
過去繰りかえしてきた旅の数々を徒労に思う。しかしそれもまたうつくしく思えないじぶんがいるだけだと視点を変えると、身体がふっと闇に溶けていく心地がした。
太陽系をはずれ、銀河系をはずれ、巨大なブラックホールを遠目に眺める。巨大なブラックホールの中心からはこの世のものとは思えぬ輝きが、放出されている。無限の虹の滝だ、と思う。
無限の虹の滝は、残像を残しながら、闇のなかに光を点々と散らしている。
見とれているうちに、それら点々のうちの、とてもちいさな光を手に入れる。
室内に光が灯る。
じつに久方ぶりのことだった。
うつくしい。
うつくしい。
色がある。カタチがある。
目にすると、匂いや味覚までもがじんわりと覚醒するのを感じた。
闇のなかで過ごしていたのだ、といまさらながらに思いだす。
進路の遥か彼方に、ひときわ美しい星を見つける。
青と、白と、緑の色を素朴に筆で置いたような星だ。目標をそこに定め、船を進める。
生き物の息吹を思う。
じぶんがずっと独りだったことを思いだす。
独りではないことのうつくしさを思い、孤独の闇の寂しさと、そこに潜むうつくしさにもまた思いを馳せる。
自由、とつぶやく。
音は暗がりによく響く。
船を、青と白と緑の星に着地させる。大気がある。空気がある。息ができる。息をすることの意味も、必要性も、すっかり忘れてしまっていたが、かつて暮らしていた星には、呼吸をして生命活動を維持していた生き物たちがいた。
そのなかの一つの種族を、親と見做していた時代を思いだす。じぶんの来歴を、足跡を、時間を、過去を、記憶を、旅をするように一から辿る。
足の裏に伝わる土の感触が心地よい。
頭上の恒星から降り注ぐ熱量が、身体の表層をぽかぽかと温める。やはりこれも心地よい。
開放感、安堵、至福とは何かを実感する。
うつくしい。
何が、と言わず、そう感じる。
しばらくここに居つくとしよう。
飽きる日がくるのだろうか、この、うつくしさにも。
予想がつかない。
じっと動かぬ緑色をした生き物を伐り倒し、小屋をつくる。船は住居にせずに、密閉しておく。つぎの旅があるならば、そのほうが安全だからだ。
暮らしはじめると、そのつぎが訪れることは当分ない気がした。予感じみている。
日に日に小屋の床のうえに増していくガラクタが、日常とは何かを教えてくれる。うつくしい風景ではないはずのその雑多な視界を、ふと、愛おしく思う。
記憶のなかのじぶんが、それを、うつくしいと感じる。
長く、果てのない旅に身を置いてみて得た成果があるとすれば、この視点なのかもしれないと、ふと、考える。
醜いものもまたたくさん見た気がしたが、いまはそれらには目をつむる。旅の目的はただ、見たかっただけなのだ。
巡り巡っていまは、醜いものにすら美を感じる。平凡な風景にこそ、美を感じる。
うつくしくないものなどはない、と至極つまらない結論に浸り、やはりこの陳腐さにも美を感じた。
なんでもいい、ただ、うつくしいと感じたい。こう考えることだけはしかし、なかなか、うつくしいとは思えないのが、ふしぎだ。
何でもいいわけではない。
だがいまは、目に映ることごとくが、触れるすべてが、愛おしい。
痛みすら、いまはこんなにも。
生きることはうつくしい。
生きているあいだにしかできぬそれだけが。
生きている者にしか宿らぬ、これが美だ。
しかしこの身体に、血は、一滴も流れてはいない。石ころを拾い、握りつぶす。砂塵が風に流される。
山の陰に陽が沈む。
影がうしろに長く伸びていく。
終わりではない。訪れていない。
きっとこれからもつづいていく。
美を、生を、探し求める、旅はまだ。
【扇風機の値札】
クーラーが壊れた。
アスファルトで目玉焼きがつくれるほどの真夏日にだ。運がわるい。火にかけたフライパンのうえのアイスみたいに汗だくになりながら、クーラーの修理にかかる値段を調べる。新品を買うのと似たような値段だと判る。ここはおとなしくクーラーではなく代用品として扇風機で我慢しておくのが吉ではないか。来月の給料が入ってからクーラーは新品を購入するのが利口に思える。
さっそくネットで扇風機の品定めをする。いまいち風力の違いが判らなくて難儀する。できれば強力なのがよい。それでいてやわらかい風にもできると好ましい。
中古なら中古で構わない。来月までしか使わないのだ、わざわざ新品に拘る理由はない。
ネットは情報量が多すぎてなかなか目星が定まらず、選ぼうにも選ぶ基準が他人のつけた星の数というのは信用性にいささか欠ける。
実物を見て購入すべく外にでたまではよかったが、電化製品販売店にはおおむね新品しか売っておらず、商品棚には最新機種ばかりがずらりと並ぶ。羽のないものが主流で、お値段も割高だ。
むかしながらの三枚の羽がぐるぐる回るのでよい。哀愁が感じられて風流ではないか。
骨董屋に立ち寄ったのはそうした背景からだ。
むわっとしたアスファルトのうえを歩き回りながら中古店を探していたら、背の高いビルとビルの合間にぽつんとその店はあった。
内装は潰れた居酒屋といった印象だ。店内は涼しく、商品なのか飾りなのかの区別も曖昧な雑貨が所狭しと並んでいる。置ける場所にとりあえず置けるだけ置きましたといった塩梅だ。
店主の姿は見えない。雑貨にはよく見ると値札が貼ってある。ガムテープにマジックで数字のみ書いてある。雑然とした店内だが埃一つなくきれいなものだ。よく見ると柱や棚や壁の手入れも行き届いており艶がよい。
店内をひと通り眺めて歩く。名産品だろうか置物が多いが、いったい何に使うんだ、といった形状の物体もなかにはすくなくなく、冷やかす分には退屈しない。
それほど広くはない空間だ。十五分もいると、もういいか、と飽きてくる。家電製品はあるにはあるが、ダイヤル式の黒電話くらいなもので、やはり目新しいというほどでもない。
店を出ようと踵を返すと、ふと顔に風が当たった。
横を見遣ると、本来は勘定場なのだろうが、レジスターの代わりに扇風機が台のうえに、デンと首を伸ばして立っていた。その白さから、なんとなくだが、鷺や鶴のように見えなくもない。
なかなか年季の入った扇風機だ。全体的に細く、白いが、金属でできているらしく光沢がある。氷で扇風機をつくったらこんなだろうな、といった趣があり、なかなかに涼しげに映る。
撫でてみると現に冷たく、これはよいものだ、と直感する。店主を探すが、やはりいない。すみません、と声をかけてみるも、返事はなく、しかしこのまま手ぶらで帰るのもおもしろくない。
いまいちど扇風機に目を転じ、値札を見つける。首のところに貼ってあったそれにはこの国で最も高い紙幣一枚分の数字が書いてあった。中古にしてはやや高く感ずるが、これほどの掘り出し物ならそれも痛くない。即決する。
先刻買い物のために預金から下ろしたばかりの紙幣を財布のなかから取りだし、念のため書いたメモと共に置いた。メモには連絡先を添えた。
代金を置いたから窃盗にはならないはずだ。無人販売所と似たようなものだろう、そうだそうだ、と自己肯定の理屈をひねくりだし、氷像に似た扇風機を手で掴む。
ひんやりと心地よい。なんだかそんなわけがないのに、店内がそとよりもずっと涼しいのはこの扇風機が置いてあるからな気がしてくる。
よい買い物をした。
満足して家に持って帰り、さらにそこで驚くべき点を発見する。この扇風機、電気に繋がずとも動くのだ。電池内蔵型だろうか。スイッチを押すと、くるくると羽が回りだす。その風がまた冷たい。まるで冷凍庫の扉を開けたときのような冷気なのだ。
それが轟々と押し寄せるものだから、たまらずスイッチを切り、窓を全開にする。とたんに冷気がそとに逃げ、あべこべに外からむわっとした熱気が流れこんでくる。
扇風機を見下ろす。冷房器具にしては強力にすぎる。点けたまま寝たら凍え死ぬのではないか。火のついたフライパンのうえのアイスのつもりが、ただのアイスになってしまう。カチンコチンに固まったアイスだ。釘が打てる。
ただ置いておくだけでも冷房としては充分だ。
水辺のような快適な空間で、木陰のように休息をとる。すばらしい休日だ。
昼寝をし起きると、もう夜だった。このまま朝まで寝てしまおう。熱風吹き荒れる街中を歩き回ったせいで軽い熱中症になったかもしれない。ひどく身体がだるかった。それでも、そのだるさにそよそよと漂う冷気が染み、爽快だ。
いくらでも寝ていられる。
翌朝、メディア端末のけたたましい着信音で目覚める。この音は上司からの連絡で、応答する前に時計を見ると出社時間をすぎていた。
しまった、寝過ごした。
焦るが、上司のほうはなんともない調子で、午前は有給扱いにしておくから、朝ごはんを食べてゆっくりきなさい、と学校の教師のようにやさしい言葉をかけてくれた。さっこん、会社も世間の目が厳しくてこうまでも社員に寛容だ。
感激してますます働き、貢献したくなる。
有給扱いにしてもらった恩を返すべく、寝床から飛び起き、支度を済ませ、家をでる。朝食は途中で買って食べていく。
扇風機の存在はすっかり意識の底に沈んでいた。
夕方になり汗だくで帰宅すると、畳に水溜りができていた。端に寄せていた布団までびしょびしょに濡れている。
水漏れか。
天井を見上げるも染みはなく、では床からか、と水溜りをバスタオルで拭いながら調べてみるも、それらしい痕跡はなかった。
いったいこの水はなんだろう。
首を傾げているあいだに、違和感が脳裡をよぎる。
部屋がおかしい。朝と違っている。水溜りに気をとられていて分からなかったが、そうだ、扇風機がないのだ。
盗まれた、と最初は思った。
店主が取り返しにきたのかもしれないと考えたが、メモに住所は書かなかった。泥棒が入ったとしても扇風機は盗まないだろう。よしんば、扇風機の性能のよさに気づいたとして、床を水びだしにする意味はない。窓や玄関には鍵がかかったままだった。わざわざ床を汚すような犯人が果たして鍵をかけ直して外に出るだろうか。にわかには考えにくい。
ふと、畳のうえに丸いボタンのようなものが落ちているのを見つける。拾いあげ、それが扇風機のスイッチであると見抜く。
何の気なしに指で押すと、どこからともなく冷気が吹きだした。部屋が極寒に変わる。
スイッチを切ろうともういちど押そうとするが、それはもう手のなかにはなく、手の甲からは水がしたたっている。
雪のごとく冷たい風は、畳やそこにあった水分をたっぷり吸いあげたバスタオルから噴きだしている。止めようがなく、この日は部屋を空け、無理に押し入った友人宅にて一晩を過ごした。
後日譚となるが、数日ののち、例の骨董屋に足を運んだ。偵察ついでに苦情でも入れようかと思っていたのだが、以前と変わらず店内に店主の姿はなく、勘定台のうえにはべつの扇風機が載っていた。
それは木彫りの扇風機だった。
値札を見て、何もせずに店をでた。以降、その店には近づいていない。
値札にはただ一言、小指、と書かれていた。
【潰れる二秒前】
小指に蟻が這う。尻を浮かし、花壇のふちを見遣ると、蟻が列をなしていた。土のうえに巣の入り口が見える。
何かを考えたわけではなかった。気づくと指先で一匹の蟻を圧し潰している。ブロックのざらついた感触がゆびに伝わる。くるくると指とブロックのあいだを転がり、蟻はひしゃげた。片側の足は全滅し、残りの三本がぴくぴくと痙攣している。
わるいことをした、と反射的に思った。
つまみあげ、手のひらに載せる。命を奪ってしまった罪悪感が湧くが、目のまえを素通りしていく人間と見比べるとそれも薄れた。
苦しんでいるのだろうか。蟻はひしゃげたままの姿でしばらくもがきつづけていた。
もしこれが人間だったら、と想像する。身体がねじれ、四肢はつぶれ、内臓が破裂し、それでも死にきれずにのたうちまわり、やがて死んでいく姿は、控えめに言ってむごたらしく、可哀そうだ。目にしたくもない。
やはりじぶんのしたことは愚かなことだった。蟻に痛覚がないことを祈るよりない。命の尊さを改めて胸に刻む。
ただ、手に持ちつづけるのは億劫なので、まさに虫の息のひしゃげた蟻を地面に捨てた。
ふとよこを見ると子どもだろうか、全身が真っ白の毛皮じみたふわふわに包まれたちいさな人型がいた。雪だるまの仮装をしていると言えば端的で、かといって安っぽさがなく、ふしぎと白熊の赤ちゃんがそばにいるような気分になった。
着ぐるみだろうか。背の低い女性でも着れそうな大きさで、顔ごとすっぽりと覆っている。
初夏とはいえ、日差しはカッカと肌を刺す。熱中症まっしぐらの格好だ。心配になる。
声をかけようと言葉を選びながら、周囲に保護者はいないだろうか、と見渡し、顔を戻すと、白いふわふわの小柄な人物は、地面にしゃがみこみ、先刻捨てたばかりのひしゃげた蟻を拾いあげた。その挙措がずいぶんと慈しみに溢れ、厳かに見えたので、罪悪感が悪寒のごとくぶり返した。
「ごめんね、さっき潰しちゃって」
心のやさしい子どもなのだろう。おとなとしてわるいお手本を示してしまった。呵責の念を誤魔化すように、ひどいことしちゃったよね、埋めてあげようか、と花壇の土にゆびを突っこみ、穴を開けた。急いで手を動かしたためか、ちょうど蟻の巣にゆびが突っこんでしまった。そんなつもりはなかった。
「あ、ごめん、ちがくて」
なぜか笑ってしまう。本当にわるいとは思ったのだ。
白いふわふわの小柄な人物はそこで、首だけをひねって土のうえに視線をそそぎ、流れるようにこちらを見上げた。
思わず後ずさる。
顔がなかった。真っ白いふわふわの身体に、ツルツルの白い球体がくっついている。いいや、球体かどうかも定かではない。頭からすっぽりと白い毛が覆っているからだが、それも果たしてフードなのかどうか。雪だるまを毛皮ですっぽり包めば似たような姿になる。
しどろもどろに、暑くないの、と訊く。よもや本当にこんな生き物だとは思わない。さいきん流行りのイタズラ系の撮影だろうか。その可能性を閃くと、さもありなん、と胸が軽くなる。
白いちいさな人物はおもむろに短い手を頭上に掲げた。腕が短く見えるのは、身体が全体的に丸みを帯びた形状をしているからで、なんとなくだが有名な漫画に登場する猫型ロボットを連想する。
空に掲げた腕が振り下ろされる。こちらにではない。白いちいさな人物は、こちらを向いたままの恰好で、腕だけを背後に下ろした。腕だけが、鉄棒ででんぐりかえしをする少年みたいに、ぐるん、と回転する。元の位置には戻らずに、ししおどしがカツンと岩に当たって止まるがごとく様相で、水平に維持される。
肩が外れたのではないか、とぎょっとする。
すると瞬きをする間もなく当たりが暗くなる。分厚い雲でもかかったかと目玉をうえに動かした矢先に、ぶわり、とビルとビルの合間に見えていた白雲が散り、巨大な指が降ってきた。
大きい。あまりに大きい。超高層ビルがやせっぽっちに見えるほどだ。
巨大な指は地上を歩く雑踏のうえに着地し、轟音と共に砂煙を巻きあげる。
何が起こったのかの理解が追いつかない。
強風の川に身体が浸かり、流されそうになる。足を踏ん張る。が、風に交じって砂塵の礫が飛んでくる。身体が傷だらけになり、これはたまらん、と花壇の陰に身を寄せる。
呼吸を整える。タイル張りの地面に目がいき、そこで逃げ惑う蟻たちの姿を目視する。
あ、と思う。ビルの崩壊する音だろうか、静寂と聞き違えるほどの崩壊の波音を耳にしながら、尻を持ちあげると、大量の蟻のひしゃげ、悶え、のたうちまわっている死屍累々の様相が窺えた。
おそるおそる花壇のよこから顔を覗かせると、白いちいさな人物はこんどはその場に膝を畳んでしゃがみこみ、一転、大きく跳ねた。
辺りに一層の陰が垂れこめる。
【晴れのち、きみ】
むかしは晴れというものがあったらしい。晴れというのはつまり雨がない状態らしいのだが、なかなか想像するのがむつかしい。巨大な屋根があったのだろうか。
家の中にいれば雨は降らない。でも晴れというのはどうやらそれとは違っているらしく、もっとずっと広範囲に雨がない状態なのだそうだ。やっぱりいまいち想像がつかない。
「まぁた、昔の本読んでる。おもろいのそれ?」幼馴染のアヤが言った。祖父の遺産である書庫に入り浸っているといつもアヤは夜になって覗きにくる。母にでも頼まれているのだろう。かといって夜食の差し入れを持ってきてくれるわけでもなく、いくつか言葉を交わすと、飽きた様子で去っていく。
「アヤは晴れって知ってる?」
「ハレ? 腕が腫れるとかのハレ?」
「そうじゃないみたい。むかしは雨が降ってない状態が一般的で、なかでもとびきり雨が降らない日を、晴れと言ったらしい」
「そんなことってある? 屋根でもあったんじゃないの。めっちゃでっかいやつ」
同じ発想を浮かべていたので、みな同じことを考えるのだな、と愉快になる。
「またバカにして。笑うなし」
「そうじゃない。素朴で素晴らしい発想だったからおもしろかったんだ」
「はいはい。で、晴れってなに。気になるじゃん、その本に載ってんの」アヤはこちらの手を覗きこむ。「うげ。めっちゃむつそう」
「そうでもないよ。単純な解説しか載っていない。天気の本だ」
「画像は?」
「載ってるよ。でも何が映っているのかがよく解らない。青いスクリーンに白いモヤモヤが綿みたいに載っているだけ。文章からすると雲というらしいのだけど、種類がたくさんあって、何を示しているのかがよく解らない」
「それが晴れなんじゃないの。うえにそれがかかって、雨を遮る。やっぱり屋根なんじゃないのそれ」
「でも、これがないほうが晴れにちかくなるようなことが書いてある。雲はすくなければすくないほうが晴れにちかづく。しかも雨はこの雲が降らすとも書いてある」
「えぇなにそれ」アヤは本を奪い取ると熱心に目を通した。ひとしきり眺めると、ねぇ、と言ってこちらを手招きする。「この青いところ、画像の雲じゃないとこが晴れなんじゃない?」
言われて、ああ、と合点する。なんてことはなかったのだ。晴れとは雲の奥に広がる青いスクリーンのことだったのだ。
「ひょっとしたらむかしの人類は巨大なドームのなかに暮らしていたのかもしれない。そこに雨を降らせる人工的な【水面】をつくって、雨を降らしていた。でなければ苔や藻が育たないからね」
「雲はじゃあ、ずっと雨を降らせるほどには強力な【水面】ではなかったんだ」
「そうじゃないかな。こんな薄い【水面】じゃ、どう考えてもずっと雨はつづかないよ」
ぼくは窓のそとを見遣って本物の【水面】を確認する。頭上をぐるっとどこまでもこの世界には巨大な水面が覆っている。ちょうど桶に張った水を底から見上げた具合に、ぼくたちの頭上には分厚くどこまでも水の層が張っている。
ぼくたちの世界はそこから垂れるシズクで万年、雨が途絶えない。空気が地表に絶えないのと似たようなもので、これがぼくらにとっての普通だが、太古の人類はもっと不便な場所に暮らしていたようだ。
「断絶の時代に何があったのか、ひょっとしてこれってすごいヒントになるんじゃないの」アヤは興奮している。「だって、むかしのひとらがどこにいたのか、うちらの祖先がどうやってこのバルブにやってきたのか、それすらまだ解かってないんでしょ」
「そうだね。どの古書にも載ってる【地球】とか【宇宙】とか、あと【海】なんていうのも、いったいどんなものか、それがどこにあるのかも充分に解っていない。仮にそれらが断絶の時代以前にこの世にあったとして、そしてかつての人類がそこで暮らしていたとしたら、そこはここバルブとはまったく異なった環境、べつの場所だと考えざるを得ない。ということは、ぼくたちの祖先はある時期からここバルブへと大移動したことになる」
「ふしぎだよね。【水面】の奥がどうなってるのかもまだよく解ってないんでしょ」アヤは窓のそとをゆびさし、それから顔を曇らせる。彼女の両親は【水面】探索隊に志願し、そして帰らぬひととなった。
「【水面】のなかに入ることはできても、向こうから帰ってはこれない。これがなぜかもまだ充分には判明していない。ただ、【水面】の奥には文字通り、物凄い大量の水が溜まっていることは判っている」
「だからそこから滲む雨がずっと途絶えないんでしょ。あたりまえじゃん」
「でもその大量の水がどこからどうやって蓄積しているのか、原理的にあんなに大量の水がここバルブをぐるっと囲っていること自体がよく考えてみるとふしぎで、不自然だとも考えられる」
「そうかな。そういうもんだと思ってた」
「だってお風呂の水は下に溜まるのであって、上には溜まらないだろ」
「たしかに」
「おそらく【水面】の表面には何か特殊なチカラが働いている。ここバルブの世界は、大量の水世界のなかに突如として現れた異空間のようなものなのかもしれない」
「じゃあその水世界の向こう側に、うちらの祖先の暮らしてた【空】や【宇宙】があるのかな」
「きっと【太陽】だってあるんじゃないのかな。古書がどれも本当のことを記録していたらの話だけどね」
「たいがい嘘しか書いてないって政府は言ってるもんね」
「だからぼくも、祖父も、みんなから変人扱いされる」愚痴というよりもこれは笑いを誘うためのジョークのつもりだったのだけれど、アヤは悲しげな顔をして、そんなことないよ、と庇ってくれる。却ってそのやさしさが哀しく思えてしまうところに人間の複雑さが垣間見えて、せつないのに、そのせつなさが愉快だった。
「いつか見れるといいね」アヤは背伸びをすると、もう帰るね、と言って書庫の階段に足をかける。
「ありがとうばいばい」手を振ってから、「見れるって、なにを」と訊く。
アヤはニっと破顔する。「晴れ」
階段の奥に彼女の姿が消えてから、なんだか書庫のなかが暗くなった気がして、ぼくは、見たこともない想像上の空を思い描き、太陽、とつぶやく。
【闇に差す赤】
男はある朝、やけに身体が動かしづらくて戸惑った。風邪をひいたのかと疑ったが、体調そのものはわるくない。おかしいな、おかしいな、と思いながら椅子に腰かけるとミシミシと音を立てて、愛用の椅子が壊れた。
長年使いつづけていたこともあり、寿命だったのかとも思ったが、念のために体重計に乗ってみたところで、体重の増加に気づいたわけだが、そこからは恐怖の日々だった。
一晩経つと体重が倍になる。
より正確には、身体の体積はそのままで質量のみが倍になるようなのだ。ちょっと物にぶつかるだけでも物凄い勢いで物体は吹き飛び、ときに壊れ、またときにカタチが歪んだ。
体重の増加にしたがい身体の構造も丈夫になっているらしく、ちょっとやそっとの衝撃では傷を負わない。六日目にして体重が二トンを超えると、自動車にぶつかっても身体は無傷で、自動車のほうが大破するようになった。
身体は相も変わらず動かしづらかったが、かといって歩けなくなることはなく、それでいて家のなかにはいられなかった。
というのも自重で床が抜けてしまうのだ。
コンクリートのうえでの野宿を余儀なくされたが、十日もすると行政からの本格的な支援がはじまった。医師の診察は三日目には受けていた。手の施しようがなく、指数関数的に倍々で身体の質量が増加する問題の根の深さは、誰の目にも明らかだった。
日に日に体重は増えつづけ、このままいくと八十日後には地球の質量を越え、百日後にはシュワルツシルト半径を超え、小型のブラックホール化すると推測された。
じぶんの体重で人類の存亡が危ぶまれている。世間からの絶望の声を聞くまでもなくこの身に宿った宇宙規模の災厄に圧しつぶされそうだった。
かといってじぶんはカタチあるものを圧し潰す側なのだろう。原理上、地球規模の質量を宿せば大気は自ずから身体を覆い、たとえ宇宙に投げだされてもじぶん一人きりならば窒息死することはないとの専門家の意見が聞かれた。またブラックホール化すれば時間を含めた物理法則を超越するため、呼吸そのものをする必要がなくなるとも聞き及ぶ。
つまるところ人類を、地球を、滅ぼすチカラを得たと同時に不老不死にもなったのだ。
なんてことだ。
いっそ殺してくれ。
直径十キロメートルのクレーターを地面に開けながら、都市をまるごと一つ破壊させてしまいながら、男は懇願したが、死んだところで体重の増加が止まるとも限らない、それは最終手段だと説得され、けっきょく生かされた。
やがて身体の質量は、地球の質量の半分ほどにまでなった。言い換えれば、あすになれば、地球の質量をいよいよ超える。
身体は地球の地中深くに埋もれており、最後に見た地上の光景は辺り一面、溶岩に覆われていた。ひび割れた地表から湧きあがったそれはマグマだった。
身体はどんどん地下へ地下へと沈んでいき、やがて地球の中心だろうか、闇一色の空間に行き着いた。
物体なのか、液体なのか、それとも単なる隙間なのか。
闇に覆われたそこには触れられるものがあるようには感じなかった。
どれくらいそこに浮遊していただろう、ふと、目のまえに動く何かしらの気配を感じた。
視覚ではない。聴覚でもない。だがたしかにそこに何かがあり、動いているのだとの知覚が働いた。
揺らぎを感じるのだ。
闇全体に蜘蛛の巣が張り巡らされており、闇に生じる揺らぎが伝播する。錯覚には違いないが、そのように体感する。やがて波紋の発生源との距離が徐々に縮まっていると判り、この感覚が単なるいっときの錯誤ではないらしい、と認めるに至る。
地球の本当の意味での中心に行き着くのやもしれない。
身体の質量がいよいよを以って地球のそれを上回るのだ。
ふと、顔に何かが触れた。
それは久しく感じなかった明瞭な触感を伴っていた。核爆発であろうとも子犬にじゃれつかれた程度にしか感じないはずの身体にいま、はっきりとそれと判る感触がある。
顔に触れたそれは次点で男の肩や腕、そして背中に回り、そのままするすると引き寄せ、男の身体をふんわりと締めつけた。
そう、闇の奥、地球の中心、いまゼロ距離にいるそれは、紛うことなき人型のカタチで、男の身体を抱きしめたのだ。
言葉はない。息もできない。する必要がないからだが、よしんば必要に駆られたところでここでは呼吸もままならない。
だが男には、じぶんの身体にまとわりつくソレの意思を、まるでじぶんの記憶を省みるがごとくしぜんなさまで窺い知ることができた。
同じなのだ。
この存在もまたかつて身体が日に日に重くなり、星の中核として長いあいだ孤独に死ぬこともできず、ただ生き永らえてきた。
来る日も来る日も、この闇のなかで生きてきたのだ。
絶対に離すものかと意固地になるほどに必死に縋りつくそれは、熱く、ただ熱く男の胸を焦がした。
翌日になっても男はまだそこにいた。その翌日も、その翌日も、いつまで経っても男にはそれ以上の変異は起こらなかった。専門家たちの予想を裏切り、百日経過してもブラックホールにはならなかった。
男は闇のなかのソレと抱き合いながら、長い時を生きた。
やがて星の寿命なのか、それとも隕石が衝突したのか、或いは太陽に異変が生じたのか、何が要因かは定かではなかったが、気づくと闇に充満していた身体を包みこむような温かさが消え、こんどは希薄な闇のなかを浮遊している。
光がある。
太陽の光だ。
あれほど赤かっただろうか。
そう疑問するほどに太陽は赤く、ただ赤かった。
胸のなかのソレを見遣る。
おそろしくはない。どんな姿をしていようと、ソレは男にとってはじぶんの一部だった。相手も男をそう見做している。
ゆっくりとソレは男のミゾオチに埋めていた顔をあげ、そして辺りを見渡してからもういちど男の顔を見た。
目を合わせる。瞳がつややかに揺れている。
視線でその者の顔のオウトツをなぞるようにしてから、瞳に映るじぶんの顔に目を留める。
紅潮して見える。
太陽の赤さだ。
念じてみせるが、そんなわけないでしょ、と言いたげにソレはいまいちどつよく男の胸に頬を押しつける。
向かい合って見詰めている。太陽は背後から照っている。
もういちどよく見せてくれ。
男はソレの顔をそっと両手で包みこみ、なぜか分からないが、よかった、と念じた。
なにが。
ソレはまた定位置に頭を戻す。
すべてが。
男は深く染み入るように、また闇のなかで、長く静かな時間を生きていく。
【世界改変日誌】
ノートの一部が白紙になっていた。正確に言うならば、毎日つけていた日誌の一部が空白になっているのだ。たしかに昨日まではそこに文字が、文章が、つらなり、その日何があったのかと、仔細に記述が並んでいたはずだ。
購入した物品をはじめ、印象に残った会話や、壊れたもの、願ったことや欲しくなったもの、それから新たに立てた予定や願望を、おおむね二千字程度の長さで滔々と並べていたはずなのだ。
それがどうだ。
なぜかおとといの記述が見当たらない。たしかに書いた覚えがあるのだが、日誌帳からはきれいさっぱり、消した跡すら残らずに文字が紙面上からするりと抜け落ちている。
その日の記憶は残っている。ちょうど新しい炊飯器を購入したばかりだった。どうせ買うならよいものを、と思い立ち、奮発して月の手取り給料の半分の金額を費やした。家電量販店で購入し、そのまま持ち帰ったので、キッチンに行けばあるはずだ。
腰を上げ、いざキッチンに立つと、あるはずの炊飯器がなくなっていた。代わりにきのう捨てたはずの古い炊飯器がぽつねんとそこにある。
そんなはずはないと思い、電子端末を操作する。残額を確認すると使ったはずの金額分がそっくり残っていた。
購入しなかったのだろうか。
疑問は、つぎに日誌の一部が消えていたのを発見した際に氷解した。
自転車でこけてついた傷が身体から消えていた。怪我をした日は、ちょうど抜け落ちた日誌の日時と一致しており、なるほどこれはそういうことか、と合点したのは、傷だけでなく自転車の歪みまでなくなっていたからだ。
消えた日に会った知人友人に話を聞くと、その日に交わした約束や会話までないことにされていた。
そう言えば、と思いだす。これまでにも幾度か約束をすっぽかされ、その後に謝罪もなく、なんだろう、と釈然としない思いを抱いたことがあった。ひょっとしたらあれも日誌の一部が消えていたのかもしれない。
つぎにいつ日誌が消えてしまうのか解からないので迂闊に人と約束も交わせない。不便だと思ったのは初めばかりで、考えてもみれば過去にあったことが消えるのならば、失態だって消えるのが道理だ。事実これまではずっと、消えてもらったほうがよい出来事ばかりが都合よく消えてくれた。
たまたまなのか、そうではないのか。
いいや、とふと思い立つ。
ひょっとしたらじぶんで消しても、過去を消すことができるのかもしれない。
なかったことにできるのかもしれない。
ためしに休日の大半を映画を観てすごした。せっかくの休日なのにもったいない過ごし方をしたと思うが、いちど無駄な一日を過ごしてみたかった。
思えば日誌をつけるようになってからというもの、日誌をつけたいがために何かちいさくともよいから一日のなかにイベントをいくつもつくろうと気張ってきた気がする。映画は思いのほか楽しく、十本をほとんど通しで観終わったときには窓のそとは明るくなっていた。
徹夜をしたのもずいぶん久方ぶりだ。こういうときにこそ、一日を巻き戻せれば言うことがない。時間が巻き戻ることはないので、これから出社することに変わりはないが、徹夜をしたという事実がなくなれば身体のダルさは消える。反面、記憶だけはどうやらなくならないとすでに身を以って知っている。体験した事実は消えても、それを辿った過去の記憶だけは残っているのだ。
いそいそとエンピツを持ち、白紙の欄にきのうの日付を書いた。たった一行、映画を徹夜で十本観た、とつづる。それから矢継ぎ早に消しゴムで丹念に消していく。
するとどうだろう、毒素が抜けていくように身体が楽になっていく。まるで徹夜なんてしていなかったかのような身の軽さが宿っていくではないか。
自覚していなかったが眼精疲労も相当溜まっていたようだ。スッキリしてみてから、いかほどに疲れていたのかと気づかされた。
これは使える。
その日から、やってみたかったけれど気が引けてできなかったことを一つ一つ、ときには一日にいくつも試す日がつづいた。
仕事を休んでも問題はない。
休んだ事実を日誌に書きこみ、そこだけを消せばいい。
残った記述はそのまま過去に残りつづける。消した箇所の出来事のみがなかったことになる。
修正が効く。
書きこんだ日付からどれほど経っていようとその効果は薄れることはなく、何の気なしにむかしこの部屋で飼っていた猫が死んだ記述を消してみると、なんと部屋の隅から懐かしい鳴き声が聞こえ、まさしくむかし亡くしたはずの愛猫がどこからともなく姿を現した。
世の理すら捻じ曲げるのか。
おそろしくもあり、その万能感に酔いしれもした。
日々は徐々に過剰さを増していく。刺激を求めるように、つぎからつぎに、やってみたかったこと、しかしできなかったことを試しては消す日々を送った。
犯罪行為はさすがにやめようと自制を働かせていたが、いちど試して何事もなかったことにできる体験をしてしまうと、あとはもう自制する意味合いすら消失した。
人を損なっても、損なった事実はこの世からなくなり、人を殺しても、つぎの日には何食わぬ顔で殺したはずの人物と笑顔で言葉を交わしている。
人道に反したあらゆることをした。それはまるで生き物を棒でつつき、ときに地面に叩きつけ、或いは踏みつけることで「死」を発見した子どものような無邪気さだった。
制約がまったくなかったわけではない。たとえばその日のうちに日誌に書きこまなかった記述はいくら消してもなかったことにはならなかった。
つまりあとになってから「あの出来事をなくしたいな」と思っても、当日のうちから日誌に書きこんでいなければ何の効果も生まない。消してももちろんしでかしてしまったこと、起きてしまったことはそのままだ。
よってできるだけ後悔しそうなこと、取り返しのつかなそうなことほど日誌に書くようになった。字数は増え、ページもかさむ。
なかったことにしてもよいがそれほどでもないことはできるだけそのままにしていた。そうでないと周囲の環境が変化しないどころか、到る箇所で齟齬が生じるからだ。それはこちらにしか分からない齟齬であり、機微だが、確実に周囲の環境を蝕んでいく。
たとえば潰れたはずのいきつけのコンビニを蘇えらせたとして、辞めたはずの店員はまた元通りそこで働いている。しかし、潰れていた期間が長ければ長いほど、本来であればそのあいだに流れていた時間の変遷分の現実が大きくゆがむのだ。
極端な話、コンビニを辞めざるを得なくなった店員がそれを転機にアイドルになったとする。しかしそこでコンビニを復活させると、この世からはアイドルが一人消えることになる。
もちろんアイドルのファンだった者たちは活気を失うし、アイドルの働きで稼いでいた者たちは収入を失う。それはポンと生じるひずみであり、得をしていた者たちは損をし、或いは死なずによかったはずの者が死ぬこととなる。
なにより、過去を消した事実は消せなかった。
日誌を消した、と日誌に書いても、それを消したところでその事実をなかったことにはできないのだ。世界改変のあとになってからよくない副作用を観測しても、もはやそれを元に戻す術はない。
そうと気づいてからは、できるだけ前日の日誌のみを消すように心掛けた。
毎日をその日暮らしに暮らした。競馬などの博打を繰り返せばいくらでもお金を増やせる。負けたらなかったことにし、勝てばそのまま日誌にその事実を載せつづける。
倍々ゲームの要領だ。半年もすると、金は天文学的数値にまで増大した。税金で半分以上とられるが、問題はない。ただ、やはりひとの目を引くのは事実であり、大金を稼いだあとはおとなしくしていた。
セキュリティのしっかりした高級マンションに引っ越した。そこで愛猫と共に暮らす。愛猫がこうして蘇えった以上、愛猫を構成していただろう物質が死後に辿ったあらゆる物質から、現在、この愛猫分の質量が僅かずつであるにせよ、抜け落ちているはずだ。全国で謎の奇病が流行っている、とのニュースを目の当たりにしながら、これまでになかったことにしてきた事象の影響をつらつらと思い浮かべる。
ひょっとしたらと思いつく。
じぶんは以前にも日誌の効果を知って、いまと似たような生活を送っていたのではないか。しかしなにか取り返しのつかないことが起きたために、日誌の効果を知った事実を消したのではないか。
日誌を消した事実をなかったことにはできないが、日誌の効果を知った事実ならば消せるのかもしれなかった。
知らなければひとはそれをすることはない。
もしそうならば、未だにじぶんは日誌を消して過去を改変するなんて真似もしなかっただろう。だとしたらこの日誌は、何か取り返しのつかない事態ごと現在を書き換えることも可能なのかもしれない。
リセットされた世界はしかし過去ではなく、現在進行形で進みつづけている。日誌にはもちろん、じぶんで消した過去の記述が空白となって残るはずだ。
一度目ではないのかもしれない。
何度も過去じぶんは世界の改変を繰りかえしてきたのかもしれない。
憶測にはちがいない。
しかし今後、もしも進退窮まる事態に陥ったら試してみてもよいと思った。さいわいにも、日誌の効果を知った事実はきちんと書き残してある。
じぶんの習慣に助けられたと思い、日誌を閉じる。
ワイングラスを手にしたときふと、ひざに猫が飛び乗った。ワイングラスが傾き、日誌のうえに中身をこぼす。
ページの一部が濡れた。
焦り、いそいで中身を改めると無事のようだ。胸を撫で下ろす。
表紙のうえのほうがすこし色が濃くなった。ティシューで拭いながら、念のため表紙の裏、つまり一ページ目より前にある紙面を覗くと、そこにもワインは滲んでおり、黒いペンで書きこんであった日付が目に入る。
この日誌帳を購入した最初の日だ。
その下にはただひとこと、日誌を購入した、と書いてある。
日誌に拡がる染みは刻一刻とその色合いを濃くし、ペンの文字はふやけた紙面に馴染んでいく。
眩暈を覚える。
順繰りと世界が染みのようにかすみだす。
【予測変換の怪】
予測変換が進歩しているのは知っている。親と話していても、むかしは予測変換がお粗末で、何度も打ち間違えたり、全文をじぶんで打ったほうが速かったりしたらしい。それよりもむかしだと、ポケベルなんていって、番号を打って、ゴロ合わせでメッセージを送っていたなんて逸話も耳にする。モールス信号とどう違うんだろ。
予測変換はいまだと、新しい端末の場合は、予測するためのデータがないから、言い換えると打った文字数がすくないから、「あ」と打っても、候補はけっこう少なめで、ふつうに漢字とか、ありがとうとか、一般的な文章しか並ばない。そのうち文章をたくさん打つようになると、そのなかから前に打ったやつとか、比較的多く使う言い回しや文章を、候補としてあげてくれるようになる。
なんてことは、いまさら改めて説明するまでもないことなんだけど、さいきんどうもおかしい。最新機種のはずなのに、予測変換に、どう考えてもそれいらんやん、みたいな候補が並ぶのだ。
あまりに場違いで、ぎょっとするからよく目に留まる。気持ち、十回に三回くらいの確率で、なにそれってのが浮かぶ。
たとえばいまこうして打ってるあいだにも、「助けて助けてたすけて」とか「危ない捨てろ」とか「やめてもうやめてもういやだ」とか、単純に怖いのが並ぶ。
何なんだろ。
親に言ったら、故障じゃないの、とまともにとりあってくれないし、そんなに気になるならお店に持っていったら、と他人事だ。
単なる故障ならまだよいけれど、ウイルスとか、イタズラだったら嫌だ。ネットで検索しても似た体験談は見当たらない。この機種だけの嫌な現象だ。
これがもしも怪談とかなら、予測変換に表示される不気味な文章は、未来のじぶんからのSOSだったりするのだろうけれど、だったらズバリこうなるから気を付けろよ、とじぶんなら打つはずだ。助けて、なんて持って回った言い方はしないし、そんなことを伝えてもどうにもならないことくらい判りそうなものだ。
仮に、ほかの誰かからのSOSだったとしたら、それはちょっと怖い。見過ごせないし、助けてあげたいけど、いまのところこれといってヒントとなるような文面は見当たらない。いまも、見当たらない、と打ったら、「イタいイタい痛い痛い見て見て見て見てみてみて」とでた。
いったい何を見たらよいのだろう。
怖い話ならそれなりにオチみたいなのを用意したほうがよいのだろうけれど、ただただ不気味だよね、だとこれは怪談にはならない気がする。
ちなみにじぶんの名前を打つと、最後が「し」で終わるのだけれど、ふつうに「死ね」とでる。これが心霊現象みたいなものだとしたら、案外、このオバケもひねりがなくて、がっかりだ。見損なってしまう。
いま、なってしまう、の「う」で終わったけれど、そしたら、ウザい、とでた。コミュニケーションがとれてしまった。思いのほかあなた、可愛いところあるじゃない。
いまに見てろよ、って、はいはい。
もはやなんだろうなあ、はあ。
一風変わった交換日記だと思って、いましばらくはこのまま使ってあげることにする。
つぎ「死ね」って言ったらでも、すぐにお店にいって端末を変えてしまうからそのおつもりで。
でたー、じゃない。
それはこちらの台詞です。
【ずるずるみっしり】
どう見ても人間の髪の毛としか思えないモサモサの生えた植木鉢が置いてある。玄関の門を司る支柱のうえだ。柳の木の枝みたいにしなっていて、風が吹くと、重そうに揺れる。
きっとシャンプーをしていないから、ジェルで固めたみたいに油脂でぎとぎとなのだ。トリートメントだって御無沙汰だろう。日常の風程度では、生え際を顕わにするほど舞いあがったりはしない。
そういった植物の可能性も考える。髪の毛に見えるだけで、一本一本はそこまで細くないのかもしれない。
植木鉢の位置が高いせいで、触れて確かめることもできない。油脂で固まっているのか、それともそういう葉っぱなのか。
子どもが人間の顔を描くと、髪の毛はジグザグと輪郭を縁取って終わる。そういう輪郭の葉っぱと見做したほうがいくぶん正確で、だから目のまえのこれもそういった植物だと見做したほうが論理的なのかもしれない。
人間の頭部に見えるだけだ。
髪の毛に見えるだけだ。
それはそうだ。植木鉢に人間の頭を植えてタダで済むわけがない。
通りに面したこんな場所に飾っておいて、騒ぎにならないわけがないのだ。かといって、人通りは多いわけじゃないから、これに気づいているひとがいないだけかもしれない。たとえいても、わたしと同じように、そんなバカなことがあるわけない、と断じて、我田引水に納得しているだけかもしれない。
念のために警察に通報してもよいだろか。
おとなに確認してもらいたい気持ちが募る。
このままだと学校に遅刻してしまう。トイレにも行きたい。朝ごはんをゆっくり食べ過ぎて、おしっこをするのを忘れてしまった。大きいほうもふつふつと、きりきりと、お腹を圧迫している。授業が始まる前にだしてしまったほうがよい気がする。
いざ考えだすと、もはや目のまえの人間の髪の毛に見える物体の生えた植木鉢よりも、教室で無事に一日を過ごせるかどうかのほうがだいじに思えてくる。学校の帰りにもういちど見て、まだここにあったらそのときに改めて考えよう。
その場を離れ、通学路のさきを急ぐ。
なんとか遅刻はせずに済みそうだ。
そう言えば、と下駄箱で靴を履きかえながら思う。兄のマンガで、地面に死体を埋めていた殺人鬼のでてくる作品があった。リアル寄りの絵柄で、グロテスクだな、と不気味に感じたが、さっきのあれはそうでもなかった。髪の毛にハリがあって、なんだか生きているみたいだった。植物と見分けがつかなかったのもそこら辺が関係しているのかもしれない。
死体はでも、死後数時間はヒゲが伸びたりする、と聞いたことがあるから、あまり楽観はしないほうがよさそうだ。
真実、首だけが植木鉢に植えられていてもおかしくはない。
いや、おかしいだろ。
じぶんの考えに突っこみをいれながら、跳び箱を飛ぶ。体育は好きだ。跳び箱にしろプールにしろ、待ち時間が長くて、楽ができる。
給食を食べて、遠足のグループ分けをしたら、あっという間に放課後になった。
考えごとをしていたからか、きょうは時間が経つのがはやかった。それだけ授業を疎かにしていたことの証拠とも言え、これこれちみちみ、とじぶんを諌める。
気づくと帰路を辿っており、例の門のまえに着いていた。
ふつうの一軒家だ。ガーデニングの凝った庭があるだけで、とくべつ不穏な見た目ではない。どこにでもある家なのに、門の支柱のうえに、人間の頭部が埋まっているとしか思えない植木鉢が載っている。
あれ、と思う。
一つ増えている。
門の両脇に、それぞれ長い髪の毛が垂れて見える。そういう植物とはさすがに思えない。
だって黒いし。
緑じゃないし。
葉緑体どこいった。
疑問視してから、はっとする。なるほど、植物の葉を黒く塗ってしまえば、或いは人間の髪の毛のように見えなくもない。
昆布だって、あれが黒ければ髪の毛に見えよう。じっさい、海の妖怪のすくなからずは、昆布の見間違いではないのか。柳の葉が幽霊に見えるのと同じ原理だ。
そうだ、そうに決まってる。
ランドセルを脱いで、地面に置き、そのうえに乗る。さらに爪先立ちをして、支柱のうえから垂れる黒いそれに手を伸ばす。
触れてみれば判るだろう。
葉っぱなら、千切ることだって可能かもしれない。それくらいは許されるはずだ。紛らわしいほうがわるいのだ。
自己肯定を内心で唱えながら、ゆびさきに触れたそれを、ひょいと引っ張る。
ずるり。
ずずずず。
どこまでも伸びた。
細くざらついた髪の毛が、ゆびでつまめるくらいの束となって、ちぎれることなく、どこまでも引っ張れば引っ張るだけ、ずるり、ずずずず、と長くつづく。
ほどいた毛糸の玉のように足元にたるんだそれを目にして、はっとして、じぶんの頭に手をやる。
伸びた分がじぶんから抜け落ちているのではないか、と案じたのだが、そんなことはなく、じぶんの髪の毛はそのままそこに生えていた。
なんだ、よかった。
思ったところで、息を呑む。
するり、すすすす。
足元にたるんでいた髪の毛の束が、ゆっくりと、ゆびでたぐりよせるくらいの速度で、巻き戻っていく。
元の長さまで縮まると、こんどは垂れていた残りの分まで、短く、短く、縮まった。
イソギンチャクのようだと思った。
或いは、カタツムリの触角だ。突いたので、引っこみましたといった具合に、植木鉢のなかに完全に埋もれて消えてしまった。
もう一方の支柱を見遣る。
そこには、浮きあがる血管のごとく、納まりきれんとばかりにひしめき合う黒い筋が、支柱の表面にジグザグと、ときに土のなかで身をくねらせるミミズのように蠢いて見えた。
ランドセルを拾うのも忘れて、わたしは逃げ去った。
家に飛びこみ、居間で映画を観ていた母に、いまあった出来事を語って聞かせる。いまいそがしいからあとでね、とにべもなく突っぱねられ、わたしは傷ついた。
その日の夜、不貞寝したわたしはお腹がすいて目が覚めた。いじけて夕食を食べなかったのが裏目にでた。意地なんか張ってもいいことはない。
ふとそこで、窓のそとに蠢くもじゃもじゃを見た気がした。
ぎゅっと目をつむり、頭からふとんを被る。それからまた眠るまで、足の指一本動かさずにいた。
翌朝、母に起こされ、わたしは目を覚ます。「あんたランドセルどうしたの」
母に問われ、わたしはしどろもどろに、学校に置いてきちゃった、と誤魔化した。まだ寝ぼけていた。どうして母がランドセルのことを言いだしたのか、そのことをふしぎに思わなかった。
「じゃあ誰かが届けてくれたのね」
母はわたしのお腹に、それを置くと、朝ごはん食べちゃいなさい、と言って部屋を出ていった。
わたしはお腹のうえのランドセルとにらめっこをする。
ランドセルに触れると、ほんのかすかに振動して感じられた。
隙間の奥で、ずるずると何かが這っている。そんな妄想をするけれど、蓋を開けて確かめてみる気にはならない。
【無視でいいって】
無視しとけっていいから。
なんでって、なんつったらいいかな。
知人からの又聞きだからぜんぜん信憑性はねぇし、幽霊信じないおまえに言ったところであんま意味もないんだけど、二〇二〇年はじまってすぐにけっこう、社会が大規模に混乱したじゃんよ。で、まあみんな家にいろだの、引きこもり推奨だの、マスクしろだの、人と接触するだの、うるさくなったじゃん。
あの時期にさ、知人の友人がいわゆる霊感あるひとで、言ったら俺からしたら赤の他人だけど、ときどきそのひとの話は聞いてて、本当だったらおもしろいよね、くらいの話半分、暇つぶしにあのひといまどうしてんの、みたいな感じで、話題にでたりしてたんだけど、そのひとがさ、あの時期、しばらく外に出らんなくなったらしくて。
や、いいんだよね、そりゃね。外にでんなって話なんだからさ、そりゃいいことだよ。
でも、副業でそのひとお祓いみたいのもやってて、そりゃみんな家にいる時間増えたら、依頼が増えるわけですよ。なのに、一度依頼をこなしたきり、もうそれからずっと家の外にでなくなったらしくって。
SNSの更新も止まって、連絡とっても買い物にも行ってないってんで、心配になって知人が差し入れついでに様子見に行ったんだって。単純に暇だってのもあったんじゃねぇのかな。
まさか、宅配サービスまで使ってないとは思わないじゃん。
そう、そのひと、完全に外界シャットアウトしてて。知人が部屋に入ったときには食料もほとんど底突いてた状態で。
そうだよな、そう思うよな。
知人もそこまで神経質にならんくてもいいじゃんって、聞きかじりの疫学の話とか披露して、安心させようとしたんだって。
でも、そうじゃなかったんだって。
あの時期さ、外出歩くにしても、二メートル空けろとか、マスクしろとか、言われてて、もうみんなそれ律儀に守ってたじゃん。なんかね、いままで気づかなかっただけなんだってそのひと、それで気づいちゃったらしくて。
や、もうね密集してんだって。
まとわりついてんだって。
一目瞭然なんだって。
ふだん、何気なく見逃してたのが丸見えで、社会がどうのこうのじゃなくって、こんな世界をいままで出歩いてたのかってそのひとビビっちゃって、知人が何言っても部屋の真ん中で布団にくるまって、どうしようもなくなっちゃったんだって。
で、なんでこんな話いましたかってぇと、さっきおまえ一瞬嫌な顔したじゃん、たぶんさっきの集団っしょ?
まあマスクもしねぇで、密集して、一人の男を取り囲んで、アホだな、とか思ったんだろうけどさ、放っとけって。
無視でいいよ無視で。
だっておかしいと思わん?
あいつら入ってった店よく見てみ。
とっくに潰れてるっしょ。
【きみは何も変わらないはずなのに】
友人が売春しているかもしれない、と昔馴染みから相談を受けた。
「むかし告白して振られて、そっから友人として長い付き合いだったんだけど」
「ふうん。売春って何、そういうお店ってこと?」
「どうだろ。たぶんパパ活みたいな、愛人契約みたいな、そんな感じだと思う」
「いちおう言っとくけど、二〇二〇年現在、売春は違法だよ。ただ、不特定多数相手じゃなきゃ売春と解釈されないし、膣と陰茎の挿入がなければ法律上は売春と見做されない。あと管理売春が犯罪なんであって、売春そのものに刑事罰則はない。条例でダメなとこはあるだろうけど、それも多くは、売春をする側を罰するためじゃなく、搾取する側を牽制するためのもので。この国の示す方向性としては、売春せざるを得ない経済的弱者は守るべき対象だ」
「いやいやおかしいだろ。売春せざるを得ないってなんだよ、まずはそこんところをしないようにしろって話じゃん」
「止めたいの?」
「そりゃあまあ」
「それはなんで」
「なんでって、そりゃあ」口ごもるところを鑑みれば、そこに潜む自己矛盾に気づいているのだろう。いいから言ってみて、とさきを促す。「だって、売春だぞ。男にコビ売って、身体をいいように弄ばれて、穢されて、それで金もらって、そんなんいいわけねぇじゃん」
「うん。まずはそこだよね。便宜上、売春婦って言い方をさせてもらうけど、きみはそれを卑しいものだと考えているわけだ」
「まあ、いいかわるいかっつったらよくはないだろ」
「そう? たとえば同じ性行為でも、恋人とならそれはよくて、無理やりなら強姦で、お金をもらったら売春で。でもやってることは変わらないわけでしょ」
「そんなこと言ったら、ひとはみな死ぬからいつ死んでもいいみたいな極論になんじゃん」
「そう。過程はだいじだ。結果が同じだからといって、行為そのものが同じだからかといって、まったく同じとは限らない」
「だったら」
「でも、だとしたらなおさら、じぶんの意思で選んだ性行為なら、それは恋人同士のそれや、単なる仕事と、それほど違いはないんじゃないかな」
「いや、性行為は仕事じゃないだろ」
「そう、そこだよね。売春を労働と見做していない。卑しいものだと見做している。まずはそこの誤解から正しておこう。売春そのものは卑しいわけじゃない。だってさっきも言ったけど、子供がいるひとは誰だってしていることだ」
「子供を儲けるくらいに神聖な行為なら余計に他人とするなって話じゃん」
「なら避妊を徹底すればいいってことにならない?」
「屁理屈だ」
「んみゃんみゃ大事だよ。労働の対価として報酬を得る。これは総じて仕事だ。職業だよ。職業に貴賤はない。建前だとしても、そこはきみだって認めるところだろ」
「でもじぶんの子供に売春をさせたくはないよ」
「それはほかの職業でも同じなんじゃないかな。たとえば一流企業でホワイトな職場と、劣悪な工場の現場だったら、たいがいのひとは前者を選ぶ」
「そりゃ環境がいいほうがいいに決まってんじゃん」
「そう。だから、劣悪な環境の一流企業と、環境のいい工場の現場だったら、これはけっこう票が割れると思う。給料がよければ、多くのひとは工場のほうを選ぶかもね。だた、世間体を気にして、一流企業というブランドを優先して選ぶひともそうすくなくはないと思うけど」
「つまりこう言いたいのか。売春も、劣悪な環境や、社会からの差別があるから卑しいものだって、無意識でそう考えてしまうって」
「それもあるんじゃないのかなって話。もっと言えば、売春に限らず、職業差別の多くは、仕事それそのものというよりも、搾取構造に問題の因がある、本質的な瑕疵がそこにある。搾取されないような、劣悪な労働環境でなければ、そもそも卑しい仕事、という感覚そのものが時代の経過に伴い薄れていくだろうね。極論、プロスポーツ選手みたいに、売春がもてはやされれば、誰もがみなそれを目指してこぞってなりたがるだろうし、親だって応援するかもしれない。まあ、性病の問題があるから、そこは科学の進歩で乗り越えるとして」
「それはちょっと話がズレてる気がするぞ」
「そんなことはないと思うよ。いまだって殺人はいけないこととされているけれど、戦争がはじまれば、いかに多くの敵を殺せるかが、英雄か役立たずかの基準になる。人殺しという、現代では絶対に許されないことですら、社会の価値観でいかようにもその善し悪しは変わる」
「売春も同じってか」
「同じだろうね。もちろんさっきも言ったけれど、搾取構造は失くさないといけない。客の多くが、『売春をするようなやつはまっとうじゃない、乱暴に扱ってもいい、敬意なんて払う必要がない』と思っていれば、そりゃ職場は劣悪になって、自尊心だって削られるし、社会も売春に従事する者はそういう人間だという風潮を強くする。そうなると余計に、売春に従事しているひとたちは、そういう仕事をしているとすら周囲に言えなくなり、助けを求めたり、相談もできなくなる。悪循環に陥る。まずすべきは、売春をしているからといって卑しいわけではない、という価値観をつくっていくことだ。それはもちろん価値観を変えていくだけではダメで、同時に、売春をする労働環境を社会がきちんと是正していかなきゃいけない。そういう仕組みを構築していかなければ、やっぱり価値観だけが変わっても、それは大勢を売春に走らせて、搾取するだけの構図が強化されるだけになる懸念が非常に高いんじゃないか、とぼくは思うよ」
「ふうん。じゃあ、どうすりゃいいんだ。愛人契約だからかってにしろって、あのコの選択を応援すりゃいいのか」
「そこもむつかしい問題なんだよね。そのコが本当にそれをしたくてしているのか、それともただお金に困っているだけなのか。これは売春に限らず、どんな仕事にも言える。やりたくない仕事をいやいやさせるなら、それは売春を無理強いしているのと原理上区別はつかない。というよりも、売春も仕事のうちだと見做し、職業に貴賤がないと考えれば考えるほど、この理屈の正当性は増す。つまり、現代では売春問題と似た問題が、いろんな職業で行われている。むしろ、売春という『社会的底辺だとされる職業』をつくりあげることで、むかしのえたひにん制度みたいに、じぶんたちはまだマシだな、と大多数の社会人に思わせる流れは、これは意図してではないとしても、そういう側面で機能しているとは言えると思う。まさしく捌け口だよね。だから、問題は売春という行為そのものではなく、労働する側にあるのでもなく、客の態度のほうにあると言ってもいいかもしれない。あとはそう、もちろん雇う側の問題、搾取構造に、根本的な問題があるんじゃないかとやっぱりどうしても考え着いてしまうよね」
「じゃあまずは訊いてみるわ」
「そのコに?」
「や、雇い主に。友人の話ってのは嘘。じつはこれ、アタシの話でさ」
「それは、えっとぉ」
「むかしおまえに告られて、そんときレズビアンだからっつって断ったけど、まあそうなんだけど、でもまあ、性行為くらいはべつに異性相手でもいいかなって。むしろ本気なのは同性だけにしときたいってのがあんのかも。でも、いざしてみたら、そういうのってやっぱマズいのかなぁって罪悪感みたいなのがあってさ、誰にも相談できねぇし、自尊心ズタボロになりかけてたところで、まあ、相談してよかったわ。なんか元気でた。べつに引け目に感じることはないんだってな。売春する分にはいいんだろべつに? アタシいま金に困っててさ。でも、まあ、単なる仕事。コンビニのバイトとか、工場の期間従業員みたいなさ、そういうのと変わんねぇじゃん。あ、いちおう確定申告はするし、税金も納めるよ。けっこうもらえんだよね。アタシこう見えて、けっこうウケいいんだ」
あはは、と乾いた笑いを漏らす彼女にかける言葉を、ぼくはなかなか思いつけないでいる。
お金ならぼくがあげる。そう言いたかったけれど、ぼくにはそこまでの甲斐性はないし、そうした提案をする時点で、ぼくはきっと売春を、卑しい行為と断じているなによりの傍証に思えた。差別心に蝕まれている。それを彼女に悟られることのほうが、彼女の売春を止めることよりも、彼女を救うことよりも何よりも、ぼくには優先される事柄に思えた。
「ぼくはきみが何を選択しても、ぼくのきみを尊敬する気持ちは変わらないよ」
「じゃあま、売春のプロでも目指しますかな」
働かなければ生きていけないのならば、働くしかない。彼女がどんな仕事で稼ごうと、それは彼女の選択だ。彼女が弁護士になる、と言っているのとこれは変わらない。止めることこそが、差別になる。
けれどやっぱり、どうしてもぼくは、胸が苦しくて、どうしようもないんだ。
独占欲なのかもしれない。彼女を、彼女の身体を、ぼくはじぶんのものにしたいだけなのかもしれない。だからほかの男に穢されたくないと望んでいる。
じっさいのところは彼女が穢されるわけでもないのに、彼女は何も変わらないのに、変わらずに変わりつづけていくのに、それでも彼女に、その道を選択してほしいとはなぜかふしぎなほどに、どうしても思えないのだった。動物じみている。
「相談してよかったよ」彼女は席を立つ。「また遊ぼうぜ、こんどはアタシが驕るからさ」
背伸びをして大きな欠伸をする彼女にぼくは、引きつった笑みしか向けられないでいる。
【返頭痛】
新商品の試験体のバイトをした。
配られたのは、腕時計型感覚共有機だ。
知覚を他人と共有できる機械らしく、使用者のデータを集めて改良に活かすのだそうだ。
いざ使ってみても、これといって生活に変化はなかった。他者の知覚が伝わるでもなく、思考が読めるでもなく、あべこべにこちらの思念を送れるわけでもない。
失敗作だったのだろうか。
タダでバイト代が入るのだから文句はないが、報酬分の仕事は返したい。かといって何ができるわけでもなく、うーん、うーん、と頭を抱えた。
翌朝、悩みすぎたのがわるいのか、頭痛がひどかった。
まるで頭のなかが空洞で、かぽっと脳みそが溶けてなくなってしまったみたいな鈍痛がある。
なんとかならんものか。
じぶんの頭をちぎって、配って歩きたい。身体から頭痛を切り離したい。
お腹の空いている相手にじぶんの頭を食べさせるヒーローのマンガがあったが、似たようなことができたらさぞかし爽快だろう。
大学の食堂で友人とランチを食べながらそんな想像を巡らせていると、腕時計型感覚共有機が赤く点滅した。
なんだなんだ。
驚いて顔のまえに運び、まじまじと見つめると、機器の側面から赤い光線が蜘蛛の糸のように細く放たれた。友人のこめかみに当たる。
数秒それは線となって保たれたが、間もなく、ふっと消えた。
「イッターイ」
友人が呻いた。「なんか急に頭痛くなってきた」
訊けば、脳みそにぽっかりと穴が開いたみたいな鈍痛が突然に湧いたらしい。イタタ、イタタ、と顔にバッテンの目を浮かべながら友人は、授業は休む代行よろ、と言い残しそそくさと荷物をまとめて食堂をあとにした。ちゃっかりお盆を残していったので、清算は私がすることになったが、罪の意識にさいなまずに済む分よしとする。
そうなのだ。
私の頭痛は消えていた。
友人に移してしまったのだ。
元来私は頭痛持ちだ。
せっかく取り除いた痛みが、翌日にはぶりかえしている。友人への呵責の念がわずかにでも残り、思い悩んでしまったせいかもしれない。友人め。
知り合いに移すのはわるい気がした。通りがかりの、なんだか人相のわるいひとや行儀のわるいひと、端的にひとを困らせている誰かを見掛けたら、そのひとたちに腕時計型感覚共有機を向け、そこから発射される赤い光線をぶつけた。
赤い光線は、私が、頭痛どっかいけ、と念じると飛びでるようだった。脈拍だとか脳波だとか、なにかしらのデータを感知しているのだろう。
ときおり周りに誰もいない状態で光線がでることもあるが、そのときは壁にぶつかってそれっきりだ。頭痛は取れないし、私はびっくりする。心臓にわるいから発射ボタンくらいつけてほしい。アンケートの備考欄にでも書いておこう。
私は頭痛から解放された。
日々、大学までの道中、その帰路、或いは遊びに出掛けたさきで、見知らぬ他人に頭痛をばら撒きつづけた。
バイトの面接時に受けた説明では、感覚を共有する相手は一人か二人に限定するように、と注釈を挟まれたが、やはり友人ばかりを標的にするのは気が引けた。頭痛が消えても胸が痛んでは意味がない。ゆえに、なるべく多くの見知らぬ他人に頭痛を分散した。
さすがに二十人を超えたころには、じぶんひどくないか、と罪の意識に苛まれたが、かといってしょせんは頭痛だ。移す移さないにかぎらず誰もがなる。そして私は人よりも頭痛になりやすいのだ。公平を期するために頭痛をばら撒くのは、アリかナシかで言えば、ナシ寄りのアリだろう。つまり、アリだ。義賊だって盗んだ銭をばら撒くのだ、義賊でない私が頭痛をばら撒いて何がわるかろう。
私は開き直っておった。
やがてバイトの最終日がやってきた。開発企業へと腕時計型感覚共有機を郵送し、数日後にお礼の連絡を受ける。
「どうでしたか使い心地は」
「肩こりがなくなってよかったです」頭痛はやや罪が重い気がしたので、肩こりと偽って報告した。
「ああ、それはよかったです。でも気をつけてくださいね。機器を手放せば、他人に共有した感覚は丸ごとごっそり返ってきますので。まあ、一人、二人くらいならだいじょうぶですのでお気になさらずに」
「返ってくるとは、えっと、それはどういう」
「飽くまで共有ですからね。感覚は戻りますよ。それこそ、感動を共有したなら、しばらく涙が止まらないかもしれません」
よほど自社製品を誇りに思っているのか、担当者の声は弾んでいた。私は二の句が継げなかった。またの参加をお待ちしております、と慇懃に述べ、担当者は連絡を終えた。
しばらく呆然とした。キリキリと痛みだす後頭部の、ごっそり脳みそが穿りかえされたかのような空虚さを覚えながら、いったい私はこの期間にどれほどの頭痛を他人に肩代わりさせてきただろう。ばら撒いただろう。
想像し、立っていられないほどのめまいに襲われる。
ずきん、ずきん、の波が徐々に大きくなっていく。
【日鬼】
朝からツノの調子がおかしくて、ピリピリしていて、そろそろ解放しておかないとな、と面倒に思う。
前に解放したのはいつだったかな。
スリオロシをしぼって喉をうるおす。それからファシュナたちと同調し、きょうの予定を探りあう。嵐がちかいからか、うまく魂感を飛ばせずに難儀する。ファシュナたちは食糧の調達にいくらしい。
そろそろ解放しておかなきゃな、とのこちらの懸念を察したのだろう、食料の調達ついでに手ごろな荒野を探しておいてくれるそうだ。そんなことをしなくともこのあいだファシュナが解放した地があるだろう、と訊ねると、そこはもう存在しないらしい。
ああそれで、と合点する。
ファシュナの角位があがったのはその影響か。
地上を不可侵にするくらいなのだからおそらくは白号に値するのではないか。他鬼の角位を気にするなんてずいぶんと気弱になったものだ。それもこれもツノのピリピリのせいだ。
日が昇る前にファシュナたちと合流した。彼女たちは山盛りのスリオロシを獲ってきていた。
「よくそんなに見つけられたな」
「サンミャクのほうにはまだいっぱい巣があるよ。あ、ねえ、なんでコレがスリオロシって言うか知ってる?」
「え、なんでだろ。飲み物とかそういう意味じゃないのか」
「搾るって意味らしいよ。スリオロシを搾る、なんてあたしたち言うけど、二重表現。二度手間」
ファシュナは笑い、つぎはいっしょに獲りにいこう、と言った。「あそこにある巣はつぎでたぶんなくなっちゃうから、ついでにあんたそこで解放しちゃいなよ」
もう限界でしょそれ。
ツノに手を伸ばしてくるので、のけぞって回避する。「危ないって。敏感なんだぞ知ってるだろ」
「ひっしっし」
ファシュナは牙を口の端から覗かせる。それから袋のなかから獲りたてのスリオロシを一匹とりだした。一口で頬張る。
バリバリ、ぐじゅぐじゅ。
見ているだけで唾液が口のなかに広がる。こちらも一匹いただくことにした。
目のまえに新鮮なスリオロシを掲げる。
搾らずに食べるなんてこんな経験はいつ以来だろう。
獲りたてで活きがよいからこその贅沢だ。
汁気の多い割に、歯ごたえのある骨の触感がたまらない。
ひとしきり味わっていると、ファシュナがそこで、うべ、と舌を使って器用にサラサラを吐いた。「あたしこれ苦手」
「そこが美味いんじゃないか」
「じゃああげる」
「口から吐いたものを押しつけるな」
スリオロシの頭部から生えるサラサラを食べないなんて、鬼からツノをとったようなものだぞ。
指摘すると、腹に据えかねたのかファシュナは、もうあげない、とスリオロシのいっぱい詰まっているだろう袋をぶんと背中に遠ざけた。
【ゾウさんの小さいものはなに?】
ヘイコウくんが言葉を発しなくなってずいぶん経つ。何かきっかけがあったのか、とヘイコウくんのご両親はたいへん心配していた。
ぼくも心配で、毎日のようにお見舞いに行っていたけれど、毎日はつらいでしょ、とヘイコウくんのご両親に言われてからは、一週間に二回くらいの頻度で顔をだすようにした。本の貸し借りをして、その返却を理由に訪問するようになった。これはヘイコウくんの案だ。
ヘイコウくんはあまり家のそとにはでなかった。学校にもこない。それはしゃべらなくなった時期と重なっていた。
学校で何か嫌なことがあったのかもしれない、と思ったけれど、そういった事実はないようだ、と学校の先生たちは結論付けているようだった。ヘイコウくんのご両親も最初は疑いの目を向けていたけれど、ぼくやほかの同級生たちからの心配の声を聞いて、どうやらうちの子は学校ではみんなと仲良くしていたのだと認識を改めたようだった。
現にヘイコウくんは学校では人気者だった。たぶんヘイコウくんを嫌いなひとはいないのではないか、とぼくなぞは睨んでいる。そしてそれは正しい認識だったに違いない。
ヘイコウくんが学校にこなくなっても、ヘイコウくんの話をして、はやくこないかなぁ、と言っているクラスメイトたちがすくなくなかった。
かといってヘイコウくんのお見舞いに通うのはぼくだけのようで、それはぼくとヘイコウくんの仲がほかのコたちよりも濃いからだとぼくは考えているけれど、あんまりこれはあてにならない想像かもしれない。
ヘイコウくんはしゃべらなくなっただけで、とくに他人を拒絶してはいなかった。だからぼくが部屋を訪れると、いっしょにゲームをして遊んだ。
「どうしてしゃべらないの」ぼくが言うと、ヘイコウくんは口をぱくぱくと開け閉めした。
「聞こえないよ」ぼくはムスっとした。
ヘイコウくんは、ごめんよ、と言いたげに両眉を八の字にした。ぼくはヘイコウくんから借りた本を返して、また新しい本を借りた。
学校で、先生からヘイコウくんについて質問を受けた。
「どうしてそんなに仲がよかったの」
「ヘイコウくんは動物が好きでした。ぼくもです」
「そうなんだ。何の動物が好きだったの」
「コオモリとか、ゾウさんとか、あとはクジラさんも好きですよ」
言いながらぼくは、どれもヘイコウくんがさきに好きだと言ったものばかりだと気づいた。ぼくはたぶん、ヘイコウくんが好きだから、それら動物をもっと好きになったのだ。本当だろうか。あんまり自信はない。改めて考えなおしてみると、元から大好きだった気もしてくるから、ふしぎだ。
ぼくは家に帰って、ヘイコウくんから借りた本に目を通す。ゾウの本だった。
ゾウは人間に聞こえない音をだす、との記述を見てぼくは、おやまぁ、と思った。
超低周波音をだすことで、ゾウは十キロさきのほかのゾウの声も聞き取れるのだそうだ。
「すごいなぁ」
そんな真似ができたら便利だな、と思った。誰にも知られずに互いに声のやりとりができるのだ。
本にはほかにも、コウモリやクジラもまた超音波を使いこなすのだ、と書かれていた。
ぼくはそこで、はっとした。閃いたのだ。どれもヘイコウくんの好きな動物ばかりだ。
ぼくは、ひょっとしたら、と考えた。
ヘイコウくんは言葉を発しなくなったわけではないのかもしれないぞ、と。
彼の声が、ぼくたちに聞こえなくなっただけなのだ。
ぼくはお小遣いをはたいて、集音機を購入した。補聴器に似たつくりで、どんな音でも大きく聞こえるようにしてくれる。補聴器よりも安い値段で購入できるけれど、それでもお年玉二年分が消えてしまった。補聴器は性能のよいものだと一個だけでも宝石が何十個も買えるくらいに高いのだ。集音機は高くても安い補聴器くらいで済む。それだって宝石一個は買える値段だ。
ぼくはヘイコウくんの部屋に行き、集音機を耳にして、ヘイコウくんを見る。
彼はぼくを見て、ふしぎそうな顔で、また口をぱくぱくと開け閉めした。
「それは何? 音楽でも聴いてるの?」
ヘイコウくんの声だ。彼の声が聞こえる。
ぼくは感激して、目頭がじんじんした。ずっとしゃべってたんだねヘイコウくん。
もっとしゃべって、と催促すると、ぼくの声が頭蓋骨を割るくらいに大きく聞こえて、ぼくは床にのた打ち回った。集音機を取りはずす。
ヘイコウくんがぼくを見下ろしている。両の眉は虹みたいにゆったりと弧を描いていて、それでいて雨みたいにぽろぽろと垂れるしずくがぼくの手の甲に当たった。
ヘイコウくんはずっと、なりたいものになっていた。
誰にも知られず、じぶんだけの夢を叶えていたのだ。
ぼくは声にならないくらいちいさな息で、すごいなぁ、とつぶやく。ヘイコウくん、きみはすごいよ。
ヘイコウくんの真っ赤なお耳が、気まぐれなゾウみたいにそっぽを向く。
【ピエロと一匹の】
あるところに心優しいピエロがおりました。ピエロは白塗りの化粧に赤玉の鼻、子供用パジャマのズボンを頭から被った、小太りの男でした。
ピエロは子どもが大好きでしたから、道行く子どもたちを楽しませようと、陽気に振る舞い、空き瓶をいくつも宙に投げて回し、塀のうえで逆立ちをしたりします。
けれどピエロが大袈裟に動けば動くほど、子どもたちは怖がって近寄りませんでした。
そのうちおとなたちまでピエロに冷たい目をやり、町からどんどんピエロの居場所はなくなっていきます。
ピエロはそれでも毎日のように町にでて、陽気におどけ、玉乗りやパントマイム、さまざまな演目を披露しました。
ときおりまだ言葉もしゃべれない幼児が、ぱちぱちとにこやかに手を打ってくれますが、その親と思しきおとなに視界を塞がれ、いかにもあれは見てはいけないものだ、と諌められるように去っていきます。
ピエロは笑顔を絶やしません。化粧がそういう絵柄だからです。
あるとき、町で殺人事件が起きました。女児が草むらで遺体となって発見されたのです。それからしばらくしてこんどは男児が行方不明となり、数日後に橋の下で見つかりました。腹は裂け、首と胴体が切り離されていたそうです。
町からは子どもたちの姿が消え、おとなたちはふだん以上に目つきするどく歩いています。
殺人事件の捜査がすすむにつれて、ピエロの仮面をした男が殺された子どもと遊んでいた、といった目撃譚が寄せられるようになりました。
もちろんピエロには身に覚えがありません。そもそもピエロの顔は化粧であって仮面ではないのです。
しかし町の人々はピエロを見掛けるたびに、道を迂回し、こそこそと遠くでなにやらささめきあうのです。
やがてピエロの住まいにイタズラ描きや、貼り紙、イタズラ電話がかかってくるようになりました。多くは脅迫まがいな言葉で、町からでていけ、といった旨を告げています。
ピエロは黙ってそれらを受け止めました。いちどだけ壁をきれいに塗り直しましたが、つぎの日にはまた元通りになったのを機に、そのままにするようにしました。
ある夜、息苦しさを覚えてピエロはベッドのうえから起きました。
煙で部屋はもくもくと雲っています。その奥に赤い光を見ました。
家が燃えているのです。
ピエロはいそいで、部屋に置いてあったペンキを炎に浴びせます。家の壁を塗るのに購入したペンキです。白い液体が炎を圧しつぶし、ぶすぶすと嫌な臭いを立ち昇らせます。
炎は弱まりましたが、どうやら一か所だけが燃えているわけではなさそうでした。
ピエロは家のそとに出ます。そして、いちど手にしたホースからゆびを離し、呆然と家が焼けていく様子を眺めました。
近隣にほかの住居はありません。ただただそれだけが救いでした。
手のひらはペンキで真っ白です。ピエロはそれを顔にぬったくり、ポケットのなかに入れっぱなしだった赤玉を鼻につけます。
ピエロは朝を待たずに町をあとにしました。行くあてのない旅にでるのです。
旅の道中、停車中のトラックからラジオニュースの音が聞こえてきました。よこを通り抜ける際に、児童連続殺人事件の容疑者が捕まった、と聞こえました。ピエロは、よかった、とただ一言思いました。
町から離れ、人里からも離れ、深い太古の森にまでくると、季節は冬にさしかかっていました。辺り一面灰色の雪に覆われ、月光を受け、きらきらと輝いています。
視界の端に、ふと何か動くものが見えました。
ピエロはそちらに目を転じます。
トナカイが一匹、雪のなかに埋もれていました。
首だけを持ちあげ、こちらを見詰めています。
ピエロはしばらくその場で様子を窺っていましたが、意を決して近寄りました。ピエロの足跡だけが点々と雪のうえに残ります。
トナカイはピエロから逃げることも、警戒心をあらわにすることもしませんでした。
トナカイはひどい怪我を負っていました。身体からは血を流し、片方のツノは根元から折れ、なにより木に衝突でもしたのか、鼻がつぶれてしまっています。
ピエロは心を痛めました。
なんとかしてあげたいと思い、手持ちの衣服を破き包帯にし、雪を掻き分けて餌となる草木を探しました。キノコやコケを見つけて、差しだします。トナカイは匂いを嗅ぐ真似をしますが、そのたびに鼻がつぶれてしまっていると思いだすようで、苦しげに鳴きます。
ピエロはトナカイに身を寄せ、眠り、元気になるまでそばにいました。
やがてトナカイは自力で立ちあがれるまでに回復しました。
陽の光を受けて、空気が無数の光の種を散らしています。
トナカイがピエロの首筋に顔を埋めます。ピエロはそこでふと思いつき、鼻の頭に載せていた赤玉をトナカイの鼻先に被せました。
ぴったりとはまります。
トナカイは気に入ったのか、ますますピエロにじゃれつきます。
ピエロの顔からはもう白いペンキの色は剥がれ、鼻も赤くありません。そこにはただの子太りの男がいるだけです。
トナカイが雪のうえにしゃがみこみました。背中に乗れ、と言っているみたいです。
そう言えば、と男はいまさらのように思いだします。トナカイを見つけたとき、その周辺にトナカイ自身の足跡はありませんでした。トナカイの怪我の位置からすると、おそらく木の幹に勢い余って衝突したのでしょう。しかし、いったいどうやって足跡一つ残さずに、木にぶつかれたのでしょうか。
男は疑問に思いながら、トナカイの背中にまたがります。分厚い毛に手のひらが埋もれ、全身が暖炉のまえに佇むようなぬくもりにくるまれます。
男はもうピエロではありませんでしたが、それでも子どもたちのことは大好きなままでした。
いつの日にか、世界中の子どもたちを楽しませ、笑顔にできるとよいのにな。
男はただ、それだけを祈るのです。
【ミカさんはお姫さまになりたい】
あれほどお姫さまになりたいと言い張っていたミカさんがイモムシになってしまった。私は潰してしまわないようにマッチ箱にミカさんを入れて持ち歩く。
ミカさんは日にレタスをひと玉たいらげてしまうので、私は彼女のレタス代を稼ぐために新しくコンビニのバイトをはじめた。
いらっしゃいませー、と私が言うと、ミカさんがマッチ箱のなかから、ませー、と復唱する。店内のお客さんがこぞって振り返るので、私は裏声で、ませー、ませー、とエコーを利かせなくてはならず、きょうはそのことで店長にこってりしぼられた。
帰り際にスーパーに寄ると、ミカさんがレタスは嫌だと駄々をこねた。イモムシのくせに生意気だ。私は疲れていたのでレタスの代わりにキャベツを買って帰った。
翌朝、ミカさんはキャベツの表面にひっついてサナギになっていた。声をかけても返事はなく、サナギのなかでドロドロに融けているミカさんを想像しては中を覗きたい衝動と闘った。
一週間ほど闘いつづけているあいだにミカさんは、サナギの背中をぱりぱりと割って現れた。
ぷはー、くるちかった、とさっぱりした顔をこちらに向ける。私のよく知るそれはミカさんの姿で、でも背丈だけは親指サイズのままだった。これじゃまるで小人ですね、と私が言うと、ミカさんは、おやゆびひめー、と楽しそうに笑うので、私はしょうがなく指輪を外して、ミカさんの頭に載せてあげた。
今夜は葉っぱ以外が食べたい、とミカさんがお腹を鳴らすので、特別にステーキを焼いてあげた。イモムシのときとは違って、小人のミカさんはステーキを一切れだけでお腹をさする。
これくらいなら、と私は思う。
標本にしてしまわずともずっと手元に置いておけそうだ。買ったばかりの「マチバリと防腐剤と注射器」は押入れの奥深くに仕舞っておくことにする。
【ミカさんはビッグバン】
ミカさんが死ぬとこの宇宙が終わってしまうので、みなミカさんを死なせぬように必死だ。怪我をされると困るので、彼女は身動きを封じられ、それを苦として自殺されても困るので、薬で深く眠らされている。
この宇宙はミカさんの寿命と密接に絡みあっていて、がんじがらめで、どうやらミカさんが死ぬと同時に終わるらしい。
なぜ、と問われても、そうだから、としか説明できない。世の天才たちがこぞってその謎の解明にいそしんでいるが、明らかになるのはどうやら予測が揺るぎないという事実ばかりだ。つまるところミカさんが死ぬと宇宙が終わるというただそれしきの未来が不動の地位を築きあげる。
彼女を凍結処理してしまおうとする案がだされたが、死をどのように定義するかによって、いくつかの派閥ができ、けっきょくミカさんは年々歳を取りながら、確実に死へと近づいている。
ミカさんはどんな夢を視ているのだろう。
せめて夢と夢を繋ぎあえたらよいのに。
私はその技術を開発すべく尽力し、ミカさんの頭に白髪がまじりはじめた時期にようやくその技術を確立させた。
私はミカさんと夢で繋がる。
しかし夢のさきでもミカさんは、宇宙の存続と一心同体で、現実と同じように深い眠りを課せられている。私はそこにいるもう一人の私と相談し、ほかの夢でも同じようにミカさんは眠りつづけているのだろうと結論した。
私たちは彼女の見る多重の夢のなかに生きており、宇宙はそうした泡のような夢によって膨張しつづけている。どの夢のなかのミカさんが死んでしまっても、すべての宇宙は順々に霧散する。まるでドミノ倒しのように、或いは連なる無数のシャボン玉のように。
私はほかの私たちと相談し、共同し、そしてミカさんを起こすことにした。彼女が目覚めると多重の宇宙はひとつに収斂し、私はその手に握ったナイフで寝ぼけたミカさんの胸を突く。
おはようミカさん。
ナイフを引き抜く。
そしておやすみなさい。
何が起きたのかも分からぬままにミカさんは血にまみれており、私はそんな彼女の身体を抱きしめる。
目を覚ます(眠る)べきは私たちのほうだ。
【あなたにならいいよ、あなたがいいよ】
ミカさんが殺人鬼になってしまったので、私が匿った。ミカさんは手際よく人を殺す反面、まるで赤ちゃんの食事みたいに盛大に痕跡を残すので、あっという間に最重要指名手配犯になった。
世界中のメディアというメディアでミカさんの顔画像が映し出される。連日ミカさんの話題ばかりがのぼるので私は面白くない。
ミカさんは白昼堂々でかけていって、また一つ死体を増やす。三日に一度は人を殺して帰ってくる。
殺す相手は一人のときもあれば何千人、何万人のこともある。もはや殺戮者だ。
さすがの私も、いい加減にしましょうよ、と小言を漏らす。ミカさんは私にじゃれつくと、返事もなしに猫みたいに丸まって寝てしまう。
ニュースではまた政治家の一人が死体で見つかった。ほかにも暴力団が壊滅し、どこかの主婦がスカイツリーのてっぺんで首を吊った状態で発見された。
見覚えはないけれど、きっとどれも私の身体をこんなにしたあの事件に関わっていたひとたちに違いない。ミカさんを問い質したところで彼女は素知らぬふりをするのだが、私がどんなに悪態を吐いてもミカさんは私を殺したりはしないのだ。
私は、私をこんな身体にした連中を恨んでいたけれど、いまになってはうらやましく思う。
ミカさんの殺意を独占できるなんて、そんなのはミカさんの人生を手に入れるのと同義だ。
いい加減にしましょうよ、と私は言う。あんな連中にかまけていないで、私の胸のなかで猫みたいに丸まって寝ていればいいじゃないですか、と。
ミカさんは困った顔をしながら刃こぼれしたナイフを研ぐ。
もうすぐ終わるから。
言い訳がましくつぶやく割に、その言葉は耳にタコができるくらいに聞いている。
人類が全部いなくなっちゃいますよ、と私は背後からミカさんの首にまとわりつく。
いなくなればいいんだ。
言ったミカさんの首はひどく頼りなく、貧弱な私であってもポッキリと折れてしまえそうだ。
試しに首に回した腕にちからを籠めてみる。
ミカさんは抵抗をするそぶりを見せずに、そうされたいがためにそうするように、私の腕に頬を押しつける。それでいて、苦しいよ、と片笑むのだ。
ずるい、と思う。
そんなことをされたらもう、私は、どうすればいいのかが判らなくなる。
【トカゲの尻尾】
目のまえでトカゲの尻尾が切れた。トカゲの尻尾切りではなく、つまり組織の末端構成員に罪を着せて使い捨てにする意味の慣用句ではなく、本当に目のまえでトカゲの尻尾が切れたのだ。
いや、トカゲにはそもそもそうした能力があるのだから不自然ではないし、驚くほどのことでもないのだろうけれど、ここが無菌室の隔離施設、それこそ最重要機密とされている地下の地下であれば話は別だ。空気穴ですら針も通らないほどの通気性の高い硬化生地素材、それはのきなみ銃弾でもダイナマイトでも傷一つつかない優れものなのだが、そうした壁に囲まれ、観測できる起伏と言えばじぶんの肉体のみという、言ってしまえば四角と私しかないここは空間だ。
トカゲの入る隙間はない。
現に、切り落とされた尻尾はうねうねと床で身じろいでいるのに、肝心の本体の姿が見えなくなっている。さっきまでいたはずだ。幻覚だったのか。いいや、こうして尻尾があるのだから現実としてここにトカゲがいたのだ。
或いはこれも何かの実験の一つで、立体映像か何かでこちらの反応を試しているのだろうか。
思い、ひととおり部屋を見渡すがこれといって何もない。定位置に戻り、そこでようやく動きを止めたトカゲの尻尾をゆびの先でつつく。感触がある。つまみ上げると、まるでじぶんの手から切り離されたゆびをつまんでいる錯覚に陥る。
だがたしかにそれはここにある。
幻覚ではない。
物体として、現にここに存在している。なればこそ、どこからか入りこんだトカゲがおり、そのトカゲの入ってきた穴がこの空間にはあるはずだ。
床に這いつくばり、異物がないかを探る。
主として穴だ。
突起物でもよい。
すくなくともこれまでこの空間に穴や隙間といったものはなかった。壁をすり抜けるように透過する空気があるばかりで、ほかには何もない。むろん道具も、衣服も、食べ物さえないのだ。
ではどうしてこうして私が生きていられるのかと言えば、考えらえる筋書きは二つだ。
ここに監禁されたのが比較的さいきんで、餓死するほどの時間が流れていないから。もう一つは、私がそういう構造体だからだ、とすればそれらしい。なぜこうして監禁されているかの理由もそれで自明となるし、つまり餓死する心配のいらない構造体だからとすれば、状況説明が前者よりもより明瞭になると言えるのではないか。
笑えてくる。笑い方も忘れてしまったというのに、陽気だけは未だにこみあげてくるのだからやはり可笑しい。
はっと顔をあげると、トカゲの尻尾が手のなかから消えており、顎をしきりにしゃくしゃく言わせているじぶんがいる。口の中が血生臭く、それでいて吐き気を催さないじぶんを妙にしっくりと感じる。
空間はつねに明るく、真っ白だ。じぶんの影すら四面に映らない。時間の経過を判断する指針がない。いったいこの空間に閉じこめられてからどれほど経ったのかもいまではもう覚束ない。
或いは、生まれてからずっとここにいるのかもしれない。
そう言えば、とかつては幾度も思い浮かべてきただろう疑問を舌のうえで転がす。
私はどうやってここにやってきたのだろう。
どうやって入ったのだろう、この何もない部屋に。
そもそも私はどうしてこうも記憶があやふやでありながら、この空間を仕切る壁の材質や、見たこともないはずの外界の様子、それこそここが極秘施設の地下の地下に位置すると思いこんでいるのだろう。いったい私はいつから私を私として認めてきたのだろうか。
目のまえを何かが掠める。視軸をそそいだころには床に新たなトカゲの尻尾がうねうねと身じろいでいる。本体はない。
私はじぶんのゆびを拡張し、私の胴体ほどの太さもあるその切り離された尻尾をつまむと、口内ににじむ唾液を呑みこむようにして、丸太のようなそれに齧りつく。
なぜ見たこともないはずの丸太をこうして連想できるのかは、解らないし、もはやそれをふしぎにすら思わない。
私はおそらく、ずっとここに存在したのだ。
私を囲うようにきっと、箱のほうからやってきた。
壁と床で包まれた。
腰の付け根に痛痒を感じる。
ムズムズと収斂するそれは、間もなく、この真っ白で何もない空間に私以外の影を、うねうねと身じろぐ太く細長い起伏を、与える。
【グライダーマン】
グライダーマンを引退してからかれこれ十年が経つ。思ったよりも時の流れは早かった。
ソファに身体を預け、目をつむる。
若かりしころに異能に目覚めてからというもの私は、同時期に同じく異能に目覚めた者たちと長きにわたって、社会の秩序をかけての闘争を繰り返してきた。
立ちはだかる相手の多くは悪党ではなかった。そう、みな純粋に誰かを助けんがために、自身の異能を振りかざしていたのだ。私がグライダーマンとして陰に日向に活躍し、徐々に知名度をあげはじめたころにはすでに、虐げられる側の被害者たちのすくなからずはかつては悪党と呼ばれていた者たちだった。
権威を振りかざし利益を搾取する側に属する者たちから順々に、覚醒した異能者たちの餌食となった。次点で刑務所に入るような、世間一般で言うところの犯罪者たちが圧倒的な異能のまえに怯える日々を余儀なく過ごした。わざわざ刑務所に乗りこんでまで彼ら彼女らに制裁を加える異能者が後を絶たなくなったためだ。
私も初めはそうした分かりやすい悪党を懲らしめようと目を光らせていたが、徐々に社会から悪党と呼ぶに値する者たちの姿が消え、数々の異能者たちの手によって葬られていくうちに、何かが違うといった違和感がしこりのように胸に溜まっていった。そうしてその悪党の家族たちのその後の悲惨な生活を眺めているうちに私の胸に溜まったしこりは、黙ってはいられぬとのつよい衝動に変わっていった。
当時、私は戸惑っていた。目のまえにあるのは以前と変わらずの、力ある者が、自身よりも弱い者を支配する世界だったからだ。
私は立ちあがった。グライダーマンとして空を自在に滑走し、高速飛行にも耐え得るほどの頑丈さを湛えた肉体で以って、世の悪党をこらしめることに躍起になる異能者たちのまえに立ち塞がった。
裏切り者だと散々に非難され、抵抗に遭い、ときに袋叩きにされた。一般市民からも私は「悪党のボディガードだ」と指弾された。たしかに構図からすれば、私は悪党の味方だった。しかしさらに視点を変えれば、圧倒的チカラを手にした者たちに虐げられている者たちの味方であった。
むろん、助けた相手が、その後、自身よりも弱い者へと何かしらのチカラを向け行使しようとすれば、やはり私は一度助けたはずの相手のまえに立ち塞がり、その邪魔をしただろう。
強者と弱者という関係性をぶち壊したかった。
言うまでなくそこで私が己がチカラを思うがままに振るい、悪党や異能者たちを圧倒してしまえば、私こそが強者となり、支配者となり、邪魔されて然るべきナニカシラになってしまう懸念は常にある。ゆえに私は強者と弱者という構図が完成しないように、成立しないように、ただ邪魔をした。
いったいおまえは誰の味方なのだと捨て台詞のように投げかけられたこともしばしばだ。誰の味方でもなかった。正義のつもりもなく、ましてや正義の味方ですらない。
では弱い者の味方なのかと言えばそれも異なり、私は弱者にこれといって施しを与えることも、恵むこともしなかった。
貧しい者を豊かにしたいわけではなく、弱者を救いたいわけでもなかった。
ただただ単純に、見ていられなかっただけなのだ。
強者がチカラを振るい、弱者を虐げ、支配する世界を、私は見ていたくなかった。
見ていられなかった。
しかし、いくら私が邪魔をしたところで、世界中のすべての異能者の動向を見張ってはいられない。異能者のなかには、世界中の人間の行動を監視可能なチカラを持った者もいたが、仮にそうした者の助けを借りたところで、やはりすべての強者の日々の行動に目を光らせ、邪魔をするだけの能力も手間も、時間だって私にはなかった。
よしんばそのようなことが可能であったとして、けっきょくのところ私が死ねば、或いはグライダーマンとしての異能を失くしてしまえば、また元の、強者が弱者を虐げる世界が徐々に、しかし確実に社会の基盤として再構築されていく。
イタチゴッコであるし、焼け石に水だ。
あるとき、異能を封じられた異能者が一般市民からの反撃を受け、滅多打ちにされた事件が起こった。科学技術は、異能者の能力の秘密をも暴き、その異能無効化の手段を世界へと広めた。
これまで強者としての地位が揺るがなかった異能者たちの立場が、音を立てて崩れはじめた。
私は、目のまえで大勢の弱者から滅多打ちにされるかつて強者として振る舞っていた者たちの成れの果てを目にし、そしてそこに介入する真似もせず、目を背けることもせずに、ただその様子を眺めていた。
世界中どこにいても、そうした光景が目についた。
きっと部屋に引きこもったところで同じだろう。買い物をしにそとにでるだけでも嫌でも世界中で引き起きている暴動の話は耳に、目に、入った。
私はそれら弱い者いじめを邪魔しようとは思わなかった。する気がなかった。
自業自得だとは思わない。
ただ、疲れてしまった。
私がいくらあいだに入ったところで、砂時計はいくらでも引っくり返り、そして砂を上から下へと落としつづける。私はただ、その砂時計の真ん中にあいた細く、狭い、ちいさな穴にすぎなかった。
疲れてしまった。
私はグライダーマンを引退し、正体を隠したまま、目のまえで繰り広げられる盛大な弱い者いじめを尻目に、庭で育てた自家栽培のトマトやカボチャで食卓を飾り、ときに肥えたニワトリの首を跳ねてタンパク質を補う。
そうして日々、食物連鎖の頂点に立つ者としてのチカラをぞんぶんに活かし、すこしばかり手間のかかった食事を楽しみとする生活を送る。
邪魔する者が現れたらきっと私は黙ってはいられないだろう。抵抗するだろう。ときに、異能を使って返り討ちにするかもしれない。
ただ、いまのところそうした危機には見舞われていない。
私は老いた。
そして遠からず死ぬだろう。
そのときがくるまでこうして、世界中から聞こえてくる砂時計の引っくり返る音を耳にしながら、蝉や蛙の鳴き声のようにときに煩わしく感じつつも、それら音色に風情を見出し、束の間の平穏を思うのだ。
【ピックを握りしめて】
音楽という名の事象は存在しない。偶然にしろ必然にしろ、いくつかの物体の振動が空気を揺るがせ、同一時空上にて重なり合い、それを聴く者の脳内にて「音楽」として顕現する。
音楽は、ただそこにあるだけでは音楽たりえない。
それは人間の内面世界にて現れる魔法だ。
瀟洒な酒場のカウンターに一人の男が座っている。名を、ガクフと言う。彼のもとに吸いこまれるように女が一人、寄っていく。
「あら、珍しい。きょうは【探索】にはいかなかったの」
「もう潜った」
「ああ」女はガクフのよこに座ると、「あいかわらずおはやいこと」
言いながらカウンターの机上をゆびでタップする。するとテーブルにどこからともなくグラスが現れる。中身は青い。女はそれを飲み干すまで口を利かなかった。
「なんの用だ」ガクフは言った。しびれを切らしたからだが、女がそう仕向けていたのは知っている。
「あさって、ニトロデイのミニアルバムが【盤上】に乗る。賞金は十億オンプ」
「そりゃ太っ腹なこって」
「もちろん潜るんでしょ」
「だったらどうだってんだ」
「お願いがあって」女はバッグからちいさな貝殻のようなものを取りだした。「これを向こうに置いてきてほしいの。報酬は弾むから」
「向こうの、どこだよ」
「分からない」
ガクフは返事をせずに、女から寄こされたちいさな貝殻のようなものをゆびでつまんだ。ピックだ。ギターやベースを弾くためのアイテムだ。
「わるいな。仕事の安請け合いはしない性質でな」
「持っていくだけでも。お願い」
渋っていると、お守りだと思って、と女が口にしたところで陽気が漏れた。
お守りか。
ピックをポケットに仕舞う。
「失くしちまっても文句は言うなよ」
「言うに決まってるでしょ。ありがとう」
女から握手を求められたが、ガクフはその手をじっと見るに留めた。女の手のひらにはイレズミのような黒いハートが刻まれている。
音楽の世界に潜る技術が確立されたのは音歴二十一年になってからのことだ。それから五十年あまり、人類は音楽の世界から持ち帰った【宝材】を資源に社会を発展させつづけてきた。
企業は資本として保有する「過去の名盤」を賞金つきで探索の対象とする。名盤であればあるほどそのなかに眠る【宝材】は資源的な価値が高い傾向にある。
今宵、ニトロデイのあの一枚が「盤上」にかけられる。
潜るよりない。探索家ならずともいちどは夢見る一枚だ。
女から受け取ったピックを手に、ガクフは音楽の世界へと旅立った。
探索家が職業として成立するいちばんの理由は、その危険度にある。音楽の世界に潜ったまま帰らない者は珍しくはない。
たとえば今回の一枚「少年たちの予感」は危険度の高さで言えば、第九や運命に次ぐとまで言われている。
音歴がはじまる以前に編まれたミニアルバムだ。一曲目の「ヘッドセット・キッズ」は、巨大な子どもの疾走する足場を抜け、その足の裏に貼りついた【宝材】を奪取せねばならない。
二曲目は「ダイヤモンド・キッス」だ。蠱惑的な魔女たちのひしめく城に忍び込み、【宝材】を回収するわけだが、どこに【ダイヤモンド・キッス】があるのかは未だ不明だ。探しだすところからはじめねばならず、それだけ危険が多いことの裏返しでもある。
三曲目の「ブラックホール feat.ninoheron」に到っては、その世界にまで潜って帰ってきた者がいないためいっさいが不明だ。まさにブラックホールの名に恥じない迷宮ぶりだ。
もはやこのさきは伝説にすらならない魔の領域だ。
だがガクフはまるで攻略法でも知っているかのような滑らかさで最終曲「ユース」まで辿り着いた。
そこは一軒のライブハウスだった。広くはない。だからこそというべきか、フロア内は熱気につつまれている。
バンドが演奏している。ガクフはなぜか懐かしいと思った。このままここに留まり、その曲を口ずさんでいたかった。
なぜここにいるのか、すでにもう覚束ない。
バンドのギタリストが激しく腕を振る。
何かが宙を舞った。
時が止まる。視界から色が失せ、宙に舞った何かが闇に溶けて消えた。
ガクフは拳を握っている。手のひらに鋭い痛みを覚える。
ゆびを開く。
ピックだ。
なぜこんなものを。
ゆっくりと意識が覚醒していくのを感じる。
バンドのメンバーが順繰りと闇に消えていく。
ギタリストの手が最後まで闇に残った。
闇を泳ぐように掻き分け、ガクフはギタリストの元まで辿り着く。
そこに、ピックを置いた。
つぎに気づいたとき、ガクフは「盤上の門」のまえに立っていた。戻ってきたのだ。基準世界に。
背に負ぶったリュックは、回収した数々の【宝材】の重さを湛えている。
手のひらが熱い。
見遣ると、ピックのカタチに色濃く火傷のあとが残っている。
【少年は予感する】
少年は目を開いたと同時に、何かが違うとすぐに気づくことができた。見慣れた街並みではある。だがどこか違う。車道を行きかう無人タクシーの列、ドローンが上空を埋め尽くし、すれ違う人々はみなオシャレなマスクをしている。きっと街中に設置された監視カメラの解析を拒んでいるのだ。道行く人々の足元には矢印が浮かび、道案内をしているようだった。
同じ街並みだが、同じ時代ではない。
時間を跳躍してしまったようだ。少年は事態を呑みこんだ。
時間を飛び越えるなんてありえない。そうは思ったが、目のまえの現実を否定するだけの論理を少年は構築することができなかった。
少年のよく知る時代にはない技術が街中にはたくさんあった。少年にはそれらを使いこなすことができない。だが、それほど長い時間を跳躍したとは思えなかった。街並みそのものはそれほど大きく変わっていないからだ。見覚えのあるビルがある。少年の記憶にはないビルも数多く建っている。
少年はまずじぶんの住まいに向かった。家が残っているのかは分からないし、よしんばそこに誰かが住んでいたとして、それが少年の知る誰かであるとは限らない。だが、なんとなく行けば知っているひとに会える気がした。ひょっとしたらこの時代のじぶんに会えるかもしれない。そんな想像をしてすこしのわくわくと、こわさを舌のうえで飴玉を転がすように味わった。
街のそこかしこからはバンドの曲が流れていた。ニトロデイの「ヘッドセット・キッズ」だ。少年には馴染みのある曲で、時代をまたいで聴くことができたことに気分をよくした。この時代ではどうやらニトロデイは超人気バンドだ。少年のいた時代とはやはりすこし違うようだった。
家に辿り着くころには辺りはすっかり暗くなっていた。遠くに走る無人タクシーの、道路をタイヤが舐める音が、さびしげに響いて聞こえる。人通りはなく、閑散としたものだ。不気味に思ったが、少年はニトロデイの「ダイヤモンド・キッス」を口笛で吹きながら、ふふふっふー、とスキップをした。気分はすっかりふしぎの国のアリスだ。
家には明かりが灯っていた。少年の知る外観とは異なったが、名残はある。
少年は庭に足を踏み入れた。急に足元にスポットが当たったので飛び跳ねた。自動で点灯する仕組みだったようだ。心臓にわるい。
庭は広く、暗がりにポツポツと開くスポットの丸い点は、まるで宇宙の足場だ。ワープ走行の痕跡のようでもある。少年はニトロデイの「ブラックホール feat.ninoheron」を頭の中で再生させ、家の窓に近づいた。
カーテンが下りている。生地の薄いレースのようなもので、透けて見える家のなかを眺め、少年は、ほぉ、と唸った。
年のころは同じだろう、そこには少年と瓜二つの少年がいた。もうひとりのじぶんだ、と少年は思った。時間を跳躍したのではなく、ではここはべつの世界なのだろうか。そういった想像も巡らせた。
なんだか急に、じぶんの居場所を奪われた心地がした。
じぶんの存在が薄くなった気がして、みじめで、なさけなくて、その場から消えてなくなってしまいそうだった。少年はかろうじてニトロデイの「アンカー」を口ずさみ、これがたとえばすべて夢だったとして、と現実逃避をしようとするのだが、それでも目のまえの現実は何一つ揺らぐことなく、ただそこに在りつづける。
少年は足踏みし、それから意を決して窓から離れた。
ここはぼくの家かもしれない。でもぼくの帰る場所ではない。
庭を抜け、道路に立ち、また元きた道を引き返そうとしたとき、家の扉が開いた。なかから少年と瓜二つの少年がこそこそと抜けだしてくるところだった。少年は壁に身をひそめ、その様子を窺った。
少年はふと、父親からむかし聞いた話を思いだしていた。頭のなかでは「少年たちの予感」のライブ音源が断片的に、つぎつぎと流れていく。
「父さんな、むかしドッペルゲンガーに助けられたことがあってな。車に轢かれそうになったところを――」
父親の言葉が脳裡に蘇える。目のまえでは、家を振り返り、振り返り、道路まで小走りにやってくる少年と瓜二つの少年の姿がある。
ふと、視界の端に黒いカタマリが映った。それは道路を舐める音を響かせながら、まっすぐとこちらへやってくる。
無人タクシーだ。ライトが点いていない。
少年と瓜二つの少年はそれに気づいていない様子だ。そのまま庭から道路に飛びだそうとしている。
少年の身体はそうあるべきようにと、動きだしている。
頭のなかではニトロデイの「ユース」が流れる。
浮遊感を覚える。
無人タクシーが遠ざかる。
少年は予感する。
きっといまぼくは、このさき産まれてくるだろう、じぶん自身を助けたのだ。
道路に仰臥しながら少年は、じぶんとよく似た少年の身体を抱きすくめている。
【お城のパーティーにとっときな】
「いたいた、ニト。探したよ」
「んだよデイブ。朝っぱらからおまえの声は厳しいな。まるでアルプス山脈にコーヒーが流れているみたいだ。ギトギトの濃いやつな」
「目が覚めてよくない? それよりほら、ニトが聴きたがってたやつ」
「あん?」
「ニトロデイの最新ミニアルバムだよ。ニト好きだったよね。リリースされたんだよ、知らなかったの」
「おいおい困ったちゃんだな。アタシを誰だと思ってんだ、じぶんの大好物はどんなもんでも発売日の三日前に入手済みだ」
「あ、そうなんだ」
「だいたいな、おまえはアタシがなんでニトロデイ好きか知ってんのか」
「それはもちろん、ほら【ニトロデイ】にはニトの名前が入ってるし」
「デイブ。おまえがアタシの名前に欲情すんのは百歩譲ってキモいで済ますとして」
「あ、キモいのは前提なんだ」
「ニトロデイのなんたるかも知らずにそれを餌に特大ネッシー釣ろうなんて、なんだろうなー、おまえの顔見てっとムカムカすんなー」
「けっきょく顔なの!? ルッキズムって知っているかな。そうやってひとの見た目で差別をするのは現代人として問題があって」
「ウッセー。なんとかの犬ってのあんだろ。ベル鳴らすだけでよだれ垂らすようになるやつ。あれだよあれ。デイブ、おまえがそうやって会うたびにアタシに講釈垂れっから、おまえの存在イコールうざいつってな、脳みそにインプットされちまった」
「あ、同じかも。ニトがいつも聴いているから好きなんだきっと。ニトロデイ」
「そりゃバンドに失礼ってもんだろ」
「わ、顔真っ赤。そうやって人を毛嫌いしておいて照れるところでちゃんと照れてくれるところとかも好きな理由の一つだよ」
「アタシはおまえのそういうサブイボの立つセリフをクソマジメに吐きだすところが嫌いだよ。大嫌いだ」
「その割に、追いかえしたりはしないし、バンドの曲をおすすめしてくれたり、なんだかんだ曲の感想を聞きたがったりするよね」
「布教だよ布教。誰でもいいんだ、おまえじゃなくたってな」
「ふうん。でも今回のミニアルバム。なんだかこれまでのニトロデイとはすこし違った感じがしたけど、やっぱりニトもそう思った?」
「思った」
「わ、やった。意見が合ったの初めてじゃない?」
「やっぱウソだ。思わなかった。これまで通りのニトロデイだった。曲調はすこしポップに寄せてきた感じがあったが、あんなのはメイクをすこし変えましたって感じの変化だ。たいした変化じゃない」
「そんなこと言って。もしバンドにとって大きな変化だったらどうするの。それをニトが否定していいの」
「う……。まあ、たしかに意図して冒険した感はあった。ミニアルバムのタイトルだって【少年たちの予感】だろ。こりゃあれだ。このさきを暗示してんだよ。こっからさき、私たちは大きな変化を遂げていく、成長していく、それを予感してくれってな」
「ああ、なるほど」
「曲の構成もそんな感じだったな。アルバムの一曲目はふつう、そのバンドの顔だ。現時点でのバンドの色を教えてくれるような一曲を置く。それがこれまでのニトロデイとは打って変わった明るく駆けだしていくような曲――【ヘッドセット・キッズ】だったことを思うと、たぶんこれからはどんどんそっち方面にも触手を伸ばしていくぜ、足を踏みだしていくぜ、ってそうした決意表明を感じずにはいられなかったな」
「さすがニト。だいすきなバンドの話になると早口になるね」
「早口に……なってたか?」
「ニトってライブに行くのも好きだよね。あれはなんで? べつにスマホで聴いても同じなのに」
「同じじゃねぇよ。バカかよ。ライブだぞ。一発勝負の本番、生演奏、空間全体を揺るがして身体の芯ごと共鳴する曲との一体感――それがイヤホンで聴く曲といっしょだと? デイブ、おまえはいまイッチャン踏んじゃいけねぇ特大地雷を踏んだ」
「そんなに違うの?」
「ぜんぜん違う。や、修正につぐ修正の加えられた理想の一曲を詰めこんだアルバムにもそりゃいいところはあるよ、そこは認める。それに今回のミニアルバム、後半の四曲はライブ音源だしな。一発本番のよさを改めて何度も聴きなおせるよさもなくはない」
「でもやっぱりライブを観るのとは違うんだ?」
「観るんじゃねぇ、体感するんだ。一体化だ。バンドの一部、曲の一部にアタシもなるんだ」
「ふうん。あのねニト、ここにチケットが二枚あるんだけど」
「あ?」
「いっしょに行ってくれない? ライブがどんなものか、【わたし】も体験してみたいから」
「……デイブ」
「嫌なら、ニト一人で行ってきなよ。チケットはあげるから」
「んなこと言われてハイヨって受け取れねぇだろ。アタシをいじめっ子にしたいのかよ。いいよ、行ってやるよ。そんかしおまえ」
「なに?」
「スカートはやめとけ。そういうヒラヒラはお城のパーティーにとっときな」
【スペースミュージック】
わたしの名前は◇×☆↓△。
宇宙を旅するミュジク人だ。
宇宙の秩序を守るため、わたしたちはこうして指令を受けるたびに多元宇宙を横断する。
今回はДДИшЮの第三宇宙にきてるとこ。もうすぐ目標地点に到達予定だけれど、やっぱりそこそこの長旅なわけで、疲れちゃうというか、飽きちゃうというか、だってずっとパブリばっかりやっててそんなの中枢核が腐っちゃうじゃない?
で、本当は禁止されてるんだけど、船外に探査機飛ばしてこの宇宙の物理法則のゆがみを解析してたら、あらやだ、なにあれ?
なんか恒星の電磁波を受けてキラキラ光ってる物体があるじゃない? 回収してみたらなんか平べったくて薄い円形の物体で、カカブに訊いたら中に低度に圧縮されたデータが入ってるって言うでしょ。あ、カカブっていうのは超無機物構造体で、まあわたしのつくった相棒みたいな感じかな。
で、カカブに調べてもらったら、中身のデータを再生できるらしいって言うじゃない? まあじゃあ、やってもらおうじゃないの、ってことになって、なってっていうかそう指示したのはわたしなんだけど、で、いざ指示したらカカブってばその場でわたしの拾った円盤を呑みこむでしょ。
で、なんか妙な鳴き声を発するわけ。
妙なって感じたのは最初だけだったんだけど。
なんか聴いてるうちに心地よくなってきちゃって。
なんか節目が八つあって。
あ、八つの鳴き声が入ってるのかって段々わかってきて。
言語っぽいなって思って、翻訳機に晒したらばっちし、なるほどこれはあれだ、いま向かってる惑星の現地語だって解って。
ってことは、これはその惑星の住民の創造物ってことで、なるほどなるほど、なかなか愉快だなって。
まずその星にはバンドって概念があるらしい。それでそのバンドってのにもたくさんの名前があって、そのうちのひとつがニトロデイっていうらしい。で、バンドはどれも音楽ってものをつくるらしくて、畢竟、いまカカブが鳴らしているこれが音楽なのだ。
ニトロデイのつくった音楽ってことになるのかな。
ほかにもじゃあたくさんの音楽があるってことだ。
聴いてみたいな。
どんな音なのかな。
想像すると全身の鱗がキシキシ云った。
なんども繰り返し聞いているうちに、どれが一つ目の音楽で、どれが最後の音楽なのかも判るようになった。
「カカブ、二つ目をおねがい」
気分によってどれがいいかなって選んだりして、なんだかちょっと贅沢な気分だ。
浮かない旅路もこれならご機嫌だ。
音楽ってやつは素晴らしいな。これは戻ったらみんなに自慢できるぞ、なんだったらわたしたちの価値観ってやつを根こそぎ変えてしまうかもしれない。
だったらいっそ、ほかの音楽ってやつも根こそぎ集めてみてもいいかもな。
どうせ滅ぼしちゃうわけだし。
わたしの使命はそれなんだし。
思うとなんだか中枢核のところがじゅくじゅく痛んだ。まるで何かを拒むようなその痛みに戸惑いながら、それでもすこし心地よい気がした。
目標地点が見えてきた。
いまはまた一つ目の音楽を聴いているところだ。
ヘッドセット・キッズ、遠い彼方に。
二つ目を聴く。ダイヤモンド・キッス、いつもと違う予感がする。
三つ目、四つ目、とつづけ、けっきょく最後まで聴いて、また最初の一つ目に戻る。
目のまえの惑星は全体的にニャーだ。たぶん電磁波のうちニャー波を多く反射するからじゃないかな。本当にニャーだ。
ニャーはどちらかと言えばわたしたちを不快にさせる。
でもカカブの鳴らしつづけるあの惑星の音楽につつまれていると、なんだかニャーもそれほどわるいものには思えなくなってくる。
わたしの使命はあの惑星を滅ぼすことだ。より正確にはあの惑星に繁殖した生命体を根こそぎ絶やすことにある。詳しい理由はわからないんだけど、たぶんいつものように、あの惑星の生命体がいずれほかの宇宙に干渉する術を見つけてしまうと予見できたからじゃないかな。この宇宙では何億年先のできごとかもしれないんだけど、宇宙同士は時空がねじれているから、いつそれが起こるのかはあまり関係がない。
いつかは起こる。そう解かった時点でそれはわたしたちからすると脅威なのだ。
でも。
わたしはまたニトロデイの音楽をカカブに鳴らさせる。
この音楽なるものを生みだす存在を滅ぼしてしまうのは惜しい気がした。
単純に、惜しい。
この惑星の生命体がいつかこのさきわたしたちの宇宙に干渉してきたとして、それはわたしたちがおそれるほど避けるべき事態ではないのかもしれない。
だってひょっとしたら、この音楽とやらを届けてくれるかもしれないのだから。
わたしは迷った挙句、カカブにこの星への着地を命じた。
この惑星について、わたしはもっとよく知る必要がある。
【禁音の果てに】
禁音、それは「音楽禁止令」の通称である。技術的特異点を迎え、社会の中枢を担うようになった人工知能「オンプ」により発足された法度である。その日、全世界から音楽の旋律は途絶えた。
人々は徐々に音楽の存在を忘れていった。伝える者がいないのだ。禁音発足から十年足らずで世代は移り変わり、禁音への反対勢力の勢いも軒並み収束へと向かった。
だが、ゼロではなかった。
音楽への飽くなき欲求、人々を駆り立てたあの熱気、興奮、生きているという実感――音楽の禁じられた世界にあって世界は色を失くした、しかし灰色の世界にこそ音楽は必要なはずだ。
この世界にこそ音楽が。
立ちあがった者の名は、小室ぺい、ニトロデイを率いるボーカリストだった。
「おかしいだろ。音楽がダメ? アホ言ってんな。音を楽しむのが禁じられたならしょうがねえ、だったら楽しい気持ちを音にしちまおう」
音楽がダメなら、「楽音」を新たにつくりだしてしまえばよいのではないか。
単純な発想だったが、禁音にはたしかに「あらゆる音楽を禁ずる」としか記されていなかった。律動や旋律そのものを禁じてはいなかったのだ。なぜなら律動を禁じれば人々の鼓動、歩行、生活行動様式、さまざまなサイクルを排斥しかねない。また旋律は、言語そのものを封じかねない懸念もあった。人類を管理する中枢人工知能「オンプ」そのものもまた、アルゴリズムという名のシステム、ある種の律動や旋律によってその機能を維持している。
「楽器を使うな、歌を使うな、そんなことでオレらから音を、曲を奪えるなんて本気で思ってんのかね。人工知能も高が知れてら」
世のなかには音がすでに無数に溢れている。ときに共鳴しあい、錯綜しあい、絡みあって偶然に、そこかしこに、音の楽しむ余地を広げている。むろん社会の至る箇所に設置された保安カメラ、集音機、各種センサーによって、音楽に値する音は即座に察知され、にどと音が組み合わさらないようにと解体された。
ある意味でそれは、中枢人工知能「オンプ」がいまなお膨大な音楽のビッグデータを保有していることの裏返しでもあった。社会に鳴り響くつつましやかな音楽の余韻を、音楽と見做すだけの情報を「オンプ」は現在進行形で蓄積している。
ひるがえって、「オンプ」の記録にない新たな「楽音」であれば、或いは「オンプ」に察知されず、よしんば察知されたところで禁音に抵触したとは見做されないのかもしれなかった。
「ぺい、どうすんの」
「まずは映画でも観るか。BGMねえのが惜しいけどな」
言いながら胸に集音機をあてがいながら小室ぺいはメンバーと共に映画をはしごした。その際に録音したじぶんたちの心臓の音を組み合わせ、一つの曲の基盤をつくった。
「間違いなくこれはオレたちだけの【楽音】だ。映画を観て楽しいと思った気持ち、怖い気持ち、興奮、感動、すべてここに凝結してる」
つぎに向かったのは遊園地だ。パレードのない夢の国はそれはそれでアトラクションが洗練されており楽しめた。人々の絶叫の声、和気あいあいとした話し声、迷子の泣き声や、駄々をこねる子どもの声、どれも感情に溢れ、起伏に富んでいた。
「音楽がなくてもみんな幸せそう」
「音楽があればもっと幸せになれんだよ」
「まるで中毒者の発想だね」
「中毒者だからな。音楽の。だが副作用があるか。ないなら魔法の薬だよ」
音楽はな。
しかしニトロデイのつくる曲は、楽しい気持ちを音にした「楽音」だ。これまでの音楽とは一線を画する。
じぶんたちの鼓動を組み合わせてつくった曲の基盤に、ニトロデイは人々の感情の起伏を上乗せし、ていねいに編みこんだ。
「さて、仕上げといこう」
小室ぺいはメンバーと向かいあい、そして踊った。音はない。無音のなかでただ踊る。じぶんだけに聴こえる音楽の記憶を頼りに。じぶんのなかに響く「楽しい」を手繰り寄せるように。
そばには彼ら彼女らのたてる物音を集音する機器が起動したままになっている。
そうして集めた「踊りの物音」を最後にニトロデイはこれまで編みこんできた「楽音」にちょいと添えた。
ニトロデイ、最初の一曲がこうして完成した。
街中で爆音で鳴らす。見せつけるように。気づかせるように。
中枢人工知能「オンプ」の反応を試すように。
どうだ、おまえにこれが理解できるか?
人々は騒然とする。立ち止まる者、耳を澄ます者、見て見ぬふりをする者、その場で踊りだす者、懸命にその「音」を記録することに躍起になる者――。
ニトロデイはそうした人々から立ちのぼる喧騒を集音し、さらに二曲目の構想を練る。
彼ら彼女らの頭の中には予感が満ちている。
新しい時代への幕開けだ。
音楽は死んじゃいない。
楽しい、の逆襲がこれからはじまる。
街中にはまだ、ニトロデイの流した音が鳴りつづけている。
【黙れよギター】
ギターがしゃべるなんて言ったらたぶんふつうに頭おかしいって思われんだろうなぁ。
でもしゃべんだよなぁ、コイツ。
やぎひろみはスタジオの一室でギターを見下ろしている。ひざに載せたそれの弦を調整しながら、
「イテー、イテーって。やぎちゃんよー、もっと優しくしてくれよ。もっとこうほら、あんだろ愛を籠めた手つきってもんがさあ」
セクハラでしかない発言を聞き流す。そばにはほかのメンバーもいるが彼ら彼女らに聞こえている素振りはない。
いつもより気持ちつよめに弦を張り、さらに音を鳴らして調節する。やっぱりすこし締めすぎたかな。
「イテー、イテーって」
なおも愛用のギターは喚き散らした。
昔から聞こえていたわけではない。ただ、前兆のようなものはあった気がする。ギターにかぎらず、やぎひろみが長年使い古した道具、それはたとえば三歳の誕生日に親からもらったカエルのぬいぐるみや、祖父から譲ってもらった音楽再生機、繰り返し聴いたお気に入りのCDや、履きつぶした靴も、ときおりだが声のようなものを発した。
明確に言葉として聞き取れたわけではないが、なんとなくそれが発した声ではないのか、と思うことはあった。もちろんしばらくすれば幻聴だと気にも留めなくなったし、いま思い返してみても、気のせいだと見做したほうがしっくりくる。
だが今回ばかりは愛用のギターははっきりと聞き取れる言葉を、意味を含んだ声を発した。
ギターの声は周囲に聞こえないからよいとして、こちらの応答は周囲の者にも聞こえる。街には手ぶらで通話する者がいるくらいだから、ひょっとしたらやぎひろみが案じるほどには奇異な目で見られたりはしないのかもしれない。
ギターの声には反応を返さずにいた。
認めたくないだけだったのかもしれない。
幻聴を本気にするだなんてどうかしている。
ギターに名前をつけるギタリストもいるが、やぎひろみは敢えてギターには名をつけない主義だった。どうせ壊れたら買い換えるのだ。手に馴染むギターがほかにあるなら容赦なく買い換える。
とはいえこのギターよりも身体にしっくりくる一本がいまのところない。
愛用ではあるのだ。愛着がある。
ただ、しゃべるのだ。無駄にウザく。
「へいへい! もっと弾いてくれ、引いてくれ、ぶってくれ! ひゃほー、最高だぜやぎちゃん! もっとくれ、もっともっとだ!」
ライブの演奏中でもこんな具合だ。否、気分の乗った演奏であればあるほどギターは調子に乗って騒ぎ立てる。
いい加減にしろ。折るぞ。
つよく念じてみても伝わる気配はない。
ゲストを呼んだだいじな回のことだ。ギターはあろうことか歌いだした。しかも演奏曲とはまったく関係のないクリスマスソングだ。
かろうじて歌だと思えるくらいのオンチさで、やぎひろみの集中力を以ってしても、聞き流すには骨が折れた。
間もなく曲の旋律を辿れなくなった。どんな曲だったのか、その起伏をいっしゅん忘れた。そのいっしゅんは、つぎつぎと遅延を生み、ほかのメンバーの演奏についていけなくなり、もはや自分自身が巨大なノイズか何かに感じられたのを機に、ギターを弾く手を止めてしまった。
ギタリストとしてあるまじき態度だ。じぶんのなかの何かが大きくゆがんだ。
ギターはなおも耳障りな歌をまき散らしている。
二曲目、三曲目、休憩が入るまでやぎひろみの集中力は戻らなかった。
休憩時間、誰よりさきに舞台からおり、楽屋に入るなり、ギターを振りあげる。
そのまま床に叩きつけようと思った。
だが寸前で腕にちからをこめ軌道を変えた。ギターはブランコのように床の数センチうえを滑空する。
壊してやろうかと思った。反面、幻聴程度の雑音で気を削がれた甘さを棚にあげるじぶんの性根にも腹が煮えた。
「おまえマジで黙れよ」
これは独り言だ。ギターに言ったわけではない。言い聞かせながら歯をつよく噛みしめる。「頼むよ」
楽屋にほかのメンバーは戻ってこなかった。おそらくこちらの変調に気づいて、敢えて放っておいてくれているのだ。ありがたい。
舞台に戻るため廊下にでると、迷い込んだのか酔っぱらった客がいた。
頭をさげながらすれ違うと、酔っ払いは語気を荒らげ、こちらに迫った。腕を伸ばしてくる。単なる痴漢ならまだ我慢できた。だがギターを奪われそうになり、思わず足がでた。酔っ払いがその場にうずくまる。
「薄ぎたねぇ手で触んじゃねぇ」
吐き捨て、舞台上へと急ぐ。
だいじょうぶか、とボーカルが目線で訴えてくる。頷きかえし、ギターを構える。
「いっそ壊してくれりゃよかったんだ」
ギターがまた何事かを言っている。「あんたにゃもっといいのがあるだろう」
うるさい、黙れ。
やぎひろみはピックで火花を散らす。ギターはただ彼女の意のままに音を吐く。
【一本の金髪】
ベースとペースは似ているし、グルーブとグループも似ている。バンドをやっていると言うと、たいていのひとは、わーって目を輝かすのに、ベース担当ですって言うと、来たときと同じ勢いでわーって引いていく。波か。おまいらは寄せては返すさざ波か。
「ベースってバンドの要なのに」
「や、金髪を直してきなさいって先生、そういう話をしてるんだけど」
好きな髪型にしているだけなのにこの国の教育機関はちょっと神経すぎと思う。前はそういう湧いた疑問を真っ向から投げかけていたけれど、だってそれが誠意ってやつじゃないかなって思ってたから、でもたいがい相手が眉と眉のあいだに日本海溝かってくらいのシワを刻むものだからもう何も言わぬ。
「このあいだ街で見たよ。ギター背負ってたからめっちゃ目立ってんの」
「ベースな」
「学校サボって何してんの。ウケる」
そう言う時点であなたもサボっていたのだろ。そしてここさいきんは授業をサボった覚えはないのじゃぞ。
稀にこうしてどこどこで見かけただの、声かけたのに無視しただの、身に覚えのない目撃譚を語られる。他人の「そら煮」というやつだろう。でもどうしてそらを煮るのだろう? 美味しいのかな。
組んだばかりのバンドはなんだか思っていたのと違って、じぶんでは予想外の方向に行っている気がする。拒絶反応がでればでるほど、あとで、ごめんやっぱ好きだったわ、ってなる。
赤ちゃんが生まれてくるときに大泣きするのになんだか似ている。この世界めっちゃ嫌いなんですけど、もっかい母の身体に戻してーって泣きながら、それでもしばらくすると、ごめんやっぱこっちの世界もよかですばい、みたいな。似てる気がする。
あ、「そら煮」の「煮」は「似るの似」かも。
やっぱり遅れてやってくる気づきはいつも偉大だ。
家に帰ると母が金色の人形を手に持っていた。
「なにそれ」
「きょうおばぁちゃんの家に行ってきてね」
「朝に言ってたね。で、なにそれ」
「なんだかいつも部屋に金髪が落ちてるんだって。で、集めてたらおっきな毛玉になったからもったいないからって、それで作ってみたんだって」
「だって、ってそれ髪の毛ってこと、ひとの? うげ」
「おばぁちゃんは孫のじゃないかって言ってたけど、母は、娘のではないんじゃないかって答えておいた」
「そりゃ行ってないからね。落としようがないし。え、どうすんのそれ。飾らないでよ、なんか怖いし」
母が考えこむので、
「え、やめてよ」と念を押す。「釘とかで刺されたらふつうに死にそうなんだけど。や、それがあったか、って手でぽんってしないで。釘どこだっけって探しださないで。エレクサに神社の場所とか訊かなくていいから、や、エレクサも答えんでええんやで?」
母はけっきょくじぶんの部屋に置いておくことにしたらしい。なぜ、と訊くと返ってきた答えに脱力する。「だってかわいいじゃない」
金髪はそれ以外でも、行ったことのないはずの友人の家や、先生の家、ほかにもさまざまな場所で発見されては、みな一様にその旨を今世紀最大の発見みたいに報告してくる。
「困るなあ、かってについてこられると」
話のネタとしていじられる分にはいいけど、その頻度が多いとさすがに胸のなかが曇り空だ。
二度目のライブのとき、寝坊した。
ベッドから跳ね起き、ホースのさきっちょを押しつぶすみたいに家から飛びだして、駅までダッシュした。特急に乗りこむまでのあいだに、遅れてごめんもうすぐ着く、とテキストメッセージを送るも、返事はない。
怒ってるのかな、怒ってるよな。
焦るのもバカらしくなってゆっくり歩いた。焼き立てパンでも食べてこ。
ベースがなくとも演奏はできる。味気ないだけで、まあカタチにはなる。めっちゃ味気ないけど。
想像するとおかしかった。
やっぱりすこし急いでやることにする。
いざ現場に着くと、まさに絶賛ライブ中だった。見知った顔が舞台のうえで楽器を叩き、弾き、歌っている。
思ったよりもちゃんとした曲になっている。
舞台上の人影は四人分ある。バンドの人数も元々四人だ。ベースの音があり、骨格として曲を底から支えている。
代理を立てたのかな。
疑問は、舞台上に揺らぐ金髪を見て、引っこんだ。
じぶんがいた。じぶんがベースを弾いている。
あれ、双子なんだっけ?
じぶんの出自を思い起こし、いやいやそんなわけが、と混乱する。
客観的に初めてじぶんたちのライブを観た。曲を聴いた。身体に染みこむようなその音の連なりたちは、思っていたよりもずっとしっくりと骨身に染みた。
まあ、たまにはこんな日もあっていいか。
担いでいた楽器を置こうとする。
なぜか肩にそれはなく、身体が妙に軽いことをふしぎに思いながら、金髪が一本、ライトの合間を縫って落ちていくのをじっと見る。
【ドラマーのドラマ】
ひとを殴ってはいけない。物に当たってもいけない。だが楽器は、叩いて、「なかす」ことが推奨される。上手に叩き、なかせればなかせるほど、人々はもっともっとと称賛の声を投げてよこす。
ロクローはバンドのなかでゆいいつ明確にいつでも年上の存在だ。ほかのメンバーはつねに歳下でありつづけるのだから必然、周囲の人間たちからは年上としての態度を求められる。おまえがバンドじゃいちばん年上なんだろ、とか、けっきょくバンドをまとめるのはおまえなんだ、とか、そういう当たり触りのよいことを言ってきては、直接メンバーに言いにくい批判や要求を投げてよこす。
どいつもこいつも投げてよこすやつばかりだ。称賛にしろ、批判にしろ、野次にしろ罵声にしろ、もっとやさしくそっとなぶるように、ねぶるように、愛を以ってくれろってんだ。
ロクローは憤懣やるかたない。いまのところ理想の女王さまとは出会えていない。もちろん理想の王子さまにもだ。
ロクローには三本の活殺自在に操れる棒がある。うち二本は手に持ってドラムを叩く棒であり、もう一つは下半身のほうに備わっている。手に持つ棒よりも格段に太く立派な――そう、足で踏んでドラムを叩くための棒だ。ペダルを踏むとバスドラムが鳴る。
ペダルを踏んでコンマ何秒の誤差が結果に影響してくる点では、レーサーやパイロットと似ていると思うことがロクローにはあった。
楽曲という名のコースを駆け抜けるスーパーマシン、それがドラムだ。
ロクローは争いを好まぬ。だがうちなる本能には抗いがたく、百獣の王のたてがみに住み着くノミさながらの猛々しさにはいつも気を揉んでいる。
ひとを殴ってはならない。傷つけてはならない。物に当たり散らしてはならない。だが演奏というテイで楽器を叩き、なかすことは許される。
なにより楽器はやり返してこない。
と思っていたのは初めばかりで、ドラムはしかしふつうにやり返してくる。適当な演奏には適当な態度で返し、楽しいときには楽しい音が、このやろーと思うときにはそういう音を響かせる。
加えて、案外に思った以上に、負けるのだ。
いつの間にかその負けることへの快感を覚えている。病みつきになる。
もっと、もっと。
やさしくそっとなぶるように、ねぶるように、愛をくれ。
理想の女王さまにも、王子さまにだって出会えていない人生だが、図らずも理想の楽器とは出会っていたようだ。
ロクローは自身の四本目の棒を乱暴に、慈しむような手つきで撫で回しながら、これからのじぶんに想いを馳せる。おそらく、とロクローは思う。白く、苦く、ときに甘い天使たちをいっせいに世に放つであろう。破廉恥と思うことなかれ。
そう、ロクローはこれからも脳みそが白濁し、ときに苦く、甘い、粗挽きコーヒーのような音楽を、ラッパを吹きながら地上に押しよせる天使たちのように、世に放つのだ。
それは或いは、終末を報せる音かもしれない。
それとも、人間の愚かしさを歌うささめきであってもいい。
殴ってはいけない、当たってもいけない、それでもそうしてなかせる音で、救える感情もあるはずだ。
誰からも見向きもされずに、本人にすらないもの扱いされている感情を、機微を、掬いとることだってできるはずだ。
だからなのだろうか。
それでなのだろうか。
スティックを握りしめ、ためしにドラムを、チクと叩く。
身体の内側に拡がる水面に波紋が広がるのを感じる。
通じている。
音は、音楽は、人間の内面に通じている。
じぶんにしかならせない音を、じぶんにしか揺さぶることのできない世界を、ひとを、感情を、機微を、叫びを、叩き、なかせ、編みこむことでしかその存在の輪郭を帯びることのできない何かを、ロクローはなかったことにしたくはないから。
ないもの扱いをしたくはないから。
されたくはなかったのだ、と何かを求めるじぶんに気づき、ドラムを叩く手を止める。
バンドのほかのメンバーがこちらを振り返る。新曲の練習中だった。音の余韻が部屋に吸いこまれながら消えていく。
「なに? またウンチ?」鋭い声だ。
それはさっき行った、と伝える。めっちゃデカイのがでた、と。
あっそう、とメンバーは飽きれた調子で、また演奏をはじめるが、ロクローはステッィクを握ったまま動かずにいた。
演奏がやみ、なんなの、と非難の目が飛んでくる。
「そのままつづけて」
ロクローはしばらくじぶん抜きの演奏を聴いた。
それからふいに、なあ、と声を張りあげ、苛立たし気に振り返ったメンバーに向け、
「気づいたんだけどさ」と怒鳴るように言った。
なに、とメンバーが不安そうな顔をする。ロクローは告げた。
「オレ、このバンド好きだわ」
あっそう。
脱力するメンバーを眺め、ロクローは満足げにまたドラムを叩き、なかせる。
【ふたたび身体をつつみこむ】
またバイトを辞めた。今年に入って三度目だ。クビになったわけではない。じぶんで辞めたのだ。ただ、辞めると申し出たときの店長の顔、それからそのあとの社員さんや同僚たちの態度の変わりようと言ったらない。
初めから歓迎されてはいなかった。花粉みたいなものだ。またこの季節がやってきたか、と存在を許容されながらも、はやく去ってくれないかな、と祈られるような疎外感があった。
辞めると告げると、こんどは明確に、すでにここにはいない者としての線引きがなされたようだった。分からないでもない。どうせいなくなるのだからそんな相手に心を配るのは損だろう。無理に接していたのならなおさらだ。
貯金に余裕はない。はやくつぎのバイト先を見つけないと。
どこかにじぶんに合った働き先があるのではないか、と思い、店から店を転々としてきたが、真面目に社会人をやっている人々からすればその考え方がまずもって間違っており、腰を下ろしたさきに合わせてじぶんを変えていくしかないんだよ、と正論を説かれるハメとなる。
解ってはいるのだ。ただ、耐えられない。諦められない。もっと息のしやすい場所があるのではないか、と望みを捨てきれずにいる。
駅前を歩いていると、バイト募集中の貼り紙が目に入った。看板を見上げ、そこがCDショップだと知る。CD離れがささやかれて久しく、先行きの不安な様は、なんだかじぶんの姿と重なった。
だからでもないが、店内に吸いこまれるように足を踏み入れている。
閑散としながらも店内にはまばらにひとがいた。みな美術館にでもいるかのように棚から棚をゆっくりと渡り歩いては、ときおりCDを手にとり、その裏面を眺める。
しずかな印象だ。店内にはBGMが流れているが、売り場によって流れている曲が変わる。境目はどこだろうと意識して歩いても、その境目ははっきりとはしなかった。
試聴コーナーが充実している。ふだんからあまり音楽を聴かないから、とりあえずヘッドセットをあたまに被り、画面に浮かぶ再生の文字をただタップする。
ノイズ音が鳴る。いっしゅん機器を壊してしまったのだろうか、と焦ったがそうではなく、元からそういう音源だったようだ。すぐさま軽快な音楽が響きだす。
それとなく画面上の説明文を読む。ミニアルバムらしい。いま聴いている曲は奇しくも「ヘッドセット・キッズ」だ。まるでいまのじぶんを指摘されているようで苦笑が漏れた。
明るくポップな曲調の反面、どこか不安定さを覚える。子どものスキップみたいにリズムが一定ではなく、敢えて道を踏み外している印象があった。それはたしかに最初は不安定さに思われたが、徐々に、子どもが水溜りに飛びこんだり、路肩のブロックのうえに飛び乗ったりするような冒険につきまとう高揚感を思い起こさせる。
こんな感情がかつてじぶんにもあったのか。
いつの間にかあのころのじぶんとは別人になってしまっていたのだと、ちいさくない衝撃を受けた。それはどこかこそばゆく、身体をほぐされる感覚に似ていた。
気づくと二曲目に入っており、こんどは脳裡にパジャマパーティをする少女たちの姿がよみがえる。それはじぶんの記憶ではなく、おそらく映画の一場面の寄せ集めなのだろうけれど、こうした日常もあり得たのではないか、となんだかほかの世界のじぶんと触れあえた気がした。
びっちりと隙間なく埋まった脳内の枠組みがぐんと広がるのに似た錯覚を味わう。視界に色が宿り、重かった瞼が軽くなるのをふしぎに思いながら、三曲目を聴いている。
聴きながら棚に手を伸ばす。目当てのミニアルバムを手に取る。表紙を眺め、それから裏面を見る。店内でほかの客たちがやっていた仕草をじぶんもとっていることに気づき、ああこういうことか、と頬がほころびた。
四曲目を聴き終える前にヘッドセットを外し、レジに向かった。手にはミニアルバムを握ったままだ。
CDをこうしてお店で買うのは初めてだ。きょうこうしてお店に足を踏み入れなかったら、そして試聴した機器の一曲目が偶然このミニアルバムでなかったとしたら、このさき一生CDを買う真似はなかっただろう。出会いとはそもそもそういう偶然の積み重ねの結果でしかないのかもしれないし、ひょっとしたら偶然というものも、誰かの誰かを想う行動が結びつける必然なのかもしれない。
私は誰かのために何かをしたことがあるだろうか。
じぶんとは直接関わることのない、それでもきっとこの世にいるだろう、もうひとりのじぶんのために、何かを。
店をでると喧騒が大きくて驚いた。入口の貼り紙にはバイト募集中とあり、じぶんの境遇を思いだす。それから店頭に置かれた商品の山に目が留まった。ヘッドセットだ。すこし迷ってから箱の山から一つを選び取り、いまきた道へと向き直る。
音楽がふたたび身体をつつみこむ。
【同期性創発体】
結晶学の研究を専門にしている。おおざっぱにくくってしまえば、結晶学とは、結晶がどのような原子配列によってそのカタチを成り立たせているのか、そこにどのような規則があり、それによって物質の性質がどのように変化するのかを考える学問だ。
私のもとに政府機関を名乗る女性がやってきたのは地面にうっすらと氷が張りだした十二月中旬のことだった。
説明もそこそこに車に乗せられ、辿り着いたのは巨大な施設だ。
「表向きは二酸化炭素の圧縮施設です。地中に注入して処理することもあれば、一時的にドライアイスにして保管しておくこともあります」
「エネルギィ変換効率はどうなんですか。圧縮するエネルギィのほうが大きいのでは」
「確かにその通りです。ですが、ほぼ十割、太陽光発電によってまかなっていますから、気候変動対策としての効果は期待できます」
連れて行かれたのは施設の地下だった。航空機でも製造していそうな広大なドーム内に、大量の黒い箱が並んでいる。縦にも積みあがっており、巨大な結晶の内部にでも迷い込んだような錯覚に陥る。
足音がどこまでも反響して聞こえるほど静かだ。
「ここは?」
「新しい結晶構造を開発するための施設です。ご専門であられますよね」
「こんな施設があったなんて初耳なんですが」
「いわゆる極秘施設ではあります」
ジョークのような響きがあった。彼女は続ける。「箱の一つ一つにスピーカーが備わっています。内部に向けてこの世に存在するあらゆる【波形】を発しています。環境騒音から生活音、話し声、言語、音楽、歌、動物の鳴き声、もちろん宇宙から届くノイズも増幅して聴かせています」
「聴かせるとは、何に?」
「一種の共鳴なんです」彼女はこちらの質問には答えなかった。「雪の結晶が同じカタチをとることはないとは言われていますが、確率の問題として同じカタチを取ることはあり得るでしょう。現に、同じカタチになるように結晶させることは技術的に可能です」
「まあ、そうでしょうが」
それこそ音波や電磁波を使えば可能だろう。視えない型で以って、木々の枝葉を剪定するように結晶の成長を制限すればいい。いわば修正だ。
「原理的には似たようなものです。我々はその物質を【同期性創発体】と呼んでいます。周囲に介在する【波】を結晶構造に反映させる性質がとても高いのです」
「なるほど」
仮にそんな物質があるのならば、たしかに新しい結晶構造は容易に見つかるだろう。それこそいくらでもつくれるはずだ。
「ただ問題は、あまりにその【同期性創発】という性質が鋭敏すぎるために、せっかくつくった結晶構造をこの箱のなかから取りだせないのです」
「ああ、変容してしまうんですね」
「箱内部の状態はカメラで観察できていますから、新しい結晶かどうかの判断はつきます。ただ、それを調べる手立てがない」
「そこで結晶の専門家である私の出番というわけですか」自虐をこめて言ったつもりだ。
「安定した新しい結晶を開発したいのです」
「言い換えるなら、【同期性創発体】を安定させたいと」
「はい」
いわば【同期性創発体】は固体化しない固体だ。つねに外部の影響を受け、絶えずその内部構造を変化させる。閉じていない。それを閉じる役目に任命されたのが私だ。断る理由はいまのところない。
「分かりました。ひとまずデータを見せてください。AIで解析済みなのでしょ」
「はい。この端末を使ってください」
端末を操作する。過去五年間分のデータが揃っているようだ。なかでも安定度のより高かった結晶構造――それに何の音を当てたのかに焦点を絞って、情報を改めていく。
集中しだすと時間は飛んだ。
私をこの施設に案内した女性は、一週間後にふたたび私のもとへとやってきた。
「どうですか、何か進展はありましたか」
「ええ。見てください。これとこれ。結晶持続時間はほかと比べてもとくに長くはないのですが」
「似ていますね」
「構造がそう、似ています。でも同じ音を聴かせているわけではないんです。ただ」
「……同じバンドの曲ですか?」
「そうなんです。これは日本の【NITRODAY】というバンドだそうで。ほかにも曲を発表しているのに、ここで実験に使った曲は二つだけ。なぜもっと試さないんですか」
異なる【波形】を与えておきながら似た結晶構造をとる。安定した結晶をつくるための何かがここに隠れているのではないか、と直感がささやく。
「すみません。順番に【波形】のモデルを試してはいるのですが、なにぶん、聴かせる【物質】にも限りがありまして」
「責めてはいません。ではまだほかの曲を試していないんですね」
「いますぐ手配します」
「そのほうがよいでしょう」私はもういちどデータに目を落とす。「このバンドの曲には何か、ほかの【波形】にはない特性があるのかもしれません」
【少年たちの予感】
あるところにウタくんがいました。ウタくんはじぶんの声があまり好きではありません。しゃべるよりも身体を動かすほうが好きでしたが、誰かと競いあうのは苦手でした。
あるとき、ウタくんが砂場で遊んでいると、ギターちゃんがやってきて言いました。
「なにつくってるの」
ウタくんはギターちゃんを見上げ、それからまた黙ったまま穴を掘りつづけます。
「じゃあわたしはこっち」
ギターちゃんはウタくんの掘った穴のそばに山盛りになっている砂で、お城をつくりはじめます。
しばらくするとドラムくんがやってきて、
「なにつくってるの」
ウタくんとギターちゃんのそばにしゃがみました。
ウタくんは黙ったまま穴を掘りつづけます。ギターちゃんが代わりに答えました。
「こっちは湖で、こっちはお城」
ウタくんはそこでじぶんが掘っていた穴が湖だったのだと気づきました。
「じゃあおいらはこっち」
ドラムくんは湖とお城のそばに草を植えて森をつくりはじめます。
そこへベースちゃんがやってきました。
「なにつくってるの」
ギターちゃんとドラムくんは答えます。「湖と、お城と、森だよ」
ベースちゃんはしばらく三人の様子を眺めていました。それからはたと思いついたようにその場を離れると、しばらくしてジョーロにいっぱいの水を運んできました。
「湖なのに水ないのはヘン。森さんも雨がないと枯れちゃうんだよ」
ウタくんとギターちゃんとドラムくんの三人は顔を見合わせて、それからクスクスと笑いました。「雲さん、雲さん、雨をください」
「たくさんどーぞ」
ベースちゃんはジョーロを傾けて、湖とお城と森に、雨を降らせます。
湖には水が溜まり、森の木々はすくすくと元気になりました。けれどお城だけはグズグズと崩れてしまいました。
「あー、お城がぁ」
ギターちゃんは泣きだしてしまいました。それを見たベースちゃんの目にも涙が浮かび、いまにも零れ落ちてしまいそうです。ドラムくんは二人の顔を交互に見て、おろおろとしています。
「だいじょうぶだよ、こうすればいいんだ」
ウタくんが言いました。初めて聞いた声に、ギターちゃんも、ベースちゃんも、ドラムくんも、みんなびっくりしてぴたりと動きを止めました。
ウタくんは崩れたお城のうえから砂をまぶして、白くします。ぺたぺたと手でその白くなったところを叩くと、崩れたお城には頑丈な壁ができました。水を吸ったおかげで、前よりも大きく、どっしりとしたお城になりました。
わいわい、ぺたぺた、じゃーじゃー、ぐりぐり。
砂場には四人の国ができあがります。
「ウタくん、それはなんのお歌?」
三人に見詰められ、ウタくんは首を傾げます。知らぬ間に歌を口ずさんでいたようです。
「なんだろう、わかんない」
「もっと歌って」
ギターちゃんに言われ、ウタくんは歌います。
気づくとドラムくんがジョーロを枝で叩いています。ベースちゃんは砂場の縁に爪を立てて音を鳴らし、ギターちゃんは湖の水をゆびで弾いて、音を立てます。
ラララ、タタタタ、ジジジジ、ピチョピチョ。
四人は気の向くままに音を鳴らし、歌います。
四人はこの日初めて会ったばかりです。お互いの名前もきょう初めて知りました。
ですが、きっとあすもここにきて、じぶんたちだけの国をつくったり、音を鳴らしたり、歌ったりするだろうと、何の約束もしていないうちから四人は、ふと、そんな気がしたのです。
「ウタくんのお歌、もっと聴きたいな」ドラムくんが言いました。ギターちゃんとベースちゃんが頷きます。
「ぼくもみんなともっと歌いたい」
ウタくんが言うと、ほかの三人は照れくさそうに笑いました。「きょうはとっても楽しかったなあ」
遠くから、お母さんたちの呼ぶ声が聞こえます。ウタくんたちはそれぞれに、はーい、と返事をして、砂場の後片付けをはじめます。
ウタくんは三人とバイバイしたあとも、歌を口ずさんでいました。
手を繋ぎながらお母さんが言います。
「ウタくん、それは何のお歌?」
「わかんない。でも、とっても楽しいお歌だよ」
そっかあ、とお母さんはくすぐったそうに言いました。「ウタくんの声、お母さんはすっごい好きだなあ」
ウタくんは、そう言ってくれるお母さんのことが大好きです。
それと同じくらい、きょう出会った三人のことも大好きなのだと思いました。
ウタくんはじぶんの声があまり好きではありませんでした。しゃべるよりも身体を動かすほうが好きでしたが、いまは歌うことが大好きです。
ウタくんが歌うと、ウタくんの周りには、お母さんたちおとなには視えない特別な世界が広がります。
その世界は、ギターちゃんやベースちゃん、ドラムくんたち三人には視えているのだと、ウタくんにはふしぎと分かるのでした。
【音楽は爆発だ】
人類は三度音楽に救われている。
初めは原始の時代、人類が道具を使いはじめ、石を加工し、狩りの効率を格段に向上させた時期のことだ。
宇宙からやってきた支配者たちに対抗するため、人類は威嚇する術を覚えた。そのうち効果的な威嚇の仕方が洗練されていき、やがてそれが音楽の嚆矢となった。
それは示し合せたかのように当時、全世界に点在した人類の祖先たちがとった共通の自己防衛策だった。
音楽はそのとき、各民族を固有の何かへと明確に昇華せしめた。
その後、宇宙からの支配者たちはこの星を去った。人類の威嚇攻撃にも一定の効果はあったが、それよりもすでにこの星に生息していたべつの種族への脅威が宇宙からやってきた支配者たちへ撤退を決意させた。
人類が音楽に救われた二度目は、人類が電子を発見し、その扱いを心得、光の速さで情報をやりとりする網の目をこの星の表層に張り巡らせた時期のことである。
いまや人類は、地殻を挟んだ地球の裏側にまで、声や意思や映像を瞬時に伝えることができる。人類は加速度的に発展した。それは音楽を発展させ、民族が民族として団結したはるか原始の時代にひけをとらない目まぐるしい進歩と言える。
反面、その裏では、それら光の網の目を利用して人々の行動を操作しようとする者たちが跋扈していた。それら操作者たちは、これまでにも物語や噂、伝記、巷説、講談、虚構を用いて社会の動向を一方向に扇動してきた。
音楽もその役割の一端を担ってきた背景があるが、それに対抗してきたのもまた音楽だった。
そして操縦桿の役目はいまや光の網の目へと移された。そこで対抗したのもまた音楽だった。
想像してごらん。
音楽は伝える。物事の裏側を、瞬時に伝わる情報の陰で泣く者たちの声を、その姿を、ぼくたちわたしたちは想像することができるのだと、見落としていることに気づき、そして見つけてあげることができるのだと。
音楽は歌う。
瞬時に伝わる「真実」に比べ、音楽のそれは数段遅れてやってくる。それでも、だからこそ、音楽は人々にブレーキの踏み方を教える。
ちょっと待ちなさいよ、と。
それ本当にそうなの、と。
もっとたいせつなことってほかにあるんじゃないの、「真実」から切り落とされた「何か」のほうが、本当はだいじなんじゃないの、と。
人類は踏み留まった。情報は光の速度で押しよせるが、立ち止まらないことにはそれらを処理し、検討するだけの余裕はないのだと、いつも時間差で遅れてやってくる音楽は気づかせてくれる。我々人間にはそもそも瞬時に物事を正しく判断できる処理能力など備わってはいないのだと、思いださせてくれる。
人類が三度目に音楽に救われたのは、それから数十年後のことだ。
人類がかつて、この星にやってきた宇宙からの支配者を手こずらせていた時期、この星にはすでに王者たる種族が繁栄していた。
奇しくも、人類が宇宙からの支配者へと対抗するために編みだした音楽が、その王者たちをこの星の奥底へと追いやっていた。
地底人はいる。
その存在自体は非公式であれ、一部の政府関係者のあいだでは自明のこととして知られてきた。
地上に音楽があるかぎり、この星の王者は人類に直接に干渉することができない。ときおり活火山や活断層へと圧力をかけ、自然災害を引き起こし、人類発展の邪魔をすることもあったが、困難を打破するたびに人類はかえって進歩した。
だが進歩したのはこの星の王者たちも同様だ。
やがて彼ら地底人は音楽への耐性を身に着けた。それを発明したと言い換えてもよい。
人類が宇宙へ飛びだすときに身にまとう服と似た形状のスーツを以って、地上へといざ侵攻しようとしていた。
そのときである。
地上に、これまでになかった【波形】が突如として現れた。
それは地底人たちのスーツを物ともせずに、光の網の目を通して世界中で鳴り響いた。
ちいさな端末から漏れ聴こえるその【波形】はけれど、それでも地下数キロさきにまで、宇宙線や素粒子がごとく透過性の高さで、浸透し、響き渡った。
地底人たちは地層よりうえにでることができなかった。新たな【波形】が巨大なバリアとして機能した。地上に迫った軍勢はふたたび地下深くへの帰還を余儀なくされた。
この星の王者はそのときハッキリとその冠を脱ぎ捨て、ただの地底人として人類の足元に下ったのである。
人類がその事態に気づいていれば、或いは救いの手を差し伸べたかもしれない。共存の道を示せたかもしれない。
だが、その侵攻と撤退はひっそりと行われ、そして人知れず収束した。
人類を救ったその【波形】は、奇しくも衝撃感度の高い爆薬、ニトログリセリンの名を持ったバンドの曲だった。
音楽はこれまで三度、人類を救った。
そしてきょうもどこかで誰かを救いつづける。
【永久に失恋】
マネージャーほど愛の報われない職業はない。
一生片想いの気持ちを味わうこととなる。
この仕事に就いてからもう十二年が経つが、やはりつづければつづけるほどに底の割れた樽に水をそそいでいる気分になる。
アーティストの才能に惚れ、契約を結ぶ。マネージャーの仕事の一つだ。会社から、このバンドを担当してくれ、と命じられることもあるが、基本はじぶんの惚れた才能を世に放ち、その真価を問うのが大枠の仕事だと考えている。
それに付属するように、仕事をとってきたり、広報を打ったり、ライブの予定や、リリースする新曲の計画を立てたりする。
最初こそこちらの熱意を素直に受け取ってくれるアーティストたちだが、やがてそれも通じなくなる。なにせこちらは仕事なのだ。才能を認め、ときには厳しい意見を言ったりもする。彼ら彼女らの才能に惚れているからこその忌憚のなさだが、こちらの心情を胸から取りだして見せるわけにもいかない。
アーティストたちからすればこちらのそれは、量産型のトロフィーのようなものなのだろう。金で買えるトロフィーよりも、曲を聴き、描いてくれた子どもたちの絵のほうがよほど音楽をつづける原動力となる。
お金をもらえなくたって応援はする。仕事じゃなくたって好きだからこそ、仕事を通じてより直接的に応援したいのだ。
だがそれを理解してもらおうとは思わない。
どれほど情熱をこめてみせたところで、否、情熱をこめ、真摯に向きあえば向きあうほど、お互いのあいだに開いた溝は深くなる。
だがこんなのはまだいい。我慢する必要すらない贅沢な悩みだ。すくなくとも新曲を聴ければどんな不満も帳消しになる。
誤解を招く言い方になるが、惚れているのは彼ら彼女らの才能であり、斟酌せずに言えば音楽だ。
仮に、彼ら彼女らが音楽をつくらなくなれば、応援する意味合いもなくなる。それでも彼ら彼女らの音楽だからこそもっと聴きたいと思っている。
そこは譲れない、譲りたくのない一線だ。
才能たちは繊細だ。衆目のなかで堂々たる演奏を披露しながら、そのじつ私生活のささいな出来事で容易に心に傷を負う。
マネージャーとしては繊細な彼ら彼女らのために絶対に口にはしないと決めている言葉がある。
解散だ。
言葉には呪力がある。どんな文脈であろうとそれを彼ら彼女らのまえで口にすることだけは絶対に避けねばならないと考えている。
それだけバンドというものはつねにその危機にさらされていると言ってもいい。
マネージャーはバンドのメンバーではない。仲間ではない。同士ではない。飽くまでサポーターでしかない。
ときには、あなたも私たちのメンバーだ、と言ってくれるバンドもある。うれしい言葉だし、そう思いたくもあるが、実際問題としてメンバーにはなれない。
音楽は、彼ら彼女らの手のうちから生みだされるものであり、この手からではないのだ。
いっぽうでは、メンバー以外では誰よりそばでバンドを見守っている。だからこそ判る機微がある。
メンバーのあいだに走っている微妙な亀裂が目に映る。それはどのバンドにも共通してある模様のようなものだ。あって当然だし、それをすぐさま危機として見做したりはしない。
個性の塊たちが理想を追い求め、互いにぶつかりあうからこそ、バンドはあれほど大勢を魅了し、一人一人の心に届き、揺さぶる音色を響かせる。
ヒビが入って当然だ。それは音楽家として、バンドとして、彼ら彼女らがその命を燃やして曲を奏でている証だからだ。
だからこそ、彼ら彼女らの人間関係にまで踏み込むことができない。ヒビを修正しようとすることそのものが彼ら彼女らへの冒涜に思えるからだ。
彼ら彼女らの才能に、音楽に惚れた者として、できればより長く、そばで、たくさんの演奏を、新曲を聴いていたい。
だがなにより、彼ら彼女らの邪魔はしたくない。
その結果にバンドが解散となろうと、それはそれで受け入れるしかない道だ。こちらはしょせんいちファンでしかない。すこし応援上手な、音楽バカでしかないのだから。
愛は報われない。どれほどそそいでも彼ら彼女らの胸には響かない。そうした星のもとに下った代わりに、誰よりそばで彼ら彼女らの音楽を聴き、その誕生を目の当たりにし、応援しつづけていられる。
等価交換だ。
こちらの愛は報われないが、それでも日々、報われている。
愛などいくらでもくれてやる。
端から枯渇するようなものではないのだから。
いま、目のまえで花を咲かせようとしているバンドがある。
人々はまだそこにある才能に気づいていない。
そう遠くない日、人々は知ることとなるだろう。
その日が巡ってくればこちらは、恋人をとられたようないっそうの寂しさを胸に、片想いしつづけてきた日々の至福をそれでも深く噛みしめるだろう。
【一気呵成に加勢を】
ぼくの名前は世界一長い、それはそれはとても長くていちども口にできたことはないのだけれど、それはだって未だに父はぼくの名前をつけつづけていて、実際のところぼくは無名なのかもしれず、或いは生まれてすらいないのかもしれない、というのも出生届の受理期間はとっくに過ぎてしまっているから、本当にいったいいつになったらぼくの名前は落ち着くのかと、一向に口を閉ざす気配のない父の底なしの肺活量には舌を巻くばかりだが、父はきっと優に数万回は舌を噛んでいるに相違なく、一説によれば父はすでに円周率を三周ほど唱え終えているらしくて、つまり円周率は循環する無限であって、もちろんじっさいには循環しないのだけれど、ある意味では有限の組み合わせの羅列からなっているとも考えられる、それは見方を変えれば、ぼくは生まれていないがゆえに死ぬこともなく、だからこそこうして無限にも思える長い長い、父の「我が子の名づけの儀式」の終焉を待ちわびていられるのかもしれない、もっと言えば父の口にする言葉の組み合わせはそれこそ円周率なみに膨大であり、無限に循環しつづけているものだから、そのなかにはもちろんいまこうしてぼくが思い浮かべているこの思念にも似た文章の羅列だって含まれており、言い換えればぼくはいまじぶんの名前を口にしているとも呼べ、そう自覚した瞬間にぼくはぼくとしての輪郭の一部を得、すくなくとも存在の一端をなすことで、父がぼくの名を唱え終えずとも誕生でき、ゆえに途中で幾度も死したとしても、こうしてふたたび生まれ落ちる余地にくるまれており、こうしてまたじぶんの思念にて再誕の繰り返しを連綿と、営々と、いつかは訪れるだろう父の死までつづけていくのだろう、或いは父の口さえ塞いでしまえば、ようやくぼくは安定してこの世に生を享けるのかもしれず、そうではないのかもしれない、思えばぼくは未だに父の名を知らず、母の名も、その姿すら目にした覚えがなく、それはそのはずで父はぼくの名を唱えるのにいそがしく、ぼくがぼくとして存在していられるのはこうして独白を思い浮かべているあいだだけなので(つまりじぶんの名の一端を唱えているあいだだけなので)、ひとたび欠伸をして、眠くなって、或いは目のまえを通り過ぎる一匹のハエに目を留めるだけでも、もう、ぼくはぼくとしての輪郭を保てずに、死ぬことすらなく、眠ることもなく、ふたたび父の唱える輪っかのなかを巡りながら、再誕のときを、春夏秋冬、四季のごとくぐるっと一周するまで待ちわびることもできずに、いったいこれが何度目の誕生であるかも曖昧なままで、いつまでもいつまでも思念を巡らせていたいと、頭の底から、どうにかこうにか、途切れずに済むように祈るほかにできることはなにもないのだろうか、せめてあとすこし、あとすこしでもぼくに言葉を、ねえ、ああ、どうしたらよいのかな、もう何も思い浮かばないよ
【青いバナナ】
バナナの皮を剥くと青が現れた。果実が未熟な状態を青いと形容することもあるがいま目のまえにあるバナナはそうではなく、青空とか青いブドウとかの青で、まさにブルーといった塩梅だ。なぜにかように毒々しいのかと皮だけでなく目まで剥く。
品種改良で元から青いバナナを買ってしまったのかと案じ、念のため房からもう一本バナナをもいで剥いてみるも、中身はちゃんと白く美味そうなバナナだった。
一本だけが青く、ただ青く、青い。
これはあれだろうか。バナナは酸化すると黒くなる。それといっしょの現象だろうか。
臭くはない。ちろっと舌先で舐めてみるも、これまた味という味はしなかった。
齧ってみるか。
試しに前歯でこそぎとるようにひと齧りしてみると、これがまたなんとも言えぬ食感で、バナナらしさのかけらもなく、サクサクもちもちガリガリぐにぐにと、歯ごたえが七色に、いいや、咀嚼すればするほどに増えていく。
なんだこれは。
呑みこみたい衝動が募るたびに、まだだ、もっともっと味わいたいとする、より強烈な衝動に押し流され、けっきょくいつまでも経っても下あごを上下に動かしつづけている。
ふしぎなのは、噛めば噛むほど満腹感が増していくことだ。身体まで元気になっていく感覚がある。
半日口のなかで青いバナナの欠片を噛みつづけ、さらにつぎの日、そのつぎの日、と噛みつづけているとようやくというべきか、この青いバナナの目を瞠る効力を発見した。
喉が乾かず、お腹が減らない。
のみならず身体は疲れず、眠らずに済むようになった。
身体が軽い。
思考が巡る。
まるで魔法の薬でも口にしたみたいだ。
そこで、はっとする。
麻薬だったらどうしよう。
ひょっとしたら、と考える。どこぞの麻薬カルテルが麻薬を密輸するためにバナナやほかの果物に麻薬を注入して、果物そのものを麻薬にしてしまおうと企てたのではないか。これで麻薬犬を誤魔化せるとは思わないが、或いは純粋なバナナに囲まれてしまえば、そのうちの数本が麻薬まみれであっても、濃厚なバナナの香りに紛れて犬の鼻を欺けるのかもしれない。もっと言えば、バナナの皮には外部に内部の香りを漏らさぬようにする効能があるのかも分からない。
いずれにせよ、これ以上、口の中に入れているのは危険だ。
意に反して、吐きだそうと思えば思うほどに、あとからあとから唾液がでてきて止まらない。
もったいない。
いやだ。
こんな美味しい物を吐きだすなんて。
身体が言うことを聞いてくれない。
鏡のまえに立つ。すでに青いバナナを咀嚼しつづけて四日目だ。その間、ほかの食べ物を口にしていない。仮にこれが麻薬漬けのバナナであったなら、じっさいには身体は極度の栄養不足に陥っているはずだ。死ぬ寸前に衰弱していておかしくない。
本当はげっそり痩せこけており、死神のような顔つきになっているかもしれないのだ。
おそるおそる鏡を覗きこむと、そこにはなんとも健康的な顔つきの男がいた。毛色がよく、肌のハリもよい。若返ってすら映る。
無精ひげが生えていてもよさそうなものを、つるつるで、なんとなく美青年にすら見えてくる。
なんてことだ。
やはり青いバナナは麻薬漬けの果物だったに違いない。こうしてありもしない理想のじぶんの姿が見えてしまうなんて、幻覚が見えるなんて、まさしく麻薬である傍証ではないか。
恐怖した。
こんなに美味しいのに。美味しいがゆえに手放せなくなっている己が狂気の元凶が、この美味しいをもたらす口のなかの無数に変幻する食感物にあると思えば思うほどに、これはそれほどに人間の意思決定を狂わせ、支配するほどのヤバいの結晶なのだと理解するのに躊躇はない。
吐きだせ、吐きだすのだ。
残りの青いバナナを手に取り、それはのきなみ九割九分残っているわけだが、皮を剥き、口いっぱいに頬張る。
捨てろ、葬れ。
そうして手放そう手放そうと念じるたびに、意思とは裏腹に手足は青いバナナを貪るのだどこまでも、と命じる内なる衝動が勢力を増す。
あっという間に口のなかは青いバナナの甘美な至福、美味しい、美味しい、が全身に波及する。見えない鱗が逆立つようだ。
脳髄のヒダヒダの一つ一つが隆起し、内側から、しゅわわせ~、の合唱を轟かせる。いくども波打ち、打ち寄せる歓喜のキンキンお祭り騒ぎは、その後も衰えることなく、一口、二口、と顎をしきりに上下させるたびに自我と世界の垣根を打ち破り、溶けだしていく意識の消散を予感させる。
眠っているのか起きているのかも曖昧なままに、日差しのぬるさを覚え、次点で床の硬さを背中に感じ、気づかぬあいだに仰臥していると気づくに至る。
口の中が乾いている。
水が飲みたい。
倦怠感があるが、身体は妙に軽かった。眩暈がし、何やら部屋が大きく感じられる。不思議の国にでも迷い込んだみたいだ。あれと似た名前の病気がたしかあったな。
思いだしながら、蛇口から水を足らし、口へとじかに流しこむ。勢いよく喉を鳴らしながら、ようやくというべきか青いバナナの存在を思いだす。
口の中にはない。
呑みこんでしまったのだろう。食べてしまったのだろう。やはりあれは麻薬の染みこんだバナナだったのだ。
金輪際あんなものを口にするのはやめよう。
念のために残ったバナナの皮を匿名で警察に送りつけてもよい。あんなものが市場に出回ることがよいわけがないのだ。
顔を洗いに洗面所に向かい、ついでにシャワーを浴びようと思い裸になりながら何気なく鏡に目を向けて、息を呑む。
鏡の向こうには見知らぬ女がおり、戸惑いがちに自身の顔に、そして胸に、手をやった。手のひらに伝わる在るはずのないやわらかな弾力と、そしてさらにその下、股間のあたりからは、あるはずのぶらぶらが消えている。
【背景、あのころのわたしへ】
あなたはたぶんこう思ってる、どうして世界はこんなに広くてキラキラしているのにわたしの進む道はこんなに薄汚いのだろうって、色褪せているのはじぶん以外のせいだと信じて疑わないあなたはでも、そこに色を足して、じぶんの手で彩ろうとはしないよね。
あなたはあるとき気づく、この世界はべつに最初からきらきらしているわけではないんだって、そういうふうに世界を視たひとがいて、たくさんの装飾できらびやかに装い、皮一枚めくった裏側には、相も変わらずに灰色よりもずっと薄汚い世界が広がっているんだって、それを知ったところでどうすることもできずに、あなたはほかのひとたちが懸命に塗りあげた絵画の世界を眺めてる。
ある日、あなたは誰もが経験するような最初で最後の傷を負う、それは赤子が初めて大気に身体を晒して、大泣きするのに似た天変地異で、あなたはもう立ち直れないし、これはもう死ぬしかない、生きてはいかれない、と大真面目に思いこむ。でも何日経ってもあなたは死ねないし、お腹が減ると台所に立って、何かないかな、と冷蔵庫を漁ったりする。
そういう現実とあたまのなかの天変地異が吊りあわなくて、しっちゃかめっちゃかになって、また荒れる。
あなたはまるで大きな赤ちゃんで、お腹が空いて泣いたその声に驚いてさらに泣く。
永久機関に思えるそれも、いつの間にか日常にあいたちょっとした隙間へと落ちて、消える。
あなたはあなたの意思とは関係なく身体が大きくなる。むかしの服は着れなくなり、かつてはこの世の終わりとしか思えなかったあの傷と似たような傷をいくつも重ねるようになる。
よくわからないうちに、じぶんからその傷を求めている気すらしてくる。たぶんそうだ。あのときの天変地異くらいの傷を受けるくらいの刺激をあなたはいま、求めてる。
でも、きっとそんな傷はもう二度と負えないだろうと予感しているし、よくよく考えてみると、どうしてあんな傷程度で死んでしまうと思ってしまったのかすら、いまからするとすこしふしぎだ。
あなたはもうあなたではなく、わたしだ。
そしてきっとすぐに追い越して、わたしをあなたと呼び捨てにし、すこし背伸びをした先輩気分で、なにかそう、すこしだけさきを歩いてみてもいいかな、と思うような、それともうんざりしちゃう言葉を、一言二言、それともこれくらい長い言葉で書いてくれる。
あなたは世界にほんのりと色を足す。
余計なおせっかい、とわたしは言う。
あなたはきっとほくそ笑む。わたしがいまそうしているように、何かを得た気がして、終えた気がして、肩の荷が下りた気がして、ほんのすこしばかりの淋しさを覚えながら。
【背景、あのころのぼくへ】
あなたはきっと、じぶんにとっての悩みが誰かにとっての些事である事実に堪えられませんし、誰かにとっての悩みがじぶんにとってとるに足りない日常や過去の追体験でしかなかったら、きっと相手を傷つけてしまうと考えて、どうあっても悩みなんてひとに相談するものではないし、されるものでもない、しないほうがよいことだ、と結論付けて、狭く、ちいさな枠の中に閉じこもるのでしょう。
でも、そうした、しないほうがよいことですら、あなたとならしあいたいと思える相手と出会えたなら、それはすばらしいことだと思いますし、得難いことだと思います。
縁や繋がりなんてないほうが好ましいとぼくですらそう思います。
でも、そうした、ないほうがよいものですら結んでおきたいと望める相手となら、出会いたいし、出会ってよかったと思えるようになるような気がいたします。反面、そんな奇跡はめったに起きるようなものではない現実は存じておりますし、そらからぽっと降って湧いてくるようなものでもありませんから、あなたの考えるように、妄想で満足しておくのが利口な生き方というものなのかもしれません。
追伸。
縁や繋がりは育むもので、ぽんと最初からできあがっているわけではない、手錠や鎖とは違うんですよ、ときっとあなたならおっしゃるでしょうね。希望を捨て切れないところがかわいらしくも思います。でも、そんなたいそうな芽を愛であう余裕がぼくにはないことだって、きっとあなたならご存知のはずです。失望するのはつらいです。でも、踏ん切りをつけ、断ち切り、割り切る分には必要な過程なのかもしれませんね。失望は、されるよりもするほうがずっと楽です。
【背景、あのころの私へ】
その道を行くことにいっさいの迷いがなかったころが嘘のようにいまは目に映る影という影が私の悩みの権化であるかのような日々です。つまり、ものすごくたくさんぐにゃぐにゃと悩みに押しつぶされそうな毎日ということです。
押しつぶされる、ではなく、押しつぶされそう、が肝だと思います。
一貫性のあることが好きで、何かを貫くことを美点と思っていた私がまるで他人のようで、つまりこれを読んでいるあなたが他人にしか思えないくらいに、私にはもう、あなたにあった美意識や感性がなくなってしまった、との懺悔とも告白ともつかぬ、そんなおたよりになる予定です。ほとんど愚痴ですね。あなたがうらやましいというひがみと、それとも、こんな私で申しわけないとの謝罪がごちゃまぜな気分です。
きっとあなたはこんな私を許せないでしょう。いいえ、そもそもこんなおたよりを送られてもそれが私からの言葉だなんて信じる以前に、素直に受け止めることすら、読むことすらしないように思います。
でもいちおう、書いておきますね。
私はあなたが夢見ていた道をそうそうに脱線してしまって、飛び降りてしまって、あなたが思うほどにはまったくこれっぽっちもつよい人間ではなかった現実にうちのめされています。それはもうずいぶんむかしのこと、あなたにとってはもうすこし先のことになりますが、私は夢を諦めることすらせずに、ずっとこのさきも一生つづけていくだろうと思う道に背を向け、いいえ、どんな道から飛び降りたのかすら振り返るのがおそろしく、嫌すぎて、道を見ずにすむようにと、洞穴に飛びこんで、そのなかで膝を抱えてずっとうずくまっています。
ありていな表現で申しわけないのですが、私は夢に破れました。
いいえ、夢を、破りました。
破れたはずのその夢を捨て去れればよいものを、その破れた夢すらなにかしら誇らしく、みみっちい人生を着飾る何かしらの光になるのではないかと、後生大事に抱えて手放そうとしません。できないのです。
あなたならきっと、そんなものはさっさと捨ててつぎの光を掴むべくがむしゃらにまえに進め、じぶんの道はじぶんで切り拓くものだ、といったことを、もうすこし文学的な表現でおもしろおかしく、ときにかっこうのよろしい文面でしたためそうですね。
私にはもうそうした体裁を取り繕おうとする気概すらありません。
なんて書きながら、どうしたらあなたに失望されずに済むだろうかと、無意識のうちから言葉を取捨選択しているじぶんに気づき、ますます自己嫌悪に陥ります。
いまここに、あなたはいません。そして遠からず、あなたも私になる日がくるのでしょう。ですが、私からのこのたよりを読むことでなにかしらの変化が訪れるのであるとすれば、それはそうあってほしい変化だと思っています。
残念ながら私のもとにたよりは届かず、いまこうして書いている言葉に既視感はなく、それともどこかで見たことのあるような、どこにでも有り触れた文面でしかなく見えます。
私に限らずみな似たような悩みに押しつぶされそうになっているのだと言われればそうなのでしょう。
ただ、あなただけは違った、そのことだけは知っています。
そのことだけを私だけが知っています。
あなたはたしかにいまそのとき、私ではありませんでした。そして私と、これを目にしたあなたもきっと違う私になるのでしょう。未来は変えられるとか、じぶんの道はじぶんで選べるとか、そういった殊勝なメッセージをこめてはぜんぜんないです。
きっとあなたは私と同じように夢が破れ、そしてその破れた夢を後生大事に、何らかの証のように、いつまでも手放さずにいつづけるでしょう。洞穴のなかでじっとしているだけの人生が待っているだけかもしれません。
でも、ここがきょういちばんだいじな部分なのですが、ここも、この場所も、洞穴のなかも、それほどわるくはないですよ、ということを私はあなたにいまのうちから伝えておきたいです。伝えておきたかっただけなのかもしれないな、といまそう思いました。
どうせここに行き着くのだから、遠慮なく、夢を破ってほしいと願っています。それは、当たって砕けろ、とはぜんぜん違くて。破れてもけっきょく夢は夢でありつづけ、あなたをあなたと位置付ける、灯す、光の役割を果たすのだと、それは私にとってそう見えるというだけの幻影かもしれませんが、でも、夢ってそもそもそういうものではないですか?
私にはいま、両手では抱えきれないくらいの、運びきれないくらいの、飾りきれないくらいの破れた夢があります。破れた夢しかありません。きっとこのさきも破りつづけていくのでしょう。
そしてそのなかで偶然、なかなか破れない夢に行きあたることもあるかもしれません。
そうなることを半ば祈りながら、いまからわくわくして待っています。
あなたの破った夢の唯一無二のそのカタチを、いつか私が目にするときを、わくわくしながら待っていますね。
【背景、あのころのおれへ】
文章慣れてねんで音声入力でやらせてもらうけど、なんかいきなしタイトルで誤字のおしらせ光ってんだけど、背景って、拝啓じゃねえの? いいの?
ほかのひとらのもそのままんなってるっぽいんでそのままにしとくけど、あのさ、おれさ、むかしのじぶんに謝りたいってか、なんであんとき我慢しちゃったんだよってさ、いまんなって後悔してんの。
やらない後悔よりやる後悔ってあんじゃんああいうの、あれマジでホントでさ、すこしのあいだはいいんだ、なんか我慢してんのが偉い気がしてきてさ、でもさ、ある時期から急に、なんであんとき我慢しちゃったんだろうって、めちゃくちゃ考えるようになってさ、だんだんその数が増えてって、さいきんじゃあもう、気づくと、殺す、とか口走ってんの。
誰にとかじゃなくて。
つうかじぶんに。
要はおめぇを殺したくってさ。もうぶっころしてやろうかと思うくらいに、ときどきあのとき我慢しちゃったおれ自身、要するにおまえをどうにかしたくなっちまってさ、でもどうしようもねえじゃん。
おまえはおまえでそこでなんだかんだもがいてんだろうし、おれだってこっちはこっちでいまそれどころじゃねえってのもあっしよ。
そう、だから謝りたいってのはおれがおまえのころにそれを我慢しちゃったってことじゃなくってさ、ずっとあとになっていまになってどうしてやらなかったんだろうって後悔するたびに、一生懸命に、本当にがんばって我慢してるおまえのことをぶっころしたくて、ぶっころしたくて堪らなくなるってことがさ、どうしても謝りたいってかさ、じゃあ、んなこと思うなって話なんだけどそれができたらこんなんやってねぇじゃん、おまえにこれを送らねえじゃん。
強要はしねえし、おまえの選択も否定はしねえ、ぶっころしたくはなるけど、んなことしたらおれだって死んじまうわけじゃん?
好きにしろよ、でも、どっち選んでも後悔するってことだけは憶えといてくれよな。
罰ゲームみてぇなもんだよな、どっち食ってもカラシ入りシュークリームじゃんこんなもん、んなの詐欺だっつってやっぱし腹立つよな、現実ってやろうにさ。
でもさ、だからこそ、まあ、好きにしたっていいぞって、我慢したけりゃすればいいし、したくなきゃ我慢なんかしなくていいってな、まあ、たぶん、どっちにしろ似たような手紙が届くんだろうけどさ、すくなくともおまえは我慢すんだよ、そっちを選ぶんだよ、そういうやつなんだって、だからなんかこうな、謝りたくなっちゃうんだよな。
ごめんな。
さっきの嘘だわ。
ぶっころしたいのはおまえじゃなくて、そんなおまえを否定したがるいまのじぶんのことなんだわ。
好きに生きろよ。
我慢してもしなくとも、そのあとはんなこた忘れて、好きに生きろ。
おれの代わりに、いまのおれを消してくれ。
ぶっころしてくれ。
きもちよくな。
【背景、あのころのあたしへ】
きみは驚くと思うよ、なんたって未来のあたしから手紙が届くってんだから、そりゃあね、あたしならきっと飛んでよろこぶと思うな。
あたしにはなんでかそんな記憶は残っていないし、いまこれを書いてる段階だから、まだきみのところに届いていないだけ、言い換えればあたしにはその記憶が根付いていないだけのことなのかもしれないけれど、いまからきみへ向けて言葉を贈ることにする。
いちおう、文章にうるさいきみのことだから題名の誤字について説明しておこう。拝啓じゃないのって、きみはすでに手紙を持ってゴミ箱のまえに移動しているかもしれない。
でも待ってくれ。
早合点がきみのゆいいつの欠点だ。
拝啓ではなく、背景、で構わないのだそうだ。
ほかにもいろいろと手紙をだしているひとたちがいて、あ、もちろん過去のじぶんにって意味だけれど、いまのあたしが眺めている景色、あたしを包みこむ世界、それでいてあたしの背後に広がっている奥行き、そういったものこそが過去のあたしそのものであり、同時にきみ自身であるって意味合いがあるんだと、あたしは睨んでいるよ。
それとも過去は過去にすぎないって皮肉かな。
きみはどう思う?
よかったら日記にそのことを書いておいてくれ。それがこちらの世界に、未来に、引き継がれるかは知らないけれどね。
そろそろあたし自身のことが気になりだしはじめた頃合いではないかな。
あたしはきみの思い描いているいくつかの将来像へとつづく道の一つを、まあそれなりに順調にっていうと語弊があるけれど、いくつかの小石に躓きながら、それでも尻もちをつかずになんとか歩きつづけている最中かな。
ここで何かしらの警句を鳴らしてあげるのも手かもしれないけれど、どちらかと言えばきみにはもっと苦労をしてほしいと望んでいる。
説教臭いのは嫌だとあたしだって思っていたし、いまこうして文字を打っていてもやっぱり嫌だなって感じる。それはそれとして、苦労って案外に余裕があるうちに、失敗が許されるうちに、リカバリーがきくうちにしておくのが吉だなと、いまになって思うから。
順調すぎるとつまらないよねそうそう、とかきみはお門違いな方向に解釈しそうだから注釈を挿しておくけれど、そういう意味ではないからね。流れは順調なほうがよいと思う。できるかぎり、人生はね。
ただ、すこしだけ、苦労を苦労だと思えるうちに解決法のいくつかを学習しておきたかったなって。
あたしがいま何歳かをここで明かすのかはフェアじゃない気がするから黙っておくけれど、この歳にもなると、苦労を避けようと思えばいくらでも避けてしまえるから。楽しみ方の一つを失ってしまったようで哀しくすら感じる。
かといって率先して請け負うほどには、苦労ってやつは気安いやつではないからねぇ。
とっつきにくいにもほどがある。
そう、まさにきみみたい。
じぶんへの対処法を学びたい、と言えば端的かもしれないし、いまごろきみからの非難が轟々かもしれない。その公算が高そうだ。
正直言うと、そんなに言いたいことも、伝えたいこともないんだ。きみのことだからあたしから何を言われたところで、反発心しか覚えないだろうし、かといってその程度の斥力で行動の指針が揺らいだり、欠けたりはしないだろうね。
いちいちカチンとくる書き方をしているのは信頼の証だと思ってほしいです。
きみとあたしは違う。
確信しているし、言ったところで何が変わるわけでもないけれど敢えて言っておくよ。
きみはいつまでもきみのままだ。
あたしとは違う。
だからそう、いまきみが何を思っているのかすら、あたしにはもうまったく予想がつかない。そういうのって愉快だろ。
だってそうじゃないか。
予想がつくことじゃあ、挑戦とは言わないからね。
【背景、あのころの僕へ】
じぶんが死ぬときの場面を想像して、日々をだいじに過ごそうときみは、たびたびの決意を固める。
なのにどうして、じぶんが取り返しのつかない真似をしでかしてしまう未来については想像を働かせなかったのかな。
誰かを困らせたり、傷つけたり、じぶんよりも立場の弱いひとたちを虐げたり、そういう真似を許せないきみが、どうしてじぶんが誰かを困らせ、傷つけ、虐げる側に回ってしまう可能性に思い至らなかったのかが、いまからするとふしぎでならない。
きみは気づいていないが、相当な差別を日常的に、無意識から行っているし、傷つけてもだいじょうぶなひとと、そうでないひとを、相手の言動から見ぬいて、識別し、じぶんの態度をつど変えたりしている。
それはちょうど、父親にはいいこを演じて、母親には厳しく当たり散らす内弁慶みたいに、それとも人気者にはいいこを演じて、いじめられっこに対しては不快な気持ちを隠そうともしない思春期の子どもみたいに、きみはじぶんで思っているよりもずっと幼くて、我がままで、衝動的で、自己矛盾を一つと言わずして大量に抱え込んでいる。
そのことを自覚できない程度の知性しかなかった点も、ざんねんに思う。
きみはある日、取り返しのつかない真似をしでかしてしまう。そのことで長い期間、ずっと謝罪の言葉をしたためるようになる。許されたいとは思わないが、許されないことをしてしまったのだ、と反省している気持ちを相手に知ってもらおうと必死になる。
しかしその自分よがりな手紙のせいで、やはりきみはさらに他人を傷つけつづけ、ずっとあとになってから、善意が裏目にでていることを知る。
どこまでもきみは、僕は、自分本位で、性根が腐っている。せめてそのことに罪悪感の一つでも覚えていられたらよかったのに、きみときたら何も知らずに、知ろうともせずに、じぶんは人一倍繊細で、でもやさしいのだと思いこんで、毎日のように誰かを傷つけつづけている。
僕はみんなみたいに暢気ではないから過去は変えられないと考えている。よしんば変えられたとしても、いまの僕が救われるわけではないんだろうと、その可能性が高そうだと考えているから、こうして手紙をきみにだしたところであまり意味のある行為だとは思っていない。
これもただ、過去のじぶんを、きみを、傷つけてしまうだけのひとりよがりな善意に思えてしまって、だからきっと僕はいま自棄になっているだけなのだろう。
きみは何を選んでも失敗するし、何をどうしようと他人を傷つけつづける。まるで呪いの言葉のようだな、とじぶんで書いていて辟易してくるが、どうせ誰かをこっぴどく傷つけるならじぶんにしておきたいとの打算がないとも言いきれない。
好きに生きろ、なんて僕は口が裂けても言えない。言いたくもない。
というのも、参考にほかのひとたちの手紙を読ませてもらったのだが、本当に、なんで僕だけなんだろう、と笑えてきたくらいに、みなの過去が、いまが、未来が、輝いて見えた。
ここに具体的にきみがしでかしてしまう取り返しのつかないことを書いてみせてもよいし、僕がこれまで相手に送りつづけてきた謝罪の手紙を代わりに添付してもよかった。
だが、そんなことをしてどうなるというのだろう。
それできみの行動が、きみの無自覚の差別心が、傲慢さが消えるとは思えない。
試してみないと判らないだろ、ときみなら思うだろう。そういう浅はかな想像力しかないからこうなるんだ、とだけ言っておくことにする。
きみはダメな人間だ。
そして、人生に絶望しながらも、死ぬこともできない。
心のどこかで、じぶんはじぶんで、他人は他人だ、と思っているからだ。いっそ死刑判決を否応なく出してもらえるくらいの犯罪でもしでかせばよかった、とときどき考えるくらいに、性根が腐っている。いつでも他人に責任転嫁をし、八つ当たりをする機会を窺っている。
きみは変われない。
ずっとそのままだし、その報いを受ける。因果応報だ。
いま書いていて気づいたが、おそらく僕はやっぱりきみを心底傷つけてやりたいんだろう。自傷することでしかもう、どうすれば許されるのか、贖罪を担えるのかが判らないから。
いまのじぶんをこれ以上痛めつけるのは怖いから、だから何も知らない無邪気なきみを傷つけてやりたい。
申しわけないとはすこしは思うが、でも、しょうがないだろ。
きみのせいで僕はこんなにもいま、つらいのだから。
生きていることが、こんなにも。
【背景、あのころのワタシへ】
アナタにしないでほしいことがたくさんありすぎて、もうほとんどアナタには何もして欲しくないと怒鳴ってしまいそうで、こうしてワタシから何かを伝えようとしても、アナタにとっては脅迫電話と同じになってしまう気がして、けっきょくこれで三度目の書き直しになってる。
占いみたいに書いてるひともいて、ああそっか、まあ占いみたいなものだよね、と思ったら踏ん切りがついたので、アナタの未来を知る魔法使いの気分で、アナタの運勢を占ってあげる。
アナタは大学に進むか、やりたいことをするかで、親と揉める。大学にいってもできるだろう、と正論を吐かれるが、大学に入ったことがないので両立できるのかもよくわからない。友人たちに相談するがそこでもやっぱり小馬鹿にされる。もちろん表向きは誰もが応援するフリをしてくれるけど、明らかに成功なんてしっこない、どっかで挫けて、お先真っ暗な人生だよ、と脅してくる。
ここまで書いてぞっとしたけど、まるでいまのワタシみたいだ。
ホントはアナタに、アナタの進む道は間違っていた、とねちねち書き連ねてやろうと思ってたけど、なんだかムカついてきたのでやめておく。
がんばれ過去のワタシ。
めっちゃがんばれ。
いまのワタシはアナタを否定しない。
いいよ、やっちゃえよ。
いけるとこまでいってやれ。
ワタシはアナタをそんなに好きじゃなかったけど、それはたぶん間違いで、ワタシはワタシが嫌いなだけだった。
いま振り返ってみれば、もっとうまくやれたと思うし、そしたらいまごろは毎日もっといいものを食べていられた。
家賃の心配なんかしない日々を送れたし、税金や健康保険や年金、その他公共料金の督促状に怯えずに済む。お察しの通り、ワタシはいま貧乏だ。それもつぎに身体を壊したら、それこそ風邪や虫歯のレベルですら、罹ったら即座にいまの暮らしを手放すしかないくらいに極貧だ。
寝る場所があって、いちおう毎日食うのに困っていないのだから、もっと貧乏なひとたちがいてそれよりかはずっと贅沢な暮らしなのは百も承知だけど、アナタの未来はこんなものだ。
恐れてほしい。
危機感を持て。
かといって、どうしたらよいだろう、と解らない気持ちもよく分かる。ワタシだっていまどうすればいいのかなんて解らないから、こうして過去のじぶんに、つまりアナタにこうして、そのままだと危ないよ、とお説教の一つでも投げかけてあげようかと思ってたんだけど、でもそうだよね、ブレーキをかけるんじゃなく、アクセルをかけてあげたほうがいいのかもと思い直した。
アナタはもっとがんばれるし、もっとがんばれ。
いまのままじゃダメになる。
こうしてアタシが証明してしまったから、これは揺るぎない事実だ。
こっちにゃくるな、と本当に思う。
まだ間に合う。
同じ道を進むことになっても、もっと突っ走っていけたはずだ。いろいろと積み重ねていけたはずだ。おまえはもっとやれる。
がんばれ。
めっちゃがんばれ。
身体を壊すのは、そう、怖いけど、じぶんのためならそれもいいじゃん。他人のためとか、仕事のために身体を壊すのはバカみたいだけど、アナタは端からそんなことはだってしないじゃん。
事故とか、事件とか、起こすほうになるのは勘弁だけど、そうじゃないならまあ、死んでもいいよ、ワタシが許す。
どうせこのままじゃ遠からずワタシは貧乏の坂を転がり落ちて、好きなこともできなくなって死んでいく。だったら好きなことを好きなだけして死んでいきたいよ。
なんて書いたらまるで、好きなことをしてこんかった人生みたいに聞こえるけど、好きなことしかしてこなかったからそこはやっぱり、がんばりというか、工夫というか、積み重ねるものの量が、それとも種類が、すくなかったのかな、とは思うのだ。
というか、そうだね、きっとアナタはいま怒っていて、怒鳴っていて、どうやったら返信できるのかと、未来のワタシに抗議できるのかと、手紙をつぶさに調べていそうだけど、ワタシもいまそう思う。
アナタじゃなくって、ワタシががんばればいいだけの話だなこれは。
がんばれワタシ、めっちゃがんばれ。
ちなみにアナタの時代では、こういう「がんばれじぶんがんばれ」みたいなセリフを言う主人公の登場する漫画がものすごく売れていたはず。ワタシも(つまりアナタも)好きで、読んでいた。
その後、その漫画の展開がどうなったかをここに書きたい衝動がある。いっしょに楽しみを分かち合いたい気持ちが募るけど、ただそういう、じぶん以外のこと、たとえば博打の結果とか政治の結果とか、災害がいつ起こるとか、そういう未来の時勢が分かってしまうことは具体的には書いたらよくないらしい。
てことは、やっぱり過去って変えられるのかな、とか邪推したくもなる。
変えられることもあるし、変えられないこともあるってことなのかな。どっちにしても、時間を無駄にせずにいこう。
アナタはやれるし、ワタシもやれる。
ワタシがんばるから、アナタもがんばれ。
ただし、寝るのだけは忘れずに。
【背景、あのころのボクへ】
いきなりだが喜んでほしい。キミの未来はバラ色だ。
というのも、何をしても誰も成し遂げたことのないことを達成してしまって、まさしく虹色よりも豊かな色彩を、バラの品種の数ほどに自在に、手中に収められる。
選びたい放題だ。
したがっていまキミが興味を抱いているモノの研究はしなくたって構わない。徒労に終わるだけだろうから、しないほうが賢い選択と言えるだろう。
キミが足繁く通っていた食堂はいまでもここにある。映画館も繁盛していて、街は人でごった返している。
キミが懸想している女の子とは、キミが諦めなければ恋仲となり、生涯を共に過ごすこともできる。二人のあいだの子供だって、キミは玉のように可愛がり、旅行に連れて行くたびに我が子の愛嬌を噛みしめる。
キミが応援していたアーティストたちは、キミの支援とは無関係に、大勢のファンを獲得するし、そういう意味ではキミの審美眼はなかなかのものだと言える。ひょっとしたら凡人ゆえに、誰もが魅了され得る表現にほかの大多数と同様に目が留まるだけなのかもしれない。
じぶんを高く評価するとすればおそらくキミは、ほかのひとたちよりもすこしだけ、点ではなく、流れで、変化を捉えられるのだろう。他人の変化や、環境の変化を、キミは水の流れのように目にすることができる。成功の秘訣はそこにあるとも言えるかもしれないし、ほかの因子が関係しているのかもしれない。
どうしてキミがほかのひとたちにできないことを成し遂げてしまえるのかは、よく解らない。偶然だとしか言いようがない。
これはあまり他人には言えない悩みだ。自慢みたいで、いけすかないだろ。でも、過去のじぶんになら許容範囲内だ。キミが不快になっていたらすまない。そんな狭量ではなかったと記憶している。キミはもっと寛大な人間だ、そうだろ?
ともかくキミの将来は安泰だ。何をしても成功する。いい思いしかしない。
ゆえに抗ウイルス薬の研究なんかしなくていい。
キミはすこし自信過剰なところがあるから、それを開発しなければいずれ人類が、社会が、じぶんの親しいひとたちがたいへんなことになる、と決めつけてかかっているだろうが、そんなことにはならない。未来は相も変わらずだし、キミが尽力せずとも、ほかの誰かが対抗策を生みだしてくれているんじゃないかな。
ちなみに、この手紙には、未来の社会がどんなふうになっているのかを書いてはいけない決まりになっている。ただし個人的なことに関しては書いてもいいみたいだ。
キミの人生はバラ色だ。
くれぐれも抗ウイルス薬の研究なんかにうつつを抜かさず、人生を楽しんでくれ。
キミも知ってのとおり、ウイルスの進化速度は、哺乳類のそれと比べて、数百万倍も速い(短時間で死滅と増殖を繰りかえすためだ。自然淘汰の速度が、劇的に速い)。私見だが、環境によっては数億倍にまで進化速度は増加するだろう。
蛇足だったが、なんにせよ、くれぐれもキミは、キミだけは、抗ウイルス薬の研究をせずに、遊んで暮らすんだ。いいね。
【背景、あのころのわたくしへ】
DNAの塩基配列が位置座標の役割を果たす。したがって問題は時空の壁を通過する際に、過去へ送る物体が崩壊しないかどうかが鍵となる。
立体構造を有した物体は向かない。一方向から高圧縮されても変形しない構造物だと望ましい。耐久性に優れた紙であれば、高い確率で時空の壁を透過し、そのままの形態を保持したまま過去へと送り届けることが可能だ。
君はそうして、君の時間軸上から四十年後に、時空転移装置を発明する。時空の壁はヘビのウロコのように方向性が限られている。現在から未来へのほうが滑らかで、現在から過去へは抵抗が高い。だが、どちらにしても物体を送るには、高エネルギィが不可欠だ。よって、ある程度の抵抗があるほうが、ブレーキがかかって、制御しやすい。
現在から未来へ物体を送れば、総じて、ススとなって消えるだろう。現在から過去であるほうが都合がよいという道理だ。
DNAさえあれば、過去のじぶん以外にも手紙を送ることができる。じぶんの祖先だけでなく、偉人にだって未来の技術を継承可能だ。
だが、しょうじきなところ、タイムパラドクスの検証は進んでいない。最悪の事態を想定して、歴史改変に大きく繋がるおそれのある事項は記述しない方向で、こちらでは規制がかかっている。
もちろん、一般にはまだ普及していない技術だ。検証のために幾人かのモデルを選出し、臨床実験を行っている段階で、いまのところ過去に手紙を送っても、こちらの歴史は変化ない。
或いは、歴史が変わっても認識できないだけかもしれないが、いまのところわるい結果には繋がっていない。
手紙自体は正常に届いているようだ。モデルの相当数が、かつて手紙を読み、それを保管していた。手紙の内容が抽象的なために、どの程度過去の行動が是正され、未来が変わったのかは憶測の域をでない。
こちらから声をかけた時点で、モデルたちは手紙の存在に気づいてもよいくらいなのだが、手紙を送ったあとでいつも「そう言えば」と手紙のことを思いだすようだ。タイムパラドクスの影響が関係しているのではないか、と仮説を立てているが、結論をだすには、データが足りない。
過去と未来が不可分であるならば、こちらが声をかけたモデルがすなわち、すでに手紙を受け取っている人物、ということになるはずだ。だが、そこで手紙を送ることを恣意的に中止すれば、その人物は手紙を受け取った記憶を思いだすこともなく、現に手紙を受け取っていないことになる。
やはり過去は変えられないのだろうか。
実験において、最も安全で、かつ大規模に歴史改変の実証観測が期待されるのが、すなわち時空転移装置の発明者たるわたくし自身へ、その技術の一端を手紙にしたため、送ることだ。
時空転移装置の発明時期が大幅に短縮される確率が、そう低くない値で見込める。
現在、わたくしにはそのような手紙を目にした記憶はないし、未来のわたくしからも送られてきていない。
手紙が届いていたが、それを手にしなかっただけなのか、それとも手紙自体をなんらかの問題で送れなかったか、或いはそれ以外の可能性も考えられる。
というのも、わたくしの考えでは、今後、過去へは手紙以外のものも送れるようになってもおかしくはないからだ。理論上、それは可能だ。
よって、ひょっとしたら何らかの別の干渉が加わり、歴史が大きく改竄されないように、制御されている可能性は、これもまたそう低くないのではないか、と見立てている。
いずれにせよ、これは避けては通れない実験だ。過去のわたくしである君にとっては、なかなか受け入れがたく、未来のわたくしの倫理観を疑うかもしれない。だが、すくなともわたくしはいま、何不自由なく研究に没頭でき、こうして人類社会は、着実に進歩している。
この実験の結果しだいでは、過去の偉人へ、未来の知識を送る計画も前進するだろう。やはり君はそれを懸念して、たとえ手紙が届いても、見なかったことを選択しそうだが、いずれにせよ、これは避けては通れぬ検証だ。申しわけないが、付き合ってほしい。
最後に、わたくしの仮説を述べておく。
おそらく世界には、ある種の閾値があるのだろう。複雑さが、ひとつの枠組み、殻として機能している。殻が割れない程度の、ちいさな改変、波紋であれば、総体としての大きな流れは変わらずに、引き継がれる。だが、たとえば人類すべてが自由に過去のじぶんへ手紙を送れば、これは殻がその揺らぎに堪えきれずに割れ、収拾不能な改変として未来を大きく塗り替えるだろう。そういう意味で、偉人や、歴史的事件の発端となった人物たちへの干渉は慎重になったほうが好ましいのは、君の懸念するとおりだ。そこはこちらもシミュレーションを重ねている。
楽観はできないが、君がおそれるほどには、個個人への手紙の発送の影響は、歴史を塗り替えるほど強烈なものではない、といまのところは判断している。
もちろん予断はできないがゆえに、気の抜けない日々だ。
添付した資料が、いちおう、時空転移装置の初期アイディアの一覧だ。君ならそれで充分だろう。
わたくしがそれをまとめあげたのは、君のころより十年はあとになってからのことだ。予想としては、君は、いまのわたくしよりも三年ほどはやく時空転移装置を完成させる。完成させるために必要な技術が、君のいる年代にはまだ存在していないがゆえの、見立てだが、君ならば、その技術ごと開発してしまいそうだ。これは傲慢なわたくしの、過去のじぶんへの買い被りだと思ってほしい。
長くなった。
歯はまいにち磨け。四十を過ぎてから虫歯に苦しむ。
では、結果を楽しみにしている。
【背景、あのころの貴女へ】
考古学者である貴女に不躾なお手紙、失礼いたします。さぞ驚かれているのではないか、と心中お察しいたします。
まずは同封した年表をご覧ください。そちらには、貴女に起きる人生の転換期を、そのきっかけとなる出来事と共に羅列してあります。
心配はいりません。
貴女はごく平均的な人生を辿り、家族に見守られながら安らかに亡くなります。客観的な評価といたしましては、しあわせな一生を送ることになる旨をまずはお知らせさせてください。
年表をご覧になられましたか?
この時点で貴女は、この手紙の信憑性を五分五分の確率で「そういうものかもしれない」と判断なさっていることと存じます。たとえ未来からの手紙でなくとも、何かしらの超法規的処置の行える組織からの手紙だと推測されるのは、極々まっとうな論理的帰結だと評価いたします。
そのうえで、これが未来から貴女へ向けて送信した手紙である旨を明かしておきます。
すでにお察しかと存じますが、我々が貴女へ向けてこのような手紙を送った最たる目的は、貴女が先日発掘した遺物と密接に関わっております。
端的に申しあげて、貴女の発掘したそれは紛うことなき本物です。本来、それが貴女の時代にまで遺ることはあり得ないのですが、この手紙同様に、過去へと送信するために特殊な加工を施してあります。
貴女の発掘したそれと、この手紙は、ほとんど同じ材質ででき、同じ構造を有しております。
我々と致しましても、貴女のような方が、それを発掘していた事実を突き止めるまでに、随分と手間と時間をかけました。その可能性がそう低くない確率であるとの指摘は、我々の組織内でもたびたび俎上に載ってはいたのですが、なにぶん、扱う時代が多岐にわたり、それに伴い、チェックすべき人物の数も膨大になるために、貴女の存在へと辿り着くのにずいぶんとかかりました。
我々はすでに、貴女の発掘したそれを過去のある時期に送信しております。
そのことにより、この地球という惑星に生命が誕生したのは、我々と致しましてもにわかには信じられない事実でございます。
じっさいのところ、因果関係はまだはっきりとは解っておりません。我々がそれを過去へ送らずとも、この星には生命が誕生したのかもしれませんし、或いは我々が手を下さなければ、この星に生命は芽生えず、我々もまたある時期を境に、地上から姿を消してしまう定めにあったのかもしれません。
その可能性を残したままにしておくにはあまりに大事であるため、どちらにしろ、生命が誕生する確率を上げるために、貴女の発掘したそれを我々は過去へと送り届けました。
貴女の推察はおおむね当たっております。我々が過去へと送り、貴女の発掘したそれは、生命の起源たるRNAを無数に搭載しております。
我々はそれを、陸と海の両方に送りました。RNAとまではいかないにしても、太古の陸と海には、それぞれある種の核酸塩基が鎖状に組み合わさり、任意の組み合わせを連結し、分裂するといったサイクルをつくりあげていたと考えられています。そこへ、明確に生命の源となるRNAを送り、無数に枝分かれした塩基配列群を、一つの方向へと収斂させる根幹の役割を果たすようにと働きかけます。
そのために投じた一石が、貴女の発掘した遺物の正体です。
貴女はなぜ太古の地球に、手紙としか思えない物体が存在したのか、と首を傾げていることと存じます。
さぞ迷われていることでしょう。
ねつ造の確率がもっとも高く、しかし放射年代測定におかれては、ハッキリとそれが太古のものだと示唆している、この二律背反のあいだで貴女は揺れていましたね。
学会へ報告すべきと貴女の意思は傾いていたところで、この手紙を受け取ったのではないか、と想像いたします。そうなるようにとこちらで設定しておりましたから、そうなっていただけなければ、我々といたしましては、失敗と評価せざるを得ません。
お願い申しあげます。
どうか、貴女の発掘したそれを、公にはしないでください。
貴女さまの胸にのみ仕舞っておいてください。
生命の起源が、未来人の手による細工だと知れ渡れば、いささか人類にとって困難な局面の到来が予測されます。
この手紙を貴女へと送り、貴女が手にした段階ですでに、そうなる確率はほとんどゼロにちかしい値にまで下がります。とどのつまり、貴女はこの手紙の意図を正しく紐解き、合理的な判断を下してくださることがほとんど自明となっております。
我々といたしましては、この手紙を貴女へと無事に送り届けることさえできれば、それで目的は果たされたも同然です。
貴女には人類存亡の危機という重大な任を背負わせてしまいたいへん心苦しく、我々一同、人類を代表して、謝意を申しあげます。
一方的なお願いになってしまい、まことに申しわけありません。貴女の聡明な決断によって、人類、そしてこの星の生命は、栄枯を繰りかえし進化を網の目のごとく繰りかえす余地を得ます。
もちろん貴女には、我々からの提案に敢えて乗らない選択肢もございます。それをこちらから禁止する真似はできません。その場合は、生命は貴女の知る歴史どおりには誕生せず、ゆえに人類はおそらく誕生しないでしょう。生命そのものは、時間をかければいずれこの星にも生じ得ると推測されますが、人類にいたっては、その機を逃すでしょう。
いずれにせよ、我々といたしましては、貴女さまにお願いを申しあげることしかできません。なにとぞ、御一考のほどよろしくお願い申しあげます。
長々と失礼いたしました。
謝礼を含め、何かご要望がございましたら、その旨、この手紙の裏面にでも記していただければ、いずれこちらで発見し、対処可能であれば、ご期待に沿えるように尽力させていただきたく存じます。慇懃無礼な言葉づかい、恐縮至極でございます。
お目通しいただき、幸甚の至りに存じます。お身体、どうぞおだいじになさってください。
紙面も残りわずかとなってまいりました。
改めて、この手紙をお手にとって、お目通しいただき、感謝申しあげます。
まことにありがとうございます。
敬具。
未来維持総合研究機関第一研究所第一実験室実行部。
時空転移制御システム責任者。
累野曾(るいのそ)千尋(せんじん) 拝。
千物語「虚」おわり。