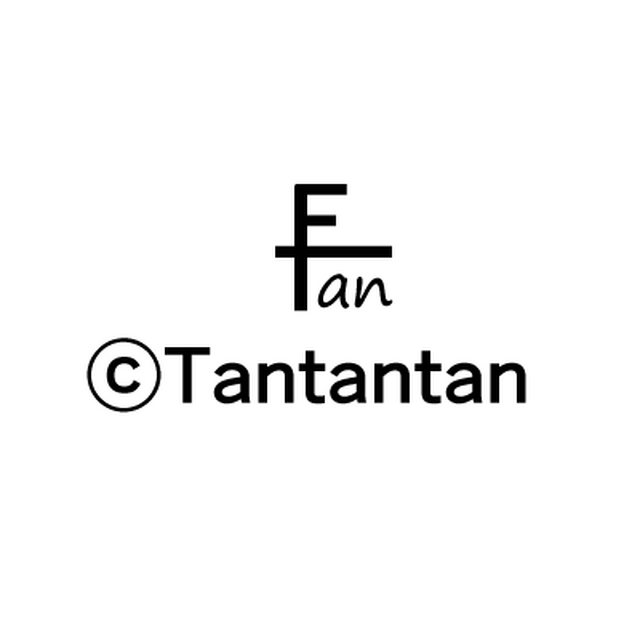四章 多目的研究センターの殺人事件
文字数 12,391文字
パトカーのサイレンが徐々におおきくなっていた。群集はへりつつあった。みな、厄介事を避けようと、立ち去ろうとしていた。
このままでは、警察が来るまえに、目撃者が全員、いなくなる恐れがあった。
成海は、立ちあがった。
「十分もすれば、機動捜査隊があらわれます。彼らの到着まで、待ってもらえないでしょうか? ほんの少し、話をきくだけです。手早く、現場検証をする刑事たちです。時間はかかりません」
人間は見まちがえるものだ。誤認を真実だと思いこむこともあった。正確な情報をえるためには、複数の目撃者が必要だった。ひとりでも遺棄した人物を見ていれば、身長、性別、格好を知ることができるはずだ。最初に左脚を目撃した者、逆に左脚を目撃していない者がいれば、死体を遺棄した時刻を限定できるはずだ。
成海は目撃者を含めた、現場の維持に努めた。
しかし、成海の訴えに、耳を貸す者はいなかった。みな、苦笑いでとおりすぎていった。街の治安は市民の協力があってこそだ。それを理解していても、疑われることへの恐怖がうわまわってしまうのだ。成海は、自分自身の無力さを思い知った。
――警察四一の成海与一がいる。それだけで住民が協力的になるんだ。
成海は、ふと、藤堂のことばを思い出した。
藁にもすがる思いで、ことばを紡ぎ出した。
「わたしは成海与一と言います。警察四一という本を出しています。いまから、捜査に来る者は、わたしの知人です。実直な警察官です。みなさんの不利になるような行動はとりません。わたしも便宜を図ります。十分だけ、待ってくれないでしょうか」
「成海与一? 警察四一の作者ですって?」
主婦の目が猫のそれにかわった。全身に好奇心を走らせていた。
「読んだことないけど、成海与一って、ビッグサイトで活動していたんだよな。葛西のとなりだ。偶然、居合わせたのか?」
会社員のふたりが談笑していた。
「じゃあ、警察の知人って、作中に出てくる藤堂平助じゃない? 実在したんだ。本物を見られるかな」
女子高生も立ちどまっていた。藤堂は警察与一に出てくる男性キャラクターのなかでも、とくに人気が高かった。じっさいに、男前だ。期待には応えられるはずだ。みな、捜査に協力する意志よりも、好奇心がうわまわったようだ。
経緯はともかく、警察への義理を果たすことはできた。
成海は安堵した。
二分ほど経ち、ちかくの交番から警察官が到着した。彼らはブルーシートで左脚を隠した。時間稼ぎするように、市民に話しかけていた。
五分後、パトカーがとまった。機動捜査隊のスカイラインといっしょだった。車道によせる。最後尾のスカイラインからふたりの刑事がおりてくる。ひとりは藤堂平助だ。もうひとりは所轄の刑事のようだった。藤堂よりも年上だ。
「また、事件に巻きこまれたのか?」
藤堂は開口一番、揶揄した。
「第一発見者は、ぼくたちじゃない。すでに発見されたあとだった」
成海は事情を説明した。機動捜査隊は慣れた作業で、ききこみをはじめた。成海と藤堂は、聞き耳を立てた。
「どうやら、この左脚は、午後三時三十分から四時のあいだに、遺棄されたようだな」
「葛西駅の風とともにといっしょだね」
「ああ。斬りとった死体の一部だけを置いている。いっしょだ。同一犯にちがいない」
「それだけじゃない。遺棄された時間帯も似ている」
「時間帯?」
「ああ。一般的に、人通りの多い時間帯は三つある。通勤ラッシュの九時まえ、昼食の十二時、夕食の十八時になる。遺棄された時刻は、そのあいだ、人の少ない時間帯に行われている」
「犯人も姿を見られるわけにはいかない。ピークを避けようとするのはとうぜんだ」
「でも、それじゃ、説明がつかない」
「どうしてだ?」
「深夜に置かなかったことがおかしくなるんだ」
藤堂はうなずいた。
「たしかに。遺棄するだけならば、姿を見られる心配の少ない深夜のほうがいい。しかし、だったら、ますます、おかしい。どうして、犯人は深夜を選ばなかったんだ?」
「きっと、ほかに目的があるんだ。愉快犯じゃない。計画性を感じる。右腕は葛西駅のまえ。左脚はショッピングモールのまえ、どちらも目立つ場所に置いている」
「右腕は風車の羽にむすばれていた。左脚は銅像の手のうえだ。見つかりやすくしているようだ」
「遺棄した目的はまだわからないけど、ほかの部位も同じような場所、ちかしい時間帯に置かれる可能性は高いんじゃないかな」
「モニュメントのある場所か?」
「言い換えれば、通行人や観光客がとおるところだ」
「わかった。所轄に連絡して、パトロールの数をふやしてもらおう。夕方四時からは学生の帰宅ラッシュになる。会社員の帰宅ラッシュは五時半だ。比較的、人の少ない時間帯は五時まえになる。また、遺棄されるかもしれない。沼田さん!」
藤堂は沼田という刑事に駆けよった。所轄の刑事らしい。敬語で、お願いしている。年齢は四十歳ごろだ。柔道経験のある耳をしている。ベテラン刑事のようだった。
警視庁の藤堂と所轄の沼田で、共同捜査をしているにちがいない。
藤堂がもどってくる。
「右腕の発見から五時間、経った。なにか、わかったことは?」
成海はたずねた。
「残念ながら、個人の特定に繋がるような手掛かりはないな。手術痕や指輪跡はなかった」
「身長と性別は?」
「片腕が35センチほどだから、160センチから164センチらしい。体毛は薄いようだ。指は細長い。細身の体格だろう」
「小柄だ。男性でも女性でもおかしくないね」
「ああ。科捜研の検査待ちだ。すぐにはわからない。胴体が見つからないかぎり、性別の即断はできないらしい。頭蓋骨、胸部、骨盤、いずれかを発見できれば、べつだがな」
「こんかいは左脚だから、あたらしい情報は出ないか」
警察官への指示を終えた沼田が引きかえしてきた。
左腕を一瞥した。
「ひさしぶりだな。おおがかりな事件が葛西で起きるのは……」
「過去にも凄惨な事件があったのですか?」成海はきいた。
「ああ。五年まえにな。葛西を本拠地にしていた暴力団があったんだ。相川会と呼ばれていた」
「暴力団?」
「広域暴力団だ。ほかの街や他県にも進出している暴力団だ。一般の企業の皮をかぶって、あちこちのビルを借りていた。五年まえ、相川会は、葛西で活動していた半グレ集団と抗争になったことがある」
「区内の警察署では、流血の金魚祭りっていう名称で、認知されている。死人ひとりを含めて、三十人ちかい死傷者が出た。相川会の幹部たちを根こそぎ逮捕した事件だ」
藤堂が言った。
「初耳だ」
「暴力団関連のニュースは、あまり出さないようにしているからな。住民の不安を煽ることになる。このバラバラ死体の事件も、口止めしている。時間の問題だろうが」
「でも、たしか、暴力団はいないって言っていたよね」
葛西駅で右腕が発見されたとき、藤堂は暴力団の介入を否定していた。
「三ヶ月まえに、暴力団が使っていた貸しビルをすべて、洗ったんだ。すみからすみまで潰した。警視庁と所轄四課の合同捜査だった。いまは一般の企業が借りている」
「当時の幹部たちは、どうしているのですか? まだ、刑務所ですか?」
沼田にたずねた。
「五年まえの事件に関与した幹部は、先月、出所している。葛西に逃げこまれたくないから、三ヶ月まえに潰したんだ。おそらく、他県の二次団体に向かったんだろう」
藤堂は茶色い封筒を成海にわたした。分厚い。五十枚は、はいっている。
「これは?」
「資料室のファイルだ。葛西で起きた事件をまとめている。流血の金魚祭りの記事もある。廃ビル、工場、駐車場、河川敷といった怪しい場所もいれている。なにか気がついたら、意見が欲しい」
成海は見出しに目をとおした。
「夜に警察署で捜査本部がひらかれる。刑事たちに配られる資料も含んでいるが」藤堂は目配せした。「内部情報は省いている。外で見られても、問題ない」
成海は封筒から流血の金魚祭りのファイルをとった。

「名前から想像はついたけど、行船公園の金魚祭りか。二万匹の金魚がならべられる有名なイベントだ。金魚の販売だけじゃなくて、金魚すくい、展示会、屋台も出ている。地元民が大勢、集まるなか、死傷者が出るほどの惨事が起きてしまった……」
「……流血の金魚祭りは、わたしが担当した事件だ」
「沼田さんが? どういう事件だったのですか?」
「数人同士の乱闘がはじまりだった。葛西を根城にしていたふたつのグループが衝突した」
「ひとつは相川会ですね。もうひとつは?」
「海外の組織とつうじている半グレだ。百人以上の規模がある」
「……厄介ですね」
「ああ。半グレは世間的には暴走族の延長に思われているが、じっさいは、まったくべつだ。若者ばかりでもない。暴力団は代紋をかかげるが、半グレは一般人に紛れこむ。実体がつかみにくい。いわゆる、マフィアだな。暴力団とやることはかわらない」
「両グループは水と油です。人の来る場所はお金も動く。金魚祭りで、シノギがぶつかったのかもしれない」
「そうだろうな」
「不運にも、相対してしまったわけですね。お互いの存在に気がついてしまった」
「ちいさな小競り合いで終わってくれたら、よかったのだが、時間が経つにつれて、お互いの仲間がふえていった。大乱闘になった。死傷者の大半は、この乱闘に巻きこまれた一般人だ」
「被害総額もかなりものになった」藤堂が言った。
「乱闘だけでは終わらなかったのか?」
「ああ、混乱にじょうじて、万引き、窃盗、強盗が起きた。どうせ、逮捕されるならば、利益をえようとしたのだろう」
「行船公園のちかくには、ショッピングモールや宝石店もあった。とくに宝石店は丸ごとだ。被害総額は五千万円にのぼると言われている」
成海は五年まえの事件を脳裏に浮かべた。
「彼らが資金源にかえていれば、現在でも活動しうる金額ですね。半グレと暴力団……。沼田さんは、流血の金魚祭りとこんかいの事件、かかわりがあると思いますか?」
「いいや。わたしは考えていない」
「どうしてですか?」
「切っ掛けがないからだ。前兆がない。さいきんは、半グレ集団の姿すら見ていない。音沙汰がないのだ。相川会も、三ヶ月まえに潰した。幹部連中は他県に移り、動きがない」
「別件の可能性は高いということですか?」
「いまのところは、無関係と踏んでいる。いまのところだがね」
「とにかく、情報がたりないんだ。ばらばら死体の遺棄だけでは、手掛かりが少ない。所轄の刑事たちと情報を共有しているが、彼らも心当たりがないらしい」
藤堂は左脚に視線を向けた。
「せめて、犯行のあった時刻、殺された場所、被害者の特定ができれば、捜査方針もきまるのだが……」
成海も身体を横に向けた。
藤堂と同じように両目を細めた。女性の銅像、しぼんだ左脚、骨の断面、黒ずんだ肌、徐々に下腿部へと焦点が移っていった。そのとき、成海の足が勝手にまえに進んだ。一気に目を見開いた。
「藤堂! 左脚の膝裏になにか、付着している!」
「なんだ? かさぶた……。いいや。できものか? ちいさい。一ミリほどの突起物だ。複数、飛び出している」
成海はセントラルを手にもった。裏側に書きいれた。三回目だった。
「――左脚の膝裏についているのは虫の卵に見える。でも、死んでいる。孵化していない。普通なら、一日で孵化する。さいきん、産み落とされた卵じゃない」
「ああ。膝の裏は銅像の下側だった。緑道にいるハエじゃないだろう」
藤堂は冷静に指摘した。
「卵のおおきさを見ても、半日は経っている。死体は二日、三日は経っている。孵化しなかったんだな。そうなると、犯行現場で付着した卵にちがいない」
だからこそ、おかしかった。
右腕にしても、左脚にしても、運ばれるときは、密封されていたのはまちがいない。
古い卵が付着していることが、おかしかった。
卵の存在そのものが矛盾している。
犯人が最初から死体を分解して、葛西にばらまくつもりだったら、すぐに、密封されたはずである。虫の卵が産みつけられる機会はなかったはずだ。
「しかし、死んだ卵が付着している」
「まさか、外で殺されたのか?」
「考えられるね。外に置いてあった死体に、ウジ虫が湧かないようにするのは、不可能だ。森のなかで、蚊に刺されないくらいむずかしい。でも、それだけだったら、卵が死んでいることに説明がつかない」
成海は死んだ卵の付着に、矛盾をおぼえていた。
「偶然でも、皮膚のなかにある卵を駆除できる可能性はかぎられている」
三秒、思案したあと、ふたたび、シャーペンを動かした。
成立する状況はひとつだけだった。
「――犯人は殺害後、死体を屋外に放置していた。そこで、虫の卵が付着した。けれど、半日以内に生育環境が激変した。きっと、犯人は死体を回収し、分割することにしたんだ。虫の卵は熱湯に弱い。犯人は斬り刻むとき、死体をお湯に浸からせた」
「血を洗い流すためだな。熱湯を使った。だから、皮膚のなかの卵は死んだ。孵化しなかった。説明がつくな。犯行現場は、屋外に繋がっている場所で、浴室のあるところだ」
藤堂のうしろで、沼田が感嘆の声を漏らしていた。
「だが……」藤堂はうなった。「あてはまる場所は、いくらでもある。一軒家すべてに、あてはまる。まだ、手掛かりは少ない」
「ああ、そういえば、ほかにも手掛かりはあったよ。左脚の内股に、白いタトゥーが彫られていた。蠍のタトゥーだ」
「白い蠍のタトゥーだと!」
沼田と藤堂は、同時に驚いていた。成海のうしろで、見合わせている。
「どうしたんですか?」
「半グレの名前だ」
「えっ?」
「彼らは自分たちを白い蠍と呼んでいたんだ」
「まさか、ふたたび、白い蠍の名前をきくとはな……。被害者は白い蠍の一員だったのか」
ふたりは捜査の見直しについて、話し合っていた。
パトロールに加えて、白い蠍のアジトを探す新班を考えているようだ。
藤堂と沼田は、とおくで、話している。小声だった。興奮した口調は怒気に似ていた。ときおり、白い蠍という名前が出た。
既視感があった。さいきん、同じ光景を目にしていた。
葛西臨海公園だ。
成海は、ようやく、思い出した。
「藤堂、白い蠍という名称は、一般的に知られている?」
たずねた。
「いいや。所轄の捜査員くらいだ。新聞記事にもあげられていない。半グレ集団は暴力団とことなり、身を隠しながら、犯罪をする。自分たちの名前をおおっぴらにしない」
「目立たないタトゥーをいれているのも同じだな。内股にいれる。白い色で染める。ズボンを履いていれば、一見して見えない。一般人に紛れこむためだ」
「いっぽう、タトゥーをいれることで、構成員の結束力を高めている。勝手に脱退できないようにもしている。白い蠍に参加していた過去を、脅迫に使えるからな」
白い蠍は、仲間内だけで呼び合う符牒である。
そう判明した途端に、成海の顔が曇った。
「……ぼくは白い蠍という名前を、少しまえにききました」
「なんだと?」
「沼田さん。もしかしたら、前兆はあったのかもしれません」
「いつ、どこできいたのだ?」
「葛西臨海公園です。きょうの午前中です。多目的研究センターの研究員と清掃員が話していました。あわてていたようでした。白い蠍の名前を出していました。口論だと思って、駆けよりましたが、不自然に誤魔化されました」
「だれが話していた?」
「三浦真さんという男性です。もうひとりは犬飼と呼ばれていました。ぼくはいまから、その三浦さんの部屋に行く予定になっています。多目的研究センターの室長に取材するためです。三浦さんもいるときいています」
「おれもいっしょに行こう。どんな事情があるにしろ、さいきん、白い蠍の話は出ていない。その三浦は重要参考人だ。沼田さん、あとをたのんでもいいですか?」
「わかった。わたしも白い蠍の情報を集めなくてはならない。所轄の刑事にしかできない仕事だ。捜査本部のひらかれる二十時までに準備しておくよ」
「よろしくお願いします。成海、おれの車にのれ」
「わかった。あ、待って」
成海は歩道で心配そうに見つめている葵を呼んだ。藤堂はようやく、葵の存在に気がついたようだ。彼女も車へと誘導した。
「だいじょうぶだ。観光本の仕事をしていてもいい。成海には、あくまでも、協力してもらっているだけだ」
微笑みを向けた。
「おれも有明第三小学校の同級生だ。少しの時間くらい、輪に加わってもいいだろう?」
後部座席のドアをあけた。へんな気遣いをしていた。
「藤堂、多目的研究センターは、工藤さんの働いていた職場だったんだ。三浦さんとも顔見知りだったらしい」
「ああ、そういうことか」
藤堂はミラーごしに彼女を見る。葵は消沈していた。
「わかっている。問いつめたりはしない。なんだったら、成海にききたいことをたのんで、外にいてもいい。念のために、顔と経歴だけは確認しておきたいんだ」
「経歴か」成海はたずねた。
「工藤さん、橋口さんは、まだ事務室にのこっているかな?」
「ええ。わたしたちが来ることも知っているから、待っていると思う」
「だったら、本人より橋口さんにきいたほうがいいかもしれない」
「やれやれ、よっぽど、信頼がないらしい。恐喝めいたことはしないよ」
「信頼していないわけじゃないよ。ただ、一般人は、必要以上に刑事を怖がるからね。ぼくはいっかい、話している。むずかしい事情だったら、歩みよれると思うんだ。情報を引き出しやすい」
「いいや。それだけじゃないね」
藤堂は不敵な笑みを浮かべた。
「さては、小学四年生のころを根にもっているんだろ? 隠し缶蹴りで、おれと三郷が成海を騙したときのことだ」
「また、古い話を……」
「気になる。何があったの?」
葵は身をのり出した。藤堂は暗い話題を避けるように、意図的に思い出を語りはじめた。愛車のスカイラインのアクセルを踏む。
「女子は知らないか。男子生徒のなかでは有名なんだがな。有明小学校の男子内で、流行っていたんだ。隠し缶蹴り。昼休みにいつも遊んでいた」
「隠し缶蹴りって遊び、はじめてきいた」
「普通の缶蹴りとちがって、鬼は缶の場所を移動できる。缶を隠すところからはじまる」
「隠れ鬼に似ているかもね。ただ、隠れているのは缶だ。仲間は鬼から逃げると同時に、缶を探すんだ。蹴り飛ばせば、勝ちになる。いっぽうの鬼は、相手を見つけたあと、本人にさわるか、全員を見つけて、缶を踏めば、勝ちになる」
「校庭のなかだから、缶を隠す場所はかぎられている。この隠れ鬼、追いかけるほうでも、逃げるほうでも、成海が強くてな。缶の置いてある場所を簡単に探してあててしまうんだ。鬼のほうでも上手い。いつも隠す場所に、虚を突かれる」
「でも、あるときから、ぼくがまったく勝てなくなった。三週間は、負けつづけたんじゃないかな。あたりまえだけどね。ぼくが負けるように仕組まれていたんだ。主犯はふたり、いま、スカイラインを運転している藤堂平助と……」
「工藤さんの雇い主だな」
「三郷算利くん?」
「ああ。おれたちは途中で、気がついたんだ。成海の土俵で勝負するべきじゃないってね。自分たちの能力を発揮できる状況をつくったほうが、確実だとわかった」
「鬼はひとり、逃げる仲間は複数の協力者、これは理解していた。でも、意識の外に、罠を張られるとは思っていなかった。当時のぼくには想像もつかない手段をとられたんだ」
「べつに、ルールは破っていないぞ」
「わからない。どうやって、成海くんに勝ちつづけたの?」
藤堂は笑った。成海は仏頂面で、外をながめた。
「有明第三小学校は生徒数が少ないだろう。すべての学年で、ニクラスしかなかった。おれは集団をまとめるのが得意だった。三郷は交友関係が広かった。みなの顔と名前を知っていた。どちらも、成海が不得意とすることだ」
「校庭には、ぼくたちだけじゃなくて、たくさんの子どもが遊んでいたんだ」
「まさか」葵は勘づいたようだ。
「信じられないだろ。ぼくが缶を隠すところを、校庭にいる子ども全員に見張らせていたんだ。缶を隠しているあいだ、藤堂たちは校舎内にいるきまりになっていた。見られることはないと安心していた」
「成海の準備ができて、おれたちが缶を探すとき、まったくべつの遊びがはじまる。成海が缶を置いた場所をききこむという遊びだ。はははっ。いまとなっては、刑事の仕事といっしょだな」
「よくみんな、協力してくれたわね」
「先生が校庭をローテーションで遊ばせていたからな。その順番のなかに、仲間をいれるのは簡単だったよ。協力のかわりに、かわるがわる隠し鬼に混ぜたんだ。成海は十人ほどの隠し鬼だと思っていたのだろう?」
「ああ。まさか、四十人ローテーションで、隠し鬼をやっていたとは思わなかった。しかも、鬼は、ぼくひとりだ」
スカイラインの速度が落ちる。
「なにが土俵で勝負しないだ。おかげで、ぼくの一人相撲だ」
成海は口をとがらせた。
「そういえば、どうやって、気がついたんだ?」
「ローテーションのおかげだよ。三週間も鬼をやれば、流石に、わかったよ。校庭にいる全員と遊んだことがあるってね」
藤堂は笑い声を噛み潰していた。スカイラインは、京葉線の線路のしたを走る。葛西臨海公園の駐車場エリアへとはいっていった。
「小学校のころの成功体験や失敗経験は、強い影響を与えるものだ。おれは自分の行動力に気がついて、刑事になった。三郷は人付き合いのよさを生かして、会社をつくった」
「ぼくがえたものは、ふたりへの不信感だったわけだ。撤回するよ。根にもっているかもしれないと、思い直すね」
「わかった。わかった。すまなかった。成海の言うとおり、おれは外で待っているよ」
藤堂は支給されている携帯電話を見た。
「上司に電話もしたいからね。その事務員と話す機会をつくってくれるだけでいい。白い蠍の件は、成海から探ってくれ」
ふたりの冗談は、車をおりると同時に終わった。
藤堂は一瞬で、捜査一課の刑事の顔にもどった。
「小学校のころの失敗経験ね……」
葵は思うところがあったようだ。離れた場所でひとり、沈んだ顔をしていた。
海のにおいが、彼女に苦い思い出を蘇らせていた。
「どうかした?」
成海は声をかけた。
葵は口をひらいては、とじていた。成海に言いたいことがあるようだ。しかし、ことばとして、あらわれなかった。葵の目には、成海が自分よりも背の低い少年に見えていた。
十数年が経ち、大人になった彼女の顔に、水の色はなかった。彼女はいま、氷の檻のなかにいた。内側からあけられない檻だ。
冷たい檻は、葵を内向的にかえていた。
成海のまえで、押し黙り、なにも話せなくなるのだ。
少女のころとかわらず、一歩、二歩、さがりつづけた。
「ううん。なんでもない」
「ふたりとも急ぐぞ」

多目的研究センターの入り口をあける。受付にいた亜紀が立ちあがった。カウンターガラスのなかを右往左往している。
手にもった受付のプレートを終了のプレートに交換した。事務室をまわりこむように姿を消した。廊下へと向かっているようだ。
「彼女が橋口さんか?」
「ああ。まちがいない」
「おれは彼女と話しているから……」
「うん。ぼくは三浦先生のところに行くよ。それとなく、白い蠍の件をきいてみる」
「たのむ。わかっていると思うが、死体の遺棄事件にかかわっているようなら、おれに交代して――」
藤堂は最後まで言わなかった。
着信音で遮られた。スーツの胸ポケットから響いている。
「沼田さんからだ。おかしいな。捜査本部の時間には、まだはやい。なにかあったのかもしれない。外で電話してくる」
「いまのかたは?」亜紀がたずねた。
「藤堂と言って……」
刑事だとは伝えなかった。
「ぼくと工藤さんの同級生です」
「そうなんだ。あとで挨拶しなくちゃね」
「約束の時間には、少しはやいですが」
時計の針は十八時を示していた。
「宇田川さんはいらっしゃいますか?」
「室長はまだ展示ホールで、シンポジウムの途中みたいね。でも、三浦さんなら、いるはずよ。受付のまえをとおっていないから」
「お邪魔して、よろしいでしょうか?」
「もちろんよ。ついてきてね」
亜紀は自分のカギをとり、オートロック認証のガラスドアをあけた。
「すべての部屋がオートロックなんですか?」
成海は玄関口のドアをとおった。
「いいえ。各部屋は普通のカギよ。まわしてあけるタイプね。出入り口、四つのドアだけが共用のオートロックになっている。成海くん、宇田川さんからスペアキーをわたされていたでしょう?」
ヘッドの厚いカギをとり出した。
「そのカギでも共有玄関をあけられる。どの部屋のカギでも、共用玄関のドアはあけられるようになっているからね。三浦さんの部屋は、室長も使っている。内鍵はかかっていないと思う」
「ぼくは、もう使いません。橋口さんにわたしておきます。室長にかえしてもらえますか?」
「ええ。わかった。まかせて」
「橋口さんは、ぼくたちを待っていてくれたんですか?」
「ええ。ついでに案内しようと思って。スペアキーをもっているのだから、ほんとうは必要ないんだけどね」
「いえいえ。スペアキーの使い方がわからなかったら、どうしようと不安に思っていましたので、助かりました。ありがとうございます」
「礼儀正しい。うん。合格ね」
亜紀は成海ではなく、葵の顔を見た。うんうんとうなずいていた。
「あとで、お茶をもってくるからね。室長の話、長いのよ」
いっぽうの葵は懐かしそうに廊下を見まわしていた。
「部屋の場所はかわらないままですか?」
「ええ。いまはシンポジウムでごたごたしているから、二階の部屋に、荷物がふえているくらいね」
亜紀は西側の通路へと向かった。両面に八室ずつ、部屋があった。一部屋ごと距離がある。元病棟だったのもうなずける。
亜紀はもっとも奥の部屋へと向かった。
理化学部門、三浦真という札がかかっている。
亜紀は二回、ノックした。おおきい音だった。成海は、亜紀の力加減がとれなくて、ヨガ教室にかよっていた話を思い出して、少し笑った。
「橋口です。失礼しますね」
彼女はドアノブをまわした。
「あれ、珍しい」
「どうしたのですか?」
「内側からカギがかかっている」
「外出中なんじゃないですか?」
「うーん。おかしい。それでも、部屋のカギはかけていないはずだけど」
「向かいの展示ホールで、シンポジウムをやっているのでしょう。部外者がはいると思って、用心したのかもしれませんよ」
「そうね。三浦先生は、慎重なところがあるからね。スペアキーを使いましょう」
亜紀はスペアキーを鍵穴に差しこんだ。箱錠から音がした。亜紀はドアノブを捻り、力強く、前方へと押した。ドアがわずか、十センチほどひらいたとき、異変は起こった。
ドアに衝撃が走り、続け様、室内からガラスの割れる音が響いた。
金属音だ。家具や機材が倒れた音だった。
「ああ、なにか置いていたのかもしれない。どうしよう!」
亜紀はあわてるように室内へとはいった。目線をさげている。彼女は床に弾き飛ばされているガラスの破片ばかり見ていた。正面には目を向けていない。
「ほうきとちりとりをもってきますね」
葵は部屋にはいらず、奥にある共用ドアへと向かった。掃除用具をいれるロッカーが置いてあった。廊下奥のガラスに、藤堂の姿が見える。多目的研究センターにもどってくるようだ。葵がドアをあけている。
「藤堂にも手伝ってもらうか」
成海は散らばったガラスを片づけるつもりで、三浦の部屋に足を踏みいれた。ドアの裏側から亜紀の溜め息がきこえてきた。そうとうな惨事になっているらしい。
成海もあとを追うつもりで、ひらいているドアのさきを二歩、進んだ。しかし、ドアの裏側に、向かうことはできなかった。成海の息が一瞬、とまった。
「な、なに……」
成海は空中の異変にふれてしまった。
目のまえをサンドバックのようにゆれている。左から右へ。右から左へ。おおきな、てるてる坊主がゆれはじめた。実験用の白衣、首元の縄、引きずりこまれた襟、異変の正体が視界にはいった。急速に、戦慄がのたうちまわった。
成海の思考は固まり、四肢は総毛立ち、身体は混乱している。
血液が驚きのあまり、沸騰しているようだった。
はげしい動悸は成海の肺を圧迫した。あらあらしく、息を吐きつづけた。
「成海……」
藤堂が背後から声をかけた。小声だった。だれにもきかれたくない内容らしい。しかし、藤堂の声よりも、成海の意識は、前方に集中していた。
「左腕が見つかった。江戸川区の教習所のまえだ」
キィ、ギー、キィ。
成海の口唇はふるえっぱなしだった。返事ができない。
「成海の予想どおりだった。人の少なくなった夕方五時ごろに置かれたらしい。最悪の事態はつづくものだな」
藤堂はドアの仕切りを跨いだ。
「これ以上、死体が出ないことを願いたいよ」
成海は首を横にふろうとしたが、動かない。
「ばらばら死体の件を、いつまでも隠し切れるとは思えない。遺棄事件として発表するにあたって、少しでも、被害者の情報をえておきたい。白い蠍の話だ」
成海は麻痺した足をどうにか、説得する。
ゆっくりと、横歩きした。
「重要参考人の三浦といったか、彼から話をききたいんだ。室長に取材をしているあいだでいい。構わないか?」
成海はことばではなく、動作によって、返事をした。
人差し指を正面に向けた。
そして、ゆっくりと、うえのほうへと動かしていった。
藤堂も天秤のように、前方へと比重を軽くしていった。藤堂の瞳孔がひらきはじめる。後ろ足の比重がおもくなった。一気に、腰がさがった。
成海と同じ衝撃を味わっているのだ。
キィ、ギー、キィ。
逆向きに身体が生えている。地面に足がついていない。
男性の首が天井に突っこんでいるのだ。太い縄で吊されている。
上衣は天井に吸いこまれ、丸くなっていた。
頭だけが袋のようにつつまれている。
彼の身体は、成海にふれられたことで回転し、あしたの天気を占っていた。
「えっ?」
亜紀が縄の軋む音に気がついた。ふたりと同じ異変を目にする。
「きゃァァァ!」
けたたましい悲鳴がはなたれた。全身に口がついているかのような大声だった。
多目的研究センター中に響きわたった。
亜紀の悲鳴をきいて、葵が駆けつけた。
ちょうど、回転がとまった。
白い袋から男性の顔が出ている。葵と目があった。
「み、三浦先生!」
――三浦真……。
藤堂が白い蠍について、話をきこうとしていた重要参考人だった。
三浦はすでに、永遠に話すことのできない死体へとかえられていたのである。