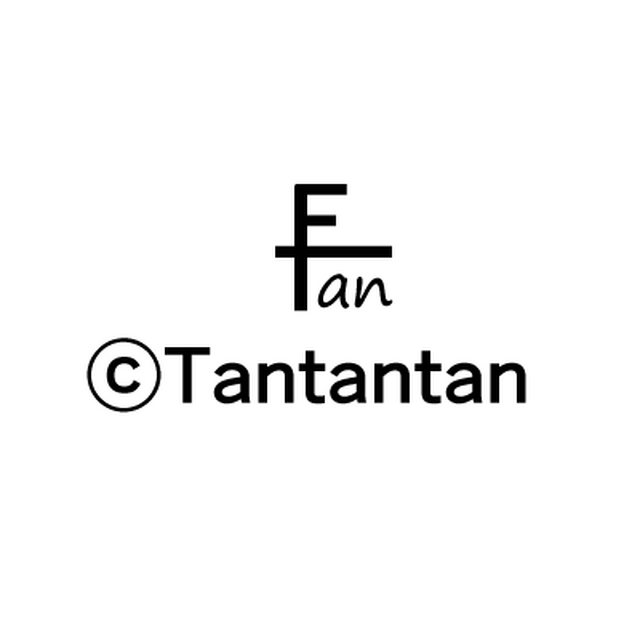五章 クローズドルーム
文字数 13,342文字
「は、はい」
成海は、多目的研究センターの関係者を現場から離れさせることを優先した。殺人ならば、だれが犯人でもおかしくないからだ。亜紀も例外ではなかった。
「そうだな。休憩室がいい。部屋の外に、人がいたら、休憩室で待たせていて欲しい。事件に気がついていない人には、まだ、知らせなくていい」
「警察には電話をした。あと五分で来るだろう」
藤堂は携帯電話をしまいながら、言った。
「すべての部屋の現状を維持したいが、おれだけでは手がたりない。いまは、目についた者を休憩室に集めるだけでいい」
「亜紀さん、こちらに……」
葵は腰が抜けた亜紀に肩を貸していた。
「なにか、あったのですか?」
二階の階段から青年がおりてきた。白い研究服を着ていた。左胸に名札がついていた。
水質環境研究所研究員、秋田進太郎と書かれていた。大学を卒業したばかりの研修生のようだった。だれよりも背が高かった。190センチはありそうだ。
「あ、秋田くん……」
亜紀は涙目で見あげていた。こんどは掘りのふかい男性が正面から歩いてきた。亜紀と身長はかわらなかった。左足を引きずっていた。
「いま、悲鳴がきこえてきたのだが……」
彼は支えられている亜紀を見て、目を丸くした。
「なんだ。また、物盗りでも、はいったのか?」
「貴方は?」
藤堂は眉をひそめた。
「なんだ。見ない顔だな。わたしは加古勝巳だ。大学病院で医師をしている。交通事故で、足を怪我してな。現場に復帰できないあいだ、毎日、カルテ整理をやらされている。しがない男だ」
「医師ですか。だったら、休憩室で亜紀さんを見てもらいますか?」
「ふむ。いつぞやの花瓶を壊したという話ではなさそうだな」
「くわしくは話せません。しかし、警察が来ることになるでしょう。そのとき、説明を受けると思います。貴方は秋田さんと言いましたね。二階には、ほかに人がいましたか?」
「いいえ。だれもいないはずです」
「でしたら、そのまま、もどらずに、みなさんといっしょに休憩室へとお願いします」
藤堂を現場にのこし、成海は全員を休憩室へと誘導した。ちかくの交番から駆けつけた警察官に、多目的研究センターの見張りをまかせた。
シンポジウムを終えた宇田川たちがもどっても、被害者の部屋へと向かわないようにするためだ。成海は三浦の部屋へともどった。
「藤堂、なにかわかったか?」
「なんとも、言えないな。自殺とも他殺ともとれる。鑑識が到着してから、死体をおろすことになるだろう。くわしい調査はまだできない」
藤堂は腕組みをしていた。慎重に室内を歩いていた。
「おれは少しおくれてから、到着した。わからないことも多い。この部屋は、最初からあいていたのか?」
「いいや。カギがかかっていた。ぼくの預かっていたスペアキーであけた。昼に宇田川室長からわたされていた」
「まさかな」藤堂は意味深につぶやいた。「だったら、窓はどうだ。ドア横にあるガラス窓が割れているぞ」
藤堂は床に倒れている脚立を跨いだ。
犯人にしろ、被害者にしろ、天井にあがるときに使った脚立にちがいない。
脚立の天板は、窓の外に出ていた。書棚も倒れていた。書棚のガラス扉は割れていた。
「フェンス塀と樹木で、見えなかったが、おれが多目的研究センターにはいる直前、窓際から物音をきいた」
「橋口さんがドアをあけたときの音だろうね」
「ドアをあけた拍子に、ガラスが割れたということか?」
「不可抗力だったんだ。ドアを押すときに音がした。立てかけられていたみたいだ。この脚立か、書棚だ。両方かもしれない」
「この死体の位置のせいだな。天井にのぼるとき、脚立を置いた。その脚立を支えるために書棚を動かした。ドアのすぐとなりになる」
「でも、それだけでは、説明がつかないね」
「ああ。普通、倒れることはないからな。ドアをあけた時点で、不安定な状態だったんだ」
「死体の足が脚立と書棚にあたったのかもしれない」
「おれも同じ意見だ。ほかに考えられない」
「脚立と書棚がドアへと倒れかかっていた。ドアをあけたとき、押し出される。ドアの進行方向は窓ガラス側だ。結果、ガシャンとなった」
「おれはガラス窓が割れる音をきいたわけだ」
藤堂は背後の事務机を気にしていた。
「藤堂、窓のしたを見て。濡れはじめている」
「窓のした? ほんとうだ。水の円が広がっている。周囲に濡れた痕跡は、ほかにない」
「雨じゃない。二階から流れているみたいだ」
藤堂は割れたガラスのあいだから顔を出した。
「エアコンか、空調か、水道管か、よく見えない。だが、壁も漏れているようだ。夏場に見る光景だな」
「外の地面はどうなっている? 真下だ。乾いている?」
「いいや。濡れている。土の色がことなっている。ずっと、二階から漏れていたみたいだな」
「藤堂、写真を撮ったほうがいい。あとで、ぼくに見せてくれ」
「ああ、わかった」
成海は藤堂といっしょにいるとはいえ、現場を歩きまわらないように注意していた。鑑識が来て、足痕、写真、指紋の確認が終わるまでは、動かないほうがいい。
ただし、時間の経過で、現場がかわることもある。
水の広がりもひとつだ。
藤堂は携帯電話を複数台、もっていた。ひとつは私用、ひとつは公用の携帯電話だ。ほんらいならば、警視庁から携帯電話をわたされる場合、階級が限定される。
しかし、初動捜査に加わることの多い藤堂は、その原則から外されている。
特別に、機密性の高い携帯電話をわたされていた。
藤堂の撮った写真は、外部に漏れることはなく、捜査陣に共有されるのである。藤堂は写真を撮り終えたあと、慎重に、死体のまえにもどってきた。
「かなり、床が濡れてきてるな。倒れた書棚までとどいている。最初から割れていたら、とっくに水浸しになっているはずだ。窓を伝っていた水が、割れたことにより、室内にはいるようになった。やはり、さっき、割れたということだな」
「藤堂……。さっきから、なにを気にしているんだ?」
「成海、こっちに来てくれ」
「いいのか?」
「ああ。すぐそこだ。事務机のうえだ。成海が廊下に出ているあいだに、見つけた」
「……ああ。なるほど」
成海は一目で理解した。筆記用具のとなりに、置いてある。
「むずかしいことになったね」
「まちがいないのか?」
「うん。この部屋のカギだ。まったく同じ形だ。理化学部門の札がついている」
「部屋のカギは、全部でいくつある?」
「ふたつだ」
「スペアキーを昼に、預かっていたと言っていたな」
「うん。そして、机のうえの本鍵だ。これで二本、そろった。室内は内側からはカギがかかっていた。ほかに出入り口はなかったのか?」
「ああ。となりの部屋も見たが、外へとつうじるドアはなかった。すべての窓ガラスには、カギがかかっている。割れていなかった」
「……密室だね。だれも殺害できない状況だ。他殺は不可能になる」
「唯一、考えられるのは自殺だが、死に方が普通じゃない。三浦という男は、そんなにおかしかったのか。異様な死に方を選ぶほどに参っていたのか?」
「いいや。ぼくの目には普通の男性に見えたよ。天井に首を突っこんで、上衣を袋のようにして、顔をつつんで死ぬ。昼に見た三浦さんからは、想像できないな……」
「人の心はわからない。成海と会ったあとに、心境の変化があったのかもしれない。だとすると、なにがあった……」
藤堂は事務机のうえを見た。書類がふたつ、置いてあった。
封筒のうえだ。研究にかんする論文のようだ。
寺崎恭吾と三浦真の名前が記載されている。簡単に読んだ。
「なにか諍いがあったようだな。データの盗用について、申し開きを求めている。寺崎という男が被害者を告発している。動機になりうるな」
多目的研究センターの玄関が騒がしくなってきた。
「到着したな。成海、鑑識が終わるまで、廊下にいてくれるか。死体をおろしたあとに、また、見てもらいたい」
「ああ。鑑識には、佐久間さんも来ているかな」
「彼に用事か?」
「用事というよりお願いかな。天井裏のほうを見てもらいたいんだ」
成海は被害者の上部にある暗闇を見ていた。真下からは梁しか見えない。
「天井裏は外と繋がっているかもしれない。少なくとも、となりの部屋まで、つづいている可能性が高い」
「どうして、そう思うんだ?」
「ふただ。天井裏は壊したのではなく、横にひらいている。ぼくの住んでいるマンションの浴室にもある。天井裏に電源やルーターを置いているんだ。この多目的研究センターは元病院だった。仮設の病棟だ」
「なるほど。いまの病院では、医療装置をネットに繋げている。医師同士の連絡だって、ネット経由だ」
藤堂も天井の暗闇を見つめた。
「回線が切れないように、無線通信の設備を天井裏に置いていたことが考えられる。設置者にとって、病棟もマンションもかわりないからな。仮設病棟ならば、マンションほどの壁は必要ない」
「うん。ホテルのように、等間隔にならべているかもしれない」
成海はドアの横から壁を見た。
部屋の壁際に蛇口がついていた。床の色は微妙に、ことなっている。かつて、浴室があったにちがいない。あとから壁を外したようだった。
被害者の部屋は、おおきな部屋ではなく、ちいさな病室の壁をとり外すことで、広い空間をとっているようだ。奥には三つ分の部屋がある。
となりの二部屋にも浴室があったことになる。
天井裏へのふたがあると予想できた。
「ぼくは、被害者が天井裏の梁に縄をとおして、首を吊っていることが気になるんだ」
被害者の上衣は、暗闇に引きずりこまれたままだった。
「これが殺人ならば、考えられる方法として……」
成海はことばを切った。
廊下から足音がきこえてきた。いちはやく、部屋を出るのだった。
廊下をとおった。
刑事たちと顔合わせしたあと、休憩室へと向かった。
休憩室は、事務室の向かいにあった。訪問客の応対をするときに使っているにちがいない。ドアをあけた。四隅に四つのソファーがならんでいる。中央には長い机があった。
本棚が目にはいった。多目的研究センター名義で出している研究論文がファイルされている。葛西臨海公園の地図、新聞、雑誌、漫画もあった。
お菓子やコーヒーも置いてある。休憩室の体裁は十分だ。憩いの場である。
しかし、だれも談笑していなかった。多目的研究センターにいた者は、すべて集められているようだったが、だれひとりとして、笑っておらず、みな、したを向いていた。
「だいじょうぶですよ。すぐに開放されます」
「わたし、まだ、信じられなくて……」
いちばん奥のソファーに橋口亜希がすわっている。
葵がとなりで話しかけていた。第一発見者のひとりである。最初に室内にはいった女性でもあった。成海は彼女たちに合流しようとした。
「あの、警察は、いま、なにをしているんですか」
途中で足をとめた。背後から声をかけられる。二階からおりてきた秋田進太郎だ。
「ぼくたちは、いつまで休憩室にいれば、いいのでしょうか?」
水質環境研究所の研究員である。恵まれた体格に反して、優男のようだ。成海が警察と協力していると知っているらしい。
「秋田さんは、彼らと話しましたか?」
「は、はい。スーツを着た男性に質問されました。ひとりひとり、きかれています。名前、立場、連絡先を伝えました」
「ほかには、なにを?」
「きょうの多目的研究センターでの行動をきかれました。被害者がどういう人物かも、知るかぎり、教えました。持ち物検査もしています」
「でしたら、彼らの現場確認が終わり次第でしょう。一時間以内にまた、刑事が来ます。そうしたら、外に出られると思いますよ」
むしろ、出入りを禁じるために、捜査員以外、追い出されるという指摘が正しい。他殺ならば、証拠品を別室に隠していることも考えられる。
容疑者が現場にいるほうが、危険だと判断される。
「後日、証言を求められるでしょう。はやければ、あすですね。そのときは、刑事のほうから来ると思います」
秋田は安心したのか、おおきく息を吐いた。胸を撫でおろし、外をながめる。
秋田のとなりで、加古勝巳が手招きしている。ふだん、カルテ整理をしていると言っていた医師だ。歩行に問題があるらしい。
机にもたれかかっていた。成海から向かった。
「おまえが警察四一の成海与一というのは、ほんとうか?」
にんまりと笑みを浮かべている。
「え、ええ」
成海は調子外れの質問を受けて、肩が落ちる。首吊り死体が発見された。その事実はすでに、伝えられているようだ。しかし、加古は緊張感をもっていないようだった。
「こりゃあ、いい。自慢できるかもしれんな」
医師という立場上、死体が珍しくないかもしれない。いっぽうで、倉庫のカルテ整理にまわされている理由にも感じられた。
「加古さんは、被害者のことを、どの程度、知られていますか?」
「三浦だったな。多目的研究センターは、三つ、四つの機関しかはいっていない。流石に、顔は知っているよ」
協力してくれる気なのは、まちがいないようだ。
「三浦さんは、特定の人と仲違いしていましたか?」
成海は昼間の口論を思い出していた。犬飼に目星をつけていた。
「ああ。口喧嘩していたよ。妙に、こそこそと、言い合っていたな」
「やはり」
予想どおりの答えだった。成海は首を縦にふった。
「お相手はとなりの公園内事務所の……」
「だれだ、そりゃ? 三浦と仲が悪かったのは寺崎恭吾だ。向かいの部屋、イノベーション室の男だ」
「えっ」驚きの声が出る。すぐにききかえした。
「両者に接点はあったのですか?」
「わたしは部外者だ。よくは知らんな。ただ、カルテ整理に飽きて、散歩しているときに、たまに見かけた。お互いに言い合っていたよ」
「どういう内容だったか、おぼえていますか?」
「聞き耳を立てたわけではないからな。たしか、納期、知られてもいいのか、破棄、五年まえ、地位、新聞、お金、物品……。きこえていたのは、そんなところだ」
「脈略がないですね。しかし、納期に破棄……。そういえば、三浦さんの部屋に、寺崎さん名義の封筒があったな。もしかして、ふたりの口論の内容って、データの盗用……」
「いや、成海さん。たいへんなことになったね!」
加古は眉をひそめた。宇田川信哉の声だった。
成海と加古のあいだに、割ってはいった。多目的研究センターの室長だ。加古はそそくさと離れていった。加古の勤めている病院に報告されると思ったのかもしれない。
「宇田川さん……」
不自然に会話をとめたように見えた。話されたくないことがあるのではないか。盗用への疑惑はました。宇田川は成海の横に立った。
「シンポジウムを終えたら、廊下に警察官が立っている。驚いたよ」
「ぼくも驚きました。まさか、取材のつもりで来たら、死体を見つけてしまって……」
「すまなかったな。わたしがスペアキーをわたしたばっかりに……。そのスペアキーも橋口くんから、かえされるとき、刑事に奪われてしまった。しばらく、仕事はできんな」
「現場にはいられると困りますからね。仕方ないですよ」
「それだけとは思えないな。最後に三浦くんと会ったのはわたしだ。疑われているかもしれん」
「事件のまえに、会ったのですか?」
「ああ。正確には、秋田くんとふたりで、彼の部屋にはいったのだ」
「いままで、展示ホールにいたのですよね。だったら、おふたりは、シンポジウムのまえに、三浦さんと話したのですね」
「ああ。成海くんと昼食をとったあとだ。彼にきみが来ることを伝えなくては、ならんかったからな」
「その時間をおぼえていますか?」
「シンポジウムがはじまったのは、午後二時すぎだった。多目的研究センターにもどったのが午後一時、発表の準備を終えたあとだったから、午後一時三十分ごろのはずだ」
「最後に、三浦さんの部屋から出たのは、どちらですか?」
「ちょっと、待ってくれ。いま、思い出すよ。三人で話していて、ええと、三浦くんは事務机にすわっていた。時間になって、いっしょに部屋を出た。ああ、そうだ!」
「どうかしました?」
「秋田くんが、名札がないと部屋にもどったのだ。彼には、この施設にある唯一の大型水槽を運ぶのを手伝ってもらっていた。ひとりでは運べない。わたしは秋田くんが出てくるのを廊下で、待っていた。だから、彼が最後に部屋を出ている」
「……秋田さんはどれくらい、室内にいましたか?」
「一分もかかっていないはずだ。名札を見つけたと言っていたよ」
「三浦さんは部屋にのこっていたわけですよね。そのとき、彼はカギをかけましたか?」
秋田が素早く三浦を殺害した可能性は、ゼロではない。
秋田ならば、高身長を生かして、天井裏に吊りさげることもできたかもしれない。
しかし……。
「いいや。カギをかけた音はしなかった」
早業の殺人だけでは、カギをかけられない。
この事件のいちばんの問題は、密室だった。
密室の謎を解かないかぎり、だれであろうと、犯行は不可能だった。
「彼は殺されたのか? それとも、みずから、死を選んだのか?」
宇田川は率直にきいた。
「まだ、わかりません。自殺の可能性もあるでしょう。三浦さんは、さいきん、かわったことを言っていませんでしたか?」
「彼にかわったこと、うーん。わからないな」
「悩みはありませんでしたか?」
「わたしにはなんとも……。でも、もしかしたら……」宇田川は自制するように否定した。「ああ、いや。おぼえていないな」
奥歯に物がはさまるような言い方だった。
「それでは、三浦さんが喧嘩しているところを見ていませんか? 特定の相手とのトラブルです。些細なことでも構いません」
成海は加古への質問を宇田川にも行った。
「……そういえば、三日、四日ほどまえに、顔を真っ赤にして、怒ったことがあったな。最初は笑い話だったが……。なんでも、天井裏に小鳥が来て、巣をつくっていると言うんだ」
「天井裏に?」
「ああ。彼はその小鳥を捕まえて、外に逃がしたと話していた。褐色の小鳥で、下面は白色、目のまわりは黄色かったらしい」
「コチドリの特徴ですね」
「ああ。流石にくわしい。この休憩室で話していた。ちょうど、そのとき、正面の芦ヶ池で、清掃と管理をしている桐生という男が顔を出していてな。窓ごしだ」
成海は昼間に芦ヶ池のなかで、作業している男を見ていた。
彼が桐生にちがいない。
「コチドリは天井裏に巣はつくらない。水場に石を集めて、巣をつくる。だから、うそじゃないかと言ったのだ。小鳥が天井裏にはいること自体、少ないからな。ドバトと間違えたのではないかという意味だったらしい。桐生くんに他意はなかったのだが……」
「三浦さんは侮辱されたと思ったのですね」
「ああ。彼は異常なくらい怒っていた。……うそに敏感になっていた。むきになってしまった」
まったくの勘違いでもないかもしれない。
「ぼくはパークトレインにのっているとき、コチドリがカラスに追いかけられているところを見ました。巣作りとまではいかなくても、天井裏に逃げこんでいた可能性はあります」
「どちらにせよ、些細なことだ」
「ええ」
「しかし、三浦くんにとっては、些細ではなかった。部屋にとじこもって、顕微鏡とにらめっこする者は、わたしみたいなお喋りか。神経質な無口か。二通りが多い」
「三浦さんは後者だった」
「ああ。いまとなっては、どちらでもいいがな。彼が死んだという事実はかわらない。残念だがね」
小声になった。
「三浦くんは、コチドリの巣作りを証明できなくて、悔しさのあまり、死を選んだ。このほうが、平和的な結末だ。だれも傷つかない」
宇田川は自分に言いきかせるようにつぶやいた。
「わたしの知っているトラブルは、これくらいだな」
成海の目を見ない。確信した。
あきらかに、隠し事をしている。
宇田川にとって、コチドリの話は、ふれられたくない話題を避けるために語ったのかもしれない。話題を逸らしたかった。
しかし、現場を見た成海にとっては、まんざら、無関係の話でもなかった。コチドリが天井裏のどこから、はいったのか、非常に興味ぶかい話だった。
「三浦さんは、それからもコチドリの話をしていましたか?」
「いいや。彼はじっさいにコチドリを捕まえるまでは、二度とこの話はしないと言っていた。休憩室にも来なくなったくらいだ。最初に話したときに、はじめてする話だとも言っていたな」
「……自室の天井裏に、コチドリがはいってきた。この話をきいていた人はどれくらい、いますか? 会話にはいっていなくても構いません。その場にいた人を知りたいのです」
宇田川は成海の態度に、面を喰らったらしい。
休憩室を見た。身体と手を向けながら、名指しであげていった。
「ほとんど、休憩室にいるな。医師の加古勝巳、水質環境研究所の秋田進太郎、留守にしているが、イノベーション室の寺崎恭吾……」
寺崎はまだ会ったことがない。
「あとは、事務員の橋口亜希……。芦ヶ池清掃係の桐生邦夫、そして、わたしだ」
「六人ですね」
成海はセントラルの裏側に書きこんだ。
「――被害者がコチドリを捕まえるために、天井裏に顔を出すことを知っていた人間は、かぎられている」
「なんだ。コチドリの話が事件と関係しているのか?」
「ええと……」
成海は返事に困った。どう誤魔化そうかと悩んでいたとき、休憩室のドアがひらかれる。刑事たちがぞろぞろとはいってきた。
藤堂の声がきこえた。刑事集団のうしろで呼んでいる。
「成海、ちょっといいか」
「宇田川さん。急用です。失礼します」
成海は会釈して、廊下に出た。
ちょうど、死体が運ばれるところだった。藤堂の許可をもらって、ちかくで見る。
三浦の顔を見た。
「首のまわりに、斜めの索条痕があるね。擦過傷は、縄でゆれているときについたんだな。顔色は全体的に青白い。眼瞼結膜に溢血点。縊死の特徴が出ている。爪のあいだは、どうだった?」
「目視だが、皮膚は付着していないようだ。割れてもいない」
「抵抗していないんだね。自殺の可能性が高まった。……あれ、後頭部に、裂傷があるな。三センチほどだ。髪の毛で見えない。周囲のふくらみはあざかな。生活反応があるようだ」
「ああ。佐久間も同じことを言っていた。被害者は頭を打った直後に、首を吊ったらしい。頭を打った金槌は上衣のなかにあった。むろん、自分で頭を殴りつけたあとに、首を吊った可能性もある。しかし、普通に考えれば、他殺だ」
「でも、現状、他殺は不可能だ。他殺ならば、密室の謎を崩さないとならない」
「密室の問題は片づくかもしれない」藤堂が言った。
「どういうこと?」
「成海が指摘したとおり、天井裏は繋がっていた。被害者の部屋には、浴槽がひとつだけのこっていた。ほんらいは三つあったようだ。三つとも天井をあけられる。天井裏のなかにはダクトがあった。そのダクトは外までつづいている」
「そうか。じつは、ぼくもさっき、天井裏の話はきいたよ」
「ほんとうか?」
「うん。被害者は休憩室で、コチドリがはいってくる話をしていた。一度、天井裏で捕まえたらしい。つまり、どこかに、コチドリがはいってこられる隙間があったことになる」
「だったら、天井裏の件は、周知の事実だったのか?」
「ああ。でも、知っていたのは六人だけみたいだ」
成海は藤堂に六人の名前を伝えた。
「少なくとも、天井裏がどこかに繋がっているのはまちがいないね」
「ダクトの出口はわかっている。いまから、行くところだ。いっしょに見て欲しい」
「わかった。まだ、現場検証は終わっていないんだよね。室内には、はいれそうにない?」
「今日中には無理だな。専門チームを呼んで、天井の板を外す話になっている。もしも、第三者の出入りがあったとしたら、遺留物が見つかる可能性があるからな」
「夜通しの作業か。あれ? でも、藤堂は捜査本部があるんじゃなかったか? 死体遺棄の事件のほうがのこっているじゃないか」
「少し、おくれることになるだろう」
「おくれる?」
成海は嫌な予感がした。
「ああ。共有しなければならない情報がふえたからだ」
藤堂は多目的研究センターの玄関ドアをひらいた。警察官が集まっている。成海たちは、少し離れた場所から、多目的研究センターの外縁をとおった。
外からは塀と樹木で、殺害現場の窓が見えない。申し訳程度に照明ポールが立っている。ポールの高い位置に監視カメラが備えつけてあった。

しかし、角度的に多目的研究センターの敷地内まで映っていないはずだ。
それでも、責任者に電話をかけている警察官の姿があった。
監視カメラの映像を確認するつもりらしい。
「共有する情報ってなんだ?」成海は道すがら、たずねた。
「おれは元々、被害者が白い蠍の名前を出していた理由をきくために、成海たちに同行した」
「まさか……」
「想像しているとおりだ。直腸の温度を測るとき、検視官にたのんで、被害者の身体をあらためさせた。左脇のしたにあった」
「白い蠍のタトゥーか?」
「ああ。殺害された三浦もまた、白い蠍の関係者だ。遺棄事件と関与しているかもしれない。だから、この事件の捜査を優先したんだ。いま、無理を言って、休憩所にいる関係者にたのんでいる。身体を見せてもらうようにな。裸にするわけじゃない。両脇と内股だけだ」
「藤堂は三浦さんが内輪もめで殺されたと考えているんだな」
「まァ、そうだったら、殺人事件がわかりやすくなるからな。天井裏にはいれると知っていたのは六人だろ? 六人のなかに、タトゥーを彫っている者がいるかもしれない」
「ほんとうに、外から部屋にはいれたかは、わからないけどね」
「霧のなかでも手をのばしつづけるのが、刑事の仕事だ。じっさいに、見てみようじゃないか。ほら、着いた。あそこだ」
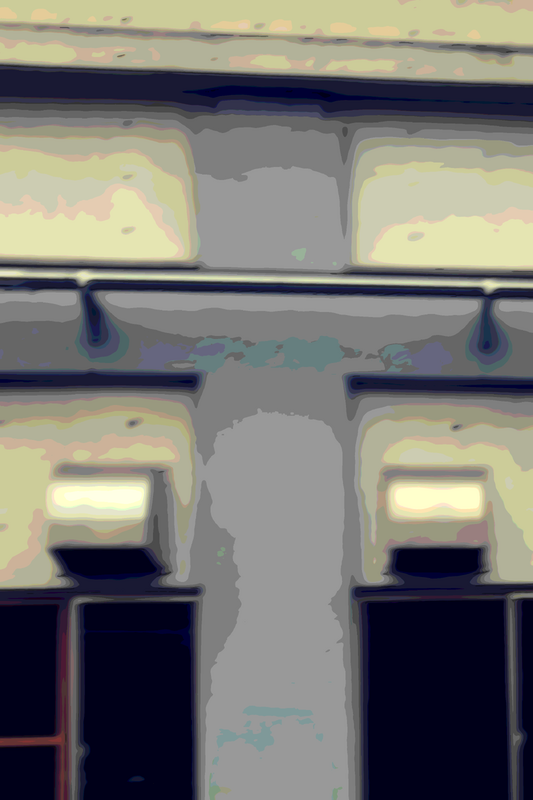
奥側玄関のとなりだった。フェンス塀はブロック塀にかわっている。塀同士の隙間からダクトが見えていた。敷地内だ。ブロック塀をのりこえる必要がある。
目当てのダクトは、白い壁の上部にあった。
成海と藤堂は、ブロック塀を軽々とのりこえた。段差に足をかければ、男性でも女性でも怪我人でも、のぼることは可能だ。同じように足をかけ、ダクトにも顔をいれられる。
「思ったよりも、おおきいダクトだな。空調がしっかりしている。仮設とはいえ、元々、病棟だっただけはある。マンションにある通気口とは、まるで、ちがうな」
「でも、ほんらいのダクト排気口じゃないね。逆L字のカバーがない」
「何者かに外されたのか?」
「わからない。だが、おかげで、十分な隙間がある。藤堂、見えるか。ダクトパイプが半分、外れている。天井裏のすみに落ちている。白いアルミのようなパイプ管だ」
「成海、どこにもさわるんじゃないぞ。埃のうえに、小鳥の足跡が見える。成海の話がほんとうならば、被害者の部屋まで繋がっているはずだ。犯人はここからはいったのか? しかし……」
「ああ、思っていたより、せまいね。たしかにはいれるかもしれない。けれど、ぼくの肩を斜めにしても、押し進むことができない」
「おれも無理だ。仮に両肩がはいっても、進むことは不可能だな」
「少なくとも、160センチ前後の痩身にかぎられるだろうね」
ふたりはブロック塀をおりた。
「160センチか。容疑者のなかでも、多くないな。宇田川、橋口、加古の三人くらいだ」
「まだ、わからないよ。なかにはいれても、じっさいに、はいったかは別問題だ。慎重に調べないといけない」
「ああ。わかっている。可能性よりも証拠だ。髪の毛、唾液、指紋、足跡、血痕、あらゆる痕跡を見つけ出さなくてはならない。鑑識と科捜研の仕事だ。ただし……」
藤堂はダクトを見あげた。
「秋田は身長的にどうあっても、無理だろう。あとのふたりはどうだ。寺崎と桐生だ。彼らの体格を知っているか?」
「寺崎さんは知らないけど、桐生さんらしき男性は、とおくから見た。小柄ではなかったね。ぼくたちとかわらない背丈に見えた」
「だったら、秋田と同じく、むずかしいか」
「橋口さんは身体が硬いらしいよ。痕跡を気にしながら、音を立てずに進めるだろうか。加古さんにしても、足を怪我している」
「どちらも、偽りの可能性がある。ときに殺意は、不利をものともしない。はっきり言って、その程度の身体的特徴は、疑われないための準備にさえ感じられる。容疑者から消去するには、もっと明確な根拠が必要だ」
「藤堂の言っていることもわかる。憶測よりも、現場不在証明のほうが重要だ。そうなると、三人のなかで、ひとり、たしかなアリバイをもつ人物を知っている」
「だれのことだ?」
「宇田川さんだ。彼はシンポジウムに参加していた。途中で、抜け出せるとは思えない」
「たしかにそうだ。いま、あがっている報告でも、展示ホールを出た者はいないらしい。作為がなければだがな」
「ほかのふたりのアリバイは?」
「橋口は事務室にいた、加古はカルテ整理をしていた。事務室には、橋口以外にほかの職員もいたらしい。加古は長電話していたと証言している。裏をとっている最中だ」
「時間帯によっては、どちらも、不可能かもしれない」
死亡推定時刻は、今日中に出るらしい。現場に駆けつけた検視官は直腸の温度と死後硬直を見て、午後二時から午後三時のあいだと推測していた。
「やれやれ。被害者の部屋にはいることが可能だとわかった途端、こんどは、アリバイの問題が浮かびあがるか」
まだ、死体を運んだばかりである。このあと、ちかくの大学で、法医解剖が行われる。正確な情報がわかるはずだ。
アリバイとの照らし合わせは、あしたからはじまるにちがいない。
「成海の初見はどうだ? どんな人物像が浮かんでいる?」
成海はすぐには答えなかった。多目的研究センターの屋上を見た。二階、一階、地面、目線を落としていった。
「藤堂は、屋根裏の散歩者という作品を知っている?」
「きいたことはある。内容は知らない」
「百年以上まえの作品だからね。もう古典だ。しかし、古典は優れているから後世にのこる。ゆえに、殺人事件を題材とした創作物では、密室、アリバイとならんで、定型と言える。屋根裏からならば、だれにも見られずに、現場の直上に侵入することができる」
「でも、多目的研究センターは二階建てだろう。被害者の部屋は一階だ。両者の状況はことなっているのではないか?」
「ああ、だから、呼び名はことなるだろうね。天井裏の散歩者だ」
「なるほど。捜査本部がひらかれるときに、使わせてもらうよ。それで、散歩者の目星はついているのか?」
「いいや」
成海は首を横にふった。
「高い壁だ。セメントを塗り立てたばかり、殺人事件の発覚はちかいのに、壁はとっくに固まって、犯人はどこよりもとおい。……ぼくたちは謎ばかり、目にしているね。密室、天井裏の散歩者、アリバイ。少なくとも、この三つの壁をこえなければならない」
成海はブロック塀を叩いた。
「この壁は、頂上が見えないくらいに高いんだ」
「まだ、見当もつかないか?」
「ああ。犯人は透明なままだ。ぼくには、透明の犯人が、天井裏から忍びよっている姿しか見えないよ」
――ほんとうに、犯人は天井裏を使ったのだろうか。
成海はいちばんの疑問を口にしなかった。
ただ、「わからない」とだけ言った。
「なに、すぐに解決するよ。今日中に、逮捕できるさ」
藤堂は成海の肩を二回、叩いた。
真夏とはいえ、すでに、夜九時だ。葛西臨海公園は暗闇につつまれている。
「思えば、きょうは、ばらばら死体の発見からはじまった。右腕、左脚……」
左腕も発見されている。
「夕方には首吊り死体だ。成海にとって、ハードな一日になってしまったな」
「ぼくよりも工藤さんに疲れが見える。事務員のころから被害者を知っている。彼女のほうが辛そうだ」
「そうだな。成海と工藤さんは、もう、かえっていい。すでに許可を出しているんだが、彼女が橋口のそばにいると言って、きかなかったんだ。成海がうながしてくれ」
「わかった。あしたもあさっても、葛西にいる。事件の捜査も、葛西の取材も、これからだ」
成海は素直に退散することにした。刑事の藤堂は、これから寝ずの捜査がはじまる。
同級生の仕事ぶりと熱心さには、頭のさがる思いだ。
少しでも、藤堂の肩の荷を軽くしたいと思った。
しかし、現在、手伝えることはない。
多目的研究センターから離れることが手伝いになる。
「はははっ。成海は心配しすぎだ」
藤堂の空笑いが響きわたった。
「容疑者のなかで、天井裏にはいれるのは三人だけだ。いま、その身体を調べている。三人のうち、ひとりからタトゥーが出れば、あとは簡単だ。芋づる式に、証拠が出てくるよ」
成海は、藤堂の調子に合わせて、相槌を打った。
「真犯人には、きっとアリバイもない」
「ああ」
「天井裏から、個人を特定できる遺留物も見つかる」
「そうだな」
「殺人の動機は、半グレ同士の内輪もめだ。すぐに逮捕状が出る。この事件はあしたで終わりだ。きっと、いい報告ができるよ」