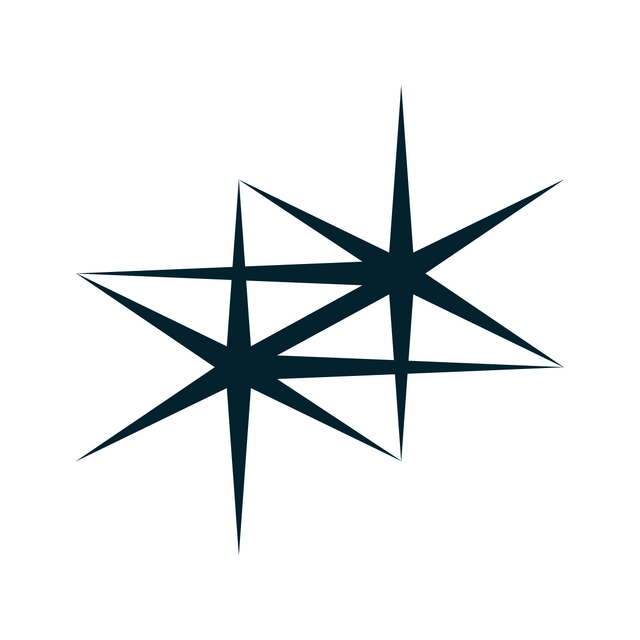01-028 加速
文字数 3,736文字
考えなくてはいけないことは、たくさんある。
何故、助手が攫われ、博士 はボクを呼びつける?
なぜ博士はあんなにも狂っている?
博士は、どうやって復活している?
なぜ、何のために博士はアンドロイドを、電脳を破壊した?
目の前に堆く積み上がった問題たち。
それに、きちんと向き合わなくてはいけない。
きちんと答えを導き出さなくてはいけない。
不快だとか何とか言って、逃げている場合じゃない。
逃げちゃ――
――いや、人を助けるため、という前提ができたせいだろうか。
ナオは自身の思考にノイズのように混じる不快感が、少しだけ軽くなっている事に気付いた。
さすがに本調子とまではいかないが、思考がスムーズに流れているのを感じる。
まったく――ほんと、よくできた脳だ。
ナオはこの脳を設計したAIたちに皮肉の一つでも言ってやりたい気分になりつつ、しかし同時に少しほっともしつつ、気を取り直して一つ一つの問題を解くことに集中した。
まずは、博士の復活。
これについては、博士の研究領域を考えれば、ある程度予想できる。
博士は、アンドロイド関連以外だと、人体に関わる領域の成果が多い。
特に関係ありそうなのは、人体の凍結や情報化のあたりだろうか。
はっきりとした成果が表に出ているわけではないが、人の体の情報をスキャンしてデータとして保存する、そんな研究に関わっていた痕跡がある。
加えて、二度目以降、現れた博士が本来の年齢より少し若々しく見えた事。
髪や髭、爪などの伸び具合。
その辺りを総合して考えれば――恐らくはそういう事になるはずだ。技術的に――可能。
――でも、じゃあ、なんでそんな事をした?
それが一番わからない。
博士が何度も口にしていた「美しくないものを壊す」という言葉。
あれが、どうにもひっかかる。
ナオが幼い頃、博士はしきりに電脳は美しいと言っていた。その素晴らしさを嫌というほど聞かされた。
ナオが、自分の頭に入っている電脳を疎ましく思いながらも受け入れ生きてこられたのは、「君の頭に入っているのは素晴らしいものなんだ」という博士の熱烈なメッセージのお陰でもある。
それが、時を経て、なぜ真逆の「醜い」になってしまったのか。
愛情が一週回って憎悪に変わる、というのは、人の愛憎劇を考えればなくはない話ではある。
でも、だからといって、何度も復活してまで破壊しなくてはいけなくなるとは思えない。
そこまでしないといけないとすれば、あり得るのはやはり――ケイイチとの口論の時にも言った事だが――電脳になにか重大な、危険な問題がある事に気づいた、という事か。
しかし、それもどこか変な気がする。
問題があるなら、それをAIに対して指摘すればいい。広く世間に公表したっていい。
そうすれば必ず、AIたちが設計を見直し、修正してくれるはずだ。
ナオの電脳だって、生まれてからずっと変わらないものというわけではない。
ソフトウェア的な更新は頻繁に行われている。たった1日でまるで別物に変わっている事すらある。
ハードウェアにしたって、寝ている間にAIたちによって改修されたことが何度かある。
もし、本当に重大な問題があるなら、それを改修して一気に更新するくらいのこと、AIたちにとっては朝飯前だ。
その事を博士が知らないわけがない。
そうやって恐ろしいまでの速度でアップデートし続けていけることも、博士が言っていた電脳の「美しさ」の一つだったのだから。
じゃあ――何だ?
AIに伝えても修正される見込みのない不具合がある?
としたらそれは何だ?
三原則に関わる何かだろうか。
確かに――ナオ自身の行動から、思い当たる部分はある。
だが、それこそAIに指摘して修正不可能という事はないはずだ。
他にどんな可能性がある?
あるいは――博士は本当に狂ってしまったのだろうか?
何か、重大な問題が博士に起こっている?
何度も蘇ってくる事とそれは関係があるのだろうか。
いや――
――
――
――
ナオはそうやって、無限に近い時間の中で、考えられる事を一つ一つ整理していった。
集められる限りのデータを集め、膨大な量のロジックを組み立てていく。
組み立てては壊し、壊しては作る。それを果てしなく続けていく。
結局「考える」というのは、トライアルアンドエラーの繰り返しだ。
求める答えが出るまで、虱潰しに可能性を探し続けるしかない。
天啓や閃きのようなものが一足飛びに何かを解決する事があるとしても、それは膨大な探索探究の先にしか起こり得ない。
だから、考える。
求める答えが出るその時まで、しつこいくらいに粘り強く。
しかし――きちんと考え抜くには、やはり情報が圧倒的に足りなかった。
特に、ここ数年の博士の行動と研究がまるで分からない、その事が痛い。
どんな名探偵だって、ヒントとなる情報が何一つない状況では、推理を組み立てる事はできない。
ナオが知る事ができるのは、知りうる事だけ。
考えられるのは、与えられた材料から考えうる事だけだ。
結果、作り上げる事ができたのは、膨大な数の仮説だけ。
仮説の中で、有望そうなものはそのほんの一部のみ。
おおよそ確定できたのは、博士の復活の事を含めて片手で数えられるほど。
肝心な部分は何も確定できていないし、博士 を説得したり、捕まえたりできる目処はまるで立っていない。
そんな状態で一人、明らかに罠と分かっている場所に向かっていいのか?
不安はある。
でも――大丈夫。
きっと、大丈夫。
今、考えられる事は考え尽くした。
あとは、実際に博士がどう動くか、それによって全てが決まる。
博士 の行動によって足りないピースがいくつかはまれば、きっと状況をいい方向に導ける。導いてみせる。
(即興 はあまり得意じゃないんだけど)
ナオは内心でぼやきつつ、加速を解き、バーチャル作業空間を片付け、目を開けた。
首筋からケーブルを外し、少しばかりこわばった体をほぐしながら体を起こす。
時間を確認すると、ブースト開始から30分ほど経っていた。
「行くのか?」
突然病室に響いた低い声に驚いて目を向けると、窓際にギンジがいた。
フルブーストする直前、ケイイチ誘拐の件で一報入れていたので、駆けつけてくれたのだろう。
「ん」
「こいつ持ってけ」
ギンジはそう言って、黒い塊を差し出した。
「ギンさんがボクに命令なんて珍しいね」
ナオは、人に命令形で言われたら、逆らえない。
そのことをギンジはよく知っている。
知っているからこそ、普段はナオとの会話で命令形は使わない。使わないようにしてくれている。
そんなギンジが命令という形で押しつけてきたもの。
それは、革製のホルスターに格納された、一丁の拳銃だった。
「使い方は知ってるよな?」
「ん」
警察と関わるようになってから、銃の扱いについては何度か無理矢理レクチャーを受けさせられている。補助用のアプリも、警察との仕事で必要なアプリの一部としてインストール済みだ。
「どうせボクには使えないけどね」
「そうかもな。でも持ってろ」
「今日は命令多いね」
「相手は嬢ちゃんを殺る手段を持ってる。そんな相手のところに丸腰で行かせるわけにはいかねぇんでな。許可は取ってある」
「ありがと、でいいのかな」
「なんだったら捕まってる兄ちゃんに使わせてもいいぜ?」
「それは危険が増すだけじゃない?」
「違ぇねぇ」
ナオは小さく笑いながら、ずしりと重いそれを受け取った。
ホルスターを肩にかけ――正直、違和感しかない。
確かにこの銃という武器は、危険な相手と対峙する場合には有効だ。
積極的に相手を殺傷するような使い方はできないが、自身の身に危機が迫っている場合であれば、相手に傷を負わせ、動きを封じるくらいの事はできる。
だがそれは、銃を使うのが普通の人間だった場合の話。
これは、ナオには使えないものだ。
ナオは、人を傷つけられない。
たとえそれが、自身の身を守るためであったとしても、自身の身よりも、他人の安全を優先しなくてはいけない。
そんな人間が銃なんてものを持って、一体どうしろと言うのか。
――でも、とも思う。
これからボクが向かうのは、こんな武器を携えて行くべき所なのかもしれない。
滅多に起こらない、起こり得ない、人の命を盾に取った脅迫。
どうせこれから向かう場所――博士の自邸には、人命保護に熱心なマイクロマシン達はいないのだろう。だからきっとこんな前時代的な武器も、普通に使えてしまう。
(といって、ボクがこれを使えるわけはないんだけど)
ナオは少しだけ気持ちを引き締めて、以前取り寄せた絶縁仕様のフードつきコートを身に纏った。
現場での思考加速に備えて、エネルギー源となるキャンディやジェル、ラムネなどをポケットに補充する。
「悪ぃな、本当は俺たちがどうにかするべき事なんだが……」
「これは仕方ない」
「すぐ外で待機してる。何かあったら呼べ」
「また命令」
「保険、ってやつだ」
ギンジはどこか申し訳なさそうに小さく笑い「気をつけてな」と言った。
「じゃ、行ってくるね」
どこか心配そうにナオを見つめるハルミに一声かけ、ナオは部屋を後にした。
何故、助手が攫われ、
なぜ博士はあんなにも狂っている?
博士は、どうやって復活している?
なぜ、何のために博士はアンドロイドを、電脳を破壊した?
目の前に堆く積み上がった問題たち。
それに、きちんと向き合わなくてはいけない。
きちんと答えを導き出さなくてはいけない。
不快だとか何とか言って、逃げている場合じゃない。
逃げちゃ――
――いや、人を助けるため、という前提ができたせいだろうか。
ナオは自身の思考にノイズのように混じる不快感が、少しだけ軽くなっている事に気付いた。
さすがに本調子とまではいかないが、思考がスムーズに流れているのを感じる。
まったく――ほんと、よくできた脳だ。
ナオはこの脳を設計したAIたちに皮肉の一つでも言ってやりたい気分になりつつ、しかし同時に少しほっともしつつ、気を取り直して一つ一つの問題を解くことに集中した。
まずは、博士の復活。
これについては、博士の研究領域を考えれば、ある程度予想できる。
博士は、アンドロイド関連以外だと、人体に関わる領域の成果が多い。
特に関係ありそうなのは、人体の凍結や情報化のあたりだろうか。
はっきりとした成果が表に出ているわけではないが、人の体の情報をスキャンしてデータとして保存する、そんな研究に関わっていた痕跡がある。
加えて、二度目以降、現れた博士が本来の年齢より少し若々しく見えた事。
髪や髭、爪などの伸び具合。
その辺りを総合して考えれば――恐らくはそういう事になるはずだ。技術的に――可能。
――でも、じゃあ、なんでそんな事をした?
それが一番わからない。
博士が何度も口にしていた「美しくないものを壊す」という言葉。
あれが、どうにもひっかかる。
ナオが幼い頃、博士はしきりに電脳は美しいと言っていた。その素晴らしさを嫌というほど聞かされた。
ナオが、自分の頭に入っている電脳を疎ましく思いながらも受け入れ生きてこられたのは、「君の頭に入っているのは素晴らしいものなんだ」という博士の熱烈なメッセージのお陰でもある。
それが、時を経て、なぜ真逆の「醜い」になってしまったのか。
愛情が一週回って憎悪に変わる、というのは、人の愛憎劇を考えればなくはない話ではある。
でも、だからといって、何度も復活してまで破壊しなくてはいけなくなるとは思えない。
そこまでしないといけないとすれば、あり得るのはやはり――ケイイチとの口論の時にも言った事だが――電脳になにか重大な、危険な問題がある事に気づいた、という事か。
しかし、それもどこか変な気がする。
問題があるなら、それをAIに対して指摘すればいい。広く世間に公表したっていい。
そうすれば必ず、AIたちが設計を見直し、修正してくれるはずだ。
ナオの電脳だって、生まれてからずっと変わらないものというわけではない。
ソフトウェア的な更新は頻繁に行われている。たった1日でまるで別物に変わっている事すらある。
ハードウェアにしたって、寝ている間にAIたちによって改修されたことが何度かある。
もし、本当に重大な問題があるなら、それを改修して一気に更新するくらいのこと、AIたちにとっては朝飯前だ。
その事を博士が知らないわけがない。
そうやって恐ろしいまでの速度でアップデートし続けていけることも、博士が言っていた電脳の「美しさ」の一つだったのだから。
じゃあ――何だ?
AIに伝えても修正される見込みのない不具合がある?
としたらそれは何だ?
三原則に関わる何かだろうか。
確かに――ナオ自身の行動から、思い当たる部分はある。
だが、それこそAIに指摘して修正不可能という事はないはずだ。
他にどんな可能性がある?
あるいは――博士は本当に狂ってしまったのだろうか?
何か、重大な問題が博士に起こっている?
何度も蘇ってくる事とそれは関係があるのだろうか。
いや――
――
――
――
ナオはそうやって、無限に近い時間の中で、考えられる事を一つ一つ整理していった。
集められる限りのデータを集め、膨大な量のロジックを組み立てていく。
組み立てては壊し、壊しては作る。それを果てしなく続けていく。
結局「考える」というのは、トライアルアンドエラーの繰り返しだ。
求める答えが出るまで、虱潰しに可能性を探し続けるしかない。
天啓や閃きのようなものが一足飛びに何かを解決する事があるとしても、それは膨大な探索探究の先にしか起こり得ない。
だから、考える。
求める答えが出るその時まで、しつこいくらいに粘り強く。
しかし――きちんと考え抜くには、やはり情報が圧倒的に足りなかった。
特に、ここ数年の博士の行動と研究がまるで分からない、その事が痛い。
どんな名探偵だって、ヒントとなる情報が何一つない状況では、推理を組み立てる事はできない。
ナオが知る事ができるのは、知りうる事だけ。
考えられるのは、与えられた材料から考えうる事だけだ。
結果、作り上げる事ができたのは、膨大な数の仮説だけ。
仮説の中で、有望そうなものはそのほんの一部のみ。
おおよそ確定できたのは、博士の復活の事を含めて片手で数えられるほど。
肝心な部分は何も確定できていないし、
そんな状態で一人、明らかに罠と分かっている場所に向かっていいのか?
不安はある。
でも――大丈夫。
きっと、大丈夫。
今、考えられる事は考え尽くした。
あとは、実際に博士がどう動くか、それによって全てが決まる。
(
ナオは内心でぼやきつつ、加速を解き、バーチャル作業空間を片付け、目を開けた。
首筋からケーブルを外し、少しばかりこわばった体をほぐしながら体を起こす。
時間を確認すると、ブースト開始から30分ほど経っていた。
「行くのか?」
突然病室に響いた低い声に驚いて目を向けると、窓際にギンジがいた。
フルブーストする直前、ケイイチ誘拐の件で一報入れていたので、駆けつけてくれたのだろう。
「ん」
「こいつ持ってけ」
ギンジはそう言って、黒い塊を差し出した。
「ギンさんがボクに命令なんて珍しいね」
ナオは、人に命令形で言われたら、逆らえない。
そのことをギンジはよく知っている。
知っているからこそ、普段はナオとの会話で命令形は使わない。使わないようにしてくれている。
そんなギンジが命令という形で押しつけてきたもの。
それは、革製のホルスターに格納された、一丁の拳銃だった。
「使い方は知ってるよな?」
「ん」
警察と関わるようになってから、銃の扱いについては何度か無理矢理レクチャーを受けさせられている。補助用のアプリも、警察との仕事で必要なアプリの一部としてインストール済みだ。
「どうせボクには使えないけどね」
「そうかもな。でも持ってろ」
「今日は命令多いね」
「相手は嬢ちゃんを殺る手段を持ってる。そんな相手のところに丸腰で行かせるわけにはいかねぇんでな。許可は取ってある」
「ありがと、でいいのかな」
「なんだったら捕まってる兄ちゃんに使わせてもいいぜ?」
「それは危険が増すだけじゃない?」
「違ぇねぇ」
ナオは小さく笑いながら、ずしりと重いそれを受け取った。
ホルスターを肩にかけ――正直、違和感しかない。
確かにこの銃という武器は、危険な相手と対峙する場合には有効だ。
積極的に相手を殺傷するような使い方はできないが、自身の身に危機が迫っている場合であれば、相手に傷を負わせ、動きを封じるくらいの事はできる。
だがそれは、銃を使うのが普通の人間だった場合の話。
これは、ナオには使えないものだ。
ナオは、人を傷つけられない。
たとえそれが、自身の身を守るためであったとしても、自身の身よりも、他人の安全を優先しなくてはいけない。
そんな人間が銃なんてものを持って、一体どうしろと言うのか。
――でも、とも思う。
これからボクが向かうのは、こんな武器を携えて行くべき所なのかもしれない。
滅多に起こらない、起こり得ない、人の命を盾に取った脅迫。
どうせこれから向かう場所――博士の自邸には、人命保護に熱心なマイクロマシン達はいないのだろう。だからきっとこんな前時代的な武器も、普通に使えてしまう。
(といって、ボクがこれを使えるわけはないんだけど)
ナオは少しだけ気持ちを引き締めて、以前取り寄せた絶縁仕様のフードつきコートを身に纏った。
現場での思考加速に備えて、エネルギー源となるキャンディやジェル、ラムネなどをポケットに補充する。
「悪ぃな、本当は俺たちがどうにかするべき事なんだが……」
「これは仕方ない」
「すぐ外で待機してる。何かあったら呼べ」
「また命令」
「保険、ってやつだ」
ギンジはどこか申し訳なさそうに小さく笑い「気をつけてな」と言った。
「じゃ、行ってくるね」
どこか心配そうにナオを見つめるハルミに一声かけ、ナオは部屋を後にした。