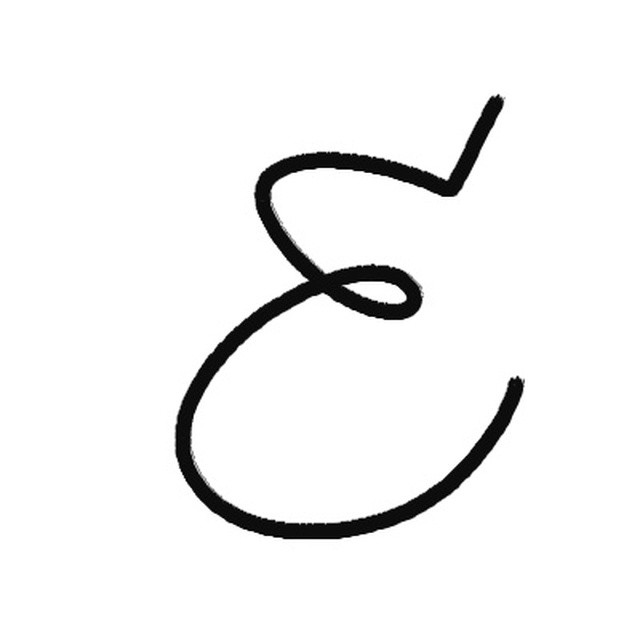第2話
文字数 6,264文字
グッドウィルの異変に最初に気づいたのは、クラスメイトのジミーだった。彼女は近所に住む赤髪の女の子で、三つ編みのおさげがトレードマークだ。言ってしまえば、彼女はグッドウィルのお世話がかりだった。会話が成り立ちづらいグッドウィルに話しかけてくれる唯一の友達で、心優しい彼女は同じクラスで嫌厭されているグッドウィルを気にかけていた。登校中のグッドウィルを見つけると彼女は隣へ駆け寄った。
「あら、おはようグッドウィル。今日は遅刻じゃないのね」
「そうだね、いつもより二十分早いだけだけど」
ジミーは眉をひそめて、グッドウィルの顔を覗く。さも当たり前かのように言うグッドウィルに違和感があった。
「…あなた、いつも何時に登校していたか覚えてる?」
「九時半頃だったかな」
「じゃあもう一個質問。あなた、今朝はどんなだった?」
「いつも通りだよ。八時に起きて朝食、その後にリュックに教科書を入れたりしてから家を出てここまで歩いてきたんだよ」
ジミーはその問答の中ですぐに違和感の正体に気がついた。会話に知性を感じるのだ。きちんとした言葉遣いは最初に気がついたが、ある一定の時点から今までの時間を答えられることはなかったし、今まで自分の行動を端的に述べるなんてことも到底できなかった。ジミーが最後に話をしたのは昨日のお昼頃で、バルスに階段下の人目が届きにくい場所で暴力を振るわれていたのを止めた時だった。
「どうも一晩のうちに賢くなったみたいね」
一方、グッドウィルはというとなにも変化を感じてはいないわけでなかった。ぼんやりと霞のかかった思考領域が晴れているという感覚があり、それはいつもよりも鮮明な思考として現れていた。道端の花が綺麗だとか、通りすがりの老人が顔馴染みの気がして、もしかしたら以前に会っていたかもしれないだとか、そんな程度のものだがそれもグッドウィルにとっては高度なものであったのだ。
しかしそうはいっても、やはり自身への認識は今までの自分に尾を引いて不変であった。自身の成長を知覚する時は決まって進行形ではなく過去形で語られるものなのだ。ちょうど赤ん坊が自身をメタ的な視点から俯瞰することもなく、知らぬ間に成長するように、グッドウィルは己の成長に気づくことなく賢くなった。その振れ幅の小さな知能向上に気づけなかったのが故に、ジミーの言葉に驚くことになった。
「僕が賢くなってるって?どうしてそう思うんだ?」
「どうもこうもないわよ。あなた自分でわからないの?傍目から見てもいつもと違うことは明らかなのに」
「いつもと違うこと…そういえば今日は寄り道せずにまっすぐ学校に来たんだ。普段なら気になった花を摘んだりしてたんだけど、そう思うよりも先に学校へ行かなきゃって思ったんだ。どうして僕はあんなにも衝動的だったんだろうね」
「わからないことだらけね。まあ話は詳しく聞くわ。とりあえず教室へ向かいましょ」
この日の学校は苦労の連続となった。クラスはたちまちグッドウィルの話題で持ちきりになった。隣の席の人、そのまた隣の席の人、その前後左右といった具合に、グッドウィルのことがクラス全員に広まるのに時間はかからなかった。思いもよらなかったのは中にはグッドウィルのことを格好良いといった評価する声まで現れたことだった。休み時間は次から次へとくる訪問者の対応に追われたが、それは幸せな不幸せで、クラスメイトとのほぼ初めての会話はとても新鮮だった。
「本当にあのグッドウィルなの?」
「なんだか雰囲気が変わったね」
「何があったの?」
突如として人気者になったグッドウィルをジミーは少し外から見ていた。
「ちょっとみんな、グッドウィルは忙しいの。ほら行くわよ」
今や必要のない案内人の役割をこなそうと、ジミーは彼の腕を取るといつものように次の授業に連れて行くなんてこともあった。
クラスの授業はこれまでにないほどにスムーズにこなすことができた。文法や物語の読解、以前はできなかった四則演算はもちろん、割合や図形の理解、紀元前まで世界中の歴史、社会構造や政治、今までは意味をなさなかった文章の羅列を余すことなく網羅することができた。不可能から可能への転換には決まって喜びを伴うもので、放課後には勉学に没頭し、図書館で本を読み漁っては、今までぼんやりとしていた日常経験を知識として結びつけもした。
それから気になる子もできた。ジミーだ。グッドウィルは自分が自分で思っている以上に彼女が側に付き添ってくれていたことに気づくことができた。きっと彼女がいなければ、学校生活は破綻していただろう。次のクラスへ遅れず参加できたのも、生き物係の仕事を手伝ってくれ、中庭のウサギたちが死ななかったのも、当時の彼なら絶対にできなかった宿題の数々も、全て彼女のおかげなのだ。それらを思うと、彼女に対してえも言われぬ特別な感情の若芽が出るのだった。
ジミー、クラスメイト、その次に気づいたのがミザリエとチャーリーだった。その日の晩、図書館に籠ったせいでいつもより二、三時間ほど遅く自宅に帰ると、台所に母の姿を見た。いつのものかわからない洗い物をしていた。
最近はほとんど会話がなかった。何が平手打ちの原因になるかわからないグッドウィルにとっては当然だった。
「母さん」
今夜は話しかけてみることにした。うまくいくような気がしたのだ。
「今朝はサンドウィッチ、ありがとう」
作り置きのせいで冷めていたことは言わないことにした。
「体調はどう?あまりよくないって言ってたけど」
毎朝グッドウィルが起きると、机の上にはプレートと朝食が置いてある。しかし、そこに母の姿はない。朝は決まって自室に篭っているのだ。必要最低限の世話、それが食事の用意であって、それ以外は知ったことではないといった態度だった。
以前、ノックもせずに部屋に入ると、そこには朝寝髪で目の下にびっしりと隈をつけた母がベッドでうずくまっていた。その時は一度で済んだが、その時の経験を糧に部屋には近寄らないようにしていた。痛みの伴う経験が彼にとって最も効用なのは間違いなかった。グッドウィルはその時に言われた「体調が悪いから」という言葉をよく覚えていたが、いつから家族がこのような形になったのかは判断がつかなかった。
肉体労働者の父はというと、朝早くから仕事で家を出ており、日中はほとんど顔をあわせることがなかった。二重苦に挟まれながらも彼は彼なりに家庭を支えていた。グッドウィルに決して暴力を振るうことはなかったし、機能しない母の代わりにグッドウィルの世話を行い、少しでも彼の居場所であろうとした。そんなチャーリーをグッドウィルは信頼していた夜の帰りをいつも楽しみにていた。
「ママ?」
返事はなかった。とりつく島がなくて、相手の様子を窺う。彼女の目玉はまるで透明なガラスの球体のようだったが、決してビイドロ玉のような美しさはなかった。もう一度声をかけようとした。
「グッドウィル?」
母がこちらを振り返る。その目に少しだけ光が射し入った。
「あら、今日は随分おそかったのね」
グッドウィルの体は無意識に強張ってしまった。
「図書館で勉強をしてたんだ」
母は目を丸くした。返事など土台期待していなかったからだ。その様子は明らかに自分の耳を疑っていた。例えばもし、赤ん坊に語りかけているときにはっきりした言葉で明瞭に返答されると誰でも驚いてしまうだろう。同じような反応が彼女の頭の中で起きていた。
「もう一度言ってくれない?」
「放課後、学校に残って勉強してたんだ。本を読んだり、今まで習った教科書を読み直したりね」
今度はグッドウィルが発声した文章の意味を理解できた。しかし、その裏で意味するものにはまだ理解が及ばなかった。
「勉強ってそんな…それにきちんと会話も…。一体何が起こっているの?」
「僕にもよくはわからない。けれど今日はなんだかすごい頭の中がスッキリしているんだ」
彼はテーブルにつくと、今日の出来事について話した。自分の体調やジミーとの会話、授業中の全能感とさえ言えるほどの知能的成長とそれに追随する知的好奇心の向上。彼は時系列順に明確かつ簡潔に伝えた。
母は彼の話を聞きながら歓喜していた。必死に首を縦に振り、一言一句に相槌を打った。自分の息子と初めて意思の疎通を図ることができたのだ。彼女は真にグッドウィルの心と自身の心が通じ合った気がした。
午後七時、その日のウィリアム家の食卓は豪華なものになった。母は父のもとへ電話をよこすと、今日は何がなんでも早く帰ってくるようにと連絡した。その後、彼女は彼が帰ってくる前に食事を用意しなくてはとは躍起になって用意を進めた。久々に車を出して一緒に行ったスーパーではあちらこちら首を振っては、メモに目を落とすという動作を何度も繰り返していた。ここまで忙しない母をグッドウィルは見たことがなかった。久しぶりに振舞われた贅沢なテーブルの上から暖色のライトが三人を照らし、その夜は初めて会話が弾んだ。
この日を境に家庭内の不和は徐々に緩和し、夕餉の食卓では以前にはなかった暖かな雰囲気が溢れるようになった。父も毎日ではないものの早く帰るようになり、共に時間を過ごすことも増えた。
その後もグッドウィルは日々を学業に費やした。放課後、二時間は机に向かうことをルーティーンとし、その結果は学校のテストのような目に見える形ですぐに現れるようになった。その度に笑顔を見せ、「エライじゃない」と褒めてくれる母のことを思うとなお一層研鑽した。
三年後、グッドウィルが中学生になる頃には、一般的な高校生の学習範囲を全てマスターしていた。一年と経たずに今までの不足を補填し、もう二年で本来身の丈には合わない分野、範囲へと手を伸ばしていた。
この頃のグッドウィルは学校が退屈で仕方なかった。学校の中ではなにもかもが学習したものばかりで、学内テストでは全てが満点、学内順位は一位を総なめにした。小学生五年生の頃のように未知との出会いに心踊ることは無くなり、授業は彼をただ無意味に縛るものとなった。友人に関しても同じだった。今まで友好関係を築いてきた友達のほとんどとは、会話をすればするほどその低脳ぶりと退屈な人間性が透けて見えてしかたがなくて自然と疎遠になった。その結果、以前とは違った一人の高校生活となったが、それに不満は感じなかった。
学校生活を唯一彩るものが放課後のルーティーンだった。未知が既知となった今、その楽しみは全く違う方向へと変化した。その変化とは、その時間をジミーと共に過ごすようになったことだ。それほど大きくない街に住む二人は小学生から同じ環境にあり、ある日、ジミーから勉強を教えてくれと頼まれてから週に三日ほど指導をしていた。
とある日、いつものように図書館の学習スペースの隅で机を隣り合わせにしてテキストを解いている時だった。いつからか沸いた疑問を解くために彼は胸の内を明かしてみることにした。
「ジミー、君に聞いてみたいことがあるんだ」
ジミーは手を止めてグッドウィルの方を見て、「ええ」と返事をした。
「君は今まで僕にたくさん良くしてくれたよね」
「ええ、まあ、そうかもね」
「僕がまともな小学校生活を送れたのは間違いなく君のおかげだ。それにはとても感謝してる。でも一つ気がかりなことがあって、当時の君はどうして僕を手助けしようと思ったの?」
「うーん、どうしてねえ…難しい質問だわ。こう答えることにしましょう。あなたが危なっかしいと思ったからよ」
歯切れの悪く聞こえた彼女の言葉を脳味噌に落とし込んでみる。それからこう尋ねた。
「じゃあもう一つ、君は僕のことをどう思ってるの?」
「……」
妙な時間が流れる。彼女は少し間を置いてからばつの悪そうな顔で言った。
「とても賢いと思ってるわ。ちいさい頃では考えられないくらいにね。何かあったのかって心配になる程よ」
グッドウィルにとって彼女と過ごす時間は心地よかった。ほんのりと暖かさを帯びて、今までのグッドウィルの人生にはなかった何かしらを感じ取らせてくれ、彼女と接すると彼の中では何かが育っていくのような感覚があった。それが何かは彼にはわからなかったが、それは良いという言葉で表現するだけではあまりにも複雑で、放ってはおけないないような何かであった。
彼女の態度を何かをはぐらかし、本質から逸らそうとしているかのようだった。この問答では満足のいく答えは得られなかった彼はどこか急いたように続ける。
「自分でもなぜだかよくわからないけれど、僕は君のことを必要以上に考えてしまっている気がするんだ。手の打ちようがなかったから、こうして君に打ち明けてみることにした。ジミーは何かわからないかい?君にも同じようなことがあるんだろうか?」
今度はもっと長い沈黙だった。グッドウィルは彼女の顔を見つめ続けていたが、彼女の表情をなんと表現すればよいのかわからなかった。
「グッドウィル、あなたはなぜかわからないけれど突然賢くなって…それはもちろん良いことだわ。けれど、それは良いことばかりではなくてね。私だってわからないことだらけなの。すこし時間が欲しいわ」
彼女はこぼすように「ねえ、グッドウィル」と言うと、別れをつげて図書館を後にした。
一人残されたグッドウィルは惚けた頭で机に向かっていた。彼の頭の中を巡るのは彼女の沈黙と表情だった。賢くなったことで何かしらの不利益を彼女に与えた可能性が思い浮かんだが、それはすぐに否定した。最も彼を悩ませたのは私にもわからないと言う言葉だった。その言葉を飲み込むには、彼女の言葉はあまりにも趣旨に欠けていて、前後の文脈が破綻している。彼女が時間的猶予を得て何を考えたいのかすらも、彼にはわからなかった。
帰宅する前にジミーの座っていた椅子を片したが重く感じた。
三週間が過ぎた。あの日以来、ジミーが放課後に図書室へ姿を現すことはなく、気がつくとグッドウィルも足が遠のいていた。廊下ですれ違った時には挨拶を無視され、同じクラスでも話すことはなかった。次の授業の準備と教室への案内も無くなってしまい、異変があったのは明らかだ。もちろんグッドウィルは思考をとめどなく回し続けたが、何一つ成果はなかった。足掛かりを得るのはさらに一週間後で、身近なところだった。
深夜、グッドウィルが自室で就寝しようとしていると、どこからか物音がした。しばらく無視をしていたがどうにも止みそうにないから、出所を探ってみることにした。ところがその詮索はすぐに中止となった。なぜならその音が夫婦部屋から聞こえる音だったからだ。グッドウィルは男女の色恋や情事は知識としては当然知っていたが、もちろん自身に経験はなかった。ここ数年、良好に向かっていた夫婦は大きな山を越えてさらに固い愛を結んでいたことは気づいていたが、その場面に出くわすのは初めてだった。
思春期の青年にこの情事が与える影響は十二分で、今までグッドウィルの中で眠っていた異性に対する興味というのを遅咲きで開花させた。そして当然その対象はジミーへと向かい、始めて自分が彼女に恋愛感情を抱いているのではないかという結論を導き出した。眠気などとうに忘れ去ったグッドウィルが最初に行ったのは、溢れた知識欲を抑えるために心理学関する書物を探すことだった。
そうして計画を企てることになった。