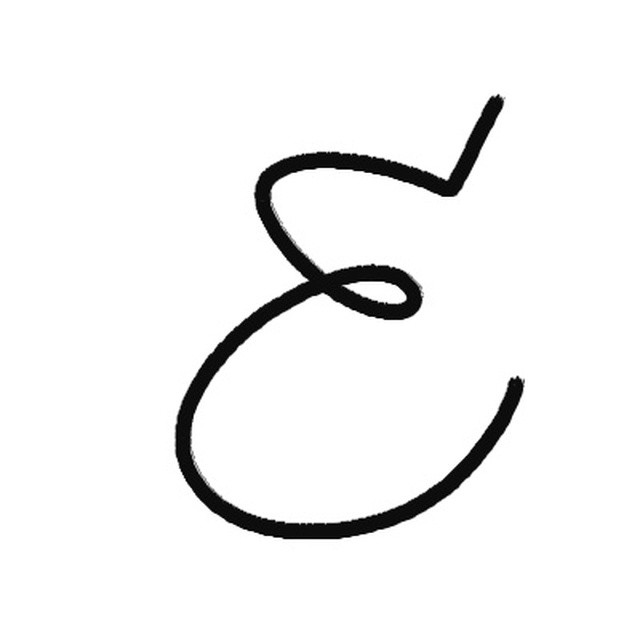第3話
文字数 10,697文字
よく晴れた日曜日であった。グッドウィルは母と共にハイキングに来ていた。頬かすめるそよ風が気持ちよくて、木々に止まった雛鳥たちがぴいぴいと鳴いている。
しばらく歩くと高い木々で足元が翳り始めた。
「休憩が必要かい?僕はもっと早く行けるんだけど」
心配の言葉をかけるが言葉だけに過ぎず、その足は遅くなる様子はなかった。
「私ももう歳なのね。あまり遠くへは行かないで。一緒に行きましょう」
乾いて固まった地面を進む。勾配のある坂を登り、一際地面が盛り上がった場所の上に立つ。その先が真暗闇の洞窟がひっそりとあった。
「見て、母さん。あんなところに洞窟があるよ。天然なのかな?興味が湧いてくるね。ちょっと入ってみない?」
「いいんだけど、ちょっとだけ休憩してからにしよう」
母はリュックからボトルを出すと水分補給をし、五分ほど休憩をした。
父は連れてこなかった。必要がないし連れてくると何かと面倒だと判断したからだった。
二人は暗くジメジメとした洞窟へと入る。中はやはり冷えていた。
「ライトを持ってきてるなんて用意がいいわね、グッドウィル」
グッドウィルはスタスタと歩いたために、二、三分もせずに奥まで到着した。
「分かれ道もなかったし、小さい泉があるだけみたいね。綺麗に光っててなんだか神秘的じゃない」
おそらく光に反応する苔のせいだよ、とグッドウィルは心の中で呟く。
全てがグッドウィルの狙い通りだった。ここまでの用意に時間はそうかからなかった。怪我をしたから救助してくれ、気になる洞窟があるから一緒に調査にきてくれ、そういうシナリオも考慮した。あの日以降、グッドウィルは時々洞窟に訪れては調査をしており、成果こそなかったものの、おかげで座標、周辺環境、構造、生息生物、気温や湿度、過去の地質学的、考古学的または神話学的な文献、全てがグッドウィルの頭の中だった。そうはいっても慎重に慎重を重ねて、前日の下見は怠らなかったのだが。
母は泉を覗き込んで観察していた。
グッドウィルが彼女の後ろに立つと、いとも容易く母は泉の中へ落とされるのだった。
よくやりましたね。
頭の中でそう響いた気がした。
一人帰宅したグッドウィルによって捜索状が出され、警察は最後に接触していたグッドウィルを調査することになった。彼の主張は自分が目を離した隙に彼女が一人でどこかへ行ってしまったというもので、少々不可解な点はあるものの、物証がなく死体も見つからないということで、この一件は不幸な事故、あるいは一過性の高い自殺として処理されることとなった。グッドウィルの近辺が落ち着くには少し時間がかかったが、こうして計画は第二段階へと移行することになった。
自分の母親を殺めるという行いをしたグッドウィルが最初に行ったのは、過去の自分の行いの重大さに気づき猛省するなどということではなく、単なる仮説の検証と状況の整理だった。グッドウィルは机に向かい、白紙を取り出すとさらさらとに書き上げていく。
まずは現在の状況。後日、母を一人探しに行く健気で可哀想な息子を装って山に入り、死体が浮かび上がってきていないことを確認した。今回の犯行で注力したのはできる限り一度目の再現をすることだ。ティムとバルスの場合、死体が発見されていないことから察するに泉に沈んでいる。水に突き落とされた人間は条件が揃えば膝丈ほどの水量でも殺すことができるが、死体を沈める場合には少し工夫を施す必要がある。今回は母を落としはしたが死には至らなかったため、無理矢理押し込んで溺死させ、その後、母のリュックに重しとなるようなものを入れた。万が一死体が腐敗性ガスによって上昇してくる可能性を考慮し、確認へ向かったが結果は良好だった。もう少し効率的な方法もあったかもしれないが、一度目の再現に重点を置いた結果だった。
次に仮説一の妖精の存否について。一度目の時の記憶はかなり曖昧なもので、ほとんど無いに等しかった。ティムとバルスともに行ったことでさえ、周りの証言がないとわからなかったほどだ。そんな中唯一覚えていたのが妖精との会話だった。泉に人を落とせばその人の知識を得るという会話が頭の中には残っていたのだ。当の本人だがこれについては疑わしく思っており、幼い自分が作り上げた妄想だと考えていた。しかしその一方で、妙に印象的なこの会話と他人から聞いた状況を合わせるに、やはりこの方法で自分の知能が上昇したと認めざるを得なくもあった。これがこの計画で検証したかった仮説一である。
確かにあの時、頭の中で声が聞こえた気がした。しかし、あの声は過度な興奮状態に陥った自身が作り出した幻聴という説を拭いきれず、妖精の実否は分からずじまいに終わった。
次に仮説二の愛の獲得について。こちらが本命であって、仮説一は副次的なものだ。仮説一が真だった場合、母を落とすことで「愛」という知識を得られるのではないかというのが仮説二だ。一度目はおそらく二人の友人(話を聞くに友人ではないが)の知識を得たいというのが叶えられたのであり、これに則って父を愛する母を落とすことで愛の正体を知ることができるのではないかというのが今回の狙いだった。
これは予想していたことだが、愛を知るという目的があまりにも抽象的で、事後目に見えてわかる変化が得られなかった。殺人後から約一週間観察を行ったが、自身に何かしらの変化は感じられなかった。こちらについては第二段階で確認することになるだろう。
一通りメモを書き終えると、初めからざっと目を通していく。全て読み終えるとグッドウィルは天井を見上げた。こうして目の前に自分の悪行を理路整然と書き上げてみると、グッドウィルの胸には罪の意識が湧いて出た。けれどそれは脆くて希薄かつ反省を含まないもので、彼の思う罪の意識とは、自分は刑法に反して罰を受けるに値する行為を行い、それを今後隠し通さなければならないというひどく実用的な罪の意識だった。
グッドウィルは我ながらとても傲慢だと感じた。彼女には彼女の罪があり、幸い顔周辺にはないが、それらは今でもずっと消えずに彼の肉体に刻まれている。怨恨が動機ならまだ筋も通っているのだが、そんなものは微塵もなかった。旧約聖書「創世記」の中でイブが蛇に唆されて知恵の実を食べたが、グッドウィルが誘われたのもやはり神秘を孕み、全能にさえも届きうる知恵だった。法知識を備えたグッドウィルが、殺人を悪いことという簡単なことをわかっていないわけはない。ただそれよりも知的好奇心が優っただけのことだった。
グッドウィルは立ち上って一息つくと、紙をくしゃくしゃにして暖炉へと投げ捨てた。
母の殺人から二週間後、彼は登校を再開した。事件が発覚してからは学校に休みを申請しており、この日から何食わぬ顔でまた学校生活を過ごし始めるはずだった。学校に着いて早々、名前は忘れてしまったが、同じクラスである女子生徒にこう話しかけられた。
「ねえグッドウィル、お母さんのことは…その…残念だったわね。けれど、安心して。私たちはあなたの味方で、あなたは一人じゃないわ」
休みの理由は教師のみに伝えていたが、どういうわけかクラス全体に事件のことは広まっていた。しかし、それはそれで後に都合が良かった。
「ああ、ありがとう」
こんな時は感情に従順になって慰めるのかと軽く軽蔑すると、ここではないと思いつつも練習通り涙を流した。
再開した学校生活で彼は一つのことを心がけた。それは意図的にジミーを避けることだった。といっても極力彼女と出会って会話が発生しないよう立ち回るだけで、要は相手を焦らし、機会を待つだけことだった。
学校が始まってから三日間、教室やカフェテリア隣に来た彼女をグッドウィルは「少し体調が悪くて」とだけ言い、その場を去るようにした。そして翌日席を開けたグッドウィルが戻ってくると、机の上にメモが貼ってあり、そこには「今日の放課後、図書館で待ってる。話がしたいの。ジミー」と書いてあった。
放課後、二人はいつも図書館で落ち合い、以前のように自学スペースの隅で机を隣合わせに座った。先に口を開いたのはジミーだった。
「お母さんのこと、聞いたわ。大変だったわね。その…体調はどう?」
「悪くはないよ」とあたかも悪そうに言う。
「そう…お父さんもさぞ辛かったでしょうね」
グッドウィルは黙りこむ。いつも静かな図書館だが今日は恐怖を感じるほどで、その沈黙がさらに彼女を追い詰める。
「私はね、グッドウィル、貴方を心配してたのよ。なかなかじっくり話す機会がなかったから…」
グッドウィルは機会を伺っている。
「学校でも元気ないみたいだし…そりゃああんなことがあったのだから元気出せって言う方が無理だけど」
相槌を軽く一回返すと、再び沈黙が降りた。すると今度はグッドウィルが口を開いた。
「ごめん、ジミー、なんて言ったらいいのか…」
グッドウィルは彼女の真正面に捉えて、まっすぐと目を見つめる。
「どうやらこういう時の僕はとても無力らしい」
ジミーを見つめる瞳から涙を流した。
「今だけでいい…今だけでいいから…僕のそばにいてくれないか」
グッドウィルがそう言い切るよりも前に、ジミーはグッドウィルを抱きしめた。力強く抱きしめられた彼女の腕に応えるように、グッドウィルは彼女の少し小さな体を抱きしめ返した。
「もちろんよ」
震える声でジミーが言った。顔は見えないが、泣いているのがわかった。
そうして彼らは数分で、永遠とも思えるような濃密な時間を過ごした。抱きしめた彼女の体はとても暖かかった。
泣き止んだ彼らは己の感情を余す所なく吐露しあった。何もかもグッドウィルの思い通りだった。まず接触を減らして不安を増大させ、さらにようやくの会話で本心を確認できるというカタルシスと自分を頼っているというアンダードッグ効果を引き起こせば良いだけのことだと考えていた。結局のところ心というのは信号に過ぎないのだとつくづく感じた。
そこからはとんとん拍子に事が進んだ。徐々に距離を縮めていった彼らは交際を始めることとなった。告白したのはジミーからで、回答は文句なしのイエスだった。こうしてグッドウィルは晴れて退屈の学校生活から一転し、愛する彼女と共に過ごす最高の学園生活を送る事となった。
中学校を卒業後、地方の高校へ進学するとさらに勉学に注力した。この段階ですでに高校科目もマスターしており、暇を持て余した彼が次に選んだ教材は法学、社会学、経済学、言語学、心理学、人間科学などあらゆる分野の大学参考書だった。中でも彼の興味を引いたのは、生物学だった。自身の知能向上の手がかりになるのではと思い、人間の脳の構造や知識の入手方法、そもそも知識そのものが何であるのかをなどを調べてきた。その関心の延長線上にあったのが生物学だった。
高校を卒業すると同時に有名大学へと進学した。大学では生物学を専攻し、人体の構造をより専門的に研究していくことにした。大学から給与型の奨学金を受け取りながら通学となり、通学時間を考慮した結果、大学近辺へ引っ越すこととなった。
ジミーは高校を卒業後、実家のパン屋で働きながら家の手伝いをしていた。二人の交際はなお続いていたが、グッドウィルの遠方への引っ越しにより、時間的、空間的距離ができてしまうのは仕方のないことだった。会う頻度はほぼ毎日から二、三ヶ月に一度に下がってしまったが、これは二人が話し合って下した決断であった。初めは彼女の感情を揺れてしまったが、将来の見通しが立ち次第同棲を始めるという約束を交わした二人の仲は雨降って地固まることとなった。
満を持して始まった大学初日、配属先となる研究所の教授アロガンと顔合わせをした。白髪の混じった口髭、少し後退した額に厳めしい顔つきはいかにも学者様といった風貌だった。コツコツと革靴を鳴らして教室に入室すると、彼は第一回目の授業としてオリエンテーションを始めた。教室と研究室を併設したクラスには三十人ほどが席に座っていた。
「私はこの学校の名誉教授アロガンだ。取り扱うものは授業によって多少異なってくるが、主として生物学を専門としている。今学期、このクラスの担当となった。よろしく頼む」
アロガンは話を始めた。
「まず初めに生物学を通して何を学びたいのかを君らに問うておきたい。その答えを己の中に持つものにとって、この四年間は非常に有意義なものになるだろう。またまだその答えを持たぬ者もそれを探求する努力を決して怠らぬよう日頃から己のセンサーの調整をしていてほしい。…ウィリアム、ウィリアムグッドウィルはいるかね?」
グッドウィルは席を立ち、返事をする。
「君が生物学を学ぶ目的は何かね?」
アロガンの視線には大きな期待が含まれていた。
「私の目的は主に脳の構造を理解し、知識とは何かを解き明かすことです」
「なるほど、脳科学的観点からみた知識か、良い答えだ」
アロガンは話を続ける。アロガンの目は再びクラス全体へと語る。
「私は学習の目的を見つけろと言ったが、そもそもまず生物学とはなにを学ぶのかを理解しなくてはならない。これもまた様々な言いようがあるが、私なりの言葉で表現するなら、つまるところ『生命』は何かを追求し、その根底にある共通原理を学ぶ学問だ。この学問には多様な切り口がある。生物を系統的に分類する分類学、進化を研究する進化学、生態を解き明かす生態学、行動を分析、研究する行動学。生体を対象にその仕組みを解明する生化学、生理学、生命の誕生や器官形成を探る発生学、遺伝子の役割を解明する遺伝子学、細胞を対象とする細胞生物学や分子生物学などの分野があるのだが…」
授業が終わると、教授はグッドウィルへ近寄った。
「グッドウィルだったな。これからよろしく頼む」
アロガンは力強くグッドウィルの手を握った。
「よろしくお願いします」
「初めての授業はどうだったかな?」
「今日の授業はまだ導入に過ぎません。早く専門的に学んでいきたいです」
「そうかそうか、それはよろしい限りだ。時に風の噂で聞いたのだが、君は入学テストで全ての科目でほぼ満点を取り、主席で入学したそうじゃないか」
「すごいことではありませんよ。要はいかに知識を持っているかですからね」
「そう簡単にできることではないさ。…そんな君に似合いの場所があるのだが興味ないかね?」
教授の話を聞くにこしたことはない、そう思ったグッドウィルが同意すると、アロガンは「立ち話もなんだから」と、二人はカフェテリアへ行くことになった。
アロガンが二人分のコーヒーを注文すると、空いている席に座った。かなり広く清掃の行き届いたカフェテリアだった。コーヒーを一口啜るとアロガンが言う。
「先ほどの話なのだがね、今、私の研究室では君の学びたがっていた脳を研究しているんだ。誰もが入れるわけではない。私が選んだ少数精鋭のグループだ。そこでは記憶や学習、予測、思考、言語などあらゆる脳の高次認知機能の仕組みを解き明かそうとしている。そこで提案なのだが、このグループに参加しないか?」
グッドウィルに断る理由はなく、むしろ成績評価につながるならと喜んで引受けた。事がすんなりと進むと、アロガンは目に見えて喜んだ。
「ならば早速案内しよう」
そう言って、立ち上がった教授に疑問を持った。
「申請書などは書かなくて良いのでしょうか?」
「いい、いい、そんなものは。それよりも君の研究部屋へと行こう」
案内されたのは『アロガン教授第二研究室』と書かれた部屋だった。中はそこそこの広さで、研究室というよりもすこし生活感のある勉強部屋といった様相だった。入って左手には壁一面に本棚が並んでおり、その本棚に向き合うような形で部屋の中央に質素なデスクとパソコンが置いてあった。部屋の右半分は給湯室のようになっており、小さなシンクや冷蔵庫、ポットなどが置いてあった。
「ここには選りすぐりの専門書が揃っているし、またすぐそこのパソコンからアクセスすれば、私の権限で最新の論文なども閲覧できる。監督者を付けられない都合上、どうしてもこの部屋での高度な実験は不可能だが、座学にはうってつけの環境というわけだな。実験をしたいときは悪いが今日のクラスで使用した教室で行ってくれ。ここにある備品なら好きに使ってくれて構わない。隣は私の部屋になっているから、私がいる時ならいつでも呼んでくれたまえ」
アロガンは部屋を歩きまりながら、楽しそうに話す。
「それから今後二、三ヶ月に一度ほどのペースで進捗を提出してくれ。そこまで慎重になる必要はないが、何をしているのかは把握しておきたいからな」
グッドウィルの正面に立ち止まると、自慢の髭をいじりながら尋ねた。
「さて、ここまでで質問はあるか?」
「…他の研究者たちに挨拶することは可能ですか?」
「…残念ながらそれは無理だな」
「どうしてかお聞かせ願えますか」
「彼らは忙しいのだ。彼らはそれぞれのタスクを抱えている。ここ最近はかなり躍起になっているようだから今日のうちに会うのは難しいだろう。また機会があれば紹介しよう。他に質問は?」
「いえ」
グッドウィルは胸の内に浮かんだ考えを押し込んで言った。
「では早速今日から研究に取り組んでくれたまえ。私はこれから会議だから、ここらでな」
「今日からですか?」
「嫌と言うなら構わない。善は急げという話さ」
アロガンはやたらとうるさい革靴をコツコツと鳴らすと、扉を開けて出ていった。
グッドウィルは椅子に腰掛けると、さっそくパソコンを起動した。研究内容はすでに目処が立っていて、それに関しては問題なかった。それよりも気がかりなのはアロガンだった。小さな違和感だが、突き詰めるに値しないし、今はこの環境を有効活用したほうが有益だとも思えた。グッドウィルは当面の自説を検証し始めた。
結局、その日はアロガンには会うことなく帰宅することにした。午後七時、帰宅したグッドウィルは食事を済ましてシャワーから出たとき、彼の携帯が鳴った。時刻を確認し、次に画面に出た名前を確認すると携帯を耳にあてる。
「やあジミー、そろそろ電話が来る頃かと思っていたよ」
「私もそろそろあなたが予想できるように頃じゃないかと予想してたところよ」
「その調子も相変わらずだね」
「引越ししてからの電話はほぼこの時間よ。あなたのことだから頭に入っていないわけないわ。それで、大学はどうだった?」
「まずまずってところだな。どうやら僕は有望株らしいよ」
「有能株?」
「教授にスカウトされてね。その教授のお膝元で研究することになったんだ」
「さすがといったところなのかしらね」
「まあうまくやるさ。これから忙しくなると思うんだけど、悪く思わないでくれよ。君と同じくらい研究も大切にしたいんだ」
「ええわかってるわ。お互いの生活があるものね。それにこっちだって忙しくなりそうだしね。私は声が聞けて満足よ」
しばらく何の意味のない会話を繰り広げると、二人は別れを告げて電話を切った。引越ししてから日課となっていたこの通話は二時間、一時間、三十分とここ最近徐々に通話時間が短くなってきていた。日課が形骸化しつつあることにグッドウィルは嬉しくもやや悲しくもあった。今一度自身の心情をまとめてみる。その時はそう遠くないだろうという予想に行き着くのは当然だった。
アロガンの元で研究を始めてから二ヶ月が過ぎた。研究は構想の段階までは順調だったが、突如としてブレーキをかけられることとなった。
「グッドウィル、今日は本報告の日なのだが、準備の程はいかがかな?」
土曜日の昼過ぎ、研究室第二へノックもせずに入ってきたアロガンはグッドウィルの背中からそう話しかけると、机へ近寄った。今日のアロガンは顔には教授の風貌が宿っていた。グッドウィルは資料を手渡すと、近くの椅子をアロガンのために持ってくる。
「前から進めていた神経伝達回路を強化する案についてなんですが、ようやく目処が立ってきました。僕が注目したのはニューロンの分化です」
アロガンは老眼鏡を鼻にかけると、ただ黙って資料に目を通していく。時々眼鏡越しにグッドウィルの顔をのぞいていた。
「前にも話した通り、この研究の出発点は知識とはなにか、そして知識の仕組みを解明することで人為的にそれを強化することができるのではないかです。そしてこの問いに関する解答が先ほど話したニューロンの分化です。従来の研究でニューロンが人間の高次機能に大きく関与していることは明白でした。成人の海馬では、どんなに歳をとっても新しくニューロンが生み出されつづけていて、学習などで海馬の活動が高まると、新生ニューロンの数が増加することが報告されていましたが、この仕組みについては全く不明でした。今回僕が発見したのは海馬にシータ波が伝わることでニューロン前駆細胞が刺激され、ニューロンへの分化が促進されるということです」
アロガンの顔は説明が進むにつれ、すこしずつ厳たるものになっていった。
「まずは実験方法からです。実験ではマウスから海馬を含むスライスを作製し、電極によりシータ波刺激を加えました。すると、海馬にあるGABA性ニューロンが興奮し、興奮性GABAの入力を受けて、ニューロン前駆細胞にカルシウム流入反応が起きることがわかりました。このカルシウム流入反応が引き金となって、ニューロンへの分化にスイッチを入れる転写因子の発現量が増加し、最終的に新たなニューロンの数が増加することがわかったのです」
「…なるほど。それで結論は?」
「いわゆる実行機能の低下を防げるかもしれないということです。人間の行動を制御する高次の認知スキルを老化させずに維持できれば、賢明な判断をより早く下せるようになり、集中力と記憶力が向上することが見込めます。もしかすると、脳を若返らせるということも夢ではありません。またうつ病などの精神病患者では海馬の新生ニューロン数も低下することがわかっています。となると、そういった疾患に対する薬剤としての活用も可能かもしれません」
アロガンはしばらく黙っていた。何度か資料をめくり直し、机にパタンと投げ捨てると、大きなため息をついた。
「簡潔に言おう。君にはがっかりだな。もう少し優秀な生徒かと思っていたよ」
彼の一言で部屋の空気は一気に支配され、何倍にも重さになってグッドウィルに降りかかった。
「具体的にどこに不足があるか教えていただけますか」
無意識に体が身構えていたグッドウィルは敵意を含んだ声色で尋ねた。
「ニューロン分化の仕組みを理論的に説明したところは褒めてやろう。確かにその解明は検証の余地があるかもしれん。もちろん詳しく見てからだが。だが、実行機能が向上するという仮説は抽象的かつ曖昧すぎる。君は実行機能という人間の賢さの一つに焦点に当てたに過ぎないんだ。人間の脳の中に細胞がどれほどあって、一つの機能のために何種類の細胞が作用していると思っている。賢さの要素一つを上げて、人間が賢くなるというのは早計だろう。単語こそ立派なもんだが、すこし空論すぎるな」
このようなアロガンをこの二ヶ月間で一度も見たことなかった。初日に会ったアロガンとはまるで別人だった。眉間に寄った皺、極端に曲がった口角、獲物を狩る老獅子のように鋭く冷酷な眼。グッドウィルを見つめるアロガンは、高圧や威圧という言葉に形を与えたかのようだった。
「確かに結論に根拠はありませんが、それはあくまで可能性の話を…」
アロガンは話を聞く素振りを一切見せなかった。
「課題はまだまだある。仮に君の仮説を実行したとして、説を立証するために被験者の健康と環境的、精神的ストレスをも管理する必要があるのはわかっているのか?ストレスは脳組織を老化させる。血流で運ばれるグルコース、ビタミン、ミネラル、脂肪、アミノ酸、電解質などの栄養素は脳にとって欠かせないものだ。当然、実験が長期化するなら老化による脳細胞の減少も考慮しないといけない。つまりだな、ニューロンが減る方法はいくらでもあるのに、簡単に検証できるわけがないだろう?マウスですら容易ではないのに人間でなんて、土台無理な話だ」
「それはそうですが、それを可能かどうか判断していくための報告であって…」
「それにだ、君は脳が若返る可能性もあると表現したが、それはどの年齢を対象にした話だ?仮に若年者の脳でこの実験を行う場合、それ以上の脳のスペックを強制的に与えるようなものだ。どう言った効果が得られるかわからないし、それこそ神の所業だとわかっているのか?…いいか。君はわかっていないようだから教えておく。今、君は小学校で自由研究を提出しろと言われているわけじゃない。権威あるアロガンのもとで、研究成果を挙げろと言われているのだ。できるかもしれない、これから考えるなんて不確定性のあるものは望んではいない。必要なのは確実と完璧だ。こんなものでは許可は下ろせない」
「しかし…」
「聞こえんのか。却下だと言っているのだ」
アロガンは一際大きな一言で会話を継続する意思がないことを示した。一言で場を制されてしまったが、グッドウィルは当然納得できなかった。アロガンはため息混じりに続ける。
「研究自体は悪い線はいっていない。だが、一度優秀な人間のもとで経験を積んだ方が良いことも確かだろう。この研究は私が引き継ごう。今後しばらくは、私がこの研究の主任となって進め、君は私のヘルプをこなしていってもらおう。それで良いかな?」
グッドウィルの顔から滲み出ている答えを受け取ったアロガンは手を突き出して彼を制した。
「私は否定の言葉が聞きたいのではない。良いか、これは君のために、そしてこれから失敗するであろう研究のために提案しているのだ。本来なら私に断られた地点で君の研究は終わっている。それを私とともに復活させ、さらなるものへ昇華させようといっているのだ。わかったな?」
大きな権威のもとにグッドウィルは下るほかなかった。アロガンは満足そうに頷くと、今日は帰るようにと伝えた。
帰り際、グッドウィルは資料とデータは他にないのかと尋ねられた。それだけだと答えると、グッドウィルはアロガンの研究室を後にした。