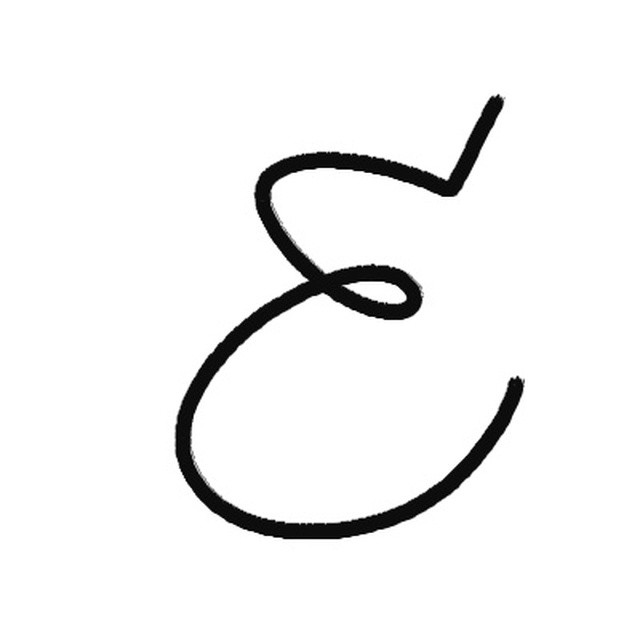第3話
文字数 1,713文字
街ゆく爆弾魔
永見エルマ
翌日も昨日と同様、春風の心地良い朝だった。起床時間、身支度、扉の立て付けの悪さ、通学路、全てが昨日通りであったが、彼の心境だけは違った。講義が終わると、彼は定位置を目指す。中庭の端のベンチは、大きなイチョウと隣接する高い建物の構造上、日中ほぼ影で覆われている。涼しげな昼下がり、青年は昨日の女子生徒について考えていた。考えている、と表現しては、いかにも恋焦がれている風だが、青年は自身が恋などをできる人間ではないことを強く自覚している。彼女に対し、恋心を抱いているわけでない。がしかし、特別な感情が湧き、彼女が思考に割り込んでくるのだった。
原因については考えるまでもなく明白だった。彼女の一言をきいて思い出したあの夏。青年が見ているのは眼鏡の女子生徒ではなく、その影に見える
ああ、またなのか。
青年はベンチに身を預けて空を見上げる。羊雲が流れる今日の空はやけに高く見えた。青年はあの子のことを思い出すことにした。
高校生になった春、青年はクラスに馴染めずにいた。人と話すのが苦手だったわけでも、周りの人が自分よりも劣っているという尖った思想を持っていたわけでもない。ただあるべくして一人だった。誰だって青年のことを見ないし、青年だって誰も見ない。それに対して悲観はしていなかったし、それでよかった。しかし、一人で完結していた青年の世界に、あの子はノックもなしに入ってきた。
放課後、教室で頭を空っぽにオスカーワイルドを読んでいた時、彼女は突然話かけてきた。
「君、いつも本読んでるね。本好きなの?」
青年の言葉に詰まったが、なんとか捻り出す。その心臓は五月蝿いほどに大きかった。
「うん」
「オスカーワイルド? 知らないけど、有名な人なの?」
「まあそれなりには」
「へー、そうなんだ」
あの子は黙ってじっと表紙を見ている。
「何か用事?」
間に耐えられなかった青年の口から本音がこぼれた。
「いいや、特に。強いて言うなら、君に話かけることが用事かな」
微笑みながら言うあの子の真意が汲み取れない青年には、返す言葉が見つからなかった。見兼ねたあの子が続けて言う。
「君っていつも一人でいるよね。嫌われているってわけでもなさそうだし、なにか理由でもあるの?」
「理由なんかないよ。ただ人と話すよりも本を読むことのほうが好きで楽しいってだけだ」
青年はあの子の方を見ることができず、仕方なく机へと視線を落とす。あの子はその視線に入り込もうと、青年の正面へ回り込むと、机に向かってしゃがみ込んだ。
「じゃあ私と話すのは楽しいかな?」
あの子の薄く伸びた目が青年を覗き込むと、青年の逃げ場は消えてしまうのだった。
青年の思い出はいつもここで止まる。これが青年とあの子の出会いだった。今振り返ってみてもやはり、あの子のことを女性として意識してはいない。これは今も当時も変わらなかった。
しかし、それならなぜ覚えているのだろうと疑問が頭の中を巡る。何か思うところがあるから覚えている。青年はそんな気がしなくもないが、物珍しいただの思い出で、それ以上でも以下でもないのだといつも通り割り切った。そんなことより今はなぜ眼鏡の女子生徒があの子を思い出すのかをそちらの方を考えることにした。
そもそも彼女とあの子の間には共通点はない。僕の知っている限りにおいてだが、彼女は教室の隅でいつも本を読んでいるが、あの子はそうではなかった。きっとあの子が読んだのはあの本が最初で最後なのだろう。それに性格だって違う気がする。彼女のことにそこまで詳しいわけではないが、服装や話し方、髪型までもが違う。静かでどこか上品さを纏う雰囲気はいかにもな文学少女といった感じだ。その点、あの子はというと、元気すぎるほどで、天真爛漫を形にしたような少女だった。お喋り好きで、いつも誰かに囲まれている。そんな子だった。感心させられるほどに、二人は異なっている。
いくら分析を重ねても、結論は見えてこなかった。これも今も昔と一緒だった。
永見エルマ
翌日も昨日と同様、春風の心地良い朝だった。起床時間、身支度、扉の立て付けの悪さ、通学路、全てが昨日通りであったが、彼の心境だけは違った。講義が終わると、彼は定位置を目指す。中庭の端のベンチは、大きなイチョウと隣接する高い建物の構造上、日中ほぼ影で覆われている。涼しげな昼下がり、青年は昨日の女子生徒について考えていた。考えている、と表現しては、いかにも恋焦がれている風だが、青年は自身が恋などをできる人間ではないことを強く自覚している。彼女に対し、恋心を抱いているわけでない。がしかし、特別な感情が湧き、彼女が思考に割り込んでくるのだった。
原因については考えるまでもなく明白だった。彼女の一言をきいて思い出したあの夏。青年が見ているのは眼鏡の女子生徒ではなく、その影に見える
あの子
なのだ。正確には青年は彼女を通して見えるあの子が気がかりなのだ。いつ何時だってあの子が青年の頭の裏側にいる。ああ、またなのか。
青年はベンチに身を預けて空を見上げる。羊雲が流れる今日の空はやけに高く見えた。青年はあの子のことを思い出すことにした。
高校生になった春、青年はクラスに馴染めずにいた。人と話すのが苦手だったわけでも、周りの人が自分よりも劣っているという尖った思想を持っていたわけでもない。ただあるべくして一人だった。誰だって青年のことを見ないし、青年だって誰も見ない。それに対して悲観はしていなかったし、それでよかった。しかし、一人で完結していた青年の世界に、あの子はノックもなしに入ってきた。
放課後、教室で頭を空っぽにオスカーワイルドを読んでいた時、彼女は突然話かけてきた。
「君、いつも本読んでるね。本好きなの?」
青年の言葉に詰まったが、なんとか捻り出す。その心臓は五月蝿いほどに大きかった。
「うん」
「オスカーワイルド? 知らないけど、有名な人なの?」
「まあそれなりには」
「へー、そうなんだ」
あの子は黙ってじっと表紙を見ている。
「何か用事?」
間に耐えられなかった青年の口から本音がこぼれた。
「いいや、特に。強いて言うなら、君に話かけることが用事かな」
微笑みながら言うあの子の真意が汲み取れない青年には、返す言葉が見つからなかった。見兼ねたあの子が続けて言う。
「君っていつも一人でいるよね。嫌われているってわけでもなさそうだし、なにか理由でもあるの?」
「理由なんかないよ。ただ人と話すよりも本を読むことのほうが好きで楽しいってだけだ」
青年はあの子の方を見ることができず、仕方なく机へと視線を落とす。あの子はその視線に入り込もうと、青年の正面へ回り込むと、机に向かってしゃがみ込んだ。
「じゃあ私と話すのは楽しいかな?」
あの子の薄く伸びた目が青年を覗き込むと、青年の逃げ場は消えてしまうのだった。
青年の思い出はいつもここで止まる。これが青年とあの子の出会いだった。今振り返ってみてもやはり、あの子のことを女性として意識してはいない。これは今も当時も変わらなかった。
しかし、それならなぜ覚えているのだろうと疑問が頭の中を巡る。何か思うところがあるから覚えている。青年はそんな気がしなくもないが、物珍しいただの思い出で、それ以上でも以下でもないのだといつも通り割り切った。そんなことより今はなぜ眼鏡の女子生徒があの子を思い出すのかをそちらの方を考えることにした。
そもそも彼女とあの子の間には共通点はない。僕の知っている限りにおいてだが、彼女は教室の隅でいつも本を読んでいるが、あの子はそうではなかった。きっとあの子が読んだのはあの本が最初で最後なのだろう。それに性格だって違う気がする。彼女のことにそこまで詳しいわけではないが、服装や話し方、髪型までもが違う。静かでどこか上品さを纏う雰囲気はいかにもな文学少女といった感じだ。その点、あの子はというと、元気すぎるほどで、天真爛漫を形にしたような少女だった。お喋り好きで、いつも誰かに囲まれている。そんな子だった。感心させられるほどに、二人は異なっている。
いくら分析を重ねても、結論は見えてこなかった。これも今も昔と一緒だった。