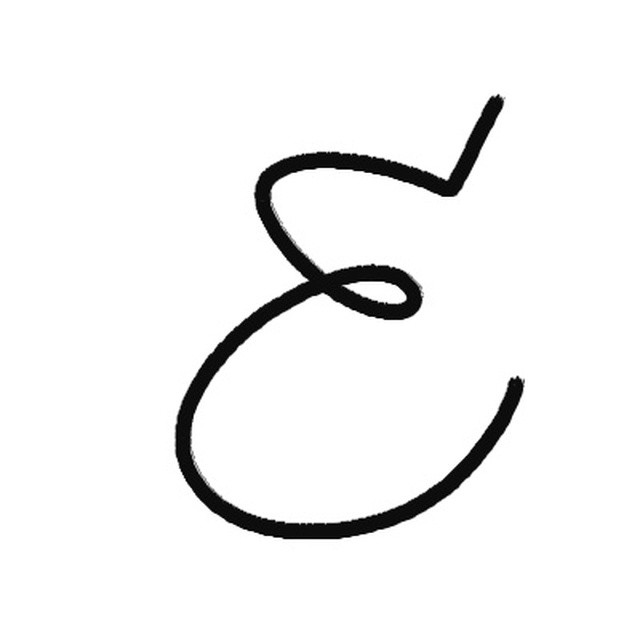第4話
文字数 1,411文字
街ゆく爆弾魔
永見エルマ
一週間後、また哲学の講義があった。この日は青年にとってはいつもと同じだった。この日が来る頃には、あの衝撃は二、三日もしないうちにすっかり頭から抜け落ちていて、眼鏡の女子生徒などもうどうでもよかった。
そもそも、青年が一方的に名前もわからない彼女に対して名前もわからない特別な感情を抱いていただけで、何か劇的な出来事が起きたわけではないのだから、至極当然のことだった。青年はそれを痛いほどに理解していた。
僕の周りで特別なことなど何も起きてはいない。人生は悲劇的なまでに非劇的なのだ。これじゃあ、あまりにも心無い。相談の相には心が無いとはよく言ったものだが、ここでもやはり心が無いようだ。それとも心が無いのは僕の方なのだろうか。あの子がいなくなってから、僕は空っぽになってしまった。いやあるいは、心奪われたと言った方が正しいのかもしれない。笑顔だとか涙だとか、憂鬱でさえも、あの頃から僕のものではなくて、まるで誰かから取ってつけたように思われてならないのだから。
青年はいつも通り角の席に座って、静かに教授の話を聞いていた。いつも通り、つまらなかった。不幸なことに、今日の授業では教授がグループを組むように指示をした。いわゆるグループディスカッションというやつだ。話すことを強制される悪しき風習に、青年は始まる前から嫌気が差していた。周囲の人が席を動かし始めてからようやく、青年もそれを真似る。
嫌なこととは往々にして重なるものだ。青年はその不幸にすぐに気がついた。机ごと振り向いた前の人物が、一週間前、栞の場所を訪ねてきた女子生徒だったのだ。
これは青年のとって紛れも無い不幸であった。得体のしれない何かに身構える必要があったからだ。
彼女と青年の間に会話はなかった。もしかしたら彼女は先週自分が話しかけたことを忘れているのではないかと感じるほどに、彼女は無機質で淡白だった。グループは出された議題について静かに話し合あう。
たった数十分の間、話し合うだけでディスカッションは終わった。しかし、何事もなくは終わらなかった。
青年はものの数十分で彼女に気を取られていた。他でもない彼女に。それは彼女が髪を耳にかけるような仕草をした時だった。どうやら彼女の癖のようで、頻繁に右手で左耳にかけていることに青年は気がついた。これはなんの変哲もない、ただの他人の癖であるし、実際青年から見れば、彼女はただの赤の他人と言って差し支えない。しかし青年とっては、彼にとっては、その赤の他人の仕草がとても重大なものだった。
あの子と全く同じなのだ。それはあの子の仕草で、あの子の癖なのだ。
ディスカッションが終わる頃には、青年はそれどころではなかった。青年は気が気でならなくて、目線も思考も全て彼女に吸い寄せられていた。
授業が終わると、彼女はグループに軽く礼を言って、風のように去った。彼女が教室を出るその一瞬まで、彼女に意識を注いでいた。
青年は心を放ったように固まって椅子に座っていた。その石化が解けるまではかなりの時間を要した。
今度も劇的なことは何一つ起きてはいなかった。しかし、青年には大きな一打であったのだ。
教室を出て、歩いて自宅へ帰る。そのわずかな時間でさえも、あの子のことを考えながら。体が、頭が、石になったかのように重かった。青年は体をベッドへ放り投げると、瞬きする間もなく眠ってしまった。
永見エルマ
一週間後、また哲学の講義があった。この日は青年にとってはいつもと同じだった。この日が来る頃には、あの衝撃は二、三日もしないうちにすっかり頭から抜け落ちていて、眼鏡の女子生徒などもうどうでもよかった。
そもそも、青年が一方的に名前もわからない彼女に対して名前もわからない特別な感情を抱いていただけで、何か劇的な出来事が起きたわけではないのだから、至極当然のことだった。青年はそれを痛いほどに理解していた。
僕の周りで特別なことなど何も起きてはいない。人生は悲劇的なまでに非劇的なのだ。これじゃあ、あまりにも心無い。相談の相には心が無いとはよく言ったものだが、ここでもやはり心が無いようだ。それとも心が無いのは僕の方なのだろうか。あの子がいなくなってから、僕は空っぽになってしまった。いやあるいは、心奪われたと言った方が正しいのかもしれない。笑顔だとか涙だとか、憂鬱でさえも、あの頃から僕のものではなくて、まるで誰かから取ってつけたように思われてならないのだから。
青年はいつも通り角の席に座って、静かに教授の話を聞いていた。いつも通り、つまらなかった。不幸なことに、今日の授業では教授がグループを組むように指示をした。いわゆるグループディスカッションというやつだ。話すことを強制される悪しき風習に、青年は始まる前から嫌気が差していた。周囲の人が席を動かし始めてからようやく、青年もそれを真似る。
嫌なこととは往々にして重なるものだ。青年はその不幸にすぐに気がついた。机ごと振り向いた前の人物が、一週間前、栞の場所を訪ねてきた女子生徒だったのだ。
これは青年のとって紛れも無い不幸であった。得体のしれない何かに身構える必要があったからだ。
彼女と青年の間に会話はなかった。もしかしたら彼女は先週自分が話しかけたことを忘れているのではないかと感じるほどに、彼女は無機質で淡白だった。グループは出された議題について静かに話し合あう。
たった数十分の間、話し合うだけでディスカッションは終わった。しかし、何事もなくは終わらなかった。
青年はものの数十分で彼女に気を取られていた。他でもない彼女に。それは彼女が髪を耳にかけるような仕草をした時だった。どうやら彼女の癖のようで、頻繁に右手で左耳にかけていることに青年は気がついた。これはなんの変哲もない、ただの他人の癖であるし、実際青年から見れば、彼女はただの赤の他人と言って差し支えない。しかし青年とっては、彼にとっては、その赤の他人の仕草がとても重大なものだった。
あの子と全く同じなのだ。それはあの子の仕草で、あの子の癖なのだ。
ディスカッションが終わる頃には、青年はそれどころではなかった。青年は気が気でならなくて、目線も思考も全て彼女に吸い寄せられていた。
授業が終わると、彼女はグループに軽く礼を言って、風のように去った。彼女が教室を出るその一瞬まで、彼女に意識を注いでいた。
青年は心を放ったように固まって椅子に座っていた。その石化が解けるまではかなりの時間を要した。
今度も劇的なことは何一つ起きてはいなかった。しかし、青年には大きな一打であったのだ。
教室を出て、歩いて自宅へ帰る。そのわずかな時間でさえも、あの子のことを考えながら。体が、頭が、石になったかのように重かった。青年は体をベッドへ放り投げると、瞬きする間もなく眠ってしまった。