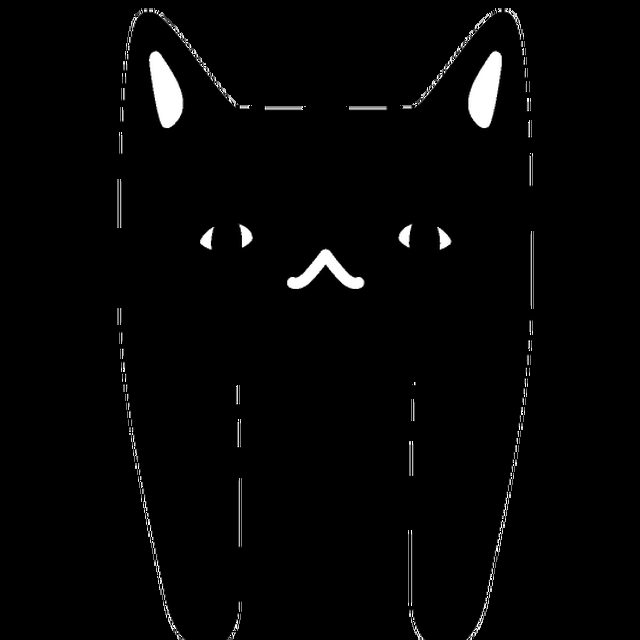第2話 春
文字数 5,314文字
ほんの数日前の終業式で年度を終えた春休み、うららかな春の陽射しを浴びながらもその眩しさに目を細める那月の耳に、柔らかく吹く風に紛れてかすかな旋律が流れ込んできた。春の柔らかな空気に浮かぶ──淡く色付く水彩。
音の出どころなんてわかっている。その姿を探し何度ものぞきに行っては、ただ誰もいない空間にグランドピアノだけを見てきた教室。構内を歩く足を速めて向かった、満開に花を咲かせた桜の木の奥。頭上からふわりと舞い落ちてくる薄桃色の花びらを見上げることもせず、那月は細く開いた窓をめいっぱいまで引き開けた。
宙を漂う花びらを巻き込んだ、ほのかな暖かさをまとった風が室内に流れ込み、音に色付く空気を絡め取る。音がやみ、そして代わりに、数ヶ月前と変わらない笑みを浮かべた男子生徒がひとり、驚いた様子もなくグランドピアノの前で顔を上げた。
「久しぶり」
「久しぶり」
那月が言葉を返すと、彼はゆっくりと窓際に近寄ってきてから、あの日と同じようにサッシに腕をかけた。
「何してんの? 今、春休みだよね」
「部活」
「へぇ、何部?」
「美術部。けど、そんなこと今はどうでもいいんだよ」
深く息をつき、どこか不満そうに発せられた那月の言葉に不思議そうに首をかしげる。軽く眉を寄せた那月に続けざま「嘘つき」と言い捨てられ、彼は何度か瞬きを繰り返してから苦笑した。
「唐突にひどくない? 何で?」
「同学年でピアノをやっている男子なんていなかった。学校にだって、本当は来てないんじゃない?」
「バレたか」
悪びれた様子もなく笑う彼に、那月は続けて口を開いた。
「そもそも、本当にこの学校の生徒なわけ?」
「あ、そこまで疑っちゃう? でも心外だな。俺、嘘なんてついてないと思うけど」
「は?」
「だって俺、同学年としか言ってなくない?」
言われてみれば、確かに……
「でも! じゃあ何で一回も、廊下とかですれ違ったりもしないんだよ」
「それについてはさっき、君が自分で言ってなかった? 学校に来てない、って」
「あ……れ? え?」と小さくつぶやく。
「ちょっと、待って……わけわかんないんだけど」
頭を抱えそうになりながら困惑する那月の姿を可笑しそうに眺めると、彼は小さなパスケースのようなものを那月に差し出した。
「じゃあ、ちょっと整理してみようか」
反射的にそれを受け取り、那月が首をかしげる。
「俺の学生証」
「新見 ……司 ?」
「俺の名前。ね? 嘘なんかついてないでしょ? 俺は正真正銘、この学校の生徒だよ。ピアノは好きで弾いてるだけだから敢えて誰かに言ってもないし、だから君の言う〝ピアノを弾く男子生徒〟に該当しないのも当然だと思わない?」
「そんなの……屁理屈じゃん」
「屁理屈だよ」
言ったところでケラケラと笑いながら言い返され、那月はぐっと口をつぐんだ。サッシに頬杖を付き直しながら、「だいたい」と司が首をひねる。
「何で君はそんなに拗ねてるわけ?」
「拗ねてないし」
「じゃあ……怒ってる?」
「怒ってもない」
「じゃあ何だよ?」
「だから、何でもないって」
不貞腐れたように言って踵を返す那月を呼び止めるように、司はその背中に口を開いた。
「君、嘘が下手だね」
「君っていうな」
勢い振り向きざま言い返してくる那月に、司は口の端を持ち上げてにやっと笑った。
「だって俺、君の名前知らないし」
その意地の悪い笑みにすら、かぁっと頬が熱くなる。
「っ……真崎那月。よろしくっ!」
「そんな怒りながらよろしくすんなよ」
ははっと笑いながら司が言ったところで、玄関ホールから部活の先輩に名前を呼ばれ、助かった、とばかりに那月は逃げるようにしてその場を走り去った。
「またね」
言って、司が軽く手を持ち上げる。桜の木の向こうに見えなくなっていく那月の背中を見送ってから、司はふと、持ち上げられた自分の手に視線を移した。
またね? 何で俺……
考えてから、ああそうか……と小さく笑った。嬉しかったんだ。カラフルだと、水彩画のようだと、そう言われたことが嬉しくて、だからきっと、あの時の彼との再会を知らず楽しみにしていたのだと。
*
新年度を迎え多くの生徒の声で久しぶりに賑わう教室で、那月は屍のように机に突っ伏していた。ぴくりとも動くことのないその脳天に、気づかわしげな声が降ってくる。
「春休みの課題、終わんなかった?」
「終わったわ。昨日めっちゃ頑張って写したわ」
投げやりに答えてから、那月はがばと顔を上げた。
「って……何でお前がここにいんだよ?!」
「今年度から復学なんだよね、俺」
「そんなこと聞いてんじゃねぇ!」
「じゃあ何? っていうかもしかして俺、君に嫌われてる?」
「だから」
那月がその先を言う前に、「君っていうな?」と司が可笑しそうに口を開いたので、那月はぐっと言葉を呑み込んだ。
「だって俺、那月に何かしたっけなあ」
腰に両手を当て、心当たりを探るように首をかしげる司に、那月はずるずると机の上に両腕を投げ出した。
だからっていきなり名前かよ? 距離感どうなってんの?
嬉しいような、けれどそう呼ばれるたび、自分の感情を自覚せざるを得ない気がして恥ずかしい。
そんなどちらともいえない、複雑な感情に緩みそうになる口元を必死で誤魔化そうとする那月の様子を気にしたふうもなく、司は続けた。
「何にせよ一年間は同じクラスなわけだし、せっかくだし俺は仲良くしたいと思ってるけど。それに、惚れてくれたんだろ?」
思いもかけない言葉に、んんっ? と一瞬思考が停止した。顔を合わせたのなんてほんの数回でしかないのに、まさかバレてるのか? いや、それならそれで、別にいいのだけれど……いや? いいのか……? そろりと見上げた視線の先で、こちらを見下ろしてくる司がしれっと笑った。
「俺のピアノ」
そっちか……と安堵するように小さく息をつきながらも、那月は投げ出した腕の間から、ごんっと机に額を打ち付けた。
同級生として日常の大半を同じ空間で過ごすようになって数週間が経ち、その間で気付いたことがある。それは──びっくりするぐらい、司はすぐに、教室から姿を消す。
とはいえ、休み時間や放課後に誰がどこで何をしていようとそれは個人の自由だし、始業のチャイムが鳴るタイミングにはしれっと教室に戻ってきているのだから、根っからのサボり癖があるというわけでもないのだろう。
名簿順に並ぶ司の席をちらと盗み見、またいないや……と那月はそっと肩をすくめた。引き戻した視線をそのまま天井に向け、目を閉じる。放課後の教室を満たすクラスメイトの喧騒の裏に、気にしなければ気にならないほどのかすかな淡い音に耳を傾け、那月はふっと小さく笑った。
「また音楽室」
つぶやくように言ってから、那月は何かを思いついたようにがばと身体を起こし、鞄をひっつかむとそのままさっさと教室を後にした。
教室が居づらいわけではなく、単に音楽室の方が落ち着くという、ただそれだけの理由だった。それが何故かを考えたことはないけれど、思い当たる節は多分にある。
家よりも、教室よりも、他のどの場所よりも、ここは静かだ。
そんなことを考えるでもなく考えながら鍵盤を叩いていた司は、廊下へ続くドアの向こうから聞こえてきた電子音に怪訝に眉を寄せ、その手を止めた。そっとピアノから離れ、躊躇うことなく一気にドアを引き開ける。そのままゆっくりと視線を落とした先、準備室のドアの前に片膝を立てて座る脳天を見下ろしながら、ちらと首をかしげた。
「盗み聞き? いい趣味してるね」
意地悪く発せられた司の言葉に何かを言い返そうとして、けれど白紙のまま廊下に投げ出されたスケッチブックと手にしたスマホに、那月はうまい言い訳も何も思い浮かばず、諦めたようにスンッ……と目を細めた。
「ごめんなさい」
「そこは素直なんだ」
ははっと笑いながら言ってくる司を見上げ、続ける。
「君の邪魔をするつもりはなかったんだけど、音消し忘れてて」
「ふぅん。で?」
「で? って……え?」
「君は君って呼ばれるのを嫌がるのに、君は俺のことを君って呼ぶの?」
「あー……えっと、何て呼ぶのが正解かわからなくて……」
「今更?」
もそもそと言ってくる那月に不思議そうに首をかしげてから、「ああ」と納得したように司は口を開いた。
「俺が休学明けで、本当なら学年1コ上なの気にしてる?」
申し訳なさそうにうなずく那月にかりかりと後ろ頭をかくと、司はよいしょ……とその隣に足を投げ出して座った。
「去年の夏前に家の方でちょっとバタついて、そのタイミングで休学した。それが落ち着いたから、そのまま辞めてもよかったんだけど、高校卒業はしとけってみんなに言われて、切りよく年度替わりから復学したってわけ」
何があったのか、気にはなるけれど聞いていいのかどうかもわからず、「そっか」とだけ言って那月は口を閉じた。
「だから……だからってのも変か。変に遠慮して距離取られんのも嫌だし、名前でいいよ。俺も前、那月って呼んだ気がするし……あ、もしかして嫌だった? 真崎の方がいいか」
急に思い出したように司に聞かれ、那月はぶんぶんと大きく首を横に振った。
「嫌じゃない。むしろ……」
「むしろ?」
「あ、いや……何でもない。那月でいい」
「そう? まぁじゃあ、ならよかった」
ふっと柔らかく笑いながら言われたその言葉を最後に、何とも居心地の悪い沈黙がその場を満たした。
どちらも何も言わないまましばらく校内の喧騒に耳にかたむけてから、「さて」とそれを破るように唐突に司が口を開いた。
「俺そろそろ帰るけど、那月は?」
言いながらその場に立ち上がる司を見上げ、「え?」と短く聞き返す。
「帰るなら一緒にどう? ってお誘い。ああそれか、盗み聞きのお詫びに飲み物くらい奢られてやってもいいけど?」
ケラケラと笑いながら言ってくる司に何度か目を瞬かせてから、苦笑する。
まぁ、クラスメイトだしな。ギクシャクしたいわけじゃないし。
そんなことを思い小さく肩を落とすと、那月は拾い上げたスケッチブックを鞄に押し込みながら口を開いた。
「いいよ、わかった。そうでもしとかないと、根に持たれそうで迷惑だ」
「一方的すぎる感情……」
不満そうに言ってから、「まぁいいや、ちょっと片してくる」と音楽室に戻っていった司は、すぐに帰りの支度も終え、廊下へと顔を出してきた。
学校を出た先にある緑道を並んで歩く司の横顔を、クロスバイクを押しながらちらと盗み見る。その位置が自分より少しだけ高いところにあり、那月は思わずその顔をじっと見上げた。
「……何?」
苦笑混じりに司に聞かれ、「いや、別に」と那月は目を逸らした。
「今日部活は? 美術部、だっけ?」
「うん。休みっていうか、絵画と立体で曜日ごとに教室の使用が分かれてるから……あっ」
「ん?」
「ちょっと待ってて」
慣れた仕草でその場にクロスバイクを止め、那月が道沿いにベンチと並んで設置された自動販売機に足を向ける。それを眺めながら司はたずねた。
「じゃあ今日は、立体の日か」
司の言葉に、「えっ?」とこちらを振り返った那月が、がたんっと取り出し口に商品が落ちてくる音に肩を跳ねさせ、慌てたように自動販売機に視線を戻した。
がたがたと取り出した缶コーヒーを両手にぶら下げ司の横に戻ると、手にした1本を司に差し出しながら那月は首をひねった。
「絵画やってるって、俺言ったことあったっけ?」
「いや、特に聞いてないけど」
差し出された缶コーヒーを受け取りながら、司は聞き返すように首をかしげた。
「俺のピアノの音を水彩画に例えるくらいだから、絵の方なんだろうなって勝手に思ってたけど、違った?」
「いや、正解だけど」
言いながらプルトップを引き起こす那月を見てから自分の手元に視線を落とし、缶に印字された『カフェラテ』の文字に、司は小さく眉を寄せた。
「これって甘い? よな?」
「うん? あ、もしかして甘いの無理だった?」
「いや、飲めなくはないけど、普段ブラックしか飲まないから」
「何それかっこいい。ブラック、とか、アメリカン、とか、俺も言ってみたいんだよなあ」
「言えば?」
不思議そうに首をかしげる司を一瞥し、那月は拗ねたように口を開いた。
「俺ブラック無理。だってコーヒー苦いじゃん」
言いながら伸びてきた那月の腕がそのまま自分の手から缶コーヒーを奪っていきそうで、司は慌ててそれを頭上に持ち上げた。
「ちょっ、何?!」
「甘いのダメなんだろ? だったら俺がもらってやろうと思って」
「ダメとまでは言ってないだろ」
「何だよ、わがままだなあ」
「何でそうなんの?」
奪われないようにと頭上に持ち上げた缶コーヒーのプルトップを、そのまま器用に片手で引き起こす。飲み口に口をつけてすぐ、司はぺろっと小さく舌を出し軽く眉をひそめた。
「あっま……」
「お前俺にケンカ売ってる? 買うよ?」
「何でよ? 売ってないし、勝手に買わないでもらえます?」
面倒くさそうに肩を落としてから、吹き出すようにふはっと笑う。その笑い声につられるようにして、那月も可笑しそうに声を上げて笑った。
音の出どころなんてわかっている。その姿を探し何度ものぞきに行っては、ただ誰もいない空間にグランドピアノだけを見てきた教室。構内を歩く足を速めて向かった、満開に花を咲かせた桜の木の奥。頭上からふわりと舞い落ちてくる薄桃色の花びらを見上げることもせず、那月は細く開いた窓をめいっぱいまで引き開けた。
宙を漂う花びらを巻き込んだ、ほのかな暖かさをまとった風が室内に流れ込み、音に色付く空気を絡め取る。音がやみ、そして代わりに、数ヶ月前と変わらない笑みを浮かべた男子生徒がひとり、驚いた様子もなくグランドピアノの前で顔を上げた。
「久しぶり」
「久しぶり」
那月が言葉を返すと、彼はゆっくりと窓際に近寄ってきてから、あの日と同じようにサッシに腕をかけた。
「何してんの? 今、春休みだよね」
「部活」
「へぇ、何部?」
「美術部。けど、そんなこと今はどうでもいいんだよ」
深く息をつき、どこか不満そうに発せられた那月の言葉に不思議そうに首をかしげる。軽く眉を寄せた那月に続けざま「嘘つき」と言い捨てられ、彼は何度か瞬きを繰り返してから苦笑した。
「唐突にひどくない? 何で?」
「同学年でピアノをやっている男子なんていなかった。学校にだって、本当は来てないんじゃない?」
「バレたか」
悪びれた様子もなく笑う彼に、那月は続けて口を開いた。
「そもそも、本当にこの学校の生徒なわけ?」
「あ、そこまで疑っちゃう? でも心外だな。俺、嘘なんてついてないと思うけど」
「は?」
「だって俺、同学年としか言ってなくない?」
言われてみれば、確かに……
「でも! じゃあ何で一回も、廊下とかですれ違ったりもしないんだよ」
「それについてはさっき、君が自分で言ってなかった? 学校に来てない、って」
「あ……れ? え?」と小さくつぶやく。
「ちょっと、待って……わけわかんないんだけど」
頭を抱えそうになりながら困惑する那月の姿を可笑しそうに眺めると、彼は小さなパスケースのようなものを那月に差し出した。
「じゃあ、ちょっと整理してみようか」
反射的にそれを受け取り、那月が首をかしげる。
「俺の学生証」
「
「俺の名前。ね? 嘘なんかついてないでしょ? 俺は正真正銘、この学校の生徒だよ。ピアノは好きで弾いてるだけだから敢えて誰かに言ってもないし、だから君の言う〝ピアノを弾く男子生徒〟に該当しないのも当然だと思わない?」
「そんなの……屁理屈じゃん」
「屁理屈だよ」
言ったところでケラケラと笑いながら言い返され、那月はぐっと口をつぐんだ。サッシに頬杖を付き直しながら、「だいたい」と司が首をひねる。
「何で君はそんなに拗ねてるわけ?」
「拗ねてないし」
「じゃあ……怒ってる?」
「怒ってもない」
「じゃあ何だよ?」
「だから、何でもないって」
不貞腐れたように言って踵を返す那月を呼び止めるように、司はその背中に口を開いた。
「君、嘘が下手だね」
「君っていうな」
勢い振り向きざま言い返してくる那月に、司は口の端を持ち上げてにやっと笑った。
「だって俺、君の名前知らないし」
その意地の悪い笑みにすら、かぁっと頬が熱くなる。
「っ……真崎那月。よろしくっ!」
「そんな怒りながらよろしくすんなよ」
ははっと笑いながら司が言ったところで、玄関ホールから部活の先輩に名前を呼ばれ、助かった、とばかりに那月は逃げるようにしてその場を走り去った。
「またね」
言って、司が軽く手を持ち上げる。桜の木の向こうに見えなくなっていく那月の背中を見送ってから、司はふと、持ち上げられた自分の手に視線を移した。
またね? 何で俺……
考えてから、ああそうか……と小さく笑った。嬉しかったんだ。カラフルだと、水彩画のようだと、そう言われたことが嬉しくて、だからきっと、あの時の彼との再会を知らず楽しみにしていたのだと。
*
新年度を迎え多くの生徒の声で久しぶりに賑わう教室で、那月は屍のように机に突っ伏していた。ぴくりとも動くことのないその脳天に、気づかわしげな声が降ってくる。
「春休みの課題、終わんなかった?」
「終わったわ。昨日めっちゃ頑張って写したわ」
投げやりに答えてから、那月はがばと顔を上げた。
「って……何でお前がここにいんだよ?!」
「今年度から復学なんだよね、俺」
「そんなこと聞いてんじゃねぇ!」
「じゃあ何? っていうかもしかして俺、君に嫌われてる?」
「だから」
那月がその先を言う前に、「君っていうな?」と司が可笑しそうに口を開いたので、那月はぐっと言葉を呑み込んだ。
「だって俺、那月に何かしたっけなあ」
腰に両手を当て、心当たりを探るように首をかしげる司に、那月はずるずると机の上に両腕を投げ出した。
だからっていきなり名前かよ? 距離感どうなってんの?
嬉しいような、けれどそう呼ばれるたび、自分の感情を自覚せざるを得ない気がして恥ずかしい。
そんなどちらともいえない、複雑な感情に緩みそうになる口元を必死で誤魔化そうとする那月の様子を気にしたふうもなく、司は続けた。
「何にせよ一年間は同じクラスなわけだし、せっかくだし俺は仲良くしたいと思ってるけど。それに、惚れてくれたんだろ?」
思いもかけない言葉に、んんっ? と一瞬思考が停止した。顔を合わせたのなんてほんの数回でしかないのに、まさかバレてるのか? いや、それならそれで、別にいいのだけれど……いや? いいのか……? そろりと見上げた視線の先で、こちらを見下ろしてくる司がしれっと笑った。
「俺のピアノ」
そっちか……と安堵するように小さく息をつきながらも、那月は投げ出した腕の間から、ごんっと机に額を打ち付けた。
同級生として日常の大半を同じ空間で過ごすようになって数週間が経ち、その間で気付いたことがある。それは──びっくりするぐらい、司はすぐに、教室から姿を消す。
とはいえ、休み時間や放課後に誰がどこで何をしていようとそれは個人の自由だし、始業のチャイムが鳴るタイミングにはしれっと教室に戻ってきているのだから、根っからのサボり癖があるというわけでもないのだろう。
名簿順に並ぶ司の席をちらと盗み見、またいないや……と那月はそっと肩をすくめた。引き戻した視線をそのまま天井に向け、目を閉じる。放課後の教室を満たすクラスメイトの喧騒の裏に、気にしなければ気にならないほどのかすかな淡い音に耳を傾け、那月はふっと小さく笑った。
「また音楽室」
つぶやくように言ってから、那月は何かを思いついたようにがばと身体を起こし、鞄をひっつかむとそのままさっさと教室を後にした。
教室が居づらいわけではなく、単に音楽室の方が落ち着くという、ただそれだけの理由だった。それが何故かを考えたことはないけれど、思い当たる節は多分にある。
家よりも、教室よりも、他のどの場所よりも、ここは静かだ。
そんなことを考えるでもなく考えながら鍵盤を叩いていた司は、廊下へ続くドアの向こうから聞こえてきた電子音に怪訝に眉を寄せ、その手を止めた。そっとピアノから離れ、躊躇うことなく一気にドアを引き開ける。そのままゆっくりと視線を落とした先、準備室のドアの前に片膝を立てて座る脳天を見下ろしながら、ちらと首をかしげた。
「盗み聞き? いい趣味してるね」
意地悪く発せられた司の言葉に何かを言い返そうとして、けれど白紙のまま廊下に投げ出されたスケッチブックと手にしたスマホに、那月はうまい言い訳も何も思い浮かばず、諦めたようにスンッ……と目を細めた。
「ごめんなさい」
「そこは素直なんだ」
ははっと笑いながら言ってくる司を見上げ、続ける。
「君の邪魔をするつもりはなかったんだけど、音消し忘れてて」
「ふぅん。で?」
「で? って……え?」
「君は君って呼ばれるのを嫌がるのに、君は俺のことを君って呼ぶの?」
「あー……えっと、何て呼ぶのが正解かわからなくて……」
「今更?」
もそもそと言ってくる那月に不思議そうに首をかしげてから、「ああ」と納得したように司は口を開いた。
「俺が休学明けで、本当なら学年1コ上なの気にしてる?」
申し訳なさそうにうなずく那月にかりかりと後ろ頭をかくと、司はよいしょ……とその隣に足を投げ出して座った。
「去年の夏前に家の方でちょっとバタついて、そのタイミングで休学した。それが落ち着いたから、そのまま辞めてもよかったんだけど、高校卒業はしとけってみんなに言われて、切りよく年度替わりから復学したってわけ」
何があったのか、気にはなるけれど聞いていいのかどうかもわからず、「そっか」とだけ言って那月は口を閉じた。
「だから……だからってのも変か。変に遠慮して距離取られんのも嫌だし、名前でいいよ。俺も前、那月って呼んだ気がするし……あ、もしかして嫌だった? 真崎の方がいいか」
急に思い出したように司に聞かれ、那月はぶんぶんと大きく首を横に振った。
「嫌じゃない。むしろ……」
「むしろ?」
「あ、いや……何でもない。那月でいい」
「そう? まぁじゃあ、ならよかった」
ふっと柔らかく笑いながら言われたその言葉を最後に、何とも居心地の悪い沈黙がその場を満たした。
どちらも何も言わないまましばらく校内の喧騒に耳にかたむけてから、「さて」とそれを破るように唐突に司が口を開いた。
「俺そろそろ帰るけど、那月は?」
言いながらその場に立ち上がる司を見上げ、「え?」と短く聞き返す。
「帰るなら一緒にどう? ってお誘い。ああそれか、盗み聞きのお詫びに飲み物くらい奢られてやってもいいけど?」
ケラケラと笑いながら言ってくる司に何度か目を瞬かせてから、苦笑する。
まぁ、クラスメイトだしな。ギクシャクしたいわけじゃないし。
そんなことを思い小さく肩を落とすと、那月は拾い上げたスケッチブックを鞄に押し込みながら口を開いた。
「いいよ、わかった。そうでもしとかないと、根に持たれそうで迷惑だ」
「一方的すぎる感情……」
不満そうに言ってから、「まぁいいや、ちょっと片してくる」と音楽室に戻っていった司は、すぐに帰りの支度も終え、廊下へと顔を出してきた。
学校を出た先にある緑道を並んで歩く司の横顔を、クロスバイクを押しながらちらと盗み見る。その位置が自分より少しだけ高いところにあり、那月は思わずその顔をじっと見上げた。
「……何?」
苦笑混じりに司に聞かれ、「いや、別に」と那月は目を逸らした。
「今日部活は? 美術部、だっけ?」
「うん。休みっていうか、絵画と立体で曜日ごとに教室の使用が分かれてるから……あっ」
「ん?」
「ちょっと待ってて」
慣れた仕草でその場にクロスバイクを止め、那月が道沿いにベンチと並んで設置された自動販売機に足を向ける。それを眺めながら司はたずねた。
「じゃあ今日は、立体の日か」
司の言葉に、「えっ?」とこちらを振り返った那月が、がたんっと取り出し口に商品が落ちてくる音に肩を跳ねさせ、慌てたように自動販売機に視線を戻した。
がたがたと取り出した缶コーヒーを両手にぶら下げ司の横に戻ると、手にした1本を司に差し出しながら那月は首をひねった。
「絵画やってるって、俺言ったことあったっけ?」
「いや、特に聞いてないけど」
差し出された缶コーヒーを受け取りながら、司は聞き返すように首をかしげた。
「俺のピアノの音を水彩画に例えるくらいだから、絵の方なんだろうなって勝手に思ってたけど、違った?」
「いや、正解だけど」
言いながらプルトップを引き起こす那月を見てから自分の手元に視線を落とし、缶に印字された『カフェラテ』の文字に、司は小さく眉を寄せた。
「これって甘い? よな?」
「うん? あ、もしかして甘いの無理だった?」
「いや、飲めなくはないけど、普段ブラックしか飲まないから」
「何それかっこいい。ブラック、とか、アメリカン、とか、俺も言ってみたいんだよなあ」
「言えば?」
不思議そうに首をかしげる司を一瞥し、那月は拗ねたように口を開いた。
「俺ブラック無理。だってコーヒー苦いじゃん」
言いながら伸びてきた那月の腕がそのまま自分の手から缶コーヒーを奪っていきそうで、司は慌ててそれを頭上に持ち上げた。
「ちょっ、何?!」
「甘いのダメなんだろ? だったら俺がもらってやろうと思って」
「ダメとまでは言ってないだろ」
「何だよ、わがままだなあ」
「何でそうなんの?」
奪われないようにと頭上に持ち上げた缶コーヒーのプルトップを、そのまま器用に片手で引き起こす。飲み口に口をつけてすぐ、司はぺろっと小さく舌を出し軽く眉をひそめた。
「あっま……」
「お前俺にケンカ売ってる? 買うよ?」
「何でよ? 売ってないし、勝手に買わないでもらえます?」
面倒くさそうに肩を落としてから、吹き出すようにふはっと笑う。その笑い声につられるようにして、那月も可笑しそうに声を上げて笑った。