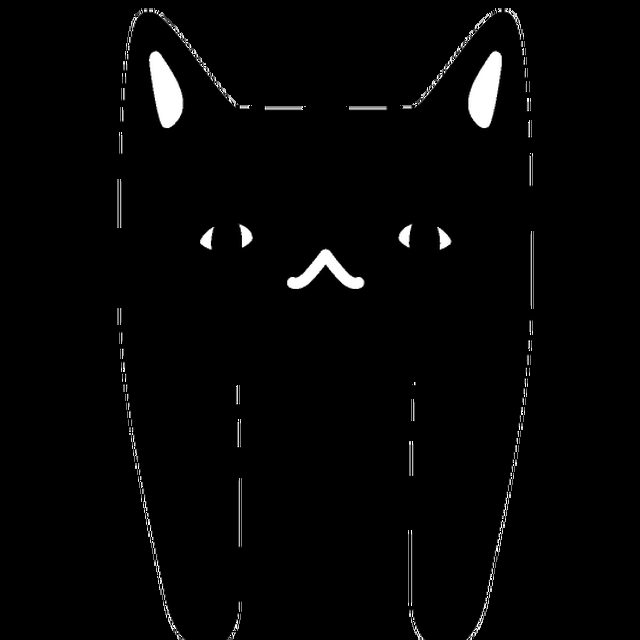第1話 冬
文字数 2,685文字
親の転勤が決まり、年が明けるタイミングで新しい高校に編入することになった。
これまで暮らしてきた土地を離れ、新しい環境で人間関係を築き直していかなければならないというのはなかなかに億劫ではあったけれど、それでも男手ひとつで自分をここまで育ててくれた父親を、「じゃあ、いってらっしゃい」と送り出すことはできず、一緒に転勤先に行くことを決めたのはつまるところ、自分の意思ではあった。
新しく通うことになる校舎を見上げる頬を、刺すような冷たさを孕む風に撫でられ、マフラーの中に首をすぼめる。白く零れる息を吐き出し、そろそろ帰ろうかと踵を返しかけたところで、冬特有の澄んだ空気に溶け込むようにかすかな旋律が聞こえた気がして足を止めた。
ピアノ?
聞こえてくる音を頼りに巡らせた視線の先、冬の寒さにその葉のすべてを落とした大木の陰にわずかに開いた窓を見つけ、校舎に近付く。そっとのぞき込んだ窓の向こうには、グランドピアノに向かうひとりの男子生徒の姿があった。
正直、ピアノはよくわからない。ピアノがというよりは、音楽全般、よくわからない。それでも今自分の耳をくすぐる音は、冬の凛とした空気を巻き込んでなお柔らかく透き通っていて、とても心地良く揺らいで聞こえた。そして何より──音が見える?
……違う。どう表現したらいいのかわからないけれど、音が──空気が音に色付いているように思えて、その音色に、そしてそれを奏でる彼の姿に、見惚れるように立ち尽くした。
唐突にピアノの音が止まり、はっと我に返った視線の先で、その窓越しに彼が軽く口角を持ち上げた。鍵盤に指をかけたまま、彼は気怠げでもなく、緩慢でもなく、ただゆっくりとその場に立ち上がった。
咄嗟に半歩足を引き、窓から少し距離を取る。彼は細く開いていただけの窓を大きく開くと、寄りかかるようにしてサッシに腕をかけた。
「こんにちは」
「……こんにちは」
気まずさに、わずかにあごを引きながら言葉を返す。
「何してんの?」
「年明けからここに通うことになったんで、その下見に」
「へぇ。何年?」
「一年」
「じゃあ、四月から二年生?」
「? ええ、まぁ」
「なら同学年だ」
口元に笑みを浮かべながら言われた言葉に何か言い返そうとして、けれどそれよりも先に彼が続けた。
「ピアノ、好き?」
唐突に聞かれ、「え?」と短く聞き返す。
「聞いてたんじゃないの?」
「聞いてたというか、たまたま聞こえてきただけというか……」
「うん」
短くうなずかれただけなのに、先を促された気がして口を開いた。
「好きとか嫌いとかはよくわからないけど、でも……綺麗だった、かな。音がすごくカラフルで」
「カラフル?」
目を瞬かせながら繰り返す彼に、「あ、えっと」と慌てて言葉を加える。
「音がっていうか……雰囲気? 音のイメージ? かな? ……極彩色っていうんじゃないけどこう、淡いのに存在感のある……夏の水彩画? みたいな? 夏空に白い雲がどーんっ! みたいな……って、ごめん。我ながら意味不明……」
しどろもどろになりながら言い募った結果尻すぼみになっていく言葉に、ふっと抑えたような彼の笑い声が重なった。居心地悪くちらと顔を上げると、彼は窓のサッシに頬杖を付き、目を細めてこちらを見ていた。思いがけず優しい笑みに、瞬間、どきりと鼓動が跳ねる。
「面白い表現するんだな」
口にしたところで、教室の奥から聞こえてきた小さなアラーム音に、彼はゆっくりと肩越しに室内を振り返った。
「もうそんな時間か」
つぶやくように言ってから、こちらに視線を戻す。
「また会えるといいな」
それだけを言ってピアノの方へ戻っていく背中に知らず手を伸ばしかけたところで、ザァっと一際強く吹き付けてきた風に煽られた前髪が視界を奪う。思わず顔を伏せさせてから薄く目を開いた時にはもう、空に溶け込む白い吐息の向こうにも、彼の姿はなかった。
名前、聞きたかったな。まぁでも……
「同学年なら、またすぐ会えるか」
そっと息をついてからふるりと身体を震わせると、首に巻いたマフラーを、口元まで埋めるようにそっと指先で持ち上げた。
新年から通い始めた高校で、けれど予想に反して彼に会うことはなかった。
廊下ですれ違うこともなければ、それらしい姿を見かけることもない。暇さえあればのぞきに行っていた音楽室に彼を見つけたことは勿論なかったし、何というか……いい加減その存在を疑いそうにもなる。
そんな懐疑心をすら抱いているくせに、構内に限らず登下校中どこかから漏れ聞こえてくるピアノの音にさえ足を止めてしまうのだから、我ながらどうかしている。そしてそれは、冬の寒さが鳴りを潜め、暖かな春の陽気が日常に顔をのぞかせるようになった今でも変わらない。
そもそも、と小さく息をつく。誰に聞いてもピアノを弾く男子生徒に思い当たらないというのだから他に探しようもなく、そして勿論あの日以来、柔らかく透き通ったように淡く、それでいてしっかりとそこに存在する水彩画のようなピアノの音を聞いてもいない。
夢──だったのだろうか。澄みきった冬の空気が魅せた、淡く色付く泡沫の夢。
春の陽射しに芽吹き、明るく色彩を帯びてきた世界を教室の窓から見下ろしながら、それでも記憶の中に残る彼の姿とその音は、夢と割り切るには些か鮮明に過ぎて、知らず小さなため息が零れ落ちていた。
「真崎 ? おーい、真崎那月 くん?」
ひらひらと顔の前で揺れる手のひらに、億劫げに顔を上げる。
「何?」
「いや、何って……朝からため息の頻度やばいけど、どしたん? 食べ過ぎ? それか、恋煩いとか?」
「はあ? 何、その二択」
目を眇めるように言い捨ててから、思考の内でその言葉が反芻される。恋……?
いやいや、と乾いた笑みが零れたところで始業のチャイムが鳴り、訝しそうに首をひねりながらも席へと戻っていくクラスメイトの背中に、改めてそっと眉を寄せた。
……恋?
知らず彼の姿を探してしまう。彼と出会った場所に何度も足を運んでしまう。ピアノの音に彼を思い出してしまう。
ここ数か月の自分の挙動を箇条書きのように思い返す。思い返すたび頬に集まってくるかすかな熱に、「うわあ……」と吐息のように声が漏れた。
まじ? 一目惚れ? いや、目っていうか、耳? いやでも、やっぱ目かも……
「焦らされてんのもきいてんよなぁ」
片手で口元を覆うようにしながらつぶやいてから、そういえば、とふと思う。視線だけを移した先をちらほらと彩る薄桃色に、すべての葉を落としたあの大木は桜の木だったのかと、そんなことを思った。
これまで暮らしてきた土地を離れ、新しい環境で人間関係を築き直していかなければならないというのはなかなかに億劫ではあったけれど、それでも男手ひとつで自分をここまで育ててくれた父親を、「じゃあ、いってらっしゃい」と送り出すことはできず、一緒に転勤先に行くことを決めたのはつまるところ、自分の意思ではあった。
新しく通うことになる校舎を見上げる頬を、刺すような冷たさを孕む風に撫でられ、マフラーの中に首をすぼめる。白く零れる息を吐き出し、そろそろ帰ろうかと踵を返しかけたところで、冬特有の澄んだ空気に溶け込むようにかすかな旋律が聞こえた気がして足を止めた。
ピアノ?
聞こえてくる音を頼りに巡らせた視線の先、冬の寒さにその葉のすべてを落とした大木の陰にわずかに開いた窓を見つけ、校舎に近付く。そっとのぞき込んだ窓の向こうには、グランドピアノに向かうひとりの男子生徒の姿があった。
正直、ピアノはよくわからない。ピアノがというよりは、音楽全般、よくわからない。それでも今自分の耳をくすぐる音は、冬の凛とした空気を巻き込んでなお柔らかく透き通っていて、とても心地良く揺らいで聞こえた。そして何より──音が見える?
……違う。どう表現したらいいのかわからないけれど、音が──空気が音に色付いているように思えて、その音色に、そしてそれを奏でる彼の姿に、見惚れるように立ち尽くした。
唐突にピアノの音が止まり、はっと我に返った視線の先で、その窓越しに彼が軽く口角を持ち上げた。鍵盤に指をかけたまま、彼は気怠げでもなく、緩慢でもなく、ただゆっくりとその場に立ち上がった。
咄嗟に半歩足を引き、窓から少し距離を取る。彼は細く開いていただけの窓を大きく開くと、寄りかかるようにしてサッシに腕をかけた。
「こんにちは」
「……こんにちは」
気まずさに、わずかにあごを引きながら言葉を返す。
「何してんの?」
「年明けからここに通うことになったんで、その下見に」
「へぇ。何年?」
「一年」
「じゃあ、四月から二年生?」
「? ええ、まぁ」
「なら同学年だ」
口元に笑みを浮かべながら言われた言葉に何か言い返そうとして、けれどそれよりも先に彼が続けた。
「ピアノ、好き?」
唐突に聞かれ、「え?」と短く聞き返す。
「聞いてたんじゃないの?」
「聞いてたというか、たまたま聞こえてきただけというか……」
「うん」
短くうなずかれただけなのに、先を促された気がして口を開いた。
「好きとか嫌いとかはよくわからないけど、でも……綺麗だった、かな。音がすごくカラフルで」
「カラフル?」
目を瞬かせながら繰り返す彼に、「あ、えっと」と慌てて言葉を加える。
「音がっていうか……雰囲気? 音のイメージ? かな? ……極彩色っていうんじゃないけどこう、淡いのに存在感のある……夏の水彩画? みたいな? 夏空に白い雲がどーんっ! みたいな……って、ごめん。我ながら意味不明……」
しどろもどろになりながら言い募った結果尻すぼみになっていく言葉に、ふっと抑えたような彼の笑い声が重なった。居心地悪くちらと顔を上げると、彼は窓のサッシに頬杖を付き、目を細めてこちらを見ていた。思いがけず優しい笑みに、瞬間、どきりと鼓動が跳ねる。
「面白い表現するんだな」
口にしたところで、教室の奥から聞こえてきた小さなアラーム音に、彼はゆっくりと肩越しに室内を振り返った。
「もうそんな時間か」
つぶやくように言ってから、こちらに視線を戻す。
「また会えるといいな」
それだけを言ってピアノの方へ戻っていく背中に知らず手を伸ばしかけたところで、ザァっと一際強く吹き付けてきた風に煽られた前髪が視界を奪う。思わず顔を伏せさせてから薄く目を開いた時にはもう、空に溶け込む白い吐息の向こうにも、彼の姿はなかった。
名前、聞きたかったな。まぁでも……
「同学年なら、またすぐ会えるか」
そっと息をついてからふるりと身体を震わせると、首に巻いたマフラーを、口元まで埋めるようにそっと指先で持ち上げた。
新年から通い始めた高校で、けれど予想に反して彼に会うことはなかった。
廊下ですれ違うこともなければ、それらしい姿を見かけることもない。暇さえあればのぞきに行っていた音楽室に彼を見つけたことは勿論なかったし、何というか……いい加減その存在を疑いそうにもなる。
そんな懐疑心をすら抱いているくせに、構内に限らず登下校中どこかから漏れ聞こえてくるピアノの音にさえ足を止めてしまうのだから、我ながらどうかしている。そしてそれは、冬の寒さが鳴りを潜め、暖かな春の陽気が日常に顔をのぞかせるようになった今でも変わらない。
そもそも、と小さく息をつく。誰に聞いてもピアノを弾く男子生徒に思い当たらないというのだから他に探しようもなく、そして勿論あの日以来、柔らかく透き通ったように淡く、それでいてしっかりとそこに存在する水彩画のようなピアノの音を聞いてもいない。
夢──だったのだろうか。澄みきった冬の空気が魅せた、淡く色付く泡沫の夢。
春の陽射しに芽吹き、明るく色彩を帯びてきた世界を教室の窓から見下ろしながら、それでも記憶の中に残る彼の姿とその音は、夢と割り切るには些か鮮明に過ぎて、知らず小さなため息が零れ落ちていた。
「
ひらひらと顔の前で揺れる手のひらに、億劫げに顔を上げる。
「何?」
「いや、何って……朝からため息の頻度やばいけど、どしたん? 食べ過ぎ? それか、恋煩いとか?」
「はあ? 何、その二択」
目を眇めるように言い捨ててから、思考の内でその言葉が反芻される。恋……?
いやいや、と乾いた笑みが零れたところで始業のチャイムが鳴り、訝しそうに首をひねりながらも席へと戻っていくクラスメイトの背中に、改めてそっと眉を寄せた。
……恋?
知らず彼の姿を探してしまう。彼と出会った場所に何度も足を運んでしまう。ピアノの音に彼を思い出してしまう。
ここ数か月の自分の挙動を箇条書きのように思い返す。思い返すたび頬に集まってくるかすかな熱に、「うわあ……」と吐息のように声が漏れた。
まじ? 一目惚れ? いや、目っていうか、耳? いやでも、やっぱ目かも……
「焦らされてんのもきいてんよなぁ」
片手で口元を覆うようにしながらつぶやいてから、そういえば、とふと思う。視線だけを移した先をちらほらと彩る薄桃色に、すべての葉を落としたあの大木は桜の木だったのかと、そんなことを思った。