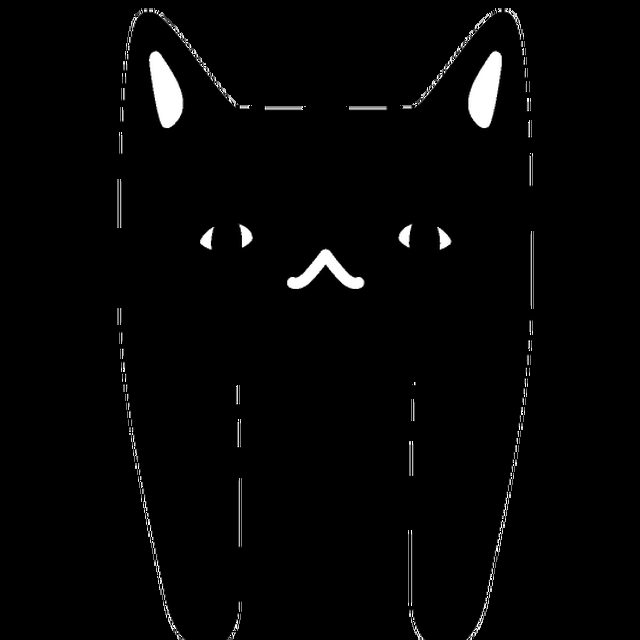第3話 夏
文字数 7,429文字
盗み聞きがバレたあの日以来、何となく一緒にいる時間が増え、そして気付けば梅雨は明け、間もなく夏を迎えようかという時期になっていた。
期末試験が近付き、その準備期間で部活動が軒並み休みになったその日の放課後、試験勉強をする気にもなれず、那月は音楽室の壁を背に直に床に座り込み、司の弾くピアノを聞きながらスケッチブックに鉛筆を走らせていた。
「試験勉強、しなくていいの?」
鍵盤を叩きながら聞いてくる司に、「お前こそ」と短く聞き返す。
「俺はほら、今学期分は復習みたいなもんだから」
「ヨユーってやつ?」
「赤をとらない程度には何とかなるんじゃない?」
ははっと軽く笑いながら答える司に、ちぇっ……と小さく舌を鳴らしてから、那月は膝の上に広げたスケッチブックに頬杖を付くようにしてたずねた。
「お前、何でピアノ始めたの?」
「急に何?」
「いや、ちょっと気になっただけ。言いたくないなら別にいいけど」
「チビどもを黙らせるためと、チビどもから逃げるため」
「チビ?」
「家の弟妹。五人兄妹の、俺一番お兄ちゃん」
「五人って……え? ま?」
「こんなことで嘘ついてどうすんだよ」
言いながら苦笑する司に、それもそうだ……と思う。
「それは何というか……すごそうだな」
「なかなか壮絶だぞ。まぁでも、もう慣れたっていうか、こういうもんだよなって感じ」
「慣れって怖いな」
那月が小さく肩をすくめたところでピアノの音がやんだ。ちらと視線を上げた先で、「まぁ、そうだな」と司が口を開いた。
「始めたきっかけはそんなもんだったし、つい最近までもそうだったかも」
「え?」
「ピアノ。今となってはもうそんなのどうでもよくって、俺がピアノが好きなだけだけど」
ふっと柔らかな笑みを浮かべながら、優しく鍵盤に触れる。そのまま音を響かせることはなく「帰るか」と続けられた司の言葉に、那月はうなずく代わりに腰を上げかけ、そしてあっ……と小さく息を呑んだ。
キーカバーを鍵盤の上に広げ、ピアノの前に立ち上がる司の横顔が西日に照らされ薄く橙に染まる。淡く色付いたままピアノのふたを閉める姿がどうしようもなく綺麗にみえて、その動きのすべてに見惚れるように、那月は知らず、そっと目を細めていた。
「……何? 見惚れてんの?」
那月のその視線に気付いたのか、からかうように司が言ってくる。
「別に」と誤魔化すように言いながら視線を移した窓の向こうが、放課後にしてはやけに眩しい。
ずいぶん日が伸びたな……と、そんなことを思うと同時に、夏のおとずれを感じもした。
学校を出てからどれくらい経ったのか、ばしゃばしゃと水溜まりを蹴散らしながら、ふたりは揃ってバス停の屋根の下に駆け込んだ。
「何っだよ、もう! 雨降るなんてひとっことも言ってなかったじゃん!?」
クロスバイクを乱暴にわきに寄せながら文句を言う那月をちらと横目に、司は雨に濡れた前髪を乱暴にかき上げた。
「夕立ちっていうにはまだちょっと時期的に早い気がするけど……ゲリラ豪雨? まぁどっちも大差ないか」
屋根の下から顔をのぞかせ空を見上げる司の横で、那月は犬のようにふるふると頭を振りながら不満そうに口を開いた。
「学校出た時はあんなに明るかったのに、急に暗くなってくんだもんなあ」
「こういう目に遭うと、夏だなぁ……ってつくづく思うよ。つーかこれ」
空を覆う雨雲と、容赦なく地面を叩き続ける雨粒とに、司が顔をしかめて続ける。
「やむのか?」
「わからん」
清々しいほどに無責任な那月の答えに、「だよな」と苦笑する。そのまま空を見上げ続ける司の横顔に、「なぁ」と那月は声をかけた。
「何?」
「雨いつやむかわかんないし、俺ん家くる? チャリ飛ばせばすぐだし、このままじゃ風邪引くだろ」
那月が引っ張り出したワイシャツの裾から、ぽたぽたと雫が滴り落ちる。そちらに向けていた視線を自分に引き戻した司は、肌に張り付く濡れたワイシャツに「確かに」と小さく息をついた。
「けど、急には迷惑だろ?」
「ああ、大丈夫大丈夫。父さん今日夜勤だし、家誰もいないから」
ワイシャツの裾を絞りながら言ってくる那月に、司が首をかしげる。
「お母さんは?」
「俺がちっさい時に離婚した」
「あー……ごめん」
「いいよ、別に。だから変に遠慮することないって言いたかっただけ」
本当に気にした様子もなく言われ、これ以上気にして遠慮するのも逆に申し訳ない気がして、司は那月の言葉に甘えることにした。
「じゃあ雨やむまで、お邪魔しようかな」
「オッケー」
短く答えてわきに寄せていたクロスバイクを引いてくると、那月は後ろに乗るよう、肩越しに司に目をやった。
玄関先にクロスバイクを止め、鍵を開けて家に入っていく那月に続くように、司も那月の家へと上がっていく。
「お邪魔します」
言ったところで、「はいよー」と間延びしたような那月の声に続き、すぐにばさっと頭の上に何かが降ってきた。
「はい、タオル」
「どうも」
わしゃわしゃと乱暴に髪を払きながら顔を上げると、いつの間にワイシャツを脱いだのか、ティーシャツ姿で頭にタオルを被った那月と目が合った。
「何?」
短くたずねる司に、「何が?」と那月も首をかしげる。
「いやお前、よく俺のこと見てるよなーって」
「気のせいだろ」
言いながらくるりと背を向ける那月に、「そうかあ?」と司がぼやくように口にする。それを聞いてか聞かずか、那月は司に背を向けたまま、廊下を進んだ先の扉を指さした。
「シャワー浴びてこいよ。突き当たりが風呂場だから」
「そこまではいいよ。タオル貸してもらったし、十分」
「いいから、俺の厚意に甘えろ」
「いや、待って。そんな雑な厚意の押し付けある?」
苦笑混じりに言ったところで、問答無用とばかりに風呂場に押し込まれ、司は扉の閉まる音を背中に聞きながら、諦めたように息をついた。
ありがたくシャワーを浴び終え、あ……と動きを止める。タオルとか勝手に借りていいのか? と風呂場から顔をのぞかせると、ちょうど見計らったように廊下側の扉が開き、タオルと着替えを手にした那月が入ってきた。
「あ、悪い」と小さく謝る那月の言葉のあとに、しばし沈黙が流れる。その裏に遠くゴロゴロ……と聞こえた雷鳴を合図にしたように、那月がぴくっと一瞬身体を強張らせてから口を開いた。
「……! タオルと、あと着替え」
「ああ、ありがと」
手にしたタオルと着替えを司に押し付けるようにしてさっさと風呂場を後にする那月の背中を、司は若干の違和感を覚えながら、首をかしげ見送った。
着替えを終え、おそらくリビングであろう場所に顔をのぞかせる。
「シャワー、ありがと」とその言葉に顔を上げた那月が、そこに立つ司の姿に一瞬ぴたと動きを止める。それから短く「ああ」とだけ言うと、那月はそわそわと視線を泳がせた。
自分で用意したのだから当然ではあるけれど、司が自分の服を着ていることが何とも気恥ずかしくて、少し目のやり場に困った。
ペットボトルに入ったお茶を二本手に、司を自分の部屋へと案内する。部屋に入ってすぐ、きょろと辺りに視線を走らせる司に、那月は小さく肩をすくめた。
「えっち」
「言い方」
苦笑混じりに言い返す司の視線の先で、那月がそっと窓に近付きカーテンを閉めた。不思議そうに首をかしげ、司が口を開きかけたところで、どうやらどこかに落ちたらしい雷の音に、「ひっ……!」と那月の肩が小さく跳ねた。
「ずいぶん近いな」
司の呑気な声の奥にも、ゴロゴロ……と雷鳴が続く。カーテンを握りしめたままその場に固まり、動くことのない那月の様子に、司は察したように「ああ」とつぶやいた。
「そういうことか」
「何が? ……っ!」
言い返したところで、遠くに聞こえる落雷の音にすら強張る身体に、言葉も硬くなる。
「怖いんだろ? 雷」
「……何のこと?」
あくまで強がり続ける那月をちらと横目に見てから、司はベッドの上に放り置かれていたタオルケットを取り上げ、首をかしげた。
「これ、借りていい?」
言いながらもすでにそれを手に、司がベッドを背もたれ代わりに床に座り込む。その様子に怪訝に眉を寄せたところで、どうやら本格的に近くに落ちたらしい、空気を引き裂くような落雷音に、那月の身体がびくっと跳ねた。
「っ! あー……」と情けない声を漏らしながら身体を強張らせる那月の腕をつかむと、「おいで」と司は自分の足の間に抱き込むように、那月を強張った身体ごと引き寄せた。頭からタオルケットを被せ、その上から優しく包み込むようにしてその身体を抱き寄せる。
「強がんなって。ほら、これでちょっとは怖いのマシになるだろ?」
「なっ……」
雷云々以前に、この状況に危うく心臓が止まりそうになる。
「ちょっ、と……あの、離してもらえません?」
言ったところで司の腕が解けることはなく、代わりにどこかお兄ちゃん味のある優しい声が頭上から降ってきた。
「下の弟も雷苦手でなあ、雷の鳴る日はよくこうしてやってんのよ」
「……弟いくつよ?」
「小三」
「小三と同じ扱いって……いや、違くて……俺は別に怖くなんてないし」
反論するそばから、一向に鳴りやむ気配を見せない雷鳴と落雷音とに、「うわあっ!」と抑えきれない悲鳴が上がる。
「はいはい。そんなしがみつきながら言われたって、説得力ないって」
呆れたように言いながらも、タオルケットの上から司がぽんぽんと優しく頭を撫でてくる。そうだけど、そうじゃなくて……と那月は混乱した思考のまま、それでも雷の音には、自分を抱き寄せる司に反射的に強くしがみついた。
「ホントにダメなんだな。ひとりの時、どうしてんの?」
「……そこにいる、もっちりフレンドかものはしさん(L)を」
もぞもぞとタオルケットの下から伸びてきた腕の指さす先、枕元に転がったかものはしのぬいぐるみを見つけた司は、ふっと小さく笑みをこぼした。
「抱きしめていると?」
「っ……だったら何だよ! どうせ俺はガキだよ、ガキですよーだ! 何か文句あるっ?!」
「文句はないけど……今のお前、煽り方が小三と一緒で可愛いよ」
くつくつと可笑しそうに司が笑う。
「うるさいっ! ちょっと、お前もう黙ってろよ」
その言葉に「はいはい」と適当な相槌を打ちながらも解かれることのない司の腕の中で、じわじわと熱を持ってくる自分の身体に、那月の思考がぐちゃぐちゃになっていく。
雷は怖いので精神的にも物理的にも司を押し退けることはできそうにない。
腕の中の温もりには安心できるのに、密着した身体から──というか服から、普段自分が使っている柔軟剤と同じ香りがして落ち着かない。
自分と同じ香りをまとった司に抱きしめられている。
違う。そうじゃない。これは自分が雷を怖がっているから側にいてくれているだけであって、それ以上でも以下でもない。
わかってる。わかってるのに……
感情がごちゃ混ぜになって思考が追い付かない。ただ自分の心臓の音だけがやたらとうるさく聞こえて、せめてこの音が司に届きませんようにと、那月は司の腕の中で、ぎゅっときつく目をつむった。
薄暗がりに目を開き、那月はぼんやりとした思考がその輪郭を取り戻すのをじっと待った。自分のものではない心臓の音と、ひとり分ではありえない温もりとにもぞもぞと身体を起こし、頭の上からはらりと落ちたタイルケットに、きょろと辺りに視線を巡らせる。
顔を上げたすぐ横で、かすかな寝息を立てる司の寝顔に驚いたように何度か目を瞬かせてから、那月はああそうか……と小さく息をつき、司の肩にそっと額を寄せた。
「やらかしたなあ」
ぽそりとつぶやき、それでも緩みそうになる口元を片手で覆い隠しながらそろりと司の腕の中を抜け出し、窓に引かれたカーテンを開く。その向こうはすでに夜の帳が下り、けれどその空気は霞が雨に洗い流されたように澄んでいて、遠くに見える星の瞬きに那月はふっと目を細めた。
そのままちらと室内に視線を戻し、四つん這いになるようにして司ににじり寄る。伸ばした手で司の頬を軽くつつきながら、那月はその寝顔をじっとのぞき込んだ。
「綺麗な顔しやがって」
「……それはどうも」
思いがけず返ってきた言葉に慌てて身体を引く。ばくばくと激しく脈打つ心臓を落ち着かせるように胸に手を押し当てる那月の前で、目を開けた司が両手を持ち上げぐっと大きく伸びをした。
「あー……悪い。お前体温高いのかな? 温くて寝ちまった」
「それは……別にいいけど。俺も寝てたし」
「ああ、まじ? よかったじゃん」
普段とは少し違う、どこか無防備な感もある笑みを向けられ、頬が軽く熱を持つ。
「……何が?」
「だって、雷鳴ってる中で寝れたってことだろ? いいことじゃん」
確かに。……確かに? 納得しそうになったところで、よっ……と司が急に目の前で立ち上がったので、那月は思わず身構えるようにしてその動きを目で追いかけた。
「さすがにそろそろ帰るわ。服、借りてっていい? 今度洗って返す」
「え? あ、ああ……」と脱力したように那月がうなずく。
「ん? どうかした?」
不思議そうに首をかしげる司に、那月は慌てて首を横に振った。
荷物を抱えた司を玄関先まで送ってから、那月はばつが悪そうに小さく顔を俯かせた。
「何か、ごめん。無理矢理引き留めるみたいになって」
「いいよ、別に。おかげで風邪引かずにすんだし、それにお前が心細い時に一緒にいられたんなら何より、ってことで」
ははっと軽く笑って答えながら那月の頭にぽんっと手を乗せると、「じゃあまたな」と言って司はくるりと踵を返した。
ちらちらと星の瞬く夜空の下を遠く小さくなっていく司の背中を見送りながら、那月はそっと自分の頭に手を乗せた。
「弟と同じ、か」
つぶやくように言いながら、那月は嬉しいのに悔しいような、複雑な感情のままかすかに眉を寄せた。
*
一学期が終わり、突入した夏休みも後半にさしかかったある日の昼下がり、春休みの反省を活かし、少しでも課題を減らすべく司を家に誘ったのは那月の方からだった。
他愛のない話をしながらそれでもいくらか課題も進み、日が落ちきる前には司も家に帰るつもりでいた。そのはずなのに──
それが今、何故こんなことになっているのか。
「ちょ、っ……と待っ……あー無理っ! 痛い痛い! 俺あんまやったことないから優しくしてって……言ったじゃん!? 言ったよね?!」
「声デカ。言われはしたけど承諾した記憶はない」
「性格悪っ!?」
「お前に言われたくない」
「何で?! 俺そんな性格悪くないし、新見さん家のお兄ちゃんといえばわりといい男で有名なんだけど?」
「知らんよ」
「ひでぇ……って、あーっバカバカ! 無理、待って! ちょっ……痛いってば。まじ死ぬ、死んじゃうって! あっ……ああっ!」
司の絶叫と前後して、画面の左右にそれぞれ異なった文字が表示される。右半分に表示された『YOU WIN』の文字の裏では、那月の操作するキャラクターがガッツポーズを決めていた。
「初心者相手にコンボ技叩き込んでくるなよ……鬼畜にもほどがある。鬼の所業」
手にしていたコントローラーを投げ出しながらベッドに倒れ込む司に、那月がケラケラと笑う。
「これでも手加減したんだけどな」
「うっわ、腹立つ」
「何でだよ。そもそもゲームしようって言いだしたのお前じゃん」
「お前が宿題飽きた、だる……とか言いだすからだろ?」
それに関しては否定のしようもなく、その言葉は無視を決め込んだ那月に苦笑を返してから、司は額にかかる前髪を、撫で付けるように両手でかき上げた。その仕草をじっと見てくる那月を見上げるようにして、ベッドに転がったまま器用に首をかしげる。
「何?」
「いや……こいつこんな顔してたんだな、と思って」
「何それ? 俺は生まれてから今までずっとこの顔だよ」
「そういうんじゃなくて」
言いながら顔を寄せてくる那月に、司はゆっくりと瞬きを繰り返した。開いた窓から流れ込んでくる少し湿った夏の風が、ひぐらしの鳴く声を運んできながらふわりとカーテンを揺らす。
「司ってさ」
「うん?」
先を促すようにうなずき、ベッドに上体を起こす。起こしたはずが、両肩にかけられた那月の手に押し戻されるようにして、司はまた、ベッドの上から那月を見上げていた。
「ちょっとたまに、無防備が過ぎるよね」
「那月?」
押さえ込まれたまま見上げた那月の顔が何かと葛藤するようにわずかに歪んでみえて、その頬に触れようとそっと腕を伸ばす。
「どうした? 大丈夫?」
聞いたところで、けれど司の指先が那月の頬に触れるより先に、肩にかけられていた手がぱっと離れ、見上げる先で那月の目元に薄く笑みが浮かんだ。
「平気。何でもない」
言いながら身体を起こした那月が、ベッドから少し距離を置いた位置に足を下ろす。続けてベッドから起き上がった司は、けれどたったの一歩を踏み出すことで、あっという間にその距離を詰めた。
那月の背中に片手を回し、その身体をそっと引き寄せる。背中に回した手でそのままぽんぽんと頭を撫でると、腕の中で那月が小さく口を開いた。
「……何?」
「いや、何かしんどそうだったから」
その言葉に、那月は司の首元に顔を埋めるようにしながら、はぁ……と深く息をついた。
たぶん司にしてみれば、以前の雷の時と同様、この行動にも何ら他意はないのだろう。それがわかるからこそ……
「タチ悪ぃ」
那月のつぶやきに、「え?」と司が短く聞き返す。
おそらく一方的にその鼓動を速めるているであろう心臓を落ち着かせるように、那月は小さく深呼吸を繰り返してから続けた。
「何でもない。これは? いくつ?」
「中三。最近、構いすぎるとガチ切れされる」
「弟?」
「妹」と短い司の答えに、「そりゃそうだ」と那月は苦笑した。
司の身体を軽く押し返し、その胸元に頭を預ける形で改めてそっと息をつく。それから思考を切り替えるようにして、那月はぱっと顔を上げた。
「悪い、遅くなって。途中まで送る」
「え? 別にいいよ」
ちらと首をかしげる司に「コンビニ」とだけ言って、那月はポケットにスマホを押し込んだ。
「俺がアイスを食いたいから、そのついでに途中まで送ってくだけ」
言いながらもさっさと自分に背を向ける那月に、司は「なるほど」と小さく肩をすくめ、自分も取り上げた荷物を肩に背負い直した。
期末試験が近付き、その準備期間で部活動が軒並み休みになったその日の放課後、試験勉強をする気にもなれず、那月は音楽室の壁を背に直に床に座り込み、司の弾くピアノを聞きながらスケッチブックに鉛筆を走らせていた。
「試験勉強、しなくていいの?」
鍵盤を叩きながら聞いてくる司に、「お前こそ」と短く聞き返す。
「俺はほら、今学期分は復習みたいなもんだから」
「ヨユーってやつ?」
「赤をとらない程度には何とかなるんじゃない?」
ははっと軽く笑いながら答える司に、ちぇっ……と小さく舌を鳴らしてから、那月は膝の上に広げたスケッチブックに頬杖を付くようにしてたずねた。
「お前、何でピアノ始めたの?」
「急に何?」
「いや、ちょっと気になっただけ。言いたくないなら別にいいけど」
「チビどもを黙らせるためと、チビどもから逃げるため」
「チビ?」
「家の弟妹。五人兄妹の、俺一番お兄ちゃん」
「五人って……え? ま?」
「こんなことで嘘ついてどうすんだよ」
言いながら苦笑する司に、それもそうだ……と思う。
「それは何というか……すごそうだな」
「なかなか壮絶だぞ。まぁでも、もう慣れたっていうか、こういうもんだよなって感じ」
「慣れって怖いな」
那月が小さく肩をすくめたところでピアノの音がやんだ。ちらと視線を上げた先で、「まぁ、そうだな」と司が口を開いた。
「始めたきっかけはそんなもんだったし、つい最近までもそうだったかも」
「え?」
「ピアノ。今となってはもうそんなのどうでもよくって、俺がピアノが好きなだけだけど」
ふっと柔らかな笑みを浮かべながら、優しく鍵盤に触れる。そのまま音を響かせることはなく「帰るか」と続けられた司の言葉に、那月はうなずく代わりに腰を上げかけ、そしてあっ……と小さく息を呑んだ。
キーカバーを鍵盤の上に広げ、ピアノの前に立ち上がる司の横顔が西日に照らされ薄く橙に染まる。淡く色付いたままピアノのふたを閉める姿がどうしようもなく綺麗にみえて、その動きのすべてに見惚れるように、那月は知らず、そっと目を細めていた。
「……何? 見惚れてんの?」
那月のその視線に気付いたのか、からかうように司が言ってくる。
「別に」と誤魔化すように言いながら視線を移した窓の向こうが、放課後にしてはやけに眩しい。
ずいぶん日が伸びたな……と、そんなことを思うと同時に、夏のおとずれを感じもした。
学校を出てからどれくらい経ったのか、ばしゃばしゃと水溜まりを蹴散らしながら、ふたりは揃ってバス停の屋根の下に駆け込んだ。
「何っだよ、もう! 雨降るなんてひとっことも言ってなかったじゃん!?」
クロスバイクを乱暴にわきに寄せながら文句を言う那月をちらと横目に、司は雨に濡れた前髪を乱暴にかき上げた。
「夕立ちっていうにはまだちょっと時期的に早い気がするけど……ゲリラ豪雨? まぁどっちも大差ないか」
屋根の下から顔をのぞかせ空を見上げる司の横で、那月は犬のようにふるふると頭を振りながら不満そうに口を開いた。
「学校出た時はあんなに明るかったのに、急に暗くなってくんだもんなあ」
「こういう目に遭うと、夏だなぁ……ってつくづく思うよ。つーかこれ」
空を覆う雨雲と、容赦なく地面を叩き続ける雨粒とに、司が顔をしかめて続ける。
「やむのか?」
「わからん」
清々しいほどに無責任な那月の答えに、「だよな」と苦笑する。そのまま空を見上げ続ける司の横顔に、「なぁ」と那月は声をかけた。
「何?」
「雨いつやむかわかんないし、俺ん家くる? チャリ飛ばせばすぐだし、このままじゃ風邪引くだろ」
那月が引っ張り出したワイシャツの裾から、ぽたぽたと雫が滴り落ちる。そちらに向けていた視線を自分に引き戻した司は、肌に張り付く濡れたワイシャツに「確かに」と小さく息をついた。
「けど、急には迷惑だろ?」
「ああ、大丈夫大丈夫。父さん今日夜勤だし、家誰もいないから」
ワイシャツの裾を絞りながら言ってくる那月に、司が首をかしげる。
「お母さんは?」
「俺がちっさい時に離婚した」
「あー……ごめん」
「いいよ、別に。だから変に遠慮することないって言いたかっただけ」
本当に気にした様子もなく言われ、これ以上気にして遠慮するのも逆に申し訳ない気がして、司は那月の言葉に甘えることにした。
「じゃあ雨やむまで、お邪魔しようかな」
「オッケー」
短く答えてわきに寄せていたクロスバイクを引いてくると、那月は後ろに乗るよう、肩越しに司に目をやった。
玄関先にクロスバイクを止め、鍵を開けて家に入っていく那月に続くように、司も那月の家へと上がっていく。
「お邪魔します」
言ったところで、「はいよー」と間延びしたような那月の声に続き、すぐにばさっと頭の上に何かが降ってきた。
「はい、タオル」
「どうも」
わしゃわしゃと乱暴に髪を払きながら顔を上げると、いつの間にワイシャツを脱いだのか、ティーシャツ姿で頭にタオルを被った那月と目が合った。
「何?」
短くたずねる司に、「何が?」と那月も首をかしげる。
「いやお前、よく俺のこと見てるよなーって」
「気のせいだろ」
言いながらくるりと背を向ける那月に、「そうかあ?」と司がぼやくように口にする。それを聞いてか聞かずか、那月は司に背を向けたまま、廊下を進んだ先の扉を指さした。
「シャワー浴びてこいよ。突き当たりが風呂場だから」
「そこまではいいよ。タオル貸してもらったし、十分」
「いいから、俺の厚意に甘えろ」
「いや、待って。そんな雑な厚意の押し付けある?」
苦笑混じりに言ったところで、問答無用とばかりに風呂場に押し込まれ、司は扉の閉まる音を背中に聞きながら、諦めたように息をついた。
ありがたくシャワーを浴び終え、あ……と動きを止める。タオルとか勝手に借りていいのか? と風呂場から顔をのぞかせると、ちょうど見計らったように廊下側の扉が開き、タオルと着替えを手にした那月が入ってきた。
「あ、悪い」と小さく謝る那月の言葉のあとに、しばし沈黙が流れる。その裏に遠くゴロゴロ……と聞こえた雷鳴を合図にしたように、那月がぴくっと一瞬身体を強張らせてから口を開いた。
「……! タオルと、あと着替え」
「ああ、ありがと」
手にしたタオルと着替えを司に押し付けるようにしてさっさと風呂場を後にする那月の背中を、司は若干の違和感を覚えながら、首をかしげ見送った。
着替えを終え、おそらくリビングであろう場所に顔をのぞかせる。
「シャワー、ありがと」とその言葉に顔を上げた那月が、そこに立つ司の姿に一瞬ぴたと動きを止める。それから短く「ああ」とだけ言うと、那月はそわそわと視線を泳がせた。
自分で用意したのだから当然ではあるけれど、司が自分の服を着ていることが何とも気恥ずかしくて、少し目のやり場に困った。
ペットボトルに入ったお茶を二本手に、司を自分の部屋へと案内する。部屋に入ってすぐ、きょろと辺りに視線を走らせる司に、那月は小さく肩をすくめた。
「えっち」
「言い方」
苦笑混じりに言い返す司の視線の先で、那月がそっと窓に近付きカーテンを閉めた。不思議そうに首をかしげ、司が口を開きかけたところで、どうやらどこかに落ちたらしい雷の音に、「ひっ……!」と那月の肩が小さく跳ねた。
「ずいぶん近いな」
司の呑気な声の奥にも、ゴロゴロ……と雷鳴が続く。カーテンを握りしめたままその場に固まり、動くことのない那月の様子に、司は察したように「ああ」とつぶやいた。
「そういうことか」
「何が? ……っ!」
言い返したところで、遠くに聞こえる落雷の音にすら強張る身体に、言葉も硬くなる。
「怖いんだろ? 雷」
「……何のこと?」
あくまで強がり続ける那月をちらと横目に見てから、司はベッドの上に放り置かれていたタオルケットを取り上げ、首をかしげた。
「これ、借りていい?」
言いながらもすでにそれを手に、司がベッドを背もたれ代わりに床に座り込む。その様子に怪訝に眉を寄せたところで、どうやら本格的に近くに落ちたらしい、空気を引き裂くような落雷音に、那月の身体がびくっと跳ねた。
「っ! あー……」と情けない声を漏らしながら身体を強張らせる那月の腕をつかむと、「おいで」と司は自分の足の間に抱き込むように、那月を強張った身体ごと引き寄せた。頭からタオルケットを被せ、その上から優しく包み込むようにしてその身体を抱き寄せる。
「強がんなって。ほら、これでちょっとは怖いのマシになるだろ?」
「なっ……」
雷云々以前に、この状況に危うく心臓が止まりそうになる。
「ちょっ、と……あの、離してもらえません?」
言ったところで司の腕が解けることはなく、代わりにどこかお兄ちゃん味のある優しい声が頭上から降ってきた。
「下の弟も雷苦手でなあ、雷の鳴る日はよくこうしてやってんのよ」
「……弟いくつよ?」
「小三」
「小三と同じ扱いって……いや、違くて……俺は別に怖くなんてないし」
反論するそばから、一向に鳴りやむ気配を見せない雷鳴と落雷音とに、「うわあっ!」と抑えきれない悲鳴が上がる。
「はいはい。そんなしがみつきながら言われたって、説得力ないって」
呆れたように言いながらも、タオルケットの上から司がぽんぽんと優しく頭を撫でてくる。そうだけど、そうじゃなくて……と那月は混乱した思考のまま、それでも雷の音には、自分を抱き寄せる司に反射的に強くしがみついた。
「ホントにダメなんだな。ひとりの時、どうしてんの?」
「……そこにいる、もっちりフレンドかものはしさん(L)を」
もぞもぞとタオルケットの下から伸びてきた腕の指さす先、枕元に転がったかものはしのぬいぐるみを見つけた司は、ふっと小さく笑みをこぼした。
「抱きしめていると?」
「っ……だったら何だよ! どうせ俺はガキだよ、ガキですよーだ! 何か文句あるっ?!」
「文句はないけど……今のお前、煽り方が小三と一緒で可愛いよ」
くつくつと可笑しそうに司が笑う。
「うるさいっ! ちょっと、お前もう黙ってろよ」
その言葉に「はいはい」と適当な相槌を打ちながらも解かれることのない司の腕の中で、じわじわと熱を持ってくる自分の身体に、那月の思考がぐちゃぐちゃになっていく。
雷は怖いので精神的にも物理的にも司を押し退けることはできそうにない。
腕の中の温もりには安心できるのに、密着した身体から──というか服から、普段自分が使っている柔軟剤と同じ香りがして落ち着かない。
自分と同じ香りをまとった司に抱きしめられている。
違う。そうじゃない。これは自分が雷を怖がっているから側にいてくれているだけであって、それ以上でも以下でもない。
わかってる。わかってるのに……
感情がごちゃ混ぜになって思考が追い付かない。ただ自分の心臓の音だけがやたらとうるさく聞こえて、せめてこの音が司に届きませんようにと、那月は司の腕の中で、ぎゅっときつく目をつむった。
薄暗がりに目を開き、那月はぼんやりとした思考がその輪郭を取り戻すのをじっと待った。自分のものではない心臓の音と、ひとり分ではありえない温もりとにもぞもぞと身体を起こし、頭の上からはらりと落ちたタイルケットに、きょろと辺りに視線を巡らせる。
顔を上げたすぐ横で、かすかな寝息を立てる司の寝顔に驚いたように何度か目を瞬かせてから、那月はああそうか……と小さく息をつき、司の肩にそっと額を寄せた。
「やらかしたなあ」
ぽそりとつぶやき、それでも緩みそうになる口元を片手で覆い隠しながらそろりと司の腕の中を抜け出し、窓に引かれたカーテンを開く。その向こうはすでに夜の帳が下り、けれどその空気は霞が雨に洗い流されたように澄んでいて、遠くに見える星の瞬きに那月はふっと目を細めた。
そのままちらと室内に視線を戻し、四つん這いになるようにして司ににじり寄る。伸ばした手で司の頬を軽くつつきながら、那月はその寝顔をじっとのぞき込んだ。
「綺麗な顔しやがって」
「……それはどうも」
思いがけず返ってきた言葉に慌てて身体を引く。ばくばくと激しく脈打つ心臓を落ち着かせるように胸に手を押し当てる那月の前で、目を開けた司が両手を持ち上げぐっと大きく伸びをした。
「あー……悪い。お前体温高いのかな? 温くて寝ちまった」
「それは……別にいいけど。俺も寝てたし」
「ああ、まじ? よかったじゃん」
普段とは少し違う、どこか無防備な感もある笑みを向けられ、頬が軽く熱を持つ。
「……何が?」
「だって、雷鳴ってる中で寝れたってことだろ? いいことじゃん」
確かに。……確かに? 納得しそうになったところで、よっ……と司が急に目の前で立ち上がったので、那月は思わず身構えるようにしてその動きを目で追いかけた。
「さすがにそろそろ帰るわ。服、借りてっていい? 今度洗って返す」
「え? あ、ああ……」と脱力したように那月がうなずく。
「ん? どうかした?」
不思議そうに首をかしげる司に、那月は慌てて首を横に振った。
荷物を抱えた司を玄関先まで送ってから、那月はばつが悪そうに小さく顔を俯かせた。
「何か、ごめん。無理矢理引き留めるみたいになって」
「いいよ、別に。おかげで風邪引かずにすんだし、それにお前が心細い時に一緒にいられたんなら何より、ってことで」
ははっと軽く笑って答えながら那月の頭にぽんっと手を乗せると、「じゃあまたな」と言って司はくるりと踵を返した。
ちらちらと星の瞬く夜空の下を遠く小さくなっていく司の背中を見送りながら、那月はそっと自分の頭に手を乗せた。
「弟と同じ、か」
つぶやくように言いながら、那月は嬉しいのに悔しいような、複雑な感情のままかすかに眉を寄せた。
*
一学期が終わり、突入した夏休みも後半にさしかかったある日の昼下がり、春休みの反省を活かし、少しでも課題を減らすべく司を家に誘ったのは那月の方からだった。
他愛のない話をしながらそれでもいくらか課題も進み、日が落ちきる前には司も家に帰るつもりでいた。そのはずなのに──
それが今、何故こんなことになっているのか。
「ちょ、っ……と待っ……あー無理っ! 痛い痛い! 俺あんまやったことないから優しくしてって……言ったじゃん!? 言ったよね?!」
「声デカ。言われはしたけど承諾した記憶はない」
「性格悪っ!?」
「お前に言われたくない」
「何で?! 俺そんな性格悪くないし、新見さん家のお兄ちゃんといえばわりといい男で有名なんだけど?」
「知らんよ」
「ひでぇ……って、あーっバカバカ! 無理、待って! ちょっ……痛いってば。まじ死ぬ、死んじゃうって! あっ……ああっ!」
司の絶叫と前後して、画面の左右にそれぞれ異なった文字が表示される。右半分に表示された『YOU WIN』の文字の裏では、那月の操作するキャラクターがガッツポーズを決めていた。
「初心者相手にコンボ技叩き込んでくるなよ……鬼畜にもほどがある。鬼の所業」
手にしていたコントローラーを投げ出しながらベッドに倒れ込む司に、那月がケラケラと笑う。
「これでも手加減したんだけどな」
「うっわ、腹立つ」
「何でだよ。そもそもゲームしようって言いだしたのお前じゃん」
「お前が宿題飽きた、だる……とか言いだすからだろ?」
それに関しては否定のしようもなく、その言葉は無視を決め込んだ那月に苦笑を返してから、司は額にかかる前髪を、撫で付けるように両手でかき上げた。その仕草をじっと見てくる那月を見上げるようにして、ベッドに転がったまま器用に首をかしげる。
「何?」
「いや……こいつこんな顔してたんだな、と思って」
「何それ? 俺は生まれてから今までずっとこの顔だよ」
「そういうんじゃなくて」
言いながら顔を寄せてくる那月に、司はゆっくりと瞬きを繰り返した。開いた窓から流れ込んでくる少し湿った夏の風が、ひぐらしの鳴く声を運んできながらふわりとカーテンを揺らす。
「司ってさ」
「うん?」
先を促すようにうなずき、ベッドに上体を起こす。起こしたはずが、両肩にかけられた那月の手に押し戻されるようにして、司はまた、ベッドの上から那月を見上げていた。
「ちょっとたまに、無防備が過ぎるよね」
「那月?」
押さえ込まれたまま見上げた那月の顔が何かと葛藤するようにわずかに歪んでみえて、その頬に触れようとそっと腕を伸ばす。
「どうした? 大丈夫?」
聞いたところで、けれど司の指先が那月の頬に触れるより先に、肩にかけられていた手がぱっと離れ、見上げる先で那月の目元に薄く笑みが浮かんだ。
「平気。何でもない」
言いながら身体を起こした那月が、ベッドから少し距離を置いた位置に足を下ろす。続けてベッドから起き上がった司は、けれどたったの一歩を踏み出すことで、あっという間にその距離を詰めた。
那月の背中に片手を回し、その身体をそっと引き寄せる。背中に回した手でそのままぽんぽんと頭を撫でると、腕の中で那月が小さく口を開いた。
「……何?」
「いや、何かしんどそうだったから」
その言葉に、那月は司の首元に顔を埋めるようにしながら、はぁ……と深く息をついた。
たぶん司にしてみれば、以前の雷の時と同様、この行動にも何ら他意はないのだろう。それがわかるからこそ……
「タチ悪ぃ」
那月のつぶやきに、「え?」と司が短く聞き返す。
おそらく一方的にその鼓動を速めるているであろう心臓を落ち着かせるように、那月は小さく深呼吸を繰り返してから続けた。
「何でもない。これは? いくつ?」
「中三。最近、構いすぎるとガチ切れされる」
「弟?」
「妹」と短い司の答えに、「そりゃそうだ」と那月は苦笑した。
司の身体を軽く押し返し、その胸元に頭を預ける形で改めてそっと息をつく。それから思考を切り替えるようにして、那月はぱっと顔を上げた。
「悪い、遅くなって。途中まで送る」
「え? 別にいいよ」
ちらと首をかしげる司に「コンビニ」とだけ言って、那月はポケットにスマホを押し込んだ。
「俺がアイスを食いたいから、そのついでに途中まで送ってくだけ」
言いながらもさっさと自分に背を向ける那月に、司は「なるほど」と小さく肩をすくめ、自分も取り上げた荷物を肩に背負い直した。