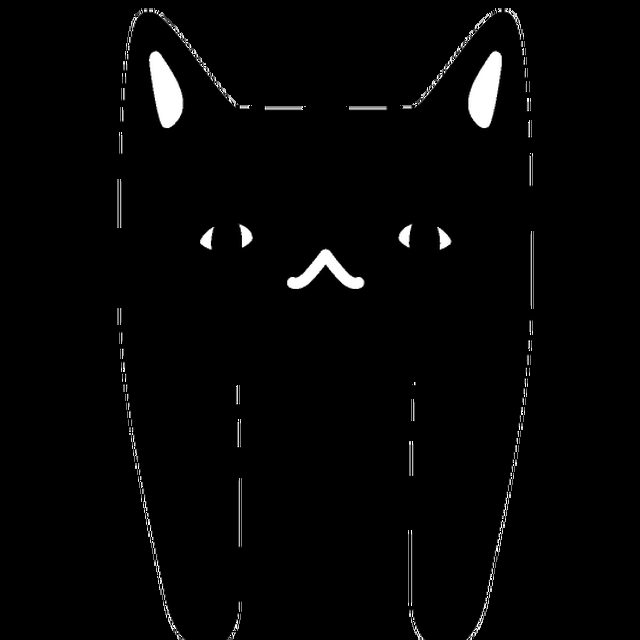第4話 秋
文字数 5,104文字
夏休みが明け、学園祭の準備に浮き立つ放課後の校内を、那月はのろのろと屋上へと足を向けた。祭りの喧騒も嫌いではないけれど、残念ながらそれも時と場合による。ただひたすらに賑やかしいこの雰囲気は、部活で展示予定の作品がいまだに真っ白いままの状況では、正直少々面倒くさかった。
校舎裏を見下ろす側にあるフェンスに背を預け、ずるずるとその場に腰を下ろす。
「参ったなあ……」
言いながら空を見上げた那月は、そのまま目を閉じ深いため息をついた。
幼少の頃から父親の帰宅を待って、自宅でひとり絵を描いて過ごす時間は多かった。その下地になるのは家の中に当たり前に存在するものや、そこから見える風景、音。学校の帰り道に見えたものなど何でもよかったし、だからこそ描くことに困ることもなかった。
それが今はどういうことだ? 一体何があった? こんなにも何のイメージも浮かばないのは初めてで、特に意図することもなく、ただ何とはなしに最近描いた絵の数々を思い浮かべた。そしてすぐに、自嘲するように苦笑する。思い出すそのほとんどがピアノの音と共にあることに気付き、「重症だな」とつぶやいたところで、ふと瞼の裏に落ちてきた影に那月は薄く目を開けた。
「……司?」
のぞき込むように自分を見下ろしてくる司に、首をかしげ、続ける。
「何してんの?」
「お前が屋上に上がってくの、見えたから」
言いながら差し出された缶コーヒーを受け取り、視線を落としてから那月は眉を寄せた。
「……無糖って書いてありますけど?」
「ブラック。って言ってみたいんでしょ?」
「だからって飲めないんじゃ意味ないし、そもそも俺何も言ってない」
「確かに」
笑いながらそう言うと、司は那月の手からひょいとそれを奪い取り、手持ち無沙汰に緩く開かれたままのその手に自分の持っていた缶コーヒーを渡した。
「はい、交換」
『無糖』と印字されたコーヒー缶を手の中で弄びながら那月の隣に腰を下ろし、続ける。
「なーんか面倒くさそうな顔してるけど?」
「実際面倒くさいことになってんだよ」
一部お前のせいでな……とは言わないまま、那月は『カフェラテ』と印字された缶コーヒーのプルトップを引き起こした。
「ふぅん」と小さくつぶやいてからちらと那月に目を向け、「で?」と短く聞いてくる司に、「え?」と那月も聞き返す。
「何が重症なの?」
「聞いてたのかよ……」
「人聞きの悪い。聞こえちゃっただけよ」
言いながらケラケラと笑う司に、肩を落とし息をついたところで、「で?」と思いがけず優しい声で司に聞き直され、那月は顔を上げた。
「俺に何か手伝えることある? 治療? わかんないけど」
促すように向けられた笑みに、那月は頬に熱が集まるのを感じながら、思わず司からぱっと視線を逸らした。
勘違いするな。これはただ、弟妹に優しいのと同じなんだから──自分にそう言い聞かせるようにゆっくりと息を吐き出してから、那月は不思議そうに首をかしげる司に苦笑を返した。
「それはいくつの弟? あ、妹か?」
「え?」と何度か目を瞬かせてから、「ああ」と司は小さく笑った。
「高二。俺の大事な友人」
「っ……! お前さあ……」
司の言葉に大きく息をつき、那月は喜ぶべきなのか悲しむべきなのか、どうにも複雑な感情のまま、背後のフェンスに背中を預け直した。
「恥ずかしいやつ。こっちが照れるわ」
「口にしなきゃ伝わらないことってたくさんあるじゃん? 察してくれ、なんて自分都合なこと言いたくないし、言われても俺も困るし。だったら潔く言っちゃった方がいい気しない? 伝わらないことを相手のせいにしたくもないしさ」
「じゃあもし……」
両手で包み込むように持ったコーヒー缶に、那月が視線を落とす。
「うん?」と先を促してくる司に、けれど那月は「何でもない」と軽く首を横に振り言葉を呑み込んだ。
「うわあ、気になる。まぁ、いいけど」
手にした缶コーヒーのプルトップを引き起こしながら、司はちらと那月を盗み見、口を開いた。
「で、どうよ? お前のここに寄ってるしわの理由、俺に話してみる気ないの?」
自分の眉間に指先を当て、そこに視線を寄せるようにしながら司がたずねる。
「ない」と短く答える那月に、司は「あっそ」とそれ以上食い下がることはしなかった。
「でも」
那月が続ける。
「ピアノ、聞かせてよ」
「え?」
「司のピアノ、聞きたい」
「そりゃ別に構わないけど……学祭終わるまで、たぶん音楽室使えないんだよね」
「そうなの?」
「使えないっていうか、部活で使われてるっていうか」
「今までは?」
「部活ない時に勝手に借りてただけ」
「……勝手に?」
司の言葉に思わず聞き返す。
「あれ? 知らなかった? 教室使うのに使用許可取る必要があるって。まぁ俺は取ったことないけど」
ケラケラと笑ってから司は続けた。
「今は学祭の練習で、部活でほぼ毎日使われてるんだよね」
「そっか」と小さく肩を落とす那月を横目に、司はコーヒーを口に含みながら何かを考えるように空を仰いだ。
翌日、午前中の授業を終え、椅子の背もたれに体重を預けて小さく息をついたところで机の上に落ちてきた影に、那月は顔を上げた。
「ちょっと付き合わない?」
軽く首をかしげるようにしながら言ってくる司に、「何?」と怪訝に眉を寄せる。
「いいから」と机の横にかけてあった那月の通学鞄を取ると、司はそれを肩に担ぐようにしながら、振り返ることもせずさっさと教室を出ていった。
わけもわからないまま司を追いかけ、その足が止まった先の教室のプレートを見上げ、那月は眉をひそめた。
「音楽室? 部活してんじゃないの?」
「昼休みはさすがにやってないみたいだな」
言いながら押し付けられた通学鞄を胸に抱え、那月はちらと司に視線をやった。司が何を考えているのかまったくわからないまま、「えーっと……」と目を瞬かせる。その視線の先で躊躇なく音楽室に入っていく司に、そのあとに続いて音楽室に入ろうとした那月の足が躊躇うようにぴたと止まった。
今まで気にもしていなかったけれど……使用許可が必要と聞いてしまったせいで、何となく入りづらい。
廊下で足を止めたままの那月を肩越しに見て、ふっと目を細めて司が笑う。
「気になんの?」
茶化すように言ったところで何も言い返してはこないまま、それでも音楽室に入ってきた那月に、司は小さく笑った。そのままピアノに足を向け、慣れた手つきでグランドピアノの屋根を持ち上げる。
その様子を見ながら、「あれ……?」と那月がつぶやいた。
「何?」
「ピアノのその、ふた? の部分開けてるの、始めて見たかも」
「ああ、よく覚えてんね。勝手に借りてる時はすぐ逃げられるように、屋根開けないからさ」
しれっと答える司に、「ん?」と首をかしげる。
「今日は?」と続ける那月に、鍵盤からキーカバーを退けながら司は答えた。
「使用許可取ったけど?」
「っ……! それ先に言ってくれないかなあ?!」
「いやいや、この情報、別にお前には必要ないでしょ」
「無駄に神経使っただろ!?」
「知らんよ」
ケラケラと笑う司を不満げに睨み付ける。それでもピアノの前に座る司の姿は、そのすべてをチャラにしてしまえるくらいには絵になっていて、那月は諦めたようにずるずるとその場にしゃがみ込んだ。
司が鍵盤を叩くのに合わせて音が広がる。ふわりと色付く旋律がその場の空気を彩っていく。ああ、やっぱり──綺麗だ。
鞄の中から引っ張り出したスケッチブックとペンケースを手にピアノに近寄ると、那月は司の座る椅子の、その半分を奪うように横から腰を下ろした。奏でる音は止めないまま、それでも座る位置だけを横にずらした司の肩に、那月は軽く体重を預けるように寄りかかった。
「重いんだけど」
苦笑する司に無言を返し、ペンケースから鉛筆を取り出す。開いたページに鉛筆を走らせながら、那月はそっと目を細めた。
音楽室を満たす音がキラキラと弾けて、白いページに色彩を落とす。
ピアノの旋律の裏にかすかに聞こえる、スケッチブックの上を軽やかに走る鉛筆の音に、司は口元に小さく笑みを浮かべた。
「役に立った?」
突然聞かれ、那月の身体が弾かれたように背筋を伸ばす。
「ピアノ」と続けられた司の言葉に、那月はふっと身体の力を抜いた。
「何だっけ? それ」
「重症で、面倒くさいことになってたんだろ? 多少は解消できた?」
言われ、ああそうか……と、まるで他人事のように、真っ白いままだったキャンバスを思い出した。それから手元のスケッチブックに視線を落とし、そこに色付く淡いイメージに苦笑する。
何がきっかけだった? ピアノなのか、司なのか。それとも司の弾くピアノなのか。もう何でもいい。どれだって構わない。大事な友人──上等じゃないか。
「ああ……助かった。ありがとう」
どこか吹っ切れたような、無防備な笑みを浮かべて言う那月に、思わずミスタッチに手が止まる。突然の静寂に、不思議そうに振り返った那月と司の視線が思いがけずぶつかり、ほんの数秒の沈黙を挟んで、那月の視線が耐えきれずにゆらりと揺れた。
「えーっと……何?」
「……もし違ったらごめん」
何をごめんされればいいのかわからず、「うん?」と那月が首をひねる
「お前って、……男が好きなの?」
たぶん、司は言葉を濁しただろうと、そんなことを考えながら、ははっと那月は笑った。
「あーうん。バレたか」
なるべく重苦しくならないようにと軽い調子でうなずいたところで、「そっか」とだけ短く返され、「え?」と思わず聞き返す。
「え?」とさらに聞き返され、那月は目を瞬かせた。
「それだけ?」
たずねる那月に、司が首をかしげる。
「それだけ? って、それ以外俺にどんな反応をしろと?」
「いや、もっとこう……驚くとか、引くとかさ? あるじゃん?」
「あるの?」
「いや、あるでしょ」
あるかな? と首をひねってから、改めて司は口を開いた。
「男も女も、どっちでもよくない? 男だから好きになるわけじゃなくて、好きになるのがたまたま男だったってだけでしょ?」
言いながらピアノを弾き直す司の耳に、はぁ……と深いため息が聞こえ、続けてすぐに、「最悪」と那月が小さく言った。
「それ、本気で言ってる?」
「何が?」と短く聞き返しながら顔を上げたところで、とんっと譜面台にスケッチブックを置かれ、司はちらと那月に目を向けた。
「男が好きって、お前その意味ちゃんとわかってる?」
思いがけず真剣な目で見返され、鍵盤を叩く手が止まった。沈黙の落ちた音楽室に、校内の喧騒が遠く流れ込んでくる。
「大事な友人でいいじゃん。それって上等じゃん。って……思った、ばっかなのに」
「那月……?」
「そこに自分も含まれるって、考えたことある?」
伸ばした手をスケッチブックにかけたまま、それを支えに上体を屈める。司の顔をのぞき込むようにしながら、那月は続けた。
「言わないと伝わんないって言ったの、お前だからな」
言葉が途切れると同時に、那月の唇が司の唇に触れる。すぐにゆっくりと離れていったその感触を確かめる間もなく、上体を起こした那月がつぶやくように口を開いた。
「帰る」
くるりと踵を返し、床に投げ置いていた通学鞄をひっつかむと、那月は逃げるように音楽室を後にした。
その背中を目で追うこともできず呆けたまま、司はそっと息を吐きだした。言葉を濁さず、俺が好きなの? と聞いてもよかったのかもしれない。
「いやでも、まさかいきなりキスされるとは思わなかったし」
驚きは、もちろんある。けれど不快だったかと聞かれるとそういうわけでもない。
案外平気なもんだな──いや、相手が那月だからか。
そんなことを思いながら譜面台に置かれたスケッチブックを手に取り、何とはなしにその表紙をぱらりとめくる。その瞬間視界に飛び込んできたのは、淡く優しいタッチで描かれた水彩画で、ページをめくるごとに、そこにはいくつもの彩の異なる鮮やかな世界が広がっていた。
「へぇ……」と小さくつぶやく。
那月の描いた絵をちゃんと見るのは、そういえば初めてかもしれない。
一枚ずつ丁寧にページをめくり、あれ? と司は首をかしげた。白紙のページを数枚挟み、これまでとは少しだけ雰囲気の違う絵に視線を落とす。その隅に鉛筆で書かれた小さな文字に、司は知らず、ふっと目を細めていた。
「音楽わかりませんって感じだったのに、わざわざ調べたのかな。俺に聞けばいいのに」
それは冬休みの学校で初めて顔を合わせたあの日、カラフルだと、夏の水彩画のようだと、那月がそう言ってくれたピアノの曲名だった。
校舎裏を見下ろす側にあるフェンスに背を預け、ずるずるとその場に腰を下ろす。
「参ったなあ……」
言いながら空を見上げた那月は、そのまま目を閉じ深いため息をついた。
幼少の頃から父親の帰宅を待って、自宅でひとり絵を描いて過ごす時間は多かった。その下地になるのは家の中に当たり前に存在するものや、そこから見える風景、音。学校の帰り道に見えたものなど何でもよかったし、だからこそ描くことに困ることもなかった。
それが今はどういうことだ? 一体何があった? こんなにも何のイメージも浮かばないのは初めてで、特に意図することもなく、ただ何とはなしに最近描いた絵の数々を思い浮かべた。そしてすぐに、自嘲するように苦笑する。思い出すそのほとんどがピアノの音と共にあることに気付き、「重症だな」とつぶやいたところで、ふと瞼の裏に落ちてきた影に那月は薄く目を開けた。
「……司?」
のぞき込むように自分を見下ろしてくる司に、首をかしげ、続ける。
「何してんの?」
「お前が屋上に上がってくの、見えたから」
言いながら差し出された缶コーヒーを受け取り、視線を落としてから那月は眉を寄せた。
「……無糖って書いてありますけど?」
「ブラック。って言ってみたいんでしょ?」
「だからって飲めないんじゃ意味ないし、そもそも俺何も言ってない」
「確かに」
笑いながらそう言うと、司は那月の手からひょいとそれを奪い取り、手持ち無沙汰に緩く開かれたままのその手に自分の持っていた缶コーヒーを渡した。
「はい、交換」
『無糖』と印字されたコーヒー缶を手の中で弄びながら那月の隣に腰を下ろし、続ける。
「なーんか面倒くさそうな顔してるけど?」
「実際面倒くさいことになってんだよ」
一部お前のせいでな……とは言わないまま、那月は『カフェラテ』と印字された缶コーヒーのプルトップを引き起こした。
「ふぅん」と小さくつぶやいてからちらと那月に目を向け、「で?」と短く聞いてくる司に、「え?」と那月も聞き返す。
「何が重症なの?」
「聞いてたのかよ……」
「人聞きの悪い。聞こえちゃっただけよ」
言いながらケラケラと笑う司に、肩を落とし息をついたところで、「で?」と思いがけず優しい声で司に聞き直され、那月は顔を上げた。
「俺に何か手伝えることある? 治療? わかんないけど」
促すように向けられた笑みに、那月は頬に熱が集まるのを感じながら、思わず司からぱっと視線を逸らした。
勘違いするな。これはただ、弟妹に優しいのと同じなんだから──自分にそう言い聞かせるようにゆっくりと息を吐き出してから、那月は不思議そうに首をかしげる司に苦笑を返した。
「それはいくつの弟? あ、妹か?」
「え?」と何度か目を瞬かせてから、「ああ」と司は小さく笑った。
「高二。俺の大事な友人」
「っ……! お前さあ……」
司の言葉に大きく息をつき、那月は喜ぶべきなのか悲しむべきなのか、どうにも複雑な感情のまま、背後のフェンスに背中を預け直した。
「恥ずかしいやつ。こっちが照れるわ」
「口にしなきゃ伝わらないことってたくさんあるじゃん? 察してくれ、なんて自分都合なこと言いたくないし、言われても俺も困るし。だったら潔く言っちゃった方がいい気しない? 伝わらないことを相手のせいにしたくもないしさ」
「じゃあもし……」
両手で包み込むように持ったコーヒー缶に、那月が視線を落とす。
「うん?」と先を促してくる司に、けれど那月は「何でもない」と軽く首を横に振り言葉を呑み込んだ。
「うわあ、気になる。まぁ、いいけど」
手にした缶コーヒーのプルトップを引き起こしながら、司はちらと那月を盗み見、口を開いた。
「で、どうよ? お前のここに寄ってるしわの理由、俺に話してみる気ないの?」
自分の眉間に指先を当て、そこに視線を寄せるようにしながら司がたずねる。
「ない」と短く答える那月に、司は「あっそ」とそれ以上食い下がることはしなかった。
「でも」
那月が続ける。
「ピアノ、聞かせてよ」
「え?」
「司のピアノ、聞きたい」
「そりゃ別に構わないけど……学祭終わるまで、たぶん音楽室使えないんだよね」
「そうなの?」
「使えないっていうか、部活で使われてるっていうか」
「今までは?」
「部活ない時に勝手に借りてただけ」
「……勝手に?」
司の言葉に思わず聞き返す。
「あれ? 知らなかった? 教室使うのに使用許可取る必要があるって。まぁ俺は取ったことないけど」
ケラケラと笑ってから司は続けた。
「今は学祭の練習で、部活でほぼ毎日使われてるんだよね」
「そっか」と小さく肩を落とす那月を横目に、司はコーヒーを口に含みながら何かを考えるように空を仰いだ。
翌日、午前中の授業を終え、椅子の背もたれに体重を預けて小さく息をついたところで机の上に落ちてきた影に、那月は顔を上げた。
「ちょっと付き合わない?」
軽く首をかしげるようにしながら言ってくる司に、「何?」と怪訝に眉を寄せる。
「いいから」と机の横にかけてあった那月の通学鞄を取ると、司はそれを肩に担ぐようにしながら、振り返ることもせずさっさと教室を出ていった。
わけもわからないまま司を追いかけ、その足が止まった先の教室のプレートを見上げ、那月は眉をひそめた。
「音楽室? 部活してんじゃないの?」
「昼休みはさすがにやってないみたいだな」
言いながら押し付けられた通学鞄を胸に抱え、那月はちらと司に視線をやった。司が何を考えているのかまったくわからないまま、「えーっと……」と目を瞬かせる。その視線の先で躊躇なく音楽室に入っていく司に、そのあとに続いて音楽室に入ろうとした那月の足が躊躇うようにぴたと止まった。
今まで気にもしていなかったけれど……使用許可が必要と聞いてしまったせいで、何となく入りづらい。
廊下で足を止めたままの那月を肩越しに見て、ふっと目を細めて司が笑う。
「気になんの?」
茶化すように言ったところで何も言い返してはこないまま、それでも音楽室に入ってきた那月に、司は小さく笑った。そのままピアノに足を向け、慣れた手つきでグランドピアノの屋根を持ち上げる。
その様子を見ながら、「あれ……?」と那月がつぶやいた。
「何?」
「ピアノのその、ふた? の部分開けてるの、始めて見たかも」
「ああ、よく覚えてんね。勝手に借りてる時はすぐ逃げられるように、屋根開けないからさ」
しれっと答える司に、「ん?」と首をかしげる。
「今日は?」と続ける那月に、鍵盤からキーカバーを退けながら司は答えた。
「使用許可取ったけど?」
「っ……! それ先に言ってくれないかなあ?!」
「いやいや、この情報、別にお前には必要ないでしょ」
「無駄に神経使っただろ!?」
「知らんよ」
ケラケラと笑う司を不満げに睨み付ける。それでもピアノの前に座る司の姿は、そのすべてをチャラにしてしまえるくらいには絵になっていて、那月は諦めたようにずるずるとその場にしゃがみ込んだ。
司が鍵盤を叩くのに合わせて音が広がる。ふわりと色付く旋律がその場の空気を彩っていく。ああ、やっぱり──綺麗だ。
鞄の中から引っ張り出したスケッチブックとペンケースを手にピアノに近寄ると、那月は司の座る椅子の、その半分を奪うように横から腰を下ろした。奏でる音は止めないまま、それでも座る位置だけを横にずらした司の肩に、那月は軽く体重を預けるように寄りかかった。
「重いんだけど」
苦笑する司に無言を返し、ペンケースから鉛筆を取り出す。開いたページに鉛筆を走らせながら、那月はそっと目を細めた。
音楽室を満たす音がキラキラと弾けて、白いページに色彩を落とす。
ピアノの旋律の裏にかすかに聞こえる、スケッチブックの上を軽やかに走る鉛筆の音に、司は口元に小さく笑みを浮かべた。
「役に立った?」
突然聞かれ、那月の身体が弾かれたように背筋を伸ばす。
「ピアノ」と続けられた司の言葉に、那月はふっと身体の力を抜いた。
「何だっけ? それ」
「重症で、面倒くさいことになってたんだろ? 多少は解消できた?」
言われ、ああそうか……と、まるで他人事のように、真っ白いままだったキャンバスを思い出した。それから手元のスケッチブックに視線を落とし、そこに色付く淡いイメージに苦笑する。
何がきっかけだった? ピアノなのか、司なのか。それとも司の弾くピアノなのか。もう何でもいい。どれだって構わない。大事な友人──上等じゃないか。
「ああ……助かった。ありがとう」
どこか吹っ切れたような、無防備な笑みを浮かべて言う那月に、思わずミスタッチに手が止まる。突然の静寂に、不思議そうに振り返った那月と司の視線が思いがけずぶつかり、ほんの数秒の沈黙を挟んで、那月の視線が耐えきれずにゆらりと揺れた。
「えーっと……何?」
「……もし違ったらごめん」
何をごめんされればいいのかわからず、「うん?」と那月が首をひねる
「お前って、……男が好きなの?」
たぶん、司は言葉を濁しただろうと、そんなことを考えながら、ははっと那月は笑った。
「あーうん。バレたか」
なるべく重苦しくならないようにと軽い調子でうなずいたところで、「そっか」とだけ短く返され、「え?」と思わず聞き返す。
「え?」とさらに聞き返され、那月は目を瞬かせた。
「それだけ?」
たずねる那月に、司が首をかしげる。
「それだけ? って、それ以外俺にどんな反応をしろと?」
「いや、もっとこう……驚くとか、引くとかさ? あるじゃん?」
「あるの?」
「いや、あるでしょ」
あるかな? と首をひねってから、改めて司は口を開いた。
「男も女も、どっちでもよくない? 男だから好きになるわけじゃなくて、好きになるのがたまたま男だったってだけでしょ?」
言いながらピアノを弾き直す司の耳に、はぁ……と深いため息が聞こえ、続けてすぐに、「最悪」と那月が小さく言った。
「それ、本気で言ってる?」
「何が?」と短く聞き返しながら顔を上げたところで、とんっと譜面台にスケッチブックを置かれ、司はちらと那月に目を向けた。
「男が好きって、お前その意味ちゃんとわかってる?」
思いがけず真剣な目で見返され、鍵盤を叩く手が止まった。沈黙の落ちた音楽室に、校内の喧騒が遠く流れ込んでくる。
「大事な友人でいいじゃん。それって上等じゃん。って……思った、ばっかなのに」
「那月……?」
「そこに自分も含まれるって、考えたことある?」
伸ばした手をスケッチブックにかけたまま、それを支えに上体を屈める。司の顔をのぞき込むようにしながら、那月は続けた。
「言わないと伝わんないって言ったの、お前だからな」
言葉が途切れると同時に、那月の唇が司の唇に触れる。すぐにゆっくりと離れていったその感触を確かめる間もなく、上体を起こした那月がつぶやくように口を開いた。
「帰る」
くるりと踵を返し、床に投げ置いていた通学鞄をひっつかむと、那月は逃げるように音楽室を後にした。
その背中を目で追うこともできず呆けたまま、司はそっと息を吐きだした。言葉を濁さず、俺が好きなの? と聞いてもよかったのかもしれない。
「いやでも、まさかいきなりキスされるとは思わなかったし」
驚きは、もちろんある。けれど不快だったかと聞かれるとそういうわけでもない。
案外平気なもんだな──いや、相手が那月だからか。
そんなことを思いながら譜面台に置かれたスケッチブックを手に取り、何とはなしにその表紙をぱらりとめくる。その瞬間視界に飛び込んできたのは、淡く優しいタッチで描かれた水彩画で、ページをめくるごとに、そこにはいくつもの彩の異なる鮮やかな世界が広がっていた。
「へぇ……」と小さくつぶやく。
那月の描いた絵をちゃんと見るのは、そういえば初めてかもしれない。
一枚ずつ丁寧にページをめくり、あれ? と司は首をかしげた。白紙のページを数枚挟み、これまでとは少しだけ雰囲気の違う絵に視線を落とす。その隅に鉛筆で書かれた小さな文字に、司は知らず、ふっと目を細めていた。
「音楽わかりませんって感じだったのに、わざわざ調べたのかな。俺に聞けばいいのに」
それは冬休みの学校で初めて顔を合わせたあの日、カラフルだと、夏の水彩画のようだと、那月がそう言ってくれたピアノの曲名だった。