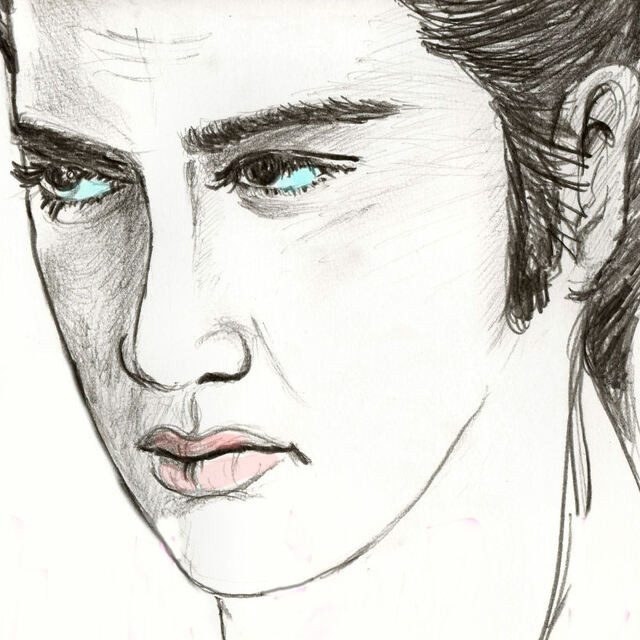第15話 救急車がきて
文字数 1,817文字
ダンス教室で頭から床に倒れた美鶴は、竜也の冷静な判断と処置によって危険な状態はなんとか避けることができた。美鶴が床に倒れこむときに、真っ逆さまに頭から落ちていたら、美鶴の命は危なかったかもしれない。
後頭部を強打すれば、彼女のこれからの生活はダンスどころではない。そうでなくても、下手をすれば首の骨を折っていたのかもしれないのだ。もし、美鶴が倒れ込んだ床が道路のコンクリートや、固いものだとしたら美鶴の命の再生はなかったのかもしれない。
美鶴が、踊っていた慎二の手からすり抜けるときに、反射的に少し身体を捻ったのが 不幸中の幸いだった。場合によっては、最悪のことも考えられたからである。
それにしても、美鶴は意識を失っていた。美しい顔は歪み口からは、何かを出していた。竜也はそれを丁寧に拭き取った。
もし、異物が器官をふさいだら、窒息を避けるための措置をしなければならないが、その心配はなさそうである。
竜也の手で赤い口紅が拭き取られると、美鶴の派手な顔付きは少し変わって見えた。 いつも、自信たっぷりな顔つきで、生き生きしている美鶴は別人だった。目をつぶり歪んだ顔で床に横たわる彼女は、他人のようだった。
竜也が美鶴の腕の脈拍を測り、心臓の辺りに手を当てると、それはしっかりと鼓動していた。どうやら命に別状は無いようである。
ダンスといっても、こういう状態で頭から倒れ込んだ場合に、最悪の状態になるケースもあるからだ。
ただし、この状態で今、楽観は出来ない。病院で適切な処置をし、頭部のレントゲンを撮って骨折の有無を確かめなければならないし、視覚や記憶、言語に異常がないか観察をしなければならない。
このままの状態で、目覚めない場合もあるし、記憶の障害になることもある。現に、美鶴は完全に意識を失っているのだから。
床に横たわっている美鶴を、心配そうに見つめている友梨の気持ちは複雑だった。始めは、自分のパートナーでもある慎二と美鶴が、華麗にダンスを踊っていたときにはジェラシーを感じていたのだ。
慎二を信じていただけに、まさか彼が美鶴と踊るとは思ってもいなかった。心の中では、美鶴に(滑って倒れて欲しい)と思ったのは事実である。そうしなければ、今まで自分が慎二と組んできたカップルという立場が、もろくも崩れてしまうと思ったからだった。
その結果、美鶴は支えるべきダンス相手の慎二の手をすり抜けて、床に倒れてしまったのだ。まさにこれは、友梨が想い描いていたことだった。
しかし、友梨の思い通りに床に倒れ込んでいる美鶴をみて自分は喜んでいて良いのだろうか。もちろん違う、そんなわけが無い。
自分は、こんな惨めになった姿の美鶴を想像したわけでは無いのだ。ただ、慎二が自分のパートナーだけであって欲しかった、それだけである。
こんな美鶴になることを望んでいたわけでは無い。そんなことを心の中で思っていた自分が、自分自身が友梨は嫌になった。この教室では誰からも慕われる優しい自分が、自分さえ良ければいいという仮面を被った女だと思うと情けなく、心から美鶴に申し訳ない気がした。
その友梨の眼には、いつしか涙が溢れていた。そして思うのである。
(こんな気持ちで、これからも慎二さんとダンスをしてもいいのだろうか?)
床の上に横たわる美鶴をみながら友梨は涙が止まらなかった。やがて、遠くの方から救急車の音がしてきた。
車は階下の入り口で止まり、タンカーを持った救急隊員が二階のダンスフロアに入ってきた。オーナーの深山暁代が、近づきオロオロしながら対応している。
「あ、ご苦労様です、あそこです」
「分かりました、あ……あそこですね」
「はい、よろしくお願いします」
白いヘルメットを被った隊員はキビキビとしていた。彼は暁代から状況を聞きながら、美鶴を凝視した後、ライトペンで瞳孔を見たり、脈拍をはかったりしていた。
「適切な対応をしておられるので、今のところ大事には至っていないように思われます」
「よかった……」
美鶴を心配そうに見つめていたダンス仲間が安堵の声を漏らした。
「しかし、詳しく検査をしてみなければわかりませんが」
「はい、美鶴ちゃんをよろしくお願いします」
いつも、堂々としている暁代は隊員に神妙に深々と頭を下げていた。
こうして、美鶴は救急車に乗せられて病院に向かった。その車に友梨が一緒に乗り込んだのである。
後頭部を強打すれば、彼女のこれからの生活はダンスどころではない。そうでなくても、下手をすれば首の骨を折っていたのかもしれないのだ。もし、美鶴が倒れ込んだ床が道路のコンクリートや、固いものだとしたら美鶴の命の再生はなかったのかもしれない。
美鶴が、踊っていた慎二の手からすり抜けるときに、反射的に少し身体を捻ったのが 不幸中の幸いだった。場合によっては、最悪のことも考えられたからである。
それにしても、美鶴は意識を失っていた。美しい顔は歪み口からは、何かを出していた。竜也はそれを丁寧に拭き取った。
もし、異物が器官をふさいだら、窒息を避けるための措置をしなければならないが、その心配はなさそうである。
竜也の手で赤い口紅が拭き取られると、美鶴の派手な顔付きは少し変わって見えた。 いつも、自信たっぷりな顔つきで、生き生きしている美鶴は別人だった。目をつぶり歪んだ顔で床に横たわる彼女は、他人のようだった。
竜也が美鶴の腕の脈拍を測り、心臓の辺りに手を当てると、それはしっかりと鼓動していた。どうやら命に別状は無いようである。
ダンスといっても、こういう状態で頭から倒れ込んだ場合に、最悪の状態になるケースもあるからだ。
ただし、この状態で今、楽観は出来ない。病院で適切な処置をし、頭部のレントゲンを撮って骨折の有無を確かめなければならないし、視覚や記憶、言語に異常がないか観察をしなければならない。
このままの状態で、目覚めない場合もあるし、記憶の障害になることもある。現に、美鶴は完全に意識を失っているのだから。
床に横たわっている美鶴を、心配そうに見つめている友梨の気持ちは複雑だった。始めは、自分のパートナーでもある慎二と美鶴が、華麗にダンスを踊っていたときにはジェラシーを感じていたのだ。
慎二を信じていただけに、まさか彼が美鶴と踊るとは思ってもいなかった。心の中では、美鶴に(滑って倒れて欲しい)と思ったのは事実である。そうしなければ、今まで自分が慎二と組んできたカップルという立場が、もろくも崩れてしまうと思ったからだった。
その結果、美鶴は支えるべきダンス相手の慎二の手をすり抜けて、床に倒れてしまったのだ。まさにこれは、友梨が想い描いていたことだった。
しかし、友梨の思い通りに床に倒れ込んでいる美鶴をみて自分は喜んでいて良いのだろうか。もちろん違う、そんなわけが無い。
自分は、こんな惨めになった姿の美鶴を想像したわけでは無いのだ。ただ、慎二が自分のパートナーだけであって欲しかった、それだけである。
こんな美鶴になることを望んでいたわけでは無い。そんなことを心の中で思っていた自分が、自分自身が友梨は嫌になった。この教室では誰からも慕われる優しい自分が、自分さえ良ければいいという仮面を被った女だと思うと情けなく、心から美鶴に申し訳ない気がした。
その友梨の眼には、いつしか涙が溢れていた。そして思うのである。
(こんな気持ちで、これからも慎二さんとダンスをしてもいいのだろうか?)
床の上に横たわる美鶴をみながら友梨は涙が止まらなかった。やがて、遠くの方から救急車の音がしてきた。
車は階下の入り口で止まり、タンカーを持った救急隊員が二階のダンスフロアに入ってきた。オーナーの深山暁代が、近づきオロオロしながら対応している。
「あ、ご苦労様です、あそこです」
「分かりました、あ……あそこですね」
「はい、よろしくお願いします」
白いヘルメットを被った隊員はキビキビとしていた。彼は暁代から状況を聞きながら、美鶴を凝視した後、ライトペンで瞳孔を見たり、脈拍をはかったりしていた。
「適切な対応をしておられるので、今のところ大事には至っていないように思われます」
「よかった……」
美鶴を心配そうに見つめていたダンス仲間が安堵の声を漏らした。
「しかし、詳しく検査をしてみなければわかりませんが」
「はい、美鶴ちゃんをよろしくお願いします」
いつも、堂々としている暁代は隊員に神妙に深々と頭を下げていた。
こうして、美鶴は救急車に乗せられて病院に向かった。その車に友梨が一緒に乗り込んだのである。