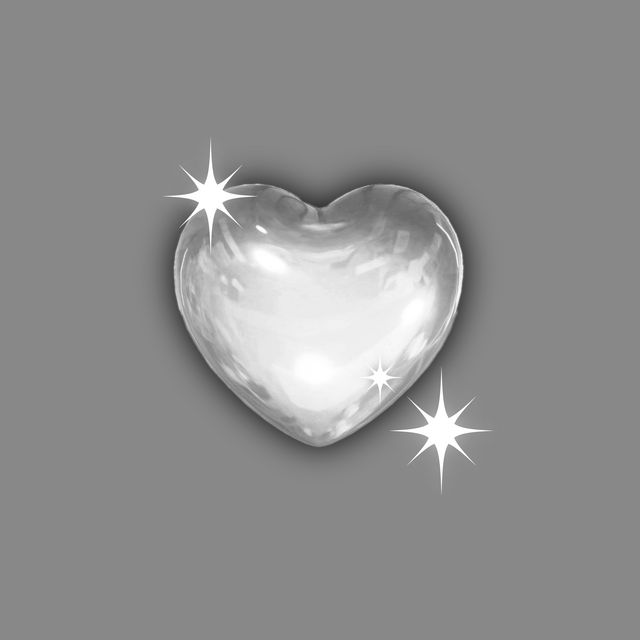第2話
文字数 5,238文字
人生に病んでいるわけでもなく、かといって特別な希望を抱いているわけでもなかった。普通の家族仲。生活のためと割り切った向上心皆無の仕事。安定した衣食住。楽しみは海外ドラマ。直近で傷ついたことといえば、半年前の婚約破棄。あとはペットのハムスターが死んだ。私の日々はそんな感じだった。ただ、なぜだろう。なんとなく物足りない。というよりむしろ有り余っていた。
私は、今日に明日が重なっていくのに飽きていた。いっそすべてが突然終わればいい。そんな漠然とした願望があった。だけど犯罪や自殺はおろか、転職や引っ越しでさえ踏み出す気力も勇気もなかった。私は地面に寝そべり、運良く食べられるのを待ちながら息をする野生動物のようなものだった。
そんなものぐさな破滅願望に都合良く寄り添うようにして現れた中野。彼と再会した夜の雨から3日後。おそらく、日本中のスマートフォンが一斉に鳴った。私のものもそうだった。画面を覗き込むと「彗星により1ヶ月以内に世界滅亡か」という文字が並んでいた。緊急アラートだった。
「何これ。なんかの配信テスト?」
職場の同僚は半笑いで言った。世界滅亡、って。納期より先に滅亡すんのかな? と。椅子で伸びをする彼に「お疲れさま」と笑った。内心で思い浮かんだのはあの日の中野のどこか申し訳なさそうな顔だ。私のブラウスの下で鳥肌が立っていた。
間も無く開かれた緊急会見で、彗星の衝突時刻も導き出されたことがわかった。日本時間で言えば11月27日の21時34分10秒。座標は忘れたけど、よりによって太平洋の若干日本列島寄りを目掛けて落下中らしい。すべてが収束するその日その瞬間に向かって、人々は突然、見えない何かから解き放たれたのだった。
初めは誰も信じていなかったと思う。私が中野の話を笑ったように、地球の滅亡なんて。世界規模の悪戯なんじゃないか。何かのメッセージなんじゃないか。本当だとしたら生き残る方法はあるのか。そもそも初めから陰謀だ──さまざまな思惑が溢れかえった。茶化して済ませようとする人間もいれば、深刻に騒ぎ立てる人間もいた。結局「で、どうしよう」といった決定打に欠ける雰囲気に満ちていた。
昨日と今日とで日常を切り替えるのはきっと難しい。朝は見慣れた犬が老人と散歩をしていたし、電車もバスも動いていたし、ネット環境も変わらずWi-Fiは宙を飛ぶ。こんなときでさえ通学、通勤を続ける日本という国だった。私も悲しく真面目なそのひとりだ。滅亡まで残り何日何時間何秒! ビルのモニターに大きく映し出されたカウントダウンを眺めながら、私は職場と自宅の往復を続けた。
私は中野にもう一度会いたかった。会って、口から出まかせのような彼の話をもっと聞いてみたかった。滅亡に関するニュースを目にするたびに思う。真実なんて別に偉くはない、と。なぜなら地球が本当に滅亡するのなら、この騒動の真相を後で誰かと語り合うことはできないからだ。だったらいっそ、いちばん意味不明で手触りの良さそうなものを心の拠り所にしたかった。確かなのは、あの日、中野の声が心地良かった。だから私は耳を傾けた。その二つだった。
そして、機会はすぐに訪れた。数日後、職場からの帰り道。あの日と同じく、コンビニの駐車場の片隅でたたずむ彼を私は見かけた。
「……中野」
一億二千万人の中に溶け込んだ自称・宇宙人。彼はまだ景色で、彼のことなんてほとんど何も知らない。宇宙人ということ以外には。わずかに受け入れている一方、まだ何も信じられない。すべて適当なのかもしれない。そういえば借りたタオルをまだ返していない。そう思ったとき「あぁ、早見さん」と柔らかな低い声がした。手のひらに汗を感じた。緊張している、と思った。
「中野。本当だったんだね。あの後に雨が止んだのも、滅亡のニュースが流れるのも」
「でしょ」
中野は別に驚いた様子もなさそうに言った。視線は遠くのどこかへ向けられている。かと思うと、突然、私を見下ろした。
「早見さんは、あの夜から何か変わった?」
返す言葉がわからず黙った。地球が終わるという怒涛の展開を、私はただ他人事のように眺めている。多分、そうすることで怖がっている。私が変わるのだとしたら、周りがどのように変わったかを知った後のような気がする。
「わかんない。なんかぼーっとしてたら世界が終わっちゃいそう」
「へー。早見さんって案外マイペースなんだね」
そう言われ笑った。マイペースだなんて、中野に言われると変な気分だった。
「あ、ちょっと待って」
突然、歩き出した中野にそう言った。まだ何か話し足りないような気がし、それ以上に聞き足りないことが有り余り、私は慌てて後をついて行った。あの日とは違い、今度は私が追いかける番だった。中野は一瞬だけ歩みを止め、私が追いつくのを待ってくれた。
「行こ。早見さん」
私は頷いた。どこに、とは聞かずに歩いた。この人は宇宙人です。彗星は彼が落としたらしいです。秘密を見せびらかしたいような、容疑者を匿うような矛盾したそんな気持ちで終わりかけの街を歩いた。道端から爆音のクラブミュージックが流れていた。若者の集団が踊り狂い、発狂しているのか興奮しているのか両方なのか、何かを叫んでいる。ビルに向かって石を投げつけ、ガラスを次々に割っている。そんな遊びに興じている。楽しそうだなと足元のガラスを踏みながら思った。
「危ない」
横断歩道を渡ろうとしたとき、中野は私を止めた。瞬間、目の前を何台もの車が走り抜けていった。最近は車もバイクも赤信号を堂々と無視をするから、気を付けなくてはいけない。緩やかな崩壊を始める秩序。救急車のサイレンの音が遠くで聞こえた。道を空けてください。通ります。そして再びガラスの割れる音。子どもが泣く大きな声が生々しい。
無法地帯を楽しむ人と日常を守ろうとする人で、すでに世の中は二分されていた。私はどちらでもなかった。ただ、滅亡を意識した途端、人の量が多く感じられるのが不思議だった。人類全員と別れる。その諦めがむしろ存在感をかき立てている気がする。死の予感が生を引き立てるように。
まだ動いている電車に乗り、3駅ほど移動した。やがて中野と私は、ほとんど誰もいないグラウンドにたどり着いた。大量のゴミや燃やされた何かが辺りには散らばっていた。サッカーや草野球で賑わうありふれたグラウンドも過去の話になりかけているのだろう。お菓子やパンの袋、空き缶、大量の薬のシートや注射器に混ざって、なぜかコンドームの空箱が潰れていた。避妊しようがしまいがどこにも着床しない精子。私は溜め息をつき、適当なベンチに腰掛ける。
「そうだ。早見さんにはもうひとつ教えてあげる」
足元のビールの空き缶を蹴った後で、中野は言った。
「滅びる日の夕方、僕を迎えにここに宇宙船が来るんだ。社用ロケット。僕はそれで故郷に帰る」
中野はグラウンドの中央、一面に広がる茶色い土を眺めていた。
「何億光年か離れた場所から、地球の最期を見るんだ」
中野は今日も心地良い声で言った。そうなんだ、と乾いた声が出た。
「だけど、ここで死ぬ私にそれを言って何か意味あるの?」
「あ、そうだね。……ごめん」
中野は申し訳なさの欠片もなさそうに私の隣に座った。
「一緒に連れて行ってあげたいけど、地球人は僕の星では暮らせないんだ。身体的に」
「別にいいよ」
私は中野の横顔を見上げた。何を考えているのかわからない。宇宙人、中野。滅亡を前に混乱する私たちに対し、あくまで見納めにやって来たという中野。彼だけが冷静なのか、狂っているのか、一体どちらなのだろう。彗星は今頃どこにいるのだろう。見上げてみても、始まりかけた夜の薄い群青が広がっているだけだった。
「僕の故郷は多分あの辺りなんだよね」
中野は空を指差し、言った。星ひとつ消すことに何の後悔も反省も抱いていないであろう彼を前に、私は複雑な気持ちになっていた。宇宙船が来るなんて信じられない。中野を疑うこともできない自分自身は、それ以上に意味がわからない。いっそ私も何かとんでもない何かをしてみたい。そう思い、殺人や強盗、放火といったありったけの罪を思い浮かべたものの、どんな罪の魅力も爽快感も中野の前では霞んだ。地球を滅ぼすことに比べればすべてのスケールが小さい。
「……お腹空いた」
私は立ち上がった。その足で近くのドラッグストアとスーパーへ向かった。私は飢えにも似た焦りを感じ始めていた。日常は終わるというのに、その何かがわからずもどかしい。苛立ってもいた。だけど、身体は身体のまま、空腹を音で知らせていた。中野は私の後をついてきた。宇宙人というより大きな犬のように。目についた食料品を次々とカゴに入れ、私はそのまま店を出た。人生初めての万引きだった。グラウンドに戻ると、何だか楽しくなって笑いが溢れた。私は小さい人間だと思う。地球が終わる。こんなときに勇気を振り絞ることが、金を払うのを止めることだなんて。
「中野。食べよ」
「いいね。ありがとー」
もう痩せる必要もないから、私は手に入れたスナック菓子をひたすら口へ運んだ。きっと人生最後のピクニックだった。結局すぐに味に飽き、最後は適当に飴を口の中へ放り込んだ。舐め慣れた苺の味を身体中に広げながら夜空を眺めた。小さい頃、お母さんがよく買ってくれた飴だ。そう思うと急に悲しい。思わず涙ぐんだせいで、遠くの星がぼやけた。この苺は今、星の味だと思った。
「中野は思ってるよりずっとやばい奴だって、中学生の自分に教えてあげたいな。だって宇宙人なんでしょ?」
涙声で私は言った。泣く予定なんてなかった。それよりも中野が慌てていることの方が想定外だった。
「早見さん。地球、滅ぼしちゃってごめんね」
「仕方ないよ。仕事なんだから」
「そうだけど……。あんまり深く考えてなかったんだよね」
中野はそう言うと、親指の腹で涙を拭ってくれた。星ひとつ無くす男にはそぐわない、繊細な動作だった。
「中野は地球でやり残したこと、ないの?」
「もう行きたい場所には行ったし、会いたい人には会ったから」
「どこに行ったの?」
「海。海はいいよね。地球の綺麗なところが凝縮されてる気がして、昔から好きだったんだ」
「そっか。あとは誰に会ったの?」
「昔のバイト先のオーナー。仕事できなさすぎてクビになっちゃったけど、楽しかったんだ。それから早見さん」
中野はそこで一度、言葉を区切った。
「なんだか無性に早見さんに会いたかったんだ。あの日、会えてよかった」
そして彼はさらに呟いた。やり残したこと、か。
「あとはセックスかな」
「え?」
「地球人とはしたことないんだよね。僕は地球人童貞」
しばらくの間、中野がスナック菓子を咀嚼する音だけが現実的に響いた。やがて黙りこくる私を彼は見た。
「冗談だよ。大丈夫だよ。今、早見さんを押し倒したりなんかしないよ」
そう言われても彼が冗談を言うこと自体が冗談に思え、食べているスナックのように軽い言葉に何も言えなかった。辺りを見回すと、遠くのベンチにカップルがいた。何かを示し合わせたようにふたりはキスを始めた。お幸せに、と私は思う。だけど、滅亡まで彼らはあと何回キスができるのだろう。そう考えると、腕を絡め合うシルエットから、聞こえるはずのない甘い言葉が聞こえてくるような気がする。
「中野」
私はふと何かを伝えたくなっていた。それが言葉以外のものである時点で手遅れだと心のどこかで理解し、同時に何が? とも思っていた。中野はすべてを予知していたかのような表情で私を見ていた。彼の話が本当なら、私たちは今、何光年もの距離を超えていることになる。彼に潜む地球外生命を、私は見つめることで感じようとしていたはずだった。気付けば中野とキスをしていた。唇が唇へ落ちる。これも地球の引力の作用なのだろうかと、塩辛さの中で思った。私の扱う物理なんてその程度だった。
「早見さんのしたいことなら、僕は付き合うよ」
唇が離れたとき、中野はそう言った。パーカーの袖を握りしめていて、私が彼を引き寄せたのだとわかった。
「じゃあ、もう一回」
私はそう言い、中野と唇を重ね続けた。宇宙人だからだろうか。彼の唇は血を忘れたかのように冷たい。何か本当どうでもいい。そう思いながら私は、地球を滅ぼすなどと言う男の唇を感じていた。キスが生み出す束の間の無重力は心地よかった。やがて中野は静かな溜め息をつき、変わらない声で言った。
「これ以上したら、元いた星に戻れなくなりそう」
「なら、これで終わりだね」
私はベンチにもたれかかった。いつの間にか遠くのカップルは姿を消していた。
「……早見さん」
突然、自分の片手を中野の両手で包まれ、私は驚いた。
「何?」
「そういえば今のが初めてのキスだ」
そう言われても地球が滅亡するまで後4日しかない。頭の中でガラスが割れる音がした。
私は、今日に明日が重なっていくのに飽きていた。いっそすべてが突然終わればいい。そんな漠然とした願望があった。だけど犯罪や自殺はおろか、転職や引っ越しでさえ踏み出す気力も勇気もなかった。私は地面に寝そべり、運良く食べられるのを待ちながら息をする野生動物のようなものだった。
そんなものぐさな破滅願望に都合良く寄り添うようにして現れた中野。彼と再会した夜の雨から3日後。おそらく、日本中のスマートフォンが一斉に鳴った。私のものもそうだった。画面を覗き込むと「彗星により1ヶ月以内に世界滅亡か」という文字が並んでいた。緊急アラートだった。
「何これ。なんかの配信テスト?」
職場の同僚は半笑いで言った。世界滅亡、って。納期より先に滅亡すんのかな? と。椅子で伸びをする彼に「お疲れさま」と笑った。内心で思い浮かんだのはあの日の中野のどこか申し訳なさそうな顔だ。私のブラウスの下で鳥肌が立っていた。
間も無く開かれた緊急会見で、彗星の衝突時刻も導き出されたことがわかった。日本時間で言えば11月27日の21時34分10秒。座標は忘れたけど、よりによって太平洋の若干日本列島寄りを目掛けて落下中らしい。すべてが収束するその日その瞬間に向かって、人々は突然、見えない何かから解き放たれたのだった。
初めは誰も信じていなかったと思う。私が中野の話を笑ったように、地球の滅亡なんて。世界規模の悪戯なんじゃないか。何かのメッセージなんじゃないか。本当だとしたら生き残る方法はあるのか。そもそも初めから陰謀だ──さまざまな思惑が溢れかえった。茶化して済ませようとする人間もいれば、深刻に騒ぎ立てる人間もいた。結局「で、どうしよう」といった決定打に欠ける雰囲気に満ちていた。
昨日と今日とで日常を切り替えるのはきっと難しい。朝は見慣れた犬が老人と散歩をしていたし、電車もバスも動いていたし、ネット環境も変わらずWi-Fiは宙を飛ぶ。こんなときでさえ通学、通勤を続ける日本という国だった。私も悲しく真面目なそのひとりだ。滅亡まで残り何日何時間何秒! ビルのモニターに大きく映し出されたカウントダウンを眺めながら、私は職場と自宅の往復を続けた。
私は中野にもう一度会いたかった。会って、口から出まかせのような彼の話をもっと聞いてみたかった。滅亡に関するニュースを目にするたびに思う。真実なんて別に偉くはない、と。なぜなら地球が本当に滅亡するのなら、この騒動の真相を後で誰かと語り合うことはできないからだ。だったらいっそ、いちばん意味不明で手触りの良さそうなものを心の拠り所にしたかった。確かなのは、あの日、中野の声が心地良かった。だから私は耳を傾けた。その二つだった。
そして、機会はすぐに訪れた。数日後、職場からの帰り道。あの日と同じく、コンビニの駐車場の片隅でたたずむ彼を私は見かけた。
「……中野」
一億二千万人の中に溶け込んだ自称・宇宙人。彼はまだ景色で、彼のことなんてほとんど何も知らない。宇宙人ということ以外には。わずかに受け入れている一方、まだ何も信じられない。すべて適当なのかもしれない。そういえば借りたタオルをまだ返していない。そう思ったとき「あぁ、早見さん」と柔らかな低い声がした。手のひらに汗を感じた。緊張している、と思った。
「中野。本当だったんだね。あの後に雨が止んだのも、滅亡のニュースが流れるのも」
「でしょ」
中野は別に驚いた様子もなさそうに言った。視線は遠くのどこかへ向けられている。かと思うと、突然、私を見下ろした。
「早見さんは、あの夜から何か変わった?」
返す言葉がわからず黙った。地球が終わるという怒涛の展開を、私はただ他人事のように眺めている。多分、そうすることで怖がっている。私が変わるのだとしたら、周りがどのように変わったかを知った後のような気がする。
「わかんない。なんかぼーっとしてたら世界が終わっちゃいそう」
「へー。早見さんって案外マイペースなんだね」
そう言われ笑った。マイペースだなんて、中野に言われると変な気分だった。
「あ、ちょっと待って」
突然、歩き出した中野にそう言った。まだ何か話し足りないような気がし、それ以上に聞き足りないことが有り余り、私は慌てて後をついて行った。あの日とは違い、今度は私が追いかける番だった。中野は一瞬だけ歩みを止め、私が追いつくのを待ってくれた。
「行こ。早見さん」
私は頷いた。どこに、とは聞かずに歩いた。この人は宇宙人です。彗星は彼が落としたらしいです。秘密を見せびらかしたいような、容疑者を匿うような矛盾したそんな気持ちで終わりかけの街を歩いた。道端から爆音のクラブミュージックが流れていた。若者の集団が踊り狂い、発狂しているのか興奮しているのか両方なのか、何かを叫んでいる。ビルに向かって石を投げつけ、ガラスを次々に割っている。そんな遊びに興じている。楽しそうだなと足元のガラスを踏みながら思った。
「危ない」
横断歩道を渡ろうとしたとき、中野は私を止めた。瞬間、目の前を何台もの車が走り抜けていった。最近は車もバイクも赤信号を堂々と無視をするから、気を付けなくてはいけない。緩やかな崩壊を始める秩序。救急車のサイレンの音が遠くで聞こえた。道を空けてください。通ります。そして再びガラスの割れる音。子どもが泣く大きな声が生々しい。
無法地帯を楽しむ人と日常を守ろうとする人で、すでに世の中は二分されていた。私はどちらでもなかった。ただ、滅亡を意識した途端、人の量が多く感じられるのが不思議だった。人類全員と別れる。その諦めがむしろ存在感をかき立てている気がする。死の予感が生を引き立てるように。
まだ動いている電車に乗り、3駅ほど移動した。やがて中野と私は、ほとんど誰もいないグラウンドにたどり着いた。大量のゴミや燃やされた何かが辺りには散らばっていた。サッカーや草野球で賑わうありふれたグラウンドも過去の話になりかけているのだろう。お菓子やパンの袋、空き缶、大量の薬のシートや注射器に混ざって、なぜかコンドームの空箱が潰れていた。避妊しようがしまいがどこにも着床しない精子。私は溜め息をつき、適当なベンチに腰掛ける。
「そうだ。早見さんにはもうひとつ教えてあげる」
足元のビールの空き缶を蹴った後で、中野は言った。
「滅びる日の夕方、僕を迎えにここに宇宙船が来るんだ。社用ロケット。僕はそれで故郷に帰る」
中野はグラウンドの中央、一面に広がる茶色い土を眺めていた。
「何億光年か離れた場所から、地球の最期を見るんだ」
中野は今日も心地良い声で言った。そうなんだ、と乾いた声が出た。
「だけど、ここで死ぬ私にそれを言って何か意味あるの?」
「あ、そうだね。……ごめん」
中野は申し訳なさの欠片もなさそうに私の隣に座った。
「一緒に連れて行ってあげたいけど、地球人は僕の星では暮らせないんだ。身体的に」
「別にいいよ」
私は中野の横顔を見上げた。何を考えているのかわからない。宇宙人、中野。滅亡を前に混乱する私たちに対し、あくまで見納めにやって来たという中野。彼だけが冷静なのか、狂っているのか、一体どちらなのだろう。彗星は今頃どこにいるのだろう。見上げてみても、始まりかけた夜の薄い群青が広がっているだけだった。
「僕の故郷は多分あの辺りなんだよね」
中野は空を指差し、言った。星ひとつ消すことに何の後悔も反省も抱いていないであろう彼を前に、私は複雑な気持ちになっていた。宇宙船が来るなんて信じられない。中野を疑うこともできない自分自身は、それ以上に意味がわからない。いっそ私も何かとんでもない何かをしてみたい。そう思い、殺人や強盗、放火といったありったけの罪を思い浮かべたものの、どんな罪の魅力も爽快感も中野の前では霞んだ。地球を滅ぼすことに比べればすべてのスケールが小さい。
「……お腹空いた」
私は立ち上がった。その足で近くのドラッグストアとスーパーへ向かった。私は飢えにも似た焦りを感じ始めていた。日常は終わるというのに、その何かがわからずもどかしい。苛立ってもいた。だけど、身体は身体のまま、空腹を音で知らせていた。中野は私の後をついてきた。宇宙人というより大きな犬のように。目についた食料品を次々とカゴに入れ、私はそのまま店を出た。人生初めての万引きだった。グラウンドに戻ると、何だか楽しくなって笑いが溢れた。私は小さい人間だと思う。地球が終わる。こんなときに勇気を振り絞ることが、金を払うのを止めることだなんて。
「中野。食べよ」
「いいね。ありがとー」
もう痩せる必要もないから、私は手に入れたスナック菓子をひたすら口へ運んだ。きっと人生最後のピクニックだった。結局すぐに味に飽き、最後は適当に飴を口の中へ放り込んだ。舐め慣れた苺の味を身体中に広げながら夜空を眺めた。小さい頃、お母さんがよく買ってくれた飴だ。そう思うと急に悲しい。思わず涙ぐんだせいで、遠くの星がぼやけた。この苺は今、星の味だと思った。
「中野は思ってるよりずっとやばい奴だって、中学生の自分に教えてあげたいな。だって宇宙人なんでしょ?」
涙声で私は言った。泣く予定なんてなかった。それよりも中野が慌てていることの方が想定外だった。
「早見さん。地球、滅ぼしちゃってごめんね」
「仕方ないよ。仕事なんだから」
「そうだけど……。あんまり深く考えてなかったんだよね」
中野はそう言うと、親指の腹で涙を拭ってくれた。星ひとつ無くす男にはそぐわない、繊細な動作だった。
「中野は地球でやり残したこと、ないの?」
「もう行きたい場所には行ったし、会いたい人には会ったから」
「どこに行ったの?」
「海。海はいいよね。地球の綺麗なところが凝縮されてる気がして、昔から好きだったんだ」
「そっか。あとは誰に会ったの?」
「昔のバイト先のオーナー。仕事できなさすぎてクビになっちゃったけど、楽しかったんだ。それから早見さん」
中野はそこで一度、言葉を区切った。
「なんだか無性に早見さんに会いたかったんだ。あの日、会えてよかった」
そして彼はさらに呟いた。やり残したこと、か。
「あとはセックスかな」
「え?」
「地球人とはしたことないんだよね。僕は地球人童貞」
しばらくの間、中野がスナック菓子を咀嚼する音だけが現実的に響いた。やがて黙りこくる私を彼は見た。
「冗談だよ。大丈夫だよ。今、早見さんを押し倒したりなんかしないよ」
そう言われても彼が冗談を言うこと自体が冗談に思え、食べているスナックのように軽い言葉に何も言えなかった。辺りを見回すと、遠くのベンチにカップルがいた。何かを示し合わせたようにふたりはキスを始めた。お幸せに、と私は思う。だけど、滅亡まで彼らはあと何回キスができるのだろう。そう考えると、腕を絡め合うシルエットから、聞こえるはずのない甘い言葉が聞こえてくるような気がする。
「中野」
私はふと何かを伝えたくなっていた。それが言葉以外のものである時点で手遅れだと心のどこかで理解し、同時に何が? とも思っていた。中野はすべてを予知していたかのような表情で私を見ていた。彼の話が本当なら、私たちは今、何光年もの距離を超えていることになる。彼に潜む地球外生命を、私は見つめることで感じようとしていたはずだった。気付けば中野とキスをしていた。唇が唇へ落ちる。これも地球の引力の作用なのだろうかと、塩辛さの中で思った。私の扱う物理なんてその程度だった。
「早見さんのしたいことなら、僕は付き合うよ」
唇が離れたとき、中野はそう言った。パーカーの袖を握りしめていて、私が彼を引き寄せたのだとわかった。
「じゃあ、もう一回」
私はそう言い、中野と唇を重ね続けた。宇宙人だからだろうか。彼の唇は血を忘れたかのように冷たい。何か本当どうでもいい。そう思いながら私は、地球を滅ぼすなどと言う男の唇を感じていた。キスが生み出す束の間の無重力は心地よかった。やがて中野は静かな溜め息をつき、変わらない声で言った。
「これ以上したら、元いた星に戻れなくなりそう」
「なら、これで終わりだね」
私はベンチにもたれかかった。いつの間にか遠くのカップルは姿を消していた。
「……早見さん」
突然、自分の片手を中野の両手で包まれ、私は驚いた。
「何?」
「そういえば今のが初めてのキスだ」
そう言われても地球が滅亡するまで後4日しかない。頭の中でガラスが割れる音がした。