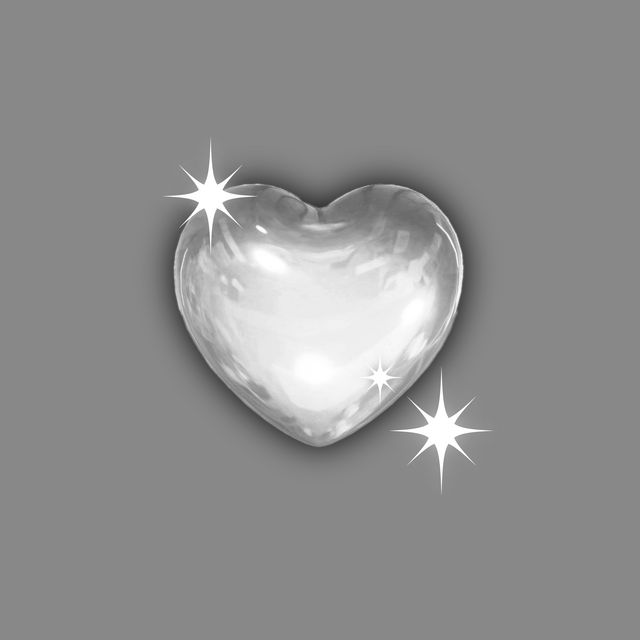第3話
文字数 2,471文字
滅亡までの残り少ない日々を私は中野と過ごした。今さら新しく一緒に生きていく人も、死んでいく人も見当たらない。そんな理由で中野といた。孤独を埋める誰か。暇を潰せる何か。そのすべての代用が彼だった。
街は日に日に不気味な静けさを増していった。サイレンや悲鳴、わけのわからない雄叫びや犬の鳴き声が、時折、静けさを切り裂くように響き渡った。私はアパートの片隅からそれらの音に耳を傾けた。壁に寄りかかり、窓を横目で眺める。青空や曇り空には何の変わり映えもない。今も彗星が落ちているなんて夢みたいだと思う。
スマートフォンを覗くと、インターネットは人々の限界を突破した声で溢れかえっている。みんな思い思いに喋っている。本物であろう死体の画像を上げ続ける人もいれば、終末飯と名付けた自炊を記録し続ける人もいる。だけど、どんなビビッドな写真も綺麗な言葉も笑える不謹慎なネタも心に響かず、私は世間と手を繋げない。自ら振りほどいているのかもしれない。全員が馬鹿だし、もう終わりなんだと周りを見下すことで。「私って冷たいの?」スマートフォンを放り投げ、隣にいる中野に尋ねてみたが、曖昧に微笑むだけでそれ以上は何も言わない。
シェルターのような部屋に守られながら、この場所でひとりきりではないことに私は安心していた。交通網は死んでいるから、家族にも友達にももう会えない。会ったところで何を話していいかわからない。だけど中野なら、ただ側にいられた。僕に人類は一切関係ないというようなニュートラルな態度は、君も発狂しようがしまいが好きにすればいいとでも言われているようで、居心地が良かった。彼をこの部屋へ呼んでよかったと私は思う。借りたタオルを口実に呼び出し「帰らないで」と言って、本当によかった。「元いた星に帰るまでの間でいいから」そう告げる私は面倒くさい女だった。そんな面倒くささでさえ彗星が焼き尽くすと思うと、口実なんて初めから必要なかったようにも思う。
「なんか、本当にすごいことになっちゃったね」
「そうだね」
「誰かのせいだー」
「僕だね」
家の中に飽きると気晴らしに外を歩いた。街は荒れ果てていた。窓の割られた車。食料のないスーパーやコンビニ。かろうじて滅亡までのカウントダウンを止めないビルのモニター。駅の地下は「私たちは死なない!」をスローガンにした団体に占拠され、商業ビルや病院といった慣れ親しんだ建物は破壊され、燃やされ、既に時の中に忘れ去られたようになっていた。「地球最高!」と騒ぐ、狂ったように明るい集団には近寄らないようにする。道端には魂の抜けた会社員が座り込み、汚れ切ったスーツ姿でどこか遠くを見ている。私の隣には鼻歌まじりの中野。
「それ何の歌?」
「中学の校歌。早見さんはもう忘れた?」
「うん」
終末を散歩しながら、私はまだ考えていた。続編を楽しみにしていた映画や、一度は食べてみたかった有名店のスイーツ。そんなことより遥かに考えるべきことが、やり残したことがあるのではないか。滅亡までのわずかな時間に使い道があるのではないか。他人ではなく自分のために。いい加減、すべてを諦めるべきだと頭では冷静に考えていた。一方で、心は何かを求めて疼いていた。同時に身体中に警告音が鳴っている。多分、中野を心で追ってはいけない。彼との間に特別な何かを芽生えさせてはいけない。本能に訴えかけるそんなアラートが。
「ねぇ。中野はどうして私といるの?」
「早見さんだからだよ」
「楽しいの?」
「楽しいよ」
なぜなら、こんな会話をしても地球は滅びるのだ。わかっている。今さらひとりを相手に深刻な感情を抱くなんて、造花に水をあげるくらい意味がない。私は足元の石を拾い、まだ割れていないカフェの窓へ投げつけた。命中。「上手いね」と中野に言われた。楽しくてなぜか困る。
**
そうしているうちに彗星の衝突予定日が訪れた。その日は中野との別れの日でもあった。故郷の星からロケットが迎えに来ると彼は言っていた。あの日キスをしたグラウンドまで。そして彼は飛び立ち、滅びゆく地球と人類を安全圏から眺めるらしい。
「昨日の続きしよう」
「いいよ」
私たちは朝からゲームをした。まるで今日がただの休日のように。中野が意外とアクションシューティングが上手いと知ったのはつい2日前だ。外から流れ込む本物の悲鳴を聞きながら、モニターの中でキャラクターが悲鳴を上げる。こんなときに侵略者から地球を守るゲームで遊ぶなんて、皮肉だった。中野はコントローラーを握りながら「早見さんのこと守るね」などと気楽で、星ひとつ滅ぼす自覚なんて、きっと最後までない。
ゲームに飽きると、ガスコンロでカップラーメンを作って食べた。最後の晩餐かもしれない食事で、私は舌を火傷した。痛い、と思った。だけど外を見れば天気がいい。美味しい匂いに満たされた空間。この部屋にはあまりにも平和な時間が流れている。私たちがどこかの宇宙人と散りゆく地球人であるのを忘れそうになる。こんな日が続けばいいと何かを錯覚しそうにもなる。満ち足りた気持ちで目を閉じると、動物の感覚に浸れる。今、陽の光を浴びているだけでこんなにも幸福でいられる。
「そろそろ行くね」
やがて、中野は見計らったように立ち上がった。どこに? という質問は無意味だから飲み込んだ。
「わかった。じゃあね」
大体の別れは乾いている方がいいと信じる私は、初めから何もなかったかのように手を振った。こんな不思議な感覚は二度と来ない。なんだか週末にでもまた会える気がする。地球の生命が続いてさえいれば。
「ありがとう」
部屋を出る中野の背中に声をかけた。靴を履いた後、一度だけこちらを振り向き、中野は言った。
「楽しかったね。早見さん」
「うん」
「きっとまたどこかで会えるよ」
宇宙は広いから。そう言い終わると同時にアパートのドアは閉まった。宇宙人の足音は遠ざかり、後はひとり、地球が滅びるのを待つだけだった。さようなら。誰に向かって発せられたのかわからない言葉が、しばらくの間、宙に浮いていた。
街は日に日に不気味な静けさを増していった。サイレンや悲鳴、わけのわからない雄叫びや犬の鳴き声が、時折、静けさを切り裂くように響き渡った。私はアパートの片隅からそれらの音に耳を傾けた。壁に寄りかかり、窓を横目で眺める。青空や曇り空には何の変わり映えもない。今も彗星が落ちているなんて夢みたいだと思う。
スマートフォンを覗くと、インターネットは人々の限界を突破した声で溢れかえっている。みんな思い思いに喋っている。本物であろう死体の画像を上げ続ける人もいれば、終末飯と名付けた自炊を記録し続ける人もいる。だけど、どんなビビッドな写真も綺麗な言葉も笑える不謹慎なネタも心に響かず、私は世間と手を繋げない。自ら振りほどいているのかもしれない。全員が馬鹿だし、もう終わりなんだと周りを見下すことで。「私って冷たいの?」スマートフォンを放り投げ、隣にいる中野に尋ねてみたが、曖昧に微笑むだけでそれ以上は何も言わない。
シェルターのような部屋に守られながら、この場所でひとりきりではないことに私は安心していた。交通網は死んでいるから、家族にも友達にももう会えない。会ったところで何を話していいかわからない。だけど中野なら、ただ側にいられた。僕に人類は一切関係ないというようなニュートラルな態度は、君も発狂しようがしまいが好きにすればいいとでも言われているようで、居心地が良かった。彼をこの部屋へ呼んでよかったと私は思う。借りたタオルを口実に呼び出し「帰らないで」と言って、本当によかった。「元いた星に帰るまでの間でいいから」そう告げる私は面倒くさい女だった。そんな面倒くささでさえ彗星が焼き尽くすと思うと、口実なんて初めから必要なかったようにも思う。
「なんか、本当にすごいことになっちゃったね」
「そうだね」
「誰かのせいだー」
「僕だね」
家の中に飽きると気晴らしに外を歩いた。街は荒れ果てていた。窓の割られた車。食料のないスーパーやコンビニ。かろうじて滅亡までのカウントダウンを止めないビルのモニター。駅の地下は「私たちは死なない!」をスローガンにした団体に占拠され、商業ビルや病院といった慣れ親しんだ建物は破壊され、燃やされ、既に時の中に忘れ去られたようになっていた。「地球最高!」と騒ぐ、狂ったように明るい集団には近寄らないようにする。道端には魂の抜けた会社員が座り込み、汚れ切ったスーツ姿でどこか遠くを見ている。私の隣には鼻歌まじりの中野。
「それ何の歌?」
「中学の校歌。早見さんはもう忘れた?」
「うん」
終末を散歩しながら、私はまだ考えていた。続編を楽しみにしていた映画や、一度は食べてみたかった有名店のスイーツ。そんなことより遥かに考えるべきことが、やり残したことがあるのではないか。滅亡までのわずかな時間に使い道があるのではないか。他人ではなく自分のために。いい加減、すべてを諦めるべきだと頭では冷静に考えていた。一方で、心は何かを求めて疼いていた。同時に身体中に警告音が鳴っている。多分、中野を心で追ってはいけない。彼との間に特別な何かを芽生えさせてはいけない。本能に訴えかけるそんなアラートが。
「ねぇ。中野はどうして私といるの?」
「早見さんだからだよ」
「楽しいの?」
「楽しいよ」
なぜなら、こんな会話をしても地球は滅びるのだ。わかっている。今さらひとりを相手に深刻な感情を抱くなんて、造花に水をあげるくらい意味がない。私は足元の石を拾い、まだ割れていないカフェの窓へ投げつけた。命中。「上手いね」と中野に言われた。楽しくてなぜか困る。
**
そうしているうちに彗星の衝突予定日が訪れた。その日は中野との別れの日でもあった。故郷の星からロケットが迎えに来ると彼は言っていた。あの日キスをしたグラウンドまで。そして彼は飛び立ち、滅びゆく地球と人類を安全圏から眺めるらしい。
「昨日の続きしよう」
「いいよ」
私たちは朝からゲームをした。まるで今日がただの休日のように。中野が意外とアクションシューティングが上手いと知ったのはつい2日前だ。外から流れ込む本物の悲鳴を聞きながら、モニターの中でキャラクターが悲鳴を上げる。こんなときに侵略者から地球を守るゲームで遊ぶなんて、皮肉だった。中野はコントローラーを握りながら「早見さんのこと守るね」などと気楽で、星ひとつ滅ぼす自覚なんて、きっと最後までない。
ゲームに飽きると、ガスコンロでカップラーメンを作って食べた。最後の晩餐かもしれない食事で、私は舌を火傷した。痛い、と思った。だけど外を見れば天気がいい。美味しい匂いに満たされた空間。この部屋にはあまりにも平和な時間が流れている。私たちがどこかの宇宙人と散りゆく地球人であるのを忘れそうになる。こんな日が続けばいいと何かを錯覚しそうにもなる。満ち足りた気持ちで目を閉じると、動物の感覚に浸れる。今、陽の光を浴びているだけでこんなにも幸福でいられる。
「そろそろ行くね」
やがて、中野は見計らったように立ち上がった。どこに? という質問は無意味だから飲み込んだ。
「わかった。じゃあね」
大体の別れは乾いている方がいいと信じる私は、初めから何もなかったかのように手を振った。こんな不思議な感覚は二度と来ない。なんだか週末にでもまた会える気がする。地球の生命が続いてさえいれば。
「ありがとう」
部屋を出る中野の背中に声をかけた。靴を履いた後、一度だけこちらを振り向き、中野は言った。
「楽しかったね。早見さん」
「うん」
「きっとまたどこかで会えるよ」
宇宙は広いから。そう言い終わると同時にアパートのドアは閉まった。宇宙人の足音は遠ざかり、後はひとり、地球が滅びるのを待つだけだった。さようなら。誰に向かって発せられたのかわからない言葉が、しばらくの間、宙に浮いていた。