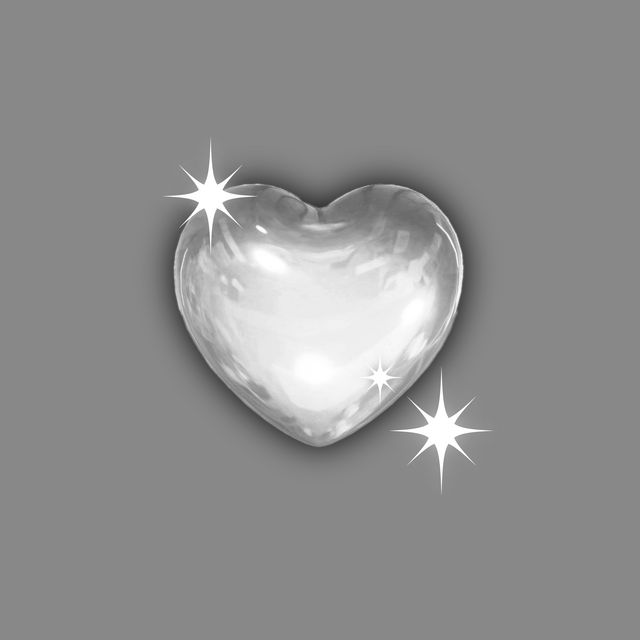第1話
文字数 4,160文字
こんなことになるなんて思ってなかった。
アパートのベランダで手すりにもたれかかり、私は湿り気のない溜め息をつく。さようなら。この世のすべてに心の中で別れを告げながら。
目の前に広がるのは、今日も見慣れた街並みだった。カラスを何羽も乗せた電線、ブロックを規則的に並べたような戸建の住宅街、遠くのマンションは崖のように切り立っている。それらはすべて夕陽に染められ、景色の温かさには一見、疑いの余地がない。なのに、オレンジが終わりの色だと私は知らされていた。
なぜなら地球はもうすぐ滅亡する。人類はすべて死に絶える。こんなにも実感はないのに、今も急速に落下し続けるひとつの彗星によって。今日の夕陽は明けない夜へ切り替わるだけで、決して明日には繋がらない。最後の太陽は地球を葬る恐ろしい怪物にも、ねぎらうように優しく照らす光にも見えた。私はいつもと変わらず眩しさに目を細めているだけだった。
今、何をしているのだろう。家族や友人、元彼、上司、ジムのインストラクター、行きつけのカフェの店員。身の回りの人物を私は思い浮かべた。彼らになんとなく同情しようとしたものの、全員で仲良く終わりを迎える今、際立って可哀想な人はいない気もする。人生なんてよくて死後のためのプロローグ。やり残したことを騒ぎ立てる人がいるのなら、そもそも生前に意味を持ちすぎなんじゃないか。
──私みたいに。
自分を使って周りを見下すのは、最初から最後まで私の悪い癖だった。私はポケットからスマートフォンを取り出し、カメラを起動した。たとえ無駄だとしても残しておきたかった。終末の記念にありふれた夕焼けの一枚を。すると、私の隣に背の高いひとりの男が並んだ。
「早見さん。何見てるの?」
ついでにその男にもレンズを向け、私は親指でシャッターを切った。男は動じることなく、柔和な表情で私を捉えていた。わかっている。この男は「別に何も見てないけど」と返す私のことしか見ていないのだ。かといって外の何かから守るわけでもなく、消滅する人類にも地球にも思い入れなど持っていない。地球を滅ぼしたのは彼だから、当然なのかもしれない。
「あとちょっとだね。中野」
「そうだね」
どこかから悲鳴と爆発音、何かを察して騒ぎ立てる鳥たちの鳴き声がした。私たちはそれらを気にも止めず唇を重ねた。離れるとまた重ねた。今の私にあるのは、誰よりも幸福な人類であるという自覚。それだけだった。
**
私が彼と出会ったのは、3週間ほど前のことだった。一日を終えようとする街を、激しい雨が叩きつけていたあの夕方。誰かが急に呼び出したような厚い雲を不思議に思いながら、私は職場から駅へ向かって歩いていた。その途中、気まぐれな親切を振りまくことになった。視界に唐突に入り込んだ、ずぶ濡れで歩く小学生くらいの女の子。私はその子に傘を差し出した。
「よかったら使って。風邪引いちゃうよ」
驚き、困ったように私を見上げる女の子に続けた。
「いらないビニール傘だし、あげる。気にしないで」
ありがとうございますと頭を下げた女の子を私は見送った。束の間、満足感に浸ると、頭上の雨をしのぐためにコンビニの軒下に駆け込んだ。そのとき、近くで煙草を吸っていたのが彼だった。彼は遠慮なく私の全身を眺め、言った。
「雨の日に人助けだなんて、優しいですね」
遠くの傘の群れを見ながら、私は首を横に振った。別に優しくはない。たとえば仕事中に明らかに忙しそうな他人を手伝わなかったり、報道される悲しい事件を遠い世界の話のように感じたり、日常は切り離し、見捨てることの方が多い。私は暇だっただけだ。彼が煙草を吸い続ける間、私は意味もなくそこに立っていた。止むどころか弱まる気配すらない雨だった。新しい傘を買うために歩き出そうとした瞬間、彼は煙草を灰皿に押し付け、言った。
「今からコーヒーでも飲みません? 暇だし」
いや、私帰るんで。そう言おうとしたはずだった。だけど気づけば「いいですよ」と言い、手招きされるがままに彼の傘の中へ入っていた。断る理由を探すより早く、彼と目を合わせていた。不慣れなシチュエーションだと思いながら、行き先も確かめないまま、知らない傘の中を歩いていた。片側だけ濡れた彼の肩を、煙草の残り香と洗剤の混ざり合った匂いを覚えている。
「ここにしましょうか」
「……はい」
一体どれくらい歩いたのだろう。彼が決めたカフェに入り、案内された席についた。ブレンドコーヒーを2つ注文した後、彼は綺麗に畳まれたタオルをバッグから取り出し「これで髪の毛、拭いてください」と言った。私は言われるがまま自分の長い髪にタオルを押し当てた。組まれたシナリオのように何かが進んでいる。逆らえない。あらかじめ用意されていたようなタオルの柔らかさを感じながら、そう思った。
「あの女の子、風邪引かないといいですね」
「そうですね」
「この辺りで働いてるんですか?」
「そうです。あなたも?」「まぁそんな感じ。雨、強いですね」
「本当ですね」……。
彼との会話は当たり障りなく盛り上がりもしない。それがかえって心地良かった。会話の途切れ目に、私たちは窓の外を見ては雨粒の落ち具合を確かめた。どこか遠い場所に逃げてきたような安心感の中に私はいた。髪の毛の先はまだ少し湿っているのに、現実感のない雨だった。コーヒーを飲み終える頃、彼は唐突に言った。
「だけど意味ないですよ。ああいう人助けしても」
「え?」
思わず聞き返す私に、彼は続けた。だってもうすぐ地球、終わっちゃうんで。ここにいる人たち、ていうか地球の全員が死ぬんですよ。
「知らなかったでしょ」
彼は柔らかく微笑んでいた。私は黙って水を飲んだ。言葉の意味が理解できず、そうするしかなかった。そして「私、そろそろ帰りますね」と立ち上がった。変な人に捕まったのかもしれない。そう思うと軽率な自分の行動に少し悔いが募る。
「……コーヒー代、ここに置いておきます」
急いで帰り支度を整える私を彼は呼び止めた。「待って」
「まだ話があるんだ。早見さん。……早見奈々さん」
私は思わず動きを止め、真正面から彼を見た。一体、どうして私の名前を知っているんだろう。肩に掛けたバッグのショルダー部分を強く握り締める。
「覚えてないかな。俺……ナカノ。ほら、中学のとき同級生だった」
立ち尽くす間、彼は通りがかった店員にコーヒーのお代わりを2杯ぶん頼んでいた。そのせいで脱力し、私は思わず椅子に座り直してしまった。確信に満ちた表情を浮かべる、初対面だと信じ切っていた目の前の男。人生のどこかで出会ったことがあるのだろうか。今になって彼を真正面から眺めると、明るい茶色の瞳、困ったように八の字を描く眉、色素の薄い優しげな顔であると気がついた。私は立ち昇るコーヒーの湯気の中で記憶のページを捲っていた。すると、突然、中学の騒がしい教室が思い浮かんだ。2年C組。陽当たりのいい席でひとり、分厚い図鑑をめくり続けていた影の薄い男の子。不思議くん扱いされていた彼の名は、中野だったはずだ。中野大地。私は目を見開いた。
「え、もしかして中野?」
「思い出した? ていうか、僕が思い出させたんだけど」
「久しぶり……。気づかなくてごめん」
今の今まで存在を忘れていた気まずさと申し訳なさで、一旦、私は目を伏せた。
「さっきコンビニで会ったなんてすごい偶然だね。中野、背すごく高くなったね」
懐かしいね。そう告げる私は大人の微笑みを浮かべていたと思う。
「僕も早見さんが懐かしいよ。そもそも、地球全部が懐かしいんだけどね」
「ねぇ、さっきから何言ってるの?」
繰り返される「地球」や「死ぬ」という言葉に私は笑った。本当に懐かしい。中学生の頃からいつも彼だけやけにスケールが大きかった。たかが理科の実験で二酸化炭素を発生させては「地球ってすごい!」などと言い、お前どこの住民だよ、とクラス全体に苦笑いされる彼の姿が、自動的に思い出される。
「僕は今、いろいろ懐かしんでるんだ」
そうなんだ、と返すと、飄々とした態度のまま彼は続けた。僕は実はこの星の生き物じゃないんだ。中学と高校の6年間をたまたま地球で過ごした、いわゆる宇宙人なんだよ。最近は故郷の惑星に戻って仕事してたんだけど……。近々、地球がなくなるとわかって見納めに来たんだ。今、彗星が近づいてるんだよ。こうしている間も。
「もうひとつの故郷とお別れだと思うと寂しくて」
「ちょっと待って」
「いいよ。いくらでも待つよ」
意味がわからない。「なんか、そういう設定なの?」そう尋ねると「実話だよ」と大真面目な返事が返ってきた。中野は言う。銀河と惑星の監査の仕事を今してるんだ。僕の故郷はまだ地球に存在を気づかれていない惑星なんだけど……。これから僕たちの銀河の領域を広げるに当たって、地球が邪魔だと判明したから、消すことにしたんだ。飛んでる彗星の軌道を上手いことずらして。
「こんなこと、誰にも言わないつもりだったのに。どうしてだろう。早見さんにはうっかり言っちゃった」
「何それ……」
「人に優しいところ、見ちゃったからかな。死ぬ前に思い残したこととかあったらさ、今のうちにやっときなよ」
別に信じなくてもいいけど。ゆっくりと美味しそうにコーヒーを飲む中野は、そう言うと話を締めくくった。私は当然、何も信じなかった。空想の玩具にされているのだと思った。一方、彼にはすべて真実だと思わせる何かがあった。彼の眼差しには人を騙そうとする不純なものを感じられない。だけど正直、騙されやすい自分を否定できない。
「意味、わかんない」
「でも、あと3日もすれば、政府からお知らせがあるかもしれないよ。日本、というか地球の終わりに関して」
彼はそこまで言うと立ち上がった。
「雨はあと10分で止むよ」
それじゃ、また宇宙のどこかで会えたら。彼は申し訳なさそうに笑い、ひとりで店を出た。私はしばらくの間、人混みに紛れ込む彼を目線で追った。宇宙人だと打ち明けられた後でも、彼はただの背の高いひとりの地球人として私の目に映った。彼の姿はすぐに見えなくなり、10分後、雨は言った通りに止んだ。マグカップの存在を思い出し、唇を当てる。コーヒーは冷め切っていた。
アパートのベランダで手すりにもたれかかり、私は湿り気のない溜め息をつく。さようなら。この世のすべてに心の中で別れを告げながら。
目の前に広がるのは、今日も見慣れた街並みだった。カラスを何羽も乗せた電線、ブロックを規則的に並べたような戸建の住宅街、遠くのマンションは崖のように切り立っている。それらはすべて夕陽に染められ、景色の温かさには一見、疑いの余地がない。なのに、オレンジが終わりの色だと私は知らされていた。
なぜなら地球はもうすぐ滅亡する。人類はすべて死に絶える。こんなにも実感はないのに、今も急速に落下し続けるひとつの彗星によって。今日の夕陽は明けない夜へ切り替わるだけで、決して明日には繋がらない。最後の太陽は地球を葬る恐ろしい怪物にも、ねぎらうように優しく照らす光にも見えた。私はいつもと変わらず眩しさに目を細めているだけだった。
今、何をしているのだろう。家族や友人、元彼、上司、ジムのインストラクター、行きつけのカフェの店員。身の回りの人物を私は思い浮かべた。彼らになんとなく同情しようとしたものの、全員で仲良く終わりを迎える今、際立って可哀想な人はいない気もする。人生なんてよくて死後のためのプロローグ。やり残したことを騒ぎ立てる人がいるのなら、そもそも生前に意味を持ちすぎなんじゃないか。
──私みたいに。
自分を使って周りを見下すのは、最初から最後まで私の悪い癖だった。私はポケットからスマートフォンを取り出し、カメラを起動した。たとえ無駄だとしても残しておきたかった。終末の記念にありふれた夕焼けの一枚を。すると、私の隣に背の高いひとりの男が並んだ。
「早見さん。何見てるの?」
ついでにその男にもレンズを向け、私は親指でシャッターを切った。男は動じることなく、柔和な表情で私を捉えていた。わかっている。この男は「別に何も見てないけど」と返す私のことしか見ていないのだ。かといって外の何かから守るわけでもなく、消滅する人類にも地球にも思い入れなど持っていない。地球を滅ぼしたのは彼だから、当然なのかもしれない。
「あとちょっとだね。中野」
「そうだね」
どこかから悲鳴と爆発音、何かを察して騒ぎ立てる鳥たちの鳴き声がした。私たちはそれらを気にも止めず唇を重ねた。離れるとまた重ねた。今の私にあるのは、誰よりも幸福な人類であるという自覚。それだけだった。
**
私が彼と出会ったのは、3週間ほど前のことだった。一日を終えようとする街を、激しい雨が叩きつけていたあの夕方。誰かが急に呼び出したような厚い雲を不思議に思いながら、私は職場から駅へ向かって歩いていた。その途中、気まぐれな親切を振りまくことになった。視界に唐突に入り込んだ、ずぶ濡れで歩く小学生くらいの女の子。私はその子に傘を差し出した。
「よかったら使って。風邪引いちゃうよ」
驚き、困ったように私を見上げる女の子に続けた。
「いらないビニール傘だし、あげる。気にしないで」
ありがとうございますと頭を下げた女の子を私は見送った。束の間、満足感に浸ると、頭上の雨をしのぐためにコンビニの軒下に駆け込んだ。そのとき、近くで煙草を吸っていたのが彼だった。彼は遠慮なく私の全身を眺め、言った。
「雨の日に人助けだなんて、優しいですね」
遠くの傘の群れを見ながら、私は首を横に振った。別に優しくはない。たとえば仕事中に明らかに忙しそうな他人を手伝わなかったり、報道される悲しい事件を遠い世界の話のように感じたり、日常は切り離し、見捨てることの方が多い。私は暇だっただけだ。彼が煙草を吸い続ける間、私は意味もなくそこに立っていた。止むどころか弱まる気配すらない雨だった。新しい傘を買うために歩き出そうとした瞬間、彼は煙草を灰皿に押し付け、言った。
「今からコーヒーでも飲みません? 暇だし」
いや、私帰るんで。そう言おうとしたはずだった。だけど気づけば「いいですよ」と言い、手招きされるがままに彼の傘の中へ入っていた。断る理由を探すより早く、彼と目を合わせていた。不慣れなシチュエーションだと思いながら、行き先も確かめないまま、知らない傘の中を歩いていた。片側だけ濡れた彼の肩を、煙草の残り香と洗剤の混ざり合った匂いを覚えている。
「ここにしましょうか」
「……はい」
一体どれくらい歩いたのだろう。彼が決めたカフェに入り、案内された席についた。ブレンドコーヒーを2つ注文した後、彼は綺麗に畳まれたタオルをバッグから取り出し「これで髪の毛、拭いてください」と言った。私は言われるがまま自分の長い髪にタオルを押し当てた。組まれたシナリオのように何かが進んでいる。逆らえない。あらかじめ用意されていたようなタオルの柔らかさを感じながら、そう思った。
「あの女の子、風邪引かないといいですね」
「そうですね」
「この辺りで働いてるんですか?」
「そうです。あなたも?」「まぁそんな感じ。雨、強いですね」
「本当ですね」……。
彼との会話は当たり障りなく盛り上がりもしない。それがかえって心地良かった。会話の途切れ目に、私たちは窓の外を見ては雨粒の落ち具合を確かめた。どこか遠い場所に逃げてきたような安心感の中に私はいた。髪の毛の先はまだ少し湿っているのに、現実感のない雨だった。コーヒーを飲み終える頃、彼は唐突に言った。
「だけど意味ないですよ。ああいう人助けしても」
「え?」
思わず聞き返す私に、彼は続けた。だってもうすぐ地球、終わっちゃうんで。ここにいる人たち、ていうか地球の全員が死ぬんですよ。
「知らなかったでしょ」
彼は柔らかく微笑んでいた。私は黙って水を飲んだ。言葉の意味が理解できず、そうするしかなかった。そして「私、そろそろ帰りますね」と立ち上がった。変な人に捕まったのかもしれない。そう思うと軽率な自分の行動に少し悔いが募る。
「……コーヒー代、ここに置いておきます」
急いで帰り支度を整える私を彼は呼び止めた。「待って」
「まだ話があるんだ。早見さん。……早見奈々さん」
私は思わず動きを止め、真正面から彼を見た。一体、どうして私の名前を知っているんだろう。肩に掛けたバッグのショルダー部分を強く握り締める。
「覚えてないかな。俺……ナカノ。ほら、中学のとき同級生だった」
立ち尽くす間、彼は通りがかった店員にコーヒーのお代わりを2杯ぶん頼んでいた。そのせいで脱力し、私は思わず椅子に座り直してしまった。確信に満ちた表情を浮かべる、初対面だと信じ切っていた目の前の男。人生のどこかで出会ったことがあるのだろうか。今になって彼を真正面から眺めると、明るい茶色の瞳、困ったように八の字を描く眉、色素の薄い優しげな顔であると気がついた。私は立ち昇るコーヒーの湯気の中で記憶のページを捲っていた。すると、突然、中学の騒がしい教室が思い浮かんだ。2年C組。陽当たりのいい席でひとり、分厚い図鑑をめくり続けていた影の薄い男の子。不思議くん扱いされていた彼の名は、中野だったはずだ。中野大地。私は目を見開いた。
「え、もしかして中野?」
「思い出した? ていうか、僕が思い出させたんだけど」
「久しぶり……。気づかなくてごめん」
今の今まで存在を忘れていた気まずさと申し訳なさで、一旦、私は目を伏せた。
「さっきコンビニで会ったなんてすごい偶然だね。中野、背すごく高くなったね」
懐かしいね。そう告げる私は大人の微笑みを浮かべていたと思う。
「僕も早見さんが懐かしいよ。そもそも、地球全部が懐かしいんだけどね」
「ねぇ、さっきから何言ってるの?」
繰り返される「地球」や「死ぬ」という言葉に私は笑った。本当に懐かしい。中学生の頃からいつも彼だけやけにスケールが大きかった。たかが理科の実験で二酸化炭素を発生させては「地球ってすごい!」などと言い、お前どこの住民だよ、とクラス全体に苦笑いされる彼の姿が、自動的に思い出される。
「僕は今、いろいろ懐かしんでるんだ」
そうなんだ、と返すと、飄々とした態度のまま彼は続けた。僕は実はこの星の生き物じゃないんだ。中学と高校の6年間をたまたま地球で過ごした、いわゆる宇宙人なんだよ。最近は故郷の惑星に戻って仕事してたんだけど……。近々、地球がなくなるとわかって見納めに来たんだ。今、彗星が近づいてるんだよ。こうしている間も。
「もうひとつの故郷とお別れだと思うと寂しくて」
「ちょっと待って」
「いいよ。いくらでも待つよ」
意味がわからない。「なんか、そういう設定なの?」そう尋ねると「実話だよ」と大真面目な返事が返ってきた。中野は言う。銀河と惑星の監査の仕事を今してるんだ。僕の故郷はまだ地球に存在を気づかれていない惑星なんだけど……。これから僕たちの銀河の領域を広げるに当たって、地球が邪魔だと判明したから、消すことにしたんだ。飛んでる彗星の軌道を上手いことずらして。
「こんなこと、誰にも言わないつもりだったのに。どうしてだろう。早見さんにはうっかり言っちゃった」
「何それ……」
「人に優しいところ、見ちゃったからかな。死ぬ前に思い残したこととかあったらさ、今のうちにやっときなよ」
別に信じなくてもいいけど。ゆっくりと美味しそうにコーヒーを飲む中野は、そう言うと話を締めくくった。私は当然、何も信じなかった。空想の玩具にされているのだと思った。一方、彼にはすべて真実だと思わせる何かがあった。彼の眼差しには人を騙そうとする不純なものを感じられない。だけど正直、騙されやすい自分を否定できない。
「意味、わかんない」
「でも、あと3日もすれば、政府からお知らせがあるかもしれないよ。日本、というか地球の終わりに関して」
彼はそこまで言うと立ち上がった。
「雨はあと10分で止むよ」
それじゃ、また宇宙のどこかで会えたら。彼は申し訳なさそうに笑い、ひとりで店を出た。私はしばらくの間、人混みに紛れ込む彼を目線で追った。宇宙人だと打ち明けられた後でも、彼はただの背の高いひとりの地球人として私の目に映った。彼の姿はすぐに見えなくなり、10分後、雨は言った通りに止んだ。マグカップの存在を思い出し、唇を当てる。コーヒーは冷め切っていた。