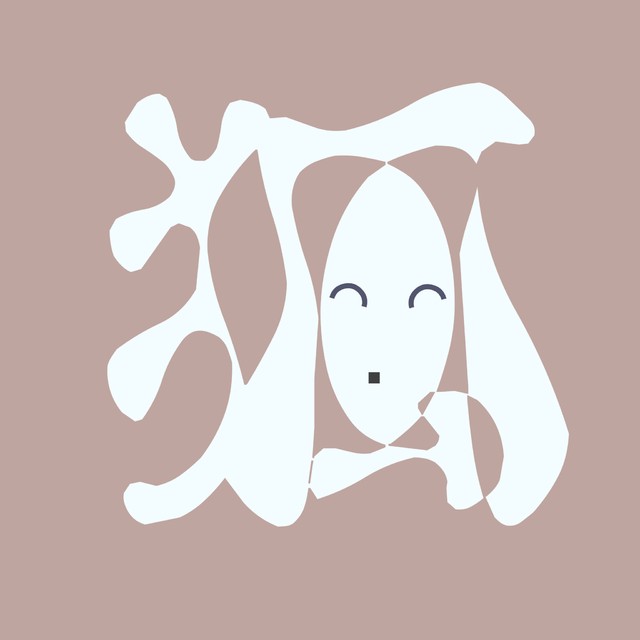13.
文字数 5,089文字
「で、奥さまはお元気?」
唐突に話題が変わった。
「げ、元気というか、まあ、元気だよ」
「なんだ、それ」
「いや、急に家族の話になったから」
「写真」
「え?」
「嫁の写真を見せろって言ってんの。あるでしょ、スマホの中に。わたしは年賀状に旦那も娘も写った家族写真を載っけてるのに、そっちはつまんない干支の図柄のばっかり。不公平じゃない」
「まあ、あるけど」
「はい。スマホを出して、写真のアプリを開く」
「不公平も何もそっちが勝手に家族写真の年賀状を送って来ただけじゃないか。こっちは頼んでないだろ」
文句は言いつつも、リクエストには応えてやることにした。
新しいところでは家族旅行の写真があったはず。そう思いながら見せる写真を見繕っていたら、スマホごと奪い取られた。
スマホを睨みつけるような表情は、さほど酔っているふうでもない。彼女は素面 でもこんな感じだったと、懐かしさのようなものがアルコールと共に全身に染み渡る。
黙って好きにさせていたら、勝手にスクロールして何枚も写真を見始めた。見られて困るものもないからいいのだが、さすがにマナー違反だろうと思って奪い返した。
「わたしとは似ても似つかない可愛らしい奥さんじゃない」
職場で知り合った妻も同い年でアラフォーだ。今さら可愛らしいもないもんだと思うが、尋深に似ていないのは確かだ。
「娘さんもお母さん似で二重でくりっとした大きなお目々。あなたも一応は二重だけど、全然ぱっちりもくりっともしていないもんね」
そんなシンプルな憎まれ口が妙に様になる女だ。それも懐かしさの血流を加速させ、怒る気力まで押し流されてしまう。
「娘さん、春っぽい名前だったわよね。うちのは夏だけど」
「さくら」
「そうだ。確か咲く桜と書いて咲桜 。可愛い名前」
さくらという音の響きも桜の花も好きだが、桜には散るイメージも付きまとう。平仮名にしようかとも思ったが、咲くという字を合わせて咲桜とした。ずっと散らずに咲いていて欲しいと。
「そっちは夏未 だったか」
結婚は彼女の方が少し先だったが、子どもは同じ年にできた。桜の季節に娘が生まれ、その年の夏に差し掛かる頃、彼女のところにも女の子が誕生した。次の春には仲良く小学生だ。
「最近はテレビの前で見様見真似で歌って踊って、大きくなったらアイドルになるとか言ってるよ」
「わあ。可愛いじゃない。うちの子はそんな活発で明るい感じじゃないのよ。人見知りだし、すっごく大人しくて引っ込み思案」
「そりゃ父親に似たんだな。母親に似なくて良かったじゃないか」
「どういう意味よ」
「まぁ、性格なんてまだまだ変わるかもしれないから、油断するなよ」
「だから、どういう意味?」
将来の夢などもっと変わっていくだろう。親としては本人がやりたいと思うことをやらせてやりたいとは思うものの、例えば芸能界なんて得体の知れない世界に娘を送り込むのは気が進まない。気は進まないが、夢が叶わずに肩を落とす娘の姿も見たくはない。
何にしてもまだまだ小さいうちから心配してもしようのないことだ。いや。育ったら育ったで、いくら親が気を揉んでみたところでどうしようもないことなのだろう。親なんて子どもが育ってしまえば、あとは無力だ。きっと。
「実はね、わたし、今、一人暮らしなのよ」
また唐突に話の流れを変えられた。しかも意味がよく分からない。
急に血管が詰まってしまったかのように答えに窮していると、彼女は残っていた酒を飲み干して、次の酒を注文した。
一人暮らしとはどういう意味か、訊ねようとしたが尋深の様子が変だ。酒を注文した後、じっと目で女将を追っている。
「どうした?」
そう問いかけると、顔を近づけてきて小声で囁く。
「あの女将さん、どこかで見たような気がするのよね……気のせいかしら」
だが、え、お前もかと言葉を挟む余地もなく「ま、そんなわけないから、きっと気のせいね」と自分で否定した。
「それにしても大丈夫なのか、そんなに飲んで」
後から来たくせに、もう酒量では追い抜かれてしまったことになる。
「大丈夫よ。酔ってるように見える?」
「いや。素面……だと思う」
すると今度は声を立てて笑い始めた。文字表記すれば、キャハハハという文字列が正に当て嵌まる笑い声だった。
やはり酔っているのかと、自信が少しぐらつき始める。
「旦那はね、ひと足先にカナダに行ったの。知ってる? バンクーバー」
話題は一人暮らしの件に戻ったらしい。
ひと足先——?
ということは彼女も後を追うということか。
咄嗟にそう思いつつも、そこにストレートに触れられない。
「バンクーバーって首都だっけ?」
「首都はオタワよ。娘は一時的に実家に預けてあるんだ」
夫婦揃ってそれぞれの会社の国際部門で働いているという話は先に聞いていた。うちとは違ってバイリンガル夫婦なのだった。
「来月にはわたしも行くの。家族でお引越し。転職するんだ、向こうの企業に。旦那もわたしも」
やはりそうだ。
今さら寂しく感じる筋合いでもないのは明らかだ。でも——では、いったいどういう感情を抱けばいいのだろう。
「正確には旦那はもう転職した。わたしも内定してる。今は今の会社の最終引継期間なの。なのに最後の最後に面倒な商談のサポートを押し付けられちゃってさ。忙しいのよ。まあ、そのおかげでこっちに来れたってのもあるんだけど。他にも諸々 整理しておかなきゃいけないことがあるし、娘は一週間だけ親に頼んだの。短期間なら孫の相手は楽しいらしいから、これも親孝行よ。日本には当分帰って来られないと思うし」
「ご両親は寂しがるんじゃないのか」
「そうね。それだけが整理のしようのない事柄かな。親のことはやっぱり気になる。でも、あの二人はあの二人で、田舎暮らしとか言って山奥に引っ込んで好き勝手にやってるから、わたしに文句を言えた立場でもないのよ。ま、わたしの方はすぐにヘマして日本に逃げ帰って来ないとも限らないけどね。でも、親のことはどうしようもないとしても、それ以外のことはちゃんとしとこうと思ったわけよ、日本を出る前に。仕事もプライベートも」
「プライベート?」
「そう。なんつーか、男関係? 整理しとこうかなって感じ?」
「げ。そんな男がいたのかよ」
「君だよ、君。あ、な、た」
至近距離で目が合った。
「唯一、わたしが振った男。たった一人のわたしの元カレ。そして元ストーカー」
思わず先に目を逸らしてしまった。
「あの夜」
どの夜だ?
言葉には出さず、グラスの中の日本酒の表面を見つめながら頭の中を高速回転させた——と言っても、僕たち二人の間であの夜なんて言える夜は限られる。
「合宿の夜。どうして告白してくれなかったの?」
また目を合わせてしまった。長い睫毛と二重瞼に守られた、その中にあの夜の星空が広がっていそうな茶色い瞳。
ほんの数センチ、手を動かすだけで触れ合えていたあの夜——。
言葉は見つからない。
ストーカーになったのは、振られた理由に納得がいかなかったからだ。彼女が何を言っているのか分からなかった。ただ、振られたという事実だけは認識できた。
あの時もっとごねておけばという後悔は自覚することすら拒絶して、コンクリート詰めにした上に鎖でぐるぐる巻きにして重しを付けて、心の奥底深くに沈めて生きてきた。その後悔の重しが取れて浮かび上がってきた気がした。
いやだ。まだ始まったばかりなのに別れるなんて——。
そう言って駄々をこねればよかった。
物分かりの良い男を気取って、彼女の申し出をすんなりと受け入れた愚か者。青二才。大馬鹿野郎。
「わたしはね、あの一年、楽しかったんだよ。合宿の夜から、あなたがわたしにやっと告白してくれたあの日までの一年間。わたしは一番楽しかったかもしれない」
また訳の分からないことを言い始めた。その一年——付き合う前の一年の間に一体何があったというのか。
「この人はこっちが背中を押してあげなきゃ、ううん、背中を押したくらいじゃ足りないか。松明 か何かで背中に火でも付けてあげなきゃ、自分から告白なんて出来ないんだろうなって思った」
自覚していたはずのことなのに、自分のことを言われているという実感が湧かなかった。ただ、背中に松明? カチカチ山じゃあるまいし。針で突くよりも酷いじゃないか——。そんなことを思った。
いや。そんなことより何より、大学時代の彼女の方はとっくの昔にこちらの想いに気づいていたということか。
「合宿のあの夜、部屋を抜け出したあなたを見かけたのは偶然だったけど、これはチャンスだと思ったの。あのロケーション。あのシチュエーション。告白するにはもってこいだって。でも、あなたは時々無駄にロマンチックなことは言うくせに、肝心なことは何も言わないんだもの。意気地なしに生きる価値なしって言ったの覚えてる? あそこまで言っても何もできないんだから、ほんともうがっかりよ。最低最悪。合宿が終わってしまったら、あれ以上の好機なんて望めないのに。馬っ鹿じゃないのって思った」
意気地なしに生きる価値なし——。
それは彼女に水泳を教えて貰うことになったら厳し過ぎてきっと逃げ出してしまうだろうという仮定の話の中で出た言葉だ。その後の自分には刺さり続けた言葉でもあったけれど、あの夜の時点では自分の恋愛に対する弱腰を揶揄されているなどとは夢にも思わなかった。
「でもね、でも、あなただってきっと後悔しているんじゃないかなって思ったの。なんであの夜に告白しなかったんだ、俺のバカバカバカ。うかうかしているとあんな可愛い女の子、すぐ他の男に取られちゃうぞ。今度こそ、今度チャンスがあったら絶対に告白してやるって、そう決心しているんじゃないかって。きっとそのはずだって思ったの。だから合宿の後、大学からの帰り道が一緒になるように何度も何度もそっちに合わせたのに。それなのに、あなたは何も言ってこない。またまたがっかりの連続よ。でも、それでも楽しかった。あなたと二人で帰る道。あれはわたしにとってはデートだったもの。お互い遠慮なく馬鹿言い合って。今なら絶対にセクハラだって訴えられそうなことを、女の子のわたしに平気で言ってくるし。腹が立つこともあったけど、腹が立つことなんて付き合っているカップルにだっていくらでもあるものでしょう。楽しかった」
あれは偶然ではなく、彼女の策略だったというのか。いや、真に受けてはいけない。後付けで揶揄 われているだけかもしれない。その手には——。
「それなのに、いくら待っても告白してこないもんだから、さすがのわたしも途中からは諦めかけてたけどね。絶対わたしの方が先に告白なんかしないって決めてたし。しないっていうか、出来ないもの、恥ずかしくて。告白なんて。でも、それでも楽しかったからよかったの」
尋深は小休止のように言葉を止めて、ほんの少しだけ酒を口に含んだ。
「で、あの日よ。こっちがもうすっかり諦めモードに入ってたっていうのに、そんな時にあなたは急に告白してきて。遅いわよ。わたしはもう一年も勝手にデートを楽しんでたっつーの。やっぱり馬鹿じゃんって思った。でも、嬉しかった。初心を思い出したというか、そうだ、わたしはこれを待っていたんだって思い出した。嬉しかったんだよ、わたしは本当に。でも——。でも、そのあとが駄目だった。あなたはわたしに一切セクハラめいたことは言わなくなっちゃった。最初のうちはわたしも気づかなかった。だけどなんか違うなあって思って、どんどん違和感が大きくなって。で、思ったの。わたし、気を遣われているんだって。こんなのやだって。前の関係の方が楽しかったって」
半ば呆然として聞いていると、彼女はまた、今度はさっきよりもさらに顔を近づけてきて、耳元で囁くようにして言った。
「せめてキスくらいしていればね——」
驚いて彼女を見たが、今度は目を合わせてはくれなかった。
澄ました表情でグラスを口元へ運ぶ横顔を黙って見ていた。
微かに開かれた唇がグラスに触れた。傾いたグラスから透明な液体が唇の隙間に染み入るように流れ込む。唇がグラスから離れ、ほんの少し上唇を舐めるような仕草と同時に白い喉が動いた。
女性が酒を飲む行為がこんなにエロティックなのだと、初めて知った。
「そんなに見ないで。冗談よ、冗談。ね。本気にして、またうじうじしないでよ。今からストーカーになんかなったら大変だよ。バンクーバーだからね」
彼女は自らの長い話を茶化して笑った。
だから、全部本当のことなんだと悟った。
唐突に話題が変わった。
「げ、元気というか、まあ、元気だよ」
「なんだ、それ」
「いや、急に家族の話になったから」
「写真」
「え?」
「嫁の写真を見せろって言ってんの。あるでしょ、スマホの中に。わたしは年賀状に旦那も娘も写った家族写真を載っけてるのに、そっちはつまんない干支の図柄のばっかり。不公平じゃない」
「まあ、あるけど」
「はい。スマホを出して、写真のアプリを開く」
「不公平も何もそっちが勝手に家族写真の年賀状を送って来ただけじゃないか。こっちは頼んでないだろ」
文句は言いつつも、リクエストには応えてやることにした。
新しいところでは家族旅行の写真があったはず。そう思いながら見せる写真を見繕っていたら、スマホごと奪い取られた。
スマホを睨みつけるような表情は、さほど酔っているふうでもない。彼女は
黙って好きにさせていたら、勝手にスクロールして何枚も写真を見始めた。見られて困るものもないからいいのだが、さすがにマナー違反だろうと思って奪い返した。
「わたしとは似ても似つかない可愛らしい奥さんじゃない」
職場で知り合った妻も同い年でアラフォーだ。今さら可愛らしいもないもんだと思うが、尋深に似ていないのは確かだ。
「娘さんもお母さん似で二重でくりっとした大きなお目々。あなたも一応は二重だけど、全然ぱっちりもくりっともしていないもんね」
そんなシンプルな憎まれ口が妙に様になる女だ。それも懐かしさの血流を加速させ、怒る気力まで押し流されてしまう。
「娘さん、春っぽい名前だったわよね。うちのは夏だけど」
「さくら」
「そうだ。確か咲く桜と書いて
さくらという音の響きも桜の花も好きだが、桜には散るイメージも付きまとう。平仮名にしようかとも思ったが、咲くという字を合わせて咲桜とした。ずっと散らずに咲いていて欲しいと。
「そっちは
結婚は彼女の方が少し先だったが、子どもは同じ年にできた。桜の季節に娘が生まれ、その年の夏に差し掛かる頃、彼女のところにも女の子が誕生した。次の春には仲良く小学生だ。
「最近はテレビの前で見様見真似で歌って踊って、大きくなったらアイドルになるとか言ってるよ」
「わあ。可愛いじゃない。うちの子はそんな活発で明るい感じじゃないのよ。人見知りだし、すっごく大人しくて引っ込み思案」
「そりゃ父親に似たんだな。母親に似なくて良かったじゃないか」
「どういう意味よ」
「まぁ、性格なんてまだまだ変わるかもしれないから、油断するなよ」
「だから、どういう意味?」
将来の夢などもっと変わっていくだろう。親としては本人がやりたいと思うことをやらせてやりたいとは思うものの、例えば芸能界なんて得体の知れない世界に娘を送り込むのは気が進まない。気は進まないが、夢が叶わずに肩を落とす娘の姿も見たくはない。
何にしてもまだまだ小さいうちから心配してもしようのないことだ。いや。育ったら育ったで、いくら親が気を揉んでみたところでどうしようもないことなのだろう。親なんて子どもが育ってしまえば、あとは無力だ。きっと。
「実はね、わたし、今、一人暮らしなのよ」
また唐突に話の流れを変えられた。しかも意味がよく分からない。
急に血管が詰まってしまったかのように答えに窮していると、彼女は残っていた酒を飲み干して、次の酒を注文した。
一人暮らしとはどういう意味か、訊ねようとしたが尋深の様子が変だ。酒を注文した後、じっと目で女将を追っている。
「どうした?」
そう問いかけると、顔を近づけてきて小声で囁く。
「あの女将さん、どこかで見たような気がするのよね……気のせいかしら」
だが、え、お前もかと言葉を挟む余地もなく「ま、そんなわけないから、きっと気のせいね」と自分で否定した。
「それにしても大丈夫なのか、そんなに飲んで」
後から来たくせに、もう酒量では追い抜かれてしまったことになる。
「大丈夫よ。酔ってるように見える?」
「いや。素面……だと思う」
すると今度は声を立てて笑い始めた。文字表記すれば、キャハハハという文字列が正に当て嵌まる笑い声だった。
やはり酔っているのかと、自信が少しぐらつき始める。
「旦那はね、ひと足先にカナダに行ったの。知ってる? バンクーバー」
話題は一人暮らしの件に戻ったらしい。
ひと足先——?
ということは彼女も後を追うということか。
咄嗟にそう思いつつも、そこにストレートに触れられない。
「バンクーバーって首都だっけ?」
「首都はオタワよ。娘は一時的に実家に預けてあるんだ」
夫婦揃ってそれぞれの会社の国際部門で働いているという話は先に聞いていた。うちとは違ってバイリンガル夫婦なのだった。
「来月にはわたしも行くの。家族でお引越し。転職するんだ、向こうの企業に。旦那もわたしも」
やはりそうだ。
今さら寂しく感じる筋合いでもないのは明らかだ。でも——では、いったいどういう感情を抱けばいいのだろう。
「正確には旦那はもう転職した。わたしも内定してる。今は今の会社の最終引継期間なの。なのに最後の最後に面倒な商談のサポートを押し付けられちゃってさ。忙しいのよ。まあ、そのおかげでこっちに来れたってのもあるんだけど。他にも
「ご両親は寂しがるんじゃないのか」
「そうね。それだけが整理のしようのない事柄かな。親のことはやっぱり気になる。でも、あの二人はあの二人で、田舎暮らしとか言って山奥に引っ込んで好き勝手にやってるから、わたしに文句を言えた立場でもないのよ。ま、わたしの方はすぐにヘマして日本に逃げ帰って来ないとも限らないけどね。でも、親のことはどうしようもないとしても、それ以外のことはちゃんとしとこうと思ったわけよ、日本を出る前に。仕事もプライベートも」
「プライベート?」
「そう。なんつーか、男関係? 整理しとこうかなって感じ?」
「げ。そんな男がいたのかよ」
「君だよ、君。あ、な、た」
至近距離で目が合った。
「唯一、わたしが振った男。たった一人のわたしの元カレ。そして元ストーカー」
思わず先に目を逸らしてしまった。
「あの夜」
どの夜だ?
言葉には出さず、グラスの中の日本酒の表面を見つめながら頭の中を高速回転させた——と言っても、僕たち二人の間であの夜なんて言える夜は限られる。
「合宿の夜。どうして告白してくれなかったの?」
また目を合わせてしまった。長い睫毛と二重瞼に守られた、その中にあの夜の星空が広がっていそうな茶色い瞳。
ほんの数センチ、手を動かすだけで触れ合えていたあの夜——。
言葉は見つからない。
ストーカーになったのは、振られた理由に納得がいかなかったからだ。彼女が何を言っているのか分からなかった。ただ、振られたという事実だけは認識できた。
あの時もっとごねておけばという後悔は自覚することすら拒絶して、コンクリート詰めにした上に鎖でぐるぐる巻きにして重しを付けて、心の奥底深くに沈めて生きてきた。その後悔の重しが取れて浮かび上がってきた気がした。
いやだ。まだ始まったばかりなのに別れるなんて——。
そう言って駄々をこねればよかった。
物分かりの良い男を気取って、彼女の申し出をすんなりと受け入れた愚か者。青二才。大馬鹿野郎。
「わたしはね、あの一年、楽しかったんだよ。合宿の夜から、あなたがわたしにやっと告白してくれたあの日までの一年間。わたしは一番楽しかったかもしれない」
また訳の分からないことを言い始めた。その一年——付き合う前の一年の間に一体何があったというのか。
「この人はこっちが背中を押してあげなきゃ、ううん、背中を押したくらいじゃ足りないか。
自覚していたはずのことなのに、自分のことを言われているという実感が湧かなかった。ただ、背中に松明? カチカチ山じゃあるまいし。針で突くよりも酷いじゃないか——。そんなことを思った。
いや。そんなことより何より、大学時代の彼女の方はとっくの昔にこちらの想いに気づいていたということか。
「合宿のあの夜、部屋を抜け出したあなたを見かけたのは偶然だったけど、これはチャンスだと思ったの。あのロケーション。あのシチュエーション。告白するにはもってこいだって。でも、あなたは時々無駄にロマンチックなことは言うくせに、肝心なことは何も言わないんだもの。意気地なしに生きる価値なしって言ったの覚えてる? あそこまで言っても何もできないんだから、ほんともうがっかりよ。最低最悪。合宿が終わってしまったら、あれ以上の好機なんて望めないのに。馬っ鹿じゃないのって思った」
意気地なしに生きる価値なし——。
それは彼女に水泳を教えて貰うことになったら厳し過ぎてきっと逃げ出してしまうだろうという仮定の話の中で出た言葉だ。その後の自分には刺さり続けた言葉でもあったけれど、あの夜の時点では自分の恋愛に対する弱腰を揶揄されているなどとは夢にも思わなかった。
「でもね、でも、あなただってきっと後悔しているんじゃないかなって思ったの。なんであの夜に告白しなかったんだ、俺のバカバカバカ。うかうかしているとあんな可愛い女の子、すぐ他の男に取られちゃうぞ。今度こそ、今度チャンスがあったら絶対に告白してやるって、そう決心しているんじゃないかって。きっとそのはずだって思ったの。だから合宿の後、大学からの帰り道が一緒になるように何度も何度もそっちに合わせたのに。それなのに、あなたは何も言ってこない。またまたがっかりの連続よ。でも、それでも楽しかった。あなたと二人で帰る道。あれはわたしにとってはデートだったもの。お互い遠慮なく馬鹿言い合って。今なら絶対にセクハラだって訴えられそうなことを、女の子のわたしに平気で言ってくるし。腹が立つこともあったけど、腹が立つことなんて付き合っているカップルにだっていくらでもあるものでしょう。楽しかった」
あれは偶然ではなく、彼女の策略だったというのか。いや、真に受けてはいけない。後付けで
「それなのに、いくら待っても告白してこないもんだから、さすがのわたしも途中からは諦めかけてたけどね。絶対わたしの方が先に告白なんかしないって決めてたし。しないっていうか、出来ないもの、恥ずかしくて。告白なんて。でも、それでも楽しかったからよかったの」
尋深は小休止のように言葉を止めて、ほんの少しだけ酒を口に含んだ。
「で、あの日よ。こっちがもうすっかり諦めモードに入ってたっていうのに、そんな時にあなたは急に告白してきて。遅いわよ。わたしはもう一年も勝手にデートを楽しんでたっつーの。やっぱり馬鹿じゃんって思った。でも、嬉しかった。初心を思い出したというか、そうだ、わたしはこれを待っていたんだって思い出した。嬉しかったんだよ、わたしは本当に。でも——。でも、そのあとが駄目だった。あなたはわたしに一切セクハラめいたことは言わなくなっちゃった。最初のうちはわたしも気づかなかった。だけどなんか違うなあって思って、どんどん違和感が大きくなって。で、思ったの。わたし、気を遣われているんだって。こんなのやだって。前の関係の方が楽しかったって」
半ば呆然として聞いていると、彼女はまた、今度はさっきよりもさらに顔を近づけてきて、耳元で囁くようにして言った。
「せめてキスくらいしていればね——」
驚いて彼女を見たが、今度は目を合わせてはくれなかった。
澄ました表情でグラスを口元へ運ぶ横顔を黙って見ていた。
微かに開かれた唇がグラスに触れた。傾いたグラスから透明な液体が唇の隙間に染み入るように流れ込む。唇がグラスから離れ、ほんの少し上唇を舐めるような仕草と同時に白い喉が動いた。
女性が酒を飲む行為がこんなにエロティックなのだと、初めて知った。
「そんなに見ないで。冗談よ、冗談。ね。本気にして、またうじうじしないでよ。今からストーカーになんかなったら大変だよ。バンクーバーだからね」
彼女は自らの長い話を茶化して笑った。
だから、全部本当のことなんだと悟った。