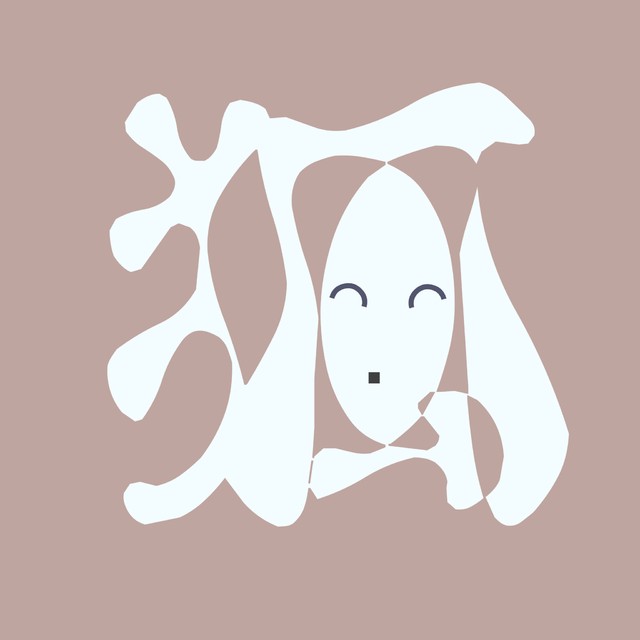1.
文字数 3,153文字
青春のことをアオハルなんて呼び始めたのは誰なんだ、ダサいにもほどがある——なんてことを随分と前から思っていた。なのに昨夜、ラジオで喋っていた若い女の子が「青春をアオハルって言うの、すっごく恰好いいよね」などと言い始めたものだからショックを受けた。
今日は出がけに架かってきた面倒な電話のせいでランチに出遅れた。入った蕎麦屋はほぼほぼ満席で、偶々 先に食べていた同じ職場の部下、小田 聡美 と向かい合っての相席になった。頼んだ日替わり定食を待つ間にそんな話をしたら、彼女から笑われてしまってまたショックを受けた。
「次長、それは単純に次長がおじさんだからですよ。そもそもアオハルって言葉、若い人が共感したからこそ広まったに決まっているじゃないですか。次長が個人的にどう思っててもいいですけど、私以外の、特に若い人たちにはダサいなんて言わない方がいいと思いますよ」
昨春の異動で彼女の上司になって一年が過ぎた。前任者からよく出来る子だからしっかり育てろと引継を受けていはいたが、想像以上だった。
仕事の出来る彼女は上司の前でも臆することなく蕎麦をすすった。旨そうに食べるのは好印象だ。職場の飲み会でも彼女はよく食べてよく飲む。見ていて気持ちがいい。
それでも長身痩躯 のモデル体型を維持している端麗な容姿に加え、仕事もできる。良い女過ぎて男には手が出しにくい存在だ。職場にいる独身の男どもが指を咥えて眺めているのがよく分かる。
「小田さんは、アオハルって言うんだ?」
アラフォーの自分と比べればかなり若い彼女だって二十代終盤。アラサーと呼ばれる世代に入っている。青春という尺度での会話においては決して若いとは言えないだろう。
「言いませんよ、そんなダサいこと」
「ほら」
「だから、わたし以外の若い人たちって言ったじゃないですか。わたしだって若い子たちの前でダサいとか言いませんから」
「この話題に関しては小田さんもこっち側ってことだ」
彼女は箸を止めたかと思うと、口を尖らせて思いがけないことを言った。
「次長、それセクハラです」
「えっ、何で?!」
彼女は答えず、俯いて笑いを噛み殺したように見えたが、またすぐに蕎麦をすすり始めた。
ちょうどそこへ小さな蕎麦が付いた焼き魚の定食が運ばれてきたので、僕も手を合わせて箸を持つ。
彼女の方はセクハラについては語らず、話題を青春に戻した。
「次長は、いつまでが青春だと思っているんですか?」
「そりゃまあ学生時代とかじゃないか?」
正確な定義など知らないが、そんなものだろう。そもそも厳格な定義があるのかどうかすら怪しいではないか。
「社会人は青春じゃないと?」
「まあ、社会人にもなったら青春だなんだと言っている場合でもないんじゃないか。そりゃ別のロジックで何歳 になっても青春だっていう意見もあるだろうけど、今言っている青春とはまた意味が違うように思うし」
食べ終わって席を立つ客もいるようだが、それでもまだ店内は満席らしい。入って来る客には店員が相席となることを断ってから案内している。ただ彼女の方が壁側に座っているので、それと向かい合う自分には店内の様子を直接窺い知ることは出来ない。
「青春18きっぷだって何歳になっても買えるみたいですしね。まぁ青春の定義なんて人によっても違うんでしょうけど、でも、三十歳まで、つまり二十代のうちは青春だっていう定義はそこそこ有力なようですよ」
話しながらも彼女が一箇所に視線を送っていることに気がついた。じっと一点を見ているわけではないが、暫くするとまた同じところに目を向けているように思える。気にはなるが気のせいかもしれないし、いちいち振り向いて確認するほどでもない。
「個人的なイメージとしては、青は青二才とか青臭いとかいう若さを表しているイメージだ。春はそのまま季節の春。命が芽吹いて活力が湧き上がるようなイメージか。ま、こんな議論こそが青臭いような気もするけど」
「中国の陰陽五行説 から来ている言葉だって聞いたこともありますけど、詳しいことは忘れちゃいました」
そんなこと、聞いたこともない。
「もしかして、小田さんって青春に詳しい?」
「そんなわけないですよ」
話しているうちにセクハラと言われた意味は分かった気がした。年齢の話をしたつもりはなかったのだが、知らぬ間にそうなっていたようだ。だがもうすっかり謝るタイミングを逸してしまっている。
「でも青春なんてもっと歳を重ねてから、振り返って思うものなんじゃないですか」
「そうかもな。でも中には自分は今まさに青春の真っ只中だ! なんて謳歌してるやつもいるんじゃないかな」
「いますね。いますけど、わたしはお友達にはなれそうにありません」
「俺もだな」
ほんの一瞬だけ目を合わせて笑った。
すると直後、彼女は徐 に顔を近づけてきたかと思うと、声のトーンを落とした。
「次長、栗色の髪の美人に心当たりありますか?」
「え?」
栗色の髪と聞いて思い浮かぶ人物は一人いた。しかし、美人かどうかは見解が分かれるところだろうと思う。何よりもう心当たりのうちにも入らないほど、古い思い出の中だけの住人だ。
「いや——、無いけど」
明確に否定した。
なのに、彼女は鋭かった。
「あるんですね?」
「いや。無いって言ったよね。どうしてあると思うの?」
「今一瞬、次長の目が泳ぎました」
「嘘だろ。いい加減なことを」
「それに」
彼女はまた一段とトーンを落として、いよいよ内緒話モードのように小声になった。
「少し前に入って来たその女性は、ずっと次長の様子を窺っているみたいです」
「え?」
驚いて振り向こうとしたのを彼女に止められた。
「駄目です。見ないで下さい」
「どうして?」
秘密を打ち明けるような表情が、少しだけ間をおいてから笑顔に変わった。
「嘘です」
何がだ?
そう突っ込む暇はなかった。
「では、わたしはお昼休みの間に済ませておきたい買い物があるので、お先に失礼します」
彼女はそう言い「ご馳走様でした」と手を合わせた。
自分の伝票を持って立ち上がろうとしたので、手を伸ばして伝票を押さえた。
「これはいいよ」
「いえ、そんなわけには」
「いいから」
「セクハラの賠償金ですか? それとも口止め料?」
悪戯っぽい笑みは年齢よりも幼さを感じさせる。
「そう取ってもらっていい」
「そうですか。では、遠慮なく。ご馳走様でした」
遠慮を見せつつ冗談も混ぜながらの引き際が絶妙だ。仕事が出来る女はこういうところもそつが無い。
これこそ口に出せばセクハラ案件だろうが、その姿はパンツスーツがとても様になっている。蕎麦屋よりもイタリアンとかフレンチが似合いそうに思うのだが、蕎麦を食べる姿にも違和感はなかった。どこまでも隙が無い。自分が独身だったとしても彼女にアタックする勇気など持ち合わせないだろう。
そうか——。
二十代でも青春なのだとすれば、彼女もまだその中を生きている。羨ましい限りだ。
彼女が席を離れると、すぐに店員が片付けに来ると同時に「相席お願いします」と声を掛けてきた。
承諾して定食の残りを平らげようとしているところへ、次の客がやって来た。と思ったのだが、席に着こうとせずに横に立ったままだ。
訝 しく思って斜め上に視線を上げると、そこにもパンツスーツの似合う女がいた。
こちらを見下ろしていたのは栗色の髪の女性だ。その存在自体は嘘ではなかったらしい。そして——。
尋深 ——。
名前を呼んだつもりが、声にならなかった。
「やっぱり、各務 君だ」
女性から君付けで呼ばれたのは何時 以来だろう。
栗色の髪——。その唯一の心当たりだった女性 。もう思い出の中にしかいないと思っていた存在。その彼女が、子どものように屈託のない笑顔でこちらを見下ろしていた。
今日は出がけに架かってきた面倒な電話のせいでランチに出遅れた。入った蕎麦屋はほぼほぼ満席で、
「次長、それは単純に次長がおじさんだからですよ。そもそもアオハルって言葉、若い人が共感したからこそ広まったに決まっているじゃないですか。次長が個人的にどう思っててもいいですけど、私以外の、特に若い人たちにはダサいなんて言わない方がいいと思いますよ」
昨春の異動で彼女の上司になって一年が過ぎた。前任者からよく出来る子だからしっかり育てろと引継を受けていはいたが、想像以上だった。
仕事の出来る彼女は上司の前でも臆することなく蕎麦をすすった。旨そうに食べるのは好印象だ。職場の飲み会でも彼女はよく食べてよく飲む。見ていて気持ちがいい。
それでも
「小田さんは、アオハルって言うんだ?」
アラフォーの自分と比べればかなり若い彼女だって二十代終盤。アラサーと呼ばれる世代に入っている。青春という尺度での会話においては決して若いとは言えないだろう。
「言いませんよ、そんなダサいこと」
「ほら」
「だから、わたし以外の若い人たちって言ったじゃないですか。わたしだって若い子たちの前でダサいとか言いませんから」
「この話題に関しては小田さんもこっち側ってことだ」
彼女は箸を止めたかと思うと、口を尖らせて思いがけないことを言った。
「次長、それセクハラです」
「えっ、何で?!」
彼女は答えず、俯いて笑いを噛み殺したように見えたが、またすぐに蕎麦をすすり始めた。
ちょうどそこへ小さな蕎麦が付いた焼き魚の定食が運ばれてきたので、僕も手を合わせて箸を持つ。
彼女の方はセクハラについては語らず、話題を青春に戻した。
「次長は、いつまでが青春だと思っているんですか?」
「そりゃまあ学生時代とかじゃないか?」
正確な定義など知らないが、そんなものだろう。そもそも厳格な定義があるのかどうかすら怪しいではないか。
「社会人は青春じゃないと?」
「まあ、社会人にもなったら青春だなんだと言っている場合でもないんじゃないか。そりゃ別のロジックで
食べ終わって席を立つ客もいるようだが、それでもまだ店内は満席らしい。入って来る客には店員が相席となることを断ってから案内している。ただ彼女の方が壁側に座っているので、それと向かい合う自分には店内の様子を直接窺い知ることは出来ない。
「青春18きっぷだって何歳になっても買えるみたいですしね。まぁ青春の定義なんて人によっても違うんでしょうけど、でも、三十歳まで、つまり二十代のうちは青春だっていう定義はそこそこ有力なようですよ」
話しながらも彼女が一箇所に視線を送っていることに気がついた。じっと一点を見ているわけではないが、暫くするとまた同じところに目を向けているように思える。気にはなるが気のせいかもしれないし、いちいち振り向いて確認するほどでもない。
「個人的なイメージとしては、青は青二才とか青臭いとかいう若さを表しているイメージだ。春はそのまま季節の春。命が芽吹いて活力が湧き上がるようなイメージか。ま、こんな議論こそが青臭いような気もするけど」
「中国の
そんなこと、聞いたこともない。
「もしかして、小田さんって青春に詳しい?」
「そんなわけないですよ」
話しているうちにセクハラと言われた意味は分かった気がした。年齢の話をしたつもりはなかったのだが、知らぬ間にそうなっていたようだ。だがもうすっかり謝るタイミングを逸してしまっている。
「でも青春なんてもっと歳を重ねてから、振り返って思うものなんじゃないですか」
「そうかもな。でも中には自分は今まさに青春の真っ只中だ! なんて謳歌してるやつもいるんじゃないかな」
「いますね。いますけど、わたしはお友達にはなれそうにありません」
「俺もだな」
ほんの一瞬だけ目を合わせて笑った。
すると直後、彼女は
「次長、栗色の髪の美人に心当たりありますか?」
「え?」
栗色の髪と聞いて思い浮かぶ人物は一人いた。しかし、美人かどうかは見解が分かれるところだろうと思う。何よりもう心当たりのうちにも入らないほど、古い思い出の中だけの住人だ。
「いや——、無いけど」
明確に否定した。
なのに、彼女は鋭かった。
「あるんですね?」
「いや。無いって言ったよね。どうしてあると思うの?」
「今一瞬、次長の目が泳ぎました」
「嘘だろ。いい加減なことを」
「それに」
彼女はまた一段とトーンを落として、いよいよ内緒話モードのように小声になった。
「少し前に入って来たその女性は、ずっと次長の様子を窺っているみたいです」
「え?」
驚いて振り向こうとしたのを彼女に止められた。
「駄目です。見ないで下さい」
「どうして?」
秘密を打ち明けるような表情が、少しだけ間をおいてから笑顔に変わった。
「嘘です」
何がだ?
そう突っ込む暇はなかった。
「では、わたしはお昼休みの間に済ませておきたい買い物があるので、お先に失礼します」
彼女はそう言い「ご馳走様でした」と手を合わせた。
自分の伝票を持って立ち上がろうとしたので、手を伸ばして伝票を押さえた。
「これはいいよ」
「いえ、そんなわけには」
「いいから」
「セクハラの賠償金ですか? それとも口止め料?」
悪戯っぽい笑みは年齢よりも幼さを感じさせる。
「そう取ってもらっていい」
「そうですか。では、遠慮なく。ご馳走様でした」
遠慮を見せつつ冗談も混ぜながらの引き際が絶妙だ。仕事が出来る女はこういうところもそつが無い。
これこそ口に出せばセクハラ案件だろうが、その姿はパンツスーツがとても様になっている。蕎麦屋よりもイタリアンとかフレンチが似合いそうに思うのだが、蕎麦を食べる姿にも違和感はなかった。どこまでも隙が無い。自分が独身だったとしても彼女にアタックする勇気など持ち合わせないだろう。
そうか——。
二十代でも青春なのだとすれば、彼女もまだその中を生きている。羨ましい限りだ。
彼女が席を離れると、すぐに店員が片付けに来ると同時に「相席お願いします」と声を掛けてきた。
承諾して定食の残りを平らげようとしているところへ、次の客がやって来た。と思ったのだが、席に着こうとせずに横に立ったままだ。
こちらを見下ろしていたのは栗色の髪の女性だ。その存在自体は嘘ではなかったらしい。そして——。
名前を呼んだつもりが、声にならなかった。
「やっぱり、
女性から君付けで呼ばれたのは
栗色の髪——。その唯一の心当たりだった