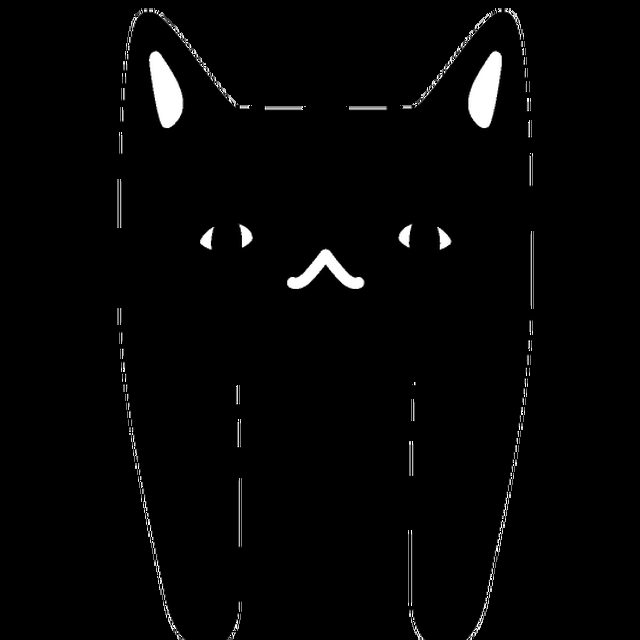第4話 冬
文字数 6,600文字
学園祭が終わると三年生は部活動も委員会も引退していき、冬期休暇の前には受験に向けての自由登校期間に入る。その期間から退寮申請の受理が始まるので、冬期休暇が目前の今、寮内も普段より少しだけ静かに感じられた。
学園祭の前、陽の落ちた街並みを一緒に見下ろしたあの日を最後に、渚紗とは校舎や寮で軽く言葉を交わすことはあってもちゃんとは話をしていない。それはつまり、あの日以降、砂凪がおとずれるタイミングでは鐘塔の鍵が開いていなかったということでもある。
メッセージを送ってみてもいいのだろうけれど、受験に向けて忙しくしているのだろうか? あるいは……避けられている……? あの日の話を、そしてあの日の自分の思考を思い出しそんなことを考えてしまうと、そう気軽にスマホを取ることもできなかった。とはいえ、この自由登校期間に入ってからも構内でその姿を見かけることはあるので、渚紗はまだ風に攫われていないし、たぶん家に帰るつもりもないのだろう。
年内最後になる登校日、鍵が開いている期待は正直あまりなかったけれど足を向け、手をかけた鐘塔の扉が静かに開き、砂凪は驚きに一瞬その動きを止めた。心臓が大きく、トクトクと脈を打つ。けれどこれがどういった感情の反映なのか……嬉しいのか、それとも怖いのか……どちらにせよ自分にとって渚紗が、そういった感情を抱くほどには特別な存在になっているということに驚き、けれどそれと同時に、ようやく自身のいろいろな思考が腑に落ちた感じでもあった。
ゆっくりと階段を登り鐘の下に顔をのぞかせると、鐘塔の縁に腰を下ろし、その向こうに広がる街並みをぼんやりと眺めていた渚紗が、縁に足をかけその場に立ち上がった。踵を返すようにふとこちらに向けられた視線が砂凪のものと交わり、渚紗は驚いたように目を丸くしてから、これまでと変わらない笑みをその顔に浮かべた。
「久しぶりね、砂凪さん」
「お久しぶりです……」
言いながらも何となくぎくしゃくと視線を逸らす砂凪に、渚紗は不思議そうに首をかしげた。
「どうしたの? 変な顔をして」
「いやっ、あの……いると、思わなかったので……」
「あら、そうなの? でも鍵が開いていたから来たのでしょう?」
「それは……そう、なんですけど……」
「もしかして、あの日の話を気にして、私があなたのことを避けていると思っていたのかしら?」
こちらに歩み寄ってきながら図星をさされ、ぐっ……と言葉に詰まる。
「砂凪さんは素直ね」
言いながらくつくつと笑い、「でもそうね……」と渚紗は続けた。
「避けては……いたかもしれないわ」
その言葉にぴりつく胸を、知らず砂凪はブレザーの上から握りしめた。
「……私、先輩の嫌がること何かしちゃいました? 鬱陶しかったですか? しつこかった?」
「まさか」
驚いたように目を瞬いてから、困ったように微笑する。
「砂凪さんには楽しい時間をたくさんもらっただけよ。だからこれは、ただただ私の問題」
それは一体……? 首をかしげる砂凪に、渚紗はふと目を細めた。
「あの日話したように、私のこれからは、これからも秦来の名の下に続いていくの。それを悪いことだとは思わないし、今更これといった不満も特にはないけれど、それでもほんの少しだけ考えてしまったの。もし私が今生で、秦来の名前を気にせず生きる選択肢を与えられたとしたら、どうしていただろう……? とね。まぁそれでもたぶん、私はこの道を選んでいたとは思うけれど。だから……そうね、しいてあなたが私に何かをしてしまったというのならば、あなたは私に、息の仕方を教えてくれた、といったところかしら」
人差し指を軽く頬に当て、言葉を探すように小さく首をかしげる渚紗に砂凪はたずねた。
「先輩は息、できてなかったんですか?」
「まさか」
「じゃあ……息苦しかったですか?」
「いいえ」
「本当に?」
砂凪が聞き返してくる言葉に、「……ええ」と渚紗が不思議そうにうなずく。
「もし先輩が本当に……」
言いながらその距離をすいと詰めると、砂凪はゆっくりと伸ばした腕を渚紗の細い首に絡ませた。
「砂凪さん……?」
「本当は秦来渚紗でいることが息苦しいというのなら、私が今ここで先輩のこと殺してあげますよ?」
「……何言っているの? 冗談はやめてちょうだい」
「冗談じゃないです。風に委ねるくらいなら私に委ねてください、先輩」
「委ねるも何も……さっきも言ったでしょう? 私は私に、息苦しさなんて感じていないわ」
「本当ですか?」
「またそれを聞くのね」
困ったように苦笑し、渚紗はそっと、自分の首に絡まる砂凪の指を解いた。
「ええ。だって私は秦来渚紗で、秦来渚紗は私だもの。だからこそできた経験や、だからこそ出会えた人たちの存在をなかったことにしてまで、違う道を歩きたいとは思わないわ。来世を迎えに行くのは、今生を生き尽くした後でも十分に間に合うはずよ」
「そう、ですよね……ごめんなさい」
つぶやくように言って腕を引き戻し、一歩後ろに下がっていく砂凪の手を取り、渚紗はふわと優しく笑った。
「ありがとう」
「……え?」
「私のことを心配してくれたのでしょう?」
「それは……」
自分の知らないところで奪われるくらいならば自分の手で奪いたいと、そんな身勝手な理由からくる行動でしかなかったことはわかっているので、間違っても肯定などできはしなかった。
口を噤んだまま何も言ってこない砂凪から手を離した渚紗は、その手でごそごそと自分のブレザーのポケットから一本の鍵を取り出した。骨董品のような小さな鍵、その上部に開いた小さな穴には赤い糸が通され、蝶々結びに結われている。
「あなたにあげるわ」
言いながらそれを砂凪の手の中に握らせる。
「ここの鍵よ。理事長室に保管されているものをちょっと拝借して、コピーを作ったの。誰にも内緒よ?」
ふふ……といたずらっぽく笑う渚紗に、「でも……」と砂凪は言葉を濁した。
「休暇明けには私も実家に帰るわ。だからきっと、それを使う機会も減ってしまうでしょう? どうせ使わなくなってしまうのなら、私が持っているよりも砂凪さんにあげたいの」
「これがないと、先輩がここに来れなくなっちゃう」
その言葉に返された渚紗の笑みに、ああ、そうか……と砂凪はふいに思い至った。きっと彼女は、もうここに来ることはないのだろう。その身を、吹く風に委ねることも。
肩を落とすように俯けた顔を撫でるように、少しだけ体温の低い渚紗の手のひらに頬を包み込まれ、砂凪はそっと顔を上げた。
「そんな顔をしないで? 年度が終われば私は卒業し、あなたは進級していく。ただそれだけのことよ」
「そうかもしれないけど、私はそれが寂しいです」
優しく顔に触れてくる渚紗の手に自分の手を重ね、猫のようにすり……と頬を寄せる。ぴくりと小さく指先を震わせる渚紗の髪を、スカートを、撫でるように柔らかく吹いた風が、その流れに甘い香りを乗せふわりと砂凪の鼻腔をくすぐった。
「この香り……」
「え?」
「前にも……先輩からいい匂いがするなって思ったことがあって……」
砂凪の言葉に、「ああ……」と思い出したようにうなずき、渚紗は砂凪の頬から引き戻した手をそのままワイシャツの胸ポケットに差し入れた。そこから取り出した小ぶりな栞を手のひらに乗せ、砂凪の前に差し出す。
「アロマオイルを染み込ませて持ち歩いているの。お気に入りの香りを身近に感じていると、少し気持ちが和らぐ気がして。よければどうぞ?」
言ってから渚紗はふっと眉尻を下げ、その顔に微苦笑を浮かべた。
「とはいっても、香りはいずれ飛んでしまうものだったわね。ごめんなさい、余計なことだったわ」
「そんなことないです」
渚紗の手のひらから栞を受け取ると、砂凪はそれに視線を落とし、そっと目を細めた。
「香りは思い出せます。知ってますか? 香りって、一番最後まで人の記憶に残るらしいですよ。だからこれ、もらってもいいですか?」
「ええ、勿論」
言って渚紗は、ふわりと笑った。
*
年が明け、迎えた新年の二か月は瞬く間に過ぎていき、気付けば数日後には三年生の卒業式が控えていた。
鐘塔の鐘の下に寝転がった砂凪は、二学期の終業式にこの場所で渚紗にもらった栞を顔の前に掲げ、じっとそれを見上げていた。
あの時渚紗が言っていたように、そこに染み込んでいたはずの甘い香りはもう、とうの昔に飛んでいる。それでも目を閉じ、すんっと小さく鼻を鳴らせばあの香りを思い出すことができるのだから、人の記憶というのは本当によくできていると思う。ごろりとそのまま寝返りを打ち、栞を胸に抱きしめるようにしながら鐘塔の向こうに青く広がる海に目を向け、砂凪はつぶやくように口を開いた。
「……海は今日も青いですよ、先輩」
「そうね」
思いがけず返ってきた言葉に驚き、「えっ?」と目を丸くする。
慌ててその場に上体を起こし声の聞こえてきた方へと視線を動かすと、階段を登り切った場所に足を止めた渚紗が砂凪に目を向け、その顔に小さく笑みを浮かべていた。
「渚紗先輩? 今日は……?」
砂凪といえど、さすがに三年生の登校日までは把握していない。首をかしげ聞いてくる砂凪の横に腰を下ろし、渚紗は口を開いた。
「卒業式の予行演習よ。何だか、あっという間にこの日がきてしまった感じだわ」
ふふ……と小さく笑う渚紗の笑顔に、自分の口元も綻ぶのがわかる。だらしなく緩みそうになる表情筋を引き締めるように両手で頬を包み込むと、砂凪がその手に持ったままの栞に目を留めた渚紗が腰かけたレンガに手を付き、すいとその距離を詰めてきた。
「それ……」と渚紗が指さしてくる先に視線を移し、「ああ……」と栞を差し出す。
「毎日持ち歩いてるんですけど、さすがに香りは飛んじゃいました」
「オイルを持ってくればよかったわね」
申し訳なさそうに言う渚紗に、砂凪はぶんぶんと慌てて手を振り回した。
「そんなっ、全然です。今日先輩に会えただけでも嬉しすぎるくらいです」
言ってから、おや? と自分の言葉に首をかしげた。これじゃあまるで、恋をしているみたいではないか……?
「あら、嬉しいことを言ってくれるのね。まぁ私も、砂凪さんに会えたらいいな……と思って来てみたのだけれど」
「私に……ですか?」
「そうよ。そうでなければ、ここに来る必要もないでしょう?」
それは確かに。
「ひとつ、砂凪さんに伝えておいた方がいいと思うことがあって」
「何ですか?」
「卒業式の日には、ここには来てはダメよ?」
その気はなくとも自然とこの場所に足が向いてしまっていそうな数日後の自分の姿が容易に想像できてしまい、だからこそ「え?」と小さく声が漏れた。それが何故かを砂凪がたずねるより先に、渚紗が続ける。
「ここの鐘が鳴る数少ないうちのひとつが卒業式なの。だから当日は、たぶん秦来の誰かがここに来るのではないかしら」
それならば確かに、卒業式の日にこの場所をおとずれるのは得策ではないのだろう。わかりました、と返そうとして、けれど寸前で砂凪はその言葉を呑み込んだ。
「じゃあ……」と代わりの言葉が口をついて出てくる。それはつまり……
「先輩とこうやって会えるのは、今日で最後ってこと……ですか?」
「そういうことになるかもしれないわね」
ちらと首をかしげながら言ってくる渚紗に、卒業という言葉が急に現実味を帯びて感じられた。IDは交換したけれど、これまでメッセージでやり取りをしたことなんて数えるほどしかない。それが会おうと思えば校舎や寮でも会うことができるという生活環境によるものだったのかどうかはわからないけれど、頻度でいえばこの後もそれは変わることはないだろうし、そうなればたぶん、今後連絡を取ることは自然となくなっていくのだろう。それで、いいのだろうか……?
違う。いいとか悪いとかでもなく、それはきっと自分が今この場所でどんな行動を取ったところで覆ることはないと、そんなことはもはや、感覚的にわかっている。それでも……それだからこそ……
ああ、そうだ。この想いは恋と認めよう。
手にした栞を指先に持ち直すと、砂凪は隣に座る渚紗との距離を詰めるようにレンガに手を付いた。そちらに身体を押し出しながら、互いの間に差し入れた栞越しに、渚紗の唇に自分の唇を重ねる。渚紗が驚いたように目を瞬くのを気配で感じながら俯き気味にそのまま身体を引き戻すと、そっと息をついてから顔を上げ、正面から渚紗を見つめ静かに微笑んだ。
「あなたのことが好きでした。あなたが助けを求めるなら、どんな手を使ってでもあなたを救い、その存在を独占したいと思うほど」
「砂凪さん……」
「でも、あなたはきっとそれを求めはしない。だから、それでいいんです」
「……ごめんなさい」
「何故先輩が謝るんですか?」
不思議そうに首をかしげる砂凪に、渚紗は続けた。
「だって私は、今生ではあなたの気持ちに応えることができないから」
「わかってます。だからさっき、私言いましたよね? それでいいって」
「でも……」
渚紗が何かを言おうとするのを遮るように、先に砂凪が口を開いた。
「先輩は、勝手に自分の首を絞めすぎです。私がいいって言ってるんだから、それは受け入れてもらわないと私が困ります」
「そう……そうね。あなたを困らせてしまうのはよくないわね。私、先輩なのに」
ごめんなさい、と続けそうになった言葉を呑み込み、渚紗はふっと柔らかく目を細めた。
「ありがとう、砂凪さん」
「いいえ。むしろそれも、私の台詞です」
言ったところで校舎の方から聞こえてくる、リンゴーン……と響く予鈴の音に、渚紗も砂凪も揃ってそちらに目を向けた。
「……戻らないと」
つぶやくように言ってその場に立ち上がった砂凪が渚紗に視線を戻し、続ける。
「先輩も、行かないと予行演習始まっちゃいますよ」
「ええ、そうね」
差し出された砂凪の手を掴み立ち上がってから、渚紗は思い付いたようにその顔を見つめ返した。
「砂凪さん」
「はい?」
「あなたにあげた鍵、少し貸してもらえるかしら?」
「え? いいですけど……?」
何だろう? と思いながらもブレザーの内ポケットから取り出した鍵を渚紗に渡す。
受け取った鍵の上部に赤い蝶々が結わったままになっていることにほんの少しだけ頬を緩め、それから渚紗はするりとそれを解いた。その行動を首をかしげ眺める砂凪に一歩踏み込み、そのスカートのポケットに手を差し込む。
「……温かいわね」
ポケットの中に鍵を落としながらつぶやく渚紗に目を瞬き、あっ……と気付いたように砂凪は慌てて口を開いた。
「鍵、内ポケットに入れてたからあったかかった? ぬるかった? ですよね……ごめんなさい」
「え? ああ、そういうつもりで言ったわけではないのだけれど……」
距離を取り直しながら困ったように笑い、渚紗は砂凪のポケットから引き戻した手に視線を落とした。
あなたの周りはいつでも空気が穏やかで、近くにいるだけで心が温かくなる……柔らかくその手を握りしめてから、渚紗はそっと、改めて砂凪の手を取った。
「先輩……?」と不思議そうにたずねてくる砂凪の、軽く持ち上げさせた小指にふわと赤い糸を絡める。
「あなたが好きよ。たぶん、あなたが思っている以上にね。だから……」
砂凪の小指に絡めた赤い糸を蝶型に結いながら、渚紗は続けた。
「私が卒業した後も、この赤い糸に私の面影を見ることがあるのなら、その時はまた、来世で会いましょう」
言って、どこか妖艶にすら感じられる笑みだけをその場に残し、渚紗はふわりとスカートのすそを翻して階段の陰へと見えなくなっていった。
その日を締めくくるクラスのホームルームを終え、砂凪はふぅ……と大きく息をつきそのまま机に突っ伏した。何をしていても、何をしていなくても、どうしたって小指の赤い糸に目が向いてしまう。渚紗の言葉を思い出してしまう。
わかっている。認めている。受け入れている。だからこそ……
直接答えを返す前に、そもそもその機会すらもあるのかどうかわからないのだから、ならばせめて、あの場所に在るすべてに、あの場所から見えるすべてに、その約束を聞き届けてもらうくらいはしてもいいだろう。
がたっと椅子を鳴らして立ち上がると、砂凪はそのまま鐘塔へと足を向けた。
学園祭の前、陽の落ちた街並みを一緒に見下ろしたあの日を最後に、渚紗とは校舎や寮で軽く言葉を交わすことはあってもちゃんとは話をしていない。それはつまり、あの日以降、砂凪がおとずれるタイミングでは鐘塔の鍵が開いていなかったということでもある。
メッセージを送ってみてもいいのだろうけれど、受験に向けて忙しくしているのだろうか? あるいは……避けられている……? あの日の話を、そしてあの日の自分の思考を思い出しそんなことを考えてしまうと、そう気軽にスマホを取ることもできなかった。とはいえ、この自由登校期間に入ってからも構内でその姿を見かけることはあるので、渚紗はまだ風に攫われていないし、たぶん家に帰るつもりもないのだろう。
年内最後になる登校日、鍵が開いている期待は正直あまりなかったけれど足を向け、手をかけた鐘塔の扉が静かに開き、砂凪は驚きに一瞬その動きを止めた。心臓が大きく、トクトクと脈を打つ。けれどこれがどういった感情の反映なのか……嬉しいのか、それとも怖いのか……どちらにせよ自分にとって渚紗が、そういった感情を抱くほどには特別な存在になっているということに驚き、けれどそれと同時に、ようやく自身のいろいろな思考が腑に落ちた感じでもあった。
ゆっくりと階段を登り鐘の下に顔をのぞかせると、鐘塔の縁に腰を下ろし、その向こうに広がる街並みをぼんやりと眺めていた渚紗が、縁に足をかけその場に立ち上がった。踵を返すようにふとこちらに向けられた視線が砂凪のものと交わり、渚紗は驚いたように目を丸くしてから、これまでと変わらない笑みをその顔に浮かべた。
「久しぶりね、砂凪さん」
「お久しぶりです……」
言いながらも何となくぎくしゃくと視線を逸らす砂凪に、渚紗は不思議そうに首をかしげた。
「どうしたの? 変な顔をして」
「いやっ、あの……いると、思わなかったので……」
「あら、そうなの? でも鍵が開いていたから来たのでしょう?」
「それは……そう、なんですけど……」
「もしかして、あの日の話を気にして、私があなたのことを避けていると思っていたのかしら?」
こちらに歩み寄ってきながら図星をさされ、ぐっ……と言葉に詰まる。
「砂凪さんは素直ね」
言いながらくつくつと笑い、「でもそうね……」と渚紗は続けた。
「避けては……いたかもしれないわ」
その言葉にぴりつく胸を、知らず砂凪はブレザーの上から握りしめた。
「……私、先輩の嫌がること何かしちゃいました? 鬱陶しかったですか? しつこかった?」
「まさか」
驚いたように目を瞬いてから、困ったように微笑する。
「砂凪さんには楽しい時間をたくさんもらっただけよ。だからこれは、ただただ私の問題」
それは一体……? 首をかしげる砂凪に、渚紗はふと目を細めた。
「あの日話したように、私のこれからは、これからも秦来の名の下に続いていくの。それを悪いことだとは思わないし、今更これといった不満も特にはないけれど、それでもほんの少しだけ考えてしまったの。もし私が今生で、秦来の名前を気にせず生きる選択肢を与えられたとしたら、どうしていただろう……? とね。まぁそれでもたぶん、私はこの道を選んでいたとは思うけれど。だから……そうね、しいてあなたが私に何かをしてしまったというのならば、あなたは私に、息の仕方を教えてくれた、といったところかしら」
人差し指を軽く頬に当て、言葉を探すように小さく首をかしげる渚紗に砂凪はたずねた。
「先輩は息、できてなかったんですか?」
「まさか」
「じゃあ……息苦しかったですか?」
「いいえ」
「本当に?」
砂凪が聞き返してくる言葉に、「……ええ」と渚紗が不思議そうにうなずく。
「もし先輩が本当に……」
言いながらその距離をすいと詰めると、砂凪はゆっくりと伸ばした腕を渚紗の細い首に絡ませた。
「砂凪さん……?」
「本当は秦来渚紗でいることが息苦しいというのなら、私が今ここで先輩のこと殺してあげますよ?」
「……何言っているの? 冗談はやめてちょうだい」
「冗談じゃないです。風に委ねるくらいなら私に委ねてください、先輩」
「委ねるも何も……さっきも言ったでしょう? 私は私に、息苦しさなんて感じていないわ」
「本当ですか?」
「またそれを聞くのね」
困ったように苦笑し、渚紗はそっと、自分の首に絡まる砂凪の指を解いた。
「ええ。だって私は秦来渚紗で、秦来渚紗は私だもの。だからこそできた経験や、だからこそ出会えた人たちの存在をなかったことにしてまで、違う道を歩きたいとは思わないわ。来世を迎えに行くのは、今生を生き尽くした後でも十分に間に合うはずよ」
「そう、ですよね……ごめんなさい」
つぶやくように言って腕を引き戻し、一歩後ろに下がっていく砂凪の手を取り、渚紗はふわと優しく笑った。
「ありがとう」
「……え?」
「私のことを心配してくれたのでしょう?」
「それは……」
自分の知らないところで奪われるくらいならば自分の手で奪いたいと、そんな身勝手な理由からくる行動でしかなかったことはわかっているので、間違っても肯定などできはしなかった。
口を噤んだまま何も言ってこない砂凪から手を離した渚紗は、その手でごそごそと自分のブレザーのポケットから一本の鍵を取り出した。骨董品のような小さな鍵、その上部に開いた小さな穴には赤い糸が通され、蝶々結びに結われている。
「あなたにあげるわ」
言いながらそれを砂凪の手の中に握らせる。
「ここの鍵よ。理事長室に保管されているものをちょっと拝借して、コピーを作ったの。誰にも内緒よ?」
ふふ……といたずらっぽく笑う渚紗に、「でも……」と砂凪は言葉を濁した。
「休暇明けには私も実家に帰るわ。だからきっと、それを使う機会も減ってしまうでしょう? どうせ使わなくなってしまうのなら、私が持っているよりも砂凪さんにあげたいの」
「これがないと、先輩がここに来れなくなっちゃう」
その言葉に返された渚紗の笑みに、ああ、そうか……と砂凪はふいに思い至った。きっと彼女は、もうここに来ることはないのだろう。その身を、吹く風に委ねることも。
肩を落とすように俯けた顔を撫でるように、少しだけ体温の低い渚紗の手のひらに頬を包み込まれ、砂凪はそっと顔を上げた。
「そんな顔をしないで? 年度が終われば私は卒業し、あなたは進級していく。ただそれだけのことよ」
「そうかもしれないけど、私はそれが寂しいです」
優しく顔に触れてくる渚紗の手に自分の手を重ね、猫のようにすり……と頬を寄せる。ぴくりと小さく指先を震わせる渚紗の髪を、スカートを、撫でるように柔らかく吹いた風が、その流れに甘い香りを乗せふわりと砂凪の鼻腔をくすぐった。
「この香り……」
「え?」
「前にも……先輩からいい匂いがするなって思ったことがあって……」
砂凪の言葉に、「ああ……」と思い出したようにうなずき、渚紗は砂凪の頬から引き戻した手をそのままワイシャツの胸ポケットに差し入れた。そこから取り出した小ぶりな栞を手のひらに乗せ、砂凪の前に差し出す。
「アロマオイルを染み込ませて持ち歩いているの。お気に入りの香りを身近に感じていると、少し気持ちが和らぐ気がして。よければどうぞ?」
言ってから渚紗はふっと眉尻を下げ、その顔に微苦笑を浮かべた。
「とはいっても、香りはいずれ飛んでしまうものだったわね。ごめんなさい、余計なことだったわ」
「そんなことないです」
渚紗の手のひらから栞を受け取ると、砂凪はそれに視線を落とし、そっと目を細めた。
「香りは思い出せます。知ってますか? 香りって、一番最後まで人の記憶に残るらしいですよ。だからこれ、もらってもいいですか?」
「ええ、勿論」
言って渚紗は、ふわりと笑った。
*
年が明け、迎えた新年の二か月は瞬く間に過ぎていき、気付けば数日後には三年生の卒業式が控えていた。
鐘塔の鐘の下に寝転がった砂凪は、二学期の終業式にこの場所で渚紗にもらった栞を顔の前に掲げ、じっとそれを見上げていた。
あの時渚紗が言っていたように、そこに染み込んでいたはずの甘い香りはもう、とうの昔に飛んでいる。それでも目を閉じ、すんっと小さく鼻を鳴らせばあの香りを思い出すことができるのだから、人の記憶というのは本当によくできていると思う。ごろりとそのまま寝返りを打ち、栞を胸に抱きしめるようにしながら鐘塔の向こうに青く広がる海に目を向け、砂凪はつぶやくように口を開いた。
「……海は今日も青いですよ、先輩」
「そうね」
思いがけず返ってきた言葉に驚き、「えっ?」と目を丸くする。
慌ててその場に上体を起こし声の聞こえてきた方へと視線を動かすと、階段を登り切った場所に足を止めた渚紗が砂凪に目を向け、その顔に小さく笑みを浮かべていた。
「渚紗先輩? 今日は……?」
砂凪といえど、さすがに三年生の登校日までは把握していない。首をかしげ聞いてくる砂凪の横に腰を下ろし、渚紗は口を開いた。
「卒業式の予行演習よ。何だか、あっという間にこの日がきてしまった感じだわ」
ふふ……と小さく笑う渚紗の笑顔に、自分の口元も綻ぶのがわかる。だらしなく緩みそうになる表情筋を引き締めるように両手で頬を包み込むと、砂凪がその手に持ったままの栞に目を留めた渚紗が腰かけたレンガに手を付き、すいとその距離を詰めてきた。
「それ……」と渚紗が指さしてくる先に視線を移し、「ああ……」と栞を差し出す。
「毎日持ち歩いてるんですけど、さすがに香りは飛んじゃいました」
「オイルを持ってくればよかったわね」
申し訳なさそうに言う渚紗に、砂凪はぶんぶんと慌てて手を振り回した。
「そんなっ、全然です。今日先輩に会えただけでも嬉しすぎるくらいです」
言ってから、おや? と自分の言葉に首をかしげた。これじゃあまるで、恋をしているみたいではないか……?
「あら、嬉しいことを言ってくれるのね。まぁ私も、砂凪さんに会えたらいいな……と思って来てみたのだけれど」
「私に……ですか?」
「そうよ。そうでなければ、ここに来る必要もないでしょう?」
それは確かに。
「ひとつ、砂凪さんに伝えておいた方がいいと思うことがあって」
「何ですか?」
「卒業式の日には、ここには来てはダメよ?」
その気はなくとも自然とこの場所に足が向いてしまっていそうな数日後の自分の姿が容易に想像できてしまい、だからこそ「え?」と小さく声が漏れた。それが何故かを砂凪がたずねるより先に、渚紗が続ける。
「ここの鐘が鳴る数少ないうちのひとつが卒業式なの。だから当日は、たぶん秦来の誰かがここに来るのではないかしら」
それならば確かに、卒業式の日にこの場所をおとずれるのは得策ではないのだろう。わかりました、と返そうとして、けれど寸前で砂凪はその言葉を呑み込んだ。
「じゃあ……」と代わりの言葉が口をついて出てくる。それはつまり……
「先輩とこうやって会えるのは、今日で最後ってこと……ですか?」
「そういうことになるかもしれないわね」
ちらと首をかしげながら言ってくる渚紗に、卒業という言葉が急に現実味を帯びて感じられた。IDは交換したけれど、これまでメッセージでやり取りをしたことなんて数えるほどしかない。それが会おうと思えば校舎や寮でも会うことができるという生活環境によるものだったのかどうかはわからないけれど、頻度でいえばこの後もそれは変わることはないだろうし、そうなればたぶん、今後連絡を取ることは自然となくなっていくのだろう。それで、いいのだろうか……?
違う。いいとか悪いとかでもなく、それはきっと自分が今この場所でどんな行動を取ったところで覆ることはないと、そんなことはもはや、感覚的にわかっている。それでも……それだからこそ……
ああ、そうだ。この想いは恋と認めよう。
手にした栞を指先に持ち直すと、砂凪は隣に座る渚紗との距離を詰めるようにレンガに手を付いた。そちらに身体を押し出しながら、互いの間に差し入れた栞越しに、渚紗の唇に自分の唇を重ねる。渚紗が驚いたように目を瞬くのを気配で感じながら俯き気味にそのまま身体を引き戻すと、そっと息をついてから顔を上げ、正面から渚紗を見つめ静かに微笑んだ。
「あなたのことが好きでした。あなたが助けを求めるなら、どんな手を使ってでもあなたを救い、その存在を独占したいと思うほど」
「砂凪さん……」
「でも、あなたはきっとそれを求めはしない。だから、それでいいんです」
「……ごめんなさい」
「何故先輩が謝るんですか?」
不思議そうに首をかしげる砂凪に、渚紗は続けた。
「だって私は、今生ではあなたの気持ちに応えることができないから」
「わかってます。だからさっき、私言いましたよね? それでいいって」
「でも……」
渚紗が何かを言おうとするのを遮るように、先に砂凪が口を開いた。
「先輩は、勝手に自分の首を絞めすぎです。私がいいって言ってるんだから、それは受け入れてもらわないと私が困ります」
「そう……そうね。あなたを困らせてしまうのはよくないわね。私、先輩なのに」
ごめんなさい、と続けそうになった言葉を呑み込み、渚紗はふっと柔らかく目を細めた。
「ありがとう、砂凪さん」
「いいえ。むしろそれも、私の台詞です」
言ったところで校舎の方から聞こえてくる、リンゴーン……と響く予鈴の音に、渚紗も砂凪も揃ってそちらに目を向けた。
「……戻らないと」
つぶやくように言ってその場に立ち上がった砂凪が渚紗に視線を戻し、続ける。
「先輩も、行かないと予行演習始まっちゃいますよ」
「ええ、そうね」
差し出された砂凪の手を掴み立ち上がってから、渚紗は思い付いたようにその顔を見つめ返した。
「砂凪さん」
「はい?」
「あなたにあげた鍵、少し貸してもらえるかしら?」
「え? いいですけど……?」
何だろう? と思いながらもブレザーの内ポケットから取り出した鍵を渚紗に渡す。
受け取った鍵の上部に赤い蝶々が結わったままになっていることにほんの少しだけ頬を緩め、それから渚紗はするりとそれを解いた。その行動を首をかしげ眺める砂凪に一歩踏み込み、そのスカートのポケットに手を差し込む。
「……温かいわね」
ポケットの中に鍵を落としながらつぶやく渚紗に目を瞬き、あっ……と気付いたように砂凪は慌てて口を開いた。
「鍵、内ポケットに入れてたからあったかかった? ぬるかった? ですよね……ごめんなさい」
「え? ああ、そういうつもりで言ったわけではないのだけれど……」
距離を取り直しながら困ったように笑い、渚紗は砂凪のポケットから引き戻した手に視線を落とした。
あなたの周りはいつでも空気が穏やかで、近くにいるだけで心が温かくなる……柔らかくその手を握りしめてから、渚紗はそっと、改めて砂凪の手を取った。
「先輩……?」と不思議そうにたずねてくる砂凪の、軽く持ち上げさせた小指にふわと赤い糸を絡める。
「あなたが好きよ。たぶん、あなたが思っている以上にね。だから……」
砂凪の小指に絡めた赤い糸を蝶型に結いながら、渚紗は続けた。
「私が卒業した後も、この赤い糸に私の面影を見ることがあるのなら、その時はまた、来世で会いましょう」
言って、どこか妖艶にすら感じられる笑みだけをその場に残し、渚紗はふわりとスカートのすそを翻して階段の陰へと見えなくなっていった。
その日を締めくくるクラスのホームルームを終え、砂凪はふぅ……と大きく息をつきそのまま机に突っ伏した。何をしていても、何をしていなくても、どうしたって小指の赤い糸に目が向いてしまう。渚紗の言葉を思い出してしまう。
わかっている。認めている。受け入れている。だからこそ……
直接答えを返す前に、そもそもその機会すらもあるのかどうかわからないのだから、ならばせめて、あの場所に在るすべてに、あの場所から見えるすべてに、その約束を聞き届けてもらうくらいはしてもいいだろう。
がたっと椅子を鳴らして立ち上がると、砂凪はそのまま鐘塔へと足を向けた。