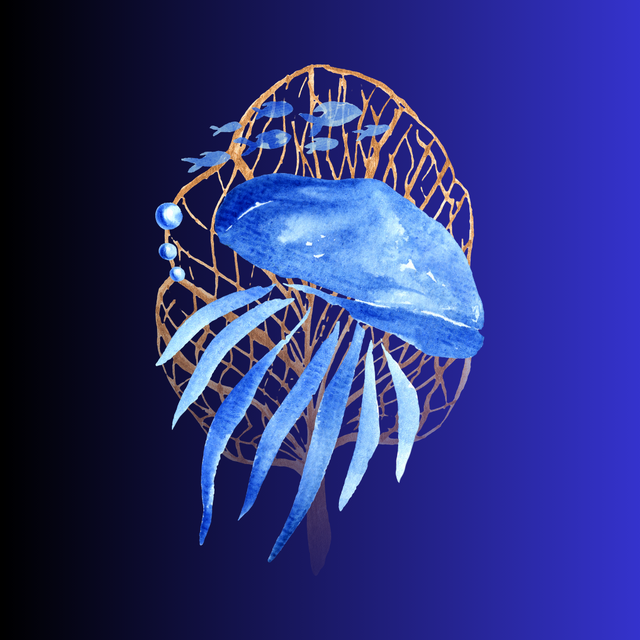第4話
文字数 4,516文字
一岐龍は時風の格子戸の前に佇んでいた。
「……紲ちゃん、大丈夫かな」
後ろ髪を引かれる思いを残しながらその場を離れる。ビルの外はまだ夜になりきれていない。じっとりと纏わりつく湿気の中に、何か生臭いような厭な匂いが混ざっていた。
久しぶりにまとまった時間を作ることができ、今日はゆっくり時風で過ごそうと考えていたが、その当てが外れてしまいどうしたものかと暮れ泥む街の中を進む。夕方特有の少し浮ついた、落ち着かない人混みの中を歩みながら……臭いが気になる。はっきりと何の臭いと判別できるほどではないのに、気がついてしまったら気にせずにいられない。
いっそ別のものでごまかそうと、通りがかりに目に入ったコーヒースタンドへ入ることにした。入り口脇のハイテーブルに両肘をついてぼんやりしていた男性客が顔を上げる。何の感情も映さないような眼が一岐を捕らえた。視線が細い糸のように一岐を絡めとる。一岐は、スッと意識を変えた。途端に、男の視線は解かれ、それは窓の方へ移される。窓を見ているのか、窓の外を見ているのか、一岐にはわからない。
ふと以前に巽と交わした会話が蘇った。沁むように広がる記憶に浸りたくなる。店員から声をかけられて注文もせずにいたことに気が付き、メニューも見ずにオリジナルブレンドを注文した。
紙コップで提供された注文のコーヒーを受け取り、一岐は少し考える。外はまだあの臭いがするのだろうか。もう少しコーヒーの香りに包まれていたかった。店内には数か所ハイテーブルがある。客は入り口脇に陣取っているあの男の他にいない。結局、一番奥側の、入口からは影になっている場所を借りることにした。
紙コップから蓋を外すと南国の果実を思わせる華やかな香りが舞遊ぶ。口に含めば、予想したよりも厚みのある質感で、熟成した赤ワインのように芳しい。一岐は気に入った。そして、自分がだいぶ動揺していたことに気がついた。
紲の白い顔を今更思い出して、体の内側をざらりと不安が撫でていく。そして、紲に今日はいつもと違うような印象を受けたことを思い出した。何がとはうまく言えないが、何かが違った。外の臭いにしろ、紲の印象にしろ、判然と言い表せない不快感に思わず眉根を寄せる。
「一岐龍さんですよね、こんばんは」
唐突に声をかけられ、一岐は壁に凭れていた身体を起した。声の主は少年と言ってもいいような、背が低く、線の細い男だった。
「あ、はい……こんばんは」
彼は愛想よく笑いながら、ファンなのだと握手を求めてきた。一岐はそれに応えつつ、どうしてこの場を逃げようかと算段を立てる。久しぶりの休み、仕事に関わることは少しでも切り離したかった。が、男は人懐っこい笑顔で一岐が注目されるきっかけとなった映画について話し始めた。
にこやかに話し続ける男の後からスッと影のようなものが揺らめいてひゅっと息を吸い込んだ。この日、二度目の感覚だった。そして、その揺らめいた影のようなものも、同じく二度目に会う人物だった。
「……こた、さん?」
あの時綉が叫ぶように呼んだ名前を、思わず口にしてしまってから、一岐は少し焦った。なぜだかは分からないが、声に出してはいけないような気がした。
コタが無言で小さく頷くと、もうひとりの男が笑顔のまま一岐の手首を掴んだ。
「ああ、コタは会ってるんですね。ボク、コタの双子の兄でサクっていいます。ちょっとですね、ややこしいことになってまして……一緒に来てほしいんですよ」
双子と言われてよく見れば、確かに容貌は似ているが、彼等が与える印象はあまりにも対照的だった。サクと名乗った彼は愛想のいい笑顔を浮かべている。しかし、その笑顔は一岐に底知れぬ不安を与えた。
「心配しなくて大丈夫ですよ。紲さんのことについても少し確認したいことがありまして。シュウから連絡するって言われてませんでした?」
「……え? ああ、綉くん……連絡って、はい……いや、でも……」
最早なにを自分が話そうとしているのかよく分からない。
「その連絡がボクたちです。すみません、手荒にはしたくないので、このまま一緒に来てもらえません?」
「一緒にって、どこ……へ!?」
皆まで言い終えないうちに、一岐は歩みだしていた。右手首はサクに掴まれている。自分のより一回りは小さいその手を振り解くことはできなそうだった。左後ろからコタがピッタリと突いてくる。完全に連行されている格好だ。さすがにこんなところを目撃されたら厄介だ。しかし、歩みは止まらない。
「ちょっと、あの……サクさん?」
「すみません、もう少しこのまま進んでくださいね」
入口脇のテーブルを通り過ぎる時、ふと気になって目をやったが、男はこちらを見向きもしなかった。入口の自動扉が開くと、男はビクッと体を震わせ、驚いたような表情で辺りを見回している。
外はいつの間にかすっかり暮れて、しっとりとした夜の帳に包まれていた。一岐の歩みは止まらない。目指す場所もわからないのに、迷う間もなく進んでいく。
「……なんだか浮ついているなあ」
サクの声色は不愉快そうだったが、その顔はにこやかなままだ。コタは無言のまま音もなく左後ろにいる。対照的な双子に挟まれたまま、一岐は地下鉄の入口に吸い込まれていった。
「……!?」
文字通り吸い込まれたのだ。階段を一段降りようとしたところで光と闇の渦に巻き込まれた。
「すみません、慣れないとちょっと気持ち悪いと思いますが……まだあなたに道を知られるわけにいかないので、もう少しの間辛抱してくださいね」
サクの声が近くでしたが、どこにいるのかその姿は見えない。自分が上を向いているのか下を向いているのか……歩いているのかすらよく判らなかった。
渦巻く光と闇が次第に混ざり合っていく。混然となった光と闇に一岐は「狭間……」と無意識に呟いた。視界は唐突に開け、一岐はエレベーターらしき物の中にいることを知る。経験上の感覚が正確であるなら下に向っていると思われたが、自信はなかった。
エレベーターがスッと停止する。だいぶ長い間乗っていたような気がするが、どれほど地下に潜ったのだろう。地下鉄に乗るためのエレベーターでこんなに長く乗るものがあるだろうかと思案していると、ヌッと扉が開いた。一岐は眼の前広がった景色に愕然とした。
「え……? なんで昼間、いや、朝?」
「すみません、ボクたちでは何をどこまで説明していいのか判断できないんです。色々と気持ち悪いと思いますが……」
サクの詫びの言葉に頷きながら一岐は辺りを見回した。確かに扉が開いてここに来たのに、背後に扉のようなものは何もなかった。それに、あんなに地下に下りる感覚がしていたのに、ここは燦々と陽の光が降り注ぐ地上だ。木漏れ日が眩しい。ついさっきまで皇都の繁華街に居たはずなのに、ここは深い森の中だ。
鳥の囀り、近くにあるのだろう小川のせせらぎ、風にそよぐ葉擦れの音……その一つ一つが煌めいて目に見えるかのようだ。森のざわめきに包まれているのに、そこには静寂があった。そういえばシンとするのシンは森と書くんだったなと、一岐はどうでもいいことを思った。そして、この数ヶ月の間ずっと感じていた、得体のしれない不安のような、居心地の悪い感覚から開放されていることに気がついた。
「具合悪くないですか?」
「いえ……気持ちが悪いほどに、気持ちいいです」
一岐の言葉に、サクが目を丸くしてから吹き出した。薄気味悪く感じていた不自然なにこやさはそこには無かった。
「どっちですか、それ」
「ああ、いや……そうですよね。あの、ここ最近感じていた居心地の悪い感じがなくて……清々しいというか……こんな森の中にいたら、そりゃそうですよね」
どう説明したらいいか判らず、一岐は首をひねる。
「居心地の悪い感じって、どんな感じでしたか?」
「ええっと、そうですね……なんだろう、服の前後ろを逆に着ているような、靴の左右を間違えて履いているような……着ぐるみ? 自分が着ぐるみで、中にいる誰かが自分とは違う動き方をしたがっている……その反対かも」
「そうですか。大丈夫そうですね……では、行きましょう」
こちらへ、と促される。コーヒースタンドを出るときのような強引さはなく、また勝手に体が進むようなこともなく、一岐は自分の意思で進むという選択をした。
「山登りするわけではないので心配しないでくださいね。10分ほど歩きます」
舗装されているわけではないが、道は歩きやすく整っていた。息をするたび、歩を進めるたび、鳥や虫の声が聞こえるたび、一岐は自分の中に、なにかキラキラしたものが降り積もっていくのを感じた。身体が震える。今自分がここに在ることへの歓喜が泉のごとく滾々と沸き溢れて、打ち震えていたのだ。
なだらかな登路の傍には生と死があった。朽ちた木の根元には小さな生命が芽吹き、萎れた花の隣にはたっぷりと膨らんだ蕾が、落ち葉を運ぶ小さな蟲たちが、木々の間には何かの実を咥えて飛び去る鳥が……一岐は『鬼』の科白を思い返していた。
『森羅万象、永劫失われぬものなど何もなし。其々は其々が在るために在り、在るがために失われ、失われるがために在る。人の理などこの世に何の意味も生さぬ。むしろ人の理が吾の如き鬼を生むのじゃ』
あの時自分はどんな心持ちでこの科白を吐いただろうか……人々の思念が寄り集まって偶像化された『鬼』は、人であり、人でない。恐れられ、疎まれ、忌み嫌われ……人々が作り上げた偶像なのにと、自分が吐き出した科白は人に対する悲憤慷慨も含んでいたが、それより鬼への哀れみの方が大きくあった。あの時は確かにそうだった。しかし、今は……
「鬼の科白ですね」
心の内で反芻しているつもりだった科白は声になっていたらしい。
「ボク、原作の小説が好きでよく読んでいました。あの鬼は……人に非ざるものでありながら、人であろうとする感じが素晴らしかったと思います」
「……ありがとうございます。確かに、あの時は人であろうとしてると……そんな鬼に、悲哀のようなものも感じていました。でも、今は……もう少し違う感じがあるかもしれません」
サクは柔らかな笑みを一岐に向けた。
「さて、着きました」
正面には子供がひとりやっと通れる程の小さな緑門があった。サクが先に立ち、一礼するとやや屈みながら中へ入っていった。振り返ると、コタが小さく頷く。一岐はサクを真似て一礼してくぐり抜ける。後にコタも続いた。
中は、入口の小ささが不思議なほどに大きな場であった。先に入ったサクが右手側にある小屋の方へ手招いている。小屋の中には猿のような置物が水を供している流し台が備えられていた。サクが両手で水を受け、手を清めた後再度両手で水を受けるとその水を口に含んだ。口をすすいだあと改めて両手を清める。見様見真似で一岐もそれを倣った。濡れた手と口元をどうするか迷っていると、コタからそっと紙を差し出される。ハンカチを持ち歩いていないことを一岐は少し恥ずかしく感じながら紙を受取り、口元と手を拭いてから、その紙を小さく折り畳んでポケットにねじ込んだ。
「……紲ちゃん、大丈夫かな」
後ろ髪を引かれる思いを残しながらその場を離れる。ビルの外はまだ夜になりきれていない。じっとりと纏わりつく湿気の中に、何か生臭いような厭な匂いが混ざっていた。
久しぶりにまとまった時間を作ることができ、今日はゆっくり時風で過ごそうと考えていたが、その当てが外れてしまいどうしたものかと暮れ泥む街の中を進む。夕方特有の少し浮ついた、落ち着かない人混みの中を歩みながら……臭いが気になる。はっきりと何の臭いと判別できるほどではないのに、気がついてしまったら気にせずにいられない。
いっそ別のものでごまかそうと、通りがかりに目に入ったコーヒースタンドへ入ることにした。入り口脇のハイテーブルに両肘をついてぼんやりしていた男性客が顔を上げる。何の感情も映さないような眼が一岐を捕らえた。視線が細い糸のように一岐を絡めとる。一岐は、スッと意識を変えた。途端に、男の視線は解かれ、それは窓の方へ移される。窓を見ているのか、窓の外を見ているのか、一岐にはわからない。
ふと以前に巽と交わした会話が蘇った。沁むように広がる記憶に浸りたくなる。店員から声をかけられて注文もせずにいたことに気が付き、メニューも見ずにオリジナルブレンドを注文した。
紙コップで提供された注文のコーヒーを受け取り、一岐は少し考える。外はまだあの臭いがするのだろうか。もう少しコーヒーの香りに包まれていたかった。店内には数か所ハイテーブルがある。客は入り口脇に陣取っているあの男の他にいない。結局、一番奥側の、入口からは影になっている場所を借りることにした。
紙コップから蓋を外すと南国の果実を思わせる華やかな香りが舞遊ぶ。口に含めば、予想したよりも厚みのある質感で、熟成した赤ワインのように芳しい。一岐は気に入った。そして、自分がだいぶ動揺していたことに気がついた。
紲の白い顔を今更思い出して、体の内側をざらりと不安が撫でていく。そして、紲に今日はいつもと違うような印象を受けたことを思い出した。何がとはうまく言えないが、何かが違った。外の臭いにしろ、紲の印象にしろ、判然と言い表せない不快感に思わず眉根を寄せる。
「一岐龍さんですよね、こんばんは」
唐突に声をかけられ、一岐は壁に凭れていた身体を起した。声の主は少年と言ってもいいような、背が低く、線の細い男だった。
「あ、はい……こんばんは」
彼は愛想よく笑いながら、ファンなのだと握手を求めてきた。一岐はそれに応えつつ、どうしてこの場を逃げようかと算段を立てる。久しぶりの休み、仕事に関わることは少しでも切り離したかった。が、男は人懐っこい笑顔で一岐が注目されるきっかけとなった映画について話し始めた。
にこやかに話し続ける男の後からスッと影のようなものが揺らめいてひゅっと息を吸い込んだ。この日、二度目の感覚だった。そして、その揺らめいた影のようなものも、同じく二度目に会う人物だった。
「……こた、さん?」
あの時綉が叫ぶように呼んだ名前を、思わず口にしてしまってから、一岐は少し焦った。なぜだかは分からないが、声に出してはいけないような気がした。
コタが無言で小さく頷くと、もうひとりの男が笑顔のまま一岐の手首を掴んだ。
「ああ、コタは会ってるんですね。ボク、コタの双子の兄でサクっていいます。ちょっとですね、ややこしいことになってまして……一緒に来てほしいんですよ」
双子と言われてよく見れば、確かに容貌は似ているが、彼等が与える印象はあまりにも対照的だった。サクと名乗った彼は愛想のいい笑顔を浮かべている。しかし、その笑顔は一岐に底知れぬ不安を与えた。
「心配しなくて大丈夫ですよ。紲さんのことについても少し確認したいことがありまして。シュウから連絡するって言われてませんでした?」
「……え? ああ、綉くん……連絡って、はい……いや、でも……」
最早なにを自分が話そうとしているのかよく分からない。
「その連絡がボクたちです。すみません、手荒にはしたくないので、このまま一緒に来てもらえません?」
「一緒にって、どこ……へ!?」
皆まで言い終えないうちに、一岐は歩みだしていた。右手首はサクに掴まれている。自分のより一回りは小さいその手を振り解くことはできなそうだった。左後ろからコタがピッタリと突いてくる。完全に連行されている格好だ。さすがにこんなところを目撃されたら厄介だ。しかし、歩みは止まらない。
「ちょっと、あの……サクさん?」
「すみません、もう少しこのまま進んでくださいね」
入口脇のテーブルを通り過ぎる時、ふと気になって目をやったが、男はこちらを見向きもしなかった。入口の自動扉が開くと、男はビクッと体を震わせ、驚いたような表情で辺りを見回している。
外はいつの間にかすっかり暮れて、しっとりとした夜の帳に包まれていた。一岐の歩みは止まらない。目指す場所もわからないのに、迷う間もなく進んでいく。
「……なんだか浮ついているなあ」
サクの声色は不愉快そうだったが、その顔はにこやかなままだ。コタは無言のまま音もなく左後ろにいる。対照的な双子に挟まれたまま、一岐は地下鉄の入口に吸い込まれていった。
「……!?」
文字通り吸い込まれたのだ。階段を一段降りようとしたところで光と闇の渦に巻き込まれた。
「すみません、慣れないとちょっと気持ち悪いと思いますが……まだあなたに道を知られるわけにいかないので、もう少しの間辛抱してくださいね」
サクの声が近くでしたが、どこにいるのかその姿は見えない。自分が上を向いているのか下を向いているのか……歩いているのかすらよく判らなかった。
渦巻く光と闇が次第に混ざり合っていく。混然となった光と闇に一岐は「狭間……」と無意識に呟いた。視界は唐突に開け、一岐はエレベーターらしき物の中にいることを知る。経験上の感覚が正確であるなら下に向っていると思われたが、自信はなかった。
エレベーターがスッと停止する。だいぶ長い間乗っていたような気がするが、どれほど地下に潜ったのだろう。地下鉄に乗るためのエレベーターでこんなに長く乗るものがあるだろうかと思案していると、ヌッと扉が開いた。一岐は眼の前広がった景色に愕然とした。
「え……? なんで昼間、いや、朝?」
「すみません、ボクたちでは何をどこまで説明していいのか判断できないんです。色々と気持ち悪いと思いますが……」
サクの詫びの言葉に頷きながら一岐は辺りを見回した。確かに扉が開いてここに来たのに、背後に扉のようなものは何もなかった。それに、あんなに地下に下りる感覚がしていたのに、ここは燦々と陽の光が降り注ぐ地上だ。木漏れ日が眩しい。ついさっきまで皇都の繁華街に居たはずなのに、ここは深い森の中だ。
鳥の囀り、近くにあるのだろう小川のせせらぎ、風にそよぐ葉擦れの音……その一つ一つが煌めいて目に見えるかのようだ。森のざわめきに包まれているのに、そこには静寂があった。そういえばシンとするのシンは森と書くんだったなと、一岐はどうでもいいことを思った。そして、この数ヶ月の間ずっと感じていた、得体のしれない不安のような、居心地の悪い感覚から開放されていることに気がついた。
「具合悪くないですか?」
「いえ……気持ちが悪いほどに、気持ちいいです」
一岐の言葉に、サクが目を丸くしてから吹き出した。薄気味悪く感じていた不自然なにこやさはそこには無かった。
「どっちですか、それ」
「ああ、いや……そうですよね。あの、ここ最近感じていた居心地の悪い感じがなくて……清々しいというか……こんな森の中にいたら、そりゃそうですよね」
どう説明したらいいか判らず、一岐は首をひねる。
「居心地の悪い感じって、どんな感じでしたか?」
「ええっと、そうですね……なんだろう、服の前後ろを逆に着ているような、靴の左右を間違えて履いているような……着ぐるみ? 自分が着ぐるみで、中にいる誰かが自分とは違う動き方をしたがっている……その反対かも」
「そうですか。大丈夫そうですね……では、行きましょう」
こちらへ、と促される。コーヒースタンドを出るときのような強引さはなく、また勝手に体が進むようなこともなく、一岐は自分の意思で進むという選択をした。
「山登りするわけではないので心配しないでくださいね。10分ほど歩きます」
舗装されているわけではないが、道は歩きやすく整っていた。息をするたび、歩を進めるたび、鳥や虫の声が聞こえるたび、一岐は自分の中に、なにかキラキラしたものが降り積もっていくのを感じた。身体が震える。今自分がここに在ることへの歓喜が泉のごとく滾々と沸き溢れて、打ち震えていたのだ。
なだらかな登路の傍には生と死があった。朽ちた木の根元には小さな生命が芽吹き、萎れた花の隣にはたっぷりと膨らんだ蕾が、落ち葉を運ぶ小さな蟲たちが、木々の間には何かの実を咥えて飛び去る鳥が……一岐は『鬼』の科白を思い返していた。
『森羅万象、永劫失われぬものなど何もなし。其々は其々が在るために在り、在るがために失われ、失われるがために在る。人の理などこの世に何の意味も生さぬ。むしろ人の理が吾の如き鬼を生むのじゃ』
あの時自分はどんな心持ちでこの科白を吐いただろうか……人々の思念が寄り集まって偶像化された『鬼』は、人であり、人でない。恐れられ、疎まれ、忌み嫌われ……人々が作り上げた偶像なのにと、自分が吐き出した科白は人に対する悲憤慷慨も含んでいたが、それより鬼への哀れみの方が大きくあった。あの時は確かにそうだった。しかし、今は……
「鬼の科白ですね」
心の内で反芻しているつもりだった科白は声になっていたらしい。
「ボク、原作の小説が好きでよく読んでいました。あの鬼は……人に非ざるものでありながら、人であろうとする感じが素晴らしかったと思います」
「……ありがとうございます。確かに、あの時は人であろうとしてると……そんな鬼に、悲哀のようなものも感じていました。でも、今は……もう少し違う感じがあるかもしれません」
サクは柔らかな笑みを一岐に向けた。
「さて、着きました」
正面には子供がひとりやっと通れる程の小さな緑門があった。サクが先に立ち、一礼するとやや屈みながら中へ入っていった。振り返ると、コタが小さく頷く。一岐はサクを真似て一礼してくぐり抜ける。後にコタも続いた。
中は、入口の小ささが不思議なほどに大きな場であった。先に入ったサクが右手側にある小屋の方へ手招いている。小屋の中には猿のような置物が水を供している流し台が備えられていた。サクが両手で水を受け、手を清めた後再度両手で水を受けるとその水を口に含んだ。口をすすいだあと改めて両手を清める。見様見真似で一岐もそれを倣った。濡れた手と口元をどうするか迷っていると、コタからそっと紙を差し出される。ハンカチを持ち歩いていないことを一岐は少し恥ずかしく感じながら紙を受取り、口元と手を拭いてから、その紙を小さく折り畳んでポケットにねじ込んだ。