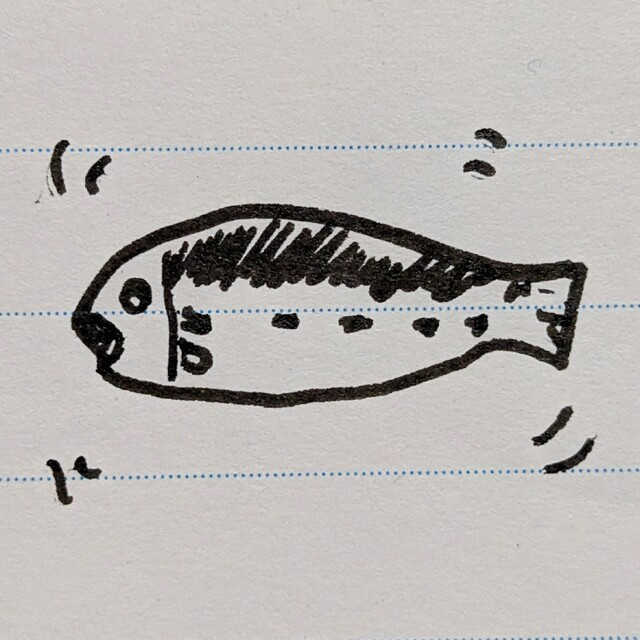2-3
文字数 2,934文字
修学旅行が終わり帰宅してからというもの、私の自涜に費やす時間と言うものは増加傾向にあった。寝物語という補助を失した為に質の落ちた妄想では性的快楽の充足から我に返るまでの時間が短縮されてしまい、私の不能という醜悪に劣等の募るのを自覚する事の方が容易であった。しかしながら快楽の最中では不能への嘱目は当然疎くなるので、いつか私の自涜への意欲というものが快速力に昇るようになっていたという訳である。勿論瘧が落ちれば索然が報いて一再ならず不能を確信し、嫌悪とそれから劣等の横溢に耐えられなくなって快楽という糊塗へ耽溺するのである。思えば索然とする要因と言うものは往時の晴天、それから行事の緩慢さが影響して彼女との接点が減少した由も一因を担っていたのだろう。確かに私は彼女が見えぬ日が続くばかりで修学旅行中に掻き抱いた艶冶を宛らの偶像を脳裏で確かめていた。
その日もまた、私は苛立ちと見紛う程の威力で恋煩いの執拗さを宛らに射精した。その次の日も、そのまた次の日も、半日と閲しなくても、私は快楽の傍にいた。その度に脳裏の性交渉の可能な物質は彼女の成分を濃厚にしていった。
私が久しく彼女を目撃したのはそれからややあってからの事で、やはりスクールバスを待っている彼女であった。その見慣れた展開に差異があるとすれば私の感情程度のもので、以前の欣喜に困惑が交っていた事である。その困惑の出所は久し振りに認めた彼女の生動が脳裏の婀娜と参酌して著しかったという違いだった。もっとも私の脳裏の存在も彼女らしさを増すにつれて動くようになったけれども、往時の段階では未だ現実世界で頻繁に眼にするような生気の感じる運動を考えていなかった。そんな中で実物の彼女は友人と会話を楽しんでいたし、たまに私と視線が交われば面映ゆげに逸する事だってした。それらの決してトルソーが行うことのできない生動は、得てして私に変化の下萌えを涵養し、また、故知らぬ安堵に導いたのである。本当に故知らぬそれであったから、私は安堵が報いた理由を考える事はしないでいた。
私の視線は彼女を逃さなかった。とはいえクラスメイト程の距離感で彼女を見詰めるのは怯懦が故に不可能であったので、他人程の径庭で岡惚れていたに過ぎなかった。
私のある種睥睨が不断であったのは、いつか彼女の生動に執着していたからなのだろう。眼を逸らさなければ逸らさぬだけ生動は甚だしく、例えば愁眉を開くような柔和さで友人との談笑に応じる手弱女の挙止、例えば奢侈である程の軽薄才子が口元に宿る言辞、笑みに歪む口元を繊弱な手で隠す様は人間らしい一入の生動を感じずにはいられなかった。それでも私はバスが到着し搭乗するまで彼女を見詰めた。見詰めれば見詰めるだけ私には譬へ無い何か変化のような角度によっては喪心のような、また喜悦にも似た感情に苛まれた。私の中の確かな瓦解が、またそれ自体を否もうと彼女を見詰めていたに違いなかった。
……今しの語りのような偶にの刺激は、畳なわる毎に生動への執着を確かに昇らせた。これらの云わば生動に繋縛された状態というものは卒業まで顕著であり、また、卒業式を以って完成に至るのである。その趨勢へ従う機縁は、やはり極めて事務的で末梢的な彼女の生動である事は自明であった。
卒業式当日、私の胸元に花飾りを付けてくれたのは何かの定めであるように彼女であった。思えば輓近の早天は凛冽である事が多かったのにその日は微睡みのような温暖が感じられていたので、朝から祥瑞を自覚しておくべきであったのだろう。
私は彼女が花飾りをさやる寸時の生動を奇しくも――必然と熟視で応じた。繊弱な腕の繊美な掌に抱擁された花飾りは得てして美貌を宿し、その妖花が却って可憐な彼女を春画のようにさえした。花飾りを学生服へ取り付ける手際は焦らすような愛撫を宛らであったし、挙止に備わる馥郁な感じ、無意識に零す呼気の婀娜な感じ、添えられた門出を祝う言葉の舌たるい感じ、それから恋煩いのような愁眉は酷く蠱惑的で、私を密やかに苛烈さを以て犯した。
私の胸に一つの春機が付けられてから一時間と閲せずに始まった卒業式を半ば晴れがましい思いで出席していたのは、無論、彼女の艶冶に犯された事実を思っていたからの事である。体育館に滲む歔欷に性的な妄想を謳歌している人間の快楽が交っているとは誰が想像しえただろうか。それは夾雑物以外の鹿爪らしさに如実であった。
ところで私は、卒業式に涙は疎か歔欷すら知らなかった。この告白をここまでの問わず語りと参酌すれば彼女への離別に悲観的にならなかった私へ疑念を抱く事に繋がるはずである。これが倒錯的な記憶、附会された懐旧でなければ私は卒業によって彼女との間に生じる疎隔を愁い人並かそれ以上に暗澹を認めていたはずなので、そこには何ら矛盾や撞着の類は存在しないはずであり、この問わず語りは成立していた。
ともあれ、私が歔欷さえ見せなかったという点に於いては、つまるところ私が青春を謳歌できなかった証跡であり、また私と言う奇矯の裏付けに過ぎなかった。もっともこの事実は近頃の私が俯瞰し導き出した形容である為に、当座の私は送辞の退屈を胸元の様子ぶる女性を宛らの花飾りをさやり俟つ事でやり過ごしていた。
やがて歔欷にいつか滂沱の涙が混じるようになっていた同級生を慨む頃に冗長な式が終わると、卒業生退場の命が耳朶を打った。成長という必然に一つの区切りを告げるある種酷薄な宣言は、これまで式特有の隊伍的であった動作を緩慢にし、ある人は解放感に安堵し、ある人は残り多さに悶えるような、また一入溢れる涙を拭うような調子で起立し退席した。私はというと素知らぬ顔で立ち上がり、散見するいかにもな卒業式らしい伏し目を否定するような精悍さで在校生の林立に彼女を探すという奇矯で振舞っていたのである。
彼女の妙麗は一種赫奕であったので目路に認める事は容易であった。体育館後方の保護者席に程近い一年生の座席の中腹に黙座していた彼女は、決して晴れやかな表情では無かったが隣に座している生徒のように眼を腫らすことも無かった。それが私には勿怪の幸いでもあって、思わず私はあたかも門出に胸躍らせる好青年の如き微笑を浮かべていた事だろう。というのも私が今し自らに認めた卒業式に対する姿勢の差異、感情の齟齬、とかく涙という俗な要素の欠落を俗でない存在と共有した気がしたからである。相似とも思えた今しがたの差異と共有は、私に倒錯的な所業で報いた。勿論、彼女が私の卒業を悲しんで涙していたとしても私は幸福であった。
*
それは中学生活最後の教室で卒業証書に付随して渡された小さな花束に存していた。私がそれに気付いた――それを想ったのは担任からの卑小にも前向きな言葉の只中であった。というのも、私の想像力は机上に臥する花束に隠顕する紙切れを仮構したからである。それはノートの端切れのようであって、また別誂えの用紙のようでもあって、至純たる恋慕でもあった。
『好きです』
柔らかな筆圧で書かれていたそれは、私の肉体を玉響にして肉感で犯した。この時ばかりはあれ程知らなかった涙を流していても不思議ではなかった。
その日もまた、私は苛立ちと見紛う程の威力で恋煩いの執拗さを宛らに射精した。その次の日も、そのまた次の日も、半日と閲しなくても、私は快楽の傍にいた。その度に脳裏の性交渉の可能な物質は彼女の成分を濃厚にしていった。
私が久しく彼女を目撃したのはそれからややあってからの事で、やはりスクールバスを待っている彼女であった。その見慣れた展開に差異があるとすれば私の感情程度のもので、以前の欣喜に困惑が交っていた事である。その困惑の出所は久し振りに認めた彼女の生動が脳裏の婀娜と参酌して著しかったという違いだった。もっとも私の脳裏の存在も彼女らしさを増すにつれて動くようになったけれども、往時の段階では未だ現実世界で頻繁に眼にするような生気の感じる運動を考えていなかった。そんな中で実物の彼女は友人と会話を楽しんでいたし、たまに私と視線が交われば面映ゆげに逸する事だってした。それらの決してトルソーが行うことのできない生動は、得てして私に変化の下萌えを涵養し、また、故知らぬ安堵に導いたのである。本当に故知らぬそれであったから、私は安堵が報いた理由を考える事はしないでいた。
私の視線は彼女を逃さなかった。とはいえクラスメイト程の距離感で彼女を見詰めるのは怯懦が故に不可能であったので、他人程の径庭で岡惚れていたに過ぎなかった。
私のある種睥睨が不断であったのは、いつか彼女の生動に執着していたからなのだろう。眼を逸らさなければ逸らさぬだけ生動は甚だしく、例えば愁眉を開くような柔和さで友人との談笑に応じる手弱女の挙止、例えば奢侈である程の軽薄才子が口元に宿る言辞、笑みに歪む口元を繊弱な手で隠す様は人間らしい一入の生動を感じずにはいられなかった。それでも私はバスが到着し搭乗するまで彼女を見詰めた。見詰めれば見詰めるだけ私には譬へ無い何か変化のような角度によっては喪心のような、また喜悦にも似た感情に苛まれた。私の中の確かな瓦解が、またそれ自体を否もうと彼女を見詰めていたに違いなかった。
……今しの語りのような偶にの刺激は、畳なわる毎に生動への執着を確かに昇らせた。これらの云わば生動に繋縛された状態というものは卒業まで顕著であり、また、卒業式を以って完成に至るのである。その趨勢へ従う機縁は、やはり極めて事務的で末梢的な彼女の生動である事は自明であった。
卒業式当日、私の胸元に花飾りを付けてくれたのは何かの定めであるように彼女であった。思えば輓近の早天は凛冽である事が多かったのにその日は微睡みのような温暖が感じられていたので、朝から祥瑞を自覚しておくべきであったのだろう。
私は彼女が花飾りをさやる寸時の生動を奇しくも――必然と熟視で応じた。繊弱な腕の繊美な掌に抱擁された花飾りは得てして美貌を宿し、その妖花が却って可憐な彼女を春画のようにさえした。花飾りを学生服へ取り付ける手際は焦らすような愛撫を宛らであったし、挙止に備わる馥郁な感じ、無意識に零す呼気の婀娜な感じ、添えられた門出を祝う言葉の舌たるい感じ、それから恋煩いのような愁眉は酷く蠱惑的で、私を密やかに苛烈さを以て犯した。
私の胸に一つの春機が付けられてから一時間と閲せずに始まった卒業式を半ば晴れがましい思いで出席していたのは、無論、彼女の艶冶に犯された事実を思っていたからの事である。体育館に滲む歔欷に性的な妄想を謳歌している人間の快楽が交っているとは誰が想像しえただろうか。それは夾雑物以外の鹿爪らしさに如実であった。
ところで私は、卒業式に涙は疎か歔欷すら知らなかった。この告白をここまでの問わず語りと参酌すれば彼女への離別に悲観的にならなかった私へ疑念を抱く事に繋がるはずである。これが倒錯的な記憶、附会された懐旧でなければ私は卒業によって彼女との間に生じる疎隔を愁い人並かそれ以上に暗澹を認めていたはずなので、そこには何ら矛盾や撞着の類は存在しないはずであり、この問わず語りは成立していた。
ともあれ、私が歔欷さえ見せなかったという点に於いては、つまるところ私が青春を謳歌できなかった証跡であり、また私と言う奇矯の裏付けに過ぎなかった。もっともこの事実は近頃の私が俯瞰し導き出した形容である為に、当座の私は送辞の退屈を胸元の様子ぶる女性を宛らの花飾りをさやり俟つ事でやり過ごしていた。
やがて歔欷にいつか滂沱の涙が混じるようになっていた同級生を慨む頃に冗長な式が終わると、卒業生退場の命が耳朶を打った。成長という必然に一つの区切りを告げるある種酷薄な宣言は、これまで式特有の隊伍的であった動作を緩慢にし、ある人は解放感に安堵し、ある人は残り多さに悶えるような、また一入溢れる涙を拭うような調子で起立し退席した。私はというと素知らぬ顔で立ち上がり、散見するいかにもな卒業式らしい伏し目を否定するような精悍さで在校生の林立に彼女を探すという奇矯で振舞っていたのである。
彼女の妙麗は一種赫奕であったので目路に認める事は容易であった。体育館後方の保護者席に程近い一年生の座席の中腹に黙座していた彼女は、決して晴れやかな表情では無かったが隣に座している生徒のように眼を腫らすことも無かった。それが私には勿怪の幸いでもあって、思わず私はあたかも門出に胸躍らせる好青年の如き微笑を浮かべていた事だろう。というのも私が今し自らに認めた卒業式に対する姿勢の差異、感情の齟齬、とかく涙という俗な要素の欠落を俗でない存在と共有した気がしたからである。相似とも思えた今しがたの差異と共有は、私に倒錯的な所業で報いた。勿論、彼女が私の卒業を悲しんで涙していたとしても私は幸福であった。
*
それは中学生活最後の教室で卒業証書に付随して渡された小さな花束に存していた。私がそれに気付いた――それを想ったのは担任からの卑小にも前向きな言葉の只中であった。というのも、私の想像力は机上に臥する花束に隠顕する紙切れを仮構したからである。それはノートの端切れのようであって、また別誂えの用紙のようでもあって、至純たる恋慕でもあった。
『好きです』
柔らかな筆圧で書かれていたそれは、私の肉体を玉響にして肉感で犯した。この時ばかりはあれ程知らなかった涙を流していても不思議ではなかった。