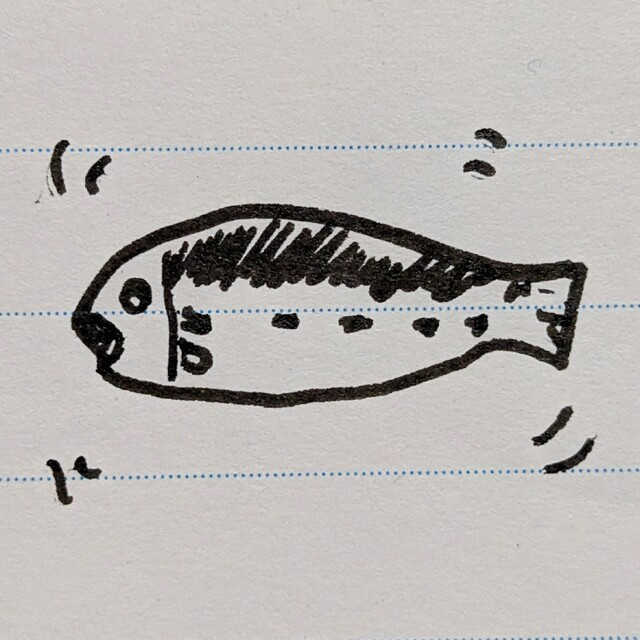1-1
文字数 3,070文字
夜寒は明媚であった。繋縛するような夜気の凛冽は居住まいを正させるように感化を示し、呼吸によって鼻腔を叩けば収斂された寒がやがて眼に沁みてくる。夜寒というあまりに静かで強かな趣と言うものは云わば手弱女の起居のように哀艶であって、また典雅でもあった。それを私は暖房で穢した。絶対的とも言えよう美を汚穢に染めたのである。すると鼻腔は手弱女を忘れ、繋縛も解かれ、機械的な温もりに傾倒するのが常であった。
常であるのは傾倒に留まらない。美を汚穢に染めた一種の涜神、一種の悔恨、それらに誘引される蠱惑的な美の影像、私の劣等の照応であるはずの確かな偶像、遍満するあまりに幸福な悲劇。それら過去の生に耽溺する云わば走馬燈のような羈絆の顕現も常無きであるのだ。というのも、いずれも私の気位の低さ――すなわち自己不全感とでも言えよう嫌悪が為すべき所業であった。
私が劣性という言葉を知ったのは中学の理科の授業でメンデルの法則という文字列に、次いで優性や劣性という言葉に蛍光ペンで線を引いた砌であった。あるいはそれ以前に何らかの拍子で耳朶を打っていたのかもしれないけれども、とかくまれ強か意識するようになったのは蛍光ペンで彩った事実があまりにけざやかに脳裏に残っているからであった。
私はなまじ漢字は得意であったから、劣性という文字の組み合わせが修飾する対象には何らかの欠如を認めることは手も無かった。すると、私は以前から自らの人間的な欠落や不備の類をけどり懊悩さえする明暮であったので、その言うに言われぬ苦しみを、原因不明の不調を患っている人が適当な病名を告げられた事によって安堵する要領で劣性というその言葉を自身に重ね自らを慰める事ができた。とはいえ実のところ名状しがたい辛苦に名が付いた事による一種の錯覚の安堵に過ぎず、また一時の有頂天に過ぎないことは当然であって、幾何も閲せずに私は人間として劣っているのだと知悉し、それからというもの劣等感との形容が相応しい抱懐が、私という倒錯者を、さも私が彩ったメンデルの法則のようにけざやかにするのであった。すなわち、云わば劣性遺伝子の叫喚である劣等感を、伴った自己嫌悪を、嫌悪への瞞着である倒錯の亢進を塞き止めるのは不可能であったように思われる。故に、その言葉との出会いは、私に厭わしい半生の序章を認めさせたと言えるはずであった。
私の宿痾でもある劣等感は、詳らかに列挙すれば私は私という人間を怪訝し頓に私が存在する意義や私が含有する価値などの至極人間味を感じずにはいられない項目に対して強か懊悩を重ねてしまうのでそれは叶わないが、それでも性癖と醜形、奇癖の都合三つは看過できないものがあった。しかるに具に話すことは含羞の至りであり後ろ暗くもありどうにも躊躇われるので、私は懊悩と陋劣な一人の大人を婉曲に語るのである。私が自らの劣等感を熟知し、私の空恐ろしい一面を誰よりも身近で理解しながらも誰よりも頗る恐れている感情の助力が語りへ嗾けるのであった。
性癖は最大の艱難辛苦であって、披瀝も憚られるような云わば恥部であった。殊に中学生になってからは界隈に多感な生徒の世俗的な話題が棚引くので自らの奇矯を憂愁せずにはいられなかった。……端的に言うならば、私が勃起不全を患っていたからのことであった。
厳密には勃起不全を患っていると信じていたに過ぎなかった。それも生来の男性的な不能、産まれながらに去勢を余儀なくされた端倪すべからざる人間の器さえを信じていたのである。なぜと言え、私は一般の男子生徒が性に目覚め性的興奮を、伴って性的快楽を求める対象――例えば端麗な人気女優であったりクラス内の些か発育の顕著な女生徒であったり、おしゃまな男子生徒が両親に内緒で購入した性的な動画であったり、私はそのいずれに於いても可能を示すことがなかったからであった。勿論、今しのいずれかの異性を対象にした性的な妄想も及ばなかった。かと言って男色の趣味も持っておらず、私の男性を見詰める視線と言うものは友人に向けるような穏当なものでしかなかったろう。つまり私は一般的な性別を全うしながらも、一般に性衝動を募らせる対象に対して亢進させる情には差異があり、かてて加えて感興は募らず、むしろ有するは含羞であり、それも私の不能への含羞、一般的でない私への含羞であって、佯狂で説明ができない現実に煩悶としながらそれでも破廉恥に起居を全うするしかなかった自分への含羞であった。すると私は私の生来の倒錯に何らかの意味があることを信じるようになり、それは産まれながらの異質を秀抜として受け入れるまでになって、やがて曲解を自恃として生動を始めるのである。そうでもしなければ私は生に耐えることは難しかった。
とはいえ私は一度も自慰行為に及んだことが無いわけではない。むしろ自涜は事務的な肉欲に駆られて模範的に、それも頻繁に行われた。私は当座に於いては可能を認める対象を知らないが故に可能である私を求めて自涜をこなしていたのであろうし、また、可能という理想と不能という現実の懸隔を埋める思いで自涜をこなしていたはずである。故に本格的な自涜――可能を伴った自涜を目路に認めることは往時には縁がなく、それを知るのはややあってからであった。
次に醜形が及ぼす嫌悪を語れば、といっても性癖と参酌すれば末梢的であるかもしれないが、面差しと身長、伴った風采へ向けられた感情であって、それだけであれば実に多感な思春期の男の懊悩に過ぎなかった。しかるに私のそれは世俗とは言えない類の、云わば自己否定に踏み入ろうとしていたのだが、人間という生き物は年嵩に近づくにつれて身嗜みを弁疏に鏡と相対する機会が多くなるので、この自己不全はある点に於いては至当なのかもしれなかった。それでも私が余人以上に自らの醜形を憂いているのは、鏡に反射する男の決して颯爽でもなければ小綺麗でもなく、精悍も感じられなければ極めて砂を噛むような天然の渋面に一種辟易としていたからであった。また、界隈で顕著であった二度目の成長期を迎える男児の散見が、私の面貌と身体に不調和を示すようになったからでもあった。というのも壮丁風の身躯を得た彼等は圭角の表情でさえも大人らしく魅せるのに対して、私は渋面を極めてロマネスクな登場人物程の滑稽さでしか扱うことができないでいたからである。
すると私には、彼等からややあって成長を迎えるのだろうとの弁疏を抱懐し生活するのが救いだった。それでいながら自分の肉体が故に身躯は不変であるという確信染みた反駁が私を縛してもいた。……やがて繋縛は第二次成長期が非望に終わった骨格の未発達と伴った筋量の未熟さが代え難い現実として残ると、未発達な未熟が故に、男性的な肉体を得た彼等がそうするであろう世俗的で乙な身嗜みを同様に扱うことがどうにも憚れるようになったのである。それどころか拒絶せねばならないとさえ思うようになった。私という男性的な欠落がもたらす彫塑的な厭わしさは得てして劣等感という径庭を育み、今となってはある種の諦念へと至らせたのだった。
最後に奇癖について触れると、壮丁を迎えぬ確信をしている点であった。それによれば私は久遠に学生を生きる気がしていて、決して成長しない事を信じているような、一つの不変を想っていた。言うなれば私が半生で虜になる面向不背への決して似る事のない相似性の先駆けであった。
久遠の学生を確信するそれは、一つの言い訳にも似ていた。それも小学生が先生に
常であるのは傾倒に留まらない。美を汚穢に染めた一種の涜神、一種の悔恨、それらに誘引される蠱惑的な美の影像、私の劣等の照応であるはずの確かな偶像、遍満するあまりに幸福な悲劇。それら過去の生に耽溺する云わば走馬燈のような羈絆の顕現も常無きであるのだ。というのも、いずれも私の気位の低さ――すなわち自己不全感とでも言えよう嫌悪が為すべき所業であった。
私が劣性という言葉を知ったのは中学の理科の授業でメンデルの法則という文字列に、次いで優性や劣性という言葉に蛍光ペンで線を引いた砌であった。あるいはそれ以前に何らかの拍子で耳朶を打っていたのかもしれないけれども、とかくまれ強か意識するようになったのは蛍光ペンで彩った事実があまりにけざやかに脳裏に残っているからであった。
私はなまじ漢字は得意であったから、劣性という文字の組み合わせが修飾する対象には何らかの欠如を認めることは手も無かった。すると、私は以前から自らの人間的な欠落や不備の類をけどり懊悩さえする明暮であったので、その言うに言われぬ苦しみを、原因不明の不調を患っている人が適当な病名を告げられた事によって安堵する要領で劣性というその言葉を自身に重ね自らを慰める事ができた。とはいえ実のところ名状しがたい辛苦に名が付いた事による一種の錯覚の安堵に過ぎず、また一時の有頂天に過ぎないことは当然であって、幾何も閲せずに私は人間として劣っているのだと知悉し、それからというもの劣等感との形容が相応しい抱懐が、私という倒錯者を、さも私が彩ったメンデルの法則のようにけざやかにするのであった。すなわち、云わば劣性遺伝子の叫喚である劣等感を、伴った自己嫌悪を、嫌悪への瞞着である倒錯の亢進を塞き止めるのは不可能であったように思われる。故に、その言葉との出会いは、私に厭わしい半生の序章を認めさせたと言えるはずであった。
私の宿痾でもある劣等感は、詳らかに列挙すれば私は私という人間を怪訝し頓に私が存在する意義や私が含有する価値などの至極人間味を感じずにはいられない項目に対して強か懊悩を重ねてしまうのでそれは叶わないが、それでも性癖と醜形、奇癖の都合三つは看過できないものがあった。しかるに具に話すことは含羞の至りであり後ろ暗くもありどうにも躊躇われるので、私は懊悩と陋劣な一人の大人を婉曲に語るのである。私が自らの劣等感を熟知し、私の空恐ろしい一面を誰よりも身近で理解しながらも誰よりも頗る恐れている感情の助力が語りへ嗾けるのであった。
性癖は最大の艱難辛苦であって、披瀝も憚られるような云わば恥部であった。殊に中学生になってからは界隈に多感な生徒の世俗的な話題が棚引くので自らの奇矯を憂愁せずにはいられなかった。……端的に言うならば、私が勃起不全を患っていたからのことであった。
厳密には勃起不全を患っていると信じていたに過ぎなかった。それも生来の男性的な不能、産まれながらに去勢を余儀なくされた端倪すべからざる人間の器さえを信じていたのである。なぜと言え、私は一般の男子生徒が性に目覚め性的興奮を、伴って性的快楽を求める対象――例えば端麗な人気女優であったりクラス内の些か発育の顕著な女生徒であったり、おしゃまな男子生徒が両親に内緒で購入した性的な動画であったり、私はそのいずれに於いても可能を示すことがなかったからであった。勿論、今しのいずれかの異性を対象にした性的な妄想も及ばなかった。かと言って男色の趣味も持っておらず、私の男性を見詰める視線と言うものは友人に向けるような穏当なものでしかなかったろう。つまり私は一般的な性別を全うしながらも、一般に性衝動を募らせる対象に対して亢進させる情には差異があり、かてて加えて感興は募らず、むしろ有するは含羞であり、それも私の不能への含羞、一般的でない私への含羞であって、佯狂で説明ができない現実に煩悶としながらそれでも破廉恥に起居を全うするしかなかった自分への含羞であった。すると私は私の生来の倒錯に何らかの意味があることを信じるようになり、それは産まれながらの異質を秀抜として受け入れるまでになって、やがて曲解を自恃として生動を始めるのである。そうでもしなければ私は生に耐えることは難しかった。
とはいえ私は一度も自慰行為に及んだことが無いわけではない。むしろ自涜は事務的な肉欲に駆られて模範的に、それも頻繁に行われた。私は当座に於いては可能を認める対象を知らないが故に可能である私を求めて自涜をこなしていたのであろうし、また、可能という理想と不能という現実の懸隔を埋める思いで自涜をこなしていたはずである。故に本格的な自涜――可能を伴った自涜を目路に認めることは往時には縁がなく、それを知るのはややあってからであった。
次に醜形が及ぼす嫌悪を語れば、といっても性癖と参酌すれば末梢的であるかもしれないが、面差しと身長、伴った風采へ向けられた感情であって、それだけであれば実に多感な思春期の男の懊悩に過ぎなかった。しかるに私のそれは世俗とは言えない類の、云わば自己否定に踏み入ろうとしていたのだが、人間という生き物は年嵩に近づくにつれて身嗜みを弁疏に鏡と相対する機会が多くなるので、この自己不全はある点に於いては至当なのかもしれなかった。それでも私が余人以上に自らの醜形を憂いているのは、鏡に反射する男の決して颯爽でもなければ小綺麗でもなく、精悍も感じられなければ極めて砂を噛むような天然の渋面に一種辟易としていたからであった。また、界隈で顕著であった二度目の成長期を迎える男児の散見が、私の面貌と身体に不調和を示すようになったからでもあった。というのも壮丁風の身躯を得た彼等は圭角の表情でさえも大人らしく魅せるのに対して、私は渋面を極めてロマネスクな登場人物程の滑稽さでしか扱うことができないでいたからである。
すると私には、彼等からややあって成長を迎えるのだろうとの弁疏を抱懐し生活するのが救いだった。それでいながら自分の肉体が故に身躯は不変であるという確信染みた反駁が私を縛してもいた。……やがて繋縛は第二次成長期が非望に終わった骨格の未発達と伴った筋量の未熟さが代え難い現実として残ると、未発達な未熟が故に、男性的な肉体を得た彼等がそうするであろう世俗的で乙な身嗜みを同様に扱うことがどうにも憚れるようになったのである。それどころか拒絶せねばならないとさえ思うようになった。私という男性的な欠落がもたらす彫塑的な厭わしさは得てして劣等感という径庭を育み、今となってはある種の諦念へと至らせたのだった。
最後に奇癖について触れると、壮丁を迎えぬ確信をしている点であった。それによれば私は久遠に学生を生きる気がしていて、決して成長しない事を信じているような、一つの不変を想っていた。言うなれば私が半生で虜になる面向不背への決して似る事のない相似性の先駆けであった。
久遠の学生を確信するそれは、一つの言い訳にも似ていた。それも小学生が先生に