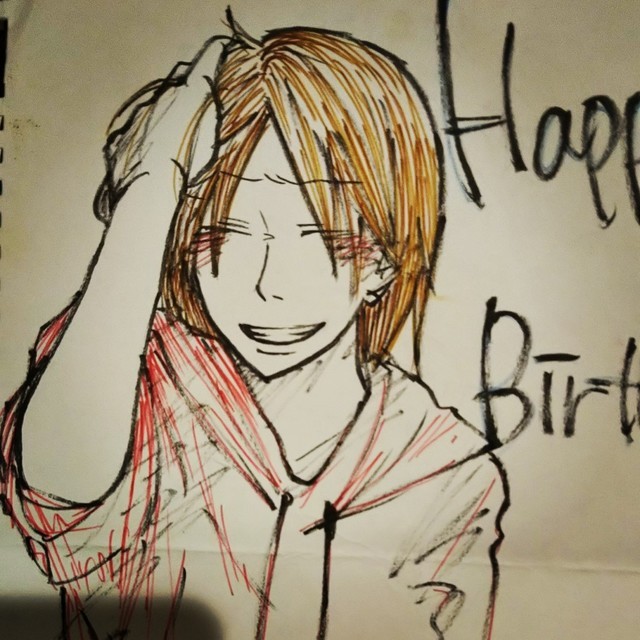第6話
文字数 2,302文字
【二〇一六年元旦】
あと九ヶ月。
お腹が苦しい。母親に恨みをぶつけられるかのごとく、ギュッ、ギュッと締め上げられる度に、こんな不自由なものを生み出した人間を呪った。
足袋から始まって肌襦袢、腰にタオルを添えて長襦袢。後ろ襟を調整したら伊達締め。そうしてようやく着物を羽織る。
一体何度締め上げたら気が済むのだろう。丸太の如く体型を調整されている以上逃げ場はなく、純粋に加えられた力が弛んだ生活をしていたお腹を叱咤した。
着付けをしている間中、母は呪文のように「ここで身体の凹凸をなくす」「ここに合わせる」「ここはしっかり締めておく」と口にした。そうやって教わってきたのかもしれない。そうやって普段使わない工程を思い出しているのかもしれない。いずれにせよあたしには関係のないことだった。
入念に飾り付けられて親族と相対する。年に一度しか顔を合わせることのない面々は、会う度「キレイになったわねぇ」「大人びたわねぇ」と自分が欲しがっていた言葉をくれた。勿論今年も母からは一度ももらわなかった。
正月は赤妻の本家に集うのが、生まれた時、いや、それ以前からの習わしだった。幼い頃は、時間が経てば自然大人達の集まる所と子供達の遊ぶ所に分かれ、庭の岩を飛び移って遊んだ。一度だけ松の木で指先を切ったことがあり、それ以来その周辺だけは近づいてはいけないことになったが、それでも十二分の広さがあり、砂利を掴んで投げては遊んだ。
二十歳に近づく今ではそんなこともなくなったが、だからといって大人の集まりに顔を出してもつまらない。加えて赤ら顔の面々は何を言い出すか分からず、一昨年冗談でも「ウチの息子の嫁に来るか」と言われた時は吐き気がした。白くたるんだ肌。あんな失敗した福笑いみたいな男に嫁ぐとか、全然笑えなかった。
そうして賑やかな場に日頃ほとんど会うことのない父親の姿を見つけても、一親族としてカウントしていた。いつだって探していたのは母だった。
母はいつもこの宴の場にいない。交代とかじゃなくて、いつもいないのだ。
冷たい廊下を進む。北にあたる台所は殊更冷えた。
母は一人、そこで次に出す料理の準備をしていた。
「どうして教えてくれなかったの?」
そう問い正す相手が紅葉ではない事は分かっていた。それでも紅葉は「ごめん」と言うと「お姉が傷つくと思って」と言った。「お母さんが望まないと思って」とも言った。
〈本当に見なきゃいけないのはお母さんじゃない〉
見えているはずなのに見てない。視野が狭い。
否。
見たくないものを見ないようにしていた。傷つかないように。
どうしてだろうと思っていた。
どうしてみんな楽しそうに飲んでいるのに、母だけがあんな寒い中で一人せっせと皆をもてなしているんだろう、と。正月の、皆が皆めでたいと笑い合う中で、どうしてその輪に入れないんだろう、と。
母は。
「……貧しい出だからって。赤妻は古くから由緒ある家柄だったんだけど、家業で失敗してから、良家と縁を結ぶことで何とか体裁を保ってた」
街道沿いに出した店の経営が座礁に乗り上げたという。出店後間も無く、一本南に県をまたぐ大通りが開通したことが一番の誤算だった。取り扱う商品が古くから愛でられてきた反物であり、気軽に立ち入れる相場でやり取りをしていない以上、新天地、まずは分母がなければ話にならない。それらは一種のブランドであり、赤妻家にとっての宝だった。
「だから閑古鳥に形骸化して赤妻のプライドだけが残った。金銭面で元々何の利益ももたらさず、おんぶにだっこだった母は、今もこうして対価を支払ってる」
労働力で。
冷たい水に手を晒しながら。
「お姉、だからお母さんは敵じゃない。お母さんだけが護ってくれてる」
叔父は笑った。あの時。
「ウチの息子の嫁に来るか」と。
あの時。
「来なさい」と母があたしを台所に呼んだ。だから母がずっとこの寒い中で、ずっとここにいたことを知った。
一番を取りなさい、と言った。
一番になりなさい、と言った。
それは。
バッグを取りに畳に上がると、振り返った時腕を掴まれた。
酒臭い息。酔った叔父が破顔する。
「エラい別嬪さんになったなぁ。ワシがもらってやろうか?」
どっと笑いが起きる。年に一度しか顔を合わせない面々。暗に許される、それは無責任な肯定。
身がすくむ。全身の鳥肌が立った。恐怖に声が出ない。
助けて、と思ったその時だった。鋭い声が飛んできた。
「触らないでいただけますか」
母はずかずかやってくると、その大きな手をピシャリと叩いた。
驚いた叔父は目を丸くしたまま見上げている。
眼前に立ち塞がる、その小さな背中。
「この子は学業でも課外活動でも常に一番を取ってきた子です。臆することなく怠惰を貪る放蕩息子や、大した才も見せず、女性にすがって生きているような老いぼれに、どうしてこの子がやれましょうか」
そうしてカズハ、と言った。あたしはハイ、と返事をした。
「あなたは自由に生きなさい」
そう言うと、母は広間の隅々まで届く大きな声を上げた。
いつもうるさいと思っていた、近所迷惑な大きな声。
「私は何を言われても、どう扱われようと結構です。でもこの子には、この子達には、自らの手で生み出し、利を得ることのできる力があります。ゆめゆめ軽んじてくれませぬよう」
言い終えると、シンとした宴の場、その真ん中を突っ切って、母は台所に戻って行った。
震えている。全身が。
紅葉、と言った。
紅葉、と。
電子家電より優秀な妹は、かすれた声にもきちんと反応して駆け寄る。そうして叔父に向かって舌を出すと、そのままあたしの手を引いた。