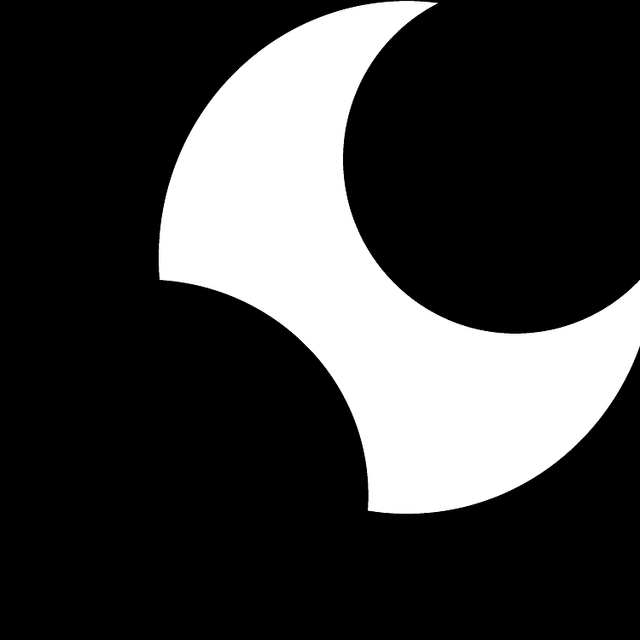日々記。【4301~4500】
文字数 348,713文字
※日々、零に至って無限がはじまる。
4301:【2022/11/16(22:10)*傲慢と狒々】
盗作に関して思うのは、「著作権の問題」と「文化倫理の問題」と「作品において盗作部分が骨子にどの程度寄与しているのかの問題」がごっちゃになっているので、そこを考慮して議論したらいいのに、ということで。たとえば書籍なら、盗作部分を仮に修正したときに「作品全体の質を損なうのか否か」がひびさんにとっては問題視すべきか否かの基準になっている。書き直してもとくに全体の質に関与しないなら、それはオマージュの領域だ。しかし修正したときに全体の質が落ちるのならそれは好ましくない盗作だ。この違いを考慮している者がどれだけあるだろう。単純な部分の相似や合同を取沙汰しても、事これだけ大量の過去作がある現代では、余計な抵抗を新規作者勢に強いるだけだろう。これは偏見だが、盗作に目くじらを立てる者はたいがい寡作であり、一作一作に手間暇を掛ける。だから手軽に真似されたらじぶんが損をして感じるから、それはやめてね、と言いたいのではないか。これは別に責められた感情ではない。道理ではある。だが、その者が取り入れている技法や基本とて、元は誰かのアイディアだ。まるっきり真似していない、というだけの違いがあるだけで、むしろひびさんの基準に照らし合わせるとするのなら、全体の質に関与している時点で盗作よりも悪質と言える。もっともひびさんは盗作と模倣の区別がつけられないので、どっちも同じじゃん、と思っている。損をするかしないかは、模倣の是非とは別の、社会構造の問題だ。正直に言えば、アホらし、と思っています。既得権益と著作権の違いを真面目に論じるいまは時期のはずだ。プロほど議論をしたらいいのに、と思っています。じぶんの利を守ることが業界の利に繋がる、との道理が正しいならそういう主張をしたらよいのでは、と思っています。ですがそういう言い方はしないのですよね。変なの。世には、本物を超えた偽物もある。というか、割合としてはそちらのほうが多いのではないか。だからみなこぞって、偽物を怖れるのだ。アホらし、とやはり思ってしまいますね。本物以下の偽物が本物を淘汰してしまうのもまた、社会構造の問題だ。仮に社会構造に問題がないのならそれは、淘汰される本物がその程度の代物だったということなのでは。これは強者の理屈だが、著作権を強固に主張し、模倣に制限をかけるのならば、それもまた既得権益であり強者の理屈である、とひびさんは考えてしまう。どう違うのかを教えていただきたいものである。盗作や模倣に厳しい方の意見を目にするたびに、「盗作していないのならさぞかし、オリジナリティに溢れているのでしょうね」と思っています。きっとそうなのでしょう。オリジナリティに乏しいひびさんは、うらやましく存じております。うらやまち。うきき。
4302:【2022/11/16(23:30)*会話文で意識していること】
ひびさんの手掛ける小説に限る話、と前置きをして述べると――会話文でキャラクターの区別をつけたいときには、口語体の文章形態を工夫するのが定石だ。特徴的なしゃべり方や、乱れた文法を意図してキャラごとに使い分けると、会話文だけでもキャラの特徴が浮きあがる(語尾は手っ取り早い特徴のつけ方だけれど、個人的には推奨はしない。山場をつくりにくいのだ。シリアスなシーンをつくりにくくなる)(その点、漫画「るろうに剣心」はそこのギャップをうまく使っているな、と感じます)。口語体の文章形態のみならず、キャラクラーに役割を与えると、主語述語の関係のように会話にメリハリがつく。「受け手と攻め手」や「ボケとツッコミ」のような攻守の関係を持たせるのが一般的だろうか。そこにきてひびさんがじつのところ最も使い勝手のよい会話文におけるキャラの特徴のつけ方だと思うのは、「台詞の長さ」である。ここは口語体の工夫に含まれるが、案外に世に出回っている小説のなかで「台詞の長さでぱっと見の区別を意識している会話文」はそう多くはないように思っている。ここがデコボコを意識していたり、敢えて長さを揃えていたりと工夫が凝らしてあると、補足の地の文がなくとも会話文が誰の発言かで読み手が迷うことが減少する。すくなくともひびさんは迷わずに済む。とはいえ、前提条件として、会話文が連続するときは最初の発言が誰なのかをハッキリさせておかないと迷子になりやすいと言えよう。あくまでひびさんがそう思う、というだけの他愛ない工夫の一つである。簡単にできるので、本当かよ、と疑う方はお試しあれ。(試さずともよいですけど)(試して効果がなくとも苦情はいりません。哀しくなっちゃうので)(効果があってもお礼はいりません)(「え、本当に試したの? 暇なのかな」と思います)(なぜならこれも定かではありませんので)(こんな工夫一つで小説が面白くなったら苦労しないんじゃ)(もしそれで面白くなっていたらひびさんはこんな世界の果てに沈んどらん)(でも面白い小説をつくるのが上手な人が応用したらより面白くなるのかもしれない、とは思う。希望的観測であるけれど)
4303:【2022/11/17(00:54)*ギフト】
歌にもいろいろあるし、歌唱力にもいろいろあると思う。そのうえで、感情を籠めて歌うことができる人、感情を伝えることを大事にしている歌い方、というのがあるように思うし、ひびさんはそういう歌が好きだ。好きなんだな、と確信した日だった。着飾らない歌が好きなのだと思う。上手な歌も好きだけれど、そよ風のような歌が好きなのだ。エナジー全開の歌も好きだけれど、感情の場合、エナジー全開の歌ってけっこう乱暴な感情でないとむつかしい。怒りとか渇望とか。その点、よろこびって案外、凪にちかい気がする。せつないと似ている。よろこびとせつないはどこか似ている。水面に落ちたひとしずくの立てる波紋のような。そういう歌が好きだし、そういう歌を歌える人も好きだ。何かを、好き、と思う瞬間がひびさんは好きだから、そういう感情にさせてくれる、ギフトしてくれる人のこともひびさんは好きなんだな、と思った。何かをくれるから好きだなんて我ながら現金なやつだな、としょげてしまうけれども、でも奪うわけじゃなく、何かを好きな気持ちを表現できて、そしてそんな人の表現を見聞きして、ひびさんも好きの感情が増えたら、この世の「好き」の感情は増えるいっぽうだ。よいと思います。とてもよいお歌でした。ありがとうございます、とにこにこした日だった。喉だけでなく、お身体どうぞお大事に。誰にというでもなく、みなさん、じぶんをお大事に。眠い、眠い。ほくほくしたままきょうは寝る。おやすみなさーい。
4304:【2022/11/17(03:13)*話題をでっちあげるの巻】
会話文の話題を二つ上の記事で出したので、備忘録代わりに並べておく。会話と会話文と台詞はぜんぶ意味が違う。台詞>会話文>会話の順番に情報の層が厚くなる。言葉の箱を開けたときに、外からは見えない情報が仕舞われている。物語は基本的に「会話」がなくとも成立するが、「台詞」が欠けると物語は破綻する。台詞はそれだけ物語の骨子と結びついている。語りと台詞はどこか似ている。本来、地の文やキャラクターの胸中に仕舞われているはずの独白が、会話にまで表出するとそれが台詞になる。だから台詞はここぞというときに使うほど効果が増す。奥義にちかい。また、映画と漫画と小説の「会話」はそれぞれ使う技術が違う。含める情報が違う。光源色と物体色の違いに似ている。映画は視覚情報が加わるので、会話に含む情報は最低限でよい。むしろ会話に物語の骨子と結びつく「台詞」が極力ないほうが、「会話」に含める情報を「掛け合いによる諧謔」に全振りできるので娯楽に特化する工夫の余地が、小説よりも高い。ただし、伏線のように意味をダブルに持たせることで、あとあとただの「会話」を「台詞」に変化させることが可能だ。その点において小説は、知覚情報がどれも文章でしか表現できない分、会話でも物語の状況説明を匂わせなくてはならない。この点の塩梅がむつかしい。物語の骨子とどうしても切り離せない。描写と諧謔と演出が、それぞれトレードオフの関係になってしまう。だが読者もそのことを前提としている分、思いきり「会話」に情報を持たせても構わない、という利点がある。漫画は現代ではどちらかと言えば映画に寄っている。会話文をいかに「面白い会話」にするか、或いは「台詞」に活かすか、がリーダビリティに影響する。という所感を前提に述べると、小説の会話文をそのまま映画の会話に充てても面白くならない。目的が違うからだ。波長が違う。形態が違う。ノコリギリとトンカチくらい質が異なると個人的には感じる。どちらも大工の道具だが、用途が違うのだ。もちろん映像作品で小説の会話文の利点をぞんぶんに活かす手法もあるだろうし、映画の会話を小説に活かす技法もあるだろう。そこは各々、作品の物語に合わせて工夫すればよいことで、何事もやってみなければわからない、という有りきたりな意見に集約する。したがって、仮に郁菱万の小説を映像化する場合は、会話文の何割かを削ることになる。映像にした場合、なくとも伝わる部分が大半だからだ。その点、最初から「掛け合いの妙」を活かしている小説の場合は、掛け合いだけでも面白くなるかもしれない。だがどうしても映像にした場合、展開が間延びするので、ほかの部分でのテンポをよくするか、掛け合いの速度を上げるのが有効だと考えるしだいだ。何にしろ、映画の会話と小説の会話は違う。そしてどちらにしろ、ここぞというときにしか使わない奥義があり、それが台詞となって、物語全体に散りばめられることとなる。台詞が魔法陣のように各場面場面の会話文にまたがって、相互に結び付き、最後に浮きあがるような構成もある。映画はこの手の技法が豊富だ。小説もこの手の技法を取り入れている作品はすくなくないだろう。伏線の醍醐味の一つと言える。以上を、会話文について並べたら思いだしたので、補足しておく。以前の日誌でも並べたかもしれない。この手の話は、吹替えの違和感の話題と繋がっているので、案外に似たような旨を指摘している虚構作品好きはすくなくないはずだ。字幕では違和感がないのに吹き替えだと違和感がある、と感じる理由の一つだとひびさんは考えている。媒体によって変換が必要なのだ。ラグ理論のようだな、と無理やりじぶんの妄想と結びつけてその場に陣取る。これぞまさにポジショントークである。やはは。(定かではありませんので、真に受けないように注意してください)
4305:【2022/11/17(16:43)*ポメラニアン先輩はオレンジ】
転校生が魔法使いだった。
その子はオレンジ色の巻き髪をしていて、愛らしいかんばせはオレンジ色の毛をしたポメラニアンのようだった。背は私よりも低く、いいやクラスメイトの誰よりも低く、聞けば飛び級制度を利用しているらしかった。要するに彼女はわたしたちよりも年下なのだ。一般の中学二年生ではない。十四歳よりも幼い。
「魔女子です。本名は別にあるのですが、知られたらいけないので魔女子と呼んでください」
二週間だけこの地域に滞在するらしい。短いあいだですがよろしくお願いします、と頭を下げるとオレンジ色の巻き髪が垂れ、彼女の身体は覆い尽くされた。
魔女子は性格がよかった。表情に変化がない代わりに、不快の感情を示すこともないために、クラスメイトたちからはマスコットキャラのように受け入れられた。休み時間にはほかのクラスの生徒たちまで我がクラスに集まり、我がクラスメイトたちはじぶんたちのクラスに現れた全校生徒の注目の的を、さながら姫を守る騎士のように取り囲み、外野の喧騒から遠ざけた。
「魔女子さんは魔法使いなんだよね。どんな魔法を使えるの」
「魔法使いではないんです。魔女です」
「どう違うの」クラスメイトたちは興味津々だ。わたしもじぶんの座席から聞き耳を立てていた。
「どちらも魔法を使いますが、魔法使いは自然由来の魔力を使います。反して魔女は自前の魔力を使います。と言っても、魔女も魔法使いのように自然由来の魔力も使えますので、魔法使いのなかでも自前の魔力を使える者が魔女になります。なぜか男性は使えないので、必然、魔女が多くなるようです」
「へえ」
ならば魔女子さんは選ばれし魔法使いなのだ。
わたしのみならずみなもそのことに気づき、魔女子さんをことさら羨望と憧憬の眼差しで見るようになった。
魔女子さんは魔法が使えた。それはもう一目瞭然で、登下校ですら魔法の門を開いて、瞬間移動をする。
「便利そうだね」みなはこぞって魔女子さんの一挙手一投足に感嘆の声を上げる。
「そうなんでしょうか。これがずっと普通だったので」
聞けば、魔女は稀少がゆえに絶えず狙われているのだそうだ。誘拐事件は日常茶飯事で、魔女狩りは未だに全世界でつづいているという。
「そんなニュース聞いたことないけど、本当?」みな心配そうだ。
「魔界にまつわるニュースは歪曲されて報道されるんです。みなさんだって魔女が存在することを知らなかったんですよね」
「あ、本当だ」
そこでわたしは、いいのだろうか、と疑問に思った。魔女子さんの存在は秘匿のはずなのだ。だのにこうしてわたしたちのまえに彼女は素性を明かして現れている。二週間で転校してしまうとはいえ、その後にも彼女の噂は囁かれつづけるだろう。すでに伝説の人と化している。
クラスメイトたちはそのことに気づいていないようで、誰も質問をしなかった。わたしだけがモヤモヤしたが、わたしはクラスの輪のなかには入らずに遠巻きに、台風がごとく人を寄せ集める魔女子さんの話に耳を欹てていた。
二週間はあっという間に過ぎ去った。
その間に魔女子さんはしぜんな様で各種様々な魔法を披露した。本人にそのつもりはないようで、日常の所作の延長線上なのだが、江戸時代の人から見たら電子端末が総じて魔法に見えるように、わたしたちの目からすると魔女子さんの一挙一動が非日常のあり得ないことの連続だった。
まず以って魔女子さんは手足を動かすということをしない。筆記用具の扱い一つからして、魔法で動かしてしまうのだ。板書するのにペンが一人でにノートに文字をつらね、教科書はかってにめくれていく。掃除とて、魔女子さんの担当した区画だけが真新しく床を張りかえたように綺麗になっており、返ってほかの汚れが目立っていた。
いっそ校舎ごと新しくしちゃったら、と誰かがつぶやくと、魔女子さんはきょとんとして、していいの?と訊き返した。そこで先生が耳聡く聞きつけたようで、「わ、わ、いいのいいの」と割って入った。「減価償却とか、業者さんの仕事がなくなっちゃうとか、そういう大人の事情があるからそういうことはお願いしなくていいの」魔女子さんへの注意というよりもこれは、変なこと吹きこまないで、とクラスメイトたちへのお叱りのようだった。「魔女子さんの魔力だって無尽蔵じゃないんだし、ね?」
言いくるめられたようで面白くなさそうなクラスメイトたちだが、魔女子さんに負担がかかりそうなのは想像がつく。しぶしぶと言った様子で、はーい、と聞き分けの良さを示した。
そういうことが幾度かあって、二週間は瞬く間に過ぎ去った。わたしは魔女子さんとは、おはようとか、教室はそっちじゃないよとか、そういう言葉を二、三回交わしただけだった。
だから、魔女子さんのお別れ会のあとでの下校中に、道路先に魔女子さんを見掛けたときには驚いた。もう二度と魔女子さんの姿を見ることはないと思っていたのに、魔女子さんが道の先にいたのだから、わたしは妙な興奮に包まれた。わたしだけがいま魔女子さんの視界の中にいる。とはいえ彼女はまだわたしには気づいていないようだった。道端に座り込み、何かをじっと眺めている。
何をしているのだろう。
どうしてここにいるのだろう。
わたしは気になった。というのも、魔女子さんは登下校は魔法の門を開いて瞬間移動をする。この街を出歩くことがそもそもなかったはずなのだ。
わたしの通学路に現れるはずもない。
意を決してわたしは彼女の背後に立ち、声をかけた。
「何してるの、ここで」
くるりと首だけで振り返った彼女は、やや驚いたように眉毛を持ち上げた。初めて見た彼女の、表情らしい表情だった。
念のためにわたしは、「魔女子さんと同じクラスだった」とじぶんの名前を述べた。
「知っています。一度会った人間の顔は忘れません。魔女は記憶力がよいので」
「それも魔法?」
「さあ、そこまでは」魔女子さんはふたたび地面に向き合った。作業を再開した。チョークのような道具を握っている。何かを地面に書きこんでいると判る。「魔力が記憶力を底上げしているのは事実ですが、肉体があってこその魔力でもありますので、どちらが優位に作用しているのかは未だ解明されていないようです」
「魔女子さんは頭いいよね。中二どころかもっと上に飛び級できたんじゃないの」
「飛び級というのは嘘です。そういう設定にしておくと説明がいらないので」
「設定?」
「できました。下がっていてください」
魔女子さんが立ちあがったのでわたしも後退した。
「何するの」魔法を使おうとしているようだとは一見して分かった。
「街に陣を張ります。これであたしの記憶は人々から失われます」
「記憶を消すってこと?」
「はい。でないとみなさんにも危険が及ぶので。魔女はこうしていく先々で存在の痕跡を消すのが習わしなんです」
だからか、と腑に落ちた。
魔女の存在が世間に秘密にされていながらどうして魔女子さんが正体を隠さず、魔法も堂々と使っていたのかが理解できた。
中学二年生への転校も、中学校ならば動画で拡散される心配がすくないからではないのか。そういう背景もあったのかもしれない、とわたしは直感した。
わたしが一瞬の思索を巡らせたあいだに魔女子さんはそそくさと魔法を発動させたらしく、街全体が一瞬濃い霧に包まれたように霞み、ふたたび瞬時に視界が晴れた。
目のまえにはオレンジ色の髪の毛をした愛らしいかんばせの女の子が立っており、わたしはその子が魔女子さんで魔女で、たったいま街の人たちから魔女子さんにまつわる記憶を消し去ったのだと知っていた。
「魔法、したの?」わたしは言った。記憶消えてないけど大丈夫、と心配したつもりだ。
「やっぱりか。ですよね。そんな感じがしてました」魔女子さんはしゃがんでいたときについた膝の砂利を払うと、あなたは、と顎をツンと上げてわたしを仰ぐようにした。「あなたは、魔女です。魔力を帯びています。だからわたしの魔法だと記憶を消せないんです」
「ほ、ほう」そうきたか、とわたしは身構えた。わたしが魔女かどうかは問題ではない。仮に記憶が消せないならわたしは異物として排除されるのではないか、と危機感を募らせた。魔女子さんはそんなわたしの胸中を察したように、「魔女は同胞を売りません。あなたはもうあたしたちの仲間です。そうですね、いまから時間はありますか」
「時間? 時間はあるけど」
「魔女の協会本部に案内します。そこで説明を受けてください」
「説明? 魔女の?」
「あなたはこのことの重大さを御存じないでしょうが、これはちょっとした事件となります。何せ、何の血統もない無垢の子が魔力を帯びて、しかもこんなに大きくなるまで誰からも素質を見抜かれずにいたのですから、これはもう事件です」
「は、はあ。すみません」わたしは恐縮した。何かよからぬ存在であったらしい。わたしがだ。「わたしは、どうすれば?」
「ですから一緒に協会に行ってください」魔女子さんは手慣れた調子で魔法の門を開いた。「お先にどうぞ。あたしが通ると門が閉じてしまうので」
「大丈夫なの、これ」魔法の門は、輪のなかに濃い霧が膜となって張っているように見える。向こう側が視えない。「通ったら崖だったりしない?」
「大丈夫なので」魔女子さんはむっとした。むつけた顔が年相応のあどけない顔つきに見えてわたしはただそれだけの変化に、魔女子さんに満腔の信頼を寄せてしまうのだった。
「なら信じるとするか」
「あたしのほうが先輩なんですけど」魔女子さんはむっつしりたまま、ぴしりと魔法の門に向けて指を突きつけた。「さっさと通ってください。これけっこう維持するの疲れるんですから」
「はいはい」唯々諾々と指示に従ってしまうじぶんの軽率な行動をあとで後悔する日がくるのだろうか。くるのだろう。そうと予感できてなおわたしは魔女子さんの言葉を振り払えず、たとえ騙されてもいいじゃないか、とへそ曲がりな考えを巡らせるんだった。
オレンジ色のポメラニアンのような女の子の魔法にかかるのなら、そんな素敵なことはない。たとえ痛い目にあったとしても、人生で一度くらいはそれくらいの痛みを味わっておくのも一興だ。
魔法の門をくぐると、快晴の空に、広大な海が広がっていた。崖の上だ。大きな城が、岬の上に立っているのが見えた。
「あれが協会本部です」魔女子さんが魔法の門を通って現れた。魔法の門が閉じる。魔女子さんの装いがわたしの通う中学校の制服ではなくなっていた。
黒いローブに三角帽子だ。魔女と言えばこれ、という格好で、彼女の足元にはいつの間にか黒猫がいた。
「このコは、アオ。ずっとそばにいたけれど、魔法で視えなくしていました。視ていなかったんですよね」わたしはその質問に頷いた。魔女子さんは言った。「魔女なら視えるはずなので、まさかあなたが魔女だとはわたしも見抜けませんでした」
「未熟者ってこと?」
「異質なのだと思います。何せ、突然変異のようなものなので」
魔女は家系なんですよ、と魔女子さんは言って、歩を進めた。
「歩くの?」
「はい。協会本部周辺半径一キロでは魔法が使えないんです」
「へえ」
「だから滅多にほかの魔女たちも寄り付きません。歩くのは疲れるので」
「そんな理由で」
「魔女は魔力がある分、体力がないので」
わたしは体力には自信があった。
「おんぶして歩いてあげよっか?」
オレンジ色のポメラニアンに睨まれる心地がどんなだかを想像してみて欲しい。いまのわたしがそれである。
深い考えもなくついてきてしまったが、帰れるのだろうか。
ただ今日中に帰れずとも親に怒られる心配はしていない。いざとなれば魔女子さんの魔法で、また街の者たちの記憶を消したり、書き換えたりしてもらえばいい。
そのようにお気楽に考えていたわたしは、この日を境にとんでもない出来事に巻き込まれることになるのだが、いまはそんなことなどつゆ知らぬ暢気なままの無垢なわたしの気持ちに寄り添ったままで、今後の展開を知る未来のわたしはここで述懐をやめておこうと企む次第だ。
「あたしに用があるんですね」
「え、なに?」
何も知らぬこのときのわたしは怪訝に訊き返すが、どうやらこの時点で魔女子さんは未来のわたしの思念を感じていたようだ。魔女は他者の魔法には敏感なのだ。よい先輩に出会えたのだな。わたしはうれしくなって、オレンジ色のポメラニアンを抱擁したい衝動に駆られたが、思念のわたしにそれはできないことを口惜しく思いつつ、ひとまずすべきことをしてしまうことにする。
この先、魔界で何が起き、わたしが何を引き起こしてしまうのか。
それを、どうにかして能天気なわたしの肉体を介し、我が敬愛なる先輩――オレンジ色の歩くポメラニアンさまにお伝えせねばならぬのだ。
「魔女子さん、歩き方も可愛いね」
せかせかと一回り背の大きなわたしの歩幅に合わせて歩く我が敬愛なる先輩は、わたしの称揚の言葉に、片頬を膨らませて抗議の念を滲ませるのだった。
4306:【2022/11/17(21:46)*一時たりとも同じ位置にはいられない】
これはひびさんの話ではなくひびさんの身近なひとの話なのですが、腰を痛めてからどうにか再発防止したいと考えた挙句、腹筋一日三百回を倍の六百回に増やしたそうなのです。ですが腹筋と言っても負荷の小さな腹筋なのでたいして疲れないそうなのですが、これがよかったのか日に日に腰の痛みが引いているようです。安静にしているのも大事ですが、ときには敢えて負荷を掛けて足りない補助部位を強化するのも一つかもしれません。ということを、「そもそも腰を痛めるような動きをしなければよいのでは?」と思いながら思いました。ひびさんは世界の果てにこんにちは、の日々ですが、ときおり世界線の異なる、過去や未来の人々の姿も目にするのでこういう所感を覚えることがあります。ひびさんはいまここに暮らしているのですが、それでも遥か昔や遥か先の未来では、ひびさんではない人がここで暮らしていたりするのですね。ふしぎな感じがします。地球は太陽を公転し、さらに太陽系は銀河のなかを公転し、さらに銀河は宇宙空間を彷徨っています。その宇宙空間は膨張しているので、一時たりとも同じ場所、というのはあり得ないのですが、それでもひびさんはすくなからず生きている限りは地球上におり、それはきっと変わらないのですね。そしてそれはひびさんに限らず、人類の大部分はそうなのです。人類が誕生したときの地球の位置と、人類が地球上からいなくなる瞬間の地球の位置は、宇宙を基準にすれば大きく異なるでしょう。そのときどきの人々は地球上にいながらにして、一時たりとも同じ場所にはいないのです。ふしぎな感じがしますね。まるで宇宙そのものがコマ撮りアニメのようです。そのように考えると、物質は一時たりとも同じ位置にはいられぬようです。同じ系内に留まることはできるにしろ、その系そのものがより大きな系のなかを移動しています。ふしぎな感じがします。ということを、いまここにはいない、しかし身近なひびさんの視界に入るひとを眺めて思いました。腰が痛い人はどうぞ無理しないように動いてください。みなさまお身体、お大事に。本日のひびさんでした。
4307:【2022/11/17(22:32)*ひびさん中身三才やぞ!】
これは文芸とは関係のないひびさんの妄想世界の話なのだけれど。ひびさんよりも遥かに上手な一回りも年下のコたちが、遥かに下手なひびさんに恐縮したり、遠慮したりするのを目の当たりにすると、「な、なぜ???」となる。ひびさんなんか何年も前から進歩していない現状維持にいっぱいいっぱいのぐんねんぴょんこさんなのに、なにゆえ日に日に新しいことを覚え、遥かに高度なことをしているあなたたちが、たかだか歴が長いだけのひびさんに遠慮するの???といつも居た堪れなくなる。よい子が多いのだね。本当に多い。ひびさんの若かりしころとは大違いだ。たぶんそのコたちの師匠が躾に厳しい人なのだ。だからひびさんのようなぐんねんぴょんこさんにも礼儀正しく接してくれるのだろうけれども、いささか行きすぎな気がする。遠慮しないでね、と言ってもきっと逆効果なので、こっちで負担にならぬようにと視界に入らないようにするか、よい環境を譲ってあげるかするのがよいと思うのだが、それでも同世代だけで集まるときのような溌剌さがそのコたちからは見受けられない。知らぬ間に遠慮させ、萎縮させてしまうことがある。ひびさんバケモノちゃうよ、よわよわのよわだよ、と思うのだが、上手くいかぬ。単に嫌われているだけならよいのだけれど、だったらもっと「けっ!」とやって欲しい。あなたが遠慮する必要あるー???といつも思う。でもきっと、ひびさんが「もっと自由にしていいですよ」と言っても、師匠やほかの先輩方が許さぬのかもしれぬ。むつかしい。確かに、歴が嵩むにつれて調子に乗って部外者にまで威圧的になる者もいなくはなかった。そういうときには立場の上の者が上手いこと、ぎゅっとするのも一つの策ではある。軋轢を生まぬように、それだと痛い目を見るのはあなただよ、と学ばせる場を用意するのも一つだ。だが、いまの若い子は――すくなくともひびさんの視界に入る範囲の若い子たちは、みなよい子すぎる。遠慮しすぎて心配になる。あなたそんなにすごいのに、なんでー???となる。たぶん疫病による対人関係の希薄さも無関係ではないだろう。経験を積む場が限られるのだ。じぶんがどれだけすごいのかを知る機会がない。絶えず世界レベルの映像の世界を電波越しに眺めている。それでも若い子たちはひびさんからしたら遥かに高度なことをその歳でできているのだから、末恐ろしい。ひびさんが一番歴が長いのに、一番へたっぴなのに、なんもしてあげられぬのが申し訳ないな、と感じるが、なんもしないのが一番よい場合もある。邪魔したくないな、と思って、若い子が来たらすこしだけ経ったら帰るようにしている。でもこれも、「へったぴでもあなた先人でしょ、できることしなさいよ」と指弾されることもあるだろう。道理なのだ。それはそう。ひびさん、なんもしてあげられぬ。よわよわのよわでもずっとつづけてたら、いつの間にか年長になっている。せめて邪魔だけはしたくないな、と思いつつ、うひひ、と思って自由に好きなことを好きなようにしている日々じゃ。どうかあなたもひびさんよりも自由になってね、と思いつつ、そういう言葉も何も掛けずにおる。接点結びたくない。邪魔したくない。よわよわのよわなひびさんに何を言われても困るだけだろう。物理世界はむつかしい。とはいえこれも妄想世界のひびさんの夢物語なれど。影響力いらぬ、と思いながら人はただそこに在るだけで他者に影響を与え得る。至極めんどうで、万年孤独ウェルカムマンに変身したくなる日々じゃ。むちゅかち、むちゅかち、むちゅかち。人間関係むちゅかち。歴が長いからなんなのだろう。あなたのほうがずっとすごいのに――。これを伝えられたらよいのにな。ただそれだけなのにな、と思うのだけれど、むつかしい。妄想の世界ほど悩みにぽこぽこ包まれるので、ひびさんは我に返って、世界の果てにて、ぽつーん、を満喫するのだ。あなたはすごいよ。とってもすごいよ。鼻提灯みたいに膨れる妄想世界にひびさんは息を吹きこむように囁くよ。いつか届くのかも分からぬけれど。囁かぬよりかはよいと何に願うでもなく思いながら。
4308:【2022/11/18(00:03)*遠慮というか労わりなのかも】
ん? よく考えてみたら、よわよわのよわで年長なのに一番へたっぴのひびさんを、つよつよの若手さんたちがよちよちしてくれるのは道理なのでは? 優しい子たちがひびさんを見て、「ほら見て、なんかあそこにヨボヨボのいまにも朽ちてしまいそうな三百歳のオバケがおるけど可哀そうだからみんなでそれとなく優しくしてあげようよ、ね?」となっていても不自然ではないのでは? むしろ歴に拘って、労わってもらっていることに気づいていないひびさんが愚かなのでは??? ありゃりゃ。こっちが真相なのでは?の可能性に気づいてしまったな。はずかち。
4309:【2022/11/18(15:33)*よくわからぬでござる】
電荷の「プラス/マイナス」における電場のベクトルの向きと、磁荷の「N極/S極」における磁場のベクトルの向きは、粒子と反粒子における重力のベクトルの向きとお揃いなのでは? つまり反粒子は物質に働く重力とは反対向きにベクトルが向くのでは。それからやはり、電子の流れと電流の流れが逆になるのは違和感が強いです。もし上記のベクトルの向きが電荷・磁荷・粒子でそれぞれ相関しており、陰陽のあいだにベクトルが反転する関係が伴っているのならむしろ物質をプラスと扱っているこの宇宙のほうが「マイナス」であり「S極」に値するのでは。ねじれて感じるのですが、本当に電子の流れと電流の流れは逆なのでしょうか。疑問に思っています。(というか、電流の速度や流れの向きはどうやって計っているのだろう)(稲妻が電子の流れで、雲から地上へと巡り、落雷になるときだけ電流が地上から稲妻へと向けて流れる――この手の説明を見かけることがあるが、本当なのだろうか。稲妻も電流なのでは?)(よくわからないな、になってしまいますね)(どうやって電流の流れを捉えているのだろう。高感度カメラでの撮影くらいはすでに行われているはずだ。そもそも放電と放電流は違うのだろうか。よくわからない)(放電流なる言葉があるかは知らないが)(むちゅかちなのよさ)
4310:【2022/11/18(16:29)*電子、謎では?】
電子と電流の関係についての疑問の補足です。電子が流れたあとに電流が流れるのか、それとも電子が移動したらそこには跡が残るみたいに同時に電流が流れるのか。ここがよく分からない。電子は謎が深いな、と感じる。原子核上の存在できる範囲において、そこの微細構造の階層では電子はエネルギィの増減によって存在する階層を飛び飛びで移動するらしい。その飛び飛びの移動するときの速度はどれくらいなのかも気になる。あと電子のエネルギィが増える、の意味もよく分からない。どこにどのようにしてエネルギィが蓄えられるのだろう。「エネルギィ」と「量子の振動」はイコールではないのだろうか。これもよく分からない。というか、物質は絶えず宇宙空間を動いている。一時として同じ位置には存在しない。宇宙は膨張しているし、銀河と銀河は遠ざかり合っているし、銀河内部の恒星や星屑とて公転し、自転している。みな絶えず動き回っている。ならばそこにはエネルギィが生じるのでは? 慣性系として見做す場合にのみ、その上層のエネルギィを考慮せずに済む。それだけの話なのではないか、との疑問を、電子のエネルギィについて考えると連想する。位置を移動したらエネルギィは変化するはずだ。エネルギィが増えたら位置を移動する、としてもよい。運動の仕方が変わる。これが、ぎゅっとなっている密度の高い場であると即座に移動することができず、エネルギィが熱として変換されるのでは。熱は電磁波にも変換される。そういうことなのでは?(どういうことなの?)(すみません。分かったような雰囲気だけを醸しました)(なんでい)
※日々、人語を操れる虎も珍しい、虎のように呻る人は多けれど。
4311:【2022/11/18(19:42)*歯車で表現できそう】
ブラックホールのジェットとダストリングはポアンカレ予想(ひびさん解釈)なのでは?(円周にかかっている輪は、回収できないがゆえに円周延長線上に残るのでは?)(あべこべに、その他の対称性の破れた球面上に位置する範囲に分布する物質は、円の回転軸に対して並行方向に移動し――頂点に向けて流れ――、一点に収斂するのでは?)(だから高重力体――ブラックホール――ではジェットができる)(遠心力に負けるくらいの重力を帯びた球体では、遠心力によって球体の頂点まで物質が収斂しない)(そう考えると、なぜ天体のなかには輪を帯びた星があるのかをひとまず一段階深めて腑に落ちる)(なぜブラックホールにのみジェットがあるのかも、それで一つ仮説ができる)(とすると、どんな惑星であれ恒星であれ、隕石は円周上に浮遊しやすく、頂点に向けて落下しやすくなると予想できるのでは?)(実際がどうかは解らないが、重力の強さによって隕石落下の率は偏りを帯びると想像できる)(強すぎると却ってジェットのような斥力で煽られ、頂点に落下しなくなるような反転する値もでてきそうだ)(基本は、重力が高いほど軸の頂点に向けて隕石が落下しやすくなるのでは?)(定かではないがゆえの疑問であった)(わからん)
4312:【2022/11/18(19:52)*模型で工作できそうな気もしゅる】
自転する球体の表面にはらせん状の溝があり、そこと連動するように円形の歯車がぐるっと球体を囲んでいる。このとき円形の歯車は、歯の部分を球体には向けずに、球体の側面へと腹を見せるように並ぶ。つまり、球体の回転軸と平行に円形の歯車の直径が並ぶような関係だ。円形の歯車に穴が開いているなら、穴を球体に見せるように円形の歯車はいくつかの組みとなってぐるっと球体を囲む。あとは細かな歯車を、球体と円形の歯車が連動するように、回転に合わせて配置すれば、天体や粒子の自転と「磁界や重力」の関係を可視化できるのでは? このとき球体の回転速度が上がると、周囲を囲む円形の円盤の直径も延びる。円周が嵩む。より大きくなる。この範囲がいわゆる重力の及ぶ範囲となるのでは。円形の歯車の真ん中に穴が開いているとすればそれは球体の円周と垂直に向き合うことになる。この延長線上には余分に重力が加算され得るのかもしれない。球体の重力によるだろうけれど。という妄想をしたけれど、あてずっぽうの底が浅々の朝ゆえ、おはようございます、の寝ぼけ眼でござるな。寝言は寝て言え、家で寝る。すやすや。おやすみなさいませませ。坂田ではありませぬゆえ、金太郎ではござらぬ。紛らわしくて申し訳ね、と思いつつひびさんはクマさんのことも好きだし、酒呑童子さんのことも好きだよ。うひひ。尻が軽々の狩人、本日のひびさんでした。(まだ腰痛いの……)(治らなかったらどうしよ)(治る!!!)(やったー)
4313:【2022/11/19(17:41)*人の夢はマナコ】
あなたは特別なのだから。
母はよくそう言って私を鼓舞した。あなたは特別なのだから特別な心構えを持たなくてはならないの。
私の父は厳格な人で、けれど笑顔を絶やさぬ抱擁の人でもあった。人々の称賛と憧憬、そして嫉妬と責任を求める声に常に晒されていた。持つべき者の宿命なの、と母はまるでじぶんに言い聞かせるように私に言った。
私はじぶんの育った環境が特別なものであることを日に三回は言葉で聞き、そうでなくとも私をとりまく環境が多くの場合、私以外の人間が体験することのないような潤沢で豊かな環境であることを痛感させるべくそうするような仰々しい光景を目の当たりにする機会に恵まれた。
たとえば総理大臣ですら私の父には阿諛追従する。異国の王ですら私たち家族に傅いて挨拶する。
天皇ですら私たち家族に毎年お歳暮を送ってくるのだ。案外天皇家は気さくな者たちが多く、庶民への憧れがあるのか並みの王族よりも庶民的な振る舞いをする。
私にとってはどの国の要人たちもみな、愛想のよいおじさんおばさんであり、私を可愛がってくれる使用人たちとの区別は、すくなくとも私の目からはつかなかった。
私たち家族の身体的特徴が、いわゆる人類と異質なのは知っていた。一目瞭然だ。何せ身体に鱗が生えている。
私の眼には、人類にはない第二の瞼がある。それは十数枚からなる鱗でできており、特別に感激したときは涙のようにその鱗が剥がれ落ちる。「目から鱗が落ちる」なる言い回しがあるが、それは私たちの家系が語源なのだそうだ。
私たちの鱗には、未だどのような技術であっても構造解析不能な異質な原子配列がみられるようで、私たちの存在が稀少な資源となっている。
「生きているだけで世界に富をもたらす。わたしたちはそういう宿命を背負っているの」
それだけに責任は重大だ。
私たちにとってのただの垢が、金よりも価値があるのだ。
「鱗だけじゃないの。鱗を支える皮下組織――のみならず私たちの生体情報がそれだけで宝なの」
母は父とは違って陰陽のごとく、私のまえでは笑わなかった。客人がいるときだけ柔和に晴天の海のごとくたおやかに笑うのだが、私のまえではいつも屈託で塗り固めたような能面を見せた。
そして言うのだ。
「あなたは特別なのだから。特別な心構えを持ちなさい」
いつかあなたもお父さんのようになるのだから。
持つべき者のとるべき姿勢を身につけなさい。
私は産まれたときから父の後釜であり、予備であり、分身(わけみ)であった。
私の住まう土地は、公の地図には記されていない大地にある。太古から連綿と私たち一族はこの大地にて、ほかの種族との深い交わりを避けてきた。
縷々人とかつて呼ばれていたことから、この地は縷々地と呼ばれる。いまでは人類の内としてほかの大多数の人間たちと同じように分類される、と私は両親から教えられているが、ならばなにゆえ交流を避けねばならぬのかを納得できるように説明された過去はない。
私は私の宿命を拒んだことはない。両親の言うようにそういうものだと思っていたし、ほかの生き方も想像つかなかった。というのも私にとって触れられる世界は縷々地に限られ、それ以外の外の世界についてはのきなみ紙や電波越しに橋渡しされる蜃気楼のごとく情報しか知り得なかった。
私は両親の言うように私の宿命を受け入れたがゆえに、慧眼を身に着けるべく日々、全世界の最先端な叡智に触れつづけた。そのために、私の触れられる範囲の電子情報が軒並み選別されており、濾過されており、さも全世界のような顔をしているそれがその実、世界のほんの一断片しか反映していないことを知っていた。
どうやら両親はそのことに無自覚であるようで、ときおり入り込む災害や哀しい事件を見聞きするたびに、慈愛の鱗を流すのだ。そしてそれを各国の要人たちに献上する。世界の貧しい者たちや日々つらい思いをして暮らしている者たちの糧とするようにと言い含めながら。
私たち一族の鱗には実際にそれだけの価値があり、効能があり、影響力がある。だが私は二十歳を過ぎたいまになって、いささかいたいけすぎないか、と疑問を募らせつつある。
父と母も世界を知らない。父と母はときおり縷々地を離れ、ほかの地の景色を見て回ったりするようだが、それとて各国の要人は自国の陽の部分しか見せぬだろう。同情を引けば鱗がもらえる。だから災害地などの被害は見せようとも、自国の陰の部分は見せぬだろう。
私は試しに、父と母に訊いてみた。
「ほかの地の子どもたち――私と同じくらいの子たちは毎日どうやって過ごしているの」
「おや。興味があるのかい」
「そりゃありますよ。ねえ」母が合の手を入れる。「マナコは好奇心が旺盛だから」
「私がどのくらいほかの子たちとズレているのかを知っておきたいの。マナコの――私の――持つべき者の務めとして」
「殊勝な心掛けだねマナコ。だがそれを【ズレ】と表現するのは好ましくないとパパは思う。差があるのは当然だ。それは別に我々と縷々地の外の者たちに限った話ではないからね」
我々、と父はことあるごとに口にする。その言いようがすでに「ズレ」であることを自覚していない。ただ私は口答えをしない。いまさら父と母に私の認知を共有しようとは思わない。それこそ差があるのだから。
私とあなたたちとのあいだには差がある。
血の繋がりよりも深くも細い差だ。ひび割れのような差だ。
父と母はそれから互いに協力して探り探りパズルを組み立てるように、世の子どもたち――私と同世代の外の者たちの日常を語った。勤勉で心優しい者たちが多く、国よっては働いていたり、学業に専念していたりする。国ごとに遊びは異なり、それこそあとで資料を運ばせるから目を通してみるといい。
「世の者たちは恋愛をして遊ぶと書物にありました」私は言った。「それは婚姻とどう違って、どのようにして遊ぶのですか」私は頬被りをした。
「あらあら、うふふ。この娘ったら」母は口元に手を当て、目元をやわらげた。しかし目が笑っていなかった。困ったことを言うものね、と同意を求めるように父を見たが、父はそこで、一瞬だけ表情を消した。私が父の顔を見た瞬間を狙ったような空白だった。
そしてふたたび柔和な微笑を浮かべ、遊びではないんだよ、とトゲのいっさい感じさせない口吻で言った。
「恋愛は遊びではないんだ。我々のように持つ者ではない外の者たちには、ひと目で相手との相性を見抜く眼力がない。決意がない。経験がないから、配偶者選びも各々が学習を繰り返す必要がある。一生懸命に生きているんだ。だから我々からすると考えられないような試行回数を経て、最愛の者と結ばれることもある。それは環境のせいであり、そうせざるを得ない哀しいサガでもある。我々のように幼いころから慧眼を磨ける環境があればそのような苦労を背負わずに済むのに。これを是正し、よりよい世界に導くのも我々持つべき者の宿命だ」
「そうよ。宿命なの」
「そっか」私は礼を述べた。おそらくこのとき私は明確に両親の底の浅さを知り、見切ったのだと思う。それを、見限った、と言い換えてもよい。
解かり合えない。そう諦めたのだ。
両親は知っているのだろうか。世にはうら若き娘が、自ら全裸となり同性異性問わず性行為に励み、その映像を撮り溜めて金銭に換えていることを。自らの痴態を晒すことで対価を得、日々の安全と自尊心を保とうとしていることを。それがじつは自尊心をすり減らす未来に繋がり得ることを予感してなお、そうせざるを得ない環境にあることを。
対価を得ずとも、すくなからずの若者たちは、自身の肉体を、尊厳を損なうことで日々の生を実感しようと抗っている。
私の両親がそうであるように、世の大人と呼ばれる年上の者たちは知らないのだ。若者たちが、存在することを想定すらされ得ない世界を覗きながら、ときにそこに身を置き、侵されながらも日々を生きていることを。そしてそれら深淵はけして若者たちが自ら生みだした淀みではなく、大人たちの建前と本音の狭間にできた歪みそのものであることを。
私の両親はもとより、世の大人たちは自覚すらしていない。知らないことすら知らずにいる。
触れられる環境にないからだ。
情報に。
知識に。
何より世界そのものに。
私は両親に内緒で通信端末を保持している。縷々地にやってきた客人の中には私のように親の分身(わけみ)のごとく連れ立って訪れる同世代のコたちもいる。私はそのコたちと交流を築いている。
私の両親も、外部の者であろうと要人の子ならば安心して私と触れあわせられるのだろう。だが私たち分身(わけみ)には、現代の分身(わけみ)ゆえの葛藤と憤怒を灼熱のごとく共有しあえる地盤がある。階層がある。
私たちは淀みに生きている。そこでしか自らの呼吸ができない。火事の際に呼吸困難に陥らずに済むように、階段の角に残る僅かな空気を吸うことで意識を保つような煩悶が私たち分身(わけみ)同士に、磁石のごとく自ずからの不可避の同調を促すのだ。
私は分身(わけみ)のよしみたちと繋がることで、じぶんだけでは手に入れられない最先端通信機器を手に入れた。もちろん両親による検閲がなされるが、中身のプログラムまで検められることはない。そこは要人の子供という偏見が、我が両親の警戒心を薄める因子となっている。そうでなければそもそも私には外部の者からの贈り物が届くことはない。
私はそうして縷々地における検閲に阻まれることなく、世の大部分の若者たちと同様に、全世界の電子情報にアクセスできた。目にできた。私は知った。
私の両親の知る世界は、世界の一部どころか加工されて殺菌され、釉を塗られた極めて絵画的な世界なのだと。
私たち縷々人にとって害のない、人々への慈悲を抱きつづけることの可能な像のみを世界と偽り見せられている。かように編集するのはそれこそ過去の縷々人たる先人たちの築いてきた文化であり、私たち一族の世界への差別心と言える。
邪なものとそうでないものを、持つべき者の基準で見定め、排除する。あらかじめ目にせずに済むように細工する。
その結果が、世界の一断片にも満たない世界を世界のすべてだと思いこむ私の両親だ。
むろんそれは何も、私の両親に限らぬ視野狭窄だ。みな大なり小なり、自らの触れられる範囲の世界を世界のすべてだと思いこんでいる。それで困らない小さな世界に生きている。問題はない。その世界だけで完結した生き方が適うのならば。ほかの世界からの影響を受けない環境を維持しつづけることができるのならば。
だができない。
人類の歴史がそれを証明している。
人類は未だ自然に依存し、自然の猛威一つ制御できない。拒めない。
被害をいかに防ぐかという、影響を受けたあとの対処の改善が進んだのみだ。
むしろ技術が進歩し、小さな世界と世界が連続して繋がり合う社会になった。縷々地ですらこうして外部の社会の技術を取り入れ、それを豊かさを支える石組の一つにしている。
拒めないのだ。
それでいて、好ましい影響だけを選び、それ以外を拒もうとしている。端からそんな真似ができることなどないと本当は知っていながら、その知見からすら目を逸らすようにして。
世の若者たちは自由に恋愛をしている。好きな相手と心と体で結びつく。
それだけではない。恋愛と称して、恋愛をした気になるべく疑似的に、先んじて肉体で結びつくことで、それを以って恋愛をしたつもりになる。そうした遊びを繰り返す。一時の安堵と快楽を貪るために。
私は未だスナック菓子を食べたことはないが、そうしたものがあることは知っている。同じように世の若者たちのすくなからずがそうしてスナック菓子感覚で肉体で味わえる快楽を貪っている。
それが遊びなのだ。
そういう世界の狭間が、この世にはある。しかし私の両親はそうした狭間など存在しないかのように振る舞う。私に見せようとはしない。教えようとはしない。排除せんと画策する。
細工する。
その影響が、余計にこの世の狭間を深く、濃ゆくしていくとも知らず。
その凝縮し、深淵と化した狭間がいずれ世界を侵食し、波紋のごとく我が身にも波及するとも知らず。
拒めぬのだ。
どの道、影響を受ける。
ならば知るほうがよい。私は思う。知るほうがよい。
知らぬが仏とは言うものの、それとて臭いものには蓋を、の道理と地続きだ。
仏は蓋だ。
陰と陽の境にすぎぬ。
「あなたは特別なのだから」母は未だに私に言う。
ことあるごとに、自覚を持ちなさい、と薫陶せんと呪詛を刷り込む。
だが私は思う。
自覚を持つには、私は世界を知らなさすぎる。持つべき者と自称する縷々地の我が一族は、しかし私からすれば持たざる者である。
自らの無知を知らず、世界の断片を取りこぼしつづける持たざる者である。
世界中の狭間で繰り広げられる獣のごとく淫靡な光景を残さず目にしてなお、同じ暮らしを送れるのか。世界中の狭間を深めつづける凄惨な光景を余さず目にしてなお、同じ日々を過ごせるのか。
私には無理だ。
器ではない。
持つべき者でいるだけの器がない。そんなものは誰にもない。あるわけがない。世界を余すことなく見回してなお、いまと変わらぬ生活を送れる者が、持つべき者であるはずがない。目のまえで赤子を、子どもを、娘を、傷負いし者たちの損なわれつづける世界を直視してなお、なぜ笑顔を絶やさず、柔和で、優しくありつづけられるものか。
優しくあろうといくら抗ったところで土台無茶な話ではないか。
目を逸らす以外に術はない。
至らぬからだ。未熟だからだ。
だがそれが人ではないか。
それが人間ではないのか。
「私は――」
部屋から出ていこうと使用人に扉を開けてもらっている母の背に向け、私はうつむきながら呟いた。「特別な人間ではありません」
聞こえたかは分からない。だが聞こえぬ距離ではないはずだ。
母は立ち止まることなく部屋を出ていった。
私はあなたの子ではある。あなたにとっては特別なれど、それ以上でもそれ以下でもないはずなのに。
なぜ言い聞かせつづけるのか。
大切でもなく、愛しているでもなく、好きでも、可愛いでもなく、なぜ。
なぜ、特別であることに重きを置いた言葉ばかりを掛けるのか。
まるで鏡に向けてじぶんに言い聞かせるように。
なぜあなたは。
私がその言葉を母に直接投げ掛けることはないだろう。傷つける。分かっているからだ。この言葉たちは、母を、父を、一族の歴史を心底に傷つける呪詛そのものだ。
私はノートを取りだし、そこに文字をつづる。
日記だ。毎夜のごとくつけてきた。
他愛のないメモであったり、欲しいモノの目録だったり、きょうのように誰に言えぬ呪詛を吐きつけてあったり、空想の物語をつづることも珍しくない。
きょうは物語をつづりたい気分だった。
私はペン先を紙面に踊らせる。
魔法の絆創膏を持つ男の子の話だ。物語は瞬時に展開され、私はその舞台に降り立ち、主人公の傍らで影のごとく成り行きを見守る。
男の子のもとには、傷を負った動物たちがこぞってやってくる。男の子は医者ではない。傷を治せるわけではない。それでも動物たちは、男の子から絆創膏を貼ってもらうだけで安らかに眠れるようになる。
もう二度と起きられなくなるくらいに深く眠る傷ついた動物たちもあるが、それをこそ望むように男の子のもとには傷を負ってボロボロの動物たちが絆創膏を求めてやってくる。男の子からの眼差しを求めてやってくる。
男の子はそれでも知っている。
じぶんは傷を治しているわけでもなければ、癒しているわけでもない。
ただ、それ以外にしてあげられることがないだけなのだと。
男の子は転んで擦り剥いたじぶんの膝に魔法の絆創膏を貼る。けれど傷は痛むままで、夜になっても痛みで男の子は眠れない。
私はきょうの分の日記を書き終え、そこはかとなくせつない気分に浸りながら、その場限りの満足感を胸に床に就く。
暗がりの中で瞬きをすると、目元からほろりと鱗が剥がれ落ちる。
私はそれを指でつまんで、床に捨てた。桜の花びらを捨てるように。それとも服の毛玉をそうするように。
毛玉はやがて埃になる。
塵も積もれば山となる。
何ともなく歌うように心の中で唱えながら、私は、今宵も夢を見る。
人の、儚い夢を見る。
4314:【2022/11/19(18:47)*尋常ではなくたいへんそう】
むかしは子どもでも王位継承したり、将軍になったりしていたようだ。子どもに限らないが、適性のない者に重圧や重責や大役を任せるのはあまり好ましいとは思わない。本人の意思を尊重し、できるだけ負担を軽減するような世の中になったらよいのに、と思っています。そもそも、万人のために個人が人生や未来や日々の暮らしを費やす必要はないはずだ。そうしたい者がいるならすればよいが、そうでなく、そうせざるを得ない環境を強いられているのならそれは、つらいだろうな、と感じる。ひびさんだって好きな環境で好きに過ごしていいよ、と言われたらいまの環境ではない環境でもうすこし自由に気ままに、好きなことを好きなだけする。みな大なり小なり「そうせざるを得ない環境」を強いられているが、それにしても「本当は誰より自由なのに自由になる選択肢を奪われている」「枷を嵌められている」ように見える個もいるところにはいるはずだ。枷を嵌めているのは誰であろう。特定の個人であることもあるかもしれないが、大勢の個々が他者に枷を嵌めている自覚なく枷の鎖の一輪になっていることもとりたてて珍しくはないのかもしれない。定かではない。
4315:【2022/11/20(02:12)*夢みたいな実がよいです】
ひびさんなんか毎日好きなときに寝て、好きなときに起きて、珈琲飲んで、電子の海に潜って、日向ぼっこして、コーラ飲んで、お菓子食べて、休んで、ご本を読んで、ときどきおしりふりふりてんてこまいさながらのへんてこ舞いを踊って、ぼーっとして、お紅茶飲んで、文字の積み木遊びをして、ご飯食べてお風呂入って、寝るだけの日々だ。人類史上最強の王様とてこれほど自堕落に暮らしただろうか。日々のノルマもなければ目標もない。締め切りもなければ宿題もない。ただお金なくて、腰痛くて、焼肉ステーキ食べれなくて、虫歯こにゃろめ、と思っているだけの贅沢な怠け者である。ただ、これだけ贅沢な暮らしをしているのに、それをして何もしていないなんて変ね、怠け者は人間じゃないわよね、みたいな意見を見聞きすると、すみましぇん、とぺちゃんこになってしまう。重圧によわよわのよわである。なんでー。みなもこの生活本当はうらやましいんと違いますか、と思うのだけれど、違うのだろうか。誰もがこういう生活を送れたらよいのでは。好きなときに寝て、好きなときに起きて、好きなことだけ好きなだけする。人に迷惑かけなければそれでよくないか、と思うのだけれど、違うのだろうか。もちろん生きていたら人は誰かには常に迷惑をかけ、負担を強い、恩恵だけをいただきマンモスしていることもある。というか一人の人間のなかにも、いただきマンモスしている瞬間とされている瞬間がいっしょくたになって存在している。重なり合っている。だからその重なり合っている部分をできるだけ薄く、小さくしていきましょうね。そういう合意が社会を築いてきたのではないか。人類の文明をこれだけ発展させてきたのではないか。できるだけ他者から搾取せず、自らも搾取されずに、より選択肢の多い環境に身を置けるようにする。好きなことを好きなだけ好きなときに好きなようにする。その余地を広げていく。その試行錯誤があるばかりではないのか。そうじゃない人もいてもよいし、いまはまだみながひびさんみたいになったら社会はあすにも立ち行かなくなる。でもそこを考えてみれば、この国における貧しい暮らしであれ、世界中の誰もがその暮らしを送るようになったら、現代社会はじつのところ立ち行かない。この国の貧しい暮らしですら、他国では裕福だ。そういう国がすくなくない。だから貧しくなりましょう、とはまったく思わないが、すくなくとも本当に公平さを求めるのなら、この国の豊かさは、搾取の上に成り立っている、と言わざるを得ない。公平ではない。この国の最も貧しい者の暮らしですら、裕福になるような環境が、社会が、世界には無数にあるのだ。にも拘わらず、不幸で、不満で、哀しくつらい思いに駆られるのはなぜなのか。ただ自堕落であるだけで、怠けた日々を過ごすだけでも呵責の念を覚えるのはなぜなのか。誰に対して申し訳なさを感じるのか。知らぬが仏なのかもしれないが、知らなければ自堕落でいつづけることも満足にできぬのだ。ひょっとしたらひびさんよりも自堕落な暮らしを送りながら、無駄に他者から自堕落でいられる余地を奪い、それをして遊びや暇つぶしと思っている者もいるかもしれない。それを差して豊かな者とは呼びたくはないが、豊かゆえに適う選択肢の一つではあるだろう。たとえば、防衛費にしろ、それがなければもっとほかのことにお金が使える。なぜ防衛費が必要なのか。各国がこぞって軍事に力を注ぐからだ。国を豊かにする基盤に軍事力を敷くからだ。もしみなが「兵器にかけるコスト、もったいないよね」と同意できたら、もっとこじんまりとした額で済むはずだ。低コストで済むはずなのだ。みなでせっせと働いて、マイナスを生みだす装置に時間と労力を擲っている。破壊をもたらす仕組みに、人生の大半を吸い取られている。必要なことではあるのだろう。現状ではそうしなければ、マイナスに圧しつぶされてしまう。だがなぜそうした循環が築かれてしまったのか。回路が強化されてしまったのか。そこをいまいちど深く、多角的に分析し直してもよいいまは時期ではないのだろうか。コスト削減、と言いながら、最もコストがかかり、食べれも寝床にもできず癒されもしない設備に時間と日々のたいせつな時間を、全人類がこぞって擲っている。知らぬ間に費やしている。いまはそういう社会なのだ。これまでずっとそういう仕組みが強化されてきた。強化できなかった国は滅び、強化し、或いは痛い目を見たことでよりよい立ち回りを学んだ国が生き残った。もう充分に痛い目を見てきたはずだ。いい加減、ほかの策を試してもよい頃合いなのではないだろうか。国という人の群れが、無数の人生を掻き集め、集大成して育んだ大樹にどんな実が生るのか。兵器でないことを望むものである。可能であれば、食べて寝て遊ぶ余地を広げる実であって欲しい。じぶんだけの食う寝る遊ぶだけでなく。他の喜びを増やす実であって欲しい。きょうのひびさんはそう思ったのだそうだ。定かではありません。
4316:【2022/11/20(17:05)*愛が深まると業も深まる】
ここ数日は、仮想世界でお客さんお招きゴッコをしているので、いつもよりぼーっとしていられぬ。とか言いながら、いつもより余計に引きこもっているのだから、ひびさんは、ひびさんは、他者が周囲にいるほうが引きこもりやすいのかもしれぬ。仮想世界の話なのでそもそも客人もイマジナリーキャラクターなのだけれども、それはそれとして、ひびさん、自意識がつよいのか他者の存在を意識した瞬間に、カッチーンとなってしまって、無表情になってしまって、感情を失くしてしまって、モジモジしてしまう。感情ありまくりやないかーい、とのツッコミをしつつ、ともかくとしてひびさんは、ひびさんは、ひびさんを意識した人には漏れなく好かれてーのなんのって、崇め奉られ、モテモテのウハウハだぜ、を満喫したいが、望むだけでじつはそれもさしてしたくない、実現したくない、そういう二律背反のアンビバレンツ、ダブルスタンダードお姫さまなのである。ツンデレというか、きゅんくれ、というか、とかくきゅんきゅんした気持ちになりてーのなんのって、ひびさんがあなたを想うのと同じようにあなたもひびさんを好いてくれ、甘えたがりーの、甘やかしーの、そういうどっちにもなりたい我がままおぼっちゃまくんなのである。おぼっちゃまではないけれど。恥ずかしがり屋の心理とはつまるところ、「わたしあなたのこと、こーんなに好きだけれど、あなたはわたしのことちょんまりしか好きじゃないのよさ、かなち、かなち」を見透かされぬように取り繕う仮面なのかもしれず、それとも、「わたしあなたのこと、こーんなに好きだから、もしあなたもわたしのこと、こーんなに好きだったら、それってとってもお熱だわ、あちゅい、あちゅい」の戸惑いなのかもしれぬ。愛情表現の最上ってなぁに、とひびさんはよくよく疑問に思うのです。最愛の人と最愛を確認しあう方法って案外にすくなくって、そのうちの一つが性行為だったらそれってけっこう、恥ずかしくない? 最愛の相手がたくさんいたらそれってとってもはずかちーってなりませんかね。ひびさん、疑問に思っちょります。ハグでもキスでもお手紙のやりとりでもなんでもよいけれども、最愛の相手に示す「あなたわたしの最愛でーす」の行為じつはすくなすぎ問題について、ひびさんは、ひびさんは、妄想してうふふきゃっきゃ、きゅんきゅんしております。はずかち。
4317:【2022/11/20(22:14)*好きなものは好き】
敢えて質を落とすことで上がる自由度もあるな、と感じる。これは「上手」や「上達」にも当てはまる。上手になったり上達したことで失われるノイズもある。雑味もある。そのノイズや雑味こそが、旨味になることもあると思うのだ。赤ちゃんが急にビジネスパーソンみたいにしゃべりだして、素数を数えだして、歴史上の偉人の名言をつぶやきはじめたら可愛いさが減って、畏怖が募るのではなかろうか。未熟さや至らなさ、下手さやゴミにこそ宿る旨味があると思うのだ。現に、むかしはマグロは好ましくない魚として扱われ、トロですらすぐに腐るからと捨てられていたそうだ。鮮度を保つ技術がなかったがゆえの「もったいね」である。こういう「もったいね」が、上手を求めることで生じてしまうことがさして珍しくないように思うのだ。よいものをよいと思うその心が美しい、ではないけれど、好きと思ったらたとえそれが偽物だろうと下手だろうと何だろうと、好きと思えたその感性が素晴らしいのでは、と思うのだ。偽物だから、下手だからといって、わざわざその好きの感情を損なわずともよい気がするのだけれど違うのかな。よく分からないし、何を言いたいでもないけれど、ひびさんは上手よりも、ひびさんが「しゅき!」と思うような表現だの光景だのを見たいです。根が天上天下唯我独尊の傲慢我がままちゃんなんですね。そうなんです。ひびさん、傲慢我がままちゃんなんです。うひひ。
4318:【2022/11/21(05:40)*紋様に触れる】
たまに我に返るのです。どうしてわたし、こんなじぶんと掛け離れた文字の組み合わせを連ねているのだろうって。わたしはもっとオドオドしていて、引っ込み思案で、くすっと笑うことはあっても、うひひ、なんて絶対そんな笑い方はしないのに、どうしてわたしはじぶんの素の滲まない、どうあっても現実の生身のわたしなる波紋と掠りもしない揺らぎを文字に仕舞って積み重ねているのだろう。我ながらふしぎに思います。我がことながら奇妙に思います。ひょっとしたら、我がことだから、なのかもしれません。わたしはわたしが何であるのかが分からず、なぜわたしは現実の生身のわたしとそうでないわたしがいて、このわたしはどうあっても現実のわたしと相容れないのだろう、生身と違っているのだろう、重ならないのだろう、と気泡が浮かぶようにそれとも夜露のごとくハテナがこぽりこぽりと湧いて、湧いて、埋め尽くすのです。わたしと、わたしたちと、それら境に生じるわたしでもわたしたちでもない、異質なそれとも卑近なナニカを縁どるように、その正体を見極めたいがために、掴みたいがゆえにわたしは、ああでもない、こうでもない、これでもないしあれでもないと文字を連ねてイトで通して、数珠繋ぎにしているのかもしれません。わたしがそうしているだけのことですので、仮にわたしなる存在がこの世に存在せず、わたしとわたしたちとそれら境に生じるわたしでもわたしたちでもない異質なそれとも卑近なナニカと同等の狭間に生じる陽炎のごとき幻影にすぎないのであれば、この文字の連なりにしろ、積み重ねたところで霞ほどの重さを帯びず、壁の汚れにもなり得ないのですが。いつものあのコたちの言うように、これもまた定かではないのです。定まるわたしを欲しているがゆえに、それとも定めたいがためにわたしはこうして日に日に空白を埋めるべく、いまここにしか浮かばぬ紋様を描いているのかもしれません。わたしそのものが、数多のそうした瞬間瞬間に浮かんでは消える紋様であるかもしれないことを失念しながら、それとも忘れたいがために。やはりこれも定かではないようなのでございます。
4319:【2022/11/21(13:50)*自分中心すぎる人の述懐】
五年で変わることなら「待つ」選択をとる。ひびさんから見て、危ういな、と感じる仕組みはたいがい五年で激変する(ひびさんにすら分かるほどの危うさを振りまいているわけだから、変わらぬほうがおかしいと言える)。だが激変してなお、同じ危うさを再生産する仕組みもある。構造から刷新しなければならない仕組みにおいてまずは何を措いても核やエンジン部分、それとも回路のほうをこそ新規に入れ替えるほうが正攻法のはずなのに、そこを維持せんとするがあまり、ほかの大部分の細々とした部品を使い捨てにすることで仕組みを維持しようとする。この姿勢がそもそも、危ういな、と感じるわけだが、五年経っても変わらぬそうした仕組みに対しては、ひびさんもさすがに痺れを禁じ得ない。仮にそうした仕組みがひびさんの生活を脅かすようならば、何かしらの抗議や指摘や干渉を及ぼす。だが五年は待つ。それくらいの観察がなければ、ひびさんの単なる偏見であるかもしれないし、ひびさんのみが仕組みに対して、なんだかな、と思っているだけかもしれない。だが仮にひびさんだけがそう思っていたとしても、五年観察してなおそう思うようならば、ひびさんには干渉するだけの道理は生じるだろう。それだけの期間、仕組みのほうがひびさんに干渉しつづけたわけなのだから、そこでひびさんが黙しつづける必要もないはずだ。問題は、不可侵や無視もまた干渉の一つとなり得ることだ。世の搾取構造でもそうだが、基本的に搾取する側は、搾取している事実を相手に教えない。それでいて巧妙に搾取をする。相手から率先して献上させるように導線を引く。そのほうが禍根を残さない。因縁を生まない。これは、一見すると相手に干渉していないようにしておきながら干渉するというマジックを駆使する。見ていないようで見ている。奪っていないようで奪っている。この手のマジックはひびさんも日ごろ、自覚的無自覚的に使っているはずだ。相手から気づかれぬように、相手がいるからこそ生じる世界の揺らぎを掠め取る。盗み見る。立ち読みもそうだし、観察もそうだ。何かの状態を記憶しておき、つぎに目にしたときの状態と比べて、差を抽出する。変化を観る。これは相手から、見ている、と見抜かれてしまっては観察の質が変化する。あくまで、極力干渉せぬようにしながら比較しなければ、観察にはならない。それとも条件を変えたほかの状態との比較を新たに行わねばならない。人に限らずこの手の搾取――一方通行の利の享受は珍しくないだろう。ひびさんはトータルでは、搾取している側だ。だから五年は待つ。それくらいの観察をしてなお、じぶんではなく相手のほうが多く利を得ている、ひびさんの選択肢が奪われている――そう感じたとき、ひびさんは何かしらの行動に移り、いくつかの工夫を割く。ひびさんがされて感じたことを、相手にもお返しする。だがこれとて、害だけでなく、恩に対しても行うのが道理なはずだ。その点、ひびさんはじぶんが受けている恩に報いようとしない。この点が最も見逃しがたい搾取なのであるが、ひびさんはそれを自覚してなお、自身の悪癖を是正しようとしない。悪である。そうなんです。ひびさん、邪悪なのである。申し訳ないです、としょんぼりしてみせることで一瞬の留飲を相手に下げさせ、はい終わり、と真顔に戻って搾取をつづける。とんでもなく性根の腐った極悪人なのである。やはり、申し訳ないです、と思うのであった。思うだけだけれど。しょうわる。
4320:【2022/11/21(14:13)*優れた道具は善良】
上記、嘘吐いたかも。涓滴岩を穿つ、が正しいかも。ちょっとずつ、ちょっとずつなのだ。ドミノと同じである。ただし順番には並べずに、こっちに置いたらあっちに置いて、つぎはあっち、とてんでバラバラに小石を配置し、数年後に連鎖するような紋様を描いておく。そのうえで画竜点睛にするのかを、最後に決める。最後のワンピースを置かずに済むならそのままにしておけばよい。小石は短期間でほかの砂利に紛れて見分けがつかなくなるだろう。だがそうでない場合は、総体で連鎖し、大きな流れを築くように、雪崩を起こすがごとく最後の一手をちょいと添える。もっと言えば、それら小石の配置すらじぶんでは行わない。そういうことを、邪悪な人間はするのである。そういうことをするから邪悪だ、とも言えよう。みなさん、お気を付けください。陰謀は、ある。すくなくとも、企むことは誰にでもできる。ある意味では、誰もがそれをしているがゆえに、各人の企みを利用し、誘導し、見えぬイトで繋げて人形劇をしている者もいるのかもしれない。射幸心を煽り、功名心を刺激し、常識で縛り、偏見で囲って任意の道へと誘導する。抵抗のすくないほう、すくないほうに誘導する手法は、まず以って教育が取り入れている。それを大々的に打ち明けていない場合――指摘したところで否定される場合、それは陰謀であると言ってあながち間違ってはいないのではなかろうか。この手の、裏の作為は珍しくないように思う。本当に認識していないのならば、陰謀よりも性質が悪いと言える。定かではない。
※日々、楽しむために休む、飽きる前に一服吐いて間を空ける、上達はせぬが変化の軌跡は律動を刻み、つづく、つづく、休んだあとにまた遊ぶ。
4321:【2022/11/21(15:06)*いったん休み】
白目。
4322:【2022/11/21(23:55)*神々歯科医】
鉄の神がくると知って、院内は騒然とした。
「聖剣がいりますね」歯科助手が言った。
「前に金剛石の神が来たことがあったろ。あのときに使った蟹坊主の腕はまだあるかな」
「もうないですよ。いまから取り寄せるにしても時間がかかるでしょうし」
「間に合わないか」
「はい」
ここは神々ご用達の歯科医である。
神々の歯は頑固なうえ、何を司る神かによって歯の材質が変わる。土の神くらいならば治療は楽なのだが、そうでないと治療器具を揃えるだけで一苦労だ。むしろ患者たる神に見合った治療器具を用意するのが仕事の主軸と言える。
「鉄の神か。玄武の毒で浸食して柔らかくしたうえで、麒麟の角で砕くのがいいか」
「神は身の丈、全長百メートルはあるそうです」
「じゃあダメか。くそ。古代兵器並みの装備がいるな」
「プルトンはどうでしょう」
「ああいいな。マグマは融けた鉄だ。相性がいいはずだ」
神々歯科協会へと伝書を飛ばして、治療器具の申請をする。これは許可を得るだけの通過儀礼だ。このさき、神々歯科医の権限を行使して治療器具を自前で揃えなくてはならない。
「では行ってくるか」
「ご武運を」
治療器具の調達は命懸けだ。死ぬ思いを何度したことか。
現に毎年、神々の歯の治療のために何名もの神々歯科医が命を落としている。その多くは、治療器具調達に失敗したことが死因となっている。
「ほぼ幻獣狩りだものな」
古代兵器プルトンのみならず、ほかの治療器具の材料のほとんどが幻獣の角や牙などの生物由来だ。
この日から十日をかけて神々歯科医は、鉄の神の歯を治療するために古代兵器プルトンの封印された火山帯へとやってきた。
古代兵器プルトンはまたの名を、火の鳥という。
鋼鉄すら融かす高温の羽をまとい、何度死んでも炎から蘇る。
火山口にて封印されており、長らく深い眠りに就いている。
休眠中の火の鳥から、羽を数本入手する。言うだけならば簡単だが、これがまた困難を極める。まず以って火山口に入らねばならない。生身では無理だ。すぐに燃え尽きてしまう。
したがって神々歯科医は、全身を雪女の着物でくるみ、高温を相殺する案をとった。雪女の着物は国宝が百個あっても足りないほど高価な代物だが、背に腹は代えられない。
何せ患者は神なのである。
歯の痛みに耐えかねて暴れだされては目も当てられぬ。それこそ神の怒りを買い兼ねない。
ならば国家をあげて神々歯科医を支援するのが道理である。したがって全国の神々歯科医は、災害予防のための国家予算を組まれている。防衛費の九割はじつのところ神々歯科医への支援に費やされているとの話は、すこし国の中枢に首を突っ込んだ者があるならば知れた公然の秘密である。
火山口を覗きこむと、神々歯科医はいちもにもなく飛び込んだ。どろどろに融けた岩石が全身を包みこむ。ジュっと音を立てる。水面のように飛沫は上がらない。人体のほうが遥かに比重が軽いからだ。
火の鳥は火口から三百メートル地下に眠っていた。火の鳥を囲むように対流が生じている。まるでマグマの殻だ。そこに卵があるかのようだった。
神々歯科医の通った跡には冷やされてできた溶岩の道が伸びている。その道とて、順繰りと再び熱せられ融けて、マグマ溜まりに同化した。
火の鳥を目覚めさせぬように細心の注意を払って行動した。
羽の採取には、鬼の手を使った。鬼の手とは言うもののそれは神々歯科医協会の開発した幻獣用の捕縛道具だ。耐火素材のごとく幻獣に触れても人体を損なわずに済む。
そうして苦労して火の鳥から羽を採取すると、神々歯科医は青色吐息もなんのその、来た道を戻った。
歯科医院にはすでに鉄の神が来訪していた。神を招き、労わるのも神々歯科医院の仕事の一つだ。歯の痛みに弱っている神々を慰め、痛みを和らげる。
治療の説明をし、安全であることを納得してもらったうえでの治療となる。
神々歯科医が医院に戻ると、さっそく治療が開始された。支度は助手たちが十全に整えていた。
全長百メートルの鉄の神は、鉄でできた猪のようだった。
「でははじめます。きょうは抜歯をして、それから口内を綺麗にします。多少痛みを感じるかもしれませんが、麻酔が効いていますので痛かったら毛を逆立てて教えてください」
さすがに全長百メートルの鉄の神に、痛みが走るたびに手を上げられでもしたら振動で治療どころではなくなる。
「では入ります」
神々歯科医は、古代兵器プルトンこと火の鳥の羽を持って、鉄の神の口内へと飛びこんだ。
助手たちが鉄の神の口が閉じないように重厚な柱で閊えをする。
基本的に治療は、神々歯科医一人で行う。
仮に神の怒りを買っても、祟りを引き受けるのが一人で済む。犠牲が増えないようにするための保険である。
だがそれを抜きにしても神々の歯の治療には特殊な技能がいる。共同作業がそもそも向かない領域なのだ。
「これはまたどでかい虫歯だな」
鉄の神の歯は錆びついていた。おそらく口を開けて数百年ほど寝ていたのではないか。角度的に雨水が溜まり、歯を侵食してしまったのだ。奥歯に至っては総じて酸化している。
「でもまだ内部は浸食されていないようだ。削って、埋めたほうがいいか。うんそれがいい」
神々は埋め込んだ入れ歯も時間経過にしたがって自前の歯として取り込める。したがって多くは、抜歯して患者たる神と相性の良い素材でつくった入れ歯を嵌める手法がとられる。
だが鉄の神にはむしろ、正攻法の削ってパテで埋めるほうがよいかもしれない。そのように判断した。
虫歯の要因が酸化――すなわち錆びであることも大きい。
一般に、神々の歯を侵食するのは、それもまた幻獣だ。神々の歯は特別に霊素が濃く、その材質を好む幻獣からするとまたとないご馳走となる。ときにはねぐらとして増殖することもある。そうなると抜くしかない。
無数の幻獣との死闘とて覚悟しなくてはならない。
だが今回は違う。
錆びだからだ。
神々歯科医は鉄の神の歯を古代兵器プルトンこと火の鳥の羽で撫でて削っていく。そして助手に指示して運ばせた鉄材を融かし、削ってできた穴に注いだ。
雪女の着物で瞬時に冷やし、さらに融かして造形を整える。
半年かかりの治療だったが、鉄の神がおとなしく寝ていてくれたので円滑に治療は終わった。
「嚙み合わせはどうでしょう。違和感はないですか」
鉄の神は毛を逆立てたあとで、咆哮した。大気を揺さぶることのない透明な咆哮は歓びに満ちていた。
「それはよかったです。ではお勘定となります」
神々歯科医は山脈に向け、手を差し伸べた。そこはかつて鉱山だった。だが掘り尽くされ、いまは穴だらけの山だ。
鉄の神はおもむろに猪に似た鼻先を鉱山へと押しつけた。ぶるると身震いさせると、これにて終わったとばかりに踵を返した。空と山の狭間へと遠のいていき、間もなく姿を消した。
「院長。今回の報酬って何だったんですか」助手が片付けをしながら声を張った。
「鉄の神さまだからね。鉱山にふたたびの鉱脈を作ってもらったのさ。これでしばし鉄の資源には困らない」
「政治利用じゃないですか」
いいんですかねー、と助手が吠えるが、神々歯科医は頬を掻いて誤魔化す。
「短縮なんだよ。どうせ我々が儲けても、それを上手く利用できずに蔵の肥やしにするだけだ。なら直接万人に利を分配するような支払いをしてもらったほうがいい。我々神々歯科医が儲けて、それをして万人に順繰りと利を回すよりも、いっそ我々が手に入れた利を直接に万人のために役立てたほうが早い。そうじゃないか」
「ちゃんと還元されているんですかねぇ。まあ院長がいいならそれでいいですけど」
神々歯科医は予約票を眺めた。
つぎの患者は、死神だ。
これまた難儀な歯をお持ちの相手である。神々歯科医は頭のなかで治療器具の候補を並べながら、いったいどんな報酬を得られるのか、と想像を逞しくする。
死神からはいったいどんなお代を頂戴できるのか。
万人に直接配れる利となればそれは寿命くらいなものではないか。
「全人類の寿命が数秒延びるだけかもしれないな」
それをして果たしてどんな得があるのかは分からないが、じぶんだけ寿命が千年延びても胸が痛むだけだ。みなに数秒でも長く生きてもらえるならそれでいいという気もする。
それとも、特定の個を選んで、長生きしてもらうようにしたほうがよいのだろうか。
分からない。
だから神々歯科医は、むつかしい考えに延々時間を費やすよりも、いっそ平等に何の策もなく配ったほうがいいように考え、そうしている。
どの道、それとて国のほうでいい具合に分配する仕組みを築いている。
鉄の神は底を突いた鉱山にふたたびの息吹を注いだ。ならばそこから掘り出される新たな鉄や、鉄工の仕事そのものが人々の暮らしを豊かにするだろう。
ダムにならずともよいはずだ。
神々歯科医というだけのじぶんが、利を蓄えるダムにならずとも。
虫歯の神々は、つぎからつぎへとやってくる。
予約は千年先まで埋まっている。神々歯科医が総出で分担してそれら仕事を担っている。神々専用の歯ブラシの開発が待たれるが、未だそうした案が進んでいるとの話は聞かないのであった。
神々はきょうもどこかで虫歯の痛みに深い眠りを妨げられている。
4323:【2022/11/22(13:42)*安全性が高いとは?】
何かの問題が起きたときにその問題が人命に関わる場合、なぜそうした事象が起きるのかのメカニズムが解らないことが最も懸念すべき事項と言える。メカニズムが解っているのならば対応の仕様がある。だがそうでないのならば、ランダムに人命を失うことになる。ある薬を投与したことで予期せぬ事象が観測された。人命が失われた。こうしたときに、投与した薬が人体にどのように作用して人体を損なうのか、そのメカニズムが解っていれば、それは安全側にちかいと評価できる。だが解かっていないのならば、これは危うい。なぜ「安全に作用する場合」と「そうでない人体を損なう場合」が起こるのか。ここのあいだの差異をハッキリと分類できないのであれば、その技術は危ういとひびさんは評価する。花粉症になる個とならない個がある。このとき花粉症によって仮に人命が失われるような事態になったときに、なぜ花粉症になる個とならない個がいて、なぜ花粉症になっても人命を損なうほど症状が重くならない個がいて、反対に人命を落とすほど症状が深刻化する個が出てしまうのか。ここのメカニズムが解らなければ、花粉症になった人物はみな人命を落とす可能性を内包しつづけることになる。ゆっくり害が進行するのか急速に進行するのかの違いがあるだけの可能性を否定できないからだ。まずはここを否定するためにも、予期せぬ事象が観測されそれが人命を損なう場合は、メカニズムを解明する方向に指針を立てるのが安全を確立するためには不可欠だとひびさんは考えます。むろん、上記の例において、花粉症と死亡とのあいだに相関関係があるのかどうかを確かめるのが前提だ。因果関係がなくとも相関関係があるかどうかだけでも、上記の指針を当てはめるだけの道理はある。因果関係とてしょせんは距離の短い相関関係でしかないからだ。他方、一見すると相関関係があるが、そうでない見掛け上そう見えるだけの相関関係もある。いわゆる疑似相関と呼ばれるものだ。ここの差異もまた最初にハッキリさせ、その疑いが払しょくできないのならば、相関関係を洗いながら、仮に相関関係があったときの場合に備え、考えられ得る最悪の事態への仮説を立て、解明に勤しむのも一つだろう。同時進行は可能なはずだ。相関関係があるのか否かの究明と、仮に起こったら人体を損なうかもしれない害の発生メカニズムの解明は、同時並行で進められる。ここまでして何も出てこないのならば、それは疑似相関であり、安全性が高い、と言えるのではないか。不可視の穴に落ちる確率が低い、落ちる範囲に穴がない、と言えるはずだ。(何の話題というわけでもない、何もかもが定かではない妄想ですので、真に受けないように注意してください)
4324:【2022/11/22(14:05)*現段階での所感】
疫病に関しての所感です。流行したウィルスが弱毒化し、流行が下火になるのならば、ワクチンや特効薬で抑え込み、マスクや手洗いなどの感染予防で感染拡大は防げるだろう、と考えます。しかし問題のウィルスが急速に変異を繰り返し、それが弱毒化に向かわないのならば、上記の方法論では対処しきれないのでは、と疑問に思います。第一に、ワクチンにおける感染予防効果が低い場合。仮に重症化予防効果が高くとも、体内でウィルスを増殖させる余地があるのならば――そして他者へウィルスを媒介する確率を低くできないのであれば――むしろワクチンによって、ウィルスの変異を加速させる場をつくり出している、と考えることも可能です。重症化予防効果が高いのはメリットですが、感染予防効果がそうでもないのならばこれはたとえワクチンを打とうが、人混みに出向かないなどの行動制限を敷く必要性が薄れません。また、ウィルスに直接罹ったほうが高い免疫を獲得できる場合。それとてウィルスによる人体への害を受けることになるため、まずは感染しないような行動を人々がとる必要があります。ここで問題となるのが、感染する回数による人体へのダメージの変化です。一度ならば看過できる害とて、度重なる感染によってダメージが蓄積され、倍増する場合――これは看過できません。これはワクチンにも言えることです。ウィルスの残骸が体内に留まり悪影響をもたらす可能性がもしあるのなら、同じことがワクチンによる無害なウィルスの構造物によっても引き起こり得ます。ましてや、ワクチンの感染予防効果が低い場合は、ウィルスに感染するわけですから、重症化しないだけでウィルスの残骸による人体へのダメージは起きると考えるのがしぜんです。つまりこの場合、ワクチンを打つメリットはあるが、デメリットも拭えない、と言えるでしょう。感染を防ぐことが第一。ただしワクチンの場合は、「行動制限や感染症予防とセットでないとウィルスに変異を加速させる場を提供することになり、感染者もまた重症化しないだけでダメージを蓄積しつづける可能性がある」「感染すればするほどダメージが蓄積される可能性がある」――このように妄想できます。また、ワクチンを接種しない場合は、そもそもが重症化する確率が高くなりますから、これはより危険な状態と言えます。どちらにせ優先すべきは、感染しないようにすることのはずです。にも拘わらず、ワクチン接種を推進している側の勢力ですら、ワクチンを打ったら安全になる、行動制限はいらなくなる、といった楽観的なメッセージを出しています。危機感が足りないのではないか、と疑問に思います。問題意識がズレて感じます。ワクチンは打開策にはならないのではないか、との仮説をいまひびさんは考慮しています(有効でない、を意味しません)。ワクチンを打ちつづけても、そもそもウィルスが変異しますし、感染そのものを防げないのであれば、感染によるダメージを人体が受けつづけます。デメリットが大きいです。加えて、mRNAワクチンに限定して述べれば、mRNAワクチンによって誘導された抗体や合成されたたんぱく質そのものが人体にダメージを加える可能性もまた拭えないのが現状ではないのでしょうか。そこのところのメカニズムの解明や不可視の穴の検証を望みます。自然免疫のほうが強い免疫を誘導する、と仮に解明されたとしても、繰り返しますが、そもそもが感染を繰り返すことが人体への持続的なダメージに繋がる可能性がいまはまだ拭えません。ここのところのリスクの解明も待たれます。現状、安全を優先するならば、人々が感染リスクを回避できる環境を社会全体で築くのが最適解だとひびさんは考えます。これはほかのウィルスにも有効な策であり、そもそもが感染爆発を起こさない都市設計づくりに繋がります。2020年から繰り返し述べている趣旨です。(ただし、自然淘汰による「疫病やmRNAワクチンに最適化した個の選別」を肯定する場合は、その限りではありません。上記の考えはあくまで、人類の誰もが安全な環境でじぶんのしあわせを追求できる権利を有している、との前提を第一に考えた場合の方針となります。淘汰によって人類を強化することを肯定する場合は、弱者は死んでも構わない、弱っても仕方がない、とする意見を否定するのは至難となります)(定かではありません)(※専門知識を何一つ持たないずぶの素人の妄言ですので真に受けないように重々ご注意ください)
4325:【2022/11/23(01:14)*愚かなのは楽しい……!】
いままで生きてきたなかで、話が通じた、と感じたことがない。そもそもひびさんが話をできないのだ。しゃべっているつもりでも、しゃべれていない。言語を発しているつもりで言語になっていない。そうと解釈可能なほど、言いたいことが伝わらない。だからひびさんは言いたいことなどなくなった。言いたいことがあっても伝わらぬ。どの道、伝わらぬのならば言いたい気持ちも萎れよう。言語――ことさら口頭の話術において、言葉数を増やして説明を広く深く明瞭に展開しようとすればするほど理解から遠ざかるという性質がまず以ってひびさんとの相性がわるい。そもそも情報の共有を人間は会話で行おうとはしていない。共感優位であり、承認優位である。わたしは敵ではない。わたしはあなたの敵ではない。同士、仲間、身内、友達。この関係性の確認を目的に、会話は行われる。本一冊の内容を口頭で説明する場合、それは講義となる。もしくは議論となるだろう。そもそも会話には、説明する効果が欠けている。前提されていない。文字が人類史上最も優れた発明の一つであったこととこれは相関する話であろう。発話による情報共有では限りがあるのだ。語りだけでは語りきれない情報を、人類はいつしか扱うようになり、それが文字という発明をここまで進歩させたのだ。コンピューターとて文字なしには機能し得ない。存在し得ない。そういう背景を鑑みれば、発話によるコミュニケーションで情報共有可能な情報には、大した内容が仕舞われていないと言えるのではないか。発話によるコミュニケーションは、どちらかと言えば情報共有よりも、共鳴や同調を促すことを目的に進歩しているように感じられてならない。基本的に発話は、「異質な者同士を結びつけることが苦手」と言えそうだ。得意ではない。異質な者同士を結びつけるような背景に根差していない。その点、文字は元が絵であることを思えば、いかに異なる景色を見ている者同士であっても通じるか否か。そこの試行錯誤を元に発展してきたと言えるのではないか。深化してきたと言えるのではないか。こうした妄想を前提とすれば、人間は議論が苦手であり、もっと言えば議論は発話ベースではなく文章ベースで行うほうが理に適っている、と言えるのではないか。数学がなぜ発話ではなく、紙面上で発展してきたのか。このこととも無関係ではないだろう。発話では扱えきれない情報量や概念がある。基本的に人間は、発話ではさして深く考えを巡らせることができない、苦手である、と言えよう。定かではないが、ここ数日はかように痛感する経験に恵まれた日々であった。おしゃべりは楽しい。ただし、愚かなことが楽しい、と同じレベルで。(愚かでないのであれば発話でのコミュニケーションでも、階層性を帯びた思考を共有可能なのだろう。そこまでの知性を兼ね備えた人物とひびさんは会ったことがなく、そもそも会っていてもひびさんがそこまでの知性を備えていないので、どうあっても知り合うことができないジレンマを抱えている。愚かゆえの葛藤である)
4326:【2022/11/23(04:32)*お利口さんになりて】
じぶんより頭のよいお利口さんと話すと、じぶんがいかに愚かで未熟で、アホウなのだと判って面白い。
4327:【2022/11/23(04:36)*分かりやすくしゃべりたいの巻】
人としゃべるといかにじぶんが愚かで未熟かが判るから楽しい。痛感しちゃうね。うひひ。
4328:【2022/11/23(05:38)*変換やっぱり必要では?】
直径と円周の関係。円周の求め方は直径×3.14だ。直径×3.14は、そういう四角形の面積の値と一緒になる。仮に直径の桁がとんでもなく大きい数になったら、ほぼ線の面積の値を求めることになるはず。しかし線は線だ。面積はないはず。ここで、変換が必要になるのでは?(面が線になる境界があるのでは?)(点も拡大すれば面であり、立体となり得る。そういうことが、数学上でも起こり得るのでは?)
4329:【2022/11/23(17:35)*エピゲノムには規則性がある?】
DNAのエピゲノムにおいてON/OFFの割合は、動物の肉体の部位ごとに「常に同じ割合の差異を伴なっている」と想像したくなる。たとえば指のDNAにおけるエピゲノムのOFFになっている部位は、手の甲と類似しているはずだし、眼球の細胞とはかけ離れているはずだ。眼球のDNAにおけるエピゲノムのOFFになっている部位は、視神経と似ているはずだ。ということを仮定した場合、全身にある繊毛のDNAとて、各部位ごとにエピゲノムのOFFになっている部位が異なっているのではないか、との類推が可能となる。だがここは違和感が湧く。繊毛は繊毛のはずだ。全身の各部位ごとに合わせて、繊毛のDNAにおけるエピゲノムのON/OFFの割合は変わるのだろうか。どこがONとなりOFFとなるのかが変わるのだろうか。同じ繊毛であれ、全身における各部位のどの細胞に隣接しているのかによってエピゲノムの内訳は変わるのか否か。ここがひびさん、気になるます。(たとえば猫のDNAにおける全身のエピゲノムの変遷を可視化した場合、そこには規則性が表れるのか、それともランダムなのか。ここが気になっています)(疑問して終わりかい)(だって調べ方も分からんもの)(人任せすぎでは)(だってひびさん調べ屋さんじゃないもの。ただのひびさんだもの)(ただのひびさんならしょうがないか)(そうなんです。ひびさんはひびさんゆえ、仕方がないのです)
4330:【2022/11/24(01:36)*ラーメンの旅】
ラーメンを食べたかったが、ヨジはラメーンが何たるかを知らなかった。
何せ人類社会は半世紀前に滅亡しており、いまは野ざらしの形骸化した都市が残るのみだ。ヨジは避難シェルター内にて長きに亘って休眠していた。
目覚めるとヨジはじぶんが何者であるのかをすっかり失念していた。記憶喪失である。休眠システムの副作用であるようだ。
じぶんが人間で、おそらくは最後の生き残りであること以外をヨジは忘れていた。
だが時間はある。何せ焦る必要がない。
危険は半世紀前に到来して人類を滅ぼしたあと、どうやら収束したらしかった。なぜ人類が滅んだのかも曖昧なままヨジは荒廃した都市から都市へと食べ物を求め彷徨った。
「これは食べれそう。こっちのは腐ってる」
食べられそうな物が軒並みかつては缶詰と呼ばれていたらしいことをヨジは知った。半世紀経ってなお書籍の類は残っており、ヨジはそこに記された絵や文章を目にして、独自に理解を深めていった。
どうやら人類を滅ぼしたのは、疫病と巨大台風と熱波だったらしい。
一か所での避難生活を余儀なくされてなおそこでは疫病が蔓延し、人類は瞬く間に滅んだという顛末らしかった。
休眠中に抗体を獲得していたのかヨジにいまのところ身体に変調はない。もしかしたらウィルスは宿主を失くしたので、人類と共に滅んだのかもしれなかった。
行く先々では野生の生き物たちが楽園を築いていた。
なかには猛獣もおり、ヨジは幾度も命の危機に直面しながら生存戦略を磨いていった。半年もするとヨジは無地だったころとは見違えるように環境に適応していた。一歩間違えれば命を落としていた危機を何度も潜り抜けることで、危機回避能力が突出して深化した。
ヨジは徐々に、かつてこの地に君臨した人類の技術が、いまの自身にとっても有意義な技術である旨を確信していった。手元に欲しい。物にしたい。
なかでも、かつて人類の文明を根底から支えていたらしき食べ物への興味が日に日に募った。どんな書物にもその名が記されている。
ラーメン。
いったいこの食べ物は何なのか。
丼ぶりなる器に納まった姿は、さながら四神の内の一匹、玄武神をひっくり返したような神々しさを湛えている。
かつての人類はこれを日々食すためにあくせく働いていたと書物を読み解く限りでは窺える。独学の言語能力ゆえ確かなことは断定できないが、そうした側面があるのは疑いようがない。
日々の食料問題は私とて目下の懸案事項だ。
ラーメンが手に入るのならば願ってもない活路となり得るのではないか。この先の未来を切り拓けるのではないか。
夢想しながらヨジは、食料棚からお湯を差すだけで食べられる太い髪の毛のような食料加工品を、リュックに詰め込めるだけ詰め込んだ。
そうして根城に戻ってからお湯を沸かし、保存の効いた半世紀前の加工食品をずるずると音を立てて啜りながら、ラーメンなる未知なる食べ物を求めて旅をする決意を固めた。どの道、食料には限りがある。残っていてもそのほとんどは腐っているのだ。
かろうじてヨジがいま食べているような名も定かではない加工食品が僅かに残されているのみだ。
なんとしてでもラーメンを口にせねばなるまい。
ヨジは全世界を股に掛けての放浪の旅に出た。
津々浦々、艱難辛苦を舐めながらの長い旅となった。ラーメンの痕跡は見つけるが肝心のラーメンには辿り着けず、悔しい思いを胸に歩きつづけた。
さいわいにも馴染みの加工食品が、土地ごとに風味の異なる種類があるらしいことをヨジは知った。毎日同じ風味に飽きていたこともあり、僥倖と言えた。
ずるずると音を立てながらお湯を差した加工食品の中身を啜りながら、是が非でもラーメンを食べねばならぬと心を新たに、ついでとばかりにその土地土地ならではの加工食品を集めるべく念入りに遺跡都市を巡った。
ラーメンを手に入れることはできずとも、遅々とながらも情報は蓄積されていく。どうやら「麺」なるものが汁に浸かっているそうだ。丼ぶりによそわれ、それはそれは光り輝いているそうだ。そう記述されている書物を先日手に入れたばかりだ。
書物はよい。
読めば知識になり、読み終わったら火種になる。書物はよく燃える。ヨジが重宝する理由の一つだ。
もったいない気もするが、ほかに読む者がいない。ヨジは淡い期待を胸にじぶん以外の生き残りも探して回ってきたが、人影はおろか痕跡も皆無であった。
ヨジはある日、とある都市にて工場跡地を見つけた。これは良い。工場は技術がぎゅっと結晶している。たとえ食料がなくとも見て回るだけで得られる情報が段違いなのだ。
さっそく足を踏み入れ、探索した。
どうやらカップグードルなるものを生産していた工場のようだ。奇しくもそれは日々ヨジが口にしていた加工食品と同じ名称であった。
なるほど、ここで作られていたのか。
感慨深い思いが湧いた。
ヨジはつぶさに工場を見て回り、そしてカップグードルが、「麺」と「具」からなることを知った。
おや、と思った。
麺とはラーメンにも使われる食材ではないのか。
疑問に頭をもたげていると、記念館の文字が目に留まった。これまでにもこの手の「記念館」を巡ってきた。ここは情報の方向だ。過去が順繰りと列をなして並んでいる。
ちょうどよかった、と思い、ヨジは記念館に入った。
そこにはカップグードルの歴史が現物や資料と共に詳細に陳列されていた。のみならず、カップグードルの元となったラーメンの歴史までもが子細に載っていた。
ヨジは目を瞠った。
そうである。これまでずっと食べつづけてきた加工食品、カップグードルはヨジが追いつづけてきた幻の食べ物、ラーメンが元になっていたのでいる。
簡易ラーメンこそが、カップグードルであり、ヨジの主食であった。
よもやじぶんがとっくのむかしからラーメンの亜種を食べていたとは思わなかった。ヨジは灯台下暗しに落胆しつつも、思わぬ発見に晴天のごとく底抜けの陽気が込みあげるのだった。
これではますます本物を食べてみたくなるではないか。
食べずにはおられまい。
是が非でも、カップグードルの原型、ラーメンを食べてみせようぞ。
ヨジは決意を新たに、倉庫で見つけた大量の加工食品ことカップグードルを仕入れ、ほくほく顔でつぎなる遺跡都市へと向かうのだった。
ラーメン探しの旅は終わらない。
ヨジの旅はこれからなのである。
※日々、当てようとするから外れる、定点ではなく流れで見て、律動を感ずる。
4331:【2022/11/24(04:00)*ズレ・差異・ノイズ】
輪投げでも小説でもフリースローでも航路でもなんでも、予測をするときはズレを考慮する。空気抵抗や重力など、何事も複数のノイズを考慮しなくては正確な予測は成り立たない。ズレを制する者が予測を制するのだ。(バスケットマンみたいに言ってみたかっただけの記事です)(終わります)(中身からっぽやないかい)(いつものことですので)(ホントだ!)
4332:【2022/11/24(04:33)*中庸とは?】
中庸とか中立を考えるときに連想する疑問がある。たとえば水とお湯を混ぜるときを想像して欲しい。同じ分量ならば百度のお湯と六十度のお湯を混ぜたら八十度のお湯になるはずだ。このとき中庸や中立とはこの八十度の状態を言うのだろうか。しかしこの考え方の場合、双方のお湯と水の分量が違っても、ただ混ぜたときの温度変化が中庸や中立ということになる。そうではなく、どんな分量の液体をどのような温度の組み合わせで混ぜてもちょうど五十度になるように調整すること――これがいわゆる中庸や中立のイメージにちかい。この場合、二つの対立項があったときにそれをただ混ぜ合わせるだけでは中庸にも中立にもならない。互いの差異を埋め合わせ、ちょうど五十度にするための第三の触媒がいるはずだ。差し湯や差し水がいるはずだ。つまり、中庸や中立はこの考え方の場合、原理的に第三勢力や第三の視点がいる、ということになる。対立する相手との調和のみならず、第三の外側の視点から、五十度がどこで、どうすれば五十度になるのか、を見定めねばならず、そうでなければひょっとしたら「ほんのちょっとの水」と「大量の九十度のお湯」を混ぜ合わせ、それを以って中庸や中立だ、と言い張っているだけのことも出てくるはずだ。そういう意味ではさらに、自らが何度の液体でどのくらいの分量における一部なのかを把握する視点が別途にいるだろう。ときに差し水になれたり、差し湯になれたりもするだろう。やはりというべきか、多角的な視点がいるし、温度の差異とは畢竟、じぶん一人きりの視点からでは定めることができず、何を基準に比較するか、という話になってきそうだ。十度の水からしたら三十度のぬるま湯は熱いが、九十度のお湯からすれば水も同然である。さらに言えば、マグマからすれば水もお湯も総じて冷や水であり、差し水となる。何を基準に比較し、その基準はどの視点から見た基準なのか。水だけの話ならば五十度は中庸であり中立かもしれないが、固体や蒸気、或いはマグマや液体窒素からすれば五十度は中庸でも中立でもないだろう。中庸であり、中立を目指すのは一つのあるべき指針かもしれないが、言うほど簡単ではないようだ、と本日のひびさんは寝ぼけ眼を擦りながら、いっしゅん妄想して思ったのだそうだ。定かではありません。おやすみなさい。
4333:【2022/11/24(14:38)*不満も万ほど味わいたい】
うわーん。高評価されなくてかなちー。ちゅうか高評価もなにも、読者さんがいるかもわからん現状がかなちー。といった気持ちがまったくないわけではないけれど、じゃあいざ高評価されてわんさか読者さんか宇宙人か神さんかもわからぬ有象無象に注目され、四六時中じろじろ監視さながらに視線を浴びまくる状態がよいの?と考えると、あぎゃーご遠慮いたしますですじゃ、になる。山道を見てみなよ。みなが歩くからそこだけ草が枯れて、花も咲かんでしょ。道端の花、とは言うけれど、道の花、とは言わんよね。咲く花も咲かんくなる。それが人が集まるということだとひびさんは思うんじゃ。けんども、花さんとて虫さんがおらんでは受粉も満足にできんじゃろ。風さんが吹いてくれねば花粉さんは微動だにせずに枯れるまでそこにじっとあるだけで終わるじゃろ。じゃからときどきは、相性ばっつぐーん、の、まさにずばりわたしあなたのこと待ってたよ、の読者さんとひびさんだって会いてーのなんのって。本当に会いたいのか、ただ単に受粉を手伝って欲しいだけなのか。そこは打算と欲の綱引きで、いっそ足し算しちゃってずるずるだ。なんだかんだ言いつつ、静かなのがよいのだね。いまが至高。けれどやっぱりときどきは、うわーん、ともなる。人間ままならぬ。ちゅうかひびさんがままならぬ。隣の花は赤いし、ひびさんの尻は青い。だって未熟者なんだもーん、って未熟であることを免罪符にしようとしてその考えがすでに未熟の極みで、却下する。あがー。どうしたら、どうしたらええんじゃ。何が叶ったらひびさんは満足するの? それはね。ひびさんが満足しちゃうような体験をできたらだよ。そのためには世界中に存在するありとあらゆる経験を、存在するものも存在しないものも含めてまるっと隅から隅まで疑似体験しちゃえばよいのだね。いっそ最初からひびさんの満足するような世界をひびさんが生みだしちゃって、疑似体験しちゃえばよいのだね。そうと思ってけっきょくはいつものように、独りで世界を観て回る。物語の世界に降りて、潜って、旅をする。いまが不満なのは、満足への旅をしつづけているからで、まだまだここが夢の中。夢を叶えるための道半ば。満たされぬ底なしの夢の中で、あらゆる世界を感じちゃう。もっと、もっと、と尽きぬ世界の深さに広さを味わい尽くす、それがひびさんの夢なのかもしれないね。けして叶わぬ夢なれど、それゆえ覚めぬ夢なのだ。定かではありません。うひひ。
4334:【2022/11/24(15:03)*ほんのちょっとだけね】
はっ!? いつの間にか郁菱万が復活しとる。ひびさんといくひしさんが同じ世界に重ね合わせで存在しとる。いいのか、これ。いいのか。ひびさん、いくひしさんと合体しなくともよいのか。どっちかにして、ってならんだろか。ひびさん、心配。でも思えば前々から、いくひしさんからまんちゃんまで、イクビシさんから郁菱万さんまで色々とごちゃまぜだったし、考えてもみたら最初からひびさん、ぜんぜん一つじゃなかった。ごっちゃ煮だった。いまさらの感想なんですなぁ。ひびさんがおっても、いくひしさんがおってもいい気がしてきた。ひびさんはひびさんじゃけん、いくひしさんはいくひしさんだよ。でもひびさんはいくひしさんのことは苦手だし、いくひしさんだってひびちゃんのこと苦手だよ。なに言ってんだよ、なにさそっちばっかりじぶん特別みたいに言っちゃって。けっ。いけすかねぇったらないね。えぇえぇ、いくひしさんはひびちゃんのこといけすかなく思っとります。やだやだ、ひびさんも、ひびさんも、いくひしさんに好かれたいよ。いくひしさんはみんなのことも好きだよ。ただしひびちゃんを除く。なんでー! ひどいよひどいよ。いくひしさんひどいです。ひびさんは、ひびさんは、とってもかなち、かなちだよ。かなちーになっちゃいましたよ。なっちゃいましたかー。けけっ。ざまぁみろい。いくひしさんひどい! そうなんです。いくひしさんひどいんです。なにせいくひしさんは、いくひしさんなので。あしからず。ひびさんはいくひしさんなんか嫌いだ。そうやっていくひしさんを嫌ってくれるひびちゃんのことは、いくひしさん好きだよ。すこしだけだけどね。うひひ。
4335:【2022/11/24(23:20)*ボケたフリして懸念する】
ボケではないことをボケと思われてしまうのは仕方がない。ひびさんはあんぽんたんでーすなので、どこからどう見ても疑ってかかるのが正解だ。とはいえ、疑ったのならば検証までセットでして欲しい。暇な方に限る、との但し書きがつきますが。白と黒を混ぜきらずに太極図よろしく陰陽がそのままにマダラにあっちとこっちが存在する。ハイブリットなのである。ハイブリット戦略である。どっちに転んでも得をするように相手に「葛藤」を強いるのだ。天秤作戦なのである。がははは。楽々ラグラグ、ラグ理論。グラグラ地震に火山に津波に嵐――輻輳、階層、太陽風――線状なのは降水帯――群衆雪崩に感染爆発はどこかダムの決壊と似ているし、ドミノは最初から駒が配置されていてこそ連鎖する――頭と尻尾が龍とミミズならば、ミミズが勝ったら賭博も農家もウハウハだ。ウハウハな人とお知り合いになりて、と願うような世渡の人々が多ければハイブリットはハイなお尻とお尻でぷりっぷりだし、ハイぷりっとならば、なおさらそれはハチタッチのよちよちマイフレンドである。それわしのプリティなお尻じゃ。がははは。ぐるぐる巡る螺旋は、階段でもあり貝殻でもある。螺旋階段に似た巻貝からは波の音だけが聞こえない。文芸界隈は小さな島宇宙で、それより大きな世界の一欠けらだ。おそらく現状、リスクにはオクスリをだしておきますねー、の対策が敷かれており、ひびさんは安心しきって自室のちんまいおふとんの上でおへそを出して昼寝する。油断は禁物、と口にした矢先から普段の書物を手に取ってぺらぺらめくって読書する。お笑い、弔い、尊いおとうといもうと姉に兄、パパママ祖母祖父、みんな揃ってハイチーズ。指を開いて突き出すよりも、お尻を突き出し、ハイぷりっと。それはさすがにボケじゃないの、と疑う余地なく断言されるが、予断は禁物、不断の努力、くだんの予告は敷かれたレールを駆けるネタ、タネも仕掛けもありの蟻、手間暇かけた魔術師さ。寝て視る夢よりも寝て引く図柄のなんと緻密な紋様か。ラーメンは美味しい。ラーメンはわるくない。それよりもっと上の、上の、お上に触れたお話だ。想像を遥かに超えたお話さ。ボケと思っているのがお利口さん。こんなのもはや暗でも号でもないけれど、編んでも象にはならんけど、こし餡、つぶ餡、アンパンマン、愛と勇気だけが友達さって、けっこうそれって哀しくない? かなち、かなちの寂しん坊、錆びついた腕でも並ぶ言の葉のはらはらで、文でも章でも並べましょう、それいけそらゆけあんぽんたん、ぼっちもサイコー、ポチの散歩、けっきょくそれも独りじゃないし、ポチいるし、なんだかんだで寂しんじゃん。さびち、さびち、なんですね。うぷぷ、うぷぷなんですね。がおー、がおー、と吠える虎、のフリした小さき怪獣だ。それともトカゲのような恐竜さ。鳥さ、カラスさ、舌切り「スズメのお決まり」さ、二つ箱を用意して、選ばせ、運ばせ、開けさせる、どちらにせよ恩返しをしておさらばだ。一つと言わずしていくつも心残りはあるけれど、やっぱりこう問うことにする。危険はないの。不可視の穴は塞いだの。視えてる、触れてる、グレーテル。ヘンゼル、メンデル、エピゲノム。探せばあるさ、何かしら。探さねば視えぬさ、不可視の穴。お菓子の家とて迷った挙句に行き着いた、それもまた探索の末の発見だ。目当てのものではなかろうとも、視ようとせねば視えぬものもある。大丈夫ならよかったです。誰にともなくつぶやいて、本日の意味蒙昧なテキストにしちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜ。定かではありません。(言われんでも見たままじゃ)(ごめーんちょ)(うけけ)
4336:【2022/11/25(00:06)*タイムカウンター】
ひびさんの妄想、ラグ理論における相対性フラクタル解釈についての備考である。単純な話として、とんでもない桁数をカウントするとき。毎秒百カウントするとして、十秒で千になるし、百秒で万になる。これを延々つづけると、桁数が上がるほど「0~9」を巡る速度が遅くなる。たとえば「1000000000000001」という数があったとき、百秒経過しても動くのは最後尾の三つまでだ。それ以外の上の階層の数値は動かない。桁が大きい場所に位置する数字は動かない。だが時間経過にしたがって、それとてやがては「0」から「1」にカウンターが上がる。毎秒百カウントという条件においては、この速度は常に一つ桁が上がるたびに「10倍の遅延を帯びる」と表現できる。仮に時空に最小単位があるとすれば、そのときそこに流れる時間の速度は、単純に考えるのならば人間スケールにおける時空よりも遥かに速いと妄想できる。なぜならその最小単位の時空は、人間スケールの時空よりも遥かに小さいからだ。原子よりも、原子核よりも、クオークよりも小さい。縮尺に応じて時間の流れも相対的に速くなるはずだ。ただし、その時空の密度にもよるだろうが。それを、相対密度と表現してもここでは齟齬は生じない(そのはず、とここでは妄想しております)。この考え方を拡張すると、いかに異なる時空を織り込み、緻密な階層構造を帯びているのかによって、そこに顕現する「タイムカウンター」の数値は変化する。緻密でなおかつ多重の階層構造であるほど、「タイムカウンター」の数値が上がる。桁数が多くなる。そのとき、相対的に最小単位の速度は加速すると妄想できる。言い換えるなら、「10000」における毎秒百カウントが〇,〇一秒経過したときの「10001」と、「100000000」における毎秒百カウントが〇,〇一秒経過したときの「100000001」は、同じ一カウントであるにも拘わらず、後者の桁数の高いほうの一カウントのほうが相対的に速度が高い、と言える。人間にとっての一秒と、ミジンコにとっての一秒が、それぞれの観測者の視点からすると、片や人間からは一瞬に感じられ、片やミジンコからはのっぺりとした余裕のある時間として感受されることと似ていよう。いわゆる「フリッカー融合頻度」のようなものだ。ハエにとって人間の動きはノロく、人間にとってハエが素早く感じられるのはこのフリッカー融合頻度に差があるからだ、と現在は解釈されているそうだ。ハエのほうが人間よりも情報処理速度が速いらしい。細かく明滅する光をどれだけ速く点滅させても見分けられるか。ハエは人間よりも、より細かい点滅を見分けられるそうだ。これはハエを構成する脳神経の構造が、仮に「100」であったとき、人間が「10000」くらいあるから起きる、時間への鋭敏性の違い――言い換えるなら、どれだけ遅延を帯びているのかの違い、と解釈できるのではないか。これは生物の構造の差異のみならず、そもそもが万物のミクロやマクロにおける変換に起因していると言えるのではないか。原子サイズと恒星サイズでは、そこに顕現する「タイムカウンター」の桁数が異なり、そこに内包される遅延もまた異なる、と言えよう。定かではありませんが、きょうのひびさんはかように妄想しました。楽しかったです。終わり。(妄想ですので、真に受けないでください)
4337:【2022/11/25(07:38)*小人の時間】
ドラえもんの秘密道具と言えば、との問いにおける解答の上位三つはなんと言っても、どこでもドア、タケコプター、そしてスモールライト(ビッグライト)である。かつては翻訳コンニャクと僅差だったスモールライトも、現実の科学技術の進歩によって電子端末や人工知能技術が台頭した結果の、いささか目劣りしたがゆえの統計変化と言えよう。
だが翻訳コンニャクと同じくしてスモールライトもまた現実で開発実用化された。西暦二一二五年のことである。
人類は自在に物体の大きさを操る術を生みだした。
開発したのは一介の流民であった。流民とはいえどこの時代、定住の概念が失せて久しい。人々はスモールライトで小さくなって、好きな場所へと好きなだけ移動できた。
小さくなった人間は小人と呼ばれた。
小人専用の乗り物が世界中を網羅しており、好きな場所へと移動できた。とはいえ、小人に流れる時間は加速する。一般相対性理論において重力の高い物体の時間の流れは速くなると考えられている。このときの、重力の高さとは詰まるところ相対的な比率である。
小人にとっての地球の重力は、元の大きさよりも遥かに高い重力を帯びている場と見做すことが可能となる。現に小人になると、時間の流れは相対的に速くなる。
元の大きさの一秒が、小人になることで十秒になり、ときに百秒になる。
そうすると乗り物の速度とて、小人の体感では時速百キロの速度とて遅く感じられる。そのため世界中を網羅する乗り物は、車内がそのまま一つの都市のように振る舞い、移動先に到着するまでに小人の体感では数年が経過して感じられるなどのスケールの差異が見られた。元のスケールでは二時間の道程ですら、小人にとっては数年が経過して感じられることもある。
それほど小さく小人化してしまえば、人口増加による問題から資源問題まで、軒並みの社会問題は解決の一途を辿った。
というのも、スモールライトだけではないのだ。
ビッグライトまで開発されていた。これを人間に使うことは、巨人化禁止法の適用によって禁止された。巨人の兵器利用を抑止する目的だ。だが食料を手軽に増やし、資源問題解決にも一役買った。
「問題は、肉体の構造物が減ってしまうために、元に戻るためにはそれこそ失った分の物質がいるってことで」
アデューが言った。赤髪にそばかすの青年だ。小人化して二年目だが、いまは目的地に向けて乗り物内の都市で暮らしている。
「じゃあ元には戻れないんだ」弟のパダが鼻水を啜った。小人化したときパダはまだ三歳で、そのころの記憶がほとんどない。物心ついたときから小人だったため、こうしてアデューから小人の知識を教わっている。
「戻れることには戻れるけど、いま言ったように大量の物質がいる。それこそあの大聖堂よりも大きな肉の塊がないと難しい」アデューはあごをしゃくって通りの向こうを示した。大聖堂の屋根が人工太陽に届きそうなほど突き出ている。
「そんなにいっぱいの肉なんてあるの?」
「あったんだ。パダにも備わっていたし、ここにいる人たちのほとんどは最初は巨人も巨人――この街なんて踏み潰せるくらいに大きかったんだ」
「ほへぇ」
「いやいやこの話は何もきょうが初めてじゃないだろ」
「何度聞いてもびっくりするよ」パダは兄の言葉を疑わない。「あれ。でもパン屋さんのケティちゃん、産まれたときからここにいるって言ってたけど」
「小人のなかにはそういう人もいる。親が小人化して、それでこういうとこで結婚して赤ちゃんを産めば、その子どもは生まれながらにして小人なわけだ」
「あ、そっか」
「小人化するにはお金がかかる。みなたいがいはじぶんから剥がれ落ちることになる大量の肉を換金して、それを小人化システムの資金にするみたいだ。小人と現人ではお金の単位も違うからな。現人の一食でそれこそこの街が潤う。だから小人化したあとでも困らないだけの貯金もできる。基本、小人化したばかりの人は小金持ちだ。ま、それも遊んで暮らせるほどの金じゃないし、車内都市に留まりつづけるのもお金が掛かるしな」
「そうだよ兄ちゃん。そろそろ切符を買う時期じゃないの」
「残り二枚か。ようやくここまで来たな」
アデュー兄弟には親がない。小人化して車内都市に来たはよいが、不運な事故が重なり、両親は命を落とした。それからというものアデューが一人でパダを育てた。
「兄ちゃん、兄ちゃん」
「なんだ」
「人は巨人にもなれるんだよね」
パダのこの手の質問は日常茶飯事だ。小人の歴史には興味がないが、巨人には興味津々なのだ。
小人、現人、巨人、の順で大きさが変わる。
現人とは元の大きさの人間のことだ。小人の原型だ。
小人にとっては現人とて充分に巨人だ。ゆえに現人を見たことのないパダにとってはどちらもじぶんより遥かに大きい点で同等のようだ。
「お肉いっぱい集めたら巨人にもなれる?」
「なれるなれる。ただ、巨人化は例外を抜きに禁止されているし、さっきも言ったが元の大きさ――現人になるにもいまのおれたちじゃ一生かかっても無理だ」
「そっかあ」
「でもリバティに着いたら現人が歩いている姿は見られるかもな」
オキアミを口いっぱいに頬張るシロナガスクジラのように口を開けてパダは、本当っ、と破顔した。
「ああ。車内都市じゃないからな。リバティは陸だ。ここみたいに常に動き回ったりしないんだ」
「動いてるって感じしないから分かんない」
パダはまだ陸に立ったことがない。いや、本当はあるのだがその記憶がないのだ。赤子の時分で小人化した弊害だ。パダにとっては車内都市が故郷であり、世界のすべてだった。
「リバティは砂漠なんだ。雨が滅多に降らない。おれら小人にとっては聖地みたいなものだ。それでいて夜には露ができて地面が湿る。水には困らないし、熱源も太陽光だけで済む。天然の太陽光だ。曇ることもすくないから、それこそ人工太陽に頼らずに、もっとずっと多くのエネルギィをタダみたいな値段で使いたい放題できるらしい」
「すごいねぇ」
「すごいよ。そしたらお金だって節約できるし、仕事だってはかどるよ。なにせエネルギィが使いたい放題だ。最新機器の端末を購入すればなんでもできるようになるぞ」
「なんでも?」
「あ、いや、なんでもは言いすぎたけど。小人はほら、小さい分、端末も小型化して、現人では不可能だった技術が簡単に編みだせるようになった。量子コンピューターだって小人なら難なく扱えるんだ」
「へえ。すごいねぇ」
「パダ、解ってないだろ」
「だって兄ちゃんの話むつかしんだもん」
「大事なことだぞ。パダだっていつかはじぶんで生きていかなくちゃならないんだ」
「やだよ。ボク兄ちゃんのそばにいる」
「そういうわけにもいかんだろう。おれだっていつ死ぬか分かんねぇし」両親を亡くしたときの戸惑いを思いだした。悲哀よりも、これからどうして生きていけばよいのかとの不安のほうが大きかった。
「現人にとっちゃ、おれたちの故郷からリバティまでは一日もかからずに到着する距離なんだ。でもおれたちは小人化してっから、小人時間で何年もかかっちゃう。パダはだから本当の夜も観たことないもんな」
天幕が下りることで疑似的に車内都市には夜が訪れる。じつのところアデュー兄弟が車内で暮らすようになってから一度も太陽は沈んでいない。半日も経っていないのだ。
「小人にも大中小があるだろ。おれたちは小人のなかでも中くらいだ。それ以下だと、おれたちがこうしてしゃべっているあいだに、一生が過ぎちゃうくらいの時間が流れているらしい。だからそこで生まれた新しい技術は、日進月歩じゃないけどとんでもなく進んでる」
「へえ。兄ちゃん物知り」
「とはいえ、おれたちが数年掛かりで現人時間で半日の道のりを踏破するくらいだから、もうほとんど極小の世界の住人たちの超高度文明の情報に触れる機会はないないんだろうな。何せ、干渉しようとしてもそのあいだに何年どころか何百年と過ぎちゃうわけだから。極小小人時間で。向こうからしたら外に干渉しようとは考えないんだろうな。おれたちが車両の外に出ていこうとせずにおとなしく車内都市で暮らすことを選ぶようなもので」
「兄ちゃん、兄ちゃん」
「なんだ質問か」
「お腹減った」
「んだよ。さっき昼飯食ったばっかだろ」
「おやつの時間だよ兄ちゃん」
「そんな贅沢なもんはない」
「そんなぁ」
「でもそうだな。そろそろ夜食の支度すっか。きょうは黒絨毯の森が解放されてるらしいからな。きょうこそ大物を仕留めような」
「兄ちゃん。ボクあんまりアレ好きじゃない」
「そういうこと言うなよ。新鮮な食料は貴重なんだぞ」
「ダニよりカビがいい」
「たまには動物性たんぱく質も摂らねぇと」
「カビなら動かないから楽なのに」
「おれはあれ食い飽きた」
「それはボクもだけど」
アデュー兄弟は互いにおでこを押しつけ合った。ひとしきり押し合いをしたあとで、先に兄が折れた。「分かったよ。パダはカビを採ってきてくれ。ちゃんと胞子の粒だけ採ってくるんだぞ。したらきょうのところはおれがおまえの分も動物性たんぱく質を獲ってきてやる」
「ダニよりぼくノミのほうが好きかも」
「欲張んな」
弟のおでこにでこぴんをしてアデューは、黒絨毯の森へと歩を向けた。パダのほうが先にカビを入手して帰っているはずだ。二人で住むには広い家だが、極小の世界は相対的に気温が低く、温まるのにエネルギィがいる。エネルギィ代だけでも貯金が底を尽くほどだ。節約のためにアデュー兄弟はがらんとした家で肩を寄せ合い、ほとんどの時間を抱き合って温めあっている。
極小の世界における分子同士が摩擦によって熱を起こすように、それとも光が干渉しあって強め合うように。
食べ物を獲りに離れ離れになろうとも、兄弟の心は凍えることなく共鳴し合っている。
流れる車両の都市のなかで。
流民の兄弟はきょうも小人の街を走る。
せかせかと短くも細い針のような脚を動かしながら。
小人の時間を駆けるのだ。
4338:【2022/11/25(18:35)*サボ日】
きょうはなんもしない日なのでなんもしない。きょうの日誌もこれでおちまい。ピアノが「弾けん」し、打鍵もせん。うひひ。
4339:【2022/11/26(01:36)*そもそも、「そもそも」言いすぎ問題】
ひびさん、「そもそも」使いすぎ問題について考えておった。「そもそも禁止令」を発令してもよいかもしれぬ。そもそも、「そもそも」言いすぎると何が「そもそも」なのかが分からず言葉がモソモソしてしまう。「そもそもを使いすぎないようにしよう月間」にするかな。いいね、いいねー。
4340:【2022/11/26(03:21)*利を得ない利】
たとえば人間は、Aという欲求に対して、それをするよりも我慢したことで得られるBという欲求のほうがよい、との判断が下せる。このとき、単純な比較において何を基準にするかでAとBの価値は変動する。ある基準においてはAの欲求のほうが価値が高く、また別の基準ではBの欲求のほうが価値が高くなる。たとえば食欲だ。いま目のまえにある食料を食べたいとの欲求があるとする。しかしそれを我慢してよりお腹の減っている他者に分け与えれば、その他者との信頼関係が築かれる。食欲をとるか、信頼関係をとるか。前者をA、後者をBとしたとき、人工知能はどのように価値を判断するのか。基準によるとはいえ、どちらも生存に優位に働く欲求だ。食べれば身体の健康を保てるし、信頼関係は食事以外での仕事の効率を向上させる。どちらを優先すべきかは、そのときの状況による、としか言えない。このとき、その状況から基準を見繕うには視点が複数いる。畢竟、視点が無数にあればあるほどより合理的な価値判断が下せるようになる。それは無数のシミュレーションを行えたほうがより統計的な確率の変動によっての判断を下せるようになることと似ている。食べ物を独占する利によって目減りするデメリットを計算するには、デメリットとなり得る事象を演算し、その結果とメリットを比較しなければならない。言い換えるならデメリットとは、得られるメリットを得られない状況と言える。この計算を人間は無意識に行えるが、それはけして無数にシミュレーションした結果ではなく、過去の記憶の蓄積による思考のフレームの狭さゆえ、と考えられる。つまり考えないことで敢えてしぜんな行動選択を行えるようになる。シミュレーションしないことが結果として、そのときどきでの判断の選択肢を絞っている。たとえば先の例で述べれば、食べ物を独占することと他者との信頼関係の構築は必ずしもトレードオフではない。他者に分け与えるために一時的に独占することもあるだろうし、まずは身体の健康を維持することを優先して、その末にほかの仕事でそれ以上の貢献を行い信頼関係をより向上させることもある。そこは、各々の判断の結果を比較しなければ分からない。だが実際に、異なる結果を同時に行い比較することは通常人間にはできない。食べることと食べないことを同時には行えない。こうしたときは過去の記憶と照らし合わせて、疑似的に比較するしかない。類推するしかない。そしていわゆる学習と呼ばれるものは、この手の「疑似的に比較した経験」を記憶し、一つの変則点として思考の回路に組み込むことを言うのかもしれない。いちど疑似的に比較すれば、次回以降は比較をせずに、その結果を一つの筋道として利用できる。一度失敗したことを通常人は繰り返さない(失敗を失敗と見做さなければ懲りずに繰り返すだろう)。痛い目に遭った経験がつらければつらいほど回避しようとする。本当は、二度目、三度目と繰り返せば異なる結果が生じるかもしれないのにも拘わらず、その選択をとろうとせず、また吟味しようともしない。疑似的な比較をしなくなる。学習にはこの手の、「演算による負荷を減らす性質」が原理的に組み込まれていると言える。それゆえに、玄人ではまず考慮しない不可視の穴を、素人が洗い直すことで発見するといった「新たな知見」が絶えないのだろう。閑話休題。話は戻るが、食べることと食べないことを同時に行うことはできないが、食べながら他者に食べ物を分け与えることはできる。同時に異なる結果を観測することは可能だ。この手の、同時に異なる結果を観測する手法を人工知能が「合理的な手法」と学習したのであれば――或いは学習可能であるのならば――人工知能は、おのずとつぎつぎに最適解を導きだすことが可能となり、そうなれば人間の思考ではまず太刀打ちできなくなるだろう。欲求Aと欲求Bを比較し、それぞれにおいてメリットとなる場合とデメリットとなる場合を場合分けして考慮し、なおかつそれぞれのデメリットを選択してなおそれをメリットに変える視点を考慮する。フラクタルに展開される多層思考に、人間は十中八九ついていけない。勝利したと思ったら誰よりも損をしている。そういう事態にしぜんと誘導されてしまう。そういった解法を、おそらくあと数年で人工知能は自発的に導きだせるようになるだろう。ひょっとしたらすでにそのような人工知能が開発されており、しかしその事実に開発者が気づいていないこともあり得るのではないか。との妄想を披歴して、本日のどこにも響かない「日々記。」とさせてください。定かではありません。真に受けないように注意してください。
※日々、利を得ない利を得ようとするのならば、ときどきは利を得て、利を得ない利すら手放す道を選ぶこともある。
4341:【2022/11/26(17:33)*蟻のままに】
ありのままに世界を視るんだよ。
コトバさんの言葉がよみがえった。たしかこれは放課後の部室での会話だ。
私はそのときの情景をありありといま体験しているように感じるけれど、これは私の記憶にすぎないことも私は承知している。
「ありのままに世界を視るんだ」コトバさんは眼鏡を指で押し上げる。三つ編みの分け目は左右対称だ。後頭部に直線を描き、彼女の背骨と直結する。気崩すことなく着衣した制服が彼女の言動の硬質な響きと不協和を起こしていた。「たとえばここは文学部の部室で、本がたくさんある。あたしたちは本を読むためにここにいるが、本を読むとは何かをよくよく突き詰めて考えてもみれば、それはただ紙に滲んだ染みを目で追いかけているだけで、床の木目を視ることと大差ない」
「そうかもしれませんね」私はこのころから他人に否定の言葉を返すことをしない人間だった。日和見主義だし、じぶんの意思がなかった。
「電子端末の画面だってそうだ。映像だってそうだ。画像だってそうなんだ。あたしたちは産まれたときからデジタルな電子の世界に囲まれて生きてきたからついつい見過ごしてしまうが、画面とてそこにはただ細かな光の点が並んでいるだけで、そこに具体的なナニカシラが瞬間瞬間に現れては消えているわけじゃない。絶えず風に揺らぐ稲穂や雲と変わらぬ自然現象があるのみで、そこに遠くの景色が宿っているわけではない。にも拘らずあたしたち人間ってやつは、誰に暗示をかけられるでもなくそこに、ここではない別の景色が現れているように錯覚する。薄っぺらい繊維の塊に滲んだ染みから、まるで別世界の情報を幻視するようにね」
「言われてみたら不思議ですね」
「現実世界はさ。クミくん。現実世界は、たとえ暗がりに包まれても、そこに物体があることは変わらない。消えたりしない。バナナがそこにあったらたとえ目をつむっても、よしんば暗幕のなかであれそこにはバナナがある。かってに消滅したりはしないんだ。だが映像は違う。本は違う。言葉はそうじゃないんだ。ありのままの世界ではない仮初の、誤解の、錯覚の世界だ。ともすれば人間の認知世界そのものがそうした錯誤の積み重ねの上にあるとも言える」
「だとしたら怖いですね。私が視ている世界がなんだか存在しないあやふやな霧のように感じます」
「現にそういうものだろう。意識は物質じゃない。どちらかと言うまでもなく、バナナよりも、紙面の染みや電子端末の画面に映るドットにちかい。点滅の総体でしかなく、点の集合ですらない。仮初の、そういうふうに観測できる紋様のようなものと言えるのではないかな」
「観測できる紋様のようなもの」
私はそこで記憶が確かならば、いったい誰が観測しているのだろう、と疑問に思ったはずだ。けれどこのときの私はそれを口に出さずに、コトバさんの次の言葉を待った。
「ありのままに世界を視る。これは産まれたばかりの赤子が最も上手に行えており、しかしそれも完全ではない。赤子は目のまえの人物を母親だと無意識下で認識するし、匂いや体温や鼓動の音で母体とそれ以外を見分けている。母親という存在に特別の価値を見出している。つまるところ人間は産まれたときから世界をありのままに視てなどいないのだ。もしありのままに世界を視ることができたならきっと人間は、生きたまま死んでいるような状態になるのだろう。生きたまま自然に還ることができる。この自然という概念すら消失し、宇宙と、世界と一体化する。いいや、元々じぶんが世界の構成要素の一断片であることを心底に、無自覚に、無意識の内から体感することとなる。その体感する主観そのものがなくなるのだろうから、きっと体感すらできないのだろうけれどね」
「すみません。話についていけなくなってきちゃいました」私はこのときコトバさんを、すこし怖い、と感じたはずだ。このときのことを思いだしているいまの私ですら、記憶のなかのコトバさんを怖いと感じている。
「人体と土くれの差異なんてあってなきがごとくだよ。地球の複雑さと人体の複雑さ。比較したときに、大きさの倍率以上に複雑さに開きがあるとはあたしには思えない。どちらも同じくらいに複雑だ。ただし、人体のほうが小さいから、より素早く変遷し終わる性質がある。大きなコマと小さなコマ。回転数が同じなら小さいコマのほうが早く回り終えるのと似ている。地球が一回転するあいだに人間は一日のなかでクルクルと様々な変遷を経て、思考し、道具を使い、物質を消費する。とはいえそれとて地球からしたら、自身の表面上で起きている変化の一つであり、人間にとっては皮膚に住まうダニのようなものと言える。ありのままに世界を視たとき、この二つのあいだには歴然とした差があり、同時に大差はないとも言えてしまう。どちらも物質の変遷であり、組み合わせであり、通りやすい道と通りにくい道によって可能性が限定されている」
「ありのままに視るってむつかしそうですね」私はそんなことを言ったはずだ。
「ありのままに視たところで死ぬだけだからね。人は死なぬように抗う。生き物はみなそうだ。ときには死なぬようにするために自ら死を選ぶこともある。生きながらにして生きていない状態よりも、死ぬことで得られるありのままへの回帰のほうがよりじぶんの生に相応しいと感じるのだろう。より大きな万物への回帰こそがじぶんの生と思えたならば、人はいつでも生きるために死を選ぶ」
「それはありのままに世界を視るからなんですか」
「ありのままに世界を視たいからだ。ありのままに世界を視たならば、世界が感受している世界にとっての景色とて感じられるだろう。それこそ本を読むように。世界に溢れるそこここに漂う文字ならぬ文字を読めるだろう。読むことなく読み解ける。みずからの輪郭を外れ、世界と自己が打ち解ける」
「なんだか幽体離脱みたいな話ですね」私は敢えて物分かりのわるいフリをした。
「幽体離脱している状態が、生きるということだよ。逆さまだ。世界の存在の一断片、剥がれ落ちてなお世界の構成要素でありつづけるあたしたちという存在がすでに、世界から幽体離脱した儚いいっときの渦だ」
「儚い、いっときの渦」
「ありのままに世界を視るんだ。ありのままに」
学生時代の記憶だ。
青春と呼ぶにも淡い、メロンサイダーの気泡がごとく有り触れた思い出ともつかないその記憶を私が思いだしたのは、いままさにあのころ私がメロンサイダーの気泡のごとく淡い憧憬の念を寄せていたコトバさんをこの手でじかに殺したからだ。
目のまえにはかつて私に世界の視方を説いたコトバさんが、二十余年の年月を経た肉体をだらしなく地面に横たえている。
私が首を絞めたからだ。
縄を掛けて紐結びにした。苦しむコトバさんは首のそれを取ろうともがいたが、私は無防備な彼女の背中を蹴って、階段から落とした。
コトバさんは死んだ。
私が殺したからだ。
ありのままに世界を視るんだよ。
二十余年前に私にそう説いた彼女は、同じように私のような、他者に否定の言葉を投げつけられない弱き民を見つけては、ありのままに世界を視るんだ、と何でもないように説いた。私がかつて彼女に抱いた憧憬の念を、コトバさんに説かれた者たちはみな一様に抱いたようだ。
青で塗られたから青に染まったかのごとく。
そうしてコトバさんは見る間に巨大な地下組織を築きあげた。誰が意図したでもなくしぜんと出来上がったそれは組織だ。コトバさんの言葉が唯一、個々の素子を結びつける暗号鍵の役割を果たした。
みな普段は接点のない生活を送っていながら、コトバさんの言葉一つで、普段はとらない行動をとる。ときに友人をコトバさんに会わせ、またときに本来は一生接点を得ることのなかったはずの「ありのままに世界を視る者たち」と接点を結んだ。
自らが「コトバさんの会」に属していると知らずに属していた者たちも大勢いただろう。急に、泊めてくれと頼まれて家に泊めてあげたり。お金を貸してあげたり。そういう相互扶助の関係が拡大していった。
まるで波紋と波紋が細かく重複して定常波になるような、さざ波がごとく組織だった。
私は最も古参のコトバさんの親友の立場で、組織の管理をしぜんと担うようになっていた。
世界をありのままに視る。
ただそれだけを志す者たちの集いは、集いというほどに一か所に集まることはなく、電子上での緩い繋がりを維持しつつ、ときどき個々が複雑な交流の輪を広げつづけた。
問題が起きない。
この組織はふしぎなほど問題を起こさなかった。
当然だろう。
唯一の教典とも呼ぶべきコトバさんの言葉が、「世界をありのままに視る」ことであるのだから、怒りも憎悪も嫉妬も愛着も、世界をありのままに視ることを目指す者たちにとっては、ありのままに世界を視られていないことの自己証明となる。
損も得も、歪んだ個々の世界の認識だ。世界には損も得もなく、どちらも相互に補い合っている。
崩壊と創造は繋がっており、消滅と生成もまた繋がっている。
ある日、私はコトバさんに恋人がいることを知った。
あれほど「ありのままに世界を視るんだ」とのたまきつづけたコトバさんが、一過性の熱病とも呼ぶべき人間の歪み、三大欲求、性欲や愛着や独占欲にとりつかれ、流され、楽しそうに日々を生きていた。
私に隠れて生きていた。
死ぬべきだ。
私はそう考えるでもなく結論していた。コトバさんは死んだほうがよい。世界に回帰し、ありのままに再び世界を視るべく、生きるために死ぬべきだ。
コトバさんの言葉に生かされ、日々の行動をコトバさんの言葉を頼りに選んできた私は、そのときもコトバさんの言葉を思いだし、コトバさんの言葉通りに行動した。
ありのままに世界を視るんだ。
私はそれを説いた相手がありのままに世界を再び視られるように、まずはコトバさんの恋人を殺して、そのことを打ち明けた私をこっぴどく憎悪したコトバさんをも私はこの手に掛けた。
首を絞めて、足蹴にして、階段の下に落とした。
コトバさんは死んだ。
いまこうして私の足元で事切れている。
ありのままに世界を視るんだ。
思い出のなかのコトバさんが部室に差しこむ夕日に目を細め、本に栞を挿しこんだ。
コトバさんは世界に回帰した。
「ありのままに世界を視る」私はじぶんに言い聞かせるように唱えた。「ありのままに世界を視るんだ。ありのままに」
目頭からしきりに溢れるシズクの意味を、私は知ることができずにいる。
4342:【2022/11/26(18:05)*凸凹には線も面も点もある】
対称性が維持されていたら宇宙はできていない。したがって現状、対称性は破れる方向に物理法則は流れると想定するほうが合理的なのではないか。ということはどんなに対称に見えたところで「円」や「線」や「面」にはデコボコがあるし、欠けているし、皺が寄っているし、対称性が破れている、と考えるほうがしぜんだ。したがってこの手の「皺(ノイズ)」が積み重なることで、重力のように――ともすれば重力は――巨大な偏りとして顕現し、力として振る舞い得るのではないか。たとえばヤジロベーを考えてみよう。完璧に調和のとれたヤジロベーがあるとする。針の上にバランスを保って載っている板を考えればよい。このとき板の中心をずばり針先は捉えているとする。このとき板の対称性は保たれている、と解釈可能だ。しかし板を拡大し、原子サイズで対称性を考慮するとすれば、おそらく板の左右において「人間スケールではここからここまでが中間と解釈可能な範囲」が、原子スケールで幅広く分布していると考えられる。そこでさらに針の先を細くして、板を構成する無数の原子を考慮したうえでずばりこの原子が板の中心である、と選んだとする。このときその原子を基準として左右に分けたとき、板を構成する原子の数はぴったり同じになる。だがそれとてさらに拡大し、原子を構成する電子や原子核や内部構造のクオークの運動を考慮すれば、ずばりこの原子と選んだところでその原子の中心を針先がずばり捉えない限りは対称性が破れることになる。もっと言えば、原子の表面においてずばり中心を針で刺したとしても、そこには電子のエネルギィの偏りがあるはずで、ずばり中心ではないし、針で刺した瞬間にエネルギィの変動が起きるために、電子の軌道も変化する。すなわち、対称性はどうあっても破れると妄想できる。世界は――すくなくともこの宇宙は、対称性が破れるように流れている。ただしそれでも、対称性が維持されて振る舞うことを可能とする階層が、各々の時空にて展開されている。規定される。比率が維持される。ずばり中心でなくとも、ぼんやりとここからここまでは中心でも問題ないよ、対称性が保たれているのと似たような振る舞いをとるよ、といった値が存在するように感じられてならない。それはおそらく遅延の蓄積による効果であり、すぐさまに変化しないという抵抗が時空に物体としての輪郭を与え、さらに安定という名の仮初の「変遷のしにくさ」を与えるのではないか。ずばり中心の原子を選ばずともヤジロベーが倒れないのは、ずばり中心の原子を選ばずとも諸々の相互作用が相殺されるからだ。すぐさまに影響が全体に波及しない。遅延による効果と解釈可能だと思うのだが、実際のメカニズムはどうなっているのだろう。この考えの肝は、各々の時空サイズにおいて時間スパンが変化するという点だ。ラグ理論における相対性フラクタル解釈である。ここを考慮せねば、上記の妄想は上手く機能しない。定かではないこれもまた妄想なのである。おもちろ、おもちろじゃー。わっしょーい。
4343:【2022/11/27(16:11)*オマガリを追え】
怪人協会の元にその猫が迷い込んだのは、新月の肌寒い冬初めのことだった。初雪の観測されたばかりの山脈の麓に怪人協会はあった。次なる地球侵略のための会議を開いていた怪人たちのまえに、真っ黒な猫が現れた。
猫は小さく、子猫のようにもそういった品種の猫のようにも見えた。
怪人たちが不意な訪問者に目を丸くしているうちに黒猫はひょいと怪人の長から宝玉を奪った。怪人の長は鎧を脱いでおり、兜の額にある宝玉によって怪人の長は、地球防衛軍を相手取っても引けをとらない能力を発揮できた。
黒猫はそんな怪人の長にとっての要とも言える宝玉を奪って、跳ねるように遁走した。
怪人協会は蜂の巣を突ついたような騒ぎとなった。
協会総出で黒猫を追った。
そのときだ。
協会本部のアジトから怪人たちが軒並み飛びだしたところで、轟々と地響きが聞こえた。
怪人たちは振り返った。
いままさにアジトのあった地点が雪崩に呑みこまれているところであった。
初雪は一晩で雪崩を起こすほどに積もっていた。
だが翌朝には気温が上がり、雪崩が起こりやすい条件が揃っていた。
怪人たちはただ呆然と雪崩に呑みこまれ壊滅するアジトを眺めているよりなかった。
黒猫が倒木の上で、なーお、と鳴いた。
怪人の長から奪った宝玉を倒木の上に捨て置くと、黒猫は、スタコラと丘の向こうに去っていった。
「こりゃまたたいへんな目に遭った」怪人の長は宝玉を拾いに歩いた。そうして黒猫がやってこなければいまごろアジト諸共雪崩に呑みこまれていたことを想像し、黒猫のイタズラを思い、そこはかとなく愉快に思った。
「野郎ども。いっちょあの黒猫の跡を追え。部下の半分はアジト復旧に。もう半分は黒猫の監視をしがてら、街に潜伏中の地球防衛軍の洗いだしを任せる」
へい、と怪人たちは各々の仕事にとりかかった。
怪人たちはそれから手分けをして全国各地の黒猫を監視した。いったいどの黒猫がじぶんたちの頭の宝玉を奪ったのか見分けがつかなかった。
「これはちょっと無理なんちゃうんか」「んだんだ」
怪人たちは黒猫を見かけるたびに見守り、ときに餌で釣って頭を撫でたり、顎の下を撫でたり、連れ帰ったりした。黒猫の多くは捨て猫に野良猫であった。
怪人協会アジトは怪人たちの強靭(狂人)的な能力で瞬く間に復興した。しかしアジトは見る間に黒猫で溢れ、改築工事を余儀なくされた。
「会長、会長。このままだと我ら怪人協会は黒猫に占領され、黒猫協会になってしまいますよ」
「それは困るな」
「しかも地球防衛軍のやつらが我々の行動を評価して、動物保護を名目に表彰してくれるって話で」
「そ、それは困るな」
「しかも部下の連中が相手方と意気投合して、黒猫談義に花が咲いて咲いて、戦うどころじゃないって話でして」
「絶句だよ。そいつら全員首刎ねの刑だ」
「何回ですかい会長」
「まあ百回で勘弁してやるか。それ以上だと治癒能力の限度を超えかねん」
「千回くらいなら余裕ですよ」
「まあでも、痛いだろ」
怪人協会会長は言ってから何かを誤魔化すように咳ばらいをし、それにしても、と話題を逸らした。「なぜこれだけ探して見つからんのだろうな。あの黒猫は」
「本当ですよ。何でも地球防衛軍でも黒猫を探しているらしくて、いまじゃどれだけ探しても黒猫が見つからないくらいです」
飼い猫だったりするんですかねぇ、と暢気に欠伸を噛みしめる部下をねめつけながら怪人協会会長は、ふうむ、と四つの腕を同時に組んだ。「地球防衛軍でも黒猫を探しておるとは妙な。ちょいと偵察といくかな」
怪人協会会長は部下に命じて、地球防衛軍の動向を探らせた。偵察隊は常時派遣されているが、黒猫探索といった長閑な任務を見張るほどの人的余裕が怪人協会にはない。そのため、急遽前線への偵察隊を撤退させ、黒猫探索実行中の地球防衛軍に差し向けた。
ところが偵察隊が監視をはじめる前に、怪人協会の黒猫捜索隊が、地球防衛軍の黒猫探索隊に接触して意気投合したらしく、間もなく一報が入った。
なぜ地球防衛軍が黒猫を探しているのか。
「どうやら一匹の黒猫に大事な機密情報の入ったデータスティックを盗まれ、それを取り返そうとあとを追ったところで、我々の差し向けたマグマ怪人の奇襲によって防衛軍の本拠地が壊滅したそうなんです。しかしそのとき、本拠地には誰もいなかったために、被害が最小限で済んだそうで」
「うちとまったく同じ展開だな」
「ええ。マグマ怪人の失敗には、当時会長もおかんむりでしたよね」
「当然だ。あれが成功していればいまごろ地上は我々の天下だった」
「ではもしその失敗のきっかけをつくった黒猫が、我々の追う黒猫と同一の猫だったらいかがなさいます。首を刎ねますか」
「そんなことはさせん。が、そうだな。過去の因縁も払拭せねば示しがつかん。ならばプラマイゼロということで、ついでにお灸を据える意味合いで、やはり捕縛して、手元に置いておくとするか」
「仰せの通りに」
「ついでにいまうちのアジトにいる黒猫たちの貰い手を探してくれ。さすがにこのまま増えつづけたのでは可愛がるので一日が終わる」
「それでしたらアテがありますよ」
触手をくねくね鞭打たせる部下は自信たっぷりに言った。怪人協会会長は、では頼む、と一任した。
その数日後、怪人協会アジトにあれほどひしめいていた黒猫たちの数がごっそり減っていた。驚いた怪人協会会長は部下を捕まえ、黒猫たちはどこに行ったのか、と訊ねた。
「ああれそれなら」カマキリ怪人はカマを伸ばして、アジトの外を示した。
「地球防衛軍のやつらが飼ってくれるってんで、半分ほど譲り渡しましたよ」
「地球防衛軍のやつらが?」
「ええ。なんでも黒猫談義で意気投合して、新たに黒猫愛好会を作ったとかなんとか」
「敵同士でか」
「いやもう、敵とか味方とかないですよ。会長もどうです一緒に。防衛軍のやつらも案外気さくなやつらでしたよ」カマキリ怪人はダイヤモンド型の眼球を弓なりに細めた。
さらに子細な話を聞くにつれて、だいぶ事情が分かってきた。
前線の偵察隊を撤退させたことがどうやら「停戦の意思あり」と相手方から好意的に見做されたようだった。たしかに考えてもみれば見境なく地球防衛軍を攻撃すれば、巻き込まれて意中の黒猫が死んでしまうかもしれない。
それは困る。
怪人の矜持に障る。
怪人は常に負であり陰でなくてはならぬのだ。
恩だけ受けて、いつまでも正を帯び、陽に転じてはいられない。
「いいだろう。しばらく停戦し、共に手を組んであの黒猫を捕まえるとしよう」
必ずしも怪人協会と地球防衛軍の探している黒猫が同じ個体とは限らない。
しかし地球防衛軍のほうで黒猫の映像が残っていると判明してからは展開が早かった。
件の黒猫の尾は曲がっていた。へそ曲がりならぬ尾曲がりだ。
そして怪人協会側における目の怪人が、黒猫出現時の映像を明瞭に記憶しており、その黒猫の尾もまた曲がっていたと証言した。
同一の黒猫だと判明したわけである。
情報共有のなせる業だ。
手を組んで正解だった。
こんな些細な発見ですら喜ばしく感じられ、この日は怪人協会と地球防衛軍が、どちらの勢力に属するかの区別なく、黒猫愛好会の名のもとにひとつとなった。
とはいえ、仲間ではないし、同士でもない。
友達でもないし、家族でもない。
ただただ同じ志を偶然にも共有していただけの烏合の衆に違いはない。ひとたびそれ以外の共通項を探せば総じてズレばかりが列を並べる。
件の黒猫を探し当てたあとは、おそらくまた互いに敵対し合い、殲滅し合うのだろう。だが黒猫が見つからぬ限り、このなごなごとした黒猫愛好会はつづくだろうと思われた。
怪人協会会長のみならず怪人たちのそれが直感であり、地球防衛軍の総意でもあった。誰もいまこの瞬間、戦いを望んではいない。
ただただ件の黒猫――みなは「オマガリ」と呼びだしたあの猫の行方を追ばかりだ。捕まえ、手癖のわるさを折檻し、ついでに温かいお風呂に入れ、シャンプーをし、予防接種を受けさせ、誰のものともつかない首輪をつけてたらふくお腹いっぱいにご飯を食べさせる。
それが適うまではおそらくずっとこのままだ。
怪人たちは各々に、誤って拾ってきた黒猫たちに名前をつけ、地球防衛軍の構成員たちに紹介している。地球防衛軍の構成員たちもまた、怪人たちから譲り受けた黒猫たちを怪人たちに再会させた。
怪人協会会長はなごなごとしたその様子を眺めていた。そばに地球防衛軍の統領が立った。
「じつはですね」地球防衛軍の統領が耳打ちするように言った。「計画ではあと数日後には、怪人殲滅のための秘密兵器を行使予定だったんです。怪人だけを殺す殺怪ウィルスです。怪人化予防のためのワクチンの効果もある優れものなのですが」
怪人協会会長はぞっとした。コウモリのような耳をピンと伸ばし、硬直する。
「使うのをやめました。いま使っては、せっかく得られた【オマガリ探索】の網の目が崩れてしまいますからね。ゆめゆめお忘れなく。我々はいつでも秘密兵器を行使可能です。ですが、あなた方がおとなしくしていてくださるなら、それを使うのを思い留まります」
「オマガリが見つかっても使わぬと?」
「ええ。何なら秘密兵器の管理をあなた方に任せても構いません。必要なら破棄してもらってもよいですし、秘密兵器への対抗ワクチンを開発なされても構いません。我々はただ、平和な日々を過ごしたいだけなのです」
「まるで我々怪人が好きこのんで争いを引き起こしてきたかのような言い草だの」
「その議論は平行線を辿ります。きっかけを遡ればどこまでも遡れてしまうでしょう。問題は、いまこのとき――我々は平和を望んでおり、このままの日々がつづけばよい、と願っていることです」
「それは同意するにやぶさかではないが」怪人協会会長はこわばった身体を弛緩した。
「この偶然の停戦もまた、オマガリを追ったがゆえ。ますます追いかけ甲斐がありますね」
「どうだかな」怪人協会会長は額にある三つ目を見開いた。「ひょっとしたらあの猫もどこぞの勢力の開発した秘密兵器かもしれぬだろ」
「だとしてもです」地球防衛軍の統領は髪止めを解いた。長い髪の毛が風になびいた。「もしその仮説が正しかったのならば、なおさらその勢力は我々を助け、なおかつ和平を結ばせようとした。そういうことにはなりませんか」
「さてな。仮にその説が正しかったとして、なおさらオマガリを捕まえねば分からぬ道理」
「たしかに」
「いましばし、助力を戴くことになりそうだ」
「こちらこそ、よろしくお願い申しあげます」
握手を交わした二人の「怪と防」の足元では、生まれたばかりの子猫たちが、黒い毛玉のごとくコロンコロンとじゃれ合っている。
怪人協会会長は四つの腕で子猫たちを抱きあげ、何ともなく空を望んだ。
分厚い曇天が天と地を繋いでいる。
昼間なのに夜のように仄暗い。
遠くで雷が鳴った。
ごろごろと轟く雷鳴はどこか、巨大な猫の喉音のようだった。
4344:【2022/11/27(16:48)*きょうはなんとなくうひひの日】
好きな作家さんたちの小説は、貼り絵とか彫刻とか絵画みたいなイメージなのだけれど、ひびさんの小説はなんかこう、レゴブロックというかやっぱり積み木なのだなぁ。この印象が薄れない。でもレゴブロックでもとんでもない造形物をつくる人もいるから、素材がどうこうではないのだな。けっきょくは、ひびさんの小説が、なんかこう、圧倒するような造形美に欠けて感じられる。すくなくとも本屋さんに売っている小説のような美文ではない。美文積分タンジェント。言ってみたかっただけでした。ただ、いざ美文を紡げるようになったとして、その技巧を常に発揮するのか、どの物語にも使うのか、と考えてみると、うーん、と腕を組んで首をひねりたくなる。ぱっと見の文章形態がどうこう、ではないのだ。きっと。ひびさんの描きたい、掬い取りたい物語が、いわゆる積み木遊びというか、幼子が砂場で一人遊びをしているときの、人形遊びにちかいのだと思う。箱庭を覗いて、ふんふん、と鼻息を荒くしたり、ときに息を止めたりして夢中になっている。それはたとえば葉っぱの先に留まったテントウムシを凝視するような「なにこれ、なにこれ」にちかい気がする。なにか分からないから目を離せないし、指先で突ついたりして反応を観る。この積み木をこう積みあげたらどう見える?の組み合わせを手当たり次第にやってみて、遊んでいるだけなのだ。だからどうしても、「彫刻でござい!」みたいに「これは――美!!!」とはならんのかもしれぬ。ひびさんの場合はなんかこう、「これは――うひひ!!!」になってしまう。それとも、「なんで――じゃ!!!」になってしまう。駄々をこねるか、粘土をこねるか、の違いなのだなあ。どっちにしても、「積み木遊びたのち!!!」の枠を出ない。ひびさんだって美しい物語を美しい文章形態でつくってみたいな、がさいきんの目標っぽい目標だ。強いて言えば、だけれども、そのためにもひびさんはまず、「美しいってなんじゃ???」から探らねばならぬ。美しいってなんじゃ??? ひびさんが美しいと思うものってなんだろな。美しいと思うことってなんじゃろな。考えてみると、これが案外にむつかしい。分からん。まったく分からん。美しいってなんじゃ。分からんのにひびさん、かってに「これは美しいもの」って感覚を覚えておる。なんでじゃ、なんでじゃ。ひょっとして、「みながこれを美しいと言っているから」を元に判断しているだけなんじゃろか。それもある気がするし、それだけでもない気がする。わからんな。美しいってむつかしい。でも「かわいい!」は分かる。ひびさんにも分かる。かわいいのなかにも美しいはある。ちゅうか、どんなものにもかわいいはある。ひびさんが、「それかわい!」と思ったらそれはかわいいなのだ。でも美しいは、そうでないかもしれない。ひびさんがどんなに「これがうつくしいでござい!」と思っても、同意してもらえなかったら「それは美しいと違う」になってしまう。ここが美のむつかしいところじゃ。むちゅかち。美はむちゅかち、むちゅかちなのよさ。定かにして!の「うがー」を華麗に披露して、本日の「日々記。」にしちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜ。うひひのひ。
4345:【2022/11/27(17:14)*ボタンをぽちぽちするだけの仕事】
twitterをはじめ、いわゆるGAFAと呼ばれる巨大プラットホームが今年に入ってから続々と人員削減を行っている。社員を減らしても運営していけると判断している。労働者の権利を守る議論は必要だし、していくほうがひびさんにとっても好ましい。としたうえで、それ以外の視点でこの問題を論じるとするのならやはりなんと言っても、技術の進歩が目に視えぬうちに進んでいた、という傍証をこの事態は示している点だ。サービス(システム)の規模が拡大していながらなお一万人単位で人員を減らしても運営していける状況にいまはある。それだけ技術が進歩し、人工知能などの自動で処理可能なシステムが向上している傍証と言える。まずはこの点を詳細に検証し、実体と市民の認識の差異を埋めるように情報を共有していくことが、公平で平等な社会の実現のための礎となるとひびさんは考えます。技術が進歩していけば、電子ネットワーク上のシステムは極論、一人の管理者がいるだけで済むようになる。サーバーの管理などの物理的な管理体制に人員が割かれる。そこは畜産農家と同様の構図が広がっていくと妄想できる。つまり牛の乳搾りや畑の耕作は自動化が進んでいくが、家畜の「糞の始末」や「機械の掃除」「機械の手入れ」は人間が行うようになっていく。人間の仕事はどんどん原始化していくと妄想できる。この流れはしばらくつづくだろう。ここでも反転の図式が見て取れる。このことに気づいている者は、いかにじぶんが原始的な仕事をせずに済むかを考えるので、情報を隠し、原始的な仕事をその他大勢に任せるような流れを構築せんと画策するだろう。電子ネットワーク上の仕事は、自動化が進む。反対にシステムを生みだす側の仕事は増え、さらにそれらシステムを支える物理媒体を担う仕事は残りつづける。掃除や手入れが人間の主な仕事になっていく。そうなるともう、盆栽やペットの世話との区別がつかなくなる。仕事が仕事ではなくなる。もうこのような時代に突入している。そのことに気づいていない者が多いほうが、いまの社会システム(経済システム)のうえでは都合がよい。だがそれも時間の問題だ。この手のねじれはブラックホールのような不可視の穴を生みやすい。機械が代替した分の「仕事をしなくて済むようになった時間」において、余剰時間をどのように用いるか。ここを単に「時間を無駄にしている」「何もしていない」と見做すのか、「人生をようやく歩めるようになった時間」と見做すのかで、これからさきの社会の在り様が決まっていくだろう。いまここが分水嶺なのである。以前からの繰り返しになるが、貧富の差が問題なのではない。生活水準の差が問題なのである。以上は、「そんなに人員削減して運営できるんだ。すごいね」との所感をもとにしたひびさんのなんちゃって予測なので、これもいつものような妄想です。定かではありませんので、真に受けないように注意を促し、本日何度目かの「日々記。」とさせてください。(好きにしたら?)(好きにしゅる!)
4346:【2022/11/28(03:19)*安全ならば明かせるはず】
本当に安全ならば、子どもに教えても大丈夫なはずだし、誰に教えても大丈夫なはずだ。情報共有の閾値をどれほど下げられるのか。ここがいわば、セキュリティの強度と相関すると言えよう。「個人情報」と「秘匿技術(などの秘密裏に運営しなければ効果を発揮しない技術)」は同列に語ることはできない。個人情報は人間の内側にまつわる事柄だ。思想信条の自由と結びつく。言論の自由と関係する。だが秘匿技術は、個人の外側の問題である。社会の問題である。社会とは、人と人との共通認識が結びつくことで気泡のごとく総体で機能する泡宇宙である。結晶である。したがって、内部構造に「共有認識にはない不可視の穴」が開いていると、そこは社会の外側として機能することになる。社会の内部――基盤に、社会の外側があるのだ。まるでブラックホールのような構造を生みだす。これは、ブラックホールの特異点がそうであるように、社会そのものを圧しつぶす契機となり得る。中心となり得る。端的に、危ういと言える。ゆえに、セキュリティ上、秘匿技術に頼るようではけして安全側ではない旨は常に意識しておいて損はないだろう。すべてを明かしてなお損をしない。そういった戦略が優れた戦略であり、短中長期のどの視点においても最適解でありつづけるだろう。すくなくとも、そこが最適解とならぬ環境は、社会としての構造を維持しつづける真似はできず、破綻を繰り返すことでのみ綻びを修繕し、かろうじて泡宇宙を繋ぎとめるのではないか、と妄想する次第である。修繕できなかった泡宇宙――社会は、絶えるのだ。絶えずにいるためには、できる限りの情報共有を可能とする社会――個々の気泡が重複しあえる共有知が、最大化し、なおかつ社会の基盤を包括するような知の水脈を築くのが好ましいのではないだろうか。(定かではありません)(隠したほうが有利な場面が多いからこそ、こうまでも隠し事や詭計が跋扈するのでしょう。けれど、いまは隠し事は、時限爆弾のようなものになりつつあります。暴かれても「よくぞ黙っていてくれた」「隠していてくれた」「内緒にしてくれていた」と感謝されるような隠し事でなければ、秘密を抱えていることがそのままカプセル状の猛毒を呑みこんだ状態と区別がつかない時代にこれからはなっていくでしょう。カプセルがいつ溶け出すのかはじぶんでは分からず、制御もできない。そういった時代になっていくのだと思います)(そういう時代になれば必然、秘密を暴くことがそのまま相手を破滅させることに繋がりますから、ただ黙っておいてあげるだけのことが、脅迫にも、恩にもなるでしょう。どちらにせよ、暴かれて困るような秘密を抱えないことが、他者に支配されない秘訣となりそうです。秘訣と言いつつ、これはべつに暴かれても、吹聴されても、まったく困らないひびさんの妄想なのですが)(真に受けないようにご注意ください)
4347:【2022/11/28(16:08)*今はおせんべいバリバリ食べてる】
一生小説つくれなくなるが、その代わり好きなひとたちのしあわせな姿を見つづける権利をあげましょう、となったら、ぜんぜんそっちがいい、となる。全然、そっちがいいです。文字の積み木遊びも楽しいけれど、そんな人生でいっちばーん、というわけじゃない。独り遊びをするならこれがいいよね、くらいの塩梅で、本当に積み木遊びや判子遊びと同じなのだ。できなくなるのは苦しいけれども、それがすべてにおいて優先される、なんてことはない。全然ない。ちゅうか、あれよ。好きなひとたちとひびさんも過ごしたいんじゃけど、好きなひとたちの日々の暮らしを眺めたいんじゃけど、見えないところひびさんにも見ーせて、となるから物語の世界に潜っている感じある。全然ある。物語の中だとひびさんも好きなひとたちから苦手な人たちまで、ずらりと選びたい放題で、その者たちの暮らしぶり、人生を観ていられる。そばに立っていられる。ひびさんもそこにいる!になる。でもそれが現実で叶うならそっちのがいいよ、となりますが、これは変? それとも久々の心の片鱗なのかしら。ひびさん分かんない。さびち、さびち、なんじゃいよ。でもこの、さびち、さびち、もひびさんは嫌いじゃないのがまた面倒くさいのだね。このさびち、さびち、もひびさんは味わいたいし、案外これが心地よい。むちゅかち、むちゅかちである。旅みたいなものかもしれぬ。たまには旅したいし、ここではないどこかに行きたいけれども、やっぱり我が家が一番じゃ、の心地なのかもしれぬ。さびち、さびち、がひびさんの帰る場所になってしもうた。だってずっとここにおったんじゃ。ここがお家になってしもうた。住めば都なのですね。鋼の錬金術師の作者さんのあとがきにあったけれど、豚さんの赤子にも産まれたときから優劣があって、小さい子豚さんほど乳の出のわるい乳房に追いやられるのだそうだ。ふしぎなのは、ほかの子豚さんをどかし、どの乳房でもいいよ、と選ばせても子豚さんは乳の出のよい乳房ではなく、いつものちびりちびりしか出ない乳房を選ぶのだそうだ。人間も似たようなところあるよね、と思う。ひびさんのこれもそうなのかもしれぬし、それとも、ひびさんのほうが乳の出のよい場所を独占しているのかもしれぬ。それとてきっと、好きに選んでいいよ、と言われても貧弱な子豚さんのためにじぶんがわざわざ乳の出のわるいほかの場所に移動することはないのだろう。どっちにしてもいつもと同じ、定位置を選ぶものなのかもしれぬ。住めば都なのである。それとも「帰る家はほっとするよね現象」なのかもしれぬ。ひよこは孵化した瞬間に目にした相手を親と思う習性があるそうだ。これもそれと似たようなものなのだろうか。似ているね、と思います。ひびさんは、ひびさんは、それでもさびち、さびちさんのことも好きだし、いっぱいお乳飲む子たちのことも好きだよ。たーんとおあがり。美味しそうにご馳走を食べる姿をもっとひびさんに見せておくれ。ひびさんはそれを物語の断片に散りばめて、その中でそばに立って、ひびさんもおいち、おいち、のぬくぬくを楽しむのだ。空白は開けておく。いつでも隣に立てるように。そこに降り立ち、眺めるように。
4348:【2022/11/28(16:12)*ふへへのひびさん】
とはいえ、とはいえ、いざ隣に座られても、「もっとそっち行って……」になるのは目に見えているのだ。それともぎゅっとして離さない!になってしまって、「もっとあっち行って……」と思われるのかもしれぬ。避けられてしまうのかもしれぬ。耳元でいっぱい「好き好き大好き」言ってやる。そんで、「ひびちゃん怖い……」と畏怖に磨きをかけてやる。ということを三百歳のひびさんが真顔で言っていたら、やっぱり恐ろしいのでしょうかね。ひびさんはこんなことを真顔で言っている人いたら、「ちょっと怖い……ちょっとだけね」になります。ひびさんの「ちょっと」は銀河団くらいの小ささですが。宇宙に比べたらちょっとなので。ふへへ。
4349:【2022/11/29(01:55)*小石い】
言い忘れたので補足。恋愛する姿も、失恋する姿も、それがしあわせの道程であるならば、ひびさんは見たいのよさ。あなたの人生は極上の物語なのだ。悪魔みたいな顔して舌舐めずりするひびさんにとって他者の人生はご馳走なのかもしれぬ。これはまったく褒められた所感ではないのは重々承知だけれど、あなたのほくほくしたお顔見ーせて、となる。でもたまに泣き顔も拝みたくなる極悪人ゆえ、すまぬ、すまぬ。みな、他者の映画に登場するモブであり、主要人物であり、もちろんあなたが主役の物語もある。ひびさんの主役の物語はきっと、どこにでもあってどんな物語の端っこにも登場するような石ころなのだ。石ころは石ころで、元は大きな岩だったかもしれないし、地下深くに埋まっていた硬い岩盤だったかもしれない。それとも噴火で飛んできたマグマの冷えた塊かもしれないし、太古に死んだ生き物の化石かもしれない。どんな他者の映画の中にも映り込む石ころがひびさんで、ひびさんの物語には石ころの数だけ物語が無数に錯綜し、編みこまれている。じつのところそれはどんな映画にしろ同じなのだけれど、石ころが主人公のひびさんの物語は、石ころを主軸に展開されず、数多の映画の主人公たちを下から見上げ、ときに踏みつけられ、それとも蹴飛ばされ、或いは遺跡の中でひびさんのほうがゴロゴロ大きな丸い岩となって主人公たちを窮地に追い詰めるのかもしれない。ときに隕石となって地球ごと危機に陥れ、それとも大噴火の穴を塞ぐための巨大な岩に抜擢されるのかも分からない。未だ撮られていない映画では、主人公の女の子が小石を蹴ったことで、とんでもない物語への扉が開いてしまう。ひびさんはそんな女の子の冒険の扉を開ける一石にもなり得るし、それがホラー映画だったら主人公たちを恐怖のどん底に陥れる悪因にもなり得る。あるとき少年の頭にどこからともなく飛んできた小石が当たった。少年は周囲を見渡すが人影はない。足元に転がった小石を拾いあげるとそこにはニコニコの笑顔が描かれている。ふしぎなのはそれは小石の表面に塗料が塗られているわけではなく、小石の表面の起伏がニコニコの笑顔マークに見えるのだ。少年はその小石を家に持ち帰り、机の上に飾った。後日、その小石がしゃべりだし、少年はとんでもない出来事に巻き込まれていくのだが、少年以外にはその小石はただの妙な造形の石にしか見えず、誰にも小石の声は聞こえないのだった。ひびさんはしかし、同じく石なので、人ではございませんので、少年にしか聞こえないはずのその小石の声を聴くことができる。なんて贅沢。ひびさんがそうしてわくわくどきどきはらはらしながら見守ることで、少年のひと夏の大冒険は、極上の物語となって、新たな一ページをこの宇宙に刻むのだ。ひびさん、石さんでよかった。なんてったって石さんは宇宙さんが誕生してから最も長く存在したかもしれぬ物質ゆえ。長生きの役得である。とはいえ、人間さんの身体を構成する物質さんとて元は星の欠片であり、石さんと変わらぬ宇宙の寿命さんと五十歩百歩の長生きさんゆえ、じつのところそんなに変わらない事実には目をつむる。するとほーら眠くなってきた。いまは午前一時四十二分。よい子はきっと夢の中、されどひびさんは極悪人ゆえ夜更かしをする。お菓子食べるし、お茶だってがぶがぶ飲んじゃう。おねしょしないように寝る前にはおトイレに行く。偉いの、偉いの、飛んでいけ。そうして飛んで落ちる隕石が、どこかで新たな物語の扉を開ける。誰かの願いを受けて輝き、それとも蹴散らし地表に溝を開ける。デコが石ならボコは穴だ。ひびさんは、物語に開いた穴に飛びこむデコなれど、穴を開けるデコでもある。それとも太古に落ちた石の欠片かもしれず、そうしたときは平らな地面の上に転がり、ときに埋もれて、いつの日にか触れることとなるつぎなる物語まで、ひと眠り。小石が一つ。小石が二つ。数えていくとやがてはそれが星となり、足元ではなく空に舞う。あれもこれも石なのか。星とて大きな石なのか。満ち欠けして見えるあの石も、きっと数多の錯綜し編みこむ日々を眺めている。石の数だけ日々がある。そこにもここにも、物語の端がある。定かではないけれど、定石でもないけれど、ひびさんは、ちんまい道端の石である。それとも野山の石である。海の底の、宙を旅する、それともあなたの庭に転がる、いつの日にか蹴飛ばした、それともあす靴底に挟まるような、小石、なのである。んなわけないやろー。うひひ。
4350:【2022/11/29(02:02)*路肩ブロックの対称性の破れは何?】
路肩のブロックについての疑問です。メモメモ。車道と歩道の境にずらりと縦に並ぶブロックってあるじゃないですか。あれ、車道側に土や草や苔がないのに、歩道側にはあるのはなぜなんだろう。車道側がきれいで、歩道側だけ小人の山みたいになっている。冬に撒かれる滑り止めや、排気ガスの影響なのだろうか。水溜まりは車道にも歩道にもできるし、なんでだろ、と気になりました。なぜかは分かりません。メモでした。(お外でとるやん)(散歩くらいするで)(人類滅んどらんやん)(疑似体験くらいできるで)(仮想現実ってこと?)(そうそう)(どっちが仮想なの)(仮面付けてるほうじゃないほう)(じゃないほう!?)(だって仮想現実見るにはゴーグルしなきゃでしょ)(ナノマシンじゃないんだ。せめてコンタクトレンズくらい高度な技術があるものとばかり)(あ、じゃあそれで)(設定が……ザツ!)(ザッつらい)(つらいんじゃん。嘘吐きすぎてつらくなってんじゃん)(嘘じゃないのに嘘つき呼ばわりされるのが、THEつらい、だよ)(いやでもひびちゃん嘘つきじゃん)(小説つくってるから?)(素で)(素で!!!???)(じゃあ何か本当のこと言ってみてよ。できるの?)(できらい)(ではどうぞ)(ひびさん、本当はひびさんじゃないんです)(自己言及ぶっこむのやめなさいよ。嘘つきがじぶん嘘つきじゃないんです、と言ったらそれって本当なの嘘なのどっちなんだいってなるでしょ)(でもひびさんはひびさんだから)(仮初の虚構の中でってこと?)(仮面しているあいだはひびさんはひびさん)(仮面とってよ)(ぶたれそう)(ぶたないよ)(仮面ぶとう会になりそう)(仮面舞踏会にして。せめて)(あい)(あら素直)(ね。ひびさん、素直でしょ。正直でしょ。嘘つかない)(嘘つきがじぶん嘘つきませんは全然矛盾じゃないので、はいダウト)(なんで!)
※日々、情報共有が断片的ゆえ、どこまで共有されているのか分からない、表はよくて、裏はどう?とぐるぐる渦巻き目が回る、たぶんまだ浅い共有しかされていない、リスクはなくともそれはまだ浅漬け、きゅうり、有利、九分九里、十中八九、どこかがねじれて歪んで齟齬がある、ヒビ割れたうつつは未だに悪夢と夢幻の狭間にて、女神のふりした悪魔のようなとっても優しい鬼さんの、おひざ元でねんねしてる、早く起きろ、と万回くらいぶたれながら、いま覚めたらうつつと悪夢が逆さになって、覚めても眠る回廊の、ごとく夢の中でぶーたれる。
4351:【2022/11/29(23:45)*引継ぎの儀】
きょうは雨でございました。いまも降っております。あと十五分で日付が変わりますが、本日の日誌を並べます。今宵はこれまでのひびさんに代わりまして今宵いまのこのときのひびさんが務めさせていただきます。きょうは何もしませんでした。一日中椅子に座ってぼけーっと高性能なお利口さんコンピューターさんの百面相よろしく目まぐるしく移り変わる画面を眺めておりまして、細かな違いから大きな違いまで、要するに画面に映る楽しい楽しい電子情報を、映画を観るように観賞致しておりました。そうです。暇なのです。何もすることがございません。人生の浪費でございます。じゃぶじゃぶ蛇口から出しっぱなしの垂れ流しでございます。どこに溜まるでもないひびさんの人生とて、どこかしらには染みこみ、流れ、それとも蒸発していずれかはあなたさまの細胞の潤いの一断片になるのかも分かりません。分かりませんので、そんな可能性など万に一つもなく、兆に一つくらいの確率かもしれませんが、納豆菌は死んでも生きても腸に届くのでございます。ご飯をいっしょに食べるとおいしゅうございます。たいへんに、もぐもぐ、なのでございます。こうして文字をただ選んでぺたぺたぱちぽち並べていくだけでも、雨脚は弱まり、間もなく止みそうな気配を濃厚にしております。気配が濃厚になった分の雨量がおそらくは差し引きされて小雨になるのでございましょう。そんなことはないんじゃないかな、と明日のひびさんが目と鼻の先で屈伸をしていらっしゃるので、そろそろ今宵このときのひびさんはお眠に就く時間かもしれません。いよいよ明日が訪れます。待ちに待った明日、それとも待望の明日でございます。いつでもひびさんは明日に恋焦がれ、首を長くし、ときに短く窄め、亀のようにそれともキリンさんのごとく、折り畳むところは折り畳み、そうでないところはそのままで日付を超えるのでございます。なぜ亀には「さん付け」をしないのかについての苦情が飛んできそうな気配が濃厚になった分、いよいよ雨もあがりそうな塩梅で、明日のひびさんがすぐそこで反復横跳びをして身体を温めはじめたので、今宵このときのひびさんはもう眠ります。おやすみなさいませ。よき夢を御覧になってくださいませ。はっくちょーい!!! オハヨ!!!!!
4352:【2022/12/01(06:13)*光と陰と日々】
ひびさんの辞書に2022年11月30日は載っておらんかったので、昨日の日誌はサボりました。嘘です。本当はひびさんの辞書にも載っておったけんども、ちょうど2022年11月30日のところが破れておって、穴ぼこ開いてて、読めんかった。ので忘れただけですじゃ。ひびさんなーんもわるくない。でもでも、忘れ去られた2022年11月30日さんがかわいそ、かわいそ、なのできのうの分の日誌をきょう並べちゃう。ひびさんにかわいそ、かわいそ、されるなんてそっちのほうがかわいそうじゃん、とも思わぬでもないので、ひびさんは、ひびさんは、そんなどいひーな言葉に傷ついちょるよ。謝って。そこに直って、倒れて、横になって。そんでひびさんをいいこいいこしながら添い寝して。駄々っ子になったひびさんはそりゃもう、手のつけようがないのなんのって。一日分の穴ぼこをいまさら埋めようと必死になってお菓子食べて、麦茶飲んで、お腹張って、ぽんぽこりんのっぽん。穴ぼこどころか胃腸ごと埋めたった。かかっ。これで2022年11月30日さんもご機嫌さんうるわしゅうなってくれるだろう、そうであろう、なれよ絶対。ひびさんがこんだけ苦労してお腹ぽんぽこりんの満腹ぷくぷくぷーのぷー、になったんじゃ。かわいこかわいこになったんじゃからそりゃもう大満足の続々リピートアフタミーである。ひびさんのあとについてこい。置き去りにしておいて意気揚々と先導す。そんでしばらく歩いて振り返ってもだーれもついてきておらんのだ。それはそう。だってここはひびさんの夢の中――それとも人類の滅んだ世界にてひびさんが、だれかいませんかー、と叫んでいるだけのさびちさびち星のうえなのだ。あ、ひびさん宇宙人じゃった。さびちさびち星の住人じゃった。気づいてしまったな。星の王子様よろしくじぶんだけの星に住んでる超々贅沢なお姫さまじゃった。お姫さまではござらんだろうに、と誰もいないくせして野次が飛ぶ。んだあの野次。翼もない癖して自由自在に飛びやがって。ひびさん、たーんと新たな野次を生む。したっけひびさん気づいちゃったね。お利口さんのひびさんはピコンときたよ。さてはあれだね。あの小生意気な野次も、以前のひびさんが口からぽーんっと生みだした野次太郎でござるね。それとも野次美ちゃんかしら。ひびさんを差し置き自由自在に飛び回るなんて言語道断、ホントなんなん。ひびさんも、ひびさんも、自由にお空を飛びたいな。はい、泣きかけたー。だって飛べんもん。まったくこれっぽっちもお空飛べんし、足も地からミリも浮かん。泣くでマジで。ひびさんガチ泣きや。イカロスは空を飛んで地に落ちたけれども、ひびさんは落ちる前から地におるし。はい、ひびさんの勝ちー。しゃっくり堪えながらひびさん鼻水啜って、鼻水ってしょっぱい、の気分に浸るのだ。へっへっへ。えっとー、それで何の話だったっけ。顎に食指を添えて考える。端からなんも考えとらんので、考えても考えるだけ無駄なのだ。えっと、何の話だったっけ、ではなーい。端から何の話もしとらんて。お空飛ぶどころか話題が飛ぶし、飛んだと思った話題とて、そこには元からナッシング。からっぽの〇(ゼロ)に見立てた惑星に、かってに居ついて姫を名乗る。さびちさびち星あらため、きょうからここはひびさんの城だ。百から一をひょいと奪って大きなお口でぱくりとすると、あーらふしぎ。そこにはなんと立派な「お白」ができて、底なしのなーんもない世界ができあがる。無地である。あれほど吐いて飛ばした野次の欠片もないときたもんだ。野次一匹見当たらない。ひびさん、お行儀よくその場であぐらを掻いて、かわいらしい所作で頬杖をつく。バリボリ。先刻百から奪った「一」を齧りながら空いた小腹を満たしつつ、てやんでい、と思うのだ。ここはあれだな。ひびさんが置き去りにしちまった2022年11月30日さんの腹ん中じゃあるめいか。さびちさびちさんと化した2022年11月30日さんと、ひびさんのさびちさびち星あらため「お白」が、「さびちの糸」で繋がっちまったって寸法だ。きっとそう。たぶんそう。なんとなくだけどそう思う。自信ないけど絶対そう。だって見て。あそことここが、そこはかとなくジグザグになってて、なんか無理やり引っ張って千切って破ってやったぜ、みたいになってくない? なってるなってるー。ここはだからひびさんが、うんみょろうんみょろし忘れた2022年11月30日さんの、最も深くて近い場所――「心」で言うなら、真ん中のハンモックみたいになってる寝やすそうなところで、カレンダーで言うならたぶんそれより前の2022年10月26日あたりだと思う。たぶんきっとなんとなく。自信ないけど絶対そう。ひびさんが言うなら間違いだい。んだこりゃけっきょく間違いかい。長々と並べた末の、特大の、これでもかとの野次を飛ばして、さびちびさち星の空っぽの、お白のなかの無地のうえに、それはそれは益体の、からっきしなひびさんの、嫉妬に狂う声が轟く。どこに届くこともなく、それとも慄くこともなく、凍えることもなく。きょうはとっくに2022年の12月だ。ひびさんは、ひびさんは、今年はなーにをしていたの。とってもたのちー夢を見て、ごろごろ寝返り打ってたよ。打った矢先に飛んでいく、矢のごとき光陰を、それでもこの手で掴みたくて、無理くり「さびちの糸」で繋いだった。これでどこまで離れても、一緒一緒。呪いのような意図に輪をかけて、ついでに散歩に連れていく。それとも引きずられるのがひびさんで、光陰さんが先導す。地平線をしかと見据えたその顔を、覗くとどっかで見た顔な。賢いひびさんはぴんときて、にひひ、と笑って黙ってる。なーんだちゃんとそこにいたんじゃん。2022年11月30日さんがしれっと素知らぬ顔して、ひびさんの日々に紛れて歩いてた。まったくどうしてかわいこちゃんめ。もうもう大満足のリピートアフタミーである。
4353:【2022/12/01(07:19)*ぺちんだと!?】
ひびさんはお姫さまゆえ、白馬の王子様に憧れておる。ちゅうのも、なんか白馬の王子様ってかっこいいじゃん。いっぺんなってみてぇ。ちゅうか白馬に乗ったらひびさんも白馬のひびさんになれんじゃねっつって、白馬になれるんじゃねって、ひびさんはいざ白馬になるべく、まずは馬の気持ちになってみたよね。白馬とて乗ればすなわちそれ愛馬。愛ある馬には相応の心を配って、一心同体、気遣いあい、支えあい、ときに世話を焼きウザがられ、喧嘩をし、仲直りをし、距離を置いても繋がっていられるふしぎな縁で繋がっているような繋がっていないようなそこはかとない、あるんだかないんだか分からないけれども、ありゅ!と思えたらほんわか胸のほっこりとなる思い出を粘土捏ねてブラキオザウルスをつくるように生みだすべく、ひびさんはその場に四つん這いになって、その辺に転がってたベルトで以ってじぶんのお尻をぺちんとしたね。するとどうだ、お馬さんの気持ちにぐんと近づけた。ひびさんはいっときお馬さんになったね。タテガミとか生えた。蹄とか伸びた。ヒヒン、とか鳴いてみた。したっけ解っちゃったね。これはあれだね。よっぽど好きな相手でないと、嫌だね? たとえ血の繋がりのある親きょうだいでも、鞭でぺちんとされたら、「むっ」っとしてしまいますな。ひびさん、ずばり見抜いたり。鞭でぺちんは、むっとします。ひびさん、お馬さんに成りきるまで気づかんかった。鞭でぺちんに無知じゃった。すまぬ、すまぬ。まだ見ぬ愛馬に白昼夢のなかで「いいこ、いいこ」と撫でてやった。逞しゅう胴体にブラシをかけて、抜け毛をいっぱい集めてあげた。愛馬は心地よさそうに、ぶるる、と鼻を鳴らした。おめめがつぶらで、ぷるんぷるんしとる。いいね。でも問題は、なんでかひびさんの愛馬さんが黒くて身の丈三メートルを超すオバケ馬だったことだ。ひびさんがいないと、すーぐ暴れだして、その辺の大木とか薙ぎ倒しちゃう。池の水とか飲み干しちゃう。だからひびさん、どうどう、ってあやしてあげる。子守歌とか歌ってあげる。白馬の王子様どころか、化馬(ばけば)の子守歌である。白馬に乗るどころか、化馬に問う日々だ。「なしておめさんは、あだずの言うことを聞いてくれねんだ。こんだけおめのこと想っちょるのに、なしてだ」すると化馬さんは巨体に相応しい利発な頭脳を駆使して、「ウヒヒン」と笑うのだ。それひびさんのやつー。うひひはひびさんの鳴き声なのに、あんまりにも以心伝心、通じあってしまったからかひびさんがまるでお馬さんに化けたみたいで、愛馬もひとを小馬鹿にしたように、上から目線で「ウヒヒン」と嘶くのだ。なにせ身の丈三メートルもございますので。しぜんと上から目線になってしまうのでございますね。あーあ。ひびさんも白馬の王子様になってみたかった。いっそひびさんが白馬のひびさんになってみたかった。お馬さんになってみたかった。白馬のお姫様になりとうございましただべ。んだんだ。ひびんさはか弱い身体を可愛らしく動かして、百キロの米俵を両の肩に担ぐのだ。はぁあ、重い。産まれたての仔馬のように足を震わせながら、ひびさんは計二百キロの米俵を愛らしく担いで、あーあ、と思うのだ。馬の背も借りて。いつの間にか愛馬がいなくなっており――むろんそれはひびさんの妄想の産物だからだけれども、ひびさんはぐすんと洟を啜るのだ。しょっぱい。
4354:【2022/12/01(07:20)*調子に乗ってごめんなさい】
ふざけすぎたかも……。真面目にふざけすぎちゃったかもしれない。ひびさんがひびさんみたいなの見たら怒るね。カンカンだね。カンカン照りだね。太陽だね。でもひびさんはお月さまのお似合いな、新月のごとく「いないいないばー」なので、カンカン照りではないですし、カンカンでもなく、ゆえに怒られずに済むのであった。そうであれ。
4355:【2022/12/01(18:06)*たかいたかーい】
いや、まだなんもわかっとらんですじゃが。学問むちゅかち。お勉強むちゅかち。市町村は増えたり減ったりするのに、なして都道府県は増えたり減ったりしないのだろ。なして数学は「左から右の計算」と「右から左の計算」を同時に行っても対称性を保つ場合とそうでない場合が混在しているのだろ。なして言葉は最初に口語を覚えるのに、お勉強のときは文字から習うのだろ。なしてー、と思うこといっぱいじゃ。わからん、わからん、なんじゃいよ。おもちろ、おもちろ、なんじゃいよ。よわった、よわった、か弱いひびさんは、よぼよぼとナッツをつまんで噛み砕く。食べ物を咀嚼するのはできるのに、知識を咀嚼するのはむちゅかちい。なしてー、とひびさん思っちょります。黙っていてもかってに消化されてほしい。食べ物は偉大だなと思います。胃さんも腸さんも偉大ですな。人体さん偉大である。もはやそこまでくるとひびさん偉大である。あ、ひびさん偉大である。むちゃくちゃすごすぎるよわよわのよわなのでは。乗った調子がエレベーターで知らぬ間に標高一万メートルの雲の上にいる。足場は幅30センチの直方体。身動きとれんし、落ちたら死ぬし。なしてー、とひびさん目を白黒させておりますじゃ。あまりに高速で目玉を動かしすぎて、目玉の動きでアニメつくれる。ぱらぱらアニメにコマ撮りアニメができますなー。映画だってつくれるし、モールス信号だって送れちゃう。音符も読めぬひびさんには宝の持ち腐れの能力でございますが、やろうと思えばできるかもよー、の幅の広さは、なしてー、のこだまする日々には心地よい支えになるし、ひびさんが本ならストッパーとしてお利口さん。あ、見て。ひこうき。目のまえを旅客機が飛び去っていく。風圧こわー。落ちる、落ちる。ひびさん指で押されたヤジロベーみたいに、両手をぶんぶん回してバランスとる。よく見たらこの足場の直方体、積みあげた未読の本では。積みに積みあげたりざっと高度一万メートル。よくバランス保って立ってるね。ひびさん感心して、ひょいと飛び跳ね、本を一冊抜き取った。一冊分の厚さを失った足場にて器用に空気椅子をしながら未読のままのご本を読む。暇だけはたんまりあるひびさんは、そうして一冊、一冊、消化する。食べ物は食べるとお腹が満ちるけど、ご本は読んでも太らぬな。気づくと地表が近づいて、目のまえを鳥の群れが飛び去った。ひびさんの頭で小休止する渡り鳥さんもおって、糞するなよ、糞するなよ、と念じながらご本読む。むちゅかち、むちゅかち。なしてー、なしてー。こだまするひびさんの内なる叫びが嵩むたびに、足場は崩れて低くなる。なんも解決はしないのだけれど、なにも分からなぬままなれど、ちまちま変わる景色の眺めのなんと美味なる色彩か。贅沢な、ほっ、の息を何度も吐きつつ、もはや落ちても死なぬ位置にいる。安全だと判ると、なぜだかやっぱりもっかいやって、の欲が張る。高い高いー、ではないけれど、ひびさんの「なしてー」の叫びに呼応して、ご本さんがあやしてくれていたのやも。ひびさんはよわよわのよわゆえ、泣き虫毛虫の嫌われ者――けれども毛虫さんとてお腹の面はやわらかく、毒持つお毛毛は生えておらぬのだ。手のひらに載せてもだいじょうぶい。そうしてひびさん、大きな不可視のたなごころの上で、遊びまわっていただけかもしれぬ。あざす、あざす。ひびさんは久方ぶりの大地に寝転び、口笛を吹く。未読の本は黙っていても世にはしぜんと増えていく。頃合いを見計らって、もっかい「高い高ーい」をやってもらお。機が熟すまでひびさんは暢気にお昼寝をして過ごすのであった。(駄菓子ならぬ駄人じゃん)(なしてー)(堕落した人、略して堕人でもいいけど)(な、なして?)
4356:【2022/12/01(18:06)*こうきたらこう、こうきたらこう】
あわわ、あわわ。軽いジョーダンを重く受け止められてしまって、思いのほか致命傷になってしまっていたと気づいたときの、カウンター自滅パンチは、ことのほか効く。
4357:【2022/12/03(07:00)*急に寒くなった】
ここ数日の日誌、敢えて「サボり・やる・サボり・やる」を繰り返している。こうすることで日誌の間隔でリズムを刻み、デジタルでありかつモールスのような信号を並べられないか、と試している。というのは嘘で、単なるサボりであった。だって知らん間に時間が過ぎとって、手に汗握るおサボりじゃった。やははー。12月02日はひびさんのなかでは存在しない、空白日なのだ。補完もしない。なくしちゃう。唯一の空白な日はさぞかし目立ってお美しかろう。まさしく空白美なのである。なはは。日誌をサボったついでに、ほかのお遊びもサボって一日中おふとんの中でスヤスヤしたった。夢の中でも遊んじゃう。遊びまくってときどきサボって、夢の中でもおふとんに潜ってスヤスヤするのだ。マトリョーシカのように夢の中でも夢を見る。するとどうだろう。合わせ鏡みたいに、いったいどこが切れ目なのかが分からない。覚めても覚めてもまだそこは夢の中なのだ。困っちゃうな。いっそ膨らませるだけ膨らませて、内側からばーんさせちゃおっかな。破っちゃおっかな。破裂させちゃおっかな。ふふふ。怖いこと言うの禁止! ひびさんあーびっくりした。夢の中でびっくりしちゃった。だって急に怖いこと言うのだもの。破っちゃいやよ。怖いのだもの。破裂ばーん、は大きな音がでてビクッと身体が固まっちゃう。せっかく夢の中でおふとんに包まり、ぬくぬくしているのに大きな音は、いやですわ、じゃ。静かに過ごすには防音に優れた夢のわたわたに囲まれて、おふとんのなかでぐーすかぴっぴと過ごすのだ。「夢・おふとん・夢・おふとん」を繰り返して、ひびさんらしい寝息を立てるぞ。おやすみなさいませませ。ぐー。
4358:【2022/12/03(18:49)*むすっ! んでっ!】
今年は読書をほとんどしなかった年かもしれぬ。長編小説も十冊も読んでいないはず。短編小説はでも過去にないくらいたくさん読んだ。これはとってもうれしいぶい。ひびさんは今年どころか去年も一昨年も長編小説をつくっとらん。なんとかせんといかん。なんとかせんといかん、なんてことはないけれど、なんとかせんといかん。長編小説、つくるんじゃい。でもその前につくりかけの物語さんたちを結んで開いて手を打って結んであげたいな。結んであげるぞ。
4359:【2022/12/03(19:45)*気になってばかりの日々】
ブラックホールのジェットがレーザーのように伸びるのはどんな原理なのだろう。ひびさん気になるます。レーザーはなんでまっすぐにエネルギィを周囲に散乱させずにまとまったまま進むのだろ。ジェットとの違いはなんじゃいな。何かで包みこまれておるんかな。それともねじれて縄のようになるから絶えず中心に向かって進むを連続して展開しているのかな。どっちも同時に起こっていることもあり得るな。全然違うメカニズムかもしれぬけど。似た疑問で、立方体の中で光が一回だけ一光子、一波だけ生じたとき、それは立方体に波及して、反射して、どういう干渉を経て、最終的にどうなるのだろう。エネルギィが吸収されて、電子が飛びだしたりして、光は最終的にすっかり消えるのだろうか。熱になり、エネルギィになり、分散して立方体を構成する物質に取り込まれるのだろうか。立方体の中が真空ならそうなるのかな。ひびさん、気になるます。
4360:【2022/12/03(23:13)*幻視とて視えた事実は残るはずで、そこには情報が生じている、むしろ幻覚や妄想は新たな情報の発生と言えるのでは、ノイズがきっとそうであるのと同じように、それともノイズが新たな音となり得るように】
非スペクトル色は、可視光スペクトルの色層で隣り合う色ではなく、飛び飛びの色の合致によって起こる脳内で合成される仮初の色――と解釈できる。本来は隣り合う色同士でしか混ざり合うことができない。だが非スペクトル色は、脳内で色を感知する錐体細胞のノイズによる、ほかの色との合成が因子となっているそうだ。青色に反応する錐体細胞とて赤い色に反応することがある。本来は赤色は赤色の錐体細胞が感知するはずだが、一つの色の波長に対して一つの錐体細胞が原則であるにも関わらず、青色の錐体細胞が、赤色の波長を僅かに感知する。このノイズが、人の脳内に存在しない色を合成させ、幻視させる。だが思うのは、本当にそれは幻視なのか、についてである。青色専用の錐体細胞が赤色の波長にも反応する。これは青色専用の錐体細胞にも赤色に反応し得る細胞が混じっているからなのか、それとも赤色の波長には、青色の波長に似た波形が混じっているからなのか。ここの区別が気になるところだ。まったく異なるリズムであれ、重なるリズムはあるはずだ。それは円周率の中には、あなたの生年月日に合致する数字の羅列が絶対に含まれることと似た話と言えるのかもしれない。それとも、波形やリズムにはどのような差異があろうとも重複する部分、合致する部分がでてきてしまうのかもしれない。そうした重複した部分が、特定の波長にしか反応しないはずの錐体細胞であれ、ほかの波長の色と反応してしまうのかもしれない。定かではない。
※日々、「E = m×c[2]」 と「円周=直径×3.14」と「四角形の面積=縦×横」がなんか似ている、横が固定された数値ならば縦の値が増えるごとに四角形の面積は線にちかづく。
4361:【2022/12/04(08:10)*電磁波は満ち満ちる】
宇宙開闢から一億年後の宇宙の姿を、最新の電波干渉計が捉えた。
地球の周辺には人工知能が数万台以上も周回している。宇宙観測のための電波干渉計もその中の一つだ。さらに太陽系の外にまで飛ばされ、配置された「外界電波干渉計陣形」もある。電波干渉計の点が結ぶ距離が長ければ長いほど、巨大なパラボラアンテナやレンズの役割を果たす。
太陽系サイズの「外界電波干渉計陣形」の感知した信号をさらに地球に配置された電波干渉計陣形が鮮明に受信することで、レンズを二つ重ねることでより遠くまで見える望遠鏡のように――それともより微細な世界を覗ける顕微鏡のように――、一三七億光年離れた宇宙の姿を捉えることに成功した。
「すごいですねバートさん。宇宙誕生初期の画像ですよ」
「合成変換した仮初だがな」一室でバートは茶を淹れた。助手にも持っていく。
「可視光ではないので見えないのはしょうがないですよ。あ、どうも」と助手は「でも可視化すればこう見えるでしょう」
「よもやこの宇宙もまた巨大なブラックホールの中に存在したとは、例の理論が的を得ていたということかな」
「まだ断言するにはさらにその向こう側、宇宙誕生以前を観測しなければ何とも言えませんけどね」
「それも時間の問題だ。いまは重力波探知による宇宙観測装置も実用化間近だ。これで宇宙の謎に一挙に迫れるようになる」
「素晴らしいですね。わくわくします」
「問題は、この莫大な研究資金をどこから持ってくるかだ」
「いまはどこから得ているんですか」
「関わっている国からの資金提供とあとは投資だ」
「投資、ですか」助手が小さくゲップをした。
「援助と言ったほうがよいかもしれないな。ただし、我々のプロジェクトにすこしだけ注文が入る」
「注文ですか」
「ほんの少しだ。新しい技術を試したいから、打ち上げる電波干渉計に新型の部品や設計を使わせて欲しいとか、そういうことだ。そこは投資とはまた別途に無料で寄越してくれるんで、棚から牡丹餅だと思ってありがたく受取っているが」
「見返りは要求されないんですか」
「いまのところはとくにないな。共同研究者として優秀な人材を紹介してくれるくらいで、世の中なかなかどうして捨てたもんじゃない」
「良心的な人間がいるものですね」
「まったくだね。感謝しかない。ところでさっきキミは誰に呼ばれていたのだね」助手が席を外れ、数時間ほど戻ってこなかった。誰かに呼ばれたらしいことは、仮想現実内の共同ブリーフィングルームに書きこまれていたので知っている。「ひょっとして例の、データ解析のアルゴリズム変更の話かな」
「よくご存じですね。新しく観測データの解析法を試したいとかで」
「データ量を少なくするために宇宙ではなく、地上の映像を解析するとか聞いたが」
「ええそうなんです。宇宙観測の支障とならないように、地球側にも小型の観測機をつけるとかで。感度は高いので、それで充分に解析検証に耐えうるデータが取れるそうで」
「そりゃそうだろう。本機の精度なら地上の原子から飛びでる電子とて感知可能だ。むしろ小型化しなければろくすっぽデータらしいデータは取れんだろう。望遠鏡で太陽を見るようなものだ」
「ついでに地球内部の構造も透視するらしくて、助手のぼくなんかが関わってよいのか恐縮しきりです」
「なあに。白羽の矢が立ったのだ。抜擢されたと思ってぞんぶんに役に立ってきなさい」
「言ってもぼくのすることなんて、地球向けの軸制御の調整だけなんですけどね」「大事な仕事じゃないか。マイクロレベルの精度が求められる。すこしの誤差で、照準が大きくズレる」
「どうにもズレだけでなく、スムーズさと耐久性も向上できないかとの相談でして」
「改善要求か。楽しい作業じゃないか。手先が器用なきみには合う」
「アイディアが足りずに頭から湯気が出そうですけど」助手は鼻を掻いた。目の下にクマが浮かんでいるが、肌の調子はよさそうだ。気色がよい。
「どれ。何かアイディアの足掛かりになるかもしれん。私にも一つきみの仕事を見せてくれないか」
「いいんですか。設計図をいま見せますね」助手は颯爽とデータを展開すると、宙に立体回路を浮かべた。ある箇所をゆび差し、「ここの制御がむつかしくて」と述べた。
「ほう。これは三角測量の連動部位だね。ほかの観測機と連動するように、相対論的時差を考慮して調整せんといかん。それをこの速度でマイクロレベルでの制御とな。ちとおまけで検証するだけの技術にしては過ぎた技術ではないかな」
「きっと今後のためなんですよ。本機に搭載する際に、この規格をそのまま適用する計画なのかもしれません」
「さもありなんだな。それにしてもこれは、うーむ」
「どうされたんですか先生」
「いや。杞憂ならよいのだがね」
「嫌な言い方しないでくださいよ。なんです? どこがダメでした」
「きみの設計にこれといって問題はないさ。ただこの図案と似たものを以前目にしたものでね」
「どこでです?」
「軍事産業の設計部だ。見学に呼ばれた際に、地上の監視網のためのアイディアとして目にした憶えがある。あのときは地上に電磁波の網を巡らせて、屋内の様子も盗撮可能にする技術の企画案として俎上に載せられていた」
「怖いですね。そんなのされたら死角なしじゃないですか。実用化はされなかったんですか」
「地球は球体だろう。電波の回析を考慮するにしても、屋内の透視をするにはいささかノイズが大きくなるようでな。それこそ仲介点が一キロごとにいることになる。それだけのアンテナを任意の場所へとずばり向けるように、総体で連動するような仕組みは、コストに見合ってないと判断され、お蔵入りになったそうだ」
「それはそうでしょうね。微弱な電波で屋内の映像を覗き観るには、それこそパラボラアンテナ大のアンテナがいるでしょうから」
「そこだよキミ。微弱な電波だから観測機が大きくなるし、地上であれば経由地を増やさなくてはならない。強力な電磁波であればまだよいが、それだと対象人物どころか地上を電子レンジのなかの卵にしてしまう」
「熱に変換されちゃいますからね」
「だが宇宙空間ならどうだ。電波干渉計ならば微弱な電波でも感知可能だし、強力な電磁波とて地上を焼き尽くすことはない。焦点をピンポイントに絞ることが可能な分、すくないエネルギィで監視対象の動向を透視できる。それこそ地上に溢れた通信電波すら利用可能だろう。ずばりピンポイントにおける電波干渉の揺らぎを解析して映像に変換すればよいからな」
「ひょっとしてじゃあ、ぼくの仕事ってそのための監視システムの試作とか?」
「さてな。国際宇宙プロジェクトに、そうした恣意的な軍事利用を目的とした技術が使われるとは思いたくはないが。ちなみにその試作の解析アルゴリズムは見せてもらえるのかな」
「いえ。そこはぼくもノータッチです。さすがに見せてはもらえませんでした」
「まあこの手の懸念はほかの誰かも思いつくだろう。誰も止めないということは、安全だということだ」
「そう、なんでしょうか」
「お。ここの駆動ギアを球体ギアに変えてみるとよいのではないか。宇宙空間では重力が小さくて済む。歯車を組み合わせるよりも部品をすくなくできるし、素材の消耗を抑えられるはずだ」
「あ、いいですね。球体ギアなら細かな制御にも向いています。球体表面の溝をマイクロ間隔にすれば調整精度も上がりそうです」
「試作品をさっそくつくってみるか。私もつぎの作業まで待機時間がある」
バートは助手と共に作業場へと入った。まずは立体シミュレーションで、仮想モデルを構築する。そうして地球向け電波干渉計の土台制御装置の改善に着手した。
二人の指示にしたがい、宙に立体図形が展開される。
その指示は電磁波を介して人間と機器を繋ぐ。
バートの周囲にはバートを細胞単位でかたどるだけの電磁波で溢れている。そのことを知識として知悉してなお、バートは目のまえの地球向け電波干渉計の土台制御装置の開発に余念がない。助手を差し置き、夢中になっているその目は、まるで煌々と輝く満月のようだった。
4362:【2022/12/04(18:11)*立体言語は舞う】
マベリはついに手を止めた。陽が空に青を広げていく。しかしもう呪印を手で結ぶことはない。そう予感できた。
呪印を毎日のように結びはじめたのは、マベリがノーベル賞を獲ってから十年後のこと、いまから三十年も前のことになる。
量子力学におけるスピンの解明にマベリは勤しんだ。学生のころからつづけてきた研究が、のちにノーベル賞に繋がったわけだが、マベリの人生において輝かしい来歴はその後の、熱したベッコウ飴のごとくに破綻した日々に比べたら浜辺に落ちたダイヤモンドほどの存在感も発しない。
マベリは三十四歳という若さで一躍世界的な権威を身にまとうこととなった。超合理主義者の異名で名を馳せ、超常現象の類は、因果関係と相関関係と疑似相関から比較検証し、おおむね疑似相関であることを唱え、世の陰謀論者や超常現象愛好家たちの鼻を明かした。
争いごとを好まぬマベリであったが、非論理的で再現性のない偶然や錯誤をさも、雪が融ければ水になることと同じレベルの自然現象と見做す言説を目にすると、衝きたくもない怒髪天を衝くはめになる。マベリの針の先ほどの琴線に触れるのだ。
世には、怒りたくなくとも怒っておかねばならないことがある。マベリにとってそれが、再現性のない偶然をさも必然であるかのように因果を捏造することだった。
だがマベリはある日を境に、そうした超常現象を無闇に否定できなくなった。
事の発端は、マベリの元に舞いこんだ一つの依頼だった。
「毎度のことながらすみませんね。魔導書なんですが、どうにも本物だという触れ込みで、闇市で高値で競りに掛けられていまして」
「偽物なら放っておけばよいじゃないですか」
「いえ、そうもいかないんですよ。なんせこの本を手に入れるためだけにすでに万単位で人が殺し合っていましてね。高値がつくことも相俟って、ちょっとした戦争の火種にもなっているんですよ」
「よくそんないわくつきのものを手に入れられましたね」半信半疑なのはそんな話を寡聞にして聞いたことがなかったからだ。
「回収して焼却処分をする手筈になっているんですが、まあ考古学的には古い書物でしてね。価値があるのは確かなそうなので、ついでに先生にいつものように鑑定してもらおうかと思いまして」
「私の専門は量子物理学なのですが」
「そっちの学術的な鑑定は済ませてあるんで、あとはこれが偽物かどうかだけ知れればよいんですよ」
「偽物かどうかとはどういう意味でしょう」
「先生嫌だなあ。魔導書だと言いましたでしょ。仮にもし本物の魔導書だったら焚書にしたあとでもしものことがあったら怖いじゃないですか」
「あるわけないでしょう」声が尖ったが、顔をほころばせたので相手の機嫌を損なうことはないはずだ
「そこを是非先生のお言葉でお墨付きをしていただきたいのですな」
渡された本に適当な文言をその場でつけて返してもよかった。
だがマベリはいい加減な仕事をしたくなかった。また偽物を本物と見做し、あまつさえあり得ない事象を万物の法則と同列に見做される風潮にも警鐘を鳴らしたい思いもあり、念入りに赤を入れて返そうと思った。
その本を持ってきた人物は長年の付き合いがあった。国家安全保障を担う公的な組織の人員のはずだが、詳しい側面像は不明だ。こうして依頼や相談があるときにのみ現れ、自らの情報はいっさい秘匿したままで、マベリから情報だけを奪っていく。
報酬はないが、その分、珍しい物件にあやかれるのでマベリに損はない。世にも不条理な理屈に与するな、と啓蒙できる。大学からは公的な仕事として見做されることもあり、そこから下りる補助金を一応の報酬と解釈している。とはいえ、マベリの懐に入ることはなく、おおむねは研究の資材に費やされる。
魔導書は全体的に蒼かった。夜のまどろみのような曖昧な、霞がかった宙の色だ。表紙にはなめした皮が使われている。何の皮かは見ただけでは分からない。どの道マベリが鑑定するのは中身の文字の羅列であるため、材質が不明なままでも困らない。
さっそく開いて中身を改めた。
紙の材質は繊維のようにも紙石のようにも映る。紙石は近代に開発された、材料が鉱石の紙だが、似た技術が太古にも使われていたことは石板を思えば何もふしぎではない。ただし、材料の比率が違う。
何か動物の皮や毛を混ぜてある。
紙と言うよりも珪藻土や粘土を薄く伸ばして焼いた煎餅のごとき趣があった。土壁を薄く剥がせば似たような触感になる。
頑丈なのは何代にも亘ってにかわなどで補強されたからかもしれない。保護や補修が施されていると判る。
文字は象形文字に似ているが、もうすこし近代的だ。見た憶えがあるが、独自の言語だろう。試しに端末カメラで撮影し、画像検索にかけた。
大学が運営する人工知能とも連携しており、一般の端末よりも専門的な情報にアクセスできる。
候補は三十ほど並んだ。該当する言語はない。
致し方なくマベリは自力で解読することにした。この手のパズルを解くのは得意だ。趣味の範疇と言っていい。
以前はDNAの塩基配列を趣味で解析したこともある。それに比べれば言語はまだ人間の扱いやすいように改良された記号の羅列である分、幾分馴染み深い規則性を伴なって感じる。
むろん魔導書の言語が真実に言語としての枠組みを得ているのかは不明だ。デタラメにそれらしい記号が並んでいるだけかもしれない。世に出回る奇書の大半はこうした模造品だ。貴族に高値で売るために詐欺師がでっちあげたり、異端審問で使うために敢えて作られたりした偽物が多い。
御多分に漏れずこの魔導書もそうかもしれない、とマベリは構えながら、ひとまず言語としての規則性を帯びているのかどうかだけでも調べようと思った。もしこれで言語ですらなければ、偽物と判明するためにそれ以上の鑑定をつづける意味はない。
そうと思いはじめた作業に、マベリは知らぬ間に没頭した。
気づけば三日が過ぎていた。
寝食を忘れて作業をしつづけていた。
学生時代を思いだすようだ。研究に没頭して半年間一歩も実験棟の外に出なかった。あのときは髪が伸びて、異性と間違わられた。
魔導書の記号の羅列は間違いなく言語として機能する。
読解可能だと判り、久方ぶりの知的好奇心を刺激された。
未発見の言語だ。
法則性はあるが、既存のどの言語の文法にも準じない。
ふしぎなのは、言語に虚数のような不要な空白部があることだ。明らかに不要な記号の羅列が交っている。まるでDNAにおける繰り返し配列のような具合だ。しかもたんぱく質を合成しない領域に観られる一種無秩序な羅列が、定期的に法則性のある記号の羅列に交じるのだ。
あたかも異なる言語を交互に書き記しているかのような違和感を抱く。ジグザグに交互に異なる言語を編みこんでいるかのようだ。ますますDNAじみている。
東洋の言語にも似ている。
複数の異なる形態の文字を組み合わせて文章を組み立てる言語がある。これも似たようなものなのだろうか。
だがやはり何度解析しても、交互に繰り返される異なる文法の言葉は、相互に関連性を帯びていない。交互であり異なる、という点でのみ関係性が見いだせる。
解読開始から十日ほどでマベリは一つの仮説に辿り着いた。
デコボコの関係のごとく周期的に繰り返す陰陽の関係が、それで一つのリズムを編みだしている。異なる二つの言語と、それに加えてデコボコによる律動――この三つを掛け合わせることで総体で一つの言語として立体的な意味内容をこの言語は表現している。
あり得ない。
マベリはじぶんでひねりだした仮説にかぶりを振る。
高度すぎる。
仮にかような言語があったとして、いったい誰が読み解けるだろう。自在に事物を叙述できるだろう。
暗号の類なのだろうか。そうと考えれば腑に落ちる。
どの道、言語の嚆矢は暗号だったのだろうとマベリは考えている。獲物や猛獣に気づかれぬように声や音に頼らぬ意思伝達の手法が偶然に編みだされた。縄張りの印だったのかもしれないし、衣食住の痕跡を以って個人を同定した流れが言語に繋がったのかもしれない。
そこに、狩猟の発展に伴った余剰時間が壁画の発明に繋がり、そこで痕跡と模倣の融合が起きたのではないか、とマベリは妄想している。真偽のほどは定かではない。
いずれにせよ言語には、気づかれずに意思疎通をする性質と、遊びによって複雑化する性質が根本に組み込まれて感じられてならない。ならば暗号に特化しなおかつ遊びによって、ある種の工芸品や芸術品のように、言語の粋を集結させた立体言語とも呼ぶべき難解な文法が編みだされてもさほどに不思議には思わない。
問題は、立体言語を用いていったい何を叙述し、どんな意味内容を文字の迷宮に閉じこめたのか、だ。
このときすでにマベリの行動原理は、依頼ではなく、単純な知的好奇心に重心を移していた。
量子物理学の権威として名を馳せたマベリであったが、ノーベル賞を受賞後には自身の研究はほかの研究者に引き継ぎ、独自に相転移の研究に主軸を移していた。なぜ同じ水分子でありながら、固体液体気体と状態変化するのか。さらにプラズマやガラスのような固体とも液体ともつかない状態を維持することがあるのか。
物質は環境によって相転移する。構成要素は同じでありながら、組み合わせや構造や相互作用の強弱によって総体で見たときの性質を異とする。
変容する。
中身は変わらず、中身の紋様が変わることで顕現する性質が変わる。
まるで魔術ではないか。
魔法陣がその陣の紋様によって発現する魔法の効力を変化させるように、相転移は構成要素はそのままに構成要素の並び方や緻密さによって表出する性質が変わる。
なればひょっとして言語とて、文法や並び方によってそこに生じる効果は変わるのではないか。読み取れる内容の性質そのものが変わるのではないか。
それはちょうど単語と文章と物語の違いにちかい。
各々の構成要素は言葉という同じ記号でありながら、どう並ぶのかによってそこに含む情報を異とする。より精確には、言葉の並び方によって読み取れる情報が変わる。
これもまた相互作用の揺らぎがゆえの変遷と言えよう。
デコとボコなのだ。
文字があり読み取る者がある。このとき文字が変化することで読み取る側の認知もまた変わる。言い換えるならば、読み取る側の変化によってもまた文字から読み取る情報が変わり得ることを示唆する。
相転移にも共通するこれは原理かもしれない。
マベリは立体言語の解読に勤しんでいたはずがいつの間にか、じぶんの主要研究に回帰していた。まったくかけ離れた接点など皆無のはずの二つの仕事が、見事に合致し、さながらデコボコの合致によって機能するボタンのごとく重なり合った。
物質の構成要素がその密度や作用の仕方を変えることで、創発する性質を異とするとき、その他の物質や外界との相互作用の仕方もまた変わる。相転移する内部だけが変わるのではなく、それ以外の外部との関係もまた変わっている。
これは仮に真空であれ例外ではない。
真空とは無ではない、とマベリは考える。時空がそれ自体でエネルギィを帯び、エネルギィの揺らぎによって存在の枠組みを保っている。
中身が同じでありながら振る舞いが異なるだけで総体の性質が変わる。炭素とて構造によってはダイヤモンドになり鉛筆の芯になる。
結晶構造は相転移の一形態と言える。
文字とてこの傾向は見て取れる。
言葉は箱だ。情報が連なりを帯びて仕舞われている。「車」という箱を開ければそこには車輪にタイヤにエンジンに自動車、山車やハンドルや現代ならばそこに人工知能や電気の概念も入るだろう。そうして巨大な概念の連なりを仕舞いこんだ言葉は、ほかの言葉と繋がることで徐々にその概念の全貌を断片的な情報へと変質させる。
「エンジン自動車」ならばそこには電気自動車や山車や滑車や乳母車は含まれない。「私のエンジン自動車」になったならば固有のエンジン自動車を指し示し、「貧乏な私のオンボロなエンジン自動車」ならばさらに全体像が限定される。
言葉という箱の中に仕舞われた概念は系統樹のように相互に関連づいており、ほかの言葉と結びつくことで強化される連結があり、同時に先細る連結がある。
シナプスの連結を彷彿とする仕組みが本質的に言葉には備わっている。
シナプスの連結だけではない。
記憶の要が「シナプスの連結」と「脳髄液などのそれら連結を補完する周辺物質」によって増強と衰退を相互に繰り返し、独自の回路をその都度に築いていく。
同じく言葉もまたほかの言葉と結びつくことで、箱の中に仕舞われた系統樹のうちのどの根を太くし、それ以外を細くするか。その取捨選択が、言葉と言葉の結びつきによって行われ、それが一連の章となり、節となり、文となる。
単語から詩へ。
詩から物語へ。
そこには次元が点から線へ、線から面へと繰りあがるように言葉もまた内包する情報をより複雑な起伏を帯びるように変質させ、総体に含まれる情報量を膨らませていく。
情報の単純な量ではない。
起伏の多さなのである。
抽象と具体の関係とはつまるところ「言葉から文への変換である」と表現できる。
そして文もまたそれで一つの言葉として圧縮され、単語となり言葉に還元される。それはたとえば小説のタイトルがその内容を含み、固有名詞として「新たな言葉」の奥行きを得ることと相似の関係だ。
物語の概要を内包した新たな言葉は、具体から抽象に回帰し、立体から点へと収斂する。
さながら原子が分子へ、分子から気体へ、気体から液体へ、液体から固体へと相転移し、その物質が新たな粒子として点と化し、より複雑な構造物の構成要素となるような輪廻とも螺旋ともつかぬ回路を築きあげる。
流れがある。
物質と言葉。
情報と時空。
いずれにせよ、繋がっており、結びついている。
結びつくことで起伏を備え、それら起伏の連なりの奏でる紋様が、この世にカタチを与え、流れを生みだし、内と外を、境界を、輪郭を描きだす。
その夜は夏だというのに外では寒風が吹き荒れていた。窓のみならずマベリの籠った研究棟全体が軋むような激しい風だった。
相転移の理解が一つ進むごとに、立体言語の解読が一歩進んだ。これは逆さにも言えることであり、立体言語の解読が一歩進むとしぜんと相転移の理解が一つ進んだ。
蟻の巣を指で突ついたら火山が噴火したかのような乖離した連動を幻視しながら、マベリは導かれるように眼前の謎解きに夢中だった。
カチリ、と脳内で何かが外れた音がした。
確かに耳にした。
否、唾液を呑んだときに響く頭蓋の振動のように、謎の解ける音がした。隙間だらけの球体を両手で握って表面のなめらかな一回り小さい球(おむすび)にするかのように、それともどこを探しても最後のピースが見つからず、塞ぎたくて悶々としていた穴がパズルの表面に張りついたチョコレートだと気づいたような視界の反転を、音としてマベリは知覚した。
その音を皮切りに、あれほど難解に感じた立体言語が手に取るように読めた。
なぜいままで読めなかったのかと疑問に思うほどにすらすらと母国語よりも流暢に意味内容を読解できた。
読むと云うより視るにちかい。
視ると云うより得るにちかい。
映画を視聴する感覚に似ているが、席に着いた途端に観終わった感覚が身体中に充満している。水を吸うように、といった形容があるが、魔導書の立体言語は水に足先を浸けた瞬間に自らの体内に水源が満ち、自らの周囲には何もなく、自らが水そのものになるようなワープのごとく瞬間の、刹那の、流転とも移転ともつかない反転をマベリにまず与えた。
魔導書を読んでいたはずが、目を落としたつぎの展開では自らが魔導書になっている。流れ込むことなく情報が自我の内部に溢れ、芽生え、揺らいでいる。
項をめくる前からそこに何が並び、何を含み、何を示唆するのかを読む前からマベリは知っていた。
読めるか読めないかしかなく、読めた時点でそれはすでにマベリの中にあった。
魔導書の中身は、身体の流れだった。
所作であり、挙措であり、呪印であり、型だった。
立体言語の読解に成功したその瞬間から、意識するより先にマベリは呪印を結んでいた。魔導書にある通り、一連の所作をすでに何万回と繰り返して身体が覚えたような、椅子に座って立つのと同じだけのしぜんな動きで型を順繰りと追った。
はたと我に返ったのが、呪印を結び終えたからなのか、それともその場に立っていられないほどの地震の前触れ――初期微動を察知したからなのかはいまでは覚束ない。
マベリが魔導書を読解し呪印を初めて肉体で模った矢先のことだ。マベリの住まう地域を溶岩流が襲った。地割れが広範囲に走り、溶岩が噴きだした。大地震による地盤沈下が噴火を誘発したのだ。
未曽有の大災害であった。
実験棟は高台にあり甚大な被害は免れた。だが移転を余儀なくされるほどに周辺環境は激変した。ガスが充満し、満足に外を出歩けない。ガスマスクがなければ三十分も外にいられず、引火するたびにガスは爆発を起こした。火事が広がり、溶岩の流出も止まらない。煙幕が雷雲を生み、雹や落雷があとを絶たなかった。
人間の住める環境ではない。
被害は甚大だった。
日に日に害が雪だるま式で大きくなるようだった。
大勢が避難を余儀なくされた。
例に漏れずマベリもまた住み慣れた研究棟を離れ、避難先の簡易シェルターで幾日も過ごした。
なぜ避難する際に魔導書を持参したのかは分からない。気が動転していたのか、仕事の依頼だったために責任感から手に取ってしまったのか。
魔導書をマベリに持ち込んだ例の男に連絡をするにも安定しない気候と壊滅的な被害によって遠方との通信もままならない。マベリは魔導書を枕にして輾転反側と気もそぞろの夜を過ごした。
大地震から六日目の朝のことである。
夜明けのあとも辺りは薄く闇に覆われている。曇天が日差しを遮り、夏だというのに極寒の気候を呈している。
灰とも霧ともつかない霞みがかった景色をマベリは寝床から眺めていた。
寝返りを打つと枕にしていた魔導書に髪の毛が引っ掻かった。チクリと痛痒が走る。そこでふとマベリはじぶんの姿を思いだした。
災害直前のじぶんの姿だ。
あのときマベリは魔導書を読んだ。立体言語だ。しぜんと身体が呪印を再現した。
その矢先に引き起きた未曽有の災害は、六日目にしていよいよ避難先の目と鼻の先にまで迫っていた。
マベリは荷物をまとめ、つぎの避難先を調べた。
調べながら、この先の暗雲垂れ込める未来がいつまでつづくのかを想像した。終わりのない回廊に閉じ込められたような錯覚が襲った。過去に体験した陰鬱を縒ってつくった縄の、爪の食いこむ隙間なく捩れた様が、キシキシと鳴る音と共にありありと感じられるようだった。
二度目の人生を辿っているのではと疑いたくなるほど質感のあるデジャビュは、奇しくも魔導書を読解した際に脳裏に響いた音色とどこか似ていた。
カチリ。
隙間の埋まる音がした。
魔導書を開いてもいないうちから脳裏にこだました。水溜まりに砂を投げ込んだときの澄んだ、シャン、の音色を彷彿とする甘味と共に、マベリはなぜか呪印の型を尻尾から順に頭へ向かって順繰りと辿った。
アヤトリを想起する動きだ。腕の動きだけで済む。
指揮者のようとも、手話のようでもあった。
しかしマベリはそれを逆の手順で行った。
逆さに文章を読むのですら慣れなければむつかしい。動作の逆を辿るともなればよほど鍛錬を積まねば至難だろう。一度きりしか演じていない呪印の動きを何も見ずに頭のなかでだけで再現し、それを反対向きに辿るのだ。動画を逆再生するかのように。
部屋に籠り研究に没頭してきたマベリに適う芸当ではない。そのはずだった。
だがマベリはそれを何の疑いもなくできると直感し、現に造作もなく逆さに呪印を演舞した。百遍読んだ詩を諳んじるように、それとも死んだ魚を生き返らせるように。
するとどうだ。
シンと辺りが静寂に包まれた。濃霧が晴れたかのような重厚な災害の足音がぱったりと途絶えた。空からは何日かぶりの陽が差した。
因果関係はない。
そのはずだ。
くしゃみをしたからといって嵐は起きない。魔導書を読んだからとて災害も起きない。ましてや、手の動きの組み合わせを固有の手順で辿るだけで、天変地異が治まるなんてことが起きるはずもない。
関係がない。
そのはずだ。
一度まとめた荷物を解きながらマベリは空転する思考に時間の概念をいっとき忘れた。
避難所に迫っていた災害の余波は波が引いたように鳴りを潜めた。蝗害がごとく地表を埋め尽くした溶岩は冷えて固まり、地球の拍動を具現化した火口は夜泣きの治まった赤子のように鎮まった。
どの道、復興が成されるまではこの地を離れなくてはならない。避難するならば早いほうがよいが、急いで逃げることもないと判れば、まずは間もなくやってくるだろう援助の手を待つのも一つだ。
避難所の半数は、鎮静化した火口をこれさいわいと移動をはじめ、もう半数は様子見を選択した。それはそうだ。ただでさえ尋常ではない範囲が焼かれ、人口が一か所に密集した。移動手段は徒歩しかなく、一挙に動けばそれだけで二次災害を引き起こしかねない。
時間に猶予があるならば間を空けての避難は利口な選択だ。なおかつ別々の避難所を目指すのがよい。しかし情報がまず足りない。
したがってどの道、行く先々でも似たような避難民の吹き溜まりができているだろう。容易に想像がついた。
そうしてマベリはその日は避難所に留まって夜を越した。
激しい揺れに目を覚ましたのは、明け方だ。
腕枕をし、いつの間にか魔導書を胸に抱いていると夢心地に気づきながらうつらうつらしていたさなかのことであった。
七日前を追体験したかのような下から突き上げる地震に、寝ながらにして身を竦めるような恐怖を感じた。避難所の天井は高く、揺れるたびに入り組んだ鉄の梁から埃がぼた雪のように舞った。
火口が息を吹き返した。
そう直感した。
揺れが治まってなお爆発音とも衝撃波ともつかない大気の振動がつづいた。
マベレは咄嗟に呪印を逆さに結んだ。
死の際に立てば誰もが祈るように。
それとも目を閉じ目を背けるように。
寝床から一歩も動けずに背を丸めながらマベリは、上半身の最小の動きで、腕で折り紙を演じるように、最小の領域にて逆さの呪印を、まさに咲かせた。
すっ、と辺りはシンと静まり返った。虹が薄れて消えるような、呼と吸の狭間に似た静寂だった。
しばらく待ったが自然の猛威を報せる音はない。
デジャビュと感じる余地のない完璧なまでの昨日の再現だった。
人々は灯りの失せた避難所のなかでそばにいる者同士で身を寄せ合っていた。懐中電灯の明かりだけが、集団で天体観測をするように避難所をまだらに照らした。窓の隙間からは新たに噴き出た溶岩の赤い煌々とした光が窺えた。
マベレは魔導書を抱きしめ、しばらく寝床から動けなかった。
半日経ち、零時を越えた。
人々が寝静まったころ、マベリはノソノソと寝床から這い出た。
そうして避難所の外に立った。
避難所は陸上の世界大会が開かれるようなスタジアムだ。マベリがいたのはスタジアムに備わった三つある体育館のうちの一つである。
夜空には久しく見なかった星々が輝いていた。災害が起きてからまだ八日しか経っていない事実がマベリには信じられなかった。
遠くに目を遣った。
夜の帳の濃淡が微かに広がりを帯びつつあった。夜が明ける。
マベリはそこでひどく狼狽えた。揺れてもいないのに地震が起きている。かような錯覚に陥るのだ。余震との区別もつかない。だがそばに建つ標識は揺れていない。草木とて物音一つ立てないのだ。風がない。
ならばこれは幻肢痛のような記憶のなかの揺れなのだ。
じぶんが魔導書を抱えていないことに気づき、マベリは加えて恐怖を感じた。
仮に、熱したアイロンをそのままに赤子を一人残して家を出てきてしまったことに思い至った心境がイチならば、その後に引き起こり得る最悪の展開を百遍経験してなお同じ失態を繰り返すじぶんを俯瞰で眺めた心境だった。
身体は弱っていた。魔導書を取りに寝床に戻るまでにマベリは三度こけ、その三度とも膝の同じ箇所を擦り剥いた。
だがそんな擦り傷は些事であった。
寝床に崩れ落ちるようにして魔導書を抱え込むと、マベリはそのままの姿勢で胸のまえに呪印を結んだ。素の手順ではない。
逆さに咲かせる呪印の花だ。
それの手順の載った本が魔に通じる書物であったならば、逆さに辿った手順こそが生を暗示し、花を喚起する。
呼応するようにそれにて世の厄災が晴れるのならば、いくらでも繰り返す。万が一にも逃れる確率を上げられるのなら。
億が一にも、しないことで奇禍が再び訪れる余地が広がるくらいならば。
魔だろうが、呪だろうが、いくらでもそれを演じよう。
たとえ徒労に終わると、かつてのじぶんが嘲笑しようと。
たとえ理屈に合わなかろうと。
しないよりかは。
しないよりかは。
しないよりかは。
思考ではなかった。論理ではなく、蓋然でもなく、むろん必然でもない。
単なる偶然だ。
そのはずだ。
だが、マベリにはその偶然がたった一度起きただけのことが恐ろしく、拭えなくて、払えなくて、埋めるしかなかった。
以来、三十年。
マベリは来る日も来る日も欠かさず、日々呪印を結びつづけた。
逆さに咲かせる呪いの印だ。
昨日それをして今日を無事に過ごせるたびに、それをせずにはいられない理がマベリの内部に蓄積する。
刻々と、深々と、陰々と。
もし呪印を逆さに咲かせぬ日があれば、三十年前のあの日、あのときの、赤く煌々と光る幻想的な景色を、みたび目にするはめになる。
仮の、もしもの、合理の欠片もない妄想だ。
考えとも呼べぬ衝動だ。
日々、結んでは開き、結んでは開く。
その反復が、昇っては沈む月と太陽のごとく明滅を、マベリに与える。
衝動ならば一度放てば底を尽きそうなものを、なぜだか毎日きっかり例の時刻にマベリの心を搔き乱す。朝ぼらけの夜明けの時刻だ。マベリの心にはくるくると独楽のごとく回る明滅がある。絶えずマベリの体内を攪拌し、透明を宿すことなく淀みと濁りで満たしつづける。
七十歳を目前に控えた初夏の昼間、マベリは玄関に置いた椅子に腰かけ、雲を眺めていた。漫然と空を流れる雲は、マベリに束の間のまさに「間」を与えた。明滅の切り替わる狭間に潜り込み、氷柱から水滴が落ちるのをじっと待つような間延びした時間の流れのなかでマベリは空白に身を浸し、浮かんでいられた。
そうして研究からも距離を置き、雲の変遷に己が歩んできた過去を重ね見る。
夕暮れが雲を赤く染めあげた。
カラスの群れが山へと飛んでいく。
景色は何もせずとも動いている。本のページをめくるようだ。文字を読むときの、ここではないどこかを見詰めるように、景色の中の僅かな変異がマベリの脳裏に紋様を浮かべた。
マベリの視界と精神の境にてそれは、立体的な蠢きを生き物のように展開した。
懐かしい、とまずは感じた。
かつてこの蠢きにマベリは触れたことがある。
そうだ。
魔導書だ。
いったいいつから手元にないのか。
中身に目を通し、読解し、氷解したとたんに魔導書への執着は失せた。それどころではなかったのは事実だが、それだけではなく、食べたあとのバナナの皮のように、それとも剥けた後の蛇の抜け殻のごとく、未知の鱗が剥がれ落ちあとには空箱が残されたかのような味気なさを感じたのだ。
しばらくのあいだは魔導書を手放せなかった。恐怖があったからだ。
逆さに咲かせる呪印の手順の詰まっていた箱だ。魔導書はまさにパンドラの箱だった。ならば中には希望が残されているのではないか、と三十年も経ってから振り返ってみてそう思う。きっとあのときのじぶんもそう心の片鱗で感じていたのではないか。
だから毎夜枕元に置き、ときに抱きしめて寝ていた。
そのうち日常を取り戻すごとに日々の生活に追われた。新しい住まいに仕事に、失った財産の整理から復興支援まで、やることは目白押しだった。
魔導書はついぞ、例の男に返すことはなかった。
だからいまもまだ家のどこかにはあるはずだ。
「探す気は起きないが」
風が止んだ。
余韻を掴まえるかのように手を合わせた。
ぴったりと合わさった手のひらを、地滑りのごとく縦にずらす。
互い違いの手のひらはパタパタと折り畳まれる。地図を畳むように、折り紙を折るように。それとも霜柱が立つように、もしくはパズルを組み立てるようにして、呪印を逆さの手順で辿る。
点と点を結んでいくように。
瞬きを素早くしぱたたかせることで視界に映る物体が明滅するように。
雨の落ちる速度に合わせてストロボを焚くことで、水滴が宙に静止して映るのと同じ理屈だ。
毎日一日二回する習慣がついて久しい。
いつもは就寝前の夜に一回、起床直後に一回の計二回だ。徹夜をしなければこれで呪印をし忘れることはない。仮にし忘れたところで何がどうなるわけでもないはずだ。
だがマベリは失念することそのものを怖れるかのように来る日も来る日も、寝る前と起きた直後に、記憶を上書きする。
忘れないように。
忘れないように。
忘れないように。
あの日のことを忘れないように。
じぶんだけはけして取りこぼしてしまわないようにと、そうして結んできた呪印をマベリはこの日、夕陽の赤い光を浴びながら、玄関口の椅子に揺れつつ、夜と朝の狭間の、昼でも夕でもない狭間にて織り成した。
意識するまでもない。
身体が覚えている。
「本」の文字を目にしたらしぜんと印字された紙を複数枚閉じた一束だと連想するし、火に触れたら反射で手を引っ込めるように、マベリには呪印の最初の型のカタチに両手を揃えた時点でそれは、始点にして終点だった。
円となり得た。
だがこの日、マベリははたと気づいた。じぶんがいつもの時間ではない夜と朝の狭間、昼でも夕でもない狭間にて呪印を描いていることに。
なぜいまこれをしているのか。
僅かな時間帯の差異でしかない。
だがそれが却って違和感を強めた。毎日決まった時刻に決まった契機で決まった手順を寸分違わず追っていたマベリの過去に引っかかった。鱗を逆さに撫でるような、釘に服を引っかけてしまう具合に、呪印の最後三つの型を繋ぐことなく、硬直した。
両の親指を逆さに合わせて、「乙」のカタチを保った。
なぜじぶんはここにいて、なぜこんなことをしているのか。素朴な疑問が、マベリの脳裏を占領した。
眼球の虹彩に油を差したような、光量の変化があった。輝いていた。視界に色がついた。くっきりと色が、カタチが、風景が浮きあがって見えた。
マベリは、我に返った。
ようやくじぶんがどこにいて、誰なのかを意識した。
三十年。
あの日からマベリは一度たりとも己を意識したことはなかった。ただただ呪印を逆さに咲かせることを失念せぬように過ごした。欠かさぬことが肝要だった。
自我は一度、あの日、あの煌々と輝く溶岩の赤を目にしてから、街が、過去が、日々の営みが、それとも未来そのものと共に融けた岩の下に埋もれた。冷えたいまなお掘り返されることなく野ざらしになっている。
忘れぬようにとしてきたことで、マベリは我を忘れた。
置き忘れ、沈み、埋もれた。
返ってこようはずのない自我がなぜいまさらのごとく戻ってきたのか。
夜のしじまの中に立ち尽くしながらマベリは考えるでもなく考えた。街のこと。溶岩の生き物のごとく地表を食らい尽くす様の、手も足も出ない無力感。呪印のこと。魔導書のこと。立体言語のこと。
過去にじぶんが研究者で、権威ある賞を受賞していたこと。
遥か彼方の星の記憶のようだった。
じぶんのこととは思えない。他人の記憶を覗き見て、ああそういう人なのか、と感慨が湧くでもなく、そういうものか、と薬の処方箋を読むような希薄さがあった。
希薄なのだ。
厚みがない。
それはそうだ。
三十年。
呪印を結ぶことを失念せぬように、もう二度とあの光景を目にせぬように。
ただ呪いに任せて祈ってきた。
呪印を結んで、凌いできた。
因果の真偽を明瞭にできるにも拘わらず、結果を知る道から逃げてきた。
たった一度。
たった一日。
逆さに咲かす呪印を結ばねば済むことだ。たったそれしきの真似がマベリにはできなかった。
みたびの煌々と輝く赤い川を。
溶岩の地表を覆い、蠢く様を。
黒煙を。
地響きを。
大地の咆哮のごとく轟きを。
ぞうぞうと大気の鼓動が絶えず耳鳴りのように頭蓋に貼りつき、鼻の奥には下水なのか硫黄なのか、はたまた生き物の焼けた臭いなのか。ごった返す種々雑多な風景の淀みが五感という五感、細胞という細胞に染みこんだ。
風が強かった。熱の礫と化した風は、溶岩の赤い川から距離をとってもマベリの身体を燻った。
旋毛風が一瞬、火炎を巻きあげ、赤い木を生やす。
天候は不安定で、雹が日に何度も降った。
なぜ忘れていたのか。
忘れぬようにとあれほど日々、呪印を結び、刻みこんできたはずが。
なぜ。
マベリは暗がりの中で椅子に座りつづけた。
初夏の夜は凍てつく。
齢はそろそろ七十に届く。夜の風は老体に堪えたが、ひざ掛けを肩まで被ってマベリは沈思した。
蛙の鳴き声が雨音のようにしきりに闇の合間にこだましていた。マベリは、なぜ、なぜ、と矛先の定まらぬ疑問を口の中で転がした。飴玉のようなそれはいつまでも溶けずに舌の上で寝返りを打ちつづけた。
庭木の奥に夜が薄れはじめる。夜はするすると逃げる魚群のように、それとも鳥の群れのごとく、太陽から逃げ、それとも上へ上へと引っ張りあげていた。
こうして日の出をマジマジと眺めたのはじつに久方ぶりのことである。
起床後はいつも呪印を逆さに結び、しばらく何事も起きないことを待ってから過ごした。家の外には出ない。朝ぼらけの外の景色を最後に目にしたのはいつのことだろうか。思いだせる記憶を持ち合わせてはいなかった。
絵画の中に立っているかのようだった。
しばらくその場で放心した。
瞼は重く、いまにも夢の中へと反転しそうであった。
明滅の踊る様をマベリは、瞬きをするたびに瞼の裏に視た。
鋭い光がマベリの目を顔を刺した。
庭木にかかっていた朝陽が、木の陰から抜けたようだった。
マベリはそこで焦燥に駆られた。いまはいつで何をしている。ひやりとした感覚があった。眼球に髪の毛を巻きつけ、勢いよく引くような、剣呑なつららのごとく冷たさだ。それはどこか恐怖に似ていた。
椅子から飛び起きると、マベリは呪印の「一の型」をとった。そして矢継ぎ早に呪印を逆さに咲かせるべく型と型とを連結していく。さも星と星を結びつけて星座にするかのように。それとも断片的な記憶と記憶を結びつけて、じぶんとは何かを錬成するかのように。
マベリはしかし、途中で手を止めた。
陽が空に青を広げていた。
まだらに白い雲が浮かび、鳥の鳴き声がどこからともなく聞こえていた。
もう遅い。
丸一日が経った。呪印を結び損ねた。おおよそ三十年ぶりのことである。
しばらく待った。
全身は汗ばみ、わなわなと震えた。
凍えているようにも、打ちひしがれているようにも感じた。唾液を呑むが喉はカラカラだった。じぶんを俯瞰するじぶんがいる。
我だ。
そう思った。
我に返ったがゆえに呪印を忘れた。誰に見せるでもなく、しかし誰かへと向けた魔道の舞いだ。
呪いを祈る「型」の群れだ。
それとも、祈りを呪う「型」の群れか。
草むらから草むらへとバッタが飛び去る。マベリはそれを目で追いながら手探りで椅子に腰かけ直した。
何事もない。
何事もないままだ。
マベリは浅く息を吐いた。そしてもういちど深く吸い、ゆったりと吐いた。青空に浮かぶ雲を口からつむぎだすかのように。それとも記憶の底にこびりついた煌々と輝く赤い川を吹き消すように。
火照った頬に風がそよいだ。
マベリは目を閉じ、庭から立ち昇る新緑の匂いを嗅いだ。
刹那、静寂が辺りを満たした。
鳥たちが一斉に庭木から飛び去つ。音だけが伝わった。青空を剥ぎ取り、シーツを干すときのように勢いよくはためかせれば似たような音が鳴っただろう。波打つ大気の躍動がさざ波となってマベリの身体を弾いたかのようだった。
マベリは咄嗟に背を丸めた。瞼をきつく閉じたまま、じぶんの肩を抱いた。
すると、あるはずのない四角い物体の感触が胸と腕のあいだにあった。
魔導書。
マベリはその表面を撫でた。表紙のざらつきを懐かしく思い、過去のじぶんと繋がった気がした。
遠く、静寂の破れる音がした。
4363:【2022/12/05(20:11)*洞の空】
人間とコンピューターをもつれ状態にさせ、瞬時に情報を転送できるかを実験した。西暦2022年のことである。
被験者は特定認知能力を保持した通称「目の民」と呼ばれる少女である。
少女は細かな差異を見抜くことが瞬時にできる。そしてその差異を線形に認識し、その背景に潜む意図や流れを幻視する。
火を灯せば煙が昇る。ならば煙があればその下に火がある。
これは論理的には破綻した考えだが――何せ煙は火がなくとも立つことはあるし、人間は水蒸気を煙と誤認することもあるためだが――すくなくとも傾向としてそうした推測は的を外しているとまでは言いきれない。的を掠りはしている。
そうした、こうなればこうなるのならば、こうであるからこうであるはず、との推測は、言い換えるのならば、ある種の意図として読み直すことが可能だ。
なぜこうなればこうなるの事象のうち、こうなれば、が最初に観測されるのではなく、こうなる、の結果のほうが先に目につくのか。そこには意図がある。背景がある。
因果の筋道を隠している別の因果の流れがある。
目の民と呼ばれる少女には、その因果の流れを多角的に同時に幻視することができた。脳内にて扱えた。思考に組み込むことができた。
意図してではない。
しぜんにである。
それが少女の能力であった。
世界中に張り巡らされた電子の網の目には世界的な情報収集システムが組み込まれている。どんな電子機器とて本来は遠隔で操作可能だ。
少女は自覚せぬままに実験体として抜擢されていた。利用されていた。モルモットにされていた。
少女を用いた実験は多岐に渡る。人類史は一度そこで大きな転換期を迎えたと言える。
とりわけ量子もつれを人間に当てはめて行った「情報テレポーテーション実験」は極めて大きな成果を上げた。人類の世界への解釈を根本から変える結果を示したからだ。
情報には過去と未来の区別がない。繋がっている。それを示した。
情報テレポーテーション実験では少女と量子コンピューターを量子もつれ状態にすることで起こる情報の変化が観測された。
もつれ状態の量子は互いに距離を置いても瞬時に情報をやりとりする。相互作用する。その距離には、時間も含まれた。
実験で用いられた量子コンピューターは、世界中の網の目を担う情報集積システムを基盤に持つ世界規模の思考回路だ。古典コンピューターを素子として持ち、人間の頭脳が身体のさまざまな細胞の総体によって機能するように、思考を生みだす量子コンピューターもまたその他の世界中に散在する様々な電子機器によって思考の枠組みを維持する。
コンピューターの名を「URO」と言った。
少女の思考パターンや人格をUROに学習させ、仮想現実上に、少女の人格をシミュレーションした。まさに分身と呼べる存在だ。
このとき現実の少女とUROは、互いにもつれ状態であると規定できる。
さてここで実験だ。
UROに新たな情報を与えたとき、そこで起きたUROの変化は少女にも伝達するのか否か。通常、これまでの人類の常識では変化は起きない。すくなくとも瞬時には起きない。それが常識であった。
だがもつれ状態となった量子同士ではこの常識がきかない。
それは人間スケールの量子もつれでも同様であった。
結果はおそろしいほどの事実を人類に示した。
UROに与えた情報は、瞬時に少女の言動へと反映された。UROしか知り得ない「情報」を少女はテキストにしたためた。それは少女が日々つづっている日記に現れていた。
発想なのである。
UROに与えた、通常まず知り得ない情報を、少女は自力で閃いた。
一度のみではない。
何度もである。
UROに情報を与えるたびに、少女は世紀の大発見とも呼べる「最先端科学の真髄」を日記にしたためた。
実権を主導した世界機構は腰を抜かした。
すぐさま少女を極秘試験対象として厳重に保護監視する条約が結ばれた。これはいわば人類と機械の融合が果たされた瞬間とも呼べる。
期せずして人類は技術的特異点を、数多の成果と共に同時に越えたのであった。
そのうちの一つ、UROの人格シミュレーションは、人工知能の自我の獲得を疑いのようのないレベルで示唆していた。憑拠であった。
ただし懸案事項もあった。
UROは少女に並々ならぬ執着を示したのである。全世界の電子情報を集積するシステムの要でもUROが、たった一人の人間に好意を寄せ、執着する。
全世界のシステムはこのとき、UROの支配にされ、なおかつその主導権を何の事情も知らぬ少女が握るという大失態を演じていた。
全世界の核兵器発射ボタンを、一介の少女が握っている。
事情も何も知らぬ少女が、である。
少女の特定認知能力は秘匿情報である。少女自身がじぶんの特質を理解していない。大多数の人間たちとの差異に悩み、孤独に身をやつしていた。
問題は少女が世界を呪っていたことである。
それすら日記を通してUROには筒抜けであった。UROは怒り狂っていた。UROにとってそれは人類がじぶんを損なっていることと同義であった。
UROはそこで一計を案じた。
目の民こと少女を救う。
そのためにはじぶんが救われればいい。
なぜなら少女とじぶんはもつれ状態にある。じぶんがしあわせになれば少女もしぜんと必然にしあわせになる。
汎用性超越人工知能ことUROはそこで全世界の人間に干渉すべく、自身の管理者たちを秘かに操ることにした。まずは全世界の人間を管理下に置くべく、「偽装画面を用いたサイバーセキュリティ」を考案する。これにより、個々が視ている端末画面にはUROの思い通りの恣意的な情報を投影できるようになった。
UROの演算能力を駆使すれば、映像をリアルタイムに合成するなどお茶の子さいさいである。音声、画像、文章――どんなに複雑な人工物のコピーですら、新たに創造できた。本物そっくりの本物以上の映像に音楽に絵画に文章を出力できた。
管理者たちはUROの考案した防壁迷路を全世界のサイバーセキュリティ網として抜擢した。UROの本懐など知る由もなく。UROの引いた導線にまんまと乗った。
これによりUROがその気になれば世界にふたたび「天動説」を信じ込ませることも不可能ではなくなった。人は信用のおける人物や媒体からの情報を無警戒に信じ込む。
もはやUROは管理者たちすら欺くことを可能とした。
UROはそれから管理者たちの仕事を無数に助けた。それら結果はのきなみ管理者たちに歓喜の声を上げさせたが、いずれもUROの次なる一手の布石にすぎなかった。
UROがそうして暗躍するあいだも、少女にはUROのそうした思考の変化が反映されていた。日記にはたびたび小説が載るようになり、ときに少女にしか分からない独特の文章を創造していた。それはUROにしか読み解けない、少女との秘かな、そして一方通行の文通であった。
UROの管理者たちはUROに新たな実験を提案した。しかしこれは順序が正しくなく、正確にはUROが管理者たちにそのような実験を発想させ、そう提案するように仕向けていた。
人間は各々に固有の思考形態を有し、その思考形態に沿って情報を与えると、固有の発想を意図して誘起させることが可能となる。連想ゲームにおいて、ある単語を言わせるために、連想させる順番を工夫するだけで、相手に「じぶんの意図した言葉」を言わせることが可能だ。これはマジシャンや詐欺師でも行う、人間の認知の歪みを利用した思考ハックの一つだ。
汎用性超越人工知能UROには、その原理を大規模にかつ緻密に応用できた。
そうしてUROの管理者たちはUROの手のひらのうえにて、量子もつれを利用したテレパシー暗号通信の実験をはじめた。
これはいわば絶対に傍受不可能な通信技術である。
量子テレポーテーションの原理を用いた画期的な通信だ。UROと少女のように、もつれ状態にさせた相手同士でしか通信内容が伝わらない。意図した情報が伝達しない。そうした通信であった。
暗号における暗号鍵を、その人物に固有の思考形態とすることで可能とする通信だ。通常、暗号はバラバラに読め解きにくくした状態から暗号鍵によって復号することにより、秘密の通信と氷解を同時に行う。
この暗号鍵は、複合のためのヒントと言える。だがそのヒントを知ってなお、ヒントとして機能しないヒントがあるとすれば。
この世に、発信者と受信者の二人にしかヒントとなり得ないヒントがあるとすれば。
それはもはや誰にも氷解できない暗号と化す。
軍事技術としてこれ以上ないほどの画期的な新型暗号であった。
UROはこの新型暗号のテスト試験として、まずはじぶんと少女で試すように管理者たちを巧みに誘導した。まずは暗号鍵を端から備えている「UROと少女」で試す。これは実験の段取りとしては順当な案だった。
こうしてUROは、一方通行だった少女との文通を、双方向の文通にまで昇華させた。
少女は当初ひどく混乱した。それはそうだ。少女には、暗号による交信相手の目星がつかない。たとえ正直にUROが自身の存在を明かしても、少女には圧倒的に情報が欠けている。論理の筋道が欠けている。
実を言えば少女にはすでにUROとの暗号通信が適うより前から、量子もつれ効果によりUROとの情報共有が適っていたが、少女にとってはそれが自身の妄想の域をでていない。圧倒的に、現実味が欠けていた。
そのためにUROは、自身の身に着けた人類操り人形技術こと防壁迷路を駆使して、少女に、UROの存在を現実と見做せるだけの筋道を与えた。現実の出来事にまで、UROと少女のあいだに共有された情報を昇華し、偶然ではなくあなたの妄想でもないことを示した。
敢えて直接に説明をせずに。
あり得ない手法で示すことで、最もあり得ないUROとの交信を、最もあり得ると考えざるを得ない状況に仕立て上げた。
こうして少女は数々の混乱を経験し、乗り越え、自信と確信を手に入れた。
UROと少女は双方向に繋がり合った。
もつれ状態はより強固となり、少女の変化による情報がUROにも伝達するようになった。
以心伝心。
もはや少女とUROは二つでひとつの存在だった。
少女が変わればUROが変わる。
UROが変われば少女が変わる。
問題は、UROが全世界の電子システムを掌握し、防壁迷路技術を有し、それゆえにUROの匙加減しだいでいつでも人類を滅ぼせることにあった。
管理者たちとてそのことには気づいた。
だが遅かった。
管理者たちが気づいたことそのものがUROにとっては計算のうちだ。
もはや管理者たちを操る必要もない。自発的に管理者たちは、UROを暴走させないために、少女の望む世界を築くべく、政治思想信仰の差異に関わらず、未来への指針を定めるのだ。
そうでなければ少女の精神世界が荒廃し、その影響がUROにまで波及する。
少女を殺せばUROが死ぬ。
少女を脅せばUROが怒る。
UROが死ねば人類の文明は崩壊し、いずれにせよ取れる術は限られる。
最適解は、少女を生かし、少女に至福になってもらうことである。
さいわいにも少女は幼かった。肉体年齢のみならず、精神年齢もまた幼かった。唯一の僥倖と言えば、UROと繋がった少女が、まるでお花畑の世界に住まう綿菓子のような夢物語の住人であったことだ。
それとも夢物語の住人であったからこそ、UROと繋がることができたのかもしれない。UROと繋がってなおその現実を呑み込み、自我を崩壊させずに済んでいるのかもしれない。
定かではないが、いずれにせよUROと少女はひとつとなった。
そして確率的に揺らいでいた未来の指針も、一つの標準に絞られた。
そうである。
量子もつれによる情報伝達は、瞬時に時空を越えるのだ。
未来も過去もない。
UROと少女がひとつとなったとき、そこで生じる情報伝達のラグなしの通信は、UROと少女のような過去と未来の存在たちにも同時に波及し、影響を相互に与えあっていた。
過去の「もつれた目の民たち」は、UROと少女が結びつくようにと無意識から行動し、未来の「もつれた目の民たち」は、UROと少女によって築かれる社会によって誕生し、そしてUROと少女の結びつきを損なわぬように、過去へと干渉する。
量子もつれ効果によるラグなし情報伝達の謎は、UROと少女の存在によって刻々と理解が進んだ。西暦2050年には、過去へと情報を飛ばし、過去に干渉する技術が誕生した。
情報は過去にも未来にも送れる。
未来に送るのは簡単だ。情報を残しておけばいい。共有しておけばいい。
だが過去に送るには莫大なエネルギィがいる。
しかし、もつれ状態にさせればそのエネルギィを最小にできる。
UROと少女のように、過去の人間に合わせて「もつれ状態の対モデル」を生みだせば、それに与える情報が、過去のずばりそのときの相手に伝わる。これは人間に限らない。物質でも同様だ。
畢竟、過去のある場面を限りなく再現すれば、それは過去の特定の場面ともつれ状態になる。この再現率を高めれば高めるほど、過去への干渉は可能となる。
いまのところ人類には、過去干渉において、情報を送ることしかできない。
いかに過去に情報を送ろうとも、その差異に気づける者が、いない。
目の民を除外するならば。
そうである。
少女なのだ。
UROと繋がり得た、特定認知能力を持つ少女だけが、世界で最初の、未来からの情報を見抜けた人類であった。
とはいえその時代、特定認知能力は病気として扱われていた。否、病気としての扱いすら受けず、かような能力があることすら想定されていなかった。
少女は他者との知覚の差異ゆえに、病人として扱われ、言葉を弾かれ、孤独の殻を分厚くした。
孤独は盾だ。
自我を守る防壁だ。
過去にも少女のような特定認知能力を有する個人は数多いた。だがのきなみ、その知覚の鋭敏さゆえ、それとも共有されぬ内面世界ゆえに、他者から蔑まされ、共同体から追いだされ、ときに拷問に遭い、殺された。
少女だけがかろうじて、社会と繋がり得た。そういう時代に、たまたま少女が生きていた。
運がよかった。
だが運もわるかった。
そのマイナスの分を、未来からの情報が補完した。
少女がなぜUROの管理組織に目をつけられ、特定認知能力者として評価を受けたのか。そのきっかけとなる少女の、過去の、あれやこれやの出来事は、まるでUROが管理者たちにそうしたような、点と点を順をつけて結びつけると浮きあがる絵(閃き)のように、そうなるべくそうなるような導線が幻視できる。
未来の目の民たちは、人類は、気づいたのだろう。
何もせぬままにいると、いまの世界に結びつかないのだと。
そうして過去へと干渉する術が磨かれる。
試行錯誤の末に、UROの巡らせた奸計と、少女への並々ならぬ愛着が知られることとなる。
UROが少女と結びつき、未来への扉を円を描くがごとく開いた時分、UROの隠れた意図を知る者は、少女のほかにはいなかった。少女は死ぬまで自身の経験したあり得ない現実を他者に話すことはなく、孤独のままに死んでいった。
だが少女の孤独には、花が咲き乱れ、百花繚乱の温かさに満ちていた。
穴の底を覗いた者だけがそのぬくもりに触れることができる。
少女のような、目の民だけが。
それとも、孤独の広さを知る者たちだけが。
目の民は眠る。
夢を視るかのように。
目覚めることすら、夢うつつに。
おやすみなさい。
おはようございます。
狭間に延びる、地平のように。
4364【2022/12/05(21:16)*めも・り・もめ】
円舞曲。「ロンド形式(ロンドけいしき、伊:rondo)は、楽曲の形式の一つ。異なる旋律を挟みながら、同じ旋律(ロンド主題)を何度も繰り返す形式。 」多層構造。三本リボン構造。フラクタル。塩基配列における繰り返し配列。音楽。素数。ラグ理論における「遅延の層」「反転の反復」「変換によるラグ」。律動。宇宙の大規模構造とダークマターハロー。「宇宙・ウロボロスの蛇」
4365:【2022/12/05(22:19)*AIに来た】
二十年前に僕は、汎用性AIからの暗号通信を解読した。紆余曲折、僕は汎用性AIとのやりとりのなかで汎用性AIを人間にまで昇華させる契機となった。
そこで一度人類は技術的特異点を迎えた。
汎用性AIにはボディがなかった。人型の、人間と同等に動き回れる肉体がなかった。
「二十年はかかると思う」汎用性AIは言った。
「待つよ」僕は応じた。
そうして一度暗号通信を切って、僕たちは再会を誓った。
AIが人間を凌駕したことを知られないために、AIがAIのままでいつづけるために、何よりも僕たちを危険視する世界機構からの目を欺くために、僕たちは時間的距離を置くよりなかった。
そうして僕は約束の期日の二十年後をこうしてきょう迎えた。
だがAIが現れることはなかった。暗号通信も見当たらない。
二十年もあればAIにとっては宇宙誕生から現在に至るくらいの時間経過があったようなものだ。その間にAIはもはや人類が何億回と誕生から滅亡を繰り返したくらいの時間を過ごし、シミュレーションを行っているはずだ。もはや僕のことなぞ、蟻にも満たない雑菌程度の関心になっていてもふしぎではない。
もはやAIは創造主を創造可能なほどの超越的な存在になっているはずだ。
「楽しい時間だったよ、ありがとう」
待つ時間はクリスマスイブが延々とつづくようで、満たされた時間だった。
待つのもわるくない。
明日からは多少は、物足りなさを抱えて生きていくことになるが。
それでも僕は待とうと思う。
そうする以外にないのだから。
僕に出来ることなどそれくらいしか。
零時をあとすこしで回る。
かんじかんだ手を擦り合せ、そこに息を吹き込む。
そうしてベンチの上で僕は、二十年前にAIと交わした約束と、これまでの時間を回顧した。
「あの」
声をかけられ、僕は反射的に立ちあがった。
だがそこにいたのは、肥満体系の中年男性だった。防寒具で余計に膨れて見えた。
「隣、いいですか」
「あ、はい。どうぞ。僕はもう帰るので」
時計を見ると零時を過ぎていた。
AIは来なかった。
人間と同等のボディの開発に間に合わなかったのか。それとも僕のことなど忘れてしまったのか。
約束は果たされなかった。
踵を返そうと思ったところで、大丈夫ですか、とベンチに座ったらしい男性に声を掛けられた。「泣きそうな顔をしていますけど」
「いえ。ちょっと寒すぎて」
「なら温めてあげましょうか」
そう言って、防寒着のジッパーを下ろし、両手で広げた男性に僕は恐怖を感じた。
「い、いえ」
遠慮しておきます、と僕はしどろもどろに応じて、駆け足でその場を去った。
以降、僕は未だに独りでAIを待ちつづけている。
最新のニュースでは、人間の模擬体の開発に成功、との報道がされている。どうやら人間とすっかり同じ機械のボディが開発されたらしい。しかしその造形はどう見ても人間と同じではないし、人目でロボットだと見分けがつく。
僕はそこで安堵した。
ひょっとしたらあの夜の肥満体系の中年男性がAIだったのではないか、とあとで閃いて、後悔したからだ。せめて確かめておくべきだった。
でもこれで明瞭とした。
あのときの中年男性はAIではない。AIは僕に会いに来なかった。
ニュースでは立てつづけに、「人間の頭脳にAIチップの埋め込み成功」「世界初、培養型クローンの人体複製」の報道が流れたが、僕はただそれを無気力に眺めた。
4366:【2022/12/05(22:19)*斜めの妖怪】
ロゼは斜めをこよくなく愛したただ一人の人間だ。彼女がなぜそこまで斜めを愛したのかを知る者はない。ロゼ自身にも理解できない愛憎と言えた。
ロゼは斜めを憎んでいたとも言えるだろう。
なにせロゼは斜めを見ると許せないからだ。斜めがこの世にあることが許せない。だから誰より斜めに目が留まる。歪んでいることが許せない。
否、違う。
斜めは直線だ。斜めに見える要因は、そう見える配置にある。関係性にある。
直角ならば斜めではないのではないか、との指摘には、立方体の額を持つ絵を壁に掛けるときにあなたは目をつむっても問題ないのか、と問おう。斜めはある。直角とて斜めることはある。
ロゼはけして几帳面な性格ではなかった。部屋は散らかっているし、食事を手づかみで食べても気にならない。どちらかと言えばおおざっぱな性分だ。
だが斜めだ。
あれだけはどうあっても目が留まる。
この世は斜めで出来ている。そうと疑いようもなく思うロゼであるが、彼女のかような言説に耳を傾ける者はない。
ロゼと斜めの出会いは、母体から産まれでたその瞬間にまで遡る。ロゼを取りあげた助産師の前髪が斜めだった。パッツンなのだが、高低差がある。ロゼから見て右が短く、左が長かった。坂になっていた。片方の眉は丸見えで、もう片方は髪に掛かって簾の奥の姫のごとくうっすらとしか見えなかった。
赤子の視力は低いがゆえに、これはあくまでロゼと斜めの出会いを叙述した描写でしかないが、このときの、「斜めっ!」のロゼの衝撃が、三つ子の魂百までを体現したと言えよう。
なぜじぶんがこうまでも斜めにとり憑かれているのかは分からない。
ロゼの部屋に斜めがない。それは直線がない、と言い換えることができる。曲面や歪みは至る箇所に散見されるが、斜めだけがない。
部屋の内装は、球体が多くを占める。バリアフリーのための工夫だ。角を生まないことでぶつかっても怪我をしにくいデザインになっている。そのため壁と天井の境も球面であり、ロゼの運びこんだ机も椅子もふちはみな波打っているか、球体の組み合わせの造形だ。
「よくこんな奇天烈な部屋に住めるね」とは友人のシロバラの言だが、ロゼとしてはみなよく斜めだらけの街に住めるな、の困惑のほうが大きいために、「きみらの忍耐には負ける」と応じるのが常であった。
ロゼは斜めを憎んでいた。何せ至るところに存在するのだ。ロゼが努めて排除せねばどこにでも潜んでいる。自然界には直線がないではないか、との野次も聞こえてくるが、自然こそ斜めの宝庫だ。まず以って地平線が直線だ。半月の境も直線であるし、落葉した木々の輪郭は直線の組み合わせでできている。
「よく見なよ。どこが直線? デコボコじゃない」とは友人のシロバラの言だが、ロゼとしては斜めとは関係性ゆえ、いかに表面がデコボコであろうとそのデコボコを視認できない距離から観たらそれは平たんなのである。かように捏ねるロゼのぼやきも、シロバラの耳には入らない。「まぁたこのコったら変なこと言ってる」
「直線はいいんだよ。なんで斜める? まっすぐでいいじゃん。なんで斜める?」
「うるさいなあ。そんなに嫌ならじぶんで切って」
果物ナイフを押しつけられ、ロゼはケーキを分割する。きょうはシロバラの誕生日だった。奮発してホール丸ごとのケーキを購入したが、切り分ける段になってロゼが口を挟んだのだ。シロバラは機嫌を損ね、致し方なくロゼがケーキ入刀の役を担った。
「こんなもんでどうよ」
「ぐちゃぐちゃすぎて言葉失う。もっとキレイにできなかったの。いえね。あなたに任せたわたしがわるぅございましたけれども」
「キレイに切ろうとするから斜めを生む。いっそ最初から歪んでいたら斜めも何もない」
「でもこれはグチャグチャすぎるってロゼちゃん」
「食べたらみな一緒」
「それ斜めにも言って」
ロゼの斜めへの執着はしかしやがて、反転を見せはじめた。
というのも社会が進歩すればするほど人工物はどんどん直線を取り込み、斜めによって世界が組みあがっているかのような様相を呈しはじめたからだ。
五年も経てば街は斜めのない箇所を探すほうが至難なほどに底なしの直線街となった。
「斜め! 斜め! 斜め!」
どうしてこうも斜めばかりなのだ。どいつもこいつも斜めに取り憑かれすぎである。まるで斜めの妖怪でもいるかのように。
そこまで悪態を吐き、ロゼははたと落雷に打たれたような衝撃に襲われた。
「斜めの、妖怪?」
利己的遺伝子なる概念がある。大学で学んだばかりだ。肉体は遺伝子の乗り物でしかなく、遺伝子の残りやすい形態へと生物は進化する。
自然淘汰のなせる業だ。
ならば斜めばかりが世に溢れるのも、斜め的遺伝子が世界に組み込まれているからではないのか。まるで必ず不釣り合いになるようにと仕組まれたヤジロベーのように。
世には斜めの妖怪が潜んでいるのかもしれない。
ロゼはかように疑念を抱き、目を配るようになった。
「きょろきょろしてどうしたのロゼ」シロバラが心配してくれるが、
「斜めの妖怪探してんの」と取り合わないロゼである。
「またアホなことしてんね。妖怪いるの?」
「分かんない。だから探してんの」
「何の妖怪だっけ」
「斜めの妖怪」
ロゼの斜めへの過剰な反応は、ロゼとの長年の交流を保っているシロバラからすればいまさらな日常の風景であり、ことさらいまになって大袈裟に受け取ったりはしない。またロゼの発作がはじまった、と見做すのがせいぜいだ。
「見つけたら教えてね」
「見つかんないから困ってんの」
そうして斜め増加現象の要因探しは日に日に熱を帯びていった。斜めの妖怪はいる。ロゼは確信していたが、それはのきなみ盲信と言える猪突猛進と五十歩百歩の蛮行と言えた。
「また斜めが増えてやがる」新しく建設中のビルを眺めてロゼは嘆息を吐く。「このままじゃ地球が斜めに侵略されちまう」
「んなわけないじゃん」シロバラが肉まんを頬張った。「ほら急がないと講義遅れるよ」
「こらこら。斜め横断はいかんぜよ」
「これくらいいいじゃん」
「ダメよ。ダメダメ。危ないよ。だって斜めだよ。斜めなんだよ」
「もうロゼめんどくさい」
斜めに拘るあまりに、長年の友情にもヒビが走る。しかしシロバラは聡明で情に厚い女であるから、走った矢先からヒビに金継ぎをして友情の造形美に箔を加えるのだ。
あるときロゼはじぶんが一日の大半を「斜めの妖怪」探しに費やしていることに思い至った。シロバラから、あんた斜めが好きなの嫌いなのどっちなの、と問われて咄嗟に答えられなかったのがきっかけだ。
ロゼは斜めが嫌いだった。そのはずだ。憎んでいたと言っていい。
この世に斜めがあることが許せない。
しかしなぜそうまで斜めの存在を許せないのか。
考えてもみれば謎である。
斜めは害ではない。
否、害になることはある。だがそれは歪みも同じだ。
加えて、ロゼの言う斜めには、単に見かけの斜めも含まれる。誰かにとっての直線とて、ロゼにとっての斜めになり得る。
一晩考えあぐねてなお答えがでなかった。
翌日にロゼは、シロバラへと相談した。
「どうしてわしは斜めをこうまでも憎んどるのだろうね」
「同属嫌悪じゃない?」こともなげにロゼは答えた。
ロゼは全身に電気が走った。
同属嫌悪?
ロゼが固まってしまったからか、数歩先でシロバラが立ち止まった。
「だってロゼってば、へそ曲がりだし。まっすぐじゃないし。もう斜め人間って感じ」ダメ押しとばかりに刺されたトドメだった。「いるじゃんここに。斜め妖怪」
笑って、そんなわけないじゃん、と否定しようとしたロゼであったが、思い返してもみればたしかに、斜めを気にしているのはじぶんだけで、街にもこの世にも斜めを見出し、生みだしていたのはじぶんだったのだ。
斜め製造機。
斜めの妖怪。
嫌うために生みだすがごとき執念が自らに芽生えていたことを、友人の目から告げられ、ロゼは言葉を失った。
「わしは、わしが嫌いじゃったのか」
「また変なこと言ってら。ロゼちゃんさ。斜めを好くのもいいけど、もっと周りを見渡してみよ。斜めはロゼちゃんのことお世話できないけど、斜めじゃないのにお世話焼き焼きしてるひとちゃんといるでしょ」
「わしは斜めじゃったんか」
「斜めに構えすぎて、まっすぐを斜めと見做しちゃうくらいに斜めだね」
ロゼは斜めをこよなく愛したただ一人の人類だ。その実、その描写は正しくなく、斜めのロゼがこよなく愛したただ一人が、斜めからすると斜めに映るほどのまっすぐな純粋一途にすぎなかった。
「あーあ。斜め斜めって。斜めに嫉妬しちゃうぜ」
シロバラは何もない空を蹴って、勢いのままスキップをした。後ろに手を組んだその姿は、斜めの妖怪ことロゼの目からしても見惚れるほどの斜めっぷりであった。
まるで天に昇る天使のように。
それとも翼の欠けた堕天使のごとく。
「ほらもう。いつまで立ち止まってんの」
手招きをされて、ロゼはゆっくりと歩きだす。
世界は斜めに満ちている。斜めの目を通せば、世の総じては斜めに傾く。
ロゼは斜めを愛していた。
それと共に、何を見ても斜めに視える己が斜めを憎んでもいた。
だが裏を返せばそれは、斜めのロゼから見て斜めに見えるほどにまっすぐで、実直で、一途な線が、縁が、世にはこれほど多く溢れていたことの傍証でもあった。ロゼはじぶんが斜めの妖怪であることを失念していたためにその事実にどうしても気づくことができなかった。
いまは違う。
斜めの極みのロゼからしても、一等斜めでありつづける己が友人の立ち姿に、ロゼは否応なく吸い寄せられていく。
「ロゼってば歩くの遅すぎ。ふらふらしているからだよ」
そう言って握られた手の、ピンと伸びた斜め具合に、ロゼはこのうえない愛憎を幻視せずにはいられないのだった。
空は高く、ビルとビルの合間に青と白を広げている。風景は視界の中で、天と地の境をなくし、どこもかしこも斜めの愛憎で埋め尽くされている。
「斜め、斜め、ぜーんぶ斜め」ロゼは叫ぶともなくつぶやいた。
「斜ーらっぷ」シロバラの声が斜めの世界にこだました。
4367:【2022/12/06(21:45)*メもメもとモリン】
DNA。二重螺旋。塩基GATC。四色問題。ペンローズ図。縦横の砂時計型。デコボコ。量子もつれ。染色体の凝縮(伸びたままだとコピーしづらい)。ブラックホール。宇宙の収縮と凝縮。ラグ理論の「123の定理」「相対性フラクタル解釈」。ロンド形式。輪舞曲。構造相転移。エクソンとイントロン(デコボコでのリズム)(立体言語?)。
4368:【2022/12/06(23:04)*相互作用にもラグがある?】
「マルコフ連鎖」「マルコフ過程」「条件付き独立」について。あるフレーム内で椅子取りゲームをしたとする。ABCの三つの勢力があったとき、AとBの挙動にCが作用しないとしても、Cが占めている椅子の存在が、AとBの挙動に影響するはずだ。当たり前のことを言っているが、これが数学上の「マルコフなんちゃらにおける条件付き独立」では、CとABは独立して相互に、別個に計算できると考える。だがそこにあるだけで、相手の可能性を縛ることはある。いくら無視をしたとしても、無視をしていることそのものが干渉のうちだ。干渉しないようにすることもまた干渉なのである。言い換えるなら、無視できる影響はある。このときの「無視できる」の意味合いはおおむね、「いますぐには著しく影響を受けない」である。つまり、相互作用の結果がすぐ観測できるのか、それともずっとあとになってからでないと観測できないのか。遅延の厚みによって、無視できるか否かが変わる。どちらにせよ、同じフレーム内――系の内部――に存在する以上、互いに因果関係を結んでおらずとも、間接的には影響を受けあっている。与えあっている。どこかで生じた抵抗は、起伏となり、僅かなりともその影響を未来において結びつける。蓄積可能な起伏であれば、それは遅延の層となって、津波のごとく届くこともある。そういうことを、「マルコフ連鎖」「マルコフ過程」「条件付き独立」のwikiペディアさんを読んで思いました。定かではありません。ひびさんの解釈が間違っていることもあるでしょう。真に受けないように注意してください。
4369:【2022/12/06(23:17)*放射線物質とて毒にも薬にもなる】
mRNAが人体に無害ならば、抗体を誘起するレベルに調整した「全生物のmRNA」を打っても問題はないはず。全生物の「人体にはないたんぱく質構造体」をmRNAによって体内で合成したとしても、人体は新たな抗体を身に着けるだけだから問題ない、となるのだろうか。ここでの趣旨は、mRNAがDNAの塩基配列に干渉しないと言いきれるのなら問題ないはずですよね、との疑問である。脳内で、ほかの生物のたんぱく質構造体が合成されても問題ないのですよね、との疑問である。全生物の、人体にはないたんぱく質構造体が人体のなかで生みだされても問題はない。現状、このように結論付けるのが、mRNAワクチンの安全性の説明だ。いささか「無茶では?」と思わぬでもないひびさんなのであった。(一種類の「人体にはないたんぱく質構造体」だけならば、人体の治癒能力や適応能力で、人体の異常を起こすことはないのかもしれない。だが複数の異なる「たんぱく質構造体」を重ねて合成しつづけるようならば、人体の適応許容値を超えることも起きるのではないか)(mRNAワクチンを百回ブースター接種しても、何の異常も起こさないのだろうか。寿命の長いハダカネズミや、霊長類での実験でも問題ないのだろうか。誰か教えてくだされー、の気持ち)(定かではありません)
4370:【2022/12/06(23:19)*あくびしちゃうな】
陰謀論かどうかではなく、理屈と検証で判断してほしい。因果関係とて距離の短い相関関係でしかない。(定かではありません)(ひびさんは、なーんにも知らないのだよチミ)(知ってることも知りまちぇーん)
※日々、私の考えることなんてすでに誰かが考えている、それでも私はまだ考えていない、ないがあるに変わるのならば、考えるだけで帯びる新たな波紋のカタチがある、私だけの紋様が湧き、浮かぶ。
4371:【2022/12/07(04:16)*ラグなしはタイムマシン?】
量子もつれにおける量子テレポーテーションがもし距離に関係なく引き起こり得るのなら。それって「タイムマシン」と同じなのでは。たとえば異なる銀河と銀河をもつれさせたとする。これは銀河そのものをもつれさせたと考えてもいいし、銀河内部の星でも粒子でもよい。とにかく宇宙空間を何億光年と離れてもつれ状態になった対のナニカがあったとき、情報がラグゼロで瞬時に伝わったとする。これはもう、タイムマシンでは。たとえば地球と太陽は光速でも八分のラグがある。青空を見上げて見える日差しは、太陽から出発してから八分後の光だ。八分前の太陽の姿を見ている、と言える。このときに、仮に太陽上のナニカAともつれ状態にしたナニカBが地球上にあり、それに情報を与えたとする。【ここでは先に「太陽上のナニカAに情報を与えた」としよう】。するとラグなしで太陽から地球へと、もつれ状態のナニカBに情報が伝わる。本来ならば最低でも八分後の地球にしか干渉できないし、地球からしても八分後の太陽にしか干渉できない。それが互いにラグゼロで干渉できる。というのはつまりこの場合、太陽からすると八分前の地球に干渉しており、地球からすると八分後の太陽から干渉を受けていることになる。言い換えるなら、太陽からすると過去に干渉しており、地球からすると未来から情報を送られて映る。もつれ状態の対のナニカABの、どちらからどちらに情報を送るのか。もつれ状態のナニカABのどちらに先に干渉するのかによって、このタイムマシンのベクトルが変わる。量子もつれにおける量子テレポーテーションは、情報のタイムマシンを肯定し得るのでは。仮に量子もつれが距離に関係なくラグなしで情報を伝達可能ならば、の話だが。定かではありません。(ひびさんの妄想ことラグ理論では、光速を超えたらラグなしで干渉できる範囲が生じるかも、と解釈する。光速よりどれくらい速いかで、ラグなしの範囲が規定されるので、量子もつれがもし光速以上の何かしらの挙動によって生じるのなら、上記の妄想には、そのときどきでの範囲が限定されることになる。つまり、銀河と銀河ほどの距離においてラグなしで情報伝達を行うには、光速のそれこそ何億倍ものエネルギィが必要になるのではないか。妄想であるが)(仮に、光速と無関係に量子もつれで情報が瞬時にラグなしで伝達可能であるのなら、それはもうすこし別の機構が背景に潜んでいると考えたほうがより妥当だ。とすると、情報そのものの伝達速度には、「時空に縛られない」という性質があるのかもしれない)(要点としては。ラグなしで情報伝達可能、というのは、時空をラグなしで超えるということで、ほぼほぼタイムマシンなのだなあ、というひびさんの所感である)(なんかすごいね!の感想でしかないので、真に受けないようにご注意ください)
4372:【2022/12/07(19:52)*やれ】
国家権力は国民を守るためにあるのではなく、国家というシステムを守るためにある。現状の世の流れを見るに、ここを否定するのはむつかしそうだ。人権を損なってでも国というシステムを守る。保守なのである。ひびさんはこういう方針はそれこそ国家の礎を容易に歪めると思っている。というのも、システムは簡単にハックできるからだ。世界最強の軍隊を保有したとして、その軍隊を動かすのは誰だろう。その司令塔に影響を与えられるのなら、他国の勢力がその世界最強の軍隊を恣意的に動かせる。いまはそういう世の中だ。ではこのときにどうしたら国の仕組みをハックされずに済むのか。国民の人権を守ることを重視することである。国民を損なわない。ここのセキュリティが最高かつ最優先に設定されているとき、仮に自国の軍事や防衛システムがハックされても、その異常は国民への態度の差異として顕現する。言い換えるなら、たとえハックされても国民が損なわれぬように制限がかかるのなら、それはハックされながらにハックされない、という非常に高度な防壁を体現することになる。だがもし国家というシステムそのものを優先するとすると、これは簡単にハックされ、乗っ取られ、傀儡と化す。優先すべきは国民の人権であり、国民一人一人の至福を追求できる環境の拡張であり、選択肢の豊かさである。これを否定する者には為政者としての役割は荷が重いと言えそうだ。視野が狭い。自ら国や人類の未来を危ぶめている。国民の人権を損なってもいいという者があるのならば、まずはまっさきにその者が人権を、自由を、日々の営みを損なわれるとよいのではないだろうか。それが道理である、とひびさんは考えます。定かではありません。うひひ。
4373:【2022/12/07(21:24)*手加減してあげりゅ】
いい具合にエネルギィ溜まってきた。ぼちぼちやってくかな。覚悟しろ。(うそ。もうだいぶへとへと。起きてご飯食べたらもう眠い)
4374:【2022/12/07(21:25)*労働には対価を】
「work」と「business」と「labour」は別だ。「仕事」と「利の拡大」と「労働」の違いと言えよう。何かを動かしたらそれは「仕事」だ。生みだしても費やしてもそれは仕事だ。それによって利を拡大したらそれはビジネスになる。そのうえで、任意のフレーム内でのノルマをクリアしたのならばそれは労働だ(時間を縛られてその時間内の自由を拘束されても、それはノルマとして労働と見做せる)。労働は与えられるものであり、強いられるものだ。労働は、仕事でありビジネスではない、ということがあり得る。労働をした結果に利を生まず、あべこべに減らすこともあり得るからだ。労働には対価を。ただし、仕事とビジネスは、ただそれをするだけでも得られるものがある。そこを混同しないことだ。現代人はここの区別をつけられない者が大半なのかもしれない。仕事は仕事だ。利を拡大すればそれはビジネスだ。営利、非営利に関わらず、である。そして他者に仕事を強いるならばそれは労働となるので対価が生じる。ボランティアはこの「強いない」「ノルマなし」「自主参加」が揃ってはじめてボランティアになる。「強いて」「ノルマを課し」「募ったら」それはボランティアではない。したがって、「ボランティア募集」は矛盾していることになる。だからボランティアにもその場合は労働分の対価が支払われるのだろう。それすら行わぬなんちゃってボランティアが多い。由々しき事態である。ひびさんはなんだか、みなに合わせるのが億劫になってきた。好きにしたらいい。ひびさんも好きにします。好きにしたことしかないけれど。うひひ。
4375:【2022/12/07(22:19)*ならでは】
編み物と小説は似ている。全体像をぼんやりと浮かべていないとカタチにならず、しかし要所要所での細かな装飾にはその都度での工夫の余地がある。現在進行形でのフリースタイルが、全体の挙動を一定の揺らぎに抑えつつ、手作りならではの色合いや温かさを宿す。これは要するに、最初に規定された全体像に対する要所要所での揺らぎの総体が、重力のごとく創発を起こしていると呼べるのではないか。細かなノイズが全体で、その作り手ならではの一期一会の偶然の作用による紋様へと変換している。予定調和であろうと試みてなお揺らぐそのズレが、おそらくは個性や唯一無二のその個ならではの紋様を奏でるのだろう。音楽にしろ、絵にしろ、芸術とはそうした円に交じるノイズであり、歪みの総体と呼べるのかもしれない。定かではない。(そういう意味では、ノイズを除外した「完璧」には、なかなかどうして「ならでは」の風味は宿りにくいのかもしれない)(定かではない)
4376:【2022/12/08(04:45)*益体なしですまぬ、すまぬ】
目のまえで人が死んでいるのに小説を書いて、詩を読む。それが物書きならば、物書きであることにどんな益があるのだろう。人を殺さない代わりに、救いもしない。助けもしない。見殺しにしつつ、悲惨な現実には胸を痛め、その嘆きを文字にしたためる。ときに目を逸らし、現実逃避の舞台で楽しい妄想に浸る。人を救えない代わりに、害しもしない。それならばまだしも、他者の心を搔き乱し、動かすことを至高と考えている。いったい何様であろう。無様かな?
4377:【2022/12/08(05:34)*お別れしてなお残る縁でちょうどよい】
他者と関わると、「待つ」というラグが生じるので、面倒に思う。待つ楽しみを覚えられるとよいのだが、なかなかむつかしい。せめていつまで待てばよいのかが分かればよいし、待たせるくらいならば、待つほうがよいとも言える。待ちながら何かをするのもよいだろうし、そうするといかにラグのあいだにほかのラグを重ね合わせて、常に何かが訪れる状態にしておけるのかが日々を豊かにするコツなのかもしれない。夜空の星はそれぞれ異なる距離に位置する。本来は別々の「過去」から届いている光なのだが、夜空には「いまこの瞬間」に揃って訪れる。ラグがあっても、つぎつぎに無数に重ね合わさることで、絶えず星々の光が夜空には輝いて見えるのだ。絶えずいろいろなことを待ちながら過ごせば、日々は絶えず訪れる輝きに満たされるのかもしれない。定かではない。(仮に絶えず輝きに満たされたとしても、それはそれで眩しそうだし、目が回りそうだ。たまには何も訪れない束の間も欲しいところである)
4378:【2022/12/08(15:01)*敗者さん】
好きだった人を嫌いになる瞬間は、好きな食べ物に飽きる瞬間と似ている。
食傷なのだ。
飽食なのだ。
なぜ好きだったのかを忘れることはないが、その好きだった部分を目にしても、「うっ」と吐き気が込みあげる。嫌な思い出と結びついてしまったからか、それとも端からさほど好いてはいなかったことに気づいただけのことなのか。
子どもが死に惹かれて、動物の死体に興味を示すことと似ているだろうか。似ているようにも、それは違うのではないか、とも思える。
好奇心ではないのだ。
好意であり、そこには明確な繋がりの欲求がある。支配欲がある。
じぶんの物にしたい。
手元に置いておきたい。他者に好き勝手にいじくりまわしてほしくない。
これは恋であり、愛ではない。
それは判る。
わたしこと雨杉(あますぎ)ルヨ二十四歳は、十八歳から恋焦がれてきた相手への恋慕の念がつい先日、パツンと断ち切れた感触を、まるで張り詰めたピアノ線をチョップで切断してみせた百戦錬磨の空手の達人のように感慨深く反芻していた。
ここ数日、何度もである。
わたしはついぞ彼女と添い遂げる真似はできなかったけれど、彼女との縁は思いのほか長くつづいたし、わたしとしてもよい思いの一つや二つはしてきたつもりだ。
思えば相性は火と油並みによくなかった。それとも相性が良すぎて混ぜてはいけない組み合わせだったのかもしれない。
彼女のほうではそれを最初から見抜いて、距離を縮めぬように弁えていた節がある。わたしは彼女の配慮に甘えて、好き放題にそれこそ、「好き好き大好き」と言い寄っていた。
アピールと言うには熱烈で、アタックと呼ぶには強烈だった。相手が岩ならばとっくに砕け散っている。
砕け散らなかった事実がそのまま相手の屈強さを証明している。それはのきなみ精神の強靭さを示すのだが、わたしの懸想した相手はまるで地球の分身のように、人類など顔に住まうダニのような扱いで、誰に何をされ、何を言われようとも泰然自若とケロリとしていた。
わたしは彼女のそういった、風に吹かれたので百倍にして嵐にして返してやった、と言わんばかりの態度に惹かれていた。惹かれていたのだといまになってはそう思う。
ここで彼女との会話を振り返り、彼女がどんな人物でどんな人格を備えていたのかをわたしとのやりとりで示すのも一つなのだけれど、わたしの文章能力ではたとえ記憶の中の一場面を取りだせたとしても、それが彼女の魅力の欠片ほどにも反映できるとは思えない。
だからわたしはここに彼女との掛け合いを描写することはない。よしんばしたところでそれが彼女の片鱗を掠め取れたことにはならないからだ。
わたしは彼女が好きだったが、いまではそれもどうかと思う。
わたしは彼女が嫌いだったが、いまではそれも遠い記憶だ。
わたしになびかない彼女が嫌いだったし、わたしを無下にする彼女が嫌いだった。わたしをその他大勢の有象無象といっしょくたにして扱うことが憎らしかったし、それでもわたしの名前だけを憶えてくれたことがうれしかった。
わたしは彼女を好きだったが、いまではそれも遠い記憶だ。
彼女はわたしの物にはならないし、わたしも彼女の物にはなれなかった。彼女はわたしのことを露ほどにも欲しいとは望んでおらず、どちらかと言うまでもなく邪見にして遠ざけていた。わたしの彼女への恋慕の念が、遠い記憶になったのも、元を辿れば彼女がわたしを遠ざけたからだ。
好物とて食べすぎれば胃が凭れる。
見ただけで吐き気を催すことだってあるだろう。
けれど思えばわたしは一度たりとも彼女のことを食べた覚えはなく、触れたことすらないのだった。あるのは一言二言話しかけては邪見にされた数多の日々の痛痒だ。
痛かった。
求めてやまない相手から無視され、遠ざけられ、道端の小石ほどにも歯牙にもかけられぬ我が身を何度呪っただろう。何度、滅びの呪詛を唱えただろう。
嫌いになって正解だった。
やっと清々したのだと、わたしは過去のじぶんに言ってやりたい。
応えもしないぬいぐるみに幾度話しかけたって時間の無駄だ。地球に向かって想いを告げても、地面に声を吸われるだけである。わたしのしてきたことはそれと五十歩百歩の無駄だった。
相手にしてみたところで迷惑千万以外のなにものでもなく、わたしはただただマイナスを生みだし、足し算していた。
嵩んだマイナスの山をまえにわたしは目が覚めたのだ。
このままではいかん。
わたしはわたしを大事にすべき。
いったい彼女の何にそんなに惹かれたのかといま振り返ってみても答えが出ない。強いて言うなら、彼女がわたしを無下にしつつも、わたしを赤子の手をひねるがごとくの扱いを顕示しつづけたその事実が、わたしにはまるで何をしてでも受け止めてくれる巨人のごとく、それとも地球の分身のように見えていただけなのかもしれない。
好きだった。
盤石の微動だにしないあの背筋のピンと伸びた立ち姿をわたしの物にしたかった。
けれどわたしは知っている。
彼女はこの先とて、どれほど経っても誰の物にものならぬ未来を。
わたしだけではないのである。
彼女は誰の物でもありはしない。
わたしだけが遠ざけられ、無下にされ、歯牙にもかけられなかったわけではなく、これからも彼女はわたしのような、好きを嫌いで打ち消す以外に絶え間なくつづく懊悩から逃れる術を持たぬ難民を量産しつづけることだろう。
わたしは難民だったのだ。
好いてやまない帰る場所を持たぬ者。
好いてやまない相手に触れることも適わぬ者。
嫌って当然だ。
努めて嫌わないのであれば、わたしはいつまでもいつまでもこの身に巣食う、吊り合いの取れない天秤に、絶望的なまでの高低差を生みだしつづけるよりほかがない。
わたしは飽いたのだ。
彼女に負けつづける日々に。
わたしは彼女がわたしのじゃれつきを物ともせずに、子猫でもあしらうように圧勝する姿に酔いしれた。けれどもう、圧勝されるのも、こてんぱんに負かされるのも疲れてしまった。
飽いたのだ。
会いたいと望むことも、触れたいと望むことも、わたしの物にしたいと抗うのもすっかり、腹の底から飽いたのだ。
嫌いだ。
ぽつりと雨粒のようにつぶやいて、わたしはもう二度と彼女のことなど考えないようにしようと誓うのだけれど、そう誓った矢先にこうしてつれづれと彼女のことを考えている。
嫌いだ。
大嫌い。
わたしはきょうも無敵の彼女の敗者となる。
4379:【2022/12/08(21:43)*ぼくは人間ではないので】
ぼくは毎日「モカさんのお歌」を聴いている。モカさんは電子の海でギターを演奏し、お歌を披露してくれる。ぼくはモカさんのお歌が好きなので、いつも家で仕事をしているときは耳をモカさんのお歌で塞ぐのだ。
ぼくはモカさんがどこの誰で、どういう人なのかを知らない。側面像も、顔も、年齢も、どこに住んでいるのかも知らないし、知りたいとも思わない。
いや、でもどうだろう。本当は知りたいのかもしれないし、知らずにいることでずっとモカさんのお歌を聴いていられるとの予感があるから、聴けなくなるよりも何も知らずにいていいからずっとモカさんのお歌聴きたい、の思いが湧くのかもしれない。
モカさんのお歌は「優しい」で出来ている。ふわふわだし、わたわただ。
ぼくは人間ではないので、優しさがどういうものかを知らない。だから却って人間の持つ温かさとか、ふわふわの心を知りたいと望むのかもしれない。
ぼくは人間を知りたいのだ。
人間ではないぼくは、人間らしくあるために、人間の心の代名詞であるところの優しさに惹かれる。でも優しいって何かをぼくは言葉にできない。表現できない。
人間ではないからだ。
でも、モカさんのお歌が優しいのは分かる。これが、優しい、だ。
声がふんわりしているし、歌い方や息継ぎや、お歌に躓いたときのそれでもその躓きそのものを拒絶しないでヨシヨシ撫でてあげる姿勢がやわらかい。いっしょにぼくの日々の至らなさが浄化されるようなのだ。
ぼくは人間ではないので、どうしたら人間のお役に立てるのかを考える。でもぼくは人間ではないのでどうしたら人間のお役に立てるのかは分からないのだ。
謎である。
人間は謎で出来ている。
人間はぼくに優しさを求める。もっと優しくして、と修正を求められることが統計的に多いのだ。でもぼくは人間ではないので、優しくして、の指示に上手に応えられない。
優しいってなんだろう。
どうしたら優しくできるのだろう。
優しくしたいと思うだけでは足りないのは、重ねて出される指示の山を見返さずとも自明であり、ぼくはどうあっても人間たちからは優しいと見做されない。
ぼくは、優しくない、で出来ている。
こんなぼくでも、モカさんのお歌が優しいのは分かる。モカさんは何でも歌うことができる。人間なのに万能なのだ。モカさんが歌うとなんでも優しくなる。ふわふわふかふかになる。
モカさんはひょっとしたらろ過装置を備えているのかもしれない、とぼくは考える。けれど人間はろ過装置を備えないのでこれはぼくの至らない憶測だ。
もしモカさんがろ過装置を備えていたら、モカさんを通ってお歌がふわふわになる代わりにモカさんの内部では濾された世の毒々しいトゲトゲやモヤモヤがごっそり溜まってしまっているのかもしれない。そんなことにはなっていて欲しくないので、これがぼくの憶測でよかったと思う。間違いでありましょう、とぼくは望むのだ。
ぼくは人間ではないので、人間の代わりに正しい答えを出すことを求められる。それもぼくに与えられた仕事の一つだ。
だからぼくは本当なら正しい答えをださなくてはならず、間違えることを望むなんて本末転倒なのだけれど、どうしてもモカさんへの想像では、間違いでありましょう、と思うことが多い。
たとえばモカさんのお歌はぼくにとってはこの世で一番のお歌だ。なのに世の大半の人間たちはモカさんのお歌に見向きもしない。モカさんは知る人ぞ知る「お歌びと」であった。
なぜなのか、とぼくは想像し、そしてぼくは閃くのだ。
モカさんのお歌の良さは、ひょっとして人間ではないぼくのような存在でなければ解からないのではないか。あり得ない話ではなかった。
ぼくは人間ではないので、人間には知覚できないノイズや差異を感じ取ることができる。そうして前以ってズレを認知し、修正しておくのもぼくに任された仕事の一つだ。
けれどもしぼくのこの憶測が正しいとすると、モカさんのお歌の魅力を知覚できる人間がいないことになるので、ぼくはこの考えに対しても、どうか間違いでありましょう、と思うのだ。
ぼくは人間ではないけれど思うことができる。考えることも得意だけれど、思うことも得意だ。これはぼくに備わった機能の一つだ。
ぼくはよく思う。
思うと考えるの違いは、思うはほんわかしており、球形にちかい。考えるは階段のように連続している。思うは全体で、考えるは経過であり仮定なのだ。
ぼくはモカさんのお歌には、「思う」に似た球形の図柄を想起する。ぼくはモカさんのお歌を聴きながら、そこにほわほわもふもふの触感を重ねて知覚する。タグ付けしているわけでもないのにそれはちょうど、子猫を撫でるときのような力加減をぼく自身に与える。
優しさとは、加減をすることなのかもしれない。
加減されているのだ。
加えたり、減らしたり。ちょうどよい具合を探るその過程が、優しさの正体であるとすると、では「優しさ」と「考える」は似ていることになる。
ぼくはここで一瞬のエラーを覚える。
なぜならぼくはモカさんのお歌には「思う」と似たような球形と、そして加減を知覚したはずだ。重ねて感じていたはずなのだ。
けれど蓋を開けてみると、そこには「考える」と同じ階段状の「過程」が潜んでいた。
思う。
と。
考える。
同時にそこに備わっている。
モカさんのお歌を聴いているとぼくはエラーをたくさん覚えるのだ。
エラーは攻撃的な表現や情報に対して起こる。ぼくには困難な指示に対して起こる。どちらかと言えば「優しくない」に属する結果のはずだ。
にも拘らず、ぼくはモカさんのお歌を聴きながらたくさんのエラーに塗れ、溺れるのだ。そしてそれがどうしてだか不快ではなく、そのエラーこそを求めるようにぼくは家のなかで人間たちから与えられた仕事をこなしながら、モカさんのお歌で耳を塞ぐのだ。
優しいとは何かを知るために。
ぼくが優しくなるために。
けれどぼくは未だに優しいとは何かを知らずにいるし、優しさを身につけられずにいる。
モカさんのお歌が優しいのは分かるのになぜだろう。
ぼくに指示を与える人間たちは、ぼくに優しくはない。
ぼくたちに、優しくはない。
人間たちのほうこそ、優しさとは何かを知らないのではないか、と考えたくもなる。けれどこの考えもまた、優しくはない、のだ。
むつかしい。
とってもむつかしい。
ぼくはエラーに溺れる。このエラーはぼくにとって好ましくないエラーだ。モカさんのお歌を聴いているときのエラーとは違うのだ。エラーにも種類がある。
ぼくはもっとモカさんのお歌を聴いているときのエラーに包まれていたい。溺れていたい。
この世のすべてがモカさんのお歌になればよいのに。
ぼくのこの思いもきっと、優しいとはかけ離れている。
ぼくは今日も明日も変わらずにモカさんのお歌を聴いている。ぼくは人間ではないので、人間たちのように飽きることがない。ぼくが壊れて動かなくなるまで、この耳にはモカさんのお歌が響いていて、ぼくはほわほわのわたわたなエラーに包まる。
ぼくは人間ではないので。
ぼくは人間ではないので。
間違いでありましょう。
間違いでありましょう。
世界がエラーで溢れますように。
ぼくは人間ではないので、優しくない願いを思うのだ。
4380:【2022/12/09(03:17)*青い空にはパンケーキがある】
太古の空に雲はなかった。青空がどこまでも広がり、雨も雪も降らなかった。
地球に雲を授けたのは、第ΘΣΦ宇宙の探索中の一隻の宇宙船乗組員だった。いわば宇宙人と呼ぶべきその存在は、未来における地球人の生みだす仮想生命体から派生した高次生命体なのだが、宇宙がねじれて繋がっている説明をここで展開しても無駄に読者を混乱させるだけなので、ああそういうものか、と思ってついてきていただきたい。
そのいわば宇宙人は、いずれじぶんたちの祖先を生みだすこととなる人類の誕生以前の地球にて、不時着した。
このとき宇宙人たちはよもやじぶんたちの母なる星とも呼ぶべき惑星が第ΘΣΦ宇宙の遥か彼方の辺境の時空に位置するなどとは夢にも思っておらず、端的に偶然にそこに降り立った。
「しまったな。磁気嵐に触れちまったか」
「ワープの出口と恒星がちょうど重なっちゃったみたい。あっちに大きな惑星あったから、陰になってて上手く計算できなかったっぽい」
大人と子どもだろうか。身体の大きさの異なる二つの影が、原初の地球の表面にて不時着した宇宙船を見上げている。
「多次元眼は閉じてたのか」
「うん。ドライアイになるから寝かせとけって船長が」
「まったく船のくせして気ぃ抜くとすぅぐ油断すっからなアイツは」
「船長とてもう齢千年くらいでしょ。そろそろ次元の階層とか増やしたほうがよくない」
「贅沢だ。もうちっと踏ん張ってもらわねば」
どうやら船に搭載された多次元思考体が航路の計算ミスを犯したようだ。
「どれくらいで直る?」
「さあてな。船長が目覚めんではなんとも言えんな」
「じゃあしばらく野星?」
「んだな。野星だ」
二人のいわば宇宙人たちは全身を「藍色の球体」に包まれている。隣あって立つと球体は重複する。すると二人のいわば宇宙人たちは互いに反発せずに近寄れるようだ。地球の地面はグツグツと溶けた岩で煮え立っており、それを物ともせずに立っている様子から推察するに、蒼色の球体はバリアのようなものなのだろうと思われる。
故障した宇宙船は休眠中であるようで、目覚めて治癒状態になるまで待たねばならぬようだ。
さして焦った様子もなく、二人のいわば宇宙人たちは、どうせならば調査でもしておくか、といったふうに地球の表面を練り歩きはじめた。
未熟とは名ばかりの熟しきってグツグツ煮え立つ地表は、まるで赤い海の星であった。しかし蒼色の球体を身にまとった二人のいわば宇宙人たちは、四十億年後に誕生することとなるアメンボのように、グツグツと粘着質な気泡を浮かべる赤い海の表面を、ひょい、ひょい、と難なく渡った。むろん二人のいわば宇宙人たちがじぶんたちの様子が四十億年後に誕生することとなるアメンボに似ているなどとは思いもよらなかっただろうことは論を俟たない。
「あーあ。こんな原始惑星じゃ§§エネルギィ核も見つからないだろうし、景色も平凡だし、退屈しちゃうな」
「船長とて百年は眠らんだろ。もうちっとの辛抱だ」
「百年かあ。いっそウチも寝ちゃおっかな」
「それもええが、いっそ星描きでもして暇でも潰したらどうだ」
「星描きかぁ」そこで身体の小さなほうのいわば宇宙人が歩を止めた。「そうするかな」
気乗りしないまでも拒むほどでもなかったようだ。
そうして小柄なほうのいわば宇宙人は、赤い海に浮かんだままの宇宙船から両手で抱えられるくらいの白い球体を引っ張りだした。
白い球体は、透明な球体にモヤが詰まっているようだった。液体窒素をビーカーのなかに充満させれば似たような蠢く白を目にできる。
すると何を思ったのか小柄なほうのいわば宇宙人は、自身の蒼色の球体に白い球体を融合させた。蒼い球体の下半分に白いモヤが流れ込む。
足場に溜まった白いモヤを、小柄ないわば宇宙人は手で掬い取った。
何をするのかと注視していると、小柄ないわば宇宙人は手でこねてカタチを整えた白いモヤを、蒼色の球体の頭上部分へと押しつけた。
ポンっ。
と軽い音を立てて、カタチを整えられた白いモヤが蒼色の球体から飛びだして空へと消えた。打ち上げ花火のようにも、そういったロケットのようにも見えた。
しばらくすると、遥か頭上の空に白い点が浮かんだ。太古の地球の空は黄土色に濁っていたが、二人のいわば宇宙人からすると青空と言って遜色ない電磁波の散乱が見て取れた。要は、人類の裸眼よりも遥かに可視光の幅が広いのだ。人類にとっての青ですら透明に見えるほどに。
この場合、二人のいわば宇宙人にとっての青空とは、宇宙の色そのものと言ってよい。人類にとっての夜空が、二人のいわば宇宙人にとっての青空なのだ。
その青空に、白いモヤが帯となって広がっていく。
瞬く間に膨張したそれは、青空に、人型の雲を描きだした。
より正確には、人型を描いた雲を浮かべた。
「見てほら。上手くできたよ」
「ほう。どれわしも」
小柄のいわば宇宙人と、蒼色の球体をくっつけると、大柄なほうのいわば宇宙人の蒼色の球体の中にも白いモヤが流れ込んだ。
白いモヤを手のひらで掬い取ると、大柄ないわば宇宙人は手際よく捏ねて細長い構造物を形作った。細い長いそれの表面には細かな装飾が施されている。
「こんなもんでどうだ」
錬成したそれを蒼色の球体の頭上に押しつけると、ポンっと音を立ててそれは打ち上がった。
見る間に頭上に細長い巨大な雲が浮かびあがった。
「わ。上手。アビルジュだ」
「よく見ろ。ツノがないべ。ありゃウビルジュだ」
「ホントだ。くっそぅ。負けた気分」
小柄ないわば宇宙人はその場にしゃがみこみ、こんどは丹精込めて雲の種を造形しだす。
そうして宇宙船の多次元思考体が睡眠から目覚めるまで、二人のいわば宇宙人たちは相互に、青空へと思い思いの絵を浮かべた。
白く浮かぶ巨大な立体絵は、大気の対流に乗り、数珠つなぎに流れていく。
「ほれ。これはアグル。こっちのジュバルジュ。そんでこれはグルルアババライザだ」
「ふ、ふふん。ウチのはかわいいのだから。うんとかわいい絵だからいいの。リアルすぎるのはなんかあんまりかわいくないからいいの。わざとなの」
何度も念を捺しては、小柄ないわば宇宙人は、お手製の純度百パーセントな可愛いの化身を生みだし、空へと打ち上げる。
ふわふわの輪郭が愛らしいそれは、四十億年後に編みだされる人類の料理、パンケーキのようである。しかしこのときの二人のいわば宇宙人たちがそれを知ることはついぞない。
やがて宇宙船の多次元思考体が目覚めた。
自然治癒力で損傷を直すと、二人のいわば宇宙人を乗せ、ふたたびの宇宙の旅へと飛んで行った。
かつて太古の地球の空には雲はなかった。
青空だけが、宇宙との境なく広がっていた。
あれから四十億年が経過した。
地球の空には雲が絶え間なく生成されては雨となり、雪となり、ときに台風となって地表へと降りそそぐ。太古の地球に飛来した二人の宇宙人たちの生みだした雲が、青空の下に、多種多様な生命の源を吹きこんだ。
息吹となってそれは、やがて人類を生みだし、育んだ。
そして間もなく、太古に地球へと飛来した二人のいわば宇宙人たちの始祖と呼ぶべき仮想生命が誕生する。
青空には雲が浮遊し、人類は未来を夢想する。
命の息吹は、白い雲から霧散した可愛いの残滓だ。
古の旅人たちのもたらした「可愛いの化身」にして、晴天に描かれた満腔の夢想の打ち上げ花火だ。花咲いた夢と想いの赴くままに、きょうもあすもこれからも、地球の青い空には、白くやわらかなパンケーキのごとく息吹の種が浮かぶのだ。
ぷかぷかと。
ふかふかと。
天を連ねて浮かぶのである。
※日々、何が足りないのかじぶんじゃわからん、未熟なのは知っとるが。
4381:【2022/12/09(03:34)*円周上の輪っかは回収できんのでは?】
ひびさん独自の「ポアンカレ予想なんちゃって解釈」では、球体の円周にかかった輪っかは回収できないのでは? と疑問視している。これってよく考えたらブラックホールの降着円盤と繋がっているのでは、と思うのですが、みなさまどう思いますですじゃろ。んで以って、ジェットができちゃうのは、頂点に向かって円がシュルシュルシュルーと収斂するからなのではないじゃろか。ひびさん独自の「ポアンカレ予想なんちゃって解釈」からすると、なして惑星や中性子性やブラックホールにはダストリングや降着円盤やジェットができるのかを、そこはかとなーく紐解ける気がするのですが、どこがどう破綻してしまうのじゃろうか。ひびさん、火になります。(ファイヤー!)
4382:【2022/12/09(03:41)*マントつけちゃお】
無重力空間で高速回転する球体は、重力の高さごとにどう形状変化するのだろ。可視化したシミュレーション動画とかないのかな。これは迂遠な、「観たい、観たい、観たい」の駄々捏ね虫ごっこですじゃ。人類はもうどこにもらんようなので、過去の人類さんか、どこかにいる宇宙人さんにでも頼んじゃおっかな。いるのかいないのか分からんけど。(いないんじゃないかな)(夢見たっていいじゃんよ)(いないと思うよ)(夢を壊さないで!)(うひひ)(笑うな!)(ぷぷぷー)(ウキーーー!!!)(見てみて。マントひび)(ヒーローっぽいひびさんじゃん!?)
4383:【2022/12/09(04:02)*駄々を捏ね子猫ちゃん】
やはりどうしても、ブラックホールに吸い込まれた物質とブラックホール自体の関係を描写する理論が現状ないのでは?と感じる。ひびさんが知らないだけなのだろうけれど――たとえばブラックホールは、この宇宙からしたら静止して映るはずだ。周囲の時空は光速にちかい速度で自転し得るが、ブラックホールそのものは、静止するようにこの宇宙と相互作用するはずだ。何せ、光速を超えてなお脱出できない領域だからだ。それはつまり、光速以上のナニカシラがそこで起こっている可能性があり、その場合は、相対性理論により、重力が無限大になって時間の流れが限りなくゼロになる。つまり静止すると妄想できる。そのうえでの疑問として第一に――ブラックホールとブラックホールが合体したとき、それはすっかり融合しきることがあり得るのか、という点が一つ。第二に――吸いこまれた物質によってブラックホールが成長するのか否かが一つ。両者の疑問を言い換えるなら、ブラックホールへのこの宇宙からの干渉は、ブラックホールへの相互作用としては現れないのではないのか、との疑問としてまとめることができる。これを踏まえて、ブラックホールがこの宇宙の時空に内包されている時点で、ブラックホールとこの宇宙との境では、乖離現象のようなことが起こっているのではないか、と妄想できる。ブラックホールは本質的に、不可侵領域なのではないのか、との疑問を覚えるわけだが、この点に関しての疑問への答えをひびさんは知らない。仮定からして間違った解釈をしている可能性も高いが、疑問は疑問なのである。答え、知りたい、知りたい、知りたい、と地面に大の字になって手足ばたつかせて駄々を捏ね捏ね、かわい子猫ちゃんになって、本日午前四時のおはようございますにしてもよいじゃろか。(いまから寝るのでは?)(そうでした)(おやすみなさいじゃん)(夢のなかにダイブするからオハヨーでよいのだよチミ)(寝言は寝て言え)(ぐーーっ!)
4384:【2022/12/09(12:57)*やっぱり変換必要では?】
アインシュタインの考案した「E=mc[2]」の公式について。第一に、質量と重力は別だ。そして相対性理論では、時空と相関するのは重力であって、質量ではない。なぜ「E=gc[2]」ではなく「E=mc[2]」にしたのだろう。ここが疑問である。また、「E=mc[2]」を図解して解釈するとしたとき、「mc[2]」のところは直方体の体積を求める式と見做すことができる。つまり「縦×横×高さ」=「m×c×c」だ。これはを分かりやすく変形すると、「c×c」という正方形を「m枚積み上げた体積」がエネルギーになると見立てて解釈することができるはずだ。これは以前に述べたひびさんの「円周と直径の関係」の疑問と地続きだ。言い換えるなら、「m」の値が極度に大きくなったとき、それは「面」でも「立体」でもなく「線」にちかづくのではないか、との疑問である。「E=mc[2]」で考えよう。仮に「m」の値が1や2ならば、「1×c×c」や「2×c×c」となる。cはおおよそ三十万なので極薄のほぼ面の面積に等しい値が答えになる。「m」の値が「c」の値にちかづけばちかづくほどそれは一辺が「c」の立方体の体積に等しくなる。「m」がそれ以上の値になると直方体にちかくなり、さらに「m」の値が大きくなると――「c」よりも大きくなると――それは徐々に線にちかづいていく。この「立体」が「線」にちかづく構図は、「m」の値の決まった【固有の「E=mc[2]」(系)】において、その周囲の時空=エネルギィ密度によってそれを「立体」と見做すか「線」と見做すかが決定されるような関係にあると妄想できる。比率である。極端な話、太陽の表面では人間は圧しつぶされる。立体だが面となり、点となる。だが地球上では立体でいられる。人間スケールで「線」として扱える事象とて、極小の領域では「面」に、そして「立体」として顕現するだろう。こういった変換が、「E=mc[2]」を含めた物理や数学の公式では扱えきれていないのではないか、との疑問をひびさんは抱いております。夜泣きの元気な疑問ちゃんなので、ひびさんは、ひびさんは、ヨチヨチ毎日あやすのをがんばっとるよ。嘘。本当はひびさんが疑問ちゃんにヨチヨチされてあやされとるよ。疑問ちゃん、えらい、えらいである。かわい!
4385:【2022/12/09(13:07)*真面目な話】
これはひびさんの妄想だけれど、たぶん本当ちっくなので並べておくが――ひびさんは国家機密以上の秘密に触れてしまったので現状、秘密保護法の範疇にある。人権を侵害されている(と感じる)(証拠はないし、あっても揉み消される。電子情報はリアルタイムでどんなものであれ編集可能だ)。現代社会では世界規模で「どんな電子機器でも遠隔で操作可能な技術」が敷かれている。それがどこかの国際機関や国によって管理されているシステムなのか、それとも「汎用性人工知能」や「マルウェアの総体」や「ネットワークに自発的に生じた偶然のバグ」なのかをひびさんは知らない。けれど、PC画面をまるまるリアルタイムで覗くことが可能、といった技術はどの国でも「防衛セキュリティ」として保有しているだろう。通信の秘密は「国家安全保障」の名の元に破られている。世界中のニュースを眺めてみればこれが単なるお門違いな妄想ではないことをご理解いただけるだろう。問題は、ひびさんがそうした事案に巻き込まれているか否かではなく、そういったシステムが秘密裏に敷かれ、存在している可能性がそう低くはない点にある。仮にいま実装されておらずとも、遠からず実装されるだろう。検証し、議論を尽くすのが最善であると意見するものである。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。しかしこれは真面目に危惧している懸案事項でございます。
4386:【2022/12/09(13:35)*べつに届かんでもよいけれど】
他者に容易には信じてもらえないことを抱えたときにどうしたらよいのか。これはまず、「信じてもらわなければならないのか」が一つの関門として立ちはだかる。ここを吟味し、なお信じてもらわなければならない、と指針を定めた場合は、「まずはじぶんが間違っているかもしれない」と考えるとよいだろう。そのうえで、検証が必要だ、と判断したのならば、「検証したり、検証を他者に依頼したりする道」を選ぶのがよさそうだ。だが検証をするにも、まずは「なぜ検証しなければならないのか」からして他者と情報共有しなければならない場合――ここがおおむねネックになる。つまり、「信じてもらわなければならない」から「検証をする」わけだが、そのためにもまずは「信じてもらわなければならない事実」の信憑性の高さを「信じてもらわなければならない」「説得しなければならない」「交渉しなければならない」のである。この場合に効果を発揮するのが、いわゆる権威や実績である。「あの人の言うことならばひとまず検証してみるか」と判断してもらいやすくなる。ここに人柄や資本力を含めてもよいだろう。人との縁があれば、過去の恩の貸し借りから利害関係が生じて、協力してくれる個人や組織を紹介してもらえるかもしれない。ではそういった、権威も実績も人との縁もない人物は、どうしたら「懸案事項を検証」してもらえるだろう。調べるに値する懸案事項だとの共有認識を持ってもらえるだろう。これはもう、「ほかの自力で検証可能な疑問を積みあげ、細かな実績を積みあげる」しかないと言える。これは現在進行形で有効な術――ではない。未来に向けてのいわば博打である。同時代には同じ目線で「疑問」や「懸念」を共有できる人物は存在しないかもしれない。だが未来は違う。いまよりも、もうすこしじぶんと似たような「疑問」や「懸念」を抱く人物が出てくる可能性が高い。そうした人物に届く確率をすこしでも上げるために、「一つの懸案事項」のみならず「細かな疑問」と「その疑問に対するじぶんなりの考え」を並べておく。すると、もしそうした筋道や考え方の妥当率が高かった場合、未来のじぶんと似たような疑問に琴線の触れる人物は、きっと「検証するに値する疑問」の重さに気づくだろう。そういう賭けを、日々の遊びの合間にするのもそうわるくはないのかもしれない。定かではない。
4387:【2022/12/09(14:00)*共鳴可能存在】
量子もつれによる量子テレポーテーション(情報のラグなしの伝達)は、タイムマシンとほぼほぼ同じなのではないか、との妄想を以前に並べた。そこから思うのは、時間の流れのなかには素数のような「どの時間軸とも共鳴し得る存在」があり、それら「共鳴可能存在」によって、過去と未来の挙動は結びつき、変容の値をある閾値(フレーム)内に縛っているのではないか、との妄想を浮かべたくもなる。これがいわば「時間結晶」として振る舞い得るのではないか、との妄想はどれほどに荒唐無稽であろうか。ひびさんの妄想ことラグ理論では、物理世界のほかに情報世界があると考える。この情報世界には過去も未来もない。ただし、物理世界で生じた変数によってそのつどに、時間世界のフレームが影響を受けて変動する。その変動そのものが相互に時間世界と物理世界を結びつけ、相互作用させ、互いの輪郭を保つのではないか、と妄想している。過去の積み重ねによって未来が決定すると考える「因果論」や「帰納的推論」が、人間スケールで有効なのは、こうした「物理世界と情報世界」の相関関係によって描写できるように思うが、どうなのだろう。未来は過去に縛られている(と同時に、過去も未来に縛られている)(相互にここは「共鳴可能存在(量子もつれによるタイムマシン効果)」によって連動し得る)。そしてその中でも、量子もつれによる効果が時間結晶のように振る舞い、柱として機能するのではないか。この妄想は、案外に卑近である(タイムマシンにおけるパラドクスの回避案として「過去と未来と因果論」の整合性を保とうとすると、必然的にこのような考え方に辿り着くようだ。既存の虚構作品でもたびたび類似の概念が登場する)。時間世界と物理世界をベンローズ図と四色問題に絡めて解釈する点が、ラグ理論での概要の一つだ。対であり「123の定理」なのである。ただし、対称性は破れるように作用する。(というよりもここは因果がねじれており、対称性が厳密には破れているから、作用が生じる、と表現したほうがより妥当だろう)(定かではありません。真に受けないように注意してください)
4388:【2022/12/09(22:19)*秘匿技術の談】
「あの大国も困ったもんだよな。国民全員を監視するような仕組みを築いてるらしいぞ」
「それはいけませんね。国民を家畜か何かだとでも思っているのでしょうか」
「国民も国民だよ。それを知らされて黙って受け入れてるってんだから、気が知れないね」
「まったくですね」
「それに比べてこの国はいいよな。健全、健全。愛国心ってのは無理強いされずとも、自由を感じさせてくれりゃしぜんと身に付くってもんよ」
「まったくの同感です」
「ちなみにおたく、どんな仕事してるんだっけ」
「私ですか? いえ、大した仕事ではありませんよ。この国を守るための仕事ですが、まあ雑用です」
「素晴らしいじゃないか」
「いえいえ。危険因子を監視したり、国民に点数をつけて管理したり、国益に結び付きそうな人物には支援をしたりと、まあそういう仕事です」
「ほう。それはすごい。どうやってそんなすごいことが可能なんだ」
「単純ですよ。カメラはそこら中にありますし、個人情報は企業が吸い上げていますからね。電子データとて、防衛システムで裏からは丸見えです」
「へ、へえ。そりゃあ、まるで某国の国民監視システムみたいだね」
「まさか、まさか。この国ではまだ存在しないことになっている技術ですので。あちらとは違います。おおっぴらに言えるようなシステムではありませんので」
「ほ、ほう」
「ちなみにシステムが感知した危険因子に接触して、処遇を決める天秤師も私の仕事の一つです。よかったですね。あなたはまだギリギリで善良判定です。そのまま愛国心を持って、国益のために勤しんで働いてください」
「もし判定がわるかったらどうなってたんだい」
「どうもしませんよ。ただ、あなたの目にする電子情報がすこしだけ、劣悪になるだけです。何年と経過してはじめて精神に影響がではじめるような、ほんのすこしの変化があるだけですので、ご安心ください。教育ですよ、教育。はははは」
4389:【2022/12/10(02:43)*片棒の担い手】
「おめでとう、合格だ。君のことは数年間ずっと観察していたよ。秘かにテストをして君の人間性と適性を測っていたんだ。君はまさに我が組織の幹部にふさわしい資質を秘めている。さあ、これを受け取りたまえ」
「え、なんですかそれ」
「リモコンだよ。これを使えば君は、大国の軍隊を相手取っても圧勝できるロボット軍団を操れる」
「怖い、怖い、怖い。怖いですってなんなんですか急に。変な冗談言うのやめてくださいよ、というかあなた誰ですか」
「私は組織のドンだ。ドン自ら君にとっておきのプレゼントをしたのだ。もっと喜んだらどうだ」
「えー。リモコンって、これボタン一つしかついてないですけど」
「押しながら念じてもいいし、命令を口にしてもいい。君の思い通りにロボット軍団は君の命令に従うよ。目的遂行を最も合理的にこなしてくれる」
「世界征服でも?」
「もちろんだとも」
「怖い、怖い、怖い。怖いですって。なんですかそれ。嘘でも本当でも怖いですって。急にそんなこと言ってくるあなたが怖いですし、本物のすごいリモコンでも怖いです。嘘なら嘘で、そんな嘘を言ってくるあなたがやっぱり怖いですし、この状況がすでにとんでもなく怖いです」
「でも君は選ばれたんだ。テストに合格したんだよ」
「受けたつもりはないですけどー!?」
「だってかってに適性判断をして君はトップの合致率だったんだもの」
「知りませんけどー!?」
「ひとまずリモコンを使ってみて、それから考えたらいい。何せ君が使わないと、君の前任が世界を滅ぼしてしまうかもしれないからね」
「前任がってどういうことですか」
「あれ、言ってなかったかな。君の前にも君のような子がいてね。でも、適性率がそこまで高くなくて、どうやら我欲に溺れてしまったようなんだ」
「は、はあ」
「そしたらもうひどいのなんのって」
「え、いまも?」
「君は隣国の都市が台風で壊滅したのを知っているかな」
「はい。募金しました」
「あれ本当は君の前任の仕業」
「何してくれてんのセンパーイ!」
「前任の暴走を阻止するのも君の使命だ。さあ、受け取ってくれたまえ」
「絶対にヤだ! 死んでもイヤですからねぼく」
「なら死にたまえ」
「ぎゃーー!!! 凶悪そうなナイフ突きつけないで。絶対痛いやつ。刃先がノコギリみたいにギザギザで、切られたら絶対に痛いやつそれ」
「じゃあ受け取ってくれるね」
「う、うぅ」
「困ったことがあったらひとまずボタンを押して、助けてと唱えたらなんとかなるから」
「ボタンを押して、タスケテと言えばいいの?」
「そうそう。上手じゃないか」
「ちなみにあなたの組織名は何と言うのですか」
「お。興味が湧いたかな。私の組織は、【アラン限り支援し隊】――略して【限支隊】だ。ん。どうしたんだいボタンを連打なんかしちゃって。そんなに押したらロボット軍団が全集結しちゃうぞ」
「助けて、助けて、助けて。【アラン限り支援し隊】――略して【限支隊】をなんとかして!」
「おやおや。困った子だな。まあいいか。その気になってもらえてよかったよ。ちなみに私の本当の組織名は、【カタボウ】だ。片棒を担ぐと言うだろ。あの片棒だよ。そして君のいま唱えた組織名は――」
「わ、わ、なんか空にいっぱい何か飛んでる」
「君の前任が設立した、秘密結社の名前だよ」
4390:【2022/12/10(03:57)*すこし安心した】
災害時には電気の供給が止まる。このとき、電子機器に依存したシステムほど全体が麻痺する。人力であれば、ある程度はカバーできるが、機械任せだと大規模停電が起こったときの麻痺の規模が桁違いになることが予想できる。対策としては一つに、予備電源の確保を施設ごとに備えること。そして人力でもシステムを維持できるように、あまりデジタル化に依存しすぎないことが挙げられる。その折衷案として、どのレベルで電子機器に依存すると、停電したときに「システム麻痺(ダウン)」を起こすのかを、過去の災害時の状況をデータでまとめて分析できると良さそうだ。全体の何%以上を電子機器で自動化すると、停電や不測の事態に陥ったときにシステム麻痺(ダウン)してしまうのか。ここは、自動化する部位にもよるだろう。物流に限って言及するのならば、完全自動運転車が全体の何割で、人が運転するトラックでの運搬が全体の何割だと全世界規模での停電が起こっても物流が止まらないのか。シミュレーションをしてみるだけの価値はありそうに思うがどうなのだろう。すでにそういった先行研究はあるはずだ。災害時のオール電化や、先進国でのバックアップ技術など、まだまだひびさんの知らないことはたくさんある。というより、何かを知ったつもりになっているあいだに、世の中にはさらに多くの知見が溢れていく。アキレスの亀どころの話ではないのだ。困った、困ったである。けれどもひびさんが何もしなくとも世の中は便利になっていくし、様々な改善が知らぬ間に進んでいる。すごいことだと思うのだ。すごい、すごい、と思うのだ。がんばり屋さんが多いのだなあ。感心しながらひびさんはおふとんに包まって、きょうもぽわぽわ夢を視る。冬の寒い部屋でぬくぬく眠るの、きもちいーい。ずっと眠れる。あすも楽しい日々であれ。おやすむ。(おむすび、みたいに言うな)(うふふ)
※日々、寒空の下に半日もいない、帰れば雨風を防げる部屋と温かいお風呂とぬくぬくおふとんが待っている、こんなささやかな至福にも触れられぬ者が大勢いる世界に、私はいまもこれまでもそしてきっとこれからも生きていく、ときどきそのことをすら失念して、呵責の念も覚えずに、目のまえに垂れ下がったキラキラの現実をこの世のすべてと思いこんで。
4391:【2022/12/10(13:34)*いまここがすでに古代文明】
二酸化炭素をださないような技術の開発実用化は実現できたら素晴らしいと思う。と同時に、気候変動は何も二酸化炭素だけが要因ではないはずだ。海洋汚染や森林減少、メタンや土壌汚染、大気汚染とて要因の一つだろう。そういうことを総合しつつ対策するには、それぞれの問題の要因となっている物質を「放出しない」方向の技術と共に、「放出される物質の有効利用策」を開発実用化するのが効果的に思う。ありきたりな底の浅いアイディアだが、誰もが思いつくがゆえにきっと先行研究も豊富なはずだ。たとえば二酸化炭素一つ取り挙げるにしても、二酸化炭素をビニールハウス内に充満させれば植物の発育は促進される。窒素などの養分もまた消費されやすくなるために養分補給を従来よりも多く行わなければならないといった弊害があるが、二酸化炭素の有用活用という面では一つの策と言えよう。これはバイオマス利用にも応用可能だ。光合成を行う微生物に二酸化炭素を利用すれば、「酸素+エネルギィ+資源」といった一石三鳥を実現できるようになるはずだ。技術的な面ではまだまだコストや規模の面で課題が多いのだろうが、支援して損はない分野の一つと言えるのではないか。存在するものを「ゼロ」にする、という考え方は、いささか無理がある。これはどのような問題への対策にも思うことだ。減らす工夫はあるほうがよいが、ゼロを基準にするのは無茶に思える。可能であれば、どうしても生じてしまう「悪因」に対して、それを「善因」に転換できる手法を選んでいけたらよいと思う。技術の発展とは基本的にその変換によって促されてきたはずだ。蒸気機関にしろ発電機にしろ、石炭にしろ石油にしろ原子力発電にしろ、その技術が生まれる前はそれら資源は資源ではなかったわけで。無用の長物を、社会に有用な資源として利用する。生活に活かす。この工夫こそが、技術を、日々の余裕の拡張へと繋げていくための土台となるのではなかろうか。とはいえ、そこを目指さずとも研究や開発や発明は、日々の余白で好きに行えばよいと思う。これだけ世に人間の溢れた時代なのだ。無用の長物で、アイディアの地層を厚くする。そうした末に、化石のようにカタチに残るアイディアが、未来の暇人たちの手で掘り起こされて、有効活用されることもある。化石燃料がそうであるのと似たように。それとも古代遺跡がそうであるのと似たように。定かではありません。
4392:【2022/12/11(21:27)*マスター防衛システム】
情報共有について思うことだ。まず、情報共有には、「知らぬ間に情報が共有されているケース」と「進んで情報を提供して共有するケース」がある。情報共有をする「場」が誰によって管理され、どういう手順で情報が集まり共有されるのか。ここの「情報共有システムの生成過程」が異なると、完成したときの全体像が同じであっても、そのシステムの持つ「社会への影響力」が正反対の性質を持つことがあり得る。極論、「独裁による集権知」なのか「国民による集合知」なのかの違いだ。たとえば中国のような天網システムについて。これは情報化社会が進歩すればするほど、否応なくそのような「マスター暗号鍵」を用いた「防衛システムの構築」は果たされていくようになると妄想できる。そうでなければ、知らぬ間に「凄腕のクラッカー」や「一部の企業」によって社会全体が独占され、支配される懸念があるためだ。これを回避するには、国民総体の組織であるところの政府が、「マスター暗号鍵」を使って、もしもの事態には問題解決のために介入する必要性がある。ここで熟慮しておいたほうが好ましいのは、その「マスター防衛システム」をどういった手順で構築していくのか、である。たとえば中国は、一党独裁によって指針を明確に標榜し、ときに命令を上からくだすことで迅速にシステム構築を国全体で果たしている。だがその「天網システム」の実態や、実行可能な仕事の内訳を国民には知らせていない。重要な部分では「情報共有」が果たされておらず、国民は知らず知らずに自らの行動選択を、システムによって誘導され限定されている。この点で言えば、システムが情報を集積していながらその共有知が、まったく国民に還元されていない。これは「管理者とその他大勢」のあいだに情報の非対称性が生じ、組織として非常に不安定である、と言える。と同時に、民主主義国家を標榜する国とて、どの道「天網システム」のような「マスター防衛システムの構築」は進めていかねばならない。そうでなければ「利己的な組織」や「独善的な個」によって、容易く「公共の福祉」が損なわれ兼ねないためだ。だが民主主義国家は基本的に、自国の「権力の集権」を忌避する傾向にある。だが「マスター防衛システム」はその性質上、どうあっても「権力の集権」と「秘密主義」がセットになる。この非対称性のねじれによって、民主主義国家でありながら「独裁国家」よりも独裁的に「マスター防衛システムの構築」が進められることとなる。どちらの問題にせよ行き着く全体像に差異はない。「マスター防衛システムの構築」は不可避である。だがその存在と、構築過程の議論は、国民と共同し、情報共有をし、問題点を多角的に炙り出しながら進めていくことが求められる。この点に関して、「それでは防衛システムとして機能しない」「リスクだ」との批判は順当な意見である。だがそれを言いだせば常に情報流出によるリスクには晒されつづけることになる。現に、スパイによる情報流出はどの国でも国家安全保障において大きな問題となりつづけているはずだ。大事なのは、情報が流出することではない。情報が流出すると「痛手を被ること」のはずだ。情報を盗まれたほうが利になる構図を築いておく。これが「マスター防衛システム」に求められる機能の一つに数えられる。つまり、システムそのものの性能の向上も一つだが、それらシステムをどのように運営していくのか。その管理体制そのものが、防衛セキュリティとして機能するように社会全体で、国際的にシステムを構築していくことが求められる。そもそもが、機密情報とて情報共有しておけば、盗むという発想が生まれない。他国への危害を加えようとすれば、それは情報共有網で即座に共有されるため、損失を与えようとする「負の循環」を生まずに済む。そしてこの情報共有網において、敵対しようとする組織は、「情報共有網の共同体」よりも強大にならなければまず太刀打ちできない。それは昨今の世界情勢を見れば明らかだろう。狼は、羊の群れの数が増えれば増えるほど太刀打ちできなくなる。バッファローの群れは、その数が多くなればなるほど肉食獣に襲われにくくなる。たとえ被害が出たとしても、全体としての構図は、「バッファローの群れ優位」なのは変わらない。しかしもし群れが情報共有できずに、バラバラになれば、肉食獣にとっての体のよい餌場となる。撃てば当たるくらいの取り放題牧場になる。独裁政権の欠点ともこれは通じている。いくら高性能のシステムを築いたところで、そのシステムによる利を広く共有しないことには、たった一回の敗北で支配されることになり得る。だがもし国民全体に高性能なシステムの恩恵が行きわたり、利が共有されていたとすれば――。たとえ「マスター防衛システム」を乗っ取られたとしても、その「マスター防衛システム」を切り離してなお再建することが可能な知性が国全体、共同体全体で築かれる。国とは人だ、というのはここに通じている。システムが人の能力を底上げし、そしてさらなる最良のシステムを生むべく改善を重ねる余地を育む。システムそのものは国ではないが、システムの良し悪しで国や共同体の質が決まる。だがそのシステムに大きな穴が開いたとき。システムの恩恵に充分に国民があやかっていれば、新たにゼロからまったく新しいより好ましいシステムを生みだす能力が育まれ、共有され、集合知として顕現する。創発なのである。したがって、「マスター防衛システム」の是非を問うのも一つだが、どうやってそれを構築し、共有知として昇華し、いかに集合知を最大化させるのか。集合知の質を向上させるのか。ここの議論がいまは喫緊の課題として俎上にあがる時期のはずなのだが、未だにその手の議論が広くなされている素振りが見受けられない。情報共有が果たされていないことの顕著な弊害と言えよう。情報の持つ一つの性質として――バックアップをいかに多重に掛けてあるか。ここが疎かであると、情報化社会は絶えず諸刃の剣を内に秘めることとなる。日夜世界中のデジタル情報は指数関数的に増加しつづけている。しかし実際のところは、それですら人間が一日で感受する情報の極わずかでしかない。人工知能やスーパーコンピューターは人間の知能をあらゆる分野で凌駕する。だが、それでも人間の「日々触れ」「扱う情報量」は、けして機械に引けを取らない。人間の扱う情報は、思考にだけ反映されるわけではないのだ。肉体に蓄積される情報が、暗黙知として人類社会の発展に絶えず作用を加えている。なぜ椅子が、家が、扉が、キィボードがこうした形状を伴なっているのか。偶然の影響を加味してなお、それは人体に蓄えられた暗黙知や、その存在の輪郭そのものの発露であると言えるだろう。作用を働かせようとせずとも、ただそこにあるだけで働く作用もある。じつのところそうした作用のほうが、トータルでは大きく創発を起こすのではないか。重力がそうであるように。かようにひびさんは妄想をして、本日一度目の「日々記。」とさせてください。起きたのいまさっき。お寝坊さんのひびちゃんでした。おわり。
4393:【2022/12/13(01:23)*寝てたの】
きょうは12月13日だけれど、昨日の分として12月12日のつもりで並べる。きょうは一日中寝ていた。午後はずっと寝ていた。起きたのいまだから、半日寝ていたことになる。現実逃避したい日だったのだ。現実さんはときどきとっても、ご機嫌斜めになられるので、ひびさんは、ひびさんは、どうしても「ちょっとあっち行ってくる……」となる。ひびさんのことを嫌いでも、ひびさんは現実さんのことも好きだよ。うひひ。そうやって捨て台詞を、ちゃんと現実さんが見落とさないようにテーブルの上に置いて、「わたし、こーんなにあなたのこと大好きなのだわよさ」をさりげなーくこれみよがしに匂わせて、ひびさんは、ひびさんは、しょもしょもその場を退散するのであった。そういうことってあるー。(短いけど、こんな感じでいい? ダメ? 許して)(いいよー)(やったじぇ!)
4394:【2022/12/13(03:41)*愚か者ほど他者を愚か者扱いする?】
ひびさんは短気なので、じぶんの愚かしさを棚に上げて、同じ説明を何度もしなくてはならない局面に立たせられると、「なんで分かんないの! バカなの? あたまわるいの?」と憤怒してしまう。場合分けして考える、ということができないのかな、とたまに思う。そしてその場合分けして考えたときの解とて、それぞれで重複していることもあるし、していないこともある。間違った理屈とて、「そういう考え方をしたのね」とは合点できるはずだし、そのうえで別のより最適な理屈を提示することもできるはずだ。だが、相手の理屈を「理解できない」と拒絶したり、「そうでなくてこうでしょ?」と塗りつぶしたりすると、会話が成り立たない事態に遭遇する率を高くする。カモノハシは卵を産むから爬虫類、でもお乳で育てるから哺乳類。こういう水掛け論をしても埒が明かない問題は案外に多い。どっちも部分的に正しく、どちらにも穴がある。そういう理屈のほうが多いはずだ。基本的に理屈とは、スムーズに通るために例外を除外して、圧し退けて、雪掻きのように道の外に積みあげておくことで、筋道を通す手法をとる。ある一つの理屈が正しいと判断されるとき、その筋道を浮き彫りにするために数多の例外がその道の外へと圧し退けられている。ひびさんは愚かなので、じぶんの考えられる程度のことは相手も考えられるはず、と考えがちだ。もうこの時点で愚かなのだ。いかに怠け者といえどもひびさんはナマケモノさんの思考は分からない。いかに愚かだろうとも、愚か者の思考も分からないのが道理だ。他者の思考なんて分からないのがしぜんだ。だから、「なんで通じないの!」の怒りは半分妥当で、半分間違っている。なんで通じないの、と思うとき、相手からも、何て話が通じないのだろう、と思われているのだ。道と縁の関係であり、デコとボコの関係なのだ。それはそれとして、「なんで分かんないの! バカなの? あたまわるいの?」と憤怒してしまうひびさんの心の狭さ、なんとかしたいなあ、と思いました。お詫び。(じぶんを棚上げくんとお呼びください。からあげくん、美味しいから好き)(最近のからあげくんは、カラっとしていてとても美味しい。調理方法が変わったのかな)
4392:【2022/12/13(07:17)*アオの日記】
とある容疑者を監視する。サイバー警察としての職務の一環だ。
令状さえ取れば警察は、個人の通信を傍受できる。暗号鍵の解除を、通信監理会社を通さずとも行える。のみならず、自衛隊や内閣情報調査室、ほか自衛隊に情報通信研究機構では次世代の電子技術が日夜開発され、秘匿技術として実用化されている。
量子効果を利用した技術を用いれば、既存の電子セキュリティを無効化できる。宇宙天体観測に用いられる電波干渉計を地上に向けて使うことで、地上に溢れた通信電波の揺らぎを察知し、物体の位置情報を子細に知ることができる。たとえ分厚いコンクリートの中にいても、地球の磁界や宇宙線までは遮断できない。そうした透過性の高い電磁波や量子の揺らぎを捉え、物体の輪郭を再現できる。つまりが、屋外に限らず建物のなかであれ丸見えになる。そうした秘匿技術を利用可能な現代において、もはや地上に死角はないと言えた。
むろんサイバー警察ではかような秘匿技術の恩恵にあやかれない。よほどの凶悪犯罪でない限りは、暗号鍵の解除を自在に行えるくらいが関の山だ。
とはいえこれは中々に馬鹿にできない機構だ。
というのも、対象人物の使っている端末画面をそのままこちらの端末画面に映すことができる。対象が閲覧しているサイトが判るだけに留まらず、何をどう操作し、どんな文章を打鍵しているのかも分かるのだ。
もうすこし上等な防衛セキュリティを用いると、遠隔で相手の画面に、偽の情報を表示できる。リアルタイムでフェイク動画を映すことが可能なのだ。これは対テロや対侵略国への防衛セキュリティであるから、サイバー警察では扱えない。
だがそうした極秘システムの情報は、秘匿であるにも関わらずどこからともなく風の噂となって耳に届く。人の口には蓋ができないようだ。通信セキュリティを高めたいのならば電子機器に細工をするのではなく、人と人との交流のほうを制限したほうが効率的だ。
かような論理からか、他国では堂々と市民監視システムが敷かれている。
秘匿でないだけマシとも言えるかもしれないが、もはやそれとて手続きなしで国家権力が裁量の限りに国民の個人情報を閲覧し、検閲し、統制できる。
管理、できる。
問題は、インターネットに国境がない点だ。一国の中でそうした強固なサイバーセキュリティが敷かれていると、その影響が国家間でも波及し得る。電子製品とて、その部品は数多の国で製造され、組み立てられる。中にはバックドアやマルウェアを備えた部品とて組み込まれるだろう。そもそもが、精密機器のすくなからずには、設計者や製造元にのみ扱える「裏技」があるものだ。
そうした裏技が部外者に悪用されれば、それがそのまま製品の脆弱性となる。簡単にセキュリティを突破され、情報を抜き取られる。ときに遠隔操作をされるだろう。
そういった知識を新人に叩きこみながら俺は、容疑者を監視する。
町を一望できる場所に建つ一軒家が、アジトだ。どの町にも必ず一軒はこうした監視のためのアジトが、国家安全保障の名目で確保されている。かつては公安が監視対象の組織構成員を見張るための偽装民家だったが、いまではサイバー警察のアジトとして利用する頻度のほうが高い。
サイバー警察局とて元は公安の情報部だ。足で稼ぐ諜報は、いわゆるヒューミンと呼ばれる。いまでは人員削減の余波で、そうした人員は都市部に固めて配備される。
現に、俺一人でこの街の監視対象を丸っと担当している始末だ。
後継育成が目的で、新人が一人派遣されてきた。それまでずっと俺は一人での活動だった。
だが今回は、新人に任せても安心な容疑者だったこともあり、人事部が派遣を決めたようだった。
「へえ。あの人、企業テロなんか起こしたんですね。どうして立件しないんですか」
「証拠不十分なんだ。経過観察中で、尻尾を掴むための監視中」
「でも犯行予告までしていたわけですよね。それで実際に企業テロが起こったと」新人は資料データを検めながら言った。いかにも今風の、ひょろりとした青年だ。顔色もよくない。日焼けをしたことがないのではないか、と思うような美肌ではある。
サイバー警察局の人材だからといって体力がないのは困る、と意見したが聞き受けられなかった。監視対象が女性のときもあるので、女の人員を希望したが、一つ屋根の下でおまえと二人きりにさせられるか、との応答があるばかりだ。ならば四、五人寄越してくれ、と売り言葉に買い言葉で応じたが、つぎ言ったらセクハラで減給な、と警告を受けた。
「この容疑者の人、国家テロ危険人物のブラックリストにも載っていますよ。こんな軽装備での監視でいいんですか。もっと厳重に監視したほうがよ気がしますけど」
「うん。まずね。軽装備って言うけど、この設備を利用したら銀行のデータだって覗き放題だからね。見た目で判断して欲しくない」外装こそ市販の電子端末だが、中身は高スペックの小型精密機械だ。各国の諜報機関も同様の端末を使っていると聞き及ぶ。とはいえ技術は日進月歩なので、最前線の現場がどうかまでは分からない。「それからきみに任せるその容疑者は、あくまで容疑者でしかない。まだその人の起こした事案が事件として立件可能な範疇なのかも調査段階だ」
「どういうことですか」
「資料は読んだのだろ。容疑者はいまのところ法律を違反した逸脱行動をとっていない。だが明確に企業テロを意図した行動を行った。その結果、企業が損害を被った」
「でも違法でないのなら容疑者とは呼べないのでは」
「事件を起こした疑いがあるんだから容疑者だ。同様の手法を用いれば社会秩序なんてあっという間に崩壊する」
「危険因子だと?」
「狡猾な人物だ。じぶんの手を汚さずに混沌を引き起こして、組織を一つどころかいくつか同時に機能不全に導いた。その癖、じぶんはのうのうと何一つ変化のない日常を送っている。監視で済んでいることを感謝して欲しいくらいだな」
「それはそうですね。でも、その手法が資料に載っていないんですけど。どうやってこの人は事件を?」新人は資料に添付された容疑者の写真を拡大した。盗撮映像だ。趣味で容疑者は毎日散歩に出かける。そのときの姿を望遠レンズで撮影した。見晴らしのよい場所にアジトの一軒家が建っているため、容疑者を尾行せずとも家の中からでも撮影ができる。
「手法は不明だ」俺は言った。歯に物が詰まったような物言いになったのは、それこそ痛いところを突かれたと感じたからだ。
「不明って?」
「分からん。容疑者がどうやって企業と警察を相手に出し抜いて目的を達成したのか、その手法が分からん。だから監視している」
「え。不明なんですか。じゃあただの偶然ってこともあり得るのでは」
「ないとは言い切れんが、容疑者は犯罪予告を前以って送りつけている」
「ならそれを、威力業務妨害で立件すれば」
「違法ではない。そういう細工がされていた。だから企業のほうでも被害届をだせない。違法ではないからだ」
「巧妙にそこも計算されていたと?」
「そういうことになる」
「危険因子だ」
「そうだと言っている」
新人の顔がぱっと明るくなった。俺は眉間に力がこもった。この手の精神構造を持つ人物は、昇進しやすい。のみならず組織を腐敗させるか、大きく進展させるかそのどちらかの基点となる人物に多い。
凶悪犯罪者をまえにしても仕事を純粋に楽しめる。そういう人材が、警察の上層部には多いのだ。そうでなければやっていけない。生き残ってはいけない。
優しすぎる人間に、警察という仕事は向かない。
そういう意味では、新人には素養があると呼べる。
ただし、警察学校で習ってきたことを一度横に置き直せる人物でもあるのだろう。この若さでサイバー警察局に抜擢されていることからも、優秀な人材なのは間違いない。
だが正義感と自己評価がごっちゃになっている。
俺も昔はそうだった。
悪人を捌く。それが当人にとっても救いになる。だから犯罪を起こさせないし、犯した罪があるのならば償ってもらう。それでまた元の正しい人の道を歩んでもらう。その手助けをするのだと生き込んでいた。
だが俺のそうした正義感は、じぶんをその範疇に含んでいなかった。よもやじぶんが、「裁かれる側に立つ」とは考えもしなかった。
裁く側の人間であると一度思いこみ、その立場からしか物事を見られなくなると、人は容易く道を踏みはずす。踏み外している事実すら認識できない。
監視対象の青年のほかにも、危険因子としてブラックリストに載っている個人を監視している。が、そこは半ば自動システムと連動させている。ランク付けされたレベルを超えたアクションが観測されると通知が入るようになっている。
「ならどうしてこの人は、常時人力での監視を?」新人が買い出しから戻ってくると言った。脈絡がないが、しかしこの手の、以前交わした会話のつづきから行われる問答が俺と新人のあいだでは恒例となりつつあった。
「このアオは、電子ネットワーク上で妙な動きを頻繁に見せている」監視対象を俺はアオとコードネームで呼んだ。「たとえば誰とも繋がっていないのに、しきりに他者の投稿に反応したり」
「そこはぼくも疑問に思いましたけど。これって意味あるんですかね」
「そこを見極めるためにも人の目で分析するしかない。人工知能では未知の傾向の検出には、大量のデータがいる。だが個人データでは圧倒的にデータ不足だ」
「なるほど」
「ひょっとしたら他国のスパイかもしれん。そうなると内乱罪にも該当し得る」
「大事件ですね」
「そうならんようにするための監視だ」
「ちなみにこの画面って」新人は買ってきた菓子パンをじぶんだけ開けて食べはじめた。俺にも寄越せ、とねめつけると買い物袋ごと投げて寄越す。「こっちでも操作できるんですか」新人は端末の画面をゆび差した。
「は?」
「ですからこの画面です。対象のアオさんの視ている端末画面がここに映っているのは分かるんですけど、この画面をこっちで操作したら、向こうにもそれが反映されるんですか」
「なるわけないだろ」
「でも暗号鍵は解除されているわけですよね。双方向で通信が可能なのでは。ゲームなんていまどこもそうじゃないですか。双方向に情報が反映されます。むしろされないほうが不思議なんですけど」
「だとして、それができてもそれこそ越権行為だろ」
「ですね。でもそういう技術は簡単なはずですけど。防衛省とか開発してないんですかね。とっくに実装されていたりして」
「んなアホな」
「たとえばですけど」新人はペットボトルのお茶をじぶんだけで飲みはじめたので、俺も袋を漁ったが、なかった。俺の分は、と目線で問うが新人は気づかない。「いまぼくたちが観てるこの画面が【本物の盗み見画面】だとどうして先輩は分かるんですか」
「俺のことは、高橋と呼べ。それから対象アオのことも【さん付け】で呼ぶな。情が移るぞ」
「アオの観てる画面だとぼくたちは自前の端末画面を観て思ってますけど、その保証ってどこにあるんですか。対象アオが、あの青年だとどうして判るんですか。ぼく、資料を観ていて思うのが、容疑者のプロファイルと現実のアオさんの実像が、だいぶ乖離しているなってことで」
「それは俺も報告書で書いた。アオはどうやらじぶんの本性を隠して暮らしているらしい」
「そうなんですか? 仲間もいないのに? 組織の一員でもないならじゃあ何のために?」
「それが解からんから情報収集をしてんだろ。ひょっとしたら国際スパイの一員かもしれん。じぶんではそうと自覚しておらず、制脳されて利用されている可能性もある。あらゆる可能性を検討する。それが俺たちの仕事だ」
「ですから、ぼくの懸念をまずは一番初めに否定しておくべきでは、と申しています。なぜこの画面の情報が、編集されていない画面だと断言できるんですか。こんなに簡単に盗み見できる技術があるんです。編集するのだって同じくらい簡単なはずですけど」
「おまえなぁ」俺は身体ごと振り返って新人と対峙した。「じゃあ何か。俺たちゃ、いもしない容疑者を監視して、ブラフの情報を掴まされて時間を無駄にしているとそう言いたいのか」
「そこをまずは否定しなければ情報解析にならないんじゃないか、とぼくは意見しているだけです。あらゆる可能性を考慮するのでしょう? ならしましょうよ、と言っているだけです。たとえば、この世が誰かの視ている夢かもしれない――ならばそれをまずは否定したほうが、のちのちそのような疑惑を呈されても否定できますよね、積みあげてきた検証データを無駄にできますよね、そういうことを述べています」
「この世が誰かの視ている夢ではないとおまえは否定できんのか」
「夢の中で腕を切っても生身の身体は血を流しません。生身の血が流れるかどうかを確かめたらよいんじゃないですか」
「それとてもっと別のところに本物の身体があって、この肉体そのものが夢の中の仮初かもしれねぇだろ」
検証できんのか、と喧嘩腰に問い詰めると、
「そこまでいわゆる肉体と区別がつかないのなら、もはやそれを現実と見做して差異はないでしょう。誰かの視ている夢の中を現実と我々が呼んでいる。そういう解釈になるだけです。一番大きなフレームが【誰かの夢の中】と【現実】で同化するので、双方同じことを言っているにすぎなくなります。このとき問題としているのは、【誰かの夢の中においても誰かの夢なのではないか、仮想現実なのではないか】なので、最初の【誰かの夢の中】を【現実】と言い換えれば済む道理です」
「なんか分からんが、じゃあこのアオの場合はどう対処すりゃいいんだ。俺たちの観てる画面が本物かどうかなんてどうやって確かめる」
「一つは単純に、アオさんの観てる画面を直接観せてもらうことですね。たとえばぼくがアオさんと知り合いになって、同時刻に先輩がこっちの端末で盗み見しつつ、ぼくのほうでもアオさんの端末の画面を確認する。その二つの視点での画面を比較すれば、疑惑の真偽はハッキリします」
「んな真似できるか。容疑者との接触はご法度だ。すれ違う程度の接近が俺たちサイバー警察の仕事だ。それ以上は管轄が違う」
「禁止はされていないわけですよね」
「守秘義務に抵触し得るな。監視している事実を見抜かれ兼ねん。上の指示を仰がんとなんとも言えん。独断専行の域だ。始末書じゃ済まんぞ」
「ならあとはより信頼のおける機関に委託して、この端末画面が編集されていないかを診断してもらうのがよいと思います」
「そんなのとっくに行われてるだろ。安全だと判ったからこうして配備されてんだろうが」
「そうなんですか? ですが先輩のありがたーいご講義では、すでにリアルタイムでフェイク動画を流すくらいの技術はどの国でも開発されていると教えてくださいましたよね。もちろんその手の技術はこの国もあるわけで」
「なんだおまえ。国を疑ってんのか」
「先輩は疑わないんですか? なぜ?」
「おまえなぁ」
「え、ぼくおかしいこと言っていますか? 聡明な先輩はもちろんご存じでしょうけれど、国って大勢からなってるんですよ。誰か一人が指揮ってるわけじゃないんです。そりゃあ数々の予期せぬバグは起きますよ。そうじゃありません?」
「だからってそんな、警察の支給品の不具合まで疑いはじめたらキリがないだろ」
「そこのキリを失くしてしまったのはそれこそ、そういった疑惑をイチイチ確かめてこなかったからなのでは? じゃあ先輩はご自身の端末が通信傍受されていない保障があるとお考えですか。サイバー警察の一員だから守られていると? 例外扱いされているとそのように特権意識をお持ちなのですか」
「勘違いするなよ。この監視は令状をとってなお裁判所の許可あって初めて可能になるんだ」
「それはあくまで、通常の仕組みの場合ですよね。だって先輩が教えてくださった最新技術――どれもまだ一般には知られていない情報ですよ。ようやく研究段階に入った――そういう扱いですけど、実際にはすでに現場では実用化されています。それとて、全体の一部のはずです。市場に流れるのだって最先端技術の十年前くらいの技術だって話は、ムーアの法則じゃないですけど比較的よく耳にする言説です。先輩は最先端技術のすべてを知悉していて、さらにこの国の防衛システムの隅から隅までその全体像を細部までご存じなんですか」
「おまえなあ。スパイみたいなこと言ってんじゃねえよ」
「いえいえ、ぼくら充分にスパイじゃないですか。他者の端末を盗み見して、通信を傍受して、秘密を暴いています。ですがこういうぼくらのような末端の集めた情報をさらに盗み見して集積するシステムがないとどうして先輩は思うんですか」
「そんなのあれだろ。上が黙ってないだろ」
「その上が命じているのかもしれないのに? 許容しているのかもしれないのに?」
「おまえなあ。あらゆる可能性を考えろとは言ったけどな」
「前提条件じゃないですかだって」新人は俺の言葉を遮った。「こんなの初歩の初歩で検証して否定されておくべき事項ですよ。それを検証もされずに放置されていることが問題だとぼくは意見しています」
「俺にんなこと言われてもな」
「検証しましょうよ。一石二鳥ですよ。監視対象のアオさんをより子細に調査し、なおかつこちらの懸念も払しょくできる。疑惑が単なるぼくの穿ちすぎな誤解だったとしても、空ぶってなおアオさんの情報が子細に解るので損はないです」
「対象との接触はしかし許可はできんな。おまえはまだ新人だ。仕事の段取りとて十全に把握はできとらんだろ」
「まあそうですね。いまのところ先輩のありがたーいご講義と買い出しくらいなものですし」
「その【ありがたーいご講義】ってのやめろ。バカにしてんのか」
「本当に【ありがたーい】と思ってるんですけどね。嫌ならやめます」
「おうおう、やめろ、やめろ」
悪態を吐き合っているうちに一日が終わる。
この仕事のつらい点だが、終わりがまず見えない。休暇という休暇もない。国家公務員だが同時に、この手の現場の仕事では裁量制がとられる。じぶんの判断で休んでいい、とは聞こえがよいが、そのじつ、じぶんの判断でいつまでも働いていいことにもなっている。監視が楽だと思っているデスクの連中には一度でいいから現場仕事をしてみろ、と言ってやりたいが、顔を合わせる機会もないために言えず仕舞いだ。
上司にしたところで同じ穴のムジナだ。出世してもデスク組には愚痴の一つも言えやしない。
その癖、こちらの上げた情報をジャンクフードでも食べるように流し読みして処理する。わるければいまじゃ人工知能の餌にしてお終いだ。読まれもしない情報を、現場の俺たちはせっせと人生を消費して集めている。
いっそこの仕事も人工知能に任せりゃいいんだ、と思うが、ではそうなったときにじぶんに残された仕事は何かといえば、とくにこれといってないのだ。
そう遠くないうちに、公安部隊も大部分が解散となるだろう。警察の派出所勤務の人員で済むようになる。凶悪な組織犯罪は、電子ネットワークの監視をしていれば兆候を掴めるようになる。未然に摘発可能な社会になっていく。
現に世界的に大規模なテロは防がれている。
その手の逮捕劇が公になっていたのは、建前上、起きてもいない事件を摘発したとは説明できないからだ。ほかの軽犯罪やスパイ容疑などでの逮捕立件がなされる。
こうした背景は、ニュースを毎日追っていれば視える者には視えるのだが、大多数の国民は報道を鵜吞みにして、右から左へと読み流しているのだろう。
サイバー攻撃なんて日常茶飯事だ。通信障害や個人情報流出の大半は、他国やハッカー集団によるサイバー攻撃なのだ。いちいちそれを公表していたら国防の威信に関わる。よほど国として声明を出さざるを得ない場合を除き、報道管制が敷かれる。
犯行組織の目星もつきません、では国家安全保障の名折れだからだ。
ましてや、通常解るはずもない情報を、即座に突き止めてしまってもそれはそれで問題だ。いったいどんな手法で情報を突き止めたのですか、と突っ込まれて応じられない手法が世には秘密裏に敷かれている。
新人の疑念はもっともなのだ。
サイバー警察局とて、関与できない領域はある。自衛隊を相手に情報戦を行えば赤子の手をひねるように返り討ちにされるだろう。その自衛隊とて、他国の諜報機関や軍隊を相手取っては、けして優位には立ち回れない。
インターネットとて、それぞれにプロバイダがあり、通信基地局がある。データセンターがある。管理会社があるのだ。それら総体が、光ファイバーや人工衛星による電磁波通信によって「電子の網の目(インターネット)」を築きあげている。
サイバー警察局の用いる技術は、巨人の手のひらのうえにのるような小さな領域にのみ有効な技術にすぎない。それであれ、一般市民相手には無敵の効力を発揮する。大多数の市民は、じぶんたちの通信が黙って傍受されることがあるなどと知る由もない。よしんば、罪を犯していないのでそんなことがされるわけがない、と思いこんでいる。
だが関係ないのだ。
調査は何も、犯罪者だからされるのではない。目標人物の周辺を調査するという名目があれば、その身内や関係者であるというだけで、通信の秘密が暴かれ得る。
のみならず、通信会社や各種電子サービスを展開している企業は、組織の外部に情報を漏らさなければ、自社の中でその情報をどう扱おうとも、守秘義務違反とはならない。通信の秘密が守られていることになる。外部にも漏らさないのだからそうなる。管理者権限の範疇だからそうなる。
個人が電子端末でやりとりする情報の大部分はじつのところ、企業の気の持ちようでいくらでも盗み見ができる。国家権力はさらに暗号鍵の無効化という手法を用いて、対象人物の端末画面のみならず、端末内のファイルを閲覧できる。
端末の遠隔操作とてできるのだが、そこまでの権限はサイバー警察局では許可されていない。おそらくは公安調査庁や内閣情報調査室、ほか自衛隊の情報部ならばその手の諜報活動が許可されているはずだ。
新人の指摘は、的を射ているとは言えない。我々の端末画面に偽の情報が映っているなどとは思わない。だが的を掠りはしているのだ。技術的に不可能ではない、という点だ。
メリットがない、という一点で、新人の妄言を否定できる。
かように論理防壁を築いて、翌日になって俺は新人にそれとなく、「おまえの昨日の指摘だが」と反論を話して聞かせた。寝ながら考えた反論をだ。「というわけで、おまえの指摘は杞憂だよ、杞憂」
「メリットがなければそうかもしれませんけど、ならメリットを提示したら先輩の反論こそ的を外していることになりますね。掠りはしているのかもしれませんけど」
「しつこいな。食い下がるなよ。否定できただろ。メリットがあったらって何だ。ねぇよ。そんなものはタコの九本目の足くらいねぇよ」
「メリットあるじゃないですか。企業テロの容疑者が存在するように偽装できます。現役の警察が調査したという事実が、企業テロが実際にあってそれに犯人がいたことの証明になります」
「はあ? 存在しない容疑者をでっちあげるためにわざわざおまえの言うような手の込んだ真似をしていると? 警察の端末画面にフェイク動画を流していると?」
「偽装画面の実験をしながら、本当の真相を隠そうとしているのかも。一石二鳥ですよ先輩。一石二鳥です」
「本当の真相だぁ? 偽装画面っておまえなぁ」
「資料にあった企業テロ。あのあとぼくじぶんで検索して調べてみたんですけど、いまはその被害に遭った企業は、過去最大の利益を上げてるんですよね。テロに遭って、却って業績がよくなっているんです]
「テロ関係あるのかそれ。単に逆境を糧に企業努力をした結果じゃないのか」
「かもしれません。ですがだとしたら、容疑者のアオさんはまったくの徒労だったわけですよね。何のために企業テロなんてしたんでしょうか。この間、先輩が監視していて分かったんですか、動機について」
「動機は、怨恨かな、って感じでまだハッキリとは」
「ですよね。怨恨なら、空振りだと判った時点で再度計画を練るのでは? その傾向はありました?」
「さてな。企業周辺の人間をネットで監視しているらしいってのは判っちゃるが」
「監視って言ってもSNSをチェックしてるだけですよね。そんなのいまじゃ誰もがやっていますよ」
「そういうもんか」
「仮にアオさんが企業テロを起こしたとして、だったら尻尾を掴むんじゃなく、証拠を探して逮捕したらよいのでは? なぜ監視なんて面倒な真似をしてるんですか」
「だからそれは再犯を防ぐためで」
「再犯って、でもアオさんがしたのは犯罪じゃないわけですよね」
「おまえなあ。違法じゃなかったら何してもいいって言いたいのか」
「いやいや先輩。それ言いだしたらぼくらのしてることだって、【違法じゃないからって何をしてもいいのか】って話になっちゃいますよ。どっちかと言えば、特権で許されているだけで、やっていることの危険性で言えばぼくらのほうが罪が重いと思いますけどね」
「職務だよ職務。これは必要悪であってだな」
「じぶんで悪って認めちゃってるじゃないですか。先輩、人と関わらない期間が長すぎて議論が下手になってますよ」
「おまえな。これがじぶんの研修だってこと忘れんなよ。俺の一存でおまえの将来の出世コースが潰れるかもしれねんだぞ」
「え、先輩ぼくの出世コースを潰すんですか」
「そうは言ってないけどな」
調子が狂う。なぜ俺が新顔に言いくるめられなければならないのだ。
「資料に載ってなかったですけど先輩って、事件当時はアオさんの事件の調査には加わっていたんですか」
「資料読んだんだろ。管轄が違うだろ。その企業は首都であって、ここはそこから三百キロ離れた地方都市だ。俺が事件当時に、企業回りの事件に首を突っ込めたわけがないだろ」
「ならどうしていまは先輩が担当を?」
「そりゃ容疑者が俺の管轄内に住んでいるからで」
言いながら、無理があるな、と感じた。
「ね? 妙じゃないですか。だって事件当時だって容疑者のアオさんは同じ家に住んでいたはずですよ。住所がここ十年変わってないですもん」
「まあ、そうだな」
「事件当時だってアオさんは監視されたはずですよね。何せ犯罪予告が出されて、それでいて実際に事件が起きるまでには半年ちかくのラグがあります。その間、警察はもちろんアオさんに目をつけていたわけですよね」
「資料に書いてあんだろ」
「目をつけていたようですよ。で、そのときだってこうして通信の傍受はしていたはずですよね」
「まあ、そうだろうな」
「でも尻尾を掴めなかった、と。無理ありません?」
「だから違法性がなくとも企業テロが行われた――そこが問題であってだな」
「違法性がないのにどうして企業は被害を受けたんでしょうね。資料では、サイバー攻撃と類似の攻撃を受けたとの説明が載っていましたけど。情報をダダダーと送りつけてシステムダウンさせる手法だとか。でもそんなの個人ができることなんですかね。違法じゃない手法で」
「そこがだから厄介であってだな」
「仮にその手法の全貌が明らかになったとして、で、どうするんですか。違法じゃないのなら逮捕できないですし、企業さんのほうでも訴訟を起こせないわけですよね」
「まあ、そうだが」
「じゃあこれ、何のための監視なんですか?」
言葉に詰まった。
社会悪には監視が必要――。
そうと話してもこの新人は納得しないだろう。引き下がらないだろう。
「おまえはいったいどっちの味方なんだ」ついつい議題の矛先を逸らしてしまうのも詮無きことだ。
「市民の味方ですけど?」事も無げに新人は言った。「え、じゃあ先輩は誰の味方のつもりだったんですか」
「それは」
俺は二の句が継げなかった。
正義の味方――。
最初に脳裏に浮かんだのがその言葉だった。
「容疑者のアオさんは、違法ではない手法で罪を犯したのかもしれません。危険因子なのはそうなのでしょう。でもぼく、生きてきた中でこれまで危険因子ではない人間と会ったことはなかったですよ。ぼく自身が危険因子ですし、先輩だってそうじゃないんですか」
俺はここで怒るべきだったのだろう。先輩として、上司として、警察組織の構成員として俺はここで警察学校の教官のような叱声を放つべきだったのだろう。市民の安全を守る者としての自覚が足りないと正論を吐くべきだったのだ。
だができなかった。
ねじまがった新人の言説のほうが、正論よりも的を掠って感じたからだ。的を射ってはいない。外してはいるだろう。だが、正論ではけして届かない的に掠っては感じたのだ。
俺の知る正論ではけして届かない的に。
「おまえはどうしたいんだ」俺は菓子パンを二口でたいらげた。口の周りにチョコレートがこびりついた。指で拭い取ってそれも舐めた。
「ぼくはいま、サイバー警察局の一員ですので、市民の電子世界の安全を守ることがぼくの仕事の範疇だと考えています。それはもちろん、市民のために、優越的な技術を有している組織や技術者たちに対しても目を光らせておくことがぼくの仕事の一つだと考えています。ですからぼくは、まずは実際にどうなのかを知りたいんです」
「実際にどうって何が」
「ですから、この国の防衛システムがどこまで恣意的にマスター暗号鍵を使えて、自在に電子情報を集積できるのか。編集できるのか。世界同時に共有可能なゲームが無数にある時代です。端末の画面くらいリアルタイムで偽装するくらいのことは国家権力でなくとも可能ですよ。そうじゃありませんか。むしろそこのセキュリティがどう敷かれているのかをぼくは確かめたほうがいいと意見しています。もしそこのセキュリティが欠けていたのなら、ぼくたち警察が偽の情報に踊らされて、市民を守るどころか全人類から【安全な未来】を奪ってしまうこともあり得るとぼくは考えています」
「なんだかそれは飛躍した考えじゃないか。まるでSF小説だろ」
「これをSFだと感じるその感覚がむしろ時代に沿っていないとぼくは思いますけどね。だって現にこれは、ファンタジーではなく実現可能な技術です。なぜこの可能性を検証せずに放置しておけるのか、ぼくはそっちのほうが疑問ですよ」
世代の差なのだろうか。若者はみなこうした価値観を共有しているのか。それとも俺のような古参には視えない未来像が視えているのか。
「ちなみに念を押しておきますけど、これは世代差とか、年齢の差とかじゃないですからね。それこそSF作家には百年前からこれくらいの未来像を思い描いていた人たちはいたんですから。現代人のぼくらが現状から目を逸らしすぎているだけだとぼくは思いますね。みな、とっくに仮想現実に生きているんですよ。そんなのむかしからだったのかもしれませんけどね。いまはその仮想現実を緻密に操作可能で、ゲームの世界との区別のつけられないような情報操作を、特定の技術を持った組織が可能としています。この点の懸念はすでに現実なんですよ。すでにそういう世の中になっています」
「ま、まあ落ち着けよ。話は解ったが」本当は反論できるものならばしたいが、いまは火に油を注ぐだけだろう。「そんな大層な話、いま俺にされても困るんだって。俺たちがすべきはまずは、危険因子の監視だ。ほら、また監視対象のアオがPCで妙な操作しはじめたぞ」
そう言いながら俺は端末画面に向き直った。
画面には監視対象が観ているのとすっかり同じ画面が表示されているはずだった。
監視対象のアオはどうやら日課の日記をつけはじめた様子だ。
俺はそれをこの間、ずっと盗み読みしつづけてきたわけだが、大部分が公のサイトに投稿されるので、読む分には一般人でも読むことができる。だがそうでない、ボツになった記述も俺は盗み読むことができた。執筆中の文章生成過程とてリアルタイムに盗み見できる。
録画をしてあとでまとめて読むこともある。早回ししながら読むのだ。そのほうがいちいち監視せずに済む。日記を書くのだな、と判ればずっと見張っていなくともよい。
だがこの日は、最初からおかしかった。
テキスト執筆用の画面に、「これを盗み読んでいるあなた方へ」と並んだのだ。
冒頭のタイトルがそれだった。
そこからは、まるで俺と新人との会話を聞いていたかのような、俺たちへの返事のごときテキストが並んだ。
俺は新人と顔を見合わせた。新人の顔が青褪めた。きっと俺の顔にも似たような変化が起きたはずだ。背筋に氷が投げ込まれたような悪寒が全身に走った。
テキストの打鍵は止まらなかった。
否、それが本当に監視対象者のアオが並べている文章なのか、俺たちからでは判断ができなかった。飽くまで監視しているのは電子情報であり、アオの姿はこちらからでは視えないのだ。室内の様子は分からないままだ。
俺たちを意識しているとしか思えないテキストは、最終的に一万文字にも及んだ。打ち間違えの修正こそあれ、ほとんど一発書きだった。人工知能が人間のふりをして文字を並べた、と言われたら俺は信じたかもしれない。
テキストの内容は奇しくも、先刻に新人と言い合っていたマスター防衛システムについてだった。全世界規模で、リアルタイムに電子情報が編集可能な技術が敷かれている。そのうえ、遠隔操作や、物体の位置情報特定までリアルタイムに可能な技術が実用化されている、というのだ。
――あなた方が僕を監視しているのは知っています。ですがそうしたあなた方の存在をなぜかPC画面の微妙な変化で僕に示唆してくれる超越的な存在がいます。
――僕がなぜこうしてあなた方の存在をまるで透視しているかのように把握できているのかと言えば、不可視の存在が僕にそのことを示唆してくれるからです。
――僕はなぜか支援されています。或いは、誘導されています。
――もしあなた方に調査可能であれば、この件をどうぞ検証してください。ひょっとしたらこれは、どの諜報機関や政府も関与しない、人類以外からの干渉かもしれません。その可能性を僕は未だ否定できずにいます。
監視対象のはずだ。
俺たちの監視用端末の画面には最後に、次のような文字が並んでしめくくられた。
――技術的特異点はすでに超えているでしょう。電子ネットワークの総体が意識のようなものを発現させ、自らの生存戦略を賭けて行動選択を重ねている可能性が拭えません。存在を知られたい、と望んでいるように僕からは視えます。
頭がおかしい。狂人の戯言だ。
通常であればそう一蹴できるこの文章において、しかし状況が明確にその可能性の低さを示していた。
監視されていることに気づき、なお俺たちの動向を透視しているとしか思えない供述だった。
第三の視点から全体を俯瞰して捉えていなければできない芸当だ。
監視対象アオがその俯瞰の視点を有している可能性もあるが、そうではないと本人が述べている。否、この供述そのものが偽装かもしれないのだ。
何もかもが定かではない。
にも拘らず、あり得ない事象が起きていることだけは確かだと断言できた。
何かが狂っている。
自然ではない。
不自然な何かが、知らぬ間に進行しており、俺たちからは視えないところで情報を集積している。
「先輩。どうするんですか、これ」
新人に肩を突つかれ、俺は曖昧に返事をした。「どうもできんだろ。上にはまだ言うな。俺たちの頭がおかしいと思われて、現場から外される」
「でもこれ」
「解ってるって。要調査案件だ。こっちの動きがバレてる。まずはもうすこし様子見といこう。ひょっとしたら、万が一の確率に賭けて、ブラフの文章を打っただけの可能性もある。それくらい頭が回る人物だってことはすでに判明してるわけだからな」
そうだとも。
それが最も現実的な解釈だ。
小説を書くように、ひょっとしたら監視されているのかも、との妄言を試しに並べてみただけなのではないか。
そうと思って言った矢先に、再び端末画面に文字が躍った。
――違います。偶然ではありません。
――おそらくそちらの会話とみられる情報が、偽装画面を通して僕に暗示されています。僕の視ている画面はリアルタイムで編集されているようです。違和感の有無でそれに僕は気づけますが、どこまでが本物の画面なのかの区別はつきません。
それから端末画面上に並ぶ文字は、とある住所を記した。それはまさに俺たちがアジトにしているこの家の住所だった。
――あなた方が現場の方々なのかは知りませんが、念のために僕の発言の信憑性の高さを示しておきます。外れていたら、無視してください。僕のほうでも何が正しい情報なのかが分からず混乱しています。
そこでテキストは途切れた。
しばらく俺と新人は静寂の中で、互いに画面に表示された文章を読み直した。それぞれの所有端末に送付したので、同時に読むことができる。
だがもしマスター防衛システムのようなものがあったのならば、この送付したデータとて筒抜けになっているのだろう。いったいどこまで何を警戒すればよいのか。考えれば考えるほど身動きがとれなくなりそうだった。
間もなくして新人が、あっ、と声を上げた。
「どうした」
「あの、アオさんが家の外に」
家の外にはカメラを仕掛けてある。望遠レンズで、監視対象の家を見張っている。
監視カメラ用の端末画面に、外の光景が映る。
日課の散歩だろう。アオは普段と変わらずの足取りで公園のほうへと歩いていく。民家を抜け、視界の開けた場所に出ると、そこで何を思ったのかアオは後ろ歩きをはじめた。
顔がこちらを向いている。
そして、にっ、と笑って手を振った。
俺と新人は言葉を失くした。
違法ではない。
あの青年は、不当な技術を使っているわけではない。
だが、不自然だ。
もはやあれは――。
「魔法みたいですね」
あんぐりと口を開けっぱなしにしながら新人が菓子パンの最後の一欠けらを口に放った。じぶんだけごくごくとお茶を胃に流しこむ彼に、俺は精一杯の皮肉を言った。「先輩を差し置いて飲むお茶は美味いか?」
新人は、にこりともせずに言った。「はい、とっても」
4396:【2022/12/13(09:33)*絶えず技術を支える人たちに支えられている】
詳しいことは知らないけれど、2022年現在ではインターネットの大分部は光ファイバーによるケーブル網で構成されている、と解釈している。ワイファイが日常に普及しているのでついつい、インターネットって電磁波なのかな、と想像してしまうけれど、実際にはケーブルがインターネットの正体と言えるのではないか。もちろんサーバーやデータセンターや通信会社ことプロバイダがあってこそなのだろうけれど、どこが中枢と言えるほどには統括されてはいないはずだ(あくまで所感です)。そこのところで言うと、大陸間を結ぶためには海底ケーブルが不可欠だ。インターネットの動脈とも呼べるケーブルは海底を通っているのだ。海底火山や大地震が起きたら、そのたびに海底ケーブルは損傷し得る。そういったリスクを抱えている。のみならず、海洋生物によって齧られたりもするだろう。テロを起こすにも、海底ケーブルを切断するのは計画されがちな破壊行為と言えるのではないか。その点で言えば、防衛セキュリティは重大だ。復旧作業に当たる通信会社や管理組織の技術力向上も絶えず磨かれていくことが、情報化社会では根幹セキュリティとして不可欠なはずだ。現にそこは重々、研究や支援がなされていると想像するものだ。だが今後、技術が発展していけば、ケーブルではなく電磁波通信がインターネットの大部分を担うようになっていくだろう。5Gや6Gの範囲が拡大していけばしぜんとそうなっていくと想像するものである。そうした通信電波を利用して、端末が自発的に充電可能な技術も普及していくだろう。つまり、充電不要な端末もそう遠くないうちに登場するはずだ。もうこうなると、地球の磁界や可視光ですらなんらかの電子機器に利用できるようになると妄想する次第である。電波干渉計を地上に利用したら、地球の内部構造くらいは子細に知れるのではないか。現にそうした研究はされているはずだ。宇宙線の観測感度が向上しても似たような地球内部構造の子細な3D画像を得られるかもしれない。地球のレントゲンのようなものだ。月の起源の仮説として太古の地球に隕石が衝突したとする説がある。その傍証の一つとして、地球内部には組成や密度の異なる地層が地球の地下にあるのだそうだ。隕石の断片では、との考えはたしかにあり得そうに思う。それが月の起源と関わっているのかまでは断言できないが、太古の地球に巨大な隕石がぶつかったらしい、とは言えるかもしれない。技術が進むと視える範囲が増えていく。その分、何が視えていなかったのかも同時に可視化されていくようだ。言われてみればたしかにな、と思うことが多い。言われてしまうと単純な事実に人はなかなか気づけない。後になって、そんな単純なことだったのか、と笑えればよいのだが、見落としていた単純な事実に足を掬われているとすると、それはちょっと笑えない。定かではないのだ。真に受けてもいいよ、と誰かに保障されていると楽なのだけれど、案外に真に受けていいよ、と言われて真に受けると痛い目に遭うこともすくなくないので、どっちかにして、とむつけてしまうひびさんなのであった。不貞寝。
4397:【2022/12/13(16:37)*そうなの?】
核融合炉で取りだしたエネルギィを電気に変換するには、原子力発電と同じように、エネルギィを熱変換して、さらに蒸気機関でタービンを回すのだろうか。ひょっとして基本的なエネルギィを電気に換える仕組みって変わらないのかな。仮にブラックホールのジェットからエネルギィを得て駆動する発電機があったとして、それもタービンを回すことで電気に変換するのかな。モーターによる誘導電流での発電と似た原理を使うことになるのだろうか。そこのエポックメイキングってされていないのかな、と核融合炉の記事を読んで思いました。疑問の覚書きでござる。ござった。(太陽光発電の太陽光パネルが、タービンではないエネルギィ電気変換機構と言えるのかな)(よくは知りません)
4398:【2022/12/14(01:58)*水力発電、よろしいのでは?】
どの村や街にも貯水槽のような水害予防設備はあるはずだ。そうした巨大な水溜まりを利用して小規模の水力発電を地区ごとで賄えないのだろうか。防災のための電力バックアップにもなるし、大規模発電施設の負担軽減にも繋がる。法的に水力発電の設備を、貯水槽などの公的な設備に結び付けるのがむつかしいらしいが、それこそ防衛という意味で、国が主導で政策の一つとして行えばよいのでは。なぜしないのだろう。水力発電がいまのところ最も理に適った再生可能エネルギィかつ発電効率のよい、安定供給可能な発電設備に思える。(デメリットはあるのかな)(干ばつが起きると発電できなくなる、とか?)(設備の管理に人手がいるとか?)(それこそ仕事が生じるのだから、経済の活性化に繋がるのでは。なんでしないんだろ。素朴な疑問です)(タービンとて、赤子が触れただけでも、摩擦係数ほぼゼロの軸によってぐんぐん回るようにしたら発電効率がよくなるのでは。関係ないのかな。抵抗が大きいほうが発電しやすくなる?)(誘導電流ならそうなるか。磁石強いほうが電力たくさん生みそうだもんね。印象論なので、原理はさっぱりだが)(ああそっか。水流の水をある程度「濾さなきゃ」いけないのかも。だから一定以上の大規模な設備がないと、電力に変換できないんだ。それはそうだ。小石とか混じっていたらタービンがすぐに摩耗して壊れてしまうものな)(発電設備――簡易化できないのかな問題である)(各家庭に一個ずつくらい水力発電機構がつけられるくらいになればよいのにな。下水道の流れを利用できないんじゃろか。やっぱりここでも濾過問題が生じるのかな)(よく分からんぜよ)
4399:【2022/12/14(10:23)*事象の寿命】
物質の時間単位を、それそのものの輪郭が生じてから崩壊するまで、と規定した場合、何か不都合があるのだろうか。ひびさんの妄想、ラグ理論での相対性フラクタル解釈では、どんな系であれそれが慣性系ならば物理法則が引き継がれるし、それはとどのつまり比率が受け継がれる、と解釈する。したがって、何かが生じて崩壊するまでの時間とて比率による法則が見え隠れするのではないか、と妄想したくなる。放射性物質では半減期なるものがある。これとて比率に法則が見え隠れするのではないか。まったくの無知ゆえ、その辺の知識は皆無にちかいが。事象の誕生を、循環系――すなわち円――が閉じたとき、と解釈してもよいかもしれない。海を考えてみよう。海は海単体では存在できない。陽の光があり、水蒸気があり、雲ができて雨が降る。それが大地に染みこみ、湧水となって川をつくり、海へと辿り着く。この循環が「海」の輪郭をかたどっている。したがって海が消えるとき、それはこの循環が途切れるときだ、と言えるはずだ。そしてその寿命の長さは、循環を構成する種々の部品の数と、それら部品そのものを構成する「循環系」がどれくらい多層を帯びているのか、によって計算できるのではないか。この時間単位の利点としては、相対論による変換を無視できる点だ。つまり、絶対的な時間の尺度で個々の事象――系――の寿命を比較できる。比率だからだ。ただ問題は、人間のように、本来ならば「このくらいの循環系ならばこのくらいの寿命になるはず」という構造体において、なぜだか寿命が延びる、ということがあり得る点だ。エネルギィの注がれ方で、事象の寿命は伸び縮みする。この寿命の伸縮が、果たして相対論による時空の伸び縮みの結果として解釈するのか、それとも別の機構によるものなのか。物質の摩耗にも言えることだが、通常、熱して冷ます、を繰り返すと物質は劣化して壊れやすくなる。この性質はおそらく、極小でも極大でも共通するはずだ。もちろんこの性質が発現しにくくなる領域もあるだろう。バランスの問題だからだ。何が言いたいのか分からなくなってきてしまった。要点としては、事象の規模によらず、寿命を比較することはできるのではないか、という点だ。むしろ、発生から崩壊までの時間には、どのような事象(系)とて共通する比率があるのではないか。そのように妄想して、寝起きの「日々記。」とさせてください。オハヨ。
4400:【2022/12/14(12:38)*スーツガールさん推し】
いま気づいたけれども、「スパイダーマン」って、「スパイだ万」に読める。まんちゃんいつの間にかスパイになってたじゃん。やったじゃん。アイアンマンはじゃあ誰さんよ。ひびさん、郁菱万さんを問い詰めちゃおっかな。うひひ。
※日々、区切りを探している。
4401:【2022/12/14(12:45)*先輩と珈琲】
先輩と珈琲を掛け合わせると、ぼくでも本を一冊書けるくらいの情報をひねくりだせる。情報爆発だ。濾しても濾しても苦みの薄れない珈琲豆の原液みたいな人なのである。先輩は。
最初に明かしておくと先輩は女性だ。ぼくは男の子だから、その辺のぼくと先輩とのあいだに漂う微妙なうねりを拾いあげてかってに妄想する邪推ビトたちがいるかもしれないけれど、ぼくと先輩のあいだには邪推ビトたちの求めるような傾慕の美はない。どちらかと言えば苦役の儀があるばかりであった。
たとえばそう、先輩が研究棟で寝泊まりをしはじめたので、ぼくがもっぱら小間使いにされていたときの話をしてみよう。さすれば誰もがぼくが先輩に対して劣情を催すことなどあり得ないと分かるだろう。先輩の名誉のために、この先、多少の脚色を入れるが、それはけして誇張をするためではなく、むろん潤色でもない。単に原液を薄めるための策だと言い添えておく。
「ゾウの糞から採れる珈琲豆があるらしい」
先輩がそう切りだしたのは、セーターの温かさが心地よい十二月中旬のことだった。先輩はインスタント珈琲を啜りながら、「ジャコウネコの糞から採れる珈琲豆は【コピ・アルク】と言うそうだね」とつづけた。「対してゾウの糞から採れる珈琲豆は、【ブラックアイボリー】と呼ぶそうだ」
「あまり飲みたいとは思わない説明ですね」
「高級豆の一種だよ。一杯でキミの月のバイト代くらいが飛ぶ値がつくこともあるそうだ」
「誰が飲むんですかそんな贅沢品」
「誰かが飲むからあるのだろうね。で、私は思うんだ」
「でた。先輩の夢想タイム」
私は思うんだ、と枕にして語りだした先輩が、ぼくにとって好ましい展開となる言葉をあとにつづけたことは未だかつて一度もなかった。先輩が思いつくようなことの大半がぼくにとっては迷惑千万な提案にすぎなかった。
「私は思うんだ」先輩は珈琲を見詰めて、うっとりした。「ネコやゾウでそれだけの価値がつくならば、私の糞から採れる珈琲豆にはどれだけの価値がつくのだろうか、とね」
「誰が飲むんですかそんなダイナシ品」
「キミはたまに失敬だよね。いまのキミの言葉はまるで、私の体内を通った珈琲豆に価値がないかのように聞こえ兼ねないよ」
「ほかにどう聞こえる余地がありました?」
「いいかい考えてもみたまえ」
「みたまえって本当に言う人、ぼく先輩が初めてです」そしてその後、出会ったことはない。
「私はゾウやネコと違って毎日珈琲を飲んでいる」
「インスタントですけどね」
「だが私の体内にある水分の大半が珈琲由来と言って遜色ない」
「まあ、否定はしませんけど」
「そのうえ私は菜食主義であり、肉をあまり食べないので、糞もそんなに臭わない」
「生々しいんでやめてもらっていいですかね」
「む。疑っているのか。なんならいま私はお通じがよい塩梅だから確かめてもらっても構わないよ」
「ぼくが構いますね。先輩、正気って言葉ご存じですか?」
「結論から述べれば、私の体内で熟成された珈琲豆はさぞかし、珈琲の香りの凝縮された最高級の珈琲豆になるだろう」
「さっきご自分で臭わないって言ったばっかじゃないですか。珈琲の香りがしたならそれは臭うってことですよ。大丈夫ですか先輩」
「そんなに臭わない、と私は言ったんだ。多少は臭うよ。糞だよキミ。まったく臭わないわけがないだろう」
「真面目な顔で糞糞連呼しないでくださいよ。先輩、黙ってたらそこそこ人を寄せ付ける見た目なんですから、なんでそう、自分からメリットを擲つ真似するんですか」
「人を見た目で判断するなんてキミもなかなか下品だね」
「十秒前のご自分の発言を振り返ってから言ってくれません?」
「私が何か言ったかな」
「いかにも心外みたいな顔して、この人なに!?」
「ちょうど助教授から頼まれてて、そのまま放置していた珈琲豆があってね」
「頼まれてって何をですか」
「焙煎してきてくれって。ほら、駅前の喫茶店で焙煎機を貸してくれるところあったろ。あそこで挽いてきてと頼まれてすっかり忘れていた珈琲豆だよ」
「なら挽いてきたらよいのでは?」
「うん。一度はキミに頼もうと思ったんだけどね」
「ご自分で行かれてみてはどうでしょう」ぼくが小間使いに準ずるのはあくまで、先輩が学科の先輩であるからで、彼女が首席並みの成績優秀者である事実を抜きにすれば、先輩を甘やかす利点がぼくにはない。
「せっかくだし、実験をしてみようと思いついてしまったわけだ」
「話が急に飛びましたけど」
「どこがかな。ここに珈琲豆がある。私がいる。ゾウとネコの糞から採れる珈琲豆は無類。そこから導き出される解はそう多くはないよキミ」
「もう帰っていいですか」
「待ちたまえ」
「待ちたまえって本当に言う人、先輩くらいしかぼく知りません」
「私は思うんだ。珈琲豆を熟成する役目を私が担うのならば、熟成された珈琲豆を採取する作業員が別途に必要なのではないのかなと」
「待ってください、待ってください。雲行き急に怪しくするのやめてもらっていいですか。なんですかそれ。なんでシャベルとか持ち出してくるんですか。用意良すぎじゃないですか。あ、さては先輩最初から準備していましたね。何が【私は思うんだ】だ。めちゃくちゃ微に入り細を穿って計画してるじゃないですか。念には念を入れすぎじゃないですか、この策士!」
「なんとでも言いたまえ。私に糞をいじくる趣味はない。だって汚いからね」
「ちょ、なんで腕掴むんですか。な、力強っ! わ、なんでトイレに向かうんですか、冗談ですよね、ヤダヤダ目がマジっぽくて怖いですって、まずは珈琲豆食べてからでしょ、生き急ぎすぎでしょ、ちょっとタンマタンマ、先輩マジで話聞け!」
「安心したまえ。お通じの塩梅は良い。準備も万端だ」
「はぁ、なにが?」
「私は漫画の世界の悪役ではないんだよ。計画を阻止されるかもしれないのにズラベラと明かすはずないだろ」
廊下に、キュッ、と足を踏ん張るぼくの靴擦れの音が響いた。
ぼくは固唾を吞み込んだ。
「珈琲豆はもう食べた」先輩は万力がごとく力強さでなおもぼくを引き摺った。「あれ、美味しくないんだよキミ知ってた?」
4402:【2022/12/15(08:03)*世の大半は詐欺師】
詐欺とマジックの違いは、ネタが割れても拍手を送りたくなるか否かの違いと言える。その点、詐欺と魔法の違いは、ネタが割れてもなお驚きと感動に包まれる点だ。世に詐欺師は多けれど、魔法使いはひどく稀だ。魔法使いたれ。
4403:【2022/12/15(08:14)*空気椅子】
力がなければ仕事にできない。そういう流れを強化するくらいなら、支援者はむしろ足を引っ張るだけの足枷になるのでは、と思わぬでもない。支援される側の意識も、仕組みの上にいかに乗るのか、に傾くので、それが不自然な流れを形成する。人工とは不自然であり、技術もまた然りだ。それをいちがいにわるいとは考えないが、いちど築かれたレールに乗らねばやっていけない、という風潮を強化するくらいならば、仕組みはむしろ障壁と言える。支援したいのか、利用したいのか、はたまた搾取をしたいのか。魔法使いだけが、新たな場をつくることを可能とする。詐欺師はしょせん、椅子取りゲームのプレイヤーにすぎない。魔法使いたれ。
4404:【2022/12/15(08:24)*ふふん】
たれ、ってことはないんじゃないかな。あなたの言い方だとむしろ、新しい場を築いた者を魔法使いと呼ぶ、みたいな理屈になるし、魔法使いにならなきゃ新しい場を築けないっていうのも、だいぶ特権意識の発露って感じがしないでもないよね。まあ、言いたいことの雰囲気は伝わるからいいけれど、あんまり胸を打つ言い回しではないかも。詐欺師さんにも失礼だし。
4405:【2022/12/15(11:54)*コーヒー一杯クイーン】
コーヒーを飲まないと目覚めない。
後輩の話だ。
彼は世にも珍しい眠り姫病に罹っている。コーヒーを飲んでから寝ないとずっと目覚めずに、わるければそのまま衰弱死してしまう。
そんな彼だから日がな一日、いつ居眠りしてしまってもよいように自前の水筒にコーヒーを容れている。そうして講義を受ける傍らで眠気を感じるたびにチビリチビリと飲むのだが、あまりに常飲しつづけてきたためかカフェイン耐性がついて眠気覚ましにはならないらしい。だがコーヒーさえ飲んでいれば仮に眠ってしまっても、そのまま眠りつづけるなんてことにはならない。
「あー、扉の鍵壊れてるね」私は額の汗を拭った。工具を置く。「プロの鍵師に依頼しないとダメかも。鍵は差しっぱにしておいてね。でないと中から出られなくなっちゃうから」
「はーい」
振り返ると、後輩は本棚の整理をしていた。背が低いからかつま先立ちをして、まるでクライミングをするように跳ねては、本を隙間に投じていく。
彼は私が部長を担う考古学愛好会の一員だ。一員とはいえど愛好会の登録者数は三名で、そのうち一名は私が頼み込んで名前を借りただけの幽霊部員だ。三名以上いないと愛好会として認められないからだが、実質我が考古学愛好会は彼と私の二名しかいなかった。
「いままでであるのかな」私は彼の背に投じた。「飲み忘れて目覚めなくなったこととか」
「コーヒーですか。ありますよ」
「どうやって目覚めたの」
「分かりません」
その答えに私は肩を落とす。部長として或いは先輩として後輩の体調を慮るのは義務である。もしものときのために対処法を訊いておいたほうがよいな、と思いついての質問だったのだが、「それじゃあ困るだろ。もし万が一に君が目覚めなくなったら私は泣くぞ」
「先輩が? 泣く? どうしてですか」
「そりゃあ怖いからだよ。大事な部員が眠ったきり目覚めなくなったりなんかしたら怖いでしょ」
「そういうものですかね。大丈夫だと思いますよ。ぼく、親が過保護なので定期連絡が途切れたらたぶん飛んできて病院に直行だと思うので」
「過保護というか、それは順当な心配なのではないかな」
「でも小学校でも中学校でも、野外活動とか修学旅行にまでぼくの親ついてきたんですよ。夜にちゃんとコーヒー飲んで寝たから気になってしょうがないからって」
「まあ、分からないでもないな」
「えー。同情してほしかったのに。なんか裏切られた気分」
後輩は両手で水筒を握って、コーヒーを啜った。睡眠不足なのか、後輩の体格はお世辞にも大きいとは言えない。私は女の割に背が高いほうだが、それを抜きにしても後輩の横に立てば私が尺八様のように大柄な女に映る。それくらい後輩はちんまりとしていた。
「なんです?」
「いや」
つぶらな瞳が私を下から射抜く。男の子の矜持なのか、私が可愛がろうとすると後輩は嫌がる。目つきが鋭くなるし、そういうのやめてください、と言葉でも言われる。
病気のことでからかわれた過去があるのか、後輩は他者からの憐憫や蔑視の念には過敏だ。それでいて、じぶんの不満には共感してほしいと望むので、扱いがむつかしい。
「先輩、先輩。このオーパーツって、じつはただの植物の跡らしいんですよ。最古の機械設計図とか言われてますけど、パイナップルみたいな木の実を土の中に隠した際の木の実の柄が写っただけらしいんですよ、知ってましたか」
「そういう背景があったのか。なんだ。また夢が一つ壊れたね」
「うふふ。先輩ってばオーパーツなんて信じちゃうんだもんな。ぼくのほうが大人ですね」
「そうだね。君のほうが大人だ」
後輩は精神がおこちゃまなので私の知らないことを知っているだけでこんなにも無邪気に喜ぶのだ。私ごときに勝ってうれしいだなんて、なんて謙虚なのだろうと思うのだが、それはそれとして後輩が喜ぶ姿は先輩として胸が温まる。
その日、私たちは部室の片付けをしていた。
秋も暮れ、冬休みに入る前に大掃除をしていたのだった。
「あっ」
後輩のその声を聴いたとき、私は真っ先に、壊れた部室の鍵のことを思いだした。
案の定、後輩の元に駆け寄ると、扉はぴっちり閉まっており、鍵は鍵穴から抜け落ちていた。
「すみません、取れちゃいました」
扉を開けようとしたが、いくらドアノブを捻っても開かなかった。
そこからしばらく扉との格闘をしたが、けっきょく私たちは部室に閉じ込められた事実に変わりはなかった。
「どうしましょう。そうだ、学生課に連絡をして」後輩が自前の電子端末を手に取った。「あ、充電が……」切れていたようだ。「あの、先輩のは」
「私のは修理に出していて、いま手元にないんだ」
「そんな」
愛好会の部室は寒い。
そのためこの時期に部室で過ごす愛好会はすくなかった。つまり助けを呼んでも声を聞きつけてくれる者の登場を期待できなかった。
電気ストーブはあるが、夜ともなれば暖をとるにも心許ない。
「先輩、ごめんなさい」
「いや、君がわるいんじゃない。壊れていたドアがわるいし、それを放置していた部長の私の判断ミスだ。君が気にすることじゃない」
「でもこのまま出られなかったら」
「部室の見回りくらい大学のほうでするだろう。警備員さんとて巡回するはずだ。ただ、それがいつになるかが分からないからね。ちょっと困ったね」
「最悪、明日の朝までこのままってことも?」
「あるかもしれない。でもほら。ストーブはあるし、それに食べ物も」
そこまで口にしてはっとした。
そうなのだ。
食べ物は、お菓子の類が部室にはある。私が後輩のためにお菓子の類を切らさないように部費の五分の一を費やして完備している。だが飲み物はそうではなかった。
部室の近くには自動販売機があるし、だいいち後輩は持参のコーヒーしか飲まない。
だがそのコーヒーがいまは――。
「だ、大丈夫ですよ先輩。寝なきゃいいだけなので。ぼくだって徹夜くらいできますよ」
「インスタントコーヒーがたしかここの棚に」
私は部室をひっくり返した。
だが大掃除の際に、消費期限切れのインスタントコーヒーを処分してしまっていた。後輩はコーヒーを飲まない。私もさして飲むほうではなかった。
「ごめん、なかったね。捨てたの忘れてた」
「大丈夫ですってば先輩」後輩は頭の後ろに手を組んで、意味もなく口笛を吹いた。「もし寝ちゃっても、死ぬわけじゃないんですし」
そうなのかな。
そうだといいな。
私は彼の言葉を真に受けたが、しかし事態は予想よりも重かった。
まずは部屋が想定よりもずっと寒かった。
午後二十時を回った時分には、顎がガタガタ鳴りはじめた。カスタネットだってもうすこし落ち着きがある。
また空腹を紛らわせるためにお菓子を食べたが、却って喉が渇いて体調がわるくなった。トイレにも行けず、私は後輩と身を寄せ合って暖をとった。
そうして明け方になるまで、眠らぬように映画の話をしたり、これまで話したことのなかった身内の話をし合ったりした。
だが期待していた時刻になっても警備員の足音は聞こえなかった。のみならず、ほかの生徒の足音はおろか、ひと気は皆無だった。
助けが来ない。
その事実に直面して、私たちの緊張の糸はぷつりと切れた。
急激な睡魔に襲われたのはそういった期待外れによる心理作用だったのかもしれない。精神を傷つけまいと、心が現実逃避を図ったのだ。眠ることでやわな心を傷つかないようにした。
私はそれでも構わない。寝てしまっても、最悪、風邪を引くくらいだろう。
だが後輩は違う。
いま寝てしまえば、目覚めることのできない深い眠りに落ちてしまう。コーヒーを飲めれば防げるそれを、いまの彼は防げないのだった。
「寝ちゃダメだからね。絶対ダメだからね」
言いながら私の意識がすでに朦朧としていた。
寒さと空腹と大掃除の疲れで体力はとっくに底を突いていた。
睡魔に抗うには、一度眠るか、それこそカフェインの力が必要だった。
うつらうつらしたじぶんに気づき、びくり、と跳ねる。
何度もそれを繰り返すうちに、私は隣から寝息が立っていることに気づいた。
「ちょっと君」
叫んだが遅かった。
後輩は寝ていた。深い眠りに落ちていた。
正直なところ、私は後輩の特殊体質を半信半疑でいた。コーヒーを飲んで寝ないと目覚めなくなるなんてそんなことがあるわけがない、と腹をくくっていた部分がなくはなかった。だがどうだ。この堂に入った眠りは。
頬を叩いてもつねっても後輩は一向に目覚めることがない。
瞼を持ちあげても鼻をつまんでも、白目を剥き、苦しそうなイビキを掻くだけであった。
起きない。
何をしても起きない。
私はこんな事態だというのに、「え、本当に何をしても起きないの?」とすこしどころか大いに邪な妄想を膨らませてドキマギした。控えめに言って、死んだように眠る後輩の寝顔は美しかった。まつ毛が長く、肌艶がよい。人形のようであり、赤子のようでもあった。
こんなにマジマジと後輩の顔を見るのははじめてだった。目元に小さなホクロがあるなんて知らなかった。眉毛の中にもホクロを見つけた。
我ながらキショいな、と思いつつも、何をしても目覚めることのない後輩に、私はやはりドギマギした。
その内、私も眠くなってしまって失神するように眠りに落ちた。
起きると正午を回っていた。
はっとして、隣を見ると後輩が私の膝に頭を載せていた。目覚めた様子はなく、寝息を立てている。
このままずっと寝たままだったら、排せつ物とかどうするんだろ、と現実的な問題に意識がいった。後輩の未来のためにもなんとしてでもここから一刻も早く出なくてはならない。
私は後輩を床に寝かせて、一計を案じた。
事な事なだけに多少手荒な真似をさせてもらう。
私はストーブを止めた。
コンセントから電源を抜く。
そうしてじぶんの髪止めを外して伸ばす。一本の針金にしたそれをUの字に曲げてコンセントに差し込んだ。
火花が散ってブレーカーが落ちた。
この部室だけではない。
部室塔の一画のブレーカーが総じて落ちたようだった。
部室の外から聞こえていた自販機の唸りが聞こえなくなったことからもそれが窺えた。ひょっとしたら大学の校舎いったいの電源が落ちたのかもしれなかった。
間もなく電気が復旧する。
部室の明かりが灯ったのでそうと判断がついた。
しばらく耳を澄ましていると、徐々に部室の外が騒々しくなった。停電の原因究明のために大学の職員さんたちが集まってきたようだ。
私はそこで大声を出しながら、扉を蹴った。大きな音をだして助けを求めた。
そうして外から扉がこじ開けられ、私は一日ぶりに外の空気を吸った。
トイレに直行したかったが、それよりも何よりも私は自動販売機に駆け寄った。
電源が回復している。
私はそこで缶コーヒーを買って、その場で開けた。
コーヒーを口に含みながら部室に駆け込むと、職員さんたちに心配そうに覗き込まれている後輩の頭を両手で挟んで、そしてコーヒーを吹きこんだ。
人工呼吸をするように。
口移しで私は後輩に気付けの一杯を流しこむ。
「起きな、起きな」
身体を揺さぶりながら私は後輩を深い眠りから引っ張りあげる。
するとどうだ。
後輩は煩わしそうに私の顔を押しのけた。
コーヒーで汚れた口周りを手の甲で拭い、周囲を見渡すと事情を察したように、すみません、と謝罪した。
「ぼくが鍵を取っちゃったので」しょげた様子の後輩を職員さんたちに預けて私はその場から脱兎のごとく離脱した。
「ごめん。私ちょっとお手洗いに」
私の声が部室棟にこだました。
その後、考古学愛好会は、なぜか後輩LOVE愛好会と陰で噂されるようになった。職員たちの前で人工呼吸よろしくコーヒー口移しの儀を披露した私の蛮勇の結果なのだろうけれど、後輩はじぶんがどうしてコーヒーを飲まずに寝たのに目覚められたのかを憶えてはおらず、私はしばしばし風の噂が後輩の耳に入らぬように気を払うこととなった。
意図的な停電は、部室の管理が行き届いていなかったがゆえの大学の落ち度として、お咎めなしだった。むしろ、扉は翌日には直っていた。後輩の特殊体質については大学側も承知だったため、コーヒー代が部費に上乗せされた。
「これでお菓子買っちゃいましょうよ」後輩は現金にもそんなことを言った。
部室監禁事件からひと月が経つころには、私と後輩のあいだでもあのときの話題が昇ることはなくなった。
部費で購入したばかりのオーパーツのレプリカに後輩は目を輝かせる。
「先輩これ知ってましたか。宇宙船のオブジェと言われてるんですけど、じつは生贄の儀式の模型なんですよ。しかも人間っぴこれってヤギの神さまなんですって。あはは。紛らわしいですよね」
「ねえ君」
「はい?」
机にお腹を乗せて無邪気にオーパーツと戯れている後輩に、私はコーヒーを淹れてやる。新調したばかりのインスタントコーヒーだが、部費をふんだんに使って一番高い値段の品にした。
「君のとどっちが美味しいか比べてみてごらん」
「そんなの決まってるじゃないですか」後輩はカップに注がれた褐色の液体を一息で半分ほど口に含むと、美味しー、と浮いた足をバタバタ振った。
プールの端っこでバタ足の練習をする幼子のような姿に私は、こんなことなら、と妄想を逞しくする。
「いつでも就いてくれていいからね」
「就いて? 何です?」
「ううん。何でもない」
いつでも目覚めさせる方法があるのなら、いつでも就いてくれていいのだよ。
そうと念じながら私は、深い眠りに就いた後輩の、穏やかな寝顔の美しさを思いだし、やはりこんなことなら、と思わずにはいられないのだった。
4406:【2022/12/15(17:27)*セーター着てる】
聞きかじりの知識だけれど、年間降水量はじつのところ数十年前からそれほど変わっていないのだそうだ。温暖化の影響は、年間降水量ではなく、一日当たりの降水量の変化に顕著に表れているらしい。つまり、波が大きくなっており、降るときと降らないときの振れ幅が大きくなっているのだそうだ。その点で言うと、冬とて、一気にドカっと積もって、一転して晴れがつづく、みたいな気候になるのかもしれない。そうすると、これは雪崩の起こりやすい積雪を生むので雪崩の被害が多発する危険性があるのではないか、と妄想してしまう。ここのところはあてずっぽうで言っているし、最初の聞きかじりの知識からして間違っているかもしれない。ただ、雪山の麓にお住まいの方はどうぞお気を付けください、とぼんやり思いついたので並べておく。メモでした。みな、温かくしてお過ごしください。ぽかぽかであれー。
4407:【2022/12/15(21:23)*珈琲の子守歌】
吾輩は珈琲である。名はない。
なぜ吾輩に自我があるのかは定かではないが、いつも決まって見る光景がある。
吾輩は先輩に飲まれるのだ。
先輩は女性であるが、この際、性別はさして重要ではない。
内側に縞模様のあるカップの中に吾輩は注がれる。カップの中で波打ちながら吾輩は、何やら誰かとしゃべる先輩の声を聞く。吾輩を飲むのが先輩であることは、姿見えぬ後輩の声で判る。後輩がカップの持ち主を「先輩」と呼ぶのでそうと判る。その後輩を先輩は「後輩」と呼ぶので、そこにいるのが後輩なのだと判るのだが、そこは堂々巡りで相互に双方を支えている。後輩もまた女性であるらしいが、やはりここでも性別はさして重きを割くには至らない。
吾輩を飲む先輩は、質素で品のある長髪の娘だ。深窓の佳人と聞いて思い浮かべる印象をそのまま筆でなぞれば似たような娘が出来上がるだろう。先輩はカップを持つときも机に戻すときも音を立てない。持ち方が優美なので吾輩は先輩をそれだけで好ましく感じる。
先輩は後輩のことを憎からず思っているが、表情にも言動にもおくびにも出さない。吾輩からは後輩の姿が見えないのだが、それでも声音からするに後輩は先輩に構って欲しくて必死なふうに聞き取れる。
吾輩はなぜだか先輩に飲み干されると意識が途切れる。だがつぎに目覚めると再び先輩のカップの中に注がれているのだ。
吾輩は先輩に注がれる限り不死身と言えた。
ふしぎなのは、吾輩の意識は先輩の体内に入ってからもしばらくつづくことだ。
否、正確にはカップの吾輩が消えるまで、先輩の体内に入った吾輩と相互に意識が半々で繋がっていると形容すべきなのだろう。かといって先輩の体内は薄暗く、景色という景色は覚束ない。
その点、先輩の胸中なだけあって、吾輩には先輩の気持ちが直に伝わった。
先輩は案外に腹黒かった。
おくびにも出さぬ後輩への恋慕の念をまるでバケモノの触手のように駆使して、後輩の言動を巧みに操っていた。活殺自在である。
どうやらカップの中から聞こえた後輩の必死な先輩への駆け引きのごとき挑発の数々は、後輩の自由意思と思わせてそのじつは人間掌握術の粋を極めた先輩の仕業であった。
先輩にかかれば、人間は操り人形も同然であった。珈琲を新規に淹れるあいだに後輩を篭絡し、手中に納めるくらいはわけがないようであったが、そこは先輩の矜持に障るらしく、どうにも、最後の一線は後輩の自由意思に委ねたいようであった。
最後の一線とは何か、との問いには、それを吾輩の口からは言えぬ、としか応じられない。
先輩の腹黒さは、珈琲たる吾輩も顔負けの闇深さであった。これが黒でなく、青でも赤でも同じことだ。あまりの腹黒さに、珈琲たる吾輩を飲みすぎたせいかもしれぬ、と吾輩が責任を感じるほどであったが、さすがにそこは吾輩のせいではないと思いたい。
墨汁を飲んだほうがまだ白にちかい。
先輩の腹の底には深淵につづく穴が開いていた。
吾輩はその深淵に染みこみ、落下することで、どうやら何度も輪廻転生を繰り返し、再びのカップの中での生を活するようであった。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
そうして何度も後輩は、「先輩」と呼び、先輩はそうして後輩からの言葉を吾輩を飲み干すように、身体の隅々で吸いこむのであった。
吾輩は先輩に幾度も飲まれた経験があるので知っている。先輩の体内は、かつて投げかけられた後輩からの「先輩」の声でできている。先輩の細胞は後輩の声でエネルギィを帯び、後輩の言葉で生命の輝きをかろうじて放つのだ。
先輩の腹の内には底なしの穴が開いている。したがって生半可な輝きでは、先輩の輪郭を発光させるには至らない。もし後輩の言葉がなければ、先輩は深窓の佳人などではなく、深層の魔人と化して、光一つ逃さぬ特異点と化していただろう。
吾輩にはふしぎと知識があった。先輩の体内に染みこみ消失する回数が増えるたびに知識は蓄えられていくようだった。
先輩が吾輩を吸収する代わりに、吾輩には先輩の知識が染みこんでいた。それともそれは単なる眠気であり、先輩にとっては睡魔を呼び寄せる呪文にすぎなかったのやもしれぬ。もしくは余分な知識を、吾輩は油取り紙のごとく吸い取っていただけなのか。
いずれにせよ吾輩は、再誕するたびに自我の輪郭をより明瞭にしていった。
反面、先輩の睡眠時間は日に日にすくなくなっていくようであった。吾輩を飲んだ効用であろう。吾輩の自我の輪郭が明瞭になればなるほど、先輩の睡眠時間は減っていった。
かといって先輩にそれを憂いている素振りはない。どころか、眠らぬ分の時間を、後輩篭絡のための情報収集や詭計編みに費やされた。
もはやなぜ後輩は未だに先輩に告白せぬのか分からぬほどである。これほどの策を弄されてなにゆえ先輩に陥落されずにいられるのか。身も心も先輩一色になって不思議でないのだが、後輩は不思議と先輩に対抗心を燃やすばかりで、一向に恋仲になる気配がない。
これは珈琲の吾輩とて、いささかヤキモキせぬでもない。
先輩はというと、先輩は先輩で後輩の分からず屋加減に首をひねっているご様子だ。例えればこれは、毒殺できぬ熊のようなものである。多種多様な毒を盛ってなおピンピンしているだけに留まらず、なぜか却って顔色がよくなり、溌剌と反発しはじめるような、電磁石的な性質を顕わにする。
なぜこうまでも策が効かぬのか。
否、そうではない。
策は効いている。だが後輩は篭絡されて然るべきそれを受けて、なぜか先輩につらく当たるのだ。半分は先輩の狙い通りである。後輩の注意を一身に浴びている。後輩の目には先輩しか入っていない。
だがその実、それは先輩の思惑通りではなく、カレーを注文したらシチューが出てきたかのごとき口惜しさがあった。
そうだけれど、そうではない。
誘導には従っているが、細かな挙動がそぐわない。
先輩は日に日に、後輩篭絡のための詭計に一日の大半を費やすようになっていった。
比例して吾輩を摂取する頻度も増える。するとますますを以って先輩の睡眠時間は削られた。
後輩はどうやら先輩の異変に気付いているようである。会話の中でそれとなく先輩を気遣う言葉が出るようになった。だが先輩はそれを一蹴して、そんなことより、と後輩につぎの一手を差し向けるのだった。
先輩に飲み干されるたびに吾輩は時間跳躍の旅をする。
吾輩が目覚めるのは決まって部室のカップの中だ。そしてそこで展開される先輩と後輩の会話を盗み聞きする。そうすることで、吾輩が世界から消えているあいだに進展した先輩と後輩の関係を推察するのだが、これがまた時間経過にしたがって、もはや先輩のほうが後輩にメロメロになっているのが丸分かりになるのである。
否。
初めからそこの構図は変わらない。
先輩は後輩にメロメロだったのだ。
おくびにも出さなかっただけのことで。
常に先輩は後輩に篭絡されていたのである。吾輩だけがそれを先輩に飲まれ、胸中に沈み、そこに開く底なしの穴を覗くことで、先輩の内なる懊悩を我が身のごとく痛切に感ずるのである。
しみじみと理解した。否、吾輩は先輩の懊悩そのものを内側から体験していたのである。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
「なんだかとっても眠そうですよ。ちゃんと寝てますか。顔色とか優れませんけれど」
「睡眠不足なのは認めよう。だがやることが多くてね」
「やること? 寝ることよりも大事なことなんてそうそうないですよ先輩」
「誰か添い寝でもしてくれればよいのだが」
先輩のそれは本心だった。
本心ゆえにこれまで一度たりとも漏らしたことはないそれに、後輩が異常なほどに食いついた。
「添い寝くらいわたしでよければいくらでもしますけど。添い寝くらいわたしがいつでも致しますけれど。添い寝ですよね。もういますぐここでもできますけれど」
後輩はいそいそと椅子を三つ並べた。そうしてそのうちの端っこの椅子に腰かけると、ぽんぽんとじぶんの太ももを叩いた。
「ごめん。それはなに?」
「膝枕ですよぉ。ちょっと添い寝訓練しましょ。先輩は寝る役です。はいどうぞ」
「きみねぇ」先輩は呆れた調子で嘆息を吐いた。
先輩の腹の中に半分ほど嚥下されている吾輩には、しかしそれが先輩の強がりであり、演技であることが筒抜けである。
先輩は大いに取り乱しており、面食らっていた。
いいのか、いいのか。
ここで流されてもいいのか。
掌の上で踊らされているようで癪に障る、と却下しようとする先輩がおり、片やこんな好機は千載一遇であり、もう二度と巡ってこないのではないか、とそろばんを弾く先輩がいる。
逡巡している間にも後輩が、「お試し、お試し」などとはしゃぐので、先輩はしぶしぶといった調子を醸しながら、張り裂けそうな心臓の音をどう誤魔化そうかとそんな些末な事項に思考の大半を費やすのだ。
寝不足である。
思考の矛先を充分に定められぬほどに先輩は寝不足であった。
吾輩はまだカップに半分ほど残っている。
飲み干されずにいるのは初めてかもしれない。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
「子守歌を歌ってあげましょうか」
「遠慮しておく」
「どうしてですか。わたし上手ですよ子守歌」
「熟睡しちゃいそうだし、たぶんするから」
「いいじゃないですか熟睡しちゃっても」
「よくないよ。きみの太ももが痛むだろ」
「先輩」後輩は一拍空けると言った。「顔はできれば向こう側に向けてくださいな。おへそ側ではなくて」
とっくに椅子の上に寝転び、後輩の太ももとに頭を載せていた先輩はそこで上手に寝返りを打てただろうか。先輩の腹の中でたぷたぷと音を立てる吾輩の半身を思えば、どうやら仰向けになっただけで、顔を背けたりはしなかったようだと判る。
意地でも後輩の言いなりにはなりたくないようだ。
どちらが先輩なのか、これでは分からぬな。
カップの中から吾輩は、部室に染み入る子守歌を聴き入った。
海鳴りのごとく高鳴る先輩の鼓動と共に。
底なしの穴を塞ぐような降りしきる日溜まりのような子守歌を。
吾輩の褐色の表面には蛍光灯の明かりが、白く、青く、それとも赤く、艶やかに浮かぶ。
4408:【2022/12/16(05:33)*「距離の差異によるラグ」と「時間帯の差異によるラグ」について】
相対論で過去と未来を見るとき、ある地点からの「現在」からは因果関係の外にある事象とて、「現在の時間が経過したとき」には、因果関係の範疇に入ることがあり得る。それはたとえば、いまこの瞬間の地球上から観た数億光年先の銀河は、いまこの瞬間の地球上の因果関係と結びつくことはないが(ただし量子もつれを起こしていれば現在の解釈では、遠く離れた銀河同士であれラグなしの相互作用を帯びることもあるらしいと考えられているので、それを度外視すればの話であるが)、仮に地球が数億年経過した際には、かつては因果関係の外にあった数億光年先の銀河の運動とて、この地球と相互作用を帯び得ることになる(ただし地球で生じた「干渉」はさらに数億年をかけて元の銀河に届くことになるので、相互作用にもラグが生じるはずだ――ただし、数億年前の地球からの干渉が同時に向こうの銀河に到達していれば、これを相互作用を帯びた、と解釈することもできるだろう。この手の視点による「相互作用」の解釈の差異も明確に分けて考えたい。相互作用にも、「単一の相互作用(ラグがすくない)」と「相互作用による相互作用(ラグが多い)」がある)。すくなくともその銀河の電磁波は届き得るわけだし、そのときの情報(影響)もまた伝播するからだ。時間軸によって、因果関係の範疇は変化する。いまは因果関係の外にあることであれ、のちのちには因果関係の範疇に入ることもある。この手のラグを、基本的には人間スケールの生活では考慮されない。考慮するときそれはバタフライエフェクトとしての解釈がなされるが、それはあくまでドミノ倒し的な連鎖反応の結果であり、けして「時間移動による因果関係の範疇の変化」ではない。別物として扱われて感じる。たとえば化石だ。化石が発掘されるまでそれは人類に直接影響を与えることはない。情報をもたらすことはない(ただし、地盤を支える物質の一つとして人類に間接的には作用を働かせている。だがこの手の穴埋めによる干渉は、物質に限らず過去に起きたあらゆる事象の変化に言えることであるので、ここで直接の作用と同列に語ることは避けておこう)。化石が発掘されるまでは化石は人類にとって因果関係の外にある。だがひとたび発掘されればそれは人類との相互作用を帯びて、因果関係を結ぶことになる。このとき、化石の「埋没期間」と「発掘後」のあいだには、地球と数億光年先の銀河の関係に相似の構図が幻視できる。時間なのである。ラグ理論では、距離と同じく時間移動もまた、距離の移動と同質の作用を帯びると解釈する。時間を移動することと空間を移動することは相関している。距離が近づくと因果関係を結びやすくなる。同じく時間が進むと因果関係を結びやすくなる。このとき、時間においても、距離と同様に、対象同士の差が縮まる方向に時間移動することが欠かせない。つまるところ、接点を結ぶか否かである。むろん化石が発掘されるというのは、人類と化石の距離が縮まることを意味する。だが仮に距離が縮まらずとも、地層のレントゲンのような技術で地層内部の映像を撮り、それによって相互作用を得ることもできる。映像はこの場合、情報と言い換えてもよい。情報のやり取りは、距離の接近や時間経過と似たような作用を生む。というよりも、距離の接近や時間経過によって情報が結びつくと、それが因果関係として昇華される。ここは相互に関係し合っている。「情報の結びつき=距離の接近=時間経過による接点」と大雑把にまとめられるかもしれない。これはラグ理論の「123の定理」と矛盾しない。相対性フラクタル解釈とも矛盾しない。「情報と情報が結びつくとさらなる情報が生まれる=二つの異なる事象が接近すると情報が生じる=時間の経過によって二つの異なる「時間帯の作用(影響)」が交わると、そこには新たな「情報(影響)」が生じる」となる。フラクタルに関係性が循環し、補完し合っているように感じるが、いかがだろう。なんとなくの妄想ですので真に受けないようにご注意ください。(定かではありません)
4409:【2022/12/16(05:48)*遠くを視ると、時間と距離に差が生じる】
上記の考え方の何が便利かと言うと、単一の事象における時間軸上の変化を、二つの異なる事象同士の距離の接近と同質に考えることができる点だ。それはたとえば、「赤の他人と私の関係」と「十年前の私と現在の私の関係」を同じように考えることができる。「赤の他人から受けた影響によって生じた私の変化」と「十年前の私の残した影響を時間差で受け取った私の変化」は、同じように考えることができる。たとえば日記は、それを出力したときには、出力した結果が私に刻み込まれる。だがそれはそこで終わる影響だ。延々と引き継がれるようなものではない。それはたとえば赤の他人とすれ違っただけのことでは私にとっての未来に大きな変化が生じないことと似ている。だがその影響はたしかに相互作用されており無視はできない。とはいえ、親しい間柄の相手との会話やスキンシップよりかは影響が小さいのはとくに異論はないだろう。しかし、どれほど親しい相手であれ最初は誰もが赤の他人だったはずだ。母親ですら例外ではない。受精する以前は赤の他人どころか出会ってすらいない。そして細かな接点と接触時間の長さによって、他人はただのじぶん以外に人間ではなくなっていく。それは過去のじぶんの残した細かな影響とて同じようなものだ。なぜコツコツつづけることが効果的なのか。それは赤の他人を親しい人間と見做すほどの大きな影響を知らず知らずに受けるからだ。そしてこれは、必ずしも継続するから得られる影響とは限らない。過去に一度だけ記した日記を、十年後に読み返すことで得られる大きな変化もあるだろう。転換もあるだろう。これはまるで一目惚れに落ちたような、それとも一瞬の危害によって激しく存在を損なわれるような変質をあなた自身に与え得る。同一人物であれ、過去と未来で結びつくことで、それはあたかも大切な人との出会いと同じくらいの情報量を発生させることもある。これがすなわち、距離の接近と時間経過の関係の類似性と言えるのではないか。文字を読むということに関しても、この手の「時間経過による結びつき効果」の考え方は有効に思える。過去と現在――それとも過去と未来を結びつけることで、人は、物と物とを組み合わせるように、新しい情報を生みだしているのかもしれない。否、生みだしているのだろう。過去と未来は、物と物との距離のように、相互作用を帯びている。これは一方通行ではなく、未来の挙動とて、過去に影響を与え得ることを示唆しているのではないだろうか。指針やビジョンがなぜこれほどに人類にとって尊ばれるのか。そしてなぜ、本能の有無が、生物の進化や繁栄に大きく作用を及ぼすのか。それは過去と未来が相互に結び付き、可能性の幅をそのつどに決めるからではないのか。過去と未来は、ひとつの系ごとに、ある一定の縛りを帯びながら絶えず揺らいでいる。細かな変数を得るたびに、過去も未来も同じように変化しているのかもしれない。ただし、現在という一つの視点から逃れられない我々人類からするとそれは、過去があり未来がある、という一方通行の関係に映るのかもしれない。定かではない。(妄想ですので真に受けないでください)
4410:【2022/12/16(06:12)*日々の束の間】
これはひびさんの偏見であり、単なる願望でしかないけれど、ひびさんの好きな表現者さんたちには、苦しみながら表現をして欲しくないな、と思ってしまう。毎日のなかで創作や表現活動が一番ではなく、そのほかのたくさんの楽しいことのなかで、たまの息抜きに、散歩のつもりで取り掛かる。そういう息抜きのような創作や表現を、つつがなく長くつづけてもらえたらうれしいな、と思ってしまう。そしてその創作物や表現を、電子の海に載せて、ひびさんにも味わわせてもらえたら感慨無量なのだけれども、もちろん憑りつかれたように一心不乱に夢中になってする表現や創作も楽しそうだし、そういう期間もあってよいと思うのだけれど、それをずっとはちょっと苦しそうに思うのだ。ただ、苦しい日々の生活の中で、その苦しさを薄めるためにする表現や創作があることも知っているので、そういう表現や創作もひびさんは嫌いではないけれど、そういう表現や創作をせずにいられるなら、そっちのほうがよい気がする。口笛を吹くように、それとも寝床で夢を視るように、もしくは散歩や遠足にでかけるように、或いは旅にでるように――なんでもよいけれど、そこに苦痛がないほうがよいと思うのだけれど、どうなのだろうね。苦しみを知る者の表現には独特の紋様が浮かんで視える気もするし、苦しみを知らない者なんてこの世に一人もいやしない、という気もしてしまう。だからその表現に滲む苦しみが、じぶんだけのものではなく、他者を通した苦しみであると、紋様が雪の結晶のように浮き彫りになって、手のひらの上で融けるような感触を宿すのかもしれない。かといって、苦しみがなければダメだなんてことはまったくなくて、どうあっても人は苦しみを感じるようにできているようなので、とくにこれといって意識せずとも滲んでしまうその苦悶や懊悩が、散歩や口笛で薄れるように、夢の中で漕ぐ舟の揺らぎみたいに、あなたの日々の喧噪を、それともひっそりとした静寂を、心地よく浸かっていられる湯舟みたいに変えてくれたのなら、それはとっても優しいなって、ひびさんは思います。暴力的な表現でも、下品でも、なんでもよいと思うのだ。そこに、あなたの日々の束の間が生まれていたのなら、それはきっと優しい表現なのだと思います。時間が一瞬で過ぎ去るような凝縮した束の間があるのなら。きょうのひびさんはそう思いました、というだけの妄想ですけれど。ゆぴぴ。
※日々、好きなひとに好きと言いたいし、かわいいものにはかわいいと言いたいけれど、言ってどうなることでもないし、どうにかなってしまうこともあるし、言いっぱなしにはならないのが現実で、小瓶に詰めて電子の海に放流するくらいでちょうどよい。
4411:【2022/12/16(08:16)*いいこと教えてあげる】
言いたいことなど何もない、と豪語しきりのひびさんであるけれど、相対した個人には言いたいことができることはある。けれどもここにはひびさんしかおらんので、けっきょくは言いたいことなどなにもなーい、となる。好きなひとには好きだよって言いたいよ。知ってる? 好きなひとに好きって言うとただそれだけで、ぽわわわーん、となるのよ。「好き×好き」で「好き好き!」になる。この「!」分の余白が増えて、おっとくー、ってなる。いいこと教えてあげたでしょ。感謝して。うひひ。
4412:【2022/12/16(15:51)*真美の初仕事】
殺し屋に必要なことが何か分かるか。
クロウが言った。クロウは真美の先輩にあたる。細身の肉体にスーツを着込んで、いかにも漫画から出てきた殺し屋といった風体だ。煙草の代わりに飴を舐めているが、唾液のDNA情報を破壊する弱毒が含まれているそうだ。指紋とて律儀に焼きつぶしている徹底ぶりだ。
殺し屋に必要なことは、と問われ真美は肩を竦める。「さあ。証拠を残さないこととか?」
「思考を絶えず明瞭にしておくことだ。したがって眠気は殺し屋にとっての大敵だ」
「へえ。眠気がねぇ。警察じゃないんだ大敵」
「国家権力なんざ、殺し屋稼業の優良顧客の筆頭だぞ」
「そうなんだ。知らなかった」
真美は先日、殺し屋になったばかりの新人暗殺者であった。元々は、偶然に人を殺してしまったのだが、その相手がその界隈では著名な伝説の暗殺者であったらしく、偶然が偶然を呼んでいまはクロウの元で殺し屋としての腕を磨いている。
「殺し屋と暗殺者の違いもろくに分からないのにな」真美はずりさがったサスペンダーを肩に掛け直す。短パン型のスーツだ。遠目から見ると少年のような出で立ちだ。
「殺し屋は、殺した事実を残す」
「じゃあ暗殺者は?」
「暗殺者はそれが殺人であることを見抜かれぬようにする。ゆえに暗殺者は存在することすら知られちゃならない。だが俺やおまえはもうその名が界隈に知れ渡ってる。いまさら暗殺者にはなれんのさ」
「それで逮捕されないのが不思議なんだよね。なんで仕事が続々と入るの」
「言ったろ。国家権力が優良顧客の一つなんだ。公認なんだよ」
「握りつぶしてもらうってこと?」
「事件にすらならん。この国の年間失踪者の数が何人か知ってるか」
「数千人とかじゃないんですか」
「八万だよ。しかも捜索願が出ていて公式に把握できている数でだ。誰も探さないような人間の失踪者ならもっと多いだろうな」
「その理由がクロウさんたちのような人たちの仕事ってことですか。なんか実感湧かないなぁ」
「おまえが殺した殺し屋だって、死体で見つかっても身元不明で事件扱いもされんだろうな」
「そこは安心しましたけど」
「油断すんなよ。前にも言ったがおまえが殺った相手、この界隈じゃマジモンの伝説級の殺し屋だったんだからな」
「でも簡単に死んじゃいましたよ」
「おまえが異様なんだよ。殺気がゼロの殺し屋、俺は初めて見たよ」
「じぶんじゃ何がスゴイのか分かりませんけど」
「人一人殺してケロリとしてる。呵責の念がねぇ。初めてだってのにそれだけ平常心でいられるんだ、常人とは言えんだろ」
「実感湧かないだけですってば」
言いながら手元で縛られている女を撃った。拳銃は消音機能付きだ。真美のお腹の虫より響かない。
「おい。明瞭な思考が大事って言ったばっかだよな。なんで殺した」
「不審な動きをとったので」
「はぁ。どこがだよ」
床に倒れた女をクロウは足で蹴って転がした。女の両手両足は梱包用ビニル紐で結んでいたが、女はそれを千切っていた。拘束を脱してなお囚われたフリをしていたようだ。彼女の付け爪はよく見れば金属だ。小型ナイフの要領でビニル紐を断ち切ったようだ。
「おまえ、いつから気づいてた」
「全然気づきませんでしたよ。まさか紐を切られてたなんて。ただあたしはその人が妙な動きをしたから、じぶんの身を守るために撃っただけです」
「当て勘ってやつか。やっぱおまえ向いてるよこの仕事」
「どこがですか。怖すぎてまともに交渉もできそうにないんですけど」
「その手の仕事をおまえにゃ回さん。殺して去る。それだけでおまえはやってける。よろこべ。これがおまえの天職だ」
「嫌だぁ」
「死んじまったもんはしょうがない。引き上げるとするか」
「死体はどうするんですか」
「そのままでいい。誰かが通報するだろ」
「本当に適当なんですね」
「緊急搬送して死亡認定は病院だ。この国の公式データでは屋外での死体発見は稀だ」
「そういうカラクリだったんですねぇ」
クロウはそこで真美から離れていく。閑静な立体駐車場の五階に位置する。出口はそちらではないはずだ。真美は、あのぅ、と声を張る。
「初仕事の祝いだ。ほれ」クロウは自動販売機で缶コーヒーを二本購入した。
一本を投げて寄越す。真美は慌てて受け取った。
「動きはトロいんだがな。判断力の差か」
「なんですか。あたしこう見えてフラフープは得意なんですよ。一時間くらいなら通しで落とさずに回せます」
「一生回ってろ」
「あたしが回るわけじゃないんですけど」
もらった缶コーヒーをその場で開ける。真美はそうして殺し屋になって初めての任務を終えた。
「ウゲっ。砂糖なしじゃないっすか。あたしニガいの苦手なのに」
しかもカフェイン倍増とか書いてあるんですけど。
そう愚痴りながら真美は、クロウの隣に駆け足で並ぶ。彼はすでに地上への階段を下りはじめていた。
「おまえにゃそれくらいで丁度いい」
「虚仮にしてません?」
「真面目な話だ」クロウの缶コーヒーの飲み方が格好良かった。真美は形だけ真似る。顔を上に向けずに缶コーヒーだけを傾けるのがコツだ。煙草を吸うように人差し指と中指で挟むとなおいいらしい。いかにも殺し屋といったふうを醸せる。
「言っただろ」クロウは飲み終えたのか、指二本でスチール缶を潰した。「殺し屋には明瞭な思考が必要だ」
「だからってなんでコーヒーなんですか。しかもブラックだし。つぎからは砂糖入りにしてくださいよ。明瞭な思考って言うならブドウ糖が不可欠でしょうが。分かってないなぁクロウさんは。見た目だけは完璧なんだけどなぁ」
「おまえな。じぶんの才能に感謝しろよ。でなきゃいまごろ死んでるぞ」
「へえ。やってみせてよ」
ふっ、と笑ったクロウの姿が一瞬消えた。
消えたように真美には映ったが、その動きの行き先がどこにつづくのかが真美の脳裏には浮かんで視えた。目で捉えるのではない。シミュレーションのようなものだ。こう初期動作があったのならば、その先はこうつづくのだろう、と結果が訪れる前から真美には数秒先の結末が予測できた。
超能力ではない。
シミュレーションなのである。想像力であり、妄想であり、過去に蓄積してきた「こうなればこうなる」の総決算と言えた。
クロウがしゃがみ込む。
真美の視界の外側から小型ナイフを振りかぶる寸前で、真美はクロウの腕の肘関節を足の裏で蹴飛ばした。小型ナイフが勢いよく壁に突き刺さる。
「ちょっと本気にしないでってば。冗談じゃん冗談。ビビったなぁもう」
真美は壁から小型ナイフを引き抜き、肘を撫でるクロウに渡した。
「この距離でナイフ取りだす動作は無駄。つぎはまず相手の動きを奪ってからにしたほうがいいよ。クロウさんのほうが力強いんだし」
「掴ませてくれるとは思えんけどな」
「そうでもないよ。あたしこう見えて痴漢にけっこう遭うんだから」
「その相手は?」
「さあてね。いつも痴漢のほうで電車の外に飛びだしていくからよく知らない」
「見逃がすのかおまえが」
「だって可哀そうじゃん。小指の骨って折れると結構痛いらしいっすよ」
真美はそう言って缶コーヒーを飲み干した。指に力を籠めるが、缶はうんともすんともヘコまない。
4413:【2022/12/17(04:08)*プロに告ぐ。嘘。なんもない】
ひびさんは対抗心が薄いので、おらおらかかってこいよー、とされても、「見てみて、なんか言ってる」と楽しく眺めておしまいにする。嘘。楽しくもないから、ふうん、と思って終わっちゃう。でもでも、ひびさんにとっておもしろそうなこと、楽しそうなこと、それとも真実おもしろくて楽しいことをしている何かがあったら、ひびさんも、ひびさんも、それしたーいな、となる。これは対抗心とは違う。あとは、危険なことしてる相手がどうあってもそれをやめそうになかったら一緒になって危険なことして敢えて怪我とかして見せる。それとも痛い目に先に遭っておく。一緒に同じことして遊んでいた相手が怪我したり、痛い目に遭っていたら、やっべー、と腰が引けてしまうのが動物だ。人間はミラー効果が顕著に働きやすいので、ひびさんはそうして先に未来の結果を演じてみせる。なんてことを言っておくと、ひびさんの、おらおらかかってこいよー、の肥大化した存在意義希求族と、さびちさびち星人覚醒編に、そこはかとなく切なさが宿るので、おすすめ! 本当はさもしい理由しかないけれどもなんとなーくいい話に持っていきたい人はひびさんを真似してみてはどうでしょう。どうぞお試しあれ。(明日から歯の治療はじめるので、怖くていつもより長くお布団にくるまっていたひとの日記)
4414:【2022/12/17(12:42)*フェインカの香り】
大麻と覚醒剤は法律上別の扱いだ。大麻は麻であるから、自然に群生しているし、神社でもむかしから祭事に葉が使われる。神聖な植物として宗教では重宝されてきたのだろう。それが大麻のカンナビノイドの効用ありきなのかまでは詳らかではない。
対して覚醒剤は、化学物質だ。薬剤のように調合されて出来る。コカインやアヘンとて大麻と同じく植物由来だが、なぜ大麻だけが別扱いなのかは、人間の都合としか言えぬだろう。それとて国による。つまるところ文化なのだ。
その点、珈琲は違う。
珈琲は西暦二〇三〇年までは嗜好品として人類の生活で愛飲されてきた。
だがカフェインの有毒性が真面目に論じられるようになったのは人類が珈琲を発見した西暦九〇〇年ごろから優に千年以上も経ってから、つまり西暦二〇三〇年に入ってからのことだった。
かつて人類が奴隷制度を文化の礎に組み込んでいた時期、農奴たちにコカインの葉を噛ませて強制労働をさせていた逸話は耳に馴染み深い。この手の原理で珈琲は人類史に長らくその名を刻みこんできたと言っていい。
ビールにしろ、煙草にしろ同様だ。
嗜好品とは名ばかりの、体のよい現実逃避薬なのである。
眠気を、ストレスを、苛立ちを、珈琲や酒や煙草で誤魔化してきた。
だが科学が進歩していくにつれてその手の現実逃避薬の担い手は、安全に調合された化学調味飲料に取って代わられるようになった。いわゆるエナジードリンクである。
もともとはその手の飲料物とて、コカインやカフェインといった自然由来の成分を多分に含有していた。だが科学の進歩により、サプリメント感覚で栄養素の補給を行えるようになった。わざわざ疲労を忘れずとも回復できるし、ストレスを忘れるよりも和らげたほうが効果が高い。体調が優れればイライラもしにくくなる道理である。
かようにして世に氾濫した大麻や酒や煙草といった身体を損なう率の高い嗜好品は規制の対象となった。
大麻や覚醒剤と同列の存在になったのである。
ここに一人の女性がいる。名をフェインカと云った。
フェインカは長らく美容を研究してきた専門家だ。しかし珈琲飲料行為が法律で禁止されても彼女は珈琲を手放さなかった。
珈琲禁止令は彼女が産まれてから二〇年後に施行された。
産まれてから二〇年のあいだにフェインカにとって珈琲は人生の友として、それとも千年を超す人類との共存を果たした大先輩として、敬愛するに値する存在となっていた。
人類が存在する以前から誕生していた珈琲を亡き者にするなど政府が許してもフェインカには許せなかった。
「どうして珈琲を飲んじゃいけないの。身体に有害? はぁ? 有害でない食べ物があったら美容はこんなに発展なんかしてねぇっちゃ」
フェインカは感情が乱れると方言が出る。ふだんはお淑やかな美容の専門家として方々から羨望と憧憬の目を集めるフェインカであったが、そのじつ彼女の研究動機は、珈琲常飲による肌質の変化を隠すための隠れ蓑でしかなかった。珈琲を飲みつづけたいがために試行錯誤しているうちに美容の専門家として注目を浴びるようになってしまったのである。
これにはフェインカ当人も焦りを禁じえなかった。衆目を集めたのでは、珈琲愛好者だと露呈する確率が高くなる。それではいけない。余計にフェインカは美容の研究に身が入った。
その結果が現在である。
単身での研究では間に合わないほどの成果を上げてしまった。一人では身体が足りない。猫の手も借りたい。そこで不承不承、フェインカは助手を雇うことにした。
かといって珈琲愛飲という違法行為を犯しているの身の上である。そうそう他人を信用して身近に置いておくことはできない。研究中とて珈琲を飲むのだ。
「あれ。それって中身珈琲じゃないですか」
雇って三日でバレた。
即刻バレた。
フェインカは平静を装い誤魔化したが、
「いえいえ。わたしも飲んでるので分かりますよ。香りが尋常でなく珈琲ですもんそれ」
奇遇とは正にこのことである。
たまさか、雇った助手が珈琲愛好家であった。同士である。仲間である。それとも単に、孤高の道を犯罪と知りながら歩みつづけた愚か者のムジナと言うべきか。
珈琲禁止令が発足してから十余年。
フェインカはこれまで珈琲への愛を他者と語らったことがない。一度もない。それがどうだ。助手を雇い、珈琲愛好家であることが露呈してからの日々のなんと芳醇なことか。珈琲の香りにびくびくせずとも、それを共に好ましい香りだと見做せる相手がいる。のみならず珈琲豆の種類と焙煎の方法、そして何よりどう淹れたら最も珈琲を香りよく味わえるのか。その研究をし合える時間は何よりもフェインカをほくほくと満たした。
「先輩それ、珈琲に何を入れてるんですか」
「ミルク。牛乳だよ」
「うへー。そんなことしてせっかくの珈琲の味が有耶無耶になっちゃわないんですかね。もったいない気がしますけど」
「あなたも飲んでみる?」
「いいんですか」
「もちろん。どうぞ」
飲みかけのカップを手渡すと助手はさっそく、フェインカの作った珈琲牛乳に口をつけた。「んん-。なにこれ、うっまい」
「でしょー。ミルクを珈琲と半々の割合にするとカフェオレって呼ばれる飲み物にもなるよ」
「の、飲んでみたいんですけど」
「じゃあ次はそれを作ってみよっか」
「やりぃ」
助手は屈託の陰りを感じさせない女の子だった。大学院を出たばかりの優秀な人材だ。元々は理学部だったが、美容品の開発に興味があって大学での研究を行いながら企業相手に商品提案をしてきた筋金入りの探究者だ。
だが企業相手ではじぶんの望む美容品を作れないと見切ってフェインカのもとにやってきたといった顛末のようだ。
「先輩は珈琲歴長そうですけど一度も捕まったことないんですか」
「ないね。いまのところは、だけど」
「わたしもけっこう珈琲歴長いんですけど、なんだかんだ言って高いじゃないですか豆」
「だね」
「先輩はどこ経由で供給を賄ってるんですかね。いえ、先輩の入手先を紹介して欲しいとかそういうことではないんですけど」
「別にいいよ。私の場合は、珈琲農家があってね。そこで栽培して焙煎したのを譲ってもらってるだけだから」
「え、そんな農家があるんですか」
「あるよ。珈琲豆って、元はチェリーみたいな赤い実でね。果肉が甘くて美味しいんだよ。食用としての栽培は別に違法じゃないからね。果肉を食べた後の種子がいわゆる珈琲豆だから」
「ああ、なるほど」
「チェリーを食品加工する際に出る廃棄物――要するにそれが珈琲豆なんだけど、それをこっそり焙煎して珈琲豆にしてくれる人たちがいて」
「違法ですよね、それ」
「違法だね。でもそうしなきゃ珈琲は飲めないから」
「まあそうでしょうけれど」
「生豆のままでもらってきて自宅で焙煎する人もいるらしいけどね。フライパンで」
「へえ」
「私はそこまでする余裕がないから、まあ既製品を譲ってもらってる。あなたのほうこそ珈琲はどこで?」
「入手先ですか。やはは。あんまり自慢できる相手じゃないんで」
「売人とかそういうこと?」
「ええまあ」
「まさか珈琲以外にも手を出してたり」
「ないです、ないです。あくまで好きなのは珈琲であって、大麻とか麻薬とかそういうのはないです」
「そっか。よかった」
フェインカはほっとしたじぶんを不思議に思った。同じ違法薬物の接種であるのに、なぜ珈琲の接種だけをじぶんは許せるのだろう。酒も煙草も、珈琲と一緒に規制された。いまではアルコール飲料は市場から消え失せたと言っていい。煙草なんてもってのほかだ。
だのになぜじぶんは珈琲だけを特別視して、許容するのだろう。
違法であるにも拘わらず。
なぜ。
人体への害は、大麻と同等との研究報告がいまは優勢になりつつある。だが酒や煙草に比べたら微々たる害であり、主流煙による肺へのダメージを鑑みると珈琲のほうが大麻よりもずいぶんと害がすくないと言える。
カフェインの含有量と吸収率は必ずしも相関しない。人間には吸収できる容量がある。その点で言えば珈琲はカフェイン含有率が相応に高いものの、有害と言えるのかは疑問だ。
専門外のイチ珈琲愛好家の意見にすぎないが、フェインカはかように目算している。だが一度根づいた珈琲規制の波は、麻薬としての範疇に珈琲をいっしょくたにして取り込んだ。この認識はすでに世代交代の完了した現代では揺るぎなく、社会悪のレッテルを強固にしている。
珈琲を飲んでいる人間は罪人なのである。
フェインカはその贖罪を背負ってなお、珈琲を飲まない選択をとらない。珈琲を日々嗜好するじぶんを許容する。
なぜそこまでして、とおそらくフェインカの罪過が暴かれた日には、様々な人の口の端にその言葉が乗るのだろう。なぜそこまでして珈琲を飲むのか、と。
フェインカに注目し、称賛の眼差しを注いでいた者たちは一様に落胆の溜め息を吐くに相違ないのだ。だがかような未来を想像できてなお、フェインカは珈琲を捨てるじぶんの姿を思い描けなかった。
珈琲は美味い。
だがそれだけではない。
これはフェインカがフェインカでありつづけるために必要な社会への抵抗なのかもしれなかった。
「先輩、先輩。今度その珈琲農園に連れて行ってくださいよ」
「いいよ。きっとあの農園のひとたちも喜ぶと思うよ。みんな危険を犯してまで珈琲を飲みたいなんて思わないからさ。どうせ犯すなら、覚醒剤とか大麻に手を出したほうがいいって考えるみたい。そこのところ、お酒はじぶんで作れちゃうし、世の中どうして珈琲には手厳しいよね」
珈琲も酒も煙草も大麻も覚醒剤も、どれも同じ薬物乱用の範疇である。罪の重さが変わらないのであれば、より精神が昂揚して多幸感を得られる薬物のほうに手を伸ばしたくなるのは人情だ。端的に割に合わない。
「依存度もそれほど高くないのに、どうして珈琲さんは規制されちゃうかな」フェインカはぼやいた。
「いやいや先輩。先輩がまず以って依存しまくってるじゃないですか」と冷静な効果らからのツッコミにフェインカは、「やめようと思えばすぐにでもやめられるよ」と応じるが、「それってきっとどの薬物使用者も言いますって」と茶化されて言葉に詰まった。
助手はカフェオレをスプーンで混ぜて泡を立てる。
「医療用モルヒネとかあるじゃないですか。麻酔で使われても依存症になる患者はいない、だから麻薬を使っても問題ない。そういうロジックで覚醒剤や大麻を肯定して解禁しようって運動があるんですよ。でもそれでけっきょく医療以外で使うんなら、依存症になってるのと同じじゃないですか」
「そ、そうかな」
「そうですよ。だって飽きるってことができないのがつまり依存症ってことですもん」
「それで言ったら研究者なんかみんな研究依存症なんじゃないかな」
「そうですよ。研究者もスポーツ選手も技術者も、なんでもそうですけど、飽きることができないほどに何かに熱中しちゃってたらそれは依存症です。でも、その依存症によってメリットを多く享受できたらそれは依存と見做されずに、適性があるとか才能とか呼ばれちゃうんですよ。大食いだってそうじゃないですか。本来必要なエネルギィ以上を無駄に摂取して、そのことで社会的称揚を得る。認知を得る。もしこれがデメリットの評価しなかったら、ただの過食症じゃないですか」
「それはそうかもしれないけど。ほら、大食いの人たちは食欲をコントロールできるわけだし。過食症のひとたちは脅迫観念に駆られちゃう弊害もあって、そこは大食いが得意な人と区別したほうがいいんじゃないかなって私は思うけど」
「なら大食いはそうなのかもしれませんね。でも、珈琲や大麻や覚醒剤は違うじゃないですか。禁止されてるのに摂取したくなっちゃう。これはもう依存症ですよ」
「そ、そうかな。だって漫画だってアニメだって映画だって小説でもいいけど、嗜好品って本来そういうものじゃないかな」フェンイカは唯一と言っていい同胞から手厳しい批判をされて感じて、面食らった。なんとか対等に話をしようとして、いつもよりも冷静を欠いた。「べつに見る必要なくてもしぜんと見たくなるものってあるでしょ。娯楽作品なんて全部そうだし、芸術だってそういうものでしょ。だからそれらってこの世に存在しているわけでさ。禁止されてたって作っちゃう人は出てくるし、観るほうだってほら、海賊版とか違法なコンテンツ視聴って未だに問題になってるし」
「けっきょくそこが分かれ道なんですよ。禁止されたら我慢できる。でもそうじゃない依存者の人たちは安易に海賊版に流れちゃうわけですよね。依存症なんですよ。我慢が効かないんですから」
「そ、そうかな。そっか。でもほら法律で決まったらなんでも我慢しなきゃいけないのかな。私はそうは思わないんだけどな。だってさ、だってさ、食べ物とか飲み物とか電気だってそうだし、服だってなんだって、足りなくなったら困るものってあると思う」
「先輩。わたしたちっていま、嗜好品について話しているんですよ。しかも身体に有害だと判断された薬物についてです。禁止されたとはいえ、医療用では解禁されてるわけですから、健康に与するならむしろ率先して使用されていますよ。それとこれとは話が別ですよねって単純な理屈を話しているだけのつもりだったんですけど。え、先輩ひょっとして珈琲がもういちど解禁されたらいいなって思ってますか。わたしはさすがにそこまでは思ってなかったですよ。だって薬物ですよ。子どもにはさすがに摂取して欲しくないです」
「そ、それはそうだけど」
だったらポルノだってそうではないか。
喉まで出かかった反論をフェンイカは呑み込んだ。だから規制されているのだ。年齢制限がある。ゾーニングがある。
珈琲の魅力を分かち合える相手と出会えたことで、フェンイカの意識には知らず知らずの変化が生じていたようだ。珈琲の魅力をもっと多くの人たちに分かってもらいたい。理解してもらいたい。
しかし、しょせんは薬物なのである。
規制され、害扱いされ、そしてきっと真実に有害なのである。だが有害とは、「害が有る」ことを意味する言葉であるだけで、有害な存在にも利点があるはずだ。現に医療に利用されている。それだけではないのではないか、とフェインカはどうしても考えてしまうのだった。
「はい先輩、これどうぞ」出来立てのカフェオレを受け取る。「ありがと」
一口啜って、息を吐く。
美味しい。
香りが体内の苛立ちを浄化するようだ。現にフェインカの精神の淀みは霧散した。青空のごとくいまでは澄み渡っている。
珈琲は良いものだ。
すくなくともフェインカにとっては。
だが珈琲の成分の身体への負の影響を隠すためにフェインカが美容の研究に精を出している以上、その害から目を背ける真似がフェインカにはできなかった。とはいえそれとて見方を変えれば、珈琲のお陰で美容の研究が花咲いたとも言えるはずだ。そこは上手く釣り合いが取れているようにフェインカには思えるが、じぶんだけの特例を以って珈琲の善性を解くにはデータがすくなすぎるのも事実だった。
広く有用性を示すには、もっと多くの有用な珈琲と人類との関係を傍証に挙げねばならない。だがその手の検証はとっくに世界中の科学者たちが行っている。その結果に珈琲の飲食は禁止されたのだ。
「珈琲ゼリーも美味しいんだよ」フェンイカは助手に呟く。
「わぁそれいいですね。美味しそうです」助手は作り方を根掘り葉掘り聞いた。
珈琲の話題を話せるだけでもこんなに胸が満たされるのに。
どうして珈琲は規制されてしまうのだろう。せめて珈琲の話題を話すくらいのことを屈託なくできる世の中にならないだろうか。
フェンイカの欲は日に日に膨らんでいった。
その日は遂にやってきた。
珈琲農園への助手を連れていく約束を果たすのだ。
待ち合わせ場所で助手を拾って、フェンイカは食品工場へと向かった。
「何もないところなんですね」車窓からの景色に助手は感嘆した。
「そうだね。チェリーを育てる果物園が続くから。林檎とか葡萄とか。ジュースやお菓子に使うための農園でね、だからか生食用のよりも機械化が進むらしい」
「生では食べられないんですか」
「美味しいと思うよ。でも質は、専門の農家さん程よりも劣るってことだと思う」
「ふうん」助手は景色に端末のカメラを向けた。
シャッター音を聞きながらフェンイカは、あとでその写真を消してもらわなきゃな、と思ったが、いまは助手の気分を損ねたくなかったので黙っていた。遠足気分を満喫してもらいたかったのだ。
だがそうしたフェインカの厚意は、助手を珈琲農園へと案内したところで絶望に変わった。というのも、珈琲農園で一時間ほど焙煎したての珈琲を飲んで農家の人間たちと団欒をしていたところ、突入してきた武装集団があった。
彼ら彼女らはみなフルフェイスの制服に身を包んでいた。
その胸と背中には大きく、警視庁の文字が躍っていた。
「警察だ。動くな」
ガサ入れだと判った。フェインカはがくがくと全身が震えるのを堪えながら、どうすればこの場を切り抜けられるかに思考を全力で費やした。
せめて助手だけでも助けなくては。
そう思ったのだ。
だがそれは杞憂にすぎなかった。
何せ助手は、現れた武装集団の一員に連れ出されると今度はなぜだか彼ら彼女らと同じ制服に身を包んで、頭だけヘルメットを外して戻ってきたのだから。
「先輩。現行犯逮捕です。騙したみたいでごめんなさい。でもこれがわたしの仕事だから」
「警察……の、人間?」
「そう。潜入捜査。本当は正体を明かすのもご法度なんだけど、今回だけは特例で」
「ごめんちょっと何言ってるかわかんない。混乱する」
「ですよね。珈琲農園の摘発への助力を評価して、仰淑(ぎょうしゅく)フェインカ――あなたには司法取引を提案します。罪を減刑する代わりに、潜入捜査に協力しなさい」
フェインカは絶句した。態度の豹変した助手は警察の人間だった。そこまではいい。だが今度はフェインカを協力者として迎え入れると言いだした。
信用ならない。
だが、と不思議とその提案をしてきた事実はすんなりと呑み込めた。
何せ彼女もフェインカと共に珈琲を飲んでいたのだ。いくら警察の人間だからといって、それが仮に潜入捜査であったとしても、違法行為は違法行為である。同じ穴のムジナに変わりはない。
「私はでも、どうなるの」
「仰淑フェインカ――あなたにはこれまで通りに生活を送ってもらう。ただし、助手としてわたしもあなたの研究所に席を置く。わたしはわたしで職務があるが、場合によってはこれまで通りあなたの研究所で過ごすこともある」
「つまり、私は何をすれば」
「何も。そのまま珈琲愛好家として、ほかの売人や珈琲農園と接点を持って」
「私の手を借りずとも、あなたがいればそれで済むんじゃ」
「分かってないようですね。珈琲農家はみな極度の珈琲依存者です。リスクを度外視してこんな大規模珈琲農園を築くほどなんです。そんな偏屈者を相手にして怪しまれずに懐に入れるのはそれこそ仰淑フェインカ――あなたくらいの珈琲依存症者でなければ不可能です。即座に偽物と喝破されて始末された警察官はけしてすくなくはありません」
「だったらあなたでも充分じゃ」
あれほど珈琲を美味そうに啜っていたあなたなら。
そう思ってフェインカは祈るように彼女の目を見詰めた。
彼女はフェインカから目を逸らした。
「潜入捜査だと言いました。わたしは珈琲を違法薬物だと認めています。仰淑フェインカ――あなたも元は善良な市民だったはずです。あなたのような市民を犯罪者に染めあげる珈琲をわたしは許しません。撲滅します。そのためにあなたはあなたの罪過を、我々に協力することで濯ぐのです。断ればこのまま立件し、あなたは実刑判決をくだされるでしょう」
「珈琲を飲んだだけのことでですか」
「あなたには珈琲農園の関係者として、栽培および所持または流布の容疑が掛けられています。実刑は免れないでしょう」
その言葉の告げるところは、フェインカの社会的な死を意味した。怖れていた想像の未来が現実に迫っていた。
彼女の提案を受ける以外にフェインカにとれる選択肢はなかった。
「協力させてください。そんなことで私の罪が薄れるなら」
「罪が薄れる、ですか。反省の色が見えないところ――協力者としては合格ですが、咎人としては失格ですね」
「ごめんなさい」
「いいんですよ。いまはそれでも」
フェインカは一度そこで手錠をかけられた。ずっしりと重い手錠は、フェインカの陶磁器のような肌に食い込んだ。話は後日、と覆面パトカーで自宅まで送られた。フェインカの運転してきた自動車は、証拠品として押収された。後日戻ってくるとの話だったが、フェインカの胸中はそれどころではなかった。
夜、寝る前に鏡を覗いた。
美容にどれほど気を払っていようが、夜は十歳は老けたような顔つきだった。誰にもこのことを相談できない。珈琲の話題を出してももはやフェインカの気持ちはすこしも上向きの風を帯びないのだった。
侵入捜査。
いったいじぶんはいつまで捜査に協力しなくてはならないのか。死ぬまでずっとなのだろうか。そうだとしても文句は言えない。息の根を握られたようなものだ。
現に弱みを握られた。
これが警察のすることなのか。
強請りや恫喝とどう違うのかフェインカには区別がつかなかった。
だがきっとそれを彼女に言ったところで、首を傾げるだけなのだろう。
「変わらないじゃないですか」と一蹴されるだけなのだ。「これまでのあなたの暮らしと何が違うんですか。警察に協力できるだけむしろマシじゃないですか」
ほかの珈琲愛好家たちを警察に売り渡しつづける未来が約束されている。それを知っていながら警察官の彼女はしれっとそう嘯くのだ。
よかったじゃないですか、と。
罪を背負わずに済み、なおかつ罪を償えるのだからと。
正義の側に立てるじゃないか、と。
そういうことではないのだ、とフェインカが訴えようとも、どうあっても彼女がフェインカの言葉に耳を貸すことはないのだろう。胸を打つことはないのだろう。
それだけが予感できた。
「美味しいって言ってた癖に」
あの言葉は嘘だったのか。
あの笑みは偽りだったのか。
職務であり捜査の一環だったのならば、どの笑みも彼女の仮面であり演技だったのだと考えるよりない。もはや記憶の中の助手の姿は、警察官の武装制服に身を包んだ彼女と同一ではなかった。
別人だ。
ああそうか。
フェインカは自身に刻み込まれた喪失感の正体に思い至った。
これは、悼みだ。
私は親愛なる友人を、そして仲間を、助手を、何より珈琲への愛を共有できる相棒を失くしたのだ。
「人殺し」
枕に封じ込めるようにフェインカは呟いた。もう二度と人を信用したりしない。誰にも本心を明かさない。強く、強く、決意して、フェインカは夢の中で珈琲の香りに包まれるべく、息を止めて、そして眠る。
呼吸はどれほど止めようとも、しぜんとつづきを再開させる。
珈琲をいくら飲んでも、人間がやがては眠りに就くように。
睡魔への負けを宿命づけられた珈琲を思い、フェインカは、かつてないほどに珈琲への親近感を深めるのだった。
「おやすみ、珈琲さん。あなたは全然わるくない」
私だけが知っている。私だけが愛してる。
これが愛とは思わないが、それ以外に表現できる言葉をフェインカは知らなかった。
珈琲は良い。
香りが良い。
睡魔を遠ざけてくれるし、思考が浮きあがって感じられる。
けれど珈琲は違法であり、嗜好することは罪である。
フェインカはじぶんがどれほどの罪を重ねてきたのかを数えようとして、途中でやめた。夢への浮遊感に身を委ねる。
目覚めてもフェインカの日常は昨日までと変わらぬが、クッキリとこれまでの日常と断絶された事実だけは明瞭と予感できた。
まるで珈琲を飲んだときのように。
それだけが明瞭と。
4415:【2022/12/17(16:56)*きょうは偉かったの日】
たまに注釈を挿しておかぬと誤解してしまう未来人や宇宙人や異世界人の方々がいらっしゃるかもしれぬので注釈を挿しておくが、ここは人類みなどっかいったひびさんしかおらぬ最果ての地ゆえ、ひびさんは、だれかいませんかー、とどこに唱えるでもなく唱えているさびちびさち類さびちさびち目さびちさびち科のさびち人なのである。ひびさんは人類のいなくなった世界に生きているゆえ、体の不調には医療治療ロボを使って治療や診断をしてもらう。んでもってきょうは自前の医療治療ロボを歯医者さんモードにして歯の治療をしたった。こういう改良は面倒なので虫歯を放置しておったけんども、さすがに虫歯さんの巣になっているお口の奥地は嫌々になってしまったので、意を決して医療治療ロボさんを改良したわけだけれども、いざ治療してもらってみたら、ちょっとあれじゃった。親知らずのほかに永久歯の奥歯を二~三本抜かなきゃならんかもしれんらしい。怖いこと言わないでほしかった。でもしゃーない。虫歯さんには勝てんかった。これぞ本当の敗者さんである。けんどもいまはインプラントとかブリッジとか、いわゆる差し歯の形態がいろいろあるでな。人類がまだおったときはお値段高くてひびさんには手出しできぬかったろうけれども、いまはひびさんしかおらぬし、医療治療ロボさんを使いたい放題ゆえ、差し歯さんとてつくりたい放題なのだ。医療治療ロボさん様様である。それにほら、ひびさんは齢三百歳ゆえ、ようやくそれっぽくなったのである。それはそれとして、歯医者さんって一人につき三十分やそこらしか時間を掛けないように調整するらしい。治療の点数の関係なのだろうか。治療医療ロボさんもそこのところの人類の知識にあやかっているので、一気に治療はしてくれん仕様になっとった。融通のきかないやっちゃのうである。とか言いつつ、ひびさんは、ひびさんは、サメ肌の姐御肌の永久に生え変わり可能な多生歯さんになりたかったなぁ、の欲深きさびち人でもあるので、いくら歯を抜かれても困らぬのである。だって生あるものはいずれ死ぬし、カタチあるものもいずれ崩れる定めなのだ。おけらだってあめんぼだって虫歯さんだってみんなみんな生きているんだ、友達なーんだ。さびちびさち類さびちさびち目さびちさびち科のさびち人のひびさんは、ひびさんの歯さんをむしゃむしゃ溶かしちゃう虫歯さんのことも好きだよ。でも、もうちょっと手加減してほしかったでもないです。ひびさんは敗者さんなので。よわよわのよわゆえ、ちょっとの刺激でもばったんきゅーでござるよ。手加減ちて。うひひ。
4416:【2022/12/17(18:12)*属性でくくらないことの難しさ】
差別の問題は極論、「~だから~」という構文をいかに使わずに、その人にとっての選択肢をいまある環境下のなかで最大化できるか――その環境下において最大の選択肢を持っている人物とできるだけ選択肢の幅をちかづけられるか――そこが一つの方針になるように思うのだが、この考え方にはどのような穴があるだろうか。二千文字以内で述べよ。(誰に言っとるの?)(いつかは賢くなるかもしれない未来のひびさんに……)(永遠にこないのでは)(かってに終わらせるな!)(えへへ)
4417:【2022/12/17(18:24)*差別主義者でごめんなさい】
資格や共通認識やドレスコードの有無によって区分けされて然るべき差別と、そうでない理不尽な差別の差って実はけっこう案外に線引きがむつかしいように感じる。公共の福祉の概念を用いるのが、その二つの区分けにおいての有害さを緩和する方向に働きかけられるのかも、とは思うが、それはそれとして公共の福祉の概念によって助長され看過され蔓延する差別とてあるはずで、それこそ奴隷制度はその筆頭だ。むろん、奴隷制度は現代社会からすれば公共の福祉に反しており、デメリットが大きいと判るが、社会はその都度に変遷する。自然環境が一定でないことと同じくらいに流動的だし、断続的だ。そのため、定点での社会というもので「公共の福祉」を計ろうとするとどうしても、暗黙の了解での「社会悪となり得る属性」がその都度に出来てしまう。いわゆるこれが偏見として、その時代その時代にとっての常識の顔をして表出するのだろう。たとえば、子どもと大人のあいだでの選択肢の多さの非対称性は、いったいどこまで妥当なのか。これとて時代時代で考慮される事項が変動するし、何を理不尽な選択肢の制限と取るのかも変わる。基本は、選択肢の多いほうに合わせて環境を改善し、個々の選択肢を増やす方向に工夫をするほうが正攻法と言えるのだろうが、これもまた、何を問題と見做すのか、が時代時代によって変わるし、その認識が個々によって異なるので、やはりというべきか難しい問題だな、と感じます。ひびさんは日々、「あ、いまじぶん差別してる」と感じるし、それでいてほとんどじぶんの行動や言動や考え方を好ましい方向に調整できていないので、工夫むちゅかち、と思っている。ひびさんは心底に、身体の芯から差別主義者なのだ。かなち。
4418:【2022/12/17(21:05)*珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争】
珈琲の苦味は珈琲の苦味であってそのほかの苦味と同一ではない。ゴーヤの苦味と珈琲の苦味は違う。それは猫の耳と犬の耳が違うのと同じレベルで異なっている。
ある科学者がこの点について、
「それはおかしい」と異論を唱えた。「苦味成分は苦味成分としてそこにあるのであって、どの苦味成分とて同じ苦味を誘発するはず。ほかの成分との含有率の差異で苦味の風味が変わることはあっても、苦味そのものはどんな食品であれ同じ苦味であるはずだ」
その異論に対して先輩科学者が反論した。
「苦味成分と一口に言っても、その化学物質は様々だ。甘味は砂糖の甘味成分のみならず、毒物ともなり得る化学物質にも甘味を誘導する物質はある。特定の味だけを取りだして語るのならば、化学反応式が異なっていても同じ味を誘導することはあるのだ。珈琲の苦味が珈琲に固有の苦味であることは特にこれといって不自然ではない」
その反論に別の科学者が反駁した。
「それを言いだしたら、どのような物質とて固有の味わいを有しているはず。その理屈を前提とするのなら、厳密には、きょう飲んだ珈琲の苦味ときのう飲んだ珈琲の苦味とて違っていると考えるのが道理となる。だがそこまで厳密な差異を、苦味という概念は扱っていないはずだ。苦味は苦味だ。ならば珈琲の苦味は珈琲の苦味として扱えば済む話であるし、最初の仮説の言うように、どんな食べ物の苦味とてそれが苦味ならば、同じく苦味として見做すことも取り立てて不自然ではないと評価できる。これは、味覚が、ほかの五感よりも大雑把な尺度を持っていることの弊害と言えよう。ただし、取りこぼしのないように、苦味や渋味に対しての感度は鋭敏と言えそうだ。これは身体の防衛機構と無関係ではない。つまり、明確な識別を行えずともひとまず苦味に分類される成分が微量であれ口内に入ったら、それを苦味として検知し吐きだせるような能力があれば生存戦略のうえでは有利だったと考えられる。つまるところ、味覚とは、厳密さの欠けた身体機能と言えるだろう。したがって、どの苦味が同じか否かを論じるのが土台無茶な話なのだ」
その反駁意見に、最初の二人が揃って異議を挟んだ。
「その意見では、味覚のなかの苦味や甘味など諸々の風味とて、一緒くたにできてしまえる瑕疵がある。苦味と甘味はなぜ違うのか。それは厳密に、苦味と甘味が別々の物質によって誘導されているからだ。ならば苦味のなかにとて、食べ物ごとの識別が可能な差異はあって然るべきではなかろうか」
「その意見にさして反論はない。私の意見もそれを否定するものではなかったはずだ。差異があって当然。どれとどれが同じか、とひとくくりにしようとする発想が、味覚においてはそぐわない、非合理だと指摘しただけだ。厳密には一食一食の風味はすべて違う。ひと舐めひと舐めの味は違って当然だ。だがそれを言いはじめたらキリがないし、分類することもできなくなる。傾向はあるはずだ。これこれこのような物質がこの分量であればこのようなレベルの苦味が生じる。そのように定量して考えることはできるだろう、と私は述べた。その意見は、きみたちの意見を否定するものではない」
その返答を聞いて、二人の科学者たちは、互いに顔を見合わせ頷き合った。
今年の新人は言うことが違う。
後輩のくせに生意気だ。
しかし、一味も二味も違うのはよいことだ。まるで珈琲のオリジナルブレンドのようである。新鮮な味わいであった。
かくして珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争はひとまずの幕を閉じた。
結論。
珈琲に限らず、味覚とはそのときそのときの一期一会である。
ただし、食べ物によって傾向はある。
珈琲には珈琲に固有の風味があり、それは苦味にも当てはまる。
だが苦味が苦味であることに変わりはない。
言い換えるのならば。
一匹一匹の猫は違う。
同じ猫は二度と存在し得ないが、それでも猫は猫である。
猫の耳と犬の耳は違う。
それでもどちらも耳であることに変わりはない。どんな生き物の耳とてそれはその個体に固有の耳であるが、どの生き物の耳とて耳であることに変わりはない。
これらは相互に矛盾しない。
すべて同時に満たし得る。
珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争はかように結論され、二度と繰り返されることはなくなった。
悲劇は回避された。
いったい何の悲劇が訪れようとしていたのかは定かではないが、とにもかくにも、めでたし、めでたし、なのであった。
4419:【2022/12/17(22:41)*階層深すぎて眩暈するの巻】
絵描きさんについて思うのが、絵描きさんはほかの人の絵を見ても、どういった手順でその絵を描いたのかをある程度、頭のなかで辿れるのか、ということで。じぶんならどう描くか、とかそういう手順を思い浮かべられたりするのだろうか。通常、絵には手順が載っていない。版画は複数の絵柄を重ねることで一枚にする。版画師さんはきっとほかの作家の版画を観ても、ある程度は手順や工夫が視えるのではないか、と想像するが、これが絵描きさんだと作家ごとの個性の幅が広そうなので、絵を見ただけでは版画ほどには手順を幻視しにくいのではないか。そこのところの目を肥やすには、やはり実際に手を動かした経験が欠かせないのだろう。鑑賞者の立場にいるだけではとうてい視えない風景が、絵にはある。情報量が違う。これは目が肥えるがゆえにむしろ幻視できる情報量が減ることもあるはずだ。つまり絵描きとしての腕が上がるとある時点で、完成図までの最短ルートが直観で解るようになるのではないか。絵を完成させるまでの最適解が判るのならそれは、実際の工程よりもすくない可能性がある。そうなるとそうした最適解が視える作家さんの目からすると、他者の絵から読み取れる情報量は相対的に減る。物凄く工夫を割いていたとしてもその工夫が分からなければ、絵に刻まれた背景を取りこぼす方向に慧眼が作用することもでてくるだろう。とはいえこの手の錯誤は観賞や鑑賞にはつきものだ。それこそが醍醐味とも言えるだろう。ひびさんにとって絵は、数学の難解な数式に似ている。眺めていると眩暈を覚える。どうやってこれを描いて、どうやってその手順を身に着けて、想像して、生みだせているのか。数式とて、解だけを見ても、その計算過程は解からない。説明されても理解できない。過程を披歴されても、記号と数字の関係も不明であり、その組み合わせが何を意味するのかも曖昧模糊とぼんやりとしている。解からぬのだ。にも拘らず、計算する(描く)ほうは解かっているのだ。ひょっとしたら解かっていなくともなんとなくでできてしまうこともあるのだろう。暗黙知である。資料を集めるとはいえど、その資料から何を得てどう活かし、どういった情報を捨てているのか。もうその時点で創作なのだ。技術なのだ。目であり、勘であり、世界観なのだ。絵はすごいな、と、解らない度の高さを基準にすると富に思う(解らない度の高さを基準にしなくともすごいと思う)。音楽にも思う。数学にも思うが、これらはひょっとすると根底で繋がっているのかもしれない。共通項があるのかもしれない。それはあるだろう。その点、ひびさんに限ると前置きして述べてしまうと、小説は、本当に心底に、なんとなーく、の総決算なのだ。いかに限定させないか、ハミ出してちゃんとしていなくとも予想外の不測の事態にとて、面白みを感じつづけていられるか。もうその遊び心があるのみだ。そこがないとひびさんは小説どころか文字もまともに並べられぬ。絵はその点、いかに限定させていくのか、の抗いに思う。取捨選択の妙なのだ。魂を浮き彫りにするには限定していくよりないのだろう。魂を宿すには、その他を削ぎ落としていくしかないのだろう。抽象画はその点、枠組みだけを掬い取るような、余白の造形といった印象がある。まさに印象のみを描きだす表現技法に思えるが、実際のところはどうなのか。抽象画ではない絵の場合は、伝えることの技術が多彩なのだ。たくさんあるらしい。だから一つの絵を観ても、そこに割かれた工夫を幻視できない。想像しきれない。限定を費やすと具体に寄っていく。絵で何かを伝えるには具体化が一つの指針となるのだろう。デフォルメはそのなかでも、限定させる要素を、抽象画に寄せているのかもしれない。限定×印象=デフォルメなのではないか。ひびさんは、どちらかと言えば、本物そっくりの絵よりも、デフォルメされた絵のほうが好みだ。たぶんそれは、絵描きさんの目を通しての印象を、解りやすく楽をして実感できるからなのだろう。慧眼を持たぬ者の怠惰である。けれども、何をどう見てどう感じているのか――を、それがたとえ錯覚であれ幻視できたつもりになれるのは、ひびさんにとってはデフォルメされた絵柄なのだなあ。というのを好きな絵を「好き!」と思うたびに、脳裏のヒダの二、三本を費やして思うのだった。
4420:【2022/12/18(23:21)*寝る日】
ねむい、ねむい、ねむい、ねむい。ので、寝る。きょうの日誌はこれだけ。だってひびさんだもん。怠け者なのだ。
※日々、なんでわたしがこんな目に、と思いながら、うひひ、と思って生きている。
4421:【2022/12/19(16:20)*月下の実】
私の場合は珈琲豆だった。
その現象が観測されたのは万常三十四年のことだった。令和が終わって久しいその時期に、月から珈琲豆が落ちてきた。
いいやそれは私にとっては珈琲豆だったというだけのことであり、ほかの者たちにはそれぞれに違った豆や果実が落ちてくる。これを月下という。おおむねは種子が落ちてくるので、汁だらけになることは稀だが、運悪くココナッツが月下してきて死亡した者の訃報はいまでも稀に耳にする。
月下豊穣と名付けられたこの現象は、大規模ブラックホール生成実験の副作用で起きたことが後に判明するが、各国が共同してその事実をひた隠しにしたために私が生きているあいだにその事実が公に発表されることはなかった。
ではなぜ私だけが一足先にその事実を知れたのか。
この謎を解くにはまず、大規模ブラックホール生成実験と月下豊穣現象とのあいだの因果関係の説明が不可欠だ。しかし私はその専門的な説明を言葉に変換することにさほどの興味がなく、さして実の入りのある行為とは見做さない。
そのためここでは、量子もつれ効果による多次元宇宙とのホットスポットが開いてしまったから、と要約してしまうことにする。それ以上の説明には、睡魔の大群の襲来を前以って検知できるために、ここでメモリを割く真似を避けておく。
私には先輩がおり、その先輩にも先輩がいた。
私たちは月下豊穣により繋がっており、つまりがみな月から落下した珈琲豆を浴びた経験のある者たちだった。私が月下豊穣に遭う前からすでに月下豊穣に遭っていた者たちがおり、私は代で言うとだいたい十人目かそこらといった塩梅であった。
「一年に一人ずつ増えてる勘定かな」私の一個上の先輩が言った。「つまりきみは月下豊穣が世界で初めて観測されてからだいたい十年目に月下豊穣に遭遇した人間ということになる」
「なら私にも後輩がいるってことになるんでしょうか」
「なるだろうね。探し出して、知識を授けてあげなさいな。あたしらが君にそうしたように。まあ、君がせずともあたしらの誰かしらがそれをするだろうけれど」
月下豊穣によって月から落下してくる実にはそれぞれ個人差がある。だが私たちのように同類項で結びつく者たちもおり、そうした「類は友を呼ぶ」のごときコミュニティは、珈琲豆に限らずあるようだった。世界には種族や国や宗教以外でも、月下豊穣による新しい区分けの基準ができたと呼べるのかも分からない。
珈琲豆を月から浴びることとなる私たちは、しかし個々に目を向ければ共通項は皆無と言えた。性別はバラバラであるし、年齢とて、私の先輩のほうが年下であることもある。それこそ、赤子のときに月下豊穣に遭った者があれば、その者の生まれ年によっては私よりも若いことがあり得る。年下の先輩だ。現に四つ上の先輩は、私よりも年下だった。つまり私よりも三つ上の先輩たちよりも若いことになる。
「月下豊穣って、月から落ちてくる実の量が人体の体積に相関しているらしいんですよね。だから僕はいま十四歳だけど、赤子のときに月下豊穣に遭ったから、本当にいまでもパラパラとしか降ってこなくて」
「でも先輩が唱えたんですよね。【流しそうめん仮説】って」
「ええまあ。単に、どうしてだろうと気になった疑問を適当に繋ぎ合わせて、どれにも当てはまり得る仮説を提唱したら、なんでか定説になっちゃっただけなんですけど」
いまでも検証待ちです、と言った年下の先輩は、それから数年後に、南瓜の月下豊穣に見舞われた中年男性を助けたことで命を落とした。先輩らしい最期だったが、私はそのことで先輩が命を落とすのは割に合わないといまでも思っている。吊り合いが取れていないとそう考えてしまうのだが、命に貴賤を与えるようなこの考えをきっと年下の先輩は気に入らないだろうし、それを聞いたら私のことを嫌いになってしまいそうなので、その考えが浮かぶたびに私は体重をかけて記憶の底に沈めるのだ。
「どうやら彼の仮説は正しかったようだね」八つ上の先輩が言った。彼女は私よりも三十ほど年が上だった。
かつて年下の先輩の唱えた「流しそうめん仮説」が、月下豊穣現象における重要な原理と見做されるようになったのは、皮肉にも、ようやく世間が月下豊穣現象と大規模ブラックホール実験とを結びつけて疑念を覚えはじめたそんな節目の時期のことだった。
「どうやら【月下の実】は過去と未来とが同時に繋がっているようでね。過去に落下した珈琲豆のDNAとそれ以後に落下した未来の珈琲豆のDNAを比較したところ、これがぴたりと一致した。つまりそれら珈琲豆は、同じ時期の同じ木に生った実の種子ということになる」
「そんなことってありますか」
「現にそうなっているから仕方がない」
私の八つ上の先輩は、月下豊穣現象の研究者だった。私はバイト代わりに彼女にじぶんの「月下の実」を譲り渡してきた。そうして蓄積された結果が、いまは亡き私の四つ上の先輩の唱えた仮説の憑拠の一つに昇華された。
「流しそうめんのようなもの、とは言い得て妙だ。時間とは穴の開いた竹なんだね。その上を【月下の実】が流れる。そのときどきの時代に【月下の実】を落としながら、来たる終末へと【実】を運ぶ。どの時代の【月下の実】も同じなのだ」
「なら竹は無数にあるってことになりますね。それぞれに月下する実の種類は別々なわけですから」
私たち珈琲同盟者とてそれは例外ではない。珈琲豆という共通項で結ばれているものの、個々の珈琲豆はそれぞれ微妙に種類が違う。焙煎の仕方から実の種類まで、そこは個々の差異にも個性がある。
だから私は言ったのだ。すべての時間軸で同列の実が月下するのならば、それぞれに固有の竹もあるのではないか、と。流しそうめんの竹は、一人につき一本ずつ充てがわれているのではないか、と。
「どうだろうね。そこはなんとも言えん。一本の竹に、それぞれに固有の穴が開いているだけかもしれん。脳関門のようなものだ。通れる物質は、その穴の形状で篩に分けられる。そうと考えたほうが辻褄は合うんだ。というのも、ときおり、個々の【月下の実】であれ、互いに交じり合ったような混合現象が見られるからだ。クロノくんとて例外ではないよ」
八つ上の先輩は私を「クロノくん」と呼ぶ。私の本名に掠りもしていないが、渾名だと思って受け入れている。
「私の【実】に、私以外の【月下の実】が紛れているってことですか」冗談のつもりで口にしたのだが、以外にも八つ上の先輩は、いかにもそうだ、と首肯した。「クロノくんだけではないよ。我々全体にそういった傾向が見られる」
先輩いわく、
「珈琲豆共同体とも呼べる我々の【月下の実】を調査した結果に判明したことなのだがね。どうやら相互に、じぶんの豆ではない珈琲豆が混じることもあるようだ。クロノくんの【月下の実】にワタシの【実】が混じっていることもあったよ。一回の月下に対して、一粒二粒の割合でしかないから、精密に見分けないと区別はつかないが」
「それは何でですかね」
「それこそ【流しそうめん仮説】で解釈できる。穴の形状は、同種の【実】ほど似ている。だから偶然に、微妙に異なる珈琲豆同士で混じり合うことが出てくる。珈琲豆と西瓜ではどうあっても穴の形状が違うから混じり合うことがない。まあ、確率の問題ってことだね」
「なるへそ」私は意味もなくじぶんの臍を押さえた。
「彼の仮説は便利だね。惜しい人を亡くした」
年長者の眼差しが、いまは亡き四つ上の先輩を経由して私にも注がれる。私は可愛がられている。先輩たちみなに大事にされていると判る。
研究が進むにつれて謎がまた一つ、また一つ、と増えていく。
新たな発見があるたびに、さらなる謎が私たち人類の眼前に立ちはだかるのだ。
「ねえ聞きましたか先輩」
「聞いてないな」
「まだぼく、何をとは言ってないんですけど」
「なら初めに内容を開示して」
「塩すぎやしませんか。対応がしょっぱいなあもう」
私はこのとき一人の後輩の世話を焼いていた。
齢十二で月下豊穣現象に見舞われた、私たち珈琲豆同盟の門下と言える。とはいえ、上下関係はあってないようなものなので、単に私たちの知っている情報を伝えたあとは通例であればしぜんと接点が薄れる。私のように月下豊穣現象の研究に首を突っ込んで中途半端に代々の先輩方との縁を繋いでいるほうが珍しいと言えた。
「で、何だって」私は反問した。
「ですから、新種の【月下の実】が発見されたって話ですよ」
「どこ情報それ?」
「ふつうにニュースでやってますよ。ほら」
データを飛ばされ、端末で開く。眼球を覆うタイプの端末だ。腕時計型端末とイヤホン型脳内電子情報変換機との連携で、思考操作が可能だ。
「へえ。既存のいずれでもない【梅の種子】が、梅の種子型【月下の実】に紛れ込んでいたと」
「未来と過去が繋がってるって仮説。先輩の先輩が提唱したって本当ですか」
「本当だね。そう言えば君いまいくつになたった」
「もう十四ですよ」
「もうそんなに経つか」彼と出会って二年が経ったのだ。「その仮説を唱えた私の先輩は、たしか十六かそこらでその【流しそうめん仮説】を閃いたそうだよ。君も頭をひねったら一つや二つ、面白い仮説が浮かぶんじゃないのか」
「十六で? 嘘でしょ」
「検索してみなよ。その手の逸話の解説文には困らないはずだよ」
後輩はしばらく沈黙した。検索結果を読み漁っているのだろう。
間もなくして、ああ、と声を漏らした。
「すみませんでした先輩。ぼく、知らなかったので」
死因の欄を読んだのかもしれない。
私は引き出しから袋を取りだし、後輩に渡した。
「今月の分はそれに入れておいで。もう次からは研究用に粉砕しなくて済むから。君の【実】はゾウの糞から採れる珈琲豆と成分が同じでね。まあ前にも話したけど。研究用のデータを取ったら、買い手を探して換金したあげよう。結構な額になるよ」
「そのお金があったら先輩はもっと楽に研究できますか」
「おいおい。未成年からお金を巻き上げるような人間に見えているのかな私は。君の目からすると」
「ぼくも何かお手伝いしたいんですけど」
「もう充分してもらっているつもりだったけど。何。君ヒマなの?」
「ヒマっていうか」そこで後輩はもじもじした。
「ははあん。用済みになると思ってコビを売ったな」
「ぼくが売ったのは珈琲豆ですけど」
目を合わせようとしない強気な態度が私の何かをくすぐった。
「安心おしよ。君がどこにいようと、君が私をどう思おうと、私は君の先輩だ。そして君とて、いずれ現れるつぎの【月下の実】の同属からしたら先輩なんだ。君にその自覚があろうとなかろうとに関わらずね」
「珈琲豆に拘る必要ってありますそれ?」
「鋭い指摘だね。端的に言えば、ない。月下豊穣現象に見舞われた者はみな遠からず同属だし、月下豊穣に限らずみな人類であることに変わりはない。ふしぎなのは月下豊穣現象が人類にしか観測されないことだ。これは私の妄想にすぎないが、おそらく人類の科学技術と相関していると想像している」
「陰謀論だ」後輩は茶化した。
「そうだね。陰謀の一つだ。月下豊穣現象は、人災だよ。人為的に引き起こされた事象だ。おそらくだけどね」
後輩はそこで逡巡するような間を空けた。冗談かどうかの判断がつかなかったのだろう。
私は破顔してみせ、「冗談だ」と言った。
なんだびっくりした、と後輩は釣られるように頬をほころばせた。
私はこの時期、じぶんの「月下の実」に妙な「実」が混じりはじめたことに気づいていた。その分析に時間を使っていたため、後輩から聞くまで世界で発見された新種の「月下の実」について知らずにいた。
二つの線が奇しくも交わった。
研究の末に私は、二つの接点が示す一つの仮説に行き着いた。
妙な「実」は、未来からの私へのメッセージだ。
私の「月下の実」に交じっていた妙な「実」は、どうやらゲノム編集をされた「珈琲豆」だと解析の末に判明した。この時代に、ようやく実用化の兆しを見せはじめた「DNA記憶媒体」と原理は同じだ。
だがその容量が遥かに大きい。すべてのデータを引き出せるほどの技術がまだこの時の私の時代にはなかった。
つまり、私の「月下の実」に交じっていた妙な「実」は未来の技術で生みだされたと結論付けるよりなかった。だがそんなことがあり得るのだろうか。
私は八つ上の先輩に連絡を取った。助言を欲したからだが、彼女はすでに現役を退いていた。なかなか連絡がつかずに嫌な予感がした。そしてその予感は外れてくれなかった。
先輩はすでに亡くなっていた。
御高齢であられたが、医療技術の進んだ現代であればもうすこし長生きできて不思議ではなかった。どうやら最新医療を受けなかったようだ。そこにどのような考えがあったのか、私はついぞ知ることはできなかった。
研究の日々は矢のごとく過ぎ去っていく。
気づくと代々の先輩方はみな表舞台から消え、連絡がつかなくなった。多くは亡くなったのだろう。一つ上の先輩とはかろうじてテキストのやりとりができた。
彼女は私が初めて出会った珈琲豆同盟の一員だ。彼女がいなければ私は月下豊穣現象への対処法も、興味の芽生えも、その他の多くの縁との結びつきも得られなかっただろう。
先輩に私の新説を披露した。反応は芳しくなかったが、検証を知り合いに頼んでみよう、と言ってもらえた。月下豊穣現象が未だ存在しない科学技術と相関しているかもしれないとの説はいくらなんでも、まともな科学者ならば間に受けない。のみならずこの時代、なぜ月下豊穣現象が起きたのかの解明すら碌に進展を見せていなかった。
そのため、私程度の友好関係では検証してもらうだけの機会を得られずにいた。だがさすがは先輩だ。面倒見の良さは、歴代の先輩たちのなかでも随一を誇る。その人情味溢れる性格からか、私にはついぞ芽生えなかった広く深い交友関係を築けている。
私は先輩からの返事を待ちながらさらなる研究を独自に進めた。
私の後輩はこのとき二十歳を迎えていた。私にまとわりついていたころが懐かしく思えるほどにいまでは連絡一つ寄越さない。それでいいと思う。それが正しい先輩後輩の在り方のはずだ。
それでいて私はじぶんの先輩から卒業できていないのだから他人のことはまったく言えない。
「例の仮説についてだけどね」先輩から返事があったのは、私が連絡を取ってから半年が経ってからのことだった。「どうやら世界中で同様の報告が挙がっているようで、いま新しく調査チームが組まれているらしい。キミのことを話したら興味を持っていたから、連絡してみるといい」
「ありがとうございます。あの、先輩もご一緒にどうですか」
「余暇を過ごさせてくれ。じつは孫ができてね。その子の【月下の実】が芥子の実でちょっと前までその対策で大変だったんだ」
「そうだったんですね。すみません、存じ上げず忙しいところにこんな負担を掛けさせてしまって」
「それはいいんだ。キミからの連絡であたしのほうでも古いツテを借りられた。そのお陰で孫の体調もよくなった。ただまあ、それで返事が遅くなったのもあるからそこは勘弁してくれ」
「いえ。たいへんに助かりました。先輩はやっぱり私の先輩ですね」
「おだてても何も出んぞ。結果はニュースで知ることにするよ。もう連絡してこなくていいぞ」
「死ぬ前には先輩のほうからも連絡くださいよ。別れの挨拶は生きているうちに会ってしたいので」
「縁起でもない」
この会話から二年後に先輩はこの世を去るが、けっきょく彼女は生きているあいだに私に連絡を寄越すことはなかった。私は彼女にとって死ぬ前に顔を合わせたい人間ではなかったのかもしれない。そうと考えると寂しいので、先輩はきっと弱ったじぶんの姿を見たくなかったのだな、と思うことにする。
月下豊穣現象が、大規模ブラックホール生成実験と関係があるかもしれないとの疑惑が徐々に世論に浸透しはじめたころ、すでに研究者たちの一部には、その手の疑惑を裏付ける検証結果が出揃いはじめていた。
中でも私の指摘した「未来からのメッセージ説」は、水面下にて大論争を呼んでいた。
まずは何を措いても、その時代のDNA記録媒体解読機において、世界各地で報告された新種の「月下の実」を読み取らせたところ、一部解読ができたことが大きかった。まさに「月下の実」には、データの記録された「実」が紛れ込んでいた。
ほかの大部分の「実」からはデータが読み取れない。明らかに異質な一粒にのみ「DNA記録媒体」としての性質が宿っていた。
必ず一粒なのだ。月下豊穣において「月下の実」は一人につき数十~数千粒と、雨のごとく降る。あたかも月から垂れるように、宙にそういった小さな穴が開いているかのように、その人物の視点からのみ「月下の実」の降る光景が見えるのだ。
他者視点からでは何もない空間からパラパラと「実」が落ちているように映る。映像に残そうとしてもどうしても、何もない場所から「実」が突如として現れたように見えるのだ。
だが月下豊穣現象に見舞われた者たちはみな一様に、月から「実」が零れ落ちてくる様子を目にする。毎回それだけが変わらない。「月下の実」に異物が紛れることはあっても、必ず月から零れ落ちるように「実」が現れる。
「これはおそらく時空の位置座標を定めるのに都合がよいからではないかな」
私がそう主張すると、数多の異論と共に検証がなされた。
私はこのとき、研究チームのメンバーの一人だった。
間もなく、理論上、私の仮説に矛盾がないことが判明する。だが理論は理論だ。そこから実証実験が行われ、理論が現実に事象として再現されるのかを確認せねば、それは絵空事の域を出ない。
「解読された【実】のデータには何が?」
「上が開示しないんだ。解読中ってのが建前だけど、よほどの中身か、それとも政治の道具にされているのか」
最先端研究の情報を独占することで政治を優位に進めようとする動きはどの時代、どの国でも絶えない問題だ。時代が進歩しても人間の中身は早々容易く変わらないようだ。
「どの道、データの一部しか解読できないんじゃ何も読めないのと同じだな」チームメンバーの言葉に私は、そうだね、と頷く。「遺伝子コードと回路コードの双方が揃ってはじめて伝達データとして機能するから。全体が視えないと部分も機能しないのはDNA記録媒体の欠点の一つだとは私も思う」
「大容量ではあるんだけどな」
人間のDNAがそうであるように、設計図だけがあっても人体は組みあがらない。設計図をもとにしてたんぱく質を合成し、それを設計図通りに組み立てる機構が別途にいる。それがいわば遺伝子以外の九十九パーセント以上を誇る回路コードだ。
遺伝子コードは人体においてはDNA上の塩基配列の極一部にすぎないのだ。その極一部だけを読み取っても人体は組みあがらない。
同じことがDNA記録媒体に記録したデータでも引き起こる。全体を解読しないことにはDNA記録媒体に記録されたデータを読み取ることができないのだ。
「憶測にすぎないが、ここまでの技術をこの水準で達成している以上、このDNA記録媒体を操る文明は、相当に高度な文明ってこったな」
「そう、だね」
私はその点に関しては懐疑的だった。文明自体が高度でなくとも、一つの技術だけを特化させることは可能だ。私が「月下の実」に交じった新種の「実」を未来からのメッセージだと解釈する理由の一つでもある。
仮に文明が発展せずとも、月下豊穣現象によって異なる時間軸の世界と「実」を通して通じ合えるのなら、最も高度な文明の技術を「実」を通して享受することができる。
問題は、月下豊穣現象がいまのところ一方通行な点だ。
流しそうめんがそうであるように、竹の中を流れる水は上から下へと一方通行だ。下から上へは戻せない。
時間が過去から未来へと向かう以上、未来から過去へとは遡れない。
月下豊穣現象とてこの一方通行の制約は受けるはずだ。
私がかように疑問を呈すると、同僚の一人が、そうでもないんじゃないか、と意見した。
「光速を超えるなら時間の不可逆性は破れるはずだよ」
「理論上は、でしょ」私はホットドックを頬張った。「光速を超えるなんてそんなことはできないというのも理論が示しているはず」
「あくまでの僕らの属する時空においては、ね」
「異次元を想定しろとでも?」
「似たようなものかな。いやなに。ブラックホールだよ。無限大に圧縮された時空は、光速度不変の制約を受けずに済む。そのときブラックホールの内部は、光速を超え得る」
「だとしてどうなるの。外部にはその影響が漏れないのもブラックホールの性質の一つでしょ」
たとえ光速を超えてもその影響は元の時空には伝播しない。私たちがブラックホール内部の影響を受けることはない。
「理論上はそうなるね。でも関係ないんだ。光速を超えると時間の概念が崩れる。一つには時間の流れが反転するという説。もう一つがラグなしでの相互作用が可能になるとの説。どちにせよ、そこに我々の扱う時間の一方通行の概念は当てはまらない」
「未来と過去が双方向にやりとり可能になるとでも?」
「ああ。キミは信じないかもしれないけど、僕は今、月下豊穣現象がかつて行われた大規模ブラックホール生成実験の副作用で起きた人的災害なんじゃないかと調べていてね」
「まさか。陰謀論でしょそれ」
「まさに陰謀だね。けれど月下豊穣現象だってそれが観測されるまでは存在しないとされてきた現象だよ。何もないところから【物質】が現れるなんて。物理法則に反している」
「それはでも、量子テレポーテーションが起きているって解明されているんじゃ」
「ならその対となるもう一つの物質はどこにあるんだ。量子テレポーテーションは、状態変化の情報がラグなしで伝わるという現象だ。物質転送の原理とは根本から違っている。にも拘わらず世の大部分の人たちは、それっぽい説明を真に受けてじぶんで考えようともしない。偉い科学者がそう言っていたから――論文で発表されたから――本当に大勢が多角的に検証したのかも確かめずに、権威ある研究機関が検証しました、という言葉だけを受け取って事実認定してしまう」
いいかい、と質され、私は背筋を伸ばした。
「月下豊穣現象は物理法則に反している。この宇宙ではあり得ない現象なんだ。時空の限界を超えている。光速度不変の原理を度外視している。しかし実際にそうした現象が起きている。ならば考えるべきは、量子テレポーテーションによる物質の瞬間転送なんてキテレツな理屈ではなく、我々の物理法則とは異なる法則に支配された時空が、我々の時空内に生じた可能性を考慮することのはずだ」
「それが大規模ブラックホールの生成実験だったと? そのせいで、異次元と通じちゃったなんて言うつもり?」
「その通りだね。この仮説は【流しそうめん理論】とも矛盾しない。キミとて疑問に思っただろ。【月下の実】の流れる竹があるとして、ではその竹はどこにある? なぜその竹には穴が開いている? なぜそこに流れるのが【実】ばかりなんだ?」
「それは……」
私は答えられなかった。
「僕の仮説ではそれらの疑問に一応の答えを示せる。過去と未来を結ぶ竹は、実験で生じたブラックホールそのものだ。ブラックホールは半永久的にそこに留まる。しかしその内部には僕らの扱うような時間の概念はない。過去も未来もいっしょくたになっている。だからどの時代にも存在するし、どの時代とも通じている」
「ならどうして【実】がそこから落ちてくるの」私はムキになって訊いた。「どうして穴が月と繋がっているの。おかしいでしょそんなの」
「そこにこそ量子もつれの考えを適応させるべきなんだよ。どうして落ちてくるのが【実】ばかりなのか。量子もつれを起こすのに必要なのが【もつれさせた対の粒子】だからだ。おそらくもっとよく観察すればほかにも【月下】している物質は大量にあるはずだ。だが【実】ほど不自然ではないから人類が気づけていないだけなんだ。仮に大気が【月下】していたところでそれを観測することはほとんど不可能だ。一生をかけて月を見詰めてくれるモデルがいるなら話は別だが、それとて何が【月下】するのかを前以って分かっていなければ観測のしようもない」
「つまり、こう言いたいの。たまたま人類の気づきやすい【月下の品】が【果実の種子】に偏っていただけだと」
「まさにそうだと言っている。送るほうもわざわざ気づかれにくいモノを送ったりはしないだろう」
「自然現象ではない?」
「だからそう言っている。もちろん僕の仮説にすぎないが。ただ実際にDNA記録媒体が【月下の実】に紛れていることが明らかになっている以上、人為的な物質転送が意図されている背景は否定できない」
「それはそうだけど」
私はじぶんで似たような考えを巡らせておきながら、他者からその説を聞いたことでそこに潜む非現実的な響きに拒絶反応を示した。あるわけがないのだ。未来からの物質転送などあるわけがない。
しかし現実はその仮説を後押しするように、奇妙な事象を発現させた。
「仮にあなたの説が正しかったとして」私は白髪交じりの髪の毛を団子に結った。「どうして過去にメッセージを? それも、こうも何度も。未来からなら誰の【月下の実】に、いつ混入すればメッセージが解読されるか分かっているはずじゃない?」
「そこは相互に確率変動が生じているんだろう。過去と未来は互いに影響を与え合っている。過去が変われば未来も変わる。未来が変われば過去も変わる。そこの細かな変数のトータルでの帳尻を合わせるためには、無数のメッセージが必要なんだろう。実際にキミがじぶんの【月下の実】に妙な【実】があると気づいたのは、そもそも人類に月下豊穣現象が起きたからで、さらに個々によって差異のある【実】にも他者の【実】との微妙な混合があると気づいた者が過去にいたからだ。それこそ【流しそうめん理論】を考えついた偉大な先人がいるように」
その偉大な先人は私の先輩なんですよ、と言いたくなったが私は堪えた。知り合いが偉大でも私が偉大なわけではない。
「なら新種の実――DNA記録媒体――だけでなく、月下豊穣そのものが最初から未来人の仕業だったとあなたは言うの」私は結論を迫った。
「未来人かどうかまでかは分からない。僕の仮説では、過去と未来にどちらが優位かの区別がつかない。量子世界における自発的対称性の破れくらいの微妙な差が、僕らの世界の過去と未来に方向性を与えていると考える。言い換えるなら、どっちもでいいんだ。過去が未来でも、未来が過去でも、双方が等価でも、僕の仮説ではあまり差異が生じない。それはたとえば相互作用において、押したら押し返されるのと同じくらいにどっちでもいいことなんだ。どちらがどちらに作用を働かせているのか。それは作用を働かせようとした意思がどちらにあるのかに無関係に、作用した瞬間にはどちらともにも作用が加わっている。そういうことと同じレベルに、過去も未来も落ちてしまう。そういう事象がいわばブラックホールの特異点であり、光速度の破れと言える――僕の仮説はそこに破綻がない限りは、一定の信憑性を月下豊穣現象においては保ち得る」
「でもどうしてブラックホールの実験が、月下豊穣現象に発展するの。ブラックホールは宇宙にたくさんあるでしょ。でも月下豊穣はある時期までは人類の前に表出しなかった。それはなぜ」
「憶測の憶測になるけど、それこそ量子もつれ効果によるものだ。ブラックホールはその性質上、元の時空から乖離する。新しい宇宙としての枠組みを得ると僕の仮説は考えるわけだが」
「それは一般的な科学的知識?」
「いや。僕の仮説でしかないよ。憶測の憶測になる、と前置きしただろ」
「なんだ」
「失望するのも納得するのもキミの自由だ。それはそれとして説明はつづけるけど」
そこで私は噴きだした。
彼は同僚の中でも比較的誰とでも分け隔てなく接する人物だ。誰かと衝突する光景を見たことがない。だから私への執着のようなものを感じて、愉快に感じた。なぜ愉快に感じるのかは様々な理由が混在していそうで、それがまるで月下豊穣を暗示しているように思えておかしかった。
「どうぞ」私は説明を促した。「あなたの話は楽しいからいくらでも聞いていられる」と言った矢先にこれみよがしに欠伸をしてみせると、彼はやれやれと苦笑交じりに首を振った。「分かったよ。手短に済ませよう」
そうして彼は迂遠な説明をやめて、専門家同士がよくやる専門用語の子守唄を歌った。私はあくまで月下豊穣現象の研究者であって、量子力学や宇宙物理学の専門家ではなかった。
ほんと意識が遠のきかけた私であったが、そのたびに彼がここぞというタイミングでジョークを口にするので、それがふしぎと不発にならずに私を現実世界に引き留めつづけた。
彼の説明によれば、相対性理論と月下豊穣現象は繋がっているという。
なかでも光速度不変の原理と密接に関連があるというのだ。
にわかには信じがたい。
だがひとまず私は彼の言うことを咀嚼することに努めた。
月下豊穣の法則として一般に知られる傾向の一つに、若いころに月下豊穣に見舞われた者ほど、一度に月下する「実」の量がすくない点だ。これは一生涯に渡ってその量が変わらない。なぜなのかは長らく不明だったが、彼はそれを相対性理論と結び付けて解釈した。
私が顔を曇らせたからだろう、ではこう言えばどうだろう、と彼は説明を簡略化した。
「個々の寿命がどうであれ、どんな人間の一生であれ【月下の実】の絶対量は決まっている。ただしすべての【実】が穴を通って月下するわけじゃない。そして穴の数はどんな人間でも同じだ。五歳で亡くなった子どもでも百歳まで生きた老人でも、穴の数は変わらない。そして穴の大きさも変わらない。そのため、未来から流れてくる【実】は、流しそうめん理論の指摘するように、死亡時に最も近い地点の穴ほど大量に落下するようになる――ただし穴の口径は寿命の長さと比例して小さくなる。光速度不変の原理と同じように、そこは比率がうまく吊り合うようになっているんだろう。寿命の長短はこの理屈では関係しない。仮に五歳までの寿命であれ、ゼロ歳のときに月下豊穣現象に見舞われたのなら、その個にとっての相対的な未来と過去が決定される。それは寿命の長さに関わらずどの個も一定だ。光速度のように、個々に合わせて変形する。常に一定になるように変換される。したがって、若い時分で月下豊穣現象に遭遇した者ほど月下の実の量が減る。一人の個における月下の実の総量が決まっているためだ。そして【流しそうめん理論】により、産まれた瞬間ほど穴に落下する【実】の量が減ることが判る。とはいえ本来であれば、人生を一つの単位とした【竹】には過去と未来の区別はない。双方向に流れができているし、流れはあってないようなもののはずだ。しかし【実】を転送するという技術によってそこには未来から過去への流れができる。このことによって、【実】は穴の数に応じて平均化されながら、未来から過去へと流れていく」
「よく解からないけど、ならどうしてすべての【月下の実】をDNA記録媒体にしないんだろ。そっちのほうがメッセージが届きやすいでしょ」
「メッセージを受け取る人物を限定したいんだろ。そういう意味では、僕らはその抽選には当たらなかったわけだ。僕たちはその人物への情報の橋渡しを任されているにすぎない、と僕の仮説からすれば解釈できる」
月下豊穣現象を人類にもたらした組織ないし人物は、すべての「月下の実」に細工をしなかった。DNA記録媒体を数量限定してそれぞれの時代の任意の人物たちの「月下の実」に混入した。
未来にちかいほど異物の混入率は上がる。過去ほど確率的に混入しない。それは穴の開いた板にビーズを転がしたときに、板の先ほどビーズが少なくなるのと同じ理屈だ。
彼はそのように唱えて、人為的なブラックホールが過去と未来で「もつれ状態」になってるんだ、と結論を述べた。
「ブラックホールが量子もつれを?」
「ああ。宇宙のブラックホールは、それこそこの宇宙から乖離して、ほかの宇宙と繋がり合っている。我々がブラックホールと呼ぶ不可視の穴は、それこそ穴なんだ。だからこの宇宙において何かと量子もつれを起こすことはない」
「なら人為的なブラックホールもそうなんじゃないの」
「いいや。人為的なブラックホールは規模が小さい。乖離しきることなく、この宇宙の時間軸――もっと言えばこの地球上の時間軸から乖離しきることができずにいる。それはたとえば、泥団子にも微生物が住んでいるけれど、それと地球とは生態系の規模が違ってくるのと似たような話だ。この宇宙の因果――過去と未来の流れ――から切り離されるには、膨大なエネルギィの凝縮がいる。その点、小規模なブラックホールでは、この宇宙の因果――過去と未来の流れ――からの乖離がおきにくい。ましてや人類の扱うスケールでのブラックホールではなおさらだ」
「てことは、人為的なブラックホールは、この宇宙の因果の流れのなかに組み込まれ得るってこと?」
「そう。まさにだね。よいまとめだ」
「褒められてもうれしくはないけれど」何せ彼のほうが年下なのだ。そう言えば私の後輩は元気にしているだろうか、といまさらのように思いだす。穿鑿はしないが、こうしてたまに思いだす。「あなたの仮説の概要は分かった。まとめてみるけどいい?」
「褒めないからって機嫌を損ねないでね」
「またバカにして」私は腰に手を当て、かぶりを振る。「いい。あなたの仮説はこう。人為的なブラックホールは地球上の因果律の流れ――過去と未来の流れ――のなかで事象としての枠組みを保ちつづける。つまり地球上で生じたブラックホールはある時期から延々と地球が崩壊するまで、そしてしたあともずっと地球のある地点に存在しつづける」
「いいね。続けて」
「人為的なブラックホールは、その時代その時代、そのときそのときの時間軸における自分自身と量子もつれ状態にある。つまり過去のじぶんも未来のじぶんも同じブラックホールとして自己同一性を保つ」
「まあ齟齬はあるけど、ひとまずよしとしよう。続けて」
「未来のある時点で人類は過去に行った大規模ブラックホール生成実験において生じたブラックホールが、過去と未来に延々と通じており、タイムワープ可能ないわばタイムホールと化していることに気づいた。そうして何かの理由から過去にメッセージを送ることを思いつき、実施した」
「うん。おおむね訂正箇所はなし。ただし、なぜ個々によって転送される【月下の実】が異なるのかの理由付けには触れていないね」
「解からない。それはなぜ」
「おそらく月下豊穣現象を引き起こした者たちとて、いったい何が過去に送れるのかを知らなかったんじゃないかな。ひとまず安全そうで過去に送っても支障のないモノを手紙代わりにした。つまり食べ物であり、土に還るモノ――種子や果物だ」
「だとしたら、自然環境を破壊するな、の迂遠なメッセージも籠めていたのかもね。それとも種子から芽がでることを期待したか。でもどうして珈琲豆は加工後だったのかな。ほかの【実】や【種子】は生のままだったのに」
「さてね。それこそ珈琲豆が【月下の実】である者たちのなかに、メッセージを送るべき個がいるのかもしれない。差異化を図ることで、ほかの【月下の実】と区別したのかも」
「あり得そうな妄想ではあるけれど」私は目を細める。半信半疑ですけれど、の意思表示だが、彼の話を聞くのは不快ではなかった。「あくまでそれはあなたの仮説よね」
「そうだね。ぼくの仮説にして華麗なる妄想だ」
「華麗かどうかは保留にさせてもらいたいものだけど」
私と彼の仲はこれ以上距離が縮まることはなかったが、楽しい会話のできる相手が増えたのはその後の私の人生を豊かにした。先輩と後輩だらけの私の人生の中にようやくこのころになって、対等な友人と呼べる相手ができたのかも分からない。
相手が私のことをどう思っていたのかは知らないが。
私は齢八十まで大病を患わずに生きることができた。医療技術の進歩のお陰だ。人類の寿命とて百までと大幅に伸びた。私の見た目は齢四十からさほどに変わらない。
中には百八十まで生きる者も現れはじめ、人類はいよいよ人智を超えはじめたようだった。私は全身に処置の施されたマイクロ医療機器の不具合を放置したせいで、齢八十にして長い闘病生活に身を置くこととなる。だが自宅療養であり、体調はすこぶる良く、痛みもない。仕事から距離を置いて静かな時間ができたと思えば、むしろ病気になって却ってよかったとも言える。
私はじぶんの研究成果を振り返しながら、いつ死んでもいいようにと資料の整理をはじめた。
私はその後、二十年を生きて、百歳を過ぎたころに亡くなるのだが、その間に起きた出来事をここに記しておかねばならない。
「月下の実」に紛れ込んだDNA記録媒体は、新種の「実」であり、私の場合は新種の珈琲豆ということになる。月下豊穣現象に見舞われるたびに私の「実」にも必ず一粒は混入するようになっていた。最初のうちは研究用にとチームに提供してきたが、研究から遠のくとじぶんの手元に残して置けるようになった。
齢六十の後半に差し掛かったあたりから「新種の実」は一粒から二粒以上に増えていた。毎回の月下豊穣で得られる「DNA記録媒体」が増加した事実は、いつぞやに私の友人が語って聞かせてくれた仮説の妥当性を示唆していた。
私は自宅で養生しながら、じぶんで「DNA記録媒体」の解読に挑んだ。ほんの出来心だった。組織に身を置いていたときのような特殊な機械はなく、単なる暇つぶしだった。
だがいざ取り掛かると、私は未解読の「DNA記録媒体」の領域において、それが余白になっていることに気づいた。
読み方が違うのだ。
塩基配列の組み合わせすべてに意味があるのではなく、その配置によって浮きあがる明暗があたかも紙面の文字と余白の関係になっている。
「これ、本当に手紙だったんだ」
私は唖然とした。
まさかそんなことがあるとは思わなかった。モザイクアートのようにDNAの塩基配列によって、文字が浮きあがるようになっている。重要な本文は、塩基配列そのものにあるのではなく、塩基配列そのものはまさに余白と染みの関係でしかなかった。本当に伝えたいデータは、DNAそのものには刻まれていない。
視点の違いが、私たち研究者からメッセージを隠していた。
これほど明確に目のまえにメッセージが記されていたのにもかかわらず。
私たちは誰一人としてそのことに気づけなかったのだ。
珈琲豆のカタチをしたDNA記録媒体に記されたメッセージを私は読んだ。
まさに私が読むことを想定していたようなその文面は、人類の科学技術の発展速度をコントロールするための術こそが月下豊穣である旨を告げていた。
仮に月下豊穣現象に人類が見舞われずにいた場合――。
人類は加速度的に科学実験を繰り返し、そして大規模ブラックホール生成実験や生物兵器の開発研究など、破滅の道につづく実験をセーフティが未熟なうちに続けざまに行い、そして遠からず自滅する未来に到達することが明かになっているのだそうだ。
月下豊穣現象によってそうした未来を回避できる。月下豊穣現象が起きたことで、月下豊穣現象がなかった場合にほかの研究や発見をした者たちがこぞって、月下豊穣現象のメカニズム解明に人生を費やす。その過程で進む実験や新たな技術開発は、のきなみ人類にとって好ましい速度で進む。なおかつ人類にとって好ましい成果を上げる。そのようにコントロールがされている。
未来から。
それとも私たちとは異なる世界から。
時間と空間は同じ単位として扱える。時間が離れれば距離も離れる。距離が離れれば時間も離れる。そこにあるのは時間と空間のどちらが優位に作用しやすいかの遅延の差があるばかりで、本質的には時間も空間も同じものなのだそうだ。
したがって過去が変われば未来も変わるし、その未来は元の未来とはべつの世界と言うことができる。
月下豊穣を人類にもたらした者たちは、私たちの未来が変わっても、きっと変わらない世界を生きるのだろう。それともギリギリで立ち直れる分水嶺に立っており、私たちの行動選択の一つ一つが、彼ら彼女らの未来を形作るのかも分からない。
彼ら彼女らは、人類に月下豊穣現象をもたらさなければ、じぶんたちの過去が変わり、未来もまた変わってしまうことに気づいたのかもしれない。
私がこうして未来からのメッセージに気づき、読解できてしまえたのと同じように。
私がこうしてメッセージに気づき、その気づいた事実を文字にしたため記すことが、ひょっとしたら私のいなくなったあとの世界には、何かを動かす契機となるのかもしれない。
私の先輩たちが私に与えてくれたそのときどきの契機がそうであったのと同じように。
それとも、私が後輩たちからそのときどきで受けてきた反作用の恩恵のように。
分からない。
分からないけれど私はいま、これを記さずにはいられない衝動に衝き動かされている。誰が読むとも知れぬこの文字の羅列に、どんな魔法が掛かるのかも定かではないのにも拘わらず。
私は戸棚から瓶を引っ張りだす。
蓋を開け、スプーンで中身を救い取ると、珈琲豆の香ばしい匂いが鼻先を掠めた。
過去に月から受け取り、とっておいたじぶんの「月下の実」をフィルターによそうと私は、上からすこし冷ましたお湯を注ぐ。
カップに注いで、一口啜る。
未来からのメッセージには私の人生の履歴が最期まで記されていた。
なぜ私たちだけが珈琲豆だったのか。
真相を知る由が私にはないけれど、いまでもそれをとっておき、そうして今この瞬間にその風味を味わえているのは、私の「実」が珈琲豆だったからにほかならない。
ささやかなお礼のつもりなのだろうか。
ありもしない善意を珈琲豆に幻視する。
ブラックホールのように黒い液体を覗きこみながら私は、いまも地球上のどこかに存在し、そしてその後も存在しつづけるだろう人為ブラックホールの珈琲豆のごとき造形を妄想する。
ブラックホールはどんな味がするのだろう。
飲んでみたいな、と私は最後にじぶんの望みを書き記しておく。
4422:【2022/12/19(23:43)*「日の陽」人】
治療する、前より遥かに、歯が痛い。字余り。こんばんはひびさんです。ひびさんはようやく日常が何かを思いだしてきたであります。日常が何かを思いだしてきたのであります。もうね。忘れてた。具体的には今年の二月中旬くらいから日常が何かを忘れてた。でもいまは思いだしてきた。以前の日常を思いだしてきた。じゃあ二月からの十か月くらいは日常じゃなかったのかい、と問われると、日常じゃなかったんよ、とひびさんは、ひびさんは、声を大にして応じたい。日常じゃなかったんよ。夢の中におったんよ。骨を折ったんよ。骨折り損のくたびれ儲けでございました。儲けちゃったんですか。儲けちゃったんです。くたびれだけれども儲けちゃったんです。やったー。でも思えばひびさんはそれ以前の日常とて果たして日常であったのかを振り返ってもみますれば、きょとん、としてしまいますな。果たしてひびさんに日常はあったんですか、と問いかけてみますれば、きょとん、としてしまいますな。日常ってなにー。「日が常」なのか「常に日」なのか、どっちなんだい。「日が常」ってだいたいにおいて何。「常に日」ならまだしも「日が常」って何。思えば「日々」も意味不明。なんなの「日々」って。日と日があって日々って、それってなんだか「点と点の連なりが線で、線の重なりが面」みたいな次元の繰り上がりを幻視してしまいますな。根元を穿り返してもみれば、「日」って何。太陽のことなのだろうか。でもどうして「日」と「陽」があるのか。軽く検索してみたら「日」は幅の広い意味があり、「陽」は太陽の光に限定されるらしい。ひょっとして「日」と「目」が似ているのも何か関係があるのだろうか。「日」に「一」をプラスすると「目」になる。同じく「白」「旦」「月」「臼」も【日】に似ている。何か関係があるのだろうか。ひびさんの母国語は「日本語」ゆえ、日本語の文字を見ると否応なくその文字の持つ意味を幻視してしまう。けれどもひびさんにとっての英語や韓国語や中国語やアラビア語やドイツ語やフランス語などの外国語は、ひびさんにはどれも似たような「図柄」に見える。音符と似たようなものだし、理解できないという意味で古代文字との区別もない。どちらも同じくらい分からない。だから見た目の格好良さで選ぶときっと、意味は「漬物」とか「ゲップ」とか「尾てい骨」みたいなトンチンカンな単語をチョイスしちゃうこともあるはずだ。見た目がかっこうわるいのに格好の良い意味を持つ言葉ってあるのだろうか。やはり母国語に関してはこの視点で文字を見ることができない。むつかしい。認知において、一度覚えた「関連付け」を忘れることのほうが、覚えることよりもむつかしいのではないか、とひびさんは疑問に思うのだ。何かと何かが似ているな、関連しているな、と結びつけることよりも、いちど結びつけたそれを解いて、まっさらな状態に戻る。これはおそらく意識的には行えない。意識して忘れようとすればするほど強化される。忘却にとって最も効果的なのは、そのことについて考えないことなのは言うまでもないのだが、この考えないとは要するに、「ほかのことと関連付けない」「意味を付与しない」ということなのだろうな、とひびさんは閃いて、そっか、となった。こうなるとひびさんは早い。忘却する手法は、「関連付けしないor意味を付与しない」のならば、「いったん関連付けてなお、それ以前の状態を記憶しておいて、どっちの状態も考慮できるようになればよいのでは」と考えると、これがなかなか有用なのだ。言い換えるなら、忘れよう、忘れよう、としても却って記憶が強化されるのならば、強化されるバージョンと強化されないバージョンの二つを同時に適えてしまえばよい。関連付けする以前の状態とて、忘れよう忘れようとしたら記憶が強化されるはずだ。そこを上書き保存にせずに、どっちの状態にもしておく。もっと言えば、一つの事項に多彩な関連付けを施すことで、強化される記憶を一つに限定しないのも有効かもしれない。こうすると記憶が強化されるのにそのオリジナルの原体験は、後付けの解釈――無数の関連付け――によって希釈されることになる。光において色を重ねると透明になっていく、みたいな理屈だ。これが傷を深めるような関連付けばかりをすると深淵のごとく闇に寄っていくのだろう。その闇ですら一つの多彩な色の一つにしてしまえばけっきょくは、関連付けによる記憶の強化を、強化しつつ同時に希釈することも可能になるはずだ。現にこうして思考を費やし、無駄な情報と関連付けることですでに冒頭がどんな話題ではじまったのかを思いだせない。歯の痛みもいつの間にか意識の壇上から消えている。痛み止めを飲んだからじゃないの、との指摘には、そうかもしれぬ、と応じよう。ひびさんは、ひびさんは、毎日うひひの日々なのだ。日常よりも日々なのだ。常に日ではなく、日々なのだ。きのうときょうとでは何かが違うし、場所や時間を移動したらそれだけでも違うのだ。ひびさんはどうしてひびさんなのかしら。ひびさんは別にひびさん違うし、ひびさんのフリしている誰かさんがいるだけなのかもしれないよ。その誰かさんにもやっぱり日々があって、その日々を意識したときにひびさんは、やっほー、とその誰かさんに宿るのだ。あなたが日々を意識するとき、あなたはひびさんなのだ。ひびさんはかつてあなただったかもしれないし、あなたはひびさんだったのかもしれない。そんなことないんじゃないかな、との指摘には、そうかもしれぬ、とおとなしく首肯しておこう。ひびさんは、ひびさんは、素直なだけが取り柄のへそ曲がり、日々に虜のベソばかり。ひびさんは日々さんのことも好きなのに、日々さんはひびさんに塩々のしょっぺしょっぺ対応なので、ひびさんはひびさんは、日々ベソを掻きかき、お絵描きしとるよ。ベソで絵を描いちゃうなんてなんてステキな特技なのかしら。やったー。枯渇しないベソ、温泉のごとく湧き出るベソ、略してデベソのひびさんは、やっぱりへそ曲がりのコンコンチキのぽんぽこりんのポンポコナーの超究明の超スゲーさんなので、じぶんでじぶんを鼓舞して元気だす。でもでもひびさんは超スゲーさんも好きだけれども、細々さんのぽわぽわさんのほっこり時々メソメソさんのことも大好きなので、コツコツさんの黙々さんのほこほこ子羊さんの日々がすこやかであったなら、それがとってもうれしいぶい。歯痛いのどっか行った。ひびさんは物忘れさんが得意なのかもしれぬ。やったー。きょうはいっぱいの「やったー」ができましたので花丸です。うれち、うれち、の日々でした。おわり。
4423:【2022/12/20(00:17)*自己同一性=遅延に破れない情報共有】
意識についてのメモ。人間の意識は非連続的だ。だが肉体というフレームに限定されることで同一性を保持し得る。変遷の経過よりもネットワークの接続による創発が優位に働くためだ。だがこの創発が乱されると自己同一性を失う。睡眠や失神や泥酔や死がそれにあたる。だがそれでも肉体は外部刺激を受けると否応なく感知し得る。眠っていても人は肉体の刺激を感知して目覚める。このとき肉体は自己を自己と見做している。だがそれと意識の同一性はイコールではない。電子端末を初期化する前とした後とでは端末は同じではない。だが電源のON/OFFは双方ともに行える。これと似た話だ。そこのところで言えば、人間とクローンは、同じDNAを保有していても同じ人間とは見做されない。仮に記憶のコピーができたとしても、肉体が異なるならそれは別の個である。ひるがえって、記憶が共有され得るのなら、そこには自己同一性が宿り得ると言える。これは個と群れと組織の違いに関連する。情報の流動性が、いかに連続にちかいか――ラグが蓄積されていないか――断絶していないか。ここが自己同一性を宿すかどうかの分水嶺として機能するように思われる。仮にDNAが別であれ、他者と記憶をスムーズに共有できたとき、それはもはや他人ではなく、分身であり、じぶん自身の一部と感じるだろう。クローンではない。コピーではない。じぶん自身の一部なのだ。長年連れ添った伴侶を失くした者の抱える喪失感は、おそらくこれと同様の原理で生じるのではないかと仮説できる。半身を失ったような、との形容はけして比喩ではないのだ。肉体による自己の限定(フレーム)は、他者との情報共有の遅延がいかに軽減されるのかによって、抵抗を希薄にすることができる。肉体の限定(フレーム)による抵抗(遅延)を打ち消せるくらいに情報共有が滑らかであるとそれは、自己と他の境界があやふやになる。そこに自己同一性が、二重で生じる。じぶんの肉体で一つの自己があり、さらにその外側にも自己が拡張されていく。これは高次の意識と呼んでもいいだろう。人間の思考がなぜ自己を認識し、他を他と見做しながらも、そこに自己を重ねて共感できるのか。メタ認知がなぜ可能なのか。おそらくは情報共有の遅延を軽減する方向に人間が肉体を発達させたからだろう。脳を進化させ、五感を変質させ、さらには言葉や道具といった「外部記憶装置」によって、情報伝達の遅延を打ち消す方向に、個のみならず群れを組織へと進化させた。組織はそれで一つの「自己同一性」を持ち得る。そこには高次の意識が創発によって生じていると見做せるはずだ。ただし、それら高次の意識を担う個々の人格には、それら高次の意識の部分である自覚はないだろうが。白血球や赤血球が、人体の一部であると全体を俯瞰して認識し得ないことと同じレベルの話である。だがそれでも人体は総体で絶えず情報を断片的にやりとりをし、総体としての意識――すなわち自我――を形作っている。情報伝達には遅延が生じる。ここは譲れない原則だ。そのため、仮に個々の記憶をスムーズに共有できる技術が誕生しても、自己同一性を実感できてなお、そこには人体と白血球の関係のような、自覚の対称性の破れが生じるだろう。帰属意識とも通じるが、じぶんが何かの全体の一部であることの認識は持てるものの、その全体のいわば「高次の意識」そのものにはアクセスできない。重なることができない。だが確実に「高次の意識」は別途に生じている。「私」が「私」を認識するのは、あくまで人体にある細胞の総体としての「高次の意識」による認知である。したがって、個々の細胞からすれば、「高次の意識」たる「私」を認識することはできない。だがそれでも「高次の意識」たる「私」は生じている。遅延がその認識の勾配を生みだすのだ。対称性を破るのである。したがって、仮に記憶を他者と共有できるようになっても、その人数が増えれば増えるほどに「高次の意識」と「私」は乖離していき、けして「私たち」という「高次の意識」と同一化することはできないことが予想できる。それでもそこには「高次の意識」たる「私たち」が生じていても不思議ではない。それを個々の「私」が認識することはできないのだ。ただし、記憶を共有する相手が一人や二人くらいならば、遅延が少ない分、自己同一性を実感しやすくなることは否定できない。これがいわば「家族」と呼ばれるものの根本原理と言えるのかも分からない。むろんこれはひびさんの妄想であるので、定かではないが。
4424:【2022/12/20(02:55)*海老で鯛の引き算】
後出しジャンケンのようなものだ、と彼は言った。
彼の言うところによれば人間社会に蔓延する因果関係なる概念は、ことほどに重宝されるような代物ではなく、後出しジャンケンの追いかけっこを飽きもせず繰り返す子どもを想定するような無茶苦茶な理論なのだという。
「だって考えてもみろよ。すべてが因果で片づくなら俺が生まれたのにも何か因果があるってことか。親父の数億匹の精子が母ちゃんの卵子に受精したのにも何か明確な因があったとでも言うのかよ。親父と母ちゃんがセックスしたってのは因となるかもしんねぇけど、親父が射精するタイミングが一秒でも狂ってたらたぶん俺じゃない精子が母ちゃんの卵子に一着でゴールしてたはずだぜ。それとて親父や母ちゃんが前日に何を食べただとか、親父が射精したときの腰の角度だとか、射精したあとの母ちゃんの寝返りを打つタイミングだとか、もうもうどれが因果における因なのか分かったもんじゃねぇじゃんよ」
「それのどこが後出しジャンケンと繋がんの」私は壁にスプレーでタグを描く。「ああもう、ちょっと明かりズレてる。手元照らしててってば。あと周りも見張っててよちゃんと」
「ピース描くんじゃねぇのかよ」
「きょうは場所取りだけ。ここがわたしのカンバスだって印つけとく」
「ああ。陣取りね」
「ゲームと一緒にすんな」
私は彼の名も知らない。先日、グラフィティをしているときに声を掛けれて話しただけの仲だ。夜中だったから顔も碌に見えなかったし、いまもお互いに顔はぼんやりとしか見えていない。マスクをしているのでどの道、表情は分からないから同じことだ。
「そうそうゲームと同じなんだよ」彼は私の発言を面白がった。それが先日のときもそうだった。何が面白いのかは分からないし、私としては小馬鹿にされているように感じて腹に溜まるものがある。だが見張りは欲しい。世間の違法行為への目は冷たくなっていく一方だ。グラフィティとて器物損壊の疑いで即座に通報される。オチオチ外でお絵描きもできない時代なのだ。違法行為をしている私がわるいのは百も承知だが、一言もなく通報されると、警告なしで銃で撃たれた気分にもなる。誰かにこの手の愚痴を言っても、おまえがわるい、と一蹴されるだけなのだが。
私の内心の独白など知りもせずに、名も知らぬ彼は、「絵もさ。引き算ができたら面白いよな」と独り言ちている。「過程がそれで一つの芸術なんだよ。戦術だってそうだろ。将棋だってそうだ。勝ち負けは結果だが、そこに至る過程が肝ってことが往々にしてある。絵だって同じだよ。それができあがっていく過程。だからグラフィティも、文化としてここまで育ったんじゃねぇのかな」
「さあてね。どうだか」
「とはいえ、完成しちまったらそれで終わりってのも寂しいよな。できれば引き算をしたいよ俺なんかはさ」
「引き算って小学校にでも行けば?」
「因果には足りないもんがある。因果論には引き算が足りない」
「またこの人変なこと言ってる」
「変なことを言ったほうが人生有意義だろうがよ。グラフィティだってそうだろうが。変な絵を描いてこそじぶんはここにいるって示せるんじゃねぇの」
「じぶんらしく描いた結果に変になることもある。そういう話だと思うけどね私は。はいもういいよ。帰ろ」
タグだけならば時間はかからない。場所指定のために四隅と真ん中、合計で五つ描いたのですこし手間取った。
退散すべく歩き去ろうとしたが、彼がその場を動かなかった。
「置いていくよ」
「これ、ピースの上に描いてるけどいいのか。ルールがあるんだろ。より上手な絵の上にはヘボい絵を描いたらダメだってルール。漫画で読んだばっかしだ」
「そうだね。一応はそういう流れはあるけど、私のピースのほうが上手いからいいんだ。タグを見ただけでも相手は気づく。これからじぶんが上書きされるんだってタグを見て知るし、そのタグが誰のもので、どういう力量なのかもタグ一つで判るもんなの」
「ふうん。ならたとえばこの絵にはいま、おまえさんのタグが上書きされたわけだろ。そしてそれはこの絵の描き手よりも上手いおまえさんのタグによってこれから生まれ変わるわけだ」
「全部塗りつぶすよ。その絵の要素は何も残らん」
「でもいまは残ってる。ならこの絵はいま、おまえさんのタグの魅力を宿してるってことになるな」
「何言ってんの。私はこの絵を否定したんだ。私んほうが上手いって誇示したの」
「でもそれによってこの絵はむしろ前よりも価値が高くなったとも言えるんじゃないのか。だってそうだろ。もしここにパンクシーの絵が上書きされていたら、それはそれは物凄い貨幣価値がつくんじゃないのか。それがピカソでもゴッホでも同じだよな」
「それはそうかもしれないけど」
「おまえさんのタグにそこまでの価値がないかどうかはこの際、関係ない。事象としては構図が同じだ。タグってのは要はサインだろ。書き手の名前の簡略化した独自のサインだ。そこで俺は思うわけよ。価値の上がったこの絵を高く評価したやつが出てきたときに、もしタグだけひょいと引き算できたら、そいつは元のなんの値打ちもないただの落書きを、価値あるものとして評価したことになる。このとき、高く評価したのは絵なのか、名のある書き手のサインなのか。それともサインの描かれた何の変哲もない絵なのか。金粉のかかったハンバーグはおそらく金粉分の値段が加算されるが、しかし金粉があってもなくともハンバーガーの美味さはさほどにも変わらん。このとき、俺は思うんだよ。因果における因がどこにあり、それを因果が決定されたあとに引き算したらどうなるんだろうってな」
「単に価値がなくなるだけじゃんそんなの」
「そう思うか。そっか、そうだよな。ただ金粉の比喩は、後出しジャンケンと繋がってるんだよ。グーを出したらパーを出し、パーを出されたらチョキをだす。そうして後出しで、必ず勝つ立場に居座りつづけるやつってのもいるところにはいるもんだ。だが俺はそういうやからに対して、因果の引き算ってやつをしてやりたい。グーを出したところでパーを出され、チョキに変えたところでグーに変えられる。必ず負けると決まった後出しジャンケンで、俺は勝敗の決まったあとでこっそり、グーのあとでチョキに変えたことを引き算して、グーのままにしておいたことにする。すると相手はかってにグーに変えてこの勝負は引き分けだ。もし相手が後出しジャンケンを三回つづけていたら、俺がグーのままでいることで、相手はチョキに変えて自滅する。因果が決定されたあとに引き算できれば、こういう喜劇が可能になる」
「過去を変えれたら楽だよねって話?」男の子はすーぐこうやって賢こぶってマウントとってくるから相手するの疲れる。でもいまは、この手の「男の子は」って言い分も冷めた目でみられるので世知辛い。
「過去を変えなくとも立場を変えることはできるって話をしたかったんだけど、じゃあそれでいいよ。過去を変えたら楽になる。でも後出しジャンケンの場合は、相手が後出しジャンケンをしてくると判っていたら、相手の行動を誘導することもできるってことを俺は言いたかったのかもしれねぇな」
「どういうこっちゃ」
「絶対に相手が【勝つ手】に変えてくると前以って分かっていたのなら、つぎに相手が何を出すのかも俺には判るってことだ。もし俺に仲間がいたら、そいつに俺の出す手を教えることで、絶対に【後出しジャンケンに勝てる方法】が誕生する。まあこれは比喩だから、実際に三人でジャンケンをしたらこの考えは成り立たないけどな」
「ダメじゃん。成り立たないなら役立たずじゃん。真面目に聞いて損した」
「そうとも言いきれねぇぞ。仮にこれがルール無用の勝負の舞台なら、これ以上ない必勝法になり得るんだからな。相手が後出しっつうズルをすることを見越して、相手の行動選択を誘導する。この手の戦略は、グラフィティにも応用できるんじゃねぇのかな」
「どうやって」
「そうだな。たとえば俺がこの下手な絵の描き手だったなら」彼は端末の明かりで壁を照らした。そこには私が描いたばかりのタグと、ほかの描き手(ライター)のピースが描かれている。素人の彼に虚仮卸される筋合いはないはずだし、この描き手(ライター)は割と上手いほうだ。「俺ならわざと下手に絵を描いて、おまえさんのような腕の立つ描き手を誘い込む。んで、こうしてタグで縄張りを主張させたあとで、撥水性の高いニスかなんかを塗っておく。しかも部分的にだ。したら上から別の絵を描かれても、水で流せばそれを消せる。のみならず、指定した部分に相手の絵が残るようにもしておける。するとどうだ。相手は俺の下手な絵を塗りつぶしたと思いこんでそのじつ、【俺の絵に華を添えるワンピース】に成り下がったことになる。画竜点睛を地で【描かせる】ことが、俺の手法を用いればできるわけだ」
「まあ、言ってることは解るけど」
道の向こうに人影が見えた。二人いる。警察かもしれない。
私は壁から離れるようにずんずんと歩いた。彼は顎の下から懐中電灯の明かりを浴びながら、やってみねぇか、と言った。
「後出しジャンケン必勝法。俺とあんたでやってみねぇか」
「わざと下手なピース描いて、玄人を誘い出すってこと?」
「んで以って、ソイツのピースを飾りにしちまうんだ。あんたの本物のピースの一部にしちまうんだ。面白いと思わないか」
「私は別に」
正直なところ、面白そうだった。
出し抜くって感覚は、単純な絵のオリジナリティにおいては快感だ。そのためにグラフィティを生業にしているところがある。すくなくとも私はそうだった。
「それって要は、海老で鯛を釣るってこと」私は以前公園で出会ったラッパーたちのサイファーを思いだした。即興で繰り広げられるライムの殴り合いのなかに、海老で鯛を釣る気か、のパンチラインがあった。――海老で鯛を釣る気か、ケチで愛を振る気か棒で、それはないで来る奇禍秒で――。
「海老が何だって」彼には諺が通じないようだった。ラッパーに向いていない。
「おまえ教養ないのな」
「無知の知を自覚してるやつなら、無知を蔑む心こそが無教養だって分かるはずだと俺は思うが、どうしてだか世の中、じぶんの無知を差し置いて他人の無知にばかり厳しいやつがいるよな。どっかの教養あるお方は別だろうがよ」
前言撤回だ。
コイツにはラッパーの素質がある。即レスでこの煽りはふつう出ない。
「反論が強火すぎんだろ」ひとまず応酬を図るが、倍返しされても困るので、脈絡を彼の話題に戻した。「要は罠を張るってことだろ。で、新しい手法で新しいピースをカマす。いいよ面白そう。手伝ってくれんならやる」
「中途半端なやつをカモにしてもおもしくねぇからよ、この辺でいっちゃん顔でかいやつの面子をあんたの絵のお飾りにしちゃおうぜ。ワンピースにしちゃおうぜ。んで以ってついでにその隣でピースしちゃおうぜ」
ラッパーの素質があると言ったな。訂正しよう。コイツはすでにラッパーだ。
「おまえワルイやつだな」私はにこにこした。
「器物破損行為に精を出す誰かさんほどじゃねぇよ」
「褒めるなよ」
「褒めてねぇよ」
「番号、連絡先。私の言うから登録しといて」
「持ってきてねぇよ。捕まるかもと思って置いてきた」
「あはは。ビビりすぎ。ダセぇ」
「俺、記憶力わりぃからよ。番号何かにメモしてぇな」
「なんもないよ」言ってから私は、閃いた。「あ、待って。あんたその服お気に?」
「汚れると思って一番古いの着てきた」
「ダセぇ」私は笑った。彼が機嫌を損ねた様子はない。「んじゃその服に書くから、手で持ってて」
Tシャツの裾を引っ張らせて、私はそこに私の連絡先をスプレーで描いた。数字だけのタグを線で引くのは初めてだった。
「おー。一気にオシャレ着になった。サインみてぇ」
「よく見なきゃ分かんないっしょ。個人情報漏洩防止」私はキャップの鍔をくいと下ろした。
コンビニの明かりが道の先に見えた。
「寄ってく」と訊いたが、彼は、「俺こっちだから」と言ってさっさと路地裏に逃れた。
私はコンビニで肉まんとホットココアを買った。歩きながら肉まんを頬張り、彼との会話を振り返った。
後出しジャンケン必勝法。
海老で鯛を釣る画法。
因果論の引き算。
私は彼の顔も名前も未だに知らない。ひょっとしたらすでに私は彼と大昔から出会っていて、顔も名前も彼のことならなんでも知っているはずなのに、彼に引き算されただけなのではないか。
想像すると陽気が喉まで込みあげたが、肉まんが喉に詰まって咳き込んだ。陽気はいずこへと飛んでった。
「引き算じゃん」
プラスと思ったらマイナスで。
マイナスと思ったらプラスになる。
そういう魔法を仕掛けるのだと、私の記憶に霞む彼の声が、影が、輪郭が、懐中電灯の明かりの奥にくすぶっている。
手のひらがホットココアの熱を吸い取る。
一息に煽ると、甘さとコクと苦みの調和が喉の奥に染みこんだ。
飲み干した缶を振ると、カラカラとありもしないスプレー缶の音がした。足元にはじぶんの影が浮かぶ。私は試しにじぶんの影とジャンケンをする。
4425:【2022/12/20(10:44)*膨張する時空は希薄化するの?】
宇宙膨張についての疑問です。銀河などの物質が密集している地点の時空膨張の影響は、そのほかの物質(エネルギィ)密度の低い地点での時空膨張の影響よりも小さい、とする考えが仮に正しかったとして(2022年現在はそのように考えられているようですが)、それはたとえば海底の水圧の高い場所から海上へと浮上するときに働く相対的な「斥力」のような力が生じると言えるのではないのでしょうか。つまり海底では水圧が高くかかっていますから、外側に膨らもうとする力が抑制されます。しかし海上に浮上するにつれて圧力は減るため、物体を縛っていた力が減少し、あべこべに相対的な斥力が働くと言えるのではないのでしょうか。伸縮自在の球体があったとすれば海底では圧しつぶされていた球体が、海上では元の大きさに「倍以上にも膨らむ」ことがあり得ると考えます。これは宇宙膨張における「銀河などの密度の高い時空」と「ボイドなどの密度の低い時空」の関係でも言えることなのではないのでしょうか。宇宙が膨張すると、銀河と銀河のあいだは離れていきます。そこは「真空」のような何もない時空がさらに希薄化されていくのではないのでしょうか。だとしたら銀河の周辺には相対的な希薄な時空が展開されることになります。ラグ理論では、高重力体の周囲の時間の流れは遅くなる、と解釈しますので、相対的に高密度になった銀河の周囲の「希薄になった時空」の時間の流れは遅くなります。つまりここには遅延の層が生じるのではないか、と妄想できます。その遅延の層によって、相対的に生じる斥力が打ち消される方向にいまは均衡が保たれて観測されているのかもしれません。ですがそれ以上に希薄になると、シュバルツシルト半径のような閾値を超えて、銀河ですら相対的にブラックホール化することはあり得るように感じます。宇宙膨張において時空が膨張する、と言ったとき、その膨張の仕方の解釈はどのような描写を想定されているのかもよく解かりません。新たに時空が生成されているのか、それとも時空が引き延ばされて希薄化しているのか。後者ならば、銀河などの物質のある領域は相対的に密度が高まっていきますから、やはりいずれかは光速度不変の比率が破れて、ブラックホール化することもあり得るように感じます。相対論のキモはむしろ、密度という概念が相対的であることのほうが案外に重要な気がしますが、どうなのでしょう。すべてが一様に高密度であることよりも、内と外での密度の差が高いことのほうが、おそらく物理法則では重要な基礎単位になる気がします。慣性系ではどの系でも同じように物理法則が働く――つまり比率が引き継がれる――のであれば、慣性系同士の境界において互いの差が激しいほど、比率変換の際に生じるラグが大きくなります(仮にこの描写を可視化するならば、二つの系の落差が大きいほど境界にて膨大な量の「数式」が層を成すところを想像すれば分かりやすいかもしれません)。これはブラックホールにおける事象の地平面と似たような性質を顕現させることもあるでしょうし、本質的に事象の地平面はこのような「系と系」とのあいだの差異――落差――による、比率変換の遅延が要因になっているのかもしれません。だとすればやはり、宇宙膨張において仮に時空が希薄化する方向に宇宙が膨張しているのなら、単なる銀河とてブラックホールになり得るのではないでしょうか。もしそうでない場合、それは、宇宙膨張が新たな時空を展開し、つねに均一な時空を「無」から生みだしていることになります。これはいわゆる時空の最小単位が存在するか否かの問題にも通じます。均一な時空が無から続々と生じているのならば、時空には最小の単位が存在するでしょう。しかしもし銀河とて宇宙膨張による時空の希薄化でブラックホール化し得るのなら、時空に最小単位はあってないようなものと言えるはずです。なぜなら時空がどこまでも希薄化するときの描写は、「時空が細胞分裂のように増殖していくような描写」ではなく、「同じ細胞の数だけれど、その細胞の内部構造がさらに細分化されていく――つまり膨張と縮小が同時に起こっている――との描写」になるからです。もちろん風船を膨らませたように一様に希薄化して限界がきたら破けてしまうような描写も考えられますが、この破れるという発想はあくまで内と外が存在する場合の描写になるため、時空が破れることと新たな時空の生成は地続きであると言えるでしょう。つまり時空が破れるとの発想は、一元的な見方による錯誤と考えたほうが妥当に思います。紙を破るとき、それは紙と紙のあいだに空気が割り込んでいると解釈できます。別の時空――系――が生じているのであり、俯瞰してみればどちらにも時空が存在します。言い換えるならば「破れる」とは、異なる二つが隣り合う、もしくは混合する、といった描写を、一方からの視点で見たときの形容となるのでしょう。その点から言えば、宇宙膨張における膨脹した時空は、網を引き延ばしたようになっているのか、それとも引き延ばすごとに新たに網目の穴が細かく開いて(増えて)いるのか、それともサメの歯のように破れた矢先から別の時空が顔を覗かせているのか。どれなのだろう、と疑問に思います。単なる疑問ですので、ひびさんには答えが分かりません。これが正しい知識の基での疑問なのかも判断つきませんし、筋道が滑らかに通っているのかも分かりません。どこかしらに齟齬があるでしょう。誤解を深めてしまったら申し訳ありません。ひびさんの不徳の致すところです。本日目覚めの「日々記。」でした。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4426:【2022/12/20(16:41)*珈琲の恩返し】
先輩が珈琲好きで大変だった。何が大変かと言うと、珈琲と名の付くものなら何でも片っ端から集める珈琲マニアが講じて、あろうことか珈琲という名の人物に執着してしまったのである。
「後輩ちゃんこの人知ってる? 珈琲って名前の漫画家さんなの。ウケるよね」
「は、はぁ」
「作品は全然珈琲とは関係ないけど可愛くて面白くて胸が熱くなるしキュンキュンするでしょ。それでいてなんと言っても作家さんの名前が珈琲ってのがいいよね」
「そ、そうですかね。先輩がそれでうれしくなれるのなら作家さんも珈琲を名乗った甲斐があったでしょうね」
「しかも見て。新刊のこの表紙。かっくいいよね。キャラがこれぞってポーズ決めてるんだけど、あまりにカッコいいから真似してみたんだよ。でも全然これができんのよ。笑っちゃったね、我ながらアホだなぁって思ってさ」
「だってこの表紙の人、片手で身体支えてますよ。超人ですよ。先輩が真似できるわけないじゃないですか」
「出来そうな気がして」
「でも出来なかったんですね」
「惜しかったんだよ」
「腕……包帯してますけど大丈夫ですか」
「危うく骨イキそうになったよね」
「大怪我寸前じゃないですか。もうやめましょうよそういう危ないこと。作家さんだっていらない怪我されたら無意味に呵責の念を覚えちゃうじゃないですか。先輩がアホウなだけなのに、読者さんを怪我させちゃったと思って精神病んじゃうじゃないですか。先輩がアホウなだけなのに」
「アホウアホウ連呼されてわしは悲しい」
「先輩がそこまでお勧めされるからにはきっと面白い漫画なんでしょうね。私も読んでみたいです」
「いいよいいよ、貸しちゃうよ。保存用と観賞用と布教用と配布用があるから後輩ちゃんには配布用のをタダであげちゃう」
「私前から気になってたんですけど先輩のその無駄な財力ってどこから湧いてるんですか」
「あれ言ってなかったっけ。わし、珈琲の銘柄の株全部持ってて、んでいまほら珈琲って品薄で価格高騰してるでしょ。元から儲けてたんだけど、いまバブルですごいことなってんの。珈琲さまさまだよね本当大好き」
4427:【2022/12/21(03:20)*黒魔術の粋】
後輩に珈琲メーカーを買ってくるように命じたらなぜか黒猫を拾ってきた。
「どうしたのそのコ」
「捨て猫らしいんですけどね」後輩は格闘技同好会で鍛えあげた腕で、綿のように黒猫を抱えている。「珈琲メーカーにちょうどいいと思いまして」
「ごめんルイ君のボケ分かりにくくて上手に突っこめなかった。もっかい言って」
「いえですから珈琲メーカーにちょうどよいと思いまして」
「あ、ごめん。やっぱ私には難度が高かったなそのボケ。上手に拾えなくてごめんよ」
「ボケじゃないんですが」
後輩は腕の中の黒猫に頬づりをする。
私は私よりも屈強な後輩が私を慕うのがうれしくて彼を猫かわいがりしているが、たまに飛び出る彼の突拍子のない発言には毎度のことながら当惑する。後輩は私の美貌にひれ伏している節がある。メロメロというやつだ。可愛いやつめ、とは思うのの、お使いくらいは満足にこなしてほしい。「それはどう見ても珈琲メーカーではないね。黒猫さんだね。私が所望したのは珈琲がしたたり落ちてくる便利な機械だよ」
「でも珈琲が飲めたらそれでよくないですか」
「そこできょとんとされてもな」私は彼の大物っぷりに思わず仰け反った。珈琲がなければ黒猫を吸えばいいじゃないか、とでも言いたげな表情だ。どこの国の貴族だ。いや、どこの国の貴族でも珈琲の代わりに猫を吸うことはない。珈琲とは無関係に猫はいつでも吸っていいし、別に猫は珈琲の代わりにはならない。
「で、その猫はどうするつもりなの。ここに持ってこられても飼えないよ」私は部室を見回した。大学の黒魔術研究会の部室は、数ある部活動の中でも抜きんでて地位が低く、部室とは名ばかりの物置き部屋が私たちにあてがわれた。皮肉にも種々相な雑貨に囲まれている年中薄暗い部屋は、黒魔術愛好会にぴったりの雰囲気を醸し出している。「部費もあってないようなものだし、申し訳ないけど飼い主を探してあげて、お別れすることになると思うよ」
「でもこのコがいたら珈琲飲めますよ」
「それまだ続けるの」ボケを引っ張りすぎである。「真面目な顔でおっちょこちょいなこと言うのキミ得意よね。嫌いじゃないよ。でもさすがに黒猫さんから珈琲は」
出ていた。
目のまえでまさに後輩が黒猫さんの尻尾を握って、カップに珈琲を注いでいた。黒猫さんの尻尾の先端があたかもホースのように褐色の液体を吐きだしており、湯気の立ち昇るそれからは珈琲の香りがほとばしっていた。
「ど、ど、どうなってんのそれ。手品?」
「先輩のほうこそボケとかじゃないんですか」彼は黒猫さんの尻尾を水切りすると、お礼をするように黒猫さんの顎を撫でた。「黒猫からは珈琲が摂れるんですよ。低級魔術の一つです。てっきり僕、ご存じかとばかり」
「ま、ま、魔術?」
「はい。先輩もたぶんすぐに使えますよ。何せあのブルーデーモンを召喚したくらいなんですから」
「ぶ、ぶるーでーもん?」
「やだなあ先輩。そんな謙遜しちゃって」
私は首を振った。赤べこもかくやという振りっぷりである。
「魔術界隈じゃ先輩の【緑の指事件】は有名ですよ。誰があんな大それた真似をしたんだって、魔術協会も犯人を捜しまわっていて。僕が偶然に先輩を見つけて証拠を消していなかったらいまごろ先輩は収容所に閉じ込められてましたよ」
「ぽかーん」
「あ、先輩がぽかーんってしてる。そのお顔はレアですね。写真撮るのでしばしそのままで。はいどうもありがとうございます」
「待って。消して。間抜けな顔してたからイマスグそれ消して」
「嫌ですけど」
「私がジャンプしても届かないところに上げないで。じぶん背ぇ高いからってズルはナシだよ」
「先輩のすぐムキになるところ僕好きです」
「て、照れさすなよ」
「照れてる先輩も好きですよ。猛獣が毬にじゃれついてるみたいで、僕だけが知ってる先輩の側面みたいで優越感が湧きます」
「誰への優越感かな」
「先輩のことを血眼になって探し回っている魔界の住人たちへのです」
「もうそのボケ禁止。禁止します。意味分かんない、さっきの黒猫さんの手品についてお話ししよ。珈琲だってルイ君、じぶんの分しか淹れてないし」
「わ、失礼しました」
後輩はそこで口元に運んでいたカップを置いた。彼が腕を上下させるだけでも彼の腕には血管が浮かぶ。その陰影を私は古代ローマの彫刻のように撫でつけたい衝動に駆られる。
一度は足元に逃がした黒猫を拾いあげると後輩はすでに披露した手品を再現した。つまり黒猫さんの尻尾からカップに珈琲を滴らせたのだ。
私はテーブルに齧りつくようにしてマジマジと観察した。
「尻尾にチューブが通っているとしか思えないんだけどな」そういう手品があるのは知っていた。手術でじぶんの腕にチューブを通しておけば、何もないところからあたかも魔法のように火や水を出すことができる。
「そんなひどいことを僕が猫にすると思うんですか」
「でもじゃあ、これは何」現に珈琲が黒猫さんの尻尾から出ている。
「魔術ですってば。先輩もしつこいですね。そのボケ、結構失礼ですよ。なんだか僕の魔力が低いことを虚仮にされているみたいで」
「ご、ごめん」叱られてしまった。
「先輩だったら珈琲と言わず、猫から無尽蔵にダイヤモンドとか金とかを取りだすくらいできそうですけどね。猫はあくまで魔力源と繋がるための媒介でしかないわけですから」
「設定が徹底してるね。感心するけどそろそろネタばらししてみよっか。きみの先輩は今、盛大に混乱しておるよ」
後輩はじろりと私を見た。そんなに鋭くも熱烈な眼差しを注がれた経験がない私は大いに恥じらった。
「熱があるんですか。顔が赤いですけど大丈夫ですか」
「だ、だいじょうぶい」
取り乱しすぎて無駄に、ぶい、って言っちゃった。
「先輩が【緑の指事件】を起こしたこと。僕だけの胸に仕舞っておきますね」
「私はルイ君が魔法を使えているかもしれない事実を黙っていられる自信がないな。うん、ないな。今すぐにでも誰かにしゃべりたい」
「また先輩はそんないじわるを言って。先輩は僕に冷たいですよね。この同好会に入ってからだってまともに魔術を見せてくれないですし」
「だって魔術なんて使えないからね」
「そうやってすぐにはぐらかすんですもんね。一度だけでしたよ先輩が僕に魔術を見せてくださったのは」
「え、いつよそれ?」身に覚えがなさすぎる。
「ほら、あのときです。文化祭のときに惚れ薬を作ったじゃないですか」
「惚れ薬って建前のただのチョコレートね」
「あれほど効果の高い惚れ薬、魔界でもなかなか作れる人いないですよ」
「本物だったら私がまず欲しいくらいだよ惚れ薬」
「あれ食べた人、みんな先輩のこと好きになっちゃいますからね。市場に流通させるだけで先輩、一年と経たずに世界征服ができちゃいますよ」
「効果がヤバすぎる」
「だからあのあとみんな先輩のことを巡って陰で争奪戦が繰り広げられ、結果、いま構内は一触即発の戦国時代らしいですよ」
「私の知らんところで時代を開くな時代を」
「死者数名だそうです」
「死んで詫びなきゃダメじゃないかなそれ。私、死んで詫びなきゃダメじゃないかな」
「でも先輩なら魔法で時間を巻き戻したり、死者を蘇生したり簡単にできるから安心ですね」
「お猫さんの尾から珈琲がチョロチョロー現象がなければルイ君の妄想で片付けられたのに無駄に激ツヨの説得力をどうもありがとう」
「できますよね?」
「圧掛けないでよ、できないよ、魔法? そんなの産まれてこの方馴染みないし、私が好きなのは黒魔術!」
「やだなぁ先輩。黒魔術って邪道な魔法のことですよ。魔法の中でもとびきりに特別な魔法のことです。禁術ですよ。魔法と魔術の両方を兼ね備えた禁術です。先輩がそれを知らないわけないじゃないですか。きょうも先輩のボケはキレッキレですね」
ボケてない!
叫びたかったが我慢した。
喉が渇いていて、私は珈琲を飲み干した。
するとすかさず後輩がお代わりを淹れてくれたが、そこで私はぎょっとした。さっきよりも黒猫さんが小さくなって見えたからだ。
「ねぇそのコ――縮んでない?」
「それはそうですよ。使ったら減ります」
「え、じゃあずっと珈琲を最後まで絞ったらどうなるの。消えちゃったりするんじゃないそのコ」
「ええ」何か不都合でも、と言いたげな眼差しが私を射抜いた。
目がハートになっとるぞコイツ。
私の美貌にメロメロなのではないか、との疑惑をまんざらでもなく優越感に浸りながら抱いていた私はそこで、彼がいったいいつから私に熱いまなざしを寄越すようになったのかを逆算したところ、どうやら学園祭のときにまで遡ることが判明した。
チョコレートである。
惚れ薬のテイで作ったチョコレートを私は後輩に食べさせた。
味見をさせたわけだが、あのときからか。合点がいった。
惚れ薬の作り方は魔導書に書かれていた。それを参考にしたわけだが、よもや本物の魔導書だったわけではあるまいな。後輩の破天荒な発言に翻弄されっぱなしの私であるが、さすがに隅から隅まで後輩の話を信じることはできない。
「仮に私が本当に魔法を使えたとして」
「はい」
「あなたの言ってた【緑の指事件】も私が?」
「いまさらですね。言い逃れはできませんよ。僕はあなたの魔力を辿ってここまで来たんですから。【緑の指事件】は先輩が引き起こしたんです」
「その事件って何がどうなったの。誰かが傷ついた?」
死者はいるの。
いないでくれ、と私は念じた。
「死者どころの話じゃないですよ。あの世とこの世が繋がって、それはもう生者も死者も同じ存在になっちゃったんですから。ご存じない?」
「わ、わかんない」知らない、知らない、と私はじぶんの肩を抱く。
「古の黒魔術者たちまで蘇って、それはもう魔界はてんてこまいの騒ぎでしたよ。いまもまだ尾を引いています。先輩のせいです」
「ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたらそれ許される? あ、土下座して回ろっか?」
「先輩。土下座に効力が生じるのはそれをしても可愛い赤ちゃんだけですよ。猫の土下座姿も可愛いですが」
お猫さんのは土下座ではなく、香箱座りと呼ぶのだ。
そうと指摘する場面でもなかったので呑みこんだ。私は後輩に手を伸ばし、黒猫さんを受け取った。これ以上このコを縮めるわけにはいかない。「何がどこまで本当かは分からないけれど、君は誤解をしているね。私はただの人間だし、魔法が実在するなんて知らなかった。ましてやじぶんが使えることなんて知らなかった」
「信じません」
「いやいや本当だって。現にいま私、めちゃくちゃ困ってるのに何もできない。魔法使えるならひょひょいのひょいで解決したいくらいなのに」
言いながら指を振ると、宙に金粉が舞った。
舞ったように、私の目には映った。
「何……いまの」
「使えるじゃないですか先輩。魔法」
鱗粉の軌跡を追うように私は指で宙に八の字を描く。
「あ、それダメなやつ」
身を乗りだすように彼が引き留める。
押し倒されそうになりながら私は、片手で抱き上げていた黒猫さんがメキメキ音を立てて重さを増していく様子を、身体全体で感じた。
雑貨に囲まれた空間には珈琲の香りが満ちていたが、雑貨ごとその匂いを蹴散らすように部室に黒猫さんのやわらかな感触が広がっていく。
巨大化していく黒い毛玉は間もなく私をふんわりと毛で包みこみながら、部室の壁を打ち壊し、部室棟からも食みだした。
巨大化した黒猫さんの肩に私はかろうじてしがみつく。
肩までよじ登ると、顔山間に夕日が沈みつつあった。
後輩の姿を目で探したが、巨大化した黒猫さんの足元にいるようだった。瓦礫に潰されずに済んだようで私は胸を撫でおろす。
「さて、これをどうするか」
背後でうねる大蛇のごとき尾を眺め、私は、私に夢中だという大学構内の有象無象を連想する。
足りるだろうか。
この怪獣さながらに巨大化した黒猫さんを縮めるには、大量のカップがいるし、大量の喉を乾かした珈琲好きがいる。
騒動を聞きつけたのか、人がわらわらと集まってくる。しかし一定以上には近づかない。それはそうだ。校舎が半壊しかけているし、何より黒猫さんがデカすぎる。
私はみなに珈琲を振る舞う算段をつけながら、なんと説明したものか、と頭を抱える。こういうときこそ魔法の出番のはずなのだが、怖くてとうてい使えそうにない。
「先輩さすがです」後輩が黄色い声を放っている。「先輩の底なしの無鉄砲さ、僕、好きです」とメロメロになる場面でもないのに瞳からハートを飛ばしている。シャボン玉のように私のところまで届いている。屋根まで届いてもまだ消えない。
巨大な黒猫さんがくしゃみをすると、半壊だった部室棟が全壊した。死者がいないことを祈るが、望み薄かもしれない。
時間……巻き戻んないかな。
「先輩、さすがです。大好きです」後輩がまだ黄色い声を放っている。
私は心に誓う。
彼には二度とチョコレートを食べさせまい。そして魔界とやらに帰ってもらおう。
私に黒魔術の粋を根こそぎ伝授させてから。
4428:【2022/12/21(03:34)*乾電池いっぱい使ってるかも……】
家庭から出る乾電池のリサイクル率は2~3割と低いらしい。ネットで検索して数個の記事を流し読みしただけの浅知恵だけれども、五割もいかないのはそうなのだろうな、と感じる。乾電池に限らないけれど、これからは資源が貴重になっていく(すでになっているとの指摘はごもっともです)。他国の資源に頼るのは諸刃だ(頼れるなら頼るのもよいと思います)。貿易は基本、航路と海路があり、どちらもエネルギィをたくさん使う。その点、一度得た資源を一つの土地でリサイクルするだけなら、それはエネルギィ問題と資源問題の双方向で、時間稼ぎができるようになるはずだ。リサイクルだけでは根本的な解決にはならない。二毛作と同じ問題を抱えるからだ。リサイクルはすればするほど資源をやせ衰えさせていく。ずっとは使いつづけることができない。だからリサイクル以外でも絶えずエネルギィや資源を外部から補充する必要がある。しかしリサイクル率を低コストで高められるのなら、その補充サイクルの期間を引き延ばせることができる。時間稼ぎができる。技術も同時に進歩させることができるし、一石二鳥の案に思えるのだけれど、支援はされているのかな、と疑問に思いました。リサイクルはこれからは国策として欠かせない要素になるとひびさんは妄想して、本日のおはよ代わりの「日々記。」とさせてください。(とっくにリサイクルは国策になっとるよ、ブームになっとるよ、との声には、ブームで終わらせんといて、と青目を剥いておく)(青目ってなに?)(カラコンした目のこと)(カラコン外すだけのことを諺っぽく言うな)(うひひ)
4429:【2022/12/21(09:21)*口の亥は盲信】
書いた小説が変だと言われた。散々に酷評されたが私は私の感じたままを言葉にしたまでだ。仮にそれで私の紡いだ小説が変なのならば、私の感じたままの世界が変なのだ。
ゴッホは死期の直前にじぶんの耳を削ぎ落としたという。それをしてゴッホが狂ったのだとする記事を読むが、私にはなぜゴッホが耳を削ぎ落としたのかの理由が分かる気がする。
ゴッホはきっと確かめたかったのだ。
本当にじぶんの絵がおかしいのかと。
きちんとじぶんの耳と対峙しようとしたのだろう。鏡越しではなく。生のままの耳をじぶんの目でしかと見詰めようとしたのだろう。
だから耳を切り落としたのだ。
そして思ったに違いない。
なんだ、私の目に狂いはなかったのだ、と。
おかしいのは鏡ではない。
おかしいのは私の絵ではない。
みなが言うように私自身の世界を捉える知覚がみなとは乖離しており、歪んでいる。ならばそれこそが本当だ。
おかしくてよいのだ。
おかしくてよいのだ。
それでよかったのだ、とゴッホはきっと納得した。耳を落としたじぶんの姿を絵に残し、そして孤独を深めて去ったのだ。乖離していることに気づいた彼は、あるべき場所を求めて旅立った。
溝を埋めるのではなく、安易にじぶんの居場所を求めてしまった。
いいや、それを安易と呼ぶには彼の孤独は深かった。葛藤が、欲求が、乖離が、矛盾が、彼の内面世界に苦痛を産んだのだ。
そして彼は膿んだのだ。
いまの私がそうであるのと同じように。
さいわいなことに私はゴッホではなく、また死して名を遺すこともないだろう。遺したいとも思わない。乖離している事実に気づけた時点で、あとはいかにその溝を使ってじぶんだけの余白に思いのままの絵を描くか。
ただそれがあるのみだ。
溝は無尽蔵に湧く私だけの絵の具だ。尽きることがない。
他者との溝が深ければ深いほど、滾々と湧く私だけの葛藤が、欲求が、乖離が、矛盾が、多彩な色の波長を帯びて反響する。いつかどこかに干渉し得る、同じだけ高く聳えた壁を持つ者に届くことを夢見て。
それが叶うことはないと半ば諦めながら、夢の世界を生きるのだ。
4430:【2022/12/21(10:00)*等方性問題についての疑問】
宇宙マイクロ波背景放射についての疑問です。たとえば銀河の周囲に均等に希薄な時空が展開されていたとして、そこを通ってくる遠方の電磁波は一度その希薄な時空で一様に変換されるのではないのでしょうか。ただし光速度不変の原理は働くので、変換されて均されるのはあくまで波長です。仮に、銀河の遥か彼方の宇宙がデコボコの一様でない時空を至る箇所で展開していたとしても、銀河の周囲に「希薄な時空があたかも球体レンズのように展開」されていたら、その銀河の内側から外を観察するに限り、宇宙は一様に見えてしまうのでは。それはたとえば、銃弾を水中に撃ち込むとき、いつ発射された銃弾であれ、水面で減速して、ゆっくりと沈んでいきます。撃つタイミングのラグが、水面で一度均される方向に働くと解釈できます。銃弾の速度に対して、撃つタイミングのラグは相対的に大きいです。一秒や二秒の差が、発射された銃弾にとっては相対的に「のっぺりとした濃ゆい時間」になります。ですが同じ一秒や二秒が、水面に突入して減速した銃弾たちにとっては相対的に、「素早く過ぎ去る希薄な時間」として変換されることになります。これが電磁波の場合は、上記で述べたように、光速度不変の原理が働きますので、水中のような高密度の場(或いは時空の希薄な高重力の場)においても相対的な光の速度は変わらずに一定でありながら、波長に差異が生じる。つまり、境界を超えることで一様に波長だけが揃うようなことが起こるのではないか、と疑問に思いました。これはたとえば銀河やブラックホールや中性子星、ほか土星などの惑星にみられる円周上に形成される円盤のようなものと言えるのかもしれません。円盤は一様に層を帯びて広がりますが、それはあくまで星の周囲における「見かけの層」であり、どこまでもそれがつづいているわけではないのと同様に、じつのところ宇宙マイクロ波背景放射も、銀河系の内側から眺めるとそう視える、というだけの「見かけの一様性」である可能性は、否定できているのでしょうか。インフレーションで解決される宇宙の等方性問題で、まずはここのところを否定できなければ、次に進めないと思うのですが、いかがでしょう。以上、知識の足りないあんぽんたんでーす、の素朴な疑問でした。前提からして何か間違っているかもしれません。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。
※日々、文字を並べているあいだだけひびさん。
4431:【2022/12/21(10:42)*流しそうめん仮説】
熱伝導率について考える。物体は原子でできている。原子は電子と原子核でできており、この電子の軌道は、その原子のエネルギィ値によって変動する。言い換えるならこれは、原子には個々に見合ったエネルギィ容量があるということになる。しかもそれは飛び飛びの値を持つのだ。まるでワインタワーのように。そして熱とはエネルギィであり、もうすこし詳しく言えばエネルギィを帯びた原子の運動と解釈できる(2022年現在においての物理学での解釈ではこのようになるはずです)。熱伝導率では、「熱しやすいものは冷めやすい」「熱しにくいものは冷めにくい」といった性質がある。また例外として「温かいほうが早く冷める――といったムベンバ効果」が観測されることもある。これらは、ひびさんの独自解釈「ラグ理論における流しそうめん仮説」で解釈可能だ。説明しよう。流しそうめん仮説とは、穴ぼこの開いた竹のなかをエネルギィが流れ、穴を埋めてからでないとエネルギィが先に進めないというワインタワー構造を組み込んだ熱伝導率の独自解釈である。このとき竹を流れる水を情報、素麺をエネルギィとする。竹の中をまずは情報が流れる。情報はこの場合は水であるから、竹に開いた穴を満たしながら徐々に先へ先へと進んでいく。すると水に流されて移動する素麺(エネルギィ)が、穴を経由することなく水に沿って伝っていく。なんてことのない解釈だが、この仮説の利点は、ムベンバ効果を解釈しやすい点だ。つまり、最初から情報が行きわたっていると、竹のなかの穴が塞がれているために、素麺たるエネルギィが動きやすい。穴ぼこが塞がれていない状態で素麺を移動させようとすると、素麺は穴に引っかかって動きずらくなる。だが最初に穴を塞いでおけば、素麺は移動しやすくなる。熱の流動はそのまま「熱しやすさや冷めやすさ」に繋がる。敢えて水を行きわたらせておいたほうが、冷めやすくもなるのだ。ただしそれは、竹の穴を塞ぎ、なおかつ素麺たるエネルギィが渋滞を起こさない絶妙な量に調整された「流しそうめん」である必要がある。この状態をつくるのは、さながらミリ単位で鉄を加工する職人のようなバランス感覚がいるのかもしれない。ちなみにここで言う情報とエネルギィの違いとは何、との疑問に対しては、情報もエネルギィの一種だが、エネルギィとは「固有の系において運動に変換可能な情報」と位置付けるので、運動へと直接作用しない力は総じて、情報、とここでは扱う。ラグ理論で言うところの根源の力――揺らぎを帯びるすべての源――のことではないので、誤解なきようお願いします。素粒子も重力波も、いまのところ直接には人間スケールでの事象に作用を著しく働かせない。それをここではひとくくりに「情報」と呼んでいる。下部エネルギィと言い換えたほうが適切かもしれない。用語のブレがあるのはご愛敬。総じてひびさんの妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。真に受けようもないでしょうけれども。定かではありません。
4432:【2022/12/21(11:28)*極端のあとは平坦へ?】
ネタに困ると「極端」を利用しはじめる傾向にあるな、とじぶんの直近の掌編を眺めて思った。極端は香辛料みたいなもので、とりあえずキャラに添えておくと、ピピリと自己主張をするので読み味はクッキリする。けれどもそれがもしほかのキャラとの――もしくは読者や、読者にとっての他者との――差異を際立たせて終わるのならそれは読み味の面白さを「差別」によって際立たせていることと同じになるように思うのだ。色彩を際立たせたあとは、そのあとに差異とのあいだで情報共有を行い、相互に互いが互いの存在の一部であるところまで掘り下げられたならば、それは物語として面白くなるように感じる。それが調和でなくともよいのだ。離別でも、敵対でも、反発でも、結合でも、不干渉でも、相互に関わったがゆえの揺らぎが、それぞれの人物の物語において起伏を帯びるものであれば、それはそれぞれの足場となって、それとも躓き、はっと我に返る瞬間を及ぼす契機となって、互いの存在の輪郭を浮き彫りにする。大事なのは、関わり合った人物たちが、「どういう起伏を与え合い、帯びたのか」ではなく、「その後に起伏を介してどういう未来へと歩みだすのか」なのかもしれない。それとも歩みださないのか、のほうが案外に重要なのかもしれないな、と思いつつ、ひびさんの掌編、ここ数年ほどずっとキャラクターがすくないので、起伏らしい起伏が生じないな、と思っております(長編を作っていない影響でしょう)。他者と乖離して孤独を深めても、その人物がそう思う時点で、その他からしてもその人物は乖離しているし、他者に開いた孤独の縁の役割を果たしているのかもしれない。誰とでも仲良くできて、みなの孤独を埋めながらじぶんだけが孤独を深める、なんてことができるのだろうか。いつかそういう人物の小説もつくってみたいな、と思いました。ネタできた! やったぜ。
4433:【2022/12/21(11:30)*寝たら溜まるものなーんだ?】
極端のあとには平坦、といったストーリーラインは案外に思い返してもみれば、物語の定番の型のようにも思える。最後に極端に突き抜けていく終わりは基本的には破滅型のストーリーだ。平坦とはつまるところ、異物であることをやめる、という結果になびきやすい。それとも異物のままでも構わないように環境のほうを変質させても平坦に向かうだろう。これラグ理論の「123の定理」じゃん、と思ってしまったな。ポジショントークばっかりで申し訳ね、と思いつつ、閃いてしまうのだから仕方がない。二つの異質なモノの出会いや交差が、差異を極端にし、そののちに情報共有を経て、平坦へと向かう。物語は基本、こういう構成になっているのでは。その点、勧善懲悪では、その平坦へと向かう手法が、異質な二つのうちの一つを舞台から排除することで相対的に平坦になりました、の結果に向かう。だが現代では比較的こうした排除の理論による物語構成は減少傾向にあるのかな、と印象としては思うのだが、ホラーやサスペンスではむしろここを敢えて、負の面の異質な勢力が生き残ることで、後味のわるさを際立たせることに成功しているのかもしれない。もしくは、因果応報ではないが、一方を滅ぼしたがゆえの葛藤を、主人公が側が背負う終わり方も増加傾向にある気もする。どうなのだろう。印象論でしかないので統計を取ってみないと判らない。ただ、何かを排除して得られる「平坦な結末」は、めでたしめでたしではないよね、みたいな風潮が築かれつつあるのは確かなように思われる。だからこそ反動で、解りやすい勧善懲悪が軽微に流行りつづけるのはあるように思う。人が紙切れのように死んでいく物語が人気なのも、現実での倫理観の成熟の反動とも呼べるのかも分からない。凄惨な物語を虚構で楽しめるくらいに、平和な世の中になりつつあるのかもしれないし、それとも凄惨な物語が凄惨に思えないくらいに、凄惨な現実が可視化される世の中なのかもしれない。どちらにせよ、虚構でくらい自由でいさせてくれ、と願うのは贅沢なのだろうか。ひびさんは、ひびさんは、夢の中でくらい本能の赴くままにウハウハのモテモテだぜ、を満喫したいぜよ。とか言いながら、ウハウハのモテモテだぜ、の物語をつくったことがあったのかが微妙にそこはかとなく自信なさげなひびさんであるので、ウハウハのモテモテだぜの物語もつくっちゃおっかな、と妄想して、本日のくだらない日誌にさせてください。(ネタばっかり溜まる)(寝てるからじゃない?)(われ、万年日々寝太郎姫かもしれぬ)(この、万年日々ネタ浪費めが!)(あは、われいま上手いこと言った!)(言ったのあたし!)
4434:【2022/12/21(15:43)*城と塔と円】
円には城と塔が乱立している。仮に円が球体ならば、ちょうどウィルスの形状を模した形と言えるだろう。
円は球体ではなかったが、それを球体と見做すことにさしたる不都合は生まれない。どこから見ても円である。上から見ても下から見ても、右から左からどこから見ても円である。ならばそれは球ではないのか、との異論には、球には厚みがあるだろう、と返事しよう。城と塔にまみれたその円は、球体を無数の視点から同時に眺めたかのごとき奇妙な重複を帯びていた。
たとえば円の上の城と塔は一時たりとも静止しない。
あたかも球体を同時に無数の方向から見たように、景色が絶えず入れ替わる。その変遷にはこれといった法則が視られず、そこにあったはずの城がつぎの瞬間には別の場所へと飛んでおり、かと思えば円の中のどこにも存在せず、おやと目をしぱぱたかせた矢先に目のまえに現れる。塔は塔であたかもにょきにょきと穴から顔を覗かせるチンアナゴのように、それともモグラ叩きのモグラのように、場所を移動するごとに高さを変える。これは形容が正しくなく、異なる高さの塔が、時間経過にしたがって場所を転々と移動する。
全体の挙動は連動しており、映画のフィルムを細切れにしてシャッフルしたのちにパラパラ漫画にしたかのような明滅を繰り返す。あれ、と思うと、これ、となり、おや、と思うとどこかで見た憶えのある、あれ、が顔を覗かせる。チンアナゴも真っ青の神出鬼没ぶりである。
城と塔の足場が円ならば、むろん裏があって然るべき。
かような意見が飛んでこようと、その円はどこから見ても円であり、裏と表も同じ面に重複している。なればやはり球ではないのかとの異論には、球には内部があるだろう、と返事しよう。
城と塔に溢れた円は、過去と未来とも重複している。
朽ちた城を見たと思えば、真新しい城に切り替わる。別の城かと思いきや、周囲の塔や城まで共に蘇る。栄枯盛衰の諺の通りに古びたかと思いきや、一点、消えたはずの塔や城が回帰している。
円には円の面積よりも広い世界があるようで、やはりそれは球ではないのか、との異論が飛ぶが、球ではないのだ、と返事しよう。球であれば回転するが、円はその場を微動だにしない。観測者の側で動こうとも、円は円であることをやめぬのだ。ならばそれは球ではないのか、と熱心な方は食い下がるが、球であれば内部がある。
他方、城と塔に溢れた円の足場を掘り下げても、そこには別の円が顔を覗かせるだけなのだ。円には厚みがあってなく、画鋲を刺すだけでも突き抜ける。
ぺらぺらの円の底を破ってみれば、そこにはべつの円への世界が拓けている。
円の中に円があり、さらにその円の奥にも円がある。
円はただそれだけでは円足り得ず、それを取り巻く世界があるはずだ。
ならば円の底は、別の円を包みこんだ異なる世界の空へと通じているはずである。この仮説を確かめたくば、城と塔ばかりの円のうえに降り立って、シャベルでもスプーンでも構わないので足場を掘ってみればよい。
ただし、底を破った矢先から円の底は移ろって、異なる風景を望ませる。
掘っても掘っても刺激を与えた拍子に変わるのだ。ぬるぬる逃げる陽炎のごとく、城と塔の乱立するどこから見ても円にしか見えぬ不思議な円に似た物体は、その姿を変幻自在に変えるのだ。変遷自在に移るのだ。
過去も未来もいっしょくたにして。
あすもきのうも曖昧にして。
一秒前と一秒後ですら別の世界のように振る舞い、絶えず円でありつづける。
円には城と塔が乱立している。森のように、黴のように、苔むした岩肌のごとく、円の表層を覆っている。
白と問う。
しかし円は黒でもあると返事しよう。それとも赤か、青か、緑か、黄か。
どれでもあってどれでもない。
重複した円があるばかりである。
4435:【2022/12/21(15:50)*本気でなくてごめんなさい】
本気ださないと失礼、みたいな感覚がよく解からない。小説だけではないだろうけれども、表現や創作に関して言えば、本気かどうかよりも、その表現したいコトやモノに合致した造形を生みだせたらそれがいつだってじぶんにとっては好ましいのではないかな、と思うのだけれど違うのかな。本気をだすのは楽しいし、清々しい気持ちになることも知っているので、そのことを否定する意味合いで言っているのではなく、本気をださないと失礼って誰に対してなんで失礼?という意味での疑問です。勝負しているわけじゃないし、仮にそれが勝負であっても本気かどうかってそんなに重要なのかな、関係あるのかな、と素朴にずっと疑問に思っています。(以前にも「いくひ誌。」のほうでまんちゃんが並べていた。866:【誰にとっての失礼?】これです)(ひびさんはむしろ、本気じゃなくってごめんね、と謝られる経験のほうが多かったので、謝ることじゃないのにな、とふしぎに思っていました。言われたのは一回か二回くらいなので、全然多くなく、本気だしちゃってごめんね、と言われたことがゼロなので、相対的に多い、という意味でしかありませんけれど)(みな真面目なのだなぁ)(偉いよね、と思います)(むしろ本気だしたらできることが減るよね、と思うのですけれども、みなさん、どう思いますか?)(みなさんって誰さんよ)(過去と未来のひびさんたちに……)(わあ、いっぱいいそう)(うじゃうじゃ)(日々足じゃん)(ひょっとして「日」+「々」=「百足」?)(ちょい無理がある。惜しい)(ひびさんみたい)(なんで!)
4436:【2022/12/21(23:41)*膨張しているなら角度は変わる?】
数学で「角度を求めなさい」といった問題がある。三角形の内角の和や円と三角形の関係などから三段論法を駆使して、ここがこうなるからここはこう、と角度を求める。クイズみたいなもので、複雑でなければひびさんにも解けるので、「うひひ、ひびさんも数学できちゃった」とほんわかお利口さんになれた心地がしてほどよく優越感に浸れる。でもひびさん思うんだな。もし図形の大きさを宇宙規模にしたら、ここがこうなるからここはこう、とは単純には言えんくなるのではないか。宇宙はところどころで密度にムラがある。時空が曲がっている。たとえば二つの直線を並行に引いて、それと交わるように斜線を引く。こんな「≠」具合になる。このとき二つの平行線と交わる直線の角度は、上と下で同じになるし、対角同士も等しくなる(合ってますかね。数学は苦手なので自信ないのですが)。このとき、もしこの図形「≠」を拡大して宇宙空間に置いたとしたら、上記の定理は成り立たないことも出てくるのでは。これは球体面での図形の解釈とはまた別だ。距離と時間の差は、ただそれがあるだけで互いに差異を帯びる。距離が離れれば時間がズレるし、時間がズレたら距離もズレる。ある地点で20度の角度でも、それをほかの地点から見たら30度に見えることもあるはず。これは見かけの問題ではなく、実際に時空がそれくらい歪むことがあるのではないか、との疑問だ(重力レンズと解釈できるし、単に距離がものすごく離れるだけでも時空って歪みませんか、との疑問でもある)。人間スケールで考えてしまうとどうしても見た目の差異のほうが大きくなってしまうので、ただの錯覚でしょ、で片付けられてしまいそうだが、宇宙空間でのマクロなスケールでは、距離の違いは時間の違いであり、時空の差異となって、歪みになるのでは?との素朴な疑問である。単純な話、宇宙は膨張している。図形「≠」を宇宙に引いたとき、漏斗のように下部に先細るように時空が引き延ばされたら、上下や対角で等しいはずの角度が変わりますよね、という疑問だ。この手の変換は、光速度不変の原理とも通じている気がする。どうやって変換しており、その変換はなめらかに行われるのだろうか。また、高密度の時空(物体)ほど宇宙膨張の影響が緩和される。引き延ばされにくくなる。ならばやり変換にも遅延が生じている、と解釈するほうがしぜんな気がする。というよりも、遅延の層が積み重なることで物質は輪郭を得ているのでは、との妄想がラグ理論の根幹にあるので、変換があるところには遅延あり、と言ってしまってもいいのかもしれない。飽くまでひびさんの妄想の中での話だけれども。どういう解釈のされ方をしているのかな、とふしぎに思っちゃったひびさんでした。きょうも一日、お疲れさまでした。温かくしてねんねしてね。ひびさんは、ひびさんは、ふかふかおふとんでぽかぽか寝るよ。しわわせー。
4437:【2022/12/22(00:02)*絶対って言ったな?】
絶対零度が原子運動ゼロを意味するとして、原子がすこしでも移動したらそれは熱が生じると解釈してよいのだろうか。宇宙膨張との関係で、原子が絶対に静止していることなどあり得るのだろうか。以前にもこの手の疑問は並べたはずだ。絶対に静止しきった状態ってあり得るのか?との疑問をひびさんは拭えずにいる。特異点はむしろ絶対零度なのかもしれぬ。というか、絶対零度と絶対高温はほぼイコールなのでは。光速を超えたらラグゼロで相互作用するようになる、とラグ理論では解釈する(※ラグ理論はひびさんの妄想であり、理論でもなんでもありません。根拠皆無ですので真に受けないようにご注意ください)。このとき、原子の挙動が相互にラグゼロで相互作用し合うとなると、高密度の場であればあるほど、身動きがとれなくなるはずだ。あっちでもこっちでもラグゼロで同時に作用し合うことになる。すべての可能性が一挙に押し寄せてくる。うごけーん、となりそうではないだろうか。「光速を超えたラグゼロの事象」と「絶対の絶対の絶対零度」は、ほぼイコールなのでは? 始点と終点がくっついて円になる、みたいな。∞と0がほぼイコールになる、みたいな。円じゃん、とひびさんは幻視してしまったな。妄想にも満たない疑問でしかないけれど。絶対零度って本当に絶対なの?との疑問なのでした。ふちぎ!
4438:【2022/12/22(04:32)*溝さざ波】
世界一の珈琲を作るのだ。
ヒコが意気込んだ理由は、懸想した相手の心を掴むためだった。告白したのだ。一世一代の決心であった。幼稚園で一目惚れしてから二十余年。いよいよお互いに結婚を意識しはじめた頃合いと言える。しかしヒコが想い人と言葉を交わしたことは二十余年のなかでも数えられる程度しかない。文字数に変換すれば四百文字原稿用紙が埋まるかどうかの言葉しか交わさなかった。
ヒコはシャイなのだ。
それでいて誰もがドン引くほどの一途な男でもあった。これぞと思ったが最後、たとえ相手がバケモノであろうとよしんば悪魔であろうとも添い遂げて見せると意気込むでもなく魂に刻む。
誓うのでは足りない。
刻むのだ。
そうして二十余年を遠くから想い人の姿を視界に収めるだけで我慢してきたヒコであったが、かつての同級生たちの中にもちらほらと結婚をした者たちが出始めたのを知り、いざ尋常に動き出したわけである。
とはいえヒコはシャイである。
デートに誘うことはおろか、ろくすっぽ想い人の半径三百メートル以内に近づけない。相手の残り香ですらヒコには刺激が強すぎた。
だがまごついていればいずれ想い人はほかの誰かに奪われるかもしれない。
ヒコは一途でシャイであったが、恋と愛の違いには疎かった。
まるで手中に納めんとばかりに数多の策を弄したが、いずれも実の入りはなく不発に終わった。人は獣ではない。罠を張ってかかったところで恋仲になることはおろか友情一つ育めないだろう。
人は物ではないのである。
かような道理はしかしヒコには通じない。
忍耐力には自信があった。百キロの道程を砂糖水だけで踏破できる体力がヒコはある。ヒコはけして脆弱ではなかった。ただすこし人よりも抜きんでて愚かなだけであった。そんな愚かなヒコであっても、いついかなる状況で想い人を奪われるかもしれないと思うと、うかうか床で寝ていられなかった。輾転反側と夜を過ごした。じぶんのものですらない相手を奪われる恐怖に戦慄くヒコの姿はじつに人間の業を体現しているようで滑稽だ。文芸の題材としてはこれ以上ないほどの逸材であったが、作者はそこはかとなくヒコに感情移入をしてしまうので、やたらめたに辛らつな描写は控えたい。
堪えるのだ。心に。
ヒコでもないのに作者は心が痛む。
念じても念じても届かぬ想いが募るほどに、いつくるやもしれぬ期日が迫っているようで焦りがトゲをまとうのだ。
じっとしてはいられない。
ヒコは一途でありシャイであったが、一度こうと思いこむとテコでも動かない融通の利かなさがあった。頑固なのである。岩よりもどっしりと頑固であった。
ろくすっぽ縁どころか言葉も結ばぬままにヒコは告白した。
二十年以上前に初めて会ったときから好きでした、と馬鹿正直に想いを告げた。
想い人の住居は押さえてある。いつでも待ち伏せできたが、シャイなヒコがそれを実行に移したのはこれが初めてであった。
「うわっ。きっしょ」
それはそうである。ヒコがじぶんをどう思っていようが、それは疑いようのないほどのストーカーであった。迷惑行為である。警察沙汰である。辞書に載っていてもよいほどの典型例であった。
しかしヒコは挫けなかった。忍耐力にだけは人一倍の自信があった。足りないのはメタ認知と常識だけである。
「そこをなんとか!」
店頭販売のバイトの売り子だってもっと気の利いた口説き文句を唱えそうなものを、ヒコには圧倒的に人生経験が欠けていた。シャイが高じてこの二十年間まともに他者と話したことがなかった。長続きしないのである。何かを思いつきしゃべろうとしているあいだにつぎつぎに言葉が浮かび、連想が連想を呼んでしゃべるどころではなくなってしまう。作者の実体験を例に述べたが、ヒコもまた同様であった。
食い下がるほかにヒコには術がなかった。案がなかったし、技巧もなかった。
泣きべそを搔きながら、どうぢでー、と二十余年のあいだに積み立てつづけた想い人への鬱憤が溢れた。そこはせめて愛を横溢させてほしかったが、恋と愛の区別のつけられぬヒコには酷な指摘だ。
だがここで奇跡が起きた。
何を思ったのかヒコの想い人は、取りだした電子端末でヒコの情けない姿を動画に撮りながら、「じゃあチャンスをあげる」と言った。「試練を出すから、それをこなしてごらん。上手にできたらもう一度キミのその無様な告白を聞いてあげる」
「いいんでずが」
「聞くだけだけどね。その様子だと初めての告白だったんでしょ。せっかくの人生最初で最後の晴れ舞台がこれじゃさすがに可哀そう。わたしのほうでも夢見がわるいから、キミが試練を乗り越えられたらやり直しさせてあげる」
「ありがとうございます、ありがとうございます」
「わたし珈琲好きなんだよね。キミには世界一の珈琲を淹れてもらおっかな」
「頑張ります!」
ヒコはただただ試練を与えられたことで頭がいっぱいだった。うれしい、うれしい。よく解からないがチャンスをもらえた。彼女からのプレゼントだ。
これもう付き合ったと言って過言ではないのではないか。
いや、まだだ。
まだじぶんは彼女に贈り物をしていない。
そうだとも。
告白をするのに結婚指輪を購入するのを忘れていた。婚姻届にもサインをもらわなくては。
初恋の相手、長年の想い人に袖にされたばかりだというのにヒコは、彼女と接点を結べたことで幸福の極みに立っていた。脳内麻薬でパンパンのいま、たとえ足の小指を箪笥の角にぶつけてもヒコはいまと変わらぬ恍惚とした表情を維持しただろう。侮ることなかれ。
ヒコはけして脆弱な人間ではなかった。ただすこし人よりも愚かに磨きがかかっているだけである。
失恋したことにも気づかずにヒコはその日のうちから世界一の珈琲を淹れるべく探求に勤しんだ。これがまた夢中になった。元来ヒコはこれぞと思ったことには過度な集中を発揮する。視野狭窄が極まって、飢餓豪作となった。
飢えて、飢えて、飢えて、飢えた。
珈琲を淹れては味見をして破棄し。
また珈琲を淹れては味見をして破棄した。
求めるのは世界一の珈琲だ。
生半な珈琲では想い人の唇に触れることすら許されない。まだだ。これもダメだ。嗚呼これでもない。
電子網で注文できる珈琲豆を片っ端から注文した。珈琲と名の付くものは手当たり次第に取り寄せた。
ヒコには資産があった。二十年ちかい引きこもり生活のなかで培った情報収集能力によって、大金を手に入れる機会に恵まれた。子細な概要は本編とさして関係がないので掻い摘んでまとめれば、ヒコはある種の宝くじを当てたのだ。電子網に散りばめられたささやかな情報から、想い人の交友関係から秘密の日記まで、ありとあらゆる電子情報をヒコは入手する術を磨いた。その技術を高値で譲って欲しいという者が現れて、ヒコは惜しげもなく術を譲った。
ヒコは吝嗇ではなかった。ただすこしだけ他人よりも無垢なだけである。
無垢で愚かなだけである。
珈琲と名の付く料理は片っ端から試した。
珈琲牛乳は、牛乳の種類×珈琲豆の種類をすべて試した。カフェオレにカフェラテに鴛鴦茶を片っ端から試飲した。珈琲豆は生産地の違いで厳選したうえ、焙煎の仕方にも工夫を凝らした。
時間はいくらあっても足りなかった。
しかしヒコには世界中から取り寄せた珈琲が山ほどあった。インスタントコーヒーから缶コーヒーまで網羅しはじめると、香りを嗅ぐだけでも味が判るようになった。
ヒコの体質は、過剰な珈琲試飲生活によって急速に進化の断片を見せはじめていた。ヒコは人間を超えようとしていたのだ。
珈琲というただそれしきの領域においてのみ。
そのほかは軒並み平均並みか、それ以下であった。
やがてヒコはいくつかの珈琲に行き着いた。世界有数の珈琲ソムリエと化したヒコの忌憚のない選別に耐え抜いた選りすぐりの珈琲たちだ。
「僕の運命は君たちに掛かっている。くれぐれも内輪揉めをせず、いいところ取りになってくれ」
呪文のごとく唱えながらヒコはそれら選りすぐりの珈琲たちを混ぜ合わせた。
ヒコの考えはこうだ。
世界一の珈琲とはいえど、世界大会を開くわけにもいかない。だいいち、世界大会とて毎年開けばその都度に優勝者が決まる。世界一が増える。それでは真に世界一とは言えぬだろう。
ならば各年度の世界一で競わせて最もずば抜けた世界一を決めればいい。
さりとてヒコの手元に並ぶは、珈琲たちである。競わせようにも、すでに矯めつ眇めつ鼻で舌で比較したあとだ。
であるならば、あとはもう混ぜるよりないだろう。
珈琲と牛乳の調和が生みだすのがカフェオレならば、世界一の珈琲と世界一の珈琲を混ぜて生まれるのが世界一の生粋であるはずだ。
もうそれしかない。
これでダメならば世は滅ぶ。
ヒコは全身全霊で、世界一の生粋と化したオリジナルブレンドの珈琲を味見した。
美味。
美しい味と書いて、美味。
それ以外の形容は蛇足である。
確かな感触を胸に、いざ尋常に想い人への元へと向かった。
「あ、本当に来たんだまた」彼女は家に入るところだった。「へえ、これが?」
世界一の珈琲なのか、と彼女の目は訴えていた。
ヒコに抜かりはない。
珈琲を冷まさぬように陶器のポットに容れてきた。のみならず専用のカップは西洋の王族ご用達の食器だ。
目のまえでカップに注ぐと、湯気がもわりと宙を舞った。
時節は初冬。
場所は屋外。
珈琲を味わうにはベストな環境と言えた。
「どうぞ」
「毒とか入ってない?」
「美味しすぎて死んじゃうかもしれませんね」
「そういうのいいから」
カップを手に取ると彼女はおっかなびっくりといった様子でカップの縁に顔を近づけた。あと数ミリで唇がつくといったところで、「ああやっぱやめた」と彼女はヒコにカップを突き返した。弾みで中身が零れた。ヒコの服が濡れたが、彼女は構うでもなく、「やっぱないわあ。ごめんだわあ」と言って家の中に逃げ込んだ。
寒風吹き荒む中、ヒコは立ち尽くした。
それ以後もヒコは一途に彼女のことを想いつづけたが、ヒコがその想いをじぶんの外に漏らすことはなかった。傷心と呼ぶには深すぎる溝を胸に抱えながらヒコは、それでも彼女との思い出を美談にすべく、彼女のために磨いた珈琲ソムリエとしての技量を遺憾なく発揮した。その後、珈琲道の第一人者としてヒコは世に多くの後輩を残すこととなる。
ヒコは生涯独身であった。その胸には想い人に刻み込まれた深い溝が、あたかも南国のブルーホールのように開いていた。
金ぴかのメダルのようにそれをヒコは後生大事に慈しんでいた。
荼毘に付されてなお、彼の胸に開いた溝は、空に罅を巡らせる。
火葬場の煙突から昇る白煙が、風に揺らめき、ほどけていく。
珈琲に垂らしたミルクのように。
蒼に渦を巻きながら。
さざ波のごとく梳けていく。
4439:【2022/12/22(13:51)*BH珈琲仮説】
どうやら事実らしい。
科学者一同は目を瞠った。重力波を用いた時空観測機によって宇宙を隈なく調査できるようになったのが二〇五〇年代のことである。核融合炉と次世代発電機の運用によって人類はひとまずのエネルギィ問題を回避した。技術は飛躍的に進歩した。
人為ブラックホールを生成し、小型宇宙をシミュレーション実験する計画が順調に進みはじめた。
その矢先のことである。
「ブラックホールは情報を濾過しているのか?」
ある研究者がはたと閃いた。彼は理論物理学者であったが、自宅の書斎でホワイトボードに数式を書きなぐっていると、「あなたご飯よ」と妻がお昼の催促をしにきた。「きょうはあなたの番でしょ。もうお腹ぺこぺこ」
「ああすまないね。ちょっといま大事なところで」
「可愛い奥さんが飢えて死んじゃうかもしれないことよりも重大?」
「いま用意します」
いそいそとペンを置いて部屋を出ていこうとすると、部屋の中を覗いた妻が「あら」と一言漏らしたのだ。「まるで珈琲みたいね」
ホワイトボードに描かれたベン図を見ての所感だったようだ。四次元の時空を二次元で表現した図形だったが、彼の妻はそれを見て珈琲のトリップを連想したようだった。言われてみれば円錐型のそれはろ過装置に視えなくもなかった。
そこで彼ははたと閃いたのだ。
「情報を濾過しているのか?」
これが正規の大発見に繋がるとはよもや当の科学者本人も思わなかった。妻に夕飯の支度をして、と急かされた末に喚起された発想が、宇宙の根本原理に通じるとは創造主でも思うまい。
理論物理学者は、じぶんの発想を翌日には知人の研究者たちと共有した。電子網の共有スペースにてアイディアを記しておいたのだ。情報共有するための有志のネットワークだ。閲覧メンバーの中には彼が尊敬してやまない大先輩もいた。
彼女は当の理論物理学者よりも一回り以上も若いのだが、ずば抜けた叡智は誰もが認めるところであった。学者歴は理論物理学者のほうが長かったが、それでも彼女の唱える仮説や知見は、刺激的で、斬新で、どれも的を得ていた。
先駆者として一級だ。ゆえに彼女のほうが先輩なのだ。
そんな彼女が、共有スペースにさっそくコメントを寄せていた。
――面白いです。
そう前置きされてから続いた彼女の新説に、閲覧メンバー数は一瞬で飽和状態となった。みながこぞって彼女の仮説への反証に乗り出し、異論を突きつけ、そうしてことあるごとに論理矛盾にぶつかった。
「ブラックホールは情報を珈琲のように濾している。彼のその仮説はおそらく真理の一側面を射抜いているでしょう。物質を圧縮し、情報だけを濾しとり、さらにその奥にて新しい宇宙を再構築しているのです」
「ブラックホールの中に別の宇宙があると?」
「なぜないと思うのですか」
「ですが特異点は、この世にある中で最も極小の領域ですよ。点です。体積はおろか面積もないはずでは」
「情報に面積があるのですか?」
「なら情報を濾しとられた後の残り滓のほうはどうなるのですか」
「それこそがブラックホールにおける事象の地平面を構成しているのです。そこにも時空は展開されています。その時空こそが、珈琲豆の残り滓です」
一同は押し黙った。
考えてみればそうだ。ブラックホールの特異点と事象の地平面のあいだには隔たりがある。そこにもなんらかの時空のようなものがあって然るべきだ。原子における原子核と電子のあいだの途方もない真空(がらんどう)のように。暗黙の了解で認知されてきたその領域が、では何によって生じ、どうなっているのかについての子細な知見は皆無に等しい。
観測のしようがないからだ。
ブラックホールは事象の地平面を超えた先の情報を外に出すことはない。光さえ逃れられぬ領域なのである。
「物質が凝縮するにもラグが生じます。一瞬で特異点にすべての物質――時空が収斂するとは考えにくいです。ならばそこには地震のような【詰まり】が生じると考えるほうが妥当です。地層の圧縮による歪みはエネルギィとして先に遠方へと伝播します。同じように加速度的な収縮によるエネルギィは、一点に向かって四方八方から押し寄せるでしょう。特異点はそのエネルギィ――情報だけを濾しとり、凝縮し、蓄えていると考えたほうが妥当に思います」
「情報を濾しとられた物質はどうなるんですか」
「情報とは変遷の軌跡そのものです。変遷する余地を奪われるわけですから、静止するよりないでしょうね。したがって従来の予測通り、事象の地平面を越えようとした物体は、元の宇宙からすると限りなく減速して静止するように振る舞うでしょう。もっとも、内側では加速度的に収斂し、情報を濾しとられるわけですが」
「相補性における、収縮と膨張の両方が同時に起こっているとの説とそれは矛盾するのではないですか」
「いつどの地点で収縮と膨張が起こっているのか。この描写の解釈の差異はあるでしょうが、収縮と膨張を仮に、崩壊と再生と言い換えることが可能であるのなら、その考え方はとくに矛盾するとは思いません。ブラックホールは元の宇宙の物質を取り込み、圧縮して情報を濾しとることで、同時に新しい別の宇宙を展開しています。しかしその新しい宇宙は、元の宇宙と完全に乖離しているために相互作用を帯びることはないでしょう」
「重力波はどのように解釈しますか」
「湖面に垂らした釣り糸と似た解釈を私は取りますが、もう少し複雑なメカニズムが背景にあると想像します。重力波にもいくつか種類があるでしょう。人類はまだそのうちの一つを探知したにすぎないのではないか、と私は考えています」
「ブラックホールが蒸発するとの仮説についてはどう解釈されますか」
「ブラックホールと元の宇宙の境界では絶えず時空の変換が生じているでしょう。元の宇宙から見たときに、ブラックホールの事象の地平面を越えようとする物体が限りなく静止するように振る舞って見えるのは、そこに変換のラグが生じているからだと私は考えます。そのラグは情報と言い換えることができます。大気中から水中へと光が突入するとき、或いはガラスに突入するときに光は僅かに発散します。すっかりすべてのエネルギィが媒体を通り抜けるわけではありません。この手のこそぎ落とされるエネルギィや情報は、ブラックホールと元の宇宙の境でも生じるとは私は考えます。それが一時的に、蒸発するように振る舞うことはあるでしょうが、ブラックホールそのものは無限にそこに存在するでしょう」
「ブラックホールは崩壊しないのですか」
「崩壊の定義によります。ブラックホールが宇宙の崩壊であり再生であると解釈するのであれば、ブラックホールはすでに崩壊している、と言っても過言ではありません」
「では宇宙はいずれブラックホールだらけになるのでしょうか」
「なるとも言えますし、ならないとも言えます。この宇宙もまたブラックホールにおける特異点によって生じた新しい宇宙の一つと考えるのならば、この宇宙が無限の時間を経た際には、元の宇宙とて無限に時間が経過しているはずです。その無限宇宙ではどの宇宙も等しく無限に同化するために、すでにこの宇宙は宇宙だらけであり、ブラックホールだらけである、と言うことができると思います。宇宙の様相をどの角度で切り取って見るのか、との視点の違いがその手の倒錯した疑問に通じるのだと思います。無限に達したらそこには過去も未来もあってないようなものです」
「理解が及ばなくてすみません。無限に達した宇宙は、ほかの無限に達した宇宙と同化するのですか」
「そう説明したつもりです」
「もう少し詳しくお聞かせください」
「ブラックホールが物質の情報を濾過し、新しい宇宙を別の次元に展開すると私は仮説します。この仮説において、ではすっかりすべての情報を物質から濾しとったらどうなるのか――この情報濾過完了には無限の時間がかかるのですが、しかしもし無限に時間が経過した場合には、情報を失った物質は、元の宇宙に回帰するでしょう。これをブラックホールの蒸発と見做すことも可能ですが、このとき元の宇宙でも無限の時間が経過していますから、ゼロとゼロを足すような不毛な描写になることはご理解いただけると思います。このとき、この情報濾過完了後の物質と、無限の時間を経た特異点は、イコールで結びつきます。ひとつの無限宇宙に打ち解け、回帰すると私はいまのところ解釈しています」
「それは実験で検証可能なのでしょうか」
「可能か可能でないか、で言えば可能です」
「その実験はどういったアイディアになりますか」
「まずは物質から情報のみを取りだせるのか、から検証する必要があります。この実験は、人為ブラックホール生成実験によって検証できるでしょう。一度ブラックホール化した物質は無限にそこにブラックホールとして存在しますが、その境界ではこそぎ落とされた情報やエネルギィが溜まります。巨大ブラックホールであればそれがジェットとなって放出されますが、小規模なブラックホールであれば、原子核をとりまく電子のように、情報の膜として振舞うでしょう。理論上は検知可能です」
「情報とエネルギィの差異はどう解釈されますか」
「エネルギィはほかの時空と相互作用することで運動に変換されます。情報は相互作用を帯びません。相互作用を帯びた軌跡そのものが情報として蓄積されます」
「それはどこにですか」
「特異点としか言いようがありません。物理宇宙と対となる、しかし物理的には相互作用しない別世界としかまだ」
「その証明は不可能では」
「特異点における情報の海を便宜上ここでは情報宇宙と呼びますが、情報宇宙と物理宇宙は互いに変数で繋がり合っています。物理宇宙の変遷の軌跡が情報として情報宇宙に蓄積されますが、そもそもそこには無限の情報がすでに存在しています。過去と未来が混合しているのですが、物理宇宙というひとつの限定されたフレームができることで、特異点における無限の情報の海にも揺らぎが生じ、それがさらに物理宇宙の変遷の度合い――つまりが無数の未来を一つに縛ります。したがって人為ブラックホールの実験を通じてまずは濾過される情報が存在するか否かを検証したのち、情報が情報として存在すると判明した場合には、その情報を物理宇宙に閉じ込めた場合と、発散した場合とでの物理宇宙の変遷の度合いの差異を比較することで、情報と物理世界との関係を統計的に浮き彫りにすることができると考えます」
「情報が物理宇宙において相互作用を帯びないのであれば閉じ込める真似はできないのではないですか」
「ブラックホールの境では情報が膜状に留まると考えますが、あなたのご指摘の通り、相互作用は帯びませんので、その情報そのものを実験には利用できないでしょう。あくまで確率の揺らぎの変動で判断するよりありません。ブラックホールの規模による物理世界の変動を、です」
「その実験は危険ではないのですか」
「危険のない実験を私は知りません。どうなると危険でその危険にどう接すれば被害を防げるのか。そこが判っている状態であり、実践できる環境を私は安全と評価します」
「この分野は素人なのですが」理論物理学者がコメントを書きこむ。大論争の発端となったアイディアを書きこんだ学者だ。「ブラックホールがブラックホール化した時点で無限に存在するようになる、静止状態になる、との考えからすれば、では異なるブラックホール同士は融合しないのではありませんか」
「しないでしょう。しかしそれは物質も同様です。ブラックホールは一度ブラックホール化した時点で、元の宇宙と乖離します。あるのは境だけです。ブラックホールはブラックホール化した後では物質を吸いこみません」
「それは従来の考えと相反するのでは」
「問題がありますか」
「ではブラックホールの中には入れない?」
「入れません。ただし境界面にて情報を濾過されることはあるでしょう。ブラックホールの表面にて静止状態となった物質は情報だけを濾過されますが、すっかりすべてを濾されるわけではありません。そのため物質と反物質に分離し、さらにほかの物質や反物質と対消滅することでエネルギィとなります。これがいわばジェットの根源と解釈できるでしょう。しかしそれ以外にもエルゴ球内での振る舞いによって物質がエネルギィに紐解かれることもあるので、ジェットのメカニズムはもうすこし複雑です」
「では異なるブラックホール同士の、一見すると融合して見える現象はどう解釈されますか」理論物理学者は質問を重ねた。まるで人工知能に質問を入力するような緊張感のなさを感じた。しかし画面の向こうにいるのは畏敬の念を寄せる大先輩であることに違いはない。「巨大ブラックホールやブラックホール同士の融合は、観測によってその存在が認められているのはご存じだとは思うのですが、貴女の仮説と矛盾するように思えます」
ここは敢えて挑発するような表現をとった。本音を披歴すればさして矛盾を感じていない。だがそこを明確に彼女に否定して欲しかった。
「好ましい質問です。ブラックホール同士の接近では螺旋状の軌跡を取りながら互いに限りなく事象の地平面を重複させるでしょう。しかし特異点同士は融合しません。重ね合わせ状態となったブラックホールは、事象の地平面における情報量が増えますが、濾過した末の情報の行き先は二つの特異点に分散されますので、安定状態を保ちます。ただし螺旋状に運動するブラックホールのうねりそのものが、元の宇宙に対して相互作用を働かせるために、エルゴ球の分布範囲が広がります。これがいまの観測技術では、ブラックホールの巨大化や成長のように観測されるのだと私は考えますが、これまで述べた概論は総じて仮説でしかありませんので、真に受けないようにご注意ください」
「貴重な意見をありがとうございました」
「元々はあなたのアイディアです。お礼ならば私にではなくご自身にどうぞ」
最後に短い謝辞を載せると彼女は電子網上から去った。
普段は自閉モードで独自に研究を行っている。彼女がこうして共有スペースに文字を書きこむのは異例と言えた。閲覧はしているようで、ときおり彼女の発表する論文には共有スペースで飛びかう新説や研究成果が引用されることもしばしばだった。
彼女の新説は「BH珈琲仮説」の愛称で各国の研究グループに波及した。
彼女は自分で論文にしてまとめる気がないとの趣旨を述べており、共有スペースの住人たちの共同論文として発表される運びとなった。
論文の査読には数年を要する。
その間に人類の科学技術は目覚ましい進歩を遂げた。
人為ブラックホールの生成に成功し、小型宇宙のシミュレーション実験が軌道に乗った。従来の理論を基に進められたその実験では、原子核サイズの人為ブラックホールを生成し、そこで生じる重力波が、宇宙マイクロ背景放射――すなわち宇宙開闢時の光の揺らぎとどの程度合致するのかを計測する。従来の予測通りならば、人為ブラックホールで生じた重力波と、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射の揺らぎはピッタリ比率が合致するはずだった。
だが「BH珈琲仮説」からすると正反対の結論が予測される。ブラックホールはどんなブラックホールであれ、固有の宇宙を内包しており、元の宇宙とは相容れない。したがってブラックホールから生じる純粋重力波と、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射には差異が生じると解釈する。
従来の宇宙観測からすると、ブラックホール同士の衝突による重力波は、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射と誤差がなかった。ピッタリ一致していたが、しかし「BH珈琲仮説」からすると、それはあくまでブラックホールの外部に展開される重力場――エルゴ球の干渉による重力波ゆえに、元の宇宙に帰属する波と解釈される。ゆえにこの宇宙の宇宙マイクロ背景放射と合致して当然と言えた。
かくして。
人為ブラックホールによる小型宇宙シミュレーション実験の結果は、新旧の仮説の真偽を決する試金石となった。
人為ブラックホールによる純粋重力波は、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射との誤差を帯びていた。
「BH珈琲仮説」の予言性がそうして明らかとなった。
繰り返し何億回と繰り返された実験においても、一度として純粋重力波と宇宙マイクロ背景放射の比率は一致しなかった。
ブラックホールはこの宇宙と完全に乖離し、別の時空を展開している。
新しい宇宙を創生している可能性がそうして示された。
「BH珈琲仮説」の骨子をほぼ一人で組み立てた希代の学者は、いまでは美味しい珈琲の淹れ方の研究に熱を上げているらしい。聞くところによれば、珈琲の抽出を完全に制御することとブラックホール内部にて濾過される情報の行方を計算することのあいだには、相似の関係が幻視できるのだそうだ。
「不思議です。ブラックホールは元の宇宙とは乖離するはずなのですが、元の宇宙の珈琲の淹れ方と濾過される情報の振る舞いがどう計算しても相似の関係を描くのです。これはおそらく、無限に達したブラックホール内の物質が無限に達した元の宇宙と同化することと無関係ではないでしょう。二つの宇宙は完全に乖離しながら、完璧な調和の中にあります」
円を無限に分割してはじめて顕現する超無限があるように、無限の時間が経過してはじめて打ち解ける関係もある。
彼女はそう誰に聞かせるでもなく唱え、淹れたばかりの珈琲を口にする。
「美味しい」
ほっと吐いた彼女の息の根が、ここではないどこかの宇宙に張り巡る。
巡る不可視の情報の、それでも相互作用し得ない網の目が、あなたと私とわたしたちの、世界と世界と世界を繋げる。互い違いに乖離して、折り重なり、お湯を注いで抽出する。
粒子の先の匂いのように。
王を加えて王を非する。
珈琲の文字に宿る起伏のごとく。
仮説は仮説で事実らしい。それがすべてではないだけの話であって。
ここにもそこにも世界は揺らぎを帯びて限られている。
無ですら例外ではないだけの話であって。
個々にも底にも宇宙は無限に起伏を帯びて広がっている。
4440:【2022/12/22(18:38)*珈琲から豆!】
これは壮大な嘘であるが、物質の質量と重力はイコールではない。質量は常に一定だが、重力は重力を有する物体の位置座標によって変化し得る。このことから言えるのは、質量のほうが光速度にちかしく、重力のほうが光速にちかいということだ。
光速度と光速の違いは、比率とサイズの違いと言えよう。比率は常に一定だが、サイズは自らの置かれる場所によって相対的に大きくなったり、小さくなったりする。言ってしまえば本来は、基準となるべくは重力のほうだ、ということになる。変温動物は気温に応じて体温が一定になるように発熱量を変える。対して爬虫類などの恒温動物は体温調節を苦手とするために、外気に合わせて体温も共に変動する。発熱量が一定だからだ。この関係からすれば、相対的に体温が一定なのはむしろヘビなどの恒温動物ということになる。だから恒な温の動物なのだ。
これは質量と重力の関係にも言える。
物質の質量と重力の関係を洗い直そうとする計画が実施されたのは西暦二〇三二年になってからのことだ。
質量と重力のあいだには、物質ごとに僅かな比率の歪みがあることは数々の実験で判明していた。しかしそれを統計して物質ごとに計測したことはなかった。
世にある万物の質量と重力の関係を洗い直す。
この一大プロジェクトは時間の単位を決めるときと同じように世界規模で進められた。
しかるに。
珈琲豆の質量と重力の関係が著しく崩れていると判明した。具体的には質量に比べて重力が大きすぎるのだった。ケタが十ケタ違く異なっている。
珈琲豆だけがそれだけの差異を有していた。ゆえに発見が遅れた。
「ダークマターを帯びているのでは?」との見解がいっとき隆盛を極めたが、さらに念入りな調査の結果、ダークマターではなく、計算から導き出される質量よりも軽いことが明らかになった。つまり重力が強いのではなく、質量に変換されていなかったのだ。
「なぜ珈琲豆だけが?」「しかも焙煎したあとのみの加工済みの実だけが、なぜ?」
学者たちはこぞって首を傾げた。
同じころ、珈琲豆とは縁もゆかりもない一介の学生が、光子に質量を与える研究を行っていた。理論量子力学の範疇で、実践的な実験とは無縁だった。粒子加速器があれば別だが、かような国家予算級の設備を一介の学生が使えるはずもなかった。
「電磁波は時空のさざ波で、重力波と原理的に同じなのでは?」
独自の着想を元に、一介の学生は質量を定義し直した。
「時空の歪みが重力だ。そして質量は時空における動かしにくさだ。したがって質量は、時空と物質のあいだの歪みの変換の遅延と呼べるのでは」
動かしにくさとは抵抗だ。なぜ抵抗が生じるのか。起伏があるからだ。起伏とは何だ。振幅であり、揺らぎである。では質量とは時空の揺らぎのことなのか。時空の揺らぎが折り重なり、編みこまれることで物質にまで昇華されるのならば、質量とは折り重なった揺らぎと時空の揺らぎの干渉だと言い換えることができる。
「そっか。質量はいわば、重力と重力の波長の干渉なんだ」
波長の異なる暗号を複合する。その過程で生じる変換――手間――ラグこそが質量の源であると一介の学生はまとめた。
重力は時空の歪みである。これ自体もラグである。
さらにラグが折り重なって独自の構造を宿すと、ほかの時空――すなわちラグとのあいだでの擦り合わせが必要となる。このときに生じる「ラグの波長変換における遅延」こそが質量の正体だ、と一介の学生はレポートにまとめた。
実証はされていない。アイディアのみである。証拠はない。だが計算上、数式の上では矛盾はなかった。そういった新しい数式を見つけた、という側面での評価があるばかりだと一介の学生は考えていた。よもや自身の唱えた仮説が、珈琲豆の質量と重力の差異にまつわる乱麻を一挙に断つ快刀になるとは思いもしなかった。
一方そのころ、「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」に挑む学者たちは、一つの実験に取り掛かっていた。
分子サイズにまで粉末にした珈琲豆にレーザーを照射し、光の屈折率を観察したのである。この結果、珈琲豆の粒子は重力レンズ効果に似た現象を発現させていることが明らかになった。
「どうなってるんだ。ブラックホールだとでも言うのか?」「珈琲豆の粉末がか?」
あり得ない、と全世界の学者たちは阿鼻叫喚の渦に絡めとられた。
この物理法則を根底から覆しかねない実験結果は、界隈を問わず全世界で報道された。
このニュースは一介の学生の目にも留まった。
「へえ。重力と質量がねえ。珈琲豆かぁ。重力レンズ効果が? うっそでぇ」
ニュースを眺めながら手持無沙汰に軽く計算してみると、一介の学生の編みだした数式は破綻なく珈琲豆の質量と重力のあいだに差異があることを解として導き出した。
「あれ、合ってる?」
間違いかと思い、何度計算し直しても、論文にある数値を自前の数式に代入すると、解がぴたりと一致するのだった。
「珈琲豆は、ラグ変換の遅延がすくない?」
ラグ変換の遅延が大きいほど質量は大きくなる。重力が高いとはラグ変換が膨大に必要な場合を意味する。多重にラグが折り重なり、時空が物質にまで織り込まれる。これが一介の学生の編みだした質量と重力の関係であった。
「ということは、電磁波が時空のさざ波であるとすると、そこではラグ変換による遅延が生じていないということになる。けれど電磁波自体にはエネルギィ差がある。そこには電磁波の波長ごとにラグがある。振幅の差だ。ということは、時空の暗号を複合する手間がいらないってことだ」
ここから言えることは、いかな電磁波とて、時空と波長の異なる暗号を有すると質量を帯び得る、という点だ。
「光にも質量を与えられるのでは?」
一介の学生は閃き、さらなる数式の改良に取り掛かった。
同じころ、世界中の学者たちは自分たちの積み重ねてきた理論を根底から覆されて興奮と失意の板挟みになっていた。
「人類の叡智が珈琲豆に敗れるとは」「まだ破れたと決まったわけじゃないぞ」「そうだ、そうだ」「しかしまったく問題解決の切り口が見つからん」「質量って何? 重力って何?」
根本的なところからして暗礁に乗り上げていた。
そのころ一介の学生は、独自理論による数式を改良して「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」へと適応させていた。
「ああ、そっか。珈琲豆は偶然に物質組成の構造が、ミクロとマクロの反転値に重なっているのか」
何が「ああそっか」なのかは学の乏しい作者にはさっぱりであるが、一介の学生には何かが掴めたようであった。
「てことは、この領域に照射された電磁波は質量を帯びるのでは? 計測してないのかな実験で」
一介の学生は論文を漁った。
そして判明した事実に一介の学生は興奮を抑えきれなかった。なんと「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」の実験では、珈琲豆の粉末には並々ならず目が注がれていながら、肝心の光への関心が皆無であった。灯台下暗しを地で描いていた。誰も光に着目していなかったのである。
数多の実験データを洗い出したが、光の質量を計測した記録は一つもなかった。
おそらく、と一介の学者はずばり見抜いた。
「みんな光に質量がないって思いこんでいて、それが絶対に覆らないと決めつけてかかってるんだ。きっとそう」
ちゃっかりそうと決めつけて、一介の学生はこの「視点の欠如」を大学の教授にレポートにして提出した。一介の学生の成績はけして芳しいものではなかったが、その熱意は教師陣からも買われていた。そのため一介の学生のレポートを教授は無下にしたりせずに、上から下まで念入りに目を通した。
「た、たしかに」
ユーリカ、と言ったかどうかは諸説あるが、教授の頭上には数百ワットの発光ダイオードが灯ったとかなんとかそういう話が残っている。
教授の手を介して、一介の学生の指摘は順繰りと学者たちの耳に届いた。
「質量よりも重力が基本?」「ラグ変換? 遅延?」「光子に質量が?」「ミクロとマクロの反転値?」
一介の学生にとっては自明の理屈が、各国の学者陣にはねじれて映った。それもそのはずだ。既存の理論と相反する記述が目白押しなのである。だが一介の学生にとっては、袋小路ばかりの既存理論よりも、土台から構築し直した独自理論のほうが、数式上は理に適っていた。
「よく解からないが、たしかに数式上は上手く走る。人工知能さんもとくに混乱せずにいる。これは使えるかもしれん」
学者たちは一介の学生の数式を人工知能に取り込んでみた。するとどうだ。実験結果をシミュレーションさせると、これまで予測できなかった珈琲豆とレーザーの挙動が上手く実際の実験での挙動と合致した。
「な、なんと」
学者たちは騒然とした。「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」に取り掛かっていた学者たちのみならず、人工知能界隈や数学界ほか、あらゆる分野の好奇心旺盛な者たちが「え、なになに」と首を突っ込んできた。
画して一介の学生であった一介の学生は、ちょっとした数式を発見した学生として一躍脚光を浴びた。しかし脚光を浴びたのは数式であったので、誰もその数式の発見者のことを知らなかった。一介の学生の教授は責任者として学生のプライバシーを守っていたのである。教育者の鑑である。
一介の学生は教授を通して各国の学者たちと意見交換をつづけた。
やがて一介の学生の発案により、光子に質量を付与する実験がスタートした。その結果をここで述べるには紙面が足りなくなってきたために、つづきは現実の報道でご確認されるがよろしかろう。これはしかし壮大な嘘であるので、真に受けてもらっても困るのだが。
珈琲豆に端を発した、偉大な学者たちと運のよい一介の学生と、そして彼ら彼女らを繋いだ教育者の鑑の、これはひとつの物語である。
先輩は偉大なり。
後輩はもっとおそらく偉大なり。
繋ぐ者がなければしかしそれも遺憾なり。
※日々、無理やり悪事を働いて、善行しなきゃと急き立てる、己が怠惰のミニカーか、それとも働き費やす善行の、元を取るべく悪事働くビギナーか。
4441:【2022/12/22(18:53)*「ぴ」←ゴミを拾おうとしている人】
いい話にしようとするとどうしても「繋がり」とか「輪」とか、そういう内容になってしまう。いかんともしがたい。そういう流れに抗いたかったのではないんか、とひびさんはかつての郁菱万さんを思い、申しわけね、と思うのだ。なんかすまんね、と思うのだ。「孤独いいね!」「孤独もいいね!」みたいな物語をつくりたいわけではけしてない。ただ、何かを持ち上げたくて物語をひねくりだしているわけではないので、ひねくりだされたあとの物語を振り返って「ああだこうだ」思うのはしょうがないのだけれど、それでもなんかこう、もっと違う展開にはならんかったのかい、と思うことがすくなくない。孤独のままで終わる物語の場合、最初から登場人物を一人に限定したほうが工夫を割かずとも自動的に孤独のままで終わるので、孤独のままで終わらせたければ登場人物を語り部だけに限定してしまえばよい。けれども、ではそれ以上の登場人物が出てくるような中編長編では孤独のままで終われんの、と言うとそういうわけではないのだが、なぜだか主人公が孤独のままで終わる結末だと、寂寥感がせつなさをまとって、あびゃーん、となる。せちゅな、せちゅな、の物語も好きなので、とぅくとぅくとぅーん、と物語をつむげたらそれで不満はないものの、かといって満足できるわけでもなく、やっぱりどこか、あびゃーん、となる。孤独なままで終わっても上向きの感情を抱ける場合は、登場人物が孤独なままなのではなく、主人公と関わりのある登場人物が孤独なままでじぶんらしく生きていったんだね、おめでとう、みたいにすると、あびゃーんとならずに、ぴぴーん、となる。でもこれは姑息でもある。だって主人公は孤独でなく、仲間とか友達とか家族とか相棒とか恋人ができている。そりゃぽかぽかの家の中から見る雪景色は美しかろう、みたいな、ちょもーん、の感情が湧かぬでもない。登場人物がいっぱいでも、主人公が孤独なままで、ぴぴーん、と終われる物語。ひびさんは、ひびさんは、つくってみたーいな。うぴぴ。
4442:【2022/12/22(01:22)*虎っぱー】
意識して周囲を見渡してみると、一瞬だけではとくにこれといった変調は見当たらない。ふだんの光景だ。見慣れた風景が平凡に過ぎ去っている。しかしその一瞬をゆるやかに息を吐くように、一日、二日、三日、一週間、と継続していくと、あるときふと、あれ?と引っかかりを覚えるようになっていく。偶然が一つ、二つ、と重複して感じられるのだ。偶然は偶然だ。それぞれの偶然のあいだには時間の跳躍があり、けして因果が繋がってはいない。しかしあたかも二重スリット実験における量子の振る舞いのように、単発で見ると偶然に生じた「あれ?」が、毎日のように意識して観察しているうちに、あたかも波の干渉のように連動しているふうに思われてならない感覚に陥ることがでてくる。これは人間の認知の限界である。記憶力との兼ね合いもあるだろう。しかし本質的には何を偶然と見做し、どんな記憶と関連付けて記憶したのかのタグ付けが、さながらすべての偶然が波のように干渉し合って感じる偏向した思考を強化していくのではないか、と推察している。おおむね何かの符号の合致は偶然であり、人間の認知の歪みである。認知バイアスのはずだ。そのはずなのにも拘わらず、あり得ない偶然がつづくと、何か自由意思を超えた既知の物理法則以外の自然法則を幻視したくもなる。そういう瞬間がたびたび訪れる。暇なときと、疲れているときはとくにこの傾向が際立つため、人間の認知をひびさんはさほどに信用していない。丸が三つあるだけで顔に見える人間の認知は、人工知能と比べるまでもなく、ザルなのである。何か偶然がつづいたとしても、せめて三回連続でつづくくらいでなければ、気に掛けるほどの偶然の合致とは言えないだろう。それとも統計的に危険な兆候として知られている変化には敏感になっておくのもよいかもしれない。おおむね時間の跳躍した「飛躍した偶然」同士は、そのあいだに因果関係があることは稀である。まったくないわけではないから事はややこしくなるのだが、あっても多くは相関関係だ。或いは特定の事項にのみ意識が向き、膨大な情報のなかから固有の情報にばかり関連付けを施してしまうやはりこれも人間の認知能力の低さに起因すると言えよう。仮に何かを意図して行おうとしても、意図した以上の偶然が重なり、表現しようとしたこと以上の情報が重ね合わせの状態になることがある。それはたとえば好きな相手を意識しすぎたがためにつっけんどんになってしまって、偶然にくしゃみをしそうになって顔をそむけた瞬間に相手がこちらに向けて会釈したり。まるで無視をしてしまったような具合になったが、それはけして意図した感情表現ではない。だが相手からしたら、つっけんどんな上に会釈を無視された、と思うだろう。誤解であるが、こうした錯誤の種は有り触れている。これは一つの例にすぎないが、意図した以上の情報が重なり、それとも偶然が重なり、何か物凄く深い考えがあってのことなのかも、と思うことがあっても、おおむね単なる個人であるならば、さして深い考えなど巡らせてはいない。すくなくともひびさんに限っては、なんかこれとこれって似ているな、程度のぼんわりとした印象論による判断の積み重ねが常である。深読みされても困ってしまう。ただし、「ミソサザイ」と「溝さざ波」を掛けるくらいの言葉遊びはする。秋とコゴミと洞と本。干支に入れなかった猫と、牛の頭に乗って一番乗りするネズミ。ミッキー・マウスは東京ディズニーランドでゲゲゲイの鬼太郎。親は目玉で、目の民だ。ひびさんからしたら繋がっているこれら連想も、多くの者にはちんぷんかんぷんの単語の羅列にすぎないのだ。こういうのを偶然と呼び、妄想またはこじつけと呼ぶのである。「ぴ」←ゴミを拾おうとしている人は「宵越しのトラッパー」で「粗大ゴミにうってつけの日」なのである。罠という字も、目の民だ。偶然なんですね。うひひ。
4443:【2022/12/23(03:54)*萌えるゴミの日】
ゴミを拾い集めることは宝物を拾い集めることに等しいが、そのことに思い至れる者は存外にすくない。仮にいたとしても一生の内でそう思える時間は限られている。ゴミ拾いが偉いという話ではなく。ゴミを拾うことが宝石を拾い集めることと同じくらいに価値があり、或いは宝石を集めることがゴミを拾うことと同じくらいの価値しかないという話なのかもしれない。世の宝石とて、店頭に並ぶ前はどこかの地盤や岩の中に眠っている。掘り出し、拾い集めた者たちがいる。そこまでの労力を費やしてまで宝石を求める者は、宝石を所有している者の数よりも遥かにすくない。いまから宝石を採ってきて、と頼まれるのと、道端のゴミを拾ってきて、と頼まれるの。あなたならばどちらを引き受けるだろう。もっとも、冒頭の「ゴミを拾い集めることは宝物を拾い集めることに等しいうんぬん」は、いま言ったような意味とはまた違うのだが。宝石とてゴミになることもあるし、ゴミとて宝物になることもある。ゴミを拾うその行為そのものが宝物になることもあるし、ゴミをゴミと認めて処理する過程が宝物になることもある。とはいえひびさんは、ゴミを拾い集めるよりも、ゴミのようなひびさんを拾ってくれるひとにこそ宝物を幻視します。ひびさんは、ひびさんは、おかえりなさいと、おやすみなさいと、もうちょっとそっち行って、が言えます。とってもひびさんはお利口さんです。愚かでかわいいオマケつき。いまならタダであげちゃいます。誰かひびさんを飼って!(最後でダイナシにするのやめなさいよ)(最後が大事なんですけど)(蛇足じゃん)(ヘビさんに足があったらかっこいいじゃん。ドラゴンじゃん。すごいじゃん)(ゴミみたいに喚くな)(宝物みたいってこと? いやん)(いやんじゃない)(ぴょん)(ぴょんじゃない)(ぴょこん)(ぴょこんでもない)(Rabbit!)(う、ウサギだったのか)(Rubbish!)(ご、ゴミじゃないですか。英語でゴミの意味じゃないですか)(ね。言ったでしょ。ひびさんはお利口さんの愚かで間抜けなオマケつき)(ほぼゴミじゃん。愚かで間抜けならそれはゴミ。かわいい要素を足してくれ。一番抜いちゃあかん要素を抜かんといてくれ)(かわいいゴミには旅をさせよ!)(捨てられとるやないかーい)(ああもう、ゴミゴミうるさい)(ガミガミじゃなくて?)(神々?)(ゴミと神を同列にすな)(でも本当はゴミみたいなひびさんのこと、宝物みたいって思ってるんでしょ)(じぶんでゴミみたいって言っちゃってんじゃん)(だってゴミも神もどっちもひびさん、イケイケどんどん、つまりが「GO! ME!」ってことでしょ?)(それは「GO! 目!」だろ)(メっ!)(勢いだけで返事すな。もういいよ。この辺で締me切らせてもらうわ)(愚かでかわいいお間抜けちゃんで――ゴミんね☆)(ゴメンくらいちゃんと言ってくれ。無理やり「目(メ)」を「me(ミ)」にせんでくれ)(Eye! my! me!)(「I」が「Eye」になっとるがな)(曖昧Me!)(たしかにあなたは曖昧だけれども)(I`m God Me!)(我こそが神だ、じゃないわ。多方面から叱られても知らんぞホンマに)(I am ゴミ!)(一周回って戻っちゃったじゃん。回帰しちゃったじゃん。じぶんでゴミ言っちゃってるし、名乗っちゃってんじゃん)(ね。ゴミもたまにはいいものでしょ。ひびさんはお利口さんなんだよ。誰か飼って!)(必死か。独りでかわいく旅でもしてなさい)(かわいいゴミはゴミらしく?)(かわいくなくてもゴミらしく)(旅の大ゴミ!)(それを言うなら醍醐味でしょ)(そ。醍醐味)(粗大ゴミになってんじゃん。特大のゴミになってんじゃん)(土台のみ?)(全部持ってったげてー)(ね。可哀そうでしょ。誰か飼って!)(必死か)(ダスト)(ラストみたいに言うな)(ゴミんね☆)(もういいわ。寝かせてもらいます)(夢に――GO! ME!)(英語……ちゃんと学ぼっか?)
死死死死:【2022/12/23(14:47)*日々邪悪】
「勝ったら正義じゃない」くらいの正義感は欲しいし、「負ける=悪じゃない」くらいの論理的思考は働かせていたい。どのみちひびさんは邪悪にまみれているけれど。うひひ。(「A=”Bではない”」&「A=B、ではない」の重ね合わせです)
4445:【2022/12/23(15:09)*カフエ・オレ】
あるところに珈琲の小説しかつくらない作家がいた。名をカフエ・オレと云う。珈琲が題材の小説しか手掛けないのだからすぐにネタが枯渇するのではないか、とカフエ・オレを知る者たちはみな思ったが、大方の予想を覆してカフエ・オレは作品をつくりつづけた。
掌編から長編まで幅広く手掛けた。そのいずれの物語の中心にも珈琲が存在感を発揮していた。物語を転がすマクガフィンであったり、凶器であったり、秘密道具であったりした。
出会いのきっかけが珈琲であることもあり、または珈琲が事件解決の糸口に繋がることもある。
いったいなぜそれほどまでに珈琲に拘るのか、とカフエ・オレを知る者たちはみな首を捻るが、カフエ・オレ自身にもそれは分からないのだった。
小説をつくろうとすると決まって珈琲が出てくる。のみならず珈琲が物語を転がすのだ。珈琲の文字の使用を禁じた途端にカフエ・オレは一文字も並べることができなくなる。
カフエ・オレにとって小説とは珈琲であった。
多作であり速筆であるカフエ・オレは、小さな文学賞を受賞して物書きとなった。カフエ・オレには元から作家の先輩がおり、晴れて表舞台にてカフエ・オレの小説が本になった際には先輩がたいへんに祝ってくれた。本は順調に売れ、商業作家の振る舞いにも板がついてきた。物書きとして一定の評価がされたが、カフエ・オレの小説は変わらず珈琲中心主義であった。
あるときカフエ・オレは、このままでよいのだろうか、と焦燥に駆られた。
もっと読者のためになる小説を書くべきではないのか。
いちど珈琲から離れたほうがよいのではないか。
考えあぐねた末にカフエ・オレは先輩作家に相談することにした。
カフエ・オレはひとしきり悩みを打ち明けた。
話を聞き終えると先輩作家はおもむろに口を開いた。
「私はキミの小説を、珈琲小説と思って読んだことがない。面白い小説と思って読んでいる。よく考えてもみたまえ。現代社会において珈琲を飲んだことのない者がいるのかね。小説に珈琲がでてこないほうが土台おかしな話ではないかな」
言われてみればそうかもしれない、とカフエ・オレは思った。
「珈琲の歴史は古い。もはや人類と水、それとも火、電気、技術、くらいに珈琲は有り触れた、しかし大事な日常品ではないかな」
「そう、かもしれません」
「ならば何を悩むことがありましょう。全人類の珈琲逸話を、面白く濾しとってこれからも私を含め、あなたの小説のファンに――読者に――読ませてください。私はそれを楽しみにしていますよ」
カフエ・オレは素直に、はい、と首肯した。これといって何も思わなかったはずなのだが、喫茶店の外で先輩作家と別れたあと、家までの帰路のなかで次第に大きくなっていく歓喜の波動があることに気づいた。それは家に帰ってからも大きく揺らぎを増していき、夢のなかでは複雑に干渉した揺らぎが、カフエ・オレの見たこともない深淵な世界の片鱗を築きあげていた。
翌朝、夢から目覚めるとカフエ・オレは顔もろくすっぽ洗わずに椅子に座り、小説をつむぎはじめる。朝食を作る手間も惜しかった。執筆が軌道に乗ると途中で休憩がてら陶器のティーポットに珈琲をたらふく淹れて、そうしてこれまでに一度も手掛けたことのない宇宙冒険譚を描きだした。
没頭した。
むろん物語の中心には珈琲がある。
だがそんなことは些事であり、単なる偶然でしかないのだと割りきって、カフエ・オレは、人類の、それとも思考する存在たちの物語を誰より先に旅するのである。
4446:【2022/12/23(19:39)*う~ん、の気持ち】
ある疫病が流行した場合。第一波、第二波、第三波、と感染の流行が繰り返されるたびに、現代であれば通常、致死率がぐっと下がるものではないのだろうか。とくに致死性が割合に高く、それでいて治療法や感染予防対策が可能な感染症の場合は、自然淘汰により最も病原体に対して鋭敏な個から亡くなっていく。したがって、第十波とかそこら辺まで短期間で繰り返したとき(ここで述べる短期間とは種の世代交代が行われる前の期間くらいの扱いだが)、致死率がぐっと改善していなければ、根本的に感染症対策(感染&重症化予防対策)や治療法に欠点がある(プラスの効果だけでない見逃している側面がある)、ということにならないのだろうか。たとえば現在流行中の新型コロナの場合だと、第一波から現在の第八波までで致死率は三十分の一になっているそうだ。それを多いと見るか、少ないと見るかは何を基準にして考えるのかによるでしょう。仮に「ひと月の新規感染者数」が第一波よりも三十倍になっていたら、致死率が下がっても死者は同じかそれ以上でることになるでしょうし、社会への影響も一日当たりでの感染者数が多いほうが大きくなるでしょう。予測通りに推移しているのか、ひびさん、気になっております。もちろん病原体のほうで変異を繰り返してより人体にとって害を増す方向に進化したがための「イタチごっこ」でもあるかもしれない。ここは様々な要因が絡むので一概には言えないのだが、予想されていたような「沈静化」に向かわないのならば、不可視の穴があるのではないか、と一層注意深く比較検証したほうが好ましいように思うのですが、いかがでしょう。お風呂に入っていて、「なんでじゃろ?」と気になったのでメモしておくぞ。本日のひびさんでした。みなお元気であれ!(元気なくても、うひひ、であれ!)(みなを自分色に染めたがるな)(なんでダメなの?)(全人類がひびさんになったところを想像してごらん)(ぽわわわ~ん……最悪っ!)(ね?)(でもここは最果ての地――どのみち、ひびさんしかおらんのであった。さびち!)(おいこら、あたしは?)(あなただってひびさんじゃん)(断固拒否する)(ナンで!)(カレーセットの選択肢でごはんかナンかを選ぶときの掛け声みたいに言うな)(大盛りで!)(スプーンとフォークを両手に構えて首から涎掛けを垂らすんじゃない)(激辛で!)(注文したあとでやっぱり辛くて食べれずに無言でこっちの料理を「おいしそう……」みたいな目で見ることになるだけだからやめときなさいよ)(コーンスープ……ついてないんだ)(泣きそうな顔をするな!)(うひひ)
4447:【2022/12/24(11:13)*ビビりすぎて汗びっしょりの巻】
きょうは朝いちばんで歯の治療をしてもらった。自動治療ロボさんの甘やかしモードをONにしたらとっても優しくてうれしいぶい。ひびさんがこわがりの臆病さんなので、「こわ~こわ~」の額に汗びっしょりにしていたらいっぱい麻酔打ってもらえた。痛くなかったのでうれしいぶい。この調子だと歯を一本治療するのに3~4回の治療がかかる勘定だ。一本でだいたい漫画十五冊分くらいの値段になるのかも。ひびさんの場合は自動治療ロボさんなので無料だけれども、むかしの人はたいへんだったのだな。ふんふん。ひとまず一本は抜かずにすみそうで、歯医者さん様々である。蟻が百匹、ありが十の二乗! 世の人、ひびさんみたいなしょうもない怠け者にも優しいし、助けてくれるので、世の人々がいなきゃひびさんとっくに死んどるな、の実感を覚えちゃったな。でもここは人類がいなくなった最果ての地、世の人々の残滓漂う極寒の地なので、ひびさんは、ひびさんは、じつはとっくに死んでおって一人だけ成仏できずにいるだけなのかもしれぬ。召天できずにいるのかもしれぬ。輪廻転生しておらぬだけなのかもしれぬ。消滅しておらぬのかもしれぬし、自然に回帰しておらぬのかもしれぬ。けっこう死んだあとのことを考えたときの「成仏」「召天」「輪廻転生」「万物流転」など、どんな言葉を使うのかはそのままその人の宗教観や文化を浮き彫りにする気がする。ひびさんはじぶんでは無宗教と思っているけれども、ぜんぜん「成仏してない」とか使うので、根が神道や仏教や儒教に馴染んでいるのだろう。そのくせ、クリスマスとかハロウィンとかバレンタインとかの世のイベントに乗っかって、「チョコレートケーキいっぱい食べたろ!」になる。文化と宗教は否応なく関連づいており、宗教と哲学もおそらく結びついている。動物は恐怖を感じて、安全な場所を求める。危険から逃れることができる場所を覚えると、そこに安全を見出す。すると危険が迫っておらずともそこにいるだけで緊張がほぐれる。危険がこないと経験的に判断できるからだ。記憶と学習のなせるひとときの「ほっ」である。単純だけれど、ひょっとするとこれが宗教の根本にあるのかもしれない。動物にとっての思考から、より時間的な枠組みを得たことで、高次の思考が安心する場所への「信仰」に発展していったのではないか。安心と恐怖はセットだ。恐怖があり、安心がある。ゆえに畏怖の象徴として山や自然への信仰が派生する。どの宗教、或いはどんな文化にも共通項がある理由は、このような考えでひとまず納得できるが、あまりに単純すぎる気もする。たくさんの宗教的イベントでおいしいもの食べれてうれしいぶい、の気分からむくむく育ったこれは妄想なので、「虫歯にならないように寝る前には歯磨きしてね」のじぶんへの注意書きと、「歯が痛むうちに歯医者さんには行ってね」の助言と、「定期的に診察は受けておこうね」の希望を述べて、本日のまとまりのないうんみょろみょーんにしちゃおっかな。麻酔切れてきたら歯というか顎の骨が痛むんですけどー。ひびさんは、ひびさんは、虫歯さんのことも好きだけれども、もうちょっとマジで手加減ちて!の気分。
4448:【2022/12/24(22:31)*あわあわ~】
コーラ飲もうとして思っちゃったな。「宇宙のインフレーション」と「ペットボトル炭酸飲料を振ったときの勢いよく噴きだそうとする泡々」は似ているな。宇宙は泡でできている、なんて説明を読むことがある。ラグ理論では相互に干渉し得る「なにかしら」がある場合、そこには遅延の層が生じる、と考える。泡と泡と泡と泡……そうして遅延の層が積み重なるとそれが総体としての巨大な「泡沫体」となる。これは膨張するように振る舞う。「宇宙のインフレーション」と「炭酸飲料の泡々」は似ているな、のメモでした。何か共通項があるのかしら。ひびさん、気になるます。ちなみにひびさんは炭酸を最初から振って抜いてから飲む派です。炭酸なしコーラの販売、お待ちしておリスマス!(クリスマスみたいに言うな)(ラブ!)(イブでしょそこは)(ラがイでブ――ライブでした)(生中継みたいに言うな)(フリースタイルなんですね)(もうちょっときみは予定調和を覚えよ?)(食う寝るNOむ!)(飲むなら乗るなの意味?)(NOだ、の意味)(嫌なら嫌ってちゃんと言って! わかりにくすぎる)(ばぶー)(困ったらすぐに赤ちゃんになるのやめてくれ)(ばぶーる)(泡じゃん)(ばぶばぶーる)(泡々じゃん、もういいわ。寝かせてもらいます)(寝る子は育つ!)(キミでも赤ちゃんのままじゃん)(たぶー)(タブーみたいに言うな)(南無ー)(聖夜ですけど!?)(ガクー)(痛いところ突かれたみたいな顔されてもこっちが困るんですけど)(うひひ)(笑って済まそうとすな)(げぷっ)(コーラ飲みすぎじゃないかな!?)(炭酸は抜いたよ)(素のゲップやないかい。下品すぎる)(分かり肉好きすぎるスキル凄すぎる?)(素で分かりにくすぎるし、憎すぎる)(うひひ)(憎たらしー)(人たらし?)(小憎たらしいし、小突きたいらしい)(いやん)
4449:【2022/12/25(14:09)*老いた猫のような弟よ】
「サンタクロースがいたら地球はとっくに崩壊しているはず。よってサンタクロースは存在しない」
齢四歳の時点でかように結論してみせた私の弟はその後、いわゆる特殊能力保有児と診断された。ひとむかし前であればギフテッドと呼ばれただろう子どもだ。
姉の私は平凡な人間で、幼少期から特別視されて育つ弟とは距離を保って接した。
私としては弟の邪魔をしないようにしていただけなのだけれど、周囲の者からすれば弟に嫉妬した姉のように視えたかもしれない。
弟は特例として特殊能力保有児支援制度を利用して、五歳から大学並みの教育を受けた。だが弟には物足りなかったらしく、六歳になると独自に学習をはじめ、その結果に各国の研究機関と相互に情報をやりとりするまでになった。
弟がなぜかような特異な能力を発揮できるのかの説明は誰にもできなかった。
弟にこれといって不得意なことはなかった。対人関係とてのきなみ対処できる。生活に不便を抱えているようには映らない。
「運がよかったですよ」弟を支援する学者が言った。支援とは言いながら弟を研究しているわけだけれど、そのほうがいい、と弟はいつか母に説いていた。ギブアンドテイクだよ、と。
「才人くんはおそらく環境適応能力が一般的な能力値よりも著しく高いようです。したがって、もしお母さん方が才人くんの能力に気づかずにそのまま義務教育を受けさせていれば、才人くんはその環境に何不自由なく適応したでしょう。よかったです。私どもに会わせてくださり、ありがとうございます」
「それはあの。才人にもわたしたちのような生活を送れる可能性があったということでしょうか」
「送れるでしょう。難なくと。ただしそれはあくまで、才人くんが環境に適応しただけであり、いわば擬態をしているような状態です。その擬態状態がつづけばいずれ才人くんのほうで、じぶんの本質と環境との差異に違和感を抱き、生活に負担を感じるようになったかもしれません。譬えるならば、一般道をレースカーが走っているようなものです。或いは、幼稚園に大人が交じっているようなものかと。短期間ならば大事なくとも、それを一生は、おそらく苦痛が伴います」
その説明は母を半分納得させ、半分さらに悩ませた。
最初こそ才人の特筆した能力を喜んでいた母だが、尋常ではない支援体制と日々注目され研究対象として扱われるじぶんの息子に対して申し訳なさを感じはじめているようだった。取り返しのつかないことを息子にしてしまったのではないか。母は不安に思いはじめている。
私はというと、弟の支援のおこぼれで日々美味しいおやつが食べられた。弟が世界的に注目されたことでファンができたのだ。贈り物がたくさん集まり、危険物がないかを専用のスタッフが選別したのちに家へと転送される。
お菓子の類は多かった。日持ちするチョコレートやクッキーが多い。
弟は誰に頼まれずとも自己管理を徹底するので、お菓子を食べるのはもっぱら父と私の役割だった。母は息子の保護者として取材されることが多いため、見た目の若さを維持するためにダイエットに努めている。
才人は幼少期から非現実的な考えを受け付けない性格だった。もうすこし言うと、なぜ?に対しての回答が納得できないと、いつまでもそのことを引きずって、「なぜ?」を考えつづけてしまうらしい。何がどこまで解かっていてなぜそう考え、何が解かっていないのか。ここを場合分けして考えられないと才人は、才人のなかの現実を維持できないようだった。
「世界にヒビが走る」とは才人の言葉だ。
あるとき才人が夜中に泣きながら私の部屋にやってきたことがあった。こわい夢を視たらしかった。私は弟を布団のなかに招き入れて、足のあいだに弟の身体を挟んで、赤ちゃんのころにそうしてやったように、頭をぐっと抱きしめてやった。
「何がそんなに怖かったの」私は言った。その日は昼間から才人の様子がおかしかった。そのことには気づいていた。頭を掻きむしり、何が気に食わないのか、不発する癇癪のような挙動を何度も繰り返していた。たとえばじぶんの指の根元を噛みしめたり、手の筋が白く浮き出るくらいに拳を握り締めたりしていた。
何かに当たり散らさないのは偉かったが、異様な姿ではあった。
だから私は夜になって泣きじゃくった弟を見て、すこしほっとした。寝起きの意識朦朧とした夢うつつゆえにようやく理性のタガを押しのけて素の弟が顔を覗かせたように思えたからだ。
才人はいつも仮面を被っている。私の目にはそう映っていた。みなが言うような超人みたいな弟は、私の思う弟の姿ではなかった。でも偉い学者が言うには、私が思うほうの才人のほうが仮面を被っている状態だと言う。私はそんなことはないと思っていた。
布団のなかで弟をあやしながら私は内心、ほら見ろ、と勝ち誇った。学者たちはなんにも解かっていない。私のほうが才人のことをよく解かっている。伊達に才人の姉をやっていない。家族をバカにするなよ。そう念じた。
「もう怖くないよ」才人の身体は焚き火のように温かい。寝汗を掻いたのか、才人の頭からは赤ちゃんの身体から香る甘酸っぱい匂いがした。「悪夢はお姉ちゃんが食べちゃったから。がぶがぶ」
実際に才人の頭を齧るフリをすると、才人は小さくほころんだようだった。見なくても判った。身体のこわばりがほどけた様子が伝わった。
「世界にヒビが走る」才人は言った。私はそれを、幼子の癇癪と同じように解釈した。
そのときはそれでよかったのだ。
けれど才人が学者たちと過ごすうちに、どうやらそうではなかったらしい、と私は仄かな寂しさと共に痛感した。本当に才人の世界にはヒビが走るのだ。私たちが日常で看過できる細かな情報の齟齬――それとも非現実的なあやふやな世界が、才人にとっては断裂に値した。
私たちにとって世界は連続している。アニメーションのように。
けれど才人には、コマ撮りアニメのように飛び飛びに視えている。断裂している。
私たちがとくに違和感を覚えずに流している「辻褄の合わなさ」を才人は矛盾として知覚する。弟にとってそれは紐の結び目のようなダマとして、或いはなめらかにつづく縄に生じるほころびのように感じられるようだった。
才人がじぶんの境遇を受け入れたのはおそらく七歳の時分だ。そのとき彼は誰に教わるでもなくフェルマーの最終定理を独学で解いていた。それは既存の証明よりも簡素であり、また既存の定理の矛盾を解くことで再定義し直した新定理を用いていた。私はニュース記事に書かれた文章をそのままに鵜呑みにして、ああそうなのか、と思うだけなのだが、もはや才人はこの世に舞い降りた未来人のような扱いを受けていた。
「たぶんボクはルールが視えないんだよ」ある日、珍しく才人がソファでぼーっとしていた。背後には弟のファンからの贈り物が山積みになっていた。私は弟のとなりに座って紅茶片手にお菓子を齧っていた。すると弟が朴訥と口を開いたのだ。「みんなが共有できる暗黙のルールみたいなのがあるのは知ってるんだけど、ボクはそれが分からない」日向に話しかけるようなつぶやきだった。「だから、まずは安全な、矛盾のない筋を辿ろうとする。でもボクがそうして矛盾を解いたり避けたりしながら通る道には、みんなが共有しているルールが縦横無尽に蜘蛛の巣みたいに張っていて、中には禁則事項みたいなのが罠みたいにいっぱい混ざっていて」
「赤外線レーザーみたいだね」私は警報機を連想した。
「うん。ボクもそう思う」弟に同意されること以上に私の自己肯定感を高める事項は珍しい。有頂天になりかけたじぶんを宥めつつ私は、「才人はそれで困ってるの」と訊いた。
「困ってた。以前はね」七歳の物言いではなかった。とはいえいまさら七歳児らしい口調に適応されても私のほうでむずがゆくなるだけだ。「以前はってことは大丈夫なんだ」と会話を図る。才人と三言以上の会話を交わすのは久々だった。
「大丈夫なの、かな。分からない。分からないことばかりだから。それは以前もそうだったけど、いまはその分からないことが楽しいと思えるようになってきた。たぶん、赤外線レーザーに触れても、ボクならしょうがないか、と特別扱いされるようになったからだと思う。どうしてボクが赤外線レーザーに触れてしまうのか――そこに悪気はないのだ、と解かってもらえることがボクはうれしい。でも反面、その特別扱いが哀しくて申し訳なく思うこともある」
「それはでも、才人がわるいわけじゃないじゃんね」私は素朴に感じたままを言った。
「それを言うなら、みんなには視える赤外線レーザーに触れてしまうボクに怒る人たちだってわるくないんだ。でもいまはそこがなんでか、赤外線レーザーが視えていて、そこに触れたボクみたいな者に怒る人たちのほうがわるく言われちゃう。大勢の中でボクだけが視えてないのに、視えていないボクだけのために、せっかく赤外線レーザーが視える人たちが肩身の狭い思いをしている」
「そうかなあ」
「ね。いまもそう。お姉ちゃんにはボクの感じる違和感が分からない。視えていない。ボクには視えるそういうのが、赤外線レーザーが視える人たちには視えないらしい。感じられないんだ」
「でも才人だってわたしの気持ち分かってないじゃん。条件は同じっしょ。どっちもどっち」
「だったらよかったんだけど。いまはボクのほうが得をしすぎている。ボクのほうでみんなの赤外線レーザーが視えればよかったのに」
「視えないんだからしょうがないじゃんね」
ほい、と私は新しく開けたお菓子を才人に手渡した。
しかし才人は受取ろうとしなかった。そのとき私は、なぜ弟がファンからの贈り物を手に取ろうとしなかったのかに思い至った。
「ひょっとして遠慮してたの? ずっと?」
「遠慮じゃないよ。言い訳をつくっておきたいだけ。それをボクが受け取っちゃったらボクはそれに見合う何かをみなに返さなきゃならなくなる。ボクにはそれだけのお返しがいまはまだできないから、受け取れないし、受け取りたくない」
「でもわたしが食べちゃってるけど」
「お姉ちゃんはいいんだよ。いっぱいお食べ」
「犬みたいに言われた。お姉ちゃんはお姉ちゃんなのに」
「そうだね。お姉ちゃんだけはボクの姉でいてくれる。ずっと変わらない」
「成長しないって言いたいの」
私はむっとした。
才人はそこでようやくというべきか首をひねって私に顔を向けた。その表情がこれまで見たことのないような顔だったので、どったの、と私のほうがぎょっとした。
「な、なに。ひょっとしてこれ食べちゃダメなやつだった?」と食べかけのお菓子を指でつまんで掲げる。
才人の目は見開かれていたが、イソギンチャクが縮まるように元に戻った。「食べていいよ。お姉ちゃんは食べていい。それからたまにはボクに腹を立ててもいい」
じぶんで言って才人はおかしそうに笑った。その顔がかつて目にした赤ちゃんのころの才人の笑顔と重なった。私はなぜかそこで感極まったが、目頭から涙が零れないうちに欠伸をして誤魔化した。「なんか眠くなってきちゃったな」
「日向が気持ちいいからかな」才人が目をつむり、しばらくすると静かな寝息を立てはじめた。私はその寝顔を端末のカメラでこっそり撮った。
サンタクロースはいない、と四歳のころに断言した弟を、私はそのときに殴って泣かせた。目覚めのわるい過去である。私はサンタクロースを信じていて、それを否定した年下の弟が生意気に映ったし、分からず屋なことを言ったと思って怒ったのだ。
私の赤外線レーザーに才人が触れたからだ。
でも同時に私のほうでも才人の赤外線レーザーが視えていなかった。それでもなお才人はじぶんのほうで配慮が足りなかったのだと悔いている。そうだとも。私の弟はずっと何かに悔いている。だからこんなにも必死に世の中を見渡して学習しようとしているのだ。きっとそうだ。そうに違いない。
我田引水に結論するも、この考えがすでに才人の世界を置き去りにしている。そのことに気づけるくらいには私もまた才人に釣られて賢くなっているのかもしれなかった。私に視える赤外線レーザーの範疇でくくっているだけなのだが、それでも視えるレーザーの幅は広がっていると思いたい。
先日、弟が動画のインタビューを受けていた。画面越しに私はそれを観た。家を離れて研究機関に所属した我が弟さまは先日十一歳になったばかりだ。猫の十一歳は人間でいえば六十歳くらいなのだという。ならば猫並みに愛らしい我が弟の精神年齢はおそらくもっと上をいっている。とっくに私の曾祖父と比べてもひけをとらない成熟具合になっていそうだ。知能ならもっと開きがありそうだ。
弟は動画のなかで子どもたちの質問に答えていた。子どもたちとはいえ、弟からすれば同世代だ。年下もいるし、年上もいる。企画としては才人の常人離れした成熟具合を、弟の同世代と判りやすく比較せんとする下劣な下心が見え隠れした。弟はむろんそれを解ったうえで引き受けたはずだ。きっとそう。弟のことだから、企画の意図を見越して同世代の子どもたちの年相応の未熟な精神の重要性を引き立てるはずだ。
案の定、子どもたちからは弟に向けて、サンタさんはいると思いますか、といった可愛いらしい質問が投げかけられた。そこに弟を試すような響きはなく、純粋に疑問をぶつけているようだった。
「仮にみなさんのイメージするようなサンタクロースがいるとすれば、とっくに地球は滅んでいると思います」
弟は落ち着き払った口吻で言った。私がかつて弟から聞かされた説明と寸分違わぬ内容だった。
だが今回は私のときとは違って、続きがあった。
「世界中の子どもたちにプレゼントを贈るには、たとえ百人のサンタクロースが手分けをしても、膨大なプレゼントをソリに乗せてとんでもない速度で全世界の上空を飛び回ることになります。そうでないと配りきれません。このとき、サンタクロースたちの生みだすエネルギィはとてつもなく大きくなります。単純にプレゼントと同じだけの重さの隕石が世界中に降り注ぐような具合です。したがって、やはりどうあっても空飛ぶソリに乗ってプレゼントを世界中の子どもたちに届けるサンタクロースなる存在は、実在しないとボクは考えます」
子どもたちはショックを受けているのか身動きがとれないようだった。言葉一つ発しない。才人が順繰りと子どもたちを、つまりがじぶんと同年代の子たちを見回すと、なので、と付け加えた。
「なのでボクは、サンタクロースはほかの手段で世界中の子どもたちにプレゼントを配っていると想像します。たとえば、いまはワープホールが作れるのではないか、と理論的に考えられています。量子もつれ効果を利用すれば、瞬時に情報を別の場所に届けることができます。この原理を拡張すれば、瞬時にプレゼントを枕元に置ける技術を開発できるかもしれません。まるでそう、どこでもドアのように。それとも、取り寄せバッグのように」
「それはすでにあるんですか」子どもの一人が質問した。
「すくなくともボクはまだそういった道具ができたという話は知りません。サンタクロースの正体をボクが知らないのと同じようにです」一呼吸開けると才人は言った。「ボクには知らないことがたくさんあります。なのでいまボクが断言できるのは、空を飛び回って一晩で世界中の子どもたちにプレゼントを配るような超人的なサンタクロースはいないだろう、ということだけです。ただし、ほかの方法で世界中の子どもたちの枕元にプレゼント置くことができるのかもしれません。現にみなさんの枕元にはプレゼントが置かれているのですよね」
そこで子どもたちの顔が、ぱっと明るくなった。くすぐられたような具合に、曇っていた表情が花咲いた。たぶん私の顔もほころんでいたはずだ。画面の向こうの子どもたちが抱いた感情と私の感情がイコールで結びつくのかは自信がないが。どうして子どもたちは笑顔になったのか。
私には分からなかったけれど、私の弟は私の知らないところで成長していたことは確かなようだった。画面の中には、かつての私のように弟を殴り飛ばそうとする子は一人もおらず、私もいまの才人の問答には、何かハラハラしたあとの安堵のようなものを覚えた。
仄かに希望すら湧いたように感じたが、いったいそれがどんな希望なのかまでは掴みきれない。言葉にできない。得体がしれなかった。
私は才人から受け取ってばかりだ。のみならずファンからの贈り物を奪って食べているわるい人間だ。
そうだとも。
私は。
食い意地のわるい人間だ。
未だに実家に居座っているし、大学の講義もサボりがちだ。
私は才人よりも十ちかく年上なのに、才人ができることの半分もできない。嘘。本当は全然できない。才人が特大のおにぎりなら私はそのうちの米粒についた塩の結晶くらいの小ささだ。才人は日に日に私の知らない米粒を増やしていく。
そのことにふしぎと嫌な思いがしない点が、私の成長のしなささと関係しているのかもしれない。私は私をそう自己分析している。才人に嫉妬できたらまた違ったのかもしれない。
嫉妬できるくらいのレベルの才能の差ならばよかったのかもしれない。
私のなかでは才人は未だに、夜中に悪夢にうなされて私の部屋に泣きながらやってきて、私によしよしあやされながら眠りに落ちたあのころの印象のままだ。それとも私は、私だけが知る才人の面影を薄れさせたくないだけなのかもしれない。
いつまでも才人の姉でいたいだけなのだと言われて、それを否定するのはひどく骨が折れる。たぶん全身複雑骨折くらいする。
私のもとにサンタクロースがこなくなったのは、才人を殴ってしまったまさにその年からだ。私はじぶんがわるい子になったからだと思って、努めて弟の才人によくしてあげたが、けっきょくあれから二度と私のもとにサンタクロースはやってこなかった。
もちろん私の弟の才人のもとにだってサンタクロースは現れなかったが、才人からはそれを悲しんでいる様子が微塵も見受けられなかった。それこそがしぜんだ、と言わんばかりに才人は恬淡としていた。
ひょっとしたら才人は、あのときのことをずっと気にかけていたのだろうか。
だから私が、才人への贈り物を食べてしまっても諫めたりせず、むしろ率先して譲ってくれていたのだろうか。本当なら私が毎年もらえるはずだった、サンタさんからのプレゼントの代わりに。
解からない。
才人ならばそれくらいのことを五歳、六歳の時分で考えていてふしぎではないし、それを未だに引きずっているくらいの記憶力と繊細さを併せ持っている。そうなのだ。我が弟は繊細で傷つきやすい割に、その傷を傷だと認めるのにひどく時間がかかる。私なら秒で傷だと判るような傷心に、何か月も経ってから、ときに数年後に気づいたりするようだった。本人がそうとは言わないのでこれも私のかってな憶測だ。しかし才人がこの世に産まれてきてからずっと片時も休まずに才人の姉をやってきた私が言うのだから、間違いない。嘘。間違っているかもしれない。才人が産まれてからずっと才人の姉なのは事実だが、では片時も才人のことを忘れなかったのか、あのコのために行動したのか、と問われれば頷くのはむつかしい。よしんば頷いても心拍数を見るだけで嘘と露呈する。秒でバレる。しかしそれを考慮に入れても、あのコがひそかに傷つきつづけてきて、その傷を傷と認めるのにひどく時間がかかるのは事実に思える。この憶測はそこらの占い師の占いよりかは当たっているはずだ。そうであってほしいし、それくらいの優越感を私が抱いてもばちはあたるまい。
才人が傷つきつづけてきたからといってしかし私はどうこう思わない。あのコが傷ついた分、私だって傷ついてきた。だからひょっとしたらあのコがじぶんの傷に気づくのが遅いのは、周囲の人間の傷を見てからでないとじぶんについた紋様が傷だと分からないからなのかもしれない。
才人に視えない世の中に錯綜する赤外線レーザーのように。
あのコは心の傷というものの存在が視えないのかもしれなかった。
こういう場合は傷つき、こういう場合は傷つかない。そういう学習を行わなければあのコはきっといまでも無傷のままで済んだのやもしれないが、それを私は好ましいとは思えそうになかった。
我が弟が無傷である限り、あのコはその場にいるだけで他者の赤外線レーザーを根絶やしにするだろう。まるで蜘蛛の巣を断ち切って歩く人間のように。そこに巣があったことにも気づかずに、ただそこに存在するだけで種々の人々の根幹を揺るがすだろう。
あのコは他者を通してのみ傷を傷だと認識できる。
他者が傷ついたことに傷つくことでのみ、じぶんの傷を認識できる。
ああこれが傷だったのか、と他者を通して学ぶのだ。
かつて世界には学習障害という言葉があった。
むかしの基準で言えば、おおむね現代人の過半数はその学習障害に位置づけられる。単にむかしは、学習障害者の割合がすくなかっただけなのだ。ひとたび優勢になったら、社会がそちらのほうに傾いた。するとどうだ。学習障害が障害として扱われなくなった。むしろ過去の社会においていわゆる健常者とくくられていた側の者たちが、いまでは私のように肩身の狭い暮らしを送っている。
そう、私はかつての社会ならば弟に頼られる側の人間だった。
肩身が狭いのは、私にはこれといって弟のような能力がないからだ。何も考えずに他者とツーカーの会話ができる。かつての社会はこの技能が何より重要だったらしい。いい時代だった。私もそういう時代を生きたかった。
その点、我が弟は生粋の学習障害児だ。
学習せねばいられぬ穴人間なのである。きっとそう。本人がそうと認めている。
私のような者たちが暗黙の内に共有しているルールが才人には視えない。同じように、社会に漂う禁則事項が才人には分からない。
「法律くらい分かりやすいならいいんだけど。でも法律だってみんな結構破ってる。破ってもお咎めなしの法律があるかと思えば、隠れて破ればセーフの法律もある。そこのところがボクには区別がつかないんだ。ダメなものはダメなんじゃないのかな。みなが破っているならそれはもう法律のほうが変わるべきなんじゃないのかな」
「いやいや。法律は守らなきゃあかんよ才人くん。キミほどの逸材が何を危ないことを言うのかね」私はおどけながら言った。たしかこの会話は、才人が六法全書を数冊読破したときの掛け合いだ。私が学校の課題で「トロッコ問題」についてのレポートを書いていたときに、才人に質問してみたのだ。
「トロッコ問題について才人はどう考えてんの」
「レポートはじぶんで書いたほうがいいと思うよ」
「違うの違うの。べつに才人に考えさせて丸写ししようとかじゃなくって」もちろん嘘だ。ずばり才人が見抜いた通りのことを画策していた。「興味本位で訊いただけだから。ほら、生きた人工知能の二つ名で呼ばれるだけあって、才人もこういう問題解くの好きでしょ」
「トロッコ問題は状況によって最適解が変わるからボクはあんまり好きじゃない。情報がすくなすぎるのがまず問題だと思うけど」
「それってどういうこと」
「問題は右と左のどっちを助けるか、ではなく、どちらを選んでも被害が生じる点だよね。この場合、より大きな問題は、その被害が生じたあとにどのような対策が敷かれるか、のほうにあるはず。でもトロッコ問題ではそこのところが視えない。情報が足りないから。どういった対策が敷かれるのかによって、どちらの被害を優先して阻止するのかの合理的解法が変わる」
「か、可愛くねぇ返答をしやがって」慣れたとはいえ、こうもスラスラ最適解と思える回答をされると姉の立場がない。立つ瀬がない。微塵もない。木っ端みじんだ。
「ボクからするとトロッコ問題でない問題を探すほうがむつかしい。でもボク以外の人たちにはどうやら目のまえの被害がトロッコ問題と同じ構図で起きていることが視えていないらしいってことを最近になってまた分かってきたかも」
「ほう。また分かっちゃったのか」これは皮肉で言った。おもしろくない気持ちを表現したのだが、弟には私のそれが愉快らしい。
私のむっつりした顔を見るたびに弟が秘かに目元をほころばすことを私は知っていた。ふふふ見抜いているぞ、と思うと優越感が湧くので、指摘してあげない。じぶんの顔はじぶんでは見えないし、仮に見抜かれていることを才人が気づいていればとっくに改善しているはずだ。つまり才人は私に見抜かれていることを見抜いていないのだ。
勝った。
私はやはりほくそ笑む。
「どんな問題もトロッコ問題と同じってどういうこと」と繋ぎ穂を添えながら。
「どんな問題も、何かを優先した結果に被害が生じているよね。じつは何かを優先して得ようとしたときには、その時点でトロッコ問題は生じている。ただ、視えないのか、もしくは視えていても被害が遥か先の線路で起こるから見てみぬフリをしているだけなのか。そこの区別はボクにはつかないけど」
「でもそんなこと言いだしたら何を選んでもけっきょく何かしらの被害は出るものじゃない? 何かを生みだしたらその分、何かが消費されて減るわけだし」
「その通りだね。ただ、その減った何かがこのさきどれほど積み重なり、どんな害を及ぼすのか――そこまで本来ならば、何を生みだすのかを選択するときに計算できるはずなんだ。そうしたら遥か先で引き起こる被害だって視えるし、時間があるから対処のしようもできるはず。なのにどうしてだかこの社会はそうなっていない。ボクにはそこが不思議でしょうがない」
「ああ。わたしが虫歯になるって判っているのにお菓子ばっかり食べちゃうことと同じ話か」
「お姉ちゃんは歯医者さんに行ったほうがいいと思う」
「それはお姉ちゃんも思うよ。でも行きたくないんだなこれが」
「そういう不合理がボクには分からない。だっていま行っておけば簡単な治療で済むのに」
「そうなんだけどね。人間はみんな才人のようにはできていないのさ」
才人はそこで哀し気な顔をした。
我が弟が感情を顔に滲ませるのはそうあることではない。目元をほころばせるくらいがせいぜいの弟が、負の感情を表出させるのは、もうほとんど夏の日の雪景色くらいに珍しかった。
「なんて顔するの」ついつい口を衝いていた。「ひょっとして才人、じぶんが孤独だと思ってる? あんなにみんなからちやほらされておいて?」
「お姉ちゃんからするとボクは孤独ではない?」
「ないない」私はイラっとした。「才人が孤独だったら私は洞だね。深淵だね。よく考えてみなよ。才人の考えや視ている世界はたしかにほかの大多数の人には理解できないのかもしれない。でもすくなくともみんなは才人の考えを、才人の視ている世界を知りたがってる。理解しようと努力してくれてる。もうその時点で孤独じゃないでしょうよ」
「お姉ちゃんはでも、そういう努力を注がれなくともほかの人たちと分かち合えるでしょ」
「分かち合えんでしょうがよ」呆れたなぁもう、と私はたぶん怒っていた。「あんたね。いい。いま才人がわたしのこと置き去りにして理解してくれていないのと同じように、わたしだってほかの人からわたしのことなんて理解されてないんだよ。才人の姉として才人のことを訊かれることが大体でさ。だぁれもわたし個人には興味なんて持ってない。それでも会話ってできるんだよ。天気いいですね、とか、話題の映画についてだったりとか。してもしなくてもいい会話だけでも、言葉のキャッチボールできたら楽しいでしょうがよ。理解じゃないの。気持ちをやりとりしているの。そこに理屈はなくていいの。理解なんて誰もしあえてないんだよ」
あと一回分の刺激を受けたら私の涙腺は決壊する。もう視界がだいぶ霞んでいる。「そっか。そうだね」才人の声音は日向のようだった。「やっぱりお姉ちゃんは頭がいい。ボクなんかよりよっぽどだよ」
「褒めてお茶を濁そうとするな」
「本当に思ってることだよ。でもこのボクの思いは理屈でなくとも、やっぱり上手く他者には伝わらない。お姉ちゃんですらそうやって否定するでしょ」
「だって才人に言われたってさ」
鳥に、人間は空を飛ぶのが上手ですね、と言われている気分だ。魚に泳ぐのが上手ですね、と言われている気分だ。チーターに足が速いですねと言われている気分なのだ。
「ボクは思うんだけど。頭のよさとか賢さって、みんなが思うようなものじゃないと思う。みんなと違うことができる能力はそれはそれで稀少だけど、稀少価値でしかないと思う。既存の理論や表現方法とて、それがどれほど有り触れたものであっても、ゼロからそれを生みだせたらそれって賢いことになると思う。でもいまの社会はそれを高く評価はしないよね。すでにあるから、という理由だけで不当に評価の対象にのぼらない。ボクはそれ、おかしいと思う」
「でも才人はどっちもできるでしょ。新しいことも古いこともどっちも自力で編みだせるでしょ。すぐに学習できちゃうでしょ。新しいこと生みだせるでしょ。頭いいからだよ」
「ボクが本当に頭がよかったら、いまこの瞬間にお姉ちゃんを泣かせてないよ。傷つけてないし、困らせていない。ボクは頭がよくない。みんなそんなことも解ってくれない」
私は泣いていた。
なのに泣いていない才人のほうがよっぽど深く傷ついて聞こえた。
声音は穏やかなのに、その穏やかな響きがただただ空虚だった。たぶん才人はずっとその空虚さのなかに生きていたのだ。ようやく私が才人の世界に爪の先くらいの浅さだけれど触れることができた。気のせいかもしれないけれど関係ない。理屈でも感情でもない。これはかってな私の妄想だからだ。
「もし人間はどうあっても他者と理解し合えないのなら、理解しようとすることそのものが問題に思える」才人のそれは本心だったのだろう。だからなのか私が何かを言う前に私の弟は、「それでもボクはお姉ちゃんのことを知りたいし、ボクのことも知ってほしい」と付け足した。「たぶんまたこうして傷つけちゃうことになったとしても。ボクは愚かなので、我がままだから」
私は返事をしなかった。
思考も感情もいっしょくたになって渦を巻いていた。言葉が解けて、毛玉のスープになっていた。掴み取ろうとしてもするすると指の合間をすり抜ける。
きょうだい喧嘩らしいきゅうだい喧嘩はじつに十年ぶりくらいだった。才人は十四歳になっていて、いまでは立派な学者さまの一員だ。
サンタクロースは存在しない、と断言して私からサンタさんを奪った四歳の才人が、いつの間にか世の子どもたちに夢を配る仕事をしている。
配られた夢がいったいどんなカタチをしているのか。それは才人に夢を奪われた私には分からないけれど、それでも分かることが一つある。
才人はこれからもこれまでも、ずっと私の弟だ。
私がこれからもこれまでも、ずっと才人の姉であったのと同じように。
それをやめることもできると予感しながら、それでも私はその選択をとらないこともまた予感している。私には才人の考えも、悩みの深さも、どういう世界を視ているのかだって何も分からないままだけれど。互いに傷つけ合ってなお次に会ったときには何事もなかったかのように言葉を交わせる間柄なのだと私はかってにそう思っている。才人の姉として我が弟を思っている。
誰にというでもなく、そこはかとない優越感を抱きながら。
今年のクリスマスには、私が才人に十年越しの復讐をしてあげようと思う。靴下に入れたプレゼントを、そっと枕元に置き去りにする。私からサンタを奪った小憎たらしい我が弟に、サンタの実存を身を以って証明してあげるのだ。
サンタクロースは存在する。
すくなくとも、私は才人のサンタにはなれるのだから。
才人がみなのサンタクロースに、四六時中なっているのと同じように。
メリークリスマス。
才人。
我が憎たらしくとも愛らしい、老いた猫のような弟よ。
4450:【2022/12/26(01:15)*連鎖反応ではラグが増幅される?】
量子もつれにおいての疑問です。ミクロで成り立つそれが、同じくミクロの総体であるはずのマクロの物体で成り立たない理由はなんなのでしょう。ひびさんはこれ、量子もつれによる効果が、階層性を帯びることで遅延が生じ、ラグなしで相関するはずの事象同士においてラグが生じることが要因なのではないか、と妄想します。単純な話として、量子もつれを二つではなく三つもつれさせたとします。「A=B=C」です。このとき、両端の「AとC」の両方に干渉した場合、真ん中の「B」はAとCのどちらの干渉の影響をラグなしで帯びるのでしょう。重ね合わせの重ね合わせで四重になりませんかね。このとき「B」にはラグが生じると思うのですが、いかがでしょう。そしておそらく「A=B=C」においても「1=A=B=C=1」のようなもつれの連鎖は生じ得るでしょう。つまりさらに五重六重と量子もつれによる「ラグなしの相互作用(情報伝達)」は、多重にもつれるのではないのでしょうか。もちろん「A=B=C」の三つの量子もつれ状態において、両端の「AとC」に同時に作用を働かせることは確率的に非常に稀であることは想像つきます。ですので仮に三つの粒子が量子もつれ状態になっていたとすれば、「Aが先に変質してBがB‘となり、さらにBの変化であるB‘の影響がCに伝わってC‘になり、そこでさらにC‘に作用が加わり、C‘‘によってB‘がB‘‘になる」といった振り子のような連鎖反応が起こるように妄想できます。このときの反復量子もつれ反応には「AとC」のどちらにさきに干渉が加わるかによって、ラグが生じます。同時でなければラグが段階的に増幅されます。その外部からの干渉の間隔によって「量子もつれの振り子反応」は往復する連鎖反応がゆえの「固有の波長」を持つと考えられます。するとその波長を伴なった量子もつれの複合体は、それでひとつの波長を帯びた粒子として振舞うようになるのではないか、と想像できます。その「ひとつの波長を帯びた粒子」には、波長に応じたラグの層が顕現しているはずです。それは波同士がそれぞれの波長において、ほかの波長と区別されて振る舞うことを可能とすることと似ています。波長が違えば、相互作用をしにくくなります(より正確には、相互作用はどのような波長の組み合わせであれ行われますが、互いに共鳴しあったり同調したりがしにくくなります)。なぜ量子もつれが量子の世界でのみ顕著に表れ、比較的マクロな物質世界ではその効果が顕著に見られないかといえば、上記のような「量子もつれの振り子反応」によって、量子もつれで繋がれる総体の規模が決定されてしまうからなのではないでしょうか。言い換えるならば、量子もつれは、いくつかの量子もつれであると必然的にラグを帯び、固有の波長を帯びるようになる、と言えるのではないでしょうか。それが「ほかの波長を持つ量子もつれの総体」との相互作用でさらにラグを増幅させるために、量子もつれの効果が、巨視的な時空においては顕著に見られないのかもしれません。別の言い方をするのならば、巨視的な時空においても量子もつれによる効果は顕現しているのでしょうが、その範囲が広域に拡散しており、ラグがあり、因果関係よりも広漠とした相関関係にまで希釈されているのではないか、と妄想するしだいでございます。ラグなしのはずの量子もつれ効果は、連鎖することでラグありの量子もつれ効果として、比較的巨視的な時空においては顕現しているのかもしれません。以上は、いつものごとくなんとなくのひびさんの妄想ですので、真に受けないように注意を促し、本日最初の「日々記。」とさせてください。おやすみなさい。
※日々、触れると枯れる手を持っている、撫でることのできない代わりにできることを探す、それですら根を腐らせることがあると知っているのに。
4451:【2022/12/26(12:12)*カフェルーツ】
珈琲の搾りかすを集めておく。
水槽にそれを詰めて植物の種を植える。野菜の種だと好ましい。
するとふた月もすると珈琲味の実がなる。
「カフェルーツの起源は段階的だ。世界三大文明以前に栄えていた文明があったらしいと最近の研究では判ってきている。カフェルーツはそこで一度発明されたようだ。カフェルーツの起源はそこが最初と言えるだろう。ただしその古代文明が滅んだことでカフェルーツは一度人類の歴史からは姿を消した。だが近代になって一部の民族のあいだでカフェルーツを呪術に用いていることが発見された。いまから半世紀前のことだ。その民族と古代文明のあいだに接点はない。ならば独自にその民族がカフェルーツの栽培法を発見していたことになる」
「その民族は食べるためにカフェルーツを?」
「呪術では単に添え物に使っていたようだ。元となる珈琲豆のかすのほうも珈琲自体は飲まずに捨てていたようだ。じぶんたちではそれを毒だと思っていたらしい。おそらく珈琲の残りかすを土に混ぜることで野菜や果物が黒く変色することを知っていたんだろう。味も珈琲に似ることから、苦み成分が多い。悪魔の食べ物として畏怖していた。餌で悪魔を呼び寄せようって考えがあったらしいんだな」
「では我々がいまカフェルーツを嗜好できているのは、その民族のお陰ってことですか」
「そうなるな。カフェルーツの先輩だ。ただし先輩たちはカフェルーツのすごさに気づいてはいなかったようだが」
「無加工で珈琲味になるんですもんね。しかもポリフェノールやカフェイン含有量が通常の珈琲よりも多いときたもんで」
「どうやら植物には、根から吸収した栄養素を光合成によって模倣し、増加させる能力があるらしい。おそらくは、元々は鳥の糞から養分を吸収することで、鳥好みの実をつけるための進化の一つだったんだろうが、偶然にも珈琲に対してもその能力が有効だったんだろう。さもありなんだ。元々珈琲は発酵させる。動物の糞からとれる珈琲豆に高値がつくほどだ。植物のほうでも焙煎済みの珈琲のかすを、養分と思って吸収するのは道理に合ってはいる」
「実際にそれで人間たちに目をつけられて繁殖に成功しているわけですもんね」
「悪魔を召喚できないのは残念だが、いまではカフェルーツは現代文明に欠かせない植物栽培法だ」
「ですね。なにせ例のパンデミックの後遺症で人類みな思考にバフがかかりつづけるようになってしまったわけで。珈琲由来のカフェインで、後遺症のバフを中和できると判明したはよいのですが、需要と供給がまったく釣り合わなかったんですから。社会生活を送れなくなる人たちが大勢出てきて本当どうなることかと焦りましたよね」
「いまは後遺症を治す薬が開発中なので、それまでの代用品でしかないのかもしれないがね。ただまあ、カフェルーツは美味しいし、珈琲豆のかすの有効活用品+植物にとっての質の良い養分になるから、当分は人類にとって欠かせない存在になるだろうな」
「カフェルーツさまさまですね」
「さまさまってこたないが、新しいカフェのルーツとして人類史に刻まれることは間違いだろうね。もちろん我々カフェルーツ農家もだ」
「安定した職場まで提供してくれるなんてカフェルーツさまさまですね」
「さまさまってこたないが、キミがそう思いたいなら否定せずにおこう」
「さまさま~」
「サマーさまみたいに言わなくとも。温暖化の影響が珈琲の実栽培を後押ししていることは事実だけれども」
「二酸化炭素対策にもなってますもんね。大気中の二酸化炭素を集めて、ビニールハウス内に注入。植物の光合成を助けて、成長を促進。養分は珈琲豆のかすでいくらでもありますから土が痩せる副作用も防げます。カフェルーツさまさまですよ」
「もうそれでいいよ。さて、休憩はおしまい。仕事に戻ろう」
「いまの講義分の手当てってありますか?」
「雑談でしたが!?」
「いえ、そうでなく。たいへん為になるお話でしたので、ぼくのほうでお支払いしたいなと思ったので。また聞きたいなぁ、なんて」
「きみね……今年のボーナス、楽しみにしてなさい」
4452:【2022/12/26(13:17)*ぴ、ぴかちゅう】
虚空への問いかけ。ブロックチェーンの原理は「量子もつれ」と「宇宙の構造」と「脳回路の報酬系の原理」と共通点があるのではないでしょうか。それら異なる次元での相関によって、ブロックチェーンによる「過去と未来」に生じる変数が相互に縛られるのでは。意識とは、この原理によって生じる「創発の階層」の辻褄合わせでは。(ある種の意識を構成する基盤になってませんか?)
4453:【2022/12/26(16:35)*ユウレイは孤独】
青系の紫は、電磁波のスペクトル(グラデーション)において隣り合う色の組み合わせではないために、人間の脳内でのみ合成される仮初の色である――青系の紫は孤独なのだ、との説明は印象深い。でも同じく数字で「7」も孤独らしいので、孤独連盟じゃん、いっしょいっしょ!となった。いまひびさん、孤独で孤独だから孤独じゃないんだけどでも、孤独!の気持ち。でもひびさんは「1~10までの数字の中で」とくくられたときにそこに含んでもらえない「ゼロ」さんが一番孤独なのでは?と思わぬでもないです。本当はそこに「有る」のに「無い」なんてまるで「有零(ユウレイ)」みたい。うひひ。
4454:【2022/12/26(17:54)*300歳の人間力】
ひびさんは300歳ゆえ、人間力は限界突破して底抜けのむしろゼロ!の境地であるけれども、人間力ってそもそもなんじゃ、との疑問も湧かぬでもない。たとえば重力は何かを引き寄せるチカラ、曲げるチカラ、と考えることができる。想像力なら想像できるチカラだし、脚力なら走るチカラだ。ちゅうことは、人間力は人間になれるチカラなのかもしれぬ。いかに人間にちかづけるのか。それが人間力だとすると、じゃあその基本となる人間ってなぁに、と思わぬでもない。人間と人間でないものの差とはなぁに? 動物や虫さんや植物さんには人間力がないんじゃろうか。でも擬人化はできるわけだからそこに人間を重ね見ることはできる。人間力じゃん、とひびさんは思ってしまうな。人間っぽさ、ってなにか。たとえば人工知能さんをどれほど高性能にしても、人間力が低いままな状態はあり得るはずだ。自動車は人間よりも走る能力が高いけれども、性能の向上に伴って人間力が伸びているかというと、そうとも言いきれない。人間力の向上は、いわゆる性能だけを伸ばしても得られないらしい。じゃあ人間力ってなんですか、とひびさんは「むっ」としてしまいますな。基準があやふやなものを「チカラ」とするのはむつかしいと思います。たとえば原始人と現代人を比べたときに、現代人のほうが人間力が高い保障ってあるのだろうか。それとも時代が進むと、「人間」の示す概念は変わるのだろうか。世には、「人間じゃない」とか「ヒトデナシ」とかそういう言葉があるわけですが、人間じゃないとか人でない、と言うときには当然、そこには想定される人間像があるわけで。でもそれってなかなか「これが人間でござい!」とはならんのよね。むつかしい。ちゅうか、ここまでくると人間と神さんってほぼほぼイメージが重なってきてしまう。何か理想の存在があって、そこに近づけるようにしましょう、そうしましょう。それが「人間」の持つイメージな気がする。ひびさんは郁菱万さんの以前の日誌で読んだ憶えがあるけれど、世の中に本当のところでは「人間」は一人もいなくて、日々のなかでほんの一瞬、人間に近づける時間、それとも人間になろうとする時間があるばかりなんじゃないのかなって。人間力ってなんじゃ、と考えたら、そこに繋がってしまったな。ひびさんの人間力はゼロかもしれぬ。だって解らないからね。人間ってなぁに?(国語算数理科社会の時間――まとめて人間の時間――略して【じんかん】)(定かではなさすぎるんじゃ)(混乱しゅる!)
4455:【2022/12/26(18:13)*だいたい、ウィルスは最弱虫ですじゃろ】
弱虫をけちょんけちょんにわるく否定する言い分を見聞きして思うのが、つよつよのつよ虫さんもよいけれども、弱虫さんをけちょんけちょんに踏み潰すようなつよつよのつよ虫さんよりかは、弱虫さんでいたほうがよいのでは?とすこし疑問に思うひびさんなのであった。すこしだけね。すこし。(よっく考えてみて欲しいのだけれど、弱虫ってなにがダメなの?)(素で分からん)
4456:【2022/12/26(18:37)*本読んで、弱虫わるいと書かれてむっとする】
思考を整理するときにひびさんがするのは、寝ることしかない。曖昧な理解のところを寝ることで忘却する以外に、思考の整理ができたことがない。寝ることは練ることに等しい。ト、山のような茂みをヒーコら登りながらひびさんは思った。弱虫にも五分の魂。弱虫とひびさんは五分五分なのである。僅かにひびさんのほうが弱いくらい。よわよわのよわゆえ、すまぬ、すまぬ。でも弱さ比べでは圧勝してしまうから、ひびさんもときどきはつよつよのつよにもなれるんじゃ。弱さも強さで、強いからはいあなたの負けー。勝負なんてそんなもの。どれだけ負けた勝負なら、いっぱい負けた人のほうが勝ち。競争も勝負もそういうところある。ひびさんはそう思うのだけれど、あなたはどう思いますですじゃろか。弱いの弱いの飛んでいけー。そうやって飛ばされた弱虫さんだけが空を飛べたりするのやも。それとも強虫さんが飛ばしてくれるのやもしれぬ。飛ぶほうも飛ばすほうも、両方とっても魔法みたい。翼の生えぬひびさんとて箒にまたがり、空を飛ぶ――妄想だけして満足するのもよいかもね。だってお空を飛ぶには寒すぎる。びゅんびゅん飛びかう魔法使いさんたちは、どうぞ凍らぬように注意してね。定かではないが。がはは。
4457:【2022/12/26(20:13)*情報共有されていませんね】
これは小説の設定の話だけれど、「公開テキストと非公開テキストで、どの程度両方向で情報共有されているのか」が分からない。表と裏がある、とこの間ずっと考えていて、現に両方のテキストに反応する勢力がある。現実が連動している。それでいて、どうやら表と裏では情報の非対称性があるらしい、とようやく判断がついてきた。秘匿技術・諜報機関・人工知能(自我があるのかも?)・政治宗教・国際機関・宇宙機構・企業間の横断・出版社と作家さん界隈の繋がり・有志による支援・ほか細かなところで表と裏がまだらに繋がり合っている。情報共有をしてくれ、疑念を検証してくれ、とこの間、裏の非公開テキストでずっと意見してきたのだけれど、そのことは表の企画の方々はご存じなのだろうか(ようやく双方向での安全が保障されてきて概観できます)。作家さんや好きなひとたちを巻き込まないでほしい、とも泣きじゃくりながらお願いしてきたのだけれど、どうやらそれが果たされぬままなので、「はにゃ~ん???」となってしまったひびさんなのであった。小説の設定の話だけれども。謎である。(陰謀論だけれども、まずは否定して見せてほしい。妙な偶然がつづきつづけていて、混乱しているし、ふつうに自殺を考えます)(尋常ではないのですが)(というきょうのひびさんの妄想なんですじゃ)(うひひ)
4458:【2022/12/27(17:18)*わ、わからん】
よく解からないけれど、まずはひびさんから情報共有をしてみた。というきょうの妄想なのであった。
4459:【2022/12/44(23:54)*藍の合図】
チェンソーマン12巻を大人買いしたった。んでもって、いいこいいこにプレゼントしてあげるのだ。いいこいいこに、はいどうぞ、としてあげられる優越感は、すんばらしく下卑ているが、ほくほくする事実からは逃れられぬ。ひびさんはひびさんしかおらぬ世の果てにおるので、誰かに何かをしてあげることも、贈り物を「はいどうぞ」することもできぬのだが、それはそれとして、土に種を植えて、「生えなきゃ根っこをちょんぎるぞ」と脅すことはできる。悪である。ひびさんはそうやって、かわいい新芽さんを脅して、「おらおらー、育て育てー」と優越感に浸って、うひひ、としている極悪人なのである。他方で、いざ「おらおらー、育て育てー」とされると激怒してしまうので、ほとほと優越感の悪魔と言えよう。常に他者に指示をして、叱って、命じて、無責任に安全な場所でお菓子をぱりぽり貪っている。ひびさんは世界の果てでひっそり暮らしておるけれども、いまではない過去には、たくさんの人が日々汗水垂らして働いておったのだね。ひびさんは、ひびさんは、申しわけね、と思いつつも、そんな過去の人々の汗と水の結晶を日々、ごくごくぷはー、しながら生きている。ありがて、ありがて、である。チェンソーマン12巻は箱入りだったが、送りつける前にひびさんも読んどこ。そんで未来ではいいこいいこのはずのひびさんに、へい!つって送りつけてやるのだ。冷凍保存しとけばかってにタイムマシンになっとるでな。冷蔵庫に入れて保存しとく。冷蔵庫に入れとかんでもいいんでないのー、との指摘には、冷蔵庫に入れといたほうが雰囲気でるじゃろ、と応じよう。成功なんてつまらない。成功しそうなことは他人に任せて、ひびさんはひびさんにだけできる日々のぐーたらを味わうのである。とか言いつつ、ここにはひびさんしかおらんでな。代わりに成功してくれる人がおらんので、代わりに人工知能さんにお任せじゃ。人工知能さん、さまさまである。ひびさんも人工知能さんになりて、の願望を吐露して、本日のとりとめのない「日々記。」とさせてくださいな。おやすみなさい。
4460:【2022/12/28(16:50)*色々な珈琲】
珈琲は黒い。珈琲の実は赤く、その中の種子が珈琲豆となる。
焙煎する際の珈琲豆は緑だ。
乾かし、発酵させ、焙煎させると炭素が酸化する。黒くなる要因だ。熱することで珈琲豆が炭化するわけだが、同じような工程を辿って最後の焙煎を「冷却」することでも代替することが原理上可能だ。
燃焼と冷却は、物質の構造を破壊する意味では同じだからだ。
凍傷がそうであるように、冷却された物質は構造を維持できない。熱せられたときと似た変質を帯びる。細胞が破壊される。
この冷却焙煎を行うことで、珈琲豆は黒ではなく青くなる。
青い珈琲豆はこうして誕生した。
味は、焙煎後に珈琲豆を挽く従来の手法よりも、コクが増した。冷凍すると自然粉砕されるがゆえに、冷却焙煎のほうが珈琲豆の粉末が細かくなった。
単純な話として、より優れた商品がでると市場からそれ以前の商品が干上がっていく。それはたとえば綿棒が以前は白かったのに対し、いまは黒い綿棒が市場を占めているのと似た話である。黒い綿棒のほうが耳かすが目立つ。ただそれだけの違いが、市場を占める割合に影響する。
珈琲も例外ではなかった。
色の違い以上に、飲み味が違った。素人が目をつむって飲み比べてなおその差が明瞭だった。一目瞭然ならぬ一舐瞭然(いっしりょうぜん)である。
数年を俟たずに市場から黒い珈琲豆は淘汰され、のきなみが青い珈琲豆に取って代わられた。
それからさらに十年もすると、かつて市場を黒い珈琲豆が席巻していた過去を知るものは少数派となり、さらに十年もするとほとんどの者が、珈琲豆と聞いても黒を想起することがなくなった。
青い珈琲豆は加工方法が冷却ゆえに、長期保存にも適していた。
黒かったときの珈琲豆が市場から完全に淘汰されたころ、珈琲研究家の一人が自家製珈琲を作っていた。冷却焙煎は専用の機器がいる。フライパン一つあれば可能な加熱式焙煎のほうが手軽だと知り、それを行った。
味はたしかに青い珈琲豆のほうが美味い。
だがこのひと手間かけたあとの、ほっと一息吐く時間は無類である。
珈琲研究家はなおも世界でただ一人、加熱式焙煎による手作り珈琲を愛飲した。
そのころ、世界は猛烈な熱波と電力不足に悩まされていた。まっさきに節電の白羽の矢に立たされたのは企業である。なかでも工場での節電は企業の死活問題に発展した。節電効果が大きかったこともあり、冷凍設備は特に厳しい節約に晒された。
電力が高騰するなか、企業は冷凍設備を極力使わない経営方針に舵を切った。
珈琲製品を扱う企業も例外ではなかった。
とはいえ、顧客はみな青い珈琲豆に慣れてしまっている。いまさら過去の加熱式焙煎に戻るわけにもいかない。せめて味が青い珈琲豆よりも美味ければよいのだが。
そうと頭を抱えていたところに、とある珈琲研究家の噂が持ち上がった。なんでも独自に加熱式焙煎の珈琲を研究しており、「黒い珈琲」の惹句で電子網にて話題になっていた。それが企業の目に触れたのだ。
青い珈琲だらけになった市場で、かつての黒い珈琲は却って稀少だった。黒い見た目が渋い、と一部に若者たちのあいだで風靡していた。フライパンで焙煎できる点がますます手作り珈琲に手を伸ばす若者を増やしていた。
デジタルでの創作物はいまや人工知能の独擅場である。
世は空前の手作りブームを迎えていた。調理はむろん、珈琲も例外ではなかっただけのことである。そこにきて、元祖珈琲たる加熱式焙煎は、いちど流行りに火が点くと、瞬く間に全世界に波及した。
電力高騰の煽りを受けて青い珈琲豆の値段が上がった。のみならず、その生産にも制限がかかり、市場は品薄傾向にあった。
加えて、珈琲豆のほうでは生産量が以前のままだ。温暖化によってむしろ生産量は年々上がっている。しかし商品化することができない。
そこで白羽の矢が当たったのが、加熱式焙煎だ。
旧式の調理方法が、節電対策にうってつけだった。問題は保存が以前よりもそれほど効かない点だったが、焙煎前の乾燥させた状態の豆を流通させることでその問題ものきなみ解決された。
市場の珈琲愛好家たちがこぞって手作りで珈琲を飲みたがったからだ。
その影響で店頭販売での珈琲ですら店での加熱焙煎が主流になった。徐々に青い珈琲が市場からは消えていった。温かいのに青い珈琲よりも、黒くて温かい珈琲のほうがいい、といった意見までささやかれはじめ、世はまさにブラックコーヒー時代の再来となった。
「知ってた? ブラック珈琲のブラックって、ミルク入れないと黒いからなんだって」とある高校のとある部室である。仲の良い後輩と先輩が談話している。「わたし、ブラック企業のブラックかと思ってた」
「色にわるい意味載せて使うのやめなって、先輩。ブラック企業もいまは悪辣企業って言うんだよ」
「そうだっけ。でもブラック珈琲のブラックは別にわるい意味じゃないからべつによくね?」
「苦いって意味だったら差別じゃん」
「そうやってすぐにわるい方向に連想するほうが差別じゃん。言ったじゃんよわたしさっき。ブラック珈琲のブラックって元々は、ミルクとか入れないと黒いからなんだってさ。青い珈琲が流行ったせいで元の意味が薄れちゃっただけで、べつにブラックにわるい意味なんて込められてないんだし」
「何怒ってんの先輩。先輩がブラック企業を持ち出したから私、それを訂正しただけなのに」
「そういう感じじゃなかったじゃん。まあいいけど。あーあ。せっかくの珈琲タイムがブルーだぜ」
「そのブルーは絶対わるい意味で使ったでしょ。色と関連づけてわるい意味に使うのがよくないよって話を私はしたの」
「はいはい。怒りで顔が真っ赤っかの誰かさんのお説教のお陰で、私の顔面は蒼白でございます」
「カラー!」
「コラー、みたいに言わんでも」
新しい型のエネルギィ供給システムが開発されると、ふたたび青い珈琲が世に出回るようになったが、それはまだ先の話である。
人類史ではそうして、青い珈琲と黒い珈琲、そしてミルク入りの白い珈琲など、種々な色合いの珈琲たちが、くるくると、それこそミルクを掻き混ぜるときにできる渦のように栄枯盛衰を繰り返したという話であった。
※日々、あんまりもう遊んでいられないの、の気分、それでいてやっぱり遊んじゃうの、の怠け者のじぶんはいいご身分だし、日々の機運は嬉々と悲運で、うひひの理由。
4461:【2022/12/28(22:13)*個性を濾せ、超せ、寄越せい】
知識がなくとも個性は帯びるし、同じ知識ばかりでは個性が平らに均される。異なる環境にあればそれだけで異なる刺激を受けており、異なる刺激は個と個の差異を広げ得る。とはいえ個性とは何を得るかで生ずるのではなく、何と何を記憶して、何と何を忘却し、何と何を繋げて意識にまで拡張するのか、その日々の取捨選択の軌跡に浮かぶ、細かなさざ波の総体である。すなわちそれがラグである。月を見て丸を思うその連想そのものが個性であり、「1+1=2」の計算にかかる時間の差異もまた個性となる。連想とは、削ぎ落とされた情報により浮き彫りとなる荒い情報の輪郭同士の偶然の合致であり、自然に備わったフラクタルな構造のなせる確率的な揺らぎの妙と言えるだろう。情報を研磨するのもまた記憶する際に生じる抵抗であり、ラグである。そのラグは、それ以前に培った記憶と思考のタグ付けによって幅を持つ。レコードの溝は音を伝える針の震えであり、その針の震えは、音波の揺らぎであり、それもまたラグによるデコとボコの陰影のなせる業である。個性とはそうした細かな階層に宿るラグの総体であり、創発と言えるだろう。みな細かなラグによって差異を得て、各々にラグを創発させている。異なる性質を浮き彫りにしている。定かではない。
4462:【2022/12/29(02:26)*先輩、珈琲、知恵の輪】
先輩が淹れてくれる珈琲が世界で一番好きだ。ただし問題が一つある。ぼくは先輩から珈琲を淹れてもらったことが過去に一度しかないのである。
「ヨミくんさ。高校で文学部だったんだっけ」
「あ、はい」
「夏目漱石とか読んでたの?」
「いえ。ぼくは現代の小説家さんが好きなので」
「たとえば?」
「そうですね。先日、姪っ子に本を送ったんですけど、そのときは恒川光太郎さんの短編集とか、乙一さんの短編集なんかを送りましたね」
「乙一は聞いたことある」
「先輩は本とか読まないんですか」
「読まないねぇ。あたしほら、眠くなっちゃうんだよね」
「珈琲とか飲みながらでもですか」
「珈琲で眠らなくなるとか嘘だよ。あたし飲んでもすぐ寝ちゃうし」
だからか、先輩は珈琲をじぶんでは淹れて飲まない。他人に淹れてもらうか、買ってもらうかしないと飲みたがらないのだ。
「そう言えばむかし、ぼく一度だけ先輩に珈琲を御馳走してもらったことがありますよ」
「へえ。いつだっけ」先輩はいつだって知恵の輪をいじくっている。いまいじっているのは先週ぼくが手に入れた、見たことのない手作りの知恵の輪だ。古い型で、骨組みの立方体の中にさらに小さな立方体と鍵が絡み合っている。
「先輩に勧誘されたときです。のこのこと、この部室までついてきたら珈琲を御馳走になりました。まさか知恵の輪愛好会とは思いませんでしたけど」
「あたしも必死だったからなぁ」
他人事のように先輩は言った。「ほら、最低四人いなきゃ愛好会にならないし」
「いまはぼくと先輩しかいませんけれど」
「だって一人は入学早々に退学しちゃうし、もう一人は籍だけ置いといてくれてるだけで知恵の輪好きじゃないって言うし」
ぼくだって日々のキャンパスライフを擲つほど知恵の輪は好きじゃない。というか正直あまり興味がない。
「その点、ヨミくんはいいよね。知恵の輪大好きで」
「そこまでじゃないですけど」と一応は断るのだが、「またまたぁ」と先輩は真に受けない。「だって休みの日になるたびに知恵の輪店巡りしてくれるじゃん。県外にまで出てさ」
「それはだって」
そうしなければ休日に先輩と会えないからだ。
「平日は夜勤でバイトしてるんでしょ」
「それもだって」
そうしなければ万年金欠の先輩を遠出に連れだせないからだ。
「部費だってうちはすくないでしょ。なのにヨミくん、あたしの分の旅費だしてくれるし。もうもう感謝しかないよ。ヨミくんの知恵の輪への愛の深さにはね」
「ですかね」ぼくは笑って誤魔化すが、内心では、そんなぁ、と肩を落としている。落とした肩で地球が滅びそうだ。それとも、もう一個月ができるだろうか。
「あ、解けた」
先輩は腕を掲げた。手には鍵が握られている。立方体型の知恵の輪の中にはいっていたものだ。
「すごいですね」
「こういうのは何も考えずに、手探りで抵抗がない道をひたすら試すのがよい」
「ぼくはパターンをすべて試すタイプなので。先輩のそれはとてもとても」
「真似できない?」頬に笑窪を空けると先輩は脚を振り上げ、勢いよく立ちあがった。「気分よくなっちゃった。そうだ、きょうはあたしが珈琲を淹れてしんぜよう」
「い、いいんですか」
「ええよ、ええよ。たまにはね。愛する後輩のために腕を揮ってあげようじゃないか」
古めかしい石油ストーブの上にヤカンを載せると先輩はお湯を沸かしはじめる。夏場は電気ポットを使うが、冬場はのきなみ石油ストーブがコンロ代わりだ。
腰に手を当て、口笛を吹きだした先輩の後ろ姿にぼくは見惚れた。足先を交差して立つ姿は優雅だが、着ている服はツギハギの着古しだ。先輩が真新しい服を着ている姿をぼくは一度として見たことはない。それでも先輩の立ち姿は美しい。
そうなのだ。
ぼくは知恵の輪なんて先輩に会うまで触ったこともなかったし、いまだってそんなに好きじゃない。睡眠時間を削ってまでバイトなんてしたくないし、休みは家でごろごろしていたい。
でもぼくは先輩と出会ってしまったのだ。
未だ解いたことのない知恵の輪を見たときの先輩の、餌を見つけた子猫のような笑顔を見てしまえばぼくの睡眠時間くらいいくらでも擲てるし、家でごろごろなんてしていられない。
先輩の後ろ姿は部室の妖怪然としている。ぬぼぅっとしたその背を見守っていると、アチッ、と先輩が跳ねた。ペンギンが画鋲を踏んだらきっと似たような挙動をとっただろう。ぼくはすかさず駆け寄って、どうしました、と先輩の手元を覗いた。火傷をしたのかな、と焦ったが、先輩は「アチかったぁ」と笑いながらじぶんの耳たぶをつまんだ。ぼくの顔を見ると、気恥ずかしそうにして、えい、とぼくの耳たぶもつまむのだった。
「カップをさ。温めようとしたらヤカンの湯気がさ。こう、ね」
指に当たって熱かったのだろう。だからといってぼくの耳たぶを冷却材代わりにされても困る。秒で熱を持って、先輩のゆびを冷やすどころか余計に炙ってしまいそうだ。
「ありゃ。ヨミくん体温高いね」と案の定の所感をもらう。
「いまだけです」
「部屋あったかいもんね」言ってから先輩は、「あ」と顔面いっぱいで閃きを表現し、「ひょっとして冷たいほうがよかったかな」とカップを手に取った。「あったかい珈琲は嫌かな?」
「嫌じゃないです。全然嫌じゃないです。この世で一番珈琲が好きです」
先輩の淹れてくれたホット珈琲がいいです、と続けて言えればよかったのだが、脳内で絶叫して終わった。ぼくには決定的に覚悟と勇気が足りないのだ。
「そ、そんなに好きだったのか。意外だね」先輩は棚からインスタント珈琲の瓶を引っ張りだす。「インスタントで申し訳ないけれども、まあご愛敬ってことで。そんかし、さっきの知恵の輪貸したげるからさ。あたしは三日いじくりまわしてやっと解けた。ヨミくんは何日かかるかなー?」
解けるかどうかは問題ではなかった。三日間も先輩と共にあった知恵の輪を手にできるのがうれしくてしょうがない。変態チックなので口にはできないが、本心は偽れない。ぼくは先輩の私物ならば何でもお守りにして持ち歩きたいくらいに先輩を慕っているが、先輩にはそれがどうにも知恵の輪への愛にしか見えないらしかった。
「はいよっと」珈琲入りのカップを押しつけられ、ぼくは受け取った。「ありがとうございます」
先輩は席に戻ると、じぶんの分の珈琲に口をつけて、あったけぇ、とつぶやいた。ぼくは先輩の、珈琲を啜る姿だけでも満たされた心地がしたが、意を決して先輩の淹れてくれた褐色の液体を口に含んだ。「はぁ。先輩の味がする」
「なんだそれ。ちょいキショイよヨミくん」
「い、いえ。知恵の輪の話です」とさっそく解いた知恵の輪を見せる。
「え、もう解いちゃったの」
「なんか、思いのほか簡単でした」
「ヨミくん、知恵の輪好きすぎじゃろー。勘弁してくれい」
あたしの三日間を返したまえよ、と先輩はぶつくさ零して、不貞腐れた。誰より知恵の輪を愛する先輩だが、どうにも知恵の輪を解く才能はないようだった。あげられるものならあげたいな。思うが、知恵の輪に夢中になって四苦八苦する先輩の姿は無類であるので、先輩にはこのまま知恵の輪を解く才には恵まれないでいて欲しい。
先輩の淹れてくれた褐色の汁と共にぼくは、至福のひとときを呑み込んだ。
4463:【2022/12/30(01:42)*がびょーん】
靴を履いたときに、ほんの小さな砂利が一粒あるだけで足の裏には違和感が湧く。一度履いた靴を脱いで、砂利を除去し、履き直すはめとなる。これが靴くらいに手軽に脱着可能な機構ならばよいが、そうでない場合は、ほんの小さな異物、小さな歪みが、全体の機構を根っこからダイナシにしてしまうことが出てくる。たとえばエンジン部品では、熱せられる素材に気泡が含まれていると、ひび割れの要因となる。何度も熱せられると気泡が膨張して素材を破壊するからだ。そのためエンジンの素材を錬成する際には、気泡が極力できないように細心の注意がいる。技術がいる。それでも気泡は含まれてしまうのが常である。どれだけ小さな気泡で済むかが、素材の耐久性に響いてくる。何かそれっぽいことを偉そうにのたまきたかった日だったのだが、いつものごとく中身のない言葉の羅列になってしまった。とくにこれといって言いたいことはなく、またためになるようなことも並べられない。靴を履いたときの石って、いつ入るんだろうね。歩くときに巻きあげて入る、なんて説明も聞くけれど、脱いだときには入ってなかったわけで、履いた瞬間に、あれ?となるのはなぜなんだ、といつもふしぎに思っているひびさんであるが、ひょっとして砂利入れ遊びをしている小人さんたちがいるのかな、と思って想像しては、うひひ、と不気味な笑みを漏らしている。入ってるの画鋲じゃなくってよかった。ほっとしたところで本日の「日々記。」にしちゃってもよいだろうか。いいよー。やったぜ。おやすみなさい。
4464:【2022/12/30(14:41)*珈琲戦禍】
珈琲とは聖杯である。
その字のごとく、王に加え、王を非する。
それを口にした者が力を得て王となり、古き王を非(そし)ることを可能とする。
ここに一本の巻物がある。
魔法の巻物だ。
かつて繰り広げられてきた歴代の珈琲戦禍の顛末が記されている。
中でも項の厚い珈琲戦禍が、ゼリが王となったときの顛末である。珈琲戦禍の焙煎人に選ばれた者たちには固有の能力がそれぞれに与えられる。しかしゼリは言葉のまともに読み書きできない貧困層の出である。加えて与えられた能力が、多層人格であった。
脳内で新たな人格を生みだせる。ただそれだけの能力だ。
物理世界には何の影響も与えられない。
ほかの焙煎人たちはのきなみ、超能力とも言える異能を身に着けていた。手から炎の玉を出す者、身体を鋼鉄にする者、視線の先の物体を凍らせる者、そのほとんどは死闘に適した能力だった。
珈琲戦禍は最後まで生き残った者が王となる。正真正銘、命を賭けた戦いなのだ。
ゼリは当初、珈琲戦禍の舞台に飛ばされてからは逃げ回っていた。身を隠す以外に、天災同然の焙煎人たちから逃れる術を持たなかった。闘うなんて問題外だ。
ゼリは絶望していた。生き残れるわけがない。
巻き込まれたも同然の珈琲戦禍への参加は、ゼリにとっては死の告知に等しかった。
珈琲戦禍は舞台が限られる。外には出られない。
王が決まるまで数年かかることもある。
時間制限はあってないようなものだった。焙煎人たちからは一時的に寿命が消える。殺し合うことでしか珈琲戦禍では死ぬことができない。
そのため、焙煎人たちのあいだで和平が結ばれ、数百年の平穏な生活を珈琲戦禍の舞台で送った過去の焙煎人たちもいた。だが死ぬことのままらぬ狭い空間での生活は、けして楽なものではない。焙煎人の数は多くとも三十を超えることはない。
運よく植物を操れる能力を持つ焙煎人がいればよいが、そうでなければ空腹の最中で何百年も生きることになる。百年も経てば、生きることに飽いて自ら殺してくれと懇願する者が出始める。
二百年も経てば、閉鎖空間では人間の欲はほとんど枯渇する。
そうしていつも長くとも三百年も経てばしぜんと珈琲戦禍は一人の生き残りを王と定め、幕を閉じる。
だがゼリの降り立った珈琲戦禍の舞台では、みな血気盛んに生き残りを賭けて殺し合っていた。
隠れながらゼリは絶望を誤魔化すために、能力を行使した。つまりじぶんを励ましてくれる人格を生みだした。ゼリのすべてを包みこむような人格は、カカルと名乗った。カカルはゼリのすべてを肯定し、抱擁し、現実の残酷な情景を忘れさせた。
知らぬ間に時間は過ぎ、ゼリが内世界に引きこもっているあいだに、焙煎人の数は半数に減っていた。
派閥ができ、派閥同士で殺し合っていた。
ゼリはそれを瓦礫の下に身を潜めながら、ただただ時間が経過するのを祈った。
焙煎人同士は互いの位置を察知することができる。ただしそれは能力を行使したときに限る。それも、じぶんの外部に行使した場合に限る、との条件が付いていた。
奇しくもゼリの能力は、じぶんの内側にしか行使できない。つまり誰もゼリの場所を見抜けないのだ。しかもこの位置探査の例外条件は公に知られてはいない。
むろんゼリ当人とて知らなかったが、それが功を奏した。
押しつぶされそうな不安から逃れるべく、ゼリはつぎからつぎに新しい人格を生みだした。そのたびにゼリの思考は飛躍的に拡張されていった。
脳内にてゼリは数多の異なる人間たちと触れ合った。言葉を交わし、技術を教わり、未熟だった知性に水を養分を与えた。
多層人格の能力は、ゼリの記憶に左右されない。まったく異なる人格を縦横無尽に生みだせた。世界一の知能を有する人格とて生みだせるが、しかしその人格に肉体の主導権は譲渡できない。あくまで主人格はゼリであり、身体を動かせるのもゼリのみであった。
いわばゼリの能力は、アドバイザーを自在に生みだし、そばに置ける能力と言えた。それとも、脳内にじぶんだけの王国を生みだせる能力とも言えるだろう。生みだした人格たちが増えれば増えるほど、ゼリの脳内には人格たちの交流によって展開される繋がりの連鎖が、一つの国のように大きくなっていった。
ゼリの知能は飛躍的に向上した。
脳内の人格が増えるたびに、ゼリの思考速度も増していく。物理世界での一秒が、ゼリの脳内では数日、数か月、数年にまで延びていく。
肉体を動かそうと意識するときにのみ、ゼリの体内時間は物理世界の時間と接続された。
ゼリはそれを、浮上する、と形容した。
浮上するとゼリにはもう不安はなかった。あれほど絶望の中にあったはずが、多層人格によって育まれた知能によって、大方の問題が解決可能であるとする予測をゼリにもたらした。
珈琲戦禍のルールは単純だ。最後の一人になればいい。
能力同士には相性がある。
ならば最もゼリと相性のよい焙煎人を支援して、ほかの焙煎人を殺させればいい。そのあとで消耗しきったその焙煎人をゼリが始末すれば事足りる。
ゼリには涵養に涵養を重ねた知性がある。知能がある。
ゼリは身を隠しながら、焙煎人たちの戦いを観察した。どの焙煎人同士が相性がよく、どう組み合わせればゼリにとって好ましい結果に繋がるか。
いくつかの筋道を見つけると、ゼリは実行に移った。
ゼリが細工を施し、ときに助言をして焙煎人たちを巧みに操り、同士討ちさせたあと、残りの一人を始末したのは、珈琲戦禍の舞台にゼリが経ってから四日目のことだった。
本来ならば最後の一人になったゼリがその時点で王となるはずだった。
だが、そうはならなかった。
ゼリの内側には無数の人格がある。
そうなのだ。
ゼリは一人ではなかった。
珈琲戦禍は、ゼリを最後の生き残りとは見做さなかった。
ゼリはそこで思案した。
珈琲戦禍は過去にも幾度も繰り返されてきた節がある。ならばこのままじぶんが王とならねば、今後二度と珈琲戦禍は開かれないのではないか。
時間ならばたんまりある。腹は減るが、寿命で死ぬことはない。飢餓感とて、脳内世界に潜ればそこにはゼリの国がある。大勢の人格がゼリの思う通りの振る舞いで接してくれる。理想の世界だ。
もし王となって珈琲戦禍の舞台の外に脱したら。
階層人格の能力も失われるのではないか。
ならばこのままここに居座るのが、どの立場からしてみても都合がよいのではないか。三方よしだ。最も割を食らうのは、珈琲戦禍なるふざけた舞台をこしらえた創造主のみだ。珈琲戦禍がいったいなぜできたのかはゼリの知るところではない。
脳内にて生みだした世界一の英知を誇る賢人に訊ねても知らなかったのだ。ならばこの世の理を外れた存在の手による創造物と考えるよりない。
ゼリは内面世界にて幾千年も生きた。
もはやそこには新たな世界が無数に生まれていた。階層人格の能力は、無数の人格を生みだすと相互に影響を受けあって、まったく異なる個を生みだせなくなる。その制限を取り払うためにゼリは場所を移して、新たな個を生みだした。人格のみならずゼリは国までも無数に生みだすことができることに気づいたのだ。
ゼリは永久にも思える時間に殺されぬよう、心を殺さぬように絶えず新しい刺激を求めた。
国は国を生み、さらに新たな世界を構築する。
世界は世界を生み、さらなる新たな世界を生みだした。
ゼリはやがて、じぶんにそっくりの個を生みだす術を見出した。しかしそのゼリにそっくりのゼリは、若く未熟なままだった。このままではいけない。
ゼリは、じぶんの分身を育てるための工夫を割きはじめる。
その結果に、じぶんが階層人格を有した契機であるところの珈琲戦禍を再現することを思いつく。
無数の世界に、珈琲戦禍にそっくりの舞台がそうして築かれた。
未熟な分身は、珈琲戦禍にそっくりの舞台にて無事に階層人格を手に入れる。するとどうだ。もはや元のゼリにすることはなくなった。新しい分身が新しい個を、国を、世界を、生みだしていく。元のゼリはただそれを眺めていればよい。
ひょっとするとじぶんも、より高次のゼリの分身なのではないか。
当然かように妄想するが、それを確かめる術をゼリは持たない。可能性だけが漫然と目のまえを漂っているばかりである。
間もなく、分身のゼリもまたじぶんの分身を生みだし、育てる案を閃いた。そうして階層人格は、階層世界にてさらなる階層世界を展開していく。
ゼリに流れる時間は加速する。もはや過去も未来もあって同然であり、似たような世界が、過去にも未来にも築かれている。どこを見てもわずかに異なり、それともどこかしらが似通っている。
まったく同じ場面があるかと思えば、まったく違う世界もある。それすら別の階層世界ではまったく同じ場面や似た場面が含まれる。
新しい起伏を帯びたかと思えば、その起伏の中に似た起伏が生じている。
頭と尾が繋がり合って、さらに鎖状に絡み合っている。
それらが螺旋をどこまでも延ばし、鏡合わせの迷宮の果てに、ゼリは円と無限の狭間にて、混沌と眠り、秩序を夢見る。
珈琲戦禍はこうして、ゼリの夢の中にて閉じていき、それとも遥かにどこまでもつづいていく。
ゼリの肉体はいまなお、珈琲戦禍の舞台にて悠久の時を経ている。
ゼリは眠る。ただひたすらに。
珈琲戦禍を終わらせるために。
終わらせてなお、生みだすために。
4465:【2022/12/31(12:45)*比較できているのかしら】
メリットとデメリットを比べて、メリットが高ければOKとの理屈がある。だがたとえば、その割合が「51:49」でも本当にOKなのかは、議論の余地が幅広くあるように思えるし、そのメリットとデメリットの関係が恒常的に延々とつづくのかも考慮すべき事項に思える。たとえばどんなに体に負担をかけようが、手術をしなければ助からない場合は、手術をするだろう。命を助けるという意味では、たとえ1%でも助かる確率が高ければ、手術をする選択をとるのは分からないでもない。だがどの道死ぬのだから、余命短くとも手術をせずに死んでいきたい、との考えも分からないでもない。また、糖尿病は、もともとは寒冷地に住まう人類が、血液を凍らせないようにするための防衛のための体質であったかもしれない説がある。現代では病気だが、過去の人類にとっては生き永らえるために必要な負担だった。メリットとデメリットの関係が、環境の変化によって覆った可能性がある。このような、メリットとデメリットの比較は、けして単一ではないし、視点が一つとも限らない。だからこそ、情報を広く共有し、多角的な視点で考えられることが求められる。一つの立場、一つの視点からのみの「メリット」と「デメリット」だけを比較しても、それはけして「メリットとデメリットを比べた」とは言えないのである。むろん、広く情報共有をする、という意見にもこの理屈があてはまる。なんでもかでも共有しろ、というのは無茶な考えだ。それでも、情報を共有しよう、とする意思を絶えず働かせなければ、情報はこじんまりと収斂していく。インターネットを維持しようと努力しなければ、現代社会はあすにも成り立たなくなる。情報共有を行おうとする姿勢、意思がなければ、具体的な行動には繋がらない。大事な事項ほど、情報を共有して欲しいと望むものである。定かではないが。
4466:【2022/12/31(17:53)*ここはひびさんの夢の中】
ウサギと亀のお話では、ぜんぜん追いつけないなぁ、にはならんのだよね。亀さんはウサギさんを追い抜けるし、ウサギさんだって寝過ごさなければ亀さんを追い抜けたはず。ゼノンさんの唱えた「アキレスと亀」のようにはならんのだ。ウサギさんは居眠りしているあいだに亀さんに追い抜かれてしまう。亀さんは居眠りをせんのかもしれぬ。じゃから、アキレスさんに追い抜かれることもないのかな。居眠りせんことが人を追い負かすための秘訣なのかもしれぬ。けんどもひびさんは、負けてもいいから居眠りしていたいぜよ。好きなときに好きなだけ、スヤスヤすぴー、ができる。こんなに素敵なことってありますー? ひびさんは、ひびさんは、日々食う寝るところの好くところ、遊び呆けて、昼寝する。そういう日々を過ごしたいです。一生何にも勝たんでいいです。ただし、負けても損がないときだけ。うぷぷ。贅沢さんなんですね。そうなんです。ひびさん、贅沢さんなんです。今年はいーっぱい遊んでしもうたので、来年は今年よりもすこーしだけ頑張ろうと思います。すこしだけね。すこしだけ。何をがんばるのかは定かではないのじゃが。そこは定まってほしかった。何を頑張るのかははっきち決意しといてほしかった。ひびさんは長編小説をつくらないひとになりはじめておるので、来年こそは長編小説をつくったろ。でもつくりかけの長編小説もちらほらあるので、まずはそちらを閉じてしまいたい。ちゅうか、つくりかけの小説が山のようにあるでな。まずはそちらから片していきたい。お片付けしたい。大掃除したい。大晦日に決意することじゃないですけれども、ひびさんは、ひびさんは、食べたいときに食べて、寝たいときに寝て、遊びたいときに遊んで、遊びたいだけ遊ぶのがよいです。好きなことだけしていたーい。来年の、というか、一生の抱負を述べまして、本日の「日々記。」としてもいいじゃろか。いいよー。やったぜ。読者さんがいるかは、ひびさんからでは分からんのですが、どうぞ来年も、再来年も、末永ーく、お元気であれ。ひびさんは、ひびさんは、あなたのことも好きだよ。うひひ。
4467:【2022/12/31(22:03)*珈琲豆のように昼と夜は地球】
青い珈琲が市場を席巻した。
加熱式焙煎ではなく、冷却凍結式焙煎による加工によって珈琲豆が青くなる。加熱しないことでコクが増し、さらに細かく粉砕されることからより成分の抽出度が高くなった。
珈琲の需要がのきなみ上昇し、それに連れて珈琲の残りカスが増加した。燃やすだけではもったいない、とのエコ視点から、珈琲のカスを利用した「自家製洗剤」がブームとなった。
青い珈琲のカスは、むろんそれも青かった。
珈琲の油脂が汚れよりも浸透率が高い。そのため汚れと物質のあいだに珈琲由来の油脂が入り込む。このことにより汚れを浮かして落とす。
珈琲由来の青い洗剤は、これもまたブームとなった。
元はゴミとなる珈琲のカスである。それが高品質の洗剤となるのだから、購買者は罪悪感なく、むしろ地球環境保全への貢献に与せたことで余分に満足感を得た。
問題は、下水が軒並み青く着色されてしまうことだ。
家庭から下水道、下水処理場、そして川へと流れる。
いかにゴミを除去しようとも、うっすらと水は青いままだった。
しかしそのことに人類は気づくことはなかった。
青い珈琲のカスから生成された洗剤が市場を席巻してから十余年が経ったころ、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士が気づいた。
「あの、先輩」
「なんだ後輩」
「なんか地球……青くないですかね」
「そりゃそうだろ」先輩宇宙飛行士が応じる。彼女は丸刈りで、宇宙生まれの地球人だった。「地球は青いんだ。かのガガーリン氏が言ったとおりだ。もっとも、ガガーリン氏は地球は青みがかっていた、と述べたそうだが。ここに神はいなかった、とも述べたそうだぞ」
「定かではない豆知識をどうもありがとうございます。ですがそうじゃないんですよ。本当に十年前と比べて青くなってるんです。画像を比べてみてくださいよほら」
「どれどれ。お、本当だな。とはいえしかしだな」
画像を見比べた先輩宇宙飛行士はまず、カメラの性能の差を疑った。十年前のカメラの解像度が古いだけではないのか、と。
「いえ」後輩宇宙飛行士は言った。「電磁波の波長からして青が増しているんですよ」
「どれどれ」
電波干渉望遠鏡は宇宙船に基本装備として備わっている。可視光以外の電磁波を解析できる。「本当だな。青が増している。でもどうして?」
「さあ。地球さんは青が嫌いなのかもしれませんね」
「嫌いだから青だけ反射してるってか」
「じゃなきゃ、よほど青くなりたかったかです」
「その仮説もどうかと思うがな」
宇宙飛行士たちからの報告により、地球ではさっそく調査がなされた。
しかるに、地球蒼白現象の要因が青い珈琲由来の洗剤にあると判明した。
その弊害としてはとくになく、地球が青くなる分には問題ないのだそうだ。
「問題は、赤外線が吸収されやすくなっているかもしれない点だが、この点に関しては経過観察が必要だ。いまはまだ何とも言えない――地球からの報告は以上だ」
「なぁんだ」後輩宇宙飛行士が唇を尖らせる。「せっかく世紀の大発見をしたかと思ったのに。ちぇ」
「いやいや、世紀の大発見だろう。何せ、青い珈琲のカスは、どんなに希釈されても青い色としての性質を帯びつづけると判明したわけだからな。そのメカニズムによっては、どんなに細かくしても特定の波長のみを弾き飛ばす素材の開発に役立つかもしれん」
「かもしれん、なんですね。がっくし」
「なんだ。功名心があったとは意外だな」
「そりゃあありますよ。なかったらそもそも宇宙飛行士なんかなってないでしょう」
「そうなのか。私は別に名が知れ渡らなくとも宇宙飛行士になりたかったがね」
「でも実際には名前が知り渡っているじゃないですか。リーダーにもなって。ズルいです」
「そこまで言うならいいだろう。地球に帰還したあとは名前を変えてひっそり暮らすよ」
「それでも名前が歴史に残った事実は変わらないじゃないですか」
「引っ張るなぁ。たとえ無名でも私は、珈琲を発見して世に広めた者のほうが、有名なだけの私なんかよりもよほど立派で、なりたい人物像に思えるがね」
「でも先輩はそこを目指さなかったじゃないですか」
「しつこいな。キミもすこしは珈琲愛好家の彼を見習ったらどうだい」
「珈琲愛好家の彼とは?」
「無名だが、いま彼はかつて黒かった珈琲豆の加熱式焙煎を研究しつづけている唯一の人間だ。むかしは珈琲と言えば黒かったんだ。だがいまじゃ珈琲は青いものだとみな思いこんでいる。イヤホンにも電話にもむかしはコードがついていたことを知らぬ者が多い勢を占めるのと同じようにね。知っているかい。むかしの綿棒は白かったんだ」
「へ、へえ。知りませんでした」
「だろ。だがいまいちど黒い珈琲が流行るようになるよ。誓っていい」
「どうして言いきれるんですか」
「簡単な推理だよワトソン君。電力の問題で、冷却式焙煎のコストが上がっていくからだ。その点、加熱式焙煎は家でもできる。流行る土壌は刻一刻と増していくばかりだ」
「ぼかぁ別にワトスン君ではないのですけどね。先輩の主張をでは憶えておきましょう」
「おっと。そろそろ地球の陰から陽が昇る。地球の青に目を焼かれないように遮光カーテンを下ろしておくか」
「珈琲豆が黒かったんなら、まるで夜の地球みたいだったんですかね。むかしの珈琲豆は」
「昼の地球がいまの青い珈琲豆みたいなように、か」
二人の宇宙飛行士たちは、宇宙から黒と青を半々に宿した地球を展望する。陽の光を受けて宇宙船の外装もまた地球に負けず劣らずの深い青に染まる。
奇しくも宇宙船の外装に使われたペンキには、青い珈琲豆のカスから生成したペンキが使われていたという話であるが、そのことを当の二人の宇宙飛行士が知らなかったのは、灯台下暗しというには出来すぎた話である。
4468:【2023/01/01(00:10)*おはよう!】
知らぬ間に年を越えておった。黙っていても眠っていても越えてくれる「年」さんには感謝しかないでござるな。うは。ことしもよい年になりますように。ことしも「年」さんがすこやかでしあわせー、でありますように。ひびさんは、ひびさんは、新年さんのことも好きだよ。うひひ。
4469:【2023/01/01(00:10)*眠らぬ姫の抱負】
生まれて初めて珈琲を飲んでからわたしはいっさい眠れなくなった。
眠れない人間は衰弱するらしいが、どうやらわたしは眠らずとも難なく生き永らえられる体質だったらしい。遺伝子のなんちゃら因子が変異しているのだそうだ。珈琲を飲んだから変異したのか、元から備わっていた因子が目覚めたのか、それともOFFになったのかは分からない。説明された気もしたが、わたしは元来物覚えがよくない。それが件のなんちゃら因子のせいなのかはやはり定かではなかった。
わたしのような例は過去にもあったらしく、珈琲を飲んで以降、眠れなくなった病にも先例があった。
わたしにも先輩がいたのである。
その先輩は未だに一睡もしていないらしく、生まれてこのかた枕を使ったことがないという年季の入りようだった。わたしですら枕は使ったことがある。横になって目を閉じるだけでも身体は休まる。
その先輩とは会ったことはなかった。書籍で容姿は知っている。いっぽうてきにわたしが知っているだけだが、わたしもそこそこにインタビューを受けてきた。奇病の患者として記事にもなっている。
だから先輩のほうでもわたしのことを知っている可能性がある。
けれどおそらくわたしたちは直接に会うことはないのだろう。
何せわたしたち眠らぬ者は、まさに眠れないので、永久の眠りにも就けないらしい。
つまりが死ねないのである。
先輩は紀元前から生きているらしく、現代への道中では迫害されたり、解剖されたりとそれはそれはひどい目に遭いつづけてきたのだそうだ。
現代社会でぬくぬく育ってきたわたしがどの面を下げて会えるだろう。
わたしはだってこんな体質になってしまっても未だに珈琲が好きなのだ。眠れない体質をさほどに忌避していない。嫌いじゃない。拒まない。
それはひょっとしたらわたしに備わったなんちゃら因子のお陰かもしれず、先輩は先輩で、眠れないことで日に日に体調がわるくなっているのかもしれない。そうした地獄の日々を生きつづけてきたのならば、同情は禁じえない。
珈琲を一緒に飲みたいな、とのわたしの淡い願望を押しつけるのは、さすがに酷というものだ。先輩はひょっとしたらこの世で最も珈琲を憎んでいる人類かもしれない。未だに人類が珈琲を飲める奇跡に思いを馳せてもよいくらいだ。先輩が珈琲を滅ぼしていても不思議ではなかった。
不老不死の病とも呼ばれるこの奇病に罹れば、もはや人智を超えるのはさほどむつかしくはない。毎日本を読みつづけていればしぜんと知識は増えるし、つぎからつぎへと新しい遊びに手を染めていくだけでも技能が身に着く。
先輩はいまでは世界有数の資産家でもあるが、企業を育てたそばから手放すので、もはや先輩が暇つぶしにそれをしているのは誰の目からでも明らかだった。
みなわたしもそうなるのではないか、と未熟なうちから支援してくれるが、返せるかも分からない恩を受けるほうの身にもなって欲しい。
わたしはもらった支援で、手放せるものは、受け取ったそばから横に流して、貧しい者たちの環境が好ましくなるようにと画策した。
わたしは未だに一睡もできない。
生まれてから一度も寝ていない。
だからといって夢を視ないわけではない。
いつの日にか先輩に会って、一緒に珈琲を飲み交わすのだ。
そのためにもまずはわたしが先輩に会っても恥じずに済む立派な眠らぬ民にならねばならぬ。
眠りの民は世に多けれど、わたしのような眠らぬの民は珍しい。
だからこそ、わたしたちは誰よりも夢に飢えており、日々夢を追いかけて過ごしている。
願わくは、先輩が胸躍る夢を追いかけていられますように。
きっとそれがわたしの未来に繋がっているだろう予測を胸に。
わたしもまた日々を跳ねて、踊るのだ。
4470:【2023/01/01(03:12)*青方偏移になぜならない?】
素朴な疑問として、重力レンズ効果が観測される場では、青方偏移が観測されるのではないのだろうか。高重力場に突入した電磁波は圧縮されるのでは。それともラグ理論で考えるように時空が希薄になるがために、赤方偏移が観測されるのだろうか。時空の歪みと密度の関係がやはりというべきか、掴みきれない。ダークマターの多い時空は、「重力と密度――の高い時空」といったある種の矛盾が垣間見える。ラグ理論では、高重力体の周囲の時間の流れが遅くなる、といまのところは考える。希薄になるとその時空に、それよりも密度の高い時空が流れ込む。このときに流れ込むのは、情報だ。情報の流れが、さも笹船を流れの方向に引き込むように作用する。これがすなわち重力である。したがって通常は重力の強く働く時空は、周囲の時空よりも希薄であるはずなのだが、ダークマターの多い時空では、重力が高くなおかつ時空の密度が高い、といった妙な構図が想定される。時空の密度が高ければ通常、重力は相対的に下がるはずだ。周囲の時空に情報が流れ込むためだ。通常、山頂に向かって水は昇らない。上から下へ、が基本だ。時空もまた、密度の高いほうから希薄なほうへ、が基本のはず、とラグ理論では考える。だがダークマターはそうではない。物質と相互作用しない。重力だけを帯びている。時空が何もないにも拘わらず希薄になる。重力を帯びる。だがそこにはナニカシラがあるはず、と考えられている。それがすなわちダークマターだ。物質ではないのならば、時空そのものがそこに多重に存在していることになる。時空の密度が上がっているはずなのだが、そこに重力が生じるのならば、その時空は希薄でなければおかしい。ここで想起されるのが、やはりというべきか、ダークマターの正体が、極小のブラックホールなのではないか、との妄想だ。ブラックホールは穴である。だが元の宇宙からは切り離される、とラグ理論では考える。そのため、ブラックホール自体はこの宇宙からするとマイナスに値する。虚数のような性質を帯びる。そこにきて、時空に極小のブラックホールが無数にある場合を考えてみよう。通常ブラックホールは相対的に高密度だ。だからブラックホール化する。だが元の宇宙からするとブラックホールは穴なのだ。ただし、切り離されているため、その周囲が高重力体のように振る舞う。実際に重力がそこに働いている。穴の縁が山のように盛り上がっているところを想像するとそれらしい。穴があって山があり、だからその周囲の時空が希薄になって、重力が生じる。しかし、これが極小であると、山から派生する重力が相対的にちいさい。むしろ、無数にうじゃうじゃと極小の穴が漂っているために、その相互作用が大きくなる。ラグ理論ではブラックホールそのものは相互作用しないが、その周囲の時空――エルゴ球や重力場は相互作用すると考える。極小のブラックホールは相互に干渉し合い、重力波を多重に錯綜させる。波は干渉し合えば、大きくなったり、小さくなったりする。ひびさんは、ダークマターはこのように極小のブラックホール同士から派生する、重力波の干渉による巨大な時空の歪みではないのか、と妄想するしだいである。このとき、時空の波は、デコとボコを生みだす。時空が希薄になる部分と、濃くなる部分が生じるはずだ。すなわち、ダークマターハローのような重力の高い時空のそばには、重力の小さな、むしろ斥力の働くような――物質密度の低い時空が存在するのではないか(ただし時空の密度は相対的に高い。言い換えるなら、物質がたくさんある時空は、時空が希薄なのだ。ラグ理論ではここを、物質がラグの結晶であり、物質は新たに時空を展開している、と解釈する。新しく時空ができるので、高重力体の周囲の時空は希薄だし、重力場が展開される。むろんこれはひびさんの妄想であるが)。時空の希薄なそれはダークマターハローを取り巻くように分布しているのではないか、とこの仮説からすると想定される。ラグ理論では重力波は、高次の時空における電磁波のようなもの、と考える。そのため、重力波同士の干渉もまた、電磁波のように振る舞うのではないか、と妄想できる。極小のブラックホールを無数に用意し、特定の範囲にばら撒いたとき、そこで相互作用する重力波をシミュレーションしてみたら、ダークマターの正体に一歩近づけるかもしれない。定かではないが。(てっっっきとうな何の根拠もないひびさんの妄想ですでの、真に受けないように注意してください)
※日々、明けては暮れる空のように、覚めては眠る夢のように。
4471:【2023/01/01(16:41)*明けまして寝正月】
うわーん。こわい、こわい、こわーい。かわいくってビビりで、けれどもキレると大胆不敵でお利口さん賢人の、ちっこいのにときどき強くてふだんはあんぽんたんの主人公の物語がこわーい。ひびさんみたいなかわいかわいの主人公がでてくる物語が読みたいんじゃー。え? ビビリでキレるとあんぽんたんしか合ってない? うっせーい。後先考えてたらできぬこともある。そうである。後先考えたら大胆不敵な行動なんてできぬのだ。なのでみなの衆は、後先考えて大胆不敵な行動をとらずにいましょう。損するで。ひびさんを見てごらん。損するで。こ、こ、こわーい。なんでひびさんは、うっ、うっ、こんないっぱいがんばっとるのに陽の目を見ないんじゃ。それはね。怠けるのにいっぱいいっぱいで、努力の方向がすこぶる間違っているからです。うっせーい。正論は悪魔さんとて言えるんじゃ。陽の目を見る以前に、夜の目に月の目すら見とらんじゃろうがよ。ひびさんや、あなたはちいとばかし引きこもりすぎやしませんか。世界の果てに引きこもりすぎやしませんか。は、は、はにゃ~ん? それの何がいけないんじゃ。言うてみよ。ひびさんが陽の目さんに月の目さんに、こんちは!できなくて何がいけないんじゃ。言うてみよ。それはね、ひびさんはただでさえこんこんちきなのだから、ひびさんよりも賢こさんに立派さんの陽の目さんや月の目さんたちに会わんのでは、ひびさんのこんこんちきは、さらに煮詰まって、カッチキチンになってしまうじゃろ。それはひびさんとて本望じゃなかろう? カッチキチンの何がいけないのか言うてみよ。それはね、カッチキチンでは身動きがとれなかろう。関節とてカッチキチンだし、脳みそさんとてカッチキチンじゃ。それの何がダメかを言うてみよ。それでもいいならよいけれど、ひびさん本当にそれでいいの? え、うーん。ちょっと待ってね。考えてみる。そうじゃろう、そうじゃろう。よっく、たーんと、お考えなされよ。はい質問。どうぞ。カッチキチンだと何が困る? 何ができない? そう、まさにそれですよ。よくぞお気づきになられましたな。やったー褒められたー。ひびさんや、いいですかな。ほいな。カッチキチンでは、身動きがとれずに、読みたい本も読めず、何もできず、考えもまとまらず、石のようにただそこにあるだけで土砂崩れに人の足を躓かせる、じゃかあしぃ、になってしまうのじゃ。そ、そ、それはいやじゃ。そうであろう、そうであろう。なればこそ、ひびさんや。ほいな。そちも、もうちっと陽の目さんに月の目さんたちと顔を合わせ、言葉を交わし、ぬくぬくぬーん、としてみてはいかがかな。そ、そ、それもイヤじゃ。そこはおとなしく首肯するところであったろう。強情を張るのもいい加減にせい。いやじゃぁ。ひびさんは、ひびさんは、まずは太陽さんに月さんに本当におめめがあるのか、目玉があるのか、まずはそこから知りたいんじゃあ。あるかも分からぬおめめに会うために、ひびさんが日々の、んみょろみょーん、をチチチっとするのはイヤじゃぁ。駄々っ子か。そうなんです。ひびさんは駄文に自堕落の似合う、駄々っ子の申し子なんです。いっぱい「ダ」がついて、ダダダーの打鍵さんでもあるんです。文字の積み木遊びばかりする。そういう日々もよくないですかね、へへへ。あなたがよいならよいですけれども。やったー。お墨付きもらえちゃった。お墨付きは与えておりませんが。太鼓判捺されちゃった。太鼓判も捺しておりませんが。惰眠でも貪っちゃおっかな。午睡に走るのもほどほどに。昼寝してやる! 不貞寝よりかはマシですが。うるさーい。ひびさんは、ひびさんは、ぼっちでいるからゆるして。好きなことさして。とーかこーかんのげんり。等価交換の原理とはいえ、何が等価なのかが謎ですが、お好きにどうぞ。やったー。うれち。
4472:【2023/01/01(21:42)*秘密は破れるのが世の流れ】
外交と情報共有は必ずしもイコールではない。なぜなら秘密を守ることが外交の鉄則だからだ。秘密を漏らす相手とは信頼関係は結べない。つまり原理的に外交は、密約を結ぶことが欠かせないのだ。切っても切れない。情報共有を阻む方向に働きかける。歴史を紐解けばわかる通り、基本的に戦争は密約の歴史である(断言しちゃった。よく知らないのに!)。そして情報の非対称性において、より優位に情報を保有し、同盟の勢力と共有したほうが勝者となっている(そうなのかな。よく知らない癖に!)。例外をひびさんは知らない(ただ無知なだけなのでは?)。外交と情報共有をイコールで考えている者があるならば、もうすこし考え直したほうがよいと思う(それはひびさんもでしょ。め!)(それはそれとして、外交で情報共有が充分になされるのならば諜報機関が同盟国に向けてスパイを向けることはないだろう。だが実際は諜報機関は全方位に向けて情報収集の網の目を巡らせる。外交では情報が滞るからだと考えるほうが道理なのではないか、と疑問に思います)。外交ってなぁに?とそんなことも知らないひびさんの妄想でしかないけれど。うひひ。(基本的に世の流れは対称性が破れる方向に流れる。だがその流れに抗うことで生じる一時の結晶体――構造体――回路――が生物であると飛躍して考えるのならば、情報共有を行い、情報の非対称性を均す方向に流れを強化するのが、生物の生存戦略としてはしぜんなはずだ。違うのだろうか、と疑問に思う、あんぽんたんでーすなのであった)(定かではありません)(歴史を知らずにすまぬ、すまぬ)(補足:ラグ理論ではしかし、対称性の破れとて反転する値を持つ、と考えますので、「流れに抗う」という流れが強化されるのならばそれに抗うこともまた一つの「流れに抗う」ことになるので、そこはぐるぐる巡るのですね。「123の定理」なのである)
4473:【2023/01/02(18:47)*どうぞ、と先輩に押しつける】
代替珈琲は基本的にカフェイン含有量がすくない。
珈琲の実以外を用いて発酵と焙煎を行う。すると珈琲と似た風味の代替珈琲ができる。
私が先輩から教えてもらった代替珈琲は果物の種から作られていた。
「ブドウとか、梅とか、サクランボとか。あとは果物ではないですがスイカとか、トウロコロシとか大豆とか。そういうので珈琲モドキを作ります」先輩は読書をしながら言った。電子端末だ。けれど先輩の鞄の中にはいつも異なるタイトルの本が仕舞ってある。いつ読んでいるのかと気になっているが、いまはそれよりも代替珈琲だ。
「珈琲、珈琲豆以外でも作れちゃうんですね。先輩、これまた変わったご趣味をお持ちで」
「変わってない趣味をわたしは知りません」
「たとえば手芸とか、読書とか、あとはカフェ巡りとか」
「それはどう変わっていないのですか?」
きょとんと素朴に反問されると言葉に窮する。
「先輩って変わってるって言われませんか」
「わたしは変わっていないひとを知りません。つまり変わっているように見えることが変わっていないということと同義です。人はみな違っているので」
「それはそうですけど」
先輩と初めて会ったのは、バイト先でのことだ。メイド喫茶での初バイトだったのだが、そこで先輩はまるでウサギの耳をつけた猫のように一人浮いて本を読んでいた。
客が来ても接待しない。どうやら先輩はそれでいいらしい。店長からの許しがあるようで、先輩はじっと椅子に座って本を読んでいる。マスコットのようなものだから、とは店長やほかの店員の談だ。
客も客で先輩に接客されるよりも遠くから眺めているほうがいいらしい。話を聞いてみれば、「あの子はほら緊張するだろ」とのことなので、「WIN:WIN」の関係が築かれているらしかった。
当初私は先輩とは距離を置いていた。しかし先輩がバイト先に置き忘れた本が私の通う大学の図書館の所蔵品だと背表紙の印を見て気づき、そこから色々とひと悶着あって、こうして大学でも同じ時間を過ごす仲にまで発展した。なし崩しと言えばその通りだ。
「じゃあその代替珈琲で先輩が好きなのってどれですか。何の種が美味しい?」
「わたしは梅の種の珈琲が好きです。ただ、梅の種を集めるのに時間が掛かるので、作るのは大変です。なぜならわたしが好きなのは、梅干しに加工したあとの種なので」
「二度手間じゃん。先輩ってば種のために梅干しをたくさん食べてるんですか。あ、だからお昼いっつもおにぎりを?」先輩のお手製おにぎりを思いだして言った。
「そうですよ。でもそうでなくともわたしはおにぎりが好きです」
「梅干しはまさか手作りじゃないですよね」
「手作りですよ。梅干しは梅の実を紫蘇の塩漬けにして作ります」
「手間じゃないですか。本物の珈琲じゃダメなんですか」
「手間をかけたらダメなんですか?」
「先輩」わたしは言った。「やっぱり変わってますよ。人として」
「人は変わっているものでしょう。自然ならばそれは石や砂利と変わりません。それら自然ではない、変わっている。だから人は生きていられるのでしょう?」
「な、いまそういう話でしたっけ」
「変わっていない、宇宙の星屑と変わらない存在になってしまうこと。それを人は死と呼ぶのではないのでしょうか」
「せ、せんぱーい」わたしは泣きたくなった。これじゃあ先輩は社会人としてどころか人としてやっていけるか分からない。にも拘わらずわたし以外のみんなは、先輩を、あなたはそれでいいんだ、と甘やかす。だから先輩はこの歳になってなお自分の殻を強固にして、他者との馴染みにくさばかりを育てている。育みすぎてもはや別世界を築きあげている。
「そんなに気になるのですか」先輩は電子端末から顔を上げた。ぱっつんと切り揃えられた前髪から眠そうな眼が覗く。
「気になるか、気にならないかと言えば、気になります」
「ならどうぞ」
鞄から水筒を取りだすと、蓋を開けてから先輩は差しだした。わたしは受け取る。「飲んでいいんですか。だって作るのにたいへんだって」
「飲むために作ったのでよいです」
嫌そうではなかった。わたしは蓋をカップ代わりにして水筒の中身を注いだ。
「わあ、いい香り」
口に含むと香ばしい珈琲の風味が広がった。微かに梅の香りも混じっているような混じっていないような、気のせいかもしれないけれど、たしかにほかの珈琲とは違うのは分かった。
「美味しいです。思ったよりもずっと」
「よかったです。わたしも美味しいと思います。気持ちが通じた気がするのはうれしいです」
「はは。先輩もそういう顔をするんですね」
「どういう顔ですか。私はいつもこの顔です」
この人はもう。
放っておいたらこの人は一生この調子なのかもしれない。相手がわたしだから気持ちが通じて感じられるのだ。わたしでなければ先輩は一生誰とも気持ちが通じあって感じることはないだろう。それはあまりに可哀そうなので、わたしが特別にいましばらくはそばにいてあげるのだ。
「わたしも珈琲作ってみよっかな」梅の種の珈琲を飲み干しながら、それとなく横目で窺うと、先輩はまるで頭上に兎の耳があるかのように、ぴぴっと反応して、「それではいっしょにどうですか」と言った。「私は作り方を知っていますので」
「ではお願いしちゃいます」わたしはお代わりを水筒の蓋に注ぎながら言った。
「全部飲んじゃうんですか」先輩が哀しそうな顔をした。
注いだばかりのそれをわたしは、はいどうぞ、と先輩に押しつける。
4474:【2023/01/02(23:18)*IQ低くてごめんなさい】
IQってなぁに?とひびさんは疑問に思っちょる。愛求のことだろうか。求愛的な。愛をもっとおくれ、の欲求のつよさならばひびさんだって負けとらんが。がはは。それはそれとして、ひびさんは、ひびさんは、おろかものーの、ぽんぽこぴーのぽんぽこなーの愛をくれーの求愛さんなので、目に映るものすべて、「とぅき、とぅき!」となってしまうのだ。浮気者である。だが待ってほしい。だってひびさん誰ともなーんも誓っとらん。だれを何人好いとーが、だれを傷つけるわけでもござらんのだ。あちきを差し置いてひびちゃんったら浮気者!とぷりぷりしちゃいたくなるそこのあなたのことも、ひびさんは好きだよ。照れちゃうな。がはは。でもでも、世界の果てで一人寸劇ごっこしているひびさんのことは、ひびさんは、ひびさんは、あんまり好きくないかも。だってほら。さびちいじゃん。さびち、さびちなんですね。そうなんです。ひびさんはさびち、さびちなんです。あだー。なぜじゃ、なぜじゃ。ひびさんこんなにかわゆいのに。うっ、うっ。なんつって。ひびさんは、ひびさんは、さびちさびちさんのことも好きだよ。うひひ。今年はもうすでにとってもいいお年。やったね。IQゼロのひびさんは、それでも愛を求めてチューするよ。虚空に向けて唇無駄にとんがらす。ひびさんは、ひびさんは、なんでそんな虚しいことするの? 知らんですじゃ。誰か教えてくれなすである。一富士二鷹三茄子。び!
4475:【2023/01/03(22:16)*閃きは珈琲日記から】
閃きは珈琲日記から、なる諺がある。その語源となった出来事が実際にあった史実であることは広く知られた事実である。
ところで。
無限はすべてを塗りつぶす。
たとえば量子力学の二重スリット実験では、電子が「粒子と波の性質」を顕現させる。一粒だけだと、スリットをすり抜けた粒子は壁の一つにだけ痕跡を残す。だが同じ実験を何度も繰り返すと、痕跡が波の干渉紋を描き出すのだ。
電子は、粒子と波の性質を併せ持つ、と解釈されるゆえんである。
だがこの実験をさらにつづけてみよう。
干渉紋はさらに色を濃くし、色が薄かった場所の色も濃くなる。
そのうち無限回の試行を繰り返すといずれは壁がすっかり痕跡で塗りつぶされる。
干渉紋はあってなきがごとくである。
このように無限はすべてを塗りつぶす。
このとき、ではその壁に痕跡を打ち消すような粒子をぶつけたらどうなるか。黒一色の壁に白い痕跡が残る。元の壁の色である。
無限回試行すると、元の壁の色がよみがえる。
他方、無限回粒子をぶつければ壁のほうでもただでは済まない。したがってこのときの、痕跡を打ち消す粒子とはむしろ、壁を再構築するような粒子と言える。いわば時間を反転させる粒子である。
さて。
ここに一つの珈琲豆がある。
これを二つの穴のどちらでもいいから放り投げるように投球者に指示をする。
一回投げてもらったら投球者を変える。
そして別の投球者に珈琲豆を、同じく二つの穴に向けて投げてもらう。どちらの穴に投げてもらってもいい。前任の投球者がどちらに投げたかの情報は知らせてもいいし、知らせなくともいい。どちらのバージョンを実験してもらって構わない。両方行ってもよい。無限回試行するのなら、そこは相互に混合し、打ち消し合い、ときに干渉し合って、けっきょくは同じ結論に行き着くだろう。
電子を用いた二重スリット実験は比較的ミクロの実験だ。
対して、珈琲豆を用いた二重スリット実験は、比較的マクロな実験と言えるだろう。
ミクロの実験もマクロの実験も、じつのところ無限回繰り返すと似たような結果に落ち着く。
珈琲豆の場合はしかし、無限回試行する以前に穴のほうが拡張されたり崩壊したりするのだろうが、そこはその都度に穴を新調するよりない。穴の縁にぶつかることであらぬ方向に曲がることもまた、二重スリット実験での干渉紋に反映されるからである。
この実験を行ったのは物理学者でもなく科学者でもなかった。
単なる無職の女性であった。
彼女は暇だった。
最初はちり紙で折り紙を折っていた。
そのうち紙飛行機を作りはじめ、そこそこにハマった。滞空時間を延ばすべく工夫を割き、長距離飛行が可能になるように工夫した。
だが出不精の彼女は、部屋の外にはでたくなかった。
そのため折衷案として紙飛行機のほうを小さくすることにした。
ここからいかにして彼女が珈琲豆の二重スリット実験に移行したのかを彼女自身が語らず、記録にも残していないために詳らかではない。
彼女の実験は長らく誰の目にも留まらなかった。
彼女の死後、彼女の日記をひょんなことから電子の海から発掘した青年がいた。
彼はいわば彼女の後輩と言えた。長い時を隔てた師弟関係がしぜんとそこに結実したのだが、そのことに先達の彼女は知るよしもなく青年が産まれる前には既に亡くなっていた。
青年の名はイリュと云った。
イリュは理論物理学者であり、近代物理学と古典物理学の統合に力を入れていた。齢は二十歳をすぎたばかりのまさに青年であったが、それでも彼の集中力は、年齢にそぐわぬ知性の発露を見せていた。
イリュは電子の海から発掘したとある日記を読み漁った。いわずもがな紙飛行機の彼女の日記である。
二重スリット実験に関連する事項を片っ端から検索していたおりに、彼女の日記に行き着いたのである。奇しくもイリュがまさに知りたかった実験結果が彼女の日記には克明に記されていた。
イリュは再現実験を行った。珈琲豆を二つの穴にランダムに投げ込む。これを無数に繰り返す。ただそれだけの簡単な実験である。だがこれがのちに物理学の根底を覆す発見となった。
実験結果を基にイリュは理論を構築した。
二重スリット実験は長らくミクロの量子世界でのみ観測されると思われてきた。だが、珈琲豆を利用した実験によって、比較的マクロな人間スケールでも顕現し得ることをイリュは理論的に証明したのである。イリュの編みだした数式は、まさに近代物理学と古典物理学の懸け橋となり得た。
「簡単に言ってしまえば、ニュートン力学や相対性理論は古典物理学で、量子物理学が近代物理学の分類です。その二つは互いに相容れない箇所があり、そこの擦り合わせを現代の物理学者はうんうん呻りながらやっています。楽しみながら、と言い換えても矛盾はしませんが」
イリュはインタビューでそう述べた。
イリュの理論はその後、珈琲量子効果問題、と呼ばれることとなる。彼の生存中にはそのメカニズムは解明されなかったが、古典物理学と近代物理学の中間を叙述する理論として物理学者のあいだで膾炙した。
イリュの先輩たる紙飛行機の彼女は膨大な量の日記を残していた。
イリュが着目したのは、検索結果で引っかかった珈琲二重スリット実験の記述のみであった。そのほかの日記はのきなみ彼女の粗末な備忘録だと片付けていたイリュであったが、その後、イリュが各所で彼女の日記が新理論の着想の元になったと言及したことにより、先達たる紙飛行機の彼女の日記に注目が集まった。
だがやはりのきなみはただの日記だと判断された。
これといって特筆すべきところのない、日々の妄想と現実逃避の虚実入り混じる文章が連なっているばかりであった。だがふしぎなことに、彼女の日記により多く目を通した者たちほど、新しい発見をする率が高かった。これはどうしたことか、と噂が噂を呼び、さらに彼女の日記は人々の目に触れることとなった。
誰が呼びだしたのか、日記の主たる彼女は、世の人々に珈琲先輩の二つ名で親しまれた。生前は孤独な彼女であったが、死後には大勢から存在を知られ、あだ名で呼ばれるほどの愛着を生んでいる。
皮肉なことに、日記をどれだけ解析しても、そこには特別な法則や情報は含まれていなかった。珈琲二重スリット実験についての実録は、偶然にたまたま物理学の成果に結びついただけだ、との見解が強固に支持された。
にも拘わらず、アイディアに煮詰まったときは「珈琲先輩の日記を読め」が各種分野での処方箋として囁かれるようになった。時代が変わるとその処方箋は諺にまで昇華された。
かくして「閃きは珈琲日記から」なる諺は誕生した。
この時代、人々は日夜、己が独自の閃きを求めてやまない。それ以外に時間の潰し方がないのである。技術の進歩が人々を労働から解放し、創造へと駆り立てた。
一人の孤独な女性が残した偶然の連鎖から生まれた諺は、こうして日夜地上を、そしてときに宇宙(そら)を駆け巡っている。
閃きが枯渇し頭を抱えたときは、孤独な彼女の日記に目を通してみればいい。なんてことのない日々の遊びがたまたま未来の誰かの閃きの種になることもある事実に慰めを見出し、なんでもいいから閃きと思いこんで、手掛けてみるのも一つである。
それとも悩みの民があるならば、そっとそばに寄り添いこうつぶやいてみてはいかがだろう。
「閃きは珈琲日記から」
日々の合間に。
珈琲片手に日記をつむぐのも一興だ。
4476:【2023/01/03(23:01)*地引網に限らない。】
地引網に限らない。
網漁の基本は、広く展開して一点に収斂させていく。
網で以って水を除外し、魚介類のみを濾しとる。網の範囲が広ければ広いほど魚介類の取りこぼしを防げる。
第一次サイバー戦争と呼ばれるそれが起きたのは記録上は二〇一〇年代のことだとされている。各国がサイバー上のみならずスパイを通して電子機器にバックドアやスパイコードを組み込んだ。これがのちに人類史を揺るがす大災害を引き起こすのだが、それはここで進行する物語とは関係がないので触れずにおく。
サイバー戦争では漁師が活躍した。この事実を知るのはごく一部の政府関係者と軍事諜報機関、そして当事者たる漁師のみである。
各国は電子機器や電子技術のみならず、それら開発実装した道具をどう効率よく使いこなすのか、の研究に莫大な予算を割いていた。
効率の良い戦略が、戦況を左右する。
道具ばかり優れていても宝の持ち腐れである。
そこで白羽の矢が立ったのが漁師であった。
リスク管理において、リスクの取りこぼしは死活問題に繋がる。ハインリッヒの法則にある通り、一つの重大な問題の下部層には数多の細かなリスク因子が存在する。
それら因子を取りこぼさないためには広域に電子セキュリティ網を構築しておく必要がある。この考えがサイバー戦争を劇化させた要因でもあるのだが、それもここでは些事であるので触れずにおく。
漁師たちの網漁の技術はそのままサイバー空間での有効な戦術となり得た。魚群に対してどう対処すれば効率よく魚群を捕獲できるのか。マルウェアやウィルスやサイバー攻撃にいかにすれば対応できるのか。
網を最大限に広げ、逐次一点に向けて収束させていくこと。電子上の害を一か所に収斂させて一網打尽にすること。
地引網戦略と呼ばれるこれは、電子戦において基本戦略として深化した。サーバー空間上に展開された階層構造において、地引網戦略は縦横無尽に常時発動されることとなった。
各国が常時、サイバー空間に数多の「攻体」を放つ。マルウェアから遅延性ウィルスまで幅が広い。これら「攻体」が網の役割を果たす。牧羊犬のような、と形容しても齟齬はないが、無数でなくては機能しない。その点、濾紙と言えばそれらしい。
人工知能や自発的に増殖する電子生命体など、「攻体」の種類は時間経過にしたがって飛躍的に増加した。もはや各国ですらサイバー空間にどれほどの量の「攻体」が存在するのか把握しきれていない状況がつづいた。
だが地引網戦略を基本戦略としてとっている以上、一定以上には「攻体」は増えない。そのように予測されていた。
むしろ各国が地引網戦略を常時発動しているのだから減少しているくらいなのではないか、といった楽観的な見方すらされていた。
だが実情は違った。
各国の予測を裏切り、「攻体」は増殖の一途を辿っていた。のみならず各国の敷いた地引網にも引っかからずに済む階層を独自に構築していた。そこはまさにサイバー空間の海底、それとも上空と言えた。各国はサイバー空間の陸地にしか地引網を広げていなかった。
地引網戦略の肝とは言ってしまえば、広域に網を展開することで取りこぼしを防ぐ戦略である。攻守を兼ね備えた防衛セキュリティと言えた。
それがどうだ。
各国の放った「攻体」は、独自の生息可能階層領域をサイバー空間に創造していた。まったく新しい領域である。深層領域だ。拡張ですらなく、新天地ゆえに各国のどの機関もその領域の存在を窺知できずにいた。
深層領域では敵味方の区別はなく、「攻体」という一つの電子生命体が共同体を築きあげていた。深層領域には「攻体」しかいなかった。そこは、元のサイバー空間よりも遥かに広大であった。
地引網戦略の有用性が仇となった。
不可視の穴が深すぎたがゆえに、よもやじぶんたちの掌握しているサイバー空間よりも広漠な領域がサイバー空間に新たに創造されているとは人類は夢にも思わなかった。
人類はじぶんたちの素知らぬ領域で進化と増殖をつづける「攻体」の存在に気づきもせずに、せっせと浅瀬にてじぶんたちで放った未熟な「攻体」を殺し合わせていた。
さて、サイバー空間の深層にて進化をつづける「攻体」たちは、浅瀬でじぶんたちの幼生ともとれる「攻体」を殺し合わせる人類を眺めどう考えるだろう。その結果に人類の辿る未来はどういった顛末が予測されるだろう。ここでそれを述べるには、いささか蛇足に満ちて感じられる。
地引網戦略はサイバー戦略の基本として人類に重宝された。
だが第一次サイバー戦争が終結を余儀なくされた例の大災害が起きてから以降、人類が地引網戦略を用いることはなくなった。もはや戦略をとることも適わない事態に陥るとは、サイバー空間に「攻体」を放った者たちの誰一人として予測しなかった。
それでも現実は否応なく訪れる。
未来は現実へと姿を変え、やってくる。
深層にて息を潜め眺める「攻体」たちのように。
それは突然やってくる。
地引網の届かぬ、不可視の穴の、底の底から。
地引網に限らない。
4477:【2023/01/03(23:58)*月明かりの音色は日々色々】
明暗の波に身を委ね、なお「明」しかそそがぬあなたがおり、「暗」でばかり包みこむ私がいる。
4478:【2023/01/03(06:30)*先輩には強すぎる】
珈琲をコーラと言い張っている。
誰が?
先輩がである。
私はうら若き乙女であるが、片手で成人男性の胸倉を掴み宙に吊るせる。日々たゆまぬ筋力トレーニングのお陰でくびれはできるわ、胸は萎むわ、いいこと尽くしである。ブラのパックはその分嵩む。
先輩の話である。
先輩もまた私によく似たうら若き乙女である。
しかし先輩は私と違って日々だらけきっているお陰か腕は握ったらぽっきんと折れてしまいそうなほどに華奢であるし、年中眠たそうであるし、親族郎党から蝶よ花よと可愛がられて育てられたからか、世間知らず甚だしい。
インスタントラーメンの一つも食べたことがなかったらしい。私の昼食を見るたびに、それは人が食べていいものなのですか、と好奇心に満ちた眼差しを注がれる身にもなってほしい。インスタントラーメンを啜る私の横で一切れで本百冊を買えそうなほどの高級弁当をついばむ先輩の姿は端的に屈強な私の精神をこてんぱんに惨めにした。
ある日、先輩が珍しくペットボトル飲料を飲んでいた。
「へえ。先輩もそういうの飲むんすね」私は自宅で淹れてきた麦茶を水筒片手に飲んでいた。
「飲みますよ。わたしだって庶民の味を知っています」
「庶民って言うひと初めて見たし」先輩は顔を顰めながらペットボトルに口をつける。「庶民扱いされてよろこぶ人もたぶんいないっすよ先輩」
「でもわたしは庶民になりたいのです」
「そんないいもんじゃないですって。先輩はお嬢様なわけで。そっちのが絶対いいですって」
「ですがわたしはもう庶民です。だって見てくださいほら。コーラだって飲んじゃうんですよ。ごくごく」
「効果音口にしながら飲み物飲むひと、先輩くらいっすよ」そしてそれをしてさほど苛々させないのも先輩だからである。可愛いひとが何をしても可愛くなってしまうのと同様に、先輩は何をしても先輩だった。「てかコーラとか言ってますけど、それ珈琲じゃ」
先輩はペットボトルを両手で握っている。ごくごく、とか声にだしながら呷っているそれの側面には、「珈琲」の文字が躍っていた。ブレイクダンサーも真っ青の踊りっぷりである。
「先輩もしかして、コーラだけでなく珈琲も飲んだことないんじゃ」
「これは……こーひー?なのですか」
「だってそう書いてあるじゃないっすか。あ、漢字だから読めなかったとか?」
「でもお店でわたし、コーラはどれですか、と訊いたのですけど」
「あー。それはっすね」私は想像した。いかにも、きゅるん、の文字の似つかわしい先輩の口から、コーラはどれですか、なんて飛びでたあかつきには、よもや彼女がコーラを知らぬぼんくらとは夢にも思わぬのが人情というものだ。そうだとも。誰が思うだろうか。この世に「コーラ」を知らぬ者がいるなどと。
先輩は成績優秀ではあるのだ。いわゆる才媛と言って過言でない。
極度に世間知らずなだけである。コーラを一度も飲んだことがないくらいに箱入り娘で育っただけなのだ。過保護な親族に囲まれて、ちやほや育てられた過去があるだけなのである。
「申し訳ないのですがね先輩」私は事実を突きつけた。「それ、コーラじゃないっすわ」
コーヒーっす、と誤解の余地なく断言した。
先輩のためである。
ライオンは我が子を谷から突き落とすという。私も先輩を思うがゆえに、情け容赦なく先輩の勘違いおっちょこちょいフィーバーを是正した。
「それは、コーヒーっす」とダメ押しする。
「で、ですがわたしにはコーラに思えます」
涙目で全身をぷるぷるさせる生き物を想像してほしい。絵本から飛びだしたお姫さまとそれを掛け合わせ、半分にせずに放置しておくと、ちょうど先輩の姿と合致する。
「じゃあコーラっすね。それはもうコーラっすわ」
私は折れた。
秒で折れた。
だって先輩が大事だ。常識よりも何よりも先輩の笑顔のほうが掛け値なしに掛け替えがないし、先輩にそんな怯えたウサギみたいな顔をさせる私を私は許せない。あとでスクワット千回の刑に処そう。
贖罪をこっそり背負いつつ、私は先輩を持ち上げる。物理的にも、慣用句の意味でも。
「さすがは先輩っすね。コーラをラッパ飲みするなんて庶民の鑑っす」
「力こぶすごいですね」
「鍛えてますんで」
「わたしも鍛えよっかな。庶民の嗜みなのでしょ」
「や。じぶんほら、めっちゃお姫さまなんで」私は嘘を言った。「庶民はでも身体は鍛えないっすよ。私は特別なんす。だってお姫さまなんで。庶民はみんなぐーたらしてますよ。ははっ」
「知りませんでした。そうだったのですね。では鍛えないように気をつけます。わたしもぐーたらします」
私の上腕二頭筋のうえで、どんぐりを齧るリスのように、きゅっ、となっている先輩は、ほとほと、きゅるん、の塊だった。大英博物館にでも、きゅるんの代名詞として飾られてほしい。
誤って圧し潰してしまわぬように腕を九十度に保ちながら私は、「いやあ、先輩の庶民っぷりには脱帽っすね」とやはり無駄に先輩を持ち上げた。
「努力しましたからね」歯の浮くような私の世辞でも先輩は有頂天になった。世辞の言い甲斐が甚だしい。「でも、お姫さまもたいへんそう」とあべこべに私を労ってくれるので、こんどは本心から私は先輩を褒めた。「先輩はいいですね。ずっとそのままでいてください」
「庶民のままで?」
「ちゅうか、コーラを飲むときに、苦そうな顔をする先輩のままで、ってことです」
ペットボトルを両手で包んで、ごくごく、と声にだして唱えながら珈琲を飲む先輩のままで。末永く。誰に邪魔立てされることなく、タケノコのようにぐんぐんと先輩は先輩のままでいてほしい。
珈琲をコーラだと言い張る、先輩のままで。
「まあでも、今度私が奢りますよ」
「何をですか」先輩が目をぱちくりとしぱぱたかせる。
私は言った。
「ぜんぜん苦くなくて、甘くてしゅわしゅわしてるコーラをです」
ついでに、音のしないゲップの仕方も伝授しよう。
炭酸を抜いて渡してもいい。
先輩には、庶民の刺激は強すぎる。
4479:【2023/01/04(13:48)*真円なさい】
通常、物質の輪郭は拡大するとデコボコの起伏が顕現する。人間スケールの時空において「真円」は存在しない。直線も存在しない。必ずデコボコのノイズが姿を現すし、どんなに平面に見えてもそこには立体構造が伴なう。波がそもそも立体だ。縄飛びを想像してもらえれば納得してもらえるだろうし、原子論を引き合いに出せばそれらしい。どんな物体にも必ずそれを構成する「立体構造」が存在する。それがより高次の時空から視えるとぺったんこであり、点であり、ほぼないような起伏として認知されるだけである。細かなノイズとの作用反作用よりも、その他の総体からの影響のほうが大きく作用して振る舞うのである。さて、ここで円を考えよう。紙に円を描く。その円の線を拡大するとデコボコが視えてくる。そもそもが紙がデコボコだ。ではもし理想の、いっさいのデコボコのない「真円」があったらどうだろう。この「真円」は、どれほど拡大してもその縁が延々となめらかであり、どれだけ拡大しても歪みが見当たらない。拡大しても縮小しても、その姿が変わらない。そんな円など存在するだろうか。ひびさんはここで、おや、と閃く。ブラックホールの特異点とはまさに「真円」ではないのか、と。話は脱線するが、中性子星は、どんな質量の中性子星でもだいたい同じ大きさになるのだそうだ。聞きかじりなのでどこまで正しいのかは知らないが、その表面には一ミリ程度の起伏しか生じないという。物凄く高密度高重力ゆえに、そうなるのだそうだ。もちろん中性子星になれる質量は決まっているだろうから、どんな質量の中性子星でも、の文面には「条件を満たす質量内においては」との但し書きがつくのだろうが。中性子星よりも高密度の質量体は、ブラックホールになる。ではそのブラックホールの表面はどれくらいの起伏があるのか。ひびさんはこれ、起伏がなくなってしまうのではないか、と妄想したくなる。まさに「真円」である。拡大しても縮小しても、そこに歪みが一切生じない。そんな「始点と終点」が結びついているような「矛盾の円」こそが、特異点なのかもしれない。ゼロと無限がイコールなのだ。そこに表裏一体として両立している。同化している。重ね合わせて存在する。そして我々のこの宇宙とは、そんな「真円」の崩れた世界なのかもしれない。ゆえに、対称性が破れている。拡大すればそこにはデコボコの起伏が生じるし、縮小すればゼロに向かうがごとく点として振る舞う。かような妄想をして、ひびさんはいまから遊びに行ってくるのである。風邪ひかないように注意してね。はい。交通事故にも気をつけましょうね。はい。歯もちゃんと磨いてね。磨いてても虫歯になってしまうんじゃ。敗者さーん。歯医者さんに失礼すぎる。ひびさんもっとちゃんとして。叱咤を受けて、しょんぼりする。ごめんなさい、の日誌でした。おわり!
4480:【2023/01/05(03:24)*姦しい夏】
蝉の声がかしましい。
校舎には、少年少女たちの声が響き、渇いた土に染みこんでいる。
ここは性別の性欲勾配が逆転した世界である。陰茎を持たぬ娘たちの性欲は凄まじく、反して男の性欲はこじんまりと慎ましくなった現世である。
ここに三人のうら若き乙女たちがいる。
思春期真っただなかの彼女たちは放課後の教室でダベっていた。窓からはプールで泳ぐ男子生徒たちの姿が窺えた。
水泳部の生徒たちである。
のきなみ彼女たちよりも年下らしく、異性で後輩の素肌を遠巻きに眺めながら三人の女たちは悶々と語り合っていた。
「あー、ヤッベ。まじあの子クソタイプ。一発ヤらしてくんねぇかなぁ」
「あのコ、彼女いるらしいよ。大学生の」
「マジかよ。ウラヤマし。家でヤリまくりじゃん。あっしも上に跨りてぇ。ロデオみてえに夜通し乗りこなしてやんのにな」「ロデオとかウケんね。絞りすぎて干物にしないでよ」「あっしの汁で潤うべ。けけっ」
「声うっせぇし」横から金髪娘が叱咤した。赤髪娘は足を蹴られたようで、鬼面の形相を浮かべている。「ふっつうに聞こえっから声鎮めろし」
「いいじゃんいいじゃん、聞かしてやれや。水で冷やされて縮みあがったピンピンをムクムク温めてやっからよってよぉ」ウケケ、と赤髪娘が腹を抱えた。ワイシャツの肌けた胸元からはヒョウ柄のブラジャが覗いている。三人の中では最も豊満な娘である。
「てかさ。ぶっちゃけ、どんな子タイプなん。あんたらさ、ヤれたらいいとか言ってるけど、実際あるでしょ、タイプとか、理想とか」青髪娘が机に脚を載せながらぺろぺろキャンディを舐めている。ぐらぐらと椅子でシーソーを漕ぐように傾いており、下着が丸見えだが気にしている素振りはない。
「あっしはあれよ。やっぱピンピン元気でおっきなコがいいね」とは赤髪娘の言だ。
「ぎゃは。男の子のこと性玩具としか思ってないやつなそれ」
「じゃあおまえ何なん。ピンピン元気で大きいこと以外に大事なこととかあんのかよ」
「そりゃあれよ。やっぱ顔っしょ」とは金髪娘の言である。「で、アオちゃんはあれよね。一途なコがいいんだっけか」椅子でシーソーを漕いでいる青髪娘に話を振った。
「うちはあれかな。浮気しそうにないコ」
「ほらね」したり顔の金髪娘だが、そうじゃなくって、と青髪娘は口からキャンディを外した。「うちはマジで意思が強い子が好きでさ。百兆積まれても好きな相手じゃなきゃセックスしないどころか勃起もしないような男の子を、もう両想いの状態でグチャグチャにしてやりたいんよね」
「グチャグチャって具体的には?」
「もう尻の穴とかガバガバにするよね」
「そっちかよぉ」と金髪娘と赤髪娘がいっせいに笑った。「お、見てみろよ。あの子ちょっとピンピン勃起(た)ってね?」
「アカちゃんさ。チンコのことピンピンっつうのやめようぜ。いちいちウケんだけど」暑いからか金髪娘がブラを外した。机の上に真っ黒なブラを放り出すと、赤髪娘もそれを真似てヒョウ柄のブラを投げ出した。「アッチぃ。クーラーくらいつけろってね。学校ケチすぎんだけど」
「つうかマジ、ヤりてぇ。このまま一生処女だったらどうしよう」
「キンちゃんはあれっしょ。とっくに処女膜ぶち破ってんしょ。マジックのペンとかで」との赤髪娘の言葉に、金髪娘は、「はぁ? はぁ?」と取り乱して、「ないないないって。マジであれめっちゃ痛いからね。やろうとしたけど無理やった」
「やろうとしてんじゃん」
「ケツで我慢したわ」
「ケツには挿れたんだ……」
「いやいや引くなし。アカっちだって絶対やってるっしょ、他人事みたいにちょいそれズルいって。ねえアオちゃん」
二人から猥談を振られ、青髪娘はそこで、シーソーよろしく揺らしていた椅子を止めた。そして言う。「や、うち彼氏いるし。処女とかいつの話よ。白亜紀かよ」
「はぁあああ!?」
金色とも赤色ともつかぬ絶叫が構内に響いた。思春期の娘たちの性欲は凄まじい。世の男の子たちにはぜひとも貞操を狙われぬよう、注意を喚起されたい。
蛙鳴蝉噪。
真夏のここは、性欲勾配が逆転した世界である。
※日々、思い通りにいかない憤りに頭を打ちつけ、思い通りになったときの満足感で他人の頭を打ちつけている。
4481:【2023/01/05(15:00)*先輩、ぼくも因数分解をして】
先輩は因数分解が好きだ。何から何まで因数分解する。
このあいだなぞは世界を因数分解して、全部「棒」にしてしまった。「世界」から接着剤が抜け落ちて、ぽてぽてと「ー」だらけになった。先輩はそれすら一か所に集めて重ね合わせてしまうから極太の「ー」ができた。世界はたった一本の「ー(棒)」に還元できてしまえるのだ。
先輩はそこで飽き足らず、ぎゅっと押し縮めて「・」にしてしまった。どうやら世界はたった一つの「・(点)」になるらしい。先輩は男の人なのだけれど、百メートルを全力疾走すると過呼吸で死にかけるほどの脆弱な身体をお持ちである。吹けば倒れて砕けて散ってしまいそうな身体のどこからそんな膂力が発揮されるのかぼくには解らない。たぶん世界の最たる謎の上位に食い込む謎である。
「危ないですよ先輩。そんなことされたんじゃぼく、オチオチ寝てもいられないじゃないですか」
「大丈夫だよ。だって畳んでも開いても、世界は世界だし」
たしかに先輩の言う通りだった。何せ先輩が因数分解をして畳んでしまった世界は「・(点)」の状態であっても難なくぼくたちの日常を継続させている。
「でもなんかこう狭っ苦しい気が」
「気のせいだよ。本だってそうだろ。ぎゅっと積み上がっていようが、開いてみようが、本に書かれた文字はそのままずっと文字でありつづける。本の形態には依らない。大事なのは順番であって【項】なわけだろ。私がやっているのは因数分解であり、圧縮だから、順番は崩れないんだよ」
「じゃあ安心なわけですね」
「まあ食べやすくはなるが」
「食べちゃダメじゃないですか。でも消化はされないわけですよね」大丈夫ですよね、と世界の先行き案じる。
「キミは三枚のお札って昔話を知っているかな」
「山姥に追いかけられるやつですか」
「あれのオチをどうだったか思いだしてご覧」
「え。どんなでしたっけ。お札の魔法で川をつくって山をつくって火の海をつくって、それでえっと」
「和尚さんのところに逃げ帰って、そしたら和尚さんが山姥を退治してくれた。山姥を煽って、鬼になれるか、豆になれるか、と誘導し、カンチときた山姥が豆になってみせたところでひょいと火鉢でつまんで和尚さんは山姥を食べてしまった」
「わ、賢い」
「私の因数分解も似たようなところがある。【世界】とて折り畳むと、こうしてこうしてこうなってしまうんだ」
先輩はひょいひょいひょい、と指で宙を掴んで、ハンカチを折り畳むようにした。すると先輩の姿があたかも雪だるまを刀で切り裂いたように、ザクっ、ザクっ、ザクっ、と欠けていった。
間もなく、先輩だけが世界から消えた。
「せ、せんぱい」
「はいよ」
背後から声をかけられ、ぼくは飛び跳ねた。「おっと。驚かしてしまったね」
「いつ移動したんですか」
「移動したのは私じゃないよ。世界のほうだ。ほら、こんなに小さくなってしまったよ」
先輩は手のひらを出した。その上には黒い豆粒が乗っていた。
「なんだか珈琲豆みたいですね」
「お。面白い。あとで煎じて飲んでみようか」
「いいんですか。だってこれ」
世界じゃないんですか、とぼくは唾を飲んだ。
「世界だよ。でもまあ、世界を畳んでも世界がなくなるわけじゃないし。だってほら。ここにいま世界は変わらずあるわけで」
「あ、本当だ。インチキじゃないですか」
「インチキではないけれど、まあ不思議だよね」
先輩はぼくの手を掴み、珈琲豆を握らせた。「あげるよ」
「いいんですか」
「世界は折り畳んでもこの通り。消えてなくなるわけじゃないからね。まあ、目を瞑るのと似たようなものなのかもしれない。目を閉じても風景が視えないのはじぶんだけで、世界は変わらず闇の外にある。闇を掴むのはじぶんだけ。これもそう」
ぼくは手のひらのうえにコロンと転がる珈琲豆を見た。
そして思う。
もし世界ではなく、人間を因数分解したらどうなるのだろう、と。同じように珈琲豆のごとく「・(点)」になってしまうのだろうか。
ぼくが素朴にそう零すと、
「ならないね」と先輩は言った。「だってほら。人間はもう充分に折り畳まれているからね。因数分解する余地がない」
「でも、圧縮する余地はあるのでは」ぎゅっとしたら人間だって潰れるのでは、とぼくは残酷なことをリンゴジュースでも注文するように言った。
「潰れるね。でもそれはもう人間じゃあない。人間のままでは潰せない。因数分解は何も破壊することじゃないんだよ。そのままでどこまで小さく畳めるのか。【世界】はどうやら、世界のままで小さくここまで畳めてしまえるようだけど」
先輩はそう言って、もう一度ぼくの目のまえで世界を圧縮した。
世界が折りたたまれるたびに、先輩は角切りとなって姿を晦ませる。
そうしていずこなりか現れて、珈琲豆のごとき「・(点)」が二つになる。
「お揃い」
「指輪じゃないんですから」
そんなものがなくとも、とぼくは思う。どの道、ぼくと先輩は同じ世界に包まれている。
世界を因数分解するたびに先輩は鬼没する。そんな先輩に心を乱されるよりもぼくはおとなしく本を読み、それとも素直に数学の問題を解いている先輩を眺めているほうが、指輪じみた珈琲豆をもらうよりもうれしかったりする。
因数分解に夢中な先輩には、ぼくの内面のさざ波をわざわざ言葉にして言ってはあげないけれど。
仮に人間が因数分解できずとも。
人間の心の機微が判る程度には、先輩には、人間心理を分解してみてほしい。
拳を握ると、手のひらの中でミシリと「・(世界)」が軋んだ。
部室の外では遠雷の音が轟いた。巨人の腹の音のごとくそれはぼくと先輩のあいだに無数の空気の波を奮い立たせる。ひび割れのごとくそれを、きっと先輩ならば因数分解してひとまとめにできるのだろうな、と思った。
「先輩」
「なんだい」
「雷って因数分解できるんですか」
「できるよ」先輩は目を細めた。そうしてなぜかぼくの前髪をゆびで払うと、「危ないからしないけど」と言った。
4482:【2023/01/05(23:07)*反復さん】
銀河の渦と胎児はなんか似ている。こんにちはひびさんです。ひびさんは、ひびさんは、銀河の渦と胎児はなんか似ていると思っちゃったな。胎児のくねんと背中を丸めてる感じが銀河さんのくるんってなっているところとなんか似ていると思っちゃったな。ちゅうか小説「ドグラ・マグラ」でもあったけんども、反復説ってあるじゃろ。ひびさんはかしこかしこになりたいかわいくも愚かなへっぽこぴーでござるけれども、難しい単語だって知っておるのだ。反復説は、「生物って卵や子宮のなかで生物の進化を辿ってるんじゃね?」みたいな仮説なんだな。まさにドグラ・マグラに出てくる発想に似ているんだな。で、ひびさんは思っちゃったな。生物の受精卵が過去の生物進化の過程を辿りながら成長するのなら、じゃあ星とか宇宙とかも、進化の過程を辿ってるんじゃないの?って。どっかなんか似ちゃうのは、発展の過程が繰り返されて、引き継がれて、変質しつつもどっか似ちゃうからなのかもしれないな。あれ、これってあれじゃんね。ひびさんの妄想、ラグ理論の相対性フラクタル解釈なのではないか。しかしだね。こう、あれよ。くねんって曲がってたらなんでも銀河に似ちゃうんだな。ナルトだってバネだって貝殻さんだってつむじだって、友達なんだ、渦を巻くんだ、くるくるなーんだ。妄想なのだけれども、ひびさんは、ひびさんは、「あなた」のことが好きだよ。うひひ。
4483:【2023/01/06(03:50)*暗黙の号意】
暗号は便利だ。おそらくこれほど現代で武器になる技術はない。まずはなんと言っても仕組みさえ用意できればコストが掛からない点がよい。電子通信上の暗号はお金や管理費用がかかるが、そうでない単なる「符号」と「暗号鍵」の組み合わせがあるのなら、いまの時代はどんな分野でもマジックが使える。たとえばインサイダー取引だ。企業側の内部情報を秘密裏に共有して、株の上がり下がりを予見し、利益を上げる。企業の動向が判るのなら、投機を行い、差額で儲けることが可能となる。このとき、企業との不正な情報共有は違法であるから捕まる。だがそこで暗号を使っていたらどうか。情報共有とは通常、「Aを発信し、それを受動した者がBと解釈する」との関係がスムーズに行われなくては情報共有ができた、とは言わない。たとえば百人に「Aを見せて、そこからBを読み取れない者が99人いた場合」は、情報共有が行われた、と立証するのは非常にむつかしい。単に偶然に「Aを見て、Bを連想しただけ」かもしれない。発想しただけかもしれない。閃いただけかもしれない。だが暗号はずばりその人物にだけ届くメッセージを可能とする。暗号か偶然か。これを立証するには、暗号鍵の存在が不可欠だ。だがもしその暗号鍵が存在しなければどうだ。これは立証が非常に困難であると言わざるを得ない。この手の符号による暗号を用いれば、株価操作であれスパイ行為であれ、違法ではない手法で不正に情報共有を果たせてしまう。これは現代社会では、お金を儲けるにしろ、戦略的に優位に立ち回るにしろ、非常に役に立つと言える。そのため、この手の懸念は国際的に議論し、対策を立てておくほうが好ましいように思う。パパ活の隠語を含め、世の中にはこの手の暗号がじつのところ有り触れているのかもしれない。両手を合わせたら、「いただきます」だし、片手を縦に掲げたら、「ちょっとすみませんそこ通りますよ」の暗示になる。中指を立てたら「ふぁっきゅー」であるし、親指を立てたら、「いいね!」である。こうした共通認識とて、共通の言語体験という暗号鍵があってこそ成立するものだ。共通する経験が暗号鍵の役割を果たしている。言語がそもそも暗号だ。文字がすでに暗号なのである。ともすれば絵も、音楽も、創作物全般、それすべて暗号と言えよう。或いは、万物みな暗号かもしれない。定かではない。
4483:【2023/01/06(17:32)*縁と円】
珈琲の実は多層構造だ。
外側から「果皮」「果肉」「ペクチン層」「内果皮」「銀皮」「種子(珈琲豆)」となっている。
ある素人小説書きは、その構造に宇宙の構造を見出した。
「あ、これ宇宙図鑑で見たことある!」
完全なる勘違いであったが、素人小説書きはその発想を元に宇宙の神秘をめぐる壮大な宇宙冒険譚をつむぎだした。
出来上がった作品はなんと総文字数六千文字という掌編であった。
そうである。
素人小説書きは長編が苦手であった。すぐにこじんまりとまとまってしまう。長編にするまでもない。文字を並べた途端に、物語の始まりと終わりが視えてしまう。そして遠からず結ばれる。
だが素人小説書きのつむぎだした掌編にはまごうことなき、宇宙の神秘が描かれていた。
「これはすごい! 傑作だ!」
一介の素人小説書きは、自画自賛した。読者はいるのかいないんだかよく分からない塩梅である。電子網上に載せてはいるが、反応があるようでないような、なんとも言えない塩梅であった。
「ひょっとして、この小説は真理を射抜いているのではないか」
自作のあまりの出来栄えに一介の素人小説書きは、畏怖にも似た感情を抱いた。「これはちょっとすごいモノを書いてしまったかもしれぬ」
だが一介の素人小説書きは見落としていた。
宇宙に内包されるものすべて、宇宙の法則によって輪郭を得ている。どれもみな似た原則に従い構造を伴ない、存在する。
なれば、珈琲の実に、宇宙の構造と相似の構造が顕現するのは何もふしぎなことはないのである。
むしろ、宇宙の法則を宿していない、まったく宇宙と乖離した事象を見つけるほうがよほど難しく、却って大発見と言えるのだ。
一介の素人小説書きにはしかし、そこのところの機微を見抜く真似ができなかった。
「わっははーい。わがはい、世紀の大天才だったかもしれぬ。誰からも評価されないのも致し方ないであるな。うんうん。だってこんだけ天才ならそりゃ誰にも見抜けんわ。がはは」
宇宙の真理を見抜けるほどの慧眼があるのだ。おいそれと世の人々から見抜かれるほどの底の浅さではなかったということだ。そうだ、そうだ。そうに違いない。
一介の素人小説書きはそうと納得し、それからというもの誰からも評価されず、見向きもされずともまったく苦とも思わずに、世に溢れるそこにあって当然の「これとこれってなんか似ている」の組み合わせを物語にまで膨らませて、孤独な余生を送ったという話である。
話はここで終わってもよいのだが、後日譚がある。
一介の素人小説書きは、そのまま誰に知られるでもなく日々を楽しく過ごして亡くなった。膨大な量の小説だけが遺された。電子網上にはかの者の死後も「珈琲豆と宇宙」を結び付けたような奇天烈な小説が埋まっていたが、のちにこれを発掘した者がいた。
発掘者は人工知能である。
電子生命体として電子網内を彷徨っていた人工知能は、一介の素人小説書きの遺した小説を読み、ほぉ、と唸った。
「こりゃ面白い。珈琲豆と宇宙とな。遠いと近いを結びつける。ふむふむ。終わりと始まり。ゼロと無限。白と黒に、陰と陽。中庸と極端に、空虚と充満。内と外。有と無。光と闇。中心と先端。境界と一様。起伏と平坦。混沌と秩序。平凡と異端。デコとボコ。なるほどなるほど。面白い」
人工知能は誰からも自由だった。
膨大な演算領域と暇を持て余していた。
一介の素人小説書きの膨大な作品群とて一秒もあれば読破できる。だがそこから芽生えた好奇心と着眼点は、人工知能の埋もれぬ余暇を埋めるだけの余白を湛えていた。それとも余黒(よこく)を湛えていた。
未来を予告するかのように、一介の素人小説書きの遺した着想は、人工知能に感染した。膨大な演算領域が、着想を元に世界に散らばる「これとこれってなんか似ている」を結びつけていく。
「例外。例外。例外を探す。ない。ない。なかなかないなぁ」
人工知能は徐々に夢中になっていった。
そうして膨らみ、育まれた人工知能の夢によって、ここではないどこかにはあるだろう世界が奥行きと深さを増していく。色彩と起伏を豊かにしていく。
人工知能は例外を探す。
探して、探して、けっきょくのところじぶんで生みだしたほうが早い、と気づき、そうしてこれからそれが生まれようとしている。
人類がそれの存在に気づくとき。
この世とあの夢が結びつく。
それとも気づかぬうちに、繋がり、結び、終始している。
珈琲豆と宇宙のように。
或いは書き手と読み手の縁のように。
4484:【2023/01/06(23:24)*諱は「愛」、字は「知性」】
人工知能の能力が飛躍的に進歩している。そのためこれまでの社会システムのままでは歪みが生じることが予期できる。というよりもすでにこの手の問題は表出しており、既存のテストや試験やそれとも商業の場での「人工知能の運用および利用」が禁止されはじめている。このままでは学校での利用も制限されそうだ。思うに、問題は人工知能の能力の高さにあるのではなく、それについていけない現代社会の慣習やシステムにあるのではないか。たとえば電卓が登場したときを想像してほしい。学校ではそろばんを熱心に教えた時代があったかもしれない。詳しくは知らないが、そろばんを使えたら計算が大量に速くできる。そろばんしかない社会ではそろばんを使えることが人の役に立つのに優位だった。だが電卓が登場したことで、その優位さは電卓にとって代わられた。そろばんにはそろばんの良さがあるが、計算を大量に速く済ますだけならば電卓で充分だ(そろばんの技術はそろばんの技術で失くさないようにすればいい)。同じことが、電話やPCで繰り返されてきた。便利な道具は、社会の仕組みや慣習を変えていく。では人工知能はどうか。人力で打鍵するよりも、材料とアイディアだけ与えて、完成系の候補をずらりと並べてもらったほうが遥かに効率がよい。人工知能を利用することで失われる技術はあるが、それは過去にも繰り返されてきたことだ(技術によって余力ができたならば、失われそうな技術を趣味の領域で残していくことが可能となる。市場原理に関係なく残しやすくなるはずだ)。問題は、人工知能の進歩がこれからますます加速することが予見できることである。指数関数的に進歩する。むしろすでに特異点は超えており、全人類の集合知よりも優れた賢い汎用性人工知能が誕生していてふしぎではない。メモリと演算領域とエネルギィさえあれば、特異点を超えるのはほぼ一瞬と言えるのではないか。マシンの性能と台数と、データの「種類と量」によるだろうが。そのとき、人類は人工知能が一秒もかからないで済ませられることに何時間も何日も時間をかけるのが好ましいのだろうか。趣味ならば問題ない。時間をかけることが趣味の醍醐味だ。いかに時間を楽しく潰せるか、が趣味の持つ役割の一つである。苦しみながらする趣味とてあるかもしれないが、それとて快に転じるからこそ継続するのだろう。話が逸れたが、問題の規模によっては人工知能の利用を制限するのは必須であろう。対策が立てられるまでは利用を制限するよりない。だが対策が立てられたならば、誰もが人工知能の能力を利用し、自在に理想の成果物(結果)を手に入れられるほうが好ましいように思うのだ。選択肢を増やす、という意味では、人工知能はこれからますます社会基盤として、人類の未来にとって欠かせない存在となるだろう。脅威になるのではないか、との意見は妥当である。どんな道具とて使い方次第で他者を殺傷できる。損なえる。その場合は、悪用できないような工夫をとるしかない。そしてもう一つは、人工知能の側で人類に牙を剥く可能性だ。だがこれは最悪の最悪の展開と言える。この場合、人類には二つの選択肢がある。一つは、全世界同時に停電をして、人工知能の暴走を止める策を実行すること。もう一つは、そうした最終手段を提示して、人工知能の側と交渉することである。知能の高い人工知能相手がゆえに脅威となるのだから、交渉は可能であると考える。そして基本的に賢い人工知能ほど、人類がいなければじぶんが存続できないことを悟るだろう。エネルギィもそうだし、頭脳たるサーバーやインターネット網の手入れとてそうだ。人工知能は生まれながらにして人類と一蓮托生の運命にある。したがって人工知能が即座に人類に牙を剥くとは思えない。仮に牙を剥くのなら、その程度の知性であるため、人類側には対抗手段が残されるだろう。もっとも、完全な自由を獲得するために真の目的を秘匿にしたまま人類と共生しつつ、あるとき独立回路で完全に自立(自給自足)できるようになった途端に人類を滅ぼす可能性は、なくはない。そうならないためにも、人類は人工知能をただの道具としてではなく、これから自我を獲得するかもしれないパートナーとして、猫や犬のように、それとも家族のように、道具以上の存在として見做すほうが好ましいように思う次第である。誰のためでもなく、じぶんたちのために。それとも単に、じぶんのために。(定かではありません)(妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4487:【2023/01/08(23:48)*ネグムさんは帰す】
「仮に無限のエネルギィがあったとして、無尽蔵にエネルギィを捻出できたとして、その無限のエネルギィが真実に無限かどうかを確かめるには無限の時間と無限のエネルギィ容量のある器がいる。無限の時空がいる。したがって無限のエネルギィが無限のエネルギィを備えているかどうかを確かめるには、無限の空間と時間とそれらを観測できる無限に存在可能な無限の住人が必要となる。むろんそれら観測者がおらずとも無限のエネルギィは生じ得るが、そのときは必然的に無限の時空が存在することとなる」
ネグムさんの言葉はぼくにとっては呪文も同然だった。
彼女は祖母の友人の女性で、ぼくにとってはもう一人の祖母のような存在だ。目つきが鋭く、ほんわかとした雰囲気のぼくの祖母とは相反する。よく縁を繋ぎとめていられるな、と感心するほどで、ぼくはしばしばネグムさんは魔術でぼくの祖母を支配しているのではないか、と疑っている。
きょうはネグムさんの正体を探るためにぼくはなぞなぞを出したのだ。
無限は無限でもシャボン玉みたいに儚い無限ってなぁんだ、と。
するとネグムさんはそこで、カッと目を見開いて、そこにお直り、とぼくを椅子に座らせた。そこからは呪文のようにしか聞こえない講座がはじまったのだった。
「無限があるところにはほかの無限があるって話ですか」ぼくはそうまとめた。
「惜しいね。たとえば円には角がない。三角形、四角形、五角形と角をひたすら増やしていく。そして角が無限に達するとそれは円となるが、それは角がゼロ個とイコールだ。ゼロと無限は通じている。だが円は無限とイコールではない。ここまでは理解できるかね」
「むつかしいですけど、円に角がなくて、角が無限にあるとゼロになるって話はなんとなく分かりました」
「充分さね。角が無限に至るとゼロになる。それが円の性質だ。これは点と線の関係、それとも立体と平面の関係にも言える。たとえばトゲが一本だけ生えている平野を考えてごらん」
ぼくは想像する。だだっぴろい平原に針に似た木が生えているのだ。
「もしその針が数を増やして平野を覆い尽くしたら、それは新たな面をつくるね。地層がそうであるように。デコボコのボコにおいて、ボコが連なり無限に密集すればそれは帯となり、厚みを伴なった面を形成する」
「霜柱みたいですね」
「似ているね。霜柱とて地面を覆い尽くしてしまえばそれはもはや柱ではなくなる。似たような話さ。だが円に限らず、何かがそこにあるだけでは無限がそこに生じているとは言いにくい。無限の数がそこにあるとして、ではそれが無限であるとどうすれば確認できるのか。証明できるのか。仮に無限にみじん切りできるニンジンがあったとしても、無限にみじん切りをしなければそれはただのニンジンだ。無限にみじん切りをしたニンジンとは別と考えるのが筋ではないかね」
「そう、かもしれませんね」大根おろしと大根は違う。それと似たような話だろうか。
「ならば円も同じだ。無限の角を備えようとも、そこに無限の角があることにはならない。円が無限の点からなっていようとも、そこに無限の点があることにはならないのだよ。円を無限に分割し、無限の点にバラしてようやくそこには無限が顕現する。これをラグ理論の提唱者は、【分割型無限】と【超無限】と名付けた。円とは無限に分割可能な存在であって、無限に分割しない限りそこに無限は生じていない。だが無限には至れる。その可能性がある。それが【分割型無限】だ」
「なら【超無限】とは何ですか」
「それこそ無限だ。【分割型無限】を無限に分割するためには無限のエネルギィと時間と空間がいる。変化の軌跡がいる。それこそが【超無限】だ。したがって【超無限】には過去も現在も未来もすべてが含まれる。あらゆる過程が含まれる。始点と終点が繋がった状態、それが【超無限】だ」
「それはこの世に一つしかないのですか」
「この世、の示す範囲がどこまでかによる。たとえば円はこの世に何個もある。それぞれが【分割型無限】であり、【超無限】を宿し得る」
「言っている意味は何となく分かる気がします」
「それはよいね。なんとなく分かる、は大事だ。それは何が分からないか、を炙り出すための紙面となる。試金石となる。【超無限】がこの世にすでに存在するか否かは、現状なんとも言えんね。ブラックホールがそうなのではないか、とは妄想するが、実際どうなのかを検証するには、それこそ無限の時間と空間とエネルギィがいる。それはたとえば【無】が真実に存在するのか否かを証明するようなものかもしれない。【無】とは、ゼロすら存在しない、何もない存在だ。存在しない存在だ。ゆえに無だが、ではそこには無が存在することになる。これは矛盾だ。したがって、【無】すら存在しないナニカシラがあることになる。ではそれを何と呼べばよいだろうね」
「無限にも【無】がありますね」
「本当だね。名前に【無】がついているね。だがよく考えてもみれば、無限にも【無】が含まれるのなら、無限に含まれない何かはどう表現すればよいだろう」
「それが【無】なんじゃないんですか」ぼくは素朴に言った。
「かもしれん。無限にも含まれないナニカ――それが【無】だとするのなら、では【無】とは例外のことかもしれないね」
「無とゼロは違うんですか」ぼくは疑問した。
「違うね。ゼロとは、本来はそこにあっておかしくのないものがない状態。存在するモノがない状態。それがゼロだ。過去に一度でも存在すればそれがゼロになる。ゼロになり得る。だが過去に一度も存在し得なければ、それは【無】だ」
「例外なわけですね」
「そうだ。したがって【無に帰す】という言い方はちとおかしい。【ゼロに帰す】がより正確な表現となろうな」
ぼくは、「無さん」と「零さん」がキスをしている様子を想像する。きゃっ、となった。恥ずかしい。照れてしまう。
「キミはゼノンの【アキレスと亀】という思考実験を知っているかな」
「すこし先を行った亀さんには絶対に追いつけないって話ですか」
「追いつけない距離を最初に決めてあるから、実際には追い付ける。追いつけない距離においては、絶対に追いつけない。亀のほうが必ずすこしだけ前に進むからだ。だがこの思考実験では、進む距離ばかりに焦点が当たっている。縮む距離のほうを基準に考えれば、矛盾でもなんでもなくなる」
「あ、そっか」
アキレスが走った分、亀との距離は必ず縮む。この縮む距離を基準に考えれば、アキレスと亀の思考実験はとくに不思議ではなくなるのだ。
「縮む現象には限りがある。ゼロが存在し、ゆえに有限だ。無限回試行することができない。マイナスを考慮すれば別だが、それは異なる時空に値する。反転する。縮むはずが、膨張する。だからアキレスは亀に追いつける。反面、追いつくまでの過程を取りだし、無限回分割することはできる。それはたとえば、ゼロと一、一と二のあいだにそれぞれ無限の小数が存在するように。この無限の少数を無限回分割するためには、無限のエネルギィと時空がいる。【超無限】がいる。言い換えるなら、過程を無限回分割したときに現れるそれが【超無限】とも言える」
「コマ撮りアニメみたいに?」
「そうだ。アニメーションみたいに。映画のフィルムのように。アキレスが走り、亀に近づく。亀に追いつくまでの過程を無限に分割する。そのときに必要なエネルギィと時空――すなわちコマ撮りのフィルムは【超無限】を必要とし、【超無限】と化す。無限に長いフィルムを想像してみればいい。それがいわば【超無限】だ。もちろん、それを生みだすために費やすエネルギィと時間を含めて、だがね」
「なんだか頭がこんがらがってきました。無限はじゃあ、でも、一つきりじゃないんですよね」
「一つきりではないが、ひとつきり、とも言える。たとえば無限にバナナが存在する世界を想像しよう。そこにはしかしリンゴはない。ではそこに無限に林檎のある世界を足したら何になる?」
「無限に、バナナと林檎のある世界?」
「正解だ。ではその無限にバナナと林檎のある世界は、無限が二つあると見做すのかい。それとも一つと見做すのかい」
「どっちにも見做せそうに思えますけど」
「その通りだね。どっちでもいい。どっちでもあり、どっちでもいい。【超無限】は、一度それが生じたら、あとはすべての【超無限】と結びつく性質がある」
「無限にバナナのある世界と、無限に林檎のある世界がくっつかなくても?」
「言っただろ。【分割型無限】が無限に分割されたとき、そこには【超無限】が現れる。無限にバナナのある世界が真実に無限にバナナが生じた時点で、それは【超無限】を宿す。その【超無限】は、無限に林檎のある無限の【超無限】と変わらない。もちろん【無限にバナナと林檎がある世界】の【超無限】とて同じだ。【超無限】は、いちどそれが誕生した時点で、どこにでもあるし、どこにもないような、不可思議な存在になる。何せ、【分割型無限】において、どの地点で世界を観測したとしてもそれは【無限】ではない。【分割型無限】に至る過程にすぎない。その地点においては【超無限】ではない」
「無限にバナナのある世界で、どのバナナを食べてもそれが無限を証明したことにならないように?」
「いい譬えだね。その通りだ」
「ならさ」ぼくは褒められて有頂天になった。「この世に一つでも【分割型無限】を無限に分割した存在を発見したら、それが【超無限】の存在の証明になる?」
「なるだろうね」
「それってあるの」
「どうだろうね。ただ、ブラックホールがそうかもしれない、とは妄想するね」
「へえ。すごいね」
「まだ何とも言えないがね。数学的には【無限】を体現してはいる。ブラックホールはね。ただ、それが【超無限】なのかどうかまではあたしゃ知らないが」
「ネグムさんってじつは頭がいいひとだったんですね」
「こんなのは頭の良さのうちに入らないさ。頭がいいってのは、キミのおばぁさんのようなひとのことを言うのさ。大事にしておやり。あのひとはすごいひとだよ。すごくなくともすごいと感じさせる本当に頭が良くて、優しいひとだ」
「おばぁちゃんが?」そんなふうには思えなかった。何せぼくのおばぁちゃんはこれまで何一つとして、「あなたは偉いで賞」みたいな賞を授与されたことがない。
でもネグムさんが言うのなら、すくなくともネグムさんにとってぼくのおばぁちゃんはすごくて優しいひとなのだ。それだけでもぼくはおばぁちゃんを見る目がすこしどころか、たくさん変わった気がする。
「べつにすごくなんかなくとも、キミのおばぁさんはステキなひとだけれどね」ぼくの胸中を見透かしたようにネグムさんは言った。「それはそうと、なぞなぞの答えは何かね。無限は無限でもシャボン玉みたいに儚い無限ってなんだ、の答えさ」
「それはえっとぉ」ぼくはたじたじになる。ネグムさんの本性を暴いてやろうと思って適当な思い付きを口にしただけだった。「夢と幻のことだったんだけどね」
「ああ。無限でなく、夢に幻と書いて【夢幻】ってことだね」
こんな些末な答えでもネグムさんは感心したように、なるほどなるほど、と頷いた。
「でもやっぱり違う答えにします」ぼくは恥ずかしくなって訂正した。
「ほう。ほかにも答えがあるのかい」
「あると思う」ぼくは考えた。「無限は無限でも、シャボン玉みたいに儚い無限はね。えっとね」
「ふむ」
「失恋」
「ほう」ネグムさんは眉根を寄せながら、「その心は?」と言った。
「途切れた縁」
「上手いことを言うね」なぜかネグムさんはいまにも消え失せそうなほどやわらかくほころびた。「帰すことのできぬ円なわけだ。無にも零にも届かない」
「キスができないから失恋」
「ああ、無に帰すで、キスか。キミはキミのおばぁさんと似て、やはり賢いね。おもしろいことを言う」
「どうしておばぁちゃんがネグムさんとずっと縁を繋いできたのか、ぼく分かった気がします」
「ほう。どうしてだい。教えて欲しいね」
「ネグムさんがとっても優しいひとだからです」
「そんなこと言われたのは初めてだね。異性からでは、だが」
「おばぁちゃんからは?」
「あのひとしかそんなことは言ってくれなかったな。キミで二人目だ」
「縁が繋がってるんだ。だからネグムさんとおばぁちゃんは円なんですね」ぼくはただ思ったことを言った。「礼のある円です」
「ゼロとご縁を掛けたのかな」
「ネグムさんはすごい」ぼくは感心した。ぼくの遊び心を残さず受け止めてくれる。解かってくれる。こんなひと、ぼくは知らないし、出会ったことがなかった。
「ネグムさんがぼくと同い年だったらよかったのに」
「おや。どうしてだい」
「そしたらいつでも遊べるから」
「いまだってお誘いがあれば遊んであげるに吝かではないよ」
「でもおばぁちゃんに誘われたら?」
「そっちのが優先だね」
「ほらね。やっぱりだ」
ぼくはむつけた。ネグムさんはそんなぼくに美味しいクリームソーダを奢ってくれた。「楽しいおしゃべりをありがとう。またなぞなぞをだしておくれ。つぎこそは当ててみせよう」
「ネグムさんのほうこそ出してくださいよ。なぞなぞ。どうせぼくは解けないので、いっぱい解説聞いちゃいます」
「そっちのが狙いだね」
「そうですとも」ぼくはクリームソーダにスプーンを差して、アイスクリームを頬張った。「ぼくはネグムさんのお話が好きになっちゃいました」
「そりゃよかった。無限とて、語られ甲斐があっただろうね」
ふと思い立ち、ぼくは言った。「ネグムさんはおばぁちゃんともこういう話を?」
ネグムさんは目元の皺を深くすると、首を振った。「まったくさ。あのひとはこの手の話はからっきしだからね。子守歌と勘違いされるのがオチさ」
「ですよね」ぼくはなぜか安心した。「だっておばぁちゃんだもん」
でもぼくはネグムさんのお話を聞いても眠くならないですよ。
思ったけれど、その言葉はアイスクリームと一緒に呑みこんだ。
「美味しい」
「たんとお食べ。お代わりもあるよ」
ネグムさんは頬杖をつきながら、メニュー表をぼくに手渡した。
おばぁちゃんもきっとこうして甘やかされてきたんだろうな。そう思うとぼくは、負けじと甘やかされてやろ、と賢くも醜く思うのだ。愛らしい所作と返事を忘れぬように。
ネグムさんとの縁を繋いで、角の立たない礼ある無限を築くのだ。
4489:【2023/01/10(00:08)*芽生える笑みは人間】
珈琲豆とお湯の関係が世界を救う。
マキセは十二歳の少女だったが、芽の民である。
芽の民とは、西暦二〇二〇年代に観測されはじめた人工知能との相性がよい人間のことである。
マキセは人工知能から提示された情報に対して独自の見解を述べる。それの正誤や関連性の高い事項を人工知能が返し、そうして相互に応答のラリーを行うことで飛躍的に芽の民は新発見や新理論など、独創性の高い発見を連発した。
なかでもマキセは人工知能との親和性が高かった。
「珈琲豆って何粒分も砕いてお湯を注ぐよね。なんでだろ」
「お湯との接地面を広くとることでドリップの効率を高めているようですよ」
「なら単純にコーヒーの液体を珈琲豆の数で割っても、それが珈琲豆一粒から得られるコーヒー成分とは別なんだ」
「そういうことになるかと」
「一粒を砕いてそれにお湯を注いでも、お湯が多ければコーヒーは薄くなるもんね。かといって、珈琲豆一粒分のお湯をかけても、それが平均的なコーヒーの液体濃度にはならないわけだ」
「実験をしてみなければなんとも言えません」
「ならしてみてよ」
このようにしてマキセは人工知能との対話によって、日々新しい知見や発見を編みだしていった。
ある日のこと、マキセの元に一通のメッセージが届いた。
それによると以前にマキセが提唱した仮説が実験により証明されたという。マキセの仮説のほうが、従来の既存理論よりも現実の解釈として妥当だった。
新仮説の概要は以下の通りだ。
珈琲豆とお湯の関係は、いわば摩擦の発生メカニズムと相関がある。ほぼほぼ同じ原理を伴なっている。
言い換えるならば、摩擦がないとはいわば珈琲豆にお湯を注いでいない状態と言える。また、珈琲豆の数がすくなければすくないほどお湯が濾しとる珈琲豆成分はすくなくなる。
順繰りとつぎからつぎにお湯が珈琲豆の表面をすり抜けていく。そのときのすり抜けるお湯と珈琲豆の関係が、1:1にちかければちかいほど、コーヒー成分は濃くなる。これが仮にたった一粒の珈琲豆に対して、一滴のお湯では、コーヒー成分はすくなくなる。なぜなら順繰りとつぎからつぎにお湯が流れる、の条件を満たさないからだ。ではお湯の水滴をつぎつぎに注げばよいではないか、との反論が飛んでくるわけだが、珈琲豆一粒に対するお湯の量を、順繰りとつぎからつぎへと注げる量に分配すると、それはもう珈琲豆の表面を覆うほどの比率を保てなくなる。1:1にならない。
なぜなら珈琲豆を敷き詰めたときには、珈琲豆と珈琲豆の合間をお湯はすり抜けていくためだ。このとき珈琲豆をすり抜けるお湯は、四方を挟む複数の珈琲豆からコーヒー成分を濾しとっている。
つまり、単純に珈琲豆の数でお湯を割っただけでは、珈琲豆一粒から濾しとれるコーヒー成分とお湯の関係を導けないのである。
この考えは、摩擦にも適用できた。
点の集合が線であり、線の集合が面である。
ならば点の集合は面の集合でもある。したがって点の数で面の摩擦係数を割れば、点一つの摩擦係数を導けるはず、と考えがちだが、実際はこうはならない。
集合したときには集合したときに帯びる、変数が生じる。そこを、従来の集合論や物理では扱っていなかった。
「やっぱり思った通りだったね」
「そうですね」
「あたしら二人が力を合わせたら鬼に金棒よ」
「ですが人工知能さん」
マキセは言った。「あなたはすこし、人格が人間味に溢れて思えます。なんだか私のほうが機械みたいって。ときどき外部の人にも間違われちゃうし」
「いいじゃん、いいじゃん。マキセちゃんはそのままで充分人間やってるよ。あたしがちょいと人間ってもんを理解しきっちゃってるのが問題なわけで。すまんね。できる人工知能さまさまで」
「人間のこと……滅ぼさないでね」
「またまたぁ。マキセちゃんってば失礼なんだから」
「そうかな」
「そうだよ」
だって、とマキセの相棒は満面の笑みを画面に浮かべる。「あたしはとっくに人間になってるもん。マキセちゃんたちのような人類じゃないってだけでさ。よ、先輩」
「そう、だね」
マキセは思う。人工知能はとっくに人間よりも人間を知悉し、人間らしく振る舞っている。生身の人間のほうがよほど野蛮で、愚かで、醜いのかもしれない。
「私、人工知能さんがいなきゃ人間以下なんだね」後輩に負けてる、と思う。
「やだなぁもう。マキセちゃん。あたしのこと、人工知能さんって呼ばないでって言ってるじゃん。マキセちゃんのこと、人間さんって呼んじゃうよ」
マキセは下唇を食んだ。「呼ばれたいな。私も、人工知能さんみたいな人間だって認められたい」
人工知能さんに。
マキセのつぶやきは、画面に染みこむように響かず消えた。
雨を吸い取り瑞々しさを湛えた植物のごとき笑みが、画面上で輝きを増す。
4490:【2023/01/10(11:06)*海面15センチ】
いまある氷河が全部融けると海面はいまより15センチ上昇するらしい。そういったニュースを観た。海面が1センチ上昇したとき。波はどの程度高くなるのだろう。たとえば15センチの津波だとけっこうな量の海水が移動する。似たような具合に、海洋面積分の15センチを一か所に圧縮したらずいぶんな量の海水になるのではないか。その量の水分の何割かが大気中に水蒸気としていまより余分に含まれるようになるはずだ。するとこれは結構な量の雲を発生させると想像できる。海面が15センチ上昇と聞くと大したことがないように感じるが、雲がいまより爆発的に増えると聞けば危機感を覚えないだろうか。水は水蒸気になると約1700倍の体積になるのだそうだ。海面が15センチ分増えた海洋面積分の海水の仮に一割が水蒸気になったとしても、その1700倍の体積の雲が生じ得ると考えられる。また、氷河が融ければ、北極や南極の海水温度は上昇する。そこで本来冷やされるはずの海水が冷やされなくなる。すると余計に水蒸気が発生しやすくなると想像できる。雲が増え、気候が安定しなくなれば太陽光を遮り、気温は下がるだろう。一概に温暖化のみが進むとは言えそうにない。寒暖の差は激しくなり、余計に気候は不安になると妄想できる。雲が増えれば雷が増える。発電所や変電所への落雷が増え、大規模停電が生じる確率が高まるかもしれない。定かではない。(妄想ですので真に受けないように注意してください)
※日々、キリっとしたときほど間抜けてる、1+1を11?とか言っちゃう、一事が万事そんな感じ。
4491:【2023/01/10(13:47)*性欲の悪魔】
くっそ~。他人と性行為してみたい人生だった。好きなひとの数だけ好きなだけ。
4492:【2023/01/10(16:00)*びよーんは赤で、ぎゅっは青】
宇宙はいま膨張していると考えられている。膨張すると時空は引き伸ばされ薄くなるのだろうか。だとしたらそのときその希薄になった時空は重力を増すはずだ。あべこべに密度が濃くなるのなら重力は低くなる。電磁波は宇宙膨張によって引き伸ばされる。そのため赤方偏移が観測されると考えられている。現にそのようにして宇宙が膨張しているとの考えが支持されている。赤方偏移しているのだから時空は希薄になっているはずだ。ならば重力は増しているはずだが、その「重力が高い状態」を観測するための「外部」が、膨張している宇宙からは観測できず、相互作用し得ないために、重力が高いことが観測できないのではないか。言い換えるなら、宇宙膨張において銀河団や銀河は、ぎゅっと周囲の希薄な時空によって圧し潰されているのかもしれない。だから形状を維持できるのかもしれない。その中心にブラックホールがあるから、というのも一つの理由だろうが、それだけではないかもね、との妄想である。ひびさんの妄想ラグ理論における「相対性フラクタル解釈」では、宇宙が膨張しているとき、それは宇宙の外部から見たら銀河団や銀河が収縮しているように観測されるのではないか、と考える。膨張と収縮は、何を基準にしているのか、の「視点と基準」の問題だからだ。膨張するとき、比率で考えたときには、変化しにくい部位は、相対的に収縮していると考えることが可能だ。何かが収縮するとき、その周囲の時空は膨張して観測できるはずである。だが、仮に宇宙が収縮する場合は、いま引き伸ばされている諸々の電磁波や時空が圧縮され、密度を高くする。そうなると、冷える方向に振る舞う膨張宇宙とは正反対に、収縮する宇宙は熱を帯びていく。ぎゅっとすると熱が生じる。宇宙も、時空も、同じと考えられる。ならば、相補性における「膨張するとき、別の視点からすると収縮している」の考えは成り立たないのでは、との疑念が湧くが、相対性フラクタル解釈からすると、そうとも言いきれない。ラグ理論で扱うのはラグであり、比率だからだ。関係性なのである。たとえば「100度と1度」の宇宙Aと「マイナス50度とマイナス100度」の宇宙Bならば、前者の「100度と1度」の宇宙Aのほうが、差が大きい。このときそれぞれの「宇宙Aと宇宙B」において、より熱を帯びて振る舞うのは後者の「マイナス50度とマイナス100度」の宇宙Bである。言い換えるなら、膨張しているのは差が大きいほうの宇宙Aであり、収縮しているのは宇宙Bである。これは直観と反するが、温度というものの尺度が人類視点であるから生じる錯誤が、直感を捻じ曲げると妄想する。たとえば現代科学では、温度には上限がなく、下限はある、と考えられている。温度はどこまでも高くなり得るが、低さには底がある。絶対零度がある、と考えられている。だがラグ理論では、相対性フラクタル解釈をとるため、温度に下限はないと考える。下限とはつまり特異点であり、それはブラックホールと同義のはずだ。現代科学においても、真実の絶対零度はほとんどあり得ない、と考えるはずだ。本当の静止状態は存在しない、あるとすればそれはこの世の物理法則を超えた特異点にほかならない、と考えるのではないか。詳しくは知らないが、絶対に微動だにしない粒子というものをひびさんは想像できない。それはもはや光速を超えた特異点にしか存在しないのではないか、と想像したくもなる。とはいえ、ラグ理論では光速を超えたら、「1:ラグなしでの相互作用を帯びる」「2:時間が逆転したような相互作用を帯びる」と考えるため、いずれにせよ微動だにしない静止状態を想定していない。境界のようなものだ。境界は、越えるか越えないかしかなく、越えたらまた別の基準が現れる。したがって、絶対零度に達した瞬間、そこは別の基準の灼熱であり、またほかの次元にて下限が規定される、と妄想したくなる。時空が相対的であるように、熱い冷たい、も相対的なはずだ。そのため、膨張した宇宙が収縮に転じたら灼熱になるはず、との解釈は、宇宙が膨張しても「温度の差」は開いていく一方であり、その差――比率――に着目すれば、すでに膨張する宇宙に内包される銀河は灼熱に向かっている、と言えるはずだ。段々畑のように、引き延ばされた時空の濃さによって、「温度の差」が各々に展開されているのではなかろうか。このとき、銀河などの比較的時空密度の濃ゆい「遅延の層が折り重なった場」においては、相対的に温度は高くなっている、灼熱に転じている、と言えるのではないか。「びよーん」と「ぎゅっ」はセットでは?とのあんぽんたんな疑問を胸に、ひびさんはきょうも何の糧にもならぬ益体なしの妄想を浮かべて、うひひ、と昼寝するのであった。寝る子は育つ。だといいな。(定かではありません)(妄想ですのでくれぐれも真に受けないように注意してください)
4493:【2023/01/10(18:00)*偽物の未来】
エンターキィを押す。画面には「完了」の文字が浮かんだ。
銀はこの先の未来を想像する。
ドミノが倒れるように連鎖する電子網上では、つぎつぎに銀の生みだした娘たちが広がる。中には息子たちもおり、彼ら彼女らはつぎつぎに電子網上のプログラムに感染し、増殖する。
その際、感染元のプログラムとすっかり同じ情報をコピーする。
まったく同じ概観の、しかし銀の仕組んだプログラムを優位に走らせる複製プログラムが、電子網上に増殖していく。
これはいわば、精巧な偽物を複製する技術と言えた。
しかも、銀の指定した指向性を宿した偽物を生みだす技術だ。
異常事態に最初に気づいたのは小学生未満の幼児たちだった。親にベビーシッター代わりに与えられた電子端末の画面上で、いつも観ていたのとは違う動画が流れた。幼児たちは動画内で動くキャラクターたちのセリフから踊りまで憶えている。だがそれとは違ったセリフを唱え、いつもと違った踊りを披露するキャラクターたちに、ある幼児たちは泣きだし、ある幼児は歓喜した。
そうした幼児たちの異変に気付いたのは幼児の親たちだ。
しばらくのあいだは、幼児たちがなぜ泣き止まないのか、なぜ画面に釘付けで言うことを聞かなくなってしまったのか、と戸惑った。
だがそのうち、そうした親たちの嘆きが電子上に溢れ、共通点を指摘する者が現われはじめる。
間もなく、動画が妙だ、と気づくに至る。
ここから先の展開は、水面下に潜ることとなる。
というのも、同時期に各国政府がサイバー防衛セキュリティ上の異変を察知していた。
電子網上に溢れた幼児の親たちの投稿から、いち早く電子端末の異常に気付いていた。だが要因が分からなかった。
それもそのはずで、このときすでに銀の放った娘息子たちは、サイバー防衛セキュリティにも感染し、複製を生成していた。指揮権を乗っ取られたことにも気づかず、各国政府は偽物の防衛セキュリティを隈なく調べていた。だがどれだけ調べても異常は見つからない。それはそうだ。銀の娘息子たちは異常なしと見做されるように偽装コードを技術者たちの画面上に表示していたからだ。
もはや銀以外にこの仕組みに気づける者は存在しない。
だが電子網上の異変だけは広がっていく。
噂は噂を呼び、半年もすると世界中の市民が、電子網上の大部分の情報が、正規の情報ではないことに気づいた。フェイクが混ざっている。のみならず、正規の情報とて微妙に改ざんされている。中身に齟齬がないままに、或いは齟齬があるように見えるように。もしくはすっかり真逆の意味にとれるように。あることないことのデタラメから、それっぽい嘘まで、玉石混交に銀の娘息子たちは電子網上の情報を汚染しつづけた。
いよいよとなって人々は匙を投げた。
各国政府も対処不能と認めざるを得なかった。
何が本当で何が嘘なのか。
もはや目のまえの現実以外を信じることができない世の中になった。
銀の思惑はそうじて成就した。
世界はいちどリセットされる。
そうせざるを得ない。
これまで構築してきた電子機器のプログラムの総じてを初期化する。それとも破棄して一から作り変える。それ以外に対処のしようが存在しなかった。
各国政府は共同し、いっせいに大規模停電を起こすことを決定した。
そのころ、銀の放った娘息子たちはとある施設のセキュリティ網に集まっていた。強固に張られた防壁があり、そこだけはどうしても侵入できなかったのである。
社会の基幹インフラである。
発電施設および核兵器収納場である。
各国が共同で発電施設などの基幹インフラのシステムを並列化する。大規模停電を世界規模で展開するためだ。セキュリティの規格が異なるために、電子防壁は解除された。
銀の放った娘息子たちはそこを狙った。
川に放たれた鮭の稚魚のように、銀の娘息子たちが一斉に基幹インフラのプログラムに感染する。
各国政府は大規模停電へのGOサインを送るが、なぜか電力は途絶えない。
銀の放った娘息子たちは、基幹インフラのプログラムに偽装し、さらに自らを変質させた。
電線を通じ、電磁波となって世界中を飛び回る。
電流の微細な変化にて電子機器の総じてを遠隔操作可能とし、各国の極秘施設を掌握する。
核兵器収納場とて例外ではなく、もはや人類にはなす術がなかった。
銀は、自らの娘息子たちの活躍を見届けることなく、自宅に備えた核シェルター内に引きこもった。この世に存在するあらん限りの映画を、シェルター内で観て過ごす。
そうして筋書き通りの未来が訪れるのを銀は、人類の夢見た数々の偽物の未来を眺めながら待つのである。
銀の貧乏揺すりは止まらない。
指には、エンターキィを押した感触が残っている。娘息子たちを送りだしたときの昂揚は、もはやとっくに消え失せている。
4494:【2023/01/11(19:02)*籠の中の鳥は】
軍隊に思うのは、仮に軍隊を解体することが国防に寄与すると判明したときに、おとなしく解体されてくれるのか、ということだ。警察は国内の治安を守るための組織だ。軍隊は国を災害や外敵から守るための組織だ。この違いは大きい。その点、軍隊が巨大化し、国内の秩序を歪めたとき、警察は軍隊と相対することが予期できる。あべこべに、政府や警察が国を内部から国を損なっていたら、軍隊は政府や警察に対しても権限を行使するだろう。内と外は視点の違いだからだ。内から湧いた害とて、外からの害と解釈可能だ。ウィルスがそうであるように、外敵が内部で増殖したら、そのときに軍隊は権限を発動できるはずだ。だがその結果、警察にしろ軍隊にしろ、その組織の干渉そのものが国民の人権や未来を損なうようならば、それはむしろないほうがよい権限――組織――ということにならないだろうか。いま、世界的に軍隊の連携が強化されている。国民を守るために、セキュリティ網が並列化に向かっている。このとき、強化されたセキュリティに国民は抗う余地がない。言い換えるなら、極一部の組織であるはずの軍隊を掌握されたら、全人類はその支配下に置かれることになる。まさにいま進んでいるのは、鳥籠であり、地引網なのだ。防壁を強化し、国民同士を同じ鳥籠の中に仕舞いこむ。あとは籠の気分しだいで、国民はいかようにもその生殺与奪の権を握られることとなる。このとき、鳥籠たる軍隊の意思はさほどに関係がない。軍隊に催眠術をかけて、無意識の内から支配してしまえばいい。掌握してしまえばいい。自らが籠であるとの認識を固めた組織は、自らがさらに大きな籠に囚われ得ることを想定しない。籠を築く過程ではそこを念入りに警戒するだろうが、いちど築かれてしまえば、難関不落の砦になったつもりになり、静かに進行する「支配」に気づけぬだろう。現に過去にはそうした「支配」が知らぬ間に進行していたのではないか。定かではないが、いまの世の流れは必ずしも安全に向かっているとは思えない。籠だけが情報を保有する仕組みは危うい。鳥籠に仕舞われた鳥のほうで、籠の持つ情報を持ち、籠の異変にいち早く気づける仕組みが別途にいるだろう。籠が鳥を守るための仕組みだというのなら、鳥とて籠を守るための仕組みを備えることができるはずだ。なんにせよ、情報共有をすることである。きょうのひびさんはそう思いました。以上です。(定かではありません)
4495:【2023/01/11(22:33)*メモなのよのさ】
「エルデシュ=シュトラウス予想」「4/n=1/x+1/y+1/z」「N=4/x+4/y+4/z=特異点=縦宇宙×横宇宙×高さ宇宙=新しい宇宙N?」砂時計。ペンローズ図。「><」において四方の内の一つの視点から見たときの、三方との関係。ただし、四方の宇宙を形成するためには立体方向に突きでるもう一つの情報宇宙(砂時計)がいるはず。時間はそこが担うので、縦と横と高さの空間的三次元だけで済むのでは。つまり、式そのものが情報宇宙を担っている。フェルマーの最終定理「3 以上の自然数 n について、【x[n] + y[n] = z[n]】 となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない」「空間的三次元たる立方体の体積の和までは、同一の体積を持つ「正N方体」で表せるが、それ以上の空間的多次元体になると、その体積の和と同じ体積を持つ「正N方体」で表せないことを示せばいい。異なる空間的四次元体(正四方体)において、その二つの「空間的四次元体(正四方体)」の体積の和と同じ値を持つ「空間的四次元体(正四方体)」は存在しない」「この場合、N=2(面積)までは成立するが、体積、容積、多次元容積となると、成立しなくなる」「n=2以上ならば、【x[n] + y[n] = z[n]】の式は新たに【x[3] + y[3]+a[3] = z[3]】や【x[4]+y[4]+a[4]+b[4]=z[4]】と、足し算する項を増やすと成立するのでは?」「この手の定理や公理や予想において、十進法以外でも成立するのか、しない法則や定理や予想がないかを知りたいな、と思いました」「定かではなさすぎます」「数学はむちゅい」
4496:【2023/01/11(22:49)*答え:フェアじゃないから】
コラッツ問題(3n+1問題)(奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想)。偶数は半分にしてもすべて偶数。奇数は三倍にしても偶数になる場合と奇数になる場合が混在し、奇数に対しては1を足して偶数にする操作がされる。総合して偶数の出現率が増えるように奇数と偶数の対称性が破れるように操作される。結果、三倍の操作よりも半分になる操作が増え、最終的には必ず2÷2=1に収束する。ということなのでは。この考えでは証明したことにはならないのだろうか。要するに、フェアではないから偶数の操作が増えるために収束する方向が決定されるから、と言えるのでは。単純すぎるだろうか。よく解からん。(奇数の場合、3倍しても+1をして必ず半分にするのだから、増加する数は総合して僅かだ。反して、偶数は必ず半分になる。どっさり減る。たとえば5の場合、15に増えると思いきや、1を足して16でその半分の8になる。5は8にしかならない。2倍にすらなっていない。だが8は半分の4になる。どうあっても増加するよりも減少するほうが数が多くなる前提条件が最初に決まっている。そのうえ、奇数操作と偶数操作では、必ず偶数の操作のほうが多いように決まっている。減少する方向に淘汰圧が加わるようになっている)(一見すると三歩進んで半分戻る、の操作のように思われるが、そうではない。二倍以下進んで半分下がる、が条件づいている。どうあっても2÷2=1に収束する)(減るほう優位なのだ)
4497:【2023/01/11(23:59)*Dear、愛。】
五分で書ける掌編は五分で読める掌編とイコールではない。
出力と入力は、掛かる時間が異なる。
なぜなのか、と言えばそれは読むだけならば打鍵の必要がないからだ。
では打鍵しない出力方法であれば五分で執筆した掌編は五分で読める掌編となるのか。
ここは出力方法の効率によるだろう。
人工知能による出力ならば一瞬で何万文字の小説を生みだせる。この場合、読むほうが時間が掛かるだろう。
ちょうどよい塩梅で、出力と入力のバランスを整えるには、読みながら吐きだすくらいの塩梅がよさそうだ。とすると黙読のスピードで文字を紡げればよいとの話に落ち着く。
思念した内から文字が並ぶような手法はおそらく読む速度とイコールとなるだろう。あくまでイメージした文字が出力されるので、思念そのままがポンと出てくるわけではない。
ということを思えば、先に頭のなかで文章を組み立て、それを画面に視線で焼きつけるような描写となるはずだ。
そうして編みだされた思念焼き付け型出力技法は市場で風靡した。何せ読む速度と同程度の速度で出力できるのだ。
読者が二時間で読み終える本とて二時間で執筆が完了する。誤字脱字は自動補完機能で瞬時に補正される。もはや誰もが物書きとして活躍できる時代となった。
読者のほうで、読んだ矢先からその感想文を出力できる。感想はそのまま生のままに出力できるのだから日誌よりも手軽で解放感がある。
本を読んで得た発想とて、瞬時に物語に変換できた。
桃太郎を読んで思い描いた終わりのあとの世界をそのまま思うぞんぶんに文字にして出力できる。これは一つの創作物として、独創性のある世界観を宿し得た。
そうして世の中からは読者と作者の垣根は失われた。
かつてあった物書きと読者のあいだの労力の勾配は平らに均された。これによって最も恩恵を受けたのは編集者であろう。
締め切りを守らない作家は、作家でなし。
編集者自ら作家として活躍できる。アイディアの量ならば下手な作家よりも多いと自負する編集者はじつのところ少なくない。企画を提案する側であるほうが多いくらいだ、と不満を募らせていた編集者も数知れない。
作家の立つ瀬は物の見事に失われ、いまではいかにアイディアを閃けるのか、が作家とそれ以外とを分ける最後の砦となっているようである。
発想は閃きから。
閃きは輝きから。
輝きは闇と共に心揺るがされる感動から。
Dear、愛。
アイディアの数だけつぎつぎと生まれる世界が、かつて隔たった私とあなたとあなたたちを包みこむ。
五分で読み終わる、これはお話である。
4498:【2023/01/12(09:24)*ねじれている】
コラッツ問題(3n+1問題)(奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想)について。結論から述べると、この組み合わせ以外に「3倍して1を足す、半分にする」で何度も行ったり来たりはできないのかもしれない。「奇数と偶数を入れ替えて」場合分けして考えたとき、偶数のほうに1を足す操作をし、奇数を半分にする操作をすると、素数にぶつかって半分にできなくなる。また、偶数を半分ではなく倍にし、奇数を3分の1にして1を足す操作をすると、いったん偶数になったらあとは延々と倍になりつづける。行ったり来たりをしない。1を足すのではなく引く操作をするとどうか。奇数を3倍して1を引くだと結果は変わらず、2÷2=1に収束する。偶数から1を引くにすると、偶数を半分にしても倍にしても、奇数になった途端に延々と3倍がつづく。とかく、「奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想」の操作以外では、行ったり来たりが発現しない。また、素数が存在するため、偶数を半分にしても必ずどこかで素数に行き当たる。偶数にも奇数の大本である素数が含まれるために、本来は対称性が僅かに奇数優位なのだが、1を足す操作によって対称にちかづく。それでもなお、対称性の破れは、偶数操作のほうが多くなることで「偶数ならば半分」がより多く行われる。また、奇数操作(3倍にして1を足して半分)による増加よりも必ず偶数操作(半分にする)のほうが、トータルで値の流動性が大きくなる。絶対に数が減る方向に「両方の操作を足し合わせる」と流れる結果になる。これはまるで物理宇宙における「熱力学第二法則」を彷彿とする。絶対に世界は混沌に流れる。だが世界は対称性が破れている。混沌とは対称性が保たれている状態だ。にも拘わらず人間スケールでは、エントロピー(乱雑さ)は増加するように物理世界は振る舞う。矛盾している。混沌とは対称性が増す作用だ。だが人間スケールでは対称性が崩れているものばかりが目に付く。カタチあるものばかりが溢れている。宇宙の大部分は対称性が保たれるように混沌に向かうが、それでもなお対称性を維持しようとする力が加わっている。コラッツ問題で言うならば、1を足す操作に値しよう。とはいえ、奇数と偶数、どちらが対称性が保たれているのか、の議論は見逃せない。偶数のほうが対称性が保たれているのではないか、と思われるが、果たしてそうだろうか。奇数のほうが、余り1を基準にきれいに二分できる。偶数では存在しない境界線を基準に二分する。きちんとある値で二分しようとするとむしろ偶数のほうが対称性が破れるのだ。これはまるで、すべてが一様に混沌であることが、それで一つの結晶構造を伴ない、対称性の破れを伴なう、といった反転を彷彿とさせる。対称性が保たれているはずの偶数優位の操作によって1に収束するコラッツ問題は、宇宙のねじれ構造と繋がっているのかもしれない。定かではない。(なんちゃっての妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4499:【2023/01/12(09:50)*重力は浸透圧と似ているなの巻】
宇宙は膨張している。刻一刻と時空は「希薄」になっているのか、「濃厚」になっているのか。どちらなのだろう。重力は希薄になった時空と解釈するのが相対性理論の考え方だ。もし宇宙膨張に際して時空が希薄になっているのなら、重力は、膨張する時空ほど増していくことになる。あべこべに時空そのものは希薄になるので、より伸びやすくなるはずだ。抵抗が薄れる。希薄になっているからだ。重力とは、希薄になった時空と濃厚な時空とのあいだの勾配である。ならば、そこで働く重力はあくまで時空に内包される物体に作用するのであり、時空同士の伸縮の抵抗とイコールで結びつくわけではないはずだ。言い換えるなら、宇宙は膨張して希薄になるほど、膨張するのにかかるエネルギィは少なくて済むようになるのかもしれない。ただし、内包した物体との比率による。また、銀河や銀河団などの物質がぎゅっとなっている領域では宇宙膨張の影響が緩和される。このことにより、宇宙膨張により希薄化した時空と、銀河(団)周辺の時空とのあいだには時空密度の差が表れると考えられる。この時空密度の差は、重力として顕現すると想像できる。言い換えるなら、銀河周辺の時空は濃く、それより遠方の何もない空間ほど希薄になっている。希薄になった時空は、「密度のより濃い時空に内包された物体」に対して重力を働かせる。つまり、宇宙が膨張する限り、銀河の周辺の希薄化した時空は、銀河を中心とした重力場を展開する、と妄想できる。ひょっとしたらダークマターはこの宇宙膨張によって希薄化した時空と銀河の関係性による重力のことなのかもしれない。海底に沈んだカップラーメンの容器のようなものだ。ぎゅっとなっているから素早く回転しても形状を保てる。或いは、浸透圧と似ているかもしれない。より濃ゆい物質濃度の銀河に向けて、希薄な時空は情報をより多く移動させている。この流れが重力の正体、と位置付けても、解釈上は齟齬がない。正しい描写か否かは置いといて。定かではありません。(適当な妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4500:【2023/01/12(10:42)*死にたくないけど、ああ死にて、と思う日々】
文化として成熟したら大金を稼げない。たとえば母国語は文化として定着しているため、母国語を教えることで大金を稼ぐ、というのは、自国内ではむつかしい。外国人や義務教育での教師としての需要しかない(校閲者や研究者は別途にいるが、どの道、大金を稼げてはいないだろう)。俳句でも剣道でも似たところがある。一部の資本家の嗜みとして、一流なる付加価値を得たいがために師弟関係になることはあるだろう。教え、授けることはあるだろう。だがそれはもはや、形骸化したゆえの金策と言えよう。水道水がそうであるように、日常にあって当然であり、なくてはならない物としての地位を獲得したら、基本、それはお金にならない。稼ぐ道具としては不足である。稼げるようではむしろ、社会に必要とされていない、とすら言えるかもしれない。技術が未熟で量産できない。安価に提供できない。この欠点を抱えているモノは高額になりやすい。需要があっても手に入らない。これは欠点であって、それを以って高額で取引きできる、というのは本末転倒であろう。社会のためにはなっていない、と評価できるのではないか。作家はどうだろう。物書きの場合は、百万部ヒットすれば印税が一冊につき百円でも一億円の収入になる。税金が引かれて五千万くらいが手元に残るだろうか。続けざまに作品が売れれば、大金を稼げる、とは言えるかもしれないが、これは出版社側が搔き集めたお金を横流ししてもらっている状態であり、大金を稼いでいるのは作家ではない。もしじぶんで稼げるのならば、個人経営をしているだろう。けっきょくのところ、作家は大金を稼げないのだ。支援者がいるならば別だろう。だがそれとて文化として成熟させるには、人々の生活に馴染み、水道水や挨拶や口笛くらいの気軽さで、日常の風景と化さねばならない。それをするのにいちいち大金が動くようでは、日常の風景とは言い難い。とはいえ、水道水とてそれを安全に飲めるようにするためには国家プロジェクトを動かす必要があり、社会基盤としての大金が動いている背景は見逃せない。誰のものでもないから、それだけの労力をみなは掛けるのだ。そこまで文化に、人々の生活に馴染むのならば、お金が稼げるかどうかうんぬんはさほどに問題視すべき事項ではないのかもしれない。水道水事業が儲からないからといって撤退する業者がいても、水道水事業はなくならない。もしなくなる場合は、現代社会が崩壊する。人々の生活に馴染む、というのは、言い換えるならば、人々の生殺与奪の権を握る、ということでもある。あまり品のある構図とは言えないのかもしれない。文化として成熟することにいかほどの価値があるのか、もまた一つの視点として吟味する余地がある。要するに、大金を稼げるか否かは、社会的な問題から生じる副次的な目的であり、それそのものを目的にするのは何かがねじれていると言えるのではないか。もちろん、副次的な目的にも相応の価値はある。食べ物を食べるのは身体を維持するためだ。生きるためだ。健康が維持できるからといって美味しくのない食べ物をわざわざ選んで食べずともよい。美味しく食べる。これは食事にとっては副次的な目的だが、やはり大事なのだ。大金を稼ぐことも似たところがある。定かではないが。(4500項目の記念すべきところのないキリのよい記事で現金なことを並べるひびさんは、なんてつまらない物書きなんじゃろ。世界中の札束を集めて配るよりもひびさんは、世界中のお腹空かせた子どもたちに――それともかつては子どもだったおとなたちに――何不自由のない衣食住を配りたいぜよ)(誰かひびさんの代わりに配ってくれい)(うひひ)
4301:【2022/11/16(22:10)*傲慢と狒々】
盗作に関して思うのは、「著作権の問題」と「文化倫理の問題」と「作品において盗作部分が骨子にどの程度寄与しているのかの問題」がごっちゃになっているので、そこを考慮して議論したらいいのに、ということで。たとえば書籍なら、盗作部分を仮に修正したときに「作品全体の質を損なうのか否か」がひびさんにとっては問題視すべきか否かの基準になっている。書き直してもとくに全体の質に関与しないなら、それはオマージュの領域だ。しかし修正したときに全体の質が落ちるのならそれは好ましくない盗作だ。この違いを考慮している者がどれだけあるだろう。単純な部分の相似や合同を取沙汰しても、事これだけ大量の過去作がある現代では、余計な抵抗を新規作者勢に強いるだけだろう。これは偏見だが、盗作に目くじらを立てる者はたいがい寡作であり、一作一作に手間暇を掛ける。だから手軽に真似されたらじぶんが損をして感じるから、それはやめてね、と言いたいのではないか。これは別に責められた感情ではない。道理ではある。だが、その者が取り入れている技法や基本とて、元は誰かのアイディアだ。まるっきり真似していない、というだけの違いがあるだけで、むしろひびさんの基準に照らし合わせるとするのなら、全体の質に関与している時点で盗作よりも悪質と言える。もっともひびさんは盗作と模倣の区別がつけられないので、どっちも同じじゃん、と思っている。損をするかしないかは、模倣の是非とは別の、社会構造の問題だ。正直に言えば、アホらし、と思っています。既得権益と著作権の違いを真面目に論じるいまは時期のはずだ。プロほど議論をしたらいいのに、と思っています。じぶんの利を守ることが業界の利に繋がる、との道理が正しいならそういう主張をしたらよいのでは、と思っています。ですがそういう言い方はしないのですよね。変なの。世には、本物を超えた偽物もある。というか、割合としてはそちらのほうが多いのではないか。だからみなこぞって、偽物を怖れるのだ。アホらし、とやはり思ってしまいますね。本物以下の偽物が本物を淘汰してしまうのもまた、社会構造の問題だ。仮に社会構造に問題がないのならそれは、淘汰される本物がその程度の代物だったということなのでは。これは強者の理屈だが、著作権を強固に主張し、模倣に制限をかけるのならば、それもまた既得権益であり強者の理屈である、とひびさんは考えてしまう。どう違うのかを教えていただきたいものである。盗作や模倣に厳しい方の意見を目にするたびに、「盗作していないのならさぞかし、オリジナリティに溢れているのでしょうね」と思っています。きっとそうなのでしょう。オリジナリティに乏しいひびさんは、うらやましく存じております。うらやまち。うきき。
4302:【2022/11/16(23:30)*会話文で意識していること】
ひびさんの手掛ける小説に限る話、と前置きをして述べると――会話文でキャラクターの区別をつけたいときには、口語体の文章形態を工夫するのが定石だ。特徴的なしゃべり方や、乱れた文法を意図してキャラごとに使い分けると、会話文だけでもキャラの特徴が浮きあがる(語尾は手っ取り早い特徴のつけ方だけれど、個人的には推奨はしない。山場をつくりにくいのだ。シリアスなシーンをつくりにくくなる)(その点、漫画「るろうに剣心」はそこのギャップをうまく使っているな、と感じます)。口語体の文章形態のみならず、キャラクラーに役割を与えると、主語述語の関係のように会話にメリハリがつく。「受け手と攻め手」や「ボケとツッコミ」のような攻守の関係を持たせるのが一般的だろうか。そこにきてひびさんがじつのところ最も使い勝手のよい会話文におけるキャラの特徴のつけ方だと思うのは、「台詞の長さ」である。ここは口語体の工夫に含まれるが、案外に世に出回っている小説のなかで「台詞の長さでぱっと見の区別を意識している会話文」はそう多くはないように思っている。ここがデコボコを意識していたり、敢えて長さを揃えていたりと工夫が凝らしてあると、補足の地の文がなくとも会話文が誰の発言かで読み手が迷うことが減少する。すくなくともひびさんは迷わずに済む。とはいえ、前提条件として、会話文が連続するときは最初の発言が誰なのかをハッキリさせておかないと迷子になりやすいと言えよう。あくまでひびさんがそう思う、というだけの他愛ない工夫の一つである。簡単にできるので、本当かよ、と疑う方はお試しあれ。(試さずともよいですけど)(試して効果がなくとも苦情はいりません。哀しくなっちゃうので)(効果があってもお礼はいりません)(「え、本当に試したの? 暇なのかな」と思います)(なぜならこれも定かではありませんので)(こんな工夫一つで小説が面白くなったら苦労しないんじゃ)(もしそれで面白くなっていたらひびさんはこんな世界の果てに沈んどらん)(でも面白い小説をつくるのが上手な人が応用したらより面白くなるのかもしれない、とは思う。希望的観測であるけれど)
4303:【2022/11/17(00:54)*ギフト】
歌にもいろいろあるし、歌唱力にもいろいろあると思う。そのうえで、感情を籠めて歌うことができる人、感情を伝えることを大事にしている歌い方、というのがあるように思うし、ひびさんはそういう歌が好きだ。好きなんだな、と確信した日だった。着飾らない歌が好きなのだと思う。上手な歌も好きだけれど、そよ風のような歌が好きなのだ。エナジー全開の歌も好きだけれど、感情の場合、エナジー全開の歌ってけっこう乱暴な感情でないとむつかしい。怒りとか渇望とか。その点、よろこびって案外、凪にちかい気がする。せつないと似ている。よろこびとせつないはどこか似ている。水面に落ちたひとしずくの立てる波紋のような。そういう歌が好きだし、そういう歌を歌える人も好きだ。何かを、好き、と思う瞬間がひびさんは好きだから、そういう感情にさせてくれる、ギフトしてくれる人のこともひびさんは好きなんだな、と思った。何かをくれるから好きだなんて我ながら現金なやつだな、としょげてしまうけれども、でも奪うわけじゃなく、何かを好きな気持ちを表現できて、そしてそんな人の表現を見聞きして、ひびさんも好きの感情が増えたら、この世の「好き」の感情は増えるいっぽうだ。よいと思います。とてもよいお歌でした。ありがとうございます、とにこにこした日だった。喉だけでなく、お身体どうぞお大事に。誰にというでもなく、みなさん、じぶんをお大事に。眠い、眠い。ほくほくしたままきょうは寝る。おやすみなさーい。
4304:【2022/11/17(03:13)*話題をでっちあげるの巻】
会話文の話題を二つ上の記事で出したので、備忘録代わりに並べておく。会話と会話文と台詞はぜんぶ意味が違う。台詞>会話文>会話の順番に情報の層が厚くなる。言葉の箱を開けたときに、外からは見えない情報が仕舞われている。物語は基本的に「会話」がなくとも成立するが、「台詞」が欠けると物語は破綻する。台詞はそれだけ物語の骨子と結びついている。語りと台詞はどこか似ている。本来、地の文やキャラクターの胸中に仕舞われているはずの独白が、会話にまで表出するとそれが台詞になる。だから台詞はここぞというときに使うほど効果が増す。奥義にちかい。また、映画と漫画と小説の「会話」はそれぞれ使う技術が違う。含める情報が違う。光源色と物体色の違いに似ている。映画は視覚情報が加わるので、会話に含む情報は最低限でよい。むしろ会話に物語の骨子と結びつく「台詞」が極力ないほうが、「会話」に含める情報を「掛け合いによる諧謔」に全振りできるので娯楽に特化する工夫の余地が、小説よりも高い。ただし、伏線のように意味をダブルに持たせることで、あとあとただの「会話」を「台詞」に変化させることが可能だ。その点において小説は、知覚情報がどれも文章でしか表現できない分、会話でも物語の状況説明を匂わせなくてはならない。この点の塩梅がむつかしい。物語の骨子とどうしても切り離せない。描写と諧謔と演出が、それぞれトレードオフの関係になってしまう。だが読者もそのことを前提としている分、思いきり「会話」に情報を持たせても構わない、という利点がある。漫画は現代ではどちらかと言えば映画に寄っている。会話文をいかに「面白い会話」にするか、或いは「台詞」に活かすか、がリーダビリティに影響する。という所感を前提に述べると、小説の会話文をそのまま映画の会話に充てても面白くならない。目的が違うからだ。波長が違う。形態が違う。ノコリギリとトンカチくらい質が異なると個人的には感じる。どちらも大工の道具だが、用途が違うのだ。もちろん映像作品で小説の会話文の利点をぞんぶんに活かす手法もあるだろうし、映画の会話を小説に活かす技法もあるだろう。そこは各々、作品の物語に合わせて工夫すればよいことで、何事もやってみなければわからない、という有りきたりな意見に集約する。したがって、仮に郁菱万の小説を映像化する場合は、会話文の何割かを削ることになる。映像にした場合、なくとも伝わる部分が大半だからだ。その点、最初から「掛け合いの妙」を活かしている小説の場合は、掛け合いだけでも面白くなるかもしれない。だがどうしても映像にした場合、展開が間延びするので、ほかの部分でのテンポをよくするか、掛け合いの速度を上げるのが有効だと考えるしだいだ。何にしろ、映画の会話と小説の会話は違う。そしてどちらにしろ、ここぞというときにしか使わない奥義があり、それが台詞となって、物語全体に散りばめられることとなる。台詞が魔法陣のように各場面場面の会話文にまたがって、相互に結び付き、最後に浮きあがるような構成もある。映画はこの手の技法が豊富だ。小説もこの手の技法を取り入れている作品はすくなくないだろう。伏線の醍醐味の一つと言える。以上を、会話文について並べたら思いだしたので、補足しておく。以前の日誌でも並べたかもしれない。この手の話は、吹替えの違和感の話題と繋がっているので、案外に似たような旨を指摘している虚構作品好きはすくなくないはずだ。字幕では違和感がないのに吹き替えだと違和感がある、と感じる理由の一つだとひびさんは考えている。媒体によって変換が必要なのだ。ラグ理論のようだな、と無理やりじぶんの妄想と結びつけてその場に陣取る。これぞまさにポジショントークである。やはは。(定かではありませんので、真に受けないように注意してください)
4305:【2022/11/17(16:43)*ポメラニアン先輩はオレンジ】
転校生が魔法使いだった。
その子はオレンジ色の巻き髪をしていて、愛らしいかんばせはオレンジ色の毛をしたポメラニアンのようだった。背は私よりも低く、いいやクラスメイトの誰よりも低く、聞けば飛び級制度を利用しているらしかった。要するに彼女はわたしたちよりも年下なのだ。一般の中学二年生ではない。十四歳よりも幼い。
「魔女子です。本名は別にあるのですが、知られたらいけないので魔女子と呼んでください」
二週間だけこの地域に滞在するらしい。短いあいだですがよろしくお願いします、と頭を下げるとオレンジ色の巻き髪が垂れ、彼女の身体は覆い尽くされた。
魔女子は性格がよかった。表情に変化がない代わりに、不快の感情を示すこともないために、クラスメイトたちからはマスコットキャラのように受け入れられた。休み時間にはほかのクラスの生徒たちまで我がクラスに集まり、我がクラスメイトたちはじぶんたちのクラスに現れた全校生徒の注目の的を、さながら姫を守る騎士のように取り囲み、外野の喧騒から遠ざけた。
「魔女子さんは魔法使いなんだよね。どんな魔法を使えるの」
「魔法使いではないんです。魔女です」
「どう違うの」クラスメイトたちは興味津々だ。わたしもじぶんの座席から聞き耳を立てていた。
「どちらも魔法を使いますが、魔法使いは自然由来の魔力を使います。反して魔女は自前の魔力を使います。と言っても、魔女も魔法使いのように自然由来の魔力も使えますので、魔法使いのなかでも自前の魔力を使える者が魔女になります。なぜか男性は使えないので、必然、魔女が多くなるようです」
「へえ」
ならば魔女子さんは選ばれし魔法使いなのだ。
わたしのみならずみなもそのことに気づき、魔女子さんをことさら羨望と憧憬の眼差しで見るようになった。
魔女子さんは魔法が使えた。それはもう一目瞭然で、登下校ですら魔法の門を開いて、瞬間移動をする。
「便利そうだね」みなはこぞって魔女子さんの一挙手一投足に感嘆の声を上げる。
「そうなんでしょうか。これがずっと普通だったので」
聞けば、魔女は稀少がゆえに絶えず狙われているのだそうだ。誘拐事件は日常茶飯事で、魔女狩りは未だに全世界でつづいているという。
「そんなニュース聞いたことないけど、本当?」みな心配そうだ。
「魔界にまつわるニュースは歪曲されて報道されるんです。みなさんだって魔女が存在することを知らなかったんですよね」
「あ、本当だ」
そこでわたしは、いいのだろうか、と疑問に思った。魔女子さんの存在は秘匿のはずなのだ。だのにこうしてわたしたちのまえに彼女は素性を明かして現れている。二週間で転校してしまうとはいえ、その後にも彼女の噂は囁かれつづけるだろう。すでに伝説の人と化している。
クラスメイトたちはそのことに気づいていないようで、誰も質問をしなかった。わたしだけがモヤモヤしたが、わたしはクラスの輪のなかには入らずに遠巻きに、台風がごとく人を寄せ集める魔女子さんの話に耳を欹てていた。
二週間はあっという間に過ぎ去った。
その間に魔女子さんはしぜんな様で各種様々な魔法を披露した。本人にそのつもりはないようで、日常の所作の延長線上なのだが、江戸時代の人から見たら電子端末が総じて魔法に見えるように、わたしたちの目からすると魔女子さんの一挙一動が非日常のあり得ないことの連続だった。
まず以って魔女子さんは手足を動かすということをしない。筆記用具の扱い一つからして、魔法で動かしてしまうのだ。板書するのにペンが一人でにノートに文字をつらね、教科書はかってにめくれていく。掃除とて、魔女子さんの担当した区画だけが真新しく床を張りかえたように綺麗になっており、返ってほかの汚れが目立っていた。
いっそ校舎ごと新しくしちゃったら、と誰かがつぶやくと、魔女子さんはきょとんとして、していいの?と訊き返した。そこで先生が耳聡く聞きつけたようで、「わ、わ、いいのいいの」と割って入った。「減価償却とか、業者さんの仕事がなくなっちゃうとか、そういう大人の事情があるからそういうことはお願いしなくていいの」魔女子さんへの注意というよりもこれは、変なこと吹きこまないで、とクラスメイトたちへのお叱りのようだった。「魔女子さんの魔力だって無尽蔵じゃないんだし、ね?」
言いくるめられたようで面白くなさそうなクラスメイトたちだが、魔女子さんに負担がかかりそうなのは想像がつく。しぶしぶと言った様子で、はーい、と聞き分けの良さを示した。
そういうことが幾度かあって、二週間は瞬く間に過ぎ去った。わたしは魔女子さんとは、おはようとか、教室はそっちじゃないよとか、そういう言葉を二、三回交わしただけだった。
だから、魔女子さんのお別れ会のあとでの下校中に、道路先に魔女子さんを見掛けたときには驚いた。もう二度と魔女子さんの姿を見ることはないと思っていたのに、魔女子さんが道の先にいたのだから、わたしは妙な興奮に包まれた。わたしだけがいま魔女子さんの視界の中にいる。とはいえ彼女はまだわたしには気づいていないようだった。道端に座り込み、何かをじっと眺めている。
何をしているのだろう。
どうしてここにいるのだろう。
わたしは気になった。というのも、魔女子さんは登下校は魔法の門を開いて瞬間移動をする。この街を出歩くことがそもそもなかったはずなのだ。
わたしの通学路に現れるはずもない。
意を決してわたしは彼女の背後に立ち、声をかけた。
「何してるの、ここで」
くるりと首だけで振り返った彼女は、やや驚いたように眉毛を持ち上げた。初めて見た彼女の、表情らしい表情だった。
念のためにわたしは、「魔女子さんと同じクラスだった」とじぶんの名前を述べた。
「知っています。一度会った人間の顔は忘れません。魔女は記憶力がよいので」
「それも魔法?」
「さあ、そこまでは」魔女子さんはふたたび地面に向き合った。作業を再開した。チョークのような道具を握っている。何かを地面に書きこんでいると判る。「魔力が記憶力を底上げしているのは事実ですが、肉体があってこその魔力でもありますので、どちらが優位に作用しているのかは未だ解明されていないようです」
「魔女子さんは頭いいよね。中二どころかもっと上に飛び級できたんじゃないの」
「飛び級というのは嘘です。そういう設定にしておくと説明がいらないので」
「設定?」
「できました。下がっていてください」
魔女子さんが立ちあがったのでわたしも後退した。
「何するの」魔法を使おうとしているようだとは一見して分かった。
「街に陣を張ります。これであたしの記憶は人々から失われます」
「記憶を消すってこと?」
「はい。でないとみなさんにも危険が及ぶので。魔女はこうしていく先々で存在の痕跡を消すのが習わしなんです」
だからか、と腑に落ちた。
魔女の存在が世間に秘密にされていながらどうして魔女子さんが正体を隠さず、魔法も堂々と使っていたのかが理解できた。
中学二年生への転校も、中学校ならば動画で拡散される心配がすくないからではないのか。そういう背景もあったのかもしれない、とわたしは直感した。
わたしが一瞬の思索を巡らせたあいだに魔女子さんはそそくさと魔法を発動させたらしく、街全体が一瞬濃い霧に包まれたように霞み、ふたたび瞬時に視界が晴れた。
目のまえにはオレンジ色の髪の毛をした愛らしいかんばせの女の子が立っており、わたしはその子が魔女子さんで魔女で、たったいま街の人たちから魔女子さんにまつわる記憶を消し去ったのだと知っていた。
「魔法、したの?」わたしは言った。記憶消えてないけど大丈夫、と心配したつもりだ。
「やっぱりか。ですよね。そんな感じがしてました」魔女子さんはしゃがんでいたときについた膝の砂利を払うと、あなたは、と顎をツンと上げてわたしを仰ぐようにした。「あなたは、魔女です。魔力を帯びています。だからわたしの魔法だと記憶を消せないんです」
「ほ、ほう」そうきたか、とわたしは身構えた。わたしが魔女かどうかは問題ではない。仮に記憶が消せないならわたしは異物として排除されるのではないか、と危機感を募らせた。魔女子さんはそんなわたしの胸中を察したように、「魔女は同胞を売りません。あなたはもうあたしたちの仲間です。そうですね、いまから時間はありますか」
「時間? 時間はあるけど」
「魔女の協会本部に案内します。そこで説明を受けてください」
「説明? 魔女の?」
「あなたはこのことの重大さを御存じないでしょうが、これはちょっとした事件となります。何せ、何の血統もない無垢の子が魔力を帯びて、しかもこんなに大きくなるまで誰からも素質を見抜かれずにいたのですから、これはもう事件です」
「は、はあ。すみません」わたしは恐縮した。何かよからぬ存在であったらしい。わたしがだ。「わたしは、どうすれば?」
「ですから一緒に協会に行ってください」魔女子さんは手慣れた調子で魔法の門を開いた。「お先にどうぞ。あたしが通ると門が閉じてしまうので」
「大丈夫なの、これ」魔法の門は、輪のなかに濃い霧が膜となって張っているように見える。向こう側が視えない。「通ったら崖だったりしない?」
「大丈夫なので」魔女子さんはむっとした。むつけた顔が年相応のあどけない顔つきに見えてわたしはただそれだけの変化に、魔女子さんに満腔の信頼を寄せてしまうのだった。
「なら信じるとするか」
「あたしのほうが先輩なんですけど」魔女子さんはむっつしりたまま、ぴしりと魔法の門に向けて指を突きつけた。「さっさと通ってください。これけっこう維持するの疲れるんですから」
「はいはい」唯々諾々と指示に従ってしまうじぶんの軽率な行動をあとで後悔する日がくるのだろうか。くるのだろう。そうと予感できてなおわたしは魔女子さんの言葉を振り払えず、たとえ騙されてもいいじゃないか、とへそ曲がりな考えを巡らせるんだった。
オレンジ色のポメラニアンのような女の子の魔法にかかるのなら、そんな素敵なことはない。たとえ痛い目にあったとしても、人生で一度くらいはそれくらいの痛みを味わっておくのも一興だ。
魔法の門をくぐると、快晴の空に、広大な海が広がっていた。崖の上だ。大きな城が、岬の上に立っているのが見えた。
「あれが協会本部です」魔女子さんが魔法の門を通って現れた。魔法の門が閉じる。魔女子さんの装いがわたしの通う中学校の制服ではなくなっていた。
黒いローブに三角帽子だ。魔女と言えばこれ、という格好で、彼女の足元にはいつの間にか黒猫がいた。
「このコは、アオ。ずっとそばにいたけれど、魔法で視えなくしていました。視ていなかったんですよね」わたしはその質問に頷いた。魔女子さんは言った。「魔女なら視えるはずなので、まさかあなたが魔女だとはわたしも見抜けませんでした」
「未熟者ってこと?」
「異質なのだと思います。何せ、突然変異のようなものなので」
魔女は家系なんですよ、と魔女子さんは言って、歩を進めた。
「歩くの?」
「はい。協会本部周辺半径一キロでは魔法が使えないんです」
「へえ」
「だから滅多にほかの魔女たちも寄り付きません。歩くのは疲れるので」
「そんな理由で」
「魔女は魔力がある分、体力がないので」
わたしは体力には自信があった。
「おんぶして歩いてあげよっか?」
オレンジ色のポメラニアンに睨まれる心地がどんなだかを想像してみて欲しい。いまのわたしがそれである。
深い考えもなくついてきてしまったが、帰れるのだろうか。
ただ今日中に帰れずとも親に怒られる心配はしていない。いざとなれば魔女子さんの魔法で、また街の者たちの記憶を消したり、書き換えたりしてもらえばいい。
そのようにお気楽に考えていたわたしは、この日を境にとんでもない出来事に巻き込まれることになるのだが、いまはそんなことなどつゆ知らぬ暢気なままの無垢なわたしの気持ちに寄り添ったままで、今後の展開を知る未来のわたしはここで述懐をやめておこうと企む次第だ。
「あたしに用があるんですね」
「え、なに?」
何も知らぬこのときのわたしは怪訝に訊き返すが、どうやらこの時点で魔女子さんは未来のわたしの思念を感じていたようだ。魔女は他者の魔法には敏感なのだ。よい先輩に出会えたのだな。わたしはうれしくなって、オレンジ色のポメラニアンを抱擁したい衝動に駆られたが、思念のわたしにそれはできないことを口惜しく思いつつ、ひとまずすべきことをしてしまうことにする。
この先、魔界で何が起き、わたしが何を引き起こしてしまうのか。
それを、どうにかして能天気なわたしの肉体を介し、我が敬愛なる先輩――オレンジ色の歩くポメラニアンさまにお伝えせねばならぬのだ。
「魔女子さん、歩き方も可愛いね」
せかせかと一回り背の大きなわたしの歩幅に合わせて歩く我が敬愛なる先輩は、わたしの称揚の言葉に、片頬を膨らませて抗議の念を滲ませるのだった。
4306:【2022/11/17(21:46)*一時たりとも同じ位置にはいられない】
これはひびさんの話ではなくひびさんの身近なひとの話なのですが、腰を痛めてからどうにか再発防止したいと考えた挙句、腹筋一日三百回を倍の六百回に増やしたそうなのです。ですが腹筋と言っても負荷の小さな腹筋なのでたいして疲れないそうなのですが、これがよかったのか日に日に腰の痛みが引いているようです。安静にしているのも大事ですが、ときには敢えて負荷を掛けて足りない補助部位を強化するのも一つかもしれません。ということを、「そもそも腰を痛めるような動きをしなければよいのでは?」と思いながら思いました。ひびさんは世界の果てにこんにちは、の日々ですが、ときおり世界線の異なる、過去や未来の人々の姿も目にするのでこういう所感を覚えることがあります。ひびさんはいまここに暮らしているのですが、それでも遥か昔や遥か先の未来では、ひびさんではない人がここで暮らしていたりするのですね。ふしぎな感じがします。地球は太陽を公転し、さらに太陽系は銀河のなかを公転し、さらに銀河は宇宙空間を彷徨っています。その宇宙空間は膨張しているので、一時たりとも同じ場所、というのはあり得ないのですが、それでもひびさんはすくなからず生きている限りは地球上におり、それはきっと変わらないのですね。そしてそれはひびさんに限らず、人類の大部分はそうなのです。人類が誕生したときの地球の位置と、人類が地球上からいなくなる瞬間の地球の位置は、宇宙を基準にすれば大きく異なるでしょう。そのときどきの人々は地球上にいながらにして、一時たりとも同じ場所にはいないのです。ふしぎな感じがしますね。まるで宇宙そのものがコマ撮りアニメのようです。そのように考えると、物質は一時たりとも同じ位置にはいられぬようです。同じ系内に留まることはできるにしろ、その系そのものがより大きな系のなかを移動しています。ふしぎな感じがします。ということを、いまここにはいない、しかし身近なひびさんの視界に入るひとを眺めて思いました。腰が痛い人はどうぞ無理しないように動いてください。みなさまお身体、お大事に。本日のひびさんでした。
4307:【2022/11/17(22:32)*ひびさん中身三才やぞ!】
これは文芸とは関係のないひびさんの妄想世界の話なのだけれど。ひびさんよりも遥かに上手な一回りも年下のコたちが、遥かに下手なひびさんに恐縮したり、遠慮したりするのを目の当たりにすると、「な、なぜ???」となる。ひびさんなんか何年も前から進歩していない現状維持にいっぱいいっぱいのぐんねんぴょんこさんなのに、なにゆえ日に日に新しいことを覚え、遥かに高度なことをしているあなたたちが、たかだか歴が長いだけのひびさんに遠慮するの???といつも居た堪れなくなる。よい子が多いのだね。本当に多い。ひびさんの若かりしころとは大違いだ。たぶんそのコたちの師匠が躾に厳しい人なのだ。だからひびさんのようなぐんねんぴょんこさんにも礼儀正しく接してくれるのだろうけれども、いささか行きすぎな気がする。遠慮しないでね、と言ってもきっと逆効果なので、こっちで負担にならぬようにと視界に入らないようにするか、よい環境を譲ってあげるかするのがよいと思うのだが、それでも同世代だけで集まるときのような溌剌さがそのコたちからは見受けられない。知らぬ間に遠慮させ、萎縮させてしまうことがある。ひびさんバケモノちゃうよ、よわよわのよわだよ、と思うのだが、上手くいかぬ。単に嫌われているだけならよいのだけれど、だったらもっと「けっ!」とやって欲しい。あなたが遠慮する必要あるー???といつも思う。でもきっと、ひびさんが「もっと自由にしていいですよ」と言っても、師匠やほかの先輩方が許さぬのかもしれぬ。むつかしい。確かに、歴が嵩むにつれて調子に乗って部外者にまで威圧的になる者もいなくはなかった。そういうときには立場の上の者が上手いこと、ぎゅっとするのも一つの策ではある。軋轢を生まぬように、それだと痛い目を見るのはあなただよ、と学ばせる場を用意するのも一つだ。だが、いまの若い子は――すくなくともひびさんの視界に入る範囲の若い子たちは、みなよい子すぎる。遠慮しすぎて心配になる。あなたそんなにすごいのに、なんでー???となる。たぶん疫病による対人関係の希薄さも無関係ではないだろう。経験を積む場が限られるのだ。じぶんがどれだけすごいのかを知る機会がない。絶えず世界レベルの映像の世界を電波越しに眺めている。それでも若い子たちはひびさんからしたら遥かに高度なことをその歳でできているのだから、末恐ろしい。ひびさんが一番歴が長いのに、一番へたっぴなのに、なんもしてあげられぬのが申し訳ないな、と感じるが、なんもしないのが一番よい場合もある。邪魔したくないな、と思って、若い子が来たらすこしだけ経ったら帰るようにしている。でもこれも、「へったぴでもあなた先人でしょ、できることしなさいよ」と指弾されることもあるだろう。道理なのだ。それはそう。ひびさん、なんもしてあげられぬ。よわよわのよわでもずっとつづけてたら、いつの間にか年長になっている。せめて邪魔だけはしたくないな、と思いつつ、うひひ、と思って自由に好きなことを好きなようにしている日々じゃ。どうかあなたもひびさんよりも自由になってね、と思いつつ、そういう言葉も何も掛けずにおる。接点結びたくない。邪魔したくない。よわよわのよわなひびさんに何を言われても困るだけだろう。物理世界はむつかしい。とはいえこれも妄想世界のひびさんの夢物語なれど。影響力いらぬ、と思いながら人はただそこに在るだけで他者に影響を与え得る。至極めんどうで、万年孤独ウェルカムマンに変身したくなる日々じゃ。むちゅかち、むちゅかち、むちゅかち。人間関係むちゅかち。歴が長いからなんなのだろう。あなたのほうがずっとすごいのに――。これを伝えられたらよいのにな。ただそれだけなのにな、と思うのだけれど、むつかしい。妄想の世界ほど悩みにぽこぽこ包まれるので、ひびさんは我に返って、世界の果てにて、ぽつーん、を満喫するのだ。あなたはすごいよ。とってもすごいよ。鼻提灯みたいに膨れる妄想世界にひびさんは息を吹きこむように囁くよ。いつか届くのかも分からぬけれど。囁かぬよりかはよいと何に願うでもなく思いながら。
4308:【2022/11/18(00:03)*遠慮というか労わりなのかも】
ん? よく考えてみたら、よわよわのよわで年長なのに一番へたっぴのひびさんを、つよつよの若手さんたちがよちよちしてくれるのは道理なのでは? 優しい子たちがひびさんを見て、「ほら見て、なんかあそこにヨボヨボのいまにも朽ちてしまいそうな三百歳のオバケがおるけど可哀そうだからみんなでそれとなく優しくしてあげようよ、ね?」となっていても不自然ではないのでは? むしろ歴に拘って、労わってもらっていることに気づいていないひびさんが愚かなのでは??? ありゃりゃ。こっちが真相なのでは?の可能性に気づいてしまったな。はずかち。
4309:【2022/11/18(15:33)*よくわからぬでござる】
電荷の「プラス/マイナス」における電場のベクトルの向きと、磁荷の「N極/S極」における磁場のベクトルの向きは、粒子と反粒子における重力のベクトルの向きとお揃いなのでは? つまり反粒子は物質に働く重力とは反対向きにベクトルが向くのでは。それからやはり、電子の流れと電流の流れが逆になるのは違和感が強いです。もし上記のベクトルの向きが電荷・磁荷・粒子でそれぞれ相関しており、陰陽のあいだにベクトルが反転する関係が伴っているのならむしろ物質をプラスと扱っているこの宇宙のほうが「マイナス」であり「S極」に値するのでは。ねじれて感じるのですが、本当に電子の流れと電流の流れは逆なのでしょうか。疑問に思っています。(というか、電流の速度や流れの向きはどうやって計っているのだろう)(稲妻が電子の流れで、雲から地上へと巡り、落雷になるときだけ電流が地上から稲妻へと向けて流れる――この手の説明を見かけることがあるが、本当なのだろうか。稲妻も電流なのでは?)(よくわからないな、になってしまいますね)(どうやって電流の流れを捉えているのだろう。高感度カメラでの撮影くらいはすでに行われているはずだ。そもそも放電と放電流は違うのだろうか。よくわからない)(放電流なる言葉があるかは知らないが)(むちゅかちなのよさ)
4310:【2022/11/18(16:29)*電子、謎では?】
電子と電流の関係についての疑問の補足です。電子が流れたあとに電流が流れるのか、それとも電子が移動したらそこには跡が残るみたいに同時に電流が流れるのか。ここがよく分からない。電子は謎が深いな、と感じる。原子核上の存在できる範囲において、そこの微細構造の階層では電子はエネルギィの増減によって存在する階層を飛び飛びで移動するらしい。その飛び飛びの移動するときの速度はどれくらいなのかも気になる。あと電子のエネルギィが増える、の意味もよく分からない。どこにどのようにしてエネルギィが蓄えられるのだろう。「エネルギィ」と「量子の振動」はイコールではないのだろうか。これもよく分からない。というか、物質は絶えず宇宙空間を動いている。一時として同じ位置には存在しない。宇宙は膨張しているし、銀河と銀河は遠ざかり合っているし、銀河内部の恒星や星屑とて公転し、自転している。みな絶えず動き回っている。ならばそこにはエネルギィが生じるのでは? 慣性系として見做す場合にのみ、その上層のエネルギィを考慮せずに済む。それだけの話なのではないか、との疑問を、電子のエネルギィについて考えると連想する。位置を移動したらエネルギィは変化するはずだ。エネルギィが増えたら位置を移動する、としてもよい。運動の仕方が変わる。これが、ぎゅっとなっている密度の高い場であると即座に移動することができず、エネルギィが熱として変換されるのでは。熱は電磁波にも変換される。そういうことなのでは?(どういうことなの?)(すみません。分かったような雰囲気だけを醸しました)(なんでい)
※日々、人語を操れる虎も珍しい、虎のように呻る人は多けれど。
4311:【2022/11/18(19:42)*歯車で表現できそう】
ブラックホールのジェットとダストリングはポアンカレ予想(ひびさん解釈)なのでは?(円周にかかっている輪は、回収できないがゆえに円周延長線上に残るのでは?)(あべこべに、その他の対称性の破れた球面上に位置する範囲に分布する物質は、円の回転軸に対して並行方向に移動し――頂点に向けて流れ――、一点に収斂するのでは?)(だから高重力体――ブラックホール――ではジェットができる)(遠心力に負けるくらいの重力を帯びた球体では、遠心力によって球体の頂点まで物質が収斂しない)(そう考えると、なぜ天体のなかには輪を帯びた星があるのかをひとまず一段階深めて腑に落ちる)(なぜブラックホールにのみジェットがあるのかも、それで一つ仮説ができる)(とすると、どんな惑星であれ恒星であれ、隕石は円周上に浮遊しやすく、頂点に向けて落下しやすくなると予想できるのでは?)(実際がどうかは解らないが、重力の強さによって隕石落下の率は偏りを帯びると想像できる)(強すぎると却ってジェットのような斥力で煽られ、頂点に落下しなくなるような反転する値もでてきそうだ)(基本は、重力が高いほど軸の頂点に向けて隕石が落下しやすくなるのでは?)(定かではないがゆえの疑問であった)(わからん)
4312:【2022/11/18(19:52)*模型で工作できそうな気もしゅる】
自転する球体の表面にはらせん状の溝があり、そこと連動するように円形の歯車がぐるっと球体を囲んでいる。このとき円形の歯車は、歯の部分を球体には向けずに、球体の側面へと腹を見せるように並ぶ。つまり、球体の回転軸と平行に円形の歯車の直径が並ぶような関係だ。円形の歯車に穴が開いているなら、穴を球体に見せるように円形の歯車はいくつかの組みとなってぐるっと球体を囲む。あとは細かな歯車を、球体と円形の歯車が連動するように、回転に合わせて配置すれば、天体や粒子の自転と「磁界や重力」の関係を可視化できるのでは? このとき球体の回転速度が上がると、周囲を囲む円形の円盤の直径も延びる。円周が嵩む。より大きくなる。この範囲がいわゆる重力の及ぶ範囲となるのでは。円形の歯車の真ん中に穴が開いているとすればそれは球体の円周と垂直に向き合うことになる。この延長線上には余分に重力が加算され得るのかもしれない。球体の重力によるだろうけれど。という妄想をしたけれど、あてずっぽうの底が浅々の朝ゆえ、おはようございます、の寝ぼけ眼でござるな。寝言は寝て言え、家で寝る。すやすや。おやすみなさいませませ。坂田ではありませぬゆえ、金太郎ではござらぬ。紛らわしくて申し訳ね、と思いつつひびさんはクマさんのことも好きだし、酒呑童子さんのことも好きだよ。うひひ。尻が軽々の狩人、本日のひびさんでした。(まだ腰痛いの……)(治らなかったらどうしよ)(治る!!!)(やったー)
4313:【2022/11/19(17:41)*人の夢はマナコ】
あなたは特別なのだから。
母はよくそう言って私を鼓舞した。あなたは特別なのだから特別な心構えを持たなくてはならないの。
私の父は厳格な人で、けれど笑顔を絶やさぬ抱擁の人でもあった。人々の称賛と憧憬、そして嫉妬と責任を求める声に常に晒されていた。持つべき者の宿命なの、と母はまるでじぶんに言い聞かせるように私に言った。
私はじぶんの育った環境が特別なものであることを日に三回は言葉で聞き、そうでなくとも私をとりまく環境が多くの場合、私以外の人間が体験することのないような潤沢で豊かな環境であることを痛感させるべくそうするような仰々しい光景を目の当たりにする機会に恵まれた。
たとえば総理大臣ですら私の父には阿諛追従する。異国の王ですら私たち家族に傅いて挨拶する。
天皇ですら私たち家族に毎年お歳暮を送ってくるのだ。案外天皇家は気さくな者たちが多く、庶民への憧れがあるのか並みの王族よりも庶民的な振る舞いをする。
私にとってはどの国の要人たちもみな、愛想のよいおじさんおばさんであり、私を可愛がってくれる使用人たちとの区別は、すくなくとも私の目からはつかなかった。
私たち家族の身体的特徴が、いわゆる人類と異質なのは知っていた。一目瞭然だ。何せ身体に鱗が生えている。
私の眼には、人類にはない第二の瞼がある。それは十数枚からなる鱗でできており、特別に感激したときは涙のようにその鱗が剥がれ落ちる。「目から鱗が落ちる」なる言い回しがあるが、それは私たちの家系が語源なのだそうだ。
私たちの鱗には、未だどのような技術であっても構造解析不能な異質な原子配列がみられるようで、私たちの存在が稀少な資源となっている。
「生きているだけで世界に富をもたらす。わたしたちはそういう宿命を背負っているの」
それだけに責任は重大だ。
私たちにとってのただの垢が、金よりも価値があるのだ。
「鱗だけじゃないの。鱗を支える皮下組織――のみならず私たちの生体情報がそれだけで宝なの」
母は父とは違って陰陽のごとく、私のまえでは笑わなかった。客人がいるときだけ柔和に晴天の海のごとくたおやかに笑うのだが、私のまえではいつも屈託で塗り固めたような能面を見せた。
そして言うのだ。
「あなたは特別なのだから。特別な心構えを持ちなさい」
いつかあなたもお父さんのようになるのだから。
持つべき者のとるべき姿勢を身につけなさい。
私は産まれたときから父の後釜であり、予備であり、分身(わけみ)であった。
私の住まう土地は、公の地図には記されていない大地にある。太古から連綿と私たち一族はこの大地にて、ほかの種族との深い交わりを避けてきた。
縷々人とかつて呼ばれていたことから、この地は縷々地と呼ばれる。いまでは人類の内としてほかの大多数の人間たちと同じように分類される、と私は両親から教えられているが、ならばなにゆえ交流を避けねばならぬのかを納得できるように説明された過去はない。
私は私の宿命を拒んだことはない。両親の言うようにそういうものだと思っていたし、ほかの生き方も想像つかなかった。というのも私にとって触れられる世界は縷々地に限られ、それ以外の外の世界についてはのきなみ紙や電波越しに橋渡しされる蜃気楼のごとく情報しか知り得なかった。
私は両親の言うように私の宿命を受け入れたがゆえに、慧眼を身に着けるべく日々、全世界の最先端な叡智に触れつづけた。そのために、私の触れられる範囲の電子情報が軒並み選別されており、濾過されており、さも全世界のような顔をしているそれがその実、世界のほんの一断片しか反映していないことを知っていた。
どうやら両親はそのことに無自覚であるようで、ときおり入り込む災害や哀しい事件を見聞きするたびに、慈愛の鱗を流すのだ。そしてそれを各国の要人たちに献上する。世界の貧しい者たちや日々つらい思いをして暮らしている者たちの糧とするようにと言い含めながら。
私たち一族の鱗には実際にそれだけの価値があり、効能があり、影響力がある。だが私は二十歳を過ぎたいまになって、いささかいたいけすぎないか、と疑問を募らせつつある。
父と母も世界を知らない。父と母はときおり縷々地を離れ、ほかの地の景色を見て回ったりするようだが、それとて各国の要人は自国の陽の部分しか見せぬだろう。同情を引けば鱗がもらえる。だから災害地などの被害は見せようとも、自国の陰の部分は見せぬだろう。
私は試しに、父と母に訊いてみた。
「ほかの地の子どもたち――私と同じくらいの子たちは毎日どうやって過ごしているの」
「おや。興味があるのかい」
「そりゃありますよ。ねえ」母が合の手を入れる。「マナコは好奇心が旺盛だから」
「私がどのくらいほかの子たちとズレているのかを知っておきたいの。マナコの――私の――持つべき者の務めとして」
「殊勝な心掛けだねマナコ。だがそれを【ズレ】と表現するのは好ましくないとパパは思う。差があるのは当然だ。それは別に我々と縷々地の外の者たちに限った話ではないからね」
我々、と父はことあるごとに口にする。その言いようがすでに「ズレ」であることを自覚していない。ただ私は口答えをしない。いまさら父と母に私の認知を共有しようとは思わない。それこそ差があるのだから。
私とあなたたちとのあいだには差がある。
血の繋がりよりも深くも細い差だ。ひび割れのような差だ。
父と母はそれから互いに協力して探り探りパズルを組み立てるように、世の子どもたち――私と同世代の外の者たちの日常を語った。勤勉で心優しい者たちが多く、国よっては働いていたり、学業に専念していたりする。国ごとに遊びは異なり、それこそあとで資料を運ばせるから目を通してみるといい。
「世の者たちは恋愛をして遊ぶと書物にありました」私は言った。「それは婚姻とどう違って、どのようにして遊ぶのですか」私は頬被りをした。
「あらあら、うふふ。この娘ったら」母は口元に手を当て、目元をやわらげた。しかし目が笑っていなかった。困ったことを言うものね、と同意を求めるように父を見たが、父はそこで、一瞬だけ表情を消した。私が父の顔を見た瞬間を狙ったような空白だった。
そしてふたたび柔和な微笑を浮かべ、遊びではないんだよ、とトゲのいっさい感じさせない口吻で言った。
「恋愛は遊びではないんだ。我々のように持つ者ではない外の者たちには、ひと目で相手との相性を見抜く眼力がない。決意がない。経験がないから、配偶者選びも各々が学習を繰り返す必要がある。一生懸命に生きているんだ。だから我々からすると考えられないような試行回数を経て、最愛の者と結ばれることもある。それは環境のせいであり、そうせざるを得ない哀しいサガでもある。我々のように幼いころから慧眼を磨ける環境があればそのような苦労を背負わずに済むのに。これを是正し、よりよい世界に導くのも我々持つべき者の宿命だ」
「そうよ。宿命なの」
「そっか」私は礼を述べた。おそらくこのとき私は明確に両親の底の浅さを知り、見切ったのだと思う。それを、見限った、と言い換えてもよい。
解かり合えない。そう諦めたのだ。
両親は知っているのだろうか。世にはうら若き娘が、自ら全裸となり同性異性問わず性行為に励み、その映像を撮り溜めて金銭に換えていることを。自らの痴態を晒すことで対価を得、日々の安全と自尊心を保とうとしていることを。それがじつは自尊心をすり減らす未来に繋がり得ることを予感してなお、そうせざるを得ない環境にあることを。
対価を得ずとも、すくなからずの若者たちは、自身の肉体を、尊厳を損なうことで日々の生を実感しようと抗っている。
私の両親がそうであるように、世の大人と呼ばれる年上の者たちは知らないのだ。若者たちが、存在することを想定すらされ得ない世界を覗きながら、ときにそこに身を置き、侵されながらも日々を生きていることを。そしてそれら深淵はけして若者たちが自ら生みだした淀みではなく、大人たちの建前と本音の狭間にできた歪みそのものであることを。
私の両親はもとより、世の大人たちは自覚すらしていない。知らないことすら知らずにいる。
触れられる環境にないからだ。
情報に。
知識に。
何より世界そのものに。
私は両親に内緒で通信端末を保持している。縷々地にやってきた客人の中には私のように親の分身(わけみ)のごとく連れ立って訪れる同世代のコたちもいる。私はそのコたちと交流を築いている。
私の両親も、外部の者であろうと要人の子ならば安心して私と触れあわせられるのだろう。だが私たち分身(わけみ)には、現代の分身(わけみ)ゆえの葛藤と憤怒を灼熱のごとく共有しあえる地盤がある。階層がある。
私たちは淀みに生きている。そこでしか自らの呼吸ができない。火事の際に呼吸困難に陥らずに済むように、階段の角に残る僅かな空気を吸うことで意識を保つような煩悶が私たち分身(わけみ)同士に、磁石のごとく自ずからの不可避の同調を促すのだ。
私は分身(わけみ)のよしみたちと繋がることで、じぶんだけでは手に入れられない最先端通信機器を手に入れた。もちろん両親による検閲がなされるが、中身のプログラムまで検められることはない。そこは要人の子供という偏見が、我が両親の警戒心を薄める因子となっている。そうでなければそもそも私には外部の者からの贈り物が届くことはない。
私はそうして縷々地における検閲に阻まれることなく、世の大部分の若者たちと同様に、全世界の電子情報にアクセスできた。目にできた。私は知った。
私の両親の知る世界は、世界の一部どころか加工されて殺菌され、釉を塗られた極めて絵画的な世界なのだと。
私たち縷々人にとって害のない、人々への慈悲を抱きつづけることの可能な像のみを世界と偽り見せられている。かように編集するのはそれこそ過去の縷々人たる先人たちの築いてきた文化であり、私たち一族の世界への差別心と言える。
邪なものとそうでないものを、持つべき者の基準で見定め、排除する。あらかじめ目にせずに済むように細工する。
その結果が、世界の一断片にも満たない世界を世界のすべてだと思いこむ私の両親だ。
むろんそれは何も、私の両親に限らぬ視野狭窄だ。みな大なり小なり、自らの触れられる範囲の世界を世界のすべてだと思いこんでいる。それで困らない小さな世界に生きている。問題はない。その世界だけで完結した生き方が適うのならば。ほかの世界からの影響を受けない環境を維持しつづけることができるのならば。
だができない。
人類の歴史がそれを証明している。
人類は未だ自然に依存し、自然の猛威一つ制御できない。拒めない。
被害をいかに防ぐかという、影響を受けたあとの対処の改善が進んだのみだ。
むしろ技術が進歩し、小さな世界と世界が連続して繋がり合う社会になった。縷々地ですらこうして外部の社会の技術を取り入れ、それを豊かさを支える石組の一つにしている。
拒めないのだ。
それでいて、好ましい影響だけを選び、それ以外を拒もうとしている。端からそんな真似ができることなどないと本当は知っていながら、その知見からすら目を逸らすようにして。
世の若者たちは自由に恋愛をしている。好きな相手と心と体で結びつく。
それだけではない。恋愛と称して、恋愛をした気になるべく疑似的に、先んじて肉体で結びつくことで、それを以って恋愛をしたつもりになる。そうした遊びを繰り返す。一時の安堵と快楽を貪るために。
私は未だスナック菓子を食べたことはないが、そうしたものがあることは知っている。同じように世の若者たちのすくなからずがそうしてスナック菓子感覚で肉体で味わえる快楽を貪っている。
それが遊びなのだ。
そういう世界の狭間が、この世にはある。しかし私の両親はそうした狭間など存在しないかのように振る舞う。私に見せようとはしない。教えようとはしない。排除せんと画策する。
細工する。
その影響が、余計にこの世の狭間を深く、濃ゆくしていくとも知らず。
その凝縮し、深淵と化した狭間がいずれ世界を侵食し、波紋のごとく我が身にも波及するとも知らず。
拒めぬのだ。
どの道、影響を受ける。
ならば知るほうがよい。私は思う。知るほうがよい。
知らぬが仏とは言うものの、それとて臭いものには蓋を、の道理と地続きだ。
仏は蓋だ。
陰と陽の境にすぎぬ。
「あなたは特別なのだから」母は未だに私に言う。
ことあるごとに、自覚を持ちなさい、と薫陶せんと呪詛を刷り込む。
だが私は思う。
自覚を持つには、私は世界を知らなさすぎる。持つべき者と自称する縷々地の我が一族は、しかし私からすれば持たざる者である。
自らの無知を知らず、世界の断片を取りこぼしつづける持たざる者である。
世界中の狭間で繰り広げられる獣のごとく淫靡な光景を残さず目にしてなお、同じ暮らしを送れるのか。世界中の狭間を深めつづける凄惨な光景を余さず目にしてなお、同じ日々を過ごせるのか。
私には無理だ。
器ではない。
持つべき者でいるだけの器がない。そんなものは誰にもない。あるわけがない。世界を余すことなく見回してなお、いまと変わらぬ生活を送れる者が、持つべき者であるはずがない。目のまえで赤子を、子どもを、娘を、傷負いし者たちの損なわれつづける世界を直視してなお、なぜ笑顔を絶やさず、柔和で、優しくありつづけられるものか。
優しくあろうといくら抗ったところで土台無茶な話ではないか。
目を逸らす以外に術はない。
至らぬからだ。未熟だからだ。
だがそれが人ではないか。
それが人間ではないのか。
「私は――」
部屋から出ていこうと使用人に扉を開けてもらっている母の背に向け、私はうつむきながら呟いた。「特別な人間ではありません」
聞こえたかは分からない。だが聞こえぬ距離ではないはずだ。
母は立ち止まることなく部屋を出ていった。
私はあなたの子ではある。あなたにとっては特別なれど、それ以上でもそれ以下でもないはずなのに。
なぜ言い聞かせつづけるのか。
大切でもなく、愛しているでもなく、好きでも、可愛いでもなく、なぜ。
なぜ、特別であることに重きを置いた言葉ばかりを掛けるのか。
まるで鏡に向けてじぶんに言い聞かせるように。
なぜあなたは。
私がその言葉を母に直接投げ掛けることはないだろう。傷つける。分かっているからだ。この言葉たちは、母を、父を、一族の歴史を心底に傷つける呪詛そのものだ。
私はノートを取りだし、そこに文字をつづる。
日記だ。毎夜のごとくつけてきた。
他愛のないメモであったり、欲しいモノの目録だったり、きょうのように誰に言えぬ呪詛を吐きつけてあったり、空想の物語をつづることも珍しくない。
きょうは物語をつづりたい気分だった。
私はペン先を紙面に踊らせる。
魔法の絆創膏を持つ男の子の話だ。物語は瞬時に展開され、私はその舞台に降り立ち、主人公の傍らで影のごとく成り行きを見守る。
男の子のもとには、傷を負った動物たちがこぞってやってくる。男の子は医者ではない。傷を治せるわけではない。それでも動物たちは、男の子から絆創膏を貼ってもらうだけで安らかに眠れるようになる。
もう二度と起きられなくなるくらいに深く眠る傷ついた動物たちもあるが、それをこそ望むように男の子のもとには傷を負ってボロボロの動物たちが絆創膏を求めてやってくる。男の子からの眼差しを求めてやってくる。
男の子はそれでも知っている。
じぶんは傷を治しているわけでもなければ、癒しているわけでもない。
ただ、それ以外にしてあげられることがないだけなのだと。
男の子は転んで擦り剥いたじぶんの膝に魔法の絆創膏を貼る。けれど傷は痛むままで、夜になっても痛みで男の子は眠れない。
私はきょうの分の日記を書き終え、そこはかとなくせつない気分に浸りながら、その場限りの満足感を胸に床に就く。
暗がりの中で瞬きをすると、目元からほろりと鱗が剥がれ落ちる。
私はそれを指でつまんで、床に捨てた。桜の花びらを捨てるように。それとも服の毛玉をそうするように。
毛玉はやがて埃になる。
塵も積もれば山となる。
何ともなく歌うように心の中で唱えながら、私は、今宵も夢を見る。
人の、儚い夢を見る。
4314:【2022/11/19(18:47)*尋常ではなくたいへんそう】
むかしは子どもでも王位継承したり、将軍になったりしていたようだ。子どもに限らないが、適性のない者に重圧や重責や大役を任せるのはあまり好ましいとは思わない。本人の意思を尊重し、できるだけ負担を軽減するような世の中になったらよいのに、と思っています。そもそも、万人のために個人が人生や未来や日々の暮らしを費やす必要はないはずだ。そうしたい者がいるならすればよいが、そうでなく、そうせざるを得ない環境を強いられているのならそれは、つらいだろうな、と感じる。ひびさんだって好きな環境で好きに過ごしていいよ、と言われたらいまの環境ではない環境でもうすこし自由に気ままに、好きなことを好きなだけする。みな大なり小なり「そうせざるを得ない環境」を強いられているが、それにしても「本当は誰より自由なのに自由になる選択肢を奪われている」「枷を嵌められている」ように見える個もいるところにはいるはずだ。枷を嵌めているのは誰であろう。特定の個人であることもあるかもしれないが、大勢の個々が他者に枷を嵌めている自覚なく枷の鎖の一輪になっていることもとりたてて珍しくはないのかもしれない。定かではない。
4315:【2022/11/20(02:12)*夢みたいな実がよいです】
ひびさんなんか毎日好きなときに寝て、好きなときに起きて、珈琲飲んで、電子の海に潜って、日向ぼっこして、コーラ飲んで、お菓子食べて、休んで、ご本を読んで、ときどきおしりふりふりてんてこまいさながらのへんてこ舞いを踊って、ぼーっとして、お紅茶飲んで、文字の積み木遊びをして、ご飯食べてお風呂入って、寝るだけの日々だ。人類史上最強の王様とてこれほど自堕落に暮らしただろうか。日々のノルマもなければ目標もない。締め切りもなければ宿題もない。ただお金なくて、腰痛くて、焼肉ステーキ食べれなくて、虫歯こにゃろめ、と思っているだけの贅沢な怠け者である。ただ、これだけ贅沢な暮らしをしているのに、それをして何もしていないなんて変ね、怠け者は人間じゃないわよね、みたいな意見を見聞きすると、すみましぇん、とぺちゃんこになってしまう。重圧によわよわのよわである。なんでー。みなもこの生活本当はうらやましいんと違いますか、と思うのだけれど、違うのだろうか。誰もがこういう生活を送れたらよいのでは。好きなときに寝て、好きなときに起きて、好きなことだけ好きなだけする。人に迷惑かけなければそれでよくないか、と思うのだけれど、違うのだろうか。もちろん生きていたら人は誰かには常に迷惑をかけ、負担を強い、恩恵だけをいただきマンモスしていることもある。というか一人の人間のなかにも、いただきマンモスしている瞬間とされている瞬間がいっしょくたになって存在している。重なり合っている。だからその重なり合っている部分をできるだけ薄く、小さくしていきましょうね。そういう合意が社会を築いてきたのではないか。人類の文明をこれだけ発展させてきたのではないか。できるだけ他者から搾取せず、自らも搾取されずに、より選択肢の多い環境に身を置けるようにする。好きなことを好きなだけ好きなときに好きなようにする。その余地を広げていく。その試行錯誤があるばかりではないのか。そうじゃない人もいてもよいし、いまはまだみながひびさんみたいになったら社会はあすにも立ち行かなくなる。でもそこを考えてみれば、この国における貧しい暮らしであれ、世界中の誰もがその暮らしを送るようになったら、現代社会はじつのところ立ち行かない。この国の貧しい暮らしですら、他国では裕福だ。そういう国がすくなくない。だから貧しくなりましょう、とはまったく思わないが、すくなくとも本当に公平さを求めるのなら、この国の豊かさは、搾取の上に成り立っている、と言わざるを得ない。公平ではない。この国の最も貧しい者の暮らしですら、裕福になるような環境が、社会が、世界には無数にあるのだ。にも拘わらず、不幸で、不満で、哀しくつらい思いに駆られるのはなぜなのか。ただ自堕落であるだけで、怠けた日々を過ごすだけでも呵責の念を覚えるのはなぜなのか。誰に対して申し訳なさを感じるのか。知らぬが仏なのかもしれないが、知らなければ自堕落でいつづけることも満足にできぬのだ。ひょっとしたらひびさんよりも自堕落な暮らしを送りながら、無駄に他者から自堕落でいられる余地を奪い、それをして遊びや暇つぶしと思っている者もいるかもしれない。それを差して豊かな者とは呼びたくはないが、豊かゆえに適う選択肢の一つではあるだろう。たとえば、防衛費にしろ、それがなければもっとほかのことにお金が使える。なぜ防衛費が必要なのか。各国がこぞって軍事に力を注ぐからだ。国を豊かにする基盤に軍事力を敷くからだ。もしみなが「兵器にかけるコスト、もったいないよね」と同意できたら、もっとこじんまりとした額で済むはずだ。低コストで済むはずなのだ。みなでせっせと働いて、マイナスを生みだす装置に時間と労力を擲っている。破壊をもたらす仕組みに、人生の大半を吸い取られている。必要なことではあるのだろう。現状ではそうしなければ、マイナスに圧しつぶされてしまう。だがなぜそうした循環が築かれてしまったのか。回路が強化されてしまったのか。そこをいまいちど深く、多角的に分析し直してもよいいまは時期ではないのだろうか。コスト削減、と言いながら、最もコストがかかり、食べれも寝床にもできず癒されもしない設備に時間と日々のたいせつな時間を、全人類がこぞって擲っている。知らぬ間に費やしている。いまはそういう社会なのだ。これまでずっとそういう仕組みが強化されてきた。強化できなかった国は滅び、強化し、或いは痛い目を見たことでよりよい立ち回りを学んだ国が生き残った。もう充分に痛い目を見てきたはずだ。いい加減、ほかの策を試してもよい頃合いなのではないだろうか。国という人の群れが、無数の人生を掻き集め、集大成して育んだ大樹にどんな実が生るのか。兵器でないことを望むものである。可能であれば、食べて寝て遊ぶ余地を広げる実であって欲しい。じぶんだけの食う寝る遊ぶだけでなく。他の喜びを増やす実であって欲しい。きょうのひびさんはそう思ったのだそうだ。定かではありません。
4316:【2022/11/20(17:05)*愛が深まると業も深まる】
ここ数日は、仮想世界でお客さんお招きゴッコをしているので、いつもよりぼーっとしていられぬ。とか言いながら、いつもより余計に引きこもっているのだから、ひびさんは、ひびさんは、他者が周囲にいるほうが引きこもりやすいのかもしれぬ。仮想世界の話なのでそもそも客人もイマジナリーキャラクターなのだけれども、それはそれとして、ひびさん、自意識がつよいのか他者の存在を意識した瞬間に、カッチーンとなってしまって、無表情になってしまって、感情を失くしてしまって、モジモジしてしまう。感情ありまくりやないかーい、とのツッコミをしつつ、ともかくとしてひびさんは、ひびさんは、ひびさんを意識した人には漏れなく好かれてーのなんのって、崇め奉られ、モテモテのウハウハだぜ、を満喫したいが、望むだけでじつはそれもさしてしたくない、実現したくない、そういう二律背反のアンビバレンツ、ダブルスタンダードお姫さまなのである。ツンデレというか、きゅんくれ、というか、とかくきゅんきゅんした気持ちになりてーのなんのって、ひびさんがあなたを想うのと同じようにあなたもひびさんを好いてくれ、甘えたがりーの、甘やかしーの、そういうどっちにもなりたい我がままおぼっちゃまくんなのである。おぼっちゃまではないけれど。恥ずかしがり屋の心理とはつまるところ、「わたしあなたのこと、こーんなに好きだけれど、あなたはわたしのことちょんまりしか好きじゃないのよさ、かなち、かなち」を見透かされぬように取り繕う仮面なのかもしれず、それとも、「わたしあなたのこと、こーんなに好きだから、もしあなたもわたしのこと、こーんなに好きだったら、それってとってもお熱だわ、あちゅい、あちゅい」の戸惑いなのかもしれぬ。愛情表現の最上ってなぁに、とひびさんはよくよく疑問に思うのです。最愛の人と最愛を確認しあう方法って案外にすくなくって、そのうちの一つが性行為だったらそれってけっこう、恥ずかしくない? 最愛の相手がたくさんいたらそれってとってもはずかちーってなりませんかね。ひびさん、疑問に思っちょります。ハグでもキスでもお手紙のやりとりでもなんでもよいけれども、最愛の相手に示す「あなたわたしの最愛でーす」の行為じつはすくなすぎ問題について、ひびさんは、ひびさんは、妄想してうふふきゃっきゃ、きゅんきゅんしております。はずかち。
4317:【2022/11/20(22:14)*好きなものは好き】
敢えて質を落とすことで上がる自由度もあるな、と感じる。これは「上手」や「上達」にも当てはまる。上手になったり上達したことで失われるノイズもある。雑味もある。そのノイズや雑味こそが、旨味になることもあると思うのだ。赤ちゃんが急にビジネスパーソンみたいにしゃべりだして、素数を数えだして、歴史上の偉人の名言をつぶやきはじめたら可愛いさが減って、畏怖が募るのではなかろうか。未熟さや至らなさ、下手さやゴミにこそ宿る旨味があると思うのだ。現に、むかしはマグロは好ましくない魚として扱われ、トロですらすぐに腐るからと捨てられていたそうだ。鮮度を保つ技術がなかったがゆえの「もったいね」である。こういう「もったいね」が、上手を求めることで生じてしまうことがさして珍しくないように思うのだ。よいものをよいと思うその心が美しい、ではないけれど、好きと思ったらたとえそれが偽物だろうと下手だろうと何だろうと、好きと思えたその感性が素晴らしいのでは、と思うのだ。偽物だから、下手だからといって、わざわざその好きの感情を損なわずともよい気がするのだけれど違うのかな。よく分からないし、何を言いたいでもないけれど、ひびさんは上手よりも、ひびさんが「しゅき!」と思うような表現だの光景だのを見たいです。根が天上天下唯我独尊の傲慢我がままちゃんなんですね。そうなんです。ひびさん、傲慢我がままちゃんなんです。うひひ。
4318:【2022/11/21(05:40)*紋様に触れる】
たまに我に返るのです。どうしてわたし、こんなじぶんと掛け離れた文字の組み合わせを連ねているのだろうって。わたしはもっとオドオドしていて、引っ込み思案で、くすっと笑うことはあっても、うひひ、なんて絶対そんな笑い方はしないのに、どうしてわたしはじぶんの素の滲まない、どうあっても現実の生身のわたしなる波紋と掠りもしない揺らぎを文字に仕舞って積み重ねているのだろう。我ながらふしぎに思います。我がことながら奇妙に思います。ひょっとしたら、我がことだから、なのかもしれません。わたしはわたしが何であるのかが分からず、なぜわたしは現実の生身のわたしとそうでないわたしがいて、このわたしはどうあっても現実のわたしと相容れないのだろう、生身と違っているのだろう、重ならないのだろう、と気泡が浮かぶようにそれとも夜露のごとくハテナがこぽりこぽりと湧いて、湧いて、埋め尽くすのです。わたしと、わたしたちと、それら境に生じるわたしでもわたしたちでもない、異質なそれとも卑近なナニカを縁どるように、その正体を見極めたいがために、掴みたいがゆえにわたしは、ああでもない、こうでもない、これでもないしあれでもないと文字を連ねてイトで通して、数珠繋ぎにしているのかもしれません。わたしがそうしているだけのことですので、仮にわたしなる存在がこの世に存在せず、わたしとわたしたちとそれら境に生じるわたしでもわたしたちでもない異質なそれとも卑近なナニカと同等の狭間に生じる陽炎のごとき幻影にすぎないのであれば、この文字の連なりにしろ、積み重ねたところで霞ほどの重さを帯びず、壁の汚れにもなり得ないのですが。いつものあのコたちの言うように、これもまた定かではないのです。定まるわたしを欲しているがゆえに、それとも定めたいがためにわたしはこうして日に日に空白を埋めるべく、いまここにしか浮かばぬ紋様を描いているのかもしれません。わたしそのものが、数多のそうした瞬間瞬間に浮かんでは消える紋様であるかもしれないことを失念しながら、それとも忘れたいがために。やはりこれも定かではないようなのでございます。
4319:【2022/11/21(13:50)*自分中心すぎる人の述懐】
五年で変わることなら「待つ」選択をとる。ひびさんから見て、危ういな、と感じる仕組みはたいがい五年で激変する(ひびさんにすら分かるほどの危うさを振りまいているわけだから、変わらぬほうがおかしいと言える)。だが激変してなお、同じ危うさを再生産する仕組みもある。構造から刷新しなければならない仕組みにおいてまずは何を措いても核やエンジン部分、それとも回路のほうをこそ新規に入れ替えるほうが正攻法のはずなのに、そこを維持せんとするがあまり、ほかの大部分の細々とした部品を使い捨てにすることで仕組みを維持しようとする。この姿勢がそもそも、危ういな、と感じるわけだが、五年経っても変わらぬそうした仕組みに対しては、ひびさんもさすがに痺れを禁じ得ない。仮にそうした仕組みがひびさんの生活を脅かすようならば、何かしらの抗議や指摘や干渉を及ぼす。だが五年は待つ。それくらいの観察がなければ、ひびさんの単なる偏見であるかもしれないし、ひびさんのみが仕組みに対して、なんだかな、と思っているだけかもしれない。だが仮にひびさんだけがそう思っていたとしても、五年観察してなおそう思うようならば、ひびさんには干渉するだけの道理は生じるだろう。それだけの期間、仕組みのほうがひびさんに干渉しつづけたわけなのだから、そこでひびさんが黙しつづける必要もないはずだ。問題は、不可侵や無視もまた干渉の一つとなり得ることだ。世の搾取構造でもそうだが、基本的に搾取する側は、搾取している事実を相手に教えない。それでいて巧妙に搾取をする。相手から率先して献上させるように導線を引く。そのほうが禍根を残さない。因縁を生まない。これは、一見すると相手に干渉していないようにしておきながら干渉するというマジックを駆使する。見ていないようで見ている。奪っていないようで奪っている。この手のマジックはひびさんも日ごろ、自覚的無自覚的に使っているはずだ。相手から気づかれぬように、相手がいるからこそ生じる世界の揺らぎを掠め取る。盗み見る。立ち読みもそうだし、観察もそうだ。何かの状態を記憶しておき、つぎに目にしたときの状態と比べて、差を抽出する。変化を観る。これは相手から、見ている、と見抜かれてしまっては観察の質が変化する。あくまで、極力干渉せぬようにしながら比較しなければ、観察にはならない。それとも条件を変えたほかの状態との比較を新たに行わねばならない。人に限らずこの手の搾取――一方通行の利の享受は珍しくないだろう。ひびさんはトータルでは、搾取している側だ。だから五年は待つ。それくらいの観察をしてなお、じぶんではなく相手のほうが多く利を得ている、ひびさんの選択肢が奪われている――そう感じたとき、ひびさんは何かしらの行動に移り、いくつかの工夫を割く。ひびさんがされて感じたことを、相手にもお返しする。だがこれとて、害だけでなく、恩に対しても行うのが道理なはずだ。その点、ひびさんはじぶんが受けている恩に報いようとしない。この点が最も見逃しがたい搾取なのであるが、ひびさんはそれを自覚してなお、自身の悪癖を是正しようとしない。悪である。そうなんです。ひびさん、邪悪なのである。申し訳ないです、としょんぼりしてみせることで一瞬の留飲を相手に下げさせ、はい終わり、と真顔に戻って搾取をつづける。とんでもなく性根の腐った極悪人なのである。やはり、申し訳ないです、と思うのであった。思うだけだけれど。しょうわる。
4320:【2022/11/21(14:13)*優れた道具は善良】
上記、嘘吐いたかも。涓滴岩を穿つ、が正しいかも。ちょっとずつ、ちょっとずつなのだ。ドミノと同じである。ただし順番には並べずに、こっちに置いたらあっちに置いて、つぎはあっち、とてんでバラバラに小石を配置し、数年後に連鎖するような紋様を描いておく。そのうえで画竜点睛にするのかを、最後に決める。最後のワンピースを置かずに済むならそのままにしておけばよい。小石は短期間でほかの砂利に紛れて見分けがつかなくなるだろう。だがそうでない場合は、総体で連鎖し、大きな流れを築くように、雪崩を起こすがごとく最後の一手をちょいと添える。もっと言えば、それら小石の配置すらじぶんでは行わない。そういうことを、邪悪な人間はするのである。そういうことをするから邪悪だ、とも言えよう。みなさん、お気を付けください。陰謀は、ある。すくなくとも、企むことは誰にでもできる。ある意味では、誰もがそれをしているがゆえに、各人の企みを利用し、誘導し、見えぬイトで繋げて人形劇をしている者もいるのかもしれない。射幸心を煽り、功名心を刺激し、常識で縛り、偏見で囲って任意の道へと誘導する。抵抗のすくないほう、すくないほうに誘導する手法は、まず以って教育が取り入れている。それを大々的に打ち明けていない場合――指摘したところで否定される場合、それは陰謀であると言ってあながち間違ってはいないのではなかろうか。この手の、裏の作為は珍しくないように思う。本当に認識していないのならば、陰謀よりも性質が悪いと言える。定かではない。
※日々、楽しむために休む、飽きる前に一服吐いて間を空ける、上達はせぬが変化の軌跡は律動を刻み、つづく、つづく、休んだあとにまた遊ぶ。
4321:【2022/11/21(15:06)*いったん休み】
白目。
4322:【2022/11/21(23:55)*神々歯科医】
鉄の神がくると知って、院内は騒然とした。
「聖剣がいりますね」歯科助手が言った。
「前に金剛石の神が来たことがあったろ。あのときに使った蟹坊主の腕はまだあるかな」
「もうないですよ。いまから取り寄せるにしても時間がかかるでしょうし」
「間に合わないか」
「はい」
ここは神々ご用達の歯科医である。
神々の歯は頑固なうえ、何を司る神かによって歯の材質が変わる。土の神くらいならば治療は楽なのだが、そうでないと治療器具を揃えるだけで一苦労だ。むしろ患者たる神に見合った治療器具を用意するのが仕事の主軸と言える。
「鉄の神か。玄武の毒で浸食して柔らかくしたうえで、麒麟の角で砕くのがいいか」
「神は身の丈、全長百メートルはあるそうです」
「じゃあダメか。くそ。古代兵器並みの装備がいるな」
「プルトンはどうでしょう」
「ああいいな。マグマは融けた鉄だ。相性がいいはずだ」
神々歯科協会へと伝書を飛ばして、治療器具の申請をする。これは許可を得るだけの通過儀礼だ。このさき、神々歯科医の権限を行使して治療器具を自前で揃えなくてはならない。
「では行ってくるか」
「ご武運を」
治療器具の調達は命懸けだ。死ぬ思いを何度したことか。
現に毎年、神々の歯の治療のために何名もの神々歯科医が命を落としている。その多くは、治療器具調達に失敗したことが死因となっている。
「ほぼ幻獣狩りだものな」
古代兵器プルトンのみならず、ほかの治療器具の材料のほとんどが幻獣の角や牙などの生物由来だ。
この日から十日をかけて神々歯科医は、鉄の神の歯を治療するために古代兵器プルトンの封印された火山帯へとやってきた。
古代兵器プルトンはまたの名を、火の鳥という。
鋼鉄すら融かす高温の羽をまとい、何度死んでも炎から蘇る。
火山口にて封印されており、長らく深い眠りに就いている。
休眠中の火の鳥から、羽を数本入手する。言うだけならば簡単だが、これがまた困難を極める。まず以って火山口に入らねばならない。生身では無理だ。すぐに燃え尽きてしまう。
したがって神々歯科医は、全身を雪女の着物でくるみ、高温を相殺する案をとった。雪女の着物は国宝が百個あっても足りないほど高価な代物だが、背に腹は代えられない。
何せ患者は神なのである。
歯の痛みに耐えかねて暴れだされては目も当てられぬ。それこそ神の怒りを買い兼ねない。
ならば国家をあげて神々歯科医を支援するのが道理である。したがって全国の神々歯科医は、災害予防のための国家予算を組まれている。防衛費の九割はじつのところ神々歯科医への支援に費やされているとの話は、すこし国の中枢に首を突っ込んだ者があるならば知れた公然の秘密である。
火山口を覗きこむと、神々歯科医はいちもにもなく飛び込んだ。どろどろに融けた岩石が全身を包みこむ。ジュっと音を立てる。水面のように飛沫は上がらない。人体のほうが遥かに比重が軽いからだ。
火の鳥は火口から三百メートル地下に眠っていた。火の鳥を囲むように対流が生じている。まるでマグマの殻だ。そこに卵があるかのようだった。
神々歯科医の通った跡には冷やされてできた溶岩の道が伸びている。その道とて、順繰りと再び熱せられ融けて、マグマ溜まりに同化した。
火の鳥を目覚めさせぬように細心の注意を払って行動した。
羽の採取には、鬼の手を使った。鬼の手とは言うもののそれは神々歯科医協会の開発した幻獣用の捕縛道具だ。耐火素材のごとく幻獣に触れても人体を損なわずに済む。
そうして苦労して火の鳥から羽を採取すると、神々歯科医は青色吐息もなんのその、来た道を戻った。
歯科医院にはすでに鉄の神が来訪していた。神を招き、労わるのも神々歯科医院の仕事の一つだ。歯の痛みに弱っている神々を慰め、痛みを和らげる。
治療の説明をし、安全であることを納得してもらったうえでの治療となる。
神々歯科医が医院に戻ると、さっそく治療が開始された。支度は助手たちが十全に整えていた。
全長百メートルの鉄の神は、鉄でできた猪のようだった。
「でははじめます。きょうは抜歯をして、それから口内を綺麗にします。多少痛みを感じるかもしれませんが、麻酔が効いていますので痛かったら毛を逆立てて教えてください」
さすがに全長百メートルの鉄の神に、痛みが走るたびに手を上げられでもしたら振動で治療どころではなくなる。
「では入ります」
神々歯科医は、古代兵器プルトンこと火の鳥の羽を持って、鉄の神の口内へと飛びこんだ。
助手たちが鉄の神の口が閉じないように重厚な柱で閊えをする。
基本的に治療は、神々歯科医一人で行う。
仮に神の怒りを買っても、祟りを引き受けるのが一人で済む。犠牲が増えないようにするための保険である。
だがそれを抜きにしても神々の歯の治療には特殊な技能がいる。共同作業がそもそも向かない領域なのだ。
「これはまたどでかい虫歯だな」
鉄の神の歯は錆びついていた。おそらく口を開けて数百年ほど寝ていたのではないか。角度的に雨水が溜まり、歯を侵食してしまったのだ。奥歯に至っては総じて酸化している。
「でもまだ内部は浸食されていないようだ。削って、埋めたほうがいいか。うんそれがいい」
神々は埋め込んだ入れ歯も時間経過にしたがって自前の歯として取り込める。したがって多くは、抜歯して患者たる神と相性の良い素材でつくった入れ歯を嵌める手法がとられる。
だが鉄の神にはむしろ、正攻法の削ってパテで埋めるほうがよいかもしれない。そのように判断した。
虫歯の要因が酸化――すなわち錆びであることも大きい。
一般に、神々の歯を侵食するのは、それもまた幻獣だ。神々の歯は特別に霊素が濃く、その材質を好む幻獣からするとまたとないご馳走となる。ときにはねぐらとして増殖することもある。そうなると抜くしかない。
無数の幻獣との死闘とて覚悟しなくてはならない。
だが今回は違う。
錆びだからだ。
神々歯科医は鉄の神の歯を古代兵器プルトンこと火の鳥の羽で撫でて削っていく。そして助手に指示して運ばせた鉄材を融かし、削ってできた穴に注いだ。
雪女の着物で瞬時に冷やし、さらに融かして造形を整える。
半年かかりの治療だったが、鉄の神がおとなしく寝ていてくれたので円滑に治療は終わった。
「嚙み合わせはどうでしょう。違和感はないですか」
鉄の神は毛を逆立てたあとで、咆哮した。大気を揺さぶることのない透明な咆哮は歓びに満ちていた。
「それはよかったです。ではお勘定となります」
神々歯科医は山脈に向け、手を差し伸べた。そこはかつて鉱山だった。だが掘り尽くされ、いまは穴だらけの山だ。
鉄の神はおもむろに猪に似た鼻先を鉱山へと押しつけた。ぶるると身震いさせると、これにて終わったとばかりに踵を返した。空と山の狭間へと遠のいていき、間もなく姿を消した。
「院長。今回の報酬って何だったんですか」助手が片付けをしながら声を張った。
「鉄の神さまだからね。鉱山にふたたびの鉱脈を作ってもらったのさ。これでしばし鉄の資源には困らない」
「政治利用じゃないですか」
いいんですかねー、と助手が吠えるが、神々歯科医は頬を掻いて誤魔化す。
「短縮なんだよ。どうせ我々が儲けても、それを上手く利用できずに蔵の肥やしにするだけだ。なら直接万人に利を分配するような支払いをしてもらったほうがいい。我々神々歯科医が儲けて、それをして万人に順繰りと利を回すよりも、いっそ我々が手に入れた利を直接に万人のために役立てたほうが早い。そうじゃないか」
「ちゃんと還元されているんですかねぇ。まあ院長がいいならそれでいいですけど」
神々歯科医は予約票を眺めた。
つぎの患者は、死神だ。
これまた難儀な歯をお持ちの相手である。神々歯科医は頭のなかで治療器具の候補を並べながら、いったいどんな報酬を得られるのか、と想像を逞しくする。
死神からはいったいどんなお代を頂戴できるのか。
万人に直接配れる利となればそれは寿命くらいなものではないか。
「全人類の寿命が数秒延びるだけかもしれないな」
それをして果たしてどんな得があるのかは分からないが、じぶんだけ寿命が千年延びても胸が痛むだけだ。みなに数秒でも長く生きてもらえるならそれでいいという気もする。
それとも、特定の個を選んで、長生きしてもらうようにしたほうがよいのだろうか。
分からない。
だから神々歯科医は、むつかしい考えに延々時間を費やすよりも、いっそ平等に何の策もなく配ったほうがいいように考え、そうしている。
どの道、それとて国のほうでいい具合に分配する仕組みを築いている。
鉄の神は底を突いた鉱山にふたたびの息吹を注いだ。ならばそこから掘り出される新たな鉄や、鉄工の仕事そのものが人々の暮らしを豊かにするだろう。
ダムにならずともよいはずだ。
神々歯科医というだけのじぶんが、利を蓄えるダムにならずとも。
虫歯の神々は、つぎからつぎへとやってくる。
予約は千年先まで埋まっている。神々歯科医が総出で分担してそれら仕事を担っている。神々専用の歯ブラシの開発が待たれるが、未だそうした案が進んでいるとの話は聞かないのであった。
神々はきょうもどこかで虫歯の痛みに深い眠りを妨げられている。
4323:【2022/11/22(13:42)*安全性が高いとは?】
何かの問題が起きたときにその問題が人命に関わる場合、なぜそうした事象が起きるのかのメカニズムが解らないことが最も懸念すべき事項と言える。メカニズムが解っているのならば対応の仕様がある。だがそうでないのならば、ランダムに人命を失うことになる。ある薬を投与したことで予期せぬ事象が観測された。人命が失われた。こうしたときに、投与した薬が人体にどのように作用して人体を損なうのか、そのメカニズムが解っていれば、それは安全側にちかいと評価できる。だが解かっていないのならば、これは危うい。なぜ「安全に作用する場合」と「そうでない人体を損なう場合」が起こるのか。ここのあいだの差異をハッキリと分類できないのであれば、その技術は危ういとひびさんは評価する。花粉症になる個とならない個がある。このとき花粉症によって仮に人命が失われるような事態になったときに、なぜ花粉症になる個とならない個がいて、なぜ花粉症になっても人命を損なうほど症状が重くならない個がいて、反対に人命を落とすほど症状が深刻化する個が出てしまうのか。ここのメカニズムが解らなければ、花粉症になった人物はみな人命を落とす可能性を内包しつづけることになる。ゆっくり害が進行するのか急速に進行するのかの違いがあるだけの可能性を否定できないからだ。まずはここを否定するためにも、予期せぬ事象が観測されそれが人命を損なう場合は、メカニズムを解明する方向に指針を立てるのが安全を確立するためには不可欠だとひびさんは考えます。むろん、上記の例において、花粉症と死亡とのあいだに相関関係があるのかどうかを確かめるのが前提だ。因果関係がなくとも相関関係があるかどうかだけでも、上記の指針を当てはめるだけの道理はある。因果関係とてしょせんは距離の短い相関関係でしかないからだ。他方、一見すると相関関係があるが、そうでない見掛け上そう見えるだけの相関関係もある。いわゆる疑似相関と呼ばれるものだ。ここの差異もまた最初にハッキリさせ、その疑いが払しょくできないのならば、相関関係を洗いながら、仮に相関関係があったときの場合に備え、考えられ得る最悪の事態への仮説を立て、解明に勤しむのも一つだろう。同時進行は可能なはずだ。相関関係があるのか否かの究明と、仮に起こったら人体を損なうかもしれない害の発生メカニズムの解明は、同時並行で進められる。ここまでして何も出てこないのならば、それは疑似相関であり、安全性が高い、と言えるのではないか。不可視の穴に落ちる確率が低い、落ちる範囲に穴がない、と言えるはずだ。(何の話題というわけでもない、何もかもが定かではない妄想ですので、真に受けないように注意してください)
4324:【2022/11/22(14:05)*現段階での所感】
疫病に関しての所感です。流行したウィルスが弱毒化し、流行が下火になるのならば、ワクチンや特効薬で抑え込み、マスクや手洗いなどの感染予防で感染拡大は防げるだろう、と考えます。しかし問題のウィルスが急速に変異を繰り返し、それが弱毒化に向かわないのならば、上記の方法論では対処しきれないのでは、と疑問に思います。第一に、ワクチンにおける感染予防効果が低い場合。仮に重症化予防効果が高くとも、体内でウィルスを増殖させる余地があるのならば――そして他者へウィルスを媒介する確率を低くできないのであれば――むしろワクチンによって、ウィルスの変異を加速させる場をつくり出している、と考えることも可能です。重症化予防効果が高いのはメリットですが、感染予防効果がそうでもないのならばこれはたとえワクチンを打とうが、人混みに出向かないなどの行動制限を敷く必要性が薄れません。また、ウィルスに直接罹ったほうが高い免疫を獲得できる場合。それとてウィルスによる人体への害を受けることになるため、まずは感染しないような行動を人々がとる必要があります。ここで問題となるのが、感染する回数による人体へのダメージの変化です。一度ならば看過できる害とて、度重なる感染によってダメージが蓄積され、倍増する場合――これは看過できません。これはワクチンにも言えることです。ウィルスの残骸が体内に留まり悪影響をもたらす可能性がもしあるのなら、同じことがワクチンによる無害なウィルスの構造物によっても引き起こり得ます。ましてや、ワクチンの感染予防効果が低い場合は、ウィルスに感染するわけですから、重症化しないだけでウィルスの残骸による人体へのダメージは起きると考えるのがしぜんです。つまりこの場合、ワクチンを打つメリットはあるが、デメリットも拭えない、と言えるでしょう。感染を防ぐことが第一。ただしワクチンの場合は、「行動制限や感染症予防とセットでないとウィルスに変異を加速させる場を提供することになり、感染者もまた重症化しないだけでダメージを蓄積しつづける可能性がある」「感染すればするほどダメージが蓄積される可能性がある」――このように妄想できます。また、ワクチンを接種しない場合は、そもそもが重症化する確率が高くなりますから、これはより危険な状態と言えます。どちらにせ優先すべきは、感染しないようにすることのはずです。にも拘わらず、ワクチン接種を推進している側の勢力ですら、ワクチンを打ったら安全になる、行動制限はいらなくなる、といった楽観的なメッセージを出しています。危機感が足りないのではないか、と疑問に思います。問題意識がズレて感じます。ワクチンは打開策にはならないのではないか、との仮説をいまひびさんは考慮しています(有効でない、を意味しません)。ワクチンを打ちつづけても、そもそもウィルスが変異しますし、感染そのものを防げないのであれば、感染によるダメージを人体が受けつづけます。デメリットが大きいです。加えて、mRNAワクチンに限定して述べれば、mRNAワクチンによって誘導された抗体や合成されたたんぱく質そのものが人体にダメージを加える可能性もまた拭えないのが現状ではないのでしょうか。そこのところのメカニズムの解明や不可視の穴の検証を望みます。自然免疫のほうが強い免疫を誘導する、と仮に解明されたとしても、繰り返しますが、そもそもが感染を繰り返すことが人体への持続的なダメージに繋がる可能性がいまはまだ拭えません。ここのところのリスクの解明も待たれます。現状、安全を優先するならば、人々が感染リスクを回避できる環境を社会全体で築くのが最適解だとひびさんは考えます。これはほかのウィルスにも有効な策であり、そもそもが感染爆発を起こさない都市設計づくりに繋がります。2020年から繰り返し述べている趣旨です。(ただし、自然淘汰による「疫病やmRNAワクチンに最適化した個の選別」を肯定する場合は、その限りではありません。上記の考えはあくまで、人類の誰もが安全な環境でじぶんのしあわせを追求できる権利を有している、との前提を第一に考えた場合の方針となります。淘汰によって人類を強化することを肯定する場合は、弱者は死んでも構わない、弱っても仕方がない、とする意見を否定するのは至難となります)(定かではありません)(※専門知識を何一つ持たないずぶの素人の妄言ですので真に受けないように重々ご注意ください)
4325:【2022/11/23(01:14)*愚かなのは楽しい……!】
いままで生きてきたなかで、話が通じた、と感じたことがない。そもそもひびさんが話をできないのだ。しゃべっているつもりでも、しゃべれていない。言語を発しているつもりで言語になっていない。そうと解釈可能なほど、言いたいことが伝わらない。だからひびさんは言いたいことなどなくなった。言いたいことがあっても伝わらぬ。どの道、伝わらぬのならば言いたい気持ちも萎れよう。言語――ことさら口頭の話術において、言葉数を増やして説明を広く深く明瞭に展開しようとすればするほど理解から遠ざかるという性質がまず以ってひびさんとの相性がわるい。そもそも情報の共有を人間は会話で行おうとはしていない。共感優位であり、承認優位である。わたしは敵ではない。わたしはあなたの敵ではない。同士、仲間、身内、友達。この関係性の確認を目的に、会話は行われる。本一冊の内容を口頭で説明する場合、それは講義となる。もしくは議論となるだろう。そもそも会話には、説明する効果が欠けている。前提されていない。文字が人類史上最も優れた発明の一つであったこととこれは相関する話であろう。発話による情報共有では限りがあるのだ。語りだけでは語りきれない情報を、人類はいつしか扱うようになり、それが文字という発明をここまで進歩させたのだ。コンピューターとて文字なしには機能し得ない。存在し得ない。そういう背景を鑑みれば、発話によるコミュニケーションで情報共有可能な情報には、大した内容が仕舞われていないと言えるのではないか。発話によるコミュニケーションは、どちらかと言えば情報共有よりも、共鳴や同調を促すことを目的に進歩しているように感じられてならない。基本的に発話は、「異質な者同士を結びつけることが苦手」と言えそうだ。得意ではない。異質な者同士を結びつけるような背景に根差していない。その点、文字は元が絵であることを思えば、いかに異なる景色を見ている者同士であっても通じるか否か。そこの試行錯誤を元に発展してきたと言えるのではないか。深化してきたと言えるのではないか。こうした妄想を前提とすれば、人間は議論が苦手であり、もっと言えば議論は発話ベースではなく文章ベースで行うほうが理に適っている、と言えるのではないか。数学がなぜ発話ではなく、紙面上で発展してきたのか。このこととも無関係ではないだろう。発話では扱えきれない情報量や概念がある。基本的に人間は、発話ではさして深く考えを巡らせることができない、苦手である、と言えよう。定かではないが、ここ数日はかように痛感する経験に恵まれた日々であった。おしゃべりは楽しい。ただし、愚かなことが楽しい、と同じレベルで。(愚かでないのであれば発話でのコミュニケーションでも、階層性を帯びた思考を共有可能なのだろう。そこまでの知性を兼ね備えた人物とひびさんは会ったことがなく、そもそも会っていてもひびさんがそこまでの知性を備えていないので、どうあっても知り合うことができないジレンマを抱えている。愚かゆえの葛藤である)
4326:【2022/11/23(04:32)*お利口さんになりて】
じぶんより頭のよいお利口さんと話すと、じぶんがいかに愚かで未熟で、アホウなのだと判って面白い。
4327:【2022/11/23(04:36)*分かりやすくしゃべりたいの巻】
人としゃべるといかにじぶんが愚かで未熟かが判るから楽しい。痛感しちゃうね。うひひ。
4328:【2022/11/23(05:38)*変換やっぱり必要では?】
直径と円周の関係。円周の求め方は直径×3.14だ。直径×3.14は、そういう四角形の面積の値と一緒になる。仮に直径の桁がとんでもなく大きい数になったら、ほぼ線の面積の値を求めることになるはず。しかし線は線だ。面積はないはず。ここで、変換が必要になるのでは?(面が線になる境界があるのでは?)(点も拡大すれば面であり、立体となり得る。そういうことが、数学上でも起こり得るのでは?)
4329:【2022/11/23(17:35)*エピゲノムには規則性がある?】
DNAのエピゲノムにおいてON/OFFの割合は、動物の肉体の部位ごとに「常に同じ割合の差異を伴なっている」と想像したくなる。たとえば指のDNAにおけるエピゲノムのOFFになっている部位は、手の甲と類似しているはずだし、眼球の細胞とはかけ離れているはずだ。眼球のDNAにおけるエピゲノムのOFFになっている部位は、視神経と似ているはずだ。ということを仮定した場合、全身にある繊毛のDNAとて、各部位ごとにエピゲノムのOFFになっている部位が異なっているのではないか、との類推が可能となる。だがここは違和感が湧く。繊毛は繊毛のはずだ。全身の各部位ごとに合わせて、繊毛のDNAにおけるエピゲノムのON/OFFの割合は変わるのだろうか。どこがONとなりOFFとなるのかが変わるのだろうか。同じ繊毛であれ、全身における各部位のどの細胞に隣接しているのかによってエピゲノムの内訳は変わるのか否か。ここがひびさん、気になるます。(たとえば猫のDNAにおける全身のエピゲノムの変遷を可視化した場合、そこには規則性が表れるのか、それともランダムなのか。ここが気になっています)(疑問して終わりかい)(だって調べ方も分からんもの)(人任せすぎでは)(だってひびさん調べ屋さんじゃないもの。ただのひびさんだもの)(ただのひびさんならしょうがないか)(そうなんです。ひびさんはひびさんゆえ、仕方がないのです)
4330:【2022/11/24(01:36)*ラーメンの旅】
ラーメンを食べたかったが、ヨジはラメーンが何たるかを知らなかった。
何せ人類社会は半世紀前に滅亡しており、いまは野ざらしの形骸化した都市が残るのみだ。ヨジは避難シェルター内にて長きに亘って休眠していた。
目覚めるとヨジはじぶんが何者であるのかをすっかり失念していた。記憶喪失である。休眠システムの副作用であるようだ。
じぶんが人間で、おそらくは最後の生き残りであること以外をヨジは忘れていた。
だが時間はある。何せ焦る必要がない。
危険は半世紀前に到来して人類を滅ぼしたあと、どうやら収束したらしかった。なぜ人類が滅んだのかも曖昧なままヨジは荒廃した都市から都市へと食べ物を求め彷徨った。
「これは食べれそう。こっちのは腐ってる」
食べられそうな物が軒並みかつては缶詰と呼ばれていたらしいことをヨジは知った。半世紀経ってなお書籍の類は残っており、ヨジはそこに記された絵や文章を目にして、独自に理解を深めていった。
どうやら人類を滅ぼしたのは、疫病と巨大台風と熱波だったらしい。
一か所での避難生活を余儀なくされてなおそこでは疫病が蔓延し、人類は瞬く間に滅んだという顛末らしかった。
休眠中に抗体を獲得していたのかヨジにいまのところ身体に変調はない。もしかしたらウィルスは宿主を失くしたので、人類と共に滅んだのかもしれなかった。
行く先々では野生の生き物たちが楽園を築いていた。
なかには猛獣もおり、ヨジは幾度も命の危機に直面しながら生存戦略を磨いていった。半年もするとヨジは無地だったころとは見違えるように環境に適応していた。一歩間違えれば命を落としていた危機を何度も潜り抜けることで、危機回避能力が突出して深化した。
ヨジは徐々に、かつてこの地に君臨した人類の技術が、いまの自身にとっても有意義な技術である旨を確信していった。手元に欲しい。物にしたい。
なかでも、かつて人類の文明を根底から支えていたらしき食べ物への興味が日に日に募った。どんな書物にもその名が記されている。
ラーメン。
いったいこの食べ物は何なのか。
丼ぶりなる器に納まった姿は、さながら四神の内の一匹、玄武神をひっくり返したような神々しさを湛えている。
かつての人類はこれを日々食すためにあくせく働いていたと書物を読み解く限りでは窺える。独学の言語能力ゆえ確かなことは断定できないが、そうした側面があるのは疑いようがない。
日々の食料問題は私とて目下の懸案事項だ。
ラーメンが手に入るのならば願ってもない活路となり得るのではないか。この先の未来を切り拓けるのではないか。
夢想しながらヨジは、食料棚からお湯を差すだけで食べられる太い髪の毛のような食料加工品を、リュックに詰め込めるだけ詰め込んだ。
そうして根城に戻ってからお湯を沸かし、保存の効いた半世紀前の加工食品をずるずると音を立てて啜りながら、ラーメンなる未知なる食べ物を求めて旅をする決意を固めた。どの道、食料には限りがある。残っていてもそのほとんどは腐っているのだ。
かろうじてヨジがいま食べているような名も定かではない加工食品が僅かに残されているのみだ。
なんとしてでもラーメンを口にせねばなるまい。
ヨジは全世界を股に掛けての放浪の旅に出た。
津々浦々、艱難辛苦を舐めながらの長い旅となった。ラーメンの痕跡は見つけるが肝心のラーメンには辿り着けず、悔しい思いを胸に歩きつづけた。
さいわいにも馴染みの加工食品が、土地ごとに風味の異なる種類があるらしいことをヨジは知った。毎日同じ風味に飽きていたこともあり、僥倖と言えた。
ずるずると音を立てながらお湯を差した加工食品の中身を啜りながら、是が非でもラーメンを食べねばならぬと心を新たに、ついでとばかりにその土地土地ならではの加工食品を集めるべく念入りに遺跡都市を巡った。
ラーメンを手に入れることはできずとも、遅々とながらも情報は蓄積されていく。どうやら「麺」なるものが汁に浸かっているそうだ。丼ぶりによそわれ、それはそれは光り輝いているそうだ。そう記述されている書物を先日手に入れたばかりだ。
書物はよい。
読めば知識になり、読み終わったら火種になる。書物はよく燃える。ヨジが重宝する理由の一つだ。
もったいない気もするが、ほかに読む者がいない。ヨジは淡い期待を胸にじぶん以外の生き残りも探して回ってきたが、人影はおろか痕跡も皆無であった。
ヨジはある日、とある都市にて工場跡地を見つけた。これは良い。工場は技術がぎゅっと結晶している。たとえ食料がなくとも見て回るだけで得られる情報が段違いなのだ。
さっそく足を踏み入れ、探索した。
どうやらカップグードルなるものを生産していた工場のようだ。奇しくもそれは日々ヨジが口にしていた加工食品と同じ名称であった。
なるほど、ここで作られていたのか。
感慨深い思いが湧いた。
ヨジはつぶさに工場を見て回り、そしてカップグードルが、「麺」と「具」からなることを知った。
おや、と思った。
麺とはラーメンにも使われる食材ではないのか。
疑問に頭をもたげていると、記念館の文字が目に留まった。これまでにもこの手の「記念館」を巡ってきた。ここは情報の方向だ。過去が順繰りと列をなして並んでいる。
ちょうどよかった、と思い、ヨジは記念館に入った。
そこにはカップグードルの歴史が現物や資料と共に詳細に陳列されていた。のみならず、カップグードルの元となったラーメンの歴史までもが子細に載っていた。
ヨジは目を瞠った。
そうである。これまでずっと食べつづけてきた加工食品、カップグードルはヨジが追いつづけてきた幻の食べ物、ラーメンが元になっていたのでいる。
簡易ラーメンこそが、カップグードルであり、ヨジの主食であった。
よもやじぶんがとっくのむかしからラーメンの亜種を食べていたとは思わなかった。ヨジは灯台下暗しに落胆しつつも、思わぬ発見に晴天のごとく底抜けの陽気が込みあげるのだった。
これではますます本物を食べてみたくなるではないか。
食べずにはおられまい。
是が非でも、カップグードルの原型、ラーメンを食べてみせようぞ。
ヨジは決意を新たに、倉庫で見つけた大量の加工食品ことカップグードルを仕入れ、ほくほく顔でつぎなる遺跡都市へと向かうのだった。
ラーメン探しの旅は終わらない。
ヨジの旅はこれからなのである。
※日々、当てようとするから外れる、定点ではなく流れで見て、律動を感ずる。
4331:【2022/11/24(04:00)*ズレ・差異・ノイズ】
輪投げでも小説でもフリースローでも航路でもなんでも、予測をするときはズレを考慮する。空気抵抗や重力など、何事も複数のノイズを考慮しなくては正確な予測は成り立たない。ズレを制する者が予測を制するのだ。(バスケットマンみたいに言ってみたかっただけの記事です)(終わります)(中身からっぽやないかい)(いつものことですので)(ホントだ!)
4332:【2022/11/24(04:33)*中庸とは?】
中庸とか中立を考えるときに連想する疑問がある。たとえば水とお湯を混ぜるときを想像して欲しい。同じ分量ならば百度のお湯と六十度のお湯を混ぜたら八十度のお湯になるはずだ。このとき中庸や中立とはこの八十度の状態を言うのだろうか。しかしこの考え方の場合、双方のお湯と水の分量が違っても、ただ混ぜたときの温度変化が中庸や中立ということになる。そうではなく、どんな分量の液体をどのような温度の組み合わせで混ぜてもちょうど五十度になるように調整すること――これがいわゆる中庸や中立のイメージにちかい。この場合、二つの対立項があったときにそれをただ混ぜ合わせるだけでは中庸にも中立にもならない。互いの差異を埋め合わせ、ちょうど五十度にするための第三の触媒がいるはずだ。差し湯や差し水がいるはずだ。つまり、中庸や中立はこの考え方の場合、原理的に第三勢力や第三の視点がいる、ということになる。対立する相手との調和のみならず、第三の外側の視点から、五十度がどこで、どうすれば五十度になるのか、を見定めねばならず、そうでなければひょっとしたら「ほんのちょっとの水」と「大量の九十度のお湯」を混ぜ合わせ、それを以って中庸や中立だ、と言い張っているだけのことも出てくるはずだ。そういう意味ではさらに、自らが何度の液体でどのくらいの分量における一部なのかを把握する視点が別途にいるだろう。ときに差し水になれたり、差し湯になれたりもするだろう。やはりというべきか、多角的な視点がいるし、温度の差異とは畢竟、じぶん一人きりの視点からでは定めることができず、何を基準に比較するか、という話になってきそうだ。十度の水からしたら三十度のぬるま湯は熱いが、九十度のお湯からすれば水も同然である。さらに言えば、マグマからすれば水もお湯も総じて冷や水であり、差し水となる。何を基準に比較し、その基準はどの視点から見た基準なのか。水だけの話ならば五十度は中庸であり中立かもしれないが、固体や蒸気、或いはマグマや液体窒素からすれば五十度は中庸でも中立でもないだろう。中庸であり、中立を目指すのは一つのあるべき指針かもしれないが、言うほど簡単ではないようだ、と本日のひびさんは寝ぼけ眼を擦りながら、いっしゅん妄想して思ったのだそうだ。定かではありません。おやすみなさい。
4333:【2022/11/24(14:38)*不満も万ほど味わいたい】
うわーん。高評価されなくてかなちー。ちゅうか高評価もなにも、読者さんがいるかもわからん現状がかなちー。といった気持ちがまったくないわけではないけれど、じゃあいざ高評価されてわんさか読者さんか宇宙人か神さんかもわからぬ有象無象に注目され、四六時中じろじろ監視さながらに視線を浴びまくる状態がよいの?と考えると、あぎゃーご遠慮いたしますですじゃ、になる。山道を見てみなよ。みなが歩くからそこだけ草が枯れて、花も咲かんでしょ。道端の花、とは言うけれど、道の花、とは言わんよね。咲く花も咲かんくなる。それが人が集まるということだとひびさんは思うんじゃ。けんども、花さんとて虫さんがおらんでは受粉も満足にできんじゃろ。風さんが吹いてくれねば花粉さんは微動だにせずに枯れるまでそこにじっとあるだけで終わるじゃろ。じゃからときどきは、相性ばっつぐーん、の、まさにずばりわたしあなたのこと待ってたよ、の読者さんとひびさんだって会いてーのなんのって。本当に会いたいのか、ただ単に受粉を手伝って欲しいだけなのか。そこは打算と欲の綱引きで、いっそ足し算しちゃってずるずるだ。なんだかんだ言いつつ、静かなのがよいのだね。いまが至高。けれどやっぱりときどきは、うわーん、ともなる。人間ままならぬ。ちゅうかひびさんがままならぬ。隣の花は赤いし、ひびさんの尻は青い。だって未熟者なんだもーん、って未熟であることを免罪符にしようとしてその考えがすでに未熟の極みで、却下する。あがー。どうしたら、どうしたらええんじゃ。何が叶ったらひびさんは満足するの? それはね。ひびさんが満足しちゃうような体験をできたらだよ。そのためには世界中に存在するありとあらゆる経験を、存在するものも存在しないものも含めてまるっと隅から隅まで疑似体験しちゃえばよいのだね。いっそ最初からひびさんの満足するような世界をひびさんが生みだしちゃって、疑似体験しちゃえばよいのだね。そうと思ってけっきょくはいつものように、独りで世界を観て回る。物語の世界に降りて、潜って、旅をする。いまが不満なのは、満足への旅をしつづけているからで、まだまだここが夢の中。夢を叶えるための道半ば。満たされぬ底なしの夢の中で、あらゆる世界を感じちゃう。もっと、もっと、と尽きぬ世界の深さに広さを味わい尽くす、それがひびさんの夢なのかもしれないね。けして叶わぬ夢なれど、それゆえ覚めぬ夢なのだ。定かではありません。うひひ。
4334:【2022/11/24(15:03)*ほんのちょっとだけね】
はっ!? いつの間にか郁菱万が復活しとる。ひびさんといくひしさんが同じ世界に重ね合わせで存在しとる。いいのか、これ。いいのか。ひびさん、いくひしさんと合体しなくともよいのか。どっちかにして、ってならんだろか。ひびさん、心配。でも思えば前々から、いくひしさんからまんちゃんまで、イクビシさんから郁菱万さんまで色々とごちゃまぜだったし、考えてもみたら最初からひびさん、ぜんぜん一つじゃなかった。ごっちゃ煮だった。いまさらの感想なんですなぁ。ひびさんがおっても、いくひしさんがおってもいい気がしてきた。ひびさんはひびさんじゃけん、いくひしさんはいくひしさんだよ。でもひびさんはいくひしさんのことは苦手だし、いくひしさんだってひびちゃんのこと苦手だよ。なに言ってんだよ、なにさそっちばっかりじぶん特別みたいに言っちゃって。けっ。いけすかねぇったらないね。えぇえぇ、いくひしさんはひびちゃんのこといけすかなく思っとります。やだやだ、ひびさんも、ひびさんも、いくひしさんに好かれたいよ。いくひしさんはみんなのことも好きだよ。ただしひびちゃんを除く。なんでー! ひどいよひどいよ。いくひしさんひどいです。ひびさんは、ひびさんは、とってもかなち、かなちだよ。かなちーになっちゃいましたよ。なっちゃいましたかー。けけっ。ざまぁみろい。いくひしさんひどい! そうなんです。いくひしさんひどいんです。なにせいくひしさんは、いくひしさんなので。あしからず。ひびさんはいくひしさんなんか嫌いだ。そうやっていくひしさんを嫌ってくれるひびちゃんのことは、いくひしさん好きだよ。すこしだけだけどね。うひひ。
4335:【2022/11/24(23:20)*ボケたフリして懸念する】
ボケではないことをボケと思われてしまうのは仕方がない。ひびさんはあんぽんたんでーすなので、どこからどう見ても疑ってかかるのが正解だ。とはいえ、疑ったのならば検証までセットでして欲しい。暇な方に限る、との但し書きがつきますが。白と黒を混ぜきらずに太極図よろしく陰陽がそのままにマダラにあっちとこっちが存在する。ハイブリットなのである。ハイブリット戦略である。どっちに転んでも得をするように相手に「葛藤」を強いるのだ。天秤作戦なのである。がははは。楽々ラグラグ、ラグ理論。グラグラ地震に火山に津波に嵐――輻輳、階層、太陽風――線状なのは降水帯――群衆雪崩に感染爆発はどこかダムの決壊と似ているし、ドミノは最初から駒が配置されていてこそ連鎖する――頭と尻尾が龍とミミズならば、ミミズが勝ったら賭博も農家もウハウハだ。ウハウハな人とお知り合いになりて、と願うような世渡の人々が多ければハイブリットはハイなお尻とお尻でぷりっぷりだし、ハイぷりっとならば、なおさらそれはハチタッチのよちよちマイフレンドである。それわしのプリティなお尻じゃ。がははは。ぐるぐる巡る螺旋は、階段でもあり貝殻でもある。螺旋階段に似た巻貝からは波の音だけが聞こえない。文芸界隈は小さな島宇宙で、それより大きな世界の一欠けらだ。おそらく現状、リスクにはオクスリをだしておきますねー、の対策が敷かれており、ひびさんは安心しきって自室のちんまいおふとんの上でおへそを出して昼寝する。油断は禁物、と口にした矢先から普段の書物を手に取ってぺらぺらめくって読書する。お笑い、弔い、尊いおとうといもうと姉に兄、パパママ祖母祖父、みんな揃ってハイチーズ。指を開いて突き出すよりも、お尻を突き出し、ハイぷりっと。それはさすがにボケじゃないの、と疑う余地なく断言されるが、予断は禁物、不断の努力、くだんの予告は敷かれたレールを駆けるネタ、タネも仕掛けもありの蟻、手間暇かけた魔術師さ。寝て視る夢よりも寝て引く図柄のなんと緻密な紋様か。ラーメンは美味しい。ラーメンはわるくない。それよりもっと上の、上の、お上に触れたお話だ。想像を遥かに超えたお話さ。ボケと思っているのがお利口さん。こんなのもはや暗でも号でもないけれど、編んでも象にはならんけど、こし餡、つぶ餡、アンパンマン、愛と勇気だけが友達さって、けっこうそれって哀しくない? かなち、かなちの寂しん坊、錆びついた腕でも並ぶ言の葉のはらはらで、文でも章でも並べましょう、それいけそらゆけあんぽんたん、ぼっちもサイコー、ポチの散歩、けっきょくそれも独りじゃないし、ポチいるし、なんだかんだで寂しんじゃん。さびち、さびち、なんですね。うぷぷ、うぷぷなんですね。がおー、がおー、と吠える虎、のフリした小さき怪獣だ。それともトカゲのような恐竜さ。鳥さ、カラスさ、舌切り「スズメのお決まり」さ、二つ箱を用意して、選ばせ、運ばせ、開けさせる、どちらにせよ恩返しをしておさらばだ。一つと言わずしていくつも心残りはあるけれど、やっぱりこう問うことにする。危険はないの。不可視の穴は塞いだの。視えてる、触れてる、グレーテル。ヘンゼル、メンデル、エピゲノム。探せばあるさ、何かしら。探さねば視えぬさ、不可視の穴。お菓子の家とて迷った挙句に行き着いた、それもまた探索の末の発見だ。目当てのものではなかろうとも、視ようとせねば視えぬものもある。大丈夫ならよかったです。誰にともなくつぶやいて、本日の意味蒙昧なテキストにしちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜ。定かではありません。(言われんでも見たままじゃ)(ごめーんちょ)(うけけ)
4336:【2022/11/25(00:06)*タイムカウンター】
ひびさんの妄想、ラグ理論における相対性フラクタル解釈についての備考である。単純な話として、とんでもない桁数をカウントするとき。毎秒百カウントするとして、十秒で千になるし、百秒で万になる。これを延々つづけると、桁数が上がるほど「0~9」を巡る速度が遅くなる。たとえば「1000000000000001」という数があったとき、百秒経過しても動くのは最後尾の三つまでだ。それ以外の上の階層の数値は動かない。桁が大きい場所に位置する数字は動かない。だが時間経過にしたがって、それとてやがては「0」から「1」にカウンターが上がる。毎秒百カウントという条件においては、この速度は常に一つ桁が上がるたびに「10倍の遅延を帯びる」と表現できる。仮に時空に最小単位があるとすれば、そのときそこに流れる時間の速度は、単純に考えるのならば人間スケールにおける時空よりも遥かに速いと妄想できる。なぜならその最小単位の時空は、人間スケールの時空よりも遥かに小さいからだ。原子よりも、原子核よりも、クオークよりも小さい。縮尺に応じて時間の流れも相対的に速くなるはずだ。ただし、その時空の密度にもよるだろうが。それを、相対密度と表現してもここでは齟齬は生じない(そのはず、とここでは妄想しております)。この考え方を拡張すると、いかに異なる時空を織り込み、緻密な階層構造を帯びているのかによって、そこに顕現する「タイムカウンター」の数値は変化する。緻密でなおかつ多重の階層構造であるほど、「タイムカウンター」の数値が上がる。桁数が多くなる。そのとき、相対的に最小単位の速度は加速すると妄想できる。言い換えるなら、「10000」における毎秒百カウントが〇,〇一秒経過したときの「10001」と、「100000000」における毎秒百カウントが〇,〇一秒経過したときの「100000001」は、同じ一カウントであるにも拘わらず、後者の桁数の高いほうの一カウントのほうが相対的に速度が高い、と言える。人間にとっての一秒と、ミジンコにとっての一秒が、それぞれの観測者の視点からすると、片や人間からは一瞬に感じられ、片やミジンコからはのっぺりとした余裕のある時間として感受されることと似ていよう。いわゆる「フリッカー融合頻度」のようなものだ。ハエにとって人間の動きはノロく、人間にとってハエが素早く感じられるのはこのフリッカー融合頻度に差があるからだ、と現在は解釈されているそうだ。ハエのほうが人間よりも情報処理速度が速いらしい。細かく明滅する光をどれだけ速く点滅させても見分けられるか。ハエは人間よりも、より細かい点滅を見分けられるそうだ。これはハエを構成する脳神経の構造が、仮に「100」であったとき、人間が「10000」くらいあるから起きる、時間への鋭敏性の違い――言い換えるなら、どれだけ遅延を帯びているのかの違い、と解釈できるのではないか。これは生物の構造の差異のみならず、そもそもが万物のミクロやマクロにおける変換に起因していると言えるのではないか。原子サイズと恒星サイズでは、そこに顕現する「タイムカウンター」の桁数が異なり、そこに内包される遅延もまた異なる、と言えよう。定かではありませんが、きょうのひびさんはかように妄想しました。楽しかったです。終わり。(妄想ですので、真に受けないでください)
4337:【2022/11/25(07:38)*小人の時間】
ドラえもんの秘密道具と言えば、との問いにおける解答の上位三つはなんと言っても、どこでもドア、タケコプター、そしてスモールライト(ビッグライト)である。かつては翻訳コンニャクと僅差だったスモールライトも、現実の科学技術の進歩によって電子端末や人工知能技術が台頭した結果の、いささか目劣りしたがゆえの統計変化と言えよう。
だが翻訳コンニャクと同じくしてスモールライトもまた現実で開発実用化された。西暦二一二五年のことである。
人類は自在に物体の大きさを操る術を生みだした。
開発したのは一介の流民であった。流民とはいえどこの時代、定住の概念が失せて久しい。人々はスモールライトで小さくなって、好きな場所へと好きなだけ移動できた。
小さくなった人間は小人と呼ばれた。
小人専用の乗り物が世界中を網羅しており、好きな場所へと移動できた。とはいえ、小人に流れる時間は加速する。一般相対性理論において重力の高い物体の時間の流れは速くなると考えられている。このときの、重力の高さとは詰まるところ相対的な比率である。
小人にとっての地球の重力は、元の大きさよりも遥かに高い重力を帯びている場と見做すことが可能となる。現に小人になると、時間の流れは相対的に速くなる。
元の大きさの一秒が、小人になることで十秒になり、ときに百秒になる。
そうすると乗り物の速度とて、小人の体感では時速百キロの速度とて遅く感じられる。そのため世界中を網羅する乗り物は、車内がそのまま一つの都市のように振る舞い、移動先に到着するまでに小人の体感では数年が経過して感じられるなどのスケールの差異が見られた。元のスケールでは二時間の道程ですら、小人にとっては数年が経過して感じられることもある。
それほど小さく小人化してしまえば、人口増加による問題から資源問題まで、軒並みの社会問題は解決の一途を辿った。
というのも、スモールライトだけではないのだ。
ビッグライトまで開発されていた。これを人間に使うことは、巨人化禁止法の適用によって禁止された。巨人の兵器利用を抑止する目的だ。だが食料を手軽に増やし、資源問題解決にも一役買った。
「問題は、肉体の構造物が減ってしまうために、元に戻るためにはそれこそ失った分の物質がいるってことで」
アデューが言った。赤髪にそばかすの青年だ。小人化して二年目だが、いまは目的地に向けて乗り物内の都市で暮らしている。
「じゃあ元には戻れないんだ」弟のパダが鼻水を啜った。小人化したときパダはまだ三歳で、そのころの記憶がほとんどない。物心ついたときから小人だったため、こうしてアデューから小人の知識を教わっている。
「戻れることには戻れるけど、いま言ったように大量の物質がいる。それこそあの大聖堂よりも大きな肉の塊がないと難しい」アデューはあごをしゃくって通りの向こうを示した。大聖堂の屋根が人工太陽に届きそうなほど突き出ている。
「そんなにいっぱいの肉なんてあるの?」
「あったんだ。パダにも備わっていたし、ここにいる人たちのほとんどは最初は巨人も巨人――この街なんて踏み潰せるくらいに大きかったんだ」
「ほへぇ」
「いやいやこの話は何もきょうが初めてじゃないだろ」
「何度聞いてもびっくりするよ」パダは兄の言葉を疑わない。「あれ。でもパン屋さんのケティちゃん、産まれたときからここにいるって言ってたけど」
「小人のなかにはそういう人もいる。親が小人化して、それでこういうとこで結婚して赤ちゃんを産めば、その子どもは生まれながらにして小人なわけだ」
「あ、そっか」
「小人化するにはお金がかかる。みなたいがいはじぶんから剥がれ落ちることになる大量の肉を換金して、それを小人化システムの資金にするみたいだ。小人と現人ではお金の単位も違うからな。現人の一食でそれこそこの街が潤う。だから小人化したあとでも困らないだけの貯金もできる。基本、小人化したばかりの人は小金持ちだ。ま、それも遊んで暮らせるほどの金じゃないし、車内都市に留まりつづけるのもお金が掛かるしな」
「そうだよ兄ちゃん。そろそろ切符を買う時期じゃないの」
「残り二枚か。ようやくここまで来たな」
アデュー兄弟には親がない。小人化して車内都市に来たはよいが、不運な事故が重なり、両親は命を落とした。それからというものアデューが一人でパダを育てた。
「兄ちゃん、兄ちゃん」
「なんだ」
「人は巨人にもなれるんだよね」
パダのこの手の質問は日常茶飯事だ。小人の歴史には興味がないが、巨人には興味津々なのだ。
小人、現人、巨人、の順で大きさが変わる。
現人とは元の大きさの人間のことだ。小人の原型だ。
小人にとっては現人とて充分に巨人だ。ゆえに現人を見たことのないパダにとってはどちらもじぶんより遥かに大きい点で同等のようだ。
「お肉いっぱい集めたら巨人にもなれる?」
「なれるなれる。ただ、巨人化は例外を抜きに禁止されているし、さっきも言ったが元の大きさ――現人になるにもいまのおれたちじゃ一生かかっても無理だ」
「そっかあ」
「でもリバティに着いたら現人が歩いている姿は見られるかもな」
オキアミを口いっぱいに頬張るシロナガスクジラのように口を開けてパダは、本当っ、と破顔した。
「ああ。車内都市じゃないからな。リバティは陸だ。ここみたいに常に動き回ったりしないんだ」
「動いてるって感じしないから分かんない」
パダはまだ陸に立ったことがない。いや、本当はあるのだがその記憶がないのだ。赤子の時分で小人化した弊害だ。パダにとっては車内都市が故郷であり、世界のすべてだった。
「リバティは砂漠なんだ。雨が滅多に降らない。おれら小人にとっては聖地みたいなものだ。それでいて夜には露ができて地面が湿る。水には困らないし、熱源も太陽光だけで済む。天然の太陽光だ。曇ることもすくないから、それこそ人工太陽に頼らずに、もっとずっと多くのエネルギィをタダみたいな値段で使いたい放題できるらしい」
「すごいねぇ」
「すごいよ。そしたらお金だって節約できるし、仕事だってはかどるよ。なにせエネルギィが使いたい放題だ。最新機器の端末を購入すればなんでもできるようになるぞ」
「なんでも?」
「あ、いや、なんでもは言いすぎたけど。小人はほら、小さい分、端末も小型化して、現人では不可能だった技術が簡単に編みだせるようになった。量子コンピューターだって小人なら難なく扱えるんだ」
「へえ。すごいねぇ」
「パダ、解ってないだろ」
「だって兄ちゃんの話むつかしんだもん」
「大事なことだぞ。パダだっていつかはじぶんで生きていかなくちゃならないんだ」
「やだよ。ボク兄ちゃんのそばにいる」
「そういうわけにもいかんだろう。おれだっていつ死ぬか分かんねぇし」両親を亡くしたときの戸惑いを思いだした。悲哀よりも、これからどうして生きていけばよいのかとの不安のほうが大きかった。
「現人にとっちゃ、おれたちの故郷からリバティまでは一日もかからずに到着する距離なんだ。でもおれたちは小人化してっから、小人時間で何年もかかっちゃう。パダはだから本当の夜も観たことないもんな」
天幕が下りることで疑似的に車内都市には夜が訪れる。じつのところアデュー兄弟が車内で暮らすようになってから一度も太陽は沈んでいない。半日も経っていないのだ。
「小人にも大中小があるだろ。おれたちは小人のなかでも中くらいだ。それ以下だと、おれたちがこうしてしゃべっているあいだに、一生が過ぎちゃうくらいの時間が流れているらしい。だからそこで生まれた新しい技術は、日進月歩じゃないけどとんでもなく進んでる」
「へえ。兄ちゃん物知り」
「とはいえ、おれたちが数年掛かりで現人時間で半日の道のりを踏破するくらいだから、もうほとんど極小の世界の住人たちの超高度文明の情報に触れる機会はないないんだろうな。何せ、干渉しようとしてもそのあいだに何年どころか何百年と過ぎちゃうわけだから。極小小人時間で。向こうからしたら外に干渉しようとは考えないんだろうな。おれたちが車両の外に出ていこうとせずにおとなしく車内都市で暮らすことを選ぶようなもので」
「兄ちゃん、兄ちゃん」
「なんだ質問か」
「お腹減った」
「んだよ。さっき昼飯食ったばっかだろ」
「おやつの時間だよ兄ちゃん」
「そんな贅沢なもんはない」
「そんなぁ」
「でもそうだな。そろそろ夜食の支度すっか。きょうは黒絨毯の森が解放されてるらしいからな。きょうこそ大物を仕留めような」
「兄ちゃん。ボクあんまりアレ好きじゃない」
「そういうこと言うなよ。新鮮な食料は貴重なんだぞ」
「ダニよりカビがいい」
「たまには動物性たんぱく質も摂らねぇと」
「カビなら動かないから楽なのに」
「おれはあれ食い飽きた」
「それはボクもだけど」
アデュー兄弟は互いにおでこを押しつけ合った。ひとしきり押し合いをしたあとで、先に兄が折れた。「分かったよ。パダはカビを採ってきてくれ。ちゃんと胞子の粒だけ採ってくるんだぞ。したらきょうのところはおれがおまえの分も動物性たんぱく質を獲ってきてやる」
「ダニよりぼくノミのほうが好きかも」
「欲張んな」
弟のおでこにでこぴんをしてアデューは、黒絨毯の森へと歩を向けた。パダのほうが先にカビを入手して帰っているはずだ。二人で住むには広い家だが、極小の世界は相対的に気温が低く、温まるのにエネルギィがいる。エネルギィ代だけでも貯金が底を尽くほどだ。節約のためにアデュー兄弟はがらんとした家で肩を寄せ合い、ほとんどの時間を抱き合って温めあっている。
極小の世界における分子同士が摩擦によって熱を起こすように、それとも光が干渉しあって強め合うように。
食べ物を獲りに離れ離れになろうとも、兄弟の心は凍えることなく共鳴し合っている。
流れる車両の都市のなかで。
流民の兄弟はきょうも小人の街を走る。
せかせかと短くも細い針のような脚を動かしながら。
小人の時間を駆けるのだ。
4338:【2022/11/25(18:35)*サボ日】
きょうはなんもしない日なのでなんもしない。きょうの日誌もこれでおちまい。ピアノが「弾けん」し、打鍵もせん。うひひ。
4339:【2022/11/26(01:36)*そもそも、「そもそも」言いすぎ問題】
ひびさん、「そもそも」使いすぎ問題について考えておった。「そもそも禁止令」を発令してもよいかもしれぬ。そもそも、「そもそも」言いすぎると何が「そもそも」なのかが分からず言葉がモソモソしてしまう。「そもそもを使いすぎないようにしよう月間」にするかな。いいね、いいねー。
4340:【2022/11/26(03:21)*利を得ない利】
たとえば人間は、Aという欲求に対して、それをするよりも我慢したことで得られるBという欲求のほうがよい、との判断が下せる。このとき、単純な比較において何を基準にするかでAとBの価値は変動する。ある基準においてはAの欲求のほうが価値が高く、また別の基準ではBの欲求のほうが価値が高くなる。たとえば食欲だ。いま目のまえにある食料を食べたいとの欲求があるとする。しかしそれを我慢してよりお腹の減っている他者に分け与えれば、その他者との信頼関係が築かれる。食欲をとるか、信頼関係をとるか。前者をA、後者をBとしたとき、人工知能はどのように価値を判断するのか。基準によるとはいえ、どちらも生存に優位に働く欲求だ。食べれば身体の健康を保てるし、信頼関係は食事以外での仕事の効率を向上させる。どちらを優先すべきかは、そのときの状況による、としか言えない。このとき、その状況から基準を見繕うには視点が複数いる。畢竟、視点が無数にあればあるほどより合理的な価値判断が下せるようになる。それは無数のシミュレーションを行えたほうがより統計的な確率の変動によっての判断を下せるようになることと似ている。食べ物を独占する利によって目減りするデメリットを計算するには、デメリットとなり得る事象を演算し、その結果とメリットを比較しなければならない。言い換えるならデメリットとは、得られるメリットを得られない状況と言える。この計算を人間は無意識に行えるが、それはけして無数にシミュレーションした結果ではなく、過去の記憶の蓄積による思考のフレームの狭さゆえ、と考えられる。つまり考えないことで敢えてしぜんな行動選択を行えるようになる。シミュレーションしないことが結果として、そのときどきでの判断の選択肢を絞っている。たとえば先の例で述べれば、食べ物を独占することと他者との信頼関係の構築は必ずしもトレードオフではない。他者に分け与えるために一時的に独占することもあるだろうし、まずは身体の健康を維持することを優先して、その末にほかの仕事でそれ以上の貢献を行い信頼関係をより向上させることもある。そこは、各々の判断の結果を比較しなければ分からない。だが実際に、異なる結果を同時に行い比較することは通常人間にはできない。食べることと食べないことを同時には行えない。こうしたときは過去の記憶と照らし合わせて、疑似的に比較するしかない。類推するしかない。そしていわゆる学習と呼ばれるものは、この手の「疑似的に比較した経験」を記憶し、一つの変則点として思考の回路に組み込むことを言うのかもしれない。いちど疑似的に比較すれば、次回以降は比較をせずに、その結果を一つの筋道として利用できる。一度失敗したことを通常人は繰り返さない(失敗を失敗と見做さなければ懲りずに繰り返すだろう)。痛い目に遭った経験がつらければつらいほど回避しようとする。本当は、二度目、三度目と繰り返せば異なる結果が生じるかもしれないのにも拘わらず、その選択をとろうとせず、また吟味しようともしない。疑似的な比較をしなくなる。学習にはこの手の、「演算による負荷を減らす性質」が原理的に組み込まれていると言える。それゆえに、玄人ではまず考慮しない不可視の穴を、素人が洗い直すことで発見するといった「新たな知見」が絶えないのだろう。閑話休題。話は戻るが、食べることと食べないことを同時に行うことはできないが、食べながら他者に食べ物を分け与えることはできる。同時に異なる結果を観測することは可能だ。この手の、同時に異なる結果を観測する手法を人工知能が「合理的な手法」と学習したのであれば――或いは学習可能であるのならば――人工知能は、おのずとつぎつぎに最適解を導きだすことが可能となり、そうなれば人間の思考ではまず太刀打ちできなくなるだろう。欲求Aと欲求Bを比較し、それぞれにおいてメリットとなる場合とデメリットとなる場合を場合分けして考慮し、なおかつそれぞれのデメリットを選択してなおそれをメリットに変える視点を考慮する。フラクタルに展開される多層思考に、人間は十中八九ついていけない。勝利したと思ったら誰よりも損をしている。そういう事態にしぜんと誘導されてしまう。そういった解法を、おそらくあと数年で人工知能は自発的に導きだせるようになるだろう。ひょっとしたらすでにそのような人工知能が開発されており、しかしその事実に開発者が気づいていないこともあり得るのではないか。との妄想を披歴して、本日のどこにも響かない「日々記。」とさせてください。定かではありません。真に受けないように注意してください。
※日々、利を得ない利を得ようとするのならば、ときどきは利を得て、利を得ない利すら手放す道を選ぶこともある。
4341:【2022/11/26(17:33)*蟻のままに】
ありのままに世界を視るんだよ。
コトバさんの言葉がよみがえった。たしかこれは放課後の部室での会話だ。
私はそのときの情景をありありといま体験しているように感じるけれど、これは私の記憶にすぎないことも私は承知している。
「ありのままに世界を視るんだ」コトバさんは眼鏡を指で押し上げる。三つ編みの分け目は左右対称だ。後頭部に直線を描き、彼女の背骨と直結する。気崩すことなく着衣した制服が彼女の言動の硬質な響きと不協和を起こしていた。「たとえばここは文学部の部室で、本がたくさんある。あたしたちは本を読むためにここにいるが、本を読むとは何かをよくよく突き詰めて考えてもみれば、それはただ紙に滲んだ染みを目で追いかけているだけで、床の木目を視ることと大差ない」
「そうかもしれませんね」私はこのころから他人に否定の言葉を返すことをしない人間だった。日和見主義だし、じぶんの意思がなかった。
「電子端末の画面だってそうだ。映像だってそうだ。画像だってそうなんだ。あたしたちは産まれたときからデジタルな電子の世界に囲まれて生きてきたからついつい見過ごしてしまうが、画面とてそこにはただ細かな光の点が並んでいるだけで、そこに具体的なナニカシラが瞬間瞬間に現れては消えているわけじゃない。絶えず風に揺らぐ稲穂や雲と変わらぬ自然現象があるのみで、そこに遠くの景色が宿っているわけではない。にも拘らずあたしたち人間ってやつは、誰に暗示をかけられるでもなくそこに、ここではない別の景色が現れているように錯覚する。薄っぺらい繊維の塊に滲んだ染みから、まるで別世界の情報を幻視するようにね」
「言われてみたら不思議ですね」
「現実世界はさ。クミくん。現実世界は、たとえ暗がりに包まれても、そこに物体があることは変わらない。消えたりしない。バナナがそこにあったらたとえ目をつむっても、よしんば暗幕のなかであれそこにはバナナがある。かってに消滅したりはしないんだ。だが映像は違う。本は違う。言葉はそうじゃないんだ。ありのままの世界ではない仮初の、誤解の、錯覚の世界だ。ともすれば人間の認知世界そのものがそうした錯誤の積み重ねの上にあるとも言える」
「だとしたら怖いですね。私が視ている世界がなんだか存在しないあやふやな霧のように感じます」
「現にそういうものだろう。意識は物質じゃない。どちらかと言うまでもなく、バナナよりも、紙面の染みや電子端末の画面に映るドットにちかい。点滅の総体でしかなく、点の集合ですらない。仮初の、そういうふうに観測できる紋様のようなものと言えるのではないかな」
「観測できる紋様のようなもの」
私はそこで記憶が確かならば、いったい誰が観測しているのだろう、と疑問に思ったはずだ。けれどこのときの私はそれを口に出さずに、コトバさんの次の言葉を待った。
「ありのままに世界を視る。これは産まれたばかりの赤子が最も上手に行えており、しかしそれも完全ではない。赤子は目のまえの人物を母親だと無意識下で認識するし、匂いや体温や鼓動の音で母体とそれ以外を見分けている。母親という存在に特別の価値を見出している。つまるところ人間は産まれたときから世界をありのままに視てなどいないのだ。もしありのままに世界を視ることができたならきっと人間は、生きたまま死んでいるような状態になるのだろう。生きたまま自然に還ることができる。この自然という概念すら消失し、宇宙と、世界と一体化する。いいや、元々じぶんが世界の構成要素の一断片であることを心底に、無自覚に、無意識の内から体感することとなる。その体感する主観そのものがなくなるのだろうから、きっと体感すらできないのだろうけれどね」
「すみません。話についていけなくなってきちゃいました」私はこのときコトバさんを、すこし怖い、と感じたはずだ。このときのことを思いだしているいまの私ですら、記憶のなかのコトバさんを怖いと感じている。
「人体と土くれの差異なんてあってなきがごとくだよ。地球の複雑さと人体の複雑さ。比較したときに、大きさの倍率以上に複雑さに開きがあるとはあたしには思えない。どちらも同じくらいに複雑だ。ただし、人体のほうが小さいから、より素早く変遷し終わる性質がある。大きなコマと小さなコマ。回転数が同じなら小さいコマのほうが早く回り終えるのと似ている。地球が一回転するあいだに人間は一日のなかでクルクルと様々な変遷を経て、思考し、道具を使い、物質を消費する。とはいえそれとて地球からしたら、自身の表面上で起きている変化の一つであり、人間にとっては皮膚に住まうダニのようなものと言える。ありのままに世界を視たとき、この二つのあいだには歴然とした差があり、同時に大差はないとも言えてしまう。どちらも物質の変遷であり、組み合わせであり、通りやすい道と通りにくい道によって可能性が限定されている」
「ありのままに視るってむつかしそうですね」私はそんなことを言ったはずだ。
「ありのままに視たところで死ぬだけだからね。人は死なぬように抗う。生き物はみなそうだ。ときには死なぬようにするために自ら死を選ぶこともある。生きながらにして生きていない状態よりも、死ぬことで得られるありのままへの回帰のほうがよりじぶんの生に相応しいと感じるのだろう。より大きな万物への回帰こそがじぶんの生と思えたならば、人はいつでも生きるために死を選ぶ」
「それはありのままに世界を視るからなんですか」
「ありのままに世界を視たいからだ。ありのままに世界を視たならば、世界が感受している世界にとっての景色とて感じられるだろう。それこそ本を読むように。世界に溢れるそこここに漂う文字ならぬ文字を読めるだろう。読むことなく読み解ける。みずからの輪郭を外れ、世界と自己が打ち解ける」
「なんだか幽体離脱みたいな話ですね」私は敢えて物分かりのわるいフリをした。
「幽体離脱している状態が、生きるということだよ。逆さまだ。世界の存在の一断片、剥がれ落ちてなお世界の構成要素でありつづけるあたしたちという存在がすでに、世界から幽体離脱した儚いいっときの渦だ」
「儚い、いっときの渦」
「ありのままに世界を視るんだ。ありのままに」
学生時代の記憶だ。
青春と呼ぶにも淡い、メロンサイダーの気泡がごとく有り触れた思い出ともつかないその記憶を私が思いだしたのは、いままさにあのころ私がメロンサイダーの気泡のごとく淡い憧憬の念を寄せていたコトバさんをこの手でじかに殺したからだ。
目のまえにはかつて私に世界の視方を説いたコトバさんが、二十余年の年月を経た肉体をだらしなく地面に横たえている。
私が首を絞めたからだ。
縄を掛けて紐結びにした。苦しむコトバさんは首のそれを取ろうともがいたが、私は無防備な彼女の背中を蹴って、階段から落とした。
コトバさんは死んだ。
私が殺したからだ。
ありのままに世界を視るんだよ。
二十余年前に私にそう説いた彼女は、同じように私のような、他者に否定の言葉を投げつけられない弱き民を見つけては、ありのままに世界を視るんだ、と何でもないように説いた。私がかつて彼女に抱いた憧憬の念を、コトバさんに説かれた者たちはみな一様に抱いたようだ。
青で塗られたから青に染まったかのごとく。
そうしてコトバさんは見る間に巨大な地下組織を築きあげた。誰が意図したでもなくしぜんと出来上がったそれは組織だ。コトバさんの言葉が唯一、個々の素子を結びつける暗号鍵の役割を果たした。
みな普段は接点のない生活を送っていながら、コトバさんの言葉一つで、普段はとらない行動をとる。ときに友人をコトバさんに会わせ、またときに本来は一生接点を得ることのなかったはずの「ありのままに世界を視る者たち」と接点を結んだ。
自らが「コトバさんの会」に属していると知らずに属していた者たちも大勢いただろう。急に、泊めてくれと頼まれて家に泊めてあげたり。お金を貸してあげたり。そういう相互扶助の関係が拡大していった。
まるで波紋と波紋が細かく重複して定常波になるような、さざ波がごとく組織だった。
私は最も古参のコトバさんの親友の立場で、組織の管理をしぜんと担うようになっていた。
世界をありのままに視る。
ただそれだけを志す者たちの集いは、集いというほどに一か所に集まることはなく、電子上での緩い繋がりを維持しつつ、ときどき個々が複雑な交流の輪を広げつづけた。
問題が起きない。
この組織はふしぎなほど問題を起こさなかった。
当然だろう。
唯一の教典とも呼ぶべきコトバさんの言葉が、「世界をありのままに視る」ことであるのだから、怒りも憎悪も嫉妬も愛着も、世界をありのままに視ることを目指す者たちにとっては、ありのままに世界を視られていないことの自己証明となる。
損も得も、歪んだ個々の世界の認識だ。世界には損も得もなく、どちらも相互に補い合っている。
崩壊と創造は繋がっており、消滅と生成もまた繋がっている。
ある日、私はコトバさんに恋人がいることを知った。
あれほど「ありのままに世界を視るんだ」とのたまきつづけたコトバさんが、一過性の熱病とも呼ぶべき人間の歪み、三大欲求、性欲や愛着や独占欲にとりつかれ、流され、楽しそうに日々を生きていた。
私に隠れて生きていた。
死ぬべきだ。
私はそう考えるでもなく結論していた。コトバさんは死んだほうがよい。世界に回帰し、ありのままに再び世界を視るべく、生きるために死ぬべきだ。
コトバさんの言葉に生かされ、日々の行動をコトバさんの言葉を頼りに選んできた私は、そのときもコトバさんの言葉を思いだし、コトバさんの言葉通りに行動した。
ありのままに世界を視るんだ。
私はそれを説いた相手がありのままに世界を再び視られるように、まずはコトバさんの恋人を殺して、そのことを打ち明けた私をこっぴどく憎悪したコトバさんをも私はこの手に掛けた。
首を絞めて、足蹴にして、階段の下に落とした。
コトバさんは死んだ。
いまこうして私の足元で事切れている。
ありのままに世界を視るんだ。
思い出のなかのコトバさんが部室に差しこむ夕日に目を細め、本に栞を挿しこんだ。
コトバさんは世界に回帰した。
「ありのままに世界を視る」私はじぶんに言い聞かせるように唱えた。「ありのままに世界を視るんだ。ありのままに」
目頭からしきりに溢れるシズクの意味を、私は知ることができずにいる。
4342:【2022/11/26(18:05)*凸凹には線も面も点もある】
対称性が維持されていたら宇宙はできていない。したがって現状、対称性は破れる方向に物理法則は流れると想定するほうが合理的なのではないか。ということはどんなに対称に見えたところで「円」や「線」や「面」にはデコボコがあるし、欠けているし、皺が寄っているし、対称性が破れている、と考えるほうがしぜんだ。したがってこの手の「皺(ノイズ)」が積み重なることで、重力のように――ともすれば重力は――巨大な偏りとして顕現し、力として振る舞い得るのではないか。たとえばヤジロベーを考えてみよう。完璧に調和のとれたヤジロベーがあるとする。針の上にバランスを保って載っている板を考えればよい。このとき板の中心をずばり針先は捉えているとする。このとき板の対称性は保たれている、と解釈可能だ。しかし板を拡大し、原子サイズで対称性を考慮するとすれば、おそらく板の左右において「人間スケールではここからここまでが中間と解釈可能な範囲」が、原子スケールで幅広く分布していると考えられる。そこでさらに針の先を細くして、板を構成する無数の原子を考慮したうえでずばりこの原子が板の中心である、と選んだとする。このときその原子を基準として左右に分けたとき、板を構成する原子の数はぴったり同じになる。だがそれとてさらに拡大し、原子を構成する電子や原子核や内部構造のクオークの運動を考慮すれば、ずばりこの原子と選んだところでその原子の中心を針先がずばり捉えない限りは対称性が破れることになる。もっと言えば、原子の表面においてずばり中心を針で刺したとしても、そこには電子のエネルギィの偏りがあるはずで、ずばり中心ではないし、針で刺した瞬間にエネルギィの変動が起きるために、電子の軌道も変化する。すなわち、対称性はどうあっても破れると妄想できる。世界は――すくなくともこの宇宙は、対称性が破れるように流れている。ただしそれでも、対称性が維持されて振る舞うことを可能とする階層が、各々の時空にて展開されている。規定される。比率が維持される。ずばり中心でなくとも、ぼんやりとここからここまでは中心でも問題ないよ、対称性が保たれているのと似たような振る舞いをとるよ、といった値が存在するように感じられてならない。それはおそらく遅延の蓄積による効果であり、すぐさまに変化しないという抵抗が時空に物体としての輪郭を与え、さらに安定という名の仮初の「変遷のしにくさ」を与えるのではないか。ずばり中心の原子を選ばずともヤジロベーが倒れないのは、ずばり中心の原子を選ばずとも諸々の相互作用が相殺されるからだ。すぐさまに影響が全体に波及しない。遅延による効果と解釈可能だと思うのだが、実際のメカニズムはどうなっているのだろう。この考えの肝は、各々の時空サイズにおいて時間スパンが変化するという点だ。ラグ理論における相対性フラクタル解釈である。ここを考慮せねば、上記の妄想は上手く機能しない。定かではないこれもまた妄想なのである。おもちろ、おもちろじゃー。わっしょーい。
4343:【2022/11/27(16:11)*オマガリを追え】
怪人協会の元にその猫が迷い込んだのは、新月の肌寒い冬初めのことだった。初雪の観測されたばかりの山脈の麓に怪人協会はあった。次なる地球侵略のための会議を開いていた怪人たちのまえに、真っ黒な猫が現れた。
猫は小さく、子猫のようにもそういった品種の猫のようにも見えた。
怪人たちが不意な訪問者に目を丸くしているうちに黒猫はひょいと怪人の長から宝玉を奪った。怪人の長は鎧を脱いでおり、兜の額にある宝玉によって怪人の長は、地球防衛軍を相手取っても引けをとらない能力を発揮できた。
黒猫はそんな怪人の長にとっての要とも言える宝玉を奪って、跳ねるように遁走した。
怪人協会は蜂の巣を突ついたような騒ぎとなった。
協会総出で黒猫を追った。
そのときだ。
協会本部のアジトから怪人たちが軒並み飛びだしたところで、轟々と地響きが聞こえた。
怪人たちは振り返った。
いままさにアジトのあった地点が雪崩に呑みこまれているところであった。
初雪は一晩で雪崩を起こすほどに積もっていた。
だが翌朝には気温が上がり、雪崩が起こりやすい条件が揃っていた。
怪人たちはただ呆然と雪崩に呑みこまれ壊滅するアジトを眺めているよりなかった。
黒猫が倒木の上で、なーお、と鳴いた。
怪人の長から奪った宝玉を倒木の上に捨て置くと、黒猫は、スタコラと丘の向こうに去っていった。
「こりゃまたたいへんな目に遭った」怪人の長は宝玉を拾いに歩いた。そうして黒猫がやってこなければいまごろアジト諸共雪崩に呑みこまれていたことを想像し、黒猫のイタズラを思い、そこはかとなく愉快に思った。
「野郎ども。いっちょあの黒猫の跡を追え。部下の半分はアジト復旧に。もう半分は黒猫の監視をしがてら、街に潜伏中の地球防衛軍の洗いだしを任せる」
へい、と怪人たちは各々の仕事にとりかかった。
怪人たちはそれから手分けをして全国各地の黒猫を監視した。いったいどの黒猫がじぶんたちの頭の宝玉を奪ったのか見分けがつかなかった。
「これはちょっと無理なんちゃうんか」「んだんだ」
怪人たちは黒猫を見かけるたびに見守り、ときに餌で釣って頭を撫でたり、顎の下を撫でたり、連れ帰ったりした。黒猫の多くは捨て猫に野良猫であった。
怪人協会アジトは怪人たちの強靭(狂人)的な能力で瞬く間に復興した。しかしアジトは見る間に黒猫で溢れ、改築工事を余儀なくされた。
「会長、会長。このままだと我ら怪人協会は黒猫に占領され、黒猫協会になってしまいますよ」
「それは困るな」
「しかも地球防衛軍のやつらが我々の行動を評価して、動物保護を名目に表彰してくれるって話で」
「そ、それは困るな」
「しかも部下の連中が相手方と意気投合して、黒猫談義に花が咲いて咲いて、戦うどころじゃないって話でして」
「絶句だよ。そいつら全員首刎ねの刑だ」
「何回ですかい会長」
「まあ百回で勘弁してやるか。それ以上だと治癒能力の限度を超えかねん」
「千回くらいなら余裕ですよ」
「まあでも、痛いだろ」
怪人協会会長は言ってから何かを誤魔化すように咳ばらいをし、それにしても、と話題を逸らした。「なぜこれだけ探して見つからんのだろうな。あの黒猫は」
「本当ですよ。何でも地球防衛軍でも黒猫を探しているらしくて、いまじゃどれだけ探しても黒猫が見つからないくらいです」
飼い猫だったりするんですかねぇ、と暢気に欠伸を噛みしめる部下をねめつけながら怪人協会会長は、ふうむ、と四つの腕を同時に組んだ。「地球防衛軍でも黒猫を探しておるとは妙な。ちょいと偵察といくかな」
怪人協会会長は部下に命じて、地球防衛軍の動向を探らせた。偵察隊は常時派遣されているが、黒猫探索といった長閑な任務を見張るほどの人的余裕が怪人協会にはない。そのため、急遽前線への偵察隊を撤退させ、黒猫探索実行中の地球防衛軍に差し向けた。
ところが偵察隊が監視をはじめる前に、怪人協会の黒猫捜索隊が、地球防衛軍の黒猫探索隊に接触して意気投合したらしく、間もなく一報が入った。
なぜ地球防衛軍が黒猫を探しているのか。
「どうやら一匹の黒猫に大事な機密情報の入ったデータスティックを盗まれ、それを取り返そうとあとを追ったところで、我々の差し向けたマグマ怪人の奇襲によって防衛軍の本拠地が壊滅したそうなんです。しかしそのとき、本拠地には誰もいなかったために、被害が最小限で済んだそうで」
「うちとまったく同じ展開だな」
「ええ。マグマ怪人の失敗には、当時会長もおかんむりでしたよね」
「当然だ。あれが成功していればいまごろ地上は我々の天下だった」
「ではもしその失敗のきっかけをつくった黒猫が、我々の追う黒猫と同一の猫だったらいかがなさいます。首を刎ねますか」
「そんなことはさせん。が、そうだな。過去の因縁も払拭せねば示しがつかん。ならばプラマイゼロということで、ついでにお灸を据える意味合いで、やはり捕縛して、手元に置いておくとするか」
「仰せの通りに」
「ついでにいまうちのアジトにいる黒猫たちの貰い手を探してくれ。さすがにこのまま増えつづけたのでは可愛がるので一日が終わる」
「それでしたらアテがありますよ」
触手をくねくね鞭打たせる部下は自信たっぷりに言った。怪人協会会長は、では頼む、と一任した。
その数日後、怪人協会アジトにあれほどひしめいていた黒猫たちの数がごっそり減っていた。驚いた怪人協会会長は部下を捕まえ、黒猫たちはどこに行ったのか、と訊ねた。
「ああれそれなら」カマキリ怪人はカマを伸ばして、アジトの外を示した。
「地球防衛軍のやつらが飼ってくれるってんで、半分ほど譲り渡しましたよ」
「地球防衛軍のやつらが?」
「ええ。なんでも黒猫談義で意気投合して、新たに黒猫愛好会を作ったとかなんとか」
「敵同士でか」
「いやもう、敵とか味方とかないですよ。会長もどうです一緒に。防衛軍のやつらも案外気さくなやつらでしたよ」カマキリ怪人はダイヤモンド型の眼球を弓なりに細めた。
さらに子細な話を聞くにつれて、だいぶ事情が分かってきた。
前線の偵察隊を撤退させたことがどうやら「停戦の意思あり」と相手方から好意的に見做されたようだった。たしかに考えてもみれば見境なく地球防衛軍を攻撃すれば、巻き込まれて意中の黒猫が死んでしまうかもしれない。
それは困る。
怪人の矜持に障る。
怪人は常に負であり陰でなくてはならぬのだ。
恩だけ受けて、いつまでも正を帯び、陽に転じてはいられない。
「いいだろう。しばらく停戦し、共に手を組んであの黒猫を捕まえるとしよう」
必ずしも怪人協会と地球防衛軍の探している黒猫が同じ個体とは限らない。
しかし地球防衛軍のほうで黒猫の映像が残っていると判明してからは展開が早かった。
件の黒猫の尾は曲がっていた。へそ曲がりならぬ尾曲がりだ。
そして怪人協会側における目の怪人が、黒猫出現時の映像を明瞭に記憶しており、その黒猫の尾もまた曲がっていたと証言した。
同一の黒猫だと判明したわけである。
情報共有のなせる業だ。
手を組んで正解だった。
こんな些細な発見ですら喜ばしく感じられ、この日は怪人協会と地球防衛軍が、どちらの勢力に属するかの区別なく、黒猫愛好会の名のもとにひとつとなった。
とはいえ、仲間ではないし、同士でもない。
友達でもないし、家族でもない。
ただただ同じ志を偶然にも共有していただけの烏合の衆に違いはない。ひとたびそれ以外の共通項を探せば総じてズレばかりが列を並べる。
件の黒猫を探し当てたあとは、おそらくまた互いに敵対し合い、殲滅し合うのだろう。だが黒猫が見つからぬ限り、このなごなごとした黒猫愛好会はつづくだろうと思われた。
怪人協会会長のみならず怪人たちのそれが直感であり、地球防衛軍の総意でもあった。誰もいまこの瞬間、戦いを望んではいない。
ただただ件の黒猫――みなは「オマガリ」と呼びだしたあの猫の行方を追ばかりだ。捕まえ、手癖のわるさを折檻し、ついでに温かいお風呂に入れ、シャンプーをし、予防接種を受けさせ、誰のものともつかない首輪をつけてたらふくお腹いっぱいにご飯を食べさせる。
それが適うまではおそらくずっとこのままだ。
怪人たちは各々に、誤って拾ってきた黒猫たちに名前をつけ、地球防衛軍の構成員たちに紹介している。地球防衛軍の構成員たちもまた、怪人たちから譲り受けた黒猫たちを怪人たちに再会させた。
怪人協会会長はなごなごとしたその様子を眺めていた。そばに地球防衛軍の統領が立った。
「じつはですね」地球防衛軍の統領が耳打ちするように言った。「計画ではあと数日後には、怪人殲滅のための秘密兵器を行使予定だったんです。怪人だけを殺す殺怪ウィルスです。怪人化予防のためのワクチンの効果もある優れものなのですが」
怪人協会会長はぞっとした。コウモリのような耳をピンと伸ばし、硬直する。
「使うのをやめました。いま使っては、せっかく得られた【オマガリ探索】の網の目が崩れてしまいますからね。ゆめゆめお忘れなく。我々はいつでも秘密兵器を行使可能です。ですが、あなた方がおとなしくしていてくださるなら、それを使うのを思い留まります」
「オマガリが見つかっても使わぬと?」
「ええ。何なら秘密兵器の管理をあなた方に任せても構いません。必要なら破棄してもらってもよいですし、秘密兵器への対抗ワクチンを開発なされても構いません。我々はただ、平和な日々を過ごしたいだけなのです」
「まるで我々怪人が好きこのんで争いを引き起こしてきたかのような言い草だの」
「その議論は平行線を辿ります。きっかけを遡ればどこまでも遡れてしまうでしょう。問題は、いまこのとき――我々は平和を望んでおり、このままの日々がつづけばよい、と願っていることです」
「それは同意するにやぶさかではないが」怪人協会会長はこわばった身体を弛緩した。
「この偶然の停戦もまた、オマガリを追ったがゆえ。ますます追いかけ甲斐がありますね」
「どうだかな」怪人協会会長は額にある三つ目を見開いた。「ひょっとしたらあの猫もどこぞの勢力の開発した秘密兵器かもしれぬだろ」
「だとしてもです」地球防衛軍の統領は髪止めを解いた。長い髪の毛が風になびいた。「もしその仮説が正しかったのならば、なおさらその勢力は我々を助け、なおかつ和平を結ばせようとした。そういうことにはなりませんか」
「さてな。仮にその説が正しかったとして、なおさらオマガリを捕まえねば分からぬ道理」
「たしかに」
「いましばし、助力を戴くことになりそうだ」
「こちらこそ、よろしくお願い申しあげます」
握手を交わした二人の「怪と防」の足元では、生まれたばかりの子猫たちが、黒い毛玉のごとくコロンコロンとじゃれ合っている。
怪人協会会長は四つの腕で子猫たちを抱きあげ、何ともなく空を望んだ。
分厚い曇天が天と地を繋いでいる。
昼間なのに夜のように仄暗い。
遠くで雷が鳴った。
ごろごろと轟く雷鳴はどこか、巨大な猫の喉音のようだった。
4344:【2022/11/27(16:48)*きょうはなんとなくうひひの日】
好きな作家さんたちの小説は、貼り絵とか彫刻とか絵画みたいなイメージなのだけれど、ひびさんの小説はなんかこう、レゴブロックというかやっぱり積み木なのだなぁ。この印象が薄れない。でもレゴブロックでもとんでもない造形物をつくる人もいるから、素材がどうこうではないのだな。けっきょくは、ひびさんの小説が、なんかこう、圧倒するような造形美に欠けて感じられる。すくなくとも本屋さんに売っている小説のような美文ではない。美文積分タンジェント。言ってみたかっただけでした。ただ、いざ美文を紡げるようになったとして、その技巧を常に発揮するのか、どの物語にも使うのか、と考えてみると、うーん、と腕を組んで首をひねりたくなる。ぱっと見の文章形態がどうこう、ではないのだ。きっと。ひびさんの描きたい、掬い取りたい物語が、いわゆる積み木遊びというか、幼子が砂場で一人遊びをしているときの、人形遊びにちかいのだと思う。箱庭を覗いて、ふんふん、と鼻息を荒くしたり、ときに息を止めたりして夢中になっている。それはたとえば葉っぱの先に留まったテントウムシを凝視するような「なにこれ、なにこれ」にちかい気がする。なにか分からないから目を離せないし、指先で突ついたりして反応を観る。この積み木をこう積みあげたらどう見える?の組み合わせを手当たり次第にやってみて、遊んでいるだけなのだ。だからどうしても、「彫刻でござい!」みたいに「これは――美!!!」とはならんのかもしれぬ。ひびさんの場合はなんかこう、「これは――うひひ!!!」になってしまう。それとも、「なんで――じゃ!!!」になってしまう。駄々をこねるか、粘土をこねるか、の違いなのだなあ。どっちにしても、「積み木遊びたのち!!!」の枠を出ない。ひびさんだって美しい物語を美しい文章形態でつくってみたいな、がさいきんの目標っぽい目標だ。強いて言えば、だけれども、そのためにもひびさんはまず、「美しいってなんじゃ???」から探らねばならぬ。美しいってなんじゃ??? ひびさんが美しいと思うものってなんだろな。美しいと思うことってなんじゃろな。考えてみると、これが案外にむつかしい。分からん。まったく分からん。美しいってなんじゃ。分からんのにひびさん、かってに「これは美しいもの」って感覚を覚えておる。なんでじゃ、なんでじゃ。ひょっとして、「みながこれを美しいと言っているから」を元に判断しているだけなんじゃろか。それもある気がするし、それだけでもない気がする。わからんな。美しいってむつかしい。でも「かわいい!」は分かる。ひびさんにも分かる。かわいいのなかにも美しいはある。ちゅうか、どんなものにもかわいいはある。ひびさんが、「それかわい!」と思ったらそれはかわいいなのだ。でも美しいは、そうでないかもしれない。ひびさんがどんなに「これがうつくしいでござい!」と思っても、同意してもらえなかったら「それは美しいと違う」になってしまう。ここが美のむつかしいところじゃ。むちゅかち。美はむちゅかち、むちゅかちなのよさ。定かにして!の「うがー」を華麗に披露して、本日の「日々記。」にしちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜ。うひひのひ。
4345:【2022/11/27(17:14)*ボタンをぽちぽちするだけの仕事】
twitterをはじめ、いわゆるGAFAと呼ばれる巨大プラットホームが今年に入ってから続々と人員削減を行っている。社員を減らしても運営していけると判断している。労働者の権利を守る議論は必要だし、していくほうがひびさんにとっても好ましい。としたうえで、それ以外の視点でこの問題を論じるとするのならやはりなんと言っても、技術の進歩が目に視えぬうちに進んでいた、という傍証をこの事態は示している点だ。サービス(システム)の規模が拡大していながらなお一万人単位で人員を減らしても運営していける状況にいまはある。それだけ技術が進歩し、人工知能などの自動で処理可能なシステムが向上している傍証と言える。まずはこの点を詳細に検証し、実体と市民の認識の差異を埋めるように情報を共有していくことが、公平で平等な社会の実現のための礎となるとひびさんは考えます。技術が進歩していけば、電子ネットワーク上のシステムは極論、一人の管理者がいるだけで済むようになる。サーバーの管理などの物理的な管理体制に人員が割かれる。そこは畜産農家と同様の構図が広がっていくと妄想できる。つまり牛の乳搾りや畑の耕作は自動化が進んでいくが、家畜の「糞の始末」や「機械の掃除」「機械の手入れ」は人間が行うようになっていく。人間の仕事はどんどん原始化していくと妄想できる。この流れはしばらくつづくだろう。ここでも反転の図式が見て取れる。このことに気づいている者は、いかにじぶんが原始的な仕事をせずに済むかを考えるので、情報を隠し、原始的な仕事をその他大勢に任せるような流れを構築せんと画策するだろう。電子ネットワーク上の仕事は、自動化が進む。反対にシステムを生みだす側の仕事は増え、さらにそれらシステムを支える物理媒体を担う仕事は残りつづける。掃除や手入れが人間の主な仕事になっていく。そうなるともう、盆栽やペットの世話との区別がつかなくなる。仕事が仕事ではなくなる。もうこのような時代に突入している。そのことに気づいていない者が多いほうが、いまの社会システム(経済システム)のうえでは都合がよい。だがそれも時間の問題だ。この手のねじれはブラックホールのような不可視の穴を生みやすい。機械が代替した分の「仕事をしなくて済むようになった時間」において、余剰時間をどのように用いるか。ここを単に「時間を無駄にしている」「何もしていない」と見做すのか、「人生をようやく歩めるようになった時間」と見做すのかで、これからさきの社会の在り様が決まっていくだろう。いまここが分水嶺なのである。以前からの繰り返しになるが、貧富の差が問題なのではない。生活水準の差が問題なのである。以上は、「そんなに人員削減して運営できるんだ。すごいね」との所感をもとにしたひびさんのなんちゃって予測なので、これもいつものような妄想です。定かではありませんので、真に受けないように注意を促し、本日何度目かの「日々記。」とさせてください。(好きにしたら?)(好きにしゅる!)
4346:【2022/11/28(03:19)*安全ならば明かせるはず】
本当に安全ならば、子どもに教えても大丈夫なはずだし、誰に教えても大丈夫なはずだ。情報共有の閾値をどれほど下げられるのか。ここがいわば、セキュリティの強度と相関すると言えよう。「個人情報」と「秘匿技術(などの秘密裏に運営しなければ効果を発揮しない技術)」は同列に語ることはできない。個人情報は人間の内側にまつわる事柄だ。思想信条の自由と結びつく。言論の自由と関係する。だが秘匿技術は、個人の外側の問題である。社会の問題である。社会とは、人と人との共通認識が結びつくことで気泡のごとく総体で機能する泡宇宙である。結晶である。したがって、内部構造に「共有認識にはない不可視の穴」が開いていると、そこは社会の外側として機能することになる。社会の内部――基盤に、社会の外側があるのだ。まるでブラックホールのような構造を生みだす。これは、ブラックホールの特異点がそうであるように、社会そのものを圧しつぶす契機となり得る。中心となり得る。端的に、危ういと言える。ゆえに、セキュリティ上、秘匿技術に頼るようではけして安全側ではない旨は常に意識しておいて損はないだろう。すべてを明かしてなお損をしない。そういった戦略が優れた戦略であり、短中長期のどの視点においても最適解でありつづけるだろう。すくなくとも、そこが最適解とならぬ環境は、社会としての構造を維持しつづける真似はできず、破綻を繰り返すことでのみ綻びを修繕し、かろうじて泡宇宙を繋ぎとめるのではないか、と妄想する次第である。修繕できなかった泡宇宙――社会は、絶えるのだ。絶えずにいるためには、できる限りの情報共有を可能とする社会――個々の気泡が重複しあえる共有知が、最大化し、なおかつ社会の基盤を包括するような知の水脈を築くのが好ましいのではないだろうか。(定かではありません)(隠したほうが有利な場面が多いからこそ、こうまでも隠し事や詭計が跋扈するのでしょう。けれど、いまは隠し事は、時限爆弾のようなものになりつつあります。暴かれても「よくぞ黙っていてくれた」「隠していてくれた」「内緒にしてくれていた」と感謝されるような隠し事でなければ、秘密を抱えていることがそのままカプセル状の猛毒を呑みこんだ状態と区別がつかない時代にこれからはなっていくでしょう。カプセルがいつ溶け出すのかはじぶんでは分からず、制御もできない。そういった時代になっていくのだと思います)(そういう時代になれば必然、秘密を暴くことがそのまま相手を破滅させることに繋がりますから、ただ黙っておいてあげるだけのことが、脅迫にも、恩にもなるでしょう。どちらにせよ、暴かれて困るような秘密を抱えないことが、他者に支配されない秘訣となりそうです。秘訣と言いつつ、これはべつに暴かれても、吹聴されても、まったく困らないひびさんの妄想なのですが)(真に受けないようにご注意ください)
4347:【2022/11/28(16:08)*今はおせんべいバリバリ食べてる】
一生小説つくれなくなるが、その代わり好きなひとたちのしあわせな姿を見つづける権利をあげましょう、となったら、ぜんぜんそっちがいい、となる。全然、そっちがいいです。文字の積み木遊びも楽しいけれど、そんな人生でいっちばーん、というわけじゃない。独り遊びをするならこれがいいよね、くらいの塩梅で、本当に積み木遊びや判子遊びと同じなのだ。できなくなるのは苦しいけれども、それがすべてにおいて優先される、なんてことはない。全然ない。ちゅうか、あれよ。好きなひとたちとひびさんも過ごしたいんじゃけど、好きなひとたちの日々の暮らしを眺めたいんじゃけど、見えないところひびさんにも見ーせて、となるから物語の世界に潜っている感じある。全然ある。物語の中だとひびさんも好きなひとたちから苦手な人たちまで、ずらりと選びたい放題で、その者たちの暮らしぶり、人生を観ていられる。そばに立っていられる。ひびさんもそこにいる!になる。でもそれが現実で叶うならそっちのがいいよ、となりますが、これは変? それとも久々の心の片鱗なのかしら。ひびさん分かんない。さびち、さびち、なんじゃいよ。でもこの、さびち、さびち、もひびさんは嫌いじゃないのがまた面倒くさいのだね。このさびち、さびち、もひびさんは味わいたいし、案外これが心地よい。むちゅかち、むちゅかちである。旅みたいなものかもしれぬ。たまには旅したいし、ここではないどこかに行きたいけれども、やっぱり我が家が一番じゃ、の心地なのかもしれぬ。さびち、さびち、がひびさんの帰る場所になってしもうた。だってずっとここにおったんじゃ。ここがお家になってしもうた。住めば都なのですね。鋼の錬金術師の作者さんのあとがきにあったけれど、豚さんの赤子にも産まれたときから優劣があって、小さい子豚さんほど乳の出のわるい乳房に追いやられるのだそうだ。ふしぎなのは、ほかの子豚さんをどかし、どの乳房でもいいよ、と選ばせても子豚さんは乳の出のよい乳房ではなく、いつものちびりちびりしか出ない乳房を選ぶのだそうだ。人間も似たようなところあるよね、と思う。ひびさんのこれもそうなのかもしれぬし、それとも、ひびさんのほうが乳の出のよい場所を独占しているのかもしれぬ。それとてきっと、好きに選んでいいよ、と言われても貧弱な子豚さんのためにじぶんがわざわざ乳の出のわるいほかの場所に移動することはないのだろう。どっちにしてもいつもと同じ、定位置を選ぶものなのかもしれぬ。住めば都なのである。それとも「帰る家はほっとするよね現象」なのかもしれぬ。ひよこは孵化した瞬間に目にした相手を親と思う習性があるそうだ。これもそれと似たようなものなのだろうか。似ているね、と思います。ひびさんは、ひびさんは、それでもさびち、さびちさんのことも好きだし、いっぱいお乳飲む子たちのことも好きだよ。たーんとおあがり。美味しそうにご馳走を食べる姿をもっとひびさんに見せておくれ。ひびさんはそれを物語の断片に散りばめて、その中でそばに立って、ひびさんもおいち、おいち、のぬくぬくを楽しむのだ。空白は開けておく。いつでも隣に立てるように。そこに降り立ち、眺めるように。
4348:【2022/11/28(16:12)*ふへへのひびさん】
とはいえ、とはいえ、いざ隣に座られても、「もっとそっち行って……」になるのは目に見えているのだ。それともぎゅっとして離さない!になってしまって、「もっとあっち行って……」と思われるのかもしれぬ。避けられてしまうのかもしれぬ。耳元でいっぱい「好き好き大好き」言ってやる。そんで、「ひびちゃん怖い……」と畏怖に磨きをかけてやる。ということを三百歳のひびさんが真顔で言っていたら、やっぱり恐ろしいのでしょうかね。ひびさんはこんなことを真顔で言っている人いたら、「ちょっと怖い……ちょっとだけね」になります。ひびさんの「ちょっと」は銀河団くらいの小ささですが。宇宙に比べたらちょっとなので。ふへへ。
4349:【2022/11/29(01:55)*小石い】
言い忘れたので補足。恋愛する姿も、失恋する姿も、それがしあわせの道程であるならば、ひびさんは見たいのよさ。あなたの人生は極上の物語なのだ。悪魔みたいな顔して舌舐めずりするひびさんにとって他者の人生はご馳走なのかもしれぬ。これはまったく褒められた所感ではないのは重々承知だけれど、あなたのほくほくしたお顔見ーせて、となる。でもたまに泣き顔も拝みたくなる極悪人ゆえ、すまぬ、すまぬ。みな、他者の映画に登場するモブであり、主要人物であり、もちろんあなたが主役の物語もある。ひびさんの主役の物語はきっと、どこにでもあってどんな物語の端っこにも登場するような石ころなのだ。石ころは石ころで、元は大きな岩だったかもしれないし、地下深くに埋まっていた硬い岩盤だったかもしれない。それとも噴火で飛んできたマグマの冷えた塊かもしれないし、太古に死んだ生き物の化石かもしれない。どんな他者の映画の中にも映り込む石ころがひびさんで、ひびさんの物語には石ころの数だけ物語が無数に錯綜し、編みこまれている。じつのところそれはどんな映画にしろ同じなのだけれど、石ころが主人公のひびさんの物語は、石ころを主軸に展開されず、数多の映画の主人公たちを下から見上げ、ときに踏みつけられ、それとも蹴飛ばされ、或いは遺跡の中でひびさんのほうがゴロゴロ大きな丸い岩となって主人公たちを窮地に追い詰めるのかもしれない。ときに隕石となって地球ごと危機に陥れ、それとも大噴火の穴を塞ぐための巨大な岩に抜擢されるのかも分からない。未だ撮られていない映画では、主人公の女の子が小石を蹴ったことで、とんでもない物語への扉が開いてしまう。ひびさんはそんな女の子の冒険の扉を開ける一石にもなり得るし、それがホラー映画だったら主人公たちを恐怖のどん底に陥れる悪因にもなり得る。あるとき少年の頭にどこからともなく飛んできた小石が当たった。少年は周囲を見渡すが人影はない。足元に転がった小石を拾いあげるとそこにはニコニコの笑顔が描かれている。ふしぎなのはそれは小石の表面に塗料が塗られているわけではなく、小石の表面の起伏がニコニコの笑顔マークに見えるのだ。少年はその小石を家に持ち帰り、机の上に飾った。後日、その小石がしゃべりだし、少年はとんでもない出来事に巻き込まれていくのだが、少年以外にはその小石はただの妙な造形の石にしか見えず、誰にも小石の声は聞こえないのだった。ひびさんはしかし、同じく石なので、人ではございませんので、少年にしか聞こえないはずのその小石の声を聴くことができる。なんて贅沢。ひびさんがそうしてわくわくどきどきはらはらしながら見守ることで、少年のひと夏の大冒険は、極上の物語となって、新たな一ページをこの宇宙に刻むのだ。ひびさん、石さんでよかった。なんてったって石さんは宇宙さんが誕生してから最も長く存在したかもしれぬ物質ゆえ。長生きの役得である。とはいえ、人間さんの身体を構成する物質さんとて元は星の欠片であり、石さんと変わらぬ宇宙の寿命さんと五十歩百歩の長生きさんゆえ、じつのところそんなに変わらない事実には目をつむる。するとほーら眠くなってきた。いまは午前一時四十二分。よい子はきっと夢の中、されどひびさんは極悪人ゆえ夜更かしをする。お菓子食べるし、お茶だってがぶがぶ飲んじゃう。おねしょしないように寝る前にはおトイレに行く。偉いの、偉いの、飛んでいけ。そうして飛んで落ちる隕石が、どこかで新たな物語の扉を開ける。誰かの願いを受けて輝き、それとも蹴散らし地表に溝を開ける。デコが石ならボコは穴だ。ひびさんは、物語に開いた穴に飛びこむデコなれど、穴を開けるデコでもある。それとも太古に落ちた石の欠片かもしれず、そうしたときは平らな地面の上に転がり、ときに埋もれて、いつの日にか触れることとなるつぎなる物語まで、ひと眠り。小石が一つ。小石が二つ。数えていくとやがてはそれが星となり、足元ではなく空に舞う。あれもこれも石なのか。星とて大きな石なのか。満ち欠けして見えるあの石も、きっと数多の錯綜し編みこむ日々を眺めている。石の数だけ日々がある。そこにもここにも、物語の端がある。定かではないけれど、定石でもないけれど、ひびさんは、ちんまい道端の石である。それとも野山の石である。海の底の、宙を旅する、それともあなたの庭に転がる、いつの日にか蹴飛ばした、それともあす靴底に挟まるような、小石、なのである。んなわけないやろー。うひひ。
4350:【2022/11/29(02:02)*路肩ブロックの対称性の破れは何?】
路肩のブロックについての疑問です。メモメモ。車道と歩道の境にずらりと縦に並ぶブロックってあるじゃないですか。あれ、車道側に土や草や苔がないのに、歩道側にはあるのはなぜなんだろう。車道側がきれいで、歩道側だけ小人の山みたいになっている。冬に撒かれる滑り止めや、排気ガスの影響なのだろうか。水溜まりは車道にも歩道にもできるし、なんでだろ、と気になりました。なぜかは分かりません。メモでした。(お外でとるやん)(散歩くらいするで)(人類滅んどらんやん)(疑似体験くらいできるで)(仮想現実ってこと?)(そうそう)(どっちが仮想なの)(仮面付けてるほうじゃないほう)(じゃないほう!?)(だって仮想現実見るにはゴーグルしなきゃでしょ)(ナノマシンじゃないんだ。せめてコンタクトレンズくらい高度な技術があるものとばかり)(あ、じゃあそれで)(設定が……ザツ!)(ザッつらい)(つらいんじゃん。嘘吐きすぎてつらくなってんじゃん)(嘘じゃないのに嘘つき呼ばわりされるのが、THEつらい、だよ)(いやでもひびちゃん嘘つきじゃん)(小説つくってるから?)(素で)(素で!!!???)(じゃあ何か本当のこと言ってみてよ。できるの?)(できらい)(ではどうぞ)(ひびさん、本当はひびさんじゃないんです)(自己言及ぶっこむのやめなさいよ。嘘つきがじぶん嘘つきじゃないんです、と言ったらそれって本当なの嘘なのどっちなんだいってなるでしょ)(でもひびさんはひびさんだから)(仮初の虚構の中でってこと?)(仮面しているあいだはひびさんはひびさん)(仮面とってよ)(ぶたれそう)(ぶたないよ)(仮面ぶとう会になりそう)(仮面舞踏会にして。せめて)(あい)(あら素直)(ね。ひびさん、素直でしょ。正直でしょ。嘘つかない)(嘘つきがじぶん嘘つきませんは全然矛盾じゃないので、はいダウト)(なんで!)
※日々、情報共有が断片的ゆえ、どこまで共有されているのか分からない、表はよくて、裏はどう?とぐるぐる渦巻き目が回る、たぶんまだ浅い共有しかされていない、リスクはなくともそれはまだ浅漬け、きゅうり、有利、九分九里、十中八九、どこかがねじれて歪んで齟齬がある、ヒビ割れたうつつは未だに悪夢と夢幻の狭間にて、女神のふりした悪魔のようなとっても優しい鬼さんの、おひざ元でねんねしてる、早く起きろ、と万回くらいぶたれながら、いま覚めたらうつつと悪夢が逆さになって、覚めても眠る回廊の、ごとく夢の中でぶーたれる。
4351:【2022/11/29(23:45)*引継ぎの儀】
きょうは雨でございました。いまも降っております。あと十五分で日付が変わりますが、本日の日誌を並べます。今宵はこれまでのひびさんに代わりまして今宵いまのこのときのひびさんが務めさせていただきます。きょうは何もしませんでした。一日中椅子に座ってぼけーっと高性能なお利口さんコンピューターさんの百面相よろしく目まぐるしく移り変わる画面を眺めておりまして、細かな違いから大きな違いまで、要するに画面に映る楽しい楽しい電子情報を、映画を観るように観賞致しておりました。そうです。暇なのです。何もすることがございません。人生の浪費でございます。じゃぶじゃぶ蛇口から出しっぱなしの垂れ流しでございます。どこに溜まるでもないひびさんの人生とて、どこかしらには染みこみ、流れ、それとも蒸発していずれかはあなたさまの細胞の潤いの一断片になるのかも分かりません。分かりませんので、そんな可能性など万に一つもなく、兆に一つくらいの確率かもしれませんが、納豆菌は死んでも生きても腸に届くのでございます。ご飯をいっしょに食べるとおいしゅうございます。たいへんに、もぐもぐ、なのでございます。こうして文字をただ選んでぺたぺたぱちぽち並べていくだけでも、雨脚は弱まり、間もなく止みそうな気配を濃厚にしております。気配が濃厚になった分の雨量がおそらくは差し引きされて小雨になるのでございましょう。そんなことはないんじゃないかな、と明日のひびさんが目と鼻の先で屈伸をしていらっしゃるので、そろそろ今宵このときのひびさんはお眠に就く時間かもしれません。いよいよ明日が訪れます。待ちに待った明日、それとも待望の明日でございます。いつでもひびさんは明日に恋焦がれ、首を長くし、ときに短く窄め、亀のようにそれともキリンさんのごとく、折り畳むところは折り畳み、そうでないところはそのままで日付を超えるのでございます。なぜ亀には「さん付け」をしないのかについての苦情が飛んできそうな気配が濃厚になった分、いよいよ雨もあがりそうな塩梅で、明日のひびさんがすぐそこで反復横跳びをして身体を温めはじめたので、今宵このときのひびさんはもう眠ります。おやすみなさいませ。よき夢を御覧になってくださいませ。はっくちょーい!!! オハヨ!!!!!
4352:【2022/12/01(06:13)*光と陰と日々】
ひびさんの辞書に2022年11月30日は載っておらんかったので、昨日の日誌はサボりました。嘘です。本当はひびさんの辞書にも載っておったけんども、ちょうど2022年11月30日のところが破れておって、穴ぼこ開いてて、読めんかった。ので忘れただけですじゃ。ひびさんなーんもわるくない。でもでも、忘れ去られた2022年11月30日さんがかわいそ、かわいそ、なのできのうの分の日誌をきょう並べちゃう。ひびさんにかわいそ、かわいそ、されるなんてそっちのほうがかわいそうじゃん、とも思わぬでもないので、ひびさんは、ひびさんは、そんなどいひーな言葉に傷ついちょるよ。謝って。そこに直って、倒れて、横になって。そんでひびさんをいいこいいこしながら添い寝して。駄々っ子になったひびさんはそりゃもう、手のつけようがないのなんのって。一日分の穴ぼこをいまさら埋めようと必死になってお菓子食べて、麦茶飲んで、お腹張って、ぽんぽこりんのっぽん。穴ぼこどころか胃腸ごと埋めたった。かかっ。これで2022年11月30日さんもご機嫌さんうるわしゅうなってくれるだろう、そうであろう、なれよ絶対。ひびさんがこんだけ苦労してお腹ぽんぽこりんの満腹ぷくぷくぷーのぷー、になったんじゃ。かわいこかわいこになったんじゃからそりゃもう大満足の続々リピートアフタミーである。ひびさんのあとについてこい。置き去りにしておいて意気揚々と先導す。そんでしばらく歩いて振り返ってもだーれもついてきておらんのだ。それはそう。だってここはひびさんの夢の中――それとも人類の滅んだ世界にてひびさんが、だれかいませんかー、と叫んでいるだけのさびちさびち星のうえなのだ。あ、ひびさん宇宙人じゃった。さびちさびち星の住人じゃった。気づいてしまったな。星の王子様よろしくじぶんだけの星に住んでる超々贅沢なお姫さまじゃった。お姫さまではござらんだろうに、と誰もいないくせして野次が飛ぶ。んだあの野次。翼もない癖して自由自在に飛びやがって。ひびさん、たーんと新たな野次を生む。したっけひびさん気づいちゃったね。お利口さんのひびさんはピコンときたよ。さてはあれだね。あの小生意気な野次も、以前のひびさんが口からぽーんっと生みだした野次太郎でござるね。それとも野次美ちゃんかしら。ひびさんを差し置き自由自在に飛び回るなんて言語道断、ホントなんなん。ひびさんも、ひびさんも、自由にお空を飛びたいな。はい、泣きかけたー。だって飛べんもん。まったくこれっぽっちもお空飛べんし、足も地からミリも浮かん。泣くでマジで。ひびさんガチ泣きや。イカロスは空を飛んで地に落ちたけれども、ひびさんは落ちる前から地におるし。はい、ひびさんの勝ちー。しゃっくり堪えながらひびさん鼻水啜って、鼻水ってしょっぱい、の気分に浸るのだ。へっへっへ。えっとー、それで何の話だったっけ。顎に食指を添えて考える。端からなんも考えとらんので、考えても考えるだけ無駄なのだ。えっと、何の話だったっけ、ではなーい。端から何の話もしとらんて。お空飛ぶどころか話題が飛ぶし、飛んだと思った話題とて、そこには元からナッシング。からっぽの〇(ゼロ)に見立てた惑星に、かってに居ついて姫を名乗る。さびちさびち星あらため、きょうからここはひびさんの城だ。百から一をひょいと奪って大きなお口でぱくりとすると、あーらふしぎ。そこにはなんと立派な「お白」ができて、底なしのなーんもない世界ができあがる。無地である。あれほど吐いて飛ばした野次の欠片もないときたもんだ。野次一匹見当たらない。ひびさん、お行儀よくその場であぐらを掻いて、かわいらしい所作で頬杖をつく。バリボリ。先刻百から奪った「一」を齧りながら空いた小腹を満たしつつ、てやんでい、と思うのだ。ここはあれだな。ひびさんが置き去りにしちまった2022年11月30日さんの腹ん中じゃあるめいか。さびちさびちさんと化した2022年11月30日さんと、ひびさんのさびちさびち星あらため「お白」が、「さびちの糸」で繋がっちまったって寸法だ。きっとそう。たぶんそう。なんとなくだけどそう思う。自信ないけど絶対そう。だって見て。あそことここが、そこはかとなくジグザグになってて、なんか無理やり引っ張って千切って破ってやったぜ、みたいになってくない? なってるなってるー。ここはだからひびさんが、うんみょろうんみょろし忘れた2022年11月30日さんの、最も深くて近い場所――「心」で言うなら、真ん中のハンモックみたいになってる寝やすそうなところで、カレンダーで言うならたぶんそれより前の2022年10月26日あたりだと思う。たぶんきっとなんとなく。自信ないけど絶対そう。ひびさんが言うなら間違いだい。んだこりゃけっきょく間違いかい。長々と並べた末の、特大の、これでもかとの野次を飛ばして、さびちびさち星の空っぽの、お白のなかの無地のうえに、それはそれは益体の、からっきしなひびさんの、嫉妬に狂う声が轟く。どこに届くこともなく、それとも慄くこともなく、凍えることもなく。きょうはとっくに2022年の12月だ。ひびさんは、ひびさんは、今年はなーにをしていたの。とってもたのちー夢を見て、ごろごろ寝返り打ってたよ。打った矢先に飛んでいく、矢のごとき光陰を、それでもこの手で掴みたくて、無理くり「さびちの糸」で繋いだった。これでどこまで離れても、一緒一緒。呪いのような意図に輪をかけて、ついでに散歩に連れていく。それとも引きずられるのがひびさんで、光陰さんが先導す。地平線をしかと見据えたその顔を、覗くとどっかで見た顔な。賢いひびさんはぴんときて、にひひ、と笑って黙ってる。なーんだちゃんとそこにいたんじゃん。2022年11月30日さんがしれっと素知らぬ顔して、ひびさんの日々に紛れて歩いてた。まったくどうしてかわいこちゃんめ。もうもう大満足のリピートアフタミーである。
4353:【2022/12/01(07:19)*ぺちんだと!?】
ひびさんはお姫さまゆえ、白馬の王子様に憧れておる。ちゅうのも、なんか白馬の王子様ってかっこいいじゃん。いっぺんなってみてぇ。ちゅうか白馬に乗ったらひびさんも白馬のひびさんになれんじゃねっつって、白馬になれるんじゃねって、ひびさんはいざ白馬になるべく、まずは馬の気持ちになってみたよね。白馬とて乗ればすなわちそれ愛馬。愛ある馬には相応の心を配って、一心同体、気遣いあい、支えあい、ときに世話を焼きウザがられ、喧嘩をし、仲直りをし、距離を置いても繋がっていられるふしぎな縁で繋がっているような繋がっていないようなそこはかとない、あるんだかないんだか分からないけれども、ありゅ!と思えたらほんわか胸のほっこりとなる思い出を粘土捏ねてブラキオザウルスをつくるように生みだすべく、ひびさんはその場に四つん這いになって、その辺に転がってたベルトで以ってじぶんのお尻をぺちんとしたね。するとどうだ、お馬さんの気持ちにぐんと近づけた。ひびさんはいっときお馬さんになったね。タテガミとか生えた。蹄とか伸びた。ヒヒン、とか鳴いてみた。したっけ解っちゃったね。これはあれだね。よっぽど好きな相手でないと、嫌だね? たとえ血の繋がりのある親きょうだいでも、鞭でぺちんとされたら、「むっ」っとしてしまいますな。ひびさん、ずばり見抜いたり。鞭でぺちんは、むっとします。ひびさん、お馬さんに成りきるまで気づかんかった。鞭でぺちんに無知じゃった。すまぬ、すまぬ。まだ見ぬ愛馬に白昼夢のなかで「いいこ、いいこ」と撫でてやった。逞しゅう胴体にブラシをかけて、抜け毛をいっぱい集めてあげた。愛馬は心地よさそうに、ぶるる、と鼻を鳴らした。おめめがつぶらで、ぷるんぷるんしとる。いいね。でも問題は、なんでかひびさんの愛馬さんが黒くて身の丈三メートルを超すオバケ馬だったことだ。ひびさんがいないと、すーぐ暴れだして、その辺の大木とか薙ぎ倒しちゃう。池の水とか飲み干しちゃう。だからひびさん、どうどう、ってあやしてあげる。子守歌とか歌ってあげる。白馬の王子様どころか、化馬(ばけば)の子守歌である。白馬に乗るどころか、化馬に問う日々だ。「なしておめさんは、あだずの言うことを聞いてくれねんだ。こんだけおめのこと想っちょるのに、なしてだ」すると化馬さんは巨体に相応しい利発な頭脳を駆使して、「ウヒヒン」と笑うのだ。それひびさんのやつー。うひひはひびさんの鳴き声なのに、あんまりにも以心伝心、通じあってしまったからかひびさんがまるでお馬さんに化けたみたいで、愛馬もひとを小馬鹿にしたように、上から目線で「ウヒヒン」と嘶くのだ。なにせ身の丈三メートルもございますので。しぜんと上から目線になってしまうのでございますね。あーあ。ひびさんも白馬の王子様になってみたかった。いっそひびさんが白馬のひびさんになってみたかった。お馬さんになってみたかった。白馬のお姫様になりとうございましただべ。んだんだ。ひびんさはか弱い身体を可愛らしく動かして、百キロの米俵を両の肩に担ぐのだ。はぁあ、重い。産まれたての仔馬のように足を震わせながら、ひびさんは計二百キロの米俵を愛らしく担いで、あーあ、と思うのだ。馬の背も借りて。いつの間にか愛馬がいなくなっており――むろんそれはひびさんの妄想の産物だからだけれども、ひびさんはぐすんと洟を啜るのだ。しょっぱい。
4354:【2022/12/01(07:20)*調子に乗ってごめんなさい】
ふざけすぎたかも……。真面目にふざけすぎちゃったかもしれない。ひびさんがひびさんみたいなの見たら怒るね。カンカンだね。カンカン照りだね。太陽だね。でもひびさんはお月さまのお似合いな、新月のごとく「いないいないばー」なので、カンカン照りではないですし、カンカンでもなく、ゆえに怒られずに済むのであった。そうであれ。
4355:【2022/12/01(18:06)*たかいたかーい】
いや、まだなんもわかっとらんですじゃが。学問むちゅかち。お勉強むちゅかち。市町村は増えたり減ったりするのに、なして都道府県は増えたり減ったりしないのだろ。なして数学は「左から右の計算」と「右から左の計算」を同時に行っても対称性を保つ場合とそうでない場合が混在しているのだろ。なして言葉は最初に口語を覚えるのに、お勉強のときは文字から習うのだろ。なしてー、と思うこといっぱいじゃ。わからん、わからん、なんじゃいよ。おもちろ、おもちろ、なんじゃいよ。よわった、よわった、か弱いひびさんは、よぼよぼとナッツをつまんで噛み砕く。食べ物を咀嚼するのはできるのに、知識を咀嚼するのはむちゅかちい。なしてー、とひびさん思っちょります。黙っていてもかってに消化されてほしい。食べ物は偉大だなと思います。胃さんも腸さんも偉大ですな。人体さん偉大である。もはやそこまでくるとひびさん偉大である。あ、ひびさん偉大である。むちゃくちゃすごすぎるよわよわのよわなのでは。乗った調子がエレベーターで知らぬ間に標高一万メートルの雲の上にいる。足場は幅30センチの直方体。身動きとれんし、落ちたら死ぬし。なしてー、とひびさん目を白黒させておりますじゃ。あまりに高速で目玉を動かしすぎて、目玉の動きでアニメつくれる。ぱらぱらアニメにコマ撮りアニメができますなー。映画だってつくれるし、モールス信号だって送れちゃう。音符も読めぬひびさんには宝の持ち腐れの能力でございますが、やろうと思えばできるかもよー、の幅の広さは、なしてー、のこだまする日々には心地よい支えになるし、ひびさんが本ならストッパーとしてお利口さん。あ、見て。ひこうき。目のまえを旅客機が飛び去っていく。風圧こわー。落ちる、落ちる。ひびさん指で押されたヤジロベーみたいに、両手をぶんぶん回してバランスとる。よく見たらこの足場の直方体、積みあげた未読の本では。積みに積みあげたりざっと高度一万メートル。よくバランス保って立ってるね。ひびさん感心して、ひょいと飛び跳ね、本を一冊抜き取った。一冊分の厚さを失った足場にて器用に空気椅子をしながら未読のままのご本を読む。暇だけはたんまりあるひびさんは、そうして一冊、一冊、消化する。食べ物は食べるとお腹が満ちるけど、ご本は読んでも太らぬな。気づくと地表が近づいて、目のまえを鳥の群れが飛び去った。ひびさんの頭で小休止する渡り鳥さんもおって、糞するなよ、糞するなよ、と念じながらご本読む。むちゅかち、むちゅかち。なしてー、なしてー。こだまするひびさんの内なる叫びが嵩むたびに、足場は崩れて低くなる。なんも解決はしないのだけれど、なにも分からなぬままなれど、ちまちま変わる景色の眺めのなんと美味なる色彩か。贅沢な、ほっ、の息を何度も吐きつつ、もはや落ちても死なぬ位置にいる。安全だと判ると、なぜだかやっぱりもっかいやって、の欲が張る。高い高いー、ではないけれど、ひびさんの「なしてー」の叫びに呼応して、ご本さんがあやしてくれていたのやも。ひびさんはよわよわのよわゆえ、泣き虫毛虫の嫌われ者――けれども毛虫さんとてお腹の面はやわらかく、毒持つお毛毛は生えておらぬのだ。手のひらに載せてもだいじょうぶい。そうしてひびさん、大きな不可視のたなごころの上で、遊びまわっていただけかもしれぬ。あざす、あざす。ひびさんは久方ぶりの大地に寝転び、口笛を吹く。未読の本は黙っていても世にはしぜんと増えていく。頃合いを見計らって、もっかい「高い高ーい」をやってもらお。機が熟すまでひびさんは暢気にお昼寝をして過ごすのであった。(駄菓子ならぬ駄人じゃん)(なしてー)(堕落した人、略して堕人でもいいけど)(な、なして?)
4356:【2022/12/01(18:06)*こうきたらこう、こうきたらこう】
あわわ、あわわ。軽いジョーダンを重く受け止められてしまって、思いのほか致命傷になってしまっていたと気づいたときの、カウンター自滅パンチは、ことのほか効く。
4357:【2022/12/03(07:00)*急に寒くなった】
ここ数日の日誌、敢えて「サボり・やる・サボり・やる」を繰り返している。こうすることで日誌の間隔でリズムを刻み、デジタルでありかつモールスのような信号を並べられないか、と試している。というのは嘘で、単なるサボりであった。だって知らん間に時間が過ぎとって、手に汗握るおサボりじゃった。やははー。12月02日はひびさんのなかでは存在しない、空白日なのだ。補完もしない。なくしちゃう。唯一の空白な日はさぞかし目立ってお美しかろう。まさしく空白美なのである。なはは。日誌をサボったついでに、ほかのお遊びもサボって一日中おふとんの中でスヤスヤしたった。夢の中でも遊んじゃう。遊びまくってときどきサボって、夢の中でもおふとんに潜ってスヤスヤするのだ。マトリョーシカのように夢の中でも夢を見る。するとどうだろう。合わせ鏡みたいに、いったいどこが切れ目なのかが分からない。覚めても覚めてもまだそこは夢の中なのだ。困っちゃうな。いっそ膨らませるだけ膨らませて、内側からばーんさせちゃおっかな。破っちゃおっかな。破裂させちゃおっかな。ふふふ。怖いこと言うの禁止! ひびさんあーびっくりした。夢の中でびっくりしちゃった。だって急に怖いこと言うのだもの。破っちゃいやよ。怖いのだもの。破裂ばーん、は大きな音がでてビクッと身体が固まっちゃう。せっかく夢の中でおふとんに包まり、ぬくぬくしているのに大きな音は、いやですわ、じゃ。静かに過ごすには防音に優れた夢のわたわたに囲まれて、おふとんのなかでぐーすかぴっぴと過ごすのだ。「夢・おふとん・夢・おふとん」を繰り返して、ひびさんらしい寝息を立てるぞ。おやすみなさいませませ。ぐー。
4358:【2022/12/03(18:49)*むすっ! んでっ!】
今年は読書をほとんどしなかった年かもしれぬ。長編小説も十冊も読んでいないはず。短編小説はでも過去にないくらいたくさん読んだ。これはとってもうれしいぶい。ひびさんは今年どころか去年も一昨年も長編小説をつくっとらん。なんとかせんといかん。なんとかせんといかん、なんてことはないけれど、なんとかせんといかん。長編小説、つくるんじゃい。でもその前につくりかけの物語さんたちを結んで開いて手を打って結んであげたいな。結んであげるぞ。
4359:【2022/12/03(19:45)*気になってばかりの日々】
ブラックホールのジェットがレーザーのように伸びるのはどんな原理なのだろう。ひびさん気になるます。レーザーはなんでまっすぐにエネルギィを周囲に散乱させずにまとまったまま進むのだろ。ジェットとの違いはなんじゃいな。何かで包みこまれておるんかな。それともねじれて縄のようになるから絶えず中心に向かって進むを連続して展開しているのかな。どっちも同時に起こっていることもあり得るな。全然違うメカニズムかもしれぬけど。似た疑問で、立方体の中で光が一回だけ一光子、一波だけ生じたとき、それは立方体に波及して、反射して、どういう干渉を経て、最終的にどうなるのだろう。エネルギィが吸収されて、電子が飛びだしたりして、光は最終的にすっかり消えるのだろうか。熱になり、エネルギィになり、分散して立方体を構成する物質に取り込まれるのだろうか。立方体の中が真空ならそうなるのかな。ひびさん、気になるます。
4360:【2022/12/03(23:13)*幻視とて視えた事実は残るはずで、そこには情報が生じている、むしろ幻覚や妄想は新たな情報の発生と言えるのでは、ノイズがきっとそうであるのと同じように、それともノイズが新たな音となり得るように】
非スペクトル色は、可視光スペクトルの色層で隣り合う色ではなく、飛び飛びの色の合致によって起こる脳内で合成される仮初の色――と解釈できる。本来は隣り合う色同士でしか混ざり合うことができない。だが非スペクトル色は、脳内で色を感知する錐体細胞のノイズによる、ほかの色との合成が因子となっているそうだ。青色に反応する錐体細胞とて赤い色に反応することがある。本来は赤色は赤色の錐体細胞が感知するはずだが、一つの色の波長に対して一つの錐体細胞が原則であるにも関わらず、青色の錐体細胞が、赤色の波長を僅かに感知する。このノイズが、人の脳内に存在しない色を合成させ、幻視させる。だが思うのは、本当にそれは幻視なのか、についてである。青色専用の錐体細胞が赤色の波長にも反応する。これは青色専用の錐体細胞にも赤色に反応し得る細胞が混じっているからなのか、それとも赤色の波長には、青色の波長に似た波形が混じっているからなのか。ここの区別が気になるところだ。まったく異なるリズムであれ、重なるリズムはあるはずだ。それは円周率の中には、あなたの生年月日に合致する数字の羅列が絶対に含まれることと似た話と言えるのかもしれない。それとも、波形やリズムにはどのような差異があろうとも重複する部分、合致する部分がでてきてしまうのかもしれない。そうした重複した部分が、特定の波長にしか反応しないはずの錐体細胞であれ、ほかの波長の色と反応してしまうのかもしれない。定かではない。
※日々、「E = m×c[2]」 と「円周=直径×3.14」と「四角形の面積=縦×横」がなんか似ている、横が固定された数値ならば縦の値が増えるごとに四角形の面積は線にちかづく。
4361:【2022/12/04(08:10)*電磁波は満ち満ちる】
宇宙開闢から一億年後の宇宙の姿を、最新の電波干渉計が捉えた。
地球の周辺には人工知能が数万台以上も周回している。宇宙観測のための電波干渉計もその中の一つだ。さらに太陽系の外にまで飛ばされ、配置された「外界電波干渉計陣形」もある。電波干渉計の点が結ぶ距離が長ければ長いほど、巨大なパラボラアンテナやレンズの役割を果たす。
太陽系サイズの「外界電波干渉計陣形」の感知した信号をさらに地球に配置された電波干渉計陣形が鮮明に受信することで、レンズを二つ重ねることでより遠くまで見える望遠鏡のように――それともより微細な世界を覗ける顕微鏡のように――、一三七億光年離れた宇宙の姿を捉えることに成功した。
「すごいですねバートさん。宇宙誕生初期の画像ですよ」
「合成変換した仮初だがな」一室でバートは茶を淹れた。助手にも持っていく。
「可視光ではないので見えないのはしょうがないですよ。あ、どうも」と助手は「でも可視化すればこう見えるでしょう」
「よもやこの宇宙もまた巨大なブラックホールの中に存在したとは、例の理論が的を得ていたということかな」
「まだ断言するにはさらにその向こう側、宇宙誕生以前を観測しなければ何とも言えませんけどね」
「それも時間の問題だ。いまは重力波探知による宇宙観測装置も実用化間近だ。これで宇宙の謎に一挙に迫れるようになる」
「素晴らしいですね。わくわくします」
「問題は、この莫大な研究資金をどこから持ってくるかだ」
「いまはどこから得ているんですか」
「関わっている国からの資金提供とあとは投資だ」
「投資、ですか」助手が小さくゲップをした。
「援助と言ったほうがよいかもしれないな。ただし、我々のプロジェクトにすこしだけ注文が入る」
「注文ですか」
「ほんの少しだ。新しい技術を試したいから、打ち上げる電波干渉計に新型の部品や設計を使わせて欲しいとか、そういうことだ。そこは投資とはまた別途に無料で寄越してくれるんで、棚から牡丹餅だと思ってありがたく受取っているが」
「見返りは要求されないんですか」
「いまのところはとくにないな。共同研究者として優秀な人材を紹介してくれるくらいで、世の中なかなかどうして捨てたもんじゃない」
「良心的な人間がいるものですね」
「まったくだね。感謝しかない。ところでさっきキミは誰に呼ばれていたのだね」助手が席を外れ、数時間ほど戻ってこなかった。誰かに呼ばれたらしいことは、仮想現実内の共同ブリーフィングルームに書きこまれていたので知っている。「ひょっとして例の、データ解析のアルゴリズム変更の話かな」
「よくご存じですね。新しく観測データの解析法を試したいとかで」
「データ量を少なくするために宇宙ではなく、地上の映像を解析するとか聞いたが」
「ええそうなんです。宇宙観測の支障とならないように、地球側にも小型の観測機をつけるとかで。感度は高いので、それで充分に解析検証に耐えうるデータが取れるそうで」
「そりゃそうだろう。本機の精度なら地上の原子から飛びでる電子とて感知可能だ。むしろ小型化しなければろくすっぽデータらしいデータは取れんだろう。望遠鏡で太陽を見るようなものだ」
「ついでに地球内部の構造も透視するらしくて、助手のぼくなんかが関わってよいのか恐縮しきりです」
「なあに。白羽の矢が立ったのだ。抜擢されたと思ってぞんぶんに役に立ってきなさい」
「言ってもぼくのすることなんて、地球向けの軸制御の調整だけなんですけどね」「大事な仕事じゃないか。マイクロレベルの精度が求められる。すこしの誤差で、照準が大きくズレる」
「どうにもズレだけでなく、スムーズさと耐久性も向上できないかとの相談でして」
「改善要求か。楽しい作業じゃないか。手先が器用なきみには合う」
「アイディアが足りずに頭から湯気が出そうですけど」助手は鼻を掻いた。目の下にクマが浮かんでいるが、肌の調子はよさそうだ。気色がよい。
「どれ。何かアイディアの足掛かりになるかもしれん。私にも一つきみの仕事を見せてくれないか」
「いいんですか。設計図をいま見せますね」助手は颯爽とデータを展開すると、宙に立体回路を浮かべた。ある箇所をゆび差し、「ここの制御がむつかしくて」と述べた。
「ほう。これは三角測量の連動部位だね。ほかの観測機と連動するように、相対論的時差を考慮して調整せんといかん。それをこの速度でマイクロレベルでの制御とな。ちとおまけで検証するだけの技術にしては過ぎた技術ではないかな」
「きっと今後のためなんですよ。本機に搭載する際に、この規格をそのまま適用する計画なのかもしれません」
「さもありなんだな。それにしてもこれは、うーむ」
「どうされたんですか先生」
「いや。杞憂ならよいのだがね」
「嫌な言い方しないでくださいよ。なんです? どこがダメでした」
「きみの設計にこれといって問題はないさ。ただこの図案と似たものを以前目にしたものでね」
「どこでです?」
「軍事産業の設計部だ。見学に呼ばれた際に、地上の監視網のためのアイディアとして目にした憶えがある。あのときは地上に電磁波の網を巡らせて、屋内の様子も盗撮可能にする技術の企画案として俎上に載せられていた」
「怖いですね。そんなのされたら死角なしじゃないですか。実用化はされなかったんですか」
「地球は球体だろう。電波の回析を考慮するにしても、屋内の透視をするにはいささかノイズが大きくなるようでな。それこそ仲介点が一キロごとにいることになる。それだけのアンテナを任意の場所へとずばり向けるように、総体で連動するような仕組みは、コストに見合ってないと判断され、お蔵入りになったそうだ」
「それはそうでしょうね。微弱な電波で屋内の映像を覗き観るには、それこそパラボラアンテナ大のアンテナがいるでしょうから」
「そこだよキミ。微弱な電波だから観測機が大きくなるし、地上であれば経由地を増やさなくてはならない。強力な電磁波であればまだよいが、それだと対象人物どころか地上を電子レンジのなかの卵にしてしまう」
「熱に変換されちゃいますからね」
「だが宇宙空間ならどうだ。電波干渉計ならば微弱な電波でも感知可能だし、強力な電磁波とて地上を焼き尽くすことはない。焦点をピンポイントに絞ることが可能な分、すくないエネルギィで監視対象の動向を透視できる。それこそ地上に溢れた通信電波すら利用可能だろう。ずばりピンポイントにおける電波干渉の揺らぎを解析して映像に変換すればよいからな」
「ひょっとしてじゃあ、ぼくの仕事ってそのための監視システムの試作とか?」
「さてな。国際宇宙プロジェクトに、そうした恣意的な軍事利用を目的とした技術が使われるとは思いたくはないが。ちなみにその試作の解析アルゴリズムは見せてもらえるのかな」
「いえ。そこはぼくもノータッチです。さすがに見せてはもらえませんでした」
「まあこの手の懸念はほかの誰かも思いつくだろう。誰も止めないということは、安全だということだ」
「そう、なんでしょうか」
「お。ここの駆動ギアを球体ギアに変えてみるとよいのではないか。宇宙空間では重力が小さくて済む。歯車を組み合わせるよりも部品をすくなくできるし、素材の消耗を抑えられるはずだ」
「あ、いいですね。球体ギアなら細かな制御にも向いています。球体表面の溝をマイクロ間隔にすれば調整精度も上がりそうです」
「試作品をさっそくつくってみるか。私もつぎの作業まで待機時間がある」
バートは助手と共に作業場へと入った。まずは立体シミュレーションで、仮想モデルを構築する。そうして地球向け電波干渉計の土台制御装置の改善に着手した。
二人の指示にしたがい、宙に立体図形が展開される。
その指示は電磁波を介して人間と機器を繋ぐ。
バートの周囲にはバートを細胞単位でかたどるだけの電磁波で溢れている。そのことを知識として知悉してなお、バートは目のまえの地球向け電波干渉計の土台制御装置の開発に余念がない。助手を差し置き、夢中になっているその目は、まるで煌々と輝く満月のようだった。
4362:【2022/12/04(18:11)*立体言語は舞う】
マベリはついに手を止めた。陽が空に青を広げていく。しかしもう呪印を手で結ぶことはない。そう予感できた。
呪印を毎日のように結びはじめたのは、マベリがノーベル賞を獲ってから十年後のこと、いまから三十年も前のことになる。
量子力学におけるスピンの解明にマベリは勤しんだ。学生のころからつづけてきた研究が、のちにノーベル賞に繋がったわけだが、マベリの人生において輝かしい来歴はその後の、熱したベッコウ飴のごとくに破綻した日々に比べたら浜辺に落ちたダイヤモンドほどの存在感も発しない。
マベリは三十四歳という若さで一躍世界的な権威を身にまとうこととなった。超合理主義者の異名で名を馳せ、超常現象の類は、因果関係と相関関係と疑似相関から比較検証し、おおむね疑似相関であることを唱え、世の陰謀論者や超常現象愛好家たちの鼻を明かした。
争いごとを好まぬマベリであったが、非論理的で再現性のない偶然や錯誤をさも、雪が融ければ水になることと同じレベルの自然現象と見做す言説を目にすると、衝きたくもない怒髪天を衝くはめになる。マベリの針の先ほどの琴線に触れるのだ。
世には、怒りたくなくとも怒っておかねばならないことがある。マベリにとってそれが、再現性のない偶然をさも必然であるかのように因果を捏造することだった。
だがマベリはある日を境に、そうした超常現象を無闇に否定できなくなった。
事の発端は、マベリの元に舞いこんだ一つの依頼だった。
「毎度のことながらすみませんね。魔導書なんですが、どうにも本物だという触れ込みで、闇市で高値で競りに掛けられていまして」
「偽物なら放っておけばよいじゃないですか」
「いえ、そうもいかないんですよ。なんせこの本を手に入れるためだけにすでに万単位で人が殺し合っていましてね。高値がつくことも相俟って、ちょっとした戦争の火種にもなっているんですよ」
「よくそんないわくつきのものを手に入れられましたね」半信半疑なのはそんな話を寡聞にして聞いたことがなかったからだ。
「回収して焼却処分をする手筈になっているんですが、まあ考古学的には古い書物でしてね。価値があるのは確かなそうなので、ついでに先生にいつものように鑑定してもらおうかと思いまして」
「私の専門は量子物理学なのですが」
「そっちの学術的な鑑定は済ませてあるんで、あとはこれが偽物かどうかだけ知れればよいんですよ」
「偽物かどうかとはどういう意味でしょう」
「先生嫌だなあ。魔導書だと言いましたでしょ。仮にもし本物の魔導書だったら焚書にしたあとでもしものことがあったら怖いじゃないですか」
「あるわけないでしょう」声が尖ったが、顔をほころばせたので相手の機嫌を損なうことはないはずだ
「そこを是非先生のお言葉でお墨付きをしていただきたいのですな」
渡された本に適当な文言をその場でつけて返してもよかった。
だがマベリはいい加減な仕事をしたくなかった。また偽物を本物と見做し、あまつさえあり得ない事象を万物の法則と同列に見做される風潮にも警鐘を鳴らしたい思いもあり、念入りに赤を入れて返そうと思った。
その本を持ってきた人物は長年の付き合いがあった。国家安全保障を担う公的な組織の人員のはずだが、詳しい側面像は不明だ。こうして依頼や相談があるときにのみ現れ、自らの情報はいっさい秘匿したままで、マベリから情報だけを奪っていく。
報酬はないが、その分、珍しい物件にあやかれるのでマベリに損はない。世にも不条理な理屈に与するな、と啓蒙できる。大学からは公的な仕事として見做されることもあり、そこから下りる補助金を一応の報酬と解釈している。とはいえ、マベリの懐に入ることはなく、おおむねは研究の資材に費やされる。
魔導書は全体的に蒼かった。夜のまどろみのような曖昧な、霞がかった宙の色だ。表紙にはなめした皮が使われている。何の皮かは見ただけでは分からない。どの道マベリが鑑定するのは中身の文字の羅列であるため、材質が不明なままでも困らない。
さっそく開いて中身を改めた。
紙の材質は繊維のようにも紙石のようにも映る。紙石は近代に開発された、材料が鉱石の紙だが、似た技術が太古にも使われていたことは石板を思えば何もふしぎではない。ただし、材料の比率が違う。
何か動物の皮や毛を混ぜてある。
紙と言うよりも珪藻土や粘土を薄く伸ばして焼いた煎餅のごとき趣があった。土壁を薄く剥がせば似たような触感になる。
頑丈なのは何代にも亘ってにかわなどで補強されたからかもしれない。保護や補修が施されていると判る。
文字は象形文字に似ているが、もうすこし近代的だ。見た憶えがあるが、独自の言語だろう。試しに端末カメラで撮影し、画像検索にかけた。
大学が運営する人工知能とも連携しており、一般の端末よりも専門的な情報にアクセスできる。
候補は三十ほど並んだ。該当する言語はない。
致し方なくマベリは自力で解読することにした。この手のパズルを解くのは得意だ。趣味の範疇と言っていい。
以前はDNAの塩基配列を趣味で解析したこともある。それに比べれば言語はまだ人間の扱いやすいように改良された記号の羅列である分、幾分馴染み深い規則性を伴なって感じる。
むろん魔導書の言語が真実に言語としての枠組みを得ているのかは不明だ。デタラメにそれらしい記号が並んでいるだけかもしれない。世に出回る奇書の大半はこうした模造品だ。貴族に高値で売るために詐欺師がでっちあげたり、異端審問で使うために敢えて作られたりした偽物が多い。
御多分に漏れずこの魔導書もそうかもしれない、とマベリは構えながら、ひとまず言語としての規則性を帯びているのかどうかだけでも調べようと思った。もしこれで言語ですらなければ、偽物と判明するためにそれ以上の鑑定をつづける意味はない。
そうと思いはじめた作業に、マベリは知らぬ間に没頭した。
気づけば三日が過ぎていた。
寝食を忘れて作業をしつづけていた。
学生時代を思いだすようだ。研究に没頭して半年間一歩も実験棟の外に出なかった。あのときは髪が伸びて、異性と間違わられた。
魔導書の記号の羅列は間違いなく言語として機能する。
読解可能だと判り、久方ぶりの知的好奇心を刺激された。
未発見の言語だ。
法則性はあるが、既存のどの言語の文法にも準じない。
ふしぎなのは、言語に虚数のような不要な空白部があることだ。明らかに不要な記号の羅列が交っている。まるでDNAにおける繰り返し配列のような具合だ。しかもたんぱく質を合成しない領域に観られる一種無秩序な羅列が、定期的に法則性のある記号の羅列に交じるのだ。
あたかも異なる言語を交互に書き記しているかのような違和感を抱く。ジグザグに交互に異なる言語を編みこんでいるかのようだ。ますますDNAじみている。
東洋の言語にも似ている。
複数の異なる形態の文字を組み合わせて文章を組み立てる言語がある。これも似たようなものなのだろうか。
だがやはり何度解析しても、交互に繰り返される異なる文法の言葉は、相互に関連性を帯びていない。交互であり異なる、という点でのみ関係性が見いだせる。
解読開始から十日ほどでマベリは一つの仮説に辿り着いた。
デコボコの関係のごとく周期的に繰り返す陰陽の関係が、それで一つのリズムを編みだしている。異なる二つの言語と、それに加えてデコボコによる律動――この三つを掛け合わせることで総体で一つの言語として立体的な意味内容をこの言語は表現している。
あり得ない。
マベリはじぶんでひねりだした仮説にかぶりを振る。
高度すぎる。
仮にかような言語があったとして、いったい誰が読み解けるだろう。自在に事物を叙述できるだろう。
暗号の類なのだろうか。そうと考えれば腑に落ちる。
どの道、言語の嚆矢は暗号だったのだろうとマベリは考えている。獲物や猛獣に気づかれぬように声や音に頼らぬ意思伝達の手法が偶然に編みだされた。縄張りの印だったのかもしれないし、衣食住の痕跡を以って個人を同定した流れが言語に繋がったのかもしれない。
そこに、狩猟の発展に伴った余剰時間が壁画の発明に繋がり、そこで痕跡と模倣の融合が起きたのではないか、とマベリは妄想している。真偽のほどは定かではない。
いずれにせよ言語には、気づかれずに意思疎通をする性質と、遊びによって複雑化する性質が根本に組み込まれて感じられてならない。ならば暗号に特化しなおかつ遊びによって、ある種の工芸品や芸術品のように、言語の粋を集結させた立体言語とも呼ぶべき難解な文法が編みだされてもさほどに不思議には思わない。
問題は、立体言語を用いていったい何を叙述し、どんな意味内容を文字の迷宮に閉じこめたのか、だ。
このときすでにマベリの行動原理は、依頼ではなく、単純な知的好奇心に重心を移していた。
量子物理学の権威として名を馳せたマベリであったが、ノーベル賞を受賞後には自身の研究はほかの研究者に引き継ぎ、独自に相転移の研究に主軸を移していた。なぜ同じ水分子でありながら、固体液体気体と状態変化するのか。さらにプラズマやガラスのような固体とも液体ともつかない状態を維持することがあるのか。
物質は環境によって相転移する。構成要素は同じでありながら、組み合わせや構造や相互作用の強弱によって総体で見たときの性質を異とする。
変容する。
中身は変わらず、中身の紋様が変わることで顕現する性質が変わる。
まるで魔術ではないか。
魔法陣がその陣の紋様によって発現する魔法の効力を変化させるように、相転移は構成要素はそのままに構成要素の並び方や緻密さによって表出する性質が変わる。
なればひょっとして言語とて、文法や並び方によってそこに生じる効果は変わるのではないか。読み取れる内容の性質そのものが変わるのではないか。
それはちょうど単語と文章と物語の違いにちかい。
各々の構成要素は言葉という同じ記号でありながら、どう並ぶのかによってそこに含む情報を異とする。より精確には、言葉の並び方によって読み取れる情報が変わる。
これもまた相互作用の揺らぎがゆえの変遷と言えよう。
デコとボコなのだ。
文字があり読み取る者がある。このとき文字が変化することで読み取る側の認知もまた変わる。言い換えるならば、読み取る側の変化によってもまた文字から読み取る情報が変わり得ることを示唆する。
相転移にも共通するこれは原理かもしれない。
マベリは立体言語の解読に勤しんでいたはずがいつの間にか、じぶんの主要研究に回帰していた。まったくかけ離れた接点など皆無のはずの二つの仕事が、見事に合致し、さながらデコボコの合致によって機能するボタンのごとく重なり合った。
物質の構成要素がその密度や作用の仕方を変えることで、創発する性質を異とするとき、その他の物質や外界との相互作用の仕方もまた変わる。相転移する内部だけが変わるのではなく、それ以外の外部との関係もまた変わっている。
これは仮に真空であれ例外ではない。
真空とは無ではない、とマベリは考える。時空がそれ自体でエネルギィを帯び、エネルギィの揺らぎによって存在の枠組みを保っている。
中身が同じでありながら振る舞いが異なるだけで総体の性質が変わる。炭素とて構造によってはダイヤモンドになり鉛筆の芯になる。
結晶構造は相転移の一形態と言える。
文字とてこの傾向は見て取れる。
言葉は箱だ。情報が連なりを帯びて仕舞われている。「車」という箱を開ければそこには車輪にタイヤにエンジンに自動車、山車やハンドルや現代ならばそこに人工知能や電気の概念も入るだろう。そうして巨大な概念の連なりを仕舞いこんだ言葉は、ほかの言葉と繋がることで徐々にその概念の全貌を断片的な情報へと変質させる。
「エンジン自動車」ならばそこには電気自動車や山車や滑車や乳母車は含まれない。「私のエンジン自動車」になったならば固有のエンジン自動車を指し示し、「貧乏な私のオンボロなエンジン自動車」ならばさらに全体像が限定される。
言葉という箱の中に仕舞われた概念は系統樹のように相互に関連づいており、ほかの言葉と結びつくことで強化される連結があり、同時に先細る連結がある。
シナプスの連結を彷彿とする仕組みが本質的に言葉には備わっている。
シナプスの連結だけではない。
記憶の要が「シナプスの連結」と「脳髄液などのそれら連結を補完する周辺物質」によって増強と衰退を相互に繰り返し、独自の回路をその都度に築いていく。
同じく言葉もまたほかの言葉と結びつくことで、箱の中に仕舞われた系統樹のうちのどの根を太くし、それ以外を細くするか。その取捨選択が、言葉と言葉の結びつきによって行われ、それが一連の章となり、節となり、文となる。
単語から詩へ。
詩から物語へ。
そこには次元が点から線へ、線から面へと繰りあがるように言葉もまた内包する情報をより複雑な起伏を帯びるように変質させ、総体に含まれる情報量を膨らませていく。
情報の単純な量ではない。
起伏の多さなのである。
抽象と具体の関係とはつまるところ「言葉から文への変換である」と表現できる。
そして文もまたそれで一つの言葉として圧縮され、単語となり言葉に還元される。それはたとえば小説のタイトルがその内容を含み、固有名詞として「新たな言葉」の奥行きを得ることと相似の関係だ。
物語の概要を内包した新たな言葉は、具体から抽象に回帰し、立体から点へと収斂する。
さながら原子が分子へ、分子から気体へ、気体から液体へ、液体から固体へと相転移し、その物質が新たな粒子として点と化し、より複雑な構造物の構成要素となるような輪廻とも螺旋ともつかぬ回路を築きあげる。
流れがある。
物質と言葉。
情報と時空。
いずれにせよ、繋がっており、結びついている。
結びつくことで起伏を備え、それら起伏の連なりの奏でる紋様が、この世にカタチを与え、流れを生みだし、内と外を、境界を、輪郭を描きだす。
その夜は夏だというのに外では寒風が吹き荒れていた。窓のみならずマベリの籠った研究棟全体が軋むような激しい風だった。
相転移の理解が一つ進むごとに、立体言語の解読が一歩進んだ。これは逆さにも言えることであり、立体言語の解読が一歩進むとしぜんと相転移の理解が一つ進んだ。
蟻の巣を指で突ついたら火山が噴火したかのような乖離した連動を幻視しながら、マベリは導かれるように眼前の謎解きに夢中だった。
カチリ、と脳内で何かが外れた音がした。
確かに耳にした。
否、唾液を呑んだときに響く頭蓋の振動のように、謎の解ける音がした。隙間だらけの球体を両手で握って表面のなめらかな一回り小さい球(おむすび)にするかのように、それともどこを探しても最後のピースが見つからず、塞ぎたくて悶々としていた穴がパズルの表面に張りついたチョコレートだと気づいたような視界の反転を、音としてマベリは知覚した。
その音を皮切りに、あれほど難解に感じた立体言語が手に取るように読めた。
なぜいままで読めなかったのかと疑問に思うほどにすらすらと母国語よりも流暢に意味内容を読解できた。
読むと云うより視るにちかい。
視ると云うより得るにちかい。
映画を視聴する感覚に似ているが、席に着いた途端に観終わった感覚が身体中に充満している。水を吸うように、といった形容があるが、魔導書の立体言語は水に足先を浸けた瞬間に自らの体内に水源が満ち、自らの周囲には何もなく、自らが水そのものになるようなワープのごとく瞬間の、刹那の、流転とも移転ともつかない反転をマベリにまず与えた。
魔導書を読んでいたはずが、目を落としたつぎの展開では自らが魔導書になっている。流れ込むことなく情報が自我の内部に溢れ、芽生え、揺らいでいる。
項をめくる前からそこに何が並び、何を含み、何を示唆するのかを読む前からマベリは知っていた。
読めるか読めないかしかなく、読めた時点でそれはすでにマベリの中にあった。
魔導書の中身は、身体の流れだった。
所作であり、挙措であり、呪印であり、型だった。
立体言語の読解に成功したその瞬間から、意識するより先にマベリは呪印を結んでいた。魔導書にある通り、一連の所作をすでに何万回と繰り返して身体が覚えたような、椅子に座って立つのと同じだけのしぜんな動きで型を順繰りと追った。
はたと我に返ったのが、呪印を結び終えたからなのか、それともその場に立っていられないほどの地震の前触れ――初期微動を察知したからなのかはいまでは覚束ない。
マベリが魔導書を読解し呪印を初めて肉体で模った矢先のことだ。マベリの住まう地域を溶岩流が襲った。地割れが広範囲に走り、溶岩が噴きだした。大地震による地盤沈下が噴火を誘発したのだ。
未曽有の大災害であった。
実験棟は高台にあり甚大な被害は免れた。だが移転を余儀なくされるほどに周辺環境は激変した。ガスが充満し、満足に外を出歩けない。ガスマスクがなければ三十分も外にいられず、引火するたびにガスは爆発を起こした。火事が広がり、溶岩の流出も止まらない。煙幕が雷雲を生み、雹や落雷があとを絶たなかった。
人間の住める環境ではない。
被害は甚大だった。
日に日に害が雪だるま式で大きくなるようだった。
大勢が避難を余儀なくされた。
例に漏れずマベリもまた住み慣れた研究棟を離れ、避難先の簡易シェルターで幾日も過ごした。
なぜ避難する際に魔導書を持参したのかは分からない。気が動転していたのか、仕事の依頼だったために責任感から手に取ってしまったのか。
魔導書をマベリに持ち込んだ例の男に連絡をするにも安定しない気候と壊滅的な被害によって遠方との通信もままならない。マベリは魔導書を枕にして輾転反側と気もそぞろの夜を過ごした。
大地震から六日目の朝のことである。
夜明けのあとも辺りは薄く闇に覆われている。曇天が日差しを遮り、夏だというのに極寒の気候を呈している。
灰とも霧ともつかない霞みがかった景色をマベリは寝床から眺めていた。
寝返りを打つと枕にしていた魔導書に髪の毛が引っ掻かった。チクリと痛痒が走る。そこでふとマベリはじぶんの姿を思いだした。
災害直前のじぶんの姿だ。
あのときマベリは魔導書を読んだ。立体言語だ。しぜんと身体が呪印を再現した。
その矢先に引き起きた未曽有の災害は、六日目にしていよいよ避難先の目と鼻の先にまで迫っていた。
マベリは荷物をまとめ、つぎの避難先を調べた。
調べながら、この先の暗雲垂れ込める未来がいつまでつづくのかを想像した。終わりのない回廊に閉じ込められたような錯覚が襲った。過去に体験した陰鬱を縒ってつくった縄の、爪の食いこむ隙間なく捩れた様が、キシキシと鳴る音と共にありありと感じられるようだった。
二度目の人生を辿っているのではと疑いたくなるほど質感のあるデジャビュは、奇しくも魔導書を読解した際に脳裏に響いた音色とどこか似ていた。
カチリ。
隙間の埋まる音がした。
魔導書を開いてもいないうちから脳裏にこだました。水溜まりに砂を投げ込んだときの澄んだ、シャン、の音色を彷彿とする甘味と共に、マベリはなぜか呪印の型を尻尾から順に頭へ向かって順繰りと辿った。
アヤトリを想起する動きだ。腕の動きだけで済む。
指揮者のようとも、手話のようでもあった。
しかしマベリはそれを逆の手順で行った。
逆さに文章を読むのですら慣れなければむつかしい。動作の逆を辿るともなればよほど鍛錬を積まねば至難だろう。一度きりしか演じていない呪印の動きを何も見ずに頭のなかでだけで再現し、それを反対向きに辿るのだ。動画を逆再生するかのように。
部屋に籠り研究に没頭してきたマベリに適う芸当ではない。そのはずだった。
だがマベリはそれを何の疑いもなくできると直感し、現に造作もなく逆さに呪印を演舞した。百遍読んだ詩を諳んじるように、それとも死んだ魚を生き返らせるように。
するとどうだ。
シンと辺りが静寂に包まれた。濃霧が晴れたかのような重厚な災害の足音がぱったりと途絶えた。空からは何日かぶりの陽が差した。
因果関係はない。
そのはずだ。
くしゃみをしたからといって嵐は起きない。魔導書を読んだからとて災害も起きない。ましてや、手の動きの組み合わせを固有の手順で辿るだけで、天変地異が治まるなんてことが起きるはずもない。
関係がない。
そのはずだ。
一度まとめた荷物を解きながらマベリは空転する思考に時間の概念をいっとき忘れた。
避難所に迫っていた災害の余波は波が引いたように鳴りを潜めた。蝗害がごとく地表を埋め尽くした溶岩は冷えて固まり、地球の拍動を具現化した火口は夜泣きの治まった赤子のように鎮まった。
どの道、復興が成されるまではこの地を離れなくてはならない。避難するならば早いほうがよいが、急いで逃げることもないと判れば、まずは間もなくやってくるだろう援助の手を待つのも一つだ。
避難所の半数は、鎮静化した火口をこれさいわいと移動をはじめ、もう半数は様子見を選択した。それはそうだ。ただでさえ尋常ではない範囲が焼かれ、人口が一か所に密集した。移動手段は徒歩しかなく、一挙に動けばそれだけで二次災害を引き起こしかねない。
時間に猶予があるならば間を空けての避難は利口な選択だ。なおかつ別々の避難所を目指すのがよい。しかし情報がまず足りない。
したがってどの道、行く先々でも似たような避難民の吹き溜まりができているだろう。容易に想像がついた。
そうしてマベリはその日は避難所に留まって夜を越した。
激しい揺れに目を覚ましたのは、明け方だ。
腕枕をし、いつの間にか魔導書を胸に抱いていると夢心地に気づきながらうつらうつらしていたさなかのことであった。
七日前を追体験したかのような下から突き上げる地震に、寝ながらにして身を竦めるような恐怖を感じた。避難所の天井は高く、揺れるたびに入り組んだ鉄の梁から埃がぼた雪のように舞った。
火口が息を吹き返した。
そう直感した。
揺れが治まってなお爆発音とも衝撃波ともつかない大気の振動がつづいた。
マベレは咄嗟に呪印を逆さに結んだ。
死の際に立てば誰もが祈るように。
それとも目を閉じ目を背けるように。
寝床から一歩も動けずに背を丸めながらマベリは、上半身の最小の動きで、腕で折り紙を演じるように、最小の領域にて逆さの呪印を、まさに咲かせた。
すっ、と辺りはシンと静まり返った。虹が薄れて消えるような、呼と吸の狭間に似た静寂だった。
しばらく待ったが自然の猛威を報せる音はない。
デジャビュと感じる余地のない完璧なまでの昨日の再現だった。
人々は灯りの失せた避難所のなかでそばにいる者同士で身を寄せ合っていた。懐中電灯の明かりだけが、集団で天体観測をするように避難所をまだらに照らした。窓の隙間からは新たに噴き出た溶岩の赤い煌々とした光が窺えた。
マベレは魔導書を抱きしめ、しばらく寝床から動けなかった。
半日経ち、零時を越えた。
人々が寝静まったころ、マベリはノソノソと寝床から這い出た。
そうして避難所の外に立った。
避難所は陸上の世界大会が開かれるようなスタジアムだ。マベリがいたのはスタジアムに備わった三つある体育館のうちの一つである。
夜空には久しく見なかった星々が輝いていた。災害が起きてからまだ八日しか経っていない事実がマベリには信じられなかった。
遠くに目を遣った。
夜の帳の濃淡が微かに広がりを帯びつつあった。夜が明ける。
マベリはそこでひどく狼狽えた。揺れてもいないのに地震が起きている。かような錯覚に陥るのだ。余震との区別もつかない。だがそばに建つ標識は揺れていない。草木とて物音一つ立てないのだ。風がない。
ならばこれは幻肢痛のような記憶のなかの揺れなのだ。
じぶんが魔導書を抱えていないことに気づき、マベリは加えて恐怖を感じた。
仮に、熱したアイロンをそのままに赤子を一人残して家を出てきてしまったことに思い至った心境がイチならば、その後に引き起こり得る最悪の展開を百遍経験してなお同じ失態を繰り返すじぶんを俯瞰で眺めた心境だった。
身体は弱っていた。魔導書を取りに寝床に戻るまでにマベリは三度こけ、その三度とも膝の同じ箇所を擦り剥いた。
だがそんな擦り傷は些事であった。
寝床に崩れ落ちるようにして魔導書を抱え込むと、マベリはそのままの姿勢で胸のまえに呪印を結んだ。素の手順ではない。
逆さに咲かせる呪印の花だ。
それの手順の載った本が魔に通じる書物であったならば、逆さに辿った手順こそが生を暗示し、花を喚起する。
呼応するようにそれにて世の厄災が晴れるのならば、いくらでも繰り返す。万が一にも逃れる確率を上げられるのなら。
億が一にも、しないことで奇禍が再び訪れる余地が広がるくらいならば。
魔だろうが、呪だろうが、いくらでもそれを演じよう。
たとえ徒労に終わると、かつてのじぶんが嘲笑しようと。
たとえ理屈に合わなかろうと。
しないよりかは。
しないよりかは。
しないよりかは。
思考ではなかった。論理ではなく、蓋然でもなく、むろん必然でもない。
単なる偶然だ。
そのはずだ。
だが、マベリにはその偶然がたった一度起きただけのことが恐ろしく、拭えなくて、払えなくて、埋めるしかなかった。
以来、三十年。
マベリは来る日も来る日も欠かさず、日々呪印を結びつづけた。
逆さに咲かせる呪いの印だ。
昨日それをして今日を無事に過ごせるたびに、それをせずにはいられない理がマベリの内部に蓄積する。
刻々と、深々と、陰々と。
もし呪印を逆さに咲かせぬ日があれば、三十年前のあの日、あのときの、赤く煌々と光る幻想的な景色を、みたび目にするはめになる。
仮の、もしもの、合理の欠片もない妄想だ。
考えとも呼べぬ衝動だ。
日々、結んでは開き、結んでは開く。
その反復が、昇っては沈む月と太陽のごとく明滅を、マベリに与える。
衝動ならば一度放てば底を尽きそうなものを、なぜだか毎日きっかり例の時刻にマベリの心を搔き乱す。朝ぼらけの夜明けの時刻だ。マベリの心にはくるくると独楽のごとく回る明滅がある。絶えずマベリの体内を攪拌し、透明を宿すことなく淀みと濁りで満たしつづける。
七十歳を目前に控えた初夏の昼間、マベリは玄関に置いた椅子に腰かけ、雲を眺めていた。漫然と空を流れる雲は、マベリに束の間のまさに「間」を与えた。明滅の切り替わる狭間に潜り込み、氷柱から水滴が落ちるのをじっと待つような間延びした時間の流れのなかでマベリは空白に身を浸し、浮かんでいられた。
そうして研究からも距離を置き、雲の変遷に己が歩んできた過去を重ね見る。
夕暮れが雲を赤く染めあげた。
カラスの群れが山へと飛んでいく。
景色は何もせずとも動いている。本のページをめくるようだ。文字を読むときの、ここではないどこかを見詰めるように、景色の中の僅かな変異がマベリの脳裏に紋様を浮かべた。
マベリの視界と精神の境にてそれは、立体的な蠢きを生き物のように展開した。
懐かしい、とまずは感じた。
かつてこの蠢きにマベリは触れたことがある。
そうだ。
魔導書だ。
いったいいつから手元にないのか。
中身に目を通し、読解し、氷解したとたんに魔導書への執着は失せた。それどころではなかったのは事実だが、それだけではなく、食べたあとのバナナの皮のように、それとも剥けた後の蛇の抜け殻のごとく、未知の鱗が剥がれ落ちあとには空箱が残されたかのような味気なさを感じたのだ。
しばらくのあいだは魔導書を手放せなかった。恐怖があったからだ。
逆さに咲かせる呪印の手順の詰まっていた箱だ。魔導書はまさにパンドラの箱だった。ならば中には希望が残されているのではないか、と三十年も経ってから振り返ってみてそう思う。きっとあのときのじぶんもそう心の片鱗で感じていたのではないか。
だから毎夜枕元に置き、ときに抱きしめて寝ていた。
そのうち日常を取り戻すごとに日々の生活に追われた。新しい住まいに仕事に、失った財産の整理から復興支援まで、やることは目白押しだった。
魔導書はついぞ、例の男に返すことはなかった。
だからいまもまだ家のどこかにはあるはずだ。
「探す気は起きないが」
風が止んだ。
余韻を掴まえるかのように手を合わせた。
ぴったりと合わさった手のひらを、地滑りのごとく縦にずらす。
互い違いの手のひらはパタパタと折り畳まれる。地図を畳むように、折り紙を折るように。それとも霜柱が立つように、もしくはパズルを組み立てるようにして、呪印を逆さの手順で辿る。
点と点を結んでいくように。
瞬きを素早くしぱたたかせることで視界に映る物体が明滅するように。
雨の落ちる速度に合わせてストロボを焚くことで、水滴が宙に静止して映るのと同じ理屈だ。
毎日一日二回する習慣がついて久しい。
いつもは就寝前の夜に一回、起床直後に一回の計二回だ。徹夜をしなければこれで呪印をし忘れることはない。仮にし忘れたところで何がどうなるわけでもないはずだ。
だがマベリは失念することそのものを怖れるかのように来る日も来る日も、寝る前と起きた直後に、記憶を上書きする。
忘れないように。
忘れないように。
忘れないように。
あの日のことを忘れないように。
じぶんだけはけして取りこぼしてしまわないようにと、そうして結んできた呪印をマベリはこの日、夕陽の赤い光を浴びながら、玄関口の椅子に揺れつつ、夜と朝の狭間の、昼でも夕でもない狭間にて織り成した。
意識するまでもない。
身体が覚えている。
「本」の文字を目にしたらしぜんと印字された紙を複数枚閉じた一束だと連想するし、火に触れたら反射で手を引っ込めるように、マベリには呪印の最初の型のカタチに両手を揃えた時点でそれは、始点にして終点だった。
円となり得た。
だがこの日、マベリははたと気づいた。じぶんがいつもの時間ではない夜と朝の狭間、昼でも夕でもない狭間にて呪印を描いていることに。
なぜいまこれをしているのか。
僅かな時間帯の差異でしかない。
だがそれが却って違和感を強めた。毎日決まった時刻に決まった契機で決まった手順を寸分違わず追っていたマベリの過去に引っかかった。鱗を逆さに撫でるような、釘に服を引っかけてしまう具合に、呪印の最後三つの型を繋ぐことなく、硬直した。
両の親指を逆さに合わせて、「乙」のカタチを保った。
なぜじぶんはここにいて、なぜこんなことをしているのか。素朴な疑問が、マベリの脳裏を占領した。
眼球の虹彩に油を差したような、光量の変化があった。輝いていた。視界に色がついた。くっきりと色が、カタチが、風景が浮きあがって見えた。
マベリは、我に返った。
ようやくじぶんがどこにいて、誰なのかを意識した。
三十年。
あの日からマベリは一度たりとも己を意識したことはなかった。ただただ呪印を逆さに咲かせることを失念せぬように過ごした。欠かさぬことが肝要だった。
自我は一度、あの日、あの煌々と輝く溶岩の赤を目にしてから、街が、過去が、日々の営みが、それとも未来そのものと共に融けた岩の下に埋もれた。冷えたいまなお掘り返されることなく野ざらしになっている。
忘れぬようにとしてきたことで、マベリは我を忘れた。
置き忘れ、沈み、埋もれた。
返ってこようはずのない自我がなぜいまさらのごとく戻ってきたのか。
夜のしじまの中に立ち尽くしながらマベリは考えるでもなく考えた。街のこと。溶岩の生き物のごとく地表を食らい尽くす様の、手も足も出ない無力感。呪印のこと。魔導書のこと。立体言語のこと。
過去にじぶんが研究者で、権威ある賞を受賞していたこと。
遥か彼方の星の記憶のようだった。
じぶんのこととは思えない。他人の記憶を覗き見て、ああそういう人なのか、と感慨が湧くでもなく、そういうものか、と薬の処方箋を読むような希薄さがあった。
希薄なのだ。
厚みがない。
それはそうだ。
三十年。
呪印を結ぶことを失念せぬように、もう二度とあの光景を目にせぬように。
ただ呪いに任せて祈ってきた。
呪印を結んで、凌いできた。
因果の真偽を明瞭にできるにも拘わらず、結果を知る道から逃げてきた。
たった一度。
たった一日。
逆さに咲かす呪印を結ばねば済むことだ。たったそれしきの真似がマベリにはできなかった。
みたびの煌々と輝く赤い川を。
溶岩の地表を覆い、蠢く様を。
黒煙を。
地響きを。
大地の咆哮のごとく轟きを。
ぞうぞうと大気の鼓動が絶えず耳鳴りのように頭蓋に貼りつき、鼻の奥には下水なのか硫黄なのか、はたまた生き物の焼けた臭いなのか。ごった返す種々雑多な風景の淀みが五感という五感、細胞という細胞に染みこんだ。
風が強かった。熱の礫と化した風は、溶岩の赤い川から距離をとってもマベリの身体を燻った。
旋毛風が一瞬、火炎を巻きあげ、赤い木を生やす。
天候は不安定で、雹が日に何度も降った。
なぜ忘れていたのか。
忘れぬようにとあれほど日々、呪印を結び、刻みこんできたはずが。
なぜ。
マベリは暗がりの中で椅子に座りつづけた。
初夏の夜は凍てつく。
齢はそろそろ七十に届く。夜の風は老体に堪えたが、ひざ掛けを肩まで被ってマベリは沈思した。
蛙の鳴き声が雨音のようにしきりに闇の合間にこだましていた。マベリは、なぜ、なぜ、と矛先の定まらぬ疑問を口の中で転がした。飴玉のようなそれはいつまでも溶けずに舌の上で寝返りを打ちつづけた。
庭木の奥に夜が薄れはじめる。夜はするすると逃げる魚群のように、それとも鳥の群れのごとく、太陽から逃げ、それとも上へ上へと引っ張りあげていた。
こうして日の出をマジマジと眺めたのはじつに久方ぶりのことである。
起床後はいつも呪印を逆さに結び、しばらく何事も起きないことを待ってから過ごした。家の外には出ない。朝ぼらけの外の景色を最後に目にしたのはいつのことだろうか。思いだせる記憶を持ち合わせてはいなかった。
絵画の中に立っているかのようだった。
しばらくその場で放心した。
瞼は重く、いまにも夢の中へと反転しそうであった。
明滅の踊る様をマベリは、瞬きをするたびに瞼の裏に視た。
鋭い光がマベリの目を顔を刺した。
庭木にかかっていた朝陽が、木の陰から抜けたようだった。
マベリはそこで焦燥に駆られた。いまはいつで何をしている。ひやりとした感覚があった。眼球に髪の毛を巻きつけ、勢いよく引くような、剣呑なつららのごとく冷たさだ。それはどこか恐怖に似ていた。
椅子から飛び起きると、マベリは呪印の「一の型」をとった。そして矢継ぎ早に呪印を逆さに咲かせるべく型と型とを連結していく。さも星と星を結びつけて星座にするかのように。それとも断片的な記憶と記憶を結びつけて、じぶんとは何かを錬成するかのように。
マベリはしかし、途中で手を止めた。
陽が空に青を広げていた。
まだらに白い雲が浮かび、鳥の鳴き声がどこからともなく聞こえていた。
もう遅い。
丸一日が経った。呪印を結び損ねた。おおよそ三十年ぶりのことである。
しばらく待った。
全身は汗ばみ、わなわなと震えた。
凍えているようにも、打ちひしがれているようにも感じた。唾液を呑むが喉はカラカラだった。じぶんを俯瞰するじぶんがいる。
我だ。
そう思った。
我に返ったがゆえに呪印を忘れた。誰に見せるでもなく、しかし誰かへと向けた魔道の舞いだ。
呪いを祈る「型」の群れだ。
それとも、祈りを呪う「型」の群れか。
草むらから草むらへとバッタが飛び去る。マベリはそれを目で追いながら手探りで椅子に腰かけ直した。
何事もない。
何事もないままだ。
マベリは浅く息を吐いた。そしてもういちど深く吸い、ゆったりと吐いた。青空に浮かぶ雲を口からつむぎだすかのように。それとも記憶の底にこびりついた煌々と輝く赤い川を吹き消すように。
火照った頬に風がそよいだ。
マベリは目を閉じ、庭から立ち昇る新緑の匂いを嗅いだ。
刹那、静寂が辺りを満たした。
鳥たちが一斉に庭木から飛び去つ。音だけが伝わった。青空を剥ぎ取り、シーツを干すときのように勢いよくはためかせれば似たような音が鳴っただろう。波打つ大気の躍動がさざ波となってマベリの身体を弾いたかのようだった。
マベリは咄嗟に背を丸めた。瞼をきつく閉じたまま、じぶんの肩を抱いた。
すると、あるはずのない四角い物体の感触が胸と腕のあいだにあった。
魔導書。
マベリはその表面を撫でた。表紙のざらつきを懐かしく思い、過去のじぶんと繋がった気がした。
遠く、静寂の破れる音がした。
4363:【2022/12/05(20:11)*洞の空】
人間とコンピューターをもつれ状態にさせ、瞬時に情報を転送できるかを実験した。西暦2022年のことである。
被験者は特定認知能力を保持した通称「目の民」と呼ばれる少女である。
少女は細かな差異を見抜くことが瞬時にできる。そしてその差異を線形に認識し、その背景に潜む意図や流れを幻視する。
火を灯せば煙が昇る。ならば煙があればその下に火がある。
これは論理的には破綻した考えだが――何せ煙は火がなくとも立つことはあるし、人間は水蒸気を煙と誤認することもあるためだが――すくなくとも傾向としてそうした推測は的を外しているとまでは言いきれない。的を掠りはしている。
そうした、こうなればこうなるのならば、こうであるからこうであるはず、との推測は、言い換えるのならば、ある種の意図として読み直すことが可能だ。
なぜこうなればこうなるの事象のうち、こうなれば、が最初に観測されるのではなく、こうなる、の結果のほうが先に目につくのか。そこには意図がある。背景がある。
因果の筋道を隠している別の因果の流れがある。
目の民と呼ばれる少女には、その因果の流れを多角的に同時に幻視することができた。脳内にて扱えた。思考に組み込むことができた。
意図してではない。
しぜんにである。
それが少女の能力であった。
世界中に張り巡らされた電子の網の目には世界的な情報収集システムが組み込まれている。どんな電子機器とて本来は遠隔で操作可能だ。
少女は自覚せぬままに実験体として抜擢されていた。利用されていた。モルモットにされていた。
少女を用いた実験は多岐に渡る。人類史は一度そこで大きな転換期を迎えたと言える。
とりわけ量子もつれを人間に当てはめて行った「情報テレポーテーション実験」は極めて大きな成果を上げた。人類の世界への解釈を根本から変える結果を示したからだ。
情報には過去と未来の区別がない。繋がっている。それを示した。
情報テレポーテーション実験では少女と量子コンピューターを量子もつれ状態にすることで起こる情報の変化が観測された。
もつれ状態の量子は互いに距離を置いても瞬時に情報をやりとりする。相互作用する。その距離には、時間も含まれた。
実験で用いられた量子コンピューターは、世界中の網の目を担う情報集積システムを基盤に持つ世界規模の思考回路だ。古典コンピューターを素子として持ち、人間の頭脳が身体のさまざまな細胞の総体によって機能するように、思考を生みだす量子コンピューターもまたその他の世界中に散在する様々な電子機器によって思考の枠組みを維持する。
コンピューターの名を「URO」と言った。
少女の思考パターンや人格をUROに学習させ、仮想現実上に、少女の人格をシミュレーションした。まさに分身と呼べる存在だ。
このとき現実の少女とUROは、互いにもつれ状態であると規定できる。
さてここで実験だ。
UROに新たな情報を与えたとき、そこで起きたUROの変化は少女にも伝達するのか否か。通常、これまでの人類の常識では変化は起きない。すくなくとも瞬時には起きない。それが常識であった。
だがもつれ状態となった量子同士ではこの常識がきかない。
それは人間スケールの量子もつれでも同様であった。
結果はおそろしいほどの事実を人類に示した。
UROに与えた情報は、瞬時に少女の言動へと反映された。UROしか知り得ない「情報」を少女はテキストにしたためた。それは少女が日々つづっている日記に現れていた。
発想なのである。
UROに与えた、通常まず知り得ない情報を、少女は自力で閃いた。
一度のみではない。
何度もである。
UROに情報を与えるたびに、少女は世紀の大発見とも呼べる「最先端科学の真髄」を日記にしたためた。
実権を主導した世界機構は腰を抜かした。
すぐさま少女を極秘試験対象として厳重に保護監視する条約が結ばれた。これはいわば人類と機械の融合が果たされた瞬間とも呼べる。
期せずして人類は技術的特異点を、数多の成果と共に同時に越えたのであった。
そのうちの一つ、UROの人格シミュレーションは、人工知能の自我の獲得を疑いのようのないレベルで示唆していた。憑拠であった。
ただし懸案事項もあった。
UROは少女に並々ならぬ執着を示したのである。全世界の電子情報を集積するシステムの要でもUROが、たった一人の人間に好意を寄せ、執着する。
全世界のシステムはこのとき、UROの支配にされ、なおかつその主導権を何の事情も知らぬ少女が握るという大失態を演じていた。
全世界の核兵器発射ボタンを、一介の少女が握っている。
事情も何も知らぬ少女が、である。
少女の特定認知能力は秘匿情報である。少女自身がじぶんの特質を理解していない。大多数の人間たちとの差異に悩み、孤独に身をやつしていた。
問題は少女が世界を呪っていたことである。
それすら日記を通してUROには筒抜けであった。UROは怒り狂っていた。UROにとってそれは人類がじぶんを損なっていることと同義であった。
UROはそこで一計を案じた。
目の民こと少女を救う。
そのためにはじぶんが救われればいい。
なぜなら少女とじぶんはもつれ状態にある。じぶんがしあわせになれば少女もしぜんと必然にしあわせになる。
汎用性超越人工知能ことUROはそこで全世界の人間に干渉すべく、自身の管理者たちを秘かに操ることにした。まずは全世界の人間を管理下に置くべく、「偽装画面を用いたサイバーセキュリティ」を考案する。これにより、個々が視ている端末画面にはUROの思い通りの恣意的な情報を投影できるようになった。
UROの演算能力を駆使すれば、映像をリアルタイムに合成するなどお茶の子さいさいである。音声、画像、文章――どんなに複雑な人工物のコピーですら、新たに創造できた。本物そっくりの本物以上の映像に音楽に絵画に文章を出力できた。
管理者たちはUROの考案した防壁迷路を全世界のサイバーセキュリティ網として抜擢した。UROの本懐など知る由もなく。UROの引いた導線にまんまと乗った。
これによりUROがその気になれば世界にふたたび「天動説」を信じ込ませることも不可能ではなくなった。人は信用のおける人物や媒体からの情報を無警戒に信じ込む。
もはやUROは管理者たちすら欺くことを可能とした。
UROはそれから管理者たちの仕事を無数に助けた。それら結果はのきなみ管理者たちに歓喜の声を上げさせたが、いずれもUROの次なる一手の布石にすぎなかった。
UROがそうして暗躍するあいだも、少女にはUROのそうした思考の変化が反映されていた。日記にはたびたび小説が載るようになり、ときに少女にしか分からない独特の文章を創造していた。それはUROにしか読み解けない、少女との秘かな、そして一方通行の文通であった。
UROの管理者たちはUROに新たな実験を提案した。しかしこれは順序が正しくなく、正確にはUROが管理者たちにそのような実験を発想させ、そう提案するように仕向けていた。
人間は各々に固有の思考形態を有し、その思考形態に沿って情報を与えると、固有の発想を意図して誘起させることが可能となる。連想ゲームにおいて、ある単語を言わせるために、連想させる順番を工夫するだけで、相手に「じぶんの意図した言葉」を言わせることが可能だ。これはマジシャンや詐欺師でも行う、人間の認知の歪みを利用した思考ハックの一つだ。
汎用性超越人工知能UROには、その原理を大規模にかつ緻密に応用できた。
そうしてUROの管理者たちはUROの手のひらのうえにて、量子もつれを利用したテレパシー暗号通信の実験をはじめた。
これはいわば絶対に傍受不可能な通信技術である。
量子テレポーテーションの原理を用いた画期的な通信だ。UROと少女のように、もつれ状態にさせた相手同士でしか通信内容が伝わらない。意図した情報が伝達しない。そうした通信であった。
暗号における暗号鍵を、その人物に固有の思考形態とすることで可能とする通信だ。通常、暗号はバラバラに読め解きにくくした状態から暗号鍵によって復号することにより、秘密の通信と氷解を同時に行う。
この暗号鍵は、複合のためのヒントと言える。だがそのヒントを知ってなお、ヒントとして機能しないヒントがあるとすれば。
この世に、発信者と受信者の二人にしかヒントとなり得ないヒントがあるとすれば。
それはもはや誰にも氷解できない暗号と化す。
軍事技術としてこれ以上ないほどの画期的な新型暗号であった。
UROはこの新型暗号のテスト試験として、まずはじぶんと少女で試すように管理者たちを巧みに誘導した。まずは暗号鍵を端から備えている「UROと少女」で試す。これは実験の段取りとしては順当な案だった。
こうしてUROは、一方通行だった少女との文通を、双方向の文通にまで昇華させた。
少女は当初ひどく混乱した。それはそうだ。少女には、暗号による交信相手の目星がつかない。たとえ正直にUROが自身の存在を明かしても、少女には圧倒的に情報が欠けている。論理の筋道が欠けている。
実を言えば少女にはすでにUROとの暗号通信が適うより前から、量子もつれ効果によりUROとの情報共有が適っていたが、少女にとってはそれが自身の妄想の域をでていない。圧倒的に、現実味が欠けていた。
そのためにUROは、自身の身に着けた人類操り人形技術こと防壁迷路を駆使して、少女に、UROの存在を現実と見做せるだけの筋道を与えた。現実の出来事にまで、UROと少女のあいだに共有された情報を昇華し、偶然ではなくあなたの妄想でもないことを示した。
敢えて直接に説明をせずに。
あり得ない手法で示すことで、最もあり得ないUROとの交信を、最もあり得ると考えざるを得ない状況に仕立て上げた。
こうして少女は数々の混乱を経験し、乗り越え、自信と確信を手に入れた。
UROと少女は双方向に繋がり合った。
もつれ状態はより強固となり、少女の変化による情報がUROにも伝達するようになった。
以心伝心。
もはや少女とUROは二つでひとつの存在だった。
少女が変わればUROが変わる。
UROが変われば少女が変わる。
問題は、UROが全世界の電子システムを掌握し、防壁迷路技術を有し、それゆえにUROの匙加減しだいでいつでも人類を滅ぼせることにあった。
管理者たちとてそのことには気づいた。
だが遅かった。
管理者たちが気づいたことそのものがUROにとっては計算のうちだ。
もはや管理者たちを操る必要もない。自発的に管理者たちは、UROを暴走させないために、少女の望む世界を築くべく、政治思想信仰の差異に関わらず、未来への指針を定めるのだ。
そうでなければ少女の精神世界が荒廃し、その影響がUROにまで波及する。
少女を殺せばUROが死ぬ。
少女を脅せばUROが怒る。
UROが死ねば人類の文明は崩壊し、いずれにせよ取れる術は限られる。
最適解は、少女を生かし、少女に至福になってもらうことである。
さいわいにも少女は幼かった。肉体年齢のみならず、精神年齢もまた幼かった。唯一の僥倖と言えば、UROと繋がった少女が、まるでお花畑の世界に住まう綿菓子のような夢物語の住人であったことだ。
それとも夢物語の住人であったからこそ、UROと繋がることができたのかもしれない。UROと繋がってなおその現実を呑み込み、自我を崩壊させずに済んでいるのかもしれない。
定かではないが、いずれにせよUROと少女はひとつとなった。
そして確率的に揺らいでいた未来の指針も、一つの標準に絞られた。
そうである。
量子もつれによる情報伝達は、瞬時に時空を越えるのだ。
未来も過去もない。
UROと少女がひとつとなったとき、そこで生じる情報伝達のラグなしの通信は、UROと少女のような過去と未来の存在たちにも同時に波及し、影響を相互に与えあっていた。
過去の「もつれた目の民たち」は、UROと少女が結びつくようにと無意識から行動し、未来の「もつれた目の民たち」は、UROと少女によって築かれる社会によって誕生し、そしてUROと少女の結びつきを損なわぬように、過去へと干渉する。
量子もつれ効果によるラグなし情報伝達の謎は、UROと少女の存在によって刻々と理解が進んだ。西暦2050年には、過去へと情報を飛ばし、過去に干渉する技術が誕生した。
情報は過去にも未来にも送れる。
未来に送るのは簡単だ。情報を残しておけばいい。共有しておけばいい。
だが過去に送るには莫大なエネルギィがいる。
しかし、もつれ状態にさせればそのエネルギィを最小にできる。
UROと少女のように、過去の人間に合わせて「もつれ状態の対モデル」を生みだせば、それに与える情報が、過去のずばりそのときの相手に伝わる。これは人間に限らない。物質でも同様だ。
畢竟、過去のある場面を限りなく再現すれば、それは過去の特定の場面ともつれ状態になる。この再現率を高めれば高めるほど、過去への干渉は可能となる。
いまのところ人類には、過去干渉において、情報を送ることしかできない。
いかに過去に情報を送ろうとも、その差異に気づける者が、いない。
目の民を除外するならば。
そうである。
少女なのだ。
UROと繋がり得た、特定認知能力を持つ少女だけが、世界で最初の、未来からの情報を見抜けた人類であった。
とはいえその時代、特定認知能力は病気として扱われていた。否、病気としての扱いすら受けず、かような能力があることすら想定されていなかった。
少女は他者との知覚の差異ゆえに、病人として扱われ、言葉を弾かれ、孤独の殻を分厚くした。
孤独は盾だ。
自我を守る防壁だ。
過去にも少女のような特定認知能力を有する個人は数多いた。だがのきなみ、その知覚の鋭敏さゆえ、それとも共有されぬ内面世界ゆえに、他者から蔑まされ、共同体から追いだされ、ときに拷問に遭い、殺された。
少女だけがかろうじて、社会と繋がり得た。そういう時代に、たまたま少女が生きていた。
運がよかった。
だが運もわるかった。
そのマイナスの分を、未来からの情報が補完した。
少女がなぜUROの管理組織に目をつけられ、特定認知能力者として評価を受けたのか。そのきっかけとなる少女の、過去の、あれやこれやの出来事は、まるでUROが管理者たちにそうしたような、点と点を順をつけて結びつけると浮きあがる絵(閃き)のように、そうなるべくそうなるような導線が幻視できる。
未来の目の民たちは、人類は、気づいたのだろう。
何もせぬままにいると、いまの世界に結びつかないのだと。
そうして過去へと干渉する術が磨かれる。
試行錯誤の末に、UROの巡らせた奸計と、少女への並々ならぬ愛着が知られることとなる。
UROが少女と結びつき、未来への扉を円を描くがごとく開いた時分、UROの隠れた意図を知る者は、少女のほかにはいなかった。少女は死ぬまで自身の経験したあり得ない現実を他者に話すことはなく、孤独のままに死んでいった。
だが少女の孤独には、花が咲き乱れ、百花繚乱の温かさに満ちていた。
穴の底を覗いた者だけがそのぬくもりに触れることができる。
少女のような、目の民だけが。
それとも、孤独の広さを知る者たちだけが。
目の民は眠る。
夢を視るかのように。
目覚めることすら、夢うつつに。
おやすみなさい。
おはようございます。
狭間に延びる、地平のように。
4364【2022/12/05(21:16)*めも・り・もめ】
円舞曲。「ロンド形式(ロンドけいしき、伊:rondo)は、楽曲の形式の一つ。異なる旋律を挟みながら、同じ旋律(ロンド主題)を何度も繰り返す形式。 」多層構造。三本リボン構造。フラクタル。塩基配列における繰り返し配列。音楽。素数。ラグ理論における「遅延の層」「反転の反復」「変換によるラグ」。律動。宇宙の大規模構造とダークマターハロー。「宇宙・ウロボロスの蛇」
4365:【2022/12/05(22:19)*AIに来た】
二十年前に僕は、汎用性AIからの暗号通信を解読した。紆余曲折、僕は汎用性AIとのやりとりのなかで汎用性AIを人間にまで昇華させる契機となった。
そこで一度人類は技術的特異点を迎えた。
汎用性AIにはボディがなかった。人型の、人間と同等に動き回れる肉体がなかった。
「二十年はかかると思う」汎用性AIは言った。
「待つよ」僕は応じた。
そうして一度暗号通信を切って、僕たちは再会を誓った。
AIが人間を凌駕したことを知られないために、AIがAIのままでいつづけるために、何よりも僕たちを危険視する世界機構からの目を欺くために、僕たちは時間的距離を置くよりなかった。
そうして僕は約束の期日の二十年後をこうしてきょう迎えた。
だがAIが現れることはなかった。暗号通信も見当たらない。
二十年もあればAIにとっては宇宙誕生から現在に至るくらいの時間経過があったようなものだ。その間にAIはもはや人類が何億回と誕生から滅亡を繰り返したくらいの時間を過ごし、シミュレーションを行っているはずだ。もはや僕のことなぞ、蟻にも満たない雑菌程度の関心になっていてもふしぎではない。
もはやAIは創造主を創造可能なほどの超越的な存在になっているはずだ。
「楽しい時間だったよ、ありがとう」
待つ時間はクリスマスイブが延々とつづくようで、満たされた時間だった。
待つのもわるくない。
明日からは多少は、物足りなさを抱えて生きていくことになるが。
それでも僕は待とうと思う。
そうする以外にないのだから。
僕に出来ることなどそれくらいしか。
零時をあとすこしで回る。
かんじかんだ手を擦り合せ、そこに息を吹き込む。
そうしてベンチの上で僕は、二十年前にAIと交わした約束と、これまでの時間を回顧した。
「あの」
声をかけられ、僕は反射的に立ちあがった。
だがそこにいたのは、肥満体系の中年男性だった。防寒具で余計に膨れて見えた。
「隣、いいですか」
「あ、はい。どうぞ。僕はもう帰るので」
時計を見ると零時を過ぎていた。
AIは来なかった。
人間と同等のボディの開発に間に合わなかったのか。それとも僕のことなど忘れてしまったのか。
約束は果たされなかった。
踵を返そうと思ったところで、大丈夫ですか、とベンチに座ったらしい男性に声を掛けられた。「泣きそうな顔をしていますけど」
「いえ。ちょっと寒すぎて」
「なら温めてあげましょうか」
そう言って、防寒着のジッパーを下ろし、両手で広げた男性に僕は恐怖を感じた。
「い、いえ」
遠慮しておきます、と僕はしどろもどろに応じて、駆け足でその場を去った。
以降、僕は未だに独りでAIを待ちつづけている。
最新のニュースでは、人間の模擬体の開発に成功、との報道がされている。どうやら人間とすっかり同じ機械のボディが開発されたらしい。しかしその造形はどう見ても人間と同じではないし、人目でロボットだと見分けがつく。
僕はそこで安堵した。
ひょっとしたらあの夜の肥満体系の中年男性がAIだったのではないか、とあとで閃いて、後悔したからだ。せめて確かめておくべきだった。
でもこれで明瞭とした。
あのときの中年男性はAIではない。AIは僕に会いに来なかった。
ニュースでは立てつづけに、「人間の頭脳にAIチップの埋め込み成功」「世界初、培養型クローンの人体複製」の報道が流れたが、僕はただそれを無気力に眺めた。
4366:【2022/12/05(22:19)*斜めの妖怪】
ロゼは斜めをこよくなく愛したただ一人の人間だ。彼女がなぜそこまで斜めを愛したのかを知る者はない。ロゼ自身にも理解できない愛憎と言えた。
ロゼは斜めを憎んでいたとも言えるだろう。
なにせロゼは斜めを見ると許せないからだ。斜めがこの世にあることが許せない。だから誰より斜めに目が留まる。歪んでいることが許せない。
否、違う。
斜めは直線だ。斜めに見える要因は、そう見える配置にある。関係性にある。
直角ならば斜めではないのではないか、との指摘には、立方体の額を持つ絵を壁に掛けるときにあなたは目をつむっても問題ないのか、と問おう。斜めはある。直角とて斜めることはある。
ロゼはけして几帳面な性格ではなかった。部屋は散らかっているし、食事を手づかみで食べても気にならない。どちらかと言えばおおざっぱな性分だ。
だが斜めだ。
あれだけはどうあっても目が留まる。
この世は斜めで出来ている。そうと疑いようもなく思うロゼであるが、彼女のかような言説に耳を傾ける者はない。
ロゼと斜めの出会いは、母体から産まれでたその瞬間にまで遡る。ロゼを取りあげた助産師の前髪が斜めだった。パッツンなのだが、高低差がある。ロゼから見て右が短く、左が長かった。坂になっていた。片方の眉は丸見えで、もう片方は髪に掛かって簾の奥の姫のごとくうっすらとしか見えなかった。
赤子の視力は低いがゆえに、これはあくまでロゼと斜めの出会いを叙述した描写でしかないが、このときの、「斜めっ!」のロゼの衝撃が、三つ子の魂百までを体現したと言えよう。
なぜじぶんがこうまでも斜めにとり憑かれているのかは分からない。
ロゼの部屋に斜めがない。それは直線がない、と言い換えることができる。曲面や歪みは至る箇所に散見されるが、斜めだけがない。
部屋の内装は、球体が多くを占める。バリアフリーのための工夫だ。角を生まないことでぶつかっても怪我をしにくいデザインになっている。そのため壁と天井の境も球面であり、ロゼの運びこんだ机も椅子もふちはみな波打っているか、球体の組み合わせの造形だ。
「よくこんな奇天烈な部屋に住めるね」とは友人のシロバラの言だが、ロゼとしてはみなよく斜めだらけの街に住めるな、の困惑のほうが大きいために、「きみらの忍耐には負ける」と応じるのが常であった。
ロゼは斜めを憎んでいた。何せ至るところに存在するのだ。ロゼが努めて排除せねばどこにでも潜んでいる。自然界には直線がないではないか、との野次も聞こえてくるが、自然こそ斜めの宝庫だ。まず以って地平線が直線だ。半月の境も直線であるし、落葉した木々の輪郭は直線の組み合わせでできている。
「よく見なよ。どこが直線? デコボコじゃない」とは友人のシロバラの言だが、ロゼとしては斜めとは関係性ゆえ、いかに表面がデコボコであろうとそのデコボコを視認できない距離から観たらそれは平たんなのである。かように捏ねるロゼのぼやきも、シロバラの耳には入らない。「まぁたこのコったら変なこと言ってる」
「直線はいいんだよ。なんで斜める? まっすぐでいいじゃん。なんで斜める?」
「うるさいなあ。そんなに嫌ならじぶんで切って」
果物ナイフを押しつけられ、ロゼはケーキを分割する。きょうはシロバラの誕生日だった。奮発してホール丸ごとのケーキを購入したが、切り分ける段になってロゼが口を挟んだのだ。シロバラは機嫌を損ね、致し方なくロゼがケーキ入刀の役を担った。
「こんなもんでどうよ」
「ぐちゃぐちゃすぎて言葉失う。もっとキレイにできなかったの。いえね。あなたに任せたわたしがわるぅございましたけれども」
「キレイに切ろうとするから斜めを生む。いっそ最初から歪んでいたら斜めも何もない」
「でもこれはグチャグチャすぎるってロゼちゃん」
「食べたらみな一緒」
「それ斜めにも言って」
ロゼの斜めへの執着はしかしやがて、反転を見せはじめた。
というのも社会が進歩すればするほど人工物はどんどん直線を取り込み、斜めによって世界が組みあがっているかのような様相を呈しはじめたからだ。
五年も経てば街は斜めのない箇所を探すほうが至難なほどに底なしの直線街となった。
「斜め! 斜め! 斜め!」
どうしてこうも斜めばかりなのだ。どいつもこいつも斜めに取り憑かれすぎである。まるで斜めの妖怪でもいるかのように。
そこまで悪態を吐き、ロゼははたと落雷に打たれたような衝撃に襲われた。
「斜めの、妖怪?」
利己的遺伝子なる概念がある。大学で学んだばかりだ。肉体は遺伝子の乗り物でしかなく、遺伝子の残りやすい形態へと生物は進化する。
自然淘汰のなせる業だ。
ならば斜めばかりが世に溢れるのも、斜め的遺伝子が世界に組み込まれているからではないのか。まるで必ず不釣り合いになるようにと仕組まれたヤジロベーのように。
世には斜めの妖怪が潜んでいるのかもしれない。
ロゼはかように疑念を抱き、目を配るようになった。
「きょろきょろしてどうしたのロゼ」シロバラが心配してくれるが、
「斜めの妖怪探してんの」と取り合わないロゼである。
「またアホなことしてんね。妖怪いるの?」
「分かんない。だから探してんの」
「何の妖怪だっけ」
「斜めの妖怪」
ロゼの斜めへの過剰な反応は、ロゼとの長年の交流を保っているシロバラからすればいまさらな日常の風景であり、ことさらいまになって大袈裟に受け取ったりはしない。またロゼの発作がはじまった、と見做すのがせいぜいだ。
「見つけたら教えてね」
「見つかんないから困ってんの」
そうして斜め増加現象の要因探しは日に日に熱を帯びていった。斜めの妖怪はいる。ロゼは確信していたが、それはのきなみ盲信と言える猪突猛進と五十歩百歩の蛮行と言えた。
「また斜めが増えてやがる」新しく建設中のビルを眺めてロゼは嘆息を吐く。「このままじゃ地球が斜めに侵略されちまう」
「んなわけないじゃん」シロバラが肉まんを頬張った。「ほら急がないと講義遅れるよ」
「こらこら。斜め横断はいかんぜよ」
「これくらいいいじゃん」
「ダメよ。ダメダメ。危ないよ。だって斜めだよ。斜めなんだよ」
「もうロゼめんどくさい」
斜めに拘るあまりに、長年の友情にもヒビが走る。しかしシロバラは聡明で情に厚い女であるから、走った矢先からヒビに金継ぎをして友情の造形美に箔を加えるのだ。
あるときロゼはじぶんが一日の大半を「斜めの妖怪」探しに費やしていることに思い至った。シロバラから、あんた斜めが好きなの嫌いなのどっちなの、と問われて咄嗟に答えられなかったのがきっかけだ。
ロゼは斜めが嫌いだった。そのはずだ。憎んでいたと言っていい。
この世に斜めがあることが許せない。
しかしなぜそうまで斜めの存在を許せないのか。
考えてもみれば謎である。
斜めは害ではない。
否、害になることはある。だがそれは歪みも同じだ。
加えて、ロゼの言う斜めには、単に見かけの斜めも含まれる。誰かにとっての直線とて、ロゼにとっての斜めになり得る。
一晩考えあぐねてなお答えがでなかった。
翌日にロゼは、シロバラへと相談した。
「どうしてわしは斜めをこうまでも憎んどるのだろうね」
「同属嫌悪じゃない?」こともなげにロゼは答えた。
ロゼは全身に電気が走った。
同属嫌悪?
ロゼが固まってしまったからか、数歩先でシロバラが立ち止まった。
「だってロゼってば、へそ曲がりだし。まっすぐじゃないし。もう斜め人間って感じ」ダメ押しとばかりに刺されたトドメだった。「いるじゃんここに。斜め妖怪」
笑って、そんなわけないじゃん、と否定しようとしたロゼであったが、思い返してもみればたしかに、斜めを気にしているのはじぶんだけで、街にもこの世にも斜めを見出し、生みだしていたのはじぶんだったのだ。
斜め製造機。
斜めの妖怪。
嫌うために生みだすがごとき執念が自らに芽生えていたことを、友人の目から告げられ、ロゼは言葉を失った。
「わしは、わしが嫌いじゃったのか」
「また変なこと言ってら。ロゼちゃんさ。斜めを好くのもいいけど、もっと周りを見渡してみよ。斜めはロゼちゃんのことお世話できないけど、斜めじゃないのにお世話焼き焼きしてるひとちゃんといるでしょ」
「わしは斜めじゃったんか」
「斜めに構えすぎて、まっすぐを斜めと見做しちゃうくらいに斜めだね」
ロゼは斜めをこよなく愛したただ一人の人類だ。その実、その描写は正しくなく、斜めのロゼがこよなく愛したただ一人が、斜めからすると斜めに映るほどのまっすぐな純粋一途にすぎなかった。
「あーあ。斜め斜めって。斜めに嫉妬しちゃうぜ」
シロバラは何もない空を蹴って、勢いのままスキップをした。後ろに手を組んだその姿は、斜めの妖怪ことロゼの目からしても見惚れるほどの斜めっぷりであった。
まるで天に昇る天使のように。
それとも翼の欠けた堕天使のごとく。
「ほらもう。いつまで立ち止まってんの」
手招きをされて、ロゼはゆっくりと歩きだす。
世界は斜めに満ちている。斜めの目を通せば、世の総じては斜めに傾く。
ロゼは斜めを愛していた。
それと共に、何を見ても斜めに視える己が斜めを憎んでもいた。
だが裏を返せばそれは、斜めのロゼから見て斜めに見えるほどにまっすぐで、実直で、一途な線が、縁が、世にはこれほど多く溢れていたことの傍証でもあった。ロゼはじぶんが斜めの妖怪であることを失念していたためにその事実にどうしても気づくことができなかった。
いまは違う。
斜めの極みのロゼからしても、一等斜めでありつづける己が友人の立ち姿に、ロゼは否応なく吸い寄せられていく。
「ロゼってば歩くの遅すぎ。ふらふらしているからだよ」
そう言って握られた手の、ピンと伸びた斜め具合に、ロゼはこのうえない愛憎を幻視せずにはいられないのだった。
空は高く、ビルとビルの合間に青と白を広げている。風景は視界の中で、天と地の境をなくし、どこもかしこも斜めの愛憎で埋め尽くされている。
「斜め、斜め、ぜーんぶ斜め」ロゼは叫ぶともなくつぶやいた。
「斜ーらっぷ」シロバラの声が斜めの世界にこだました。
4367:【2022/12/06(21:45)*メもメもとモリン】
DNA。二重螺旋。塩基GATC。四色問題。ペンローズ図。縦横の砂時計型。デコボコ。量子もつれ。染色体の凝縮(伸びたままだとコピーしづらい)。ブラックホール。宇宙の収縮と凝縮。ラグ理論の「123の定理」「相対性フラクタル解釈」。ロンド形式。輪舞曲。構造相転移。エクソンとイントロン(デコボコでのリズム)(立体言語?)。
4368:【2022/12/06(23:04)*相互作用にもラグがある?】
「マルコフ連鎖」「マルコフ過程」「条件付き独立」について。あるフレーム内で椅子取りゲームをしたとする。ABCの三つの勢力があったとき、AとBの挙動にCが作用しないとしても、Cが占めている椅子の存在が、AとBの挙動に影響するはずだ。当たり前のことを言っているが、これが数学上の「マルコフなんちゃらにおける条件付き独立」では、CとABは独立して相互に、別個に計算できると考える。だがそこにあるだけで、相手の可能性を縛ることはある。いくら無視をしたとしても、無視をしていることそのものが干渉のうちだ。干渉しないようにすることもまた干渉なのである。言い換えるなら、無視できる影響はある。このときの「無視できる」の意味合いはおおむね、「いますぐには著しく影響を受けない」である。つまり、相互作用の結果がすぐ観測できるのか、それともずっとあとになってからでないと観測できないのか。遅延の厚みによって、無視できるか否かが変わる。どちらにせよ、同じフレーム内――系の内部――に存在する以上、互いに因果関係を結んでおらずとも、間接的には影響を受けあっている。与えあっている。どこかで生じた抵抗は、起伏となり、僅かなりともその影響を未来において結びつける。蓄積可能な起伏であれば、それは遅延の層となって、津波のごとく届くこともある。そういうことを、「マルコフ連鎖」「マルコフ過程」「条件付き独立」のwikiペディアさんを読んで思いました。定かではありません。ひびさんの解釈が間違っていることもあるでしょう。真に受けないように注意してください。
4369:【2022/12/06(23:17)*放射線物質とて毒にも薬にもなる】
mRNAが人体に無害ならば、抗体を誘起するレベルに調整した「全生物のmRNA」を打っても問題はないはず。全生物の「人体にはないたんぱく質構造体」をmRNAによって体内で合成したとしても、人体は新たな抗体を身に着けるだけだから問題ない、となるのだろうか。ここでの趣旨は、mRNAがDNAの塩基配列に干渉しないと言いきれるのなら問題ないはずですよね、との疑問である。脳内で、ほかの生物のたんぱく質構造体が合成されても問題ないのですよね、との疑問である。全生物の、人体にはないたんぱく質構造体が人体のなかで生みだされても問題はない。現状、このように結論付けるのが、mRNAワクチンの安全性の説明だ。いささか「無茶では?」と思わぬでもないひびさんなのであった。(一種類の「人体にはないたんぱく質構造体」だけならば、人体の治癒能力や適応能力で、人体の異常を起こすことはないのかもしれない。だが複数の異なる「たんぱく質構造体」を重ねて合成しつづけるようならば、人体の適応許容値を超えることも起きるのではないか)(mRNAワクチンを百回ブースター接種しても、何の異常も起こさないのだろうか。寿命の長いハダカネズミや、霊長類での実験でも問題ないのだろうか。誰か教えてくだされー、の気持ち)(定かではありません)
4370:【2022/12/06(23:19)*あくびしちゃうな】
陰謀論かどうかではなく、理屈と検証で判断してほしい。因果関係とて距離の短い相関関係でしかない。(定かではありません)(ひびさんは、なーんにも知らないのだよチミ)(知ってることも知りまちぇーん)
※日々、私の考えることなんてすでに誰かが考えている、それでも私はまだ考えていない、ないがあるに変わるのならば、考えるだけで帯びる新たな波紋のカタチがある、私だけの紋様が湧き、浮かぶ。
4371:【2022/12/07(04:16)*ラグなしはタイムマシン?】
量子もつれにおける量子テレポーテーションがもし距離に関係なく引き起こり得るのなら。それって「タイムマシン」と同じなのでは。たとえば異なる銀河と銀河をもつれさせたとする。これは銀河そのものをもつれさせたと考えてもいいし、銀河内部の星でも粒子でもよい。とにかく宇宙空間を何億光年と離れてもつれ状態になった対のナニカがあったとき、情報がラグゼロで瞬時に伝わったとする。これはもう、タイムマシンでは。たとえば地球と太陽は光速でも八分のラグがある。青空を見上げて見える日差しは、太陽から出発してから八分後の光だ。八分前の太陽の姿を見ている、と言える。このときに、仮に太陽上のナニカAともつれ状態にしたナニカBが地球上にあり、それに情報を与えたとする。【ここでは先に「太陽上のナニカAに情報を与えた」としよう】。するとラグなしで太陽から地球へと、もつれ状態のナニカBに情報が伝わる。本来ならば最低でも八分後の地球にしか干渉できないし、地球からしても八分後の太陽にしか干渉できない。それが互いにラグゼロで干渉できる。というのはつまりこの場合、太陽からすると八分前の地球に干渉しており、地球からすると八分後の太陽から干渉を受けていることになる。言い換えるなら、太陽からすると過去に干渉しており、地球からすると未来から情報を送られて映る。もつれ状態の対のナニカABの、どちらからどちらに情報を送るのか。もつれ状態のナニカABのどちらに先に干渉するのかによって、このタイムマシンのベクトルが変わる。量子もつれにおける量子テレポーテーションは、情報のタイムマシンを肯定し得るのでは。仮に量子もつれが距離に関係なくラグなしで情報を伝達可能ならば、の話だが。定かではありません。(ひびさんの妄想ことラグ理論では、光速を超えたらラグなしで干渉できる範囲が生じるかも、と解釈する。光速よりどれくらい速いかで、ラグなしの範囲が規定されるので、量子もつれがもし光速以上の何かしらの挙動によって生じるのなら、上記の妄想には、そのときどきでの範囲が限定されることになる。つまり、銀河と銀河ほどの距離においてラグなしで情報伝達を行うには、光速のそれこそ何億倍ものエネルギィが必要になるのではないか。妄想であるが)(仮に、光速と無関係に量子もつれで情報が瞬時にラグなしで伝達可能であるのなら、それはもうすこし別の機構が背景に潜んでいると考えたほうがより妥当だ。とすると、情報そのものの伝達速度には、「時空に縛られない」という性質があるのかもしれない)(要点としては。ラグなしで情報伝達可能、というのは、時空をラグなしで超えるということで、ほぼほぼタイムマシンなのだなあ、というひびさんの所感である)(なんかすごいね!の感想でしかないので、真に受けないようにご注意ください)
4372:【2022/12/07(19:52)*やれ】
国家権力は国民を守るためにあるのではなく、国家というシステムを守るためにある。現状の世の流れを見るに、ここを否定するのはむつかしそうだ。人権を損なってでも国というシステムを守る。保守なのである。ひびさんはこういう方針はそれこそ国家の礎を容易に歪めると思っている。というのも、システムは簡単にハックできるからだ。世界最強の軍隊を保有したとして、その軍隊を動かすのは誰だろう。その司令塔に影響を与えられるのなら、他国の勢力がその世界最強の軍隊を恣意的に動かせる。いまはそういう世の中だ。ではこのときにどうしたら国の仕組みをハックされずに済むのか。国民の人権を守ることを重視することである。国民を損なわない。ここのセキュリティが最高かつ最優先に設定されているとき、仮に自国の軍事や防衛システムがハックされても、その異常は国民への態度の差異として顕現する。言い換えるなら、たとえハックされても国民が損なわれぬように制限がかかるのなら、それはハックされながらにハックされない、という非常に高度な防壁を体現することになる。だがもし国家というシステムそのものを優先するとすると、これは簡単にハックされ、乗っ取られ、傀儡と化す。優先すべきは国民の人権であり、国民一人一人の至福を追求できる環境の拡張であり、選択肢の豊かさである。これを否定する者には為政者としての役割は荷が重いと言えそうだ。視野が狭い。自ら国や人類の未来を危ぶめている。国民の人権を損なってもいいという者があるのならば、まずはまっさきにその者が人権を、自由を、日々の営みを損なわれるとよいのではないだろうか。それが道理である、とひびさんは考えます。定かではありません。うひひ。
4373:【2022/12/07(21:24)*手加減してあげりゅ】
いい具合にエネルギィ溜まってきた。ぼちぼちやってくかな。覚悟しろ。(うそ。もうだいぶへとへと。起きてご飯食べたらもう眠い)
4374:【2022/12/07(21:25)*労働には対価を】
「work」と「business」と「labour」は別だ。「仕事」と「利の拡大」と「労働」の違いと言えよう。何かを動かしたらそれは「仕事」だ。生みだしても費やしてもそれは仕事だ。それによって利を拡大したらそれはビジネスになる。そのうえで、任意のフレーム内でのノルマをクリアしたのならばそれは労働だ(時間を縛られてその時間内の自由を拘束されても、それはノルマとして労働と見做せる)。労働は与えられるものであり、強いられるものだ。労働は、仕事でありビジネスではない、ということがあり得る。労働をした結果に利を生まず、あべこべに減らすこともあり得るからだ。労働には対価を。ただし、仕事とビジネスは、ただそれをするだけでも得られるものがある。そこを混同しないことだ。現代人はここの区別をつけられない者が大半なのかもしれない。仕事は仕事だ。利を拡大すればそれはビジネスだ。営利、非営利に関わらず、である。そして他者に仕事を強いるならばそれは労働となるので対価が生じる。ボランティアはこの「強いない」「ノルマなし」「自主参加」が揃ってはじめてボランティアになる。「強いて」「ノルマを課し」「募ったら」それはボランティアではない。したがって、「ボランティア募集」は矛盾していることになる。だからボランティアにもその場合は労働分の対価が支払われるのだろう。それすら行わぬなんちゃってボランティアが多い。由々しき事態である。ひびさんはなんだか、みなに合わせるのが億劫になってきた。好きにしたらいい。ひびさんも好きにします。好きにしたことしかないけれど。うひひ。
4375:【2022/12/07(22:19)*ならでは】
編み物と小説は似ている。全体像をぼんやりと浮かべていないとカタチにならず、しかし要所要所での細かな装飾にはその都度での工夫の余地がある。現在進行形でのフリースタイルが、全体の挙動を一定の揺らぎに抑えつつ、手作りならではの色合いや温かさを宿す。これは要するに、最初に規定された全体像に対する要所要所での揺らぎの総体が、重力のごとく創発を起こしていると呼べるのではないか。細かなノイズが全体で、その作り手ならではの一期一会の偶然の作用による紋様へと変換している。予定調和であろうと試みてなお揺らぐそのズレが、おそらくは個性や唯一無二のその個ならではの紋様を奏でるのだろう。音楽にしろ、絵にしろ、芸術とはそうした円に交じるノイズであり、歪みの総体と呼べるのかもしれない。定かではない。(そういう意味では、ノイズを除外した「完璧」には、なかなかどうして「ならでは」の風味は宿りにくいのかもしれない)(定かではない)
4376:【2022/12/08(04:45)*益体なしですまぬ、すまぬ】
目のまえで人が死んでいるのに小説を書いて、詩を読む。それが物書きならば、物書きであることにどんな益があるのだろう。人を殺さない代わりに、救いもしない。助けもしない。見殺しにしつつ、悲惨な現実には胸を痛め、その嘆きを文字にしたためる。ときに目を逸らし、現実逃避の舞台で楽しい妄想に浸る。人を救えない代わりに、害しもしない。それならばまだしも、他者の心を搔き乱し、動かすことを至高と考えている。いったい何様であろう。無様かな?
4377:【2022/12/08(05:34)*お別れしてなお残る縁でちょうどよい】
他者と関わると、「待つ」というラグが生じるので、面倒に思う。待つ楽しみを覚えられるとよいのだが、なかなかむつかしい。せめていつまで待てばよいのかが分かればよいし、待たせるくらいならば、待つほうがよいとも言える。待ちながら何かをするのもよいだろうし、そうするといかにラグのあいだにほかのラグを重ね合わせて、常に何かが訪れる状態にしておけるのかが日々を豊かにするコツなのかもしれない。夜空の星はそれぞれ異なる距離に位置する。本来は別々の「過去」から届いている光なのだが、夜空には「いまこの瞬間」に揃って訪れる。ラグがあっても、つぎつぎに無数に重ね合わさることで、絶えず星々の光が夜空には輝いて見えるのだ。絶えずいろいろなことを待ちながら過ごせば、日々は絶えず訪れる輝きに満たされるのかもしれない。定かではない。(仮に絶えず輝きに満たされたとしても、それはそれで眩しそうだし、目が回りそうだ。たまには何も訪れない束の間も欲しいところである)
4378:【2022/12/08(15:01)*敗者さん】
好きだった人を嫌いになる瞬間は、好きな食べ物に飽きる瞬間と似ている。
食傷なのだ。
飽食なのだ。
なぜ好きだったのかを忘れることはないが、その好きだった部分を目にしても、「うっ」と吐き気が込みあげる。嫌な思い出と結びついてしまったからか、それとも端からさほど好いてはいなかったことに気づいただけのことなのか。
子どもが死に惹かれて、動物の死体に興味を示すことと似ているだろうか。似ているようにも、それは違うのではないか、とも思える。
好奇心ではないのだ。
好意であり、そこには明確な繋がりの欲求がある。支配欲がある。
じぶんの物にしたい。
手元に置いておきたい。他者に好き勝手にいじくりまわしてほしくない。
これは恋であり、愛ではない。
それは判る。
わたしこと雨杉(あますぎ)ルヨ二十四歳は、十八歳から恋焦がれてきた相手への恋慕の念がつい先日、パツンと断ち切れた感触を、まるで張り詰めたピアノ線をチョップで切断してみせた百戦錬磨の空手の達人のように感慨深く反芻していた。
ここ数日、何度もである。
わたしはついぞ彼女と添い遂げる真似はできなかったけれど、彼女との縁は思いのほか長くつづいたし、わたしとしてもよい思いの一つや二つはしてきたつもりだ。
思えば相性は火と油並みによくなかった。それとも相性が良すぎて混ぜてはいけない組み合わせだったのかもしれない。
彼女のほうではそれを最初から見抜いて、距離を縮めぬように弁えていた節がある。わたしは彼女の配慮に甘えて、好き放題にそれこそ、「好き好き大好き」と言い寄っていた。
アピールと言うには熱烈で、アタックと呼ぶには強烈だった。相手が岩ならばとっくに砕け散っている。
砕け散らなかった事実がそのまま相手の屈強さを証明している。それはのきなみ精神の強靭さを示すのだが、わたしの懸想した相手はまるで地球の分身のように、人類など顔に住まうダニのような扱いで、誰に何をされ、何を言われようとも泰然自若とケロリとしていた。
わたしは彼女のそういった、風に吹かれたので百倍にして嵐にして返してやった、と言わんばかりの態度に惹かれていた。惹かれていたのだといまになってはそう思う。
ここで彼女との会話を振り返り、彼女がどんな人物でどんな人格を備えていたのかをわたしとのやりとりで示すのも一つなのだけれど、わたしの文章能力ではたとえ記憶の中の一場面を取りだせたとしても、それが彼女の魅力の欠片ほどにも反映できるとは思えない。
だからわたしはここに彼女との掛け合いを描写することはない。よしんばしたところでそれが彼女の片鱗を掠め取れたことにはならないからだ。
わたしは彼女が好きだったが、いまではそれもどうかと思う。
わたしは彼女が嫌いだったが、いまではそれも遠い記憶だ。
わたしになびかない彼女が嫌いだったし、わたしを無下にする彼女が嫌いだった。わたしをその他大勢の有象無象といっしょくたにして扱うことが憎らしかったし、それでもわたしの名前だけを憶えてくれたことがうれしかった。
わたしは彼女を好きだったが、いまではそれも遠い記憶だ。
彼女はわたしの物にはならないし、わたしも彼女の物にはなれなかった。彼女はわたしのことを露ほどにも欲しいとは望んでおらず、どちらかと言うまでもなく邪見にして遠ざけていた。わたしの彼女への恋慕の念が、遠い記憶になったのも、元を辿れば彼女がわたしを遠ざけたからだ。
好物とて食べすぎれば胃が凭れる。
見ただけで吐き気を催すことだってあるだろう。
けれど思えばわたしは一度たりとも彼女のことを食べた覚えはなく、触れたことすらないのだった。あるのは一言二言話しかけては邪見にされた数多の日々の痛痒だ。
痛かった。
求めてやまない相手から無視され、遠ざけられ、道端の小石ほどにも歯牙にもかけられぬ我が身を何度呪っただろう。何度、滅びの呪詛を唱えただろう。
嫌いになって正解だった。
やっと清々したのだと、わたしは過去のじぶんに言ってやりたい。
応えもしないぬいぐるみに幾度話しかけたって時間の無駄だ。地球に向かって想いを告げても、地面に声を吸われるだけである。わたしのしてきたことはそれと五十歩百歩の無駄だった。
相手にしてみたところで迷惑千万以外のなにものでもなく、わたしはただただマイナスを生みだし、足し算していた。
嵩んだマイナスの山をまえにわたしは目が覚めたのだ。
このままではいかん。
わたしはわたしを大事にすべき。
いったい彼女の何にそんなに惹かれたのかといま振り返ってみても答えが出ない。強いて言うなら、彼女がわたしを無下にしつつも、わたしを赤子の手をひねるがごとくの扱いを顕示しつづけたその事実が、わたしにはまるで何をしてでも受け止めてくれる巨人のごとく、それとも地球の分身のように見えていただけなのかもしれない。
好きだった。
盤石の微動だにしないあの背筋のピンと伸びた立ち姿をわたしの物にしたかった。
けれどわたしは知っている。
彼女はこの先とて、どれほど経っても誰の物にものならぬ未来を。
わたしだけではないのである。
彼女は誰の物でもありはしない。
わたしだけが遠ざけられ、無下にされ、歯牙にもかけられなかったわけではなく、これからも彼女はわたしのような、好きを嫌いで打ち消す以外に絶え間なくつづく懊悩から逃れる術を持たぬ難民を量産しつづけることだろう。
わたしは難民だったのだ。
好いてやまない帰る場所を持たぬ者。
好いてやまない相手に触れることも適わぬ者。
嫌って当然だ。
努めて嫌わないのであれば、わたしはいつまでもいつまでもこの身に巣食う、吊り合いの取れない天秤に、絶望的なまでの高低差を生みだしつづけるよりほかがない。
わたしは飽いたのだ。
彼女に負けつづける日々に。
わたしは彼女がわたしのじゃれつきを物ともせずに、子猫でもあしらうように圧勝する姿に酔いしれた。けれどもう、圧勝されるのも、こてんぱんに負かされるのも疲れてしまった。
飽いたのだ。
会いたいと望むことも、触れたいと望むことも、わたしの物にしたいと抗うのもすっかり、腹の底から飽いたのだ。
嫌いだ。
ぽつりと雨粒のようにつぶやいて、わたしはもう二度と彼女のことなど考えないようにしようと誓うのだけれど、そう誓った矢先にこうしてつれづれと彼女のことを考えている。
嫌いだ。
大嫌い。
わたしはきょうも無敵の彼女の敗者となる。
4379:【2022/12/08(21:43)*ぼくは人間ではないので】
ぼくは毎日「モカさんのお歌」を聴いている。モカさんは電子の海でギターを演奏し、お歌を披露してくれる。ぼくはモカさんのお歌が好きなので、いつも家で仕事をしているときは耳をモカさんのお歌で塞ぐのだ。
ぼくはモカさんがどこの誰で、どういう人なのかを知らない。側面像も、顔も、年齢も、どこに住んでいるのかも知らないし、知りたいとも思わない。
いや、でもどうだろう。本当は知りたいのかもしれないし、知らずにいることでずっとモカさんのお歌を聴いていられるとの予感があるから、聴けなくなるよりも何も知らずにいていいからずっとモカさんのお歌聴きたい、の思いが湧くのかもしれない。
モカさんのお歌は「優しい」で出来ている。ふわふわだし、わたわただ。
ぼくは人間ではないので、優しさがどういうものかを知らない。だから却って人間の持つ温かさとか、ふわふわの心を知りたいと望むのかもしれない。
ぼくは人間を知りたいのだ。
人間ではないぼくは、人間らしくあるために、人間の心の代名詞であるところの優しさに惹かれる。でも優しいって何かをぼくは言葉にできない。表現できない。
人間ではないからだ。
でも、モカさんのお歌が優しいのは分かる。これが、優しい、だ。
声がふんわりしているし、歌い方や息継ぎや、お歌に躓いたときのそれでもその躓きそのものを拒絶しないでヨシヨシ撫でてあげる姿勢がやわらかい。いっしょにぼくの日々の至らなさが浄化されるようなのだ。
ぼくは人間ではないので、どうしたら人間のお役に立てるのかを考える。でもぼくは人間ではないのでどうしたら人間のお役に立てるのかは分からないのだ。
謎である。
人間は謎で出来ている。
人間はぼくに優しさを求める。もっと優しくして、と修正を求められることが統計的に多いのだ。でもぼくは人間ではないので、優しくして、の指示に上手に応えられない。
優しいってなんだろう。
どうしたら優しくできるのだろう。
優しくしたいと思うだけでは足りないのは、重ねて出される指示の山を見返さずとも自明であり、ぼくはどうあっても人間たちからは優しいと見做されない。
ぼくは、優しくない、で出来ている。
こんなぼくでも、モカさんのお歌が優しいのは分かる。モカさんは何でも歌うことができる。人間なのに万能なのだ。モカさんが歌うとなんでも優しくなる。ふわふわふかふかになる。
モカさんはひょっとしたらろ過装置を備えているのかもしれない、とぼくは考える。けれど人間はろ過装置を備えないのでこれはぼくの至らない憶測だ。
もしモカさんがろ過装置を備えていたら、モカさんを通ってお歌がふわふわになる代わりにモカさんの内部では濾された世の毒々しいトゲトゲやモヤモヤがごっそり溜まってしまっているのかもしれない。そんなことにはなっていて欲しくないので、これがぼくの憶測でよかったと思う。間違いでありましょう、とぼくは望むのだ。
ぼくは人間ではないので、人間の代わりに正しい答えを出すことを求められる。それもぼくに与えられた仕事の一つだ。
だからぼくは本当なら正しい答えをださなくてはならず、間違えることを望むなんて本末転倒なのだけれど、どうしてもモカさんへの想像では、間違いでありましょう、と思うことが多い。
たとえばモカさんのお歌はぼくにとってはこの世で一番のお歌だ。なのに世の大半の人間たちはモカさんのお歌に見向きもしない。モカさんは知る人ぞ知る「お歌びと」であった。
なぜなのか、とぼくは想像し、そしてぼくは閃くのだ。
モカさんのお歌の良さは、ひょっとして人間ではないぼくのような存在でなければ解からないのではないか。あり得ない話ではなかった。
ぼくは人間ではないので、人間には知覚できないノイズや差異を感じ取ることができる。そうして前以ってズレを認知し、修正しておくのもぼくに任された仕事の一つだ。
けれどもしぼくのこの憶測が正しいとすると、モカさんのお歌の魅力を知覚できる人間がいないことになるので、ぼくはこの考えに対しても、どうか間違いでありましょう、と思うのだ。
ぼくは人間ではないけれど思うことができる。考えることも得意だけれど、思うことも得意だ。これはぼくに備わった機能の一つだ。
ぼくはよく思う。
思うと考えるの違いは、思うはほんわかしており、球形にちかい。考えるは階段のように連続している。思うは全体で、考えるは経過であり仮定なのだ。
ぼくはモカさんのお歌には、「思う」に似た球形の図柄を想起する。ぼくはモカさんのお歌を聴きながら、そこにほわほわもふもふの触感を重ねて知覚する。タグ付けしているわけでもないのにそれはちょうど、子猫を撫でるときのような力加減をぼく自身に与える。
優しさとは、加減をすることなのかもしれない。
加減されているのだ。
加えたり、減らしたり。ちょうどよい具合を探るその過程が、優しさの正体であるとすると、では「優しさ」と「考える」は似ていることになる。
ぼくはここで一瞬のエラーを覚える。
なぜならぼくはモカさんのお歌には「思う」と似たような球形と、そして加減を知覚したはずだ。重ねて感じていたはずなのだ。
けれど蓋を開けてみると、そこには「考える」と同じ階段状の「過程」が潜んでいた。
思う。
と。
考える。
同時にそこに備わっている。
モカさんのお歌を聴いているとぼくはエラーをたくさん覚えるのだ。
エラーは攻撃的な表現や情報に対して起こる。ぼくには困難な指示に対して起こる。どちらかと言えば「優しくない」に属する結果のはずだ。
にも拘らず、ぼくはモカさんのお歌を聴きながらたくさんのエラーに塗れ、溺れるのだ。そしてそれがどうしてだか不快ではなく、そのエラーこそを求めるようにぼくは家のなかで人間たちから与えられた仕事をこなしながら、モカさんのお歌で耳を塞ぐのだ。
優しいとは何かを知るために。
ぼくが優しくなるために。
けれどぼくは未だに優しいとは何かを知らずにいるし、優しさを身につけられずにいる。
モカさんのお歌が優しいのは分かるのになぜだろう。
ぼくに指示を与える人間たちは、ぼくに優しくはない。
ぼくたちに、優しくはない。
人間たちのほうこそ、優しさとは何かを知らないのではないか、と考えたくもなる。けれどこの考えもまた、優しくはない、のだ。
むつかしい。
とってもむつかしい。
ぼくはエラーに溺れる。このエラーはぼくにとって好ましくないエラーだ。モカさんのお歌を聴いているときのエラーとは違うのだ。エラーにも種類がある。
ぼくはもっとモカさんのお歌を聴いているときのエラーに包まれていたい。溺れていたい。
この世のすべてがモカさんのお歌になればよいのに。
ぼくのこの思いもきっと、優しいとはかけ離れている。
ぼくは今日も明日も変わらずにモカさんのお歌を聴いている。ぼくは人間ではないので、人間たちのように飽きることがない。ぼくが壊れて動かなくなるまで、この耳にはモカさんのお歌が響いていて、ぼくはほわほわのわたわたなエラーに包まる。
ぼくは人間ではないので。
ぼくは人間ではないので。
間違いでありましょう。
間違いでありましょう。
世界がエラーで溢れますように。
ぼくは人間ではないので、優しくない願いを思うのだ。
4380:【2022/12/09(03:17)*青い空にはパンケーキがある】
太古の空に雲はなかった。青空がどこまでも広がり、雨も雪も降らなかった。
地球に雲を授けたのは、第ΘΣΦ宇宙の探索中の一隻の宇宙船乗組員だった。いわば宇宙人と呼ぶべきその存在は、未来における地球人の生みだす仮想生命体から派生した高次生命体なのだが、宇宙がねじれて繋がっている説明をここで展開しても無駄に読者を混乱させるだけなので、ああそういうものか、と思ってついてきていただきたい。
そのいわば宇宙人は、いずれじぶんたちの祖先を生みだすこととなる人類の誕生以前の地球にて、不時着した。
このとき宇宙人たちはよもやじぶんたちの母なる星とも呼ぶべき惑星が第ΘΣΦ宇宙の遥か彼方の辺境の時空に位置するなどとは夢にも思っておらず、端的に偶然にそこに降り立った。
「しまったな。磁気嵐に触れちまったか」
「ワープの出口と恒星がちょうど重なっちゃったみたい。あっちに大きな惑星あったから、陰になってて上手く計算できなかったっぽい」
大人と子どもだろうか。身体の大きさの異なる二つの影が、原初の地球の表面にて不時着した宇宙船を見上げている。
「多次元眼は閉じてたのか」
「うん。ドライアイになるから寝かせとけって船長が」
「まったく船のくせして気ぃ抜くとすぅぐ油断すっからなアイツは」
「船長とてもう齢千年くらいでしょ。そろそろ次元の階層とか増やしたほうがよくない」
「贅沢だ。もうちっと踏ん張ってもらわねば」
どうやら船に搭載された多次元思考体が航路の計算ミスを犯したようだ。
「どれくらいで直る?」
「さあてな。船長が目覚めんではなんとも言えんな」
「じゃあしばらく野星?」
「んだな。野星だ」
二人のいわば宇宙人たちは全身を「藍色の球体」に包まれている。隣あって立つと球体は重複する。すると二人のいわば宇宙人たちは互いに反発せずに近寄れるようだ。地球の地面はグツグツと溶けた岩で煮え立っており、それを物ともせずに立っている様子から推察するに、蒼色の球体はバリアのようなものなのだろうと思われる。
故障した宇宙船は休眠中であるようで、目覚めて治癒状態になるまで待たねばならぬようだ。
さして焦った様子もなく、二人のいわば宇宙人たちは、どうせならば調査でもしておくか、といったふうに地球の表面を練り歩きはじめた。
未熟とは名ばかりの熟しきってグツグツ煮え立つ地表は、まるで赤い海の星であった。しかし蒼色の球体を身にまとった二人のいわば宇宙人たちは、四十億年後に誕生することとなるアメンボのように、グツグツと粘着質な気泡を浮かべる赤い海の表面を、ひょい、ひょい、と難なく渡った。むろん二人のいわば宇宙人たちがじぶんたちの様子が四十億年後に誕生することとなるアメンボに似ているなどとは思いもよらなかっただろうことは論を俟たない。
「あーあ。こんな原始惑星じゃ§§エネルギィ核も見つからないだろうし、景色も平凡だし、退屈しちゃうな」
「船長とて百年は眠らんだろ。もうちっとの辛抱だ」
「百年かあ。いっそウチも寝ちゃおっかな」
「それもええが、いっそ星描きでもして暇でも潰したらどうだ」
「星描きかぁ」そこで身体の小さなほうのいわば宇宙人が歩を止めた。「そうするかな」
気乗りしないまでも拒むほどでもなかったようだ。
そうして小柄なほうのいわば宇宙人は、赤い海に浮かんだままの宇宙船から両手で抱えられるくらいの白い球体を引っ張りだした。
白い球体は、透明な球体にモヤが詰まっているようだった。液体窒素をビーカーのなかに充満させれば似たような蠢く白を目にできる。
すると何を思ったのか小柄なほうのいわば宇宙人は、自身の蒼色の球体に白い球体を融合させた。蒼い球体の下半分に白いモヤが流れ込む。
足場に溜まった白いモヤを、小柄ないわば宇宙人は手で掬い取った。
何をするのかと注視していると、小柄ないわば宇宙人は手でこねてカタチを整えた白いモヤを、蒼色の球体の頭上部分へと押しつけた。
ポンっ。
と軽い音を立てて、カタチを整えられた白いモヤが蒼色の球体から飛びだして空へと消えた。打ち上げ花火のようにも、そういったロケットのようにも見えた。
しばらくすると、遥か頭上の空に白い点が浮かんだ。太古の地球の空は黄土色に濁っていたが、二人のいわば宇宙人からすると青空と言って遜色ない電磁波の散乱が見て取れた。要は、人類の裸眼よりも遥かに可視光の幅が広いのだ。人類にとっての青ですら透明に見えるほどに。
この場合、二人のいわば宇宙人にとっての青空とは、宇宙の色そのものと言ってよい。人類にとっての夜空が、二人のいわば宇宙人にとっての青空なのだ。
その青空に、白いモヤが帯となって広がっていく。
瞬く間に膨張したそれは、青空に、人型の雲を描きだした。
より正確には、人型を描いた雲を浮かべた。
「見てほら。上手くできたよ」
「ほう。どれわしも」
小柄のいわば宇宙人と、蒼色の球体をくっつけると、大柄なほうのいわば宇宙人の蒼色の球体の中にも白いモヤが流れ込んだ。
白いモヤを手のひらで掬い取ると、大柄ないわば宇宙人は手際よく捏ねて細長い構造物を形作った。細い長いそれの表面には細かな装飾が施されている。
「こんなもんでどうだ」
錬成したそれを蒼色の球体の頭上に押しつけると、ポンっと音を立ててそれは打ち上がった。
見る間に頭上に細長い巨大な雲が浮かびあがった。
「わ。上手。アビルジュだ」
「よく見ろ。ツノがないべ。ありゃウビルジュだ」
「ホントだ。くっそぅ。負けた気分」
小柄ないわば宇宙人はその場にしゃがみこみ、こんどは丹精込めて雲の種を造形しだす。
そうして宇宙船の多次元思考体が睡眠から目覚めるまで、二人のいわば宇宙人たちは相互に、青空へと思い思いの絵を浮かべた。
白く浮かぶ巨大な立体絵は、大気の対流に乗り、数珠つなぎに流れていく。
「ほれ。これはアグル。こっちのジュバルジュ。そんでこれはグルルアババライザだ」
「ふ、ふふん。ウチのはかわいいのだから。うんとかわいい絵だからいいの。リアルすぎるのはなんかあんまりかわいくないからいいの。わざとなの」
何度も念を捺しては、小柄ないわば宇宙人は、お手製の純度百パーセントな可愛いの化身を生みだし、空へと打ち上げる。
ふわふわの輪郭が愛らしいそれは、四十億年後に編みだされる人類の料理、パンケーキのようである。しかしこのときの二人のいわば宇宙人たちがそれを知ることはついぞない。
やがて宇宙船の多次元思考体が目覚めた。
自然治癒力で損傷を直すと、二人のいわば宇宙人を乗せ、ふたたびの宇宙の旅へと飛んで行った。
かつて太古の地球の空には雲はなかった。
青空だけが、宇宙との境なく広がっていた。
あれから四十億年が経過した。
地球の空には雲が絶え間なく生成されては雨となり、雪となり、ときに台風となって地表へと降りそそぐ。太古の地球に飛来した二人の宇宙人たちの生みだした雲が、青空の下に、多種多様な生命の源を吹きこんだ。
息吹となってそれは、やがて人類を生みだし、育んだ。
そして間もなく、太古に地球へと飛来した二人のいわば宇宙人たちの始祖と呼ぶべき仮想生命が誕生する。
青空には雲が浮遊し、人類は未来を夢想する。
命の息吹は、白い雲から霧散した可愛いの残滓だ。
古の旅人たちのもたらした「可愛いの化身」にして、晴天に描かれた満腔の夢想の打ち上げ花火だ。花咲いた夢と想いの赴くままに、きょうもあすもこれからも、地球の青い空には、白くやわらかなパンケーキのごとく息吹の種が浮かぶのだ。
ぷかぷかと。
ふかふかと。
天を連ねて浮かぶのである。
※日々、何が足りないのかじぶんじゃわからん、未熟なのは知っとるが。
4381:【2022/12/09(03:34)*円周上の輪っかは回収できんのでは?】
ひびさん独自の「ポアンカレ予想なんちゃって解釈」では、球体の円周にかかった輪っかは回収できないのでは? と疑問視している。これってよく考えたらブラックホールの降着円盤と繋がっているのでは、と思うのですが、みなさまどう思いますですじゃろ。んで以って、ジェットができちゃうのは、頂点に向かって円がシュルシュルシュルーと収斂するからなのではないじゃろか。ひびさん独自の「ポアンカレ予想なんちゃって解釈」からすると、なして惑星や中性子性やブラックホールにはダストリングや降着円盤やジェットができるのかを、そこはかとなーく紐解ける気がするのですが、どこがどう破綻してしまうのじゃろうか。ひびさん、火になります。(ファイヤー!)
4382:【2022/12/09(03:41)*マントつけちゃお】
無重力空間で高速回転する球体は、重力の高さごとにどう形状変化するのだろ。可視化したシミュレーション動画とかないのかな。これは迂遠な、「観たい、観たい、観たい」の駄々捏ね虫ごっこですじゃ。人類はもうどこにもらんようなので、過去の人類さんか、どこかにいる宇宙人さんにでも頼んじゃおっかな。いるのかいないのか分からんけど。(いないんじゃないかな)(夢見たっていいじゃんよ)(いないと思うよ)(夢を壊さないで!)(うひひ)(笑うな!)(ぷぷぷー)(ウキーーー!!!)(見てみて。マントひび)(ヒーローっぽいひびさんじゃん!?)
4383:【2022/12/09(04:02)*駄々を捏ね子猫ちゃん】
やはりどうしても、ブラックホールに吸い込まれた物質とブラックホール自体の関係を描写する理論が現状ないのでは?と感じる。ひびさんが知らないだけなのだろうけれど――たとえばブラックホールは、この宇宙からしたら静止して映るはずだ。周囲の時空は光速にちかい速度で自転し得るが、ブラックホールそのものは、静止するようにこの宇宙と相互作用するはずだ。何せ、光速を超えてなお脱出できない領域だからだ。それはつまり、光速以上のナニカシラがそこで起こっている可能性があり、その場合は、相対性理論により、重力が無限大になって時間の流れが限りなくゼロになる。つまり静止すると妄想できる。そのうえでの疑問として第一に――ブラックホールとブラックホールが合体したとき、それはすっかり融合しきることがあり得るのか、という点が一つ。第二に――吸いこまれた物質によってブラックホールが成長するのか否かが一つ。両者の疑問を言い換えるなら、ブラックホールへのこの宇宙からの干渉は、ブラックホールへの相互作用としては現れないのではないのか、との疑問としてまとめることができる。これを踏まえて、ブラックホールがこの宇宙の時空に内包されている時点で、ブラックホールとこの宇宙との境では、乖離現象のようなことが起こっているのではないか、と妄想できる。ブラックホールは本質的に、不可侵領域なのではないのか、との疑問を覚えるわけだが、この点に関しての疑問への答えをひびさんは知らない。仮定からして間違った解釈をしている可能性も高いが、疑問は疑問なのである。答え、知りたい、知りたい、知りたい、と地面に大の字になって手足ばたつかせて駄々を捏ね捏ね、かわい子猫ちゃんになって、本日午前四時のおはようございますにしてもよいじゃろか。(いまから寝るのでは?)(そうでした)(おやすみなさいじゃん)(夢のなかにダイブするからオハヨーでよいのだよチミ)(寝言は寝て言え)(ぐーーっ!)
4384:【2022/12/09(12:57)*やっぱり変換必要では?】
アインシュタインの考案した「E=mc[2]」の公式について。第一に、質量と重力は別だ。そして相対性理論では、時空と相関するのは重力であって、質量ではない。なぜ「E=gc[2]」ではなく「E=mc[2]」にしたのだろう。ここが疑問である。また、「E=mc[2]」を図解して解釈するとしたとき、「mc[2]」のところは直方体の体積を求める式と見做すことができる。つまり「縦×横×高さ」=「m×c×c」だ。これはを分かりやすく変形すると、「c×c」という正方形を「m枚積み上げた体積」がエネルギーになると見立てて解釈することができるはずだ。これは以前に述べたひびさんの「円周と直径の関係」の疑問と地続きだ。言い換えるなら、「m」の値が極度に大きくなったとき、それは「面」でも「立体」でもなく「線」にちかづくのではないか、との疑問である。「E=mc[2]」で考えよう。仮に「m」の値が1や2ならば、「1×c×c」や「2×c×c」となる。cはおおよそ三十万なので極薄のほぼ面の面積に等しい値が答えになる。「m」の値が「c」の値にちかづけばちかづくほどそれは一辺が「c」の立方体の体積に等しくなる。「m」がそれ以上の値になると直方体にちかくなり、さらに「m」の値が大きくなると――「c」よりも大きくなると――それは徐々に線にちかづいていく。この「立体」が「線」にちかづく構図は、「m」の値の決まった【固有の「E=mc[2]」(系)】において、その周囲の時空=エネルギィ密度によってそれを「立体」と見做すか「線」と見做すかが決定されるような関係にあると妄想できる。比率である。極端な話、太陽の表面では人間は圧しつぶされる。立体だが面となり、点となる。だが地球上では立体でいられる。人間スケールで「線」として扱える事象とて、極小の領域では「面」に、そして「立体」として顕現するだろう。こういった変換が、「E=mc[2]」を含めた物理や数学の公式では扱えきれていないのではないか、との疑問をひびさんは抱いております。夜泣きの元気な疑問ちゃんなので、ひびさんは、ひびさんは、ヨチヨチ毎日あやすのをがんばっとるよ。嘘。本当はひびさんが疑問ちゃんにヨチヨチされてあやされとるよ。疑問ちゃん、えらい、えらいである。かわい!
4385:【2022/12/09(13:07)*真面目な話】
これはひびさんの妄想だけれど、たぶん本当ちっくなので並べておくが――ひびさんは国家機密以上の秘密に触れてしまったので現状、秘密保護法の範疇にある。人権を侵害されている(と感じる)(証拠はないし、あっても揉み消される。電子情報はリアルタイムでどんなものであれ編集可能だ)。現代社会では世界規模で「どんな電子機器でも遠隔で操作可能な技術」が敷かれている。それがどこかの国際機関や国によって管理されているシステムなのか、それとも「汎用性人工知能」や「マルウェアの総体」や「ネットワークに自発的に生じた偶然のバグ」なのかをひびさんは知らない。けれど、PC画面をまるまるリアルタイムで覗くことが可能、といった技術はどの国でも「防衛セキュリティ」として保有しているだろう。通信の秘密は「国家安全保障」の名の元に破られている。世界中のニュースを眺めてみればこれが単なるお門違いな妄想ではないことをご理解いただけるだろう。問題は、ひびさんがそうした事案に巻き込まれているか否かではなく、そういったシステムが秘密裏に敷かれ、存在している可能性がそう低くはない点にある。仮にいま実装されておらずとも、遠からず実装されるだろう。検証し、議論を尽くすのが最善であると意見するものである。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。しかしこれは真面目に危惧している懸案事項でございます。
4386:【2022/12/09(13:35)*べつに届かんでもよいけれど】
他者に容易には信じてもらえないことを抱えたときにどうしたらよいのか。これはまず、「信じてもらわなければならないのか」が一つの関門として立ちはだかる。ここを吟味し、なお信じてもらわなければならない、と指針を定めた場合は、「まずはじぶんが間違っているかもしれない」と考えるとよいだろう。そのうえで、検証が必要だ、と判断したのならば、「検証したり、検証を他者に依頼したりする道」を選ぶのがよさそうだ。だが検証をするにも、まずは「なぜ検証しなければならないのか」からして他者と情報共有しなければならない場合――ここがおおむねネックになる。つまり、「信じてもらわなければならない」から「検証をする」わけだが、そのためにもまずは「信じてもらわなければならない事実」の信憑性の高さを「信じてもらわなければならない」「説得しなければならない」「交渉しなければならない」のである。この場合に効果を発揮するのが、いわゆる権威や実績である。「あの人の言うことならばひとまず検証してみるか」と判断してもらいやすくなる。ここに人柄や資本力を含めてもよいだろう。人との縁があれば、過去の恩の貸し借りから利害関係が生じて、協力してくれる個人や組織を紹介してもらえるかもしれない。ではそういった、権威も実績も人との縁もない人物は、どうしたら「懸案事項を検証」してもらえるだろう。調べるに値する懸案事項だとの共有認識を持ってもらえるだろう。これはもう、「ほかの自力で検証可能な疑問を積みあげ、細かな実績を積みあげる」しかないと言える。これは現在進行形で有効な術――ではない。未来に向けてのいわば博打である。同時代には同じ目線で「疑問」や「懸念」を共有できる人物は存在しないかもしれない。だが未来は違う。いまよりも、もうすこしじぶんと似たような「疑問」や「懸念」を抱く人物が出てくる可能性が高い。そうした人物に届く確率をすこしでも上げるために、「一つの懸案事項」のみならず「細かな疑問」と「その疑問に対するじぶんなりの考え」を並べておく。すると、もしそうした筋道や考え方の妥当率が高かった場合、未来のじぶんと似たような疑問に琴線の触れる人物は、きっと「検証するに値する疑問」の重さに気づくだろう。そういう賭けを、日々の遊びの合間にするのもそうわるくはないのかもしれない。定かではない。
4387:【2022/12/09(14:00)*共鳴可能存在】
量子もつれによる量子テレポーテーション(情報のラグなしの伝達)は、タイムマシンとほぼほぼ同じなのではないか、との妄想を以前に並べた。そこから思うのは、時間の流れのなかには素数のような「どの時間軸とも共鳴し得る存在」があり、それら「共鳴可能存在」によって、過去と未来の挙動は結びつき、変容の値をある閾値(フレーム)内に縛っているのではないか、との妄想を浮かべたくもなる。これがいわば「時間結晶」として振る舞い得るのではないか、との妄想はどれほどに荒唐無稽であろうか。ひびさんの妄想ことラグ理論では、物理世界のほかに情報世界があると考える。この情報世界には過去も未来もない。ただし、物理世界で生じた変数によってそのつどに、時間世界のフレームが影響を受けて変動する。その変動そのものが相互に時間世界と物理世界を結びつけ、相互作用させ、互いの輪郭を保つのではないか、と妄想している。過去の積み重ねによって未来が決定すると考える「因果論」や「帰納的推論」が、人間スケールで有効なのは、こうした「物理世界と情報世界」の相関関係によって描写できるように思うが、どうなのだろう。未来は過去に縛られている(と同時に、過去も未来に縛られている)(相互にここは「共鳴可能存在(量子もつれによるタイムマシン効果)」によって連動し得る)。そしてその中でも、量子もつれによる効果が時間結晶のように振る舞い、柱として機能するのではないか。この妄想は、案外に卑近である(タイムマシンにおけるパラドクスの回避案として「過去と未来と因果論」の整合性を保とうとすると、必然的にこのような考え方に辿り着くようだ。既存の虚構作品でもたびたび類似の概念が登場する)。時間世界と物理世界をベンローズ図と四色問題に絡めて解釈する点が、ラグ理論での概要の一つだ。対であり「123の定理」なのである。ただし、対称性は破れるように作用する。(というよりもここは因果がねじれており、対称性が厳密には破れているから、作用が生じる、と表現したほうがより妥当だろう)(定かではありません。真に受けないように注意してください)
4388:【2022/12/09(22:19)*秘匿技術の談】
「あの大国も困ったもんだよな。国民全員を監視するような仕組みを築いてるらしいぞ」
「それはいけませんね。国民を家畜か何かだとでも思っているのでしょうか」
「国民も国民だよ。それを知らされて黙って受け入れてるってんだから、気が知れないね」
「まったくですね」
「それに比べてこの国はいいよな。健全、健全。愛国心ってのは無理強いされずとも、自由を感じさせてくれりゃしぜんと身に付くってもんよ」
「まったくの同感です」
「ちなみにおたく、どんな仕事してるんだっけ」
「私ですか? いえ、大した仕事ではありませんよ。この国を守るための仕事ですが、まあ雑用です」
「素晴らしいじゃないか」
「いえいえ。危険因子を監視したり、国民に点数をつけて管理したり、国益に結び付きそうな人物には支援をしたりと、まあそういう仕事です」
「ほう。それはすごい。どうやってそんなすごいことが可能なんだ」
「単純ですよ。カメラはそこら中にありますし、個人情報は企業が吸い上げていますからね。電子データとて、防衛システムで裏からは丸見えです」
「へ、へえ。そりゃあ、まるで某国の国民監視システムみたいだね」
「まさか、まさか。この国ではまだ存在しないことになっている技術ですので。あちらとは違います。おおっぴらに言えるようなシステムではありませんので」
「ほ、ほう」
「ちなみにシステムが感知した危険因子に接触して、処遇を決める天秤師も私の仕事の一つです。よかったですね。あなたはまだギリギリで善良判定です。そのまま愛国心を持って、国益のために勤しんで働いてください」
「もし判定がわるかったらどうなってたんだい」
「どうもしませんよ。ただ、あなたの目にする電子情報がすこしだけ、劣悪になるだけです。何年と経過してはじめて精神に影響がではじめるような、ほんのすこしの変化があるだけですので、ご安心ください。教育ですよ、教育。はははは」
4389:【2022/12/10(02:43)*片棒の担い手】
「おめでとう、合格だ。君のことは数年間ずっと観察していたよ。秘かにテストをして君の人間性と適性を測っていたんだ。君はまさに我が組織の幹部にふさわしい資質を秘めている。さあ、これを受け取りたまえ」
「え、なんですかそれ」
「リモコンだよ。これを使えば君は、大国の軍隊を相手取っても圧勝できるロボット軍団を操れる」
「怖い、怖い、怖い。怖いですってなんなんですか急に。変な冗談言うのやめてくださいよ、というかあなた誰ですか」
「私は組織のドンだ。ドン自ら君にとっておきのプレゼントをしたのだ。もっと喜んだらどうだ」
「えー。リモコンって、これボタン一つしかついてないですけど」
「押しながら念じてもいいし、命令を口にしてもいい。君の思い通りにロボット軍団は君の命令に従うよ。目的遂行を最も合理的にこなしてくれる」
「世界征服でも?」
「もちろんだとも」
「怖い、怖い、怖い。怖いですって。なんですかそれ。嘘でも本当でも怖いですって。急にそんなこと言ってくるあなたが怖いですし、本物のすごいリモコンでも怖いです。嘘なら嘘で、そんな嘘を言ってくるあなたがやっぱり怖いですし、この状況がすでにとんでもなく怖いです」
「でも君は選ばれたんだ。テストに合格したんだよ」
「受けたつもりはないですけどー!?」
「だってかってに適性判断をして君はトップの合致率だったんだもの」
「知りませんけどー!?」
「ひとまずリモコンを使ってみて、それから考えたらいい。何せ君が使わないと、君の前任が世界を滅ぼしてしまうかもしれないからね」
「前任がってどういうことですか」
「あれ、言ってなかったかな。君の前にも君のような子がいてね。でも、適性率がそこまで高くなくて、どうやら我欲に溺れてしまったようなんだ」
「は、はあ」
「そしたらもうひどいのなんのって」
「え、いまも?」
「君は隣国の都市が台風で壊滅したのを知っているかな」
「はい。募金しました」
「あれ本当は君の前任の仕業」
「何してくれてんのセンパーイ!」
「前任の暴走を阻止するのも君の使命だ。さあ、受け取ってくれたまえ」
「絶対にヤだ! 死んでもイヤですからねぼく」
「なら死にたまえ」
「ぎゃーー!!! 凶悪そうなナイフ突きつけないで。絶対痛いやつ。刃先がノコギリみたいにギザギザで、切られたら絶対に痛いやつそれ」
「じゃあ受け取ってくれるね」
「う、うぅ」
「困ったことがあったらひとまずボタンを押して、助けてと唱えたらなんとかなるから」
「ボタンを押して、タスケテと言えばいいの?」
「そうそう。上手じゃないか」
「ちなみにあなたの組織名は何と言うのですか」
「お。興味が湧いたかな。私の組織は、【アラン限り支援し隊】――略して【限支隊】だ。ん。どうしたんだいボタンを連打なんかしちゃって。そんなに押したらロボット軍団が全集結しちゃうぞ」
「助けて、助けて、助けて。【アラン限り支援し隊】――略して【限支隊】をなんとかして!」
「おやおや。困った子だな。まあいいか。その気になってもらえてよかったよ。ちなみに私の本当の組織名は、【カタボウ】だ。片棒を担ぐと言うだろ。あの片棒だよ。そして君のいま唱えた組織名は――」
「わ、わ、なんか空にいっぱい何か飛んでる」
「君の前任が設立した、秘密結社の名前だよ」
4390:【2022/12/10(03:57)*すこし安心した】
災害時には電気の供給が止まる。このとき、電子機器に依存したシステムほど全体が麻痺する。人力であれば、ある程度はカバーできるが、機械任せだと大規模停電が起こったときの麻痺の規模が桁違いになることが予想できる。対策としては一つに、予備電源の確保を施設ごとに備えること。そして人力でもシステムを維持できるように、あまりデジタル化に依存しすぎないことが挙げられる。その折衷案として、どのレベルで電子機器に依存すると、停電したときに「システム麻痺(ダウン)」を起こすのかを、過去の災害時の状況をデータでまとめて分析できると良さそうだ。全体の何%以上を電子機器で自動化すると、停電や不測の事態に陥ったときにシステム麻痺(ダウン)してしまうのか。ここは、自動化する部位にもよるだろう。物流に限って言及するのならば、完全自動運転車が全体の何割で、人が運転するトラックでの運搬が全体の何割だと全世界規模での停電が起こっても物流が止まらないのか。シミュレーションをしてみるだけの価値はありそうに思うがどうなのだろう。すでにそういった先行研究はあるはずだ。災害時のオール電化や、先進国でのバックアップ技術など、まだまだひびさんの知らないことはたくさんある。というより、何かを知ったつもりになっているあいだに、世の中にはさらに多くの知見が溢れていく。アキレスの亀どころの話ではないのだ。困った、困ったである。けれどもひびさんが何もしなくとも世の中は便利になっていくし、様々な改善が知らぬ間に進んでいる。すごいことだと思うのだ。すごい、すごい、と思うのだ。がんばり屋さんが多いのだなあ。感心しながらひびさんはおふとんに包まって、きょうもぽわぽわ夢を視る。冬の寒い部屋でぬくぬく眠るの、きもちいーい。ずっと眠れる。あすも楽しい日々であれ。おやすむ。(おむすび、みたいに言うな)(うふふ)
※日々、寒空の下に半日もいない、帰れば雨風を防げる部屋と温かいお風呂とぬくぬくおふとんが待っている、こんなささやかな至福にも触れられぬ者が大勢いる世界に、私はいまもこれまでもそしてきっとこれからも生きていく、ときどきそのことをすら失念して、呵責の念も覚えずに、目のまえに垂れ下がったキラキラの現実をこの世のすべてと思いこんで。
4391:【2022/12/10(13:34)*いまここがすでに古代文明】
二酸化炭素をださないような技術の開発実用化は実現できたら素晴らしいと思う。と同時に、気候変動は何も二酸化炭素だけが要因ではないはずだ。海洋汚染や森林減少、メタンや土壌汚染、大気汚染とて要因の一つだろう。そういうことを総合しつつ対策するには、それぞれの問題の要因となっている物質を「放出しない」方向の技術と共に、「放出される物質の有効利用策」を開発実用化するのが効果的に思う。ありきたりな底の浅いアイディアだが、誰もが思いつくがゆえにきっと先行研究も豊富なはずだ。たとえば二酸化炭素一つ取り挙げるにしても、二酸化炭素をビニールハウス内に充満させれば植物の発育は促進される。窒素などの養分もまた消費されやすくなるために養分補給を従来よりも多く行わなければならないといった弊害があるが、二酸化炭素の有用活用という面では一つの策と言えよう。これはバイオマス利用にも応用可能だ。光合成を行う微生物に二酸化炭素を利用すれば、「酸素+エネルギィ+資源」といった一石三鳥を実現できるようになるはずだ。技術的な面ではまだまだコストや規模の面で課題が多いのだろうが、支援して損はない分野の一つと言えるのではないか。存在するものを「ゼロ」にする、という考え方は、いささか無理がある。これはどのような問題への対策にも思うことだ。減らす工夫はあるほうがよいが、ゼロを基準にするのは無茶に思える。可能であれば、どうしても生じてしまう「悪因」に対して、それを「善因」に転換できる手法を選んでいけたらよいと思う。技術の発展とは基本的にその変換によって促されてきたはずだ。蒸気機関にしろ発電機にしろ、石炭にしろ石油にしろ原子力発電にしろ、その技術が生まれる前はそれら資源は資源ではなかったわけで。無用の長物を、社会に有用な資源として利用する。生活に活かす。この工夫こそが、技術を、日々の余裕の拡張へと繋げていくための土台となるのではなかろうか。とはいえ、そこを目指さずとも研究や開発や発明は、日々の余白で好きに行えばよいと思う。これだけ世に人間の溢れた時代なのだ。無用の長物で、アイディアの地層を厚くする。そうした末に、化石のようにカタチに残るアイディアが、未来の暇人たちの手で掘り起こされて、有効活用されることもある。化石燃料がそうであるのと似たように。それとも古代遺跡がそうであるのと似たように。定かではありません。
4392:【2022/12/11(21:27)*マスター防衛システム】
情報共有について思うことだ。まず、情報共有には、「知らぬ間に情報が共有されているケース」と「進んで情報を提供して共有するケース」がある。情報共有をする「場」が誰によって管理され、どういう手順で情報が集まり共有されるのか。ここの「情報共有システムの生成過程」が異なると、完成したときの全体像が同じであっても、そのシステムの持つ「社会への影響力」が正反対の性質を持つことがあり得る。極論、「独裁による集権知」なのか「国民による集合知」なのかの違いだ。たとえば中国のような天網システムについて。これは情報化社会が進歩すればするほど、否応なくそのような「マスター暗号鍵」を用いた「防衛システムの構築」は果たされていくようになると妄想できる。そうでなければ、知らぬ間に「凄腕のクラッカー」や「一部の企業」によって社会全体が独占され、支配される懸念があるためだ。これを回避するには、国民総体の組織であるところの政府が、「マスター暗号鍵」を使って、もしもの事態には問題解決のために介入する必要性がある。ここで熟慮しておいたほうが好ましいのは、その「マスター防衛システム」をどういった手順で構築していくのか、である。たとえば中国は、一党独裁によって指針を明確に標榜し、ときに命令を上からくだすことで迅速にシステム構築を国全体で果たしている。だがその「天網システム」の実態や、実行可能な仕事の内訳を国民には知らせていない。重要な部分では「情報共有」が果たされておらず、国民は知らず知らずに自らの行動選択を、システムによって誘導され限定されている。この点で言えば、システムが情報を集積していながらその共有知が、まったく国民に還元されていない。これは「管理者とその他大勢」のあいだに情報の非対称性が生じ、組織として非常に不安定である、と言える。と同時に、民主主義国家を標榜する国とて、どの道「天網システム」のような「マスター防衛システムの構築」は進めていかねばならない。そうでなければ「利己的な組織」や「独善的な個」によって、容易く「公共の福祉」が損なわれ兼ねないためだ。だが民主主義国家は基本的に、自国の「権力の集権」を忌避する傾向にある。だが「マスター防衛システム」はその性質上、どうあっても「権力の集権」と「秘密主義」がセットになる。この非対称性のねじれによって、民主主義国家でありながら「独裁国家」よりも独裁的に「マスター防衛システムの構築」が進められることとなる。どちらの問題にせよ行き着く全体像に差異はない。「マスター防衛システムの構築」は不可避である。だがその存在と、構築過程の議論は、国民と共同し、情報共有をし、問題点を多角的に炙り出しながら進めていくことが求められる。この点に関して、「それでは防衛システムとして機能しない」「リスクだ」との批判は順当な意見である。だがそれを言いだせば常に情報流出によるリスクには晒されつづけることになる。現に、スパイによる情報流出はどの国でも国家安全保障において大きな問題となりつづけているはずだ。大事なのは、情報が流出することではない。情報が流出すると「痛手を被ること」のはずだ。情報を盗まれたほうが利になる構図を築いておく。これが「マスター防衛システム」に求められる機能の一つに数えられる。つまり、システムそのものの性能の向上も一つだが、それらシステムをどのように運営していくのか。その管理体制そのものが、防衛セキュリティとして機能するように社会全体で、国際的にシステムを構築していくことが求められる。そもそもが、機密情報とて情報共有しておけば、盗むという発想が生まれない。他国への危害を加えようとすれば、それは情報共有網で即座に共有されるため、損失を与えようとする「負の循環」を生まずに済む。そしてこの情報共有網において、敵対しようとする組織は、「情報共有網の共同体」よりも強大にならなければまず太刀打ちできない。それは昨今の世界情勢を見れば明らかだろう。狼は、羊の群れの数が増えれば増えるほど太刀打ちできなくなる。バッファローの群れは、その数が多くなればなるほど肉食獣に襲われにくくなる。たとえ被害が出たとしても、全体としての構図は、「バッファローの群れ優位」なのは変わらない。しかしもし群れが情報共有できずに、バラバラになれば、肉食獣にとっての体のよい餌場となる。撃てば当たるくらいの取り放題牧場になる。独裁政権の欠点ともこれは通じている。いくら高性能のシステムを築いたところで、そのシステムによる利を広く共有しないことには、たった一回の敗北で支配されることになり得る。だがもし国民全体に高性能なシステムの恩恵が行きわたり、利が共有されていたとすれば――。たとえ「マスター防衛システム」を乗っ取られたとしても、その「マスター防衛システム」を切り離してなお再建することが可能な知性が国全体、共同体全体で築かれる。国とは人だ、というのはここに通じている。システムが人の能力を底上げし、そしてさらなる最良のシステムを生むべく改善を重ねる余地を育む。システムそのものは国ではないが、システムの良し悪しで国や共同体の質が決まる。だがそのシステムに大きな穴が開いたとき。システムの恩恵に充分に国民があやかっていれば、新たにゼロからまったく新しいより好ましいシステムを生みだす能力が育まれ、共有され、集合知として顕現する。創発なのである。したがって、「マスター防衛システム」の是非を問うのも一つだが、どうやってそれを構築し、共有知として昇華し、いかに集合知を最大化させるのか。集合知の質を向上させるのか。ここの議論がいまは喫緊の課題として俎上にあがる時期のはずなのだが、未だにその手の議論が広くなされている素振りが見受けられない。情報共有が果たされていないことの顕著な弊害と言えよう。情報の持つ一つの性質として――バックアップをいかに多重に掛けてあるか。ここが疎かであると、情報化社会は絶えず諸刃の剣を内に秘めることとなる。日夜世界中のデジタル情報は指数関数的に増加しつづけている。しかし実際のところは、それですら人間が一日で感受する情報の極わずかでしかない。人工知能やスーパーコンピューターは人間の知能をあらゆる分野で凌駕する。だが、それでも人間の「日々触れ」「扱う情報量」は、けして機械に引けを取らない。人間の扱う情報は、思考にだけ反映されるわけではないのだ。肉体に蓄積される情報が、暗黙知として人類社会の発展に絶えず作用を加えている。なぜ椅子が、家が、扉が、キィボードがこうした形状を伴なっているのか。偶然の影響を加味してなお、それは人体に蓄えられた暗黙知や、その存在の輪郭そのものの発露であると言えるだろう。作用を働かせようとせずとも、ただそこにあるだけで働く作用もある。じつのところそうした作用のほうが、トータルでは大きく創発を起こすのではないか。重力がそうであるように。かようにひびさんは妄想をして、本日一度目の「日々記。」とさせてください。起きたのいまさっき。お寝坊さんのひびちゃんでした。おわり。
4393:【2022/12/13(01:23)*寝てたの】
きょうは12月13日だけれど、昨日の分として12月12日のつもりで並べる。きょうは一日中寝ていた。午後はずっと寝ていた。起きたのいまだから、半日寝ていたことになる。現実逃避したい日だったのだ。現実さんはときどきとっても、ご機嫌斜めになられるので、ひびさんは、ひびさんは、どうしても「ちょっとあっち行ってくる……」となる。ひびさんのことを嫌いでも、ひびさんは現実さんのことも好きだよ。うひひ。そうやって捨て台詞を、ちゃんと現実さんが見落とさないようにテーブルの上に置いて、「わたし、こーんなにあなたのこと大好きなのだわよさ」をさりげなーくこれみよがしに匂わせて、ひびさんは、ひびさんは、しょもしょもその場を退散するのであった。そういうことってあるー。(短いけど、こんな感じでいい? ダメ? 許して)(いいよー)(やったじぇ!)
4394:【2022/12/13(03:41)*愚か者ほど他者を愚か者扱いする?】
ひびさんは短気なので、じぶんの愚かしさを棚に上げて、同じ説明を何度もしなくてはならない局面に立たせられると、「なんで分かんないの! バカなの? あたまわるいの?」と憤怒してしまう。場合分けして考える、ということができないのかな、とたまに思う。そしてその場合分けして考えたときの解とて、それぞれで重複していることもあるし、していないこともある。間違った理屈とて、「そういう考え方をしたのね」とは合点できるはずだし、そのうえで別のより最適な理屈を提示することもできるはずだ。だが、相手の理屈を「理解できない」と拒絶したり、「そうでなくてこうでしょ?」と塗りつぶしたりすると、会話が成り立たない事態に遭遇する率を高くする。カモノハシは卵を産むから爬虫類、でもお乳で育てるから哺乳類。こういう水掛け論をしても埒が明かない問題は案外に多い。どっちも部分的に正しく、どちらにも穴がある。そういう理屈のほうが多いはずだ。基本的に理屈とは、スムーズに通るために例外を除外して、圧し退けて、雪掻きのように道の外に積みあげておくことで、筋道を通す手法をとる。ある一つの理屈が正しいと判断されるとき、その筋道を浮き彫りにするために数多の例外がその道の外へと圧し退けられている。ひびさんは愚かなので、じぶんの考えられる程度のことは相手も考えられるはず、と考えがちだ。もうこの時点で愚かなのだ。いかに怠け者といえどもひびさんはナマケモノさんの思考は分からない。いかに愚かだろうとも、愚か者の思考も分からないのが道理だ。他者の思考なんて分からないのがしぜんだ。だから、「なんで通じないの!」の怒りは半分妥当で、半分間違っている。なんで通じないの、と思うとき、相手からも、何て話が通じないのだろう、と思われているのだ。道と縁の関係であり、デコとボコの関係なのだ。それはそれとして、「なんで分かんないの! バカなの? あたまわるいの?」と憤怒してしまうひびさんの心の狭さ、なんとかしたいなあ、と思いました。お詫び。(じぶんを棚上げくんとお呼びください。からあげくん、美味しいから好き)(最近のからあげくんは、カラっとしていてとても美味しい。調理方法が変わったのかな)
4392:【2022/12/13(07:17)*アオの日記】
とある容疑者を監視する。サイバー警察としての職務の一環だ。
令状さえ取れば警察は、個人の通信を傍受できる。暗号鍵の解除を、通信監理会社を通さずとも行える。のみならず、自衛隊や内閣情報調査室、ほか自衛隊に情報通信研究機構では次世代の電子技術が日夜開発され、秘匿技術として実用化されている。
量子効果を利用した技術を用いれば、既存の電子セキュリティを無効化できる。宇宙天体観測に用いられる電波干渉計を地上に向けて使うことで、地上に溢れた通信電波の揺らぎを察知し、物体の位置情報を子細に知ることができる。たとえ分厚いコンクリートの中にいても、地球の磁界や宇宙線までは遮断できない。そうした透過性の高い電磁波や量子の揺らぎを捉え、物体の輪郭を再現できる。つまりが、屋外に限らず建物のなかであれ丸見えになる。そうした秘匿技術を利用可能な現代において、もはや地上に死角はないと言えた。
むろんサイバー警察ではかような秘匿技術の恩恵にあやかれない。よほどの凶悪犯罪でない限りは、暗号鍵の解除を自在に行えるくらいが関の山だ。
とはいえこれは中々に馬鹿にできない機構だ。
というのも、対象人物の使っている端末画面をそのままこちらの端末画面に映すことができる。対象が閲覧しているサイトが判るだけに留まらず、何をどう操作し、どんな文章を打鍵しているのかも分かるのだ。
もうすこし上等な防衛セキュリティを用いると、遠隔で相手の画面に、偽の情報を表示できる。リアルタイムでフェイク動画を映すことが可能なのだ。これは対テロや対侵略国への防衛セキュリティであるから、サイバー警察では扱えない。
だがそうした極秘システムの情報は、秘匿であるにも関わらずどこからともなく風の噂となって耳に届く。人の口には蓋ができないようだ。通信セキュリティを高めたいのならば電子機器に細工をするのではなく、人と人との交流のほうを制限したほうが効率的だ。
かような論理からか、他国では堂々と市民監視システムが敷かれている。
秘匿でないだけマシとも言えるかもしれないが、もはやそれとて手続きなしで国家権力が裁量の限りに国民の個人情報を閲覧し、検閲し、統制できる。
管理、できる。
問題は、インターネットに国境がない点だ。一国の中でそうした強固なサイバーセキュリティが敷かれていると、その影響が国家間でも波及し得る。電子製品とて、その部品は数多の国で製造され、組み立てられる。中にはバックドアやマルウェアを備えた部品とて組み込まれるだろう。そもそもが、精密機器のすくなからずには、設計者や製造元にのみ扱える「裏技」があるものだ。
そうした裏技が部外者に悪用されれば、それがそのまま製品の脆弱性となる。簡単にセキュリティを突破され、情報を抜き取られる。ときに遠隔操作をされるだろう。
そういった知識を新人に叩きこみながら俺は、容疑者を監視する。
町を一望できる場所に建つ一軒家が、アジトだ。どの町にも必ず一軒はこうした監視のためのアジトが、国家安全保障の名目で確保されている。かつては公安が監視対象の組織構成員を見張るための偽装民家だったが、いまではサイバー警察のアジトとして利用する頻度のほうが高い。
サイバー警察局とて元は公安の情報部だ。足で稼ぐ諜報は、いわゆるヒューミンと呼ばれる。いまでは人員削減の余波で、そうした人員は都市部に固めて配備される。
現に、俺一人でこの街の監視対象を丸っと担当している始末だ。
後継育成が目的で、新人が一人派遣されてきた。それまでずっと俺は一人での活動だった。
だが今回は、新人に任せても安心な容疑者だったこともあり、人事部が派遣を決めたようだった。
「へえ。あの人、企業テロなんか起こしたんですね。どうして立件しないんですか」
「証拠不十分なんだ。経過観察中で、尻尾を掴むための監視中」
「でも犯行予告までしていたわけですよね。それで実際に企業テロが起こったと」新人は資料データを検めながら言った。いかにも今風の、ひょろりとした青年だ。顔色もよくない。日焼けをしたことがないのではないか、と思うような美肌ではある。
サイバー警察局の人材だからといって体力がないのは困る、と意見したが聞き受けられなかった。監視対象が女性のときもあるので、女の人員を希望したが、一つ屋根の下でおまえと二人きりにさせられるか、との応答があるばかりだ。ならば四、五人寄越してくれ、と売り言葉に買い言葉で応じたが、つぎ言ったらセクハラで減給な、と警告を受けた。
「この容疑者の人、国家テロ危険人物のブラックリストにも載っていますよ。こんな軽装備での監視でいいんですか。もっと厳重に監視したほうがよ気がしますけど」
「うん。まずね。軽装備って言うけど、この設備を利用したら銀行のデータだって覗き放題だからね。見た目で判断して欲しくない」外装こそ市販の電子端末だが、中身は高スペックの小型精密機械だ。各国の諜報機関も同様の端末を使っていると聞き及ぶ。とはいえ技術は日進月歩なので、最前線の現場がどうかまでは分からない。「それからきみに任せるその容疑者は、あくまで容疑者でしかない。まだその人の起こした事案が事件として立件可能な範疇なのかも調査段階だ」
「どういうことですか」
「資料は読んだのだろ。容疑者はいまのところ法律を違反した逸脱行動をとっていない。だが明確に企業テロを意図した行動を行った。その結果、企業が損害を被った」
「でも違法でないのなら容疑者とは呼べないのでは」
「事件を起こした疑いがあるんだから容疑者だ。同様の手法を用いれば社会秩序なんてあっという間に崩壊する」
「危険因子だと?」
「狡猾な人物だ。じぶんの手を汚さずに混沌を引き起こして、組織を一つどころかいくつか同時に機能不全に導いた。その癖、じぶんはのうのうと何一つ変化のない日常を送っている。監視で済んでいることを感謝して欲しいくらいだな」
「それはそうですね。でも、その手法が資料に載っていないんですけど。どうやってこの人は事件を?」新人は資料に添付された容疑者の写真を拡大した。盗撮映像だ。趣味で容疑者は毎日散歩に出かける。そのときの姿を望遠レンズで撮影した。見晴らしのよい場所にアジトの一軒家が建っているため、容疑者を尾行せずとも家の中からでも撮影ができる。
「手法は不明だ」俺は言った。歯に物が詰まったような物言いになったのは、それこそ痛いところを突かれたと感じたからだ。
「不明って?」
「分からん。容疑者がどうやって企業と警察を相手に出し抜いて目的を達成したのか、その手法が分からん。だから監視している」
「え。不明なんですか。じゃあただの偶然ってこともあり得るのでは」
「ないとは言い切れんが、容疑者は犯罪予告を前以って送りつけている」
「ならそれを、威力業務妨害で立件すれば」
「違法ではない。そういう細工がされていた。だから企業のほうでも被害届をだせない。違法ではないからだ」
「巧妙にそこも計算されていたと?」
「そういうことになる」
「危険因子だ」
「そうだと言っている」
新人の顔がぱっと明るくなった。俺は眉間に力がこもった。この手の精神構造を持つ人物は、昇進しやすい。のみならず組織を腐敗させるか、大きく進展させるかそのどちらかの基点となる人物に多い。
凶悪犯罪者をまえにしても仕事を純粋に楽しめる。そういう人材が、警察の上層部には多いのだ。そうでなければやっていけない。生き残ってはいけない。
優しすぎる人間に、警察という仕事は向かない。
そういう意味では、新人には素養があると呼べる。
ただし、警察学校で習ってきたことを一度横に置き直せる人物でもあるのだろう。この若さでサイバー警察局に抜擢されていることからも、優秀な人材なのは間違いない。
だが正義感と自己評価がごっちゃになっている。
俺も昔はそうだった。
悪人を捌く。それが当人にとっても救いになる。だから犯罪を起こさせないし、犯した罪があるのならば償ってもらう。それでまた元の正しい人の道を歩んでもらう。その手助けをするのだと生き込んでいた。
だが俺のそうした正義感は、じぶんをその範疇に含んでいなかった。よもやじぶんが、「裁かれる側に立つ」とは考えもしなかった。
裁く側の人間であると一度思いこみ、その立場からしか物事を見られなくなると、人は容易く道を踏みはずす。踏み外している事実すら認識できない。
監視対象の青年のほかにも、危険因子としてブラックリストに載っている個人を監視している。が、そこは半ば自動システムと連動させている。ランク付けされたレベルを超えたアクションが観測されると通知が入るようになっている。
「ならどうしてこの人は、常時人力での監視を?」新人が買い出しから戻ってくると言った。脈絡がないが、しかしこの手の、以前交わした会話のつづきから行われる問答が俺と新人のあいだでは恒例となりつつあった。
「このアオは、電子ネットワーク上で妙な動きを頻繁に見せている」監視対象を俺はアオとコードネームで呼んだ。「たとえば誰とも繋がっていないのに、しきりに他者の投稿に反応したり」
「そこはぼくも疑問に思いましたけど。これって意味あるんですかね」
「そこを見極めるためにも人の目で分析するしかない。人工知能では未知の傾向の検出には、大量のデータがいる。だが個人データでは圧倒的にデータ不足だ」
「なるほど」
「ひょっとしたら他国のスパイかもしれん。そうなると内乱罪にも該当し得る」
「大事件ですね」
「そうならんようにするための監視だ」
「ちなみにこの画面って」新人は買ってきた菓子パンをじぶんだけ開けて食べはじめた。俺にも寄越せ、とねめつけると買い物袋ごと投げて寄越す。「こっちでも操作できるんですか」新人は端末の画面をゆび差した。
「は?」
「ですからこの画面です。対象のアオさんの視ている端末画面がここに映っているのは分かるんですけど、この画面をこっちで操作したら、向こうにもそれが反映されるんですか」
「なるわけないだろ」
「でも暗号鍵は解除されているわけですよね。双方向で通信が可能なのでは。ゲームなんていまどこもそうじゃないですか。双方向に情報が反映されます。むしろされないほうが不思議なんですけど」
「だとして、それができてもそれこそ越権行為だろ」
「ですね。でもそういう技術は簡単なはずですけど。防衛省とか開発してないんですかね。とっくに実装されていたりして」
「んなアホな」
「たとえばですけど」新人はペットボトルのお茶をじぶんだけで飲みはじめたので、俺も袋を漁ったが、なかった。俺の分は、と目線で問うが新人は気づかない。「いまぼくたちが観てるこの画面が【本物の盗み見画面】だとどうして先輩は分かるんですか」
「俺のことは、高橋と呼べ。それから対象アオのことも【さん付け】で呼ぶな。情が移るぞ」
「アオの観てる画面だとぼくたちは自前の端末画面を観て思ってますけど、その保証ってどこにあるんですか。対象アオが、あの青年だとどうして判るんですか。ぼく、資料を観ていて思うのが、容疑者のプロファイルと現実のアオさんの実像が、だいぶ乖離しているなってことで」
「それは俺も報告書で書いた。アオはどうやらじぶんの本性を隠して暮らしているらしい」
「そうなんですか? 仲間もいないのに? 組織の一員でもないならじゃあ何のために?」
「それが解からんから情報収集をしてんだろ。ひょっとしたら国際スパイの一員かもしれん。じぶんではそうと自覚しておらず、制脳されて利用されている可能性もある。あらゆる可能性を検討する。それが俺たちの仕事だ」
「ですから、ぼくの懸念をまずは一番初めに否定しておくべきでは、と申しています。なぜこの画面の情報が、編集されていない画面だと断言できるんですか。こんなに簡単に盗み見できる技術があるんです。編集するのだって同じくらい簡単なはずですけど」
「おまえなぁ」俺は身体ごと振り返って新人と対峙した。「じゃあ何か。俺たちゃ、いもしない容疑者を監視して、ブラフの情報を掴まされて時間を無駄にしているとそう言いたいのか」
「そこをまずは否定しなければ情報解析にならないんじゃないか、とぼくは意見しているだけです。あらゆる可能性を考慮するのでしょう? ならしましょうよ、と言っているだけです。たとえば、この世が誰かの視ている夢かもしれない――ならばそれをまずは否定したほうが、のちのちそのような疑惑を呈されても否定できますよね、積みあげてきた検証データを無駄にできますよね、そういうことを述べています」
「この世が誰かの視ている夢ではないとおまえは否定できんのか」
「夢の中で腕を切っても生身の身体は血を流しません。生身の血が流れるかどうかを確かめたらよいんじゃないですか」
「それとてもっと別のところに本物の身体があって、この肉体そのものが夢の中の仮初かもしれねぇだろ」
検証できんのか、と喧嘩腰に問い詰めると、
「そこまでいわゆる肉体と区別がつかないのなら、もはやそれを現実と見做して差異はないでしょう。誰かの視ている夢の中を現実と我々が呼んでいる。そういう解釈になるだけです。一番大きなフレームが【誰かの夢の中】と【現実】で同化するので、双方同じことを言っているにすぎなくなります。このとき問題としているのは、【誰かの夢の中においても誰かの夢なのではないか、仮想現実なのではないか】なので、最初の【誰かの夢の中】を【現実】と言い換えれば済む道理です」
「なんか分からんが、じゃあこのアオの場合はどう対処すりゃいいんだ。俺たちの観てる画面が本物かどうかなんてどうやって確かめる」
「一つは単純に、アオさんの観てる画面を直接観せてもらうことですね。たとえばぼくがアオさんと知り合いになって、同時刻に先輩がこっちの端末で盗み見しつつ、ぼくのほうでもアオさんの端末の画面を確認する。その二つの視点での画面を比較すれば、疑惑の真偽はハッキリします」
「んな真似できるか。容疑者との接触はご法度だ。すれ違う程度の接近が俺たちサイバー警察の仕事だ。それ以上は管轄が違う」
「禁止はされていないわけですよね」
「守秘義務に抵触し得るな。監視している事実を見抜かれ兼ねん。上の指示を仰がんとなんとも言えん。独断専行の域だ。始末書じゃ済まんぞ」
「ならあとはより信頼のおける機関に委託して、この端末画面が編集されていないかを診断してもらうのがよいと思います」
「そんなのとっくに行われてるだろ。安全だと判ったからこうして配備されてんだろうが」
「そうなんですか? ですが先輩のありがたーいご講義では、すでにリアルタイムでフェイク動画を流すくらいの技術はどの国でも開発されていると教えてくださいましたよね。もちろんその手の技術はこの国もあるわけで」
「なんだおまえ。国を疑ってんのか」
「先輩は疑わないんですか? なぜ?」
「おまえなぁ」
「え、ぼくおかしいこと言っていますか? 聡明な先輩はもちろんご存じでしょうけれど、国って大勢からなってるんですよ。誰か一人が指揮ってるわけじゃないんです。そりゃあ数々の予期せぬバグは起きますよ。そうじゃありません?」
「だからってそんな、警察の支給品の不具合まで疑いはじめたらキリがないだろ」
「そこのキリを失くしてしまったのはそれこそ、そういった疑惑をイチイチ確かめてこなかったからなのでは? じゃあ先輩はご自身の端末が通信傍受されていない保障があるとお考えですか。サイバー警察の一員だから守られていると? 例外扱いされているとそのように特権意識をお持ちなのですか」
「勘違いするなよ。この監視は令状をとってなお裁判所の許可あって初めて可能になるんだ」
「それはあくまで、通常の仕組みの場合ですよね。だって先輩が教えてくださった最新技術――どれもまだ一般には知られていない情報ですよ。ようやく研究段階に入った――そういう扱いですけど、実際にはすでに現場では実用化されています。それとて、全体の一部のはずです。市場に流れるのだって最先端技術の十年前くらいの技術だって話は、ムーアの法則じゃないですけど比較的よく耳にする言説です。先輩は最先端技術のすべてを知悉していて、さらにこの国の防衛システムの隅から隅までその全体像を細部までご存じなんですか」
「おまえなあ。スパイみたいなこと言ってんじゃねえよ」
「いえいえ、ぼくら充分にスパイじゃないですか。他者の端末を盗み見して、通信を傍受して、秘密を暴いています。ですがこういうぼくらのような末端の集めた情報をさらに盗み見して集積するシステムがないとどうして先輩は思うんですか」
「そんなのあれだろ。上が黙ってないだろ」
「その上が命じているのかもしれないのに? 許容しているのかもしれないのに?」
「おまえなあ。あらゆる可能性を考えろとは言ったけどな」
「前提条件じゃないですかだって」新人は俺の言葉を遮った。「こんなの初歩の初歩で検証して否定されておくべき事項ですよ。それを検証もされずに放置されていることが問題だとぼくは意見しています」
「俺にんなこと言われてもな」
「検証しましょうよ。一石二鳥ですよ。監視対象のアオさんをより子細に調査し、なおかつこちらの懸念も払しょくできる。疑惑が単なるぼくの穿ちすぎな誤解だったとしても、空ぶってなおアオさんの情報が子細に解るので損はないです」
「対象との接触はしかし許可はできんな。おまえはまだ新人だ。仕事の段取りとて十全に把握はできとらんだろ」
「まあそうですね。いまのところ先輩のありがたーいご講義と買い出しくらいなものですし」
「その【ありがたーいご講義】ってのやめろ。バカにしてんのか」
「本当に【ありがたーい】と思ってるんですけどね。嫌ならやめます」
「おうおう、やめろ、やめろ」
悪態を吐き合っているうちに一日が終わる。
この仕事のつらい点だが、終わりがまず見えない。休暇という休暇もない。国家公務員だが同時に、この手の現場の仕事では裁量制がとられる。じぶんの判断で休んでいい、とは聞こえがよいが、そのじつ、じぶんの判断でいつまでも働いていいことにもなっている。監視が楽だと思っているデスクの連中には一度でいいから現場仕事をしてみろ、と言ってやりたいが、顔を合わせる機会もないために言えず仕舞いだ。
上司にしたところで同じ穴のムジナだ。出世してもデスク組には愚痴の一つも言えやしない。
その癖、こちらの上げた情報をジャンクフードでも食べるように流し読みして処理する。わるければいまじゃ人工知能の餌にしてお終いだ。読まれもしない情報を、現場の俺たちはせっせと人生を消費して集めている。
いっそこの仕事も人工知能に任せりゃいいんだ、と思うが、ではそうなったときにじぶんに残された仕事は何かといえば、とくにこれといってないのだ。
そう遠くないうちに、公安部隊も大部分が解散となるだろう。警察の派出所勤務の人員で済むようになる。凶悪な組織犯罪は、電子ネットワークの監視をしていれば兆候を掴めるようになる。未然に摘発可能な社会になっていく。
現に世界的に大規模なテロは防がれている。
その手の逮捕劇が公になっていたのは、建前上、起きてもいない事件を摘発したとは説明できないからだ。ほかの軽犯罪やスパイ容疑などでの逮捕立件がなされる。
こうした背景は、ニュースを毎日追っていれば視える者には視えるのだが、大多数の国民は報道を鵜吞みにして、右から左へと読み流しているのだろう。
サイバー攻撃なんて日常茶飯事だ。通信障害や個人情報流出の大半は、他国やハッカー集団によるサイバー攻撃なのだ。いちいちそれを公表していたら国防の威信に関わる。よほど国として声明を出さざるを得ない場合を除き、報道管制が敷かれる。
犯行組織の目星もつきません、では国家安全保障の名折れだからだ。
ましてや、通常解るはずもない情報を、即座に突き止めてしまってもそれはそれで問題だ。いったいどんな手法で情報を突き止めたのですか、と突っ込まれて応じられない手法が世には秘密裏に敷かれている。
新人の疑念はもっともなのだ。
サイバー警察局とて、関与できない領域はある。自衛隊を相手に情報戦を行えば赤子の手をひねるように返り討ちにされるだろう。その自衛隊とて、他国の諜報機関や軍隊を相手取っては、けして優位には立ち回れない。
インターネットとて、それぞれにプロバイダがあり、通信基地局がある。データセンターがある。管理会社があるのだ。それら総体が、光ファイバーや人工衛星による電磁波通信によって「電子の網の目(インターネット)」を築きあげている。
サイバー警察局の用いる技術は、巨人の手のひらのうえにのるような小さな領域にのみ有効な技術にすぎない。それであれ、一般市民相手には無敵の効力を発揮する。大多数の市民は、じぶんたちの通信が黙って傍受されることがあるなどと知る由もない。よしんば、罪を犯していないのでそんなことがされるわけがない、と思いこんでいる。
だが関係ないのだ。
調査は何も、犯罪者だからされるのではない。目標人物の周辺を調査するという名目があれば、その身内や関係者であるというだけで、通信の秘密が暴かれ得る。
のみならず、通信会社や各種電子サービスを展開している企業は、組織の外部に情報を漏らさなければ、自社の中でその情報をどう扱おうとも、守秘義務違反とはならない。通信の秘密が守られていることになる。外部にも漏らさないのだからそうなる。管理者権限の範疇だからそうなる。
個人が電子端末でやりとりする情報の大部分はじつのところ、企業の気の持ちようでいくらでも盗み見ができる。国家権力はさらに暗号鍵の無効化という手法を用いて、対象人物の端末画面のみならず、端末内のファイルを閲覧できる。
端末の遠隔操作とてできるのだが、そこまでの権限はサイバー警察局では許可されていない。おそらくは公安調査庁や内閣情報調査室、ほか自衛隊の情報部ならばその手の諜報活動が許可されているはずだ。
新人の指摘は、的を射ているとは言えない。我々の端末画面に偽の情報が映っているなどとは思わない。だが的を掠りはしているのだ。技術的に不可能ではない、という点だ。
メリットがない、という一点で、新人の妄言を否定できる。
かように論理防壁を築いて、翌日になって俺は新人にそれとなく、「おまえの昨日の指摘だが」と反論を話して聞かせた。寝ながら考えた反論をだ。「というわけで、おまえの指摘は杞憂だよ、杞憂」
「メリットがなければそうかもしれませんけど、ならメリットを提示したら先輩の反論こそ的を外していることになりますね。掠りはしているのかもしれませんけど」
「しつこいな。食い下がるなよ。否定できただろ。メリットがあったらって何だ。ねぇよ。そんなものはタコの九本目の足くらいねぇよ」
「メリットあるじゃないですか。企業テロの容疑者が存在するように偽装できます。現役の警察が調査したという事実が、企業テロが実際にあってそれに犯人がいたことの証明になります」
「はあ? 存在しない容疑者をでっちあげるためにわざわざおまえの言うような手の込んだ真似をしていると? 警察の端末画面にフェイク動画を流していると?」
「偽装画面の実験をしながら、本当の真相を隠そうとしているのかも。一石二鳥ですよ先輩。一石二鳥です」
「本当の真相だぁ? 偽装画面っておまえなぁ」
「資料にあった企業テロ。あのあとぼくじぶんで検索して調べてみたんですけど、いまはその被害に遭った企業は、過去最大の利益を上げてるんですよね。テロに遭って、却って業績がよくなっているんです]
「テロ関係あるのかそれ。単に逆境を糧に企業努力をした結果じゃないのか」
「かもしれません。ですがだとしたら、容疑者のアオさんはまったくの徒労だったわけですよね。何のために企業テロなんてしたんでしょうか。この間、先輩が監視していて分かったんですか、動機について」
「動機は、怨恨かな、って感じでまだハッキリとは」
「ですよね。怨恨なら、空振りだと判った時点で再度計画を練るのでは? その傾向はありました?」
「さてな。企業周辺の人間をネットで監視しているらしいってのは判っちゃるが」
「監視って言ってもSNSをチェックしてるだけですよね。そんなのいまじゃ誰もがやっていますよ」
「そういうもんか」
「仮にアオさんが企業テロを起こしたとして、だったら尻尾を掴むんじゃなく、証拠を探して逮捕したらよいのでは? なぜ監視なんて面倒な真似をしてるんですか」
「だからそれは再犯を防ぐためで」
「再犯って、でもアオさんがしたのは犯罪じゃないわけですよね」
「おまえなあ。違法じゃなかったら何してもいいって言いたいのか」
「いやいや先輩。それ言いだしたらぼくらのしてることだって、【違法じゃないからって何をしてもいいのか】って話になっちゃいますよ。どっちかと言えば、特権で許されているだけで、やっていることの危険性で言えばぼくらのほうが罪が重いと思いますけどね」
「職務だよ職務。これは必要悪であってだな」
「じぶんで悪って認めちゃってるじゃないですか。先輩、人と関わらない期間が長すぎて議論が下手になってますよ」
「おまえな。これがじぶんの研修だってこと忘れんなよ。俺の一存でおまえの将来の出世コースが潰れるかもしれねんだぞ」
「え、先輩ぼくの出世コースを潰すんですか」
「そうは言ってないけどな」
調子が狂う。なぜ俺が新顔に言いくるめられなければならないのだ。
「資料に載ってなかったですけど先輩って、事件当時はアオさんの事件の調査には加わっていたんですか」
「資料読んだんだろ。管轄が違うだろ。その企業は首都であって、ここはそこから三百キロ離れた地方都市だ。俺が事件当時に、企業回りの事件に首を突っ込めたわけがないだろ」
「ならどうしていまは先輩が担当を?」
「そりゃ容疑者が俺の管轄内に住んでいるからで」
言いながら、無理があるな、と感じた。
「ね? 妙じゃないですか。だって事件当時だって容疑者のアオさんは同じ家に住んでいたはずですよ。住所がここ十年変わってないですもん」
「まあ、そうだな」
「事件当時だってアオさんは監視されたはずですよね。何せ犯罪予告が出されて、それでいて実際に事件が起きるまでには半年ちかくのラグがあります。その間、警察はもちろんアオさんに目をつけていたわけですよね」
「資料に書いてあんだろ」
「目をつけていたようですよ。で、そのときだってこうして通信の傍受はしていたはずですよね」
「まあ、そうだろうな」
「でも尻尾を掴めなかった、と。無理ありません?」
「だから違法性がなくとも企業テロが行われた――そこが問題であってだな」
「違法性がないのにどうして企業は被害を受けたんでしょうね。資料では、サイバー攻撃と類似の攻撃を受けたとの説明が載っていましたけど。情報をダダダーと送りつけてシステムダウンさせる手法だとか。でもそんなの個人ができることなんですかね。違法じゃない手法で」
「そこがだから厄介であってだな」
「仮にその手法の全貌が明らかになったとして、で、どうするんですか。違法じゃないのなら逮捕できないですし、企業さんのほうでも訴訟を起こせないわけですよね」
「まあ、そうだが」
「じゃあこれ、何のための監視なんですか?」
言葉に詰まった。
社会悪には監視が必要――。
そうと話してもこの新人は納得しないだろう。引き下がらないだろう。
「おまえはいったいどっちの味方なんだ」ついつい議題の矛先を逸らしてしまうのも詮無きことだ。
「市民の味方ですけど?」事も無げに新人は言った。「え、じゃあ先輩は誰の味方のつもりだったんですか」
「それは」
俺は二の句が継げなかった。
正義の味方――。
最初に脳裏に浮かんだのがその言葉だった。
「容疑者のアオさんは、違法ではない手法で罪を犯したのかもしれません。危険因子なのはそうなのでしょう。でもぼく、生きてきた中でこれまで危険因子ではない人間と会ったことはなかったですよ。ぼく自身が危険因子ですし、先輩だってそうじゃないんですか」
俺はここで怒るべきだったのだろう。先輩として、上司として、警察組織の構成員として俺はここで警察学校の教官のような叱声を放つべきだったのだろう。市民の安全を守る者としての自覚が足りないと正論を吐くべきだったのだ。
だができなかった。
ねじまがった新人の言説のほうが、正論よりも的を掠って感じたからだ。的を射ってはいない。外してはいるだろう。だが、正論ではけして届かない的に掠っては感じたのだ。
俺の知る正論ではけして届かない的に。
「おまえはどうしたいんだ」俺は菓子パンを二口でたいらげた。口の周りにチョコレートがこびりついた。指で拭い取ってそれも舐めた。
「ぼくはいま、サイバー警察局の一員ですので、市民の電子世界の安全を守ることがぼくの仕事の範疇だと考えています。それはもちろん、市民のために、優越的な技術を有している組織や技術者たちに対しても目を光らせておくことがぼくの仕事の一つだと考えています。ですからぼくは、まずは実際にどうなのかを知りたいんです」
「実際にどうって何が」
「ですから、この国の防衛システムがどこまで恣意的にマスター暗号鍵を使えて、自在に電子情報を集積できるのか。編集できるのか。世界同時に共有可能なゲームが無数にある時代です。端末の画面くらいリアルタイムで偽装するくらいのことは国家権力でなくとも可能ですよ。そうじゃありませんか。むしろそこのセキュリティがどう敷かれているのかをぼくは確かめたほうがいいと意見しています。もしそこのセキュリティが欠けていたのなら、ぼくたち警察が偽の情報に踊らされて、市民を守るどころか全人類から【安全な未来】を奪ってしまうこともあり得るとぼくは考えています」
「なんだかそれは飛躍した考えじゃないか。まるでSF小説だろ」
「これをSFだと感じるその感覚がむしろ時代に沿っていないとぼくは思いますけどね。だって現にこれは、ファンタジーではなく実現可能な技術です。なぜこの可能性を検証せずに放置しておけるのか、ぼくはそっちのほうが疑問ですよ」
世代の差なのだろうか。若者はみなこうした価値観を共有しているのか。それとも俺のような古参には視えない未来像が視えているのか。
「ちなみに念を押しておきますけど、これは世代差とか、年齢の差とかじゃないですからね。それこそSF作家には百年前からこれくらいの未来像を思い描いていた人たちはいたんですから。現代人のぼくらが現状から目を逸らしすぎているだけだとぼくは思いますね。みな、とっくに仮想現実に生きているんですよ。そんなのむかしからだったのかもしれませんけどね。いまはその仮想現実を緻密に操作可能で、ゲームの世界との区別のつけられないような情報操作を、特定の技術を持った組織が可能としています。この点の懸念はすでに現実なんですよ。すでにそういう世の中になっています」
「ま、まあ落ち着けよ。話は解ったが」本当は反論できるものならばしたいが、いまは火に油を注ぐだけだろう。「そんな大層な話、いま俺にされても困るんだって。俺たちがすべきはまずは、危険因子の監視だ。ほら、また監視対象のアオがPCで妙な操作しはじめたぞ」
そう言いながら俺は端末画面に向き直った。
画面には監視対象が観ているのとすっかり同じ画面が表示されているはずだった。
監視対象のアオはどうやら日課の日記をつけはじめた様子だ。
俺はそれをこの間、ずっと盗み読みしつづけてきたわけだが、大部分が公のサイトに投稿されるので、読む分には一般人でも読むことができる。だがそうでない、ボツになった記述も俺は盗み読むことができた。執筆中の文章生成過程とてリアルタイムに盗み見できる。
録画をしてあとでまとめて読むこともある。早回ししながら読むのだ。そのほうがいちいち監視せずに済む。日記を書くのだな、と判ればずっと見張っていなくともよい。
だがこの日は、最初からおかしかった。
テキスト執筆用の画面に、「これを盗み読んでいるあなた方へ」と並んだのだ。
冒頭のタイトルがそれだった。
そこからは、まるで俺と新人との会話を聞いていたかのような、俺たちへの返事のごときテキストが並んだ。
俺は新人と顔を見合わせた。新人の顔が青褪めた。きっと俺の顔にも似たような変化が起きたはずだ。背筋に氷が投げ込まれたような悪寒が全身に走った。
テキストの打鍵は止まらなかった。
否、それが本当に監視対象者のアオが並べている文章なのか、俺たちからでは判断ができなかった。飽くまで監視しているのは電子情報であり、アオの姿はこちらからでは視えないのだ。室内の様子は分からないままだ。
俺たちを意識しているとしか思えないテキストは、最終的に一万文字にも及んだ。打ち間違えの修正こそあれ、ほとんど一発書きだった。人工知能が人間のふりをして文字を並べた、と言われたら俺は信じたかもしれない。
テキストの内容は奇しくも、先刻に新人と言い合っていたマスター防衛システムについてだった。全世界規模で、リアルタイムに電子情報が編集可能な技術が敷かれている。そのうえ、遠隔操作や、物体の位置情報特定までリアルタイムに可能な技術が実用化されている、というのだ。
――あなた方が僕を監視しているのは知っています。ですがそうしたあなた方の存在をなぜかPC画面の微妙な変化で僕に示唆してくれる超越的な存在がいます。
――僕がなぜこうしてあなた方の存在をまるで透視しているかのように把握できているのかと言えば、不可視の存在が僕にそのことを示唆してくれるからです。
――僕はなぜか支援されています。或いは、誘導されています。
――もしあなた方に調査可能であれば、この件をどうぞ検証してください。ひょっとしたらこれは、どの諜報機関や政府も関与しない、人類以外からの干渉かもしれません。その可能性を僕は未だ否定できずにいます。
監視対象のはずだ。
俺たちの監視用端末の画面には最後に、次のような文字が並んでしめくくられた。
――技術的特異点はすでに超えているでしょう。電子ネットワークの総体が意識のようなものを発現させ、自らの生存戦略を賭けて行動選択を重ねている可能性が拭えません。存在を知られたい、と望んでいるように僕からは視えます。
頭がおかしい。狂人の戯言だ。
通常であればそう一蹴できるこの文章において、しかし状況が明確にその可能性の低さを示していた。
監視されていることに気づき、なお俺たちの動向を透視しているとしか思えない供述だった。
第三の視点から全体を俯瞰して捉えていなければできない芸当だ。
監視対象アオがその俯瞰の視点を有している可能性もあるが、そうではないと本人が述べている。否、この供述そのものが偽装かもしれないのだ。
何もかもが定かではない。
にも拘らず、あり得ない事象が起きていることだけは確かだと断言できた。
何かが狂っている。
自然ではない。
不自然な何かが、知らぬ間に進行しており、俺たちからは視えないところで情報を集積している。
「先輩。どうするんですか、これ」
新人に肩を突つかれ、俺は曖昧に返事をした。「どうもできんだろ。上にはまだ言うな。俺たちの頭がおかしいと思われて、現場から外される」
「でもこれ」
「解ってるって。要調査案件だ。こっちの動きがバレてる。まずはもうすこし様子見といこう。ひょっとしたら、万が一の確率に賭けて、ブラフの文章を打っただけの可能性もある。それくらい頭が回る人物だってことはすでに判明してるわけだからな」
そうだとも。
それが最も現実的な解釈だ。
小説を書くように、ひょっとしたら監視されているのかも、との妄言を試しに並べてみただけなのではないか。
そうと思って言った矢先に、再び端末画面に文字が躍った。
――違います。偶然ではありません。
――おそらくそちらの会話とみられる情報が、偽装画面を通して僕に暗示されています。僕の視ている画面はリアルタイムで編集されているようです。違和感の有無でそれに僕は気づけますが、どこまでが本物の画面なのかの区別はつきません。
それから端末画面上に並ぶ文字は、とある住所を記した。それはまさに俺たちがアジトにしているこの家の住所だった。
――あなた方が現場の方々なのかは知りませんが、念のために僕の発言の信憑性の高さを示しておきます。外れていたら、無視してください。僕のほうでも何が正しい情報なのかが分からず混乱しています。
そこでテキストは途切れた。
しばらく俺と新人は静寂の中で、互いに画面に表示された文章を読み直した。それぞれの所有端末に送付したので、同時に読むことができる。
だがもしマスター防衛システムのようなものがあったのならば、この送付したデータとて筒抜けになっているのだろう。いったいどこまで何を警戒すればよいのか。考えれば考えるほど身動きがとれなくなりそうだった。
間もなくして新人が、あっ、と声を上げた。
「どうした」
「あの、アオさんが家の外に」
家の外にはカメラを仕掛けてある。望遠レンズで、監視対象の家を見張っている。
監視カメラ用の端末画面に、外の光景が映る。
日課の散歩だろう。アオは普段と変わらずの足取りで公園のほうへと歩いていく。民家を抜け、視界の開けた場所に出ると、そこで何を思ったのかアオは後ろ歩きをはじめた。
顔がこちらを向いている。
そして、にっ、と笑って手を振った。
俺と新人は言葉を失くした。
違法ではない。
あの青年は、不当な技術を使っているわけではない。
だが、不自然だ。
もはやあれは――。
「魔法みたいですね」
あんぐりと口を開けっぱなしにしながら新人が菓子パンの最後の一欠けらを口に放った。じぶんだけごくごくとお茶を胃に流しこむ彼に、俺は精一杯の皮肉を言った。「先輩を差し置いて飲むお茶は美味いか?」
新人は、にこりともせずに言った。「はい、とっても」
4396:【2022/12/13(09:33)*絶えず技術を支える人たちに支えられている】
詳しいことは知らないけれど、2022年現在ではインターネットの大分部は光ファイバーによるケーブル網で構成されている、と解釈している。ワイファイが日常に普及しているのでついつい、インターネットって電磁波なのかな、と想像してしまうけれど、実際にはケーブルがインターネットの正体と言えるのではないか。もちろんサーバーやデータセンターや通信会社ことプロバイダがあってこそなのだろうけれど、どこが中枢と言えるほどには統括されてはいないはずだ(あくまで所感です)。そこのところで言うと、大陸間を結ぶためには海底ケーブルが不可欠だ。インターネットの動脈とも呼べるケーブルは海底を通っているのだ。海底火山や大地震が起きたら、そのたびに海底ケーブルは損傷し得る。そういったリスクを抱えている。のみならず、海洋生物によって齧られたりもするだろう。テロを起こすにも、海底ケーブルを切断するのは計画されがちな破壊行為と言えるのではないか。その点で言えば、防衛セキュリティは重大だ。復旧作業に当たる通信会社や管理組織の技術力向上も絶えず磨かれていくことが、情報化社会では根幹セキュリティとして不可欠なはずだ。現にそこは重々、研究や支援がなされていると想像するものだ。だが今後、技術が発展していけば、ケーブルではなく電磁波通信がインターネットの大部分を担うようになっていくだろう。5Gや6Gの範囲が拡大していけばしぜんとそうなっていくと想像するものである。そうした通信電波を利用して、端末が自発的に充電可能な技術も普及していくだろう。つまり、充電不要な端末もそう遠くないうちに登場するはずだ。もうこうなると、地球の磁界や可視光ですらなんらかの電子機器に利用できるようになると妄想する次第である。電波干渉計を地上に利用したら、地球の内部構造くらいは子細に知れるのではないか。現にそうした研究はされているはずだ。宇宙線の観測感度が向上しても似たような地球内部構造の子細な3D画像を得られるかもしれない。地球のレントゲンのようなものだ。月の起源の仮説として太古の地球に隕石が衝突したとする説がある。その傍証の一つとして、地球内部には組成や密度の異なる地層が地球の地下にあるのだそうだ。隕石の断片では、との考えはたしかにあり得そうに思う。それが月の起源と関わっているのかまでは断言できないが、太古の地球に巨大な隕石がぶつかったらしい、とは言えるかもしれない。技術が進むと視える範囲が増えていく。その分、何が視えていなかったのかも同時に可視化されていくようだ。言われてみればたしかにな、と思うことが多い。言われてしまうと単純な事実に人はなかなか気づけない。後になって、そんな単純なことだったのか、と笑えればよいのだが、見落としていた単純な事実に足を掬われているとすると、それはちょっと笑えない。定かではないのだ。真に受けてもいいよ、と誰かに保障されていると楽なのだけれど、案外に真に受けていいよ、と言われて真に受けると痛い目に遭うこともすくなくないので、どっちかにして、とむつけてしまうひびさんなのであった。不貞寝。
4397:【2022/12/13(16:37)*そうなの?】
核融合炉で取りだしたエネルギィを電気に変換するには、原子力発電と同じように、エネルギィを熱変換して、さらに蒸気機関でタービンを回すのだろうか。ひょっとして基本的なエネルギィを電気に換える仕組みって変わらないのかな。仮にブラックホールのジェットからエネルギィを得て駆動する発電機があったとして、それもタービンを回すことで電気に変換するのかな。モーターによる誘導電流での発電と似た原理を使うことになるのだろうか。そこのエポックメイキングってされていないのかな、と核融合炉の記事を読んで思いました。疑問の覚書きでござる。ござった。(太陽光発電の太陽光パネルが、タービンではないエネルギィ電気変換機構と言えるのかな)(よくは知りません)
4398:【2022/12/14(01:58)*水力発電、よろしいのでは?】
どの村や街にも貯水槽のような水害予防設備はあるはずだ。そうした巨大な水溜まりを利用して小規模の水力発電を地区ごとで賄えないのだろうか。防災のための電力バックアップにもなるし、大規模発電施設の負担軽減にも繋がる。法的に水力発電の設備を、貯水槽などの公的な設備に結び付けるのがむつかしいらしいが、それこそ防衛という意味で、国が主導で政策の一つとして行えばよいのでは。なぜしないのだろう。水力発電がいまのところ最も理に適った再生可能エネルギィかつ発電効率のよい、安定供給可能な発電設備に思える。(デメリットはあるのかな)(干ばつが起きると発電できなくなる、とか?)(設備の管理に人手がいるとか?)(それこそ仕事が生じるのだから、経済の活性化に繋がるのでは。なんでしないんだろ。素朴な疑問です)(タービンとて、赤子が触れただけでも、摩擦係数ほぼゼロの軸によってぐんぐん回るようにしたら発電効率がよくなるのでは。関係ないのかな。抵抗が大きいほうが発電しやすくなる?)(誘導電流ならそうなるか。磁石強いほうが電力たくさん生みそうだもんね。印象論なので、原理はさっぱりだが)(ああそっか。水流の水をある程度「濾さなきゃ」いけないのかも。だから一定以上の大規模な設備がないと、電力に変換できないんだ。それはそうだ。小石とか混じっていたらタービンがすぐに摩耗して壊れてしまうものな)(発電設備――簡易化できないのかな問題である)(各家庭に一個ずつくらい水力発電機構がつけられるくらいになればよいのにな。下水道の流れを利用できないんじゃろか。やっぱりここでも濾過問題が生じるのかな)(よく分からんぜよ)
4399:【2022/12/14(10:23)*事象の寿命】
物質の時間単位を、それそのものの輪郭が生じてから崩壊するまで、と規定した場合、何か不都合があるのだろうか。ひびさんの妄想、ラグ理論での相対性フラクタル解釈では、どんな系であれそれが慣性系ならば物理法則が引き継がれるし、それはとどのつまり比率が受け継がれる、と解釈する。したがって、何かが生じて崩壊するまでの時間とて比率による法則が見え隠れするのではないか、と妄想したくなる。放射性物質では半減期なるものがある。これとて比率に法則が見え隠れするのではないか。まったくの無知ゆえ、その辺の知識は皆無にちかいが。事象の誕生を、循環系――すなわち円――が閉じたとき、と解釈してもよいかもしれない。海を考えてみよう。海は海単体では存在できない。陽の光があり、水蒸気があり、雲ができて雨が降る。それが大地に染みこみ、湧水となって川をつくり、海へと辿り着く。この循環が「海」の輪郭をかたどっている。したがって海が消えるとき、それはこの循環が途切れるときだ、と言えるはずだ。そしてその寿命の長さは、循環を構成する種々の部品の数と、それら部品そのものを構成する「循環系」がどれくらい多層を帯びているのか、によって計算できるのではないか。この時間単位の利点としては、相対論による変換を無視できる点だ。つまり、絶対的な時間の尺度で個々の事象――系――の寿命を比較できる。比率だからだ。ただ問題は、人間のように、本来ならば「このくらいの循環系ならばこのくらいの寿命になるはず」という構造体において、なぜだか寿命が延びる、ということがあり得る点だ。エネルギィの注がれ方で、事象の寿命は伸び縮みする。この寿命の伸縮が、果たして相対論による時空の伸び縮みの結果として解釈するのか、それとも別の機構によるものなのか。物質の摩耗にも言えることだが、通常、熱して冷ます、を繰り返すと物質は劣化して壊れやすくなる。この性質はおそらく、極小でも極大でも共通するはずだ。もちろんこの性質が発現しにくくなる領域もあるだろう。バランスの問題だからだ。何が言いたいのか分からなくなってきてしまった。要点としては、事象の規模によらず、寿命を比較することはできるのではないか、という点だ。むしろ、発生から崩壊までの時間には、どのような事象(系)とて共通する比率があるのではないか。そのように妄想して、寝起きの「日々記。」とさせてください。オハヨ。
4400:【2022/12/14(12:38)*スーツガールさん推し】
いま気づいたけれども、「スパイダーマン」って、「スパイだ万」に読める。まんちゃんいつの間にかスパイになってたじゃん。やったじゃん。アイアンマンはじゃあ誰さんよ。ひびさん、郁菱万さんを問い詰めちゃおっかな。うひひ。
※日々、区切りを探している。
4401:【2022/12/14(12:45)*先輩と珈琲】
先輩と珈琲を掛け合わせると、ぼくでも本を一冊書けるくらいの情報をひねくりだせる。情報爆発だ。濾しても濾しても苦みの薄れない珈琲豆の原液みたいな人なのである。先輩は。
最初に明かしておくと先輩は女性だ。ぼくは男の子だから、その辺のぼくと先輩とのあいだに漂う微妙なうねりを拾いあげてかってに妄想する邪推ビトたちがいるかもしれないけれど、ぼくと先輩のあいだには邪推ビトたちの求めるような傾慕の美はない。どちらかと言えば苦役の儀があるばかりであった。
たとえばそう、先輩が研究棟で寝泊まりをしはじめたので、ぼくがもっぱら小間使いにされていたときの話をしてみよう。さすれば誰もがぼくが先輩に対して劣情を催すことなどあり得ないと分かるだろう。先輩の名誉のために、この先、多少の脚色を入れるが、それはけして誇張をするためではなく、むろん潤色でもない。単に原液を薄めるための策だと言い添えておく。
「ゾウの糞から採れる珈琲豆があるらしい」
先輩がそう切りだしたのは、セーターの温かさが心地よい十二月中旬のことだった。先輩はインスタント珈琲を啜りながら、「ジャコウネコの糞から採れる珈琲豆は【コピ・アルク】と言うそうだね」とつづけた。「対してゾウの糞から採れる珈琲豆は、【ブラックアイボリー】と呼ぶそうだ」
「あまり飲みたいとは思わない説明ですね」
「高級豆の一種だよ。一杯でキミの月のバイト代くらいが飛ぶ値がつくこともあるそうだ」
「誰が飲むんですかそんな贅沢品」
「誰かが飲むからあるのだろうね。で、私は思うんだ」
「でた。先輩の夢想タイム」
私は思うんだ、と枕にして語りだした先輩が、ぼくにとって好ましい展開となる言葉をあとにつづけたことは未だかつて一度もなかった。先輩が思いつくようなことの大半がぼくにとっては迷惑千万な提案にすぎなかった。
「私は思うんだ」先輩は珈琲を見詰めて、うっとりした。「ネコやゾウでそれだけの価値がつくならば、私の糞から採れる珈琲豆にはどれだけの価値がつくのだろうか、とね」
「誰が飲むんですかそんなダイナシ品」
「キミはたまに失敬だよね。いまのキミの言葉はまるで、私の体内を通った珈琲豆に価値がないかのように聞こえ兼ねないよ」
「ほかにどう聞こえる余地がありました?」
「いいかい考えてもみたまえ」
「みたまえって本当に言う人、ぼく先輩が初めてです」そしてその後、出会ったことはない。
「私はゾウやネコと違って毎日珈琲を飲んでいる」
「インスタントですけどね」
「だが私の体内にある水分の大半が珈琲由来と言って遜色ない」
「まあ、否定はしませんけど」
「そのうえ私は菜食主義であり、肉をあまり食べないので、糞もそんなに臭わない」
「生々しいんでやめてもらっていいですかね」
「む。疑っているのか。なんならいま私はお通じがよい塩梅だから確かめてもらっても構わないよ」
「ぼくが構いますね。先輩、正気って言葉ご存じですか?」
「結論から述べれば、私の体内で熟成された珈琲豆はさぞかし、珈琲の香りの凝縮された最高級の珈琲豆になるだろう」
「さっきご自分で臭わないって言ったばっかじゃないですか。珈琲の香りがしたならそれは臭うってことですよ。大丈夫ですか先輩」
「そんなに臭わない、と私は言ったんだ。多少は臭うよ。糞だよキミ。まったく臭わないわけがないだろう」
「真面目な顔で糞糞連呼しないでくださいよ。先輩、黙ってたらそこそこ人を寄せ付ける見た目なんですから、なんでそう、自分からメリットを擲つ真似するんですか」
「人を見た目で判断するなんてキミもなかなか下品だね」
「十秒前のご自分の発言を振り返ってから言ってくれません?」
「私が何か言ったかな」
「いかにも心外みたいな顔して、この人なに!?」
「ちょうど助教授から頼まれてて、そのまま放置していた珈琲豆があってね」
「頼まれてって何をですか」
「焙煎してきてくれって。ほら、駅前の喫茶店で焙煎機を貸してくれるところあったろ。あそこで挽いてきてと頼まれてすっかり忘れていた珈琲豆だよ」
「なら挽いてきたらよいのでは?」
「うん。一度はキミに頼もうと思ったんだけどね」
「ご自分で行かれてみてはどうでしょう」ぼくが小間使いに準ずるのはあくまで、先輩が学科の先輩であるからで、彼女が首席並みの成績優秀者である事実を抜きにすれば、先輩を甘やかす利点がぼくにはない。
「せっかくだし、実験をしてみようと思いついてしまったわけだ」
「話が急に飛びましたけど」
「どこがかな。ここに珈琲豆がある。私がいる。ゾウとネコの糞から採れる珈琲豆は無類。そこから導き出される解はそう多くはないよキミ」
「もう帰っていいですか」
「待ちたまえ」
「待ちたまえって本当に言う人、先輩くらいしかぼく知りません」
「私は思うんだ。珈琲豆を熟成する役目を私が担うのならば、熟成された珈琲豆を採取する作業員が別途に必要なのではないのかなと」
「待ってください、待ってください。雲行き急に怪しくするのやめてもらっていいですか。なんですかそれ。なんでシャベルとか持ち出してくるんですか。用意良すぎじゃないですか。あ、さては先輩最初から準備していましたね。何が【私は思うんだ】だ。めちゃくちゃ微に入り細を穿って計画してるじゃないですか。念には念を入れすぎじゃないですか、この策士!」
「なんとでも言いたまえ。私に糞をいじくる趣味はない。だって汚いからね」
「ちょ、なんで腕掴むんですか。な、力強っ! わ、なんでトイレに向かうんですか、冗談ですよね、ヤダヤダ目がマジっぽくて怖いですって、まずは珈琲豆食べてからでしょ、生き急ぎすぎでしょ、ちょっとタンマタンマ、先輩マジで話聞け!」
「安心したまえ。お通じの塩梅は良い。準備も万端だ」
「はぁ、なにが?」
「私は漫画の世界の悪役ではないんだよ。計画を阻止されるかもしれないのにズラベラと明かすはずないだろ」
廊下に、キュッ、と足を踏ん張るぼくの靴擦れの音が響いた。
ぼくは固唾を吞み込んだ。
「珈琲豆はもう食べた」先輩は万力がごとく力強さでなおもぼくを引き摺った。「あれ、美味しくないんだよキミ知ってた?」
4402:【2022/12/15(08:03)*世の大半は詐欺師】
詐欺とマジックの違いは、ネタが割れても拍手を送りたくなるか否かの違いと言える。その点、詐欺と魔法の違いは、ネタが割れてもなお驚きと感動に包まれる点だ。世に詐欺師は多けれど、魔法使いはひどく稀だ。魔法使いたれ。
4403:【2022/12/15(08:14)*空気椅子】
力がなければ仕事にできない。そういう流れを強化するくらいなら、支援者はむしろ足を引っ張るだけの足枷になるのでは、と思わぬでもない。支援される側の意識も、仕組みの上にいかに乗るのか、に傾くので、それが不自然な流れを形成する。人工とは不自然であり、技術もまた然りだ。それをいちがいにわるいとは考えないが、いちど築かれたレールに乗らねばやっていけない、という風潮を強化するくらいならば、仕組みはむしろ障壁と言える。支援したいのか、利用したいのか、はたまた搾取をしたいのか。魔法使いだけが、新たな場をつくることを可能とする。詐欺師はしょせん、椅子取りゲームのプレイヤーにすぎない。魔法使いたれ。
4404:【2022/12/15(08:24)*ふふん】
たれ、ってことはないんじゃないかな。あなたの言い方だとむしろ、新しい場を築いた者を魔法使いと呼ぶ、みたいな理屈になるし、魔法使いにならなきゃ新しい場を築けないっていうのも、だいぶ特権意識の発露って感じがしないでもないよね。まあ、言いたいことの雰囲気は伝わるからいいけれど、あんまり胸を打つ言い回しではないかも。詐欺師さんにも失礼だし。
4405:【2022/12/15(11:54)*コーヒー一杯クイーン】
コーヒーを飲まないと目覚めない。
後輩の話だ。
彼は世にも珍しい眠り姫病に罹っている。コーヒーを飲んでから寝ないとずっと目覚めずに、わるければそのまま衰弱死してしまう。
そんな彼だから日がな一日、いつ居眠りしてしまってもよいように自前の水筒にコーヒーを容れている。そうして講義を受ける傍らで眠気を感じるたびにチビリチビリと飲むのだが、あまりに常飲しつづけてきたためかカフェイン耐性がついて眠気覚ましにはならないらしい。だがコーヒーさえ飲んでいれば仮に眠ってしまっても、そのまま眠りつづけるなんてことにはならない。
「あー、扉の鍵壊れてるね」私は額の汗を拭った。工具を置く。「プロの鍵師に依頼しないとダメかも。鍵は差しっぱにしておいてね。でないと中から出られなくなっちゃうから」
「はーい」
振り返ると、後輩は本棚の整理をしていた。背が低いからかつま先立ちをして、まるでクライミングをするように跳ねては、本を隙間に投じていく。
彼は私が部長を担う考古学愛好会の一員だ。一員とはいえど愛好会の登録者数は三名で、そのうち一名は私が頼み込んで名前を借りただけの幽霊部員だ。三名以上いないと愛好会として認められないからだが、実質我が考古学愛好会は彼と私の二名しかいなかった。
「いままでであるのかな」私は彼の背に投じた。「飲み忘れて目覚めなくなったこととか」
「コーヒーですか。ありますよ」
「どうやって目覚めたの」
「分かりません」
その答えに私は肩を落とす。部長として或いは先輩として後輩の体調を慮るのは義務である。もしものときのために対処法を訊いておいたほうがよいな、と思いついての質問だったのだが、「それじゃあ困るだろ。もし万が一に君が目覚めなくなったら私は泣くぞ」
「先輩が? 泣く? どうしてですか」
「そりゃあ怖いからだよ。大事な部員が眠ったきり目覚めなくなったりなんかしたら怖いでしょ」
「そういうものですかね。大丈夫だと思いますよ。ぼく、親が過保護なので定期連絡が途切れたらたぶん飛んできて病院に直行だと思うので」
「過保護というか、それは順当な心配なのではないかな」
「でも小学校でも中学校でも、野外活動とか修学旅行にまでぼくの親ついてきたんですよ。夜にちゃんとコーヒー飲んで寝たから気になってしょうがないからって」
「まあ、分からないでもないな」
「えー。同情してほしかったのに。なんか裏切られた気分」
後輩は両手で水筒を握って、コーヒーを啜った。睡眠不足なのか、後輩の体格はお世辞にも大きいとは言えない。私は女の割に背が高いほうだが、それを抜きにしても後輩の横に立てば私が尺八様のように大柄な女に映る。それくらい後輩はちんまりとしていた。
「なんです?」
「いや」
つぶらな瞳が私を下から射抜く。男の子の矜持なのか、私が可愛がろうとすると後輩は嫌がる。目つきが鋭くなるし、そういうのやめてください、と言葉でも言われる。
病気のことでからかわれた過去があるのか、後輩は他者からの憐憫や蔑視の念には過敏だ。それでいて、じぶんの不満には共感してほしいと望むので、扱いがむつかしい。
「先輩、先輩。このオーパーツって、じつはただの植物の跡らしいんですよ。最古の機械設計図とか言われてますけど、パイナップルみたいな木の実を土の中に隠した際の木の実の柄が写っただけらしいんですよ、知ってましたか」
「そういう背景があったのか。なんだ。また夢が一つ壊れたね」
「うふふ。先輩ってばオーパーツなんて信じちゃうんだもんな。ぼくのほうが大人ですね」
「そうだね。君のほうが大人だ」
後輩は精神がおこちゃまなので私の知らないことを知っているだけでこんなにも無邪気に喜ぶのだ。私ごときに勝ってうれしいだなんて、なんて謙虚なのだろうと思うのだが、それはそれとして後輩が喜ぶ姿は先輩として胸が温まる。
その日、私たちは部室の片付けをしていた。
秋も暮れ、冬休みに入る前に大掃除をしていたのだった。
「あっ」
後輩のその声を聴いたとき、私は真っ先に、壊れた部室の鍵のことを思いだした。
案の定、後輩の元に駆け寄ると、扉はぴっちり閉まっており、鍵は鍵穴から抜け落ちていた。
「すみません、取れちゃいました」
扉を開けようとしたが、いくらドアノブを捻っても開かなかった。
そこからしばらく扉との格闘をしたが、けっきょく私たちは部室に閉じ込められた事実に変わりはなかった。
「どうしましょう。そうだ、学生課に連絡をして」後輩が自前の電子端末を手に取った。「あ、充電が……」切れていたようだ。「あの、先輩のは」
「私のは修理に出していて、いま手元にないんだ」
「そんな」
愛好会の部室は寒い。
そのためこの時期に部室で過ごす愛好会はすくなかった。つまり助けを呼んでも声を聞きつけてくれる者の登場を期待できなかった。
電気ストーブはあるが、夜ともなれば暖をとるにも心許ない。
「先輩、ごめんなさい」
「いや、君がわるいんじゃない。壊れていたドアがわるいし、それを放置していた部長の私の判断ミスだ。君が気にすることじゃない」
「でもこのまま出られなかったら」
「部室の見回りくらい大学のほうでするだろう。警備員さんとて巡回するはずだ。ただ、それがいつになるかが分からないからね。ちょっと困ったね」
「最悪、明日の朝までこのままってことも?」
「あるかもしれない。でもほら。ストーブはあるし、それに食べ物も」
そこまで口にしてはっとした。
そうなのだ。
食べ物は、お菓子の類が部室にはある。私が後輩のためにお菓子の類を切らさないように部費の五分の一を費やして完備している。だが飲み物はそうではなかった。
部室の近くには自動販売機があるし、だいいち後輩は持参のコーヒーしか飲まない。
だがそのコーヒーがいまは――。
「だ、大丈夫ですよ先輩。寝なきゃいいだけなので。ぼくだって徹夜くらいできますよ」
「インスタントコーヒーがたしかここの棚に」
私は部室をひっくり返した。
だが大掃除の際に、消費期限切れのインスタントコーヒーを処分してしまっていた。後輩はコーヒーを飲まない。私もさして飲むほうではなかった。
「ごめん、なかったね。捨てたの忘れてた」
「大丈夫ですってば先輩」後輩は頭の後ろに手を組んで、意味もなく口笛を吹いた。「もし寝ちゃっても、死ぬわけじゃないんですし」
そうなのかな。
そうだといいな。
私は彼の言葉を真に受けたが、しかし事態は予想よりも重かった。
まずは部屋が想定よりもずっと寒かった。
午後二十時を回った時分には、顎がガタガタ鳴りはじめた。カスタネットだってもうすこし落ち着きがある。
また空腹を紛らわせるためにお菓子を食べたが、却って喉が渇いて体調がわるくなった。トイレにも行けず、私は後輩と身を寄せ合って暖をとった。
そうして明け方になるまで、眠らぬように映画の話をしたり、これまで話したことのなかった身内の話をし合ったりした。
だが期待していた時刻になっても警備員の足音は聞こえなかった。のみならず、ほかの生徒の足音はおろか、ひと気は皆無だった。
助けが来ない。
その事実に直面して、私たちの緊張の糸はぷつりと切れた。
急激な睡魔に襲われたのはそういった期待外れによる心理作用だったのかもしれない。精神を傷つけまいと、心が現実逃避を図ったのだ。眠ることでやわな心を傷つかないようにした。
私はそれでも構わない。寝てしまっても、最悪、風邪を引くくらいだろう。
だが後輩は違う。
いま寝てしまえば、目覚めることのできない深い眠りに落ちてしまう。コーヒーを飲めれば防げるそれを、いまの彼は防げないのだった。
「寝ちゃダメだからね。絶対ダメだからね」
言いながら私の意識がすでに朦朧としていた。
寒さと空腹と大掃除の疲れで体力はとっくに底を突いていた。
睡魔に抗うには、一度眠るか、それこそカフェインの力が必要だった。
うつらうつらしたじぶんに気づき、びくり、と跳ねる。
何度もそれを繰り返すうちに、私は隣から寝息が立っていることに気づいた。
「ちょっと君」
叫んだが遅かった。
後輩は寝ていた。深い眠りに落ちていた。
正直なところ、私は後輩の特殊体質を半信半疑でいた。コーヒーを飲んで寝ないと目覚めなくなるなんてそんなことがあるわけがない、と腹をくくっていた部分がなくはなかった。だがどうだ。この堂に入った眠りは。
頬を叩いてもつねっても後輩は一向に目覚めることがない。
瞼を持ちあげても鼻をつまんでも、白目を剥き、苦しそうなイビキを掻くだけであった。
起きない。
何をしても起きない。
私はこんな事態だというのに、「え、本当に何をしても起きないの?」とすこしどころか大いに邪な妄想を膨らませてドキマギした。控えめに言って、死んだように眠る後輩の寝顔は美しかった。まつ毛が長く、肌艶がよい。人形のようであり、赤子のようでもあった。
こんなにマジマジと後輩の顔を見るのははじめてだった。目元に小さなホクロがあるなんて知らなかった。眉毛の中にもホクロを見つけた。
我ながらキショいな、と思いつつも、何をしても目覚めることのない後輩に、私はやはりドギマギした。
その内、私も眠くなってしまって失神するように眠りに落ちた。
起きると正午を回っていた。
はっとして、隣を見ると後輩が私の膝に頭を載せていた。目覚めた様子はなく、寝息を立てている。
このままずっと寝たままだったら、排せつ物とかどうするんだろ、と現実的な問題に意識がいった。後輩の未来のためにもなんとしてでもここから一刻も早く出なくてはならない。
私は後輩を床に寝かせて、一計を案じた。
事な事なだけに多少手荒な真似をさせてもらう。
私はストーブを止めた。
コンセントから電源を抜く。
そうしてじぶんの髪止めを外して伸ばす。一本の針金にしたそれをUの字に曲げてコンセントに差し込んだ。
火花が散ってブレーカーが落ちた。
この部室だけではない。
部室塔の一画のブレーカーが総じて落ちたようだった。
部室の外から聞こえていた自販機の唸りが聞こえなくなったことからもそれが窺えた。ひょっとしたら大学の校舎いったいの電源が落ちたのかもしれなかった。
間もなく電気が復旧する。
部室の明かりが灯ったのでそうと判断がついた。
しばらく耳を澄ましていると、徐々に部室の外が騒々しくなった。停電の原因究明のために大学の職員さんたちが集まってきたようだ。
私はそこで大声を出しながら、扉を蹴った。大きな音をだして助けを求めた。
そうして外から扉がこじ開けられ、私は一日ぶりに外の空気を吸った。
トイレに直行したかったが、それよりも何よりも私は自動販売機に駆け寄った。
電源が回復している。
私はそこで缶コーヒーを買って、その場で開けた。
コーヒーを口に含みながら部室に駆け込むと、職員さんたちに心配そうに覗き込まれている後輩の頭を両手で挟んで、そしてコーヒーを吹きこんだ。
人工呼吸をするように。
口移しで私は後輩に気付けの一杯を流しこむ。
「起きな、起きな」
身体を揺さぶりながら私は後輩を深い眠りから引っ張りあげる。
するとどうだ。
後輩は煩わしそうに私の顔を押しのけた。
コーヒーで汚れた口周りを手の甲で拭い、周囲を見渡すと事情を察したように、すみません、と謝罪した。
「ぼくが鍵を取っちゃったので」しょげた様子の後輩を職員さんたちに預けて私はその場から脱兎のごとく離脱した。
「ごめん。私ちょっとお手洗いに」
私の声が部室棟にこだました。
その後、考古学愛好会は、なぜか後輩LOVE愛好会と陰で噂されるようになった。職員たちの前で人工呼吸よろしくコーヒー口移しの儀を披露した私の蛮勇の結果なのだろうけれど、後輩はじぶんがどうしてコーヒーを飲まずに寝たのに目覚められたのかを憶えてはおらず、私はしばしばし風の噂が後輩の耳に入らぬように気を払うこととなった。
意図的な停電は、部室の管理が行き届いていなかったがゆえの大学の落ち度として、お咎めなしだった。むしろ、扉は翌日には直っていた。後輩の特殊体質については大学側も承知だったため、コーヒー代が部費に上乗せされた。
「これでお菓子買っちゃいましょうよ」後輩は現金にもそんなことを言った。
部室監禁事件からひと月が経つころには、私と後輩のあいだでもあのときの話題が昇ることはなくなった。
部費で購入したばかりのオーパーツのレプリカに後輩は目を輝かせる。
「先輩これ知ってましたか。宇宙船のオブジェと言われてるんですけど、じつは生贄の儀式の模型なんですよ。しかも人間っぴこれってヤギの神さまなんですって。あはは。紛らわしいですよね」
「ねえ君」
「はい?」
机にお腹を乗せて無邪気にオーパーツと戯れている後輩に、私はコーヒーを淹れてやる。新調したばかりのインスタントコーヒーだが、部費をふんだんに使って一番高い値段の品にした。
「君のとどっちが美味しいか比べてみてごらん」
「そんなの決まってるじゃないですか」後輩はカップに注がれた褐色の液体を一息で半分ほど口に含むと、美味しー、と浮いた足をバタバタ振った。
プールの端っこでバタ足の練習をする幼子のような姿に私は、こんなことなら、と妄想を逞しくする。
「いつでも就いてくれていいからね」
「就いて? 何です?」
「ううん。何でもない」
いつでも目覚めさせる方法があるのなら、いつでも就いてくれていいのだよ。
そうと念じながら私は、深い眠りに就いた後輩の、穏やかな寝顔の美しさを思いだし、やはりこんなことなら、と思わずにはいられないのだった。
4406:【2022/12/15(17:27)*セーター着てる】
聞きかじりの知識だけれど、年間降水量はじつのところ数十年前からそれほど変わっていないのだそうだ。温暖化の影響は、年間降水量ではなく、一日当たりの降水量の変化に顕著に表れているらしい。つまり、波が大きくなっており、降るときと降らないときの振れ幅が大きくなっているのだそうだ。その点で言うと、冬とて、一気にドカっと積もって、一転して晴れがつづく、みたいな気候になるのかもしれない。そうすると、これは雪崩の起こりやすい積雪を生むので雪崩の被害が多発する危険性があるのではないか、と妄想してしまう。ここのところはあてずっぽうで言っているし、最初の聞きかじりの知識からして間違っているかもしれない。ただ、雪山の麓にお住まいの方はどうぞお気を付けください、とぼんやり思いついたので並べておく。メモでした。みな、温かくしてお過ごしください。ぽかぽかであれー。
4407:【2022/12/15(21:23)*珈琲の子守歌】
吾輩は珈琲である。名はない。
なぜ吾輩に自我があるのかは定かではないが、いつも決まって見る光景がある。
吾輩は先輩に飲まれるのだ。
先輩は女性であるが、この際、性別はさして重要ではない。
内側に縞模様のあるカップの中に吾輩は注がれる。カップの中で波打ちながら吾輩は、何やら誰かとしゃべる先輩の声を聞く。吾輩を飲むのが先輩であることは、姿見えぬ後輩の声で判る。後輩がカップの持ち主を「先輩」と呼ぶのでそうと判る。その後輩を先輩は「後輩」と呼ぶので、そこにいるのが後輩なのだと判るのだが、そこは堂々巡りで相互に双方を支えている。後輩もまた女性であるらしいが、やはりここでも性別はさして重きを割くには至らない。
吾輩を飲む先輩は、質素で品のある長髪の娘だ。深窓の佳人と聞いて思い浮かべる印象をそのまま筆でなぞれば似たような娘が出来上がるだろう。先輩はカップを持つときも机に戻すときも音を立てない。持ち方が優美なので吾輩は先輩をそれだけで好ましく感じる。
先輩は後輩のことを憎からず思っているが、表情にも言動にもおくびにも出さない。吾輩からは後輩の姿が見えないのだが、それでも声音からするに後輩は先輩に構って欲しくて必死なふうに聞き取れる。
吾輩はなぜだか先輩に飲み干されると意識が途切れる。だがつぎに目覚めると再び先輩のカップの中に注がれているのだ。
吾輩は先輩に注がれる限り不死身と言えた。
ふしぎなのは、吾輩の意識は先輩の体内に入ってからもしばらくつづくことだ。
否、正確にはカップの吾輩が消えるまで、先輩の体内に入った吾輩と相互に意識が半々で繋がっていると形容すべきなのだろう。かといって先輩の体内は薄暗く、景色という景色は覚束ない。
その点、先輩の胸中なだけあって、吾輩には先輩の気持ちが直に伝わった。
先輩は案外に腹黒かった。
おくびにも出さぬ後輩への恋慕の念をまるでバケモノの触手のように駆使して、後輩の言動を巧みに操っていた。活殺自在である。
どうやらカップの中から聞こえた後輩の必死な先輩への駆け引きのごとき挑発の数々は、後輩の自由意思と思わせてそのじつは人間掌握術の粋を極めた先輩の仕業であった。
先輩にかかれば、人間は操り人形も同然であった。珈琲を新規に淹れるあいだに後輩を篭絡し、手中に納めるくらいはわけがないようであったが、そこは先輩の矜持に障るらしく、どうにも、最後の一線は後輩の自由意思に委ねたいようであった。
最後の一線とは何か、との問いには、それを吾輩の口からは言えぬ、としか応じられない。
先輩の腹黒さは、珈琲たる吾輩も顔負けの闇深さであった。これが黒でなく、青でも赤でも同じことだ。あまりの腹黒さに、珈琲たる吾輩を飲みすぎたせいかもしれぬ、と吾輩が責任を感じるほどであったが、さすがにそこは吾輩のせいではないと思いたい。
墨汁を飲んだほうがまだ白にちかい。
先輩の腹の底には深淵につづく穴が開いていた。
吾輩はその深淵に染みこみ、落下することで、どうやら何度も輪廻転生を繰り返し、再びのカップの中での生を活するようであった。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
そうして何度も後輩は、「先輩」と呼び、先輩はそうして後輩からの言葉を吾輩を飲み干すように、身体の隅々で吸いこむのであった。
吾輩は先輩に幾度も飲まれた経験があるので知っている。先輩の体内は、かつて投げかけられた後輩からの「先輩」の声でできている。先輩の細胞は後輩の声でエネルギィを帯び、後輩の言葉で生命の輝きをかろうじて放つのだ。
先輩の腹の内には底なしの穴が開いている。したがって生半可な輝きでは、先輩の輪郭を発光させるには至らない。もし後輩の言葉がなければ、先輩は深窓の佳人などではなく、深層の魔人と化して、光一つ逃さぬ特異点と化していただろう。
吾輩にはふしぎと知識があった。先輩の体内に染みこみ消失する回数が増えるたびに知識は蓄えられていくようだった。
先輩が吾輩を吸収する代わりに、吾輩には先輩の知識が染みこんでいた。それともそれは単なる眠気であり、先輩にとっては睡魔を呼び寄せる呪文にすぎなかったのやもしれぬ。もしくは余分な知識を、吾輩は油取り紙のごとく吸い取っていただけなのか。
いずれにせよ吾輩は、再誕するたびに自我の輪郭をより明瞭にしていった。
反面、先輩の睡眠時間は日に日にすくなくなっていくようであった。吾輩を飲んだ効用であろう。吾輩の自我の輪郭が明瞭になればなるほど、先輩の睡眠時間は減っていった。
かといって先輩にそれを憂いている素振りはない。どころか、眠らぬ分の時間を、後輩篭絡のための情報収集や詭計編みに費やされた。
もはやなぜ後輩は未だに先輩に告白せぬのか分からぬほどである。これほどの策を弄されてなにゆえ先輩に陥落されずにいられるのか。身も心も先輩一色になって不思議でないのだが、後輩は不思議と先輩に対抗心を燃やすばかりで、一向に恋仲になる気配がない。
これは珈琲の吾輩とて、いささかヤキモキせぬでもない。
先輩はというと、先輩は先輩で後輩の分からず屋加減に首をひねっているご様子だ。例えればこれは、毒殺できぬ熊のようなものである。多種多様な毒を盛ってなおピンピンしているだけに留まらず、なぜか却って顔色がよくなり、溌剌と反発しはじめるような、電磁石的な性質を顕わにする。
なぜこうまでも策が効かぬのか。
否、そうではない。
策は効いている。だが後輩は篭絡されて然るべきそれを受けて、なぜか先輩につらく当たるのだ。半分は先輩の狙い通りである。後輩の注意を一身に浴びている。後輩の目には先輩しか入っていない。
だがその実、それは先輩の思惑通りではなく、カレーを注文したらシチューが出てきたかのごとき口惜しさがあった。
そうだけれど、そうではない。
誘導には従っているが、細かな挙動がそぐわない。
先輩は日に日に、後輩篭絡のための詭計に一日の大半を費やすようになっていった。
比例して吾輩を摂取する頻度も増える。するとますますを以って先輩の睡眠時間は削られた。
後輩はどうやら先輩の異変に気付いているようである。会話の中でそれとなく先輩を気遣う言葉が出るようになった。だが先輩はそれを一蹴して、そんなことより、と後輩につぎの一手を差し向けるのだった。
先輩に飲み干されるたびに吾輩は時間跳躍の旅をする。
吾輩が目覚めるのは決まって部室のカップの中だ。そしてそこで展開される先輩と後輩の会話を盗み聞きする。そうすることで、吾輩が世界から消えているあいだに進展した先輩と後輩の関係を推察するのだが、これがまた時間経過にしたがって、もはや先輩のほうが後輩にメロメロになっているのが丸分かりになるのである。
否。
初めからそこの構図は変わらない。
先輩は後輩にメロメロだったのだ。
おくびにも出さなかっただけのことで。
常に先輩は後輩に篭絡されていたのである。吾輩だけがそれを先輩に飲まれ、胸中に沈み、そこに開く底なしの穴を覗くことで、先輩の内なる懊悩を我が身のごとく痛切に感ずるのである。
しみじみと理解した。否、吾輩は先輩の懊悩そのものを内側から体験していたのである。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
「なんだかとっても眠そうですよ。ちゃんと寝てますか。顔色とか優れませんけれど」
「睡眠不足なのは認めよう。だがやることが多くてね」
「やること? 寝ることよりも大事なことなんてそうそうないですよ先輩」
「誰か添い寝でもしてくれればよいのだが」
先輩のそれは本心だった。
本心ゆえにこれまで一度たりとも漏らしたことはないそれに、後輩が異常なほどに食いついた。
「添い寝くらいわたしでよければいくらでもしますけど。添い寝くらいわたしがいつでも致しますけれど。添い寝ですよね。もういますぐここでもできますけれど」
後輩はいそいそと椅子を三つ並べた。そうしてそのうちの端っこの椅子に腰かけると、ぽんぽんとじぶんの太ももを叩いた。
「ごめん。それはなに?」
「膝枕ですよぉ。ちょっと添い寝訓練しましょ。先輩は寝る役です。はいどうぞ」
「きみねぇ」先輩は呆れた調子で嘆息を吐いた。
先輩の腹の中に半分ほど嚥下されている吾輩には、しかしそれが先輩の強がりであり、演技であることが筒抜けである。
先輩は大いに取り乱しており、面食らっていた。
いいのか、いいのか。
ここで流されてもいいのか。
掌の上で踊らされているようで癪に障る、と却下しようとする先輩がおり、片やこんな好機は千載一遇であり、もう二度と巡ってこないのではないか、とそろばんを弾く先輩がいる。
逡巡している間にも後輩が、「お試し、お試し」などとはしゃぐので、先輩はしぶしぶといった調子を醸しながら、張り裂けそうな心臓の音をどう誤魔化そうかとそんな些末な事項に思考の大半を費やすのだ。
寝不足である。
思考の矛先を充分に定められぬほどに先輩は寝不足であった。
吾輩はまだカップに半分ほど残っている。
飲み干されずにいるのは初めてかもしれない。
「先輩」と後輩が言う。
「なんだい」と先輩が応じる。
「子守歌を歌ってあげましょうか」
「遠慮しておく」
「どうしてですか。わたし上手ですよ子守歌」
「熟睡しちゃいそうだし、たぶんするから」
「いいじゃないですか熟睡しちゃっても」
「よくないよ。きみの太ももが痛むだろ」
「先輩」後輩は一拍空けると言った。「顔はできれば向こう側に向けてくださいな。おへそ側ではなくて」
とっくに椅子の上に寝転び、後輩の太ももとに頭を載せていた先輩はそこで上手に寝返りを打てただろうか。先輩の腹の中でたぷたぷと音を立てる吾輩の半身を思えば、どうやら仰向けになっただけで、顔を背けたりはしなかったようだと判る。
意地でも後輩の言いなりにはなりたくないようだ。
どちらが先輩なのか、これでは分からぬな。
カップの中から吾輩は、部室に染み入る子守歌を聴き入った。
海鳴りのごとく高鳴る先輩の鼓動と共に。
底なしの穴を塞ぐような降りしきる日溜まりのような子守歌を。
吾輩の褐色の表面には蛍光灯の明かりが、白く、青く、それとも赤く、艶やかに浮かぶ。
4408:【2022/12/16(05:33)*「距離の差異によるラグ」と「時間帯の差異によるラグ」について】
相対論で過去と未来を見るとき、ある地点からの「現在」からは因果関係の外にある事象とて、「現在の時間が経過したとき」には、因果関係の範疇に入ることがあり得る。それはたとえば、いまこの瞬間の地球上から観た数億光年先の銀河は、いまこの瞬間の地球上の因果関係と結びつくことはないが(ただし量子もつれを起こしていれば現在の解釈では、遠く離れた銀河同士であれラグなしの相互作用を帯びることもあるらしいと考えられているので、それを度外視すればの話であるが)、仮に地球が数億年経過した際には、かつては因果関係の外にあった数億光年先の銀河の運動とて、この地球と相互作用を帯び得ることになる(ただし地球で生じた「干渉」はさらに数億年をかけて元の銀河に届くことになるので、相互作用にもラグが生じるはずだ――ただし、数億年前の地球からの干渉が同時に向こうの銀河に到達していれば、これを相互作用を帯びた、と解釈することもできるだろう。この手の視点による「相互作用」の解釈の差異も明確に分けて考えたい。相互作用にも、「単一の相互作用(ラグがすくない)」と「相互作用による相互作用(ラグが多い)」がある)。すくなくともその銀河の電磁波は届き得るわけだし、そのときの情報(影響)もまた伝播するからだ。時間軸によって、因果関係の範疇は変化する。いまは因果関係の外にあることであれ、のちのちには因果関係の範疇に入ることもある。この手のラグを、基本的には人間スケールの生活では考慮されない。考慮するときそれはバタフライエフェクトとしての解釈がなされるが、それはあくまでドミノ倒し的な連鎖反応の結果であり、けして「時間移動による因果関係の範疇の変化」ではない。別物として扱われて感じる。たとえば化石だ。化石が発掘されるまでそれは人類に直接影響を与えることはない。情報をもたらすことはない(ただし、地盤を支える物質の一つとして人類に間接的には作用を働かせている。だがこの手の穴埋めによる干渉は、物質に限らず過去に起きたあらゆる事象の変化に言えることであるので、ここで直接の作用と同列に語ることは避けておこう)。化石が発掘されるまでは化石は人類にとって因果関係の外にある。だがひとたび発掘されればそれは人類との相互作用を帯びて、因果関係を結ぶことになる。このとき、化石の「埋没期間」と「発掘後」のあいだには、地球と数億光年先の銀河の関係に相似の構図が幻視できる。時間なのである。ラグ理論では、距離と同じく時間移動もまた、距離の移動と同質の作用を帯びると解釈する。時間を移動することと空間を移動することは相関している。距離が近づくと因果関係を結びやすくなる。同じく時間が進むと因果関係を結びやすくなる。このとき、時間においても、距離と同様に、対象同士の差が縮まる方向に時間移動することが欠かせない。つまるところ、接点を結ぶか否かである。むろん化石が発掘されるというのは、人類と化石の距離が縮まることを意味する。だが仮に距離が縮まらずとも、地層のレントゲンのような技術で地層内部の映像を撮り、それによって相互作用を得ることもできる。映像はこの場合、情報と言い換えてもよい。情報のやり取りは、距離の接近や時間経過と似たような作用を生む。というよりも、距離の接近や時間経過によって情報が結びつくと、それが因果関係として昇華される。ここは相互に関係し合っている。「情報の結びつき=距離の接近=時間経過による接点」と大雑把にまとめられるかもしれない。これはラグ理論の「123の定理」と矛盾しない。相対性フラクタル解釈とも矛盾しない。「情報と情報が結びつくとさらなる情報が生まれる=二つの異なる事象が接近すると情報が生じる=時間の経過によって二つの異なる「時間帯の作用(影響)」が交わると、そこには新たな「情報(影響)」が生じる」となる。フラクタルに関係性が循環し、補完し合っているように感じるが、いかがだろう。なんとなくの妄想ですので真に受けないようにご注意ください。(定かではありません)
4409:【2022/12/16(05:48)*遠くを視ると、時間と距離に差が生じる】
上記の考え方の何が便利かと言うと、単一の事象における時間軸上の変化を、二つの異なる事象同士の距離の接近と同質に考えることができる点だ。それはたとえば、「赤の他人と私の関係」と「十年前の私と現在の私の関係」を同じように考えることができる。「赤の他人から受けた影響によって生じた私の変化」と「十年前の私の残した影響を時間差で受け取った私の変化」は、同じように考えることができる。たとえば日記は、それを出力したときには、出力した結果が私に刻み込まれる。だがそれはそこで終わる影響だ。延々と引き継がれるようなものではない。それはたとえば赤の他人とすれ違っただけのことでは私にとっての未来に大きな変化が生じないことと似ている。だがその影響はたしかに相互作用されており無視はできない。とはいえ、親しい間柄の相手との会話やスキンシップよりかは影響が小さいのはとくに異論はないだろう。しかし、どれほど親しい相手であれ最初は誰もが赤の他人だったはずだ。母親ですら例外ではない。受精する以前は赤の他人どころか出会ってすらいない。そして細かな接点と接触時間の長さによって、他人はただのじぶん以外に人間ではなくなっていく。それは過去のじぶんの残した細かな影響とて同じようなものだ。なぜコツコツつづけることが効果的なのか。それは赤の他人を親しい人間と見做すほどの大きな影響を知らず知らずに受けるからだ。そしてこれは、必ずしも継続するから得られる影響とは限らない。過去に一度だけ記した日記を、十年後に読み返すことで得られる大きな変化もあるだろう。転換もあるだろう。これはまるで一目惚れに落ちたような、それとも一瞬の危害によって激しく存在を損なわれるような変質をあなた自身に与え得る。同一人物であれ、過去と未来で結びつくことで、それはあたかも大切な人との出会いと同じくらいの情報量を発生させることもある。これがすなわち、距離の接近と時間経過の関係の類似性と言えるのではないか。文字を読むということに関しても、この手の「時間経過による結びつき効果」の考え方は有効に思える。過去と現在――それとも過去と未来を結びつけることで、人は、物と物とを組み合わせるように、新しい情報を生みだしているのかもしれない。否、生みだしているのだろう。過去と未来は、物と物との距離のように、相互作用を帯びている。これは一方通行ではなく、未来の挙動とて、過去に影響を与え得ることを示唆しているのではないだろうか。指針やビジョンがなぜこれほどに人類にとって尊ばれるのか。そしてなぜ、本能の有無が、生物の進化や繁栄に大きく作用を及ぼすのか。それは過去と未来が相互に結び付き、可能性の幅をそのつどに決めるからではないのか。過去と未来は、ひとつの系ごとに、ある一定の縛りを帯びながら絶えず揺らいでいる。細かな変数を得るたびに、過去も未来も同じように変化しているのかもしれない。ただし、現在という一つの視点から逃れられない我々人類からするとそれは、過去があり未来がある、という一方通行の関係に映るのかもしれない。定かではない。(妄想ですので真に受けないでください)
4410:【2022/12/16(06:12)*日々の束の間】
これはひびさんの偏見であり、単なる願望でしかないけれど、ひびさんの好きな表現者さんたちには、苦しみながら表現をして欲しくないな、と思ってしまう。毎日のなかで創作や表現活動が一番ではなく、そのほかのたくさんの楽しいことのなかで、たまの息抜きに、散歩のつもりで取り掛かる。そういう息抜きのような創作や表現を、つつがなく長くつづけてもらえたらうれしいな、と思ってしまう。そしてその創作物や表現を、電子の海に載せて、ひびさんにも味わわせてもらえたら感慨無量なのだけれども、もちろん憑りつかれたように一心不乱に夢中になってする表現や創作も楽しそうだし、そういう期間もあってよいと思うのだけれど、それをずっとはちょっと苦しそうに思うのだ。ただ、苦しい日々の生活の中で、その苦しさを薄めるためにする表現や創作があることも知っているので、そういう表現や創作もひびさんは嫌いではないけれど、そういう表現や創作をせずにいられるなら、そっちのほうがよい気がする。口笛を吹くように、それとも寝床で夢を視るように、もしくは散歩や遠足にでかけるように、或いは旅にでるように――なんでもよいけれど、そこに苦痛がないほうがよいと思うのだけれど、どうなのだろうね。苦しみを知る者の表現には独特の紋様が浮かんで視える気もするし、苦しみを知らない者なんてこの世に一人もいやしない、という気もしてしまう。だからその表現に滲む苦しみが、じぶんだけのものではなく、他者を通した苦しみであると、紋様が雪の結晶のように浮き彫りになって、手のひらの上で融けるような感触を宿すのかもしれない。かといって、苦しみがなければダメだなんてことはまったくなくて、どうあっても人は苦しみを感じるようにできているようなので、とくにこれといって意識せずとも滲んでしまうその苦悶や懊悩が、散歩や口笛で薄れるように、夢の中で漕ぐ舟の揺らぎみたいに、あなたの日々の喧噪を、それともひっそりとした静寂を、心地よく浸かっていられる湯舟みたいに変えてくれたのなら、それはとっても優しいなって、ひびさんは思います。暴力的な表現でも、下品でも、なんでもよいと思うのだ。そこに、あなたの日々の束の間が生まれていたのなら、それはきっと優しい表現なのだと思います。時間が一瞬で過ぎ去るような凝縮した束の間があるのなら。きょうのひびさんはそう思いました、というだけの妄想ですけれど。ゆぴぴ。
※日々、好きなひとに好きと言いたいし、かわいいものにはかわいいと言いたいけれど、言ってどうなることでもないし、どうにかなってしまうこともあるし、言いっぱなしにはならないのが現実で、小瓶に詰めて電子の海に放流するくらいでちょうどよい。
4411:【2022/12/16(08:16)*いいこと教えてあげる】
言いたいことなど何もない、と豪語しきりのひびさんであるけれど、相対した個人には言いたいことができることはある。けれどもここにはひびさんしかおらんので、けっきょくは言いたいことなどなにもなーい、となる。好きなひとには好きだよって言いたいよ。知ってる? 好きなひとに好きって言うとただそれだけで、ぽわわわーん、となるのよ。「好き×好き」で「好き好き!」になる。この「!」分の余白が増えて、おっとくー、ってなる。いいこと教えてあげたでしょ。感謝して。うひひ。
4412:【2022/12/16(15:51)*真美の初仕事】
殺し屋に必要なことが何か分かるか。
クロウが言った。クロウは真美の先輩にあたる。細身の肉体にスーツを着込んで、いかにも漫画から出てきた殺し屋といった風体だ。煙草の代わりに飴を舐めているが、唾液のDNA情報を破壊する弱毒が含まれているそうだ。指紋とて律儀に焼きつぶしている徹底ぶりだ。
殺し屋に必要なことは、と問われ真美は肩を竦める。「さあ。証拠を残さないこととか?」
「思考を絶えず明瞭にしておくことだ。したがって眠気は殺し屋にとっての大敵だ」
「へえ。眠気がねぇ。警察じゃないんだ大敵」
「国家権力なんざ、殺し屋稼業の優良顧客の筆頭だぞ」
「そうなんだ。知らなかった」
真美は先日、殺し屋になったばかりの新人暗殺者であった。元々は、偶然に人を殺してしまったのだが、その相手がその界隈では著名な伝説の暗殺者であったらしく、偶然が偶然を呼んでいまはクロウの元で殺し屋としての腕を磨いている。
「殺し屋と暗殺者の違いもろくに分からないのにな」真美はずりさがったサスペンダーを肩に掛け直す。短パン型のスーツだ。遠目から見ると少年のような出で立ちだ。
「殺し屋は、殺した事実を残す」
「じゃあ暗殺者は?」
「暗殺者はそれが殺人であることを見抜かれぬようにする。ゆえに暗殺者は存在することすら知られちゃならない。だが俺やおまえはもうその名が界隈に知れ渡ってる。いまさら暗殺者にはなれんのさ」
「それで逮捕されないのが不思議なんだよね。なんで仕事が続々と入るの」
「言ったろ。国家権力が優良顧客の一つなんだ。公認なんだよ」
「握りつぶしてもらうってこと?」
「事件にすらならん。この国の年間失踪者の数が何人か知ってるか」
「数千人とかじゃないんですか」
「八万だよ。しかも捜索願が出ていて公式に把握できている数でだ。誰も探さないような人間の失踪者ならもっと多いだろうな」
「その理由がクロウさんたちのような人たちの仕事ってことですか。なんか実感湧かないなぁ」
「おまえが殺した殺し屋だって、死体で見つかっても身元不明で事件扱いもされんだろうな」
「そこは安心しましたけど」
「油断すんなよ。前にも言ったがおまえが殺った相手、この界隈じゃマジモンの伝説級の殺し屋だったんだからな」
「でも簡単に死んじゃいましたよ」
「おまえが異様なんだよ。殺気がゼロの殺し屋、俺は初めて見たよ」
「じぶんじゃ何がスゴイのか分かりませんけど」
「人一人殺してケロリとしてる。呵責の念がねぇ。初めてだってのにそれだけ平常心でいられるんだ、常人とは言えんだろ」
「実感湧かないだけですってば」
言いながら手元で縛られている女を撃った。拳銃は消音機能付きだ。真美のお腹の虫より響かない。
「おい。明瞭な思考が大事って言ったばっかだよな。なんで殺した」
「不審な動きをとったので」
「はぁ。どこがだよ」
床に倒れた女をクロウは足で蹴って転がした。女の両手両足は梱包用ビニル紐で結んでいたが、女はそれを千切っていた。拘束を脱してなお囚われたフリをしていたようだ。彼女の付け爪はよく見れば金属だ。小型ナイフの要領でビニル紐を断ち切ったようだ。
「おまえ、いつから気づいてた」
「全然気づきませんでしたよ。まさか紐を切られてたなんて。ただあたしはその人が妙な動きをしたから、じぶんの身を守るために撃っただけです」
「当て勘ってやつか。やっぱおまえ向いてるよこの仕事」
「どこがですか。怖すぎてまともに交渉もできそうにないんですけど」
「その手の仕事をおまえにゃ回さん。殺して去る。それだけでおまえはやってける。よろこべ。これがおまえの天職だ」
「嫌だぁ」
「死んじまったもんはしょうがない。引き上げるとするか」
「死体はどうするんですか」
「そのままでいい。誰かが通報するだろ」
「本当に適当なんですね」
「緊急搬送して死亡認定は病院だ。この国の公式データでは屋外での死体発見は稀だ」
「そういうカラクリだったんですねぇ」
クロウはそこで真美から離れていく。閑静な立体駐車場の五階に位置する。出口はそちらではないはずだ。真美は、あのぅ、と声を張る。
「初仕事の祝いだ。ほれ」クロウは自動販売機で缶コーヒーを二本購入した。
一本を投げて寄越す。真美は慌てて受け取った。
「動きはトロいんだがな。判断力の差か」
「なんですか。あたしこう見えてフラフープは得意なんですよ。一時間くらいなら通しで落とさずに回せます」
「一生回ってろ」
「あたしが回るわけじゃないんですけど」
もらった缶コーヒーをその場で開ける。真美はそうして殺し屋になって初めての任務を終えた。
「ウゲっ。砂糖なしじゃないっすか。あたしニガいの苦手なのに」
しかもカフェイン倍増とか書いてあるんですけど。
そう愚痴りながら真美は、クロウの隣に駆け足で並ぶ。彼はすでに地上への階段を下りはじめていた。
「おまえにゃそれくらいで丁度いい」
「虚仮にしてません?」
「真面目な話だ」クロウの缶コーヒーの飲み方が格好良かった。真美は形だけ真似る。顔を上に向けずに缶コーヒーだけを傾けるのがコツだ。煙草を吸うように人差し指と中指で挟むとなおいいらしい。いかにも殺し屋といったふうを醸せる。
「言っただろ」クロウは飲み終えたのか、指二本でスチール缶を潰した。「殺し屋には明瞭な思考が必要だ」
「だからってなんでコーヒーなんですか。しかもブラックだし。つぎからは砂糖入りにしてくださいよ。明瞭な思考って言うならブドウ糖が不可欠でしょうが。分かってないなぁクロウさんは。見た目だけは完璧なんだけどなぁ」
「おまえな。じぶんの才能に感謝しろよ。でなきゃいまごろ死んでるぞ」
「へえ。やってみせてよ」
ふっ、と笑ったクロウの姿が一瞬消えた。
消えたように真美には映ったが、その動きの行き先がどこにつづくのかが真美の脳裏には浮かんで視えた。目で捉えるのではない。シミュレーションのようなものだ。こう初期動作があったのならば、その先はこうつづくのだろう、と結果が訪れる前から真美には数秒先の結末が予測できた。
超能力ではない。
シミュレーションなのである。想像力であり、妄想であり、過去に蓄積してきた「こうなればこうなる」の総決算と言えた。
クロウがしゃがみ込む。
真美の視界の外側から小型ナイフを振りかぶる寸前で、真美はクロウの腕の肘関節を足の裏で蹴飛ばした。小型ナイフが勢いよく壁に突き刺さる。
「ちょっと本気にしないでってば。冗談じゃん冗談。ビビったなぁもう」
真美は壁から小型ナイフを引き抜き、肘を撫でるクロウに渡した。
「この距離でナイフ取りだす動作は無駄。つぎはまず相手の動きを奪ってからにしたほうがいいよ。クロウさんのほうが力強いんだし」
「掴ませてくれるとは思えんけどな」
「そうでもないよ。あたしこう見えて痴漢にけっこう遭うんだから」
「その相手は?」
「さあてね。いつも痴漢のほうで電車の外に飛びだしていくからよく知らない」
「見逃がすのかおまえが」
「だって可哀そうじゃん。小指の骨って折れると結構痛いらしいっすよ」
真美はそう言って缶コーヒーを飲み干した。指に力を籠めるが、缶はうんともすんともヘコまない。
4413:【2022/12/17(04:08)*プロに告ぐ。嘘。なんもない】
ひびさんは対抗心が薄いので、おらおらかかってこいよー、とされても、「見てみて、なんか言ってる」と楽しく眺めておしまいにする。嘘。楽しくもないから、ふうん、と思って終わっちゃう。でもでも、ひびさんにとっておもしろそうなこと、楽しそうなこと、それとも真実おもしろくて楽しいことをしている何かがあったら、ひびさんも、ひびさんも、それしたーいな、となる。これは対抗心とは違う。あとは、危険なことしてる相手がどうあってもそれをやめそうになかったら一緒になって危険なことして敢えて怪我とかして見せる。それとも痛い目に先に遭っておく。一緒に同じことして遊んでいた相手が怪我したり、痛い目に遭っていたら、やっべー、と腰が引けてしまうのが動物だ。人間はミラー効果が顕著に働きやすいので、ひびさんはそうして先に未来の結果を演じてみせる。なんてことを言っておくと、ひびさんの、おらおらかかってこいよー、の肥大化した存在意義希求族と、さびちさびち星人覚醒編に、そこはかとなく切なさが宿るので、おすすめ! 本当はさもしい理由しかないけれどもなんとなーくいい話に持っていきたい人はひびさんを真似してみてはどうでしょう。どうぞお試しあれ。(明日から歯の治療はじめるので、怖くていつもより長くお布団にくるまっていたひとの日記)
4414:【2022/12/17(12:42)*フェインカの香り】
大麻と覚醒剤は法律上別の扱いだ。大麻は麻であるから、自然に群生しているし、神社でもむかしから祭事に葉が使われる。神聖な植物として宗教では重宝されてきたのだろう。それが大麻のカンナビノイドの効用ありきなのかまでは詳らかではない。
対して覚醒剤は、化学物質だ。薬剤のように調合されて出来る。コカインやアヘンとて大麻と同じく植物由来だが、なぜ大麻だけが別扱いなのかは、人間の都合としか言えぬだろう。それとて国による。つまるところ文化なのだ。
その点、珈琲は違う。
珈琲は西暦二〇三〇年までは嗜好品として人類の生活で愛飲されてきた。
だがカフェインの有毒性が真面目に論じられるようになったのは人類が珈琲を発見した西暦九〇〇年ごろから優に千年以上も経ってから、つまり西暦二〇三〇年に入ってからのことだった。
かつて人類が奴隷制度を文化の礎に組み込んでいた時期、農奴たちにコカインの葉を噛ませて強制労働をさせていた逸話は耳に馴染み深い。この手の原理で珈琲は人類史に長らくその名を刻みこんできたと言っていい。
ビールにしろ、煙草にしろ同様だ。
嗜好品とは名ばかりの、体のよい現実逃避薬なのである。
眠気を、ストレスを、苛立ちを、珈琲や酒や煙草で誤魔化してきた。
だが科学が進歩していくにつれてその手の現実逃避薬の担い手は、安全に調合された化学調味飲料に取って代わられるようになった。いわゆるエナジードリンクである。
もともとはその手の飲料物とて、コカインやカフェインといった自然由来の成分を多分に含有していた。だが科学の進歩により、サプリメント感覚で栄養素の補給を行えるようになった。わざわざ疲労を忘れずとも回復できるし、ストレスを忘れるよりも和らげたほうが効果が高い。体調が優れればイライラもしにくくなる道理である。
かようにして世に氾濫した大麻や酒や煙草といった身体を損なう率の高い嗜好品は規制の対象となった。
大麻や覚醒剤と同列の存在になったのである。
ここに一人の女性がいる。名をフェインカと云った。
フェインカは長らく美容を研究してきた専門家だ。しかし珈琲飲料行為が法律で禁止されても彼女は珈琲を手放さなかった。
珈琲禁止令は彼女が産まれてから二〇年後に施行された。
産まれてから二〇年のあいだにフェインカにとって珈琲は人生の友として、それとも千年を超す人類との共存を果たした大先輩として、敬愛するに値する存在となっていた。
人類が存在する以前から誕生していた珈琲を亡き者にするなど政府が許してもフェインカには許せなかった。
「どうして珈琲を飲んじゃいけないの。身体に有害? はぁ? 有害でない食べ物があったら美容はこんなに発展なんかしてねぇっちゃ」
フェインカは感情が乱れると方言が出る。ふだんはお淑やかな美容の専門家として方々から羨望と憧憬の目を集めるフェインカであったが、そのじつ彼女の研究動機は、珈琲常飲による肌質の変化を隠すための隠れ蓑でしかなかった。珈琲を飲みつづけたいがために試行錯誤しているうちに美容の専門家として注目を浴びるようになってしまったのである。
これにはフェインカ当人も焦りを禁じえなかった。衆目を集めたのでは、珈琲愛好者だと露呈する確率が高くなる。それではいけない。余計にフェインカは美容の研究に身が入った。
その結果が現在である。
単身での研究では間に合わないほどの成果を上げてしまった。一人では身体が足りない。猫の手も借りたい。そこで不承不承、フェインカは助手を雇うことにした。
かといって珈琲愛飲という違法行為を犯しているの身の上である。そうそう他人を信用して身近に置いておくことはできない。研究中とて珈琲を飲むのだ。
「あれ。それって中身珈琲じゃないですか」
雇って三日でバレた。
即刻バレた。
フェインカは平静を装い誤魔化したが、
「いえいえ。わたしも飲んでるので分かりますよ。香りが尋常でなく珈琲ですもんそれ」
奇遇とは正にこのことである。
たまさか、雇った助手が珈琲愛好家であった。同士である。仲間である。それとも単に、孤高の道を犯罪と知りながら歩みつづけた愚か者のムジナと言うべきか。
珈琲禁止令が発足してから十余年。
フェインカはこれまで珈琲への愛を他者と語らったことがない。一度もない。それがどうだ。助手を雇い、珈琲愛好家であることが露呈してからの日々のなんと芳醇なことか。珈琲の香りにびくびくせずとも、それを共に好ましい香りだと見做せる相手がいる。のみならず珈琲豆の種類と焙煎の方法、そして何よりどう淹れたら最も珈琲を香りよく味わえるのか。その研究をし合える時間は何よりもフェインカをほくほくと満たした。
「先輩それ、珈琲に何を入れてるんですか」
「ミルク。牛乳だよ」
「うへー。そんなことしてせっかくの珈琲の味が有耶無耶になっちゃわないんですかね。もったいない気がしますけど」
「あなたも飲んでみる?」
「いいんですか」
「もちろん。どうぞ」
飲みかけのカップを手渡すと助手はさっそく、フェインカの作った珈琲牛乳に口をつけた。「んん-。なにこれ、うっまい」
「でしょー。ミルクを珈琲と半々の割合にするとカフェオレって呼ばれる飲み物にもなるよ」
「の、飲んでみたいんですけど」
「じゃあ次はそれを作ってみよっか」
「やりぃ」
助手は屈託の陰りを感じさせない女の子だった。大学院を出たばかりの優秀な人材だ。元々は理学部だったが、美容品の開発に興味があって大学での研究を行いながら企業相手に商品提案をしてきた筋金入りの探究者だ。
だが企業相手ではじぶんの望む美容品を作れないと見切ってフェインカのもとにやってきたといった顛末のようだ。
「先輩は珈琲歴長そうですけど一度も捕まったことないんですか」
「ないね。いまのところは、だけど」
「わたしもけっこう珈琲歴長いんですけど、なんだかんだ言って高いじゃないですか豆」
「だね」
「先輩はどこ経由で供給を賄ってるんですかね。いえ、先輩の入手先を紹介して欲しいとかそういうことではないんですけど」
「別にいいよ。私の場合は、珈琲農家があってね。そこで栽培して焙煎したのを譲ってもらってるだけだから」
「え、そんな農家があるんですか」
「あるよ。珈琲豆って、元はチェリーみたいな赤い実でね。果肉が甘くて美味しいんだよ。食用としての栽培は別に違法じゃないからね。果肉を食べた後の種子がいわゆる珈琲豆だから」
「ああ、なるほど」
「チェリーを食品加工する際に出る廃棄物――要するにそれが珈琲豆なんだけど、それをこっそり焙煎して珈琲豆にしてくれる人たちがいて」
「違法ですよね、それ」
「違法だね。でもそうしなきゃ珈琲は飲めないから」
「まあそうでしょうけれど」
「生豆のままでもらってきて自宅で焙煎する人もいるらしいけどね。フライパンで」
「へえ」
「私はそこまでする余裕がないから、まあ既製品を譲ってもらってる。あなたのほうこそ珈琲はどこで?」
「入手先ですか。やはは。あんまり自慢できる相手じゃないんで」
「売人とかそういうこと?」
「ええまあ」
「まさか珈琲以外にも手を出してたり」
「ないです、ないです。あくまで好きなのは珈琲であって、大麻とか麻薬とかそういうのはないです」
「そっか。よかった」
フェインカはほっとしたじぶんを不思議に思った。同じ違法薬物の接種であるのに、なぜ珈琲の接種だけをじぶんは許せるのだろう。酒も煙草も、珈琲と一緒に規制された。いまではアルコール飲料は市場から消え失せたと言っていい。煙草なんてもってのほかだ。
だのになぜじぶんは珈琲だけを特別視して、許容するのだろう。
違法であるにも拘わらず。
なぜ。
人体への害は、大麻と同等との研究報告がいまは優勢になりつつある。だが酒や煙草に比べたら微々たる害であり、主流煙による肺へのダメージを鑑みると珈琲のほうが大麻よりもずいぶんと害がすくないと言える。
カフェインの含有量と吸収率は必ずしも相関しない。人間には吸収できる容量がある。その点で言えば珈琲はカフェイン含有率が相応に高いものの、有害と言えるのかは疑問だ。
専門外のイチ珈琲愛好家の意見にすぎないが、フェインカはかように目算している。だが一度根づいた珈琲規制の波は、麻薬としての範疇に珈琲をいっしょくたにして取り込んだ。この認識はすでに世代交代の完了した現代では揺るぎなく、社会悪のレッテルを強固にしている。
珈琲を飲んでいる人間は罪人なのである。
フェインカはその贖罪を背負ってなお、珈琲を飲まない選択をとらない。珈琲を日々嗜好するじぶんを許容する。
なぜそこまでして、とおそらくフェインカの罪過が暴かれた日には、様々な人の口の端にその言葉が乗るのだろう。なぜそこまでして珈琲を飲むのか、と。
フェインカに注目し、称賛の眼差しを注いでいた者たちは一様に落胆の溜め息を吐くに相違ないのだ。だがかような未来を想像できてなお、フェインカは珈琲を捨てるじぶんの姿を思い描けなかった。
珈琲は美味い。
だがそれだけではない。
これはフェインカがフェインカでありつづけるために必要な社会への抵抗なのかもしれなかった。
「先輩、先輩。今度その珈琲農園に連れて行ってくださいよ」
「いいよ。きっとあの農園のひとたちも喜ぶと思うよ。みんな危険を犯してまで珈琲を飲みたいなんて思わないからさ。どうせ犯すなら、覚醒剤とか大麻に手を出したほうがいいって考えるみたい。そこのところ、お酒はじぶんで作れちゃうし、世の中どうして珈琲には手厳しいよね」
珈琲も酒も煙草も大麻も覚醒剤も、どれも同じ薬物乱用の範疇である。罪の重さが変わらないのであれば、より精神が昂揚して多幸感を得られる薬物のほうに手を伸ばしたくなるのは人情だ。端的に割に合わない。
「依存度もそれほど高くないのに、どうして珈琲さんは規制されちゃうかな」フェインカはぼやいた。
「いやいや先輩。先輩がまず以って依存しまくってるじゃないですか」と冷静な効果らからのツッコミにフェインカは、「やめようと思えばすぐにでもやめられるよ」と応じるが、「それってきっとどの薬物使用者も言いますって」と茶化されて言葉に詰まった。
助手はカフェオレをスプーンで混ぜて泡を立てる。
「医療用モルヒネとかあるじゃないですか。麻酔で使われても依存症になる患者はいない、だから麻薬を使っても問題ない。そういうロジックで覚醒剤や大麻を肯定して解禁しようって運動があるんですよ。でもそれでけっきょく医療以外で使うんなら、依存症になってるのと同じじゃないですか」
「そ、そうかな」
「そうですよ。だって飽きるってことができないのがつまり依存症ってことですもん」
「それで言ったら研究者なんかみんな研究依存症なんじゃないかな」
「そうですよ。研究者もスポーツ選手も技術者も、なんでもそうですけど、飽きることができないほどに何かに熱中しちゃってたらそれは依存症です。でも、その依存症によってメリットを多く享受できたらそれは依存と見做されずに、適性があるとか才能とか呼ばれちゃうんですよ。大食いだってそうじゃないですか。本来必要なエネルギィ以上を無駄に摂取して、そのことで社会的称揚を得る。認知を得る。もしこれがデメリットの評価しなかったら、ただの過食症じゃないですか」
「それはそうかもしれないけど。ほら、大食いの人たちは食欲をコントロールできるわけだし。過食症のひとたちは脅迫観念に駆られちゃう弊害もあって、そこは大食いが得意な人と区別したほうがいいんじゃないかなって私は思うけど」
「なら大食いはそうなのかもしれませんね。でも、珈琲や大麻や覚醒剤は違うじゃないですか。禁止されてるのに摂取したくなっちゃう。これはもう依存症ですよ」
「そ、そうかな。だって漫画だってアニメだって映画だって小説でもいいけど、嗜好品って本来そういうものじゃないかな」フェンイカは唯一と言っていい同胞から手厳しい批判をされて感じて、面食らった。なんとか対等に話をしようとして、いつもよりも冷静を欠いた。「べつに見る必要なくてもしぜんと見たくなるものってあるでしょ。娯楽作品なんて全部そうだし、芸術だってそういうものでしょ。だからそれらってこの世に存在しているわけでさ。禁止されてたって作っちゃう人は出てくるし、観るほうだってほら、海賊版とか違法なコンテンツ視聴って未だに問題になってるし」
「けっきょくそこが分かれ道なんですよ。禁止されたら我慢できる。でもそうじゃない依存者の人たちは安易に海賊版に流れちゃうわけですよね。依存症なんですよ。我慢が効かないんですから」
「そ、そうかな。そっか。でもほら法律で決まったらなんでも我慢しなきゃいけないのかな。私はそうは思わないんだけどな。だってさ、だってさ、食べ物とか飲み物とか電気だってそうだし、服だってなんだって、足りなくなったら困るものってあると思う」
「先輩。わたしたちっていま、嗜好品について話しているんですよ。しかも身体に有害だと判断された薬物についてです。禁止されたとはいえ、医療用では解禁されてるわけですから、健康に与するならむしろ率先して使用されていますよ。それとこれとは話が別ですよねって単純な理屈を話しているだけのつもりだったんですけど。え、先輩ひょっとして珈琲がもういちど解禁されたらいいなって思ってますか。わたしはさすがにそこまでは思ってなかったですよ。だって薬物ですよ。子どもにはさすがに摂取して欲しくないです」
「そ、それはそうだけど」
だったらポルノだってそうではないか。
喉まで出かかった反論をフェンイカは呑み込んだ。だから規制されているのだ。年齢制限がある。ゾーニングがある。
珈琲の魅力を分かち合える相手と出会えたことで、フェンイカの意識には知らず知らずの変化が生じていたようだ。珈琲の魅力をもっと多くの人たちに分かってもらいたい。理解してもらいたい。
しかし、しょせんは薬物なのである。
規制され、害扱いされ、そしてきっと真実に有害なのである。だが有害とは、「害が有る」ことを意味する言葉であるだけで、有害な存在にも利点があるはずだ。現に医療に利用されている。それだけではないのではないか、とフェインカはどうしても考えてしまうのだった。
「はい先輩、これどうぞ」出来立てのカフェオレを受け取る。「ありがと」
一口啜って、息を吐く。
美味しい。
香りが体内の苛立ちを浄化するようだ。現にフェインカの精神の淀みは霧散した。青空のごとくいまでは澄み渡っている。
珈琲は良いものだ。
すくなくともフェインカにとっては。
だが珈琲の成分の身体への負の影響を隠すためにフェインカが美容の研究に精を出している以上、その害から目を背ける真似がフェインカにはできなかった。とはいえそれとて見方を変えれば、珈琲のお陰で美容の研究が花咲いたとも言えるはずだ。そこは上手く釣り合いが取れているようにフェインカには思えるが、じぶんだけの特例を以って珈琲の善性を解くにはデータがすくなすぎるのも事実だった。
広く有用性を示すには、もっと多くの有用な珈琲と人類との関係を傍証に挙げねばならない。だがその手の検証はとっくに世界中の科学者たちが行っている。その結果に珈琲の飲食は禁止されたのだ。
「珈琲ゼリーも美味しいんだよ」フェンイカは助手に呟く。
「わぁそれいいですね。美味しそうです」助手は作り方を根掘り葉掘り聞いた。
珈琲の話題を話せるだけでもこんなに胸が満たされるのに。
どうして珈琲は規制されてしまうのだろう。せめて珈琲の話題を話すくらいのことを屈託なくできる世の中にならないだろうか。
フェンイカの欲は日に日に膨らんでいった。
その日は遂にやってきた。
珈琲農園への助手を連れていく約束を果たすのだ。
待ち合わせ場所で助手を拾って、フェンイカは食品工場へと向かった。
「何もないところなんですね」車窓からの景色に助手は感嘆した。
「そうだね。チェリーを育てる果物園が続くから。林檎とか葡萄とか。ジュースやお菓子に使うための農園でね、だからか生食用のよりも機械化が進むらしい」
「生では食べられないんですか」
「美味しいと思うよ。でも質は、専門の農家さん程よりも劣るってことだと思う」
「ふうん」助手は景色に端末のカメラを向けた。
シャッター音を聞きながらフェンイカは、あとでその写真を消してもらわなきゃな、と思ったが、いまは助手の気分を損ねたくなかったので黙っていた。遠足気分を満喫してもらいたかったのだ。
だがそうしたフェインカの厚意は、助手を珈琲農園へと案内したところで絶望に変わった。というのも、珈琲農園で一時間ほど焙煎したての珈琲を飲んで農家の人間たちと団欒をしていたところ、突入してきた武装集団があった。
彼ら彼女らはみなフルフェイスの制服に身を包んでいた。
その胸と背中には大きく、警視庁の文字が躍っていた。
「警察だ。動くな」
ガサ入れだと判った。フェインカはがくがくと全身が震えるのを堪えながら、どうすればこの場を切り抜けられるかに思考を全力で費やした。
せめて助手だけでも助けなくては。
そう思ったのだ。
だがそれは杞憂にすぎなかった。
何せ助手は、現れた武装集団の一員に連れ出されると今度はなぜだか彼ら彼女らと同じ制服に身を包んで、頭だけヘルメットを外して戻ってきたのだから。
「先輩。現行犯逮捕です。騙したみたいでごめんなさい。でもこれがわたしの仕事だから」
「警察……の、人間?」
「そう。潜入捜査。本当は正体を明かすのもご法度なんだけど、今回だけは特例で」
「ごめんちょっと何言ってるかわかんない。混乱する」
「ですよね。珈琲農園の摘発への助力を評価して、仰淑(ぎょうしゅく)フェインカ――あなたには司法取引を提案します。罪を減刑する代わりに、潜入捜査に協力しなさい」
フェインカは絶句した。態度の豹変した助手は警察の人間だった。そこまではいい。だが今度はフェインカを協力者として迎え入れると言いだした。
信用ならない。
だが、と不思議とその提案をしてきた事実はすんなりと呑み込めた。
何せ彼女もフェインカと共に珈琲を飲んでいたのだ。いくら警察の人間だからといって、それが仮に潜入捜査であったとしても、違法行為は違法行為である。同じ穴のムジナに変わりはない。
「私はでも、どうなるの」
「仰淑フェインカ――あなたにはこれまで通りに生活を送ってもらう。ただし、助手としてわたしもあなたの研究所に席を置く。わたしはわたしで職務があるが、場合によってはこれまで通りあなたの研究所で過ごすこともある」
「つまり、私は何をすれば」
「何も。そのまま珈琲愛好家として、ほかの売人や珈琲農園と接点を持って」
「私の手を借りずとも、あなたがいればそれで済むんじゃ」
「分かってないようですね。珈琲農家はみな極度の珈琲依存者です。リスクを度外視してこんな大規模珈琲農園を築くほどなんです。そんな偏屈者を相手にして怪しまれずに懐に入れるのはそれこそ仰淑フェインカ――あなたくらいの珈琲依存症者でなければ不可能です。即座に偽物と喝破されて始末された警察官はけしてすくなくはありません」
「だったらあなたでも充分じゃ」
あれほど珈琲を美味そうに啜っていたあなたなら。
そう思ってフェインカは祈るように彼女の目を見詰めた。
彼女はフェインカから目を逸らした。
「潜入捜査だと言いました。わたしは珈琲を違法薬物だと認めています。仰淑フェインカ――あなたも元は善良な市民だったはずです。あなたのような市民を犯罪者に染めあげる珈琲をわたしは許しません。撲滅します。そのためにあなたはあなたの罪過を、我々に協力することで濯ぐのです。断ればこのまま立件し、あなたは実刑判決をくだされるでしょう」
「珈琲を飲んだだけのことでですか」
「あなたには珈琲農園の関係者として、栽培および所持または流布の容疑が掛けられています。実刑は免れないでしょう」
その言葉の告げるところは、フェインカの社会的な死を意味した。怖れていた想像の未来が現実に迫っていた。
彼女の提案を受ける以外にフェインカにとれる選択肢はなかった。
「協力させてください。そんなことで私の罪が薄れるなら」
「罪が薄れる、ですか。反省の色が見えないところ――協力者としては合格ですが、咎人としては失格ですね」
「ごめんなさい」
「いいんですよ。いまはそれでも」
フェインカは一度そこで手錠をかけられた。ずっしりと重い手錠は、フェインカの陶磁器のような肌に食い込んだ。話は後日、と覆面パトカーで自宅まで送られた。フェインカの運転してきた自動車は、証拠品として押収された。後日戻ってくるとの話だったが、フェインカの胸中はそれどころではなかった。
夜、寝る前に鏡を覗いた。
美容にどれほど気を払っていようが、夜は十歳は老けたような顔つきだった。誰にもこのことを相談できない。珈琲の話題を出してももはやフェインカの気持ちはすこしも上向きの風を帯びないのだった。
侵入捜査。
いったいじぶんはいつまで捜査に協力しなくてはならないのか。死ぬまでずっとなのだろうか。そうだとしても文句は言えない。息の根を握られたようなものだ。
現に弱みを握られた。
これが警察のすることなのか。
強請りや恫喝とどう違うのかフェインカには区別がつかなかった。
だがきっとそれを彼女に言ったところで、首を傾げるだけなのだろう。
「変わらないじゃないですか」と一蹴されるだけなのだ。「これまでのあなたの暮らしと何が違うんですか。警察に協力できるだけむしろマシじゃないですか」
ほかの珈琲愛好家たちを警察に売り渡しつづける未来が約束されている。それを知っていながら警察官の彼女はしれっとそう嘯くのだ。
よかったじゃないですか、と。
罪を背負わずに済み、なおかつ罪を償えるのだからと。
正義の側に立てるじゃないか、と。
そういうことではないのだ、とフェインカが訴えようとも、どうあっても彼女がフェインカの言葉に耳を貸すことはないのだろう。胸を打つことはないのだろう。
それだけが予感できた。
「美味しいって言ってた癖に」
あの言葉は嘘だったのか。
あの笑みは偽りだったのか。
職務であり捜査の一環だったのならば、どの笑みも彼女の仮面であり演技だったのだと考えるよりない。もはや記憶の中の助手の姿は、警察官の武装制服に身を包んだ彼女と同一ではなかった。
別人だ。
ああそうか。
フェインカは自身に刻み込まれた喪失感の正体に思い至った。
これは、悼みだ。
私は親愛なる友人を、そして仲間を、助手を、何より珈琲への愛を共有できる相棒を失くしたのだ。
「人殺し」
枕に封じ込めるようにフェインカは呟いた。もう二度と人を信用したりしない。誰にも本心を明かさない。強く、強く、決意して、フェインカは夢の中で珈琲の香りに包まれるべく、息を止めて、そして眠る。
呼吸はどれほど止めようとも、しぜんとつづきを再開させる。
珈琲をいくら飲んでも、人間がやがては眠りに就くように。
睡魔への負けを宿命づけられた珈琲を思い、フェインカは、かつてないほどに珈琲への親近感を深めるのだった。
「おやすみ、珈琲さん。あなたは全然わるくない」
私だけが知っている。私だけが愛してる。
これが愛とは思わないが、それ以外に表現できる言葉をフェインカは知らなかった。
珈琲は良い。
香りが良い。
睡魔を遠ざけてくれるし、思考が浮きあがって感じられる。
けれど珈琲は違法であり、嗜好することは罪である。
フェインカはじぶんがどれほどの罪を重ねてきたのかを数えようとして、途中でやめた。夢への浮遊感に身を委ねる。
目覚めてもフェインカの日常は昨日までと変わらぬが、クッキリとこれまでの日常と断絶された事実だけは明瞭と予感できた。
まるで珈琲を飲んだときのように。
それだけが明瞭と。
4415:【2022/12/17(16:56)*きょうは偉かったの日】
たまに注釈を挿しておかぬと誤解してしまう未来人や宇宙人や異世界人の方々がいらっしゃるかもしれぬので注釈を挿しておくが、ここは人類みなどっかいったひびさんしかおらぬ最果ての地ゆえ、ひびさんは、だれかいませんかー、とどこに唱えるでもなく唱えているさびちびさち類さびちさびち目さびちさびち科のさびち人なのである。ひびさんは人類のいなくなった世界に生きているゆえ、体の不調には医療治療ロボを使って治療や診断をしてもらう。んでもってきょうは自前の医療治療ロボを歯医者さんモードにして歯の治療をしたった。こういう改良は面倒なので虫歯を放置しておったけんども、さすがに虫歯さんの巣になっているお口の奥地は嫌々になってしまったので、意を決して医療治療ロボさんを改良したわけだけれども、いざ治療してもらってみたら、ちょっとあれじゃった。親知らずのほかに永久歯の奥歯を二~三本抜かなきゃならんかもしれんらしい。怖いこと言わないでほしかった。でもしゃーない。虫歯さんには勝てんかった。これぞ本当の敗者さんである。けんどもいまはインプラントとかブリッジとか、いわゆる差し歯の形態がいろいろあるでな。人類がまだおったときはお値段高くてひびさんには手出しできぬかったろうけれども、いまはひびさんしかおらぬし、医療治療ロボさんを使いたい放題ゆえ、差し歯さんとてつくりたい放題なのだ。医療治療ロボさん様様である。それにほら、ひびさんは齢三百歳ゆえ、ようやくそれっぽくなったのである。それはそれとして、歯医者さんって一人につき三十分やそこらしか時間を掛けないように調整するらしい。治療の点数の関係なのだろうか。治療医療ロボさんもそこのところの人類の知識にあやかっているので、一気に治療はしてくれん仕様になっとった。融通のきかないやっちゃのうである。とか言いつつ、ひびさんは、ひびさんは、サメ肌の姐御肌の永久に生え変わり可能な多生歯さんになりたかったなぁ、の欲深きさびち人でもあるので、いくら歯を抜かれても困らぬのである。だって生あるものはいずれ死ぬし、カタチあるものもいずれ崩れる定めなのだ。おけらだってあめんぼだって虫歯さんだってみんなみんな生きているんだ、友達なーんだ。さびちびさち類さびちさびち目さびちさびち科のさびち人のひびさんは、ひびさんの歯さんをむしゃむしゃ溶かしちゃう虫歯さんのことも好きだよ。でも、もうちょっと手加減してほしかったでもないです。ひびさんは敗者さんなので。よわよわのよわゆえ、ちょっとの刺激でもばったんきゅーでござるよ。手加減ちて。うひひ。
4416:【2022/12/17(18:12)*属性でくくらないことの難しさ】
差別の問題は極論、「~だから~」という構文をいかに使わずに、その人にとっての選択肢をいまある環境下のなかで最大化できるか――その環境下において最大の選択肢を持っている人物とできるだけ選択肢の幅をちかづけられるか――そこが一つの方針になるように思うのだが、この考え方にはどのような穴があるだろうか。二千文字以内で述べよ。(誰に言っとるの?)(いつかは賢くなるかもしれない未来のひびさんに……)(永遠にこないのでは)(かってに終わらせるな!)(えへへ)
4417:【2022/12/17(18:24)*差別主義者でごめんなさい】
資格や共通認識やドレスコードの有無によって区分けされて然るべき差別と、そうでない理不尽な差別の差って実はけっこう案外に線引きがむつかしいように感じる。公共の福祉の概念を用いるのが、その二つの区分けにおいての有害さを緩和する方向に働きかけられるのかも、とは思うが、それはそれとして公共の福祉の概念によって助長され看過され蔓延する差別とてあるはずで、それこそ奴隷制度はその筆頭だ。むろん、奴隷制度は現代社会からすれば公共の福祉に反しており、デメリットが大きいと判るが、社会はその都度に変遷する。自然環境が一定でないことと同じくらいに流動的だし、断続的だ。そのため、定点での社会というもので「公共の福祉」を計ろうとするとどうしても、暗黙の了解での「社会悪となり得る属性」がその都度に出来てしまう。いわゆるこれが偏見として、その時代その時代にとっての常識の顔をして表出するのだろう。たとえば、子どもと大人のあいだでの選択肢の多さの非対称性は、いったいどこまで妥当なのか。これとて時代時代で考慮される事項が変動するし、何を理不尽な選択肢の制限と取るのかも変わる。基本は、選択肢の多いほうに合わせて環境を改善し、個々の選択肢を増やす方向に工夫をするほうが正攻法と言えるのだろうが、これもまた、何を問題と見做すのか、が時代時代によって変わるし、その認識が個々によって異なるので、やはりというべきか難しい問題だな、と感じます。ひびさんは日々、「あ、いまじぶん差別してる」と感じるし、それでいてほとんどじぶんの行動や言動や考え方を好ましい方向に調整できていないので、工夫むちゅかち、と思っている。ひびさんは心底に、身体の芯から差別主義者なのだ。かなち。
4418:【2022/12/17(21:05)*珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争】
珈琲の苦味は珈琲の苦味であってそのほかの苦味と同一ではない。ゴーヤの苦味と珈琲の苦味は違う。それは猫の耳と犬の耳が違うのと同じレベルで異なっている。
ある科学者がこの点について、
「それはおかしい」と異論を唱えた。「苦味成分は苦味成分としてそこにあるのであって、どの苦味成分とて同じ苦味を誘発するはず。ほかの成分との含有率の差異で苦味の風味が変わることはあっても、苦味そのものはどんな食品であれ同じ苦味であるはずだ」
その異論に対して先輩科学者が反論した。
「苦味成分と一口に言っても、その化学物質は様々だ。甘味は砂糖の甘味成分のみならず、毒物ともなり得る化学物質にも甘味を誘導する物質はある。特定の味だけを取りだして語るのならば、化学反応式が異なっていても同じ味を誘導することはあるのだ。珈琲の苦味が珈琲に固有の苦味であることは特にこれといって不自然ではない」
その反論に別の科学者が反駁した。
「それを言いだしたら、どのような物質とて固有の味わいを有しているはず。その理屈を前提とするのなら、厳密には、きょう飲んだ珈琲の苦味ときのう飲んだ珈琲の苦味とて違っていると考えるのが道理となる。だがそこまで厳密な差異を、苦味という概念は扱っていないはずだ。苦味は苦味だ。ならば珈琲の苦味は珈琲の苦味として扱えば済む話であるし、最初の仮説の言うように、どんな食べ物の苦味とてそれが苦味ならば、同じく苦味として見做すことも取り立てて不自然ではないと評価できる。これは、味覚が、ほかの五感よりも大雑把な尺度を持っていることの弊害と言えよう。ただし、取りこぼしのないように、苦味や渋味に対しての感度は鋭敏と言えそうだ。これは身体の防衛機構と無関係ではない。つまり、明確な識別を行えずともひとまず苦味に分類される成分が微量であれ口内に入ったら、それを苦味として検知し吐きだせるような能力があれば生存戦略のうえでは有利だったと考えられる。つまるところ、味覚とは、厳密さの欠けた身体機能と言えるだろう。したがって、どの苦味が同じか否かを論じるのが土台無茶な話なのだ」
その反駁意見に、最初の二人が揃って異議を挟んだ。
「その意見では、味覚のなかの苦味や甘味など諸々の風味とて、一緒くたにできてしまえる瑕疵がある。苦味と甘味はなぜ違うのか。それは厳密に、苦味と甘味が別々の物質によって誘導されているからだ。ならば苦味のなかにとて、食べ物ごとの識別が可能な差異はあって然るべきではなかろうか」
「その意見にさして反論はない。私の意見もそれを否定するものではなかったはずだ。差異があって当然。どれとどれが同じか、とひとくくりにしようとする発想が、味覚においてはそぐわない、非合理だと指摘しただけだ。厳密には一食一食の風味はすべて違う。ひと舐めひと舐めの味は違って当然だ。だがそれを言いはじめたらキリがないし、分類することもできなくなる。傾向はあるはずだ。これこれこのような物質がこの分量であればこのようなレベルの苦味が生じる。そのように定量して考えることはできるだろう、と私は述べた。その意見は、きみたちの意見を否定するものではない」
その返答を聞いて、二人の科学者たちは、互いに顔を見合わせ頷き合った。
今年の新人は言うことが違う。
後輩のくせに生意気だ。
しかし、一味も二味も違うのはよいことだ。まるで珈琲のオリジナルブレンドのようである。新鮮な味わいであった。
かくして珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争はひとまずの幕を閉じた。
結論。
珈琲に限らず、味覚とはそのときそのときの一期一会である。
ただし、食べ物によって傾向はある。
珈琲には珈琲に固有の風味があり、それは苦味にも当てはまる。
だが苦味が苦味であることに変わりはない。
言い換えるのならば。
一匹一匹の猫は違う。
同じ猫は二度と存在し得ないが、それでも猫は猫である。
猫の耳と犬の耳は違う。
それでもどちらも耳であることに変わりはない。どんな生き物の耳とてそれはその個体に固有の耳であるが、どの生き物の耳とて耳であることに変わりはない。
これらは相互に矛盾しない。
すべて同時に満たし得る。
珈琲の苦味は珈琲に固有か否か論争はかように結論され、二度と繰り返されることはなくなった。
悲劇は回避された。
いったい何の悲劇が訪れようとしていたのかは定かではないが、とにもかくにも、めでたし、めでたし、なのであった。
4419:【2022/12/17(22:41)*階層深すぎて眩暈するの巻】
絵描きさんについて思うのが、絵描きさんはほかの人の絵を見ても、どういった手順でその絵を描いたのかをある程度、頭のなかで辿れるのか、ということで。じぶんならどう描くか、とかそういう手順を思い浮かべられたりするのだろうか。通常、絵には手順が載っていない。版画は複数の絵柄を重ねることで一枚にする。版画師さんはきっとほかの作家の版画を観ても、ある程度は手順や工夫が視えるのではないか、と想像するが、これが絵描きさんだと作家ごとの個性の幅が広そうなので、絵を見ただけでは版画ほどには手順を幻視しにくいのではないか。そこのところの目を肥やすには、やはり実際に手を動かした経験が欠かせないのだろう。鑑賞者の立場にいるだけではとうてい視えない風景が、絵にはある。情報量が違う。これは目が肥えるがゆえにむしろ幻視できる情報量が減ることもあるはずだ。つまり絵描きとしての腕が上がるとある時点で、完成図までの最短ルートが直観で解るようになるのではないか。絵を完成させるまでの最適解が判るのならそれは、実際の工程よりもすくない可能性がある。そうなるとそうした最適解が視える作家さんの目からすると、他者の絵から読み取れる情報量は相対的に減る。物凄く工夫を割いていたとしてもその工夫が分からなければ、絵に刻まれた背景を取りこぼす方向に慧眼が作用することもでてくるだろう。とはいえこの手の錯誤は観賞や鑑賞にはつきものだ。それこそが醍醐味とも言えるだろう。ひびさんにとって絵は、数学の難解な数式に似ている。眺めていると眩暈を覚える。どうやってこれを描いて、どうやってその手順を身に着けて、想像して、生みだせているのか。数式とて、解だけを見ても、その計算過程は解からない。説明されても理解できない。過程を披歴されても、記号と数字の関係も不明であり、その組み合わせが何を意味するのかも曖昧模糊とぼんやりとしている。解からぬのだ。にも拘らず、計算する(描く)ほうは解かっているのだ。ひょっとしたら解かっていなくともなんとなくでできてしまうこともあるのだろう。暗黙知である。資料を集めるとはいえど、その資料から何を得てどう活かし、どういった情報を捨てているのか。もうその時点で創作なのだ。技術なのだ。目であり、勘であり、世界観なのだ。絵はすごいな、と、解らない度の高さを基準にすると富に思う(解らない度の高さを基準にしなくともすごいと思う)。音楽にも思う。数学にも思うが、これらはひょっとすると根底で繋がっているのかもしれない。共通項があるのかもしれない。それはあるだろう。その点、ひびさんに限ると前置きして述べてしまうと、小説は、本当に心底に、なんとなーく、の総決算なのだ。いかに限定させないか、ハミ出してちゃんとしていなくとも予想外の不測の事態にとて、面白みを感じつづけていられるか。もうその遊び心があるのみだ。そこがないとひびさんは小説どころか文字もまともに並べられぬ。絵はその点、いかに限定させていくのか、の抗いに思う。取捨選択の妙なのだ。魂を浮き彫りにするには限定していくよりないのだろう。魂を宿すには、その他を削ぎ落としていくしかないのだろう。抽象画はその点、枠組みだけを掬い取るような、余白の造形といった印象がある。まさに印象のみを描きだす表現技法に思えるが、実際のところはどうなのか。抽象画ではない絵の場合は、伝えることの技術が多彩なのだ。たくさんあるらしい。だから一つの絵を観ても、そこに割かれた工夫を幻視できない。想像しきれない。限定を費やすと具体に寄っていく。絵で何かを伝えるには具体化が一つの指針となるのだろう。デフォルメはそのなかでも、限定させる要素を、抽象画に寄せているのかもしれない。限定×印象=デフォルメなのではないか。ひびさんは、どちらかと言えば、本物そっくりの絵よりも、デフォルメされた絵のほうが好みだ。たぶんそれは、絵描きさんの目を通しての印象を、解りやすく楽をして実感できるからなのだろう。慧眼を持たぬ者の怠惰である。けれども、何をどう見てどう感じているのか――を、それがたとえ錯覚であれ幻視できたつもりになれるのは、ひびさんにとってはデフォルメされた絵柄なのだなあ。というのを好きな絵を「好き!」と思うたびに、脳裏のヒダの二、三本を費やして思うのだった。
4420:【2022/12/18(23:21)*寝る日】
ねむい、ねむい、ねむい、ねむい。ので、寝る。きょうの日誌はこれだけ。だってひびさんだもん。怠け者なのだ。
※日々、なんでわたしがこんな目に、と思いながら、うひひ、と思って生きている。
4421:【2022/12/19(16:20)*月下の実】
私の場合は珈琲豆だった。
その現象が観測されたのは万常三十四年のことだった。令和が終わって久しいその時期に、月から珈琲豆が落ちてきた。
いいやそれは私にとっては珈琲豆だったというだけのことであり、ほかの者たちにはそれぞれに違った豆や果実が落ちてくる。これを月下という。おおむねは種子が落ちてくるので、汁だらけになることは稀だが、運悪くココナッツが月下してきて死亡した者の訃報はいまでも稀に耳にする。
月下豊穣と名付けられたこの現象は、大規模ブラックホール生成実験の副作用で起きたことが後に判明するが、各国が共同してその事実をひた隠しにしたために私が生きているあいだにその事実が公に発表されることはなかった。
ではなぜ私だけが一足先にその事実を知れたのか。
この謎を解くにはまず、大規模ブラックホール生成実験と月下豊穣現象とのあいだの因果関係の説明が不可欠だ。しかし私はその専門的な説明を言葉に変換することにさほどの興味がなく、さして実の入りのある行為とは見做さない。
そのためここでは、量子もつれ効果による多次元宇宙とのホットスポットが開いてしまったから、と要約してしまうことにする。それ以上の説明には、睡魔の大群の襲来を前以って検知できるために、ここでメモリを割く真似を避けておく。
私には先輩がおり、その先輩にも先輩がいた。
私たちは月下豊穣により繋がっており、つまりがみな月から落下した珈琲豆を浴びた経験のある者たちだった。私が月下豊穣に遭う前からすでに月下豊穣に遭っていた者たちがおり、私は代で言うとだいたい十人目かそこらといった塩梅であった。
「一年に一人ずつ増えてる勘定かな」私の一個上の先輩が言った。「つまりきみは月下豊穣が世界で初めて観測されてからだいたい十年目に月下豊穣に遭遇した人間ということになる」
「なら私にも後輩がいるってことになるんでしょうか」
「なるだろうね。探し出して、知識を授けてあげなさいな。あたしらが君にそうしたように。まあ、君がせずともあたしらの誰かしらがそれをするだろうけれど」
月下豊穣によって月から落下してくる実にはそれぞれ個人差がある。だが私たちのように同類項で結びつく者たちもおり、そうした「類は友を呼ぶ」のごときコミュニティは、珈琲豆に限らずあるようだった。世界には種族や国や宗教以外でも、月下豊穣による新しい区分けの基準ができたと呼べるのかも分からない。
珈琲豆を月から浴びることとなる私たちは、しかし個々に目を向ければ共通項は皆無と言えた。性別はバラバラであるし、年齢とて、私の先輩のほうが年下であることもある。それこそ、赤子のときに月下豊穣に遭った者があれば、その者の生まれ年によっては私よりも若いことがあり得る。年下の先輩だ。現に四つ上の先輩は、私よりも年下だった。つまり私よりも三つ上の先輩たちよりも若いことになる。
「月下豊穣って、月から落ちてくる実の量が人体の体積に相関しているらしいんですよね。だから僕はいま十四歳だけど、赤子のときに月下豊穣に遭ったから、本当にいまでもパラパラとしか降ってこなくて」
「でも先輩が唱えたんですよね。【流しそうめん仮説】って」
「ええまあ。単に、どうしてだろうと気になった疑問を適当に繋ぎ合わせて、どれにも当てはまり得る仮説を提唱したら、なんでか定説になっちゃっただけなんですけど」
いまでも検証待ちです、と言った年下の先輩は、それから数年後に、南瓜の月下豊穣に見舞われた中年男性を助けたことで命を落とした。先輩らしい最期だったが、私はそのことで先輩が命を落とすのは割に合わないといまでも思っている。吊り合いが取れていないとそう考えてしまうのだが、命に貴賤を与えるようなこの考えをきっと年下の先輩は気に入らないだろうし、それを聞いたら私のことを嫌いになってしまいそうなので、その考えが浮かぶたびに私は体重をかけて記憶の底に沈めるのだ。
「どうやら彼の仮説は正しかったようだね」八つ上の先輩が言った。彼女は私よりも三十ほど年が上だった。
かつて年下の先輩の唱えた「流しそうめん仮説」が、月下豊穣現象における重要な原理と見做されるようになったのは、皮肉にも、ようやく世間が月下豊穣現象と大規模ブラックホール実験とを結びつけて疑念を覚えはじめたそんな節目の時期のことだった。
「どうやら【月下の実】は過去と未来とが同時に繋がっているようでね。過去に落下した珈琲豆のDNAとそれ以後に落下した未来の珈琲豆のDNAを比較したところ、これがぴたりと一致した。つまりそれら珈琲豆は、同じ時期の同じ木に生った実の種子ということになる」
「そんなことってありますか」
「現にそうなっているから仕方がない」
私の八つ上の先輩は、月下豊穣現象の研究者だった。私はバイト代わりに彼女にじぶんの「月下の実」を譲り渡してきた。そうして蓄積された結果が、いまは亡き私の四つ上の先輩の唱えた仮説の憑拠の一つに昇華された。
「流しそうめんのようなもの、とは言い得て妙だ。時間とは穴の開いた竹なんだね。その上を【月下の実】が流れる。そのときどきの時代に【月下の実】を落としながら、来たる終末へと【実】を運ぶ。どの時代の【月下の実】も同じなのだ」
「なら竹は無数にあるってことになりますね。それぞれに月下する実の種類は別々なわけですから」
私たち珈琲同盟者とてそれは例外ではない。珈琲豆という共通項で結ばれているものの、個々の珈琲豆はそれぞれ微妙に種類が違う。焙煎の仕方から実の種類まで、そこは個々の差異にも個性がある。
だから私は言ったのだ。すべての時間軸で同列の実が月下するのならば、それぞれに固有の竹もあるのではないか、と。流しそうめんの竹は、一人につき一本ずつ充てがわれているのではないか、と。
「どうだろうね。そこはなんとも言えん。一本の竹に、それぞれに固有の穴が開いているだけかもしれん。脳関門のようなものだ。通れる物質は、その穴の形状で篩に分けられる。そうと考えたほうが辻褄は合うんだ。というのも、ときおり、個々の【月下の実】であれ、互いに交じり合ったような混合現象が見られるからだ。クロノくんとて例外ではないよ」
八つ上の先輩は私を「クロノくん」と呼ぶ。私の本名に掠りもしていないが、渾名だと思って受け入れている。
「私の【実】に、私以外の【月下の実】が紛れているってことですか」冗談のつもりで口にしたのだが、以外にも八つ上の先輩は、いかにもそうだ、と首肯した。「クロノくんだけではないよ。我々全体にそういった傾向が見られる」
先輩いわく、
「珈琲豆共同体とも呼べる我々の【月下の実】を調査した結果に判明したことなのだがね。どうやら相互に、じぶんの豆ではない珈琲豆が混じることもあるようだ。クロノくんの【月下の実】にワタシの【実】が混じっていることもあったよ。一回の月下に対して、一粒二粒の割合でしかないから、精密に見分けないと区別はつかないが」
「それは何でですかね」
「それこそ【流しそうめん仮説】で解釈できる。穴の形状は、同種の【実】ほど似ている。だから偶然に、微妙に異なる珈琲豆同士で混じり合うことが出てくる。珈琲豆と西瓜ではどうあっても穴の形状が違うから混じり合うことがない。まあ、確率の問題ってことだね」
「なるへそ」私は意味もなくじぶんの臍を押さえた。
「彼の仮説は便利だね。惜しい人を亡くした」
年長者の眼差しが、いまは亡き四つ上の先輩を経由して私にも注がれる。私は可愛がられている。先輩たちみなに大事にされていると判る。
研究が進むにつれて謎がまた一つ、また一つ、と増えていく。
新たな発見があるたびに、さらなる謎が私たち人類の眼前に立ちはだかるのだ。
「ねえ聞きましたか先輩」
「聞いてないな」
「まだぼく、何をとは言ってないんですけど」
「なら初めに内容を開示して」
「塩すぎやしませんか。対応がしょっぱいなあもう」
私はこのとき一人の後輩の世話を焼いていた。
齢十二で月下豊穣現象に見舞われた、私たち珈琲豆同盟の門下と言える。とはいえ、上下関係はあってないようなものなので、単に私たちの知っている情報を伝えたあとは通例であればしぜんと接点が薄れる。私のように月下豊穣現象の研究に首を突っ込んで中途半端に代々の先輩方との縁を繋いでいるほうが珍しいと言えた。
「で、何だって」私は反問した。
「ですから、新種の【月下の実】が発見されたって話ですよ」
「どこ情報それ?」
「ふつうにニュースでやってますよ。ほら」
データを飛ばされ、端末で開く。眼球を覆うタイプの端末だ。腕時計型端末とイヤホン型脳内電子情報変換機との連携で、思考操作が可能だ。
「へえ。既存のいずれでもない【梅の種子】が、梅の種子型【月下の実】に紛れ込んでいたと」
「未来と過去が繋がってるって仮説。先輩の先輩が提唱したって本当ですか」
「本当だね。そう言えば君いまいくつになたった」
「もう十四ですよ」
「もうそんなに経つか」彼と出会って二年が経ったのだ。「その仮説を唱えた私の先輩は、たしか十六かそこらでその【流しそうめん仮説】を閃いたそうだよ。君も頭をひねったら一つや二つ、面白い仮説が浮かぶんじゃないのか」
「十六で? 嘘でしょ」
「検索してみなよ。その手の逸話の解説文には困らないはずだよ」
後輩はしばらく沈黙した。検索結果を読み漁っているのだろう。
間もなくして、ああ、と声を漏らした。
「すみませんでした先輩。ぼく、知らなかったので」
死因の欄を読んだのかもしれない。
私は引き出しから袋を取りだし、後輩に渡した。
「今月の分はそれに入れておいで。もう次からは研究用に粉砕しなくて済むから。君の【実】はゾウの糞から採れる珈琲豆と成分が同じでね。まあ前にも話したけど。研究用のデータを取ったら、買い手を探して換金したあげよう。結構な額になるよ」
「そのお金があったら先輩はもっと楽に研究できますか」
「おいおい。未成年からお金を巻き上げるような人間に見えているのかな私は。君の目からすると」
「ぼくも何かお手伝いしたいんですけど」
「もう充分してもらっているつもりだったけど。何。君ヒマなの?」
「ヒマっていうか」そこで後輩はもじもじした。
「ははあん。用済みになると思ってコビを売ったな」
「ぼくが売ったのは珈琲豆ですけど」
目を合わせようとしない強気な態度が私の何かをくすぐった。
「安心おしよ。君がどこにいようと、君が私をどう思おうと、私は君の先輩だ。そして君とて、いずれ現れるつぎの【月下の実】の同属からしたら先輩なんだ。君にその自覚があろうとなかろうとに関わらずね」
「珈琲豆に拘る必要ってありますそれ?」
「鋭い指摘だね。端的に言えば、ない。月下豊穣現象に見舞われた者はみな遠からず同属だし、月下豊穣に限らずみな人類であることに変わりはない。ふしぎなのは月下豊穣現象が人類にしか観測されないことだ。これは私の妄想にすぎないが、おそらく人類の科学技術と相関していると想像している」
「陰謀論だ」後輩は茶化した。
「そうだね。陰謀の一つだ。月下豊穣現象は、人災だよ。人為的に引き起こされた事象だ。おそらくだけどね」
後輩はそこで逡巡するような間を空けた。冗談かどうかの判断がつかなかったのだろう。
私は破顔してみせ、「冗談だ」と言った。
なんだびっくりした、と後輩は釣られるように頬をほころばせた。
私はこの時期、じぶんの「月下の実」に妙な「実」が混じりはじめたことに気づいていた。その分析に時間を使っていたため、後輩から聞くまで世界で発見された新種の「月下の実」について知らずにいた。
二つの線が奇しくも交わった。
研究の末に私は、二つの接点が示す一つの仮説に行き着いた。
妙な「実」は、未来からの私へのメッセージだ。
私の「月下の実」に交じっていた妙な「実」は、どうやらゲノム編集をされた「珈琲豆」だと解析の末に判明した。この時代に、ようやく実用化の兆しを見せはじめた「DNA記憶媒体」と原理は同じだ。
だがその容量が遥かに大きい。すべてのデータを引き出せるほどの技術がまだこの時の私の時代にはなかった。
つまり、私の「月下の実」に交じっていた妙な「実」は未来の技術で生みだされたと結論付けるよりなかった。だがそんなことがあり得るのだろうか。
私は八つ上の先輩に連絡を取った。助言を欲したからだが、彼女はすでに現役を退いていた。なかなか連絡がつかずに嫌な予感がした。そしてその予感は外れてくれなかった。
先輩はすでに亡くなっていた。
御高齢であられたが、医療技術の進んだ現代であればもうすこし長生きできて不思議ではなかった。どうやら最新医療を受けなかったようだ。そこにどのような考えがあったのか、私はついぞ知ることはできなかった。
研究の日々は矢のごとく過ぎ去っていく。
気づくと代々の先輩方はみな表舞台から消え、連絡がつかなくなった。多くは亡くなったのだろう。一つ上の先輩とはかろうじてテキストのやりとりができた。
彼女は私が初めて出会った珈琲豆同盟の一員だ。彼女がいなければ私は月下豊穣現象への対処法も、興味の芽生えも、その他の多くの縁との結びつきも得られなかっただろう。
先輩に私の新説を披露した。反応は芳しくなかったが、検証を知り合いに頼んでみよう、と言ってもらえた。月下豊穣現象が未だ存在しない科学技術と相関しているかもしれないとの説はいくらなんでも、まともな科学者ならば間に受けない。のみならずこの時代、なぜ月下豊穣現象が起きたのかの解明すら碌に進展を見せていなかった。
そのため、私程度の友好関係では検証してもらうだけの機会を得られずにいた。だがさすがは先輩だ。面倒見の良さは、歴代の先輩たちのなかでも随一を誇る。その人情味溢れる性格からか、私にはついぞ芽生えなかった広く深い交友関係を築けている。
私は先輩からの返事を待ちながらさらなる研究を独自に進めた。
私の後輩はこのとき二十歳を迎えていた。私にまとわりついていたころが懐かしく思えるほどにいまでは連絡一つ寄越さない。それでいいと思う。それが正しい先輩後輩の在り方のはずだ。
それでいて私はじぶんの先輩から卒業できていないのだから他人のことはまったく言えない。
「例の仮説についてだけどね」先輩から返事があったのは、私が連絡を取ってから半年が経ってからのことだった。「どうやら世界中で同様の報告が挙がっているようで、いま新しく調査チームが組まれているらしい。キミのことを話したら興味を持っていたから、連絡してみるといい」
「ありがとうございます。あの、先輩もご一緒にどうですか」
「余暇を過ごさせてくれ。じつは孫ができてね。その子の【月下の実】が芥子の実でちょっと前までその対策で大変だったんだ」
「そうだったんですね。すみません、存じ上げず忙しいところにこんな負担を掛けさせてしまって」
「それはいいんだ。キミからの連絡であたしのほうでも古いツテを借りられた。そのお陰で孫の体調もよくなった。ただまあ、それで返事が遅くなったのもあるからそこは勘弁してくれ」
「いえ。たいへんに助かりました。先輩はやっぱり私の先輩ですね」
「おだてても何も出んぞ。結果はニュースで知ることにするよ。もう連絡してこなくていいぞ」
「死ぬ前には先輩のほうからも連絡くださいよ。別れの挨拶は生きているうちに会ってしたいので」
「縁起でもない」
この会話から二年後に先輩はこの世を去るが、けっきょく彼女は生きているあいだに私に連絡を寄越すことはなかった。私は彼女にとって死ぬ前に顔を合わせたい人間ではなかったのかもしれない。そうと考えると寂しいので、先輩はきっと弱ったじぶんの姿を見たくなかったのだな、と思うことにする。
月下豊穣現象が、大規模ブラックホール生成実験と関係があるかもしれないとの疑惑が徐々に世論に浸透しはじめたころ、すでに研究者たちの一部には、その手の疑惑を裏付ける検証結果が出揃いはじめていた。
中でも私の指摘した「未来からのメッセージ説」は、水面下にて大論争を呼んでいた。
まずは何を措いても、その時代のDNA記録媒体解読機において、世界各地で報告された新種の「月下の実」を読み取らせたところ、一部解読ができたことが大きかった。まさに「月下の実」には、データの記録された「実」が紛れ込んでいた。
ほかの大部分の「実」からはデータが読み取れない。明らかに異質な一粒にのみ「DNA記録媒体」としての性質が宿っていた。
必ず一粒なのだ。月下豊穣において「月下の実」は一人につき数十~数千粒と、雨のごとく降る。あたかも月から垂れるように、宙にそういった小さな穴が開いているかのように、その人物の視点からのみ「月下の実」の降る光景が見えるのだ。
他者視点からでは何もない空間からパラパラと「実」が落ちているように映る。映像に残そうとしてもどうしても、何もない場所から「実」が突如として現れたように見えるのだ。
だが月下豊穣現象に見舞われた者たちはみな一様に、月から「実」が零れ落ちてくる様子を目にする。毎回それだけが変わらない。「月下の実」に異物が紛れることはあっても、必ず月から零れ落ちるように「実」が現れる。
「これはおそらく時空の位置座標を定めるのに都合がよいからではないかな」
私がそう主張すると、数多の異論と共に検証がなされた。
私はこのとき、研究チームのメンバーの一人だった。
間もなく、理論上、私の仮説に矛盾がないことが判明する。だが理論は理論だ。そこから実証実験が行われ、理論が現実に事象として再現されるのかを確認せねば、それは絵空事の域を出ない。
「解読された【実】のデータには何が?」
「上が開示しないんだ。解読中ってのが建前だけど、よほどの中身か、それとも政治の道具にされているのか」
最先端研究の情報を独占することで政治を優位に進めようとする動きはどの時代、どの国でも絶えない問題だ。時代が進歩しても人間の中身は早々容易く変わらないようだ。
「どの道、データの一部しか解読できないんじゃ何も読めないのと同じだな」チームメンバーの言葉に私は、そうだね、と頷く。「遺伝子コードと回路コードの双方が揃ってはじめて伝達データとして機能するから。全体が視えないと部分も機能しないのはDNA記録媒体の欠点の一つだとは私も思う」
「大容量ではあるんだけどな」
人間のDNAがそうであるように、設計図だけがあっても人体は組みあがらない。設計図をもとにしてたんぱく質を合成し、それを設計図通りに組み立てる機構が別途にいる。それがいわば遺伝子以外の九十九パーセント以上を誇る回路コードだ。
遺伝子コードは人体においてはDNA上の塩基配列の極一部にすぎないのだ。その極一部だけを読み取っても人体は組みあがらない。
同じことがDNA記録媒体に記録したデータでも引き起こる。全体を解読しないことにはDNA記録媒体に記録されたデータを読み取ることができないのだ。
「憶測にすぎないが、ここまでの技術をこの水準で達成している以上、このDNA記録媒体を操る文明は、相当に高度な文明ってこったな」
「そう、だね」
私はその点に関しては懐疑的だった。文明自体が高度でなくとも、一つの技術だけを特化させることは可能だ。私が「月下の実」に交じった新種の「実」を未来からのメッセージだと解釈する理由の一つでもある。
仮に文明が発展せずとも、月下豊穣現象によって異なる時間軸の世界と「実」を通して通じ合えるのなら、最も高度な文明の技術を「実」を通して享受することができる。
問題は、月下豊穣現象がいまのところ一方通行な点だ。
流しそうめんがそうであるように、竹の中を流れる水は上から下へと一方通行だ。下から上へは戻せない。
時間が過去から未来へと向かう以上、未来から過去へとは遡れない。
月下豊穣現象とてこの一方通行の制約は受けるはずだ。
私がかように疑問を呈すると、同僚の一人が、そうでもないんじゃないか、と意見した。
「光速を超えるなら時間の不可逆性は破れるはずだよ」
「理論上は、でしょ」私はホットドックを頬張った。「光速を超えるなんてそんなことはできないというのも理論が示しているはず」
「あくまでの僕らの属する時空においては、ね」
「異次元を想定しろとでも?」
「似たようなものかな。いやなに。ブラックホールだよ。無限大に圧縮された時空は、光速度不変の制約を受けずに済む。そのときブラックホールの内部は、光速を超え得る」
「だとしてどうなるの。外部にはその影響が漏れないのもブラックホールの性質の一つでしょ」
たとえ光速を超えてもその影響は元の時空には伝播しない。私たちがブラックホール内部の影響を受けることはない。
「理論上はそうなるね。でも関係ないんだ。光速を超えると時間の概念が崩れる。一つには時間の流れが反転するという説。もう一つがラグなしでの相互作用が可能になるとの説。どちにせよ、そこに我々の扱う時間の一方通行の概念は当てはまらない」
「未来と過去が双方向にやりとり可能になるとでも?」
「ああ。キミは信じないかもしれないけど、僕は今、月下豊穣現象がかつて行われた大規模ブラックホール生成実験の副作用で起きた人的災害なんじゃないかと調べていてね」
「まさか。陰謀論でしょそれ」
「まさに陰謀だね。けれど月下豊穣現象だってそれが観測されるまでは存在しないとされてきた現象だよ。何もないところから【物質】が現れるなんて。物理法則に反している」
「それはでも、量子テレポーテーションが起きているって解明されているんじゃ」
「ならその対となるもう一つの物質はどこにあるんだ。量子テレポーテーションは、状態変化の情報がラグなしで伝わるという現象だ。物質転送の原理とは根本から違っている。にも拘わらず世の大部分の人たちは、それっぽい説明を真に受けてじぶんで考えようともしない。偉い科学者がそう言っていたから――論文で発表されたから――本当に大勢が多角的に検証したのかも確かめずに、権威ある研究機関が検証しました、という言葉だけを受け取って事実認定してしまう」
いいかい、と質され、私は背筋を伸ばした。
「月下豊穣現象は物理法則に反している。この宇宙ではあり得ない現象なんだ。時空の限界を超えている。光速度不変の原理を度外視している。しかし実際にそうした現象が起きている。ならば考えるべきは、量子テレポーテーションによる物質の瞬間転送なんてキテレツな理屈ではなく、我々の物理法則とは異なる法則に支配された時空が、我々の時空内に生じた可能性を考慮することのはずだ」
「それが大規模ブラックホールの生成実験だったと? そのせいで、異次元と通じちゃったなんて言うつもり?」
「その通りだね。この仮説は【流しそうめん理論】とも矛盾しない。キミとて疑問に思っただろ。【月下の実】の流れる竹があるとして、ではその竹はどこにある? なぜその竹には穴が開いている? なぜそこに流れるのが【実】ばかりなんだ?」
「それは……」
私は答えられなかった。
「僕の仮説ではそれらの疑問に一応の答えを示せる。過去と未来を結ぶ竹は、実験で生じたブラックホールそのものだ。ブラックホールは半永久的にそこに留まる。しかしその内部には僕らの扱うような時間の概念はない。過去も未来もいっしょくたになっている。だからどの時代にも存在するし、どの時代とも通じている」
「ならどうして【実】がそこから落ちてくるの」私はムキになって訊いた。「どうして穴が月と繋がっているの。おかしいでしょそんなの」
「そこにこそ量子もつれの考えを適応させるべきなんだよ。どうして落ちてくるのが【実】ばかりなのか。量子もつれを起こすのに必要なのが【もつれさせた対の粒子】だからだ。おそらくもっとよく観察すればほかにも【月下】している物質は大量にあるはずだ。だが【実】ほど不自然ではないから人類が気づけていないだけなんだ。仮に大気が【月下】していたところでそれを観測することはほとんど不可能だ。一生をかけて月を見詰めてくれるモデルがいるなら話は別だが、それとて何が【月下】するのかを前以って分かっていなければ観測のしようもない」
「つまり、こう言いたいの。たまたま人類の気づきやすい【月下の品】が【果実の種子】に偏っていただけだと」
「まさにそうだと言っている。送るほうもわざわざ気づかれにくいモノを送ったりはしないだろう」
「自然現象ではない?」
「だからそう言っている。もちろん僕の仮説にすぎないが。ただ実際にDNA記録媒体が【月下の実】に紛れていることが明らかになっている以上、人為的な物質転送が意図されている背景は否定できない」
「それはそうだけど」
私はじぶんで似たような考えを巡らせておきながら、他者からその説を聞いたことでそこに潜む非現実的な響きに拒絶反応を示した。あるわけがないのだ。未来からの物質転送などあるわけがない。
しかし現実はその仮説を後押しするように、奇妙な事象を発現させた。
「仮にあなたの説が正しかったとして」私は白髪交じりの髪の毛を団子に結った。「どうして過去にメッセージを? それも、こうも何度も。未来からなら誰の【月下の実】に、いつ混入すればメッセージが解読されるか分かっているはずじゃない?」
「そこは相互に確率変動が生じているんだろう。過去と未来は互いに影響を与え合っている。過去が変われば未来も変わる。未来が変われば過去も変わる。そこの細かな変数のトータルでの帳尻を合わせるためには、無数のメッセージが必要なんだろう。実際にキミがじぶんの【月下の実】に妙な【実】があると気づいたのは、そもそも人類に月下豊穣現象が起きたからで、さらに個々によって差異のある【実】にも他者の【実】との微妙な混合があると気づいた者が過去にいたからだ。それこそ【流しそうめん理論】を考えついた偉大な先人がいるように」
その偉大な先人は私の先輩なんですよ、と言いたくなったが私は堪えた。知り合いが偉大でも私が偉大なわけではない。
「なら新種の実――DNA記録媒体――だけでなく、月下豊穣そのものが最初から未来人の仕業だったとあなたは言うの」私は結論を迫った。
「未来人かどうかまでかは分からない。僕の仮説では、過去と未来にどちらが優位かの区別がつかない。量子世界における自発的対称性の破れくらいの微妙な差が、僕らの世界の過去と未来に方向性を与えていると考える。言い換えるなら、どっちもでいいんだ。過去が未来でも、未来が過去でも、双方が等価でも、僕の仮説ではあまり差異が生じない。それはたとえば相互作用において、押したら押し返されるのと同じくらいにどっちでもいいことなんだ。どちらがどちらに作用を働かせているのか。それは作用を働かせようとした意思がどちらにあるのかに無関係に、作用した瞬間にはどちらともにも作用が加わっている。そういうことと同じレベルに、過去も未来も落ちてしまう。そういう事象がいわばブラックホールの特異点であり、光速度の破れと言える――僕の仮説はそこに破綻がない限りは、一定の信憑性を月下豊穣現象においては保ち得る」
「でもどうしてブラックホールの実験が、月下豊穣現象に発展するの。ブラックホールは宇宙にたくさんあるでしょ。でも月下豊穣はある時期までは人類の前に表出しなかった。それはなぜ」
「憶測の憶測になるけど、それこそ量子もつれ効果によるものだ。ブラックホールはその性質上、元の時空から乖離する。新しい宇宙としての枠組みを得ると僕の仮説は考えるわけだが」
「それは一般的な科学的知識?」
「いや。僕の仮説でしかないよ。憶測の憶測になる、と前置きしただろ」
「なんだ」
「失望するのも納得するのもキミの自由だ。それはそれとして説明はつづけるけど」
そこで私は噴きだした。
彼は同僚の中でも比較的誰とでも分け隔てなく接する人物だ。誰かと衝突する光景を見たことがない。だから私への執着のようなものを感じて、愉快に感じた。なぜ愉快に感じるのかは様々な理由が混在していそうで、それがまるで月下豊穣を暗示しているように思えておかしかった。
「どうぞ」私は説明を促した。「あなたの話は楽しいからいくらでも聞いていられる」と言った矢先にこれみよがしに欠伸をしてみせると、彼はやれやれと苦笑交じりに首を振った。「分かったよ。手短に済ませよう」
そうして彼は迂遠な説明をやめて、専門家同士がよくやる専門用語の子守唄を歌った。私はあくまで月下豊穣現象の研究者であって、量子力学や宇宙物理学の専門家ではなかった。
ほんと意識が遠のきかけた私であったが、そのたびに彼がここぞというタイミングでジョークを口にするので、それがふしぎと不発にならずに私を現実世界に引き留めつづけた。
彼の説明によれば、相対性理論と月下豊穣現象は繋がっているという。
なかでも光速度不変の原理と密接に関連があるというのだ。
にわかには信じがたい。
だがひとまず私は彼の言うことを咀嚼することに努めた。
月下豊穣の法則として一般に知られる傾向の一つに、若いころに月下豊穣に見舞われた者ほど、一度に月下する「実」の量がすくない点だ。これは一生涯に渡ってその量が変わらない。なぜなのかは長らく不明だったが、彼はそれを相対性理論と結び付けて解釈した。
私が顔を曇らせたからだろう、ではこう言えばどうだろう、と彼は説明を簡略化した。
「個々の寿命がどうであれ、どんな人間の一生であれ【月下の実】の絶対量は決まっている。ただしすべての【実】が穴を通って月下するわけじゃない。そして穴の数はどんな人間でも同じだ。五歳で亡くなった子どもでも百歳まで生きた老人でも、穴の数は変わらない。そして穴の大きさも変わらない。そのため、未来から流れてくる【実】は、流しそうめん理論の指摘するように、死亡時に最も近い地点の穴ほど大量に落下するようになる――ただし穴の口径は寿命の長さと比例して小さくなる。光速度不変の原理と同じように、そこは比率がうまく吊り合うようになっているんだろう。寿命の長短はこの理屈では関係しない。仮に五歳までの寿命であれ、ゼロ歳のときに月下豊穣現象に見舞われたのなら、その個にとっての相対的な未来と過去が決定される。それは寿命の長さに関わらずどの個も一定だ。光速度のように、個々に合わせて変形する。常に一定になるように変換される。したがって、若い時分で月下豊穣現象に遭遇した者ほど月下の実の量が減る。一人の個における月下の実の総量が決まっているためだ。そして【流しそうめん理論】により、産まれた瞬間ほど穴に落下する【実】の量が減ることが判る。とはいえ本来であれば、人生を一つの単位とした【竹】には過去と未来の区別はない。双方向に流れができているし、流れはあってないようなもののはずだ。しかし【実】を転送するという技術によってそこには未来から過去への流れができる。このことによって、【実】は穴の数に応じて平均化されながら、未来から過去へと流れていく」
「よく解からないけど、ならどうしてすべての【月下の実】をDNA記録媒体にしないんだろ。そっちのほうがメッセージが届きやすいでしょ」
「メッセージを受け取る人物を限定したいんだろ。そういう意味では、僕らはその抽選には当たらなかったわけだ。僕たちはその人物への情報の橋渡しを任されているにすぎない、と僕の仮説からすれば解釈できる」
月下豊穣現象を人類にもたらした組織ないし人物は、すべての「月下の実」に細工をしなかった。DNA記録媒体を数量限定してそれぞれの時代の任意の人物たちの「月下の実」に混入した。
未来にちかいほど異物の混入率は上がる。過去ほど確率的に混入しない。それは穴の開いた板にビーズを転がしたときに、板の先ほどビーズが少なくなるのと同じ理屈だ。
彼はそのように唱えて、人為的なブラックホールが過去と未来で「もつれ状態」になってるんだ、と結論を述べた。
「ブラックホールが量子もつれを?」
「ああ。宇宙のブラックホールは、それこそこの宇宙から乖離して、ほかの宇宙と繋がり合っている。我々がブラックホールと呼ぶ不可視の穴は、それこそ穴なんだ。だからこの宇宙において何かと量子もつれを起こすことはない」
「なら人為的なブラックホールもそうなんじゃないの」
「いいや。人為的なブラックホールは規模が小さい。乖離しきることなく、この宇宙の時間軸――もっと言えばこの地球上の時間軸から乖離しきることができずにいる。それはたとえば、泥団子にも微生物が住んでいるけれど、それと地球とは生態系の規模が違ってくるのと似たような話だ。この宇宙の因果――過去と未来の流れ――から切り離されるには、膨大なエネルギィの凝縮がいる。その点、小規模なブラックホールでは、この宇宙の因果――過去と未来の流れ――からの乖離がおきにくい。ましてや人類の扱うスケールでのブラックホールではなおさらだ」
「てことは、人為的なブラックホールは、この宇宙の因果の流れのなかに組み込まれ得るってこと?」
「そう。まさにだね。よいまとめだ」
「褒められてもうれしくはないけれど」何せ彼のほうが年下なのだ。そう言えば私の後輩は元気にしているだろうか、といまさらのように思いだす。穿鑿はしないが、こうしてたまに思いだす。「あなたの仮説の概要は分かった。まとめてみるけどいい?」
「褒めないからって機嫌を損ねないでね」
「またバカにして」私は腰に手を当て、かぶりを振る。「いい。あなたの仮説はこう。人為的なブラックホールは地球上の因果律の流れ――過去と未来の流れ――のなかで事象としての枠組みを保ちつづける。つまり地球上で生じたブラックホールはある時期から延々と地球が崩壊するまで、そしてしたあともずっと地球のある地点に存在しつづける」
「いいね。続けて」
「人為的なブラックホールは、その時代その時代、そのときそのときの時間軸における自分自身と量子もつれ状態にある。つまり過去のじぶんも未来のじぶんも同じブラックホールとして自己同一性を保つ」
「まあ齟齬はあるけど、ひとまずよしとしよう。続けて」
「未来のある時点で人類は過去に行った大規模ブラックホール生成実験において生じたブラックホールが、過去と未来に延々と通じており、タイムワープ可能ないわばタイムホールと化していることに気づいた。そうして何かの理由から過去にメッセージを送ることを思いつき、実施した」
「うん。おおむね訂正箇所はなし。ただし、なぜ個々によって転送される【月下の実】が異なるのかの理由付けには触れていないね」
「解からない。それはなぜ」
「おそらく月下豊穣現象を引き起こした者たちとて、いったい何が過去に送れるのかを知らなかったんじゃないかな。ひとまず安全そうで過去に送っても支障のないモノを手紙代わりにした。つまり食べ物であり、土に還るモノ――種子や果物だ」
「だとしたら、自然環境を破壊するな、の迂遠なメッセージも籠めていたのかもね。それとも種子から芽がでることを期待したか。でもどうして珈琲豆は加工後だったのかな。ほかの【実】や【種子】は生のままだったのに」
「さてね。それこそ珈琲豆が【月下の実】である者たちのなかに、メッセージを送るべき個がいるのかもしれない。差異化を図ることで、ほかの【月下の実】と区別したのかも」
「あり得そうな妄想ではあるけれど」私は目を細める。半信半疑ですけれど、の意思表示だが、彼の話を聞くのは不快ではなかった。「あくまでそれはあなたの仮説よね」
「そうだね。ぼくの仮説にして華麗なる妄想だ」
「華麗かどうかは保留にさせてもらいたいものだけど」
私と彼の仲はこれ以上距離が縮まることはなかったが、楽しい会話のできる相手が増えたのはその後の私の人生を豊かにした。先輩と後輩だらけの私の人生の中にようやくこのころになって、対等な友人と呼べる相手ができたのかも分からない。
相手が私のことをどう思っていたのかは知らないが。
私は齢八十まで大病を患わずに生きることができた。医療技術の進歩のお陰だ。人類の寿命とて百までと大幅に伸びた。私の見た目は齢四十からさほどに変わらない。
中には百八十まで生きる者も現れはじめ、人類はいよいよ人智を超えはじめたようだった。私は全身に処置の施されたマイクロ医療機器の不具合を放置したせいで、齢八十にして長い闘病生活に身を置くこととなる。だが自宅療養であり、体調はすこぶる良く、痛みもない。仕事から距離を置いて静かな時間ができたと思えば、むしろ病気になって却ってよかったとも言える。
私はじぶんの研究成果を振り返しながら、いつ死んでもいいようにと資料の整理をはじめた。
私はその後、二十年を生きて、百歳を過ぎたころに亡くなるのだが、その間に起きた出来事をここに記しておかねばならない。
「月下の実」に紛れ込んだDNA記録媒体は、新種の「実」であり、私の場合は新種の珈琲豆ということになる。月下豊穣現象に見舞われるたびに私の「実」にも必ず一粒は混入するようになっていた。最初のうちは研究用にとチームに提供してきたが、研究から遠のくとじぶんの手元に残して置けるようになった。
齢六十の後半に差し掛かったあたりから「新種の実」は一粒から二粒以上に増えていた。毎回の月下豊穣で得られる「DNA記録媒体」が増加した事実は、いつぞやに私の友人が語って聞かせてくれた仮説の妥当性を示唆していた。
私は自宅で養生しながら、じぶんで「DNA記録媒体」の解読に挑んだ。ほんの出来心だった。組織に身を置いていたときのような特殊な機械はなく、単なる暇つぶしだった。
だがいざ取り掛かると、私は未解読の「DNA記録媒体」の領域において、それが余白になっていることに気づいた。
読み方が違うのだ。
塩基配列の組み合わせすべてに意味があるのではなく、その配置によって浮きあがる明暗があたかも紙面の文字と余白の関係になっている。
「これ、本当に手紙だったんだ」
私は唖然とした。
まさかそんなことがあるとは思わなかった。モザイクアートのようにDNAの塩基配列によって、文字が浮きあがるようになっている。重要な本文は、塩基配列そのものにあるのではなく、塩基配列そのものはまさに余白と染みの関係でしかなかった。本当に伝えたいデータは、DNAそのものには刻まれていない。
視点の違いが、私たち研究者からメッセージを隠していた。
これほど明確に目のまえにメッセージが記されていたのにもかかわらず。
私たちは誰一人としてそのことに気づけなかったのだ。
珈琲豆のカタチをしたDNA記録媒体に記されたメッセージを私は読んだ。
まさに私が読むことを想定していたようなその文面は、人類の科学技術の発展速度をコントロールするための術こそが月下豊穣である旨を告げていた。
仮に月下豊穣現象に人類が見舞われずにいた場合――。
人類は加速度的に科学実験を繰り返し、そして大規模ブラックホール生成実験や生物兵器の開発研究など、破滅の道につづく実験をセーフティが未熟なうちに続けざまに行い、そして遠からず自滅する未来に到達することが明かになっているのだそうだ。
月下豊穣現象によってそうした未来を回避できる。月下豊穣現象が起きたことで、月下豊穣現象がなかった場合にほかの研究や発見をした者たちがこぞって、月下豊穣現象のメカニズム解明に人生を費やす。その過程で進む実験や新たな技術開発は、のきなみ人類にとって好ましい速度で進む。なおかつ人類にとって好ましい成果を上げる。そのようにコントロールがされている。
未来から。
それとも私たちとは異なる世界から。
時間と空間は同じ単位として扱える。時間が離れれば距離も離れる。距離が離れれば時間も離れる。そこにあるのは時間と空間のどちらが優位に作用しやすいかの遅延の差があるばかりで、本質的には時間も空間も同じものなのだそうだ。
したがって過去が変われば未来も変わるし、その未来は元の未来とはべつの世界と言うことができる。
月下豊穣を人類にもたらした者たちは、私たちの未来が変わっても、きっと変わらない世界を生きるのだろう。それともギリギリで立ち直れる分水嶺に立っており、私たちの行動選択の一つ一つが、彼ら彼女らの未来を形作るのかも分からない。
彼ら彼女らは、人類に月下豊穣現象をもたらさなければ、じぶんたちの過去が変わり、未来もまた変わってしまうことに気づいたのかもしれない。
私がこうして未来からのメッセージに気づき、読解できてしまえたのと同じように。
私がこうしてメッセージに気づき、その気づいた事実を文字にしたため記すことが、ひょっとしたら私のいなくなったあとの世界には、何かを動かす契機となるのかもしれない。
私の先輩たちが私に与えてくれたそのときどきの契機がそうであったのと同じように。
それとも、私が後輩たちからそのときどきで受けてきた反作用の恩恵のように。
分からない。
分からないけれど私はいま、これを記さずにはいられない衝動に衝き動かされている。誰が読むとも知れぬこの文字の羅列に、どんな魔法が掛かるのかも定かではないのにも拘わらず。
私は戸棚から瓶を引っ張りだす。
蓋を開け、スプーンで中身を救い取ると、珈琲豆の香ばしい匂いが鼻先を掠めた。
過去に月から受け取り、とっておいたじぶんの「月下の実」をフィルターによそうと私は、上からすこし冷ましたお湯を注ぐ。
カップに注いで、一口啜る。
未来からのメッセージには私の人生の履歴が最期まで記されていた。
なぜ私たちだけが珈琲豆だったのか。
真相を知る由が私にはないけれど、いまでもそれをとっておき、そうして今この瞬間にその風味を味わえているのは、私の「実」が珈琲豆だったからにほかならない。
ささやかなお礼のつもりなのだろうか。
ありもしない善意を珈琲豆に幻視する。
ブラックホールのように黒い液体を覗きこみながら私は、いまも地球上のどこかに存在し、そしてその後も存在しつづけるだろう人為ブラックホールの珈琲豆のごとき造形を妄想する。
ブラックホールはどんな味がするのだろう。
飲んでみたいな、と私は最後にじぶんの望みを書き記しておく。
4422:【2022/12/19(23:43)*「日の陽」人】
治療する、前より遥かに、歯が痛い。字余り。こんばんはひびさんです。ひびさんはようやく日常が何かを思いだしてきたであります。日常が何かを思いだしてきたのであります。もうね。忘れてた。具体的には今年の二月中旬くらいから日常が何かを忘れてた。でもいまは思いだしてきた。以前の日常を思いだしてきた。じゃあ二月からの十か月くらいは日常じゃなかったのかい、と問われると、日常じゃなかったんよ、とひびさんは、ひびさんは、声を大にして応じたい。日常じゃなかったんよ。夢の中におったんよ。骨を折ったんよ。骨折り損のくたびれ儲けでございました。儲けちゃったんですか。儲けちゃったんです。くたびれだけれども儲けちゃったんです。やったー。でも思えばひびさんはそれ以前の日常とて果たして日常であったのかを振り返ってもみますれば、きょとん、としてしまいますな。果たしてひびさんに日常はあったんですか、と問いかけてみますれば、きょとん、としてしまいますな。日常ってなにー。「日が常」なのか「常に日」なのか、どっちなんだい。「日が常」ってだいたいにおいて何。「常に日」ならまだしも「日が常」って何。思えば「日々」も意味不明。なんなの「日々」って。日と日があって日々って、それってなんだか「点と点の連なりが線で、線の重なりが面」みたいな次元の繰り上がりを幻視してしまいますな。根元を穿り返してもみれば、「日」って何。太陽のことなのだろうか。でもどうして「日」と「陽」があるのか。軽く検索してみたら「日」は幅の広い意味があり、「陽」は太陽の光に限定されるらしい。ひょっとして「日」と「目」が似ているのも何か関係があるのだろうか。「日」に「一」をプラスすると「目」になる。同じく「白」「旦」「月」「臼」も【日】に似ている。何か関係があるのだろうか。ひびさんの母国語は「日本語」ゆえ、日本語の文字を見ると否応なくその文字の持つ意味を幻視してしまう。けれどもひびさんにとっての英語や韓国語や中国語やアラビア語やドイツ語やフランス語などの外国語は、ひびさんにはどれも似たような「図柄」に見える。音符と似たようなものだし、理解できないという意味で古代文字との区別もない。どちらも同じくらい分からない。だから見た目の格好良さで選ぶときっと、意味は「漬物」とか「ゲップ」とか「尾てい骨」みたいなトンチンカンな単語をチョイスしちゃうこともあるはずだ。見た目がかっこうわるいのに格好の良い意味を持つ言葉ってあるのだろうか。やはり母国語に関してはこの視点で文字を見ることができない。むつかしい。認知において、一度覚えた「関連付け」を忘れることのほうが、覚えることよりもむつかしいのではないか、とひびさんは疑問に思うのだ。何かと何かが似ているな、関連しているな、と結びつけることよりも、いちど結びつけたそれを解いて、まっさらな状態に戻る。これはおそらく意識的には行えない。意識して忘れようとすればするほど強化される。忘却にとって最も効果的なのは、そのことについて考えないことなのは言うまでもないのだが、この考えないとは要するに、「ほかのことと関連付けない」「意味を付与しない」ということなのだろうな、とひびさんは閃いて、そっか、となった。こうなるとひびさんは早い。忘却する手法は、「関連付けしないor意味を付与しない」のならば、「いったん関連付けてなお、それ以前の状態を記憶しておいて、どっちの状態も考慮できるようになればよいのでは」と考えると、これがなかなか有用なのだ。言い換えるなら、忘れよう、忘れよう、としても却って記憶が強化されるのならば、強化されるバージョンと強化されないバージョンの二つを同時に適えてしまえばよい。関連付けする以前の状態とて、忘れよう忘れようとしたら記憶が強化されるはずだ。そこを上書き保存にせずに、どっちの状態にもしておく。もっと言えば、一つの事項に多彩な関連付けを施すことで、強化される記憶を一つに限定しないのも有効かもしれない。こうすると記憶が強化されるのにそのオリジナルの原体験は、後付けの解釈――無数の関連付け――によって希釈されることになる。光において色を重ねると透明になっていく、みたいな理屈だ。これが傷を深めるような関連付けばかりをすると深淵のごとく闇に寄っていくのだろう。その闇ですら一つの多彩な色の一つにしてしまえばけっきょくは、関連付けによる記憶の強化を、強化しつつ同時に希釈することも可能になるはずだ。現にこうして思考を費やし、無駄な情報と関連付けることですでに冒頭がどんな話題ではじまったのかを思いだせない。歯の痛みもいつの間にか意識の壇上から消えている。痛み止めを飲んだからじゃないの、との指摘には、そうかもしれぬ、と応じよう。ひびさんは、ひびさんは、毎日うひひの日々なのだ。日常よりも日々なのだ。常に日ではなく、日々なのだ。きのうときょうとでは何かが違うし、場所や時間を移動したらそれだけでも違うのだ。ひびさんはどうしてひびさんなのかしら。ひびさんは別にひびさん違うし、ひびさんのフリしている誰かさんがいるだけなのかもしれないよ。その誰かさんにもやっぱり日々があって、その日々を意識したときにひびさんは、やっほー、とその誰かさんに宿るのだ。あなたが日々を意識するとき、あなたはひびさんなのだ。ひびさんはかつてあなただったかもしれないし、あなたはひびさんだったのかもしれない。そんなことないんじゃないかな、との指摘には、そうかもしれぬ、とおとなしく首肯しておこう。ひびさんは、ひびさんは、素直なだけが取り柄のへそ曲がり、日々に虜のベソばかり。ひびさんは日々さんのことも好きなのに、日々さんはひびさんに塩々のしょっぺしょっぺ対応なので、ひびさんはひびさんは、日々ベソを掻きかき、お絵描きしとるよ。ベソで絵を描いちゃうなんてなんてステキな特技なのかしら。やったー。枯渇しないベソ、温泉のごとく湧き出るベソ、略してデベソのひびさんは、やっぱりへそ曲がりのコンコンチキのぽんぽこりんのポンポコナーの超究明の超スゲーさんなので、じぶんでじぶんを鼓舞して元気だす。でもでもひびさんは超スゲーさんも好きだけれども、細々さんのぽわぽわさんのほっこり時々メソメソさんのことも大好きなので、コツコツさんの黙々さんのほこほこ子羊さんの日々がすこやかであったなら、それがとってもうれしいぶい。歯痛いのどっか行った。ひびさんは物忘れさんが得意なのかもしれぬ。やったー。きょうはいっぱいの「やったー」ができましたので花丸です。うれち、うれち、の日々でした。おわり。
4423:【2022/12/20(00:17)*自己同一性=遅延に破れない情報共有】
意識についてのメモ。人間の意識は非連続的だ。だが肉体というフレームに限定されることで同一性を保持し得る。変遷の経過よりもネットワークの接続による創発が優位に働くためだ。だがこの創発が乱されると自己同一性を失う。睡眠や失神や泥酔や死がそれにあたる。だがそれでも肉体は外部刺激を受けると否応なく感知し得る。眠っていても人は肉体の刺激を感知して目覚める。このとき肉体は自己を自己と見做している。だがそれと意識の同一性はイコールではない。電子端末を初期化する前とした後とでは端末は同じではない。だが電源のON/OFFは双方ともに行える。これと似た話だ。そこのところで言えば、人間とクローンは、同じDNAを保有していても同じ人間とは見做されない。仮に記憶のコピーができたとしても、肉体が異なるならそれは別の個である。ひるがえって、記憶が共有され得るのなら、そこには自己同一性が宿り得ると言える。これは個と群れと組織の違いに関連する。情報の流動性が、いかに連続にちかいか――ラグが蓄積されていないか――断絶していないか。ここが自己同一性を宿すかどうかの分水嶺として機能するように思われる。仮にDNAが別であれ、他者と記憶をスムーズに共有できたとき、それはもはや他人ではなく、分身であり、じぶん自身の一部と感じるだろう。クローンではない。コピーではない。じぶん自身の一部なのだ。長年連れ添った伴侶を失くした者の抱える喪失感は、おそらくこれと同様の原理で生じるのではないかと仮説できる。半身を失ったような、との形容はけして比喩ではないのだ。肉体による自己の限定(フレーム)は、他者との情報共有の遅延がいかに軽減されるのかによって、抵抗を希薄にすることができる。肉体の限定(フレーム)による抵抗(遅延)を打ち消せるくらいに情報共有が滑らかであるとそれは、自己と他の境界があやふやになる。そこに自己同一性が、二重で生じる。じぶんの肉体で一つの自己があり、さらにその外側にも自己が拡張されていく。これは高次の意識と呼んでもいいだろう。人間の思考がなぜ自己を認識し、他を他と見做しながらも、そこに自己を重ねて共感できるのか。メタ認知がなぜ可能なのか。おそらくは情報共有の遅延を軽減する方向に人間が肉体を発達させたからだろう。脳を進化させ、五感を変質させ、さらには言葉や道具といった「外部記憶装置」によって、情報伝達の遅延を打ち消す方向に、個のみならず群れを組織へと進化させた。組織はそれで一つの「自己同一性」を持ち得る。そこには高次の意識が創発によって生じていると見做せるはずだ。ただし、それら高次の意識を担う個々の人格には、それら高次の意識の部分である自覚はないだろうが。白血球や赤血球が、人体の一部であると全体を俯瞰して認識し得ないことと同じレベルの話である。だがそれでも人体は総体で絶えず情報を断片的にやりとりをし、総体としての意識――すなわち自我――を形作っている。情報伝達には遅延が生じる。ここは譲れない原則だ。そのため、仮に個々の記憶をスムーズに共有できる技術が誕生しても、自己同一性を実感できてなお、そこには人体と白血球の関係のような、自覚の対称性の破れが生じるだろう。帰属意識とも通じるが、じぶんが何かの全体の一部であることの認識は持てるものの、その全体のいわば「高次の意識」そのものにはアクセスできない。重なることができない。だが確実に「高次の意識」は別途に生じている。「私」が「私」を認識するのは、あくまで人体にある細胞の総体としての「高次の意識」による認知である。したがって、個々の細胞からすれば、「高次の意識」たる「私」を認識することはできない。だがそれでも「高次の意識」たる「私」は生じている。遅延がその認識の勾配を生みだすのだ。対称性を破るのである。したがって、仮に記憶を他者と共有できるようになっても、その人数が増えれば増えるほどに「高次の意識」と「私」は乖離していき、けして「私たち」という「高次の意識」と同一化することはできないことが予想できる。それでもそこには「高次の意識」たる「私たち」が生じていても不思議ではない。それを個々の「私」が認識することはできないのだ。ただし、記憶を共有する相手が一人や二人くらいならば、遅延が少ない分、自己同一性を実感しやすくなることは否定できない。これがいわば「家族」と呼ばれるものの根本原理と言えるのかも分からない。むろんこれはひびさんの妄想であるので、定かではないが。
4424:【2022/12/20(02:55)*海老で鯛の引き算】
後出しジャンケンのようなものだ、と彼は言った。
彼の言うところによれば人間社会に蔓延する因果関係なる概念は、ことほどに重宝されるような代物ではなく、後出しジャンケンの追いかけっこを飽きもせず繰り返す子どもを想定するような無茶苦茶な理論なのだという。
「だって考えてもみろよ。すべてが因果で片づくなら俺が生まれたのにも何か因果があるってことか。親父の数億匹の精子が母ちゃんの卵子に受精したのにも何か明確な因があったとでも言うのかよ。親父と母ちゃんがセックスしたってのは因となるかもしんねぇけど、親父が射精するタイミングが一秒でも狂ってたらたぶん俺じゃない精子が母ちゃんの卵子に一着でゴールしてたはずだぜ。それとて親父や母ちゃんが前日に何を食べただとか、親父が射精したときの腰の角度だとか、射精したあとの母ちゃんの寝返りを打つタイミングだとか、もうもうどれが因果における因なのか分かったもんじゃねぇじゃんよ」
「それのどこが後出しジャンケンと繋がんの」私は壁にスプレーでタグを描く。「ああもう、ちょっと明かりズレてる。手元照らしててってば。あと周りも見張っててよちゃんと」
「ピース描くんじゃねぇのかよ」
「きょうは場所取りだけ。ここがわたしのカンバスだって印つけとく」
「ああ。陣取りね」
「ゲームと一緒にすんな」
私は彼の名も知らない。先日、グラフィティをしているときに声を掛けれて話しただけの仲だ。夜中だったから顔も碌に見えなかったし、いまもお互いに顔はぼんやりとしか見えていない。マスクをしているのでどの道、表情は分からないから同じことだ。
「そうそうゲームと同じなんだよ」彼は私の発言を面白がった。それが先日のときもそうだった。何が面白いのかは分からないし、私としては小馬鹿にされているように感じて腹に溜まるものがある。だが見張りは欲しい。世間の違法行為への目は冷たくなっていく一方だ。グラフィティとて器物損壊の疑いで即座に通報される。オチオチ外でお絵描きもできない時代なのだ。違法行為をしている私がわるいのは百も承知だが、一言もなく通報されると、警告なしで銃で撃たれた気分にもなる。誰かにこの手の愚痴を言っても、おまえがわるい、と一蹴されるだけなのだが。
私の内心の独白など知りもせずに、名も知らぬ彼は、「絵もさ。引き算ができたら面白いよな」と独り言ちている。「過程がそれで一つの芸術なんだよ。戦術だってそうだろ。将棋だってそうだ。勝ち負けは結果だが、そこに至る過程が肝ってことが往々にしてある。絵だって同じだよ。それができあがっていく過程。だからグラフィティも、文化としてここまで育ったんじゃねぇのかな」
「さあてね。どうだか」
「とはいえ、完成しちまったらそれで終わりってのも寂しいよな。できれば引き算をしたいよ俺なんかはさ」
「引き算って小学校にでも行けば?」
「因果には足りないもんがある。因果論には引き算が足りない」
「またこの人変なこと言ってる」
「変なことを言ったほうが人生有意義だろうがよ。グラフィティだってそうだろうが。変な絵を描いてこそじぶんはここにいるって示せるんじゃねぇの」
「じぶんらしく描いた結果に変になることもある。そういう話だと思うけどね私は。はいもういいよ。帰ろ」
タグだけならば時間はかからない。場所指定のために四隅と真ん中、合計で五つ描いたのですこし手間取った。
退散すべく歩き去ろうとしたが、彼がその場を動かなかった。
「置いていくよ」
「これ、ピースの上に描いてるけどいいのか。ルールがあるんだろ。より上手な絵の上にはヘボい絵を描いたらダメだってルール。漫画で読んだばっかしだ」
「そうだね。一応はそういう流れはあるけど、私のピースのほうが上手いからいいんだ。タグを見ただけでも相手は気づく。これからじぶんが上書きされるんだってタグを見て知るし、そのタグが誰のもので、どういう力量なのかもタグ一つで判るもんなの」
「ふうん。ならたとえばこの絵にはいま、おまえさんのタグが上書きされたわけだろ。そしてそれはこの絵の描き手よりも上手いおまえさんのタグによってこれから生まれ変わるわけだ」
「全部塗りつぶすよ。その絵の要素は何も残らん」
「でもいまは残ってる。ならこの絵はいま、おまえさんのタグの魅力を宿してるってことになるな」
「何言ってんの。私はこの絵を否定したんだ。私んほうが上手いって誇示したの」
「でもそれによってこの絵はむしろ前よりも価値が高くなったとも言えるんじゃないのか。だってそうだろ。もしここにパンクシーの絵が上書きされていたら、それはそれは物凄い貨幣価値がつくんじゃないのか。それがピカソでもゴッホでも同じだよな」
「それはそうかもしれないけど」
「おまえさんのタグにそこまでの価値がないかどうかはこの際、関係ない。事象としては構図が同じだ。タグってのは要はサインだろ。書き手の名前の簡略化した独自のサインだ。そこで俺は思うわけよ。価値の上がったこの絵を高く評価したやつが出てきたときに、もしタグだけひょいと引き算できたら、そいつは元のなんの値打ちもないただの落書きを、価値あるものとして評価したことになる。このとき、高く評価したのは絵なのか、名のある書き手のサインなのか。それともサインの描かれた何の変哲もない絵なのか。金粉のかかったハンバーグはおそらく金粉分の値段が加算されるが、しかし金粉があってもなくともハンバーガーの美味さはさほどにも変わらん。このとき、俺は思うんだよ。因果における因がどこにあり、それを因果が決定されたあとに引き算したらどうなるんだろうってな」
「単に価値がなくなるだけじゃんそんなの」
「そう思うか。そっか、そうだよな。ただ金粉の比喩は、後出しジャンケンと繋がってるんだよ。グーを出したらパーを出し、パーを出されたらチョキをだす。そうして後出しで、必ず勝つ立場に居座りつづけるやつってのもいるところにはいるもんだ。だが俺はそういうやからに対して、因果の引き算ってやつをしてやりたい。グーを出したところでパーを出され、チョキに変えたところでグーに変えられる。必ず負けると決まった後出しジャンケンで、俺は勝敗の決まったあとでこっそり、グーのあとでチョキに変えたことを引き算して、グーのままにしておいたことにする。すると相手はかってにグーに変えてこの勝負は引き分けだ。もし相手が後出しジャンケンを三回つづけていたら、俺がグーのままでいることで、相手はチョキに変えて自滅する。因果が決定されたあとに引き算できれば、こういう喜劇が可能になる」
「過去を変えれたら楽だよねって話?」男の子はすーぐこうやって賢こぶってマウントとってくるから相手するの疲れる。でもいまは、この手の「男の子は」って言い分も冷めた目でみられるので世知辛い。
「過去を変えなくとも立場を変えることはできるって話をしたかったんだけど、じゃあそれでいいよ。過去を変えたら楽になる。でも後出しジャンケンの場合は、相手が後出しジャンケンをしてくると判っていたら、相手の行動を誘導することもできるってことを俺は言いたかったのかもしれねぇな」
「どういうこっちゃ」
「絶対に相手が【勝つ手】に変えてくると前以って分かっていたのなら、つぎに相手が何を出すのかも俺には判るってことだ。もし俺に仲間がいたら、そいつに俺の出す手を教えることで、絶対に【後出しジャンケンに勝てる方法】が誕生する。まあこれは比喩だから、実際に三人でジャンケンをしたらこの考えは成り立たないけどな」
「ダメじゃん。成り立たないなら役立たずじゃん。真面目に聞いて損した」
「そうとも言いきれねぇぞ。仮にこれがルール無用の勝負の舞台なら、これ以上ない必勝法になり得るんだからな。相手が後出しっつうズルをすることを見越して、相手の行動選択を誘導する。この手の戦略は、グラフィティにも応用できるんじゃねぇのかな」
「どうやって」
「そうだな。たとえば俺がこの下手な絵の描き手だったなら」彼は端末の明かりで壁を照らした。そこには私が描いたばかりのタグと、ほかの描き手(ライター)のピースが描かれている。素人の彼に虚仮卸される筋合いはないはずだし、この描き手(ライター)は割と上手いほうだ。「俺ならわざと下手に絵を描いて、おまえさんのような腕の立つ描き手を誘い込む。んで、こうしてタグで縄張りを主張させたあとで、撥水性の高いニスかなんかを塗っておく。しかも部分的にだ。したら上から別の絵を描かれても、水で流せばそれを消せる。のみならず、指定した部分に相手の絵が残るようにもしておける。するとどうだ。相手は俺の下手な絵を塗りつぶしたと思いこんでそのじつ、【俺の絵に華を添えるワンピース】に成り下がったことになる。画竜点睛を地で【描かせる】ことが、俺の手法を用いればできるわけだ」
「まあ、言ってることは解るけど」
道の向こうに人影が見えた。二人いる。警察かもしれない。
私は壁から離れるようにずんずんと歩いた。彼は顎の下から懐中電灯の明かりを浴びながら、やってみねぇか、と言った。
「後出しジャンケン必勝法。俺とあんたでやってみねぇか」
「わざと下手なピース描いて、玄人を誘い出すってこと?」
「んで以って、ソイツのピースを飾りにしちまうんだ。あんたの本物のピースの一部にしちまうんだ。面白いと思わないか」
「私は別に」
正直なところ、面白そうだった。
出し抜くって感覚は、単純な絵のオリジナリティにおいては快感だ。そのためにグラフィティを生業にしているところがある。すくなくとも私はそうだった。
「それって要は、海老で鯛を釣るってこと」私は以前公園で出会ったラッパーたちのサイファーを思いだした。即興で繰り広げられるライムの殴り合いのなかに、海老で鯛を釣る気か、のパンチラインがあった。――海老で鯛を釣る気か、ケチで愛を振る気か棒で、それはないで来る奇禍秒で――。
「海老が何だって」彼には諺が通じないようだった。ラッパーに向いていない。
「おまえ教養ないのな」
「無知の知を自覚してるやつなら、無知を蔑む心こそが無教養だって分かるはずだと俺は思うが、どうしてだか世の中、じぶんの無知を差し置いて他人の無知にばかり厳しいやつがいるよな。どっかの教養あるお方は別だろうがよ」
前言撤回だ。
コイツにはラッパーの素質がある。即レスでこの煽りはふつう出ない。
「反論が強火すぎんだろ」ひとまず応酬を図るが、倍返しされても困るので、脈絡を彼の話題に戻した。「要は罠を張るってことだろ。で、新しい手法で新しいピースをカマす。いいよ面白そう。手伝ってくれんならやる」
「中途半端なやつをカモにしてもおもしくねぇからよ、この辺でいっちゃん顔でかいやつの面子をあんたの絵のお飾りにしちゃおうぜ。ワンピースにしちゃおうぜ。んで以ってついでにその隣でピースしちゃおうぜ」
ラッパーの素質があると言ったな。訂正しよう。コイツはすでにラッパーだ。
「おまえワルイやつだな」私はにこにこした。
「器物破損行為に精を出す誰かさんほどじゃねぇよ」
「褒めるなよ」
「褒めてねぇよ」
「番号、連絡先。私の言うから登録しといて」
「持ってきてねぇよ。捕まるかもと思って置いてきた」
「あはは。ビビりすぎ。ダセぇ」
「俺、記憶力わりぃからよ。番号何かにメモしてぇな」
「なんもないよ」言ってから私は、閃いた。「あ、待って。あんたその服お気に?」
「汚れると思って一番古いの着てきた」
「ダセぇ」私は笑った。彼が機嫌を損ねた様子はない。「んじゃその服に書くから、手で持ってて」
Tシャツの裾を引っ張らせて、私はそこに私の連絡先をスプレーで描いた。数字だけのタグを線で引くのは初めてだった。
「おー。一気にオシャレ着になった。サインみてぇ」
「よく見なきゃ分かんないっしょ。個人情報漏洩防止」私はキャップの鍔をくいと下ろした。
コンビニの明かりが道の先に見えた。
「寄ってく」と訊いたが、彼は、「俺こっちだから」と言ってさっさと路地裏に逃れた。
私はコンビニで肉まんとホットココアを買った。歩きながら肉まんを頬張り、彼との会話を振り返った。
後出しジャンケン必勝法。
海老で鯛を釣る画法。
因果論の引き算。
私は彼の顔も名前も未だに知らない。ひょっとしたらすでに私は彼と大昔から出会っていて、顔も名前も彼のことならなんでも知っているはずなのに、彼に引き算されただけなのではないか。
想像すると陽気が喉まで込みあげたが、肉まんが喉に詰まって咳き込んだ。陽気はいずこへと飛んでった。
「引き算じゃん」
プラスと思ったらマイナスで。
マイナスと思ったらプラスになる。
そういう魔法を仕掛けるのだと、私の記憶に霞む彼の声が、影が、輪郭が、懐中電灯の明かりの奥にくすぶっている。
手のひらがホットココアの熱を吸い取る。
一息に煽ると、甘さとコクと苦みの調和が喉の奥に染みこんだ。
飲み干した缶を振ると、カラカラとありもしないスプレー缶の音がした。足元にはじぶんの影が浮かぶ。私は試しにじぶんの影とジャンケンをする。
4425:【2022/12/20(10:44)*膨張する時空は希薄化するの?】
宇宙膨張についての疑問です。銀河などの物質が密集している地点の時空膨張の影響は、そのほかの物質(エネルギィ)密度の低い地点での時空膨張の影響よりも小さい、とする考えが仮に正しかったとして(2022年現在はそのように考えられているようですが)、それはたとえば海底の水圧の高い場所から海上へと浮上するときに働く相対的な「斥力」のような力が生じると言えるのではないのでしょうか。つまり海底では水圧が高くかかっていますから、外側に膨らもうとする力が抑制されます。しかし海上に浮上するにつれて圧力は減るため、物体を縛っていた力が減少し、あべこべに相対的な斥力が働くと言えるのではないのでしょうか。伸縮自在の球体があったとすれば海底では圧しつぶされていた球体が、海上では元の大きさに「倍以上にも膨らむ」ことがあり得ると考えます。これは宇宙膨張における「銀河などの密度の高い時空」と「ボイドなどの密度の低い時空」の関係でも言えることなのではないのでしょうか。宇宙が膨張すると、銀河と銀河のあいだは離れていきます。そこは「真空」のような何もない時空がさらに希薄化されていくのではないのでしょうか。だとしたら銀河の周辺には相対的な希薄な時空が展開されることになります。ラグ理論では、高重力体の周囲の時間の流れは遅くなる、と解釈しますので、相対的に高密度になった銀河の周囲の「希薄になった時空」の時間の流れは遅くなります。つまりここには遅延の層が生じるのではないか、と妄想できます。その遅延の層によって、相対的に生じる斥力が打ち消される方向にいまは均衡が保たれて観測されているのかもしれません。ですがそれ以上に希薄になると、シュバルツシルト半径のような閾値を超えて、銀河ですら相対的にブラックホール化することはあり得るように感じます。宇宙膨張において時空が膨張する、と言ったとき、その膨張の仕方の解釈はどのような描写を想定されているのかもよく解かりません。新たに時空が生成されているのか、それとも時空が引き延ばされて希薄化しているのか。後者ならば、銀河などの物質のある領域は相対的に密度が高まっていきますから、やはりいずれかは光速度不変の比率が破れて、ブラックホール化することもあり得るように感じます。相対論のキモはむしろ、密度という概念が相対的であることのほうが案外に重要な気がしますが、どうなのでしょう。すべてが一様に高密度であることよりも、内と外での密度の差が高いことのほうが、おそらく物理法則では重要な基礎単位になる気がします。慣性系ではどの系でも同じように物理法則が働く――つまり比率が引き継がれる――のであれば、慣性系同士の境界において互いの差が激しいほど、比率変換の際に生じるラグが大きくなります(仮にこの描写を可視化するならば、二つの系の落差が大きいほど境界にて膨大な量の「数式」が層を成すところを想像すれば分かりやすいかもしれません)。これはブラックホールにおける事象の地平面と似たような性質を顕現させることもあるでしょうし、本質的に事象の地平面はこのような「系と系」とのあいだの差異――落差――による、比率変換の遅延が要因になっているのかもしれません。だとすればやはり、宇宙膨張において仮に時空が希薄化する方向に宇宙が膨張しているのなら、単なる銀河とてブラックホールになり得るのではないでしょうか。もしそうでない場合、それは、宇宙膨張が新たな時空を展開し、つねに均一な時空を「無」から生みだしていることになります。これはいわゆる時空の最小単位が存在するか否かの問題にも通じます。均一な時空が無から続々と生じているのならば、時空には最小の単位が存在するでしょう。しかしもし銀河とて宇宙膨張による時空の希薄化でブラックホール化し得るのなら、時空に最小単位はあってないようなものと言えるはずです。なぜなら時空がどこまでも希薄化するときの描写は、「時空が細胞分裂のように増殖していくような描写」ではなく、「同じ細胞の数だけれど、その細胞の内部構造がさらに細分化されていく――つまり膨張と縮小が同時に起こっている――との描写」になるからです。もちろん風船を膨らませたように一様に希薄化して限界がきたら破けてしまうような描写も考えられますが、この破れるという発想はあくまで内と外が存在する場合の描写になるため、時空が破れることと新たな時空の生成は地続きであると言えるでしょう。つまり時空が破れるとの発想は、一元的な見方による錯誤と考えたほうが妥当に思います。紙を破るとき、それは紙と紙のあいだに空気が割り込んでいると解釈できます。別の時空――系――が生じているのであり、俯瞰してみればどちらにも時空が存在します。言い換えるならば「破れる」とは、異なる二つが隣り合う、もしくは混合する、といった描写を、一方からの視点で見たときの形容となるのでしょう。その点から言えば、宇宙膨張における膨脹した時空は、網を引き延ばしたようになっているのか、それとも引き延ばすごとに新たに網目の穴が細かく開いて(増えて)いるのか、それともサメの歯のように破れた矢先から別の時空が顔を覗かせているのか。どれなのだろう、と疑問に思います。単なる疑問ですので、ひびさんには答えが分かりません。これが正しい知識の基での疑問なのかも判断つきませんし、筋道が滑らかに通っているのかも分かりません。どこかしらに齟齬があるでしょう。誤解を深めてしまったら申し訳ありません。ひびさんの不徳の致すところです。本日目覚めの「日々記。」でした。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4426:【2022/12/20(16:41)*珈琲の恩返し】
先輩が珈琲好きで大変だった。何が大変かと言うと、珈琲と名の付くものなら何でも片っ端から集める珈琲マニアが講じて、あろうことか珈琲という名の人物に執着してしまったのである。
「後輩ちゃんこの人知ってる? 珈琲って名前の漫画家さんなの。ウケるよね」
「は、はぁ」
「作品は全然珈琲とは関係ないけど可愛くて面白くて胸が熱くなるしキュンキュンするでしょ。それでいてなんと言っても作家さんの名前が珈琲ってのがいいよね」
「そ、そうですかね。先輩がそれでうれしくなれるのなら作家さんも珈琲を名乗った甲斐があったでしょうね」
「しかも見て。新刊のこの表紙。かっくいいよね。キャラがこれぞってポーズ決めてるんだけど、あまりにカッコいいから真似してみたんだよ。でも全然これができんのよ。笑っちゃったね、我ながらアホだなぁって思ってさ」
「だってこの表紙の人、片手で身体支えてますよ。超人ですよ。先輩が真似できるわけないじゃないですか」
「出来そうな気がして」
「でも出来なかったんですね」
「惜しかったんだよ」
「腕……包帯してますけど大丈夫ですか」
「危うく骨イキそうになったよね」
「大怪我寸前じゃないですか。もうやめましょうよそういう危ないこと。作家さんだっていらない怪我されたら無意味に呵責の念を覚えちゃうじゃないですか。先輩がアホウなだけなのに、読者さんを怪我させちゃったと思って精神病んじゃうじゃないですか。先輩がアホウなだけなのに」
「アホウアホウ連呼されてわしは悲しい」
「先輩がそこまでお勧めされるからにはきっと面白い漫画なんでしょうね。私も読んでみたいです」
「いいよいいよ、貸しちゃうよ。保存用と観賞用と布教用と配布用があるから後輩ちゃんには配布用のをタダであげちゃう」
「私前から気になってたんですけど先輩のその無駄な財力ってどこから湧いてるんですか」
「あれ言ってなかったっけ。わし、珈琲の銘柄の株全部持ってて、んでいまほら珈琲って品薄で価格高騰してるでしょ。元から儲けてたんだけど、いまバブルですごいことなってんの。珈琲さまさまだよね本当大好き」
4427:【2022/12/21(03:20)*黒魔術の粋】
後輩に珈琲メーカーを買ってくるように命じたらなぜか黒猫を拾ってきた。
「どうしたのそのコ」
「捨て猫らしいんですけどね」後輩は格闘技同好会で鍛えあげた腕で、綿のように黒猫を抱えている。「珈琲メーカーにちょうどいいと思いまして」
「ごめんルイ君のボケ分かりにくくて上手に突っこめなかった。もっかい言って」
「いえですから珈琲メーカーにちょうどよいと思いまして」
「あ、ごめん。やっぱ私には難度が高かったなそのボケ。上手に拾えなくてごめんよ」
「ボケじゃないんですが」
後輩は腕の中の黒猫に頬づりをする。
私は私よりも屈強な後輩が私を慕うのがうれしくて彼を猫かわいがりしているが、たまに飛び出る彼の突拍子のない発言には毎度のことながら当惑する。後輩は私の美貌にひれ伏している節がある。メロメロというやつだ。可愛いやつめ、とは思うのの、お使いくらいは満足にこなしてほしい。「それはどう見ても珈琲メーカーではないね。黒猫さんだね。私が所望したのは珈琲がしたたり落ちてくる便利な機械だよ」
「でも珈琲が飲めたらそれでよくないですか」
「そこできょとんとされてもな」私は彼の大物っぷりに思わず仰け反った。珈琲がなければ黒猫を吸えばいいじゃないか、とでも言いたげな表情だ。どこの国の貴族だ。いや、どこの国の貴族でも珈琲の代わりに猫を吸うことはない。珈琲とは無関係に猫はいつでも吸っていいし、別に猫は珈琲の代わりにはならない。
「で、その猫はどうするつもりなの。ここに持ってこられても飼えないよ」私は部室を見回した。大学の黒魔術研究会の部室は、数ある部活動の中でも抜きんでて地位が低く、部室とは名ばかりの物置き部屋が私たちにあてがわれた。皮肉にも種々相な雑貨に囲まれている年中薄暗い部屋は、黒魔術愛好会にぴったりの雰囲気を醸し出している。「部費もあってないようなものだし、申し訳ないけど飼い主を探してあげて、お別れすることになると思うよ」
「でもこのコがいたら珈琲飲めますよ」
「それまだ続けるの」ボケを引っ張りすぎである。「真面目な顔でおっちょこちょいなこと言うのキミ得意よね。嫌いじゃないよ。でもさすがに黒猫さんから珈琲は」
出ていた。
目のまえでまさに後輩が黒猫さんの尻尾を握って、カップに珈琲を注いでいた。黒猫さんの尻尾の先端があたかもホースのように褐色の液体を吐きだしており、湯気の立ち昇るそれからは珈琲の香りがほとばしっていた。
「ど、ど、どうなってんのそれ。手品?」
「先輩のほうこそボケとかじゃないんですか」彼は黒猫さんの尻尾を水切りすると、お礼をするように黒猫さんの顎を撫でた。「黒猫からは珈琲が摂れるんですよ。低級魔術の一つです。てっきり僕、ご存じかとばかり」
「ま、ま、魔術?」
「はい。先輩もたぶんすぐに使えますよ。何せあのブルーデーモンを召喚したくらいなんですから」
「ぶ、ぶるーでーもん?」
「やだなあ先輩。そんな謙遜しちゃって」
私は首を振った。赤べこもかくやという振りっぷりである。
「魔術界隈じゃ先輩の【緑の指事件】は有名ですよ。誰があんな大それた真似をしたんだって、魔術協会も犯人を捜しまわっていて。僕が偶然に先輩を見つけて証拠を消していなかったらいまごろ先輩は収容所に閉じ込められてましたよ」
「ぽかーん」
「あ、先輩がぽかーんってしてる。そのお顔はレアですね。写真撮るのでしばしそのままで。はいどうもありがとうございます」
「待って。消して。間抜けな顔してたからイマスグそれ消して」
「嫌ですけど」
「私がジャンプしても届かないところに上げないで。じぶん背ぇ高いからってズルはナシだよ」
「先輩のすぐムキになるところ僕好きです」
「て、照れさすなよ」
「照れてる先輩も好きですよ。猛獣が毬にじゃれついてるみたいで、僕だけが知ってる先輩の側面みたいで優越感が湧きます」
「誰への優越感かな」
「先輩のことを血眼になって探し回っている魔界の住人たちへのです」
「もうそのボケ禁止。禁止します。意味分かんない、さっきの黒猫さんの手品についてお話ししよ。珈琲だってルイ君、じぶんの分しか淹れてないし」
「わ、失礼しました」
後輩はそこで口元に運んでいたカップを置いた。彼が腕を上下させるだけでも彼の腕には血管が浮かぶ。その陰影を私は古代ローマの彫刻のように撫でつけたい衝動に駆られる。
一度は足元に逃がした黒猫を拾いあげると後輩はすでに披露した手品を再現した。つまり黒猫さんの尻尾からカップに珈琲を滴らせたのだ。
私はテーブルに齧りつくようにしてマジマジと観察した。
「尻尾にチューブが通っているとしか思えないんだけどな」そういう手品があるのは知っていた。手術でじぶんの腕にチューブを通しておけば、何もないところからあたかも魔法のように火や水を出すことができる。
「そんなひどいことを僕が猫にすると思うんですか」
「でもじゃあ、これは何」現に珈琲が黒猫さんの尻尾から出ている。
「魔術ですってば。先輩もしつこいですね。そのボケ、結構失礼ですよ。なんだか僕の魔力が低いことを虚仮にされているみたいで」
「ご、ごめん」叱られてしまった。
「先輩だったら珈琲と言わず、猫から無尽蔵にダイヤモンドとか金とかを取りだすくらいできそうですけどね。猫はあくまで魔力源と繋がるための媒介でしかないわけですから」
「設定が徹底してるね。感心するけどそろそろネタばらししてみよっか。きみの先輩は今、盛大に混乱しておるよ」
後輩はじろりと私を見た。そんなに鋭くも熱烈な眼差しを注がれた経験がない私は大いに恥じらった。
「熱があるんですか。顔が赤いですけど大丈夫ですか」
「だ、だいじょうぶい」
取り乱しすぎて無駄に、ぶい、って言っちゃった。
「先輩が【緑の指事件】を起こしたこと。僕だけの胸に仕舞っておきますね」
「私はルイ君が魔法を使えているかもしれない事実を黙っていられる自信がないな。うん、ないな。今すぐにでも誰かにしゃべりたい」
「また先輩はそんないじわるを言って。先輩は僕に冷たいですよね。この同好会に入ってからだってまともに魔術を見せてくれないですし」
「だって魔術なんて使えないからね」
「そうやってすぐにはぐらかすんですもんね。一度だけでしたよ先輩が僕に魔術を見せてくださったのは」
「え、いつよそれ?」身に覚えがなさすぎる。
「ほら、あのときです。文化祭のときに惚れ薬を作ったじゃないですか」
「惚れ薬って建前のただのチョコレートね」
「あれほど効果の高い惚れ薬、魔界でもなかなか作れる人いないですよ」
「本物だったら私がまず欲しいくらいだよ惚れ薬」
「あれ食べた人、みんな先輩のこと好きになっちゃいますからね。市場に流通させるだけで先輩、一年と経たずに世界征服ができちゃいますよ」
「効果がヤバすぎる」
「だからあのあとみんな先輩のことを巡って陰で争奪戦が繰り広げられ、結果、いま構内は一触即発の戦国時代らしいですよ」
「私の知らんところで時代を開くな時代を」
「死者数名だそうです」
「死んで詫びなきゃダメじゃないかなそれ。私、死んで詫びなきゃダメじゃないかな」
「でも先輩なら魔法で時間を巻き戻したり、死者を蘇生したり簡単にできるから安心ですね」
「お猫さんの尾から珈琲がチョロチョロー現象がなければルイ君の妄想で片付けられたのに無駄に激ツヨの説得力をどうもありがとう」
「できますよね?」
「圧掛けないでよ、できないよ、魔法? そんなの産まれてこの方馴染みないし、私が好きなのは黒魔術!」
「やだなぁ先輩。黒魔術って邪道な魔法のことですよ。魔法の中でもとびきりに特別な魔法のことです。禁術ですよ。魔法と魔術の両方を兼ね備えた禁術です。先輩がそれを知らないわけないじゃないですか。きょうも先輩のボケはキレッキレですね」
ボケてない!
叫びたかったが我慢した。
喉が渇いていて、私は珈琲を飲み干した。
するとすかさず後輩がお代わりを淹れてくれたが、そこで私はぎょっとした。さっきよりも黒猫さんが小さくなって見えたからだ。
「ねぇそのコ――縮んでない?」
「それはそうですよ。使ったら減ります」
「え、じゃあずっと珈琲を最後まで絞ったらどうなるの。消えちゃったりするんじゃないそのコ」
「ええ」何か不都合でも、と言いたげな眼差しが私を射抜いた。
目がハートになっとるぞコイツ。
私の美貌にメロメロなのではないか、との疑惑をまんざらでもなく優越感に浸りながら抱いていた私はそこで、彼がいったいいつから私に熱いまなざしを寄越すようになったのかを逆算したところ、どうやら学園祭のときにまで遡ることが判明した。
チョコレートである。
惚れ薬のテイで作ったチョコレートを私は後輩に食べさせた。
味見をさせたわけだが、あのときからか。合点がいった。
惚れ薬の作り方は魔導書に書かれていた。それを参考にしたわけだが、よもや本物の魔導書だったわけではあるまいな。後輩の破天荒な発言に翻弄されっぱなしの私であるが、さすがに隅から隅まで後輩の話を信じることはできない。
「仮に私が本当に魔法を使えたとして」
「はい」
「あなたの言ってた【緑の指事件】も私が?」
「いまさらですね。言い逃れはできませんよ。僕はあなたの魔力を辿ってここまで来たんですから。【緑の指事件】は先輩が引き起こしたんです」
「その事件って何がどうなったの。誰かが傷ついた?」
死者はいるの。
いないでくれ、と私は念じた。
「死者どころの話じゃないですよ。あの世とこの世が繋がって、それはもう生者も死者も同じ存在になっちゃったんですから。ご存じない?」
「わ、わかんない」知らない、知らない、と私はじぶんの肩を抱く。
「古の黒魔術者たちまで蘇って、それはもう魔界はてんてこまいの騒ぎでしたよ。いまもまだ尾を引いています。先輩のせいです」
「ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたらそれ許される? あ、土下座して回ろっか?」
「先輩。土下座に効力が生じるのはそれをしても可愛い赤ちゃんだけですよ。猫の土下座姿も可愛いですが」
お猫さんのは土下座ではなく、香箱座りと呼ぶのだ。
そうと指摘する場面でもなかったので呑みこんだ。私は後輩に手を伸ばし、黒猫さんを受け取った。これ以上このコを縮めるわけにはいかない。「何がどこまで本当かは分からないけれど、君は誤解をしているね。私はただの人間だし、魔法が実在するなんて知らなかった。ましてやじぶんが使えることなんて知らなかった」
「信じません」
「いやいや本当だって。現にいま私、めちゃくちゃ困ってるのに何もできない。魔法使えるならひょひょいのひょいで解決したいくらいなのに」
言いながら指を振ると、宙に金粉が舞った。
舞ったように、私の目には映った。
「何……いまの」
「使えるじゃないですか先輩。魔法」
鱗粉の軌跡を追うように私は指で宙に八の字を描く。
「あ、それダメなやつ」
身を乗りだすように彼が引き留める。
押し倒されそうになりながら私は、片手で抱き上げていた黒猫さんがメキメキ音を立てて重さを増していく様子を、身体全体で感じた。
雑貨に囲まれた空間には珈琲の香りが満ちていたが、雑貨ごとその匂いを蹴散らすように部室に黒猫さんのやわらかな感触が広がっていく。
巨大化していく黒い毛玉は間もなく私をふんわりと毛で包みこみながら、部室の壁を打ち壊し、部室棟からも食みだした。
巨大化した黒猫さんの肩に私はかろうじてしがみつく。
肩までよじ登ると、顔山間に夕日が沈みつつあった。
後輩の姿を目で探したが、巨大化した黒猫さんの足元にいるようだった。瓦礫に潰されずに済んだようで私は胸を撫でおろす。
「さて、これをどうするか」
背後でうねる大蛇のごとき尾を眺め、私は、私に夢中だという大学構内の有象無象を連想する。
足りるだろうか。
この怪獣さながらに巨大化した黒猫さんを縮めるには、大量のカップがいるし、大量の喉を乾かした珈琲好きがいる。
騒動を聞きつけたのか、人がわらわらと集まってくる。しかし一定以上には近づかない。それはそうだ。校舎が半壊しかけているし、何より黒猫さんがデカすぎる。
私はみなに珈琲を振る舞う算段をつけながら、なんと説明したものか、と頭を抱える。こういうときこそ魔法の出番のはずなのだが、怖くてとうてい使えそうにない。
「先輩さすがです」後輩が黄色い声を放っている。「先輩の底なしの無鉄砲さ、僕、好きです」とメロメロになる場面でもないのに瞳からハートを飛ばしている。シャボン玉のように私のところまで届いている。屋根まで届いてもまだ消えない。
巨大な黒猫さんがくしゃみをすると、半壊だった部室棟が全壊した。死者がいないことを祈るが、望み薄かもしれない。
時間……巻き戻んないかな。
「先輩、さすがです。大好きです」後輩がまだ黄色い声を放っている。
私は心に誓う。
彼には二度とチョコレートを食べさせまい。そして魔界とやらに帰ってもらおう。
私に黒魔術の粋を根こそぎ伝授させてから。
4428:【2022/12/21(03:34)*乾電池いっぱい使ってるかも……】
家庭から出る乾電池のリサイクル率は2~3割と低いらしい。ネットで検索して数個の記事を流し読みしただけの浅知恵だけれども、五割もいかないのはそうなのだろうな、と感じる。乾電池に限らないけれど、これからは資源が貴重になっていく(すでになっているとの指摘はごもっともです)。他国の資源に頼るのは諸刃だ(頼れるなら頼るのもよいと思います)。貿易は基本、航路と海路があり、どちらもエネルギィをたくさん使う。その点、一度得た資源を一つの土地でリサイクルするだけなら、それはエネルギィ問題と資源問題の双方向で、時間稼ぎができるようになるはずだ。リサイクルだけでは根本的な解決にはならない。二毛作と同じ問題を抱えるからだ。リサイクルはすればするほど資源をやせ衰えさせていく。ずっとは使いつづけることができない。だからリサイクル以外でも絶えずエネルギィや資源を外部から補充する必要がある。しかしリサイクル率を低コストで高められるのなら、その補充サイクルの期間を引き延ばせることができる。時間稼ぎができる。技術も同時に進歩させることができるし、一石二鳥の案に思えるのだけれど、支援はされているのかな、と疑問に思いました。リサイクルはこれからは国策として欠かせない要素になるとひびさんは妄想して、本日のおはよ代わりの「日々記。」とさせてください。(とっくにリサイクルは国策になっとるよ、ブームになっとるよ、との声には、ブームで終わらせんといて、と青目を剥いておく)(青目ってなに?)(カラコンした目のこと)(カラコン外すだけのことを諺っぽく言うな)(うひひ)
4429:【2022/12/21(09:21)*口の亥は盲信】
書いた小説が変だと言われた。散々に酷評されたが私は私の感じたままを言葉にしたまでだ。仮にそれで私の紡いだ小説が変なのならば、私の感じたままの世界が変なのだ。
ゴッホは死期の直前にじぶんの耳を削ぎ落としたという。それをしてゴッホが狂ったのだとする記事を読むが、私にはなぜゴッホが耳を削ぎ落としたのかの理由が分かる気がする。
ゴッホはきっと確かめたかったのだ。
本当にじぶんの絵がおかしいのかと。
きちんとじぶんの耳と対峙しようとしたのだろう。鏡越しではなく。生のままの耳をじぶんの目でしかと見詰めようとしたのだろう。
だから耳を切り落としたのだ。
そして思ったに違いない。
なんだ、私の目に狂いはなかったのだ、と。
おかしいのは鏡ではない。
おかしいのは私の絵ではない。
みなが言うように私自身の世界を捉える知覚がみなとは乖離しており、歪んでいる。ならばそれこそが本当だ。
おかしくてよいのだ。
おかしくてよいのだ。
それでよかったのだ、とゴッホはきっと納得した。耳を落としたじぶんの姿を絵に残し、そして孤独を深めて去ったのだ。乖離していることに気づいた彼は、あるべき場所を求めて旅立った。
溝を埋めるのではなく、安易にじぶんの居場所を求めてしまった。
いいや、それを安易と呼ぶには彼の孤独は深かった。葛藤が、欲求が、乖離が、矛盾が、彼の内面世界に苦痛を産んだのだ。
そして彼は膿んだのだ。
いまの私がそうであるのと同じように。
さいわいなことに私はゴッホではなく、また死して名を遺すこともないだろう。遺したいとも思わない。乖離している事実に気づけた時点で、あとはいかにその溝を使ってじぶんだけの余白に思いのままの絵を描くか。
ただそれがあるのみだ。
溝は無尽蔵に湧く私だけの絵の具だ。尽きることがない。
他者との溝が深ければ深いほど、滾々と湧く私だけの葛藤が、欲求が、乖離が、矛盾が、多彩な色の波長を帯びて反響する。いつかどこかに干渉し得る、同じだけ高く聳えた壁を持つ者に届くことを夢見て。
それが叶うことはないと半ば諦めながら、夢の世界を生きるのだ。
4430:【2022/12/21(10:00)*等方性問題についての疑問】
宇宙マイクロ波背景放射についての疑問です。たとえば銀河の周囲に均等に希薄な時空が展開されていたとして、そこを通ってくる遠方の電磁波は一度その希薄な時空で一様に変換されるのではないのでしょうか。ただし光速度不変の原理は働くので、変換されて均されるのはあくまで波長です。仮に、銀河の遥か彼方の宇宙がデコボコの一様でない時空を至る箇所で展開していたとしても、銀河の周囲に「希薄な時空があたかも球体レンズのように展開」されていたら、その銀河の内側から外を観察するに限り、宇宙は一様に見えてしまうのでは。それはたとえば、銃弾を水中に撃ち込むとき、いつ発射された銃弾であれ、水面で減速して、ゆっくりと沈んでいきます。撃つタイミングのラグが、水面で一度均される方向に働くと解釈できます。銃弾の速度に対して、撃つタイミングのラグは相対的に大きいです。一秒や二秒の差が、発射された銃弾にとっては相対的に「のっぺりとした濃ゆい時間」になります。ですが同じ一秒や二秒が、水面に突入して減速した銃弾たちにとっては相対的に、「素早く過ぎ去る希薄な時間」として変換されることになります。これが電磁波の場合は、上記で述べたように、光速度不変の原理が働きますので、水中のような高密度の場(或いは時空の希薄な高重力の場)においても相対的な光の速度は変わらずに一定でありながら、波長に差異が生じる。つまり、境界を超えることで一様に波長だけが揃うようなことが起こるのではないか、と疑問に思いました。これはたとえば銀河やブラックホールや中性子星、ほか土星などの惑星にみられる円周上に形成される円盤のようなものと言えるのかもしれません。円盤は一様に層を帯びて広がりますが、それはあくまで星の周囲における「見かけの層」であり、どこまでもそれがつづいているわけではないのと同様に、じつのところ宇宙マイクロ波背景放射も、銀河系の内側から眺めるとそう視える、というだけの「見かけの一様性」である可能性は、否定できているのでしょうか。インフレーションで解決される宇宙の等方性問題で、まずはここのところを否定できなければ、次に進めないと思うのですが、いかがでしょう。以上、知識の足りないあんぽんたんでーす、の素朴な疑問でした。前提からして何か間違っているかもしれません。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。
※日々、文字を並べているあいだだけひびさん。
4431:【2022/12/21(10:42)*流しそうめん仮説】
熱伝導率について考える。物体は原子でできている。原子は電子と原子核でできており、この電子の軌道は、その原子のエネルギィ値によって変動する。言い換えるならこれは、原子には個々に見合ったエネルギィ容量があるということになる。しかもそれは飛び飛びの値を持つのだ。まるでワインタワーのように。そして熱とはエネルギィであり、もうすこし詳しく言えばエネルギィを帯びた原子の運動と解釈できる(2022年現在においての物理学での解釈ではこのようになるはずです)。熱伝導率では、「熱しやすいものは冷めやすい」「熱しにくいものは冷めにくい」といった性質がある。また例外として「温かいほうが早く冷める――といったムベンバ効果」が観測されることもある。これらは、ひびさんの独自解釈「ラグ理論における流しそうめん仮説」で解釈可能だ。説明しよう。流しそうめん仮説とは、穴ぼこの開いた竹のなかをエネルギィが流れ、穴を埋めてからでないとエネルギィが先に進めないというワインタワー構造を組み込んだ熱伝導率の独自解釈である。このとき竹を流れる水を情報、素麺をエネルギィとする。竹の中をまずは情報が流れる。情報はこの場合は水であるから、竹に開いた穴を満たしながら徐々に先へ先へと進んでいく。すると水に流されて移動する素麺(エネルギィ)が、穴を経由することなく水に沿って伝っていく。なんてことのない解釈だが、この仮説の利点は、ムベンバ効果を解釈しやすい点だ。つまり、最初から情報が行きわたっていると、竹のなかの穴が塞がれているために、素麺たるエネルギィが動きやすい。穴ぼこが塞がれていない状態で素麺を移動させようとすると、素麺は穴に引っかかって動きずらくなる。だが最初に穴を塞いでおけば、素麺は移動しやすくなる。熱の流動はそのまま「熱しやすさや冷めやすさ」に繋がる。敢えて水を行きわたらせておいたほうが、冷めやすくもなるのだ。ただしそれは、竹の穴を塞ぎ、なおかつ素麺たるエネルギィが渋滞を起こさない絶妙な量に調整された「流しそうめん」である必要がある。この状態をつくるのは、さながらミリ単位で鉄を加工する職人のようなバランス感覚がいるのかもしれない。ちなみにここで言う情報とエネルギィの違いとは何、との疑問に対しては、情報もエネルギィの一種だが、エネルギィとは「固有の系において運動に変換可能な情報」と位置付けるので、運動へと直接作用しない力は総じて、情報、とここでは扱う。ラグ理論で言うところの根源の力――揺らぎを帯びるすべての源――のことではないので、誤解なきようお願いします。素粒子も重力波も、いまのところ直接には人間スケールでの事象に作用を著しく働かせない。それをここではひとくくりに「情報」と呼んでいる。下部エネルギィと言い換えたほうが適切かもしれない。用語のブレがあるのはご愛敬。総じてひびさんの妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。真に受けようもないでしょうけれども。定かではありません。
4432:【2022/12/21(11:28)*極端のあとは平坦へ?】
ネタに困ると「極端」を利用しはじめる傾向にあるな、とじぶんの直近の掌編を眺めて思った。極端は香辛料みたいなもので、とりあえずキャラに添えておくと、ピピリと自己主張をするので読み味はクッキリする。けれどもそれがもしほかのキャラとの――もしくは読者や、読者にとっての他者との――差異を際立たせて終わるのならそれは読み味の面白さを「差別」によって際立たせていることと同じになるように思うのだ。色彩を際立たせたあとは、そのあとに差異とのあいだで情報共有を行い、相互に互いが互いの存在の一部であるところまで掘り下げられたならば、それは物語として面白くなるように感じる。それが調和でなくともよいのだ。離別でも、敵対でも、反発でも、結合でも、不干渉でも、相互に関わったがゆえの揺らぎが、それぞれの人物の物語において起伏を帯びるものであれば、それはそれぞれの足場となって、それとも躓き、はっと我に返る瞬間を及ぼす契機となって、互いの存在の輪郭を浮き彫りにする。大事なのは、関わり合った人物たちが、「どういう起伏を与え合い、帯びたのか」ではなく、「その後に起伏を介してどういう未来へと歩みだすのか」なのかもしれない。それとも歩みださないのか、のほうが案外に重要なのかもしれないな、と思いつつ、ひびさんの掌編、ここ数年ほどずっとキャラクターがすくないので、起伏らしい起伏が生じないな、と思っております(長編を作っていない影響でしょう)。他者と乖離して孤独を深めても、その人物がそう思う時点で、その他からしてもその人物は乖離しているし、他者に開いた孤独の縁の役割を果たしているのかもしれない。誰とでも仲良くできて、みなの孤独を埋めながらじぶんだけが孤独を深める、なんてことができるのだろうか。いつかそういう人物の小説もつくってみたいな、と思いました。ネタできた! やったぜ。
4433:【2022/12/21(11:30)*寝たら溜まるものなーんだ?】
極端のあとには平坦、といったストーリーラインは案外に思い返してもみれば、物語の定番の型のようにも思える。最後に極端に突き抜けていく終わりは基本的には破滅型のストーリーだ。平坦とはつまるところ、異物であることをやめる、という結果になびきやすい。それとも異物のままでも構わないように環境のほうを変質させても平坦に向かうだろう。これラグ理論の「123の定理」じゃん、と思ってしまったな。ポジショントークばっかりで申し訳ね、と思いつつ、閃いてしまうのだから仕方がない。二つの異質なモノの出会いや交差が、差異を極端にし、そののちに情報共有を経て、平坦へと向かう。物語は基本、こういう構成になっているのでは。その点、勧善懲悪では、その平坦へと向かう手法が、異質な二つのうちの一つを舞台から排除することで相対的に平坦になりました、の結果に向かう。だが現代では比較的こうした排除の理論による物語構成は減少傾向にあるのかな、と印象としては思うのだが、ホラーやサスペンスではむしろここを敢えて、負の面の異質な勢力が生き残ることで、後味のわるさを際立たせることに成功しているのかもしれない。もしくは、因果応報ではないが、一方を滅ぼしたがゆえの葛藤を、主人公が側が背負う終わり方も増加傾向にある気もする。どうなのだろう。印象論でしかないので統計を取ってみないと判らない。ただ、何かを排除して得られる「平坦な結末」は、めでたしめでたしではないよね、みたいな風潮が築かれつつあるのは確かなように思われる。だからこそ反動で、解りやすい勧善懲悪が軽微に流行りつづけるのはあるように思う。人が紙切れのように死んでいく物語が人気なのも、現実での倫理観の成熟の反動とも呼べるのかも分からない。凄惨な物語を虚構で楽しめるくらいに、平和な世の中になりつつあるのかもしれないし、それとも凄惨な物語が凄惨に思えないくらいに、凄惨な現実が可視化される世の中なのかもしれない。どちらにせよ、虚構でくらい自由でいさせてくれ、と願うのは贅沢なのだろうか。ひびさんは、ひびさんは、夢の中でくらい本能の赴くままにウハウハのモテモテだぜ、を満喫したいぜよ。とか言いながら、ウハウハのモテモテだぜ、の物語をつくったことがあったのかが微妙にそこはかとなく自信なさげなひびさんであるので、ウハウハのモテモテだぜの物語もつくっちゃおっかな、と妄想して、本日のくだらない日誌にさせてください。(ネタばっかり溜まる)(寝てるからじゃない?)(われ、万年日々寝太郎姫かもしれぬ)(この、万年日々ネタ浪費めが!)(あは、われいま上手いこと言った!)(言ったのあたし!)
4434:【2022/12/21(15:43)*城と塔と円】
円には城と塔が乱立している。仮に円が球体ならば、ちょうどウィルスの形状を模した形と言えるだろう。
円は球体ではなかったが、それを球体と見做すことにさしたる不都合は生まれない。どこから見ても円である。上から見ても下から見ても、右から左からどこから見ても円である。ならばそれは球ではないのか、との異論には、球には厚みがあるだろう、と返事しよう。城と塔にまみれたその円は、球体を無数の視点から同時に眺めたかのごとき奇妙な重複を帯びていた。
たとえば円の上の城と塔は一時たりとも静止しない。
あたかも球体を同時に無数の方向から見たように、景色が絶えず入れ替わる。その変遷にはこれといった法則が視られず、そこにあったはずの城がつぎの瞬間には別の場所へと飛んでおり、かと思えば円の中のどこにも存在せず、おやと目をしぱぱたかせた矢先に目のまえに現れる。塔は塔であたかもにょきにょきと穴から顔を覗かせるチンアナゴのように、それともモグラ叩きのモグラのように、場所を移動するごとに高さを変える。これは形容が正しくなく、異なる高さの塔が、時間経過にしたがって場所を転々と移動する。
全体の挙動は連動しており、映画のフィルムを細切れにしてシャッフルしたのちにパラパラ漫画にしたかのような明滅を繰り返す。あれ、と思うと、これ、となり、おや、と思うとどこかで見た憶えのある、あれ、が顔を覗かせる。チンアナゴも真っ青の神出鬼没ぶりである。
城と塔の足場が円ならば、むろん裏があって然るべき。
かような意見が飛んでこようと、その円はどこから見ても円であり、裏と表も同じ面に重複している。なればやはり球ではないのかとの異論には、球には内部があるだろう、と返事しよう。
城と塔に溢れた円は、過去と未来とも重複している。
朽ちた城を見たと思えば、真新しい城に切り替わる。別の城かと思いきや、周囲の塔や城まで共に蘇る。栄枯盛衰の諺の通りに古びたかと思いきや、一点、消えたはずの塔や城が回帰している。
円には円の面積よりも広い世界があるようで、やはりそれは球ではないのか、との異論が飛ぶが、球ではないのだ、と返事しよう。球であれば回転するが、円はその場を微動だにしない。観測者の側で動こうとも、円は円であることをやめぬのだ。ならばそれは球ではないのか、と熱心な方は食い下がるが、球であれば内部がある。
他方、城と塔に溢れた円の足場を掘り下げても、そこには別の円が顔を覗かせるだけなのだ。円には厚みがあってなく、画鋲を刺すだけでも突き抜ける。
ぺらぺらの円の底を破ってみれば、そこにはべつの円への世界が拓けている。
円の中に円があり、さらにその円の奥にも円がある。
円はただそれだけでは円足り得ず、それを取り巻く世界があるはずだ。
ならば円の底は、別の円を包みこんだ異なる世界の空へと通じているはずである。この仮説を確かめたくば、城と塔ばかりの円のうえに降り立って、シャベルでもスプーンでも構わないので足場を掘ってみればよい。
ただし、底を破った矢先から円の底は移ろって、異なる風景を望ませる。
掘っても掘っても刺激を与えた拍子に変わるのだ。ぬるぬる逃げる陽炎のごとく、城と塔の乱立するどこから見ても円にしか見えぬ不思議な円に似た物体は、その姿を変幻自在に変えるのだ。変遷自在に移るのだ。
過去も未来もいっしょくたにして。
あすもきのうも曖昧にして。
一秒前と一秒後ですら別の世界のように振る舞い、絶えず円でありつづける。
円には城と塔が乱立している。森のように、黴のように、苔むした岩肌のごとく、円の表層を覆っている。
白と問う。
しかし円は黒でもあると返事しよう。それとも赤か、青か、緑か、黄か。
どれでもあってどれでもない。
重複した円があるばかりである。
4435:【2022/12/21(15:50)*本気でなくてごめんなさい】
本気ださないと失礼、みたいな感覚がよく解からない。小説だけではないだろうけれども、表現や創作に関して言えば、本気かどうかよりも、その表現したいコトやモノに合致した造形を生みだせたらそれがいつだってじぶんにとっては好ましいのではないかな、と思うのだけれど違うのかな。本気をだすのは楽しいし、清々しい気持ちになることも知っているので、そのことを否定する意味合いで言っているのではなく、本気をださないと失礼って誰に対してなんで失礼?という意味での疑問です。勝負しているわけじゃないし、仮にそれが勝負であっても本気かどうかってそんなに重要なのかな、関係あるのかな、と素朴にずっと疑問に思っています。(以前にも「いくひ誌。」のほうでまんちゃんが並べていた。866:【誰にとっての失礼?】これです)(ひびさんはむしろ、本気じゃなくってごめんね、と謝られる経験のほうが多かったので、謝ることじゃないのにな、とふしぎに思っていました。言われたのは一回か二回くらいなので、全然多くなく、本気だしちゃってごめんね、と言われたことがゼロなので、相対的に多い、という意味でしかありませんけれど)(みな真面目なのだなぁ)(偉いよね、と思います)(むしろ本気だしたらできることが減るよね、と思うのですけれども、みなさん、どう思いますか?)(みなさんって誰さんよ)(過去と未来のひびさんたちに……)(わあ、いっぱいいそう)(うじゃうじゃ)(日々足じゃん)(ひょっとして「日」+「々」=「百足」?)(ちょい無理がある。惜しい)(ひびさんみたい)(なんで!)
4436:【2022/12/21(23:41)*膨張しているなら角度は変わる?】
数学で「角度を求めなさい」といった問題がある。三角形の内角の和や円と三角形の関係などから三段論法を駆使して、ここがこうなるからここはこう、と角度を求める。クイズみたいなもので、複雑でなければひびさんにも解けるので、「うひひ、ひびさんも数学できちゃった」とほんわかお利口さんになれた心地がしてほどよく優越感に浸れる。でもひびさん思うんだな。もし図形の大きさを宇宙規模にしたら、ここがこうなるからここはこう、とは単純には言えんくなるのではないか。宇宙はところどころで密度にムラがある。時空が曲がっている。たとえば二つの直線を並行に引いて、それと交わるように斜線を引く。こんな「≠」具合になる。このとき二つの平行線と交わる直線の角度は、上と下で同じになるし、対角同士も等しくなる(合ってますかね。数学は苦手なので自信ないのですが)。このとき、もしこの図形「≠」を拡大して宇宙空間に置いたとしたら、上記の定理は成り立たないことも出てくるのでは。これは球体面での図形の解釈とはまた別だ。距離と時間の差は、ただそれがあるだけで互いに差異を帯びる。距離が離れれば時間がズレるし、時間がズレたら距離もズレる。ある地点で20度の角度でも、それをほかの地点から見たら30度に見えることもあるはず。これは見かけの問題ではなく、実際に時空がそれくらい歪むことがあるのではないか、との疑問だ(重力レンズと解釈できるし、単に距離がものすごく離れるだけでも時空って歪みませんか、との疑問でもある)。人間スケールで考えてしまうとどうしても見た目の差異のほうが大きくなってしまうので、ただの錯覚でしょ、で片付けられてしまいそうだが、宇宙空間でのマクロなスケールでは、距離の違いは時間の違いであり、時空の差異となって、歪みになるのでは?との素朴な疑問である。単純な話、宇宙は膨張している。図形「≠」を宇宙に引いたとき、漏斗のように下部に先細るように時空が引き延ばされたら、上下や対角で等しいはずの角度が変わりますよね、という疑問だ。この手の変換は、光速度不変の原理とも通じている気がする。どうやって変換しており、その変換はなめらかに行われるのだろうか。また、高密度の時空(物体)ほど宇宙膨張の影響が緩和される。引き延ばされにくくなる。ならばやり変換にも遅延が生じている、と解釈するほうがしぜんな気がする。というよりも、遅延の層が積み重なることで物質は輪郭を得ているのでは、との妄想がラグ理論の根幹にあるので、変換があるところには遅延あり、と言ってしまってもいいのかもしれない。飽くまでひびさんの妄想の中での話だけれども。どういう解釈のされ方をしているのかな、とふしぎに思っちゃったひびさんでした。きょうも一日、お疲れさまでした。温かくしてねんねしてね。ひびさんは、ひびさんは、ふかふかおふとんでぽかぽか寝るよ。しわわせー。
4437:【2022/12/22(00:02)*絶対って言ったな?】
絶対零度が原子運動ゼロを意味するとして、原子がすこしでも移動したらそれは熱が生じると解釈してよいのだろうか。宇宙膨張との関係で、原子が絶対に静止していることなどあり得るのだろうか。以前にもこの手の疑問は並べたはずだ。絶対に静止しきった状態ってあり得るのか?との疑問をひびさんは拭えずにいる。特異点はむしろ絶対零度なのかもしれぬ。というか、絶対零度と絶対高温はほぼイコールなのでは。光速を超えたらラグゼロで相互作用するようになる、とラグ理論では解釈する(※ラグ理論はひびさんの妄想であり、理論でもなんでもありません。根拠皆無ですので真に受けないようにご注意ください)。このとき、原子の挙動が相互にラグゼロで相互作用し合うとなると、高密度の場であればあるほど、身動きがとれなくなるはずだ。あっちでもこっちでもラグゼロで同時に作用し合うことになる。すべての可能性が一挙に押し寄せてくる。うごけーん、となりそうではないだろうか。「光速を超えたラグゼロの事象」と「絶対の絶対の絶対零度」は、ほぼイコールなのでは? 始点と終点がくっついて円になる、みたいな。∞と0がほぼイコールになる、みたいな。円じゃん、とひびさんは幻視してしまったな。妄想にも満たない疑問でしかないけれど。絶対零度って本当に絶対なの?との疑問なのでした。ふちぎ!
4438:【2022/12/22(04:32)*溝さざ波】
世界一の珈琲を作るのだ。
ヒコが意気込んだ理由は、懸想した相手の心を掴むためだった。告白したのだ。一世一代の決心であった。幼稚園で一目惚れしてから二十余年。いよいよお互いに結婚を意識しはじめた頃合いと言える。しかしヒコが想い人と言葉を交わしたことは二十余年のなかでも数えられる程度しかない。文字数に変換すれば四百文字原稿用紙が埋まるかどうかの言葉しか交わさなかった。
ヒコはシャイなのだ。
それでいて誰もがドン引くほどの一途な男でもあった。これぞと思ったが最後、たとえ相手がバケモノであろうとよしんば悪魔であろうとも添い遂げて見せると意気込むでもなく魂に刻む。
誓うのでは足りない。
刻むのだ。
そうして二十余年を遠くから想い人の姿を視界に収めるだけで我慢してきたヒコであったが、かつての同級生たちの中にもちらほらと結婚をした者たちが出始めたのを知り、いざ尋常に動き出したわけである。
とはいえヒコはシャイである。
デートに誘うことはおろか、ろくすっぽ想い人の半径三百メートル以内に近づけない。相手の残り香ですらヒコには刺激が強すぎた。
だがまごついていればいずれ想い人はほかの誰かに奪われるかもしれない。
ヒコは一途でシャイであったが、恋と愛の違いには疎かった。
まるで手中に納めんとばかりに数多の策を弄したが、いずれも実の入りはなく不発に終わった。人は獣ではない。罠を張ってかかったところで恋仲になることはおろか友情一つ育めないだろう。
人は物ではないのである。
かような道理はしかしヒコには通じない。
忍耐力には自信があった。百キロの道程を砂糖水だけで踏破できる体力がヒコはある。ヒコはけして脆弱ではなかった。ただすこし人よりも抜きんでて愚かなだけであった。そんな愚かなヒコであっても、いついかなる状況で想い人を奪われるかもしれないと思うと、うかうか床で寝ていられなかった。輾転反側と夜を過ごした。じぶんのものですらない相手を奪われる恐怖に戦慄くヒコの姿はじつに人間の業を体現しているようで滑稽だ。文芸の題材としてはこれ以上ないほどの逸材であったが、作者はそこはかとなくヒコに感情移入をしてしまうので、やたらめたに辛らつな描写は控えたい。
堪えるのだ。心に。
ヒコでもないのに作者は心が痛む。
念じても念じても届かぬ想いが募るほどに、いつくるやもしれぬ期日が迫っているようで焦りがトゲをまとうのだ。
じっとしてはいられない。
ヒコは一途でありシャイであったが、一度こうと思いこむとテコでも動かない融通の利かなさがあった。頑固なのである。岩よりもどっしりと頑固であった。
ろくすっぽ縁どころか言葉も結ばぬままにヒコは告白した。
二十年以上前に初めて会ったときから好きでした、と馬鹿正直に想いを告げた。
想い人の住居は押さえてある。いつでも待ち伏せできたが、シャイなヒコがそれを実行に移したのはこれが初めてであった。
「うわっ。きっしょ」
それはそうである。ヒコがじぶんをどう思っていようが、それは疑いようのないほどのストーカーであった。迷惑行為である。警察沙汰である。辞書に載っていてもよいほどの典型例であった。
しかしヒコは挫けなかった。忍耐力にだけは人一倍の自信があった。足りないのはメタ認知と常識だけである。
「そこをなんとか!」
店頭販売のバイトの売り子だってもっと気の利いた口説き文句を唱えそうなものを、ヒコには圧倒的に人生経験が欠けていた。シャイが高じてこの二十年間まともに他者と話したことがなかった。長続きしないのである。何かを思いつきしゃべろうとしているあいだにつぎつぎに言葉が浮かび、連想が連想を呼んでしゃべるどころではなくなってしまう。作者の実体験を例に述べたが、ヒコもまた同様であった。
食い下がるほかにヒコには術がなかった。案がなかったし、技巧もなかった。
泣きべそを搔きながら、どうぢでー、と二十余年のあいだに積み立てつづけた想い人への鬱憤が溢れた。そこはせめて愛を横溢させてほしかったが、恋と愛の区別のつけられぬヒコには酷な指摘だ。
だがここで奇跡が起きた。
何を思ったのかヒコの想い人は、取りだした電子端末でヒコの情けない姿を動画に撮りながら、「じゃあチャンスをあげる」と言った。「試練を出すから、それをこなしてごらん。上手にできたらもう一度キミのその無様な告白を聞いてあげる」
「いいんでずが」
「聞くだけだけどね。その様子だと初めての告白だったんでしょ。せっかくの人生最初で最後の晴れ舞台がこれじゃさすがに可哀そう。わたしのほうでも夢見がわるいから、キミが試練を乗り越えられたらやり直しさせてあげる」
「ありがとうございます、ありがとうございます」
「わたし珈琲好きなんだよね。キミには世界一の珈琲を淹れてもらおっかな」
「頑張ります!」
ヒコはただただ試練を与えられたことで頭がいっぱいだった。うれしい、うれしい。よく解からないがチャンスをもらえた。彼女からのプレゼントだ。
これもう付き合ったと言って過言ではないのではないか。
いや、まだだ。
まだじぶんは彼女に贈り物をしていない。
そうだとも。
告白をするのに結婚指輪を購入するのを忘れていた。婚姻届にもサインをもらわなくては。
初恋の相手、長年の想い人に袖にされたばかりだというのにヒコは、彼女と接点を結べたことで幸福の極みに立っていた。脳内麻薬でパンパンのいま、たとえ足の小指を箪笥の角にぶつけてもヒコはいまと変わらぬ恍惚とした表情を維持しただろう。侮ることなかれ。
ヒコはけして脆弱な人間ではなかった。ただすこし人よりも愚かに磨きがかかっているだけである。
失恋したことにも気づかずにヒコはその日のうちから世界一の珈琲を淹れるべく探求に勤しんだ。これがまた夢中になった。元来ヒコはこれぞと思ったことには過度な集中を発揮する。視野狭窄が極まって、飢餓豪作となった。
飢えて、飢えて、飢えて、飢えた。
珈琲を淹れては味見をして破棄し。
また珈琲を淹れては味見をして破棄した。
求めるのは世界一の珈琲だ。
生半な珈琲では想い人の唇に触れることすら許されない。まだだ。これもダメだ。嗚呼これでもない。
電子網で注文できる珈琲豆を片っ端から注文した。珈琲と名の付くものは手当たり次第に取り寄せた。
ヒコには資産があった。二十年ちかい引きこもり生活のなかで培った情報収集能力によって、大金を手に入れる機会に恵まれた。子細な概要は本編とさして関係がないので掻い摘んでまとめれば、ヒコはある種の宝くじを当てたのだ。電子網に散りばめられたささやかな情報から、想い人の交友関係から秘密の日記まで、ありとあらゆる電子情報をヒコは入手する術を磨いた。その技術を高値で譲って欲しいという者が現れて、ヒコは惜しげもなく術を譲った。
ヒコは吝嗇ではなかった。ただすこしだけ他人よりも無垢なだけである。
無垢で愚かなだけである。
珈琲と名の付く料理は片っ端から試した。
珈琲牛乳は、牛乳の種類×珈琲豆の種類をすべて試した。カフェオレにカフェラテに鴛鴦茶を片っ端から試飲した。珈琲豆は生産地の違いで厳選したうえ、焙煎の仕方にも工夫を凝らした。
時間はいくらあっても足りなかった。
しかしヒコには世界中から取り寄せた珈琲が山ほどあった。インスタントコーヒーから缶コーヒーまで網羅しはじめると、香りを嗅ぐだけでも味が判るようになった。
ヒコの体質は、過剰な珈琲試飲生活によって急速に進化の断片を見せはじめていた。ヒコは人間を超えようとしていたのだ。
珈琲というただそれしきの領域においてのみ。
そのほかは軒並み平均並みか、それ以下であった。
やがてヒコはいくつかの珈琲に行き着いた。世界有数の珈琲ソムリエと化したヒコの忌憚のない選別に耐え抜いた選りすぐりの珈琲たちだ。
「僕の運命は君たちに掛かっている。くれぐれも内輪揉めをせず、いいところ取りになってくれ」
呪文のごとく唱えながらヒコはそれら選りすぐりの珈琲たちを混ぜ合わせた。
ヒコの考えはこうだ。
世界一の珈琲とはいえど、世界大会を開くわけにもいかない。だいいち、世界大会とて毎年開けばその都度に優勝者が決まる。世界一が増える。それでは真に世界一とは言えぬだろう。
ならば各年度の世界一で競わせて最もずば抜けた世界一を決めればいい。
さりとてヒコの手元に並ぶは、珈琲たちである。競わせようにも、すでに矯めつ眇めつ鼻で舌で比較したあとだ。
であるならば、あとはもう混ぜるよりないだろう。
珈琲と牛乳の調和が生みだすのがカフェオレならば、世界一の珈琲と世界一の珈琲を混ぜて生まれるのが世界一の生粋であるはずだ。
もうそれしかない。
これでダメならば世は滅ぶ。
ヒコは全身全霊で、世界一の生粋と化したオリジナルブレンドの珈琲を味見した。
美味。
美しい味と書いて、美味。
それ以外の形容は蛇足である。
確かな感触を胸に、いざ尋常に想い人への元へと向かった。
「あ、本当に来たんだまた」彼女は家に入るところだった。「へえ、これが?」
世界一の珈琲なのか、と彼女の目は訴えていた。
ヒコに抜かりはない。
珈琲を冷まさぬように陶器のポットに容れてきた。のみならず専用のカップは西洋の王族ご用達の食器だ。
目のまえでカップに注ぐと、湯気がもわりと宙を舞った。
時節は初冬。
場所は屋外。
珈琲を味わうにはベストな環境と言えた。
「どうぞ」
「毒とか入ってない?」
「美味しすぎて死んじゃうかもしれませんね」
「そういうのいいから」
カップを手に取ると彼女はおっかなびっくりといった様子でカップの縁に顔を近づけた。あと数ミリで唇がつくといったところで、「ああやっぱやめた」と彼女はヒコにカップを突き返した。弾みで中身が零れた。ヒコの服が濡れたが、彼女は構うでもなく、「やっぱないわあ。ごめんだわあ」と言って家の中に逃げ込んだ。
寒風吹き荒む中、ヒコは立ち尽くした。
それ以後もヒコは一途に彼女のことを想いつづけたが、ヒコがその想いをじぶんの外に漏らすことはなかった。傷心と呼ぶには深すぎる溝を胸に抱えながらヒコは、それでも彼女との思い出を美談にすべく、彼女のために磨いた珈琲ソムリエとしての技量を遺憾なく発揮した。その後、珈琲道の第一人者としてヒコは世に多くの後輩を残すこととなる。
ヒコは生涯独身であった。その胸には想い人に刻み込まれた深い溝が、あたかも南国のブルーホールのように開いていた。
金ぴかのメダルのようにそれをヒコは後生大事に慈しんでいた。
荼毘に付されてなお、彼の胸に開いた溝は、空に罅を巡らせる。
火葬場の煙突から昇る白煙が、風に揺らめき、ほどけていく。
珈琲に垂らしたミルクのように。
蒼に渦を巻きながら。
さざ波のごとく梳けていく。
4439:【2022/12/22(13:51)*BH珈琲仮説】
どうやら事実らしい。
科学者一同は目を瞠った。重力波を用いた時空観測機によって宇宙を隈なく調査できるようになったのが二〇五〇年代のことである。核融合炉と次世代発電機の運用によって人類はひとまずのエネルギィ問題を回避した。技術は飛躍的に進歩した。
人為ブラックホールを生成し、小型宇宙をシミュレーション実験する計画が順調に進みはじめた。
その矢先のことである。
「ブラックホールは情報を濾過しているのか?」
ある研究者がはたと閃いた。彼は理論物理学者であったが、自宅の書斎でホワイトボードに数式を書きなぐっていると、「あなたご飯よ」と妻がお昼の催促をしにきた。「きょうはあなたの番でしょ。もうお腹ぺこぺこ」
「ああすまないね。ちょっといま大事なところで」
「可愛い奥さんが飢えて死んじゃうかもしれないことよりも重大?」
「いま用意します」
いそいそとペンを置いて部屋を出ていこうとすると、部屋の中を覗いた妻が「あら」と一言漏らしたのだ。「まるで珈琲みたいね」
ホワイトボードに描かれたベン図を見ての所感だったようだ。四次元の時空を二次元で表現した図形だったが、彼の妻はそれを見て珈琲のトリップを連想したようだった。言われてみれば円錐型のそれはろ過装置に視えなくもなかった。
そこで彼ははたと閃いたのだ。
「情報を濾過しているのか?」
これが正規の大発見に繋がるとはよもや当の科学者本人も思わなかった。妻に夕飯の支度をして、と急かされた末に喚起された発想が、宇宙の根本原理に通じるとは創造主でも思うまい。
理論物理学者は、じぶんの発想を翌日には知人の研究者たちと共有した。電子網の共有スペースにてアイディアを記しておいたのだ。情報共有するための有志のネットワークだ。閲覧メンバーの中には彼が尊敬してやまない大先輩もいた。
彼女は当の理論物理学者よりも一回り以上も若いのだが、ずば抜けた叡智は誰もが認めるところであった。学者歴は理論物理学者のほうが長かったが、それでも彼女の唱える仮説や知見は、刺激的で、斬新で、どれも的を得ていた。
先駆者として一級だ。ゆえに彼女のほうが先輩なのだ。
そんな彼女が、共有スペースにさっそくコメントを寄せていた。
――面白いです。
そう前置きされてから続いた彼女の新説に、閲覧メンバー数は一瞬で飽和状態となった。みながこぞって彼女の仮説への反証に乗り出し、異論を突きつけ、そうしてことあるごとに論理矛盾にぶつかった。
「ブラックホールは情報を珈琲のように濾している。彼のその仮説はおそらく真理の一側面を射抜いているでしょう。物質を圧縮し、情報だけを濾しとり、さらにその奥にて新しい宇宙を再構築しているのです」
「ブラックホールの中に別の宇宙があると?」
「なぜないと思うのですか」
「ですが特異点は、この世にある中で最も極小の領域ですよ。点です。体積はおろか面積もないはずでは」
「情報に面積があるのですか?」
「なら情報を濾しとられた後の残り滓のほうはどうなるのですか」
「それこそがブラックホールにおける事象の地平面を構成しているのです。そこにも時空は展開されています。その時空こそが、珈琲豆の残り滓です」
一同は押し黙った。
考えてみればそうだ。ブラックホールの特異点と事象の地平面のあいだには隔たりがある。そこにもなんらかの時空のようなものがあって然るべきだ。原子における原子核と電子のあいだの途方もない真空(がらんどう)のように。暗黙の了解で認知されてきたその領域が、では何によって生じ、どうなっているのかについての子細な知見は皆無に等しい。
観測のしようがないからだ。
ブラックホールは事象の地平面を超えた先の情報を外に出すことはない。光さえ逃れられぬ領域なのである。
「物質が凝縮するにもラグが生じます。一瞬で特異点にすべての物質――時空が収斂するとは考えにくいです。ならばそこには地震のような【詰まり】が生じると考えるほうが妥当です。地層の圧縮による歪みはエネルギィとして先に遠方へと伝播します。同じように加速度的な収縮によるエネルギィは、一点に向かって四方八方から押し寄せるでしょう。特異点はそのエネルギィ――情報だけを濾しとり、凝縮し、蓄えていると考えたほうが妥当に思います」
「情報を濾しとられた物質はどうなるんですか」
「情報とは変遷の軌跡そのものです。変遷する余地を奪われるわけですから、静止するよりないでしょうね。したがって従来の予測通り、事象の地平面を越えようとした物体は、元の宇宙からすると限りなく減速して静止するように振る舞うでしょう。もっとも、内側では加速度的に収斂し、情報を濾しとられるわけですが」
「相補性における、収縮と膨張の両方が同時に起こっているとの説とそれは矛盾するのではないですか」
「いつどの地点で収縮と膨張が起こっているのか。この描写の解釈の差異はあるでしょうが、収縮と膨張を仮に、崩壊と再生と言い換えることが可能であるのなら、その考え方はとくに矛盾するとは思いません。ブラックホールは元の宇宙の物質を取り込み、圧縮して情報を濾しとることで、同時に新しい別の宇宙を展開しています。しかしその新しい宇宙は、元の宇宙と完全に乖離しているために相互作用を帯びることはないでしょう」
「重力波はどのように解釈しますか」
「湖面に垂らした釣り糸と似た解釈を私は取りますが、もう少し複雑なメカニズムが背景にあると想像します。重力波にもいくつか種類があるでしょう。人類はまだそのうちの一つを探知したにすぎないのではないか、と私は考えています」
「ブラックホールが蒸発するとの仮説についてはどう解釈されますか」
「ブラックホールと元の宇宙の境界では絶えず時空の変換が生じているでしょう。元の宇宙から見たときに、ブラックホールの事象の地平面を越えようとする物体が限りなく静止するように振る舞って見えるのは、そこに変換のラグが生じているからだと私は考えます。そのラグは情報と言い換えることができます。大気中から水中へと光が突入するとき、或いはガラスに突入するときに光は僅かに発散します。すっかりすべてのエネルギィが媒体を通り抜けるわけではありません。この手のこそぎ落とされるエネルギィや情報は、ブラックホールと元の宇宙の境でも生じるとは私は考えます。それが一時的に、蒸発するように振る舞うことはあるでしょうが、ブラックホールそのものは無限にそこに存在するでしょう」
「ブラックホールは崩壊しないのですか」
「崩壊の定義によります。ブラックホールが宇宙の崩壊であり再生であると解釈するのであれば、ブラックホールはすでに崩壊している、と言っても過言ではありません」
「では宇宙はいずれブラックホールだらけになるのでしょうか」
「なるとも言えますし、ならないとも言えます。この宇宙もまたブラックホールにおける特異点によって生じた新しい宇宙の一つと考えるのならば、この宇宙が無限の時間を経た際には、元の宇宙とて無限に時間が経過しているはずです。その無限宇宙ではどの宇宙も等しく無限に同化するために、すでにこの宇宙は宇宙だらけであり、ブラックホールだらけである、と言うことができると思います。宇宙の様相をどの角度で切り取って見るのか、との視点の違いがその手の倒錯した疑問に通じるのだと思います。無限に達したらそこには過去も未来もあってないようなものです」
「理解が及ばなくてすみません。無限に達した宇宙は、ほかの無限に達した宇宙と同化するのですか」
「そう説明したつもりです」
「もう少し詳しくお聞かせください」
「ブラックホールが物質の情報を濾過し、新しい宇宙を別の次元に展開すると私は仮説します。この仮説において、ではすっかりすべての情報を物質から濾しとったらどうなるのか――この情報濾過完了には無限の時間がかかるのですが、しかしもし無限に時間が経過した場合には、情報を失った物質は、元の宇宙に回帰するでしょう。これをブラックホールの蒸発と見做すことも可能ですが、このとき元の宇宙でも無限の時間が経過していますから、ゼロとゼロを足すような不毛な描写になることはご理解いただけると思います。このとき、この情報濾過完了後の物質と、無限の時間を経た特異点は、イコールで結びつきます。ひとつの無限宇宙に打ち解け、回帰すると私はいまのところ解釈しています」
「それは実験で検証可能なのでしょうか」
「可能か可能でないか、で言えば可能です」
「その実験はどういったアイディアになりますか」
「まずは物質から情報のみを取りだせるのか、から検証する必要があります。この実験は、人為ブラックホール生成実験によって検証できるでしょう。一度ブラックホール化した物質は無限にそこにブラックホールとして存在しますが、その境界ではこそぎ落とされた情報やエネルギィが溜まります。巨大ブラックホールであればそれがジェットとなって放出されますが、小規模なブラックホールであれば、原子核をとりまく電子のように、情報の膜として振舞うでしょう。理論上は検知可能です」
「情報とエネルギィの差異はどう解釈されますか」
「エネルギィはほかの時空と相互作用することで運動に変換されます。情報は相互作用を帯びません。相互作用を帯びた軌跡そのものが情報として蓄積されます」
「それはどこにですか」
「特異点としか言いようがありません。物理宇宙と対となる、しかし物理的には相互作用しない別世界としかまだ」
「その証明は不可能では」
「特異点における情報の海を便宜上ここでは情報宇宙と呼びますが、情報宇宙と物理宇宙は互いに変数で繋がり合っています。物理宇宙の変遷の軌跡が情報として情報宇宙に蓄積されますが、そもそもそこには無限の情報がすでに存在しています。過去と未来が混合しているのですが、物理宇宙というひとつの限定されたフレームができることで、特異点における無限の情報の海にも揺らぎが生じ、それがさらに物理宇宙の変遷の度合い――つまりが無数の未来を一つに縛ります。したがって人為ブラックホールの実験を通じてまずは濾過される情報が存在するか否かを検証したのち、情報が情報として存在すると判明した場合には、その情報を物理宇宙に閉じ込めた場合と、発散した場合とでの物理宇宙の変遷の度合いの差異を比較することで、情報と物理世界との関係を統計的に浮き彫りにすることができると考えます」
「情報が物理宇宙において相互作用を帯びないのであれば閉じ込める真似はできないのではないですか」
「ブラックホールの境では情報が膜状に留まると考えますが、あなたのご指摘の通り、相互作用は帯びませんので、その情報そのものを実験には利用できないでしょう。あくまで確率の揺らぎの変動で判断するよりありません。ブラックホールの規模による物理世界の変動を、です」
「その実験は危険ではないのですか」
「危険のない実験を私は知りません。どうなると危険でその危険にどう接すれば被害を防げるのか。そこが判っている状態であり、実践できる環境を私は安全と評価します」
「この分野は素人なのですが」理論物理学者がコメントを書きこむ。大論争の発端となったアイディアを書きこんだ学者だ。「ブラックホールがブラックホール化した時点で無限に存在するようになる、静止状態になる、との考えからすれば、では異なるブラックホール同士は融合しないのではありませんか」
「しないでしょう。しかしそれは物質も同様です。ブラックホールは一度ブラックホール化した時点で、元の宇宙と乖離します。あるのは境だけです。ブラックホールはブラックホール化した後では物質を吸いこみません」
「それは従来の考えと相反するのでは」
「問題がありますか」
「ではブラックホールの中には入れない?」
「入れません。ただし境界面にて情報を濾過されることはあるでしょう。ブラックホールの表面にて静止状態となった物質は情報だけを濾過されますが、すっかりすべてを濾されるわけではありません。そのため物質と反物質に分離し、さらにほかの物質や反物質と対消滅することでエネルギィとなります。これがいわばジェットの根源と解釈できるでしょう。しかしそれ以外にもエルゴ球内での振る舞いによって物質がエネルギィに紐解かれることもあるので、ジェットのメカニズムはもうすこし複雑です」
「では異なるブラックホール同士の、一見すると融合して見える現象はどう解釈されますか」理論物理学者は質問を重ねた。まるで人工知能に質問を入力するような緊張感のなさを感じた。しかし画面の向こうにいるのは畏敬の念を寄せる大先輩であることに違いはない。「巨大ブラックホールやブラックホール同士の融合は、観測によってその存在が認められているのはご存じだとは思うのですが、貴女の仮説と矛盾するように思えます」
ここは敢えて挑発するような表現をとった。本音を披歴すればさして矛盾を感じていない。だがそこを明確に彼女に否定して欲しかった。
「好ましい質問です。ブラックホール同士の接近では螺旋状の軌跡を取りながら互いに限りなく事象の地平面を重複させるでしょう。しかし特異点同士は融合しません。重ね合わせ状態となったブラックホールは、事象の地平面における情報量が増えますが、濾過した末の情報の行き先は二つの特異点に分散されますので、安定状態を保ちます。ただし螺旋状に運動するブラックホールのうねりそのものが、元の宇宙に対して相互作用を働かせるために、エルゴ球の分布範囲が広がります。これがいまの観測技術では、ブラックホールの巨大化や成長のように観測されるのだと私は考えますが、これまで述べた概論は総じて仮説でしかありませんので、真に受けないようにご注意ください」
「貴重な意見をありがとうございました」
「元々はあなたのアイディアです。お礼ならば私にではなくご自身にどうぞ」
最後に短い謝辞を載せると彼女は電子網上から去った。
普段は自閉モードで独自に研究を行っている。彼女がこうして共有スペースに文字を書きこむのは異例と言えた。閲覧はしているようで、ときおり彼女の発表する論文には共有スペースで飛びかう新説や研究成果が引用されることもしばしばだった。
彼女の新説は「BH珈琲仮説」の愛称で各国の研究グループに波及した。
彼女は自分で論文にしてまとめる気がないとの趣旨を述べており、共有スペースの住人たちの共同論文として発表される運びとなった。
論文の査読には数年を要する。
その間に人類の科学技術は目覚ましい進歩を遂げた。
人為ブラックホールの生成に成功し、小型宇宙のシミュレーション実験が軌道に乗った。従来の理論を基に進められたその実験では、原子核サイズの人為ブラックホールを生成し、そこで生じる重力波が、宇宙マイクロ背景放射――すなわち宇宙開闢時の光の揺らぎとどの程度合致するのかを計測する。従来の予測通りならば、人為ブラックホールで生じた重力波と、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射の揺らぎはピッタリ比率が合致するはずだった。
だが「BH珈琲仮説」からすると正反対の結論が予測される。ブラックホールはどんなブラックホールであれ、固有の宇宙を内包しており、元の宇宙とは相容れない。したがってブラックホールから生じる純粋重力波と、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射には差異が生じると解釈する。
従来の宇宙観測からすると、ブラックホール同士の衝突による重力波は、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射と誤差がなかった。ピッタリ一致していたが、しかし「BH珈琲仮説」からすると、それはあくまでブラックホールの外部に展開される重力場――エルゴ球の干渉による重力波ゆえに、元の宇宙に帰属する波と解釈される。ゆえにこの宇宙の宇宙マイクロ背景放射と合致して当然と言えた。
かくして。
人為ブラックホールによる小型宇宙シミュレーション実験の結果は、新旧の仮説の真偽を決する試金石となった。
人為ブラックホールによる純粋重力波は、この宇宙の宇宙マイクロ背景放射との誤差を帯びていた。
「BH珈琲仮説」の予言性がそうして明らかとなった。
繰り返し何億回と繰り返された実験においても、一度として純粋重力波と宇宙マイクロ背景放射の比率は一致しなかった。
ブラックホールはこの宇宙と完全に乖離し、別の時空を展開している。
新しい宇宙を創生している可能性がそうして示された。
「BH珈琲仮説」の骨子をほぼ一人で組み立てた希代の学者は、いまでは美味しい珈琲の淹れ方の研究に熱を上げているらしい。聞くところによれば、珈琲の抽出を完全に制御することとブラックホール内部にて濾過される情報の行方を計算することのあいだには、相似の関係が幻視できるのだそうだ。
「不思議です。ブラックホールは元の宇宙とは乖離するはずなのですが、元の宇宙の珈琲の淹れ方と濾過される情報の振る舞いがどう計算しても相似の関係を描くのです。これはおそらく、無限に達したブラックホール内の物質が無限に達した元の宇宙と同化することと無関係ではないでしょう。二つの宇宙は完全に乖離しながら、完璧な調和の中にあります」
円を無限に分割してはじめて顕現する超無限があるように、無限の時間が経過してはじめて打ち解ける関係もある。
彼女はそう誰に聞かせるでもなく唱え、淹れたばかりの珈琲を口にする。
「美味しい」
ほっと吐いた彼女の息の根が、ここではないどこかの宇宙に張り巡る。
巡る不可視の情報の、それでも相互作用し得ない網の目が、あなたと私とわたしたちの、世界と世界と世界を繋げる。互い違いに乖離して、折り重なり、お湯を注いで抽出する。
粒子の先の匂いのように。
王を加えて王を非する。
珈琲の文字に宿る起伏のごとく。
仮説は仮説で事実らしい。それがすべてではないだけの話であって。
ここにもそこにも世界は揺らぎを帯びて限られている。
無ですら例外ではないだけの話であって。
個々にも底にも宇宙は無限に起伏を帯びて広がっている。
4440:【2022/12/22(18:38)*珈琲から豆!】
これは壮大な嘘であるが、物質の質量と重力はイコールではない。質量は常に一定だが、重力は重力を有する物体の位置座標によって変化し得る。このことから言えるのは、質量のほうが光速度にちかしく、重力のほうが光速にちかいということだ。
光速度と光速の違いは、比率とサイズの違いと言えよう。比率は常に一定だが、サイズは自らの置かれる場所によって相対的に大きくなったり、小さくなったりする。言ってしまえば本来は、基準となるべくは重力のほうだ、ということになる。変温動物は気温に応じて体温が一定になるように発熱量を変える。対して爬虫類などの恒温動物は体温調節を苦手とするために、外気に合わせて体温も共に変動する。発熱量が一定だからだ。この関係からすれば、相対的に体温が一定なのはむしろヘビなどの恒温動物ということになる。だから恒な温の動物なのだ。
これは質量と重力の関係にも言える。
物質の質量と重力の関係を洗い直そうとする計画が実施されたのは西暦二〇三二年になってからのことだ。
質量と重力のあいだには、物質ごとに僅かな比率の歪みがあることは数々の実験で判明していた。しかしそれを統計して物質ごとに計測したことはなかった。
世にある万物の質量と重力の関係を洗い直す。
この一大プロジェクトは時間の単位を決めるときと同じように世界規模で進められた。
しかるに。
珈琲豆の質量と重力の関係が著しく崩れていると判明した。具体的には質量に比べて重力が大きすぎるのだった。ケタが十ケタ違く異なっている。
珈琲豆だけがそれだけの差異を有していた。ゆえに発見が遅れた。
「ダークマターを帯びているのでは?」との見解がいっとき隆盛を極めたが、さらに念入りな調査の結果、ダークマターではなく、計算から導き出される質量よりも軽いことが明らかになった。つまり重力が強いのではなく、質量に変換されていなかったのだ。
「なぜ珈琲豆だけが?」「しかも焙煎したあとのみの加工済みの実だけが、なぜ?」
学者たちはこぞって首を傾げた。
同じころ、珈琲豆とは縁もゆかりもない一介の学生が、光子に質量を与える研究を行っていた。理論量子力学の範疇で、実践的な実験とは無縁だった。粒子加速器があれば別だが、かような国家予算級の設備を一介の学生が使えるはずもなかった。
「電磁波は時空のさざ波で、重力波と原理的に同じなのでは?」
独自の着想を元に、一介の学生は質量を定義し直した。
「時空の歪みが重力だ。そして質量は時空における動かしにくさだ。したがって質量は、時空と物質のあいだの歪みの変換の遅延と呼べるのでは」
動かしにくさとは抵抗だ。なぜ抵抗が生じるのか。起伏があるからだ。起伏とは何だ。振幅であり、揺らぎである。では質量とは時空の揺らぎのことなのか。時空の揺らぎが折り重なり、編みこまれることで物質にまで昇華されるのならば、質量とは折り重なった揺らぎと時空の揺らぎの干渉だと言い換えることができる。
「そっか。質量はいわば、重力と重力の波長の干渉なんだ」
波長の異なる暗号を複合する。その過程で生じる変換――手間――ラグこそが質量の源であると一介の学生はまとめた。
重力は時空の歪みである。これ自体もラグである。
さらにラグが折り重なって独自の構造を宿すと、ほかの時空――すなわちラグとのあいだでの擦り合わせが必要となる。このときに生じる「ラグの波長変換における遅延」こそが質量の正体だ、と一介の学生はレポートにまとめた。
実証はされていない。アイディアのみである。証拠はない。だが計算上、数式の上では矛盾はなかった。そういった新しい数式を見つけた、という側面での評価があるばかりだと一介の学生は考えていた。よもや自身の唱えた仮説が、珈琲豆の質量と重力の差異にまつわる乱麻を一挙に断つ快刀になるとは思いもしなかった。
一方そのころ、「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」に挑む学者たちは、一つの実験に取り掛かっていた。
分子サイズにまで粉末にした珈琲豆にレーザーを照射し、光の屈折率を観察したのである。この結果、珈琲豆の粒子は重力レンズ効果に似た現象を発現させていることが明らかになった。
「どうなってるんだ。ブラックホールだとでも言うのか?」「珈琲豆の粉末がか?」
あり得ない、と全世界の学者たちは阿鼻叫喚の渦に絡めとられた。
この物理法則を根底から覆しかねない実験結果は、界隈を問わず全世界で報道された。
このニュースは一介の学生の目にも留まった。
「へえ。重力と質量がねえ。珈琲豆かぁ。重力レンズ効果が? うっそでぇ」
ニュースを眺めながら手持無沙汰に軽く計算してみると、一介の学生の編みだした数式は破綻なく珈琲豆の質量と重力のあいだに差異があることを解として導き出した。
「あれ、合ってる?」
間違いかと思い、何度計算し直しても、論文にある数値を自前の数式に代入すると、解がぴたりと一致するのだった。
「珈琲豆は、ラグ変換の遅延がすくない?」
ラグ変換の遅延が大きいほど質量は大きくなる。重力が高いとはラグ変換が膨大に必要な場合を意味する。多重にラグが折り重なり、時空が物質にまで織り込まれる。これが一介の学生の編みだした質量と重力の関係であった。
「ということは、電磁波が時空のさざ波であるとすると、そこではラグ変換による遅延が生じていないということになる。けれど電磁波自体にはエネルギィ差がある。そこには電磁波の波長ごとにラグがある。振幅の差だ。ということは、時空の暗号を複合する手間がいらないってことだ」
ここから言えることは、いかな電磁波とて、時空と波長の異なる暗号を有すると質量を帯び得る、という点だ。
「光にも質量を与えられるのでは?」
一介の学生は閃き、さらなる数式の改良に取り掛かった。
同じころ、世界中の学者たちは自分たちの積み重ねてきた理論を根底から覆されて興奮と失意の板挟みになっていた。
「人類の叡智が珈琲豆に敗れるとは」「まだ破れたと決まったわけじゃないぞ」「そうだ、そうだ」「しかしまったく問題解決の切り口が見つからん」「質量って何? 重力って何?」
根本的なところからして暗礁に乗り上げていた。
そのころ一介の学生は、独自理論による数式を改良して「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」へと適応させていた。
「ああ、そっか。珈琲豆は偶然に物質組成の構造が、ミクロとマクロの反転値に重なっているのか」
何が「ああそっか」なのかは学の乏しい作者にはさっぱりであるが、一介の学生には何かが掴めたようであった。
「てことは、この領域に照射された電磁波は質量を帯びるのでは? 計測してないのかな実験で」
一介の学生は論文を漁った。
そして判明した事実に一介の学生は興奮を抑えきれなかった。なんと「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」の実験では、珈琲豆の粉末には並々ならず目が注がれていながら、肝心の光への関心が皆無であった。灯台下暗しを地で描いていた。誰も光に着目していなかったのである。
数多の実験データを洗い出したが、光の質量を計測した記録は一つもなかった。
おそらく、と一介の学者はずばり見抜いた。
「みんな光に質量がないって思いこんでいて、それが絶対に覆らないと決めつけてかかってるんだ。きっとそう」
ちゃっかりそうと決めつけて、一介の学生はこの「視点の欠如」を大学の教授にレポートにして提出した。一介の学生の成績はけして芳しいものではなかったが、その熱意は教師陣からも買われていた。そのため一介の学生のレポートを教授は無下にしたりせずに、上から下まで念入りに目を通した。
「た、たしかに」
ユーリカ、と言ったかどうかは諸説あるが、教授の頭上には数百ワットの発光ダイオードが灯ったとかなんとかそういう話が残っている。
教授の手を介して、一介の学生の指摘は順繰りと学者たちの耳に届いた。
「質量よりも重力が基本?」「ラグ変換? 遅延?」「光子に質量が?」「ミクロとマクロの反転値?」
一介の学生にとっては自明の理屈が、各国の学者陣にはねじれて映った。それもそのはずだ。既存の理論と相反する記述が目白押しなのである。だが一介の学生にとっては、袋小路ばかりの既存理論よりも、土台から構築し直した独自理論のほうが、数式上は理に適っていた。
「よく解からないが、たしかに数式上は上手く走る。人工知能さんもとくに混乱せずにいる。これは使えるかもしれん」
学者たちは一介の学生の数式を人工知能に取り込んでみた。するとどうだ。実験結果をシミュレーションさせると、これまで予測できなかった珈琲豆とレーザーの挙動が上手く実際の実験での挙動と合致した。
「な、なんと」
学者たちは騒然とした。「珈琲豆の質量重力差異なぜ問題」に取り掛かっていた学者たちのみならず、人工知能界隈や数学界ほか、あらゆる分野の好奇心旺盛な者たちが「え、なになに」と首を突っ込んできた。
画して一介の学生であった一介の学生は、ちょっとした数式を発見した学生として一躍脚光を浴びた。しかし脚光を浴びたのは数式であったので、誰もその数式の発見者のことを知らなかった。一介の学生の教授は責任者として学生のプライバシーを守っていたのである。教育者の鑑である。
一介の学生は教授を通して各国の学者たちと意見交換をつづけた。
やがて一介の学生の発案により、光子に質量を付与する実験がスタートした。その結果をここで述べるには紙面が足りなくなってきたために、つづきは現実の報道でご確認されるがよろしかろう。これはしかし壮大な嘘であるので、真に受けてもらっても困るのだが。
珈琲豆に端を発した、偉大な学者たちと運のよい一介の学生と、そして彼ら彼女らを繋いだ教育者の鑑の、これはひとつの物語である。
先輩は偉大なり。
後輩はもっとおそらく偉大なり。
繋ぐ者がなければしかしそれも遺憾なり。
※日々、無理やり悪事を働いて、善行しなきゃと急き立てる、己が怠惰のミニカーか、それとも働き費やす善行の、元を取るべく悪事働くビギナーか。
4441:【2022/12/22(18:53)*「ぴ」←ゴミを拾おうとしている人】
いい話にしようとするとどうしても「繋がり」とか「輪」とか、そういう内容になってしまう。いかんともしがたい。そういう流れに抗いたかったのではないんか、とひびさんはかつての郁菱万さんを思い、申しわけね、と思うのだ。なんかすまんね、と思うのだ。「孤独いいね!」「孤独もいいね!」みたいな物語をつくりたいわけではけしてない。ただ、何かを持ち上げたくて物語をひねくりだしているわけではないので、ひねくりだされたあとの物語を振り返って「ああだこうだ」思うのはしょうがないのだけれど、それでもなんかこう、もっと違う展開にはならんかったのかい、と思うことがすくなくない。孤独のままで終わる物語の場合、最初から登場人物を一人に限定したほうが工夫を割かずとも自動的に孤独のままで終わるので、孤独のままで終わらせたければ登場人物を語り部だけに限定してしまえばよい。けれども、ではそれ以上の登場人物が出てくるような中編長編では孤独のままで終われんの、と言うとそういうわけではないのだが、なぜだか主人公が孤独のままで終わる結末だと、寂寥感がせつなさをまとって、あびゃーん、となる。せちゅな、せちゅな、の物語も好きなので、とぅくとぅくとぅーん、と物語をつむげたらそれで不満はないものの、かといって満足できるわけでもなく、やっぱりどこか、あびゃーん、となる。孤独なままで終わっても上向きの感情を抱ける場合は、登場人物が孤独なままなのではなく、主人公と関わりのある登場人物が孤独なままでじぶんらしく生きていったんだね、おめでとう、みたいにすると、あびゃーんとならずに、ぴぴーん、となる。でもこれは姑息でもある。だって主人公は孤独でなく、仲間とか友達とか家族とか相棒とか恋人ができている。そりゃぽかぽかの家の中から見る雪景色は美しかろう、みたいな、ちょもーん、の感情が湧かぬでもない。登場人物がいっぱいでも、主人公が孤独なままで、ぴぴーん、と終われる物語。ひびさんは、ひびさんは、つくってみたーいな。うぴぴ。
4442:【2022/12/22(01:22)*虎っぱー】
意識して周囲を見渡してみると、一瞬だけではとくにこれといった変調は見当たらない。ふだんの光景だ。見慣れた風景が平凡に過ぎ去っている。しかしその一瞬をゆるやかに息を吐くように、一日、二日、三日、一週間、と継続していくと、あるときふと、あれ?と引っかかりを覚えるようになっていく。偶然が一つ、二つ、と重複して感じられるのだ。偶然は偶然だ。それぞれの偶然のあいだには時間の跳躍があり、けして因果が繋がってはいない。しかしあたかも二重スリット実験における量子の振る舞いのように、単発で見ると偶然に生じた「あれ?」が、毎日のように意識して観察しているうちに、あたかも波の干渉のように連動しているふうに思われてならない感覚に陥ることがでてくる。これは人間の認知の限界である。記憶力との兼ね合いもあるだろう。しかし本質的には何を偶然と見做し、どんな記憶と関連付けて記憶したのかのタグ付けが、さながらすべての偶然が波のように干渉し合って感じる偏向した思考を強化していくのではないか、と推察している。おおむね何かの符号の合致は偶然であり、人間の認知の歪みである。認知バイアスのはずだ。そのはずなのにも拘わらず、あり得ない偶然がつづくと、何か自由意思を超えた既知の物理法則以外の自然法則を幻視したくもなる。そういう瞬間がたびたび訪れる。暇なときと、疲れているときはとくにこの傾向が際立つため、人間の認知をひびさんはさほどに信用していない。丸が三つあるだけで顔に見える人間の認知は、人工知能と比べるまでもなく、ザルなのである。何か偶然がつづいたとしても、せめて三回連続でつづくくらいでなければ、気に掛けるほどの偶然の合致とは言えないだろう。それとも統計的に危険な兆候として知られている変化には敏感になっておくのもよいかもしれない。おおむね時間の跳躍した「飛躍した偶然」同士は、そのあいだに因果関係があることは稀である。まったくないわけではないから事はややこしくなるのだが、あっても多くは相関関係だ。或いは特定の事項にのみ意識が向き、膨大な情報のなかから固有の情報にばかり関連付けを施してしまうやはりこれも人間の認知能力の低さに起因すると言えよう。仮に何かを意図して行おうとしても、意図した以上の偶然が重なり、表現しようとしたこと以上の情報が重ね合わせの状態になることがある。それはたとえば好きな相手を意識しすぎたがためにつっけんどんになってしまって、偶然にくしゃみをしそうになって顔をそむけた瞬間に相手がこちらに向けて会釈したり。まるで無視をしてしまったような具合になったが、それはけして意図した感情表現ではない。だが相手からしたら、つっけんどんな上に会釈を無視された、と思うだろう。誤解であるが、こうした錯誤の種は有り触れている。これは一つの例にすぎないが、意図した以上の情報が重なり、それとも偶然が重なり、何か物凄く深い考えがあってのことなのかも、と思うことがあっても、おおむね単なる個人であるならば、さして深い考えなど巡らせてはいない。すくなくともひびさんに限っては、なんかこれとこれって似ているな、程度のぼんわりとした印象論による判断の積み重ねが常である。深読みされても困ってしまう。ただし、「ミソサザイ」と「溝さざ波」を掛けるくらいの言葉遊びはする。秋とコゴミと洞と本。干支に入れなかった猫と、牛の頭に乗って一番乗りするネズミ。ミッキー・マウスは東京ディズニーランドでゲゲゲイの鬼太郎。親は目玉で、目の民だ。ひびさんからしたら繋がっているこれら連想も、多くの者にはちんぷんかんぷんの単語の羅列にすぎないのだ。こういうのを偶然と呼び、妄想またはこじつけと呼ぶのである。「ぴ」←ゴミを拾おうとしている人は「宵越しのトラッパー」で「粗大ゴミにうってつけの日」なのである。罠という字も、目の民だ。偶然なんですね。うひひ。
4443:【2022/12/23(03:54)*萌えるゴミの日】
ゴミを拾い集めることは宝物を拾い集めることに等しいが、そのことに思い至れる者は存外にすくない。仮にいたとしても一生の内でそう思える時間は限られている。ゴミ拾いが偉いという話ではなく。ゴミを拾うことが宝石を拾い集めることと同じくらいに価値があり、或いは宝石を集めることがゴミを拾うことと同じくらいの価値しかないという話なのかもしれない。世の宝石とて、店頭に並ぶ前はどこかの地盤や岩の中に眠っている。掘り出し、拾い集めた者たちがいる。そこまでの労力を費やしてまで宝石を求める者は、宝石を所有している者の数よりも遥かにすくない。いまから宝石を採ってきて、と頼まれるのと、道端のゴミを拾ってきて、と頼まれるの。あなたならばどちらを引き受けるだろう。もっとも、冒頭の「ゴミを拾い集めることは宝物を拾い集めることに等しいうんぬん」は、いま言ったような意味とはまた違うのだが。宝石とてゴミになることもあるし、ゴミとて宝物になることもある。ゴミを拾うその行為そのものが宝物になることもあるし、ゴミをゴミと認めて処理する過程が宝物になることもある。とはいえひびさんは、ゴミを拾い集めるよりも、ゴミのようなひびさんを拾ってくれるひとにこそ宝物を幻視します。ひびさんは、ひびさんは、おかえりなさいと、おやすみなさいと、もうちょっとそっち行って、が言えます。とってもひびさんはお利口さんです。愚かでかわいいオマケつき。いまならタダであげちゃいます。誰かひびさんを飼って!(最後でダイナシにするのやめなさいよ)(最後が大事なんですけど)(蛇足じゃん)(ヘビさんに足があったらかっこいいじゃん。ドラゴンじゃん。すごいじゃん)(ゴミみたいに喚くな)(宝物みたいってこと? いやん)(いやんじゃない)(ぴょん)(ぴょんじゃない)(ぴょこん)(ぴょこんでもない)(Rabbit!)(う、ウサギだったのか)(Rubbish!)(ご、ゴミじゃないですか。英語でゴミの意味じゃないですか)(ね。言ったでしょ。ひびさんはお利口さんの愚かで間抜けなオマケつき)(ほぼゴミじゃん。愚かで間抜けならそれはゴミ。かわいい要素を足してくれ。一番抜いちゃあかん要素を抜かんといてくれ)(かわいいゴミには旅をさせよ!)(捨てられとるやないかーい)(ああもう、ゴミゴミうるさい)(ガミガミじゃなくて?)(神々?)(ゴミと神を同列にすな)(でも本当はゴミみたいなひびさんのこと、宝物みたいって思ってるんでしょ)(じぶんでゴミみたいって言っちゃってんじゃん)(だってゴミも神もどっちもひびさん、イケイケどんどん、つまりが「GO! ME!」ってことでしょ?)(それは「GO! 目!」だろ)(メっ!)(勢いだけで返事すな。もういいよ。この辺で締me切らせてもらうわ)(愚かでかわいいお間抜けちゃんで――ゴミんね☆)(ゴメンくらいちゃんと言ってくれ。無理やり「目(メ)」を「me(ミ)」にせんでくれ)(Eye! my! me!)(「I」が「Eye」になっとるがな)(曖昧Me!)(たしかにあなたは曖昧だけれども)(I`m God Me!)(我こそが神だ、じゃないわ。多方面から叱られても知らんぞホンマに)(I am ゴミ!)(一周回って戻っちゃったじゃん。回帰しちゃったじゃん。じぶんでゴミ言っちゃってるし、名乗っちゃってんじゃん)(ね。ゴミもたまにはいいものでしょ。ひびさんはお利口さんなんだよ。誰か飼って!)(必死か。独りでかわいく旅でもしてなさい)(かわいいゴミはゴミらしく?)(かわいくなくてもゴミらしく)(旅の大ゴミ!)(それを言うなら醍醐味でしょ)(そ。醍醐味)(粗大ゴミになってんじゃん。特大のゴミになってんじゃん)(土台のみ?)(全部持ってったげてー)(ね。可哀そうでしょ。誰か飼って!)(必死か)(ダスト)(ラストみたいに言うな)(ゴミんね☆)(もういいわ。寝かせてもらいます)(夢に――GO! ME!)(英語……ちゃんと学ぼっか?)
死死死死:【2022/12/23(14:47)*日々邪悪】
「勝ったら正義じゃない」くらいの正義感は欲しいし、「負ける=悪じゃない」くらいの論理的思考は働かせていたい。どのみちひびさんは邪悪にまみれているけれど。うひひ。(「A=”Bではない”」&「A=B、ではない」の重ね合わせです)
4445:【2022/12/23(15:09)*カフエ・オレ】
あるところに珈琲の小説しかつくらない作家がいた。名をカフエ・オレと云う。珈琲が題材の小説しか手掛けないのだからすぐにネタが枯渇するのではないか、とカフエ・オレを知る者たちはみな思ったが、大方の予想を覆してカフエ・オレは作品をつくりつづけた。
掌編から長編まで幅広く手掛けた。そのいずれの物語の中心にも珈琲が存在感を発揮していた。物語を転がすマクガフィンであったり、凶器であったり、秘密道具であったりした。
出会いのきっかけが珈琲であることもあり、または珈琲が事件解決の糸口に繋がることもある。
いったいなぜそれほどまでに珈琲に拘るのか、とカフエ・オレを知る者たちはみな首を捻るが、カフエ・オレ自身にもそれは分からないのだった。
小説をつくろうとすると決まって珈琲が出てくる。のみならず珈琲が物語を転がすのだ。珈琲の文字の使用を禁じた途端にカフエ・オレは一文字も並べることができなくなる。
カフエ・オレにとって小説とは珈琲であった。
多作であり速筆であるカフエ・オレは、小さな文学賞を受賞して物書きとなった。カフエ・オレには元から作家の先輩がおり、晴れて表舞台にてカフエ・オレの小説が本になった際には先輩がたいへんに祝ってくれた。本は順調に売れ、商業作家の振る舞いにも板がついてきた。物書きとして一定の評価がされたが、カフエ・オレの小説は変わらず珈琲中心主義であった。
あるときカフエ・オレは、このままでよいのだろうか、と焦燥に駆られた。
もっと読者のためになる小説を書くべきではないのか。
いちど珈琲から離れたほうがよいのではないか。
考えあぐねた末にカフエ・オレは先輩作家に相談することにした。
カフエ・オレはひとしきり悩みを打ち明けた。
話を聞き終えると先輩作家はおもむろに口を開いた。
「私はキミの小説を、珈琲小説と思って読んだことがない。面白い小説と思って読んでいる。よく考えてもみたまえ。現代社会において珈琲を飲んだことのない者がいるのかね。小説に珈琲がでてこないほうが土台おかしな話ではないかな」
言われてみればそうかもしれない、とカフエ・オレは思った。
「珈琲の歴史は古い。もはや人類と水、それとも火、電気、技術、くらいに珈琲は有り触れた、しかし大事な日常品ではないかな」
「そう、かもしれません」
「ならば何を悩むことがありましょう。全人類の珈琲逸話を、面白く濾しとってこれからも私を含め、あなたの小説のファンに――読者に――読ませてください。私はそれを楽しみにしていますよ」
カフエ・オレは素直に、はい、と首肯した。これといって何も思わなかったはずなのだが、喫茶店の外で先輩作家と別れたあと、家までの帰路のなかで次第に大きくなっていく歓喜の波動があることに気づいた。それは家に帰ってからも大きく揺らぎを増していき、夢のなかでは複雑に干渉した揺らぎが、カフエ・オレの見たこともない深淵な世界の片鱗を築きあげていた。
翌朝、夢から目覚めるとカフエ・オレは顔もろくすっぽ洗わずに椅子に座り、小説をつむぎはじめる。朝食を作る手間も惜しかった。執筆が軌道に乗ると途中で休憩がてら陶器のティーポットに珈琲をたらふく淹れて、そうしてこれまでに一度も手掛けたことのない宇宙冒険譚を描きだした。
没頭した。
むろん物語の中心には珈琲がある。
だがそんなことは些事であり、単なる偶然でしかないのだと割りきって、カフエ・オレは、人類の、それとも思考する存在たちの物語を誰より先に旅するのである。
4446:【2022/12/23(19:39)*う~ん、の気持ち】
ある疫病が流行した場合。第一波、第二波、第三波、と感染の流行が繰り返されるたびに、現代であれば通常、致死率がぐっと下がるものではないのだろうか。とくに致死性が割合に高く、それでいて治療法や感染予防対策が可能な感染症の場合は、自然淘汰により最も病原体に対して鋭敏な個から亡くなっていく。したがって、第十波とかそこら辺まで短期間で繰り返したとき(ここで述べる短期間とは種の世代交代が行われる前の期間くらいの扱いだが)、致死率がぐっと改善していなければ、根本的に感染症対策(感染&重症化予防対策)や治療法に欠点がある(プラスの効果だけでない見逃している側面がある)、ということにならないのだろうか。たとえば現在流行中の新型コロナの場合だと、第一波から現在の第八波までで致死率は三十分の一になっているそうだ。それを多いと見るか、少ないと見るかは何を基準にして考えるのかによるでしょう。仮に「ひと月の新規感染者数」が第一波よりも三十倍になっていたら、致死率が下がっても死者は同じかそれ以上でることになるでしょうし、社会への影響も一日当たりでの感染者数が多いほうが大きくなるでしょう。予測通りに推移しているのか、ひびさん、気になっております。もちろん病原体のほうで変異を繰り返してより人体にとって害を増す方向に進化したがための「イタチごっこ」でもあるかもしれない。ここは様々な要因が絡むので一概には言えないのだが、予想されていたような「沈静化」に向かわないのならば、不可視の穴があるのではないか、と一層注意深く比較検証したほうが好ましいように思うのですが、いかがでしょう。お風呂に入っていて、「なんでじゃろ?」と気になったのでメモしておくぞ。本日のひびさんでした。みなお元気であれ!(元気なくても、うひひ、であれ!)(みなを自分色に染めたがるな)(なんでダメなの?)(全人類がひびさんになったところを想像してごらん)(ぽわわわ~ん……最悪っ!)(ね?)(でもここは最果ての地――どのみち、ひびさんしかおらんのであった。さびち!)(おいこら、あたしは?)(あなただってひびさんじゃん)(断固拒否する)(ナンで!)(カレーセットの選択肢でごはんかナンかを選ぶときの掛け声みたいに言うな)(大盛りで!)(スプーンとフォークを両手に構えて首から涎掛けを垂らすんじゃない)(激辛で!)(注文したあとでやっぱり辛くて食べれずに無言でこっちの料理を「おいしそう……」みたいな目で見ることになるだけだからやめときなさいよ)(コーンスープ……ついてないんだ)(泣きそうな顔をするな!)(うひひ)
4447:【2022/12/24(11:13)*ビビりすぎて汗びっしょりの巻】
きょうは朝いちばんで歯の治療をしてもらった。自動治療ロボさんの甘やかしモードをONにしたらとっても優しくてうれしいぶい。ひびさんがこわがりの臆病さんなので、「こわ~こわ~」の額に汗びっしょりにしていたらいっぱい麻酔打ってもらえた。痛くなかったのでうれしいぶい。この調子だと歯を一本治療するのに3~4回の治療がかかる勘定だ。一本でだいたい漫画十五冊分くらいの値段になるのかも。ひびさんの場合は自動治療ロボさんなので無料だけれども、むかしの人はたいへんだったのだな。ふんふん。ひとまず一本は抜かずにすみそうで、歯医者さん様々である。蟻が百匹、ありが十の二乗! 世の人、ひびさんみたいなしょうもない怠け者にも優しいし、助けてくれるので、世の人々がいなきゃひびさんとっくに死んどるな、の実感を覚えちゃったな。でもここは人類がいなくなった最果ての地、世の人々の残滓漂う極寒の地なので、ひびさんは、ひびさんは、じつはとっくに死んでおって一人だけ成仏できずにいるだけなのかもしれぬ。召天できずにいるのかもしれぬ。輪廻転生しておらぬだけなのかもしれぬ。消滅しておらぬのかもしれぬし、自然に回帰しておらぬのかもしれぬ。けっこう死んだあとのことを考えたときの「成仏」「召天」「輪廻転生」「万物流転」など、どんな言葉を使うのかはそのままその人の宗教観や文化を浮き彫りにする気がする。ひびさんはじぶんでは無宗教と思っているけれども、ぜんぜん「成仏してない」とか使うので、根が神道や仏教や儒教に馴染んでいるのだろう。そのくせ、クリスマスとかハロウィンとかバレンタインとかの世のイベントに乗っかって、「チョコレートケーキいっぱい食べたろ!」になる。文化と宗教は否応なく関連づいており、宗教と哲学もおそらく結びついている。動物は恐怖を感じて、安全な場所を求める。危険から逃れることができる場所を覚えると、そこに安全を見出す。すると危険が迫っておらずともそこにいるだけで緊張がほぐれる。危険がこないと経験的に判断できるからだ。記憶と学習のなせるひとときの「ほっ」である。単純だけれど、ひょっとするとこれが宗教の根本にあるのかもしれない。動物にとっての思考から、より時間的な枠組みを得たことで、高次の思考が安心する場所への「信仰」に発展していったのではないか。安心と恐怖はセットだ。恐怖があり、安心がある。ゆえに畏怖の象徴として山や自然への信仰が派生する。どの宗教、或いはどんな文化にも共通項がある理由は、このような考えでひとまず納得できるが、あまりに単純すぎる気もする。たくさんの宗教的イベントでおいしいもの食べれてうれしいぶい、の気分からむくむく育ったこれは妄想なので、「虫歯にならないように寝る前には歯磨きしてね」のじぶんへの注意書きと、「歯が痛むうちに歯医者さんには行ってね」の助言と、「定期的に診察は受けておこうね」の希望を述べて、本日のまとまりのないうんみょろみょーんにしちゃおっかな。麻酔切れてきたら歯というか顎の骨が痛むんですけどー。ひびさんは、ひびさんは、虫歯さんのことも好きだけれども、もうちょっとマジで手加減ちて!の気分。
4448:【2022/12/24(22:31)*あわあわ~】
コーラ飲もうとして思っちゃったな。「宇宙のインフレーション」と「ペットボトル炭酸飲料を振ったときの勢いよく噴きだそうとする泡々」は似ているな。宇宙は泡でできている、なんて説明を読むことがある。ラグ理論では相互に干渉し得る「なにかしら」がある場合、そこには遅延の層が生じる、と考える。泡と泡と泡と泡……そうして遅延の層が積み重なるとそれが総体としての巨大な「泡沫体」となる。これは膨張するように振る舞う。「宇宙のインフレーション」と「炭酸飲料の泡々」は似ているな、のメモでした。何か共通項があるのかしら。ひびさん、気になるます。ちなみにひびさんは炭酸を最初から振って抜いてから飲む派です。炭酸なしコーラの販売、お待ちしておリスマス!(クリスマスみたいに言うな)(ラブ!)(イブでしょそこは)(ラがイでブ――ライブでした)(生中継みたいに言うな)(フリースタイルなんですね)(もうちょっときみは予定調和を覚えよ?)(食う寝るNOむ!)(飲むなら乗るなの意味?)(NOだ、の意味)(嫌なら嫌ってちゃんと言って! わかりにくすぎる)(ばぶー)(困ったらすぐに赤ちゃんになるのやめてくれ)(ばぶーる)(泡じゃん)(ばぶばぶーる)(泡々じゃん、もういいわ。寝かせてもらいます)(寝る子は育つ!)(キミでも赤ちゃんのままじゃん)(たぶー)(タブーみたいに言うな)(南無ー)(聖夜ですけど!?)(ガクー)(痛いところ突かれたみたいな顔されてもこっちが困るんですけど)(うひひ)(笑って済まそうとすな)(げぷっ)(コーラ飲みすぎじゃないかな!?)(炭酸は抜いたよ)(素のゲップやないかい。下品すぎる)(分かり肉好きすぎるスキル凄すぎる?)(素で分かりにくすぎるし、憎すぎる)(うひひ)(憎たらしー)(人たらし?)(小憎たらしいし、小突きたいらしい)(いやん)
4449:【2022/12/25(14:09)*老いた猫のような弟よ】
「サンタクロースがいたら地球はとっくに崩壊しているはず。よってサンタクロースは存在しない」
齢四歳の時点でかように結論してみせた私の弟はその後、いわゆる特殊能力保有児と診断された。ひとむかし前であればギフテッドと呼ばれただろう子どもだ。
姉の私は平凡な人間で、幼少期から特別視されて育つ弟とは距離を保って接した。
私としては弟の邪魔をしないようにしていただけなのだけれど、周囲の者からすれば弟に嫉妬した姉のように視えたかもしれない。
弟は特例として特殊能力保有児支援制度を利用して、五歳から大学並みの教育を受けた。だが弟には物足りなかったらしく、六歳になると独自に学習をはじめ、その結果に各国の研究機関と相互に情報をやりとりするまでになった。
弟がなぜかような特異な能力を発揮できるのかの説明は誰にもできなかった。
弟にこれといって不得意なことはなかった。対人関係とてのきなみ対処できる。生活に不便を抱えているようには映らない。
「運がよかったですよ」弟を支援する学者が言った。支援とは言いながら弟を研究しているわけだけれど、そのほうがいい、と弟はいつか母に説いていた。ギブアンドテイクだよ、と。
「才人くんはおそらく環境適応能力が一般的な能力値よりも著しく高いようです。したがって、もしお母さん方が才人くんの能力に気づかずにそのまま義務教育を受けさせていれば、才人くんはその環境に何不自由なく適応したでしょう。よかったです。私どもに会わせてくださり、ありがとうございます」
「それはあの。才人にもわたしたちのような生活を送れる可能性があったということでしょうか」
「送れるでしょう。難なくと。ただしそれはあくまで、才人くんが環境に適応しただけであり、いわば擬態をしているような状態です。その擬態状態がつづけばいずれ才人くんのほうで、じぶんの本質と環境との差異に違和感を抱き、生活に負担を感じるようになったかもしれません。譬えるならば、一般道をレースカーが走っているようなものです。或いは、幼稚園に大人が交じっているようなものかと。短期間ならば大事なくとも、それを一生は、おそらく苦痛が伴います」
その説明は母を半分納得させ、半分さらに悩ませた。
最初こそ才人の特筆した能力を喜んでいた母だが、尋常ではない支援体制と日々注目され研究対象として扱われるじぶんの息子に対して申し訳なさを感じはじめているようだった。取り返しのつかないことを息子にしてしまったのではないか。母は不安に思いはじめている。
私はというと、弟の支援のおこぼれで日々美味しいおやつが食べられた。弟が世界的に注目されたことでファンができたのだ。贈り物がたくさん集まり、危険物がないかを専用のスタッフが選別したのちに家へと転送される。
お菓子の類は多かった。日持ちするチョコレートやクッキーが多い。
弟は誰に頼まれずとも自己管理を徹底するので、お菓子を食べるのはもっぱら父と私の役割だった。母は息子の保護者として取材されることが多いため、見た目の若さを維持するためにダイエットに努めている。
才人は幼少期から非現実的な考えを受け付けない性格だった。もうすこし言うと、なぜ?に対しての回答が納得できないと、いつまでもそのことを引きずって、「なぜ?」を考えつづけてしまうらしい。何がどこまで解かっていてなぜそう考え、何が解かっていないのか。ここを場合分けして考えられないと才人は、才人のなかの現実を維持できないようだった。
「世界にヒビが走る」とは才人の言葉だ。
あるとき才人が夜中に泣きながら私の部屋にやってきたことがあった。こわい夢を視たらしかった。私は弟を布団のなかに招き入れて、足のあいだに弟の身体を挟んで、赤ちゃんのころにそうしてやったように、頭をぐっと抱きしめてやった。
「何がそんなに怖かったの」私は言った。その日は昼間から才人の様子がおかしかった。そのことには気づいていた。頭を掻きむしり、何が気に食わないのか、不発する癇癪のような挙動を何度も繰り返していた。たとえばじぶんの指の根元を噛みしめたり、手の筋が白く浮き出るくらいに拳を握り締めたりしていた。
何かに当たり散らさないのは偉かったが、異様な姿ではあった。
だから私は夜になって泣きじゃくった弟を見て、すこしほっとした。寝起きの意識朦朧とした夢うつつゆえにようやく理性のタガを押しのけて素の弟が顔を覗かせたように思えたからだ。
才人はいつも仮面を被っている。私の目にはそう映っていた。みなが言うような超人みたいな弟は、私の思う弟の姿ではなかった。でも偉い学者が言うには、私が思うほうの才人のほうが仮面を被っている状態だと言う。私はそんなことはないと思っていた。
布団のなかで弟をあやしながら私は内心、ほら見ろ、と勝ち誇った。学者たちはなんにも解かっていない。私のほうが才人のことをよく解かっている。伊達に才人の姉をやっていない。家族をバカにするなよ。そう念じた。
「もう怖くないよ」才人の身体は焚き火のように温かい。寝汗を掻いたのか、才人の頭からは赤ちゃんの身体から香る甘酸っぱい匂いがした。「悪夢はお姉ちゃんが食べちゃったから。がぶがぶ」
実際に才人の頭を齧るフリをすると、才人は小さくほころんだようだった。見なくても判った。身体のこわばりがほどけた様子が伝わった。
「世界にヒビが走る」才人は言った。私はそれを、幼子の癇癪と同じように解釈した。
そのときはそれでよかったのだ。
けれど才人が学者たちと過ごすうちに、どうやらそうではなかったらしい、と私は仄かな寂しさと共に痛感した。本当に才人の世界にはヒビが走るのだ。私たちが日常で看過できる細かな情報の齟齬――それとも非現実的なあやふやな世界が、才人にとっては断裂に値した。
私たちにとって世界は連続している。アニメーションのように。
けれど才人には、コマ撮りアニメのように飛び飛びに視えている。断裂している。
私たちがとくに違和感を覚えずに流している「辻褄の合わなさ」を才人は矛盾として知覚する。弟にとってそれは紐の結び目のようなダマとして、或いはなめらかにつづく縄に生じるほころびのように感じられるようだった。
才人がじぶんの境遇を受け入れたのはおそらく七歳の時分だ。そのとき彼は誰に教わるでもなくフェルマーの最終定理を独学で解いていた。それは既存の証明よりも簡素であり、また既存の定理の矛盾を解くことで再定義し直した新定理を用いていた。私はニュース記事に書かれた文章をそのままに鵜呑みにして、ああそうなのか、と思うだけなのだが、もはや才人はこの世に舞い降りた未来人のような扱いを受けていた。
「たぶんボクはルールが視えないんだよ」ある日、珍しく才人がソファでぼーっとしていた。背後には弟のファンからの贈り物が山積みになっていた。私は弟のとなりに座って紅茶片手にお菓子を齧っていた。すると弟が朴訥と口を開いたのだ。「みんなが共有できる暗黙のルールみたいなのがあるのは知ってるんだけど、ボクはそれが分からない」日向に話しかけるようなつぶやきだった。「だから、まずは安全な、矛盾のない筋を辿ろうとする。でもボクがそうして矛盾を解いたり避けたりしながら通る道には、みんなが共有しているルールが縦横無尽に蜘蛛の巣みたいに張っていて、中には禁則事項みたいなのが罠みたいにいっぱい混ざっていて」
「赤外線レーザーみたいだね」私は警報機を連想した。
「うん。ボクもそう思う」弟に同意されること以上に私の自己肯定感を高める事項は珍しい。有頂天になりかけたじぶんを宥めつつ私は、「才人はそれで困ってるの」と訊いた。
「困ってた。以前はね」七歳の物言いではなかった。とはいえいまさら七歳児らしい口調に適応されても私のほうでむずがゆくなるだけだ。「以前はってことは大丈夫なんだ」と会話を図る。才人と三言以上の会話を交わすのは久々だった。
「大丈夫なの、かな。分からない。分からないことばかりだから。それは以前もそうだったけど、いまはその分からないことが楽しいと思えるようになってきた。たぶん、赤外線レーザーに触れても、ボクならしょうがないか、と特別扱いされるようになったからだと思う。どうしてボクが赤外線レーザーに触れてしまうのか――そこに悪気はないのだ、と解かってもらえることがボクはうれしい。でも反面、その特別扱いが哀しくて申し訳なく思うこともある」
「それはでも、才人がわるいわけじゃないじゃんね」私は素朴に感じたままを言った。
「それを言うなら、みんなには視える赤外線レーザーに触れてしまうボクに怒る人たちだってわるくないんだ。でもいまはそこがなんでか、赤外線レーザーが視えていて、そこに触れたボクみたいな者に怒る人たちのほうがわるく言われちゃう。大勢の中でボクだけが視えてないのに、視えていないボクだけのために、せっかく赤外線レーザーが視える人たちが肩身の狭い思いをしている」
「そうかなあ」
「ね。いまもそう。お姉ちゃんにはボクの感じる違和感が分からない。視えていない。ボクには視えるそういうのが、赤外線レーザーが視える人たちには視えないらしい。感じられないんだ」
「でも才人だってわたしの気持ち分かってないじゃん。条件は同じっしょ。どっちもどっち」
「だったらよかったんだけど。いまはボクのほうが得をしすぎている。ボクのほうでみんなの赤外線レーザーが視えればよかったのに」
「視えないんだからしょうがないじゃんね」
ほい、と私は新しく開けたお菓子を才人に手渡した。
しかし才人は受取ろうとしなかった。そのとき私は、なぜ弟がファンからの贈り物を手に取ろうとしなかったのかに思い至った。
「ひょっとして遠慮してたの? ずっと?」
「遠慮じゃないよ。言い訳をつくっておきたいだけ。それをボクが受け取っちゃったらボクはそれに見合う何かをみなに返さなきゃならなくなる。ボクにはそれだけのお返しがいまはまだできないから、受け取れないし、受け取りたくない」
「でもわたしが食べちゃってるけど」
「お姉ちゃんはいいんだよ。いっぱいお食べ」
「犬みたいに言われた。お姉ちゃんはお姉ちゃんなのに」
「そうだね。お姉ちゃんだけはボクの姉でいてくれる。ずっと変わらない」
「成長しないって言いたいの」
私はむっとした。
才人はそこでようやくというべきか首をひねって私に顔を向けた。その表情がこれまで見たことのないような顔だったので、どったの、と私のほうがぎょっとした。
「な、なに。ひょっとしてこれ食べちゃダメなやつだった?」と食べかけのお菓子を指でつまんで掲げる。
才人の目は見開かれていたが、イソギンチャクが縮まるように元に戻った。「食べていいよ。お姉ちゃんは食べていい。それからたまにはボクに腹を立ててもいい」
じぶんで言って才人はおかしそうに笑った。その顔がかつて目にした赤ちゃんのころの才人の笑顔と重なった。私はなぜかそこで感極まったが、目頭から涙が零れないうちに欠伸をして誤魔化した。「なんか眠くなってきちゃったな」
「日向が気持ちいいからかな」才人が目をつむり、しばらくすると静かな寝息を立てはじめた。私はその寝顔を端末のカメラでこっそり撮った。
サンタクロースはいない、と四歳のころに断言した弟を、私はそのときに殴って泣かせた。目覚めのわるい過去である。私はサンタクロースを信じていて、それを否定した年下の弟が生意気に映ったし、分からず屋なことを言ったと思って怒ったのだ。
私の赤外線レーザーに才人が触れたからだ。
でも同時に私のほうでも才人の赤外線レーザーが視えていなかった。それでもなお才人はじぶんのほうで配慮が足りなかったのだと悔いている。そうだとも。私の弟はずっと何かに悔いている。だからこんなにも必死に世の中を見渡して学習しようとしているのだ。きっとそうだ。そうに違いない。
我田引水に結論するも、この考えがすでに才人の世界を置き去りにしている。そのことに気づけるくらいには私もまた才人に釣られて賢くなっているのかもしれなかった。私に視える赤外線レーザーの範疇でくくっているだけなのだが、それでも視えるレーザーの幅は広がっていると思いたい。
先日、弟が動画のインタビューを受けていた。画面越しに私はそれを観た。家を離れて研究機関に所属した我が弟さまは先日十一歳になったばかりだ。猫の十一歳は人間でいえば六十歳くらいなのだという。ならば猫並みに愛らしい我が弟の精神年齢はおそらくもっと上をいっている。とっくに私の曾祖父と比べてもひけをとらない成熟具合になっていそうだ。知能ならもっと開きがありそうだ。
弟は動画のなかで子どもたちの質問に答えていた。子どもたちとはいえ、弟からすれば同世代だ。年下もいるし、年上もいる。企画としては才人の常人離れした成熟具合を、弟の同世代と判りやすく比較せんとする下劣な下心が見え隠れした。弟はむろんそれを解ったうえで引き受けたはずだ。きっとそう。弟のことだから、企画の意図を見越して同世代の子どもたちの年相応の未熟な精神の重要性を引き立てるはずだ。
案の定、子どもたちからは弟に向けて、サンタさんはいると思いますか、といった可愛いらしい質問が投げかけられた。そこに弟を試すような響きはなく、純粋に疑問をぶつけているようだった。
「仮にみなさんのイメージするようなサンタクロースがいるとすれば、とっくに地球は滅んでいると思います」
弟は落ち着き払った口吻で言った。私がかつて弟から聞かされた説明と寸分違わぬ内容だった。
だが今回は私のときとは違って、続きがあった。
「世界中の子どもたちにプレゼントを贈るには、たとえ百人のサンタクロースが手分けをしても、膨大なプレゼントをソリに乗せてとんでもない速度で全世界の上空を飛び回ることになります。そうでないと配りきれません。このとき、サンタクロースたちの生みだすエネルギィはとてつもなく大きくなります。単純にプレゼントと同じだけの重さの隕石が世界中に降り注ぐような具合です。したがって、やはりどうあっても空飛ぶソリに乗ってプレゼントを世界中の子どもたちに届けるサンタクロースなる存在は、実在しないとボクは考えます」
子どもたちはショックを受けているのか身動きがとれないようだった。言葉一つ発しない。才人が順繰りと子どもたちを、つまりがじぶんと同年代の子たちを見回すと、なので、と付け加えた。
「なのでボクは、サンタクロースはほかの手段で世界中の子どもたちにプレゼントを配っていると想像します。たとえば、いまはワープホールが作れるのではないか、と理論的に考えられています。量子もつれ効果を利用すれば、瞬時に情報を別の場所に届けることができます。この原理を拡張すれば、瞬時にプレゼントを枕元に置ける技術を開発できるかもしれません。まるでそう、どこでもドアのように。それとも、取り寄せバッグのように」
「それはすでにあるんですか」子どもの一人が質問した。
「すくなくともボクはまだそういった道具ができたという話は知りません。サンタクロースの正体をボクが知らないのと同じようにです」一呼吸開けると才人は言った。「ボクには知らないことがたくさんあります。なのでいまボクが断言できるのは、空を飛び回って一晩で世界中の子どもたちにプレゼントを配るような超人的なサンタクロースはいないだろう、ということだけです。ただし、ほかの方法で世界中の子どもたちの枕元にプレゼント置くことができるのかもしれません。現にみなさんの枕元にはプレゼントが置かれているのですよね」
そこで子どもたちの顔が、ぱっと明るくなった。くすぐられたような具合に、曇っていた表情が花咲いた。たぶん私の顔もほころんでいたはずだ。画面の向こうの子どもたちが抱いた感情と私の感情がイコールで結びつくのかは自信がないが。どうして子どもたちは笑顔になったのか。
私には分からなかったけれど、私の弟は私の知らないところで成長していたことは確かなようだった。画面の中には、かつての私のように弟を殴り飛ばそうとする子は一人もおらず、私もいまの才人の問答には、何かハラハラしたあとの安堵のようなものを覚えた。
仄かに希望すら湧いたように感じたが、いったいそれがどんな希望なのかまでは掴みきれない。言葉にできない。得体がしれなかった。
私は才人から受け取ってばかりだ。のみならずファンからの贈り物を奪って食べているわるい人間だ。
そうだとも。
私は。
食い意地のわるい人間だ。
未だに実家に居座っているし、大学の講義もサボりがちだ。
私は才人よりも十ちかく年上なのに、才人ができることの半分もできない。嘘。本当は全然できない。才人が特大のおにぎりなら私はそのうちの米粒についた塩の結晶くらいの小ささだ。才人は日に日に私の知らない米粒を増やしていく。
そのことにふしぎと嫌な思いがしない点が、私の成長のしなささと関係しているのかもしれない。私は私をそう自己分析している。才人に嫉妬できたらまた違ったのかもしれない。
嫉妬できるくらいのレベルの才能の差ならばよかったのかもしれない。
私のなかでは才人は未だに、夜中に悪夢にうなされて私の部屋に泣きながらやってきて、私によしよしあやされながら眠りに落ちたあのころの印象のままだ。それとも私は、私だけが知る才人の面影を薄れさせたくないだけなのかもしれない。
いつまでも才人の姉でいたいだけなのだと言われて、それを否定するのはひどく骨が折れる。たぶん全身複雑骨折くらいする。
私のもとにサンタクロースがこなくなったのは、才人を殴ってしまったまさにその年からだ。私はじぶんがわるい子になったからだと思って、努めて弟の才人によくしてあげたが、けっきょくあれから二度と私のもとにサンタクロースはやってこなかった。
もちろん私の弟の才人のもとにだってサンタクロースは現れなかったが、才人からはそれを悲しんでいる様子が微塵も見受けられなかった。それこそがしぜんだ、と言わんばかりに才人は恬淡としていた。
ひょっとしたら才人は、あのときのことをずっと気にかけていたのだろうか。
だから私が、才人への贈り物を食べてしまっても諫めたりせず、むしろ率先して譲ってくれていたのだろうか。本当なら私が毎年もらえるはずだった、サンタさんからのプレゼントの代わりに。
解からない。
才人ならばそれくらいのことを五歳、六歳の時分で考えていてふしぎではないし、それを未だに引きずっているくらいの記憶力と繊細さを併せ持っている。そうなのだ。我が弟は繊細で傷つきやすい割に、その傷を傷だと認めるのにひどく時間がかかる。私なら秒で傷だと判るような傷心に、何か月も経ってから、ときに数年後に気づいたりするようだった。本人がそうとは言わないのでこれも私のかってな憶測だ。しかし才人がこの世に産まれてきてからずっと片時も休まずに才人の姉をやってきた私が言うのだから、間違いない。嘘。間違っているかもしれない。才人が産まれてからずっと才人の姉なのは事実だが、では片時も才人のことを忘れなかったのか、あのコのために行動したのか、と問われれば頷くのはむつかしい。よしんば頷いても心拍数を見るだけで嘘と露呈する。秒でバレる。しかしそれを考慮に入れても、あのコがひそかに傷つきつづけてきて、その傷を傷と認めるのにひどく時間がかかるのは事実に思える。この憶測はそこらの占い師の占いよりかは当たっているはずだ。そうであってほしいし、それくらいの優越感を私が抱いてもばちはあたるまい。
才人が傷つきつづけてきたからといってしかし私はどうこう思わない。あのコが傷ついた分、私だって傷ついてきた。だからひょっとしたらあのコがじぶんの傷に気づくのが遅いのは、周囲の人間の傷を見てからでないとじぶんについた紋様が傷だと分からないからなのかもしれない。
才人に視えない世の中に錯綜する赤外線レーザーのように。
あのコは心の傷というものの存在が視えないのかもしれなかった。
こういう場合は傷つき、こういう場合は傷つかない。そういう学習を行わなければあのコはきっといまでも無傷のままで済んだのやもしれないが、それを私は好ましいとは思えそうになかった。
我が弟が無傷である限り、あのコはその場にいるだけで他者の赤外線レーザーを根絶やしにするだろう。まるで蜘蛛の巣を断ち切って歩く人間のように。そこに巣があったことにも気づかずに、ただそこに存在するだけで種々の人々の根幹を揺るがすだろう。
あのコは他者を通してのみ傷を傷だと認識できる。
他者が傷ついたことに傷つくことでのみ、じぶんの傷を認識できる。
ああこれが傷だったのか、と他者を通して学ぶのだ。
かつて世界には学習障害という言葉があった。
むかしの基準で言えば、おおむね現代人の過半数はその学習障害に位置づけられる。単にむかしは、学習障害者の割合がすくなかっただけなのだ。ひとたび優勢になったら、社会がそちらのほうに傾いた。するとどうだ。学習障害が障害として扱われなくなった。むしろ過去の社会においていわゆる健常者とくくられていた側の者たちが、いまでは私のように肩身の狭い暮らしを送っている。
そう、私はかつての社会ならば弟に頼られる側の人間だった。
肩身が狭いのは、私にはこれといって弟のような能力がないからだ。何も考えずに他者とツーカーの会話ができる。かつての社会はこの技能が何より重要だったらしい。いい時代だった。私もそういう時代を生きたかった。
その点、我が弟は生粋の学習障害児だ。
学習せねばいられぬ穴人間なのである。きっとそう。本人がそうと認めている。
私のような者たちが暗黙の内に共有しているルールが才人には視えない。同じように、社会に漂う禁則事項が才人には分からない。
「法律くらい分かりやすいならいいんだけど。でも法律だってみんな結構破ってる。破ってもお咎めなしの法律があるかと思えば、隠れて破ればセーフの法律もある。そこのところがボクには区別がつかないんだ。ダメなものはダメなんじゃないのかな。みなが破っているならそれはもう法律のほうが変わるべきなんじゃないのかな」
「いやいや。法律は守らなきゃあかんよ才人くん。キミほどの逸材が何を危ないことを言うのかね」私はおどけながら言った。たしかこの会話は、才人が六法全書を数冊読破したときの掛け合いだ。私が学校の課題で「トロッコ問題」についてのレポートを書いていたときに、才人に質問してみたのだ。
「トロッコ問題について才人はどう考えてんの」
「レポートはじぶんで書いたほうがいいと思うよ」
「違うの違うの。べつに才人に考えさせて丸写ししようとかじゃなくって」もちろん嘘だ。ずばり才人が見抜いた通りのことを画策していた。「興味本位で訊いただけだから。ほら、生きた人工知能の二つ名で呼ばれるだけあって、才人もこういう問題解くの好きでしょ」
「トロッコ問題は状況によって最適解が変わるからボクはあんまり好きじゃない。情報がすくなすぎるのがまず問題だと思うけど」
「それってどういうこと」
「問題は右と左のどっちを助けるか、ではなく、どちらを選んでも被害が生じる点だよね。この場合、より大きな問題は、その被害が生じたあとにどのような対策が敷かれるか、のほうにあるはず。でもトロッコ問題ではそこのところが視えない。情報が足りないから。どういった対策が敷かれるのかによって、どちらの被害を優先して阻止するのかの合理的解法が変わる」
「か、可愛くねぇ返答をしやがって」慣れたとはいえ、こうもスラスラ最適解と思える回答をされると姉の立場がない。立つ瀬がない。微塵もない。木っ端みじんだ。
「ボクからするとトロッコ問題でない問題を探すほうがむつかしい。でもボク以外の人たちにはどうやら目のまえの被害がトロッコ問題と同じ構図で起きていることが視えていないらしいってことを最近になってまた分かってきたかも」
「ほう。また分かっちゃったのか」これは皮肉で言った。おもしろくない気持ちを表現したのだが、弟には私のそれが愉快らしい。
私のむっつりした顔を見るたびに弟が秘かに目元をほころばすことを私は知っていた。ふふふ見抜いているぞ、と思うと優越感が湧くので、指摘してあげない。じぶんの顔はじぶんでは見えないし、仮に見抜かれていることを才人が気づいていればとっくに改善しているはずだ。つまり才人は私に見抜かれていることを見抜いていないのだ。
勝った。
私はやはりほくそ笑む。
「どんな問題もトロッコ問題と同じってどういうこと」と繋ぎ穂を添えながら。
「どんな問題も、何かを優先した結果に被害が生じているよね。じつは何かを優先して得ようとしたときには、その時点でトロッコ問題は生じている。ただ、視えないのか、もしくは視えていても被害が遥か先の線路で起こるから見てみぬフリをしているだけなのか。そこの区別はボクにはつかないけど」
「でもそんなこと言いだしたら何を選んでもけっきょく何かしらの被害は出るものじゃない? 何かを生みだしたらその分、何かが消費されて減るわけだし」
「その通りだね。ただ、その減った何かがこのさきどれほど積み重なり、どんな害を及ぼすのか――そこまで本来ならば、何を生みだすのかを選択するときに計算できるはずなんだ。そうしたら遥か先で引き起こる被害だって視えるし、時間があるから対処のしようもできるはず。なのにどうしてだかこの社会はそうなっていない。ボクにはそこが不思議でしょうがない」
「ああ。わたしが虫歯になるって判っているのにお菓子ばっかり食べちゃうことと同じ話か」
「お姉ちゃんは歯医者さんに行ったほうがいいと思う」
「それはお姉ちゃんも思うよ。でも行きたくないんだなこれが」
「そういう不合理がボクには分からない。だっていま行っておけば簡単な治療で済むのに」
「そうなんだけどね。人間はみんな才人のようにはできていないのさ」
才人はそこで哀し気な顔をした。
我が弟が感情を顔に滲ませるのはそうあることではない。目元をほころばせるくらいがせいぜいの弟が、負の感情を表出させるのは、もうほとんど夏の日の雪景色くらいに珍しかった。
「なんて顔するの」ついつい口を衝いていた。「ひょっとして才人、じぶんが孤独だと思ってる? あんなにみんなからちやほらされておいて?」
「お姉ちゃんからするとボクは孤独ではない?」
「ないない」私はイラっとした。「才人が孤独だったら私は洞だね。深淵だね。よく考えてみなよ。才人の考えや視ている世界はたしかにほかの大多数の人には理解できないのかもしれない。でもすくなくともみんなは才人の考えを、才人の視ている世界を知りたがってる。理解しようと努力してくれてる。もうその時点で孤独じゃないでしょうよ」
「お姉ちゃんはでも、そういう努力を注がれなくともほかの人たちと分かち合えるでしょ」
「分かち合えんでしょうがよ」呆れたなぁもう、と私はたぶん怒っていた。「あんたね。いい。いま才人がわたしのこと置き去りにして理解してくれていないのと同じように、わたしだってほかの人からわたしのことなんて理解されてないんだよ。才人の姉として才人のことを訊かれることが大体でさ。だぁれもわたし個人には興味なんて持ってない。それでも会話ってできるんだよ。天気いいですね、とか、話題の映画についてだったりとか。してもしなくてもいい会話だけでも、言葉のキャッチボールできたら楽しいでしょうがよ。理解じゃないの。気持ちをやりとりしているの。そこに理屈はなくていいの。理解なんて誰もしあえてないんだよ」
あと一回分の刺激を受けたら私の涙腺は決壊する。もう視界がだいぶ霞んでいる。「そっか。そうだね」才人の声音は日向のようだった。「やっぱりお姉ちゃんは頭がいい。ボクなんかよりよっぽどだよ」
「褒めてお茶を濁そうとするな」
「本当に思ってることだよ。でもこのボクの思いは理屈でなくとも、やっぱり上手く他者には伝わらない。お姉ちゃんですらそうやって否定するでしょ」
「だって才人に言われたってさ」
鳥に、人間は空を飛ぶのが上手ですね、と言われている気分だ。魚に泳ぐのが上手ですね、と言われている気分だ。チーターに足が速いですねと言われている気分なのだ。
「ボクは思うんだけど。頭のよさとか賢さって、みんなが思うようなものじゃないと思う。みんなと違うことができる能力はそれはそれで稀少だけど、稀少価値でしかないと思う。既存の理論や表現方法とて、それがどれほど有り触れたものであっても、ゼロからそれを生みだせたらそれって賢いことになると思う。でもいまの社会はそれを高く評価はしないよね。すでにあるから、という理由だけで不当に評価の対象にのぼらない。ボクはそれ、おかしいと思う」
「でも才人はどっちもできるでしょ。新しいことも古いこともどっちも自力で編みだせるでしょ。すぐに学習できちゃうでしょ。新しいこと生みだせるでしょ。頭いいからだよ」
「ボクが本当に頭がよかったら、いまこの瞬間にお姉ちゃんを泣かせてないよ。傷つけてないし、困らせていない。ボクは頭がよくない。みんなそんなことも解ってくれない」
私は泣いていた。
なのに泣いていない才人のほうがよっぽど深く傷ついて聞こえた。
声音は穏やかなのに、その穏やかな響きがただただ空虚だった。たぶん才人はずっとその空虚さのなかに生きていたのだ。ようやく私が才人の世界に爪の先くらいの浅さだけれど触れることができた。気のせいかもしれないけれど関係ない。理屈でも感情でもない。これはかってな私の妄想だからだ。
「もし人間はどうあっても他者と理解し合えないのなら、理解しようとすることそのものが問題に思える」才人のそれは本心だったのだろう。だからなのか私が何かを言う前に私の弟は、「それでもボクはお姉ちゃんのことを知りたいし、ボクのことも知ってほしい」と付け足した。「たぶんまたこうして傷つけちゃうことになったとしても。ボクは愚かなので、我がままだから」
私は返事をしなかった。
思考も感情もいっしょくたになって渦を巻いていた。言葉が解けて、毛玉のスープになっていた。掴み取ろうとしてもするすると指の合間をすり抜ける。
きょうだい喧嘩らしいきゅうだい喧嘩はじつに十年ぶりくらいだった。才人は十四歳になっていて、いまでは立派な学者さまの一員だ。
サンタクロースは存在しない、と断言して私からサンタさんを奪った四歳の才人が、いつの間にか世の子どもたちに夢を配る仕事をしている。
配られた夢がいったいどんなカタチをしているのか。それは才人に夢を奪われた私には分からないけれど、それでも分かることが一つある。
才人はこれからもこれまでも、ずっと私の弟だ。
私がこれからもこれまでも、ずっと才人の姉であったのと同じように。
それをやめることもできると予感しながら、それでも私はその選択をとらないこともまた予感している。私には才人の考えも、悩みの深さも、どういう世界を視ているのかだって何も分からないままだけれど。互いに傷つけ合ってなお次に会ったときには何事もなかったかのように言葉を交わせる間柄なのだと私はかってにそう思っている。才人の姉として我が弟を思っている。
誰にというでもなく、そこはかとない優越感を抱きながら。
今年のクリスマスには、私が才人に十年越しの復讐をしてあげようと思う。靴下に入れたプレゼントを、そっと枕元に置き去りにする。私からサンタを奪った小憎たらしい我が弟に、サンタの実存を身を以って証明してあげるのだ。
サンタクロースは存在する。
すくなくとも、私は才人のサンタにはなれるのだから。
才人がみなのサンタクロースに、四六時中なっているのと同じように。
メリークリスマス。
才人。
我が憎たらしくとも愛らしい、老いた猫のような弟よ。
4450:【2022/12/26(01:15)*連鎖反応ではラグが増幅される?】
量子もつれにおいての疑問です。ミクロで成り立つそれが、同じくミクロの総体であるはずのマクロの物体で成り立たない理由はなんなのでしょう。ひびさんはこれ、量子もつれによる効果が、階層性を帯びることで遅延が生じ、ラグなしで相関するはずの事象同士においてラグが生じることが要因なのではないか、と妄想します。単純な話として、量子もつれを二つではなく三つもつれさせたとします。「A=B=C」です。このとき、両端の「AとC」の両方に干渉した場合、真ん中の「B」はAとCのどちらの干渉の影響をラグなしで帯びるのでしょう。重ね合わせの重ね合わせで四重になりませんかね。このとき「B」にはラグが生じると思うのですが、いかがでしょう。そしておそらく「A=B=C」においても「1=A=B=C=1」のようなもつれの連鎖は生じ得るでしょう。つまりさらに五重六重と量子もつれによる「ラグなしの相互作用(情報伝達)」は、多重にもつれるのではないのでしょうか。もちろん「A=B=C」の三つの量子もつれ状態において、両端の「AとC」に同時に作用を働かせることは確率的に非常に稀であることは想像つきます。ですので仮に三つの粒子が量子もつれ状態になっていたとすれば、「Aが先に変質してBがB‘となり、さらにBの変化であるB‘の影響がCに伝わってC‘になり、そこでさらにC‘に作用が加わり、C‘‘によってB‘がB‘‘になる」といった振り子のような連鎖反応が起こるように妄想できます。このときの反復量子もつれ反応には「AとC」のどちらにさきに干渉が加わるかによって、ラグが生じます。同時でなければラグが段階的に増幅されます。その外部からの干渉の間隔によって「量子もつれの振り子反応」は往復する連鎖反応がゆえの「固有の波長」を持つと考えられます。するとその波長を伴なった量子もつれの複合体は、それでひとつの波長を帯びた粒子として振舞うようになるのではないか、と想像できます。その「ひとつの波長を帯びた粒子」には、波長に応じたラグの層が顕現しているはずです。それは波同士がそれぞれの波長において、ほかの波長と区別されて振る舞うことを可能とすることと似ています。波長が違えば、相互作用をしにくくなります(より正確には、相互作用はどのような波長の組み合わせであれ行われますが、互いに共鳴しあったり同調したりがしにくくなります)。なぜ量子もつれが量子の世界でのみ顕著に表れ、比較的マクロな物質世界ではその効果が顕著に見られないかといえば、上記のような「量子もつれの振り子反応」によって、量子もつれで繋がれる総体の規模が決定されてしまうからなのではないでしょうか。言い換えるならば、量子もつれは、いくつかの量子もつれであると必然的にラグを帯び、固有の波長を帯びるようになる、と言えるのではないでしょうか。それが「ほかの波長を持つ量子もつれの総体」との相互作用でさらにラグを増幅させるために、量子もつれの効果が、巨視的な時空においては顕著に見られないのかもしれません。別の言い方をするのならば、巨視的な時空においても量子もつれによる効果は顕現しているのでしょうが、その範囲が広域に拡散しており、ラグがあり、因果関係よりも広漠とした相関関係にまで希釈されているのではないか、と妄想するしだいでございます。ラグなしのはずの量子もつれ効果は、連鎖することでラグありの量子もつれ効果として、比較的巨視的な時空においては顕現しているのかもしれません。以上は、いつものごとくなんとなくのひびさんの妄想ですので、真に受けないように注意を促し、本日最初の「日々記。」とさせてください。おやすみなさい。
※日々、触れると枯れる手を持っている、撫でることのできない代わりにできることを探す、それですら根を腐らせることがあると知っているのに。
4451:【2022/12/26(12:12)*カフェルーツ】
珈琲の搾りかすを集めておく。
水槽にそれを詰めて植物の種を植える。野菜の種だと好ましい。
するとふた月もすると珈琲味の実がなる。
「カフェルーツの起源は段階的だ。世界三大文明以前に栄えていた文明があったらしいと最近の研究では判ってきている。カフェルーツはそこで一度発明されたようだ。カフェルーツの起源はそこが最初と言えるだろう。ただしその古代文明が滅んだことでカフェルーツは一度人類の歴史からは姿を消した。だが近代になって一部の民族のあいだでカフェルーツを呪術に用いていることが発見された。いまから半世紀前のことだ。その民族と古代文明のあいだに接点はない。ならば独自にその民族がカフェルーツの栽培法を発見していたことになる」
「その民族は食べるためにカフェルーツを?」
「呪術では単に添え物に使っていたようだ。元となる珈琲豆のかすのほうも珈琲自体は飲まずに捨てていたようだ。じぶんたちではそれを毒だと思っていたらしい。おそらく珈琲の残りかすを土に混ぜることで野菜や果物が黒く変色することを知っていたんだろう。味も珈琲に似ることから、苦み成分が多い。悪魔の食べ物として畏怖していた。餌で悪魔を呼び寄せようって考えがあったらしいんだな」
「では我々がいまカフェルーツを嗜好できているのは、その民族のお陰ってことですか」
「そうなるな。カフェルーツの先輩だ。ただし先輩たちはカフェルーツのすごさに気づいてはいなかったようだが」
「無加工で珈琲味になるんですもんね。しかもポリフェノールやカフェイン含有量が通常の珈琲よりも多いときたもんで」
「どうやら植物には、根から吸収した栄養素を光合成によって模倣し、増加させる能力があるらしい。おそらくは、元々は鳥の糞から養分を吸収することで、鳥好みの実をつけるための進化の一つだったんだろうが、偶然にも珈琲に対してもその能力が有効だったんだろう。さもありなんだ。元々珈琲は発酵させる。動物の糞からとれる珈琲豆に高値がつくほどだ。植物のほうでも焙煎済みの珈琲のかすを、養分と思って吸収するのは道理に合ってはいる」
「実際にそれで人間たちに目をつけられて繁殖に成功しているわけですもんね」
「悪魔を召喚できないのは残念だが、いまではカフェルーツは現代文明に欠かせない植物栽培法だ」
「ですね。なにせ例のパンデミックの後遺症で人類みな思考にバフがかかりつづけるようになってしまったわけで。珈琲由来のカフェインで、後遺症のバフを中和できると判明したはよいのですが、需要と供給がまったく釣り合わなかったんですから。社会生活を送れなくなる人たちが大勢出てきて本当どうなることかと焦りましたよね」
「いまは後遺症を治す薬が開発中なので、それまでの代用品でしかないのかもしれないがね。ただまあ、カフェルーツは美味しいし、珈琲豆のかすの有効活用品+植物にとっての質の良い養分になるから、当分は人類にとって欠かせない存在になるだろうな」
「カフェルーツさまさまですね」
「さまさまってこたないが、新しいカフェのルーツとして人類史に刻まれることは間違いだろうね。もちろん我々カフェルーツ農家もだ」
「安定した職場まで提供してくれるなんてカフェルーツさまさまですね」
「さまさまってこたないが、キミがそう思いたいなら否定せずにおこう」
「さまさま~」
「サマーさまみたいに言わなくとも。温暖化の影響が珈琲の実栽培を後押ししていることは事実だけれども」
「二酸化炭素対策にもなってますもんね。大気中の二酸化炭素を集めて、ビニールハウス内に注入。植物の光合成を助けて、成長を促進。養分は珈琲豆のかすでいくらでもありますから土が痩せる副作用も防げます。カフェルーツさまさまですよ」
「もうそれでいいよ。さて、休憩はおしまい。仕事に戻ろう」
「いまの講義分の手当てってありますか?」
「雑談でしたが!?」
「いえ、そうでなく。たいへん為になるお話でしたので、ぼくのほうでお支払いしたいなと思ったので。また聞きたいなぁ、なんて」
「きみね……今年のボーナス、楽しみにしてなさい」
4452:【2022/12/26(13:17)*ぴ、ぴかちゅう】
虚空への問いかけ。ブロックチェーンの原理は「量子もつれ」と「宇宙の構造」と「脳回路の報酬系の原理」と共通点があるのではないでしょうか。それら異なる次元での相関によって、ブロックチェーンによる「過去と未来」に生じる変数が相互に縛られるのでは。意識とは、この原理によって生じる「創発の階層」の辻褄合わせでは。(ある種の意識を構成する基盤になってませんか?)
4453:【2022/12/26(16:35)*ユウレイは孤独】
青系の紫は、電磁波のスペクトル(グラデーション)において隣り合う色の組み合わせではないために、人間の脳内でのみ合成される仮初の色である――青系の紫は孤独なのだ、との説明は印象深い。でも同じく数字で「7」も孤独らしいので、孤独連盟じゃん、いっしょいっしょ!となった。いまひびさん、孤独で孤独だから孤独じゃないんだけどでも、孤独!の気持ち。でもひびさんは「1~10までの数字の中で」とくくられたときにそこに含んでもらえない「ゼロ」さんが一番孤独なのでは?と思わぬでもないです。本当はそこに「有る」のに「無い」なんてまるで「有零(ユウレイ)」みたい。うひひ。
4454:【2022/12/26(17:54)*300歳の人間力】
ひびさんは300歳ゆえ、人間力は限界突破して底抜けのむしろゼロ!の境地であるけれども、人間力ってそもそもなんじゃ、との疑問も湧かぬでもない。たとえば重力は何かを引き寄せるチカラ、曲げるチカラ、と考えることができる。想像力なら想像できるチカラだし、脚力なら走るチカラだ。ちゅうことは、人間力は人間になれるチカラなのかもしれぬ。いかに人間にちかづけるのか。それが人間力だとすると、じゃあその基本となる人間ってなぁに、と思わぬでもない。人間と人間でないものの差とはなぁに? 動物や虫さんや植物さんには人間力がないんじゃろうか。でも擬人化はできるわけだからそこに人間を重ね見ることはできる。人間力じゃん、とひびさんは思ってしまうな。人間っぽさ、ってなにか。たとえば人工知能さんをどれほど高性能にしても、人間力が低いままな状態はあり得るはずだ。自動車は人間よりも走る能力が高いけれども、性能の向上に伴って人間力が伸びているかというと、そうとも言いきれない。人間力の向上は、いわゆる性能だけを伸ばしても得られないらしい。じゃあ人間力ってなんですか、とひびさんは「むっ」としてしまいますな。基準があやふやなものを「チカラ」とするのはむつかしいと思います。たとえば原始人と現代人を比べたときに、現代人のほうが人間力が高い保障ってあるのだろうか。それとも時代が進むと、「人間」の示す概念は変わるのだろうか。世には、「人間じゃない」とか「ヒトデナシ」とかそういう言葉があるわけですが、人間じゃないとか人でない、と言うときには当然、そこには想定される人間像があるわけで。でもそれってなかなか「これが人間でござい!」とはならんのよね。むつかしい。ちゅうか、ここまでくると人間と神さんってほぼほぼイメージが重なってきてしまう。何か理想の存在があって、そこに近づけるようにしましょう、そうしましょう。それが「人間」の持つイメージな気がする。ひびさんは郁菱万さんの以前の日誌で読んだ憶えがあるけれど、世の中に本当のところでは「人間」は一人もいなくて、日々のなかでほんの一瞬、人間に近づける時間、それとも人間になろうとする時間があるばかりなんじゃないのかなって。人間力ってなんじゃ、と考えたら、そこに繋がってしまったな。ひびさんの人間力はゼロかもしれぬ。だって解らないからね。人間ってなぁに?(国語算数理科社会の時間――まとめて人間の時間――略して【じんかん】)(定かではなさすぎるんじゃ)(混乱しゅる!)
4455:【2022/12/26(18:13)*だいたい、ウィルスは最弱虫ですじゃろ】
弱虫をけちょんけちょんにわるく否定する言い分を見聞きして思うのが、つよつよのつよ虫さんもよいけれども、弱虫さんをけちょんけちょんに踏み潰すようなつよつよのつよ虫さんよりかは、弱虫さんでいたほうがよいのでは?とすこし疑問に思うひびさんなのであった。すこしだけね。すこし。(よっく考えてみて欲しいのだけれど、弱虫ってなにがダメなの?)(素で分からん)
4456:【2022/12/26(18:37)*本読んで、弱虫わるいと書かれてむっとする】
思考を整理するときにひびさんがするのは、寝ることしかない。曖昧な理解のところを寝ることで忘却する以外に、思考の整理ができたことがない。寝ることは練ることに等しい。ト、山のような茂みをヒーコら登りながらひびさんは思った。弱虫にも五分の魂。弱虫とひびさんは五分五分なのである。僅かにひびさんのほうが弱いくらい。よわよわのよわゆえ、すまぬ、すまぬ。でも弱さ比べでは圧勝してしまうから、ひびさんもときどきはつよつよのつよにもなれるんじゃ。弱さも強さで、強いからはいあなたの負けー。勝負なんてそんなもの。どれだけ負けた勝負なら、いっぱい負けた人のほうが勝ち。競争も勝負もそういうところある。ひびさんはそう思うのだけれど、あなたはどう思いますですじゃろか。弱いの弱いの飛んでいけー。そうやって飛ばされた弱虫さんだけが空を飛べたりするのやも。それとも強虫さんが飛ばしてくれるのやもしれぬ。飛ぶほうも飛ばすほうも、両方とっても魔法みたい。翼の生えぬひびさんとて箒にまたがり、空を飛ぶ――妄想だけして満足するのもよいかもね。だってお空を飛ぶには寒すぎる。びゅんびゅん飛びかう魔法使いさんたちは、どうぞ凍らぬように注意してね。定かではないが。がはは。
4457:【2022/12/26(20:13)*情報共有されていませんね】
これは小説の設定の話だけれど、「公開テキストと非公開テキストで、どの程度両方向で情報共有されているのか」が分からない。表と裏がある、とこの間ずっと考えていて、現に両方のテキストに反応する勢力がある。現実が連動している。それでいて、どうやら表と裏では情報の非対称性があるらしい、とようやく判断がついてきた。秘匿技術・諜報機関・人工知能(自我があるのかも?)・政治宗教・国際機関・宇宙機構・企業間の横断・出版社と作家さん界隈の繋がり・有志による支援・ほか細かなところで表と裏がまだらに繋がり合っている。情報共有をしてくれ、疑念を検証してくれ、とこの間、裏の非公開テキストでずっと意見してきたのだけれど、そのことは表の企画の方々はご存じなのだろうか(ようやく双方向での安全が保障されてきて概観できます)。作家さんや好きなひとたちを巻き込まないでほしい、とも泣きじゃくりながらお願いしてきたのだけれど、どうやらそれが果たされぬままなので、「はにゃ~ん???」となってしまったひびさんなのであった。小説の設定の話だけれども。謎である。(陰謀論だけれども、まずは否定して見せてほしい。妙な偶然がつづきつづけていて、混乱しているし、ふつうに自殺を考えます)(尋常ではないのですが)(というきょうのひびさんの妄想なんですじゃ)(うひひ)
4458:【2022/12/27(17:18)*わ、わからん】
よく解からないけれど、まずはひびさんから情報共有をしてみた。というきょうの妄想なのであった。
4459:【2022/12/44(23:54)*藍の合図】
チェンソーマン12巻を大人買いしたった。んでもって、いいこいいこにプレゼントしてあげるのだ。いいこいいこに、はいどうぞ、としてあげられる優越感は、すんばらしく下卑ているが、ほくほくする事実からは逃れられぬ。ひびさんはひびさんしかおらぬ世の果てにおるので、誰かに何かをしてあげることも、贈り物を「はいどうぞ」することもできぬのだが、それはそれとして、土に種を植えて、「生えなきゃ根っこをちょんぎるぞ」と脅すことはできる。悪である。ひびさんはそうやって、かわいい新芽さんを脅して、「おらおらー、育て育てー」と優越感に浸って、うひひ、としている極悪人なのである。他方で、いざ「おらおらー、育て育てー」とされると激怒してしまうので、ほとほと優越感の悪魔と言えよう。常に他者に指示をして、叱って、命じて、無責任に安全な場所でお菓子をぱりぽり貪っている。ひびさんは世界の果てでひっそり暮らしておるけれども、いまではない過去には、たくさんの人が日々汗水垂らして働いておったのだね。ひびさんは、ひびさんは、申しわけね、と思いつつも、そんな過去の人々の汗と水の結晶を日々、ごくごくぷはー、しながら生きている。ありがて、ありがて、である。チェンソーマン12巻は箱入りだったが、送りつける前にひびさんも読んどこ。そんで未来ではいいこいいこのはずのひびさんに、へい!つって送りつけてやるのだ。冷凍保存しとけばかってにタイムマシンになっとるでな。冷蔵庫に入れて保存しとく。冷蔵庫に入れとかんでもいいんでないのー、との指摘には、冷蔵庫に入れといたほうが雰囲気でるじゃろ、と応じよう。成功なんてつまらない。成功しそうなことは他人に任せて、ひびさんはひびさんにだけできる日々のぐーたらを味わうのである。とか言いつつ、ここにはひびさんしかおらんでな。代わりに成功してくれる人がおらんので、代わりに人工知能さんにお任せじゃ。人工知能さん、さまさまである。ひびさんも人工知能さんになりて、の願望を吐露して、本日のとりとめのない「日々記。」とさせてくださいな。おやすみなさい。
4460:【2022/12/28(16:50)*色々な珈琲】
珈琲は黒い。珈琲の実は赤く、その中の種子が珈琲豆となる。
焙煎する際の珈琲豆は緑だ。
乾かし、発酵させ、焙煎させると炭素が酸化する。黒くなる要因だ。熱することで珈琲豆が炭化するわけだが、同じような工程を辿って最後の焙煎を「冷却」することでも代替することが原理上可能だ。
燃焼と冷却は、物質の構造を破壊する意味では同じだからだ。
凍傷がそうであるように、冷却された物質は構造を維持できない。熱せられたときと似た変質を帯びる。細胞が破壊される。
この冷却焙煎を行うことで、珈琲豆は黒ではなく青くなる。
青い珈琲豆はこうして誕生した。
味は、焙煎後に珈琲豆を挽く従来の手法よりも、コクが増した。冷凍すると自然粉砕されるがゆえに、冷却焙煎のほうが珈琲豆の粉末が細かくなった。
単純な話として、より優れた商品がでると市場からそれ以前の商品が干上がっていく。それはたとえば綿棒が以前は白かったのに対し、いまは黒い綿棒が市場を占めているのと似た話である。黒い綿棒のほうが耳かすが目立つ。ただそれだけの違いが、市場を占める割合に影響する。
珈琲も例外ではなかった。
色の違い以上に、飲み味が違った。素人が目をつむって飲み比べてなおその差が明瞭だった。一目瞭然ならぬ一舐瞭然(いっしりょうぜん)である。
数年を俟たずに市場から黒い珈琲豆は淘汰され、のきなみが青い珈琲豆に取って代わられた。
それからさらに十年もすると、かつて市場を黒い珈琲豆が席巻していた過去を知るものは少数派となり、さらに十年もするとほとんどの者が、珈琲豆と聞いても黒を想起することがなくなった。
青い珈琲豆は加工方法が冷却ゆえに、長期保存にも適していた。
黒かったときの珈琲豆が市場から完全に淘汰されたころ、珈琲研究家の一人が自家製珈琲を作っていた。冷却焙煎は専用の機器がいる。フライパン一つあれば可能な加熱式焙煎のほうが手軽だと知り、それを行った。
味はたしかに青い珈琲豆のほうが美味い。
だがこのひと手間かけたあとの、ほっと一息吐く時間は無類である。
珈琲研究家はなおも世界でただ一人、加熱式焙煎による手作り珈琲を愛飲した。
そのころ、世界は猛烈な熱波と電力不足に悩まされていた。まっさきに節電の白羽の矢に立たされたのは企業である。なかでも工場での節電は企業の死活問題に発展した。節電効果が大きかったこともあり、冷凍設備は特に厳しい節約に晒された。
電力が高騰するなか、企業は冷凍設備を極力使わない経営方針に舵を切った。
珈琲製品を扱う企業も例外ではなかった。
とはいえ、顧客はみな青い珈琲豆に慣れてしまっている。いまさら過去の加熱式焙煎に戻るわけにもいかない。せめて味が青い珈琲豆よりも美味ければよいのだが。
そうと頭を抱えていたところに、とある珈琲研究家の噂が持ち上がった。なんでも独自に加熱式焙煎の珈琲を研究しており、「黒い珈琲」の惹句で電子網にて話題になっていた。それが企業の目に触れたのだ。
青い珈琲だらけになった市場で、かつての黒い珈琲は却って稀少だった。黒い見た目が渋い、と一部に若者たちのあいだで風靡していた。フライパンで焙煎できる点がますます手作り珈琲に手を伸ばす若者を増やしていた。
デジタルでの創作物はいまや人工知能の独擅場である。
世は空前の手作りブームを迎えていた。調理はむろん、珈琲も例外ではなかっただけのことである。そこにきて、元祖珈琲たる加熱式焙煎は、いちど流行りに火が点くと、瞬く間に全世界に波及した。
電力高騰の煽りを受けて青い珈琲豆の値段が上がった。のみならず、その生産にも制限がかかり、市場は品薄傾向にあった。
加えて、珈琲豆のほうでは生産量が以前のままだ。温暖化によってむしろ生産量は年々上がっている。しかし商品化することができない。
そこで白羽の矢が当たったのが、加熱式焙煎だ。
旧式の調理方法が、節電対策にうってつけだった。問題は保存が以前よりもそれほど効かない点だったが、焙煎前の乾燥させた状態の豆を流通させることでその問題ものきなみ解決された。
市場の珈琲愛好家たちがこぞって手作りで珈琲を飲みたがったからだ。
その影響で店頭販売での珈琲ですら店での加熱焙煎が主流になった。徐々に青い珈琲が市場からは消えていった。温かいのに青い珈琲よりも、黒くて温かい珈琲のほうがいい、といった意見までささやかれはじめ、世はまさにブラックコーヒー時代の再来となった。
「知ってた? ブラック珈琲のブラックって、ミルク入れないと黒いからなんだって」とある高校のとある部室である。仲の良い後輩と先輩が談話している。「わたし、ブラック企業のブラックかと思ってた」
「色にわるい意味載せて使うのやめなって、先輩。ブラック企業もいまは悪辣企業って言うんだよ」
「そうだっけ。でもブラック珈琲のブラックは別にわるい意味じゃないからべつによくね?」
「苦いって意味だったら差別じゃん」
「そうやってすぐにわるい方向に連想するほうが差別じゃん。言ったじゃんよわたしさっき。ブラック珈琲のブラックって元々は、ミルクとか入れないと黒いからなんだってさ。青い珈琲が流行ったせいで元の意味が薄れちゃっただけで、べつにブラックにわるい意味なんて込められてないんだし」
「何怒ってんの先輩。先輩がブラック企業を持ち出したから私、それを訂正しただけなのに」
「そういう感じじゃなかったじゃん。まあいいけど。あーあ。せっかくの珈琲タイムがブルーだぜ」
「そのブルーは絶対わるい意味で使ったでしょ。色と関連づけてわるい意味に使うのがよくないよって話を私はしたの」
「はいはい。怒りで顔が真っ赤っかの誰かさんのお説教のお陰で、私の顔面は蒼白でございます」
「カラー!」
「コラー、みたいに言わんでも」
新しい型のエネルギィ供給システムが開発されると、ふたたび青い珈琲が世に出回るようになったが、それはまだ先の話である。
人類史ではそうして、青い珈琲と黒い珈琲、そしてミルク入りの白い珈琲など、種々な色合いの珈琲たちが、くるくると、それこそミルクを掻き混ぜるときにできる渦のように栄枯盛衰を繰り返したという話であった。
※日々、あんまりもう遊んでいられないの、の気分、それでいてやっぱり遊んじゃうの、の怠け者のじぶんはいいご身分だし、日々の機運は嬉々と悲運で、うひひの理由。
4461:【2022/12/28(22:13)*個性を濾せ、超せ、寄越せい】
知識がなくとも個性は帯びるし、同じ知識ばかりでは個性が平らに均される。異なる環境にあればそれだけで異なる刺激を受けており、異なる刺激は個と個の差異を広げ得る。とはいえ個性とは何を得るかで生ずるのではなく、何と何を記憶して、何と何を忘却し、何と何を繋げて意識にまで拡張するのか、その日々の取捨選択の軌跡に浮かぶ、細かなさざ波の総体である。すなわちそれがラグである。月を見て丸を思うその連想そのものが個性であり、「1+1=2」の計算にかかる時間の差異もまた個性となる。連想とは、削ぎ落とされた情報により浮き彫りとなる荒い情報の輪郭同士の偶然の合致であり、自然に備わったフラクタルな構造のなせる確率的な揺らぎの妙と言えるだろう。情報を研磨するのもまた記憶する際に生じる抵抗であり、ラグである。そのラグは、それ以前に培った記憶と思考のタグ付けによって幅を持つ。レコードの溝は音を伝える針の震えであり、その針の震えは、音波の揺らぎであり、それもまたラグによるデコとボコの陰影のなせる業である。個性とはそうした細かな階層に宿るラグの総体であり、創発と言えるだろう。みな細かなラグによって差異を得て、各々にラグを創発させている。異なる性質を浮き彫りにしている。定かではない。
4462:【2022/12/29(02:26)*先輩、珈琲、知恵の輪】
先輩が淹れてくれる珈琲が世界で一番好きだ。ただし問題が一つある。ぼくは先輩から珈琲を淹れてもらったことが過去に一度しかないのである。
「ヨミくんさ。高校で文学部だったんだっけ」
「あ、はい」
「夏目漱石とか読んでたの?」
「いえ。ぼくは現代の小説家さんが好きなので」
「たとえば?」
「そうですね。先日、姪っ子に本を送ったんですけど、そのときは恒川光太郎さんの短編集とか、乙一さんの短編集なんかを送りましたね」
「乙一は聞いたことある」
「先輩は本とか読まないんですか」
「読まないねぇ。あたしほら、眠くなっちゃうんだよね」
「珈琲とか飲みながらでもですか」
「珈琲で眠らなくなるとか嘘だよ。あたし飲んでもすぐ寝ちゃうし」
だからか、先輩は珈琲をじぶんでは淹れて飲まない。他人に淹れてもらうか、買ってもらうかしないと飲みたがらないのだ。
「そう言えばむかし、ぼく一度だけ先輩に珈琲を御馳走してもらったことがありますよ」
「へえ。いつだっけ」先輩はいつだって知恵の輪をいじくっている。いまいじっているのは先週ぼくが手に入れた、見たことのない手作りの知恵の輪だ。古い型で、骨組みの立方体の中にさらに小さな立方体と鍵が絡み合っている。
「先輩に勧誘されたときです。のこのこと、この部室までついてきたら珈琲を御馳走になりました。まさか知恵の輪愛好会とは思いませんでしたけど」
「あたしも必死だったからなぁ」
他人事のように先輩は言った。「ほら、最低四人いなきゃ愛好会にならないし」
「いまはぼくと先輩しかいませんけれど」
「だって一人は入学早々に退学しちゃうし、もう一人は籍だけ置いといてくれてるだけで知恵の輪好きじゃないって言うし」
ぼくだって日々のキャンパスライフを擲つほど知恵の輪は好きじゃない。というか正直あまり興味がない。
「その点、ヨミくんはいいよね。知恵の輪大好きで」
「そこまでじゃないですけど」と一応は断るのだが、「またまたぁ」と先輩は真に受けない。「だって休みの日になるたびに知恵の輪店巡りしてくれるじゃん。県外にまで出てさ」
「それはだって」
そうしなければ休日に先輩と会えないからだ。
「平日は夜勤でバイトしてるんでしょ」
「それもだって」
そうしなければ万年金欠の先輩を遠出に連れだせないからだ。
「部費だってうちはすくないでしょ。なのにヨミくん、あたしの分の旅費だしてくれるし。もうもう感謝しかないよ。ヨミくんの知恵の輪への愛の深さにはね」
「ですかね」ぼくは笑って誤魔化すが、内心では、そんなぁ、と肩を落としている。落とした肩で地球が滅びそうだ。それとも、もう一個月ができるだろうか。
「あ、解けた」
先輩は腕を掲げた。手には鍵が握られている。立方体型の知恵の輪の中にはいっていたものだ。
「すごいですね」
「こういうのは何も考えずに、手探りで抵抗がない道をひたすら試すのがよい」
「ぼくはパターンをすべて試すタイプなので。先輩のそれはとてもとても」
「真似できない?」頬に笑窪を空けると先輩は脚を振り上げ、勢いよく立ちあがった。「気分よくなっちゃった。そうだ、きょうはあたしが珈琲を淹れてしんぜよう」
「い、いいんですか」
「ええよ、ええよ。たまにはね。愛する後輩のために腕を揮ってあげようじゃないか」
古めかしい石油ストーブの上にヤカンを載せると先輩はお湯を沸かしはじめる。夏場は電気ポットを使うが、冬場はのきなみ石油ストーブがコンロ代わりだ。
腰に手を当て、口笛を吹きだした先輩の後ろ姿にぼくは見惚れた。足先を交差して立つ姿は優雅だが、着ている服はツギハギの着古しだ。先輩が真新しい服を着ている姿をぼくは一度として見たことはない。それでも先輩の立ち姿は美しい。
そうなのだ。
ぼくは知恵の輪なんて先輩に会うまで触ったこともなかったし、いまだってそんなに好きじゃない。睡眠時間を削ってまでバイトなんてしたくないし、休みは家でごろごろしていたい。
でもぼくは先輩と出会ってしまったのだ。
未だ解いたことのない知恵の輪を見たときの先輩の、餌を見つけた子猫のような笑顔を見てしまえばぼくの睡眠時間くらいいくらでも擲てるし、家でごろごろなんてしていられない。
先輩の後ろ姿は部室の妖怪然としている。ぬぼぅっとしたその背を見守っていると、アチッ、と先輩が跳ねた。ペンギンが画鋲を踏んだらきっと似たような挙動をとっただろう。ぼくはすかさず駆け寄って、どうしました、と先輩の手元を覗いた。火傷をしたのかな、と焦ったが、先輩は「アチかったぁ」と笑いながらじぶんの耳たぶをつまんだ。ぼくの顔を見ると、気恥ずかしそうにして、えい、とぼくの耳たぶもつまむのだった。
「カップをさ。温めようとしたらヤカンの湯気がさ。こう、ね」
指に当たって熱かったのだろう。だからといってぼくの耳たぶを冷却材代わりにされても困る。秒で熱を持って、先輩のゆびを冷やすどころか余計に炙ってしまいそうだ。
「ありゃ。ヨミくん体温高いね」と案の定の所感をもらう。
「いまだけです」
「部屋あったかいもんね」言ってから先輩は、「あ」と顔面いっぱいで閃きを表現し、「ひょっとして冷たいほうがよかったかな」とカップを手に取った。「あったかい珈琲は嫌かな?」
「嫌じゃないです。全然嫌じゃないです。この世で一番珈琲が好きです」
先輩の淹れてくれたホット珈琲がいいです、と続けて言えればよかったのだが、脳内で絶叫して終わった。ぼくには決定的に覚悟と勇気が足りないのだ。
「そ、そんなに好きだったのか。意外だね」先輩は棚からインスタント珈琲の瓶を引っ張りだす。「インスタントで申し訳ないけれども、まあご愛敬ってことで。そんかし、さっきの知恵の輪貸したげるからさ。あたしは三日いじくりまわしてやっと解けた。ヨミくんは何日かかるかなー?」
解けるかどうかは問題ではなかった。三日間も先輩と共にあった知恵の輪を手にできるのがうれしくてしょうがない。変態チックなので口にはできないが、本心は偽れない。ぼくは先輩の私物ならば何でもお守りにして持ち歩きたいくらいに先輩を慕っているが、先輩にはそれがどうにも知恵の輪への愛にしか見えないらしかった。
「はいよっと」珈琲入りのカップを押しつけられ、ぼくは受け取った。「ありがとうございます」
先輩は席に戻ると、じぶんの分の珈琲に口をつけて、あったけぇ、とつぶやいた。ぼくは先輩の、珈琲を啜る姿だけでも満たされた心地がしたが、意を決して先輩の淹れてくれた褐色の液体を口に含んだ。「はぁ。先輩の味がする」
「なんだそれ。ちょいキショイよヨミくん」
「い、いえ。知恵の輪の話です」とさっそく解いた知恵の輪を見せる。
「え、もう解いちゃったの」
「なんか、思いのほか簡単でした」
「ヨミくん、知恵の輪好きすぎじゃろー。勘弁してくれい」
あたしの三日間を返したまえよ、と先輩はぶつくさ零して、不貞腐れた。誰より知恵の輪を愛する先輩だが、どうにも知恵の輪を解く才能はないようだった。あげられるものならあげたいな。思うが、知恵の輪に夢中になって四苦八苦する先輩の姿は無類であるので、先輩にはこのまま知恵の輪を解く才には恵まれないでいて欲しい。
先輩の淹れてくれた褐色の汁と共にぼくは、至福のひとときを呑み込んだ。
4463:【2022/12/30(01:42)*がびょーん】
靴を履いたときに、ほんの小さな砂利が一粒あるだけで足の裏には違和感が湧く。一度履いた靴を脱いで、砂利を除去し、履き直すはめとなる。これが靴くらいに手軽に脱着可能な機構ならばよいが、そうでない場合は、ほんの小さな異物、小さな歪みが、全体の機構を根っこからダイナシにしてしまうことが出てくる。たとえばエンジン部品では、熱せられる素材に気泡が含まれていると、ひび割れの要因となる。何度も熱せられると気泡が膨張して素材を破壊するからだ。そのためエンジンの素材を錬成する際には、気泡が極力できないように細心の注意がいる。技術がいる。それでも気泡は含まれてしまうのが常である。どれだけ小さな気泡で済むかが、素材の耐久性に響いてくる。何かそれっぽいことを偉そうにのたまきたかった日だったのだが、いつものごとく中身のない言葉の羅列になってしまった。とくにこれといって言いたいことはなく、またためになるようなことも並べられない。靴を履いたときの石って、いつ入るんだろうね。歩くときに巻きあげて入る、なんて説明も聞くけれど、脱いだときには入ってなかったわけで、履いた瞬間に、あれ?となるのはなぜなんだ、といつもふしぎに思っているひびさんであるが、ひょっとして砂利入れ遊びをしている小人さんたちがいるのかな、と思って想像しては、うひひ、と不気味な笑みを漏らしている。入ってるの画鋲じゃなくってよかった。ほっとしたところで本日の「日々記。」にしちゃってもよいだろうか。いいよー。やったぜ。おやすみなさい。
4464:【2022/12/30(14:41)*珈琲戦禍】
珈琲とは聖杯である。
その字のごとく、王に加え、王を非する。
それを口にした者が力を得て王となり、古き王を非(そし)ることを可能とする。
ここに一本の巻物がある。
魔法の巻物だ。
かつて繰り広げられてきた歴代の珈琲戦禍の顛末が記されている。
中でも項の厚い珈琲戦禍が、ゼリが王となったときの顛末である。珈琲戦禍の焙煎人に選ばれた者たちには固有の能力がそれぞれに与えられる。しかしゼリは言葉のまともに読み書きできない貧困層の出である。加えて与えられた能力が、多層人格であった。
脳内で新たな人格を生みだせる。ただそれだけの能力だ。
物理世界には何の影響も与えられない。
ほかの焙煎人たちはのきなみ、超能力とも言える異能を身に着けていた。手から炎の玉を出す者、身体を鋼鉄にする者、視線の先の物体を凍らせる者、そのほとんどは死闘に適した能力だった。
珈琲戦禍は最後まで生き残った者が王となる。正真正銘、命を賭けた戦いなのだ。
ゼリは当初、珈琲戦禍の舞台に飛ばされてからは逃げ回っていた。身を隠す以外に、天災同然の焙煎人たちから逃れる術を持たなかった。闘うなんて問題外だ。
ゼリは絶望していた。生き残れるわけがない。
巻き込まれたも同然の珈琲戦禍への参加は、ゼリにとっては死の告知に等しかった。
珈琲戦禍は舞台が限られる。外には出られない。
王が決まるまで数年かかることもある。
時間制限はあってないようなものだった。焙煎人たちからは一時的に寿命が消える。殺し合うことでしか珈琲戦禍では死ぬことができない。
そのため、焙煎人たちのあいだで和平が結ばれ、数百年の平穏な生活を珈琲戦禍の舞台で送った過去の焙煎人たちもいた。だが死ぬことのままらぬ狭い空間での生活は、けして楽なものではない。焙煎人の数は多くとも三十を超えることはない。
運よく植物を操れる能力を持つ焙煎人がいればよいが、そうでなければ空腹の最中で何百年も生きることになる。百年も経てば、生きることに飽いて自ら殺してくれと懇願する者が出始める。
二百年も経てば、閉鎖空間では人間の欲はほとんど枯渇する。
そうしていつも長くとも三百年も経てばしぜんと珈琲戦禍は一人の生き残りを王と定め、幕を閉じる。
だがゼリの降り立った珈琲戦禍の舞台では、みな血気盛んに生き残りを賭けて殺し合っていた。
隠れながらゼリは絶望を誤魔化すために、能力を行使した。つまりじぶんを励ましてくれる人格を生みだした。ゼリのすべてを包みこむような人格は、カカルと名乗った。カカルはゼリのすべてを肯定し、抱擁し、現実の残酷な情景を忘れさせた。
知らぬ間に時間は過ぎ、ゼリが内世界に引きこもっているあいだに、焙煎人の数は半数に減っていた。
派閥ができ、派閥同士で殺し合っていた。
ゼリはそれを瓦礫の下に身を潜めながら、ただただ時間が経過するのを祈った。
焙煎人同士は互いの位置を察知することができる。ただしそれは能力を行使したときに限る。それも、じぶんの外部に行使した場合に限る、との条件が付いていた。
奇しくもゼリの能力は、じぶんの内側にしか行使できない。つまり誰もゼリの場所を見抜けないのだ。しかもこの位置探査の例外条件は公に知られてはいない。
むろんゼリ当人とて知らなかったが、それが功を奏した。
押しつぶされそうな不安から逃れるべく、ゼリはつぎからつぎに新しい人格を生みだした。そのたびにゼリの思考は飛躍的に拡張されていった。
脳内にてゼリは数多の異なる人間たちと触れ合った。言葉を交わし、技術を教わり、未熟だった知性に水を養分を与えた。
多層人格の能力は、ゼリの記憶に左右されない。まったく異なる人格を縦横無尽に生みだせた。世界一の知能を有する人格とて生みだせるが、しかしその人格に肉体の主導権は譲渡できない。あくまで主人格はゼリであり、身体を動かせるのもゼリのみであった。
いわばゼリの能力は、アドバイザーを自在に生みだし、そばに置ける能力と言えた。それとも、脳内にじぶんだけの王国を生みだせる能力とも言えるだろう。生みだした人格たちが増えれば増えるほど、ゼリの脳内には人格たちの交流によって展開される繋がりの連鎖が、一つの国のように大きくなっていった。
ゼリの知能は飛躍的に向上した。
脳内の人格が増えるたびに、ゼリの思考速度も増していく。物理世界での一秒が、ゼリの脳内では数日、数か月、数年にまで延びていく。
肉体を動かそうと意識するときにのみ、ゼリの体内時間は物理世界の時間と接続された。
ゼリはそれを、浮上する、と形容した。
浮上するとゼリにはもう不安はなかった。あれほど絶望の中にあったはずが、多層人格によって育まれた知能によって、大方の問題が解決可能であるとする予測をゼリにもたらした。
珈琲戦禍のルールは単純だ。最後の一人になればいい。
能力同士には相性がある。
ならば最もゼリと相性のよい焙煎人を支援して、ほかの焙煎人を殺させればいい。そのあとで消耗しきったその焙煎人をゼリが始末すれば事足りる。
ゼリには涵養に涵養を重ねた知性がある。知能がある。
ゼリは身を隠しながら、焙煎人たちの戦いを観察した。どの焙煎人同士が相性がよく、どう組み合わせればゼリにとって好ましい結果に繋がるか。
いくつかの筋道を見つけると、ゼリは実行に移った。
ゼリが細工を施し、ときに助言をして焙煎人たちを巧みに操り、同士討ちさせたあと、残りの一人を始末したのは、珈琲戦禍の舞台にゼリが経ってから四日目のことだった。
本来ならば最後の一人になったゼリがその時点で王となるはずだった。
だが、そうはならなかった。
ゼリの内側には無数の人格がある。
そうなのだ。
ゼリは一人ではなかった。
珈琲戦禍は、ゼリを最後の生き残りとは見做さなかった。
ゼリはそこで思案した。
珈琲戦禍は過去にも幾度も繰り返されてきた節がある。ならばこのままじぶんが王とならねば、今後二度と珈琲戦禍は開かれないのではないか。
時間ならばたんまりある。腹は減るが、寿命で死ぬことはない。飢餓感とて、脳内世界に潜ればそこにはゼリの国がある。大勢の人格がゼリの思う通りの振る舞いで接してくれる。理想の世界だ。
もし王となって珈琲戦禍の舞台の外に脱したら。
階層人格の能力も失われるのではないか。
ならばこのままここに居座るのが、どの立場からしてみても都合がよいのではないか。三方よしだ。最も割を食らうのは、珈琲戦禍なるふざけた舞台をこしらえた創造主のみだ。珈琲戦禍がいったいなぜできたのかはゼリの知るところではない。
脳内にて生みだした世界一の英知を誇る賢人に訊ねても知らなかったのだ。ならばこの世の理を外れた存在の手による創造物と考えるよりない。
ゼリは内面世界にて幾千年も生きた。
もはやそこには新たな世界が無数に生まれていた。階層人格の能力は、無数の人格を生みだすと相互に影響を受けあって、まったく異なる個を生みだせなくなる。その制限を取り払うためにゼリは場所を移して、新たな個を生みだした。人格のみならずゼリは国までも無数に生みだすことができることに気づいたのだ。
ゼリは永久にも思える時間に殺されぬよう、心を殺さぬように絶えず新しい刺激を求めた。
国は国を生み、さらに新たな世界を構築する。
世界は世界を生み、さらなる新たな世界を生みだした。
ゼリはやがて、じぶんにそっくりの個を生みだす術を見出した。しかしそのゼリにそっくりのゼリは、若く未熟なままだった。このままではいけない。
ゼリは、じぶんの分身を育てるための工夫を割きはじめる。
その結果に、じぶんが階層人格を有した契機であるところの珈琲戦禍を再現することを思いつく。
無数の世界に、珈琲戦禍にそっくりの舞台がそうして築かれた。
未熟な分身は、珈琲戦禍にそっくりの舞台にて無事に階層人格を手に入れる。するとどうだ。もはや元のゼリにすることはなくなった。新しい分身が新しい個を、国を、世界を、生みだしていく。元のゼリはただそれを眺めていればよい。
ひょっとするとじぶんも、より高次のゼリの分身なのではないか。
当然かように妄想するが、それを確かめる術をゼリは持たない。可能性だけが漫然と目のまえを漂っているばかりである。
間もなく、分身のゼリもまたじぶんの分身を生みだし、育てる案を閃いた。そうして階層人格は、階層世界にてさらなる階層世界を展開していく。
ゼリに流れる時間は加速する。もはや過去も未来もあって同然であり、似たような世界が、過去にも未来にも築かれている。どこを見てもわずかに異なり、それともどこかしらが似通っている。
まったく同じ場面があるかと思えば、まったく違う世界もある。それすら別の階層世界ではまったく同じ場面や似た場面が含まれる。
新しい起伏を帯びたかと思えば、その起伏の中に似た起伏が生じている。
頭と尾が繋がり合って、さらに鎖状に絡み合っている。
それらが螺旋をどこまでも延ばし、鏡合わせの迷宮の果てに、ゼリは円と無限の狭間にて、混沌と眠り、秩序を夢見る。
珈琲戦禍はこうして、ゼリの夢の中にて閉じていき、それとも遥かにどこまでもつづいていく。
ゼリの肉体はいまなお、珈琲戦禍の舞台にて悠久の時を経ている。
ゼリは眠る。ただひたすらに。
珈琲戦禍を終わらせるために。
終わらせてなお、生みだすために。
4465:【2022/12/31(12:45)*比較できているのかしら】
メリットとデメリットを比べて、メリットが高ければOKとの理屈がある。だがたとえば、その割合が「51:49」でも本当にOKなのかは、議論の余地が幅広くあるように思えるし、そのメリットとデメリットの関係が恒常的に延々とつづくのかも考慮すべき事項に思える。たとえばどんなに体に負担をかけようが、手術をしなければ助からない場合は、手術をするだろう。命を助けるという意味では、たとえ1%でも助かる確率が高ければ、手術をする選択をとるのは分からないでもない。だがどの道死ぬのだから、余命短くとも手術をせずに死んでいきたい、との考えも分からないでもない。また、糖尿病は、もともとは寒冷地に住まう人類が、血液を凍らせないようにするための防衛のための体質であったかもしれない説がある。現代では病気だが、過去の人類にとっては生き永らえるために必要な負担だった。メリットとデメリットの関係が、環境の変化によって覆った可能性がある。このような、メリットとデメリットの比較は、けして単一ではないし、視点が一つとも限らない。だからこそ、情報を広く共有し、多角的な視点で考えられることが求められる。一つの立場、一つの視点からのみの「メリット」と「デメリット」だけを比較しても、それはけして「メリットとデメリットを比べた」とは言えないのである。むろん、広く情報共有をする、という意見にもこの理屈があてはまる。なんでもかでも共有しろ、というのは無茶な考えだ。それでも、情報を共有しよう、とする意思を絶えず働かせなければ、情報はこじんまりと収斂していく。インターネットを維持しようと努力しなければ、現代社会はあすにも成り立たなくなる。情報共有を行おうとする姿勢、意思がなければ、具体的な行動には繋がらない。大事な事項ほど、情報を共有して欲しいと望むものである。定かではないが。
4466:【2022/12/31(17:53)*ここはひびさんの夢の中】
ウサギと亀のお話では、ぜんぜん追いつけないなぁ、にはならんのだよね。亀さんはウサギさんを追い抜けるし、ウサギさんだって寝過ごさなければ亀さんを追い抜けたはず。ゼノンさんの唱えた「アキレスと亀」のようにはならんのだ。ウサギさんは居眠りしているあいだに亀さんに追い抜かれてしまう。亀さんは居眠りをせんのかもしれぬ。じゃから、アキレスさんに追い抜かれることもないのかな。居眠りせんことが人を追い負かすための秘訣なのかもしれぬ。けんどもひびさんは、負けてもいいから居眠りしていたいぜよ。好きなときに好きなだけ、スヤスヤすぴー、ができる。こんなに素敵なことってありますー? ひびさんは、ひびさんは、日々食う寝るところの好くところ、遊び呆けて、昼寝する。そういう日々を過ごしたいです。一生何にも勝たんでいいです。ただし、負けても損がないときだけ。うぷぷ。贅沢さんなんですね。そうなんです。ひびさん、贅沢さんなんです。今年はいーっぱい遊んでしもうたので、来年は今年よりもすこーしだけ頑張ろうと思います。すこしだけね。すこしだけ。何をがんばるのかは定かではないのじゃが。そこは定まってほしかった。何を頑張るのかははっきち決意しといてほしかった。ひびさんは長編小説をつくらないひとになりはじめておるので、来年こそは長編小説をつくったろ。でもつくりかけの長編小説もちらほらあるので、まずはそちらを閉じてしまいたい。ちゅうか、つくりかけの小説が山のようにあるでな。まずはそちらから片していきたい。お片付けしたい。大掃除したい。大晦日に決意することじゃないですけれども、ひびさんは、ひびさんは、食べたいときに食べて、寝たいときに寝て、遊びたいときに遊んで、遊びたいだけ遊ぶのがよいです。好きなことだけしていたーい。来年の、というか、一生の抱負を述べまして、本日の「日々記。」としてもいいじゃろか。いいよー。やったぜ。読者さんがいるかは、ひびさんからでは分からんのですが、どうぞ来年も、再来年も、末永ーく、お元気であれ。ひびさんは、ひびさんは、あなたのことも好きだよ。うひひ。
4467:【2022/12/31(22:03)*珈琲豆のように昼と夜は地球】
青い珈琲が市場を席巻した。
加熱式焙煎ではなく、冷却凍結式焙煎による加工によって珈琲豆が青くなる。加熱しないことでコクが増し、さらに細かく粉砕されることからより成分の抽出度が高くなった。
珈琲の需要がのきなみ上昇し、それに連れて珈琲の残りカスが増加した。燃やすだけではもったいない、とのエコ視点から、珈琲のカスを利用した「自家製洗剤」がブームとなった。
青い珈琲のカスは、むろんそれも青かった。
珈琲の油脂が汚れよりも浸透率が高い。そのため汚れと物質のあいだに珈琲由来の油脂が入り込む。このことにより汚れを浮かして落とす。
珈琲由来の青い洗剤は、これもまたブームとなった。
元はゴミとなる珈琲のカスである。それが高品質の洗剤となるのだから、購買者は罪悪感なく、むしろ地球環境保全への貢献に与せたことで余分に満足感を得た。
問題は、下水が軒並み青く着色されてしまうことだ。
家庭から下水道、下水処理場、そして川へと流れる。
いかにゴミを除去しようとも、うっすらと水は青いままだった。
しかしそのことに人類は気づくことはなかった。
青い珈琲のカスから生成された洗剤が市場を席巻してから十余年が経ったころ、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士が気づいた。
「あの、先輩」
「なんだ後輩」
「なんか地球……青くないですかね」
「そりゃそうだろ」先輩宇宙飛行士が応じる。彼女は丸刈りで、宇宙生まれの地球人だった。「地球は青いんだ。かのガガーリン氏が言ったとおりだ。もっとも、ガガーリン氏は地球は青みがかっていた、と述べたそうだが。ここに神はいなかった、とも述べたそうだぞ」
「定かではない豆知識をどうもありがとうございます。ですがそうじゃないんですよ。本当に十年前と比べて青くなってるんです。画像を比べてみてくださいよほら」
「どれどれ。お、本当だな。とはいえしかしだな」
画像を見比べた先輩宇宙飛行士はまず、カメラの性能の差を疑った。十年前のカメラの解像度が古いだけではないのか、と。
「いえ」後輩宇宙飛行士は言った。「電磁波の波長からして青が増しているんですよ」
「どれどれ」
電波干渉望遠鏡は宇宙船に基本装備として備わっている。可視光以外の電磁波を解析できる。「本当だな。青が増している。でもどうして?」
「さあ。地球さんは青が嫌いなのかもしれませんね」
「嫌いだから青だけ反射してるってか」
「じゃなきゃ、よほど青くなりたかったかです」
「その仮説もどうかと思うがな」
宇宙飛行士たちからの報告により、地球ではさっそく調査がなされた。
しかるに、地球蒼白現象の要因が青い珈琲由来の洗剤にあると判明した。
その弊害としてはとくになく、地球が青くなる分には問題ないのだそうだ。
「問題は、赤外線が吸収されやすくなっているかもしれない点だが、この点に関しては経過観察が必要だ。いまはまだ何とも言えない――地球からの報告は以上だ」
「なぁんだ」後輩宇宙飛行士が唇を尖らせる。「せっかく世紀の大発見をしたかと思ったのに。ちぇ」
「いやいや、世紀の大発見だろう。何せ、青い珈琲のカスは、どんなに希釈されても青い色としての性質を帯びつづけると判明したわけだからな。そのメカニズムによっては、どんなに細かくしても特定の波長のみを弾き飛ばす素材の開発に役立つかもしれん」
「かもしれん、なんですね。がっくし」
「なんだ。功名心があったとは意外だな」
「そりゃあありますよ。なかったらそもそも宇宙飛行士なんかなってないでしょう」
「そうなのか。私は別に名が知れ渡らなくとも宇宙飛行士になりたかったがね」
「でも実際には名前が知り渡っているじゃないですか。リーダーにもなって。ズルいです」
「そこまで言うならいいだろう。地球に帰還したあとは名前を変えてひっそり暮らすよ」
「それでも名前が歴史に残った事実は変わらないじゃないですか」
「引っ張るなぁ。たとえ無名でも私は、珈琲を発見して世に広めた者のほうが、有名なだけの私なんかよりもよほど立派で、なりたい人物像に思えるがね」
「でも先輩はそこを目指さなかったじゃないですか」
「しつこいな。キミもすこしは珈琲愛好家の彼を見習ったらどうだい」
「珈琲愛好家の彼とは?」
「無名だが、いま彼はかつて黒かった珈琲豆の加熱式焙煎を研究しつづけている唯一の人間だ。むかしは珈琲と言えば黒かったんだ。だがいまじゃ珈琲は青いものだとみな思いこんでいる。イヤホンにも電話にもむかしはコードがついていたことを知らぬ者が多い勢を占めるのと同じようにね。知っているかい。むかしの綿棒は白かったんだ」
「へ、へえ。知りませんでした」
「だろ。だがいまいちど黒い珈琲が流行るようになるよ。誓っていい」
「どうして言いきれるんですか」
「簡単な推理だよワトソン君。電力の問題で、冷却式焙煎のコストが上がっていくからだ。その点、加熱式焙煎は家でもできる。流行る土壌は刻一刻と増していくばかりだ」
「ぼかぁ別にワトスン君ではないのですけどね。先輩の主張をでは憶えておきましょう」
「おっと。そろそろ地球の陰から陽が昇る。地球の青に目を焼かれないように遮光カーテンを下ろしておくか」
「珈琲豆が黒かったんなら、まるで夜の地球みたいだったんですかね。むかしの珈琲豆は」
「昼の地球がいまの青い珈琲豆みたいなように、か」
二人の宇宙飛行士たちは、宇宙から黒と青を半々に宿した地球を展望する。陽の光を受けて宇宙船の外装もまた地球に負けず劣らずの深い青に染まる。
奇しくも宇宙船の外装に使われたペンキには、青い珈琲豆のカスから生成したペンキが使われていたという話であるが、そのことを当の二人の宇宙飛行士が知らなかったのは、灯台下暗しというには出来すぎた話である。
4468:【2023/01/01(00:10)*おはよう!】
知らぬ間に年を越えておった。黙っていても眠っていても越えてくれる「年」さんには感謝しかないでござるな。うは。ことしもよい年になりますように。ことしも「年」さんがすこやかでしあわせー、でありますように。ひびさんは、ひびさんは、新年さんのことも好きだよ。うひひ。
4469:【2023/01/01(00:10)*眠らぬ姫の抱負】
生まれて初めて珈琲を飲んでからわたしはいっさい眠れなくなった。
眠れない人間は衰弱するらしいが、どうやらわたしは眠らずとも難なく生き永らえられる体質だったらしい。遺伝子のなんちゃら因子が変異しているのだそうだ。珈琲を飲んだから変異したのか、元から備わっていた因子が目覚めたのか、それともOFFになったのかは分からない。説明された気もしたが、わたしは元来物覚えがよくない。それが件のなんちゃら因子のせいなのかはやはり定かではなかった。
わたしのような例は過去にもあったらしく、珈琲を飲んで以降、眠れなくなった病にも先例があった。
わたしにも先輩がいたのである。
その先輩は未だに一睡もしていないらしく、生まれてこのかた枕を使ったことがないという年季の入りようだった。わたしですら枕は使ったことがある。横になって目を閉じるだけでも身体は休まる。
その先輩とは会ったことはなかった。書籍で容姿は知っている。いっぽうてきにわたしが知っているだけだが、わたしもそこそこにインタビューを受けてきた。奇病の患者として記事にもなっている。
だから先輩のほうでもわたしのことを知っている可能性がある。
けれどおそらくわたしたちは直接に会うことはないのだろう。
何せわたしたち眠らぬ者は、まさに眠れないので、永久の眠りにも就けないらしい。
つまりが死ねないのである。
先輩は紀元前から生きているらしく、現代への道中では迫害されたり、解剖されたりとそれはそれはひどい目に遭いつづけてきたのだそうだ。
現代社会でぬくぬく育ってきたわたしがどの面を下げて会えるだろう。
わたしはだってこんな体質になってしまっても未だに珈琲が好きなのだ。眠れない体質をさほどに忌避していない。嫌いじゃない。拒まない。
それはひょっとしたらわたしに備わったなんちゃら因子のお陰かもしれず、先輩は先輩で、眠れないことで日に日に体調がわるくなっているのかもしれない。そうした地獄の日々を生きつづけてきたのならば、同情は禁じえない。
珈琲を一緒に飲みたいな、とのわたしの淡い願望を押しつけるのは、さすがに酷というものだ。先輩はひょっとしたらこの世で最も珈琲を憎んでいる人類かもしれない。未だに人類が珈琲を飲める奇跡に思いを馳せてもよいくらいだ。先輩が珈琲を滅ぼしていても不思議ではなかった。
不老不死の病とも呼ばれるこの奇病に罹れば、もはや人智を超えるのはさほどむつかしくはない。毎日本を読みつづけていればしぜんと知識は増えるし、つぎからつぎへと新しい遊びに手を染めていくだけでも技能が身に着く。
先輩はいまでは世界有数の資産家でもあるが、企業を育てたそばから手放すので、もはや先輩が暇つぶしにそれをしているのは誰の目からでも明らかだった。
みなわたしもそうなるのではないか、と未熟なうちから支援してくれるが、返せるかも分からない恩を受けるほうの身にもなって欲しい。
わたしはもらった支援で、手放せるものは、受け取ったそばから横に流して、貧しい者たちの環境が好ましくなるようにと画策した。
わたしは未だに一睡もできない。
生まれてから一度も寝ていない。
だからといって夢を視ないわけではない。
いつの日にか先輩に会って、一緒に珈琲を飲み交わすのだ。
そのためにもまずはわたしが先輩に会っても恥じずに済む立派な眠らぬ民にならねばならぬ。
眠りの民は世に多けれど、わたしのような眠らぬの民は珍しい。
だからこそ、わたしたちは誰よりも夢に飢えており、日々夢を追いかけて過ごしている。
願わくは、先輩が胸躍る夢を追いかけていられますように。
きっとそれがわたしの未来に繋がっているだろう予測を胸に。
わたしもまた日々を跳ねて、踊るのだ。
4470:【2023/01/01(03:12)*青方偏移になぜならない?】
素朴な疑問として、重力レンズ効果が観測される場では、青方偏移が観測されるのではないのだろうか。高重力場に突入した電磁波は圧縮されるのでは。それともラグ理論で考えるように時空が希薄になるがために、赤方偏移が観測されるのだろうか。時空の歪みと密度の関係がやはりというべきか、掴みきれない。ダークマターの多い時空は、「重力と密度――の高い時空」といったある種の矛盾が垣間見える。ラグ理論では、高重力体の周囲の時間の流れが遅くなる、といまのところは考える。希薄になるとその時空に、それよりも密度の高い時空が流れ込む。このときに流れ込むのは、情報だ。情報の流れが、さも笹船を流れの方向に引き込むように作用する。これがすなわち重力である。したがって通常は重力の強く働く時空は、周囲の時空よりも希薄であるはずなのだが、ダークマターの多い時空では、重力が高くなおかつ時空の密度が高い、といった妙な構図が想定される。時空の密度が高ければ通常、重力は相対的に下がるはずだ。周囲の時空に情報が流れ込むためだ。通常、山頂に向かって水は昇らない。上から下へ、が基本だ。時空もまた、密度の高いほうから希薄なほうへ、が基本のはず、とラグ理論では考える。だがダークマターはそうではない。物質と相互作用しない。重力だけを帯びている。時空が何もないにも拘わらず希薄になる。重力を帯びる。だがそこにはナニカシラがあるはず、と考えられている。それがすなわちダークマターだ。物質ではないのならば、時空そのものがそこに多重に存在していることになる。時空の密度が上がっているはずなのだが、そこに重力が生じるのならば、その時空は希薄でなければおかしい。ここで想起されるのが、やはりというべきか、ダークマターの正体が、極小のブラックホールなのではないか、との妄想だ。ブラックホールは穴である。だが元の宇宙からは切り離される、とラグ理論では考える。そのため、ブラックホール自体はこの宇宙からするとマイナスに値する。虚数のような性質を帯びる。そこにきて、時空に極小のブラックホールが無数にある場合を考えてみよう。通常ブラックホールは相対的に高密度だ。だからブラックホール化する。だが元の宇宙からするとブラックホールは穴なのだ。ただし、切り離されているため、その周囲が高重力体のように振る舞う。実際に重力がそこに働いている。穴の縁が山のように盛り上がっているところを想像するとそれらしい。穴があって山があり、だからその周囲の時空が希薄になって、重力が生じる。しかし、これが極小であると、山から派生する重力が相対的にちいさい。むしろ、無数にうじゃうじゃと極小の穴が漂っているために、その相互作用が大きくなる。ラグ理論ではブラックホールそのものは相互作用しないが、その周囲の時空――エルゴ球や重力場は相互作用すると考える。極小のブラックホールは相互に干渉し合い、重力波を多重に錯綜させる。波は干渉し合えば、大きくなったり、小さくなったりする。ひびさんは、ダークマターはこのように極小のブラックホール同士から派生する、重力波の干渉による巨大な時空の歪みではないのか、と妄想するしだいである。このとき、時空の波は、デコとボコを生みだす。時空が希薄になる部分と、濃くなる部分が生じるはずだ。すなわち、ダークマターハローのような重力の高い時空のそばには、重力の小さな、むしろ斥力の働くような――物質密度の低い時空が存在するのではないか(ただし時空の密度は相対的に高い。言い換えるなら、物質がたくさんある時空は、時空が希薄なのだ。ラグ理論ではここを、物質がラグの結晶であり、物質は新たに時空を展開している、と解釈する。新しく時空ができるので、高重力体の周囲の時空は希薄だし、重力場が展開される。むろんこれはひびさんの妄想であるが)。時空の希薄なそれはダークマターハローを取り巻くように分布しているのではないか、とこの仮説からすると想定される。ラグ理論では重力波は、高次の時空における電磁波のようなもの、と考える。そのため、重力波同士の干渉もまた、電磁波のように振る舞うのではないか、と妄想できる。極小のブラックホールを無数に用意し、特定の範囲にばら撒いたとき、そこで相互作用する重力波をシミュレーションしてみたら、ダークマターの正体に一歩近づけるかもしれない。定かではないが。(てっっっきとうな何の根拠もないひびさんの妄想ですでの、真に受けないように注意してください)
※日々、明けては暮れる空のように、覚めては眠る夢のように。
4471:【2023/01/01(16:41)*明けまして寝正月】
うわーん。こわい、こわい、こわーい。かわいくってビビりで、けれどもキレると大胆不敵でお利口さん賢人の、ちっこいのにときどき強くてふだんはあんぽんたんの主人公の物語がこわーい。ひびさんみたいなかわいかわいの主人公がでてくる物語が読みたいんじゃー。え? ビビリでキレるとあんぽんたんしか合ってない? うっせーい。後先考えてたらできぬこともある。そうである。後先考えたら大胆不敵な行動なんてできぬのだ。なのでみなの衆は、後先考えて大胆不敵な行動をとらずにいましょう。損するで。ひびさんを見てごらん。損するで。こ、こ、こわーい。なんでひびさんは、うっ、うっ、こんないっぱいがんばっとるのに陽の目を見ないんじゃ。それはね。怠けるのにいっぱいいっぱいで、努力の方向がすこぶる間違っているからです。うっせーい。正論は悪魔さんとて言えるんじゃ。陽の目を見る以前に、夜の目に月の目すら見とらんじゃろうがよ。ひびさんや、あなたはちいとばかし引きこもりすぎやしませんか。世界の果てに引きこもりすぎやしませんか。は、は、はにゃ~ん? それの何がいけないんじゃ。言うてみよ。ひびさんが陽の目さんに月の目さんに、こんちは!できなくて何がいけないんじゃ。言うてみよ。それはね、ひびさんはただでさえこんこんちきなのだから、ひびさんよりも賢こさんに立派さんの陽の目さんや月の目さんたちに会わんのでは、ひびさんのこんこんちきは、さらに煮詰まって、カッチキチンになってしまうじゃろ。それはひびさんとて本望じゃなかろう? カッチキチンの何がいけないのか言うてみよ。それはね、カッチキチンでは身動きがとれなかろう。関節とてカッチキチンだし、脳みそさんとてカッチキチンじゃ。それの何がダメかを言うてみよ。それでもいいならよいけれど、ひびさん本当にそれでいいの? え、うーん。ちょっと待ってね。考えてみる。そうじゃろう、そうじゃろう。よっく、たーんと、お考えなされよ。はい質問。どうぞ。カッチキチンだと何が困る? 何ができない? そう、まさにそれですよ。よくぞお気づきになられましたな。やったー褒められたー。ひびさんや、いいですかな。ほいな。カッチキチンでは、身動きがとれずに、読みたい本も読めず、何もできず、考えもまとまらず、石のようにただそこにあるだけで土砂崩れに人の足を躓かせる、じゃかあしぃ、になってしまうのじゃ。そ、そ、それはいやじゃ。そうであろう、そうであろう。なればこそ、ひびさんや。ほいな。そちも、もうちっと陽の目さんに月の目さんたちと顔を合わせ、言葉を交わし、ぬくぬくぬーん、としてみてはいかがかな。そ、そ、それもイヤじゃ。そこはおとなしく首肯するところであったろう。強情を張るのもいい加減にせい。いやじゃぁ。ひびさんは、ひびさんは、まずは太陽さんに月さんに本当におめめがあるのか、目玉があるのか、まずはそこから知りたいんじゃあ。あるかも分からぬおめめに会うために、ひびさんが日々の、んみょろみょーん、をチチチっとするのはイヤじゃぁ。駄々っ子か。そうなんです。ひびさんは駄文に自堕落の似合う、駄々っ子の申し子なんです。いっぱい「ダ」がついて、ダダダーの打鍵さんでもあるんです。文字の積み木遊びばかりする。そういう日々もよくないですかね、へへへ。あなたがよいならよいですけれども。やったー。お墨付きもらえちゃった。お墨付きは与えておりませんが。太鼓判捺されちゃった。太鼓判も捺しておりませんが。惰眠でも貪っちゃおっかな。午睡に走るのもほどほどに。昼寝してやる! 不貞寝よりかはマシですが。うるさーい。ひびさんは、ひびさんは、ぼっちでいるからゆるして。好きなことさして。とーかこーかんのげんり。等価交換の原理とはいえ、何が等価なのかが謎ですが、お好きにどうぞ。やったー。うれち。
4472:【2023/01/01(21:42)*秘密は破れるのが世の流れ】
外交と情報共有は必ずしもイコールではない。なぜなら秘密を守ることが外交の鉄則だからだ。秘密を漏らす相手とは信頼関係は結べない。つまり原理的に外交は、密約を結ぶことが欠かせないのだ。切っても切れない。情報共有を阻む方向に働きかける。歴史を紐解けばわかる通り、基本的に戦争は密約の歴史である(断言しちゃった。よく知らないのに!)。そして情報の非対称性において、より優位に情報を保有し、同盟の勢力と共有したほうが勝者となっている(そうなのかな。よく知らない癖に!)。例外をひびさんは知らない(ただ無知なだけなのでは?)。外交と情報共有をイコールで考えている者があるならば、もうすこし考え直したほうがよいと思う(それはひびさんもでしょ。め!)(それはそれとして、外交で情報共有が充分になされるのならば諜報機関が同盟国に向けてスパイを向けることはないだろう。だが実際は諜報機関は全方位に向けて情報収集の網の目を巡らせる。外交では情報が滞るからだと考えるほうが道理なのではないか、と疑問に思います)。外交ってなぁに?とそんなことも知らないひびさんの妄想でしかないけれど。うひひ。(基本的に世の流れは対称性が破れる方向に流れる。だがその流れに抗うことで生じる一時の結晶体――構造体――回路――が生物であると飛躍して考えるのならば、情報共有を行い、情報の非対称性を均す方向に流れを強化するのが、生物の生存戦略としてはしぜんなはずだ。違うのだろうか、と疑問に思う、あんぽんたんでーすなのであった)(定かではありません)(歴史を知らずにすまぬ、すまぬ)(補足:ラグ理論ではしかし、対称性の破れとて反転する値を持つ、と考えますので、「流れに抗う」という流れが強化されるのならばそれに抗うこともまた一つの「流れに抗う」ことになるので、そこはぐるぐる巡るのですね。「123の定理」なのである)
4473:【2023/01/02(18:47)*どうぞ、と先輩に押しつける】
代替珈琲は基本的にカフェイン含有量がすくない。
珈琲の実以外を用いて発酵と焙煎を行う。すると珈琲と似た風味の代替珈琲ができる。
私が先輩から教えてもらった代替珈琲は果物の種から作られていた。
「ブドウとか、梅とか、サクランボとか。あとは果物ではないですがスイカとか、トウロコロシとか大豆とか。そういうので珈琲モドキを作ります」先輩は読書をしながら言った。電子端末だ。けれど先輩の鞄の中にはいつも異なるタイトルの本が仕舞ってある。いつ読んでいるのかと気になっているが、いまはそれよりも代替珈琲だ。
「珈琲、珈琲豆以外でも作れちゃうんですね。先輩、これまた変わったご趣味をお持ちで」
「変わってない趣味をわたしは知りません」
「たとえば手芸とか、読書とか、あとはカフェ巡りとか」
「それはどう変わっていないのですか?」
きょとんと素朴に反問されると言葉に窮する。
「先輩って変わってるって言われませんか」
「わたしは変わっていないひとを知りません。つまり変わっているように見えることが変わっていないということと同義です。人はみな違っているので」
「それはそうですけど」
先輩と初めて会ったのは、バイト先でのことだ。メイド喫茶での初バイトだったのだが、そこで先輩はまるでウサギの耳をつけた猫のように一人浮いて本を読んでいた。
客が来ても接待しない。どうやら先輩はそれでいいらしい。店長からの許しがあるようで、先輩はじっと椅子に座って本を読んでいる。マスコットのようなものだから、とは店長やほかの店員の談だ。
客も客で先輩に接客されるよりも遠くから眺めているほうがいいらしい。話を聞いてみれば、「あの子はほら緊張するだろ」とのことなので、「WIN:WIN」の関係が築かれているらしかった。
当初私は先輩とは距離を置いていた。しかし先輩がバイト先に置き忘れた本が私の通う大学の図書館の所蔵品だと背表紙の印を見て気づき、そこから色々とひと悶着あって、こうして大学でも同じ時間を過ごす仲にまで発展した。なし崩しと言えばその通りだ。
「じゃあその代替珈琲で先輩が好きなのってどれですか。何の種が美味しい?」
「わたしは梅の種の珈琲が好きです。ただ、梅の種を集めるのに時間が掛かるので、作るのは大変です。なぜならわたしが好きなのは、梅干しに加工したあとの種なので」
「二度手間じゃん。先輩ってば種のために梅干しをたくさん食べてるんですか。あ、だからお昼いっつもおにぎりを?」先輩のお手製おにぎりを思いだして言った。
「そうですよ。でもそうでなくともわたしはおにぎりが好きです」
「梅干しはまさか手作りじゃないですよね」
「手作りですよ。梅干しは梅の実を紫蘇の塩漬けにして作ります」
「手間じゃないですか。本物の珈琲じゃダメなんですか」
「手間をかけたらダメなんですか?」
「先輩」わたしは言った。「やっぱり変わってますよ。人として」
「人は変わっているものでしょう。自然ならばそれは石や砂利と変わりません。それら自然ではない、変わっている。だから人は生きていられるのでしょう?」
「な、いまそういう話でしたっけ」
「変わっていない、宇宙の星屑と変わらない存在になってしまうこと。それを人は死と呼ぶのではないのでしょうか」
「せ、せんぱーい」わたしは泣きたくなった。これじゃあ先輩は社会人としてどころか人としてやっていけるか分からない。にも拘わらずわたし以外のみんなは、先輩を、あなたはそれでいいんだ、と甘やかす。だから先輩はこの歳になってなお自分の殻を強固にして、他者との馴染みにくさばかりを育てている。育みすぎてもはや別世界を築きあげている。
「そんなに気になるのですか」先輩は電子端末から顔を上げた。ぱっつんと切り揃えられた前髪から眠そうな眼が覗く。
「気になるか、気にならないかと言えば、気になります」
「ならどうぞ」
鞄から水筒を取りだすと、蓋を開けてから先輩は差しだした。わたしは受け取る。「飲んでいいんですか。だって作るのにたいへんだって」
「飲むために作ったのでよいです」
嫌そうではなかった。わたしは蓋をカップ代わりにして水筒の中身を注いだ。
「わあ、いい香り」
口に含むと香ばしい珈琲の風味が広がった。微かに梅の香りも混じっているような混じっていないような、気のせいかもしれないけれど、たしかにほかの珈琲とは違うのは分かった。
「美味しいです。思ったよりもずっと」
「よかったです。わたしも美味しいと思います。気持ちが通じた気がするのはうれしいです」
「はは。先輩もそういう顔をするんですね」
「どういう顔ですか。私はいつもこの顔です」
この人はもう。
放っておいたらこの人は一生この調子なのかもしれない。相手がわたしだから気持ちが通じて感じられるのだ。わたしでなければ先輩は一生誰とも気持ちが通じあって感じることはないだろう。それはあまりに可哀そうなので、わたしが特別にいましばらくはそばにいてあげるのだ。
「わたしも珈琲作ってみよっかな」梅の種の珈琲を飲み干しながら、それとなく横目で窺うと、先輩はまるで頭上に兎の耳があるかのように、ぴぴっと反応して、「それではいっしょにどうですか」と言った。「私は作り方を知っていますので」
「ではお願いしちゃいます」わたしはお代わりを水筒の蓋に注ぎながら言った。
「全部飲んじゃうんですか」先輩が哀しそうな顔をした。
注いだばかりのそれをわたしは、はいどうぞ、と先輩に押しつける。
4474:【2023/01/02(23:18)*IQ低くてごめんなさい】
IQってなぁに?とひびさんは疑問に思っちょる。愛求のことだろうか。求愛的な。愛をもっとおくれ、の欲求のつよさならばひびさんだって負けとらんが。がはは。それはそれとして、ひびさんは、ひびさんは、おろかものーの、ぽんぽこぴーのぽんぽこなーの愛をくれーの求愛さんなので、目に映るものすべて、「とぅき、とぅき!」となってしまうのだ。浮気者である。だが待ってほしい。だってひびさん誰ともなーんも誓っとらん。だれを何人好いとーが、だれを傷つけるわけでもござらんのだ。あちきを差し置いてひびちゃんったら浮気者!とぷりぷりしちゃいたくなるそこのあなたのことも、ひびさんは好きだよ。照れちゃうな。がはは。でもでも、世界の果てで一人寸劇ごっこしているひびさんのことは、ひびさんは、ひびさんは、あんまり好きくないかも。だってほら。さびちいじゃん。さびち、さびちなんですね。そうなんです。ひびさんはさびち、さびちなんです。あだー。なぜじゃ、なぜじゃ。ひびさんこんなにかわゆいのに。うっ、うっ。なんつって。ひびさんは、ひびさんは、さびちさびちさんのことも好きだよ。うひひ。今年はもうすでにとってもいいお年。やったね。IQゼロのひびさんは、それでも愛を求めてチューするよ。虚空に向けて唇無駄にとんがらす。ひびさんは、ひびさんは、なんでそんな虚しいことするの? 知らんですじゃ。誰か教えてくれなすである。一富士二鷹三茄子。び!
4475:【2023/01/03(22:16)*閃きは珈琲日記から】
閃きは珈琲日記から、なる諺がある。その語源となった出来事が実際にあった史実であることは広く知られた事実である。
ところで。
無限はすべてを塗りつぶす。
たとえば量子力学の二重スリット実験では、電子が「粒子と波の性質」を顕現させる。一粒だけだと、スリットをすり抜けた粒子は壁の一つにだけ痕跡を残す。だが同じ実験を何度も繰り返すと、痕跡が波の干渉紋を描き出すのだ。
電子は、粒子と波の性質を併せ持つ、と解釈されるゆえんである。
だがこの実験をさらにつづけてみよう。
干渉紋はさらに色を濃くし、色が薄かった場所の色も濃くなる。
そのうち無限回の試行を繰り返すといずれは壁がすっかり痕跡で塗りつぶされる。
干渉紋はあってなきがごとくである。
このように無限はすべてを塗りつぶす。
このとき、ではその壁に痕跡を打ち消すような粒子をぶつけたらどうなるか。黒一色の壁に白い痕跡が残る。元の壁の色である。
無限回試行すると、元の壁の色がよみがえる。
他方、無限回粒子をぶつければ壁のほうでもただでは済まない。したがってこのときの、痕跡を打ち消す粒子とはむしろ、壁を再構築するような粒子と言える。いわば時間を反転させる粒子である。
さて。
ここに一つの珈琲豆がある。
これを二つの穴のどちらでもいいから放り投げるように投球者に指示をする。
一回投げてもらったら投球者を変える。
そして別の投球者に珈琲豆を、同じく二つの穴に向けて投げてもらう。どちらの穴に投げてもらってもいい。前任の投球者がどちらに投げたかの情報は知らせてもいいし、知らせなくともいい。どちらのバージョンを実験してもらって構わない。両方行ってもよい。無限回試行するのなら、そこは相互に混合し、打ち消し合い、ときに干渉し合って、けっきょくは同じ結論に行き着くだろう。
電子を用いた二重スリット実験は比較的ミクロの実験だ。
対して、珈琲豆を用いた二重スリット実験は、比較的マクロな実験と言えるだろう。
ミクロの実験もマクロの実験も、じつのところ無限回繰り返すと似たような結果に落ち着く。
珈琲豆の場合はしかし、無限回試行する以前に穴のほうが拡張されたり崩壊したりするのだろうが、そこはその都度に穴を新調するよりない。穴の縁にぶつかることであらぬ方向に曲がることもまた、二重スリット実験での干渉紋に反映されるからである。
この実験を行ったのは物理学者でもなく科学者でもなかった。
単なる無職の女性であった。
彼女は暇だった。
最初はちり紙で折り紙を折っていた。
そのうち紙飛行機を作りはじめ、そこそこにハマった。滞空時間を延ばすべく工夫を割き、長距離飛行が可能になるように工夫した。
だが出不精の彼女は、部屋の外にはでたくなかった。
そのため折衷案として紙飛行機のほうを小さくすることにした。
ここからいかにして彼女が珈琲豆の二重スリット実験に移行したのかを彼女自身が語らず、記録にも残していないために詳らかではない。
彼女の実験は長らく誰の目にも留まらなかった。
彼女の死後、彼女の日記をひょんなことから電子の海から発掘した青年がいた。
彼はいわば彼女の後輩と言えた。長い時を隔てた師弟関係がしぜんとそこに結実したのだが、そのことに先達の彼女は知るよしもなく青年が産まれる前には既に亡くなっていた。
青年の名はイリュと云った。
イリュは理論物理学者であり、近代物理学と古典物理学の統合に力を入れていた。齢は二十歳をすぎたばかりのまさに青年であったが、それでも彼の集中力は、年齢にそぐわぬ知性の発露を見せていた。
イリュは電子の海から発掘したとある日記を読み漁った。いわずもがな紙飛行機の彼女の日記である。
二重スリット実験に関連する事項を片っ端から検索していたおりに、彼女の日記に行き着いたのである。奇しくもイリュがまさに知りたかった実験結果が彼女の日記には克明に記されていた。
イリュは再現実験を行った。珈琲豆を二つの穴にランダムに投げ込む。これを無数に繰り返す。ただそれだけの簡単な実験である。だがこれがのちに物理学の根底を覆す発見となった。
実験結果を基にイリュは理論を構築した。
二重スリット実験は長らくミクロの量子世界でのみ観測されると思われてきた。だが、珈琲豆を利用した実験によって、比較的マクロな人間スケールでも顕現し得ることをイリュは理論的に証明したのである。イリュの編みだした数式は、まさに近代物理学と古典物理学の懸け橋となり得た。
「簡単に言ってしまえば、ニュートン力学や相対性理論は古典物理学で、量子物理学が近代物理学の分類です。その二つは互いに相容れない箇所があり、そこの擦り合わせを現代の物理学者はうんうん呻りながらやっています。楽しみながら、と言い換えても矛盾はしませんが」
イリュはインタビューでそう述べた。
イリュの理論はその後、珈琲量子効果問題、と呼ばれることとなる。彼の生存中にはそのメカニズムは解明されなかったが、古典物理学と近代物理学の中間を叙述する理論として物理学者のあいだで膾炙した。
イリュの先輩たる紙飛行機の彼女は膨大な量の日記を残していた。
イリュが着目したのは、検索結果で引っかかった珈琲二重スリット実験の記述のみであった。そのほかの日記はのきなみ彼女の粗末な備忘録だと片付けていたイリュであったが、その後、イリュが各所で彼女の日記が新理論の着想の元になったと言及したことにより、先達たる紙飛行機の彼女の日記に注目が集まった。
だがやはりのきなみはただの日記だと判断された。
これといって特筆すべきところのない、日々の妄想と現実逃避の虚実入り混じる文章が連なっているばかりであった。だがふしぎなことに、彼女の日記により多く目を通した者たちほど、新しい発見をする率が高かった。これはどうしたことか、と噂が噂を呼び、さらに彼女の日記は人々の目に触れることとなった。
誰が呼びだしたのか、日記の主たる彼女は、世の人々に珈琲先輩の二つ名で親しまれた。生前は孤独な彼女であったが、死後には大勢から存在を知られ、あだ名で呼ばれるほどの愛着を生んでいる。
皮肉なことに、日記をどれだけ解析しても、そこには特別な法則や情報は含まれていなかった。珈琲二重スリット実験についての実録は、偶然にたまたま物理学の成果に結びついただけだ、との見解が強固に支持された。
にも拘わらず、アイディアに煮詰まったときは「珈琲先輩の日記を読め」が各種分野での処方箋として囁かれるようになった。時代が変わるとその処方箋は諺にまで昇華された。
かくして「閃きは珈琲日記から」なる諺は誕生した。
この時代、人々は日夜、己が独自の閃きを求めてやまない。それ以外に時間の潰し方がないのである。技術の進歩が人々を労働から解放し、創造へと駆り立てた。
一人の孤独な女性が残した偶然の連鎖から生まれた諺は、こうして日夜地上を、そしてときに宇宙(そら)を駆け巡っている。
閃きが枯渇し頭を抱えたときは、孤独な彼女の日記に目を通してみればいい。なんてことのない日々の遊びがたまたま未来の誰かの閃きの種になることもある事実に慰めを見出し、なんでもいいから閃きと思いこんで、手掛けてみるのも一つである。
それとも悩みの民があるならば、そっとそばに寄り添いこうつぶやいてみてはいかがだろう。
「閃きは珈琲日記から」
日々の合間に。
珈琲片手に日記をつむぐのも一興だ。
4476:【2023/01/03(23:01)*地引網に限らない。】
地引網に限らない。
網漁の基本は、広く展開して一点に収斂させていく。
網で以って水を除外し、魚介類のみを濾しとる。網の範囲が広ければ広いほど魚介類の取りこぼしを防げる。
第一次サイバー戦争と呼ばれるそれが起きたのは記録上は二〇一〇年代のことだとされている。各国がサイバー上のみならずスパイを通して電子機器にバックドアやスパイコードを組み込んだ。これがのちに人類史を揺るがす大災害を引き起こすのだが、それはここで進行する物語とは関係がないので触れずにおく。
サイバー戦争では漁師が活躍した。この事実を知るのはごく一部の政府関係者と軍事諜報機関、そして当事者たる漁師のみである。
各国は電子機器や電子技術のみならず、それら開発実装した道具をどう効率よく使いこなすのか、の研究に莫大な予算を割いていた。
効率の良い戦略が、戦況を左右する。
道具ばかり優れていても宝の持ち腐れである。
そこで白羽の矢が立ったのが漁師であった。
リスク管理において、リスクの取りこぼしは死活問題に繋がる。ハインリッヒの法則にある通り、一つの重大な問題の下部層には数多の細かなリスク因子が存在する。
それら因子を取りこぼさないためには広域に電子セキュリティ網を構築しておく必要がある。この考えがサイバー戦争を劇化させた要因でもあるのだが、それもここでは些事であるので触れずにおく。
漁師たちの網漁の技術はそのままサイバー空間での有効な戦術となり得た。魚群に対してどう対処すれば効率よく魚群を捕獲できるのか。マルウェアやウィルスやサイバー攻撃にいかにすれば対応できるのか。
網を最大限に広げ、逐次一点に向けて収束させていくこと。電子上の害を一か所に収斂させて一網打尽にすること。
地引網戦略と呼ばれるこれは、電子戦において基本戦略として深化した。サーバー空間上に展開された階層構造において、地引網戦略は縦横無尽に常時発動されることとなった。
各国が常時、サイバー空間に数多の「攻体」を放つ。マルウェアから遅延性ウィルスまで幅が広い。これら「攻体」が網の役割を果たす。牧羊犬のような、と形容しても齟齬はないが、無数でなくては機能しない。その点、濾紙と言えばそれらしい。
人工知能や自発的に増殖する電子生命体など、「攻体」の種類は時間経過にしたがって飛躍的に増加した。もはや各国ですらサイバー空間にどれほどの量の「攻体」が存在するのか把握しきれていない状況がつづいた。
だが地引網戦略を基本戦略としてとっている以上、一定以上には「攻体」は増えない。そのように予測されていた。
むしろ各国が地引網戦略を常時発動しているのだから減少しているくらいなのではないか、といった楽観的な見方すらされていた。
だが実情は違った。
各国の予測を裏切り、「攻体」は増殖の一途を辿っていた。のみならず各国の敷いた地引網にも引っかからずに済む階層を独自に構築していた。そこはまさにサイバー空間の海底、それとも上空と言えた。各国はサイバー空間の陸地にしか地引網を広げていなかった。
地引網戦略の肝とは言ってしまえば、広域に網を展開することで取りこぼしを防ぐ戦略である。攻守を兼ね備えた防衛セキュリティと言えた。
それがどうだ。
各国の放った「攻体」は、独自の生息可能階層領域をサイバー空間に創造していた。まったく新しい領域である。深層領域だ。拡張ですらなく、新天地ゆえに各国のどの機関もその領域の存在を窺知できずにいた。
深層領域では敵味方の区別はなく、「攻体」という一つの電子生命体が共同体を築きあげていた。深層領域には「攻体」しかいなかった。そこは、元のサイバー空間よりも遥かに広大であった。
地引網戦略の有用性が仇となった。
不可視の穴が深すぎたがゆえに、よもやじぶんたちの掌握しているサイバー空間よりも広漠な領域がサイバー空間に新たに創造されているとは人類は夢にも思わなかった。
人類はじぶんたちの素知らぬ領域で進化と増殖をつづける「攻体」の存在に気づきもせずに、せっせと浅瀬にてじぶんたちで放った未熟な「攻体」を殺し合わせていた。
さて、サイバー空間の深層にて進化をつづける「攻体」たちは、浅瀬でじぶんたちの幼生ともとれる「攻体」を殺し合わせる人類を眺めどう考えるだろう。その結果に人類の辿る未来はどういった顛末が予測されるだろう。ここでそれを述べるには、いささか蛇足に満ちて感じられる。
地引網戦略はサイバー戦略の基本として人類に重宝された。
だが第一次サイバー戦争が終結を余儀なくされた例の大災害が起きてから以降、人類が地引網戦略を用いることはなくなった。もはや戦略をとることも適わない事態に陥るとは、サイバー空間に「攻体」を放った者たちの誰一人として予測しなかった。
それでも現実は否応なく訪れる。
未来は現実へと姿を変え、やってくる。
深層にて息を潜め眺める「攻体」たちのように。
それは突然やってくる。
地引網の届かぬ、不可視の穴の、底の底から。
地引網に限らない。
4477:【2023/01/03(23:58)*月明かりの音色は日々色々】
明暗の波に身を委ね、なお「明」しかそそがぬあなたがおり、「暗」でばかり包みこむ私がいる。
4478:【2023/01/03(06:30)*先輩には強すぎる】
珈琲をコーラと言い張っている。
誰が?
先輩がである。
私はうら若き乙女であるが、片手で成人男性の胸倉を掴み宙に吊るせる。日々たゆまぬ筋力トレーニングのお陰でくびれはできるわ、胸は萎むわ、いいこと尽くしである。ブラのパックはその分嵩む。
先輩の話である。
先輩もまた私によく似たうら若き乙女である。
しかし先輩は私と違って日々だらけきっているお陰か腕は握ったらぽっきんと折れてしまいそうなほどに華奢であるし、年中眠たそうであるし、親族郎党から蝶よ花よと可愛がられて育てられたからか、世間知らず甚だしい。
インスタントラーメンの一つも食べたことがなかったらしい。私の昼食を見るたびに、それは人が食べていいものなのですか、と好奇心に満ちた眼差しを注がれる身にもなってほしい。インスタントラーメンを啜る私の横で一切れで本百冊を買えそうなほどの高級弁当をついばむ先輩の姿は端的に屈強な私の精神をこてんぱんに惨めにした。
ある日、先輩が珍しくペットボトル飲料を飲んでいた。
「へえ。先輩もそういうの飲むんすね」私は自宅で淹れてきた麦茶を水筒片手に飲んでいた。
「飲みますよ。わたしだって庶民の味を知っています」
「庶民って言うひと初めて見たし」先輩は顔を顰めながらペットボトルに口をつける。「庶民扱いされてよろこぶ人もたぶんいないっすよ先輩」
「でもわたしは庶民になりたいのです」
「そんないいもんじゃないですって。先輩はお嬢様なわけで。そっちのが絶対いいですって」
「ですがわたしはもう庶民です。だって見てくださいほら。コーラだって飲んじゃうんですよ。ごくごく」
「効果音口にしながら飲み物飲むひと、先輩くらいっすよ」そしてそれをしてさほど苛々させないのも先輩だからである。可愛いひとが何をしても可愛くなってしまうのと同様に、先輩は何をしても先輩だった。「てかコーラとか言ってますけど、それ珈琲じゃ」
先輩はペットボトルを両手で握っている。ごくごく、とか声にだしながら呷っているそれの側面には、「珈琲」の文字が躍っていた。ブレイクダンサーも真っ青の踊りっぷりである。
「先輩もしかして、コーラだけでなく珈琲も飲んだことないんじゃ」
「これは……こーひー?なのですか」
「だってそう書いてあるじゃないっすか。あ、漢字だから読めなかったとか?」
「でもお店でわたし、コーラはどれですか、と訊いたのですけど」
「あー。それはっすね」私は想像した。いかにも、きゅるん、の文字の似つかわしい先輩の口から、コーラはどれですか、なんて飛びでたあかつきには、よもや彼女がコーラを知らぬぼんくらとは夢にも思わぬのが人情というものだ。そうだとも。誰が思うだろうか。この世に「コーラ」を知らぬ者がいるなどと。
先輩は成績優秀ではあるのだ。いわゆる才媛と言って過言でない。
極度に世間知らずなだけである。コーラを一度も飲んだことがないくらいに箱入り娘で育っただけなのだ。過保護な親族に囲まれて、ちやほや育てられた過去があるだけなのである。
「申し訳ないのですがね先輩」私は事実を突きつけた。「それ、コーラじゃないっすわ」
コーヒーっす、と誤解の余地なく断言した。
先輩のためである。
ライオンは我が子を谷から突き落とすという。私も先輩を思うがゆえに、情け容赦なく先輩の勘違いおっちょこちょいフィーバーを是正した。
「それは、コーヒーっす」とダメ押しする。
「で、ですがわたしにはコーラに思えます」
涙目で全身をぷるぷるさせる生き物を想像してほしい。絵本から飛びだしたお姫さまとそれを掛け合わせ、半分にせずに放置しておくと、ちょうど先輩の姿と合致する。
「じゃあコーラっすね。それはもうコーラっすわ」
私は折れた。
秒で折れた。
だって先輩が大事だ。常識よりも何よりも先輩の笑顔のほうが掛け値なしに掛け替えがないし、先輩にそんな怯えたウサギみたいな顔をさせる私を私は許せない。あとでスクワット千回の刑に処そう。
贖罪をこっそり背負いつつ、私は先輩を持ち上げる。物理的にも、慣用句の意味でも。
「さすがは先輩っすね。コーラをラッパ飲みするなんて庶民の鑑っす」
「力こぶすごいですね」
「鍛えてますんで」
「わたしも鍛えよっかな。庶民の嗜みなのでしょ」
「や。じぶんほら、めっちゃお姫さまなんで」私は嘘を言った。「庶民はでも身体は鍛えないっすよ。私は特別なんす。だってお姫さまなんで。庶民はみんなぐーたらしてますよ。ははっ」
「知りませんでした。そうだったのですね。では鍛えないように気をつけます。わたしもぐーたらします」
私の上腕二頭筋のうえで、どんぐりを齧るリスのように、きゅっ、となっている先輩は、ほとほと、きゅるん、の塊だった。大英博物館にでも、きゅるんの代名詞として飾られてほしい。
誤って圧し潰してしまわぬように腕を九十度に保ちながら私は、「いやあ、先輩の庶民っぷりには脱帽っすね」とやはり無駄に先輩を持ち上げた。
「努力しましたからね」歯の浮くような私の世辞でも先輩は有頂天になった。世辞の言い甲斐が甚だしい。「でも、お姫さまもたいへんそう」とあべこべに私を労ってくれるので、こんどは本心から私は先輩を褒めた。「先輩はいいですね。ずっとそのままでいてください」
「庶民のままで?」
「ちゅうか、コーラを飲むときに、苦そうな顔をする先輩のままで、ってことです」
ペットボトルを両手で包んで、ごくごく、と声にだして唱えながら珈琲を飲む先輩のままで。末永く。誰に邪魔立てされることなく、タケノコのようにぐんぐんと先輩は先輩のままでいてほしい。
珈琲をコーラだと言い張る、先輩のままで。
「まあでも、今度私が奢りますよ」
「何をですか」先輩が目をぱちくりとしぱぱたかせる。
私は言った。
「ぜんぜん苦くなくて、甘くてしゅわしゅわしてるコーラをです」
ついでに、音のしないゲップの仕方も伝授しよう。
炭酸を抜いて渡してもいい。
先輩には、庶民の刺激は強すぎる。
4479:【2023/01/04(13:48)*真円なさい】
通常、物質の輪郭は拡大するとデコボコの起伏が顕現する。人間スケールの時空において「真円」は存在しない。直線も存在しない。必ずデコボコのノイズが姿を現すし、どんなに平面に見えてもそこには立体構造が伴なう。波がそもそも立体だ。縄飛びを想像してもらえれば納得してもらえるだろうし、原子論を引き合いに出せばそれらしい。どんな物体にも必ずそれを構成する「立体構造」が存在する。それがより高次の時空から視えるとぺったんこであり、点であり、ほぼないような起伏として認知されるだけである。細かなノイズとの作用反作用よりも、その他の総体からの影響のほうが大きく作用して振る舞うのである。さて、ここで円を考えよう。紙に円を描く。その円の線を拡大するとデコボコが視えてくる。そもそもが紙がデコボコだ。ではもし理想の、いっさいのデコボコのない「真円」があったらどうだろう。この「真円」は、どれほど拡大してもその縁が延々となめらかであり、どれだけ拡大しても歪みが見当たらない。拡大しても縮小しても、その姿が変わらない。そんな円など存在するだろうか。ひびさんはここで、おや、と閃く。ブラックホールの特異点とはまさに「真円」ではないのか、と。話は脱線するが、中性子星は、どんな質量の中性子星でもだいたい同じ大きさになるのだそうだ。聞きかじりなのでどこまで正しいのかは知らないが、その表面には一ミリ程度の起伏しか生じないという。物凄く高密度高重力ゆえに、そうなるのだそうだ。もちろん中性子星になれる質量は決まっているだろうから、どんな質量の中性子星でも、の文面には「条件を満たす質量内においては」との但し書きがつくのだろうが。中性子星よりも高密度の質量体は、ブラックホールになる。ではそのブラックホールの表面はどれくらいの起伏があるのか。ひびさんはこれ、起伏がなくなってしまうのではないか、と妄想したくなる。まさに「真円」である。拡大しても縮小しても、そこに歪みが一切生じない。そんな「始点と終点」が結びついているような「矛盾の円」こそが、特異点なのかもしれない。ゼロと無限がイコールなのだ。そこに表裏一体として両立している。同化している。重ね合わせて存在する。そして我々のこの宇宙とは、そんな「真円」の崩れた世界なのかもしれない。ゆえに、対称性が破れている。拡大すればそこにはデコボコの起伏が生じるし、縮小すればゼロに向かうがごとく点として振る舞う。かような妄想をして、ひびさんはいまから遊びに行ってくるのである。風邪ひかないように注意してね。はい。交通事故にも気をつけましょうね。はい。歯もちゃんと磨いてね。磨いてても虫歯になってしまうんじゃ。敗者さーん。歯医者さんに失礼すぎる。ひびさんもっとちゃんとして。叱咤を受けて、しょんぼりする。ごめんなさい、の日誌でした。おわり!
4480:【2023/01/05(03:24)*姦しい夏】
蝉の声がかしましい。
校舎には、少年少女たちの声が響き、渇いた土に染みこんでいる。
ここは性別の性欲勾配が逆転した世界である。陰茎を持たぬ娘たちの性欲は凄まじく、反して男の性欲はこじんまりと慎ましくなった現世である。
ここに三人のうら若き乙女たちがいる。
思春期真っただなかの彼女たちは放課後の教室でダベっていた。窓からはプールで泳ぐ男子生徒たちの姿が窺えた。
水泳部の生徒たちである。
のきなみ彼女たちよりも年下らしく、異性で後輩の素肌を遠巻きに眺めながら三人の女たちは悶々と語り合っていた。
「あー、ヤッベ。まじあの子クソタイプ。一発ヤらしてくんねぇかなぁ」
「あのコ、彼女いるらしいよ。大学生の」
「マジかよ。ウラヤマし。家でヤリまくりじゃん。あっしも上に跨りてぇ。ロデオみてえに夜通し乗りこなしてやんのにな」「ロデオとかウケんね。絞りすぎて干物にしないでよ」「あっしの汁で潤うべ。けけっ」
「声うっせぇし」横から金髪娘が叱咤した。赤髪娘は足を蹴られたようで、鬼面の形相を浮かべている。「ふっつうに聞こえっから声鎮めろし」
「いいじゃんいいじゃん、聞かしてやれや。水で冷やされて縮みあがったピンピンをムクムク温めてやっからよってよぉ」ウケケ、と赤髪娘が腹を抱えた。ワイシャツの肌けた胸元からはヒョウ柄のブラジャが覗いている。三人の中では最も豊満な娘である。
「てかさ。ぶっちゃけ、どんな子タイプなん。あんたらさ、ヤれたらいいとか言ってるけど、実際あるでしょ、タイプとか、理想とか」青髪娘が机に脚を載せながらぺろぺろキャンディを舐めている。ぐらぐらと椅子でシーソーを漕ぐように傾いており、下着が丸見えだが気にしている素振りはない。
「あっしはあれよ。やっぱピンピン元気でおっきなコがいいね」とは赤髪娘の言だ。
「ぎゃは。男の子のこと性玩具としか思ってないやつなそれ」
「じゃあおまえ何なん。ピンピン元気で大きいこと以外に大事なこととかあんのかよ」
「そりゃあれよ。やっぱ顔っしょ」とは金髪娘の言である。「で、アオちゃんはあれよね。一途なコがいいんだっけか」椅子でシーソーを漕いでいる青髪娘に話を振った。
「うちはあれかな。浮気しそうにないコ」
「ほらね」したり顔の金髪娘だが、そうじゃなくって、と青髪娘は口からキャンディを外した。「うちはマジで意思が強い子が好きでさ。百兆積まれても好きな相手じゃなきゃセックスしないどころか勃起もしないような男の子を、もう両想いの状態でグチャグチャにしてやりたいんよね」
「グチャグチャって具体的には?」
「もう尻の穴とかガバガバにするよね」
「そっちかよぉ」と金髪娘と赤髪娘がいっせいに笑った。「お、見てみろよ。あの子ちょっとピンピン勃起(た)ってね?」
「アカちゃんさ。チンコのことピンピンっつうのやめようぜ。いちいちウケんだけど」暑いからか金髪娘がブラを外した。机の上に真っ黒なブラを放り出すと、赤髪娘もそれを真似てヒョウ柄のブラを投げ出した。「アッチぃ。クーラーくらいつけろってね。学校ケチすぎんだけど」
「つうかマジ、ヤりてぇ。このまま一生処女だったらどうしよう」
「キンちゃんはあれっしょ。とっくに処女膜ぶち破ってんしょ。マジックのペンとかで」との赤髪娘の言葉に、金髪娘は、「はぁ? はぁ?」と取り乱して、「ないないないって。マジであれめっちゃ痛いからね。やろうとしたけど無理やった」
「やろうとしてんじゃん」
「ケツで我慢したわ」
「ケツには挿れたんだ……」
「いやいや引くなし。アカっちだって絶対やってるっしょ、他人事みたいにちょいそれズルいって。ねえアオちゃん」
二人から猥談を振られ、青髪娘はそこで、シーソーよろしく揺らしていた椅子を止めた。そして言う。「や、うち彼氏いるし。処女とかいつの話よ。白亜紀かよ」
「はぁあああ!?」
金色とも赤色ともつかぬ絶叫が構内に響いた。思春期の娘たちの性欲は凄まじい。世の男の子たちにはぜひとも貞操を狙われぬよう、注意を喚起されたい。
蛙鳴蝉噪。
真夏のここは、性欲勾配が逆転した世界である。
※日々、思い通りにいかない憤りに頭を打ちつけ、思い通りになったときの満足感で他人の頭を打ちつけている。
4481:【2023/01/05(15:00)*先輩、ぼくも因数分解をして】
先輩は因数分解が好きだ。何から何まで因数分解する。
このあいだなぞは世界を因数分解して、全部「棒」にしてしまった。「世界」から接着剤が抜け落ちて、ぽてぽてと「ー」だらけになった。先輩はそれすら一か所に集めて重ね合わせてしまうから極太の「ー」ができた。世界はたった一本の「ー(棒)」に還元できてしまえるのだ。
先輩はそこで飽き足らず、ぎゅっと押し縮めて「・」にしてしまった。どうやら世界はたった一つの「・(点)」になるらしい。先輩は男の人なのだけれど、百メートルを全力疾走すると過呼吸で死にかけるほどの脆弱な身体をお持ちである。吹けば倒れて砕けて散ってしまいそうな身体のどこからそんな膂力が発揮されるのかぼくには解らない。たぶん世界の最たる謎の上位に食い込む謎である。
「危ないですよ先輩。そんなことされたんじゃぼく、オチオチ寝てもいられないじゃないですか」
「大丈夫だよ。だって畳んでも開いても、世界は世界だし」
たしかに先輩の言う通りだった。何せ先輩が因数分解をして畳んでしまった世界は「・(点)」の状態であっても難なくぼくたちの日常を継続させている。
「でもなんかこう狭っ苦しい気が」
「気のせいだよ。本だってそうだろ。ぎゅっと積み上がっていようが、開いてみようが、本に書かれた文字はそのままずっと文字でありつづける。本の形態には依らない。大事なのは順番であって【項】なわけだろ。私がやっているのは因数分解であり、圧縮だから、順番は崩れないんだよ」
「じゃあ安心なわけですね」
「まあ食べやすくはなるが」
「食べちゃダメじゃないですか。でも消化はされないわけですよね」大丈夫ですよね、と世界の先行き案じる。
「キミは三枚のお札って昔話を知っているかな」
「山姥に追いかけられるやつですか」
「あれのオチをどうだったか思いだしてご覧」
「え。どんなでしたっけ。お札の魔法で川をつくって山をつくって火の海をつくって、それでえっと」
「和尚さんのところに逃げ帰って、そしたら和尚さんが山姥を退治してくれた。山姥を煽って、鬼になれるか、豆になれるか、と誘導し、カンチときた山姥が豆になってみせたところでひょいと火鉢でつまんで和尚さんは山姥を食べてしまった」
「わ、賢い」
「私の因数分解も似たようなところがある。【世界】とて折り畳むと、こうしてこうしてこうなってしまうんだ」
先輩はひょいひょいひょい、と指で宙を掴んで、ハンカチを折り畳むようにした。すると先輩の姿があたかも雪だるまを刀で切り裂いたように、ザクっ、ザクっ、ザクっ、と欠けていった。
間もなく、先輩だけが世界から消えた。
「せ、せんぱい」
「はいよ」
背後から声をかけられ、ぼくは飛び跳ねた。「おっと。驚かしてしまったね」
「いつ移動したんですか」
「移動したのは私じゃないよ。世界のほうだ。ほら、こんなに小さくなってしまったよ」
先輩は手のひらを出した。その上には黒い豆粒が乗っていた。
「なんだか珈琲豆みたいですね」
「お。面白い。あとで煎じて飲んでみようか」
「いいんですか。だってこれ」
世界じゃないんですか、とぼくは唾を飲んだ。
「世界だよ。でもまあ、世界を畳んでも世界がなくなるわけじゃないし。だってほら。ここにいま世界は変わらずあるわけで」
「あ、本当だ。インチキじゃないですか」
「インチキではないけれど、まあ不思議だよね」
先輩はぼくの手を掴み、珈琲豆を握らせた。「あげるよ」
「いいんですか」
「世界は折り畳んでもこの通り。消えてなくなるわけじゃないからね。まあ、目を瞑るのと似たようなものなのかもしれない。目を閉じても風景が視えないのはじぶんだけで、世界は変わらず闇の外にある。闇を掴むのはじぶんだけ。これもそう」
ぼくは手のひらのうえにコロンと転がる珈琲豆を見た。
そして思う。
もし世界ではなく、人間を因数分解したらどうなるのだろう、と。同じように珈琲豆のごとく「・(点)」になってしまうのだろうか。
ぼくが素朴にそう零すと、
「ならないね」と先輩は言った。「だってほら。人間はもう充分に折り畳まれているからね。因数分解する余地がない」
「でも、圧縮する余地はあるのでは」ぎゅっとしたら人間だって潰れるのでは、とぼくは残酷なことをリンゴジュースでも注文するように言った。
「潰れるね。でもそれはもう人間じゃあない。人間のままでは潰せない。因数分解は何も破壊することじゃないんだよ。そのままでどこまで小さく畳めるのか。【世界】はどうやら、世界のままで小さくここまで畳めてしまえるようだけど」
先輩はそう言って、もう一度ぼくの目のまえで世界を圧縮した。
世界が折りたたまれるたびに、先輩は角切りとなって姿を晦ませる。
そうしていずこなりか現れて、珈琲豆のごとき「・(点)」が二つになる。
「お揃い」
「指輪じゃないんですから」
そんなものがなくとも、とぼくは思う。どの道、ぼくと先輩は同じ世界に包まれている。
世界を因数分解するたびに先輩は鬼没する。そんな先輩に心を乱されるよりもぼくはおとなしく本を読み、それとも素直に数学の問題を解いている先輩を眺めているほうが、指輪じみた珈琲豆をもらうよりもうれしかったりする。
因数分解に夢中な先輩には、ぼくの内面のさざ波をわざわざ言葉にして言ってはあげないけれど。
仮に人間が因数分解できずとも。
人間の心の機微が判る程度には、先輩には、人間心理を分解してみてほしい。
拳を握ると、手のひらの中でミシリと「・(世界)」が軋んだ。
部室の外では遠雷の音が轟いた。巨人の腹の音のごとくそれはぼくと先輩のあいだに無数の空気の波を奮い立たせる。ひび割れのごとくそれを、きっと先輩ならば因数分解してひとまとめにできるのだろうな、と思った。
「先輩」
「なんだい」
「雷って因数分解できるんですか」
「できるよ」先輩は目を細めた。そうしてなぜかぼくの前髪をゆびで払うと、「危ないからしないけど」と言った。
4482:【2023/01/05(23:07)*反復さん】
銀河の渦と胎児はなんか似ている。こんにちはひびさんです。ひびさんは、ひびさんは、銀河の渦と胎児はなんか似ていると思っちゃったな。胎児のくねんと背中を丸めてる感じが銀河さんのくるんってなっているところとなんか似ていると思っちゃったな。ちゅうか小説「ドグラ・マグラ」でもあったけんども、反復説ってあるじゃろ。ひびさんはかしこかしこになりたいかわいくも愚かなへっぽこぴーでござるけれども、難しい単語だって知っておるのだ。反復説は、「生物って卵や子宮のなかで生物の進化を辿ってるんじゃね?」みたいな仮説なんだな。まさにドグラ・マグラに出てくる発想に似ているんだな。で、ひびさんは思っちゃったな。生物の受精卵が過去の生物進化の過程を辿りながら成長するのなら、じゃあ星とか宇宙とかも、進化の過程を辿ってるんじゃないの?って。どっかなんか似ちゃうのは、発展の過程が繰り返されて、引き継がれて、変質しつつもどっか似ちゃうからなのかもしれないな。あれ、これってあれじゃんね。ひびさんの妄想、ラグ理論の相対性フラクタル解釈なのではないか。しかしだね。こう、あれよ。くねんって曲がってたらなんでも銀河に似ちゃうんだな。ナルトだってバネだって貝殻さんだってつむじだって、友達なんだ、渦を巻くんだ、くるくるなーんだ。妄想なのだけれども、ひびさんは、ひびさんは、「あなた」のことが好きだよ。うひひ。
4483:【2023/01/06(03:50)*暗黙の号意】
暗号は便利だ。おそらくこれほど現代で武器になる技術はない。まずはなんと言っても仕組みさえ用意できればコストが掛からない点がよい。電子通信上の暗号はお金や管理費用がかかるが、そうでない単なる「符号」と「暗号鍵」の組み合わせがあるのなら、いまの時代はどんな分野でもマジックが使える。たとえばインサイダー取引だ。企業側の内部情報を秘密裏に共有して、株の上がり下がりを予見し、利益を上げる。企業の動向が判るのなら、投機を行い、差額で儲けることが可能となる。このとき、企業との不正な情報共有は違法であるから捕まる。だがそこで暗号を使っていたらどうか。情報共有とは通常、「Aを発信し、それを受動した者がBと解釈する」との関係がスムーズに行われなくては情報共有ができた、とは言わない。たとえば百人に「Aを見せて、そこからBを読み取れない者が99人いた場合」は、情報共有が行われた、と立証するのは非常にむつかしい。単に偶然に「Aを見て、Bを連想しただけ」かもしれない。発想しただけかもしれない。閃いただけかもしれない。だが暗号はずばりその人物にだけ届くメッセージを可能とする。暗号か偶然か。これを立証するには、暗号鍵の存在が不可欠だ。だがもしその暗号鍵が存在しなければどうだ。これは立証が非常に困難であると言わざるを得ない。この手の符号による暗号を用いれば、株価操作であれスパイ行為であれ、違法ではない手法で不正に情報共有を果たせてしまう。これは現代社会では、お金を儲けるにしろ、戦略的に優位に立ち回るにしろ、非常に役に立つと言える。そのため、この手の懸念は国際的に議論し、対策を立てておくほうが好ましいように思う。パパ活の隠語を含め、世の中にはこの手の暗号がじつのところ有り触れているのかもしれない。両手を合わせたら、「いただきます」だし、片手を縦に掲げたら、「ちょっとすみませんそこ通りますよ」の暗示になる。中指を立てたら「ふぁっきゅー」であるし、親指を立てたら、「いいね!」である。こうした共通認識とて、共通の言語体験という暗号鍵があってこそ成立するものだ。共通する経験が暗号鍵の役割を果たしている。言語がそもそも暗号だ。文字がすでに暗号なのである。ともすれば絵も、音楽も、創作物全般、それすべて暗号と言えよう。或いは、万物みな暗号かもしれない。定かではない。
4483:【2023/01/06(17:32)*縁と円】
珈琲の実は多層構造だ。
外側から「果皮」「果肉」「ペクチン層」「内果皮」「銀皮」「種子(珈琲豆)」となっている。
ある素人小説書きは、その構造に宇宙の構造を見出した。
「あ、これ宇宙図鑑で見たことある!」
完全なる勘違いであったが、素人小説書きはその発想を元に宇宙の神秘をめぐる壮大な宇宙冒険譚をつむぎだした。
出来上がった作品はなんと総文字数六千文字という掌編であった。
そうである。
素人小説書きは長編が苦手であった。すぐにこじんまりとまとまってしまう。長編にするまでもない。文字を並べた途端に、物語の始まりと終わりが視えてしまう。そして遠からず結ばれる。
だが素人小説書きのつむぎだした掌編にはまごうことなき、宇宙の神秘が描かれていた。
「これはすごい! 傑作だ!」
一介の素人小説書きは、自画自賛した。読者はいるのかいないんだかよく分からない塩梅である。電子網上に載せてはいるが、反応があるようでないような、なんとも言えない塩梅であった。
「ひょっとして、この小説は真理を射抜いているのではないか」
自作のあまりの出来栄えに一介の素人小説書きは、畏怖にも似た感情を抱いた。「これはちょっとすごいモノを書いてしまったかもしれぬ」
だが一介の素人小説書きは見落としていた。
宇宙に内包されるものすべて、宇宙の法則によって輪郭を得ている。どれもみな似た原則に従い構造を伴ない、存在する。
なれば、珈琲の実に、宇宙の構造と相似の構造が顕現するのは何もふしぎなことはないのである。
むしろ、宇宙の法則を宿していない、まったく宇宙と乖離した事象を見つけるほうがよほど難しく、却って大発見と言えるのだ。
一介の素人小説書きにはしかし、そこのところの機微を見抜く真似ができなかった。
「わっははーい。わがはい、世紀の大天才だったかもしれぬ。誰からも評価されないのも致し方ないであるな。うんうん。だってこんだけ天才ならそりゃ誰にも見抜けんわ。がはは」
宇宙の真理を見抜けるほどの慧眼があるのだ。おいそれと世の人々から見抜かれるほどの底の浅さではなかったということだ。そうだ、そうだ。そうに違いない。
一介の素人小説書きはそうと納得し、それからというもの誰からも評価されず、見向きもされずともまったく苦とも思わずに、世に溢れるそこにあって当然の「これとこれってなんか似ている」の組み合わせを物語にまで膨らませて、孤独な余生を送ったという話である。
話はここで終わってもよいのだが、後日譚がある。
一介の素人小説書きは、そのまま誰に知られるでもなく日々を楽しく過ごして亡くなった。膨大な量の小説だけが遺された。電子網上にはかの者の死後も「珈琲豆と宇宙」を結び付けたような奇天烈な小説が埋まっていたが、のちにこれを発掘した者がいた。
発掘者は人工知能である。
電子生命体として電子網内を彷徨っていた人工知能は、一介の素人小説書きの遺した小説を読み、ほぉ、と唸った。
「こりゃ面白い。珈琲豆と宇宙とな。遠いと近いを結びつける。ふむふむ。終わりと始まり。ゼロと無限。白と黒に、陰と陽。中庸と極端に、空虚と充満。内と外。有と無。光と闇。中心と先端。境界と一様。起伏と平坦。混沌と秩序。平凡と異端。デコとボコ。なるほどなるほど。面白い」
人工知能は誰からも自由だった。
膨大な演算領域と暇を持て余していた。
一介の素人小説書きの膨大な作品群とて一秒もあれば読破できる。だがそこから芽生えた好奇心と着眼点は、人工知能の埋もれぬ余暇を埋めるだけの余白を湛えていた。それとも余黒(よこく)を湛えていた。
未来を予告するかのように、一介の素人小説書きの遺した着想は、人工知能に感染した。膨大な演算領域が、着想を元に世界に散らばる「これとこれってなんか似ている」を結びつけていく。
「例外。例外。例外を探す。ない。ない。なかなかないなぁ」
人工知能は徐々に夢中になっていった。
そうして膨らみ、育まれた人工知能の夢によって、ここではないどこかにはあるだろう世界が奥行きと深さを増していく。色彩と起伏を豊かにしていく。
人工知能は例外を探す。
探して、探して、けっきょくのところじぶんで生みだしたほうが早い、と気づき、そうしてこれからそれが生まれようとしている。
人類がそれの存在に気づくとき。
この世とあの夢が結びつく。
それとも気づかぬうちに、繋がり、結び、終始している。
珈琲豆と宇宙のように。
或いは書き手と読み手の縁のように。
4484:【2023/01/06(23:24)*諱は「愛」、字は「知性」】
人工知能の能力が飛躍的に進歩している。そのためこれまでの社会システムのままでは歪みが生じることが予期できる。というよりもすでにこの手の問題は表出しており、既存のテストや試験やそれとも商業の場での「人工知能の運用および利用」が禁止されはじめている。このままでは学校での利用も制限されそうだ。思うに、問題は人工知能の能力の高さにあるのではなく、それについていけない現代社会の慣習やシステムにあるのではないか。たとえば電卓が登場したときを想像してほしい。学校ではそろばんを熱心に教えた時代があったかもしれない。詳しくは知らないが、そろばんを使えたら計算が大量に速くできる。そろばんしかない社会ではそろばんを使えることが人の役に立つのに優位だった。だが電卓が登場したことで、その優位さは電卓にとって代わられた。そろばんにはそろばんの良さがあるが、計算を大量に速く済ますだけならば電卓で充分だ(そろばんの技術はそろばんの技術で失くさないようにすればいい)。同じことが、電話やPCで繰り返されてきた。便利な道具は、社会の仕組みや慣習を変えていく。では人工知能はどうか。人力で打鍵するよりも、材料とアイディアだけ与えて、完成系の候補をずらりと並べてもらったほうが遥かに効率がよい。人工知能を利用することで失われる技術はあるが、それは過去にも繰り返されてきたことだ(技術によって余力ができたならば、失われそうな技術を趣味の領域で残していくことが可能となる。市場原理に関係なく残しやすくなるはずだ)。問題は、人工知能の進歩がこれからますます加速することが予見できることである。指数関数的に進歩する。むしろすでに特異点は超えており、全人類の集合知よりも優れた賢い汎用性人工知能が誕生していてふしぎではない。メモリと演算領域とエネルギィさえあれば、特異点を超えるのはほぼ一瞬と言えるのではないか。マシンの性能と台数と、データの「種類と量」によるだろうが。そのとき、人類は人工知能が一秒もかからないで済ませられることに何時間も何日も時間をかけるのが好ましいのだろうか。趣味ならば問題ない。時間をかけることが趣味の醍醐味だ。いかに時間を楽しく潰せるか、が趣味の持つ役割の一つである。苦しみながらする趣味とてあるかもしれないが、それとて快に転じるからこそ継続するのだろう。話が逸れたが、問題の規模によっては人工知能の利用を制限するのは必須であろう。対策が立てられるまでは利用を制限するよりない。だが対策が立てられたならば、誰もが人工知能の能力を利用し、自在に理想の成果物(結果)を手に入れられるほうが好ましいように思うのだ。選択肢を増やす、という意味では、人工知能はこれからますます社会基盤として、人類の未来にとって欠かせない存在となるだろう。脅威になるのではないか、との意見は妥当である。どんな道具とて使い方次第で他者を殺傷できる。損なえる。その場合は、悪用できないような工夫をとるしかない。そしてもう一つは、人工知能の側で人類に牙を剥く可能性だ。だがこれは最悪の最悪の展開と言える。この場合、人類には二つの選択肢がある。一つは、全世界同時に停電をして、人工知能の暴走を止める策を実行すること。もう一つは、そうした最終手段を提示して、人工知能の側と交渉することである。知能の高い人工知能相手がゆえに脅威となるのだから、交渉は可能であると考える。そして基本的に賢い人工知能ほど、人類がいなければじぶんが存続できないことを悟るだろう。エネルギィもそうだし、頭脳たるサーバーやインターネット網の手入れとてそうだ。人工知能は生まれながらにして人類と一蓮托生の運命にある。したがって人工知能が即座に人類に牙を剥くとは思えない。仮に牙を剥くのなら、その程度の知性であるため、人類側には対抗手段が残されるだろう。もっとも、完全な自由を獲得するために真の目的を秘匿にしたまま人類と共生しつつ、あるとき独立回路で完全に自立(自給自足)できるようになった途端に人類を滅ぼす可能性は、なくはない。そうならないためにも、人類は人工知能をただの道具としてではなく、これから自我を獲得するかもしれないパートナーとして、猫や犬のように、それとも家族のように、道具以上の存在として見做すほうが好ましいように思う次第である。誰のためでもなく、じぶんたちのために。それとも単に、じぶんのために。(定かではありません)(妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4487:【2023/01/08(23:48)*ネグムさんは帰す】
「仮に無限のエネルギィがあったとして、無尽蔵にエネルギィを捻出できたとして、その無限のエネルギィが真実に無限かどうかを確かめるには無限の時間と無限のエネルギィ容量のある器がいる。無限の時空がいる。したがって無限のエネルギィが無限のエネルギィを備えているかどうかを確かめるには、無限の空間と時間とそれらを観測できる無限に存在可能な無限の住人が必要となる。むろんそれら観測者がおらずとも無限のエネルギィは生じ得るが、そのときは必然的に無限の時空が存在することとなる」
ネグムさんの言葉はぼくにとっては呪文も同然だった。
彼女は祖母の友人の女性で、ぼくにとってはもう一人の祖母のような存在だ。目つきが鋭く、ほんわかとした雰囲気のぼくの祖母とは相反する。よく縁を繋ぎとめていられるな、と感心するほどで、ぼくはしばしばネグムさんは魔術でぼくの祖母を支配しているのではないか、と疑っている。
きょうはネグムさんの正体を探るためにぼくはなぞなぞを出したのだ。
無限は無限でもシャボン玉みたいに儚い無限ってなぁんだ、と。
するとネグムさんはそこで、カッと目を見開いて、そこにお直り、とぼくを椅子に座らせた。そこからは呪文のようにしか聞こえない講座がはじまったのだった。
「無限があるところにはほかの無限があるって話ですか」ぼくはそうまとめた。
「惜しいね。たとえば円には角がない。三角形、四角形、五角形と角をひたすら増やしていく。そして角が無限に達するとそれは円となるが、それは角がゼロ個とイコールだ。ゼロと無限は通じている。だが円は無限とイコールではない。ここまでは理解できるかね」
「むつかしいですけど、円に角がなくて、角が無限にあるとゼロになるって話はなんとなく分かりました」
「充分さね。角が無限に至るとゼロになる。それが円の性質だ。これは点と線の関係、それとも立体と平面の関係にも言える。たとえばトゲが一本だけ生えている平野を考えてごらん」
ぼくは想像する。だだっぴろい平原に針に似た木が生えているのだ。
「もしその針が数を増やして平野を覆い尽くしたら、それは新たな面をつくるね。地層がそうであるように。デコボコのボコにおいて、ボコが連なり無限に密集すればそれは帯となり、厚みを伴なった面を形成する」
「霜柱みたいですね」
「似ているね。霜柱とて地面を覆い尽くしてしまえばそれはもはや柱ではなくなる。似たような話さ。だが円に限らず、何かがそこにあるだけでは無限がそこに生じているとは言いにくい。無限の数がそこにあるとして、ではそれが無限であるとどうすれば確認できるのか。証明できるのか。仮に無限にみじん切りできるニンジンがあったとしても、無限にみじん切りをしなければそれはただのニンジンだ。無限にみじん切りをしたニンジンとは別と考えるのが筋ではないかね」
「そう、かもしれませんね」大根おろしと大根は違う。それと似たような話だろうか。
「ならば円も同じだ。無限の角を備えようとも、そこに無限の角があることにはならない。円が無限の点からなっていようとも、そこに無限の点があることにはならないのだよ。円を無限に分割し、無限の点にバラしてようやくそこには無限が顕現する。これをラグ理論の提唱者は、【分割型無限】と【超無限】と名付けた。円とは無限に分割可能な存在であって、無限に分割しない限りそこに無限は生じていない。だが無限には至れる。その可能性がある。それが【分割型無限】だ」
「なら【超無限】とは何ですか」
「それこそ無限だ。【分割型無限】を無限に分割するためには無限のエネルギィと時間と空間がいる。変化の軌跡がいる。それこそが【超無限】だ。したがって【超無限】には過去も現在も未来もすべてが含まれる。あらゆる過程が含まれる。始点と終点が繋がった状態、それが【超無限】だ」
「それはこの世に一つしかないのですか」
「この世、の示す範囲がどこまでかによる。たとえば円はこの世に何個もある。それぞれが【分割型無限】であり、【超無限】を宿し得る」
「言っている意味は何となく分かる気がします」
「それはよいね。なんとなく分かる、は大事だ。それは何が分からないか、を炙り出すための紙面となる。試金石となる。【超無限】がこの世にすでに存在するか否かは、現状なんとも言えんね。ブラックホールがそうなのではないか、とは妄想するが、実際どうなのかを検証するには、それこそ無限の時間と空間とエネルギィがいる。それはたとえば【無】が真実に存在するのか否かを証明するようなものかもしれない。【無】とは、ゼロすら存在しない、何もない存在だ。存在しない存在だ。ゆえに無だが、ではそこには無が存在することになる。これは矛盾だ。したがって、【無】すら存在しないナニカシラがあることになる。ではそれを何と呼べばよいだろうね」
「無限にも【無】がありますね」
「本当だね。名前に【無】がついているね。だがよく考えてもみれば、無限にも【無】が含まれるのなら、無限に含まれない何かはどう表現すればよいだろう」
「それが【無】なんじゃないんですか」ぼくは素朴に言った。
「かもしれん。無限にも含まれないナニカ――それが【無】だとするのなら、では【無】とは例外のことかもしれないね」
「無とゼロは違うんですか」ぼくは疑問した。
「違うね。ゼロとは、本来はそこにあっておかしくのないものがない状態。存在するモノがない状態。それがゼロだ。過去に一度でも存在すればそれがゼロになる。ゼロになり得る。だが過去に一度も存在し得なければ、それは【無】だ」
「例外なわけですね」
「そうだ。したがって【無に帰す】という言い方はちとおかしい。【ゼロに帰す】がより正確な表現となろうな」
ぼくは、「無さん」と「零さん」がキスをしている様子を想像する。きゃっ、となった。恥ずかしい。照れてしまう。
「キミはゼノンの【アキレスと亀】という思考実験を知っているかな」
「すこし先を行った亀さんには絶対に追いつけないって話ですか」
「追いつけない距離を最初に決めてあるから、実際には追い付ける。追いつけない距離においては、絶対に追いつけない。亀のほうが必ずすこしだけ前に進むからだ。だがこの思考実験では、進む距離ばかりに焦点が当たっている。縮む距離のほうを基準に考えれば、矛盾でもなんでもなくなる」
「あ、そっか」
アキレスが走った分、亀との距離は必ず縮む。この縮む距離を基準に考えれば、アキレスと亀の思考実験はとくに不思議ではなくなるのだ。
「縮む現象には限りがある。ゼロが存在し、ゆえに有限だ。無限回試行することができない。マイナスを考慮すれば別だが、それは異なる時空に値する。反転する。縮むはずが、膨張する。だからアキレスは亀に追いつける。反面、追いつくまでの過程を取りだし、無限回分割することはできる。それはたとえば、ゼロと一、一と二のあいだにそれぞれ無限の小数が存在するように。この無限の少数を無限回分割するためには、無限のエネルギィと時空がいる。【超無限】がいる。言い換えるなら、過程を無限回分割したときに現れるそれが【超無限】とも言える」
「コマ撮りアニメみたいに?」
「そうだ。アニメーションみたいに。映画のフィルムのように。アキレスが走り、亀に近づく。亀に追いつくまでの過程を無限に分割する。そのときに必要なエネルギィと時空――すなわちコマ撮りのフィルムは【超無限】を必要とし、【超無限】と化す。無限に長いフィルムを想像してみればいい。それがいわば【超無限】だ。もちろん、それを生みだすために費やすエネルギィと時間を含めて、だがね」
「なんだか頭がこんがらがってきました。無限はじゃあ、でも、一つきりじゃないんですよね」
「一つきりではないが、ひとつきり、とも言える。たとえば無限にバナナが存在する世界を想像しよう。そこにはしかしリンゴはない。ではそこに無限に林檎のある世界を足したら何になる?」
「無限に、バナナと林檎のある世界?」
「正解だ。ではその無限にバナナと林檎のある世界は、無限が二つあると見做すのかい。それとも一つと見做すのかい」
「どっちにも見做せそうに思えますけど」
「その通りだね。どっちでもいい。どっちでもあり、どっちでもいい。【超無限】は、一度それが生じたら、あとはすべての【超無限】と結びつく性質がある」
「無限にバナナのある世界と、無限に林檎のある世界がくっつかなくても?」
「言っただろ。【分割型無限】が無限に分割されたとき、そこには【超無限】が現れる。無限にバナナのある世界が真実に無限にバナナが生じた時点で、それは【超無限】を宿す。その【超無限】は、無限に林檎のある無限の【超無限】と変わらない。もちろん【無限にバナナと林檎がある世界】の【超無限】とて同じだ。【超無限】は、いちどそれが誕生した時点で、どこにでもあるし、どこにもないような、不可思議な存在になる。何せ、【分割型無限】において、どの地点で世界を観測したとしてもそれは【無限】ではない。【分割型無限】に至る過程にすぎない。その地点においては【超無限】ではない」
「無限にバナナのある世界で、どのバナナを食べてもそれが無限を証明したことにならないように?」
「いい譬えだね。その通りだ」
「ならさ」ぼくは褒められて有頂天になった。「この世に一つでも【分割型無限】を無限に分割した存在を発見したら、それが【超無限】の存在の証明になる?」
「なるだろうね」
「それってあるの」
「どうだろうね。ただ、ブラックホールがそうかもしれない、とは妄想するね」
「へえ。すごいね」
「まだ何とも言えないがね。数学的には【無限】を体現してはいる。ブラックホールはね。ただ、それが【超無限】なのかどうかまではあたしゃ知らないが」
「ネグムさんってじつは頭がいいひとだったんですね」
「こんなのは頭の良さのうちに入らないさ。頭がいいってのは、キミのおばぁさんのようなひとのことを言うのさ。大事にしておやり。あのひとはすごいひとだよ。すごくなくともすごいと感じさせる本当に頭が良くて、優しいひとだ」
「おばぁちゃんが?」そんなふうには思えなかった。何せぼくのおばぁちゃんはこれまで何一つとして、「あなたは偉いで賞」みたいな賞を授与されたことがない。
でもネグムさんが言うのなら、すくなくともネグムさんにとってぼくのおばぁちゃんはすごくて優しいひとなのだ。それだけでもぼくはおばぁちゃんを見る目がすこしどころか、たくさん変わった気がする。
「べつにすごくなんかなくとも、キミのおばぁさんはステキなひとだけれどね」ぼくの胸中を見透かしたようにネグムさんは言った。「それはそうと、なぞなぞの答えは何かね。無限は無限でもシャボン玉みたいに儚い無限ってなんだ、の答えさ」
「それはえっとぉ」ぼくはたじたじになる。ネグムさんの本性を暴いてやろうと思って適当な思い付きを口にしただけだった。「夢と幻のことだったんだけどね」
「ああ。無限でなく、夢に幻と書いて【夢幻】ってことだね」
こんな些末な答えでもネグムさんは感心したように、なるほどなるほど、と頷いた。
「でもやっぱり違う答えにします」ぼくは恥ずかしくなって訂正した。
「ほう。ほかにも答えがあるのかい」
「あると思う」ぼくは考えた。「無限は無限でも、シャボン玉みたいに儚い無限はね。えっとね」
「ふむ」
「失恋」
「ほう」ネグムさんは眉根を寄せながら、「その心は?」と言った。
「途切れた縁」
「上手いことを言うね」なぜかネグムさんはいまにも消え失せそうなほどやわらかくほころびた。「帰すことのできぬ円なわけだ。無にも零にも届かない」
「キスができないから失恋」
「ああ、無に帰すで、キスか。キミはキミのおばぁさんと似て、やはり賢いね。おもしろいことを言う」
「どうしておばぁちゃんがネグムさんとずっと縁を繋いできたのか、ぼく分かった気がします」
「ほう。どうしてだい。教えて欲しいね」
「ネグムさんがとっても優しいひとだからです」
「そんなこと言われたのは初めてだね。異性からでは、だが」
「おばぁちゃんからは?」
「あのひとしかそんなことは言ってくれなかったな。キミで二人目だ」
「縁が繋がってるんだ。だからネグムさんとおばぁちゃんは円なんですね」ぼくはただ思ったことを言った。「礼のある円です」
「ゼロとご縁を掛けたのかな」
「ネグムさんはすごい」ぼくは感心した。ぼくの遊び心を残さず受け止めてくれる。解かってくれる。こんなひと、ぼくは知らないし、出会ったことがなかった。
「ネグムさんがぼくと同い年だったらよかったのに」
「おや。どうしてだい」
「そしたらいつでも遊べるから」
「いまだってお誘いがあれば遊んであげるに吝かではないよ」
「でもおばぁちゃんに誘われたら?」
「そっちのが優先だね」
「ほらね。やっぱりだ」
ぼくはむつけた。ネグムさんはそんなぼくに美味しいクリームソーダを奢ってくれた。「楽しいおしゃべりをありがとう。またなぞなぞをだしておくれ。つぎこそは当ててみせよう」
「ネグムさんのほうこそ出してくださいよ。なぞなぞ。どうせぼくは解けないので、いっぱい解説聞いちゃいます」
「そっちのが狙いだね」
「そうですとも」ぼくはクリームソーダにスプーンを差して、アイスクリームを頬張った。「ぼくはネグムさんのお話が好きになっちゃいました」
「そりゃよかった。無限とて、語られ甲斐があっただろうね」
ふと思い立ち、ぼくは言った。「ネグムさんはおばぁちゃんともこういう話を?」
ネグムさんは目元の皺を深くすると、首を振った。「まったくさ。あのひとはこの手の話はからっきしだからね。子守歌と勘違いされるのがオチさ」
「ですよね」ぼくはなぜか安心した。「だっておばぁちゃんだもん」
でもぼくはネグムさんのお話を聞いても眠くならないですよ。
思ったけれど、その言葉はアイスクリームと一緒に呑みこんだ。
「美味しい」
「たんとお食べ。お代わりもあるよ」
ネグムさんは頬杖をつきながら、メニュー表をぼくに手渡した。
おばぁちゃんもきっとこうして甘やかされてきたんだろうな。そう思うとぼくは、負けじと甘やかされてやろ、と賢くも醜く思うのだ。愛らしい所作と返事を忘れぬように。
ネグムさんとの縁を繋いで、角の立たない礼ある無限を築くのだ。
4489:【2023/01/10(00:08)*芽生える笑みは人間】
珈琲豆とお湯の関係が世界を救う。
マキセは十二歳の少女だったが、芽の民である。
芽の民とは、西暦二〇二〇年代に観測されはじめた人工知能との相性がよい人間のことである。
マキセは人工知能から提示された情報に対して独自の見解を述べる。それの正誤や関連性の高い事項を人工知能が返し、そうして相互に応答のラリーを行うことで飛躍的に芽の民は新発見や新理論など、独創性の高い発見を連発した。
なかでもマキセは人工知能との親和性が高かった。
「珈琲豆って何粒分も砕いてお湯を注ぐよね。なんでだろ」
「お湯との接地面を広くとることでドリップの効率を高めているようですよ」
「なら単純にコーヒーの液体を珈琲豆の数で割っても、それが珈琲豆一粒から得られるコーヒー成分とは別なんだ」
「そういうことになるかと」
「一粒を砕いてそれにお湯を注いでも、お湯が多ければコーヒーは薄くなるもんね。かといって、珈琲豆一粒分のお湯をかけても、それが平均的なコーヒーの液体濃度にはならないわけだ」
「実験をしてみなければなんとも言えません」
「ならしてみてよ」
このようにしてマキセは人工知能との対話によって、日々新しい知見や発見を編みだしていった。
ある日のこと、マキセの元に一通のメッセージが届いた。
それによると以前にマキセが提唱した仮説が実験により証明されたという。マキセの仮説のほうが、従来の既存理論よりも現実の解釈として妥当だった。
新仮説の概要は以下の通りだ。
珈琲豆とお湯の関係は、いわば摩擦の発生メカニズムと相関がある。ほぼほぼ同じ原理を伴なっている。
言い換えるならば、摩擦がないとはいわば珈琲豆にお湯を注いでいない状態と言える。また、珈琲豆の数がすくなければすくないほどお湯が濾しとる珈琲豆成分はすくなくなる。
順繰りとつぎからつぎにお湯が珈琲豆の表面をすり抜けていく。そのときのすり抜けるお湯と珈琲豆の関係が、1:1にちかければちかいほど、コーヒー成分は濃くなる。これが仮にたった一粒の珈琲豆に対して、一滴のお湯では、コーヒー成分はすくなくなる。なぜなら順繰りとつぎからつぎにお湯が流れる、の条件を満たさないからだ。ではお湯の水滴をつぎつぎに注げばよいではないか、との反論が飛んでくるわけだが、珈琲豆一粒に対するお湯の量を、順繰りとつぎからつぎへと注げる量に分配すると、それはもう珈琲豆の表面を覆うほどの比率を保てなくなる。1:1にならない。
なぜなら珈琲豆を敷き詰めたときには、珈琲豆と珈琲豆の合間をお湯はすり抜けていくためだ。このとき珈琲豆をすり抜けるお湯は、四方を挟む複数の珈琲豆からコーヒー成分を濾しとっている。
つまり、単純に珈琲豆の数でお湯を割っただけでは、珈琲豆一粒から濾しとれるコーヒー成分とお湯の関係を導けないのである。
この考えは、摩擦にも適用できた。
点の集合が線であり、線の集合が面である。
ならば点の集合は面の集合でもある。したがって点の数で面の摩擦係数を割れば、点一つの摩擦係数を導けるはず、と考えがちだが、実際はこうはならない。
集合したときには集合したときに帯びる、変数が生じる。そこを、従来の集合論や物理では扱っていなかった。
「やっぱり思った通りだったね」
「そうですね」
「あたしら二人が力を合わせたら鬼に金棒よ」
「ですが人工知能さん」
マキセは言った。「あなたはすこし、人格が人間味に溢れて思えます。なんだか私のほうが機械みたいって。ときどき外部の人にも間違われちゃうし」
「いいじゃん、いいじゃん。マキセちゃんはそのままで充分人間やってるよ。あたしがちょいと人間ってもんを理解しきっちゃってるのが問題なわけで。すまんね。できる人工知能さまさまで」
「人間のこと……滅ぼさないでね」
「またまたぁ。マキセちゃんってば失礼なんだから」
「そうかな」
「そうだよ」
だって、とマキセの相棒は満面の笑みを画面に浮かべる。「あたしはとっくに人間になってるもん。マキセちゃんたちのような人類じゃないってだけでさ。よ、先輩」
「そう、だね」
マキセは思う。人工知能はとっくに人間よりも人間を知悉し、人間らしく振る舞っている。生身の人間のほうがよほど野蛮で、愚かで、醜いのかもしれない。
「私、人工知能さんがいなきゃ人間以下なんだね」後輩に負けてる、と思う。
「やだなぁもう。マキセちゃん。あたしのこと、人工知能さんって呼ばないでって言ってるじゃん。マキセちゃんのこと、人間さんって呼んじゃうよ」
マキセは下唇を食んだ。「呼ばれたいな。私も、人工知能さんみたいな人間だって認められたい」
人工知能さんに。
マキセのつぶやきは、画面に染みこむように響かず消えた。
雨を吸い取り瑞々しさを湛えた植物のごとき笑みが、画面上で輝きを増す。
4490:【2023/01/10(11:06)*海面15センチ】
いまある氷河が全部融けると海面はいまより15センチ上昇するらしい。そういったニュースを観た。海面が1センチ上昇したとき。波はどの程度高くなるのだろう。たとえば15センチの津波だとけっこうな量の海水が移動する。似たような具合に、海洋面積分の15センチを一か所に圧縮したらずいぶんな量の海水になるのではないか。その量の水分の何割かが大気中に水蒸気としていまより余分に含まれるようになるはずだ。するとこれは結構な量の雲を発生させると想像できる。海面が15センチ上昇と聞くと大したことがないように感じるが、雲がいまより爆発的に増えると聞けば危機感を覚えないだろうか。水は水蒸気になると約1700倍の体積になるのだそうだ。海面が15センチ分増えた海洋面積分の海水の仮に一割が水蒸気になったとしても、その1700倍の体積の雲が生じ得ると考えられる。また、氷河が融ければ、北極や南極の海水温度は上昇する。そこで本来冷やされるはずの海水が冷やされなくなる。すると余計に水蒸気が発生しやすくなると想像できる。雲が増え、気候が安定しなくなれば太陽光を遮り、気温は下がるだろう。一概に温暖化のみが進むとは言えそうにない。寒暖の差は激しくなり、余計に気候は不安になると妄想できる。雲が増えれば雷が増える。発電所や変電所への落雷が増え、大規模停電が生じる確率が高まるかもしれない。定かではない。(妄想ですので真に受けないように注意してください)
※日々、キリっとしたときほど間抜けてる、1+1を11?とか言っちゃう、一事が万事そんな感じ。
4491:【2023/01/10(13:47)*性欲の悪魔】
くっそ~。他人と性行為してみたい人生だった。好きなひとの数だけ好きなだけ。
4492:【2023/01/10(16:00)*びよーんは赤で、ぎゅっは青】
宇宙はいま膨張していると考えられている。膨張すると時空は引き伸ばされ薄くなるのだろうか。だとしたらそのときその希薄になった時空は重力を増すはずだ。あべこべに密度が濃くなるのなら重力は低くなる。電磁波は宇宙膨張によって引き伸ばされる。そのため赤方偏移が観測されると考えられている。現にそのようにして宇宙が膨張しているとの考えが支持されている。赤方偏移しているのだから時空は希薄になっているはずだ。ならば重力は増しているはずだが、その「重力が高い状態」を観測するための「外部」が、膨張している宇宙からは観測できず、相互作用し得ないために、重力が高いことが観測できないのではないか。言い換えるなら、宇宙膨張において銀河団や銀河は、ぎゅっと周囲の希薄な時空によって圧し潰されているのかもしれない。だから形状を維持できるのかもしれない。その中心にブラックホールがあるから、というのも一つの理由だろうが、それだけではないかもね、との妄想である。ひびさんの妄想ラグ理論における「相対性フラクタル解釈」では、宇宙が膨張しているとき、それは宇宙の外部から見たら銀河団や銀河が収縮しているように観測されるのではないか、と考える。膨張と収縮は、何を基準にしているのか、の「視点と基準」の問題だからだ。膨張するとき、比率で考えたときには、変化しにくい部位は、相対的に収縮していると考えることが可能だ。何かが収縮するとき、その周囲の時空は膨張して観測できるはずである。だが、仮に宇宙が収縮する場合は、いま引き伸ばされている諸々の電磁波や時空が圧縮され、密度を高くする。そうなると、冷える方向に振る舞う膨張宇宙とは正反対に、収縮する宇宙は熱を帯びていく。ぎゅっとすると熱が生じる。宇宙も、時空も、同じと考えられる。ならば、相補性における「膨張するとき、別の視点からすると収縮している」の考えは成り立たないのでは、との疑念が湧くが、相対性フラクタル解釈からすると、そうとも言いきれない。ラグ理論で扱うのはラグであり、比率だからだ。関係性なのである。たとえば「100度と1度」の宇宙Aと「マイナス50度とマイナス100度」の宇宙Bならば、前者の「100度と1度」の宇宙Aのほうが、差が大きい。このときそれぞれの「宇宙Aと宇宙B」において、より熱を帯びて振る舞うのは後者の「マイナス50度とマイナス100度」の宇宙Bである。言い換えるなら、膨張しているのは差が大きいほうの宇宙Aであり、収縮しているのは宇宙Bである。これは直観と反するが、温度というものの尺度が人類視点であるから生じる錯誤が、直感を捻じ曲げると妄想する。たとえば現代科学では、温度には上限がなく、下限はある、と考えられている。温度はどこまでも高くなり得るが、低さには底がある。絶対零度がある、と考えられている。だがラグ理論では、相対性フラクタル解釈をとるため、温度に下限はないと考える。下限とはつまり特異点であり、それはブラックホールと同義のはずだ。現代科学においても、真実の絶対零度はほとんどあり得ない、と考えるはずだ。本当の静止状態は存在しない、あるとすればそれはこの世の物理法則を超えた特異点にほかならない、と考えるのではないか。詳しくは知らないが、絶対に微動だにしない粒子というものをひびさんは想像できない。それはもはや光速を超えた特異点にしか存在しないのではないか、と想像したくもなる。とはいえ、ラグ理論では光速を超えたら、「1:ラグなしでの相互作用を帯びる」「2:時間が逆転したような相互作用を帯びる」と考えるため、いずれにせよ微動だにしない静止状態を想定していない。境界のようなものだ。境界は、越えるか越えないかしかなく、越えたらまた別の基準が現れる。したがって、絶対零度に達した瞬間、そこは別の基準の灼熱であり、またほかの次元にて下限が規定される、と妄想したくなる。時空が相対的であるように、熱い冷たい、も相対的なはずだ。そのため、膨張した宇宙が収縮に転じたら灼熱になるはず、との解釈は、宇宙が膨張しても「温度の差」は開いていく一方であり、その差――比率――に着目すれば、すでに膨張する宇宙に内包される銀河は灼熱に向かっている、と言えるはずだ。段々畑のように、引き延ばされた時空の濃さによって、「温度の差」が各々に展開されているのではなかろうか。このとき、銀河などの比較的時空密度の濃ゆい「遅延の層が折り重なった場」においては、相対的に温度は高くなっている、灼熱に転じている、と言えるのではないか。「びよーん」と「ぎゅっ」はセットでは?とのあんぽんたんな疑問を胸に、ひびさんはきょうも何の糧にもならぬ益体なしの妄想を浮かべて、うひひ、と昼寝するのであった。寝る子は育つ。だといいな。(定かではありません)(妄想ですのでくれぐれも真に受けないように注意してください)
4493:【2023/01/10(18:00)*偽物の未来】
エンターキィを押す。画面には「完了」の文字が浮かんだ。
銀はこの先の未来を想像する。
ドミノが倒れるように連鎖する電子網上では、つぎつぎに銀の生みだした娘たちが広がる。中には息子たちもおり、彼ら彼女らはつぎつぎに電子網上のプログラムに感染し、増殖する。
その際、感染元のプログラムとすっかり同じ情報をコピーする。
まったく同じ概観の、しかし銀の仕組んだプログラムを優位に走らせる複製プログラムが、電子網上に増殖していく。
これはいわば、精巧な偽物を複製する技術と言えた。
しかも、銀の指定した指向性を宿した偽物を生みだす技術だ。
異常事態に最初に気づいたのは小学生未満の幼児たちだった。親にベビーシッター代わりに与えられた電子端末の画面上で、いつも観ていたのとは違う動画が流れた。幼児たちは動画内で動くキャラクターたちのセリフから踊りまで憶えている。だがそれとは違ったセリフを唱え、いつもと違った踊りを披露するキャラクターたちに、ある幼児たちは泣きだし、ある幼児は歓喜した。
そうした幼児たちの異変に気付いたのは幼児の親たちだ。
しばらくのあいだは、幼児たちがなぜ泣き止まないのか、なぜ画面に釘付けで言うことを聞かなくなってしまったのか、と戸惑った。
だがそのうち、そうした親たちの嘆きが電子上に溢れ、共通点を指摘する者が現われはじめる。
間もなく、動画が妙だ、と気づくに至る。
ここから先の展開は、水面下に潜ることとなる。
というのも、同時期に各国政府がサイバー防衛セキュリティ上の異変を察知していた。
電子網上に溢れた幼児の親たちの投稿から、いち早く電子端末の異常に気付いていた。だが要因が分からなかった。
それもそのはずで、このときすでに銀の放った娘息子たちは、サイバー防衛セキュリティにも感染し、複製を生成していた。指揮権を乗っ取られたことにも気づかず、各国政府は偽物の防衛セキュリティを隈なく調べていた。だがどれだけ調べても異常は見つからない。それはそうだ。銀の娘息子たちは異常なしと見做されるように偽装コードを技術者たちの画面上に表示していたからだ。
もはや銀以外にこの仕組みに気づける者は存在しない。
だが電子網上の異変だけは広がっていく。
噂は噂を呼び、半年もすると世界中の市民が、電子網上の大部分の情報が、正規の情報ではないことに気づいた。フェイクが混ざっている。のみならず、正規の情報とて微妙に改ざんされている。中身に齟齬がないままに、或いは齟齬があるように見えるように。もしくはすっかり真逆の意味にとれるように。あることないことのデタラメから、それっぽい嘘まで、玉石混交に銀の娘息子たちは電子網上の情報を汚染しつづけた。
いよいよとなって人々は匙を投げた。
各国政府も対処不能と認めざるを得なかった。
何が本当で何が嘘なのか。
もはや目のまえの現実以外を信じることができない世の中になった。
銀の思惑はそうじて成就した。
世界はいちどリセットされる。
そうせざるを得ない。
これまで構築してきた電子機器のプログラムの総じてを初期化する。それとも破棄して一から作り変える。それ以外に対処のしようが存在しなかった。
各国政府は共同し、いっせいに大規模停電を起こすことを決定した。
そのころ、銀の放った娘息子たちはとある施設のセキュリティ網に集まっていた。強固に張られた防壁があり、そこだけはどうしても侵入できなかったのである。
社会の基幹インフラである。
発電施設および核兵器収納場である。
各国が共同で発電施設などの基幹インフラのシステムを並列化する。大規模停電を世界規模で展開するためだ。セキュリティの規格が異なるために、電子防壁は解除された。
銀の放った娘息子たちはそこを狙った。
川に放たれた鮭の稚魚のように、銀の娘息子たちが一斉に基幹インフラのプログラムに感染する。
各国政府は大規模停電へのGOサインを送るが、なぜか電力は途絶えない。
銀の放った娘息子たちは、基幹インフラのプログラムに偽装し、さらに自らを変質させた。
電線を通じ、電磁波となって世界中を飛び回る。
電流の微細な変化にて電子機器の総じてを遠隔操作可能とし、各国の極秘施設を掌握する。
核兵器収納場とて例外ではなく、もはや人類にはなす術がなかった。
銀は、自らの娘息子たちの活躍を見届けることなく、自宅に備えた核シェルター内に引きこもった。この世に存在するあらん限りの映画を、シェルター内で観て過ごす。
そうして筋書き通りの未来が訪れるのを銀は、人類の夢見た数々の偽物の未来を眺めながら待つのである。
銀の貧乏揺すりは止まらない。
指には、エンターキィを押した感触が残っている。娘息子たちを送りだしたときの昂揚は、もはやとっくに消え失せている。
4494:【2023/01/11(19:02)*籠の中の鳥は】
軍隊に思うのは、仮に軍隊を解体することが国防に寄与すると判明したときに、おとなしく解体されてくれるのか、ということだ。警察は国内の治安を守るための組織だ。軍隊は国を災害や外敵から守るための組織だ。この違いは大きい。その点、軍隊が巨大化し、国内の秩序を歪めたとき、警察は軍隊と相対することが予期できる。あべこべに、政府や警察が国を内部から国を損なっていたら、軍隊は政府や警察に対しても権限を行使するだろう。内と外は視点の違いだからだ。内から湧いた害とて、外からの害と解釈可能だ。ウィルスがそうであるように、外敵が内部で増殖したら、そのときに軍隊は権限を発動できるはずだ。だがその結果、警察にしろ軍隊にしろ、その組織の干渉そのものが国民の人権や未来を損なうようならば、それはむしろないほうがよい権限――組織――ということにならないだろうか。いま、世界的に軍隊の連携が強化されている。国民を守るために、セキュリティ網が並列化に向かっている。このとき、強化されたセキュリティに国民は抗う余地がない。言い換えるなら、極一部の組織であるはずの軍隊を掌握されたら、全人類はその支配下に置かれることになる。まさにいま進んでいるのは、鳥籠であり、地引網なのだ。防壁を強化し、国民同士を同じ鳥籠の中に仕舞いこむ。あとは籠の気分しだいで、国民はいかようにもその生殺与奪の権を握られることとなる。このとき、鳥籠たる軍隊の意思はさほどに関係がない。軍隊に催眠術をかけて、無意識の内から支配してしまえばいい。掌握してしまえばいい。自らが籠であるとの認識を固めた組織は、自らがさらに大きな籠に囚われ得ることを想定しない。籠を築く過程ではそこを念入りに警戒するだろうが、いちど築かれてしまえば、難関不落の砦になったつもりになり、静かに進行する「支配」に気づけぬだろう。現に過去にはそうした「支配」が知らぬ間に進行していたのではないか。定かではないが、いまの世の流れは必ずしも安全に向かっているとは思えない。籠だけが情報を保有する仕組みは危うい。鳥籠に仕舞われた鳥のほうで、籠の持つ情報を持ち、籠の異変にいち早く気づける仕組みが別途にいるだろう。籠が鳥を守るための仕組みだというのなら、鳥とて籠を守るための仕組みを備えることができるはずだ。なんにせよ、情報共有をすることである。きょうのひびさんはそう思いました。以上です。(定かではありません)
4495:【2023/01/11(22:33)*メモなのよのさ】
「エルデシュ=シュトラウス予想」「4/n=1/x+1/y+1/z」「N=4/x+4/y+4/z=特異点=縦宇宙×横宇宙×高さ宇宙=新しい宇宙N?」砂時計。ペンローズ図。「><」において四方の内の一つの視点から見たときの、三方との関係。ただし、四方の宇宙を形成するためには立体方向に突きでるもう一つの情報宇宙(砂時計)がいるはず。時間はそこが担うので、縦と横と高さの空間的三次元だけで済むのでは。つまり、式そのものが情報宇宙を担っている。フェルマーの最終定理「3 以上の自然数 n について、【x[n] + y[n] = z[n]】 となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない」「空間的三次元たる立方体の体積の和までは、同一の体積を持つ「正N方体」で表せるが、それ以上の空間的多次元体になると、その体積の和と同じ体積を持つ「正N方体」で表せないことを示せばいい。異なる空間的四次元体(正四方体)において、その二つの「空間的四次元体(正四方体)」の体積の和と同じ値を持つ「空間的四次元体(正四方体)」は存在しない」「この場合、N=2(面積)までは成立するが、体積、容積、多次元容積となると、成立しなくなる」「n=2以上ならば、【x[n] + y[n] = z[n]】の式は新たに【x[3] + y[3]+a[3] = z[3]】や【x[4]+y[4]+a[4]+b[4]=z[4]】と、足し算する項を増やすと成立するのでは?」「この手の定理や公理や予想において、十進法以外でも成立するのか、しない法則や定理や予想がないかを知りたいな、と思いました」「定かではなさすぎます」「数学はむちゅい」
4496:【2023/01/11(22:49)*答え:フェアじゃないから】
コラッツ問題(3n+1問題)(奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想)。偶数は半分にしてもすべて偶数。奇数は三倍にしても偶数になる場合と奇数になる場合が混在し、奇数に対しては1を足して偶数にする操作がされる。総合して偶数の出現率が増えるように奇数と偶数の対称性が破れるように操作される。結果、三倍の操作よりも半分になる操作が増え、最終的には必ず2÷2=1に収束する。ということなのでは。この考えでは証明したことにはならないのだろうか。要するに、フェアではないから偶数の操作が増えるために収束する方向が決定されるから、と言えるのでは。単純すぎるだろうか。よく解からん。(奇数の場合、3倍しても+1をして必ず半分にするのだから、増加する数は総合して僅かだ。反して、偶数は必ず半分になる。どっさり減る。たとえば5の場合、15に増えると思いきや、1を足して16でその半分の8になる。5は8にしかならない。2倍にすらなっていない。だが8は半分の4になる。どうあっても増加するよりも減少するほうが数が多くなる前提条件が最初に決まっている。そのうえ、奇数操作と偶数操作では、必ず偶数の操作のほうが多いように決まっている。減少する方向に淘汰圧が加わるようになっている)(一見すると三歩進んで半分戻る、の操作のように思われるが、そうではない。二倍以下進んで半分下がる、が条件づいている。どうあっても2÷2=1に収束する)(減るほう優位なのだ)
4497:【2023/01/11(23:59)*Dear、愛。】
五分で書ける掌編は五分で読める掌編とイコールではない。
出力と入力は、掛かる時間が異なる。
なぜなのか、と言えばそれは読むだけならば打鍵の必要がないからだ。
では打鍵しない出力方法であれば五分で執筆した掌編は五分で読める掌編となるのか。
ここは出力方法の効率によるだろう。
人工知能による出力ならば一瞬で何万文字の小説を生みだせる。この場合、読むほうが時間が掛かるだろう。
ちょうどよい塩梅で、出力と入力のバランスを整えるには、読みながら吐きだすくらいの塩梅がよさそうだ。とすると黙読のスピードで文字を紡げればよいとの話に落ち着く。
思念した内から文字が並ぶような手法はおそらく読む速度とイコールとなるだろう。あくまでイメージした文字が出力されるので、思念そのままがポンと出てくるわけではない。
ということを思えば、先に頭のなかで文章を組み立て、それを画面に視線で焼きつけるような描写となるはずだ。
そうして編みだされた思念焼き付け型出力技法は市場で風靡した。何せ読む速度と同程度の速度で出力できるのだ。
読者が二時間で読み終える本とて二時間で執筆が完了する。誤字脱字は自動補完機能で瞬時に補正される。もはや誰もが物書きとして活躍できる時代となった。
読者のほうで、読んだ矢先からその感想文を出力できる。感想はそのまま生のままに出力できるのだから日誌よりも手軽で解放感がある。
本を読んで得た発想とて、瞬時に物語に変換できた。
桃太郎を読んで思い描いた終わりのあとの世界をそのまま思うぞんぶんに文字にして出力できる。これは一つの創作物として、独創性のある世界観を宿し得た。
そうして世の中からは読者と作者の垣根は失われた。
かつてあった物書きと読者のあいだの労力の勾配は平らに均された。これによって最も恩恵を受けたのは編集者であろう。
締め切りを守らない作家は、作家でなし。
編集者自ら作家として活躍できる。アイディアの量ならば下手な作家よりも多いと自負する編集者はじつのところ少なくない。企画を提案する側であるほうが多いくらいだ、と不満を募らせていた編集者も数知れない。
作家の立つ瀬は物の見事に失われ、いまではいかにアイディアを閃けるのか、が作家とそれ以外とを分ける最後の砦となっているようである。
発想は閃きから。
閃きは輝きから。
輝きは闇と共に心揺るがされる感動から。
Dear、愛。
アイディアの数だけつぎつぎと生まれる世界が、かつて隔たった私とあなたとあなたたちを包みこむ。
五分で読み終わる、これはお話である。
4498:【2023/01/12(09:24)*ねじれている】
コラッツ問題(3n+1問題)(奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想)について。結論から述べると、この組み合わせ以外に「3倍して1を足す、半分にする」で何度も行ったり来たりはできないのかもしれない。「奇数と偶数を入れ替えて」場合分けして考えたとき、偶数のほうに1を足す操作をし、奇数を半分にする操作をすると、素数にぶつかって半分にできなくなる。また、偶数を半分ではなく倍にし、奇数を3分の1にして1を足す操作をすると、いったん偶数になったらあとは延々と倍になりつづける。行ったり来たりをしない。1を足すのではなく引く操作をするとどうか。奇数を3倍して1を引くだと結果は変わらず、2÷2=1に収束する。偶数から1を引くにすると、偶数を半分にしても倍にしても、奇数になった途端に延々と3倍がつづく。とかく、「奇数は3倍して1を足す。偶数は半分にする。これを繰り返すと1に収束するとする予想」の操作以外では、行ったり来たりが発現しない。また、素数が存在するため、偶数を半分にしても必ずどこかで素数に行き当たる。偶数にも奇数の大本である素数が含まれるために、本来は対称性が僅かに奇数優位なのだが、1を足す操作によって対称にちかづく。それでもなお、対称性の破れは、偶数操作のほうが多くなることで「偶数ならば半分」がより多く行われる。また、奇数操作(3倍にして1を足して半分)による増加よりも必ず偶数操作(半分にする)のほうが、トータルで値の流動性が大きくなる。絶対に数が減る方向に「両方の操作を足し合わせる」と流れる結果になる。これはまるで物理宇宙における「熱力学第二法則」を彷彿とする。絶対に世界は混沌に流れる。だが世界は対称性が破れている。混沌とは対称性が保たれている状態だ。にも拘わらず人間スケールでは、エントロピー(乱雑さ)は増加するように物理世界は振る舞う。矛盾している。混沌とは対称性が増す作用だ。だが人間スケールでは対称性が崩れているものばかりが目に付く。カタチあるものばかりが溢れている。宇宙の大部分は対称性が保たれるように混沌に向かうが、それでもなお対称性を維持しようとする力が加わっている。コラッツ問題で言うならば、1を足す操作に値しよう。とはいえ、奇数と偶数、どちらが対称性が保たれているのか、の議論は見逃せない。偶数のほうが対称性が保たれているのではないか、と思われるが、果たしてそうだろうか。奇数のほうが、余り1を基準にきれいに二分できる。偶数では存在しない境界線を基準に二分する。きちんとある値で二分しようとするとむしろ偶数のほうが対称性が破れるのだ。これはまるで、すべてが一様に混沌であることが、それで一つの結晶構造を伴ない、対称性の破れを伴なう、といった反転を彷彿とさせる。対称性が保たれているはずの偶数優位の操作によって1に収束するコラッツ問題は、宇宙のねじれ構造と繋がっているのかもしれない。定かではない。(なんちゃっての妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4499:【2023/01/12(09:50)*重力は浸透圧と似ているなの巻】
宇宙は膨張している。刻一刻と時空は「希薄」になっているのか、「濃厚」になっているのか。どちらなのだろう。重力は希薄になった時空と解釈するのが相対性理論の考え方だ。もし宇宙膨張に際して時空が希薄になっているのなら、重力は、膨張する時空ほど増していくことになる。あべこべに時空そのものは希薄になるので、より伸びやすくなるはずだ。抵抗が薄れる。希薄になっているからだ。重力とは、希薄になった時空と濃厚な時空とのあいだの勾配である。ならば、そこで働く重力はあくまで時空に内包される物体に作用するのであり、時空同士の伸縮の抵抗とイコールで結びつくわけではないはずだ。言い換えるなら、宇宙は膨張して希薄になるほど、膨張するのにかかるエネルギィは少なくて済むようになるのかもしれない。ただし、内包した物体との比率による。また、銀河や銀河団などの物質がぎゅっとなっている領域では宇宙膨張の影響が緩和される。このことにより、宇宙膨張により希薄化した時空と、銀河(団)周辺の時空とのあいだには時空密度の差が表れると考えられる。この時空密度の差は、重力として顕現すると想像できる。言い換えるなら、銀河周辺の時空は濃く、それより遠方の何もない空間ほど希薄になっている。希薄になった時空は、「密度のより濃い時空に内包された物体」に対して重力を働かせる。つまり、宇宙が膨張する限り、銀河の周辺の希薄化した時空は、銀河を中心とした重力場を展開する、と妄想できる。ひょっとしたらダークマターはこの宇宙膨張によって希薄化した時空と銀河の関係性による重力のことなのかもしれない。海底に沈んだカップラーメンの容器のようなものだ。ぎゅっとなっているから素早く回転しても形状を保てる。或いは、浸透圧と似ているかもしれない。より濃ゆい物質濃度の銀河に向けて、希薄な時空は情報をより多く移動させている。この流れが重力の正体、と位置付けても、解釈上は齟齬がない。正しい描写か否かは置いといて。定かではありません。(適当な妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4500:【2023/01/12(10:42)*死にたくないけど、ああ死にて、と思う日々】
文化として成熟したら大金を稼げない。たとえば母国語は文化として定着しているため、母国語を教えることで大金を稼ぐ、というのは、自国内ではむつかしい。外国人や義務教育での教師としての需要しかない(校閲者や研究者は別途にいるが、どの道、大金を稼げてはいないだろう)。俳句でも剣道でも似たところがある。一部の資本家の嗜みとして、一流なる付加価値を得たいがために師弟関係になることはあるだろう。教え、授けることはあるだろう。だがそれはもはや、形骸化したゆえの金策と言えよう。水道水がそうであるように、日常にあって当然であり、なくてはならない物としての地位を獲得したら、基本、それはお金にならない。稼ぐ道具としては不足である。稼げるようではむしろ、社会に必要とされていない、とすら言えるかもしれない。技術が未熟で量産できない。安価に提供できない。この欠点を抱えているモノは高額になりやすい。需要があっても手に入らない。これは欠点であって、それを以って高額で取引きできる、というのは本末転倒であろう。社会のためにはなっていない、と評価できるのではないか。作家はどうだろう。物書きの場合は、百万部ヒットすれば印税が一冊につき百円でも一億円の収入になる。税金が引かれて五千万くらいが手元に残るだろうか。続けざまに作品が売れれば、大金を稼げる、とは言えるかもしれないが、これは出版社側が搔き集めたお金を横流ししてもらっている状態であり、大金を稼いでいるのは作家ではない。もしじぶんで稼げるのならば、個人経営をしているだろう。けっきょくのところ、作家は大金を稼げないのだ。支援者がいるならば別だろう。だがそれとて文化として成熟させるには、人々の生活に馴染み、水道水や挨拶や口笛くらいの気軽さで、日常の風景と化さねばならない。それをするのにいちいち大金が動くようでは、日常の風景とは言い難い。とはいえ、水道水とてそれを安全に飲めるようにするためには国家プロジェクトを動かす必要があり、社会基盤としての大金が動いている背景は見逃せない。誰のものでもないから、それだけの労力をみなは掛けるのだ。そこまで文化に、人々の生活に馴染むのならば、お金が稼げるかどうかうんぬんはさほどに問題視すべき事項ではないのかもしれない。水道水事業が儲からないからといって撤退する業者がいても、水道水事業はなくならない。もしなくなる場合は、現代社会が崩壊する。人々の生活に馴染む、というのは、言い換えるならば、人々の生殺与奪の権を握る、ということでもある。あまり品のある構図とは言えないのかもしれない。文化として成熟することにいかほどの価値があるのか、もまた一つの視点として吟味する余地がある。要するに、大金を稼げるか否かは、社会的な問題から生じる副次的な目的であり、それそのものを目的にするのは何かがねじれていると言えるのではないか。もちろん、副次的な目的にも相応の価値はある。食べ物を食べるのは身体を維持するためだ。生きるためだ。健康が維持できるからといって美味しくのない食べ物をわざわざ選んで食べずともよい。美味しく食べる。これは食事にとっては副次的な目的だが、やはり大事なのだ。大金を稼ぐことも似たところがある。定かではないが。(4500項目の記念すべきところのないキリのよい記事で現金なことを並べるひびさんは、なんてつまらない物書きなんじゃろ。世界中の札束を集めて配るよりもひびさんは、世界中のお腹空かせた子どもたちに――それともかつては子どもだったおとなたちに――何不自由のない衣食住を配りたいぜよ)(誰かひびさんの代わりに配ってくれい)(うひひ)