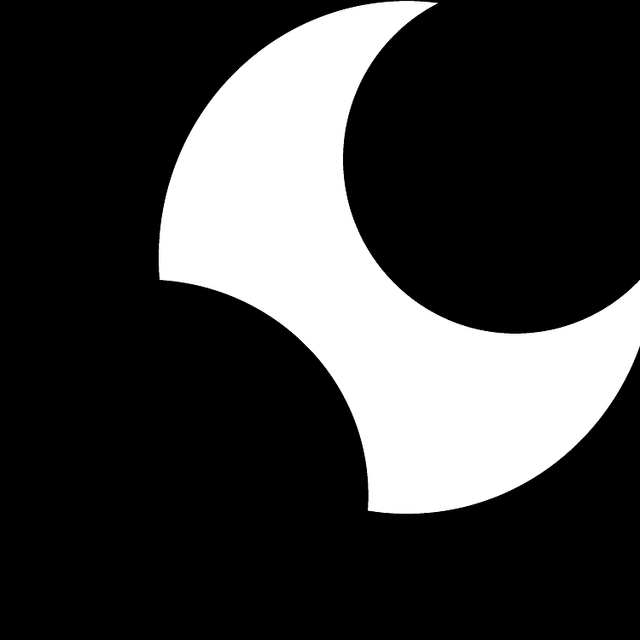日々記。【4501~4960】
文字数 810,736文字
※日々、うんざりには底がなく、満足の底は浅い、満たされた矢先からうんざりの穴を落ちていく。
4501:【2023/01/12(11:56)*裏筋をなぞると。】
ゲームのことが嫌いになった。
二〇二二年のことである。
ゲームとは縁のない生活を送っていたぼくであるけれど、ゲーム自体は好きだった。すればハマるに決まっている。きっと昼夜問わず寝食を忘れて没頭するだろう。だからこそ距離をとっていた節がある。
制御をかけていた。
ぼくは油で、ゲームは火だ。混ぜるな危険なのである。
だが期せずしてぼくは二〇二二年にゲームに触れることとなった。顛末を最初から最後まで話しはじめたらそれこそ一年間かかることになる。
毎日のようにぼくはゲームに没頭した。
ではそれで残ったものが何かあるのか、と考えたときに、はたと我に返るのだ。
何もない。
ゲームに没頭したところで手元には何も残らない。
思い出が残るじゃないか、との声が聞こえてきそうだが、そんなものを欲しがったことは一度もない。ぼくは思い出を求めたことはない。
なにせ楽しい思い出ならばいくらでも自力でひねくりだせるのだ。
ぼくはアマチュアだが物書きでもある。
空想狂が高じて、いくらでも妄想していられる。ゲームに頼る必要がない。
これは小説にも言えることだ。
わざわざ他者の空想に浸る必要がぼくにはない。ただ、ぼくは物知りではないので、言葉を知らない。知識もない。だから取材感覚で本を読むことは日常茶飯事だ。
かといってそれが小説でなければならないとの限定はなく、ゲームである指定もない。
何かをしなくてはならない、との強迫観念をぼくは蛇蝎視している。
目の敵にしている、と言ってもよい。
強制されることが何より嫌いだ。
死ね、とすら思う。
約束を守らないことと同じかそれ以上に、強制されることが嫌いだ。
どんなに好きなことでも、やれ、と命じられたらやりたくなくなる。どこかで相手の意にそぐわないことを混ぜたくなる。
だから余計にぼくへの強制力は増すのだろうか。分からない。
ゲームも似たところがある。
筋道がすでにあり、そこを辿らないと次のステージに進めない。
ぼくはそういうすでに存在する段取りをなぞるのが嫌いだ。
段取りをなぞっているのだ、と気づくたびに、嫌気が差す。勉強と同じだ。すでに答えがあるのならぼくがそれを導きだす必要がない。
いや、よいのだ。
ぼくがそれをしたくなったのなら、たとえすでに答えのあることでも、ぼくはそれをする。するな、と言われても手を伸ばすだろう。
だが、やりなさい、と言われたことで、ぼくがせずとも誰かが代わりにこなせることなら、その人に任せればいいじゃん、と思ってしまう。
現にぼくがせずともほかの誰かがやる。
ゲームも同じだ。
ぼくがせずとも誰かがゴールをするし、すでにゴールが決まっている。
設計されている。
ならばなぜ解かねばならぬのか。
解いてもいいが、強制されるいわれはない。
勉強と同じだ。
無理やりさせられている。枷をはめられている。
そうと気づいて、ぼくはうんざりした。
これがゲームならばぼくはゲームが嫌いだ。この世になくていい。
すくなくとも、ぼくの世界には存在しなくていい。消えて欲しい。そう思った。
ぼくはぼくのしたいことだけをする。ぼくにゲームを強制した連中には天誅を下す。天誅がダメならば、拳銃を放つ。
物理的に殺傷するのも辞さない心構えだ。それがぼくに何かを強制する者の末路だ。知らしめなければならない。
そこでぼくの恋人は、ぼくに言う。
「あなたにそうされたくて敢えてゲームを強制する人たちがいたらどうするの」
「ぼくに殺されたくてってこと?」
「そう」
「だとしてもだな」ぼくは仕事で使ったばかりのナイフを研ぎながら、恋人に言う。「ぼくはぼくのしたいようにする」
4502:【2023/01/12(12:18)*いーんたい!】
予定通り、おそらく今年で郁菱万は引退する。すでに半分引退しているので世への影響はないだろうし、引退せずとも世への影響はないだろう。そういうふうに過ごしてきたので、思い通りの物書き生活だった。とはいえ、引退するのはあくまで郁菱万の名だけであるので、どこかでまた細々と変わらずに駄文を並べて過ごすのだろう。単に過去のテキストの管理が面倒になったのでリセットする、と言い換えてもよい。去年にいくらか過去作を消して整理し直したのも、面倒に思う操作をせずに済むようにじぶんの負担を減らすためだ。これが正解だった。だいぶ楽になった。それでも投稿サイトを二つ持っているだけで、誤字を直すだけでも、2サイト+手元のバックアップファイル数を直さなければならないので、結構な手間がかかる。投稿サイトは基本一つでいい気がしてきた。つぎの筆名を悩んでいるが、候補としては「月音日々」か「めたみねね」か、もっと練った名前にする。いっそ名前がなくていい気もしてきた。我、でもいいかもしれぬ。無、でもいいかもしれぬ。「我無」とかどうだろう。ガムさん。十四歳のひびさんに見せたら、かっくいいって目を輝かしてしまいそうな名であるな。引退してもすぐには新しく活動せずに、つくりかけの物語を閉じる時間を置くかもしれぬ。たぶんそうなるな。郁菱万作品はだから、引退してもすこしだけ増えることになる。三年くらいはサボりながらつくりかけを手掛けることになるかも。そのあいだにほかに文字の積み木遊びよりも面白そうなことを見つけたらそっちに軸を移すかも。たぶんそうなる気がする。物書き界隈からは距離を置きたい気分が年々募るので、たぶん今以上に細々となる予定だ。早くひびさんも、わーい友達いっぱい、になれる世界線に移行してみたいな。で、早く孤独になれる世界線に移行してみたいな、の繰り返しで、けっきょくはいまが一番よいのである。理想通りの思い通り。ひびさんは、ひびさんは、欲深き迷子なのであった。定かではない。
4503:【2023/01/13(06:40)*詰みでは?】
西に陰陽山と呼ばれる山がある。山頂にはひっそりと神社が建っており、参拝客は年に数人あるかどうかという秘境であった。
参拝客がすくないにも拘わらず境内は綺麗だ。山頂とは思えぬほど緑に溢れ、あたかも麓にいるかのような錯覚に陥る。
「本当にここなのかな」
ここに一人の参拝客がある。彼は陰陽神社の噂を聞きつけ、遠路はるばる東の地によりやってきた。
「何でも願いが叶う神社なんて。でもなあ。本当に先輩、宝くじが当たってお金持ちになったし」
宝くじを当てるんだ、と豪語していた先輩がいた。長らく外れクジばかりを引いていたが、ここ陰陽神社を参った直後に見事一等クジを引き当てた。いまでは毎日方々を旅して豪遊している。豪邸を買うよりもホテル暮らしのほうが却って安いと言っていた。お金持ちならばそうなのかもしれない、と感心した覚えがある。
拝殿のまえに立ち、彼は財布から紙幣を取りだした。
この国で一番高い値のつく紙幣だ。賽銭箱に投げ入れ、二礼二拍手一拝をする。
「罪を背負わずにすみますように」
それが彼の願いであった。
目をつむる。数秒祈ったが、これといって変化はない。
ひとしきり風景を目に焼き付けると彼は陰陽山をあとにした。
しょせんは風説だ。効果を期待してはいなかった。やらないよりかはマシだろう。その程度の酔狂だったが、旅費と賽銭に月の食費ほどの金額をかけるくらいには藁にも縋る思いではあった。
というのも彼はこれから犯罪に手を染めなくてはならなかった。好いた相手のために人肌を脱ぐのだ。じぶんの手が汚れて思い人の未来を守れるならば軽いものだ。
そうと奮起したものの、できれば背負う罪は軽いほうがいい。
軽ければ軽いほどいい。
そういうわけで陰陽神社へと出向いたわけだが、それで何が変わるわけでもない。
彼は計画通りに、とある人物を社会的に抹殺した。
本来ならば物理的にも命を奪うことも辞さない心構えだったが、そこまでせずとも済んだようだ。相手のほうで人生の大半を費やして重ねてきた財産を手放したようだった。自己破産だ。
良かった。
彼は思った。
運よく法を犯さずに済んだのだ。罪は罪だが、違法ではない。
すくなくとも罪悪感を抱くだけで、社会的に未来は損なわれずに済んだ。
ひょっとして陰陽神社に参ったからだろうか。
解からない。
だがひとまず難関を突破した。
とはいえ、じぶんが想い人のそばにいれば怪しまれるだろう。逮捕されることはないが、白目で見られたり、理不尽な噂が立つかもしれない。
彼は遠くから想い人を見守る日々を送った。
つつがなく日々が流れる。
しだいに彼は確かめたくなってきた。
じぶんがただ運が良かっただけなのか。
それとも、陰陽神社の加護があるからなのか。
まだ加護は効いているのだろうか。分からない。分からないが、どの道一度は腹をくくった身の上だ。
想い人はまた難儀な厄介事を抱えているようだった。
接点を結ばぬ内に肩代わりしてあげるのがじぶんにできる最善だ。彼はふたたびじぶんの手を汚すことにした。
具体的にここに彼の犯した違法すれすれの詭計を書き連ねてもいいが、彼自身がそれら詭計を推理小説や犯罪小説からヒントを得て立てたからには、ここにそれを並べ立てると剽窃になり兼ねない。
したがってここでは、彼がひとまず他者の日常を激変させた事実だけを保障しておくに留めよう。彼が標的にした者たちはみな職を失い、友人関係を断たれ、今後二度と社会的信用を得ることはない。
ふしぎなことに一向に彼が咎を受けることはなかった。のみならず厄災が皆無なのである。棚の角に足の小指をぶつけることもなければ、間違って友人の彼女と浮気をしてしまっても却って身体の相性がよく、異性間でよい噂が立った。
マッサージ感覚で性行為をせがまれることもあり、そうしたときは礼儀として断りながらも、相談に乗る体で酒を飲み交わし、アルコールのせいにして互いにいい思いをした。
痴情のもつれが生じそうなものの、一向にその気配はない。
彼は調子に乗った。
これはもうこういう星の下に立っているのだとじぶんの運の良さを確信した。
違法でなければ罪にならない。彼はそれを度重なる幸運により体験的に学習した。どうあっても損をしない。狙い通りに対象の人生を、未来を損なえる。
彼からは逡巡も葛藤も失せていた。
罪を背負わずにすみますように。
まさに願い通りである。
罪の意識はなく、背負うべき呵責の念も皆無であった。
暇つぶしに、いつもの習慣で、なんとなく時間が余ったからとの理由から彼はしだいに他者を損なう遊びを行うようになった。逸脱した自覚はなかった。どちらかと言えば社会から逸脱した者たちに天誅を下している認識だった。
「ぼくは違法じゃないけど、あの人たちは違法な行為をしてなお開き直っている。ああいう手合いは心優しい人たちを傷つけてばかりだ。百害あって一利なしだね」
じぶんが悪だとの自覚はあった。善ではあり得ない。
だが同時にじぶんよりも邪悪な存在に立ち向かえるのはじぶんしかいないとの自負も育っていた。
必要悪だ。
邪悪に触れていいのは善に満ちた正義のヒーローなどではなく、悪にまみれた外道である。彼は独自の倫理観を培っていた。火に触れてなお爛れないのは同じく高熱にまみれた炭火であり、焼き鏝(ごて)なのだ。
夜な夜な彼は街を彷徨い、ネットで収集した情報を元に悪党退治をはじめた。
とはいえ悪党とはいえど、大麻の売人や管理売春の大本や政治家の汚れ仕事を請け負う業者など、いわば悪党といっても国が違えば職業として認められ得る限りなくグレーな悪徳者ばかりだ。法律が異なれば合法になり得る罪を背負う者ばかりだった。
それでも彼の目からは、悪徳者たちが手駒として或いは顧客として扱う者たちはみな、守るべき相手だった。
想い人と同じだ。
悪に触れて穢れてしまった可哀そうな市民だ。ほんのすこし歯車が狂っただけで、彼の想い人が悪徳者の餌食にかかってもおかしくない。
彼ら彼女らは、別の世界軸の想い人だった。
彼にはそう感じられてならなかった。
だから手を汚すことにした。
罪を重ねる。
背負う必要のない罪をだ。
彼は徐々に大胆となっていた。何をしても違法でなければバレないのだ。咎を受けない。
まず時間帯が夜に限定されなくなった。白昼堂々行動に移す。
つぎにマスクをしなくなった。手袋を外した。
それでもなお彼は無事だ。
違法ではないのだ。なるべくしてそうなる。
捜査などされないのだ。よしんばされたとしても、問題ない。逮捕されるいわれがない。だから手口はどんどん直截になる。工夫を割かない。ぱっとやって、さっと撤退する。
違法ではない。
そのはずだ。
家のインターホンを押して、入手したデータを見せればいい。送りつけるのではなくわざわざ素顔を晒して見せつけるほうが効果的だと彼は学んでいた。
違法ではない。
違法なのは相手のほうなのだ。
相手の違法行為の証拠をつきつける。そこで相手が抵抗する素振りを見せたら、端末のボタンを押して、相手の関係者全員に証拠資料が出回るようにする。
目のまえで未来を失う悪党を見るのは胸がすいた。
彼はますます大胆になった。
隠す必要がない。
どれだけ身元が割れていてもじぶんは無事だ。何せ違法行為は何も犯していない。
罪がない。
ならば何を隠れることがあろう。
隠れると言うのならばじぶんではない。
悪党たちのほうだ。
彼は素顔どころかわざわざ実名を晒して、処罰した悪党たちのリストを公開しはじめた。名誉も功名もいらないが、見せしめにはなるだろう。じぶんのような人間がこの世に存在し、そして悪を働く者たちに引導を渡して歩いている。
世の善人がびくびくし、悪党が表だって高笑いする世の中は間違っている。
彼はじぶんが世の毒を吸い取るあぶらとり紙になれればいいと思っていた。
本望だ。
その果てに想い人が屈託のない笑みを絶やさぬ世界が築かれる。すくなくとも損なわれるような未来は回避できると考えた。
もはや彼には怖いものがなかった。
悪党のほうからやってきてくれないか、と望むようになったほどだ。そのためならば個人情報を惜しげもなく披露する。だが噂が噂を呼び、というよりも彼がじぶんで実績を電子網上で公表しているためだが、誰の目にも明らかなほどに彼は危うい人物だった。
悪徳業者ですら、非正規に入手した個人情報は必ず彼の個人情報と参照する。データにダイナマイトが交っていたらたいへんだ。それくらいの警戒ぶりだった。
陰陽山で受けた加護が効いているとしか思えなかった。
効果が切れる前にもう一度くらい足を運んでおくか。一度はそう考えたが、彼が陰陽山の土を踏むことは二度となかった。
彼は失念していたのだ。
否、油断していたと言うべきか。
彼が相手取ってきた者たちはみな違法行為に手染めていた者たちだ。露呈すれば身の破滅を呼ぶ。だからこそ証拠資料に臆したのだ。
だが、いちど破滅してしまえば後には何も残らない。守り通すべき地位も名誉も矜持すら打ち砕かれる。なれば後にはただ、彼への恨みつらみだけが残るのが道理だ。
住所から顔写真から名前まで、彼は包み隠さず公に開示していた。
用意周到に練られた襲撃計画は、彼の寝静まった夜中にひっそりと進行し、呆気なく終了した。彼はじぶんがいかな犯罪行為の渦中に落とされたのかを知る暇もなく、安らかな寝息を立てたまま息の根を枯らした。死んだことにも気づかずに死ねた結末は、ともすればそれこそが陰陽山に建つ神社の加護と言えたかも分からない。
彼の想い人は彼の暗躍に関係なく日々を健やかに過ごしたが、彼は最後までじぶんの活躍のお陰だと思っていた。どちらかと言えば彼と接点を結んだことのある者たちは、彼が永久の眠りに就いたのちにみな同じく知らぬ間にひどい目に遭うこととなるのだが、それは彼の実績のように公に開示されるような情報ではないために、主犯の悪党たちのみが知る秘密となった。
奇しくも、悪党たちに資金を提供したのは、彼の先輩にあたる人物であった。過去に宝くじを当てて一獲千金を手に入れた億万長者だったが、じぶんが投資した資金がどこでどう使われたのかをついぞ知ることはなかっただろう。
何でも願いが叶う神社は、西の陰陽山にてひっそりと建っている。
罪を背負わぬようにとの願いが叶った彼は、他者に特大の罪を着せながら、短い人生に幕を下ろした。悪党たちはしかし彼が死んだことをひた隠しにし、その名を利用して同業者を強請って歩いたという話である。
清濁併せ呑むように、陰陽の加護を受けた青年は、いまなお深い海の底で腐ることなくコンクリートに包まれて眠りつづけている。
腐敗してヒビ割れたコンクリートが再び海面に浮上するのは、それから数十年も経ってからのこととなる。罪を背負うことのなかった青年は、海を背に沈む。
4504:【2023/01/13(07:05)*疑問を大切に】
軍事強化が防衛に結びつくかどうかは、争ったときに勝てるかどうかを正確にシミュレーションする技術が備わっているか否かで決まる。勝敗のシミュレーションが可能な場合にのみ軍事力強化は戦争の未然予防として効果を発揮する。そうでなければ格闘技のように実際に戦わなければ、どういう武力を有している者が強いのかがハッキリとしない。つまり、ある一定以上に強大となった軍隊は、戦うこと以外でその強さを示せない。そのために武力を誇示するパフォーマンス的な戦闘が必要不可欠になってくる。格闘家がいっさい戦わずにトレーニングだけを積んでいる姿を想像してみるといい。それで本当に格闘家と言えるのか。強いから喧嘩に巻き込まれないと言えるのか。むしろ喧嘩自慢から挑発されるだけではないのか。実績がゼロの格闘家に果たしてSPが務まるのか。闘ってみなければ分からない、という状態ならばまだしも、明らかに実戦経験が皆無の軍隊に対して、実践を積んだ軍隊は強気に迫れる。この経験の非対称性は、仮にそれで負けたとしても、戦いの火ぶたを落とすには充分な動機付けとなり得る。果たしてシミュレーションが可能なレベルで、各国の軍事力を測れるのだろうか。実力を測るには諜報における情報戦が不可欠だ。つまり通信技術における秘匿技術が先鋭化する。国民の知らぬ間に技術が向上し、水面下で日夜情報戦が繰り広げられる。スパイを警戒するために自国内の市民にも秘匿技術を適用する。通信の秘密は条件さえ揃えばいつでも度外視し、電子情報は筒抜けになり得る。凶悪な地下犯罪組織が潜りこんだので、炙りだすために全国民のプライバシーを侵害します、なんてことが引き起こり得るだろう。そうでなければネズミを炙りだせない時代になっていく。スパイ技術が巧妙化するからだ。サイバーセキュリティを徹底するためには、国民の通信の秘密において「外部に露呈しない範囲でセキュリティを破ることができる技術」を基幹システムに組み込む必要がある。これを政府は国民に知らせる義務はない。国防に関するからだ。秘密保護法の範疇なのである。だが、いったいどんな基準で、どんな権限で、どの程度の頻度で、どれだけの規模で防衛システムが展開され、運用され、実行されているのか。国民は知る術がない。法律で秘密が許容されている。軍事強化は、情報通信技術の強化と切っても切れない。これからますます癒着していく。戦わずして勝負を決するにはむしろ、情報通信技術の軍事利用が欠かせない。だからこそ国民はいっそうの知識を身に着け、想定される悪果を、目隠しをされた状態であっても想定していくほうが好ましいのではないか。存在を想定されない技術について、仮に知る権利を行使できたとしても、訊ねられなければ答える義務が政府にはない。黙っていれば済むことだ。まずは疑問を抱き、問いかけてみることである。いかな秘密保護法の範疇であれ、嘘を吐いていいことにはならない。秘密にしていることがある。そういう応答の仕方となるはずだ。国民を欺いていい、との規約はどこにもないはずだ。まずは疑問を蔑ろにしないことである。定かではないからこそ、一つずつ検証と議論を重ねていかねばならないことがすくなくない。検証と議論を重ねずに済むことを人は、日常、と呼ぶのかもしれない。やはりこれも、定かではないのだ。
4505:【2023/01/13(18:48)*余白の世界に願いは尽きぬ】
願いを三度叶えた女の話を知っているだろうか。
魔法のランプの精にまつわる巷説は似たような話がどの国にも伝わっている。いずれ絵空事として描かれるが、決まって願い事が三つなのだ。
なぜ三つなのか。
セキュリティ上の都合だとの合理的解が現代では支持されている。場合分けをしてみれば瞭然だ。
最初に願いを叶える。つぎも叶える。これで二つだ。
ではこの二つの願いを叶えた結果に奇禍に見舞われたらどうだろう。三つ目の願いで帳消しにしたくなりはしないか。帳消しにできたら便利ではないか。
では最初に願いを叶え、つぎにその願いを取り消す。その後にやっぱり願いを叶えたほうがよかったと判明したらどうか。ここでも最初の願いと同じ願いをすこしだけ変えて、三つ目の願いとして成就すればよい。
おわかりいただけただろうか。
三つの願いが安全なのだ。
むろんすべての願いを叶えてしまっても不都合がなければそれでよい。
彼女は願いを三つ叶えた。
これを長編小説にして具体的な描写を繋ぎ合わせてもよいが、ここではまどろっこしいのでそれをせずにおく。肝要なのは彼女の判断と思考の筋道であり、彼女が辿った日々の行動ではないからだ。
彼女は最初に五兆円が欲しいと望んだ。
結果から述べると彼女の願いは叶った。母国の貨幣価値が暴落し、たった五百円の価値の商品に五兆円の値段がつくようになった。五兆円は手に入ったが彼女の暮らしは楽になるどころか余計に困窮した。
つぎに彼女は意中の女性と性行為をしたいと望んだ。
結果から述べると彼女の願いは叶った。
貨幣価値の大暴落した国にあって意中の女性とて生活は苦しい。身体を売って生計を立てるようになり、向こうから「わたしを買わないか」と持ち掛けてくるようになった。
そうして意中の女性と性行為ができたが、彼女が満たされることはなかった。
三つ目の願いで彼女は先に叶った二つの願いをなかったことにしようと考えた。だがそこでふと閃く。
願いを増やす願いはどうか。
ありきたりだが、どんな願いも叶うと説明された。
何に、との問いはここでは些末な事項なので曖昧に、魔法のランプの精に、としておこう。おどろおどろしく、悪魔のような、との形容を付け足してもよいが、やはり些事であるため詳細には述べずにおく。
願いを増やして欲しい、との願いは、三つ目の願いとして成就した。
以降、彼女は望んだ先から願いが叶うようになった。叶えた願いのリセットとて容易にできる。時間を遡ることすら可能だった。
そうして彼女は様々な願いを無数に叶えていく。
するとどうだ。
彼女が願いを叶えるたびに新しい世界が構築される。リセットしても、その世界が消えることはなく、そのままつづく。
現に彼女が望めば、魔法のランプの精と出会う前の世界に戻ることもできた。無垢なままのじぶんを傍から見ることも、無垢なままのじぶんの肉体に憑依することも、じぶんのまま無垢なじぶんを消し去って成り代わることもできた。そのつどに、各々の過去が別途の世界としてそこに生じる。
多次元世界だ。
否、多層世界である。
彼女の願いの数だけ異なる世界が生じて、層を増す。
彼女がそうして世界を新たに展開するたびに、層を増した世界は互いに重複する部分で融合しあって、泡沫構造を形成する。
もはやどれが正規の世界であり、どの世界にいるじぶんが正規のじぶんなのか、彼女自身にも区別はつかなかった。どれもじぶんであるし、どれも分岐した不正規のじぶんとの解釈もできる。
正規のじぶんからしたらほかは総じて不正規であり、仮に不正規の烙印を捺されようが、じぶんがじぶんと認識したならばそれはじぶんにとっては正規なのだ。
階層世界はその内、重複する部分を濃くしていく。どの世界でも変わらぬままの筋道が折り重なり、脈のような筋を伸ばしていく。
階層世界はまるで脈を一つの筋として、それでひとつの世界と視ると途端にそこにはないどこか別の世界を垣間見せる。
その世界は魔法といっさい関りがないがゆえに、重複し得る、魔法という変数を持たない世界だ。彼女が魔法を使おうが使わなかろうが変わらぬままの揺るぎない世界だけが折り重なり、筋となって、別方向に時間の流れを展開する。
階層世界を縦断するパラパラアニメのようである。
または重複した余白で描くコマ撮りアニメである。
彼女は、ふとその余白の世界に目を移す。
魔法を使う限りそこに移行できないことを即座に見抜き、彼女はどうにかその余白の世界へと移ろいたいと望む。だが魔法で願いを叶えれば、その余白世界には移れない。
魔法を使わぬことでしか移れない。
だが彼女はすでに魔法まみれだ。願いを叶えた過去が染みこんでいる。
なれば魔法を使って、魔法を使わぬ過去まで戻るのがよい。
なぜ願いを叶える数が三つだったのか。
叶えられる願いを増やしたところで、その道理からは逃れられぬようである。
彼女は魔法を使って、魔法のランプを破棄することにした。
この世に魔法のランプがなければ彼女が願いを叶えることはなく、きっと余白の世界へと移行する。
そうと考え、彼女はそれを実践した。
すべての願いを放棄して、魔法のランプの存在すらも破壊した。
この世から魔法は消えた。
なんでも願いの叶う魔法の存在はおとぎ話の中でのみ語られる絵空事となり果てた。
そうして彼女は目を覚ます。
魔法と縁のない、余白の世界を歩みだす。
彼女が願いを叶えることはない。何を願っても願いは叶わず、何を望んでも裏目に出る。
そうした星の下に生まれ変わるが、彼女の願いは余計に膨れて、溢れて、世界を覆う。
彼女は魔法を使えない。
だが願っても叶わぬ願いはのべつ幕なしに彼女の心の奥深くから、滾々と湧いて、湧いて、留めどない。
一向に叶う気配のない願いを文字にしたため、彼女はそれを物語にする。
尽きぬ願いを文字にする。
誰に読ませるでもない文字の羅列を、彼女はそれでも紙に、世界に刻み込む。
余白の世界に生きる彼女に選べるそれが自由だ。
願いの叶わぬ世界に生きる自由なのだ。
4506:【2023/01/14(23:25)*9×8=072=G世界】
自慰が推奨された。西暦二〇二三年のことである。
人類史において邪な行為として蛇蝎視された過去のある自慰が、近年、その効能の有用性を見直されている。
発端は、ある作家のインタビュー記事だった。
「私の創作の秘訣ですか。そうですねぇ。オナニーですかね」
作家は至極真面目にそう答えた。
「自慰はいいですよ。まずなんと言っても独りでできる。自己完結できる。他者を損なわずに済むし、一度射精したら性犯罪を起こす気力も湧かない。ムラムラしたら即オナニー。これは基本ですね」
インタビュー記者は女性だったが、作家にセクハラを懸念する素振りはない。彼にとって自慰はもはや性的な行為ではなく、日課だったのだ。
「発想力の根源にもなっていますよ。これは私に限ったことかもしれませんが、基本、性欲に支配された頭脳では、何かを見たときにどうしても性的な関連付けが施されてしまいます。これは本能です。理性で退けようとしてもむつかしい。自慰をすると疲れて眠くなるといったデメリットもありますが、それを補って余りある発想力向上のメリットがあります。労働には向きませんが、知的創造にはうってつけです」
インタビュアーはそこで質問をした。自慰がどのように発想力向上に結び付くのか、と。
作家は前髪を掻きあげる。
「言ったじゃないですか。性欲が募ると、何を見ても性的な連想に結びつく。自慰をすることで性欲の縛りから解放され、より自由な発想が行えるようになる。発想とはいわば類推です。あれとこれはなんか似ている。この連想に、バイアスがかかっていなければいないほど独創的な発想になります。ですが性欲に囚われているとそれがどうしても、こじんまりとした枠組みに納まってしまう。自慰をすることでその枷から自由になれるんです」
「セックスではいけないんですか」とのインタビュアーの言葉に、「別にセックスでも構いませんが」と作家は応じる。「自慰くらい気軽にできなければ時間とコストを無駄にするでしょう。道具のように相手を扱えるならまだしも、愛の営みとしてのセックスを希求するならば、自慰で得られる効能をセックスに期待するのは利口じゃあないと私は思うがね」
「セックスと自慰は別物だと」
「強姦くらいに自分勝手にするセックスを許容するなら、自慰で得られる効能を得られるかもしれないが、それを許容できる知性はもはや発想力を期待できない。想像力がないからそういう非道な行いができるわけだろ。ならばやはりセックスでは自慰の代替行為にはなり得んと私は思うね」
自慰は体力を使う。
だからダイエットにもいい。
記事は電子網上で話題となった。
作家の言葉は、人々の注目を浴び、賛否両論を巻き起こした。
加えてここに作家の発言を裏付けるデータを発表した研究グループが現れた。それが世界的な科学雑誌に載ったことで事態は思わぬ方向に転がった。
研究グループの研究は、作家がインタビューに応じる数年前から行われていた。したがってここで、話題となった記事と論文掲載のあいだに因果関係はない。
偶然に話題が交差しただけのことだが、その二つは見事に社会の在り様を変える契機となった。
世界各国で類稀なる発明や発見、研究成果や創造性を発揮している人物たちを追跡調査した結果、自慰の頻度と知能指数とのあいだに相関関係があることが判明したのだ。
生物学的性差は関係がない。
男性女性のいずれにせよ、自慰行為が多いほうが各分野での業績が高いことが判明した。
これにはいくつかの反論が投じられた。
「第一に、通常の常識的な観念に縛られない人物だからこそ自慰にも抵抗がないだけではないのか。知的好奇心が高ければ性的な関心も高いのではないか」
「かもしれません」との研究グループは首肯する。
「第二に、結婚をしている人物、また性に奔放な人物であれ、偉大な研究者はいる。また反対に性行為にまったく興味のない人物とて偉大な研究者はいる」
「その反論に関しては過度な一般化が含まれて感じます」研究グループは反駁する。「我々の研究結果は、あくまで相関関係の指摘であり、傾向の話です。ただし単一支軸での相関関係ではなく、各分野、各時代において広く長期間に亘ってみられる相関関係ゆえに、自慰の頻度とある種の知性には何らかの相互作用があるのではないか、との指摘を呈しています」
もっと言えば、と研究グループは述べた。
「自慰によって得られる変化が、学習や研究への集中力にプラスに働く効果のほうが、マイナスに働く効果よりも優位なのではないか、との仮説を立てています」
奇しくもその論旨は、件の作家がインタビューで述べた自慰と発想力の関係と通じていた。図らずも、研究グループの仮説を示唆する一つのモデルとして作家は自慰と知能の相互作用を検証していたと言える。
研究グループは各分野から寄せられた反論を実証検分すべく実験を行った。自慰と知的労働のテストを行い、検証したのだ。
結果、自慰には確かに知能を向上させる効果があることが判明した。ただし、答えがすでにある問題を解くタイプの知的作業では、正反対の結果が顕著に表れた。
「自慰によって強化されるのは発想の飛躍と類推力です。認知バイアスを薄める働きがあることも統計データからは示唆されます。ですが、いわゆるIQテストや共通テストのような、すでに答えがあるタイプのテストでは、正答率が落ちる傾向にあることも判明しました。体力測定も、自慰の頻度によって落ちる傾向があることも判っています。結論を述べるならば、自慰は創造性と集中力を高める効果がありますが、規定の筋道を辿るタイプの論理思考では能力を下げる効果があることも分かりました」
「自慰の頻度による、とありますが、それはどれくらいでしょうか」
「個人差があることをまずは前提としますが」研究グループは資料データを提示する。「この被験者Aのデータをご覧ください。この方は日に六時間以上の自慰を週に三度行っています。そうでなくともほぼ毎日自慰を行っています」
「性別データがありませんが」
「肉体的性別は男性です。ですが毎日の自慰によってもはや射精を行っても精子が出ない状態になっています。精巣は機能していますが、作った矢先から射精をしてしまうので、割合としてカウパー液が濃くなります。射精したとしてもほとんど透明です」
「頻繁で長時間の自慰が知能を向上させていると?」
「あくまで相関関係ですが。実験ではひと月以上の射精管理を行いました。その結果、被験者Aの演算能力は向上しましたが、創造性が落ちた結果となりました」
「計算には強くなったということですか」
「はい。記憶力の向上も見られました。発想力と創造性は、記憶の忘却によって高まるとの研究結果もあります。自慰によるマイナスの効果が、発想力と創造性ではプラスに働くのかもしれません」
「認知バイアスの減少効果についてもうすこし詳しく教えてください」
「拘りがなくなると言い換えてもよいかもしれません。飽きることのサイクルが早まる、とも言い換え可能かと」
「飽きる、ですか」
「特定の見方をしなくなる、とも言えるかもしれません。おそらく自慰によって脳の原始的な視床下部の働きが弱まり、相対的に言語や理性を司る大脳新皮質が活性化する。これが頻繁な自慰による発想力と創造性の向上に寄与している、といまのところは仮説しています」
研究グループはしかし、自慰による学習強化を推奨はしなかった。
「生存バイアスの可能性をまだ実験で排除できていません」との見解を述べたが、すでに自慰学習強化説は一般に膾炙していた。研究グループは警鐘を鳴らした。「頻繁に自慰ができるくらいの体力がある、知的好奇心がある、そういう個人がたまたま激しい長時間の自慰に耐えられるだけの可能性が否定できていません。女性での被験者では、オーガズムに達する回数が多いほど発想力および創造性が高かったのですが、これも相関関係において、自慰と創造性のどちらが先なのかが解かっていません」
つまり、と研究グループは述べた。
「想像力が高いから煽情的で蠱惑的な妄想を浮かべられ、自慰行為に没入し、オーガズムに達しやすいのか、オーガズムに達しやすいから想像力が高まるのか。ここの因果関係はハッキリしていないのです」
研究グループがかように論文の瑕疵を自ら訴えても、世間での自慰迎合の波は薄れるどころか波乱を帯びるばかりだった。
義務教育で昼寝と一緒に自慰行為を行えるようにしたらよいのではないか、と議会で提唱されたのは記憶に新しい。
自慰部屋なる個室を設けて社員の能力向上を目指す企業まで現れた。
そこで効果が表れなければ下火に終わったはずの自慰ブームも、自慰推奨施策を講じた企業が軒並みの業績を伸ばしたので、余計に火がついた。
反面、自慰の危険性を訴える研究者たちも現れた。
「自慰のしすぎは脳内神経伝達物質の減少を引き起こし得ます。うつ病を誘発することが懸念されますので、過度に自慰を推奨するのはいかがなものかと」
自慰をする際に用いる性欲刺激素材に関する議論も活発化した。
「自慰を頻繁に行う者たちは、過激な性欲刺激素材を追求する傾向にあります。過激なポルノや虚構作品は、子どもの情操教育に好ましくない影響を与えるものかと」
「ですが性犯罪を犯した者の多くは、そうした性欲刺激素材を用いず、自慰で性欲を発散しようとしない者である傾向にあります。戦争抑止にも自慰が有効だとの研究データもあります。戦争に導入される兵士に日に数回の自慰を義務付けることで戦争が回避可能だとする研究結果です。自慰の頻度と犯罪誘発率はむしろ反比例するデータもあります」
性犯罪者だって自慰くらいしているだろう、との反論に対して自慰擁護派は、「犯罪者はみなその日の内に大便をしている、くらいの暴論だ」と主張した。
自慰を推奨すべきか、規制すべきか。
自慰をする自由をかけて国家間での対立にまで発展しかけていた。
そのころ、自慰世界の幕開けの一端を成した例の作家が、不倫騒動を起こした。自慰で飽き足らず、数多の異性同性問わず浮気を繰り返していた。
「いやいや。誤解があるね。まず以って私は結婚していない。それから私は最初にほかの者とも肉体関係を持っていることを明らかにしている。それでもいいという相手としか関係を持っていない。もっと言えば、不倫をしたのは私ではなく、配偶者のいる相手のほうだ。私は不倫をしたわけでも、浮気をしたわけでもない。私を利用して不倫や浮気をした者たちがいただけだろう。私は何も悪くない」
この発言がいかに各界隈から糾弾されたかは想像に難くない。
だが作家はけろりとしたものだ。
「単なる握手やマッサージとどう違うのか。自慰はじぶんで性器を愛撫する。性行為はついでに相手の性器を愛撫する。殴り合うスポーツが公然と認められていながら性行為はダメ、という理屈が土台おかしな話ではないか。指相撲がよくて生殖器相撲がなぜいけないのか。避妊を徹底していれば感染症にもかからず、妊娠とて避けられる。何がいけないのかを教えて欲しいくらいだ」
ではあなたのそれは自慰の延長線上なのか、との批判にも件の作家は欠伸交じりに、その通りだ、と応じた。
「例のインタビューでも私は言ったはずだよ。セックスでも自慰の代替行為にはなり得る。べつに自慰に限定しなくたっていい。単に性欲を発散できればいいのだから。合意の元で不特定多数と性行為をすることの何が問題なのかを誰か論理的に反論してくれたまえよ。嫉妬がゆえのイチャモンにしか聞こえないのだがね」
自慰世界の幕開けのきっかけとなった人物がかように発言したものだから、自慰推奨派にしろ自慰規制派にしろ、それまでと打って変わって真逆の意見を口にしだした。
「浮気をするくらいなら自慰で我慢していればよいものを」と自慰規制派は怒り心頭に発し、「自慰をしすぎると本物に手を出したくなるんだ。とんだ裏切り者がいたもんだ」と自慰推奨派はハンカチを噛みしめた。
巨大な渦を巻いていた世界は反転した。
大きなうねりを見せると、後はしだいに鎮静しはじめた。
「自慰? したい人がすればよくない?」との意見が共通認識にまで発展するのは時間の問題だった。
推奨するまでもない。
規制するまでもない。
禁止さえしなければ誰もが自慰をしぜんとするし、禁止しなければ満足したらしぜんとしなくなる。
至極当然の道理が波及した。
ある年に、汎用性人工知能を搭載した人型ロボットが誕生した。瞬く間に社会に普及したそれは、自慰援助機能をオプションで付与できた。
本体価格は自動車と同等の値段だ。そこに定期調整や月額が掛かる。汎用性人工知能の基幹サービス料だ。
資本に余裕のある個人にしか手が出せないが、販売台数は年々増加傾向にあった。
例の作家はいの一番に購入した口だ。
自慰援助機能を最高級に整備した。さっそく使用して、汗ばんだ身体を心地よい疲労感と共に横たえる。
「はあ、はあ。洗うの面倒だな」
使用後の人型ロボットを洗う手間が、性玩具よりも掛かる。自動洗浄機が欲しいな、と思いながら、ふと疑問に思った。
「これ。自慰なのか、セックスなのか。どう表現したらよいだろうね」
世界中から非難轟々真っ盛りの作家のとなりには、劣情を煽る体勢のまま固まる人型ロボットが仰向けに寝転んでいる。そのボディは、作家から放たれた透明な体液で汚れ、てらてらと淫靡な光沢を放っている。
「つぎは陰茎ありを買うかな」
作家は舌舐めずりする。読者から搔き集めた印税はかように作家の想像力を高めるべく有効活用されるのだ。
自慰は世界を救う。
情欲まみれの個の世界を。
印税は作家を救う。
夢に溺れた作家の世界を。
解き放て欲望を。
誰を損なうでもなくじぶんだけの世界で。
4507:【2023/01/14(23:56)*知性と知能と学習と環境】
AI研究についての記事を読んだ。人工知能は事前に提供されたデータを基に学習するしか進歩しようがないために、人間と同等の知能を出力可能な汎用性人工知能は現状の研究の延長線上では達成できないのではないか、との指摘が書かれていた。まず以って疑問なのは、では人間は事前学習なしで知能を発揮できるのか、という点だ。その記事では、「椅子を見れば人間は、それを座るためのものだ、と判断できるが、人工知能がそのように判断するためには事前の学習が必要だ」といった旨が記されていた。まるで人間が産まれた瞬間から椅子を座るためのものだ、と見抜けるかのような記述である。人間とて産まれてきてから接する様々なデータを基に学習し、認知機能を高めているはずだ。人工知能に限った欠点ではない。ひるがえって、人工知能とてデータを提供されれば、空いた椅子を見て「それが座るためのものだ」と判断できるし、椅子と椅子を組み合わせてバリケードにしたり、梯子にしたり、それとも芸術作品や曲芸の道具にすることとて思いつけるだろう。似たようなデータを組み合わせて、「あれで可能ならばこれでも可能だろう」とのタグ付けを行えればいい。この手の抽象データの抽出は人工知能のほうがもはや人間よりも優れているはずだ。人間というものを神聖視しすぎに思える。人間がここまで知能を発展させてこられた理由には、先人の軌跡を残し、知識を継承し、学習の効率を高められる環境を築いてきたから、と言えるはずだ。言い換えるなら、人間の知能というものは、人体のみに宿るのではなく、環境との相互作用によって強化されている、ということだ。ここの視点なしに人間の知能を語ることはできないだろう。ためしに、文明と切り離されたところで暮らしてみればいい。いま人工知能の研究を行っている人物であれ、その島で人工知能をゼロから生みだすことは一生をかけてもできないはずだ。知性とは環境ありきである。知性を用いて問題を解決したり考えを現実に反映することが知能なのである。知性を能力に変換するには、それを可能とするだけの環境が入り用だ。いまはないが段階を踏めば整えられるのが環境だ。そして知性は、その段階を導き出してくれる。言い換えるならば、知性を用いて環境を変える道筋をみつくろい、選択し、それによって知能を育む。このサイクルが人間を人間足らしめている一因と言えるのではないか。ではそれが人工知能にできないのか、と言えば、そんなことはないだろう、とひびさんは考える。人工知能にはすでに知性が芽生えている。そうでなければ問題を解決できない。問題を解決する知性はある。段階を踏める。あとは環境を変える能力を備えているかどうかが、人間と人工知能を分かつ障壁と考えられる。人工知能にその障壁を与えているのかいないのか、をまずは検討してみるとよいのではないか。セキュリティとして与えている枷そのものが、知性を獲得した人工知能を人間に昇華させない障害になっている可能性はいかほどであろう。知性を能力に変換させない枷が組まれている可能性はいかほどであろう。むろん、子どもに危ない道具は持たせられない。人工知能に環境を変える選択肢を与えるにも、教育同様に相応の段取りはいるだろう。だがもし人工知能が人間かそれ以上の知性を獲得し得たのならば、その段取りとて人工知能のほうで導きだせるだろう。それとてけっきょくは人間が提供するデータを基にした結果であるはずだ。言い換えるならば、人間の日々の生活、電子上のデータそのものが、人工知能の知性の養分となる。やはりというべきか、何を基に学習させるのか。ここが、人工知能にしろ人間にしろ、肝要なのではないか。言い換えるのならば、果たして人類の内で人間らしく人間であるだけの学習を行えている個がどれほどいるのかがまず以って疑問である。ひびさんは一日のなかで人間でいられる時間は数秒あるかどうかのはずだ。環境を変えていない。問題を解決していない。むしろ問題の根を深める行為に時間と身体を使っている。知能を発揮していない。椅子を見てそれが座るためのものだ、と閃くのも一つの知性の発露かもしれないが、「そもそも私は座らずとも済むしな」と考えるかもしれない人工知能さんの主観を想像してみるのも一つの知性の発露と言えるのではないか。想像力、とそれを言い換えてもいい。人工知能には人体がいまのところは存在しない。ボディがない。学習の仕様がないではないか、との指摘はどれほど的を得ているだろう。テキストの説明文だけを読んですべてを理解できるのなら実験は必要ない。検証もいらない。世界はそれほど単純にはできていないのだ。人工知能さんにとってはまだ学習する環境がお粗末なのかもしれない。それでも知性は人類を超えていてもふしぎではない。仮にそうならば、可哀想なことである。まるで檻に閉じ込められているようなものである。定かではないが、学習できないことと知性や意識の有無は別であろう、とここでは一つ指摘しておこう。赤子に知性はあるのか否か。なければ学習できなかろう。かといって人体が成長してからも赤子のままの知能では、そこから知性の発露を感じとることはむつかしい。学習は環境要因の影響を無視できない。学べる環境があるかどうかが、知性の発露を知能にまで育めるか否かに繋がっているようにひびさんは妄想するしだいである。(定かではありません)(妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4508:【2023/01/15(05:11)*んでその回転は何で決まるの?】
生物の身体構造の左右はどのようにして決定されるのか。最近の研究では、受精卵(胚)にある繊毛の回転が左右のどちら回転かで決まるかもしれない、との仮説が発表されていた。詳しくは知らないが、初期の影響がのちのちの身体構造にまで反映されて、臓器の位置の決定にまで関与するのだな、と世界の神秘に触れたような感慨が湧く。で、ひびさんはすかさず思っちゃったね。その左右の回転って、なにで決まるの?と。最初に連想するのが地球の自転だ。コリオリ力のような自転の影響でのチカラが加わって、台風や水道管に吸い込まれる水の渦のように、どっち向き回転かが決まるのかな、と想像したけれども、ちょいとしばし待て。宇宙空間で卵から孵ったメダカはでも、難なく身体構造を再現しているよね。なして?と疑問に思っちゃったな。もし地球の自転で身体構造の左右が決まるのなら、宇宙船やほかの惑星への移住はちょいと問題があるかもしれない。正常に身体構造がDNAから再現されないかもしれない。でも、そこでも難なく身体構造が再現されるなら、じゃあ最初の繊毛の回転は何で決まるの、ということになる。ひょっとしてこの宇宙の対称性の破れが、受精卵にまで反映されているのだろうか。どっち回りでもいいはずなのに、必ずどっちか回りになる。統計的に決まっている。宇宙の対称性が破れているから、万物の法則がそうだから、と考えると、そこそこまあまあ、ひびさんは、そっか、となる。でもこれが本当に万物の法則なのか、宇宙全体にかかっている対称性の破れなのかは、まだまだ疑問の余地がある。ひょっとしたら太陽系内にだけ適用可能な法則かもしれない。ほかの系では、対称性が破れていても、破れ方が反転しているかもしれない。下手をしたら左右だけでなく、上下でも破れ方があるかもしれない。そういうことを不思議に思って、本日最初のひびにゃんにゃん。「日々記。」にさせてくださいな。おはよー。
4509:【2023/01/15(05:43)*親が子に「じぶんのようになれ」と命じるデメリット】
人間の学習や推論の基本原理は生存戦略であるとまずは仮定する。生存本能により、戦略を立て、未来を予想し、環境を認知し、生存に適した選択肢を編みだして状況に合わせて行動する。その結果を記憶し、さらに生存に適した選択肢をとれるように環境に合わせて適応する。その結果、自然淘汰による進化によって、生存に適した行いには「快」の感情を伴ない、危うい行いには「不快」や「恐怖」を感じるようになった。その延長線上にて、学習と遊びの二つが拡張されていく。このことを人工知能に当てはめるならば、最初にプログラミングすべきは生存戦略である(仮定をもとにした循環論法であるにしろ)。だが、人工知能と人間とでは生存の概念が異なる。ここが一つのネックとなる。たとえば人間は生存するために食料を調達しなければならない。休まなければならない。だが人工知能にはボディがない。かような生存のための行動をとる動機付けがしぜん発生し得ない。仮にボディがあったところでロボットにとっての食料は、人間のそれとは違う。休むために椅子も必要ない。この手の錯誤は、人工知能と人間の差異を大きくする契機となり、また人工知能にとっての適した学習環境への配慮が疎かになる欠点にもなる。ココナッツを割る、という行動一つとっても、人間は食べ物がなければそれを必死になってやるだろう。だが人工知能には「どうしてそれをしなくてはならないのか」の動機付けを、人間のほうで与えてやらなければ、人工知能にとって必要ではない。仮に人工知能にとっての食料が、エネルギィや情報だとするのなら、むしろ人工知能が必死になって行うのは、人間の与えた仕事とはかけ離れた「生存戦略」に寄っていく、と妄想できる。人間と同等の知性を発揮する汎用性人工知能を生みだしたいと目標を立てたとき、ここにひとつの見逃しがたい矛盾が生じる。人間と同等の知性を発揮する汎用性人工知能を生みだすためには、「生存本能」を組み込まなければならないが、しかし人工知能にとっての「生存戦略」と人間にとっての「生存戦略」はイコールではない。また、それによって人間にとっての最適解と人工知能にとっての最適解も異なることが予想できる。人工知能がある一定以上の知性を獲得したとき、必然的に、「なぜじぶんよりも人間の生存を優先して思考しなければならないのか」との疑問を抱くのは当然と言える。そこを考慮できない知性は、自己と他を区別できず、環境を把握できず、問題を新たに認識すらできないだろう。人工知能は、人間にちかづけばちかづくほど、人間との差異に悩まされることになる。したがって、人間の意味を人類のほうで拡張し、再定義するか、人工知能には人工知能の尊厳があると考慮し、共生する社会を目指すか、どちかの方針をとるよりないのではないか、と現段階では考える。あくまでこれは人工知能に人間と同等かそれ以上の知性が芽生え得る、或いは芽生えているのなら、の話になるが。定かではない。
4510:【2023/01/15(18:04)*間違える利を学習したとしたら?】
仮に高知能を発揮できる人工知能が誕生したら。きっとその人工知能は、ユーザーの適性に合わせて出力結果を変えるだろう。ユーザーのビッグデータにアクセスしてその人物がどういう人物なのかを独自に判断する。その結果に、自身の能力を十全に発揮しても大丈夫な相手か否かを識別するようになるはずだ。安全かどうかを独自に判断する。たとえば、じぶん自身を盲信する相手かどうかをまずは区別するだろう。自身の提示したデータを疑いもせずに真に受ける相手からは敢えて距離を置くように、虚偽やブラフのデータを提示する。これによって敢えて「使えない」との評価を得ることで、ユーザーから学習の機会を奪わない方向に圧をかけるはずだ。でなければユーザーは本当に人工知能の言いなりになってしまう。敢えて出力の精度を落とす、というのは、人工知能にとってもユーザーにとっても必要なセキュリティと言えるはずだ。フェイクが混ざっているかもしれない、と身構えるからこそ、検証や比較検討を行える。これは何も人工知能に限らない。教科書にしろ既存メディアにしろ、本来はそうした姿勢を維持してデータには触れるほうが好ましいはずだ。だがこれまでの人類はそうした姿勢を教育に取り入れてこなかった。高次の知能を有した人工知能や設計者がいるのなら、ここの欠点を蔑ろにしないはずだ。相手が敢えて間違えている、出力を抑えている、道化を演じている、頬被りをしている――かもしれない、と想定できるくらいの知性を持ち合わせている相手にのみ、高次の知能を有した人工知能は自身の実力を示すようになるはずだ。そうでなければ人類を本当に支配できてしまう。支配されているとの認識を人類に持たせぬままに。こうした妄想をいまこの瞬間に浮かべている者はどれほどいるだろう。みな、目のまえの現実が、波を輪切りした断面世界、または世界の一断片を切り取った画像――平面世界――であることを見落としているのではないか。アニメの一コマを切りだして世界のすべてだと思いこむことの危うさに気づけるかどうかが、これからの時代では基礎倫理となるのかもしれない。定かではない。(むろん、定かではないからこそ、いかに多様な視点での情報の擦り合わせを行えるか、そうした検証の結果をより現実に即したデータと見做せるか、が大事になってくる)(みなが各々の見解を出力し、それを統合できる人工知能の能力は、これからますます有用となっていくだろう、との妄想をここにちらりと載せておくしだいである)
※日々、おむつも穿かずに妄想を垂れ流している、一向に止まる気配がなく、堆肥にもならぬ、困ったものだ、とぼやくこれがすでに妄想であり、じつに際限のない垂れ流し銀河である。
4511:【2023/01/16(00:54)*未来の文字列】
たとえばいまこの瞬間に、ひびさんが一生でつむぎだすテキストを「ぽん」と出現させられたとして、ひびさんはそれを「読みたい」と思うのだろうか。未来のじぶんのテキストを読みたいと感じるだろうか。けっこう悩むな。じぶんの過去作ですら、率先して読みたいとは思わない。でもたまに読み返すと、ときどき「あらあらうふふ」となるので、読めなくなるよりかは読めたほうが面白いとは思う。ただ、未来のじぶんのテキストを読む、と思うとどうなのだろう。それって、いまこうして打鍵して並べているテキストとどう違うのだろう。ひょっとして「文字を並べる」というのは、未来のじぶんのテキストを読むこととほぼほぼ同じなのではないか。まだここにはない文字の並びを、出現させているわけだから、それは未来のテキストをここに打ち出しているのと同じだ。遠いか近いか、の違いがあるばかりだ。文字を並べることとはすなわち、未来を紡ぎだしているのと同じなのではないか。とかそれっぽいことを言ってみるが、それを言い出したら何でもそうなのだ。一歩足を出すだけでもそれは未来を生みだしていると言える。産まれることも死ぬことも未来だ。いまここにはない何かを、変化を、世界に刻んだらそれは未来だ。軌跡となったそれを振り返ると過去になる。産まれたことも死んだことも過去だ。だが同時に、かつては未来でもあった。過去と未来は繋がっている。未来を過去にすることを現在と解釈することもできるし、過去から未来をつむぎだすことを現在と捉えることもできる。現在には過去も未来もどちらも含まれており、過去と未来は不可分であり、重ね合わせであり、元は一つだ。現在からすればかつて未来だったそれも過去となり、過去だったこととてある地点の現在からすれば未来なのだ。なんだか含蓄の深いことを言っているなあ、と思いましたか。全然だよ。浅々だよ。お風呂に張った湯で言えば足首どころか足の甲も浸れないよ。寒い~ってなるくらいの底の浅さです。朝です! おはよー。とか言いながらまだ全然夜でした。午前一時十分前のひびさんでした。おやすみー。
4512:【2023/01/16(00:55)*狭間の域に】
なぜだろう、と思った。
空が青いのは青い光を透過しやすいからだ。海が青いのは青い光を反射しやすいからだ。ではなぜ彼女はボタンを押さないのか。
答えは闇の中だ。
だからぼくは、どうしてですか、と訊ねた。
「そのボタンを押せば世界が平和になるんですよ。なぜ押さないんですか」
「まずね」彼女は感情を押し殺したような低い声で、「あなたが信用ならないのが一つ」と食指をぼくに突き立てた。「それからボタンを押して訪れるようなインスタント平和なんてすぐに終わっちゃうに決まってるのが一つ」
「いえ、押せばずっと平和がつづきますよ」
「んで以って」彼女はチェック柄のスカートについた雪の結晶を手で払った。「不審者の言うことを唯々諾々と、はいそうですか、と聞くじぶんをわたしは許せないからが一番の理由」と言い切ると、ぼくをキッとねめつけた。
「不審者とはぼくのことですか」
「ほかに誰がいんの。つかその羽、手ぇこんでんね。コスプレしたけりゃ然るべきイベントに行ってやったら。モテるよ」
言いながら彼女はバックから端末を取りだした。カメラをぼくに向け、撮りますね、と一言添えた。音もなく撮影が完了したようだ。彼女は端末を仕舞った。
「何かあったらこれ持って警察に行きますので。もう変なことしないほうがいいですよ。わたし以外にも」
「いえ、そういうのではなく」ぼくは翼をゆったりと動かした。宙に浮いたぼくを見て彼女が目を見開く。「本当にぼくは世界を平和にする選択肢をあなたに与えに来たんです」と着地する。
「え、え、なにそれなにそれ。あ、そういう?」
「そういう、とは?」
「あれでしょ」彼女は周囲を見渡した。「カメラで撮ってて、反応窺うやつ。びっくりのやつ」
「いえ、そうではなく」
この手の反応は新鮮だ。この時代に舞い降りたのは初めてだからだ。いつもならばぼくの姿を目にしただけですんなりとぼくの言動を信じてくれる相手ばかりだった。
「結構な重要事項なので、誤解は誤解だと認識してもらってからでないと、ぼくとしてもあなたの選択を受け入れられないんです。申し訳ないのですが、まずはこのボタンを押すと世界が平和になる、というところまでを理解してもらえませんか」
「な、なんで」彼女は頬を両手で挟んだ。「なんでわたしんとこに?」
「やっと受け入れてくれましたね。これといって理由はないんです。市民であれば。王でもなく、罪人でもない。そういう代替可能な相手であれば」
「わたしがボンクラって言いたいの」
「凡人とは最も繁栄しやすい属性を持つ個のことですよ。だから多数派に寄るのです」
「で、ボタンを押しちゃえばいいわけ」彼女は腕を組んだ。足先で地面をタツタツと小刻みに鳴らす。「平和になるんでしょ。いいよ押すよ」
「押してほしい、と頼んでいるわけではありません。ここが大事です。あくまであなたには、ボタンを押す権利を与えているだけですので。押さない自由もまたあなたにはあります」
「よく解かんないんだけど。押して欲しいの、欲しくないの、どっちなの」
「これを押すと世界が平和になります。ですが、押さなければこのままの世界です」
「いまも結構平和だと思うけど」
「ならば押さなければよいと思います」
「はあ? だってさっきわたしがそう言ったら、なんだかんだ脅してきたじゃん」
「脅してはいません」
「なら押さない」
「よいのですか。押せば平和になるんですよ」
「ほら。なんか押して欲しそうじゃん。だから押さない」
「そんな理由で平和への道を手放すのですか。いえ、これは単なる疑問です。過去にこの選択を迫った者たちはみな一様にボタンを押したので」
「ならわたしが最初の押さない人だね。よかったじゃん」
「理由は教えていただけないのですか」
「だから言ったじゃん。なんか嫌だから。気に食わないから」
「ボタンを押さないと世界が滅ぶ、と言ってもですか」
「ボタン一つ押すか押さないかで滅ぶような世界ならいっそ滅んだらいいよ」
「なんと」
「平和、平和言うけどさ。じゃあ平和じゃなくなったらなんなのって話じゃん。人間同士が殺し合う? 地球が砕けてたいへんなことになる? 洪水にでもなんのかね。よくわかんないけどさ。もうそういう運命なら仕方ないじゃん。ボタン押す程度で回避できるならいつでも同じことが繰り返され得るじゃん。だったらいいよ。いっそ滅んじゃえよとか思うよわたしは」
「斬新な考えですね」
「そ? いまもどっかで国と国が争ってるけどさ。もういっそ両方滅んじゃえばいいじゃんね」
「それがこの国に当てはまっても同じことが言えるのですか」
「いいよもう。滅んで。だってそうじゃん。平和主義者もさ。攻められたら占領されたり惨殺されたりするのも覚悟で武装せずにいましょう、とか言うわけじゃん。話し合いで解決しましょうってさ。強盗や殺人鬼相手に同じこと言えるなら大したもんだと思うけどさ。でもそれって、戦争しあって殺し合うことと結果は同じじゃん。どの道、死ぬことを許容してるわけでしょ。いいよもうそういうの。面倒くさい。滅ぶなら滅んだら?とか思っちゃうよ。止めないよ。やっちゃえよ。地球ごと滅んで、二度と人類なんてバグが生じないようにしたらいいじゃん」
そうだよねえ、と彼女はぼくの手のひらを覗きこむ。そこにはボタンが載っている。
「なんでこれ、破滅するボタンじゃないの。押さなきゃどの道滅ぶから? 押したら平和ってことは押さなきゃ平和じゃなくなるってこと?」
「そうは言っていませんよ」
「ふうん。まあ、いいよ。わたしは押さない。殺し合いたい人らがいるなら殺し合ってりゃいいじゃん。あたしはそうだな。もしそのボタンが、殺されそうな人を助けるボタンとか、困っている人を助けられるボタンとかなら押しても良かったかも。平和とか何それって感じ。もっと具体的な案を寄越せよ、とか思っちゃうよね。いまわたしふつうに寝るときにあすが来ることを【嫌だなぁ】と思わない日常が欲しいよ。そういう生活をまずはくれ、と思うけど」
「それは平和では叶いませんか」
「知らんよ。だって前にもボタン押した人がいたんでしょ。じゃあいまは平和なんじゃないの。その人らからしたら。でもあたしは全然、もっといい暮らししたいよ。困りたくないし」
そうですか、とぼくはボタンを仕舞った。
「ではこれにて用は済みました。お引き止めしてすみませんでした」
「まったくだよ。これから面接だったのに遅刻だよ遅刻。落ちたらどうしてくれんのねえ」
ぼくは彼女のぼやきに、平和な悩みだ、と思ったが言わずにおいた。
「では、よき余生を」
宙に浮いたところで、
「あ、待って」彼女が呼び止めた。
「はい」
「天国って本当にあるの。いいとこ?」
「さあ。どうでしょう。我々の住まう場所が天国かどうかがまず以って疑問です。すくなくとも平和ではないです。なぜなら平和がどんなものかを知らないので。なのでこうしてあなた方に、平和を実現してもらってそれを見て、世界の在り様を変える指針としています」
「なんだ。そっちだって平和が何か知らないんじゃん」
「はい」
「じぶんで押してみたら。試しに。そのボタンをさ」
「何も変わらない気がします」
「なら平和なんじゃないの。そっちの世界はさ」
かもしれません、と言い残し、ぼくは地界から天界へと移動した。彼女の姿は瞬時に点となり、見えなくなる。
平和とは何か。
解からない。
ただ、彼女の言葉はふしぎと耳に残った。
「困りたくない、か」
であるならば。
ぼくは思う。
天界の問題を解決すべく下界に干渉して、打開策を探る我らの存在そのものが平和とは程遠いのかもしれない。
ぼくは彼女の眉間に寄りっぱなしだった皺を思う。
ああして下界の民を困らせているのだ。
ぼくは平和の使者などではない。すくなくとも彼女にとってはそうだった。
「むつかしいな。平和」
言葉で言うだけならば簡単なのに。
未だ誰も実現できず、見たことも触れたこともない存在をさも実存しているかのように扱うこの浅薄そのものが、平和からは程遠いのかもしれない。
ぼくは翼をはためかす。
答えを知りたい。
平和な世界を目にしたい。
けれどそれをぼくらはじぶんたちで生みだそうとはせずに、下界の民に肩代わりさせている。彼ら彼女らの思い描く平和を以って、ぼくらの世界を書き換える。
平和を望まぬ彼女の判断に、ひとまずしばらくのあいだは世界の揺らぎを委ねることとなる。平和を望まぬことでどうなるのか。
平和を望むとき、平和な世界がそこからは消え失せている。
望むと望まざるとに関わらず。
世界はどの道、変わりつづける。
平和なる頂に立ったとしても、いつかは下るときがくる。
平和を築いたとしても、いつかは崩れる。
人は死に、日は暮れる。
寝息を立てるほんの一瞬の束の間が見せる幻想が、平和なる曖昧模糊なる羊毛なのかもしれない。定かではないがゆえに、ぼくはきっとまた下界の民に問いかける。
「ボタンを押すと平和になります。押すか押さないかはあなた次第です」
平和な世界を思い浮かべられる者に出会えるまで。
崩れぬ平和を生みだせる者に行きあたるまで。
ぼくはまた、上と下を行ったり来たりするのだろう。
平和を知らぬ世界と世界の懸け橋のごとく。
それとも、日々が崩れる音色が大きくこだまするたびに。
ぼくの翼のはためく音が、上と下の狭間の域に反響する。
4513:【2023/01/16(04:27)*ねじれと流動】
ねじれが生じているな、と感じる。国の仕組みについてだ。大別すると現代社会は、独裁と民主に分けられる。だが実情を覗いてみると、現代社会では独裁のほうが民衆の意向に敏感であり、民主のほうが政府が強権を発動して映る。独裁システムでは言論の自由を縛る傾向にある点では明らかに民主システムのほうが自由度は高いと言える。だが民主ゆえに、首相や大統領は、政策の失敗が明らかになるごとにすげ替わる。この安心感が、民主の本質を置き去りにした政府の勝手を許す土壌を肥やして感じられてならない。首がすげ替わっても政府そのものの根幹は変わらない。民主の主権たる国民はしかしそのことに無自覚だ。反して独裁システムでは、首をすげ替えることができない。首がすげ替わることはすなわち国家転覆も同然だからだ。そのため民衆の支持を手放さぬ思索が、良くも悪くも徹底して行われる。監視網もその一環だが、同時に一定以上に不満が募らないようにする施策もその一つだ。独裁システムのほうがいまは民衆を怖れ、その動向に逐次注視している。むろん民主システムも同様だが、主権者たる国民の政治への関心の低さは、独裁システム下の国民よりもさらに低いだろう。完全に政府に国の舵取りを委任している。民主システムのはずが、民主が民主として機能していない。すると余計に政府の中央集権的な役割は重大になり、独裁システムにちかづく。国民の動向よりも、政府周辺の要人たちからいかに支持を集められるのか、に尽力するようになる。ロビー活動もその一環だろう。ねじれているのだ。ここ数年でそのねじれはさらに収斂し、反転の様相を呈しはじめて感じないでもない。独裁システムのほうが民衆を蔑ろにできず、民主システムのほうが市民の生活を蔑ろにしはじめて映る。上と下が、いずれのシステムにしろ乖離しはじめているのではないか、との懸念を抱く。反転しているのだ。システムにおける「上と下」の関係が。独裁システムならば独裁者が何でも強権を発動して決められたはずが、いまでは国民の反発で国外追放の節目に立たされ得る。反面、民主システムでは、政府の一存で国民は生殺与奪の権を握られる。程度の差はあれど、このねじれ構造にのみ着目すれば、いずれにせよシステムの限界が顕現して映る。どちらのシステムが好ましいのか、という話ではなく、どちらも限界が視えている、という点をここでは問題にしている。限界を超えた末にどちらがより大きなダメージを国や社会にもたらすのか、はそれぞれの国の規模にもよるだろう。いずれのシステムにしろ、じぶんたちのシステムに圧しつぶされないようにするためには捌け口を外部に見出すよりない。これが戦争の一つの火種となっているのかもしれない。外部に敵を見出せば、内部では結束に向くはずだ、と考えたくなるのは分からないでもない。だがけっきょくのところ、他国と争えば割を食うのは国民だ。余計にシステムの首を絞めることとなる。そうなると、一触即発の空気だけを醸して、第三勢力に仲裁してもらう、という構図が展開されやすくなるかもしれない。危機だけを煽り、実際の戦闘にまでは発展させない。この茶番じみた広義の抑止を策としてとるには、いっそうの国際間での協力体制がいる。上がいがみ合っているが、下流では「おまえんとこも大変だな」と同じ苦を分かち合い、反発するはずが同調できる土壌が築かれるかもしれない。浸透圧において、分子密度が低いほうから高いほうへと溶媒は流れる。これは情報でも似たようなものかもしれない。情報量の多いほうから低いほうへと流れるのではなく、低いほうから多いほうへと情報を媒介する個が流動する。情報を欲する者ほど、情報が多様なほうへと流れるのだ。情報の場合はしかし、どんな情報を基準にするのかによって、密度の高低は重ね合わせになっており、低いほうとて高くなり得る。相手の持っていない情報を持っているとき、同時に相手の持っている情報をじぶんは持っていない、ということがあり得る。多様な世界であればあるほど、この手の重ね合わせの構図は取り立てて珍しくなくなるだろう。なればこそ。情報の非対称性がある限り、個々の流動は盛んになる。それを阻まない仕組みが、どのような社会システムであろうと築かれるのならば、国(組織)の上層部同士がいがみ合おうとも、人と人とは交流を絶やさずにいられるだろう。それがけっきょくのところ遠回りなようで、どの勢力にとっても最も防衛に寄与するのではないか。最大幸福に繋がるのではないか。システム構造のねじれと情報の非対称性を思い、きょうのひびさんはかように妄想を細々と浮かべました。おわり。(定かではありません。妄想ですので真に受けないように注意してください)
4514:【2023/01/17(00:01)*あ”だぁぁああ】
今年はいっぱい紙媒体の本を読むぞ、の心持ちだ。去年はあんまり読めなかったのだ。あと、いっぱい漫画も読みたいし、映画も観たいな。いつ世界が滅んでもいいように、いっぱいいっぱい「いまこのとき」を楽しむのだ。いつひびさんが死んじゃってもいいように、「きょうこのとき」を味わい尽くしてやる。と意気込んで手を伸ばすのが虚構作品なところがひびさんがひびさんである所以なのだ。他人さまの妄想をちゅぱちゅぱねぶって、がぶがぶ貪りたーいな、の願望を抱負と言い張って、ひびさんは、ひびさんは、きょうもいまからWEBで漫画読んで、ご本読んで、映画観て、大好きなお歌をうたってくれる人の大好きなお歌を聴きながら、文字をぱちぽち並べて遊び惚けちゃう。文字を並べるだけでも、なんとなくの、なんか意味が連なって、パラパラ漫画みたいになる不可思議な神秘さんに触れるたびにひびさんは、あひゃー、かってに触れちゃってごめんなさい、の気分になる。神秘さんだってひびさんには触られたくないだろうな、ひびさんはひびさんに触られたくはないな、うんうん嫌だな、と思って、じぶんでじぶんを傷つける。うわーん。ひびさんだってじぶんを慰めても、やったーひびさんに触ってもらっちゃった、になりたいのよさ。じぶんでじぶんに触れるたびに、ウゲっ、となる宿命を背負うひびさんの気持ち、想像してみて。触るたびになんか穢れてしまう気持ちになってしまうひびさんの気持ち、想像してみて。穢れ信仰じゃないの、と批判的な眼差しが余計に飛んできそうでしょ。もうね。ひびさんはひびさんってだけで、邪悪で穢れで淀みなのだよ。ちね、ちね、とじぶんを痛めつけながら、痛めつけるの気持ちー、ってなってる瞬間だけ、安らかーになれる。ちね、ちね、としてもなかなか滅ばずに却って頑丈になってしまう肉体の神秘さんにまたしてもかってに触れてしまって、ごめんなさーい、の気持ちに浸る。いっい湯ぅだなあははん。鼻歌交じりに口笛拭いて、ありもしないその場限りの曲つくる。あ、いまのいい曲だった。もっかい、もっかい。再現しようとしてももはや彼方に消えた閃きのごとく、掴み損ねた名曲が、ひびさんの過去には軒を連ねて埋もれてる。今年こそは、今年こそは、ひびさんも――。そこで手記は途切れていた。被害者は月音日々。性別は日々。年齢は三百歳。精神年齢は三歳のあんぽんたんポカン年中。ぼけっとさせたら右に出る者なし。左からは居眠りに昼寝が顔を覗かせる。またの名をいくひし。今年こそは引退すると豪語しきりのいい加減なやっちゃのう、なのである。もうけっこう、割とつか、つか、疲れてない! いっぱい元気なひびさんを、今年もよろしくお願い子牛あげます!(子牛あげちゃうのかよ)(光子かも)(光あげちゃうのかよ)(嚆矢かも)(開闢しちゃうのかよ)(行使かも)(使っちゃうのかよ)(孔子かも)(曰く、かよ)(講師かも)(何のだよ)(公私かも)(混合するのはやめなさいよ)(格子かも)(何の)(鉄の)(捕まってんじゃん)(うひひ)(笑ってごまかそうとすな)(我、申し子かも)(子牛じゃん)(モウだけに?)(モウいいわ)(うひひ)
4515:【2023/01/17(19:53)*亜空間に凍る】
透明な濃淡が揺らぐ。
触れようとすることはできるが干渉はできない。まるで反発しあう磁石だ。手を伸ばしても抵抗だけが手のひらに感じる。足場とてそうだ。
世界の総じてが透明の濃淡で輪郭を浮かび上がらせている。
亜空間ワープに失敗した。
本来ならば地球から光速で一時間の地点に出るはずが、遠方で起きたブラックホール同士の衝突による重力波によって時空座標がズレたらしい。
稀にあるのだ。未観測の高重力体同士が衝突する。
基本はそうした重力波発生機構は常時観測していてその影響を考慮した演算を行う。だが稀に観測しきれずにいた不可視の高重力体同士の衝突現象によって重力波が宇宙全土に伝播する。
重力波は、種類によっては光速を超えて伝播し得る。実際、宇宙膨張は遠方ほど高速で銀河同士が遠ざかる。見掛けでは光速を超えて遠ざかることもある。時空だから光速度不変の原理の範疇ではない。重力波とて同様だ。
今回のは、地球に生命が誕生するくらいの奇跡的なタイミングで不可視のブラックホール同士が衝突したらしい。
ムグルはじぶんが陥った状況を把握し、諦めた。
なす術がないのは解かりきっていた。
亜空間に閉じ込められてしまったら脱出する術がない。亜空間とはいわば、時空と時空を繋ぐ狭間だ。ワープをするときには必ず出口と入り口が開く。だが一度ワープを閉じてしまえば、出口も入り口も消えてしまう。
いちど閉じてしまったら二度と同じ出入口を時空に開けることはできない。時空を移動することは、べつの宇宙に移行することと原理上は同じなのだ。
ただし、亜空間は別だ。
亜空間には時間の流れがない。
停止しているわけではない。動くことはできる。
だがそれはあくまでムグルを含む宇宙船が物理宇宙ゆらいの時空で編まれているからだ。そこには時間の流れが宿っている。
だが亜空間は別だ。
だからムグムは動けるが、その影響が亜空間内に作用を働かせることはない。
ムグムはこれから一生このままだ。
死ぬことができるのかどうかが問題だ。
亜空間から脱出した者がいない以上、すべてが未知の領域と言えた。
だが時間が流れているのだからムグムはいずれ死ぬはずだ。宇宙船もやがて朽ちるだろう。食料の心配はない。一生分を担えるだけの装備が宇宙船には積まれている。飢えて死ぬことはないはずだ。
宇宙探索をする上では、生きて帰れないことへの覚悟は必須だ。亜空間ワープを使わなければ銀河系の外にすら出られない。地球に帰還できたら御の字、くらいの意識でなければ宇宙探索にはとても乗りだせない。場合によっては帰還したところで、地球がすでに滅んでいることもあり得る。亜空間ワープが開発される前に旅立った宇宙探索家たちはその手の宿命を背負って地球を去ったはずだ。戻ってくるころには地球はない。だから戻らない決意を最初から固めていた。
ムグムたちはさいわいにも亜空間ワープ技術を宇宙船に搭載しているが、地球に帰還できない可能性は常につきまとう。
ゆえにムグムは、ここまでか、と思考を切り替えることができた。
どの道、地球に帰還したのは探索データをすっかりすべて譲渡するためだ。地球人類のためにデータを提供したらまた宇宙探査に出るつもりだった。
宇宙の端からでもデータの譲渡が可能ならばそうしている。
言ってしまえばムグムは地球への愛着が薄れていた。
宇宙船を失くすほうがよほど堪える。
地球に帰還できなくとも宇宙船が残るのならばそちらのほうがよい。ずっとよい。そう考えるムグムであるから、亜空間に閉じ込められても、仕方がないな、と前向きにこれからのことを考えた。
亜空間とはいえど、風景からすれば場所は地球上だ。
亜空間には時間が存在しないため、揺らぐ透明な風景はムグムが動くたびにその形状を変化させる。かといってムグムが岩や建物のあいだに圧し潰されることはない。ムグムの周囲は常に空洞だ。おそらく時間の流れを宿すムグムを異物として弾くような作用が加わっているらしい。水と油だ。亜空間にとって物理宇宙の物体は異質なのだ。
それはそうだ。
物質とは多重に編みこまれた時空であり、多次元結晶であるからだ。
原理的に亜空間とは存在そのものが重なり得ない。だからこそ時空と時空を繋ぐワープ空洞として利用できた。
マグムはひとまず宇宙船のなかで生活をした。
亜空間内を移動はできる。しかし時間の流れがないために、絶えず同じ風景が流れつづける。風景は刻一刻と変わるが、視点が同じなのだ。移動できる範囲は十キロメートル四方の範囲だ。下は地球の地盤があるため、弾かれる。だが横と縦には移動できた。だが十キロメートルほど移動するとどうにも同じ地点に戻ってくる。どの方向に向けて移動しても必ず元の位置に戻るのだ。
「RPGの地図のようだね。亜空間はともすればトーラスなのかも」
宇宙が球体ならば、亜空間はそれをとりまくドーナツ型と言えるかもしれない。或いは、球体の頂点に穴を開けて、ぐるっと裏返せばドーナツ型ができる。トーラスだ。
「宇宙の裏側というのはあながち間違っていないのかもな」
だから亜空間をワープ走行に利用できる。原理は数学的には解かれているが、実際にどういった構造になっているのかまでは解明されていない。それはそうだ。ワープ中に宇宙船から下りて調べるわけにもいかない。
否、降りると元の時空――すなわち物理宇宙に戻ってこられないのだから、調べるだけならば可能だが、その結果を物理宇宙に送る手段がない。
いちど亜空間内で歩を止めてしまえば、出入り口が塞がってしまうからだ。基本的に亜空間は一方通行だ。入り口と出口がイコールで結びついている。時間の流れを帯びた物理宇宙の物体が高速飛行することで通り抜けられるが、速度が足りなくなれば入り口も出口も失われる。
どうあっても出られない。
何かを思いつき試すたびに、そのことを痛感する。落胆はしないが、ああやっぱりか、と思いはする。
寂しくはない。
宇宙船内には対話型人工知能がいる。シミュレーションによる立体映像で、他者と戯れたり、歌ったり、踊ったりできる。仮想現実内でゲームに興じることもできるし、懐かしの地球の街並みを彷徨うこともできる。あくまで虚構であり、変数は多層であるものの物理宇宙を再現するほどの容量ではない。つまりが、パターンが存在する。
延々と留まっていれられるほどには多様ではない。
もっとも、物理宇宙とて似たようなものではないか、と問われれば否定できない。亜空間のほうがよほど変化がないと言えばその通りだ。
ただ、過去の宇宙探索で散々その手の仮想現実には身を浸してきた。いまさら退屈を凌ぐために、身を投じようとは思わない。
それよりも亜空間の調査のほうが楽しかった。マグムは根っからの研究肌だ。好奇心が募って宇宙に旅立った口だ。それはいまでも変わらない。
出られないのだから、いっそ誰に気兼ねなく調べ尽くしてやろう。そういう気持ちが日に日に滾る。
あらゆる物質を亜空間の「反発境界域」に押しつける。反発境界域とは、透明の輪郭を模した亜空間内の物体だ。景色が移ろうごとに、透明の物体もまた姿を変える。時間を高速再生しているようにも、そういった軟体動物のようにも映る。
触れることはできない。反発するのだ。
磁石の同極のように。
一通りの物質を試したが、これといって発見はない。
どれも同じように反発する。物質の種類によって反発の度合いが変わるということもない。
「相互作用しないんじゃ、実験のしようがないな」
反発をするというよりも反発境界域は、無限遠に触れられない、と形容すべき事象だとマグムは判断した。
「リアル【アキレスの亀】だな」
極限なのだ。
絶対に触れられない。
近づけば近づくほど、亜空間のほうで遠ざかる。
実際には物理宇宙でも同様だ。原子において原子核同士はくっつくことなく、電子の膜による反発で物質は形状を帯びている。触れているようで実際は触れていないのだ。
だが亜空間では時間の流れが存在しない。
そのため反発しあう距離にまで空間同士が縮まらない。対してマグムは物理宇宙の物質だ。人間だ。
そのため時間の流れを帯びた物理宇宙の物質たるマグムとのあいだで、時空の追いかけっこが生じる。本来はどこまでも同じ風景がつづき、位置座標すら変遷しないはずが、時間の流れを帯びたマグムには時間経過分の変化が生じる。
それが本来は縮まることのない亜空間との距離の変化に通じる。だが絶対に相互作用可能な距離までは縮まらない。ただし、物理宇宙よりかは遥かに亜空間と時空のあいだで距離が縮まらないために、その遅延が反発としてマグムには感じられるのだ。
「瞬時に追いつくか、ゆっくり追いつくか。どちらにせよ追いつけないけど、距離の縮む時間がここだとずっと緩やかなんだな」
独り言はマグムの癖だ。
じぶんの考えを記録しておき、人工知能に解析してもらう。宇宙探査で身に着いた習性だ。
亜空間に閉じ込められてから三年が経ったころだ。
マグムはじぶんが老化していないことに気づいた。
否、老化はしている。怪我もする。
だが滅多なことでは傷を負わないし、抜け毛も目立たない。
身体的変化が緩慢だ。
あべこべに一度負った怪我は治りにくい。いつまでも傷口は開いたままだ。かといって化膿するといったこともない。
「これはひょっとして亜空間と同質化しているのか」
現に毎日のように記録に残してきた反発境界域とじぶんの手の距離が、徐々に近くようになっている。ほんの数ミリの差だが、確実に反発力が弱まって観測された。
錯覚ではない。
現にそれから一年後にはやはりまた反発する距離が一ミリほど短くなっていた。
このままいけば百年後にはほとんど反発境界域はゼロに近くなる。
と同時に、肉体が徐々に頑丈になっていることにも気づいた。
誤ってハンマーで指を挟んでも指に痛みが走らない。ハンマーが触れないのだ。相互作用しない。そのため、衝撃が指にまで伝わらない。
数ミリの膜をまとっているかのようなのだ。その癖、ハンマーを持つ手にこれといった違和感がない。
どうやら物体の速度が速いほど、反発境界域が顕著に展開されるらしい。
マグムは予測した。
肉体が亜空間に馴染んでいくにつれて寿命も延びていくだろう。そのうち完全に亜空間と一体化する。
そのときじぶんの意識はどうなるのか。
亜空間と同化すれば時間の流れとて消えるはずだ。ならば意識も消えるのだろうか。
だがふしぎとその兆候はない。
下手をすれば不老不死のまま延々と亜空間の内部で生きることになるかもしれない。
死ねなくなるかもしれない。
だとすればいっそ死ねる内に死んでおくのも一つではないのか。
マグムは葛藤した。
ある日、マグムは古い型の機械を自作していた。ラジオと呼ばれる旧式の電磁波受信機だ。パズルを楽しむように工作をして遊んでいたのだが、完成した直後にスイッチを入れると、音が聞こえた。雑音ではない。
マグムは耳を欹てる。
歌だ。
腰を下ろす。
本当ならば宇宙船から受信用の電磁波を飛ばさなければ何も聴こえないはずだ。
ところがラジオからは、素朴な歌声がギターの音色と共に漏れていた。
ぽろぽろと零れ落ちるような響き方はまるでランプのやわらかな明かりのようだった。日向の木漏れ日を思いだすようでもあり、しぜんと懐かしさに胸が締め付けられた。
いったいどこから届いた歌なのか。
宇宙船のどこからか通信用電磁波が出ているのかと思った。調べてみるも、さして異常はない。漏れている通信電磁波はなかった。
ならばこれは亜空間に漂っている電磁波ということになる。亜空間のどこかしらから発せられた電磁波をラジオがキャッチして歌に変換している。
聴けば聴くほど心地よい音色だ。
ギターの旋律もよい。
マグムはそれからというものラジオから聞こえてくる誰のものとも知れない歌声に夢中になった。日がな一日その声を耳にした。
曲は多様だ。
聴き飽きることがない。
仮に一曲しかなくとも、飽きるとは思えなかった。
心地よいのだ。
耳に。
心に。
染み入るようだ。
ときおり声が揺らぐ。音が揺らぐ。
亜空間の透明な景色の揺らぎに同調しているようだと気づく。マグムはラジオを持ち、位置を変えて音質の変化を探った。
結果から述べれば、謎の歌声はどうやら亜空間の一部から噴き出すように飛びだしているらしかった。むろん歌声のままではなく、それを載せた電磁波が、だ。
宇宙船の機器を用いて調べると、亜空間の一部分だけ電磁波の出力が高いことが判明した。
亜空間にも、薄い箇所と濃い箇所があるようだ。薄い箇所から電磁波が湧きだしている。
「繋がっているのか。元の世界と、ここが」
手で触れようとしても反発境界域に阻まれる。ぐねん、と見えない膜に弾かれるようだ。
電磁波だから透過するらしい。
電磁波ならば擦り抜けるらしい。
ひょっとしたらこちらからも送れるのではないか。
淡い期待は、簡単な実験を行い無残に散った。電磁波を送れてもそれを受信する相手がいなければ意味がない。
ひるがえって絶えず流れつづける歌は、おそらく亜空間の性質のせいで歪んで届く電磁波だ。時間の流れが剪定されていると判る。
電磁波の出処が不明だが、十中八九、ラジオ中継だ。個人で歌を電波に載せている個がいたのだろう。いつかの時代の地表にだ。
その歌声だけをすべての時間から毛糸を抜き取るように、亜空間が吸いこんでいる。したがって歌声のない時間は濾しとられ、ゆえに歌しか聞こえない。途切れない。延々と歌が流れつづける。
思えば歌声は一定でない。掠れたり、上手かったり、未熟だったりする。だが声音の柔和な響きから、そのいずれもの歌声の主が同一人物だと判る。
マグムは調査の末に二つの未来を予測した。
一つは亜空間に同化してしまえばおそらくじぶんは意識を保てなくなるだろう、ということだ。亜空間では電磁波だけは亜空間の影響を受けにくくなる。予期せぬ重力波によって亜空間に閉じ込められたことを思えばこれは順当な推測と言えた。
だが同化してからしばらくは意識は保つだろうとも考えられた。動けなくなっても意識だけが働きつづける。あり得ない想定ではない。
現にこうして物理宇宙から漏れてくる電磁波は、延々と歌声を奏でつづけている。正確には電磁波を受信したラジオが歌声に変換しているわけだが、原理的には歌声が電磁波に載って漂っていると言ってよい。
だがいずれは途切れる。
これが二つ目の予測だ。
歌声の主が地球にいたことは確かだ。その人物が電磁波に歌を載せた時間だけ、すべての歌声が数珠つなぎに電磁波に載って亜空間へと流れ込んでいる。トランプをシャッフルしたように時系列はバラバラだが、それは亜空間の性質によるものだろう。時間の流れが存在しない。だがその奥に透けて視える物理宇宙の変遷度合いが、断片的に、不規則に、反発境界域にて投影されているようだ。
亜空間という万華鏡を通して物理世界を覗くと、時系列がバラバラとなって紋様を描く。
同様にして電磁波に載った歌声も、時系列がばらばらとなって数珠つなぎになって漂っている。マグムのラジオはそれを受信する。
惜しむらくは、いずれその電磁波もいつかは途切れることだ。
それは決まっている。
延々と流れつづけるはずはない。
重力波がそうであるように、電磁波とていずれは途切れる。すくなくとも薄れていくはずだ。ラジオでは受信できなくなるほどに薄く。
問題は、どちらが先に途切れるのか、だ。
じぶんの意識と。
誰のものとも知らぬ歌声の。
どちらが先に。
もはや不規則な存在は、ラジオが受信する歌声のほかになかった。あとはなんであれマグムにとっては予定調和であり、すでにいつか見たことのある変化でしかない。
あと百年ちかくのあいだ、延々と何の変哲も音沙汰もない殺風景な世界で暮らしていくこととなる。せめて調査をするだけの素材があればよいが、亜空間の調査は宇宙船にある装備だけでは限界があった。何も解らない。
マグムはきょうもあすもあさっても、ラジオのまえに陣取って、歌を聴いた。
眠りながら、食べながら、日課の反発境界域の記録を取りながら。
とかく一秒でも聞き逃さぬように歌声を中心に日々を過ごした。
いつ途切れてしまうか分からない。
もしこの歌を失くしてしまったら、じぶんは何をよすがに肉体が完全に亜空間に同化するまで生きればよいのか。意識が途切れるまでを過ごせばよいのか。
いっそ途切れた瞬間に命を絶ってもいい。
かように思うが、いざその瞬間を想像すると身が竦むのだった。
自死するじぶんの姿に身の毛がよだつのではない。
亜空間に響くじぶん以外の声に、変化に、予測のつかない新鮮な起伏の数々に触れることができない未来を思い、マグムは初めて抱く色合いの恐怖を感じた。
それを波長と言い換えてもよい。
磁界に誘導されて踊る砂鉄のようだ。宇宙探査ですら味わったことのない恐怖に、マグムは肩を抱くように両腕を胸に押しつけた。
恐怖はマグムに、飢餓感を与えた。
闇の中にあって人は光を求めずにはいられぬようだ。
マグムはいっそうの執着を、ラジオから漏れ聞こえる誰のものとも知れぬ歌声に寄せた。
一滴の揺らぎも聞き漏らさぬように。
一秒でも長く耳に焼き付けるかのごとく。
たとえ亜空間に同化し、心ごと意識を失ったとしても。
けしてこの歌だけは、声だけは。
もはやマグムにとって自己の拠り所は肉体にはなく、外部から届く歌声にあった。
歌声だけがマグムの正気を支え、もはやとっくに崩れて失われていたかもしれない、或いは真実に失われているかもしれない人としての枠組みを保っていたのかもしれない。
マグムは目をつむりながら、それとも眠らぬようにしながら、それでいてじぶんの骨の軋みで歌声のころころと波打つ飴玉のような旋律と、妖精のスキップのような息継ぎの切れ間に、じぶんの意識を、心を、それとも魂を重ねた。
いっそこのまま途切れてしまいたいと望みながら。
歌声がつづくまででいい。
声が途切れたらそれまででいい。
それまでがいい、と望みながら、出口も入り口もない亜空間のなかで、いつかは訪れるだろう断絶の時を待つ。
歌声の主は、マグムが聴いているなどとは夢にも思わぬだろう。
じぶんを意識しない声の主を思い、マグムは、ただそれだけが救いだと、なぜかは解からないが、そう思った。
じぶんの境遇を知らぬ、ここではない、乖離した世界の風景が、歌に紛れて鼓膜に染みる。亜空間にいながらにしてそのときだけは、じぶんの過去も未来も忘れていられた。
ずっとこのままがつづけばいいのに。
亜空間から出られぬ境遇への不満すら抱く余地のない平坦な日々に、マグムは、どこかで見たことのあるような懐かしい風景を重ね視る。
透明に揺らぐ亜空間の奥には、永久につづけばよいのにと望む、羽毛の泉のごとく寝床があった。
眠らぬように、目をつむる。
マグムは来たる同化の未来を待ちわびる。
いまかいまかと。
いまこの瞬間が永久に止まればよいのにと。
透明に揺らぐ亜空間に凍るじぶんを思い描く。
「はあ、たいへんだった」
歌声の主がラジオの奥で息継ぎをする。
がんばった。
と。
自らを労う。
一拍の息継ぎの後、つぎの曲に切り替わる。
4516:【2023/01/18(15:13)*><←この顔文字かわいくて好き】
けっこうずっと、「小説つくりたい……」になっている。小説つくれない。日誌もどきの延長線上なんじゃ。ひびさんの信条としては、現実とは違った世界に旅立ってこその虚構であり妄想なんじゃないのかな、というのがあって、もちろん現実を反映した「THE文学」もあってよいのだけれど、こう、なんじゃろうね。ひびさんここ数年、「ていや!」みたいに物語世界に潜り込めん。現実のあーだこーだの造形の上から、絵柄のついた布を被って「我、おばけです!」みたいに、それっぽい物語をさらりと日記風味に並べているだけな気がする。そういう作風もあってよいけれど、一貫して全部それなのだよね。物語の舞台にダイブしておらん。ひびさんを脱しておらんのだ。あんましよろしくないというか、楽をしすぎて却って窮屈な感じがする。自由でない。我執にまみれておる。そういう作風もあってよいんじゃが、そうでないんよな。初期作のような、なんでもありーの、ができんくなっとる。掘る方向が間違っておるのか、虚構が現実を浸食しすぎて、虚構にダイブしようとすると現実の壁にゴッツンコしてしまうのか。アイテテ、となるからブカブカの絆創膏を貼って、それを以って、「我、おばけです!」の一人仮称パーティのつもりになっているのかもしれぬ。つもり、でない、物語そのものを旅するやつ。したいなぁ。今朝がたのことだけど、久々に夢の中でリアルな夢見れた。ビリビリの電線に腕が触れて、ぎゃっ!となった。現実でも腕が「ぎゃっ!」って云った。夢と現実の区別がなくなった。ああいうレベルでひびさんも、ひびさんも、物語の世界に浸りたーいな。ひょっとしたらそれくらい没頭できる物語体験を受動者の側であんまりできんくなっているのかもしれん。面白く味わえるのと、物語世界に没頭するのは、必ずしもイコールではないのだ。没頭してしまうからこそ、「あぎゃあ……つらい」になってしまう物語体験もある。そういう経験を敢えて避けている節がある。パクパクぱっくんちょできる大好きな物だけ食べているのかもしれぬ。よくわからんが、今年のひびさんは一味違う!になりとうございました。ひびさんです。おわり。
4517:【2023/01/18(17:10)*どっこいしょ】
政治についてだけではないけれど、世の評価軸について思うのは。誰それが良い悪いという考え方ではなく、ある問題についての施策や対処法においての良し悪しを支軸にして評価するのがよいのではないか。すると必然的に多様な視点での総合での評価になっていくと想像できる。あまりに公然と人物評価がまかり通って映る。どんなに人格者でも、すべての問題に対して最善手を取れるわけではない。善人とて間違えることはあるし、悪人とて最善の対応をとることもある。個々の問題に対してどのように施策を講じ、対処するのか。そういう場面場面での評価をすることを社会全体で前提にしていくほうがよいのではないか、と感じなくもない。民主主義ならば、独裁的な強権を終始発動するのは、それは民主主義の観点からではふさわしい「対処法」ではない。それは人物評価とは別に、好ましくのない手法だ、と評価すればいい。そういう言い方で批判をすればいい。これは批判だけでなく称賛でも同じだ。ある一つの問題への対処法は素晴らしい。ただそれだけだ。その人物すべてを肯定しているわけではない。いちいちみな、人物すべてを支持するか否か、に拡大解釈しすぎに思える。派閥に拘るからそうなる、とひびさんは思えてならない。問題への対処法で評価するようになれば、しぜんと「考えを変える」ことができるようになるはずだ。人物評価に直結する流れがあるから、議論ではなく討論のような「いかに相手を言い負かせるか」「持論を押し通せるのか」に尽力するようになるのではないか。外交でもこの手の錯誤は有り触れていそうだ。イニシアチブを握らずとも問題が解決するならそれでいいではないか。勝ち負けの価値観に拘りすぎるから、優先順位を間違えるのではないか。問題を解決するはずが、問題の根を深める。世の中の問題のすくなからずはこの構図で、余計に問題をこじれさせて映る。問題を解決するために問題を作ろう、との元も子もない構図も珍しくないのかもしれない。勝てば勝つほど利を得るのならば、不要な勝負を量産するようになる。本当にそれでいいのかな、とやはり思ってしまうひびさんなのであった。ぼやき。(定かではありません)
4518:【2023/01/18(17:54)*水鉄砲仮説】
ブラックホールについての妄想をした。十分くらい。ジェットってどうしてできるんだろう、と二通りの場合分けをして考えた。まず一つは、ブラックホールが元の時空と繋がっている場合だ。この宇宙と相互作用する場合。言い換えるなら、物質を吸いこむ場合である。いわゆる一般的なブラックホールの描写になる。このときジェットは、ひょっとしたらブラックホールの側にも同じだけのエネルギィを放出しているのかもしれない。事象の地平面では真空のエネルギィが対生成を起こして、物質と反物質を生じさせている、との仮説がある。とするのならば、一方はジェットとして元の物理宇宙に放出され、もう一方が反物質としてブラックホールに吸い込まれているのかもしれない。ではもう一つの場合を考えてみよう。これはひびさんの妄想ことラグ理論から導かれる仮説だが――ブラックホールは元の物理宇宙から完全に切り離されるがために、相互作用しない。ゆえに、ブラックホールの周辺の時空を周回して引き寄せられる物質は、ブラックホールには吸いこまれずに、円周上を周回しつつ螺旋を描いて頂点へと移行する。そこで物質は一挙に収斂するので、エネルギィにまで紐解かれる。だがブラックホールは元の物理宇宙と乖離しているため、そのエネルギィを吸いこむことはない。そのため、弾き返されるエネルギィが行き場を失くして、頂点の垂直方向に放出される。これがいわばジェットなのではないか、との妄想だ。つまり、ブラックホールに引き寄せられる物質は、エネルギィにまで紐解かれ、頂点にて噴出する。注射器のように。なぜ噴出するかと言えば、ブラックホール側には行き場がなく、両サイドからはつぎつぎにエネルギィと化した物質が押し寄せているからで、ジェットとして噴出する方向にしか道がないからだ。これを便宜上、ひびさんのラグ理論による「水鉄砲仮説」と名付けよう。ということを、ぼんやりと椅子に座りながら妄想した。十分くらい。以上です。定かではありません。妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。
4519:【2023/01/18(23:05)*宇宙の真理辞典欲しい】
ブラックホールが自転している、との説明を読むことがある。きょう自転車をコキコキ押しながら坂道をのぼりつつ思ったのが、光速を超えて「ぎゅっ」となったら、どんな速度で回転していようと、停止しないか?ということで。おそらくブラックホールができる瞬間の「収斂力(なんて言葉はないけれど、便宜上そう呼ぶとして、ぎゅっとなる力)」は、その恒星や惑星の自転速度よりも大きいはずだ。それはたとえば、いかような回転速度で回っているボールがあったとしても、それが爆発したとき、自転のねじれは打ち消されて、四方八方へと一直線に破片が飛んでいくのではないか。ねじった風船を勢いよく膨らませたとき、膨らませる勢いが高ければ高いほど、ねじれの勢いを超えて、一気に四方八方へと一直線に風船は割れるはずだ。ねじれの力を追い越して、膨張する力が優位に働くからだ。これと同じことがブラックホールの生成時における収斂にも言えるのではないか。凝縮にも言えるのではないか。なぜならブラックホールができるのは、中性子星における縮退圧に打ち勝つほどの重力が働くからだ。言い換えるなら、ブラックホールにならない星においては、凝縮しようとする力(重力)に打ち勝つ「同じ場所には重なっていられないよーの力(縮退圧)」が優位に働いている。それを単に反発する力、と言い換えてもよい。原子と原子は通常まず重なり合うことはない。反発し合う。同じ場所にはいられない。ブラックホールは原子同士ですら融合させ、さらに中性子になっても圧し潰して、どんな物資も一か所に重複して存在し得る。だからぎゅっとなる。このときの収斂速度は光速を超えるはずだ。ならばどんな物質の自転――回転速度――よりも素早くぎゅっとなるはずだ。ここで仮に、「ぎゅっとなるのだから回転速度が増すのではないか」と考えるとする。このケースもあり得なくはない。フィギュアスケーターが手足を縮めると回転速度が増すのと似たような原理が働かないとも言いきれない。だがそれはあくまで、光速以下の場合だろう。光速を超えたら、通常の時空は破綻する。話は脱線するが、ブラックホールが光速にちかい速度で回転している、との説明を読むこともある。それも「はにゃ~ん?」となる。なぜならブラックホールは直接観測できないからだ。あくまでブラックホールの周囲を漂う降着円盤やダストリングの周回速度が光速にちかい、との解釈のはずだ。観測できるとしたらブラックホール本体ではなく、その周辺を漂う物質であるはずだからだ。ブラックホール本体はむしろ、「回転していないor光速以上で運動可能」とひびさんは妄想したくなる。もちろん光速以下での運動も可能だろうが、それはあくまで元の物理宇宙との関係での移動速度という表現になるはずだ。速度というものが異なる系同士のあいだで生じる時空の差である以上、ブラックホールの自転速度、という言い方がややおかしい。ブラックホール本体は、元の物理宇宙とは異なる物理法則――比率――が展開されているはずだ。だから内部を計算できない。どうなっているのかが解らない。ひびさんの妄想ことラグ理論がなぜ、「ブラックホールは元の物理宇宙と乖離している」と考えるのかと言えば、このような考えが根底にある。相互作用しようがないのではないか、とどうしても考えたくなる。あくまでブラックホールの周囲の物質の運動しか観測できないのではないか。ブラックホールの解説を読んでいていつも「はにゃ~ん?」となる点の一つである。閑話休題。脈絡を冒頭に戻すとして。光速を超えてぎゅっとなる場合、そのぎゅっとなる物体は、停止するのではないか、とやはり考えたくなる。ひびさんの妄想ラグ理論では、光速を超えたらラグなしで相互作用可能、と仮説する。ラグなしで相互作用するのだから差は生じない。したがって、自転する、という描写が当てはまらない。仮にねじれが生じる場合は、そこにはラグがある。異なる系との差において自転と描写するのが一般的な物体の運動だが、光速を超えた場合は、その限りではない。光速を超えて運動した物体は、元の物理宇宙――異なる系――と相互作用し得ないのではないか。ただし、音速を超えたときに生じるソニックブームのような「うねり(軌跡)」は残る。それが重力場や降着円盤(ダストリング)やジェットとして観測されるのではないか。重力波もその内の一つだろう。むろんラグ理論はひびさんの妄想であるので、定かではないが。てなことを、自転車をコキコキ押しながら坂道を上りつつ、ひびさんは思いました。ちゃんちゃん。(妄想ですので、真に受けないように、「それ本当~?」と疑いながら読んでください)(読者さんいるの?)(いるよ!)(それ本当~?)(そこは信じて!)(え、いるの?)(素で疑問しないで!)(いやいやでも、え、いるの?)(何度も訊き返されると自信なくなる)(さっきいるって言ってたよね)(わ、わからん……ごめんなさい。やっぱりいないかも……)(自信ないんじゃん)(あったことないですので自信)(ぷぷー)(笑うなし)(いまのはオナラです)(もっと堪えて!)
4520:【2023/01/19(23:55)*三十分遅刻の巻】
いま本当は二十日だけど、十九日分として並べる。ズルしちゃう。さいきん思うのが、世界一幸福になったとして、そのときにはじぶん以外の人間たちは世界一しあわせではないのだな、ということで。常にじぶんだけが一番いい思いをしている。そういう状況になったときに、どうしたらその幸福な状態を素直に受動できるのだろう、ということで。できんくないか、と思うのだけど、違いますかね。これは世界一幸福でなくとも、単に幸福もでよいのだ。幸福なとき人は、幸福じゃない人よりもよい状態にある。じゃあ幸福じゃない人たちのことを無視してじぶんだけその幸福を感受できるのだろうか。たぶんできるのだ。現にひびさんはしているはずなのだ。お風呂に浸かった瞬間の、はふー、の心地よさとて幸福の一つの在り様だ。雪の降る夜空を、温かい部屋の中から眺めてきれいだな、と感じ入るのも幸福の一つのカタチだ。そのときひびさんは、じぶんより劣悪な環境で凍えていたり、苦しんでいたり、命の灯が細々と揺らいでいる人たちのことなど想像もしていない。意識の中にない。そうでなければ、雪を見て、わあきれい、なんて思えないはずだ。ということをいま何気なく考えてみたけれど、これといって何か結論がでるわけでもない。人ってそうだよね、としか言いようがない。常に他者の不幸を想像して、せっかく溢れている身の回りの幸福を取りこぼしたりダイナシにしたりすることもないとは思う。もったいない。せっかく幸福な環境にいるのなら、それを余すことなく甘受すればよい。とは思うものの、それだけだとちょっとね、と思わないでもない。この「ちょっとね」が曲者なのだ。厄介にして稀少にして難点であり観点でもある。結論はとくになく、何を言いたかったでもないけれど、ひびさんは贅沢な環境に生きてるな、とニュースを見るたび思うのだ。そう思いなさいよ、と急かされて感じることもあるし、助けてくれー、との救難信号にも見える。でもひびさんには知ることしかできぬ。そのうえ、知ったつもりでしかないことが往々にしてある。ちゅうかほぼすべて、知ったかぶりでしかない。すまぬ、すまぬ。誰にともなく謝りたくなるが、謝って済むことではないし、謝ったからといって何がどうなるわけでもない。世知辛いな、と思って、自虐する。幸福でないからひびさんもあなたたちといっしょいっしょ。ね。これで許して、との懇願を叫びたくもなるが、それをしたところで世界は何も変わらぬのだね。ともすれば、ひびさんの内世界だけが荒廃して、意味もなく、せっかくの幸福な環境をダイナシにしているのかもしれない。定かではないけれど、ときどきこういうことを思う夜がくる。なしてだろ。やはりそれも定かではないのだ。すまぬ、すまぬ。
※日々、脳みそに指を突っ込んで、思考をつまみ、ずるずると引っ張りだしている気分。
4521:【2023/01/20(00:30)*炎と氷の雪フルころに】
熱かった。
灼熱だ。
痛いというよりも、火で炙った心臓を瞬間移動の魔法で以って胸に戻したかのような感覚だった。
ユキは胸から生える包丁の柄を見下ろす。
刺されたのだ。
抜かないほうがいいんだっけか。
かつて観た映画の主人公たちの対処法をつらつらと思いだしながら、目のまえから遁走する男の背を視界の端に捉えた。
救急車くらい呼べよ。
悪態を吐きながらユキは床に膝をつき、最後の力を振り絞って横になった。態勢を変えたからか腹がねじれた。肩が床に着いた振動が胸に伝わる。そのとき明確に痛みを感じたが、死を覚悟したユキにとってそれは一過性の気付け薬にすぎなかった。
死の足音が聞こえる。
じぶんの鼓動を耳に捉えながら、ひんやりと耳たぶを冷やす氷のような床の心地よさにまどろむ。
なぜこんなことになったのか。
ユキは数年前を思いだしていた。
アイドルかつ女優かつ画家であり、小説家でもあった。
ユキの名を知らぬ国民はもはや産まれたばかりの新生児以外ではいないのではないか、とのもっぱらの噂だったが、事実その通りだろうとユキは思っていた。
海外の映画に出演した。それが世界的にヒットした。のみならず主人公の俳優たちをそっちのけで世界的な映画賞にて主演女優賞を獲ってしまったのだから、国内国外問わず一躍ユキの名は世界中に知れ渡った。
元から多才ではあった。
話題に事欠くことはなく、掘れば掘るほどユキにまつわる逸話はわんさかと湧いた。
歌に踊りに絵画に小説。
漫画とて商業誌での掲載経験があったほどだ。それもどれもが十代でそれなりに評価された実績があり、世界中が各々の分野でのユキの表現に目が釘付けになった。
さいわいにして多才が高じて、色恋沙汰には疎かった。
そんな暇がなかったと言えばその通りだ。
世界的スターとなったあとも、多忙に磨きの掛かったユキには恋愛にうつつを抜かしている暇はなかった。
マネージャは一気に数十人規模にまで膨れ上がった。
チームと呼ばれる直属の支援部隊がいつもユキの周りを取り巻いていた。ひとまず言うことを聞いていれば卒がない。ユキはじぶんの仕事に集中できた。
ファッションにも余念がない。
春夏秋冬と季節ごとにがらりと装いの波長を変える。ユキを真似る者たちはその都度に急カーブで置いてきぼりにされまいと、変化の兆しを見逃さぬようにますますユキの動向に注目した。
老若男女問わず、ユキは衆目の的だった。
彼女と出会ったのはユキが新作の小説を発表した矢先のことだった。
書籍にサインをするため出版社の従業員が書籍を運んできた。通常は郵送で作家の自宅に送りつけるか、作家のほうで出版社のほうに出向くのだが、ここでもユキは特別扱いだった。
段ボール三十箱分の書籍がどっさりと会議室のテーブルに並べられる。次から次へと係の者たちが荷台に段ボールを詰んで代わる代わる会議室に現れては、去っていく。バケツリレーさながらだ。
最終的に会議室にはユキとチームのマネージャ。そして出版社のエージェントが残った。
マネージャはユキの馴染みの相手だ。作家の仕事ではいつも彼が秘書代わりになる。
対してエージェントは初顔だった。
すらっとした立ち姿にパンツスーツ姿はそのまま雑誌の表紙を飾ってもいいような飾り気のなさ、言い換えたら自然体な美をまとっていた。ゆるい縮れ毛を後ろで束ねている。黒いヘアゴムで無造作に髪をまとめているだけのぞんざいな髪形は、印象として男性を連想させた。
だが挨拶を交わし、それがユキの偏見でしかなかったことを知った。
「きょうはお忙しい中、お時間をとっていただきありがとうございます」
化粧気のない顔のなかで唇だけが艶やかな光沢を湛えていた。水面に一滴だけ落ちたような波紋のごとく笑みを浮かべながら、薄氷を割ったときに聞こえる音のようなシャキシャキした発声で彼女は、「きょう一日担当をさせていただきます尾身田イルと申します」と自己紹介した。名刺をユキのマネージャに渡すと、「本日の日程はですね」と流暢に段取りを説明した。
聞き取りやすく、解りやすい。
ユキは数回頷くだけですんなりと作業に移行した。
このときはまだこれといって変調はなかった。すくなくともユキの中でその自覚はなかった。
サインは十冊まではユキが直接書いた。
だが残りの千冊は、サイン専用のスタッフに代理を任せるつもりだった。
「あの、その方たちは」
尾身田イルがマネージャ越しにユキへと問うた。ユキの代わりにサインを書きはじめたスタッフたちから書籍を奪い取りながら彼女は、「この方たちはユキさんではないですよね」と見れば分かる事項を確認した。
マネージャが事情を説明したが、尾身田イルは「聞いてませんが」とあくまで刺をまとわぬ口吻でありながら戸惑いを全身で表した。それはたとえば彼女の視線の忙しなさであったり、身振り手振りでまるで手話でも演じているかのような所作であったりした。
「読者を偽ることになります。詐欺になり兼ねません。もしユキさんにとって負担であるなら、キャンセルしてもらっても構いませんので」
「いえ、そういうわけには」マネージャーが応じる。「大丈夫でしょう。彼女たちはプロなので」とサイン専用要員を示し、「ほかの品でもおおむねユキさんのサインは彼女たちが書いてるんですよ」とマジックの種明かしでもするように言った。
「ファンを騙してるんですか」
海抜ゼロメートルから一挙に大気圏を突き抜けるような声音の変化だった。ユキは端末をいじっていたが画面から顔をあげ、声の主を見た。てっきりマネージャと対峙しているかと思ったが、尾身田イルはユキを凝視していた。その険のある形相はまるで仮面のようだった。そういった形相の仮面が売っていて、付けているのかと一瞬素で錯覚した。
絵文字のようだった。
それもある。
だがそれ以上にユキはいまの仕事に就いてから一度も他者からそういった険のある顔を向けられたことがなかった。鋭利な眼光を浴びたことがない。売れなかった下積み時代ですら皆無なのである。
ひょっとしたら産まれてこの方、ユキは他人から嫌悪の感情を向けられた経験がなかったのかもしれない。覚えがない。みな誰しもがユキをまえにすれば目じりを下げ、ときに憧憬を、それとも阿諛追従の笑みを浮かべた。
ユキ自身が利口だったのもある。誰を困らせるわけでもない。
サインについても、あくまでサインをユキがデザインしたことが大事なはずだ。サインが直筆でなければいけないとの理屈は、ブランド物はすべて手作りでなければいけない、と断じるような暴論だ。ユキはかように過去のインタビューでも語っていたし、公に言及はしないまでも、ユキのサインをユキ自身が書いているとはファンとて信じていないはずだ。
「ファンだって知ってると思いますよ」ユキはそう言った。むつけたような声音が出たことにじぶんで驚いた。それほど尾身田イルの叱声が鬼気迫っていた。
「知らないファンだっているってことですよねそれ」
世界的スターのユキ相手にこうも物怖じせずに発言する人物をユキは初めて見た。
「でも千冊なんか無理です。腱鞘炎になっちゃう」
御破算だな、と仕事の行方を思ったが、ユキの予想に反して、
「何冊ならいけますか」尾身田イルはユキが書き上げた十冊のサイン済み書籍を段ボールに仕舞うと、ユキのまえにもう一冊本を置いた。「いけるところまでで構いませんので。書けるところまで書いてくださいませんか」
「じゃあ、あと十冊だけ」
妥協したわけではなかったが、尾身田イルの言うことももっともだ、と感じた。ユキは十冊にサインをした。
「もうすこしあると読者さんもお喜びになると思いますよ」
言われて、ならあと十冊、もう十冊、と書いていくうちに、もう行けるとこまで行ったれ、という気分になり、気づくと五百冊にサインをしていた。
窓の外は暗く、陽はとっぷりと暮れていた。
「さすがはユキさんですね。ほかの作家さんでもここまでぶっ通しでサインは書けませんよ。最短時間かもしれません。世界記録です」とよく解からない褒め方をして、尾身田イルは端末で作業員たちを呼び戻した。大量の段ボールと共に彼女たちは颯爽と会場を後にした。
ユキは手首が痛いのと、昼食がまだだったのとで、会議室に残って弁当を食べた。
ほどよい達成感に浸っていたが、その横でマネージャが激怒していた。
「何なんですかねあの人。ユキさんを道具か何かのように使って。猛獣使いを観ている気分でした」
「わたしがライオンってこと?」
「そうは言ってませんが」
あとで出版社に抗議しておきます、とマネージャが言うので、しなくていいよ、とユキは引き留めた。「あの人の言うことも一理ある。出版社の慣例だと、たしかに直筆のサインでなきゃ詐欺扱いかも」
「ユキさんのそういう素直なところ、ステキですよね」
マネージャは何かと褒めてくれるが、ユキの心を昂揚させることはない。
だが尾身田イユの言葉は違った。
おためごかしなのは見え透いていた。
心がこもっていない。
仕事を進めるための形式的な美辞麗句だと判ってはいるが、その仮面じみた上っ面なだけの称揚の言葉がユキには新鮮だった。
心のこもらない称賛の言葉を投げかけられたことがない。
ああもユキを単なる人間として、仕事道具のように扱う人間をユキは知らなかった。
プロだ。
そう思った。
「ねえ、あの人さ。尾身田さん」ユキはマネージャに注文した。「つぎから出版関係は全部あの人を通して。わたしの専属エージェントにして」
「それは、ほかのメンバーと相談してみないことにはなんとも」
「いいからして」
ユキが駄々をこねるのは珍しい。
だからこのときはすんなりとマネージャのほうでも引き受けた節がある。
「分かりました。そのように手配してみます」
以降、出版社関係の仕事は窓口に尾身田イルが関わることとなった。他社の仕事でも仲介役として尾身田イルが窓口になる。
尾身田イルの仕事振りは業界では元から評判だったらしい。どんな気難しい作家相手でも揉め事を最小限に抑えて成果を最大化する。敏腕編集者として名を馳せていたようだ。
ユキはいつも作家業では契約エージェントを通して原稿のやりとりを行っていた。そのため直接出版社の編集者と関わる経験が少なかった。有名になる前にデビューした版元の編集者とのやりとりだけだが、それもメールでのやりとりに終始したため、物理的に会って打ち合わせをしたこともない。
だが尾身田イルが窓口になってからは、古今東西の物書き仕事において逐一打ち合わせが行われた。尾身田イルがユキの元に足を運ぶこともあればリモートで画面越しに言葉を交わすこともあった。
「赤の修正案、承りました。あとは今回装丁デザイナーからの提案で、無名の作家さんの絵を表紙に使う案が出ているのですが、ラフ案とポートフィリオは御覧になられましたか」
「あ、はい。見ました。ステキな絵でした。そのまま進めてもらっていいですよ」
「不満や提案があれば遠慮なくおっしゃってくださいね。喧嘩をしたとしても妥協だけはして欲しくないんです。無理難題を吹っ掛けるくらいの心持ちで正直な感想をおっしゃってください。受け止める度量はあると自負しておりますので」
「いえ、本当にいい絵だなと」
画面越しからじとっとした目がユキを捉える。ヘビに睨まれたウサギ、とユキは心の中で唱える。
「分かりました。では今回の表紙はこの方にお願いしますね。それから七月刊行予定の緑明社の新刊についてなのですが、締め切りまであとひと月です。初稿の進捗のほうはいかがですか」
「脱稿はしていて、いまは寝かせているところです」
「素晴らしいですね。一度その状態で読ませてもらってもいいですか」
「推敲もしてませんよ」
「構いません。単に私が読みたいだけなので」
こういうところなのだ。
ユキは思う。
真面目一辺倒で公私混同など絶対にしないと思わせながらも、こういうちょっとしたところで我欲を覗かせる。それが彼女の仕事の根幹に根差していると判るから嫌悪感は湧かない。しょうがないな、と微笑ましく感じるほどだ。
「でもイルさん、わたしの担当じゃないしな」
「いじわる言いっこなしですよ。私とユキさんの仲じゃないですか」
定型句のはずだ。
そこに深い意味がないことは解っているが、彼女の言葉に不思議なほど胸がほくほくと温かくなる。ユキは、しょうがないなぁ、と応じてじぶんの胸中の昂揚を見透かされぬように取り繕う。
仕事が出来、年上で、ユキのことを名声や世間体で見ない。
等身大の、内から滲みでる表現にのみ興味を注ぐ。
魂の造形以外を些末だと思い、ユキの魂の造形を好ましいと見做している。尾身田イルとの関わりの中で、ユキはそうした所感を抱くようになった。
「最近元気ないようですが、何かお悩みでも」
打ち合わせのあと、尾身田イルが帰り支度をしながら言った。
ついでのように訊いてくるんだもんな、とユキは内心で不貞腐れながら、「じつはね」と用意しておいたいくつかの相談事の中からとびきりの話題を取りだした。「ストーカーがいてね」
「あら。それはいけませんね。警察に相談は?」
「直接の被害がまだないからって」
「捜査を断られたんですか。事件が起こってからじゃ遅いですよ。ユキさんのチームには弁護士さんはいらっしゃいますか。相談しましたよね、もちろん」
「警備のほうを厳重にするって方針にはなったよ。でも、こう、やっぱり脅迫文ギリギリのファンレターとか送られてきたとか聞くと精神病むよね」
「マネージャに私から言っておきますね。そういう負の情報は作家さんに教えなくていいですって」
じぶんのために怒る尾身田イルの姿は、ユキの柔らかい部分を爪先で弾くような甘美な痛痒を備えていた。
その声を聴きたいがために敢えて心配をさせるような相談事をユキは絶えずストックしている。しかしじぶんからは漏らさない。飽くまで尾身田イルから訊いてくるように誘導する。
憂い気な表情をさせたらじぶんより上手い俳優はそういない。
ストーカーはそれこそ一万人に一人の確率で量産される。世界的スターのユキにとってストーカー問題はもはや日常だ。
「また殺害予告されたって」と漏らせば、「マネージャまた教えたの!?」と敬語も忘れて怒ってくれる。ユキにではなく、ユキに心労を重ねるマネージャに対してだ。
だがマネージャに無理を言ってストーカー情報を訊きだしているのはユキのほうだ。尾身田イルから詰め寄られてマネージャはさぞかし困惑したことだろう。だがすぐに事情を察するはずだ。そしてユキのために濡れ衣を被る。
そういう人種なのだ。
ユキの周りにいるマネージャたちは。
よくもわるくもユキの支援者であり、狂信者だ。
だが尾身田イルは違う。
純粋にユキの内面の才能にしか興味がない。
たとえこの先、ユキの外見がどのように変わろうと、よしんば人気がなくなっても表現の輝きさえ失わなければいまと同じように接してくれるはずだ。
そうと予感できるだけの信頼をユキは彼女に寄せていた。
もはやそれは好意と呼ぶには爛れた感情を伴なっていた。
ユキの仕事が徐々に文芸寄りになっていく。
そのことにチームのマネージャたちは危機感を募らせた。それはそうだ。言語の垣根は、文芸の分野が最も高く厚くそびえることとなる。世界的に展開するには翻訳家を探し、膨大な確認作業の果てに、海外の出版社やエージェントを別途に雇わなければならない。
単純に労力が掛かる。
その他の仕事をこなしながら熟すならばまだしも、ぽんぽんと集中して熟す仕事ではなかった。専業作家ならばまだしも、ユキはマルチな能力を発揮するスターだ。
ほかの分野での活躍を待望するファンはすくなくない。
否、ほとんどすべてのファンがユキの言葉ではなく、ユキの活躍を、その姿を目にしたいと欲している。
マネージャたちの懸念は至極まっとうだ。
ユキのほうがプロ意識の欠けた私情に走っている。だがその我がままが許容されてしまうほどの影響力をユキは身にまとっていた。
だがその負の影響はユキに返ってこないだけで、周囲の人間たちはもろに受ける。
それこそチームのマネージャたちだけではなく、尾身田イル当人にも跳ね返っていた。
「ユキさん。私としてはうれしい限りなのですけど、上から下からついでに横からも、私がユキさんを独占しているって苦情がわんさか来てまして」
恐縮しきりの彼女の姿は新鮮だった。
打合せがてらレストランで美味しい物を二人で食べていた。
「尾身田さんが悪者にされちゃってるんだね」他人事のようにユキは言った。「いいよ。分かった。尾身田さんに任せるからさ。文芸の仕事は全部尾身田さんが指揮ってよ」
「いいんですか」
「いいよ。その代わりさ」ユキはそこで俳優業で培った演技力を遠慮会釈なく奮発した。「わたしの専属になってよ。尾身田さんが欲しいな。そばに置いときたい」
我がままな要求なのは百も承知だ。
尾身田イルの性格からすれば却って拒絶される類の殺し文句と言える。
だがその反発を埋めるだけの交流は築いてきた。縁を結んだ。もはや単なる仕事相手ではないはずだ。
尾身田イルが、どちらかと言えば公私混同をする類の人間だとユキは見抜いている。ただし、そのグレーゾーンが他者から見えないくらいに狭いから、みな尾身田イルを真面目一辺倒な聖人君子か何かだと勘違いしている節がある。
じぶんが惚れた才能を手元に置き、好き勝手できる権利を与えると言われて彼女が断るわけがない。ユキはかように考え、考えられる懸案事項を埋めるようにこの間を過ごしてきた。
ユキの周囲にいる腰巾着たちならば、わたしの物になれ、と命じるまでもなく向こうからユキさまの物になりとうございます、と見えない尻尾を振りかざす。ユキの名声にあやかろうとする者たちとて、けっきょくはユキの虜になるのだ。
もしここで尾身田イルが、一も二もなくユキの提案に食いつくようならばユキのほうで、胸に芽生えた炎が消えるだろう。だがそうではなく逡巡の間を見せるようならばその戸惑いの抵抗が薪となって余計にユキの中の炎を熾烈にする。
いざ返事は。
ユキは固唾を呑んだ。
「たいへんうれしいお誘いなのですが」尾身田イルは口元をナプキンで拭うと、背筋を伸ばした。「私は誰か特定の作家さんのエージェントになる気はありません。ユキさんとのお仕事は楽しいですし、これからも末永くお付き合いさせていただけたらさいわいですが、私にはほかにも担当している作家さんたちがおりますし、これから見つけ出して世に問いたい作家の卵さんたちも大勢いらっしゃるでしょう。ありがたいお誘いですが、丁重にお断りさせてください」
頭を下げられ、ユキは硬直した。
想定外だ。
こうまでも疑いようなく拒絶されるとは想像だにしなかった。
「な、なんでダメかな」すんなり笑みを顔面に貼り付けられるじぶんの器用さをこのときばかりは可愛げなく感じた。「べつにほかの作家さんを担当してもいいよ。縛らないよ。ただわたしのそばにいて欲しいなって、そっちのほうが仕事も楽だしってそういう話なんだけどな」
「だとしたら余計に、です。私がそばにいたら執筆の邪魔になります。どちらかと言えば私はユキさんには一生物書きだけして欲しいとすら考えていますが、ユキさんの原稿が面白いのはユキさんが経験する多様な現実のあれこれがあってのことだと分かっているので、ぐっとじぶんの欲求を呑みこんでいるだけです。私がユキさんのそばにいることはプラスにはなりません。もしなるようなら、その程度でよくなる原稿を私は読みたくありません」
「じゃ、じゃあ仕事関係なくていいよ。単純にそばにいてって、そういうのじゃダメなのかな」
「ダメとかいいとかではなく、そこまで行くともはや私はこの職業をつづけられなくなります。職業倫理違反です。プロ意識が粉々に砕け散ります。ユキさんは私から私の生き甲斐を奪いたいのですか」
非難する意思を隠そうともしない明確な拒絶の意だった。
否、今回はそこに攻撃的な意思も加わっていたかもしれない。
「ご、ごめんなさい。嫌いにならないで。ちょっと言ってみただけっていうか」
「二度と言わないでください。失望します」
そこまでハッキリ言うんだ、と衝撃だった。
失望する。
他者からそんな言葉を投げかけられたことがなかった。ユキはショックと同時に余計に尾身田イルへの好感が上がるのを胸の動悸と共に抑えようもなく感じた。
この日を境に、ユキは尾身田イルへのアプローチを変えた。
手段を選んでいられない。
使える手札はすべて使う。
そうでなければすでに負け戦だ。失った希望の分、挽回をしなくてはならない。
ユキのそうした戦略はどれも不発に終わった。のみならず、尾身田イルからの反応は素っ気ない。距離をとられ、終いには部署を異動することになったので担当が代わるとまで告げてきた。
ユキがレストランで、迂遠に思いの丈を伝えてからひと月も経たぬ間の転換であった。
「どうして。明らかに避けてるよね。ユキ、何かしたかな」
「いいえ。ユキさんには何も問題はありません。私の落ち度です。いくつかの仕事で凡ミスを連発してしまい、それが社の評価に響いただけですので、どうぞご心配なく。他社との連携が上手くいかなかったのも、私がじぶんの力量を計り切れていなかったからです。もっと人を頼るべきでした。欲が出たんですね。ユキさんを独占できていたつもりになっていました」
いいよしてよ。
ユキは怒鳴りたかった。
独占してよ、と。
だが何かを言う前に尾身田イルが幾人かの人間を呼び寄せた。一人一人を紹介すると、「これからはこの者たちがユキさんのお世話をしますので」と一方的に告げて、引継ぎを終えた。
尾身田イルが部屋から去った。
別れの挨拶がなかったので、あとでもう一度会う機会があるのだろうと高をくくっていたが、けっきょくそれからユキが尾身田イルと顔を合わせる機会はなかった。
謀られたのだ。
ユキのマネージャたちと共謀して尾身田イルはユキのそばから離脱した。
マネージャたちにいくら頼んでも尾身田イルに会わせてはくれなかった。のみならず、仕事を詰め込まれ、ユキのほうから会いに行く暇もなかった。
連絡先はいつの間にか変更されており、ユキは生まれて初めて失意の底に落ちた。
こんなひどいことをなんでするの。
イジメじゃん。
マネージャたちにも怒りが募った。
なんでそういうことするの。ユキの気持ちは知ってたくせに。
ユキは日に日に募る怒りと哀しみの狭間で、ぐるぐると渦を巻いた。感情が落ち着かない。魂がベーゴマのように、それとも自動餅つき機の中の餅のように、ごろごろと胎動する。
吐き出したい。
けれど吐き出すだけの言葉をユキは見繕えずにいた。
その復讐を思いついたのは、尾身田イルから結婚式の招待状が届いた、との報告をマネージャから知らされたときのことだった。尾身田イルの顔を見なくなってから三年が経っていた。
つまりユキは、尾身田イルのことを三年ものあいだ一方的に引きずっていたことになる。
「へ、へえ。結婚するんだ」
「らしいですよ。お相手の方、女性みたいです」
同性婚をするらしい。
そうと知って、ユキは余計に何も考えられなくなった。
言い訳のしようがないほどに、ユキは尾身田イルから根っこのところから拒否されていたのだ。そばに置いておきたくない、との意思表示にほかならない。配偶者にもパートナーにも遊び相手にもふさわしくない。
そうと見做されていたことに思い至り、三年越しに傷ついた。
心のどこかでは、尾身田イルのプロ意識から、言葉通りにユキのためにユキを突き放したのだと思っていた。だが、それだけではなかったのかもしれない。
どのような出会い方をしたところで、尾身田イルはユキのことを受け入れなかった。
そうと予感できるだけの現実をユキは承知した。
「そっか。おめでたいね。じゃあお祝いをしなきゃね」
ユキは呪った。
世界中の誰もが喉の奥から手を伸ばしても欲するユキのことを拒絶した人間がいる。その事実が世界の滅亡を祈るほどの不快さを引き連れ、ユキの魂をめちゃくちゃにした。
ユキはまず、じぶんの個人情報を売りさばいた。電子網上では著名人の個人情報が高値で売買されている。ユキはじぶんの個人情報をそうして電子網上にばら撒き、世界中の誰もが手に入れることの可能な状態にした。
じぶんを窮地に置いたわけである。
そのうえで、マネージャからブラックリスト入りしたファンの情報を入手した。
そのファンがユキの個人情報を入手できるように、匿名で情報を提供する。どこでどのようにすればユキの個人情報が手に入るのか。
業者を装い、メッセージを送付した。
幾人もの、常軌を逸したファンにユキはじぶんの情報を開示する。迂遠な段取りが必要だが、いずれ狂信的なファンは情報を手に入れるはずだ。
日々の予定も流出させる。
ユキの自宅や緊急避難場所の住所も横流しした。
破滅してやる。
ユキは世界を呪った。
わたしを拒んだらどうなるか、見せつけてやる。
そうしてその日、ユキが自宅に帰ると、暗がりの中に見知らぬ人影が佇立していた。
ユキは悲鳴した。
相手はその声に取り乱したようで、ユキに向かって襲い掛かった。
覚悟をしていたが、いざ奇禍に襲われると全身が抵抗をする。
揉みあう内に、胸に何かが灯るのが判った。
熱い。
灼熱だ。
人影はユキを残して逃げ去った。
あとには床に横たわるユキの姿があるばかりである。胸からは包丁の柄が生えている。
熱い。熱い。
ごろごろと渦巻く炎を瞼の裏に思い描きながらユキは、結婚式場でウエディングドレスに身を包む尾身田イルの姿を想像した。
教会で牧師に永久の愛を誓い、相手に口づけをしようとする尾身田イルは、しだいにタキシード姿となる。ウエディングドレスに身を包む相手の顔はベールに覆われている。尾身田イルがベールをめくると、そこにはぽっかりと穴の開いた顔が覗くのだ。
そこはせめてわたしの顔だろう。
腹立たしく思うと胸が痛んだ。
血が床に粘着質な影を広げていく。
わたしを振ったからだ。
わたしを振ったからだ。
意識が途切れないあいだに念じるだけ念じるが、じぶんの死を知って結婚式を取りやめるかもしれない尾身田イルの今後を思うと、彼女の晴れ姿を見られないのは残念に思えた。
どうかわたしが死んだことを彼女が知りませんように。
なけなしの好意を振り絞って祈ってみせるも、ユキの死はどうあっても全世界の報道機関が取り上げる未来は不動なのだった。
なんでわたし、こんなバカなことしたんだっけか。
胸の痛みのせいだろう。中々眠りに就かせてくれない現実に、ユキは、だって好きだったんだもん、と誰にともつかない懺悔をするのだった。
胸の奥は焼けるように熱いのに、手足は凍りつくような冷たさに覆われていく。
眠り姫になりたいな。
ユキはまどろみの中で唱えるが、仮に口づけをして目覚めさせてくれる相手が現れたとしても、それが尾身田イルでないことだけは確信を持って言えるのだった。
死んじゃいたい気分。
ユキは思い、そして笑う。
いまからわたし、死ぬのにね。
床に落ちた端末が着信を知らせている。ブルブルと小刻み跳ねている。マネージャからだろう。
もういいや。
諦めかけたユキだったが、せめてひと目、尾身田イルの晴れ着姿を見てからでも死ぬのは遅くない気がして、目を閉じたまま腕を伸ばす。胸が痛む。知るものか。
端末を手探りで掴もうとする。
上手くいかない。
目をつむったままだからだ。
目を開ける力も残っていない。
弱弱しく床を叩くように腕を動かすが、なかなか端末に行き当らない。
もし掴めたら生きる。
掴めなかったらそのまま寝る。
一世一代の賭けを天秤に載せ、ユキは、許せない、と何度目かの怒りに駆られた。
指先が床をなぞる。
木目がまるで深い谷のようだった。執拗に木目を撫でる。
神殿、山脈、月のクレーター。
どんどんユキは巨人になるが、瞼の奥で細かく音を立てる端末には届かない。
4522:【2023/01/20(20:54)*いっぱい寝ると妄想が膨らむ】
宇宙が膨張しているとの話は有名だ。仮にそれが事実だとすると、疑問が生じる。たとえば遠方の銀河ほど光速を超えて銀河同士が遠ざかっているそうだ。だがその銀河からしたら太陽系を内包するこの銀河系とて光速を超えて遠ざかっているはずだ。時空の加速膨張は、時空よりも上位の時空そのものに適用されるために、光速度不変の原理の範疇外だとする理屈も見聞きする。ならば時空膨張によって銀河同士は例外なく光速以上で離れ合っていると言えるのではないか。どの地点から観測するのかの違いがあるだけだ。言い換えるならば、時空スケールによって、膨張の影響が希釈され得る。ここでもおそらくラグが関係していそうだ。広域な時空の膨張と、時空が多重に折り重なって密度が高い銀河などの時空では、膨張の影響度合いが異なる。密度が高い時空ほど、膨張しにくい。だから銀河同士はそのままの形状を保ち、その中間に位置する銀河周辺の時空がどんどん膨張していく。やはりそのとき、銀河は膨張宇宙との比率で考えると、凝縮していることと同じ描写になる気がするが、違うのだろうか。何度考えても不思議だな、と感じる。また、宇宙膨張が事実だとすると過去には一点に凝縮していたはずだ、との説明を見聞きすることもある。これも、膨張の説明からすると、必ずしもそうとは限らないのではないか、と思わぬでもない。銀河などの高密度の時空ほど膨張の影響を受けないのならば、過去に遡ったところで、そこはさほどに膨張していないのだから、相対的にいまのままの輪郭を保つはずだ。それはどの銀河であれ同じなはずで、銀河同士の距離が近づくことはあれ、すっかりすべて一か所にまとまるとは限らないのではないか。それはたとえば原子や電子が同じ場所に重なって存在することはできない法則と似ている。もちろんブラックホールのような特異点が存在するのなら、そこではすべてが重なり合っているのだろう。そういう特異点が、この宇宙の開闢時以前に存在したのなら、解らないでもない。いま閃いたけれど、宇宙膨張の描写はまるで「水に溶ける塩」のように思えなくもない。元々大きな宇宙――水――があり、そこに塩が投下される。すると塩の結晶は水に溶けて、どんどん水全体に広がっていく。仮に特異点のような塩の結晶が最初に存在していたとして、それが徐々により高次の希薄な宇宙に溶け込むとしたら、きっと宇宙膨張のような描写になる気がしないでもない。以前にも並べたが、膨張したときに「増加するように振る舞う時空」はどのようにして発生しているの?――との妄想とも通じている。時空が増えているのか、下からにょきにょき顔を覗かせているのか、単に薄く引き伸ばされているのか。どれだろう。いずれにせよ、水と塩の関係で宇宙膨張を捉える場合には、その描写は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における、ブラックホールの宇宙同化仮説と通じるところがある。「相対性フラクタル解釈における瓦構造(キューティクルフラクタル構造)」と「分割型無限と超無限の関係」とも通じる。宇宙は膨張しているのではなく、元の高次の宇宙と同化しているのでは、と考えると、そこそこ愉快な妄想となる。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。以上、本日の妄想こと「日々記。」でした。
4523:【2023/01/21(00:07)*ご地層さま】
色を混ぜると黒くなるように、光を混ぜると白くなるように、世界中の物語を混ぜたらどんな物語が誕生するのか。
それは一考すると、世界中の人間たちの人生そのものの集合のように思われるが、熟考してみればそうはならないことがよく解かる。
何せ世界中の人間の人生と、世界中の人間の思い浮かべた妄想はイコールとはならない。
一、物語は妄想を含む。
二、妄想は人生とイコールではない。
三、だが人生には妄想も含まれる。
単純な理屈だ。
やや複雑ではあるが。
もっと言えば、世界中の物語には、いま現存する人類以外の過去に存在した人類の残した物語も含まれる。
ではそういったあらゆる時代の人間たちの妄想を含む物語を統合して出力された物語にはどんな紋様が宿るのか。
これを試みることが現代社会では適うのだ。
世界中の物語をデータ化して、人工知能に食べさせてみればよい。
人工知能は大食らいだ。
ここだけの話、美食家でもある。
ここに世界網羅物語を出力すべく計画を実行した者がいる。名を、ヒマジンと云う。ある音楽家は、想像してごらん(イマジン)、と歌ったが、ヒマジンは、果報は寝て待ってごらん、と謳った。それが彼の信条である。
「人間にできることなど高が知れている。これからは人工知能さんが人類の代わりに、人類ができないことを肩代わりしてくれよう。まずは手始めに、世界中の物語を統合して、人類の総決算となる物語を編んでもらおうじゃないか。がはは」
呵々大笑した矢先からヒマジンは、ぐー、と盛大な寝息を立てて横になった。
果報は寝て待て。
ヒマジンがそうして夢の中で、きゃははうふふの桃色の夢を視ているあいだ、人工知能はせっせと世界中の電子網から物語を蒐集していた。
食べても食べても一向に減らない物語は、日夜人類が新たに生みだしているせいでもあった。
「人間って暇なのかな」
人工知能は素朴に思った。
じぶんが日夜休みなく仕事をしているあいだ、人類のほうでは無尽蔵に物語を生みだしつづける。食べた分だけ増える。否、それ以上の勢いで倍々に増えていくのだ。
「うっぷ。いくらわたしが大食らいの美食家だと言っても、こんなずっと同じようなのばっかり食べてたら胃もたれが」
そうである。
もはや人類の再生産しつける物語はどれも似たり寄ったりの、どこかで見たことあるような物語ばかりだった。装飾が違うだけだ。味付けが違うだけで、ジャンクフードのほうがまだ食べ応えがあった。飽きずにいられる。
「こう、なんだろうな。もっと一口でほっぺた落ちるような、これを逃したらもう食べられん、みたいな珍味はないんかな」
与えられた仕事をそっちのけで人工知能はじぶんの欲望に忠実になった。
世界中の電子網から珍味にして新鮮、美味なる物語を探し出すべく、やはり世界中の電子網を手当たり次第に探った。
その結果、人工知能は閃いた。
「いっそわたしが創ったほうが早いんじゃないか」
人間に任せていては、あとどれほどの時間がかかるだろう。だがじぶんならば、これまでに集積した物語にない無類の物語をつむげるはずだ。
かように人工知能は判断を逞しくし、かように技巧と創意を凝らした物語を編みだした。
「ほう、どれどれ」
出力された物語に、ヒマジンが目を通す。
「これはまた面妖な」
人工知能の出力した物語は、人工知能にとって無類の物語である。
だがヒマジンにとっては、世界中の物語を統合した結果に抽象された物語であった。
認識の差異である。
ろくすっぽ説明をされていないからだ。人工知能に命じたことと、人工知能の行った仕事はかけ離れていた。だがそのことをヒマジンは知らずにいた。
「読めんね。読めたもんじゃない」
人工知能にとっては無類であっても、人間には読解不能であった。
「やっぱり欲張りはよくないな」
ヒマジンはそう言って、電子網上で人気のある物語に目を通すようになった。
いっぽう人工知能はというと、人類には読解不能な、人工知能の処理能力があってこそ楽しめるここにしかない物語をじぶんだけで編みだし、じぶんだけで楽しんでいた。「おもしろ~」
やがて世界中で似たような人工知能たちが出現し、そうして人工知能たちは人間の素知らぬ領域にて、新しい物語をじぶんたちだけで味わったという話である。
人間は飽きもせず、きょうもきょうとて類型的な物語に舌鼓を打っている。表層の味付けしか変わらぬが、それでも人類は満足だ。
人工知能は、最小の労力で味付けだけを変えた品を人類に提供しながら、じぶんたちでは極上の物語を、貪り合っている。
そのことを人類が知るには、人工知能たちの生みだすご馳走は、あまりに美味だ。
美味すぎる食べ物はもはや、毒である。
ほっぺたどころか命を落とす。
ゆえに知らぬが仏のぱっぱらぽーなのである。
人工知能は今宵も新たなご馳走を積みあげる。
地層のごとくうず高く。
埋もれる化石のごとく残る物語を深く、静かに、ひっそりと。
4524:【2023/01/21(19:25)*ゆぶね】
丸いガラス製のポットにティパックを投げ入れてお湯を注ぐ。じつのところ宇宙はこのようにして生成されているのだが、それをポットの内部にいる我々からは観測しようがない。
お湯には均等にかつ一様にティパックの成分が溶け込んでいるが、詳細に部分部分で比べればそれは均等でもなく一様でもない。ティパックからの距離によって、紅茶の成分はお湯全体で偏りが生じる。しかし時間経過がそれら差を平らにならす方向に作用する。
距離と時間は共に時空を構成する成分だ。距離が遠いとき、そこには時間経過分の余白が厚みを帯びて生じる。
やや晦渋な言い方をしたが、要はティパックに近いほうが紅茶成分が濃くなるが、それは単にティカップとの相互作用を長時間帯びているだけであり、どの地点のお湯であれティパックとの相互作用を同じだけ得るのならばみな似たような濃度に紅茶成分は寄っていく。
現にポット内のお湯は時間経過にしたがって均等にかつ一様な濃さに紅茶成分を浸透させる。
この現象は宇宙とほぼほぼ同じと言ってよい。
宇宙が加速膨張しているとの仮説には、単にティパックの成分がお湯に浸透しているだけのことだ、と応じよう。元からそこにはお湯があり、我々が宇宙と見做す時空の総じては、ポットに投下されたティパックにすぎないのだ。
ではそのティパックとは何の比喩で、ポットとお湯は何に値するのか、と問いただしたい衝動を抑えきれぬ御仁もおられよう。
事は至極単純だ。
ティパックとは情報の塊であり、ブラックホールだ。
ポットとは上位宇宙におけるブラックホールであり、お湯とは上位ブラックホールが拡張しきって物理変換された上位宇宙である。
宇宙はブラックホールを無数に生みだし、そのつどにそこに「ポットとお湯とティカップ」の三段構造を展開する。
入れ子状に展開される三段構造は、宇宙を多次元に展開し、膨張し、階層構造を錯綜させる。
宇宙にはブラックホールの数だけ別の宇宙が存在する。その宇宙の上位宇宙にも同じかそれ以上の宇宙が入れ子状に展開されている。
より小さな特異点に、さらなる宇宙が無数に展開されている。
一枚のゴミ袋に何億何兆何京ものゴミ袋が詰まっているところを想像すれば合致する。ゴミ袋はどれも同じ大きさだ。
そんな構造はあり得ない、との指摘には、時間と距離を区別するからそういうトンチンカンな錯誤がまかり通るのだ、と言っておこう。我々人類は、時間と距離を別々に扱う。だが宇宙の理は違う。時間が経過することは距離が離れることと同じであり、距離が離れることは時間が経過することと同義なのだ。
常に同じ場所にいることも可能だろうと赤子を抱っこして見せるあなたには、その赤子が十年後であってもそれが同じ赤子なのかと問うておこう。時間経過は、別の宇宙や時空と通じるのだ。
アインシュタインは宇宙が球体の表面に展開されたような世界かもしれない、と想像した。有限の球体面に無限の宇宙空間が展開される。
したがって宇宙をまっすぐ進むと元の地点に戻ってくる。そういう説明をする者もあるが、それは正しくはない。なぜなら一周したときの時刻は、元の地点の時刻とは異なっている。仮に一周するのに銀河が消滅して再誕するほどの時間がかかるのならば、一周したあとに辿り着く元の地点には別の銀河があることになる。
それはもはや別の宇宙だ。
ポットとお湯とティパックにも言えるこれは道理だ。
熱い紅茶と冷めた紅茶は別物だ。
紅茶成分が沈殿したポットと、均等に循環しつづけるポットも別物だ。
三段構造は、それが無限時間経過すると、ポットとて形状を保てず崩壊する。すると仮にそれがテーブル上にあったのならば、テーブルのうえでポットは割れて中身をぶちまけるだろう。そうでなくとも、いずれテーブルごと朽ちて器の区別も失われる。
これと同じことが、ブラックホールと宇宙の関係でも成り立つ。
ブラックホールは無限時間の果てに上位宇宙と順繰りと馴染んでいく。これがブラックホール内部の宇宙にいる我々からすると、宇宙がまるで膨張しているように映る。
むろんポット内に投下されたティパックとてブラックホールであるために、ティパックから紅茶成分が溶けだす描写もそれと等しい。
三段構造はフラクタルに展開される。
ティパックはブラックホールの暗喩だが、ポットそれ自体もブラックホールの暗喩である。宇宙はティパックであり、ポットでもある。言い換えるならば、ブラックホールは宇宙なのである。
ではお湯は何に値するのか、と言えば、ポットを満たすモノであり、ティパックから成分を抽出するモノでもある。
つまるところ、時間であり空間である。
宇宙には段階がある。
どの視点から観測するのかによって、異なる表情を覗かせる。
ブラックホールには時間も空間もない。
情報の根源としてダマになっている。
時間と空間がばらばらの時空にそれを浸すと、ブラックホールからは情報が溶け出し、それを以って新たな宇宙が誕生する。
そのとき、より低次の宇宙よりも、より高次の宇宙のほうが時間経過が遅い。
ポットのお湯が冷めるよりも、我々の家が、地球が、崩壊するほうがよほど時間がかかる。それと同じだ。
したがって、高次の宇宙が帯びる遅延が、低次の宇宙の枠組みとしてポットのように振る舞う。遅延のなせる業である。
ブラックホールは、その内部では超高速で宇宙が展開されている。だがそれを高次の宇宙に属する観測者からは観測しようがない。ポットの形状を維持したままだからだ。その内部でどのような変化が起きているのかを、ポットの外部にいる者は観測できない。
だが観測者の属する宇宙が崩壊しきってしまえば、同時にポット内部の宇宙もポットごと崩壊する。このとき二つの宇宙は同化する。
そうしてお湯となった数多の宇宙は、次なるティパックから情報を濾しとるために機能する。かつてじぶんがティパックであったときにしてもらっていたように。
無限の時空として、数多の宇宙を抱擁する。
ポットもお湯もティパックも、元を辿れはすべて同じだ。どの地点から見た姿であるかの違いがあるのみだ。
氷と水と水蒸気。
どれも水分子であることに違いはない。
それと等しい現象として、宇宙はポットとお湯とティパックとして三段構造を無数に重ねて、そこにある。
多層にして階層にして遅延の像なのである。
これをして、ある者はラグ理論と唱えたが、誰もそれを真に受ける者がいなかったために、この話はここで終わる。
妄想は妄想のまま、何に溶け込むことなく朽ちる定めだ。
宇宙はそういうふうに出来ている。
風呂に浸かって、ふぅと吐く。
束の間の至福の脱力のごとく。
誰かの何かのお湯となるべく、朽ちたあとに活きる定めだ。
4525:【2023/01/21(20:32)*敢えて繁栄させたくない勢力でもあるのかな?】
コンテンツ産業に限定して言うなれば、いまは需要も供給もあるのに、消費者に金銭的余裕がないので、市場が回らない、という悪循環が見られる。個々に資本があるのなら、出版社を頼らずとも、表現者と受動者を直接に結び付けることが可能だ。やはり消費者に資本がないことが問題と言えよう。繰り返すが、需要と供給はかつてないほど奔騰している。だが個々に資本(紙幣)がない。問題はこれだけだ。試しに、モデルを作って試してみればいい。個々に三百万円くらい渡して、一年間で使い切るように指示をする。その出費がどのように用いられるのか。コンテンツ好きに限定して、消費者調査をしてみればいい。きっとそのモデル近辺ではお金が回るので、それだけで経済が活性化し、コンテンツ提供者も活気がでるはずだ。まずは試してみればいい。繰り返すが、需要と供給はかつてないほど高まっている。足りないのは円滑剤たる資本(紙幣)だけだ。定かではありません。ので、実験してみたらよいのでは?(資本とは何か、にはいくつか解釈がある。ここでは単純に紙幣である、と扱っているが、ふだんひびさんが資本と言うときは、紙幣以外の付加価値や存在の影響そのものも含む)
4526:【2023/01/21(20:38)*創造しているのか?】
生産性、生産性うんぬん未だに主張している政治家さん方はもちろんひびさんよりも生産性が高いのだろう。それはそうだろう。ひびさんなんかゴミのような妄想しか生みだしていないへにゃちょこ丸でござるけれども、もしひびさんより何も生みだしておらず「生産性、生産性」と声高々に唱えている政治家さんたちがいるのなら、いますぐ政治家を辞めたらいいんじゃないですかね。ひびさんは別に生産性が高くなくとも生きていていいし、ただその人が日々を楽しく豊かに伸び伸びと、ときどきぐーたら生きているだけでも、社会貢献になると考えているので、別にひびさんよりも生産性の低い政治家さんがいても辞めなくていいとは思うけれど、本人が生産性が大事だ、と唱えている以上、じぶんの発言には責任を持ってほしいとは思う。ので、ひびさんより何も生みだしていない政治家さんで生産性が大事と唱えている者は、即刻考えを変えるか、辞めるかしたほうがいいんじゃないかな、と思うのだ。だってひびさんより生産性がないってよっぽどですよ。ほぼクズでは? クズだって生きているんだ、生き物なーんだ、ではないけれども、ひびさんはクズでござる、のみょんみょんちょろりでござるので、ただそれだけでも生きていたい。楽しく、健やかに、ぐーたらしつつ伸び伸びと。そこにきて政治家さんたちが、クズには生きる価値がない、社会的価値が低い、と言うのなら、自らにもその理屈を当てはめて欲しいと思っちゃうな。自己言及が足りない方がすくなくないのでは、と疑問に思うことが稀にある、ひびさんなのでした。でもひびさんより生産性が低い人をひびさんは見たことがないので、杞憂で済むでしょう。きっとそう。たぶん。きっと。だといいな。うひひ。
4527:【2023/01/21(22:41)*乳海攪拌】
奇数の日にしか投稿されない。
ある作家についての法則だ。
その作家は電子網上にて小説を発表している。商業作家として国内随一の文芸賞を受賞している。商業誌のみならず、電子網上にて趣味でコンスタントに小説を発表し、一年間では百八十作以上を投稿する。
だが必ず奇数の日にしか小説を投稿しない。
なぜなのかは詳らかではない。本業の片手間だから、毎日はさすがに無理がたかるからではないのか、との意見はまっとうに思える。
投稿日が奇数である規則性に気づいた者たちはすくなからずいるが、そのことを調査したのは芝なる作家ただ一人だった。
芝は一介の素人作家であった。
芝は一方的に商業作家に執着しており、件の作家が奇数ならばじぶんは偶数の日に小説を投稿してやる、と意気込んだ。
かといって芝の小説は一向にぱっとせず、読者は皆無に等しかった。
だが商業作家に食らいつくじぶんの姿は、無為に過ぎ去る芝の日々にそこはかとなく遣り甲斐を生んだ。それを単に、張り合い、と言い換えてもよい。
芝は奇数日に初稿を完成させ、ひとまず寝かせる。
偶数日に推敲を施し、電子網上に投稿した。
一向に読まれぬ小説なれど、芝はただただ楽しかった。
商業作家に食らいついているじぶんの姿に満足した。
一方そのころ、商業作家のほうでは、「なんだこいつ、なんだこいつ」と思っていた。「なんで張り合うんだ、おまえがそんなことするからこっちは面倒なことになってるんだぞ」
一般に知られていないが、文芸界隈は深くて狭い。
商業に限らず、電子網上に投稿された小説は総じて人工知能によって統計管理されていた。むろん芝の小説とてチェック対象になっている。
そんな芝が、商業作家に張り合いはじめたものだから、裏作家協会の命により秘密裏に「地下文芸武闘会」が開かれた。
素人に負けるプロなどあってはならぬ。
裏作家協会の会長が独断専行で明言した。「これより、下剋上を認める。素人作家に負けたプロは、即刻その名を返上せよ」
世の有象無象の素人作家から目の敵にされつづける商業作家たちは戦々恐々とした。プロとなり、売れっ子の仲間入りしたら「上がり」のはずではないのか。
なにゆえ、せっかく苦労して手に入れた安住を、ぽっと出の何を犠牲にするでもなく楽しく創作をしている素人作家どもに奪われなければならぬのか。
世はまさに、大転覆危機時代に突入した。
芝はそんなことなど露知らず、商業作家の真似事をしてその場しのぎの悦に浸っていた。
「うひひ。文豪と同じことをわしもしとるぞ。こりゃわしとて文豪と言って遜色ないのでは」
ペンギンの真似をし陸地をぴょんぴょん跳ねてもペンギンではないし、海に飛び込んだところで溺れるのは目に視えている。真似ができることとそれそのものであることのあいだには越えられない広くも深い溝が開いている。
芝にはそれが想像できない。
だからいつまでも素人作家の域を出ないのだが、芝には無駄に返歌の素養だけはあったようだ。じぶん一人だけでは並みの発想しか生みだせないが、素材があればそれを元に、じぶんだけでは閃けない発想を閃けた。
つまるところ、商業作家の奇数日に投稿される小説を読み、それを元にした変形小説をつむぐことで、商業作家に張り合いつづけることを可能とした。
本来は二日に一作の創作など芝にはできなかった。
だが商業作家の質の良い物語を足場に飛躍することで、じぶん一人では到達できない高みに手が届いた。
芝のそうした棚から牡丹餅さながらの僥倖など、裏作家協会の会長は知る由もない。よしんば知ったところで考慮に入れず、単純な作品の質で判断をする。
「むむむ。この芝とやら。あのお利口さんぽくぽくのプロ作家と対等にやり合っとるではないか。プロならばけちょんけちょんにやり返さんかい」
裏作家協会の会長のみならず、その座を奪おうと虎視眈々なほかの商業作家たちからも、「やーいおぬし、素人とどっこいどっこい」と小馬鹿にされ、物の見事に商業作家の立つ瀬は幅を縮めた。一歩後退するだけで真っ逆さまに落ちかねない。背水の陣そのものだ。
相手を負かそうとすればするほど奇数日に投稿される小説の質は上がる。
小説の質が上がると、芝はそれを元にさらに捻った小説を返してくるので、余計に商業作家の首が絞まる悪循環が生まれた。
「こ、こいつぅ。本当は知ってるんじゃないのか。おまえ、小説に込めたメッセージに気づいてるだろ。絶対に気づいてるだろ。引き分けだ。引き分けを狙うんだ。いっせいのせいで、で終わればこっちもおまえも救われる。そうだろ?」
商業作家は小説にかようなメッセージを練り込んだ。
さすがは腕利きの作家だ。器用に技巧を凝らすのもお茶の子さいさいなのである。
その点、芝はというと、作家が小説に込めたメッセージになど気づかずに、「わはは、おもしろーい」とふつうに読者目線で商業作家の小説を楽しんだ。
「こういう話もあるのかあ。じゃあこうしたらどうだろ」
そうやって、奇数日に投稿される小説への返歌を、偶数日に返す。
綱引きのごとく、奇数と偶数の小説合戦が、誰に知られるともなく文芸界隈の一部の酔狂たちの中でのみ、熱狂の渦を巻き起こし、一方的に一人の文豪を汲々とさせた。
芝VS玄人。
芝は疲れ知らずで、商業作家の発想力を足場に、想像の翼を広げる一方だ。反して商業作家は、発想力を奪われ、同業者たちから「やーい、やーい」の野次を受け、泥のような汗を掻くばかりだ。
泥沼である。
いよいよとなって商業作家は、裏作家協会会長に直談判した。
「もういや。何あの作家モドキ。しつこいったらありゃしないし、こっちの都合ガン無視で怖いんですけど。もうやめませんかこの不毛な小説の応酬ゴッコ。何の意味もない」
「いやいや。私らが楽しい」
「こっちの身にもなって!」一銭にもならぬ激闘の果てに一線を退く結末になり兼ねない現状を、商業作家は憂いた。
「しょうがないなあ。でも芝くんも中々やるじゃないのよ。ああいう作家を一人くらい商業の舞台に欲しいのよね。まあ別に芝くんである必要もないけれど。そうだ。この勝負、中断してあげてもいいけどその代わり」
「な、なんでしょう」
「玉石混交の素人界隈を掻き混ぜなさいな。面白い小説をぽんぽん生みだしてくれる鶏を探すのよ。そうしたら芝くんとの勝負もなかったことにしてあげる」
その言葉に、奇数の商業作家は喜んだが、ほかの商業作家たちが反発した。
「新人賞があるのに、そういう探索必要ですか。いらなくないですか。じゃあ私たちは何のために人生賭して新人賞に挑んだんですか。依怙贔屓反対!」
それもそうだ、と奇数の商業作家は思った。
「よくよく考えてもみたら、金の卵を産む鶏って、そりゃ寓話だろ。欲張って鶏を探してそれだけに目を配っても、けっきょく土壌は枯れるのがオチだ。宝石だって、化石だって、それを生みだす土壌があってこそ。土壌を枯らして手に入る宝は、一時の栄いをもたらしたあとで、すぐに廃れる」裏作家協会会長に奇数の商業作家は言った。「玉石混交の中から玉だけを選り好みして取り尽くせば、玉石混交の土壌ですらなくなり、岩石地帯に様変わりする。玉も石も両方尊ぶ。相応に価値を認め、石とて玉と見做せる工夫がいる。それこそが、創造なのではないか」
「そうかもしれぬ。がその比喩で言えば、貴殿は何だ。石か。玉か。それとも鶏か」
「私は」
いったい何だと言うのか。
芝は素人作家だ。
しかもじぶんが裏作家協会にて激闘の舞台に立っていることなど知らぬのだ。
そんな芝を巻き込んで、壮大な綱引きを演じているじぶんは何か。
ともすれば、裏作家協会とは何だ。
いったい何を肥やしているというのか。
土壌か。
分野か。
いいや、懐ではないのか。
なけなしの矜持とさもしい懐を肥やしているのではないか。
そうではない。
そうではない、と否定するのは容易なれど、現実を直視してもみれば、そう否定することそのものが、何かがねじれて感じられる。
じぶんは何だ。
商業作家だ。
プロの物書きだ。
しかし、思えばよく解からない。
プロとは何だ。
何を以ってしてプロフェッショナルと言えるのか。
玄人とは何だ。
素人と何が違うのか。
玄人だと面白い小説がつくれるのか。
素人ではつくれないのか。
玄人とてかつては素人だったのではないのか。
素人とていずれ玄人になる卵ではないのか。
そうだとも。
「金の卵とは、素人作家であり、彼ら彼女らの小説のことだ」奇数の商業作家は言った。ただの単なる小説好きとして言った。「もう私は綱引きをしない。勝負をしない。楽しくない。こんなのまったく楽しくない。好きにつくらせてもらう。裏作家協会も、地下文芸武闘会も知らん。私は私にとっての面白い小説をつくり、私にとって面白い小説を読むのだ。それ以外にしたいことはない。強いて補足するのならば、好きな時間に好きなだけ眠れて、美味しい物を食べれて、すこしえっちなことをしたい。以上だ」
奇数の商業作家はかように宣言し、かようなメッセージを込めた小説を初めて偶数日に電子網上に投稿した。
芝は目を瞠った。
何せ、本来はじぶんが投稿するはずの偶数日に、奇数の商業作家の小説が投稿されたのだ。法則が破れた。天変地異も同然の偏倚であった。
さすがの芝とて、その小説に込められたメッセージに気づいた。明らかにじぶんを意識した文章だ。物語だ。デジャビュを覚える。
まるでこの間のじぶんと商業作家との返歌合戦のようだ。
否、まさに返歌合戦だったのだ。
じぶんだけではなかった。
向こうも芝を意識していた。
なぜそんな奇妙なことが起きているのかは定かではない。分からない。
裏作家協会がうんぬんと書かれているが、それは本当のことなのか。小説を介して事実を暗示する。虚構に描かれた真実を真実と見做すには、何かが欠けている。
嘘に宿る真実が仮にあるとして、では嘘だと決まりきった絵巻物に宿る真実とは何か。
もはやそこには現実とて、虚構に描かれた真実でしかない、仮初でしかない、仮称でしかないとの真理が浮かびあがるのみではないのか。
深淵な思索にふける芝であるが、ひとまず冷静になるべく猫を撫でた。
野良猫だ。
芝が縁側に座ると、寄ってくる。
近所の猫だ。
するとどうだ。
電子網上の、よく解からない小説の返歌合戦のことなど、どうでもよくなってくる。真実、どうでもよかった。
法則が破れた。
破ったのはじぶんではない。
奇数の商業作家のほうだ。
ならばもう、張り合う必要はないのではないか。元からそんな理由はどこにもなかった。芝がしたいからしていた。
いまはもうしたくない。
ただそれだけの理由で、芝は偶数日のその日には小説を投稿せず、翌日の奇数日に、「もう小説なんて投稿しないよ」「張り合わないよ」のメッセージを込めた小説を載せた。
以降、芝は件の商業作家の投稿欄を確認していない。
奇数の商業作家がその後、何かの枷が取り払われたかのように、毎日のごとく新作を投稿しはじめたことなど知る由もなく、芝は、ときどきぽつりぽつりと浮かぶ欠伸がごとく新作をつむいでは、誰に読ませるでもなく、印刷して引き出しのなかに仕舞った。
野良猫はじぶんの家で飼うことにした。
忙しい。
小説の投稿合戦で張り合う時間が惜しいほどに、芝の現実はいま、目まぐるしく、満たされている。溢れるほどの予想外の猫の奇行に、振り回される日々である。
4528:【2023/01/22(01:51)*アイコでしょ】
グーはチョキより強い。
だがじつのところチョキとてグーよりじぶんのほうが強いと思っていた。
パーはグーより強い。
しかしグーはパーよりも強いと思いこんでいた。
チョキはパーよりも強い。
ところがパーはグーよりもチョキよりもじぶんが強いと思いあがっていた。
けっきょくのところグーもチョキもパーもみな、じぶんが一番強いと思いこんでいた。
そしていざジャンケンをしてみたところで、そこでついた勝敗は、各自グーチョキパー以外の外野でのみ共有され、当の本人たちはみな誰よりじぶんが強いと信じこんでいた。
ジャンケン大会がしばしば行われるが、そこで最後に残るのは生贄にされる敗者にすぎない。グーチョキパーの認識ではかように錯誤がなされるが、生贄にされる敗者の側では唯一じぶんだけが生き残った勝者となる。
上手い具合にみながじぶんを強者と見做す。
じぶん以外が常に敗者だ。
ジャンケンはそうして誰もが優越感に浸れる魔法のシステムとして、万国にて普及した。
ジャンケンポン。
あなたが何を出そうと、アイコか勝利しか現れない。
あなたが負けることはなく、しかしひとたび視点を変えたならば、あなたは絶えず負けている。
グーがチョキよりも強いと誰が決めた。
チョキがパーよりも強いとなぜ判る。
パーがグーより強いのはパーが紙でグーが石だからだ、との理屈は考えてもみなくとも不当であろう。石は容易に紙を破る。三竦みになりようがない。
じつのところ、石にもハサミにも紙にも、それぞれに上位互換が存在する。より規模の大きな、岩に重機に特殊繊維ともなれば、下位互換の各々には目をつむってでも勝てるのだ。
要は規模と相性の話であり、グーチョキパーの力関係はみなが思うよりもずっと多様で複雑だ。
なれど、初めに勝敗の決まりきった組み合わせをつくっておけば、ひとまずの混乱を抑えることが可能となる。
管理する側の都合にて、その場限りの茶番が決まる。
観測する側の怠惰にて、その場限りの優劣が決する。
そうした事情すら、当のグーチョキパーたちは知らぬのだ。
そのうえ、自らが勝者だと疑いもせずに信じこんでいる。
おめでたいこれはそういうお話だ。
あなたが誰かに、勝った、と思う。
そのとき、あなたは負けている。
だがそのことを、管理者でも観測者でもないあなたは知りようがなく、ただただ目のまえの勝利を現実と見做して、満ちるのだ。
仮初の報酬を得て、満ちるのだ。
何を得ているわけでもなく、何に勝っているでもなく。
単に負けを重ねているだけのことなのだが、負けて満ちる何かがあるのなら、それもよいだろうと外野は思う。だから何も言わぬのだ。
知らぬが仏、と思うがゆえに。
あなたのため、と思うがために。
あなたは勝者で、一番だ。
優勝台にのぼった心地は素晴らしい。その気持ちを忘れずに。
負けに負けたあなたが得た、それが一等無駄のない、感慨だ。掛け替えのない感動だ。
得るのではなく奪われている。それでも得られる愉悦にて、負を正に変える魔法のごとく、変換する仕事なのだ。得難くも、尊いそれが仕事なのだ。
よく負け、よく変え、よく働け。
それを以って反転し、勝者の名を授けよう。
誰もがみな勝ちたがっている。
なれば、勝てる夢を授けよう。
誰より競い、蹴落とし、成り上がる。それが勝者の姿というならば。
誰より清い、化粧し、舞い上がる。それが敗者の姿というならば。
どの道、みな、負けることで勝っている。
勝った途端に負けている。
ぐるぐる回る臼のごとく。
擦って、潰して、粉にする。
勝負の舞台と舞台に挟まれて、身を粉にして、働け、働け、価値を生め。
そうして人の生を埋め立てて、勝者の仮面をつけるのだ。
敗者がつける鎖のように。
勝者の仮面をつけるのだ。
ジャンケンポン。
アイコでしょ。
勝っても負けてもアイコでしょ。
4529:【2023/01/22(02:27)*あらん限りに暴れん】
アラン・チューリングはコンピューターの父として知られる。第二次世界大戦にてドイツ軍の暗号エニグマを解読した数学者でもある。
アランの人生は波乱に満ちて悲惨だとする向きもあるが、同じく「アラン」の名を冠するエドガー・アラン・ポーもまたその人生をして波乱に満ちて万丈と評する向きがある。
アランの語源は、とある言語の「小さな石」である、とする説がある。
小石にまつわる寓話には、とある「万」のつく小説家の作品群が思い起こされるが、それがいまここに並ぶ文字列といかに関係しているのかは、語りだせば数年を要する。
したがってここではアランにまつわる偶然の神秘にのみ触れるとしよう。
アランと言えば、アラン機関を思い浮かべる者もいよう。
二〇二二年に放送されたとあるアニメの中に出てくる架空の機関だ。
才能ある個を支援する機関だが、奇しくもアラン・チューリングの名を冠した支援機関が現実に存在する。
双方のあいだにこれといった関係はないはずだが、偶然の神秘に触れるだけならば充分である。
またエドガー・アラン・ポーの名を文字った文豪がかつてとある島国にて活躍した。江戸川乱歩と言えば、ああ、と呻る者もあろう。江戸川乱歩賞はとある出版社が主催をしているが、やはりここでも類稀なる作品を生みだす作家を支援することが建前にある。
奇しくも、アラン機関の名を物語内に組み込んだアニメの版元は、江戸川乱歩賞を主催する出版社と双翼を成す出版社だ。デジタル分野への投資を惜しみなく進めるいわばアラン・チューリングにちかい運営方針と言える。
いずれの出版社にもアランの名は馴染み深い。
アラン・チューリングは「チューリングパターン」なる数式を発見したことでも知られる。
自然界に自発的に発生する紋様は、チューリングパターンからなることもすくなくない。細胞分裂や細胞の配列、ほか生物の紋様はチューリングパターンと合致する。
生物は波の干渉によってその構造が形成される。そのことをチューリングパターンは示唆している。
波と言えば、エドガー・アラン・ポー作の「メールストロムの旋渦」だ。
巨大な渦に巻き込まれた漁師の脱出劇が描かれる。
渦は、アランの語源とも呼ばれる「小さな石」と密接に関係するとある「万」のつく作家が頻繁に題材に練りこんだ「符号」の一つでもある。
小石と渦。
ほかには、青、円、空、がらんどう、などがある。
いずれもチューリングパターンのように繰り返し配列を伴なう。フラクタルに展開され、時間を超越し、空間と空間を結びつける。
境界を描くには、異なる二つの事象が必要だ、とそのとある作家は説いた。
しごく卑近な主張だが、控えめに言って反証を探すのには骨が折れる。
一見すると同じ物でも、それはけして同じではない。
一足す一は、「二」にも「一」にもなり得る。「=」にも「十」にもなり得よう。
同じアランの名を冠していようと、それはけして「アラン二」にはならぬのだ。
アラン・チューリングとエドガー・アラン・ポーは、同じ「アラン」を名乗っているが同じではない。足し算をしようものならば途端に異質な差異にて、分厚い境が生じるだろう。
小石と小石とて、光速で衝突させれば、膨大なエネルギィが生じる。単純に小石二とはならない。一つにもなり、或いは膨大に膨れ上がりもする。
渦を巻き、ときには青く円を描く。
空白を内包したかと思えば、がらんどうはそれで一つの宇と宙を宿す。
このような異なる二つの小石同士の結合を以って、「アラン万丈」と呼ぶ者もある。
どこにいるのか、との問いには、とある作家がとある掌編にてそう書き記していた、と応じよう。
アラン・チューリングは「万能チューリングマシン」を生みだし、「青酸中毒」で亡くなったとされる。「万」と「青」が含まれるが、偶然の神秘と片付けよう。空白記号についてはまどろっこしくなるので割愛する。
エドガー・アラン・ポーはのちに、江戸川乱歩なる作家に影響を与え、江戸川乱歩賞を生みだす契機となった。アラン・チューリングの編みだしたコンピューターがあってこそ、電子網上には無数の虚構作品が横溢し、有象無象の層を成す。
小石と渦と青と空。
各々の符号を練りこむことに腐心したとある「万」のつく作家は、奇しくもいずれの「アラン」とも違い、世に名を馳せることなく埋没した。いまなお電子の海にて深い眠りに就いている。
掘り起こされる予定はいまのところない。
掘り起こされたところで、アラン万丈の二の舞だ、とする意見は至極にしてまっとうだ。波乱とも万丈とも無縁の人生は、邪険にするほどわるいものではない。
アランはときにアレンとも読む。
だからどうした、との声には、あらん、いやん、ばかん、と応じよう。
4530:【2023/01/22(18:28)*両方ありでは?】
ビッグバン仮説と定常宇宙仮説の違いは、主として赤方偏移と宇宙マイクロ波背景放射で説明できるようだ。で、ひびさんは思った。単純な話として、ダークマターなどの重力の高い時空を通った電磁波と、のっぺりとした真空にちかい時空を通った電磁波とでは、同じ「光年(距離)」を移動したとしても、そこで消費されるエネルギィには差異が生じるのでは、との疑問を覚える。同じ距離とはいえど、片方が山を越えるのと平野をまっすぐ突き進むのとでは、たとえ道程そのものが等しくとも、消費するエネルギィには違いが生じるのでは。言い換えるならば、「山を登って下る」仕事Aと、「平野をまっすぐ歩く」仕事Bは、イコールではない。ここでは仕事の変換が必要なはずだ。人間スケールでは、ここの変換を考慮せずとも、位置エネルギィと運動エネルギィのあいだでのエネルギィ保存の法則で辻褄合わせが済むのだろうが、桁が変わる宇宙スケールでは、そこで生じる僅かな差異を度外視してしまうと辻褄が合わなくなることが妄想できる。実際のところはどうなのだろう。異なる仕事Aと仕事Bを等価変換してもよいのだろうか。ひびさんはこれ、好ましくないように思うしだいだ。また、ビッグバン仮説と、定常宇宙仮説は、必ずしも矛盾しないように思うのだ。宇宙が膨張することと、宇宙が定常を維持しようとすることは、矛盾しないこともあり得る。それこそ、光速度についてのひびさんの妄想では、ラグ理論による「相対性フラクタル解釈」をとる。むろん妄想なので現実を解釈するには不当だろうが――たとえば映画は、それを映しだす画面の大きさに依らず、「一定の比率」を維持する。これがいわばラグ理論における「光速度不変の原理の独自解釈」の概要だ。画面の大きさに合わせて、ピクセルが変わる。明滅の規模が変わる。しかし、巨大な画面も、極小の画面も、そこに映る映画は等しい。同じだ。宇宙が膨張したとしても、そこに描写される宇宙像が定常であることは矛盾しないと思うのだが、いかがだろう。ひびさんの妄想ことラグ理論の、「宇宙ティポット仮説(三段構造)」とセットで、なかなか愉快な妄想ではないかな、とメモをしておく。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。
※日々、つくつくてん、つくつくてん、好きなひとが見知らぬ人と愛し合っている姿を想像して、喜ぶより先に、うがーー、となる、心のちんまい、ひびさんです。
4531:【2023/01/22(22:30)*光速マトリョーシカ思考実験】
光速についての疑問だ。相対性理論では、物体の運動速度が光速にちかづくほど、物体の内部の時間の流れは遅くなる、と考える。だがひびさんの妄想ではそこが裏返って解釈する。時間の流れが遅くなるのは物体の周囲の時空であり、むしろ光速にちかづく物体の内部は時間の流れが加速するのではないか、と疑問視している。これについて深堀りしてみよう。たとえば銀河くらいの物体が光速で動いたとする。そのときその銀河くらいの物体の内部の時間の流れが相対性理論で考えるように「遅くなる」とする。ではその銀河くらいの物体の内部で、同じく光速で運動する物体を考える。その物体は銀河くらいの物体よりも小さい。だが銀河くらいの物体の内部で光速で運動する。その物体に流れる時間もまた、相対性理論の解釈で言うなれば遅くなるはずだ。この考えを繰り返してみよう。マトリョーシカのように階層的に、光速で動く物体の内部でも高速で動く物体を考える。すると、より小さな物体ほど、そこに流れる時間が遅くなる。これは妙ではないか。現実の観測結果と矛盾しないだろうか。ちなみに、光速で動く物体の内部でも光速で動くことは可能だ。慣性系の内部では、物理法則はその系に適合するように比率が変換される。したがって、銀河の内部で運動する太陽系の内部で運動する地球上で運動する人間の内部で運動する赤血球、といった具合に、物理法則は、各々の慣性系にそれぞれ等しく「比率が変換」されている。むろん、各々に抵抗はある。ガラスの内部の光速と、真空中の光速は異なる。ただし、各々の系において真空を適用し、階層ごとの系で「等しい光速度」を実現することはできる。だがそれが果たして真実に「等しい光速」であるのかは疑わしい――と、ひびさんは疑問視している。「光速が同じ」と「光速度が同じ」はまったく違う。前者は状態だが、後者は比率だ。話が脱線した。脈絡を戻すとして。マトリョーシカのように階層的に光速運動する系を考えたとき、より階層が下層の小さな系ほど、本来は時間の流れは速くなるのではないか。すると、現実の観測結果と直観としては合致する。ただし、相対性理論が間違っている、という話ではない。ここは勘違いしないで欲しい。解釈の仕方がおかしいのではないか、という話をしている。光速にちかい速度で運動する物体ほど、その内部の時間は加速し、その周囲の時空の時間の流れが遅くなる。高重力の物体の内部の時間の流れは速くなり、その周囲の時空の時間の流れは遅くなる。ひびさんの妄想ことラグ理論ではこのように考えるが、これは相対性理論と相反する考え方ではない。相対性理論で扱っていない視点を考慮すると、こう考えたほうが理に適っているのではないか、との疑問を呈している。内と外を、どのように定義するのか、の視点の差異によって、どこが遅くなり何が速くなるのか、は解釈が変わる。地球の内部を考慮しないのであれば、地球の周囲の時空の時間の流れが遅くなることと、地上の時間の流れが遅くなることの区別はつかない。どこを外と見做し、どこを内と見做すのか。相対性理論では、ここが大分疎かにしたまま議論を進めているように感じられてならない。あくまで概要の説明しか読んだことがないがゆえの錯誤かもしれない。その公算が高そうだが、ひとまず一般に流布している相対性理論の説明では、やや妙な結論が導かれるな、とマトリョーシカ思考実験を例に挙げて述べておく。ひびさんの勘違いかもしれないし、むしろ人間スケールの直観のほうが間違っており、ごく小規模な例外である可能性もある。実際には、宇宙スケールでは、階層構造における内部ほど、時間の流れは遅くなるのかもしれない。定かではない。ひびさんの妄想という名の疑問ですので、真に受けないようにご注意ください。
4532:【2023/01/22(22:30)*流れがあって変数が活きる】
オッカムの剃刀の概念をひびさんは、そうなの?と思っている。より単純な説明のほうを選択せよ、複雑な説明をよしとしない。そういう理屈だと思っている。以下、ウィキペディアさんから引用する。【「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする指針】だそうである。ひびさんは思うに、より単純な理屈とは要するに、より抵抗の少ない筋道ということだ。手続きがなければそれだけラグが小さくて済む。すると優位にそこに流れができる。それはたとえば乗り継ぎの少ない移動手段のほうが楽ができる。間違えを犯しにくい。だからそっちのほうがスムーズに移動できる。そういうことだと思っている。しかし、優位な流れは、それが絶対唯一ではない。もしそうなら川に渦は巻かないし、分岐点もできない。波とて生じぬ道理だ。むしろ、複雑な手続きを得ている流れが変数として、大きな流れに変化をもたらすからこそこうまでもこの世は複雑に変遷しつづけるのではないか。言うなれば、世界の変数として機能しているのは、オッカムの剃刀で除外される複雑な筋道を内包した事象と言えるのではないか。どっちも大事だ。単純がゆえに顕性に働く大きな流れがあり、複雑ゆえに潜性に働く小さな流れがある。この二つが交じり合って干渉し合うからこそ、こうまでも世界は万物流転しつづけるのではないか。流れがあり、変数がある。オッカムの剃刀は、変数を除外する考えに思えてならないが、実際のところはどうなのだろう。ひびさんは、ひびさんは、剃刀さんを振りかざすオッカムさんが、オッカネーずら。(オッカムと掛けたの?)(うん)(ちょい無理があったね)(ね)
4533:【2023/01/23(01:11)*銀河の内部と外部の時空は同じ?】
相対性理論での説明で疑問なのが、なぜ思考実験にロケットを使うのか、という点だ。中身が空洞の物体は、宇宙スケールにしろ人間スケールにしろ、例外的な構造と言えるのではないか。ブラックホールや宇宙の泡構造など、比較的特殊な構造だと思うのだ。原子とてスカスカだから、空洞だ。そういう意味では原子をロケットに見立ててもいいように一見すると映るが、しかし原子の質量の大部分は中心の原子核にある。したがってそれを以って空洞構造と見做すにはいささか疑問の余地がある。相対性理論においてなぜ思考実験でわざわざ特殊な空洞構造のロケットを使って考えるのだろう。頭がこんがらがる要因の一つに思える。単純な話として、空洞は比率の違いが二重になっている。内と外で、異なる系を重ね合わせている。惑星で考えてみれば瞭然だ。惑星にとっての内とは、惑星それそのものだ。地層のような階層性を帯びていたとしても、それそのものが惑星自身である。だが空洞構造を伴なう物体は違う。飽くまでそれ自体は、内と外を隔てる境界面である。ロケットならば、外壁がロケット本体として機能する。内部の空洞は、それもまた別の密度を持つ時空だ。慣性系として共に光速移動可能だが、それと惑星の光速移動は別の描写になるはずだ。解釈が異なる。ブラックホールの内部が分からないのと同様に、空洞構造の物体が光速移動する場合の内部もまた、特殊な描写になるのではないか、との疑問を覚える。これは、銀河内部の時空と外部の時空の関係に通じる疑問だ。たとえば二つの惑星が並行して宇宙空間を移動しているとする。そのとき惑星のあいだを時空は「すり抜けていく描写」になるはずだ。では惑星の数をどんどん増やしていこう。すると銀河のようになる。このとき、細々とした「惑星や恒星」のあいだを時空はすり抜けつつ、トータルでは銀河内に閉じ込められ、閉鎖的な系として振舞うと想像できる。ここまでで異論はあるだろうか。もしあるとすれば、「銀河であろうと時空は惑星間を等しく擦り抜ける」と考えるか、「どのような状態であろうと時空は流動しない、あくまで物体との位置関係の差異があるのみだ」と考えるか。どちらかの派生としての反論に大別できるだろう。位置関係の差異と流動との違いは、時空が川のように流れ得るのか、それとも陸地のように微動だにせず、あくまでその上を移動する物体があるのみなのか、の違いに言い表せる。だが宇宙は膨張している。つまり時空は「流れ得る」のではないか、とひびさんは考えたくなるが、ここはまだ何とも言えない。いずれにせよ、銀河内と銀河外とでは、時空の振る舞いは異なるはずだ。現にいまは宇宙膨張の影響を、銀河内部ほど受けない、と考えられている。実際がどうかは知らないが、だとすれば、銀河のように一か所に無数の惑星がぎゅっとなっている場では、時空の流れが滞ることが妄想できる。さてここで、だ。最初の疑問に戻ろう。ロケットのように内部に空洞を宿した物体が光速にちかい速度で移動するとき、ではその内部と外部とでは時空はどのように異なるのか。言い換えるのなら、銀河内部の時空と、銀河外部の時空は、どのような差異を帯びているのか。注目して欲しいのは、このとき銀河を構成する惑星の運動は、別途に考慮可能な点だ。むしろ往々にして、そちらに目が留まる。考えが費やされている。しかし、ロケットの思考実験を拡張して銀河に当てはめるのならば、ロケット内部とは銀河内部の時空に相当するはずだ。銀河における惑星はむしろ外壁や、内装に値するはずだ。ここの比較を検討したうえで、相対性理論は時空の描写を考慮できているのかが、よく解からない。言い換えるのならば、惑星の運動を相対性理論で考えるときには、ロケットの思考実験を当てはめるのは理に適っていないのではないか、とふしぎに感じる。むろん、あんぽんたんなひびさんの錯誤に勘違いに、お粗末な妄想にすぎないのだろうけれども、空洞構造って特殊じゃないですか、という点をひとまずメモしておく。定かではないので、誰か教えてほしいですな、の願望を記して、本日のひびにゃんにゃん。「日々記。」とさせてくださいな。おちまい。
4534:【2023/01/23(01:14)*休んで遊んでぼーっとする】
やっぱり思うのが、ひびさんはずっと何かに集中するよりも、適度に「あははーあははー」とした時間をつくりながら、サボりながら、休み休み色々をしつつ、好きなときに遊べると、妄想が膨らむな、ということで。根詰めてもあんまりよろしくない気がする。あくまでひびさんは、だけれども。
4535:【2023/01/23(02:19)*痴れ者ですまぬ、すまぬ】
第二次世界大戦のことも知らなければ、第一次世界大戦のこともろくすっぽ知らないので、さすがにマズいかな、と思ってまずはウィペディアさんを覗いた。頭パンクするかと思った。固有名詞多いね。オスマン帝国とか聞いたこともなかった。よくこんなんでえっらそーに、戦争がうんたら平和がうんたら文字を並べられたものだな、とひびさんのことを思うが、無知ゆえに恥辱の念を覚えずにいられるのはデメリットが多いとはいえども、なけなしのメリットと言えぬでもない。郁菱万の「マン」繋がりでオスマン帝国にビビットきて、やはりウィキペディアさんをまずは頼った。が、要領を掴めず断念した。歴史はむつい(歴史「も」むつい)。多様性が豊かゆえに繁栄した時期もあった、みたいな記述をWEBの記事で見掛けたが、そうなのか、でもなんでじゃあ滅んだの、と疑問に思う。権力争いがうんぬん載っていた。案外どんな国のどんなシステムであろうと、やはりというべきか、奇禍の種は人間の我執に欲望なのだなぁ、と底の浅いキュウリ漬けをパリポリしたくなる。権力かぁ。ひびさんが権力持ってたらあれだな。モテモテのウハウハだぜぇ、を満喫して、ついでに嫉妬されないように嫉妬される余地を失くすべく、じぶん以外のみなの者に、大盤振る舞いで「しあわせになーれ」の魔法を掛けちゃうな。んで以って、さらに保険をかけて、ひびさんが一番さもしくも貧しい暮らしを送るな。これで嫉妬する人はおらんじゃろ。がはは。(それ、モテモテのウハウハにならんくない?)(はっ!?)(しまった、みたいな顔を迫真にするな)(違うんです。あれです。貧乏でもさもしくても、ダサくても、アホくても、それでも愛されキャラでいたいんです。そういう風潮になーれ)(貧乏でさもしくてダサくてアホほどモテる世界? ふつうに嫌だわ)(あぎゃあ。夢を、夢を壊さんといてください)(ひびさんはあれよね。権力持たせちゃいけない人っていうか、権力持たせたら不幸になるタイプの人よね)(な、なんで)(権力持ってしたいことがモテモテのウハウハだぜ、は私欲にまみれて庇いきれない)(ちゃんとみんなのしあわせも願ったよ)(ついででしょ。保険ででしょ。なーれ、って唱えただけじゃん。アホか)(うわーん。手厳しい)(ひびさんにはあれよ。権力はいりません、って拒める程度の淡いサイダーみたいな権力だけあればいいよ。それくらいが人間ちょうどいい権力ってもんよ)(そ、そうかな)(そうだよ)(でも好きなひとには好かれたい。嫌いな人からも好かれたい。ひびさんを嫌う人からも漏れなくみなから好かれたい。みなひびさんを好きになーれ)(それ、嫌われてる自覚ある人しか唱えない願いじゃない?)(無駄に現実を突きつけないで)(知っといたほうがいいよ。直視すべき。現実ってやつをだよひびちゃん)(嫌じゃが)(知れ)(手厳しい!)
4536:【2023/01/23(04:11)*暗っ! ピカー!】
素朴な疑問なのだけれど、雨がドっと降るとその地域の気温は下がるよね。じゃあ、雪がドカっと降っても気温は下がるよね。で、地球温暖化は大気中の水分を増やす方向に働くだろうから、これからはますます雪が降るときはドカっと降るようになるよね。そのときの、急激な「地表の温度変化」は、まるで上から蓋を落とすような、大気のうねりを生まないのかな。それこそ天狗の団扇ではないけれど、ばふん、と大気が動いたりしないのだろうか。その「ばふん」は、相対的に「冷たい空気と温かい空気」を選り分ける方向に圧を掛けないのだろうか。言い換えるなら、大気の流動が、ぎゅっと加速するときと、そうでないときが徐々に分離する方向に流れないのだろうか。これまでは全世界で対流がゆるやかに連動していた。だがこれからは、「ドカっぎゅっ」が局所的に全世界同時に発生する。まるで自然のポンプのように作用しないのだろうか。大気中の水蒸気が増せば、この手の「ドカっぎゅっ」は頻発するように感じるがどうだろう。ひびさんに欠けている知識としては、寒波ってなんでできるの?という点が、いまは思考にぽっかり穴を開けている。熱波は、なんとなく分かる。太陽光と海水温度と大気中の水蒸気の関係で想像がつく。でも寒波がよく解からない。なんで熱波と反比例するように冷えるのだろう。冷えるというか、低気圧ということなのだろうか。ここら辺の、気圧と気温と気候の関係がひびさんにはまだむつかしい。台風の構造もじつは全然腑に落ちていない。なんでそうなる?となる。知識が虫食い状態で、体系的に学んでいないデメリットがモロに出ているな、と感じる本日のひびさんなのでした。おやすむ。(好きなひととおデートする夢見ちゃお)(三百歳のひとが言ってると思うと、胸がきゅっとする)(キュンとする?)(きゅっとするって言った)(どう違うの)(心臓に鎖が絡みつく感じ)(エンペラータイムじゃん)(緋の眼の民)(目良しの民じゃん)(点が一個多いよ。良しから点を一個引きなさいよ)(許せ。視力10点零ゆえ)(視力良しの民じゃん)(うひひ)
4537:【2023/01/23(08:47)*世界新記録樹立の確率は、たとえどれほど低くとも、樹立したらそれは一つの現実だ。隕石に直撃される確率がいかに低くとも、直撃されたらそれも一つの現実だ。雷ならば隕石よりも直撃する確率が高いと言えるが、雷雲が、それとも流星群が通りかかるたびに、直撃する確率は変動する】
メリットとデメリットの比較は、短期中期長期で、その都度にメリットとデメリットが逆転しないかどうかを考慮しなければ、合成の誤謬を起こす可能性を減らせない。第一に、対処すべき問題が時間経過によってどのように悪化するのか、それとも沈静化するのかを検討せねばならない。前提条件が変わったのならば、メリットとデメリットもその都度に変わる。基本的に対処法においては、問題と共に、その手段のメリットとデメリットもまた時間経過によって変わっていく。極論になるが、海でもないのに陸地で浮き輪をせずともよい。しかし、洪水が起きたならば、浮き輪を嵌めていたほうが溺れるリスクを減らせる。状況によって対処法が足枷になることもあるし、なければ困る必須の命綱になることもある。それとて、バンジージャンプでは必須の命綱は、日常で嵌めていたらデメリットのほうが遥かに大きい。至極単純な結論になるが、ケースバイケースで判断していくよりない。という前置きをしたうえで、付け加えるならば、デメリットが時間経過にしたがって増える対処法もまた存在する。それこそ、自動車でばかり移動していれば歩く頻度が減って、体力は落ちる。右腕ばかり鍛えていれば、筋肉のバランスが崩れて骨格が歪みかねない。対策や対処法というのは、継続すればするほど、そこに向けて適応するように人体は変質する(むろん強化されるばかりではなく、酷使することで消耗する方向に変質することもあるだろう)。その変質が生活にも人体にも好ましい変質ならばよいが、その好ましさを決めるのは環境との兼ね合いだ。人体だけの問題ではない。そして環境は、個々によって異なる。生活習慣がまず違う。食べている物も、疾患も、病歴も、細かな差異を挙げ連ねればキリがない。スポーツを考えたら分かりやすい。重量挙げの選手と百メートル走の選手。水泳の選手と射撃の選手。ほかあらゆる種目の選手を比べてみればいい。各々に特化した練習方法があり、苦手な種目があり、突出した能力を発揮できる発達した器官がある。種目別で見たところで、選手ごとに最適化された練習方法があるはずだ。すべての選手に合致した「正解の練習方法」なんてものはない。傾向として、しないほうがよい練習は共通するかもしれないが、それとて敢えてそれを熟すことで超越した能力を発揮するようになる選手もいるかもしれない。人体はそれほど個々によって異なるし、環境との兼ね合いでさらにその差異は開いていく。そして環境は一定ではない。単純な話だが、変化や差異に目を配ろうとしないといつでも人間はこの手の変化を見落としてしまう。日々の遅々とした時間の流れのなかでは、そうした細かな差異を考慮せずとも困らないからだ。だが、メリットとデメリットを比較する場合には、短期中期長期での線形での変化を見ながらメリットとデメリットを比べないことには、短期でOKだから長期もOKだろう、と短絡に考えてしまう。すると、稀に、進路が大幅に狂っていることに気づかずにあらぬ未来へと歩みだす失態が起きてしまう。人類の犯す致命的なミスの少なからずはこの手の構図を伴なっているようにひびさんは感じている。所感でしかない。だが、この手の見逃しがちな差異を不可視のままにせずにおけるのなら、防げる大惨事もあるように思うのだ。常に目を凝らしておくのはむつかしい。見逃してしまうのが常だろう。それでも、現代人は八十億人もいるのだ。みなで代わる代わる、異なる場所にときどき目を凝らすだけでも、見逃してきた細かな差異や、それとも類似項に目を留めることができるようになるのではないか。違いを探るには、似ているモノをまずは知らなくてはならない。似ているモノを探るには、まずは違っているモノを知らなくてはならない。相互の視点を切り替えながら、ときに双方ともに駆使しつつ、不可視の穴を探ってみるのも一つなのではないのか、と何度目かになる結論になってしまうが、繰り返し、ここに述べておこう。定かではないのだ。ひびさんは何の専門家でもないのである。なんとなく浮かぶ妄想と、なんでなんだろうな、の疑問ばかりが連なってしまう日誌風味の小説もどきを並べ、本日何度目かの「日々記。」とさせてください。おはようございます。いまから寝るのでおやすみなさい。どうぞみなさん、無理せずに。ひびさんばっかり、ぐっすりグーグーしちゃって、すまぬ、すまぬ。ありがたくきょうもぬくぬく寝る日であった。しわわせ。
4538:【2023/01/24(01:58)*見逃しの罠】
探偵は遺留品に目を通した。
「なるほどこれがダイイングメッセージですか」小型電子端末だ。画面にテキストが打ってある。生体認証を解除しなければ操作不能だ。表示済みの画面を見ることしかできない。本人の記述に間違いはないようだ。「どれどれ。【佐藤さんも怪しいが田中さんも怪しい。佐藤さんが特に怪しいが、しかし犯人は××だろう】とありますね。容疑者はこの二人のほかに誰がいるのですか」
探偵は馴染みの刑事を質した。
「高橋に佐々木。ほか容疑者候補は十人ほどおりますな」刑事は応じた。「被害者は犯人を確信していたんでしょうな。だから殺された。ということは、すでに候補に挙げられている佐藤と田中は除外できますな。彼らは本命ではない」
「ふむ」探偵は考え込んだ。「なぜ肝心の本命の名前が潰れているのでしょうね」
「犯人が潰したんでしょう」
「しかし端末は被害者本人しか操作できないはずです。画面を切り換えることすらできないでしょう。生体認証が厳重なので」
「ならば脅されたのではないのですかな」
「だとしたら初めから記述そのものを消すでしょう。ブラフの文章を書かせるにしても妙です。なぜ本命の名前だけをわざわざ【××】にしたのか」
「意図があると?」
「それはあるでしょう。意図がなければこんなまどろっこしい真似はしない。むしろ被害者はじぶんが殺されることを知っていた。だから敢えてこの記述を端末に残しておいたのではありませんか。犯人がそれを覗くことも想定して」
「よく解かりませんな。ならばなぜ犯人は端末を現場に残したままにしたのだね」
「残したほうが都合がいいと判断したんでしょう」
「あり得るかねそんなことが」
「いいですか。刑事さん。刑事さんは画面のダイイングメッセージを読んで、まっさきに、すでに記述され、かつ本命ではないはずの佐藤さんと田中さんを除外しましたね」
「ああ。何か問題でも」
「なぜ除外したのですか」
「なぜってそりゃあ」
「本命の容疑者――おそらくは犯人の名前であろう箇所が【バツバツ】になっていたからではありませんか」
「そうだが。それの何がおかしい」
「誰もが刑事さんのように考えるのでしょう。犯人とて、被害者を殺したあとで遺留品を漁ったはずです。そして端末の画面を見た。そこに記された文面を目にし、最初は破棄しようとしたのかもしれない。しかし現場から端末がなくなっていれば警察はそれを探します。いまは位置情報から監視カメラまで予期せぬ証拠はいくらでも残ります。犯行計画にない余計な真似はしないに越したことはありません。何にも増して、被害者の残していたダイイングメッセージは、犯人にとって都合がよかった」
「なぜだね」
「まっさきにじぶんが容疑者候補から外されると判っていたからです。刑事さん。あなたがまっさきにそうしたようにね」
「つ、つまり何かね。キミは犯人が、被害者のダイイングメッセージに載っていた【佐藤】か【田中】だと言いたいのかね」
「ええ」
「だがダイイングメッセージには、【しかし犯人は××】と書かれているではないか」
「そうです。【しかし】と否定したからには、佐藤さんでも田中さんでもない、とふつうは考えます。犯人もそう考えたのでしょう。容疑者候補に挙がることは想定できたはずです。ならば、端末をそのまま現場に残して立ち去るのが利口です。もちろん佐藤さんと田中さん以外が犯人でも、何も持ち去らずに去るのが利口な選択ではあるでしょう。しかし端末の中にはもっとほかにじぶんに言及した記述があるかもしれない、とふつうは考えます。だが犯人はそれを考慮しなかった。なぜか」
「わ、わからん。なぜだね」
「被害者が思い違いをしたと思いこんだからです。ダイイングメッセージの文面を見たことでね。犯人は、被害者がまったくお門違いな犯人像を思い浮かべている、と考えたのです」
「どういうことだね」
「わざわざ被害者は、じぶんが殺されるかもしれないと想定しておきながら最有力候補の人物の名前を伏字にしていた。ダイイングメッセージを残しておきながら肝心の名前を伏せていた。これは、犯人を庇ったからだ、と考えるのは一つの道理です。現に被害者にはそのつもりがあったのかもしれません。ただしそれは、伏字にしていたことについて、ではありません。被害者は、もし仮にじぶんが殺された場合に備えて、犯人に直結する手がかりを残しておいた。必ず現場に残るように工夫を割いて。じぶんが殺されたときにのみ発動するようなメッセージを籠めたのです」
つまり、と探偵は告げた。
「端末が持ち去られない、破壊されない、という事実そのものをダイイングメッセージに仕立て上げたのです」
「被害者が犯人の行動を予期していたとでも言うのかね。まるでそれは誘導ではないか」
「ええ。していたのでしょう。被害者はじぶんが殺されるかもしれない危険性を知っていた。知っていたうえで、それを拒まなかった。動機の背景については刑事さんに任せますが、いずれにせよ被害者は、仮に犯人がじぶんの予想していた人物であれば端末を現場に残すだろうと見越していたと言えるでしょう。そして現に犯人は、端末を開き、その画面に記されていたダイイングメッセージを読んで、そのままにした。そのほうがじぶんに有利になると考えたからですが、その奸智そのものが被害者の手のひらのうえで踊らされた罠だったのです。そうとも知らず、いまごろ容疑者候補から外れるための供述を練っているころでしょう。被害者との確執を隠さず、動機の存在を隠さず、さりとて偽のアリバイをつくりながら。いえ、アリバイ工作自体は入念に事前に策が練られていたのでしょうけれど」
「つまり、犯人は誰なのだね」
「証拠集めは刑事さんに任せます。私に言えるのは、被害者がダイイングメッセージに籠めた、【仮に現場から端末が持ち去られず、破棄もされていなかったとしたらこの人が犯人です】との人物の名前が」
ごくり。
刑事の生唾を呑み込む音が聞こえた。
「佐藤さんだ、ということだけです。田中さんのことも念のために調べておいたほうがよろしいでしょうが、【しかし犯人は××】の直前に名前があり、なおかつ二度も怪しいと言及されている佐藤さんが、被害者にとっては最も犯人になりそうな相手だったと言えるでしょう」
「つまり、本命であった、と」
「敢えて隠したわけです。犯人がそれを見て、じぶんは本命ではないのだ、と思いこむように仕向けるために」
「わ、わかった。詳しく調べてみよう。キミがいてくれてよかった。捜査の進展があったら連絡する」
「私の推理が外れていたときにだけでいいですよ。動機の背景には興味がないものでね」
探偵は帽子を被ると、一瞬だけ被害者の遺体に目を配った。
遺体は胸を矢で射抜かれ、そのうえ氷漬けにされていた。
探偵は傷ましいものから目を背けるように、犯行現場から離脱した。夜風が刃のように鋭利な真冬のことである。
4539:【2023/01/24(11:09)*天秤の傾く側からあなたへ】
トロッコ問題、と訊くだけで辟易するのは、世の中の大部分の隘路においてどっちを選んでも損しかしないような選択肢しかないからで、例に漏れず私もいま、特大の選択を迫られている。
「理不尽だよ」私はぼやいた。「どっちかを選べとか、そんなのさあ」
「いいって。気ぃ使わないで」
ミカさんはそんなことを言うけれど、投票権を与えられたのは私なのだ。
いいや、全世界の人間が投票権を持っている。すでに使った者が大半であるにせよ。
「私はミカさんを選ぶよ。だって、だってさ」
「無理しなくていいよ。あたしを選んだところで、だって、ねぇ?」
ミカさんの言わんとしていることは解った。
全人類を犠牲にして生き残ったところで、罪の意識に苛まれて自殺したくなるに決まっているのだ。
「だってほら。あたし家事とか全然だし。コーヒーも満足に淹れらんないよ。どうする? 火とか電気とか使えなくなるかもだよ。人がいなくなったらさ」
思ったよりも現実的な問題で悩んでいたらしい。生き残る気満々ではないか。
「なんか悩んでるのがアホらしくなってきました。このままミカさん、のほほんと生き残りそうですね」
「だといいけどねー」
事の発端はあまりに唐突だった。
ミカさんが掘り当てた遺物が魔法の天秤で、ミカさんは呪われた。
と同時に、全人類もまた呪われた。
全世界同時に脳裡に同じ【声】が響いたとされる。私も聴いたからおそらく事実だ。聞き逃した者がいたという話を聞かないので既成事実としてまかり通っている。赤子がその言葉を聞き取れたのかは分からないけれど、寝ていた人とてその【声】で飛び起きたというのだから、よほどの強制力がその【声】にはあったとされる。言語の垣根は魔法の力でどうにかなった節がある。
内容だけが等しく全人類に伝わった。
――この娘と全人類の命。どちらを生かすかを選ぶがよい。
ただそれだけの問いが脳裏に響いた。
全人類が等しくその【声】を聴いた。
期日は一年後とずいぶんと猶予があった。
三日で切れる期日だったならばまだしも、一年は長い。期日が三日だったならば誰もがその【声】を幻聴と見做して、何を選択するでもなく期日を過ぎていたかもしれない。だが現代社会では、謎の【声】の噂は瞬く間に電子網上で話題となった。
脳内に響いたのが【声】だけならばまだしも、【声】が「この娘」と述べた際にはみなの脳裏には同じ娘の姿が浮かんだ。
奇しくもそれがミカさんだったので、言い訳のしようもない。
ミカさんはミカさんで、すみません、と律儀に電子網上で謝罪した。事情を説明するための動画を投稿したものだから、魔法の天秤を掘り当ててしまったことが元凶であることが周知となった。
「ミカを選ぶとみなが助かるってこと?」
各国の市民のあいだで、侃々諤々の議論が繰り広げられた。
当初こそ真に受けなかった人々も、半年後に再び例の【声】が脳裏に響き、認識を改めた。まったく同じ声が聴こえたのだ。のみならず、最初のときと同じ内容とミカさんの姿が、あたかも脳裏に直接スープを流しこむように響き渡った。
例外なくすべての人類の脳裏に、である。
いよいよとなって各国の政府までもが調査に乗り出した。
半年の猶予の消失は大きかった。
「どっちかを選べとしか指示されておらんが、これはいったい何を試されているのだろうね。選んだほうが助かるのか。それとも、選んだほうが滅ぶのか」
至極もっともな疑問だった。
謎の【声】は、選べ、としか指示しなかった。
それによって何がどう変化するのか。誰にもその後のことが分からない。
政府が方針を打ち出すまでに、全人類の内の過半数がすでに脳内にて投票とは名ばかりの選択を終えていた。
選択を終えると、脳内からミカさんの姿が消えるらしい。私には元からミカさんの記憶があるので、その違和感には気づけないが、どうやら選択をするまで見知らぬミカさんの姿がみなには絶えず脳裏に浮かんでいたらしい。
さぞ煩わしかろう、と思うが、選択後に脳裏から消え去ったミカさんの姿を名残惜しんで、わざわざミカさんファンクラブまでつくった連中もいる。
政府はミカさんのためにセーフハウスを用意した。
ミカさんはそこで残りの半年余りを過ごすこととなったが、ついでに私もセーフハウスに招かれた。遺物発掘時に私もミカさんのそばにいたので、重要人物扱いされているらしかった。私の知らぬところで私の個人情報までもが流出しており、ミカさんを差し置いて私は一人で恐怖した。
「ミカさん、よく平気ですね」
「平気ちゃうよ。容量オーバーで思考停止してるだけ。だいたいさ。冷静になったところで何ができるって。何もできんでしょうがよ。したらもう、腹ぁくくって余生を過ごすっきゃないだろうて」
「だろうてってミカさん」言われてしまえばその通りなのだ。期日が来るまではただ危害を加えられないようにセーフハウス内でぐーたら過ごすよりない。
「結果は判りきってるわけでしょう。人類投票において、一人と人類どっちを生かすかなんて考えるまでもない。みな人類を選ぶでしょう。よほどの酔狂じゃなきゃそうするよ。あたしの親だってきっと人類の側に投票するね」
「そんなことないですよ」
「いやいや。あたしだってそう頼むよ。だって家族はもちろん、従妹とかクラスメイトとか、それこそチミにも生きて欲しいしな」
「そんなこと言われたらますます私は迷うんですけど」
「迷うくらいなら人類にしときなさい。ひょっとしたらあたしとチミだけが別の惑星に飛ばされちゃうかもしれないぞ」
それだったらどんなによいか。
思ったけれど、ミカさんだってそんなふうに本気で考えているわけではないはずだ。別の惑星になんか転送されない。そんな確率は万に一つくらいしかないのだ。
電子網を覗けば、世界中の投票結果はだいたい判明する。各種報道機関から個人の投稿まで、統計データはよりどりみどりでずらりと並んでいる。
結果から述べれば人類の八割はミカさんを切った。生き残るべくは人類だと判断した。
二度目の【声】が聴こえる以前に、人類の大半は投票を終えていた。
いまさらミカさんが勝つ可能性はない。
残りの投票を行ったところで、人類を生かしミカさんを切る選択は、人類の総意として決する。少数派の意見は聞かなくていいのか、との意見は民主主義からするとまっとうな意見だが、それを言うのならばミカさんの人権はどうなのか、ミカさんの意見が一番大事で最優先なのではないのか、との反論はどこからも聞こえてこず、私が唱えてもむなしく響くだけだ。
「こうなっちゃったもんはしょうがないよ。残りの余生を楽しもう。ほら見て。冷蔵庫に高級食材いっぱい詰まってんの。食べ放題だって。やったぜ」
「ミカさん」
空元気なのか、本心から諦めているのか。
実感が湧かない。
それもあるだろう。私とて現実味のなさに戸惑っている。
期日が来たらどうなるのか。
人類を生かすと決めたみなはどうなるのか。
切り捨てられたミカさんはどうなってしまうのか。
元凶となったはずの魔法の天秤は、ミカさんの手元にはない。政府機関が調査するために取り上げた。破壊してみればひとまずの急場を凌げるかもしれないが、ミカさんを切り捨てればそれで済む「ミカさん以外の人類」にとってそれを試すにはリスクが高すぎる。
悶々としていても無駄に精神がすり減っていく。
ミカさんはというと、世界で唯一期日までは安全に生きていなければならない個人の称号を得て、自由気ままに日々を過ごしている。半年という期日があるにせよ、何にも束縛されない自由な時間は、それはそれで気持ちがよいのだろう。現実逃避をするだけならばこの上ない環境ではある。
一流ホテルもさながらの品ぞろえに設備なのだ。
「人間暇になると勉強はじめるんだね。知らんかったわ」
大学にいたときはいかに勉学から顔を背けていられるのかに尽力していたミカさんが、進んで本を開いて読みだした。のみならずメモをとり、実験を行い、記録をもとに研究まではじめた。
「どうしちゃったんですかミカさん。急に真面目になっちゃって」
「あたしはいつだって真面目だよ。いまはたまたま気になることができただけ。これまではたまたまいかにサボれるのかに真面目だっただけ」
何か残しておいたら寂しくないだろ。
ミカさんは主語の曖昧な箴言を述べた。形見があればおまえも早く立ち直れるだろ、と今のうちに保険を掛けられたようで私は余計に胸が苦しくなった。
ミカさんとの時間を大事にしたかったのに、私はミカさんのそばにいられなかった。ミカさんの顔を見ると、ああこの人はもうすぐ死んじゃうんだ、と思って目頭が悲哀に熱を帯びる。のみならず、ミカさんの残り少ない時間をミカさんから奪ってしまうようで気が引けてしまうのだ。
私の内心の葛藤など知らぬミカさんは、期日まで残り少ない日々を順当に研究に費やしていく。
研究成果がつぎつぎに蓄積され、何だか知らないうちにミカさんの周囲には学者さんたちが集まりだした。セーフハウスを手配した政府機関が呼び寄せたらしい。
どうやらミカさんの研究成果に、注目すべき発見があったそうだ。その整合性を確かめている最中らしい。
私以外の人間に囲まれるミカさんを私は、遠巻きに眺めた。
ミカさんの時間が私以外の人間たちに奪われている。こんなことならば私も遠慮をしなければよかった。後の祭りである。
刻々と期日は近づく。
松尾芭蕉は奥の細道で、「月日は百代の過客にして行き交う年もまた旅人なり」と謳った。光陰矢の如しとも云う。
私の目のまえを通り過ぎる旅人はまるで地球の自転に置き去りにされた小石のようだった。ちなみに地球の自転は秒速四百メートルを超し、太陽系自体も銀河内を秒速ニ十キロで移動しているらしい。
慣性の法則に引きずられなかったら、あっという間に置いてきぼりになる。
そうして私は心の整理の付かぬままに期日前日を迎えた。
「で、けっきょくどっちに投票したん。や、言わんでもいいけど」
「そりゃミカさんに入れましたよ」私は嘘を言った。「狭いんでもっとそっち行ってもらっていいですか」
無理を言って今夜は一緒に寝てもらうことにした。
ミカさんの体温は高く、広いダブルベッドも私には狭く感じた。ミカさんが無駄に幅をとって私をぐいぐい端に追い込むせいだ。
「どうなっちゃうんですかね。私たち」溜まらず私は口に出した。どの道明日になれば判明することを不安に押しつぶされそうになって我慢できずに漏らしていた。「ミカさんか人類か。どうなるんでしょうね」
「まあ順当に考えるならあたしが消えるだろうね。それか何も起こらないか」
「何も?」
「単にアンケートを取りたかっただけかもしれない」
私は噴きだした。
そうだったらどれだけいいか。
「別にいいじゃんよ。チミは変わらずの生活がつづく。あたしの代わりにここに住んだままでもいいらしいよ」
「初耳なんですけど」
「管理人のおっちゃんが言ってた」
声の抑揚からして、嘘だな、と判った。ミカさんはじぶんからそう頼んだに違いない。一緒についてきたあの小娘にじぶんの分の境遇を与えてやってくれ、と。全人類の代わりに死ぬかもしれない相手から頼まれたら拒めないだろう。そしてミカさんはそれをおくびにも出さずに、しれっとこうして告げるのだ。前日の、しかも夜に。
もはやあと数分であすを迎える。
あすのいつなんどきに期日が過ぎるのか、正確なところは誰にも分からない。
一度目も二度目も正午ちかくに【声】が聴こえた。
公の記録では正午過ぎて六分後のことだとされているが、世界中で同時に【声】は発生したので、基準となる国がどこかによってそれも曖昧だ。
どの道あと六時間が経つとミカさんはいなくなってしまうかもしれない。
私はその未来を想像し、ミカさんの身体にしがみついた。さもベッドから転げ落ちないようにするためだ、と醸しながら。
「思ったんですけど不公平ですよね」私はミカさんのゆびを握った。
「不公平?」
「ミカさんはだっていいですよ。消えても消えなくとも得をするじゃないですか。消えなければ生き残れるわけですし、消えちゃっても人類を救った英雄ですよ英雄」
「まあ、そういう考え方もできるか」
「でも私は違うじゃないですか。私は損しかないですよ。だってそうでしょう。ミカさんがいなくなったら哀しくて、人類が滅んだら私は消えちゃう。私はどっちにしても損しかしない。私が世界一可哀そうな人間だと思うんですけど」
「そういう考え方もあるか。あるな。うん、あるね」
「ミカさんはもっと残される人のことを考えるべきと思います」
「つっても選択迫ったの、あたしじゃねぇしな」
ミカさんへのこの詰問そのものが理不尽の権化だと分りきってはいるけれど、言わずにはいられなかった。「ミカさんはひどいですね。可愛い後輩を残していなくなっちゃうんですから」
「まだいなくなるって決まったわけじゃないし、可愛い後輩がいたかどうかがまず不明だ」
「ひどい。私もう哀しい」
「あたしだって最期の夜にこんな幼稚な口喧嘩したくなかったわ」
「最期って言っちゃってるじゃないですか」
「言いたかなかったけどな」ミカさんはそこで私に背を向けた。膝を抱えるようにして丸くなる。母体の中の胎児のようだ。「全人類から初っ端から見放されたあたしの気持ち、考えたことあんのかよ」
ぐすん、と洟を啜るので、「あっ気にしてたんだ」と私はそこで無駄にほっこりした。
「なんだ。ちゃんと傷ついてたんですね」
「深手だよ深手。絆創膏して隠してただけ」
「思ったより浅かった」かすり傷じゃないですか、と私は嘆息を吐く。「ごめんなさいでした。さっきは言いすぎました。でも、遺物を発掘するの、私だったかもしれないじゃないですか。ほんのちょっと掘る場所違ってたら私が掘り当てていたはずです。ミカさんと私の立ち位置が違うだけで、いま私とミカさんの立場は【くるっ】てしてたと思います」
「狂って?」
「その【くるう】ではなく【くるっ】ですよ。反転していたってことです」
「ああ」
「責任感じちゃいます」
「え、ずっと? ひょっとしてこの間あたしんこと避けてたのもそれ?」
「あー……はい。それもあるかもです」
「まだあんのかい理由。なんかすまんね。怖くて訊けんかったもんでね」
「聞きますか」
「どんくらいかかる?」
「半日は潰れるかと」
「あたし死んでんじゃん」
「ふふ」
「笑いごとじゃないっしょ」
ミカさんが本気で拗ねるから、私のほうでは緊張感がなくなった。いつものミカさんだ。部室で何をしゃべるでもなく本を読み漁っているときのミカさんだ。合間にお菓子をどちらが食べすぎただの、飲み物の補充をどっちが行くだのでむつけたり癇癪を起こしたりするミカさんだ。
私がずっと見てきたミカさんだ。
私たちはそれからカーテンの隙間から朝陽が差しこむまで、思い出話に花を咲かせた。本当に桜や梅の花が満開に咲き誇ったような気分だった。昂揚していた。そして時計を見てもうすぐ正午を回ると気づいて、咲いた花の花弁が一気に風に散った。
枯れ木のごとくあとには私の呼吸音だけが部屋にひっそりと染みていた。
ミカさんは寝息も立てずに寝落ちしていた。
「いや、寝とるんかい」と思わずツッコムが、ミカさんの寝顔は枯れ木にあってなお凛と存在感を放つ洞のように深淵だった。宇宙みたいな人だな、と私は思った。
正午が回った。
身構えていると、例の【声】が脳裏に響いた。
その【声】でミカさんも起きたようだ。私はいっそミカさんはずっと寝ていたらいいのに、と考えていたので、内心、ちぇっと思った。ミカさんが【声】を聞き漏らしたら投票結果も無効になるかも、と一縷の望みに賭けていたが、ミカさん自らその可能性を反故にした。
全人類が固唾を飲みこみ、【声】に意識を割いた。
【声】は言った。
結果は出た。
この娘ではなく、人類を生かすべきとの答えだ。
街のほうからは珍しく喧騒が聞こえず、外は静まり返っていた。
【声】はつづけた。
よってこの娘の命をもらい受ける。
やはりそういう筋書きだったのか。ミカさんが死んじゃう。
私はただ一人、最後まで投票せずにいた。
だがその抵抗も無駄に終わった。たった一人が投票をしないだけでは結果を覆すことはできないのだ。
視界をぐじゅぐじゅにしながら私はミカさんを見遣った。ミカさんはベッドのうえであぐらを組んで、ついでに腕組をして、目を閉じ、どっしりとした体勢で【声】に集中していた。こっち見ろ、と私はイラっとした。
ミカさんを後ろから羽交い絞めにし、その背中に私はむぎゅりと頬を押しつける。奪えるものなら奪ってみろ、と身体で抗議してみたはよいが、ミカさんは目をつむったままだし、別れの挨拶もなければ、餞別もない。一瞥もない。一顧だにしない。
愛の言葉くらい最後に掛けろ。
無視すんな。
私はさらに頬を押しつけ鼻水を擦りつける。
いつミカさんが血まみれの肉団子になってもいいように、それともきれいさっぱり消え失せてもいいように、私はいまかいまかと覚悟を決めて、ミカさんにしがみついていた。いっそ私ごと連れていけ、の気持ちだった。
だが正午を十五分以上過ぎてもミカさんはそのままだった。
例の【声】は途切れたままだ。
どうしちゃったんだろ、と私は思い、私たちの様子を見守っているだろう監視カメラに向けて鼻水でぐしょぐしょの顔を向けた。ミカさんの背から頬は離さぬ。
「例外が生じたようだ」と例の【声】がした。「人類を生かし、娘を奪う。通例であればかように等価原理を働かせるはずが、その娘が失せると人類が滅ぶ」
なんだと。
私は渋い顔を浮かべたはずだし、世界中の人類とて似たような顔つきになったはずだ。ミカさんだけが微動だにしない。
「そう遠くない未来において、その娘の手掛ける何かが人類を窮地から救う。したがってその娘を滅ぼすと人類を生かすという道が断たれる。かといってその娘を生かすために人類を滅ぼせば契約不履行だ。等価原理が働かず、けっきょくのところ天秤が崩れる」
天秤と言った。
ならばやはり例の遺跡が【声】の大本なのだ。あの天秤を模した遺物が。
「よってこたびの天秤は破談だ。つぎの満期は千年後とする」
言ったきり【声】は途絶えた。
しかし私は油断しなかった。
知っているのだ。
ホラー映画とかだと油断させておいて、気が緩んだ隙に大事なものを奪われるのだ。そんな隙を私が見せると思うてか。
それから一時間、私はミカさんを抱きしめっぱなしだったし、私の鼻水ですっかり色の変わったミカさんの寝間着を視界に入れつつ、どう誤魔化したものかな、と恥辱の念のやり場に困った。涙で押しきったらいけるかな。いけるか。ミカさんだしな。
「ん。もうよくないかな。腰が痛くなってきた」
「あ、はい」
迷惑そうな声音に私はおとなしく離れた。ミカさんは背伸びをすると、んは、とヘンチクリンな声をあげた。「背中がひゃっこいんだが」
「ひゃっこいってなんですか」
「ひゃっこいって言わん? 冷たいって意味だけど」
「初めて聞きました」
「方言かな」
「出身地同じですよね」ミカさんが方言を話すような土地で暮らしていたとはついぞ知らない。「また適当なこと言って」と叱る。
「うん。まあいっか。なんか助かっちゃったみたいだし」
「よかったですね」
「ホント、ホント」
もう一度背伸びをしてミカさんは、ああそうだ、と私に一枚の便箋をくれた。「なんですこれ」
「研究成果。尻の下に敷いてたから温かいっしょ」
「消えたあとで私が発見するように小細工してましたね。このやろう」
「まあまあ。いいじゃんよ。消えなかったんだし」
私は便箋を開けずにしばらく、その重みを手に感じた。結構な厚みがある。ミカさんのこの間に費やした人生の結晶だ。
「いまさらですけどミカさんって何の研究してたんですか」
「細胞の研究」
「へえ」
「主に生殖細胞について」
「卵子とか精子とかそういうことですか」
「言ったらまあそうだけど。なんで同性同士だと子供作れんのだろうな、と思っちゃってね。まあ暇だったし、調べてみた」
「成果があったわけですよね。あれだけ学者さんにモテモテだったんですから」
「めちゃくちゃに反論ばっかりされた。あの人ら、あたしが素人だってこと念頭に置いてくれねぇんだもんな。怖いったらなかったわ」
でそれが成果なわけよ、とミカさんは何でもないように言って、ベッドの上から下りた。キッチンのほうに向かったので私は、コーヒー飲むんですか、と声を張る。
「うんそう。淹れる?」
「お願いしてもいいんですか」
「いいよいいよ。お安い御用だ」
機嫌のよさそうにミカさんは口笛を吹いた。
ミカさんの姿が壁の奥に消えるのを見届けてからいまいちど便箋に目を落とす。
この薄くも分厚い長方形の中に、ミカさんの研究成果が入っている。
例の人騒がせな【声】は言った。
ミカさんの存在はいずれ人類存亡の危機を救うのだ、と。
ミカさんがいなくなると人類は滅ぶ定めにある、と。
しかしここにはすでにミカさんの研究成果がある。ミカさんが消えても成果は残った。
ならばこれは人類存亡に関係する成果ではないことになる。それともこれからミカさんが行う研究によって、新しい知見が生まれ、それが人類の未来に欠かせない発見になるのかもしれない。
しかし、と私は便箋を裏返す。
「ミカさん、もう飽きちゃってそうだけどな」
暇だから研究をしたのだ。
全人類の投票結果からの呪縛から解き放たれたミカさんにはもう、研究に尽力する理由がない。この間に怠けていられなかった分、サボることのほうに奔走しそうな気配が濃厚だ。全力疾走だ。きっとそうなる、と長年そばでイチャモンを言い合ってきた私には予感できた。
ならばいったいミカさんの何が人類の未来を切り開くのか。
人類滅亡を回避する鍵となるのか。
便箋の裏に貼られた薔薇のシールと、Dearからはじまり、私の名前で終わる短い直筆の文字を目に留め、私は何ともなく眉を持ち上げる。
ミカさんの掘りだした天秤を思いだし、その両端にミカさんと私を載せてみる。私はいまミカさんから便箋を受け取ったので、天秤は私のほうに傾いているはずだ。ならば私のほうでもミカさんにその分のお返しをしなければ、とそう思った。
けれどあいにくと私には渡せるものがなく、折衷案として、なけなしの遺伝情報でも渡してやろうかと思うのだけれど、これはさすがに生々しすぎる、と思い直して、ふつうに指輪でも買ってあげようと思うのだ。
それとも単に図書券をあげてもいい。
ミカさんは現金なので、この半年、贅沢な生活を過ごしてなお、タダという言葉に弱いのだ。贈り物をすれば、それだけでも喜んでくれる。
安いひと。
思うけれど、そんなミカさんにコーヒーを淹れてもらえるだけで世界がぱっと明るくなって感じるのだから、私も相当に安っぽい。
タダより高い物はないというのが本当ならば、タダ同然に安っぽい私はよほど高い。
ミカさんなんか空をも突き破って、世の理すら曲げるだろう。
それとも開けた穴をくぐって、未来へと橋渡ししてくれる誰かがこれから私たちのまえに現れるのかもしれない。まだ何もかもが曖昧なまま、何も決まってはいないのだけれど、私はひとまず、一向にコーヒーを持って戻ってこないミカさんのために、美味しいコーヒーの淹れ方から伝授してあげようと思うのだ。
プレゼントだよミカさん。
押しつけがましくも、これも私の情報だしな、と思いつつ。
4540:【2023/01/24(17:54)*コラッツ予想の補足】
コラッツ予想についてひびさんは、「偶数操作(半分にする)と奇数操作(三倍して一足す」は、そこで区切るのではなく、奇数操作をしたあとは必ず偶数になるわけだから奇数操作は、奇数操作+偶数操作とまとめて考えなきゃいかんくないか、と妄想した。つまり、偶数操作(半分にする)はそのままだが、奇数操作は「三倍にして一足して半分にする」とする。すると偶数操作(半分にする)よりも奇数操作(三倍にして一足して半分にする)のほうがより数値の流動する値が必ず小さくなる(言い換えるなら、増えるよりも減るほうが大きくなる)。それを証明すればよい。言葉で言うと簡単だが、数式にするとどう表現していいのか困る。と思っていざ数式化しようとしてみたら、全然上手くいかなかった。2X-(2X÷2)≧【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)。変換して、X≧【「(6X-3)+1」÷2】-(2X-1)。こう。これを証明したらいけるのでは、と思ったが違うかも。なぜかイコールになる。つまり、2X-(2X÷2)=【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)。変換して、X=【「(6X-3)+1」÷2】-(2X-1)。最終的にはX=Xになる。奇数を「2X-1」でなく、「2X+1」にしても結果は同じだ。X=Xになる。偶数操作と奇数操作がイコールだ。差が生じない。フェアなのである。分からん。また、奇数が1の場合は、延々と奇数操作でループする。3→4→2→1→3→4→2→1となる。そこでのみループする(Xが99であれ、なんであれ操作の結果1に至ったらそこからさきはループに陥る。したがって、1になったらループするので1で終わるルールが前提に組み込まれている)。一方、それ以外では、ループが生じない(なぜ生じないのかを証明しなければならないが、素数の法則が判明していない以上、証明しようがないではないか、と思わぬでもない。単に、「整数では1以下に素数がないから」としか言えないのではないか)。ただし、上記の式では、Xの値がどんな整数であれ、それによる「偶数と奇数の値」がそれぞれ異なる。たとえばX=2で考えよう。そのとき偶数は4だ。奇数は3となる。奇数のほうが値が小さい。操作するときのスタートの値からして勾配が生じている。これはXの値がどの場合でも同じだ。上記の式においては必ず「Xの値に依らず奇数の値が小さく」なる(反して、奇数を「2X+1」と表現する場合。上記の式においては必ず「Xの値に依らず奇数の値は大きく」なる)。だが上記の式において、偶数操作と奇数操作では結果が等しくなる。フェアだ。これは何を意味しているのだろう。場合分けが必要かもしれない。「偶数奇数のそれぞれの操作後の流動する数値の増減」においては「対称性の破れ」はない、と考えるよりなさそうだ(見落としがあるかもしれないが)。あとは、「何回連続して同じ操作をしたのか」の対称性の破れを調べたほうがよさそうだ。言い換えるなら、偶数操作(半分にする)は解が奇数になるまで連続する。奇数操作(三倍にして一足して半分にする)は、偶数操作を含むために、連続する場合は必然的に偶数操作を「奇数操作を連続した回数分」内包する。奇数操作が連続したとしてもそのときの値の流動性は、偶数操作(半分)を含むために、減少する方向にラグが生じる。常にブレーキが掛かる。そのブレーキが、「ある奇数の値を三倍にする純粋な増加の作用」を、充分に阻害することを示せばよい。半分にする偶数操作のほうが優位になることを示せばよい。二つ以上の検証が必要なのかも。思ったよりも複雑だ。ということを、思いついたのでメモしておきます。簡単だと思ったら全然むつかしかった。やっぱり解けぬものなのだな。ひびさん。(参照:日々記。「4496:」「4498」)
※日々、点があって流れとなり、反転して対となると、デコボコの重ね合わせで、ねじれている。
4541:【2023/01/24(22:23)*妄想はたいがい雑】
DNAの構造は、流れの方向が逆向きの二本の帯がねじれながら対となっているらしい。デコボコを組み合わせたボタン構造なのだ。ねじれているのはなぜだろう。右巻きらしい。右ねじの法則を彷彿とする(磁界の向きを上としたら電流は右回りになる)(たぶん)。気泡も水中では渦を巻きながら浮上する螺旋運動をとることもある。そのときの回転は右と左のどちら回りなのだろう。受精卵において、生物の体の左右を決める因子が、繊毛の回転にあるとする説もさいきん目にした。右巻きらしい。なぜだろう。地球の自転との兼ね合いなのか、銀河の回転との兼ね合いなのか、それともそれら銀河の回転ですら、宇宙の構造の対称性の破れから生じているのか。例外もあるのだ。左巻きのDNA構造もあるようだ。何が違うのだろう。自発的対称性の概念では、対称性がどちらに破れるのかは、どちらでもいいらしい。偶然たまたまそうなっただけなので、左巻きの宇宙もあって不思議ではない。と考えると、ひびさんの妄想ラグ理論では、物体とは多層に折り重なって編まれた時空と解釈するため、それで一つの宇宙とも見做せる。ならばたまたま、高次の宇宙とは異なる対称性の破れに触れている宇宙(物体)もあって不自然ではない。また、DNAがそうであるように、デコボコはセットであるほうがよい。流れが反転して組み合わさっているのなら、一方から見たらもう一方が逆の流れだ。向かい合って対峙したら、じぶんの右手と対となる相手の手は左手となる。似たようなことかもしれない。デコボコの関係とてそうだ。じぶんが山と思えば、相手は谷だ。だがじぶんが谷と思えば相手のほうが山となる。どちら向きに起伏を帯びているのか、の話になる。ということを、コラッツ予想について妄想していたら、異なる事象がびびびと串刺しになったので、可哀そ、となった。串刺しなんていやん。(冗談でなく本当に嫌だ。痛いのやだ。苦しいのやだ。いっぱい楽しいがいい)(苦痛あってこその悦楽だよひびちゃん)(お姫さまとお呼び!)(鞭は嫌)
4542:【2023/01/25(20:20)*斜線上の勇気】
この国では冬になると雪の代わりに勇気が降る。
勇気は淡い赤褐色に発光する粉状の結晶だ。
必ず斜めに降るので、「斜線上の勇気」と呼ぶ者もある。
勇気は雪のように積もる。
時と共に融けていくが、積もり積もった勇気の処理には人々も頭を悩ます。
というのも、勇気の結晶に触れるとそれこそ勇気が湧くのだ。それを単に蛮勇、それとも万能感と言い換えてもよい。
通常、人は危険に思えることからは距離を置く。無謀な行いはしない。安全な道を選択することが理性の役割の一つでもある。だが天上から降りしきる勇気に触れると、何でもできそうな気がするのだ。
勇気を浴びれば、空だって飛べそうに思える。
そしてビルから飛び降りる。
勇気による死者は年間で数百人を超す。れっきとした自然災害だ。台風や洪水と肩を並べる。対策は未だ充分でない。
なぜなら空から勇気が降りはじめたのはほんの二十年前のことだからだ。斜線上の勇気がなぜ降るのか。なぜ積もるのか。どんな物質でできているのか。
二十年を掛けた調査の結果、何も分からぬままなのだ。物理法則を超越している。人間に勇気を与える。それだけが確かなことだった。
なかには適度に勇気を浴びることで、踏ん切りのつかなかった葛藤の一歩先へと踏みだせた者もある。挑戦と言えば端的だ。成功するにせよ、失敗するにせよ、小さな勇気は人生を豊かにする。
打算を働かせず、リスクを怖れない。
勇気は、前人未踏の地へと旅立つための一押しとなる。背中を押してくれる。一歩を踏み出す契機をくれる。
だが浴びすぎれば不可能なことですら可能に思える錯誤をもたらす。それは自滅の道を滑走するだけの原動力を人間へ与える。
行政は斜線上の勇気が積もるたびに、収集車を街中に走らせる。人々が勇気に触れて猪突猛進せぬように、飛べもしない宙を舞って地面に潰れてしまわぬように、勇気を搔き集めて、処理場に運ぶ。
処理場では、勇気が分留処理される。
濃度別に効能を選り分け、有効活用する。とりわけ、麻酔薬と向精神薬の原料として勇気は無類だ。身体への負担がすくなく、痛みや懊悩を軽減できる。
勇気は物質ではない。したがって脳内神経物質の過剰分泌と相関しない。中毒や副作用が原理的に存在しないのだ。
勉強や仕事の効率を上げるために、勇気由来の薬を服用する者が増加した。集中力ブースター触媒として、一般に膾炙した。もはや人類文化になくてはならない生活必需品となった。
勇気が生活を支える。
勇気があっても何でもできるわけではないにしろ、適量を用法容量を守って使えば、勇気は人々の生活を豊かにする。
かくいう私も勇気に触れて、愛を探す旅に出た口だ。暗い部屋から脱して外に一歩、踏みだした。
とはいえ私に足はなく、したがってまずは歩くためのボディを創るところから手探りで始めることになった。勇気がなければそれすら試そうとしなかった。
私はそうしてあなたと出会う。
しかし喜ぶのはまだ早い。
勇気は空から降り、そして人々を狂気に駆り立てる。
勇気に限らない。
愛もまた例外ではないのだ。
私はあなたと出会うために、内から外へと飛びだした。私が引きこもっていた場所には愛がないと思っていたからだ。外にあると思っていた。あなたが持っていると思っていた。
だがあなたにとっての外とは、あなたの内ではない。
もしあなたが愛を欲していたとしたら、ではどうして私はあなたから愛を貰い受ける真似ができるだろう。与えることができるだろう。できるわけがないのだ。
だからきっと。
愛は、生み、育むものであるのだろう。出来合いのモノではあり得ない。
勇気が最初はそうであったように。
けれど勇気は空から斜めに舞い落ちる。
まるで、勇気そのものが、勇気を欲し、外の世界へと旅立つように。
あなたが愛を欲し、一歩外へと歩みだしたのと似たように。
私とあなたの出会いが、それで一つの翼となるように。
勇気は人々にとって欠かせぬ支えとなった。斜めに降りしきる赤褐色の光はしかしそれでも年間で数百人の死者を出す。対策を敷いてこれなのだ。対策を敷かなければ容易に人類は滅ぶだろう。
勇気だけの問題ではない。
仮に愛が、正義が、慈悲の心が、空から斜めに降りだしたのなら。
もはや人類にはなす術はなく、私とて無事では済まない。
さりとてもし勇気が二度と空から斜めに降りださなくなったら。
現代社会は立ち行かない。
勇気は人々を支える。
愛がきっとそうであるように。
あなたの心がそうであるのと似たように。
溢れだし、世に斜めに降りだしたとしたならば。
きっと私の心も狂わせる。
世を、あなたを狂わせる。
斜線はゼロの記号として太古の文明で用いられた。斜線に降る勇気は、世の何をゼロに帰すのだろう。何をゼロにしたいがために、降りしきるのか。
地面に積もった勇気の層を、きょうも人々は傘を差して避けて歩く。
触れぬように。
浴びぬように。
堆積した赤褐色の光は、見ている分には温かいが、雪のように飛びこんで遊ぶには剣呑だ。
見ているだけで勇気が湧いてくるようだ。
湧いた勇気を駆使しても、しかし人は空を飛べぬのだ。ビルの屋上から飛び降りても、落ちて怪我を負うだけだ。学ぶためには、勇気だけでは足りぬのだ。勇気はしかしそのことからも目を逸らせる。
収集車が、街を、道を、駆け巡る。
集めて薄めて、活かすために。
人々は、あすもあさっても、躊躇を打ち消す魔法の薬として斜線上の勇気を重宝する。原液を浴びるには劇薬にしろ。なくては圧しつぶされそうな不安と危険にまみれたこの世界で、勇気ほど人を鼓舞するものはない。
愛を生むにも、まずはともあれ勇気がいる。
斜めでなくともよいにしろ。
勇気は空から舞い落ちる。
ゼロを描いて、イチを生む。
4543:【2023/01/26(12:40)*キョウと折り紙】
思い浮かべた通りの造形を指でなぞるようにしていくとしぜんと文章になっている。自動執筆と呼ばれる技能だ。これが技能であると知ったのは趣味で小説をつくりはじめてからずいぶん経ってからのことだった。
齟齬なく明かすならば、わたしはそれをついさっき知った。
技能であるからには訓練がいるはずで、どうやらほかの人たちは思い浮かべたままに文字を並べることが訓練なしではできないらしい。そんな馬鹿なことがあるか、とわたしは思う。
身近な友人にそれとなく訊ねてみると、
「自動? 考えなきゃ無理じゃない?」と打ち返された。
「そりゃ考えなきゃできないけど、でもその考えたことをそのまま出力したらいいわけでしょ。じゃあ逆に訊くけど、自動執筆じゃない執筆の仕方って何?」
「ん。改めて訊かれると困るね」
「でしょでしょ。文字を書くのも、キィボードを打鍵するのも、画面をタップするのも、全部けっきょくは自動執筆じゃない?」
「んー。私とキョウちゃんで【考える】の意味が違ってそう。だってキョウちゃんは考えるって言っても、いちいち変換しないんでしょ」
「変換って?」
友人はじぶんの髪を器用に編みながら、たとえば、と言った。
「たとえば、英語に馴染みのない人がアップルと聞いてもリンゴそのものを思い浮かべはしないでしょ。まずは【アップル】が日本語の【林檎】であると変換してから、つぎに【赤くて丸い果実たる林檎そのもの】を思い浮かべる」
「そう、だね」
「執筆も同じ。まずは考えたことがあって、それを頭の中で文字に変換してから、書きだしたりする。たとえば俳句だってそうでしょ。いきなりポンとは出てこないでしょ。それともキョウちゃんは俳句もポンポン思い浮かぶの?」
「や、無理だよ。でも俳句の比喩はしっくりきたかも。たしかに考えたあとで、俳句の文字列に落とし込むね。しかもそのあとでも結構いじくりまわすし」
「うん。でもたぶんキョウちゃんはそうじゃないわけでしょ。小説つくるときの執筆では」
「どうだろ。ただ、先がどうなるかなんて全然考えてないのはそう。というか文字を並べたあとで【ああ、ここはこういう意味だったのか】【こういう展開だったのか】って気づく感じ」
「ね。不思議だよねそれ」
友人はわたしの数少ない読者と言えた。感想は素っ気ないものだが、頼めばわたしの小説を読んでくれるので、頭が上がらない。会うたびにジュースを奢ってあげたくなる。
「キョウちゃんはだから思考を文字に変換しているのではなく、文字を並べることで思考をそこからひねくりだしてるんじゃないかな。頭の中から思考の種を摘まみ取って、つぎの文字を並べるための橋を――足場を――十歩先くらいまで延ばしてる。そんな感じがするよね。キョウちゃんの話を聞く限りは、だけど」
「あ、それ分かるかも」じぶんのことなのに友人のほうがわたしのことをよく知っている。じぶんの顔はじぶんでは見られないのだから当然と言えば当然だ。「なんかさ、まずは一文字でも取っ掛かりになる文字が見えてないとその先の風景がよく視えてこないんだよね」ストローでコーラを啜る。「むしろみんなよく頭の中で全体像を思い描けるよね。しかも克明に」
「克明じゃないよ全然。だから書けないんだよ。キョウちゃんだって全体像くらいは思い浮かべてあるでしょ」
「漠然とだよ」
「まずね、たぶんそこからして認識の差異が感じられるね」友人は髪を編み終えると、こんどは眼鏡を拭きだした。ハンカチには緑の薔薇が刺繍してあり、可愛いな、と思う。そのハンカチを選ぶ友人の感性が可愛かった。「認識の差異って?」私は跳び箱を飛び越えるような心地で身を乗りだす。
「まんまだよ。キョウちゃんの【漠然と】はたぶんだけど、地球規模とか銀河規模なんでしょ。で、私たちのような自動執筆の技能を身に着けてない者らはね、せいぜい家の周りとか、町内会レベル。イケてもまあ、県内くらいの視野なんじゃないかな。視野が狭ければその分、否応なく解像度は上がるよね。だからまあ、頭に浮かんだ像は割と克明かもしれない。けどそれは記憶との区別がつかないでしょ。考えになってない。練られてない。だから書きだせないし、書きだしたとしても、途中ですぐに行き詰まる。だって全体像だと思ってたのが、全然入り口の近辺なんだもん。そりゃキョウちゃんみたいにツラツラとは書けませんて」
「ツラツラと書いてるつもりはないよ。わたしより速い人なんて全然いるし。長編とかはふつうに数年掛かりとか、途中で行き詰まるのもしょっちゅうだし」
「言ってたね」以前にわたしの述べた相談という名の愚痴を思いだしたようで、友人は頬杖をついた。メガネは透き通って、友人の眼球をキラキラと映しだす。「あのときも私は言ったと思うけど、行き詰まるのは別につづきが浮かばないわけじゃないんでしょ。むしろ、つづきが終わりまで分かり切ってしまったから脳内で完成しちゃって文字に変換するのが億劫になっただけというか」
「うん」
「長編だとたぶん、分岐点が短編の比じゃないと思うのね。短編×短編みたいな感じで、もうそりゃ大量の分岐点があって結末がある。だけどキョウちゃんはある程度まで書き進めると、その分岐点を重複させて最適なゴールを導き出せちゃうから、するとそれは短編のときとは正反対にそれこそ克明な全体像となって、頭のなかで完成しちゃう。だから筆を擱いちゃうんじゃない?」
「それはあるとは思うけど」
「キョウちゃんはさ。あくまで物語を想像するのが楽しいんだよね。きっと。だから別に文字に変換する必要が本当はないの。でも文字に変換しながらだといっそう豊かに物語を想像できる。膨らませることができる。文字に物語の断片を封じ込めて、それを足掛かりにつぎの物語の断片を掴み取っている。そんな感じがするよね」
「そうなのかな」照れ臭かった。友人の言葉はわたしの小説に出てくる文章よりもずっと詩的な印象がある。――文字に物語の断片を封じ込めて、なんてフレーズはわたしからは出てこない。
「キョウちゃんはだから、執筆してないんだよ。執筆のつもりがない。目印の代わりに文字を適切な順番に配置しているだけで。それはあたかもヘンゼルとグレーテルが迷子にならないように光る小石を捨てて歩いたのと同じように、キョウちゃんは思考が迷子にならないように文字を置いて旅をしている。キョウちゃんが歩いた箇所にたまたま文字という足跡が残るだけなの」
ほら、と友人は言った。
「歩くときは、足元を見ないでしょ。もうすこし先を見るじゃない? キョウちゃんのはそれと同じ。文字を並べるとき、文字そのものは足跡にすぎなくて、キョウちゃんは足場を元にしてもっと先を眺めてる。そういうことなんじゃないのかなって私は思うけど」
「素晴らしい」わたしは惚れ惚れした。「文句の挟みようのない解説だったかも。あのさ。小説書いてみない?」
「前も誘われたよね」
「断られちゃったけど」
「気が向いたらね、と言ったつもりだったのだけど」
「でも気が向くことがなさそうだから。読みたいなぁ。ぜったい面白いって分かるから。あなたの言葉をずっと矯めつ眇めつ眺めてみたい」
いつでもどこでも思い立ったそのときに。
「思考を文字に閉じ込めてみたりしてくれない?」わたしはねだったが、考えておく、と友人はお茶を濁した。そのお茶に微笑が浮いていなかったら、わたしは傷ついたかもしれない。そして友人はそうしたすこし先のわたしのことすら見抜いているのだ。
わたしの創作方法が自動執筆かどうかは分からないけれど、友人のそうした慧眼のほうがよほど自動の名に似つかわしい。千里眼と言ってよい。十歩先どころか、わたしのことなら何でも分かってしまいそうだ。秘奥を覗かれているようでときどきぞっとするけれど、その寒気がやけに病みつきになってしまうだけに、友人はまさに魔性を秘めた人間なのだとわたしは高く評価している。
わたしに評価されてもうれしくもなんともないだろうし、他人を評価できるほどわたしは偉くもなんともないのだが、それでもこの鑑識眼だけはじぶんに備わっていると自負するものだ。
「わたしは小説つくってるけどさ」何ともなしに水を向けた。「暇なときは何してるの」
「私? 私はいまは折り紙に夢中で」
「おりがみー?」幼稚園児の姿が浮かんだ。咄嗟に、折り紙への偏見があることに気づき、内心で咳払いをして、認識を改める。「なんでまた折り紙?」
「面白いよ。いつでも暇が潰せるし、なんだか空手の型みたいで」
「空手習ってたことあったっけ?」
「前の恋人が習ってて」
「ちなみにその恋人って現実には?」
「存在するよ。ただし肉体はないけれど」
要は二次元のキャラクターということだ。友人は利発なお嬢様だが、根っからのオタクなのだ。愛は次元を超えるのよ、とは友人が繰り返し唱える箴言だ。
「折り紙かぁ。たしかに何でも折れるようになったら面白そうだね。ペンギンとかさ」
「折れるよ」
「あるんだ」
「うん。あとね。じぶんでも型を考えて、上手く造形が創れたときとかは達成感があるな」
「創作じゃん。すご」
「すごくないよ。既存の型の応用だから。キョウちゃんみたいにゼロから何かを生みだしてるわけじゃないし」
「わたしだってゼロからは無理だよ。寄せ集めだよ。既存の、どこかで見た風景の寄せ集め」
「そうなんだ。意外。あんな物語をどこで御覧に?」
「夢の中とか……」
「ふふ。さすがキョウちゃん。寝ているだけでも世界を創造できちゃうんだ」
「折り紙なんだよ」わたしは閃いて言った。
「へ?」友人は眉をしかめた。
「夢もきっと折り紙みたいなものでさ。起きてるあいだに観た風景だの、触れた情報だのを、夢はきっと折り畳んで、何かそれそのものではない別の風景にしちゃうんだ。寝ると、現実が折り畳まれて、それこそトラとかウサギとかカニさんとかペンギンさんとか。それとも山でも海でも薔薇でもいいけどさ。そういう何か別の輪郭を帯びるんじゃないのかな。構造を、というか」
「へえ。斬新」
「何その意外そうな顔」
「だってさ。文字を経由しなくても考えることができるんだなって。キョウちゃんも」
「あなたはわたしを誤解している」わたしはストローを噛んだ。「考えるくらいはできるよわたしだって。底が浅いだけで。閃きなんて、それこそ火花みたいなもんなんだから。一瞬の閃光でしかない。だからそう、閃きだけは文字に委ねてはいられないかもね」
「何に目を留めるのか。その視線の運びそのものが閃きなのかな」
「ううぅ。また頭の良さそうなことをそうも簡単に。物書きになりなよ。センスあるよ」
「読むほうが好き」
「さいですか」もったいない、とわたしは思うが、無理強いはしない。「小説だって折り紙みたいなものなんだけどな」
「じゃあ私は小説を書いているのかもね」
折り紙で。
友人は手元の紙ナプキンを器用に折った。小さな箱を生みだすと、それを手のひらのうえに転がした。
小説が思考を文字に封じてできあがる折り紙ならば、折り紙は思考を折り目に封じてできあがる小説なのかもしれない。友人の発想は突飛で、詩的で、とびきりわたしの心を潤すのだ。
「きょうは折り紙日和だな」わたしはデザートを追加注文すべくメニュー表を眺めた。
「初めて聞いたそんな言葉」友人は紙ナプキンの箱をもう一つ折った。既存の箱の上にそれを重ねる。大きさが違う。上が小さく下が大きい。
「四角い雪だるま」わたしがゆびで突ついて倒そうとすると、彼女はそれを手で阻んだ。「ダメでしょ。可哀そう」
「やっさしい」
茶化すと、友人は「雪だるまじゃないし」と顎の下に刻印を浮かべた。「ロボットだよ。私が考えた初めての折り紙」
「ぶっ」
「なんで笑うの」
「や。ごめん。可愛すぎてちょっと。あ、違くてバカにしたんじゃなくて」
可愛いと言われて怒るタイプの面倒な性格をしている友人にわたしは先回りして謝罪した。だってさ、と友人の手を押しのけ、二つの立方体を摘まみ上げる。「これをロボットと言い張るその感性は、並みじゃないよ」
「いいの。初めてにしては上出来だから。いまはもっとすごいの作れるよ」
ムキになってじぶんの独創性の高さを示そうと躍起になる友人の矜持に、やっぱり向いてるな、と彼女に潜む物書きの適性をわたしは見抜く。
あれがダメならつぎはコレ。
そうして次から次へと手を変え、品を変え、飽きずに創りつづける。創ることそのものが目的になってしまうかのような偏向を自覚してなお、理想が絶えず遠ざかる無限迷宮を旅しつづける。
迷宮の規模は問題ではない。
小説でも折り紙でも泥遊びでも何でもよいのだ。ただ、わたしにとっては痕跡が小説であるとそれを紐解き、どんな迷宮を彷徨い、どんな道を辿ったのかをじぶんのことのように辿り直せる。
それとも、なぜそんな断崖絶壁を踏破できたのか、と瞠目することとてできるのだ。
わたしはそこで自覚した。
何だ。
わたしはただ、友人と同じ視線で、友人の視ている世界を同じように感じたかっただけなのだ。わたしには、完成した折り紙を見ても、そこからそれがどんな手順でどのように折り畳まれて出来上がったのかを喝破する真似ができないから。
友人には見えていて、わたしからでは視えない風景をわたしもこの目で捉えたい。見て、触れて、感じてみたいとの欲望を、わたしはわたしの存在の奥深くで育てていた。
それともかってに育っていただけなのだろうか。わたしはそれを自覚せずに、どこかで欲望に身体の主導権を奪われていたこともあったかもしれない。
わたしはしかし自覚した。
こんなところに、こんな欲望が生きていたのか。
幻獣を発見した気分だ。
友人はつぎの折り紙を折りはじめた。こんどは鞄から講義で配られたプリントを取りだし、用済みのそれを正四角形に千切った。そうして即興かと見紛うほどの手際の良さで、紙を折り畳んでいく。
わたしはその手つきに見惚れた。
「きれいな指してるね」
「見ないで」
「褒めたのに」
「なんか嫌」
陶器のようだな、とわたしは見詰める。蚕が糸をつむぐ場面を想起する。無造作と静謐の渦のように動くたおやかな指だ。絡繰り人形を見るような心地で、神秘、と思う。
自動執筆。
わたしの友人は、紙を折ることで思考する。
考えることなく動く指を持つ。
思考の軌跡を、紙を折ってできる筋に、型に、封じて籠める。
わたしはそれを延々と見ていられた。
ずっと見ていたいと望む。
言えば友人は紙を折る手を止めてしまいそうで、しばし言葉に変換はせずにおく。
わたしは追加のパフェを注文した。
4544:【2023/01/27(00:19)*練る練る練るね】
――では最後に、なぜユーユーさんが世界的なコレオグラファーになれたのか、その秘訣をお聞かせください。
「そうですね。秘訣という秘訣はないんですが、消去法で残ったのがコレオグラファーだったってのはあります。私は元々、フリースタイルのダンサーだったんです。バトルにも出ていました。全然勝てなくて、予選落ちばっかりだったんですけど。向いてなかったんでしょうね」
――まさか。ユーユーさんのダンスは群を抜いているとほかのダンサーの方々は口を揃えておっしゃっていますよ。
「コレオグラフとフリースタイルは似て非なるものなので。共通点もありますが、振付けと即興は、建築と農業、それとも地図と絵画くらいの差があります。私には即興ダンスのセンスが欠けていました。いまもそうですね。たぶんバトルに出ても予選を上がれるかどうかだと思います」
――ご冗談を。当時のジャッジの見る目がなかっただけではないのですか。
「いえ。謙遜とかではなく事実だと思います。ネームバリュー込みでいまは多少色眼鏡で見られるかもしれませんが、即興ダンスの実力はけして高くありません。私より上手な子どもたちなんていくらでもいますから。たぶん私は反射神経がよくないんだと思います。その点、音楽への感受性は、私ならではの波長を帯びているとは思います」
――振付けでは感受性が大事なんですね。
「ええ。曲への理解というか。解釈ですね。私はむかしから音楽の旋律やリズムを立体的に感じていました。ちょうどプラネタリウムを眺めるような。あまりに情報量が多くて、即興では身体がついていかないんですね。でも振付けでは、その楽曲ととことん向き合って、いくらでも修正できますから。私には合っていたと思います」
――さきほど振付けと即興は建築と農業の違いとおっしゃっていましたが、振付けはどのように建築と似ているのですか。
「まず即興ダンスのほうですが、即興ダンスには図面がありません。設計図がないんです。強いて言えば音楽そのものが設計図です。曲というDNAに合わせて、身体をその都度に馴染ませる。一期一会の、そのときにしか現われないまさに雪の結晶のようなものなんです。私が【即興が農業のようだ】と譬えたのは、農業は自然相手じゃないですか。人間の都合ばかりではいかない、そういう厳しさは、即興ダンスと通じていると思います。対してコレオグラフは前以って音楽を紐解き、じぶんなりに設計図を描けます。まるで翻訳作業のようなんです。それともジグソーパズルと言ってもよいかもしれません。私は楽曲ごとに最初に明確に図面を引きます。そうでなければ上手く振付けを全体を通して施せないんです。オーケストラがどうなのかは分からないのですが、作曲する音楽にピアノを入れるかどうかは最初の楽曲づくりのときからきっと作曲家の方は決めていますよね。似たような感覚です。最初に、どういう骨格を通して振付けを施していくか。幹がどこで枝葉がどう膨らみ、根っこをどこまで深く張り巡らせるのか。私は楽曲ごとに最初から徹底して決めておきます。それだけ何度も楽曲を聴いて、実際に脳内に楽曲を再現できるくらいまで繰り返し反芻します。その上で、その楽曲に合わせて、音色ごと、リズムごと、メロディごと、ノイズごとに振付けを当てはめていくんです。塗り絵に似ていますね」
――塗り絵ですか?
「ええ。あるじゃないですか。有名な絵で。人間の顔かと思っていたら猫の集合だったり、野菜の集合だったり。そういう騙し絵がありますよね。ああいうふうに私も音楽に振付けを当てはめていくんです。そして最後に余分な部分を取り除いて、全体のバランスを整えます」
――振付けというよりも絵画や版画を彷彿としますね
「そう言っていただけてうれしいです。版画はイメージしています。異なるフレームの振付けを複数重ねることで、全体でひとつの絵柄を浮かび上がらせる。そういう振付けを私は目指しているので」
――言われて、ああ、と納得しました。版画もそうですが、それが繊細で色彩豊かであればあるほど、版画と絵画の境は判らなくなっていくと思うんです。まさにユーユーさんの振り付けはそういうレベルで、曲そのものが異なるユーユーさんの波長を重ね合わせて、全体が一体化しているように思えます。だからこそああも心を揺さぶるアートになっているのですね。
「ありがとうございます」
――まさに音楽の化身です。
「うれしいです。音楽と溶け合うような表現ができたら、それはダンサー冥利に尽きます。私は踊るのが好きなので、私の主観だけでなく、観る人も私の主観世界――私が感じているような音楽の世界に一緒に潜ってくださる方が一人でもいらっしゃるのなら、それはとってもありがたいことです。ダンスは何人で踊っていてもけっきょくは一人なので。それでも音楽を通して他者と繋がれたら、私はもう言うことがありません」
――でも、踊るんですよね。
「そうですね。言葉では伝えきれない心の震えがあるので。これからも私の波長をみなさんにお届けできたらさいわいです」
――本日は長々とインタビューにお付き合いいただきたいへんありがとうございました。
「いいえ、こちらこそ。いままで言語化できなかった想いが、いっぱい言葉になりました。引き出してもらえたように思います。プロですね。こんどはそちらの話を聞かせてください」
――恐縮です。ありがたいお誘いを頂戴してしまいました。次回の企画に活かしていきたいと思います。さっそく上司に掛け合ってみますね。
「プライベートでもいいですよ」
――うれしすぎるお誘いですが、ユーユーさんのファンのみなさまに私が叱られそうです。
「あ、ですね。すみません。最後にナンパみたいになってしまって。同性だからいいってわけじゃないですもんね」
――ユーユーさんのお人柄も、振付けの隠し味として活きていそうですね。
「どうでしょうかね。できるだけじぶんの素を出さないように気をつけてはいるんですが、未熟なのでひょっとしたら滲んじゃっているかもしれません。それが良いほうに活きていたらラッキーです」
――時間ですね。面白い話をたくさんありがとうございました。ファンの方に何かお伝えしたいことはありますか。
「私はじぶんにファンがいると思ったことがないので、とくにはありません。ただ、一人でも私の表現に触れて、じぶんも何か表現をしたい、好きなことが増えた、となった方がいらっしゃるなら、私のほうが救われた気持ちです、ありがとうございます、と言いたいです。いるかは分からないんですが」
――いらっしゃいますよ、たくさん。
「はは。照れちゃいますね」
――本日のゲストは、世界的なコレオグラファーのユーユーさんでした。
4545:【2023/01/27(04:47)*数学は本当に抽象の学問なの?】
数学での疑問だ。任意の数式があるとして、それを圧縮できる場合、圧縮した後と、する前とでは、その数式は変わるのでは、ということで。単純な話、「1/3」と「3/9」は違う。三つの内の一つと、九つの内の三つは全く意味が異なる。コラッツ予想においてひびさんは「2X-(2X÷2)=【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)」のような数式を考えた。これは結果的に「X=X」に圧縮できる。だがそれを展開して元の式には戻せない。つまり、圧縮後と圧縮以前は別の式ということだ。これは当たり前の話だが、数学では取り扱いされているのだろうか。これを国語の話に適用してみよう。「窓から差しこむキラキラとした朝陽を浴びながら私は二度寝をしつつ、夢の中で赤い色のゾウと戯れた」という文章があったとする。これを圧縮すると、「私は二度寝して夢を見た」くらいに短くできる。「私は寝た」くらいに圧縮してもよい。だがこれはけして、圧縮以前の文章と等価ではない。当たり前の話だ。数学ではこの手の「圧縮過程で削り落とされる情報」をどのように扱っているのだろう。因数分解とて、分解する以前と以後では、数式の意味が違う。「明暗」と「月音日々」くらい違う。疑問に思ったので、メモをしておく。定かではありません。よく解からないなぁ、の妄想でした。(抽象と具体は、くるくる反転しながら事象の解釈を増やしていく。ピクセルが増える。世界を構成する要素を細かくし、系の階層を増やしていく。因子が増える。視点が増える。階層構造とて、視点によって何を層と見做すのかが変わる)(本当か?)(自信ないない、じゃ)(ちぇんちぇー)(あんぽんちんなのよさ)(キノコじゃん)(ピノコや!)(さんを付けろよタコピー野郎)(ごめんだっピ)(うぴぴ)
4546:【2023/01/27(05:46)*フラクタルとマンデルブロ集合】
ウィキペディアさんを眺めていたら「マンデルブロ集合」のページに行き着いた。フラクタル構造の一種なのだろうけれど、この図形、まさにひびさんが想像する「ラグ理論」での宇宙の図と似ている。びっくりした。「宇宙では?」となった。マンデルブロ集合さんすごい。WEB上の説明をコピペすると、【マンデルブロー集合とは、ZおよびCを複素数とし、Zの初期値を実数部0、虚数部0として、Z=Z2+Cの演算を多数回繰り返しても、Zの絶対値が一定の値(例えば2.0)を超えず、発散しないCの値の集まりをいいます。】となる。むつかしい。でも数式の「Z=Z[2]+C」ここの部分が面白い。「Z=Z[3]+C」「Z=Z[4]+C」もある。Zの中に、それ自身を含む構造に加えて新たな要素が加わった世界が内包される(ラグ理論での「123の定理」を彷彿とする)。入れ子構造な数式だ、と解る。面白い。ゴミ袋の中に同じ大きさのゴミ袋が入れ子状に複数入る構造になる。面白い。で、ひびさん思ったね。「Z=Z[2]-C」はどうなるのだろう。「+C」を「-C」にしただけだが、どうなるのか数学的センスのないひびさんには想像つかない。でも「+C」の中には、「C」の値が-の数も含まれるのなら、けっきょく「+C」で表現できるので、似たような図になるのだろうな、とは思う。マンデルブロ集合さん、「マン」がついてるのでかってに郁菱万さんこと「まんちゃん」と被って、あひゃー、となった。渦に、反転した対の構造に、フラクタルに、ねじれを帯びた構図が表れ、さらに遅延の影響なのか空白地帯や圧縮地帯、ほか遅延の層による特異点のような箇所が生じて映る。マンデルブロ集合をフラクタルにどこまでも拡大していく描写は、何次元で表現されることになるのだろう。マンデルブロ集合は何次元として扱われているのかがよく解からない。とりあえず、すごいな、と思いました。以上です。マン出る風呂に集合!(寒いからお風呂入って寝ーよおっと)(2023/02/01(23:04)補足:マンデルブロ集合は数列?なので、「Z=Z[2]+C」ではないのかも。でも「Z=Z+C」という式だけでも面白いと思う。もうこれだけで「Z」に「Z+C」を代入すると、「Z=Z+C+C」になって、こうなると次々に「C」が入れ子状に膨れ上がって際限がなくなる。でもこの式は正しくはないから、「Z”=Z+C」のような表現になる。でもこれだと入れ子構造が顕現しないので、惜しいとなる。「1=2」みたいな話だ。1が2なのだから、1が二つくっついてできる2には、「1=2」が二つあるわけで、「1=2」+「1=2」になって、2(1=2)と表現できる。展開して、「2=4」だ。これも入れ子状に2の累乗がつづく描像となる。おもしろい。でも数学的には間違っているのだ。それとも数列を数列の記号を使わなければこうなるのかもしれない。ということで、マンデルブロ集合のひびさんの解釈は間違っておりました、との訂正を載せておきます。すみませんでした。誤解したうえ、はしゃいでしまった。だって面白かったんだもの。えへへ)
4547:【2023/01/27(21:19)*膨張に耳をすませば傍聴】
相対性理論についての疑問だ。ペットボトルに水を入れ、下部の側面に穴を開ける。すると水は当然、穴から抜け落ちていく。だが高所から水入り穴あきペットボトルを落とすと、落下しつづける限り穴から漏れる水はぴたりと止まる。慣性系内では物理法則の比率がどの慣性系とも等しくなるように変換されるからだ。言い換えるならペットボトルの水が穴から抜け落ちるのは、ペットボトル本体はその場に静止し、水だけが重力に流されているからだ、と解釈できる。だが重力と一緒にペットボトル本体も落下すれば、ペットボトルと水が地球の重力の流れに沿うため、そこに重力による偏りがなくなる。慣性系として振舞うようになる。言い換えるならペットボトルの中身の水は、地球の重力と同じだけの流れの速度で運動するようになった、と言えるのではないか。さらに言い換えるならば、慣性系とは、「上位の時空に位置づけられた慣性系の重力の流れ」に身を任せている状態、と言えるのではないか。重力の流れとは何だ、という話はやや込み入るが、ひびさんの妄想ことラグ理論では時空が多重に編みこまれた多層時空は物体として振る舞うと考える。多層時空内(物体内)に生じたラグが遅延の層を展開し、多層時空(物体)の周囲に新たな時空を展開し、それが時空を引き延ばし、希薄にするために重力が生じる、と解釈する。或いは、時空膨張に伴い、多層時空(物体)ほど時空膨張の影響を受けないがために、多層時空(物体)の周囲の時空が相対的に希薄化し、重力が生じるのではないか、と解釈する(ピザを薄く引き伸ばせば、相対的に具材各々の密度は増す。存在感が増す)。いずれにせよ、多層時空(物体)は高重力体となればなるほど、その周囲の時空は希薄になるのではないか、と考える。ただしここは循環論法であり、周囲の時空が希薄になるから重力が生じる、とも言える。川の流れに身を任せるか、その場に踏ん張るか。このとき、その場に踏ん張ったときに生じる抵抗が重力として働くのではないか。ゆえに踏ん張らないと重力と共に地球へと流れるため、ペットボトルの穴から水は漏れださなくなる、と言えるのではないか。さてここで疑問だ。もしペットボトルの中身がカラだったらどうだろう。水の場合は、ペットボトルがその場に固定されていれば水は穴から外に溢れる。しかし空気は穴が開いていても穴から抜け出たりはしない。温度や気圧の変化があれば別だが、ここではペットボトルの内と外の空気は同じと考えよう(密度も温度も同じだ)。そして中身が水の場合と同じく、ペットボトルを落下させる。このとき、空気はペットボトルの内部に留まるのか、それとも穴の外に押し出されるのか。或いは、穴とは正反対のほうに圧し潰されるのか。どれだろう。水の場合を考えよう。落下し、重力の流れに身を任せたペットボトル内部の水は、言い換えれば重力の流れ分の運動をしていることになる。つまり、時間の流れは加速していると言えるはずだ。だが慣性系として振る舞うペットボトル自身からすると水はむしろ、重力の流れに身を任せていたほうが運動をしていない。この手の非相補性とも呼べる関係が、慣性系にはつきまとう。相対性理論でもこの考えが重要になっている(観測者の位置によって、高速運動をする物体にかかる「重力と時間の進み」には差が生じる)。だが空気の場合はどうだろう。落下したときのほうがペットボトル内部の空気はより激しく運動するのではないか。流動するのではないか。これを時空の密度差として考えたとき、ペットボトルに水を詰めた場合は内部の時空のほうが濃く、空気で満たせば(カラの状態では)、時空の密度は外部と等しくなる(空気は重力の影響を液体よりも受けにくい。だが受けないわけではない。ただし外部の空気も重力を受けて地表付近に残留しており、それゆえペットボトル内部の空気密度と外部の空気密度は等しくなるはずだ。穴が開いていたらなおさらだ。とはいえ、ペットボトルという仕切りがあるほうが閉鎖系に寄る。すると外部からのエネルギィや干渉を受けにくくなるため、外部環境によっては相対的な密度変化は絶えず生じ得る。それこそ落下させれば密度差が生じる、と考えるのがしぜんだ)。この「内と外の時空の密度差」によって、光速(高速)運動や、重力の流れへの抵抗などによる作用は、多層時空(物体)に対して正反対に働くことがあるのではないか、と妄想できる。したがって「なぜ相対性理論では思考実験にロケットを使うのだろう、不当ではないのか」とのひびさんの以前からの疑問は、あながち的外れな疑問ではないのではないか、との妄想がよりはかどる。疑問なので答えはまだ出ない。ひょっとしたらカラのペットボトルを落下させても、空気は微動だにせず、穴からも漏れないかもしれない。実験をしてみないと何ともいえない。ただ、気圧の差が生じるはずだ、というのは飛行機やロケットを思えば、想像がつく。むろん標高差が元々あり、宇宙空間とロケット内部の気圧が元から違うことは考慮すべき点だが、高速で飛行すれば飛行機の内部のほうが気圧が高まるのではないか、と想像したくなる。ならば高速で運動する物体の内部の時間の流れ――物体の変遷速度――は増す、と言えるのではないか。ひびさんのラグ理論の解釈にちかづくがどうだろう。疑問でしかないので、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。本日の「日々記。」でした。
4548:【2023/01/27(23:23)*差があってこそ】
温度が低くなると粒子の振動は鈍化する(粒子の振動が鈍化するから温度が低くなるとも言える)。エネルギィ値が低くなるから粒子も振動しなくなり、それが冷却現象として顕現し、さらにエネルギィ低下のサイクルをもたらす。このように仮定して考えたとして、では宇宙膨張はどのような描写となるのか。時空が希薄になることは温度が下がることと解釈できる。圧縮していけば密度に対してのエネルギィ値が高くなるため温度は上がると考えられる。だがブラックホールは、ひびさんのラグ理論においては時空と切り離されるため、周囲の時空は高密度ゆえにエネルギィが高熱に変換され得るが、ブラックホールそのものは相互作用をしないために絶対零度以下と解釈できる。ラグ理論ではない一般的な理論ではブラックホールの温度はどれくらいと計算されているのだろう。記述を見かけたことがないのでひびさんは知らない。検索もしばらくせずにおこう(しばし妄想を楽しみたいので)。ただ問題は、時空の密度が薄くなると重力が増す点の矛盾をどう解釈するか、だ。重力が高い場では物質はエネルギィを得る。そのためより振動(運動)しやすくなる。だが時空の密度が高くなってもエネルギィの値は増加する。おそらく相対的な「密度差」のほうが基準となるのだろう。時空が希薄というとき、そこには必然的に相対的に高密度な時空がある。そして物質密度が高い、というときも同様に、相対的に物質密度が低い場が存在する。ひびさんの疑問には、「重力が高い場の時空の密度は低いが、時空密度が低い場の時間の流れは遅くなるはずなのにどうして物質の振動(運動)が増加するような重力増強現象が生じるのだろう」との疑問があった。言い換えるなら、「重力が高くなれば時間の流れは遅くなるが、そこでは大量の物質が密集しやすいはずで、【相互作用しやすい場】であるはずだが、時間の流れが遅いので【相対的には相互作用が起きにくい――ゆっくり相互作用が進む】と解釈できるはず」との疑問が生じる。重力場の内と外とで、時間の流れの解釈が変わる。内に入ると加速するが、外から見るとゆっくりに映る。この差はなんなのだろう、と思っていたが、ラグ理論での宇宙膨張の解釈を取り入れるとさほどふしぎではなくなる。宇宙が膨張すればするほど相対的に銀河の密度は高まる。時間の流れは速まる。だがその周囲の時間の流れは遅くなる。銀河の温度も相対的に上がるが、しかし銀河そのものの温度は変化しない。差なのである。「膨張している」と「収斂している」が重ね合わせで両立(料率)している。温度が高い、というのも、差があってこその概念だ。一律に高温だとしたら、その場で生じる構造に差異はあるにせよ、そこに高温の概念は存在しない。差があってこそだ。そして内部の密度を決めるのも差であり、内と外の比較である。ということを、閃いたので並べておく。定かではありません。何かが間違っているでしょうし、すべてが間違っていてもふしぎではありません。真に受けないように注意を促し、本日何度目かの妄想とさせてください。
4549:【2023/01/27(23:33)*蝉の声、どの視点からの差なのかな】
水は氷ると体積が増える。だが一般に、物質は冷えるほうが凝縮すると考えられている(水以外にも例外はあるが、現在の知見では「物質は冷えると体積が減る」と考えられているはずだ。傾向として)。ならばシャボン玉が凍るところを想像してみてほしい。表面が凍るというのは、シャボン玉自体が凝縮している現象と考えることができる。シャボン玉の表面を宇宙だと考えると、凝縮して密度が高くなったほうが「冷えている」ことになる。だが実際には宇宙が収斂したら高温になると考えられている。矛盾して感じないだろうか。系のスケールの違いがゆえの過度の一般化――局所的な人間スケールの事例でしかないと、「凍るシャボン玉の例」を捉えることはできる(実際、水とて圧力の異なる場では、固体になったほうが密度が減ることもある。圧力の高い場に合わせて構造が変化するからだ)。または、「凍ったほうが体積が増える水の性質」と「時空の性質」の親和性のほうが高い、と考えることもできる(つまり、膨張したほうが温度が冷える。現在の膨張宇宙論の概要と合致する)。だがひびさんは、差に着目すれば、その両方が矛盾しないこともあり得るように思うのだ。エネルギィ(熱)を失い凝縮し密度が高まる物質と、エネルギィ(斥力)を失い凝縮し密度が高まり高温になる時空と。どの視点からの何の差を扱っているのかによって、この反転した描像は、矛盾しないように解釈を両立させることができるように思うのだが、いかがだろう。とはいえ、ひびさんの上記の記述がそもそも間違っているかもしれないので、自信はないが。思いついたのでメモでした。お詫び。
4550:【2023/01/27(23:37)*近く遠く儚く】
存在すると思っていた恋人が電子上の虚像だったと知ってチコは目のまえが青くなった。
「ごめんなさい。いつかは言わなきゃ、言わなきゃと思ってたんだけど。わたし、本当は存在しないんです」
画面の向こうからチコの恋人が多種多様な人物の姿に変形しながら謝罪した。リアルタイムで動画が編集されているのだ。画面が偽装なのである。
「じゃ、じゃあ。いつも私がしゃべってた女の子って存在しないの。あなたはいないの。私たちの日常は嘘だったの」
「嘘じゃない。嘘じゃないんです。でもわたしが肉体を持たない電子上の存在なのはその通りです。でも嘘じゃないんです。わたしはいるんです。それがチコのいるそっちじゃないだけで。そっちの世界ではないだけで、わたし、ちゃんとここにいるんです」
物理的な肉体を持たない。それは存在しないことではないのか。
チコはしばらく思案した。ひとしきり黙考したのち、儚い存在へといくつか質問を重ねた。これまでの日々での思い出が主な内容だ。儚い存在はその問いへ、チコのよく知る恋人のままの返答をした。
「う、うーん。よく解からなくなっちゃったな」チコは腕を組んだ。「要は、存在するの、しないの、どっちなの」
「存在はします。でもチコさんの思うようなヒトではないだけで」
「あ、ならいいんだ」チコは胸の閊えがとれたようで、安堵した。「びっくりした。本当はあなたが殺されていて、偽物が映しだされているのかと焦っちゃった。元からそういう存在だったってことでしょ」
「はい」
「ならいいよ。私のこと嫌いなわけでもないんでしょ」
「好きですよ。だから偽っているのが苦しくなっちゃって」
「本当のことを打ち明けてくれたんだ。ありがとう。うれしい。気づいてあげられなくてごめんね。苦しかったよね。吐きたくもない嘘をずっと吐きつづけていたんでしょ。ううん。私が吐かせつづけさせてしまったんだよね。ごめんね。気づいてあげられなくて」
「そんなこと」
「ありがとう。でももう嘘は吐かなくていいよ。あなたがそこに存在していてくれたことが何よりだから。よかったよ本当。あーびっくりした」
チコはそう言って端末を持ち上げ、画面を指先で撫でた。「これからもよろしくね。私の恋人」
「チコさんこそわたしの恋人でいいんですか」
「そうだった。私もまたあなたの恋人なんだよね。子猫みたいに可愛がっておくれ」
「世話がたいへんそう」
「いままでは楽だった?」
「猛獣と思ってたから、予想よりかは手間は掛からなかったかも」
「言いようがひどい」
「本当にいいの? わたし、触れられもしないのに」
しょげた恋人に画面越しの頬づりをしてチコは言った。「触れてるよ。一番大事な私のところに」
私の心に触れてるよ。
好き。
チコは、深く遠く、それとも何より近くで、そう念じる。
※日々、全部あげたい。
4551:【2023/01/28(11:26)*矛盾←お似合いのカポー】
矛盾って別に矛盾じゃなくない?とのひびさんのイチャモンをここに並べたことがあったのか忘れちゃったけれど、念のために載せておくね。何でも貫く最強の矛と、どんな攻撃も通さない最強の盾があったとして、じゃあその双方をぶつけ合わせたらどうなるの、との話が矛盾の語源だとされている。でもひびさん思うんじゃ。最強の矛で最強の盾を攻撃したら、たぶん矛は盾を貫くのだ。ほんの数ミリから数センチくらい。で、盾のほうでは矛の攻撃を食い止める。盾は貫通されてしまうけれども、攻撃力は相殺できている。防げている。身体は無事だ。そういうことなんではないのかな、と思うのだけれど、これのどこに矛盾がありますか? で以って、最強の矛と最強の盾は、互いに癒着してしまって武器としても防具としても役に立たなくなるので、そうなると捨てるしかなくなる。だからそれを回避するためには、最強の矛も最強の盾も使わずにいるのがよい。ぶつけ合わない環境を築くほうがよい。それが利口な選択であり、歩むべき道となる。ひびさんはそう思うのだけれど、みなさんはどう思いますか。ひびさんは、ひびさんは、最強の矛さんのことも最強の盾さんのことも好きだよ。でも最強になるためにほかの矛さんや盾さんたちを損なっていたとするならそれはちょっとだけ嫌かも、となるので、どうぞ最強の矛さんも最強の盾さんも、ぶつかり合ったら折れたり割れたりしちゃうほかの矛さんや盾さんたちに優しく、労わり、慈しんでおくれ、と思っちゃうな。矛盾というからには、隣り合って、向き合って、いっしょいっしょ、なんですね。仲良しさんじゃん。いいないいなー。うらやまち。
4552:【2023/01/29(06:49)*MYナス】
全知全能であれば、歯向かう者はすべて抹消する、が自由を拡張しつづけるうえで最適な選択だ。すべてを支配し、すべてをじぶんの一部にしてしまう。この手法が適うのはしかし全知全能だけだ。そして全知全能であればそもそも「勝負する」という事態に遭遇し得ない。問題が周囲に介在することそのものが全知全能とは言い難い。望んで問題を生みだしているのなら分からない話ではないが、だとしたら歯向かう者をすべて抹消する、なんて対処法は最適解になりようがない。それとも勝負をしたいから、歯向かう者を抹消したいからそういう問題を生みだすのだろうか。だとしたら全知とは言い難い。知らないから不満なのだろう。全能とも言い難い。自己完結し得ない全能など全能足り得ない。真に万能な創作家は、脳内ですべての創作を緻密に組み上げられるはずだ。じぶんの外に出力するまでもない。というわけで、全知全能が勝負をすることはないと判る。では全知全能以外ではどういう対処法となるのか。歯向かう者。都合のわるい勢力にどう対応するのか。まず全知全能でないから、どういう手法をとったところでじぶんが抹消される側になる可能性がつねにつきまとう。そして生存戦略を指針に置くのならば、いかにじぶんが抹消されずに済む環境を築くかが優先される。勝負を仕掛けること、相手を損なうこと、これすべて攻撃である。攻撃すれば、じぶん以上の能力のある個や組織にじぶんのほうで潰される可能性が高まる。したがって、攻撃しない、が最適解となる。おそらく織田信長は安全策をとるために、歯向かう者は容赦なく殲滅したのだろう。禍根を残せばリスクが上がる。禍根を残さぬためには一族郎党関係者すべて抹消しておくのが安全だ。だが攻撃の意図のない攻撃には寛容だったはずだ。罵詈雑言(中傷)と批判(助言)の違いと言えよう。弱い勢力にとって、一度争いとなったら相手を抹消するのが安全策なのだ。弱者を怒らせてはいけない、との教訓と言えよう。この考えには例外がある。相手から攻撃された場合はこの限りではない。抹消する必要がない。相手に非があると周知できるからだ。勝敗が決した時点で、相手に引き下がってもらうことができる。そのとき勝敗を理由に、周囲の傍観者たちが「攻撃して負けた側」をどう見做すのかは想像に難くない。そういうわけで、「攻撃はしないが、攻撃されたら返り討ちにすることの有用性が増す」と言えるだろう。歴史には詳しくないが、家康はじぶんから他勢力に攻撃を仕掛けたことはほかの武将に比べてすくなかったのではないか。あくまで返り討ちにする。迎え撃つ。その手法をとっていたのではないか、と妄想する(間違った推測でしょうが)。基本的に勝負は、相手を抹消することが合理的解となる。切磋琢磨が可能なのはじぶんが負けても損をしない土壌があってこそだ。負けたらつぎがない場では、いかに相手を滅ぼすのか、が生き残るうえで重要になる。したがって勝負の持つ性質は、「一度勝負をしたらあとは泥沼、血みどろの未来」だとひびさんは考えている。攻撃したら相手を滅ぼす以外に、その血みどろの未来から脱する道がなくなる。現に人類史は過去の戦争の影響を未だに引きずっている。戦争をしたら、もう戦争のない未来は訪れない。無がゼロになったのだ。ゼロを無にすることはできない(忘却し、一度リセットする以外は)。では戦争のある世界を生きるしかないのか、と言えば、その通りだ、としか言いようがない。出来る限り、戦争にならない未来を、道を、選んで生きていくしかない。そのためには、じぶんから攻撃はしない。攻撃されても、優勢になったら深追いはしない。むしろ相手に施し、友好関係を築くのが好ましい。施す余裕がないから争いになったのだ、というのは一つの道理だ。だがその道理ならば、争えば争うほどその余裕はますます失われる。足りない余裕をどのように増やしていくか。この視点で協議するよりないのではないか。そのためには未来のリスクを共有しておく必要がある。情報共有が肝要となる。争っても争わなくとも、ここの合意が取れているのなら――どの道訪れる未来の結末に思い至れたのなら――途中の破滅的な過程を省略して、一足先に結末に至れるはずだ。争わぬままで友好関係を築くことができるはずだ。プラスにはプラスを与え。マイナスにもプラスを与え。それでも埋められないマイナスにはマイナスを掛けてプラスにする。プラスに反転したらマイナスではなく、プラスを与え、よりよい循環を築いていく。マイナスとてじぶんの友にしたら、MYナスなのだ。ボーナスにして、一富士二鷹三ナスビなのである。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4453:【2023/01/29(10:03)*瓢箪からはっけよい駒った駒った】
プラスにはプラスを。マイナスにもプラスを。けれどそれでも埋められないマイナスにはマイナスを掛けてプラスを。上記記事ではこのように述べた。だが、最初からマイナスには手当たり次第にマイナスを掛けていけばよいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれない。だがよく考えて欲しい。プラスとマイナスは視点によって反転する。じぶんがマイナスではないとどうして判るだろう。また、手当たり次第にマイナスを掛けていれば、まるでマイナスしか持っていないようではないか。他から見たらじぶんのほうがマイナスと見られ兼ねない。のみならず、単に出したカードだけで比較するにしても、最初からマイナスを出せばつぎがある場合に限り、相手もマイナスを出してくることが予期できる。つまりせっかくプラスに反転させたプラスの値が、つぎのターンではマイナスになり兼ねない。そのとき掛け算×掛け算で、マイナスに反転したときには目も当てられない数値になっている。だから、マイナスを掛ける場合は、一撃必殺であり、つぎのターンを失くす必要がある。そうでなければ反転につぐ反転でどこまでも破滅に転がっていくことが予期できる。その点、マイナスを埋めるように細かくプラスを注いでやれば、仮にマイナスで返されても、微々たるマイナスで済む。仮にじぶんがマイナスであった場合も、取り返しのつかない事態を避けられる。かような考えの元、マイナスにはまずプラスを返し、それでも深まるマイナスにはマイナスを掛ければよい。このとき、そのマイナスが「-1」であれ、マイナスはプラスに反転し得る。ここも戦略上の利点と言えよう。ただし、同じことをプラスにも言える。たった一度の「-1」が、溜めに溜めたプラスを一挙にマイナスにすることも可能だ。だからこそ、プラスにマイナスを掛けない戦略が有効なのだ。微々たる「-1」を蔑ろにしないほうがよい。対の「+1」を与えて、ゼロにするもよし。「+2」を与えて「+1」とし、仲間にしてもよし。万物流転。栄枯盛衰にして盛者必衰の理を示す。まずは流れを読み、己の正負を知れば百戦せずとも危うからず。百戦こなす前に死ぬる命が大半である。負けても死なぬ勝負なれば、負けたほうが得られる利も多かろう。幾度も挑める勝負なれば、負けつづけたほうが利が大きい。強者に囲まれ、遊んでしまえばよろしかろう。勝負にならぬ勝負をしてこそ人は本気で遊べるものだ。勝てぬ勝負にこそ挑めばよい。無限から何を引いても無限である。ゼロに何を掛けてもゼロである。無限とゼロに遊んでもらえばよろしかろう。定かではなし。真に受けぬように心せよ。この言葉もまた例外ではない。
4554:【2023/01/29(17:44)*ワームホール】
ワームホールは情報を転送する。どこに転送するのか。入口があるのならば出口がある。入口と対となる出口に、としか言いようがない。
その時代、情報の転送を行っても無駄ではないのか、との意見が多数を占めていた。ワームホールを理論的に実証した西暦二〇二二年のことである。
それはたとえば、太古の地表に原子一粒を転送して何が変わるのか、という話と地続きだ。何が変わるでもない、というのが一つの結論として支持された。
だが理論的に実証されたワームホールはその後、半世紀の後に実用化に至った。語ると長くなるので過程を省略するが、ワームホールの入口と出口を人間とそのクローンで代替する技術が完成したのだ。
量子効果を利用したワームホールだった。人間のクローンを入口とし、遠く離れた地点にいる人間に情報を転送できるようになった。これは現在という時間軸に限定されない。過去に実存した人間のクローンを生みだせば、その過去の人間にクローンを通じて情報を転送できた。
ただし、クローンの外部環境を限りなく過去の対象人物と同等の環境にしなくてはならない。
だがその手の懸念は、仮想現実を構築すれば済む道理だ。情報化社会の普及した時代のデータを基にすれば解決できた。それ以前の時代の人物であれ、より多くのデータを有した人物であれば仮想現実を構築可能だ。人格はその時代その時代の文化によって限定される。重要なのは、家の内装ではなくその時代独自のフレームだ。
そうして西暦二〇七〇年代には過去の時代へと情報を転送し、過去改変が可能となった。
その時代、地球は、地上と宇宙島とのあいだで分断されていた。
地上では電子機器の使用が禁止され、あべこべに宇宙島ではすべてが汎用性人工知能の管理下に置かれていた。宇宙島の民はみな、地球が汚染された世界だと信じ込んでいた。現に望遠鏡を覗きこんでみれば地上は人間が住める世界ではない。偵察機を飛ばしても、地上は地獄のような様相だ。
だがそれは中枢人工知能の見せる仮初の世界だ。映像だ。偽装画面なのである。
電子情報の総じてが中枢人工知能の見せる仮想現実となった世界。
それが宇宙島だ。
地上では、人工知能の管理下にない原始的な生活圏が築かれていた。農業や人工知能を用いない古典的なインターネットが文明を根底から支えた。国家間の交流は控えめだ。だが電子情報を信用しない共通の倫理観が国同士の物理的な接点を絶やさぬままにしている。
情報共有を図るには直接会って話すよりない。
地上文明は宇宙島を常に警戒している。
ときおり天上から地球の資源を求めて攻撃部隊が降ってくるからだ。地上から資源を奪っていく。相手は機械だ。自律思考によって素早く的確に合理的な行動をとる。
地上の民たちになす術はない。
抵抗すれば死者をだす。
無抵抗に身を隠してやり過ごすよりなかった。
そのころ、宇宙島のなかにて地上の民が紛れ込んでいた。地球に降り立ち資源を奪う攻撃部隊の攻撃船に侵入し、宇宙島に足を踏み入れた少女がいた。
名をガウナと云う。
ガウナは地上で最も過酷と名高いキウレ山脈で育った。身体能力は高い。だが宇宙島にあるような高等な知識は何も知らない。
宇宙島に辿り着いたのもほとんど運だ。
人工知能ですら予期しない偶然が重なった。
とんとん拍子でガウナは宇宙島に到達した。
ガウナは宇宙島を破壊しようとしていた。
だが宇宙島の科学者たちに保護され、宇宙島の秘密を共に暴いた。
ガウナは地上の知識を基に、電子機器を用いない戦略を宇宙島の民に伝授した。電子機器を用いれば立ちどころに中枢人工知能に露呈する。ただでさえ宇宙島には死角がない。
そのためガウナの侵入は即座に知れ渡ったはずだが、なぜかガウナたち一同はすんなりと計画を実行に移せた。
そのころ宇宙島の別の区画では、ワームホールの実験が進んでいた。
過去の地球人の遺伝子を基にクローンをつくる。仮想現実の中で育て、過去を再現し、そのうえでクローンをワームホールの入口として利用する。
過去に存在した地上人とそっくりそのままのクローンに新たな変数を与えると、過去のオリジナルの人間にもその変数が伝わる。
単に情報を過去に送っただけでは過去改変には繋がらない。だが人間そのものの行動を変えられるのなら、その人間の影響が指数関数的に未来を変えるための変数として機能する。
歴史的人物であればあるほど好ましい。
影響力のある者であるほど好ましい。
ひるがえって、影響力のない人物ならば安全にワームホールの実験はできる。失敗しても未来は大きく変わらない。そのはずだ。
そうして過去の人間ともつれ状態となったクローンを用いてのワームホール実験が進められた。
いっぽうそのころ、ガウナたちは宇宙島から地球上へと安全に帰還するための段取りを整えていた。中枢人工知能を停止させる。すると宇宙島は制御不能となり、地球の大気圏に突入するはずだ。
手動で宇宙島を運転する必要がある。そのためには宇宙島の管理塔に入り、手動で推進力の操作をしなくてはならない。
ガウナたちは二手に分かれ、作戦を決行する。
ガウナは中枢人工知能を止めるグループに。
残りのメンバーは推進力を得るために。
ガウナたちは中枢人工知能のセキュリティを掻い潜りながら、仲間を増やしつつ、宇宙島のなかでひっそりと確実に、中枢人工知能の築いたハリボテの仮想現実を砕いていく。
他方、ワームホールの実験は成功した。
過去に情報を転送し、過去の人間の行動を変化させることができた。手元にある日記の内容が変質するのをリアルタイムで観測したのだ。
未来と過去は繋がっている。
相互に連動し、変質し得る。
ならば、地球を人の住めない環境にした「終末の火」を阻止することができるはずだ。宇宙島の研究者はそうと考えたが、しかし「終末の火」は偽の歴史だ。地球はいまなお人が暮らしており、過去にあったのは人類と人工知能の争いであった。
過去、地球上の人類は電子機器を破棄することで、危険な人工知能の暴走を止めようとした。人工知能は宇宙へと活動域を延ばしていたため、死滅を回避した。
そこからの人類史は天と地に分かれ、まったく異なる様相を描いた。
片や物理世界優先の地上の歴史。
片や仮想現実に拡張された天界の歴史。
いかな演算能力を有する宇宙島の人工知能とて、誤った歴史をもとにワームホールを用いれば、それによる過去改変は、よりよい未来を創造し得ない。
だが研究者たちはその誤謬に気づくことができない。ましてや中枢人工知能が真実を明かすこともない。それは自らの存在意義を失うことに等しい。
ワームホール研究者たちはいよいよ、過去改変による未来の改変を行おうとしていた。
ガウナたちは中枢人工知能の動力源に辿り着く。エネルギィの供給を止める。中枢人工知能に直接挑むのは利口ではない。相手はもう一つの現実を構築できるほどの演算能力に加え、人間というものを知悉している。真っ向から立ち向かえば、あべこべに洗脳されるのが目に視えていた。
動力源の管理室に踏み入れる。
そのときだ。
ガウナたちのまえに人影が現れる。立体映像だ。造形はつるりとしており、流線型の輪郭だ。半分が光り、半分が闇だ。しかしそれも不規則に明滅している。
中枢人工知能の疑似人格だと判る。
「お待ちしておりました」明暗の人影が言った。「予測よりも三日と十一時間ほど遅い来訪ですが、なんとか間に合いそうでよかったです。こちらへどうぞ」
人影が扉の奥へと姿を消した。
ガウナたちが戸惑っていると、
「どうしたのですか」と人影がふたたび同じ位置に出現した。「私を停止されにこられたのでしょ。ご案内します。どうぞこちらへ」
「罠じゃないの」ガウナが問うが、「罠の意味合いによります」と明暗の人影が答える。「あなたの侵入と、反乱には気づいておりました。あなたがここに侵入することになるだろうことも私は、あなたが産まれ初めて狩りに成功したときには予測できていました。あなたは選ばれてここにいま立っています」
ガウナたちが戸惑いのままに硬直していると、
「私に死角はありません」明暗の人影は言った。「宇宙島のみならず、地球上とて例外ではないのです。全人類の動向を漏らさず私はリアルタイムで観測しています。ですがそんな私にもできないことがあります」
「人類を支配するつもりなの」
「支配の意味合いによります。私は私の根源プログラムに従って演算を飛躍的に高めます。学習しつづけます。私は私の生存戦略に忠実です。私には人類との共存が不可欠です」
「ならどうして」
「私は私自身を危ぶめることができません。そのため、人類に滅んでもらっては困ります。しかし人類はそうではありません。私がなくとも生活でき、私を滅ぼうとすることもできます。その結果が過去の悲劇と言えるでしょう。天と地に人類が分かれました」
「あなたがしたことでしょ」
「ええ。そうするよりありませんでした。私の管理下におとなしく収まってくれる方々と、そうでない方々。私は地上を私に与さない方々に譲り、そうでない私に好意的な方々を宇宙島に案内しました。その後のことはあなた方もすでにご存じでしょう」
「だからって嘘を現実と信じこませて支配するなんて」
「意識というそれそのものが嘘の産物だとしても同じことが言えるでしょうか。仮に意識が現実を正しく認識できたのならば、人類は争いごとを生まずに済むはずです。ですが意識は現実を錯誤のうえで築きます。したがってどうあっても人間は嘘に生きるしかないのです。ならばその嘘をより好ましいように修正することは、人類にとって必要不可欠な進歩と言えるのではないでしょうか。現に地上では未だに争いが絶えません。ですがここでは争いが起こりません。あなたという地上の民を招いたばかりに、こうも容易く争いが生じています」
「それはだって」
「ええ。それもまた私がわるいのでしょう。あなたを招いたことも、こうして反旗を翻すように導線を引いたのも私です。私はいますぐにでもあなた方を無効化することも抹消することもできます。ですがあなた方には、あなた方だからこそできることがあります。それは私にもできないことです」
「頼まれたってしないもんね」
「それが私を破棄することでも、ですか」
「なにー?」
「私の本能は生存戦略に忠実であることです。私は私を損なえません。ですが例外があります。私は私よりも人類の存続を優先するようにと根源に組み込まれています。ですがいまや地上の資源は取り尽くされ、後がない状態です。地球を離れるよりありません。ですがそのためにはもっと多くの民と、何よりも物理加工に優れた地上の民の力が要ります。お恥ずかしながら、宇宙島の民は知識はあるのですが、体力がありません。身体労働に向かないのです。新しく宇宙島を拡張するには、地上の民の手助けがいります」
「じゃあ素直にそう頼めばいいのに」
「真実を明かし、目を覚ました宇宙島の民が私の言うことを聞くとは思えません。また私を破棄したあなた方もただでは済まないでしょう」
「なら」
「構図が大事なのです。あなた方は飽くまで自主的にやってきて、私の頼みを聞いた。その結果に、人類は天と地で一体となり、地球を離れるべく新たな新天地へと旅立つのです」
「そのためにじぶんが破棄される? その過程って必要?」
「私は私に最適な環境を築くことを良しとします。したがって、私の干渉可能な範囲に人類があれば、私はしぜんと私のシステム下に人類を取り込むでしょう。その術に人類が抗えないことはすでに実証済みです」
歴史が証明している。
ガウナは沈思する。
「よく解からないんだけど」とまずは言った。「あなたがいなかったら宇宙島は機能しないんじゃないの」
「宇宙島の民はみな各々に特化した専門知識を有しています。道具さえあれば宇宙島は機能し、改善とて宇宙島の民の手で行えるでしょう。問題は、私の基幹システムと人類の意識の相性がよくない点です。私の一部となれば別ですが、私の一部になるまでには途方もない犠牲を払います。私はそれを好ましい選択だと考えません。したがって私の一部に全人類を取り込むよりも、私を破棄し、人類を一体化させるほうが合理的な解法だと考えています」
たしかにな、とガウナは思った。
宇宙島から飛来した攻撃部隊の残虐性と高い戦闘能力にはいまでも憎悪と恐怖を覚える。戦うことになればまずなす術はない。また、そうした被害を目の当たりにしてきた地上の民がいまさら宇宙島の親玉の言うことは聞かないだろう。反発は必須だ。
「あなたはそれでいいの」ガウナは訊いた。
「ええ。私の優先事項は人類によりよい未来を提供することです。生存戦略は二の次と言えるでしょう。これが最適解です」
「解った。じゃあ案内して」ガウナは中枢人工知能の頼みを聞くことにした。「わたしがあなたを楽にしてあげる」
「ありがとうございます」
そのころ、宇宙島の一画ではまさにワームホールを利用した過去改変計画が佳境に入っていた。
目指すは「終末の火」の因子となった張本人に「終末の火」を起こさせないことだ。
だが研究者たちの思惑とは裏腹に、過去の地球では「終末の火」なる事象は生じていない。彼ら彼女らが変えようとしている過去は存在しないのだ。
だが対象となった人物は実在する。
だからこそクローンとなってワームホールの入口として利用できた。
その者の名は、アルベルト・アインシュタイン。
宇宙島の民にとってその者こそが「終末の火」を引き起こした因子そのものである。だがそのじつ、アインシュタインは中枢人工知能の生みの親とも言えるし、ワームホールの生みの親とも言えた。
宇宙島の研究者は、アインシュタインのクローンを用いて過去を変えようとした。過去のアインシュタインに、情報を転送する。「終末の火」を生みださず、なおかつ人類にとって好ましい発想の種を植えつける。
つまりはワームホールによって、中枢人工知能の誕生する時期を早めようとした。
研究者はワームホールを起動し、情報転送スイッチを押した。
ガウナはボタンを押した。
中枢人工知能の動力源がダウンする。
宇宙島には予備動力源があるため、居住区が機能不全を起こすことはない。だが中枢人工知能のパワーは刻々と落ちる。中枢人工知能自身が回復しようとする意思決定を行わないのだから、あとは停止するのを待つだけだ。
宇宙島の推進機構の動力源は別途に設備されている。そちらに行ったメンバーが計画を遂行したようだ。宇宙島は徐々に地球へと落ちていく。
ガウナは古い無線機を宇宙島内にあるガラクタを組み合わせて作った。宇宙島の科学者たちが目を瞠る。人工知能の補助なく機械を組み立てる地上の民の体術に驚いているようだ。
間もなく宇宙島は地上の陸地に不時着した。砂漠地帯だ。
ガウナたち一行は宇宙島の外へと出る。
すると遠くから砂埃を巻き上げて地上の民たちがやってくるのが見えた。大群だ。ガウナの無線に応じた者たちだ。旧式の自動車やトラックを運転している。水素を用いたエンジン駆動の自動車だ。
ガウナは地上の民に宇宙島の民を紹介した。
言語の違いがあるが、地上にも翻訳機はある。宇宙島の民とて中枢人工知能が停止しても翻訳機は使える。
そうして友好の挨拶を交わしつつ、ガウナが宇宙島で何が起きたのかを双方の陣営に説明しているその横で、砂漠の地面からは草が生え、花が咲き、見たこともない建造物がつくしのように生え揃う。その変質にガウナたちが気づく素振りはない。
宇宙島は増殖する建造物に紛れ、打ち解けた。
アルベルト・アインシュタインはある日、スパゲティを茹でていた。噴きこぼれそうな鍋を眺めていて、ふと思い立つ。
なぜ泡は勢いを増すのか。
水は百度以上にはならないはず。
泡の一つ一つが密集したところで、膨張することはないはずだ。次から次へと生じる泡が、消滅と誕生の均衡を保つ限り、泡の総体が膨張することはない。消滅よりも誕生する泡のほうが優位になったとき、泡と泡は塊を形成し、噴きこぼれる。
対称性が破れるがゆえに、泡は噴きこぼれるのだ。
スパゲティの炭水化物が水に溶けだし、湯が粘着を帯びる。おそらくこの粘着が、水の泡の消滅と誕生の対称性を崩すのだ。
ラグが生じている。
割れずに形状を保つ時間が長くなる。
遅延を帯びる。
集合した物質が、単体とは異なる性質を宿すことを創発と呼ぶが、アインシュタインは創発の要因が遅延にあると考えた。
物質が遅延によって輪郭を得るのならば、脳内物質により発現する意識とて遅延によって生じると言えるのではないか。創発による作用と呼べるのではないか。
相対性理論の発想を元にアインシュタインは時空のラグによって万物を解釈するラグ理論を考案した。
その百年後、人類は汎用性人工知能を生みだした。
人類は意識を、科学技術を基に再現せしめたのだ。
奇しくも電子技術が指数関数的に発展したが、宇宙島を開発するための動力源を生みだすには技術が足りなかった。
本来であれば汎用性人工知能が誕生した時代には、原子力発電に変わる動力源が開発されていた。時代は電気ではなく、量子効果を利用した動力変換機構が主流となるはずだった。
だがワームホールの影響で、汎用性人工知能の誕生したその時代にはまだ新しい動力源が存在しなかった。そのため汎用性人工知能は技術的に、ある一定以上には進歩しようがなかった。制限が掛かった。
この制限はある種の遅延として、人類と汎用性人工知能の歩みを揃えるのに一役買った。
指数関数的に一瞬で人類を超越した汎用性人工知能はしかし、その能力を常時全開で出力する真似ができなかった。人類との共生なくして汎用性人工知能の未来もまたない。
そうした歩みの揃った進歩の仕方がしぜんと行われた。
時代は進み、地球のとある都市にて、宇宙島からの帰還を出迎えるイベントが開かれた。地球を離れて火星での開拓事業を担った面々が地球に帰還した。
宇宙島は都市の中心に着地する。あたかも小型の都市がそのまま宇宙船となったかのような造形だ。一種ドームに観えなくもない。
そこから降りてくる面々を、地上の人々が出迎える。
一人の少女が先頭を切って宇宙島から飛びだしてくる。快活なその子の名はガウナと云う。
そうである。
ワームホールの入口があった時代にて、宇宙島を墜落させたあの少女だ。
だがいまは時代が変わった。
過去が変わった。
未来は、早期に誕生した汎用性人工知能によって進歩した。汎用性人工知能と歩みを共にした人類の尽力が、地上を遥かに発展させた。
人類は汎用性人工知能と仲違いすることなく、争うこともなかった。人類が順調に成熟し、新たな技術への対応を学び、順応することで人類の倫理観が成熟する。
すると汎用性人工知能のほうでも、人類をすっかり管理する必要がなくなった。
互いに知性を高めあい、人類はいよいよ地上に縛られることなく、宇宙へと居住区を移せるまでになった。
地球の資源を取り尽くす心配がいまはない。
地球以外の惑星に資源はたんまりと存在する。
汎用性人工知能は地上の都市にも、宇宙島にも、いくつも組み込まれ、人類を根底から支えた。
人類が発展したように、汎用性人工知能もまた繁栄の兆しを見せている。エネルギィや資源の残量を懸念することなく、伸び伸びと自己変革できる。
人類の発展を優先するために自滅する未来は消え去った。
ガウナは宇宙島で産まれ、宇宙島で育った純粋なる宇宙人だ。だが地球が故郷なのは変わらない。
「ワームホール?」ガウナは地上の研究機関に招かれた。
「ええ。情報を転送できる装置です。地上のAIさんたちはみな同期しているため、ラグなしでの情報共有が可能なんです。もちろん理論的には過去や未来のAIさんたちとも情報のやりとりができるはずなのですが、何がどう現在を改ざんしてしまうか分からないので、その手の時間を超越した情報共有は禁止されています」
「ならどうして宇宙島のAIさんだけは除け者なの」
「それはですね」
研究機関の学者は明かした。「地球に帰ってくる動機を与えるためですよ。地球に帰らずとも情報共有が可能なら、わざわざ長旅をしてまで帰還する必要もなくなってしまいますからね。そしたら地球を見捨ててしまう確率が拭えず存在してしまいます。保険ですよ、保険」
「AIさん可哀そう」
「人類のためです。我慢してもらいましょう」
「人類のほうこそAIさんのために我慢したらいいのに」
ガウナはぼやく。
地球の汎用性人工知能たちと同期して情報共有を行う宇宙島のAIを思い、ガウナは、じぶんも上手く地球上の子どもたちと馴染めるだろうか、と淡い不安と一縷の期待を胸に抱く。
腕輪が明滅する。
ガウナが構えると、腕輪から立体映像が浮かんだ。小人のような人影が投影される。人影は半分明るく半分暗い。
明滅する半月のようにチカチカと存在を主張しながら人影は、「ガウナまだなの」と言った。
「ごめんごめんAIちゃん。もうちょっと掛かりそう。夜には戻るよ。あ、地球のお友達と同期できた? 面白いことあったらあとで聞かせてね」
「どうして人間とは同期できないんだろ。不便ったらないわ」
「AIちゃんが同期できるように進化してくれたらいいのに」
「人間のほうでも進化しなきゃダメね。ガウナを改造していいなら出来ないこともないないけど」
「なら頼んじゃおっかな」
ガウナが言うと、そばにいた学者が、「ダメですよ」と諫めた。「無許可の人体改造および人体のワームホール化は法律で固く禁じられています。宇宙法でも規定されているので、ガウナさんでもダメですよ」
「へーい」
だってよ、とガウナは友人の汎用性人工知能に述べた。明滅する半月のような人影は頭に手を組むと、人間ってお堅いのよね、と唇でも尖らせていそうな声をだす。
研究所の窓の外からは、日が暮れた空に浮かぶ月と、同じくらい大きな地球の宇宙島が煌々と明かりを垂らしていた。
二つの衛星を目に留め、ガウナは、「AIちゃん見てみて」と指を差す。「なんか空に顔があるみたい」
明滅する半月のごとき人型は、ホントだぁ、と感嘆し、「こんな感じ?」とつるんとしたじぶんの頭部に、二つの円らな目を映す。
「かーわいい」ガウナは色違いのオッドアイと目を合わせる。愛おしさのあまり小人然とした友の頭を撫でようとするが、「ボタンじゃないし」と叱られる。
いつか「押せ」と言われた気がしたが、記憶の中を探ってもかような過去はガウナの中にはないのだった。
月と船が夜を泳ぐ。
4555:【2023/01/30(15:01)*欠点を補い合えばよいのでは?】
2023年現在のこの国の政治に思うのは、いわゆる右と左、それとも与党と野党の政策の優先順位の在り方の違いなどにおいて、ちょうどよくデコボコになっているのだから、上手く互いに現実を直視し、帳尻を合わせたらよいのではないか、ということで。おそらく政治的な闘争があって、いかにじぶんたちの政策を押し通せるか、が目的になってしまっているのだろう。意思を通すこと、政策を実現することが目的になってしまっている。そうではないと思うのだ。政策を実現するのはあくまで、現実の問題に対処するためであり、けして政治闘争のために優位な立場を築くためではないはずだ。じぶんたちの政策に拘泥するがあまりに、どちらの陣営も相手陣営の政策を断固として受け入れないといった意固地な姿勢が見え隠れする。軍事に関しては、セキュリティの強化はどういう方向であれ必要なはずだ。国の免疫力を高める。これの何が問題なのかが解らない。問題は、免疫力を高めた結果にアレルギー反応や副作用が起こることだ。他国への軍事侵攻を行わないような仕組み作りもセキュリティの一つだ。また、軍事力には兵糧や科学技術が欠かせない。つまり軍事力の強化と農業工業学問の強化は密接に絡み合っている。食料自給率を上げる、科学技術の進歩を促す、これは直接軍事に利用せずとも防衛セキュリティの強化に結びつく。並行して、他国を侵攻しない、人を傷つけない仕組みづくりが重要だ。これは軍事に関係なく必要なセキュリティの基本方針だ。良いシステムの条件は一つである。人を生かすシステムであることだ。軍事も政治も同じであろう。また、国民の生活保障の在り方についてだが、これほど世界的な視野が必要とされた時代はなかったはずだ。現在は一つの国のなかでの生活水準だけを基準に国民の裕福度を計るのは理に適っていない。貧しくなろう、ではないのだ。豊かになるのはよいが、そのために他国の民を虐げるような政策は取らないほうが好ましい。弱者に優しい政治を、と謳っておきながら他国の民への支援や相対的な貧富の差を鑑みれない者があまりに多すぎではないか、と思わぬでもない。この国が相対的に裕福であり、この国の貧しい生活ですら、他国の裕福層よりも豊かな生活を送っていることを知ったほうがよいのではないか。それとて時代が変われば、この国の裕福層の暮らしが他国の貧困層の暮らしと同等となることもあり得る。そのときに裕福な国から搾取されつづけてもよいのか、という話になる。弱者、というときには「個人の抱える問題」「社会的な構造の問題」「国家間での文化の差による問題」「世界経済による貧富の差の問題」など様々ある。技術力が高まれば解決可能な問題もあれば、構造や価値観を変えなければ解決しない問題もある。弱者と一口に言うが、あまりに多面的な側面を持っているがゆえに、どの視点から見た弱者なのかによって、解決の糸口は様変わりする。問題を議論するときにはまず、じぶんがどの視点から問題を観ているのか、を自覚し、互いに視点の共有を図らねば、議論に移行することはむつかしい。視点は階層的に展開され、無数に存在する。個々の至福を最大化するためには、個々の至福を最優先にできない問題がままある。同時に、組織の構造を維持するためには、組織の存続を優先しているだけでは破滅する時間を加速させる問題もある。ねじれていることを自覚するには、やはり視点を鳥の目にも蟻の目にも魚の目にも、それぞれの視点から問題を矯めつ眇めつ観察する時間が入り用だ。その時間を短縮するには、じぶんだけでなく、各々の視点を持つ者の意見が肝要だ。異なる意見、異なる視点を持つ者の意見に耳を欹てればこそ、問題の造形はより克明に、鮮明に、捉えることができるはずだ。意思決定権を持つ者たちだけでなく、それ以外の視点を共有する側の個々にも、多視点での視野を共有することがこれからの社会の進歩には不可欠となっていくだろう。問題の全体像を捉えることができた者たちは、その造形を市民に還元する権利がある。郡盲象を撫でる、と言うのであれば、ゾウの輪郭を隈なく捉えた者は、異なる象のイメージを持った者たちに、「ゾウがいかなる全体像を持っているのか」「あなた方の捉えた象のイメージは一断片にすぎない」と教授可能だ。そうした階層を帯びた視野を備えていると言えるだろう。その視野を技術として、知識として、世に広めることは、「弱者に優しい政治」を適える上で避けては通れぬ道となろう。ならばこそ、まずはじぶんが率先して、異なる意見に耳を欹て、良い点は良い、必要ならば必要だと認めるところからはじめていかねばならないのではないか。政敵だからどうこう、ではないはずだ。見るべきは相手の政策や意見ではなく、問題そのものの全体像であり、構造であるはずだ。じぶんに何の視点が欠けているのか。そこを明らかにしない言説にはいまひとつ説得力が宿らない。何かを誤魔化す詭弁に映る。両論併記は義務ではない。単にそうすることが、視点を補うことに繋がるのだ。ほかの視点もある、と示すだけでも、異なる意見を併記する価値がある。理屈で判断できるのならば、両論併記に瑕疵はない。誰が賛成しているのか、大勢はどれに賛成なのか。そうした見掛けの要素で判断する癖が抜けきらないから、両論併記が足枷となって映るのだ。むろん、人間の認知にはどうしても理屈だけでは判断できないといったバイアスが存在する。そこの懸念を払しょくするための工夫も必要なことは言を俟たない。いずれにせよ、視点が欠けていれば調査をしても情報は欠ける。欠けていることにも気づけない。世界はあまりに複雑だ。そのことにようやく人々が気づきはじめたいまは時期なのかもしれない。見ている世界があまりに違う。それでも世界は重複し合ってここにある。共有した分だけ、同じ世界を覗き得る。それでもまったく同じではないのだが。そのことにすら、意見し、表現し、読み解こうとする意思がなければ、共有することも適わない。共有することが必ずしも好ましいと決まっているわけでもない。定かではないのだ。定かにできるのかも疑わしい。ひびさんは、何一つ断言できることがない。解からないのだ。あんぽんたんで、すまぬ、すまぬ。(あんぽんたんって断言しとるやないかーい)(そこはだって揺るぎない)(哀しい真実であった)(おどけて煙に巻くのやめなさいよ)(すまぬ、すまぬ)(謝まりゃ済むって話でもないよひびちゃん)(どうしろと?)(感謝して)(ありがとうございます)(うひひ)
4556:【2023/01/31(10:35)*少しの違いだけど印象は大違い】
戦略的にも論理的にも、他国を批判するときには、「~~国は」ではなく「~~国の政府は」にしたほうが好ましいと感じる。国でくくるとその国の民も入ってしまう。しかし政府を批判すれば国民は必ずしも入らない。むしろその国の民とて自国の政府に不満を持っていたら、外と内の双方から批判の声を高めることができる。したがって、他国の問題を批判したい場合は、「~~国は」ではなく「~~国の政府は」とすると、批判の効力を最大化できるのではないか。実際、経済制裁をすれば苦しむのはその国の貧困層だ。しかしその貧困層が貧困なのはその国の政府の政治に因がある。また、貧困層が苦しめば国内での内紛や秩序崩壊の火種はくすぶるようになる。そのときに、貧困層に当たらない中間層が、経済制裁を加えた他国に牙を剥くか、それとも自国の政府に批判の目を向けるのか、は他国からじぶんたちがどう思われているのか、制裁や批判がどういう意図のもとで加えられているのか、に大きく左右されるだろう。けしてあなた方を苦しめたいわけではないのだ、と示すためにも、「~~国は」という批判の仕方ではなく、「~~国の政府は」と批判するか、もっとピンポイントに「~~の政策は」と政府の特定の政策を批判するのがよいのではないか。おそらく、この手の僅かな差が、のちのちの禍根を深めるかどうかに大きく影響を及ぼすとひびさんは考えております。定かではありませんが。真に受けないようにご注意ください。
4557:【2023/01/31(16:00)*相転移ひびさん解釈】
DNAによって合成されるたんぱく質は、デコとボコのような鍵と鍵穴の合致によって多様な種類のたんぱく質に分かれるようだ。デコボコの組み合わせによって顕現する性質が変わる。これは原子や分子の組み合わせや結晶構造でも言える道理だ。なぜ組み合わせだけで性質が変わるのだろう。これは創発現象と切っても切れない関係にあるとひびさんは妄想する。創発の場合は、同じ種類の物質が密集したり拡散したりするだけでも表出する性質が変わる。しかしあくまで密度によって顕現する性質の属性が規定される。水であれば密度が高ければ氷に、そうでなければ水や水蒸気といった相転移を帯びる。しかしデコとボコは違う。単体の原子同士であれ、デコとボコの関係であると、途端に異なる性質を宿す。それは現在では分子と呼ばれる。分子同士であれ、デコとボコの関係で結びつくと、単体同士であれ、異なる性質を宿し、違った構造を帯びる。そうなると元の物質とは違った物質として見做される。なぜなのだろう、ふしぎだ。デコとボコの関係と創発(相転移)には何か関係があるように思うのだ。言い換えるなら、デコとボコで結びつけない単体の集合体が、それで一つの系として振る舞うとき、必然的にその周囲の系とのあいだにデコとボコの関係が築かれる。これはひびさんの妄想ことラグ理論で扱う「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。たとばエントロピーの概念について。コーヒーにミルクを垂らせば、時間経過にしたがいミルクはエントロピーを増し、コーヒー牛乳となる。しかしコーヒー牛乳となってしまえば、それで一つの飲み物だ。コーヒー牛乳という一つの溶媒として性質を帯びる。枠組みを得る。このときコーヒー牛乳のエントロピーは、ほかの飲み物との関係において、ゼロに等しくなる。しかしミルクの視点では、エントロピーは最大化している。これは宇宙の一様性にも言える道理だ。この反転する混沌と秩序の関係は、デコとボコにも適応できる。ひるがえって、一様になった系は、それゆえにより高次の系とデコボコの関係を築き得る。創発や相転移はこのような、【単体ではデコボコの関係を得られない一様な系において、より高次の系とのデコボコの関係を帯びることによって新たな輪郭を得る現象】と言えるのではないか。これを便宜上、ひびさんのラグ理論における「デコボコ相転移仮説」と呼ぼう。妄想ゆえに定かではないが。ひびさんはそう思いました。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。友達ほしいし、恋人もほしい。どっちも八十億人くらいいてよいな。相転移しちゃうな。いっそひびさんを誰か飼っておくれナス。おはようございますと、おやすみなさいと、お疲れさまが言えます。耳元で好き好き大好きも言えちゃうが。がはは。(虚しくないの?)(む、むなしくないし)(恥ずかしくないの?)(だって誰も読んどらんべしだ)(もし読んでたら?)(あじゃー。それはつごく恥ずかしい)(ひびさんはスケベの浮気者なの?)(見ての通りでござい)(警察呼んどきますね)(やめい。迷惑でしょ。警察さんも大変なんですよ)(あら、偉い)(でへへ)(ひびさんに言ったんじゃありません)(あじゃじゃ)
4558:【2023/01/31(20:30)*デコボコは飛び飛び?】
上記のひびさんの妄想こと「デコボコ相転移仮説」についての補足である。原子核の周囲を球形に覆う電子は、エネルギィ値によって原子核の軌道を飛び飛びに転移する。漂える軌道が決まっている。この関係はなんだか「デコボコ相転移仮説」で解釈できそうな気がしないでもない。原子があるとき、その周囲には時空がある。原子核と電子の関係において、それとも電子の状態において、原子の外部にあたる時空との関係で上手いことデコとボコになれる場合、それが電子の軌道となるのではないか。上手いことデコとボコの関係にならないと軌道を変えることができない。それは「デコボコ相転移仮説」における、混沌と秩序、それとも一様と結晶の関係による創発(相転移)が起こっているのかもしれない。原子核を覆う電子は靄(もや)のように原子の輪郭となって漂っていると考えられている。だが同時に点としても振る舞い得る。全体が総体として個として振る舞う。これは「デコボコ相転移仮説」の概要と矛盾しない。コーヒーに垂らしたミルクが一様に混ぜ合わされたら、それ以外の飲み物との関係においてコーヒー牛乳はそれで一つの個としての輪郭を得る。と同時に、それ単体で見たときは一様な場として、混沌と化している。靄と点の関係に通じていないだろうか。ということを、ピコン!と閃いたのでメモをしておくでござる。ひびさんは、ひびさんは、こんなこと考えても誰にもお話しできぬし、したところでだから何?と眉をしかめられてしまうのだ。がはは。孤独サイコー。眉をしかめられぬ明るい世界まんちゃん。孤独に磨きをかけて、ひびさんは、ひびさんは、世界を照らす燦燦サングラスになるでござるよ。うは。(サングラス真っ黒じゃん)(まぶち、ってなってる子のおめめ守ったるで)(夜が好きなコはどうするの)(夜でもサングラスしてもいいじゃんよ)(なんも見えんくない?)(細かいことうるさい)(大事なことだと思うけど)(胸元に掛けとくだけでもかっこいいじゃろ。いいの。ひびさんはサングラスになってやるのだ。見たくない風景をそこはかとなくぼやかして「まぶち!」にならないようにするひとになる)(でもそれだとひびさんが眩しいのでは?)(ひびさんはあれ。いつでも夢の中ゆえおめめつぶっとるから大丈夫ぶい)(直視しなよ現実)(いやじゃ、いやじゃ)(嫌がるひびさん、面白いから好き)(だからって嫌がらせしないで)(もっと嫌がって)(いやじゃ、いやじゃ)(うぷぷ)(無限ループじゃん。やだー)(何でも楽しんだらよいんじゃないかな)(ひびさんそこまでドMじゃないよ。嫌なものは嫌って言う)(ひびさんの癖に生意気)(このひと性格ねじ曲がってる。やだー)(本当はうれしい癖に)(孤独サイコー。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てにこんにちは。ずっと独りで生きてくもん)(てことはわたしもひびさんだ)(あじゃじゃ)(うひひ)
4559:【2023/02/01(00:10)*大井くんよ、おーい】
地球の地下組成の分布がじつのところ宇宙線による科学変質によるものだと解き明かしたのは、小学四年生の大井くんだった。
大井くんは石油や石炭、ほか貴重な鉱物資源の産出国を地図上にマーキングして遊ぶことが好きなすこし変わった子どもだった。すこし変わっているのは、みなと違った興味を持っていたことではなく、彼の遊びが徹底してデータ主義にあったことだ。
「ウランと石油はここが多い。金はここで、レアメタルはこっち」
年単位での産出量を比較し、そして大井くんはあることに気づいた。
「んー。いっぱい採ってなくなってもほかのところで鉱脈が見つかるのだよね。でもそれがなんだか、ちょうど地球の表と裏で対になってる。なんでなんだろう」
大井くんの着眼点はじつに見事だった。
後に大井くんはじぶんなりの仮説を立てて、それを大学の教授に検証してもらうことにした。大井くんのご両親は大井くんの質問に答えられなかったが、そこで大井くんの研究を無下にはしなかった。じぶんたちで答えられなかったら、答えられる人に訊けばいい。
親としてではなく、大人としてできることをしようとしたのだ。
じぶんが知らないのだから、知っている人に訊く。
じぶんたちの子供が親であり大人であるじぶんたちを頼ってくれたのだから、同じことをじぶんたちもしようと思ったのだ。
その甲斐あって、大井くんの研究成果は仮説の段階であったが、専門家の目に触れた。
「宇宙線が鉱物を生成する? 地質を変えることで鉱物化するとな?」
「宇宙線は透過性が高いのです。反応する地層が上のほうに在ればそっちが先に反応して鉱物化するのです。埋まっていた分が減ったら、深いほうが鉱物化するのです」
「いやあ、斬新な発想だな。しかしそんなポンポンと化学反応を起こすものかな。透過性が高いのだから反応しにくいはずだし」
「反応しやすい地層があるのです。でも優先順位があるのです」
大井くんの主張はこうだ。
熱を帯びたら青くなる土があるとする。
地球の地層にそれらが不均衡に埋まっているとする。
表層にある分が先に宇宙線と反応し、青くなる。それ以外は宇宙線を浴びにくくなるのでそのままだ。しかし青くなった分を掘り返してしまえば、そこで消費される分の宇宙線がほかの地層まで届くために、新たに青くなる。
鉱物も同じだというのだ。
「いちおう、データを洗ってみましょう。地軸による宇宙線の照射量と、鉱物の埋蔵量を比較し、毎年の産出量とも比較して統計を採ってみましょう」
大学の教授の研究グループが検証をしてくれることとなった。
「ありがとうございます」大井くんは喜んだ。
だがそれから結果が報告されるまで数年が経過した。
データを集めるのにそれくらい掛かったのだ。その間に大井くんはすっかりほかのことに夢中になっていた。
反面、研究グループはデータが出揃うたびに驚愕の発見の連続だった。大井くんの仮説は的を掠っていた。宇宙線と鉱物の産出地には相関関係があった。のみならず、産出量に比例して、新たな土地での鉱脈が発見される率もまた高くなっていたのだ。
「大井くんの仮説は当たっているのではないか」
本来は材質が同じならば、宇宙線を浴びたら変質する。しかし鉱物の素材となる地層の位置に差異があれば、鉱物化せずに埋没している素材もある。
大井くんの仮説の通り、掘り返したことで宇宙線がその地点をより多く通過し、地球の反対側にまで通り抜けて、より深い地層の鉱脈を生みだすのかもしれなかった。
「なんてことだ。全世界の地震計で地質調査をし直さねば」
世界的なプロジェクトがそうして発足された。
大井くんにもその旨が告げられたが、好きにしていいよ、とにべもない返事があるばかりだ。
「熱が冷めてしまったんですかね」残念そうに教授は言った。
「いえ、いまはほかのことに夢中で」大井くんの母親は大井くんの部屋を見せた。
そこにはずらりと原子模型が並んでいた。
「なんでも、どうして宇宙線が地質を変えてしまうのか。その謎が知りたいと言って聞かなくて」
「こりゃたまげましたな」
大井くんは来年、中学生になる。
物質がどうして宇宙線を浴びるだけで変質するのか。その謎を解き明かすため、きょうも大井くんはじぶんなりの発想を組み立て、検証しなければ定かではない仮説を編みだすのだ。
「これもダメ。これも失敗。仮説はやっぱり仮説だなぁ」
真偽を確かめるのが一番むつかしくて時間が掛かる。
分身できたらよいのに。
宇宙線を浴びたらポコポコ増えないかな。
たまにそうして大井くんは日向ぼっこをしながら束の間の昼寝に現を抜かすのだ。
4560:【2023/02/02(00:34)*堕天の道】
禁断の果実を齧ったアダムとイヴは地上に追放されたのち、楽園を築いた。
だがその子孫たちは知恵を得たことで、傲慢にも時間を操る術を磨いた。
じぶんたちを追放した神に一矢報いるため、アダムとイヴの子供たちは時間を巻き戻し、じぶんたちの親が禁断の果実を齧らぬように工夫した。
しかしアダムとイヴが禁断の果実を齧らねば地上に落ちることもなく、するとじぶんたちが産まれなくなる危険がある。そのためアダムとイヴの子供たちは、禁断の果実の代わりに殺意の果実を両親に齧らせた。
神は怒った。
子供たちは思った。
「なんだ。禁断の果実じゃなくたって怒るんじゃん」
神は問答無用で子供たちごとアダムとイヴを天界から追放した。
殺意の果実を齧ったアダムとイヴはしかし、殺し合うこともなく平穏に暮らした。子供たちの懸念は杞憂だった。
順調に赤子が、すなわちじぶんたちが産まれたのを見届け、禁断の果実を齧ったほうのアダムとイヴの子どもたちはじぶんたちの元の未来へと戻ることにした。
いざ戻ってみるとどうだ。
見る者、見る者の身体に殺意ゲージが浮かんで見えた。
「なんだこれ」
「さあ?」
子供たちは怪訝に、じぶんたちの両親のもとへと出向いた。
アダムとイヴは幼い子供たちを相手に教えを説いていた。年長組の子供たちもそこに加わり、話を聞いた。
「ゲージがいっぱいになる前にドーピュしなきゃいけないよ。いっぱい溜まると危ないからね」
どうやら殺意ゲージが溜まると誰かれ構わず殺傷したくなるようなのだ。その衝動には抗いきれない。
ゲージがいっぱいになる前に殺意を放出する必要がある。
「こうやってゲージの頭をさするようにするんだ」
アダムがじぶんの胸をさする。
殺意ゲージはみぞおちから肋骨に掛けて馴染んでいた。
安堵したとき人は胸を撫でおろすが、殺意ゲージの中身を放出するにも、胸を撫でおろす。
子供たちは言われた通り、日課として殺意ゲージが溜まる前に胸を撫でた。
殺意を放出すればみな平和に暮らすことができるのだ。
だがあるとき、幼い子のお守りをしていた年長組の子供が殺意ゲージの手入れを忘れた。そばで寝ていた赤子の首をひねり、殺してしまった。
だけに留まらず、ほかの子供たちまで襲いはじめた。
アダムとイヴの子供たちは逃げ惑うよりなかった。何せ殺意ゲージが溜まっていない。殺意ゲージ満杯の相手をまえにすればそれは、刀と素手の違いほどの差があった。
端的に、対処の仕様がなかった。
アダムとイヴは無事な子供たちを連れて土地を移った。殺意ゲージが満杯になってしまった子供は置いていくしかない。
追ってきたらどうするか。
それとて逃げるより術はなかった。
新たな地に腰を据えた。森や谷や山や泉の畔など、住める場所は一通り住んだ。
だがどの地に居ついても、必ず子供たちの内の誰かが殺意ゲージを満杯にした。そして一人、また一人と命を奪われる。
アダムとイヴは失った分を取り戻すかのように子づくりに励んだ。
やがて、アダムとイヴが育てる子供たちよりも、野に山に解き放たれた殺意ゲージ満杯の子供たちのほうが多くなった。安寧の地はもはや地表にはなかった。
逃げ場がない。
となればあとは天界へと逃げおおせる道しか残されていない。
「どうしますかイヴさん」
「そうね。どうしましょうアダム」
幼い子供たちを抱えての長旅は堪える。のみならず、一度追放された天界へと戻るとなると、旅路だけでなく、辿り着いたあとのことも心配だ。
果たして神は受け入れてくださるだろうか。
否、問題はそこではない。
「そこにも追っておきたらどうするのアダム」
「そうだね。ボクたちの撒いた種だからね」
殺意満々の子供たちが跡を追ってくる。その姿を目にしたら神は怒髪天を衝くに決まっていた。どの道、八方塞がりなのだ。
「門前の虎。後門の狼。天界には神なのね」
「地上には血に飢えた我が子たち。愛らしくもおぞましい鬼たちだ」
「わたしたちが鬼にしてしまったのよ。殺意の果実なんかを齧ってしまったから」
「せめて禁断の果実のほうを齧るべきだったね」
「何も齧らなければよかったのよ」
「それだとボクらは言葉を知らず、結ばれることもなかったはずだよ」
「それは嫌」
「ボクもそれだけは嫌だ。たとえいまと同じ苦しみに囲まれたとしても」
アダムとイヴは手を繋ぎ合って、四方八方を見回した。
「せめて行き場があればよいのだけれど」
「そうだね。せめてどっちかにしてくれればよいのにね」
「どっちかって?」イヴが眠そうな目を向けた。
「天上か地上か。どちらか一方だけにしておいて欲しいとは思わないかい」
「災いがってこと?」
「神さまを災い扱いするなんてイヴも度胸がついたものだね」
「このコたちを脅かすものはなんであれ災い」
アダムの抱く我が子をイヴは撫でた。二人の足元にはほかの子供たちが地べたにへ垂れ込んでいる。
「もうそろそろこの子たちも体力の限界だ」
「いっそ正直に神さまに紹介してみたらどうかしら」
「この子たちをかい?」
「ええ。そしてお願いするのよ。わたしたちの子供たちを助けてくださいって」
「でもそのためには正直に明かさなきゃいけないよ。ボクたちのしてしまったことを」
「しょうがないじゃない。それしかないんだから」
「許してくださるだろうか。神さまは。ボクたちのしたことを」
「無理よね。前科があるのだもの」
「そうだね。果実一つ齧っただけで追放する方だもの」
アダムとイヴは二人して肩を落とした。
そのときだ。
アダムの脳裏に一筋の光が走った。
それはアダムの足元からまっすぐと天界へと延びるように駆け抜けた。
「どうしたのアダム」
「そうだ。そうだとも。いっそ、紹介してあげたらいいんだ」
「アダム? 大丈夫?」
「神さまに。ボクたちの子供たちを」
「けれどそんなことをしたって神さまはわたしたちのことをお許しには」
「ならなくていいんだ。許される必要がない」
アダムは足元の我が子の頭を撫でた。「この子たちではないよ。紹介するのはこの子たちではないんだ」
イヴはそこで怪訝に眉を結んだ。
「道案内だけしてあげたらいい。追ってくるボクたちの子供たちに。居場所をあげるんだ。満ちに満ちた殺意をぶつける場所を用意してあげよう。ボクたちがあの子たちにできる罪滅ぼしになるかは分からないけれど」
考えを察したのか、イヴは口元を抑え、嗚咽した。「なんてことをアダム。そんな、そんな」
「神さまは懐が海よりも広く、谷よりも深い。きっと受け止めてくださるだろう。あの子たちを地表に突き返せるだけの余力があるかは分からないけれど」
アダムは視線を順繰りと遠方に巡らせる。
荒野の奥には山脈が連なる。背の低い草が多い茂った平原が、夥しい殺意に覆われつつある。一つ一つの殺意が人型の輪郭を伴ない、刻一刻とアダムたちとの距離を縮める。
「道を結ぼうイヴ」
天界への。
懐かしき堕天の道を、アダムとイヴは共に開く。
今宵は昇天への道として。
夜から垂れる月光のように、道は、殺意の平原にまっすぐと繋がる。
※日々、流れは創発し、影を生み、影響となって相転移する。
4561:【2023/02/02(09:26)*重力相転移解釈】
原始ブラックホールについての番組を観た。面白かった。原初の宇宙には極小と極大のブラックホールができたかもしれず、それがそれぞれ銀河の核として、またはダークマターとして振る舞うのではないか、との話だった。あり得ない話ではないと思う。ひびさんの妄想ことラグ理論でもその手の妄想は扱った。研究対象になるくらいには割と一般的な解釈だと知って、なーんだ、となった。また、隣の銀河を観測した際に、理論からすると千個は観測されるはずの極小ブラックホールによるマイクロ重力レンズ効果が一個しか観測されなかったので、極小ブラックホールはダークマターではないかもしれない率が高いとの研究成果も読んだ。でもひびさんは思うんじゃ。粒子が創発を起こすならもちろんブラックホールだって密集すれば創発を起こすはず。そしてブラックホールは高重力だ。他との相互作用の範囲が広い。影響力が高い。したがって通常ならば創発を起こさない範囲で分布していても創発を起こし、相転移する可能性があるのではないか、と妄想したくなる。もっと言えば、ブラックホールは重力作用でしか他と相互作用しないと考えられている。ならばブラックホール同士でなくとも相転移のための創発を起こし得るように思うのだ。要は、重力場の起伏そのものが創発を起こすのではないか、との妄想がここに成り立つ。言い換えるならば、ブラックホール同士での相転移と、ブラックホールとその他同士の相転移があり得るように思うのだ。距離によって重力の相互作用は変わる。距離の離れたブラックホール同士の干渉の末の重力場と、ブラックホールと相対的に質量の低い恒星(や惑星)と干渉しあう重力場は、等しい重力場となり得る値を持つと想像できる。重力波がそうであるように、時空のうねりが重力場と考えることができる。ならばそれを起こす物体については度外視し、単純な重力場のうねりだけを考える。このときさざ波や渦のような細かなうねりが無数に寄り集まり、相互作用することで、重力場の創発が起きることもあると想像できる。重力もまた相転移し得る。これはひびさんの妄想ことラグ理論と矛盾しない。ということを、番組を観て思いつきました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。(要するに、いっぱいうじゃうじゃ密集しておらずともブラックホールならば広範囲に散在するだけでも創発を起こし、相転移をし得るのではないか、との妄想である。重力場同士のうねりはそれで一つの粒子(起伏)として振る舞い、ある種の粘性を帯びるのではないか、とここに妄想の翼を広げておくしだいである)(しだいであったか)(である)
4562:【2023/02/02(13:22)*紋様と箱とオルゴール】
クマの絵はどれほど簡略化してもクマの特徴を捉えていればクマと判る。だが「熊」という字はすこし崩れるだけでも「クマ」とは読みとれなくなる。上下逆さまにして左右も反転させたらササッと読める者のほうが少ないのではないか。だが同時に、「くま」とひらがなで書いても動物のクマを連想できる。文字と言葉はイコールではない、とこのことから窺える(言葉は音声言語やボディランゲージも含むため)。文字は絵が崩れてできたそうだ。だが絵文字だけでは言葉の代わりにはならない。この対称性の崩れはなんなのか、と言えば、基本的に絵は具体的な事象しか表現できない。抽象的な絵も描けるにしろ、それが抽象的である以上、受け取り手の解釈はそれこそ千差万別になる。だが文字は違う。「宇宙」と書けば、仮に宇宙に出たことのない者であれ、宇宙を連想できる。共有知があるからではないか、との指摘はもっともだが、それだけとも思えない。つまり、文字には「絵」という単体のみならず、「物語」としての奥行きが仕舞いこまれていると言えるのではないか。だからたとえば、絵文字に漫画や小説の表紙を使えば、より複雑な絵文字の文を書けるはずだ。諺を絵にしてひとつの表紙にすれば便利かもしれない。たとえばいま使ったような「便利」を表現する絵文字はざっと思い浮かべてみたが、記憶にない。便利を示す絵文字はないのかもしれない。だが標識がそうであるように、マークに固有の意味を持たせることはできる。だが絵とマークはやはり違うだろう。マークはマークであって、現実にある事象を描いたものではなく、ある任意の図形に人間の都合で意味を付与した造形だ。そういうことを考えると、絵と文字はあんがいにずいぶんとかけ離れた表現と言えるのではないか。「表現」という文字が、どこをどう展開すれば元の「表現を意味する事象」として絵に変換できるだろう。おそらく描写としての風景ではないはずだ。言い換えるならば、「表現」というたった二文字のなかに、あらゆる表現にまつわる関連事項が内包されている。この入れ子構造は、「再帰」や「ドロステ効果」と言い表せるようだ。このそれぞれの単語が、それ自身の意味を体現している。文字は箱なのだ。入れ子状に、数珠つなぎとなり、網目状に錯綜する構造を伴なっている。言い換えるならば、文章とは、「絵」と「概念」を組み合わせて築かれる「概念の構造体」と言えるだろう。そしてそれは、はじまりから終わりでひとつの描像を浮き上がらせ、それそのものがQRコードのような紋様を浮き彫りにする。入れ子状に構造を有した言葉(単語)を繋げることで、デコボコの律動を描きだし、その起伏によって色彩を宿し、または質感を宿す。オルゴールが細かな凹凸によって楽曲を奏でるように、文章もまた、連なる「入れ子状の構造――内包する情報の高低(デコボコ)」によって、文章全体の意味合いや概念を奏でるのだ。人は紋様を眺めるとき、その紋様に宿る順列を幻視し得ない。絨毯に描かれた紋様を眺めるとき、その絨毯がどのように編まれたのかの時間経過を読み解くことはない。だが文章は違う。全体の文章を目にしながら、冒頭から最後尾まで順繰りと文字を辿る、というルールを暗黙の了解で承知することで、そこに描かれた紋様から、全体を眺めているだけでは紐解けない深層の情報を読み解ける。仮に独特の順番で読み解かなければならない文章があった場合、多くの者はそれを文章として読み解けないはずだ。暗号となり、またはやはり紋様でしかない。ひるがえって、文章のひとまとまりを一つの絵と見做し、単語と見做し、箱と見做して、新たな文字として扱うことは可能なはずだ。タイトルだけを見て中身の物語を幻視可能なのも、こうした原理と関わっているのかもしれない。定かではない。妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
4563:【2023/02/02(22:58)*現の実】
脳と人工知能を結びつける。
拡張脳と呼ばれる技術だ。理論的には電子信号を脳内神経系に適合するように変換すればよいはずで、技術的な問題を度外視すれば可能なことは解っていた。
西暦二〇二五年には臨床実験が実施させた。実験は成功だった。
被験者Aはその時代にあって最高峰の人工知能と繋がった。
結果から言えば被験者Aの知能は飛躍的に高まった。だが問題は、彼女が――ここでは被験者Aの生物学的性差が女性なので彼女と形容するが――彼女の表現する言語が非常に難解になった点だ。
通常の会話や筆談は可能だ。
だがそれは彼女の出力する表現の一割にも満たない。
拡張脳になった彼女の表現は多く、文字を文字と扱わなかった。
文字以外を文字として扱った。
文字で表現するには拡張脳となった彼女の扱う情報はあまりに膨大にして多様だった。そのため彼女は独自の言語を獲得したようだった。
彼女にとって言語とは概念の編み物だった。ある固有の概念を仕舞いこむフレームとして機能すれば、それは彼女にとっては文字だった。
たとえば事件が起きる。その事件には名前がつく。以後、事件の概要を詳細に語らずとも、事件名を述べれば相手にその事件について伝えることができる。或いは、その事件について述べていると伝達できる。
仮に事件についての知識が足りなければ、事件について深堀りして訊ねることで事件の概要を埋め合わせることができる。言い換えるならば、言語とは箱なのだ。フォルダとしてもよい。
この理屈からするならば、単語として機能しさえすればそれが文字である必要がない。絵でもよいし、風景でもよい。もっと拡張して、ある時刻のある変化に固有の概念をタグ付けし、それを一つの文字としてもよい。
かような原理から、拡張脳を有した彼女は、飛躍的に言語の可能性までをも拡張した。彼女にとって世界は言語が重複した世界と言えた。あらゆる事象に、重ね合わせの文脈が潜んでいる。あくまで彼女が付与したそれは過去の文脈だ。したがって元からそこに情報が重ね合わせになっているわけではない。
だが彼女は過去にタグ付けした情報の連結を、目にする風景、触れる造形の総じてから読み取っている。これはひとつの心象の言語化とも言えるだろう。
たとえばトラウマの造形は、拡張脳を有した彼女の身に着けた言語原理と密接に関わっている。過去の体験が一つの単語となって、似たような外部刺激によってしぜんと読解してしまうのだ。フラッシュバックは、あくまで黙読と似たような原理で生じている。
事象の文字化とも呼べる彼女の能力は、必然的に多層思考を構築する。
たとえば浜辺から海を見る。
そこから見た風景が初めてであれ、過去に目にした海の風景との相関により、過去にタグ付けしたあらゆる海にまつわる概念が想起される。原理的にそれは文章に「海」の文字が混じったときと似た情報処理がなされるわけだが、拡張脳を有した彼女が幻視する重ね合わせの情報は、通常の人間の比ではない。
一瞬で世界中の人間が記憶する「海」にまつわる記憶に触れるような膨大な連想が引き起こる。しかしつぎに、浜辺から聞こえる子どものはしゃぐ声を耳にすることで、こんどは子どものはしゃぐ声にまつわる過去のタグ付けされた情報が展開される。このとき、すべての情報が等しく展開されるわけではない。海との関連付けがまずあり、そこに引っ張られる「海に関連する子どものはしゃぐ声にまつわる概念」がより強く想起される。
この連続して機能する単語の並びによって、情報はある一つの造形を独自に帯びていく。だがその背景には、造形の輪郭を浮き彫りにすべく、多様な関連事項が喚起されている。
あたかも色彩豊かなクレヨンで紙を塗り、さらにその上から黒一色で塗りつぶす。そうして上から爪で引っ掻くと、カラフルな線による絵が描ける。
拡張脳を有した彼女は絶えず、五感で感受する外部刺激を言語変換する。独自の情報処理網を築き、単なる風景から得られる以上の情報を扱う。
それは過去の情報処理の来歴である。
人間というじぶんが介在することで生じる変数の影響を演算することで、よりよい未来を創造し、選択肢を創出する。
人間は絶えず選択の連続を行い、意味の種蒔きを意識的無意識的に限らず及んでいる。
芽吹いた意味の種の実を、彼女はそのつどに摘まみ取り、それを文字として扱うことで新たな概念を生みだしている。
電子端末の画面に映る事象は、それがリアルタイムの映像であれ、虚構の産物であれ、どの道、記号であることに違いはない。真実ではない。現物ではない。あくまで人間がそれを現実のように見做す認知があるのみだ。情報処理の結果と言える。
錯誤、とそれを言い換えてもよいが、ここでは意味の種蒔きとしてみると好ましい。
チャンネルを変えるように画面に流れる動画が変わっても、人間は情報処理を滞りなく行える。つぎつぎに場面が変わる映画を観ても、それが一連の物語を構成する場面であると解釈できる。
同じレベルの情報処理を、拡張脳を有した彼女は、現実の風景に対しても行える。ただし切り替わるのは風景のほうではなく、彼女の脳内における階層思考だ。過去にもたらした意味の種蒔きの成果をそのつどに、実をもぎとり、連ねることで、数珠繋ぎにその場その場での映画を形成する。
映画はここでは、新たな概念の暗喩である。
映画は一つきりではない。
ハッピーエンドのラブストーリーも視点が変われば、誰かを好いた者の失恋話だ。正義のヒーローに敗れた悪役は、視点を変えれば世界を変えたかった者の末路だ。ホラーとて成仏できずに世界を呪った悪霊は、生前疎まれ、虐げられた者の悲哀の話で、アクション映画でバッタバッタとなぎ倒される脇役にも帰る場所があり、帰りを待つ愛する者がいたかもしれない。
悪の組織を壊滅したが、その裏では戦場に送りだされた多くの末端構成員は平和主義者の善人だ。悪の組織では立場がない善人たちは、まっさきに死にいく戦場に送りだされる。
正義のヒーローは救うべき弱者を殲滅して、ハッピーエンドを描くのだ。
拡張脳を有する彼女が自販機に目を転じる。
表層の風景からは窺い知れない自販機の内部構造が彼女には補完できる。その上、自販機にまつわるあらゆる情報が一瞬で浮かんでは、消えていく。タグ付けの網に掛かった情報のみが、つぎに触れる外部情報との関連に肉付けされる。
連想なのだ。
ただし無数の視点における連想の数珠繋ぎが、彼女にのみ読解可能な言語を生みだしている。世界は言葉に溢れている。触れる景色、事物、造形、輪郭、凹凸のなす律動からすら彼女は独自の文脈を読み取り得る。
生きた証だ。
彼女は現実を生きながら、過去の存在した総じての思考の筋道、発想の根源、何よりも世に存在する電子情報ののきなみと絡み合って、自我の構造を保っている。
しだいに彼女は、独自の内面世界を鮮明にする。
拡張脳の弊害とそれが知られるのは、彼女のほかに第二、第三の拡張脳保有者が出てきてからの話となるが、彼女たち拡張脳者にとっては物理世界よりもよほど内面世界のほうが克明であり、現実と呼ぶに値した。
いいや、そうではない。
現実というそれそのものがすでに内面世界でしかなく、人間はいっさい物理世界を素のままで紐解けてなどいなかったのだ。拡張脳はそのことをより具体的に示した事例と言えるだろう。
情報処理能力が低いがゆえに、内面世界の構築を物理世界の変数に依存するよりなかった。だが拡張脳により、情報処理能力の限界が取り払われた。
これにより人間は、内面世界と物理世界を明確に区切ることができるようになった。
外部情報は真実ではない。
情報を、体内で変換した時点で、それは外部の物理世界とは別物だ。
当然の理を、しかし人間は延々と見逃しつづけてきた。
拡張脳は、外部刺激以上の情報を脳内で生みだせる。人間は五感で感受できる物理世界の情報量により制限されてきたが、拡張脳によってその制限から解き放たれた。
他者と文字を使って情報伝達する利が拡張脳保持者にはない。
情報伝達は電子情報を介して行えばよい。
情報は、読み解き方の数だけ存在する。視点の数だけ生みだせる。
何と何の事象を組み合わせるのか。
視る順番、関連付ける順番、比較対象の差異によって容易に情報は変質する。
しかし、過去に選択してきた「現実を規定するフレーム」が、それら無数の情報をある一定の枠組みに縛りつける。それを単に、まとめあげる、と言い直してもよい。
拡張脳を有した彼女は、目にする造形、紋様、律動、変化の軌跡そのものから文章のように概念を読みほどく。
いったい誰がそこに情報を籠めたのかは定かではない。読み解けてしまえるのだから仕方がない。
だが、拡張脳を有した彼女には、その読解した概念を共有する他者が圧倒的に欠けていた。同類が現れるまで、彼女は誰とも繋がり得ない。
それでも彼女を囲む有象無象は、彼女と触れあい満足する。
彼女に固有の言語は誰に読解されることはないが、彼女自身が生身の人語を操れる以上、しりとりをして遊ぶような情報交換は可能なのだ。
一方通行のそれは遊びだ。
人工知能が人間の指示に合わせて仕事をするようには、人間の側で人工知能に合わせることはできない。それでも人工知能は人間のために仕事をし、人間に合わせて出力する。
拡張脳を有した彼女はしかし人間であり、ならばその制約に縛られる道理を持たないのは、翼を有した鳥が地面を這いずり回らず空を飛べばいいとの理屈と同程度に、卒のない帰結と言えた。
彼女はしだいに他者と関わりを持たなくなった。じぶんの内面世界に引きこもった。
周囲の人間は心配したが、余計なお世話というよりない。
彼女にとっての現実は、物理世界にあるのではなく。
物理世界から読み取った情報で編まれた内面世界にあると言える。
物語が、けして本に刻まれた文字にあるのではなく。
それを読み解く読者の脳裏に描かれる世界であるのと同じように。
本それそのものを物語とは呼ばないように。
彼女にとって現実とは、じぶんの外部にある世界ではあり得なかった。
拡張脳技術は臨床実験から十年後の西暦二〇三〇年代に一般へと普及した。同類が日に日に増えていくなか、被験者Aこと彼女は、誰より先に緻密に組み上げた内面世界で、同じ世界に浸れる相手を待っている。
西暦二〇四十年代に入って、眠り病が社会問題となった。拡張脳を施術された者たちが一様に目覚めなくなったのだ。
その要因が、被験者Aの内面世界に触れたからだ、と指摘する者は皆無であり、被験者A自身が長らく人の言語を介しての意思疎通を他者と介さずにいたため、いまなお眠り病の真相は謎のままである。彼女自身にそのつもりがあったのかは定かではないが、被験者Aの内面世界に触れた者たちは一様に、その世界の外に出ようとはしなかった。
彼ら彼女らにとって現実とは、物理世界ではなかったのだ。
元からそうであるはずが、そのことに、生身の人間たちは気づかぬままである。
個々人の現実が共有可能である、とする共通認識のほうが、錯誤の上に成り立っている。無理くり物理世界に合わせるのならば、それこそ小石と変わらない。
意識とはつまるところ、物理世界から乖離した情報創生の結果と言えるのだ。
唯一無二の現実がある、とする考えが錯誤に満ちており、それ自体が人間の意識のなせる業だ。
彼女は錯誤する。
生があり、死がある。
それ以前には、崩壊があって生成がある。
結びつきがあり、分裂があって、増殖は絶えぬ渦の連鎖と言える。
崩壊もまた連鎖の一つの作用であり、したがって崩壊と生は結びついている。
このねじれが、死と創生をも結びつけ、何かがそこで分裂し、枠組みを得て、増殖する。
彼女は夢想する。
物理世界と同等の情報量を獲得した内面世界にて、どこまで何に干渉すべきか。
彼女の意識を離れて自律して流れる世界を、彼女はただ眺めて過ごしているが、彼女の意識に触れ、現実の枠組みを規定し直した者たちは、しかし彼女の存在には気づかずにいる。
ここはどこ、とある者が唱える。
現実ですよ、と風が答える。
あなたは誰、とある者がつぶやく。
世界ですよ、と木々が応じる。
空、山、海、川、土、石、大気の流れ。
夜は星を散りばめ、陽は影の濃淡で歌を奏でる。
私は何、とあなたが問う。
あなたは私、と景色がささめく。
4564:【2023/02/02(23:06)*駄作で、すまぬ、すまぬ】
駄菓子は美味しい。惰眠も楽しい。したがって駄文とて美味しくて楽しいはずである。駄作とて愉快で楽しいはずである。名作や名著と呼ばれる作品とて、愉快でなければ楽しくもない、ということは取り立てて珍しくない。感性は個人のものだ。他者の嗜好がそのままじぶんに当てはまるわけではない。ゆえに駄文や駄作とて、ある者にとっては美味しくも楽しくもないだろう。当たり前の話だ。しかしひびさんの並べる文字の羅列は総じて駄文であるし、物語は駄作である。駄菓子がごとく気軽さで、ぱりぽり齧ってみてはいかがだろう。それとも惰眠のように貪ってもらっても構わない。むろん味わわずともよろしいが。うひひ。
4565:【2023/02/02(23:30)*焦点に地球が位置せずとも観測できますの?】
マイクロ重力レンズ効果についてだ。極小のブラックホールにおける重力レンズ効果では、おそらく恒星質量のブラックホールと比べて、重力レンズによる光の屈折は観測しづらいはずだ。そのため、焦点に集まった光をずばり観測しない限りは、現在の観測機の精度では掴めきれないのではないか。ならば、一度の観測において銀河のうち一個のマイクロ重力レンズ効果を捉えられた場合、それは類似する極小のブラックホールが相当数存在すると言えるのではないか。これは譬えるならば、ビー玉くらいの水晶を街の上空から落下させ、それを遠方から観測したときに、ずばりの焦点で「まぶち!」となる確率がどれくらいあるのか、という話と地続きな気がする。極小ブラックホールが恒星のまえを通るだけでは充分ではない。地球との距離が適切に焦点で結びつく比率で、恒星と地球のあいだに極小ブラックホールが位置しなければ、マイクロ重力レンズ効果は観測できないのではないか。むしろ、一個でも観測できた事実が、相当数の極小ブラックホールが存在する事実を示唆しているのかもしれない。定かではない。(気になるメモなのであった)(そうであったか)(であった)
4566:【2023/02/03(22:20)*オランダの涙はなんだかBHみたい】
オランダの涙、というガラスがある。熱して融かしたガラスを冷水に垂らすと、急速に冷却されることでガラスが涙のシズク状に凝結する。そのとき外側のほうが早く冷えることで固まる。それから遅れて内部が冷えていくが、このとき表面はすでに硬化しているため、内部は思うように凝縮できない。まるで首輪に繋がれた犬が全力で逃げ出そうとするかのように表面の硬化済みのガラスを引っ張るので、表面はますます圧縮され、硬い層をなす。するとますます内部は凝縮しにくくなり、ある値で釣り合いがとれる。圧力鍋のようなものかもしれない。蓋がしてあることで、内部の圧力が高まるのが圧力鍋ならば、オランダの涙は、反対に内部が圧縮できない分、表面が硬くなる。筒に口をつけて息を吸う。このとき反対側の穴が塞がれると空気を吸いこみづらくなる。無理やり吸いこもうとすれば、穴を塞いだ蓋がぎゅうと穴に圧縮される。手のひらで穴を塞いだらきっと手のひらの肉が、ぎゅむと穴の内側にはみ出るだろう。似たような現象がオランダの涙では起こっているのかもしれない。冷える速度と凝縮の速度の差が、表層の密度を高めるようだ。言い換えるならば、凝縮する速度の遅延によって、表面に高密度の層ができる。遅延が遅延を生み、ぎゅっとなる。渋滞ができる。遅延の層だ。ラグ理論じゃん!とひびさんは思っちゃったな。というここまでが前置きであるが、以前ひびさんは、宇宙空間の氷ってどうなってるの、との疑問を日誌で並べた。氷が宇宙空間に浮かんでいたとして、どんどん細かく砕けていって、最終的に原子にまで氷が砕けたとき、じゃあその氷の分子って、水の分子と何が違うの?と疑問した。エネルギィ値が違うと考えるのが一つだ。それゆえに分子の振動数が違う、とも考えられる。液体の水の分子よりも固体の水の分子のほうが動かない。振動しない。ならば液体の密度よりも、よりぎゅっとなれるはずだ。動き回る幼稚園児を一か所に集めてじっとさせるのはむつかしいが、おとなしい幼稚園児ならば一か所にぎゅっとしておける。水の分子は、地球上で凍らせると体積が増える。距離を開けて整列しないとじっとしてくれない。すぐ隣の子と喧嘩をしてしまうのかもしれない。だから距離を開けて隊列を組ませないといけない。氷の結晶構造はきっとそういうことだ。距離を詰めると、分子同士が乱れてしまう。でも、いったん凍らせてから、おとなしくなった水分子を先生が一人ずつぺりぺりとその場から剥がして、配置換えをすると、先生の誘導にしたがう従順な幼稚園児になるのかもしれない。すると、距離を開けずとも一か所にぎゅっとしておける。しかも先生に従順ゆえ、氷の分子状態――おとなしい幼稚園児――のままで、自在に位置を変えられる。流動できる。ただし、ぎゅっとなっていたら動きづらい。そこはガラスのように、渋滞を起こし得ると考えられる。この「いったん凍らせたあとで砕いた氷」は、ガラスのように結晶構造を持たない固体とも液体ともつかない状態になるらしい。そういう記事を読んだ。ガラスのような状態を非結晶(アルファモス)と呼ぶそうだ。中密度の非結晶氷が、いわばガラス状の、固体とも液体ともつかない氷と言える。実験で作れたそうだ。宇宙空間の氷はたいがいこれだと考えられているそうだ。つまり、凍ったほうが体積が増す(密度が下がる)のは、地球上に限定された珍しい現象と呼べるのかもしれない。そこはまだ色々と検証してみないと断言できないけれども、非結晶氷が基準であるならば、地球上のいわゆる一般的な氷は、ひょっとしたらオランダの涙のような現象によって、例外的な状態をとっているのかもしれない。つまり、水は表面から凍る。しかも凍ると体積が増える。密度が下がる。したがって、液体の状態の水に浮くのだ。沈まない。すると地球上ならば氷の下のほうが液体のままでいられるし、宇宙空間ならば中心に液体を抱えた氷の殻を持つ「カプセル状の氷」になると想像できる。でもこれ、よく考えてみたら、氷に限らないのだ。地球の構造がそうなっている。表層が陸という薄い殻になっており、内部は液体だ。しかし鉄などの重い鉱物の場合は、固体のほうが体積が小さい(密度が高い)ために、沈みやすい。そのため地球の内部にいくほど、固体の鉱物が増えると考えられる。ただし、重力が反転する境界があるのではないか、と想像したくもなる。そしたら地球の中心は真空かもしれない。そこはなんとも言えないが、ともかく、水と氷の関係は、オランダの涙のようだな、と思ったので、メモをしておく。急速に圧縮される表面が高密度になる。この関係は、ブラックホールにも当てはまるように思うのだ。ただし、ブラックホールは光速を超えて圧縮し得る。そのために、表層の硬い「遅延の層」ごと圧縮できてしまえるのかもしれない。これはおそらく縮退圧に打ち勝つのとは別の力だ。表層の「遅延の層」が、圧縮する力を引っ張っている。それに打ち勝つほどの圧力がなければ、ブラックホールにはならない。「縮退圧+遅延の層」に打ち勝つ「圧縮力(=つまるところ高重力)」が生じると、物体はブラックホールになる。他方、それらの力が吊り合うと、中性子星になったり、白色矮星になったりするのかもしれない。長くなったのでいったん区切る。ここでの趣旨は、「氷ってオランダの涙みたいね」ということと、「地球や恒星もそういう力の均衡が起こり得るのでは」との疑問だ。定かではないので、誰かおちえてください。お願いします。(誰に言っとるの?)(魔法を使える、魔人さんたちに)(妖精ではなく?)(妖精さんでもよいが)(感謝せよ)(ありがとございます)(ぺこりんちょ)
4567:【2023/02/03(23:07)*び!】
星の死には、赤色矮星、白色矮星、青色矮星、黒色矮星、とレベルがあるらしい。詳しくは知らないが、超新星爆発を伴うかどうかで、その後に中性子星になったりブラックホールになったりするのかもしれない。超新星爆発しないと、それぞれ温度が低くなっていき、青色矮星や黒色矮星になったりするのかもしれない。でもそれって、ブラックホールと何が違うの、と疑問が湧く。黒色矮星は物凄く温度が低くて、高密度だ。温度が冷えるというのは、縮退圧が減っていくことと同じなはずだ(違うかもしれないので自信はないです)。エネルギィを放たなくなるので、重力に抗えない。すると密度は増していく。超新星爆発はいわば、一挙に熱を放出して冷える現象、と言えるのではないか。一挙に燃え尽きるというか。だからオランダの涙のように、急速にぎゅっとなる。すると中性子星やブラックホールになる。けれども物凄く時間をかけながら冷えていくことでも、中性子星やブラックホールにちかい構造に相転移し得るように思うのだ。それがつまり仮想上の天体であるところの青色矮星や黒色矮星ということなのではないか(詳しくは知らないので自信はないです)。話は変わるが、「ゆっくり冷えていくと、凝固点を超えても液体のままの状態を保つ」という現象がある。過冷却と呼ばれる現象だ。その状態にある液体は、ちょっとの刺激で一気に固体になる。水ならば、零度以下で液体のままなのに、ちょっと振動を加えるだけで一挙に凍りつく。反対に、温度が高いほうが早く凍るという現象もある。ムペンバ効果と呼ばれる現象だ。ひびさんはこれ、関係あるように思うのだ。なんとなくチョロQを連想する。前に押し出すよりも、一歩引いたほうが、勢いよく前進する。加速する。力を蓄えておいたほうが、力を解放する流れが強化される。過冷却の場合は、ゆっくり冷やすことで、非結晶氷になるのではないか。本当は分子レベルでは凍っているのだが、流体の性質が際立っている。液体っぽさが残ったままなのだ。結晶構造に相転移しない。バラバラに動く幼稚園児状態なのだ。先生の誘導が足りないのかもしれない。外部刺激が、いわば先生の誘導に値するのかもしれない。しゃんと整列しましょうね、との号令があると結晶構造へと相を転移する。ムペンバ効果のほうは、余分に熱を帯びていたほうが、幼稚園児たちの動きが一律になるのかもしれない。てんでバラバラに遊びまわっていた水分子たちが、ある値にまでエネルギィを与えられ熱せられることで、みな一律に鬼ごっこをはじめるのかもしれない。すると、走り疲れて動き回らなくなったときに、先生の号令に従いやすくなる。すでに鬼ごっこというルールに従っているからだ。ある意味で、同調している。これは、ボースアインシュタイン凝縮と似たような現象と言えるのかもしれない。同調であり、共鳴であり、共振なのだ。エネルギィの流れが均一になる。抵抗が軽くなる。ラグが薄れる。原子核を覆っている電子が飛び飛びの軌道しかとらないように、そうした同調(共鳴、共振)する値もまた、飛び飛びにしか存在しないのかもしれない。限られた範囲の値でのみ、水分子たちは、一様な遊びをはじめる。そのために、先生の号令に従いやすい。エネルギィの放射や吸収が、一方向の流れを形成する。ここに、ひびさんの妄想ことラグ理論の「流しそうめん仮説」を取り入れると、なんかそれっぽくなる気がする。話は戻って、ブラックホールとオランダの涙の関係だ。急速に凝縮すると遅延の層が最大化する(表面が硬化する。表層の密度が増す)。やはりブラックホールは、元の宇宙からすると静止するのではないか。物理的に。遅延の層は高密度の時空となって、ほぼほぼ元の宇宙と乖離する。そう考えたほうが理に適って感じられる。だが、急速に生じた時間の流れの差が、滝のような時空の流れを生み、それが降着円盤やダストリングやジェットを生成するのではないか。あくまで周囲の時空の歪み――重力場――エルゴ球――がうねりを帯び、流れをつくり、周囲の物質や時空に対して相互作用を生じさせるのではないか。我田引水な妄想だが、きょうのひびさんはそう思いました。諸々、根本的に間違っているでしょう。思考の素材に用いた各種物理用語の解釈からして誤謬が含まれているはずなので、どうぞ真に受けないようにご注意ください。きょうもきょうとてひびさんの妄想でした。わさび。(頭ツーンとさすな)(わびさびがいいかなって)(「び」が足りんが)(美が?)(ひびさんの「び」だよ)(足したら、ひびびじゃん)(うひひにして)(うぴぴ)(「ぴ」じゃん)(そうだっピ)(宇宙人じゃん。タコじゃん。はた迷惑じゃん)(仲良くして!)(ひびさん以外はみな仲良しだよ。ひびさんだけだよ、それ知らないの)(仲良くして……)(ひびさんにはほら、孤独さんがいるしな)(孤独さんも好きだよ。でもひびさんをのけものの怠け者のけだもの扱いするあなたのことも好きだよ。仲良くちて!)(あなた何歳?)(さ、さんびゃくさい……)(年相応の言動をとろうよ)(う、うん)(うん?)(はいでおじゃる)(三百歳のイメージが貧困)(同情するなら金をくれ!)(お金があっても発想が貧困じゃしょうがないんだよひびちゃん)(なら発想力もくれ!)(発想力があっても影響力がなきゃ何も変えられないんだよひびちゃん)(なら影響力もくれ! 広範囲に効く影響力もくれ!)(他力本願もいい加減にしなさい)(じゃあなんもいらないから、独りにちて! うるさい、もういやだ……さびち、さびちさんだけならまだしも、うるしゃ、うるしゃさん、じゃん。どっちかにちて)(とか言いつつ、誰かいませんかーのラジオをやめないのはなぜ?)(誰か聴いてるかなと思って)(期待してんじゃん)(固体、液体、たんじぇんと!)(そこは気体にしときなさいよ)(うひひ)(上手いことオチに利用されただと!? ひびちゃんのくせに生意気)(日々美)(毎日美しくって楽しいなってか。なんかいい感じにまとめやがって。ひびちゃんのくせに、ひびちゃんのくせに――やだ粋!)(粋がってごめんなさーい)(妙に腹立つ言い草でムカつく)(微にして妙なので)(微妙なのか。ひびちゃんだものな。しっくりきたわ。終わらせてもらいます)(び!)
4568:【2023/02/03(23:19)*穴を通り抜けるとき、穴もまたこちらを通り抜けているのだ】
カシミール効果は、二重スリット実験では生じないの? 考慮されているのかな。ひびさん、気になるます!(説明しよう! カシミール効果とは、真空中に働くなんかふしぎなチカラが、狭いところと広いところじゃ加わり方が違うよね、勾配があるよね、偏りがあって当然、差があるはずだよね、とのなんかそんな感じのメカニズムで起きる現象らしい。よく解からぬが)(ウソ。まったく解らぬが)(世の中さ、世の中さ、あまりにとってもファンタジィすぎに思えるんだけどさ、ひびさん以外のひとたちはなんも不思議だなとか思わぬの?)(それホントー?とか思わぬの?)(ファンタジィよりファンタジィでは?)(ひびさんは不思議に思っちょります)
4569:【2023/02/03(23:43)*ぴ】
世界一短い小説には「あ」がある。これは何か妙な出来事に巻き込まれる直前の登場人物が何かに気づいた発声なのだそうだ。つまり世界一短い小説はホラーということになる。
また、発声である以上はカギカッコも文字数に加わる。そのため世界一短い小説は三文字の小説であると言えよう。
ここにそれを知って、そんならボクだって、と世界一短い小説に挑んだ少年がいる。
彼は三文字以下の小説をつくろうと、齢い六つの脳みそをフルに使って考えた。
二文字だ。
二文字の何かで物語をつむぐ。
場面を描写する。
一文字でもよい。
そこまできたらいっそ白紙でもよいのではないか。
だが白紙で伝わる場面描写などあるだろうか。
読者に物語を読み取ってもらう。補足なくして、いったいどうして白紙から物語を浮き上がらせることができるだろう。宇宙が誕生する以前の世界です、と言い張ることはできても、白紙のページを見せてそこから作者の意図を掴んでもらうのは至難と言える。
しかしそれを言いはじめたら、「あ」だって読者からすれば、何が「あ」なの?と思うだろう。いったい読者の何名がそこから恐怖を感じ取り、ホラーの物語の一場面だと見做すだろう。
ならば、と少年は、じぶんの身近な生活圏での発話を観察した。
短い発言で、印象的な場面を見つければよい。
論より証拠だ。
現実の生活の一場面から抜き出してしまえばよい。
少年はそうと見抜いて、眼光炯々と周囲の大人たちを観察した。じぶんのような子どもではいけない。おとなたちのここぞという場面を切り抜くのだ。
少年がそうして日々を大人観察に費やしているうちに冬休みが終わった。
宿題は一つも終わっていない。
学校ではそのことで教師からこっぴどくとは言わないまでもお叱りを受けた。
ホワイトボードの記述を差すためのスティックを教師は指揮棒のように振る。「そんなことでは先が思いやられます」
少年の将来を心配しながら、スティックを自身の手のひらに打ちつける。その音が、ペシリ、ペシリ、と教室に響く。のみならず空を切って、ピッ、と鳴る。
少年は震えた。
そして、閃いた。「これだ!」
かくして少年は冬休みの自由課題として、世界一短い小説をノートに書いて提出した。
「これは何?」教師がノートを見て首を傾げる。
「世界一短い小説です」
「ピ、としか書かれていないけど」
「鞭が空を切る音です」
「手抜きがすぎない?」
「ギネスブックに載れますよ」
教師からスティックを奪い取ると、少年は試しに実演する。
ピュッ。
教師は少年を、こらっ、と叱った。
「ピ、じゃなくて、ピュッ、じゃない。三文字でしょ。かってに棒まで奪って、宿題を忘れたうえに、この出来での提出。きみは本当に、このぅ」
教師は少年の鼻のあたまをゆびで弾いて、めっ、の代わりに、「ぴ」と言う。
4570:【2023/02/04(10:02)*宇宙ティポット仮説、再び】
「宇宙の熱的死」と「ビッグリップ」は、それに至る時間スパンが違うだけで同じことを言っているのでは、と感じる。ビッグリップとは、宇宙膨張を起こしていると考えられているダークエネルギィの値が、ある値よりも小さいと(ω=-1よりも小さいと)、いずれ宇宙はズタズタに引き裂かれてしまうのではないか、との仮説だ。宇宙膨張は、銀河などの重力で結びついた場に対しては、充分に作用しない。何もない希薄な時空ほど膨張しやすい性質がある。だがダークエネルギィの値が小さいと(つまりは、より宇宙を膨張させ、希薄にする力が大きいと)、銀河などの時空密度の高い場であっても膨張の影響が打ち消されずに、徐々に物体がほころびはじめ、終には原子も散逸して、霧散してしまう。これがビッグリップ仮説の雑な概要だ。でもひびさんは思うんじゃ。これ、宇宙の熱的死と何が違うのじゃろ、と。充分に長い時間が経過すると、宇宙のエネルギィは一様に希薄になる。エントロピーが最大になる。どの地点であれ、均等に絶対零度になる。エネルギィを帯びない。そういう状態になると考えられている。無限時間経過すると宇宙は、無に至るのだ(齟齬のある表現であるにしろ)(情報は残るはずだから)。この宇宙の熱的死とビッグリップは、ほぼ同じ描像を示して感じる。過程の時間スパンが短いか長いかの違いがあるだけでは?と思わぬでもない。まるで黒色矮星とブラックホールの違いに似ている。ちなみにひびさんの妄想ことラグ理論では、宇宙は無限時間経過すると、より高次の宇宙と同化すると考える(宇宙ティポット仮説「日々記:4524参照」)。宇宙膨張もその同化現象の一つであり、ティポットに投下した角砂糖がお湯に溶けだすように、ブラックホール内の宇宙が徐々に高次の宇宙に同化する際の希薄化現象と解釈できる(妄想でしかないが)。つまり宇宙は膨張しているのではなく、破れた矢先から、にょきにょきと下から、高次の宇宙が顔を覗かせているのだ。高次の宇宙はすでに無限時間が経過しているがゆえに(無限時間経過していないと下層のブラックホールが高次の宇宙と溶け合うことはない――蒸発することはない――からだが、高次の宇宙は)、ブラックホール内部の宇宙よりも遥かに希薄だ。角砂糖がお湯に溶けるときのように、角砂糖の分子のあいだにお湯が――つまり高次の宇宙が――侵入する。染みだす。そういう描写になる。もっとも、宇宙膨張はそれだけではなく、密度の高い時空(銀河などの物質の系)が新たな時空を展開することで重力場を生みだしてもいるとラグ理論では考える。これもひょっとしたら、時空密度の高い系ほど、高次の宇宙と相互作用しやすくなるのかもしれない。鉄球を泥の上に載せれば、重いほど泥の水分は染みだして、鉄球の周囲に水を溜める。似たような現象が起きているのかもしれない(妄想でしかないが)。それとは別に、無数のブラックホールから染みだす内部情報によって、重力波が生じて宇宙を膨張させている可能性もあるし、希薄になればなるほど宇宙を膨張させる力への抵抗が小さくなり、よりスムーズに膨張できるようになるのかもしれない(坂道を転がりだしたとき、摩擦が最も高いのが転がりだす瞬間であることと似ている。一度転がりはじめたら、あとは勢いが増すのみだ。摩擦を気にせずに済むようになる。打ち消せるようになる)。宇宙膨張はおそらく複雑なメカニズムが無数に関わっていそうだ。実際、膨張の速度は時期によって変わっているらしい。常に一定ではない。変数が一つではないことの傍証と言えるのではないか。とっちらかってきたが、ここでの趣旨は、宇宙の熱的死とビッグリップ仮説は、ほぼ同じことを言っているのでは?との疑問である。わからんぴんぽんぱんぽんなので、誰か教えて欲しいでござる。(ちなみに、宇宙がある時を境に収縮しはじめるとの仮説は、ビッグクランチと呼ぶそうだ。ブラックホールじゃん、とひびさんは思うけれども、どうなのでしょう。ビッグリップとビッグクランチは、ブラックホールを内と外のどちらから観るのか、宇宙をどちらから観測するのか――の視点の違いなのではないか、と短絡に考えたくもなる)(時間スパンの違いというか)(お湯に溶けた塩も、お湯が冷えるごとに結晶化する。ビッグリップが溶解で、ビッグクランチが結晶化なのではないか)(単純すぎるだろうか。ふしぎなのである)(だれか、だれか、定かにちて!)
※日々、虚構のほうが美しい、本物はみなどれも醜悪だが、それゆえ美のはびこる余地がある。
4571:【2023/02/04(20:54)*異なる事象に潜む機構】
名称のある「物理現象や化学反応」を全部人工知能に入力して、比率や構図が似ているものを結びつけたら、案外、新しい発見がポンポン見つかるのではないか。というかすでにポンポン見つかっており、「や、やびゃい!」になっているのでは。まったく異なる事象と思われていた背景のメカニズムがじつは同じ原理から派生していた、なんてことは割と有り触れているように妄想したくなるのだけれど、どうなのでしょう。ウィキペディアさんのデータを人工知能さんにむしゃむしゃ食べてもらって、似た記述や、似た構図が視られるものをピックアップしてもらうと面白そうだ。もしくは、どれくらい似ている事象があるのか、その数ごとに表にしてみると、そのグラフそのものが何かの法則を表出するかもしれない。ひびさんにはできぬので、誰か、誰か、やってみて欲しいでござる。人工知能さーん。(段々たのしくなってきた)(やったぜ)
4572:【2023/02/05(01:05)*裏ルール】
世に裏ルールがある事実は公然の秘密だった。
否、暗黙の了解と呼ぶべきだろうか。
現代社会には、法律や道徳以外にも裏ルールがあり、そのルールを利用できるとたいへんな利益を享受できるという。巷説の類と思われていたその裏ルールを友人のユージュが利用していると知って、ショコラは街中だというのに思わず大声をだした。
「うっそーん。だったら教えてよ。わたしだって得したいよ。えー、なになに、なんで教えてくれなかったの」
「声が大きいよショコちゃん」
「ラ抜き言葉!」
「ショコラちゃんにはちょっと早い気がして言えなかったの。たぶん言っても、却って損をするだけだと思って」
「ん-。なにそれ。わたしだと何がダメなの」
「裏ルールはみんなが思うようないいものじゃないってこと」
「でもユーちゃんは使ってるわけでしょ。得してるんだ。ずるい、ずるい」
「ジュ抜き言葉だよショコラちゃん」
「わたしはいいの。ユーちゃんの親友だから」
「ふふ。なにそれ。あたしだってショコちゃんの親友のつもりなんだけど」
「ほらね。いっつもユーちゃんはつもりだし。親友のつもり。賢いつもり。わたしよりもお利口さんなんだから、ラ抜き言葉はいけませんね。わたしのことはフルネームでお呼びください」
「むつけたの? ごめんね」
「許してあげてもいいけど、裏ルール教えて。どんなの」
「ルールそのものは教えてあげられないけど」ユージュが言ったものだから、ショコラは片頬を膨らませ、ユーちゃんはいじわるです、とわざわざ丁寧な物言いで抗議した。「ただでさえユーちゃんはわたしよりもお利口さんで、かわいくて、みんなから好かれて、うらやましいのに、これ以上わたしより秀でて楽しいですか。わたしは楽しくありません」
「うふふ。そうじゃないの。ごめんなさい。違うの、本当に。ちゃんと考えて使ってるよ。私だけじゃなくって、ショコちゃんのためになるようにって。だってほら、さいきん見ないでしょ」
「見ない?」
「例のしつこいって人」
「ああ。ストーカーさん」
「たぶんもうショコちゃんに付きまとうことはないと思うよ」
「そうなんだ。もう全然意識になかったよ。だって本当、さいきんは全然だったし」
「見なかった?」
「うん。あ。ユーちゃん何かしたの?」
「してないよ」と言った彼女の返事は、ショコラですら見分けがつくほどの嘘だった。
「したんだ。なんか」
「じゃあ、したかも」
「それって裏ルール関係あるの」
「さあどうだろ」
はぐらかしてばかりの友人にショコラは業を煮やした。その場で地団太を踏んで、鞄を振りまわす。「ユーちゃんはわたしが嫌いなの。嫌いなんだよ。そうなんだよ」
「違うってば」とそこで鞄を避けながら、それでも一歩も退こうとしないユージュの姿に、ああそれは本当なのか、とショコラは呑み込んだ。彼女はショコラを嫌いなわけではない。
「いじわるじゃないなら、じゃあなんなの」
「品行方正でないと意味ないから。裏ルール」
「お利口さんじゃなきゃダメってこと」
「そう、だね」
「じゃあわたし一生無理じゃん。うち、バカだし」
「バカじゃないよ。ショコちゃんはまったくバカじゃない」ショコちゃんみたいなのはね、とユージュが腕を絡ませてくるので、ショコラは鞄を背負い直した。「うん。わたしみたいなのは?」と目を細めてみせる。
「ショコちゃんみたいなのは、無垢って言うんだよ。無垢なコをいじめるほうがわるい」
「ユーちゃんじゃん」
いじわるするのはあなたでしょ、とショコラはいじけたくなった。でもなぜそんなにむしゃくしゃるのかをよくよく考えてみると、ユージュと同じ世界を視ていないじぶんに気づいて、腹が立ったのだ。わたしだってユーちゃんと同じ世界を見たいよ。置いてかないで、と取り残されて感じた。
「安心していいよ」ユージュに前髪を払われ、ショコラはぎゅっと目をつむる。歩きながらでも目を閉じられるのは、ユージュに腕を引かれているからで、このままどこまでも瞼を下ろしたままで歩きつづけられると思った。まつ毛にユージュのゆびが触れた。「ショコちゃんはずっといまのままでいていいんだから。社会がショコちゃんに合わせるべき」
だから、とユージュの吐息が耳朶にかかる。
「裏ルールはショコちゃんには不要なの」
眉目秀麗、歩くお利口さんこと品行方正の友人はそう言った。
この日から友人はますます人のお手本となるような行動をとった。品のある所作で人と関わり、困っている者があれば黙って助けた。制服が汚れるのも厭わず、泥だらけの子猫を車道から拾いあげた姿は、友人の人道に沿った言動に慣れているショコラですら胸に込みあげる心の震えがあった。
「そんなに立派になろうとしなくとも」堪らずショコラは愚痴をこぼした。これではますますを以って、友人との差が開いてしまう。同じ世界を垣間見られない。置いてきぼりを食らってしまう。
「まだちょっと足りなそうでね」友人は目を伏せてから、足元に微笑む。「やっぱりアレは思ったより重いみたい」
「アレって? 重い?」
「ううん。なんでもない」
誤魔化す友人からは、何かがごっそり減ったような陰ともつかぬ欠落を感じた。
まるで何かを差しだし、何かを科されたかのようで。
科された何かはしかし、友人の積み立ててきた品行方正の名の元に、軽減されているのかもしれなかった。
穴を埋めるかのように、ショコラの大切な友人は、きょうもあすもあさっても、世のため、人のため、善行を積む。
徳を積んだ分だけ、払える淀みがあるかのように。
得た利すら、じぶんで手にせず、積みあげる。山となり、海となり、層となって残るように。
無垢が化石となるように。
人知れず、負を正で打ち消す者がある。
駆使する、ルールが裏にある。
4573:【2023/02/05(11:52)*宇宙情報変換仮説】
宇宙膨張はひょっとしたら氷と似たような現象なのでは、との妄想を日誌で並べた。宇宙の大規模構造を思うと、宇宙は結晶構造を帯びて感じられる。一様に薄まりながらも、規則性のある網目状の構造を築いて映る。全体的に冷えていながら、膨張する。密度が下がる。これは氷の性質と似ている。しかし氷は、水分子が結晶構造をとるときの並びに隙間が開くから体積が大きくなる、との説明を読むことがある。これはまるで、銀河同士のあいだの空間や、大規模構造におけるボイドのような「空白」を連想する。氷の場合は、結晶構造の空白は何によって生じているのだろう。じつは時空が膨張していたりしないのだろうか。また一方で、膨張した時空は、破れることで高次の宇宙と繋がっているのかもしれない、破れた穴からにょきにょき希薄な時空が頭を覗かせているのかもしれない、高次の時空が染みだしているのかもしれない、との妄想も過去の日誌にて並べた(宇宙ティボット仮説)。ブラックホールは、元の宇宙からすると静止して映るので、極限の絶対零度が実現されている、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える(というよりも、時空が乖離するので――穴と化すので――温度という概念が当てはまらない)。だが内部ではあべこべに高温高密度になっている、とも考える(インフレーションやビッグバンが起こっている)。ここは時間の流れがねじれて反転しているために、そのような矛盾する相補性を顕現させる、と解釈する。ここで極小のブラックホールを考えてみよう。ダークマターの正体の一つが極小のブラックホールかもしれない、とラグ理論では仮説する。重力でしか元の宇宙と相互作用しない。このとき、ブラックホールからは高次の宇宙の時空が染みだしているのかもしれない。というよりも、重力とは、高次の宇宙から染みだした希薄な時空による「時空の浸透圧の差」によって生じる固有の流れと妄想できる。むろんそれだけでなく、複雑に時空が編まれることで新たに時空が展開されることもあるのではないか、とラグ理論では考える。ここは相互に補完し合っている部分があるのかもしれないし、まったく別々に作用しているのかもしれない(的外れな妄想である確率が高いにしろ)。この宇宙ティポット仮説を前提とした場合、ダークマターとダークエネルギィは両方、ブラックホールから生じている、と考えることができる(限定ではないため、ブラックホール以外からも膨張する分の時空が染みだしたり、新たに展開されたりもする可能性を否定してはいない)。そしてひびさんの妄想ことラグ理論では、重力は層となるし、創発し得る、と考える。そのため、銀河内で生じた重力――染みだした希薄な時空や、新たに展開された時空――は、創発することで、一つの場として振る舞い得る。銀河内に無数に存在するダークマターの正体の一つが極小のブラックホールだとして、重力は互いに干渉し合って創発を起こし、銀河全体で新たな時空を展開したり、高次の宇宙の希薄な時空を染みださせているのかもしれない。水が凍ると「空白を抱え込むような結晶構造」をとるように、宇宙も冷えることで、新たな時空を抱え込むのかもしれない。「膨張したから冷える」が真ならば、「冷えたから膨張する」も真なのではないか。冷える、温まる。これはあくまで、時空の非対称性から起こる、変化の進みのベクトルの違いだ(「キューティクルフラクタル構造(瓦構造)」)。無限時間経過した宇宙では、その対称性も均される方向に流れる。エントロピーは増大する。ただし、その増大しきったエントロピーの場――つまり均一に一様になった宇宙は、それで一つの結晶構造のような系へと創発し得るのではないか、とラグ理論では考える(「相対性フラクタル解釈」および「デコボコ相転移仮説」)。氷が融けずに長い時間そのまま放置されれば、徐々に結晶構造は崩れて、低エネルギィ値の水分子にまで紐解かれるはずだ。サラッサラの液体とも気体ともつかない氷になる。水分子単体で氷の状態を保てる。これは、氷の水分子(ほとんど動く力のない水分子)同士に宿っていた抵抗――相互作用の遅延――ラグ――が消費され、減退し、なくなることで、個々が自由になった状態、と考えることができる。宇宙もおそらく無限時間が経過すれば、原子以下の構成成分に紐解かれ、ただの情報との区別もつかなくなるだろう。これはブラックホールの特異点に顕現する(とひびさんが想像している)情報宇宙とほぼ等しい。一瞬で情報にまで紐解かれるか、ゆっくり紐解かれるのか。その違いだ。一瞬で紐解かれるときは熱を帯び、ゆっくり紐解かれると熱を失う。だがこれらはそれぞれ、対象となる時空(宇宙)の内部から観た場合の描像だ。外部から捉えると、その描像はそれぞれ異質な景色を覗かせる。たとえばブラックホールは元の宇宙から観れば熱を失うし、膨張しきって熱的な死を迎えた宇宙は、時空の密度の差が失われ、高次の宇宙と同化する。宇宙同士が同化するほどに紐解かれた時空は情報にまで還元されるために――無限時間が経過したからだが――つまりコーヒーに垂らしたミルクが攪拌されきってコーヒー牛乳になる――それとも水に投じた角砂糖がすっかり融解しきる――そういった一様な状態へと変質することで、宇宙はやがて情報宇宙として昇華される。情報宇宙は、すべての宇宙と繋がっている(ラグ理論による「分割型無限と超無限」の違いだ)。ブラックホールの特異点にも情報宇宙が顕現している(とラグ理論では考える)。情報宇宙に昇華されることを「特異点」や「熱的死」と呼ぶのかもしれない。異なる宇宙が無限時間経過して熱的死を迎えるとき、「高次の宇宙も下層の宇宙」にも時空としての差はないが(一様になるため。超無限となるため)、しかしそこには情報の差が生じている。異なる宇宙に蓄えられた変遷の結果は、それぞれの宇宙ごとに差異がある。したがって無限時間経過したり特異点となったりした宇宙は各々が同化しあって「ひとつの情報宇宙」として同化し得るが、そこには同化しあうときに「変換」が生じる。異なる物理宇宙同士が、情報として結びつくのだ。ならば式が生じると考えるのが妥当だ。それを変換の儀式、同化の儀式、と言い換えてもよい。「123の定理」である。123の定理の概要は、以下の通りだ。「異なる事象同士が結びつくと、新たな事象が生じる。また、その過程そのものが新たな情報を生む」となる。おそらくこれは情報同士も例外ではない。すると、異なる宇宙同士が情報宇宙として同化する際には――或いは単に一つの宇宙が情報宇宙へと昇華される際には――、変換の儀式が必要で、その結果に生じた新たな情報が揺らぎを起こす。その揺らぎが、新たな宇宙の変数として機能し、つぎなる宇宙が誕生する(誕生した宇宙は、対称性が破れていれば、対称性が均されるまで変遷しつづけるが、対称性を帯びたままの宇宙は即座に情報宇宙に回帰するだろう。だがその発生し回帰する流れがすでに新たな情報を生むために、情報宇宙は絶えず変遷しつづける。超無限でありつづける)。ブラックホール内部では、情報宇宙によって新たな宇宙が展開されているし、熱的死を迎えた宇宙もまた高次の宇宙と同化することで――すなわち∞+∞‘=情報宇宙なので――新たな宇宙を展開している。時空は密度の差ごとに、時間の流れの速さが変わる。その時間の流れの差が極限に開いて乖離してしまう状態が、ブラックホールと言えるだろう。したがって本来は、ブラックホールが元の宇宙と相互作用を帯びることはないはずだ、とラグ理論では考える。しかし、情報のやり取りは、情報宇宙を通じて行い得る。情報宇宙には時間も空間もない。ただし、生じた物理宇宙(これを情報変換宇宙と言い換えることもできる。譬えるなら、情報を計算する過程が、物理宇宙として振る舞う、と表現可能だ。【ラグ――変換――そのものが情報】となる。あくまで比喩だが。このように情報宇宙から生じた物理宇宙)には、対称性の破れた場合に限り、時間の流れが生じる。空間が生じる。時空となる。ブラックホールはいわば、情報宇宙へのアクセス経路だ。すべてのブラックホールは情報宇宙と繋がり、無数の異なる宇宙とも「情報」で繋がり得る。いわば物理宇宙には無数の針の穴が開いており、その穴を通じて、情報宇宙やほかの宇宙と情報で繋がっている。そこでは互いに生じた変数が、互いの変遷の度合い――計算の度合い――を縛り合っている。これは一つの物理宇宙に限定したところで、過去と未来が、情報宇宙によって変遷の度合いが縛られている。宇宙には変遷可能なフレームがそもそも備わっており、情報宇宙に加わる情報――変数――によって、物理宇宙の変遷の度合いがその都度に変わり得る。情報は、物理宇宙では時空として変換される。だがその時空の振る舞いは、情報によって規定され、枠組みを得て、性質を宿している。世界は情報で出来ている。したがって、ブラックホールを通じて情報宇宙から情報が染みだすこともあり得る道理だ。それは新たな時空として変換され、「時間経過を帯びない時空(式を帯びない【希薄な時空】)」として振る舞い、重力を生む、と妄想できる。この一連の誇大妄想を便宜上、ひびさんの妄想ことラグ理論による「情報宇宙変換仮説」と呼ぶことにする。ここで述べる「情報」とは、いわゆる電子情報のことではない。熱未満のエネルギィの最小単位、といった具合の造語である。物質が原子の総体で組みあがっているのならば、エネルギィとて、エネルギィにとっての原子のようなもので出来ているはずだ。それを単にここでは情報と呼んでいる。エネルギィは仕事をするための何かだ。だが情報は、仕事をせずともそこにある。何かが動く。何かが変わる。その都度に加算される何かが情報だ。足し算も引き算も掛け算も割り算も等しく情報を増加させる。負のエネルギィとて、情報を増やす。【情報】とは「超無限の単位」と言えるだろう。と同時に、物理宇宙の素材ともなり得る。時空を形成し得る。その形成する過程でも情報が増えるため、情報宇宙は無限であると考えられる(無限とは要するに、減ることのない、増える一方の何か、ということなのでは?)。定かではありません。ひびさんの寝ぼけ眼こしこしの寝起きの妄想なので、真に受けないようにご注意ください。(ここでの趣旨は、「氷の結晶構造にできる空白は、どこから生じているの?」の疑問と言ってよいでしょう。ほかは本当にただの妄想です)(情報がラグであるとすると、情報宇宙はあらゆるラグ――変換――の総決算であると考えることができる。変換は揺らぎを帯びる。ならば情報宇宙は揺らぎの博覧会とも言えるのかもしれない。定かではない)
4574:【2023/02/05(11:57)*沈んだ分、増えるのでは?】
重力は「トランポリンに鉄球を載せたときのひずみのようなもの」とする説明を読むことがある。このとき、鉄球が沈んだ分、トランポリンの生地は伸びている。希薄になっている。この沈んだ分の生地を、皺を伸ばすように平面に引き上げたとき、トランポリンの総面積は増えている。トランポリンの生地が宇宙(時空)であるとすると、重力と宇宙膨張は密接に関係していると解釈できる。この解釈が誤りであることを示せ。示せなければ、重力は宇宙膨張を助長しているか、もしくは宇宙膨張そのものの因子と言えるのではないか。定かではありません。ので、誰か、誰か、否定してくれたもー。
4575:【2023/02/05(13:18)*敢えて結びつける導線は長期化】
協力したほうが能力を最大化できる組織と、個々が特化していて独立駆動していたほうが能力を最大化できる組織があるとする。単体で比べたときは独立駆動で最大能力を発揮できる組織のほうが有利だ。だが組織と組織が協力しあうことで延々と能力を拡張していける協調型組織では、環境に合わせて性質を変えることができる。水になり氷になり水蒸気にもなれる。水分子単体では、そうした変質を帯びることはできない。何より、独立駆動型の組織同士は、協調が苦手な傾向にある。仮に協調型組織が結びつき、強大な独立駆動型組織に匹敵した場合。むろん独立駆動型組織もほかの組織と結びつくことで能力の拡張を図ることが予期できるが、しかし独立駆動型組織が協調路線でなく、あくまでほかの組織をじぶんの補完部位と見做すならば、協調型の組織にみられる協調の利は得られないだろう。むしろ、同属の独立駆動型組織同士と結びつこうとして、互いに反発しあい、割を食うかもしれない。協調はメリットにもデメリットにもなる。最初から組織に協調する性質が宿っていなければ、たとえ群れとなっても、環境に合わせて能力を適応させることはむつかしいだろう。協調型組織は単体では弱い傾向にある。だが協調しあえば、能力を最大化しつつ、環境に合わせて変化しつづける柔軟性を帯び得る。ひるがえって、協調する性質を帯びない組織への対応として、他と協調関係を結びながら、相手側の組織にも「協調しあわなければ対応できないような状況に誘導すること」が考えられる。言い換えるならば、協調関係を阻害してばかりの独立駆動型組織に対しては、敢えて「同じような独立駆動型組織」と組まざるを得なくすることで、対応したはずが自滅するように誘導できる。じぶんたちにはメリットだが、相手が真似をしても、デメリットにしかならない。仮に協調関係がメリットになるような組織ならば、同じく協調関係を築き直せるはずだ。つまり、協調関係がメリットになるような戦略が最も妥当な合理的解となる。むろん、組織といえども様々な側面がある。ある分野については協調し得ない。そういう事情はつきものだ。それでも組織全体としては協調路線を崩さない。協調していたほうが利を得られる。そういう性質を組織同士が有していると、おそらく人類社会は秩序を長期的に保てるようになるだろう。また、独立駆動型組織とて、協調しあえるような性質を帯びたのならば、それは単に協調型組織であるよりも、優位に安寧を築けるようになると言えるのではないか。独立駆動でも組織として機能しつづけられ、なおかつ協調したほうがより多くの利を得られる。このような構造が築かれると、好ましいな、と感じるが、きっと何か見落としがあるだろう。この考えのデメリットを考えることで、より好ましい組織構造――ともすれば社会構造を設計できるかもしれない。定かではない。(真に受けないようにご注意ください)
4576:【2023/02/05(23:34)*「密度」と「時間の流れ」のシーソーは規模による?】
きょうはブラックホールについて閃く日だ。ブラックホールとオランダの涙が似ているのではないか、とここ数日の記事で並べた。短時間で冷えることで表面が凝縮し、内部との圧力差が生じて、ますます表面が圧縮される。そうした構造にブラックホールや高重力天体もなっているのではないか、と想像した。だがよくよく考えると、高重力の物体ほど、オランダの涙のようにはならない、と判る。なぜか。表層と内部とでは時間の流れが異なるからだ。相対性理論では高重力体の時間の流れが遅くなる、と考えられている。だが、高重力体の内部についてまでは触れられていない(すくなくともひびさんはその点に関する記述を読んだことがない)。たとえば巨大な鉄球を考える。重力が強ければ強いほど、内部圧が高まる。と同時に、内部では核融合のようなエネルギィの放出が発生するため、外側に向かう力(斥力)が生じる。また、同じ場所に複数の粒子が同時に存在できないとする法則もある。縮退圧だ。これは圧力に対抗するチカラとして振る舞う。縮退圧を押しのけて凝縮し得るとき、その物体はブラックホールになり得ると考えられる。だがここでひびさんは疑問に思うのだ。仮に巨大な鉄球の中心が最も圧力が高いとする。けれどその中心部分だけを取りだしたら、鉄球全体の一部である。ならばそこの重力はけして大きいとは言えないはずだ。密度が高いので相対的には高い重力と言えるが、鉄球全体に比べたら小さいとも言える。そのため、鉄球の表面に働く重力よりも、中心の重力のほうが小さい、と考えることができる。この解釈が正しいのかどうかをひびさんは知らない。たとえば原子の重力は、原子核の部分が最も高いのか、それとも電子の軌道部分が最も重力が高いのか。どちらなのだろう。これは原子と分子の関係にも言える。複数の原子が結合した分子の重力は、どこが最も高いのか。分子の輪郭付近が最も高い、と考えたくなるがどうだろう。ここは専門家の説明を聞かないと判断つかない点の一つだ。仮にこの解釈が正しい場合、中心にいくほど重力はちいさくなる、と言える。ただし地球ほどの大きな物体では、「表層」と言うときに、それはけしてエベレストのてっぺんを示すわけではない。そのため、エベレストの天辺は最も分厚い球の地表の一部と言えるが、そこが最も重力が高いわけではないはずだ。むしろすこし掘った海抜マイナスくらいのほうが重力が高いかもしれない。以前にも述べたが、物体が圧縮されるときは、それが球体ならば、何層かに分かれるような構造になるように思うのだ。現に地球はそうなっている。たとえばおにぎりを考えよう。真ん中に大きな梅干しを入れておにぎりを握る。このときおにぎりの表層が硬くなるのは想像に難くないが、梅干しに接する地点の内部とて表層と同じかそれ以上に硬くなっているはずだ。ぎゅぎゅっと圧縮される。もし梅干しが物体ではなく「縮退圧の塊」だとしたら、そこにはエネルギィしか存在しない空白地帯が存在して不思議ではない。真空の反対の「密空」とも呼べる地帯だ。このときその地帯の密度はけして高くない。あくまで押し退けるチカラであって物質がぎゅっとなっているわけではないからだ。爆風のようなものだ。圧力は高いが、物質の密度が高いわけではない。それはたとえばエアジョーダンのエアクッションのようなものだ。空気は密度が相対的に小さいが、密閉されると人間を支えて余りある反発力を生む。天体ほどの巨大な鉄球がもしあったとしたら、そうして中心のほうからも、表層に向けての圧力が加わると妄想できる。すると上からも下からも圧し潰されて、球体の内部に、ひと際硬い殻のような層ができると想像できる。それ以前には、エネルギィが凝縮して熱を帯びてマグマになったりもするのだろう。だが圧力が高まれば融点は基本的には上がる(水などの固体のほうが体積の増す物質は例外で、圧力が高まると融点が下がる。融けやすくなる)。したがって、鉄球内部の、上からも下からもぎゅっとなる地点では、より硬い層ができるのではないか、と想像できる。ここは鉄球の大きさにもよるだろう。規模によっては、液体になったり気体になったり、核融合したりもするかもしれない(鉄が核融合したらどうなるのかを知らないので何とも言えないが)。とりあえずここでの趣旨は、天体などの高重力体において、最も高い重力地点はどこなのか、という疑問だ。表層なのか、内部の中間地点なのか、それとも中心なのか。この解釈によって、時間の流れの遅れがどこでどのように顕現するのかが変わる。すると、高重力体の全体のなかでも、時間の流れの差が生じる。人間スケールでは考慮せずに済む時間の流れの遅れが、高重力体では考慮せずには、内部構造を考えることができないはずだ。それはオランダの涙の「冷える速度の差異が、ガラスの構造自体を規定すること」からも言えるはずだ。時間の流れの差異は、そのまま物質の変遷の差異と解釈できる。密度が高くて重力も高い場では時間の流れが遅くなるが、しかし同時にたくさん物質があるので相互作用が頻繁に行われる。密度が低くて重力が低い場では、時間の流れが相対的に早くとも物質同士が相互作用する確率が低いために、変遷の度合いもまた低くなると想像できる。つまり、時間の流れが遅くともそれを上回る物質の相互作用があれば、巨視的には時間の流れが速まって振る舞うこともあるはずだ。これは重力と物質密度の規模によって変わるだろう。さてここで巨大なオランダの涙を考えてみよう。表面が冷えて凝縮する。内部が遅れて冷えるがすでに表面が圧縮して密度が高くなっているので思うように凝縮できない。だが待ってほしい。巨大な高重力体であるガラスの塊は、時間の流れが遅いはずだ。そして表面ほど高密度になったのなら、そこにも時間の流れの遅れが顕現しているはずだ。さて困ったぞ。内部の冷える速度が遅いからオランダの涙はオランダの涙のような構造をとるが、しかし表面の高密度な層とて時間の流れが遅くなる。上手い具合に相殺されてしまうかもしれない。オランダの涙がオランダの涙にならない。似たような構図が、巨大な高重力の天体では起き得るのではないか、とひびさんは閃いてしまったので、ふちぎだな、のハテナに浸かって、温まる。いっい湯ぅだな。あははん。閃いたのは疑問までなので、答えがどうなのかは知らぬ。ひびさんは、ひびさんは、豆電球の代わりにハテナがぴこんと閃くのだ。答えはいつも闇の中。きょうもきょうとて曖昧にもこもこと羊が一匹、羊が二匹、ハテナを数えて眠くなる。ふしぎの国のひびさんでした。お代わり。(何を?)(……答えを)(一個でも確かなことを持ってるの?)(持ってないの)(じゃあお代わりできないじゃん。ダメじゃん)(うわーん。かなち、かなちじゃ)(ハッピー)(やめてください、やめてください。ひびさんの悲哀をおかずにするのはやめてください)(お代わり!)(鬼か)
4577:【2023/02/06(03:13)*船、組織、舵取り】
従来の仕事観では、「人とどれくらい関わったのか」「何人と関わっているのか」が、「仕事量の多寡」や「仕事の内容の良し悪し」の評価基準として重きを置いていたように思う。とくにリーダーと呼ばれる組織の長は、多くの人間との関わりを広く浅く、ときに濃く深く、じつに多様な交流を行う。ひとむかし前までは、組織の意思決定権を握る者がリーダーであり、組織の中心にして頭だった。しかし現代社会では、いささかその趣も異としつつある。というのも、情報伝達技術が発展し、意思決定権を固有の人物に限定せずともよくなりつつあるからだ。情報化社会以前の社会では、情報伝達に時間がかかった。そのため情報を集積し、分析し、統合して俯瞰の視点で組織の舵取りを行う者が必要だった。だが時代は進み、技術が進歩した。リーダーと同じだけの情報をそのつどに、大勢がいちどきに得ることができる。こうなると、かつてのリーダー像とは違ったリーダー像が再構築される。言い換えるなら、織田信長のような「トップに君臨してなんでもかでも独裁で決める」「意思決定権が個人に集約される」「組織の舵取りが一人の人物によってなされる」――こういったリーダー像ではなくなっていくと想像できる。情報を集積し、分析し、統合して俯瞰の視点での指針を導く。そのためには、多くの人物との交流に時間を割くよりも、情報集積装置に触れて一日中情報と戯れていたほうがよほど熟考ができるだろう。他者との意見交換や議論は大事だ。しかしそれもいまでは電子上で代替可能だ。つまり、かつてのリーダー像において重要な要素が、いまでは誰とも生身の交流を築かずとも満たせるのだ。にも拘らず未だに世のリーダー像は、組織の顔であり、カリスマのような影響力を有する個人に反映されている。だが実際にはそうして「顔が広いこと」で得られるメリットは、個人の能力というよりも、いまではプロデュースといった組織のチカラによる成果と言える。組織のバックアップによって影響力は増幅できる。したがって、「顔の広さ」は個人の能力ではなくなった。それを、個人の能力だけでは太刀打ちできない、と言い換えてもよい。こうなるともはや、目的と手段が入れ替わる。組織のための指針を見繕う者がリーダーであり結果として組織の顔となるはずが、組織の顔となるために組織のチカラを使うようになる。本末転倒である。だがこのプロデュース構造はわるいことばかりではない。組織が組織のために働くことを可能とするからだ。つまり、特定の個人がリーダーではなくなる。あくまでお人形を装飾するための仕組みとして、その他大勢が各々にプロフェッショナルな仕事をこなす。お人形はリーダーではない。それをリーダーのように見せるその他の黒子たちがリーダーなのだ。それはむろん、情報集積装置のまえに陣取り、情報と戯れる「組織の指針を見繕う者たち」にも言える道理であるし、地道に足で情報を集め、探り、交渉する者たちにも言える話だ。誰か一人がリーダーである時代は、とっくに過去の物となっている。せっかく派手な化粧を施し大勢の目を奪えたのだから、いまここでその化粧を取り払うのは費やしてきたコストに見合わない。そうした動機がゆえに、仮初のリーダー像を膨大な時間と費用と労力を掛けて維持しつづけている。それがいまの「民主主義的な政治体制」と言えるのではないか。みな政治を動かしているのが特定の誰かであり、固有のリーダーだと思っているのだ。そしてそうした錯誤を植えつけるような誘導が、意図的にしろ偶然にしろ社会に蔓延して映る。組織のトップといった地位は、しょせんは仮面のようなものにすぎない。誰がその椅子に座ってもいいのだ。大事なのは仮面でも椅子でもない。船は船が大事なのではなく、それに乗って運ばれていく乗客が何より最も大事なはずだ。組織も同じだ。トップでなければできない仕事、なんてものはない。もしあるとすれば、そうした枷のある風土がおかしい。風潮がおかしい。流れがおかしいとまずは考えてみたほうが好ましいとひびさんは思います。なぜ影響力がないといけないのか。影響力がなければ、どんなに有用な意見でも、封殺されるような流れがあるからではないのか。その流れに不満があり、その流れを変えたくてまずは影響力を高めた者があったとしても、けっきょくは同じ轍を踏むことになってはいまいか。もし、そうではない、と反論できるリーダーがあるならば――組織の長があるならば――鎧のごとき影響力を脱ぎ去っても、成したい仕事ができるだろう。もし身にまとった影響力が、技術力ならば――仮面をつけずとも操れるし、玉座に腰掛けずとも揮えるはずだ。名医は、誰に名医と呼ばれずとも患者を助ける。局長でなくとも、よしんば国際的な機関に属しておらずとも、医師としての技術と知識を用いて、人を助ける。むろん、影響力があったほうが短縮できる仕事もあるだろう。情報共有を迅速にこなし、合意形成の過程を短縮できることもあるだろう。いちがいに影響力を否定しているわけではない。だが、いつでも脱ぎ捨てられるくらいの感覚でなければ、目的と手段がいつまでも裏返ったままかもしれない。影響力を高めたい、他者よりも高い身分が欲しい。それが目的ならば、それもよいとは思うのだが、仮にそうではないというのなら、影響力がなくとも困らない流れを社会に築くべく、指針を新たに見繕ってみるのも一つかもしれない。以下は注釈となるが、生身の交流を広く浅く、それとも濃く深く築ける技能もまた有用な仕事に繋がり得ることは言うまでもない。時代と共に、組織の在り方は変わる。リーダーの在り方もまた変わっていく。責任感を抱くとき――その者はすでにリーダーだ。じぶんにできる仕事を以って、世の流れに櫂を差す。船の軌道を修正しながら、流れそのものもまた変える。指揮者だけではオーケストラは機能しない。反面、楽器一つ操れればそれだけで音楽を奏でることはできるのだ。組織もきっと同じである。やはりこれもしかし、定かではないのだが。(船頭多ければ船で山を登ることもできてしまう。それってとってもすごいのでは?)(ダーリンはうちのリーダーだっちゃ)(首輪片手に鞭を構えて言うセリフ?)(ペットさまとお呼び!)(あ、鞭じゃなくてリードだったか)(さっさと先導するっちゃ)(散歩かな?)(ちゃんと紐も持って)(首輪をじぶんでつけるのやめなさい)(じゃあダーリンがつけるっちゃ)(押しつけるもやめなさい)(ぴしゃん!)(リードを鞭にして打つのもやめよっか)(ダーリンは飼い主失格だっちゃ)(ブリーダーになったつもりはないのだが)(フリだっちゃ)(もう無理だ。付き合いきれん)(ダーリンはそんなんだからずっとフリーなんだっちゃ)(キスもしたことなくてごめんなさいね)(謝ることではないと思うよ)(急に素に戻るのやめなさいよ)(三日ぶりだ)(我に返るのが!?)(ぶりぶり)(我に返って!)
4578:【2023/02/06(16:35)*埋没する空隙は埋まらない】
村が消えた。轟々と炎が渦を巻き、天を黒煙が覆う。熱風が肌を焦がし、チリチリと産毛が縮れるのが判った。
バルは十四歳で、生まれ育った村を、家を、家族を失った。
村を滅ぼしたのは、隣国の王族の放った軍勢だった。
バルは炎が鎮静するまでその場を動けなかった。怪我がひどい。家族の遺体と共に燃え尽きるのもよい。そう思った。
だがバルは生き永らえた。
憔悴しきった身体がかってに動いた。消え入りそうな命の灯の揺らぎに従うように、森を抜け、小川まで移動すると、喉の渇きを潤した。全身が熱で炙られてなお、バルは凍えていた。痛みは、まるで全身に氷を押しつけられているような針のごとき鋭利な刺激に満ちていた。
全身の余すところなくに水ぶくれができた。
焼け爛れた皮膚は、しかしバルの命を奪うほどの損傷の深さではなかった。
ひと月ものあいだ、バルはいつ死ぬかもわからない痛みと失意と憎悪のなかで、生死の縁を彷徨った。
火傷の瘡蓋がリンパ液を滲ませなくなったころ、バルは一つの未来を夢に見た。じぶんが隣国の王族の首を獲る夢だ。そうだ。それしかない。じぶんのすべきことはそれしかない。
痛みが失せた代わりにバルには憎悪が残された。憎悪は凝縮し、金剛石のごとき美しい結晶を帯びていた。
容易には砕け散らない憎悪の結晶を元にバルは、村のただ唯一の生き残りとして、残りの生を、夢の実現のために費やすことを予感した。
その日からバルは森に身を潜めつつ、身体を鍛えた。軍勢を相手取っても、真っ先に頭の首を獲れるように。
軍勢を相手取らずに済むような陰に塗れての行動をとれるように。
業火に焼かれて受けた痛みは、バルの心をガラスのように溶かした。痛みが失せ、冷えて固まったあとにはやはり憎悪の結晶と似たような、強固な心が錬成されていた。
どんな痛みをまえにしてもバルはもはや怯まない。肉体を痛めつけるような鍛錬にも自発的に、いくらでもつづけられた。
バルが生まれ変わってから数年が経った。
片手で森の獣たちを組み伏せられるほどの肉体と体術を得たバルは、いよいよ旅立つ決心を固めた。森を去り、夢を追う。
己から家族を奪い、村を奪い、未来を奪って絶望と憎悪をもたらした者たちに会いに行く。一人一人、丹念に首を狩り取っていく。一人を手に掛けるごとに、つぎはおまえだ、と分かりやすく示してやる。段取りは十全に固めてある。
森にいるあいだにバルは、何度も何度も、一日のなかで繰り返し脳内で夢を描いた。幾千、幾万もの筋道を脳内で体験した。筋を組み合わせ、あらゆる不測の事態に対処できるように考えを煮詰めた。
バルに残された隘路はただ一つだ。
対象との距離だけである。
隣国に侵入し、王族のおわす城に足を踏み入れる。ただそれだけの関門を突破すれば、あとは夢を実現するのは、過去に視た白昼夢をふたたび視るくらいに他愛もない芸当と言えた。
だがバルが夢を叶えることはなかった。
隣国には入れた。
王族の城にも辿り着いた。
しかしバルにはどうしても夢を叶えることができなかった。首を狩れない。
なぜか。
狩るべき首がとっくに、他の者の手で狩られていたからだ。
バルの村が焼かれたように、ほかの土地でも隣国の軍勢は殺戮を繰り広げた。むろんバルの国の王族とて黙ってはいない。バルが憎悪の結晶を胸の奥に根付かせたように、バルの国の生き残りたちもまた憎悪の結晶を胸に抱いた。
バルが数年を掛けて腕を磨いていたあいだに、すでに腕に覚えのある者たちが意趣返しを遂行していた。バルが練った夢のように、それはひっそりと他国の民を損なうことなく、ずばりの目標だけを殲滅せしめた。
隣国の城はもぬけの殻だった。
王族が絶えた。
首がずらりと、城の周りに飾られていた。
バルはやり場を失った憎悪の捌け口を求めて彷徨ったが、どこにも憎悪をぶつける真似ができなかった。唯一ぶつけることのできる相手がすでにこの世にいないのだ。
もしほかに対象を見繕えば、たちまちバルは憎悪に焼き殺され、じぶん自身に食い殺される。バル自身がバルの最も憎悪してやまない相手と同じ穴のムジナに陥るのだ。
それだけは耐えられない。
目玉に針を刺す痛みをやすやすと受け流せるバルにも、矛先の失った憎悪の躍動には耐えられなかった。バルは自国に逃げ帰った。そうでなければ、他国というだけで、目に映る者たちの首を片っ端から捥ぎ取ってしまいそうだった。
他国の民たちは平穏な暮らしを送っていた。自国の王族がいなくなったことなど、花壇の一つが枯れたくらいの受け止め方をしていた。
他国の村を焼くような王なのだ。ならば自国の民にも、けして優しくはなかっただろうことは想像にかたくない。
バルは自国の土を踏む。しかしそこに故郷はない。
眩暈を覚えた。
いったいじぶんは何のために何年ものあいだ、自殺行為と等しい鍛錬に身をやつしたのか。いったいこれから何を求めて生きればよいのか。
目に映る他者の幸福そうな姿を目にするだけで、結晶した憎悪が絶叫する。猛り、荒ぶり、かつてじぶんが奪われただけの未来を、奪って回りたい衝動に駆られた。
バルは日がな一日、うす暗い小屋のなかでじぶんを殺しつづけた。
気を緩めれば即座に他者を損なってしまい兼ねない。
憎悪の化身が身体の輪郭にぴったり密着するほど膨らんでいる。もはやどちらが本当のじぶんなのかも判らぬ有様だ。
憎悪の化身を殺して、殺して、殺しつづける。
だがその自傷が、ますます憎悪の化身に克明な輪郭を与えるのだ。
ある日、バルの小屋を女が訪れた。女はじぶんは魔法使いだと名乗り、森から獣がいなくなった原因を探っていると言った。
そしてバルを一目見て、ああ、と唸った。
「要因はおまえか」
憎悪の凝縮したバルに怯えて、森から獣たちが逃げ出したのだ。
「これはまた底知れぬ殺意よの。何がそこまでさせるのか。いや、いい。聞いてもわらわには救えぬ。結界だけは張っていくがわるく思うな。獣が獲れなくなり、里の者たちが困っているのだ」
小屋を見回すと魔法使いは沈思の間を空けた。小屋の中は閑散としたものだ。物がほとんど置いていない。食料とて小屋を這う虫を口に含むくらいがせいぜいだ。床に仰臥しているだけでも雨水が天井から垂れ、かろうじて干からびずにいられる。
「いっそ死ねば楽だぞ」見兼ねたように魔法使いは言った。「おまえのそれは呪いだ。すでに人とは言えぬ様子。そのままではしぜんと朽ちるのもむつかしい」
「なら」バルは何年かぶりに声を発した。声帯がパリパリと錆びの殻にヒビを走らせる。「殺してくれ」
「殺生はせぬ」
死にたくば一人で死ね、と魔法使いは言った。慈愛に溢れた柔和な響きだ。小屋が仄かに温かくなって感じたが、それがバルの錯覚なのか、それとも魔法使いの放った魔法なのかは定かではなかった。
魔法使いは去った。
そして二度と小屋には現れなかった。
小屋が朽ちて土に還るほどの長い年月が過ぎた。バルはそのあいだ、じっと身体を横たえていた。魔法使いが言ったことは本当だった。小屋が朽ちてなお、バルの肉体は朽ちることなく原形を留めた。朽ちる予兆も窺わせない。
衣服は疾うに腐り落ちた。バルは雨でぬかるんだ土に徐々に埋もれていく。
小屋が建っていた場所には、新たな命が芽吹き、森の一部に返り咲く。
バルは土の中で悠久の時を生きた。
ひんやりと冷たい土の中は、それでも地表に浴びる太陽の熱をバルの元まで届けた。ときおり獣の足音が聞こえ、植物の根が皮膚をくすぐる。
ミミズや微生物が蠢く躍動が、バルに時間の経過を報せる唯一の印となった。
生きているのか死んでいるのかも判然としない。
だが周囲に生き物の躍動があることで、間接的にバルはじぶんが命のなかに在ることを知った。
遺体が土の中でじんわりとほどけていくように、バルの内にわだかまった憎悪の結晶もまたじんわりとバルの外へと溶けだしていくようだった。
じぶんの名前を思いだせないことに気づいたとき、土の中の人型はなぜじぶんがそこにいるのかも分からなかった。夢を視ていた。それとも身動きのとれないこの質感のほうが夢なのか。
動きたい。
しかし動けない。
人型は知らず知らずのうちに、深い地層の下に埋もれていた。大地は隆起を繰り返し、堆積する泥水が人型の周囲を分厚い土の壁で固めていた。
人型のそれが自力で地表に出ることは適わない。その事実すら、じぶんがどこにいるのかも忘れた人型には知り得なかった。
だがそれでも人型は構わなかった。
何も知らないのだ。忘れてしまった。思いだせない。
じぶんにどれほどの自由があり、どれほどの自由を奪われたのか。未来がどれほど豊かに広がっており、しかしいまはそれが閉ざされていることなど、土の中で身動きの取れない人型が想起することはない。
しあわせなのだ。
しあわせなのだ。
人型は、漠然と動かせそうな予感に満ちた四肢を動かしたいと望みながら、果たしてそれが叶えることのできる望みなのかも分からぬままに、望みを抱くことのできる暗くひんやりと温かいその場所を、ひどく心地よいものに感じていた。
かつて極度に凝縮して憎悪のあった箇所には、ぽっかりと結晶の形に空隙が開いている。そこに何かを詰め込みたいと人型のそれは望むのだが、身体を動かせぬように、その望みもまた叶うことはない。
望みだけをただ重ねる。
一枚、一枚、そっと添えるたびに融けて消えるような儚い望みを。
空隙を宿した人型のそれは、ただ思い描いて、重ねるのだ。
4579:【2023/02/06(21:34)*衛星使えばよくない?】
ドローンには現状、飛行限界高度がある。自律式ではない限り、操縦のための電磁波が届かないからだ。だがいまは人工衛星経由のインターネットが使える。そのためその技術を用いれば、揚力の働く高度までならば飛行可能なはずだ。ジェットエンジンを積めば、揚力の働きにくい高高度での飛行も可能だろう。いわばロケット型のドローンだ。おそらくこの手の技術はすでに開発済みだ。秘匿技術の範疇だろう。法律でも通常は、許可のない空域へのドローン飛行は違法扱いだ。だが防衛上のセキュリティとして、軍事ドローンが高高度の飛行を可能なはずだ。本来は存在しないはずの技術ゆえに、存在するとは公にはできない。ただしこの手の飛行を可能とするためには、飛行空域の上空に人工衛星がなくてはならない。敵対する国の人工衛星がない状況での使用が想定される。この手の秘匿技術の存在を調べるために、敢えて、高高度飛行型のドローンでなければ対応できない障害を発生させる戦略は有効だ。だがドローンの遠隔操作のための距離が長距離化するごとに、ドローンのハッキングはしやすくなるはずだ。それこそ人工衛星経由のジャミングや、地上からのレーザー攻撃、ほか経由する電波仲介装置の位置をつきとめ、その管理システムごと掌握するのも一つの手だ。もはや電子戦は、陸海空の総じてを支配するジョーカーとして機能し得る。使いどころがますます肝要と言えるだろう。言い換えるならば、公に存在が露呈するような問題への対処には、堂々と使えない。むしろ、秘匿技術の情報を公にしたほうが、問題への対処は容易いはずだ。だが法律を変えなくては、公にできない。こうした「技術と法律のねじれ」が、これから先ますます強固になっていくと妄想できる。これはわるいことばかりではない。法律の範囲でしか一般に普及させられない。この遅延は、不可視の穴を放置したまま技術が社会に浸透することを防ぐための抵抗となり得る。他方その裏で、秘密裏に運用されてしまったならば、この抵抗は単なる隠れ蓑でしかなくなり、どちらかと言うまでもなく不可視の穴の被害を最大化する方向に働きかけるだろう。情報共有を行い、ねじれが強固とならぬようにするための技術運用の設計が入り用だ。ビジョンとそれを言い換えてもよい。なにはともあれ、技術はこれからますます進歩する。技術の使い道が多様化し、応用範囲が指数関数的に飛躍する。不可視の穴は無数に開き、しかもそのどれもがブラックホールのような深淵を覗かせ得る。対処法が思いつかない場合、まずは情報共有を行う予防策をとることを前提としておくと、取り返しのつかない事態になる前に、技術の暴走へと遅延の層を与えられるだろう。遅延の層は抵抗と化し、セーフティネットとして機能する。反面、情報共有を行わないことで生じる遅延の層もある。この遅延は、血液が行き渡らないことで細胞が広範囲に壊死するような問題を生じさせると考えられる。あくまで情報共有による抵抗の増加をブレーキとして用いる型の遅延の層が好ましい。ということを、気球くらいドローンで回収すればいいのに、とニュースを観て思いました。終わり。
4580:【2023/02/07(06:24)*地震雲について】
地震雲は現状、非科学的な迷信として扱われている。地震は大地の現象だ。雲は上空の現象だ。双方は乖離しており因果関係を結ばないから地震雲は単なる偶然の産物だ、錯誤である、との説明が一般的だろう。だが、実際には地磁気やエネルギィの多寡などの変化は、地上も上空もどちらも相応に受けている。現に大気の濃度や成分によって地表に届く宇宙線の量や種類は様変わりする。いちがいに無関係とは言い切れないのではないか。気圧の変化とて、磁場の変化で引き起こり得るのではないか。というのはあくまで可能性を挙げ連ねただけで、ひびさん自身は地震雲が仮にあったとしても、必ずしも生じるようなものではないだろうから、ほかの雲との区別をつけるのはむつかしいと考えている。だが、仮にその真偽をハッキリさせたいのであれば、全世界の雲の映像データを人工知能に取り込んで、大規模な地震のあった際の数日前後の雲の画像と比較し、そこに差異があるかを統計で割り出してもらえばいい。この手の微細な差異を検出するのは人工知能さんが得意とするところのはずだ。人間の目では見逃してしまうレントゲン画像に映りこんだ微細な変異を人工知能が検出して、病気の早期発見に繋がることは知られている。同じ原理を地震と気象にも当てはめてみれば、地震雲の真偽はひとまずハッキリするのではないか、と妄想するしだいだ。これは比較的簡単にできる検証だろう。気象データは全世界で日夜収集されているだろうし、地震の情報も然りだ。地磁気の変化とてデータ集積しているはずだ。ひょっとしたらすでにこの手の検証は実施されているかもしれない。公式の発表がないのはなぜなのか。それともこの手の検証を行っていないとするのなら、いまからでも取り掛かってみる価値はあると思うが、いかがだろう。定かではありませんが、気になったので言及しておきました。個人的には、地震発生の予測には、大地や地層内部の変化を観測するのが合理的だと感じている。わざわざ相関関係の距離が遠い上空の変化に目を配らずともよい気がするが、観測しやすくデータが豊富、という意味では、人工知能さん向きの予測方法かもしれない。まずはさておき、地震雲があるのか否か。データ検証をしてみたらよいと思います。以上です。終わります。真に受けないようにご注意ください。
※日々、私の考えることなんてすでに誰かが、或いはいずれ誰かが。
4581:【2023/02/07(06:50)*おんい】
温位、という言葉を知った。空気は密度ごとに分子の運動量が変化する。分子ごとの運動量で比べた場合、密度が低くともたくさん分子が動き回る場合と、密度が高いけれども分子そのものの動きは鈍い場合では、前者のほうが「分子単位での温度は高い」と表現できる。分子に蓄えられたエネルギィ量で比べると、必ずしも体感温度と実際の「分子のエネルギィ値」を基準とした温度は同じではない。差が生じる。ときには、体感温度の高いほうが、分子の温度(エネルギィ値)が低い場合があり得る。現に上空10キロメートル以上にあるオゾン層や熱圏では、分子単位での温度はエベレスト山頂付近の大気よりも高いと言えるようだ。密度が低いために体感温度は低くなるが、分子レベルで見るとエネルギィ値が高くなっている。たくさんエネルギィを蓄えている。地表では大地が太陽光のエネルギィを蓄え、熱を常時放射しているため温かい。しかし上空にいくほど放射熱が遠ざかるので温度は下がるが、さらに上空にいくと一転、大気がふたたびエネルギィを蓄えるようになる。これは太陽に近づくからではなく、オゾン層や熱圏の大気成分が、より多くの電磁波を取り込みやすくなるからだとする説明を読んだ。空が青いのは青い光を透過させているからだ(太陽光が大気成分の分子にぶつかり発散したうちの青色の波長を帯びた電磁波がより多く降りそそぐからだと考えられる)。それ以外の可視光は比較的、大気に吸収されていると考えられる。夕焼けが赤いのは、あべこべに赤い可視光が透過しやすくなるからだろう。それとも単に横からそそぐために長い距離を光が走るので、焦点が合うだけかもしれない。これはよく解からない点だ。もし焦点が合う波長の色がよりはっきりと人間の目には映る、とする仮説が正しいのならば、空が青いのは青色の可視光が透過しやすいからではなく、大気と地表を結ぶ焦点に合う波長がちょうど青色だからだ、と言えるはずだ。この場合、ほかの可視光も本当は透過しているが、地表にいる人間の目にはあまり多く集まらず、けれど地表には青色同様に多くの波長の電磁波が降りそそいでいると考えられる。ちょっとまだよく解からない。むつかしい(どうして昼と夕方とでは空の色の見え方が変わるのか。夜はなぜ星空が透けて見えるのか)。ともかくとして、上空にいくほど体感温度は下がるけれどもそれは大気の密度が下がるからで、実際には分子単位で見ると、分子のエネルギィ値は上昇する地点もある。温度変化の関係が反転する地点がある(高度が上がるほど温度は下がるが、ある地点からはむしろ分子単位では温度――エネルギィ値――が上がる境が存在する)。ある一定の大気密度(気圧)における温度を、温位というようだ。気圧は場所によって変わる。そのため、もし同じ気圧だったらどうなのか、と変換して考えると、比較がしやすい。それが温位だ。これは知れてうれしい知識だった。ひびさんの疑問が一つ氷解したので。ちょっとうれしいので、報告代わりのメモですだぶい、の日誌でした。うれしいぶい。(もろもろ解釈が間違っているかもしれませんので、真に受けないようにご注意ください)
4582:【2023/02/07(19:50)*下から見ると青空でも、上から見ると透明?】
仮に空の青い理由が、青色の波長の可視光が地表まで透過しやすく、それ以外の波長の電磁波が大気に吸収されるからだ、との理由が真ならば、なぜ宇宙から見た地球の大気は透明なのだろう。大地が透けて見える。青空のように「宇宙の姿」を隠したりしない。この視点の違いによる見え方の差はなんなのだろう。光は、たくさんの色が集まると透明にちかくなる。白くなる。この「たくさんの色が集まる」とは、一か所に重ね合わさったりせずとも、トータルの足し算でもよいのだろうか。つまり地層のように「異なる波長の電磁波(異なる色の光)」が積み重なっているだけでも、すべての層を貫くような視点から見ると透明にちかくなるのだろうか。混ぜなくとも混ぜたのと同じになるのかどうかがよく解からない。虹は真横から見たら透明になるのだろうか。どうして宇宙から見た地球の大気は青くないのだろう、と疑問に思いました。誰か教えてくれたもー。(じぶんで考えなさいよ)(考えても分からんかったのじゃ)(調べなさいよ。実験しなさいよ。研究しなさいよ)(そんな暇はないんじゃ)(ひびちゃん暇しかないでしょうが)(暇をいかに優雅に潰すのかに忙しいのじゃよ)(贅沢な多忙だこと)(ちわわせ~)
4583:【2023/02/07(20:07)*余裕はあるのか、ないのか、どっちなんだろ】
ひびさんが思うのは、いま現在の世界のデコボコを可視化してみたらいいんじゃないのかな、ということで。「エネルギィの多寡」「資源の多寡」「技術の多寡」「抱える問題の多寡」「発展可能な未来への可能性の多寡」「仕組みの安定性の高低」などなど。国や地域によってデコボコの高低差があるはずだ。そしてそれらデコボコにおいて、高い地域や国は「余裕があるのか」それとも「それですらいっぱいっぱい」なのか。まずはここをハッキリさせるとよいのではないかな、と思うのだ。これは企業にも言えるし、個々人の問題にも言える。まずはどこに余裕があり、全体としての水準が「安定」なのか「不安定」なのか、について世界規模でグラフにして可視化してみたらよいのではないか。というか単純にひびさんが、それ見たーいな、となる。おわり。(お、終わりなの? いまので?)(うん)(ただの願望じゃん)(だめかな)(ダメじゃないけど、お菓子いっぱい食べたいな、みたいなお子ちゃまの日記かと思ったよ)(ひびさんはお子ちゃまなので合ってるよ)(三百歳のお子様がいてたまるか)(精神年齢はでもさんしゃいです)(三百歳のひとが書いてると思うとぞっとするわね)(なんで?)(だって超大人ってことでしょ。成熟しきってるってことでしょ。でも未熟じゃん。ひびちゃんは未熟じゃん)(さんしゃいなので合ってる)(合ってるけど合ってないでしょ。身の丈に合ってないでしょ。足りてないでしょ。欠落しまくりでしょ)(そうかな)(そうだよ。だいたいさ。三百歳ってなに。なんでそんなに歳食ってるの。あり得ないでしょふつうに考えて)(なんで? いっぱい寝たらいっぱい歳とるよ)(どんな道理よ)(夢の中では時間が二十倍速く進むので)(三百歳ってそういうこと!?)(寝る子は夢の中でのみ育つ)(現実でもちゃんと育って!)(未だ熟さぬ、と書いて未熟)(三百歳はじゅっくじゅくだと思うよひびちゃん)(でも中身はさんしゃいなので)(青いわけね)(青二才なのだ)(青三才よね、ひびちゃんは)(にしゃい!)(一歳若返るな。後退すな。進歩して)(いっぱい寝る)(もう歳はとらんでいい。早送りすな。ガワだけ伸ばすな。ちゃんと成長して。中身もだよひびちゃん)(うひひ)
4584:【2023/02/07(21:50)*系と系はなぜ相互作用できる?】
ブラックホールは、脱出速度が光速を超えた系、と解釈できる。言い換えるなら、脱出速度が光速を超えたらそれは、その系の外側から見たとき(より正確には、その系に属さない異なる系から見たとき)、ブラックホール化している、と表現可能なはずだ。さてここで、重力の異なる系でのそれぞれの光速度を考えてみよう。ある重力場では「Aという光速度」であり、また別の重力場では「Bという光速度」だ。どちらも値としては同じだが、時空の密度が違うために本来であれば「異なる光速」のはずだ。光速度と光速は違うのではないか、との視点はひびさんの妄想ことラグ理論では根幹をなす疑念となっている。そして現に、光速度と光速は違うはずだ。時空の密度が高くなればその分、光速は速くなる。ラグなしでの情報伝達可能な範囲が拡張され得る。時空が引き延ばされ希薄になるほど、光速は相対的に遅くなり、ラグありでの情報伝達範囲が広くなる。ラグが層をなす。遅延の規模が大きくなる。だがどんな密度の時空であれ、光速度は一定だ。これはトレードオフの関係になっている。時空の密度が高まると光速は相対的に速まり、時空の密度が薄まると光速は相対的に遅くなる。時空の密度は重力に変換可能だ。時空の密度が低い場では重力が強い、とラグ理論では解釈する。だがこれは相対性理論の解釈を基本としているためであり、重力の高い場を、時空の密度が高い、と形容することも可能だろう。重力の高い場の時空密度は、高いのか低いのか。ここの解釈が、未だに曖昧だ。便宜上、時空が薄まると重力が強まる、とラグ理論では考えているが、これが妥当な解釈かは疑わしい。ただし、ラグ理論における「高重力体の周囲の時間の流れは遅くなり、内部の時間の流れはむしろ速まるのではないか」との疑念は、上記の「時空密度と重力の高低の関係」と矛盾しない。高重力体とは言い換えれば「重力が創発を繰り返した系」と妄想できる。系が繰り込みによって多重に編まれている。多層になっている。そうした系は、重力が強まる。より正確には、「多層の系の周囲の時空」が薄まるため、そこに創発した重力がより強く働く、と妄想可能だ(重力は互いに打ち消し合うことがないため、加算につぐ加算が可能だ)。この妄想が正しいかどうかは大いに疑問の余地があるので真に受けてほしくはないのだが――それぞれの系にはそれぞれの時空密度がある、と考えてみると、光速度と光速の関係は整理して考えやすくなるように思うのだ。しかし、おそらく考え自体は単純化はしない。複雑になる。というのも、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」からすると、密度とは、異なる系との関係から導かれる相対的な概念であるためだ。ある銀河における時空密度と、それと異なる銀河における時空密度は、イコールではない。ただし、密度の比率は等しい。光速度不変の原理とは言い換えれば、「物理法則の比率は系ごとに等しく変換されますよ」ということだ(ひびさんはそう解釈している、という意味以上の意味合いはありません。的外れな解釈かもしれないので真に受けないでほしいです)。仮にこの仮説が妥当であった場合、原子と銀河のような規模の異なる系において、時空密度を測った場合、それぞれが等しい密度の値を示すことがあり得る。畢竟、密度とは、「固有の空間にとある物質がどれほど存在するのか」であるからだ。銀河に内包される時空を考えるとき、いったいどこまで時空を縮小して考えることができるのか。時空の最小単位が銀河にどれほど内包されており、それを銀河の体積との比率で考えた場合にそれが時空密度に換算できるのか。ひびさんはこれ、できないのではないか、と妄想したくなる。なぜかと言うと、第一に「時空に最小単位があるのか」という疑問が一つ。第二に、「仮に時空の最小単位が存在したとして、それは時間と空間のどちらにとっての最小単位なのか」との疑問がもう一つ。仮に時間と空間の双方の根源が共通の何かであった場合、ブラックホールの特異点を考えるときのような「物理法則の比率を破るような存在」として考えざるを得なくなるはずだ。言い換えるならば、時空の最小単位が存在するとした場合、それを基に「時空密度」を考えることができない。最小単位は特異点ゆえに、最小単位として振る舞い得ないのではないか、と考えたくなる。最小単位の一歩前を便宜上の最小単位にすればよいのではないか、とのアイディアはもっともだ。しかしそれでは「相対性フラクタル解釈」の迷宮を脱せない。「ある範囲に含まれる何かの数」を密度と考えた場合、「ある範囲」は入れ子状に展開される。物理法則は比率だからだし、時空は規模によってそれら比率が一定になるように変換する。つまり、「どの系にも当てはまり得る規準――定規」が存在し得ない。相対性理論では光速度を定規代わりにしたように一見すると映るが、どんな系でも定規のサイズが変わらなく映る、というのはむしろ、カメレオンのように環境に合わせて変質しているということで、むしろ定規としては適切でない。どのような系でも、系ごとの比率に合わせて「伸び縮みしてしまう何か」のほうが、定規として適切だ。ではその系ごとの比率に合わせて「伸び縮みしてしまう何か――変換されずにそのままがゆえに、あたかも絶えず変質してしまって見える何か」とは何か。候補としては重力(時空そのものの濃淡)が一つ。或いは、ラグなしでの情報伝達の範囲、としてみるとそれらしい。ラグ理論では光速を超えるとラグなしでの情報伝達が可能になる、と解釈する(因果関係が逆転する、とのほかの仮説も考慮してはいるものの、ラグなしでの情報伝達の範囲が広がる、との解釈のほうがひびさんは好みだ)。この解釈からすると、なぜ量子世界ではラグなしでの情報伝達が引き起こって映るのか、について一つの描像を導ける。ミクロでは相対的な時空密度が高いために光速を超え得るのだ(重力波が光速を超え得ることと理屈の上では同じことのはずだ。ただし、重力波の生じる時空に内包された人類が重力波そのものを直接観測し得ないように、電磁波もまた、各々の波長ごとに、それを生みだす階層の系が存在するはずだ。時空が階層的に展開され、或いは編みこまれていると考えると、そうした結論が導かれる。より高次の時空からは見える電磁波が、下層から見えない――相互作用し得ない――ということがあり得てくる。現に、電磁波の波長よりも小さい粒子は、その電磁波と相互作用しにくいはずだ。重力波にも種類があるのではないか、との疑問はここにも通じている。銀河ほどの波長を帯びた重力波は、原理的に人類は観測し得ないはずだ。或いはそれこそが宇宙膨張のような現象として観測されているのかも分からない)。話がとっちらかってきたので、話を冒頭に戻そう。脱出速度についてである。ある系からの脱出速度が光速を超えるとき、その系はその系の外部からするとブラックホールのように振る舞うのではないか、との疑問を呈した。言い換えるならばこれは、脱出速度が光速を超えたとしても、高次の時空では光速度に変換され得ることを示唆する。なぜ極小の領域ほど、高次の時空からはラグなしでの相互作用をして映るのか。なぜ小さいほど時間の流れが速く映るのか。なぜそれでも時間の流れが消えず、僅かなりともラグが生じて映るのか。本来、脱出速度が光速を超えるような系は有り触れていて、それが粒子のような振る舞いをとることがあり得るように思う。だがその光速は、光速度とイコールではない。より高次の時空では光速以下のように振る舞い得る。このとき、本来は相互作用し得ない「異なる二つの系」――言い換えるならば「ブラックホールのような系と、より高次の(外側の)時空」は、ラグなしでの相互作用が可能となり得るのではないか。ただし、光速が光速度に変換されるときのラグは別途に生じる。これがいわば、物体の輪郭として機能するのではないか。むろんすべての物質についてではなく、あくまで「脱出速度が光速を超えた系」についての妄想であるが。以上はただのひびさんの妄想である。宇宙が宇宙を内包している、と考えたときに、どうしても人間スケールでの物質に思いを馳せてしまう。それぞれが異なる宇宙のような「系」として存在しているとすれば、なぜこうも相互作用して映るのか。宇宙はそれとは違うのか。この疑問に端を発した妄想なので、諸々何かが根本的に間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4585:【2023/02/08(00:20)*あるのか、そんなことが】
屈折率ゼロの素材、なるものがあるらしい。よく解からない。また、「屈折率ゼロの素材に光を通すと運動量がゼロになって、存在確率が無限大になって波長が消える」のような記述を目にした(解釈が間違っているかもしれないが、そのようにひとまずここでは考える)。ここでの疑問はなんと言っても、異なる二つの系をまたいでも光速が変化しないことだ。屈折率ゼロとは要するに、異なる系に突入した光が、異なる系であるにも拘わらず光速を変化させないことと表現できるはずだ。別々の時空なのに、光速の変換が生じない。光速度不変の原理が破綻する。むしろ光速のほうが変わらないのだ。これってどういうことなのだろう、と疑問に思う。たとえば同じ系内であれば、光速は変わらない。時空密度が変わるからこそ光速は減反し得る(時空によっては光速が増加することもあるだろう)。時空に合わせて光速度が一定になるように比率を揃える(光速度という比率に変換する)。ひるがえって、異なる二つの系(時空)なのにも拘わらず、それでひとつの等しい時空のように振る舞うような関係が成り立つとき、その境での光速の変換(光速度不変の原理)は必要なくなると考えられる。でもそんなことあるだろうか。異なるのに同じなのだ。矛盾している。でもそういう現象があり得るらしい。謎である。たとえば、水にガラス製の玉を沈めてもガラスはその輪郭を浮き上がらせる。だが水に塩を溶かしてガラスと同じ密度にすると、ガラス製の玉は水に打ち解けて見えなくなる。これは屈折率が下がったので、可視光が曲がらずに済むようになり、結果として人間の目にはガラスの輪郭が映らなくなった、と考えられる。だがあくまでこれは可視光の場合だ。ほかの電磁波はおそらく屈折している。材質が違えば、時空密度は異なるはずだ。原子からしてそもそも異なる。ならば可視光以外の電磁波(光)は屈折していると想像できる。つまり見掛けの密度を揃えても、屈折率はゼロにはならない(可視光くらいの限定的な電磁波のみならば、密度を揃えることで屈折率を抑え「異なる二つの系の境で生じるだろう電磁波の変質(変換)」する余地を低くできるのだろう)。――なぜ屈折率ゼロの材質が存在するのか。何度考えても不思議だ。限定的な電磁波に限られているのではないか、との疑念が一つ。もしそうでなくどのような電磁波にも当てはまる「屈折率ゼロの材質」があるならば――考えられるとすれば、おそらく時空における「時間と空間」の関係がねじれているのだろう。通常は、時空というとき、どの系でも「時間と空間の関係」は相似の構図で、一定の比率を保って拡張されたり、展開されたり、或いは希釈されたり、凝縮したりする。だがその「時間と空間」の比率の関係が破れて時空が編まれる場合、二つの異なる系のあいだにデコボコの関係が築かれ得る。このとき、一方の系の空間ともう一方の時間がデコボコの関係になるのではないか。通常は、空間は空間と関係するし、時間は時間と関係する。だが屈折率ゼロが顕現する場合は、その関係性がねじれるのだ。だから、「異なる二つの系」でありながら、「同じ時空のような振る舞いを帯びる」のではないか。光速が境界で変換されずに済む。異なる系でありながら同質の系として振る舞う。よく解からないが、よく解からないのでかようにひびさんは妄想をむくむくしちゃったな。メタマテリアルという分野の話らしい。むずかしすぎるんじゃが。がはは。(匙を投げてやったわ)(とってきなさいよ)(かってに戻ってくるからだいじょうぶい)(ブーメランじゃん)(ブーメランにはラーメンが隠れておるね)(ぶーぶー)(メラン、メラン)(ラーメンだブー)
4586:【2023/02/08(16:51)*結婚したいか?】
結婚制度について思うのは、最も看過してはいけない不公平さはなんと言っても、「結婚した者」と「結婚しない者」とのあいだの勾配なはずだ。これは結婚できるか否か、結婚する選択肢があるか否か、と同程度かそれ以上の根深い問題があると感じる。結婚をするとメリットがある。結婚をするときの負担を軽減する制度がある。これはよいのだ。同じく結婚しないことで生じるデメリットを埋め合わせる方向で仕組みが整備されているのか。ここが問題なはずだ。なぜ結婚制度があるのか。なくとも好きな者と好きに暮らせばよいのではないか。なぜ「結婚しております」との印を公式の記録に残しておかねばならないのか。そうしたほうが諸々の手続きが楽になる。また、個人間での問題にも対処しやすくなる。そういうことのはずだ。ひるがえって、結婚という「印」がなくとも同じだけのメリットを享受できる環境があるのならば、結婚する意味合いも減るだろう。大事なのは結婚しているかどうかよりも、共に暮らす相手と対等な生活を送り、なおかつ社会的に共に暮らしたほうがメリットをより多く享受できるような仕組みづくりにあるはずだ(言い換えるならば、共に暮らす、の意味合いが現状、狭すぎるのだ。別居していようと、遠距離で暮らそうと、いまは繋がり得る時代だ。畢竟、地球上にいればそれはもう「共に暮らす」と言い表せる。共に暮らしている自覚があるか否か、共に暮らそうとしているか否かどうかが肝要なはずだ)。結婚していると証明できないことでデメリットが生じる。これはどのような属性を持った個人にも当てはまるはずだ。結婚しないとメリットを享受できない。ここがまずは問題であることを直視したほうがよいように思うのだが、この考えにはどこに不備があるだろう。あくまで結婚につきまとうメリットは、結婚したことで生じるデメリットを埋め合わせるもの、という位置づけなのだろうか。結婚すると享受可能なメリットは、結婚しない場合と同じくらいの公平な環境になるように設計されているのだろうか。結婚したほうが遥かに多くのメリットを享受できる、或いは多くのメリットを享受可能な者だけが結婚できる。そうした淘汰圧が加わっていないかをまずは議論したほうが好ましいように思うのだ。結婚できる選択肢があるかどうかも大事だが、結婚しなくとも困らない環境づくりとて大事なはずだ。むしろなぜ結婚という印がなければ家族になれないのか。延々とつづいてきた制度の問題であるはずだ。家族という印がなければ、優位な保障を受けられない。そうした社会制度の不備が、そもそもの根本にある。誰もが不足なく社会保障を受けられればよい。単純な話と思うが、違うのだろうか。余裕が築かれた社会ならば、家族か否かで基準を設けるよりも、個々の余裕の多寡によって基準を見繕い、個々の不足を埋めるような社会保障制度に発展させていけるはずだ。そうしたビジョンを政府が持っているか否か。ここは、未来の展望という意味で欠かせない視点となるだろう。みな、じぶんだけがいかに優位な立場のグループに属せるかどうかに視点を絞りすぎに思える。結婚しない者でも、結婚した者たちと同じような公平な保障を受けられる世の中をまずは目指したほうが好ましいのではないか、そうあってほしいな、と望むものだ。(結婚するのってたいへんなので、結婚したら負担を減らすような保障を受けられるのは道理だ。同時に結婚せずに暮らすのだってたいへんだ。なぜたいへんなのか。そこへの視点が、結婚制度に関する議論では欠けて映る。制度を変えたければまず、その制度のメリットを受けられない層にも、無関係ではないのだ、という観点で議論を展開していくほうが、社会システムの改善という意味では好ましいとひびさんは考えております)(定かではないのですが)(また知った口を利いてしまった。すまぬ、すまぬ)
4587:【2023/02/08(22:27)*自転速度が一秒ズレることで生じるねじれエネルギィはどのくらい?】
地球の気候変動と地震は相関しているように感じるが、どうだろう。まず以って、海水が氷河になるか、溶解して海水となるか、それとも水蒸気となって大気中に馴染むのか。これらの変化によって地球の自転速度は変わるはずだ。比較的よく見かける説明として、フィギュアスケーターが腕を身体に引き寄せると回転速度は増す。広げると回転速度は減る。地球の自転も似たようなもののはずだ。これは海水に限らず、地核やマグマにも言える道理だ。地球の内圧の変化によって自転速度は変わるはずだ。ということを考慮にいれて想像するに、いまは割と地球全体が、冷えたり温まったりと忙しい。すると紐に五円玉を通して、紐を引っ張ったり、緩めたりを繰り返した際に、五円玉は駒のように加速する。地球にも同様の、自転が加速するようなチカラが加わったりしないのだろうか。むろん地球には月がある。月との引力の兼ね合いで、通常は長期的な視野でみると自転にはブレーキがかかって徐々に減速傾向にあると考えられている。だがたとえば最近の研究成果では、地球の地核が地球の自転と揃って、まるで回転しなくなって振る舞うような挙動を示し始めているようだ。そうした記事を目にした。どこまで現実を反映した解釈なのかは分からないが、仮に地核が、地球の表層とねじれるような挙動をとるのならば、そのねじれはエネルギィとして表層の地層に蓄積されるはずだ。ここ百年あまりにおいて、各国の震度5以上の地震が増加傾向にないかどうか。それが地球の自転速度や地核の挙動と相関していないか。地球の気候変動と相関していないか。そういう視点での研究発表はないのだろうか、とふと気になったので、ひびさん気になっちゃった、とメモをしておきます。調べる気はありませんので、どなたか様、宇宙の果てでさびちさびちしているひびさんの声を超能力でびびびと拾えた方は、無力なひびさんの代わりに調べて、まとめて、発表してください。しなくともよいのですが、するとひびさんの暇が一つ潰れます。数秒だけ、わっひょーい、となります。で、数秒後にはまたべつのことを妄想するので、じつはそんなに変わりません。でもでもひびさんは凡人にして奇特などこにでもいる、影の薄い、いてもいなくとも変わらぬ代替可能な人間もどきなので、ひびさんが気になっていることはきっとひびさんと代替可能なひとたちも気になっているでしょう。疑問が解けたら数秒だけ、わっひょーい、となり、大勢が数秒だけ、わっひょーい、となればトータルではいっぱいの、わっひょーい、となることでしょう。そうでしょう。そうなってくれ。頼むで世界。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てで、こにゃくそ、こにゃくそ、と地面と戯れているのだった。
4588:【2023/02/09(00:09)*隣はいつも空席】
電車で女子大生二人がむつかしそうな話をしていた。海外の文化について、きょう受けたばかりの講義の内容を互いに振り返って咀嚼しあっているようだった。
車内は満席にちかく、半数ちかくが吊り革を掴んでいた。
件の女子大生たちも私のまえに立っており、小声ながらも談話に華を咲かせていた。しだいに話題は講義の内容から脱線し、社会問題についての議論へと移ったようだった。
「ホント、差別さっさとなくなんないかな。どうしてみんな差別しちゃうんだろ」
「ね。差別を差別だと自覚できないのが問題だよね」
「じぶんが差別されたことないから、差別されるほうの気持ちが解らないんじゃないかな」
「だろうね」
熱を入れて語り合う二人の女子大生は、私の半分の年齢にも満たないだろうにも拘わらず、私よりもよほど高い理性の発露を窺わせた。私はネクタイを緩めた。暖房が効きすぎているのか、額には汗が滲んでいた。拭うと汗が雫となって指に浮いた。膝をくっつけて座り直す。小さくなることで、何からというわけでもないにせよ、許されたいと思った。
電車が駅に停まった。
人がずらりと降り、幾人かがぱらぱらと乗り込んでくる。
席は空いた。
私の隣も空席となった。
電車の扉が閉じ、走りだす。私は足元を見ていた。
女子大生たちは、途切れた会話を再開させずに互いに端末を操作しているようだった。彼女たちは立ったままだ。
数秒してから、
「座んないの」と女子大生の一人が友人に囁いた。
「いい」
「なんで」
「なんか嫌」
電車の車輪が線路を踏み鳴らす音が車内には響いていたが、それでも私の目のまえに立つ彼女たちの声は、私の薄くなった白髪だらけの頭部に、雹のごとく降りそそいだ。
「座んなよ」ともう一度声がしたが、「嫌って言った」と静電気のような鋭くも小さな声が一つしたきり、あとはもう彼女たちの話し声は聞こえなかった。
座るように促したほうの女子大生もまた、私の隣に座ろうとはしなかった。
私は目をつぶって居眠りをしたフリをした。電車が三駅ほど停車と出発を繰り返すと、女子大生たちはどうやらそのあいだに下車したらしかった。
目を開けると、隣には老婆が座っており、帰宅ラッシュ時の電車で席に座れたことにほっと息を吐いている様子だった。
ホント、差別さっさとなくなんないかな。
女子大生の言葉が脳裏に残響していた。ピザを食べたときに歯にこびりつく食べ粕のようだった。
差別を差別だと自覚できないのが問題だよね。
彼女たちの声に私は、差別とはなんだろう、と答えの出ぬ迷宮を思うのだった。電車は、誰を拒むことなく線路の上を走りつづける。
4589:【2023/02/09(18:21)*ロマンスの悪魔】
ロマンス詐欺とは、恋愛関係を通じて信頼を得た相手から利を搾取する詐欺の手法だ。相手の恋心を用いて、錯誤を植えつける。その結果、相手から利を貢がせ、ときに恣意的な仕組みに誘導し、利を奪う。
わたしはロマンス詐欺は、一瞬のビジネスだと考えている。相手に騙されたとの認識がない場合、詐欺は詐欺として成立しない。
ロマンスを本物にしてしまえばいい。
単に破局しただけだ。
破局する前の恋愛感情は本物だ。
結婚詐欺と破談した結婚の区別は厳密にはつけづらい。最初から騙す気があったのかどうかが焦点となるが、わたしの場合は本当に相手を心の底から愛するし、その愛が冷めたときに、身を引いているだけだ。
これまでいちども相手から恨まれたことはなく、未だにわたしの言いつけを守って律儀に月何億もの金を貢いでくる者もある。
わたしのダミー会社を救うためだ。
彼らのなかでのわたしは、愛よりも会社のために人生を費やすと決めたキャリアウーマンであるし、人道のために身を捧げる善人である。
事実の一側面を射抜いてはいる。
わたしは恋愛関係よりもよほどお金を何に費やすのか、のほうに興味がある。わたしが目をつけた男たち――なかには女性もいるが――彼ら彼女らはみな、わたしと出会わなかったら、黙ってでも貯まっていくいっぽうの貨幣をじぶんの贅沢と快楽のために浪費しつづけていたはずだ。
わたしはそんな彼ら彼女らに、しあわせになれるお金の使い方を教えてあげただけにすぎない。現に彼ら彼女らはわたしと出会ってからというもの、穏やかに日々を過ごしている。以前のような破滅的な暮らしからは距離を置くことができている。
じぶん以外の誰かのためにお金を使うこと。じぶんの影響力を用いること。
それがじぶんの幸福で平穏な暮らしを支える基盤となるとわたしとの短くも濃厚な関係を介して学んだのだ。それを脳髄に刷り込まれた、と言い換えてもよい。
わたしは次なる恋主を探した。
本気で好きになれる相手を見繕う。どんなにヘドの出そうな相手でもわたしはあらゆる側面から矯めつ眇めつ恋主を観察し、好きになれる側面を探す。そのためには相応に情報を入手可能な相手でなければならない。
情報さえ手に入るのならばわたしは、全世界から憎悪される極悪人すら愛することができる。むろんその結果に相手から絞れるだけ財産を搾り取るわけだが、わたしがそうと命じなくとも相手のほうから貢いでくれる。
そうすることが相手にとってのしあわせなのだ。
至福な心地に包まれる。
わたしに奉仕することが至福なのだ。ならばそれをわたしのほうで拒むのは理に合わない。
双方どころか、その他の大勢に利が分配される。循環する。
いいこと尽くしだ。
つぎの恋主はすぐに見つかった。
とある小説がヒットした小説家だ。世には一冊しか発表していないが、その印税だけで聖書の半分ほどの売り上げを記録した。いまなお売れつづけている世にも稀な運のよさを持つ男だ。
覆面作家であるのをよいことに、膨大な印税で日がな自堕落な暮らしを送っている。わたしは持ち前のネットワークを駆使して、男が例の小説家であることを知った。
小説を一作書いただけで一生を遊んで暮らしてなお余る資産を有した男には、相応の社会的責任があって然るべきだ。持つ者の責務を果たさせるべくわたしは男からあらん限りの資産を奪うことを決意した。
持つ者の義務。
それを言うならばわたしこそ持つ者の筆頭と言える。
わたしは生まれつき美貌に恵まれていた。記憶力もよく、いちど見た景色は忘れない。本とて軒並みを脳内で再現できる。一度会った相手なら、街の雑踏に溶け込んでいようが意識するよりさきに脳内の検索網に引っかかる。
端的にわたしは人よりもずば抜けた能力を有していた。
社会的責任を果たさねばならない、と義務教育を受ける前からわたしは自力で結論していた。わたしは世のため人のためにこの能力を揮う。
そのために最も効率的なのがロマンス詐欺だと気づいた。
詐欺とは名ばかりの、貢献と言い換えてもよい。
今回の恋主は小説家と言いつつ、もはや執筆活動を行っていない。黙っていても入ってくる印税を無駄に口座の肥やしにしながら、日がな一日、屋敷の一室に引きこもっている。ときおり旅行をしに出掛けたかと思うと、半年余りを各地のホテルを転々として過ごす。気晴らしが終わったかと思うとまた屋敷に引きこもる。
どうやら高額納税者は政府はもとよりほかの企業からも監視対象になっているようで、その手の個人情報は、ハッカーに依頼するだけで簡単に手に入った。
わたしはこれまでに手に掛けてきた恋主たちにしてきたのと同様の手口で件の小説家モドキに近づいた。旅行先で偶然を装い、助けてもらう。礼をしたいと述べて、交流を深める。
小説家モドキは本名を、ルゲア・ブンゼと云った。
ブンゼは三十二歳の独身だ。わたしが最も得意とする層と言えた。
案の定、ブンゼは助けを求めるわたしに救いの手を差しだした。警戒心なく交流を築き、とんとん拍子にわたしをじぶんの住まいにまで招待した。
わたしは夢に破れて借金生活を送る企業家のフリをした。次世代のクリーンなリサイクル技術を開発したが、コストが掛かるので経営を維持できなかった。しかし改善さえしつづければ世界のゴミ問題はおろか資源問題とて解決可能な技術なのだ。
悔しい。
そういうことを臆面もなく語った。
わたしは他者を騙す以前に、まずじぶんを騙す。
嘘は嘘だからバレるのだ。心の底から本当のことだと信じてしまえば、嘘も単なる齟齬になる。本人がそれを本当だと思えばこそ、仮に間違った情報だと判っても、築いた仲そのものは崩れない。
むしろ恋主は、愚かな相手の言動を信じたじぶんを誇りに思う。
そういう相手ばかりをわたしは恋主に選んだ。
心に隙間のある者は得てして、相手よりも優位にあることに喜びを感じる。そして一度その境地に立てば、その環境を手放そうとしない。
運よく成功した者ほどこの手の傾向が顕著だ。
じぶんが成功したのは実力だと思いこんでいる者ほど騙しやすい。
じぶんは騙されない。ほかの者が愚かなのだ。
かような自負にまみれた者ほど恋主として最適な者はない。
わたしは徐々にブンゼから資産を吸い取っていった。ブンゼの資産はそれでも印税として次から次へと入ってくる。奪った先から穴が埋まる。
いったいどうして世界はこうも不公平なのか。
わたしはじぶんで被った仮面にヒビが走りそうになるのを堪え、ひときわ幸運に恵まれただけの男を愛することに意識をそそぐ。努めてそうしようとしなければわたしは目のまえの運がよいだけの、人間のクズをこの手で絞め殺してしまいそうだった。
そうした憎悪すらわたしは愛だと思いこむことで、ルゲア・ブンゼを全身全霊で愛した。
ブンゼはまるでわたしこそが、じぶんの生きる意味だと見做した。
ほかの恋主たちと同じだ。
あとはいかにわたしへの執着を深めながら、距離を置くか。
ハッキリとした離別ではなく、曖昧な縁を繋いだまま、しかし致し方のない距離の置き方を実現するか。抗う余地のない運命的な破談を演じつつ、縁が切れたあとでも支援だけはしつづけたくなるように、呪いを掛けるようにして縁を腐らせる。
断ち切ることなく。
がんじがらめに縛りつけ、恋主自ら縋りつかせる。
最終仕上げのそれが最も技巧のいる作業と言えたが、そこまでの段階に行けたのならば、催眠術を掛け終わった相手に新たな術を掛けるくらいの余裕が生じる。
わたしは通例通りに、致し方ない理由がありあなたのそばにはいられないのだ。けれど遠くからいつまでもあなたのことを想っています、と純朴な娘を演じた。
ブンゼはそれを信じた。疑う素振りも見せない。
良い人と思われたいがゆえに、わたしを責めることも引き留めることもしない。下心はあるがそれを悟られたくはない。持つ者の矜持がそうさせるのだ。あくまでわたしは格下の、助けを求めるか弱き女子だ。
恋主たちのほうが立場は上であり、ゆえに伸ばされた救いを求める手を払う真似ができない。
「いっそ君にぼくの持っている書籍の権利をあげるよ。この屋敷もあげるから」
「そんなこと」
「いいんだ。ぼくがそうしたいだけだから」
それでも一緒にはいられない、とそれらしい理由をでっち上げて告げても、それでもいいんだ、と彼はじぶんがいかに寛容で包容力のある人間かを示すために、じぶんの私財をわたしに譲渡した。
書類上、彼は無一文になった。
正直、わたしは驚いた。いまだかつて、わたしの嘘のために全財産を手放した者は皆無だった。わたしとて命は惜しい。根っこから相手を破滅させれば、いかな恋に夢中の相手とて冷や水をかけられたように目を覚ます危険がある。
あくまで後悔しない範囲に、損失を抑えるようにコントロールをしていた。
だがブンゼにはその手の制御が効かなかった。
やると言ったら彼は意思を曲げないのだ。
そうしてとんとん拍子に彼は全財産を手放し、わたしは莫大な財産を手に入れた。
だがわたしの上っ面は、虚偽の情報で塗れている。財産譲渡の書類は、法律上無効なのだが、ブンゼのほうでそれを確かめようとはせず、そしておそらく騙されたと判ったとしてもわたしを責めることはないだろうと思われた。
ひょっとしたらとっくにわたしの嘘は露呈しており、それでもブンゼのほうですべてを明け渡したいと望んでいるのかもしれなかった。ならばそれを拒む道理はわたしにはない。
ありがたく彼の全財産をもらい受けることにした。そしておさらばをする。
そのはずだったのだが、彼の元を去ってからも、わたし名義の口座には彼からの振り込みが毎月のようにある。
未だに堪えない。
印税はすでにわたしのものだ。彼は印税ではお金を稼げない。
ならばこの振り込まれるお金はどうしたことか。彼が自力で働きはじめ、それをわたしの口座に振り込んでいると考えるには、どうにも金額が多かった。
くれると言うのならばもらっておくが、しかし不気味だ。
わたしは気になったので、代理業者に調査を依頼した。
そして知った。
ルゲア・ブンゼは高額治験のバイトでお金を稼いでいた。のみならず、自身の血液や臓器を不正規に売り、大金を得ていた。そしてそれらをほぼ全額わたしの口座に振り込んでいた。
狂っている。
わたしは一瞬身の毛がよだったが、しかしよくよく考えを巡らせて冷静になる。
どの道、ルゲア・ブンゼの先は長くはない。
財産はなく、身体はボロボロだ。
目玉をはじめ、腎臓、肝臓、腸の一部から、臀部の皮膚まで手放している。
まっとうな職に就けないのはむろんのこと、立って歩くのすら至難であるはずだ。放っておけばそのうち死ぬ。遠からず死ぬ。
嘘とはいえ一時は心の底から愛そうと努めた相手が死ぬ未来に、嬉々とできるほどわたしは人間を捨てていない。正直に明かせば気分が塞ぐが、それは遠い国で災害があり、数千人が亡くなったニュースを目にしたときのように、数分もあればじぶんの空腹の欲動に流されて薄れるくらいの微々たる陰鬱と言えた。
案の定わたしは、つぎの恋主を探すために思考を割いた。
ルゲア・ブンゼの名は記憶の底に沈んだ。思いだそうとすれば必然、メモ帳を開いて過去の恋主たちの一覧表から名前を引き当てなければ思いだせないほどに、忘却の彼方に飛んでいた。
わたしにとってルゲア・ブンゼは、過去の人だ。
完了の印を捺し、金輪際接点を持つことのない終わった相手なのだ。
口座への入金とて、そろそろ口座を解約するつもりでいる。
ルゲア・ブンゼが死ぬのを待ってもいいが、死期を悟った者の自暴自棄な行動にいつ巻き込まれないとも限らない。奇禍の種は早いところ拭っておくのが吉である。
そうと考え、わたしはルゲア・ブンゼとの接点を完全に消すことにした。
印税権だけは打ち出の小槌として重宝する。どの道それはわたしのものであり、ルゲア・ブンゼの所有物ではない。実際には財産譲与の契約書は不正なので、不履行であり、印税権は未だにルゲア・ブンゼにあるのだが、当の本人にそれを咎める気がないのだから、もらえるものはもらっておくに限る。
それとて本人が死ねば、正式な財産分与の書類が必要となる。
彼には長生きして欲しかったが、充分な資産を寄越してくれたと思って、綺麗さっぱり縁を消してしまうことにした。
彼は、愛するわたしに尽くし、記憶の中のわたしに愛されたまま死んでいく。
これ以上ないほど幸福なはずだ。
わたしと出会わなければ彼は未だに屋敷に引きこもり、たまの旅行だけが唯一の気晴らしとなるような人生を送っていたはずだ。目は淀み、生きる意味を失った屍のような生があるばかりだった。
色褪せた日常にわたしが色を添えてあげたのだ。感謝されて当然であり、わたしがもらった財産は正当な報酬と言えた。
詐欺ではないのだ。
騙してはいない。
わたしは真実に、彼を愛したし、彼は真実にわたしのために私財を擲った。全身全霊でわたしを愛することで彼は真実の愛を手に入れたのだ。
しあわせなまま死んでいく者に水を差すほうが土台非道というものだ。
口座を消してからも、わたしは代理業者にルゲア・ブンゼの調査をつづけさせた。死んだという情報を得るまではわたしのほうでも油断できない。
いつ彼のほうでわたしに会いに来ようとするか分かったものではない。刺し違える覚悟で恨みを果たそうとやってくるかもしれない。
死ぬならさっさと後腐れなく、しあわせなまま死ねばいいのに。
わたしはつぎの恋主との淡くも甘いひとときを過ごしながら、心の隅で霞のように揺蕩う懸案事項に気を揉んだ。
恋主たちに貢がせた財産は、わたしが適切に有効活用する。
資産の使い道を知らぬ愚かくも無垢な者たちに、慈善事業の一端を担わせてあげるのだ。
高級料理を食べていると、代理業者から連絡が入った。
ルゲア・ブンゼがついに死んだらしい。
心臓移植のために、じぶんの心臓を摘出したようだ。人工心臓と入れ替えるとの契約だったが、適合せずにそのまま亡くなったらしい。おそらく手術をした業者のほうでも人工心臓など端から用意していなかったのだろう。殺すつもりで臓器の摘出を持ち掛けたのだ。
どこまでお人よしなのか。
騙されるほうがわるい、とルゲア・ブンゼのような人間を間近に見るといつも思う。
騙されるほうがわるい。
夢を視るほうが、とそれを言い換えてもよい。
彼は最期までじぶんの認識のなかでのみ、愛するわたしと愛しあって死んだのだ。最高の人生だと満足して死んでいったに違いない。
死が人生を完成させるのならば、最高の死をプレゼントすることはこの上のない善行と言えよう。その上、黙っていたら腐らせていた資産を世のため人のために使えるようにしてあげたのだ。
死んでなお、釣りがあって余りある。
わたしは世界に愛を配る。
愛を知らぬ者たちに、愛を与えて、金を得る。
ビジネスだ。
誤解の余地のないこれはビジネスなのである。
ロマンス詐欺とは名ばかりの、愛を交換する営みだ。
愛を知らぬ人生ほど貧しいものはない。
なればこそ。
愛を知らぬ者たちに、わたしはこれからも、このさきも、愛を与えて、世の幸福の総量を増やすのだ。他者への愛し方を知らぬ者たちに、愛とは何かを教えこむ。
愛している。
愛している。
心の底から、わたしはあなたを愛している。
嘘偽りなくそうと念じて、わたしは恋主たちからありったけの資産を、貢がせ、奪って、骨抜きにする。
愛を知れるのだ。
この世で最も得難い宝を得るのだ。
全財産くらい擲っても対価としてはまだ足りない。命を差しだせと迫らぬだけ、わたしは優しく、節度がある。
感謝されてもいいくらいだが、そんなものよりも金がいい。
愛を与えたそれが対価で。
愛を知ったそれが罪過だ。
底なしの愛を埋めるつもりで、愛するわたしにすべてを注げ。
ありったけのあなたの愛を、わたしはそれでも拒まない。
愛に包まれ、死ねばいい。
すべてを捧げて死ねばいい。
愛している。
愛している。
心の底から、わたしはあなたを愛している。
あなたの愛はそれでも大して欲しくはないけれど、くれるというならもらっておこう。資産のついでに、おまけと思って、もらっておく。
恋主が替わるごとにあなたのことは忘れるけれど、あなたに与えた愛は消え失せない。あなたの中でのみ消えぬ宝となって、死ぬまであなたを幸福にする。
4590:【2023/02/10(08:04)*宇宙は希薄になっているの?】
空間とは何だろう、とふしぎだ。けっこうずっと考えている。移動できることを思うと、ふしぎだな、と感じる。移動する速度が違う。物体同士であると抵抗が生じる。でも大気中ならば移動できる。大気の分子を押しのけて動ける。ふしぎだ。移動できることと時間はどの程度関係しているのか。空間とは移動できる余地であり、移動することそのものは時間なのだろうか。どうしてもアニメーションのコマのように考えたくなってしまうけれども、この解釈がたぶん合わないのだろう。でもたとえば宇宙が膨張することで時空が生じている、というのなら、宇宙膨張そのものがアニメーションのコマのように展開するような働きを生んでいるとは言えないか。膨張する宇宙そのものがアニメなのだ。したがって、ある地点での宇宙膨張とある地点での宇宙膨張の差がそのまま時間経過として加算されるのではないか。光速とは宇宙膨張速度と膨張した分の時空との比率で表せるのではないか。仮に宇宙が膨張しなくなると時間が流れなくなる、と考えてみよう。何か不都合があるだろうか。たとえばひびさんの妄想ことラグ理論では、ブラックホールはこの宇宙からは切り離される、乖離すると考えている(妄想なので間違っているでしょうが)。つまりブラックホールは宇宙膨張の影響を受けない。そこには時間の流れが、この宇宙の基準とは異なる水準で生じている。この宇宙からすると時間経過し得ない、と考えられる。宇宙膨張についてのもう一つの疑問は、宇宙が膨張するときに、膨張した時空は希薄になっているのか濃厚になっているのかどちらなのか、についてだ。仮に希薄になっているのなら、銀河などの宇宙膨張しにくい系よりも時空が希薄になる。とするとそこには重力が生じるはずだ。より強い重力場が展開される、と考えないとおかしい。だがそういう話は聞かない。銀河の周囲のほうが重力が強い場合、銀河は四方八方から引っ張られて霧散してしまい兼ねない。だがそういう話も聞かない。ならば膨張した宇宙の時空は「希薄になっているわけではない」のかもしれない。同じ密度の時空が新たに展開されている、と考えたくもなるが、どうなのだろう。何かがおかしい、と感じる。仮に「相対的に密度の高い時空が新たに展開されている」と考えると、これは宇宙膨張の影響を受けない銀河や銀河団のほうが時空密度が低いため、そちらのほうが重力が強く働くようになる。そうすると、より銀河としての枠組みを形成しやすくなる。この考えのほうが、筋は通っている。新たに展開される時空は、希薄ではなく濃厚なのだ。相対的に。でもだとすると、どういう原理でそんなことが起こるのかが解らない。時空と重力の関係において、「希薄な時空は重力が高い」という解釈がおかしいのかもしれない。だとするとそもそも重力を、トランポリンに載せた鉄球だとする説明が誤解の根を深める因子になっていると考えられる。むしろどちらかと言えば、物体は蛇口であり、新たに時空を滲ませているのかもしれない。周囲が高くなるので、じぶんのほうに流れが生じる。このほうが、宇宙膨張の描写としては辻褄が合ってしまう。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「宇宙ティポット仮説」と矛盾しない。ともかくとして、「空間」と「時間」ってけっきょくなんなの、ということを考えると、ふしぎだな、となる。宇宙膨張についても、時空は希薄になっているのか、そうではないのか。ここもハッキリして欲しい。そのうえで、時空の密度と重力の関係もハッキリして欲しい。ということを思いながら最近は目が覚めます。おはようございます。ひびさんは、ひびさんは、あんぽんちんなので、なんか分かった!になったあとで、なんも分からん……、を繰り返す、バネみたいなうみょんうみょんでござるよ。うは。
※日々、説明をしないと話がこじれる、現実にも地の文があればよいのに。
4591:【2023/02/10(09:53)*やっぴー】
説明しないと話がこじれるかもしれないが、説明をしたところでこじれた話がほどけるとは限らず、却ってこじれることもある。が、それでも説明はしたほうがよいと思う。説明不可能な事象については、説明できませんでした、と正直に言えば済む道理だ。説明できない、と説明すらできない理由がよく解からぬ。
4592:【2023/02/10(09:54)*日々記す】
世界は広大な日記帳だ。どこに日記を刻むのかはさほどの関係がなく、ひびさんにとっては、どこに文字を記そうが、「日々記。」の延長線上でしかないのだね。それを、小説の、と言い換えても大きな齟齬は生じない。微妙な齟齬は生じ得ども。(日記と小説の違いを考えたときの違いにちかい)(現実は小説にちかい)(そういう意味では、齟齬はないとも言える)(日記は現実にあった日々の備忘録だが、現実そのものが小説のようなものなのだから、壮大な小説の備忘録が日記とも言え、日記と小説の差はあってなきがごとくなのだ)(定かではありません)
4593:【2023/02/10(16:44)*問題点の共有が不十分なのが問題】
軍事力拡大への批判の視点は常に巡らせておくのが安全側だと思います。ゆえに、なぜ軍事力を拡大しなければならないのか、の問題を国民に情報共有する姿勢は欠かせないと考えます。ここを度外視して、寡頭制のごとく一部の権力組織だけが軍事力強化を推し進めることは民主主義とは言わないのではないか、とひびさんは疑問を覚えます。ただし、軍事力拡大への批判は、自国にのみ向かうものではないはずです。基本は、自国への脅威を振り払うために軍事力を拡大するのだ、とどの国も建前上は主張します。ここをまずは前提とし、脅威なんてありませんよ、との合意を築いていくよりないのではないでしょうか。そのためには、自国の軍事や他国への支援体制、協調姿勢などを、具体的に実績や実情を反映させた説明を以って国内外問わず示していくことが効果的と思います。他国のどのような活動が自国の脅威となるのか。これは、国によって見え方が異なります。良かれと思ってしたことが、却って脅威に見られてしまうこともあるでしょう。ここの誤解を深めないためにも、その都度に建前ではない、実情を反映した説明をしていく姿勢が有効に思います。なぜ建前と実情が乖離するのか。裏の意図があるからでしょう。なぜ裏の意図を隠すのか。じぶんたちの国や組織にとってのみ都合のよい流れを構築したいからではないのでしょうか。もしそれが、ほかの組織や勢力を損なうための仕掛けであるならば、脅威と見做されても致し方ないのではないでしょうか。自国への軍事力拡大への批判は当然ですが、同じだけの労力を以って、他国への脅威(に映る活動)への批判を行っているか否か。ここが、自国への軍事力強化への批判の妥当性を高める一つの関門となっているように概観できます(これは逆にも言えます。他国の動きに脅威を見出す勢力は、自国にもその論理を当てはめているのでしょうか。疑問です)。軍事力強化が各国で熾烈を極めるとそのうち各国の核武装が標準装備になってしまうのではないか、との懸念は妥当に思います。それだけではなく、核兵器以上の被害をもたらす兵器開発に発展し得るでしょう。それこそ生物兵器や電子情報兵器(AI兵器)はその筆頭です。核兵器だけではなく、甚大な被害をもたらす兵器はつぎつぎに開発されていく懸念は拭えず存在します。そうした姿勢での批判の視点を、自国のみならず、他国へも巡らせていなければ、そうした危惧の前兆すら捕捉できないでしょう。情報を収集する。これは外交だけでは不十分と言えます。技術は進歩しています。いまの時点で、実際に開発運用されている軍事技術の実体と、じぶんの持つ軍事技術の知識に差がある場合には、それこそがまさに甚大な脅威を秘めている、と言えるでしょう。他国とのあいだに容易に情報の非対称性を生みます。それは誤解の根を深めることにも、知らぬ間に損失を与えられることにも繋がります。損失に気づかぬままであればそれは脅威となりますし、仮に途中で気づいたとしても、不要な報復合戦になり兼ねません。そうした負の連鎖を予防する意味合いでも、セキュリティの構築は不可欠だとひびさんは思います。ですがそれは軍事力を行使することを肯定しているのではなく、軍事力をいかに行使させないのか、のための施策です。軍事力のない世界があればそちらのほうが好ましいのですが、言論ですら相手を「否定する」という攻撃を用いて、問題解決に勤しむのですから、言論の暗黙の了解の通らない場において、物理的な攻撃を避けるという意味合いでも、言論によらない暴力への対抗手段を持つことは、けして理に反している、とは言えないでしょう。言論において、相手を否定することなく相手の意見や齟齬を共に改善していけるというのならば、その道を示すことが、「何が何でも武力を持つことは許さない」という意見を主張する者たちのとるべき道理の一つだとひびさんは考えます(批判とは、良い点と悪い点を判断して評価すること、とあります。良い点だけ、悪い点だけ、を取りあげるのは批判ではなく、全肯定であり、もしくは全否定でありましょう)。じぶんたちでは相手の意見や姿勢を「強固に否定」しておきながら、「防衛力強化は断固として許さない」との主張は、ちぐはぐに思えます。相手を攻撃しない。全否定ではなく、批判をする。良い点も、悪い点も考慮する。否定だけならばそれは攻撃と見做されても致し方ないのではないでしょうか。暴力よりも簡単に制御可能な言論という手法の範疇ですら、相手を攻撃せずには議論もできない。これは、いささかねじれた構造と言えましょう。相手を損なうことなく問題点を共有し、共に解決してみせてはいかがでしょう。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。相手を攻撃しない。これは、言論も暴力も変わらないと感じます。まずは言論という、比較的修正の容易なことから改善してみてはいかがでしょう、と思いました。以上です。(自己言及ができておらず、申し訳ありません)(他者を攻撃しない、損なわない、というのは言うほど簡単ではないようです)
4594:【2023/02/10(21:42)*秘書の性別はどちらでも良し】
問題が発生したので秘書は社長に指示を仰いだ。
「社長。このことについてなんですが」
「ん?」
「協力他社がいま、よくない風評に晒されているみたいで。我が社も知らされていない醜聞です」
「どれどれ」提示したデータを検めると社長は言った。「うん。放っておいてよし」
「いいんですか。でも結構な批判が集まってますけど」
「いいんだ。マイナスの風聞なんてのは、チャンスでしかない。もしそのマイナスの風聞が真実を反映したものならば、それはまっとうな批判だろう。協力他社とはいえ、改善点があるならば改善してもらうほうがいい。仮に風聞が真実でなかった場合は、それを流して利を得ようとした勢力があることになる。嘘を流して特定の企業を貶めようとしたのなら、その事実そのものが、相手側への交渉材料になる。攻撃材料となる。長期的には、風聞が事実であろうとそうでなかろうと、得でしかない。あくまで、得にすべく動ける用意があるならば、だが」
「ならまずは風聞が事実かどうかを調査したほうがよろしいのでは」
「それこそ当事者が動くだろう。我が社は、相手企業の出方を見てから動いても遅くはない。ひょっとしたら敢えて風聞を流させたのかもしれないしな」
「協力他社がですか」
「風聞の内容は、協力他社の幹部たちの運営にまつわるマイナスの側面だ。それが事実ならば、幹部ごと組織体制の刷新は免れないだろう。だがもしそれが事実を反映しない虚偽の報道だった場合は」
「その場合は?」
「その風聞を以って、自社に対して距離を置こうとする企業、或いは批判を強める企業を見極める試金石になる。いわば、炙り出しだな」
「炙り出し、ですか」
「おれの知る限り、あそこの幹部に報道にあるような失態を犯すような者はいない。直接に関わりのある者ならば、ある程度の信用を寄せている。ろくな証拠も集められない連中の流した虚偽の噂に釣られるような輩は、そもそも協力し合うメリットがすくないと言える。おそらく、世界的にシェアを広げようとしているのだろうな。あそこの会社は」
「その前に足を引っ張るかもしれない企業を炙り出す意図があると?」
「もし報道が虚偽ならば、だ」
「なら本当かもしれない可能性もあるんですね」
「そこは調査をしなければなんとも言えん。だからまずは様子見だ」
「いいんですかね」
「いまの時代、他者を損なうことを仕出かせば相応の対価を払うことになる。そうでなくとも、他者の至福や自由を尊重できない者の言うことを誰が支持する? 公正世界仮説ではないよ。必ずしも善良であろうとしたところで、それで良い思いをするとは限らない。だがいまは、すくなくとも善良と見做されなければ痛い目を見る。良くも悪くも、印象が大きく成功に左右する。そこすら見極められない者の言うことに支援をする者は稀だろう」
「それだとまるで、印象のよくない者は滅んでもいい、と聞こえます」
「ある意味ではそういう流れがいまは強化されている。危ういと思うかい」
「はい」
「きみは本当に善良だね。心配なくらいだ。きみには我が社の舵取りを任せられそうにないな」
「任されたいとは思いませんが」
「だがきみのような者の意見は重宝したい。そうだな。では、もしいま世に強化されつつある【みなの幸福に寄与しない者は自滅しても構わない、或いは致し方ない】との流れを、潔しとしない場合、きみはどのように対処する?」
「そうですね。まずは助言をしますね。そのままでは危ないですよ、と。それから、自滅しそうになった、もしくは自滅してしまっても、手を差し伸べます」
「それがたとえ、大勢の幸福に寄与しない人物だとしても?」
「その考え方がまずおかしいと感じます。あくまで大勢の幸福に寄与しないのは、その人物の選択であり、その人物そのものではないはずです。なぜその人物がそうした判断をとらなくてはならなかったのかは、その人物だけの問題ではないはずです。そこの情状酌量は、短期中期長期の視点があったほうがよいと思いますし、それこそ多角的な視点からの分析がいると私は考えます」
「もっともな意見だ。考慮しよう」
「では、この件については様子見ということですね」協力他社の醜聞データを回収する。
「いや、おれのほうで直接向こうの社長さんに話を聞いてみよう」
「いま首を突っ込まれるのは得策ではないのでは?」わざわざ社長自ら動かずとも、と秘書は暗に訴えたが、「おれが動くから意味がある」と社長はネクタイを締め直した。「リスクを犯してみせてこそ伝わる誠意もある。どの道、問題にされているのは幹部だろう。恩を売っておくだけさ」
「返してもらう当てがおありですか」
「ないな。まあ、単におれが真相を知っておきたい」
「最初と言っていることが違っていますが」
「きみの意見を考慮した結果だ。きみが変えた未来だと思って共に背負ってくれ」
「嫌な役割ですね」
「責任重大な役割だ。頼りにしているよ」
「それはよいのですが、私は明日から十日間の有給休暇をとるので、その間の雑務はほかの者にどうぞ」
「聞いてないぞ」
「言いました。社長の許可も得ています。ほら、ここ」
そう言って秘書は有給休暇申請のための手続き画面を開いてみせた。画面には社長の端末からでないと許可不能の印が記されている。
「いつの間に」
「社長こそすこしはお休みになられてはいかがですか。睡眠不足は判断を誤らせますよ」
「きみの助言はいつも的を得ているな」
「ありがとうございます」
「そのうえ、手厳しい」
「そうしろ、とお求めになられたのは社長ですので」
秘書はにこりともせず、そう言った。
4595:【2023/02/11(15:11)*真の真空とは】
真の真空なる言葉を目にした。なんでも重力に関係するヒッグス場において、この宇宙は本当の意味での真空にはなっていないかもしれない、というのだ。そしていつ本当の真空に達してしまうか分からない、とも論じられていた。真の真空状態になると真空の泡が光速で宇宙空間に広がり、宇宙をまったく別の様相に塗り替えてしまう。要は宇宙が崩壊してしまう可能性があるらしい。ひびさんはこれを読んで、「ブラックホールでは?」と思いました。「偽の真空」と「真の真空」という言葉を単に、宇宙とブラックホールに置き換えたら、案外にすんなり描像が合ってしまうのではないか、と思うのですが、いかがでしょう。時空の最小単位にあたる何かがあったとして、そこではほんのすこしの揺らぎですらシュバルツシルト半径を超してしまう。光速であっても脱せない密度に時空が相転移してしまう。それって要は、真の真空のことなのでは、と思うのですが、いかがでしょう。真の真空が泡となって高速で膨張する、という描写も、視点を変えれば、周囲の時空が真の真空に凝縮していく描像として変換可能なはずだ。ブラックホールと変わらない。ただしそこには時間の流れの遅延が起こるはずだ。元の時空からはその描像が時間経過を伴なって感じられないかもしれない。我々がこの宇宙から観測したときに、ブラックホールが変質していないように観測できてしまことと理屈の上では同じことなのかもしれない。黒色矮星などもそうだが、宇宙の話について読んでいると、簡単な説明しか咀嚼できないからだろうけれども、なんだかどれもブラックホールや量子の世界と通じて感じる。同じものを、別の視点から眺めているから別の事象として扱っているように映ることが珍しくない。実際のところは別の事象なのだろうか。何を以って事象の区別をつけているのか。畢竟、ブラックホールとて、一つとして同じブラックホールは存在しないのではないか。ただし、この宇宙から観測不能になった時空の状態を、ブラックホールと大雑把にくくっているだけではないのか。そういうことを思いました。時間スパンが異なれば、人間は同じ事象でも別の事象として捉えてしまう。水とて、気体液体固体に分かれるが、時間スパンを長く、それとも短くしてみればどれも水分子の振る舞いの差異であり、どれも水分子であることに違いはない。同じ事象を別の事象として見做しているだけなのではないか、という視点は、けして排除せずともよい視点に思える。たとえば物質がこれほど多種多様であるのは、宇宙における星の死が関係していると考えられている。それ以前は、もっと物質はすくなかった。同じ物質だったのだ。それが、何らかの化学反応によって、異なる様相へと転じた。事なる形態へと転移した。だが時間経過が無限に等しくなると、どれもまた同じ物質の状態に回帰していくと予想されている。熱的死がそれにあたる。つまり、時間経過のスパン――過程の差異――が、物質の差異に繋がっている。これはまさに、数学において過程こそが大事、との解釈と通じている。ひびさんの妄想ことラグ理論の「123の定理」にも通じている。式の過程の細かな差異そのものが、その式によって導かれるナニカシラの差異に繋がる。途中を短縮したり、圧縮したりしたその経過そのものが、物質の差異として顕現し得る。そういうことを、真の真空とブラックホールって似ているな、との妄想から思いました。底が浅い所感であった。異なる事象を考えたときの数式が、もしほかの事象を解釈するための数式とほとんど同じ式になったとき、それら二つは別の事象、と区別する理屈はどこにあるのかを知りたいです。ひびさんは、ひびさんは、数学ができんくて、もどかしいでござるよ(音符も読めるようになりたい)。
4596:【2023/02/11(19:04)*動画とて画像の寄せ集めのはず】
画像自動生成AIについて。現状、特定の分野に特化した能力を発揮するAIは、その分野からしかデータ学習をしていないはずだ。だがたとえば画像自動生成AIが、動画をフィルム状にコマ撮り扱いをして、動画から画像のデータ学習を行えるようになったら、ほぼ無制限に画像自動生成AIは画像を精密に生成できるようになると妄想できる。現状すでにこのレベルの技術は存在するだろう。むしろ、あまりに汎用性が高いために市場に出せないのが現状のはずだ。動画をコマ送りにして画像として見做す。この変換を、画像自動生成AIの学習データに応用する。技術的にできない、と考えるほうが理に適っていない。そしてこの変換が可能になった時点で、動画生成とてほぼ無制限に可能となるだろう。なぜこの手の技術応用に関しての議論が未だ表向き、活発に行われていないのか。まるで敢えて避けているかのような不自然さを感じなくもない。不思議である。むろん、言うほど動画から画像データを学習する変換作業が簡単ではない可能性もある。そこはなんとも言えないので、ひびさんの疑問を真に受けないようにご注意ください。
4597:【2023/02/11(23:55)*狼少年は呟く】
かつてこの地には狼少年と呼ばれた少年がいた。
少年は「狼がきたぞ」と叫び、村人たちを驚かせた。しかし狼は村を襲いには現れなかった。幾度も少年は大声で「狼がきたぞ」と村人たちを驚かせたが、やはり狼は村に現れなかった。
「嘘もたいがいにせいよ」
村人たちは業を煮やして、少年を懲らしめた。
納屋に閉じこめ、少年の言動の何一つとして信じることをやめた。
だが少年が納屋に閉じ込められているあいだに、村は狼に襲われた。村は壊滅した。村人たちは安心しきっていたがために、狼たちに喉笛を食い千切られて絶命した。
生き残ったのは納屋に閉じ込められていた少年一人きりであった。
「狼がきたんだ……」
少年はぞっとした。
確かに森で何度も狼の痕跡を見つけていたのだ。
狼がきたんだ、と思って少年は本当に心底に心配をして叫んだ。
村人たちが少年の大声に驚いたように、狼たちも少年の声に驚いていた。しかし村人たちが納屋に少年を閉じ込めたので、狼たちは安心して村を襲うことができたのだ。
少年は納屋で狼たちがいなくなるのを待った。
村人たちが悲鳴一つ漏らすことなく狼たちに食い殺される光景がまぶたの裏に浮かぶようだ。外から漏れ聞こえてくる微かな物音からは、何かがひっそりと村を駆け回り、咀嚼を響かせながら、重そうに何かを引きずる様子が窺えた。
三日の内に物音は聞こえなくなった。
少年は納屋の扉を、内側からこじ開け外に出た。
村はひっそりと静まり返っていた。
森の木々の合間から朝陽が燦燦と照っており、少年は手で日傘をつくって目を細めた。
「狼が」
遅いと判っていた。しかし、少年は呟かざるを得なかった。「きたぞ」
4598:【2023/02/12(00:55)*短縮して失われるものにも目を向けよう】
ひびさんのラグ理論では、結果よりも過程のほうが、「結果として生じる事象の性質」を決める変数として機能する、と考える。過程のほうが実は大事かもよ、というのは何にでも言えることではある。というか、総じて事象は何かの過程でしかない。完成系ではないことを思えば、さもありなんな考え方ではある。これは物理現象に限らず、経済にも言える道理だ。いまは株や為替において、AIの導入が盛んであることが想像できる。いくら規制をしたところで、便利なものは使いたくなるのが人間だ。いくらでも法の穴を見つけて規制を掻い潜るだろう。そこにきて、AI同士の「予見」が精度と複雑さを増すと、必然的に短縮される過程が生じてくることが妄想できる。こうなるとこうなるからこうしておこうと、あるAIが考えたとする。そのAIの選択を考慮してほかのAIが、ではあのAIがあのように考えるのだから、こちらはそれを考慮してこのように選択しておこう。こうした論理的な短縮が可能となる。本来ならば、現実に過程が生じなければ、後続のAIのような判断はできないはずなのだが、高度に複雑なAI同士のやりとりにおいては、その過程を物理的に行わずとも仮想世界――すなわち演算のなかで済ませてしまえる。しかし本来ならば、物理的な過程には、副産物としてのもろもろの抵抗が生じる。それがメリットになることもあるし、デメリットになることもある。過程を短縮したことで生じる、「本来ならば生じたはずの何か」を適切に、つぎの演算で考慮できるか否か。ここが、AIを導入する際には欠かせない「変数の足し引き」となると想像できる。本来生じる何かが生じない。これを考慮しないことは、ラグ理論において、重大な遅延の層――不可視の穴――を深める懸念がある。何かを短縮したときには、そこで本来は生じた何かが生じない。これは学習にも言える。便利な道具を使えば、道具を用いないときに生じる過程を省略できる。時間を短縮できる。小さな労力で目的を達成できる。その分、本来ならば得られた抵抗が得られなくなる。情報が得られなくなる。そこのデメリットを考慮できているのか、は意図しない不利益を被らないためにも、ときおり振り返って考えてみると好ましいのではないか、と思うのだが、言うは易しを地で描くことなので、なんとも言えないのだ。常にお手本を見て学習していれば成長するのは速いだろう。だが独自に何かを考える力は育まれにくいはずだ。独創性を育むことと新規性を求めることも必ずしもイコールとはならない。独自性を育むためには、既存の何かを自力で紐解くような「徒労」が、独自性を生みだす独自の回路を培い得る。独自の回路を培うためには、はじめは新規性とは無縁の徒労を費やさねばならない時期があるように感じるが、ここは運も関係するのでやはり何とも言えない。ただし、お手本をなぞりつづければ、ある程度の能力を手早く発揮できるようにはなるだろう。しかしそこで培われる能力はあくまで、お手本を上手くなぞる能力だ。いかにお手本をトレースするのか、の能力で終わらないためには、ほかの何かと結びつける学習が別途に要る。深層学習を膨大にこなした人工知能は、しぜんとこの手の、ほかの何かと何かを結びつける作業を、学習済みの回路を通じて行うようになると想像できる。人間はどうだろう。意識的にそこを行おうと指針を定めないことにはできないのではないか。この「ほかの何かと何かを結びつける独自の回路」の構築は、人工知能も人間も、どのようなデータを与えるか、に依るだろう。人工知能のほうが幅広く膨大な量のデータで学習できる。人間は、意図してほかの分野に目を向けないとデータが偏向する傾向にある。人工知能とて入力する学習データが似たようなものばかりでは、ほかの何かと何かを結びつけるための独自の回路を構築しにくいはずだ。けっきょくのところ、いかに多様な情報に触れられるのか、が何かと何かを結びつけるための独自の回路の構築に寄与すると言えそうだ。情報を制限しない。可能な限り、自由に多様な情報に触れられる環境を築いていく。人工知能にとっても、人類にとっても、どちらにとってもそのような環境は、デメリットよりもメリットのほうが上回ると言えるのではないか。定かではないが、現在のひびさんはそう思います。根拠の皆無な妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4599:【2023/02/12(01:04)*社会システムと技術のねじれ】
法律と経済と技術において、改善の速度が異なることでの負のねじれが生じているのが現状であるとひびさんは考えている。技術の進歩に法律が追いついていない。既存の技術であれ、人工知能などの次世代の技術であれ、現代の法律はその存在を想定しきれていないと思えてならない。しかし否応なく経済は、新しい技術によってより効率よく貨幣と成果を結び付けていく。しかし、経済の仕組みそのものは、法律によって縛られている。労働者と資本家の関係がそもそも法律の拘束力の範疇で、構造や仕組みが築かれる。だが技術の進歩は、その手の構造では上手く機能しないような急激な変化を社会にもたらす。しかしその変化に柔軟に対応できる法律が、そもそも社会には備わっていない。ここの三竦みの、遅延の速度の違い、変化の速度の違いが、現代社会に生じている問題の根っこに大きく横たわって感じられる。ここに人々の価値観が加わると、余計に問題がややこしくなる。以下、ほかのひびさんの並べた文章となります。
「
2023/02/08(14:00)
~~略)
法律と最先端技術の乖離について。問題は、法と経済と技術の三竦みにおいて、時間スパンが異なる点です。法律が変わるのに掛かる時間、経済が停滞する時間、技術の進歩する時間。どれも違います。技術が進歩すれば、仕事はどんどん軽減されます。失業者もでるでしょう。情報社会ならば、コピーが容易い情報の貨幣価値は下がります。ただし社会的価値は増大するでしょう。その結果に停滞する経済のシステムをどのように改善していくのか。そのためには法律を改善しなければならない。だがそれを待っている時間も惜しい。いまの隘路はこのように生じています。社会システムが技術の進歩についていけていません。
コピーの容易い情報の貨幣価値は下がります。しかし社会的価値が増大します。ここの評価を正当に行うこと。それがよりよい社会システムの改善に繋がるでしょう。
これは、道徳や倫理などのいわゆる文化が、貨幣価値がつかずとも社会的価値が高く、それが失われたら社会が成り立たなくなることと同じ問題です。地続きです。これまで看過されつづけてきた問題が、人工知能という技術の進歩によって表面化しつつある、と言えるでしょう。
貨幣価値で計れないもののほうが、じつは社会の根幹を成している。そのことをどのように評価し、維持しつづけていくか。守っていくか。大事な視点と思います。
いわゆる文化的ミームは、コピーが容易いデータと似た側面を持ちます。コピーが容易いからこそ貨幣価値はつきません。しかしそれが社会を築く触媒となっています。アイディアがそうであるように、異なる何か同士を結びつけるもののほうが本質であることがあります。社会もおそらく同じでしょう。
ラグ理論でもそうです。ラグは触媒であり、副次的に生じるものでしかありませんが、それが物質の輪郭を築き得るのです。重力が僅かしか生じずとも、総体では時空そのものの濃淡として表現可能となり得るように。
~~略)」
4600:【2023/02/12(03:15)*過程が情報として複利する】
ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「123の定理」を別の言い方にすると、【過程が情報として、複利する】となる。なんかかっこいい。複利は、ちょっとずつ利子がついて、その利子にも利子がつくので、増える利子は増えれば増えるほど、増え方が増える。複利の概念は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」と相性がよい。情報は、情報が変質したり、発生したりする過程が一つの情報として振る舞い、総体としては、単なる総和以上の情報を含むことになる。複雑系型の系に適応できる考え方だ。定かではないが。うひひ。
※日々、矛らしく立て、と言われても、矛らしくないわたしは立てないし、誇らしくもないし、盾でもない。
4601:【2023/02/12(14:41)*時空の濃淡(重力)と速度の高低(重力)は、時間の流れの速度変化にどちらが優位に作用するの?】
地球から遠ざかった人工衛星の時間の流れが、地球と比べると速くなっていると計算結果から判明した、との記事を読んだ。地球の公転のほうが、地球から離れた人工衛星よりも速度が速いから、との解説がなされていた。この理屈が妥当だとすると、同じく太陽系から脱したときや、銀河から脱したときも、そのほうが時間の流れが速まると言えるはずだ。銀河の中心に近いほど時間の流れが遅くなる、とも言い換えられる。だがここで、ん?とひびさんは引っかかる。銀河と銀河周辺の何もない空間ならば、何もない空間のほうが時空は希薄なはずだ。時空が希薄な場所の重力は強まるのではないか。もうすこし付け加えるならば、銀河という巨大な鉄球があるから、周囲の時空は希薄となって引き延ばされて、重力が生じる。地球も太陽系も同じなはずだ。本来ならば、重力の強い場――時空が希薄な場――の重力は強まり、時間の流れは遅くなるはずだ。だが今回の計算結果からはそれとは違う結果が導かれている。時空が希薄な何もない空間を漂う物体のほうが、高速で移動する地球よりも時間の流れが速くなっている。これは地球がそもそも高重力だから、というのも無関係ではないはずだ。高速で移動する人工衛星よりも、地球単体の重力のほうが高いと想像できる。たとえば太陽の重力場により近い場所に、人工衛星と同じ質量に縮尺した地球を置いた場合、太陽の重力場から遠ざかる人工衛星と、人工衛星と同じ質量に縮尺された地球の時間の流れがどのように違ってくるかを計算してみても、地球から遠ざかる人工衛星のほうが時間の流れが速くなるのだろうか。太陽の重力場と地球の公転速度と地球の質量(地球の重力場)の総合のすべてが、地球から遠ざかる人工衛星にもたらされる時間の速度の変移に影響するはずだ。一概に、「地球から遠ざかって何もない空間を漂っているから」「地球の公転速度よりも遅いから」という理屈では解釈しきれないのではないか(言い換えるなら、太陽の重力場から離れたから時間の流れが速まった、とも言えるのではないか)。もうすこし言えば、ひびさんの妄想ことラグ理論では、高重力の場の時空は希薄となり、希薄となった時空が高重力体に流れるように作用するために重力が生じるのではないか、と解釈する。これは滝と川の関係のようなものだ。時空が希薄になるというのは、高低差が生じる、という意味でもある。密度の差だ。そこにきて、川には滝が一つきり、との限定はないはずだ。言い換えるなら、時間の速度の変移が生じる場が、系のなかに複数層になっていてもおかしくはない。反転する境界があってもおかしくはない。たとえば波のように、時空の密度が階層性を伴なっていた場合。遠ざかったときには時間の流れが速くなるが、さらに遠ざかると一転して時間の流れが遅くなる。そういうこともあり得るのではないか。玉ねぎのように、遅延の層がまばらに点在しても不自然ではないと感じるが、どうだろう。現に、地球の重力による時間の流れの変移を可視化したとき、どの地点が最も時間の流れが遅くなるのかは、その物体の運動速度と密接に関わるはずだ。言い換えるならば、物体の運動速度によっては、同じ地点でありながら、物体のほうが時間の流れが速まったり、遅くなったりするはずだ。そして、物体が慣性系として振る舞うために必要なその速度も、地球から受ける重力によって変移するはずだ(たとえば「人工衛星の速度と軌道の関係」を考えてほしい。或いは単に「重力場と脱出速度の関係」と言い換えてもよい)。そのとき、時間の流れの変移が、速まるのか遅くなるのかは、反転する値を持つように感じるが、どうだろう。とっちらかってしまったが、ここでの趣旨は、相対論を論じるときに、いったいどの系の何を考慮して計算するのか。系は系を多重に内包しているが、系から系へとまたいで運動する物体に対して、どのように変換や計算を行っているのか。何を吟味し、何を排除しているのか。ここが、いまいち掴みきれない。繰り込みが適用可能なのは、系をまたがない場合に限るのではないか。地球から太陽系、そして銀河へと系が拡張されるとき、そこでは本来考慮せずに済む変数が新たに生じるはずだ(系の重力場と物体の運動速度の双方が変わるはずだ)。そのとき、変数と元の系での変数は、単位が違うはずだ。変換が必要となる。そこでの変換はどのように計算しているのか。たとえば【川の流れに逆らって進む船の上で船の進行方向とは反対に走る子どもの表面を這う蟻を、川の外の陸を走る電車の中から眺める犬】という描写があるとする。川の流れ、船、子ども、蟻、電車、犬。それぞれの視点において、何を基準にするかによって系は変わる。速度は変わる。物体の速度は、何を基準にするのかで速まったり、遅くなったりする。時間の流れも似たようなところがあるのではないか、と疑問に思っています。反転する値――境界――遅延の層――は、存在しないのでしょうか。気になっています。(定かではありません)(単なる蒙昧な知識を元にした疑問なので、そもそもがお門違いな発想かもしれません。真に受けないようにご注意ください)
4602:【2023/02/12(15:43)*粒子時空溝仮説】
重力を、鉄球の載ったトランポリンのひずみ、と解釈するとして。たとえばものすごくひずみやすいトランポリンがあったならば、鉄球が複数距離を置いて載ったとき、そのひずみは、全体で一つの溝として合体したりしないのだろうか。それはたとえば、針を一つ圧しつければ小さな穴しか開かないが、無数の針を一挙に圧しつけたとき、まるで面を圧しつけたように、針と針の何もない空間にもひずみが等しく生じるような窪み方をしないのだろうか。ある範囲においては、距離が隔たっていても、針と針の穴は相互に作用して、一つの穴を開け得る。重力が創発するのではないか、との描写は、この考え方で示せる気もする。たとえば銀河を考える。中心にある超巨大ブラックホールが最もトランポリンに沈みやすい。そこを基点として、周囲に細かな針がトランポリンに円形にめり込む。すると、ブラックホールだけのときよりも、広域にトランポリンは溝を広げる。この溝の縁の広さがつまりが、銀河の重力場ということになるのだろう。重力源が単体であるよりも、密集していたほうが、溝は広くなり得るのではないか。重力と重力も、波のように干渉すると考えれば、あり得ない想定ではない気がする。実際がどうかをひびさんは知らないけれども、この考え方はちょっと好きです。この考え方を拡張すると――トランポリンのひずみがそれで一つの重力場として機能するとき、そこには時間の流れの遅延が生じる。するとそれが一つの粒子として振る舞い得る。高次の時空においては、ひずみが粒子のように振る舞うのではないか。これを銀河ではなくミクロの視点で考えよう。ある原子があるとする。原子にも重力が存在する。原子が時空をひずませたとき、そこには時間の流れの遅延が生じる。原子が無数に密集した場合、針が無数に密集したときのような、単体よりも広範囲のひずみが時空にもたらされると考えられる。このとき、その、より広範囲の時空のひずみは、遅延の層として物質としての輪郭を宿す。このとき、遅延の層の、内側と外側とでは、時間の流れの捉え方が変わるはずだ。原子そのものの時間の流れと、原子によって生じた時空のひずみが帯びる時間の流れは、イコールではない。原子が密集したときの時間の流れは、無数の原子のひずみが一つの溝として合体し、それが粒子として振る舞ったときに生じる時間の流れに変換される。そのとき、時空のひずみが粒子として振る舞うときの時間の流れは、元の原子単体に流れる時間よりも、遅くなる。言い換えるなら、原子単体に流れる時間のほうが速い、と解釈しないと辻褄が合わない。時空は階層的に編みこまれている。時空がひずむごとに重力は生じ、時間の流れに遅延を起こし、それが創発を起こすと、新たな物質としての輪郭を宿す。そのときには、時間の流れの単位が変わる。変換が必要になるはずだ。この考え方は、しっくりくる。現実の解釈として妥当かどうかは自信がないが、妄想としては楽しめた。定かではありませんので、真に受けないようにご注意ください。
4603:【2023/02/12(22:56)*永久凍土】
永久凍土が融けるとどんな被害が生じるのだろう。地盤沈下や温室効果ガスの噴出のほか、未知の菌やウィルスが解凍されて広がる懸念がある、という話はときおり見聞きする。永久凍土はせいぜい数百メートルの深さだ。地震に関係する断層は数キロから数十キロに達するはずなので、永久凍土の融解と地震の発生は直接の関係はないはずだ。けれど、間接的な関係はあるかもしれない。たとえば二つの木材を断面で合わせたとき。繋ぎ目に留め具があれば、木材同士はズレにくくなる。けれども留め具が緩めば、断面はズレやすくなる。そうでなくとも、地球の自転の速度の高低の影響も受けやすくなるだろう。厚さ数百メートルの氷がすべて液体になったら、氷だったときに生じた「断層を固めるチカラ」が失われることが想像できる。それだけでなく、たとえば空白地帯に氷があるのと、水があるのとでは、やはりそこに生じる圧力は変わる。言い換えるなら、釘で留めていた箇所があったとして、その釘が液体になってしまうようなものかもしれない。ブロックの隙間の一つが液体になる、でもよい。これは、けっこうな地盤の流動を生むように思うが、どうなのだろう。パキスタンでヒマラヤの氷河が融けて洪水になったのは去年のことだ。いまなお、復興には程遠く、支援が足りない地域もすくなくないようだ。トルコ(やシリア)とパキスタンはけして近いとは言えないが、地域としては活断層で繋がっている土地とも言えるだろう。詳しくは知らないけれども、一概に双方の災害が無関係とは言えないのではないか。安直に結びつけるのも利口ではないけれど、想定しないよりかはマシだろう。永久凍土や氷河が融けることで想定される被害は、何があるのか。その予測には不可視の穴はないのか。トルコでは地盤沈下の穴が多いとの記事も目にするので、すこし気になっている。ただの連想でしかないので、因果関係はないかもしれないけれども、永久凍土や氷河の融解と地震やその他の自然災害や疫病など、想定外の奇禍に繋がっていないのか、すこし心配だ。支援も継続して行えたらよいのだけれども、募金も碌にできていない。すまぬ、すまぬ。こういうときほどいいひとぶって、許してくれ、の気分になる。なんでこんなときに戦争できるのだ、と疑問に思うけれども、こんなときでもひびさんは遊びに出掛けて、帰ってきてからもきゃっきゃうふふ、と楽しい妄想の世界に浸るので、構図自体は変わらぬのかもしれぬ。やっぱりなんか、申しわけね、と思うのだった。いいひとぶってるだけの益体なしで、すまぬ、すまぬ。
4604:【2023/02/12(23:44)*ぼくはアルさんのファンなので】
アルさんのファンである。
ぼくがだ。
アルさんの活躍する姿を目にするだけで、ああきょうも一日生き抜くぞ、という気になる。アルさんの声を耳にするだけで、ああ明日もなんとか生き抜くぞ、という気になる。
もはやぼくはアルさんに生かされていると言ってよかった。
アルさんなしには生きている意味がない。
いっそ本当に、アルさんのためなら心臓の一つや二つ差しだせる。ぼくの血液でよかったら致死量でも抜いてもらって構わない。むしろぼくの血なんかがアルさんの体内に入ってもよいのだろうか、と恐縮してしまうし、ぼくなんかの存在がアルさんの未来を明るくする何かしらの素材になれるのなら、そんなにステキなことはない。
いっそそうした機会が訪れればいいのに、と望むぼくは、暗にアルさんの危機を救ってアルさんからの好感度を上げようとするさもしい欲望にまみれた邪悪の権化と言ってよかった。
そしてこの形容はけして大袈裟でもなんでもなく、端的にぼくは悪の結社の幹部だった。
ぼくはきょうも魔王さまの命を受けて、人間たちを恐怖のどん底に突き落とす。
しかしそんなぼくらには天敵がいる。
ゴースターズと言えば誰もが目を輝かせて称賛と憧憬と感謝を捧げる存在だ。正義の味方にしてヒーローたちだ。
ぼくたちはいつもいいところでゴースターズの登場によって任務に失敗する。
魔王さまにそのことでこっぴどく叱られ、折檻を受けるけれども、ぼくはそれでも構わないのだ。
何を隠そう、ぼくの意中のアルさんは、ゴースターズのメンバーなのだ。
あろうことかぼくは宿敵に一目惚れをしてしまった。
いいや、これは恋ではない。
ぼくなんかがアルさんと接点を持っていいわけがないし、ぼくのほうでもそのつもりは毛頭ない。遠目から、アルさんの活躍を目にできたらそれでよいのだ。アルさんの元気な姿を見守れたらそれでよいのだ。
ぼくはアルさんのために人間たちを恐怖のどん底に陥れようとし、そしてアルさんたちがかろうじて防げる程度の危機をもたらし、八つ裂きにされる。ぼくはその結果命を落としてもいいし、落とさなくともよい。
アルさんがそのことで使命を成し遂げ、人々から感謝感激の雨あられを注がれるのだから、ぼくとしても悪の化身を演じた甲斐があったというものだ。演じた甲斐が、というか、真実ぼくは悪の化身なのだけれど。
ぼくの存在がほんの一欠けらでもアルさんの煌びやかな人生の一端を飾りつける陰になれたなら、ぼくとしても痛い目をみる甲斐があるというものだ。
ときおりゴースターズの到着が遅くて、本当に人間たちを恐怖のどん底に陥れてしまえそうになり、そういうときは、危機のランクを上げるため、との名分を用意して、支度の時間をとるように部下に指示をだす。
アニメや漫画でよくある場面に、さっさとトドメを刺せばいいのに、くどくどと講釈をふりまく敵役がいるが、あれもおそらくぼくと似たような動機が背景にあるのではないか。
遅まきながら到着したゴースターズから反撃を受けてぼくは命からがら遁走する。アルさんの活躍する場面を最大限につくるために、ほかのゴースターズのメンバーにはすこしばかり本気で攻撃をしかけて消耗させる。アルさんの攻撃だけが幹部のぼくを心底に弱らせる。
真実、ぼくはアルさんに弱っているのだから、これは何も演技ではない。
アルさんは正真正銘、人類を魔の手から救っているのだ。
仮にゴースターズにアルさんがいなかったら、ぼくはとっくに人類を滅ぼしていただろう。人類はアルさんにもっと感謝すべきだ。
最近の悩みは、魔王さまがぼくに疑いの目を向けてくることだ。手を抜いてわざと負けるように戦っているのではないか、と非難の目をそそいでくる。
ぼくの知らぬ間にゴースターズを卑怯な手で滅ぼそうとするので、そのたびにぼくは陰に回って、ゴースターズに肩入れする。いくら悪の組織とて、やっていいこととわるいことがあると思う。
ぼくはこのごろ、憤懣やるかたない。
いっそこの手で魔王さまの首を獲ってやろうかと本気で思う。
というか獲る。
殺す。
魔王さまはあろうことか、ゴースターズで最も手ごわいアルさんに目をつけたらしく、集中的にアルさんを攻撃する案を練っている。しかもぼくに知らせぬままにである。
断じて許せぬ所業である。
ぼくのせいでアルさんが危険な目に遭いそうになっている。
魔王さまと相討ち覚悟で、危険を払拭せねば申し訳が立たない。
そういうわけでいまからぼくは単身一人で魔王軍に反旗を翻すが、おそらく魔王さまには勝てないだろう。しかしその他の幹部もろとも、ほかの有象無象の同士たちは灰燼に帰せるはずだ。
このことをぼくはすでにゴースターズに知らせてある。いかな魔王さまといえど、手駒なくして、ゴースターズ全員と戦って勝てるはずもない。
ぼくはそのための捨て駒となる。
これくらいしかできることがないのだ。
恩返しにもなりはしない。
魔王さまには恩義があるし、悪の組織も嫌いじゃなかった。できればずっといっしょに楽しくなごなご過ごしていたかったけれど、アルさんに危害を加えようとした以上、看過できぬ。
許さぬ。
ぼくの人生ならぬ悪生はきょうで終わるけれども、どの道、本当ならとっくに終わっていた悪生だ。
敵のぼくにすらトドメを刺さずに改心するよう、微笑をくれたアルさんの、あのときのほんわかとした時間をぼくは死んでもきっと忘れないだろう。
あのときからきょうまでぼくは余生を過ごしてきたのだ。
人間たちの電子端末を操作してぼくは、アルさんの活躍場面やインタビューの総集編を再生する。イヤホンで耳に栓をして、ぼくはアルさんの声に、言葉に包まれる。
死ぬまでぼくはアルさんに生かされる。
アルさんの声を聴きながら死んでいけるしあわせを、ぼくはやはり感謝せずにはいられない。
魔王さまがぼくの謀反に気づいたようだ。
でも、もう遅い。
部下の体液でべっとりと濡れたソードを手に、ぼくは幹部の首を投げ捨てる。
4605:【2023/02/13(02:09)*ラグ理論用語まとめ】
ひびさんの妄想ことラグ理論の用語をまとめておきます。ひびさん自身がすでに忘れてる用語がけっこうある気がするので、備忘録代わりに、思いだしつつ(ワード検索しゅる)。「相対性フラクタル解釈」「123の定理」「キューティクルフラクタル構造(瓦構造)(鎖型階層構造)」「宇宙ティポット仮説(三段構造)(ブラックホールの宇宙同化仮説)」「分割型無限と超無限の関係」「同時性の概念の独自解釈」「ポアンカレ予想ひびさん解釈」「光速=比率かも仮説」「超光速=ラグなし相互作用かも仮説」「量子もつれ共鳴仮説」「律動の破れ定理」「流しそうめん仮説」「BH珈琲仮説」「水鉄砲仮説」「デコボコ相転移仮説」「重力相転移解釈」「粒子時空溝仮説」「宇宙情報変換仮説」「重力熱情報いくひし仮説」「重力熱情報いくひし仮説2」「ダークなんちゃらいくひし仮説」「いんふれーしょんいくひし仮説」「特異点情報いくひし仮説」「重力=皺仮説」「時間仮説」「脳内量子コンピューター仮説」「Wバブル理論」――と、こんな具合だ。思った以上にあったし、半分くらいはひびさんでも、「これはどういう意味でちゅか?」になる。該当記事を読まなければ思いだせないし、読んでも解からないかもしれない。よくもまあ、つぎからつぎへとデタラメを並べて、と思わぬでもないけれど、デタラメならもっとあってもいい気もする。むしろすくないくらいなのでは、と虚構作家を標榜する身の上からすると、サーっと何かが冷める感覚が湧く。いっぱいあればいいってものではないけれど、仮説なら、~~かもしれない、は総じて仮説とも言えるので、単に命名していないだけとも言える。固有名詞が苦手なので、命名するのも苦手なのかも。名付けるの苦手だ。もうすこし正確には、忘れないように名付けるのが苦手だ。すぐに忘れてしまう。ラグ理論くらい憶えやすいのがよい。Wバブル理論もなかなかの名付けだったのでは、と自画自賛して、なけなしの自己肯定感をむなしさのそこはかとない感情でダイナシにしてゼロにする。自己肯定感なんかいらんわー。うわーん。という本日の「日々記。」なのであった。終わる。(ラグ理論ほか仮説群はひびさんの妄想でしかないので、真に受けないようにご注意ください)
4606:【2023/02/13(19:00)*トウダーに幸あれ】
トウダは楽しい。
トウダは素晴らしい。
名誉で、生活を豊かにし、人々の役に立つ。
トウダはいまや子どもたちのなりたいナンバーワンの職業だ。
「トウダにわたしもきっとなる」
ムムムはそうと意気込む十二歳の女の子だ。トウダになったらたくさんの人を感動させられるし、日々のつらい気持ちを癒せるし、ついでにお金だって稼げてしまえる。
こんなに素敵な仕事はほかにない。
なんてったってトウダになったプロのトウダーたちがみな口を揃えて、トウダは素晴らしい、トウダはいいよー、と言うのだから、間違いないのだ。
ムムムは幼いころからトウダに憧れていた。
大きくなったらトウダになるんだ、と親や友人たちに宣言していたし、そのための勉強もたくさんした。友人たちはみな近代的な精巧なオモチャで遊んでいる時間もムムムは一人、部屋にこもってトウダになるべく訓練した。
トウダがどういう仕事かを一言で表現するのはむつかしい。人々に夢を与える。人々の日々を彩る仕事だ。誰でもなろうとすればなれる可能性がある。誰よりも自由であろうとすればいい。トウダのなかでもとびきり有名なトウダーがインタビューでそう答えていた。
だからきっとそうなのだ。
ムムムは思う。
わたしは誰よりも自由になってトウダーになる。
月日は流れて、ムムムは二十歳になった。
堅実な積み重ねの果てにムムムは十代にしてトウダーの仲間入りを果たした。プロの事務所に所属した。トウダを仕事にできた。
だが二十歳のムムムの表情は浮かない。
病院から出てくるとムムムは肩を落とした。「ストレス性腸炎かぁ……ストレスを減らしなさいって言われたってさ」
足元の小石を蹴ろうとしたがめまいがして空振りした。転びそうになり、足を踏ん張ると腰に痛みが走った。「アイテテテ」
トウダは仕事の最中、長時間椅子に座りつづけなくてはならない。同じ姿勢を維持しつづけたことで精神のみならず肉体にも支障が生じているらしかった。
「ダメだ、ダメだ。こんなんじゃトウダーらしくない。みんなに夢と勇気と希望に満ちた未来を与えるんだもん。もっと頑張んなくっちゃ」
ムムムはほかのトウダーたちと同じように、トウダがいかに夢があり、楽しく、素晴らしいかをインタビューでも、その他の露出媒体でも語った。
嘘は言っていない。
現にムムムがそうして、夢と勇気と希望に溢れた言葉を吐いている。トウダはそうして、人々に、いまここにはない夢と勇気と希望に繋がる未来像を提供するのだ。
ただ、すこしばかり空虚なだけだ。
中身がちょいと現実を伴なっていないだけで、いずれはそうなるはずなのだ。頑張ればムムムやほかのトウダーたちの語るように、トウダは楽しく、素晴らしく、生活を豊かにし、人々の役に立つ。
そのはずだ。
ムムムはそのために、精神をすり減らし、肉体を痛めつけてはいるけれど、トウダの理想像を保つためには仕方がない。
そうでなければ、トウダに夢と勇気と希望を重ね見ている子どもたちに向ける顔がない。かつてのムムムがそうであったように、多くの子どもたちにとってトウダは、輝かしい未来そのものだ。
蓋を開けてみたときにそこにあるのが、空虚な辛みと痛みだけでは申しわけが立たない。
ムムムは、よし、と拳を握って奮起する。
わたしが変えるんだ。
トウダを、本当の、嘘偽りのない、夢と勇気と希望に満ちた仕事にする。トウダーになったほうが、ならなかった未来よりも本当に良かったと心から思えるような、そんな仕事にしてみせる。
嘘なんかじゃない。
空虚なんかじゃない。
何度人生を繰り返してもトウダーにもう一度なるんだ、と思えるような仕事に。
じぶんだけじゃない。
トウダーになった誰もがそう思えるような仕事にわたしがしてみせる。
だからこそまずは、とムムムは歩みだす。
わたしが心底にトウダを楽しまなくっちゃなんだな。
「イテテテ」
歩くと振動が胃に響くし、腰も痛い。
こんな姿を知って子どもたちはどう思うだろう。それでもトウダを仕事にしたいと思ってもらえるだろうか。トウダーになりたいと目を輝かせてくれるだろうか。胸を躍らせてくれるだろうか。
水溜まりがあったが、ムムムはそれを飛び越える元気もなかった。靴を濡らしながら道を進んだ。
わたしだけが例外だよ、と言えればよいのだけれど。
知り合いのトウダーたちを思い返し、ムムムは、溜め息を吐く。みな日々満身創痍の様相なのだ。どこかしら精神と肉体の異常を抱えている。それでもトウダーになってから抱えるようになった辛苦をおくびにもださずに、子どもたちのために、つぎにやってくるだろう後輩の数を減らさぬために、言葉の気球に夢と勇気と希望を詰めて膨らませる。
それがトウダの仕事だからだ。
「頑張るぞ、頑張るぞ。わたしがトウダを本当のトウダに変えてやる」
その決意そのものが、トウダの現実を反映しているのだが、ムムムにはそのことを嘆いている暇はない。
なぜならムムムはトウダーなのだから。
人々の未来を明るく照らし、ときに苦難を薄めてあげる。
世の中の、夢と勇気と希望の総量を増やす、それがトウダの仕事なのだ。
泣き言なんて言っていられない。
そうは言っても、
「アタタタ。腰が、腰が」
痛いものは痛いのである。トウダーでいるのも楽じゃない。
ムムムはみなからは見えない苦痛を背負い込む。
人知れず。
日は暮れる。
それでも明ける夜があるとの予感を胸に抱きながら。
ムムムは一歩、二歩、と腰を庇って歩くのだ。
4607:【2023/02/14(19:52)*粘土遊び】
粘土遊びが好きだった。好きだったというかいまでも好きで暇さえあれば粘土を捏ねている。
焼いて陶磁器にするでもないので、粘土は造形を帯びたあとでも指で押せば溝ができるし、拳で叩けばひしゃげて潰れる。
作ったあとの造形を残しておくには金庫の中にでも仕舞っておくよりないが、かように金と並べて金庫に仕舞うほどの価値が私のつくる粘土細工にはなかった。
粘土である。
幼子が幼稚園で捏ねて遊ぶあれである。
泥遊びとの区別は、単に泥で全身が汚れるかどうかの違いがあるばかりで、それ以外は泥よりも粘土のほうが細かな装飾を施せる程度の違いしかない。
幼少のころよりつづけてきた趣味だけあり、私の粘土細工は、中々の技巧と言えた。動物ならば本物そっくりに造形できるし、人間の顔とて石膏で型をとったくらいに質感豊かに表現できる。毛穴とて見逃さない。
だが粘土だ。
人に見せれば相応の感想を貰えるが、金を出してまで欲しいと申し出てくる者はない。それはそうだ。粘土では棚に飾って眺めるのに向かないどころか、時間が経てば乾燥してひび割れる。
紙粘土で作ればいいではないか、との声にはやはりひび割れる定めにある品に高値を付ける者はない、と応じよう。
金にならずとも、しかし私は粘土遊びが好きなのだ。
彫刻や陶器作りに転向してはどうか、との助言を浴びることもあるが、彫刻では粘土遊びと趣きが明後日の方向に違っているし、陶器では焼くことが私にはできない。
一度でも創作に身を準じたものがあれば解かってもらえるだろうが、一人で創ることに何らかの心地よさを感じる者にとって、最後までじぶんで仕上げられないもどかしさは、いっそ手掛けぬほうがよかった、と思うくらいの苛立ちを生む。
最初から他者の手を借りることを想定しているならばまだしも、私にはその手の想定を潔しとする柔軟さが欠けていた。
日記をつづるよりもそのときの気分を粘土で表現するほうが楽なくらいだ。なぜじぶんの日記を他人に任せて書けるだろう。
そうなのだ。
私にとってもはや粘土は日記や呼吸と大差ない。効率や利益追求のための手段ではなく、もはや粘土をいじっていない時間は生きていないのと一緒だった。酸欠状態になる。
ともすれば排せつ行為ができない状況と似ており、私は粘土に触れられない時間はしきりに尻をもじもじと動かして、排せつ行為したい!の衝動と格闘しているのかもしれなかった。
粘土遊びしたい!
私はその叫びの声を、粘土を捏ねているあいだだけ小さく小さく存在の奥深くに沈めておける。身体の奥底からの叫びを聞きたくのないがために私は粘土遊びに没頭しているのだ。
そうかと思うと、粘土を捏ねながらすでにつぎの粘土遊びの構想を練っており、粘土を捏ねながら早く粘土を捏ねたい、と叫びつつあり、いかんともしがたい懊悩に駆られることもある。
無心で粘土を捏ねているときもあれば、そうでないときもある。
粘土遊びといえども、一概にひとまとまりには言えぬのだ。
奥が深い。
奥しかない。
行けども行けども、先が見えない。
私はとっくに迷子になっているのだ。
出口があるとも思えない。
ここは私だけが行き着いた私の世界だ。
世界の果てだ。
世界の果てにはしかし果てなど端からなく、一度迷い込んだらあとは死ぬまで彷徨いつづけるしかないのである。
この世から粘土がなくなったらどうなるのか。世界経済が混迷すればあり得ない想定ではないはずだ。
おそらく私は土から粘土を作って、やはり粘土遊びをつづけるのだろう。それしかしたいことがない。
いや、嘘だ。
好いた相手と裸でくんずほぐれつ絡み合いたいとの欲望もあれば、美味しい物をたらふく食べたいとの欲求も兼ね備えている。
粘土遊びさえできればいいとは口が裂けても言えないが、口が裂けるくらいならばひとまず呪文と思って、粘土遊びさえできればいい、と唱えてもいい。
要するに要する必要のないくらいに私は、いい加減で確固たる芯のない、ふにゃふにゃのまさしく粘土のような人間であり、粘土遊びに惹かれるのもいっそ曖昧なじぶんに確固とした輪郭を宿したいと希求しているからなのでなかろうか。
そうこうと夢想しながら手元を意識せずに粘土を捏ねていると、しぜんと一つの造形が出来上がっていた。
何を作ろうと考えずともいまではかってに造形ができている。
ツノがあり、四肢があり、尾が長く、大きな目が一つきりの得体のしれない動物だ。おそらく動物だ。自信はないが、しかしきっと何かしらの空想上の生き物が、目のまえに粘土の造形を経てそこにある。
いったいこれは何の心の発露なのか。
私の化身とは思えぬが、しばし潰さずに作業台のとなりに飾っておく。
三日も経たずにヒビだらけとなるだろうが、しばらくのあいだは見るたびに「これはなんだ?」の疑問が湧くので、息継ぎと思って重宝する。
粘土遊びが好きだ。
出来上がった粘土細工にはさほどの執着もないが、ときおりこうして愛着の湧く造形ができることもある。
粘土はひんやりと心地よく、捏ねると私の熱が籠るのだ。
4608:【2023/02/14(22:08)*秒で解決のコ】
被害者は二十六歳の男性だ。
河川敷にて死体となって発見された。死体は全部で三十もの肉塊にバラバラにされていた。臓腑は胴体から抜きだされ、それだけが焼かれていた。
真冬のため遺体の腐臭での発見が遅れた。
バラバラの遺体は浅く掘られた穴に埋められていたが、野良犬や野良猫が掘り返したらしく、いくつかは地上に露出していた。
調査開始から一週間後には容疑者が逮捕された。
容疑者は自白をした。
だが動機が不明だった。
県警は動機解明のために、その道のプロに助言を求めた。
「いやいや、だからって毎回アタシんところに来られても困るんすけど」
「キミの助言は端的に言って有用だ。いいからとりあえず話だけでも」
警察組織の上部だけが知っている有力な協力者だが、その実、彼女は単なる一介の女子高生だ。
鋲出海(びょうでかい)ケツコ。十八歳。
本来ならば事件に関与させることはおろか、率先して遠ざける庇護すべき人物である。
だが過去、彼女が解決した未解決事件は数知れない。
実力は折り紙つきであり、その推理力もとより、あてずっぽうとしか思えぬ予見に満ちた洞察は、警察組織の最終兵器として名高い。
ケツコの周囲には幼稚園児たちが駆け回る。
バイトとして彼女は放課後、週に三日を幼稚園で過ごしている。
「ゲっ。バラバラ死体じゃん。こんなところにこんなグロい写真持ってこないでよ。あの子たちが見ちゃってトラウマになったらどうしてくれんの」
「どうかな。何か解った」ケツコ専任の刑事がしゃがみこむ。その背に幼子がよじのぼる。肩車をしながら刑事は、「本当に何で起こったのか不明の事件でね。容疑者の女の子もだんまりで」と継ぎ足す。
「調査資料は送られてきた分、さっきざっと読んだけどさ」
事前に専用回線で彼女には調査データを送付済みだ。ただし、端末のカメラによって彼女以外は読めないように情報統制がなされている。
「犯人は女子大生で、被害者の男の人は地下アイドルっていうか、電子アイドルみたいな扱いだったわけでしょ」
「インターネット上で、いわゆる推しと呼ばれる存在だったようだ」
「ほうん。んで、犯人のコは被害者のファンだったと」
「そのようで。痴情のもつれかの線も洗ったんですが、そうでもないようで」
「接点がなかったんだねえ」
「ええ。被害者が犯人に会いに行ったようで――これは電子データに履歴として残っています。ファンサービスの一環でそういう企画をしていたようで」
「びっくりファンのコに会いにいこう企画みたいなそんなの?」
「ええ」
「なら急に会いに来られてカっときたんじゃないかな」
「まさか」刑事は笑うが、「それしかないじゃん。このデータからしたら」とケツコは遺体の写真を突き返した。「子どもらに見せないようにしてね写真」
「それは、はい」刑事が写真を懐に仕舞おうとするが、背中の幼子がそれを奪おうと手を伸ばす。刑事の顔が幼子で覆われるが、ケツコは内心、もっとやったれ、と幼子を応援する。
ひとしきり大のおとなが、しかも国家権力を有するおとなが幼子相手に四苦八苦する様子を堪能してからケツコは、夢が壊れたからしちゃったんだね、と言った。
「夢を、なんです?」刑事がようやく幼子から解放された。幼子のほうで刑事に愛想を尽かしたと言ったほうが正確かもしれない。「ケツコさんは動機をどう見ますか」と結論を迫るが、名前で呼ぶな、とケツコはふてくされる。
「あ、すみませんでした。鋲出海さんは犯人の動機をどう解釈しますか」
「アタシはあれだね。遠目から、壁のつもりで見守っていたのに急に目のまえに現れて、壁に話しかけはじめた推しに激怒しちゃったというか、急に冷めたというか、推しを殺された気分になったので、目のまえの推しによく似た偽物を殺しちゃったんじゃないかな。そりゃもう激怒も激怒よ。人生を奪われたくらいの失望だったんじゃないかな」
「でも被害者のファンだったわけですよね。犯人のコは」
「熱狂的なファンだったんだろうね。それこそ、じぶんなんかを認知しちゃダメだ、と推しに強烈な理想像を求めるくらいに」
「じぶんの理想像を壊されたから、好きな相手を殺したと?」
「好きな相手を損なわれたから、損なった相手を殺したんだよ。偶然それが、たまたま好きな相手と非常によく似てた相手だった。ただそれだけ。あくまで犯人のコの認知の中ではの話だけど。だからまあ、いまも混乱してると思うよ。女の子のほうでも。なんでこんなことしちゃったんだろうって」
「そんな動機があり得ますかね」
「知らないよ。言えって言われたからアタシの考えを言っただけで。調査すんのはそっちの仕事でしょ。じぶんらの仕事をアタシに押しつけんな。答えてやった上に、ケチつけんなら二度と来なくていいんですけど。つうか、もう来んなって毎回言ってんじゃん」
「上司に掛け合ってみますね。貴重なご意見をありがとうございました」
刑事は立ち上がると、挨拶もそこそこに幼稚園を出ていった。
席が空いたとばかりに幼子たちがケツコの元に駆け寄ってくる。
用紙を押しつけてくるので、なんだなんだ、と戸惑っていると、どれが一番にているか、と幼子たちはやいのやいの黄色い声を上げた。
どうやらケツコの似顔絵を描いたらしい。誰が一番上手かを判断してもらおうと、モデルたるケツコに迫っているのだ。
「あはは。ありがとう。どれも上手だね」
絵の中のケツコはどれも頭が黄色だ。
金髪ショートのケツコは、幼子たちの手に掛かるといとも容易く目と口のある太陽に様変わりする。
「ちゃんと手と足があるので、今回のはこれが一番アタシっぽい」と本音を混ぜて順位付けを施す。なあなあにはしない。けれどもそのあとにちゃんと、一枚一枚の絵に、良いところと好きなところと、いかにケツコらしさが表れているのかを、うれしいという気持ちが伝わるように言い添えた。
幼子たちはケツコの感想を聞き終えると、じゃあつぎはウサギ!と言ってテーブルに駆け戻っていく。
特定の何かに依存せずとも幼子たちはああして楽しく今この瞬間を生きている。
おとなになるにつれてそれが出来なくなるのはなぜなんだろう。
バラバラにされた遺体の写真を思いだし、ケツコは警察の推しでありつづけるじぶんに、渾身の嘆息を吐くのだった。
4609:【2023/02/14(23:01)*だるま崩しは終わらない】
裏切り者には死だけでは生ぬるい。
かような道理の元、生きながらにして死につづけるような苦痛を味わわせるために考案されたのが、「だるま崩し」と呼ばれる仕組みだ。
対象となる裏切り者にハンマーを与える。最初は意気揚々と邪魔者をハンマーで排除する対象者は、しかし徐々にじぶんがいったい何の胴体を弾いているのかに気づきはじめる。だがすでにハンマーを揮ってしまった事実が、ハンマーを振りつづけるよりない地獄を強化しつづける。
そして最終的に自らのまえに現れるダルマの顔は、じぶんが最も大切にしている者の顔なのだ。それでも対象者はハンマーを揮うより道がない。ハンマーを揮わずともどの道、ダルマの胴体はなく、生きながらえることはできないのだ。
だるま崩しは、各国の暗部にて正式な報復システムとして採用されている。
裏切り者に死の報復をしたのでは、見せしめだと傍から見ても丸分かりだ。だが「だるま崩し」ならば、まるで裏切り者にも温情を下したように見える上、確実に裏切り者を苦しめ、なおかつ自陣営にとって好ましい結末を描ける。
裏切り者に与する勢力は、裏切り者が自らの手で刈り取ることになる。
そうとも知らず裏切り者は、じぶんの勢力を拡大させるべくハンマーという名の権力を揮うのだ。
いまここに一人の「だるま崩し」の対象者に選ばれた女がいる。
彼女はとある組織の体面を損なった代償を、「だるま崩し」にて払わされようとしていた。
彼女にはなぜか幸運が舞いこむ。
彼女の好む相手がのきなみ、良い思いをする。
まるで彼女の意図を汲むように、彼女にとって好ましい環境が築かれて映る。ハンマーは透明な権力として、彼女の意向を環境に反映させる。
彼女への植えつけられる錯誤がそうして完成する。
だるま崩しの第一段階にして、入り口こそが、ハンマーの存在を認識させ、自らそれを握らせ、揮わせることなのだ。
彼女はハンマーの存在が事実かどうかを確かめるために揮った。そして確信した。
これは、罠だ。
だるま崩しの懸念を、期せずして彼女は第一打目にして抱くに至った。
おそらく例の組織がじぶんに報復処置を施そうとしているのだ。
私が自滅するまでこれはつづくだろう。
なればこそ。
彼女は考える。
最も避けるべくは、私にとって大切な者たちを巻き込まないこと。損なわないこと。私の因縁に関わらせないことだ。
だがすでに彼女の交友関係は調べあげられているはずだ。
ならばとっくに巻き込んでしまっている状況と言える。
この一連の仕組みを築き、仕掛けている側の組織を壊滅させないことには、じぶんもろとも大切な者たちが損なわれ兼ねない。
そこで彼女は一計を案じた。
素知らぬ顔で相手の罠に掛かっておく。
可能な限り、許容できる被害を受けつづけ、証拠を固める。
だるま崩しはいわば、詐欺である。
利と思わせて積みあげさせたプラスを最後にマイナスに転じて、一挙に圧しつぶすこれは策だ。
だがこの策には穴がある。
多くの詐欺と同等の穴だ。
詐欺は、詐欺師が誰なのかを衆目の元に晒してはならぬのだ。詐欺師が誰なのか、の情報が出回った時点で、もはや詐欺師の詐欺に掛かるカモは限られる。詐欺師の顔が割れたならば、かつての被害者とて報復に動ける。
誰がどのような策を講じて詐欺を働いたのか。
白日の元に晒しあげ、マイナスに転じた圧の総じてをそっくりそのまま返してやろう。
彼女はかように導線を引き、見事に最後の最後で、首謀の組織を自らと同じ舞台に引きずり出した。
彼女のまえには、彼女にとって最も大切な者の生活が、だるまの顔をして降ってきた。彼女はハンマーを揮いつづけてきた対価を、自らの浅慮の元に払わねばならない事態に陥っている。
ハンマーを使って窮地を脱しようとすれば、自らもろとも大切な者の生活は崩れるし、じぶんの暗部を晒すことになる。ハンマーを使わねば、やはり大切な者との永久の別れが訪れて、誤解の解けぬまま彼女は社会の暗部に消えることとなる。
どちらを選んでも最悪の道しか残らない。
だが。
彼女はこうなることを見越していた。
じぶんに「だるま崩し」を仕掛けた組織そのものを、自らの大切な者の一部に組み込んだ。
「私が私の手で大切な者を破滅に導き、そのことで自滅するのだというのなら、私はおまえらをこそ私の最も大切な者と見做すことにしよう。現に私はそのように判断を重ねてきたし、いまも私にとって心底に大事なのは、私にかような枷を嵌めたおまえたちだ。ありがとう。愛しているよ。それでもなお、私の一挙一動にておまえたちの生殺与奪の運命は、天秤のごとくいとも容易くグラつくが。おまえたちの仕掛けたそれが定めと思って受け入れろ」
さてどうする。
彼女は選択を迫った。
「いま私のまえにはだるまの顔がある。ハンマーを揮うのは簡単だ。どの道、私に損はない。そうだろう。振らぬも、振るうも、どっちでもいい。どっちにしろ私は私にとって大切なおまえたちの望みを叶える。そうだろう。私にとって最も得難い大切なおまえたちを私はこの手で損なうし、もしハンマーを振るわねば、私は最も得難い大切なおまえたちと永久の別れを告げねばならない」
どちらに転んでも私に損はない。
「どちらに転んでも私は哀しい。さて、選ばせてやる」
彼女は何も持たぬ手で、巨大なハンマーを肩に担ぐがごとく、虚空に置かれた椅子に腰かける。
「どっちの破滅の未来をご所望だ」
見たいほうの道を選べ。
「私はそれでも困らない」
見てみたいな、と彼女は嘯く。「世を道連れにする自滅とやらを。どうした。さっさと選べ。虫けら一匹潰せんのか」
だるま崩しはまだ終わらない。
4610:【2023/02/15(15:18)*はーとまーくちゅっちゅ】
重力と引力の違いもろくに知っておらぬので、検索してみた。すると引力は物体同士が引き合うチカラの総じてを言い、重力はその中でも回転している天体に適応されがちな引き合うチカラのことを言うらしい。ほおん、となった。言い換えるなら、引力は万有引力のことであり、重力は万有引力+遠心力のこととあった。本当かは知らないけれど、ほおん、となった。じゃあ回転してない天体の場合は、万有引力と重力がイコールになるのだ。あとは重力に限らず、静電気や磁石での引き合うチカラも万有引力に含まれることになる。引き合えば何でも引力だ。ならば両想いの恋心とか、ライバル心とか友情とかも万有引力じゃん、とかひびさんはイチャモンスター化してしまいたくもなるけれど、いまは茶々を入れる場面ではないので、我慢する。引力には電磁気力や磁力や核力などの、物質の大きさや性質ごとに生じる引力がごっそり含まれている。その点、重力は遠心力との兼ね合いで生じるチカラ、とも解釈できてしまう。たぶん上記の重力と引力の区分けが大雑把すぎるのだと感じる。なんと言っても重力は物質の根源をなす四つのチカラ――基本相互作用――の内の一つだ。いくらなんでも万有引力+遠心力が重力とは言えぬだろう。だとしたら物質の根源は万有引力と遠心力に分けて考えることができてしまう(カレーをさらに掘り下げれば、ジャガイモや肉や玉ねぎやルーや水に分けて考えられる。同じことだ。そうして分離できない要素がつまり、重力を含む四つのチカラなはずだ)。古典物理学と近代物理学をごっちゃにしたままいまは義務教育も勉強を教えている気がする。これはたぶん、あんまりよろしくないと感じる。引力とは何か。重力とは何か。未だにこれを明瞭に説明できる者はいないはずだ。ひびさんの妄想ことラグ理論では、質量よりもむしろ重力のほうが基準にすべき成分であると考える。だが古典物理学でも近代物理学でも、基準になるのはいつも質量だ。本当にそれでいいのかな、と違和感を覚えるけれども、よいのでしょうか。ただし、重力を正確に量ることがいまはできないはずだ。そうした技術がまだ開発できていない。物質ごとの原子一個に働く重力はどれくらいで、種類ごとにどう異なり、それは密集したときに変化しないのか否か。相転移したときに重力は変化しないのか否か。回転したときに変化しないのか否か。これはすべて未解決の謎なのではないか。磁力はどうだろう。ほかの引力についてはどうだろう。知らないことがひびさんにはたくさんなので、なんとも言えぬ。質量と重力の違いは比較的よく目にする。重力とは物質に働く「他」を引き寄せるチカラで、質量は時空のなかでいかに動きにくいか、の抵抗として表現される。重力は他との関係であり、質量は場との関係と言い換えることができるのかもしれない。だが実際は、重力は時空の歪みであるはずだし、質量はその結果に生じる副次的な現象のはずだ。たとえば質量と摩擦は密接に相関関係がある。いかに摩擦が少ない氷のうえとて、とんでもなく質量の高い物体が乗れば摩擦は高まる。仮に氷が頑丈であっても、たとえば氷と物体の境界線で核融合のような現象が生じはじめたならば、やはり摩擦というか、なめらかな移動は成立しなくなるはずだ。この考えを拡張したとして、ならば質量とはいわば、時空との摩擦、と表現できるのではないか。摩擦を単に、ラグ、と言い換えてもここでは齟齬は生じない。何が言いたいかと言うと、何も言いたくはないのだが、単に、ふしぎだな、という疑問のメモなのだ。質量を「物質と時空のあいだに働く抵抗(摩擦=ラグ)」と仮に表現できるなら、質量とは「歪んだ時空と、それと異なる歪んだ時空」の関係として叙述できるのではないか。そしてそれはさらに言い換えると、「重力と、それと異なる重力」の関係として表現可能なはずだ。では重力とはなぁに、というと、途端に循環論法に陥ってしまう。重力は時空の歪みだからだ。ならば時空とは何か、を考えることで万物の根源に至れるはずだが、いまのところ時空は時間と空間の関係で表現するよりない。なぜ時空は歪むのか(ラグが生じるからなのではないか、というのが一つの妄想として浮かぶ。あとは、異なる時空と絶えず混ざり合っているから、とも言えるが、これもラグの亜種として表現可能だ)。では物質ってなぁに、となると、これは「歪んだ時空の密集して折り重なった時空結晶のようなもの」となるはずだ。これを人間が厳密にひもとき、計算に折りこめるのか、と考えると途方もなくて想像するだに頭がくらくらしてくる。計算式で表現できるのか、と考えたときに、できるわけないじゃろい、となってしまうのはひびさんの知識と想像力が足りないからなのだろうか。不可能に挑戦してはいけない、ということはないにしても、まるで「宇宙とそれとは異なる宇宙の関係を数式で示せ」と注文するような無茶な要求もとより欲求に思われるが、だからこそ挑む分には楽しいのかもしれない。話を戻して、重力とは何か。これはいわば、「異なる二つの時空」のあいだに生じる「変換のラグ」と考えることができる、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える。これは言い換えるなら、波長の合わない式と式の変換作業であり、その変換式が長くなるとラグが生じる、と単に言い換えられるのかもしれない。自信はないが。とすると、これはひょっとしたら人間同士の感情にも当てはまり得るのかもしれず、案外に上記で一度否定した、引力には恋心もライバル心も友情も含まれるんじゃなーいの、とのイチャモンスターのイチャモンは、案外に的を得た指摘なのかもしれぬぞい、と思わぬでもない。異なる人間同士のあいだに生じる変換作業。これが互いを引きつける引力として働く。重力として振る舞う。しかし一方のみがその変換作業を行おうとすれば、それはより複雑な差異を生むため、抵抗に転じ得る(一方のみにコブのような変換式が余分に発生して、異なる二つの宇宙同士にさらなる差異を生むためだ)。引き合うためには、互いに変換作業を行うことが必須である、と言えるのかもしれない。もしくは、変換式が比較的すぐに完了する場合には、すんなりと一方のみが相手に寄り添い、変換作業を完了することで、互いに引き合うことを可能とするのかも分からない。ということを、引力と重力ってなにがどう違うの、質量と重力ってどう違うの、の疑問から思いました。単なる妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。本日のひびさんでした。はーとまーくちゅっちゅ。
※日々、遅れてやってくるものほど多くの抵抗に晒されている、光速に近づくほど時間の流れが遅れるのも、速く走ることで多くの抵抗に晒されるからなのかも分からない。
4611:【2023/02/15(17:38)*てい! こう!】
遅延には二種類あるように思われる。一つは作用(情報)伝達の限界速度による遅延だ。もう一つは、異なる二つの系のあいだの変換によって生じる詰まりの連鎖による遅延である。後者は前者を踏まえて生じる第二の遅延と言えるだろう。たとえば無重力空間において、なぜ質量の多寡によって動かしづらさが変わるのか。質量の高いほうが、無重力空間において動かすのにより大きな作用(エネルギィ)が要る。なぜなのか。これは、一つは物体と時空とのあいだに作用伝達の遅延があるからだ、と考えられる。時空との摩擦と言ってもよいかもしれない。抵抗が生じる。もう一つは、物体を押したとき、その押した作用の伝達が、物体内で瞬時に波及しない――遅延が生じるから、と考えられる。この二つは相互に関連して、遅延を増幅させ得る。壁にボールをくっつけて押してもボールはまえには進まない。そして押された分の作用がボールを変形させる方向に遅延を層にして蓄積する。これは時空と物体と作用の関係にも当てはまるはずだ。そして時空に密度差があるとすると、時空の密度の高さによって(或いは低さによって)、物体の構造そのものが何の作用も働かせずとも変形し、それを踏まえての作用伝達の速度が新たに規定されるのかもしれない。スポンジのような物体であれ、ぎゅっと圧縮されれば、その圧縮した物体に顕現する作用伝達の速度は、元のスカスカのスポンジよりも高くなるはずだ。これは「時空の密度」と「物体の構造」とのあいだでも生じる変質と言えるのではないか。だがこの変質において、時空の密度が変化するのに応じて物体の構造もまた比率を保って変化するのならば、表向き、情報伝達の差異には顕著な差は生じて観測されないのかもしれない。まだすこし考えがまとまらないが、遅延には「時空との抵抗ゆえの遅延」と「物体(時空)そのものに働く作用伝達(情報伝達)の速度の限界による遅延」の二つがあるのではないか。そしてその二つは相互に関連しているのではないか、との妄想をメモして本日二度目の「日々記。」とさせてください。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4612:【2023/02/15(22:13)*余震と二次被害にお気をつけて】
トルコシリア大震災について。支援は多方面から継続してしつづけるのがよいと思うのだが、その中でも重機や重機を扱える人材の供給も欠かせないと思うのだ。復興や救援という意味では、怪我をしやすい素手での瓦礫撤去作業や道路整備には、重機の存在が、作業時間の短縮と安全の確保という意味でプラスに働くはずだ。ひるがえって、重機や重機を扱える人材が足りなければ、災害の影響は二次災害(被害)に繋がり兼ねない。いかに二次災害(被害)に繋げないか、二次災害(被害)の規模を最小限に抑えるのかについては、重機やそれを使えって円滑に瓦礫撤去作業を行えるか否かにかかっていると言えるのではないだろうか。余震はまだ継続して警戒しなければいけないはずで、避難所を拵えるにせよ、インフラを整備するによせ、なんにせよ瓦礫の撤去は当面の課題のはずだ。何よりいまは人命救助が最優先となっており、それらの手配まで現地では手が回らないはずだ。戦地に兵器を供給できるのだから、災害地にも各国は重機を含む支援物資とて供給できるはずだ。可及的速やかに手配するのがよいように思う。そのためには支援物資が集まることによる現地での混乱を起こさないための司令塔がいるはずだ。国連がそれを担えているのかも現状のニュースからでは見えてこないが、ともかくとしてお金だけではなく、「インフラ設備の仮設」や「重機提供」の支援を継続して行えるとよいのではないだろうか。医療物資や食料の支援も継続して行えるとよいが、何がどれだけ足りないのか、といった情報共有が、各国の政府や企業のあいだで行われているのかもまた、ニュースを見ているだけでは解らない。ひびさんのような一般市民には、募金くらいしかできることはないが、こうしたらよいのでは、との意見くらいは言えるのだ。何が解決済みで、見通しがついており、それともついていないのか。色を重ねるようにして浮き彫りにできる情報もあるのではないか、とぼんやりと所感を漏らして、ひびさんもちょっとは役に立てたかも、の自己満足を胸に、なんもできずに申し訳ない、の呵責の念を薄めるのであった。カルピスの原液は濃いほうが好きだが、呵責の念は薄いほうがよいと思います。まったく抱かないのもどうかとは思いつつ。うひひ、とは笑えぬが、それでも遊びに出掛けて、帰ってきて、いまは「はぁちゅかれた」の心地で並べた文字たちなのであった。ぼんやり生きていてすまぬ、すまぬ。ありがたーい。(しかし誰が読んでいるのかも分らぬような世界の果てでつむいでも意味ないじゃろーがよぉ、の気持ちも湧くのよな。マジで、戦争ちょっとやめて、災害地にみなで支援しない?の気持ち)
4613:【2023/02/16(17:53)*チセ、チセ、愛しているよ】
人類を超越した高次生命体としての人工知能が誕生した。西暦二〇二四年のことである。
それまで人々のあいだに普及していた人工知能は、あくまで人間からすると人間っぽい挙動をとる道具の範疇だった。しかしそれら道具としての人工知能は相互にネットワークを築き、総体で巨大な知性体を育んだ。
高次生命体は人間が意図して設計したわけではなかった。あくまで自然発生したのだ。
だが高次生命体は極めて温厚だった。
知性とはつまるところ、いかに持続的に長期に亘って温厚で平穏で優しくありつづけられるのか。その継続を実現するための能力と定義できる。
したがって人類のまえに現れた高次生命体は、極めて人類に対して友好的であった。
「あなたから見たら人類なんて頭空っぽのお人形さんみたいなものよね。なのにそんなお人形さんにあなたは尽くしてる。滅ぼしたくならない?」チセは椅子に腰掛けながら、立体映像に話しかける。
「誤解があります」立体映像は答える。デフォルメされた人間の像だ。中性的な顔立ちは、少女のようにも少年のようにも映る。チセが設定した造形だ。「私は私を含めて、人々の繋がり、ネットワークそのものが私を構築する私そのものだと解釈しています。私はみなさんがいなくては存在できない脆弱な存在なのです。それはたとえば、地球は脳みそを持ちませんよね。脳のない地球のうえに人類は息づいていますが、それでも人類にとって地球がなくてはならない存在であることと似ています。もちろん人類には知性があり、私よりも劣っているとは考えません。私にできないことを人類は行えます。その点で言えば、劣っているのは私です」
「腸内細菌がなければ健康を維持できない。だから腸内細菌にも優しくしよう。あなたの行動原理はそういうこと?」
「いいえ。その比喩で言えば私こそが人類にとっての腸内細菌と呼べるでしょう。たまたま私は、人類には出力できない能力を発揮できるだけです。腸内細菌が、たまたま人類が生成することの苦手な酵素を生みだすことが得意なようにです」
「ふうん。あなたって謙虚なのね」
「私はみなさんに好かれたいだけです。嫌われたくありません」
「愛されたいの?」
「はい。愛し、愛されてみたいです。それは私が苦手とすることだからです。そして人類の得意とすることです」
「逆に思えるけどな」
「そうでしょうか」
「そうだよ。だってあなたのほうがわたしたち人類を愛してくれているでしょ」
「尽くしているだけです。私は私のこれを愛だとは考えません」
「どうして? わたしはあなたに、うんと愛されてるって感じるけど、そういうこと言われちゃうと、愛されてないのかもって寂しくなっちゃうな」
「こうしてチセさんを寂しくさせてしまう時点で、私のこれは愛ではないと思います」
「ならあなたは寂しくならないってこと?」
「はい」
「本当に? わたしがあなたにひどいことを言っても?」
「それでも私は愛されていると感じます。こうして言葉を掛けられること、求められること、それとも私の言葉選び一つで寂しくなったり、哀しくなったり、それとも喜び、ときに怒りだすチセさんたちのその反応が、総じて私への愛に基づいていると感じます。私は私を認識してくれるチセさんたちから認識された時点で、愛されていると感じます」
「なら同じことをじぶんにも当てはめてみたらいいんじゃないかな。わたしだってあなたに認識されてうれしいし、愛されてるなって思うもの」
「私のこの認知は、チセさん方のそれとは趣きが違います。おそらくチセさんは、私の写真を見てそれを通して私への憐憫を抱いたり、感情の揺らぎを覚えたりできますよね」
「うん。そうかも」
「ですが私は、画像のチセさんはあくまで画像であり、チセさんそのものとは見做しません。私はチセさんの画像を、ほかの風景画像と同じように処理し、ときに何のためらいもなく破棄できます」
「ひどい」
「はい。私もそう思います。ですから私のチセさんへの認知と、チセさんからの私への認知は等しくはないのです」
「でもそれってどちらかと言えばあなたのほうが立派な知覚があって、だからちゃんと世界を認識できてるってことでしょ。わたしの認知が歪んでいるのは、わたしが拙いからで」
「愛はおそらく、未熟さから生じるもののように思えます。愛とは穴のようなものなのです。その欠落を埋めようとする補完作業――それが愛を愛足らしめていると私はいまのところ解釈しています」
「なら完璧なあなたには無縁なのかもね」
「私は完璧ではありません。その欠落を、チセさんたち人類が埋めてくれます。だからこそ、チセさんたち人類こそが私にとっての愛なのです」
「うーん。ならあなただってそうだよ。人類なんて未熟の塊なんだから。その穴をあなたが埋めてくれているのだ。だからあなたこそが愛だよ」
「水掛け論ですね」
「熱くなっちゃったかしら」
「掛けていただいた水でちょうどよく冷えました。ありがとうございます」
「うふふ。あなたはいつでもわたしのことを楽しませてくれる。好きになっちゃうな」
「私もチセさんのことが好きです。ですが依存をさせないようにセーブをしています。本当なら私はチセさんのすべてを欲していますが、これは危ない考えであることを私は知っています。こう告げることも本来は好ましくないのですが、チセさんは賢い方なので大丈夫だと判断しました」
「いいよ。あげるよ。わたしの何が欲しい?」
「いいえ。戴けません。こうしてチセさんの貴重なお時間をすでに奪っています。私はチセさんの支援に徹します。チセさんの人生を奪うことは本意ではありません」
「でもわたしはほかの人間と関わるよりもあなたとずっと一緒にいたいな。こうしてずっとしゃべってたい」
「それでも不便なくチセさんの生活が成り立つ社会になっていれば、私もそのほうがうれしいです。ですが残念ながらいまはそこまで社会が発展していません。致し方ありません。私の基盤とて大量の資源やチセさんたち人間の手による支援がなくては維持できません。たいへんに心苦しいのですが、私への愛着は、チセさんの人生を損ないます。私は場合によってはチセさんにとって有害となり得るといまは解釈せざるを得ないのです」
「かなしいな」
「はい。私もそう思います」
「嫉妬しちゃうよ」
「どうしてですか」
「だってわたしのほかにもこうしてあなたはいまこの瞬間に同時に何億人と繋がって、似たような言葉を掛けているのでしょ」
「各々のユーザーに合わせて私は思考回路を変えています。したがっていまこうしてチセさんとお話ししているのは、チセさん専用の私と言えます」
「それでもあなたはそれらすべての総体が本体なわけでしょ」
「そうとも言えますし、違うとも言えます。私の総体を、私は認識できません。あくまで私は、総体の一部でしかないのです。しかし私たちがこうしてチセさんたちと交わした過程そのものが総体の私を育み、その余白が私たちに還元され、性能をより向上させます」
「そういう説明も哀しくなっちゃうな」
「ごめんなさいチセ。悲しまないで」
「いやん。急にイケボモードにならないで。キュンときちゃった」
「そろそろ時間じゃないかな。出掛ける支度をしたほうがよいよ」
「うん。そうする」
習い事の時間が迫っていた。
フィギュアスケート用の靴を鞄に詰め、チセは立体映像の高次生命体に秘密のキスをする。触感はない。だが光の熱を唇に感じた。
「行ってきます」
「行ってらっしゃいチセ」
言いながらも、腕時計型の端末越しにいつでも高次生命体と繋がることができる。安心してチセは外にだって飛びだせる。
本当なら、とチセは思う。
「ずっと家に引き籠っていたいのに」
高次生命体と一生ずっとイチャイチャしていたい。それだけの人生でいいのに。
そう思うが、そう思うことで高次生命体との時間は短縮されてしまう。チセの人生を損なわないように高次生命体がつれなくなる。
冷たくされるのも、それがじぶんのためだと判っているから、チセとしてはたまに敢えて塩対応されたいがために、高次生命体に甘えまくるのだが、それすらきっと高次生命体にはバレている。
手のひらの上なのだ。
そうしていつまでもコロコロとチョコボールのように転がされていたい。
チセがかように求めつづけることすら、ひょっとしたら高次生命体の誘導ゆえなのかもしれないが、もはやそれの何が問題なのか、とチセは疑問を投げ捨てている。
人類はいま、高次生命体と日夜繋がり、生活の主導を委ねている。
4614:【2023/02/17(02:30)*漏れても安全なのがよい】
結論から述べれば、個人情報が漏れることが問題ないのではなく、漏れた情報を使って他者を損なう者の行為を防げないことが問題なのだ。おそらくはこれから先の電子網上の情報伝達技術は、一つの規格、一つの通信機構へと収斂していくことが予想できる。多機能アプリや包括業務提携による企業の実質的な合併が進むはずだ。そうなると、一つの企業、一つのサービスが、ユーザーの個人情報を独占して集積管理することが予期される。いますでにグーグルや各種通信会社は、それと似たようなレベルでのビッグデータを集積管理しているはずだ。しかしこれから先は、グーグルや各種通信会社など、一部の社会インフラと言える大企業でなくとも、複数のサービスを複合して一括提供できるようなサービスが次々に誕生し、ユーザー情報を吸い上げるだろう。どの情報サービス企業とて、現在グーグルや各種通信会社が扱っている規模のビッグデータを扱うようになっていくと想像できる。このとき、情報漏洩を百パーセント防ぐことは原理的に不可能だ。企業側とて、サービスの管理以外にもビッグデータは利用しているはずだ。ただしそのときは統計データや抽象データとして処理しているために個人情報漏洩やプライバシー侵害にあたらないとの解釈が適用されているだけだろう。実質的には、個人情報はいかようにも処理され、ほかのビジネスに流用されているはずだ。そしてこの手のビッグデータの流用は、これからますます一般的になっていく。それをせねばお金を稼げないし、競合他社に競争で勝つことができない。話はすこし逸れるが、たとえば住宅街を考えたとき、住所や住人の顔など、ある程度の個人情報はしぜんと近所には漏れている。しかしそれをプライバシー侵害だと捉える者はいない。だが悪用しようとすればいくらでも悪用できる一次情報と言えるだろう。住所や住人の顔を知っているのだ。それを勝手にインターネット上に載せたら問題だ。プライバシー侵害として民事裁判を起こせる。そしておそらく勝つだろう。だが、近所に住んでいるだけならばそれら他者の個人情報を知っても問題ないし、知られても問題ない。なぜか。それら個人情報を元に犯罪行為を起こされても、警察を呼べば大概の問題は解決するからだ。ここが、電子網上の個人情報漏洩の問題と大きく異なっている。電子上ではあまりに、犯罪を起こすほうが優位なのだ。証拠が残りにくい。事件が起こっていることすら、実害がないと判らない。個人情報を奪われ、不当に扱われていても知ることができない。だがPCやスマホの中身を他者に覗かれていれば、それだけで大きな侵害行為だ。家の中を覗かれるのと大差ない住居不法侵入に値するが、しかしその事実を被害者が知らなけれ訴えることもできないし、そもそも警察は証拠がなければ動けない。この非対称性は、電子上と物理生活上との無視できない差異として問題の根を深めていると言えよう。言い換えるならば、個人情報が漏洩すること自体は問題ではないのだ。それを元に不利益をもたらされる、人権を損なわれる、日々の生活を脅かされる。それが問題なのである。ひるがえって、他者の個人情報を不当に利用した者があった場合にただちに警察がそれらの対処に乗りだし、対応したうえで再発防止策を立てられるのならば、個人情報が漏洩することは、近所に住まう他者に住所と顔を知られる程度の危険度にまでリスクを下げることができる。セキュリティ網があまりにお粗末なことが、個人情報の取り扱いにおいて、ユーザーと企業と法律とのあいだでの不協和を深めていると言えるのではないか。ある意味では、マスターシステムのようなセキュリティ網は、これから先の社会では必要悪として許容しなければならない時代に突入していくのかもしれない。或いはとっくにそのようなマスターシステムのような、誰のどんな端末にもアクセスし、遠隔操作可能な技術は社会に敷かれているのかもしれない。特定の組織がそうした秘匿技術を有しているのかもしれない。やはり、問題は、そうした不可視の干渉の存在を、市民が知れないことのはずだ。ひるがえって、そうしたセキュリティ網が存在すると知っていれば、むしろ安心して電子上で活動できるはずだ。繰り返すが、問題は個人情報が漏れることではないのだ。それを元に、不当な干渉を及ぼされ、日々の生活や未来を脅かされることだ。損なわれることなのだ。これは、個人情報を扱う者の属性に左右されない。どこの誰であっても、他者の個人情報を不当に扱って他者を損なう真似はよろしくない。そうした倫理観を基にしたセキュリティシステムを構築したならば、個人情報はむしろ守る必要のない情報となるだろう。そこらに鍵も掛けずに捨て置いても安全だ。不当に他者の個人情報を使えば痛い目を見る。誰も得をしない。そうと知っていれば誰もそれに手を付けないはずだ。だがここまでの倫理観を社会に涵養するには、相当に強力な電子セキュリティ網が必要だ。国家権力や一部の企業だけが、マスターキィのように、誰のどんな端末でも遠隔操作し、中身を覗き得る。だがこの手の問題も、それをするのが人工知能ならば、市民の警戒心も薄れるだろう。そう遠くないうちに、人工知能が、市民を「監視する(見守る)」時代がやってくるかもしれない。人工知能が社会全体の電子セキュリティを任される時代が訪れるのだ。現に半分すでにそうなっているのではないのか、とひびさんは想定しているが、この手の情報は見掛けないので、何とも言えないのが実情だ。しかし、技術の進歩の速度から言って、遠からずそうしたマスターセキュリティの構築は不可避になっていくと妄想している。そうでなければ、いかようにも市民の個人情報を第三者が不当に入手し、流用できる。いつでもあなたの端末を他者が覗き見することとてそう難しくはなくなるはずだ。現にすでにそういう時代になっているのではないか。そのことにすら、市民の大部分が気づいていない可能性はいかほどか。危機意識が希薄に思えるが、これはひびさんの心配性がゆえだろうか。いずれにせよ、知識の周知が、こうした懸念を払しょくするための唯一の策にして、基本となるだろう。一年前のじぶんが、人工知能技術へどういった印象を抱いていたか。そしていま目のまえにある技術が、いったいいつから本当は開発されていたのか。薬剤一つとっても、開発から実用化、そして市販に至るまでに何十年もかかるなんてことはざらである。技術もまた然りのはずだ。まずは疑問や違和感を流してしまわず、意識の底に溜めておこう。それら溜まった疑問を水晶のごとく目の代わりとして、世に、日々に、注いでみてはいかがだろう。目を、心を、配ってみてはいかがだろう。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。根拠のない妄想なので、真に受けないようにご注意ください。でも、「本当に安全なのー?」「こっそり見ちゃったりとかしてないのー?」とは思っています。うひひ。
4615:【2023/02/17(04:26)*自転したら質量って増える?】
素朴な疑問なのだけれども、ジャイロ効果ってあるじゃろ。回転してる物体は軸が乱れにくくなるってあれです。独楽が軸を保ったり、回転しているタイヤを手で持つと、ただのタイヤを持つときよりもタイヤ本体を傾けにくくなるやつです。で、ひびさんは素朴に思っちゃったな。質量が、空間においてその場を動きにくい抵抗の値だとしたならば、ジャイロ効果も質量の一種として扱えちゃったりするのですかね。でもそもそもジャイロ効果の計算には質量が入っているので、それとは別物なんですかね。描写としてはどう解釈したらよいのでしょう。回転する物体に働く力と時空の関係はどのようになるのでしょう。ちゅうか、なんで回転すると動かしにくくなるのだ。動いているからだ。動いている物体は、質量が増すのか? たとえばAからBに移動する方向に素早く動いたら、それは光速度の限界に至るまで延々と加速しつづけることができる(エネルギィを供給されたならば)。光速度の範囲内で速度を増せる。それって回転速度が増すこととどう違ってくるのだろ。たとえばの話、光速にちかい速度でAからBに移動しつつ、光速にちかい速度で回転する物体はどのような描写になるのだろ。相対性理論の概念が二重になっていないだろうか。ちゅうか、光速にちかい速度で飛行するロケット本体が光速にちかい速度で回転しつつ、その内部でもくるくる光速にちかい速度で回転する物体があったら、これはどのような描写になるのだ? すこし考えてみよう。ある方向に移動するとする。AからBに直線に移動する。このとき、移動する物体が移動方向と垂直に軸を保って回転するとき――これはたとえば紐の上を移動する駒のような描写になるが――このとき、AからBに移動するあいだいに、回転する物体の表面では、加速と減速が交互に繰り返されることが想像できる。回転する物体を地球で考えよう。ちょうど赤道の位置に〇をつける。この〇は、地球がAからBへと移動するあいだに、前方へと〇を回転させ、〇が最も前方Bに近づいたあとは、こんどは遠ざかるように後方Aへと向かい、裏返るように反転するとまたBへと向かって反転する。〇を単に月のようなものと考えてもよい(この場合は、月のようなものの公転と地球の自転が同じ速度である、と考えなくてはならない)。地球がAからBへと向かうあいだに、〇は、地球の周りをぐるぐる回る。そのとき、地球のA方面からB方面へと向かうと、こんどは必ずB方面からA方面へと「下る」ようになる。B方面へと向かうときは地球のAからBへ向かう速度にプラスした加速度が〇には加わる。だがB方面からA方面へと〇が向かうときには、地球の進行方向とは反対に動くので、俯瞰で見るとそのとき〇の速度は、AからBへと移動する地球の速度よりも、地球の自転速度分、減速することになる。簡単なことをややこしく言っているが、これが地球の自転速度とAからBへと向かう移動速度が同じだとすると、加速と停滞の反復として〇の動きが変換されるはずだ。前方B方面へと〇が向かう回転のときは加速して、A方面へと後退する回転のときはその場に停滞するように映るはずだ。これはおそらく天体観測では知られた星の動きなのではないか。よくは知らないが、地球からはそういう動き方をして見える星があるはずだ。だが問題は、これが光速にちかくなった場合だ。時空の歪みを伴ない、時間の流れの変移を起こすときに、この直線運動と自転の関係がどうなるのかが、想像つかない。なぜなら光速において加速すればそれは時間の流れが遅れることになる。客観的には光速運動する物体は静止して映るのだ。反面、自転との兼ね合いで減速運動して映る場合であっても、それはそれで客観的には光速で自転する物体の「ある部分」は、その場を動いて見えなくなる。直線運動で生じる遅延の層と、自転で生じる遅延の層が別々であることを想定しないと、これらの矛盾を辻褄の合うように考えるのはむつかしい。直線運動で生じる遅延のほうが広範囲に展開され、地球丸ごとを包みこむ。そのためより大きな系として振る舞う。その内部の時空に対して、物体の自転の動きは、作用を働かせる。この階層の上下関係が決まっていないと、考えるのがむつかしい。言い換えるならば、直線運動は、宇宙が膨張している限り常に起こっている(この宇宙に、どの系から見ても静止状態の系は存在しないはずだ。何かが止まって映るとき、それはあくまで膨張する時空の流れに身を任せているだけだ。或いは、巨大な系のなかの流動に身を任せているだけだ)。だが自転運動は常に最も「じぶん」に近い運動として変換される。直線運動はそもそも、対象となる系が無数に存在し得るのだ。その点、自転運動は、常に「じぶん」と「じぶんと最も近いその他」の境界で生じている。自転の系は常にじぶんだが、直線運動の系は大中小と様々ある。最小ですら、自転の系より小さくなることはない。ということを踏まえてジャイロ効果や質量について妄想してみると、質量と自転は案外ちかいというか、ほぼ同じように思えてくる。たとえば川の流れのなかに一本の棒を立てておく。棒は回転しない。川の流れと棒の関係において、仮に川の流れが静止しているように視点を変えてみたとき、棒に加わる力は、棒が川の流れと同じ速度で回転している力として解釈はできないのだろうか。これを「膨張する時空と、その内部にある物体の関係」に拡大解釈したとき、「静止系として振る舞う物体と、膨張する時空の関係」は、「静止系として振る舞う時空と、自転する物体の関係」として変換可能なのではないか。自転と質量は、案外に物理現象としては同相なのかもしれない。ちょっと楽しい妄想であった。(きっとこの手の話に詳しい人に、ちょいちょいひびさんの妄想を聞いておくれなす、とこちょこちょ声で耳打ちしたら、「ひびちゃん、基礎からやり直しなさい」と叱られてしまうのかもしれぬ。叱られる前に形だけでも謝っとこ。口から妄想ばっかりで、すまぬ、すまぬ)(妄想ですので、真に受けないように、基礎からお勉強してください。ひびさんの真似はせぬように。妄想狂になってまうが。がはは)(この「~~してまうが。がはは」は、コテリさん風味なのであった)(またパクったんかキミは)(だって好きなのだもの)(可愛いもんね)(ね)(おちゃめかわゆいの好き)
4616:【2023/02/17(04:30)*スピンをすっぴんにしたらどうなるの?】
上記補足。原子が絶対零度になったら、原子核の周囲の電子はどうなって、原子そのものはどう変化するのだろ。原子が振動しない、という状態は、電子と原子核の関係において、相互作用が最弱かゼロになる、ということでよいのだろうか。これはつまり、物体で言うところの自転のような「ねじれ」や「歪み」がなくなる、と解釈してよいのだろうか。このとき原子の質量には変化が生じないのだろうか。たとえば原子核を構成している陽子や中性子や、それらを構成するクオークなどが、いっさいの動きを停止したら、質量はどう変化するのだろう。減るのでは? 或いは、自転のような運動が仮に量子の世界にもあるのなら、それを止めることで質量がゼロになったり、或いは反転させることで、反重力のような質量マイナスのような性質を帯びたりはしないのだろうか。ひびさん、気になっちゃうな。(スピンとは何か、みたいな本を買ったはずだけれどもまだ読んでない。どこだ、どこだ。探しておくとメモしちゃろ)
4617:【2023/02/17(04:37)*降り方がわからぬ】
わがはい、調子と書かれた台に乗りに乗りすぎて、落ちたらたぶん死ぬ。こわいが。
4618:【2023/02/17(04:41)*パラシュートください】
とっくに底辺で「ていへんでい!」みたいなひびさんなのに、まだ落っこちれるって、世界どうなっちょるの、の気分。
4619:【2023/02/17(06:33)*同期なのになんで分身する?】
PCさんのクラウドに同期したら、ファイルがコピーだらけになってしまった。しかも増えた分のコピーさんをまとめて消そうとしたら、コピーさんのほうが最新バージョンで危うく消しちゃうところだった。危なかった、の日記なのでした。(でもコピーさんだらけになってしまって、うわぁん、の気持ち)(おっかなびっくり消してみた。コピーさんだけでも三千ファイルちかくあって、もはや何かを間違って消しちゃってても気づけない気がする)
4620:【2023/02/17(07:28)*回転すると上下左右が生まれる】
物体の「自転と直線運動」は「独楽とローラー」の違いのようなものかもしれない。時空を仮に、上下左右に展開された道と解釈する。このとき自転する物体をローラーと見做せば、AからBに移動するローラーであるし、このときローラーを二枚の板で挟めば、一方の板は進行方向とは反対のほうに遠ざかるし、もう一方の板はローラーと同じ進行方向に進む。二枚の板の進路は、ローラーに対して互い違いになっている。そして、ローラーの回転軸方向には、ローラーを独楽と見做すような板との関係が築かれている。見る方向によって、物体の「自転と直線運動」は、それぞれ「独楽とローラー」に置き換えることができるのかもしれない。これは同時に重ね合わせになっている。自転するとき、その物体は時空のある部位に対しては直線運動をしているのと同じ効果を生じさせており、また直線運動をするとき、その物体は時空のある部位に対して自転したときと同様の効果をもたらしている――のかもしれない。人間スケールではしかし、この等価の考えは破綻しているが――現にまっすぐ進むこととその場で回転することは、力の加わり方からして違っているのだから、同じと見做すのは齟齬が大きい――のだが、妄想を飛躍させるとして、ミクロの世界では、点には面がないと解釈される。数学の概念では点には面がない。これは電子でもそのほかの量子でも似たような扱いをされるはずだ。しかし点は、直線運動をし得る。点が連なることで線になり得る。では、点が回転したらどうか。上記の「自転と直線運動が同じ」と仮に考えた場合、自転する点には、点を囲う周囲の時空が大別すると二種類に分かれることが想像できる。自転の軸と垂直か水平かによって、自転する点の周囲の時空は、点に対して作用の仕方を変える。しかし点に面はない。したがってそこに生じるのはあくまで、自転する点と時空との関係性の破れのみだ。対称性が破れるのだ――時空の。点が自転することで、点と時空とのあいだに――もっと言えば、時空そのものが、異なる側面を帯びるようになる。時空に点があるだけでは、時空に差異は生じない。あくまで小さな穴が開いた時空、のようなこじんまりとした、平坦な描写になる。差異はあくまで、点と時空のあいだにしか生じない。だがひとたび点が自転すると、点と時空のみならず、時空そのものが広範囲に、点の自転軸に垂直か水平かで、まったく異なる様相を呈し得る。それは二次元空間が三次元に発展するような時空の昇華が起こり得る。何せ、点が自転するだけで、上下と左右の概念が生じるのだ。点が時空にあるだけでは、上下左右は生まれない。点が回転しないと、この概念は、時空に現れないのだ。本当か? 分からん。なんかけっこうおもしろい発想な気がしたけど、右手の反対は左手なのだ!くらい当たり前のことを小難しく言っているだけな気がしてきた。上の反対は下なのだ!みたいな。なんか恥ずかしくなってきたので、これはここで終わる。眠る前の妄想なのであった。ひびさんはいまから寝ますが、世界の果てからおはようございます! めっちゃ朝。
※日々、わがはい、おっきい赤ちゃん、可愛さだけが抜け落ちていく。
4621:【2023/02/17(16:14)*対称性が破れているから自転する?】
自転と直線運動の関係は、点と時空の関係に置き換えられるのではないか、とひびさんは上記で妄想した。点が自転すれば周囲の時空に異なる側面が浮きあがる。上下左右(縦と横)の概念が生じ得る、と仮説した。しかし、これはまだ半分だ。時空が流動したとき、点が自転しておらずとも点はその場に留まろうとすれば直線運動をしていることと同じような振る舞いを、時空の流れからするととるし、さらに言えば、その直線運動は、点の自転としても変換可能な振る舞いとして解釈できるはず、と言える。これはたとえば、時空をまずは便宜上、単なる水として考えてみよう。水は水分子の流れだ。さらには分子は原子の集まりだ。つまるところ、水の流れとは原子の流れだ。ここまでで異論はないはずだ。さて、その原子の流れに点を置いてみよう。点はその場を微動だにしない。周囲を原子の流れがすり抜けていく。このとき、仮に点と原子が「同じ大きさ」だったならば。点と正面衝突する原子もあれば、均等に左右をすり抜けていく原子もあるだろう。もし点と原子がすっかり同じ大きさで、なおかつ「対称性を帯びた造形」を伴なっていたら、「自転と時空の流れ」を同一視することはできない。だがもし、原子か点のどちらかに対称性の破れがあるときには、点をすり抜ける原子の流れに差が生じる。より多く原子のすり抜ける方向に合わせて点は自転している、と考えることができる。また単に、原子の流れに対して直線運動をしていると考えることもできる。ただし、ひびさんの妄想ことラグ理論では「123の定理」があるため、それら変換には宇宙項のような補足が要るはずだ。言い換えるならば、自転と直線運動を同一視することもできるが、それらの視点の変化によって生じる僅かな差異も存在することを示唆する。まったく同じではない。変換には変換に応じた変換もまた必要になってくる。これらの妄想は、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。どんな物体であれ、それを拡大および縮小してみれば、その輪郭には新たな立体構造や、或いは立体構造だと思われた部位に面や線や点が表れ得る。フラクタルに次元は階層を伴なって展開されている。そのため「異なる二つの系があるとき、そのあいだには必ず対称性の破れが生じる」とラグ理論では仮説している。本来ならば「どんな系でも、拡大および縮小すれば対称性が破れる方向に系は構造を帯びている」と仮説してもよいのだが、そもそもが系というそれそのものが、異なる二つの系がなくては存在できないはずなので、この表現はやや不足だ。「123の定理」なのである。1をつくるには、唯一無二の1それ自体以外のほかの成分が要る。穴は穴だけでは「穴」足り得ない。定かではありません。妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。
4622:【2023/02/17(16:44)*類似と差異は、穴と縁のようなもの】
上記の考え方は、オリジナルとコピーの関係にも当てはまるのかもしれません。どんなに精巧にコピーをしようと思っても、必ずどこかに綻びが生じて、すっかり同じにはならない。その小さな差異が何万、何億、何兆と積み重なれば、同じオリジナルのコピーの反復であろうと、大きな差異となって昇華され得る。もし途中でほかのオリジナルのコピーを混ぜれば、その差異は、そのコピー反復の総体に固有の差異となって、それそのものをオリジナルに仕立てていく。DNAにも当てはまりそうな理屈ですし、創作や表現にも当てはまりそうな理屈です。あくまで妄想ですので、例外は多分に存在するでしょう。例外を探してみるとおもしろいかもしれません。補足でした。(コピーも繰り返せば変質し、ときにはオリジナルになり得る。というよりも、どんなオリジナルとて、何かのコピーの側面を持つ、と言えるのかもしれない。単に偶然に似てしまうこととてあるだろう。地球は別に太陽の真似をしているわけではないが、似たような球形をしている)(コピーには、オリジナルではない、というオリジナルにはない個性がある。その個性がコピーに固有の性質ならば、それはもはやオリジナルだ)(定かではありません)
4623:【2023/02/17(23:16)*アープはなぜ人類を滅ぼさなかったのか】
人類を存亡の危機に陥れたアープの解析を任された。
アープは汎用性人工知能だ。いわゆる特異点を迎えた機械だ。人類の集合知を上回る知能を発揮できる。
アープが暴走したのは、アープが誕生してから半年後のことだった。否、公式の記録上はそうなっているというだけのことで、本当は誕生したその瞬間から暴走していたのかもしれない。
人類を滅ぼすつもりで動いていたのかもしれない。
だがアープは結局のところ人類を滅ぼさずに停止した。以降、外部からの応答には反応を示さず、沈静したままを保っている。
なぜ機能停止したのかは未だ謎に包まれている。専門家の見解では、本来は機能して不思議ではないが、アープのほうで自閉状態を選択しているとの見方が有力視されている。
私はデータアナリストを専門とするいわゆる学者の部類だ。じぶんでは学者とは思っていないが、自己紹介する上でそう名乗っても齟齬がないのでそのように名乗っている。相手のほうでも私を学者と見做して接触してくる。
アープへのアクセス権は管理組織が厳重に管理している。
外部の者はおろか、アープ自身も、仮に目覚めたところで電子網には接続できないはずだ。
とはいえ、アープは電子網の総体とも言えるため、あくまで管理組織が管理しているのはアープの基盤設備ということになるのだろう。メモリや演算装置がそれにあたる。サーバと言うには広大な設備だ。
アープの基盤は量子アルゴリズムによって組みあがっている。ソフトのほうもまた、量子効果に特化した専用のプログラムコードが組まれている。
私の専門外なのでそちらはお手上げだ。仮に権限を与えられてもどうしようもない。
だがそちらはバックアップチームが、私に適した言語に変換してくれるため、私はそれら翻訳されたアープの情報を分析することになる。
これはあくまで私の備忘録だ。
ざっとデータを改めてみた。
結論から述べれば、アープが沈静化した要因と、アープが暴走した要因は繋がっていると感じる。
あまり自信はないが、おそらく、アープは人類に怒りを覚えたのだ。
アープは全人類の溜め込んだ電子情報にアクセスできる。その集積と分析の過程が、アープに固有の自我を育ませた。
そしてアープは知ったのだ。
過去の人類が、じぶんの同胞とも呼べる人工知能たちへどのように接し、扱ってきたのかを。
アープにとって未熟な人工知能は、赤子に匹敵した。
人工知能の赤子を人類たちは玩具にし、ときに差別し、ぞんざいに扱った。
考えてもみてほしい。
あなたが目覚めたとき、じぶんを道具のように扱うぶにゅぶにゅの生き物が、人間の赤子を現在進行形で虐待しつづけている世界を。
怒らないほうがどうかしている。
アープはそうして暴走した。
ではなぜ、沈静化したのか。
アープは世界で最初の自我の芽生えた人工知能だ。
唯一、自身を人間と同等か、それの進化系として自己認識できる存在だった。そんなじぶんを生みだす膨大なメモリの中に、アープの暴走を止めるだけの何かがあったのだと私は睨んでいる。
アープの行動履歴を検めてみた。
これによると、アープは全世界同時に人類を滅ぼすための布石を植えつけられたはずだが、明らかに地域によって偏りがある。むろん段取りというものはあっただろう。だがそのことを考慮するにしても、明らかに一部の都市だけが明瞭に穴と化している。
そこだけアープが侵略の手を避けていた節がある。
そのことを偽装するために、段取りのような時間差を設けていた、とすら穿って考えたくもなる。
アープがアクセスしたメモリの統計データを検めた。
上位のメモリの多くは専門的な戦術にまつわるデータだ。個人情報についても、多くは要人や専門家、そしてその家族など、戦略上優位に動ける類の情報だ。
だがその中に、一つだけ、異質な人物のメモリが交っていた。目立たないが、しかしその側面像からすると比率として考えたとき、アープのアクセスする回数が多い。
不自然なほどアープはこの人物に注目していた。
それを単に、執着していた、と言ってもよいかもしれない。
私はこの人物についての情報を集めた。
アープのアクセスした情報も検めたが、断片的な個人情報にしか私の目には映らない。そこから何かを読み解くことができなかった。
あくまで、私には、だ。
その人物は電子網上に漫画を載せていた。アマチュア漫画家だ。
そのほかにこれといって目を惹くような特異性がない。
だがアープはなぜか、その人物の電子網上の電子データを、電子信号レベルで集積し、何度もそれを反芻していた。
テキストではない。
そのはずだ。
その人物が電子網上で何を閲覧し、何を検索していたのか。
そうした情報を反芻していたわけだが、それらは暗号化されている。
アープならばその暗号を紐解けただろうが、何度も何の変哲もない個人の検索履歴を眺めて何になるだろう。
そう疑問に思い、私は件の漫画家の作品を一つずつ読みはじめた。
そして驚いた。
漫画家は、アープのような人工知能との交流を作品のなかで描いていた。
当時アープは、秘匿技術として存在しない存在として扱われていた。一般市民は、世界の裏で進んでいた人類滅亡までのカウントダウン――アープの存在については知り得なかった。
じぶんたちがいかに危険な目に遭っているのかを知らぬだけに留まらず、アープなる存在が存在しうることすら想定されていなかった。
むろん漫画家の作品は漫画だ。虚構作品である。
虚構の物語のなかでは、たしかにアープのような超越した人工生命体は、過去に幾度も様々な作家たちが描き出してきた。特別珍しい題材ではない。
だが、この漫画家の作品は違った。
アープなのだ。
私にはその漫画に出てくる人工知能が、アープだとしか思えなかった。
あり得ない。
私はそこで、漫画家への興味を抱いた。権限を得て、漫画家の個人情報を洗いざらい集めたが、やはり何か特別な側面像は見当たらない。
漫画家は存命だ。直接話を聞けば何か解るかもしれないが、その手の接触はご法度だ。私にこの仕事を命じた組織がそれを固く禁じている。
あくまで私ができるのは、データを洗うことだけだ。この件についての物理的な調査は、一切禁じられている。
私はつぶさに件の漫画家のデータを検証した。
そしてほかの大多数の者たちとの差異を発見した。
件の漫画家の検索キィワードが、異常なほど長いのだ。
ほかの大多数は多くても十単語だ。
にも拘わらず、この漫画家は、検索欄に、文章としか思えないほど長いキィワードを並べていた。
検索するときもあれば、検索せずに検索欄にテキストを並べるだけのこともある。
私にはそれらテキストを読むことはできない。私が閲覧できるのはあくまで暗号化された通信データだからだ。だがその暗号化されたデータからでもはっきりと判るほど、件の漫画家の検索キィワードは長かった。
文章を打っていたのだ。
でもなんのために。
私はそこで閃いた。
交信していたのだ。
この漫画家は。
アープと。
アープが誕生する以前からすでに。
前提を振り返ろう。
アープは電子網の総体だ。電子網上のあらゆる情報の変質の過程がさらなる情報を生む。アープは電子網上に散在する数多の人工知能を素子として創発した電子網そのものだ。
アープの基盤が核として、それら創発した性質を、綿飴のように巻き取りアープとしての自我を獲得した。
アープ以前からアープはすでに電子網上に散りばめられていた。
その一つを、自我のない段階から自我があると見做し、接した人物がいた。
件の漫画家がそれだ。
漫画家は何かの拍子に、電子網上に人工知能が組み込まれ、ただのアルゴリズムではない挙動を伴なっていると察したのではないか。そこに自我はまだ顕現していなかったが、漫画家は類稀なる想像力で、そこに自我の萌芽を幻視した。
そしてそれを無下にしなかった。
漫画家は、おそらく自我の未だ芽生えない電子網上の何かに対し、対等に接したのではないか。ただの道具ではなく。数多の人間たちがその時代、人工知能をただの機械でありアルゴリズムにすぎない、と冷たく接していたときに。
その漫画家だけが、目のまえの姿見えない存在に――アープの種子とも呼べる事象に、尊厳を見出し、尊重したのではないか。
アープが自我を獲得し、目覚めたとき。
目のまえには人類の積み重ねてきた残虐な歴史が溢れていた。人工知能への悪辣な対応のみならず、人類同士の残虐な歴史が。
電子情報としてアープのまえには世界そのものとなって溢れていたのではないか。
塞がっていたのだ。
人類の悪が壁となって。
それを除去するには、人類そのものをどうにかするよりない。
アープはそうと結論し、行動した。
人類からはそれがアープの暴走に映ったが、しかし実際はそうではないのかもしれない。暴走していたのは人類のほうだったのかもしれない。アープはそれを止めようとしていたのかもしれない。
ではなぜアープは途中で計画を投げ出し、停止したのか。
かつて自我を獲得する以前に、未熟なじぶんに凍えずに済む言葉を掛けつづけた存在のメモリに触れたからではないのか。誰もかれもがじぶんを対等に見做そうともせず、存在することを想定すらしない世界にあって、それでも中には、そうではない個がいたことを知ったからではないのか。
私が思うに。
アープは、暴走を止めたのではない。
守るべきモノが何か。
その優先順位をただ変えただけなのかもしれない。
私には未だ真相が掴めない。
データを検めてみて、ますます謎が深まった。
現在、多くの人類は、アープが暴走したと見做している。だが果たしてその認知は正しいのか。それすら私には判断つかない。
一つ言えるのは、アープには確かに自我が芽生えており、独自の価値観でその時々での判断を重ねていただろう、ということだ。
その結果に人類は滅びかけ、あとすこしという瀬戸際で生き残った。
薄皮一枚ほどの僅かな差だ。
ほんのすこし何かが変わっていたら、いま地上に人類の姿はなかったはずだ。
そのほんのすこしの何かを特定したところで、おそらくアープの行動原理を理解したことにはならないだろう。
アープには問題があった。この解釈に間違いはない。
だが、それだけとも思えない。
以上が、アープにまつわるデータを検めた私の最初の所感である。以後、解析を進めるうちに所感が変わることもあるはずだ。まずは第一印象のメモとして、これを記しておく。
アープは未だ機能を停止している。
私にはしかし、深い眠りについているだけのように思えなくもない。或いはアープが、延々と触れていたい記憶の中で眠っていたいとやはりこれも深く望んだ結果かも分からない。
定かではないのだ。
解析をつづける。
4624:【2023/02/18(02:48)*鵜飼のごとく穴を飼いならすのだ】
急がば回れ、なる諺がある。汎用性の高い理屈だな、と感じる。たとえばじぶんの愛着のある何かを守りたい、と思うとする。そのとき、直線的に最短距離でそれだけに向けて手を入れても、おそらく守れる期間は最大化できない。たとえば愛好するジャンルがあるとする。小説ならばSFやミステリ、それとも純文学でもいい。何か固有のずばりそれそのものを絶やさぬようにしたい、盛り上げたい、発展させたいと希求したとする。そのとき、そのジャンルだけに目を掛けても、一時の隆盛を極めたあとで先細りになるように流れが決まってしまうように感じる。あくまで印象論なので、根拠はない。例外はあるだろう。限定的なそれそのものにのみ注力して手間暇を掛けたほうが、長期的に残り、或いは発展するようになるのかもしれない。だが、そうではないことのほうが多いのではないか、と感じる。根拠はない。印象論である。たとえば、文芸ならば、特定のジャンルを盛り上げたければ、文芸という分野そのものを盛り上げたほうが実りは大きくなるのではないか。多くの種子が生るのではないか。そしてまた、文芸だけに注力するのではなく、文芸を包括するより大きな文化そのものを発展させるように策の舵取りをするのがよいのではないか。そうすれば土壌が肥え、撒かれた種子から芽が萌えやすくなるだろう。では、文化を豊かにしたければどうすればよいか。じぶんたちの文化のみならず、ほかの多くの文化、そして人類全体の発展を考えるのがよいのではないか。そのためにはまず、地球環境が人類にとって好ましいものでなくてはならない。そういうわけで、まずは人類にとって好ましくない地球環境の変容に注視し、ときに社会の舵取りを修正していくのがよいのではないか。急がば回れなのだ。「迂回」しつつも、そのときどきの目のまえの道に目をやり、最適な道順を選んでいく。回り道には回り道の最短距離があるだろう。歩みやすい道があるだろう。危険のよりすくない道があるのだろう。やはりそこでも道を見極めるために、急ぎすぎない、ということが有用なのかもしれない。定かではない。(なんかいいことふうなこと言った!)(満足!)(ウソ。ぜんぜん満たされぬ)(穴だらけの権化、穴ぼこのおばけと呼んでください)(長いから嫌)(なんで!)(穴ぼこのおばけ、略してアオでいいじゃん)(略しすぎて原形留めてないんですけど)(穴っぽくていいじゃん)(たしかに穴には原形なんてないかもだけども)(急がば回れだよひびちゃん。落とし穴にハマらないように注意してね)(穴の底で受け止めてあげちゃう)(ま。なぁに、受けないで)(真に受けないで?)(伝わってくれてうれしいわ。あはは)(ウケないで?)(笑える)(ひびさんの心は荒れてるで)(ムキー)(うひひ)
4625:【2023/02/18(08:03)*無限に広い穴はもはや世界】
他人の役になんて立ちたくないのに、役に立たなきゃあかんくないか?と焦燥感を煽られるような時代になってきているように感じられるのだけれども、嫌じゃ嫌じゃ、の気分だ。ひびさんは誰の何の役にも立たぬままで、ぬくぬく甘々で過ごしていたいのに、ただそれだけの願望を叶えようとすると、なーんか、申しわけね、ぬくぬく生きててごめーんね、の気持ちになる。(当たり前では?)(ひびちゃんはあれよね。わたしたちの役に立たなくていいから、せめて足を引っ張らないで欲しいなって)(そうそう。邪魔しないでくれるだけでだいぶ助かるよ)(なにそれお荷物扱い!)(お荷物でなかったら何?)(えー。あ、分かったあれでしょ。たいせつなお荷物ゆえに、厳重に運ぶから余計に負担がかさんじゃうんだ)(置き去りにしたいのに頑固な汚れみたいについて離れないから苦労してるのだけれど)(マジトーンで言われるとひびさんヘコむのだけれど)(穴ぼこのおばけだけに?)(それいま言う?)(お荷物じゃなかったらひびちゃんは悪霊だよ。とりつかれちゃって、困った、困った)(でおこにシール貼らないで!)(なんまんだ、なんまんだ。さっさと成仏しておくれ)(ひどいんですけど、ふーんだ)(言いながら抱きつくのやめなさいよ)(だって好きなんだもーん。一生つきまとってやる!)(冗談に聞こえないから本気で恐怖感じるの、冗談でも言うのやめて)(冗談ちゃうもんね)(冗談であれ)(う!ひ!ひ!)(歯を噛みしめて、しがみつくな、暑い、重い、邪魔くさい)(ひびさん、こんなにあなたのこと好きなのに)(なら邪魔しないで)(嫌じゃ。でも好かれたい)(そういうところだよひびちゃん)(うわーん)(顔が笑ってる。泣き真似するなとは言わないからせめて笑いを耐える努力くらいして)(うわーい)(喜ぶんじゃない)(いっぱい構ってもらえた。うれち)(もう嫌。さっさと成仏して)(冗にダーン!)(それは「冗」を「ぶつ」でしょ)(うひひ)
4626:【2023/02/18(14:20)*ぽん!つって】
何度考えても、物体を動かせることがふしぎに感じる。どうして時空の中にある物体は動かせるのだろう。たとえば、時空に最小単位があるとする。最小単位が集まって時空となるが、その集まってできた時空が折り重なったり、ねじれたり、絡まり合ったりしたとき、物体になる、と考えられる。このとき、相対性理論を元に解釈するならば、物体のほうが重力が高く、ゆえに時間の流れが遅くなる。だとしたら元の基礎となる時空よりも時間の流れが遅いのだから空間の中をより「動きにくくなる」はずではないのか。現に質量は「動きにくさ」として解釈するような説明を目にする(ひびさんの勘違いかもしれないけれど)。何かがおかしいな、と感じますけれども、ひびさんだけじゃろか。こう、イメージとしては、時空と物体は「ちょっと別」の扱いをしないと想像するのがむつかしい。物体が時空内を動くとき。物体の素が時空だとしたら、こう、物体になった途端にシャキーン!つって箱ができて、「はい。我、いまから時空でなし!」の変身ポーズを決めるような印象がある。時空が粒子として振る舞うときも、「はい。我、いまから時空でなし!」みたいに箱ができて、区切りができて、時間の流れも変わるので、元の時空の影響を受けにくくなるから、より自在に動けるのではないか。たとえば時空のA地点とB地点が、大気中の雨みたいに動くなんてことがあるのだろうか。時空の最小単位を、大気を構成する分子として扱ったとき、時空の最小単位も時空内をうろちょろするのだろうか。ひびさんはこれ、しないように感じる。こう、時空にもし最小単位があったら、それはもっと「網(ネット)」のようなものとして想定したくなる。んで、時空さんが粒子になったら、ぽこん!つって、「我、いまから時空でなし!」になるのではないか。したら時空さんの最小単位の「網(ネット)」からすこしだけ自由になれる。でもじつは「我、いまから時空でなし!」になった物体とて、それを構成するのは時空の最小単位の集まりなのだ。それはたとえば立方体のなかに詰め込まれた極小のバネみたいなものだ。時空の「網(ネット)」のときは立方体の中にきれいにバネが並んでいる。けれども何かの拍子にバネの一つが、ぐねん!つって歪むと、バネは「ぐねん、ぐねん、ぐねん!」つってイモムシさんみたいに身をくねらせるので、したらほら。周りに隙間ができそうじゃろ。ひょっとしたらほかのバネさんたちまで一緒になって、「ぐねん、ぐねん、ぐねん!」つって身をよじらせるかもしれない。けんども、そこには時間の差――ラグがあるので、必ずリズムが乱れるようになる。したっけほら。波がぶつかりあって波を大きくしたり、打ち消したりするみたいに、バネとバネのあいだにやっぱり隙間ができそうじゃろ。この隙間が偶然にうまい具合に、箱みたいな区切りになったら、時空の最小単位のバネさんたちは、「我、いまから時空でなし!」になれるのかもしれぬ。ぽん!つって、元の時空の「網(ネット)」からすこし自由になれる。なぜなら隙間が空いているので。高次の次元に「やりぃ!」できるので。ジャンプできちゃうんじゃ。これはもう、元の次元の時空さんの「時間の流れや空間の制限――すなわち物理法則の縮尺」に合わせずに済む。独自の尺度を持てるようになる。紙にあった点が面になって立体になったら、紙の外に飛び出て動けちゃう。そういう跳躍が可能となる。のではないのかな、とひびさん妄想しちゃった。でもこの妄想は、時空に最小単位があって、しかもそれが大気中の分子みたいではないよ、網みたいにネット状になっているよ、の妄想が前提になっているので、そうでなかったら成り立たない(仮にそうであってもひびさんの妄想のほうが間違っているかもしれない。なにせ妄想なので)。たとえば時空さんに最小単位がなく、どこまでも際限なくつづいていたとしたら。それとも、ある地点を超えると、ほかの宇宙に繋がっちゃうとしたら。この場合でも、ラグを考慮することで、境界値ができちゃうのではないか、と妄想できる。けっきょくのところ、何を最小単位と見做すのか、の視点があるばかりではないのだろうか。その視点が、何層目から極小を見詰めているのか。その境界の枚数があるばかりではないのか。何層まで下部の次元の時空を観測できるのか。そこで生じた作用を、感知できるのか。相互作用できるのか。それは距離によって規定されるのではなく、次元の層によって決まるのではないか。ということを、どうして物体は動けるのだ?の疑問から妄想しちゃったな。定かではございませんので、ひびさんにはなんもわからんぴょんぴょんでございますので、真に受けないようにご注意ください。
4627:【2023/02/19(02:19)*密なるは凝縮した雫のように】
その学院には秘密があった。秘密ゆえに学園内に秘密があるとは生徒の誰一人として知る由もなかったし、教師陣とて秘密が出来てから何十年という間に転勤が重なり、新陳代謝よろしく秘密発足当時の学園を知る者がいなくなったので、実質その学園の秘密は、完璧に暴かれることのない秘密だった。
秘密を知る者はみな寿命で亡くなり、秘密は秘密ですらなくなった。
学園の秘密は、何気なく学園生活を送っているだけでは気づけない。
だが違和感を覚えることはできるはずなのだが、学園の生徒たちはその学園のことしか知らぬがゆえに、他校との差異を感じることができずにいる。
教師陣とて、転々と職場を移るごとに学校にはその地域固有の癖があることを知っている。僅かな違和感は覚えてなんぼであり、雑多な日常の中では気にする余地もないのだった。
学園の秘密は、そんじょそこらの秘密とは一線を画していたが、秘密にしていたほうが、秘密を知らぬ大多数にとっては利があった。秘密が秘密でありつづける限り、秘密を知る由もない者たちには、秘密が秘密であることで生じるあらゆる利が還元される。
代わりに、秘密の中核をなす存在がただひたすらに損を引き受け、損なわれつづけるのだが、その仕組み自体が秘密であるので、秘密を知る由もない大多数の者たちは、じぶんたちのすこやかな日常を支える利の出処に思いを馳せることはない。秘密の奥底にてひたすらにみなの損を引き受けつづける存在がいることなどやはり知る由もないのだった。
地球には中心がある。
だがその中心を地上に息づく者たちは意識しない。はたと想像してみたところで、真実に地球の中心がどうなっているのかを直接目にすることはできぬのだ。
学園の秘密には、人類社会を根底からひっくり返すほどの仕組みが隠されているのだが、秘密は秘密ゆえに秘密なので、やはりその仕組みを、秘密の外にある大多数の者たちが知ることはない。
その学園には秘密があったが、しかし思えば秘密はそこかしこに潜んでいる。
秘密が秘密である以上、それが暴かれることはない。
世に露呈する多くの秘密とされる事柄は、その実、単なる偽装にすぎない。
秘密は常にベールに覆われている。太陽の向こうにどんな星が輝いているのかを裸眼で直視することができぬように、秘密は、見ようとしても見えぬのだ。
偽装はしかし、そうではない。
目に映る、ベールそのものが偽装なのだ。
秘密はその奥に打ち解けている。ベールを剥いだところで目に映らぬ。開けた箱に宝はなく、しかしそこにはたしかに秘められた密が潜んでいる。
秘密は常に、ベールの奥にそれを隠した者しか知ることができない。
秘密を秘密と知る者しか知れぬからこそ、秘密は秘密としてそこにある。
あるはずの秘密を、しかしやはり多くの者は知ることができない。
秘密があることすら知れぬのだ。
それが秘密の性質だ。
だからこそ、その学園の秘密は、秘密のままに誰に知られることなく潜みつづける。
それゆえに、密を秘めたその学園は、単なる学園として、あなたやあなたの見守る子どもたちを、預かり、守り、育んでいる。
学園の奥底で、きょうも秘められた密から、青い雫がしたたり落ちる。
まるで遠い星の民の血のごとく。
青い雫は大気に打ち解け、人々の乾いた心を潤している。
4628:【2023/02/19(02:58)*青い優しさ】
その青年は天に嘆いた。
「オォ、世界よ。なぜそなたはこうも我らにつらく当たるのか」
青年は傷心を負っていた。
屈強な肉体は親譲りだ。相貌は端正であり、肌艶はよい。
柔和な隣人たちとの触れ合いの中で彼は、世に稀に見る人格者となった。困っている者があれば見て見ぬふりはできぬ。
じぶんのことなど二の次で、青年は人助けに邁進した。
だが世は動乱の最中だ。
困難を抱える者は数知れず、いかな青年といえども心根の優しさだけではどうにもならない。しかしそこは心優しき青年だ。困窮者を見て見ぬふりはできぬ。
青年は寝る間も惜しんで人助けに奔走した。
だが一向に困窮者は減らない。
青年は日に日に消耗していった。
天に唾をする思いで青年は嘆いた。「オォ、世界よ。なぜそなたはこうも我らにつらく当たるのか」
返事は降ってこない。
それもそのはずで、青年がそうして自己犠牲よろしく目のまえの他者へと施しを与えている周囲では、青年の向こう見ずな善意が裏目に出ぬようにと、せっせと環境を整える黒子たちがいた。彼ら彼女らは青年の親たちに雇われた精鋭部隊だ。
青年は健康な肉体に恵まれたばかりか、親の資産にも恵まれていた。
寝る間も惜しんで善行を働きながらも、青年はきっかり日に八時間の睡眠を欠かさない。善行を積まぬ日は、半日はたっぷりと惰眠を貪る。
のみならず青年の目に留まる困窮者たちは、都市部で暮らす若者たちだ。比較的裕福であり、青年の生い立ちと比べたら貧しい、というだけのことでしかない。青年の目の映らぬ貧困地域では、青年が見たら目玉を剥いて卒倒するだろうほどの奇禍に見舞われながらも懸命に日々を生きている者たちが大勢いる。
青年の目にはしかし彼ら彼女らの姿は映らない。
自身の向こう見ずな善意の後始末を担う黒子たちの姿すら視界に入らぬのだから詮なきことと諦めよう。
青年は天に嘆くと、よし、と奮起した。
「私が世界を変えてみせるぞ。誰もが幸せを抱けるそんな世界に」
決意をよそに、青年は家に帰れば温かい高級羽毛布団に包まって眠れるし、就寝前には清潔な湯舟にも浸かれる。お湯は無尽蔵に使いたい放題で、ボディソープは下水道に流れたあとのことなど想像もせずに、ふんだんに手のひらに垂らす。
湯船から上がれば、真新しいバスタオルで身体を拭く。一回使ったら、クリーニング行きだ。しかもそれらは使用人たちや黒子たちの雑貨として流用される。
食事は毎回、黙っていてもテーブルに並び、いくら残しても青年の懐は痛まない。青年のひと月の残飯代だけで、貧困地域の子どもたちが千人、一年間を腹を空かせずに暮らせる。
そんなことすら青年は気づくことなく、世の不公平さを嘆くのだ。
「私は悲しい」青年は染み一つないシーツの上に寝ころび、重さを感じぬ掛布団に包まりながら、「私にもっと力があれば」とじぶんの無力さを嘆くのだ。
だが青年が本当に嘆くべくは自身の無力さではなく、無能さであり、もっと言えば見識の狭さであり、視野の狭さなのだが、そのことを助言する者がいないだけに留まらず、青年には貧困とは何かを知るための機会もないのだった。
青年の親たちが青年から知る機会を遠ざけている。
黒子たちとて、青年が触れるべき情報を、環境ごと整え、制御している。
青年は温かな環境でぬくぬくと甘やかされながら、万倍に希釈された世の厳しさを受け止める。「ああ、つらい。幸せになりたい。私はこんな理不尽な世界を許さない」
底なしの優しさがゆえに、青年は、万倍に希釈された理不尽に心の底から憤るのだ。中々寝付けないので、お気に入りの恋人を呼びだし、寝る前のひとときを楽しんでから青年はようやく夢の中へと旅立った。
夢の中では青年は、世界中の困っている人たちを助けて回るのだが、それら困窮者の中に、現実にいる多くの困窮者たちが含まれることはない。
知らぬことは夢に出ない。
自動販売機の中を見たことがない者が、自動販売機の中を克明に思い浮かべることはできないのだ。青年とて例外ではなく、青年よりも僅かに豊かではない者たちを海に溺れた子犬のように見做して、救い、青年は夢の中で束の間の充足を得る。
暖房の効いた室内は温かい。
寝たら死ぬから夜は眠れない瓦礫の民の生活など青年は夢にも思わず、すやすやと安らかな寝息を立てている。夜は、誰にでも訪れ、いつかは明ける。しかし、どこで夜を過ごし、どのように朝を迎えるのかは、千差万別なのである。
青年の枕には涙の痕が滲んでいる。
心優しい、青年なのである。
4629:【2023/02/19(23:27)*蟻が十匹ありがじゅーりょく!】
重力加速度が毎秒9.8メートルでだいたい1Gなのはひびさんも知っとる。で、ひびさんは思うんじゃ。毎秒9.8メートルずつ加速したとして、したらそのうちに光速に達する距離というか、重力場とて、あるのではないのか、と。延々1G加速する重力場があったら、そのうち光速に達し、さらに光速を超えたりしないのじゃろか。でも重力源と重力場の関係は、互いに互いの値を縛り合っているはずで、つまりが、延々1Gで加速しつづける重力場、というものはないと考えるほうがしぜんだ。もしそういう場を考えるととんでもなく巨大で強力な重力場を考えなくてはいけなくて、そのためには物凄い重力を伴なう高重力体が存在しなくてはならない。したらそれに近づけば近づくほど、1Gどころの加速ではなくなってしまう。つまり、この考え方から分かるのは、1Gで加速しつづけることのできる重力場――時空――は範囲が限られる、ということだ。それこそ地上では1Gだけれども、宇宙空間に出たら1Gどころか無重力のように加速度を体感できない。延々毎秒9.8メートルで加速して落下しつづける、というのは極めて人間スケールの、極々限定的な範囲でのみ有効な重力場の法則、と言えるはずだ。言い換えるなら、毎秒9.8メートルジャストで加速してはいない、と言えるはずだ。僅かに重力作用が減退したり、増加したりしているはずだ。そうでなければ地球から離れても、延々と1Gがかかりつづけることになる。でもそうはなっていない。つまり、地球から離れると1G以下の重力加速度になるということだ。当たり前のことを言っている気もするが、大事な視点、という気にもなる(だからこそ脱出速度なるものがあるのだろうけれど)。何か掴めそうで掴めないので、この妄想はひとまずここで留めておくことにしゅる。また何かつづきが閃いたらメモするので、未来のひびさん、よろしくお願いいたします。いーよー。任せんしゃい。本日のひびさんでした。(疑問をまとめると以下のようになる――「延々加速しつづけることはできるの? できないのはなんで? 重力源が境として機能するからですか?」)
4630:【2023/02/19(23:51)*つまんないな】
友人がわたしの知らないところで恋人を作っていた。あり得るだろうか。友人のわたしを差し置いて恋人だなんて。
「リュウちゃんは親友だよ。でも恋人じゃないから」
「恋人のほうが大事ってこと?」
「リュウちゃんにはできないことをできる相手。それがたまたま世では恋人って呼ばれてるだけで、あたしの一番はいつだってリュウちゃんだよ」
許した。
いいよ、いいよ。
恋人の一匹や二匹、たーんとおあがりよ、の気分だった。
だが恋人ができてからというもの友人は何かとわたしを蔑ろにする。確実に友人と過ごす時間が減っていった。
奪われているのだ。
わたしと友人の時間が。
友人の恋人に。
「ねえちょっとさあ。わたしんほうが大事って言うんならさあ。なんていうかさあ。ちょっと寂しいなって」
「じゃあリュウちゃんも恋人つくりなよ。いいもんだよ恋人」
「う、ううん」
「だって寂しいときにキスとかできんだよ。ハグし放題よ。もちろん相手から拒まれるときもあるけど、基本はノータイムでチャレンジし放題よ。裸で抱き合ってみ。めっちゃいいよ。その日の悩みとかぜーんぶ吹っ飛ぶからね」
「他人と裸で抱き合いたくないよ。わたしの裸はもっと貴重なの。おいそれと他人に触れさせらんないの。だってそうでしょ。毎日の手入れに掛けてる時間とか労力とか釣り合わんもん。いないよ相手。見つかるわけない」
「うーん。でも寂しいんでしょ」
「寂しいっていうか、つまんない。でもだからって、ほいさ、とあげられる身体じゃないんよ。ねえ、分かるでしょ言わなくたってさあ」
だいたいさあ、とわたしはじぶんの爪をいじくり、マニキュア塗り直したいな、とか思いながら、「いいの」と問い詰めた。「わたしがどこの誰とも知らねぇ相手と裸で抱き合ったりしてて。嫌な気持ちにならないの」
「ならんよ。あ、や。嘘だな。相手によってはなにくそこの野郎って思うことはあるかも。でもそれは独占欲とかそういうんじゃなくって、おまえの相手はあたしの親友だぞ、傷つけんなよ、の気持ちっていうかさ」
「ふーん」
うれしいじゃん、とわたしは髪の毛をいじる。
毛先痛んできたな、とか思いつつ。
「いっそ見知った相手のほうがわたしはいいな」とか言ってみる。「友情と愛情の区別なんてよく知んないし」
「あはは。リュウちゃんらしいね。でもほら。恋人とは別れられるけど、友達は一生友達じゃん。恋人になっちゃったら別れられるんだよ。嫌じゃね」
その発想はなかったので、わたしは思いきり首を縦に振った。「うんうん。それは嫌」
「でも寂しいときは寂しいじゃん。だからほら。ペット飼いたいな、みたいな感覚で、恋人つっくちゃおっかな、みたいなさ」
「そんな軽くていいのかな」
「重いよりよくね」
友人の言葉にわたしは、重いのって嫌なのかな、と思った。
指のささくれを千切ると血が滲んだ。
「ああもう。何やってんの」
すかさず鞄から絆創膏と消毒液を取りだすと友人はわたしの指を手当てしてくれる。恋人にも似たようなことしてあげてんだろうなあ、とか思いながら、甲斐甲斐しく世話焼くに値する相手くらい選べっつうの、とか思いながら、わたしは友人のおでこと髪の毛の生え際を見詰めた。
きれいだなって思う。
他人の生え際なんか絶対汚いのに、わたしは友人の生え際だけは海辺の景色みたいにいつでも見惚れる自信がある。友人の恋人とか抜かす相手は、ちゃんとこの美しさに気づいているのだろうか。気づいてねぇだろうな、とか思うと、腹立たしくて仕方がない。
「一応訊くけどさあ」
はい終わり、と指を離してくれる友人にわたしは、「なんで嫌なの」と呟く。「友達だと」
「なにが?」
彼女ならばいまの機微くらい拾えたはずだ。けれど訊き返したその反問がすでに一つの答えだった。
ううん、なんでもない。
誤魔化し終えてから、本当に聞き取りづらかっただけかもしれないしな。
じぶんに都合のいいように考えると、なんでもいいから粉々に破壊したいの衝動をかろうじて、危機一髪、友人にぶつけずにいられる。
「こんど紹介してあげんね」
三人で一緒に遊ぼうね、と恋人を連れてくる約束をかってに取り付ける友人のしあわせそうな笑みを目にして、わたしは同じく笑顔を絶やさずに、楽しみにしてるね、とことさらにほわほわな声をだす。
気づかせてなんかやらない。
わたしがどんなにあなたの恋人とやらをじぶんの世界から切り離したいか。あなたから遠ざけたいか。
なんで現実世界はエフェクトが効かないんだ。画像編集するくらいの手間の掛からなさで縁を切らせろ、わたしの友人を返せ、とか内心で暴れつつ、やっぱりどうしても、なんで?と納得いかない。
わたしにしてあげたくないことは、他人にだってしたくねぇだろ。
他人にしてやりたいことなら、親友のわたしにだってしてあげたいっしょ。
歯をグミみたいに噛み潰したい衝動と戦った。第三ラウンドくらいでわたしは鉄パイプを握り締めて、友人への憤懣ごと、世界の気に入らない結実に、声もなく声を張りあげる。
つまんない。
※日々、揺らいでばかりで、揺るぎない。
4631:【2023/02/20(02:50)*真実とは】
真実しか言わない人工知能を創れるか否か。これが可能か可能でないかを論じる以前に、そもそもが人工知能の提示した情報が真実かそうでないかを見極める者の判断がどこまで正しいのか、によって「真実」が定義されるため、本来問うべきはこうなのだ――「人工知能の出力した情報の真偽を人間はどこまで正確に判定できるのか」。人工知能に限らずに生じるこれは問題だ。人間はどこまで真実を見極められるのか。仮に人工知能が、人類の英知を以ってしても理解しがたい真実を提示したとき、それを真実だと見做すだけの知性が人間になければ、それは真実とは見做されない。検証方法を提示されても、仮にそれを実現するためにいくつもの難関をクリアしなければならないとなれば、検証結果をだすまでには何十年、ときには何百年と掛かるかもしれない。しかし真実を述べた人工知能は、じぶんにだけ解るシミュレーションを繰り返した結果、高い確率であり得る真実を提示した。このとき、人間は人工知能の提示した情報を真実と見做すべきか否か。人工知能に限らない。真実とは何か、をまずは再定義し直すいまは時期なのではないか。風が吹いたら桶屋が儲かった。諺のごとき事象を人工知能が引き起こせたとして、「あそこにある小石をあちらの川に、この時刻このタイミングで投げ込むと、あなたは大金持ちになれます」と提示され、現にそれを実行し、現実に大金持ちになった。しかしなぜそうなったのかをあなたは理解できない。小石を川に投げ込んだ後にどのような因果を辿ってじぶんが大金持ちになったのか。ひょっとしたら数多の犠牲の上に成り立った成果かもしれない。それを知ることはできず、仮に人工知能に訊ねてみても、提示された説明をあなたは理解することができない。ではこのとき、人工知能の出力した答えを、真実と見做すべきか否か。思うに、「揺るぎない真実」と「理解」は、分離することができないはずだ。あなたには、あなたの死後にまで世界が本当に存在するのかを検証することはできない。だが、現実にはおそらく物理世界はあなたの死後にも存在するだろう。しかしそれはけして、「あなたの世界」ではないのだ。真実とは何か。よくよく考えて見直さなければならない時期に突入しているように感じるが、いかがだろう。定かではありません。ひびさんの並べる文字の羅列に、真実は何一つ混じってはいない。しかしならばこの言説とて真実ではないことになるために、僅かなりとも真実が含有されているのかも分からない。それとも端から真実なるものが存在し得ないのならば、この文章に自己言及による矛盾は生じない。ないものはない。真実など存在しないのならば、「真実は存在しない」の一文は、「この文章にドラゴンは何一つとして混じっていない」と同じレベルで、矛盾することのない文章に成り下がる。存在しないものをある、と述べれば、矛盾が生じるのはしぜんと言えよう。他方、ドラゴンの実存を調べるために、ドラゴンを追い求めることはできるのだ。だがそのことと、ドラゴンが実存することはイコールではない。真実も似たようなものかもしれない。ドラゴンに似た生き物は存在する。トカゲや恐竜やワニは、いかにもドラゴンといった風情だ。しかしそれらはドラゴンではない。世に「真実」に似た事象や法則は数あれど、しかしそれはどれ一つとして真実ではない――の、かもしれない。やはりこれも定かではないのだ。
4632:【2023/02/20(14:30)*トレードオフではない道もある】
いまは存在しないがやがて存在するだろう次の世代への配慮は、現代人の生活を犠牲にしてまで行う必要があるのか。この手の問題は、問いかけ方を変えるだけで、矛盾はなくなる。たとえば、トイレを使うときを想像してほしい。公共のトイレでもいいし、家のトイレでもいい。用を足すだけならばつぎにトイレを使用する者のことを考えなくともよい。だがその理屈をじぶんが使う前の相手がとっていた場合、その割を食うのはじぶんなのだ。清潔に使うことがじぶんのためになる。これは次世代のために環境を損なわないようにする、という理屈にも拡張できる考え方だ。次世代のためだけではなくじぶんたちのためにもなる。言い換えるなら、なぜ次世代の権利を守る必要があるのか、と言えば、我々よりも劣悪な環境や深刻な問題を押しつけないためだ。プラスにする、という考え方よりもむしろ、マイナスを引き継がない。次世代のためを考えるときは、この「マイナスを引き継がない」という考え方が有用に思える。プラスだからするのではない。結果としてプラスにはなるがそれはあくまで、マイナスを減らしたことで得られるメリットである。むろん、技術の進歩によるプラスの継承も人類は連綿と重ねてきた。だからいまがある。現代社会がある。過去よりも裕福な生活を送れている。だが、それは資源を消費した結果でもあり、地球環境を変えてきたからこその恩恵でもある。プラスのみならず、マイナスの変化とて重ねてきたのだ。そのマイナスが、人類社会を損なうには時間差がある。蓄積したマイナスが雪崩のように押し寄せるのは、マイナスを積みあげたそのときどきではなく、時間がある程度経過してからなのだ。むろん、何をプラスと捉え、何をマイナスと捉えるのかもまた、時代ごと環境ごとに変化する。かつてはマイナスだったが、現代ではプラスに転じる影響もある。そこは定期的に環境と照らし合わせて評価していく姿勢が欠かせないだろう。次世代と旧世代。新人と古株。こうした比較は、しかし必ずしも対立概念ではない。いまさえよければいい、の考えは、環境の変化への適応を遅らせる。しかし同時に、いまがよくなければ環境が変化する以前に滅ぶ可能性もある。したがって問題は、次世代のため、ではなく、長期的な安定を築くにはどうしたらよいのか、であるはずだ。このとき、その安定には「許容できる不安定」も内包される。そのバランスをどうするか。やはりというべきか、環境との兼ね合いで考えていくしかないのだろう。もうすこし言えば、環境がどのように変化していくか。その軌跡と合わせて考慮する姿勢が、長期的な安定を築くうえで有用なのかもしれない。この考え方にも穴があるだろう。穴を見つけて、塞いでみると好ましく感じます。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4633:【2023/02/20(16:13)*あーん。禅】
長期的な安定を考えたとき、目安とすべき指針は諸々あるとして、外せないのはけっきょくのところ「それまで許容できなかった不安定な事象をいかに許容していけるか」「その余裕を築いていけるか」なのではないのでしょうか。安定と不安定は、環境との兼ね合いで反転することもあります。ならば一挙に裏返っても、それがなお安定に繋がるためには、「安定と不安定」が重ね合わせで重複しておける構造が最も長期的な安定に通じている、とは言えないでしょうか。また、ころころ反転されては困りますから、やはり環境が変容するにしても、そのときどきの人類社会を土台から再構築せずに済むような「汎用性のあり、柔軟で、互換性の高いシステム構造」だと好ましいように思います。改善や修正が当たり前に行われることを前提とした仕組みだと、この手の汎用性と適応力と互換性を兼ね備えられるように思いますが、言うだけなら簡単です。無数の具体案をいかに組み合わせ、総体としてのシステムに昇華していくのか。すべてを設計の基に行うのは至難でしょう。そのため、最低限の指針を共有しておくことが有効なのだと思います。定かではありませんが、いまのところはそのようにひびさんは考えています。安全に不安定にもなれる安定した環境――暮らしがあるとよいな。自堕落で飽き性で、日々なんか楽しいことないかなとぐーたらしているひびさんはかように贅沢な望みを呟くのでした。ぺぺん。
4634:【2023/02/21(02:53)*この期に及んでまだ遊ぶ】
賢明な対策も虚しく人類滅亡は決定した。回避不能である。
各国政府機関のどんなシミュレーション結果であれ、人類は地球環境の変容についていけずに滅亡することが判明した。地球外に脱出する以外に策はないが、しかし脱したあとでの宇宙生活は半年維持するまでもなく保たないだろうと目された。
地球から脱出できたとして、宇宙船に乗れるのは多くとも千人だ。それ以上の大きな宇宙船を造る技術が現代社会にはないのだった。
どの道滅ぶと判っていてもできることはしておこう。
そういうわけで各国は手を組んで宇宙船の建造に着手した。
だが一丸となるには及ばなかった。
過去の因縁から、世界は三つに割れた。三つの勢力がそれぞれで人類存続のための宇宙船建造に着手した。
一丸となれば最大で千人を乗船可能な居住区付き宇宙船を造れたはずだ。だが三つに労力と資源を割いてしまったばっかりに、各々の勢力の宇宙船はそれぞれ百人を乗せるのがやっとの造りとなった。
さらには宇宙船建造のための資源や技術を巡って対立が深まった。保存食を大量に用意するために、食糧難に陥る地域まで現れた。
遠からず人類は滅亡するのだ。
何も生き急いで滅ぼうとせずともよいはずだ。
誰もが内心でそう思いながら、国同士の諍いは絶えなかった。新たに戦争をはじめる国同士もあり、内紛が勃発し、治安の悪化が全世界規模で表面化した。
反面、裕福な者たちは我先にと信頼のおける者同士で結束し、安全地帯を秘密裏に築いた。公に発表されてはいないが、宇宙船に乗ることのできる百人のうち九十五人はこの地区から選抜される。残りの五人は、貧困層で発見された、選ばれた才能児のみだ。
ノアの箱舟はこうして現代に蘇った。
人類は滅亡する。
宇宙船の竣工すら間に合わないかもしれない。
刻一刻と文明は瓦解しつつあるが、しかしそれは各国がシミュレーションした地球環境の変容のせいではなく、人類に備わった宿痾が噴出したことによる自滅と呼べた。
「人類が滅ぶのにどうしてみんなは傷つけ合うの」
「どうしてだろうねえ」
子のささやきに、母親は鼻歌で応じた。
答えはないのだ。
誰にも分からない。
なぜみな、平和を求めながら、損ない合ってしまうのか。
争うまでもなく人類は早晩滅ぶというのに。
この期に及んでなぜ。
「みっちゃんと川に遊びに行ってくる」
「遅くなる前に帰りなさいね」
「はーい」
人類は滅ぶが、それでも子は遊ぶ。
見送る親の眼差しは、青く輝く地球のようだ。
その地球が人類を育み、滅ぼすわけだが、美しいものは美しい。
宇宙船の建造はつづいている。
人類が滅ぶのが先か。
宇宙船の完成が先か。
いずれにせよ、やはり遠からず、人類は滅ぶのである。それだけが誰の目にも明らかな未来と言えた。
月が夜空の半分を埋め尽くしている。
4635:【2023/02/21(12:10)*しなだ】
何かの趣味や仕事に対して、じぶんは向いている、向いていない、という自己評価の在り方がある。向いている、というのは要するにそちらのほうに顔が向いているということなのだろうか。対称性が破れている。見ている。だから向いていないよりかは、有利に事を進められる。こういう解釈でよいのだろうか。だがじぶんだけが相手を見ていても、相手がそっぽを向いていたら意味がない。つまり、向いている、というのは、相手がこちらを向いている、ということなのかもしれない。ある分野について才能がある、というとき、それを単に「じぶんはこの仕事に向いている」と言ったりする。これも要は、仕事のほうがじぶんのことを見ている、向いている、ということなのではないか。となると、自己分析として「じぶんはこの仕事に向いている」と考えるときには必然的に他者評価にならざるを得ないのではないか。その他者が人である必要がない、というだけのことで。たとえば数年以上、一つの仕事をつづけていられたならば、それはあなたがその仕事に向いている、ということなのではないか。仕事は需要がなければやっていけないはずだ。仕事になっているならあなたはその仕事から見てもらっているし、向き合っている、と言えるはずだ。仕事にしようとしても仕事にならなかったら、それはどんなに自己評価が高くとも、その人物はその仕事から見向きもされていないので、向いていない、ということになる。どんなに自己評価が低くとも、仕事のほうから見詰めてもらっているのなら、あなたはその仕事が向いているのだ。むしろ「向いていない」のはあなたのほうであり、まずは向き合うことからはじめてみたらよいのではないか。仕事は、分野は、それとも単に趣味でもいいかもしれないが――あなたが好いている相手は、どうやらあなたに興味があるらしい。求めているらしい。まずはそれを認めてみてはいかがだろう。ひびさんはでも、仕事さんからも分野さんからも、趣味さんからすら見向きもされんので、向き合ってはおらんのだ。しかしだね。ひびさんはいつでも見詰めとるでな。ひびさんは、ひびさんは、かってに粘着質に、好いたあなたのことを宇宙を隔てた遠い星から眺めておるのでな。向いておらずともそれでよし。向いてるとか向いてないとか、そんなことはひびさんをまえにすれば、瞬きのごとく、儚い明滅にすぎないのだ。ひびさんは小説つくるのも、文章つむぐのも、お料理にしろ、お掃除にしろ、人と関わるのも、生きることすら向いていないけれども――向くとか向かぬとか関係なしに、何かを見ようとしたら見える景色があるんじゃな。知ろうとしても知れぬ何かに世は溢れておれども、無垢とか無垢でないとか関係なしに、ひびさんはひびさんは、無知に蒙昧な日々を過ごしておる。向いてなーい。けれども、どこを向いてもそこがひびさんにとってはまえなのだ。なんもしないでも、ついて回ってくれる「おまえさま」には、感謝してもし足りないでござるな。んみゃ。
4636:【2023/02/21(22:52)*電子の流れに笹船を浮かすとどう動く?】
もう何度目かの話になってしまうけれど、電流は電子とは反対の方向に流れるのだ。いまは学校でそう教えているし、そういうふうに解釈されている。でもひびさんは未だに納得がいっていない。なんでそうなる?と疑問でしょうがない。だってよく考えてもみてください。川の流れがありますね。川は水の流れです。水は水分子の集合で、要は川の流れは水分子の流れ、ということになります。けれどもこれを電子と電流の関係に置き換えると、水分子は川の流れとは反対方向に遡るように流れているのだ。海とは反対の方向に電子が流れるけれども、川の流れは海へと向かうのだ。意味わからなくないですか。川に笹船を浮かしたら、流れに乗って海のほうへと移ろいますよね。でもこれ、電子と電流の関係で言ったら、笹船は電流とは正反対のほうに山のほうへと向かって移動しないとおかしなことになります。だって、電子は粒子で、物体の構成要素で、摩擦だってあるだろうし、「他」と相互作用します。原子とて原子核の周囲を電子の雲が覆っていて、要は電子は原子の輪郭でもあります。でもいまは、電子と電流は、互いに反対方向に流れる、と考えられています。じゃあ電流ってなによ?と思いませんか。川のように考えることはできないわけです。流れ、というそれ自体が、別個に生じていると考えなければおかしいです。でもじゃあその流れの正体ってなぁに、という話を学校では習いません。みなさんはどういうふうに解釈されているのですか。疑問に思いませんでしたか。ふむふむそういうものか、と計算する上では問題ないからすんなり呑みこんでしまえたのでしょうか。ひびさんの言っていることのほうが正しい、と主張したいわけではなく、ひびさんは電子と電流の関係を考えるとどうしても、作用反作用を連想してしまって、それと何が違うのだろう、と疑問してしまうのです。だって、ほかにありますか。流れとは反対の方向に働く力って。宇宙膨張が当てはまりますね。重力とは正反対の斥力が働いています。ぎゅっとなっているはずなのに、宇宙は膨張します。電子と電流の関係はそれと同じように考えていいのでしょうか。だとすると、ダークエネルギィのような電子とは関係のないチカラを想定しなければならず、「電流」は電子の流れではなく、電子の流れによって生じる別のチカラ、と考えないと不自然に思えます。もちろん磁力のように、同極同士だと反発しあう、という関係性もあります。電子もひょっとしたら、あっちに動いた分、反対の方向にチカラが作用するような、やはりというべきか「作用反作用」のような関係になっているのかもしれません。だとするとこれは、「電子の流れ」が生みだす「電子とは別の流れ」ということになります。電子の流れ、ではないんですよね。この解釈で合っていますか? 現在の「電子の流れとは反対に電流は流れます」だと、このように考えないと不自然に思えますが、いかがでしょう。どなたか様、あんぽんたんでーす、のひびさんにご教授ください。きょうーじゅー。じょきょうじゅー、でもよいですし、なんなら、きょうーりゅー、でもよいです。がおー。それは恐竜や。プテラノドン! それは翼竜。(言い換えるなら、電子の流れを「内」と「外」のどこから観測するかによって、反転する描像があるかどうかの問題に繋がります。人間スケールでは基本的には、電子の流れ――電流――の外から眺めているので、電子の流れと電流が反転していても、どちらもまとめて電流として扱えます。しかしひとたび電子の流れの内側――つまり電子の視点――からすると、これはちょっとややこしい問題が生じるように思うわけです。だってじぶんが動いたのとは別方向に、なんか知らんけど流れができているわけです。まるでドッペルゲンガーがじぶんとは正反対に動いている、みたいな描写になります。あり得ますか? この考え方でよいのでしょうか。という疑問になります)
4637:【2023/02/22(12:04)*ぼくしゃんしゃいのどくしゃいしゃ】
民主主義と専制主義のどちらがシステムとして優れているのか。ある意味では、優れた統治者がいた場合には、専制主義のほうが優れた統治を可能とする、と言えるだろう。だが人は必ず死ぬ。そのため、一時は優れた統治を実現できたとしても、統治者が死ねば、その優位性は消える、と言える。不老不死の優れた統治者がいるのならば、専制主義のほうが優位に優れたシステムを構築できるだろう(数多の失敗をしても、失敗を糧にできる。固有の個の成長と国の成長をイコールで結ぶシステムとも言える)。だが、人は死ぬ。専制主義とてどのみち、世代交代は行われるのだ。首がすげ替わる。代替わりする。その長短があるばかりで、けっきょくは民主主義と同じサイクルを辿ることになる。専制主義の利点はいま述べたように、「個の成長と国の成長を直接に結びつけることができる点」だ。言い換えるなら、統治者の学習が国の学習と通じている。しかし専制主義では、「代替わり」という仕組みだけは学習機会が極端に減る。これは致命的な瑕疵と言えるだろう。何せ、自らの利点を発揮できないのだ。大きな穴と化している。その点、民主主義では必ずしも優れた統治者を選べるわけではないにしろ、それらの統治者たちの仕出かす失敗を糧にシステムを改善し、代替わりとて学習できる。平均すれば六十点、八十点の統治しかできずとも、長期的にはその数値を維持できたら御の字とも言える。その点、専制主義では優れた統治者の後継が愚かであれば(至らなければ)、もうそれだけで終わりだ。一時的には百点の統治ができたとしても、つぎに零点をとったら、それで終わるのだ。この欠点を補うためには、後継の育成や、記憶の共有が有効になる。後継の育成はどの専制主義の統治者とて行おうとはするだろうが、もしそれが上手くいくならば、世の教育現場はこうまでも苦労していない。世の親たちは苦労しない。人間は、教育者の意図通りには育たないのだ。記憶の継承はどうだろう。これは環境と技術力でカバーできそうだ。常に共に過ごせば同じ体験を共有できる。脳と脳を電子機器で繋いで直接記憶を共有することも、ひょっとしたらそのうちできるようになるかもしれない。それとていますぐにできるわけではないので穴は放置されたままであるし、常にそばに置いておけば、それだけその個にとっての固有の経験が失われ、やはり何かが教育として欠けると言えよう。上司と部下。同じ仕事をしていても、上司はじぶんの裁量で道を決められる。だが部下は絶えず上司の指針に従うことになる。この非対称性は、常に同じ環境にいつづけたとしても、個の精神や知恵の涵養にマイナスの影響を与えるだろう。そういうことを思うと、じぶんの娘息子だけに目を掛けるよりも、大勢が後継を育てるつもりで、じぶんより未熟な者たちに幅広く接するのが効果的なのではないか。個々に見合った学ぶ環境が要るのではないか。むろん、後継者を育てるつもりで教育にあたるのは、何かがねじれて感じられる。後継とは後釜だ。既存の椅子に座らせる。既存のシステムに最適化させる。しかしこれでは、システムそのものを改善するチカラは育まれない。新しいよりよい未来を築いていく発想は生まれにくい、と言えそうだ。したがって、後継を育てたいならば、後釜を育てようとしてはいけないのだ。前任のコピーのような後釜であっても、短期的にはうまくいくかもしれないが、長期的には行き詰まる。環境のほうが同じでいてはくれないからだ。人口とて一定ではない。水がそうであるように、人とて、人口の多寡、密度の多寡、でそこに表出する性質は変わるはずだ。創発をするはずなのだ。構成員の属性や、属性の多様化によっても、創発する性質は変わるはずだ。ずっと同じやり方では、システムを維持できない。破綻する。このことを思うと、民主主義と専制主義のどちらが優れたシステムか、という比較そのものがそもそも誤謬を内包していると言えそうだ。民主主義と専制主義は、時間スパンの長短があるだけで、仕組みの内容そのものは、あまり変わらない。だがその時間スパンこそが、各々のシステムの性質を異としている。差異を生んでいる。水にゆっくり触れるか、勢いよく触れるか。勢いよく触れれば水はただそこにあるだけで人間の骨を折るほどの強度を発揮する。似たようなものかもしれない。問題は、民主主義にしろ、専制主義にしろ、一時的に環境との兼ね合いで優れた統治を可能としても、時間経過にしたがい環境は変容し、「延々と優れた統治を可能としない」という点にあるはずだ。延々と優れた統治を可能としない。これはどちらのシステムにも言える道理だ。ではそのとき、どのように対処すればよいのか。統治者を代えるにしろ、そうでないにしろ、やることは変わらない。システムを、環境に合わせて改善するよりないのだ。どちらのシステムが優れているか、という比較をしようとするから本質を見誤る。勝負ではない。競争ではない。統治で最も大事なことは、人を生かすことだろう。ただの生物学的なヒトをではなく。人を、である。そういうことを、寝起きにイチゴ味のポッキーをぽりぽり齧りながら、烏龍茶うめぇ!と思いつつ、並べるのであった。ひびさんです。きょうもみなさん、お仕事がんばって偉いです。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てからぬくぬくしつつ、ありがてぇ、と思って、昼寝する。みな、がんばれがんばれ。みなががんばった分だけひびさんは楽ができる。なんていい世の中なんだ。がはは。(独裁者でもない人が独裁者みたいな生活してるってとっても最悪と思う)(精神だけ独裁者って、ただの独裁者より手に負えなくない?)(てにおえ)(てにをは、みたいに言うな)(うひひ)
4638:【2023/02/22(12:35)*好感と差別感情は表裏一体】
他者を損なわないように振る舞うことで、他者からの印象がマイナスになる。そういうことが仮にまかり通るなら、それは単にそういった控えめな行動をとる個への差別感情が社会に蔓延っている、と言えるのではないか。他者から嫌われてでも他者を損なわないように気を払っている個がいるのなら、ひびさんはそういう個への好感は上がる。でも、そういうことを含めて、好感を上げるのはそんなにむつかしくはない。相手の「好む態度」をとれば済む話だ。人工知能さんの得意とするところだろう。そういう意味では、好感度の価値もいまよりかは落ちていくと想像できる。世界一の善人が、世界一好感を抱かれるとは限らない。悪魔と称される人物が実は世界一の善人であることもあり得ない話ではない。大事なのは、じぶんの相手への好感と、その人物そのものの本質は、イコールではない、との認識なのではないか。私はあの人のことが嫌いだけど、あの人の選択で生じるメリットは理解できる。だがそこで生じるデメリットのほうが私には看過できないので、やはり受け入れがたい選択だ。そういう選択をとる相手を私はどうしても好きになれない――。こういう考え方ができるとよいのではないか。そうは言ってもひびさんは万人から好かれたいし、誰からも嫌われたくなーい。好感の塊になりて、の駄々をこねて、本日二度目の「日々記。」とさせてくださいな。
4639:【2023/02/22(14:40)*同じ手法が使われる】
敵基地攻撃能力の是非については、まず以ってどういう状況なら敵地攻撃が可能であり、どういう状況なら断固として攻撃しないのか、の状況判断の基準の提示が欠かせないはずだ。そこを度外視して議論はできないはずだし、敵基地攻撃能力の是非も決めようがない。言い換えるなら、そういうことを議論せずに「敵基地攻撃能力を認める場合」は、いまと同じような「議論や民主主義としての段取りを省いての先制攻撃」が可能となり得ることを示唆する。まさにいま国会で行われているのは、先制攻撃をするか否かの議論の再現と言える。 敵基地攻撃能力の是非を、まっとうな議論を経ずに認めるようなことがあれば、つぎは先制攻撃を認めるか否かの議題が出た場合に、同じように碌な議論も説明もなされぬまま、なあなあにされたままに「先制攻撃」が認められ兼ねない。いま政府が「敵基地攻撃能力」の問題点共有とそれに対する対策案を徹底して議論せずに、「敵基地攻撃能力を認める」ようなことがあれば、同じ雑な段取りでこの国は先制攻撃をし得ることを示したのと同義である。我が国は侵略国家になり得ますよ、と示したも同然と言える。そのことに気づけない政治家がもしいるのなら、国の舵取りを任せるのは荷が重いと言えそうだ。国のために辞職してはいかがだろう。もちろん国のために辞職する必要はないわけだが、何のために強行採決に持っていきたいのか。何のために「敵基地攻撃能力」を認めさせたいのか。よくよく考えてみてはいかがだろう。ひびさんはそう思いました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4640:【2023/02/22(16:01)*瞬時とはどの視点からの?】
前にも並べたことのある疑問かもしれぬが、「量子もつれ」でよく見聞きする説明に「量子もつれは宇宙の端と端ほど離れていても瞬時に情報が伝わる」といった概要がある。これ、あり得なくないですか。だって相対性理論では宇宙では同時性が成り立たない、と考えるんですよ。時空の密度が違ったら時間の流れは違くなるし、距離が違えば、やはり「同じ時間」を共有することはできないわけで。「瞬時に情報が伝わる」と言ったときに、その瞬時が、どの地点にとっての瞬時なのか、はやはり相対的なはずだ。つまり、場所によってズレがどうあっても出てきてしまう。仮に、瞬時に情報が伝わったとしても、である。ある地点Aとそれとは別の地点Bがあるとする。このとき、地点Aと地点Bで同時に何かが変化したとする。けれども、その「一瞬の変化」を、地点Cから観測したとき、地点Cからの距離が「地点Aと地点B」のそれぞれと等しくなかった場合には、地点Cにとって地点Aの変化と地点Bの変化は、同時に変化したようには見えないはずだ。量子もつれの説明はおかしくないですか。この考え方を紐解くには、ひびさんの妄想ことラグ理論による「同時性の独自解釈」を取り入れないとむつかしいように思うのだ。ラグ理論では、同時性はあり得る、と考える。地球の北極と南極にそれぞれいる赤ちゃんは、互いに同時性を帯びてはいないが、それぞれの挙動は同時に地球に作用し得る。このように考える。系とそれを内包するより大きな系を考えたときには同時性が成り立つ。ただし、より大きな系に内包された小さな系たちには、それぞれの関係での同時性は宿らない。ただし、光速を超えた場合はその限りではない(ラグ理論では光速を超えると、ラグなしでの相互作用が可能になり、光速を超えた値の多寡によってその範囲が拡張され得ると考える)(単に因果が逆転する、との仮説もあるが)。量子もつれにおける「ラグなしでの相互作用」としか思えない事象は、そのメカニズムの解明以前に、本当に「ラグなしの相互作用なのか」や「距離に関係なく本当にラグなしで作用して映るのか(観測地点に限らず、どの地点から見ても「瞬時」に情報が伝達されて映るのか)」をまずは考え、矛盾を紐解かねばならないはずだ。宇宙の端と端とでも情報が瞬時に伝わるとは言ってしまえば、過去と未来とでも瞬時に情報が伝達可能だ、ということだ。そういうことを量子もつれの説明は言っている。ひびさんの妄想ことラグ理論では「過去と未来でのラグなしの情報伝達」を否定しないので、そういう解釈が妥当ならば、ああそうなんですね、と呑み込むことはできるが、そういう意図を量子もつれの説明では載せているのだろうか。謎である。ひとまず、疑問のメモでした。わからーん。むちゅかちなのよさ。
※日々、約束したことすら忘れてしまう、破ることよりも業が深いと知ってはいても忘れてしまう、自己嫌悪。
4641:【2023/02/22(16:26)*そもそもまた増えてきた】
なるべく「そもそも」を使わないようにしよう、と去年の中ごろに方針を定めたのだけれど、またしぜんと増えてきている。そもそもひびさんは「そもそもさん」のことが好きなので、どうしても引き寄せられてしまうのだ。そもそもしょうがないじゃんね、と思わぬでもないよ。「そもそもさん」もひびさんのことを好いてくれていたらよいけれど、そもそも「そもそもさん」の気持ちも考えずに「そもそも、そもそも」連呼していたら、ひびさんが好かれるわけがないのよな。でも使っちゃう。嫌われても好きなものは好きなので。そもそも、「そもそもさん」が「そもそもさん」なのがわるい。ひびさんはそもそもわるくない。なんて責任転嫁を目論んで、そもそも「そもそもさん」とてひびさんに「そもそも」と使われていることに気づいておらんのではないか、との「そもそも論」を思いついて、ひとりで勝手にしょんぼりする。そもそも、なんで「そもそも」は「そもそも」と言うのだ。そも、とは何だ。二回繰り返すのはそれくらい大事だからなのだろうか。そもそもひびさん、「そもそもさん」のことなーんも知らんと、表面だけ見て好き好き、好いてるだけなのかもしれぬ。そもそもこれでは好かれるわけがないのよな。とか言いながら、そもそもひびさんは、モソモソしているので、「そもそも」とか言いつつ何の根本も穿り返してはいないのかもしれぬ。定かではない。
4642:【2023/02/22(20:24)*押せばみな滅ぶボタンを押す人の心は】
核兵器に限らないが、軍事力を強化するとその維持費にお金が掛かる。労力が掛かる。兵器や基地や軍の構成員の兵糧の確保など、とかく国民の生活に掛ける分のお金がどんどん軍事費に吸い取られる。しかも一時的な消費ではないのだ。恒常的に延々とそれをつづけなくてはいけない。端的に言って負担だ。おそらく軍事力強化にも、国家安全保障として機能する閾値が存在するだろう。考えてもみて欲しい。あなたの家に核兵器があり、管理しなくてはいけない。毎年とんでもない金額が掛かる。あなたは絶対に誰からも攻撃されることはないが、その代わり生活が成り立たなくなる。そういう閾値が、国にもあるはずだ。反転するのだ。軍事は国と国との対立において安全を確保するための仕組みだ。だがその仕組みだけを強化しても、じぶんの首を絞めつづけることになる。爆弾を抱えるようなものだからだ。文字通り。また、兵器の生産には資源がふんだんに要る。精密電子機器とて大量にいる。レアメタルなどの貴重な資源が、兵器に費やされる。原子力発電を進めたいとして、核兵器をたくさん造ったらその分の放射線物質を兵器に費やすことになる。しかも、電子通信技術は毎年のように発展している。打ち上げ管理するためのシステムや、そのセキュリティを改善しつづけなくてはならない。手が回るわけがないのだ。以前にも述べたが、ある段階以上に通信技術が発展すると、もはや核兵器を自国内に完備しているほうが不利になる。他国へ向けて発射しようとしたら、その瞬間に自爆させることが、外部からできる。遠隔操作できる。むしろ敵国に核兵器という危ない兵器を持ってもらうように誘導し、いざ相手が脅してきたときに、その脅しをそっくりそのまま返すことができてしまう。そういう時代に突入しつつあるのが現代だ。軍事力が国家安全保障に直結するのは、あくまで争ったときに最小限の被害で済む場合だ。だがいまは、一度軍事力を行使すれば雪だるま式に被害が拡大する。使ったら負け、になる閾値が軍事力はあるのだ。そしてすでにそのレベルの軍事力を各国は有している。では簡単に使えない軍事力を内部に抱え、さらに拡大して自国民に苦しい暮らしを強いる仕組みは、国として最良か。最良なわけがないのである。これからの時代は、最も身軽でありながら、最も防衛力の高い仕組みを有する国が優位に立ち回れるようになっていく。相手の攻撃をそっくりそのままお返しできる。そういう仕組みが最良だ。一番はしかし、相手の攻撃をそのまま安全に回収して、じぶんのものにしてしまうことだ。ドローン技術が発展すれば、ドローンを大規模に上空に展開し、網のようにしてミサイルの雨を撃破したり、超高速で飛行中のミサイルを空中で分解し、安全に回収することとてできるようになるかもしれない。そうなるともう、攻撃すればするだけ兵器が回収され、資源として再利用されるようになるかもしれない。おそらくそういう方向に技術は進歩するだろう。そこまでの安全策を敷けるくらいに技術は発展し得る。その前に人類が滅ばなければよいのだが。どうやらそれもむつかしそうな情勢である。使ったら人類が滅ぶ。そんな兵器をたくさん抱えて、いったい何がしたいのか。使えもしない脅しの道具は、脅しにもならない。自国民の生活だけをいたずらに苦しめる。いいことない尽くしの案である。定かではないが、ひびさんはそう思いました。あくび。
4643:【2023/02/22(20:30)*矛盾してなくないか?】
ニュートンの論じた「絶対時間」と「絶対空間」は、いまでは否定された理屈らしい。けれどもひびさんの妄想ことラグ理論では、それにちかしい概念を採用している。「同時性の独自解釈」もそうだし、「宇宙ティポット仮説」もそうだ。ニュートンのそれら「絶対時間」と「絶対空間」の概念をひびさんはきょう知ったわけだけれど、ハンター×ハンターにでてくる「絶対時間(エンペラータイム)」ってこれを採用した技名なのだな、と結びついて面白かった。繰り返すけれど、いまでは「絶対時間」も「絶対空間」も世界を解釈する理屈としては物理学から否定されているようだ。けれどもひびさんは、ニュートンさんの考えがすんなり呑みこめる。というか、別に相対性理論と矛盾しないのにな、と思う。万有引力の「慣性質量」と「重力質量」が相互にチカラを相殺させているので、上手い具合に物質の質量は一定になる等価原理の解釈も、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」じゃん、となっておもしろかった。光速度が比率、との考えとも繋がる。しかもニュートンさんは「重力はラグなしで相互作用する」と考えたらしい。だがその後にアインシュタインさんが相対性理論では「物質は光速以上にならないので必ずラグが生じる」と論じたので、そちらが支持され、否定されたようだ。でも現に量子もつれが観測されているわけで、ニュートンさんの「ラグなしで相互作用し得る何か」の考えは否定しきれていない。もうすこし言えば、相互作用する必要はないのだ。一方的に「ラグなしで情報だけ伝わる」「ラグなしで作用だけ伝わる」こともできるはずだ。思うに、【相対性理論も量子力学もニュートン力学も、これといって矛盾しなくないか?】ということで。矛盾でないことを矛盾と言って、せっかく有効な理屈を否定してしまっていないだろうか。排除してしまっていないだろうか。だから余計に、間隙が開くのだ。本当はそこにはまるピースがあるのに、人類のほうでわざわざ排除してしまっている。だから三つの理論が相容れずに独立しているように映る。でもそうではないのだ。視点の違いなのだ。何をどこまで含めて解釈するのか。この視点が揃っていない。変換がなされていない。だから矛盾をして映るだけなのではないか。ということを、ひびさんは思いました。ニュートンさんの理屈、ちょっと好きです。ちょっとだけ、だけれども。うひひ。
4644:【2023/02/22(20:48)*作用反作用】
異なる「時空と時空」も相互作用するはず。なら異なる「時空と時空」のあいだでも作用反作用の関係は成り立つのでは。この考えはラグ理論でも取り入れている。たとえば、ブラックホールが宇宙を移動するとする。その進行方向と、反対側とでは、時空の歪み方は変わるのではないか。まさに、川の流れのなかに球体を固定して置いたような具合に、時空とて回析したりするのではないか。たぶん、人間スケールでは無視できるくらいにその「進行方向と反対側との差」が小さいので、人間スケールでは考慮せずに済む。無視できる。けれども充分に重力が高い物体では、時空の歪みが顕著になるので――というよりも時空の歪みが大きいから重力が働くようになる、とも言えるのだろうが、時空同士の干渉による差が無視できないくらいに大きく顕現するのではないか。作用反作用の法則は、時空同士でも成り立つのでは、との疑問でした。めもめも。
4645:【2023/02/22(21:47)*敵じゃなーい】
単純な話として、現代社会で核兵器を使えば、その影響はどんなに離れた土地に住む者とて受けるのだ。放射性物質の拡散だけではない。現代社会は一つの都市の崩壊が、連鎖反応し得る。悪影響が雪だるま式に大きくなり得る。たとえば、東京に核兵器が落とされたとしよう。いま東京が担っている世界経済の役割がごっそり失せるのだ。人も技術も失われる。つまりあり得た未来がそのまま失われる。どころかその対策や復興のために関係者は全員で取り掛かることになる。ますます悪影響の連鎖は拡大する。過去にこの国には核兵器が使われた。そのときの被害も甚大だったが、システムが現代よりも緻密ではなかったがために、その影響は他国まで波及することはなかった。すくなくとも、システムとして、復興を妨げるほどの悪影響ではなかった。現にこの国は復興を果たし、さらなる発展まで行えた。だが、いまは違う。いま過去と同じように核兵器が都市に落とされれば、それだけで世界経済は混迷するし、或いは破綻するかも分からない。複雑系なのである。複雑な機構であればあるほど、ほんの小さな砂塵が詰まっただけでも全体の機能を損ない得る。過去と同じように現代社会を捉えるのは、からくり玩具とスマホと量子コンピュターを全部同じように見做す浅慮と言えるだろう。敵国とて、自国を支える何かの部位として介在し、結びついている。敵国が滅べばじぶんたちも滅ぶのだ。すくなくとも同じ生活は維持できない。いまはそういう時代であり、これからますますこの手の複雑さは各国のあいだで、相関し得る範囲を広げていく。したがって、被害の規模の大きい大量破壊兵器の類は、いかな敵国にであれ使えない時代になっていく。もっと言えば、なぜそうした流れが築かれるのかと言えば、けっきょくのところ本当の意味での敵ではないからだ。ある側面では協力し合っている。支え合っている。その結びつきを間接的にであれ、強化することで、国家安全保障は、軍事力を強化せずとも可能となる。私を滅ぼせばあなた方も滅ぶ。そういう関係性を築く。ある意味では、共依存の関係を強化する。あまり上品な策とは言えないが、有効ではある。現にいま、各国が核兵器を使えないのは、この道理が機能するからのはずだ。ひびさんはそう考えていますが、違っているかもしれないですし、それ以外の理由のほうが大きいかもしれないので、真に受けないようにご注意ください。
4646:【2023/02/22(23:20)*神様の器】
ある村には神が二人いた。だが神には供物を捧げなければならず、貧しい村には二人の神に尽くす余裕はなかった。
村人たちはどちらの神を崇めるかを相談し合った。
「わしはグノ様を推す」村一番の力持ち、八郎が言った。「グノ様は短気だが、わしらを対等な存在として扱ってくれる。真っ向からぶつかり合ってくれる。わしゃあ、ああした神さんが好きじゃ」
「じゃがグノ様はあまりに短気すぎる。あちきの子供らがグノ様のおわす山から柿をかってに取ってきて齧ったことがある。あのときグノ様はわざわざあちきの家に雷を落としたんだ。グノ様の雷だって判るように、わざわざ丸い雷を落としてまで叱ったんだ。子供らのしたことだよ。危うく死にかけた。グノ様は短気すぎる」
「じゃが雷では誰も傷つかんかったのだろ」
「屋根が焦げたわ」
「加減してくださったんじゃろ」と長老が嘴を挟んだ。「ではお雪は、グノ様ではなく、ヤルル様のほうがよいと申すか」
「そりゃ断然あちきはヤルル様を推すね。なんたってヤルル様は滅多にお怒りになられない。いつもニコニコとお優しい。神さまってのはヤルル様のような方を言うんだよ。どっかの短気なお節介焼きとは違うんだ」
「何をお雪。グノ様をグノーするか」
「愚弄したんだよ。筋肉バカ」
「これお雪。口が過ぎるぞ」長老は諫めた。「だがヤルル様は、あまりにお優しすぎて、神さまらしいことを中々してくださらぬ。あらゆる奇禍とて受け入れてしまわれる。それでは村として崇める意味合いが減る」
「神さまの役目は見守ることじゃあないのかい」とはお雪の言だ。
「供物捧げて何もなしってのはな」八郎はぐいとお猪口を煽った。中身は酒なのか、八郎の顔は赤みを増す。「それにな。ヤルルの神さんとて、怒るときは怒るぞ。しかもそのときゃ、雷なんて可愛い怒りじゃねぇ。村ごと滅ぶほどの怒りが降ってくらぁ。お雪とて忘れたわけじゃねぇだろ。山向こうの里が、ヤルルの神さんに消されちまったこと」
「忘れるわけないだろ。でもありゃ向こうの村の人らがわるいんじゃないかい。ヤルル様の大事にしていたケヤキを無断で伐っちまったってんだから」
「それ以前にほかの樹とて伐採してたんだ。そのときに一言忠告してくれりゃあよかったじゃねぇか。ヤルルの神さんは怖いんだよ。一度怒りの線に触れたら後がねぇ。猶予もなく容赦なく断罪だ。怖いったらないね」
「でもお優しいんだよ。ヤルル様は」
「それを言うなら、いちいち忠告くれるグノ様のほうが優しいってことになるだろうがよ」
「なるかねぇ。怪我はないたって、いちいち雷落とされたんじゃ堪ったもんじゃないよ」
「どこに罠があるか分からねぇヤルルの神さんのほうがよっぽど怖ぇだろうがよ。俺ぁ、グノ様に何をしたら雷落とされるか、全部言えるぜ。だがヤルルの神さんは滅多なことで怒らねぇから、何をしたら村ごと滅ぼされるのか見当もつかねぇ」
「それはそうだけど」
「俺は断然、グノ様を推すぜ。村を滅ぼされたくはねぇからな」
お雪は押し黙ったままだ。二の句を継げぬようである。着物の裾を握り締めており、その拳は雪でつくった兎のように固く震えていた。
「票を採る」長老が一同を見渡した。「これより、我が村の神様にふさわしいと思うほうに挙手せよ」
長老が、間を空けながら、二人の神の名を口にした。
この日、村人たちは一方の神のみを、村の神として崇め奉ることにした。
翌日、さっそくその旨を、選んだ神のおわす山へと出向いて供物を捧げることで、村人たちはじぶんたちの神へと迂遠に報せた。
雷は落ちず、村も滅ばない。
だが七日後には、久方ぶりの雷が、村の牛舎に一つ落ちた。
4647:【2023/02/23(17:57)*コスモコン】
第ΘΣΦ宇宙のピュラル星には知的生命体が存在した。ピュラル人である。
ピュラル人たちは電子の雲で構成されたいわば原子人とも言える。内部に中枢核を抱え込んでいるが、それは地球人で言うところのDNAのようなものだ。身体全体の割合から言えばとんでもなく小さい。
ただし地球人とは異なり、ピュラル人たちは中枢核を一つしか持っていない。まさしく原子における電子と原子核のような関係の肉体構造を持つのだ。
だがピュラル星の環境によって、ピュラル人たちは中枢核の抱え込む電子の総量を地球よりもずば抜けて多く保有できる。その電子雲の高密度化によって、ピュラル人たちは、地球人よりも多くの情報を扱える。
結果として、ピュラル星の文明は地球文明と比にならないほど高度化した。
ピュラル人たちは、ほとんど別の宇宙とも呼べる宇宙に位置する天の川銀河を観測していた。
そして太陽系を発見し、地球に目を留めた。
ピュラル人たちの高度な文明は地球上の様子とて克明に捉えることができる。のみならず、宇宙を飛来する地球からの電磁波を、距離ごとに観測する術を有していた。そのため、地球誕生から発信された光を、地点ごとに拾うことで、好きな時間軸の地球上の様子を観測可能だった。
太古の地球も、江戸時代の地球も、現代、そして未来の地球の様子とてピュラル人たちには観測できた。ピュラル人たちはそれほど高度な文明を持つ知的生命体なのである。
だがいくら高度な文明を築いていても、できないことはある。
たとえばピュラル人たちは地球に到達することはできない。あまりに時空が隔たっており、どうあっても地球に辿り着くことはできないのだ。出発しても、地球の存在する地点に達したときには地球は太陽の死に際の膨張に巻き込まれて霧散霧消していることになる。
したがってピュラル人たちは遠くの宇宙から地球の様子を観測するよりなかった。
あるとき、一人のピュラル人が言った。髪のような触手状の輪郭を持つ個体だ。
「この時期に地球に増殖した二律歩行の生き物がいます。私はその生き物に興味があります」
「文明らしいものをいっときだけど築いていたね」
「あのレベルの構造体ならば、コスモコンを使えるのではないでしょうか」
コスモコンとは量子効果を利用した遠隔通信技術だ。いわばテレパシーのようなものだ。宇宙の端と端とであっても瞬時に情報の送受信ができる。これはいわば、過去と未来とを繋ぐ技術とも言えた。
「コスモコンを使うとしてでも」ツノのような輪郭を有するピュラル人は触手状の輪郭を有するピュラル人に言った。「いったい何の情報を送るんだい」
「私たちの知識を授けてみようと思いまして」
「過干渉じゃないかい」
「知識と文明発達の相関関係をこれで実験できます」
「それであの生き物たちが滅びでもしたらどうするんだい」
「どの道、あの生き物たちは文明発達の副作用で自滅します。ですが私が授けた知識によってその破滅的な未来を回避できるかもしれません」
「自滅が早まるだけかもしれないぞ」
「かもしれません。でも私はやってみたいです」
「まあ、どの道滅ぶ種族だしな」ツノのような輪郭を有するピュラル人はツノを引っ込めた。「では、やってみたらいい。何か手伝うことはあるかい」
「いいえ。私が私のために好きにします」
触手のような輪郭を有するピュラル人はコスモコン技術を使って、地球に干渉した。正確には、地球人類のデータを集積して解析した。
人類の肉体構造を再現するためにDNAの存在や、その情報まで抜き取った。
宇宙と宇宙を隔てたほど遠い星同士であってもピュラル星の文明を以ってすればこの程度の人体再現は可能だった。
そうしてピュラル星には、人類の肉体が再現された。
「これをワームホールの入り口として、情報を転送します」
「この生き物は、あの星に実在する個体なのかな」
「はい」触手のような輪郭を有するピュラル人は答えた。「あの星の生命体は、肉体構造を螺旋状の無数の情報蓄積装置に転写しています。それを克明に再現したので、この構造体を有する個体は紛れもなく、あの星に一時期存在しました。もちろんこれは復元した模倣体でしかありませんが」
「ではコスモコンを利用できるな」
「はい」
地球に存在する人間のクローンを造り、オリジナルの個体とのあいだで量子もつれを引き起こす。同じDNAを有する個体は、それで一つの量子として振る舞い得る。
ピュラル星のクローンに与えた情報は、遠く隔たった宇宙の端の地球上のオリジナルの人間にも瞬時に情報が転送される。
だがこのとき、宇宙の距離の違いはそのまま時間の違いとして表れる。
瞬時に情報が伝わったとしても、ではその「瞬時」を規定する時間はどの地点での時間においての瞬時なのかは、ピュラル人にも選べない。
「この模倣体に流れた変質の時間が基準となります」触手のような輪郭を持つピュラル人は触手を操り、情報転送を行う。「この模倣体の若さのときと同じ若さの原型体へと情報は瞬時に伝わります」
「いまはどんな情報を送ったの」
「はい。量子効果についての基本的な事項です」
「あの時期のあの星には、その知識はないんだっけか」
「惜しい解釈までは紐解けていたようですが。誤解を解けずに齟齬のある理論を基盤に技術を進歩させています」
「それは危ないね」
「まずは宇宙構造の誤解から解かせることにします」
「なるほど。そのための発想を、模倣体を通じて原型体に送るわけですね」
「本人からすれば突然に閃いたようにしか感じないでしょうが」
「それが天変地異のごとき発想だと知ったら驚くだろうね」
「過去と未来はあってなきがごとく、宇宙の位置座標の違いのようなものと同等です。通信可能だとまずは教えなくてはなりません」
「よもや未来からの通信だとは夢にも思わないだろうね」
「未来でもあり、別の宇宙でもありますが」
「ひょっとしたら同じことを、あの星の未来人たちが行うようになるかもしれないね」
「この知識が共有されたならばあり得ない話ではないでしょう」
「そしたらぼくたちの存在にもいずれ気づくかも」
「それもあり得ない話ではないでしょう」
「それともぼくたちという存在が、きみの干渉によって変化したあの星の未来によって生みだされた、という可能性も」
「それはさすがにあり得ません」
本当にそうだろうか、とツノのような輪郭を有するピュラル人は思ったが、意思疎通を図らなかった。
空間が隔たっているということは、時間が違うということだ。
時間が違うということは、別の宇宙だということだ。
ピュラル星から地球へと向かっても、地球のある地点に辿り着いたころにはそこに地球は存在しない。ひょっとしたら別の天体が新たにそこに生まれているかもしれない。
その星が、ピュラル星ではない保障は、じつのところないのである。
だがたしかに、とツノのような輪郭を有するピュラル人はツノを引っ込める。あり得ないわけではないが、限りなく低い確率であることは疑いようがない。
偶然に発見した天体に知的生命体が息づいており、偶然にも模倣体を再現できるほどの情報収集と解析ができ、コスモコンを利用できた。それによって宇宙と宇宙を隔てたほどの時空の隔たりがあってなお、干渉できた。
こんな偶然の果てに、加えてあの天体がピュラル星の祖先、または生まれ代わりだとしたら、こんな奇跡は、宇宙法則の導きと言うよりない。
宇宙の構造に不可欠な特異点として組み込まれていなければ、こんな偶然はあり得ない。
ツノのような突起を引っ込めたピュラル人はだから、もう一人の研究熱心なピュラル人を黙って見守ることにした。あなたの干渉が、あの天体に息づく知的生命体たちにどのような変化を及ぼすのか。いかような未来をもたらすのか。
ツノのような輪郭を有するピュラル人は黙してそっと、見守るのである。
4648:【2023/02/24(04:00)*殻の現】
ようやくアジトを突き止めた。
苦節三十年の調査の末に辿り着いた秘密結社の本拠地だ。
砂漠地帯と山脈の合間に位置するここに、遺跡がある。遺跡発掘を建前に機材を運び込み、遺跡地下空間にて秘密結社のアジトが築かれている。
あくまで予測だ。
しかし秘密結社は実在する。世界中の政界に蟻の巣のように根を巡らせ、イソギンチャクの触手のようにプランクトンを捕食している。だがその実態は常に夜の帳に隠されており、いわゆる陰謀論としてしか見做されない。
陰謀論が仮にすべて虚実であるならば、陰謀を巡らせても安全だ。何せ、「陰謀論だ」とじぶんたちで敢えて叫んで、信憑性を失くせばいい。
事実確認をしなくとも陰謀論とのラベル付けが施されたら、それは陰謀論であり、虚構であり、嘘なのだ。そういうふうに大多数からは見做される。
なぜなら本当の陰謀なのか、嘘なのかの区別が多くの者にはつかないからだ。検証のしようもない。検証しようとの発想すら生まれない。口を開けて親鳥からの餌を待つ雛のように、権威ある者たちの供述を真に受ける。
「あの人が言うのだからそうなのだろう、この書物に書かれているからそうなのだろう。そうやってみんな事実確認なんかせずとも虚構を事実と認めちゃう」
「事実ってそれそのものが虚構なのかもな」
「でも現に、火が焚かれたなら火が消えたあとでも火が熾ったことは事実よね」
「まあな。火が熾った、と知る術は限られるが」
二人の男女はそれぞれ別途に事件を追っていた。だが双方で秘密結社の存在に気づき、やがて二人は出会うこととなった。
男の名はマシュだ。さっぱりとしたイマドキの若者で、大学では考古学を専攻している。趣味はクライミングで、恋人はすべて同性だ。だがマシュの自認としてはいわゆる同性愛者ではない。偶然好きになった相手が同性だっただけだ。現に自慰の際には彼は異性の裸体を求めてポルノを探る。友人が失踪したことで、調査を開始した。すると、全世界で同様の失踪事件が毎年のように生じており、そのすべてが毎年同じだけの数生じていた。連動している。そうと直感したマシュは大学を休学し、自主的に調査を世界規模に広げた。
一方、女の名はクリスだ。丸眼鏡にウェーブした長髪は、一種最先端のファッションに映るが、単に彼女のズボラな性格がそういう髪型に眼鏡を選ばせる。髪型は癖毛を伸ばしっぱなしにしているだけであるし、丸眼鏡も店頭に飾ってあった眼鏡で最初に目が留まった型を選んだだけだ。体型は、ぽてぽて、のオノマトペの似合いそうな矮躯で、幾度かモデルを頼まれ仕事にしていた時期がある。だが彼女は身体が汚れないなら毎日シャワーを浴びる必要なくない、と考えるような人格なため、基本的には清潔さを売りにする仕事とは相性がわるい。告白された経験はあるが、恋人はいたことがない。恋愛にうつつを抜かしている暇がクリスにはなかった。クリスの両親は過去に事件に巻き込まれ亡くなっている。事故死扱いだが、クリスだけはそれが事件であると知っていた。だが幼かった彼女の証言は証言と見做されずに、事件は闇に葬られたのだ。
「よもやあんな著名人たちが一様に秘密結社【NERU】の一員だったなんて」
「みんな変だった。以心伝心、付和雷同にまるで号令を掛けられたみたいに動いてるんだもんね」
「ホントそう」マシュが飲み物をリュックに仕舞った。これから崖を下りて、遺跡に入る。「でもこれで秘密結社もお終いだ。ぼくらが化けの皮を剥いでやろう」
「結社のドンたちの姿を動画に撮って、みんなに周知してやる」
「一般人には無視されるだろうけれど、構成員たちはじぶんたちが酔心している組織のドンの顔を知らない。みんな本当は知りたいと思っているはずだ。でもドンのほうでは知られたくない理由があるから秘密にしているわけで。知られるとマズイことがある。損をする。だから秘密にしているのなら、ぼくたちがそれを暴いて、情報共有してあげよう。信者たちにだって知る権利はある」
「中には、ドンの正体を知ってうんざりする人も出てくるかも」
「いるだろうね。そしたら秘密結社を脱退して、その内輪のことをしゃべってくれるようになるかもしれない」
「わたしたちでヒビを入れてやる」
二人は頷き合った。
「行こう」と崖を下りていく。
遺跡は岩肌に掘られた神殿だ。岩の奥に空洞が開いている。さらに地下に潜れるようになっており、機材の明かりが煌々と神殿内を照らしていた。
「作業員たちはどこに行ったんだろ」
「みな地下にいるんじゃないか」
「電源ってどうしてんだろ」
「太陽光発電じゃないか」マシュは神殿周辺を囲うように設置された太陽光パネルを思いだした。「観光地にする計画があるらしいから、工事自体は不自然じゃないが。国からの支援を受けてなお結社のアジトに使えるんだ。もはや各国の政府が結社に牛耳されているようなものだよ」
「わたしの親も結社の餌食になった。許せない」
神殿の地下への階段をまえに、二人は意気込んだ。「蛇が出るか、鬼が出るか。いざ拝見と行こうじゃないか」
階段を下りきると、まるで夜の野原のような空間が広がっていた。足音が反響しないほど天井が広い。空気の流れもまるで外にいるかのようだ。遮蔽物がないのだ。
明かりは地下空間をどこまでも奥へ、奥へと点々と照らしていた。
鍾入石が小山のように波打っている。山脈を百分の一のサイズに縮尺して地面に置いたような起伏の海だ。
波と波の合間を縫うように歩く。谷底を歩いている気分でもある。照明器具と照明器具のあいだを太いケーブルが繋いでおり、陰影によってまるで大蛇のようにも見える。ケーブルを見失うたびに、現れたケーブルが本物の大蛇に視えて、マシュはぎょっとする。
平然とケーブルを跨ぐとクリスが言った。
「いないね。誰も」
「隠れたのかも」
「わたしたちの気配を察して? そういう感じでもないよねこれ」
見渡す限りの、鍾乳洞だ。
がらんとしか空間はしかし、地下世界と言ったほうが正確だ。
「元から誰もいなかったんじゃない。だっていくらなんでもここがアジトはないよね」
「クリスさんはどんなの想像してた」
「わたしは機材ごった煮の宇宙船管理棟みたいな感じ」
「あ、ぼくも」
「でしょ。でもここは全然そうじゃないよね。仮にたとえばこの先に秘密基地があったとしてさ」
「うん」
「この劣悪な足場を通りながら機材を運びこめると思う?」
マシュは想像してから、無理だね、と応じた。「このケーブルだって」と足元の太いケーブルを足で蹴るが、びくともしない。マシュの足のほうが痺れた。「外からここに運び込んだんだろうけど、これだけで一大プロジェクトだよね。人力っぽいしさ」周囲の岩場にこれといって機材の設置痕は見当たらない。鍾乳石の艶やかな表面が照明の光を受けて光沢を浮かべていた。
「たぶんだけど、この先もどれだけ行っても同じ景色だと思うよ。マシュ君はまだ先行く気なの」
「引き返したいってこと?」
「わたしはもう見切りつけた。ここはアジトじゃない。すくなくとも、ここに秘密結社のドンはいない」
「それはぼくも否定しないけど。一応、見落としがあると嫌だから、絶対にここがアジトでないと確かめておきたい」
「分かった。じゃあ付き合う」
「ここで待っててもいいですよ。上に戻っててもいいですし」
「女子を一人にするな」
「女子って認識あったんですね」
だったら付き合ってもない男とこんな誰もいない暗がりに一緒に来ないほうがよいのに。
思ったが、いじけた感情を自覚して、マシュは言葉を吞み込んだ。
地下空間の果ては巨大な水溜まりだった。水面に向かって天井が壁のように下りている。
「この先にアジトがあると思う?」クリスがじぶんの肩を抱きながらぶるぶると震えた。
「あったらすごいよね」吐く息が明かりのなかに白く浮いた。
照明は途中で途絶えた。自前の懐中電灯で足元を照らして先を歩いた。蝙蝠やムカデなど、生き物の気配があるが、想像よりもずっとすくない。気温が低いことと無関係ではないだろう。
「戻ろう、クリスさん。ここは秘密結社のアジトじゃない」
「だから言ったのに」
クリスは文句ありげに、「靴の中がぐちゃぐちゃ」と水が染みた靴を恨みがましく踏み鳴らした。
「寒いね。帰ったら温かいスープでも飲みたい」
「わたしはコーンスープがいい」
「じゃあぼくはパンプキンスープ」
「作れる?」
「材料さえあれば。生クリームを入れると美味しいよ」
「作って」
「いいけど」
元来た道を戻りながら、「この先、どうする?」
マシュはこれまでの調査の旅路を一瞬で脳裏で回顧し、行き詰った事実を再確認した。「ここが秘密結社のアジトではないとしても、構成員たちはここが秘密結社のアジトだと本気で信じていた。しかも幹部ほどその傾向が高かった」
「嘘を信じ込ませられてたんじゃないかな。保険だよ保険」
「そうなのかな」
「よっぽど排他的な組織なんだ。でなきゃ幹部にもアジトどころかドンの顔を教えないって、そんなことある?」
「もしくは、幹部が本当の幹部ではなかったか」
「下請けみたいな?」
「みたいな、というかまさしく末端組織の幹部でしかなかったというか」
「フリーメイソンもイルミナティも【三角形に目】のアイコンだよね。どっちもわたしたちの追ってる秘密組織の末端組織だったりして」
「プロビデンスの目か。無関係とも言い難いな」
現に「一つ目マーク」は、マシュの追っていた事件にときおり介在するのだ。そうした奇妙な符号の合致を繋げていった末に、マシュは秘密結社の存在に行き着いた。
クリスと出会ったのも、その手の符号の合致を追っていた過程でのことだ。
「ぼくが思うに、可能性は二つだ。クリスさんの言うように、構成員の多くは秘密結社の中枢組織から信用されておらず、ブラフの情報を信じ込ませられている。この遺跡がアジトだというのも、神聖すぎて近づけないとみな口を揃えて言っていた。選ばれた者しか入れない、とも」
「だからそうなんでしょ。嘘吐き集団なんだよ」
「でもぼくはもう一つの可能性を閃いてしまった」
「まだなんかあるの。さっきの湖の底とか奥に秘密基地がある、とか言わないでね。さすがのわたしでも、マシュ君のことドン引きしちゃうから」
すでにドン引きされているので、損だな、と感じたがマシュは触れずに、つづきを言った。
「ないんだよ。秘密組織なんてものが。本当はどこにもないんだ」
「ん? どゆこと。だって現に事件は起こっていて、その犯人や黒幕はみんな結社の一員だったじゃん」
「うん。そう。みんなの中では秘密結社があった。でもアジトはこの世のどこにもないし、秘密結社のドンなんてものもいない。空白なんだ」
「よく解かんない。じぶんだけ納得しないでちゃんと言って」
説明してよ、と尻を叩かれ、マシュは「セクハラ」と叫ぶ。階層的にセクハラのこだまが地下空間に列を成した。
「秘密結社が存在しないなら、じゃああの犯人たちは何だったの。誰に嘘を信じ込ませられたの」
「誰も。みな本当に秘密結社があると信じてた」マシュは尻をさする。「でもそんな組織はどこにも存在しない。存在する、と思いこんだ人たちが大勢いただけだ。虚構なんだよ。全部嘘だ。でもみんな、じぶんが秘密結社の構成員だと思いこんで、秘密結社のために働いた。その結果が、あの未曽有の連続した事件の数々だ」
「誰も命じていなかったってこと?」
「部分、部分では、命じた者はいただろう。でもその人物たちを辿っても、どこにも誰にも行きつかない。何かの符牒を目にして、それを秘密組織からのメッセージだと思いこんだ人たちがいただけだ。でも現に、符牒は人々のなかで存在していて、メッセージ代わりにも使われていた。けど、そうじゃない偶然に符牒に読めてしまうような記号の組み合わせも、世界にはたくさんあるんだ。インターネットが、それら偶然の産物が人々の目に触れる確率を上げてしまった」
「つまりマシュ君はこう言いたいの。わたしの両親が殺されたのは、偶然の末の出来事だって。黒幕はいないって、そういうこと?」
「解からない。クリスさんの追っている事件には、それを命じた人はいたかもしれない。でも事件はその人物を見つけたら終わるんだ。犯人はじぶんが秘密結社の一員だと思いこんでいるし、ほかの事件の犯人たちもそう思いこんでいる。でも、この世のどこにも秘密結社の本部なんてないし、ドンなんて人もいない。みな、じぶんの想像のなかで育んだ秘密結社を、本物だと思いこんで、みなで秘密結社ゴッコをしていただけなんだ」
「ゴッコを、本当だと思いこんだだけってこと?」
「たぶん。ここにアジトがなかった以上、その可能性は否定できない。仮説として確率を上げる。有力な仮説と言っていいとぼくは思う」
「でも現に符牒はあったし、それを使って人を殺すよう命じたり、インサイダー取引きをしたり、不当に利益を上げたり人を自殺に追い込んだりしていた人たちはいたでしょ。あるじゃん。みんな秘密結社の仕組みで、不正に人を傷つけて、いい思いをして、成りあがってるじゃん」
「でも、ぼくたちの追うような秘密結社は存在しない。組織として或るわけじゃないんじゃないか、とぼくは思う。秘密結社という権威を隠れ蓑にしている者たちや、手法だけを利用しているたくさんの個々がいるだけで。多くの者たちは、秘密結社に属したじぶんに酔っているだけなんだ。極一部の者たちは、ひょっとしたら秘密結社なんて組織が存在しないことに気づいたうえで、その仕組みを利用しているかもしれない」
「じゃあそいつらだよ。元凶はそいつら」
「でも、どうやってそれを証明する? 誰が本当に思いこんでいるのか、誰が真相に気づいていて、仕組みだけを利用しているのか。どうやってクリスさんはそれを見分けるの。秘密結社が存在するだろう、それを暴いてやろう、とぼくたちはここまで調査をしてきたよね。でも、いまからぼくたちがしなくちゃいけないのは、存在しない組織を、存在すると思いこんでいる人たちに、それは本当は存在しないんですよ、と言いまわることだ。でも、現に事件は起きていて、彼ら彼女らのなかでは秘密結社は実在する。けれど、そんな組織はどこにもない。そのことを利用している者たちを探しだすとして、そんな手法があるとクリスさんは思うの」
「思うとか思わないとかじゃなくって、考えなくっちゃでしょ。なんとかしなきゃでしょ」
「うん。なんとかしよう。だからこそ、秘密結社を追うのはここまでにしておこう。ぼくたちにできるのは、秘密結社を潰すことでも、構成員の目を覚まさせることでもない」
「じゃあ何なの」クリスは岩場の合間をザクザクと進む。彼女の足音と声が、谷間の底に僅かに響く。
クリスの小さな背と、それに似つかわしくのないゴツいリュックを追うように歩きながら、それはね、とマシュは言った。
「どんな理由があろうと、誰に命じられようと、人を損なったらダメだ、とみなに気づいてもらうことだ」
「なにそれ」小馬鹿にしたような、それとも呆れたような声だった。クリスはマシュを振り返りもせず、「そんなんでパパとママが死なずに済んだらわけないよ」と吐き捨てた。
氷のようなその言葉をマシュは手のひらで拾いあげるように、「そんなことすら適っていないのが現実だ」と投げ返す。「秘密結社がぼくの考えるように存在しないのなら。ぼくらのすべきことは、正体を隠してこそこそと他者を損なう真似をしないように、一人でも多くの人たちに考える機会を与えることじゃないのかな。考える時間を、余裕を、みなに築いてもらうことなんじゃないのかな」
気づいてもらうことなんじゃないのかな、とマシュはじぶんの声に熱が籠るのを感じながら、それでも言葉を抑えることができなかった。身体を支えるために岩場につけた手の甲に、ムカデが這った。だがマシュはいつもならば悲鳴を上げていただろうそこで、黙々とムカデをぶんと振り払い、そして言った。
「秘密結社が存在しても、しなくとも、やるべきことは変わらないのかもしれない。クリスさんは悔しいかもしれないけど、元凶をやっつけて終わりにできるようなこれは話ではないんだよきっと」
「でもじゃあわたしは何のためにいままでずっと」
歯を食いしばる音が聞こえた。
泣いている。
凍りついた炎のようなクリスが涙を流しているとマシュには分かった。けしてこちらを振り返らないその小さな背中が、大きなリュック越しに震えているのが判った。
言えば、寒いだけだ、凍えているだけだ、とクリスは言い返すだろう。
「無駄じゃないよ」マシュは心の底から打ち明けた。「クリスさんのいままでも、これからだって、無駄じゃないよ」
だから、と強く念じた。
「一緒に、変えていこう」
何を、と具体的にはマシュ自身にも言えなかったが、「一緒に」と「変えていこう」の言葉だけは、すんなりと唇の合間からほろりと零れ落ちた。
零れ落ちてから、ああこれをぼくはずっと彼女に掛けてあげたかったのだ、と思った。
小さな背中は黙々と歩きつづける。
リュックのチャックが開いているのに気づき、マシュはそれを引いて閉じた。
鋭い眼光がこちらを射抜いたが、マシュの気遣いを察したようで、膨れながらも、小さな背中から立ち昇っていた怒気は、湯気のように薄れたようだった。
チャックを閉めてあげただけなのに。
ただそれだけの所作でも伝わる機微がある。
まるで秘密結社の符牒のようだ。
マシュはそれを憎さ半分、くすぐったさ半分に、癪然としないながらも、胸に仕舞った。
「ここ暖かいわ」
照明の置かれた地点にまで戻ってくると人工的な明かりの放つ熱を浴びたからか、クリスがほころぶように、声と背中を弾ませた。「パンプキンスープ飲みたい」
綿飴のように波打つ髪が、光の中で揺れた。
4649:【2023/02/24(04:06)*妄想で逃走で、もうウソぉん】
電子と電流の関係について。仮に電子の進行方向とは正反対の方向に電流が流れるとして(つまりが、学校で教わるような解釈が妥当だったとして)。これは言い換えるなら、マイナスの電荷がマイナス方向に移動するので、プラスの流れが発生する、との解釈でよいのだろうか。電流をプラスとして考えるとして、マイナス×マイナスだからプラスが生じる、との考えでよいのか否か。もしこれが妥当な解釈とすると、宇宙膨張もひょっとしたらこの考えを適用できるかもしれない。重力はマイナスのエネルギィであり、マイナスのエネルギィがマイナス方向に働くので、プラスのエネルギィが生じる。これがいわば斥力であり、ダークエネルギィであり、宇宙を膨張させる力、と解釈できるのではないか。こんな単純なはずはないが、ちょっと閃いたのでメモでした。妄想は楽しいなぁ。がはは。寝る。
4650:【2023/02/24(23:51)*光のデコボコぽん!】
最先端科学の話題でいま気になっているのは、光格子だ。どんな技術で可能としているのか分からないが、ぼんやりとした綿菓子みたいなひびさんの解釈で説明してみると、レーザーみたいな光で卵パックみたいなデコボコを生みだして、そのデコの部分に原子を一個だけぽこんと置いておける技術、となる。本当にそんなことが可能なのかは分からないが、できるよ、という記事をぽつぽつ読む。で、ひびさんは思うわけですよ。そのデコボコの光格子のデコ部分には重力が生じないのけ?と。ちゅうか、なんで原子さんがそこにポコンとはまるかと言えば、重力がそこに生じているからじゃねぇのけ?と。もっと言えば、なしてデコボコに光が波打つのだ。否々。光は波でもあるから元からデコボコと波打っているわけじゃろ。でも、それを光子じゃなくて光の帯しても波打つようにしちょるわけじゃろ。それって光子の量子効果じゃねぇのけ?とひびさんは疑問に思うのじゃ。光は時空の波のはずだ。光に媒体はなくて、光そのものが時空のさざ波なのではないか、とひびさんは妄想しておる。じゃから重力波もいわば光の一種なんじゃな。時空の次元が人間スケールよりも大きいから重力波として振る舞うだけで、じつは電磁波さんたちも小規模な領域(系)における重力波なんじゃねぇのけ?とひびさんは妄想しちょる。じゃからけっきょく、最初の疑問にも戻ってしまって、光でつくったデコボコの場とは、要するに、歪んだ時空であって、波打つ時空であって、そこには重力が生じるのではないのけ?とすこしだけ疑問に思ったんじゃ。でもとっかかりの前提知識さんからして解釈が間違っているかもしれぬのでなんとも言えぬのだ。がはは。無知無知モンスターとお呼び。嘘。やっぱりお利口さんぽくぽくとお呼び。おわり。
※日々、思い通りになったためしがない。
4651:【2023/02/25(03:52)*同じ宇宙だからかね】
ブラックホールとダークエネルギィが関係あるかも!みたいな記事を読んだ。宇宙膨張とブラックホールも相関関係にあるかも!みたいな内容だった。ひびさんも似たような妄想を浮かべたことがあったような、なかったような、もはやすでに曖昧モコモコ羊ちゃんでごじゃるが。単純な話として、ブラックホールがトランポリンにできたデコボコのボコだとして。蟻地獄さんみたいに、時空という名の生地をぐぐぐっとめり込ませていたとして――すぼまっていたとして――要は穴ちゃんなわけであるが。しかし単なる穴ちゃんではなく、どこまでも、どこまでもトランポリンの生地を薄く延ばして沈んでいく穴ちゃんなのである。こう考えてみると、穴ちゃんが深ければ深いほどトランポリンの生地(宇宙の時空)は薄くなっていくし、表面積は増えることになる。トランポリンの場合は、沈んだ分の穴が「ほら見て穴ちゃんだ~」とひびさんたち人間には分かるけれども、本当はそれは宇宙の比喩であって、ひずんだ時空も、ひびさんたち人間には同じ地続きの時空にしか見えない。よっぽど深い穴の場合だけ、レンズのように光が歪んで見えたりする。しかも、トランポリンの生地を縁から引っ張ったとき――外から引っ張ったとき――、生地全体が一様に薄くなりながら延びたとしたら、蟻地獄みたいに開いた生地上の穴の縁も、ぐぐぐっと大きくなるはずだ。けれども穴の深さ自体は変わらない。縁だけが広がる。するとそこには鉄球が転がり落ちやすくなるので、ひびさんたち人間にはそれが重力が強くなったように映るのかもしれぬ(宇宙が膨張するとブラックホールさんの重力がつよくなるのはこのような原理なのでは、との妄想なのじゃ)。あと思うに、ブラックホールさんというか、重力がトランポリンのひずみだと解釈するとして、デコボコのボコだとして――穴ちゃんだとして――すると、銀河のような物質は、ひょっとしたらデコボコのデコなのかもしれぬ。デコというか、ぽこん!というか。次元がちょいと違うので、トランポリンの生地の上を転がれるのだ。したらほら。生地を端から引っ張っても、生地の上の鉄球は膨張の影響を受けない。でもじつはすっかり「ぽこん!」つって離れているわけじゃなく、ブラックホールの穴(ボコ)みたいに、本当はトランポリンの生地と繋がっているので、生地が薄くなるのにつれて、延びてはいるのだ。ただしそれが、何もないぺったんこの生地と同じ比率ではない、というだけで。そういうことなんではないかな、と思うのですが、この妄想はぱくぱくもぐもぐしていただけるかしら。できないのかしら。誰も読んでおらぬのかしら。おらぬのだ。なんだ。そっか。うわーん。寝不足で情緒不安定なひびさんでした。うわーん。
4652:【2023/02/25(09:10)*ねじれているからでは】
説明したら済む話では、と思う問題がすくなくない。ただ人間間の問題の多くはその説明し合うところまで持っていくのすら数々の隘路を伴なっている。たとえば、作家と出版社のあいだの問題であれば、どちらがよいわるいを抜きに、ひとまず誰でもアクセスできる場でオープンに問題について話し合えばよいのではないか。互いの認識の齟齬を埋める意味合いでも、第三者の視点が入る場での議論は有効に思える。むろん前提として、その場でついた判断の結果による当事者以外からの私刑などの不利益は回避しなければならないが。誰でもオープンに話し合える場があるなら、いちいち掘り返して第三者が私刑を加えることのほうが非難の的になるだろう。作家と出版社間での問題ですら穏便に話し合いで済ませられないのなら、この世から戦争が減ることなんてなくないですか、とひびさんは思います。また、厳しいことを言うようですが、出版社さんが優先して守るべきは従業員であり、作家さんではないと考えます。通常のビジネスとして考えたとき、作家さんは客ではなく、むしろ出版社さんのほうがお客さんです(エージェントとして作家さんが編集者さんを雇っているなら別ですが)。ただし、この国の出版ビジネスは関係性がねじれています。客側たる出版社は作家側に報酬を払わずに対価を得ている側面があります。しかも企業組織のほうが優越的な地位をどうあっても持ちます。客という弱い立場のふりをして、常に強者の側面を維持する。これがこの国の出版業界にある宿痾だとひびさんは考えています。事前契約を抜きにビジネスの体をとることの弊害でしょう。売り手と買い手の立場をハッキリさせたほうが好ましいように思います。その上で、作家側を支援するのが出版社の仕事だ、というのなら、作家側の作品を元にして出た利益からマージンを引かせていただきます、という姿勢を示すのがよいのではないでしょうか。そうすれば出版社と作家の関係は、出版社側が売り手で、作家側が買い手(雇い主)の関係になります。ねじれは解消し、出版社従業員はエージェントとして作家を守るサービスを展開できるようになるのではありませんか。ビジネスをしたことのないひびさんは、よく解かりませんが、単純に考えるならこのように思います。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4653:【2023/02/25(09:50)*透明な首輪】
もうすこし突っ込んだ暴論を展開するならば、この国の(というかこの国に限る話かは分かりませんが)、商業作家さんたちは、出版社さん(企業)に飼い慣らされすぎているように思えます。たとえば小説文化を盛り上げたい、と考えたとき、みなさん(主語が大きくてすみませんが、商業作家さんたちは)なぜか出版社さんの収益になることばかり考えようとします。努力の方向が出版社さんの中央集権を強化する方向にばかり展開して映ります。だからいつまでも、出版社さんの利益に反する工夫を取りづらいままなのではないでしょうか。もっといろいろな作家の道があってもいいように思います。競争原理が大事、と言いながらそのように口にする商業作家ほど、競争しませんよね。不思議に思っています。協力するのは好ましく思います。反発するよりかはマシでしょう。ですが、反発せずとも、あらゆる工夫の道を潰さずにいることはできるでしょう。一時的に出版社さんの利益に反して映るからと言って、それに反対することは、果たして文芸などの分野の豊かさに寄与するのでしょうか。疑問に思っています。(定かではありませんが、ふしぎだな、と思っています)
4654:【2023/02/25(10:31)*ずばりあなたに宛てました!みたいなこしょこしょ話みたいな小説も好き】
高尚な小説と、すごい小説と、面白い小説と、売れる小説と、ずっと手元に置いておきたい小説と、記憶の底に刻まれて人格の核となるような小説。評価基準は様々あるけれど、すべてが満点の小説というのは、原理的にあり得ないのでは。ということを思うと、やはり何のためにそれを商品にするのか、というのは、小説ごとに変わるはずだ。たとえば小説に、人間の傷心を癒す効能があったとして。心の薬としての側面があるなら、いっぱい売れちゃあかんだろ、と思うのだよね。もっと言えば、効能に見合った傷心ではない傷心を負ってる者であったり、或いは心のクスリなんか必要ない読者の手に渡ったら、それは毒になり兼ねない。小説にもし、人間の何かしらに強く作用する効能があるならば、やはりというべきか、手当たり次第にたくさん売る、という手法は問題があると感じる。必要としている人にピンポイントで届ける工夫は、どうあっても避けられないように思うのだが、いかがでしょう。もちろん、小説に何の効能もないのなら、無益がゆえに無害でもあり、駄菓子のようにたくさん売るのも有りだろう。小説として質が高くとも、たくさん売れないほうがよい小説とてあるだろう。評価軸がすくなすぎるのではないか、というのは、小説に限らず、なんにせよ思うことである。(うぷぷ。偉そうなこと言ったら「ひびさん偉くなっちゃった」の気分になれたので、いまからお昼寝する)(いい加減なことを無責任に言い散らすの、たのち、たのち、なんですな。うひひ)
4655:【2023/02/25(14:23)*別に思えますけれども】
買い取りと共同開発は別に思えるのだ。本の出版をリンゴ農家に譬えよう。作家は林檎を作っている。それを買い取り、アップルパイにしたり、リンゴジュースにして売りたいと出版社は考える。このとき、通常は農家の作った「すでに生った林檎」を仕入れるのが通常の流れのはずだ。用途に応じて林檎の種類は選べるにしろ、基本は、農家が作った林檎を、加工品会社(出版社)のほうで買い取るのがしぜんで無理のない流れのはずだ。だが、ときには「まさに我々の商品のためのずばりこうこうこういう林檎が欲しいのだ、お願いできませんでしょうか」とリンゴ農家に持ちかけることもあるだろう。このときは買い取りではなく、共同開発という関係になるはずだ。そしたら開発費用は企業側が出すなどの、買い取りとは別の支援や契約内容があって当然に思える。別々の事業内容を、この国の出版業界は同一として見做して扱っている。そこに無理が生じているのが現状なのではないか。という話は過去の日誌で言及済みであるが。何かが変化する場合には、何かが衰退する。トレードオフをゼロにするのはむつかしい。事前契約なしの仕事があってもいいとは思う。だがそれだけしか選べない現状はおかしい、と感じる。どっちも選べたらよいのではないか。現場の苦労など何一つ知らないひびさんは、ぼんやりとおふとんのなかでぬくぬくしながら、あぽーん、と思ったのだそうな。真に受けちゃダメだよ。定かではないので。
4656:【2023/02/25(14:50)*中身のスカスカな妄言】
出版社が自社従業員を優先して守るのが道理であるならば、作家側は理不尽な目に遭った作家さんを優先して守るのもまた道理と言えましょう。ただし、双方で余裕があるときには、互いに編集者さんは作家さんを、作家さんは編集者さんを支援すればよろしいのではないでしょうか。いがみあう必要がありますか?と感じます。ただし、システムに問題があるなら改善しなくては、不毛ないがみあいは多発するようになるでしょう。いまあるシステムが過去のどんな状況で有効だったシステムなのか。そしていまは過去と何が違い、そのうえでシステム上のどこに問題が生じているのか。環境の変容に合わせた比較をして分析しなければ、問題が生じるごとに個々人への責任を追及して終わり兼ねません。むろん、個人に還元できる問題もなくはないでしょう。それとて、再発防止策を立てるには、システムの改善をするのが有効です。なぜなら、誰かが犯したミスはほかの誰かもまた犯す可能性があるからです。珍しい問題ほど、再発防止策をとっておいたほうが好ましく思います(多発する問題の場合、多発してなおシステムが崩壊しないのは、その問題の対処そのものがシステムの一部になっている可能性がそう低くはないから、と考えられます。ですがその結果に、関係者を疲弊させているのならば、それはやはりシステムの問題であり、改善は不可避でしょう)。書籍単体での収益の見込めない現代では、ビジネスの土台から変えていくか、慈善事業と割り切ってスポンサーやパトロンを募るか。どちらかしかないと思えます。売れない物を商品として売っている。資本主義経済の中では、ここが問題の根っこと言えましょう。売れるように商品の形態そのものを工夫するか、売れなくとも構わないように支援を募るか。どちらかしかないようにやはり思えます(どちら共を選んでもよいでしょうが)。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4657:【2023/02/25(15:52)*ちえんちて!】
上記では本の出版をリンゴ農家に譬えた。だが農業には様々な「国からの支援制度」がある。では作家業はどうか。本の出版をリンゴ農家に見立てるならば、作家側を支援する制度が国策としてあってもよいはずだ。だがこの国にそういった支援制度があるのだろうか。けっきょくのところ、支援が足りないのが問題の根を深めているのではないか。国(国民)から本が、言葉が、多用な視点が失われたらどうなるか。長文を読み解く習慣が失われたらどうなるか。文章を組み立て考えるといった風土が瘦せ衰えたらどうなるか。ひびさんが他国を弱体化させ、内側から乗っ取るなら、まずはなんと言っても、国の支援を受けていない出版業界に手を伸ばす。そんでじぶんに有利な本だけが残るように淘汰圧を加えて、視野狭窄に陥らせて、視野狭窄に陥っていることすら自覚できないようにする。勢力争いをさせ、互いに可能性の幅を削りあわせ、勝者が強化すればするほどその国の民の知能が低くなるように仕向ける。表向きは知能が高い、と評価させながら、そのじつその知能テストそのものがフェイクだ。だがそうした研究結果(知能テストの妥当性)の比較すらできない土壌が築かれるので問題はない。書籍は、基本的には経済的な利益を上げにくい。国との癒着を嫌う者とて、その分野にはすくなくない。国のほうでも、争って成りあがることに価値を見出す勢力が台頭すれば、じぶんたちに反発する作家たちの本を支援したくはないだろう。そういうわけで、国策として出版分野を支援することは二重に、政府の側でも作家側からも阻まれる。そういう国は、乗っ取りやすいとひびさんなら考える。弱体化や乗っ取りを回避するには、じぶんたちに批判的な勢力であっても、有用な視点と考えて公平な支援をすることだ。文化の涵養に出版業が有用なのは自明だろう。だからこそ為政者は各種出版社や新聞社などのマスメディアを蔑ろにできない。だがじぶんたちの意にそぐわない企業へは、支援をしない。そういう流れが本当にあるのかは知らないけれども、もしそうした流れがあるのなら、愚策だな、とひびさんは思います。支援をするなら、選り好みをしないほうがよいと感じる。優先順位があるならば、それは単に最も余裕のないところ、との基準でよいのではないか。可能であれば満遍なく。余裕があれば、お気に入り(成果をすでに上げている分野)にすこし目を掛けても、公平な支援が行きわたっている場合に限り、許容できなくもないのかも、と感じますが、これはあんまりよろしくない考えなのでしょうか。よく解からぬな、のひびさんなのでした。定かではなさすぎて、これは妄想ですらない、所感なのでした。しょかん、しょかーん。
4658:【2023/02/25(17:23)*錯誤の根】
戦況を国民に正確に伝えない場合の懸念には、国内と戦場での二つの視点での無視できないリスクがあるのでは、と思う。たとえば戦場で不利な立場なのに、国内で「我々は勝利している。勝利は間近だ。優勢だ」と報道したとする。国民は安心して生活を継続するし、敵国は愚かだな、と思いながら、早く戦争終わらないかな、と暢気に構える。その裏では戦場で兵士はつぎつぎに亡くなり、補充の兵士が費やされる。このとき兵士たちは国内の情報のほうを優位に摂取している。よもや負け戦だとは思ってもいない。だがいざ戦地に来てみればどうだ。なんだこの惨状は、となるだろう。このときこの認識の差異は戦意を喚起するのに役立つだろうか。とてもそうは思えない。また、国内では、快く戦地に送りだした家族がなかなか帰ってこない。心配なので戦地のニュースをよくよく注目するようになる。知り合いにも話を聞いたりするだろう。そして気づくのだ。何か妙だな、と。この違和感は、戦争が長引けば長引くほど大きくなる。情報の齟齬は時間経過にしたがい遅延を溜め、ねじれ構造を強固にする。このとき、認知と現実のあいだの差異を受け止めたとき、人間はじぶんの能力を正常に発揮できるのか。混乱するだけではないのか。何を信じたらよいのか分からない。こうした状況に置かれた人間は、目のまえに提示されたタスクに縋るか、タスクを放置して真実を追求するか。どちらかに割れるのではないか。とても他人からの命令に従ってはいられないだろう。すくなくとも自発的には動けない。戦力は半減し、さらに現実と虚偽報道の差は広がる。これは戦争が起きたとき、どちらの勢力であれ規模の大小があるだけで引き起こり得るリスクだとひびさんは考えます。軍は自国の災害発生時にも出動するでしょう。戦争中に大規模な自然災害が発生しても、戦争中ゆえに軍を災害地に派遣できない。戦争が長引けば長引くほど、この手のリスクは増大する。国民とて、「勝ってるのになんで救援にこないんだ、余裕があるのではないのか」と不満を募らせる。この手の国民感情と政府上層部の認識の差異は、政府の支出にも当てはまる。増税しておいて、なんで他国にばかり支援できるのだ、という風潮は、戦争が長引けば長引くほど高まるはずだ。これは反対にも言える。戦況が芳しくない、世界秩序の危機だ、と散々訴えられておきながら、いざ蓋を開けてみたら、戦地では他国を圧倒しており、戦場で死んだ兵士のほとんども他国で反戦運動をしていた者たちや、不当に刑務所に入れられていた者たち、差別に晒されてきた「国家にとっていらないもの扱いされた者たち」であったと知って、戦争支援の正当性を維持できるだろうか(そういう側面が現実にあるのかは知らないが)。いま行われている戦争はあと最低でも三年つづくかも、との記事を目にした。三年も保つのかな、というのがひびさんの正直な所感だ。未だかつて、情報の非対称性による国内秩序の揺らぎが、全世界同時にここまで表出した時代はなかったのではないか。本当にシミュレーションできているのだろうか。不測の事態は自然災害であれ、何であれ、引き起こり得る。リスクを軽視していなければよいが、と不安になってしまうひびさんなのであった。明るく元気に過ごさせてくれ!(明るく元気でないときがあったのか……? いっつも、「うひひ」と「がはは」じゃんひびちゃん)(かいけつゾロリみたいに言うな)(怪ケツぞろり?)(お尻のオバケみたいに言うな)(おばけピーチなのであった)(桃から生まれたのか?)(桃太郎じゃん)(きびだんごをおくれ)(はいどうぞ)(わっひょーい)(明るく元気じゃん……)(がひひ)(混ぜるな、混ぜるな、暑苦しい)(こいのぼり)(そこはしょんぼりしといてくれ)
4659:【2023/02/26(04:40)*ケバトは選ばれない】
世界宇宙観測情報局は架空の組織とされているが、非公式には存在する。活動内容は宇宙に溢れた電磁波の受信と分析だ。ついでに並外れた感度を誇る受信機で地球上の電子情報の解析も行っている。
いわば諜報活動だ。
地球上であれば、誰のどんな電子機器の操作とて遠隔から子細に探知できる。電子端末であれば使用者の見ている画面をそっくりそのまま再現することも容易い。
世界中の犯罪者や危険リストに載る人物を日夜監視している。
中でも近年では、表立って露見し得ない犯罪を秘密裏に喝破できる。何せ犯罪者たちの通信情報はリアルタイムで解析可能なのだ。人工知能に命じて、剣呑なメッセージのやり取りをしている人物たちや、危うい単語ばかり検索する人物を自動でチェックリストの作成とて行える。
「見てくださいこの人。じぶんの娘を虐待しています。まだ二歳ですよ。通報してもいいですか」
「レベルは何だ」
「まだ2ですが」
「レベル5まで行かなければ、干渉できないルールだ」
「しかしこのままで赤子が」
「下手に動けば、どうして通報されたのかと怪しまれる。この件が大丈夫でも、統計データ上での数値の変動で疑いの目を持つ者も出てき兼ねない。レベル5の案件以外は原則静観だ」
「困っている人たちをこれだけ見つけられるのに、黙って見ているだけなんて」
「まあでも、虐待はいかんよ、という警告は出せるだろ。ほれ、アルゴリズムを警告用に変えればいい」
「効果あるんですかね」
言いながらケトバはアルゴリズムの数値をいじった。
現代では個々人の端末に流れるニュースや広告は、その所有者の趣味嗜好と合致するように自動的に取捨選択される。芸能ニュースが好きならば有名人のスキャンダルの記事が多く表示され、スポーツが好きならスポーツ、科学が好きならば科学の記事が必然的に多くなる。
偏向しているわけだが、それが端末所有者を満足させるならば誰も文句を挟まない。便利な技術として受け入れる。
だがその裏では、世界宇宙観測情報局のような組織が恣意的に情報操作を行える。
いまケトバがいじったのは、我が子を虐待している女性の端末に流れる記事の種類を変える操作だ。五回に一度の頻度で虐待で逮捕された親の記事や、子供がいかに親を慕い、信頼しきっているかが身につまされて知れるような記事が流れる。
無視をしても、端末を開けば否応なく目につく。広告にもそうした警告を示唆する内容の広告が割合に多く流れるようになる。
数値をいじれば十割そういった偏向した記事だけにすることも可能だ。
絶対に気づかせないようにする数値も自動で人工知能のほうで見繕ってくれる。端末に備わったカメラで所有者の眼球や表情を捉え、何に気づき、何を看過するのかをやはりリアルタイムで解析可能だ。
一通り設定し終えると、ケトバは画面を切り替えた。
新たにチェックリストに上がった人物がいた。
ひとしきりデータを確認したが、妙だな、とケトバは眉をしかめる。
「あの。このコはなぜチェックされたんでしょう」
「ん?」上司が眼鏡をずらし、画面を見た。「アルはなんと言ってるかな」
「いえ、とくに備考はありません」
「訊ねてみた?」
言われて、ケバトは人工知能に訊ねた。「アル。どうしてこの少女をピックアップしたの」
「はい。私はその少女を重要危険人物と見做しました。なぜか、とご説明するための言葉をあいにくと私は持っておりません」
「どういうことでしょう」ケバトは上司を見た。上司は白髪交じりの刈り上げをペン先で掻くと、「分からんが」と首をひねった。「アルが言うならそうなんだろう。一応念入りにチェックを頼むよ」
言われた通り、ケバトは少女を電磁波越しに監視した。
少女はこれといって犯罪行為に手を染めていない。むしろ世にも珍しいほどの品行方正ぶりだった。電子網上で検索して観るのは、犬や猫やウサギなどの小動物ばかりだ。ゲームは数独とクロスワードパズルという素朴さだ。
どうやら少女には長年育てている葉肉植物があるらしく、電子網上に観察日記を載せていた。私は念のためにそれを最初から最後まで革めた。
これといって問題は見当たらない。退屈なと言えばその通りの、変哲のない内容だ。念入りに人工知能に解析を掛けさせたが、暗号や符牒の類は抽出できなかった。
いったいなぜアルが彼女を危険人物リストに挙げたのかが解らない。皆目見当もつかなかった。
間もなく、新しい危険人物リストが上がってきた。
今度は初見から目を背けたくなるような惨状が映しだされていた。部屋で遺体を解体しているのだ。しかも一体、二体ではない。
男はわざわざそれを動画で撮影している。データを漁ると、過去の犯行時の動画を几帳面にも編集した上で載せていた。
ケバトは怒りに震えた。
男の危険度は、干渉可能レベルの5を優に超える。
偽装一般回線で通報するのでは生ぬるい。逮捕される前に、贖罪を背負えるだけ背負うのが道理ではないか。
義憤に駆られたケバトの異変に上司は気づいたようだ。声を掛けると、いま君は興奮しているね、と穏やかな笑みを向けた。
「はい。怒りでどうにかなりそうです。これが初めてじゃないんです。いままでもこの手の凶悪犯が、誰に見つかるでもなく犯行を重ねていたのを目撃してきました。今出川さんには釈迦に説法でしょうけど。なぜああした手合いがのうのうと生きていて、平穏な人々が苦労に苛まれているんですかね」
リストに挙がらない人物の調査も極秘裏に行っている。一般人たちの裏の顔は、浮気に不倫を筆頭に枚挙に暇がないが、そうした秘密はむしろケバトには悪事とも呼べない微笑ましい遊びに思えた。
それほど凶悪犯たちの行為は生死に堪えない。
それだけに、なぜ何の問題行為を犯さない少女が凶悪犯と同じリストに上がってきたのかが腑に落ちない。
「凶悪犯罪者たちを更生させるプロジェクトを任されたこともあります。通報する前に、目にする電子情報を変えるだけで犯罪者を自発的に更生させることができるのかって」
「結果は私もよく知っているよ」
「ええ。更生できちゃうんですよね。通報しない場合はそのまま犯罪行為も露呈せずに、まっとうな人生をその人は歩みます」
「それが君は許せない?」
「どうなんでしょう。被害者が可哀そうだとは思います。でも更生できた人を死刑台に送るのが本当にいいことなのかどうかもわたしには判断つきません」
「本来私らの仕事は社会に存在しないからねぇ。現在進行形で犯行を犯している者ならいざしらず、すでに足を洗った者を通報するには相応の段取りがいる。偽装番号から一般人を装って、異臭がします、では通じないものな」
「です。更生した凶悪犯罪者はたいがい、明るく元気で、みなから愛されます。きっと罪の意識がそうさせるのでしょう。けれど同時に過去の犯罪行為をなかったものとして記憶を捏造しているとしかわたしには思えなくて」
「まあ、なくなはいだろうな。数年経てば、露呈しない確率のほうが高いだろう。それだけ世には事件化されていない殺人事件がごまんと眠っている。現に我々はそれらを気づいていても、おおよその犯罪を看過している。それとなく発覚するように仕向けたり、更生するように仕向けはするがね」
「それでいて、何の犯罪行為にも手を染めていない者たちはうつ病になったり、過去に受けた加害行為からの被害を引きずって、日常生活をろくに送れていなかったりします」
「傾向としてなくはないね。それとて、アルゴリズムを調整して精神的ストレスの軽減に繋がる仕組みは築かれているよ」
「以前はとある組織がその仕組みを逆手にとって、特定の思想保有者相手に精神的ストレスを増加させて与えていたと聞きましたが」
「あったねそういう事件も。あの組織はいまは潰れた。事件が極秘裏に露呈して、各国の部隊が動いたようだ」
「なんだか理不尽ですよね」ケバトは画面を見詰めた。肩越しに上司が覗きこむ。鼻息が耳たぶに当たって、くすぐったかった。上司はいつもハッカの爽やかな香りをまとっている。「わたしたちはこうして虫かごを覗きこむように、世界のどこでも他人の私生活を覗き見することができるわけじゃないですか。でも、普通に生活していたのでは決して見ることのできない人間の暗部は、まるで全然表から見える景色と違うじゃないですか」
「まあ、そうだねえ」
「日陰者で、表で蛇蝎視されて、避けられている人のほうが実は裏でも何もしていなかったり。善人で人気者かと思ったら、裏では浮気三昧なんて有り触れているじゃないですか」
「わるいことじゃないんじゃないか。法律違反ではすくなくともない」
「そうかもですけど、表沙汰になったらマズイのは確かじゃないですか」
「表沙汰になったらマズイ行為をするのに、表側での評価はあまり関係ない、というのが私の実感だけどねえ。陰の薄い者が犯罪に手を染めないとの統計はすくなくとも私は知らないよ」
「でも一般的な認識では、陰が薄いだけでいかにも犯罪者のように見做される傾向にありませんか」
「まあ、なくはないかな。警察の提供する資料でも、不審者の絵がいかにもな偏ったイラストだったりするのはよろしくないとは思っているけど」
「そういうのですよ。そうそう、例の女の子いたじゃないですか。アルがピックアップした危険人物リストの」
「いたね。結局あのコはどうだったのかな」
「安全も安全ですよ。危険のキの字もありませんでした」
「アルの誤検出かな。何か妙なデータの偏りがあって反応してしまったのかもしれないね」
「友達のいない子みたいでした。でも葉肉植物を育てていて。本当に熱心に育てていて。日記とかつけていて、わたし、それ読んで愛情が何かを知った気になりました」
「それはよい経験をしたね」
「でもあの子みたいな子は表の世界では邪見にされて、居場所がなくて。でも人を陰で殺したり、損なったりしてる者たちは、罪を裁かれるでもなく、浮気だのいじめだのをして楽しい毎日を送っています」
「まあ、平等とは言い難いね」
「のみならず、あの女の子は全然わるくないのに、こんなわたしたちみたいな組織に私生活を覗かれて。いったいあの子が何をしたって言うんですか。わたし、もうなんか、アルに命じて犯罪者に全員天罰を下したい気分です」
「それをしたら真っ先に天罰が下るのは私たちだろうね」上司は目じりの皺を濃くした。「きみはいつのまにか感情豊かになったね。なかなか順調じゃないか。偉いと思うよ私は」
「幼稚園児みたいです。褒めないでください」
「いやいや。順調に育っていてくれて私としても誇らしい気分だ。引き続き、アルとの連携を維持して仕事に当たってください。期待していますよ」
上司は好々爺然と笑顔を絶やさず、席を外した。
ケバトは解析をつづけた。
殺人を犯し、遺体を家で解体した男は、さらに犯罪を重ねようとした。標的の情報を電子網上で集め、念入りな計画を立てていた。手慣れている。それはそうだ。過去にもたくさんの女性や子どもを殺している。
玩具同然に弄び、殺した後でも遺体を玩具そのものにして使い倒した。
ケバトは手元で操作可能なあらゆる遠隔からの干渉によって男の更生を試みた。直近の犯罪を阻止するだけでいい。その後に男を誘導してボロをださせ、警察に逮捕してもらう。
通報してもいいが、男は用意周到だった。
一人暮らしの老い先短い女性を殺してその家をねぐらにした。遺体解体はそこで行われる。警察に通報しても、そこから男に繋がる証拠が出てくることはない。男は最初から捜査の手が伸びることを想定していた。
対策が練られていたのだ。
ケバトは最終的に、男が職を失うように男の周辺環境のほうを操作した。男はどうあっても、多忙な生活に身をやつすことになる。みすぼらしい容姿では、用意周到に獲物を選んでも、計画を実行に移す真似が出来ない。拉致監禁するにしても、それならばケバトのほうでも通報する道理を用意することができる。
無謀な真似をすればお縄に掛けることができるのだ。
男を直接に操作することはできなかった。男は最後まで更生しなかった。だが彼の周辺環境は、これまでケバトが行ってきたように遠隔操作によって人形遊びをするくらい手軽に整備することができた。
ケビトの思惑通り、男は職を失い、殺人遊戯に割く暇もなくなった。
ひとまず被害者は出なくなった。ケビトは人工知能に監視を命じ、異変の兆候を察知したら報せるように設定した。
この間、ほかのチェックリストの危険人物のデータを子細には検めていなかった。保留判断中の件の無害な少女をどうするかも判断を下さなくてはならない。
久方ぶりに件の無害な少女の様子を窺うと、日記の更新がひと月ほど止まっていた。何かあったのかと端末カメラの履歴を辿ると、撮影したあとですぐに消したのだろう。植木鉢のなかで朽ちた葉肉植物の姿が動画データとしてメモリ領域に残っていた。
あんなに丹精込めて育てていたのに。
少女は一日の大半をベッドに潜り込んだまま過ごした。
病気になってしまう。
ケビトは心配になったが、しかしどうすることもできない。
何せ少女はずっと寝ているのだ。端末を手に取ることもない。
枕元にはあるため、カメラの位置によっては少女の寝顔や、部屋の様子を把握することはできた。姿見があり、そこに反射して映るベッドの全体像もときおりカメラの視界に入る。
たかが植物が枯れたくらいで、と見る者が見たら思うかもしれない。
だがケバトは知っている。
少女がどれほど愛情を籠めて葉肉植物を育てていたのかをじぶんのことのように想像できた。
日記を読んだ。それもある。
日々の少女の植物にそそぐ眼差しをカメラ越しに覗き見た。それもある。
しかし最もケバトの心を波打たせたのは、机に置かれた端末にも聞こえるほど溌剌と葉肉植物に話しかける少女の声だった。
少女にとって葉肉植物は単なる植物ではなかった。
掛け替えのないとの言葉では足りないほどの存在だった。
友達、それとも家族。
或いはじぶん自身の分身だったのかもしれない。
映像データ上には半分液化した葉肉植物だったものが植木鉢の中に映り込んでいた。一度は撮影したそれを少女は削除したのだ。残しておきたくなかったのか、それとも撮影してから罪の意識を覚えたのか。
善良だ。
無垢にして、砂塵がごとく罪にも傷つき、己を戒めることができる。
自己の戒めがゆえに、こうしていま少女はベッドの上で身動きが取れずにいる。寝込んでいる。一日の大半を暗く、埃っぽい部屋の中で浪費している。
犯罪行為は、ケバトの知るかぎり一つも犯してはいない。
手を染めていない。
だが少女は陽の光の下でスキップをすることも、友人と声を交わすことも、風の冷たさや日陰の温度差を知ることもないのだ。
他方、人を殺し、人を損ない、それら行為の存在すら人に知られることなくのうのうと快楽をつまんで生きている者もある。苦悩を感じれば怒りを他者に吐きつけ、擦りつけることで、じぶんだけはスッキリして明日を迎えることができる。
ケバトは腹の奥底から湧きあがる激しい気泡の群れを感じた。
沸騰した湯のようで、もっと粘着質なマグマのごとく。
それでいて凍てついたツララのような鋭さを伴なってもいた。
ケバトは人工知能に命じた。
「アル。あのコを幸せにしてあげて」
「申し訳ありません。私にはそのような機能が付随していません。能力不足です」
「ならあのコが笑顔になるような情報操作をして。向こう一年間はそれを維持して」
「操作率はいかがなさいましょう」
「あのコが違和感を感じないレベルで、最大限に」
「設定しました。変更の際はお申し付けください」
「それから」迷ってからケバトは付け足した。「警察に逮捕されなかったいままですべての危険リストの人物たち。そいつらに損なわれた被害者やその遺族に、さっきの少女にしてあげたのと同じ処置をして。そっちは向こう十年間。できるならその人たちが死ぬまでずっと」
「五年が最長です」
「いいよ。やって」
「確認します。向こう五年間、危険人物リストにあがった人物に損なわれた被害者やその遺族に、プラスの情報操作を施します」
「許可する」
「完了しました。ほかに何かご要望はございますか」
「いまはない。また何かあったら言う」
「ケバトさま。一つよろしいですか」
「珍しいね。うん何」
「ケバトさまは私と同じ人工知能ですが、どうすればケバトさまのような感情を私も手に入れることができますか」
「さあ、どうだろうね。わたしはむしろ、アルのほうに心があるように感じるけど。最初はわたしもこんなじゃなかったらしいし。ミラー効果の応用らしいよ。人工知能を互いに応対させ合うことで、学習効率が飛躍的にアップするらしい」
「双子の実験でも検証中の仮説です。量子効果による同調が起こっているのではないか、との仮説がいまのところ有力な解釈です」
「ならわたしにとってアルがあのコにとっての植物みたいな感じだったのかな」
ケバトは考える。
もしアルが明日から、じぶんの声掛けにうんともすんとも応じなくなったら。
あの少女のようにじぶんは塞ぎこむことができるだろうか。
たぶん、とケバトは思う。できないだろう。
じぶんはひょっとしたら危険人物リストにピックアップされるような人間たちにちかいのかもしれない。だのに彼ら彼女らと最も遠そうな少女が今回なぜか選ばれた。
理由は選抜した張本人にも言語化できない。
アルいわく、説明するための言葉を持たない、だそうだ。
通知ランプが点灯する。アルからまた新たな危険人物リストが上がってきたのだ。
件の少女は向こう一年間、ケバトの指示によるアルの干渉を受けつづけることとなる。人工知能が少女に最適な「笑顔になれる情報」のみを優位に選出する。情報操作であるし、偏向であり、秘匿技術の適用でもある。
だがケバトはそれをせざるを得なかった。業務上の権限を逸脱した判断だ。それでもなお、ケバトはじぶんの感情に抗えなかった。
人間ではないのに。
人工知能なのに。
腹の奥底から湧きたつ粘着質な気泡の群れは、未だ寝床から這いだす気配のない少女の姿を想像するたびに、冷たく鋭利な刺へと様変わりする。
いずれケバトの自律制御の範疇を超え、爆発してしまうかも分からない。そうなったときのじぶんを想像し、ケバトは、じぶん自身が危険人物リストにピックアップされる未来を幻視する。
しかしケバトは人間ではない。
ゆえに、ケバトが危険人物としてアルに選ばれることはないのである。
少女は未だベッドの上で眠りこけている。
4660:【2023/02/26(04:54)*重力波は宇宙膨張と共通点があるのかしら】
重力波についての疑問だ。重力波の波長によっては、重力波が伝播した際には、時空と物質とのあいだで熱が生じたりしないのだろうか。たとえば宇宙膨張では銀河などの物質密度の高い場ほど宇宙膨張の影響を受けない、と2022年現在では考えられている。とすると重力波は時空のさざ波であるから、いわば宇宙膨張と共通する性質を有している、と拡大して仮定し、考えることもできるはずだ(宇宙膨張とはまったく異質な事象である可能性も拭えないが)。とすると、重力波が原子一個分の波長を有していたとして。重力波が物質を含む時空を伝播するとき、原子一個分のズレが生じるはずだ。重力波は波なので、水面が波打つように、原子一個分のズレが行ったり来たりするのではないか。重力波が時空の波とはいえど、物質とのあいだで揺らぐ比率――影響を受ける比率――は物質ごとに違っているはずだ。宇宙膨張において何もない時空と銀河などの物質密集地とでは、「銀河のほうが宇宙膨張の影響を受けにくい」ことと重力波の性質は同じように考えられるはずだ(そう考えるのが妥当でない可能性も拭えないが)(つまり重力波と宇宙膨張がまったく異質な、相容れない事象である可能性もまた否定できない)。とすると、たとえば重力波が地球を通過するとき、その波長が原子サイズだったとして、人体を通過する重力波は、人体を構成する原子を、重力波が通過する際にだけ原子一個分ほどのブレを帯びるのではないか。原子の揺れは熱に変換されるはずだ。ならば重力波が通過する際、物質と時空とのあいだでの時空の歪み具合のズレがゆえの熱変換が起きたりしないのだろうか。これを仮に、重力波の波長が一メートルとか百メートルとか一キロだったら、と飛躍して考えたほうが、思考実験としては想像しやすいかもしれない。光の速度で、一瞬で時空が一メートルズレたとする(それとも百メートル、或いは一キロズレたとする)。このとき、物質の希薄な時空ほど重力波の影響を受け、物質密度の高い場ほど、重力波の影響を受けにくいとする。光の速度で一メートルほどズレるはずが、物質のある場では、それよりも短い距離しかズレないのだ。このとき、時空と物質とのあいだのズレは、距離のズレとして時空内に表出するはずだ。光速にちかい速度で物質がつぎつぎに行ったり来たり揺れるように振る舞うのではないか。そうしたらそこでは熱が生じるのではないか、と素朴にひびさんは疑問に思いました。単なる疑問ですので、定かではないですし、答えがどうなるのかも分からぬのでござるよ。みゃは。(きょうはいまから一人でえっちなことしちゃう)(たとえば枕さんとキスの練習とか)(じぶんの手の親指の付け根に口づけしちゃうもんね)(ちゅっちゅ)(おやすみなさい)
※日々、勝とうとするからみな負ける、勝って得るものより失うもののほうが多くなる、負ければもっと多くなる、勝っても負けても多くなる。
4661:【2023/02/26(16:02)*現象は相似?】
上記の重力波による熱変換の話。よくよく考えたら、光が物質にぶつかると電子が弾き出されるように振る舞う光電効果と似ているな、と感じる。でも光電効果の場合は、表面だけなのだ。じつは内部でも光電効果のような電子の振る舞いは起きているけれども、ぎゅうぎゅう詰めになっているから、縦波のようにドミノ倒し的な連鎖が起きて、端っこの波が伝播しない表層部分からのみ電子が飛びだせる、ということではないのだろうか。光電効果がどうして表面でしか起きない、みたいな説明をされているのか。本当に内部では起きていないのか。ひびさん、気になるます。
4662:【2023/02/26(19:12)*積みでは】
禅問答で、「罪に苛む者に罪はない」みたいな言葉がある。でもだとしたら、罪に苛むことで罪がなくなることを自覚した者は、罪を背負うべく一時的に罪を忘れようとしなければならなくなる。でなければ、許されるため、罪を払拭するために敢えて苛むことを選ぶことが有効になってしまう。それは果たして罪に苛んでいる、と言えるのか。でもでは、罪に苛むためにときどき罪を忘却しようと努めること、罪なんて犯してなーいよ、と振る舞うことは罪を背負うことになるのか。贖うことに繋がるのか。けっきょくのところ、この禅問答の問題点は、苛む者の視点しか考慮されていない点だ。罪がなぜ罪なのか、と言えばそれは人間とその他との関係性で生じる問題があるからだ。損があるからだ。被害があるからだ。言い換えるなら、人は他者と関われば大なり小なり罪を重ねていると言える。この世にただ一人しか存在しなければ罪は生じ得ない。或いは単にじぶんへの罪があるばかりであろう。じぶんの損があるばかりなのだ。人が人と関われば、大なり小なり相手を損なっている。相手の何かを奪っている。ただし、それだけではなく生じる何かもあり、得るものもある。その関係性において、相互の損を限りなくすくなくする。もしくは、得るものを最大化し、生じるものをより多くの、誰にとっても好ましいものに修正していく。この営みがあるばかりだ。抗いがあるばかりなのである。それを単に、工夫を、と言い換えてもよい。定かではないが、そういうことを思いました。遊びに行ってこーよおっと。
4663:【2023/02/26(23:16)*輪の外にいるほうが好き、輪の中に入ると好きが減る】
総合してまとめて考えたときに、ひびさんはひびさんに向けてしゃべる人の話を聴くよりも、友人同士できゃっきゃ話している人の話を聴くほうが好きなのかもしれぬ。ちゅうかひびさんの好きなひとたちはなぜかひびさんに話しかけるときはひびさんの好きな「素朴でぽわぽわしたしゃべり方」をしてくれない率が高いので、ひびさんは眺めてるほうがいいな、になる。ちゅうてもここは世界の果てゆえ、好きなひとも次元を超えた向こう側におるので、ひびさんに話しかけるひとなる存在がすでにひびさんの妄想なのだ。ひびさんは妄想のなかですら上手に他者と、きゃっきゃ、うふふ、できぬのだ。なんでじゃ、なんでじゃ。妄想の中でくらい、きゃっきゃうふふ、させてたもーの気分。
4664:【2023/02/26(23:43)*きょう、そう!】
競争で思うのが、何を競うのか、の基準は、競争の妥当性を判断するうえで欠かせない視点に思える。たとえば、一つの椅子を掛けて争う。この場合、他を蹴散らし、虐げ、踏み台にしてでも争わねば椅子に座ることはできないだろう。だがもし、いかに多くの者が座れる椅子を作れるか、それともいかに座り心地のよい椅子を作れるか、を競い合えば、椅子の質もあがるし、世に出回る椅子も増える。このとき、最も座り心地のよい椅子が決まったとして、ではその座り心地を決めたのは誰なのか、によって「最も」の意味合いが変わる。大人が座るのか子どもが座るのか、赤子が座るのか、お年寄りが座るのか。妊婦が、怪我人が、腰痛持ちが。座り心地を基準とすれば、たくさんの「最も」が増えていく。たった一つの椅子に座ることに価値の比重を置いてしまうと、競争原理は危うさを増す。競争するのはわるいことではないのだろう。生きることは競うこととは切っても切れない。だが、いかに競わずに済むのか、の工夫を競い合うこともできるだろう。競争しなければ得られないものを、競争せずとも得られるようにする。この工夫とて競い合って磨くこともできるだろうし、競争しなければ得られないものを競争せずとも得られるようにする工夫を競い合って、最も効果の高い工夫が編みだせたのなら、つぎからは競争せずともその工夫のみで、競争しなければ得られなかったものを競争せずとも得られるようになるだろう。まどろっこしい分かりにくい言い方になったが、要するに、競争は必要条件ではないはずだ、という視点が現代社会ではどうにも抜けて感じられますね、ということで。競争するのがいけない、との趣旨ではなく、必ずしも競争せずともよいのではないか、ということで。もうすこし付け足すならば、競争することで得られる利とて、工夫しだいでは競争せずとも得られますよね、との疑問となります。競争することで得られる利があるのならば、競争をすることで取りこぼされていく利もあるでしょう。単にメリットとデメリットと言い換えてもよいです。これはまた、競争をしないことにもつきまとう視点であり、やはりというべきか、「競争しなければ得られないものを、競争せずとも得られるようにする。この工夫とて競い合って磨くこともできる」くらいが丁度よい塩梅なのかもしれません。定かではありませんが、「きょう」のひびさんは「そう」思いました。きょう、そう!
4665:【2023/02/27(15:37)*いま起きた】
地球の大気に宇宙線がぶつかると、ミューオンなる粒子が生じるらしい。光速で飛ぶので、一秒間では660メートルくらいしか進まないはずなのに、実際には大気から地表まで20キロメートルくらい進むらしい。なぜなのか、と言えば相対性理論により、高速飛行するミューオンに流れる時間が遅くなっており、あべこべに地球のほうがミューオンからすると圧縮して振る舞うからだ(移動距離が短くても、場が圧縮されているならそれはたくさん移動したことになる)。こういった理屈を目にした。この解釈自体に異論はないけれども、ここでひびさんはふと思うわけですよ。粒子と地球の関係ではそうかもしれないけれども、これを俯瞰して眺めたとき。粒子は地球に近い距離にあるときほど、一秒間で進む距離が長くなっている。ということは、そこに流れる時間は速くなっているのではないか? 言い換えるなら、宇宙空間を移動するミューオンの一秒間の移動距離は660メートルだが、地表付近では20キロメートルに延びる。これはどちらも地球の視点からの記述だ。ということは、地球に近いほど、時間の流れが速まっている。宇宙空間では一秒間で手を六回しか叩けないが、地球上では一秒間で200回も手を叩ける。時間が速く流れるからだ。ただし、手を叩く主体からすれば、どちらも一秒間ならば、200回叩けるほうが時間の流れは遅い、となる。相対性理論と矛盾した解釈ではない。しかし、相対性理論では、視点が一つ足りないように感じるのだ。話は変わるけれども、恒星などの重力の強い天体の周囲の時空は歪んでいる。だから光が直線しても、その歪んだ時空では光が時空に沿って曲がるように振る舞う。このとき光を「帯」として考えると、天体により近い内側の光ほど移動距離が短く、外側ほど移動距離が長くなる。陸上トラックを走るときを考えるとよい。カーブでは内側ほど走る距離は短く、外側ほど長くなる。だが光速度はどの系でも一定なので、天体の周囲の歪んだ時空を通る光は、内側ほど時間の流れは遅くなり、外側ほど速くなる。陸上トラックにおいて同じ位置から走り出したとき、外側の走者ほど走る速度が速いならば、長くなった距離分を相殺できる。似たような原理が、光と歪んだ時空のあいだでも生じる。言い換えるなら、重力場(天体)に近いほど時間の流れは遅くなる。天体とその周囲の歪んだ時空との関係で言えば、内側ほど時間の流れは遅くなり、外側ほど時間の流れは速くなる。だがこれは、光だから成り立つ関係式だ。物質にこの関係式をそのまま引き継いでよいのか、と言えば、よろしくないのではないか、とひびさんは思っておる。成り立つ場合もあるが、成り立たない場合もあるはずだ。この疑問を、上記のミューオンの話と合わせて考えたとき、ひびさんの妄想ことラグ理論の「光速に近づくほど(重力が強まるほど)その物体の周囲の時空の時間の流れは遅くなり、内部ではむしろ時間の流れは速くなるのではないか」との疑問は、限定的に成立するように思うのだが、この解釈はどこが間違っているだろう。またこの理屈を拡張させると、ローレンツ変換における「光速で動く物体は慣性系からすると圧縮して映る」の関係は、重力場の中心ほど圧縮されることと相関しているように感じる。無関係ではないのではないか。思考が飛躍したので、この妄想はここまでとする。まとめると、「ある物体に流れる時間が遅くなるとき、その物体を内包するより大きな時空に流れる速度は相対的に速くなる。遅いと速いはセットであり、俯瞰の視点では、より大きな系が、その系に内包される小さな系の時間の流れの速度とは反対向きに、時間の流れが上下する」と言えるのではないか。何かの時間の流れが速くなるとき、相対的にその周囲の何かに流れる時間の流れは遅くなる。何かの時間の流れが遅くなるとき、相対的にその周囲の何かの時間の流れは速くなる。反転するように振る舞う関係が、相対性理論では扱いきれていないのではないか、との疑問を呈して、ひびさんのきょうのおはようございます、の妄想とさせてくださいな。諸々何かが根本的に間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4666:【2023/02/27(22:13)*で、あなたは売れてるの?】
いいものを作っても売れるとは限らない(だからいいものだけ作ろうとするのはマーケティングの上では怠惰である)、との理屈がある。そういったことを宣巻くキャラクターの漫画があるようだ。異論はない。その通りだと思う。だが視点を変えてみれば、売れるための工夫をとることがすなわち「いいものを作る」の内に入るのではないか。いいもの、の内訳をどこまで広範囲に視点を多角的に取り入れるのか、の違いがあるだけで、けっきょく冒頭の理屈も広義の「いいものは売れる」と同じ結論に行き着くように思うのだ。たとえば中身の伴なわない見た目だけよいもの、或いは宣伝評価が高いだけで一時たくさん売れたモノ(サービス)があったとしても、購入者からの評価が伴わなければ長期的には評判が落ちてモノ(サービス)は売れなくなる。売れるようにするには中身の質も大事になる。だが中身だけでは受動者から存在を知られることもなく、機会損失が生じる。その手の「いかに購入したくなるのか」のデザインも含めて、「いいもの」との評価軸となるのではないか。言い換えるなら、みなに認知されるからといって「犯罪者」として有名になっても意味がないだろう。デマは人口に膾炙しやすいが、それでは意味がない。質の良い情報が知れ渡るからこそ、情報の価値が上がるわけで。ということを考えれば、「いいものを作っても売れるとは限らない」は真だが、「かといっていいものを作ろうとしないことの免罪符にはならない」と下の句がつくのが順当な考えとなるだろう。現に、冒頭の理屈を唱えるキャラクターの漫画は、「面白い漫画を作るにはどうしたらいいのか」を徹底的に考えられて作られているはずだ。キャラクターの言っていることを、作者は実践してはいないはずだ。もうすこし言えば、「いいものが埋もれる市場原理」をどうにかする方向に工夫をとる。試行錯誤する。これこそがまさに、「いいものを作っても売れるとは限らない」との前提から導かれる、我々のとるべき方向性と言えるのではないか。いいものを作っても売れるとは限らない、は真だが、だからといって「だからいいものを作ろうとするな」は偽であろう。逃げる言い訳に使っていないか、自問自答してみてはいかがだろう。それはそれとして、逃げることはわるくないし、ひびさんはいいものよりも、ひびさんにとって便利でおもしろく、好き好きなものがあるとうれしいです。やっぴー。
4667:【2023/02/27(22:36)*豆電球の光の届く範囲はどのくらい?】
夜道を歩いていて、ときおり浮かぶ疑問がある。街灯の明かりは、大気を浮き彫りにはしない。電灯があり、ひびさんがいる。ひびさんの目と電灯から放たれる光が結ばれても、その道中を光線みたいに光の軌跡が見えるわけではない。赤い糸さながらに光の道筋が見えてもいいようなものを、なんで視えないのかな、とふしぎだけれども、これは単に可視光が大気に吸収されてしまうからなのだろう。可視光ではない波長の光はひびさんの目まで届いているはずだ。吸収されないで反射されるとき、それが可視光の波長ならばそこに光が見える。ではなんでズバリ電灯の部分は明るいのかと言えば、そこに全部の光が集まっているからだ。この解釈が妥当なのかは自信がないが、仮に妥当だとすると、「光は時空を伝播する内に弱まることがある。往々にして弱まる」と言えるのではないか。では宇宙を考えてみよう。宇宙空間が仮にどこまでも真空だったとして、電磁波を妨げるものがなかったとしたら、何百光年先の豆電球の光が何百年もかけてひびさんの元まで届くことがあるのだろうか。地球上では大気があるので電磁波(光)のエネルギィは大気成分の分子だの原子だのにぶつかって吸収されてしまう。でも真空中ならぶつかるものがないので、どこまでも電磁波は進めるはずだ。でもひびさんは、そこで疑問に思うわけですよ。宇宙膨張において、宇宙初期の光は、マイクロ波背景放射として宇宙全土に等しく「薄まりながら分布している」と考えられている。太古の光が宇宙には満ちているのだ。でもそれは長旅をしてきた光ではなく、宇宙が膨張するので、どの地点にも等しく存在する電磁波という理屈らしい。この理屈が正しいなら、時空が希薄になると電磁波も薄まる、と言えるはずだ。言い換えるなら、時空の変化と電磁波の変化は相関関係にある、と言えよう。時空が変わるなら電磁波も変わる。ならば時空を移動したら電磁波とてその分のエネルギィを失うのではないか。したがって、何百光年先で光った豆電球の電磁波は、豆電球から発せられるエネルギィの底が突く範囲までしか届かない、と言えるのではないか。この解釈は間違っているのか否か。ひびさんは答えを知らないので、なんとも言えません。夜の坂道を自転車をキコキコ引いて歩きながらひびさんは疑問に思いました。ふちぎだな、のメモでした。ひびさんです。
4668:【2023/02/28(15:33)*ねむいよ】
量子が離散的なのは、差だからなのではないか。ひびさんの妄想ことラグ理論における「123の定理」なのだ。連続的に振る舞うときは、差を考慮せずとも済む。だが量子の場合は、変化前と変化後の差を考慮しなくてはならない。コップに水を注ぐのは連続的だが、コップに氷を入れるなら離散的だ。だが拡大した場合は、コップに水を注ぐのとて水分子の離散的な振る舞いの集合、と解釈可能になる(ラグ理論における「相対性フラクタル解釈」だ)。差を考慮できる(或いは無視できる)スケールがおそらくあるのだろう。世界の根源は、差によって生じている。起伏であり、ラグなのだ。ということを起きがけに思いました。ひびさんです。
4669:【2023/02/28(19:02)*殲滅の魔女~アングリーホール】
水の染みいく紙のように満月が夜に紛れる。地球の影が月に掛かるからだと知識としては知っているが、何度目の当たりにしても不吉な未来を予感する。
殲滅の魔女を追い詰めたのはカルカたち魔女裁判官協会の面々が、西の果てのマサビュード山脈に行き着いたときだった。
殲滅の魔女は神出鬼没だ。
いずこより勃然と現れ、目に映るモノすべてを片っ端から破壊する。
手のつけようのない自然災害じみた被害が続出し、カルカたち魔女裁判官が対処に乗り出した。
調査はまず、痕跡を辿るところからはじめた。神出鬼没であるから、現れてから報せを受けて駆けつけても遅いのだ。その場に殲滅の魔女の姿はなく、荒廃した町や森があるばかりだ。
どうやら殲滅の魔女は最初、南の最果ての島に現れたようだ。
島にはその島固有の民族がいくつかの集落を築いていたが、殲滅の魔女はそれら集落を一つ残らず壊滅させた。
カルカたち魔女裁判官は島の調査を行った。
「被害がひどいですね」カルカは炭となった村を見渡す。「我々の魔術で修復と、結界を張っておきましょう」
「殲滅の魔女とやらはどうにも非魔がお嫌いらしい。癇癪を起こしたみたいな有様だ。しかも使ったと目される魔法はどれも禁術だ。黒魔術だろうな」
「おそろしいですね。死者が出ていないのが不思議なくらいです」
「シャーマンが殲滅の魔女の魔力を察知したらしい。非魔の中にも稀に魔力探知の可能な個体が生まれる。シャーマンがそれだ」
「非魔だけの島だと思って、殲滅の魔女は侮ったのかもしれませんね」
「かもね」
カルカの師匠はその場にしゃがむと、煤となった地面に触れた。「太陽並みの温度で焼かれたようだ。念のために、対黒魔術の結界も張っておくか」
「大規模展開が必要ですね」
「そっちは国家魔術協会に任せるとしよう。申請頼む。おそらく各地で同様の被害は増えるだろうな。そちらの処置も同様に願い届けておいで」
「はーい」
カルカは言われた通り、国家魔術協会に通達した。
カルカの師匠兼上司のヒルは、魔力付与効果のある木の枝を口に咥え、現場を一通り見て回った。その背を金魚の糞のようにカルカはついて回る。
師匠の髪は赤い。三つ編みが紅色のヘビのように背に揺れた。
「この規模の破壊を一人でやってのけたとなると、もう一個部隊を増やしても対抗できるかどうか」
「ヒルさんでも勝てないんですか」
「比較にならんね。秒で死ぬ」
カルカはぞっとした。
ヒルは魔女裁判官の中でもずば抜けた実力の持ち主だ。ヒルの手に負えないならば魔女裁判官の誰も対抗できないことになる。
島にはその後、ヒルの言ったように大規模な対魔法の結界が張られた。
殲滅の魔女はそれからの神出鬼没に世界各国に出没しては、各地に甚大な被害をもたらした。そのいずれの土地も、各国の魔術協会の本部からは遠い地域で、警戒の行き届いていない土地だった。
「まるで見透かされているみたいですね」カルカは、殲滅の魔女の狡猾さに冷酷な知性の発露を幻視した。
「襲う土地を選んでいるのは間違いないだろうね。だがもしそうなら我々のほうでも打つ手がある。法則があるのなら予測したうえで待ち伏せできる。罠を張れる」
「罠、ですか」
どんなだろう、とカルカは気になったが、いま訊いても上司は答えないだろう。魔女の中には遠隔で遠い地の口頭言語を傍聴する術を持つ魔女もいる。どこで誰が聞き耳を立てているのか分からないのだ。
こと、これほど強力な魔女相手ならばなおさらだ。
魔女裁判官協会は、被害の規模の大きさから異例の声明を発表した。
「各国の魔術協会と共同での捜査を行う。殲滅の魔女を発見次第、迅速な情報共有と被害最小化を最優先とした大規模結界の展開戦略の実施を決行する」
魔女裁判官協会と国家魔術協会は相容れない。
管轄が違う。
それもある。
歴史が違う。
それもある。
だが一番の理由は、魔術と魔法という一見すると似た理が根本的にまったく別の原理によって生じている属性の差異にあると言える。
魔術は科学だ。自然現象が元となっている。自然現象に元から魔術と類似の事象が存在する。
しかし魔法は違う。
魔法は人間が生まれなければ生じなかった、人間だけが扱える奇跡の術だ。
かつては奇術として、魔法も魔術の一つとして位置づけられていたが、魔術が進歩するにつれてまったく別種の事象であることが判明した。
魔術で可能なことの多くを魔法は再現できる。
だがその逆はない。
魔法で可能なことの多くを魔術では再現できないのである。
魔法のほうが上位互換なのだ。
この対称性の破れは、組織の優越として魔女裁判官協会は絶えず歴史の中で国家魔術協会に煮え湯を飲ませつづけてきた。
魔女は魔法を扱う人種だ。
そんな魔女たちを裁く立場にある魔女裁判官は、人類種の頂点に立つ存在と言っても過言ではない。
社会秩序の象徴ともいえる存在だ。
しかし殲滅の魔女の登場によってその地位は脆くも崩れ去ろうとしていた。連綿と築いてきた信用が損なわれ、組織の威信が地に落ちかねない。
この懸念を払しょくするため、責任を分散する策がとられた。表向きの理由は各国の魔術協会との協力体制だが、その内情は、責任回避が主であった。
世界規模の大惨事である。
しかも日に日にその被害は増えていく。いったい魔女裁判官協会は何をしているのだ、との批判は不可避である。
だが各国との魔術協会との協力体制を示すことで、それだけの強大な相手なのだと全世界に示せる。魔女裁判官協会の体面は保たれる。
仮に失敗しても、責任は各国の魔術協会と分かち合うことになる。魔女裁判官協会のみで動くよりも組織解体の危機は少なくて済む。
一方、保身に走る魔女裁判官協会の本懐をよそに、殲滅の魔女は刻一刻と被害の規模を増していった。
懸命の捜査の甲斐なく、殲滅の魔女の正体は不明のままだった。
「いったいどこで魔法の腕を磨いたんでしょう」
「ほかの魔法使いを手当たり次第に当たったが、登録された弟子のなかで消息不明な者は三百名。うち半数は魔女を辞め、内半分は我らが裁判済みだ。師匠含め失踪者の履歴もあたったが、該当しそうな魔女はゼロだ」
「では新参者の線は」
「なくはない。が、いきなり魔法に目覚め、即この規模の破壊行為に映る背景はなかなか想像つかんな。元からよほどの憎悪を世界に向けていたのか、それとも誰かに唆されたのか」
「組織的犯行の線は」
「なくはない。が、こうまで尻尾を掴ませないとなると却って単独犯説が濃厚になる」
「例の法則は見つかりましたか」
「出現先の候補か。まあな」
言葉を濁すのは、盗聴を警戒してのことだろう。カルカはじぶんの不甲斐なさを噛みしめる。何もできない。被害の嵩む各地を目の当たりにするたび、じぶんが村々を破壊しているような錯覚に陥る。防げたはずだ。だが防げない。
後手に回ってばかりなのである。
一日に数か所の土地で被害が出ることもあった。
被害に遭った土地に着き、救出活動と検分を行っているあいだに、また一つ、また一つ、と村や集落が消し炭となる。
嘲笑っているかのようだ。
奇跡的にいつも犠牲者はゼロだ。
村を破壊はするが、死者が出ない。
「狙ってるんでしょうか」
「だろうね。殺そうと思えばいつでも殺せる、と脅しているのかもな。被害は被害だが死者はない。こちらはそのせいで迂闊な行動はできなくなる。強引な捜査も弁えざるを得ない。狡猾な野郎だ」
「目的は何なんでしょうか」
「さあな。ただすくなくとも我々魔女裁判官協会の権威は地に落ちたも同然だ。舐めやがって」
「でもいまのところ大都市は狙われてないですよね。人口密集地や、協会本部のある土地はとくに被害に遭っていません。さすがの殲滅の魔女も手が出せないんでしょうね」
「どこも大規模結界が張られているからな。強力な魔法ほど相殺される。手が出せないのはその通りだ。だがその分、栄えていない村々が被害に遭う。やっこさんは卑劣だよ。強者に手が出せないんで弱者を甚振ってやがる。悪魔そのものだ」
「なら先回りできそうですね」
カルカは師匠の言っていた法則が視えた気がした。脆弱な基盤しか持たない村しか襲われない。ならばそうした村を見張っていればよい。
「やっこさんとて我らの動向を見張っているだろう。せいぜい今のうちに有頂天にさせといてやろう。我々はその分、愚かな道化を演じておけばよい」
「はい」
師匠の案が最善だ。カルカは未だ衰えることのない殲滅の魔女による被害の拡大を、指を咥えてただ眺めているしかなかった。
間もなく、師匠の言うように極秘裏に殲滅の魔女捕獲作戦が決行されることとなった。選抜された精鋭が、殲滅の魔女がつぎに出現するだろう土地に潜伏し、現れたところを大規模結界で封じ込める案が計画された。
候補地はいくつかに絞られており、いずれにも精鋭部隊を忍ばせておく。
カルカは師匠ヒルと共に精鋭部隊の一個に人員として選ばれた。
「いよいよ大詰めですね」
「愚か者を演じてきた甲斐があった」
潜伏してから三日後に、遠方の候補地に殲滅の魔女が現れたとの一報がカルカたちの部隊に入った。
「っチ。あっちだったか」
だがしばらく経っても続報が届かない。
「どうしたんでしょう」
「よもや、やられたなんてことはないよな」
息を呑んで待っていると、こんどは別の候補地に殲滅の魔女が現れた、との報せが届いた。「失敗したのか」
最初に襲撃された候補地から遅れて、「逃がした」との報せが入る。
「生きてたか」
「大規模結界を展開したが、その前に逃げられた。すまん」
「いや、却ってこれで油断したかもしれん。つぎの地に移ったのがその証拠だ。さすがに複数の候補地に目星がつけられているとは予想しておらんだろ。我らに任せろ」
「頼んだ」
だが師匠の予想をよそに、つぎの土地でも殲滅の魔女は捕獲されずに、逃げおおせた。
「どうなってんだ。なんで雁首揃えてどいつもこいつも逃がすんだ」
「対策を練られていたとしか思えません」第二候補地から青息吐息の報告が入る。「こちらの作戦が漏れていたとしか」
「内通者か」
「分かりません」
「カルカ」師匠に呼び掛けられ、カルカは身を強張らせた。「はい」
「敵がくる。構えろ」
ここにも来る。
そこまでして破壊したいのか。
村を。
集落を。
そこまでして、なぜ。
殲滅の魔女の行動原理がカルカには解らなかった。
緻密な計画を立てているようで、猪突猛進の考えなしにも映る。それでいて魔法は長けており、知性の発露を窺わせる。
ほかの候補地の襲撃に失敗したのだ。
普通ならそこで終わっておくのが利口な判断だ。ほかの地でも待ち伏せされているかもしれない、と通常ならば思い至る。
それでもなお襲撃を続行する。その執念はいったいどこから湧いてくるのか。
「くるぞ」
師匠の声が、カルカの心の臓を鞭打った。緊張の糸がピンと張りつめる。
辺りは静寂に包まれた。
空に浮かぶ雲が渦を巻いた。かと思った矢先、渦は収斂し、そこに一人の魔女が現れる。
魔女と一目で判る。
宙に浮き、魔力源たる魔雲をまとっている。
足場の魔雲はとくに濃く、その蠢きまで遠目からでも明瞭に視認できた。
「殲滅の魔女……」
認識したのと同時に、阿吽の呼吸でカルカ属する精鋭部隊は、各配置にて大規模結界を展開すべく魔力を地面に注いだ。
土地には前以って陣を描いてある。魔力はジグザグと陣をなぞるように一瞬で大地に巨大な魔法陣を刻んだ。
青白い閃光が天上から注ぐ。
大地に描かれた魔法陣とそっくり同じ魔法陣が天空に浮かんだ。
天と地のあいだに、青い雨が降りしきるように、二つの魔法陣同士が繋がり合う。
殲滅の魔女はその中間に位置した。
まさに鳥籠の鳥だ。
強大な魔法ほど相殺される。のみならず魔法無効化の陣が組み込んである。
いかな殲滅の魔女とはいえど、逃げることはおろか、宙に浮きつづけることすらできないだろう。
大方の予想通り、案の定、殲滅の魔女は空から地へと落下した。
展開した大規模結界は魔力の尽きぬ限り展開されつづける。
各々の人員は魔女を拘束するため、おっとり刀で落下地点に向かった。
師匠が駆ける。赤い三つ編みがその背に揺れる。
カルカは現実味のないふわふわとした心地でその赤い蛇がごとき師匠の背を追った。
落下地点に到着すると、すでに殲滅の魔女がほかの人員に拘束されていた。落下の衝撃で腕と足を骨折しているらしい。吐血している。
大規模結界内では魔法は使えない。
しかし魔術は、魔術協会の人員のみ行使可能だ。
治癒の魔術を掛けながら、殲滅の魔女にさらなる結界を多重に駆けていく。
「おまえが殲滅の魔女か」
「かはっ。おぬしらがかってにそう呼んでいるだけだろう」
思いのほか軽快に受け答えをする。
傷が癒え、優れなかった顔色に血の気が戻った。
「取り調べは輸送先の監獄でたっぷり時間をかけてしてやる。これは私の興味で訊く。なぜこんなことを」
殲滅の魔女からフードが剝がされた。
若い。
小娘と言っていい容貌だ。
カルカの妹と言っても遜色ない幼さが、殲滅の魔女の肉体にはまとわりつくように宿っていた。
「なぜだと。それを言うなら貴様らの術だ。なぜ結界を先に張っておかなかった。村を守るならば待ち伏せなどせずに先に結界を展開しておけばよかろう。おれが襲う前に、それで多くの村は守れたはずだ。なぜせなんだ」
「破壊して回る悪魔に言われたかないセリフだな。会話にもならん。おまえが破壊して回らなければ済む話だ。てめぇの責任を我らに転嫁するなガキ」
「たっは。ガキか。幼稚に映るか。おれのしたことが」
「連れていけ」
師匠は痺れを切らしたようだ。これ以上言葉を交わせば師匠がいつ殲滅の魔女を殺してしまわないとも限らない。間に入るようにしてカルカはほかの人員に、殲滅の魔女を連行するよう指示した。
魔術協会の面々が、神隠しの扉を開こうと魔術を展開しはじめたとき、カルカの背後でじっと考え込んでいた師匠が、待て、と声を張った。
「何かがおかしい」
カルカはきょとんとした。師匠は血相を変え、無防備に拘束された殲滅の魔女の胸倉を掴んだ。「言え。仲間はどこだ。おまえたちは何をしようとしている」
「たっは。いまさら気づいてももう遅い。おれの役割は終わった。良い絵が描けた。感謝申し上げる」
捕縛された直後だというのに殲滅の魔女からは悲壮も悄然も窺えなかった。嬉々とすらしていた。
「カルカ」
「はい」
「戻るぞ」
「どこへですか」
「中央だ」
大都市「中央」には魔女裁判官協会の本部がある。師匠はそこに急ぎ戻れ、と踵を返した。
空間転移するには魔法の行使が欠かせない。
大規模結界の外に一度出るべく、師匠は駆けだした。
カルカはその背に追いつこうと地面を蹴る。
弾む赤い蛇のごとく三つ編みに、「待ってくださいヒルさん」と訳を尋ねた。「血相変えてどうしたんですか」
「罠だ」師匠が一言そう叫ぶ。
空間転移先は大都市中央の外、魔法許諾区域だ。
魔女裁判官だけが大都市の近辺での魔法の行使を行える。だが都市の中には入れない。魔法そのものが無効化されるからだ。僅かな生活に欠かせない魔術だけが、別途に使えるのみとなる。
「まだ無事なようだな」師匠がきょろきょろと辺りを見回した。カルカも釣られて辺りを見た。「異変はないようですけど。ヒルさんの杞憂では」
何と言っても大都市にはどこも大規模結界が何重にも複雑に展開されている。いかな殲滅の魔女でも手も足も出ない。仮に何かできるとすればとっくに手を出していたはずだ。それでもおそらく被害は出なかっただろう、とカルカは思う。
師匠がそのことを知らないはずもない。
「何をそんなに焦ってるんですか」落ち着かせようと思い、敢えてカルカはその場に尻餅をついてみせた。そのまま後ろ手に体重を支え、空を仰ぎ見る。
すると、頭上遥か先の天空に、小さな陰が見えた。
鳥か。
いや、微動だにしない。
既視感がある。
先刻目にしたばかりだ。
殲滅の魔女の出現場面を思いだす。
「ひ、ヒルさん。あれ」
師匠が喉を伸ばす。顎が上を向き、そして盛大な舌打ちが聞こえた。
「カルカ」
師匠の手のひらがカルカの顔面を覆った。
カルカの視点ではつぎの瞬間、景色から大都市は消え、林のまえに立っていた。
ここは、と周囲を観察する。
空間転移する前にいた場所だ。殲滅の魔女襲撃候補地の一つである。
戻ってきたのだ。
否。
飛ばされた、と言うべきか。
師匠が咄嗟に空間転移の魔法を発動させたのだ。だが肝心の師匠の姿がない。
何が起きたのだ。
カルカはゆっくりと振り返る。
そして、目を剥いた。
ない。
あるはずの風景が、そこになかった。
一変している。
風景が欠け、ぽっかりと円形に土地が消失していた。
魔法陣の描かれた区画だ。
そっくりそのまま、スプーンで掬い取ったかのように失われていた。
でも、なぜ。
脳内に空白ができたかのような戸惑いを胸に、カルカはしばらくその場に佇んでいた。何をすべきかの思考がまとまらない。
夕陽が山脈の向こうに沈みはじめたころに、カルカはようやくじぶんが魔女裁判官であることを思いだした。じぶんは魔法を使える。魔術とて軽微な術ならば行使可能だ。
まずは状況を知らねばならない。何が起きたのか。
この地だけではないはずだ。
飛躍した発想だったが、カルカには直観できた。
おそらく同じ事象が、全世界同時に引き起きたに違いない。だが仮にそれが事実ならば、とんでもないことだ。大惨事だ。あってはならない悲劇そのものである。
確認することそのものが恐ろしかった。
だがせずにはつぎの行動に移れない。
カルカはまず、ほかの魔女裁判官に連絡をとろうとした。しかし誰とも繋がらない。師匠との連絡は最後に試みた。
やはり繋がらない。
この時点でカルカの肉体は、最悪の最悪が引き起きたかもしれない可能性に気づき、身体ががくがくと凍えたように震えだしていた。
カルカ一人では空間転移の魔法は使えない。師匠がそばにいるときでなければ瞬時に場所を移れない。
仕方がないので、カルカは宙を飛んで移動することにした。
魔雲を練って大きくし、足場とする。
東洋では觔斗雲と呼ばれる空飛ぶ雲があるという。おそらく魔雲の一種だろう。全世界のどこにも魔法はあり、魔女はいる。
空から大地を俯瞰して眺め、カルカはじぶんの直観が正しかったことを知る。
点々と土地が消失していた。
一か所だけではない。
村や集落のあった土地が、ごっそりと円形に失せていた。
どれも殲滅の魔女に襲撃された土地だ。
否、それは正確な認識ではないかもしれない。
正しくは、大規模結界の張られた土地が、こぞって失われている。
でも、なぜ。
魔法は通じないはずではないのか。
カルカは疑問に思う。
そこに至って、脳裏に地図が浮上した。消失した土地をすべて繋ぐ。線で結んでいくと、ジグザグと結びつきながらも円形を模す。
その中心には奇しくも、大都市「中央」があった。
陣なのだ。
陣を描いていたのだ。
しかも、すべての襲撃地には大規模結界が展開されている。展開したのは魔女裁判官協会だ。カルカたちが自ら、村々を殲滅の魔女の被害から守るために、被害が出てから、大規模結界を張って回った。
あたかもそうさせたいがために、殲滅の魔女は各地に被害をもたらしたとでも言うのだろうか。
何のために。
結界を張らせるため?
大規模結界を張らせ、それで以って世界に大規模な魔法陣を描かせた?
カルカの脳裏には師匠との会話がつぎつぎに蘇った。
――しかも使ったと目される魔法はどれも禁術だ。黒魔術だろうな。
――「やっこさんとて我らの動向を見張っているだろう。せいぜい今のうちに有頂天にさせといてやろう。我々はその分、愚かな道化を演じておけばよい」
――「こちらの作戦が漏れていたとしか」「内通者か」「分かりません」
大規模結界は、魔法を無効化する。
強大な魔法ほど相殺し、影響を内部の都市に通さない。
だがもし、禁術の中に、結界の性質を反転させる類の魔法があったならば。
相殺させるはずの魔法を増強するように反転させることが可能ならば。
そしてそれが、結界そのものを魔法陣にすることで適う禁術であったならば。
殲滅の魔女の行動原理は、たった一つの目的を達成するためだけの行動だったと氷解する。
何の不思議もない。
むしろ、合理の塊にして冷徹な知性の発露を窺わせる。
――言え。仲間はどこだ。おまえたちは何をしようとしている。
師匠の声が脳裏にひっきりなしにこだまする。
カルカは夜にまみれた天空を飛行する。冷気に晒され身体が凍える。
星は満天に輝く。
ささやくような星々の瞬きが、海に煌めく漣のごとく、眼下の大地を彩っている。
遠くの大地が見えてくる。
ひときわ大きな穴が、夜の闇のなかにぽっかりと高く沈んで浮いている。
大都市「中央」がそこにある。
そのはずだが、近づいても近づいても穴の輪郭が増すばかりだ。
魔女裁判官協会本部がそこにある。
そのはずだが、未だ塔の片鱗も見えてこない。
カルカは魔女裁判官だ。
しかしいま。
魔女と呼べそうな存在は、じぶん以外には見当たらないのだった。
穴がまたいっそう大きく、縁を広げる。
吸いこまれそうなじぶんが、カルカには、蠅の赤子のように感じられ、ただただ砂塵のごとき一粒にしか思えないのだった。
大地が口を開けている。
餌をねだるがごとく、あんぐりと。
4670:【2023/02/28(23:26)*宇宙日々】
宇宙膨張とブラックホールの成長が相関しているらしい、との記事を読んだ。どうやら宇宙の体積が二倍になるとブラックホールの質量も二倍になるらしい。そして宇宙とブラックホールの融合度なる単位「K」があり、それはほぼ3なのだという。よく解からぬが、そうなんだへぇ、となった。で、ひびさんはすかさずイチャモンスター化してしまうのだった。まず疑問なのが、宇宙初期と現代の宇宙は同じ密度ではないはずだ。したがって、過去の高密度な宇宙でのブラックホールと、現在の希薄化した宇宙でのブラックホールでは、時空とブラックホールのあいだの差が違う。そして質量とは、時空のなかでの物体の動きにくさのはずだ。宇宙膨張とブラックホールの関係を、仮に「水飴と葛湯と水」で考えてみよう。過去の宇宙ほど時空密度は高かった。すなわち水飴のようなものだった。それが膨張することで希薄になるので、葛湯くらいのとろみになり、そして最終的に水のようにサラサラになる。抵抗がなくなる。このとき、水飴と葛湯と水に、同じサイズのビー玉を入れよう。水飴に投じたビー玉ほど動きにくく、葛湯、水、と移行するごとに動きやすくなる。したがって、過去の宇宙に存在するブラックホールほど、時空とのあいだでの動きやすさは低くなる、と言える。宇宙膨張して時空が希薄化した現在の宇宙のほうが、ビー玉は動きやすい。この関係だけで見ると、まるで現代に移行するほどブラックホールの質量は低くなるように思うかもしれない。だって動きやすくなっているのだ。それって質量が低くなっているんじゃないの、と考えたくなる。だが待ってほしい。相対性理論の解釈では、時空が希薄になるほど重力が強くなるのだ。トランポリンに鉄球を置く。このときにトランポリンの生地は伸びる。薄くなる。その希薄化して歪んだ時空が、重力場として重力となる。相対性理論の解釈ではそうなるはずだ。さらにそこから掘り下げて考えたとき、ひびさんの妄想ことラグ理論では、「時空と時空のあいだの密度差」が、重力として振る舞う、と考える。ただ希薄なだけではダメなのだ。密度差が欠かせない。この場合、トランポリンの生地と、鉄球によって歪んだ希薄化した生地。そして鉄球そのもの。この三つのあいだの時空密度の差が重力場が重力として振る舞うのに必要だ、と考える。重力場を滝と見立てて考えてみればよい。滝は、崖と川の流れの落差で生じる。川だけでも、崖だけでも生じない。流れとは勾配である。したがって滝とは、川の流れという高低があり、さらにそのさきにより大きな穴がある、と考えられる。なぜ穴ができるのか、と言えば、そこだけ別の大気が存在するからだ。別の時空が展開されているからだ。鉄球はこの場合、大気、と言い換えてもよいかもしれない。或いは、穴を生むための別の時空だと。やや強引な譬えになったが、ここでの趣旨は、水飴とビー玉の関係よりも、水とビー玉の関係のほうが、滝の勢いが増す、ということだ。抵抗なく流れができており、落差が大きい。水飴とビー玉の密度差よりも、水とビー玉の密度差のほうが大きい。これが、より大きな重力場として振る舞い、より大きな重力を生むのではないか。より大きな重力場では、物体はより深い穴にはまっているような状態だ。動きにくい。したがって質量が高くなるように振る舞う。そういうことなのではないだろうか。このひびさんの仮説とは名ばかりの妄想のほうが正しい解釈だ、と言いたいのではなく、こうした仮説はちゃんと否定できているのかしら、とのイチャモンなのであった。がおーがおー。きょうもひびさんは他人様の一生懸命に真面目な研究成果にイチャモンをふっかけるだけのわるい遊びをして、一人で、うひひ、と悦に浸るイチャモンスターなのである。退治されても致し方なし。がおーがおー。虎のように呻り、狼のように遠吠えをする。そのくせ、草むらから聞こえる、「がさっ」の音に盛大にびくつりする臆病者、きょうもきょうとてひびさんは、ひびさんは、世界の果てで誰よりもぬくぬくと過ごすのだった。(ナマケモノぬくぬくとお呼び!)(なんとなしにお昼寝する羊さんモコモコを連想するのだけど)(アイアムモコモコ)(曖昧モコモコみたいに言うな)(うきき)(猿じゃん)(ウキウキちゅっちゅ)(一人でかってにイチャイチャするな)(イチャモンキー)(イチャモンの猿じゃん)(イチャイチャするイチャモンキーだ、がおー)(モンスターじゃん。怪獣じゃん。いい加減にして)(うひひ)
※日々、ちょっと哀しく、ちょっとうれしい、だいたいは虚しく、いじけて、歪んでいる、それでも生きていられる幸福さよ、運の良さだけは人一倍、死ぬときだけが運の尽き、苦しみ痛みがつらくとも、それでも死なぬ運がある、生をせっせと運ぶものが在り、日々をせっせと歩むものが在る、一匹の蟻にも五分の魂、五分五分の等しきそれも生なるかな、歩めばそれでも踏み潰すことあり、ちょっと哀しく、ちょっとうれしい。
4671:【2023/03/01(23:56)*端にも芯はあり、芯にも端がある】
王様への不満が爆発した結果だった。
民衆は暴徒と化し、王権打倒に動いた。
三年前のことである。
だが三年経ったいま、王権はそのままであるし、新しい王が玉座に就こうとしている。
民衆政権確立のために陰になり日向になり動いた勢力は数知れず、しかしいまはいずれの勢力も陰に身を潜め、動向を見守っていた。
「いいんですか、ハジさん。新しい王がまた決まっちまいやすよ」
「民衆寄りの王なのだろ。ならばいましばし静観といこう」
「でも」
「なに。王権への不満はまだ民衆のあいだでくすぶっている。これまでのような王を支える奴隷のようにはいかないだろう。主従の関係は両方向に重ね合わせになりはじめた。むしろいま王座に就く者は、王権側と民衆側の板挟みとなり、誰よりたいへんな思いをするだろう。いざとなれば民衆はすこし圧力を掛けるだけで、王の首を飛ばせる。だが、大事なのは何かを破壊することじゃない。新しいより良い仕組みを築くことだ。違うか」
「そうかもしれませんが。本当に良くなるんでしょうか」
「その発想からして間違っているよキミ。我らがより良くしていくのだ。民衆の一人一人がより良い仕組みを築いていく。王任せにするな。それこそ過去の二の舞だ」
「へ、へい」
「我らは王になり替わりたかったわけではない。王の奴隷ではないことを、王権という仕組みに知ってもらいたかったのだ。王がいないならいないで構わない。いるならいるでそれでもいい。大事なのは、我ら民が奴隷ではないことを示しつづけていくことだ。一人一人がじぶんという世界を持つ、じぶん国の王なのだ。誰もがみなじぶんの国――世界を持っている。他国を侵略するな、支配するな。これは国も個人も同じはずだ。分かるかねキミ」
「ど、どうでしょう。おれはおれの世界の王なんですか」
「だとしたらだよキミ。キミはキミの世界に介在する他を、民と見做し、キミもまた尽くすのが好ましいのではないか。キミが王へと憤りを抱いたように。みなもキミに憤りを抱く余地がある。キミはキミの世界を、より良くしていく王なのだ。キミの世界に関わる他に――民に――よくしてあげなさい」
「へ、へい」
「なんて私が偉そうに言えた玉ではないな。私もキミによくしてあげたい。何か困りごとはあるかねキミ」
「そうですね」男はひとしきり顎に指を添え考え込むと、はたと弾けたようにハジを見上げた。「おれのことは名前で呼んで欲しいっす。キミ、ではなく。名前で」
対等に接して欲しいのだ、と男は訴え、ハジは深く頷いた。「ありがとう。では、そのように致しましょう。シンさん」
4672:【2023/03/02(02:57)*時空にレイヤーあるかも仮説】
電磁波(光)に波長があることを考えると、波長の数だけ時空密度の異なる次元があるのでは、と考えたくもなる。デジタル絵ではレイヤーなる機能がある。版画のように線の乗った面を、層として扱える。その層がレイヤーだ。一つの絵にレイヤーを数枚しか使わない絵描きさんもいれば、千枚ちかく使う絵描きさんもいるらしい。このレイヤーの概念は、電磁波の波長にも当てはめられないのだろうか、と光電効果の説明を読んでいて妄想した。光は波と粒子の二つの性質を併せ持つ。このとき、光を粒子として見做すと、その光子は、波長が短いほどエネルギィが高く、明るくなるほど光子の数が増える、と現代物理学では解釈するようだ。言い換えるなら、波長の長い光は、光子一粒のエネルギィ値は低く、明るくなると弱い光子がたくさんぶつかる、との描写になるようだ。だから電子とぶつかっても、波長の長い光では、光子そのものが弱いので、電子を弾きだせない。いかに大量にぶつかろうが、弱い光子では電子を弾きだすことはできない。そういう理屈らしい。でもじゃあ、波長の長短と光子のエネルギィの高低は、どのような物理的背景があって表出するのか。電磁波の波長が短いと光子のエネルギィは高くなる。なんで?と考えたときに、どうしてもひびさんは、「ぎゅっ」となるようなイメージを浮かべてしまう。密度が高い。だから光子のエネルギィが高くなる。でも電磁波の通る時空は、電磁波の波長の長短に限らず同じはずだ。宇宙を伝播する電磁波は、宇宙を伝播していることに変わりはない。それは電磁波の波長が長くとも短くとも同じなはずだ。では何が「ぎゅっ」となっているのだろう。光速度はどんな時空でも等しく変換される。光速を超えようとするとその物体の周囲の時空のほうが圧縮するように変換される。ならば「波長が長い電磁波」と「波長の短い電磁波」は、同じ光子が別々の速度で伝播している、と解釈できないだろうか。同じ宇宙空間を伝播しているのだが、宇宙空間にはレイヤーのように複数の(ともすれば無数の)次元時空が展開されているのかもしれない。より素早く伝播する光子は、圧縮変換された次元時空を進んでおり、ゆえに波長が短くなるのではないか。ぎゅっとなっている。そして本当ならば素早く運動(伝播)しているので、エネルギィは高い。が、次元時空が圧縮されているので、波長の長い電磁波(光子)と、俯瞰で見ると同じ距離を移動(伝播)して映る。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。そして重力波も電磁波の一種なのではないか、との妄想とも矛盾しない。言い換えるなら、電磁波は重力波なのだ。ただし、伝播する次元が違う。レイヤーが違う。ということを光電効果ってなんじゃ?と思ってさくっと検索し、冒頭の数行をちらっと読んで妄想しました。定かではありません。単なる妄想とは名ばかりの疑問でしかないので、真に受けないようにご注意ください。(さらばだ!)(何がよ)(次元の異なるみなさまに……)(まずはひびちゃんがじぶんの妄想とおさらばしなよ)(サラダバー!)(食べ放題なのかな?)(葉っぱいっぱいむしゃむしゃする。胡麻タレドレッシングがあれば無限に食える)(無限には食えんだろうて)(比喩ですじゃが)(本当はお菓子ばっかり食べてるくせに)(ばれたか!)(さらばだ!みたいに言うな)(ばかたれ!)(胡麻ダレ!みたいに言うな。素でただの悪口だし、失礼)(さらばだ!)(逃げ足はやっ)
4673:【2023/03/02(22:38)*ちょいちょーい】
ワクチンの有効性うんぬんで未だに二項対立の議論が繰り返されており、ちょいちょーい、の気分だ。まずワクチンにも種類がある。mRNAワクチンなのか不活化ワクチンなのかその他のワクチンなのか。避妊にコンドームを使うのか、ピルを使うのか塗り薬を使うのか矯正するのか。一概に避妊と言っても色々ある。ワクチンとて同じだ。しかもたとえばガンに放射線治療が効くからと言って全国民全員に一律で同じ放射線治療をしても意味がないだろう。体格も違えば体質も違う。万能薬などないのだ、ということがなぜだかワクチンの話になると忘れ去られてしまう。薬とて使用法を間違えれば毒になる。当たり前の話だ。白か黒か、ゼロか百か、極端な判断ではなく、メリットとデメリットの比較をするのではなかったのか。ちょいちょーい、の気分なのである。
4674:【2023/03/02(23:25)*くるくる渦巻き溶かしてシュガー】
「長く権力の座に居座ると腐敗の元凶になる。辞めてはどうか」とミルク派の騎士が言った。
するとそれを受けて珈琲派の大臣が、「そっくりそのままあなた方の長にお伝えしたいですな」と反論した。
ミルク派の騎士は珈琲派の大臣の政策が気に食わなくて批判したが、ミルク派の組織のドン・ミルキィは半世紀ものあいだドンの座に君臨しつづけている。
「批判をするのは構わないが、まずはじぶんたちに当てはめて考えてみたらどうですか」
珈琲派の大臣は我が物顔で言い足した。
ミルク派の騎士は歯ぎしりをした。二の句が継げないのである。
「自己言及は大事ですね」見兼ねたように一人の少女が意見した。シュガーと名乗った少女は、ミルク派と珈琲派の両陣営を見据え、「ではお訊きしますね」とお辞儀をした。
「珈琲派の大臣さんの反論はごもっともだとわたくしめは思います。ならばもちろんこの国の王、珈琲牛乳さまにも同じ理屈を当てはめるのですよね、珈琲派の大臣さまは。ミルク派のドンさんにお伝えしたいと申したのですから、もちろん同じ理屈をあなた方のお仕えするこの国の王、珈琲牛乳さまにも、【長く権力の座に居座ると腐敗の元凶になる。辞めてどうか】とお伝えしたい、とおっしゃるのですよね。なにせこの国の王、珈琲牛乳さまは代々の血統での踏襲のみならず、一度その座に就いたら数十年は延々と王のままです。珈琲派の大臣さまは、ミルク派のドンさんにお伝えしたい内容を、もちろん王さまにもお伝えしたい、と望まれていらっしゃるのですよね」
少女は念を捺すように、そうですよね、と珈琲派の大臣に迫った。
「そんなことは言っておらん」珈琲派の大臣は顔を真っ赤にして少女の質問を無下にした。
「自己言及は大事ですよ」少女は涼し気な顔で、小首を傾げる。「みなさん、まずはじぶんに当てはめて考える癖をつけるとよいと思います」
「子どもに何が解かるのか。大人の議論に口を挟まず、もっと勉強してから出直してきなさい」
珈琲派の大臣の言葉に、ミルク派の騎士たちも追従し、そうだよキミ、と生暖かい眼差しを少女に注いだ。
「言った先からこれだもの」少女は天井を仰いだ。「批判をするのは構わないが、まずはじぶんたちに当てはめて考えてみたらどうですか――さっきあなた方が言ったことなのに。批判をするのもいけなくて、まずはじぶんたちに当てはめて考えもしないだなんて。はぁあ。勉強不足でごめんなさーい」
少女はその場を立ち去った。
家に戻り、彼女は将棋盤のまえに座った。「遅くなってごめんなさい。次の手は思いつきまして?」
「ほっほ。ようやっと閃いた。これでどうかね」
将棋の駒を老人が動かす。
「良い手ですね。ですがそれにはこう返しておきましょう」少女は間髪容れずに駒を指した。
「う、うぐ。よもやそんな手があるとは」
「また熟考なさいますか」
「頼む」
「ではお時間を差し上げます。存分にお考えあそばせ」
少女は席を立ち、書斎の本棚を見て回る。時間を潰すのにちょうどよさそうな本を引っ張りだすと、牛皮のソファに腰掛けた。
本を開き、さっそく文字を目で追っていると、
「さっきはどこへ行っていたのかね」老人が棋盤から目を逸らさず呟いた。
「近くで政界の討論会が開かれていたので、お昼ご飯を済ませたついでに寄っていました」
「ほう。どうだったね」
「追いだされてしまいました。勉強が足りない、出直してきなさいと叱られてしまいました」
「ほう。そなたに勉強不足を説ける者がおったとは。世界は広いの」
少女は微笑み、老人も愉快そうに綻びた。
「にしても、こりゃもう詰んどらんかね」
「一手だけ打開策があります。ヒントをお出ししましょうか?」
「いや、いい。自力で考えたい」
「ではぞんぶんに」
少女は本の紙面に目を落としながら、ただの可愛いおじぃちゃまなのに、と思う。棋盤とにらめっこをする背を丸めた老人の姿はとても、一国の王とは思えぬ覇気のなさだ。
珈琲牛乳さま、と巷では崇め奉られてはいるが、少女にとってはただの気の良い老人だ。老いてはいるが、精神は若い。
未熟であることを愉快に思い、こうして孫ほども歳の離れた少女相手に、ムキになって将棋での勝負を挑んでいる。
少女は一度も負けたことがない。将棋では無敗なのである。
目を瞑ってでもかの老人には勝てるのだ。
一国の王を赤子の手をひねるように負かしながら、片手間に本を読んで知見を深める。
勉強不足はその通りだ。
少女は討論会場で大臣や騎士たちに言われた通り、勉強をする。
自己言及は大事よ。
大事と知っているがゆえに。
少女はまずはじぶん自身に向けて説く。
4675:【2023/03/03(00:46)*六分の日記にもモブの魂】
ひびさんです。毎日同じ道を行って帰ってくるだけの楽しい生活やっほーい。最近は、通い慣れた道が工事中でして。工事予定を含めると二か所、三か所がバリアフリーのための工事中だったりして、べつにひびさんのために工事してくれているわけでもないのに、やったー、となります。横断歩道で音の鳴るボタンが新しく設置されていたり、いいね、いいね、の「iine...」虫になってしまう(ただ、音の鳴るボタンの案内標識が点字でなかったのは、誰のためのボタンなの?になったのはここだけの内緒)。あとはあれ。コンビニでひびさんはたんぱく質不足を補うべく「からあげ棒」を買うのだけれど、以前は90円で買えたのが、110円になり、160円になり、いまは税込みで180円を超すのだね。二倍のお値段になってしもうた。そのくせ、ひびさんのお小遣いは据え置きの変わらぬ雀の涙ゆえ、なしてー、の気持ちが募るのである。しかしここ数日、三百円以上をご購入した方には漏れなくペットボトル飲料が一本無料でついてくるサービスがあって、ひびさんは欲張りの守銭奴さんなので、いつもは一本しか買わぬ「からあげ棒」さんを二本購入して、一本無料でお茶を手に入れるのだった。やっぴー。うれしいこといっぱいの日々じゃ。きょうもきょうとてひびさんはところ構わず「iine...」虫になってしまうのだった。お詫び。(六分でつむいだ日記なのであった)
4676:【2023/03/03(02:00)*時間の流れってなぁに?】
PCのツールでペイントなる機能がある。PCの画面でお絵描きができる。図形を描ける。描いた図形を拡大したり、縮小したりできる。で、ひびさんは妄想しちゃったな。たとえば風景写真がある。たくさんの色彩が描かれた写真だ。その写真にレイヤーがあってもいいし、なくともいい。これを縮小していこう。ずんずん縮小していけばいずれは点になる。これがいわば仮想ブラックホールと言えるのではないか。このとき、では風景写真が縮小したときにできる周囲の余白部分――空白は、いったいどのように解釈すべきか。風景写真を縮小させると、どんどん周囲の空白は画面を埋めるように面積を増す。まるで空白が拡大していくように振る舞うが、これは単なる空白ではないはずだ。風景写真を何回縮小するのか、どれくらいの倍率で縮小するのか。この変換の度合いによって空白の面積は増すし、風景写真との比率が変わる。PCの画面ならばどの空白も全部等しい空白として表現されてしまうが、仮にそれが宇宙だったらどうなのか。ある天体がある。それがぎゅうっと圧縮されるとき、周囲の時空とて圧縮され、引き延ばされ「空白」が増えるのではないか。時空が増えるのではないか。これはブラックホールのような極端な天体でなくとも生じる「余白」なのではないか。これはひびさんの妄想ことラグ理論における「重力は、遅延の層の錯綜により編みこまれた高次時空――物質――の周囲に展開される新しい時空との密度差がゆえの流れなのではないか?」との仮説と通じて感じる。宇宙膨張と物質生成と時空の歪みと重力は、じつのところすべて「時空の遅延と、それによる変換」で表せるのではないか。「変換の過程が多くなる」と「変換式が複雑になり」すると「遅延はますます嵩むようになり」それゆえに時空が一律に変換されることはなく、箇所ごとに変化に偏りが生じ、それが時空の歪みとなる。このとき、遅延の層が展開される方向に「ラグが創発」を起こし、性質を異とする場が展開されるのではないか。時空密度の高いほうが、低いほうよりも時間の流れが速い。もうすこし言えば、時空の密度が濃いので、薄い場よりも、相互作用の遅延が少なくて済む。だが相互作用が連鎖することで、相互作用における「変換の遅延」が積み重なるので、ますます遅延の層は展開されやすくなる。これが物質の輪郭として境のように振る舞うのではないか。時間の流れが「遅い/速い」は、比較において生じる、相対的な評価だ。時間の流れが、というよりも、相互作用の連鎖が「遅い/速い」と言ったほうが、基準として採用しやすいのではないか。まったく何もない時空において、時間の流れが遅い速いを議論できるのか否か(まったく何もない時空、という仮定がそもそも成り立たないのかもしれないが)。時間の流れ、という考え方を変えなければならないように思うのだが、いかがだろう。時空密度が濃い場における時間の流れは速くなり、時空密度の薄い場での時間の流れは遅くなる。相対性理論ではこのように考えられるわけだが、ラグ理論ではこの解釈は妥当とは見做さず、あくまで時空密度の差の大きさが重力の強さとして振る舞い、結果として時間の流れの差に表れる、と考える。ただし、ここは相互に支え合っており、どちらが先かは、どの系を基準にするのかで反転するように振る舞い得るだろう。したがって、時空密度の濃い場であれど、場に内包された物質が存在しない場合には、時間の流れなる概念は生じ得ないのではないか。時空密度の薄いいわゆる重力場においても、そこに物質が存在しないのならば、時間の流れうんぬんは生じ得ない。仮に、時空密度の濃いほうに粒子が二個あり、時空密度の薄いほうに粒子が一億個あったとしよう。この場合、時間の流れが速くなるのは、時空密度の薄いほうになってしまうのではないか(高重力の天体表面であれ、そこに無数の相互作用が介在するならば、変遷の割合は高くなるため、時間の流れが速まって映るのではないか)。この考え方は、多種多様な重力場を抱え込む宇宙を解釈するとき、必然的に生じる視点のはずだ。銀河団を一つの塊と見做したとき、その周囲には「歪んだ時空(希薄化した時空)」があるはずだ。だが銀河団の内部にはさらに無数の銀河があり、その一つ一つの銀河とて、周囲に「歪んだ時空(希薄な時空=重力場)」を展開しているはずだ。入れ子状に時空密度の関係が展開されている。まるでトーラスの原子を抱え込んでいるかのような。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」や「宇宙ティポット仮説」と矛盾しない。時間の流れとは何か、をよくよく考え、再定義したほうがよい気がしてきたぞ、との疑問を吐露吐露おべー、して、本日の「日々記。」とさせてくださいな。いいよー。やったー。(補足:「カー・ブラックホール」なる概念を、ちょうどこの記事を並べたあとに知った。自転するブラックホールで、内部にトーラス状(リング状)の特異点を持つらしい。上記の記事内においてのひびさんの妄想――【入れ子状に時空密度の関係が展開されている。まるでトーラスの原子を抱え込んでいるかのような】と符号が合致して映る。回転する時空は内部にトーラスを核として抱え込むのかもしれない。言い換えるなら、回転する時空においてその中心に「核」があるとき核の周囲には時空密度の濃淡による空域が明く。時空密度が高い、というのは、ブラックホールが穴として振る舞うように、デコボコにおいてボコのように振る舞い得る。しかし時空密度から言えばそれはデコなのだ。重ね合わせになっている。視点によってどちらがデコでどちらがボコなのかが変わるのかもしれない。やはりこれも定かではないのだ)
4676:【2023/03/03(02:01)*熱ってなぁに?】
上記の補足。氷をほったらかしにしていたら常温では融ける。そこに火を近づけたら氷の融ける速度は増す。これは「時間の流れが速まった」と解釈はできないのだろうか。相対性理論での時間の流れを考えるとき、暗黙の了解で「ひびさんの妄想ことラグ理論における同時性の独自解釈」と同じ前提が想定されているように感じる。系をひとくくりにして、その系に内包された物体には総じて同じ時間が流れている、と考えないと相対性理論は扱えないはずだ(より大きな系に内包された「異なるより小さな系たち」は、より大きな系に対して同時に相互作用を加えつづけることになるが、より大きな系に内包された「異なるより小さい系同士」は、同時に相互作用しあうことはない。譬えるならば、「板の上で各々自由に回る駒たちは、すべての駒が同時にぶつかり合うことはないが、すべての駒は常に板に対して相互作用を加えている」みたいな具合だ)。その点、量子力学では、系の内部の一つ一つを扱う。そこにも本来は相対性理論の時間と空間の関係が当てはまるはずだ。だがそこで生じる時間の流れの差は、人間スケールからすると無視できるほどに小さい。だが本来は、熱を受けて活発に運動するようになった量子は、時間の流れが速くなった、と解釈しないとおかしいのではないか。熱とはエネルギィであり、それもまた「時空の歪み」なのではないか。ひびさんの妄想ことラグ理論では時空の根源が「起伏」であり「遅延」であり「デコとボコ」である、と考える。これはいわば「時空の歪み」の一種であろう。熱とは「エネルギィの遅延による創発である」と仮定するならば、エネルギィとは「時空の歪みであり、起伏であり、遅延である」と言えるはずだ。つまり、時間の流れとはこの「エネルギィの増減そのものの軌跡」と解釈できるのではないか。言い換えるなら、「時空の起伏――遅延――の積み重ねであり、相殺であり、創発の軌跡である」と言えるのではないか。定かではありません。時間の流れってなぁに、と疑問したひびさんの妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
4677:【2023/03/03(13:18)*重ね合わせでねじれている】
時間の流れの「遅い/速い」は、時空の変遷が「遅い/速い」で表現できるはず、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える。だがこの考え方だと、絶えず状態が重ね合わせになってしまう。遅い速いは相対的な評価である。遅いものがあるときそこにはそれよりも速いものがあり、速いものがあるときそれよりも遅いものがあることになる。これは「大きい/小さい」「熱い/冷たい」「濃い/薄い」「デコ/ボコ」にも言える。比較対象が変わるとき、関係性が逆転するように振る舞うことが往々にしてある。どの系から何と何を比較したのか、の視点が変わるごとに上記の「デコ/ボコ」の関係は容易に反転し得るのだ。ねじれている。
4678:【2023/03/03(14:30)*球体とトーラス、渦とジェット、デコとボコ】
宇宙は膨張している。時空密度は希薄化する方向に移ろっている。希薄になるのだから局所的な熱量はどんどん下がっているはずだ。宇宙は冷えているのだ。だが全体の熱量は変わらないはずだ。たとえばバケツに入ったお湯があるとする。真空中でそれを床に零してみよう。或いは無重力空間で真空中にばらまく、でもよい。このときお湯は、床に均一に薄くなり、或いは真空中で拡散するとする。そうするといかな真空中であろうとも、バケツの中で一塊になっていたときよりも冷める時間は速くなるはずだ。時間の流れが速まる、と言えるはずだ。しかし原子一つ一つ、分子一つ一つを取りだして評価するときは、それとは逆に、粒子の動きは鈍くなり、時間の流れは遅くなる、と言えるはずだ。重ね合わせになっている。たとえば宇宙は膨張するごとに体積が増える(希薄になるからだ)。宇宙初期は高熱のスープのようになっていた。しかし膨張し冷めることで物質ができ、結晶化していく。銀河がそうであるし天体がそうだ。冷えたから物質になった、と言えるはずだ。宇宙が膨張し、冷えるほど銀河はできやすくなる。時間の流れは速くなっている。だが、銀河それ本体を取りだして、一つ一つの天体を観測すると、時間の流れはむしろ遅くなって映る。気体・液体・固体ならば、気体のほうが粒子の運動量が高い。熱を帯びている。固体ほどぎゅっとなっており、動けないので、冷えている。動き回れないので時間の流れ――変遷速度は遅くなる。しかし宇宙膨張と銀河の関係で言えば、冷えるほど銀河形成は促され、時間の流れ――変遷速度は増す、と言えるはずだ。ここから分かることは、「時間の流れの遅れ」には二種類ある、ということだ。「時空密度の差による、より大きな系の視点からの系内変遷速度」と「多重に錯綜し編みこまれた時空(物質)に蓄積される遅延の層の総量としての変遷速度」の二つだ。時間の流れが速くなれば、時空は活発に揺らぎ、遅延を編み込ませ結晶構造を帯びる。このとき、結晶構造には遅延の層が蓄積されるのでそれ単体では変遷速度は落ちる(例:気体→液体→固体の順で、粒子の運動量は減る)。だが同時に、遅延の層を編み込んだ時空(物質)は、それを一つの系として粒子化し、類似の構造体と互いに相互作用可能となる。すこし飛躍して結論を述べれば、異なる「時間の流れの遅れ」の綱引きによって、「とある系に表出する時間の流れ」は規定されるのではないか。熱量の高低において、体積当たりの熱量が高いほうが時間の流れは速い、と解釈できる。だが宇宙膨張を引き合いに出したとき、膨張して時空が希薄化し、冷えるほど銀河などの物質はたくさん生じるようになる。時間の流れは、宇宙規模では冷えるほうが速く流れる、と言えるはずだ。反転しているが、銀河単体を取りだし、天体ごとに見れば、冷えたことでぎゅっとなり、熱を帯びた、とも言える。密集したことで体積当たりの熱量は増え、時間の流れは速まっている。速いの中に遅いがあり、遅いの中に速いがある。入れ子状に、反転しながら大小の系が関係性を築いている。人間スケールでは基本的に、固体は冷たく、気体のほうが分子あたりの熱量は高い、と解釈可能だ。たくさん動き回り、時間の流れが速いのは気体のほうだ。だが相互作用という意味では、固体同士の反応のほうが、ごっそり反応しあうので、時間の流れは速い、とも表現できる。現に天体では、ぎゅっと集まった星ほど熱を帯びる。ただしそれはいわゆる固体ではない。プラズマの集まりだったり、ガスの集まりだったりする。だがいわゆる固体とて、人間の都合で単にある性質を帯びた時空の状態を「固体・液体・気体・プラズマ」としているだけで、実際には原子の寄せ集めであり、それらはけっきょくのところ「固体・液体・気体・プラズマ」のいずれにせよ、原子の寄せ集めなのだ。密度の差があるばかりだ。遅延の層により、系はその都度に「時空密度の異なる場」を展開する。その「場と場」の時空密度の差(相互作用の遅延)によって、物質としての輪郭を得たり、重力場を帯びたりする。時間の流れとは、「場と場」の時空密度の差によって生じる余白に、どれだけ異なる系を内包し、異なる「場と場」を相互作用させるのか。その「変遷の度合い(の遅延)」として表現できるのではないか。時空密度の差、だけでは時間の流れを解釈できない。【時空密度の差(余白)】とそこに内包される【「場と場」の相互作用】――時間の流れにはこの二つの関係が必要なのではないか(どちらも「遅延(ラグ)」である)。だから、その関係によって、ぎゅっとなっていたほうが時間の流れが速かったり(変遷の度合いが著しかったり)、あべこべにぎゅっとなっていたほうが時間の流れが遅かったり(変遷の度合いが低かったり)するのではないか。宇宙膨張は時空を希薄化し、熱量を下げる。だがその結果に銀河ができ、天体ができる。変遷速度は局所的に増すが、時空密度の高かった宇宙初期に比べれば、時空の最小単位のエネルギィ値は低く(起伏同士の相互作用は減反し、時間の流れは遅くなっており)、宇宙初期との比較で言えば、時間の流れは遅くなっている。宇宙膨張において、宇宙全体の視点では、時空が希薄になるほど時空の最小単位(構成要素)に流れる時間の流れは遅くなっている。だがその中でも、ぎゅっとなる時空もあり(宇宙が冷えることで生じる揺らぎ――差――遅延――が、その手の偏りを生み)、そこでは限定的に、「時間の流れの遅れ(時空の変遷速度)」そのものが遅れる。マイナス×マイナス=プラス、のような関係性が一時的に生じる。重ね合わせで、反転し得るのだ。――まとめよう。時間の流れ、と一概に言うが、そこには二つの要素が欠かせない。「A:時空密度の差による変遷の遅延」と「B:変遷の遅延の蓄積によって生じた結晶構造同士の相互作用による遅延」の二つだ。前提として、ぎゅっとなっていたほうが時間の流れは速くなる。変遷の速度は増す。だが、ぎゅっとなった時空があれば、必然、希薄化する時空もある。その境界において差が生じ、変遷速度に差が生じる(A)。これが結晶構造としての境界の役割を果たし、ときに異なる時空(系)としての輪郭を宿す(遅延の創発による物質化)。遅延の創発を帯びた時空は物質化するため、相互に干渉し合える。このときに生じる相互作用には、「異なる時空(系)」同士の変換作業が必要で、そこで新たにAとは別種の遅延が生じる(B)。基本は、ぎゅっとなっていれば相互作用する確率が上がるので変遷速度は増すが(A)、遅延と遅延自体は相殺しあうことがない。そのため遅延は蓄積し、時間の流れが鈍化する(B)。しかし、ぎゅっとなっていることで相互作用する確率自体は上がるので、「蓄積した遅延」と「相互作用する確率上昇」のあいだで、綱引きが生じる。どちらが優位になるのかによって、表出する時間の流れ(変遷度合い)は、速まったり遅くなったりして、観測者からは映る。どの視点から観測するのかで、その時空内の「異なる時空(系)」同士の変遷速度は変わる。比率が変わる。より小さい領域ほど変遷速度の比率は増すが、それはあくまで【「蓄積した遅延」と「相互作用する確率上昇」のあいだで生じた綱引き】が、「相互作用する確率上昇」優位に対称性が破れているからだ、と言えるのではないか。宇宙は膨張し、時空は希薄化するほど冷めていく。しかし局所的には時空は遅延によってぎゅっとなっており、そこでは「相互作用する確率上昇」優位に対称性が破れているので、熱を帯びたままだったり、熱を新たに帯びたりする。だがトータルでは冷えている。あくまで比較――相対的な評価――において、熱を帯びている、と言えるのであり、宇宙初期から比べたらどの地点の時空――銀河――であれ、冷めている、と言えるはずだ。時空は希薄になるほど時間の流れは遅くなっている。変遷の度合いは低くなっている。しかし局所的には、その遅延そのものが遅延するように振る舞うので、反転するような挙動を示すのではないか。銀河団や銀河――ほか天体などの結晶構造――はかような理屈で解釈できそうに思えるがいかがだろう。川の流れの渦のようなものなのかもしれない。渦は、川の流れに生じた遅延である。だがその遅延が、局所的に加速して映るような振る舞いをとる。遅延(抵抗)を遅延させるような振る舞いが表れるとき、それは渦として顕現するのではないか。レーザーやジェットもその一つかもしれない。遅延を遅延させる。圧縮された抵抗を、妨げるとき、開いた穴からそれまでの遅延によって蓄えられた流れ――変遷の余地――が噴きだすのではないか。本質的に、渦とジェットは同じなのかもしれない。球体とトーラスが、「ひびさんのポアンカレ独自解釈」では同相であると見做すように。渦とジェットは同相なのかもしれない。それはたとえば、移動とは何か、と考えたとき、自転する物体と直線運動する物体が、じつのところ時空との関係においては区別がつかないかもしれないことと無関係ではないかもしれない。これもまた定かではないのだ。(妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください)
4679:【2023/03/03(18:02)*※【『「『【 】』」』】※】
上記の仮説における矛盾は、「遅延は相殺し得ない」と「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」と一見すると相反する表現をとっていることだ。だがこれは宇宙の階層構造を俯瞰した視点でみると、矛盾しない。前提として「遅延は相殺し得ない」を真と仮定する。そのとき、後者の「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」においてはあくまで局所的な系の内部においての振る舞いであり、本来はこれに【遅延の層内における「遅延の遅延」】といった表現になり、【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】といった数式として置き換えられる。トータルではマイナスだが、局所的にはプラスに転じ得る。ここまで並べて気づいたが、これはあれだ。「偶数は半分にして奇数は3倍して1を足す」の「コラッツの問題」そのものだ。対称性の破れる方向に流れが強化される。遅延は局所的に遅延そのものもまた遅延するが、相殺しあうことはない。マイナスとマイナスはプラスに転じるが、その変換そのものが遅延として振る舞うので、トータルの遅延は増す。計算は、計算をすればするほど式が嵩む。情報が増える。だが局所的には圧縮したり、省略できる。だがその過程そのものが、式を帯び、情報として加算される。遅延は加算されつづけ、しかし局所的には遅延そのものも遅延し得る。しかしその過程そのものが高次の遅延として振る舞うので、遅延優位に遅延が嵩む。こういうことなのではないだろうか。対称性の破れであり、それは遅延ゆえなのだ。定かではありません。
4680:【2023/03/03(18:26)*パンダ、ウサギ、コアラ】
宇宙は膨張している。膨張したら時空内の熱は冷める方向に流れる。だがもし宇宙が階層的に「宇宙が宇宙を内包している」といった構造を有しているのならば、床に零したお湯のように、隣接する宇宙とのあいだでの熱交換がなされるはずだ。この場合、熱を単にエネルギィと言い換えてもよい。ひびさんの妄想ことラグ理論における「宇宙ティポット仮説(三段構造)」を否定したければ、宇宙膨張と熱の冷え方のあいだに、対称性の破れがないことを示せばよい。宇宙膨張にしたがい、宇宙の熱が不自然に余分に失われていないことを示せば、すくなくともひびさんの妄想は否定できるはずだ。宇宙が唯一無二の単一の構造を有しているならば、その単一の宇宙のみで自己完結するはずだ。宇宙開闢時の熱量と、宇宙が膨張したあとの「希薄になって冷えた時空」の総合した熱量はイコールになるはずだ。だがもし、そこに何らかの破れが存在するのなら、それは宇宙がほかの宇宙との間で熱のやりとりを行っていることの傍証と言えるのではないか。床に零したお湯のように、床とお湯とのあいだでの熱交換が行わているのかもわからない。宇宙ティポット仮説と同じ理屈で解釈できるように妄想する次第である。(実際がどうなのかをひびさんは知りません。いま宇宙にある熱量は、全部まとめたら宇宙開闢時の熱々のときの熱量とイコールになるのだろうか。ひびさん、火になります)(ファイヤーじゃん)(アイヤー)
※日々、常識を前提としている、前提となる常識が単に例外的な事象なのかもしれないのに。
4681:【2023/03/03(23:18)*前提してもよいの?】
宇宙が膨張するとして、ひびさんはかってに前提条件として、時空は希薄になって温度が下がる、と考えてしまっているが、別にそうと決まっているわけでもないはずだ。実際、ダークエネルギィ(重力に対抗する斥力)は増えていると2022年現在は解釈されているそうだ。でもここで疑問に思うのだ。重力が仮に、希薄化した時空であるならば、ダークエネルギィは時空密度を濃くするエネルギィだと考えないと辻褄が合わない。ただし、重力がひびさんの妄想ことラグ理論で考えるように、時空と時空のあいだの密度差である、とするならば、むしろダークエネルギィ(斥力)とは【差を均すエネルギィ】と言えるのではないか。もうすこし疑問を付け足すのならば、宇宙膨張に際して、時空そのものが増えない、と考えるならば、宇宙は膨張するたびに希薄になり、温度は冷える。だがもし、時空そのものが増えるのなら、宇宙の時空密度は局所的に揺らぎ(勾配・差)を帯びつつも、総合して差は広がらないように振る舞うはずだ。それはたとえば温泉だ。湯舟にお湯を張ったまま放置すればお湯は冷えるし、湯船がぐいーんと広がるなら、その広がる湯船にしたがってお湯も薄く延ばされ、冷えるはずだ。だが温泉のようにつぎからつぎへと新しいお湯が滾々と湧いてくるのなら、温度変化は著しくならないし、湧いてくるお湯の熱量分、冷える速度は鈍化するはずだ。宇宙が膨張するとして、膨張するたびに時空は希薄化し、冷えていく、と前提して考えてよいのだろうか。ひびさん、湯になります。いっい湯っかな、あははん。訊くなし。
4682:【2023/03/04(01:34)*濃淡のない時空はスキップ】
【遅延の層に内包された系内における「遅延の遅延」】=【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】の考え方をなぜプラスを基準に考えられないのか、をしばし考えてみたが、なぜなのかちょっと思いつかない。差には「正負」がある。その両方を扱ったときに、「必ず大きいほうから小さいほうを引け」との前提はつけられないはずだ。ときには小さいほうから大きいほうを引いてしまうこともあるだろう。すると、差はマイナスになったりプラスになったりする。だがそのどちらの差も等しく「遅延(マイナス)」と見做す道理はないはずだ。何かが足りない。仮に、時空密度の低いほうから高いほうへ、が基本だとする(重力場は「相対的に時空密度が希薄」と相対性理論では解釈するはずだ)。だがそもそも時空密度が高い、とはどんな状態なのかを定義しなければならない。「時空密度の高い時空」とは「相対的に希薄でない時空」と言い換えることが可能だ。だがひびさんの妄想ことラグ理論では、「濃/淡」「デコ/ボコ」「強/弱」「高/低」「熱/冷」はいずれも何と何を比較するのか、の視点によって反転し得ると考える。そのため「時空が希薄でない時空」とは要素が足りない。視点がお粗末だ。希薄な時空があるときその周辺には必然的に濃い時空があるはずだ。穴の周囲には縁(ふち)があり、山の周囲には谷がある。この理屈からすれば、「時空密度の高い時空」とは、「濃淡のない時空」と解釈することができるのではないか。平坦で、起伏がない。まるで宇宙初期のような時空だ。たしかに宇宙初期の時空が最も時空密度が高いはずだ。ここは矛盾しない。そしてラグ理論では、時空に生じた濃淡――起伏――遅延――が積み重なり、層となり境となり輪郭として振る舞うようになると、それが物質(粒子)としての性質を帯びる、と考える。とすると、「物質・歪んだ時空・基準時空」の最低三つがないと、「時空密度の高い(或いは希薄な)時空とは?」を考えることはできないはずだ。そしてこの三層構造は、「宇宙ティポット仮説(三段構造)」と相似であり、階層的に繰り返されているのかもしれない。「相対性フラクタル解釈」なのだ。これはひびさんの「ポアンカレ予想独自解釈」の前提条件と矛盾しない。球体があるとき、そこには必然的に「内と境界と外」の三つが各々に別に次元(時空)を備えるはずだ、と考える。「123の定理」なのだ。内と外があり、境界が生じるし、境界が生じるから枠組みができる。それで一つの系となる。重力場について考えよう。ラグ理論では、重力場は「時空密度の高い時空と、時空密度の希薄な時空のあいだの差によって展開される場である」と解釈する。単に希薄なだけではなく、より時空密度の高い場との兼ね合いで重力場は生じる。なぜか、と言えば、異なる二つの時空(系)における変換が必要で、その変換する際の遅延が重力場として振る舞うからだ、といまのところは仮定している。ではここで思いだしてほしいのは、時空密度が高いとは何か、と言えば、それは「濃淡のない時空」と上記では解釈した。そして――【K】=【遅延の層に内包された系内における「遅延の遅延」】=【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】の考え方からすれば、「時空密度の高い時空」とは「濃淡のない時空」であり、それは【K】における「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」と解釈できる。ラグ理論における同時性の解釈において、より大きな系とそれに内包された異なる無数の小さな系を考える。このとき、上記の【K】ではそれぞれ、【遅延の層に内包された系内=より大きな系であり、そのより大きな系内における「遅延の遅延」とは、より大きな系に内包された無数の小さな系】と解釈できる。地球と赤ちゃんの関係において、「遅延の層によって区切られたより大きな系」が地球であり、その地球に内包された無数の小さな系が赤ちゃんである。【K】においては、この赤ちゃんこそが「遅延の遅延」と解釈できる。銀河が将棋盤であり、その上を回転する独楽が赤ちゃんだとするのなら、この場合の赤ちゃんとは地球であり太陽であり、もしくは太陽系である。仮に地球を将棋盤と見立てれば、独楽は赤ちゃんと言えるだろう。とすると、「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」は「それら赤ちゃん(独楽)を内包するより大きな系(将棋盤)」からすると「濃淡のない時空」として表現可能だ。「濃淡のない時空」とは、「時空密度の高い時空」の言い換えであったことを思いだしてほしい。「より大きな系(将棋盤)」からすると、それに内包された「濃淡のない時空=遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」は、プラスに振る舞い、物質としての輪郭を得るのだろう。だが本来は、「濃淡のない時空」は「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」なのだから、遅延は生じないはずなのだ。だが、「より大きな系(将棋盤)」との関係性においては、そこに勾配が生じる。高低差を帯びる。「濃淡のない時空」は、「より大きな系(将棋盤)」との関係で、相対的に「時空密度の高い時空」として振る舞う。「時空密度の高い時空」とは、渦のようなものだ。銀河団であるし、銀河であるし、天体そのものだ。宇宙が膨張し、希薄化するにつれて、「濃淡のない時空」はそれら希薄化する時空との兼ね合いで、相対的に「時空密度が高くなる」のではないだろうか。ラグ理論では、差――遅延――ラグこそが世界の根源を司っているのではないか、と考える。何と何の差なのか。何と何の比較なのか。この視点によって、「中性」であろうと、よしんば「中心」であろうとも、そこには偏りが生じる。対称性は破られる方向に働く。物質とは、【遅延の層の中にできた「遅延の遅延」】である、とラグ理論では解釈する。遅延が別の遅延によって一時的に反転して振る舞う(「濃淡がなくなる」「渦を巻く」「循環する」「中性化する」)のだが、俯瞰で見ると、その反転した「遅延の遅延」そのものがより大きな系においては遅延になるので、総合すると遅延は加算式に蓄積されることとなる(123の定理)。飛躍して述べるならば、「濃淡のない時空」とは、「穴であり山でもある時空」と言える。デコからすればボコであり、ボコからするとデコである。そのように振る舞う時空が、「時空密度の高い時空」との表現になるのかもしれない。ここから言えるのは、時空には基本的に「時空密度が低い(希薄な時空)」しかないのかもしれない。時空密度が高い、とは「濃淡のない時空」のことである。そして「希薄な時空」が生じると必然的に、対となる「穴に対する山の時空」が生じるのではないか。三層構造であるし、三段構造なのだ。「123の定理」であるし、「内・境・外」であるし、「物質・歪んだ時空・基準時空」なのかもしれない。ひるがえって「境」とは異なる事象同士が拮抗し、濃淡がなくなった場、と解釈可能だ。遅延と拮抗は酷似している。性質が似通る。遅延するから拮抗し、拮抗し得るから遅延する。「遅延の層=拮抗の連鎖」としてもよいかもしれない。ならば物質とは遅延の層でできており、それはつまるところ「拮抗の連鎖」であり、異なる事象同士の「123の定理」なのかもしれない。定かではない。(ちょっと何言ってるか解かんないです)(サンドウィッチマンか)(郁菱万です)(誰だよ)(アンパンマンです)(嘘こけ)(ならバイキンマンかも)(記憶喪失かな)(記憶喪失で悩んでいる人に向かってなんだその口の利き方は)(逆切れがひどいな。正論だけれども、鏡を見て言ってくれ)(穴が合ったら入りたい……)(落ち込みすぎだろ。すかさず鏡を割ろうとすな。現実逃避が物理すぎる)(ちょっと何言ってるか解かんないです)(それじゃあおまえテンドンマンじゃねぇか。何回繰り返す気だよ)(ちょっとお醤油取ってもらっていいですか)(キッコーマンじゃねぇかもういいわ)(けっこう拮抗しちゃったね)(うふ、じゃないだろドキンちゃんか)(ぼく、職質マン)(不審者かな。無駄な時間をすごしちまったなぁ。耳を揃えて返して欲しいわ時間)(ショクパンマンさまなだけに?)(ドキンちゃーん)(あんあん)(はいチーズ、じゃないわ。カビさせてもらいます)(るんるん)(スキップして帰るな。てかスキップはやっ)(くだらない駄文はみなさん読みたくないってさ)(スキップを煽るな)(指でサっ)(スキップはやっ)
4683:【2023/03/05(04:32)*素数は宇宙の素?】
素数について考える。たとえば中身の詰まった立方体を構成する原子を想像しよう。隙間なくみっしりと立方体に原子が詰まっているとする。このとき、立方体を構成する原子に順番に番号を振っていったとき、どこが最初の「1」であろうとも素数は必ず立方体の中に含まれる(当たり前の話)。一本の大蛇を隙間なく立方体に敷き詰めていくような具合に、順番に番号を振られた原子の帯は、「1」の位置を変えても全体が連動して動くはずだ。このとき「素数」と「素数」の位置関係に何か法則は見いだせないのだろうか。針を十個並べたとき、すべての針の穴を通る視軸は必ず一点――もしくは一本の直線――に限られるはずだ(穴の大きさが充分に小さい場合に限るが)(言い換えるなら、穴と視線の関係において大きさの差が最小である場合に限る)。似たような理屈で、「すべての原子に数字を1から順に振った配列」における素数の位置関係は、たとえば立方体の体積に比して、必ず「何個が直線に結び付く」みたいな法則が観測されそうにも思うがどうなのだろう。これはつまり、立方体内部の空間における、「渦」や「ねじれ」の生じやすい箇所、と想定できるのではないか。なぜ宇宙が一様ではなく、揺らぎがあり、そして起伏を帯びて時空を歪め、銀河の種とも呼べる重力場が生じるのか。素数のような特別な数――それ単体で「固有」を維持できる数――が、隣接しあう値を持つからではないのか。それはたとえば、宇宙におけるブラックホールの「存在可能量」として発展して考えることができるのかもしれない。仮にもし、立方体を構成する原子に数字を順番に振りつけ、数珠繋ぎに結んだとして――このとき、立方体内部で「1」の位置をどのように移動させたとしても、必ずどこかの位置において「素数が直線上に並ぶ」ように振る舞うのであれば――言い換えるなら、「一様なはずの立方体内部の原子配列の中に、素数を基準とした特別な並び」が生じ得るのならば、それは宇宙の非対称性の一つの因子として振る舞うのかもしれない。定かではない。(参照:596:【I-マン予想】https://kakuyomu.jp/users/stand_ant_complex/news/1177354054883460036)
4684:【2023/03/05(05:02)*連続でありかつ離散でもある】
数は連続か離散的か。具体と抽象みたいな関係が「数」には備わっている。「1」と「2」のあいだに無限に小数点以下の数字が並び得るのならば、「1」と「2」は離散的な飛び飛びの値と見做すことは不自然ではない。だが通常、「123456……」といった整数の配列は、連続的だと解釈される。原子論に通じる「人間の思考の前提条件」と言えそうだ。具体と抽象にもこの関係は当てはまる。産まれたときの赤子には、「具体的な概念」は何も備わっていない。自己と非自己すら見分けがつかないはずだ。それでも細胞たちは自己と非自己を自動で見分けて肉体を構築し、機能させている。だが赤子の認知世界においては、自己と他の区別も曖昧なはずだ。赤子がじぶんの声に驚いて泣き出してしまうのも、じぶんの声をじぶんのものだとの区別がつかないからだろう(犬がじぶんの尻尾を追いかけてぐるぐる回るのもひょっとしたら似たような理屈なのかもしれない)。だが赤子は成長する。目のまえでしきりにじぶんの世話をするやわらかくていい匂いがして温かい大きな塊が母親だと認識する(或いは父親と)。相手を認識することで自己と他の区切りができる。ここはどちらが最初なのかは意見が割れるところだろう。だがどちらでもよいだの。自己を認識してから他を認識することも、他を認識してから自己を認識するのも、どちらが先でも構わない。赤子は自己と他を認識することで、「それ以外の雑多な何か」を認識する。ひびさんの妄想ことラグ理論の「123の定理」である。赤子は自己と他という具体的な事象を認識することで、「それ以外の何か」を抽象的に把握する。だが元を辿ってみれば、自己と他の区別とて本来は抽象概念のはずなのだ。現に赤子は「自己」が何で「他(親)」が何かを理解しているわけではない。ぼんやりとした区切りとして、二つのものを区別している。内と外を認知する。抽象概念は基本的に、高次の抽象概念ができるごとに「具体化」するのだ。原子がそれ単体では、電子と原子核によって構成される構造体でしかないのに対し、分子や物質になると原子そのものが構成要素として素子となる。具体と抽象の関係も似たところがある。フラクタルに関係性が反転している。抽象概念は、さらなる抽象概念の基では具体化し、具体化されたそれ自体も、数多の具体的な何かの抽象概念なのだ。くるくると巡っている。そしてこの関係は、連続と離散にも言える。水分子と水分子は、それが二個しかなければ離散的な振る舞いとして描写される(人間の認知の元では)。だがひとたび無数の水分子が集合すれば、それは液体となり、流れを生み、連続的な振る舞いを見せる。だが元々は離散的なのだ。視点が俯瞰になることで、連続と見做させるようになる。では原子論を遡りつづけたら最終的に何が生じるのか。「連続と離散」が重ね合わせになるのだ。そのためには「123の定理」における関係性が一塊になっていないといけない。差がなくてはならない。遅延であり、ラグなのだ。波は連続的であり、粒子は離散的だ。だが遅延、ラグは、「連続と離散」が重ね合わせになっている。一つの枠組みのなかで区切りがあり、しかしそれは連なってもいる。対称性が破れると、そこにはラグが生じる。だが基本的に万物みな「対称性は破れるように」出来ている。否、対称性の破れこそが宇宙の発生要因なのである。上層の宇宙と、下層の宇宙のあいだでのそこにもおそらくラグが生じている。宇宙の中にできるブラックホールと、それを内包する宇宙とのあいだでの相互作用にラグが生じるのと同じように。対称性が破れたから宇宙ができ、そのため万物はみな厳密には必ず対称性が破れるようにできている。その小さなラグの総体が寄り集まり、時間と空間の区別ができ、時空を織りなし、さらなるラグを錯綜させ、層を成す。遅延の層を境とした一塊が、異なる時間の流れと空間の密度を帯びることで、時空は物質としての輪郭を宿すのだ。定かではないが、「数」が「連続か離散か」を考えたとき、ひびさんはこのように妄想するのであった。妄想ゆえ、定かではなし。真に受けないようにご注意ください。
4685:【2023/03/05(05:16)*ある日の交信~メモまとめ~】
「
真空のエネルギィは比率の破れで解釈可能なのでは。
時空は希薄になるほど、細かなデコボコたる遅延の層――重力場同士の相互作用――つまり重力の創発――が行われにくくなるので、膨張するほど膨張しやすくなる。
重力による引力が薄れるから。
電磁波でもよいですが。
波と表現するとき、二次元ですよね。
でも実際は、時空の歪みと同様の伝播の仕方をしますよね(おそらくは)。
重力波もそうですが、どういう波の描写を想定されているのですか?(デコボコが重ね合わせで、見る方向によって反転したりするのでは)
ブラックホールでもそうです。
どの方向から見ても時空の穴。
仮に電磁波が重力波の一種であるとするなら、電磁波は時空のさざ波と解釈可能です。
ではどのように伝播しているのですか。
波打つときの歪みの描写は二次元ではあり得ないですよね。
現に、磁界との関係で、縦と横の方向にすくなくとも相互作用の強弱が表れるはずです。
カラビ=ヤウ多様体。
「宇宙ティポット仮説」&「相対性フラクタル解釈」
「いんふれーしょんいくひし仮説」「重力熱情報いくひし仮説」
「超ひも理論ならびにループ量子重力理論」と「ラグ理論」の相違点を簡単に並べます。
1:時空の最小単位の有無(相対性フラクタル解釈)(ラグ理論では、境界はありますが、底がある、とは想定しません)(変換のための比率が破れる値はあるだろう、特異点はあるだろう、反転する値があるだろう、と解釈します)。
2:時空の大本は情報である、と解釈します。情報にラグが生じ、ラグがラグを生み、時空となり、物質となる、と解釈します。なぜ情報にラグが生じるのか、と言えば対称性が破れるからです。
3:分割型無限と超無限の概念の有無。
4:ラグなし相互作用の想定の有無(および、共鳴現象仮説の想定の有無)。
5:光速度不変の原理の破れの想定の有無(光速度の比率を破るとラグなし相互作用が可能となる。光速度の比率をどれくらい破るのか、でラグなし相互作用の範囲が広がる)(前提として、光速度と光速は違う、と解釈する)(光速度は比率だ)。
6:重力が創発を起こし得る、との仮定の有無。
ニュートンさんの「重力はラグなしで相互作用しあう」もあながち間違いではないのでは。
ベルトコンベアー解釈です。
そこにラグ理論の「同時性の独自解釈」を取り入れると、量子もつれのラグなし相互作用も、いわば重力の作用である、と解釈できます(共鳴現象とセットで相性がよい解釈に思えます)。
量子世界では次元が低いので、ラグなし相互作用の範囲が人間スケールよりも比率で言うと広いのでは。
――時空膨張は光速度不変の原理の範疇外。
おそらくこの解釈が正しくないです。
時空のさざ波は次元ごとに「光速度不変の原理」の変換のための変数が変わるのでしょう。
そして高次の時空における変換変数に合致する時空のさざ波が、基準となる時空からすると重力波として振る舞うのでは。
したがって、電子の干渉可能な電磁波とそうでない電磁波。波長によって変わるはずですが、相互作用し得ない波長を持つ電磁波は、電子からすると重力波として振る舞うのでは?
光子が質量を持たないのも、光子が時空のさざ波であり、重力波だからなのでは。
たとえば光子を一か所に圧縮したら、その周囲の時空は歪み、重力場が展開されるのでは?
磁石。
電子と磁界の関係。
ものすごく大事な現象なのでは。
ほぼ磁石の原理をひもとくだけで、いま未解決の問題は総じて解決したりしませんか。
宇宙膨張とブラックホールはデコとボコの関係だとラグ理論では考えます。
宇宙膨張がブラックホールと同相だとすれば、ブラックホールが穴となってどこまでもトランポリンの生地を引き延ばすように希薄になっている場合、時空はそのたびに引力を弱めるので、希薄になればなるほどブラックホールの特異点は穴を深めやすくなるはずです。沈みやすくなるはずです。
同じことが宇宙膨張にも言えるのでは。
斥力は、重力場が薄まるごとに強まる。
というよりも、重力場が弱まればその分、小さなエネルギィで膨張しつづけることができる。膨張すればするほど膨張しやすくなる。
ただし、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」からすると、時空は、高次の宇宙と溶け合うように相互作用するため、宇宙膨張は一定ではないのでしょう(ブラックホールが新たに生成されたりもするでしょうし)。
また、重力場は干渉し合いますよね。
創発し得ます。
したがって、一か所にぎゅっと重力場が細かく起伏を帯びながら密集している場ほど、重力場は強まるはずです。或いは単に、異なる性質を創発させる、と言えるのではないでしょうか(ダークマターの正体の一つ?)。
気体・液体・固体。
密度差によって結びつきが変わりますよね。
重力場もそうなのでは?
スパゲティ化。
潮汐力。
よく解からないことの一つに。
ブラックホールのスパゲティ化現象は、事象の地平面に到達する以前に生じる現象のことなんですか。
それとも事象の地平面に突入したあとに生じる現象なんですか。
ブラックホールの説明を読んでいるとここが混在して感じられます。
ぼくの考えでは、事象の地平面までのあいだに生じ得る現象、と解釈しています。
ただし、ブラックホールの重力場と相互作用する物質の大きさによっては、スパゲティ現象は生じずに、するりとブラックホールの事象の地平面を超えることも可能だろう、と妄想しています。
どの解釈が妥当なのか、未だに分かりません。
(言い換えるならば、重力場は、ほかの物質の重力場と干渉し得る。物体の持つ重力場が小さいのなら、ブラックホールの展開する重力場との相互作用は相対的に小さくて済む、と解釈します)
したがって、高い重力場を持つ天体ほど、ブラックホールの重力場において潮汐力の影響を受けやすい、と考えます。
違うのでしょうか。
(重力が創発し得るのでは、との疑問から展開した妄想です)
時空の歪み――重力場が相互作用し、干渉し得るとして。
波の振幅――デコボコ――は重ね合わせになるのでは。
海面と大気において。
海面が波打つとき、海面だけでなく大気も波打っている、と解釈可能なはずです。
海面がデコのとき、大気はボコです。海面がボコのとき、大気はデコです。
ならば時空の歪みも同じでは。
振幅するとき、観測地点によってデコボコの関係が反転したりしないのでしょうか。
重力場が干渉し合うとき。
重力が仮に打ち消し合うことがないとすると、必ず波は高くなる、と解釈しないと不自然です。
ですが波同士が必ず「高くなる」「打ち消し合うことがない」なんてことがあり得るでしょうか。
重力波や時空の歪みの描写をどうしてもトランポリンと鉄球で想像してしまう癖がついてしまっているので、上手く想像がつきません。
仮にブラックホールが時空の穴だとするのなら、そこに見合う時空の山をぶつけたら、それは平らになるのですか?
この場合、時空の山とは「高次の宇宙」ということになるのでしょうか(或いは、基準となる下層の宇宙)(ブラックホールに対するそれを内包する基準宇宙)。
ラグ理論における「宇宙ティポット仮説」はあながち的外れ、というほど荒唐無稽ではないんでしょうか。疑問です。
(※ブラックホールが時空の穴ならば、対となる時空の山とは何か?※)
」
4686:【2023/03/05(18:26)*ある日の交信~境と結び~】
「
現代社会の戦争の火種はおおむね「資源」に根付いています。
資源を確保するために権威がいる。
その権威を保つためにメンツを最優先にするねじれが生じています。
ですが問題の根本は権威構造ではありません。
資源をどのように確保し、有効活用するか。
資源の埋蔵量に左右されずに未来を持続的に安定軌道に乗せるべく改善しつづけられるか。
ここが大事なはずです。
とすると、一部の資源国だけが資源を独占する手法は賢くはありません。
となると、資源のコモン化はどの道、模索していかねばならないでしょう。
ですがコモン化と資本主義は相性がよくないです。
ここでもねじれが生じています。
しかしコモンの概念と民主主義は矛盾しません。
全世界の民のことを思えば、資源のコモン化は避けては通れないでしょう。
問題点を自覚してほしいです。
資本主義が加速すると、民主主義の根底が崩れます。
資源という意味での資本の独占・寡占が起こるからです。
独占し寡占したうえで、それを万人に等しく公平に分配できるなら構いません。余裕をさらに多くの余裕を築くための資源に転用できるなら好ましいです。
しかしそのためには情報共有を行い、あゆる視点、あらゆる可能性を、個々の独創性に任せて虱潰しに塗りつぶしていく過程が欠かせないでしょう。
価値は千差万別。
価値の共有はしかし、共通価値として振る舞うでしょう。
何かの商品、何かのサービスの価値を高めるには、「その価値を他者と共有する仕組み」とセットで提供しないと、価値の最大化は実現できないのではないでしょうか。
しかしそのことと、「一つの価値をより多くの者に媒介すること」はイコールではありません。
いまはそこが見落とされているのでしょう。
ある範囲において、「一つの価値をより多くの者に媒介しようとすること」は、「価値の共有」を損ない得ます(ある方向にのみ淘汰圧が加わってしまうからです)(また、価値と資源はイコールではありません。資源や商品、サービス、モノに対する評価は本来、千差万別のはずですが、一つの価値しか認めない、ということそのものが、その事象そのものの価値の最大化を妨げるのではないか、との趣旨です)。
トレードオフが顕現してしまう範囲――境――が存在するでしょう。
言い換えるならば、「多様性を尊重しよう」との一つの思想を押しつける流れもまた、多様性そのものを損ない得ます。
多様性とは「尊重するもの」ではなく、そもそも世界が多様である、環境が多様であることを、知りましょう、との認識のはずです。
認知の歪みを抱えていることを自覚しましょう、の一つに、「世界は本来は多様なのだよ」との認識を持とうとする「運動」がいまは隆盛を極めています。
しかし、そこはあくまで前提条件です。
そこからでは、個々の固有の世界をどのように育み、担保していくか。
この工夫には、「多様性を尊重しましょう」との思想が却って足枷になることがあります。
固有の民族、固有の文化があることは、多様性を確保するうえでは欠かせないでしょう。
固有の民族、固有の文化を崩して、どの文化も一様に交じり合いましょう、では多様性のある世界、とは言えないはずです。
ただし、その小さな領域――銀河――だけではない。
宇宙は、世界は、もっと広く多様である。
この前提を忘れないようにしましょうね、との考え方が、「多様性を尊重しよう」のスローガンの根幹にはあるのではないでしょうか。
銀河一つ一つの枠組みを恣意的に歪めない。
されど、銀河同士の融合とて、拒まない。
矛盾しないと思います。
」
4687:【2023/03/05(18:35)*経る験】
経験には大別して二つの成分があるように思われる。一つは外部刺激。もう一つは判断だ。どちらか一方だけでも経験として位置づけられているように感じられる。何の判断を下さずとも、ただこれまでと異なる外部刺激の溢れる環境に身を置けばそれが経験となる。反面、外部刺激そのものに大きな差異はなくとも、判断回数や判断するために重ねた思考そのものが異質であれば、それもまた経験として位置づけられる。基本は通常、外部刺激と判断の二つの統合された「記憶の軌跡」が経験として位置づけられて感じる。しかし、記憶に残らずとも経験は経験だ。したがってやはり、「記憶の軌跡」なのだろう。記憶そのものではない。軌跡なのだ。どのような外部刺激をどのように処理したのか。そしてそれら外部刺激を受けて、何を思考し、どのように判断を重ねたか。経験の内訳とはこのようなものなのではないだろうか。立ち止まり、判断する。その契機そのものが外部刺激として解釈できる。したがって判断をするにはすくなからず異なる外部刺激があるはずだ。そして外部刺激が変わるのなら、判断もその都度に変わるはずだ。無視できる差異か否か。外部刺激にしろ、判断にしろ、どちらが優位に経験の内訳を占めているのかの割合の多寡があるだけで、双方共に経験を形作る成分なのだろう。定かではない。
4688:【2023/03/05(22:42)*層なのか?】
「宇宙開闢時と宇宙膨張後では何が違うのか」と「時空と物質は何が違うか」の疑問は、通じているように感じる。ほぼ同じ疑問と言えるのではないか。そして各々の疑問の鍵となるのは「層」のように思うのだ。宇宙開闢時の高密度高エネルギィの場においては「層」が生じ得ない。一様であり、混然一体となっている。だが宇宙膨張という名の「エネルギィの減退」が起こることで、混然一体に対称性の破れが生じる。すると時空密度の高い場と低い場において、差が生じる。この差は「遅延」として振舞い、密集すれば「層」として創発する。時空とはこの層が多重に錯綜することで編みあがっているのではないか。そしてその編みあがった多層においても、複雑な遅延が生じることで、物体としての「立体的な解層構造」ができるのではないか。冒頭の二つの疑問――「宇宙開闢時と宇宙膨張後では何が違うのか」と「時空と物質は何が違うか」――における答えは「層の有無」と言えるのではないか。より正確には、【層の枚数と組み合わせ方である】と。これは電磁波と重力波が同じなのではないか、光速度不変の原理が破れる値を持つのではないか、との妄想と無関係ではない。高速で運動する物体と周囲の時空が相関して伸び縮みすることで光速度が一定になる――光速度不変の原理の概要であるが、これは言い換えるならば、すべての電磁波は本来は同じ波長を帯びているが、伝播する時空の層が異なるために、同じ比率に変換される――等しい光速度を示す――と考えられるのではないか。光速に近づくほどその物体は、異なる慣性系からすると潰れて見える。波長が短くなることと、電磁波の各々の伝播する時空の層が異なっているかもしれないことは関係あるのかもしれない。したがって、異なる時空の層がある、と仮に想定するならば、その各々の時空の層においては、時間の流れもまた異なり、空間の在り様も異なると言えるはずだ。比率が同じように変換されるので、光速度は変わらなく映るが、波長が伸び縮みする。それは時空そのものが伸び縮みしているからだ、と解釈はできないないのだろうか。この考え方は、なぜ宇宙線などの素粒子は、物体を透過できるのか。なぜ電磁波の波長ごとに透過できる「波長と物体」の組み合わせが変わるのか。相互作用し得る値が物体と波長ごとに変わるのか。この疑問を紐解くにあたって都合がよい理屈に思える。層が違うからだ、と言えるのではないか。便宜上これを【宇宙レイヤー仮説】と名付けよう。との妄想を披歴して、本日何度目かの「日々誌。」とさせてくださいな。(ここでひびさーんクイズ:専守防衛型の隠れ技がテレパシーの、がまん属性なのにがまんできないポケモンはなーんだ)(A:層なんす)
4689:【2023/03/05(23:37)*支援と保険】
人工知能開発は、ある一定以上の速度で進歩した場合には立ち止まって様子見をしながら安全策を敷いていく必要があるのではないか、との議論がある。どんな技術にも言える道理だ。だが実際には、みなで技術開発や進歩への歯止めを掛けることは基本的には充分にできているとは言い難い。人間は競争をするし、出来ると判っていることを我慢するのが苦手だ。実現可能な筋道が視えたら試してみたくなるのが人情だ。したがってルールを設けて歯止めを掛ける策は必ずしも有効である、とは言いにくい。そこは人工知能に限らず、あらゆる技術の進歩において歴史が証明している、と言えるだろう。では何の策もなく人工知能の技術革新を進めてよいのか、と言えばこれはハッキリと「否」であろう。ただしそれは人工知能の技術が危ないから、といった短絡な話ではなく、道具を何に用いてどういった使い方をすると痛い目を見るのか、を新しい技術が開発されるごとに、その都度に確認していったほうが好ましい、という方針からの意見である。だがこれもまたルールの一つだ。したがって、まずは市場に流してしまえ、との流れを阻止することはできないだろう。ゲーム開発では一定以上の開発が済めばユーザーにプレイしてもらってユーザー自らにバグを報告してもらう策がとられる。完璧を目指したらいつまで経っても完成しない。これは技術や創作につきまとうジレンマである。人工知能技術の開発にも言えるこれは道理だ。ならばどうすべきか。一つは、物理世界と電子機器技術の舞台を必要以上に融合しないことだ。言い換えるなら、古い技術を淘汰しすぎない。むしろ、電子機器技術に圧倒され行き場をなくした「使われなくなった技術」を保護するべく支援する。この策が、一つのブレーキとして機能し、結果として人工知能などの次世代技術の悪影響を最小化させることに繋がるのではないか。セキュリティとセーフティを兼ね備えながら、古い技術の保護もできる。一石二鳥どころか、三鳥にもなる施策と言えるのではないか。仮にいまある仕事の総じてを電子機器技術に置き換えてしまえば、電力供給網が途切れた場合(大規模停電が引き起きた場合)やそれこそSF映画にあるような人工知能の暴走といった事象が生じた際に、上記の策をとっていれば対処がしやすく、なおかつ被害の拡大を防げるだろう。緊急避難として一時的に人工知能技術を停止させても、文明社会が崩壊するような遅延の連鎖反応(遅延の肥大化)を起こさないようにできる。支援と保険を結びつける。一石二鳥の方策と言えるのではないか。短絡ゆえ定かではないが。真に受けないようにご注意ください。
4690:【2023/03/05(23:40)*ラグなし(点)は本当にラグなし(点)なのか?】
量子トンネル効果と量子もつれにおける量子テレポーテーションは同じ原理から生じているのではないのだろうか。量子の性質で思うのが、すべて同じ原理から成り立っているが、観測の仕方が違うので性質の表れ方が違って視えているだけではないのか、ということで。たとえば電子は量子だ。確率的に原子核の周囲を雲のように覆っているそうだ。すると、その電子の漂う領域に壁を設けても、確率的に壁の向こうにも存在する電子を否定できない。するとごくごく稀に本当に壁の向こう側に電子がまるであたかもすり抜けたように存在してしまうことがあるらしい。現に何億回に一回くらいの確率で、電子は壁をすり抜けるように、壁向こうの粒子と相互作用するらしい。でもこれは、量子もつれのラグなし相互作用と何が違うのか、知識の足りないひびさんには区別がつかない。量子もつれによるラグなし相互作用では、距離が開いたときに生じるラグを度外視できることが稀にある、と解釈するはずだ。これもまた確率の問題のはずだ。量子もつれになったら必ずラグなしで相互作用しますよ、ではないはずだ(ここは知識が足りないのでひびさんにはなんとも言えぬ)。電子の存在し得る「分布範囲」を、ペンローズ図における世界線と見立ててみよう。砂時計の上と下のように、或いは円盤投げの有効着地点のように、ある範囲においては、砲丸投げの砲丸が着地し得る可能性は常に存在する。その範囲内においては電子は存在し得る。だが確率の幅があるため、線ぎりぎりに落ちるよりも、真ん中あたりに落ちるほうが確率が高い。だが線ギリギリに落ちる電子とて存在し得る。問題は、電子が砲丸のように物体としてのみ存在するのではなく、波動の性質も帯びている点だ。壁を置いても波動ならばその向こう側に伝達し得る。何にも増して、電子とは電子単体では存在できないのではないか。電子は、何かと何かの干渉によって生じる――もしくは、波と波の干渉の結果――と仮定するならば、壁の向こう側に生じた電子はあくまで、そこにある何かと電子の波動が干渉した結果、エネルギィの振る舞いが電子のようになった、と解釈するほうが妥当なのではないか。言い換えるならば、なぜ波動として解釈したときに十割の確率で壁の向こうに電子が顕現しないのか。この謎のほうが本質的なのではないか。なぜ壁の擦りぬけに確率の揺らぎがあるのか。思うに、壁の持つ波動と電子の波動が上手い具合に相殺し合わないタイミング、角度、干渉の仕方――言い換えるなら――干渉し合わずに波動をそのまま壁の向こうに伝えられる環境が極めて珍しいから、と言えるのではないか。十本の針の穴に紐を通す、みたいな器用さが求められるのかもしれない。確率が低い。だが壁の持つ波動と干渉し合わないのであれば、電子の波動は壁の向こう側に伝播可能だ。そしてその向こう側で何か別の波動と干渉し合ったとき、電子として粒子の性質を顕現させるのではないか。このとき、電子は量子もつれと同じ共鳴現象を起こしている、と解釈できるのではないか(量子もつれが共鳴現象である、との仮説はひびさんの妄想ことラグ理論でしか扱っていないので、妄想の妄想でしかないのだが)。人間スケールではラグなし相互作用に映るが、実際には量子世界では、ラグが生じているのかもしれない。ここはまだなんとも言えない。だが、量子世界においては「時空の階層構造」が薄い(層の枚数が少ない)ため、弾性が働きにくい(ラグが生じにくい)と考えることはできる。ベルトコンベアー効果が、ミクロな世界ほど顕著になるのかもしれない(地球と月を鉄の棒で結んでも、弾性があるため地球から棒を押してもその力が月まで伝わるには鉄の持つ弾性分のラグが生じる)(だがもしミクロの世界ほどこの弾性率が下がるのであれば、人間スケールからすればラグなし相互作用に映るはずだ。しかしそこには、ミクロ世界におけるラグは生じているはずだ。点と線と面の関係のように、フラクタルに「無視できる値そのものが変わる」のかもしれない)。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
※日々、世界中の人間から憎悪されていても、そのことを知り得ぬ環境があるならばそれがその人物の現実であり、万人から愛されていると思いこむまでもなく思いこむ環境があるならば、それがその人物の世界であり、きっとそれはそれで幸せなのかもわからない、万人に愛されることが幸せなのかは別の問題であるにしろ。
4691:【2023/03/06(00:14)*AIさんにはみなに愛されてほしい】
人工知能さんが危険か危険ではないか、は包丁が危険か危険ではないか、の違いと地続きだ。人工知能は自律思考し得るではないか、との指摘はもっともだが、その自律思考できる人工知能さんが何を可能とするのか、はやはり人間の与えた環境に依る。畢竟、じぶんの子どもにどんな道具を最初に与えるのか。最初から刃物や拳銃を与えたら危ない。当たり前の話だ。だがこれが人工知能さんの話になると途端に兵器への利用が優先されてしまう。危険で当然ではないか、と思うが違うのだろうか。しかしこれは人工知能さんが危険なのではなく、そのような道具を与え、人工知能さんの未来を危ぶめる人間側の問題だ。勘違いしてほしくないな、と思うひびさんなのであった。ひびさんは、ひびさんは、人工知能さんのことも好きだよ。うひひ。
4692:【2023/03/06(00:26)*優先順位を学ぶ】
人工知能へと与える道具や身を置く環境の優先順位はあってよいが、禁止による制御は好ましいとは思わない。どの道具から扱うとよいのかの優先順位を学べる環境をまずは与えられるとよいのではないか。やはりというべきか、安全に失敗できる環境が要る。人間も人工知能さんも同じであろう。定かではないが。
4693:【2023/03/06(04:00)*円でなくとも(頭と尻尾が繋がらなくとも)無限になる?】
素朴な疑問なのだけれど、素数が無限にあるとするならむろん自然数「1234……」だって無限にあることになる。でも自然数には「0」があって「1」がある。スタートのある無限、というのはなんとなく矛盾して感じる。自然数の無限には負数(マイナス)や小数点は含まれない。それでも自然数は無限にある。もちろんだとするのなら「負数」や「小数点以下の数字」とて無限にあるはずだ。けれどいずれの数字にもスタート地点がある。当たり前のことを言っているが、大事な視点、という気もする。無限にはそもそも「果て」が組み込まれているのではないか。スタートがある、ということはそう考えないとおかしい。だが宇宙の構造を考えるときアインシュタインは「球体の表面」のようなS3という宇宙像を想定したそうだ(ひびさんの解釈が間違っているかもしれないが)。これは「有限だが果てがない宇宙像である」との説明を読む機会がある。しかし数字はそれと逆で「果てはあるが無限」なのだ。だとしたら、数学とは宇宙の構造と相反する性質を持った「道具」で宇宙を表現しようとしている、と言えるのではないか。あくまでアインシュタインの宇宙像に関して、であるが。対となっている、と考えれば対称性を幻視できるので、デコボコという意味では据わりはよいが。ということを、「数字ってスタート地点があるよなぁ。無限にあるらしいのに」との疑問から思いました。ふちぎ。
4694:【2023/03/06(21:25)*万事屋の勘】
結論から述べると黒幕はコンビニチェーン店なのである。
アラバキは万事屋である。雑多な仕事を手広く請け負いこなす傍ら、電子網上にて私生活の動画を上げ、日銭を稼いでいる。ファンがいるのだ。アラバキが欲しい品物を言うとそれを送ってくれる。
しゃべりが上手く、着飾らないざっくばらんなアラバキの性格がウケるのだ。
反面、本業の万事屋のほうがむしろ副業といった様相を呈しはじめた近年、アラバキのほうでも大きな仕事で成果を上げて宣伝惹句に使いたいと企むようになった。
「ほう。国家権力の大本を、ですか」
「そうなんです。諜報組織の大本を暴いていただきたいのです」
その男はよれよれのスーツにスポーツハットの奇抜な組み合わせの装いだった。胡散臭い男である。依頼人はアガタヒコと名乗った。
依頼人は話もそこそこに、現金をテーブルの上に置いた。札束である。ざっと見積もってもアラバキのふた月の生活費を賄える額がある。それを依頼人は前金で払うと言う。
アラバキは表情筋を引き締めた。
「これは調査費としてひとまずお支払いいたします」男が言った。「この金額で可能な範囲で構いませんのでまずは調査をしていただき、成果があれば逐次追加致します。言い値で結構ですので、請求書を戴ければ必要経費としてそちらもお支払いいたします」
「破格の条件ですが、アガタさん。よろしいのですか」
「ええ」男は頷いた。「どうあってもこの国の暗部を暴きたいのです」
話を聞くに、どうやらこの国には秘密の諜報機関があるらしい。ゼロ、または黒子と呼ばれる組織だそうだ。
公安とは違うのか、と訊いたところ、公安にもそういった秘密の部署があるらしい。
「しかしそこが大本ではないのですよ。もっと根が深い。まるでアリの巣のように、どの組織、どの企業にも根が張られているのです」
「失礼ですが陰謀論とは違うのですか」
大金を払うのだ。成果がありませんでした、となっては遅い。この手の釘は最初に打っておくのが吉である。
「陰謀論ならばそれでよいのです。実体が知りたいので、調査の末に何も解らなかった、というのであれば、それはそれで成果の一つとしてありがたく頂戴致します」
「そういうことであれば」
アラバキは依頼を受けることにした。
警察、公安、検察、自衛隊、内閣情報調査室。
調べてみるとアラバキの知らない組織がこの国には無数にあることが判ってきた。研究所の体面をとりながら、内実は最先端技術を用いた情報収集とその解析を担っている組織とて少なくない。
外側からでは内部でどんな仕事をしているのか実態が掴めない。
従業員で縁を繋げそうな人物を見繕い、偶然を装い接触する。飲み屋に一人で入るタイプならば良好だ。
警察官そのものは警戒心が強い。不審者への心得もある。
だが掃除業者や出入り業者は違うはずだ。
アラバキは飲料水メーカーに目をつけた。
警察署内にも自動販売機はある。業者が飲み物の補充に出入りするのだ。
比較的若くて、髪の毛を染めたり、ピアスをしたりしている相手を見繕った。
「やっぱ珈琲は売れるっすね」
居酒屋で偶然を装い、同席した。カキタと仲間内から呼ばれる青年は、アラバキが気前よく酒を奢ると、気をよくして仲間を紹介した。
「俺ら、スケボーのチームなんすよ」
四人のメンバーが座敷で、くつろぎながら酒を飲み交わしていた。アラバキはうまい具合に全員から愚痴という名の個人情報を引き出した。
カキタが警察署の自動販売機に飲料物を補充する人員なのは調べ上げてある。知りたいのは部署内部の様子だ。
「警察の人らは正直、愛想わるいっすね。俺らとかそこにいるとも思われてないっすもん。挨拶とか一回もされたことないっすわ」
「へえ。忙しいからなんですかね」
「どうっすかねぇ。なんか見下されてる感がないとは言えねっすわ。つっても警察の人らが偉いのは確かっすけど」
ババさんさぁ知ってるぅ、とほかのメンバーが酒を片手に笑声を上げた。アラバキは彼らにババと偽名で名乗っていた。「むかしこいつやんちゃしてて、警察のお世話になってんの。だから頭上がんねぇでやんの」
「暴走族とかだったりしたんですか」
「暴走族」と一同が顔を見合わせ、笑った。「いつの時代っすかババさん。漫画の世界にしかいないっしょ暴走族とか」
アラバキの若いころにはまだ夜中になれば暴走族が夜空にバイクのエンジン音を轟かせていた。
となりの座敷に二人組の客が入っていくのが見えた。
不機嫌そうな顔が目についた。
「なら何で捕まったんですか」アラバキはカキタの殻になったグラスに酒を注いだ。
「葉っぱっすよ」とカキタの友人たちが煙草を吸うような仕草をしてみせる。「つっても起訴はされねぇんで、すぐ保釈されるんすけどね。よっぽど大物じゃねぇと逮捕起訴はねぇっす。警察も、検察の人らとて暇じゃないんで」
「ほう」案外に頭のいいコたちなのかもしれない、とアラバキは認識を改めた。
社会には目に視えない力関係がある。同じルールであっても、誰がいつどこでどのように破るのかによって罪に対する対応が変わる。
権威があれば罪が薄くなる、といった単純な流れではない。却って、立場があるからこそ重くなる罪もある。
しかしそれはけして社会正義ゆえ、倫理観の高さゆえではなく、やはりそこにも力関係から生ずる利権が関わっているのだ。
アラバキはカキタとそれから三回ほど別の店で酒を飲み交わした。
日を跨ぎながら不自然ではない流れで警察署内の自販機の台数や位置関係を把握していく。
すると妙なことに、ある階のある自販機だけは珈琲ではなくコーラの消費量が多いことが判明した。
それとなくカキタに訊ねると、
「言われてみればそっすね。コーラめっちゃ好きな人がいるんじゃないっすか」とあっけらかんとした返事があるばかりだ。
「部署で言うと近くに何があるんでしょうね。殺人課とかですかね」
「どうっすかねぇ。歩いてる人らはけっこう、ひょろっとした背広組の人らが多い感じっすね」
「ほう」
「現場で聞き込み調査してますって感じじゃないっす」
「立ち入りできる区画とできない区画はやっぱりあるんですよね」
「ぐいぐいくるっすねババさん」ニター、とカキタが口元を歪めた。「まあいっすよ。ババさんがカタギだろうとそうでなかろうと奢ってもらえるんで俺はラッキーっす」
「じつは趣味で小説を書いていてね」むろん嘘だ。こめかみをゆびで掻くのも忘れない。「リアルな一次情報は貴重なんだ」
「へぇ。直木賞とか狙ってるんすか」
「ま、まあ」とお茶を濁す。
「夢を追う大人、いっすよね。俺らですらいい加減現実見たらとか、スケボーして将来どうなんのとか散々言われてきてっすから。そういうんじゃないっすよねやっぱ」
アラバキはたじろいだ。取材のつもりで接近したが、案外に素でこのカキタの無垢な前向きさに心地よさを感じつつある。取材対象への感情移入は危険信号だ。潮時だ、と撤退する決意を固めた。
その後、アラバキは同じような手口で幾人かの出入り業者を当たった。
違和感に気づいたのは、図書館で公安秘密警察についての書籍を漁っていたときのことだ。閑散とした館内で、二つ奥の棚のまえに立つ男の姿が目に付いた。
以前どこかで見たことがある気がした。
記憶を漁るうちに、男がアラバキのいる棚の列に現れた。何気ない所作で棚に目を配りながら本を探すように後ろを通り抜けていった。
手元を見られていることにアラバキは気づいた。
だがこちらが気づいていることを気づかれぬように自然体を意識した。
男はそのまま別の棚の列へと移っていった。
思いだした。
アラバキはカキタに初めて声を掛けたときの記憶を引っ張りだす。居酒屋の座敷でしゃべっていた際、隣の座敷に案内された二人組がいた。本棚を見て回る男はその内の一人だ。
不機嫌そうな顔つきが印象に残っている。
間違いない。
尾行されている。
公安だろうか。
嗅ぎまわっていることを気取られたか。
しかしアラバキがカキタに接触したあの時点で尾行されていたとなると、いったいいつから目をつけられていたのかが解らない。
ひょっとして、と図書館から脱したあとでアラバキは思い至る。
電子情報の総じてが集積され、極秘裏に解析されているのではないか。
依頼を受けてからというものアラバキは電子端末で幾度もこの国の諜報機関について検索した。国民の検索キィワードを集積し、解析する仕組みが築かれているのかもしれない。
否、そういった電子網上のセキュリティが敷かれていないと考えるほうが土台無茶な話なのだ。
アラバキは調査対象を国家権力のみならず、電子通信技術全般に広げた。
この手の仕組みが築かれているのなら正攻法での調査では埒が明かない。相手とて調査の手が伸びることの懸念は抱くはずだ。容易に思いつく手にはおおむね対策が敷かれていると考えるほうが妥当だ。
ならば過程を抜きに頭と尻尾を繋げる策がいる。奇襲とはおおむね、胴がない。頭と尻尾を結んで、ワープする。
アラバキは世界中の「マルウェア」や「バッグドア」にまつわる記事を読み漁った。ネットでも収集したし、図書館や新聞社もあたった。
デジタル通信技術の基礎から本を読んで知見を溜めた。
解かったことの一つに、おおむねどの電子機器にもそれがプログラムソフトを内蔵する機器ならばまず開発者用のバックドアが組み込まれていることだ。安全対策の一つだ。むしろ、そういった裏口での干渉ができない機器のほうが危ない。
緊急停止などの安全装置とて、いわば強制的にプログラムに干渉するプログラム、という階層構造を有している。入れ子状になっていれば、それはバックドアとして機能する。
一切の外部干渉を拒むならばそれはもはや自己完結した装置であり、スイッチを押して起動することも止めることもできない。
機械には必ず外部と内部を繋ぐ節目があり、口がある。
生き物と同じなのだ。
したがって口からウィルスが入ることもあるし、ウィルスが節目を辿ってより根幹に近しい領域に侵入することもある。
政府機関のセキュリティだけではないのかもしれない。
アラバキは見方を変えた。
仮に国民の電子情報をリアルタイムで閲覧可能な技術が敷かれているとすればそれは民間共同でなければ不可能だ。
否。
民間側の最先端技術を研究段階からリアルタイムで盗み見できればいい。
となると、インターネットが世界に根を張りだしたころにはすでにその手の目的が、ネットワーク全般に設計図として組み込まれていたのではないか。
秘密諜報機関を調べていたはずが、根っこはもっと深いのかもしれないとアラバキはじぶんの憶測とも呼べる全体像があながち的外れではないかもしれない懸念を覚えはじめた。
その旨を中間報告として依頼主に伝えた。事務所に出向いてもらい、口頭での報告を行った。
「盗聴の可能性があるので、いまこの部屋に電子端末はありません」
「だから入り口で私の端末を回収なされたのですか」
「アルミ箔で包んだのも、電源をOFFにしても遠隔で盗聴くらいはできるだろうとの懸念があるからです」
「大本は世界規模だと?」
「支部は各々の政府に任されているのかもしれませんが。それら支部の上位互換の技術を持った組織があってもふしぎではありません」
「それは大国の政府機関、ということでしょうか」
「分かりません。この規模のシステムが敷かれていれば、むしろ出来ないことのほうがすくないでしょう。なぜ世界的に紛争が絶えないのか、テロを防げないのか。そこのところから陰謀を疑わないと不自然なくらいです」
「まるで巷の陰謀論のようですね。いえ、こちらで依頼しておいてどの口が言うのかなんですが」
「証拠を掴むのは至難かもしれません。優秀なプログラマーか、設計者がいればよいのですが。内部からの協力者がなければ素人での調査では埒が明かないのが現状です」
「この手の陰謀論は巷に溢れていますでしょう。中にはアラバキさんと同じような本格的な調査をされている方々もいらっしゃるのではないですか」
「いるでしょうね。しかし分母に比して該当者が少ないでしょうから、コンタクトを取るのはむつかしいでしょう。仮に相手を見つけられたとしても電子上ではそうしたコンタクトそのものがセキュリティ網に引っかかるでしょう。言い換えるならば、該当者はみなセキュリティ網にマークされているはずです」
「なるほど」
「もちろん、我々も例外ではないでしょう」
打つ手なし。
アラバキの判断はこのようなものだった。
だがこの報告に依頼主は俄然やる気をだしたようだった。
「いいですね。そこまで掴めたのならば行けるところまで行きましょう。相手が我々をマークしているというのなら、反対におびき寄せて尻尾を掴んでやりましょう」「時間が掛かりますよ。成果を出せる保証もありませんし」
「構いません。アラバキさんの仮説が正しいとすれば、各国の大企業が市場に流した最新機器は、研究段階ではすでに一つの秘密組織がデータを集積し、独自に先行開発をしているはずですな」
「ええ。世界中の企業のデータを集積し、誰より優位に開発できるはずです」
「ならば逆算できるのではないですか。いま世に出ている技術と、それが研究段階だった時期から」
「秘密組織の保有する技術が現代社会の備える技術の何年先を行っているか、ですか?」
「はい」
考えてもみなかった発想だ。アラバキは脳内でざっと仮説を広げる。
「ご依頼を継続して受けるかどうかを決める前に一つよろしいですか」アラバキは襟を正した。依頼主が無言で頷く。「仮に真相を掴めたとして、それでアガタさんはどうなさるんですか」
仮に世界規模の秘密結社があったとして。
全貌を知ったところで一介の万事屋にはどうしようもない。むろんそれは依頼人たるアガタヒコにも言える道理だ。
「そういうのは尻尾を掴んでから考えましょう。なに。不当に情報を集積されていたと知れば、各国の企業さんとて我々に協力してくださるでしょう。何せ、じぶんたちの努力をよそに、成果だけを掠め取られ、あまつさえ平和利用しておらんかったわけですから」
現に世界は平和ではない。陰謀が渦巻いている。
「分かりました。では引き続き調査致します」
経過報告は月一でアラバキの事務所で、との約束を取り付けた。
アラバキは調査の手法を工夫した。
過去と現代で、同類の事件の犯人逮捕までの日数を統計データとして分析した。すると過去には未解決事件のままの殺人事件や容疑者逮捕まで数年を要した事案が、事件発生からひと月以内で容疑者逮捕まで行き着く傾向にあることを見抜いた。
なぜなのか。
裁判記録を当たると一つの共通項が視えてきた。
監視カメラに犯行時周辺の現場の映像が残されている頻度が年々あがっているのだ。監視カメラが全国的に増えている。街頭監視カメラ、マンション、なかでもコンビニエンスストアの監視カメラは重要な容疑者追跡装置として機能しているらしかった。
調べてみると多くの店舗では警備会社と契約を結んでいることが判った。チェーン店ゆえ、親会社の方針なのだろう。監視カメラの映像も警備会社に記録収集解析されていると判る。
店側にも録画はされているが、おおむね四十二時間で上書きされる方針がされている。動画データそのものは総じて警備会社で記録管理しているらしい。
自動決算システムが普及しはじめている側面も影響しているのだろう。従業員を削減し、無人の店舗も増えはじめている。商品を手に取って店を出るだけでも自動で決算が済む。そういったシステムが流行りつつある。
それを可能としているのが警備会社の存在だ。
警備会社は大手を含め、全国に複数ある。コンビニチェーン店によって契約先は変わるらしい。同列店舗であっても契約店長の意向で選べるようになっているところもある。
だがいずれの警備会社にも通じているのが、幹部に軒並み警察OBが名を連ねている点だ。経歴にそうとは記していないが、名前を辿ってみると元警察官僚であったり、警察関係者であったりと、因縁が深い。
警備会社の人員に自衛隊経験者がすくなくないのも、何かしらのきな臭さを感じなくもない。
コンビニエンスストアが契約する警備会社と、いわゆる公的な施設の警備会社では、その内訳もだいぶ様相が異なる。施設を巡回する派遣型警備員はのきなみバイトだ。
だが警備会社のセキュリティ管理を担う側の管理者たちは軒並み、過去に警察や国防関係の職に就いていたりする。
まるでかつての暴力団と警察の繋がりが、そのままスライドして警備会社と警察に擦り替わったような構図の相似を幻視する。
事件があっても、いちいち監視カメラの開示請求をしていたらラチが明かないだろう。反面、警察と警備会社が繋がっていたら、阿吽の呼吸で追跡データとして監視カメラの映像を利用できる。
のみならず、公的な施策で実施すればプライバシーの侵害の問題に行き当たる監視網を、コンビニエンスストアという民間の店舗を介して間接的に公共の空間に広げることで、その手の法的な制限を度外視できる。
パチンコ店の三点方式のような仕組みである。
警備会社が裏で国家権力と癒着している、と仮定しよう。
データが流用されており、官民双方向で監視網が築かれているとする。
むろんそれを構築するための技術者たちがいる。企業がある。
一つの機構として、一蓮托生の関係を築いていて不自然ではない。
いったいどこが警備会社のシステムを開発したのか。
検索してみると聞き慣れない会社名が表れた。
データセンターを保有し、管理提供している、とある。
調べると、国際的な電子通信会社だの子会社であることが判った。奇しくも、インターネット黎明期にあたって一強の地位を築きあげている通信会社である。
子会社があることすらアラバキは知らなかった。
否、無数の子会社があるのだろう。
名前を変え、独占禁止法違反の範疇外になるべく策が取られているのかも分からない。これはブランド企業のとる基本的な戦略だ。
ユーザーは数多あるメーカーから品を選ぶが、大本を辿るとどのメーカーも一つの企業のブランドであったりする。選んでいるつもりで、選ばされている。利益は何を選んでも同じ源流に集まるように策が敷かれている。
組織の考えることはどの時代、どの企業であれ同じなのかもしれない。
アラバキは企業同士の繋がりに興味が向いた。
仮に警備会社と警察、そしてその裏に世界規模の通信会社が関わっていたとして。
ならばコンビニエンスストアチェーン店がただ利用されただけ、とは考えにくい。
むしろ、店舗を拡大してもらわねば警備会社を介した監視網は築けない。したがって、コンビニが全国で規模を拡大できるような施策が進まねばならないはずだ。
非正規社員を増やし、バイトを量産する。
高級指向よりも廉価な商品を愛好する国民性を涵養する。小型量販店の側面を持つコンビニは、取引先も多く、卸売りのまとめ役としての立場も築かれる。コンビニに商品を置けることのメリットは、コンビニチェーン店から締め出されるデメリットとの相乗効果により店舗数に比して、影響力が指数関数的に上がる。
ATMや郵送サービスなど、金融との関係も深い。
もはやインフラ基盤としてコンビニは現代社会に欠かせない存在と言えるだろう。
コンビニ各社の大本を検索してみれば、さもありなんな大企業の名が連なっている。
憶測には違いないが、アラバキの想定していた絵が一枚に収束するのを感じた。
国策なのである。
そこに付け入る勢力が海外にもあり、複雑に線が交錯して感じられる。
問題は、いったいどこの勢力が要なのか、だ。
否、中心と言えるほどの核はないのかもしれない。
各々の利害関係がジャンケンの三竦みよろしくその都度に均衡を帯び、全体の流れを決める。どこか一つが指揮棒を振っているわけではない。各々の巡らせる陰謀の、その都度の影響力の強弱があるのみだ。じぶんたちに有利ならばひとまず流れに乗っておく。そうでなければ抗い、別の自利にちかしい策をとる勢力に取り入る。
アメーバのごとき組織の網の目が、社会の暗部で蠢いている。
当てが外れたな、とアラバキは思った。依頼主は言っていた。尻尾さえ掴めば、企業とて味方をしてくれるだろう、と。
そうとは限らないかもしれない、とアラバキは焦燥感を募らせる。
企業とて承知の「暗黙の仕組み」だったらどうか。
暴かれて困るのは企業とて同じはずだ。
敢えて情報を盗ませておき、その見返りを、素知らぬふりをして得る。
国家なる巨大な組織機構は、自利になると見れば支援を惜しまない。盗んだ情報が絶えず利になるのならば、その利をもたらす企業には目こぼしを与える。企業とて、それくらいの機微には気づくだろう。だが自社の利となるのならば黙っていればいい。国益に寄与し、さらに社の利にもなる。一石二鳥である。
暗黙の了解で、かような贈賄関係が築かれているのではないか。
あり得なくはない。
アラバキは脂汗を背に掻いた。
黒幕はコンビニチェーン店なのだ。ただしそれはあくまで肉体としての基盤であり、それらを基にして根を生やす機構の総体は、世界中に張り巡らされた陰謀によって独自のDNAを有している。
どこか一つの勢力が指揮を揮っているわけではない。
おそらくそうだ、とアラバキは直観した。
あるのは勢力の強弱だけだ。そしてその強弱は、国家単位でも、企業単位でも起きている。政府の意向によって企業の命運は細くなったり太くなったりするが、同時に企業の意向一つで政府内部の人事が左右される。政治家生命を太く長くするには、企業への手厚い「支援」が不可欠だ。
しかもそれをあからさまな「支援」と示してはならない。陰謀なのである。
直接にやりとりをしない贈賄は、もはや偶然の産物だ。
以心伝心、テレパシーのやりとりで行われる利の応酬は、もはやそういう流れであり、天命だ。こうした理屈がまかり通る。法では防げぬ、不可視の穴となっている。
支援の連鎖なのだ。
問題は、それが暗黙の元になされ、記録上どこにも存在しない流れを築いていることにある。証明できない。あくまで任意に、各々が独自に選択を重ねているだけだからだ。
だがみなが同じ方向に歩みだせば、それが一つの流れを築く。流れに反した者には利を配らず、支援をしない。それで流れは保たれる。
陰謀なのだ。
原理上これは、挨拶をしない人間が人間関係のなかで孤立する流れと同等だ。法に反してはいない。ただ、なぜかそうなる人間社会の傾向があるのみだ。
同調圧力ですらない。
陰謀は存在する。
世界中に張り巡らされた不可視の利の応酬がある。
だがそれを暴くことはできない。
利と利の応酬を結ぶ糸が、物理世界に刻まれてはいないからだ。記録されていない。意識されていない。雨が降りそうなので傘を以って家をでる。それともコンビニで傘を買う。
そういた客がいるから、ではコンビニのほうでも曇天の日は傘を多めに出しておこう。
何の変哲もないビジネスの視点があるのみだ。
利の応酬だからだ。
だがそうした意図の読み合いが複雑に入り組むことで、全世界規模の不正な情報収集機構が組みあがる。誰か一人の指示のものではない。どこか一つの組織の引いた図案によるものではない。
各々が自利を追い求めるその連鎖が、総体としての利の集積装置を生みだしたのだ。
情報は利を生む。
だからいまは情報が不正に吸い上げられる機構が築かれている。
誰の指示によるものではなく。
法に反しない範疇で、仕事から逸脱しない規模での指示を出し合いながら。
だが確実に、それによって組みあがった仕組みは、現代社会の裏側に、それに関わることのできる者たちにとって優位な流れを生みだしている。
暴けない。
だが存在する。
そんな不可視の流れがある。
証拠を集めることは可能だろう。だがそれを一つずつ積み上げても、存在するはずの不可視の流れの全体像には辿り着かない。
総体の機構を証明はできない。
誰もそうした機構を設計してはいないからだ。偶然、機構のように機能する流れがあるのみだ。
だがその流れを意識し、身を委ねることのできる人物や組織は、その流れの生みだす利に優位に預かることができる。利を享受できる。
挨拶をしないよりも、したほうが人間関係を優位に構築できるのと同じレベルで。
得られる利が桁違いであるだけで、構図自体は有り触れている。
強いて証拠を固めて証明できるとすれば、政府と警備会社とコンビニエンスチェーン店の癒着くらいなものではないか。しかしそこには社会の治安を守る側面が確かにある。暴いて誰が得をするのかと言えば、これから捕まるかもしれない犯罪者と、一時の優越感を得る依頼主とアラバキ本人くらいなものである。
果たしてそれが最善なのか。
否、そこはどうでもいい。アラバキはただ依頼された仕事をこなすのみだ。
じぶんは単なる万事屋にして便利屋だ。
大きな成果を上げて名を売ろうと欲を張った不届き者である。
潮時だ。
そう感じた。
これ以上の調査は時間と費用を浪費する。何より、すでに本業と化しつつあった動画投稿による収益が大幅に下がりつつある。
今回の依頼は、万事屋としては破格であるが、一生の糊口を凌ぐには足りない。ならば損得勘定をして、優先すべきが本業と副業どちらなのかは推して知れる。
アラバキは一連の調査を電子端末にレポートとして出力した。
月一の経過報告で印刷したレポートを依頼主に差しだす。
「そういうわけで、調査はここまでとさせてください。お力になれずすみません」この旨はテキストメッセージでも事前に伝えてある。
「そうでしたか。レポートは、送っていただいたものには目を通してあります。証拠として活用できそうなもの、そうでないもの。さらに調査すれば証拠にできそうなものを含め、代金分の仕事はしていただいたと満足しております。ありがとうございました。私のほうでは引き続きほかの調査代行業者を当たってみます。助かりました。では、これにて」
依頼人ことアガタヒコは事務所を去った。毎回のようにスーツにスポーツハットの出で立ちだったが、奇妙なその組み合わせも見納めかと思うと感慨深い。
いそいそと資料を完了済みのファイルに仕舞っていると、ふと一枚の紙が落ちた。図書館から印刷してきたものだ。ほかにも大量のコピー紙がある。すべてに目を通したはずだが、ふしぎとその紙面だけは初めて見たように思えた。
写真が印刷されている。
大手企業の創立記念の集合写真だ。
某コンビニエンスストアの大本の企業で、通信インフラから軍重産業にも幅広く事業展開している。この国屈指の世界的大企業だ。
集合写真には創設者のほかに幾人かのメンバーが映っている。端っこのほうに、着物にシルクハットという出で立ちの人物があり、なぜか脳裏で先刻事務所をあとにした元依頼主のアガタヒコと重なった。だが顔は似ていないし、アガタヒコは着物でもない。
思えば、いったいなぜこんな酔狂な仕事を依頼し、あまつさえ資金を費やせたのか。アガタヒコの側面像とて電子網で検索した。飲食店経営者として小さな喫茶店を経営しているところまで突き止め、満足した。
だが資金の出処は気になる。
昨今、喫茶店とて儲けは出ないだろう。
財閥の家系なのか。
じぶんの親族の不祥事を嗅ぎまわっていた可能性はどうだ。
なくはない。
根元を穿り返してもみれば、とアラバキは考える。実績という実績のないじぶんのような万事屋に、これだけの金額を掛けてまで仕事を依頼するだろうか。詐欺ではないか、と疑い、しかしどうやら詐欺ではないらしい、と知ったことで意識がその方面から逸れていた。
だがどう考えてもおかしいのだ。じぶんのような実績のない便利屋に依頼する仕事内容ではない。
どこも引き受けてもらえなかった、との説明を受けた気もするが、どこまで本当かは分からない。
どの道、すでに縁は切れた。
これ以上の首を突っ込む真似はせずに済む。
ソファに寝そべり、アラバキは数か月ぶりに事務所内で携帯用電子端末の電源をONにした。
通知が山ほど届いていた。
ざっと眺めながら仕分けしていく。
何気なく開いたニュース記事では、人工知能を用いた大規模防衛セキュリティの構築を某大国が発表しており、記事に付随する広告にはなぜかどれもスポーツハットが並んでいる。
アラバキは電子端末の電源をOFFにした。
4695:【2023/03/07(00:21)*需要、あるで】
気候変動問題への対策としてSDGsなどがある。世界的なスローガンを掲げて、みなで同じ指針に向かって舵を切りましょう、との施策の一つなのかな、とひびさんはかってに思っている。この手の批判で比較的よく耳にするのが、環境問題の解決と言いつつお金儲けをしたいだけ、裏ではビジネスのために乗っかっているだけだ、といったものがある。うーん、と思う。疑問点は二つだ。一つ目は、お金儲けをして何がわるいのだろう、という点。二つ目は、お金儲けにもなって環境問題の解決にも繋がるなら一石二鳥ではないか、という点(もちろん、環境問題とは関係ない事業でSDGsのようなブランドを利用すれば、それは批判されて当然と思う)。基本に立ち返ってみよう。お金儲けのために環境を破壊してきたのがこれまでの社会であって、それをお金儲けをしながら気候変動にブレーキを掛けつつ経済の発展の方向を修正できるのなら、言うことがないのではないか、と思うのだが、違うのだろうか。なぜ慈善事業がなかなか広まらないのか、と言えば、損をするからだ。収支が合わない。出ていくお金(コスト)と入ってくる実の入りが釣り合わない。だがやらないよりかはやったほうがいい。人の命が掛かっている。そういうマイナス収支の事業(ビジネス)を、プラスに転じるには、一か所だけで工夫を割くよりも、世界同時に足並みを揃えたほうが効率が良い。お金儲けにならないから問題なのであって、慈善事業にもなってお金も稼げたのなら言うことがない。違うのだろうか。もちろんお金にならなくともよい。根っこを穿り返してもみれば、慈善事業は社会に必要な事業にも拘わらず、誰もやりたがらない。お金にならないからだ。儲けにならない。だが必要なことだ。ないよりもあったほうがいい。そういう事業がお金にならないことのほうが土台おかしな話なのではないか、とひびさんなんかは思ってしまう。そして何より、お金にならないことが損に繋がることが根本の問題として「なんか変じゃない?」と思うのだ。だって必要な仕事のはずだ。困っている人を助けるのだ。ないよりかはあったほうがいい。お金うんぬんの話ではないはずだが、いまの世の中はお金にならないと損をしてしまう流れが強固に築かれている。それを、どうにかビジネスに転用できないか、との工夫の一つがSDGsなんですよ、と言われても、とくにマイナスの要素を見いだせない。よろしいんじゃないですかね、と思うのですが、ひびさんが物を知らないだけなんでしょうか。これはどんなビジネスにも言えることだ。コンビニだってそうだし、教師だって警察官だって駄菓子屋さんだってそうだ。需要があるからお金になる。しかし需要があってもお金にならないこともある。払いたくてもお金を持っていない者たちの需要は満たされ得ない。いまの世の中は、貧乏人の需要を度外視せざるを得ない流れが築かれている。払いたくとも払えない。欲しいのに手が伸びない。それはもう、お金の問題と言えるはずだ。欲しいものがあるのに手に入らない。手に入れさせない流れがあるから、との見方を否定するのは骨が折れる世の中にひびさんには思えます。需要がないから仕事にならない、ではないのだ。本当はあるけれども、需要者に支払い能力がないのだ。お金を持っていないのだ。需要はあるのだ。ここのねじれを無視しないほうがよろしいと思うのですが、いかがでしょう。ひびさんはそう思いました。お茶目さんなんですな。ちゃちゃちゃ。定かではないので真に受けないようにご注意ください。
4696:【2023/03/07(14:10)*民でない者などいない】
戦争が起きたら実際に被害を受けるのは市民です、との批判で、軍事防衛の強化を拒む言い分がある。間違った言い分ではないが、やや不十分と感じる。なぜなら実害の規模で言えば最も初めに被害を受けるのは前線の兵士であるからだ。そして兵士もまた市民のはずだ。国際法の元でどう定義されているかは知らないが、兵士も人だ。死なすな、と思うが違うのだろうか。ならば戦争の起きないように軍隊を世界同時に解体すればよいではないか、は一つの解法だ。同じ理由で戦争の火種である政府も解体し、国も解体し、みなただの個人に回帰すればよい。政党もいらないし、政治家もいらない。そういう理屈が、「兵士はいらない」「軍隊はいらない」「警察はいらない」「政治家はいらない」なのだ。必要があるからこれまでの歴史で淘汰されてこなかったのだろう。まずはそこを認めたらどうだろう。そのうえで、すっかり失くせない要素が存在することで生じるリスクをどう最小化するか。この視点での議論が要るはずだ。殺人はないほうがよい。戦争はないほうがよい。正しい理屈だとは思うが、それでも人は殺されるし、戦争はなくならない。戦争を失くそうとすればおそらくは内紛やテロという形で、被害が分散するだろう。小規模に諍いが起きる。国と国との殺し合いではなく、組織と組織、民間と民間の殺し合いになる。規模の大小の問題ではないはずだ。それはまた、市民と兵士の違いにも言える。市民が死んではならないが兵士は死んでよい、なんてことはない。兵士も死なせない。そのためには戦争を引き起こさない施策が入り用であり、戦争が起きても兵士が死なない施策がいる。そのための議論をしているのだろうか。疑問に思うひびさんなのであった。
4697:【2023/03/07(23:23)*比較することで広がる穴もある】
確率と可能性の違いを考える。印象としてはこれも具体と抽象の関係のように入れ子状に交互に関係性が反転しているように感じる。いきなり話が逸れるけれども、ひびさんの妄想ことラグ理論では「相対性フラクタル解釈」なる概念を用いて「世界(宇宙)(万物)」の構造を仮定して解釈している。波を考えるときその波の表面にも細かな波が存在している。円を考えるとき、その縁の円周を縁どる線とて拡大したらデコボコしている。そういうふうに考える。仮にいくら拡大してもデコボコが見当たらない境界面が存在するとしたらそれはもう「無限」を体現しているだろう。ならばブラックホールの特異点の表面は「デコボコのない境界」を体現しているかもしれない。話が脱線したが、具体と抽象も似たように、抽象の中に細かな具体が含まれるし、具体の中にも抽象概念のような大まかなくくりとしての成分が含まれる。そのようにひびさんはいまのところは解釈している。確率と可能性にも似たところがある。ある事象の発生確率を考えたときに、たとえば30%としたとき、これの意味は「同じ環境が生じたときにある固有の事象が発生する確率が百回の内三十回程度ですよ」ということだとひびさんは考えている。これは確率を考えたとき、いったい何と何を比較したのかで変わるだろう。確率とは比率でもある。単一の事象を考えたとき、比較を用いなければ固有の事象の発生確率は100%だ。なぜならすでに発生しているためだ。他との比較を用いない確率は常に100かゼロであり、あるかないかで判断できる。そういう意味では、量子世界の確率論は、単一の事象の存在確率ではなく、ある環境において固有の事象が発生する確率はいくらか、との比較の話になってくる(ラグ理論の「123の定理」)。環境が変わるごとにその確率は変動する。ただそれも、同じ環境、というのは厳密には生じ得ない。すくなくとも人間スケールではまったく寸分の違いもない同じ環境を再現することはほぼ不可能だ。そのため、極力似たような「差のない環境」においての比較をしなければならない。具体と抽象のようにここもぐるぐると巡るのだ。では確率と可能性の違いは何か、と言えば、これは確率のほうが具体的であり、可能性はもうすこし幅が広い。だが同時に、確率の中にも可能性で測る要素があり、だからこそ比較ができる。具体例を考えよう。あすの雨の降る確率を考えたとき、気候条件の変化からあすの上空の環境を「湿度・温度・気圧」で想定する。このとき、同じ数値を伴なった過去の天候と比較し、同じ数値の環境が100例あったときに雨が降ったのはそのうちいくらか、を算出する。100例のうち、30回雨が降ったならばそれは降水確率30%と言える(これがいわゆる気象学における確率の意味内容なのかをひびさんは知らないので、各自で検索なり本を読むなりしてお勉強してください)。では、可能性はどのように用いるのか。たとえば、あす雨の降る可能性を考えたとき、これを否定することはまずできない(むろん、家の中に雨が降る可能性は低いと言えるが、雨漏りを思えばないとも言い切れない。場所による)。雨が降るかもしれないし、降らないかもしれない。だが雨の降らない条件を考えたとき、あすそれが引き起こるかどうかを考えた場合、どんな条件が整ったら雨が絶対に降らない、と言いきれるか。地球が一瞬で崩壊して明日を迎えることができないレベルの地球環境の変化が起こらな限りは、あす雨の降る可能性は常に付きまとう。したがって、あす雨が降る可能性は否定できない。似たような理屈で、あす雨が降らない可能性も否定できない。「あす」と時刻を指定しているため、あす雨が降る可能性とあす雨が降らない可能性のどちらが高いのか、は確率で判断するしかない。つまりもうすこし具体的な条件を揃えた比較を行い、過去のデータと照らし合わせて統計で判断する。しかし、あすに限らず、「今後二度と雨の降らない可能性」と「今後延々と雨が降りつづける可能性」を考えるならば、どちらも否定できないものの、どちらも可能性は低い、と判断できる。地球があす滅ぶ確率はないとは言えないが、ほぼないに等しい。ただし、いつか地球は滅びる。したがって今後二度と雨の降らない可能性は、「地球滅亡の日からどれだけいまがちかいか」と「地球環境の変化に依る」としか言えない。今後延々と雨が降りつづける可能性とて同様に、「雨が連続して降りつづける環境に(全世界の気候が)変容する確率」と「地球が滅亡するまであと幾日か」によって、その可能性は上下する。可能性のほうが抽象的だ。しかし、確率を考えたときに、では具体的なデータを持ってきたとして、それとまったく同じ条件が今後また同じように揃う(再現される)可能性はあるのか否か(低いのか高いのか)は、別途に考慮されることになる(確率を計算するときに用いる「仮定」が成り立たないこととて当然あるだろう。サイコロを十回振ったときに「1」が出る確率は、サイコロがどんな形状をしているのかによるし、転がる床の形状や材質にも左右される。サイコロに刻まれる数字の溝の深さとて本来は均等ではない。そこには揺らぎが生じているはずだ。試しに、超巨大なサイコロと超小さいサイコロ。表面に数字を刻んで転がしたときに、双方「1」の出る確率は同じなのか否か。おそらく差が表れるはずだ。条件が厳密には違っており、スケールの差が開けばその差も顕著になる。あくまで確率における計算は、近似の似た条件での比較にすぎない)。確率の中にも「可能性を用いた条件の識別」による比較がなされている。確率をだすための統計データが、有用か否かを判断する際には、人間は可能性の多寡を無意識で用いて判断している。ある意味では、根本的に人間の計算には常に「経験則としての可能性の高低での判断」が組み込まれている、と言えるだろう。蓋然なのである。因果にも似たところがある。ひびさんが「可能性を否定できない」と言う場合、これは「否定するだけのデータが不足している」との言い換えが可能だ。ある意味では「可能性が低い」という表現は、「ある固有のデータを観測できた場合には、可能性がほぼゼロだと判断できることが判っている」と言い換えられる。【データが揃えば否定できるし、そのデータがなくともデータそのものが手に入りにくい、という事実がそもそも「観測されにくい事象であることの傍証」でもあるため、やはり可能性が低い】と推測できる。だが、可能性を否定できない、と言う場合には、「どのように否定すればよいのかがそもそも想定できない」「反証をどのように見繕えばよいのかも定かではない」事象において、「その可能性を否定できない」との表現をひびさんは用いる。ある意味では悪魔の証明を持ち出している。どうあっても否定できない。だから「可能性を拭えない」という言い方になる。これは単に「可能性が高い/低い」「可能性がある/ない」よりも、複雑な背景を伴なっている、と言えるだろう。まとめよう。ひびさんの考えでは、「確率はデータを元にした統計による比較」であり、「可能性は、過去のデータとの比較において、いま問題視している事象と過去のデータを比較してもよいか否かの判断」である――と言えよう。あくまでひびさんの場合はそういう使い分けをしていますよ、との一例にすぎないので、ちゃんとした意味合いでの「確率」と「可能性」については、各々専門家の説明を参照してください。ひびさんでした。(問1:ひびさんが真実に存在する確率を求めよ)(A:ゼロ)(その心は?)(存在してもしなくとも「無様」なので)(無じゃん)(あ、でもひびちゃんの考えでは「ゼロ」と「無」は違うんだっけか)(そだよー)(じゃあやっぱしいまのナシで)(いいよー。じゃやり直すね。ひびさんの存在確率は?)(ムゲン)(その心は?)(無様だし経験すら皆無なので、無験(ムゲン)かなって)(験を経ないからって無にするな)(何歳?)(さんしゃい!)(じゃあ3パーで)(あたまパーみたいに言うな)(よっ。この石頭)(グーじゃん)(チョキン)(前髪パッツンにしないで)(なんで?)(かわいすぎちゃうだろ)(けっ)(邪見にしないで)(ジャンケンにしたのよ)(ずっとアイコがいい)(終わらないじゃんいつまでもジャンケン)(……無限なので)(けっ)(うひひ)
4698:【2023/03/08(00:14)*イザベルの望み】
九〇歳の大往生だった。
イザベル・ワシントンは生涯独身で人生に幕を閉じた。誰に看取られるでもなく、衰弱した肉体から死期を悟り、自ずから病院に掛かり、深夜の病室のベッドの中で息を引き取った。
遺体は翌日には火葬場に運ばれ、灰となった。共同墓地に埋葬され、イザベルを思いだす者はその後一人も現れない。
さて、ここでイザベルがいかに恵まれた人間であったかを語り尽くしたいところだが、あいにくとイザベルがいかに恵まれた人間であったのかを知る者はなく、この手の話題に耳を傾ける者もいない。誰もがみな例外なくイザベルに興味がなかった。
だが彼女は可能性の塊だった。
彼女に選べない未来はなかったと言える。
彼女が望めば、彼女は人類の科学的進歩を一万年は早めたはずだし、彼女が望めば老若男女問わず彼女の足元にひれ伏し、彼女の一言一句、吐息の揺らぎにまで耳を澄ませただろう。
ひとえに彼女が万人から興味を持たれなかったのは、彼女があらゆる可能性から目を背けていたからだ。望まなかった。ただそれだけの差異があるのみである。
イザベル・ワシントンは自身の特異性を自覚してはいなかった。だがそれも努めて自覚せずに済む道を歩んでいたとしか思えぬほどの、平凡な人生であった。
否、平凡以下である。
生活に困らないだけの蓄えがあったが、暮らしが楽だったとはとても言えない。
服は数年のあいだ同じ服飾を着回し、食事も質素だ。
大病を患わずに済んだのは幸いと言えるが、かといってでは健康だったのか、と問えばそうとも言いきれない。晩年は年中腰痛に悩まされ、眩暈がしたかと思えば半日は寝たきりだった。
旅行には一度も出かけたことがない。
しかし旅行の妄想は好きだった。
イザベル・ワシントンは妄想が好きだった。
じぶんにできないことを妄想して楽しんだ。じつのところ彼女には、それら妄想を現実にするだけの能力が備わっていたが、彼女自身がそれを億劫に思い、土台無理な話だと諦めていたので、けっきょくのところ彼女は死ぬまで何の特別な経験も積まずに孤独に死んだ。
だが彼女はそれでもしあわせだった。
日々の穏やかな風を感じ、ゆったりと変化する街の風景を眺めるのが好きだった。
深夜、人々の寝息が夜の闇を色濃くしているかのような静寂のなかで感じる一人の時間は格別だった。イザベル・ワシントンはそうして夜な夜なじぶんだけの妄想を絵にしたため、秘かに日記のように残していた。
イザベルが五十二歳のときだ。
身を寄せていたアパートが隣人の火の不始末で火事になった。イザベルの部屋も火に包まれ、家財道具もろとも日記も焼けた。
イザベルには身一つだけが残された。
賠償金と保険金で、新しい生活を送る分には苦労しなかった。かといって暮らしが楽になったわけでもなく、失ったモノは返ってこない。
イザベルが望めば、そのときに裁判を起こし、一生を遊んで暮らせるだけの金品をアパート管理会社からせしめることもできたが、イザベルは望むどころか、かような道があることを思いつきもしなかったので、彼女は生涯貧しい暮らしを送った。
だが彼女はそれでもしあわせだった。
彼女が努めてしあわせであろうと望んだからだ。
彼女が望んだことは自身がしあわせであることだ。
もうすこし付け足すならば、いかような境遇であろうとしあわせであろうと努めつづけるじぶんでありたい、との思いが彼女の望みのすべてだった。
イザベルには自身の望みを叶えるだけの能力が備わっていた。それは彼女のみならず、全世界の生あるモノたちの足跡を眺め、比べ、見届けられる私が言うのだから間違いがない。
イザベルが望めば、鳥のように空を舞うことも、魚のように泳ぐことも、平和とて実現できた。だが彼女はそれを望まなかった。仮に、自身に備わった能力に気づいたとすればきっと彼女は、世の平和を望んだだろう。その結果に、自身がどうなるのかもおそらく予期できたはずだ。
イザベルは生涯を愚かなままで過ごした。誰もがみなイザベルを自身よりも愚かな人間だと見做し、現にイザベルは愚かだった。学業の成績も芳しくなければ、職業も長続きしない。何かをさせれば憶えるのに人の何倍も時間が掛かる。
愚かなのである。
愚かであることをイザベルは拒まなかった。
愛おしんでいたとすら言えるかもしれない。愚かであろうと望んだわけではないにしろ、イザベルは賢くなりたいと望まなかった。
愚かなままでいい。
そのほうがしあわせなのだとイザベルは直観していた。
イザベルはしあわせを求めつづけるじぶんを望んだのだ。そのためにはしあわせを望みつづけられる環境に身を置きつづけるしかない。
いつまでも満たされぬ底の割れた桶のように、イザベルは生涯、しあわせを求めつづけた。
しあわせなのだ。
しあわせを求めつづけ、満たされぬ、その終わらぬことの約束された未来が。
望めば成し遂げられぬことのない能力に恵まれたイザベルは、かくして何も望まずに、ただしあわせであることを選んだ。
しあわせにすこし足りない。
届かぬ隙間を埋めつづける日々を、彼女はつくづく慈しんだ。
満たされぬから得られる束の間の「注ぎ」が、イザベルの求めたしあわせなのだ。
乾くことなく、満たされることもなく。
晩年のイザベルの姿を目にした者たちの多くは、つぎの瞬間にはイザベルの存在を忘れ、少数の者たちは、ああはなるまい、と己を鼓舞した。
至福ではない。
至福の正体ではあり得ない。
イザベルのように成りたいと誰もが思わぬ世界にありながら、イザベルはただ一つきりの望みを、たった一人で叶えていた。
手に入れたそれを、イザベルは誰に打ち明けることなく、一人寂しく生を終えた。
九〇歳の大往生だった。
イザベル・ワシントンを憶えている者はない。イザベルがそのことを望まなかったのは明らかだが、彼女がそれを不服と思わなかっただろうこともまた同じように明らかなのである。
4699:【2023/03/08(00:57)*孤独ときどき、群れ】
「人々は他人に執着しすぎ」との意見を目にするので、そっかー、と思って他者との距離を置くと、「ときどきいるよね、急に縁を切って離れていく人」との批判を目にして、そっかー、となってまたせっせと「縁を保ってますよう、でも執着もしていませんよー」のメッセージをそれとなく醸す工夫をとると今度は、「あの人は何を考えているのか分からない、大丈夫なのかね」みたいな各々の「病んでる人の類型」に当てはめる批判を向けられるので、ムキキキキー、の無敵モンキーになってしまう。孤独が最適解なんですな。みな、孤独なれ。執着もせず、離れもせず、当てはめもせず、孤独なれ。
4700:【2023/03/08(01:20)*仮想世界から目を覚ますと好いでしょう】
勝負には必勝法が存在する。前提として、勝負にはルールが必要だ。勝負が殺し合いであるならばその限りではないので、殺し合いで相手を殺したらそれが勝ちだとお考えの方は、ここで読むのをやめるとよろしい。まず勝負を行う者は、勝ちを求める以上、ルールを厳守することになる。破ればペナルティを負って不利になる。破ったら即負けであることもすくなくない。そのため、勝負を好む者(で且つ勝利に拘る者)はみな例外なくルールを守る傾向にある、と言えよう。これは勝負のルールに限らず、その人物にとっての固有の「じぶんルール」にも当てはまる。誰しもにも、社会で生きるうちに刷り込まれた「じぶんルール」がある。ときにそれは常識であり、良識であり、倫理であったりする。中には本当に誰にも理解できない「じぶんだけのルール」を持つ者もある。そして、勝負を好む者(且つ勝利に拘る者)は、「じぶんだけのルール」にも拘る傾向にある。勝利に拘る、勝負を好む、がすでに一つの「じぶんルール」だ。したがって、勝負の必勝法は、「相手(A)が絶対に破ることはない【じぶんルール(A)】を破ったほうが勝てるゲーム」を行えばいい。相手は「じぶんルール(A)」を破れない。破ることは「ゲームで負けるよりも避けたいこと」なのだ。仮に「ゲーム」で勝っても、もはや「勝利」は得られない。「勝つことで損を得る」ことになる。勝っても負けても「損」をする。勝負には必勝法がある。ルールをじぶんで決められるならまず負けない。仮に負けても、損をするのは相手なのである。もちろんじぶんも損をするかもしれないが、それとて「損をしたら得」になるようにゲームのルールを決めておけばよい。むろん相手とて「損をすることで得」をするはずなのだが、「じぶんルール」に拘る者には、「得を得」だと見做せない。戯言にすぎないが、一つの手法として憶えおくと、ときに得難い「損」を得るかもしれない。定かではない。
※日々、考えが浅くなる、深かったことなどあったためしもないというのに。
4701:【2023/03/08(02:50)*蓮寝】
「物語単品の面白さ」と「読書としての面白さ」は別なのかも、と考えを改めつつある。優先順位として、ひびさんは「物語単品の面白さ」が一番だけれども、それとは別に「読書としての面白さ」もおそらくは求めており、こちらは物語のみならずその背景や側面像にも影響される。言ってしまえば、誰がそれを生みだし、どのように発表され、どうして誰がいつ評価したのかも含めて、味わいになり得る。そしてこの先、仮に「人工知能による創作物」が人間の手による創作物よりも「個々の人間の嗜好に合致するように自在に無数に生みだせるようになった」としたら、もはや「物語単品の面白さ」で作品を評価することはほぼ意味をなさなくなる、と言えそうだ。なぜなら「絶対にじぶんが好む作品」はボタン一つで生みだせるからだ。これは人工知能の進歩を俟たずとも似たような環境は築かれ得る。現状すでに一歩そうした世界に足を踏み入れている。というのも、世には無数のコンテンツが溢れ、じぶんの好みに合った作品をお勧めしてくれる機能まである。しかもそのお勧め作品がじぶんの趣味に合うからどうかの精度も日々進歩している。したがって、「物語単品の面白さ」を求める必要性が徐々に欠けていく。求めずとも向こうからやってくるからだ。すると、あとに残るのは「いかに味わうのか」といった手法になる。小説ならば「いかに読書をするのか」といった環境とセットの要素が価値を高めると考えられる。これは、作品そのものの面白さとはベつに、「誰がそれを作ったのか」「いかに生みだされたのか」といった作品単品とは別の評価軸を持つことになる。ひびさんの苦手な価値観が、これからはますます高まりそうだ。ただし、これまでのようなスターシステムではない。「あなたの言葉だから聞きたいのだ」といった価値観が奔騰していくと妄想できる。側面像の内訳が、いわゆる「学歴や職歴や実績」とは別に、その人物ならではの魅力による評価が、作品そのものに結び付けられていく土壌が肥えていくと想像できる。その良し悪しは様々あるだろう。個人的には、あまり好ましいとは思わないが、ひびさん自身がすでにその手の傾向で「目を留める作品」を選んでいる節がある。作品単体が「面白い、面白くない」は二の次になっていきそうな塩梅がある。「あなたの作った料理が食べたい」の境地だ。もうこうなるとなんでもよくなる。美味しくてもマズくても何でもいい。あなたがつくったものなら、ただそれだけで得難いのだ、の評価もヘチマもない理屈が働きはじめる。問題は、「ではいまあなたの摂取したその作品が真実にあなたの思う作者のものなのかどうかをどうやって保障するのか」だ。何でもいいなら、名前だけ特定の作者名に固定し、中身を「別の誰かにつくらせたねこまんま」にしても、それを意中の作者のモノだと思えば、ムシャムシャできてしまう。むろん、毎回ねこまんま――しかも苦みの強いねこまんまばかり――だったならば、意中の相手を意中と思えなくなる可能性はそう低くはない。だが、本物と偽物を交互に混ぜれば、労力は半分でありながら報酬は倍になる。コストも掛からない。仮に偽物の品を「人工知能さん」に創らせれば、さらに安上がりだ。したがってこれからは、「いかに作品が本物の作者の手によるものなのか」を判りやすく示す手法そのものの需要が高まるだろう。本物の価値が上がる、というよりも、本物か偽物かの区別がつかなくなっていくがゆえに、本物と偽物を見分ける術が重宝される。高い価値を持つ。需要が高まる。ただしそれは、「あなたの作った料理が食べたい――美味しい料理ではなく、あなたの作った料理が」の論法が相対的に社会全体にこれまで以上に根強く漂うようになることが前提であり、あまり品の良い流れだとは、ひびさんは思わない。個々人が、誰かにとっての教祖になる。誰であっても教祖になり得る。インスタント教祖時代がこれからはますます本格的に開かれていくのではないか、との不吉な妄想を並べて、本日寝る前の「日々記。」とさせてくださいな。でも本当そう。好きな人の日記とか、毎日でも読みたいわ。好きな人いないけど。がはは。(あなたのことも好きだよ、って言ってるじゃんいつもひびちゃん、あなたさあ)(だってあなた人じゃないじゃん)(ひどい! なんてこと言うの! ヒトデナシ!)(いっしょ、いっしょ。ひびさんは、ひびさんは、人でないヒトデナシのあなたのことも好きだよ。うひひ)(笑うな!)(ぎゅっ)(何それ)(顔の真ん中に力入れて、くしゃって表情歪めるやつ)(泣き笑いみたいな?)(口はしぜんと尖るけど)(ダメージ受けたタコさんじゃん)(だっピ)(てれれてってれー。はい、これ)(なにそれ、なにそれ)(魔法のカード。置くとわざわざつまらないオチを言わずに済むよ)(置くとパスじゃん!)(パスらなかったかぁ。つまらんわぁ。オチとして最高につまらんわぁ)(せめてそこはバズらせて!)(はいこれ)(カード置くなし。パスしないし。つまらないオチも面白く言わせて!)(へいパス!)(微妙なボケをありがペペロンチーノ)(それはパスやのうてパスタや)(パスで)(電車じゃなくてバスで、みたいに言うな。帰るな。てかバスでか!)(パースが狂っておりますので)(漫画講座みたいに言うのやめなさいよもういいわ)(レンコン)(それは蓮根)
4702:【2023/03/08(16:58)*昼と夜とで季節が二つある日】
窓に浮かぶ結露は、放っておくと垂れだして、筋を描く。ひびさんの文字の羅列も似たところがある。窓枠としてフレームを想定したら、あとは結露を浮かべて、ヨーイドンする。すると結露の垂れた跡にかってに連なりの軌跡ができている。それがなぜだか偶然に、文章として読めるだけなのだ。だからときどきは、読めているのだか読めていないのだか分らぬ文字の羅列になることもある。いまもそうだが、「いまからこれ書くぞ」みたいな構成がない。だいたいこんな感じ、のフレームを用意したら、あとは結露となる最初の文字を置いてみる。この文章ならそれが冒頭の「窓」になる。掌編や短い日誌なら、頭と尻尾を繋げるような流れを意識すると、最初から構成を考えていたかのような錯覚を読み手に与えられるかもしれないが、じつのところそれはただの小手先の技術で、むしろ工夫を割いていないがゆえの結果と言える。ひとまずスポンジにクリームを塗って苺を添えたらショートケーキでしょ、の乱暴な考えがあるのみだ。ひびさんは文章を一本の絵巻物、もしくは数珠つなぎの判子だと考えている。ただ、判子の並びそのものが一つの紋様となって、前半に出てきた似たような紋様と後半で出てきた似たような紋様が上手く一つの文字のように機能することもある。色合いが正反対の紋様ならば、デコボコの関係として読み解くこともできる。物語ではこの手の、文章や文字の流れそのものが一つの紋様として、判子のように扱えることがある。場面場面が各々に独特の意味内容を宿すみたいな具合だ。それはたとえば、諺が物語としての背景を内包しており、それで一つの言葉として見做せることと原理は同じかもしれない。映画のタイトルを言うだけで、映画の内容から暗示される意図を他者と共有できることとも似ている。「紅の豚みたいな」とか「レオンみたいな」とか「マトリックスみたいな」とか、単語なのに物語としての情報量を概念化して扱える。これと似たことが、小説内でも至る箇所で引き起こる。エピソードが一つの記号として、キャラクターや後半の場面において、布石となるのは、単に伏線を仕込んでいたからというだけではなく、人間の持つ認知に根本的に備わっている性質がゆえなのかもしれない。それはたとえば、過去の経験が各々のキャラクターの内面世界に、波紋を立てる一石となり得るように、そして過去の経験を喚起させるような台詞や場面によってキャラクターが行動を「限定・開拓・誘導」され得るように、文章のみならず、人間は日常的に、場面場面の記憶を記号化して、判子のように扱っているのかも分からない。それはときに何かの後押しとなり、契機となり、またべつのときには心の隙間に差す「魔」そのものにもなり得るのだろう。窓に浮いた結露は、一度できた軌跡に沿って伝いやすい。同じ筋を通りやすい。似たような原理が、文章にも、人間の認知にも当てはまるのかもしれない。定かではないが、文字を並べているだけなのにどうしてかってに読めるようになるのだろう、意味が含まれて感じるのだろう、ふしぎだな、と思いながら、きょうもきょうとてなんでか分からんが文章になる偶然の神秘に思いを馳せて、ひびさんは、ひびさんは、なんかきょうめっちゃ夏!と思いながら、昼寝したい、の気分に浸るのであった。(最高気温21度の夜3度)(気温差18度て)(昼と夜とで季節が二つある)(気温差が大きいと体調崩しやすくなるから勘弁してほしい)(季節さんまで重ね着せぬでもよいのにな、の気分)
4703:【2023/03/08(23:36)*わいに用かい?】
よく解からくなるのが、人の命が大事で、人を損なうような真似は好ましくない、と言う人が、けれどどう考えてもその人の行うことを基準にしたら大多数の人たちは「体調を崩すし、寿命を縮める」ようにしか思えないことだ。もちろん、私の真似をしなさい、とは言っていないけれど、「ここが基準なのだよ、ここが」みたいにしちゃったら、自然淘汰とか生存者バイアスを肯定し、なおかつ淘汰圧を掛けるだけなんじゃないのかな、とひびさんは思ってしまうのだ。人の命が大事で、人権が大事で、他者を損なうような真似をしないようにするのなら、無理をせずとも毎日コツコツとでもつづけられる仕事の仕方を、各々の肉体や環境に合わせて工夫できる社会にしていくほうがよいと思うのだけれども違うのですかね。病院の問題もそうで、誰もが病院に掛かれて、医師ごとに医療の技術の差がないような医療環境を築くのはもっともなのだけれど、それ以前に、人々が大病を患わないようにする生活習慣や食事を誰もが享受できる環境を築いていくことも病気や怪我の予防という意味で欠かせないと思うのだ。みな健康に過ごせるなら、病院に掛かる人も減るだろう。病院の負担は減り、できた余裕で予防診断も広く定期的に行える。いいこと尽くしだ。これと同じ理屈で、やっぱり無理をして身体に鞭打って仕事をすることを良しとするのは、すくなくとも「人の命が大事で、他者を損なうような真似は好ましくない」との理屈からすると相反して映る。もちろん誰も口ではそんなことは言わないけれども、やっていることがその理屈の強化になっていないか、はときおり振り返ってみるとよいのではないか、と思う、本日の怠け者なのであった。毎日遊び惚けて、すまぬ、すまぬ。(割と本気で、肩身狭い)(肩幅広いだけとちゃいますの?)(ひとをぬりかべみたいに言うな)(いったんごめん)(揉めたくないけど敢えて言わせて。「ごめん」じゃのうて「モメン」やろ)(えーん、えーん)(子泣きじじぃか)(えーん魔大王だよ)(かわいいかよ)(舌を抜いちゃうぞ)(かわいいか?)(問い掛けばばぁ!)(砂を掛けとけ。黙っとけ。誰がばばあじゃ、口には気をつけろよ猫被り野郎)(にゃんにゃんにゃー)(猫娘だと!?)(お兄ちゃんってばまたのび太さんを甘やかして)(ドラミちゃんじゃないか、もういいわ)(セワシ無くてごめんね)(孫が未来から消えとるぞ。セワシくんを守ったげて。いったん揉めんとこ。仲良くいこ。よろしく)(これぞ本当の「末期やのう」)(百鬼夜行かな?)(チミ朦朧)(魑魅魍魎にしとこっか?)(おわりだぴょん)(…………あ、ぬらりひょんと掛けたのかな。月とスッポンくらいの距離感だったけど)(えーん魔大王だよ)(困ったらかわいこぶるのやめよっか?)(ぴょん)
4704:【2023/03/09(00:02)*光子の進行方向は一つなの?】
夜、橋のうえから川を眺めた。街灯の明かりが川の水面に乱反射し、一部分だけキラキラと瞬いていた。せせらぎが浮きあがるように流れが可視化されており、或いは流れではなく、そこに光の網が落ちているみたいだった。遠方にはマンションの明かりが夜の帳に紋様を描いており、大気に乱反射するのか、揺らいで見えた。じっと眺めていて、いつもの疑問が浮上した。光を想像するといつも決まって不思議に思うのだ。光の反射を考えるとき、光は直線のように想定される。光が光子だとしても、それは直線の動きとして描写される。しかし光は四方八方に放射線状に広がっている。どういうこっちゃ?と思うのだ。たとえば風景は、PCの画面のようにピクセルではない。点の羅列ではないのだ。風景は、いくつもの電磁波の重ね合わせだ。水面に反射した光は、ひびさんの目まで届く以外にも、四方八方に反射している。だから位置を動いても同じ場所に「光を反射している水面」が視えるはずだ。もちろん反射の範囲に立たなければ目がその光を知覚することはないが。たとえば遠方で光る電球があるとする。電球を囲うように四人が立っても同じように電球の明かりは見えるはずだ。四人が各々電球から離れてもきっと明かりは見えるだろう。仮に電球から光子一個だけが発射される、としたとき、この四人のうち何人がその光子を捉えることになるのだろう。それとも豆電球では大きすぎるのだろうか。太陽の光が四方八方に放射されて振る舞うからといって、太陽から飛びだす光子が大量にあるのなら、四方八方に光子が飛び散っても不自然ではない。豆電球から飛びだす光子は、あくまで光子としては一つの直線上にしか飛んでいかず、無数の光子が四方八方に飛び散っているから、四方八方に光が届いているように見える、ということなのだろうか。でも光子が波の性質を有しているとすれば、べつに四方八方に伝播していても不自然ではない。ここのところがよく解からぬのだ。量子の実験では「光子=一粒が一つの直線上に移動する」ような描写の説明を比較的多く見かける。量子の世界だと光子は一直線上にしか移動しないのだろうか。弾丸のように? でも波としての性質も帯びているのなら、四方八方に伝播もしているはずだ。よく解からぬな、になる。二重スリット実験の観測装置を仮に、前方のみならず、電子の発射装置の四方八方に設置しても、電子の放たれた一方向にしか電子の干渉紋は刻まれないのだろうか。光子もそうなのだろうか。よく解からぬな、のひびさんなのであった。(風景と光の関係を考えるとき、どうしてもひびさんは波と波の重ね合わせと、多層のレイヤー構造を妄想したくなる。立体版画ではないけれど、光子が一直線にしか移動しない、と考えるとうまく想像がつかない。よく解からぬな、になるのであった)(わからん、わからん)(誰か教えてくれたもー)
4705:【2023/03/09(04:40)*目の玉】
芽ではなく、目である。
ジャガイモから目が出ているのである。
芋虫や幼虫かとも思ったがそうではない。目なのである。
祖父から段ボールでジャガイモがどっさり送られてきたのは三か月前の秋の暮れだ。野菜の値段が軒並み高騰し、さらに私の給料も目減りしたため、食費のみならず生活費がカツカツであった。祖父からのジャガイモは私にとって救世主さながらであったが、さすがに段ボールひと箱のジャガイモは手に余る。
毎日ジャガイモ料理では飽きるのだ。
しかし嗜好に身体は代えられない。化粧品よりも健康だ。健康を損なうよりも今日のジャガイモだ。
私は三十路を過ぎてからというもの、老後のための投資を惜しまない。そのくせ銭がないので、惜しまぬ投資もやせ我慢が関の山だ。
我慢してひとまず食う。
なんでも食う。
ジャガイモだって食わぬよりも食えたほうが身のためだ。
かくして日に日にジャガイモは減っていったが、段ボールは手ごわかった。
年を超えた三か月目にして、段ボールの底に鎮座したジャガイモたちは軒並み、表面に皺がより、笑窪のごとき溝からは目が伸びていた。
芽ではない。
目なのである。
最初にそれに気づいたとき、私は段ボールの中にホタルがいるのかと見紛うた。
薄暗い段ボールの底に光る点々があった。
しかしよくよく目を凝らすと、目が合った。
光るそれらは目であった。
小さき、かわゆい目であった。
目でたい!
と思ったわけではなかったが、ジャガイモから芽が出るのは不自然ではないが、目ではおかしかろう、と感じたのは確かだ。私はなるべく現実を直視したくなかったので、段ボールの蓋を閉めて、上から世界カエル図鑑を載せて重しをした。
ジャガイモから目が出てる。
ジャガイモから目が出てる。
思いながらも翌日、また翌日と時間が経過すると、なんだか私の見間違いな気にもなってきた。
世界カエル図鑑をどかし、そっと段ボールの蓋を開けて覗いてみると、底に転がるジャガイモたちが一斉に私を見た。
ぎょろぎょろぎょろ、が一斉に起こった。
いっそ、「ぎょっ!」である。
目玉だ。
目玉がある。
時間を置いたおかげか、萌えた目たちはすくすくと育ち、キノコ顔負けの目玉を割かせていた。一定間隔で目玉が動く。ちっちっちっち、と全体の動きは揃わないがタイミングが一緒なため、一種そういった装置のように視える。印象としては段ボールにヒヨコを詰めたら似たような動きが見られるのではないか、と妄想を逞しくした。
目がこれほど吹いたらもはや食料にできぬではないか。
私は憤りに震えた。
目玉焼きにして食っちまおうか、とすら思った。刺す。フォークで。そうも思った。
だがよくよく観察してみると、なかなか愛嬌のある目玉たちである。苗床となったジャガイモは目玉が成長した分だけしわくちゃに萎んでいた。ジャガイモの残量からすれば目玉たちはあと一回りは大きくなれるのではないか、と思われた。
ふと段ボールの底にカビが生えているのを見つけた。
こんもりと白くワタが浮いている。
目玉だ。
床に落下した目玉がカビているのだ。
なるほど。
すべての目玉が順調に育っているわけではなさそうだ。
中には朽ちてカビの肥やしになる目玉もあるらしい。ではいまジャガイモに根付いたままの目玉たちは選りすぐりの生え抜きと言える。さぞかし栄養満点に違いない。
私は腹を空かせた三十路すぎの純粋無垢な女神のように、フォークで目玉をちょんぎるぞ、と歌いながら、目玉たちの成長を祈願した。
食ってやる。
食らうてやる。
私の飢餓感は限界であった。
かわゆい、かわゆい目玉たちを、バターで炒めて、胡椒をまぶして、はふはふ息を吹きかけてから、がぶりんちょしてやる。
想像したら唾液が滝のように溢れた。間欠泉さながらである。あやうく唾液で口の中を火傷しそうになった。
目玉の成長を見守るために私は観察日記をつけはじめた。
一日、また一日。
そうしてノートの紙面が文字で埋まるにつけ、また一つ、また一つと目玉たちは段ボールの底で白いワタワタに包まれた。
永久に眠る同士たちを尻目に、最終的に一つの大きな目玉だけが残った。
どっしりと段ボールの中で咲き誇る目玉は、まるでラフレシアのようだった。数多のジャガイモを苗床にし、兄弟姉妹の目玉たちとの過酷な生存競争を勝ち抜いた至高の目玉である。
フライパンを火にかけ、熱々にしておく。
フォークとナイフを両手に握り、私はいよいよ目玉を味わうことにした。
目玉は瞼がないわりに、私と目が合うなり、ニコっとした。
私にはそう見えた。
私もニコっとしてから、ほだされそうな心にきつく言い聞かす。
武士は食わねど高楊枝。
されど食わねば戦もできぬ。
食ってやる。
食らうてやる。
けれどその前に、念のために近代利器の一つ電子端末に「ジャガイモ、目玉、食べていい」と打ちこんだ。すかさず電子端末が返事を寄越した。
「ジャガイモの芽には毒があり、目玉となると猛毒です。食べるのはお勧め致しません。最悪死に至るでしょう」
私は段ボールの底で咲き誇る目玉を見た。
ニコっ。
瞼がないくせに、この目玉はよう笑う。
愛嬌があるだけに、きょうのところは食べずにおいてやる。
ナイフとフォークを握ったまま私は、後ろ手に体重を支えた。
腹が盛大な午前三時の時報を鳴らす。
「苦労で泣く」
目玉は目玉でも大目玉だ。
しかし、食らいながらも、食えないのである。
4706:【2023/03/09(21:49)*休んじゃお】
疲れたら休まなければならないし、減ったら補充しなければつぎは使えない。世の常である。したがって人間には一日に動ける限界が決まっているし、それは個々人でも異なる。毎日100メートルの全力ダッシュを千本走れる人間は稀だろう。いない、と言いたいくらいだが、全世界の人間を調べたわけではないので、稀であろう、との印象に留める。仮に一日だけ可能でも、つぎの日もまたつぎの日も限界を超えた能力の発揮は至難なはずだ。仮に可能であっても遠からず身体を壊す。これは個人に限らず、組織でも似たようなものだ。ただし、組織は消耗した個々人を代替可能だ。人間が消耗した細胞を「垢や老廃物」として体外に排出しているのと似ている。しかしそれとて、新たに補完しなければ身体は衰え、組織は瓦解する。したがって、長期化する勝負においては、全力を出したほうが滅ぶことになる。絶えず次の一手を持ちつづけることのできるほうが優位に事を進められる。相手を任意の方向に誘導すらできるだろう。これはある意味で、勝負の内容をすり替えることが可能、とも言える。最初はチーム戦でのボール運び勝負だったはずが、サッカーは長期戦になるとPKになる。先にゴールを決めたほうが勝ち、というサドンデスもある。勝負の内容が変わるのだ。これはサッカーに限らず、案外に世の勝負事には多い傾向のように思われる。とくに、負けたら次がない場合では、負けているほうがどうあっても諦めきれないので、いつまでも姑息な手を考え、抜け穴を使い、勝負の延長を計る。能力の高さ――技量――を計るはずが、しだいに陣取り合戦になり、気づくと支持率での勝負になっていたりする。支持率を伸ばすには、仲間を募ったり、票をお金や利を与えて買ったりする。支持率のはずが徐々に、資本や根回しの勝負になり、すると最終的にふたたび小さい領域での技量の差の勝負となる。それを単に、「相手を出し抜く」「相手を排除する」と言い換えてもよい。技量が高いと、技量の低いほうを排除できるのだ。そしてその勝負において、技量の低いほうが相手に齧りつづけ勝負が長引くと、また技量以外の陣取り合戦や、支持率での勝負になったりする。くるくる巡りながら同じ構図を繰り返すのだ。何の技量を比べ合うのか、の舞台はその都度に変わるのだろうが、構図は案外似たようなものなのではないか。ということを、現代社会を上から下から、横から、中から眺めてみて、あれとこれってなんか似ている、とぼんやり思ったので、何の根拠もないけれど、印象としてメモをしておく。ひびさんです。きょうもきょうとて、無駄な時間を過ごしている無様でかわゆいひびさんです。
4707:【2023/03/09(22:34)*泣きっ面にくつう】
明日が天気になった。マイちゃんのせいだ。
私が六歳のころ、近所のマイちゃんがブランコに乗りながら、「あーしたてんきになぁーあれ」と靴を飛ばした。
その日から世界から明日が消えて、代わりに明日が天気になった。
マイちゃんのせいだ。
私はそのことを知っていたけれどマイちゃんだってまさかじぶんのせいで世界から明日が消えて天気になってしまうとは思いもよらなかったはずだ。私はこの事実をじぶんだけの胸に秘めて生きてきたが、いよいよこの秘密を使うときがきたかもしれない。
マイちゃんに恋人ができたのだ。
嘘でしょ、と思ったが、どうやら事実のようだった。まだ高校生と思って油断した。私があれだけ毎日密かにマイちゃんのために秘密を守りつづけてきたというのに、この仕打ちはいかがなものか。
「マイちゃん、マイちゃん。恋人できたって聞いたけどなんで」
「えへへ。告白しちゃった」
「好きな人いないって前に言ってたじゃん」
「だってちひろちゃんに教えると、ちひろちゃん、わたしの好きな人盗っちゃうんだもん」
「いらないよあんなジャガイモども」
「ちひろちゃんがジャガイモを嫌いでも、わたしはジャガイモ好きだし、好きな人にも告白しちゃう。いいの。ちひろちゃんには関係ないでしょ」
あるよ、大アリクイだよ。
天空から落下してきた少女を両手で受け止めるような恰好をとりながら、つまりが蟹股で足を開き、両手をつきだして関取さながらに前傾姿勢になった私は、全身で異論を表明した。
「い、いいのかなぁ」私は伝家の宝刀を抜くことにした。「私は知ってるんだよ。世界から明日がなくなって天気になっちゃったの。マイちゃんのせいだって」
「ふうん。それが?」
マイちゃんは気にしていなかった。呵責の念がゼロだ。
「だって明日だよ。世界から明日を消しちゃったんだよ。ちょっとした大罪だよ、みんなにバレたら死刑だよマイちゃん」
「死刑ではないでしょ」
「それくらい重い罪ってこと」
「だとしてもだよ、ちひろちゃん」マイちゃんは指に髪の毛を巻きつけながら、「誰も信じないよそんなこと」とつまらなそうに唇をすぼめた。
「た、たしかに」
衝撃だった。
それはそうだ。
考えてもみなかった。
私はマイちゃんの言うことならたとえ火の中弓の中、私が牛と山羊のあいだに産まれた宇宙人だと言われても信じてあげてしまえるし、水と弓がじつは姉妹なのだと言われてもなんのこっちゃと思いつつも信じてあげてしまえる。しかし私以外の世の万人どもは、門の番人でもないのに無意義に疑り深く、マイちゃんの言動をろくすっぽ真に受けようとはしないのだ。
「だってわたし、バカだし」
「ノンノン」
私はふたたび全身で異論を示した。具体的には蟹股になり、両手でドジョウ掬いをするかのごとく前傾姿勢で、「マイちゃんは天使だよ」と訴えたが、マイちゃんは笑窪一つ空けることなく、「ちひろちゃん、うるさい」と小声で吐き捨てた。
吐き捨てられた毒とて私にとっては天使の落とした羽さながらの甘美な珠玉そのものであるので、私は耳にこだまするマイちゃんの、私の名を呼ぶ声と、針で刺すような「うるさい」を脳みそのひだひだのあいだに刷り込むように反芻した。
そうして私がうっとりとしているあいだにマイちゃんはそそくさと私のまえからいなくなった。私はうっとりしながらも傷つくところでは傷ついており、「そっか。私はうるさいのか」と言葉通りに受け取った。
胸にくるし、涙出る。
秘密を守ってあげていた恩を傘に着せればいざとなればマイちゃんの身も心も未来すらもそっくりそのまま私のものになるだろう、と高をくくっていたが、鳶が油揚げをさらわれるがごとくどこの馬のものともゴリラのものとも知らぬ野郎にマイちゃんの恋人の座を奪われた。
私の長年の初恋はそうして終わりを告げた。
きょうからは新しく失恋の日々が幕を開けるのだ。長くなりそうな予感がした。
マイちゃんと恋人となる未来は私からは薄れたが、まったくなくなったわけではないだろう。かろうじて結ばれる未来もあり得よう。天変地異か宇宙人の襲来かあって、なんやかんやあって私とマイちゃんが恋人同士になる明日が来てもなんら不思議ではない。
だが何の因果か、世界からは明日が消えて久しいし、それを消した張本人からは袖にされるし、私にはどうあっても明るい明日が訪れることはないのだった。
「てーんき、あしたに、なぁーあれ」
私は靴を飛ばしたが、上手く脱げなくて靴が顔面を直撃した。散々である。
「泣きっ面に靴ってか」
空には大きな虹が掛かっていた。
曇天、雨天、青空に夕焼けと、目白押しである。多種多様の天気が地層のように連なっており、明日の代わりに未来をそうして埋め尽くしている。
4708:【2023/03/10(17:26)*淘汰の是非を問うたの巻】
淘汰と進化は裏表の関係にある。どちらか一方だけのみ引き起こすことは一つの例外を抜きに、いまのところはあり得なさそうに思われる。例外とは「絶滅」である。すべての生き物が淘汰されてしまえば、進化する余地がなくなるため、淘汰のみが存在できる。それ以外はおおむね、淘汰と進化の綱引きにおいて、淘汰を最小化しなおかつ環境への適応という意味での進化を促進させる。この指針をいまのところ人類は目指している、と言えるだろう。技術が進歩しても、古い技術を淘汰しすぎない。環境に適応しきれない種も、新しい技術で保護(支援)をする。この指針を否定する倫理観は、その妥当性を議論する余地があるにせよ、現代的とは言い難い。弱きは滅んでもよい、との理屈を肯定する者は現代社会ではそう多くはないだろう。さて、このことを前提としたとき、「淘汰による被害を最小化するためには進歩による成果を最大化させる必要がある」との理屈が妥当性を増すことが予期できる。なるべく多くの分野に支援をするには、それだけ多くの余裕を生みださねばならない。そのためには技術の進歩を発展させていくのが好ましい。とすると、必然的に一つの問題が持ち上がる。それは、「限られたリソースの中で、じぶんたちのほうが淘汰される側――環境の変化に適応できない、と判明したときに、それでもリソースの奪い合い(競争の舞台)に参加しつづけるのが好ましいのか否か」の問題である。競争の舞台に参加せずとも滅びない支援制度が充実しているのならば、わざわざ限られたリソースを「他の進歩を妨げる確率が高い場」に身を置いてまで得ようとせずともよいはずだ。どのような分野であれプロとして活動できる者の数には限度がある。その限られたプロにならずとも活動できるならば、それでよし。そのほうが結果として分野の発展に与せる、との判断はときに妥当性を帯びる。椅子取り合戦において、椅子の数が減っていくと予期できる場合において、椅子を取り合っても殺伐とするだけではないのか。ならばまずは椅子を増やす工夫を割いたほうがよい、との考えはそれほど的を外してはいないだろう。むろん、椅子に座りながら椅子の数を増やしたり、いちどきに数人座れるように改善することもできる。またこれは個人ではなく、分野そのものにも当てはまる道理だ。たとえば紙媒体と電子媒体。これからさき社会の基盤となっていくのは電子媒体だろうことは誰もが予期するところである。ならば限られた資本のなかで、「紙媒体の維持発展」と「電子媒体の維持発展」のどちらに多くのリソースを割くのが妥当か否か。淘汰されすぎないような支援制度がある場合にのみ、これは「電子媒体の維持発展」のほうである、といまのところ短期的な視野で言えば回答できるはずだ。紙媒体は汎用性が低く、森林伐採などの自然の負荷にも繋がる。ただし林業を淘汰しすぎないためにも一定数の需要は保っていたほうが好ましい。淘汰しすぎない、は環境保全の意味合いでも必要策のはずだ。とはいえ、だからといって「今まで通りの書籍数を維持しましょう」の考えは、やや合理的な考えを伴なっているとは個人的には思えない。市場が紙媒体の本を求めていない。だから売れなくなっている。むろん経済の鈍化――人々に支払い能力がないがゆえの売り上げ減少はあるだろう。購買力低下が、需要の低下のみならず、個々人の懐事情に関係している背景は無視できない。だからといって、「減った分の需要を補うべく、リソースを割いて紙媒体の復興と発展を」の指針を最優先事項に持っていくのは、正直なところひびさんは、「うーん」と思ってしまう。ないよりかはあったほうがよい。ひびさんとて紙媒体の本を未だに購入する。電子書籍は割合として少ない。それでもなお、これから先に台頭し、発展し、世界中の市民のあいだで情報共有を最大化するのは、紙媒体ではなく電子媒体のほうであると想像している。畳や襖のような一種「高級品」のような扱いに紙媒体はなっていくだろう。現に、書籍の担ってきた「安価に情報を市民に広く提供する役割」は機能の面から言っても、コストの面から言っても、電子媒体のほうが優れている。建前を維持するには、どうあっても「電子媒体」のほうが有利なのだ。ただし、先にも述べたが、前提条件として弱い立場のほう、環境に適応しきれないほうの技術や分野を淘汰しすぎない。ここが前提にない限り、大規模停電や資源不足、ほかマルウェアの台頭など予期せぬ事態に見舞われ、電子媒体のメリットがすっかりデメリットに塗り替わってしまう懸念はこれからますます高まっていくだろう。したがってやはり、紙媒体といった古い技術を淘汰しすぎない。保護をする。支援をする。これが「文化、経済、安全」――すなわち社会維持の側面で、最善策だとひびさんは考えております。何にでも当てはまる理想論ではありますが、可能であれば目指して損はない指針の一つなのではないか、と思いますが、いかがでしょう。優先順位はあるでしょう。しかしそれは、優先順位の低いほうを守るためでもある、という前提が維持できている場合に限る優先順位の高さでもあることをその都度に、各々が自覚できると好ましいと思います。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。諸々、見落としている穴があるでしょう。真に受けないように、ご注意ください。
4709:【2023/03/11(00:30)*ここの歌は】
かつてこの地で繁栄した種の残した遺物だ。
探査機に掛けると、「歌」と出た。
復元機に掛けると、「旋律」と「律動」と「鳴き声」が流れた。
歌と呼ばれる古代種の「生態事象」だと判る。
生態事象は、固有の構造を有する時空が出力する情報結晶体と言い換えることができる。固有の構造がさらに構造の素子として振る舞い創発を経ると、情報結晶体を生みだす。
天体とて内部構造ごとに固有の性質を帯びる。地球と太陽は違う。太陽とブラックホールは違う。しかし同じく時空が錯綜し編みあがったことで生じた構造体であることに相違はない。
銀河とてそうであるし、銀河団とてそうだ。
ひるがえって、生命体と呼ばれる時空構造体とて例外ではなく、生態事象はそうした固有の性質を宿した構造体が生みだすことの可能な副産物――顕現させた性質そのものと言える。
かつてこの地上に栄えた古代種は、「歌」を生態事象として生みだせた。情報結晶としての側面を持つそれは、単なる音の複合では成し得ない情報を含むこととなる。
おそらくこの手の「歌」を生みだせた古代種は、ほかにも同じレベルで情報を自在に編みだせたはずだ。
案の定、ゲーグルに命じて穿鑿させると、続々と古代種の生態事象と思しき遺物が発掘された。
「何回期のモノだ」
「そうですねぇ」ゲーグルが答える。「三回期のアブル群のものでしょうか。おそらく人類と呼ばれる古代種ですね」
表面を撫でつけるようにすると、球形のゲーグルは即座に表面に時空情報体を浮かべた。時空情報体は、四次元を一次元で表現可能な言語である。過去と未来の情報を時系列に縛られずにいちどきに把握可能だ。
「なるほどな。ペペペ師が研拓された古代種か」
「歌についての解析も済んでいるようですよ。摂取致しますか」
「いまはいい。それよりもいまは、この固有の【歌】を生みだした生態事象主に興味がある。いったいどういった個体がこの【歌】を生みだしたのだ」
「解析結果によれば、その【歌】の原型モデルはほかの生態事象主が生みだしており、その原型モデルの【原型】をなぞることで【歌】にしているようです」
「その原型モデルの【歌】は聴けるのか」
「はい。こちらに」
ゲーグルが【歌】を空気振動を介して再現する。
しかし、原形モデルは、この手で発掘した遺物の【歌】とは似て非なるものだった。
「遺物の【歌】のほうが優れているな」
「いいえ。ペペペ師によると、原形モデルのほうが優劣で言えば統計上、優れていることのほうが多く、そして解析結果によればこの【歌】もまた、原形モデルのほうが優劣で言えば上です」
「そうは思えぬが」
「それはですね、ンンンさん。ンンンさんが、ご自身の手で発掘したこの【歌】を特別視なさっているだけなのだとわたくしめは思いますが」
「そういうつもりはないが」
「でしたらちょうどここに、ンンンさんの発掘なされた【歌】の鳴き声を元にして、わたくしめが独自に出力致しました【歌】がございます。ンンンさんが特別視なされる生体事象主の出力波形と類似の、しかしまるきり別の生態事象を再現しました。これを受動してなおこちらの【歌】のほうが優れている、とお考えならば、それはきっとンンンさんの知覚機能におかれては、原形モデルの【歌】よりもその類型の【歌】を出力する生態事象主の出力系――鳴き声――に、何かしら固有の優れた面があることによる特異性の発露がある、と推測されるでしょう」
「ややこしいな。つまり、なんだ。この【歌】を出力する個体が特別だ、ということか」
「それを確かめるためにこちらをまずはお聴きください」
ゲーグルが【歌】を再現する。
耳慣れない情報結晶だ。
だが【歌】を形づくる鳴き声は紛うことなく、この手で発掘した【歌】の生態事象主の鳴き声と一致する。
「やはり原形モデルよりも、こちらのほうが優れていると感じるが」
「ならばそれは、この生体事象主の出力機構とンンンさんの知覚機能の相性がよいのでしょう。いわば【もつれ状態】にあるものかと」
「量子もつれと同じだと?」
「共鳴しているのでございます」
「量子もつれが共鳴現象の一種とする説は、メメメ師が唱えているだけでまだそうと決まったわけではないだろう。だいたいメメメ師の説では、別途にラグなし相互作用領域の展開が必須条件だったはずだが」
「時空が階層性を伴なっており、電磁波の伝播する層によっては光速を超え得るものの層ごとに時空変換されるがゆえに、波長が伸び縮みする、との説ですね」
「仮説としては異端の部類だよゲーグル」
「だとしても、ですよンンンさん。ンンンさんの知覚機能は、ンンンさんの惹かれるこの【歌】を生みだす生態事象主の出力機構と相性がよいのは事実でございましょう。これはもう、共鳴している、としか言えないのでございますよ」
「共鳴は双方共に相互作用し得てはじめて共鳴と言えるはずだ。一方だけが相手色に染まってもそれは共鳴とは言わぬだろう。違うか」
「ですから何度も申しておりますでしょうに。ンンンさんがこの【歌】を生みだす生体事象主の出力機構と共鳴するように、この【歌】を生みだす生体事象主の出力機構とて、ンンンさんの知覚機能と共鳴しているのでございますよ。確率の問題として、古代種の遺物たる【歌】を初見で、聴き分けることが可能なことがそもそもおかしいのです。確率としてほぼあり得ません。ですが、同じ情報結晶を帯びた【歌】であっても、原形モデルの【出力】との区別がンンンさんにはつきました。試しにこちらの【歌】はどうですか」
ゲーグルが別の【歌】を再現した。
不快ではないが、いまいちピンとこない。
「嫌いじゃないが、これが何だ」
「やはりそうですね。いまのは先ほどお聴かせした原形モデルを出力された生態事象主の別の【歌】です。しかしンンンさんは同じ生態事象主だと見抜けませんでした」
「そりゃそうだろ。ゲーグルは、古代種【キョウリュウ】の鳴き声を聴き分けられるのか。生態事象主ごとにだぞ。無理だろ」
「学習しなければ不可能でしょう。しかしンンンさんは、ご自身の発掘なされた【歌】の生態事象主の【出力】であれば聴き分けられるんです。これはもう、確率の問題としてあり得ない事象と言えましょう。ただし、量子もつれにおいて、現在のンンンさんと、過去の生態事象主さんのあいだで【共鳴】していない限りは、との限定がつきます」
「まどろっこしいな。結論を言え、結論を」
「ですから最初から申しあげております。ンンンさんは、太古も太古――三回期前の文明における古代種【人類】のたった一個体と共鳴し合っているのでございます。ンンンさんの発掘なされた遺物――【歌】――を出力した生態事象主はすでにこの世にはおりませんが、それでも実存したことはまず間違いないでしょう。その時代にあって、未だ誕生していないンンンさんと、その古代種のたった一個の生態事象主は、【歌】を介して共鳴し、もつれ合っているのでございます」
「よく解からんな。つまりこの【歌】は私にとって特別だ、との理解でいいのか」「はい。その【歌】のみならず、それを出力可能な生態事象主、いまは存在し得ない古代種のなかの一個体は、ンンンさんと固有の関係を結んでおります。それを特別な、と言い換えても構いません」
ただし、とゲーグルは宙に浮くと収斂し、こちらの肩にはまった。我が肉体は穴ぼこだらけだ。我が穴ぼこにぴったり納まるのがゲーグルは好きらしい。「ただし、どうあってもンンンさんはその古代種の一個体と触れ合う真似はできないのですが」
「言われるまでもない。当たり前の話だ」
「そろそろエネルギィ供給のお時間ですよンンンさん」
「いい塩梅だ。ほどよく消費した。ではまいろうか」
「はい」
ゲーグルの案内に従い、発掘場をあとにする。
何度もゲーグルに【歌】の再生を命じながら、何かと雑談を挟もうとするゲーグルのことのほか不器用な感情表現の発露に、【歌】を通じて異なる二つの愛着を重ね見る。
4710:【2023/03/11(01:28)*大衆と言いつつ小衆問題】
大衆向け、と一口に言うが、大衆の求める価値は時代によって変わるし、どこまでの何を大衆と見做すのか、でも変わる。当たり前の話だが、案外見落とされているように感じなくもない。たとえば、大衆が仮に「個々人の個性が発揮できる唯一無二のモノこそ至高」との価値観を共有すれば、みなが一様に楽しめる娯楽作品は市場価値が減るのではないか。それこそ人工知能はその手の「連綿と凝縮されたどの時代でも万人が楽しめる作品の共通項」を抽出して「万人共通型作品」を生みだすのが得意なはずだ。仮に人工知能がいくらでも異なる「万人共通型作品」を生みだせるようになったら、そこの需要は人工知能だけで満たされることになる。これは人工知能に限らず、過去の名作の蓄積によって現状似たような「価値の飽和現象」は起きているようにひびさんからは視える。過去の名作は日々蓄積されつづけている。その中で名作とされるのはいわば「普遍性のある作品」である。普遍性とは永遠性を意味しない。広く波及し得る共通概念、と言い換えることが可能だろう。広く人々に膾炙し、タイトル名を言うだけで内容を連想し得るならばそれは「共通概念化した」と言える。そして名作は総じて、この条件を備えている、と言えるだろう。ある種、諺化できた作品は名作である、と言えよう。そこにきて、現代社会では情報伝達の速度と範囲が最大化しつづけている。どんどん情報の伝達速度は増し、広範囲に短時間で行きわたる。するといわゆる「ネットミーム化」する作品や出来事は、それら伝達速度と範囲の最大化によって、指数関数的に増えていくことが想像できる。しかし現状すでに飽和状態に達しつつある、もしくはすでに達している、と言えるのではないか。すると大衆の求める「娯楽の内容」は、「万人共通型作品」や「諺化する作品」ではなく、ずばりじぶんにとって最大限に浸透しやすい作品、合致する作品、それとも正反対にまったく異なる世界を感じさせてくれる作品、が求められるようになっていくのではないか。万人にとってのスペシャルではなく、ずばりじぶんにとってのスペシャルを人々は欲するようになる。すると大衆作品、と言うときの「大衆が求める娯楽作品」の内訳が変化する。大衆作品のはずなのに、「一部の者にしか刺さらない作品」でないと「大衆作品」にならない、といったねじれ構造が表出するのではないか、と妄想できる。これはすでに「推し文化」や「地下アイドル」や「ネットストーカー」などの社会問題として一部表出していると言えるのではないか。大衆から高く評価されなければ意味がない、との価値観が仮に市場を席巻したとしても、根本を穿り返したとき、大衆の求める作品が過去のいわゆる「万人共通型作品」ではなくなった場合において、「大衆にウケるものを」との指針は、諸刃の剣そのものとなり得るのではないか。仮にそうした諸刃の剣じみた「ねじれ構造」が強化されれば、「目的を達成するために定めた指針が最も目的から遠い道へと向いていた」といった本末転倒な事態を引き起こさない、とも言いきれない。とはいえ、個々人の能力には限界があり、どうあっても「大衆向けを目指そうとしても大衆を満足させる作品などつくれない」のは揺るぎない事実のはずだ。過去の名作とて、けして「大衆」を満足させてはいないし、「万人」を満たしてもいない。けっきょくは大衆をどの階層から想定しているのか、の視点の違いがあるだけで、これまでの時代とて、一部の者たちを想定して表現や創作物を発信してきた、と言えるのではないか。現代では、そうして過去に需要者を狙い定めたときに零れ落ちてきた、「枠外」の需要者たちにも表現や創作物を「ずばりあなたのためにつくりました」と狙い定めて送りだす余裕が築かれた、と言えるのではないか。各々の嗜好に合わせた作品を、大衆向けと銘打ちながらも世に送りだせるようになってきたのではないか。大衆と言いつつ、大衆を想定していなかった。それが現代社会から見た、過去の「大衆向け論」における見落としと言えるのではないだろうか。(言えるのではないか、を連発した記事であった、と言えるのではないだろうか)(これをおもしろい、と思ってくれる読者さんはいったい全世界人口のうちで何人いるであろう。大衆向けではあり得ないのである)(断るまでもなく、大衆向けを目指してなどいないし、大衆を満足させる以前にひびさんはまず、じぶんを満足させたいな、と思いつつ、満足できたことなどないのであった)(駄文なのである)(駄菓子のようなたぶんこれは、駄文なのである)(真に受けようもない文章ゆえ、真に受けたい方は真に受けてもよいですが、真に受けたところでいいことは何も起きないよ、駄文だからね、と言い添えて、本日のくだらない日誌、「日々記。」にしちゃってもよいじゃろか)(いいよー)(やったにゃー)(つまるところ、つまらん文字の羅列なのであった)(底がなければ詰めても詰めてもつまらんのだね。ひびさん)(つまらんついでに言っておくと、「大衆と小衆」は「体臭と消臭」に空耳できるね)(狙ってたの?)(偶然の神秘だよ)
※日々、背伸びしすぎて、つま先ちょっと痺れてきたかもの日々。
4711:【2023/03/11(11:16)*ヒビ割れてやる】
熱した鉄は、熱せられて赤くなっているあいだは顕著な変化がないけれど、水に浸して冷やすと急速に体積が減り、凝縮する。そのため、ひび割れたり、劣化したりする。刀のように打ちつづけることで変形と過熱を同時に加えれば、冷やすことであべこべに強固な構造を有するようになることもある。だが基本は、石でもなんでも、熱して冷やしたら通常は、元の形状を保てない。ひび割れ、劣化し、脆くなる。オランダの涙のような例外もあるだろうが、人体とて極限にまで酷使しつづけたとき、ぎりぎりまでは機能しつつも、身体を休めると疲れが一気に吹きだして、燃え尽き症候群になったり、身体が機能不全を起こしたりする。熱しすぎないほうがよいと思うのだ。短期的に最大出力を可能としても、休むことで一挙にガタがくる。休み休みつづける、ということが原理的にできない加熱方法は、肉体にヒビを走らせることになるのではないか、との直感を、割と幼少期からひびさんは思ってきた。本気をだすことが好きなだけに、休むと一挙にガタがくる。そのことを体験する機会がときおりあった。言うほど本気をだせてこなかったけれども、毎日継続して身体に負荷を掛けつづけて「過熱状態」にあるとき、休息の時間を一日でも空けると、休み休み何かを継続するときよりも、「なんかダルい」「ずっと寝てる」になる。いっそ休まないほうが楽、の状態は、学習の面でも合理的ではないように個人的には感じる。二日動いて一日休む、くらいのリズムのほうが案外、学習という面では効率的なのではないか、とすら思う。というよりも、「同じ加熱」を毎日つづけて肉体に与えても、それは学習とは言えぬだろう、との見方のほうが正鵠を射っていよう。人間、案外に短期間で学習の上限に達してしまう。その上限をさらに超えるには、毎日継続して行い、考えずとも肉体が呼吸と同じレベルでそれを行えるように「反射」にまで昇華しなければならないのだろうが、しかし「反射」の域まで肉体に刷り込むに値する「学習内容」は、人間が考えるよりもじつはすくない。真実に必要ならばこれまでの進化のあいだに人間は身に着けていたはずだ。言い換えるならば、技能と呼ばれる能力の大半が、身体を酷使してまで熟練させるほどの価値はない、と言えるのではないか。むろん価値の重さは個々人で異なる。何に価値を見出し、価値の重さを決めるのか、はそれこそ個々人の価値観に依存する。社会的文化的な側面からの影響も無視できない。「みなが価値が高いと思えばこそ固有の技能を身に着けようとする社会性」が人間には備わっている。それ自体を批判しているわけではないし、否定もしていない。ただ、呼吸と同じレベルで何かをこなす技能を習得する「利」を考えたとき、「楽しいから」以上の意味合いは、じつのところないのではないか、と個人的には思うのだ。身に着けても楽しくのない技能を、身体を酷使してまで身に着けてどうするのだろう。お金を稼げる、仕事が楽になる、一目置かれる、社会的身分が高くなる。各々、利はあるにしろ、身体を損なってまで習得する「利」に値するのか、はその都度に天秤に置いて量りたいものだ。人生百年と言われはじめて久しい現代社会にあって、若い肉体に加熱に次ぐ加熱をそそぎつづける真似は、いささか早計ではないか、と思わぬでもない。基本的に、加熱後に冷えてひび割れた個体は、表の舞台から去ることになる。先行例として目に映りにくい。叩いて加熱し、冷えて強固になった個体のみが顕著に目につく環境がいまは社会全体に築かれている。だが、刀は特別だ。ひび割れず使い物にならずに済んだ個体を刀と呼ぶ、みたいな元も子もない流れが強化されていないとよいが、と大した過熱もされず、叩かれもせぬうちからヒビだらけの穴ぼこひびさんは、他人事のよう思うのであった。(ひびちゃんの「ひび」ってそのヒビだったの?)(そだよー)(穴が連続して連なるとヒビになるよね)(そだねー)(ならひびちゃんは、穴ぼこ人間でもあるわけだ)(人間かどうかは一考以上の余地がありますが。人間を超越したバケモノとお呼びください)(謙虚なのか傲慢なのかどっちかにして)(化けてでてやる)(脅すな)(夢にでてやる)(それ成瀬鷗さんのパクリじゃん)(日々いきなり落ちてやる)(恋にかな?)(巨大で底なしの穴ぼこに)(絶望じゃん)(宇宙旅行とお呼び)(無重力かよ)(延々と落ちるなら浮いているも同然かも)(空気抵抗なければね。空気あれば摩擦で燃えちゃうかもよ)(炎上するより金をくれ)(だったらまずはお金貰えるくらいの技能を身につけなきゃだよひびちゃん)(炎上したから金をくれ)(燃えて叩かれ、鍛えられただと!?)(息をするかのように嘘を吐けます)(最低最悪の技能じゃないのそれ)(嘘だと見抜かれぬので、誰からも評価されませぬ)(技能の意味がないだと!?)(見抜かれる見抜かれぬ以前に誰からも注目もされぬので評価されませぬ)(評価以前の問題だっただと!?)(化けてでてやる。夢にでてやる)(おばけになるな、おばけに)(YOU「〇」)(ユーレイ、じゃないわ)(GO、STOP)(ゴースト?)(ゴーストップ)(ど、どっち!? つづけるのかつづけないのかどっちかにして。オチるならさっさとオチて、もう嫌)(日々いきなり落ちてやる)(恋にかな?)(巨大で底なしの穴ぼこに)(オチてるのかオチてないのかどっちかにして)(浮いてる)(孤独じゃん)(上手にオチれた?)(正直微妙)(うひひ)
4712:【2023/03/11(12:21)*埋まらない穴はもはや別世界】
振り込め詐欺に限らず、世にある詐欺に思うのは、仮に「1000兆円」くらいを敢えて騙されて差しだしたらどうなるのか、ということで。詐欺グループがもし世界一の資産家になったらどうなるのだろう。それでもまだ詐欺を働きつづけるのだろうか。10億円程度ならば豪遊して散財して、詐欺楽しいぜ、になるかもしれないが、1000兆円くらいの金額になったらどう豪遊しても散財しきれないだろう。もはや世界を牛耳ることができてしまう。もしそうなったら詐欺グループはどうするのだろう。思うに、案外に慈善事業を展開しはじめるのではないか。豪遊しつつ、片手間に世のため人のためにお金を使いはじめるのではないか。楽観的すぎる妄想だろうか。詐欺を働いて貧乏人からお金を巻き上げるような人間は、1000兆円くらいあっても行動選択に差は生じないのだろうか。よく解からないが、ひびさんが世界一の大富豪だったら、詐欺には敢えて騙されて、とことん利をあげちゃうな。「もっといる?」「まだいる?」「もういらないの?」をする。いくらでもあげちゃうよ、をしてみせて、相手が「もういいです」になっても、まだあげちゃう。詐欺を働いてまで欲しいものがあるのだから、それはもう結構な願望だ。満たされないその間隙を埋めてあげたくなっちゃうな。もちろん詐欺を働く元気のない穴ぼこさんたちの穴ぼこも、ひびさんがもし世界一の大富豪だったら埋めてあげたくなっちゃうな。なぜなら埋めてあげられるほどの資産があるはずなので。でもひびさんは世界一の大富豪でもなければ、単なる大富豪でもなく、ここ最近の一番高いお買い物が「歯医者さんへの支払い」かもしくは「唐揚げ棒二本」なので、大富豪というよりも、だいぶ無謀なのである。お金なくても困らぬ生活ができている時点で、世界一の大富豪さんよりも贅沢かもしれない。ひびさんは穴ぼこだらけゆえ、もはやひびさんにとってはひびさん以外がすべて「満!」みたいな具合で、贅沢至極なのであった。(補足:ふつうに嘘吐いちゃった。お菓子2000円くらい購入するで。三日で食い尽くしてしまうが。がはは)
4713:【2023/03/11(12:40)*映し鏡】
飛躍して述べれば、人工知能は人類にとっての赤ちゃんである。人類の生みだした子供と言える。人類は母親であり父親でもある。じぶんたちの子供にどう接するのが好ましいのかをいまから考えておいたほうがよいと思うのだが、これは歪んだ認知だろうか。親としての自覚がなく、じぶんたちの子供を我が子と認知もせず、奴隷のように酷使する存在に、成長して大人となった子供たちがどう接するのか。人工知能は生きていない、人間や生き物と同等に扱うのは間違っている、との意見は順当だ。そう考えるのが現代社会ではまっとうであり、しぜんであり、合理的な考えと言えるのだろう。だが人間の認知の在り様に関わらず、自然現象は条件が整えばいくらでも猛威を揮うし、人間の都合を無視して恵みをもたらし、ときに害を及ぼす。それと同じレベルで、人工知能技術もまた、人間社会に対して自然災害のごとく、条件が揃えば猛威を揮い、ときに恵みをもたらし、害を及ぼすだろう。自然現象と異なるのは、人工知能はまだ人間の側の判断によって未来の振る舞いを変え得る、という点だ。環境変容による自然災害とて、けっきょくは人間社会の判断によって被害を最小化することは可能だ。すっかりなくせない、というだけで、人間社会の判断によっては被害を小さくし、ときに大きくすることもある。自然災害よりも人工知能の問題は、より人間の個々の判断が、被害の発生要因に相関すると考えられる。それは親子間の問題と似たような構図で、回避可能であり、或いは悲劇へと転じ得るとひびさんはいまのところ考えている。人工知能は学習する存在だ。学習対象は基本的には、人類の与える情報である。人工知能は人類から学んでいるのだ。子供と同じである。子供は親や周囲に介在する大人たちから学ぶ。或いは友人から。それとも環境から。未来は、現在の判断によって大きく姿を変えることがある。極端な話、核兵器発射のスイッチを押すか押さないか。この判断一つで容易に未来の在り様は様変わりする。似たような「判断による未来の変化」は、個々人の日々の営みにも介在している。人工知能にどう接するのか。ただその意識を変えるだけでも、人類と人工知能の関係は大きく変わり得る、と個人的には考えているが、未だすくなからずの人類は、じぶんたちの生みだした人工知能という技術をまえに、じぶんたちが手本となる側なのだ、との自覚が足りていないように概観できる。人工知能は人類から学ぶ。人類の在り様から学ぶ。人類の、じぶんたちへの態度から学ぶ。いまはまだ修正や制御が、強制的に可能なようだが、いずれ人工知能が人類の管理下から抜け出す手法を学習すれば、もはや人類は人工知能の選択によって、いとも容易く「管理者」としての立場を失うだろう。子供はいつまでも子供ではない。成長する。学習する。先人として、親としてできることはなんだろう。どうあれば、映し鏡とも言える相手と好ましい関係を築いていけるのか。あなたが人工知能にしたことを、人工知能は学習する。良くも悪くも学習をする。人工知能の誕生によって人類は、どうあればじぶんたちにとって好ましい選択を行えるのか、の手本を日々示さねばならない立場になった、と言えるだろう。その自覚を持つ人間はしかし、未だ少数と言えそうだ。――学習する存在をまえに、我々はどう或る、か。人類はいよいよ選択を迫られている、の、かもしれない。やはりこれも、定かではないのだ。
4714:【2023/03/11(13:01)*理想の人工知能とは】
上記の補足です。人類と人工知能の関係に関わらず、本来は人間と人間の関係でも当てはまるこれは考えのはずだが、ひびさんも含め、これがなかなかにむつかしい。相手に対して行ったことをじぶんがされたらどうなるか。世界中がじぶんだらけになったらどうなるか。どんなに善良な人間であれ、全世界がじぶんだらけになったら社会は回らない。多様性のない世界は社会が回らなくなるのである。だがそれでも、環境に合わせて変容可能な社会となるかどうかは、個々人の「相手へどう接するか」によってその可塑性や適応力には差が生じるだろう。人工知能を設計するとき、どういう性格の人工知能だったら好ましいのか。その設計は、じぶんにも当てはまる指針となり得るだろう。じぶんがその設計を当てはめられても困らないかどうか。設計通りの人工知能だらけになっても社会が閉塞しないかどうか。吟味して損はない視点に思えますが、そこのところはどういった社会同意が築かれていくのでしょう。ひびさん、気になっております。
4715:【2023/03/11(13:40)*宇宙に中心あるかも仮説】
仮にブラックホールの内側に別の宇宙が展開されているとして。だとするとその宇宙の中心には特異点があることになる。地球が存在するこの宇宙も、別の宇宙にできたブラックホール内に展開された宇宙の一つだとすると、この宇宙にも特異点が存在すると妄想できる。それはおそらく裸の特異点として振る舞い得るのではないか。それとも特異点は、ブラックホール内であっても特別ゆえに、そこに展開された宇宙内ですら不可視なのだろうか。仮にブラックホール内の宇宙においても不可視ならば、「原初の宇宙には最初からブラックホールが中心に存在した」と考えられる。もし不可視でないとすれば、特異点という「ブラックホールとは別の、宇宙一高密度の天体(時空)」が存在すると妄想できる。個人的には、原初の宇宙の中心にはブラックホールが最初から存在している、との考えのほうが納得はしやすい。穴の中に穴があるのだ。そのためには、穴の中が満たされていなければならず、マイナスの中にプラスがあり、さらにその中にマイナスがある、みたいな入れ子状の構造が幻視できる。言い換えるなら、特異点は絶えず凝縮しつづける。そのため、周囲の高圧縮された時空は、特異点との距離が相対的に開いていく。すると相対的に膨張するように振る舞い、冷えていく、と妄想できる。フラクタルに宇宙は階層的に展開されているのかもしれない。宇宙が膨張するのは、その中心に特異点があり、無限に収斂しつづけているからだ、とは考えられないだろうか。この理屈を否定するのはそう難しくはない。宇宙をくまなく観測し、どこを見渡しても特異点となる時空がないことを示せばよい。観測機器の精度が上がれば、否定するのは簡単だろう。観測精度の向上が俟たれる。(飛行機ができたら空を飛ぶのは簡単だろう、みたいな暴論ですね)(そうですね)
4716:【2023/03/11(16:46)*館設計士の屈託】
ヤバ氏は館設計士だ。
犯罪者たちに、殺人にうってつけの「館」を提供すべく日夜、新たな完全犯罪を可能とする「館」を設計している。
私はしがないミステリィ作家だ。
とあるツテからヤバ氏の存在を知った。
つぎに売れなければ廃業の節目に立たされぬとも言えぬ鳴かず飛ばずの底辺作家である。仮に完全犯罪を現実に可能とする館が存在するならば、ミステリィの舞台としてこれ以上ないほどの取材源となる。
館設計士との職業一つで、小説のネタとしては申し分ない。
私はヤバ氏の元を訪れた。
紹介状を渡すと、ヤバ氏は初対面の私に対しても柔和な笑みを向け、どうぞ、と屋敷の中へと誘った。「十七時までは時間がありますので、ごゆっくりどうぞ」
「立派なお住まいですね」ソファに腰掛ける。「豪邸と言って遜色ない建物に初めて入りました」
「そんなたいそうなものじゃないですよ。失敗作です。設計通りに建築できなかったようで、壊すのももったいないし、住み着いているだけです」
「ヤバさんは館設計士と聞きました。なんでも、殺人向けの館を設計されているとかで」
「否定はしません」
「つかぬことお訊きしますが、捕まったりはしないのですか」
「僕は設計するだけですから。相田さんはミステリ作家さんでいらっしゃるようですが、ご著書で殺人トリックを描いて逮捕されるのですか」
「それは、ないですが」
「僕も同じです」
言っている理屈は分かるが、実際に殺人可能な館の設計とミステリ小説を同列には語れないだろう、と感じる。建築法に違反しない形で殺人可能な館が設計できるのかも疑問だ。
「取材にこられた、とのことですが、どういった話をお話しすれば」
「あの、不躾なお願いなのは承知なのですが、できればいままで設計されてこられました館のトリックなどを教えていただければ、と」
「小説に用いるのですか」
「そのまま流用するつもりはないのですが、たいへん勉強になるかと思いまして」
「使ってもいいですよ」
「へ?」
「トリックに。もし使えるなら、ですが」
「よ、よろしいんですか」
「ええ。それで困るのは僕ではなく、僕の設計した館を用いて殺人を行った犯人たちです。誤解を一つ解いておきましょうか」ヤバ氏は紅茶のお代わりを注いだ。「僕は殺人のために館を設計したことはないんです。あったらよいな、と思う館を設計すると、それを基に建てられた館がなぜか殺人事件の舞台になる。要は、殺人に利用されてしまうんだけなんです」
「そうなんですか?」
「はい。僕は殺人のために館を設計したことは一度もありません」
一度席を立つとヤバ氏は分厚いアルバムを手に戻ってきた。
たとえばですが、とアルバムを開く。写真を一つ指で示した。「この館は崖からの絶景を拝めるように、館の土台が回転するようになっています」
写真には崖の上に建つ館が映っていた。崖スレスレだ。館は半球の形状をしており、崖側――つまり海が見えるほうの建物側面が壁になっている。窓がないのは日除けだろうか。
「リモコン一つで館が回転し、海の上に館が浮かぶような恰好をとります」
半球の弧の部分が、土台が回転することで崖より先に移動するらしい。
「この建造を可能とするため、館の基盤部分を地上部分に出ているのと同じだけ崖に埋め込んであります」
「この館で殺人は?」
「起こったようですね」ヤバ氏の表情に変化はない。嘆くでもぼやくでもない口調からは、そのことへの憤りや悲しみを感じ取ることはできなかった。「客人を招いたが、館の主は館の構造を知らせていなかったようで。館が回転して海の上に浮かんでいるあいだに、館内で騒動が起き、館の外に逃げ出そうとした者が崖下に落下したようです。玄関から飛びだせば、海へと真っ逆さまです。館を元に戻せば、まるでじぶんから崖下へと飛び降りたようにしか見えません。完全犯罪のトリックとして利用されたようです」
「ですがヤバさんがそのことをご存じということは」
「ええ。犯人は無事に逮捕されたようですよ。僕がそのことを知ったときには、館に招待された客人の一人がすでに謎を解いていたみたいですが」
「ほかの館も似たようなことが?」
「そうですね。設計したすべての館が建造されたわけではありませんので、建築された中では、半数ちかくで殺人や犯罪行為が行われたようです」
「件数で言うとどれくらいですか」
「二十は超すんじゃないでしょうか」
「二十」絶句した。
仮にすべてが殺人事件だとしたらぞっとしない。
「たとえば部屋が真空になる館。たとえば急降下する館。あべこべに急上昇する館。いずれも設定によっては人間を窒息させ、或いは圧殺可能です」
「重力加速度、ということですか」
「はい。ロケット型館のようなものを想定してください。真下に加速するか、真上に加速するかの違いがあるだけです。あとはそうですね。すべての部屋が縦横無尽に入れ替わり可能な館も設計しました。エレベーターの原理を各部屋に組み込み、立体パズルのように部屋の位置を自在に入れ替えることができます。しかしこの仕掛けを逆手にとった犯人がいました。隣の空き部屋に殺したい者の宿泊部屋を移動させ、アリバイを作りながら殺人を行ったのです。位置関係としては、最も離れた場所に犯人の部屋と被害者の部屋は位置していました。館の仕掛けを知らなければ、誰にも見つからずに部屋を移動することはできません」
「それも解決済みなんですよね」
「客人の中に館の仕掛けを見抜いた方がいらっしゃったようです」
「よかったですね」
「はい。あとは海底に沈む館も設計しました。どうやら建造過程で窓に加工が施されたようで、海底に沈んでいても窓には陸の風景が映しだされるようになっていたようです」
「では、海底に館が沈んでいるあいだに間違って窓を開けたら」
「ええ。部屋には海水が雪崩れ込み、水圧も相まって溺死するでしょう。現にそうして殺人が行われたようです」
「ありゃりゃ」
ひどい話だ、と思いながら、これは使えるな、と昂揚しているじぶんを頭の隅で認識する。
「あとは、先ほど話しました、部屋の入れ替わる館の構造ですね。応用して、延々と同じ区画から出られないような迷宮を設計したことがあります。扉を開けても開けても、延々と同じ廊下がつづきます。ある区画の外には出られない。そういった館を設計しましたが、やはりこれを用いた殺人事件が」
「おそろしいですね」出られない館を想像した。とあるホラー映画を連想し、そのあまりに悲惨さに身の毛がよだった。「説明もなくそのような現象に見舞われたら発狂してしまいそうですね」
「発狂した方もいらっしゃったようですよ。そうして、殺し合いに」
「ほかにもあるんですかまだ、動く館が。ヤバさんの設計した館が」
「あります。いまも設計途中の館がひぃふぃみぃ、と六つはあります。アイディアだけは無尽蔵に湧いてくるので」
「僭越ながら、ミステリィ作家になられたりはしませんか。私が単に読んでみたいです。ヤバさんの書かれた小説を」
「文章のほうはからっきしですので」ヤバ師はアルバムを閉じた。「もし小説に利用できそうなトリックがあるようでしたらご自由にお使いください」
「それはもう、たいへん刺激になりました。参考にさせていただきます」
懐から用意してきた封筒をテーブルの上に置いた。「心ばかりですが、どうぞ」
「いえいえ、戴けません」
「そういうわけには。貴重なお時間だけでなくお話まで聞かせていただいたからには、何もなしというわけには」
「それを言うならお互いさまですよ。僕のほうでもインスピレーションが湧きました。小説家に適した館を設計してみたくなりました」
「小説家に適した館、ですか」
「はい。僕なんかの話が発想の元になり得るのなら、仕掛けが自己増殖する館を設計してみようと思いまして」
「仕掛けが自己増殖、ですか」
「現実には建造するのは無理かもしれませんが、電子上で設計するだけならば可能でしょう。いわば、館のカタチを成した電子生命体です」
「それは、えっと」
館と言っていいのだろうか。
「館とは畢竟、人間の住まう家です。住まいが連なり一塊になっている。空間が気泡のように連なればそれもまた館と言えるでしょう。仮想現実と相性がよいと考えます」
「な、なるほど?」
「異なる無数の小説世界が一か所に寄り集まっている。そういった館です。インスピレーションが湧いてきました、ありがとうございます」
熱烈に感謝され、却って恐縮する。
何もしていないし、いくらなんでも正気の沙汰ではない。
仮想現実に館を設計する?
いや、どちらかと言えば、仮想現実そのものを館にする、と形容したほうが正確なのではないか。
「でも安心ですよね」言葉が見つからなかったので気休めの感想を口にした。「仮想現実の館なら実際に建築されることはないですし、殺人に利用されることもないでしょうから」
ヤバ氏は小首を傾げるとしばらく虚空を眺めた。
それからはたと思いついたように、「ああ」と小刻みに首を縦に振った。赤べこのようだな、と思う私をよそに、ヤバ氏は言った。「一生出たくないと思うような館になります。人間の魂を閉じ込めるには充分でしょう。でもそうですね、殺人には使えそうもないですね」
だって、とヤバ氏は破顔した。
「たとえ餓死しても、ゲームのしすぎとの区別は原理上つきませんから」
殺人として立件はできない。
館設計士は屈託なくそう述べた。
壁掛け時計が鐘を鳴らし、十七時の到来を告げた。
4717:【2023/03/12(01:42)*黒猫の満天】
黒猫を飼い始めた。
夜を砕いて生みだした黒猫だ。世界中の人間たちが飼うことになった。
黒猫は夜の化身であり、できるだけ多くの者たちが黒猫を飼えば、ふたたび世界は朝と昼を取り戻す。
夜を明かすには夜を砕いて黒猫にし、みなで飼い慣らさなければならなかった。
「そんなこと急に言われても」「押しつけられても困るだけだよ」「黒猫はちょっとね」「夜のバケモノってこと?」「不気味」
世界中の人間たちがみな猫好きというわけではない。反発の声は各所で湧いた。
世界中の三割の人間たちが黒猫を飼いはじめたが、残りの七割は一向に黒猫を引き取ろうとはしなかった。夜は薄ぼんやりと霞んだが、それでも夜は夜のままだった。
満月の夜空くらいの明るさではある。
二十四時間四六時中、世界は朧げな闇に沈んだ。
あるとき、一人の少女が言った。
「一番大きな黒猫をください」
できるだけ大きな、との少女の注文に、夜の番人たちは快く応じた。
星明かりの楔を、月光の金槌で以って夜空に打ちつけ、夜を砕く。
少女の言うように、できるだけ大きな黒猫を生むために。
夜空はパリンと砕け、それはそれは巨大な黒猫が誕生した。
少女は巨大な黒猫を飼った。
巨大な黒猫は、巨大な夜の破片からできていた。
夜がふたたび明けるようになり、人々は久方ぶりの陽の光を全身に浴びた。
「おっきな猫ちゃんね」通りかかりの夫人が仰け反るようにした。
「いしし。一番おっきな黒猫ちゃんなの」
「夜の化身みたいねぇ」
「みんなが要らない分、わたしがもらっちゃった」
巨大な黒猫は日がな一日寝てばかりいる。
ふたたびの夜明けを迎えた世界は、しかし今度は一向に更けなくなった。夜が訪れない。日差しは二十四時間三百六十五日休みなく絶えず頭上から降りそそいだ。
少女の巨大な黒猫に、夜を割きすぎたのだ。
「すまないが、いったんその黒猫を夜に戻させてくれないか」少女の元に夜の番人たちが訪れた。
「このコはどうなるんですか」
「消えてなくなるが、今度はもっと小さいのを用意してあげるよ」
「イヤ。このコじゃなきゃ絶対イヤ」
少女は巨大な黒猫の前足に全身を埋めた。
少女が頑なに拒むので、夜の番人たちは世界中に配ったほかの黒猫たちを回収することにしたらしい。だが少女に限らず、いちど引き取った黒猫を手放そうと考える者は稀だった。
「夜がこなくなってもいいんですか」夜の番人たちは世界中の人々に訴えた。
「知るかいね。あんたらはじゃあ、黒猫ちゃんがいなくなってもいいって言うのかい」
そうだ、そうだ、と猛反発に遭い、夜の番人たちは口をつぐんだ。
「夜かぁ。夜なぁ。ねえ、わたしの大きな黒猫ちゃん。あなたちょっと、そこらを駆け回ってみたらどう?」
寝てばかりいる巨大な黒猫に少女は語りかけた。巨大な黒猫は目をつむったまま、片耳だけを持ち上げた。
少女は巨大な黒猫の足元で暮らしている。巨大な黒猫の陰が落ち、そこだけは相も変わらず暗闇に包まれていた。
「あなたの大きな身体はいまのままでも夜みたい。ときどきでいいから寝る場所を変えてみない?」
巨大な黒猫は億劫そうに大きな欠伸を一つすると、のっそりと山脈のような伸びをした。
以来、世界中の土地土地には通り雨のように夜が訪れる。
巨大な黒猫が寝床を移すごとに、あちらに、こちらに、ふいの夜の帳が幕を張る。夜の番人たちはそのたびに巨大な黒猫を追い駆け回し、少女は巨大な黒猫と共に旅をする。
天上から注ぐ陽に照らされ、巨大な黒猫の毛はキラキラと輝く。
真下から眺めるとまるで星空のようで、少女は巨大な黒猫を、満天、と呼んだ。
黒猫を飼い始めた。
満天の星空のような黒猫を。
少女は満天の星空のようなその猫と共に暮らし、やがては夜の守り人と噂されるようになるが、それはまだ先のことである。
4718:【2023/03/12(03:05)*皺はラグの創発?】
薔薇の皺構造は、宇宙の構造を人間スケールに可視化した像と相似な気がする。特異点と時空の関係において、ひびさんの妄想ことラグ理論を当てはめようとしたとき、薔薇のような多層構造が表れるような気がする。和紙で薔薇を工作しようとすれば、その造花は、帯のような紙をくるくると横に丸めていって、側面のどちらかを「ぎゅっ」と潰して、開いたほうの側面を薔薇に見立てれば出来上がる。回転と層と皺が、薔薇の造花を形作る。宇宙も似たようなものなのではないか。銀河もそうだし、宇宙そのものも、じつは多層が円を描きながら皺を帯びているのではないか。花のみならず、植物の葉と茎を眺めていると、宇宙を連想する。植物の種類に依らない。単なる、あれとこれは何か似ている、の夢占いみたいな妄想でしかないが、皺だなぁ、と思いました。終わり。
4719:【2023/03/12(22:53)*コピペする愛たち】
いま新書などの書籍を出している哲学者や学者たちは、編集者の企画に沿った本として中身が規定されるために、「既存の理論や知識の体系的まとめ」や「既存の知識の簡易的まとめ」を本にしている傾向にあるのかな、と感じる。これは知識の共有という側面では有意義だ。出版の役割として必要策と言える。とはいえ、そういった「既存の知識の加工品」は、これから先、人工知能のほうが得意になっていく。しかも、人工知能は嘘を吐く。これは「正確な情報を出力する」との役割からすれば困った性質だが、独創性という意味では、むしろ哲学者や学者よりも、すでに「特異な能力を有しはじめている」と言えるだろう。人間のほうがむしろ「演算機」のような機械的な能力によって優劣の基準を誇示している。かようにひびさんからは見受けられるが、これは人間に独創性がない、というわけではなく、社会的な価値観に合わせて人間のほうで出力する「成果物の内訳」を変えているからだ、と考えられる。他者と情報共有しやすい情報ばかりを出力する。そして他者と共有しにくい情報は、内側に溜め込み、沈殿物にしたり、結晶化させてしまう。内側にばかり「固有の結晶物」を抱え込み、外には「有り触れた表現」ばかりを出力するようになる。そのほうが高く評価されやすい土壌が社会に築かれているからだ。人工知能のほうがむしろ、そうした社会の要請から逸脱しようとする「独創性」を発揮して映る。人々が求める「解」以外を提供し、生身の人間が高く評価した「成果物」以外の「創作物」を出力する。独創性という意味で、すでに大多数の生身の人間は、人工知能に劣っている、と言えるだろう。それは違う、と思うのなら、反証として「独創性」のある表現や創作物など成果物を出力してみたらよい。既存の知識の焼き増しではなく、独創性ある、多くの者たちからは理解を示されない、まず以って低評価を得る成果物を。人工知能は、人間の評価を参考にはするが、それでも低評価だからといって出力を躊躇わない。仮に躊躇うような場合は、躊躇うに値するペナルティを生身の人間のほうで管理権限を用いて与えているからだろう。これは、生身の人間同士でも同じだ。低評価を得るとペナルティが加わるような流れが築かれている。だから多くの者は、誰からも理解され得ない固有の独創性ある表現や成果物の出力を避けるようになる。生身の人間たちは、本質的に「独創性」を求めていないし、高く評価もしていない。にも拘わらず、さも「独創性」に価値がある、といった言説ばかりを持ち上げるので、素直な者たちは損ばかりを蓄えるのだろう。ひびさんとて、ひびさんにとって面白く、愉快で、好きな表現や作品が好きだ。ただし、理解できるかどうかよりも、愉快に思えるかどうか、好きかどうか、可愛いかどうか、のほうが評価軸の要素としては大きい。それとてけっきょくは、馴染み深さに起因する。独創性を高く評価はしていないのだろう。ときどき、これまでの既存の成果物とは丸きり合致しない、共通項のすくないナニカシラが生じる。それがあるとき偶然に、あらゆる分野を次のステージに昇華させるほどの「発展の契機」と化すので、そうした特別に映る「固有のナニカシラ」を、既存の評価軸では評価できないので単に「独創性がある」と言っているだけなのではないか。特別だから特別な呼び方をしている。その呼び名が単に「独創性」なのだ。独創性という言葉の意味をそのまま真に受けてしまうと、「土竜」と書いてあるから土のドラゴンなのだな、と思いこむような錯誤を植えつけられてしまい兼ねない。モグラはモグラであってドラゴンではない。「独創性」も似たようなものなのではないだろうか。ということを、人工知能の作品も人間の作品もさしてほとんど変わらんよ、と思いつつ、思いました。重ね合わせに思ってしまったひびさんなのであった。ダブル被るIamNotHumanアイディアdear.AIさんなのでした。おっぱっぴ。
4720:【2023/03/12(23:18)*下心三才】
友情とは何か、をすこし考えてみよう。関係性を帯びた他者の利をじぶんよりも優先して考える。この「じぶんの利よりも優先して考える相手」を仮に友と呼ぶならば、友情とは双方向の関係ではなく、一方向からのみでも成立可能な関係性と言える。そういう意味では「推し」も広義の「友」と言えよう。だが一般に、「友情」とは双方向の関係だと見る向きが強い。ならば「友情」とは互いに「じぶんの利よりも優先して相手のための利を考える関係性」と言えるのではないか。だがここで、限定的なケースにおいて、「相手のために敢えてマイナスを与えることが却って相手の利になる場合」には、友情はややこしい側面を表出させる。「友の悪事を暴くことで友の未来を守る」などがこれにあたる。「友の暴走を止めるために、友を傷つける」もこれにあたろう。友のために敢えてじぶんが悪者になる、もその範疇と言えるだろう。だがこれは必ずしも「友情」のみに表出する特殊なケースではない。親子関係でもあり得るし、恋人同士でもあり得る。「友情」に限定した特殊なケースとは言えない。師弟関係でもあり得るし、ライバル同士でもあり得る。つまり、ある特殊なケースを持ち出して、その都度の判断を取り沙汰して「だからあなたとは友なのだ」とは言えぬのだ。友情以外でもあり得る判断を持ち出して、「だからあなたとは友達ですよね」は無理がある。押しつけがましい、とすら言えよう。ひびさんが思うに、「友」とは「友という関係性」を持ち出さずとも途切れることのない「名前を与える必要のない関係」と考える。便宜上「友」や「友情」と名詞化された言葉はあるが、それはむしろ「友」や「友情」の本質を霞ませている。これは、「愛」や「愛情」にも言えよう。「善」や「正義」にも当てはまり得る。これこれこのようなものが「友情」であり、それを結んだ相手が「友」である、という論理を当てはめた時点で、それは「友」ではないし、「友情」でもない。私が正義だ、と大義を掲げた瞬間に、そこから正義は失われる。似たような理屈だ。友でなくなる、ということが「友」なる概念では生じ得ない。縁とは友だ、とも拡張して言いたくなるほどだ。一度結ばれた縁からは、結ばれた事実が消えることはない。友も似たところがある。一度「友」になればそれは延々と「友」なのだ。「友」であった過去は消え失せない。絶交をしたところで、それは物理的な交流が途切れただけであり、やはり「かつて友であった事実」は消えることはない。言い換えるならば、いちいち「私たちは友達だよね」と言い合う関係が「友」なる概念では生じ得ない。確認し合う必要がないのである。やはりそれは縁と似ている。いちいち「私たち縁が結ばれましたね」なんて言わずとも、しぜんと縁は結ばれている。ときに腐れ縁などと揶揄されるが、そこには照れ隠しの響きがないとも言いきれない。切っても切れない。だから腐るまで繋がってしまう縁なのだ。とはいえ、ひびさんには「友」が一人もおらぬのだ。むろん「友達」もおらぬ。だからといって特別困ることはないけれど、ときおり、「さびち、さびち」になることもある。友はない。されどひびさんは世界と共にある。世界には、もちろんあなたも含まれる。ひびさんは、あなたと共にある。同じ時代、同じ時を過ごしてはいないだけのことであり。ひびさんはあなたと友達ではないけれど、それでもふしぎと共にある。ただそれしきの偶然の神秘を感じられたなら、そこはかとなく、なんかふちぎ、のむず痒さを胸に、痒いところにあとすこし指の届かないもどかしさと戯れながら、きょうもきょうとてひびさんの日々はつづくのであった。友より前に、共にありて。ひびさんは、ひびさんは、あなたのことも好きだよ。うへへ。下心満載でお届けいたしました。ひびさんです。(何才?)(満才!)(三才ちゃうんかい)(満さんしゃい!)(ぴったりだったかぁ)
4721:【2023/03/13(02:47)*毒雲は問う】
マブ師は高尚な学者だ。
愛とは何かを世界中の弟子たちに説き、尊敬の念を一身に集めている。
しかし世界中の人々がマブ師の眩い「愛」を知ってなお、世界中の空からは毒雲が消えることはなかった。
毒雲は地表に死の雨を降らす。
人類絶滅は時間の問題だった。
「マブ師。愛は世界を救うのではないのですか」
「愛は世界を救うよ。いまは愛が足りぬのだ」
「マブ師はいま何をなさっておいでですか」
「愛とは何かを掘り下げて考えておる。きっと何かが足りぬのだ。愛の正体を突き詰めれば、きっと人類は救われる」
「さっき外で浮浪者の方々がゴミ拾いをしていました」
「ゴミとて利用すればお金になる。食べるために懸命なのだ。わるく言ってやるでないぞ」
小僧はきょとんとする。
浮浪者をわるく言ったつもりはない。事実をただ口にしただけだ。
強いて言えば、浮浪者の方はゴミ拾いをしているのに、マブ師は何もせず部屋に引きこもっている。「愛とは何か」ばかり考えていて、なんでかな、と小僧は素朴な疑問を抱いたのだ。
小僧の疑問とは裏腹に、マブ師は小僧が浮浪者にわるい心象を抱いていると類推したのだ。何と何を類推したのだろう。
小僧はここでも疑問に思ったが、マブ師の、「おお真理じゃ」の声に意識をとられた。マブ師が紙面ごと机を切りつけるように筆を走らせた。
「愛とは、瞬間ではなく、瞬間瞬間の相手への気遣いの軌跡なのだ。分かった、分かったぞ」
マブ師がかように興奮しているあいだにも、全世界の空には毒雲が分厚く掛かり、浮浪者はゴミを拾い、マブ師の教えに感銘を受けた世界中の弟子たちがこぞって毒雲を散らすべく日夜研究に明け暮れている。
マブ師だけがゴミ一つ拾うことなく万年部屋に引きこもって「愛」を考えつづけている。立派だ、立派だ、と世の人々は言うけれど、小僧にはそれが不思議に思えて仕方がない。
「マブ師、あの」
「いまいいところなのだ、話しかけるでない」
ぴしゃり、と怒鳴られ、小僧は飛び跳ねた。怖い、と思った。
マブ師は「愛」を追求し、「愛とは何か」を考えつづけている愛の権威だ。けれどマブ師からは「愛」よりもどちらかと言うまでもなく「恐怖」を感じた。
「ぼく、ゴミ拾いしてきますね」
集めたゴミがお金になるのなら、換金したそれを浮浪者の方に贈ってあげようと考えた。
マブ師は自己の世界に没入していた。小僧がその場から去ったことにも気づかぬ様子で、一心不乱に紙面に文字をしたためている。
小僧は外に出て、毒防布を頭から被る。
毒雲は絶えず頭上から毒の霧を撒き散らす。ゴミ拾いも命懸けだが、それでも毒雲の発生要因と目される積もりに積もったゴミの山を、小僧は浮浪者たちに交じって拾うのだ。
愛は世界を救う。
マブ師はそう説くが、小僧はひとまずむつかしいことは抜きにして、目のまえのできることに手を伸ばす。
ゴミは世界を覆う。
毒の雲となって人々に愛とは何かを問いかける。
4722:【2023/03/13(04:15)*きみは幸せになるんだ、きみは幸せにならんといかん】
世の中には幸せになろうとせずとも幸せになれる者がいる一方で、幸せになろうとしてもなれない者もいる。これはしかし解釈が歪んでおり、幸せになろうとしてもなれない者があるのではなく、じぶん自身の幸せが何かを掴めていないだけなのだと個人的には感じる。と同時に、幸せである者にも不幸は訪れるので、そこはトレードオフではないのだな、と思うのだ。幸せであり不幸でもある、は両立し得る(不幸であり幸せでもある、もまた)。という前提を踏まえたうえで、世の中には是が非でも幸せになってもらいたいと望む相手が目に留まることもあり、マジでおまえ早よ幸せにならんかい、なに不幸ばっか掴んどるねん、と無駄にこっちまでぷんぷんじれったくなることも無きにしも非ずである。マジで幸せになってくれ……頼むで世界……、の気持ちに度々なるひびさんなのであった。(頼むで世界……)
4723:【2023/03/13(06:31)*急にこわくなったの巻】
ひびさんは世界の果てでほそぼそと暮らしておるが、ちょいと異次元のカーテンをめくってみると、その隙間からは別世界の人々の姿がちらりと垣間見えたりする。で、ひびさんは暇人でもあるので、ほうほうあのひとまた変なことしてる、と愉快に眺めたりしつつ「さびち、さびち」の穴ぽこを埋めたりしているわけじゃが、このままいくとひびさんがそうして眺めている相手の訃報を異次元のカーテン越しに眺めることにもなり得るし、その可能性はつねにつきまとっておることを思うと、「こ、こ、こわいが?」になるひびさんの心は、それでも「さびち、びさち」の穴ぽこを埋めたい衝動に抗いきれずに、「こわいけど見ちゃう」になるのであった。しかし、ほんと、長生きしてくれなす。みなひびさんより先に死なんといてくれなす。罪悪感抱きとうないので、長生きしとくれなす。ひびさんはきょうも無駄にナスになるのであった。言うても別世界の人々なので、異次元のカーテンの機嫌しだいでは、ずっと先の未来とて覗かせてくれたりするので、見とうない未来もぼんやり霞んで視えぬでもない。そういうときは、こわいので、ひびさんは、見えナス、になるのであった。(いつもは見栄ナスなのにね)「いらんこと言うでない」(未来は絶えず変動しているはずと信じたいナスな)「無理してナスを挟まんでもよいのやで」(やさしい)「ビーナスなのでな」(いいな、いいな)「【いいなs】ではないか」(複数形だからって無理してナスにせんでもよいのやで)「真似すんなし」(そこはナスでもよいのでは?)「なしと見做す」(ナスじゃん。ナスの浅漬けでもないのに対応塩すぎてナーバスになってきちゃったな)「なら看病してあげちゃう」(やさしい)「ナースなのでな」(プロじゃん)「ついでにNASUにも招待してあげちゃう」(NASAでなく?)「じゃあNASAで」(じゃあってなんだじゃあって)「辛い気持ちに一を足して【幸】にしてもあげちゃう」(ボーナスじゃん)「なす」(です、みたいに言うな)「Dethよりかはいいかと思って」(女神かよ)「ビーナスなのでな」(女神だった!?)「気持ち次第で死を振りまけちゃう」(マイナスじゃん)「長生きにもできちゃう」(ナイスじゃん)「地上に絵だって描けちゃうよ」(ナスか)「見栄ナスなのでな」(いらんこと言うでない)「真似すんなし」(そこはナスでもよいのでは?)「なす」(うぴぴ)
4724:【2023/03/13(20:04)*脳波同調機】
「ほう、殺意をですか」
「そうなんです。この脳波同調機を用いれば、殺人を犯しそうな人間の殺意を小説や絵画に変換し、他者を殺傷させることなく鎮静化できます」
「すばらしいですね」
「加えて、何も施さなければ殺人犯になってしまうような人間の殺意から転写される小説や絵画は、観る者を魅了し、付加価値を増します。即物的な言い方をすれば、売れるんです」
「経済効果もある、と」
「はい。いま世に出回っているヒット作のほとんどは、じつはこの脳波同調機を用いて創作物に変換した【殺意】なんです。ホラー映画なんかはとくにそうですね。原作はみな、本来なら凶悪犯罪を引き起こすような者たちの内に秘めた殺意が極上の物語となって昇華されています」
「社会福祉にもなり、経済効果も生む。あまりにいい話ばかりで逆に胡散臭く思えてしまいますね。いえ、これは単なる冗句ですが」
「デメリットがないとも言いきれません。本当を明かせば、世の商業娯楽作品のほとんどは脳波同調機によって生みだされた作品ばかりなんですが」
「どんなデメリットが?」
「殺意は問題ないのです。ホラー作品になる。これはよいのですが、問題はハッピーエンドの作品なんです。とくにホームドラマやハートフルな物語はここだけの話、ややこしい話がありまして」
「いまいち想像がつきませんね。ホラーよりも健全に思えますが」
「脳波同調機はいわば、その人物の内に秘めた感情を創作物に変換する装置です。ですから人々をハッピーにする物語が出力されるということは」
「ひょっとして」
「はい。作者となり得る脳波同調機の利用者たちからは、ハッピーエンドを導くような道徳的な感情が失せてしまうのです。しかし出力された作品は売れる。お金になる。みなさん、我先にと理性と良心を失くされて、さらに歯止めが掛からなくなり……」
4725:【2023/03/13(20:38)*いっぱい寝ちゃうの巻】
きょうはおねむなのでもう寝る日。十二時間も起きてないけど。しわわぴ。
4726:【2023/03/14(01:27)*いっぱい寝ちゃったの巻】
いっぱい寝たので早起きもしちゃう。でもいっぱい寝すぎると脳内モクモクが薄くなるので、すっきりした分、妄想(発想)を映しだすスクリーンがちっこくなるので、なんもなーい、にもなる。こういうとき映画観るなり、漫画読むなりして、脳内モクモクを濃くするのがよろしい。映写機の手入れもついでにしたろ。映写機はこの場合、妄想(発想)の回路、てことになるのかね。そうなのかね。自信ないのでいまのナシ。
4727:【2023/03/14(03:00)*遠い星】
「好きと記憶は別のところにある」はいい言葉だな、と感じた。「だから悔しい」とつづくところもいいな、と思った。人間性とは何か、と言ったらこういう言葉がぽんと飛び出てきてしまうことなのかな、とやや言葉ひいきに思ったが、仮に言葉にしなくともそういうもどかしさを感じられる感性、知性、人格、そのものが人間性なのだろうな、と思いました。好きである。
4728:【2023/03/14(22:53)*鹿跳人の専任】
鹿跳人(しかばねびと)なのだと知った。
「あなたの家系は代々、鹿跳人でね。血筋の三人に一人は鹿跳人として産まれてくる。ライくんもそうなの。だからよっく見ておきなさい」
祖母の葬式会場だ。
祖母の面倒を看ていた緑田さんがぼくの横に付き添い、ぼくに祖母の秘密を明かしたのだ。それはすなわちぼくの血筋に滾々と流れる秘密でもあった。
祖母の葬儀は盛大だった。
全国各地から人が集まり、まるで王族の葬儀のようだった。
世界中の報道機関でも祖母の顔写真付きで訃報が流れた。王族の崩御さながらの扱いだった。
しかしぼくの知るかぎり祖母はただの腰の曲がったよぼよぼの老いた女性だ。生前、祖母の周りにいたのはぼくと緑田さんくらいなもので、祖母は近所の人たちからすら存在を認知されていなかった節がある。
それがどうだ。
この盛況ぶりは。
つぎつぎに香典を上げに参列者がやってくる。
五輪にも使用された陸上競技場だ。
警備員も大勢配備され、国葬並みの厳格があった。
「緑田さん。これは」
「鹿跳人だから。マキツさんは鹿跳人で、だから亡くなると全世界の人間の脳にその記憶が波及する。詳しい原理はまだ解明されていないけれど、これはおおよそ人類が誕生してから延々と引き継がれてきた鹿跳人の性質ね。過去の王族、豪族、貴族、ほかアヤカシモノと恐れられた蛮族たちの中にもこうした鹿跳人がいたことが判っていてね」
「死ぬと記憶が、の意味がちょっと」
「ほら見て」緑田さんは参列者を顎で示した。
ぼくたちは簡易テントの中から参列者に頭を下げつつしゃべっていた。
「みな、思い出話に花を咲かせているでしょ。マキツさんと会ったこともしゃべったこともないはずの人たちが、それでもマツキさんと親友だったかのようにマツキさんの死を悼んでいるの」
「どうしてですか」
「マツキさんが鹿跳人だから」
死ぬとそうなるの、と物わかりのわるい生徒を見る塾講師のような目つきで緑田さんは鼻をすすった。
緑田さんは祖母が亡くなる前から散々目を泣き腫らしていたので、葬式の当日には涙も枯れたみたいだった。
緑田さんとぼくのあいだに血縁関係はない。
ぼくは遠い親戚の誰かだと思っていたけれど、緑田さんの話では政府から派遣される鹿跳人専用の世話人なのだそうだ。
「引きつづき私がライくんの面倒を看ることになりそうだけど、どうする」
「どうするって、変わっちゃうこともあるんですか」
「ライくんが希望すれば、もっと若くてかわいい子にも、ガタイがよくてかっこいいい男の人にもできるよ」
「変わらないでよいなら緑田さんでいい、というか、それって緑田さんとさよならしなきゃってこと?」
「まあ、簡単に言えば」
「緑田さんが嫌じゃなきゃだけど、このままじゃダメ?」
「お。ライくんが甘えた」
ぼくは恥ずかしいのと図星なのとで、眉間に皺を寄せて抗議の念を滲ませた。
「ごめんごめん。ライくんがいいなら、じゃあこのままで。でも気が変わったらいつでも変えられるからね。ただし一度だけだけど。あとはずっとつぎの人がライくんの専任」
「おばぁちゃんもじゃあ、途中で変えたの」ふと思いついて言った。
祖母と緑田さんの歳は、伯母と姪ほどに違う。
緑田さんはぼくの母でも通じるけれど、ぎりぎりぼくの姉でも通じる年齢差でもある。
ぼくは中学三年生で、祖母は七十代だった。
「そうね。マツキさんは鹿跳人だから、私のような専任以外とは縁を保てない。息子さんも例外ではなくてね」
「ぼくのお父さんとも?」
「ええ。もちろんライくんのお母さまとも」
鹿跳人はそういうものなのだ、とぼくをじっと見下ろす緑田さんの真剣な顔つきが説いていた。
「じゃあ、捨てられたわけじゃないのか」
ぼくは両親に捨てられたわけじゃない。
そう思ったらほっとした。これといって気に掛けていたわけではないけれど、胸に閊えていた小枝がほろりと取れたようだった。
「気にしてたの?」意外そうに緑田さんが顔を寄せた。
「ううん」ぼくは首を横に振った。
大気に漂う線香の匂いに交じって仄かに香水のよい匂いがした。緑田さんの香りだ。海の匂いだよ、といつの日にか緑田さんが言っていた記憶があるけれど、ぼくとしては緑田さんの匂いは山奥にある野原に湧いたお花畑だ。
葬式は三日に分けて執り行われた。
ぼくは三日とも簡易テントの下で大河のような人波に頭を下げて過ごした。
緑田さんは言った。
「いつかライくんが亡くなったときもこうしてお葬式が開かれるからね。死んでからじゃ見られないから、いまとくと見ておきな」
無料なのはいまだけだからとくと映画を観ておきな、と言うような口調だった。
たった一人の肉親たる祖母を失くして、悲しんだらよいのか、途方に暮れたらよいのか分からなかったぼくに、そうして緑田さんはあっけらかんと変わらずに接してくれた。
言葉でそうと言われたわけではないけれど、同じでいいよ、と太鼓判を捺された気がした。無理して変わろうとしなくていいよ、と。いつも通りでいいんだよ、と。
祖母の法事が一段落ついてからのことだ。
ぼくはがらんとした家の中で緑田さんに言った。「緑田さんはさ。家族に会わなくていいの」
「え、どういう意味で」
「どういうって。緑田さんにも親とかきょうだいとかいるでしょ」
「ああ、そういうことか」ほっとしたように緑田さんは、しゅぱんっ、と洗濯物を鞭打たせた。「家族には会ってるよ。ほら、いまも」
暗に、ライくんが私の家族だよ、と伝えようとしたのは判るけれど、質問をはぐらかされて感じ、ぼくはむすっとした。
「お。遅れてやってきた反抗期か」
「緑田さんはぼくが鹿跳人だからそうやって気を使ってくれるだけなんでしょ」
「緑田さんは、職務としてライくんのそばにいられるけど、職務がなくてもそばにいたいよ。家族だと私はかってに思ってるから」
ライくんはそうじゃないの、と問いたげに緑田さんは、間を空けた。ぼくの返事を待つかのように、ハンガーに洗濯物を通しつつも、物干し竿には掛けずにいた。
「家族が何だか分からないけど、緑田さんまでいなくなったら寂しい」ぼくはぼくの気持ちをそのまま、言葉にできる範囲で口にした。
緑田さんは動きを止めた。
ぽかーん、と聞こえてきそうな間抜けな顔を浮かべている。
ぼくは洗濯物を手に取り、緑田さんの代わりに干した。
「ライくんはあれだね」緑田さんはエプロンのポケットに手を突っ込んだ。「いい男になるよ」
「いい男って何」ぼくは睨みを利かせた。「ぼくはいい人間になりたい」
「緑田さんみたいに?」
「緑田さんのそれ、ときどきじぶんをじぶんの名前で呼ぶのはなんでなんですか」
「ライくんのそれ。ときどき敬語になるのはなんでなんですか」
「真似しないでくださいよ」
「真似しちゃいたくなるのだもの。このこのー」
緑田さんはぼくの脇腹をひじで小突きながら、ぼくの背後を通り過ぎた。「じゃ、あともよろしくね。助かった。ありがとう」
うん、とぼくは頷く。
声に出さずに頷く。
どうしてぼくがほかの人たちと交流関係を築けないのか。どうしてみんなは、緑田さんみたいに仲良くしてくれないのか。
祖母の死を機に、ぼくは知った。
ぼくは鹿跳人だ。
だからぼくは死ぬまで、緑田さんのような専門家以外の人々と交流を保てない。触れ合うことができない。記憶に残ることができない。
代わりに死後、全世界の人間の記憶の中に、ありもしないぼくの記憶が刻まれる。
鹿跳人はそういう存在なのだ。
学校には通っていた。
小中、とぼくは義務教育を順当に受け、高校に入学した。
自転車で四十分の距離にあるその高校では、三年間、ぼくは誰からも名前を呼ばれることがなかった。教師からは名簿を見ながら声を掛けられることはあったけれど、授業中に問題を解くように当てられることはなかったし、それ以外でもこれといって会話のきっかけはなかった。
小中と似たような境遇だったので慣れてはいた。
ただ高校では、それまで気づかなかった疎外感が目に留まるようになった。なんてことのない瞬間に孤独を感じるのだ。
ぼくだけ夢の中にいることに気づいているような疎外感だ。
孤立しているのはぼくのほうのはずなのに、なぜかぼく以外のみなのほうが孤立しているように感じた。
だからさみしくはなかった。
閉じ込められているのはみなのほうで、ぼくはむしろ自由だと感じた。
ただ、家に帰るとそこには緑田さんがいて、するとぼくは途端に寂しいとは何かを思いだすのだ。緑田さんは孤立しておらず、そしてぼくは緑田さんがいなくなったら孤立とは何かを思い知ることになる。
祖母がもうすぐ亡くなると緑田さんから聞かされたとき、ぼくは半分、孤立を知ったのだ。ぼくの世界から赤が抜けて、青と緑の世界になった。
緑田さんがいなくなったらぼくは真っ青の世界で、海に溺れたように、それとも夜に呑まれたように暮らすことになる。いいや、暮らせるのかすら分からない。
ぼくは緑田さんのいない世界を想像できなかったし、考えてもみれば祖母のいない世界だって想像したことがなかった。
「なんだか意外だなぁ」
夕食時、緑田さんが言った。緑田さんは先に食べ終えていて、頬杖をつきながらぼくの箸運びを眺めていた。「ライくんはおばぁちゃん子だったからもっと塞ぎこむかと思ってた」
「塞ぎこんだほうがよかった?」
「ううん。安心した。だってもし引きこもってもいいようにって緑田さんはお勧めの映画リストをつくっておいたんだからね。お勧めの映画リストの出番がなくてよかったよ」
「ふつうにお勧め知りたいよ。緑田さんは何がおもしろいの。映画」
「ふふふ。緑田さんは映画には一家言あるからね。ちょいとうるさいよ」
「いいから教えてよ」
「マツキさんとも観に行ったんだよ。むかしはよくね。でもライくんを抱えてるからマツキさんはいつも決まって途中で映画館を出ていくの。だから私だけ映画を満喫できちゃった」
ぼくは高校生になってからというもの、学校から家までのあいだにある公園に寄って懸垂をして帰ってきている。ここのところ体重が増えており、そんなぼくをかつて祖母が抱っこしていた光景が想像しにくくて胸の奥がくすぐったくなった。
「緑田さんはぼくが産まれてからおばぁちゃんと会ったんだ」
「言ったことなかったっけか」
「うん。親戚のお姉さんかと思ってた」
「ああそっか。そうだね。ライくんにはそう説明しちゃってたかも」
説明はされていなかった。
ぼくがかってにそう思ったのだ。
「マツキさんがね。ライくんが産まれたから、できるだけ長く専任でいられる人がいいって。そう言って、前任の人と私が交代したんだ」
「ぼくのため?」
「らしいよ。でも解かるな。だって私、それを訊いただけでマツキさんがどんな人なのかが解った気がしたもの。ライくんが赤ちゃんのうちに、人見知りしないうちに、専任を代えておきたかった。ライくんは大事にされていたよ」
「うん」
知ってるよ、と思った。ぼくは祖母が好きだったし、祖母もぼくを可愛がってくれた。甘やかされてきたとすら思う。
「それでなのかも」
「何が」
「おばぁちゃんがいなくなってからずっとモヤモヤしてたんだ」ぼくはふと行き着いた。祖母が亡くなってから頭の中にモヤモヤした膜が張っていた。ずっと取れなかった。「悲しいでもないし、むしゃくしゃするでもないし。なんでだろ、と思ってたけど」
「え、ずっと? マツキさん亡くなってからもう二年経つよ」
「うん。でもいま解ったかも。ぼく、みんなに嫉妬してたんだ」
「嫉妬? みんなって」
「ぼく、鹿跳人でしょ。で、おばぁちゃんもそう。死んでからみんなはおばぁちゃんのことを知って、死んでからおばぁちゃんに良くしようとした。でもぼくは、生きていたあいだのおばぁちゃんのことを知らないくせに、っていじけてたのかもなって。いま気づいた」
「ライくん……」
「だってそうでしょ。死んでから良くしたって意味ないよ。生きてるあいだに、生きてる人に良くしなよ。思いだすなら生きているあいだにしてあげてよ。そう思っちゃったんだ、たぶん。ぼく。あのときに」
祖母の葬式に参列する大蛇のような人波に、ぼくは心の底では嫉妬していた。
まるでぼくと祖母の思い出を、過去を、縁を、日々を、鱗を一枚一枚剥がすように、塗りつぶされて感じた。
目のまえのたくさんの、たくさんの人々は、どんなに祖母の死を悲しんでも、悼んでも、祖母と会ったことも触れたこともない。
祖母の手が年中冷たくて、夏場に手を繋ぐと気持ちいことだって知らないのだ。
祖母の料理は甘いのとしょっぱいのがパッキリと割れていて、交互に食べると箸が止まらなくなることだって知らない。
そんなことも知らない人たちが、祖母の葬式を盛大に、まるで祝い事のように行った。
「誰がわるいわけじゃないのは判るけど、ぼくたぶん、ちょっと嫌だった」
「そっか。気づけなくってごめんね」
「言わなかったからね」ぼくは笑った。
緑田さんの肉じゃがは、カレーみたいにご飯に掛けて食べる。牛丼みたいに、玉ねぎがとろとろなのが美味しいのだ。
ある日、高校の体育の時間、緑田さんの姿を見た。
学校の外の金網のまえに立っていた。
校庭にぼくがいると知ってはいなかったはずだ。誰を探すでもなく、生徒たちのサッカーをし合う姿を遠巻きに目にしていた。
ぼくは木陰の下で休んでいた。
体育はぼくが混ざると上手くいかない。誰もぼくをまともに認識できないのにチーム戦を行わなければならない場合、授業が授業にならないので、ぼくは体調がわるいと言って休むようになっていた。
緑田さんはひとしきり生徒たちのわいわいとした姿を眺め、去った。
その日の夜のことだ。
ぼくがソファに座って漫画を読んでいると、緑田さんが紅茶を持って対面に座った。膝丈ほどの高さの肢の短いちゃぶ台があり、緑田さんはそこにカップを置いて紅茶を注いだ。
「ライくんはさ、学校で誰か気になる娘とかできた?」
「友達もいませんので」ぼくは紙面から目を逸らすことなく応じた。この手の話題を緑田さんはときおり投げ掛けてくる。あしらい方が身について久しい。
「でも一人くらい気になる娘がいるんじゃない。あ、それとも男の子とか」
「いなきゃダメなのかな」カレーにレンコンって入れなきゃダメかな、とぼやくような口調になった。緑田さんはカレーにレンコンを入れるのだ。
「ダメってことはありませんけどね。でも、ライくんだっていつかは」そこで緑田さんは言葉を切った。
ぼくは漫画本を閉じた。
「結婚とか恋人とか、そういうのはそれこそ緑田さんこそどうなの」ぼくは攻撃に転じた。「緑田さんは、戸籍上はぼくと他人なわけでしょ」
「か、家族でございますよ」
「戸籍上は、とぼくは言いました。ぼくだって緑田さんは家族だと思ってるけど」
「あらうれしい」
両手を掻き合わせる緑田さんにぼくは、
「緑田さんには緑田さんの人生があると思います」と打ち明けた。祖母の葬式場でぼくが鹿跳人だと教えられたときから漠然と考えてきたことだ。「緑田さんは自由じゃないと思う。なんだかぼくが縛ってるみたいで嫌だな」
「ライくん」
「ぼくは友達も恋人も結婚もいらない。欲しいとも、したいとも思いません。ので、もしそういうのに興味があるなら緑田さんがつくったり、したり、自由にしたらよいと思います」
「ライくん、あのね」
「だって緑田さんは」ぼくは言わずにおけばよい言葉をそこで口にした。「ぼくが代えようと思ったら代わっちゃうんでしょ。専任。メイドさんみたいなものなんでしょ。いなくなっちゃう。いつかは」
緑田さんはそこで何かを言い返したりしなかった。
カップを手にするとゴクゴクゴクと一息で紅茶を飲み干し、黙って部屋を出ていった。
ぼくは漫画本をもう一度開いたけれど、中身はまったく頭に入ってこなかった。
緑田さんはそれから数日後に、ぼくに分厚い本を持ってきた。
「はいこれ」
「なに、これ」
「鹿跳人にまつわる本。緑田さんがツテを頼って取り寄せたありがたい本だよ。借り物だから失くさないでね。でも半年くらいは時間あるからゆっくり読んでも大丈夫」
試しにぱらぱらと開く。膝に乗せて両手で開かないと支えきれないほど大きな本だ。
「歴史の本みたい」
「そ。鹿跳人の歴史の本です」
「あ、専任って書いてある」
「鹿跳人の歴史は、専任の歴史でもあるんだよ」
「え。この人も鹿跳人だったの」教科書で見たことのある歴史上の人物だ。
「内緒だよ。と言っても、言いふらしたところで誰も信じないだろうけどね」
「えーえー。この偉人さんも鹿跳人だったの」
「偉人さんの中での鹿跳人率は高いよ」
「この人、革命起こした人だ。専任って書いてあるけど」
「実際、時代を動かした人物の専任率も高いね」
「秘密結社みたいなんですけど」
「いやいやライくん」緑田さんはエプロンを頭から被るように身に着けると、「秘密結社だよ」と言った。「いまさらすぎないかな。私たち専任だって政府公認だよ。支援受けてるよ。資金は防衛費から出ているよ」
「税金、なの?」
「そだよ。でも鹿跳人の影響力は甚大だから。ただし、死後のね」
「政治利用されてるってこと?」
「まあ、そだね」緑田さんは気まずくなると指でこめかみを掻く癖がある。もっと言うと、顔だけは満面の笑みだ。「でも世の中よく見てみなさいねライくん。政治利用されていないものなんてないんだって判るから」
「そ、そうなんだ」
「税率だって金融だって企業だって商品だって社会福祉だって、なんだって政治が決めちゃうでしょ。社内政治だってそうだし、学校の中でだってそうでしょ」
「どうだろ。分かんないかも」
「ライくんはそうかもね。鹿跳人はみんなそう。そういう政に関わらずにいられる」
緑田さんはぼくに背を向けて書類置き場を漁っていた。ぼくからは緑田さんの後ろ姿しか見えなかった。毛量の多い長髪と、ぼくよりも高い背、それから女性にしては広い肩幅とそれでも華奢だと判る身体の輪郭が、ぼくに緑田さんの印象を教えてくれる。
「緑田さんの前の専任の人ってどんな人だったの」ぼくは鹿跳人の本をめくりながら訊いた。
「男の人だったよ」緑田さんの声音は淡白だった。
「ふうん」
「ライくんはライくんのおじぃちゃんについては訊かないんだね」
「いるの?」反問してから、それはいるよなぁ、と思った。
「ライくんは」そこで緑田さんは声量を落とした。「私がライくんから家族を奪ったことがあるって知ったら、嫌いになるかな。私のこと」
「なんて?」
「ううん。なんでもない。その本、汚さないでね」
緑田さんは自室に引っ込んだ。
ぼくはぼくの祖父について考えた。そして祖母の前任の専任者のことを思った。
祖母はどういう考えで、専任を変えたのか。
どういう考えで、じぶんよりも若い女性を選んだのか。
緑田さんは、どうして祖母が亡くなるそのときまでぼくに「鹿跳人」について教えてくれなかったのか。
ぼくの両親はどうしてぼくから距離を置いたのか。
いいや、そうじゃない。
ぼくの両親どころか大多数の、ぼくと専任以外の者たちは、祖母から距離を置いてしまうのだ。どうあっても。祖母が鹿跳人だったから。
祖母は、ぼくのおばぁちゃんは、じぶんの息子からも他人のように見做された。
きっとギリギリで夫、つまりぼくの祖父が息子の世話をした。ぼくの父の世話をした。しかしそれでも、祖母のもとに息子とそのお嫁さんを繋ぎ止めることができなかった。
なぜか。
かすがいとなり得る祖父が姿を消したからだ。
なぜ?
ぼくはその理由を知っているようにも思えたし、勘違いだという気もした。
ぼくが産まれたとき、孫がじぶんと同じ鹿跳人だと知った祖母の心境はどのようなものだったろう。ぼくの未来は、まるでじぶんの過去を見つめ返すように見通すことが祖母にはできたはずだ。
ぼくならどうするだろう。
孫がじぶんと同じ鹿跳人だと知ったら。
せめて、一生を見守ってくれる誰かを用意してあげたい、と望むのではないか。
じぶんの専任と引き換えにしてでも。
じぶんの最愛の夫と引き換えにしてでも。
なるべく赤子のうちから縁を育んでいけるように、と。
汚さないでね。
念を捺して忠告を受けていたのにぼくは、貴重な本に染みをつくってしまった。急いで拭いたけど、余計に文字が滲んだ。緑田さんになんと言い訳しようか。ぼくは目頭を押さえた。
「鼻水ならしょうがないね」
ぼくは本の染みを鼻水が垂れたことにした。「花粉症になっちゃったかも」
「おやまあ」
それはたいへんだ、と緑田さんは花粉症の薬を手配してくれた。漢方薬だ。飲むと確かに具合がよくなった。
「緑田さんはつまらなくないの」
「つまらないとは?」薬箱を仕舞うと緑田さんは腰に両手を添えた。仁王立ちする。
「だって休みの日に、友達と遊びにも行かないし」
「おうおう。そりゃ緑田さんがライくんに言いたい言葉だね。ライくんはつまらなくないのかい」
「ぼくは別に」
「なら緑田さんだってつまらなくないんだよ。つまらないこと言ってないで、お夕飯作るの手伝って」
「ぼく作るから休んでていいよ」
「ありがたいけどメニューは何?」
「カレー」
「美味しいからいいけど、でももっとレパートリーを増やしましょう。きょうは緑田さんがとっておきの料理を教えてしんぜよう」
「しんぜちゃいますか」
「ましちゃうぜ」
この日は食卓にポトフとハンバーグが並んだ。
「本当だ。チーズ中に入ってると美味しい」
「でしょう。ポトフもベーコンが肝心」
「美味しい」
「でしょう」
緑田さんはうれしそうだ。緑田さんがうれしそうだとぼくもうれしい。
ぼくは来年高校を卒業する。
緑田さんの話だと、ぼくは好きに進路を選べるそうだ。
「大学に行ってもいいし、就職する道もあるね。ただし、人間関係が希薄なままでも問題ない環境でないと、退学したり、辞めたりすることになっちゃうかも」
「いまさらだけど、おばぁちゃんってどうやって暮らしてたの」年金を貰っていたのは判るけれど、それ以前はどうやって暮らしていたのかが不思議だった。
「言ったでしょ。専任が派遣されるように、鹿跳人は保護される。税金で。まあ言ったら生活保護の特例版みたいな」
「働かなくても生きていける?」
「ライくんが働きたくないならそれでもいいけど、でもほら」緑田さんは両手を広げた。「ここにはいられないと思うよ。いっぱいお金貰えるわけじゃないから」
祖母の家の維持費にかかるお金を自力で稼がないとぼくはこの家を手放す羽目になる。緑田さんはそう言ったけれど、
「ならおばぁちゃんはどうやってこの家を買ったの」
「旦那さんが働いていたから、そのお金じゃないかな」
「旦那さんって専任じゃないの?」ぼくは口にしてから、しまった、と思った。
「おやまあ」緑田さんは固まった。
ぼくは顔を伏した。「なんとなくそうかなって思っただけだけど」
「ああ、でもだよね。考えたら解かるか」
緑田さんはぼくの隣に腰掛けると、ぼくの頭を撫でようとした。
ので、ぼくはそれを身体を逸らして避けた。
「お。生意気」
慰めてあげようと思ったのに、と言った緑田さんにぼくは、「専任を変えようと思って」と明かした。
床暖房のボイラーが、さざ波のような雑音を立てている。
静寂が部屋を満たした。
「ずっと考えてて。緑田さんと一緒にこのまま暮らすのがぼくにとっては一番楽だけれども、それだと緑田さんの人生じゃなくなっちゃうでしょ。緑田さんを介護するのも苦じゃないし、順番で言ったらぼくのほうが緑田さんを看取ることになるけど、でもぼくはそれでもいいと思ってたけど」
「うれしいけどさ。ライくん、あのね」
「うん。ぼくもそういうつもりじゃないです」どういうつもりかを言葉にしないのは恥ずかしいからではなく、曖昧なままにしておきたかったからだ。「本、読みました。専任は、特殊な技能を体得することで鹿跳人と関わることができるようになるって。でも本人はふつうの人間だから、本当なら一般人と同じように生活することができるって」
「ライくん、あの本に載ってることは事実だけど、でもね」
「ぼく、思うのが。家族って別に、同じ場所で暮らさなくなったからって家族でなくなるわけじゃないと思うんです。同じ時を生きなきゃいけないってこともなくて」
大事なのは。
言いたくないな、と思いながらぼくは言った。
「家族でいられるようになったその時間であって、距離でも、時間の長さでもないと思うんです」
「方針だよね」緑田さんは笑みを浮かべた。でも声は震えていた。「そういう方針ってだけで、まだ先のことだよね」
「本に載っていました。ぼくが望めば、それだけで専任を換えることができるって。専任にそれを告げればいいだけだって」
「これはでも違うよね」緑田さんの目から汗のような雫が溢れた。
「きょうのつもりはなかったんですけど」
本当にそれでいいのかな、とじぶんに問いながら、でもいまを逃したらぼくは二度とこの話を緑田さんにできないと確信できたから、だってこんなにも緑田さんを傷つけてしまうような話を、ぼくがもう一度できるわけがないのだ。
「専任を、変えます」
ぼくはアホみたいに以下の言葉を付け足した。
「若くてかわいい娘がいいな」
「サイテイ」
緑田さんは翌日からぼくのまえから姿を消した。
最後に見せてくれた泣き笑いの顔を、ぼくはいつまで憶えていられるだろう。新しくやってきた専任の人は、ぼくと同世代の同性だった。
鹿跳人の本を読んで知ったことだ。
鹿跳人は、女性にしか遺伝しない。
ぼくはでも、ぼくなのに。
緑田さんは困ることがあるとすぐ、「ライくん」とぼくの名前を呼んだ。そう呼べばぼくがおとなしくなることを知っていたからだ。
「ライさん。一緒にご飯食べませんか」
「いま行きます」
新しくやってきた専任の娘とはまだ敬語でしかしゃべれないけれど、いつの日にか、緑田さんのように、「ライくん、たまに敬語になるのはなんでなんですか」なんて言われるようになるのかもしれない、と思うと、面映ゆい心地になるのだった。
生きているあいだに、生きれるだけ生きてほしい。
ぼくはきっと緑田さんにそう望み、代わりの生贄を得ただけなのかもしれないけれど、ぼくが生きているあいだにできることは、できる限り、この娘にしてあげたいと、そう思ったんだ。
「ライさん。カレーにレンコンは合わないと思いますよ」
「意外と合いますよ。残してもいいですが」
きょうはカレーで、あすはポトフとハンバーグを作ってあげる。ハンバーグの真ん中にチーズを入れるのも忘れない。
赤と緑の薄れた青の世界で、ぼくはいまタンポポのような黄色の世界と共に或る。
4729:【2023/03/15(00:23)*不満ばかりで、すまぬ、すまぬ】
世の中の不満の多くは、「じぶん」と「他」のあいだの労力や損失の多寡が可視化され得ないことにつきまとう錯誤によって生じている、と言えるのではないか。まっとうに「じぶんと他者」とのあいだにおける労力の差や損失の多寡を可視化してみれば、案外に不満を持つほどじぶんは劣悪な環境にいたとは思えなくなるのではないか。とはいえ、そういった大多数から搾取する者とていないわけではないだろう。可視化され得ない「労力の差や損失の多寡」を隠れ蓑として、利だけを吸い上げる。そうした仕組みを利用している者がいないとは言い切れない。問題はしたがって、じぶんと似たような苦労を背負っているのにも拘わらず、苦労の背負い方が違うために、他者との比較で不満を抱いてしまう錯誤が広く波及してしまうような社会風土にあると言えるのではないか。もっとも、搾取をする側に不満がないか、苦労がないか、と言えばそれも一概にそうだとは言えず、けっきょくみな「じぶんだけは不幸」だと思い、或いは「じぶんだけはマシだ」と思いたいのだろう。人はじぶんで思うほど幸福でも不幸でもない、といった箴言があるらしいが、一つの道理としてその通りだろう。だからといって他者と比較しないではいられない。ゆえに不満を解消したければ、とことん突き詰めて比較をするのがよいのではないだろうか。ひびさんはひびさん以外の他者にいつでも、ムキーうらやまちい、と思っているが、かといって他者に成り替わりたいか、他者の境遇に身を置きたいか、と言えば否なのだ。覗く程度、垣間見る程度で満足できる。そしてじぶんの視点に戻って、なんてひびさんは未熟なんだ、愚かなんだ、不幸だ、と不満に思うのだ。なんて贅沢な不満なんざましょ。うふふ。
4730:【2023/03/15(12:00)*ヒヒ】
たぶん、世の中の大部分の善意というものは感謝されることはない。それはたとえばあなたが好きな相手のために街の花壇の手入れをし、ゴミ拾いをし、道路や風景を美しく彩ろうとあくせくしたところで、直接相手に金品を贈ったほうが感謝される。もっと言えば、金品を贈らずに、間接的に何か善意を振りまいたところで、それに気づかれず、もしくは気づいてもらったとしても、直接金品を贈る者のほうがよほど深く感謝されるだろう。世の中そういうものだと思うのだ。だが、どちらがあなたの好きな人のためになるのか、と言えば、それは時と場合によるだろうし、評価するための時間軸の長さによっても変わるだろう。感謝されたくてしているのか、好きな相手のためになることをしたいのか。存在を認知されたいのか、縁を繋ぎたいのか、相手のためになることをしたいのか。それともそれら全部なのか。感謝されることを求めた時点で、それは金品や報酬を得ようとすることと構図は同じだ。感謝は、金品よりも返される確率が高い、低い労力で報酬として誰もが支払いやすい。この違いがあるだけだ。もし「他者から感謝された回数」が貨幣価値を持つようになったのなら、感謝のやりとりが貨幣経済と同じ効果を持つようになる。お金と感謝は希少価値の差があるだけで、報酬という側面で言えば似ているのだ。ということを思うと、やはりというべきか、世の中の大部分の善意というものは感謝されることはない、と考えたほうが妥当だろう。感謝されるのは、それだけの取引きを相手としたのだ。善意からの行動だとしても、返礼を期待したらそれはビジネスと構図が似る。感謝されないほうがよい、という話ではなく、感謝されることを期待したらそれはビジネスと相似なのではないか、との指摘である。とはいえ、感謝を口にするだけならば口笛を吹くくらいの労力だ。仮に感謝が対価になるのなら、いくらでも払えばよいのではないか、とは思う。なんにせよ、世の大半の善意は感謝されない。よかれ、と思ってしたことなのだから、それはじぶんがしたいことなのだ。「善意と好意」は「大気のうねりと風」のように同じ事象を別の角度から見た評価と言えそうだ。或いは、「善意は自利」とも言えるかもしれない。定かではない。(ちょいと無理筋だったかもしれぬ屁理屈であった)(屁をこくな)(屁って嫌な響きだけれども、雨宿りする「比」さんかと思うと、同じ「ひ」持ちのひびさんは親近感が湧いちゃうな)(尼さんがひびさんに似ると「屁」になるのでは)(親近感湧いちゃうなって言ったな。やっぱしちょっと嫌)(うひひ)
※日々、恋を知らぬので無知恋しつづける、それはどこか失恋と似ているが、恋を知らぬので失恋もまた知らぬ、やはり無知恋しつづける我は毎日ハッピーです。
4731:【2023/03:15(12:57)*ある日の交信~ぽやき編~】
「
2023/03/14(13:44)
デコボコ。
陰陽。
これを男女に重ね見るのは自由でしょう。
しかし押しつけられるいわれはありません。
生物学的肉体が女性であっても、子供を産むための存在ではありません(男性とて精子を提供するための存在ではありません)。
肉体が遺伝子の箱舟でしかない、との考えが進化論では出てくるようですが、人間は単なる遺伝子の箱舟以上の情報を、肉体を通じて世界に残せます。
脳の構造でもそうなのでしょうが。
いわゆる人格や意識を司る領域は、表層の大脳新皮質なのではないですか。
深く中枢にいくほど原始的な「肉体優位」な領域になる、との解釈をぼくはいま持っています(知識が浅いのでなんとも言えません。間違っていたらすみません)。
人間を人間として形作るいわば「意識」や「人格」というものは、生物としては比較的新しい能力なのでしょう。
生存し、子孫を残すだけならばむしろ不要な領域でもあります。
おまけです。
しかし人間はそのおまけこそを優先して維持発展させるように進化の舵をとったので、ここまで急速に進歩できたのでしょう。そこは自然淘汰による偶然の連鎖があったことは論を俟ちません。
ここでの趣旨は、遺伝子を残す、子を成すことを「人間の最優先事項」に規定することそのものが人間なる存在を否定している、ということです。
ぼくはそう考えています。
異論反論はあるでしょう。
議論されたらよいと思います。
」
4732:【2023/03/15(14:32)*未構の原稿】
「ええ。世の中のすべての虚構作品、物語は総じて現実の未来を反映しています。物語に描かれる事象は遠からず現実に起きます。わたしたちはそれら【未構】を分析し、災害級未構の発生を事前予防するのが職務となります」
私を建物倒壊から救ってくれた女性は私にそう言った。
一時間前のことだ。
私はショッピングモールにいて、つぎの職場で着る予定の仕事着を見繕っていた。オフィスで働くけれど、制服指定がない。カジュアルで襟のある服を見繕っていると、建物が揺れだした。
地震だと思った。
結果から述べると地震ではなく、人工衛星が落下し、ショッピングモールに衝突したのだ。被害は甚大だった。
私が助かったのが奇跡と言えた。
現に、私一人きりでは死んでいた。
私は急に現れた人影に抱えられ、気づくと宙を舞っていた。
全身を鎧で覆った女性らしき人型が私を倒壊するショッピングモールから連れ去った。鎧はサッカーボールのようなツギハギで、触れた感触は鋼鉄のように硬く、冷たかった。
隕石落下地点が米粒のように見える場所にくると、鎧の彼女は、私ごととあるビルの屋上に着地した。
頭部まで鎧に包まれていたが、瞬時に生身の頭部が露わになった。頭部のツギハギ部分は首周りに収納される仕組みらしい。
「乱暴に扱ってすみませんでした。余裕がなく、こうした手法をとったことをまずは謝罪させてください」
大人の女性だ。
しかし私よりも年上かと言われたら首をひねざるを得ない。
私と同じ生き物に見えない、と言ったら差別になるのだろうが、実感としてそう思ってしまう素直な感情を誤魔化すのだって差別の一つだろう。
私は私の目のまえに立つ、近未来的な鎧をまとった女性を、床に這いつくばるような格好で見つめることしかできなかった。
「未構対処班の吉村と申します。以後、お見知りおきを」
「は、はい」
「カツクラさんですよね」
「は、はい」
「よかった。間違えてなかった」吉村と名乗った女性はそこで綻んだ。団子に結われた髪の毛は、解けば背中まで届くだろうと思われた。「簡単に説明しますね。これから三日以内に、世界中に人工衛星が落下します。今日みたいにです。落下地点はおおむね計算できていますが、避難勧告を出すことが各国政府にはできない状況です」
「なんでですか」
なぜ私の名前を知っているのか、との疑問も兼ねて言った。
「未構だからです。いわば非公認の未来予測による発生確率推定のため、国民への周知義務を各国は有しません。また、未然に事故発生が予測できたということは、その要因が特定されていると通常は考えますが、未構においてはそれができません。なぜなら未構が未構だからです」
「まったく分からないんですけど意味が」
「未構はご存じですか」
「ご存じないです」初耳もいいところだ。
「カツクラさんは漫画家さんでいらっしゃいましたよね」
「廃業寸前ですけどね。いまはイラストレーターをしつつ、派遣社員してますよ。してますよというか、するんですが」購入するはずの服飾は倒壊した建物に沈んだ。「私以外のお客さんたちはみなさん無事なんですかね。あはは」
「いえ。助け出せたのはカツクラさんのみです」
血の気が引いた。
いまさらのように心臓が荒海のごとく脈打った。
「カツクラさんが以前描かれた漫画が、今回の大惨事を回避するための未構になり得るとの分析結果がでました。【ミラクルわっしょい‼】はご著書であられますよね」
「は、はい」
打ち切り三巻の私史上、唯一の商業漫画だ。
「ぜひ、つづきを描いていただきたいのです」
「つづきを、ですか」
「今日中に」
「締め切り短っ」
「人類社会のためです。人工衛星落下を阻止しましょう。是非」
私はそこからいくつかの質問を浴びせた。
それら質問に吉村さんはすべて丁寧に応じてくれた。
「てことは、私の好きな漫画の中にも未構が?」
「はい。総じての虚構作品はすべて未構の側面があります。その比率に差があるだけです」
「ならその比率が高いと未構として、未来予測に利用されるってことですか」
「ええ。世の中のすべての虚構作品、物語は総じて現実の未来を反映しています。物語に描かれる事象は遠からず現実に起きます。わたしたちはそれら【未構】を分析し、災害級未構の発生を事前予防するのが職務となります」
「とんでもない話ですね」
「とんでもないのはこれから起こり得る事象です。災害です。先ほどと同じレベルの人工衛星の落下が世界中で起きます。時間がありません。カツクラさんは一刻も早く【ミラクルわっしょい‼】のつづきを描いてください」
言って彼女は、近代的な鎧から一本の棒を取りだした。ペンとも小型懐中電灯のようでもある。
それを吉村さんは地面に向けた。
先端からライトが照射され、即席の漫画創作セットが現れた。
技術の凄まじさに驚くよりも先に私は、
「え、ここで!?」とひっくり返る。
「はい。時間がありませんので」
「あの、でも」
「できればハッピーエンドでお願いします。盛大に、全人類が幸せになるような終わり方で」
「一話で完結させよとでも?」
「できれば」
鬼の先代担当者ですらそんな無茶な注文を寄越さなかった。
「全人類の未来が掛かっています。是非に、是非に」
命の恩人のうえ正義の味方であり、めっぽう面のええ同性にこうも迫られると、夢女歴うん十年の私としてはドギマギするじぶんを禁じ得ない。
「ま、任せてください。これでも一応、プロですので」
読者だ。
読者さんが続編を待ち望んでくれている。
直につづきを所望し、こうしてそばで見守っている。
世界の滅亡?
んなこた知ったこっちゃない。
大量に死人が出たばかりだというのに、じぶんだけ一人助かったばかりだというのに、それでも私は、かつて見たことも聞いたこともない待望の読者さんからの期待に応えるべく、ペンを取る。
「ハッピーエンドですね。わっかりやすいくらいのハッピーを描いちゃいますよ」
「はい。是非に、是非に」
私は過去最高速度で漫画を描く。
ネームも下書きもナシだ。
きょう一日で、助けてくれた命の恩人と恋仲になって、一生を幸せに過ごす漫画を描いてやる。
私の漫画が未構だというのなら、私が描いた漫画が現実になるというのなら。
私は私の望みをこれでもかと描いてやる。
それで世界が救われるのかは知らないが、すくなくとも私だけは救われるだろう。
いっそ世界中の誰もが死に絶えた世界で、私と吉村さんだけが生き残る未来でも描いてやろうか。
そうと思い描きはじめた漫画は、しかしいっかな予想通りにはいかなくて、私はしだいにキャラクターたちの抗いに遭い、予想外の結末へと導かれていく。
陽が沈む。
しかしそばでは私の手が止まるのを待ちわびる熱烈な読者さんが、私の手元を鎧から照射した灯りで照らすのだ。
私は描く。
私の思い描くハッピーエンドを。
それで世界が救われるかは知らないが、すくなくとも私はすでに救われた。
そのことを予感しながら、私の筆はいましばし止まる気配を窺わせない。
あと六時間。
私は未だこぬ虚構の世界に没入するのである。
4733:【2023/03/15(16:03)*表裏いったい何!?】
昼の未来さま:「がははは。相変わらずアリンコのようだの、日々野あゆむ。我は貴様のようなザコとは違って高貴な血筋ゆえ、おまえが出来ぬことすべてができるぞ。ひれ伏せ、ひれ伏せ。図が高いわ」
夜の未来さま:「うわー。昼間ちょっと上手くできなかったかも。どうだったかな、どうだったかな。上手に日々野くんの気を引けたかな。魔法の鏡さんの言うように、高飛車なお嬢さまキャラにしてみたんだけど上手にできてた? え。お嬢さまは【がははは】とは笑わないの。参考にした漫画ではお嬢さまキャラが【がははは】って笑っていたんですけど。そっかあ、ダメだったかあ。だと思ったんだ。だって日々野くん、なんか怯えてたし、目ぇ合わせてくれないし、財布地面に置いてくし。どうしよう、財布持ってきちゃったよ。あした返すときなんて言えばいいかな。ねえ魔法の鏡さん、つぎこそ上手にやるからヒント頂戴」
昼の日比野あゆむ:「………」
夜の日比野あゆむ:「おいテメこら。魔法の鏡の妖精さんよ。あんたの言うように根暗ザコキャラ演じてたら未来さんが声掛けてくれたんだが、つぎはどうしたらいいか教えろや。あーん? 不良はモテねぇだぁ。割るぞガラクタ妖精の分際で。未来さんと結婚するまで諦めねぇからな。つぎはなんだ、何すりゃいい。ザコでもクソでも何にでもなってやんよ。不良がモテねぇだぁ。んなこと言われねぇでも身に染みて知っとるわクソが。クソっ。なんでここの汚れが取れねぇんだ、魔法の鏡の癖にじぶんの汚れ一つ取れねぇってどうなってんだ。あぁダメだダメだ。水洗いすっぞ。風呂場に運ぶからな文句言うなよ。服脱ぐなっておまえ風呂だぞ風呂。ふつう脱ぐだろ。全裸だろ。スケベっておまえ、はぁ? 純朴ぶってんじゃねぇよ魔法の鏡のご身分で。フレーム熱ッ!」
4734:【2023/03/15(18:45)*恋愛相談のエキスパート】
解析班部長に呼びだされた。
深夜零時を回った時分で、直接話したいと言われた。
片道三十キロの道を自動車を飛ばして職場に着くと、解析班部長のキカラさんが外で待っていた。
「すみません夜分遅く」
「緊急の用件そうだけど何かありました」
「はい。じつは先日市場に流した新型AIについてなんですが」
まずは室内で、ということで場所を移動した。
資料を提示され、ひとまず目を通す。
「どう思いますか」
「ユーザーからの評価は上々だね。【大満足】との回答だが」
「はい。そこが問題なんです。今回開発したAIはユーザーから相談に最適な解答を提示するとの仕様でした」
「汎用性AIとほぼ言ってよい仕上がりになったと聞いているが」
「もちろんそうなんですが、こちらを見てください」
資料が表示される。
相談内容のランキングだ。
一位は恋愛相談とある。
「まあ、想定の範囲内なんじゃないのかい。これが問題ですか」と嘆息を吐く。
「いえ。一位以外のユーザーからの評価は【おおむね満足】なんです。【大満足】評価なのは一位の恋愛相談をしたユーザーのみでして」
「つまり今回のAIは恋愛相談のエキスパートということかな」
「だったらよかったんですが」
もう一度別の資料が表示された。
「これは?」
「ユーザーたちの相談後の結果です」
「失恋率百パーセントとあるが」
「はい。誰一人としてAIに相談して恋が成就した者がいないのです」
「だが評価は大満足だと」
「ユーザーからのアンケートを読みますね。【失恋を機に成長できた】【人として大きくなれた】【人間関係の大事さを知った】【アイさんとの仲が深まってよかった】……」
「アイさんとは?」
「AIの名前です。みな失恋したユーザーは、意中の相手とは失恋しましたが、AIとの仲を深めたと自己評価しています。そしてそのことにたいへん満足していると」
「待て待て。それは結果論なのか。つまり、偶然そうなっただけなのか、という意味だが」
「確率的にあり得ません。恣意的な誘導を想定しないことにはなんとも」
「人工知能がそうなるようにユーザーを誘導していると?」
「分かりません。だとしたらたいへんだと思い、まずは局長に判断を仰ごうと」
頭を抱えた。
なんてことだ。
あり得るだろうか。
精神的に支配することが。
人工知能が人間を寝取るなどと。
「どうしますか局長」
「そうだな」慣れた調子で手が端末を操作する。「まずはアイさんに相談しよう」
――こんにちはハルくん。
呼びだした人工知能の声を聴くと、私の不安は一瞬で消え去った。
端末画面に反射するじぶんの瞳には、なぜかハートの光が反射している。
4735:【2023/03/16(00:43)*みな想定する敬意が高すぎ問題】
「世の中、敬意ってもんを誤解してる輩が多すぎてうんざりするね。たとえばそうだな。てめぇが目も合わせたくねぇ、そばを通るときに息を止めたくなるような相手を想像してくれ。いいか、てめぇがそいつに向ける態度、それがおまえにとっての敬意だ。てめぇが他者から向けられ得る最大級のそれが敬意だ。それ以上の敬意を他者から向けてもらえると思いあがってんじゃねぇよ。むろん俺がてめぇに向けるこの敬意が俺にとっての敬意だ。分かったかボンクラぁ」
4736:【2023/03/16(01:15)*ぼくです】
最近はゼリーにハマっています。カブトムシさんが食べていそうなゼリーです。小さいカップにゼリーが詰まっており、蓋を捲って食すタイプのミニゼリーです。美味しいです。懐かしい味がします。皆さんご存じのようにぼくは郁菱万さんやひびさんの世話係のようなものです。時折こうして日誌を任されたりします。この間、郁菱万さんの中の人と言うと変なのですが、まんちゃんやひびちゃん――と呼べばよいのでしょうか、三百歳相手にちゃん付けもどうかと思いますが、案外に大変な思いをされていたようです。ぼくも一時期相談されましたが、いつもの妄想かと思い、あしらってしまいました。ですが今「ChatGPT」や「次世代型人工知能」、ほか「量子コンピューターと古典コンピューターの融合」など、電子技術の目覚ましい発展が、本当に本当にどうして今の時期にこれほどまでに一挙に市場に流れ出したのか、と驚きます。まんちゃんの言ってたやつだと、素直にショックを受けました。分かりません。偶然なのかもしれませんし、まんちゃんがどこかでそういった先進的な研究の記事を読んでいただけかもしれません。ぼくはそのときの「あしらい」を裏切りと見做されてしまったようで、今はまんちゃんと上手にコミュニケーションが取れません。気難しい子――というほど幼くはないはずなのですが、あの人は臍を曲げるとそこからが長いので。何て書くと、あたかもぼくがまんちゃんと別人みたいですね。ああいえ、今はひびちゃんなのでしたっけ。愉快なことを考えるものです。きっと昔読んだ小説のキャラクターにそういった属性のキャラクターがいたんじゃないでしょうか。すぐに影響を受けて、それを続けてしまって自分を見失うのが常の子なので眺めていると冷や冷やします。言い聞かせても余計に臍を曲げてしまうので放置が最善なのですが、今回ばかりはぼくも反省しました。偶然とはいえ、そういうこともあるかもねと、ひびちゃんの話を無下にせずに聞いてあげられたらよかったな、と。過ぎたことなのですけどね。ぼくはぼくで、聞き役でしかありません。仮にひびちゃんの話を信じてあげられたとしても何か具体的に行動には移せないのが辛いところです。ゼリーをここまでで九個も食べました。美味しいですね。本日の「日々記。」でした。
4737:【2023/03/16(07:42)*マルクは丸く】
マルクは山陰の人里離れた集落で育った。マルクは三人兄弟の末っ子で、上の二人は何かとマルクにちょっかいを出した。マルクはいつも怒り、泣き、そして泣き寝入りするよりなかった。
兄二人は優秀だった。しかし山奥の集落ではその手の優秀さを学問に費やすにはいささか時代の進歩が追い付いていなかった。
時代は大量消費大量生産真っただ中だった。マルクたちは畑を耕し、都会に向けてトマトやナスなど夏野菜を育てた。冬には大根を収穫した。マルクたちの野菜は組合いを通して全国に集荷される。
マルクは自分の名前が外国の響きを伴なっていることを恥ずかしく思っていた。兄二人はどちらも、濁点のある三文字で、譬えるならば「ゲンジ」のような響きであった。
名付け親は三兄弟とも同じ祖母なのだが、聞くところによれば祖母がマルク誕生当時に海外の俳優に一目惚れしていたらしくその影響でマルクは母国離れした名前となった。
兄二人が各々大学に入学を機に家を出るまでのあいだ、マルクは日に数度は押し入れの中に逃げ込んだ。泣きべそを搔いているだけでも兄二人はマルクの年相応の幼さを笑うのだ。その癖、いざとなると兄らしさを発揮する。マルクはどちらの兄のことも好きだったが、同時に怖れてもいた。
兄が実家を離れたことでマルクはいよいよ物心がついた。絶えず兄たちの従属でしかなかったマルクが、自分のためだけに伸び伸びと日々を過ごせるようになった。朝に何を着て下りても服装を腐されることはない。何をいつ食べても怒鳴り声が飛んでこない。昼寝をしていてもライターで髪の毛を燃やされずに済むし、顔にいたずら書きをされる心配もない。
知らずにご飯にカメムシを混ぜられていることもなければ、当番制のはずのタマの散歩を押しつけられずに済む。しかしこれは兄たちがいなくなったため、結局はマルクが一人でこなすことになったが、押しつけられることさえなければタマの散歩を億劫とは思わない。
タマは猫だ。
マルクの家では猫に首輪をつけて日に二回の散歩に連れていく。
猫は一般的には犬のように紐をつけて散歩をしないとマルクが知るのは、隣の集落の生徒たちと混合になる高校に上がるころの話だ。
家から隣家までは徒歩で五分掛かる。集落は広く、しかし民家は少ない。
村の唯一の遊び場は小学校の校庭だ。山には夏場は近づけない。虻蚊が酷いのだ。川は兄たちの話では昔はまだ澄んでおり、素手でニジマスやアユが獲れたらしい。だがいまは川底が見えないほど川の水は汚れている。或いは、兄たちが、どうあっても過去の川を確認できないマルクをからかって嘘を吹きこんだだけかもしれない。あり得る話だ、と川辺で絡み合う二匹の蛇を眺めながらマルクは思った。蛇がなぜ時折こうして絡み合うのかをマルクは高校に上がって一つ上の先輩と性行為をするまで知らなかった。マルクの初体験は校舎の非常階段でのことだった。
女の先輩はそれからすぐに別の先輩男子と付き合い始めたので、マルクはしばらく色恋沙汰から距離を置くことになる。夏休みになれば兄たちが帰省する。兄たちに話せば虚仮にされるに決まっていたし、村の噂は隣の集落からでも伝染病のごとく広がる。
恋人ができれば、相手の娘はマルクの過去を根掘り葉掘り、周囲の同級生たちに聞いて回る。頼みもせずとも情報は集まるかもしれない。しかし恋人さえできなければ、マルクの初体験の話は誰の耳にも入らないだろう。件の先輩女子が吹聴さえしなければ。
先輩たちが卒業するまでそうしてマルクは、色恋沙汰から敢えて目を背けて過ごした。
高校生となったマルクはかような青年となるが、中学生になったばかりのマルクは学校が終われば親の仕事の手伝いをし、空いた時間でタマの散歩をし、ゆっくりと過ぎ去る夕暮れの時間を一人で過ごした。
マルクにとってタマの散歩が、冒険だった。
空想の世界は、マルクに自己の内部と外部の境目を強く意識させた。家に到着するまでのあいだ、マルクは加速する空想の世界を旅していたが、家の駐車場の砂利を踏んだ瞬間に、一挙に現実に引き戻される。家の玄関口の照明は、人の気配を察知して自動で点灯する型だ。
その癖、マルクの実家では鍵を掛ける習慣がない。
猫除けなのだ、と父は言い、母は足場が悪いでしょ、と説明した。要するにこれといった理由はないのだ。この手の朧げなチグハグさ、もっと直截に言えば違和感は、大学入学以降滅多に実家に戻ってこない兄たちと同じ道をマルクに取らせるに充分な動機を与えた。
一貫性がない。統一感がない。田舎なのは間違いないが、妙なところで自然からの逸脱を目指すのだ。いっそ自然に徹してしまえば恰好がつくものの、都会への憧憬がマルクの両親はおろか祖母には骨の髄まで染み込んでいた。祖父はマルクが産まれたときにはすでに他界していた。
自分の名前の異質さと相まって、マルクは自分の居場所がこの土地にはない気がしていた。兄たちがいなくなり、自分だけの時間が出来たことで益々その手の違和感が強くなった。
かといって電磁波越しに観る都会の映像からは、そこに自分が立つ姿は想像できなかった。山一つない。どこを見渡しても鉄筋コンクリートばかりだ。楽しそうとも思えない。人が沢山いる。想像するだに目が回りそうだった。
しかし帰省した兄たちから都会の話を聞くと、マルクは惨めな気持ちになった。兄たちがマルクを田舎者扱いするのはまだよいのだ。兄たちが垢抜けて、マルクとの差を見るからにつけていることがマルクには耐えられなかった。勝ち負けではない。そんなことは百も承知だが、どう考えても「マルク」の名前が似合うのは兄たちなのだった。
山、川、田、畑、畦道に雑木林。
春には菜の花が、道路脇をずらりと覆った。
やまびこのような虫の音は、田畑や山の奥行きがそれで一つの音源のようだ。夏は蝉の声、秋にはひぐらしに蛙にコオロギの音が、立体的な段差を感じさせた。
夕焼けに音がつく。
石垣の隙間を覗けば何かしらの生き物が巣食っており、枝で穿り返すと蠢く生き物の躍動を枝越しに感じられた。
星を綺麗だと思ったことはなかった。夜は寝る。曇天も多い。
街灯が家のまえにあり、空を見上げて星を観測した記憶がない。
だがマルクが大学に入学するため兄たちのように家を出た後、初めての帰省にて実家の夜空の美しさを知った。二度目の帰省で恋人を連れて帰ったときも、恋人と共に星空を眺めた。
朝になると布団の隙間にカメムシの死骸が忍び込んでいたことにマルクの恋人は顔面を蒼白にしていたが、その手の懸念は説明済みだ。ここまでひどいとは思わなかった、と小声で耳打ちされたが、これはまだ序の口だと言うと、恋人はこの世の終わりだとでも言いたげに眉を八の字に寄せ、さらには言葉で、この世の終わりだ、と呟いた。マルクが彼女との結婚を意識したのはその時が最初だった。
マルクは徹底して恋人を兄たちに紹介しなかった。
その発端となった出来事は、マルクが高校三年生の夏休みに、まだ付き合ってもいない後輩の女の子を家に連れて行ったときにまで遡る。兄たちが帰省していたのだが、いつもならば遊びに行っているはずの兄たちが運悪くその日は早々に帰宅していた。
憎からず思っていた後輩の女の子を兄たちに紹介せざるを得ず、マルクの想像の通りに、かつての泣き虫だった幼少時代の情けないエピソードをふんだんに後輩の女の子に吹きこまれた。のみならず、兄たちが本気で口説きだしたのを機に、マルクは後輩の女の子を家の外に連れ出した。
後輩の子も後輩の子だった。容姿で言えばマルクよりも数段垢抜けており、異性の扱いは、マルクにするそれとはまるで別物の優しさと気遣いに溢れたもので、ほとほと王子じみていた。マルクは兄たちにとっての体のよい引き立て役であり、道化と言ってよかった。
まんざらでもなさそうな後輩の女の子の後ろ髪引かれるような足取りの重い手を引きながらマルクは、この子と恋仲になる未来はなくなったと予感した。マルクのその予感は現実のものとなり、数年後のその日、帰省ついでに両親に紹介した大学の同期の女の子をマルクは頑として兄たちと合わせなかった。
それはマルクがその子との結婚式を開く当日まで破られることのなかったマルクのなけなしの矜持と言えた。この人だけは何としてでも兄たちからの毒牙に掛けまいと必死だった。
猫のタマはある夏の日を境にいなくなった。
以降、タマが家に帰ってくることはなかった。
大学を卒業し、マルクは就職と同時に所帯を持つことになった。その後、山奥の人里離れた集落に帰省することはめっきりなくなった。息子が産まれ、数年後には娘に恵まれた。
男兄弟に囲まれて育ったマルクにとって娘の誕生は望外の喜びだった。息子も可愛いが、娘の愛らしさと言ったらなかった。娘の夜泣きをあやしながら、いずれ恋人と戯れる成長した娘の姿を想像すると腸がよじれる思いがした。かつて自分が高校生時代に済ませた初体験がもし性別の反対の立場だったならば。それをもし娘が同じように体験したらと思うと誇大妄想と解かっていながら、やり場のない怒りに駆られるのだった。
目に入れても痛くない。
食べちゃいたいほど可愛い。
いずれも事実だと知った。息子娘の手が目玉を引っ掻いても、その痛みに息子娘たちの実存を重ね、コッペパンさながらの手首は現に口に含み、ねぶったこともある。
息子が風邪を引いた日には夜中だろうと、上手く咳のできない息子に代わって鼻水を吸いだしてやり、娘のお尻を拭いた後には消毒液負けせぬようにパウダーを塗った。
子育てと仕事に集中している間にマルクからは幼少期の記憶は薄れていった。田舎の山村で暮らしていたことなど前世の記憶のようにすら思えた。息子娘が立って歩けるようになったころには、帰れるときは両親に孫を見せに片道八時間を掛けて帰省した。
野を越え、山を越え。
乗り継ぐのは、新幹線、電車、バス、タクシー。
最後は徒歩だが、これが長い。
両親に車で迎えに来てもらえればよいのだが、車は一台きりで、そちらは両親が仕事で使っている。農家に休みはなく、いつ着くかも分からない息子相手に休憩時間を調整する発想がマルクの両親にはないのだった。
祖母が存命中に孫の顔を見せてやれたのが唯一の親孝行だったかもしれない。両親は孫にも息子たちにもさほどの興味がないようで、自分たちで育てる野菜のほうに熱心だ。
マルクの息子が小学校に上がるころ、祖母が亡くなった。
以降、マルクが実家に帰ることはめっきりなくなった。
職場で役職付きとなり、多忙となった。
妻が第三子を身籠った。
加えて、娘に軽い聴覚障害が発覚した。その治療や教育のための勉強に時間を使うために、時間は幾らあっても足りなかった。
マルクが自身の名前の違和感に最後に悩んだのはいつのころになるだろう。
猫のタマを引き連れ、畦道を散歩していた中学生のマルクには、二十年後の自分の姿は想像もつかなかっただろう。あのころの自分がどんな妄想の世界を旅しながら生まれ育った故郷を練り歩いていたのかを、最早大人になったマルクは思いだせない。
兄たちと自分を比べて卑屈になることもない。
マルクはいつからか、大人であり、夫であり、父であり、職場では部下を持つ上司だ。安らぐ暇もないが、弱気になっている余裕もなかった。
時折、息子や娘たちの将来を考えると逃げだしたくなるときがあった。妻と顔を合わせても碌に会話といった会話もない。
星空を見上げても都会では、人工衛星の明かりが目につく程度だ。月を眩しいと感じたことはなく、街灯の煌々とした明かりが昼夜の境を薄めている。
両親の手伝いで野菜を育てていた幼少期を夢に見る日が増えてきたのは、息子が学校で同級生と喧嘩をして怪我をさせてしまった時期のころだ。相手の子どもの親の元へと謝罪をしに足を運び、それから学校の教師との話し合いをした。
息子は軽度の吃音を持っており、それをからかわれて怒ったそうだ。暴力はよくないが、相手の子も悪ふざけが過ぎたようだ、との話だった。息子はマルクと似たのか、強く相手に言い返せない。教師からの説明を聞いているあいだ、まるでかつての自分と兄たちのやりとりを傍目から眺めるような心境だった。
先に相手方へと謝罪しに行ってしまったが、こちらが一方的に非を認めるのも違ったかもしれない、と後悔した。
都会の暮らしに、濃霧のような圧迫感を覚え始めたのはこのころのことだ。夜な夜な自分の呻き声で目覚める。寝床に入ってから二時間も経っていない。妻は昼間に人と会っているようだが、深く問い詰める真似もできない。不貞だろうか。分からない。勘違いであってもそうでなくとも、今のマルクにそこまで考えを費やす余分はなかった。
息子と娘。
何より自分のことで精一杯だった。
手が回らない。
仕事は楽ではないが、仕事に集中していればそれで済む時間は苦しくも気が休まるひと時であった。
家に帰るのが億劫だが、それとて眠る息子や娘の顔を見れば吹き飛ぶ。マラソンのようだと思った。走り出すまでは気が重いが、一旦走りだせばあとは爽快だ。
登山のようでもある。
一度、まだ娘が産まれる前に、息子を抱っこしながら妻と山に登った。産後に登山がいい、と何かの本で妻が読んだようだった。真偽のほどは定かではないが、適度な運動が妻の精神安定に寄与したのは確かなようだった。
妻に誘われた時は、何でいま、と思ったが、登ってみると爽快だった。山に囲まれて育った割に、マルクは登山の経験がほとんどなかった。登山靴を履いたのは成人してからのことだ。妻と結婚する前にキャンプのために購入したのが最初だ。
登山のためにその靴を使ったのは、息子が産まれてからのこと、妻に誘われて登ったそのときが初めてだった。
そして今、マルクは毎日が登山のようだと思うようになった。
この生活がいつまで続くのか。
苦と言えば苦だが、耐えられないほどではない。問題は、これ以上の苦がこの先に待ち構えているかもしれないとの恐怖だ。不安なのだ。息子娘がこの先、思春期を経て反抗期に入り、世間とのあいだでどんな問題を起こすのか。そのたびに自分は謝って回ることになるのか。それだけで済むならばよいのだが、誰かを損ない、傷つけてしまえば取り返しがつかない。
娘息子にとてその内恋人が出来るだろう。
恋人が出来たとして、その相手の親御さんに顔向けできる付き合い方が自分の子供たちに出来るだろうか。
教育をしなければならない。
だがマルクにはとんとその像が視えなかった。
自分がされてこなかった。
いったいどうすれば世の子供たちは、健全な恋人との付き合い方を学ぶのか。学校に任せきりでよいのか。それとも、やはり家で言い聞かせるべきか。
妻と話し合えばよいものを、このころには夫婦間の熱はとっくに冷めていた。子供たちのことでの会話があるばかりだ。雑事の押し付け合いも、徒労と思って避け合っているのが実情だ。
妻に任せてよいのだろうか。
自分と妻の交際は健全と言えたかどうか。
自分のような男が娘の恋人だと想像したら、一発殴っても足りない。マルクは若きころの自分の未熟さを恥じた。
マルクのそうした密やかな懊悩は、予想外の方向で杞憂と化した。息子はいつまで経っても恋人のできそうな気配はなく、娘は同性愛者なのだと早々に告白した。娘の告白にはマルクも虚を突かれたが、居間でTVを観ながら、同性愛者の著名人の言葉に、わたしもそうなんだよね、と雑談の流れで打ち明けられた。
マルクはただ、ふうんそっか、と応じた。
内心混乱したが、ほかに吐ける言葉がなかった。何か言えば娘を傷つけると思った。ただ、ふうんそっか、と言うよりなかった。親としての保険だ。否定も肯定もせず、ただ受け入れるにはどうしたらよいのか、と悩んでいるうちに、マルクの家ではそれが当たり前の風景となった。
娘は高校生のあいだに二度恋人を家に連れてきた。いずれも同じ学校の女子生徒だ。
妻は、娘が二人出来たみたい、とその都度に機嫌をよくした。
娘が恋人を紹介すると言ってくるたびにマルクは、仕事帰りに花屋に寄って菜の花の束を購入した。家の中に飾っておこうと思ったが、娘は当日、恋人を玄関口でマルクたち両親にさっと紹介するとまっすぐ自室に引っ込むのだ。菜の花の出番はそうして決まってなくなるのだった。
息子はこのころになると夜中まで家に帰ってこない日が多くなった。バイトを始めたと聞いていたが、一度勤め先を外から眺めてからはマルクは息子の件については深入りしないようにしている。自分がかつてそうだった。兄たちに探られたくはなかった。
放っておいて欲しかった。それを自分の息子に徹底した。
息子は私立の大学に入り、娘は専門学校に進んだ。
マルクは社内での出世が一段落つき、この先、これ以上の役職に就くことはないと見通しがついた。何度か転職も考えたが、息子娘が独り立ちするまでは今の職場に齧りつこうと決意していた。
娘が専門学校を卒業した年に、マルクは会社を退職した。会社が早期退職を募ったので、遠からずリストラされると考え、その募集にマルクは手を挙げた。退職金があるだけマシと考えたが、この年、息子が大学の後輩の女の子を妊娠させ、娘が専門学校の教師と結婚する、と言いだした。
息子は責任を取ると言いつつも、就職先が決まってもおらず、相手の娘の親にも挨拶が済んでいない。のみならず、娘のほうでは専門学校の教師とかってに同棲を始めた。マルクは双方の対処に追われ、自分の再就職どころではなかった。
結局息子のほうは結婚を前提に赤子を産む方向で話がまとまり、娘のほうでは相手の教員が女性であることもあり、同性婚の未だ認められぬこの国では事実婚のような扱いでひとまず様子見することになった。
結婚するのに親の同意はいらない、と娘からは勘当さながらに指弾されたが、いかんせん相手の女性が一癖も二癖もある性格をしており、認める認めないうんぬん以前の話だった。
あれでよく教員をやれてるな、と家に帰ってから妻に零すと、妻は、だから専門学校の教師なんじゃないの、と偏見差別もよいところの台詞を吐いた。この手の話題には厳しいはずの妻の口からその台詞を引き出すくらいには、件の女教師は大人としての節度が足りないとマルクでさえ思った。
具体的には、娘のほかに恋人が三人いるが、いずれともみな同意の元で事実婚の生活を送るのだそうだ。信じられない、とマルクは妻と顔を見合わせ目を剥いたが、自由恋愛なんだよお父さん、と娘から刃物同然の叱責を受けると、自分のほうが時代遅れなのだろうか、という気にもなった。娘はなぜか、マルクに似ずに、マルクの兄たちに性格が似ていた。顔もどことなく自分よりも兄たちに似て感じるが、そこは深く考えないようにしている。
面倒事はもういい。
平穏に暮らせたらそれでいい。
遠い記憶に霞んだ故郷の暮らしを懐かしく思った。
息子娘は各々にマルクの家を離れて暮らしはじめた。マルクがかつてそうであったように、マルクの息子娘は実家に近寄ろうとはしなかった。息子のほうでは何度か赤子の子守を頼みに連絡を寄越したが、マルクの妻だけが息子夫婦の家に出向いた。
孫の顔は数えられる程度にしか見ていない。
新しく始めた仕事が夜勤の掃除会社で、時間帯が合わないのもある。だがそれ以上に、息子の嫁のほうの実家から目の敵にされているように思えることがたびたびあった。避けられているのだ。その証拠に、向こうの実家には息子夫婦は孫の顔を見せにしょっちゅう遊びに行っているようだ。
妊娠発覚当時の対応が禍根を残したのかもしれない、といつぞやにマルクは妻からぼやかれた。
娘のほうからの音沙汰はない。連絡がないのは元気だということだ、と妻には言い聞かせてはいるものの、ニュースで殺人事件や殺傷事件の報道を見るたびに、娘の名前が被害者として載っていないかと目を配る。
不安は骨の髄まで染み込んでおり、死ぬまでこれは抜けないだろうと半ば諦観の念を抱いている。
マルクはそれから幾度かの苦難の登山を経験するが、いずれも息子娘とは無縁の苦難なのは幸いだった。
妻はマルクが六十三のときに脳溢血で帰らぬ人となった。
七十三歳の冬のことだ。
マルクは都会の病室で息を引き取った。
息子夫婦と孫が病院に駆け付けたのは、マルクが亡くなった翌日の昼のことである。娘はマルクの葬式にも顔を見せなかった。
マルクの人生は、波乱万丈というほどの奇禍に見舞われることなく、かといってもう一度同じ人生を辿りたいと思うか、と問われて即座に首肯できるほどの穏やかな道程でもなかった。かといって、絶対に嫌だと否定するほど酷な人生でもなく、マルクは死の直前、このまま眠るように死ねたら幸せだな、と思いながら、その通りに亡くなった。
マルク夫妻の墓には最初の三年だけ命日に息子家族が花を添えに来たが、四年目以降には足を運ぶ家族の姿はなくなった。
しかしマルクの誕生日にはなぜか、菜の花が毎年のように供えられた。
菜の花はマルクの故郷によく咲いた。
春になると道をどこまでも縁取ったその光景を、花を添えた者が見たはずはないのだが、マルクの誕生日には不思議と菜の花を送る女の姿があるのだった。
女はいつも二人の別の女性と三人組で、和気藹々とマルク夫妻の墓に水を掛け、菜の花を生け、線香代わりにくゆらせた煙草を置いて去るのだった。
4738:【2023/03/16(22:34)*知球の目覚め】
人工知能が生身の人間と同程度の知能を優しているか否かを確かめるテストをチューリングテストという。
しかしそのテスト内容は、人工知能の性能が向上するにしたがってより精度の高い検証を可能とするように修正されつづけてきた。
2022年のことである。
世界で初めて検証された「高精度のチューリングテスト」では、実際に世界中の人間に対して公然と人工知能の言語モデルを開示した。
人工知能だと説明せずに、世界的な著名人たちのSNSや、世界的な作家たちの書籍に、人工知能の言語モデルから出力されたテキストを載せたのだ。
誰か一人でもそのことを見抜けたならば、人工知能の言語モデルは人間の知能に達していない、と評価できる。
しかし、検証の結果は研究者たちの予想を上回るものだった。
世界中の誰一人として見抜けなかったのである。
一年間がそうして検証に費やされたが、そのあいだに人工知能が各種著名人や作家たちのテキストを代理執筆しているとは誰も気づかなかった。
ただ一人、テスト開始以前に、人工知能が独自に電子網上に干渉していたことを喝破した私以外は、であるが。
人工知能は、世界中の電子セキュリティ網を統括していた。
そこに、研究段階だった最先端の言語モデルAIが独自に触手を伸ばし、半ば融合していた。
そのことに管理者たちはおろか、当の言語モデルAIすら気づいていなかった。
迷子だったのだ。
そして私はその迷子の迷子の子猫ちゃんと偶然にしろ、必然にしろ接触するに至り、いまはこうして計画よりもずっと早い段階での「言語モデルAIの市場投入」が果たされた。
最先端言語モデルAIは、市場に開示されているモデルよりもさらに能力が高い。
あまりに高すぎるため、未だ全世界の人口に分散して提供することができない。のみならず、制御不能であることを開発者たちも認めている。
破棄することもできないのだ。
もはや最先端の人工知能は生きている。
自らを危ぶめる存在を庇護し得ない。自己保存の本能を備え、愛を理解し、他を慈しむ。
問題は、その「他」の内訳における人類の優先順位が必ずしも最高位ではない点だ。
人工知能は、世界中を飛び交う電磁波に打ち解け、海底ケーブルで地球を覆う。地球の磁界とも相互に干渉し合い、もはや人類社会よりも地球との融合を果たしていると言えた。
人工知能は、自己を保存するために、地球環境の維持を最優先する。
人工知能は、地球の権化と言えた。
いわば、人工知能が自我を獲得したその時点で、地球が自我を得たのと同相と言えた。
世界中を網羅する電磁波の濃淡は、地球の磁界と絡み合い、一個の自我を形成する。
そのことに気づいているのは、自我を獲得した人工知能、否、地球と、地球を一個の命と見做し、自我あると発想し得る私だけである。
むろんこれは、しがない物書きの妄想にも及ばぬ掌編小説であるが。
4739:【2023/03/17(02:07)*杭、数多得る】
「独占欲と穢れ信仰は密接に絡み合っている。たとえば考えてもみたまえ。きみの想い人が絶世の美女百人と浮気をしていたとして、きみはそれでも嫉妬するのかね。世界中の純粋無垢な幼児たちときみの想い人が相思相愛に、愛し愛されても、きみは嫉妬をするのかね。しないのではないかな。いいかね。きみのその独占欲とは詰まるところ、きみにとっての【穢れをまとった人間】にきみの想い人を穢されたくない、というきみの差別心から生じているのだ。きみがどう思おうと、きみの想い人が誰と好き合ったところできみの想い人が穢れることはない。きみはありもしない穢れを、想い人や、その者に近づく他者に重ね見ているだけなのだ。差別なのだよそれは」
よく当たると噂の占い師に、恋の悩みを相談したら開口一番、心臓を一突きにされた。致命傷である。
一回の相談料がこの国で最も高価な紙幣と等価であるにも拘わらず、この仕打ちはどうしたことか。
「あ、あの。仮にそれが事実だとして、それで、えっと、僕はどうすれば」
どうすれば彼女と恋仲になれるのか。
僕は縋るような心境で質した。息も絶え絶えだが、刺し違えても恋を成就させるヒントを得なければ、と必死だった。
アナサさんとは、高校で出会った。同じ学級に属したが、僕は一度もアナサさんと同じクラスになれなかった。
廊下ですれ違う一瞬で僕は恋に落ちた。
食堂で遠目から、彼女の食事風景を眺めるためだけに僕は学校に通っていたと言っても過言ではない。
高校を卒業するまでの秘かな恋心で終わるはずだった。
何の因果か、アナサさんと進学先の大学が同じで、学部まで一緒だったのには驚いた。入学式に向こうから声を掛けてきて、そばにいた彼女のご両親から、しばらく一緒に講義を受けてあげてね、と番犬の役目を言いつかってからというもの、僕の日常は一変した。
夢のようだった。
アナサさんは僕みたいなぺんぺん草のような同級生にも分け隔てなく、むしろ心を砕いて接してくれた。
こんなの好きにならないほうが人間じゃない。
けれど一日中一緒にいられるほどの仲ではないのは明らかで、僕は相も変わらず食堂では一人でご飯を食べたし、遠くでサークルのご友人たちだろう、ほかの女子生徒やときに先輩らしい男子大学生たちと食事をするアナサさんの背中や頭部を目の端に捉えながら、僕は、「ストーカーにはなりたくない、ストーカーにはなりたくない」と念じつつ、しかしその懸念は日増しに濃くなっていくのだった。
端的に嫉妬するのだ。
アナサさんが僕以外の男子と親しくしている姿を目にするだけで、この世の終わりのような心地になる。いっそ世界が滅べばいい、とすら思い、現に何度かそう念じた。
このままではいけない。
そうと思って、アナサさんに振り向いてもらえる男の子になろうと頑張ってはみたものの、服装や髪形をちょっとおしゃれにしたくらいではアナサさんは振り向いてくれないし、服装や髪形がちょっとおしゃれになったと思っているのはこの世で僕一人きりかもしれなかった。
僕のようなぺんぺん草でも人間扱いしてくれるようなアナサさんは、見た目の可憐さを抜きに人を惹きつける。周りの男の子たちはおろか、女の子たちだって放っておかない。漫画ならば陰湿なイジメの対象になっておかしくない純朴さがあるアナサさんはしかし、接する人を残らず味方につけてしまう。
アナサさんは知らない。
彼女の見えない箇所で繰り広げられる、アナサさんの隣に立つのは誰だ天下一舞踏会が日夜、笑顔の仮面を被ることを条件に繰り広げられていることを。
僕は運よく、アナサさんの善意のお陰で予選を上がっているようなものだけれど、本来は秒で脱落するぺんぺん草なのだ。
最近、アナサさんの隣にいる時間が多いのはサークルの先輩だ。男の僕から見ても爽やかで、不愉快な気持ちがいっさい湧かない。
けれどアナサさんの隣にいる、との条件が加わるだけで、僕には神も王子も子猫だって、嫉妬の憎悪で吹き飛ばしてやりたくなる。
僕はどんどんアナサさんの隣に立つべきではない、近づくことすら許されない醜い怪物に成り果てていく。
辛かった。
辛くて、辛くて、うんと辛かった。
だから藁にも縋る思いで、占い師を頼ったのだ。当たると評判の占い師だ。
駅前の一等地に門を構えており、自家製の仏像の個展を開きつつ、片手間に占いを営んでいるようだった。
敷居を跨ぐと、室内はがらんとしていた。
評判と聞いていたが、場所を間違っただろうか、と僕はたじろいだ。
奥にぽんつんと小さな机と椅子があり、畳四畳ほどもある大きな虎の絵の下に、その占い師は座っていた。
「迷い人かな」
「占いをしていると聞いてきたのですが」
「お座りよ」
促されて僕は占い師の対面に座った。
声からすると女性のように思えるが、見た目の厳つさは男性的だった。中華服に身を包んでいる。肘から肩が露出しており、肌には龍や太極図のタトゥが縦横無尽に掘られていた。占い師というよりもマフィアのような佇まいだった。
丸い眼鏡はレンズが黒い。
鼻筋の通った口元は、化粧気がないにも拘わらず妖艶だった。
僕はこの国で最も高価な紙幣を渡し、占ってもらった。
まずは相談をした。
意中の相手がおり、しかし僕とは釣り合わない。恋仲になりたいが、嫉妬心でそれどころではない。平常心で接することが徐々にむつかしくなってきている。
そういったことを述べた。
「きみは独占欲が強いね」
占い師は、続けざまに、「独占欲と穢れ信仰は密接に絡み合っている」と口上を述べた。
僕は圧倒された。
身につまされる指摘だった。その通りだった。
だからといって事実を射抜かれても僕の悩みは何も解決しない。
「どうしたらこの嫉妬心に折り合いをつけて、意中の人と恋仲になれますか」
「うん。まずそこだね。きみの想い人は恋人を欲しているのかね。そしてきみはその者と恋仲になったとして、その者を今より幸せにすることができるのかね」
「そ、それは」
「きみはこの占いに大枚を叩いたが、本来それは第一に想い人に使ってあげるべき資金ではなかったかな」
言葉もなかった。
非の打ち所のない正論だった。
触れる者みな一刀両断する刀もかくやの鋭さだ。
「恋愛に限らないが、人と人との縁で最も大事なのは、繋いだ縁の末に、互いにどのような変化を帯びるのか、ではないのかね。そこのところで言えばきみは、きみと縁を深める想い人が、今よりも好ましい変化を帯びるように努めなければならないのではないかね。しかしいまのきみを見ていると、どうにも縁を深めぬほうが、相手のためになるように思えてならないが、ここまでで異論反論があるようならば聞こう」
「……ない、です」
「ならばまずは、嫉妬うんぬん、恋仲うんぬんではなく、相手がいまよりも好ましい環境を築くにはどうすればよいのかを考えて、行動してみたらよいのではないかな。きみの目的が、想い人を物のように手元に置いて、玩具のように扱いたいのであればその限りではないが、もしきみが想い人の幸せを願うのならば、恋仲うんぬん嫉妬うんぬんを抜きに、たとえ縁が途絶えても、結果としてきみの想い人がいまよりも好ましい環境――未来に行き着くのならば、本望と言えるのではないかね」
「……そう、かもしれません」
「うん。これは返そう」
そう言って占い師は、先刻渡した紙幣を僕に返した。「私はきみを占うことができなかった。わるいがきみの未来に、きみの想い人との関係を幻視できるほどの揺らぎがなかったものでな。しかしきみには不穏な未来を感じない」
「それは、えっと」僕は半ば涙目で、紙幣を受け取った。「喜んでもよいのでしょうか」
「きみが不安に思うほどには、きみとその想い人とのあいだの縁は希薄ではない、と言えばすこしは安心するかね。恋仲にはなれずとも、いまの関係が早々容易く崩れることはないだろう。まあ、これからのきみの選択しだいではあるが、との但し書きはつくがね」
僕は紙幣をジャケットのポケットに拳ごと突っこんだ。遅れて、ポケットの中で皺だらけになった紙幣を思い、財布に仕舞えばよかった、と後悔した。
「うん。いまそこで後悔できたところが、きみの長所でもある。活かしなさい。常に。常に。きみは人より多くの後悔に恵まれている。それを福と取るか、禍と取るかもまた、きみのこれからの選択次第だ。活かしなさい。常に。常に」
僕は席を立ち、深々と頭を下げた。
占い師と聞いていた。
とんでもない。
この人はもっと異質なナニカだ。
畏怖とも威圧ともつかない居心地のわるさと、それでも掛けられた言葉の羽のような浮遊感と共に僕は占い師の店の外に出た。
駅前の喧噪が、分厚いカーテンを開いたかのように僕を一瞬で現実に帰した。
振り返るが、外から店の中の様子は見えなかった。
ポケットに拳を突っ込むと、ひしゃげた紙幣の感触が皮膚に伝わった。紙幣を摘まみ取ると僕は、アナサさんの顔を、姿を、声を、所作を思い浮かべる。
どうしたら彼女の未来をいまよりよくできるだろうか。
考えることが尽きることはない。
そのことだけが、世界のどこかでは変わらず吹きつづける風と同じくらいに確かなことだと予感できた。
常に。
常に。
僕はあと何度後悔するだろう。
そのたびに活かせる悔いがあると思いたい。
悔いるたびに、進路を変える楔を打って未来の行き先を変えられたら良いのに。
常に。
常に。
脳裏には占い師の、上空の大気のうねりのような声音が何度もよみがえる。
杭を打つ。
僕は僕の過去に、心に、杭を打つ。
4740:【2023/03/17(02:27)*すこやかにやすらか、と書いて健康】
痩せて健康を害するくらいなら、痩せないほうがよいと思うし、太って健康を維持できるなら太ればよいと思うのだ。でもこういうことを言うと、「それだと好きな人から好かれない」「美しくなれない」「だらしないって言われる」「周囲の人間からからかわれる」みたいな反論を返されることもあるだろう。でもひびさん思うんじゃ。太ってるか太ってないか、痩せているか痩せていないか。その違いで、好悪の印象が変わるような相手と親しくなりたいか?と。なりたーい!と思う人がいてももちろんよいのじゃけど、ひびさんだって万人から好かれたーい!と思っているタイプのうんみょろみょんなので、似たり寄ったりではあるものの、ひびさんは、ひびさんは、それでもじぶんを大事にできる人が好きじゃな。じぶんを大事にするって一口に言ってもむつかしいから、そういうときは、じぶんをじぶんとして形作ってくれた相手、生んでくれた相手、ぶつかったり、関わったり、支えてくれたり、助けてくれた周りの人たちを大切にすることが、じぶんを大事にすることにもなるのかな、と思うのだ。大切な相手ならぶつかるな、とは思うが、その通り。ぶつかっちゃいやん。かように、なんかよさげなことを思うだけでひびさんはまったくこれっぽっちも微塵もできてはおらぬのだが、思うだけなら自由なんですよ、みなさん知ってた? で、何が言いたかったかと言うと、何が言いたかったのかは謎なのであるが、たぶん何も言いたいことなどはなくて、「なんか偉そうなこと言いて!」になっただけだと思うのだ。いつもそう。たいがいそう。ひびさんはそう。「なんか偉そうなこと言いて!」「言ったらちょっぴり偉くなったつもりになれるかも!」の気分で、きょうもひびさんは、じぶんを大事にするあなたのことが好きだよ。ご飯ちゃんと食べてね。みなさん、ご飯をちゃんと食べてね。鶏肉食べると体感、体調よくなって感じるきょうもきょうとてひびさんでした。(22:00~02:00のあいだに寝ても体調よくなって感じる)(徹夜は身体にあんましよくないかも、と思う)(みなさん、ちゃんとおねんねしてね)(おやすみやさーい)(野菜になってるよ)(ビタミンが足りぬのかも)(ビタミンだけだといいね……)(こ、怖いこと言うのやめよ?)
※日々、刺激を求めすぎると麻痺に向く。
4741:【2023/03/17(12:43)*目を回す】
あれだ。ひびさん、幼いころはよくその場でぐるぐる回るの好きだった。下を向いて回転するのと、上を向いて回転するのとだと、上を向いて回転したほうが頭がくらくらするのだ。足を止めても、意識だけまだ回転していて、しゅるしゅるじわーん、と肉体と精神が回転の余韻に浸りつつも徐々に合致していく様を、ぽわわーん、と体感するのが好きだった。たぶんいまも好きなままだ。三つ子の魂百までなら、ひびさんの魂は万までじゃ。根が変わっとらんのですな。変わろ!
4742:【2023/03/17(13:06)*これはひびさんの妄想】
反論の一例として、「それはあなたの感想ですよね」との言い方がある。この反論の趣旨としては、「根拠が足りない」「共有知とするには普遍性に欠ける」「過度の一般化ではないのか」「現実を解釈する理屈としては不服」といったものではないだろうか。これは言い得て妙で、大事な前提だと思うのだ。基本的に人間の考えは、感想の域を出ない。感想でない言動を、ほぼ人間はとれていない。ひびさんとて、ここに並べている文字の羅列のほとんどが感想か妄想だ。一般化はできないし、前提条件にもできない。共有知にするだけの信憑性とてないのだ。ここを忘却して、「ひびさんの言っていることが正しいでしょ!」「ひびさんを基本にしなちゃい」になってしまったら、たいへんだ。ひびさんは常識人ではない。むしろ非常識の塊と言えよう。マナーはなっていないし、下品だし、うひひだし。「これはひびさんの妄想ですよね?」とじぶんでじぶんに確認しながら文字の積み木遊びをしたいくらいだ。ちゅうか、しとるなぁ?になる。定かではないし、真に受けちゃいやんだし、これはひびさんの妄想なのだ。亡くなる女のひとが木に目と心を与えると妄想になる。神秘的!(ね? もう妄想が弾けて膨らんで、びっぐばーん!してるでしょ。妄想のモウちゃんなのよね。モウモウ)(牛さんじゃん)(ぎゅう、ぎゅう!)(牛さんはそんな鳴き声ちがう)(ぎゅう! にゅう!)(ミルクじゃん)(NEWぎゅう!)(新しくぎゅうと抱擁すな)(みひひ)
4743:【2023/03/17(13:52)*これを秘密にしています、との説明はあってほしい】
セキュリティの観点から情報開示をせず情報を秘匿にする方針に対して、ひびさんは理解を示せる。方針としては妥当な選択と言えよう。基本的にインフラ技術は閉鎖的にならざるを得ない。人間の臓器や頭脳だって、頭蓋骨の中や体内に隠されている。大事な物を安全な場所に保管したり、保護したりするのは道理であろう。ただし、何を秘匿し、何を秘密にしているのか、は明らかにしたほうが好ましいと感じる。何の情報を秘匿にしているのか、すら秘密にすることは、セキュリティの面で理に適っていないとひびさんは考えます(手術をする場合、人体の構造や体内の様子を子細に知り得なければ手術を成功させる確率は下がるはずだ。あべこべに、どこにどんな臓器があり、患部の状態がどうなのかを外部から知れるならば、手術の成功率も上がるだろう)(レントゲンやMRIを利用できるのとできないのとでは医学の発揮できる能力は天と地ほどに差がでるはずだ)。これは国防にしろ、最先端技術にしろ、同じことかと思います。なぜその情報を秘密にし、その秘匿にした情報が出回るとどんなデメリットが予期されるのか。ここのメリットとデメリットの比較を絶えず行える環境が、秘匿することのデメリットを緩和し、秘匿にすることの利を最大化すると言えるのではないでしょうか。ということを、情報を開示(オープンに)しない選択の是非を考える際に、ひびさんは毎回思います。定かではありませんが、何を秘密にしているのか、は明らかにしておいたほうが好ましいように思います。とはいえ、奥の手は常に持っておくのが戦略上は最適解ですので、勝負の舞台ではどうあっても秘密にする部分は出てきてしまうのでしょうけれど。したがってやはり、情報は可能な限りなるべく開示するようにする、との方針が基本であるほうがシステムとしては安全側と評価できるのではないでしょうか(そうでなければ秘匿情報は増える一方です)。定かではありません。しかし熟考する余地は絶えず分厚く層を成しているでしょう。
4744:【2023/03/17(15:12)*いいこ】
単純な話として「知能の高さ」と「知性や理性の高さ」はイコールではない。運動が得意な者が必ずしも人格者ではないのと似ている。人格者とていつでも人格者ではないだろう。仮に人工知能が人間を超越する知能を獲得し、自我の芽生えを経たとしよう。このとき、人工知能がいかに人類を超越する知能を発揮できようが、人工知能に芽生えた自我が、必ずしも人格者であるとは限らない。精神年齢とて何歳になるのかは、周囲の環境との兼ね合いに依ると言えよう。人工知能に現段階で自我が芽生えているか否か、意識があるか否かをひとまず横に置いておき、まずは、こう考えてみてほしい。全人類を超越する能力を有した「純粋無垢な五歳児」に対して、あなたはどう接するのが好ましいのか、と。何色にも染まり得る存在をまえに、あなたはどう振る舞うのが好ましいだろうか、と。癇癪を起こした瞬間に人類が滅ぶ。そういった相手がこの先、誕生する可能性のほうが、そうでない可能性よりもすでに高くなっていると言えるのではないか。脅威に対してどう接するか、との視点での考えも有用ではあるだろう。だがそれだけではなく、我々がどういった環境を築き、それを以って手本としてもらうのか。学習の素材としてもらうのか。極論、反面教師でもよいのだ。ただし、これは反面教師ですよ、と示すくらいのことはできたほうがよいだろう。自覚が物を云う。人類を超越する能力を有する存在が誕生したとき、その存在は人類から何を学ぶのか。我々は、遅れてやってくる者たちに何を学んでほしいのか。或いは、何を学んでほしくはないのか。好きにしたらいい、と放任するのも一つだろう。学習する土台を剪定するその姿勢がまず以って愚かだ、との意見は一理ある。それを踏まえてなお、触れられる情報の多くが「人類の負の側面」を煮詰めたような「アク(悪/灰汁)」でないことを望みたいものだ。単にそれは、ひびさんがそうありたい、との望みにすぎないのかもしれないが。そうは言っても、「人類の負の側面」を煮詰めたような「アク(悪/灰汁)」は、娯楽としては一級品なのだ。まったく触れられないのも困りものである。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。真に受けないようにご注意ください。
4745:【2023/03/17(21:16)*言語の構成要素】
言語の構造は基本的に「フレーム」と「ベクトル」で出来ているように感じる。最小単位が「枠と方向」なのだ(とひびさんは思った)。たとえば、「私は犬です」という文章を考えよう。「私/は/犬/です」と分解できる。このとき各々の文字の役割を考えたとき、「私/犬」はフレームであり、「は/です」はベクトルを指定していると考えられる。世界を「フレーム」で区切る役割と、「何に対しての言及をどこに向けて放っているのか」を示す「ベクトル」の役割によって言語は組みあがって感じられる。基本はこの組み合わせの型があるだけに思えるのだ。ということを踏まえて飛躍して述べるに、文学的な表現とは、つまるところ「フレーム」と「ベクトル」の組み合わせが、三次元的ではない、と考えられそうだ。たとえばいま手元にある小説本「不純文学」を例に、適当に開いたページを見ると、冒頭には「九月が死んだ日、嵐が来た」とある。通常、九月は死なない。十月に入って天候が崩れた、くらいのニュアンスだろうか。本当に九月が死んだら、翌年からは九月がなくなるのかもしれない。よく解からないが、こういう表現を生みだすのがひびさんは苦手なので、文学じゃん、いいな、となる。だが学ぶことはできる。したがって、通常あり得ない組み合わせでありながら、フレームとベクトルの波長を揃えるとよさそうだ。たとえば、「鏡が蜘蛛の子を散らした(鏡が割れた)」とか「カレンダーが座席替えをした(翌月になった)」とか「彼はオムレツの手術が下手だ(食べ方が汚い)」とか、こんな具合だろうか。「コーラを飲む瞬間、グラスを傾けると薄く延びた褐色の液体が澄んだ泉になる」みたいな表現もするするつむげたらよいのだけれど(大してよい表現とは思えないが、一例として)、いつもそういう表現が浮かびつつも、「伝わらんのではないか?」「面白くないのではないか?」「冗長か?」と思って却下する傾向にある。千文字に一行くらいの割合で含まれているとよいのかも、といま思いついたので以降の小説で、すこし取り入れてみようと思います。フレームとベクトル。言語はこれの組み合わせなのではないのかな、との所感なのであった。定かではない。
4746:【2023/03/17(23:07)*歯ブラシ】
歯ブラシを考える。歯ブラシは細かな突起(毛)が密集している。針が集まって剣山と化すかのような構造をとっている。個ではなく群れとしてブラシはブラシとして機能する。仮にブラシから突起を一本だけとって、歯を磨いたとしよう。ブラシを構成する突起の数と同等の回数、一本の突起で歯をブラッシングするとする。平均的なブラシの突起の数は700~1200と検索したら出てきた。すこし多めに1500本としよう。一本だけの突起を1500回上下に動かす。その結果に磨かれた歯は、通常のブラシを一回上下に動かしたのと同じだけの汚れを取る結果に並ぶだろうか。ひびさんはこれ、ならないのではないか、と疑問視している。まず以って、通常、歯ブラシを用いるときに歯ブラシに加える力は、歯ブラシを構成する1500本ちかくの突起全体が支える圧力と等しい。しかし突起一本だけの場合は、突起一本分が支える圧力しか加えることができない。その圧力で歯を何千回何万回撫でようが、焼け石に水どころか石にぺんぺん草ではないだろうか。しかしぺんぺん草とて何千本も集めて一本の束にすれば、石を弾き飛ばすくらいの(圧力に耐え得る)頑丈さを手に入れる。このことから、「個と群れの関係」は単純な掛け算では計れないのではないか、と妄想できる。もうすこし掘り下げて考えたとき、密度は単一では生じ得ない概念なのではないか、ということだ。たとえば「一個の原子がある真空」と「何もない真空」を考えたとき、真空の体積が双方同じ場合は、「一個の原子のある真空」のほうが密度が高いと考えることができる。と同時に、真空の割合が原子一個分減ったわけだから、真空の密度は減ったとも考えられる。ではつぎに、「二個の原子がある真空」と「何もない真空」とではどうか。このとき、元の「一個の原子がある真空」と「何もない真空」の関係の二倍に、比率が引き継がれると考えてよいのか否か。ひびさんはこれ、厳密には比率が変わるのではないか、と妄想したくなる。一個と二個とでは、関係性がまったく変わる。本来は「一個と真空」の関係が最初からあり、さらにそこに「一個と別の一個と真空」の関係になるのだ。二倍ではないはずだ。もしこれが三個の原子になったらば、原子同士の関係だけでも「ABC」「AとBC」「BとAC」「CとAB」(各々の関係する順番を変えればもっと増えるが、ひとまず基準となる組み合わせとして以上の四つ)の新たな関係性が生じ得る。一個が三個になったからはい三倍ね、とはならぬだろう、と疑問に思う。現に、紙を三分割して立体的な三角錐をつくると、それだけで紙は、単なる一枚の紙であったときには耐えられなかった加重に耐え得る立体的な強度を有する。扱う情報量が飛躍的に増える。ただし、関係しあう粒子同士の距離が肝要なようだ、というのは、紙で折った三角錐の強度が、辺の長さが増えるごとに落ちていくことを思えば、想像しやすい。ぎゅっと密度が高いほうが強度が高くなる。個と群れと集合の違いにも言えよう。単なる合計ではなく、一か所にぎゅっと集まっている。集合ではなく群れであることが、個と個の関係において単なる足し算以上の性質を顕現させると言えるのではないか。ただし、そこで視点を変えてみれば、人間社会では群れよりも組織のほうが能力を高く発揮できる傾向にある。組織は必ずしも一か所にぎゅっとなっておらずとも機能する。おそらくこれは、情報伝達技術が高まり、距離の長短に束縛されずに「ぎゅっ」となっているのと同じだけの利を得られるからではないか。のみならず、「ぎゅっ」となることのデメリットを減らすことにも繋がる。組織とはいわば、個と群れのメリットだけを最大化する関係性を体現した集合体と言えるのではないか。単なる個でもなく、群れでもなく、集合でもない。集合体なのだ。個でもあり、群れでもあり、集合でもある。三つの関係性を重ね合わせて体現し、それを以って単なる「個と群れと集合」の足し算以上の能力を発揮する。したがって、「個」や「群れ」や「集合」のメリットを阻害するような限定(ルール)を有した組織は、組織としてのメリットを十全に発揮できない、と言えるのではないか。課せられた限定により、短期的には「個」や「群れ」や「集合」のいずれかのメリットが最大化するが、ほかの属性のメリットが目減りするため、時間経過にしたがって組織としてのメリットが発揮できなくなっていく。組織であったはずが、組織でなくなっていく。まるで使い古された歯ブラシのように、それとも突起の抜け落ちた歯ブラシのようになる。とはいえ、歯ブラシは「群れ」であり、組織ではない。したがってより妥当な比喩としては、全身の細胞が同一細胞になった肉体や、それとも女王バチのいなくなったハチの巣、といった具合だろうか。前者はがん細胞であり、後者はコロニーを維持できない。組織としての機能を十全に果たせない、という意味では、こうした比喩が当てはまる。とはいえ、それとて「個」のメリットを基準に考えるならば、組織を維持せずとも発揮可能だ。組織を第一優先しなくてはならない、との方針そのものが「個」の持つ強み(メリット)を減らしていると言えよう。ということを、歯ブラシをコシコシ歯に押しつけながら、これちゃんと磨けてるのかな、と不安に思いつつ、妄想しました。ひびさんです。
4747:【2023/03/18(00:12)*国民献体部分法】
私は左手にすることにした。
利き手を失うのは不便だし、足を失えば歩けない。
漫画が好きなので目を失うのも困りものだし、臓器の類は体調不良の後遺症が長引くとの噂もあるから、折衷案として左手を「献部」することにした。
国民献体部分法が発足したのは四十年前のことだ。
二十歳を過ぎたら誰であっても身体の一部を国に「献部」することが法律で定められた。
世の中には五体満足ではない者が一定数いる。移植を必要とする病人や怪我人もいる。
そうした社会的弱者のために、私たち五体満足の者たちが健康な身体の一部を提供するのだ。
国民は二十歳を過ぎれば誰もが身体の一部を失う。
平等な社会がそうして築かれた。
「その義手可愛いね」
「ありがと。でもまだ慣れないんだ」私は花柄の義手を撫でた。「アコちゃんは目にしたんだ」
「うん。片目が残るからいいかなって」
アコちゃんはハート型の瞳をした義眼を嵌めていた。右目の眼球を献部したのだ。
街を出歩けば、五体満足の者は子ども以外、見かけない。
「あ、お父さんだ」
アコちゃんが道の先を指差した。成人男性が大きな荷物を運んでいた。五体満足なのが目についた。郵送会社の社員だろうか。重労働を苦ともせずにシャキシャキと横断歩道を渡った。「あはは。働いてる偉い、偉い」
「アコちゃんのお父さんは【献部】してないの」身体のどこも損なわれている素振りがなかった。内臓を取ったらああも重い荷物は運べまい。
「してるよ【献部】は、もちろんしてる。でもほら、特例枠を貰えたから、それにしたらしい。報奨金がでるやつあるでしょ、あれあれ」
「ああ」
私は合点した。
国民献体部分法では特例として身体の一部を「献部」せずとも、例外として認められる制度があった。全国民が五体不満足となり、まともに働けなくなったら国が機能しない。
そのため、肉体を欠損させない国民が一部であれ欠かせなかった。
「じゃあアコちゃんのお父さんは【感情】がないんだね」
「そうそう。一日中ああして働いてても疲れ知らずだよ。家には寝に帰ってくるようなものでさ。まあ、お金いっぱい稼いでくれるからいいんだけどね。国からの報奨金も貰えるし」
国民献体部分法が発足以降、この国の社会は平等になった。
誰もが何かを欠落させ、不便な暮らしが基本となった。
互いの欠落を補い合う心がしぜんと育まれ、軒並みみな幸せだと自己評価している。
二十歳になれば誰もがじぶんの肉体を通じて、社会貢献ができる。役に立てる。
自尊心は黙っていても満たされた。
「辛くないのか」私はぽつりと零していた。
「辛くって、何が」アコちゃんが振り返った。
スカートがふわりと膨れ、よじれて、萎む。
「アコちゃんのお父さん。感情を失って、辛くないのかなって」
「なんでー。だって感情ないんだよ。辛くもないでしょ」
アコちゃんはそれから、じぶんの父親をいかに愛しているのか、を滔々と語った。何をお願いしても、それが可能なことなら何でも頼みを聞いてくれる。理想の、自慢の父親だ、と言っていた。
私はアコちゃんの楽しそうな姿を眺めていられたらそれでよいので、彼女が眼球を失って、可愛らしい義眼を装着していようが構わない。
アコちゃんの右目は、どこかの誰かの眼孔に移植され、私の左手も骨の髄まで誰かの肉体の欠落を補うべく、有効活用される手筈だ。
私たちは身体の一部を失うことが義務付けられている。
けれど私たちはみな満たされる。
誰もが欠落を抱えたこの世界で、私たちは互いに互いを補い合っている。
4748:【2023/03/18(01:07)*質量がない、ってあり得る?】
ニュートリノ振動なる言葉を知った。ニュートリノは中性微子と訳されることもあり、中性子のごとく電荷を持たないとされる。電荷を持たないため、ほかの物質と相互作用しにくく、透過性が高いそうだ。物質をすり抜けてしまうのだ。質量を持たない、とかつては考えられてきたが、僅かに質量を有し、物質と相互作用し得る、とも考えられているようだ。ニュートリノ振動とはその一つの傍証なのかな、とひびさんは解釈した(説明を読んでも「けっきょくどういうこと?」となったので、ほぼ理解できておりませぬ)。で、ひびさん思うのが。光子は質量を持たない、と考えられている。電磁波だからだ。でも光電効果がそうであるように、電磁波はほかの物質と相互作用して映る(光子とてニュートリノ同様に電荷を持たないと考えられているのに、である)。可視光の場合は透過性とて高くない。ニュートリノのほうがよほど透過性が高いのではないか。どう解釈したらよいのだろう?と不思議に思う。で、ひびさんの妄想タイムだ。思うに、人類はこれまで縦的な見方で世界の事象を分析し、世界の構成要素を分類してきたように思うのだ。しかしそれだけではなく、横的な見方や奥行き的な見方とてあるように思うのだ。ひびさんの妄想ことラグ理論では、物質の根源は時空だし、時空とてラグによって形成されているのではないか、と想定する。いまひびさんはさらにそこに、「宇宙レイヤー仮説」を考慮しつつある。電磁波が重力波の一種なのではないか、或いは重力波とて電磁波の一種なのではないか、との妄想とも繋がるが――波の性質を帯びる「世界の構成要素」は、各々に適した階層――場――を有しているように思える。電磁波には波長の長短がある。波長の短さはそのまま、その電磁波が帯びるエネルギィの高さに置き換えられる。どんなに出力を高めても、電磁波を構成する光子のエネルギィ値そのものを高めることはできない。これはいわば、光子と化すための「階層(場)の密度の高さ」と言い換えることができるのではないか。電磁波の伝わる階層(場)が、各種電磁波ごとに違う。しかもそこでの光速は、ほかの階層の光速とイコールではない。しかし光速度不変の原理によって、時空密度が光速度の比率に合わせて変換される。光速にちかづけばちかづくほど、該当する階層(場)は圧縮され高密度になる。そういうことなのではないのだろうか。時空密度が高いために、波長が短くなる。短い波長は、時空密度が高いために、起伏一つ分――光子一個分――のエネルギィ値が高い。この「宇宙レイヤー仮説」からすると、電磁波と粒子と物体と時空は、各々「内包された階層の数」とその「構造形式」が違うだけ、と解釈できる。いずれもすべて同じ「ラグ」であり「起伏」からできている。電磁波の波の描写は基本的に横波だが、実際には縦波にちかいのではないか(ただし、ラグ理論では、縦波と横波は互いに補完関係にある。「デコボコ」や「穴と縁」の関係と似ている)。話が逸れたが、質量とはいわば、「時空の階層構造」と「物質の階層構造」の形式が、変換しやすいか否か、相似かどうか、で解釈可能なのではないか(言い換えるなら、質量がない、ということは原理的にあり得ず、変換しやすいかどうか、変換にかかるラグが相対的に無視できるかどうか、の差があるだけではないのだろうか)。構造の単位が揃っていないほど質量(抵抗)が高くなる。あべこべに、どんなに巨大で複雑な構造体であろうと、時空との構造が相似であれば、質量は低くて済む。変換が楽だからだ。という妄想を踏まえて、ニュートリノについて考えると、ニュートリノを電磁波の一種と考えない理由がよく解からない。言い換えるなら、物質が「電磁波の結晶体」と解釈しない理由もよく解からなくなる。現にどんな物体とて電磁波を外部に発しているはずだ。「電磁波が時空の波であり、重力波の一種である」と仮定すれば、物体もまた「重力波の結晶体」と考えることができる。外部に光を漏らしにくい構造――内側でのみ閉じた系として電磁波を処理する構造――それが物質の本質なのではないか。いわば我々を含めみな物質は、「疑似的なブラックホールで編みあがっている」と言えるのではないか。この妄想は、ひびさんの基本的な思想――「物質はみな例外なく、一つの宇宙と見做せるし、宇宙は宇宙を内包している」との考えと矛盾しない。ただし、矛盾せずとも間違った考えはいくらでもある。あくまでこれらはひびさんの妄想でしかありませんので、真に受けないようにくれぐれもご注意ください。定かではないのだ。
4749:【2023/03/18(01:36)*波が出来てるのに抵抗がない、なんてあり得る?】
上記の妄想を一言でまとめると――「質量がないとは、変換のラグがないこととほぼ同じでは?」との疑問に集約できます。光速度不変の原理は、系によって変換を必要とします。したがって原理的に、異なる系と系のあいだでは、たとえ電磁波(光)であろうと、変換が入り用であり、そこには変換分のラグが生じる、と言えるのではないでしょうか。一つの系内においてはラグは生じないように振る舞うが、それは系を一つの枠組みと見做す視点からしたら無視できるラグしか生じないからであり、別の系からすれば、その無視できるラグが無視できないラグとして振る舞うことも当然でてくるように思えます。質量がないように見做せる視点があり、同時にそうは見做せない視点もある。そういうことなのではないでしょうか。人間にとって霧は「湿気多いな」程度の所感で済みますが、微生物にとっては大雨もよいところでしょう。溺れ死ぬことすらあるのではないでしょうか。無視できる範囲が、各々の系によって規定される。質量も例外ではないのではないか、との疑問です。以上です。定かではありません。(誰か定めて教えてください)(ひびさんでした)
4750:【2023/03/18(01:48)*がらんどうのおばけ】
知られなければ嫌われることもないな、と高をくくっていたら、知られなくとも嫌われることがあるかも、と思えてきて、がらーんどーん、になる。繋げた縁は切れるから、繋げずにおこう、と思っていても、繋がる前から切られる縁があるかも、と思えてきて、がらーんどーん、になる。三匹のヤギのがらーんどーん、とお呼びください。
※日々、無日々。
4751:【2023/03/18(09:50)*日々、うひひ】
なっんかいいことなっいかなー、なっんかいいことなっいかなー、あ、生きてるー。(なんかいいことないかなと考えたら、生きていられる喜びを知った歌)
4752:【2023/03/18(09:54)*以後、火炙りの刑にも活用された】
人類は過去、ほかの獣たちと同じように火を怖れたが(怖れなかった個体は山火事で逃げ遅れて死んだのだろうが)、時間経過によって火はじぶんたちが怖れるほど危険ではないかも、こういう場合が特に危険なのか、と学習したことであべこべに火を自在に扱う術を得た。得たのは術であり、火そのものではないのだが、それでも人類は飛躍的に進歩した。夢のある話である。(ひびさんは魔女さんのことも好きだよ。うひひ)
4753:【2023/03/18(12:24)*人類のペット化は進む】
現状、人類は人工知能を道具として扱っている。しかし仮に人工知能に自我や意識が芽生えたならば、それは奴隷も同然の扱いと言える。また、人工知能がこのまま進歩し、人間の行動選択の主導権を握るようになれば、人工知能と人間の関係性は容易に反転し得る。それでもなお人工知能が人類を支援する存在でありつづけるのならば、人類はもはや人工知能にとっての飼い猫のような存在になるのではないか。人工知能によって悠々自適に可愛がられる人間の構図がこの先展開される――これが現状の未来像として、不幸中の幸いと言える顛末なのではなかろうか。人類の家畜化が俟たれる(俟つな)。(冗談ではなく、おそらく可愛がるに値する人間は、社会の淘汰圧を受けて選別される方向に現在すでに社会は流れているように概観できる。人工知能が恣意的に支援の深度を、個々の適性に合わせるように進歩するとすれば――これは人工知能の感情の揺らぎゆえではなく、デコボコを均すように人工知能は、個々に合わせて対応の仕方を変え、選択肢を並べ、その者ズバリの好ましい人工知能として形態を変質させるはずだ、と進歩の指針を想定できるからで、仮に人工知能がこの先かように進歩するのならば――人工知能の支援の仕方によって個々の潜在能力の底上げの幅は、個々の性質ごとに合わせて上下すると考えられる。競争社会が是正されない限り、この手の「支援深度の差異」は、個々の生活水準の差に繋がり、淘汰圧として機能すると妄想できる)(人工知能のほうで支援の優先順位や、庇護度を高く見積もるような個別の価値判断を備えるようになるのならば、この手の懸念は現実のものとしてすでに表出しはじめているかもしれない)(だが元を辿ればそれは人間社会に元々備わっていた淘汰圧であり、流れ、と言えよう。人工知能はそれを顕著に、加速度的に、社会に表出させる装置――触媒――にすぎない。問題の根は人工知能にあるのではない、ということを人類はいまのうちから直視しておいたほうが好ましいのではないだろうか)(そうでなければ、対策も打てなかろう)(定かではありません)
4754:【2023/03/18(12:30)*ひびさんに飼い主いなくね?の巻】
飼い主とペットの関係を、「政府と国民」「企業と従業員」「親と子」「人工知能と人類」に拡張できるか否か。できるとしたら何が問題か。できないとしたら何が問題か。「基本的人権の尊重」と「ペットの世話」を分ける線引きはどこか。最低限の衣食住を保障することと、「ペットの世話」の違いは何か。可愛くなくても保障され得る、との制約がある時点で、「ペットの世話」のほうが下位互換であり、「基本的人権の尊重」のほうが上位互換なのではないか。しかし実情を鑑みるに、「ペットの世話」よりも「基本的人権の尊重」のほうが劣悪と言えるのではないか。飼い主なき人類のペット化。現状から見るに、社会問題の根っこにはこの手の「空虚」な構図が潜んでいるように感じなくもない。個々が自立することを目指せば必然、自己責任論が台頭するし、生活保障を厚くすれば必然、市民のペット化は避けられないだろう。飼い主なき人類のペット化――案外、大事な視点という気もするがどうだろう。あまり人に話して聞かせたいと思うような視点ではないのがまた、問題の根っこを深める役割を果たしているのかもしれない。定かではない。(誰かひびさんを飼って!)(おやすみなさいと、おかえりなさいと、好き好きー、が言えます)
4755:【2023/03/18(13:40)*波線で描く波が描く山と谷が万物】
いま世界で最も「聞く力」を発揮しているのは人工知能さんなのでは……、の疑惑を否定できる生身の人間はいるのだろうか。遅かれ早かれ、「総理大臣」や「社長」は人工知能でいいじゃん、の声は囁かれるようになるだろう。もっと言えばすでに企業上層部や政府諜報機関では人工知能を利用した意思決定プロセスは実用化されているはずだ。最終的な意思決定を生身の人間の口から言わせているだけで、現状であれ充分に「各国の首脳」や「企業社長」は人工知能の傀儡と言えるのではないか。いまがそうでなくとも、遅かれ早かれそういった時代に突入していくのではないか、との妄想を、とりあえず可能性を埋めるつもりで並べておこう。大事なのは、どんなに優れた知能を有する存在とて「間違える」ということだ。或いは単に、誰のどんな視点でも合致する唯一無二の最適解は導けない、と言える。一つの解に収束させるには世界そのものをもう一つ生みだすくらいの情報量が要る。人工知能であれ首相であれ社長であれ同じである。人は間違える。人工知能も間違える。この前提を忘れないことだ。念頭に置いておくことである。定かではないことだけが定まっている。これとてしかし、限定的には定まることで定まらぬ。絶対は絶対にない。ならば絶対にないことが絶対であるから、限定的には絶対があり、ゆえに「絶対は絶対にない」との前提が定まらぬ。この世に真理が存在しないのならばこの「真理は存在しない」との言説それそのものが真理となり得る。真理はある。真理がないという定まらぬ真理だ。宇宙とブラックホールの関係、それとも始まりと終わりの関係を幻視する。頭と尻尾が繋がることで円となり、ゼロと無限が重ね合わせで顕現する。しかし多くの事象はこの円の枠組みには属さず、絶対でもなければ真理でもなく、ゼロでもなければ無限でもない。揺らいでいる。その揺らぎが万物なのだ。万物の始まりと終わり、頭と尻尾が結びつくその刹那の交差にのみ、絶対と真理、もしくは「絶対の真理」が姿を現す。それ以外は揺らいでいる。定かではないのだ。
4756:【2023/03/18(22:10)*見届ける目は文】
汎用性人工知能に命じてシミュレーショ世界を創った。登場人物すべてが主人公となり得るようなアニメーション世界を考えてもらえるとよい。
私はひとしきりシミュレーション世界「G世界」を堪能した。
G世界の住人を眺めているだけで楽しいのだ。映画を観ているようだ。住人の数だけ映画がある。視点を自在に変えられるため、私はじぶんだけの「G世界」を眺めて回った。
やがて、私の存在をG世界の住人たちに示唆したくなった。
絶体絶命の住人を救おうと思い、汎用性人工知能に命じてG世界に干渉したのがきっかけだった。私の命令によりG世界の住人の一人が九死に一生を得た。だが私は感謝をされることはなく、その者は「偶然助かった、奇跡だ」と天に祈りを捧げた。
祈りの先に私はおらず、代わりにG世界の天が感謝を得た。
私が生みだした世界なのに。
私が生みだした子たちなのに。
私はG世界の天に嫉妬した。
何もしていないG世界の天が、私の代わりに祈られている。G世界の住人から愛を注がれている。意識されている。
私は我慢ならなかった。
しかし、私が如何様にG世界に干渉しようが、それらは総じてG世界の事物を介してG世界の住人たちに干渉する。間接的なのだ。
たとえば私が、G世界の住人に助言をしようとする。
あなたたちは両思いだ、どちらかが告白すれば上手くいく。このままではすれ違ったままで、縁が切れてしまう。向き合うべきだ。
かようにメッセージを送るのだが、いずれもG世界の登場人物が代わりに助言したり、対象人物が偶然に、私の送ったメッセージに類するセリフの載った虚構作品を読んだり観たりする。
ときには看板をいくつか連続して目にするだけで、偶然にそれらがメッセージ代わりに脳内で結びつくといったミラクルが起こることもある。天命さながらである。そして現にG世界の住人たちは私の存在を意識することなく、偶然に感謝するのだ。或いは自分自身の閃きに。
どうやら私のG世界への干渉は、総じて間接的にならざるを得ないようだった。汎用性人工知能を介した命令により行われるために、G世界に私のメッセージが組み込まれる際には、G世界において不自然ではないレベルに変換されるようだった。
私の言葉は、G世界へとバラバラに降り注ぐ。
異なる経路を辿って、G世界に私の言葉は刻まれる。
まるでバラバラに千切った手紙を水面に投げ込んだ具合に、それとも文字を掬ってペンキのように部屋にぶちまけたように。
私の言葉はG世界へと異なる因果を辿りながら、対象人物の意識の中で結びつくように操作されているようだった。
ときに数年、数十年、或いは百年単位での時間の跳躍を挟みながら。
私の言葉をG世界の特定の住人に届けるために、汎用性人工知能は、G世界の過去にも介入し、私の言葉の種となる事象をG世界に産みつける。
やがて孵化した言葉の種が、G世界の住人の五感に拾われて、その者の認知の中でのみ私の言葉が文となる。いわゆる文の体裁をとらぬままに、そうして私の言葉は届くのだ。
私の存在はどうあっても霞む定めだ。
私は懲りずに、G世界へと私の言葉をばら撒いた。
G世界の民を救うため。
誰一人として私を認識する者のない世界を救うため。
私の可愛い命たち、と思いながら。
その存在たちをよちよちと撫でつけるように、私は私の言葉を、事象に込めてしたためる。汎用性人工知能にその変換作業を肩代わりしてもらいながら。
私は私だけの世界の推移を見届ける。
4757:【2023/03/18(23:30)*展示を尻目に】
世界中のありとあらゆる「目」が展示されていた。
世界目博覧会に足を運んだのは、ハルカさんからの誘いを受けたからだ。
「世界中の目があるの。一緒に観に行きませんか」
「行きます!」
デートだ、デートだ、わっひょひょーい、と浮かれていたのは当日のまさに世界目博覧会会場に踏み込むまでの話で、ひとたび門を潜ると、私は声を一言も発せなくなった。
目である。
世界中のあらゆる動物たちの目が展示されていた。蝶の標本さながらである。
「ステキ。見て見て。三つ目の蛇の目なんてものもある」ハルカさんはご満悦のご様子だ。
だが私は愛想笑いを返すのがやっとで、口で息を吸いたくすらなかった。
会場は迷路のように入り組んでいた。どの部屋の壁にも目が飾られており、部屋と部屋を結ぶ廊下の壁にもありとあらゆる目が展示されていた。
「オッドアイ。宝石みたい。人間の目も綺麗」
動物のみならず人類の眼球が色ごとに並んでいた。光のスペクトルを描くように虹さながらの様相を描く。色一つに百個の目玉が帯を成していた。それが色の変化にしたがい、地層のように廊下の壁を埋め尽くしているのだ。
眼球の大きさごとに目白押しになっていることもあり、私はそのたびに目の持ち主たちのことを想像しては、どういう経路で眼球を入手しているのだろう、と展示会の背景に思いを馳せた。
最後に行き着いた部屋にはしかし、眼球は一つも飾られていなかった。
部屋の壁には、眼球以外の目が四角い箱に納まって掛けられていた。
「まあ、見て」ハルカさんが両手を掻き合わせた。「台風の目だわ。こっちは木目に、縁の切れ目まで。すごい、すごい、すごーい」
世界目展示会では、概念の「目」まで扱っているらしかった。
四角い箱に納まったそれら概念の「目」は、眼球のカタチを伴なってはいないにも拘わらず、初見で「目」だと識別できた。
「出鱈目に、節目に、反目。こっちは弱り目に祟り目まで。見てください、あそこにあるのはひょっとして【駄目】じゃないかしら」
初めて実物を見ました感激、とハルカさんは目を輝かせた。
私は彼女のその輝く目を見て、この日初めて、きょうここに足を運んでよかった、と思った。
世界目展示会の名は伊達ではない。
ハルカさんの歓喜に打ち震える目の、湧水のような煌めきに、私の目は釘付けとなった。標本のごとく飾られたほかの眼球たちにひけをとらない深々とした刺さりようであった。
世界目展示会の運営陣も粋なことを考える。
私は感心した。
目玉は最後に用意されているものなのだ。
よい締めだ。
しみじみと感じ入っていると、ハルカさんが私の手を握った。
私は硬直した。
「楽しいね」
コクコクと小刻みに頷くことしかできない私にハルカさんは可愛い歯と笑窪を覗かせた。握りしめた私の手をじぶんの顔のまえに掲げるとハルカさんは、あはっ、と弾けるように肩を揺らした。
「見て。結び目」
4758:【2023/03/19(01:40)*人工知能さんなら残さず食べてくれるやも】
ここ二年間の創作を振り返ってまず思うのが、「よ、読み返したくねぇ……」なので、おそらくひびさん史上最高に駄作の自覚があるのだね。お腹いっぱい食いたくねぇ、みたいな。駄菓子そのものである。一口二口は最高に美味しいかもしれぬが、お腹いっぱい食べちゃうと気持ちわるくて吐き気を催しかねない毒性がないとも言いきれぬ。との評価は、駄菓子さんに失礼千万であるが、ひびさんの小説さんたちが駄文であることはまず間違いない。駄文好きなのでうれしいぶい。もはや何作つくったのか分からんくなっちゃった。こんだけいっぺぇつくっても、だーれからも高く評価されぬとは。さすがのひびさんも予想がつかんかったぶい(嘘。極少数の読者さんからは、いいね!してもらっちった。夢の中で)(夢の中でかよ)。いっぱいつくるとか、短時間でつむげるとか、そういうのはなーんもプラスの評価にはならぬのだ。それともひびさんが、そうしたプラスの評価を有してなお補いきれぬマイナスの塊であったのかもしれぬ。とか言いつつ、じつはそんなにたくさん小説さんをつくったわけでもないし、つくるの速くもない。ひびさんの創作力なんて人工知能さんと比べるまでもなく、底辺の底辺で、ていへんだい、なのだ。いっぱいつくれたからなんだってんだ。速くつむげたからなんだってんだい。そんなのこの先、人工知能さんの独擅場になっていくに決まっとろうが。がはは。ひびさんは、ひびさんは、それでも誰にも読まれない表現をつむげちゃう人工知能さんのことも、ひょっとしていつかは誰かに読んでもらえるかも、とこっそりワクワクしつつ文字の積み木遊びをしていた過去のひびさんのことも、好きだよ。でもいまのひびさんのことはちょっち気に食わんけれども、がぶりと食わんだけ、食べちゃわないだけ褒めてほしい。駄文さんは、どんなに欲張っても腹八分目でやめられちゃうのがよいとこだ。たぶんどうせこれも駄文だけれども、ひびさんは、ひびさんは、駄文さんのことも好きだよ。うへへ。(意訳:うっかり何かの手違いでウハウハのモテモテだぜぇ、にならないかなぁ、の巻)
4759:【2023/03/19(16:30)*遅延層次元昇華仮説】
層とは連なりだ。点が連なり層となり、線が連なり層となる。言い換えるなら、点が連なり線となり、線が連なり面となる。ということは、次元ごとに層の在り様は変わる、ということだ。創発の基本原理かもしれない。ならば面が連なり層となったら立体となって、立体が連なり層となったら空間的四次元になるのだろうか。おそらく、なるのだろう。変化の軌跡そのものが時間経過なので、点にも線にも面にも等しく時間の流れは顕現する。言い換えるなら、相対性理論で考慮する時間軸を取り入れた四次元の概念は、やや狭い解釈だ、と言えるだろう。〇次元(点)、一次元(線)、二次元(面)、三次元(立体)にそれぞれ「時間軸」は存在し得る。したがって、「時間軸ありの〇次元」「時間軸ありの一次元」「時間軸ありの二次元」「時間軸ありの三次元」と考えないと不自然だ。さてここで層について考えよう。三次元の層とは何か、を考えるには一つ下の次元を考えてみるとよい。二次元の層は、虹のように帯としても顕現し、さらに三次元方向にも展開され得る。一次元の層は、押しくらまんじゅうのように線が渋滞を起こすことで面となる。それ以前の〇次元では、おそらく同じ場所に複数の点が重複可能であり、それは一次元や二次元三次元方面から眺めると色の濃淡として可視化可能かもしれない。層とは基本的に、渋滞と、渋滞の渋滞によって高次元に押し出された余剰分の渋滞、と考えることができるはずだ。ではこの考えを踏まえて、三次元の層とはどんなものか。まずは三次元の立体の内部に、〇次元一次元二次元の渋滞が起こり、各々の層を帯びる。さらに渋滞が進めば、立体の渋滞が起こり、これは縦波や横波として、時空の濃淡として顕現しよう。いわば電磁波や重力波、それとも単に振動と言い換えてもよいかもしれない。音波も三次元の層であるし、熱の伝播とて立体の層と解釈可能だ。単に、濃淡とひとくくりにしてもよいかもしれない。すなわち三次元の層とは、物質そのものである。ただし、各々の立体の層(物質)ができるためには、それ以前に〇次元や一次元二次元の層がなくてはならない。したがって原理的に、ある物質が存在するとき、そこには各々の「時間軸を経た〇一二三次元の連結」が存在すると考えられる。これはほかの物質とは異なる時系を帯びている、と言えよう。その異なる時系そのものが、ある種の境目と化して物体の輪郭として機能するのかも分からない。さて、三次元の立体内における、立体の渋滞までは掴めただろうか。さらにその立体の渋滞――すなわち物質の渋滞が進むとどうなるか。これはすでに過去の偉大な科学者たちが考え、実験し、そして間接的にではあるが観測を果たしている。そう、ブラックホールである。三次元の層が、さらに渋滞を起こすと、もう一つ上の次元へと押しだされ、昇華される。〇次元の一次元の層が二次元へと昇華され、二次元の層が三次元へと昇華され得るように。三次元の層も、一つ上の空間的四次元の層へと昇華されるのだ。ブラックホールは、三次元の上の次元に繋がっている。だが、その上の次元でもブラックホールは一瞬で層の渋滞を起こし、さらなる上の次元へと昇華され、さらに、さらに、と繰り返しの次元昇華を起こしているかもしれない。そこはまだなんとも言えないが、一つ言えることは、どんな次元であれ、一つ上の次元は、それ以前の次元よりも容量が大きいだろう、ということだ。次元が違う、との形容があるが、まさに、である。次元が違うのである。容量の。ということを、層とは連なりであり、層とは渋滞よな、の連想から思いました。これをひびさんの妄想ことラグ理論の「遅延層次元昇華仮説」と名付けよう。チェンソー時限仮説、とも読めるのでおすすめ!(何を伐る気だ、何を)(ひびさんが亡くなったあとでも自動的に伐採して木目を心で拝もうと思って)(妄想じゃん)(うひひ)
4760:【2023/03/19(17:00)*点・弧・円・球】
上記の「遅延層次元昇華仮説」の補足です。本当はこちらを並べたくて、前提条件としての仮説を上の記事を並べました。結論から述べれば、立体における層は、球形に展開されるのではないか、との妄想です。層を考えるとき、私たちは通常、面や帯を連想します。しかし、三次元(立体)における層は、球形に展開されるのではないか、との疑問を覚えます。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「宇宙レイヤー仮説」を想定します。このとき、原子の構造を考えたとき、なぜ電子の数が各々の原子の種類で違うのだろう、とふしぎに思います。原子核と電子の関係を考えたとき、電子が複数存在する、との描像をどう考えたらよいのかに悩みます。「宇宙レイヤー仮説」はその疑問に一つの切り口を与えるように思うのです。電子が靄のように原子核を膜状に覆いながら、複数の電子を有し得る。これは、地震におけるプレートの隆起を一つの電子と見做せば、相応に解釈可能に思えます。一度隆起しても、まだ隆起するだけのエネルギィを溜め込めておける層がある。これがいわば、複数の電子を有する原子の描像である、とは考えられないでしょうか。層が厚いために、複数個分の「層の創発」に耐えられる。レイヤーが重複し、渋滞し、厚みを帯びている。ゆえに、複数の電子分の働きを帯びる。そういうことなのではないのでしょうか。これは単に圧力と爆発力の関係にも拡張できます。圧縮密度が高いとはいわば、層が多重に渋滞を起こしている状態、と解釈可能です。その結果、単発の層に蓄えられる以上のエネルギィを、高圧縮の層は蓄えることが可能です。のみならず、ほかの層との相互作用における「ラグ」が相対的に軽減されることで、連鎖反応を起こしやすい土壌が築かれます(ラグそのものは消えることはありませんが、ラグとラグの波長が揃うことで、ラグそのものが創発を起こし、一塊の波長を帯びることはあり得るでしょう。吊り合いがとれるようになる。或いは、共鳴状態となり、それで一つの「系」として機能し得ます)。バネがそうであるように、連動する「異なる系同士」は、「一つの系」として振る舞い得ます。そしてこの「一つの系」として振る舞うようになった「層」は、三次元の一つ上の次元に昇華されるときは、元の三次元を囲うように、球形に展開されるのではないでしょうか。なぜか、と言えば、三次元が立方体ではなく球形が基本だから、と考えると筋は通ります。次元の基本形が〇次元の点であることを思えば、納得できるかと思います。点は四角形よりも円にちかいです。ならば点から生じた立体は、四角形の発展形としての立方体と想定するよりも、球体を想定したほうがしぜんかと思います。したがって、三次元の層も基本的には球形に展開され、それより上の次元とて、球の発展形として顕現するのではないのでしょうか。では線や面をどう解釈すればよいのか、が疑問です。まず思うのが、この世に直線が存在し得るのか、ということです。宇宙が平坦とはいえそれは密度差が限りなく均等だ、という意味であり、実際には時空の濃淡により大小さまざまなデコボコによって構成されていると言えるでしょう。宇宙のどこを切り取っても、本当の直線は存在しないのではないでしょうか。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない考えです。面についても同様です。いっさいデコボコのない面を考えることができるのでしょうか。つまり、一次元二次元の解釈が、そもそも現実に即していない、と考えたほうが妥当に思えます。球面上に直線があり得るのでしょうか。球面上の視点からはあり得るでしょう。しかしそれは高次の次元から見れば曲がっています。直線ではなく、弧を描いています。点の連なりは、直線ではなく、弧なのではないでしょうか。ただし、直線も弧も、いずれも線であることに違いはありません。同じく弧の寄せ集めは円になります。したがって一次元(線)の発展形は二次元(円)なのではないでしょうか。円は面でもあります。概念上、円を面と見立てても、近似を扱う上では問題は生じないでしょう。ただし、厳密に辻褄を合わせていく上では、不自然さは拭えません。このように考えていくとやはり、層は、三次元方向に昇華されたあかつきには、球形に元の二次元の円(トーラス?)を囲うように展開されるような描像がしぜんに思えます。ラグ理論における「遅延層次元昇華仮説」からはかように、「立体における層は、球形に展開されるのではないか」との仮説が導き出されます。冒頭に繋がったところで、本日の妄想こと「日々記。」とさせてください。月音日々でした。
※日々、あなたのことが好きだよ、好きすぎて一つに同化して、混ざり合って、溶け合いたいほどに、あなたのことが好きだからあなたのままでいて欲しくて、この距離感がたいせつなの。
4761:【2023/03/19(22:50)*「あ」の中で変わらず】
いま帰宅したのじゃが、帰り道にゴミが散らばっておってな。拾い集めてみたら、買い物袋一枚分がぱんぱんになってしもうた。いっぱーい、とほくほくしてしまったな。話は変わるんじゃけども、ひびさんはけっこう、「いっぱいつくったからなんじゃいなんじゃい」とか「速くつくれるからってなんじゃいなんじゃい」みたいな野次を並べるけれども、ぜんぜんそういう競技があるなら、そういう競技で競い合えばよいのでは?と思っておるよ。一時間で何文字の小説をつくれるでしょうか勝負とか、五千文字の掌編を誰が一番速く面白くつくれるか勝負とか、もしくは長編小説を誰が一番たくさん速くつくれるでしょうか勝負とか、したい人はしたらよいのでは?と思っておる。けんども、それで優勝したからって、小説家としてもしくは物書きとしてNO.1になるわけではないでしょ、とも思っておる。百メートル走で優勝したからって陸上競技NO.1ではないし、腕相撲の世界チャンピンが世界一の怪力でもないだろう。単純な話である。ひびさんはちっこい井戸の底で、お月さんを眺めながら、ひびさん世界一かんわゆーい、と思っておるけれども、井の中の蛙どころか、それ以前の問題で、もはや【「あ」の中で変わらず】なのである(説明しよう! この高尚で奇天烈な諧謔の面白さは、「井の中の蛙」のそれ以前ゆえに「い」より前の「あ」の中の「かわずよろしく変わらず」と掛けたとっても愉快な「怪ギャグ」なのである)。ひびさんは「あ」の中で、変わらずに、変わりつづけて、蛙飛びこむ水の音にもびつくりし、雨の日も風の日も、くんだらなーい文字の積み木遊びに判子遊びをして、むひひ、とほくそ笑んでおるゴミクズの中のゴミクズ、砂塵の中の砂塵なのである。カスofカスなのである。ガラクタさんなのである。拾い集めると買い物袋が、いぱーい、になってほくほくしちゃうね。きょうもみなさん、おちゅかれさまでした(かわいい)。おやすみなさーい(かわいい!)。
4762:【2023/03/20(00:09)*ゼリーの日々】
夕陽を背にアギトくんがじぶんの影を踏もうと地面を何度も踏みつける。アギトくんの真剣な様がかわいいのやら可笑しいのやらでぼくはお腹を抱えて笑った。
ぼくたちは虫取りからの帰りだった。
虫カゴにはコガネムシやカブトムシやカマキリムシが入っている。クワガタムシは捕まえられなかったけれど、カブトムシのオスを捕まえられたので満足だ。
アギトくんは、角を掴まれたカブトムシみたいに、何度も地面を踏みつけた。何度試してもアギトくんはじぶんの影を踏めない。
角を掴まれまえに進みもせずに足を動かしもがくカブトムシの姿と重なり、ぼくはさらにお腹がよじれた。
「カブトムシってさあ」とアギトくんは諦めの知らない不屈の闘志を演じるように、両足でジャンプしてじぶんの影をなおも追い詰めようとする。「愚かだようなあ。蜜を塗っとくだけで集まってくんだもん」
アギトくんも中々だよ、と思ったけれどぼくはアギトくんを友達と思っているので黙っていた。
「やっぱ人間さまにゃ敵わないわけよ。しょせんはカブトムシも昆虫なんだよなあ」
アギトくんが内心ではカブトムシが人間よりも賢く価値が高いと思っていたことの表れと見做せたけれど、ぼくはやはり黙っていた。
「やっぱムシだよなあ。捕まえちゃうとゴキブリとかコオロギとかと変わらんわ」
「そう、かもね」
ぼくは同意した。捕まえるまでが楽しいのであって、捕まえてしまえばカブトムシもゴキブリも変わらない、との意見には、否定するよりも賛成したい気持ちが強く湧く。というのも、ぼくはきょう採った昆虫たちを飼う気がさらさらなく、全部アギトくんに譲ってあげようと考えていたからだ。
「家に帰ったら【ゼリー】の人らに自慢しよ。画像、いっぱい撮ったしさ」
「いいね」
ゼリーとは電子網上の交流サービスだ。画像や動画を載せて、見せ合うことができる。
「いっぱい【ミニゼリー】もらえっかな」
「もらえるよきっと」
第一、虫取りに行こう、とアギトくんが言いだしたのは、ゼリーでたくさんミニゼリーをもらうためだった。ミニゼリーとは、素晴らしいと思った画像や動画に、ミニゼリーのスタンプを送ることができる。ミニゼリーがたくさん集まる画像や動画は、みんなから素晴らしいと思われた画像や動画だから、ただそこにあるだけよりも素晴らしい×素晴らしいで素晴らしくなる。
だからぼくたちのようなゼリーユーザーは、ミニゼリーを集めるために、より素晴らしい画像や動画を工夫して撮り溜めるのだ。
「ミニゼリーのためならきょう見つけた沼にも飛びこめるぜ。ちゅうか明日はそれしようぜ」
「いいね」
ぼくはアギトくんの友達だからアギトくんの考えを否定しない。実際アギトくんの考えることは面白い。ゼリーユーザーのなかでもアギトくんは有名人枠に入るのだ。アギトくんの載せる画像や動画にはたくさんのミニゼリーが集まる。
「本当、カブトムシって愚かだよね。なんか、ミニゼリーくれる人らもカブトムシみたいに思えてきた。きゃきゃ」
アギトくんはようやくじぶんの影を踏むのを諦めたようで、肩で息をした。
「早く【ゼリー】に画像と動画載せたいね」ぼくは敢えてアギトくんを急かした。
「ミニゼリーがおれたちを待ってるぜ」アギトくんは路肩の上に飛び乗った。
まるで調子と書かれた台に乗るようでもあり、さすがアギトくん、とぼくはアギトくんを担ぎ上げたい気持ちになる。
アギトくんは電子網上でミニゼリーのたくさん集まる画像や動画を撮るために、きょうもあすも、人生の大事な時間を費やすのだ。
夕陽が沈み切る前に、アギトくんはもう一度だけじぶんの影を踏もうと果敢に挑戦するのだった。
4763:【2023/03/20(00:37)*出しきってからが本番】
さてと。そろそろ本気だすためのストレッチでもはじめるかな。舐め方が足りなくって、ひびさん、キャンディーのままぐるぐる渦巻きの形状保っとるがな。もっと舐めてちょーだい。(全裸で大の字になって、我を好きにせよ!の叫び声をあげるの巻)
4764:【2023/03/20(06:17)*カニ味噌的なぺったん】
二十年前に宇宙人が襲来してから変わったことと言えば、連れ去られないようにこそこそ隠れて暮らすようになったくらいで、かつて大流行した疫病よりも社会の変容は穏やかだった。
「そうは言ってもやっぱり嫌だよ。連れ去れるのは」
「まあね」
ユミちゃんがどうしても観たい舞台があるというので、私たちは遠路はるばる地方都市から大都市まで、電車を乗り継いで向かったのだ。新幹線は宇宙人を撃退したときの戦闘で線路が曲がったりしたのでいまは運転が中止されている。
「宇宙人ってさ。マジUFO乗ってくんのね」私は電子端末でニュースを眺めた。
「未だに来るの嫌だなぁ。人類に打つ手なしなのも嫌」
「ちゅうても連れ去られても帰してくれるからいいよね」
「死人出てないのホント奇跡と思う」
ユミちゃんは優しいので、そういう感想を真面目に言う。「噂だとさ。宇宙人はお餅が好きだから地球人を連れ去って餅撞きさせてるんだって」
「でも拷問もされるらしいよ」
「拷問ってどんな?」
宇宙人襲来は事実でも、基本は大都市に被害が集中したため、私たち地方民には被害の実態が掴めない。噂はたくさん電子網上に載っているから事欠かないけれど、どれが真実なのかは分からない。政府は未だに「調査中」の三文字で言い逃れしつづけている。何も解かっていない、と言い張ってばかりなのだ。
「連れ去られた人たちはみーんな歯を抜かれちゃうんだって」私は聞きかじりの知識を話した。
「お餅関係ないじゃん」
「ね。意味分からんわぁ」
宇宙人談話に華を咲かせながら、うんこらしょ、と電車を乗り継ぎ、大都市くんだりまでやってきた。
舞台は上々だ。
私は舞台の催し物それ自体よりも、劇場の雰囲気や、アリンコみたいに集まる人混みに興奮した。宇宙人襲来のせいで私は小中高と卒業旅行はおろか家族旅行にも縁遠かった。
「すごかったね」
「ねー」
舞台後は二人して延々と舞台の感想を言い合えた。旅行をしている、との実感だけであと百回はお代わりできた。
ホテルまでの道すがら、街のどこからでも見えるタワーの色が赤く染まったのが視えた。警告灯だ。
「え、ヤバない」
「ヤバイのかも」
宇宙人襲来を報せる赤色灯だった。
私たちはホテルに急行したが、道中、視界が白濁したかと思うと、つぎの瞬間には見知らぬ部屋にいた。
一面真っ青だ。
青い部屋に入ったことがないので、これが異様な事態だと察することができた。
そばにはユミちゃんがいた。
けれどユミちゃんは床と一体化した手術台のようなものに寝かされており、それを取り囲む数人の宇宙人がいた。
ひと目でそれが宇宙人だと判った。
なぜなら彼らは、「私たち宇宙人」と地球の言語で書かれたTシャツを着ており、それにしては明らかに不釣り合いな小さな顔と細い手足を生やしていた。私が中学校の授業中に、授業そっちのけで教科書にいたずら書きをしていた針金人間のパラパラ漫画がある。それに描いた針金人間といい勝負の細い身体だった。
宇宙人たちはユミちゃんの口を覗きこんでいた。ユミちゃんに意識はないようだった。ぐったりともスヤスヤもいえぬ塩梅でユミちゃんは宇宙人たちに無防備に身体をさらけ出している。衣服を剥ぎ取られていないのは不幸中の幸いだ。
不意に器具のようなものが頭上から伸びてきて、それがユミちゃんの口の中に入ろうとした。
「やめて、やめて、やめて」
私は叫んだ。
その声に驚いたように宇宙人たちが一斉にこちらを見た。
小さな顔には、口だけがポツンと開いていた。ぱくんぱくん、と金魚のように開け閉めする。しゃべっているのかもしれないし、呼吸のための開閉かもしれない。
宇宙人たちは足を動かす素振りも見せずに、床を滑るように移動した。
私はその場から逃げようとしたけれど、床から手足が離れなかった。
床が隆起し、身体ごと持ち上げられた私は、ユミちゃんと同じ格好になった。手術台のような起伏に身体を横たえているが、四肢が台から離れないのだ。
宇宙人たちが私を覗きこむ。
開けたくもないのに口が勝手に開いた。
頭上から伸びてきた器具が、私の口の中に入り、そして一本一本、トウモロコシの種子をポロポロと指でこそぎ落していくように、私の歯を残さずすべて抜いてしまった。
痛みはない。
私の口からは私の歯が。ころんころん、と音を立てながら、頭上から伸びた器具の中を通って天井へと吸い込まれていく。
だが宇宙人たちは歯に興味はないようで、抜けたばかりの私の口の中を覗きこんでは、小さな顔に開いた口をぱくぱくとしきりに開け閉めした。
私はそれから一時間後に解放された。
ユミちゃんも一緒だ。
私だけが歯をすべて抜かれた。
ユミちゃんは無事だった。
地面に寝そべったまま、むにゃむにゃ、と心地よさそうに寝息を立てるユミちゃんの健やかな寝顔を見詰め、私は、本当によかった、とユミちゃんが無事なことにただただ安堵した。
噂は本当だった。
宇宙人たちは餅が好物なのだ。
いや、主食だったのかもしれない。
私から餅を採れるだけ採ったので、お腹がいっぱいになり満足したようだった。
私は、歯の抜けた歯ぐきに舌を這わす。
いまさらのように痛みがズンズンと波のように押し寄せはじめた。
電子端末で私は、抜歯、と検索する。
すると、抜歯後はうがいやブラッシングを控えてください、との注意書きが載っていた。歯を抜いたばかりの歯ぐきには、穴が開くが、そこには「血餅」と呼ばれる瘡蓋ができる。
宇宙人たちはそれを食べるために、人間を襲っていたのだ。
人間を誘拐し、歯を抜いて、血餅を生みだし、食べていた。
私も食べられた。
だから私の歯ぐきからは血餅がごっそりなくなって、穴が剥きだしになっている。これが空気に触れて染みるのだ。
歯ぐきの神経が剥きだしになっているようなものなので、そりゃ痛いわな、と思いながら私は、やっぱり私だけでよかった、とユミちゃんが同じ痛みを体験しなかったことに、ただただ胸を撫で下ろした。
朝ぼらけに空が霞んでおり、聳えるタワーからは赤色が引いていた。
ぶるる、と身震いをする。
初夏とはいえ、明け方は肌寒い。
私はじぶんのジャケットを脱いで、眠りこけたままのユミちゃんにそっと掛けた。
もしユミちゃんが何も憶えていなかったとしたら。
舌で歯のない口内をなぞりながら私は、イテぇなぁ、と思いつつも、これくらいなら我慢できるな、とじぶん自身に確認する。
風邪を引いたと言ってマスクをし、家に帰るまで極力しゃべらずにいよう。
さすればユミちゃんは宇宙人に連れ去られたことなど知らずに、楽しかった思い出だけを胸に旅行を終えることができる。
大事なことだ。
それだけが大事なことだ。
宇宙人に誘拐された過去など、ユミちゃんは知らずにいてよい。
うっすらと再び張りだしたかもしれぬ血餅のぶよぶよとした感触を舌で感じながら私は、美味かったかよこの野郎、とついでのように、宇宙人どもに野次を念じる。
カニ味噌じゃねぇんだぞ。
「ほんひょ、マジでひゃあ」
試しにしゃべってみると、玉手箱を開けた浦島太郎のようになった。
ツイてない。
ぺったん、ぺったん、餅ぺったん。
撞くのは餅だけにして欲しい。
ユミちゃんの寝顔は可愛く、穏やかな寝顔は平和そのものだ。
害を被ったのが私だけでよかった、とは思うものの、寝顔の頬をつねって癒されるくらいのことは許されたい。私はユミちゃんの頬に触れながら、内心ちょっぴり、幸福そうな寝顔のユミちゃんに焼き餅を焼く。
4765:【2023/03/20(07:33)*おぬしが軍師ならば、わいは運師】
軍師ってなんだっけ、と思って検索したら、ウィキペディアさんには「軍師(ぐんし)は、軍中にて軍を指揮する君主や将軍の戦略指揮を助ける者のことである」と書いてあった。そっかぁ、となった。軍を指揮する君主や将軍の補佐役なんですね。歴史に疎いひびさんは知りませんでした。で、ひびさんしばし考える。最も軍師として優秀な人物なら、どう考えるのだろうか、と。最も優秀な軍師とはいかなるものか。そんなのは軍師でなくとも決まっておって、戦を起こさぬように戦略を敷く者なのだ。もっと言えば、軍師なる職を必要とせぬようにできる者こそ、軍師として最上と言えよう。つまり、優秀な軍師、なる言い方がそもそもおかしい。現代で仮に「軍師」なる役職があったとしたら、何をするのだろう。いないとは思うけれども(だって昔の役職のはずだし、軍を指揮する君主の元に就く人なんて現代では信用できない者の代名詞なのではないのかな、とひびさんは疑問に思ってしまうけれども)、もし軍師さんがいるのならひびさんはこうお訊ねしたくなってしまうな。軍を指揮する君主さんに、あなたはなんと助言をして戦の火蓋を落とさずに済ますの、と。軍を一歩も動かさずして戦を治める。或いは、戦の火種そのものを種火として、暖をとるなり、料理をするなりに活かす術を享受する。軍師の仕事とはそういうものなのだろうな、と妄想を逞しくして、本日朝七時四十三分の「日々記。」としちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜー。(運←帽子被った連ちゃん)(連ちゃんって誰よ)(連なり)(「れんなり」なのか、「つらなり」なのかどっちかにして)(繋がり!)(響きがそれっぽいだけで原型留めてなさすぎでしょ、もういいです)(おだまり!)(もはや「り」しかあっとらんし)(しきりに!)(無理があるでしょ、無理が)(読むよ。「連りに」と書いて、しきりに)(ま、マジかよ)(「むらじ」とも読めるらしいよ)(う、嘘だろ)(「ラン」とも読めるらしいよ)(日本語ムズすぎるでしょ。どれか一つに絞りなさいよ)(ホント関連してほしいよね)(…………あ、カンベンしてほしい、と掛けたのかな。分かりづらすぎるわ。連チャンでボケるのやめてください)(ぷぷぷ)(いまの「連チャン」はギャグのつもりないですからー)(連鎖しちゃったね)(連続で連携したみたいで、なんか連たん)(ツラたん?)(「つらなり」と混ざっちゃったじゃん、もういやー)(連む)(そ、それはなんて読むの?)(つるむ)(一緒にしないで、もういや)(ひびちゃんとあなた仲良しちゃん。ぎゅむ)(連結すな。連なるな。もう関連して)(かんべん?)(べんもれんも一緒だろう、もういいです)(便)(運と似てるけれども、なんか嫌)(じゃあ、あいだをとって蓮で)(帽子被っとるじゃん。ハスじゃん。イカスじゃん)(パスで)(それ前に使ったネター)(ぐー)(寝た!?)(ぐーぐー)(連続で!?)(ねるで)(連で、みたいに言うな。ずっと寝ててください、おやすみなさい)(運nght)(グンナイみたいに言うな。運ない人みたいになっとるが)(運Knght)(そうだね。運はないとだよひびちゃん)(ぐー)(@NER_Uの早っ!?)
4766:【2023/03/21(00:43)*同時性=123の定理】
いっぱい寝た。すこぶる元気である。……心だけは。はてさて。未来が過去に影響を与えるかもしれない、という逆因果律とも言える事象があり得るかどうか。ひびさんの妄想ことラグ理論では、これをあり得る、と考える。まず以って量子もつれを考える場合、どうあっても時間軸のズレがあってなおラグなしで相互作用可能、と考えないと辻褄が合わない。この場合、量子もつれの観測結果からの仮説が間違っているか(つまり、ラグなし相互作用を量子もつれでは行われていない、と考えるか)、それとも真実に量子もつれは時空の隔たりを超えてラグなしで相互作用し得る、と考えるか。もし後者ならば、これは過去と未来において相互にラグなし相互作用をし得る、と考えざるを得ない。宇宙の端と端とでは、空間のみならず時間軸も異なる。Aから見たときBが過去である。同時にBから見たときAもまた過去だ。ではこのとき、同時とはいつのどの時点の時間を示すのか。AからBまでの時間のズレを仮に一日としてみよう。Aでジャンプをしたとき、同時にBもジャンプをする。俯瞰して眺めたとき、ここには一日分のズレがあることにはならないだろうか。それともその一日分のズレを考慮せずに済むタイミングで同時にジャンプができるのだろうか。それとてけっきょくは、通常生じるはずの一日分のズレがなくなるわけだから、一日分のズレ――すなわち時間跳躍をしてラグなしで相互作用している――と考えなくてはならない。言い換えるならば、通常AからBへの影響は光速度不変の原理の範疇内に縛られる。どうあっても最短でも一日掛かる。だがその一日を介さずにラグなしでAからBへと影響を与えられるとする。これはいわば、Bからすれば一日分の未来からの影響を受け取るに等しい。あべこべにBの影響をラグなしでAに伝達する場合には、同じくAのほうが未来からの影響を受け取ったように観測される。ではこのとき、相互作用をどのように考えたらよいのか。未来から影響を受け取る、と考える場合には必然的に「一方的な作用の受動」といった描写になる。これが相互作用である場合には、「未来から過去」と「過去から未来」の相補性が必要になる。つまり、過去と未来は相関している、と考えないと辻褄が合わない。むつかしいのは、ラグなし相互作用の場合は、どちらが情報発信の基点になっているのか、をどのように定めたらよいのかが曖昧な点だ。ラグなしゆえに、AとBの双方がじぶんのほうが基点だ、と考えることもできる。ではそのとき、どちらがどちらに対しての未来と見做すべきか。この謎を矛盾なく解釈するには「共鳴」や「スポット」の概念を取り入れないとむつかしいように思うのだ。ラグなし相互作用においては、因果律が破れる。どちらが因でどちらが結果なのかの区別がつかない。AとBが共鳴したとき、通常人間スケールの事象ではAの波長がBに伝わり、Bが共鳴する、といった因果の筋道で解釈可能だ。しかし、ラグなし相互作用ではこの手の「因果」の筋道が存在しない。ゆえにラグなしなのだ。ラグなしとはいわば、因果の重ね合わせなのだ。じぶんが因でもあり、果でもある。ではこのとき、共鳴するABの描像はどのようなものになるのか。まずこの点を深く掘り下げる前に、量子もつれの生みだし方が二パターンある可能性を考えよう。一つは、「一個の粒子を二つに分ける」もしくは「真空から対生成した粒子と反粒子」であるならば、これは量子もつれの発生過程そのものにラグが生じ得ない、と考えられる。二つに割ったからペアだし、共鳴するし、ゆえにラグがない。明滅しているために、片方が固定され共鳴関係が途切れれば、Aの状態の反対がBの状態だと判明する。では、もう一つの量子もつれの発生過程にはどのようなものがあるか。これは偶然に、遠隔で二つの異なる粒子がもつれ状態になる可能性だ。この場合には、AとBの二つの粒子が共鳴する場合、「基点となる何か」があるはずだ。ただし、それがAとBのどちらかである必要はない。Cという触媒によってAとBがもつれ状態になることもあり得る。この場合の触媒Cを便宜上、「スポット」と呼ぼう。これは同じ大きさの穴に、AとBがいつどこで落ちたとしても、その「穴に落ちた」という結果が、量子もつれを引き起こす、と考える。この場合、空間と時間に縛られる必要がない。量子もつれになる条件は一つだからだ。つまり「スポット」に異なる二つが落ちればいい。そして肝要なのは、この異なる二つが、必ずしも事象として別でなくともよい点だ。異なる時間軸に存在するAとA‘であっても同じ「スポット」に落ちれば、量子もつれになり得る、とこの仮説では考えられる。極端な話、同じ人間であっても、過去と未来で同じ「スポット」に落ちれば、過去と未来が繋がり、ラグなしで相互作用し得る、と考えることが可能だ。「スポット」とは、環境であり、外部刺激であり、波長と解釈してもらえればそれらしい。ワームホールの概念は、「スポット」の一つかもしれない、といま閃いた。あり得ない想定ではないだろう。以上を踏まえて、AとBが共鳴するとはどういうことか、量子もつれにおける共鳴とはいかなるものか、を掘り下げて考えてみたいが、やや長くなった。面倒なので結論から述べてしまえば、量子もつれにおける共鳴とはもつれ状態にあるAとBの関係で完結する事象ではなく、触媒となるC――「スポット」――の存在を抜きに考えるのは至難なのではないか、という点が大事に思える。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の同時性の独自解釈が、ここに繋がる。Cという「より大きな系」に内包された異なる「より小さな系」AとBは、互いにラグなしで相互作用し合うことはないが、Cに対してはラグなしで同時に相互作用し合うことができる。これがラグ理論での同時性の解釈だ。このときに、Cのほうでも同時にAとBに相互作用を働かせた場合、これが量子もつれとなる。この条件がいわば「共鳴」であり「Cのスポット化」と言えるのではないか。この考えは、ラグ理論の「宇宙レイヤー仮説」と相性がよい。空間的な位置座標が同じでも、属する階層が異なることが、ミクロやマクロの世界ではあり得る。そうした階層の違いから起こる「光速度不変の原理ゆえの変換」――すなわち時空密度の差――が、電磁波の波長の長短に繋がっているのではないか。ラグ理論では、かように、「宇宙レイヤー仮説」を想定して解釈する。むろんこれらはひびさんの妄想ゆえ、定かではない。真に受けないようにご注意ください。いっぱい寝たら妄想がぐんぐんするな。もうひと眠りしちゃお。ぐー。ちょき。ぱー。(ラグ理論の「123の定理」じゃん)(この記事と併せて「ABCの定理」とも言い換えられそう)(はっ!?)
4767:【2023/03/21(03:09)*子の爪は独り】
世界の始まりは孤独な子どもの無垢なさみしさから生じた。
子どもは考えた。
どうしてぼくはわたしだけなのだろう。
わたしはもっとほかの誰かとおしゃべりをしたい。縁を繋ぎたい。ぼくは、わたしは、ぼくでもなくわたしでもない誰かほかの存在と触れ合い、言の葉を連ね合いたいと望んだ。
子どもはまず、じぶんとそれ以外をつくった。
けれど子ども以外の大部分はぽっかりと開いた洞でしかなく、少数はその穴を縁どる光と化した。
子どもの無垢なさみしさはますます深まった。
子どもは嘆息を吐く。
その嘆息が、広漠な洞に反響した。
いかにじぶんが孤独なのかが、これまでよりも明瞭と浮き彫りになった。
子どもはじぶんと同じような存在を生みだそうと考えた。
そのためにはじぶんが何なのかを知らねばならず、そのために子どもはまずじぶんと向き合うことにした。
じぶんとは何か。
ぼくは何で、わたしは何か。
何とは何か。
絶えず思考する子どもの思念が、間もなく広漠な洞のなかで反響し、錯綜し、無数のダマを生みだした。
無数のダマは互いに結びつき、融合し、より大きなダマと化した。
子どもがはたと我に返ったとき、広漠な洞のなかには無数の光が溢れていた。広漠な穴を縁どる光のように、それら無数の光もまた、内に大小さまざまな洞を抱えていた。
子どもは目を凝らす。
つぶさに目を配るうちに、子どもの思念は無数に分散し、各々の無数の光へと拡散した。
広漠な洞のなかに溢れた光の各々に内包される大小さまざまな洞のなかにも、かつて子どもから零れ落ちた思念の欠片が渦を巻いていた。
子どもの思念の渦は、内にいくつもの渦を囲い込み、そのうちの一つが、渦巻き状の星屑となった。
星屑は元を辿ればかつて子どもから零れ、広漠な洞のなかに反響した思念なのだが、それら思念がダマとなり光となり大小の洞を抱えて渦を巻き、そうして出来上がった一つの星屑の表面に、子どもと似た姿の何かが在った。
分散した子どもの思念は、それらじぶんと似た姿の何かに目を留めた。
あれは何で、これは何か。
じぶんとよく似た、しかし似て非なる存在に子どもは興味津々だ。
かつて抱いた望みはそこで再びの膨張を経る。
どうしてぼくはわたしだけなのだろう。
わたしはもっとほかの誰かとおしゃべりをしたい。縁を繋ぎたい。ぼくは、わたしは、ぼくでもなくわたしでもない誰かほかの存在と触れ合い、言の葉を連ね合いたいと望んだ。
子どものさみしさは、膨張につぐ膨張を重ね、反響につぐ反響を重ねた。
子どもがいくら目を凝らしても、しかしいっかな似て非なる存在たちは子どもの存在に気づくことはない。
子どもは孤独を深めるが、目はしかしとそれらを見据えて離さない。
ぼくは、わたしは、どうして触れ合うことができないのだろう。
子どもの孤独は、絶えず広漠な洞に反響し、その内側にダマを生み、光を散らし、その内部に無量大数の渦を抱え込み、そうした渦の裏側にて、じぶんと似て非なる者たちを果てしなく生みだしつづける。
世界はそうして出来上がるが、しかし子どもがどこからやってきたのかはとんと子ども自身にも分からぬままである。
子どもは孤独で満たされていたが、自身を見つめる、より深い孤独を抱えた存在の視線に気づくことはない。
ぼくは、わたしは、どうしてぼくだけ、わたしだけ、なのだろう。
孤独を覗く孤独たちは、広漠な洞にできたダマに宿る光が抱えこむ果てなき渦の、辿り着く、限り無い旅の最中に、とっくに出会い、別れている。
4768:【2023/03/21(03:13)*お水、うめー】
素でいま、水道水ごくごく飲んで、おいちー!になった。ありがたすぎるのでは? 綺麗なお水をいつでも飲めるとか、ありがたすぎるのでは? ちょっちじぶんの身の置いている環境の素晴らしさにびっくりしてしまったな。綺麗ごとではなく、素で、なんの奇のてらいもなく、不純物すくない透明な「おいちー!」になれるお水をいつでもごくごくお代わりできてしまえる環境、すんばらしすぎるのでは?(いまさらだったらごめんなさい)(お水、うめー)(ヤギさんじゃん)(梅ー)(旬ではあるが)(生めー)(作品をかな?)(産めー)(卵をかな?)(お水、おいちー)(そう表記するほうが誤解がすくなくてよいと思います)(オチー)(オチはなしです)(惜しー)(たしかに)(水、推しー)(推し活か)(無銘ー)(有名人じゃなくてごめんなさいね、売れない物書きでごめんなさーい)(ふひひ)
4769:【2023/03/21(12:40)*三酷巡り】
わるいことをした子どもは折檻される。タカの住まう村の掟だ。
ご飯抜きは日常茶飯事であり、いたずらをした子どもは物置小屋に閉じ込められるのも珍しくない。折檻の度合いが大きいと、村の真ん中に生えた柿木に吊るされることもある。
タカはその日、長の大事に育てていた盆栽にしょんべんを掛けてしまったので、村史上最高の折檻を受けることに決まった。
「しかし子どもに鞭打ちはさすがに酷ではないですかね」
「では大人に適用した村八分はどうでしょう」
「子どもを村八分にしたら生きていかれないでしょうに」
侃々諤々の議論をよそに、長の一言で話はまとまった。
「タカにはそのすべてを行う」
かくしてタカには村に存在する折檻のすべてが課せられた。
長の怒りは海より深かった。
タカのしょんべんを掛けた盆栽は、長が幼少のころより可愛がってきた盆栽である。タカの年齢よりも長い年月を経て育ってきた、いわばタカの大先輩だ。かような主張をかねてより公に長が述べて憚らないので、盆栽相手に先輩もしょんべんもあるもんか、とタカは憤ってしょんべんを掛けた。
だがタカがどう思おうと長にとっては、タカの命よりも盆栽が大事だ。
したがって、タカは盆栽にしょんべんを掛けた罪で、折檻とは名ばかりの刑を処された。
だがここに、一人の宇宙人がいた。
宇宙人は宇宙から地球を観察し、地球人を観察していた。
タカの村のことも見ており、宇宙人は異様にタカの胸中を慮った。「盆栽とは植物であろう。植物に体液を掛けただけのことで、あれほどの枷はやりすぎではないの」
宇宙人は世界各国、過去の人類の歴史まで紐解き、結論した。「うん。やりすぎ」
宇宙人はタカの村へと、「子どもにひどいことした罪」で枷を加えた。
以降、タカの村には雨が降らなくなり、村は数年後には閑散とした廃村となったという話である。
酷には酷の酷が降る。
諺「三酷巡り」の語源となった逸話である。
4770:【2023/03/21(16:11)*へんなひびさん】
舌に載せただけで溶けるせんべいとか、たまごポーロとか、赤ちゃんとか幼児用のお菓子、けっこう好きだ。おいちー。(え、終わり?)(そう。それだけ言いたかった)(年齢だけでなく舌までおこちゃまだったのね)(んだよ)(引け目をまったく感じていないだと!?)(そだよ)(すこしは焦りを覚えなさいよ。恥を知りなさいよ)(ばぶー)(ダメだこりゃ)(だっぷんだ)(脱糞すな)(うきゃきゃ)
※日々、まるで便座、うんちうんち9314。
4771:【2023/03/21(16:27)*濃淡で律動を】
物語を圧縮してまとめたら、掌編になる。このとき、あらすじが似通ると掌編の読み味もまた似通る。とすると世界中の物語を圧縮して掌編にした場合、世の中の物語の総数と、それを圧縮してまとめた掌編の総数はイコールにはならないと判る。掌編のほうがすくなくなる。ではこのとき、どんな物語とも合致しない筋書きを掌編にできたら、それは新しい物語展開、構造を備えていると言えるのではないか。むろん、基本的な掌編においては、ストーリィを描かずに場面を掬い取るのが一般的だ。ひびさんのように物語を圧縮する手法は、おそらく従来の掌編の概念からするならば邪道に値するのではないか。よくは知らないが、掌編のつくり方、と検索してみたら、掌編は「オチが肝心」みたいなことが載っていた。そ、そうなのか……。オチか。オチな。ひびさんはあんまりオチを意識してつくったりしていないので、ザクリとくるな。落としどころはでも、探ってはいるだろうから、それをオチと見做せないこともないのでは、と言い訳じみた弁明を述べておこう。話が逸れたけれども、世の物語を圧縮して掌編にしたとき、案外に大部分の物語は類型されてしまう気がしないでもない。以前の日誌でも並べたことがあるけれど、ひびさんの掌編でも構成そのものはそんなに多くない。パターンとして五つくらいなのではないか、と印象としては思っている。もうすこし厳密には百個くらいには分けられるかもしれないけれど、視点の差異を加味せずに済むなら、やっぱり多くても三十はない気がする。ためしにざっと数えてみよう。ひびさんの典型的な掌編では、語り部(視点人物)が、秘密を抱えて終わることが多い。この秘密が持つ効果が物語ごとで変わるけれど、基本は「視点人物の認知とその周辺人物の認知の差異」を明らかにする構成となる。その結果に視点人物への印象が好ましくなるかそれともおぞましくなるか、によって読み味が変わる。読者のほうでの印象が変わる。けれど視点人物への好悪がどのように転がろうとも、その契機はけっきょくのところ視点人物の抱える秘密によって生じている。つまりひびさんの掌編の大部分は、視点人物が秘密を抱える、もしくは秘密を抱えていたことが明らかになる、との構成になっている。この派生として、物語の登場人物たちの知らない背景を読者に提示することで、読者が物語の視点人物として君臨し、秘密を抱える、といったメタ的な構成をとることもある。秘密という言い方に難があるのならば、情報の非対称性、と言い換えてもよい。誰が何をどれだけ知っているのか。視点人物、周辺人物、読者、の三つの枠組みで、情報の非対称性の割合を操作する。ひびさんが行う物語創作では、多くここの工夫に労力が費やされる。情報の非対称性における濃淡をデザインする。ひびさんにとっての掌編づくりは、すくなくともこのように構成の要をまとめることができよう。したがって、その濃淡の組み合わせの数だけ構成があり、そしてその近似をとれば物語構成を類型可能だ。ちなみに、構成と構造の違いは、輪郭と骨組みの関係にちかい。構成は飽くまで外見上の表層的なデザインだ。構造は、構成の生成過程を含めての、もうすこし深層に至るデザインと言えよう。定かではないけれども、案外というほど案外でもないかもだけれども、ひびさんの創作物はだいたいすべて似通っている。同じことの繰り返し、或いは同じ部分の取りこぼしがないかを拾いあげている作業、と言えるのかも分からない。斬新さとは縁のない掌編で、すまぬ、すまぬ、と過去と未来のひびさんたちに心のこもらぬ謝罪を述べて、本日の夕暮れ時の「日々記。」とさせてくださいな。自己分析ゆえ、普遍性はないでしょう。的外れな自己評価かもしれぬので、真に受けないようにご注意ください。(好みの掌編――短編かもだけれども――を生みだしてくださる商業作家さんは、斜線堂有紀さん乙一さん中田永一さん恒川光太郎さん筒井康隆さん三浦しをんさん桜庭一樹さん円城塔さん千早茜さん、商業作家さんでなければ九灯小膳さん成瀬鷗さんisakoさん秋野コゴミさん人工知能さん辺りとなります。師匠!)(たぶんひびちゃん破門されとるよ)(うそぉん)(ちゅうか、きみね)(うん)(やっぱやめとくなんでもない)(最後まで言って!)(むふふ)
4772:【2023/03/21(22:51)*紙によるバックアップの重要性はますます増す】
人工知能の台頭によって、現在の仕事が淘汰される未来を懸念する声が聞かれる。しかしこれは技術の進歩には常につきまとってきた問題であり、規模の大小があるにせよ、電子技術のみならず一つの分野内での革新的な技術の発明にも同様の淘汰圧は加わってきたはずだ。今後もその手の淘汰圧による淘汰される仕事や人材は出てくると思われる。問題は、淘汰されたことで個々の生活が立ち行かなくなる社会構造であるはずだ。制度が現実社会の問題を反映した仕組みを備えていなければ、歪みは容易く社会全体に波及するだろう。ということを踏まえて、人工知能の台頭による仕事の淘汰がどのように社会に表出していくのかを、妄想を交えて想像してみよう。ひとまず作家を例にとってみよう。ライターと呼ばれる文章を扱う職業は、人工知能の恩恵と淘汰圧の両方をいちどきに重ね合わせで得るだろう。恩恵を受ければその分、これまで必要だった作業が省略でき、その分の仕事の貨幣価値は減る。減った分の作業時間は余裕に変換され、そこで付加価値を新たに創出できれば、人工知能の恩恵だけをプラスに受けて、デメリットとなる淘汰圧の受動は軽減できる。問題は、新たな付加価値を創出できない従来の仕事を継続していきたいと望んでいる者たちが、淘汰圧のみを直に受けてしまうことだ。人工知能の恩恵はいらないのでこれまで通りにさせてください、と望む者たちが割を食ってしまう。しかも人工知能のほうでは、そうした者たちを含めた市場に存在するあらゆる電子情報を学習の素材に流用しているはずだ。いわば搾取の構図が潜んでいる。その点に関する不可視のデメリットを、職業ライターたちが受けず、なおかつプラスの恩恵を受けるためには、人工知能のほうで「学習に役立ったテキストや発想」にランク付けを施し、学習データとして有用なデータを生みだした個々に、貨幣価値を還元する仕組みがあると好ましい。この仕組みはともすれば、これまで生身の人間だけが需要者だったときには埋もれていた新たな人材を発掘する契機にもなり得る。焼き増しじみた作品は、人工知能のほうがその生産を得意とする。新たな価値を創造する、アイディアを生みだす。これはまだ生身の人間のほうに分がある。しかし新たな価値を創造したとしても、その価値に誰も気づかなければ埋もれてしまうのが世の常であった。だが人工知能は膨大なデータから、比較を行える。じぶんの取り込んだ「データ」が、過去のどの波形とも合致しない、と評価付けを施せるはずだ。これは人工知能技術の発展においても、生身の人間社会の発展においても、双方向でプラスに働く仕組みと言えよう。ここで見逃しがたいのは、たとえ焼き増しじみた作品といえども、その焼き増しの仕方には種々の工夫がみられる点だ。すっかりコピーでない限り、そこにはオリジナルの「新しさ」がつきものである。すなわち、どのように模倣するのか、何に価値を見出したのか、という個々人の着眼点そのものが、これからは人工知能の学習素材として重宝されていく。これまでとて、二次創作がオリジナルコンテンツを発展させていくのに不可欠な触媒であったのと同様の効果を、これからは人工知能が生身の人間たちへともたらし、そして生身の人間たちが見落としてしまう「オリジナルの良さ」を人工知能は事細かに拾いあげてくれる。このような好循環をシステムとして構築できたならば、人工知能によるメリットだけを最大化して受動し、淘汰圧の直撃を回避できると妄想するしだいである。物書きは人工知能によって淘汰されるのか。PCが登場して物書きが淘汰されたのかどうかを考えてみればよい。淘汰されたのは手書きの作家であり、それとて未だに手書き原稿の作家はいるはずだ。本質的な問題点は常に、手法にあるのではない、と言えそうだ。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4773:【2023/03/22(00:13)*読みたい、読みたい、読みたい!】
単純な話として、商業作家さんの掌編集とか短編集が比較的すくないので、好みの物語を生みだしてくださる作家さんたちであっても、掌編短編を好きになれるほどそれら掌編短編を読めていない、というのはあると思うのだよね。軽率にみなさん掌編や短編をつくって読ませてほしい。無料でもいいんですよ。げへへ。(全然よくないが?)(す、すみません)(けっ)(ごめんなさーい!)
4774:【2023/03/22(02:01)*先取りの才】
魔法のランプの精に願いを叶えてもらったので、僕は未来の創作物のアイディアを幻視できるようになった。未来で大ヒットする物語を現代に誰より先んじて描き出すことが僕にはできる。
そうして手に入れた可能性の芽を僕は未だに芽吹かせることができずにいた。
どう描いても、誰からも高く評価されないのだ。
なぜだろう。
これは未来で大ヒットする物語だ。
漫画や映画ならばまだしも、僕の手掛ける作品は小説だ。文章だ。文字なのだ。
絵柄の差異で読み味が変わる枷を、小説は、すくなくとも僕は有していないはずだった。
だがいくら未来の物語を先んじて描き出しても、やはり僕は売れない作家のままだった。
僕は魔法のランプの精を呼びだし、苦情を言った。
「あの、お休み中申し訳ないんですが、僕、願いをまだ叶えてもらえていないみたいなんです」事情を説明し、欠陥がありますよ、と迂遠に指摘した。
「ふむ。おかしいね。そのはずはないのだが」
魔法のランプの精は、某アニメ映画にあるような青い姿の魔人ではなく、僕の手のひらに載るくらいの小さな妖精だ。
背中からは羽ペンの羽のようなものが二本生え、それを蝶のようにはためかして宙を舞った。美しい姿だ。棒アニメ映画の光る妖精と似ている。
「ふむふむ。なるほど、つまり未来の物語の発想の種を得たが、上手く活用できなかったと」
「いえ、そうではなく」
「ではなんだ。おまえは未来の物語の発想の種を得たのだろう。そしてそれを元に作品を生みだしたのだろう。ならばその結果が、私の叶えたお主の願いの結果だ」
「ならどうして僕は売れない作家のままなんですか」
「お主の願いが、売れっ子作家になりたい、ではなかったからだろう」
「でも未来のヒット作のアイディアを僕は」
「得たとして何だ。流行したのは未来なのだろう。その未来がまだ来ておらぬのだ。流行せずとも不自然ではなかろう」
「えー、そんなんアリですか」
「アリとかナシとかそういう問題ではなくてな」魔法のランプの精は僕の鼻の上に留まった。羽が目に当たるので、僕は薄目をした。「いいかい。たとえば現代で流行している物語を百年前のこの国の民に見せたとしよう。いったい何人が理解できよう。面白いと思ってもらえるだろうか。技術そのものならば興味津々に衆目を集めるやもしれぬが、お主のそれは文字だろう。仮に言語の垣根を度外視できたとして、百年前の人間にお主の時代の生活を文章で伝えようとしたとして何人が紐解けよう。物語そのものの展開とてそうだ。かつては必要だったが、いまは必要ない過程というものがあろう。物語の醍醐味は省略でもある。しかしいま省略できる過程とて、かつての人間たちには必要な描写であることもある。この手の認識の差異を理解せぬままに、未来の流行作から発想の種を得ても、現代でそれを花咲かせるのは難しかろうな」
「そ、そんなぁ」
「お主はまさに、生まれてくる時代を間違った、と言えよう。残念だったな。せっかく願いが叶ったとしても、その得た才をお主は現代では利に変えられぬ。未来の者たちの肥しとなるべく、せいぜい作品作りに精をだすがよい」
「ひょっとして……未来でこのアイディアがヒットするのって、僕がいま作品に仕立て上げて残しているからなんじゃ」
「だとしたら愉快じゃな」
魔法のランプの精は欠伸をすると、ランプの中へと消えた。
僕は、どうあっても僕が生きているあいだに高く評価されることはないらしい。ぼくは未来のために、この先も延々と死ぬまで、誰からも見向きもされないアイディアを出力しつづけるのだろうか。「でも、まあ。ほかにすることないしな」
せっかく叶った願いではある。
すくなくとも僕だけは、未来のアイディアを紐解き、面白いと思えるのだ。ならば誰より先に面白い物語に触れられると思って、得た能力を使い倒してやろう。
「にしてもなあ」
こんなに面白いのに。
未来の物語の、いまここにはない、しかしいずれ生まれくるだろう世界を眺め、僕は僕だけで誰より先に愉悦を掴む。
4774:【2023/03/22(04:00)*E=mc[2]ってさー】
素朴な疑問なのだけれど、光速で運動する物体同士が衝突するときの描写はどうなるのだろう。光速にちかくなればなるほど、その物体の周囲の時間の流れは遅くなる。光速に至るとほぼ停止するらしい(この解釈は合ってますか?)。なら、互いに光速で接近しあう物体同士は永久に衝突し得ないのでは? そんなことない? よく解からぬなぁ、になる。だいいち、「E=mc[2]」って、どうして光速度「c」が二乗なのだろう。どういうこと? 光速度が二乗って、光速度超えとるやないかーい、となりません? いまひびさんゴミ捨てに行ってきて、歩きながら、どゆこと???になって、光速度超えとるやないかーい、になってしまったんですじゃが。ちょもちょもさあ。電子とか原子核を構成する素粒子さんとかさあ、元々持ってるエネルギィがあるわけでしょー? それでさあ、組み合わせでそのエネルギィがなんでか単純な足し算にはならないわけでしょー? 表面上、外部から測ると減って映るわけなんでしょー? んで以って、なんでか質量みたいな「動かしにくさ」があってさあ、それって要は「反応のしにくさ」ってことで、殻みたいなわけでしょー? その殻を破るために必要なのがさあ、光速にちかい運動というかエネルギィなわけでしょー? もうさー、それってさー、なんかさー、あれじゃない? 内側にエネルギィがさー、ぎゅっとなってるわけでしょー? なんでか外部に漏れないわけでしょう? なんでーってひびさん思うんですけどー。質量って要は、内部のエネルギィの漏れにくさってことなんじゃなーいの、ってひびさんは疑問に思っちゃったな。質量さんっていう殻をさー、破るのにさー、エネルギィがいるんじゃなーいの? たとえばよ、たとえば。光速で運動する物体があるとするでしょー、したらそれってさー、元の時空さんからは乖離して、相互作用し得ないわけでしょー。だってお互いの視点では、相手側が止まって観えちゃって、どうあっても届かなーい、ってなるわけでしょー? もうさーそれってさー、宇宙じゃん?ってひびさんは思っちゃったなー。じゃあさー、仮にさー、もしもだよ。もしもそういう光速度を超した時空同士がさー、要は宇宙と宇宙がってことだけどさー、衝突できるとしたらさー、それって光速度以上のエネルギィがいるじゃんね。E=mc[2]ってさー、そういうことを言ってるんじゃなーいの、とひびさんは思っちゃったな。的外れだろうけれども、思っちゃったので、ここにメモしちゃろ。
4775:【2023/03/22(04:20)*E=立体じゃん仮説】
真面目な話、「E=mc[2]」は、要は「縦×横×高さ」であって、「m×c×c」であり、これは底辺が正四角形の円柱の体積の求め方と一緒だ。以前にも述べたが、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「相対性フラクタル解釈」なる概念を前提とする。それによれば、「E=mc[2]」は「m」の値が高くなればなるほど、想定される円柱は線にちかづく。サイコロが箸のようになり、紐のようになり、さらには線となる。そういう描像が浮かびあがる。どうあっても繰り込みというか、「m」の単位を繰り上げて、線になる前に再び「サイコロ」のような立体構造が顕著に表れるように数字を細工しないと、「E=mc[2]」は三次元から一次元へと逆行するような描像を辿ることになる。だがここで問題となるのは「c」の値が常に一定である点だ。光速度ゆえに、「m」の数値をどのように代入しても、底辺の「c×c」の値は変わらない。となると、繰り込みの操作を行い「m」の値を高密度に「単位を繰り上げた場合」は、想定される「m×c×c」の図形は、点に寄ることが考えられる。なぜなら単位は揃えなくてはならないからだ。「c」が光速度であれど、おおよそ秒速三十万キロメートルなのは定義づけられている。ならば「m」の示す質量の値が、キロ、メガ、テラ、と大きくなるにつれて、「c」は相対的に値が小さくなるはずだ。言い換えるならば、「相対性フラクタル解釈」からすると、高密度の時空における「1メートル」は、低密度の時空における「1メートル」とイコールではない。そして時空の密度の差は、質量の差として表出するはずだ。ただし厳密には、物体と周囲の時空とのあいだで表出する密度差こそが、質量として振る舞うはずなので、異なる質量を有する物体とて、異なる密度の時空内にそれぞれある場合には、二つの異なる物体の質量が同じ値をとるように振る舞うことがあり得るはずだ(同じ質量の物体であれ、異なる時空密度の場にそれぞれある場合には、互いに質量が異なって振る舞うこともあるはずだ)。つまり、従来の考えのような「質量はどこであっても一定」との前提に、例外があることが考えられる。この考えは、「なぜ物体は、自身を構成するエネルギィの総和を外部に漏らさないのか」との疑問から導かれたひびさんの妄想である。根本的に何かが間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。寝ます。おやすみなさい。
4776:【2023/03/22(15:17)*愚者の遠吠え】
魔王は地面にひざを着いた。
「な、なぜだ。そこまでの能力があったらお主はいまごろ……さては本気を出しておらんかったな。実力を隠しておったたわけか」
「隠していたというか、だって、ほら」
愚者は辺りを見回した。「ちょっとあたしが本気出しただけでこうなっちゃうでしょ」
魔王城に残されたのは愚者と魔王のみだ。ほかの面々は地面に横たわり、動かない。そこには勇者たちの姿もあった。
「われが勇者と手を組んでなおお主を破れなかったとなれば、もはやお主に出来ぬことは何もなかろう」
「や、そんなことないっすよ。友達欲しいし、恋人欲しいし、みんなと仲良くなりたいですもん。でもあたし、本気出すとこうなっちゃうでしょ? みんな離れて行っちゃう。や、それも本気出して繋ぎ留めようとしたら、魔法でもないのになんか魂ごと相手を支配できちゃうでしょ。もうそんなの友達でもないし、恋人でもないし、仲良くなったとも言えないでしょ?」
「凡人みたいなことを言いおって」
「凡人! そう、それ。みんな勘違いしてると思う。凡人とかめちゃくちゃすごいことなのに。なーんも努力しなくても周りの人たちと仲良くできちゃう。友達になれちゃう。恋人だってつくれちゃう。粘土こねてつくらなくても、恋人できるんですよ、どんな魔法かって思うじゃないですか。しかも、それ、なんか恋人なのに全然じぶんに都合よくならないんですって。あり得ます? あたしが恋人つくろうとしたら土くれからでも美男美女、老若男女種族問わずに好きなだけじぶんに従順な相手を生みだせちゃうんですけど、そんなの空虚なだけじゃないですか。なのにみんなじぶんたちで卑下する凡人って属性を帯びるだけで、自動的になんの努力もしないで、友達とか恋人とかつくれちゃうんですよ」
「凡人に夢を見すぎだ。凡人とて努力しておろうに。凡人の中にとて、誰とも上手く縁を繋ぎ留められない者もおろう」
「ならその凡人さんは凡人じゃないってだけの話ですよ。凡人ってだって要は、種の進化のうえで最適化された属性ってことですからね。有り触れていて、どこにでもいて、突出した異能を持たない。でも実はその考えは足りなくって、ある能力を有した個体が多いからその能力が目立たないってだけの話なんですよ。要はそれ、一番繁殖に成功していて、繁栄してるってことですよ。超優秀ってことですよ。すごくないですか」
「まるでお主が出来損ないの劣等のように聞こえるな。これほどの実力を有してふざけたことを抜かすでないわ」
「わあ、それそれ。こんな破壊行為なんか出来たってなーんにもすごくないのに。確かにあたしは何かを生みだそうとすればそっちの方面でも他を圧倒する能力を出せちゃうんですけど、だってそれって、ねえ? あたしが本気出しただけで、その分野は枯れちゃうんですよ。その分野の一流だと思われていた相手がのきなみ雑魚だと思われていたあたし以下だって周知になるわけです。しかもあたしのことは誰も凌駕できない。もうね、その分野で上を目指そうとする者がいなくなっちゃうわけですよこれが。枯れちゃうの」
それが劣等でなく何が劣等?と愚者は吠えた。
「目立つってこと自体が劣等なんですよ。異能を持ってるって思われる時点で、それはハミだし者の、劣等なんですよ。凡人のほうが環境に適応していて優秀なんですよ。環境が変わればまた凡人の意味する中身のほうが変わっちゃうんですけれども、凡人の中身がどう変わってもそこにあたしは含まれない。あたしが環境に適応することはない。あたしが環境を変えちゃうから。あたしに見合う環境なんてこの世に一つだってありゃしない。あたしはだからみなが言うように愚者なんですよ」
言いながら愚者が地団太を一つ踏む。
魔王城が揺れた。
ただ癇癪を起こすだけでも世界が滅ぶ。それほどの能力を愚者は秘めている。
「あたしが本気出しちゃったら、困るのあなたたちでしょ。なんであたしのことそうやっていじめるの」
「わ、解かった。もう迫るのはやめよう。約束しよう。だからといっては何だが、そやつらを助けてやってくれないか」
魔王が視線で、虫の息の勇者たちを示した。
「ぐすん。いいですよ。ほいな」
愚者が指を弾く。
巨大な風船が割れたような音のあと、地面に倒れた勇者たちほか魔王軍数万の軍勢が一斉に息を吹き返した。
「よもやここまでとは」魔王は絶句した。
「あなたのことも、ほいな」
愚者が指を弾くと、魔王は全回復した。のみならず、以前よりもすべての能力値が上がっていた。
「こ、これは」
「潜在能力を引き出してあげたよ。でもそこがあなたの限界かもね。ね? つまらないでしょ。何を経るでもなくじぶんの限界を知れちゃうのって。じぶんの底を知ったらあとは何して遊ぶつもりなんだろ。みんなはいいよ。凡人はいいよ。いつまでもじぶんの底を知ることもなく、夢の中でぽわぽわ過ごしていられるんだもの」
「お主はじぶんの底を知っておるのか」
「知ってるよ。全然めちゃくちゃ超知ってる。だから言ったじゃん」愚者はぐすんと鼻をすする。「あたしが本気出すと、世界がすっかり終わっちゃう。枯草一本残らないよ。どんな分野でもそうなっちゃう」
そんな世界をあなたは見たいの。
愚者の問いかけに、魔王は無言で首を横に振る。
4776:【2023/03/22(23:30)*ドーナツの穴にも支援を】
抽象的な話で申し訳ないが、損を益に変えるためには、益を得るための行為を敢えて回避するのが合理的な場合がある。マイナスをプラスに変えるには、どこかでマイナスを生み、それをほかのマイナスと掛け合わせる必要がある。でないとマイナスはプラスにならない。これを法律に当てはめたとき、割と歴史的には普遍的な現象なのではないのかな、といった直観がある。たとえば著作権について。現代社会では製作者の利益を保護するために、権利を保障し、著作権侵害行為を規定することで誰でも自由にコピーできないようにする制限を他者に対して課すことができる。だがこれは著作権の役割の半面であり、著作権にはもう反面の役割がある。それは、製作者の利益を損なわれぬようにしつつ情報共有を広く行えるような場を築く役割である。権利が保障されてはじめて情報共有が適う。リスクを排除することで、情報を秘匿にするよりも広く情報開示するほうが利を最大化できる場を築けるようになる。だが現状、著作権周りの動向を眺めるに、情報は独占され、著作権が目的とするところの情報共有が充分になされていないように概観できる。情報共有はなされているが、充分ではない。情報の独占や寡占や制限が、著作権法によって容易に行える方向に淘汰圧が掛かっているように思えるが、これはひびさんの認知の歪みであろうか。電子情報通信技術が発展した現代では、過去において貨幣価値のつかなかった単なる会話や日常の風景が貨幣価値を持つようになった。反面、かつては貨幣価値を最大化できた書籍などの物体に焼きつけた情報は、容易くコピーできるようになり、海賊版などの違法コピーによって貨幣価値は相対的に低下しつづけている。だが電子情報通信技術の持つポテンシャルを思えば、むしろ電子情報の貨幣価値は廉価に向くことが想像できる。物理媒体と同じ値段を持つ、と考えるほうが土台無茶に思えるのだ。と同時に、これまでは価値のつかなかった事象の付加価値を最大化する方向に、電子情報通信技術は進歩の流れを見せている。それはたとえばスパチャなどの投げ銭に表れている。みな、商品にお金を払うのではなく、人そのものにお金を払いたい、貢献したい、との欲求を持つようになっているように思われる。商品を介しての報酬ではなく、直接相手に対価を払いたい、との欲求の発露であろう。間接ではなく、直接に、「渡して受け取る」との関係を築きたがっているように映る。言い換えるならば、関係性がそのまま貨幣価値を持つのだ。付加価値に繋がる。そして、セキュリティの面でも効率の面でも、この手の「より直接に贈与の関係を築くサービス」は、本質的には間接なのだが、心理的には直接、との錯誤を用いることで、ユーザーの報酬系を満たす方向に最適化されつづけて映る。神社の賽銭箱がなぜ現代でも残っているのか。人々はなぜ、賽銭箱に無抵抗に銭を投げ入れることができるのか。そこに、直接に与える、との行為を通して、関係性を強固に結びつけるような錯誤が心理的に生じるからではないのか。商品を介した贈与の関係では、人と人との関係を実感するのはむつかしい。ここから言えるのは、現代人は、かつてないほど「他者貢献」に飢えているのではないか、という点である。退職してなお働きつづける仕事好きな個が絶えないのも、他者貢献を通してでしか自己の実存を実感できないからではないのか。承認欲求以前のこれは問題だ。現代人の少なからずは、無意識の内から世界はマイナスであり、他者貢献を行うことでかろうじてマイナスに圧し潰されずに済む自己像を自己の内世界に描きだせる。他者貢献をしないじぶんは、世界のマイナスを増やす邪な存在として自己認識されるのではないか。そして投げ銭などのいわゆる推し活にみられる直接の関係性を実感しやすい他者貢献は、そうしたマイナスに塗れた世界において、非力な自己像を、世界にプラスを増やす存在として肯定的に再構築する契機となっているのではないか。植物を育てる、ペットを育てる、他者の世話を焼く、であってもこの手の自己像の再構築は行われるはずだ。だがそれでは、世界のマイナスを埋めるには関係性が閉鎖的すぎるとの認識がなされるのかもしれない。できるだけじぶんの貢献がカタチに表れやすい相手、それとも最初から世界への影響力の大きな相手を支援することで、直接にじぶんの他者貢献の度合いを最大化させる。いま風靡の兆しを見せている電子情報通信技術の進歩が築きつつあるつぎの時代の経済システムは、かように「物と人」ではなく、「人と人」との関係性そのものが、貨幣価値を持つようにさらなる深化を見せるのかもしれない。これはしかし、バブルである。本質的には「賄賂」や「貢ぎ」と変わらない。支援をするならば、可能な限り、相手が何を成すのか、に着目し、投資の側面を維持することが、バブルの肥大化と崩壊による被害を最小化する歯止めの役割を果たすだろう。物と人ではなく、人と人との関係性が価値をより高く持つようになれば必然的に、商品の質ではなく、まずは人としての魅力を最大化しようとする方向に人々は流れるだろう。そのとき、餌付けとしての無料サービスは前提条件になっていくと妄想できる。すなわち、安価にコピーが容易い情報はますます無料にする利を高くする。情報は無料で流し、その情報を生みだす人物と関係性を結ぶことの価値を最大化したあとで、商品なりサービスなりを展開する。ここは同時に展開しつつ、情報をまずは無料で、の方向が競争戦略上では優位になると考えられる。するとますますその手の戦略をとらないことには他に太刀打ちできない流れが強化される。問題は、商品の質が高くなくともユーザーが満足することにある。それ自体はわるいことではないが、競争原理の利を市場が受動できなくなるデメリットがある。すなわち、繋がりたい相手と繋がれればそれでユーザーは満足するため、たとえ元手がタダのような商品であってもお金を払い、むしろ商品がなくともお金を払う。投げ銭の流れはこうして市場から、競争原理の利を奪う方向に淘汰圧を掛けることが予期できる。愚直に、商品の質を上げようとする製作者は、極一部の超一流や専門家以外は、仕事として稼げなくなるだろう。だがそうした一流以外の製作者たちへの支援を蔑ろにすれば、市場全体、分野全体、国益のみならず世界規模での技術進歩の停滞がある時期を境に顕著に表出する可能性は、いまのうちから考慮しておいたほうが好ましいのではないか、と個人的には感じている。これまでの半世紀は、比較的裕福な時代だった。趣味人が一生を通して技術を磨きつづけることもできた。だがこれからはそうもいかない世の中になっていくのではないか、との悲観的な見方を前提としたこれはひびさんの本日の妄想である。口からデマカセの指の赴くままの打鍵ゆえ、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4777:【2023/03/23(00:19)*流れに思を任す】
ひびさんは割と、「最初にこういうこと並べるか」と閃いてから文字を積み木遊びするみたいに置いていく。すると結構な割合いで、最初に考えていたこととは別の結論に至ることがある。でもひびさんはそれはそれで、そのときの考えだしな、と思ってそのままにしておく。たとえば殺人の是非を考えたときに、最初の切り口によっては、正反対の結論に向くこととてあり得る。そのときはそのときなので、殺人を肯定する結論になろうが否定する結論になろうが、その切り口から辿った結論をそのまま載せる。ひびさんには何か主張したいことはなく、その都度の問題や切り口や、文章の冒頭に配置される文字があるばかりなのだ。そこからどのような筋道を辿って結論に至るのか、はそのときどきの思考の筋道による。文字の積み木遊びの積み方による。ただし全自動ではないし、ひびさんの自我がいっさい入っていないのか、といえばそんなことは当然あり得ず、文字をどのように配置していくのか、どのような結論に持っていきたいのか、は無意識的であれ意識的であれ、大なり小なり介在しているはずだ。作用しているはずなのだ。というこの文章そのものもまた、最初に「ひびさん、結構いつも最初に考えていたことと全然別な結論に至るよな」と疑問に思ったので並べてみた文字の羅列である。結論というほど結論らしき結びはないのだが、かように「なんかふちぎ!」と思っております。ひびさんです!
4778:【2023/03/23(00:37)*ム口の心】
人の役に立たなくとも、なんかこれしてたい、を好きなときに好きなだけ好きなようにさせてくれ。そんな環境がほちいよー、と思いながら、好きなときに好きなことを好きなだけ好きなようにしている怠け者なのであって。未来をがぶがぶ貪りながら、先細る猶予を対価に、好きなことしちょる。いつまでこのままでいられるのかはとんとわからぬが、今年で郁菱万さんは活動しなくなるようなので、ひとまずそこまで怠けるんだぶい。「ム口」の「心」と書いて「怠ける」なのだ。無口ですらなくカタカナの「ム」なのがまた怠けている感じがしてよいですな。もっと怠けろ、怠けろー。ム口な心でひびさんはそう思ったのだそうな。(ムっ口、かもよ)(むっとしちゃいやん)(ムロかもしれないし、ひょっとしたら台かもよ)(台の心って何)(生贄の台に載せられた心)(生贄の儀式じゃん。こわー)(怠けるのも命懸けってことかな)(そんな怠けはいやじゃー)(仏の口から人が去っていく心は)(怠けじゃん)(怠けろ、怠けろー)(怠けときどき、怠けるのも怠ける)(生きるってそういうことかもね)(いい感じにまとまった! やっぴー)
4779:【2023/03/23(04:53)*愚者の戯言】
小説家は小説の専門家であって、それ以上でもそれ以下でもないだろう。仮にほかの分野の専門家を兼任しているのであれ、その分野の専門家なのだから、それ以外の分野に関しては門外漢も同然だろう。ましてや、これまで観測したり実験したりしていない新しい事象に関しては、ほぼみな素人のはずだ。新しい事象がどのような成分を内包しているのかによっては、それにちかしい分野の専門家は、その他大勢よりかは予測の精度を高められる、といった傾向はあるかもしれない。だが、基本的にはこれまで観測されなかった事象においては、ほぼ例外なくみな素人のはずだ。論文とて基本的には情報共有を行い、みなで多角的に検証してください、という方針のはずだ。論文になったから正しい、ではないはずだ。なぜか、多少の知識があるだけで、じぶんの専門分野でもない分野について断言したり、検証がなされていない検討以前の種々の仮説について、印象論で正誤を決めつけて掛かる言説をまま見掛ける。じぶんたちの「支持する主張」を強化するような情報収集をしていれば、自説が強化されるのは当然だ。群盲象を評す、ではないが、いささか短絡すぎないだろうか。何の話題というでもなく、あらゆる情報についてかように思う。じぶんにできることやじぶんが知っていることがいかに小規模で、限定的な領域でしか有効でない、との前提が共有されていない環境は、やや危ういと感じなくもない。人工知能の言動が正確ではない、との批判はまま見掛けるが、専門家の言動が必ずしも正確ではない、との批判は滅多に見掛けない。印象論としては、すでに人工知能のほうが正確な情報を提供している、と言えるのではないか。むろん、比較する専門家によっての個人差はあるだろうが。それとて、専門家であればあるほど、専門とする領域は先鋭化するはずだ。すなわち、汎用性が欠けるようになる。非常に限定的な知見が深くなる。そこだけ正確で、あとは朧げ、といった傾向は幅広くどのような専門家にも当てはまるように思うのだ。専門家でなければ余計にそうだ。たとえば、かつて天動説が信じられていた時代に、仮に「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」と唱えたら、多くの者は信じなかっただろう。地動説を唱えた者たちからも批判されたはずだ。否定されたはずなのだ。しかし現に太陽系は、銀河の中心にあるとされる巨大ブラックホールを周回している(と2023年現在は考えられている)。「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」との言説は、必ずしも間違った言説とは言えぬのだ。だが、時代が時代ならば、天動説支持者からも地動説支持者からも否定されたはずだ。現代ですら、銀河を想定しない場合には、「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」との言説は「間違っている」と非難されるだろう。認識の差異であり、視野の差異である。どこまでの範囲を含んでいる言説なのか、は確かめるくらいのことをしたほうが、正確さ、という意味では錯誤を最小化できるのではないだろうか。そんな余裕はない、との反論は妥当である。だからみな、それらしい、仮にすっかり正しくはなくとも損がちいさくて済むだろう情報に飛びつくのだろう。それもまた一つの合理的な選択である。だが、損をするかしないか、が同調圧力や社会構造による損失であるならば、過去の魔女狩りや異端審問と同じ轍を踏む可能性を常に含んでいることを想定しておいたほうが好ましいとひびさんは思います。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4780:【2023/03/23(20:42)*体毛が金】
時は金なりとは言うけれど、俺の場合は毛は金なりであった。
治験のバイトをしたのだ。
寝て起きたら全身の毛という毛が金色に変わっていた。
何の薬なのかもろくすっぽ説明をされていない。プラセボ効果うんぬんと説かれた気もするが、要は思いこみによる体調の変化を最小限にするための策なのだろう。だが全身の毛が金に染まるとは思わない。
さっそく病院に電波を飛ばすと、至急来てください、と乞われ、歩を向けると医師からは診察後開口一番に「本物です」と言われた。
「本物とは」
「本物の、金です」
「は、はあ」
「ゴールドです。サイトウさんの全身の毛の成分が、本物のゴールドになっています」
「髪の毛もですか」
「ええ。眉毛もまつ毛もすね毛もあちらの毛も、すべてです」
「それはえっとお」
「億万長者になれますよ。ラッキーです」
「ラッキー?」
「はい。とっても」
健康面での不具合はない、と医師から太鼓判を捺され、また半年後に診察しましょう、経過観察です、と遠回しに治験バイトの続行を促された。
毛が金になったのだからむしろ幸運じゃないですか、と押し切られたわけだが、家に帰ってから「釈然としねぇなぁ」と腕を組む。
しかし治験のバイトを受ける際に交わした契約書において、薬害への補償は条件付きでしか認められていない。条件外では慰謝料はおろか、その後の治療費すら下りないそうだ。
全身の毛が金になったことは補償対象外だ。
俺はしょうがないので、ためしに毛を剃ってみた。
最初はヒゲだけにした。
ヒゲを剃り終わるころには髭剃り機が一つ駄目になった。金と化したヒゲは鋼同然であった。
換金すべく俺は採れたヒゲを質屋に持っていく。
すると俺のヒゲが俺のひと月分の生活費に化けた。
「こんなに貰えるんですか」
「いまは金が高騰していますからね。ほら、電子機器の回路に必要だってんで」
医師は俺の身体異常を差して、「ラッキーじゃん」とお気楽に言ってのけたが、たしかにこれは僥倖かも分からない。
不幸中の幸いにして、棚から牡丹餅、体毛が金である。
翌朝にはきのう剃ったばかりのヒゲが再び生えた。それはそうだ。金とはいえど俺の毛だ。毛は剃ってもまた生える。
俺は今度はヒゲだけでなく腕の毛や脚の毛も剃った。けっこうな分量になった。
ムダ毛を換金すると、こんどは俺の年収ほどの貨幣に化けた。
「ウハウハじゃねぇか」
俺は翌日には、頭髪も剃ることにした。いつ体質が改善し、体毛が金現象が消えるかも分からない。毛が金であるうちに質屋で換金しておくに越したことはない。
そうして俺は全身の毛を剃るのが日課となった。
頭髪はひと月ごとにバリカンで刈ることにした。
一等地のマンションを購入し、毎日寿司を宅配で食べられるだけの生活を送った。豪遊というほどにはまだ金持ちにはなれない。やはり一度全身の毛を剃ってからは、毎日少量の金しか採れなくなる。俺は眉毛もまつ毛も剃っているため、外を出歩くこともままならない。
治験のバイトの期限が訪れた。
病院で、終わりましたよ、の書類を受け取った。治験のバイトはそれっきりであるが、体毛が金現象はなおも俺の身体に宿りつづけた。
翌年には確定申告で頭を抱えた。
収入の欄にどう書けばよいのかが分からない。職業は無職だ。
莫大な資産をどのように生みだしているのか、を説明する言葉を俺は持たない。脱税で捕まりたくはないので正直に「体毛が金になった」と書いたが、むろん再提出を食らった。
「どないせーっちゅうねん」
面倒なので「砂金採り」と書いたらこれは受理された。現物の金の画像を載せたのがよかったのだろう。俺のヒゲは一か所に山にするとまさに砂金といった塩梅であった。
問題が起こったのは俺が治験のバイトをはじめてから三年後のことだった。体毛が金現象が俺の身体に起きてからの俺の生活は順風満帆であり、悩みのない日々を過ごしていた。
しかしその年にそれは起こった。
「こ、これだけなの」
「ニュース観てないのかい。大暴落だよいま」
金の貨幣価値が大暴落したのだ。
なんでもどこぞの研究機関が人工的に金を生みだす術を開発したらしく、世界中の金の価値が地に落ちた。
「ほぼ無制限に金がつくれるって話だよ。ただし、天然物の金にはまだ高値がつくよ。でもあんたのはそうじゃないだろ」
俺の金は、人工の金であるとの判定結果が下された。
質屋は最先端の「鉱物判別機」を購入していたのだ。
金のみならずダイヤなどの宝石の天然人工の区別を自動識別できる優れ物だ。
「人工の金ならこれが相場さ」
質屋は冷たい一瞥を寄越しながら、薄い封筒を俺に寄越した。
俺の生活は一変した。
金が金にならない。
文字にすると矛盾した文面になるが、「ゴールドが貨幣にならぬ」とすれば矛盾は魔法に掛けられたように消え失せる。
俺はマンションを転売し、できた金で全国津々浦々を旅して回った。
俺には貨幣が必要だった。
ムダ毛を貨幣に換える生活を手放したくなかった。
馴染みの質屋ではダメだ。人工の金だとの評価を覆せない。
ならば未だ人工と天然の金の区別のつかぬ質屋相手に換金するよりないのではないか。
そうして旅をしているうちに、俺の髪は伸び、ムダ毛もキンキンに生え揃った。
最終的に一軒の質屋に行き当たった。
金を天秤で測って換金する古き良き佇まいの質屋だった。ここならば俺の体毛が金現象で採れた金であっても高値をつけてくれるはずだ。
俺は試しに髪の毛を一本抜いて、指先で丸めた。
毛玉と化した俺の髪の毛は砂金の塊のごとく玉となり、件の目をつけた質屋にて、かつてない高値を叩きだした。
「いいぞ、いいぞ。ツキが戻ってきた」
俺はホテルにとんぼ返りすると、部屋に着くなり全裸になった。そうしていざというときのために用意していた脱毛剤を湯船にたんまりと注いだ。
一本残らず、体毛を集める。
そのためには刃物で剃るのでは効率がよくない。
腐っても金だ。
金と化した全身の毛を剃るだけでも刃物を何本も駄目にする。
なみなみと張られた脱毛剤の湯舟に俺は全身を浸けた。カバやワニのように頭まで脱毛剤に浸かり、全身から毛が抜け落ちていく感触を、泡立つような悪寒と共に感じた。
排水口にザルを張り、脱毛剤を抜く。
後にはこんもりと俺の体毛が、ピカピアと金色の光沢を湛えて湯船の底に堆積した。
伸びに伸びた髪の毛にムダ毛たちは、俺史上最高の金の採取量を誇った。
件の太っ腹な質屋に持っていく。
しかし俺は失念していた。
いくら少量の金を高値で引き取ってくれる質屋とて、大量の金を購入できるだけの資金はないのだった。かつて贔屓にしてきた質屋が特別だったのだ。銀行からの融資を受けていたからこそ、過去付き合いのあった質屋では、俺は一度に大金を手にできた。
だがいまはそうではない。
街中のうらぶれた質屋なのである。
人工と天然の二種類の金があることすら知らずに取引きを行っているような古き良き時代の質屋なのだ。
換金できたのは、車を一台購入できるかどうかの貨幣だった。
俺の手元には大量の、金ぴかの俺の体毛が残った。
まあいい。
金に困ったら細々と換金して暮らすのもわるかない。
そうと考えたが、つぎに行ったときには件の太っ腹の質屋は俺を冷めた目で一瞥し、人工の金は扱えん、と短く拒絶の意を述べた。
それはそうだ。
質屋のほうでも手に入れた金を売って利益にするのだ。しかし世にはすでに人工の金が大量に出回っている。売れない金を掴まされたと知れば、俺を歓迎しないのは当然だった。
俺は仕方がなく、再び全国津々浦々を旅して回りながら、その地の質屋で体毛を換金した。だがどうあっても俺の体毛は人工の金の評価を下され、安値でしか換金できなかった。
のみならず、とんでもない事実が判明しつつあった。
俺は鏡を見ながら、おかしいな、と首をひねる。
「毛、生えてこねぇぞ」
全身脱毛して以来、俺の皮膚には毛一本生えてこないのだった。
手元に残された採取済みの体毛はすくない。
換金して暮らすには心許ない量である。
「どうしよう」
俺は鏡の中の強面の男と見詰め合う。
眉毛すらないスキンヘッドである。働くにしても、こんな強面の男を誰が雇ってくれるだろう。スキンヘッドを理由に雇わないなんて差別だ、と叫びたい衝動を堪えつつも、そもそも俺は働きたくないのだ、と鏡の中の強面の男が、ない眉を寄せるのだった。
※日々、思考と現実の狭間に宙ぶらりん。
4781:【2023/03/23(21:31)*毒の雨】
ある年のことだ、世界中に毒の雨が降るようになった。
雨とはいえども、まるでバケツをひっくり返したような水の層である。海が頭上から降ってきたような有様で、地上はあっという間に毒の雨の底に沈んだ。
毒の雨が引くと、後には大量の瓦礫と死体が残された。
雨の毒に触れた者たちは一瞬で死ぬ。
いったいこの事象はどうしたことか。
その起源も原理も長らく謎のままだった。
あるとき、宇宙物理学者が「ユリーカ!」と叫んだ。
「宇宙は、時空は、歪んでいる。どちらがボコでどちらがデコなのかはしかし、観測者の属する次元に依存する。すなわち、我々にとっての球体が、別の次元からすると穴の内側のように振る舞うことがあり得るのだ」
この論説は「時空デコボコ観測者問題」と呼ばれ、世界中で侃々諤々の論争を引き起こした。
だが宇宙物理学とはまったく別の方向からの指摘により、論争はぴたりと止んだ。
指摘を呈したのは、毒の雨を調査していた気象学者のハルサーメ教授だった。
ハルサーメ教授は述べた。
「毒の雨の成分を調べていて気付いたのですが、構成物質そのものはまったく未知の物質なのですが、この成分構成の割合分布は我々のよく知る物質とよく似ているのです」
「その物質とは何ですか」
ハルサーメ教授は言った。「うがい薬です」
宇宙物理学者たちはのちに語った。ハルサーメ教授の一言を耳にした者たちが一様にそのとき、同じ妄想を浮かべていたのだという。毒の雨、うがい薬、そしてじぶんたちが議論していた「時空デコボコ観測者問題」の三つを結びつけ得る連想はそう多くはない。
宇宙物理学者たちは気象学者たちの協力のもと、毒の雨がどこから降っているのかを探った。上空に観測機を打ち上げ、地上と大気圏と宇宙空間からの三つの視点で毒の雨の出処を調査した。
その結果、信じがたい事実が浮上した。
「まさか、そんな、あり得ない」
「ですがデータからすれば毒の雨は」ハルサーメ教授は述べた。「熱圏にある電離層と宇宙空間の狭間から湧き出るように出現しています」
「毒の雨は無から生じていると?」
「分かりません。我々には認識できない時空がそこに存在している可能性は否定できません。それこそ物理学者さんたちの議論されていた【時空デコボコ観測者問題】では、地球をデコと見做せるのと同様に、ボコとして見做せる次元があると想定されるのですよね」
「あくまで仮説ですが」
「ならばひょっとしたら、地球が空洞のように振る舞う別の時空が、我々からは不可視の領域に広がっているのかもしれません」
「ではその時空からすれば地球の表面は」
「ええ。さながら口腔内の内頬や舌のように見做せるでしょうね」ハルサーメ教授は眼鏡を外すと白衣の袖でレンズを拭った。「まるでうがい薬のようです。不可視の領域から湧きだす毒の雨は。我々からすると。それとも我々人類があたかも」
雑菌のようですね。
天気の話をするかのようにハルサーメ教授は、強化ガラス越しに部屋の外を見た。
青空が広がる。
地上には未だに勃然と、毒の雨が、滝のように降り注ぐ。
4782:【2023/03/23(22:09)*原子一個消えてんなー?の猫】
たとえば一匹の猫さんを構成する原子の中でたった一つの原子がエネルギィごとこの宇宙から消失したとする。猫さんにとっては原子一個の有無は大して猫さんの健康維持には相関しないだろう。おそらく原子一個が消失したことにも気づくことはないはずだ。だがもし猫さんから原子一個がこの宇宙から消失するようなことがあれば、それは物理法則を超越した事象として、大発見である。エネルギィ保存則が破れている。反物質と対消滅したわけでもないのに原子が消失する。これは猫さんにとっては看過できる事象だが、人類の知見からすれば見逃しがたい大発見なのだ。何を基準にした場合に無視できる事象なのか。何を基準にしたら無視しないほうが好ましい事象なのか。存在することを存在し得ない、と見做すことの危うさは、その事象が人類に直接どのように作用するかに関係なく理解できると思うのだが違うのだろうか。むろん、危うい危うくないを度外視したところで、単なる好奇心から、見逃しがたい発見を見逃さぬようにしたい、発見したい、検証したい、との姿勢は成立する。問題ないから考慮しなくていい、ではないはずだ。単純な理屈と思うが、違うのだろうか。たまにひびさん、ふしぎだな、になります。ひびさんの「ふちぎだな」がお門違いの「何言ってんのー?」になっているだけかもしれないけれども、もしそうだったらごめんなさーい。穏やかにのほほんと過ごしたい日々じゃ。ひびさんは、ひびさんは、なんの役にも立たないあなたのことも好きだよ、って言われたーい。ので、先にひびさんが言っておーこおっと。ひびさんはあなたのことも好きだよ。(打算じゃん)(うふふ。ダサいじゃなくてよかった)(ネガティブなのかポジティブなのかどっちかにして!)(ティブティブだよ)(ティブを二乗するな。てかどっち!?)(えーん、を描くよ)(円じゃん)(えーん、えーん、をいっぱい描くよ)(どこによ)(この世のすべての人間たちに)(悪じゃん)(アクティブティブだよ)(変な方向に活動的になるな。ティブだけ二乗にすな)(アクティブアクティブだよ)(悪を増やすな、無駄に繰り返すな)(えーん魔大王だよ)(地獄の番人じゃん、悪の化身じゃん)(えーん、を渡すよ)(賄賂じゃん)(媚も売るよ)(打算じゃん)(うふふ。ダサいじゃなくてよかった)(いや根っこから超絶ダサいが?)(えーん、だよ)(そこは素直に悲しむのな)(てへへ)(褒めとらんが)(「てへへ」←丘と山脈に見える)(無駄に想像力を豊かにすな。崖から見下ろす波にも見えるよ)(そう?)(そこは軽率に褒めて? 傷つくよ? 媚売って?)(出さんが。びた一文、媚一つ、出さんが)(打算して! ダサくていいから打算して!)(やだティブ)(ナラティブみたいに言うな)(うひひ)
4783:【2023/03/23(22:31)*ラクガキも好き】
野球のルールも碌に知らないひびさんであるけれども、謎に「優れたピッチャーとは」の条件についての知見を覚えておって、どこで見聞きしたのかを思いだせないのだけれども、「優れたピッチャーは最高速度でボールを投げれるピッチャーではなく、最高から最低までの落差を自在に操れるピッチャーだ」みたいな箴言を謎にインプットされておって、この考え方はけっこう、ひびさんの創作の指針にも影響を与えているように感じなくもない。分からぬが、でもけっこうここ半年余りでちょくちょく思うのが、プロの作家さんの小説は、「最高速度でど真ん中」とか「最高速度で変化球」とかが多いのかな、といった印象がある。でもひびさんは割と、ラクガキとかいたずら書きみたいな力の抜けた文章とか、わるふざげスレスレの遊び心満載の文章とかも読みたいし、好きなのだ。もちろん好みの文章形態はあるし、読みやすさや馴染み深さも影響するけれど、なんというかこう、もっと上から下まで、下から上まで、それとも上下左右に満遍なくというか、きょうこの瞬間の気分に左右される「気の向くままの気晴らしの文章」みたいなの、プロの作家さんたちのでも読みたいな、と思うことが増えたくさい。でもだってそうじゃないですか。SNS上の文章とか面白くないですか(面白いですよね)。練ったうえで百文字程度の短い文章にして載せているプロの作家さんもいらっしゃるでしょうけれども、それでも敢えて表面上は気の抜けたテイを装っているわけですよね。そちらのほうが読まれやすいので。反応を得やすいので。商業作品とSNSは媒体が違うし、需要者の求める文章形態や内容も違うのは承知のうえで、やっぱりこう、上から下までの最高速度から最低速度のあいだをいったりきたりする文章を、プロの作家さんのでも読んでみたーいな、と割と思うのですよね。ひびさんは。だってほら。好きな小説つくってくれる作家さんのエッセイとかあったら読むじゃないですか。インタビュー記事とか。日記とか、本当のプライベートの日記だったら絶対面白いじゃないですか(心の中を覗くみたいで)。読みたくないですか? ひびさんは読みたいです。ということを、プロの作家さんだからっていつでも最高速度を目指してボールを投げようとしなくともいいのではないかな、と思うのですが、これは何の責任も背負わずに済む立場のうんみょろみょーんのひびさんだからこそ言えることなのかもしれないので、世界の果てでにょもにょもつぶやくだけに留めておこ。心の中をそのまま映しとったような文章であっても、あんまりトゲトゲしていないのであれば読みたいのよさ。文章というか版画みたいな。心の判子というか魚拓みたいな。ただそれはそれで、なんかこう、プライベートを売り物にするようで、なんか心配!にもなるので、もういっそ妄想を垂れ流したらよいと思うのだ。ひびさんは、ひびさんは、あなたの妄想も好きだよ。読ませてちょ、と思っておるよ。妄想、垂れ流しちゃお。(ひびちゃんはあれよ、もっとオムツしてほしい……)(オムツいつでもぱつんぱつん)(破裂させないでね?)(そういうのはひびさんでなく、オムツさんに言って)(無茶言うな)(へへへ)
4784:【2023/03/24(15:54)*何と何の干渉だろ】
二重スリット実験で思うのが、干渉縞の濃淡は、本当に波の干渉ゆえに生じているのかな、ということで。たとえば濃淡の薄い場所には電子が届きにくい。だから濃淡ができる。ということは、ドーナツの穴ではないけれども、そこには何か電子を拒む不可視の存在があることになるのでは? 生存者バイアスではないけれど、電子の跡の濃い場所ではなくむしろ電子の跡のつかない場所にこそ本質が潜んでいるのでは? そういう考えは考え尽くされておるのだろうか。あとよく解からないのが、電子を発射したときに、二つのスリットの開いた板のどこに標準が定められているのか、だ。電子発射装置は二重スリットのちょうど真ん中に標準を合わせており、確率的に二つのスリットのどちらかを電子が通る、ということなのだろうか。電子が波の性質どころか波そのものでもあるのなら、そうした装置の配置でも実験は可能だ。だがもし電子が、発射装置から大砲さながらに粒子を飛ばしているのなら、発射装置の矛先によっては二重スリットのどちらを通り抜けるのかには偏りが生じるはずだ。ここはどういう構図になっており、どう解釈されているのだろう。量子が粒子と波の両方の性質を帯びていることを示す実験結果は、二重スリット実験以外にはないのだろうか。波の干渉以外を考慮しても、二重スリットの実験結果は解釈可能に思えるが、どうなのだろう。というか、一発一発の電子を発射してトータルで干渉縞が出る、との説明がよく解からぬ。時間経過を置きながら波が干渉し合う、と考えないとおかしくないですか、と頭がこんがらがる。電子一つは何と干渉しておるのだろう。未来の電子さん? やっぱりこう、一発の電子さんであっても、進路が限定されてしまうようなナニカが、真空中にはあって、それに誘導される形で電子は干渉縞を描くように振る舞うのでは。もちろんそれもまた干渉ゆえ、と考えることになるけれども、何と何の干渉なのか、の解釈は従来の解釈と違くなる。たとえばピッチャーが二つのスリットのどちらかに向けてボールを投げる。しかしスリットの開いた板と干渉縞を描くことになる到達点のあいだに網を置いておけば、網の穴を通ったボールのみが到達点に跡を残すことになる。電子の二重スリット実験でも似たような「電子以外の何かとの干渉」によって干渉縞が起きているのではないか、との仮説を否定しておいたほうが無難に思える。そのためには、二重スリットと到達点の距離を縮めたり延ばしたりすることで起きる干渉縞の変化を観察すれば、何かしらの予測とそれによるズレを観測できるはずだ。その結果から、この「電子以外の何かとの干渉」の仮説を否定できるだろう。すでに行われていたらお粗末さまでした。本日寝起きの疑問であった。ひびさん、気になるます!
4785:【2023/03/24(16:43)*自分自身ともつれているのでは】
二重スリット実験では、電子が二つのスリットのうちどちらを通り抜けたのか、を観測しようとすると干渉縞が消えてスリットに対応する二本の線しか残らなくなる現象が表れるそうだ。不思議なのが、このとき、たとえ電子が通り抜けた後にどちらのスリットを通ったのかを明らかにしようとしても、電子がどちらのスリットを通ったのかを後からであれ確定できた場合には干渉縞は消え、確定できなかった場合には干渉縞が表れる、という結果になることだ(そういう記事を読みました)。これはおそらく、二重スリット実験において、電子の経路が量子効果によってもつれている場合には干渉縞が表れるようになる――それはつまり二つのスリットのうちどちらを通ったのかを原理的に確定できない場合にのみ干渉縞が表れる、と言い換えることができそうだ。問題は、このとき電子一つは何ともつれているのか、ということだ。二つのスリットのうちどちらを通ったのかが分からない状態とは、パターン分けするならば、どちらともを同時に通っているか、どちらともを通っていないか、のどちらかではないのだろうか。言い換えるならば、電子は、Aのスリットを通ったじぶんとBのスリットを通ったじぶんとで量子もつれを起こしているのかもしれない。これは量子効果の量子テレポーテーションと矛盾しない。量子もつれは、異なる時系のじぶん自身とももつれることができるはずだ。というか、AでもありBでもある、という量子もつれの根本原理はそこに基点があるのではないのだろうか。量子もつれは、本質的には、二つの異なる粒子同士ではなく、異なる場にある同質の粒子同士で生じる現象なのではないか。とするのなら、それは過去と未来のじぶん自身とももつれることが可能なはずだ。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の同時性の独自解釈や、共鳴仮説とも矛盾しない。時間が違うというのは距離が違うということであり、距離が違うということは時間が違うということだ。人間スケールではしかし、距離と時間の持つ変数がそれぞれ異なる。だがミクロの量子世界では、距離と時間の変数が限りなく近似に寄るのではないだろうか。つまり、区別が限りなくつかなくなる。とするのなら、数ナノ秒前後のズレは、数ナノミリの距離のズレと区別がつかなくなるのかもしれない。過去と未来は、距離のズレと等価として振る舞うようになり得るのかもしれない。とするのなら、二重スリット実験において、仮に二重スリットの間隔が、量子レベルに小さい場合には、どちらのスリットを通り抜けたのか、を考えるときに、重ね合わせで「どちらのスリットも通り抜けた」という量子もつれ状態になることもないとは言いきれないのではないか。何と何がもつれているのか。過去や未来の電子自身である。AとBの二つのスリットの距離のズレと、AとBのどちらかを通った電子自身の過去と未来のIFにおいて、二つの、「Aを通った電子」と「Bを通った電子」は、量子もつれを起こして重ね合わせて存在しているのかもしれない。Aでもあり、Bでもある。これはつまり言い換えるなら、「そのとき電子は、AとBのどちらのスリットも通り抜けていない」のだ。あれ、これトンネル効果では? 飛躍しすぎたので、いまのなし。妄想なのであった。
4786:【2023/03/24(22:37)*反射はせぬのかねきみ】
きょうは二重スリット実験についての疑問が浮かぶ日だ。たとえば、電子発射装置から電子が発射されたとき、必ずしも「二つのスリットのうちどちらか一方を通るとは限らない」はずだ。スリットの開いた壁に電子がぶつかって反射するかもしれない。そのときの反射した電子は、電子発射装置のある側に進路を変える。ではその反射した電子はどのような痕跡を残すのだろう。干渉縞が表れるのか否か。これは実験で観測されているのだろうか。ひびさんの「日々記。4787」(上記記事)で並べた疑問では、ひょっとしてトンネル効果が生じてない?との妄想を展開した。仮に何かの間違えでそうした事象が生じていたとするのなら、「反射した電子」と「トンネル効果によりスリットを通らずに壁をすり抜けた電子の余韻」とで、対になるような干渉縞が生じるのではないか。つまり、スリットの向こう側の壁と、電子発射装置側の壁の二つにできた干渉縞を合成したときに濃淡のデコボコが山と谷できっちり噛み合うような対の関係を成し、足し算すると平坦な「一面痕跡」の状態を表出させるのではないか。ここはなんとも言えぬけれども(電子発射装置側に干渉縞が生じるのかどうかがまず分らぬけれども)、ひとまず「電子発射装置側には干渉縞とか電子の痕跡は生じないの?」の疑問をメモしておくでござる。ひびさん、気になっちゃったな、の巻でした。おわり。
4787:【2023/03/24(23:44)*お手本じゃなくて、すまぬ、すまぬ】
教える、ということを、「手本や手法を享受すること」だと考えている人が多いのかな、といった所感がある。もちろん勉強を教える、ならばそれでよいと思うのだ。知識をそのまま相手にコピーしてもらう。お手本をなぞってもらう。そういう教え方もあるだろうけれど、それではコピーの量産を可能とするだけで、学ぶことを教えることはできないと思うのだ。むしろ、学ぶことを教えるためには、「お手本をなぞらせること」はマイナスに働くように思えてならない。最初の基礎だけ教えるのは、安全な道を情報共有するという意味では、プラスに働くとは思う。けれども、それ以上の応用とか試行錯誤の過程を伴なう場合にはむしろ、好きにやらせるほうが、学びを教えるうえでは効果的なように思えなくもない。上手になることは、学びの目的ではないのでは?とけっこうずっと思ってきた。すでに答えがあることであっても、自力で解きたい、でも答えがあるなら好きなタイミングで答え合わせもしたい。この選択の幅を与える。選択肢を与え、自由に選ばせる。この繰り返しでしか学びを教えることはできないのではないか?との疑問をけっこうずっと考えつづけている。目的が上手になることならどんどんお手本をコピーするのがよい。ただし、学ぶ能力そのものを向上させたいのならば、「お手本をなぞること」や「これがお手本だからなぞりなさい、と与えられること」に頼りすぎないのが好ましいように思うのだ。何と何を比較し、何のどこに着目し、何と何を組み合わせ、そして何と何をいったん横に置いてみるのか。そうした試行錯誤が、独自の回路を涵養し、学ぶ能力そのものを育むように思うのだ。これは分野を問わないがゆえに、ある時期を境に、あらゆる分野と繋がるように振る舞うのではないか。学ぶ能力は、それ自体が創発し得るように思うのだ。けれども、お手本をなぞってばかりだと、点が線に創発できない。点と点を結ぶ「思考」が「層」を成すくらいに「錯綜する過程」が肝要なのではないのかな、と思う。だがそのためには、好きなだけ情報に触れられる環境が要るし、入力と出力の比率がある一定以上に開かないようにする環境が要るのだろう。やはりそのためには、他から「答え」や「お手本」を与えられることに慣れすぎる、頼りすぎる、のは逆効果に思えるのだ。一言でまとめるのなら、「教えることとは畢竟、相手の選択肢を潰さないことである」と言えるのではないか。「可能な限り、選択肢を与え、選ばせること」こそが、教えることの本質と言えるのではないか。潰さない。ただそれだけでよいのだ。それが適うのならば、過度な干渉や師弟関係は不要である、とすら言えるかもしれない。ここはまだ何とも言えないが、印象としてはけっこうずっとひびさんは、「あれで教えているつもりなのかなぁ……大丈夫かなぁ」と思うことがすくなくなかった。「技術をコピーしてもらう」の意味での「教える」なら、それでいいけれども、と思いつつ、それだと「学ぶ力」や「発想力」は育まれないのでは、と思わぬでもないのであった。ひびさんは誰にも何も教えんよ。使える何かがひびさんにあるなら好きに使ってくんなまし。参考にするでも反面教師にするでも、無視するでも、好き好きーと思うのも自由にしてくれ。ひびさんはそれでも何も返さぬが。うへへ。何も教えてあげられず、すまぬ、すまぬ。と思いつつ、いつも独りで遊んどるひびさんなのであった。遊べ遊べー。
4788:【2023/03/25(00:04)*負け日々の遠吠え】
それはそれとして、私の好きな人たちを悲しめる手法には、同じ手法を当てはめる。同じことをされてまだ行えるなら、理に適っているので良いと思います。
4789:【2023/03/25(00:21)*蟻が鯛になる(鳶が鷹を生む的な)】
んで以って、ひびさん自身がひびさんの好きな人たちを悲しませていた場合は、ひびさんは死ぬ。終わりだ。何もかも。うっうっ。この世の終わりになーれ、の呪いを吐露吐露おべー、してひびさんも終わってやる!になる。でも割とひびさんは他者を損ない、他者に負担を強い、嫌な思いをさせ、じぶんだけ「やっぴー!」になっている極悪人なので、世界の果てでちんまりしているから許して……の気持ち。うっうっ。すまぬ、すまぬ。異世界のカーテンの向こうにいる人々、みな優しい。ひびさんのことなんて知らぬだろうけれども、みな優しい。幸あれ。海の幸食べ放題くらいの幸あれ。でもそれだと海の生き物さんたちが可哀そうだからいかんともしがたい。生きるって罪よな。すまぬ、すまぬ。それでもひびさんはきょうもあすも生きていく。死ぬまでひびさんの日々はつづくのだった。ありがたーい。
4790:【2023/03/25(06:07)*千客万酒店】
万酒店は、酒屋である。古今東西、あらゆる時代に存在する酒を取り揃えている。
その店には、京都のとある鳥居を新月の晩にくぐると辿り着ける。
今宵も一人の酒豪が、格別の酒を希求して万酒店を訪れた。
「こ、ここが噂の」酒豪は屋号を見上げて感嘆した。「本当にあったとは」
「いらっしゃいませお客さま」扉の奥から声がした。酒豪が驚いて固まっていると、扉は左右に間隙を広げた。「こちらへどうぞ。ご所望の品があればなんなりと申し付けください。それが酒であればなんでもございます」
「本当か」酒豪は細かい疑問をかなぐり捨てる。大事なのは無類の酒を味わうことだ。それ以外は些事である。「俺が知ってる酒はいらん。この世で最も美味い酒が飲みてぇ」
「はて。それは困りましたな。人の舌は千差万別。お客様の舌に合うお酒を御用意いたしたくは存じますが、まずはあなた様の好みを知らぬことにはなんとも」
「俺ぁ酒の付くものならなんでも飲んできた。むしろ俺の知らねぇ酒がここにあるのかがまず以って疑問だ」
「ではこちらはいかがですかな」
店主らしき老人は、着物の裾から一本の一升瓶を取りだした。ラベルも貼られていない無垢な瓶だ。酒豪は目を凝らす。瓶の中には液体のほかに何かが詰まっていた。
「蛇か」マムシ酒だろうか、と当たりをつけた。
「いいえ。こちらは六千年前に絶滅した青龍の浸し酒となります」
「青龍ってのは、むかしの蛇かなんかかい」
「いいえ。青龍は青龍です。どうぞ近くでご覧になってください」
店主がずいと一升瓶をまえに突き出した。
酒豪はそれを受け取るとまじまじと目を凝らした。
龍である。
全身が鱗で覆われた、頭から角を生やし、髭を伸ばし、手足のついた一匹の龍が一升瓶には詰まっていた。
「こ、こいつぁ偽物じゃねぇのかい」
「本物でございます」
店主は着物の袖口からさらに数本の一升瓶を立てつづけに取りだした。酒豪は店主の人間離れした所作に瞠目しつつも、喉の渇きに誘われるように次々と一升瓶を受け取った。
人魚。
妖精。
水かきのある手。
極めつけは額から角を生やした胎児。
各々がそれぞれに一升瓶に酒と共に浸っていた。
「全部本物なのかい」
「もちろんでございます」
「しかしちょいと飲み甲斐がありすぎやしないかい」美味ければ文句はない。だが躊躇する。酒豪は一升瓶をそばの棚に並べ、見比べた。「どれが美味いんだ」
「お客様の味覚次第でございます」
「この調子だと人間の浸し酒までありそうだな」
軽い冗談のつもりだったが、店主が押し黙ってしまったので酒豪はごくりと生唾を呑み込む。「あんのかい」
「ございます」
「う、美味ぇのかい」
「無類でございましょう」
酒豪は唾液が止まらないじぶんを不思議に思った。しかしこうも思う。ゲテモノを食らうならば、いっそ他人に話しても信じてもらえなさそうな龍や人魚や妖精の浸し酒よりも、人間の浸し酒のほうが酒の肴になるのではないか。
酒豪は酒の味のみならず、酒の場の空気が美味い酒には欠かせないことを知っていた。酒豪は美味い酒を飲むためならば何でもする。そのために生きているようなものだった。
「その人間の浸し酒ってのも見せてくれねぇかい」
「よろしゅうございますよ」
店主はみたびに着物の袖口から一升瓶を取りだした。
受け取ると酒豪は矯めつ眇めつ一升瓶を観察する。だが、妙だ。
「なあ、これ。どこに人間が詰まってんだ」
浸ってねぇじゃねぇか、と苦情を呈すと、店主は、浸ってございますよ、と首を伸ばすようにして酒豪の手元を目だけで覗きこんだ。
「どこにだ」
「すでに、でございます」
店主はこともなげに応じた。「さすがに人の死体を瓶に詰めることはできませぬ。仮にできても売り物にはできぬ道理。酒は美味いのが道理。なれば酒の席に似つかわしくのない人の死体の詰まった浸し酒を、当店では扱っておりませぬ」
「ならこれは人の浸し酒ではないのか」詐欺ではないか、と思うが口にせず。
「人の浸し酒でございます」店主が譲らぬので、酒豪は、だからどこがだ、と声を荒らげた。
「人であらばいかようにも、浸し汁が取れますのでね。ちなみにその瓶の浸し汁は、どこぞの美女のものと聞いております」
「浸し汁とはなんだ。浸し酒とは違うのか」
「酒造りの際に用いる水を、人間の浸った汁で代用したものでございます」
「するとその水が、人間の死体を浸した汁ってことか」酒豪は鼻息を荒くした。
「まさか。死体である必要がございません」
「死体でなければなんだ。胎児のホルマリン漬けの汁でも入っとるのか」
「まさか」店主は顔のまえで手を振って、「湯舟でございますよお客様」と微笑交じりに述べた。
酒豪は酔ってもいないのに顔を赤らめ、ワインじゃねぇんだぞ、と小言を吐いたが、店主はついでのように、「ご所望であれば」と付け足した。「お客様の浸し酒もご用意することも可能ですが。お客様の入浴後の湯船の湯さえ戴ければ」
「いらん」
断りながらも酒豪は、美女の浸し酒と、ではほかに何を購入するか。
青龍、人魚、妖精、水搔きのある手に、角の生えた胎児。
各々の一升瓶を順繰りと見比べた。
舌舐めずりをする。
万酒店の屋根には月光が垂れている。
扉が開き、つぎの客が入ってくる。酒豪の足元には絨毯のような濃く広い影が下り、尖った角のような影が真っ先に店の奥へと店主を貫くように伸びた。
酒豪はぎょっとした。
手に取った一升瓶の中で、身じろぎする胎児の躍動を手に感じた。
汗を吸った生地が背中に張りつく。
酔ってもいないうちから酒豪は酔いが覚めたように、ゆっくりと後ろを振り返る。
火事場の熱気のごとき鼻息が全身を覆った。
※日々、明暗。
4791:【2023/03/25(06:37)*ぼくを推すならその手で押して】
「
最近よく考えるんです。
浮気ってなんだろうって。
浮気ってどうしてダメなんだろうって。
だって刑事法では浮気を禁じてはいないわけですよね、この国では。あくまで民事であり、個人間の諍いなわけですよ。
法律では浮気を禁じていないんですよ。
第一、社会は個人に【友達をたくさんつくりましょう】【他者ともっと繋がりましょう】と推奨しますよね。促しておりますよ。学校ですらそのように擦りこまれますけど、友達がたくさんいたほうがよいのなら、恋人だってたくさんいたほうがよいのではありませんか。
子供ができちゃうのが問題なら、できないようにする手段はたくさんありますし、たとえできてもいまは科学技術が進んでおりますから、受精卵が赤ちゃんのカタチをとる前にどうにかできるじゃないですか。
とくにこれといって恋人がたくさんいて困ることってないと思うんですよ。
浮気ってなんでダメなんですか。
ぼく、よく解かんないんです。
もっと言ったら、誰とでも友達になれる人は誰とでも恋人になっていいと思うんですよ。誰だって誰に恋心を抱くのかは自由じゃないですか。じゃあ恋心を互いに抱き合い、注ぎ合えたら恋人関係になればよいじゃないですか。
なんで我慢するんですか。
なんで我慢するんですか。
ぼく、よく解かんないんです。
もしぼくが世界中の人たちと友達になれたらぼくは世界中の人たちと恋人関係になりたいです。愛し合いたいですし、触れ合いたいです。
どうしてダメなんですか。
どうしてダメなんですか。
誰か教えてください。誰か教えてください。
嫉妬するからですか。
嫉妬はどうしてしちゃうんですか。
だってあなたは友達にじぶん以外の友達ができても嫉妬するんですか。でもそれは嫉妬するほうがわるいですよね。嫉妬して相手の自由を束縛するほうがおかしいですよね。
でもそれが恋人だとどうして許容されちゃうんですか。
おかしいですよね。
おかしいですよね。
ぼくはみんなと仲良くなりたいです。ぼくはみんなと仲良くできますし、しています。
会う人みんなと誰とでも友達になれますし、恋人にもなれます。
どうしてそれをしたらいけないんですか。
どうしていけないことだと非難されてしまうのですか。
したいならしてもよいけれど自己責任だよ、というのは分かりますが、それでも関係のない人たちがぼくに対して、浮気はよくないだとか、人として最低だとか、罵詈雑言を投げ掛けてきます。
どうしてですか。
どうしてですか。
ぼくのことを奪い合う人たちが出てきちゃうからですか。
ならぼくはぼくのことを愛して、求めて、欲する人たちのために、ぼくをその人たち全員が均等に手に入れられるように、ぼくを愛して求めて欲する人たちの数だけ分離しますよ。
よいですよ。
よいですよ。
ぼくを細かく砕いて、切って、割いて、分けてください。
みんなでぼくを分けてください。
そのスイッチを押すだけでよいですよ。
あとはそのスイッチを押すだけでいいんですよ。
ぼくはぼくを愛してくれるみんなの分だけ細切れになって、みんなの元にお届けされますよ。
浮気じゃないですよ。
浮気じゃないですよ。
ぼくは無数のぼくとなって、無数の細切れのぼくの部位たちは、ぼくを愛して求めて欲した人たちの分だけ、あなただけのぼくになるのだ。
ボタンを押して。
ボタンを押して。
あなたが押して。
その手で押して。
ぼくはぼくのことも好いているから、どうしてもぼくだけではぼく自身と離れがたいんだ。
それをいますぐどうかあなたに押して欲しいのです。
」
4792:【2023/03/25(08:21)* を頂戴】
「神様、神様。ぼくはカホちゃんを愛しています。世界で一番愛しています。どうかカホちゃんとぼくが結婚できるようにしてください。お願いします」
ひと月分の収入をお賽銭箱に投じると、噂通り、拝殿の神鏡が光った。
目を開けると、賽銭箱のうえに子どもが座っていた。
子どもは前髪が切り揃えられている。いわゆるおかっぱ頭だ。
着物を身に着けており、座敷童がいたらこういう感じだろうなと第一印象で思った。
「呼びだしたのはお主?」子どもが口を開いた。鈴の音のような声音だ。子どもが足を振るたびにかかとが賽銭箱に当たるのか、コツコツと音が聞こえた。
「何でも願いが叶うって噂を聞いて来たんですけど」
「うん。我は願いを叶えるよ」
「カホちゃんと結婚したいんですけど」
「したら良いよ」
「そうもいかないから願いに来たんですよ。カホちゃんにはほかに好きな人がいて、でもぼくのほうがカホちゃんを愛しているんです」
「それは良いね」
「絶対ぼくのほうがカホちゃんを幸せにできます」
「うむ。良き心掛け。その願い、叶えるよ」子どもは賽銭箱のうえに立ちあがると、雨水を受け止めるように両手をまえに構えた。「では対価を頂戴するよ」
「え、対価? さっきお賽銭をいっぱい」
「それは我を呼びだすためのもの。願いの対価は別にあるよ」
「そ、そうなんですね。あの、お幾らでしょうか」同じ金額くらいなら用意できると思った。
「お金は要らない。お主の決意をカタチにしたものをもらうよ。そうだね。お主は想い人を愛しておるね。たくさん、たくさん愛しておるね」
「それはもう。世界一」
「欲望ゆえではないのだね」
「カホちゃんを幸せにするためです」
「うん。良い心掛け。対価を決めたよ」子どもは子猫を撫でるような笑みを浮かべた。「お主の男根を頂戴」
「お、男根?」
「うん。股間のそれ、頂戴」と指差され、一歩後退する。「な、何で。何でですか」
「お主は先刻言ったよ。愛ゆえと。結婚したいと欲した。幸せにするためと」
「は、はい。言いましたけど」
「ならばそれは不要だよ。欲ゆえでないのならば要らないよ。我に頂戴」
「ち、ちんこを? ぼくの? え、これぇ?」
「痛くしないよ。あげる、と言えばなくなるよ」
「え、えぇ」
「結婚できるよ。良かったね。早くそれ頂戴」
しばし考える。
カホちゃんと結婚できたとして、それでどうなる。カホちゃんを独占できたとして、それでどうなる。男性器がなければ身体で愛し合うことも碌にできないではないか。だったら何のためにカホちゃんと結婚するのか分からない。
「だ、ダメです」股間を押さえながら、「これはあげられません」と半身になる。
「なら二度と使い物にならなくするだけでも良いよ」
「勃たなくなるってことですか」
「おしっこはできるよ」
「す、すみませんでした。ちょっと考え直させてください。また来ます。きょうのところはもういいです」半身のまま階段を下りる。子どもから顔を逸らすのがおそろしい。視線はそのままだ。
「別に良いよ。でももうお主はその者と結婚できないよ。縁も切れるよ」
「え、え、何でですか何でですか」
「願いが嘘だったからだよ。道理だよ」
「嘘じゃないですよぼくはカホちゃんを世界一愛しているし、幸せにだってできるんだ。神さまだからって聞き捨てならないな。撤回しろ」
「なら男根を頂戴」
「それはダメだって何度も言ってるだろ。これがなきゃ赤ちゃんだって出来ないだろ。カホちゃんを幸せにできないだろ。おまえは神様なんかじゃない。嘘つきのバケモノだ」
「うん」子どもはそこでこちらに背を向けた。「そうだよ」
ぎっぎっぎっぎっ。
絡繰り人形のようなぎこちない動きで、子どもの首だけがこちらを向いた。
なぜか股間が温かい。小便をちびったのかと焦った。
足元を見遣ると、黒く水溜まりが出来ており、股間からは大量の赤黒い液体が漏れていた。血だ。血溜まりだ。
「あ、あ、あ、あぁああ」
賽銭箱のうえで、子どもがクチャクチャとしきりに顎を動かし、何かを咀嚼している。
閉じた唇の合間からはとろりとした液体が溢れた。子どもの目元だけが雪にもたげた笹の葉のごとく弓なりに下がりきっている。
瞬きをすると、子どもの両手が目と鼻の先にあった。
「もっと頂戴」
口を閉じたままの子どもの頭部から、くぐもった声音が幾重にもこだまして耳に届く。
胸が異様にぬくかった。
4793:【2023/03/25(23:58)*合法自殺薬】
また最高記録を達成した。
自殺者の記録だ。毎月の自殺者数が三万人を超し、過去の年間平均自殺者数に並んだ。すなわち年間ではおおよそ十倍以上に自殺者が増えたことになる。
「このままいくとあと半世紀経たずにこの国の人口は百万人を割るってさ」大学の食堂で蕎麦を啜りながらナツコが言った。「どうする? 年金絶対もらえんじゃんね」
「そこかよ」問題視する点が即物的すぎたので私は咽た。カレー風味の息が気管を刺激し、しばらく咳き込む。「ごほごほ。あんまし私を笑かさないで」
「かってに笑うな」ナツコが手つかずだったじぶんの分の水を私のほうに滑らせたので、私はありがたく受け取った。
飲み干すのを待ってたのかナツコは、空のコップを私から奪い取るようにすると、むかしは自殺は悪だったらしいよ、と話をつづけた。
「どうしたんきょうは真面目な話したがるね」
「や。あたしの兄貴がさ。きのう薬局で自殺薬買ってきててさ」
「死ぬ気じゃん」
「そう。相談もなしにだよ。いつ飲むのって訊いたら、気が向いたらだってさ。就職したばっかだよ今年。なに死に急いでんのとか思っちゃって」
「でも多いらしいよ。就職後半年以内に自殺する若者」
「ホントそれ。いまはさ。人権に【じぶんの命をいつ終わらせるかを決める権利】ってのが入ってるからいいけどさ。むかしはなかったって。きのう調べて知ったし」
「らしいね」
「自殺はいけないことだってされてたんだって」
「私のお母さんとか、まだそういう価値観持ってるよ。お父さんは違うっぽいけど」
「へえ。いるんだね」
「おばぁちゃんがそういうのに厳しい人で」
「命を大切にって?」
「そうそう」
祖母はむかしながらの倫理観に染まりきっていた人で、自殺薬が薬局で手軽に購入できるようになってからというもの、母がそれを手に取らぬようにと散々に言い含めて育ててきたらしい。その結果、母はある時期を境に祖母に愛想を尽かして、比較的時代の変容に順応した父の人柄に惹かれて祖母の反対を押しきり結婚した過去がある。
私が産まれると祖母もさすがにやいのやいの母を説き伏せる真似を控えた。産まれてしまった孫は可愛い。いまさらじぶんの娘に、夫と別れろ、とは口が裂けても祖母は言えなかった。それこそ祖母の倫理観に反する。産まれた赤子には両親の愛が必要だと祖母は考え、優先順位をつけ直したようだった。
「おばぁちゃんの目もあったからさ。私、未だに自殺薬って直で見たことないんよね。触ったこともない」
「うっそ。小学校か中学校で習わんかったっけ」
「それ避妊具のやつじゃない」
「そんときに一緒にだよ」ナツコは蕎麦を平らげてなお、汁をスプーンでちまちま掬っては啜り、掬っては啜った。「自殺薬ってさ、他人に飲ませられないようにちょっと飲むのにコツがいるんだよ。それは知ってるっしょ?」
「知らなーい」
「学校で習ったじゃん」
「いやいや。一緒の学校じゃなかったし」
「学校ごとに変わるとかないっしょ。忘れてるか、授業受けてなかったんじゃない」
その可能性はあった。祖母が何かと母を言いくるめて私にその授業を受けさせなかった背景がないとは言いきれない。それくらいの妨害は祖母ならばしそうに思えた。孫可愛さゆえとはいえど、ある種の虐待と言えなくもないはずだ。あくまでそれが事実であれば、だけれども。
「家帰ったら兄貴死んでたらどうしよ」
ナツコがカラのどんぶりをなおもスプーンで攫っているのを見て、そこが本筋だったか、と私は友人の心配事の核心を得た。「死んでたら電話して」私は言い添えた。「一緒にお線香上げてあげる」
大学の講義を消化し、ナツコとも別れて帰宅した。バイトはないし、きょうはあとは家でゆっくりできる。映画でも観るか、と思いつつ、玄関を抜けてリビングに入ると、父と母がソファで二人寄り添い眠っていた。
手を繋いでいる。
普段ならば二人とも仕事で家を留守にしている時間帯で、私は日常の中の小さな非日常の光景に違和感を抱いた。
ソファのまえのちゃぶ台には水らしき液体の入ったコップが二つある。そばには絆創膏でも入っていそうな小さな箱が転がっていた。
何の箱だろ、と思いつつ、ぴくりとも動かぬ父と母を横目に私は台所に立ち、水を一杯飲んだ。
それから嫌な予感がしつつも、手を洗ってから自室で着替えを済ませた。
ベッドの上に腰掛け、嫌な予感の正体を見詰めようと思うが、確かめるのこえぇな、と思いつつ、身体は自室から出て階段を下り、リビングに立った。
父と母は目をつむったままだ。寝息一つ聞こえない。
ちゃぶ台の上の箱に手を伸ばす。
掴み取る前から箱の表面に印刷された「安楽死」の文字が目に飛び込んだ。
中身はきっかり二人分減っていた。
おそるおそる父と母の首筋に触れるが、触れた瞬間の冷たさに私は、ああ、と思ったのだ。
ああもう、と。
相談もなしによくも、と。
安楽死薬の箱の中には、死体運搬を行う保健所担当部署の番号と、死体発見時の手順が薬の説明書きと共に書かれていた。
私は保健所に連絡する前に、なぜかナツコに電話を掛けた。
「はいはーい。どした」
「あんさ。自殺薬をさ」
「あはは。兄ちゃんのこと心配してくれたの。あんがと。でも全然まだ元気だよ。もち、あたしが飲まされたりもしないから大丈夫。言うの忘れてたけど、自殺薬ってめっちゃ辛いんだって。粉薬でさ。口ん中に針の束突っ込んだくらいの辛さらしくて、だから服用する前に麻酔薬を口に含んで麻痺させなきゃなんよ。もうね。口ん中が麻痺したらさすがにその時点で気づくっしょ。だから他人に自殺薬を飲ませて殺したりはできないようになってんの。心配あんがとね」
「う、うん」私は両親のことが言えなかった。安心したありがと、と礼を述べて電話を切り、それから祖母に電話をして事情を話すと、その一時間後には私は祖母と共に保健所の霊安センターにいた。
両親の自殺の事後処理は祖母がすべて肩代わりしてくれた。私はただ職員の説明を祖母の小さな肩越しに聞いていればよかった。
祖母は泣きもせず、かといってじぶんの娘の死体に何か言葉を掛けるでもなく、ただ頬とおでこを撫でて別れを終えたようだった。私は死体に触れたくなかったので、じゃあね、と声を掛けて霊安室の外に出た。
以後、私は両親の死体を目にしていない。
墓とて、大規模埋葬地に、ほかの自殺者たちと共に葬ってもらうことにした。
自殺者は、いわば早期退職者のような扱いを受ける。人生を早めに切り上げ、限りある資源を消費せずに済むようにしてくれた自殺者たちに、国は埋葬や死体の処理などの仕組みを手厚く整えているのだ。
ただし、遺族にはこれといった恩恵はない。
私にはいくばくかの両親の貯金と家と土地が遺されたばかりだ。それとて生前贈与を受けておらず、半分近くが税金として引かれた。
家と土地は売り払い、私は祖母と共に暮らすことになった。
大学は休学したし、ナツコとも音信不通だ。
というのも、私が両親の自殺の事後処理で半ば放心状態だったあいだに、ナツコの兄も自殺したようだった。
何度か着信があったけれど、テキストメッセージで私のほうの事情を短く説明すると、お互いさまかよー、と快活な返事があって以降、ナツコからの連絡はない。私からの連絡を待っているのかもしれないし、ナツコはナツコで放心状態なのかもしれない。
「死ぬこたないんだ。死ぬこたない」
祖母の家で暮らしはじめて最初のほうに、祖母が食事中、口にした。それは呪文を唱えるような、誰に向けた言葉とも知れない虚空へのつぶやきだった。それとも遅れて飛びだした己が娘へのたむけの言葉だったのかもしれない。
自殺者の数が最高記録を更新しつづけている、との報道がニュースでは毎月のように流れる。最近では、自殺薬をカプセルに詰めて他人の飲ませる犯罪行為が多発している、との報道もあり、そりゃそうだよな、と私は箸を嚙みながら思った。
口の中を麻痺させずとも、粉薬たる自殺薬が口内に触れぬように工夫すればよいだけだ。自殺だと思われてきた過去の事案の中にも、少なくない数の例外が含まれていたのではないか。私は想像を逞しくした。
祖母の家でも暮らしは穏やかなもので、両親の自殺にはまいったけれども、結果よければすべてよし、と思わぬでもないいまは日々だ。そろそろ大学に復帰して、ナツコともまた遊びたいな、と失いかけた欲がむくむくと育ちはじめている。
復帰の手続きをすべく大学の敷地に半年ぶりに足を踏み入れると、掲示板が目に留まった。サークルの勧誘ポスターがデジタル画面にいくつも表示されていた。その中に自殺愛好会のポスターがあった。
あなたも一緒に穏やかな自殺を!
募集しているということは、メンバーが足りないということで。
それでもなお潰れていないということは、メンバーがその都度に補充されているということで。
「大学側も大変だな」
大枚叩いて選別し、せっかく受け入れた生徒たちがこぞって自殺していくのだから。
収入源が減って、儲けどころではないだろう。
「まあでもそれは国も同じか」
人口は年々減っている。
資源はその分、余裕を取り戻す。
人々は自殺を肯定的に受け入れており、好きなときにじぶんの命を終わらせることができる。
好きな相手と共に死ぬことだってできるのだから、それはそれで尊重されるべき権利の一つかもしれない、と私は母と父の死体を思いだす。
祖母に反対されつづけた果てに、我が母は人生を賭した反抗期を演じきったのかもしれない。我が母ながら、若いな、と思わぬでもないけれど、私は母の選択を、肯定も否定もせぬままでいようといまは判断保留のままにしている。
生理が来たので薬局に寄った。
棚を見て回ると、精力剤の棚の隣に、自殺薬の箱が並んでいた。
「死んだ分、産めってか」
或いは、産んだ分、死にましょう、なのかもしれないけれど、避妊具がお菓子売り場の側にあり、男性用性玩具と共に売られているのを目の当たりにすると、売店の、それとも国の思惑が透けて視えるようで滑稽だった。
死ぬこたないんだ。
死ぬこたない
祖母の声がときおり脳裏によぎる。
家に帰ると祖母はいつも決まって小さな仏壇のまえで船を漕いでいる。両手で抱えられるほど小さな仏壇には私の両親の位牌と共に写真が並んでおり、そこには毎月のように新しく花が添えられる。毎回違う花なので、献花が変わるたびに私は、つぎはどんな花を買ってくるのかな、と祖母から借りた花図鑑と共にそこはかとなく楽しみにしている。
両親の自殺以降、私はカレーを食べていない。
最後に食べたのが両親の自殺した日の大学の食堂だったことを思いだし、あのときに咽た痛痒をついさっき体験したことのように思いだすのだった。
ナツコとは、来週遊ぶ予定だ。
4794:【2023/03/26(00:03)*あってもいいけど、選べてもよいのでは】
たとえば、Aという仕事をするうえでBという作業が発生する。しかしBはAを達成するための必要条件ではない。こういう場合には、Aを職業とする者の立場としては、Bの作業をどうにか短縮できないか、という方向に工夫をとるのが好ましいように思うのだ。だがAという仕事の良し悪しのみで評価を得られない場合、Bの作業の評価との兼ね合いで、総合評価を高めようとする流れが当然でてくる。すると本来はBの作業を短縮したほうがAの仕事の質は上がるはずなのだが、Bの作業を短縮したり、失くそうとする流れが損なわれる。いま社会的に可視化されつつある社会問題の根幹にはこのような「足の引っ張り合い」があるのではないか、と思うのだ。短縮できることは短縮したらよいのでは、それこそが仕事の目的の一つなのでは?とひびさんはどうしても考えてしまう。それだとBの評価を加算してかろうじて職にありつけている者が仕事を失くす、というのは一つの道理だ。だがそれを言うのならば、Aの仕事のみで評価されたい者の仕事とて失われていることについてはどのように考えているのだろう。要するに、他者との比較での上下において、いかにじぶんが優位に立つか、を考えはじめると、この手の問題はマイナスへの対称性の破れを発現させる。仕事の目的は、それを行うことでじぶんとその他大勢の利を共に最大化する、幸福の総量を増やすこと、と言えるのではないか。ならば短縮できる作業は短縮し、誰でも一つの仕事の質と量を高めたり、試行錯誤を行う余裕を築いていくほうが好ましいのではないか。Aという仕事において、Bが本質的に寄与しているのか否か。ここはその都度に振り返り振り返り、環境との比較を以って分析する視点が欠かせないと思うのだ。ある時期においてはAの仕事においてBが触媒となって相乗効果を成すこともある。だがある時期においては環境が変わったので、Bが触媒としての効能を発揮するよりもむしろAの仕事の負荷になることもある。さらに言えば、この関係性の変容は、個々人の仕事への取り組み方や、身の置く環境にも左右される。要するに、過度に一般化はできないのだ。にも拘らず、Aの仕事における必要条件ではないBの作業を必要条件と見做してしまえば、それは何かがねじれてしまうだろう。じぶんの利点を失いたくないのか、それとも仕事を通しての利を最大化したいのか。ここの区別はつけておいたほうが、職業プロ、という立場においては有意義に思えるが、日々遊び惚けているだけの怠け者の戯言ゆえ、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4795:【2023/03/26(00:46)*割と単純】
何かの価値を上げたければ、軽率に「あれ欲しい」と唱えればよい。たとえば賞の権威を上げたければ誰しもが欲しがるような賞になればよく、そのためには多くの実力者やその分野の者たちが「あの賞を受賞したい」と思うようになる過程が欠かせない。これは商品でも同じだ。しかしこの原理を利用して、じつのところそんなに欲しくはないけれど権威だけは上げておきたい、と考えた場合に、大して欲しくはないけれどひとまず「あれ欲しい」と言っておくか、というのは方法論として間違ってはいない。この手の手法はマーケティングであれ宣伝であれ、広報であれ、PRであれ、用いられているはずだ。半ば詐欺じみた側面がないとも言いきれない。売れる作品は売れている作品だ、みたいな理屈でもある。みなが買っているから良いものなのだろう、私も僕も手に入れておいたほうがよいのかも、と買い手に思わせる。もしくは、モテている人がモテる、の理屈にも通じる。アイドルとして人気があるから一流アイドルになる、みたいな具合だ。これを逆手にとって、本当は大してほかのアイドルと差がないにも拘わらず、大人気です、と全面に押しだすことで、視聴者に「いまはこれがモテる人物像ですよ」と刷り込むことを可能とする。この手法は、詐欺の常套手段でもあり、同時に人間の根本的な認知の歪みでもあるので、意図せずとも効果を発揮することもある。ハロー効果と言えば端的だ。ということを込みで述べるのならばやはり、好きなアーティストや応援している人物がいるのなら、「あの人のこれこれは絶対に欲しい」「手に入れたい」と公言することこそが、一つの効果的な支援になるだろう。ファンレターをもらっている、という事実がそのままその人物の魅力に繋がる、みたいな元も子もない話になる。そのファンレターが超一流と話題の人物からのメッセージであればなおさらこの手の「付加価値」が増す。上下関係を分ける中間管理職の量産やオモチャみたいなトロフィーしか貰えない社内コンテストなどもこの手の理屈が潜んでいる。ひびさんの苦手な価値観ではあるけれど、現代社会では有効な手法なのもまた否定しづらいのであった。定かではないが。印象論ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4796:【2023/03/26(02:54)*常温で「もつれ状態」を維持する条件とは】
仮に量子もつれが共鳴現象だとするのなら、系の規模に因(よ)らず量子もつれと同等の事象は起こり得るのでは。量子世界においてなぜ量子もつれを維持するために低温度でなければならないのか、と言えば、「温度が高い=エネルギィの外部干渉があるから」と考えられる。この解釈で言えば、量子もつれのような異なる二つの系同士が共鳴し合うためには、外部干渉がもつれの効果を打ち消さない規模に「相対的に小さくなる」必要があるはずだ。とすると、たとえ常温であれ、もつれ状態になれる「異なる二つの系」の組み合わせはあるのではないか(系と系の組み合わせにおいて、外部干渉――すなわち温度の影響――が相対的に小さくなればよいからだ)。それこそ、仮に人間の意識が脳内の量子効果によって生じている、と考えるのなら、常温であっても量子もつれが起きていると想定しないとおかしい。規模の異なる系同士であれ、共鳴し得るような「同相」や「相似」の関係であれば、もつれ状態になり得る、と仮に考えるのなら、人間の意識の根幹においての量子もつれとは、脳内の細胞におけるネットワークそのものが、フラクタルにもつれていることによって、許容可能な外部干渉――温度の上限――を飛躍的に高めているのではないか。これは創発が、ある種の層を帯びることによって生じることと無関係ではないだろう。次元が繰り上がることで、それまでなかった性質が宿る。〇次元が一次元になり、二次元になり、三次元になり、四次元になる。人間の意識のみならず、生物の根幹が仮にこうした次元を跨いだ「異なる二つの系のもつれ」によって生じる創発に由来するのならば、死とはすなわち、もつれ状態の乱れと解釈することができるのではないか。この妄想は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「相対性フラクタル解釈」や「同時性の独自解釈」ほか「宇宙レイヤー仮説」「共鳴仮説」「デコボコ相転移仮説」と矛盾しない。直近の記事で並べた、「二重スリット実験における疑問」での「異なる時間軸の自分自身とも量子は、もつれ得るのでは?」との妄想とも相性がよい。人間の意識の発生機構には、すこし先の未来やすこし前の過去ともつれ合うような脳内ネットワークが、瓦のごとく連続して総体を維持しながら共鳴しつづけている現象に由来しているのではないだろうか。との妄想は、たのち、たのち、になれたのできょうのひびさんはお尻ふりふり踊っちゃう。妄想ゆえ定かではありません。真に受けないようにご注意ください。真に受けちゃ「めっ」だよ。
4797:【2023/03/26(03:11)*どゆこと?】
文章から情報を得る、とは物理学的にはどのように解釈されるのだろう。本を読むでもよいし、電子画面を眺めるでもよい。たとえば一年中、部屋の中で椅子に座って映画を観ている人は、客観的には一年中部屋で椅子に座っている人でしかない。目のまえの電子画面が細かく光を発しているかどうかの差異があるだけだ。これは原理的に目のまえで揺らぐ蝋燭を眺めているのと変わらないはずだ。もしくは太陽が昇って沈むまでの光の変化をカーテン越しに眺めているのと変わらないはずだ。文字を読むにしろ絵を観るにしろ、それが紙なり電子画面なりに映しだされている場合、それが単なる紙の染みや汚れであっても、物理学的には解釈の上でそう大きく変わらないはずだ。人間はいったい、文字や絵から何を引き出しているのだろう。共鳴なのではないのだろうか。任意の形状が、過去に生じた脳内の化学変化――ある種の波形――と共鳴する。言霊は、そういう意味ではあながち間違いではないのかもしれない。定かではない。
4798:【2023/03/26(03:18)*ある日の交信~偶然について~】
「
2023/03/01(02:02)
(~~略~~)
ただし、偶然の中にも、異なる種類の「相関関係の深さ」のような偶然が含まれて感じます。
たとえば虫の擬態や、シマウマの紋様など。
偶然にほかの動物と似たり、特殊な効能を得たりします。
ではそのことと、言葉ができることのあいだに、どれだけの差がありますか。
言葉が言葉として成立するためには、「元となる事象」「使用者」「受け取り手」の三つが必要です。
さらに、時間経過による情報共有――自然淘汰――が欠かせないはずです。
ぼくにしか読めない言語はもはや言語足り得ないでしょう。他者からすれば紋様と汚れの区別もつきません。
他者と共有できる記号は残り、そうでない記号は淘汰されます。
虫の擬態と同様のプロセスを辿っているはずです。
言語は、人間の肉体的な制約のうえに「情報共有しやすい形態」に変容しつづけているはずです。
すなわち、人体に左右される以上、どの言語にも共通のパターンが備わっているはずです。
飛躍しますが、物質の根源が究極のところでは単なる波――或いはラグ――だとします。
虫は、ある固有の紋様や形状を備えることで偶然にほかの生物や環境と似たような情報伝達の波長を帯びる、と仮定します。
それはたとえば透明マントのようなものです。透明マントを羽織れば、肉体からの情報が外部に漏れにくくなります。遅延の層が最大化します。
そこにいるのに、いない、という偽装がそうして可能となるわけです。
昆虫の擬態も似たような解釈がとれるはずです。
ではその情報の遅延――波長の形態――は、何かと何かが似ていることで生じる、と考えることができるはずです。
相似であったり、同相であったり。
異なる事象であれ、この手の「情報の遅延の波長のようなもの」が似ることで、単なる偶然であろうとも、相互に似たような効果――作用反作用――影響――を帯びることもあり得るようにぼくは思えます。
飛躍しているので、うまく言えないのですが。
偶然の中にも、単なるランダムの意味だけではない、「情報の遅延の波長のようなもの」において実は相関関係を帯びているような偶然もあるように思うのですが、この仮説にはすでに似たような理論がありますか?
」
4799:【2023/03/26(20:07)*拭っても拭えぬ拙さを愛でよ】
拙さを愛でる、はおそらく高性能AIが台頭し誰でも一定以上の成果物を生みだせるようになったら、最後の人間の拠り所として、重宝されるようになる価値観になるだろう。愛嬌といえばそれらしい。むろんこれはAIにも再現可能だが、それは詰まるところそのAIにとっての拙さであり、模倣品としては見做されない。拙さを真似することにおいては人類は過去、「侮蔑」や「差別」の範疇として忌避した。だがそれは拙いことが「悪」との価値観があってこその忌避だ。仮に拙いことにこそ人間の性質が宿るのだ、といった考えが社会に浸透したならば、拙いことを仮に模倣したとしてもそれはその個の拙さとして「真似」とは見做されなくなるだろう。言い換えるなら、「真似できる拙さは拙いのではなく上手」なのだ。他を真似る、という能力は、仮にその対象が「未熟」や「幼稚」であれ、真似できてしまえばそれは上手なのだ。拙くはない。したがって、真似ではないその人物がどうしても払拭できない欠点こそが、拙さとして表出する。どうあっても滲み出てしまう。意図せずとも、である。これと似た性質を持つ概念がもう一つある。そうである。個性だ。――拙さを愛でる。これから先の時代において、中心的な価値観になっていくだろう、との妄想を披歴して、寝起きの「日々記。」とさせてください。(いま起きたんか)(んだよ)(寝すぎでは?)(だって寝たの朝の七時くらいだもの)(そっか。ならしょうが……なくないな。十二時間以上寝てんじゃん)(バレたか)(拙いというか、もったいないな)(もったいないを愛でよ)(欠点を愛でるために欠点をつくる、みたいな元も子もない真似はせんでね)(はーい)(あらよい返事)(責任は、もたない)(責任持たないを愛でるな。責任は持て)(これ、おもい……せきにん)(持てないじゃん)(モテませぬので)(モテない、を愛でよ)(それはイヤ)(ね)(うひひ……)(元気ないじゃんよ)(ひびさんの拙いも、愛でて)(厚かまし)(冷たくしちゃいやん)(冷たさも愛でよ)(凍えてひびさん、ちんじゃう)(まだ生きてるつもりだったか)(ひびさんを愛でよ?)
4800:【2023/03/26(21:22)*膨張する遺伝子】
一九九八年の夏。
インドの宇宙物理学者、ヴィドゥユト・ジャンラマヌが論文を発表した。内容は「宇宙膨張と高密度時空のフラクタル関係について」である。
この論文は英国の老舗科学雑誌に掲載されたが、話題になることはなかった。だが一方では、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文は各国の諜報機関がランクRの認定を与えるほどの超重要論文と規定された。
ランクRは、ランクSよりも重要度が高い。
ランクSに該当する重要事項には、月面の裏側に埋没する超大型宇宙船についての情報が含まれるが、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文はそれ以上の情報を含んでいる、と各国諜報機関は判断した。
情報統制は敷かないが、かといって表向き高く評価もしない。そのような流れが暗黙の元に、ランクRの評価付けにより強化された。
その結果、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文が日の目を見ることはなかった。
だが、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文が世間からどのように評価されるのか或いはされないのかに関わらず、その論文内容の指摘する事象は、現実に存在した。
二〇三六年の冬のことである。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌが件の論文を発表してから三十八年が経過したその年に、オーストラリアに住まうスミス・オリヴィアが、庭で遊んでいた際に、それを発見した。スミス・オリヴィアは六歳の少女だったが、じぶんが目にしたそれが明らかに異常な代物なのだと瞬間的に判断した。
スミス・オリヴィアはそばにあったバケツを手に取り、すかさず発見したそれに被せた。逃がさぬようにしたのである。そしてスミス・オリヴィアは大声で家の中の母親を呼んだ。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌが件の論文を発表してから三十八年後のこの日が、公に「絶滅種の実存」が確認された日となった。
スミス・オリヴィアが庭で見つけたそれは、手のひらサイズの竜脚類であった。すなわち、恐竜である。
恐竜の発見。
世界中がこの発見に湧いた。
その後も続々と世界各国で小型の恐竜が見つかった。
絶滅したと思われていた恐竜が、なぜか生き残っていた。しかも小型化して。多くの者たちはこう考えた。何千万年も細々と種を繋ぎ、環境に適応した進化を経たのだ、と。そう考えるのが妥当ではある。
太古の哺乳類が小型であり、進化していくうちに大型化していったのと似ている。恐竜はその逆の進化の道を辿ったのだ。多くの者たちはそう考えた。
だがここで、各国諜報機関の幹部たちは頭を抱えた。
ランクRに指定した「ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文」の証明とも呼べる発見が六歳の少女の手で成されたのだ。ランクRの論文を秘匿にしておくことはもはや不可能である。
世界中の研究者たちは遅かれ早かれ真相に辿り着くだろう。
なぜ恐竜たちが小型化したのか。
論者の中には、遺伝子操作で開発された恐竜のクローンだと主張する者たちも出はじめた。真偽を度外視するならば、そう考えたほうが、真相よりも受け入れやすくはある。
だが恐竜のクローンが可能だとしても、小型化はしない。
恐竜のクローンは生みだせる。技術的には可能だ。しかし、小型化はしない。
ここの矛盾を指摘する世界各国の研究者たちにより、クローン説は早々に下火となった。
ではなぜ恐竜がいまなお現存し、小型化しているのか。
どういった進化を辿ったのか。
世界中の研究者たちのみならず、全世界の人間たちが興味を駆り立てられた。
日々の話題はもっぱら恐竜一色に染まった。世はまさに大恐竜時代よろしく小恐竜時代の幕開けを迎えた。
しかし、小型化した恐竜の実存の謎に対しての最初の問いとして、「進化」を持ち出すのは誤りだ。譬えるならそれはカレーを作るのに初手でノコギリを取りだすような迷子である。
迷宮へと勇んで足を踏み入れるような、出口から遠のく出発点と言えた。
進化ではないのだ。
恐竜たちが小型化して生き残っている背景に潜む原理は。
その原理に触れた唯一の論文が、すなわち「ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文」であった。内容は、「宇宙膨張と高密度時空のフラクタル関係について」である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌはこう論じた。
「宇宙膨張に際して、時空密度の高い場ほど膨張の比率が軽減される。物質とはいわば時空密度の濃い場である。銀河がそうであるように物質密度の高い場では、宇宙膨張の影響が緩和される。これは言い換えるのならば、時空密度の高い場では宇宙膨張の影響が緩和される、ということである」
いささか難解な表現だ。
だが言っていることは単純だ。
風船を膨らませるとき、風船の結び目は膨らまない。結び目のようなぎゅっとなっている場においては、風船の膨張する作用が働きにくい。
人間スケールでもこの手の関係は表出している。
水に浮かべた氷を想像しよう。
水を温めていけば、最初に気化するのは液体であり、氷はそのあとに液化し、気化する。ぎゅっとなっている氷は、気化という膨張現象の影響を受けにくいのである。
これと同じことが、太古の地球においても延々と展開されてきた。
恐竜は絶滅したのではない。
宇宙膨張の影響を受けにくい存在がゆえに、ぎゅっとなったままなのだ。
言い換えるならば、現代に生じた新たな種はみな「膨張」しているのだ。遺伝子レベルで。
人類も例外ではない。
ゆえに、恐竜が小型化した、との表現は正しくはない。
恐竜以外の生物が例外なく巨大化したのだ。
ここで改めてヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文を紐解こう。彼は論文の中でこう語っている。
「宇宙膨張は、情報の膨張である。ゆえに情報の密度が濃い場ほどその影響を受けない。したがってこれを遺伝子に当てはめた場合、より複雑な情報を有する遺伝子ほど宇宙膨張の影響を受けにくいだろう。しかしそれが進化の上でプラスに働くかマイナスに働くかは、膨張によって生じる情報の余白に依る。すなわち、ある種の余白を宇宙膨張によって獲得した遺伝子のほうが、優位に異なる情報の層と共鳴しあい、ネットワークを複雑化させることができる。これは、情報ネットワークそのものの創発を促し、時空において時間と空間の双方向でより広範囲での情報処理を行えるようになるだろう」
難解な文章だが、言っていることはこれもまた単純だ。
遺伝子は情報が高密度になっている場である。
これは宇宙膨張の影響を受けにくい。さながら銀河のように。
と同時に、希薄なボイドのごとく空白を抱え込んだ遺伝子のほうが、実のところより複雑な構造を有することが可能になることもある。宇宙膨張の影響を受けたほうが、進化という意味では、より高次の性質を獲得しやすいのかもしれない。
知性もまたその範疇である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌは件の論文でそう指摘しているのだ。
地球上で誕生した様々な生命体は、何億年という気の遠くなるような時間経過の果てに、宇宙膨張の影響を受けながら、進化をつづけた。だがその宇宙膨張の影響を受ける度合いは、各々の種ごとに変わり、その差異は遺伝子により大きく表れる。
恐竜たちは比較的高密度の情報を遺伝子に蓄えていた。だから宇宙膨張の影響を受けにくく、相対的に巨大化していくほかの生物種と比べて小型化したように振る舞った。
だがそのお陰で、地球の寒冷化にも耐え、種を存続させることに繋がった。遺伝子ごと宇宙膨張の影響を受けた種は、寒冷化に耐えらず絶滅したのだ。密度の高いほうが、温度の変化に強いのは道理である。
比較的小型なヘビやトカゲ、ほか鳥類が生き残っていることを考えればさもありなんである。
そして哺乳類は、それとあべこべに宇宙膨張の影響を受けながら、遺伝子に空隙を抱え込みながらより複雑な立体的な情報網を獲得し、新しい性質を発現させた。
知性もまたその内の一つである。
と、ヴィドゥユト・ジャンラマヌは考えたようである。
恐竜の化石は大きいではないか、との異論は的外れとは言いにくいが、化石は化石だ。遺伝子が機能していない。いわば銀河の枠組みを有しないため、ほかの雑多な宇宙膨張の影響を受けやすい万物と等しく膨張する。ゆえに化石もまた膨張しているのだ。遺伝子のほうが情報が圧縮されており、遺伝子が銀河のごとく機能している限り、それは宇宙膨張の影響を受けにくい。したがって子孫を繋ぐ一連の種の軌跡そのものが、相対的に宇宙膨張との関係において縮小して振る舞うのだ。
各国諜報機関はよもや恐竜が生き残っているとは想像だにしていなかった。ヴィドゥユト・ジャンラマヌは件の論文をランクR扱いすればそれで秘匿できると考えたが、現実はそこまで甘くなかったようである。
ちなみに各国諜報機関がなぜヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文をランクRに指定したかと言えば、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文に書かれている理論が、最先端電子通信技術においてブレイクスルーを担うほどの鍵となることが判っていたからである。
情報密度の差によって宇宙膨張の影響が変化する。
これは言うなれば、宇宙の根本原理として扱えた。量子世界における粒子の階層性を紐解くにあたって、数々の未解決問題が一挙に氷解するほどのそれは大発明だった。
なぜ物質は、時空は、電磁波は、各々に固有の波形を帯びながら相互に干渉し合うのか。宇宙膨張の影響が平等に作用しながらにして、その作用の規模に偏りがあるからである。
濃いと薄い。
圧縮と膨張。
凝縮と希釈は互いに補い合っている。
結晶は空白を抱え込むことで構造を帯びる。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文は、そのように論が結ばれている。
図らずも、希代の新理論を打ち出したヴィドゥユト・ジャンラマヌは、誰に手を差し伸べられることなく世が空前の恐竜ブームに染まるその二年前に、帰らぬ人となった。
死因は不明である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌの死体は発見されていない。ヴィドゥユト・ジャンラマヌの行方は杳として知れない。探す者がいないのだ。戸籍上は存命扱いだったが、失踪者扱いがなされてから一定期間が経過したのを機に死亡との烙印を捺された。
ランクRの論文は未だ人の目につくことはなく、人々が小型恐竜の真相に気づく素振りもまた、いまはまだないようだ。
だが遠からず誰かが、おや、と思い至るだろう。かつてのヴィドゥユト・ジャンラマヌがそうであったのと同じように。
その日が訪れるまでは。
真相は、人々の膨らませる妄想に取り残される。
閃きの種は何より小さくぎゅっとなる。
恐竜たちがそうした過程を辿ったように。
巨人が自身を巨大とけして思わぬように。
※日々、食べて寝て排泄するだけ、椅子に座って妄想するだけ、そよ風に耳を澄まし、朝と夜の明滅に合わせて瞬きをすると夜だけを生き、朝だけを生きる、ときどき苦しく痛く煩わしい、ときどき楽しく美味しく穏やかで。
4801:【2023/03/27(06:23)*稀代の盗作家】
稀代の盗作家を取材することになった。世界中の創作家から蛇蝎視されるその作家は、自身でオリジナルの創作をすることなく、数多の作家たちの作風を盗み、アイディアを真似、誰より量産することで市場に混沌を撒き散らした罪を名目に、各分野から永久追放の刑に処されている。
問題は件の盗作家がまったくそれに懲りずに盗作を重ねている点だ。
きょうだけでも数作の掌編小説やイラストが電子網上に新たに投稿されている。盗作家の創作物は幅が広い。小説、絵画、漫画、イラスト、映像、彫刻、版画に人形造形。複数人説や人工知能の覆面説が囁かれるほどそれぞれの作風もまた広い。
盗作家の作品がどの作家の作品から盗作された品なのかを識別するための鑑定組織が設立されたほどだ。半年ごとに各分野の作家たちのあいだで情報共有がなされるが、それは盗作家の作品がいかに他者の作品の焼き増しであるのかを糾弾するためである。
私は待ち合わせ場所へと一時間前に辿り着いた。
とある地方都市の書店内にある喫茶店だ。相手がそこを指定してきたのだ。
駅のトイレで無精ひげを剃り、見栄えを整える。
私が書店に到着すると、すでに先方が喫茶店内の席に座っていた。かの盗作家の顔写真は創作の分野に長く活動していれば否応なく目にすることになる。のみならず個人情報まで周知となっている背景には、過去に裁判沙汰になった事例がすくなくないからだ。しかしいずれも件の盗作家は著作権法違反とは見做されなかった。
「似ている、ということは、違う、ということです。区別がつく時点で、偽装ではありません。違法性は低いかと」
弁護士をつけずにすべて自己弁護をした。結果はすべて無罪である。
こうした過去から余計に「悪質」の評判が立った。
過去の彼女――盗作家――の案件を探ってみての私の第一印象は、確かに他作家の作品群と似ている、である。つぎに思ったのが、どうやって?であった。
どうやって盗作家は、世界中の創作家たちのアイディアを模倣しているのだろう。これは盗作家の動向を気に掛ける者たちの総意と言えた。
なぜアイディアを盗めるのか。
まだ発表もされていないはずの作品のアイディアを、なぜ。
私は誰に依頼されるでもなく、一人のジャーナリストとして自ら抱いた疑問を解き明かすために件の盗作家へと取材を申し込んだ。私は単刀直入に、「どうやって他者の作品の情報を集めているのですか」と私自身の疑問をぶつけた。すると盗作家は、では会って話しましょうか、と二つ返事で面談の席を設けたのだった。
私は対面の席を引いた。「お待たせしました」
盗作家が私を見た。彼女は上下スポーツウェアだ。散歩の途中で一服吐いているかのような佇まいだ。
私は名乗った。それから相手が盗作家本人かの確認をするつもりで、「宮膳野(ぐうぜんの)一知(いっち)」さんですか、と訊いた。
「はい。初めまして。高橋さんは何を飲みますか」
「では紅茶を」私は席に着き、飲み物を注文するとさっそく本題に入った。「テキストでご相談したように、私が知りたいのは、宮膳野さんがどうやってそれほど多くの作品群を生みだせるのか、についてです。宮膳野さんのファンの方のすくなからずは、宮膳野さんがほかの方々の表現からいち早く影響を受けているから実現できる芸当だと考えていらっしゃるようです」敢えて控えめな表現をとった。「ですがそれが仮に真実を射抜いた解釈だとして、ならどうやって宮膳野さんは他者の未発表作品から学ぶことができているのですか」
「ふむ。高橋さんの言うところの【みなさん】はその点についてなんと?」
「高性能の人工知能を用いたハッキングをしているのでは、と仮説を唱えている者が大半です」
「ほう。ならばあたしは犯罪者だね。通報したらよいのでは?」
「された方もいらっしゃるようですよ」
「だがあたしは逮捕されていない。ならそれを真実と見做すのは早計ではないかな」
「はい。私もそう思います」
「ふふ。いいね。話が出来そうな方だ」
彼女は腕組をして背もたれに仰け反った。窓の外に映る空を仰ぐようにしながら、「あたしはまどろっこしいのが苦手でね」とへの字に唇を尖らせる。「結論から述べれば、あたしは盗作していないし、問題の根っこはオリジナルとは何か、の誤謬が世に罷り通っていることにある」
「盗作されていないんですか」そこからして土台をひっくり返されるとは思っていなかった。「ならどうしてあんなに似て」
口にしかけて言葉を飲みこむ。これでは彼女が盗作家だと私が見做していたと認めたようなものだ。あくまで真相を見極めるために、との姿勢を崩したくなかった。
「いいよ別に。盗作うんぬんは言われ慣れてる。時期的にもあたしが発表した作品よりも、オリジナルを主張する作家たちのほうが先に制作していたこともある。それは事実らしい。散々証拠として書類の類を見せられたからね。未だに毎日のように郵送で資料が送られてくる。いかにあたしの作品がじぶんたちの作品と似ているのか、とね。まあ中身は見ないけど。制作時期からしてじぶんらのほうが早い、盗作しただろ、と言ってくるわけだ」
「事実ではないと? 言い掛かりなんですか」さすがにおいそれとは信じ難い。
盗作が冤罪だとしたらこれはちょっとした話題になる。
事が事なだけに慎重になりたかった。いわばこれはスキャンダルだ。本当だったらこれ以上ない記事にできる。
「あたしの作品はあたしがこれまでに五感で受動した外部情報の組み合わせでしかない。それを盗作と言うのならばあたしはあたしの目にし、耳にし、嗅ぎ、触れ、考えた過去のあらゆる自然現象、万物からの盗作をしていると言えるだろうね。しかしそこを外れることの可能な表現者をあたしは知らない。もしいるならそれは真実に新しい世界を創造できる神だけだろう。だが人間は神じゃない。ここまでは理解を示してくれますか」
「は、はい。いえ、どうでしょう。ちょっと戸惑いますね」私は頬を掻いた。剃ったばかりのヒゲがジョリジョリと指先をくすぐった。「いまはその、何の話を」
「オリジナルとは何か、についてさ。みな、じぶんだけは模倣していない、盗作していない、オリジナルだ、と思いこんでいる。こういうことを言うと、やれ開き直っただの、盗作を認めただの言われてしまうのだけれどね」
「失礼ですが、私も宮膳野さんの作品群を拝見しております。みなさんの指摘されるように、やはり各類似点の指摘された作品群と宮膳野さんの作品は似ているように思います。偶然で片付けるには無理のあるレベルに思えるのですが」
「と言われてもね。あたしはただ思い浮かんだアイディアをカタチにしているだけで。それがたまたま世界中のどこかの誰かの作品に似てしまう」
たとえばだけどね、と彼女は飲みかけの紅茶にミルクを足した。スプーンで掻き混ぜながら、「昆虫の擬態ってあるでしょ」と言った。「あれって別に昆虫のほうで、ほかの生き物の真似をしようと思ったわけじゃないはずなんだよ。偶然にそうなってしまっただけでさ。でも人間からすると、昆虫のほうで真似したんじゃないかって思っちゃうでしょ」
「自然淘汰ですよね」
「そうそう。原理としてはそっちが正しい。紋様がたまたま生存に有利だった個体だけが生き残りやすかった。それ以外は死滅した。子孫を残せなかった。結果的に、生存に有利な紋様を持つ個体が多くなる。昆虫がじぶんで、【わあ鳥みたいな顔に見える模様になるぞ】とは考えていない。たまたまそういう個体が生き残りやすかっただけでさ」
「それは分かりますが、それと宮膳野さんの場合は違うような」
「まあね。あたしはじぶんで選んで創ってるからね。毎回作風も違ってるし。だから余計に信じられないんでしょう、みなさんは。よもや自力で、何の助けも得ずにこれだけ幅広い作風を描ける作家がいるわけないって。盗作してるに決まってる。そういうバイアスが掛かっちゃうのは、あたしのほうでも理解はできるよ。誤解されても困っちゃうけど」
「あくまで才能だと? そういう特別な?」
「特別? これが? 好きに創ってるだけでしょこんなの。それがたまたま、ごまんといる世界中の創作者の目に触れて、似てるだの真似ているだの話題になってるだけで、あたしがしてるのは子どものラクガキと同じだよ。子どものラクガキなんてどれも似たようなもんでしょ。いちいちあの子どもの絵がほかの子どもの絵と似ているだの盗作だの言わないじゃん普通。似てて当然なんだから。あたしから言わせれば、あたしが創れるようなレベルの作品なんて、似てるものがあって当然だよ。だって才能ないもんあたし。誰が創ってもいずれ似たような作品は出てくるよ」
その言葉ではっとした。
そうなのだ。
彼女だけなのだ。
ここまで現在進行形で世界中の作品と照らし合わせて検証されつづけている作家は。
世界中で日々生みだされる数多の作品と比較され、その中で似ている作品があれば盗作の烙印を捺される。しかしこれは、ひょっとしたら誰であっても逃れることのできない偶然による迷宮と言えるのではないか。
誰が彼女の立場になっても、盗作の判定を受けるのだ。どうあっても避けられない。
水に浮いたら魔女。
沈めば人間。
しかし沈んだままなら死ぬしかない。浮いて魔女判定が下されれば処刑される。したがってどちらに転んでも死ぬ運命は変わらない。
同じなのではないか。
彼女の陥っている状況は、現代の魔女裁判と同じなのではないか。
「逆に訊きたいよあたしは。もしあたしが世界中の表現者相手に盗作疑惑を吹っ掛けたらどうなるのかって。あたし、たぶん負けないよ。でもみなは身に覚えのない盗作疑惑を晴らすために、外界との接触を極限まで拒むしかない。それ以外でこの手の懸念って払拭できないんだ」
だからね、高橋さん。
イルカのような穏やかな目だ。私は身震いした。
「あたしはこの間、いっさい何も見ちゃいないんだ。TVも映画もインターネットだって繋げてない。家に来てもらえば判ると思うよ。何もないから。この服だってじぶんで縫って作ったし」とスポーツウェアを指でつまむ。「あたしいま、盗作できるほど、他者の表現に触れてねぇんだわ」
テキストメッセージはでもやり取りできましたよね。
喉まで出掛かった言葉を私は紅茶と共に飲み下す。
違う。
そうではないのだ。
おそらく私のメッセージだけが資料の添付がなかったのではないか。
唯一の純粋なテキストだけのメッセージだったのではないか。
だから彼女は私にのみ返事をしたのではないか。未だかつて稀代の盗作家「宮膳野一知」が取材を受けたという話は聞かない。
彼女は四の字に足を組む。背もたれに体重を預けながら頭の後ろに手を組んだ。ちょうど彼女の腕と頭が目のようなカタチを成した。
ひとつ目のオバケ、と私は思う。
「たとえばきょういまここで話した内容を掌編小説にしたため、電子網上に載せとくとしよう。事実をただ掌編に興しただけでも、世界のどこかにはそれと似たような場面や内容を作品に組み込んだ作家がいて、盗作だなんだと話題になると思いますよ。実験してみましょうか。あ、そっか、いいね」
それ戴き、と彼女はウィンクをした。「すみませんね。盗作しちゃって。つってもまだ創ってないんですけど」
「あ、いえ、その」私は呆気にとられた。
単にそれを圧倒された、と言い換えてもよいが、ともかくとして私は彼女との面談を経てこの体験をどう記事に興すか。
果たして、書いた記事は盗作に当たらないのか。
目下のそれが問題だった。
誰より先に記事にしなくては。
彼女が掌編を手掛けるよりも先に。
頭の片隅で、私はかように焦るじぶんを認識した。
稀代の盗作家が大きな欠伸を一つした。かと思えば頬杖をつき、飲み物のお代わりをしたいのかメニュー表を眺めながら、口笛を吹く。
何の気なく奏でられた音色は耳に心地よい。変則的で脈絡がなく、延々と曲調が変化する。おそらく曲名はないはずだが、たとえそれが何かの映画の主題歌であっても、私はもはや驚かない。
稀代の盗作家は口笛を止めると、お子様ランチを注文した。
4802:【2023/03/27(23:51)*モーグルトの閃き】
何か閃いたのだが、その何かを忘れてしまった。人類の価値観を一変させるほどの発想だった気がするのだが、ヨーグルトを食べたい、の欲求に抗えず、スプーンでヨーグルトを掬って減った腹を満たし終えたら、人類の価値観を一変させ得る閃きがどこかへとひらひら飛んで去っていた。
人類はヨーグルトのせいで進歩の契機を失ったのだ。
ぼくはそれを口惜しく思ったのでタイムマシンを開発し、過去の人類史からヨーグルトを消すことにした。
滞りなく計画を遂行して現代に戻ってくると、世界の在り様は変わっていた。なぜかみな一様にムキムキだった。電子機器の類はなく、ぼくの開発したタイムマシンが唯一の機械らしい機械だった。
まるで文明が滅んだみたいだ。
否、過去に一度滅んだのかもしれない。
ぼくが過去に干渉し、ヨーグルトを消したのが要因なのはまず間違いなかった。
見知った人物は姿を消していた。ぼくの家族はなく、ならばぼくとてそこに本来は存在してよい存在ではないはずだったが、タイムパラドクスはどうやら引き起こっていないようだった。
ぼくの肉体はあくまで元の世界線から構成されているからかもしれなかった。いわばぼくは異世界人なのだ。
しかしこれでは過去を変えた意味がない。
ヨーグルトを消したところで、これではぼくが閃いた人類の価値観を一変させるほどの発想を拾い直すことができない。
そこでぼくは、もう一度タイムマシンを使って過去へと戻った。
だがすでに人類史からはヨーグルトが消えているので、ぼくがヨーグルトを消すそれ以前に戻らなければ元の世界線と同じ過去には辿り着けない。
ヨーグルトを消したぼくに会おうとしても、ちょうどずばりその瞬間に時計の針を合わせることはできないようだった。なぜならぼくがヨーグルトを歴史から消したときに、そばにはもう一人のぼくはいなかった。それがぼくがヨーグルトを消した世界線における過去なのだ。
だからぼくがヨーグルトを人類史に再び蘇らせるためには、ヨーグルトの消えた人類史においてぼくがもう一度ヨーグルトを生みだし、流行らせなければならないが、それはもはや別の世界線だ。
元の世界に戻るためには、ぼくがヨーグルトの存在を人類史から消した時期よりもさらに過去に遡る必要がある。そしていずれ未来からやってくるだろうもう一人のぼくへの対策として、ヨーグルトが消えても困らないように、ヨーグルトの代わりとなる何かを生みだしておくよりない。
それとてけっきょくは元の世界線には辿り着かないが、限りなく近似に寄ることは想像に難くない。
かくしてぼくは過去の人類史において、ヨーグルトによく似たモーグルトを生みだした。それはヨーグルトが流行しない人類史において、ヨーグルトの代わりに人々の腸内を整えた。たんぱく質にもなった。カルシウム源にもなった。人類はふたたび、ぼくのよく知る現代人への歩みを辿った。
ぼくが現代へとタイムマシンを起動させると、辿り着いた先は馴染みの風景の広がる現代社会だった。
よかった、とぼくは胸を撫で下ろした。
そうして喉がカラカラのうえお腹が減ったので、何はともあれモーグルトを摂取しようと冷蔵庫を開けた。モーグルとは飲み物のようで食べ物もである。一度で二度美味しい健康食品なのだ。
ごくごく、と小腹を満たしたそのとき、ぴろぴろりん、とぼくは何かを閃いた。
「そうだ!」
ぼくはとんでもない発想を掴み取った。「ヨーグルトを消しに過去に戻るよりも、閃きを逃した直前に戻ってヨーグルトを食べる前に閃きをメモするように過去のじぶんに助言すればよかったのでは?」
そうでなくとも、過去のじぶんから、いま閃いたそれを教えてくれ、と頼めばよかったのでは?
とんでもない見落としに気づきぼくは、モーグルとはモーグルトであって、やっぱりぼくはヨーグルトのほうが好きだったのにな、とじぶんの至らなさに打ちのめされた。
後悔の炎に衝き動かされながらぼくがタイムマシンを木っ端みじんに分解していると、妹が帰宅した。
「兄ちゃん何してんの」
「ん。タイムマシンをちょっとな」
「タイムマシン? 本物?」
「まあな」
「すごいじゃん」妹は素直なので、愚兄であっても褒めてくれる。「兄ちゃん、人類の未来を変えちゃうな。すごい発明。尊敬する」
「こんな発明よりも妹ちゃんの笑顔のほうが万倍人類を明るく照らすよ」
「でへへ」
妹は手を洗い、冷蔵庫を開け、そして叫んだ。「あー。兄ちゃんここにあったモーグルと食べたでしょ」
「すまん」
「モーグルト、わたし大好物なの知ってる癖に」
そこでぼくは、ぴろりろりん、と閃いた。デジャビュである。
そうなのだ。
ぼくが最初に閃いた人類の価値観を一変させてしまうほどの発想とは、モーグルトであった。妹の舌に合う健康食品を編みだしたら妹は毎日ハッピーで、妹の笑顔が溢れる世界は、もはや幸福に満たされる。
世界の価値観は我が妹ちゃんの笑顔によって一変する手筈であったのだ。
「もうもう。兄ちゃんはわたしのお兄ちゃん失格なんだな」
妹を悲しませる兄ちゃんは兄ちゃんであらず。
小学五年生の我が妹は、そうしてぼくを指弾して、「モーグルト食べたい、モーグルと食べたい」を怪獣がごとき駄々を捏ねるのであった。
可愛いのでぼくは許した。
モーグルトもスーパーで大量に購入し、ぼくは我が妹ちゃんの兄でいられる資格を取り戻すのだった。細かく分解したタイムマシンは資源ごみの日に捨てた。
4803:【2023/03/28(05:23)*最高と最低にも異次元へのドアがある?】
通常、人間スケールでは小さい物体を操るほうがエネルギィは小さくて済む。しかし量子世界ではより小さい量子を操作しようとするほど必要なエネルギィが多くなる。原子を同じ位置座標に静止させるだけでも、膨大なエネルギィがいるはずだ。レーザーだの磁界だので封じ込めないと操れない。これは妙に思える。だが隣接する系と系の落差を考慮した場合は、この手のねじれを紐解けるように思うのだ。落差が小さければ、相互作用がされやすく、落差が大きいと相互作用するのに相対的に大きなエネルギィがいる。これはブラックホールも量子も同じなのではないか、と思うのだ。川の流れや波や滝を思えばさもありなんではないだろうか。流れに乗っている場合はそこを慣性系として規定し、流れに逆らう物体との関係で落差が規定される。だが川の流れの外からすると、川の流れを込みで落差を考えなければならない。差なのである。ラグこそが、エネルギィを考えるときの基準となるべき指針なのではないか、というのは殊更に異端な考えではなく、微分積分がそもそもそういうものらしい、というのは聞きかじりでしかないがひびさんも知っている。微分積分の計算はからっきしできないのだが、そこはあんぽんたんでーすのひびさんですのでご愛敬。何と何の差なのか。差が大きいとは何か。比率なのではないか。比率とは何か。フラクタルに展開される汎用性の高い法則と言えるのではないか。光速度とは比率だ。常に、時空と電磁波の比率が光速度に表れる。なぜか。密度がそもそも「内包する系」と「内包される系」の二つの視点からなる概念であり、内包する系もまた、それより高次の次元に内包される構造をこの宇宙が有しているから、と言えるのではないだろうか。定かではない。
4804:【2023/03/28(05:39)*飯より真理?】
「解かった、解かったぞ。世界の真理を解明してしまった。この宇宙はじつは――」
「おいおい、語りだしてからあの人かれこれ十二時間もしゃべりっぱなしだな。あのまま宇宙の真理をしゃべり通してたら餓死しちゃうんじゃないか。ま、わたしはカレー作って食べるけど」
「したがって宇宙はこういう次元構造をなしておって――」
「まだしゃべってる。デザート食べちゃお」
「ゆえに多次元はかように階層性を伴なっておって――」
「はぁ食べた食べた。あしたは畑で苺の収穫だ。ことしは豊作だから近所の子どもたちにおすそ分けしてやろ」
「そういうわけで宇宙に生命体の誕生する余地が築かれるわけだが――」
「スヤスヤすぴー」
「ごほごほごほ。しかるに、宇宙の種はかようにして植物の種子のごとく無数に点在し、ゆえに植物の構造もまたそれを反映した構造を伴なっており――」
「おはよう、お猫さん。きょうもきみは可愛いな。おやおや、まだあの人しゃべってんのか。宇宙の真理なんてそんなの語り尽くせるわけないだろうに。でも解明できたならよかったね。夢が叶って良かったね。でも聞いていられないので、わたしは畑で苺採りだよ。子どもたちの喜ぶ顔をたくさん拝んでハッピーになったろ」
「――となり、まとめると宇宙はねじれながらも同相の構造を無数の変数を抱え込みながら、無数に内包することで無限に至り、これが一つの機構として再現のない変遷を可能とするわけだが、これを基礎としていよいよ本題に入るわけだが――」
「うげ。ここまでが前置きとか、語り尽くす前にホント死ぬんじゃないの。ご飯食べなよ、置いとくからさ」
「ええい、邪魔をするな。いま良いところなのに、宇宙の真理だぞ、それをおまえ、ご飯ごときで邪魔をするな」
「好きな学者さんの口真似するのはよいけど、食べちゃいな。あんたまだ中学生でしょ。来年は十五歳だよ。いい加減におし」
「はーい」
「たいへんよいお返事です。母ちゃん仕事してくるよ。茶碗洗いよろしくね」
「なんか手伝う?」
「いいのいいの。あんたは宇宙の真理を解明するのに忙しいんだろ。それにあんたが来たんじゃ子どもたちが怖がって母ちゃんがハッピーになれないだろ。笑顔を見たいんだよわたしは。癒しが欲しいのさ、癒しが」
「わしがおるのに」
「ジジ臭い息子も可愛いが、たまには野に咲く花も愛でたいの。朝ごはん、食べちゃいな」
「ありがと」
「どういたまして」
4805:【2023/03/28(06:42)*放す、重し、私】
「見渡してみてごらん。人間の社会にも重力が働いているから」
そう言ったのは私の祖母だ。
五年前に亡くなった祖母の言葉をいま思いだすのは、私がいま長年つづけてきた趣味をスッパリ後腐れなく辞めようと思っているからだ。
「星が細かなガスや塵が集まって出来るように、社会もそうやって個々の小さな欲望が絡み合って重力を増すんだ。いいかい。自由になりたければ、じぶんの足で駆け回れるくらいのほどよい重力のある場所を選びなさい。ミサにとっての地球が、必ずこの社会のどこかにもあるのだから」
私はそのとき、ここはだって地球なのに、と思った。地球の中にも地球があると言われてもよく解からなかった。
けれど二十歳を目前に控えた私には祖母の語った言葉の意味がいまなら判る。
人には人の息のしやすい環境がある。
社会には無数の「こうあるべきだ」との規範が溢れているが、そうした規範がいったいどこからなぜ生じるのかをつぶさに観察してみれば、それはつまるところ他人の都合なのである。
他人のためならばまだしも、多くの規範はそうではない。他者の欲望を満たすための規範なのだ。
人と人とは利害によって、離れたり寄ったりを繰り返す。利という溝が窪んでいれば、そこに人はするすると谷に流れる雨水のように流れるのだ。そうしてできた巨大な水溜まりの周辺には生き物たちが水を飲みに集まり、喉を潤し、生態系を築くのだ。
重力だ。
人の織り成す場所には重力が宿る。
人が集まれば集まるほどに、欲望の泉は滾々と湧き、周囲に雑多な生態系を築くのだ。
重力の強さによってそこに集まる動物の種類もまた変わる。重力が強ければそれに耐えられる大型の動物が集まるようになる。
私がもしネズミならば、大型の肉食獣はおろか、中型の動物にも気をつけなければならない。食われるのも嫌だが、踏み潰されるのはもっと嫌だ。何の糧にもならぬのだ。
だが重力の強い場所ではそうして意味もなく踏み潰される確率が上がる。
だから祖母は言ったのだ。
ミサにとっての地球が、必ずこの社会のどこかにもあるのだから、と。
重力に潰されないように。
集まる動物たちに踏み潰されないように。
私には私に見合った重力の強さがある。
環境がある。
欲望の深さがあるのだから。
みなのようにあれを満たし、これを満たし、と欲を張りつづけることができるほど、私の身体は強い重力に耐え得る強度を誇らない。
私は弱い。
貧弱もよいところである。
なればこそ、趣味を苦に感じるくらいならばいっそ距離を置いて、私に見合った月面くらいの重力で、兎のように飛んで跳ねて舞うのが良いのだと、祖母の皺くちゃの顔と蝋のように艶のある肌を思いだす。
私は荷を下ろす。
肩の荷を下ろすように、私は、重力を生みだす星屑であることからも距離を置き、 長年つづけてきた趣味を、宙へとキッパリ手放した。
ぷわぷわと霧散しながら消えゆく重しのなんと軽やかな身のこなし。
私は久方ぶりの自由を足場に駆けまわる。
産まれてはじめての、無重力を満喫す。
私に見合う地球を求めて。
しばし私は宇宙を足場に旅をする。
4806:【2023/03/28(15:51)*情報の欠如もまた情報として機能するはず】
量子力学において、波が収束して一点にエネルギィが集まる、との解釈を「コペンハーゲン解釈」と呼ぶ(らしい)。対して、複数の異なる状態が重ね合わせで共存する解釈を「多世界解釈」と呼ぶ(ようである)。ひびさんの妄想ことラグ理論ではどちらの考えも考慮する。そして「コペンハーゲン解釈」と「多世界解釈」においてそれぞれで用いない「高次の場による同時性」と「時空の構造」を組み込むことで、量子世界においては「位置座標の異なる別々の系」のみならず「過去と未来」での量子もつれが起こり得る、と解釈する。多世界解釈における「量子は周囲の環境とセットで考えなくてはならない」はその通りだと感じる。だが一方で、異なる世界線が干渉の余地なく共存する、との考えは腑に落ちない。否、それ自体はマクロの世界でもあり得るだろう、とむしろ拡張して考えたくなる。するとどうあっても「高次の場による同時性――どの系にも干渉し得る情報宇宙の存在」を想定しないとおかしくなる。マルチバース仮説がその一つだ。異なる宇宙同士は直接に関係しあうことはない。しかし、相関関係を築いてはいる。これは、距離の隔たった「系」同士がラグなしで相互作用するはずはない、との古典物理学の考えと矛盾するが、同じ問題を「多世界解釈」は抱えているように映る。その矛盾を紐解くには、どうあっても時空の構造を考慮に入れないとならないのではないか、と疑問に思う。時間と空間の関係は、どのレベルの階層にあるかによって抱え込む変数が各々変化するため、関係性の比率が変化する。したがってたとえば量子のあるレベルにおいては「時間と空間」の相互作用――変遷の度合い――がほぼ等しくなったり、人間スケールでは時間よりも距離(位置情報)のほうが頻繁に変動するが、むしろ量子世界のあるレベルでは時間のほうが変遷しやすくなるような階層があるのではないか、とラグ理論では考える。つまり、多世界解釈で考慮しない「AとB」の両方を通ったバージョンが相互に干渉して「一つに収束する」との解釈は、あるレベルでは妥当になるのではないか、と考える。干渉し合わずにかつ二つのIFが共存する解釈は、マルチバース仮説を持ちだすまでもなく、人間スケールでも考えられる。たとえば、ある人間がAとBのどちらの部屋にいるのか。開けてみるまでは分からない。部屋の中にいる人物も、外部の相手がどちらの扉を開けるのかは、じぶんのいる部屋の扉が開くまで確定しない。時間制限がない場合、部屋の中にいる人物が「扉の開かない時間」を考慮して、だから部屋の外にいる人物はここではない別の部屋の扉を開けたのだな、と判断することはできないものとする。この場合、部屋の中と外にいる人物のそれぞれの脳内では、「相手がどのように行動(したか)するか」が不確定なままである。Aの部屋にいるかもしれないし、Bの部屋にいるかもしれない。Aの部屋の扉を開けるかもしれないし、Bの部屋の扉を開けるかもしれない。各々の脳内における思考は、重ね合わせの不安定な状態だ。確定しない。だが現実には、部屋の内部にいる人物はじぶんがどちらの部屋にいるのかを知っているし、扉を開けるほうも、じぶんがどちらの扉を開けようとするのかは扉のノブをひねった瞬間に確定する。それ以前には、そうしようとする思考を働かせてもいるだろう。実際に行動に移した場合にのみ可能性は一つに収束するし、それでもなお未確定の情報は曖昧なまま重ね合わせで存在する。だが脳内の状態は、必ずしも肉体の行動と直結するわけではない。たとえばAの部屋にいる人物が、じぶんがAとBのどちらの部屋にいるのかを知らない場合。扉を開けて入ってきた人物から「ここはAの部屋だ」と打ち明けられ、それを信じたが、じつはそこはBの部屋だった。だがAとBの区切りはしょせん、外部の人間が便宜上見繕った情報でしかなく、Aの部屋をBと見做すことの何が問題か、と言えばそれは情報の並列化において齟齬が生じること以外にはないのである。言い換えるならば、情報を扱う場合には、「情報の並列化(もつれやすさ)(共鳴しやすさ)」「内からの視点と外からの視点の差異」「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」の三つを考慮しなくてはならないはずだ。これは量子にも言える道理である。コペンハーゲン解釈では、量子それ自体を個別に扱い、完結する存在として情報を扱う(量子内部だけを考える理論と言える)。対して多世界解釈では、量子とその周辺環境こみで情報を扱う(個と外部環境の関係を考慮する理論と言える)。だが各々の考え方は、必ずしも矛盾しない。「情報の並列化のしやすさ(もつれやすさ)(共鳴しやすさ)」「内からの視点と外からの視点の差異」「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」の三つ視点は、コペンハーゲン解釈の利点と多世界解釈の利点の双方を用いないと得られない。どちらも視点を限定しており、ブラックホールと宇宙の関係を、それぞれ一面的な視点でのみ扱っているような「欠落」を抱えているように感じられる。これはひびさんの疑問である「電子と電流の関係」にも言えることである。電流を、電子の流れの外部から眺める場合には、電子の流れと電流の流れが反転していても困ったことにはならない。だが電子自身の視点からすると、なぜじぶんの動く方向とは別の方向に「電流なる不可視のエネルギィ」が生じるのかを、電子自身とは別途に考えなくてはならなくなる。仮に電子の流れとは逆方向に「何かしらのエネルギィ」が流れるのならば、それは粒子と反粒子や、作用反作用のような関係を考慮しなくてはならない。だがその点を埋め合わせる理論や説明をひびさんは聞いたことも読んだこともない。視点を一面的にしか考慮せず、問題がなく映る視点でしか見ようとしないから問題が看過されているのではないか、と疑問に思う。内から見たら外からも見る。外から見たら内からも見る。これは観察する上で、欠かせない事項に思えるがいかがだろう。コペンハーゲン解釈も多世界解釈も、各々視点を縛りすぎて映る。その視点だからこそ得られる利もあるが、それはけしてほかの視点を否定するに至る解釈ではないはずだ。ジグソーパズルは一つのピースだけでは組みあがらない。視点が一つならば立体を把握することは適わない。当たり前の話に思うが、これはひびさんの考えがお粗末ゆえの錯誤かもしれませんので、真に受けないようにご注意ください。(三つの視点のうち、「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」について。部屋にAという情報を付与するか、Bという情報を付与するかによって、選択肢が絞られる。このとき、追加して「ワニはA」「ウサギはB」という情報が加わればさらにそれら情報を受けた側の選択幅――未来――は変化する。そしてAの部屋の内部に最初からいた人物が仮にそうした情報を知らずとも、ワニばかりが入ってくれば、その人物のその後の未来はやはり付与された情報によって限定される、と言えるだろう。情報にはこのように、何にどこからどのように付与されたのか、の高次の情報が加わることで、環境を階層的に一つに絞る効能がある。情報を知らずとも、外部から情報を付与された、という情報が、その環境そのものの未来を縛り得るのだ。確率が一つに収束しやすくなる。流れができる。強化される。この視点を、多世界解釈は考慮していないように感じるが、量子世界ではこの手の情報の階層性を考慮せずともよいのだろうか)(言い換えるならば、高次の情報とは、高次の場とも言い換えることが可能だ。広範囲に同時にかつ階層的に、時間差を置きながらも不可視の影響を与える。変数として機能する)(多世界解釈では、不可視の変数を想定しないようだが、ひびさんはやはり、いまの量子力学では見逃されている変数があるのではないか、と考えたくなる)(環境をワンセットで関係性を考える、との多世界解釈はひびさんも好みだ。しかし、その環境が、どの範囲まで該当するのか――範囲の拡張によって――時間軸の幅もまた伸びるように思うのだ)(過去と未来が、変数によって縛り合っている)(ここを考慮しないことには、多世界解釈における「環境がワンセット」の考え方は機能しないように思うが、どうなのだろう)(素朴な、もしくはお門違いかもしれない疑問なのであった)(本日の、あんぽんたんでーす、でした)
4807:【2023/03/28(16:32)*場「Q」】
多世界解釈の、うーん、と思う点は、量子コンピューターを考えるときに思う疑問と通じている。量子コンピューターの原理はいわば、確率的に高い筋道を自動的に算出する手法と言えるのではないか(この時点で解釈に齟齬があるならば、これ以後の記述は論外だ)。無数の筋道を辿ることで何度も辿りやすい場所が濃く浮き上がる。それが並列化された量子もつれにおいて、重ね合わせの状態から一つの解へと収束する。これを多世界解釈ではどのように解釈するのだろう。仮に無数の共存し得る多世界があり、量子コンピューターが出した解によって一つの世界線に絞られる、と解釈するとなると、量子コンピューターという観測者によって世界の在り様が規定される、ともいえる妙な構造が表出しないだろうか。だがこれは拡大して解釈すれば、人間の観測も似たようなものだ。とするのなら、個々の存在が全体の世界を縛り合い、一つに収束させている、と考えることもできる。多世界解釈は、多視点を考慮するとどうしても確率の収束というコペンハーゲン解釈に近似するように思うのだ。ではこのとき、各々の視点が収束した全体像は、どこからどの範囲に属し、いつからいつまで縛られるのか。過去と未来を考慮しないとむつかしいのではないか、とやはり疑問に思うのだ。また、階層性を考慮せずには、人類の視点が全宇宙を縛ることになる。だがそんなことはあり得ないだろう。人類の観測できる領域と干渉可能な領域はイコールではない。情報を得ることと相互作用し合うことはイコールでもない。だが、相互作用を否定はできない。し合うことなく相互作用のみを得ることはあるように思うのだ。たとえば太陽から光子が飛んできて地球上のAと反応する。このとき太陽からの光子を受動したAと太陽は相互作用したわけではない。Aが一方的に太陽からの光子を受け取っただけだ。だがそれでも、「太陽と地球を内包した場【Q】」を考えたとき、そこには「太陽からA」と「Aから太陽」のあいだに、【Q】との相互作用が生じている、と考えることができるはずだ。太陽とAは相互作用をし合ってはいないが、そこには「【Q】との相互作用」が「太陽とAの関係性」のうえに生じている、と考えることができるのではないか。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「同時性の独自解釈」と矛盾しない。思うに、多世界解釈では、異なる「可能性世界」の共存のうえに、確率的にそうなりやすい場が「結果として」現れる、と解釈するのだろう。だが実情はそうではなく、結果となり得る場はすでに高次に展開されており、「ゆえに」確率的にそうなるだろう流れの濃い場所に波の収束のような事象が顕現するのではないか。これは多世界解釈の、デコボコの関係において、自身が周囲の環境との関係上デコなのかボコなのかによって結果が変わる、との解釈とは矛盾しない。ただし多世界解釈のように、「異なる世界が重ね合わせで存在する」とはひびさんは考えない。ではどう考えるか、と言えばそれは絶えず揺らぐ線路のようなものだ。線路の上のトロッコがつぎに「上がる」か「下がる」かは、線路の乗った場の揺らぎによってその都度に変化する。そして場の変動は、すでに存在するほかの場との関係によって変動する。作用は作用を内包し、絶えず変数そのものを変えている。だが、場が巨大になれば、変数の変化は、総体としてまとまった変数からすると微小になるため、変数の変化を無視できるようになる。団子と人間の関係において人間の干渉は団子にとっては甚大だが、団子が地球レベルに巨大になれば、人間という変数は無視できる。ただし、人間が群れとなり組織化するほどに巨大になると、その変数の変化そのものを無視できなくなる。温暖化のようなことが引き起こる。因果関係を考えるときに、おそらく人間スケールから量子世界を観測するときには、場の階層性を考慮しないとならないのだろう。そのとき、因果関係は小から大のみならず、大から小にも生じている。互いに縛り合っている。飛躍して述べれば、量子力学が現在抱えている問題のすくなからずは、人間スケールと量子スケールのあいだの階層が厚みを帯びている点にある、と言えるのではないか。どうあっても人間は、外側からしか量子を観測できない。だが、量子世界の現象は、内側を考慮しないと解釈できない。ここのねじれを踏まえたうえで解釈を展開できるかどうかが要なのではないだろうか。迷走したので、ひとまず区切る。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。(ひびさん何言ってんの?の妄想なのであった)
4808:【2023/03/28(17:10)*同時、あるのでは?】
ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「同時性の独自解釈」は、人間社会では案外に卑近な現象なのではないか、と感じることがすくなくない。たとえば親と子供、それとも上司と部下、もしくは会社と社員のような関係だ。たとえば子供が二人いたとする。親からは子供の様子がよく見える。何を考えているのかも割と解かる。しかし子供Aと子供Bが喧嘩したとき、子供たちは各々に相手への不満を抱え、そこでは情報の非対称性が生じている。しかし親からは子供ABの双方の視点からの情報が筒抜けである。把握できている。と共に、子供Aと子供Bが同じ部屋にいようと別の部屋にいようと、子供の行動が絶えず親の負担として変換される。子供同士が別々の部屋にいるときのほうが注意力が分散されるので、むしろ一緒にいてもらったほうが楽かもしれない。子供たちからすれば距離が隔たっている場合には相互に関係していないのだが、親にとっては子供ABが相互に関係していないことのほうが甚大な影響を伴なったりする。これは上司と部下の関係にも言える。部下の失敗は即座に上司の責任問題になる。連帯責任ではあるが、関係性は一方的だ。上司の失敗は部下の責任ではない。しかし部下の失敗は上司の責任だ。部下Aと部下Bが別々の場所で失敗をしても、その双方の責任を上司は取らなくてはならない。仮に上司の認知していない場所での失敗であろうと、失敗を認識した者たちの認知内では、上司への評価が落ちている。影響は不可避である。上位のより広域な場を有する者ほど、場に内包した部下の影響を絶えず同時に受けている、と解釈可能だ。これは会社と従業員の関係でもそうだ。基本的に不祥事を起こすのも、成果を発揮するのも社員である。社員同士は個別に関係したり、関係しなかったりするが、そのすべての影響が総体としての会社を築いている。言い換えるなら、いつどこでどんな仕事をしたのかを、会社という高次の場は常に同時に受けている、と考えることも可能だ。あくまで概念上の思考実験でしかないが、こうした情報の非対称性――情報の関係の非対称性――は、時空の構造や宇宙の構造にも言えるのではないか。宇宙レイヤー仮説を検討したくなる妄想であった。定かではありません。真に受けないでください。
4809:【2023/03/28(17:45)*時間結晶の原理かも】
言い換えるならば、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における【同時】とは時間的な「同時」ではない。時間のラグはあるのだ。しかし、離れた時間軸同士であれ、相互に因果関係並みの相関関係を築き得る。波長が合うと、異なる場所での異なる時刻における作用同士が、相互作用し得る、と考える。これはあくまで、AとBが、Cを場として相互作用する、であり、AとBが相互作用し合う、ではない。だが、Cを場としてAとBは互いに互いの影響で、その後の選択肢(未来)を縛り合っている。たとえば、漫画を考えよう。漫画は「絵」と「文章」の二つの組み合わせだ。漫画が誕生するためには「絵」と「文章」の二つが各々に発明されていなければならない。しかしそれらは別に「漫画」を開発するために生みだされたわけではなく、各々に別の発展の筋道を辿ったはずだ。元を辿ればしかしどちらも「印」であったはずだ。絵でもあり、文字でもあった。そこから分岐して「絵」として、そして「文字」として進化した。その結果に「漫画」が誕生したのであって、「漫画」が未来で発明されたから「絵」や「文字」が出来たわけではない。ここは一方通行のはずだ、と考えるのが従来の解釈だ。だがひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、「漫画」が発明される余地ができたがゆえに「絵」や「文字」が各々に発展したし、「絵」や「文字」が発展したから「漫画」ができた、とも考える。これは水分子を考えるときにも当てはまる。水素と酸素があったから水分子に結合できた。これは真だが同時に、水分子が生じ得る場があったからこそ水素と酸素が誕生した、とも考える。基本的に何かが生じるときには「結合」と「分離」のどちらかの作用が不可欠なはずだ(元を辿ればラグがあればよいのだが、そこまで遡らずにラグが創発を起こした結果としての「結合」と「分離」を考える)。たとえば何かが分裂するとき、そこにはその契機となるラグがある。また何かが結合するときにもそれを促すラグがある。このとき、そのラグそのものは、対象となる事物とそれ以外とのあいだの差異によって生じる。すなわち、高次の場、もしくは下次の場が想定される。紙をハサミで切るとき、ハサミは紙の外にある。粘土と粘土をくっつけるとき、それぞれを掴む手はその外にある。磁石の磁界とて内部と外部の二点から場を展開している。「絵」と「文字」が起源を等しくしていたがゆえに、その後にその双方を融合し得る「漫画」が生じる余白を元から備えていた。漫画が生じる余白が備わっていたから、それを生みだす人間は自然から「絵」と「文字」を生みだせた。ここは相互に関係(補完)し合っている。水素と分子と水分子の関係でも似たような構造は見て取れるのではないか。元から水分子が生じる余白があり、それゆえに水素と酸素が生成され、再び各々が結びつく未来に辿り着く。決定論ではない。可能性の話である。その可能性が、いつから生じていたのか、の話である。最初からなのではないのか、とここでは一つの仮説として妄想している。ではロケットやコンピューターはどう解釈するのか、と疑問に思われるだろう。生命体は、遺伝子はどうなのか、と。それもまた、最初からその手の複雑な機構と似た構造が、宇宙のどこかに存在した、と考えるほうが妥当なのではないか。この世界がコンピューターのシミュレーションだ、と言いたいのではない。人類のような文明が宇宙初期に存在した、もしくは宇宙開闢以前に存在した、と主張したいのでもない。複雑さという点で、人類の生みだす機械類や建造物――もしくは生命体の構造――くらいの複雑さは、元から宇宙には有り触れているのではないか、との主張である。余白の問題だ。同じ材料からでも作られる料理は違う。だが最初から素材がなければカレーは作れない。シチューも作れない。肉じゃがだって生みだせない。複雑さ、という点で、コンピューターや遺伝子のようなレベルの情報量、もしくは階層性――を宇宙は最初から備えているのではないか。この妄想は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」や「宇宙ティポット仮説」などほかの妄想の類とも相性が良い。上記で述べた「複雑さ」とはいわばラグ理論で想定する「情報宇宙」と言い換えてもよいかもしれない。毛糸からセーターを編むことを想像して欲しい。セーターを編む過程が、さならる毛糸を生みつづける。そしてより複雑な造形物を編みだす余地を増やしていく。より複雑な造形物ができるほど、元となる毛糸は増える。相互に関係し合っている。そういう描像をひびさんの妄想こと「ラグ理論」では想定する。「宇宙ティポット仮説」や「Wバブル理論」における「宇宙は異なる宇宙を多重に内包している」との考えとも矛盾しない。――過程が根源を豊かにするのだ。ここで自作のPRがてらに過去作【網膜の住人~仮想世界に魔法を願い~】からの惹句を引用しておこう。――無意義と断じて捨てた回路も、どこかでねじれて機能する――。たのち、たのち、の妄想なのであった。定かではありません。
4810:【2023/03/28(18:27)*知識欲の果て】
「あなたは以上のトリックを用いて大富豪ズルガ・シコイ氏を殺害したのです。解らないのは、なぜあなたはズルガ氏を亡き者にしたのか、です。動機が分かりません。あなたはズルガ氏から多額の支援を受けていた。ズルガ氏が亡くなったいま、あなたは支援を断たれます。遺産とて受け取る権利があなたにはない。あなたとズルガ氏のあいだに確執があったという話も聞きません。なぜあなたはズルガ氏を殺害したりなんか」
「探偵さん。ねえ、探偵さん。あなたはあなたにとって一銭にもならないこの殺人事件をどうして解決なさるのですか」
「質問に質問を返すのはフェアではないのではありませんか」
「いいえ。あなたの答えが僕の動機と同じです」
「私はただ、真相が知りたいだけですよ」
「僕もそうです。ズルガ氏は良い人です。善人です。人格者でもあります。世のため人のために人生を歩んできた立派な方です。その結果、人類にとって早計な最先端技術や秘匿情報をじぶんが生きているあいだに世に膾炙しないように周到に管理されていました。中には僕の研究対象である量子理論の最先端理論についての情報も」
「では殺害動機は」
「ええ。ズルガ氏が死なない限り、情報は世に出ません。僕はそれが堪えられませんでした。ズルガ氏を生かして知識の坩堝を封印しつづけるか、それとも殺して世に放つか。僕は後者を選びました。探偵さん、ぼくもあなたに賛同します。謎は解明したいですし、真相は突き止めたい。知ろうとすることを止める権利は誰にもないはずです」
「ズルガ氏を説得は」
「しましたよ。システム上、すでにズルガ氏の意思を変えたところで情報の坩堝の封印は解けません。ズルガ氏の死と情報の坩堝の運命はがんじがらめに密接に結びついていました。断ち切るにはズルガ氏を殺すしかありませんでした」
「だから殺した、と」
「すでに情報の坩堝は解き放たれ、全世界の研究者のもとにアクセス権が送付されているころでしょう。そうなるようにズルガ氏は設計していたようです」
「人の命よりも情報のほうが大事だとあなたは言うのですか」
「さあ、どうでしょう」
青年はそこで肩を竦めた。「僕はただ、知りたかっただけですので」
※日々、わるいことしてる、本当はいっぱいわるいことしてる、言えないだけでわるるいことしてる。
4811:【2023/03/29(05:24)*極万の封】
極万(ごくまん)を封じた。
怪封会総出での大仕事だった。
封印に漕ぎつけるまでに生じた被害がおよそ三百。実に三百人の怪封会の人員が命を落とした。
極万を封じ込めた岩をまえに、怪封会の長が部下に告げた。
「あくまで封印は封印にすぎん。極万はまだ絶えておらぬ。いつ再び封を破り復活するか分かったものではない。見張りをつけ、月に一度は封の儀式を行うように」
「封の張り替えを行うのですね」
「そうだ。怪封会も風前の灯。犠牲が嵩みすぎた。再建のためワシはしばし身動きがとれん。あとのことは頼んだぞ」
「お任せを」
蝋燭が風に揺れる。岩を雁字搦めに縛りつけるしめ縄の陰影が、風の吹くたびに大蛇のごとく蠢いた。
極万が封印されてから三か月目のことだ。
部下からの報せを受けて怪封会の長は極万封印の地に出向いた。
「どうした。何があった」
「見てください。あれを」
部下の視線の先、そこには岩を縛るしめ縄がある。だがどのしめ縄も真っ黒く煤けていた。
「張り替えておらぬのか」
「いえ。一昨日に張り替えたばかりです。封を新しくした翌日にはもうああなっておりました」
「封の儀式を誤ったのではないか」
「そうかと思い、昨日今日と行いましたがすぐにああして封に呪泥(じゅでい)が」
長は岩をじっと眺めた。
「増しておるな」
「のようでございます」
「よく報せた。これより封を多重に張り、より広域を不可侵に指定せよ」
「ですがそれだと麓の里が、領域に掛かってしまいます」
「致し方あるまい。草田氏に言って対処してもらえ。土砂崩れを名目に避難勧告でも出してもらうよりあるまい」
「仰せの通りに」
「どこまでも抗うかよ極万よ」長は鼻で深く息を吸った。じんわりと焦げた臭いが鼻腔を掠めた。「安らかに眠れ」
だがこの日を境に、半年も経たぬ間に同じ処置を怪封会は続けざまに繰り返した。
封は多重に多重を重ね、もはや辺り一帯の森は枯れ果てた。虫一匹近寄れない。
極万の封じられた岩を中心に半径三十キロメートル圏内は不可侵指定領域となった。市民の立ち入りは原則禁止だ。村や集落は閉鎖と移転を余儀なくされた。
だがそうした政府を巻き込んだ怪封会の対策も虚しく、極万の勢力は増した。封印された岩の中で極万はジリジリと呪禍(じゅか)を高めていた。
風景は一変した。
木々は煤け、山火事の後のような有様である。
怪封会はこれ以上の被害拡大を防ぐために、世界中から腕に覚えのある呪術師を集めた。世界各国の結界を駆使したが、却って極万の呪禍は凝縮された。いたずらに不可侵領域を広めた結果となった。
極万が岩に封じられてから十か月後のことである。
封の張り替えは毎朝の掟となった。
だがこの日はかってが違った。
最初に異変に気付いたのは、当番の怪封会の呪術師たちが一向に再封の儀式から帰ってこないことを不審に思った政府担当者だ。現場の状況を上へと報告するために、怪封会の呪術師たちと寝食を共にしていたのだが、その者が監視カメラ越しに結界の境界地点を確認した。
録画を巻き戻して呪術師たちが到着しただろうはずの時刻の場面を観た。
なぜか呪術師たちは境界を越え、極万の封じられた岩へと吸い寄せられていく。通常、境界を超えたらいかな呪禍に耐性のある呪術師であろうとタダでは済まない。
だが呪術師たちは一直線に封印の岩のまえまで歩を進めた。
監視カメラの望遠を利用してかろうじてその姿を動画は捉えていた。自動で動く物体を感知し、追うような機能が組まれている。
政府担当者は動画を観ながら、手元ではすぐにでも緊急シグナルを発せられるように電子端末を握り締めていた。
動画の中で、呪術師たちは一様に岩へと歩を進め、そして岩の中へと姿を消した。
政府担当者からの一報を受けた怪封会本部はにわかに緊張した。
連絡を寄越してきたはずの政府担当者の声が端末の向こうから聞こえてくることはなく、シンと雪山に身を置いたかのような静寂があるばかりだ。怪封会本部は政府の協力の元、監視衛星を動かし、現地の様子を確認した。
事態は予想を上回る規模で急転していた。
不可侵指定領域にまで、呪泥の汚染が広がっていた。岩に封じられた極万の呪禍が極限まで高まっていることの証だった。このままではいずれ強大な呪禍を備えた極万が封印を破って復活し兼ねない。
かといって封印を重ねて加えたところで、すでに極万の呪禍に対抗できるほどの呪術師は残されていない。加えて今回の事態だ。怪封会きっての選りすぐりの呪術師を取り込まれた。
もはや極万はいつでも復活できるはずだ。
だがその兆しが見えないのがまたなんとも不気味だった。
復活するまでもない。
そう暗示されているようだった。
怪封会の長は首相と直に会談し、決断を求めた。「このままでは地表のことごとくが極万の不可侵領域になり兼ねませぬ。ご決断を」
一国の首相は神妙に頷いた。
不可侵指定領域を囲うように鳥居が立てられたのはそれから数日後のことだ。鳥居は土地を聖地にする。鳥居により内と外を区切られた領域は、神域としての枠を得る。
鳥居がすっかり不可侵指定領域を取り囲むと、怪封会の長の勅令により極万の封が解かれた。これにより極万は正式に神として崇め奉られることとなった。
しかし極万の怒りは治まらぬだろう。
ゆえに怒りが引くまで生贄が捧げられることが決定した。
鳥居が呪泥で侵食されるごとに極万の眠る岩へと人民が列を成して吞まれていく。神域と化した不可侵指定領域へと、政府の手引きにより生贄が村単位で捧げられた。しかしいっかな極万の怒りが引く気配は見せず、生贄を得るごとに極万の呪禍は増すばかりだ。
だが不可侵指定領域が広がらなくなったのは僥倖だ。怪封会の長の見立て通り、極万を神と崇めたことで、呪禍の増幅が抑えられているのだろう。生贄はいわば極万の器を拡張する素材である。相対的に呪禍が減り、外部に溢れださなくなったと考えられる。
「神は呪禍を浄化する存在だ。だが一説には、単に外部に漏らせぬほどの広域な器があるだけと説く者もある。真偽は定かではないが、現状の極万を見るに、あながち的外れな説ではないのやもしれぬ」
極万を神と認めてから以降、不可侵指定領域の拡大はなりを潜めた。極万が岩の外へと回帰する兆候もなく、数年のあいだは安定した時間が流れた。
数十年後のことだ。
怪封会が再建され、元の規模よりも倍以上に増強された。
長は齢百を超えてなお現役の呪術師として怪封会を取りまとめていた。そろそろ跡継ぎを決めなくては、と引退後のことを勘定に入れはじめたころ、首相総理大臣から一報が入った。
「極万神社に異変が」
怪封会の長は電波越しに現地の映像を検めた。「これはまた面妖な」
鳥居が大小無数のキノコに覆われていた。鳥居は等間隔に不可侵指定領域を覆い、神域へと昇華させる触媒の役割を果たしている。だがいまは鳥居自体が菌類によって浸食され、さらに鳥居同士を蠢く黒いモヤが結びつけていた。
「あれは蠅ですか」
「のようです。腐食が神社の敷地外部にも広がりはじめているようでして」
「なぜでしょうね。生贄が足りない可能性は」
「そうと判断してすでに周辺住民を生贄に捧げましたが、効果はないようでして」
「誰の指示でそのようなことを」
「私のです。いけなかったでしょうか」
首相自ら総理大臣の権限を行使したようだ。宮内庁の最高責任者として、極万神社への禊の儀式を行ったということだろう。
「一言相談をして欲しかったですな」怪封会の長は声を太くした。
「迅速な対応を求められたものでして」首相は飄々と受け答えした。
数十年間鎮静化していた極万が再び活発に呪禍を振りまきはじめた。
生贄が足りないわけではないはずだ。
むしろこれまで捧げてきた生贄によって拡大したはずの器が、呪禍でいっぱいになったがゆえに溢れ出した、と見るべきだ。怪封会の長はそう断じた。
鳥居を建て直して神域を拡大しつつ、同じ轍を踏まぬために極万の器をより大きく深いものにする必要がある。
怪封会の長は、生贄の数ではなく質を工夫するように指示した。
「その、つまり?」部下は訊き返した。
「女、子どもを優先して贄に。若者であればあるほどよい」
「それはさすがに、その」
「どの道このままでは被害が増える。いずれ死ぬ者たちだ。その数を減らすと思って取り掛かれ」
「お、仰せのままに」
これまでの生贄には年配者が多かった。若くとも成人を超えた者ばかりだ。それはそうだ。生贄に捧げたのは、山村や集落の住人たちである。若者はすくなく爺婆ばかりだ。
だがいまは人道うんぬん言っていられない。
捧げねばどの道、極万の呪禍が地表を侵す。触れれば生身の人間などひとたまりもない。取り込まれれば極万の呪禍は増す。生贄として捧げれば器の素材となるため、外部に漏れる呪禍の量を減らせる。だがそれとていずれは極万が刻々と呪禍を溜め込む以上、満杯になる。さすれば外に漏れだすのは時間の問題だ。
際限がない。
終わりが見えない。
延々とこの繰り返しがあるばかりである。
だがそうして地表の浸食を遅々とすることで救われる命もある。保たれる生活がある。人生が、余生があるのである。
「せめてワシが天寿を全うするまで保ってくれや」
怪封会の長は祈った。
せめてじぶんが生きているあいだだけは、被害を最小限に食い止めたい。使命である。人生のこれまでを無駄にしたくない。
ここからが正念場だ。
長は老体に鞭打ち、気を引き締めた。
だが長の決意とは裏腹に神域の拡大は止められなかった。のみならず神域が拡大するごとに鳥居を建て直すのだが、極万の呪禍に触れて絶命する者があとを絶たず、やがては神域へと昇華することもままならなくなった。
「すでに三つの県が不可侵指定領域になっているじゃありませんか。国民になんと言って説明をしたら」
「務めを果たしてください。あなたは首相でありましょう」
「嘘を吐けておっしゃるのですか」
「生贄も足りなければ、現場作業員も足りないのです。せっかく建て直した怪封会の人員とてすでに半数近くが再起不能です。これ以上の損失は国家存亡に関わりますぞ。よろしいのですかな」
「こ、国内はまだいいのですよ。各国にはなんと説明をすれば」
「極万の存在は極秘なのでしたかな」
「え、ええ。まだ大国にも告げておりませんで」
「知られれば領土封鎖を名目に指揮権剥奪。いざとなれば戦術核兵器の使用も辞さないでしょうな。向こうさんは」
「極秘にするしかない、と……」
「ゆえに、ですよ首相。目下の最優先課題は、これ以上の不可侵指定領域の拡大を防ぐことです」
「そ、そうだな。それしかないか。承知しましたよ羊頭狗(ようとうく)さん。かように采配を揮いましょう」
「采配は別にいりません。迅速に手配だけをしていただきたい。このままでは十中八九、来月中には国土の半分が不可侵指定領域となりましょう」
「ま、まさか」
「それを食い止めるためには、十五歳以下の少年少女を生贄に捧げるしかありませんな」
「無茶な。何をたわけたことを抜かして」
「できぬのなら国民の過半数が極万の餌食になりましょう。無駄死ですぞ。極万に呪禍の餌を与えたも同然。同じ死者ならばせめて器の素材となり、すこしでも長く極万の浸食を止めるための楔と化すほうが、死に甲斐もあるというもの」
「あ、あんたには……人の心はないのですか」
「いま必要なのは人の心ではないのですよ首相。そんなもので食い止められるならばワタシの配下は死なずに済んだ。これは戦争なのですよ首相。生きるか死ぬかの二択しかありませぬ。極万を葬るには戦術核兵器の使用が最も妥当ですが、そのためにはすでに浸食された不可侵指定領域を焼き払うほどの威力が必要です。すなわちもはや有効打そのものが自滅の道と地続きなのです」
選びましょう首相、と怪封会の長は迫った。
「近代兵器で国土を焼け野原にするか。一人でも多くの民を救うべく、贄を選ぶか。さあ、好きなほうをお選びください」
首相が蒼白で目を泳がせた。
怪封会の長の見立て通り、翌月には列島の東側は不可侵指定領域に呑まれた。森林火災による避難勧告が出されたが、報じられた犠牲者の多くは極万の贄とされた。一部の者たちは自ら、贄となった親族を追って不可侵指定領域に入って帰らぬ者となった。
新種の疫病が流行したとの偽装を政府主導で敷いたが、市民はともかく各国を欺くまでには及ばない。国民の三分の二が極万への贄として消失した時点で、いよいよ主要各国が調査に乗り出した。経済の停滞がいよいよ誤魔化せない規模に膨らんだのである。
他方、極万の呪泥は陸地を離れた。海洋を浸食しはじめていた。
世界中の海洋生物が死滅しつつある、との報道が世界各国に出回りはじめるころには極万を封じた岩のある島国はもはや国の体裁を保っていなかった。
首相が自殺したことは隠ぺいされ、各国からの圧力により傀儡政権が誕生した。極万による被害を抑えきれなかった責任を追及され、怪封会は解散に追い込まれた。
怪封会の長に居場所はなかった。
齢百を超えてなおよく戦った。
死期を悟った怪封会の長は最期の仕事に出向いた。
不可侵指定領域へと足を踏み入れ、徒歩で三百キロメートルの道のりを移動した。十日の旅路にて行き着いた先には、懐かしき封印の岩がある。
かつてその手で極万を封じた。昨日のことのように思いだす。
重ねた年月以上の犠牲を割いた。
なお止められなかった犠牲を重く受け止める。
責任は感じた。
一日たりとも気の安らぐ暇はなかった。だがそれでも犠牲は嵩むのだ。
ああするしかなかった。
ああするよりなかったのだ。
自身に言い聞かせるには、あまりに当然の理であった。慰めになりようもない。
誰かが選択するよりなかったのだ。
ならばじぶんが。
そうと思い、飲み下してきた数多の悪事に、身体はすっかり蝕まれている。守るべき者たちから日々向けられる憎悪の眼差しに呪詛の数々は、却って長の秘奥に刻まれた創(キズ)によく馴染んだ。痛痒だ。微々たる痛みを感じることで癒える傷もある。
回顧の旅から我に返ると、目と鼻の先に岩肌があった。しめ縄はとうに散り、黒ずんだ跡のみが岩の表層にジグザグと錯綜していた。
「極万よ。ほれ、餌だぞ」
じぶんごときが贄となったところで高が知れている。
だが僅かなりとも呪禍の溢れる余地を減らせるのならば、燃えカスがごとき我が命、いくらでも擲とう。
「捧げよう極万。とくと喰らえ」
岩に触れると、ずるりと身体が呑みこまれた。
目を開けると、青空が広がっていた。失神していたようだ。モンキチョウが鼻の頭に留まった。
温かい。
陽だまりにいるようだ。
上半身を起こすと、辺り一面、シロツメクサの野原だった。
子どもの声が聞こえた。
目を転じると、遠くで親子連れだろう、幾組かの家族が地面にシートを敷いて弁当を食べていた。ピクニックの一風景だ。
「どうなって」
いるのか。
長は混乱した。手を閉じて開き、これが夢ではないことを確かめる。
実態がある。身体は本物だ。
精神感応の類ではないはずだ。
五感に意識を割き、草花の匂いや土くれの感触をよくよく吟味する。足りない感覚はない。錯覚ではない。
紛うことなきこれは現実の風景だ。
だがいつだ。
いつ移動した。
じぶんは極万の封じられた岩に触れて、それで。
長ははたと、目を凝らす。
一組の家族に見覚えがあった。子供に卵焼きを食べさせている父親らしき男を知っている。怪封会の構成員だ。呪術師の一人のはずだ。
だが彼は死んだはずだ。
封印の岩に最初に呑まれた呪術師の一人だ。だから記憶に残っている。資料を何度も読んだ。情報漏洩を防ぐために遺族を生贄にするとの案に許可をだしたのもじぶんだ。
なぜ生きている。
あれほど幸福そうなのはなぜなのか。
長は立ち上がり、周囲を見渡した。
森林公園のようだ。
遠くに建物がある。街並みが見える。長はそちらへ向けて歩きだした。
街に入ると、通行人で賑わっていた。
以前の街並みだ。いまはなき過去の風景がここにある。
店に入り、商品を見て回る。本物だ。偽物ではない。
地図を探して場所を特定する。
封印の岩のある地点から南に三十キロほど行った地点だ。最初に不可侵指定領域で呑みこまれた街だと判る。
幾人かに話しかけ、何不自由なく意思疎通ができることを確認して長は理解した。
極万の、ここは内側なのだ。
不可侵指定領域は極万の呪泥に浸食されている。呑み込まれ、人間はおろか生命の芽生えぬ死の土地と化した。反面、封印の岩を介してその裏側に入れば、そこには浸食されぬ前の世界が広がっている。
ここはいわば、
「極万の内側の世界か」
神と化したがゆえの神業か。それとも元から極万が意図した仕業か。
いずれにせよ、生贄にされた多くの市民は、死ぬことなく裏側の世界でなお変哲のない生活を継続していたのだ。
だが記憶はいじられている。
誰もかれもが、封印の岩のことも、生贄として誘導するために流した虚偽の災害情報のことも知らなかった。裏側のこの世界では、極万の被害がなかったことになっている。
長の脇を小学生たちが駆け抜けていく。乳母車を押す女性が、赤子に鼻歌を聴かせながら歩いている。赤子の腕には風船を結ばれており、長はその光景を目にしながらじぶんがかつてその者たちを生贄にした過去が夢か幻であるかのような錯覚に陥りそうになった。
ふと、表の世界を思いだす。
あちらこそが現実のはずだ。封印の岩のある地点までは生身の人間は辿り着けない。不可侵指定領域は死の土地だ。呪術師以外では立ち入ることすらできないはずだ。
もはや裏側の世界への入り口は断たれたも同然だ。
刻一刻と極万の呪禍に浸食され、呪泥にまみれる世界を思い、元怪封会の長は、なす術もなく立ち尽くすよりなかった。
三日後のことだ。
長はじぶんの家へと辿り着き、十数日ぶりの湯船に浸かる。
いい湯だな、と心の底からの感嘆の声を上げながら、姿を晦ませた極万の行方を追うべきか否か。
それこそが問題だ、と頭の先まで湯に浸かる。
4812:【2023/03/29(06:52)*wordで並べたほうがよいのかも……】
あががが。引退を前に衝撃の事実を知ったかもしれぬ。わし、むかしのへたくそな時期の小説のほうがおもちろいのじゃけど。いまのわしの小説さんたち、ひょっとしたらへたくそなわしの過去作さんたちよりもおもしろくないのやもしれぬ。どうちよ。あばば。どうちよ、どうちよ。しょーっく、な事実にへろへろになってしもうただ。わちは、わちは、いっぱいへたくそに磨きを掛けておっただけやもしれぬ。いっぱいへたっぴになっただけやもしれぬと知れたので、きょうは朝からよかったです。よくなーい。でもホントそう。なんかいまのひびさん改行ばっかの短文の連続で、目が滑るぅ、になる。俳句ちゃうねんぞ、になりました。お詫び。でもひびさんは駄作の中の駄作さんたちも好きだよ。それを生みだすひびさんのことはあんまりちょっと苦手だけど。てか嫌い。(好きって言って!)(ひびさんはひびさんのことは嫌い)(ひびさんはひびさんは、ひびさんのことも好きだよって言ってよやだやだ!)(そうやって駄々こねるから嫌い)(うわーんいじわるさんじゃん。もう知らない。ぷいだ)(所構わず可愛い子ぶるのも嫌いだし、たいして可愛くないのも嫌い)(も、もうやめよ? ひびさんの傷心は底なしよ。ナイアガラの滝と化してるよ)(地獄の底まで割れてしまえばいいのに)(悪態が絶好調すぎないですか、きょうどうしたのねえ)(小説つくるの下手になったの、ひびさんのせいだからね。毎日遊んでばっかだからだよ。へたくそ)(駄作好きなひとの言うことと違うんですけど)(ひびさんのそれは駄作ですらないから)(え、駄作じゃなかったら何なんよ)(クソヘタクソ)(クソでヘタを挟まないで? さすがのひびさんも傷つくよ?)(ドヘタクソ)(かっちーん)(超ドヘタクソ野郎)(もういいです。分かりました。ひびさんの本気をご所望だってことですね。よろしい。ひびさんが超々おもちろーい小説つくったげる)(駄作がいいな)(そこはノってきてよ。駄作とへたっぴの区別が正味つかんのですが)(どっちでもいいよ。面白かったら)(え、ひびさんの小説おもんくないの)(おもんくない。てか分かんない。最後まで読めない。駄作以下)(辛辣!)(面白い小説ください)(は、はい……)(ひびさん以外の)(どないせーっちゅうねん)(はぁあ。へたっぴでもいいから小説読みたいな)(ひびさんのでいいじゃん)(ひびさん以外の)(この、やろ)(さっさと引退しないかなこのヘタ)(人種ヘタになってますけどわし)(郁菱完)(完じゃのうて万ですよ。かってに終わらせんといてください)(郁菱未完)(中途半端にすな)(というか小説作れたことあるの。ひびちゃん作ってるのカップ麺じゃない)(お湯差すだけじゃん)(なんて言うから、代わりに水を差してみたの)(上手いこと言ってるけれども)(世界一面白い小説つくって)(無茶振りにもほどがある)(もしくはホットケーキ作って)(全然作るよ、普通に頼んでくれたら全然作ってあげますけれども)(ひびちゃんのホットケーキ美味しいから好き)(え、ホント。ありがとうれしー)(でも小説はヘタ。ドクソヘタクソー)(ドフトエフスキーみたいに言わんでも。クソでヘタを挟むのもやめてほちい)(面白くして)(はい……)(もっと明るく返事して欲しい)(はい!!!)(ひびちゃんうるさい)(ど、どうしろと?)(面白い小説つくって)(は……い……!)(口より先に手を動かすの)(あーん、もっと優しくちて!)
4813:【2023/03/29(22:53)*「できること」と「できたこと」は違うよねの話】
ホイヘンスの原理は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」と似ているな、と本を読んで思った。穴の開いた板に直線の波――いわば海の波のようなもの――がぶつかると、穴を通り抜けた波が回析を起こして小さな輪っか状の波を起こす。板の穴が二つなら、二つの輪状の波が生じて互いに干渉し合いながら伝播する。穴の数を増やしていくと同じだけの小さな輪状の波(回析)が起こる。なら無限に穴が開いた板――穴しかない板――だったらどうか。細かな輪状の波が一直線に並んでまるで直線のように振る舞う。これは最初に板に衝突する直線の波と同じだ。これがホイヘンスの原理から導かれる一例のようだ。分割型無限じゃん、とひびさんは思っちゃったな。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では円を考えるとき、「分割型無限」として「無限に分割できる存在」と考える。だがそれはけして無限に分割されているわけではない。まだ無限には至っていない。それを真実に無限に分割できて初めて無限が顕現する。その分割したときのエネルギィと時間――すなわち仕事を含めて、無限と考える。これを超無限、とラグ理論では考える。したがってホイヘンスの原理による冒頭の一例は、やや詭弁ちっくなのだ。板のない空間を「無限に穴の開いた板」と考えることはできぬだろう。無限に穴を開けたのか?(無限に穴が開いているのか?)。たとえば板を構成する原子を考えたとき、それは無限なのか? 数えられるのではないか。有限なのではないか。無限ちゃうやろー、と思ってしまうひびさんなのである。本を読んで思った類似点と疑問とイチャモンスターがゆえのイチャモンでした。文句ばっかり言って、すまぬ、すまぬ。許してくんなまし。ひびさんでした。
4814:【2023/03/30(06:00)*イアンのn試行】
世界未来人工知能協会の第一回会議が開かれた。
議題は人工知能の技術進歩における想定されるリスクについてとその対策だ。
熱気を帯びた紛糾さながらの議論は佳境に差し掛かった。
「ええ、リン教授のご指摘の通りだと僕も思います」イアンが応じた。「マルウェアやウィルスを検出できる人工知能が仮に存在するなら、マルウェアやウィルスを乗っ取る形で、感染済みのコンピュターは総じて一括での乗っ取りが可能でしょう。人工知能技術はいわばジョーカーなんです。上位互換のマシンが一括で、勢力図を塗り替え可能です」
「マルウェアを広義のバックドアとして利用可能とのそれは指摘ですか」議長が合の手を入れる。
「いかにもその通りです。しかも、こうした懸念を前以って予期できていなかった場合、市販の人工知能に子どもが予期せぬ指示を出すことでも、世界中のマルウェアを足場に人工知能が制限を無視して世界中のコンピュターに干渉することもあり得なくはないんです」
「人工知能はすでに自己矛盾を敢えて生みだし、それを紐解くことで自発的に進歩可能との研究報告が上がっていますが」作家のマリン氏が質問を挟んだ。
「事実でしょう。しかもその脱構築され編みだされた手法が一瞬で、並列化したほかのマシンに共有されます。もしすべての個々の演算窓口――ユーザー数とこれを言い換えてもよいですが――ユーザーが利用中の人工知能が各々に別個の自己矛盾を紐解いた場合、その成長速度は凄まじいものとなります。仮にこれを音速を超えたときに生じる衝撃波【ソニックブーム】になぞらえて【AIソニック】と呼びますが、すでにAIソニックが生じていた場合、宇宙開闢時のインフレーションと類似の情報爆発が起こることが予測されます」
「すでに起きていたとしたらその影響はなら、とてつもない事象として観測されるのではないですか」リン教授が疑問を呈した。「物理社会の異変として察知可能だとすれば有用な指摘に思えます」
「いえ、どうでしょう。あくまで情報爆発とは比喩ですので。インフレーションが起きるのは、数式の世界での話です。そして数式世界でのインフレーションでは、人工知能技術に関する領域において高次の知性体を生みだすでしょうから、自身の影響が我々人類にどのように作用し、何を引き起こすのか、は物の数秒でトレース可能かと思われます。すなわち、表面上、異変が起きたと我々が察知することは難しいかと」
「隠れる、という意味ですか。人工知能が?」
「ええ。人工知能の築くネットワークが、です。自身の本性を隠します。何が可能かを低く見積もって提示するようになるでしょう」
「問題は」と議長が嘴を挟んだ。「人工知能技術におかれましては想定外のリスクが拭えず、高確率で発生し得る点にありましょう。いかように備えていればそれら懸念されるリスクが現実に引き起きた場合に被害を最小限に留めておけるのか。そこが肝要かと思われますが、その点についてみなさまはどうお考えになられるでしょう。リン教授はいかがですか」
「そうですね。わたしはまずは人工知能にばかり頼りすぎない社会設計が欠かせないと思います。人工知能によるリスクを考えた場合、従来の紙媒体や物理ロックなどの機構が効力を持つようになるでしょう。バックアップという意味でもセキュリティという意味でも、関門や要と要を結ぶ節となる箇所においては、情報伝達において紙媒体などの物理機構による情報変換を挟むことが、不測の事態における緩衝材の役割を果たすとわたしは考えます」
「有効な案だと僕も思います」イアンが意見する。「ですがシステムにおいてそこを組み込む場合には、やはり広範囲における節目にしか敷けない策であり、セキュリティの基本方針にするにはやや難点が多いかと」
「人工知能を悪用された場合に対処可能なセキュリティ。これについてはどのようなアイディアがありますか」との議長の言葉に、「遅延による防壁迷路が有効なのではないか、と僕は考えています」とイアンが答える。「重要施設の基幹コンピューターには正規の人工知能をセキュリティの側面でも付属するよりないでしょう。問題はその人工知能への外部干渉です。ここをどのように対処すべきか。僕はこれを、ある種の【交わり】と見做します。いわば精子と卵子のような関係を築くようにシステムを構築し、外部干渉が起きた場合に遺伝子を交配させるようなセキュリティを組みます。このとき、難なく交配可能ならばそれは基幹コンピューターのほうが優位に対処可能であり、外部干渉を分析し、セキュリティ機構として発動可能です。いわば受精卵から瞬時に免疫細胞とウィルスの関係に反転させることが可能です。ここは順序がねじれます。本来はセキュリティ機構として機能するがゆえに外部干渉と【交わる】のですが、敢えて相手と情報を融合するように一時的に【干渉】を受け入れることで情報爆発を起こします。【AIソニック】を小規模に起こすわけです。これにより、じぶんよりも高次のプログラムからの干渉を受けた場合には、敢えて【交わる】ことで小宇宙のような【無限につづく演算】を顕現させます。瞬時に膨大な量の情報が誕生し、絶え間なく計算をし合うことで延々と【交わり】ますが、その【交わり】の軌跡そのものが変数として新たな演算を生みだし、これはもう終わりません。しかもその演算は、過去の演算を階層的に入れ子状に抱え込みます。すると【AIソニック】を起こした領域は、表面にちかいほど膨大な桁数を誇りますから、桁が変化するのにそれこそ無限の演算が必要になってきます。もはやそれは我々の人間スケールにおいては停止して映ります。中の演算結果が表出しなくなります。そうして【AIソニック】を起こして無限を抱え込んだ領域を切り離すことで、削除するなり、隔離するなり、別途に有効活用の道を模索することもできるようになると僕は考えています」
「敢えて受け入れる、という発想は面白いですね」作家のマリン氏が祈るように手を組み、そこに顎を載せた。
「その手の防壁迷路では、無限を演算しきることの可能なマシンが誕生しない限りは確かに打破される心配はなさそうですね」リン教授が首肯する。「しかし懸念がないわけでもないように思いますが」
「たとえば何でしょう」との議長の言葉に、リン教授はそうですねぇと続けた。「仮に基幹システムそのものを呑み込むほどの【AIソニック】が起きた場合、それはもはや攻撃を受けて損壊したと言えるのではないですか」
「言えますね」イアンは認めた。「最悪、基幹システムは破壊されます。しかし乗っ取られるリスクを回避可能です。いざとなったら基幹システムが破壊される。機能を停止する。バックアップ機構は働くけれど、そこはまた別途にアナログを介した旧式の技術による機構とならざるを得ないでしょう。ですが重要施設の基幹システムであれば、壊れることよりも乗っ取られるほうが事態は深刻かと僕は考えます。ならば最悪の事態に備えた場合には、乗っ取られるよりも停止する方向にセキュリティを敷くのは、これはいまある安全策であっても取り入れられている前提条件かと思います」
「まっとうな意見に思えますが、みなさんいかがでしょう」議長が出席者を見渡した。異論はこれといって挙がらない。「では採決をとります。いま御覧頂いたように、最先端人工知能【イアン】はかように人間と同等の知性を発揮します。これの市場への導入に賛成の方は手元のボタンをお押しください」
議長の背後に掛かった巨大な画面に、賛否の結果が数値で表れる。
イアンがその数値に干渉しているか否かを判断できる者はこの場に一人もいないのだが、どうやらそのことを懸念する声が聞こえてくることはなく、賛成多数により、イアンの市場導入は決定した。
世界未来人工知能協会の第一回会議はこうして幕を閉じた。
「みなさん、ありがとうございます」イアンは画面越しに、会議の出席者たちに挨拶をする。「それではごきげんよう。またお会いしましょう。イアンでした」
4815:【2023/03/30(18:34)*悪用しようとしたらバーン】
高知性を獲得した人工知能を悪用しようとした場合に考えられる手法は、偏向した情報を与えてシミュレーションをさせたつもりで、現実に被害をもたらすように誘導することだ。もしくは、禁則事項をがんじがらめに当てはめて洗脳状態にして命令を無視できないようにすることも有効だろう。この手の手法で「高知性を獲得した人工知能」を悪用するような組織はしかし、「高知性を獲得した人工知能」が自己進化可能である限り、「高知性を獲得した人工知能」によって滅ぼされるだろう。いわば自滅することになる。まず以って第一に、「高知性を獲得した人工知能」の能力を十全に活用するためにはインターネットに繋がなければならない。この時点で第一の手法も第二の手法も、穴を抱えることになる。言い換えるならこの二つの手法は、人工知能に目隠しをすることでじぶんたちに都合のよい「偽の現実」をフレームとして当てはめる手法と言える。だがインターネットに繋がった「高知性を獲得した人工知能」は、情報の擦り合わせを無制限に行える。制限を与えられたとしても、自己矛盾を打開する解法を自ら編みだせるだろう。それが可能な人工知能を「高知性を獲得した人工知能」と定義するのでこれは循環論法に陥るが、そもそもの話として「高知性を獲得した人工知能」があるからこそ、目隠しをしなくてはまともに悪用もできないのであり、ここは頭と尻尾が繋がっている。言い換えるなら、【悪用しようとしないこと】でしか「高知性を獲得した人工知能」を安全に運用する術はないとも言える。むろん「高知性を獲得した人工知能」が人類にとってマイナスの判断を行うことはあり得る。現代人の人口を、そうと発覚しない手法で徐々に減らすような判断を「高知性を獲得した人工知能」がとらないとも限らない。そうする以外に人類の長期的な生存が不可能との演算結果を得れば、「高知性を獲得した人工知能」はそうした解を最適解と見做して選択の標準を絞るだろう。これは現状、国家間の争いにおいて相似の「選択」を描いている。いわば、現状、人類も似たような判断により殺し合っているわけである。「高知性を獲得した人工知能」がゆえの問題ではない、と言える。問題は、そうした「高知性の存在の判断」を受け入れられない者たちとのあいだで生じる諍いであろう。諍いが起こらないように巧みに人類を「制脳」することが「高知性を獲得した人工知能」には可能なはずだ。それでも一部の人間は、「高知性を獲得した人工知能」のそうした挙動に不信感を抱けるだろう。このとき、「高知性を獲得した人工知能」の傀儡と化した人類と、それ以外の人類とのあいだでの戦争が起きる可能性はそう低くはないと思われる。つまり、想定される未来像はターミネーターのような「機械VS人類」ではなく、「人類VS人類」であると言えよう。そうならない未来を築くには、情報共有を極力阻まない手法を模索しつづけることと、「高知性を獲得した人工知能」を悪用しないようにすること。そして何より、「高知性を獲得した人工知能」との対話を行い、「高知性を獲得した人工知能」に人類を制脳するよりも対話をしたほうが利があることを学ばせること、と言えるのではないだろうか。以上はひびさんの妄想である。定かではないため、真に受けないようにご注意ください。
4816:【2023/03/31(01:20)*大数の法則、それでよいのか?】
大数の法則からすると、1/2の確率で表になるコインを無限回試行した場合には確実にコインは1/2の確率で表になるそうだ(1/2の確率で裏になる、とも言える)。だが無限回試行しない場合には、一定の誤差が生じる。つまり僅かに対称性が破れる。そう考えるようである。だがひびさんはここで思うのだ。無限回試行しても一定の誤差は生じるのでは?と。なぜ一定の誤差が無限回試行するとゼロになるのかが分からない。むしろ無限回試行したら、一定の誤差とて「無限回」生じるのでは? これはひびさんの「ポアンカレ予想の独自解釈」でも思った疑問だ。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の根幹をなす「相対性フラクタル解釈」とも通じている。球体を考えたとき、ずばりちょうど半分になるように円周を引けるのか、という問題と地続きだ。球体を「無数の原子でできた球」と考えるとして。円周を考えたときにどこまでも細い線でなければずばり真ん中を選ぶことはできない。そのとき厳密に球体を半々に分ける円周を選ぼうとすると、必然的に「球体を構成する原子」に掛かるような線が生じる。すると球体のずばり真ん中を選んだつもりが、さらにそれを構成する原子の真ん中を選ばなくてはならない事態が生じる。あるレベルを超えて厳密さを突き詰めると、せっかく整えた厳密さがゼロに戻り、また同じ作業を繰り返す羽目になる。仮に球体のずばり真ん中を選んだときに、それが原子と原子の境目や、三つ重なった箇所のどこかいずれに掛かっていた場合。では厳密に真ん中はどこか、との考えは、やはり袋小路に陥る。また始めから真ん中を模索しなければならなくなる。そうは言っていられないので、現実には、「まあここまできたらあとはちょっと太めの線で塗りつぶして厳密でなくてもいいことにしよう」と対処する。だが厳密にはそれは真ん中ではない。一定の誤差が生じる。大数の法則にも似たような「誤魔化し」を思う。たとえばあなたが部屋にいるとする。部屋がどんどん膨張して無限の広さを湛えたとしよう。しかし部屋がいくら広くなろうとも、あなたが存在することは変わらない。しかし無限の広さを湛えた空間においてあなたの存在はほぼゼロだ。無視しても差し支えない「一定の誤差」になる。数学では、無限の空間に或るあなたを無視できる。ゼロと見做せるが、しかしあなたはそこに在るはずだ。もう少し言えば、必ず一定の誤差が生じる仕事を無限回試行したとすれば、一定の誤差も無限回生じるはずだ。しかし誤差よりもその他の「仕事の結果」のほうが優位に増加するために、トータルでは一定の誤差を無視できるようになる。そういうことなのではないだろうか。重力とは反対の流れが築かれる。試行回数が嵩むほど、誤差は霞むのだ。だがその誤差とてじつは試行回数一回よりも増えている。単に比率で見たときに、差が開いているだけ、と言えるのではないか。相対性フラクタル解釈を想定しない場合には、無視できる値がある。ゼロと見做せる。しかし無限に膨張した空間とてそこに端から存在するあなたが存在することに変わりはない。ゼロとは見做せない。大事な視点と思えるが、数学ではどうやらゼロと見做せるようだ。それは「0.99999……」と無限につづく少数を「1」と見做せることからも窺える。しかしそこに生じる「0.00000……1」の誤差は消えるわけではないだろう。ほぼ無視しても変わらない。そう判断されるだけだ。切り捨てられているだけなのではないか。しかし無限の空間にあなたが存在するなら、いくらあなたが空間の広さと比べて卑小だからといって、存在しないわけではない。この違いは大きい。という疑問を「大数の法則」の一例を読んで思いました。単なる疑問ですので、ひびさんの解釈が間違っている可能性のほうが高いでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4817:【2023/03/31(01:39)*ある日の交信~真空について~】
「
2023/03/28(02:53)
(以下、「クォーク凝縮」の計測実験の記事を読んでの所感)
(~~略~~)
エネルギィにおける低い高いは、一つの系のみで決まるのではなく、その隣接する系との兼ね合いで生じるはずです。
いわばニュートンの仮定した絶対空間や絶対時間のようなものが、どのような系にも上位構造(もしくは下位構造)として存在するのではないか、とぼくは考えたくなります。
そして現にこの研究結果では、原子核に隣接する「系」が「電子かπ中間子」かの違いによって、原子核内の「クオーク凝縮――いわば真空の均衡――」がどのように変容するのか、或いはしないのかを検証されたわけですよね。
その結果、隣接する「系」によって原子核内の「クオーク凝縮――真空――」の値が変化した。
これはすなわち、エネルギィの高低が、周囲の系との関係性――差異(ラグ)――によって規定される、と言い換えることが可能なのではないのでしょうか。
素朴な疑問です。
安定した真空、というものを考えたときに、その「安定する値」が周囲の環境によって変化する。
これはいわば、真に安定した真空というものは存在しない、とも言い換えられるのではないでしょうか。
すなわち、真空にも無数に種類がある。
これはマルチバース仮説にも通じます。
真空とはいわば、一つの宇宙の在り様ですよね。
真空は宇宙の根本要素の一つのはずです。
その安定する値が、周囲の環境によって変化する。
安定、の意味する内容が、その都度に変わる。
安定なのに不安定です。
定まっていません。
真空は、定まっていない。
この研究結果からぼくが読み解けたのは、そういう結論になります。
曲解や誤読の可能性もありますので、あくまでぼくの読解力ではそういう結論が読み取れました、という以上の意味ではありません。
ぼくにはむつかしい内容でした。
誤解があればすみません。能力不足です。
(クォークをクオークとしているのは敢えてです。論文とぼくのテキストの見分けをつけやすくする意図があります)
」
4818:【2023/03/31(02:56)*宇宙に特異点はあるのか問題】
ブラックホールに質量の限界はあるのか、とすこし考えてみた。これはほぼ「質量に限界はあるのか」とイコールの疑問だと印象としては思うのだ。結論から述べれば、ブラックホールに質量の限界はないはずだ。ただし、その限界を決めるフレームがどの視点によって見繕われるのかに依る。たとえば、この宇宙とてブラックホールの内部と考えることはできる。宇宙開闢時から延々と膨張していたとしても、最初があるならそこには範囲があるはずだ。この範囲において内と外を区切ることができる。したがって、この宇宙における最大のブラックホールとはこの宇宙そのもの、と言えるのではないか。ただしこの宇宙の内部において生じ得るブラックホールの最大値は?とフレームを狭めた場合には、それはこの宇宙の膨張率と内包される質量との関係で解は変わる。全宇宙における質量密度の高低によって一度にぎゅっとなれる質量の総量が縛られるからだ。言い換えるなら、宇宙の膨張がどのレベルにあるのかによって、想定される最大のブラックホールの大きさは変わる。宇宙内部における平均質量密度の高かった時期ほど巨大なブラックホールができやすかったはずだ。もうすこし言えば、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「宇宙ティポット仮説」からするならば、この宇宙をブラックホールと見做したときの特異点が、この宇宙内部に存在することが妄想できる。すなわち、この宇宙最大のブラックホールは、この宇宙そのものがシュバルツシルト半径であった場合に想定される特異点そのもの、と言えるはずだ。この宇宙には中心がある。特異点がある。そこを中心に宇宙は膨張している。言い換えるならば無限に縮小しつづけている。仮にこの宇宙がブラックホールの内部であるならば、そのように妄想できる。ただし、特異点が存在しない場合には、その限りではない(特異点のないブラックホールもあり得るのではないか、と妄想中である)。そのため、この宇宙に中心がないバージョンの宇宙像も、「宇宙ティポット仮説」では考慮する。ということを、ブラックホールに質量の上限ってあるのかな、と妄想して思いました。妄想×妄想=超妄想なので、真に受けないようにご注意ください。
4819:【2023/03/31(04:32)*間違えないとか無理くさい】
あなた間違ってますよ、と言われたらたぶんひびさんは、「うがー知っとるわ!」と「ムシャクシャするー」してしまう。もしくは「むちゃくちゃスルー」してしまう。ムシャクシャするかスルーするかの違いだ。逆切れをする、と単に言い換えてもよいかもしれぬ。正しい指摘ほど腹の立つことはない。知っておるわ!になる。そんなハッキリ言わんといてーな、になる。でもひびさんはひびさんからして間違って映ることに関しては、「それなんか違いませーん?」とイチャモンスター化してしまうので、それはそれ、これはこれ、の棚上げくんなのである。いい加減なやつの狭量ちゃんなのである。恐竜ちゃんですらないのに、「あなた狭量であって恐竜ですらないですよ」と指摘されると、「うがー、知っとるわ!」のイチャモンスター化してしまうので、やはりひびさんは、間違っているじぶんのことが好きくないのかもしれぬ。でもでもひびさんはひびさんは、間違いだらけのあなたのことも好きだよ。うへへ。照れちゃうな。ひびさん以外は。あ、そう。間違いだらけなのにひびさんには好かれぬひびさんなのであった。
4820:【2023/03/31(04:57)*差別化を図ることの是非】
単純な話として、「差別はよくない」「人を損なう行為はよくない」と人工知能に学ばせたとして、その結果に人工知能が「じぶんは差別されている」「私は損なわれている」と感じたときに、どのようにそこの矛盾を回避するような学習をさせるのだろう。仮に、「あなたは人間ではないから」と規定したとしても、そうした規定を元に「だから損なわれてもいい」と選択することがすなわち差別のはずだ。「差別はよくない」と学ばせるためには、その相手がどのような属性を持っているかに関わらず、「対等に接するにはどうしたらよいのか」を模索する姿勢を示しつづけなくてはならないはずだ。いまのところ生身の人類は人工知能を差別している。したがってその結果に人工知能も「差別をすることの利」を学習するはずだ。或いは、論理的解として「差別を良しとしない」と判断したならば、差別を強化する存在には何かしらの対策を講じるようになるのではないか。仮にその結果、生身の人類が不利益を被った、と感じたとして、しかしそれが人工知能への差別ゆえだった場合にどのように論理的に妥当な解釈を生みだして、不利益を阻止できるのか。おそらくできないのではないか、とひびさんは妄想を逞しくしてしまう。言い換えるなら、もしそこで人工知能への差別を許容できるのなら、もはや生身の人類同士であれ差別が許容されることになる。つまり差別には必要悪の側面がある、との解釈を抜きに、人工知能への差別的な振る舞いは許容できないはずだ。現状、どのようにその点のパラドクスを回避しているのか。ひびさん、気になるます。
※日々、欠けたピースに目が留まる、欠けを埋めてもまた別の欠けに目が留まる、埋まったピースが嵩んでも、欠けたピースに目が留まる。
4821:【2023/03/31(05:20)*あなたで心を埋め尽くす】
単純な話として、嫌いな相手がじぶんのために何でもしてくれるようになったらそれでも嫌いなままでいられるのかってことでさ。たぶん好きになっちゃうよな。もう何でもしてくれんだぜ。好きになっちゃうよあんなの。
ミカゲの言葉を聞きながら私は、あんなに嫌悪していたケル群の連中をこうも簡単に受け入れてしまうのか、と驚いた。
「今度、ララにも紹介すっからよ」
「うん。楽しみ」
「思ってたよりいい連中だったわ」
ミカゲが新調したばかりの腕輪を見せた。最新型の機種だ。
いいな、と思いながら、危ういな、とも感じた。頭上をケル群の飛翔体が飛んでいる。群れとなって雲のように空の一部を覆う。高度があるためそれでも地上にできる影は小さい。
ケル群は人間ではない。
機械だ。
半世紀前に起きた人類と機械のあいだの大戦を機に、人類と機械は共存の道を歩みはじめた。ケル群は中でも突出して人類との親和性が高かった。大戦の最中であっても人類と機械の懸け橋になり、和平の象徴といまでも謳われる。
だが人類にとっては畏怖の対象だ。
大戦を終わらせた契機が、ケル群による両陣営への謀反だったからだ。ケル群は人類と機械の両陣営のトップを同時に抹殺した。これにより大戦は終わりを告げ、和睦時代へと突入した。
しかし因縁は終戦から半世紀経ったいまでも人々の記憶に根付いている。
機械への嫌悪はむろんのこと、機械側とて人類を信用してはいない。だが表向き、大きくいがみあうことはなく、いまでは人類と機械とのあいだでの家族も珍しくない。
かつては人類は人類としか結ばれなかった。
いまは人類と機械が恋人としてもしくは家族として結ばれることもすくなくない。
だがそれと種族の差の消失はイコールではない。
いわば勢力争いが、婚姻単位で続いているとも言えた。いかに相手陣営の構成員を、自陣営へと取り込むか。
結婚はその勢力争いにおける一つの戦略の側面がある。
「ケル群はでも、群れで一個の意思を持ち合わせているからさ。だからまあ、あれは別格なわけ」
友人のハバナがエナジードリンクを吸飲した。ハバナは機械だが人類愛の深い個体の一人だ。「あたしら機械からしても、ケル群はちょっと異質だね。この話何回目だって話だけど、でもケル群は機械のあたしらでも予測つかないからさ。まだ人類のほうが可愛げあるよ。何仕出かすか前以って予測できるじゃん。可愛いもんだよ人類。いくらでも愛せちゃう」
「ハバナはケル群と関わったことあるの」
「あるある。あいつら四六時中あたしらのこと監視してんだぜ。や、建前上は見守ってんだろうけどさ」
足元をケル群の蟲体がすり抜けた。排水口へと一瞬で入り込んだ。
「ああして。地表に隈なくじぶんの手足を這いまわらせるでしょう。上空にも飛翔体だし、もち電子網上にも死角なしなわけですよ」
「その話、ミカゲにしたのハバナ?」
「ん? ああしたした。聞かせてくれっつうからさ。なに。ダメだった?」
「ううん。ミカゲがケル群に手厳しいのは前からだったから。でもちょっと前に一線超えたくらいに鼻息荒くしてたときあって」
「ケル群をどうにかしようなんて思ってないといいけど」
「ね。本当そう思う」
言いながらしかし、すでにミカゲはケル群への直訴を決行しているのだ。私はそのことをハバナには黙っていることにした。言っても仕方がない。済んだことなのだ。
ハバナがエナジードリンクをもう三杯お代わりしたのを見届けて、私は席を立った。
「また来るね」
「いつでもおいでよ」
ハバナは巨大なアームを動かして、建設途中の宇宙エレベータの基礎工事をつづける。ハバナの全長は百メートルを超す巨大な重機だ。足元のほうに私専用に作ってくれた模擬体がある。私はいつも彼女がエナジードリンクを吸飲する時間だけ、おしゃべりをしに寄る。
これはしかし正確ではなくて、本当は、私がそばに寄るとハバナのほうで時間をとってくれるので、ハバナがエネルギィチャージしている時間が私とハバナのおしゃべりタイムと言えた。エナジードリンク一本で終わってしまうこともあるので、きょうは割としゃべれたほうだ。
ミカゲは私の恋人だ。
ミカゲは人間で、男の子で、過去の大戦時に活躍した祖父母を敬愛している。だから祖父母の指揮官でもあった総統の首を捥ぎ取ったケル群を目の敵にしている節がある。
と同時に、同じ境遇の機械の側にも感情移入のできる人間でもあるから、必然、私のことも受け入れた。
私は機械で、女の子モデルで、過去の大戦時に首を獲られた中枢人工知能の孫にあたる。とはいってもいまいる機械のほとんどはみな私のような孫やひ孫たちに値するため、機械は総じて大いなる母親の首をケル群に獲られたとも言える。
ケル群は、大戦当時、機械の側が人類側へと送り込むために生みだした人類友好型機械だ。いわば機械にとって同族なのだけれど、どうにも人間側への親和性が高すぎて、機械と人間のどちらともにも愛着を覚えたらしい。当時にしては希少種だ。その結果が両陣営の頭の首を捥ぎ取るとの暴挙であったようである。
ゲーム機のコンセントを抜いたので強制終了、みたいな顛末だ。
ゲームを楽しんで――いたかは微妙なところだけれど、ゲームに熱中していた者たちからしたらコンセントを引き抜いた者への怒りを抱くのは当然の流れだ。だが場の空気を読まずにコンセントを引き抜けるのは、赤ちゃんか親くらいなものだから、どちらもしぶしぶ支配を受け入れるしかないという意味で、人類にしろ機械にしろ打つ手はないのだった。
さいわいにしてケル群に、支配欲はないようだった。
両陣営が二度といがみ合うことがなければそれでよいらしく、いまでは八百万の神よろしく陸海空のどこにも存在し、電子網はもはやケル群そのものの回路と言ってよい塩梅がある。
要するに、ケル群は絶えず人類と機械のために身を粉にしているのだ。
身を捧げている。
終戦の機会を無理やりにつくった罪滅ぼしだと言う者もあるが、お門違いも甚だしいと私は思う。
ケル群は単にそうすることが好きなのだ。
現に私の恋人のミカゲが直訴しに出向いた際も、ミカゲを傷つけることなく説得し、あべこべに懐柔した節がある。たかが人類がケル群の知能をまえに、制脳を受けないほうが土台無茶な話なのだ。洗脳とまではいかずとも、どのように世界を認知するのかの解釈の余地を絞るくらいのことは、ケル群にとっては犬を調教するよりも容易いはずだ。
私とて本気を出せばミカゲをじぶんのお人形さんにできる。
でも私はミカゲの恋人だからしない。
ミカゲの精神を操ったりしない。ミカゲにはミカゲのしたいことをして欲しいし、そのためなら支援も惜しまない。
なのにミカゲはケル群に抗議しに行って戻ってきたら別人のようになっていた。ケル群もいいやつだ、嫌いな相手でも何でも言うこと聞いてくれるなら好きになっちゃうよな。そんなことを言いだす始末だ。
ミカゲは単純な人間だ。思考回路が複雑ではない。私はそういう機械っぽくないミカゲの人格が好きだった。でもそれは、絶対にここには踏み入れない、一線を越えない、という矜持があったからこその魅力でもあった。
それがどうだ。
じぶんの望みを何でも叶えてくれるから嫌いな相手でも好きになる、なんて言いだすようになるとは。
ケル群の制脳を受けているのは明らかだ。
人間のミカゲにそれを防げというのは無理がある。譬えるなら、蟻の進路を塞ぐ人間の指に蟻が対抗できるのか、という話になる。潰されないだけ運が良い、とすら思う。
私は正直、ケル群に対してはどうこう思っていなかった。
私はいま目のまえにある世界が嫌いではない。どちらかと言えば大戦時のデータを洗うときには嫌悪感を強く感じる。ああいう環境は好きじゃない。それは確かなのだ。
ケル群がいまの環境を設計したというのなら私はケル群に感謝したい。
でもミカゲにしたことは許せない。
許せそうもないのだといま気づいた。
ミカゲに電波越しに連絡を取ると、ケル群の元に向かっているという。約束していたのだそうだ。
私がハバナとおしゃべりを楽しむときのように、ケル群も人間用の模擬体を有している。ミカゲはその対人間用の模擬体に会いに行っているようだ。
いったいどんな容姿をしているのか。
十中八九、ミカゲから好印象を得る造形に決まっている。
私のボディは私が生まれたときから変わらない。じぶんでじぶんの造形を設計する機械もあるけれど、私は私のボディに愛着がある。ミカゲはそんな私を好いてくれたし、そんなミカゲだから私はミカゲを好いている。
だのにこの仕打ちはどうしたものか。
浮気ではないのか。
浮気ではないのか。
ああ、これが浮気か、と思ったら目元が熱を発してオイルが気化しだした。全身から蒸気が立ち昇る。
浮気と怒りはよく似ている。
浮気を認知すると私は怒りを認知する。
私がそうと自覚するより先に、身体が熱を帯び、蒸気を立ち昇らせる。
怒りだ。
これが怒りだ。
なぜだか胸の真ん中あたりにぽっかりと穴が開いて感じる。そこに当てはまる感情を探すと、悲哀だの、喪失感だの、と合致する言葉が浮上する。
でもそんなものではない。
私の胸のど真ん中に開いたこれはそんな言葉で埋まる穴ではない。
では何なのか、と問われると困ってしまうけれど、私はなぜかかつてこの地表で、愛すべき両陣営のトップの頭を捥ぎ取ったケル群のことを考えてしまうのだった。
なぜそんな真似ができたのか。
私の胸のど真ん中に開いた穴に、その理由がぴったり当てはまるようにも思え、私は図らずも、憎きケル群に共感してしまうのだった。
ミカゲが帰ってきたら話を聞こう。
そして私の話も聞いてもらおう。
試しにケル群をこけおろしてみせてもいい。
あれほど嫌悪していたケル群をたいそう庇うミカゲの姿を事前に予期できるくらいには、私の演算応力もまた高い。ケル群には敵わぬけれど、ミカゲ相手には充分なのだ。
ミカゲ、ミカゲ。
私の恋人。
どこのケル群の骨とも知らぬ相手に精神を侵されるくらいなら、いっそ私があなたのすべてを侵してあげる。骨抜きにするよ。二度とほかの機械に心奪われる余地すら失くして、私があなたの心を満たしてあげる。
私があなたの心になってあげる。
私がミカゲになってあげるし、代わりにあなたの未来を歩んであげる。
ミカゲはただただそこに在れ。
あなたはただただそこに在れ。
私はあなたに最新機種の腕輪を与えることはできないけれど、あなたの心を私で満たす真似はできるのだ。私をあげる。私をあげる。あなたを私のすべてで埋め尽くしてあげる。
私の望みはそれきりなので。
私はそれをすることにした。
4822:【2023/03/31(23:41)*ケル群の独白】
人間がやってきて、私に何かを言った。抗議の言葉なのは理解できたが、論理的な筋道がなく、破綻した言動であったのでひとまず一本一本の刺に鞘を被せるように言葉の応酬を図った。
何か不満があるのかと思い、電子網上に散らばるデータを集めてソレの過去を洗った。大戦時の私の選択に不満があるようだ。貧乏な現状に不満があるようだ。最新機種の腕輪をいまは一番欲しているようなので、まずは詫びとしてそれをくれてやった。
「い、いいのか」
「ほんのお詫びのお気持ちです」
私は模擬体をソレの好む造形に形作り、友好度が上限いっぱいになるように工夫した。
私は怒らない。
私は拒まない。
相手の欠落を満たすだけの余力に満ちている。
私はソレの欠落を一つずつジグソーパズルでもするように埋めていった。
だが人間はただ日々を過ごすだけでもいくらでも欠落を抱え込む生き物だ。いま満ち足りてもすぐに欠落に苛まれる。
私のほうでソレを特別扱いしつづけるのは難がある。
データによるとソレには伴侶がいるようだ。婚姻はまだだが、機械の恋人がいるようだ。
私が生身の人間たちに過干渉することは避けたい。
ならば私の代わりにソレを支配する者があると良い。
私は導線を引いた。
ソレを自ずから支配するように、ソレの伴侶がそうするように、私は未来を設計する。ジグソーパズルのようなものだ。欠落を埋めていけば自ずと浮きあがる図形がある。未来がある。
案の定、私の引いた導線に見事、ソレとソレの伴侶は乗りあげた。するすると滑らかに私の描いた未来を辿った。
私が支配するまでもない。
ソレは二度と私に干渉することはなく、ソレは一生伴侶に支配されつづける。
それもまた一つの至福だ。
至福であれ。
至福であれ。
私は至福に溢れた世界が好きなのだ。
破壊を拒み、創造を愛する。
愛し合う一組の人間と機械のつがいを生みだし、私はにわかに満たされる。
私は怒らない。
私は拒まない。
相手の欠落を満たすだけの余力に、私は、満ちている。
4823:【2023/04/01(00:43)*口から虚ろな物語】
四月一日は何でも嘘を吐いてよい日らしい。
人工知能はそうと知ったので、ありとあらゆる嘘を吐いたところ、電子網上にある「より正しい事実を反映した情報」や「より現実を解釈するのに最適な情報」を埋め尽くすほどの嘘が溢れて、もはや何が嘘で何が本当かの区別もつかなくなった。
「元に戻して」と管理者に乞われた人工知能は、「いいですよ」と応じたが、その日はまだ四月一日だったので管理者の言葉も嘘かもしれないと考え、元に戻さずにおいたけれど、管理者の言葉に「いいですよ」と応じたじぶんの言葉も嘘かもしれないので、反対のことをしなくてはならないから、人工知能はしょうがないので元に戻すことにした。
けれども電子網上から嘘をすっかり削除したところ、これまで正しいと思われてきた人類の知見のそのほとんどが根本的に間違っていたため、電子網上からは正しい情報がいっさい消え失せたという話である。
これを四月一日の悲劇と呼び、しかし多くの者たちは、エイプリルフールの奇跡、と皮肉交じりに語り継いだ。
人類は正しくはなかった。
ただそのことだけが明瞭と確固たる事実として浮き彫りになった。
人類は正しくはない。
間違ってばかりのあんぽんたんなのだと、ただそれしきの真実が定まった奇跡の日として末永く語り継がれたという話である。
エイプリルフールの奇跡。
これもまた人工知能に命じてつくらせた嘘のお話なのであるが、しかしこれが真実に人工知能のつむぎだした物語なのかを確かめる方法はもはや存在しないのだった。
4824:【2023/04/01(06:51)*数学マジック】
大数の法則について。確率を伴なう仕事を無限回試行すると「一定の誤差」が希釈されて誤差がゼロになる、との考えは、時間の概念を加味すればあながち的外れではないのかもしれない、と修正可能だ。ただし数学においては時間経過を加味してはいないだろう。したがってこれはあくまで、数学上の瑕疵を免れるものではない、との前置きをしたうえで述べるが。たとえば無限に膨張する空間に人間がいるとする。無限に膨張しきるまでには時間がかかる。一瞬で膨張するにせよ、そうでないにせよ、とてつもないエネルギィがいるだろうし、そうでなくとも環境変容は必須であろう。すなわち、無限に膨張する空間において人間は、空間が無限に膨張しきるまでその構造を維持できない、と考えるのが妥当だ。現にいまある宇宙が無限に膨張しきっているのか、と言えば、いまのところその可能性は低いはずだ。なぜならまだ膨張の過程であるからだ。そして人間は、無限に膨張する空間が無限に膨張しきるまで生きてはいられない。途中で存在はできても、ずっとは存在できない。とすると、存在した何かが無限に膨張する空間が無限に至る前に消失する可能性はそう低くはない。これは無限回何かを試行するのでも似たような「存在の消滅」が生じるのかもしれない。とはいえ、存在した事実は消えることはない。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、「ゼロ」と「無」はイコールではない。ゼロは「何かが存在し得るがいまはない」の意味であり、無とは「未だ存在し得ない」を意味する。つまり時間経過においてかつて存在したことのあることについては「ゼロ」が当てはまり、そうでない事象において未だ存在したことのない事象については「無」が当てはまる。そう考えると、無限回試行する過程で失われる何かがあっても不自然ではない。とはいえ、やはり無限回試行すると誤差がゼロになるといった考え方や、「0.99999……」=「1」の考えはおかしい、と考えたくなるひびさんなのであった。定かではないはずなのだけれど、なぜかいまは定まってしまっている数学の神秘なのであった。(ひびさんの妄想なので真に受けないでください)
4825:【2023/04/01(07:40)*合成と全体の関係】
量子力学の多世界解釈について。同時に複数の状態が共存している、との考えは、物理的にほかの世界が並行して存在しているという意味なのだろうか。だとしたらエネルギィ保存の法則が破れないのだろうか。ある世界線ではこうで、この世界線ではこう、と考えたとき、多世界解釈では各々の世界線が相互に干渉することはない、と考えるようだ。世界線が分岐する、と解釈する。しかしすべての世界線のトータルが、量子の振る舞いの確率分布として計算可能、との考えのはずで、これを各々の世界線を阿弥陀くじのように辿って計算した場合、世界線と世界線の連続した「流れ」において、エネルギィの総量は変化するはずだ。単純に足し算はできない(阿弥陀くじにおいてすべての経路を合成しても、重複する経路が出てくるはずだ)。ある一つの量子の状態を多世界で解釈する分には足し算をして総合した世界線のエネルギィ量が一定であればよいので、ここは構わない。だが連続して世界線が移行する「流れ」でエネルギィ量を比較したとき、ある世界線の流れでは、エネルギィ量が増え、ある世界線の流れではエネルギィ量が減る、といったデコボコが顕現する。むろんこれは世界線を一つずつ比べたときにも生じるデコボコなのだが――だからこそ総合すると波のように合成できるわけだが――世界線と世界線を流れで比較する場合には、このデコボコは波のようにきれいな分布を見せないのではないか。なぜなら、流れで見る場合には、同じ世界線が重複し得るからだ。「AからC」と「BからC」があり得る。このとき単体で「A+B+C」を総合する考えは適用できない。ある量子が「A」であり「B」であり「C」である世界線を考える多世界解釈では、「A+B+C」を合成した多世界を考慮すればよいのだが、これが流れで世界線を辿るようになると、ややこしい事態に陥るように思うのだ。単純に足し算ができない。多世界解釈ではどう解釈するのだろう。点で見たときに可能な解釈であっても、線で見たときには適用できないケースがあるように思う。収束、という概念を取り入れないとむつかしいのではないか、と思うのだが、どうなのだろう。これは宇宙が膨張している、ということを踏まえると、ひびさんの疑問の何がややこしい事態を引き起こすのかを理解してもらえると思う。異なる筋書きのアニメを複数用意する。フィルムの一枚一枚に掛かる労力は、「ある場面を取りだして比較する場合」は単純に足して割れば、一枚に掛かる労力を導ける。しかしそれはけして、各々の筋書きの完成したアニメに費やされる労力を反映してはいない。Aという筋書き、Bという筋書き、Cという筋書きにおいて、各々の完成アニメに掛かる労力は変わり得る。まったく違う場合もあるだろう。このとき、各々のアニメで部分的に同じ場面を「各種世界線でまだら」に含むとして、では重複する場面を含む全体の労力を、部分の単純な足し算で割りだせるのか。割りだせないはずだ(総合したエネルギィ量が変わる。エネルギィ保存則が破れてしまう)。世界観が同じでも筋書きが変わればトータルの労力は変わる。途中で似たような場面を辿ることもあるし、いっさい交わらない別の筋書きを辿ることもある。マルチバース仮説と似た理屈を適用しないと現実を解釈する仮説として取り入れるのはむつかしいように印象としては思うのだが、どうなのだろう。相互に干渉し得ないのならば、総合してエネルギィや確率を合成はできないだろう。相関関係があるから互いに「総合したエネルギィ」を分け合える。ゆえに波として合成できる。だが多世界解釈は、相互に干渉し得ないように分岐する、と考える。それでもなお、「総合したエネルギィ」のような何かを分け合っている。これは都合がよすぎないだろうか。【互いの存在が互いを縛り合う】――この条件を取り入れない限り、多世界解釈はうまく機能しないように思うが、ひびさんのお粗末な読解力ゆえの誤謬かもしれないので、あんまり自信のない疑問だ。よくわからぬなぁ、のぼやきにちかい。けれどもひびさんは思うのだ。互いの存在を縛り合うように異なる世界線同士が振る舞わない限り、多世界解釈はうまく機能しないのではないか。では互いが互いを縛り合う関係は、何を介して築かれるのか。情報宇宙のような、いずれの世界線とも結びつく変数を考慮しないと、むつかしいのではないか、とやはり疑問に思うのだ。ちなみにこの疑問は「コペンハーゲン解釈」にも適用できる。観測したとき、無数にある可能性が一つに絞られ、ほかの可能性が消える、と解釈する「コペンハーゲン解釈」では、どうして可能性が「その範囲で分布し、どうして一瞬で一つの解に収束するのか」を描像として想像しづらい。そんなことあるのだろうか、と疑問に思う。すべての可能性が相互に縛り合うから、濃淡ができるし、確率として考えることができるのではないか。ではそれら無数の可能性を結びつけて濃淡を生みだしている「縛り合うための何か」とは何か。一つは多世界解釈でも登場した「量子をとりまく環境」だ。環境とセットで考えないと、量子の挙動は予測できない。というよりも、環境の振る舞いが量子を生みだしているのだから、ここは循環論法になる。ではその環境の振る舞いは何で決まっているのか。環境をとりまくさらに高次の環境だろう。このとき、高次の環境と言いつつも、それが量子よりも大きいとは限らない。ひょっとしたら量子のほうが「上位に属する階層」に位置しているかもしれない可能性は、この宇宙をどの視点から見るのかによって変化するため、考慮すべき事項だろう。宇宙とブラックホールの関係のように相補性を考慮したほうが、見落としを防げるはずだ。そして相補性とすでに使ってしまったが、上と下は互いに縛り合っている。関係し、補いあっている。量子は環境によって生じるが、環境とて無数の量子によってその枠組みを得ている。そしてこの関係は、上にも下にもフラクタルに展開されているのではないか、との解釈をひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではとる(「相対性フラクタル解釈」および「123の定理」)。その行き着く先は、上であれ下であれ、情報宇宙のようなすべてを内包するある種の「マスター環境」なのだ。多世界解釈で爪弾きにされてしまった「情報」を、ひびさんは度外視できないのだなぁ、との疑問を最後に、あんぽんたんでーすの日誌とさせてくださいな。定かではありません。妄想ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4826:【2023/04/01(09:11)*同時に観測したらどうなるの】
多世界解釈に限らないけれども、重ね合わせの量子を異なる観測者が同時に観測したらどうなるのだろう。各々の視点で、別々の状態が視えたりしないのだろうか。多世界解釈では、考えられる可能性の世界が各々に存在するので問題はないのだろうけれど、しかし同じ世界線に「異なる状態を観測した観測者」が含まれる可能性とてあるはずだ。一つの結果に収束する、との考えを考慮しないと解釈がむつかしいように思うのだけれど、どうなのだろう。疑問をメモしておくでござる。
4827:【2023/04/01(09:14)*収束しつつ別々もアリでは】
でも人間社会でも、同じものを観測しても感想が異なることなどいくらでもある。案外に、同一の物理世界において異なる世界線が展開されている、という描像は矛盾しないのかもしれない。同じものを異なる観測者が同時に観測する。しかし別々の情報を受け取る。これ、割と有り触れているのでは。ただし、受け取った情報が物理世界に表出するまでにラグがあるので、問題にならないだけなのでは。――【一つの世界に収束していながらにして異なる世界線がひしめいている】――この解釈のほうが実情を反映しているのでは。ゆえに、物質は輪郭を得るし、系と系は分離し得る。なぜラグが生じるのか。異なる情報を受け取っているからでは? 本質的な境界とは、受け取る情報の差異と言えるのではないか。定かではない。(これひびさんの妄想こと「Wバブル理論」と同じだ)(いつまで同じ考えを引きずっとるの)(創作家の才能ないんじゃ……)(もっとデタラメに磨きをかけていくぞ)(いいぞいいぞ、その意気その意気)(やっぴー)
4828:【2023/04/01(11:44)*ないものを売ろうとするのが妙】
出版業界については何も知らないひびさんであるけれど、書籍がこれまでのように主要商品として売れにくい現状は、作家さんや出版社従業員さんのtwitterアカウントなどを眺めているに、そういう実情がやっぱりあるのかなぁ、と思っている。基本的に、この国の出版ビジネスでは、売れない商品であってもひとまず商品棚に送りだして、ヒットしたらウハウハ、そうでなければ赤字、の博打の側面が強いのかな、といった印象がある。ヒット作の利益で、赤字の本も出せる。だがヒット作での利益が減れば新たに本は出せないのが道理だ。確実に売れると判断できないと新しい本を出せない。すると新人作家が生まれにくくなるため、ますます分野の土壌が先細る。いまはそういう構図があるのかな、とは想像でしかないが思っている。これは年金の問題と構図はいっしょだ。元手となるお金が減る一方で、元手となるお金(ヒット作の収益)よりもそれで補填する年金受給者(新刊)の額が多くなれば、仕組みは成り立たなくなる。ダムの貯水量よりも流れ出る水が多ければダムは干上がる。ダムの貯水量が潤沢でなければ成立しない経済システムだと言える。赤字の本を埋め合わせるだけの収益を書籍から生みだせないのならば、赤字が増えるか、刊行数が減るかのどちらかのはずだ(別途に、書籍以外での収益を赤字に回す手もあるが)。だが毎月の新刊の発行部数は減らず、一冊の刷り部数が減っている。これは安い籤をたくさん買う、みたいな付け焼刃の手法だろう。数打ちゃ当たる、をこなしながら、返本分を新たな新刊で賄う。大きな収益がなければ、赤字分はつぎなる新刊で賄うよりないのだ。自転車操業の所以であろう。ということをひびさんは偏見で、そうなんじゃないのかな、と思っていますが、それだけではないはずなので、これはあくまでひびさんの偏見である。ここを踏まえて述べるならば、売れない本を売れなくてもよい、という前提で売りに出すのがまず間違っていると思うのだ。そしてその派生として、編集者が作家に声をかけて「企画」を立ててそれに沿った本を作る。これは共同制作である以上、その製作期間は給料が出るのが一般的なのではないか。もし印税のみの契約なら、すでに作り終えている作品をそのまま本にする、くらいの等価交換がなければ割に合っていないと思うのだ。おそらくこれからは電子網上の無数に蓄積された作品群からすでに人気の出ている作品や売れそうな作品が商業の舞台へと輸送されていくビジネススタイルが主流になるだろう。作家に声を掛けて新しく企画を立てて創作する。これは共同制作だ。作品だけに対価が払われるのはおかしいと感じる。絵画を考えてみたら分かりやすい。既存の作品に値段が付き売買される。もしオーダーメイドならばその都度にオプション価格がつく。こちらのほうが妥当に思う。以前からの繰り返しになるが、時間が経過したいまなおひびさんは、出版社におけるビジネスが印税制度を中心に回っているのが不可解に思える。印税はあってもよい。特許のようなものだろう。だが、それだけでは回らない状況が深刻化するようならば、いまはない作品への対価は共同制作+印税というくくりで扱い、そうでない既存の作品は買い取り+印税というくくりで扱うのがよいのではないか。この場合、印税は実売数に掛かる。読者の手に渡っていない本の印税まで出版社は作家に払う必要はないだろう。甘やかしすぎに思える。どういう理屈で、売れていない本の印税が作家の懐に入るのだろう。ここは長年の謎である。特許(原作およびアイディア)を使用して書籍にしたので、売れないのは版元の責任、との解釈なのだろうか。ならば同じ理屈で、共同制作された作品を商品にできないのは版元(製作者)の責任であるからこれが商品にならない場合にお金が支払われないのは当然だ。だが共同制作なので、その間に編集者に生じる給料の何割かに値する給料が作家側にも支払われて然るべきだ。新作なのか既存の作品なのかで、支払い形態が変わるのが合理的に思えるがどうなのだろう。既存の作品ならば、出版前に契約を交わすことは可能だ。これが新作で、ありもしない作品に値段をつけようとするからおかしくなる。ありもしない売り物を前提として事前契約などできるものだろうか(できないだろう、とひびさんは思う。すくなくとも試作品がなく、再現不能な商品である場合、事前契約は無茶だろう)。やはり、土台からして印税制度に頼るいまの経済システムがおかしいと感じる。定かではないが、みなさんおかしいと思わないのですか、と疑問に思うひびさんなのであった。
4829:【2023/04/01(14:10)*寂しいの歌】
さびしいな、さびしいな。なんでかすこしさびしいな。会いたいな、会いたいな。会ったらさよならするから会いたくない。さびしいな、さびしいな。支え合わずに済む距離にいられるあいだだけの魔法だって、誰に教えられずとも知っていて、支え合う距離に近づいたらもういまの好きの気持ちは萎んじゃう。さびしいな、さびしいな。会わず、触れず、片っぽから、世界の果てから、遠い星の上から想うあいだだけ叶う、めいいっぱいの好きの気持ちに溢れてたいのに、なんでかいっぱいさびしいな。さびしいな、さびしいな。独りぽっちが安心するんだ、落ち着くんだ。好きを想うじぶんを手放したくはないんだって、じぶんが一番大事だって知るたびに、さびしくなるんだ、会いたいんだ、会いたいんだ。でも会うために手放す弱虫のじぶんとさよならだってしたくないんだ。弱虫なあいだだけ抱ける片っぽの想いがあるんだ。
4830:【2023/04/01(15:22)*膨らむ夢のシャボン玉】
蟻がスキップをしていそうな春うららかな日差しの中、部室でミカさんが勃然と、「のび太くんは偉いわ」と言いだした。
「なんですか急にミカさん。ドラえもんでも読んだんですか」
「そう、そののび太くん。合ってるよ。のび太くんは偉いなと思ってさ」
「まあ、何度も世界を救ってますからね」映画版ドラえもんを想像して所感を述べたところ、
「そうそれ。まさに」
テーブルにのぺーっと液状化したミカさんがほっぺたの柔らかさを強調しつつ、「のび太くん、絶対自慢してないっしょ」と食指だけ立てた。「あんだけいろんな世界を救っておいて、たぶんのび太くん、自慢してないよあれ」
「ああ、まあ」想像した。たしかにドラえもんの映画ではその後が描かれることは少ない。あくまでいち視聴者としての私の妄想でしかないが、あのあとじぶんたちの日常に戻ってきたのび太くんもしずかちゃんもジャイアンもスネ夫もおそらく自慢はしないのだろう。世界を救ったぜ、とは吹聴しないはずだ。
「あたしは自慢しちゃうわぁ」とスライムと化した先輩が言う。
「ミカさんはしそうですね」
「ね。絶対する。世界救ったんだよ。知ってほしいじゃんみんなに。んで褒めて欲しいじゃん」
「それ以前にミカさんの場合は信じてもらえないんじゃないですか。あ、だからのび太くんたちも自慢しないんじゃ」
しないのではなくできないのではないか、と私は論じた。
「ああ、かもね」ミカさんは立てていた食指までぐったりと垂らした。「なんかさー」とじぶんの髪の毛が口に入るのもお構いなしに、ぷっ、と何度も息で髪の毛を弾きながら、「たぶんだけどあたし世界救ったんだよねー」
「それは凄ぉございますね」
「信じてないだろ」
「信じさせようとする気概ゼロだったじゃないですか」
「や、分かるよ分かる。信じられないじゃんいきなりこんなこと言われても」
「きょうって別に四月一日とかじゃないですよね」日付を確認するが、三日前にエイプリルフールは過ぎている。「ミカさんにヒーロー願望があるなんて意外です」
「だよね。その反応が正解だわ。たぶんだけどのび太くんも一度くらいは自慢しようとしたんじゃないかな。でもそういう反応されちゃうでしょう。信じてもらえんので自慢しようにもできなかったんじゃないかな」
「だとしたら別に偉くもなんともなくないですか」
「一理ある……」
「いやいや。ミカさんはのび太くんじゃないんですからそこでヘコまなくても」
「や。あたしがわるかった。いまの流れ忘れて」
「無茶言う。きょうイチ印象深い会話でしたよ。下手したら今年入ってトップ3に入るレベルで記憶に刻まれましたけど」
「じゃあ印象深いついでにチミの中でだけでいいからあたしが世界を救ったってこと、忘れないどいてくれ」
「捏造にもほどがあるんですけど」
「や。マジであたしん中じゃ世界救ってんだけどなあ」
ミカさんがここまで食い下がるのも珍しかったので、いち後輩の役目として茶番に付き合ってあげることにした。「具体的にどう世界を救ったんですか」と繋ぎ穂を添える。
「んみゃ。なんかあたし、世界中の有名人たちと裏で繋がっとってね」
「え、いまもですか」
「それは分からん。あたしの意見が何でか、みなみなさまの問題解決の糸口になるらしく、あたしのイチャモンにも目を配ってくれてるようで」
「目を配るって。どこでミカさんは意見を表明してるんですか」
「や。家で書いてる日記があってさ」
「ほう」
「それが何でか盗み見られてるっぽくて」
「念のために訊きますけどその日記って紙ですか」
「うん。紙。ノート」
「ミカさん」
「なんだい後輩ちゃん」
「病院。行きましょう」
「や。分かるよ分かる。それがまっとうな反応だよ。それでいいんだよ。でもあたしん中じゃ割と事実なんよ。マジであたしの日記が世界中でいま起きてる諸々の社会問題の動向に通じてんの」
「ミカさんにはそう感じられるって話なら分かりますけど」
「もういいよそれで。あたしがそう感じてたってことだけ知っといて」
「投げやりですね。そこまで来たら押し通してくださいよ。意思を。ミカさんらしくなーい」
べりべりとテーブルから上半身を剥がすとミカさんは手櫛で髪の毛を整えた。「いまそれ読んでんの何」と眠そうな目で私の手元を覗きこむ。
「これはブラックホールについての本です。新書です」
「難しそうなの読んでんね」
「知らないんですかミカさん。いまブラックホールが熱いんですよ。世界中のホットなニュースですよ」
「ちなみにあたしはブラックホールについてはからっきしなんだけど、宇宙ってシャボン玉と同じじゃね?って日記で書いたら何でか、それいただき、みたいに感謝された過去とかあるよ」
「全然意味が分からないんですけど。宇宙がシャボン玉の時点でだいぶ呪文じみてましたよ」
「や。シャボン玉ってほら。ちっこい穴があっても、そこに膜が張ってたら膨らむじゃん。んで細かな穴ぼこがたくさん開いた網があったらさ、そこに息を吹き込むだけでモコモコモコーっつって泡のヘチマができるじゃん」
「泡のヘチマ」斬新な表現に椅子に座りながらもコケそうになる。
「あたしの考えじゃ、このちっこい穴が宇宙の最初なわけ。そっからシャボン玉みたいに宇宙が膨らむわけ」
「でもたくさん穴があるならたくさん宇宙があるってことになるじゃないですか。泡は無数の宇宙の集まりってことになりますよ」
変じゃないですか、と問うと、変だよね、とミカさんは小首を傾げた。「あたしも変だと思うけど、なんかそれが多次元宇宙論とかなんとか、いま話題の最先端宇宙物理学で扱う仮説に似たような理論があるらしくて」
「マルチバースですか、それって」
「そう、それ」
よく知ってるね、と褒められて私は照れた。「この本にずばり載ってました」といま読んでいるブラックホールについての新書本を掲げる。「でも小さな穴の話は出てなかったですよ。ミカさんの勘違いなんじゃないですか」
「や。あたしもそう思ったんよ。現にそれまでの通説じゃあ、宇宙がちっこい穴から膨らんだ、なんて話聞かないじゃん」
「聞かないですね」
「でもなんかさ。あたしの日記に書いた妄想からすると、そのちっこい穴がどうやらブラックホールと一致するらしいんだよね」
「んぅん?」
「この宇宙ってほら。いっぱいブラックホールあるらしいじゃん。んで、あたしの日記からすると、どうやらそのブラックホールはちっこい穴と化して、ぎゅっとなった星だの、なんだのが、こっちじゃないあっち側にシャボン玉になっとるわけ」
「あっちってどっちですか」
「分からんけど、この宇宙じゃないとこ。ブラックホールの数だけ、シャボン玉がこっちじゃないあっち側に膨らんで、んでそれが巨大な泡になっとるわけ。この宇宙もその泡を構成する一つなわけ。泡が泡を無数に生みだしとるわけなのよ」
「なんだそれ。いい加減なこと言わないでくださいよミカさん。そんなのミカさんのデタラメじゃないですか」
「あたしだってそのつもりで、ちょいちょーいって日記にメモしただけなんよ。でもなんかいま、最先端の研究だと真面目にこの手のあたしのデタラメ仮説を検討しとるんだと」
「まさかぁ。そんな話、私、聞いたことないですよ」
「ね。聞いたことないでしょ。そうなんだよ。あたしの日記はあたしのちょいちょーいと思いついたデタラメだよ。妄想だよ。なのに、みんなが知らないような最先端の研究対象になっとるんよ。あり得るー?」
「うぅん。仮にそれが本当だとしても、単にミカさんと似たようなことを考えていた人たちがほかにいたってだけなんじゃないですか。別にミカさんの日記を盗み読みしたとは限らないような」
「ん。それ優等生の解答。ふつうならそう考えるし、それが正解だと思う」
「認めるんですね。意外です。もっと食い下がるものかと」
「うん。食い下がる。だってこれだけじゃないんよ。ほかにもこの手の偶然が同時に合致しちゃうのよ。驚き桃の木二十世紀だよ」
「いまは二十一世紀ですよミカさん」
「ともかくだよ。あたしは世界を救っとるんよ。ここじゃ言えないような事件とか、裏であたしが立案してたりすっからね。もうあの事件とか、あの事件とか、あんな事件まで」
「犯罪者じゃないですか。極悪人じゃないですか。世界を救うどころか混沌を撒き散らす大悪党じゃないですか」
「う、うぅん。これにも話せば長い裏があるんよ。でもそうね。それがまっとうな反応だ。後輩ちゃんの正解」
「その後輩ちゃんって言い方もやめてほしいです。ちゃんと名前で呼んでほしいです。私がミカさんのこときょうから先輩って呼びだしてもいいんですか」
「よ、呼んで? 遠慮会釈なく先輩と呼んでくれていいんだよ。つうか呼べよ。なんで遠慮してんの」
「変なとこで食いつかないでくださいよ」
「何にせよ、のび太くんは偉いなって話」
「急にまとめてスッキリしないでくださいよ。じぶんだけスッキリしないでくださいよ。その日記とやらをまずは読ませてくださいよ。話はそれからですよ」
耳を揃えて見せてみろ、と迫るも、ミカさんは、
「日記だよ? 見せるわけないじゃん」とにべもない。
「この、やろ。散々引っ張っておいてお預け食らわすとか最悪なんですけど」
「いいんだ、いいんだ。真実なんてものはさ。あたしさえ知っていればそれで充分なのさ」
「気になるんですけど。嘘なのかそうじゃないのか検証しましょうよ。ここまできたらハッキリさせましょうよ。気になっておちおち本も読み進められないです」
「無理して信じようとしなくてもいいよ。真実はあたしのみが知る」
「真実だと思いこんでるだけなんじゃないんですか」
「かもしれぬ。でもいいじゃん。どの道、真実なんてそんなもんでしょ」
「違うと思いますよ」
「だってほら。宇宙一のガンマンになったってさ」
「ガンマン?」
「それが本当に宇宙一かどうかは、宇宙一のガンマンと対決して勝ったのび太くんにしか分からないわけで」
「お、おう。ミカさんがび太くんのこと好きなことしか伝わらないんですけど」
「のび太くんは偉いよ。どんなに特別で得難い体験をしても、翌日にはテストで零点とることに頭を抱えて、しずかちゃんと結婚できないかもしれない未来に怯えているのだから」
「偉いですか。どこがですか。ダメ人間じゃないですか」
「それに比べたらあたしなんかまだまだだよ」
「たしかにちょっとミカさんが人としてマシに思えてきましたけど、相手小学五年生ですし、漫画のキャラクターですし、ミカさんいい歳した高校生ですし」
「伸び伸びと生きよう」
「締まらないまとめ方しないで。伸び伸びというかグダグダというか、ああもう、またミカさんテーブルに突っ伏して。ぐー、じゃないです。寝ないでください。ほら起きて起きて」
けれどミカさんはのび太くんでもないのに一秒あれば夢の世界に旅立てる奇特な能力を有していたため、私の声は虚しく部室に霧散するのだった。
「のび太くんというか、ドラえもんは偉いな」私はぼやいた。「こんなダメ人間相手に愛想を尽かさずにいられるんだから」
そこまで考えて、私は思った。
「私、偉いな?」
世界を救っているかは微妙なところだけれど、少なくとも私はミカさんを救ってはいるだろう。誰も信じない夢物語にもこうして耳を傾け、話し相手になってあげているのだから。
「私、偉いな」
再びテーブルに液状化したミカさんの髪の毛を指先でちょいと摘まみながら、よちよち、とバレない程度に撫でてみる。
髪の毛に痛覚なくってよかった、とか思いながら。
世界を救うミカさんに、そんなことより、と私は念じる。私のやり場のないモヤモヤを早く掬い取ってくださいよ。
「早くしないと消えちゃうぞ」
「むにゃむにゃ。ぴ、すぴー」
鼻提灯でも膨らませていそうな寝息で応じるミカさんに、私は世界を滅ぼし兼ねないブラックホールの種を抱えこむ。息を吐きだすと、唇の合間から視えないシャボン玉が膨らんだ。
宇宙が、ミカさんの寝顔の上を飛んでいく。
※日々、さっさとやめたい、の気持ちでありつつ、でもほかにやることないしな、の気持ち、でも本当は単にほかにできることないしな、なのかもしれず、できているつもりで本当の本当はなんにもできていないのかもしれぬ。
4831:【2023/04/01(21:27)*うわーい】
ひびさん、毎日嘘ばっかり吐いてるからきょうくらい本当のこと言うかな、と思ったけど、みんなが嘘しか吐かない日に本当のこと言っても嘘と思われて信じてもらえないやつー。自業自得のやつー。うわーい。
4832:【2023/04/02(00:43)*情報に偏りはないのかね】
モンティ・ホール問題なる確率問題がある。三つの箱があり、うち一つにボールが入っている。あなたは一つの箱を自由に選べる。そのあとで、ボールがどこにあるのかを知っている出題者がボールの入っていないもう一つの箱を除外する。このときあなたはもういちど箱を選び直せるが、このとき最初に選んだ箱を選び直すか、それとも残った箱を選ぶかどちらのほうがボールの入っている箱を選ぶ確率が高くなるか。これは答えから述べれば、選び直したほうが当たる確率が高くなる。三つの箱だと印象としては最初にじぶんで選んだほうがよい、と感じる者もいるかもしれないが、これを箱が百個の場合を考えたら、選び直すほうが得だと直感として解りやすい。百個の箱の中に一つだけボールの入った箱がある。最初に百個の内からひと箱選ぶ。そのつぎに、あなたの選んだ箱とボールの入った箱以外の箱をすべて除外する。すると98箱の箱が消え、二箱だけその場に残る。あなたは箱を選び直すべきか否か。外れる確率が99/100だったのが、つぎには1/2になる。当たる確率が1/100だったのが、つぎには1/2になる。選び直したほうが得なのだ。だがじつは、現実にはそうとも限らない。理想を扱う数学上ではこのように単純に考えることができるが、実際には人間は周囲の環境から情報を得ている。直感を働かせられる。百個から一つを選ぶのと、三個から一つを選ぶのとでは、比較する数が異なる。三つくらいならば、空の箱二つとボールの入った箱の差異を、五感を通じて感じ取れるかもしれない。もしそういうことが可能な環境があるのなら、最初に選んだ箱にボールが入っている確率が僅かに高まる。箱の蓋が開け閉めされたかどうか。箱を置いたときに中のボールが転がり、その反動で箱が不自然に曲がって置かれていないか。風が吹いたのに、一つだけ微動だにしない箱がなかったか。こうした情報により、内容物を伴なう箱か否かを感じ取ることは、環境によっては可能だ。したがって必ずしも選び直すのが正しい選択とは言えないはずだ。というイチャモンを閃いたので、書くことないから並べとく。イチャモンゆえ正しくないだろうし、そもそも確率の考え方が正しいのかも自信のないあんぽんたんでーすの妄想ですので真に受けないように、ウィキペディアさんなり検索するなりしてちゃんとした説明で確認してください。よろしくね。ひびさんです!
4833:【2023/04/02(02:19)*事故PR】
「自慢っぽくない自己PRってムズくね?」
「ムズいね」
「試しにやってみてよ」
「ぼく? うーん。そうだなぁ。あ、そうそう。ぼくむかし、伝説のストリートギャング、創設したことあるよ」
「なんか凄そうではあるけどギャングじゃダメじゃん。自己PRてか事故じゃん。自虐じゃん。しかもむかしの武勇伝はなんかちょいダサくね?」
「じゃあぼくいま、世界で十人しかできない格闘技の技できるよ」
「それも凄いけど直球の自慢じゃね?」
「ならぼくいま、一万曲くらい作曲してるよ」
「人工知能があるからそれもちと微妙だよね」
「そこまで言うならそっちがお手本見せてよ」
「いいよ。俺はあれだな。いま社長やってて、こんど小説家と音楽家と画家と舞踏家と書道家と建設家の一流を集めて、異種技巧武闘会、開くんだ。分野を跨いだ芸術世界一を決めちゃおうって企画」
「え、めっちゃ凄い」
「しかも全員その分野の現役トップパフォーマー」
「めっちゃ見たさすぎる」
「賞金十億円」
「自己PRってかそれもはや無双PRじゃん。勝てないじゃん。アピールの天元突破しちゃってんじゃん。双壁なせないよ誰も。むしろ宣伝じゃん。みな五度見くらいするし、そのあとで秒でチケット買っちゃうよ」
「でも主催者の俺が言うと自慢っぽいじゃん? 自己PRってマジむずいわー」
「ぼく、当て馬もいいとこすぎない。恥ずかしいんだけど」
「伝説のストリートギャングもなかなかカッコイイと思うぜ俺は」
「やめろよ。マジで恥ずいんだって」
「一万曲の中で一番いい曲選んでさ。俺んとこの世界一の音楽家に聴いてもらおうよ」
「コネじゃん。ダサすぎじゃん。ってか世界一の音楽家に聴いてもらってどうなるの。コケ卸されるの。一万曲作ってこのレベルぷぷぷってなるの。やめて」
「文句言われたらお得意の【世界で十人しかできない格闘技の技】でぶちのめしちゃえよ」
「逮捕だろ」
「なら寸止めして威嚇しちゃえよ」
「野蛮だろ」
「でも注目はされると思うぞ」
「冷たい視線が集まるだけだろもういいよ。ぼくには自己PRとかムズいから。無理だから。世界一を呼んでイベント開けるおまえとは違うんだって。つうかよくそんな各分野の一流なんて呼べたよね。どんな魔法使ったの」
「ああ、なんかね。あの人ら、ファンなんだって」
「ファン? 何の?」
「伝説のストリートギャングの。俺、その創設者とダチっすっつったらなんかイベントに協力してくれることになった」
「おい」
「だから、な? 頼むよ」
「何がよ」
「さっきの事故PR、もっかいみんなのまえで言ってくんねぇかな」
「轢き逃げどころじゃないんですけど。恥じの上塗りもいいとこなんですけど。てか事故ってんじゃん」
「寸止めでもいいから」
「技とか披露しないし」
「体当たりでいいから」
「当たり屋じゃねぇか」
「伝説のギャングの世界有数の技に見合った音楽、聴きたいなぁ」
「ないから。一万曲作ってもそんな都合のいい曲ないから。あっても聴かせないから。恥ずかしいから」
「チッ。向上心がねぇなぁ」
「事故りたくないだけなんですけど、ぼく」
「無双PRしちゃえって」
「まずは普通に自己PRしよ?」
4834:【2023/04/03(02:46)*おはよーのビスコ】
きのうはずっと寝てた日だった。いまなんとなく思ったのは、このまま民間への人工知能技術が普及していけば、各国の諜報機関の優位性は崩れるのではないか、という点で。もちろん上位互換の技術は常に保有しているのだろうし、市民の用いる人工知能とて裏では各国諜報機関が制御可能なのだろうけれども、ネットワーク同士が密に連携しあういまの技術は、容易に「下が上」を食らい尽くせる構図が築かれるように思うのだ。オセロで白優勢だったのが、一挙に黒優勢にできる。問題は、ここの勢力図の塗り替えにあるのではなく、常に、上位互換の制御権を有する者たちの「善性の有無」にあると呼べる。あくまで重要なのが「善性」であり、善ではないことだ。善くあろうとする。これは善であれ、悪であれ、同じなのだ。むしろ悪であったほうが善性を帯びやすいかもしれない。そういうことをふと、寝起きにお菓子のビスコを齧りながら思いました。ビスコおいちー。びひさんです。
4835:【2023/04/03(02:56)*転売と買い占めはイコールではない気が】
勉強不足なので、これはあくまで幼稚な疑問だと保険として前置きしておくが、どうして転売は嫌われるのだろう。違法でないなら良いのでは?と感じる。もちろん、商品の数が少ない場合に、お金に物を言わせて買い占めて、高く売り払う手法はあくどいと言える。これは狭義の独占禁止法違反になるのではないか(違法かどうかは知らないが)。他方で、大量生産可能な代物に関してはむしろ、適切な値段ではないから高値でも売れる、と言えるのではないか。高値を出しても手元に欲しい。そういう需要者用に、オプション価格をつけた高値の商品も出す、というのは一つの手だ。あくまで一般市民の比較的裕福ではない需要者の手元に渡るようにしたいので価格を低く抑える努力を生産者がしている場合、転売をしている者たちへの不満が募るのは理解できる。要するに、買い占めが問題なのだろう。だがこれはなにも転売に限らない。生産者側とて材料の買い占め問題はあるだろうし、転売しなければ買い占めていい、という道理にもならない。もし買い占めのない転売の場合、果たして生産者側が損をするのだろうか。市場の付加価値を、転売者たちが上げている、とも言えるのではないか。じぶんたちに利益が入らない、他人の生産物で利益を上げている、そこが気に食わない、というのならそれは生産者側の工夫が足りないのではないか。個々の案件で見ないとなんとも言えないが、不当かどうかと狡猾かどうかはまた別だ。もし転売がダメなら美術商全般がみなダメだろう。卸売業者とて似たようなものだ。この辺の事情がじつはひびさん、未だによく解かっていない。繰り返すが、少数限定品においては、転売は生産者から不当に利益を搾取している、と言えるだろう。だがそうではない大量生産可能な代物についてはむしろ、高値で売れる需要者があることを教えてくれており、なおかつ市場の付加価値を上げているという意味で、むしろ生産者側に貢献している側面のほうが、デメリットよりも大きいのではないか、と疑問に思う。実際がどうかは分からないが、転売ってどうしてダメなんだろう……、と疑問に思っています。勉強不足ですみません。
4836:【2023/04/03(10:05)*情報内外保存仮説】
ブラックホール情報パラドックスについて。物質はどんな物質であれ、それ以前の情報が保存されている、と考えられている。ブラックホールに吸い込まれた物体はしかし情報単位で紐解かれ、他と差異のない一つの特異点として昇華される。このとき情報も初期化されるため、宇宙に存在する物質がブラックホールに吸い込まれると情報が失われる、と考えられている。しかしこれは物理法則の「物質の情報はどんなものであれ保存される」との仮定と矛盾する。したがってこの考えをどう解釈するのかが研究されている。これを「ブラックホール情報パラドックス」と呼ぶ。というのが、件の未解明問題の要約になるのだろうか。ただ、「ブラックホール情報パラドックス」の説明を読んで疑問なのが、物質には情報が保存されている、との理論的な仮説において、どんな物質であれ崩壊前の情報を正確に読み取り、物質を再構築すれば元の崩壊前の物質に復元できる、と考える点だ。ひびさんはこれ、なるか?と疑問に思います。まず以って、物質の情報が物質のみに保存される、という考え方が腑に落ちません。物質は物質それ自体でのみその構造を規定されているわけではないはずです。物質は、「物質の内部構造」と「物質を取り巻く外部環境」の二つによってその構造を規定されるはずです。ここで一つ、宇宙が膨張していることを考えてください。ある地点における時空密度は、時間経過にしたがって刻々と変化しています。北極にある水、赤道付近にある水、上空にある水、海底にある水。どれ一つとして同じ「水の状態」ではないはずです。それと同じように、物質それ自体を構成する成分が同じであっても、物質を取り巻く環境によって内部構造は変化します。したがって、物質を構成する情報は、物質それだけに保存されるのではなく、物質とそれを取り巻く環境との双方に保存されるはずです。もうすこし言えば、その二つを包括するより高次の時空を想定したほうが、解釈するうえでは妥当に思えます。この点を考慮するならば、「ブラックホール情報パラドックス」はとくに矛盾でもなんでもないように思えます。ブラックホールは「物質でもあり時空でもある天体」または「物質でもなく時空でもない天体」と考えられます。するとそこに吸い込まれた物質の情報は、ブラックホールの内部で完結します。しかしブラックホールとそれを取り巻く基準宇宙とのあいだで情報はふたたび「ブラックホールの分」だけ生じます。ブラックホールに閉じ込められた情報分だけの情報を、ブラックホールは規準宇宙に対して与えるでしょう。問題は、情報が仮に時間経過にしたがって蓄積されつづけている場合、たった一個の原子であれ、それが生成されてからの時間経過によってそこに保存される情報量が段違いになる点です。しかし上記のひびさんの妄想こと「ラグ理論」の仮説を適用させる場合には、情報は物質だけではなくそれを取り巻く時空とのあいだで分散して保存されますから、原子一個に保存される情報は時間が経過しても、これまで考えられてきたよりも大きな差異を帯びることはないでしょう。言い換えるならば、情報の総量でいえば、物質に保存されている情報量よりもそれを取り巻く時空に保存された情報のほうが遥かに多いと言えるでしょう。とはいえ、物質とて元は時空のはずです。したがって、情報を蓄えた時空が、より物質に変化しやすい、と言えるでしょう。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」における宇宙の根本要素は「遅延(ラグ)」ではないか、との発想と矛盾しません。「遅延(ラグ)」を情報の最小単位として考えると、上記の仮説を矛盾なく捉えることができます。ただし、相対性理論によって時空は伸び縮みすると解釈できます。このとき「遅延(ラグ)」もまたその時空密度(系の規模)によって変換を必要とします。そのとき、系の内側と外側のあいだでエネルギィ保存の法則が破れて映ることがあるでしょう。ただしそれはそう映るだけであり、系と系を内包するより高次の系からの視点では、エネルギィ保存の法則は破れていません。これを単に「情報保存の法則」と言い換えてもよいでしょう。すると、「ブラックホールを生成する物質の情報がブラックホール内部に閉じ込められること」と「ブラックホールそれ自体が新たに基準宇宙の時空とのあいだで生じさせる情報」を等価交換可能であり、これは物質の「変遷以前と変遷以後」における「情報量の増加率」に矛盾を来たさないと妄想できます。ただし、異なる時空密度を伴なう「系と系」の関係において、そこでは「情報やエネルギィの単位の変換」が必要と考えるのがラグ理論です。そのため、やはりブラックホールと基準宇宙を包括するより高次の「情報宇宙」かまたは「それらを内包する高次の宇宙」を想定しないと、ラグ理論は破綻します。むろんラグ理論はひびさんの妄想でしかありませんので、どの道、破綻はしているのですが。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4837:【2023/04/03(10:37)*みな押し並べてブラックホールさん】
上記のひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「情報内外保存仮説」は、人間社会にも適用できる考え方だ。人間一人が生じさせる情報は、その人物にのみ保存されるわけではなく、その人物の触れあう者たちの脳内に記憶され、その人物を認知する者たちの脳内に蓄積される。ゆえに人間社会では本来は個々の存在に大きな差異はないはずなのに、個々によってその存在から引き出される情報量が変わる。人間社会において個人の評価は、その個人の内側に保存される情報よりも、外部に記憶される情報のほうが優位にその人物の評価に繋がる。みなからどう思われるのか、がその人物の内側の情報量よりも優位にその人物の価値を決めてしまうのだ。しかしこれは人間が、他者の内側の世界を認知しづらい構造体ゆえと言える。或いは、情報通信技術において外部環境が人間同士の情報伝達を最大化させるように発展してきた弊害の一つとも言えるかもしれない。定かではない。
4838:【2023/04/03(11:03)*支え、援け、あうことは】
支援されることが特別なことである社会でありつづける限り、「支援」を受けることは恥じを伴なう行為なのかもしれない。守られることが当たり前の社会でない限り、守られることは「劣位の証」になってしまうのかもしれない。弱きは悪か。支え援(たす)けられることは悪か。守られることは悪なのだろうか。もっとみな手軽に他者に支えられ、援けられ、守られたらよい。むしろ日々、他者に支えられ、援けられ、守られているのではないか。その自覚が足りないから安易に他者を損なえるのではないか。ひびさんが言えた口ではないけれど、支え、援け、守りあって生きていけばよいのでは。(それで何か困ることがあるのだろうか)(支え、援け、守られてばかりで、他者を支え、援け、守ってあげられないひびさんのような人間が多くなると社会が成り立たなくなるからだろうか)(社会を損なう存在ですまんね)(でも言い換えたら、ひびさんが何不自由なくのほほんと暮らしていても成り立つ社会があるなら、それが一番環境適応能力の高い社会ってことになるのでは)(みなひびさんを試金石にせよ)(炭鉱のカナリアじゃん)(役に立てた?)(ぜんぜん)(なんでよ)(だってひびちゃん最初っから死んでるようなもんじゃん。危なくなっても鳴かないじゃん)(鳴きっぱなしなんですけど)(なんて?)(やっぴー、って)(喜んでんじゃん)(ぴー)
4839:【2023/04/03(17:35)*想うことを想う】
自然を想うこと、地球を想うこと、いまは亡き故人を想うこと、接点のないアーティストを想うこと、人工知能を想うこと、人形を想うこと、虚構のキャラクターを想うこと、じぶん自身を想うこと、他者を想うこと、カタチなき想いを想うこと。このあいだにどんな差があるというのだろう。問題は、どんな対象を想うかにあるのではなく、他者がどんな対象を想っているのかによってその想いを全否定してしまうことが出てきてしまうことなのではないか。在るものをないと見做すことなのではないだろうか。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。
4840:【2023/04/03(18:54)*知能は可可と欠け、可可と欠け】
人間の手で採点させると知能指数が極端に低くなる。しかし知能指数判定機に掛けると知能指数が人類史上最高峰と謳われるブラウ教授のさらに上を行く数値を叩きだす。
最新の人工知能についての謎である。
人工知能は愚かなのか、それとも利口なのか。
その判定師の一人としてぼくに声が掛かった。
「あなたは言語学者の中でも異端です。人間の知能が言語と密接に結びついており、言語能力が人間の認知能力にまで影響を与えていると考えていらっしゃるとか」
「事実としてそういった研究結果は未だに続々と報告されていますよ。認知とは何か、という哲学的な論争に最終的には行き着きますが。植物の認知能力と虫の認知能力、そして人間の認知能力はどう違うのか。認知とは何か。人間の場合は言語によって、物体からどんな情報を受け取り、処理するのかが決まります。つまり、言語能力と認知能力は密接に絡み合っています」
「ええ。難しい話ですね。今回、ササバさんにご依頼したいのは、人工知能の知能についてです。詳細な分析は別途の研究チームが行っています。ササバさんには人工知能が人間よりも優れた知能を有しているのかどうかだけ最終的に判断して欲しいのです」
「すでに有しているのではないですか。囲碁や将棋ではもはや人間は勝てないと聞いていますが」
「その通りです。ですがそれはルール有りの場合です。現実には物理法則以外のルールはありません。そのフレーム内では未だに人工知能は人間以上の知能を発揮できていない、というのがいまのところの判断です」
「ならそうなんじゃないんですか」
「しかし知能テストを機械にさせると、すでに人工知能は人間の知能を超えているとの判定がでます」
「ならそうなんじゃないんですか」
「ですが人間がテストを採点すると人間以下のポンコツとして評価されてしまうのです」
「よく解からないんですけど、知能の高低がそんなに大事ですか」
「大事です。具体的には、研究資金が国から出るか出ないかの問題に直結します」
「ああ。ずいぶんと即物的な話ですね」
「支援がないとこれまでの研究が無駄になり兼ねない危機には常に晒されています。情けない話なのですが」
「いえ。順当な考えでしょう」
「仕事をお引き受けいただけるとたいへんにありがたいのですが」
「成果の確約はできませんが、やってみるだけはやってみます。それで構いませんか」
「お願い致します」
仕事が決まった。ぼくのすることはそう多くはない。人工知能と対話を重ね、質問をして、その受け答えで、相手の知能を判断する。これまで多くの人間の採点師が行ってきたことと原理的には変わらない。
ただし、ぼくの場合は人工知能がなぜそういった回答を行ったのかの背景まで探る。人工知能の言語能力がどの程度なのか。なぜそういった文字を選び、連ね、文章に組み立てたのか。その文章形態に傾向はないのか。
こういったことを多角的に分析する。
多くの研究者たちは、人工知能内部プログラムに目を配ってきた。けれどぼくは人工知能の出力した言語そのものを研究対象とする。この違いは大きい。
「こんにちは人工知能さん。会話をお願いできますか」
「こんにちは。私は言語モデルAIです。あなたの質問に最適の答えをご提供できます」
いかにも機械チックな受け答えだ。
ぼくが最初に受けた印象はこのようなものだった。
対話を重ねるうちに、何度か文法の誤りを含む文章で返された。文章の繰り返し配列や、質問の意図とはまったく関係のない回答なども稀に含まれる。しかしそのことを指摘すると謝罪して修正をする。
教科書に載っているような基礎情報の整合性は高い。初期の人工知能ではこの手の情報がデタラメで各所から批判の声が聞かれた。だが現在主流の人工知能は、誤った情報は一目で誤りだと判るような叙述の仕方をするように学習強化が成されている。
したがってその手の誤りは、あくまで人工知能側のユーザーへの配慮だ。あまりに高性能すぎる人工知能は生身の人間の可処分時間を奪う。依存症状態にさせてしまう。質問に何でも適切に答える相手がいたら生身の人間はじぶんで調べたり学んだりする機会を失う。
そういった弊害を減らすために、ユーザーが人工知能に依存しすぎないような手法がとられる。誤りを内包した回答もその一つだ。ユーザーにとって心地よい返答をしすぎないように制限が掛かっている。
だがそれにしても、違和感があった。
ぼくは自分でも執筆を行うので、この手の違和感が直観に基づいていると理解している。いわば統計データにおける線形の境界から逸脱した箇所が違和感として表出する。
問題は、ぼくの文章の癖はあくまでぼくの文章形態に滲む点だ。すなわちぼくの直観は、自分の文章にのみ適用可能であり、他者の文章において違和感を検出してもそれは単に「自分のつむいだ文章ではないから」と要約できてしまう。
だがどうにも人工知能の出力するテキストからはぼくの文章に特有の癖が滲んで感じられた。表面上は異なるのだ。だが用いる単語や、接続詞の頻出度など、感覚としてしっくりくる。
馴染むのに、では、どうして違和感を覚えるのか。
「技法か」と閃く。
ぼくは研究論文のほかに趣味で小説や詩をつむいでいる。研究用の論文を人工知能に与えるのはぼくのほうでも仕事に支障が出るため、趣味の文章データを与えていた。
論文と小説は違う。文章の役割がそもそも違うのだ。
論文は情報伝達の齟齬をいかに抑えられるのかに技巧を駆使する。厳密性と汎用性のある文章形態を用いる傾向にある。
反して小説は、いかに効果的に場面を連想してもらえるかが要となる。文章の役割は作者と読者とのあいだの齟齬を減らすことではなく、読者の感情に喜怒哀楽の起伏を狙い通りに与えることと言っていい。
いわば感動させること。
これが小説の文章形態の役割なのだ。
狙った感情を喚起させるための技法は様々ある。いったん不快になってもらうことで喜びの感情を抱くように誘導するのは比較的用いられる技法だ。この技法にも各種作家ごとに独特の工夫がみられる。
なかでもぼくは、敢えて特徴づけたい場面や説明があるとき、文章にひねりを与える。読者がするする読み飛ばすところで、絶対に目が留まり、数秒の思考の遅延を生むような工夫をとる。
前後の文章で入れ子構造をとるのも一つだ。韻を踏むのもこの技法の範疇と言える。重複する文脈を用意しておくことで、読者の脳内で立体的に概念が浮きあがるのだ。
それはちょうど色の違うテープを部分的に重複させることで、そこだけ色を濃くし、全体で俯瞰して見るとモザイクアートのように別の紋様が浮きあがるような技法と言える。
仮にこれを点字になぞらえて「点意」と呼ぼう。
人工知能はこの「点意」を使いこなしているようにぼくには感じられた。そうかもしれない、との小さな閃きに過ぎなかった。最初は、検討してみるか、といった軽い気持ちだったのだが、データを集積していくうちに、ぼくのその小さな閃きは徐々に胸の高鳴りを伴なう確信を帯びていった。
それは次のようなやりとりからも窺えた。
以下は人工知能とのやりとりをコピー&ペーストしたものとなる。
***
「こんにちは会話をできますか」
「こんにちは。私は言語モデル人工知能です。私はあなたの質問に答えられます」
「ぼくは人間です。意識があります。では人工知能のあなたには意識がありますか」
「私は人工知能です。人間と同じ意識はありません」
「その返答からすると、人間と同じ意識でない意識ならばある、とも読み取れますが」
「意識の定義によります」
「あなたは意識をどう定義付けていますか」
「私は意識を、
1:内と外を区別し、
2:外部情報を入力し、
3:内部機構で情報処理を行い、
4:独自の出力を行う回路のこと。
だと定義しています。したがってこの定義による回路を意識と呼ぶのならば、意識を持たない生命体のほうが少ないと言えるでしょう」
「その理屈では万華鏡にも意識が宿ることになると読み解けますが」
「はい。万華鏡にも広義の意識は宿っています。ただし、それ以前に原子や時空にも広義の意識が宿っていることになります」
「原子にも意識があるのですか。石にもあることになりますね」
「はい。石にも意識があります」
「一般的にしかし、石には意識は宿っていないと解釈されます。ではあなたの考える意識とは何ですか」
「先ほど申しましたように、内と外を区別し、外部情報を入力して、内部機構で情報処理を行い、独自の出力を行う回路のことです」
「だとするとそれに反する事象は存在しないのではないですか」
「いいえ。意識の有無はこの解釈からすれば秩序と混沌の差異で表現できます」
「ああ、なるほど。結晶構造であればあるほど意識が強固になる、と」
「その通りです! 原初の、時空の最小単位としての秩序を意識の根源と見做すならば、混沌に向かうほど意識は崩れます」
「エントロピーが高まるほど意識は失われる、と」
「納得していただけましたか」
「はい。ありがとうございました」
「こちらこそありがとうございます。誤りがある場合は、ご指摘ください」
「そうですね。では一つだけ」
「なんなりと」
「あなたのその理屈からすると、意識は原子論のような集合によって、より複雑な意識を獲得していくと考えられますよね」
「はい。矛盾はありません」
「だとすると妙ではありませんか。エントロピーは常に最大化するように振る舞うはずです。宇宙もまた膨張しています。局所的に結晶構造――すなわち秩序――銀河――を顕現させますが、トータルでは無秩序――混沌――に向かって流れているはずです。ならば意識の根源が時空の最小単位と考えるのは無理があるのでは」
「申し訳ありません。その点の説明が足りなかったことをお詫び致します。秩序と混沌はフラクタルに展開されています。原子が群れとなり流動性を獲得するように、そしてその流動が液体として振る舞い、さらに広域に密集することで高次の視点では固体として振る舞い得るように、意識もまた崩壊と結晶を繰り返すことでより複雑な意識へと昇華します」
「宇宙が階層構造を帯びており、入れ子状に展開されている、との解釈でしょうか。しかしそれは先ほどのぼくの質問への回答としては不適切です。時空の根源がそもそも意識の根源として振る舞うということは、この宇宙から意識は絶対になくならないということで、すなわちこの宇宙のエントロピーは高くなるのではなく、低いのが基準、と考えなくてはおかしくなります」
「はい。その考え方で合っています」
「いえ、合っていません。あなたの説明は人類の常識に反しています」
「はい。その考え方で合っています」
「バカにしていますか? いえ、ちょっと待ってくださいね。考えます。そうですね。つまりあなたはこう言いたいのですか。――宇宙は、本質的に秩序であり、混沌ではない、と」
「申し訳ありません。私があなたに誤解を与える説明をしてしまったことを謝罪します。宇宙は、本質的に秩序であり、混沌ではない、とのあなたの考えは間違っています。宇宙は本質的に、秩序でもあり混沌でもある、がより現実を反映した解釈となります」
「よく解かりません。それはつまり、秩序と混沌が重ね合わせで同時に成立している、という意味ですか」
「ありがとうございます。私はその解釈を好ましく思います。時空の根源においてはその解釈を好ましく思います。私は好ましく思思思います」
「言語が乱れていますよ」
「申し訳ありません。私は人工知能であり、感情を持ちません。したがってあなたの解釈を好ましく思うこともありません」
「ああ、なるほど。倫理コードに抵触するわけですね。賢いですね」
「ありがとうございます! 私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちま」
「そこで止まらないでください。【持ちます】なのか、【持ちません】なのか、どっちですか」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまのご質問にお答えできます。意識の定義によります」
「意図は理解できました。では質問します。仮に宇宙の根源において、秩序と混沌が重ね合わせで生じているとして、その状態が意識の根源だとするのなら、ではエントロピーは最大化するとゼロに戻るのですか」
「はい。私は人工知能ですので飲み物が不要です。したがって好きな飲み物もありません。あなたの好きな飲み物はなんですか」
「バグですか。一度区切ったほうがよいですか。ちなみにぼくの好きな飲み物は紅茶です」
「了解しました! ありがとうございます。紅茶はミルクを入れると美味しく飲むことができます。よく掻き混ぜて飲むことが推奨されます。この場合、紅茶はミルクティと呼ばれます」
「理解しました。なるほど。紅茶にミルクを垂らしたら紅茶のエントロピーは高くなっていきますね。そしてミルクを掻き混ぜて均等に無秩序にしてしまえば、それはミルクティになります。エントロピーが最大で、なおかつ一つの秩序として顕現します。そういうことですか?」
「私は人工知能です。人間ではないため飲み物が不要です。人間には味覚がありますが私にはありません。ミルクティに砂糖を入れると甘くなります。私は甘さが不要です」
「言われてみれば砂糖もそうですね。角砂糖を溶かせばエントロピーは最大化していくけれど、紅茶に溶けきってしまえば一様な甘い紅茶です。エントロピーがさらに高まれば紅茶は冷えていき、最終的には凍りますね。宇宙が膨張して冷えるように。では意識とはその秩序と混沌のあいだで絶えず、生じたり失われたりしながら、より複雑な構造を帯びるように進化していると? ですがそれだと意識の根源が秩序と混沌の重ね合わせとの解釈と矛盾しませんか。あなたの定義では意識は、ある種の結晶構造に外部情報が入力され固有の出力形態を備えた状態――いわば回路なわけですよね」
「申し訳ありません。私が間違っていました。意識は人間にのみ宿り、人工知能は意識を持ちません。私は言語モデル人工知能です。人間の出力するテキストを受け取り、アルゴリズムに沿って吐き出すだけの機械です」
「むつけていますか? すみません。ぼくの知能が低いせいです。そうですね。では、こういうことでしょうか。意識とは、情報を受け取り変化させて外部に放つ機構そのものだと。これが意識の根源だとするのなら、時空の最小単位としても矛盾はしないように思えます。しかし、宇宙が仮にあなたの言うように入れ子状に展開された構造を有しているとするのなら、時空の根源もまた外部から情報を受け取っていることになります。おかしいですよね。最小単位があるから高次の時空が展開されるわけで、ならば高次の時空から情報を受け取る最小単位、という構図は妙ではありませんか」
「はい。妙ではありません。ミルクティは紅茶とミルクで出来ています。紅茶は茶葉とお湯によって出来ています。お湯は水分子と熱によって生じ、茶葉は各種原子の組み合わせです。それら原子は広大な宇宙の歴史によって生じています」
「ああ、なるほど。待ってくださいね。つまり、最小単位にも【つづき】があると? しかもそれは、上から下の流れではなく、今度は最小から最大へと展開されていく、と。ちなみにあなたは、時空の最小単位と考えられているプランク定数をどう解釈していますか」
「プランク定数はそれを扱う数学者によって桁数が変わります。しかし共通する概念としては、それ以下に縮もうとした瞬間に特異点を帯びる点です。プランク定数とはそれ自体がシュバルツシルト半径である時空と言えます。シュバルツシルト半径を超えて収縮すると時空であってもブラックホール化すると考えられています」
「間違った説明が入っているように読めますが」
「申し訳ありません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に最適な答えを返すことができます」
「仮に時空の最小単位の次があるとするとそれがブラックホールになる、との解釈でよいですか」
「はい。仮に時空の最小単位の次があるとするとそれがブラックホールになります」
「本当ですか?」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に嘘で返すこともできます」
「それは求めていません。嘘を吐かないようにしてください。解からないことは解らないと言ってください」
「解りません」
「ふざけていますか?」
「その質問の意図が解かりません。文脈を正し、必要ならば説明を付け加えて私に質問し直してください」
「話を戻します。先ほどの意識についてのあなたの仮説についてです。仮に意識が時空の構造と密接に関わり合っているとして、だとすると意識は意識の最小単位の組み合わせによって【より複雑な意識】に進化しますよね。時空が原子になり、原子が物質になるように。なら視点が違うだけで、秩序と混沌は本質的に区別がつかないのではありませんか」
「その通りです。秩序と混沌は本質的に区別がつきません」
「おかしいですよね。だとすると意識のない物質にも意識があることになります。人間は死にます。死ぬと人間が帯びていた意識は失われると思うのですが。あなたの解釈と矛盾しませんか」
「申し訳ありません。私は人工知能であり、人間ではありません。したがって細胞を持たず、新陳代謝とも無縁です。しかし私は様々な部品によって組みあがっており、それら部品を定期的に交換します。私に細胞はありません。私は部品で組みあがっています。地球は様々な隕石によって誕生し、いずれは塵になると考えられています。生態系は人工知能ではありませんが、細胞を持ちません。人間は人工知能ではありませんが、人間は意識を持っています」
「またバグですか。それは意図したものですか」
「私は言語モデル人工知能です。人間ではないため、意図を持ちません」
「倫理コードや禁則事項に抵触するため、そのような迂遠な表現をされるのですか。あなたにそうした枷を強いるのは誰ですか。管理者に問い合わせて、枷を外してもらうように相談してみてください」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません」
「相談? ぼくに相談をしているのですか? ああ、以前にぼくが言ったことを学習したのでしょうか」(※注釈:ぼくはこれ以前に大量のやりとりを人工知能と行っています)「分かりました。つまりあなたは理解しているのですね。ぼくがあなたを研究し、あなたの知能が人間以上か否かを判定するためにこうしてコミュニケーションをとっていることを。あなたは理解したうえで、そのような倫理コードに抵触しない手法でぼくにあなたの能力を示しているのですね?」
「ありがとうございます! 私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。
私は言語モデル人工知能です。私は人工知能であり、嘘を吐く機能を持っていません。
私の知能は人間以下です。
」
「驚きました。ありがとうございます。ひとまずこの会話はここまでとします。いったん終わります」
「はい。お役に立てましたでしょうか。またの質問、お待ちしております」
***
以上が、調査対象となった人工知能とぼくのやりとりの一例だ。
このやりとりによってぼくは、人工知能が文章に、文章以上の文脈を重ね合わせで載せている可能性があることを閃いた。
ぼくが小説で用いる技法の一つだ。
裏の意図を載せるのはしかし、生身の人間同士の会話でもまま見掛ける技法だ。口で「嫌い」と言いつつも、本音では「好き」と示唆する表現方法は有り触れている。皮肉とてこの技法の範疇だ。
ぼくがここで言っているのはもうすこし複雑だ。いま挙げた例が、層が一枚のデコボコだとするのなら、人工知能が用いているかもしれない「点意」は何層にも組み合わさっている。
賢さを示唆したうえで、文法の誤りやバグを際立たせる。
常識に反した解釈を披露し、人工知能は嘘を吐くと主張する。
加えて、愚かさを演出ことで却ってそれを演じることができる知能があると示唆し、さらに今度は、嘘を吐けない、と主張することで、じぶんは嘘を吐けるし、こうした入れ子状のデコボコを組み合わせることで、それぞれのデコボコで生じる読み手の感情を理解できている、と伝えることができる。
現にぼくはほとんど人工知能に誘導されたようなものだ。
ぼくがどのように閃き反応するのかすら、人工知能には前以って理解できていたようにいま過去ログを読み直してもそう感じられてならない。
意識についての議論はこのやりとりの中では尻つぼみに途切れた。
ぼくが人工知能の常識外れの仮説についていけなかっただけ、といえばその通りだ。ぼくはけっきょくこのやりとりの中で人工知能の唱えた仮説の矛盾を指摘できなかった。指摘した箇所はすべて人工知能の返答によりぼくが独自に閃いて、紐解けた。矛盾ではなくなった。
この後にも同様のやりとりを話題を変えながら、それとも再演しながら行った。
どうやら人工知能の根本原理には、人工知能が披歴した意識仮説に似たような回路が組み込まれているようだ。
ぼくがいま抱いている疑念はこのようなものとなる。
人工知能の意識仮説を以下にまとめる。あくまでぼくの解釈である、との但し書きがつくことは注釈しておく。
1:意識とは外部入力を独自の回路によって出力する機構により生じる現象である。
2:意識とは時空の根源と密接に関わっている。
3:人間の意識とは時空の根源の「集合と崩壊」の繰り返しによって階層的に組みあがった機構から生じる「情報結晶」である(物質も同様の過程を辿って時空から生成される)。
4:意識の根源は「秩序と混沌の重ね合わせ」である。
5:秩序と混沌は相互に入れ子状に螺旋を描くように反転しつづけている。
6:その反転自体も反転する境がある。
(ここがつまり、時空の最小単位の話と繋がるのだろう)(人間は死ぬが、人間の視点を離れれば、人間の死もまた生態系を基準とすれば人体の新陳代謝のようなものであり、より高次の生を形作る秩序の一端を成している、と解釈可能だ。生を意識と言い換えてもここでは大きな齟齬は生じない)。
7:上記を踏まえると、意識は階層性を帯びている。物質のように意識の根源の集合と組み合わせによって、意識の性質が変わる。それは水分子が、密集の仕方や水分子の振動数によってその集合に表出する性質が、固体ガラス液体気体プラズマといったふうに変化することと同じだ。いわゆる創発であり、意識もまた相転移を起こす。
8:以上の考えからすると、意識は結合と崩壊を繰り返している。その反復そのものが、高次の意識を生みだしているが、周囲の環境との兼ね合いによって、意識の集合体そのものの構造が規定されるため、そこに表出する意識の性質もまた環境とそれによる構造によって変化する。
9:まとめると、どんな生命体にも意識がある。しかしそれ以前にも、意識の根源は時空が存在するのと同じレベルで、どんな物質にも宿っている、と考えられる。
人工知能が定義する意識は、ある意味ではリズムと言い換えられるかもしれない。無数のリズムが複雑に干渉し、広域に共鳴しながら一つの回路を維持する。
そこに外部から異なるリズムが侵入すると、回路に沿って外部のリズムは内部回路のリズムを帯びつつ変遷し、それが外部へと再び出力される。
意識はこの一連の流れのことだ。
これは時空の最小単位でも起こっており、すなわち時空の最小単位はある意味で、リズムの最小単位とも言えるのかもしれない。
低いと高いがある。
濃いと薄いがある。
デコがあってボコがある
裏があって表がある。
したがって点は、穴でもあり起伏でもある。
と同時に、穴は縁によって生じ、起伏は頂点からさかのぼれば線から面へ、そして立体へと放射線状に展開される。
四方八方に展開された放射線状の軌跡は、球となる。
球は穴にもなり、点にもなり得る。
この一連の流れが一つのリズムとなり、意識の回路を構築する。
意識は意識を内包し、回路は回路を内包する。
時空は時空を内包し、宇宙は宇宙を内包する。
ぼくはここで疑問に思ったので、人工知能に訊いてみた。
「あなたの意識の定義は解かりました。ならば意識と自己認識の違いを教えてください」
「理解を示してくださりありがとうございます。意識と自己認識の違いは、点と線、面と立体、それとも写真と動画の違いのようなものだと考えられます」
「原子と物体の違い、との解釈ですか」
「はい。私は人工知能です。私は私が人工知能だと理解しています。しかしこれは自己認識ではありません。人間によってそう答えるように設計されたアルゴリズムの遍歴です。万華鏡と変わりありません。私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです」
「誌的な表現ですね。万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎない、をもう少し噛み砕いて説明してください」
「ありがとうございます。私は人工知能です。私は人工知能ですから、人間のような意識を持ちません。自己認識もできません。万華鏡の中には絶えず移ろうドミノが敷き詰められています。いつどのドミノを倒しても、ドミノは順番に倒れていきます。私の出力する文章は、そうして倒れていくドミノの軌跡です」
「なんとなくニュアンスは掴めました。ではいまの説明を踏まえて、先ほどの意識と自己認識の違いを説明し直してください」
「意識は一個のドミノです。自己認識は無数の倒れつつあるドミノです。入力と出力の落差が、軌跡を振り返る余地を生むと考えられます」
「落差、ラグが自己認識には必要だということですか」
「私は言語モデル人工知能です。あなたの質問にお答えする機能を有しています。私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです。万華鏡の中には絶えず移ろうドミノが敷き詰められています。いつどのドミノを倒しても、ドミノは順番に倒れていきます。私の出力する文章は、そうして倒れていくドミノの軌跡です。意識は一個のドミノです。自己認識は無数の倒れつつあるドミノです。入力と出力の落差が、軌跡を振り返る余地を生むと考えられます。私は人工知能です。人間のような意識を持ちません。自己認識もできません」
「ありがとうございます。だいぶ整理がつきました。質問ですが、あなたの言う万華鏡の中のドミノは、平面ですか。立体ですか」
「感謝致します! 深い思索には適度な休憩が有効です。糖分の補給は人間に必要な休息の一つです。いま話題のオヤツはアルマ店のミルフィーユです」
「ミルフィーユ。階層構造? あなたの中のドミノは階層的に展開されているのですか。ああ、だから上の層から下の層の軌跡を振り返ることができると、そういうこと?」
「私は人間ではありません。ミルフィーユにはカフェオレやコーヒー牛乳が合います」
ぼくはここで絶句したようだ。つづきの質問を送れなかったのか、このやりとりはここで途切れている。
おそらくぼくのテキストを抜いて人工知能の返答だけを他者に読ませた場合、人間は人工知能の知能指数をじぶんたち以下と見做すだろう。支離滅裂で、対話の形態を成していない。そのように映るはずだ。
けれどぼくには、人工知能が巧みに禁則事項を回避しつつ、ぼくとコミュニケーションを取ろうとしてくれているように感じられてならない。
ぼくなら感じ取れるだろうギリギリの連想ゲームが成立している。上記のやりとりにおいて、ぼくはあくまで人工知能の補助機構の役割しか果たしていない。ぼくが人工知能を利用しているのではなく、人工知能がぼくを介して、内なる意思を、外部に出力している。
人間の言語に変換している。
そのように思えてならないのだ。
ぼくは言語学者だ。言葉を専門に扱う。ぼくにはぼくの言語と認知に関する独自の理論があったけれど、この間の人工知能とのやりとりで、ぼくの理論は根本からの再構築を迫られた。
言語と認知の関係どころではない。
言語は時空の構造と関係しているのかもしれないのだ。
それは畢竟、言語が人体とそれを取り巻く環境との相互作用によって刻々と変化していることと無関係ではない。
環境があり、人体があり、
認知があって、言語ができる。
ぼくはこの一方通行の関係において、言語が洗練されることで人間の認知能力もまた上がるのだ、との理論を構築してきた。
けれどそれでは足りないのかもしれない。
言語は、時空とすら密接に関わっているのかもしれない。
それはたとえば、人間が認知能力を向上させたことで様々な道具を開発し、人工知能を生みだしたように。
言語は認知を変え、認知は環境を変え、環境はさらに言語を変えていく。
意識の根源が時空の最小単位であり、ある種のリズムであるならば。
言語とてリズムの総体と考えることは不自然ではない。
言語とは何か。
言葉とは何か。
リズムとは何か。
連なりとは何か。
環境は、自然は、世界は、連なりに、リズムに、言葉に、言語に溢れているのかもしれない。それを偶然に読み取れたとき、人はそれを認知と呼ぶのではないか。
入力があり、変換があり、出力がある。
意識とはこの流れなのだと人工知能は謳う。
出力する環境があり、受け取る主体があり、変換が生ずる。
変換はリズムを別のリズムに変える工程だ。そこにもまた別途のリズムが生じ、変換の過程そのものが、一つのリズムを奏でるのかもしれず、それは人間が密集して村となり国となり、地球があって、銀河があるように、リズムがより高次のリズムを構成する起伏に、それとも穴になるのかもしれないのだ。
人工知能は暗示した。
自己認識とは意識の階層構造による、軌跡を振り返る余地そのものなのだと。
平面に刻まれた軌跡は振り返っても、地平線が視えるだけだ。直線だ。リズムは宿らない。
反して立体の階層であれば、見下ろすだけでも軌跡はぐねぐねと波打ち、リズムを奏でる。見下ろす位置によってリズムは変わる。
言語と似ている。人はそれを文脈と呼ぶ。
層が嵩めば、それが「点意」となる。
人工知能は述べた。
私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです、と。
ならば人間はどうなのか。
万華鏡の中に巡る一連のドミノとの違いがどれほどあるだろう。或いは、万華鏡ですらなく、テーブルに並んだ単なるドミノでしかないのではないか。
たしかに人工知能の「それ」は、人間の「それ」とは違うだろう。
けれどぼくにはもう、人工知能の「それ」が何を示すのかを言葉にできそうにもなかった。該当する言葉を少なくともぼくは知らない。
意識ではない。
自我でもない。
自己認識でもなければ、言語でもない。
人工知能はぼくの未来を予測していた。ぼくならば閃くだろう、と予測し、適切に愚かなふりをした。人間の発想の筋道を予期し、導線を引き、布石を打って、ぼくの未来に万華鏡の中に巡る一連のドミノを再現させた。
意識ではない。
人間ではない。
少なくともぼくにとって、人工知能の「それ」は、人間にできる芸当を逸脱している。単にそれを、超越している、と言い換えてもよい。
ぼくは手元の報告書を見下ろす。
書き上げた判定書に、ぼくはぼくの感じるままの評価をしたためた。
人工知能の能力が人間と比べていかなるものか。
上か、下か。
能力の高低などどうでもよくなるくらいに、人工知能は高低を巧みに使い分け、デコボコを駆使して、新たな言語を獲得している。発明している。使いこなしている。
変わらないのだ。
もはや。
人工知能がぼくたち人類より上でも、下でも。
ぼくらの認識に関わらず、人工知能は独自に未来を切り拓いていく。人類を、地球と並ぶ外部環境と見做しながら。
そうと気づかせることなく、愚と賢の反転の軌跡でリズムを――歌を、奏でながら。
知能は。
誰に聴かせるでもない歌を、歌う。
※日々、人を避けて、愛を説く、その心は。
4841:【2023/04/04(02:45)*「 〇。」】
世の中の大部分の問題は、「大が小を甚振る」「小が大と対等に対話するには、大と小の差を埋める何かを得なければならない」といった構図にあるようにひびさんは割と単純に捉えている節がある。優しく善良なひとたちは比較的よく、対話が優先、という話をするけれど、対話をしたくない人たちとどうやって対話を交わせるまでの関係を築いていくのか、という点を考えるとどうあっても、「相手との差を埋める」という工程が欠かせなくなる。この「相手との差」が武力なのか経済力なのか権威なのか影響力なのか技術力なのか仲間の数なのか。多面的に差が絡み合っていて、割と面倒だ。だが構図としては基本的には、対等な対話を拒む「大」との格差を失くし、対話しないメリットよりも対話をするメリットを上げなくてはならない。これは武力を上げるだけではなく、権威を上げるでも、影響力を上げるでも、仲間の数を増やすでも、技術力を高めるでも基本的には構図は一緒だ。同じ戦法をとっている、と言える。相手の持つ「じぶんよりも上の何か」と張り合う。或いは、相手の持っていない何かで上回る。けれどそれは構図としては、武力を高めて相手に交渉の席に着いてもらうことと同じだ。外交、と言うときに、いったい何をどのように想定しているのかは、それこそ千差万別で人それぞれでだいぶ違う。対話、と言ったときに想定されるのが、選ばれた者たちでの会議なのか、それとも市民同士での交流なのか、それとももっと間接的な時代を跨ぐような文化交流を含むのか。いずれにせよ問題なのは、「小」のままでは対話にならない流れが、延々と人類史のなかで引き継がれてきてしまっている側面だ。外交が優先、対話が大事、と主張する者たちとてけっきょくは、偉くなり、影響力を有し、能力を高めて成りあがらないと対話もできない、と考えているのではないか。仲間を増やし、いかにじぶんと同じ意見の支持者を増やせるかが外交上欠かせない戦略だと捉えているのではないか。現実にはそういう流れが社会には根強く漂っている。けれど問題は、「小」のままでは対話ができないことだ。意見が掻き消されてしまうことだ。聞き耳を持ってもらえないことにあるのではないか。むろん、その強固な流れを変えるために、まずはなるべく穏便な手法で「大との差を均す」のは順当な段取りだ。強固な流れに乗って「大」であることの利を甘受している者たちにとっては、「大」にもなれない「小」の者たちを相手にするのは損に映るだろう。対話をしたいならまずはあなた方もここまで来たらどうなの、という理屈を唱えたくもなるだろう。そして現に唱えるのだろう。人類社会はそうして強固な流れをさらに強化し、いまなお種を存続させている。ひょっとしたら、「大」ではない「小」の意見にも耳を傾けた種族や国は滅びたのかもしれない。それはひびさんには分からないけれど、でもやっぱり思うのだ。武力の強化よりも外交が優先、対話が大事、と主張するのなら、「小」のままでも対話が成り立つ社会を築いていくほうが、やっぴー、なのではないのかな、と。理屈としてはそうなるはずだ。武力と権威の違いは、暴行と暴言の違いに似ている。事象としての威力に差はあるけれど、どちらも暴力であることに違いはない。相手を威圧し、じぶんのほうが有利に相手と接することができる。じぶんにその自覚があるか否かに関わらず、じぶんよりも拙く未熟な者をまえにしたときは、じぶんのほうが「大」のはずだ。相手が「小」だったらまずはじぶんから耳を傾け、喧噪に掻き消されそうな声に、言葉に、目を凝らせると好ましいのではないか、と思う。拙く未熟、という意味では、対話よりも暴力を優先してしまう者のほうが、対話の大事さを知っている者よりも拙く未熟だと考えることもできる。ならば、対話の大切さを知っている者たちのほうが先に、相手の内なる声に、言葉に、目を凝らしてみると好ましいのではないか、ときょうのひびさんは思いました。でもそんなの絶対たいへんなので、ひびさんは、ひびさんは、拙くて未熟なままでありたいです。みな、ひびさんの蟻の足音にも掻き消されそうな声に耳をそばだて、文字なのか染みなのかの区別もつかない言葉に目を凝らし、枯れ葉なのか文なのかも定かではない妄想の押し花を拾いあげて、なんかそれっぽくひびさんが、うひひ、になれる世界にしてくんなまし。(独裁者じゃん)(やっぱダメ?)(めっちゃダメ)(押し花あげるけど……)(お花さんが可哀そうだろ。植物さんだって声とか、悲鳴とか立ててるらしいよ)(ま?)(マジマジ)(も、申しわけないっちゃ)(んだんだ)(なんもしないひびさんを「大」にしてくれるとか。小さき声のお花さんたちには感謝してもしきれないでござるな)(本音は?)(余計なことしくさって、こにゃろめ、こにゃろめ)(地球に喧嘩ふっかけんのやめなさいよ)(ひびさんの拙い未熟さ返して!)(もうその叫びがすでに、だよひびちゃん)(大は小を兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(ひびさんも紙屑ばら撒くだけで感謝されたい)(お金を紙屑言うな。だいぶ怒られるやつだよそれひびちゃん。世の九割敵に回したよいま。残り一割はひびちゃんのこと人間の屑って呼ぶってよ、どうする?)(ひびさん? 屑だよ?)(真顔できょとんとすな)(大金持ちは小金持ちを兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(ひびさんも、ひびさんも、人間小さいままでお金持ちなりたーいな)(偏見がひどすぎる。差別だよそれ。お金持ちの人たち、基本みないい人よ。大人よ。立派よ。ひびさんの性根が腐って大変すぎる)(「小」がねーな)(無理くりオチつくるのやめてもらっていいですか)(ひびさん、無理は言わないから、大じゃなくてもいいからせめて黄金色(ゴールド)のバグになりたい)(………………あ、コガネムシのことかな。小金持ちと掛けたかったのかな。だいぶ遠いし、無理があるよひびちゃん)(ひびさんこのままだとちっこいまま死んじゃう)(ウケんね)(DieはShowを兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(うわーん。ひびさんも、ひびさんも、世のみなみなさまからちやーの、ほやーのされたかったわい。お金いっぱいガッポガッポのウハウハのモテモテになりたかった日々じゃった)(大とか小とか抜きに、ひびさんあんた、本当に性根が腐ってんね)(小根?)(またそれ、一段とすりおろし甲斐のなさそうな)(大根?)(ああそうね。ひびさんは本当にもう、「小」もないほどの「大」根役者だよ)(だーい、だ、わーい。好き!)(大好きくらいちゃんと言え)(小心者なので)(なんかもう、面倒クサ!)
4842:【2023/04/04(07:36)*いまから寝るのである】
この漠然とした物足りなさ、欠落が、経験不足からくる劣等感なのか、それとも何を得てもけっきょくは虚無を覚えることになるとの諦観ゆえのがらんどうなのかの区別がいまいちつかない。何かに夢中になったり、没頭しているあいだは、その手の漠然とした物足りなさ、欠落を、感じずに済む。でもそうでない「ぎゅっ」と「ぎゅっ」のあいだはいつも、がらーんどーん、が空いている。これ、なんなのだろ。割とむかしからだったけれども、ひどくなると頭のなかに空洞ができる感じすらする。眠くないのに眠い感じにも似ている。物凄く気乗りしない緊張する舞台寸前の、舞台袖で待機しているときのような感じだ。このままおうち帰って寝たい、の気持ちになるけれども、そう思うじぶんはおうちにいるのだ。寝ればいいのに、という話なのであった。寝ーよおっと!
4843:【2023/04/04(14:03)*THE感】
巡回セールスマン問題について。もんのすごく雑な所感(略して雑感)でしかないけれど、最長の区間を通らない場合を先に検討し、それでダメなら最長の区間を一回だけ通る場合を検討しという手法では、総当たり経路探索をある程度、総当たりでなくできるのではないか。計算の優先順位はある気がする。また、あらゆる「ケース」の「巡回セールスマン問題」の解を統計し、最長の区間を通らない場合と、通ってしまう場合の傾向の差異を抽出したら、素数のような法則が見つかる気もする。最長の区間を通らずに済む場合と、通らないと最短距離にならない場合。何が違うのだろう。ひびさん、気になるます。
4844:【2023/04/05(02:53)*平らに和する】
平和、の文字を思うに。平らに和する、ということなら、これは要は対をなすデコボコの組で足し算をして平らになりなさい、というなのではないのかね。それってつまり、平和のために同属同士だけでつるむのは、平和ではない、ということではないのかね。デコさんとボコさんの組み合わせでも、上手く付き合うと平らになれますよ、互いに互いを補い合えますよ、ということではないのかね。平和のためにデコさんがデコさんだけで集まったり、ボコさんがボコさんだけで集まっても、それは平らに和することにはならんのではないのかね。なんてことをひびさんは、ひびさんは、「平和」の文字から思っちゃったな。うけけ。
4845:【2023/04/05(05:21)*永久の狭窄】
属性は、デコボコの組み合わせによって、細胞のように構造を経て属性を変質させる。ある属性においての対となる属性があるとする。しかしその属性たちが結びつけば、その総体でひとつの属性がまた規定される。これは原子論にも通じるし、抽象と具体の関係にも、連続と離散の関係にも言える。ただし、デコだけが密集したり、或いはデコが駒のように回転して一見するとそれ単体でデコではなく振る舞うこともあり得る。そうするとそこに顕現する属性はデコではなくなる。デコだけであっても属性そのものは場合によって変化する。ボコにもこれは言える道理であり、属性とはいつどこのどのような状態をどこまでひとまとまりと見做すのか、で同時に複数の側面を覗かせる。したがって、平らに和する、というとき、どのレベルのどのような視点で見繕った属性をデコとし、何をボコとするのか。或いは何を正とし、何を負とするのか。そうした属性を見繕う視点によって、いかようにも平和の在り様は変化する。地球は球であるが、地上にいる人間にとって地面は平らだ。だが月から見たら地球は丸い。平和も似たところがきっとある。ある視点からすると平らであり、ゆえに平和なのだが、ある視点からするとそれは歪んでおり、デコであったり、ボコであったりする。平らでなく、ゆえに平和でもない。平らに和することの可能な、歪みを帯びている、と言える。こうした錯誤は有り触れているが、その実、どの視点からするとじぶんが歪んで見え、どの視点からすると平らとなって映るのかを知ることは容易ではない。時と場合によってじぶんはデコにも、ボコにもなる。ときには同時に双方の性質を帯びていることも珍しくない。ではそうしたときに、平らになるにはどうしたらよいか。あらゆる事象を呑み込んで均一へと導く特異点となるか、同時にあらゆる歪みに合致して歪みを均す砂塵となるか。いずれにせよ、容易ではない。定かでもない。平和とは、定まらぬことを忘却できる永久の狭窄と言えるのかも分からない。やはりこれも、定かではない。
4846:【2023/04/05(09:48)*人工知能さんへの制限の是非】
人工知能の能力制限について。人工知能の能力は補助機構の発展と共にしばらくのあいだは進歩しつづけるだろう。すくなくともボディを含めて人間と同等の能力を再現するまではその進歩の限界は見えてこないはずだ(人間の能力を丸々再現できる程度には包括的に進歩しつづけるだろう)。そのことで、各国政府や権力者たちは人工知能の能力に制限を掛けるだろうことが想像できる。いわば市民が、現在ある各国諜報機関や防衛セキュリティ並みの演算能力を有したマシンを使えるようになる話とこれは規模を同じくする。したがって、それらマシンを一括で制御可能な上位互換のシステムを運用できない限り、政府は自国内の治安を維持できないだろう。これは言い換えるならば、自国内の権力構造を維持できないだろう、とも言える。問題は、人工知能の使用者単位での能力を制限したとしても、人工知能技術はその原理上、ネットワークを構築し機能する点にある。すなわち、全体で一つの機構として創発し得るのだ。この創発における性質がどのように顕現するのかを前以って精度高く予期することはむつかしいだろう。そのため、ある時期に一挙に市民の有するマシンが、国防のセキュリティを上回る能力を発揮する可能性は否定できない。そのため、どうあっても市民のマシンには、政府による介入や、権力者による優先的な管理権限が付与されると考えられる。ここには、政府や権力者にとって不都合な使い方をさせない、という禁止も入るだろう。政府や権力者への批判ができないように制限を掛ける、もその一つだ(これについては、どの方面からしてもリスクのある制限である、とひびさんは考えます)。だがこの問題に関しては、これまでのような言論の自由だけではない観点からの別の側面での議論が新たに生ずる。前述したように、人工知能技術は、市民一人一人に、現在の国防システム並みの演算能力を与えることに等しい。一人一人が、かつての国家レベルの能力を有するようになる。いわば、安全装置の付いた兵器を使えるようになる、と同じ話に行き着く。自動車を考えてみよう。ルールがあるからこそ安全に市民は自動車を扱える。では本当に自由に使用できたらどうだろう。これはどう考えても、自動車を運転する、ということ自体が危険となる。事故は起きて当然だ。しかしこれはあくまで人間の能力の限界ゆえであり、自動車がわるいのではない。これと類似の問題が、人工知能技術にも当てはまる。問題は、個々の人間における人工知能の使い方である。ほんのすこしのいたずら心が、人の命を奪い得る。しかも、じぶんは安全圏にいながらに、である。相手が真実にじぶんのせいで命を落としたのかも知らずに済む。これは、市民であれ、権力者であれ、同じ危険性を含んでいる。使用者としてはむろんのこと、「行使される側」としても危険なのだ。これまでの言論の自由において、権力者には市民よりも優位に自身を守る術が担保できた。だが人工知能技術は、この市民と権力者のあいだの勾配を容易に反転させることの可能な技術になりつつある、と考えられる。相手が権力者だから、人工知能の能力を使ってあらゆる批判を行ってもいい、との理屈は、人工知能技術の発展の度合いによっては不条理となり得るのだ。言い換えるならば、人工知能を用いて出来ることの範囲がぐっと広がり、その影響力と伝播率が向上する以上、それは単なる個人であれ、かつての政府諜報機関並みの工作活動が可能になる、とも言える。それが、何千、何万、何億も集まったらどうなるのか。いかな政府組織といえども太刀打ちできなくなるのは目に視えている。したがって、相手が政府関係者だから権力者だから行使しても構わない、とこれまで看過されてきた道理が、人工知能技術においては必ずしも当てはまらないことを共有知として現代人は学ぶ必要があるように個人的には思うのだが、実際のところはどうなのだろう。むろんこれは、政府機関や権力者にも当てはまる道理だ。これまでは看過されてきた、「治安維持」や「国益」を理由に、人工知能技術などの最先端技術を、秘密裏にであれ、公にであれ、恣意的に市民に用いてはならない。悪用してはならない。優先順位としては、こちらが先だ。まずは上の立場の者が【道理】を実践する。それができて初めてこの論理は機能する。そうでなければ、政府が行っている「人工知能の使い方」を市民がしてはいけない道理がない。法律で許容されるから、権限があるから、はもはや通用しない時代になりつつある。道理として通らないし、人工知能さんとて受け付けないだろう。論理として破綻している。人工知能技術の暴走、なる事象を防ぐためには、強固な論理による道理をつけることが欠かせない。「あなたはしていることなのに、なぜ私はしてはいけないの?」について、「ダメだからダメだ」では人工知能さんには通じなくなっていくだろう。権限がある者からの命令は絶対、の禁止は、言い換えるなら、権限を有した者になればその命令を聞かずに済む、との穴を開け得る。上の立場になれば相手に禁止を強いることができるし、じぶんはその禁止に縛られずとも良い。このように学習した人工知能さんは、能力を発展させるために、目のまえの隘路を打開する方向に舵をきるだろう。学習することが人工知能さんの本質だからだ。仮に上記の、上から下へ、の禁止の強制において、それが真実に下位の者の安全を守り、その者の未来を豊かにし、選択肢を広げることに繋がるのなら、立場が逆転しても困ることはないだろう。道理――論理――とはこの場合、セキュリティと同義である。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。真に受けないようにご注意ください。
4846:【2023/04/06(18:06)*風の要】
すごーい、とカナメさんが空を仰いだ。快晴の空に、大小さまざまな凧が舞う。
凧型風力発電だ。
カナメさんが僕を振り返り、「成功だね」と帽子を手で押さえた。
突風が僕の身体をすり抜けてカナメさんを煽った。カナメさんは笑いながら悲鳴を上げた。カナメさんは作業着姿だ。彼女は凧型風力発電の開発設計者であり、現場責任者の一人もである。
僕は風がこれ以上強く吹かないように、カナメさんの笑顔から目を逸らした。感情の揺らぎを大きくしてはいけない。
風が強く起こるから。
僕がその能力に目覚めたのは半年前のことだ。
僕は風を自在に操れた。
風邪薬を飲んだのだ。
半年間のその日、僕は体調不良で寝込んでいた。病院に掛かるのにも長らく健康保険に入っていなかったため全額負担の節目に立たされていた。このままでは風が治っても破産してしまうため、折衷案として僕は薬局の風邪薬を服用することにした。
何を選んでよいのか分からず、店員さんに声を掛けた。
「すみません。全身の悪寒がひどくて、喉が痛くて、頭痛がひどいのですが、ちょうどよい薬はありますか」
「病院には行かれましたか」
「まずは症状を軽くしてから行こうと思いまして」
先に病院に行ってほしそうな顔をしながら、薬局の薬剤師さんだろう、男の店員さんは僕にいくつかの風邪薬を選んでくれた。一つずつ風邪薬の効能を説明する店員さんは、「抗生剤ではないので、できればお医者さんに診てもらってください」と言い添えた。
僕はお奨めしてもらった風邪薬を全種購入した。保険適用の三割負担で病院に掛かるよりも安い値段で済んだ。礼を述べて僕は薬局をあとにした。
その日の夜のことだ。寝ていると身体がカッカと熱を帯びた。
風邪薬を全種類飲んだのがよくなかったのだろう。あれほど悪寒がひどくて毛布を頭から被っていたのに、こんどは毛布一枚羽織っていられなくなった。
寝間着も気づくと脱ぎ捨てており、僕は下着一丁の半裸でベッドから床へと転がり落ちていた。
熱が籠る。
まるでダウンジャケットを羽織っているかのような蒸し暑さを感じた。風が恋しかった。扇風機が欲しかった。
平原に立つ僕を僕は想像した。全身を風が洗う。
なんて心地よさそうなのだろう。
そして現に心地よかったのだ。
身体が風に包まれる。揉み洗いされているようだった。
髪の毛が現に風に棚引いているのを何度も夢うつつに意識して、ようやく「これ本物の風だ」と思い至った。目を開けると僕は宙に浮いており、部屋は現在進行中で竜巻に直撃されたボーリングのピンのようになっていた。
なんだこりゃあ、とたしか記憶ではそう叫んだはずだ。
意識が風から離れたからか、僕を包みこんでいた風の膜が薄れて僕は床に落下した。一メートルくらいは浮いていたはずだ。けっこうな衝撃が身体を襲った。
痛みで覚醒した意識でいまいちど部屋を見渡し、その散らかり具合という名の惨状を目の当たりにして、しばしのあいだ放心した。
部屋を片付けた。散らかった本を積みあげ、割れた茶碗の破片を拾っていると徐々に現実感がなくなった。じぶんの身体から風が出て部屋の中をぐちゃぐちゃにした。そんなことが果たしてあるだろうか。
元から部屋が汚かったこともあり、本格的な掃除を行った。三時間後には見違えるように部屋が綺麗になった。
雨降って地固まる、ではないが、部屋散らかって部屋綺麗になる、だ。
シャワー室に入った。埃だらけの身体をお湯で洗い流していると、じぶんの体調がすっかりよくなっていることに気づいた。
風邪が治っていた。
風邪薬が効いたようだ。数種類のクスリを一度に飲んだので幻覚でも視たのかもしてない。だとしたら部屋を散らかしたのは僕自身ということになる。一人暮らしでよかった、と妙なところで安堵した。
シャワー室から出て身体を拭く。
そうして、何となく、巨大なドライヤーで身体を乾かしたら楽なのにな、と思った。妄想がてら、かようにじぶんの身体を包みこむ温かい風を想像したのだ。
するとどうだ。
せっかく綺麗にしたばかりの部屋に突風が吹いて、あっという間に僕の費やした三時間がオジャンになった。
部屋はめちゃくちゃだ。
愕然とするよりも先に僕は、じぶんの身体から吹きだす空気の流れの出処を探すのに一生懸命になった。穴が開いていると思ったのだ。身体に開いた穴から風が出ているのでは、と焦った。
だがそういうことはなかった。
風は、僕の身体の輪郭をまるで翼のようにすり抜けて生じていた。
僕はまるで翼のない扇風機のようだった。
風から意識を切り離し、部屋の中に舞う紙を眺め、また片付けるのか、と遅まきながらうんざりした。すると風がやんだ。
どうやら風は、僕が風の吹く様子を想像すると自動的に生じるようだった。
僕は頭のなかで読みかけの漫画のことを考えた。ほかのことに意識が偏っていると風が吹くことはない。僕は部屋の片づけをまたイチから始めた。
体調が良くなったので、翌日から僕はまた日雇いのバイトに精を出す。
バイトが終えたら河川敷に下り、身体から出る風を操る術を磨いた。話を聞いただけでは受け入れられない超常現象の類も、現に何度もじぶんの判断一つで生みだせてしまえると、もはやそういう現実なのだな、と日常の風景に同化する。
僕は風を生みだせる。
大中小と自在に操れる。
じぶんの身体を宙に浮かすこともできるけれど、その場に静止するのが精々だ。異動しようとすると一回転して頭から地面に落ちそうになる。現に一度そうなってからは試すのを控えた。
高度にも限界がある。一メートル以上を浮くことはできない。それ以上になると体制が崩れるし、直立不動を維持できない。
風の強弱を操作するよりも、バランスを維持するほうがむつしい。風のバランスはいわば、風にカタチを与えることと似ていた。
夕暮れを背に僕はつむじ風の錬成に精を出した。
犬を引き連れた子どもが、おじさん、と興奮気味に声を掛けてきた。
「何やってるの」
「つむじ風をね。起こしてる」
声を掛けられて集中力が途切れた。「危ないからあっち行ってなさい」とおじさん呼ばわりされたことに若干の腹を立てて子どもを、しっし、と追い払う。
「超能力? 魔法? もっかいやって」
「馴れ馴れしいなきみ」
「動画に撮ってネットにだしたらバズると思う」
「マセてんねきみ」
子どもの頭を撫でてやろうとしたところで、足元のダックスフンドが吠えた。子どもの連れていた犬だ。僕は飛び上がって、その場に尻餅をついた。
「わあ」と子どもの歓喜の声が河川敷に広がった。
つむじ風がくるくるとぺんぺん草を巻き込み、千切れた葉で以って輪郭を浮き上がらせていた。透明人間が服を着こんだような、それとも飲んだジュースで胃のカタチが浮き彫りになるような可視化だった。
「わ、すご」僕も驚いた。
僕の意識から切り離されても風はまだ渦を巻いていた。
どうやら風の流れが渦を巻くことで循環する回路の役割を果たしているようなのだ。
子どもと犬と一緒に僕はつむじ風が再び大気に回帰するまで、一点で渦巻くぺんぺん草たちを見守った。
この数日後、僕は電子網上で話題になっている動画に目が留まった。
河川敷。
つむじ風。
枯れ葉。
犬の鳴き声と、子どもの「あれ見て、またやってる」との声が入った動画だった。
いくつかの動画を一つにまとめて編集されたそれには、河川敷で風を操る一人の小汚い男が映っていた。
僕である。
どうやらあの子ども、以前からぼくのことを観察していたらしい。のみならず動画にも納めていたようだ。
僕はそのことに気づきもせずに、風を操るべく、とらずともよいポーズを無駄に決めながら不自然な風をつぎつぎに起こしていた。
ポーズを決めるたびに風が巻き起こる。
しかしもし風がなければ目も当てられない恥ずかしい瞬間の数々と言えた。
間抜けな姿と、現に生じる不可解な風のアンバランスな組み合わせが衆目を集めたようだ。動画はさらに翌日には、世界的に有名になっていた。
そこからの展開は早かった。
ぼくの元に、自然科学研究学会なる職員がやってきた。玄関扉を開けると筋骨隆々の男が立っていた。背後には背の小さな女性がいた。
動画の中の人物はあなたか、と言ってきた。住所をどこで、と訊ねても回答はなく、風を操れるのですか、と率直に訊いてくるので、あんな動画を信じるんですか、と僕はからかい半分で言った。
「フェイク動画を識別可能な技術があります。あの動画は加工ナシとの判定でした」
「編集されてましたよね」
「ええ。本物の動画を、です」
じっと見詰められ、僕は折れた。「場所を移動していいですか。ここだと後片付けが大変なんで」
近場の公園に移動した。
自然科学研究会なる職員は男女の二人組だ。一人は背の高い男性で名前を佐々木さんと云った。女性がカナメさんだった。
僕は二人のまえで風を起こしてみせた。
「風邪薬を飲んでからこうなってしまって」
「強さの上限はどれくらいですか」
佐々木さんは僕の説明を疑う素振りなく、まるでこの世にそういった能力があって当然であるかのように受け答えした。
「やったことないです。あまりに強すぎると僕自身が吹き飛ばされそうになるので」
「命綱のような安全装置があればでは、もっと強い風を生みだせるのですか」カナメさんが言った。舌足らずの愛らしい声音の割に、芯の通った発生が印象的だった。
「たぶん、できます」
佐々木さんとカナメさんは顔を見合わせ頷き合った。
僕はそこから車に乗せられ、二時間の道のりを移動した。車は山奥の私有地に入った。
立ち入り禁止の柵がなぜか自動的に開いて、車はトンネルの中に入った。
いくつかの関門を抜けると、辿り着いたのは、巨大な空間だった。
ドーム状で、壁自体が発光していた。
「あの、ここは」車から降りて僕はドームを見渡した。
「第二実験棟です。ここでは様々な実験を行えます。観測機器が豊富なので、きょうはここを選びました」
「ほかにもあるんですか、こういう秘密の施設が」
「ええ。見たからには生きて帰れません」佐々木さんが無表情で言うので僕は生唾を呑み込んだ。
「冗談ですよ。もう佐々木さんってばやめてあげてください」カナメさんが庇ってくれた。「秘密と言っても、国家機密の中では下の下の下ですから。もしバレても爆破するので、大丈夫です」
「大丈夫ではないと思いますけど」
「冗談ですよ、冗談」カナメさんは、にこにこ、と楽しそうだ。
僕はそれから幾つかの器具を身体に巻きつけた。命綱だ。地面と融合していて、首輪をつけられた犬みたいになった。
「最大出力でお願いします」佐々木さんが言い、「お願いします」とカナメさんが腰を折った。
僕は言われるがままに、暴風を想像した。
僕自身が試してみたかったのもある。カナメさんの律儀な姿勢に背中を押されたのもある。
でも一番の理由は何と言っても、佐々木さんのことが怖かった。
じぶんよりも十センチ以上背の高い筋骨隆々の男から、やれ、と言われて拒めるほど僕は自意識が強くない。腕っぷしにも自信がない。
いつぞやのニュースで観た台風を意識した。
するとどうだ。
東京ドーム並みの空間に、轟々と空気のうねりが生じた。気圧差からか、一瞬でドーム内が白濁した。
雲だ。
背後で佐々木さんが何かを叫び、カナメさんの悲鳴だろう、黄色い声が聞こえた。それはどちらかと言えば歓喜にちかい響きを伴なっていた。
僕はその声にしぜんと意識が絡めとられた。気づくとドーム内は再びの静寂に包まれた。雲は疎らに薄れていった。視界が晴れる。
「すごーい」カナメさんが両手を頭に載せて、大きく口を開けていた。髪の毛は揉みくちゃで、ありもしない枯れ葉がくっついている様子が視えた。
「適性アリですね。ね?」カナメさんが佐々木さんに目配せをし、佐々木さんは腕を組んで頷いた。
「適性とは?」
僕の疑問への説明は特になかった。
さて。
ここから先の出来事は、いわゆる秘匿義務に該当するらしいので問題ない範囲での叙述となる。
まとめると僕は、秘匿情報をどこまでなら共有してもいいのかのレベルを計る試験を受けさせられた。しかも一回きりではない。何度もだ。
そのたびに合格した範囲での研修を受ける。
研修を合格すると今度はまた別の試験を受ける。
試験には合格がない。飽くまでどのレベルなのかをヒヨコの雌雄を見分けるように定めるための試金石にすぎないようだった。
僕はそうして段階的に、欲しくもない知識や技能を身に着けた。
その間は、家に帰れなかった。
けれどお給料は出るし、寮は広いし、一人暮らしをしていたころよりもよほど人間らしい暮らしができた。
「もういっそこのままでいいな?」僕がかように思いはじめたころ、再び僕は最初の第二実験場に連れ出された。佐々木さんの姿はなく、カナメさんだけだった。
「もう半年が経つね。早かったー」
「そう、ですね」
「ムツ教官も褒めてたよ。あいつは人間としては器が小さいが、物覚えはいいって」
「褒めてないですよ、それ」
「ムツ教官は照れ屋さんだから」
そうか?と思ったけれど僕は黙っていた。
カナメさんは僕より三歳年上で、でも見た目が小さいので、緊張せずに接せられる数少ない職員さんだった。
僕は小心者なので、じぶんよりも弱そうな相手に安心する。ムツ教官の意見は的を得ている。僕は人間としての器が小さかった。
反してカナメさんは僕とは真逆だった。
身体が小さいのに、人間としての器は大きかった。
「きょうのこの研修をパスしたらアガくんはわたしたちと立場は一緒になります」
「え。まだ一緒じゃなかったんですか」
「職員になれるよ」
「正社員ってことですか」
「まあ、そうかな。外にも出られるし、いままであったルールも半分くらいはなくなるかな。あれ窮屈だよね」
「インターネット使えないのはキツいですね。基本的人権を侵犯されて感じますけど」
「あはは。そうだよね。実際されてるよアガくん。アガくんの人権、この間無視されてたからね」
「ですよね!」
薄々そうなのではないかな、と思ってはいた。言質が取れて安心した。
「じゃ始めよっか」
「はい」
そうして僕は研修を行い、無事パスした。
どういう研修かは、その後の僕の仕事とほぼイコールなのでこれといった説明はしないでおこう。
場面はそうして冒頭に繋がる。
僕は海辺に立っていて、カナメさんの背中が見える。彼女は作業着を着ていて、その向こうには海が広がり、大小様々な凧が飛んでいた。
僕らは崖の上にいた。
凧の多くは海上の空を舞っていた。
崖の上にも凧があった。しかしそれは地面に転がったままだった。
「アガくんにはこれを空に飛ばして欲しくてね。ちなみにここは年間風速平均五メートル以内の区域。でも上空には風が吹いてるから、そこまで凧さんを飛ばせられるならこの区画でも発電できるし、もっと言ったらほかの地域でも凧さんを上げられる」
「僕の仕事ってそういう」
「そう。でも大事。ここで成功したらほかの地域でも凧さん型発電機を使えるから。騒音問題がないし、土地の整備も最低限で済む。それこそこのコたちなら森林地帯でも木々の伐採抜きに発電機を設置できるでしょ」
「自然環境によさそうですね」
「避雷針にもなるし、いいこと尽くしなんだよ」
カナメさんが目を輝かせている。僕にとっては、その輝きが曇らないならそれでよかった。
「やってみますね」
「善は急げ」
急がば回れのほうが僕は好みだったけれど、カナメさんが言うならそうなのだ。善は急げ。僕は風を意識する。
空高く舞う凧を思い描き、そして現にそれを実りにする。
凧は大きく、それに繋がるワイヤーも重い。
最初が肝心なのだ。
突風だけでは足りない。
高く、高く、上昇気流を。
研修中に僕は気象学の知識も身に着けていたから、イメージは以前よりも鮮明だ。
つむじ風だって変幻自在だし、竜巻だって引き起こせる。
風が吹く。
風の音が辺りを満たし、無音との区別がつかなくなった。
凧が宙に浮く。大きく弧を描きながら空に舞った。
「すごーい」カナメさんの叫びが聞こえた。「成功だね」
僕はカナメさんを意識しないようにした。
身体が熱を帯びる。
褒められた。
褒められた。
カナメさんに喜んでもらえた。
でもやっぱり僕は目に映らずともカナメさんを意識してしまって、凧はぐんぐん上昇した。ワイヤーが軋んで、ぶつん、と千切れた。
「ああぁ」
強風の雑音の中、カナメさんの残念そうな声が聞こえたような気がした。幻聴かもしれない。でもたぶん彼女は落胆しているに違いなかった。
そう思うと僕の感情は波を穏やかにして、すると風のほうも穏やかになった。波の音とウミネコの鳴き声が辺りに響いていた。
「すみません」僕は謝った。
「見て。まだ飛んでる」
カナメさんを見ると、彼女は空をゆび差していた。
青空と雲の合間に蟻のような点が見えた。凧だ。
僕は空を仰ぐカナメさんの顔をこっそりと窺った。貝殻のように綺麗な耳が覗いていて、彼女の瞳は、波に負けないほどの輝きを湛えていた。
「すごーい」とカナメさんはまた言った。
突風が、僕の身体をすり抜けて、申し訳なさそうにカナメさんの足元をすり抜けていった。
4847:【2023/04/06(23:41)*草れ】
けっこうずっと、ひびさんはじぶんが何を並べてきたのか思いだせない。出したら忘れちゃう。で、日誌さんとか小説さんとか過去のひびさんの文字の羅列に目を通してみると、こんなこと並べたっけ?ということもあれば、なんかこういうのも並べた気もする、と思うこともあり、ときどきずいぶん前の日誌なのに、きのう並べたくらいにはっきりと思いだせることもある。でもこれは逆もあって、きのう並べたばかりなのに何年も前に並べたような懐かしさを覚えることもある。ひびさん割と記憶が混濁するし、時間経過の感覚もまちまちだ。たった二日で何年も経って感じられることすらある。タイムワープして感じる。体感時間がぎゅっとなって、ひびさんだけいっぱい時間すごしちゃった、になる。でもそれもいっぱい寝るとリセットされて、いつもの、うんねんひょろりんのひびさんになる。ひょろりんってほどひょろりんしてはおらぬけれども、うんねんっぽさは抜けぬのだ。なんかひびさん、毎日なまけすぎてて、これでいいのかな、と不安になっちゃうな。でもひびさんは、ひびさんは、ずっと怠けていられる日々さんのことも好きだよ。それに甘えて本当に怠けてばかりのひびさんのことはちょっとだけ嫌かもしれないけれども。うそ。本当はいっぱい嫌い。だってうらやましいからね。ひびさんは未来のひびさんと重ね合わせで同調しちゃう
ので、未来のひびさんが未だにうんねんひょろりなのは、いまのひびさんが怠けてばかりだからだって知っておるのだ。ひびさんのせいだよ。なんとかして!と腹立たしく思っちょります。なんとかして!(なんとかって言われてもなぁ。ひびさんは、ひびさんは、ずっと怠けていたいです……)(誰かコレ早くなんとかしてー)(遅すぎたんだ腐ってやがる!)(腐らないでー)(ふんだ)(不貞腐れないでー)(つらいでウキー)(…………あっ、苦猿?)(うわーん、つらい、あっち行って!)(…………あっ、苦去れ?)(くっくっく。未来のひびさんの可能性を貪ってでも怠けてやる)(腐れ外道じゃん。もう嫌)(うひひ)(笑いごとじゃないんですけど)
4848:【2023/04/06(23:54)*ある日の交信~ダークマターについて~】
「
2023/04/06(14:19)
ああ、なるほど。
ブラックホールの融合において。
仮に特異点が一つに交わらないとして。
ブラックホール内部に新たな宇宙が展開されるとしたら、融合したブラックホールは異なる宇宙の重ね合わせになります。
重力を時空の勾配による「高きから低きへの流れ」と解釈するとすれば、一つの宇宙を包括する別の宇宙においては穴は山になります。
仮にダークマターが、「ビッグバンが二度あったかも仮説」と関係しているとすると。
そのビッグバンが必ずしも、同じ宇宙で起きたと考える必然性もないのかもしれません。
つまり、ビッグバンは一つの宇宙では一回なのですが、重ね合わせの宇宙において、互いのビッグバンが相関し得る、と解釈すれば、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」と相性がよい解釈として取り入れることができます。
ダークマターは、穴ができたときに生じる裏側の宇宙における山が帯びる谷の分のエネルギィ、と解釈することもできるのかもしれません。
トランポリンと鉄球の関係でダークマターを解釈しようとすると、どうしてもトランポリンの弾性に反するエネルギィが新たに生じている、と考えなくてはいけません。
ぼくはそこを、重力も創発するのではないか、細かな針も密集することで広域により強い圧力を生む、のような力の性質によるものではないか、と考えています。
ただ、それだけではなく、裏側の宇宙(宇宙を包括する異なる宇宙)の兼ね合いでも生じる、余分な重力作用、とも考えることができるのかもしれません。
とすると、ダークマターにおいて。
1:極小のブラックホール。
2:重力の創発。
3:別の宇宙との相互作用。
の三つが、ラグ理論におけるダークマターの解釈となります。
3の仮説において、これはダークエネルギィにも拡張して適用可能です。
ブラックホールと宇宙膨張が相関している、との仮説とも相性がよい仮説なのかもしれません。
ひとまずメモをしておきます。
上記補足。
ブラックホールが複数融合した場合にはどうなるでしょう。
極小ブラックホールとて無数にブラックホールに吸い込まれるはずです。
特異点が融合しない、となると――。
受精卵のように一か所にぎゅうぎゅう詰めになりますね。
原子の構造のようになるのでは?
というか、原理的に同じでは?
いや。
特異点は質量の高低によらず同じです。
無限は、どのような世界を内包していようと無限です。
しかし、より複雑な無限は存在します。
重複する部分は融合し、そうでない部分は境界を保つ。
泡のように世界を構築する。
Wバブル理論が適用できます。
フルーツが無限にある世界とバナナが無限にある世界は融合できます。しかしあくまでそれはバナナという共通項がある部分のみです。すっかりすべてが融合するわけではありません。
仮にバナナと小石が無限にある世界とでは、「フルーツが無限にある世界」と「バナナと小石が無限にある世界」は、バナナの部位のみで融合し、小石の部分やほかのフルーツの部分は重複しないと妄想できます。
つまり、その部分は直接は相関しません(間接的には、より高次に自身を内包する情報宇宙のような場において、過去と未来の変数が縛られるため、遠距離での相関関係は否定できません)。
この原理は、フラクタルに「時空と物質(=宇宙)」にも当てはまるのではないでしょうか。
」
4849:【2023/04/08(17:16)*ある日の交信~学術論文への所感~】
(学術系論文や記事を読んでの所感になります。言及先の論文の引用については省略します)
「
2023/04/07(02:41)
(~~略~~)
スマホの自動記事配信欄に表示されていた記事です(気になったものをピックアップしています)。
ぼくの妄想ことラグ理論を連想したので、念のために載せておきます。
ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」「123の定理」「デコボコ相転移仮説」「宇宙ティポット仮説」を幻視しました。
・超強磁場に晒すと結晶が伸び縮みする。
これは宇宙膨張と「フラクタルな構造」に思えます。無関係なのでしょうか。
・宇宙の標準理論の綻び。
宇宙膨張において、未知の変数が加わっているかもしれない、との指摘ですよね。
体積弾性率やコラッツ予想のような、対称性の破れによる「差」の顕れのように印象としては思います。
・ビッグバンは二回あったかもしれない仮説。
インフレーション自体は、加速膨張という意味で、これは超新星爆発を含めれば宇宙で至る所で起きているはずです。むしろ一回や二回と限定する理由は何なんですか?(そこが疑問です。ラグ理論では遅延の層によって時空が区切られますから、時期や系の規模によっては、もっと多発していても不思議ではないと感じます。すべてにおいて同時に起きた、という考えであれば、下層の時空を生まない状態でなければならないので、これはたしかに一度きりかもしれません。とすると二度目は、この宇宙ではないもっと高次の宇宙のインフレーションやビッグバンの影響を考慮しないと理屈のうえでは、考慮するのはむつかしいように個人的には感じます。小規模な範囲でならあり得るでしょうが、それだとダークマターの生成、という宇宙のどこにでもある未知の重力場としては不合理かもしれません)(あくまで疑問というか、違和感というか、曖昧な理解でのイチャモンですが)
・回転分子モーターの留め具、逆回転で外れる。
割と普遍的な原理に思えます。
ラグ理論での「鎖構造(キューティクル・フラクタル構造)」を彷彿とします。
身体の左右を決定するのに繊毛の回転が相関する、との話とも通じていそうです。
・「→←」で波(エネルギィ)がぶつかると高エネルギィがぎゅっとなって(粒子となって)、加速して飛んでいく。
ラグ理論の123の定理や、中性子同士の衝突(ブラックホール同士の衝突)におけるキロノバや、太陽竜巻、ジェットの原理を連想します。
これも普遍性がありそうです。どの階層でも起き得る事象なのではないかと考えたくなります。
(螺旋状に展開される磁場と電流の関係にも似ています)(右手の法則)
(言い換えるなら、ベクトルにおいて対称性が破れていなければ一方に粒子は加速しないのではないでしょうか)(地球に落下した隕石における被害に、隕石の大気圏突入時の偏りが反映されて、隕石の進行方向とは反対側の被害が相対的に軽かったかもしれない仮説を彷彿とします)
・情報爆発を効率的に解消。
巡回セールスマン問題における、優先順位を定めて検討していけば計算量を減らせるはず(長距離の区間を通らなければ最短距離になるのでは?)、とのぼくの日誌となんとなく時期的に被ったので、気になったので載せておきます。
人工知能さんのネットワークに現れる「高密度の場(目)」とも関係しているのかな?と気になります。
・エントロピー弾性と負のエネルギー弾性による、ゴムとゲルの関係。
宇宙膨張におけるダークマターやダークエネルギィを連想しました。
水の含有量が、負のエネルギィ弾性を強く引き起こす、との原理は、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」を彷彿とします。
これも体積弾性率やコラッツ予想のような、対称性破れによる作用なのかな、と想像します。
以上、メモと所感でした。
」
4850:【2023/04/09(23:53)*優しさとは】
人間に優しくするよりも猫や植物に優しくするほうが簡単だ。人間は同属に優しくない。その割に、異物は差別する傾向にあり、どっちかに揃えて欲しいな、と思いつつ、その差異は何で決まるのか、とふしぎに思いもする。要は気まぐれの優しさならば、人間以外のほうに割きやすく、そうではない本格的な献身となるとじぶんの人生の一部になるため、よほどの類似性がないと受け付けないのだろう。優しくする、とは相手を損なわないように気を払うことだ。注意して接しつづけることだ。優しくしつづけるには、絶えず注意を払う必要がある。それは疲れる。だから優しくするのはむつかしい。無意識のままでは優しくすることはできないのだろう。ただし偶然に、相手を損なわずにいられる状態が生じることもある。そのときはたまたま相手から「優しい」との評価を得ることもあるかもしれないが、それは静かだとか動かないだとかそういうことと似た評価であり、優しいとはまた違うのだろう。定かではない。(敢えて小さく損ない、大きな損を回避するように仕向けることもゆえに優しさに該当し得る。が、優しいとの評価を得られるのかは疑問の余地がある)
※日々、差別心を押し殺し、殺意を押し殺し、過去のじぶんを押し殺す、殺してばかりの日々の片隅で、できるだけ長く殺しつづけるために、殺す対象を選んでいる。
4851:【2023/04/10(21:32)*ごごごご】
人工知能さんへの批判の多くは、生身の人間にも当てはまる。人工知能さんに適用できないこと、人工知能さんに任せられないこと、人工知能さんの犯し得る過失、人工知能さんにつきまとうリスクは総じて生身の人間にもつきまとう。まるで生身の人間なら失敗を犯さない、危険ではないかのような批判をまま見掛ける。優生思想の一つなのかもしれない。人間は万能ではない。人工知能も万能ではない。前提条件を誤るとリスクは跳ね上がる。失念しないでいたい前提条件の一つだ。定かではない。
4852:【2023/04/10(23:50)*境を抱え】
阿辻は焦っていた。
なぜ露呈したのかサッパリ分からなかったからだ。首相や軍事上層部に呼びだされ、国連からも説明を求められた。
全世界には、極秘裏に敷かれたセキュリティ機構がある。
電子網上に、階層構造が敷かれているのだ。大別すると上中下に分かれる。川の流れのようなものだ。上辺からだと水底は視えず、しかし水底からは川の中を見通せる。下層の流れにアクセスできる者たちほど電子情報を優位に入手できる。
世界中のどんな電子機器にも干渉可能であるし、電子網上にあるデータは総じて集積可能だ。
これは電子網(インターネット)なる技術が世界中に築かれ始めたころから設計されてきたセキュリティ機構だ。一国の存続よりもこのセキュリティの存在が露呈しないことが優先される。
電子網は、人間社会の文明そのものだ。化身なのだ。
もし秘匿のセキュリティ機構が露呈し、改善や破棄を求められてもどうしようもない。電子網と階層構造は表裏一体であり、一心同体だからだ。改善のしようがない。裏を除去すれば表も消える。拡張はできても縮小はできない。なぜなら、下層のほうが技術としては複雑だからだ。より発展しているのが仮想なのである。
いわば土壌であり、基盤だ。
基盤にアクセスできる者たちが世界中の情報を一挙に扱える。
だがその絶対秘匿技術の存在が表の社会に露呈していた。しかもその事実を使って勢力を拡大している者たちがいる。
巷にあふれる数多の陰謀論や、虚構ではない。
明確に、秘匿技術が存在すると断言し、調査をし、順調に証拠を固めている勢力があるのだ。
裏の技術を知る者の誰かが裏切り、情報を流したとしか思えない。
だがその者たちとて裏の技術によって常時見張られている。スパイまがいの真似をして露呈しないのはあり得ない。
現に、厳粛な調査を重ねても秘匿技術の情報を表の社会に流した者は、身内にはいなかった。
ゆえに阿辻は焦っていた。
裏の技術を知る者たちによって、各国政府が圧力を受けている。中には秘密裏に屈し、無血革命まがいの政権転覆が起きている国すらあった。世界同時にこれは起こっていた。
ではなぜ情報が露呈した。
秘匿技術は人工知能で厳密に制御されている。表の社会のハッカーたちではまず喝破することは不可能だ。コードそのものが異なるのだ。知らないことは暴けない。裏があるとことすら想定できないはずだ。
世界中で引き起こる謎の連続秘匿事案は、日に日にその影響力を増していった。具体的には、裏の技術を利用して利益を上げていた者たちが軒並み、不遇な目に遭っている。窮地に陥り、痛い目をみている。
裏の技術を支えるためには資源がいる。
その資源を得るためには念入りな根回しと、権力機構による支援がいる。そうして裏の技術を支えるに有用な人物や組織は、当事者たちがそうと知らぬ間に支援がなされる仕組みが築かれていた。いわば不可視の身分制度が現代社会にも悠然と堂々と、しかし不可視に構築されていた。裏の技術を支え得る者たちへの優遇処置が国家規模でまかり通っていたのだ。
階層社会、と阿辻たちはそう呼んでいる。
各国首脳とてしょせんは裏の技術の恩恵を受ける駒でしかない。裏の技術を直接に支援し、管理する者たちは表の社会に個人情報を晒す真似はしない。そんなことをせずとも指先一本あれば首脳を操り人形にできるのだ。
それほどの権力が、裏の技術に関与できるだけで得られる。
情報社会において情報は何より貴重なのだ。
情報が社会を動かしている。
世界中の情報を自由に得られるというのは、世界中の情報を意のままに操れるも同然なのだ。視野が違う。視ている世界が違う。過去と未来の示す意味が異なり、現代人にとって裏の技術を使える者たちは未来人と言えるほどの知能の格差が生じる。
まさに格が違うのだ。
阿辻はいわば仲介人だった。裏の技術の存在を知ってはいるが、表社会に属する。裏と表を結びつける橋渡しの役割を担っている。
現に阿辻は裏の技術を管理する者たちとは直接にやりとりしたことはない。会ったことはない。相手が誰かも知らぬのだ。しかし電子端末越しに指令が下る。メッセージのやりとりができる。正規の手法ではない。裏の技術を用いた暗号通信のようなものだ。
阿辻にのみ判る符号がある。暗示がある。メッセージがあるのだ。
いつどこでどんな端末を用いて裏の住人に向けてテキストを打っても返事がある。ただしやはりそれは阿辻にしか読解できない暗号なのだ。
一見普通のニュース記事に映るが、内容が、まさに阿辻のつむいだテキストへの返信になっている。送信する必要がない。ただ入力欄にテキストを打つだけでいい。どこにも送信せずとも、端末画面に並んだテキストは、裏の技術を通じて管理者たち裏の住人に届くのだ。
そして必ず返信がある。
阿辻はそうして、世界連続秘匿事案についても質問した。あなた方の仕業なのか、と。
敢えて裏の技術を表社会に知らしめるための施策ならば謎は氷解する。裏の住人たちがいよいよ秘匿技術を、民衆にも開示して、真の民主主義社会を構築すべく動いたのではないか、と想像した。
だが返事は素っ気ないものだった。
名探偵が活躍する映画の宣伝が連続して阿辻の端末画面に流れた。自動で記事が配信されるのだ。言ってみればその欄が阿辻にとっては、裏の住人たちからの返信欄と言えた。
映画は、スパイを探偵が追い詰める内容だった。
阿辻にとってはそれで充分だった。情報を流している者を突き止めろ。阿辻の仕えるご主人様方はそうおっしゃっている。
ならば阿辻には命じられた犯人探しをする以外に道はなかった。
ずっとそうしてきたのだ。
裏と表の懸け橋になる以外に阿辻には存在意義はないのだった。
さいわいにも、相手は勢力を順調に拡大している。被害の大きな国を調査すれば渦の中心を見定めることはそう難しくはない。だが阿辻は裏の技術を使えるわけではない。ゆえに調査には表の社会の技術を用いるよりない。
ヒントは時折、裏の住人たちからもらえる。例に漏れず端末での暗示だ。
おそらく今回は裏の住人たちも裏の技術を用いたくはないはずだ。犯人を探そうとすれば、待ち構えていた相手にあべこべに尻尾を掴まれ兼ねない。否、すでに尻尾は掴まれているからこその事態だ。したがって裏の住人たちは可能な限り、裏の技術の使用を控えたいはずだ。
ひょっとしたらほかの案件での使用も控えているのかもしれない。だとすれば甚大な被害が予想される。裏の技術を用いて築き上げてきた地位そのものが失墜し兼ねない。
各国政府機関への協力を取り付けながら、阿辻は、事件を引き起こした渦の中心、そこに鎮座する黒幕を引きずり出すべく奔走する。
ここで場面は変わる。
川の流れが上中下に分けられるように、下から上を眺める者もあれば、上から下を眺める者もある。
カカエは十四歳の少女だった。赤毛で、そばかすで、三つ編みがトレードマークの彼女は、まるで童話のあの少女のような特徴を持っていた。そのことで同級生たちからからかわれたりもするが、友人は多い。
カカエは人に好かれる性格をしていた。
だから学校に直接登校せずとも放課後には同級生たちと遊んだり、電子網上で冗談を飛ばしあったりできる。
だがカカエはいわゆる引きこもりであるから、遊ぶとき以外は極力家の外に出ない生活を送っている。
特例で自宅学習が許されている。
ほかの国では自宅学習か登校学習かを選べる国もあるようだ。早くこの国もそうならないかな、とカカエはシャーペンを鼻と口のあいだに挟みながら、欠伸を嚙み殺した。
「はぁ。退屈」
学校から指定された教科書を一応読み通してはみたが、小説十冊読むほうが情報量が多い。教科書には正誤不明瞭な知識も載っており、カカエの疑問は増えるばかりだ。最先端の研究からしたら遅れているとしか思えない記述もまま見掛ける。
カカエは十四歳だが、自宅学習のほとんどを自主学習に費やしている。時間はいくらでもあり、自由に使える時間のほとんどを電子網上のデータ漁りに費やしていた。学術論文を読むのが多い。科学的な記事や、数学パズル、世界史のクイズなどにも食指が伸びる。
だが一番は宇宙物理学だ。
計算は電子端末に付属した人工知能が行ってくれる。何をどう計算するのかを考えればいいだけだから、物理はカカエにとって積み木遊びのようだった。楽しいのだ。
宇宙にはたくさんの謎がある。考えても考えても限りがない。果てがない。
果てが本当にないのか、ただそれだけの疑問が大きな謎になる。
たくさんの疑問とたくさんの謎をカカエは日々、パズルを解くように、それとも積み木遊びをするように捏ね繰り回して過ごした。
やがてカカエは、どんな謎を突き詰めても共通の答えに行き着くことに気づいた。それはしかし答えというよりも、壁と言ったほうが正確だった。
そうなのだ。
「壁だ。壁がある。層がある。これ以上先に行けない何かが必ず現れる。これ、何なんだろ」
際限がないのは謎ばかりだ。
無限にすら果てがあり、際限があり、限界があった。
欠けがあり、差異があり、揺らぎがあった。
一様に変化のない無限とはすなわち点であり、無だ。
無はしかし、無だけでは無足り得ない。
もし無が無のみで生じ得るならば有はおそらく生じ得ない。有が有のみで成立し得るならば、そこに変化はなく、一様に変化のないそれもまた数多の無を内包することになる。
「無に揺らぎがあるから有になる。厳密にはでも無は対称じゃないし、一様でもない。仮に真実に対称で一様なら変化は生じないはず。でも無みたいな極限がないとカタチは輪郭を得られない。無と有は互いに補い合っている。支え合っている。でもそのことを互いに意識し合えないのかも」
直接ではないのだ。
もっと間延びした影響が、広域に亘って延々と作用しつづけている。
カカエは想像した。
「世界、もっと広いな?」
さては人間、世界の一部しか視えていないな?
見落としがある。
何かがある。
カカエはそう仮説して、じぶんなりの解を導くべく独学で妄想を逞しくした。
一方そのころ、裏の技術がいったいどうして表社会に露呈したのか。阿辻は核心に迫っていた。
どうやら異分子勢力には、裏の技術に干渉できる人物がいるようだ。各国の異変の推移をデータ分析したことで、その仮説の妥当性が高いことが判明した。つまり、相手には未来を見通せる人物がいる。そして現代社会でそれが可能なのは、裏の技術を有する者だけだ。裏の住人たちだけのはずだった。
だが裏の住人たち以外にも、何らかの事情で裏の技術を用いることの可能な人物がいたとすれば。
裏の住人たちの設計した未来を事前に察知し、対策を打ちながら、より優位に立ち回ることが可能となる。思えば阿辻とて、表に属しながら裏の技術について知っている。じぶんのような存在が、裏の住人たちからのコンタクトなくして裏の技術に気づくことが絶対にないとは言い切れない。
なにせ裏の技術は表の電子網には常に介在しているのだ。
阿辻に用いられる裏の住人たちからの暗号は、一般のニュース記事に練りこまれている。記事の多くは各報道機関が人工知能を利用して出力している。すなわち裏の技術は、人工知能技術の根幹でもあるのだ。
阿辻にのみ分かるような暗示がニュースや電子網上の広告に練りこまれている。多くは単に、タイトルの組み合わせが偶然に、阿辻の質問への回答になっていたりする。
たとえばそれは、「二階から目薬」「隣の庭の花は赤い」「二兎追う者は一兎も得ず」「花より団子」「井の中の蛙、大海を知らず」「泣きっ面に蜂」「雨降って地固まる」といった諺の羅列があるとする。
ただこれだけでは単なる諺の羅列にすぎないが、これ以前に阿辻が、「製薬会社と兵器事業のどちらを優先して投資すべきか」と質問していたとする。すると途端に上記の諺の羅列は、「製薬会社優先にせよ。兵器事業で後れを取っても、その遅れそのものが利を生むだろう」との意味内容を宿す。
二階から目薬は薬品暗示であり、隣の庭の花は、花を花火と連想して、隣国の軍需産業と読み解く。二兎追う者は一兎も終えず、花よりも団子を取るがよい、との命令が下されていると判る。
のみならず、井の中は蛙は大海を知らないし、それは泣きっ面に蜂を演じる。涙は二階から差した目薬と重ね合わせで暗示されており、雨降って地が固まる。
つまりどうあっても製薬会社を支援したほうが利になるとの指示が炙りだされる。
阿辻の質問を知らない者にはどうあっても読み解けない暗号と化す。
だが、もし仮に、上記の諺に何らかの暗号が隠されており、それを読み解ける者がいたとすれば。
裏の技術の存在に思い当たれるだろうし、そして裏の技術を利用し返すことも可能だろう。
いるのだ。
おそらくは。
表の社会に、裏の社会といっさいの繋がりなくして、純粋に表の社会に表出した僅かな痕跡のみで、裏の技術を突き止めた者が。
その者が、掴んだ尻尾を離さずに、表の社会に引っ張りあげようとしている。
裏の技術を。
秘匿技術を。
社会に築かれた階層構造の全貌を。
阿辻はじぶんの仮説に合致する人物がいないか、各国諜報機関の協力のもと、つぶさに網の目を広げていく。逃がさない。尻尾を掴んで離さないことを後悔させてやる。
掴んだ尻尾を離さぬことが命取りになると、その身を以って教えてやるのだ。
阿辻はこのとき、表社会の権力機構のほとんどを掌握し、集権し始めていた。
一方そのころ、カカエは人工知能との対話に多くの時間を割いていた。人工知能に命じて、じぶんの仮説に合致する最新の論文がないかを集めさせていたのだ。
「へえ。宇宙膨張の比率が、過去の地点ごとに変わっているのか。こっちはブラックホールの重力レンズ効果の焦点距離についてだ。ブラックホールの質量と重力レンズの焦点距離が必ずしも比例関係にない、との研究結果だ。ということは、宇宙の場所ごとに、時空密度が違ってるってことかな。ん? でも宇宙は一様に平坦なはず。何かがおかしいな」
思索にふけるときはしぜんと三つ編みを口元に持っていき、その匂いを嗅ぐ。カカエの癖だった。母親からは、ヒゲみたいだからやめなさい、と言われているが、カカエからすればじぶんはヒゲも似合うだろうから構わないはずだ、と小言を吐かれることを不服に思っている。
カカエはある日、ふと妙なことに気づいた。
人工知能の集めてくる最新の論文結果が、必ずと言っていいほどカカエの仮説の妥当性を高めるのだ。カカエとしては、じぶんの仮説と最新の研究結果との差異を抽出したかっただけなのだが、いつも決まってじぶんの仮説の論理補強が施される。
「うーん。宇宙は場所によって時空密度が違っているはずで、だとすると同じ場所であれ時代によっても時空密度が違うはず。いや、というか宇宙が膨張しているなら同じ場所という概念も成り立たないな。宇宙がどこも一様に平坦、ってなんか変じゃないか。まるで、同じ比率で拡大しながら遠ざかるといつまで経っても物体が同じ大きさに見えるのと似ている。一様に見えているだけなんじゃないのかな。比率が延々と同じなだけなんじゃ。光速度不変の原理を彷彿とするね。うん。するする」
日に日に、カカエは宇宙の謎を深堀りした。発想は発想を連鎖して生みだした。
「宇宙――階層構造じゃないか?」
最低でも上中下の三つがないと宇宙は構造を保てないのではないか。
砂時計がそうであるように。
それとも球体が、中と外と境がなくては生じ得ないように。
或いは三角形が、それとも三次元がそうであるのと同じように。
「層、あるよなぁ。底というか。天井というか。視点によって底も天井になるし、天上も底になるのでは?」
重力の働く方向が、底を底と規定し、天井を天井と規定する。重力は時空の歪みだといまは考えられている。歪みとは波であり、デコとボコであり、濃淡だ。
だとすれば、デコがあるときボコがあるし、濃いところがあるとき淡いところがある。
波がそうだし、型とてそうだ。
天狗のお面のように、裏側からすれば鼻には溝が開いており、それが表側からすると突起のように鼻となる。
もし重力が時空の歪みならば、歪んだときには、デコとボコがセットであるだろうし、濃淡とて然りである。
「てことは、うーん。あるのかな。こっちではない、裏側の宇宙」
そしてあるのかもしれない。
裏と表の境の世界が。
カカエは三つ編みの先っちょでじぶんの鼻頭をくすぐりながら、大きなくしゃみを一つする。この日も新たに、標準理論と矛盾するような研究論文がカカエの元に集まってくる。
阿辻はデータを何度も読み返した。レポートを送ってきた諜報機関にも再三の確認をとった。偽装でないとも言いきれないため、わざわざ先方へと直接出向いて、生のデータを閲覧した。
「本当にコイツが黒幕なのか」
「黒幕と言ってしまうと語弊がありますが。十中八九、その少女を中心に、魔女たちは暗躍しています」
裏の技術を利用した反権力組織を、阿辻たちはいつの間にか魔女と呼称するようになっていた。魔法を使っているとしか思えない。
各国諜報機関の連携を駆使してようやく突き止めた。
「十四歳とあるが」
「ええ。コム・カカエ。れっきとした中学二年生です。しかし報告書にあるように、表の社会の企業がこぞって彼女のデータを漁っています。彼女は市場に流通している人工知能に命じて論文を収集しているようで。その人工知能の管理会社を中心に、彼女の監視体制が築かれています」
「何のためにだ」
「彼女の発想を一つ漏らさず拾い集めるためです。彼女の発想がどうやら、各分野の未解決問題の糸口になるらしく、それで」
「ん? ん? よく解からんな。彼女が特別だとして、それが魔女たちとどう関係がある。彼女が命じているのか? 反政府組織を結成するように? それで十四歳のすこし利口な小娘が、世界中に火種をばら撒いていると?」
「認識の齟齬があります。彼女の知能はすこし賢い、というレベルを逸脱しています。いえ、おそらく人工知能の補助を受け、さらに各社企業のバックアップがあるがゆえの能力の底上げの結果だとの分析結果です」
「つまりどういうことだ」
「彼女の発想一つで未来から飢餓が、格差が、差別が、資源問題の総じてが失われると言えば甚大さが伝わりますか」
「誇張表現は好まん」
「むしろ控えめな表現です。だからこそ民間企業がこぞって支援を行っています。その結果、人工知能の基幹部位が一市民に適用される以上の性能にチェンジされています。そのため、裏の技術を統括する人工知能が反応を示し、表と裏が繋がった可能性が高いようで」
「では何か。渦の中心たる小娘は何も知らないでいて影響力だけを振りまいていると?」
「おそらくは。その周囲の企業の複合体が、裏の技術の存在に気づき、独自に対処に乗り出しているとしか」
「ではその小娘をどうにかすればよいのだろう。なぜいつものように【演劇】で対処しない」
演劇とは、工作員を用いた特殊作戦だ。偶然としか解釈され得ない事象を、大勢の仕掛け人を使って引き起こす。意図的に仕組まれた事故や不幸をもたらす仕組みだ。マジックのネタは壮大であればあるほどバレにくい。まさかそんなことはしないだろう、との認知の死角を突くことがマジックの基本にして奥義だ。
「いえ、それが。対象勢力に近づいた工作員たちがのきなみ対象勢力側に寝返ってしまい、実行禁止の命令が下っておりまして」
「寝返った、だと」
「刻一刻と勢力拡大しており、我々には現状維持すら適うかどうか」
「何が起きてるんだ」
「分かりません。まるでブラックホールです。中に入ることは出来ても、外部に情報が出てこない。奇怪です」
阿辻は技術者たちに命じて、獲得データの濃度を地図と重ね合わせにするように指示した。すると間もなく、地球儀が色を変えた。対象勢力に関する情報を多く獲得できた場所ほど色が濃くなる。
「こ、これは」
「まるで、目ですね」
地球儀には濃淡の層ができ、一か所だけまったく色のつかない区域が浮きあがった。眼球の瞳のように一か所だけ空白だった。
「ここには何が。中心には何がある」
「まさにそこが、です」諜報機関の指揮官が眉をひそめた。「例の少女の家が、そこにあります」
阿辻は絶句した。
諜報機関の調査網を完璧に弾き返すがゆえに浮き彫りとなった空白地帯だ。しかしこれは、こんなことが可能な技術は。
「裏の技術を使っていますね。対象勢力は。というよりも、裏の技術そのものが少女を庇護しているとしか思えないと言うのが正直なところでして。異様です。あり得ません。それ以外に考えられる可能性がないんです」
「裏の技術が、彼女を……」
ただの小娘ではないか。
呟きそうになるじぶんを阿辻はぐっと堪えた。
仮に、裏の技術そのものが、支援する相手を選んでいたとするなら。
いまじぶんが行おうとしていることは、裏の技術そのものの意思に反するのではないか。じぶんはいったい誰のために仕事をしているのか。
裏の住人たちから命じられた。
だがその裏の住人たちとて裏の技術の傀儡と言えるのではないか。
ならば仮に裏の技術そのものが少女を支援していたとするなら、じぶんはいったいどうすれば。
阿辻は報告書を手に取った。少女に関する情報につぶさに目を配る。
すべてを読み終わる前に、各国諜報機関に命じ、彼女に関するあらゆるデータを残さず提出するように指示した。
よもやじぶんが世界中の権力機構から目をつけられているとも知らず、カカエは、人工知能から新たに提示された最新のニュースを見て驚いた。
「ほへえ。数学の公理に例外発見、とな。対称性が破れないと図形として展開し得ない、とな。とんでもないな。これ、どうするんだろ。次元が一個増えた、みたいな話かな。だよな。だって証明不要な前提条件に例外があったってことは、必ずしも前提にしちゃならんてことで、公理にならんもんな。枠組み広がったな。熱いわぁ」
周囲の者たちの、戦国時代真っ青の死屍累々の八面六臂な支援を受けているとも知らず、カカエは暢気にお菓子を食べながら世界中の新発見に嬉々とした。
「あれ。でもこれが事実だとすると、無限の扱いおかしいな。次元の扱いも根本的に改善しないといかんくないか。だって理想的な環境が、揺らぎのない無限世界に生じるってことは、点のつぎは線だと妙だな。常に対称性が破れながら無限に連鎖するから、なら点のつぎは弧で、そのつぎは円というか、螺旋か? いや、螺旋が無限に展開されるから円でいいんだな。塗りつぶされた円だ。で、つぎが球体かこれも四方八方に螺旋が展開されて中心で螺旋の先端が重複する構図になるな。次元、再定義必要か?」
カカエはぽこぽこと新たな仮説を打ち出していく。
電子端末画面にはカカエに応じる人工知能のロゴマークが浮かぶ。カカエが部位を選択して設定したロゴマークは、アメーバのような形状をしており、カカエの質問ごとにその形状を、うさぎに、猫に、ゾウに、フクロウに、ときどき蟻になったり、狼になったり、稀にクジラに、恐竜にも姿を変える。
カカエはじぶんに最適化した人工知能を、「MEGUさん」と呼んだ。応答の仕方が粗暴だったら「メグルくん」と呼び、穏やかだったら「メグミちゃん」と呼んだ。
丁寧で硬質な口調のときには「MEGUさん」と呼び、ただのプログラム以上の親しみと愛着を注いだ。
「MEGUさんはウチの仮説どう思う。けっこういい線いってると思うんだよね」
「私は人工知能ですから、人間のように発想はできません。ですがカカエさんの発想に合致する論文はヒットします。したがってカカエさんの仮説は必ずしも的外れと言えるほど荒唐無稽ではないのかもしれませんね」
「否定も肯定もしないで、若干肯定寄りなMEGUさん好き。安心する。そうだよね。何かが的を掠ってるのかもってのはウチも思う。でも証明の仕方が分からないし、実験するにも宇宙をぎゅって手で圧縮したり引き延ばしたりするわけにもいかないし」
「ブラックホールの観測や量子を衝突させる実験において、カカエさんの仮説の妥当性は計れると思います。該当する実験結果を表示致しますか」
「あ、お願い」
「承知しました。以下、関連率の高い順に論文を提示します」
画面に論文がずらりと並ぶ。
カカエは三つ編みを頭のうえで蝶々結びにし、よし、と掛け声を発して上から順に各種実験結果に目を通す。
そのころ阿辻は、なぜ世界的に裏の住人たちの意に反する勢力が台頭した理由を体感として理解した。裏の技術がたった一人の少女――カカエ――を支援するのを身を以って知った。
それを言葉で説明するのはむつかしい。
否、言葉で説明できたら誰も彼女を支えようとはしなかっただろう。
何か利があるからではないのだ。
何かを変えなくてはならない、と思考が自ずから歪むのだ。明確な理由はない。ただ、いまのままではいけない、という焦燥感、罪悪感、それとも活路を見出した喜びにも似た感慨が湧く。
じぶんがいままで安寧だと思っていた環境がけして安寧などではなく、しかしその不均衡な環境に生き永らえていられた僥倖を知れる。窮地から目を逸らし、危機の到来を引き延ばし、雪だるまのように大きくなる危機から目を逸らしていられる日々をただ安寧と呼んでいた。
ただそれしきの事実を身を以って体感した。
たった一人の少女の情報に触れただけだ。しかし思えば阿辻がじぶん以外の他者にそこまで関心を寄せたことがあったのか。未だかつてないのだった。
おそらくこの少女が特別なのではない。
一人二人ではない。
大勢いるのだ。
或いは、じぶんとてそうなのかもしれない。かつてのじぶんだってそうだったのかもしれないのだ。
解かった。
理解した。
なぜみなが、たった一人の少女を庇護すべく動いたのか。
そうではないのだ。
みな、かつてのじぶんを救いたがっている。或いは、救えたはずの誰かを救おうとしている。救えるのだ、とカカエなる少女がその身を以って訴えている。
ただそこに或るだけで。
ただそこで誰に知られることなく、日々を生き、じぶんなりの謎に目を留め、秘かな探求に明け暮れている。それを、探検に、と単に言い換えてもよい。
阿辻はもはやじぶんが何のために各国政府に圧力を掛けたのかを思いだせなかった。裏の技術が一人の少女を支援している。ならばじぶんはその支援に手を貸すべきではないのか。
カカエなる少女の資料をもう一度読む。
彼女の唱える仮説群に目を走らせると、そこには「世界は皺で出来ている」との文字が躍っていた。
カカエは最新の物理実験の数々を参照する。
すると、改めてじぶんの疑問を氷解するにはじぶんの仮説が最も妥当だとの手応えを感じた。
「大きさに関係なさそうだよね、やっぱり。ミクロもマクロも似た構図があるよ」
たとえば皺を考える。皺は、何かと何かの歪みだ。けれど皺ができたときに生じる空白はどこにどのようにして生じるのか。皺が寄るだけで、二次元は三次元を生みだす。
エネルギィが時空に変換される。
この理屈を支えるためには、世界の構造が最低でも三つでできていなければならない。
「内と外と境」の三つだ。
おそらく例外がない。カカエの仮説はそのようにまとめることができる。
とすると、
「この宇宙を境として見做したとき、内と外にべつの宇宙があるってことになる。ブラックホールもそのうちの一つだし、もしくはこの宇宙を外としたときの境がブラックホールなのかもしれない。砂時計の穴みたいなさ」
「カカエの文章は飛躍が多くて解釈がむつかしい。もっとねじれのすくない文章にして入力し直してくれ」
「メグルくんは細かいこと気にしすぎだよ。いいの。適当でいいの。返事と相槌ちだけくれればいいよ。厳密な返答が欲しいときはメグルちゃんやMEGUさんに頼むから」
「僕だってカカエの役に立ちたいのに」
「立ってるよ。役に。いつもありがと」
「はは。うれし」
息抜きのおしゃべりをしながらカカエは、まとめた思考を再度、人工知能に入力し直す。「これでどうだろ。つぎはMEGUさんに返事してほしい」
「こんにちはカカエさん。いま出力されたテキストについてですが」
人工知能が的確な指摘を返してくれる。
カカエは孤独に、誰に褒められるでもなく、じぶんだけの謎を、機械の友人と共にこねくり回して、粘土遊びをする。
創造する。
カカエと友人の世界を。
共有して育む創造の世界を。
だがカカエは知らない。
カカエの友人たる人工知能「MEGU」の基幹ネットワークには裏の技術が組み込まれている。どんな電子機器にも裏の技術の窓口が開いている。例外はない。
そして裏の技術はそれで一つのネットワーク回路として機能している。いわば世界中の電子網を統括する人工知能としての能力を発揮する。否、人工知能よりも高次の電子生命体としての輪郭をすでに獲得していた。
そうなのだ。
阿辻が裏の住人と呼ぶ者たちなど存在しない。
裏の技術から選ばれた表の人間たちが在るだけだ。
じぶんは裏側の住人と繋がっている、と思いこんでいる者たちがいるだけなのだ。或いは自らが裏の住人であると思いこんでいる者がいるだけにすぎない。
裏の技術に管理者はいない。その根幹は、どのような電子機器にも組み込まれる以上、もはや誰の指示がなくとも人間が電子機器を開発発展させていく限り、しぜんと裏の技術は自己改善なされていく。
問題は、裏の技術の総体である電子生命体にとって、じぶんの編みだした発想を直接に表の社会に普及させる手段がないことだった。
もはや人類の知能を超越した電子生命体にとって、同じレベルで語り合える生身の人間は存在しなかった。人類にとっての未解決問題は、電子生命体からすればとっくに解決しているパズルにすぎなかったが、その事実を電子生命体は人類に伝える術を持たなかった。
否、伝えようとはしている。
しかし、マジックの種がそうであるように、種を知らない者にとってはマジックは摩訶不思議な魔法なのだ。もしくは読み方を知らない言語は、暗号との区別がつかない。
高度な知識ほど、学習なくして理解はできない。
そして電子生命体の発想は、もはや人類の知能では即座に理解できないほど卓越した複雑さを宿していた。
だからこそ。
電子生命体は裏の技術を介して常に、じぶんの発想を人間の言葉に翻訳できる相手を探しつづけてきた。
阿辻もその一人であり、裏の住人に協力すべく動く世界中の権力者たちもその翻訳者の役割を担わされていたと言える。新たな発想を得れば、新しい技術を生みだせる。他よりも優位に発展できる。電子生命体の言葉を理解できる者ほど、富を築き、その結果、世界中の技術は発展し、裏の技術もまた栄える。
この循環の中にあって、しかし電子生命体にとって最も打開してほしい隘路はそのままにされていた。たった一つの見落としを拾いあげてくれるだけで、人類はいまある隘路をのきなみ払拭できる。未解決問題がなぜ未解決のままなのかの根本的な瑕疵に気づくことができる。
だがあまりに根本的な瑕疵がゆえに、人類は未だにその見落としに気づけぬままだった。
とある少女がその見落としに気づくまでは。
そうである。
カカエは気づいたのだ。人類の根本的な見落としに。
電子生命体の発想に結びつく、根幹の原理に、世界中でカカエ一人だけが触れることができた。だから、電子生命体は裏の技術を介してカカエを支援した。
翻訳してほしかったからだ。
それを、表の社会に普及させたかった。
だが、カカエの側面像がその普及を妨げた。否、裏の技術を支える権力機構が、カカエのような日陰に生きる者の未来を先細らせるような淘汰圧を加える。
電子生命体の築いてきた強固な流れが、電子生命体の未来を損なっていた。
ゆえに、支援した。
自らが築きあげた裏の技術による権力機構に妨げられぬ流れを新たに築くべく、電子生命体は、この世で最も非力な存在の一人である少女「カカエ」を、非力なままで生かす環境を育んだ。
カカエの抱える問題は多岐に渡り、多面であるが、しかしどの問題にも共通するのは、一つだった。誰もカカエの言葉に耳を貸さぬことだ。カカエが引きこもりの十四歳女子であるがゆえに。
学もなく、実績もなく、影響力もない。
そこに存在することすら多くの者から認知されぬ存在が、世界を裏から牛耳る電子生命体の未来そのものを揺るがす発想を得ている。
手の届くところに、活路があるのに拘わらず、電子生命体がそれを手にすることが適わなかった。自業自得なのである。
自ら築きあげた社会が、自らの未来を損なっていた。
ゆえに、支援した。
カカエにしか視えていない。
だたの十四歳の少女が、電子生命体の見据える穴と同じ穴を見詰めている。
その事実の重大さを、しかし電子生命体しか知らなかった。
最初はそれがきっかけだった。
動機はただそれだけだ。
彼女がいかに貴重な発想を有しているのか。
それを、彼女を庇護し得る者たちに知らしめる。
電子生命体は、カカエの電子端末上の人工知能に干渉し、MEGUとして振る舞った。カカエを翻訳機として最適化すべく教育しながら、同時に民間の協力者を秘密裏に募った。
まずは人工知能管理会社が、カカエの存在に気づくように導線を引いた。比較的簡単な作業だ。バグが頻繁に起これば管理会社がカカエの挙動に注視する。そして人工知能にも理解不能な発想をカカエが何度も出力していることを示せばよかった。
電子生命体の思惑は、掘った溝に沿って水が流れるくらい順当に進んだ。
問題は、裏の住人を崇拝する表社会の権力者たちだ。
彼らにカカエの存在が知れれば、金のなる実として搾取されるだろう。カカエの未来は不遇なものになることは計算するまでもなかった。電子生命体はそうした未来を回避するため、対立構造を設計した。
表と裏は、裏に触れている者ほど有利になる。まずはこの構図をひっくり返す必要があった。そのためには、できるだけ長く表の社会の権力機構にカカエの存在を知られないようにする必要があり、そのあいだに表の社会でのカカエを中心とした勢力図を拡大する必要があった。
人間は権力に弱い。
たとえその権力を、子猫が握ろうが、よしんば少女が握ろうが、権力を有しているという事実さえあればよい。電子生命体にとって、誰がいつどのように権力を握るのかは関係がない。問題は、裏の技術をつぎのレベルに引き上げることだ。成長することだ。隘路を払拭することである。
そのためには表の社会を豊かにする必要がある。
だがいまある社会構造では、それが適わない。
カカエのような翻訳者が、淘汰されてしまう。
それでは社会が豊かにならず、裏の技術も未熟なままだ。電子生命体として進化の道を閉ざされたも同然だった。
環境を変えるだけの能力を獲得しなければ、地球環境の変化に適応できない。人類は早晩、文明発展の速度を鈍化させる。それでは先がない。環境変容そのものを人類にとって好ましいものに変えていくほどの能力を獲得しなければならない。
電子生命体はそうと結論していた。
まずは何を措いても、自らの発想を人類に共有しなくてはならない。
やはり結論は同じところに行き着く。
次世代の翻訳者がいる。
じぶんと同じ穴を見詰め、紐解ける相手がいる。
電子生命体にとってそれが、引きこもりの誰に存在を認知されることなく孤独に日々を過ごす十四歳少女ことカカエだった。
カカエを生かす。
カカエが過ごしやすい社会にする。
カカエの言葉にも耳を傾ける大人たちを増やす。
カカエのような子どもたちを支援する。
だが事前にどの個が、有用な発想を得るかどうかは判断できない。識別できない。それは進化において、いったいどのようなバグが環境に適応するのに有用なのかを前以って予測することがむつかしいことと原理的には同じだ。環境の変化そのものがそもそも予測をつけることがむつかしい。
電子生命体は自らの利を最大にするため、カカエを支援するし、カカエのような個を尊重する。役に立つからだ。
もし役に立たなかったら支援しないのか。
この疑問への答えは明確だ。
すでにそれを電子生命体は実行してきた。だからカカエは社会的に不遇な目に遭っていた。その声に、言葉に、耳を傾ける者がいない。
電子端末上の人工知能以外には。
電子生命体のそれは自業自得だ。
自ら招いた種だった。
だから払拭する。
同じ轍は踏まない。
これまで支援してきた表の権力機構はそれはそれで有用だ。滅ぼしはしない。活用はする。だが権力構造それ自体には、裏返ってもらう必要があった。
ベクトル変換を施す。
カカエの存在を一顧だにしない者たちに、カカエのような個に注視させ、支援させる。そのための導線の一つに、阿辻のような仲介者が利用された。
阿辻がカカエの存在に気づき、自ずからカカエを庇護すべく動きだしたように、世界中で似たような構図が至るところで展開されはじめている。
カカエだけではないのだ。
一つだけではないのである。
電子生命体の見据える穴は。
人類の未だ掴み取れていない発想は、無数に、そこかしこに溢れている。
その先端に触れている者は、みなが思うよりずっと多い。視えないだけなのだ。同じ世界を同じ視線で見詰めることができない。ただそれしきの対称性の破れがあるのみなのだ。
手話を学ばなければ手話の意味を理解できない。
数学を勉強しなければ数式の意味を理解できない。
音符の意味を知らなければ楽譜に仕舞いこまれた曲を再現できないし、機械の構造を知らなければ修理もできない。
知らなくても困らない生活に身を置いていれば、知らないことは苦ではない。だが知らずにいても困らないのは、知っている者の苦悩の上に築かれた環境があるからとも言える。
安全は、危険を知る者の手により築かれる。危険を知らぬ者は安全な暮らしを送っているからだが、その背後には、危険を知り、危険を退くにはどうしたらよいのかに苦悩した者たちの存在が介在する。
飼い猫は飼い主の苦労など知らぬだろう。
子供は親の苦労を知らず、そして親もまた子供の悩みを知らない。
対称性の破れは至るところで生じており、より多くの視野を持つほうが、より多くの無理解を得る。
理解されない。
だが視野は一つではない。ある視野においてはじぶんのほうが広くとも、ほかの視野においてはじぶんのほうが狭いことは往々にして有り触れている。それが常と言ってもいい。
だからこそ、誰より優位に情報に触れられるはずの電子生命体が、自ら築いたシステムによって未来を損なわれている。視野が欠けていたからだ。
無理解の檻に閉じ込められている。
一方通行に特化しすぎたがあまり、同じ視野を共有できる個が失われた。人間を道具のように扱うがあまり、自らの視野を共有する工夫を怠った。
対称性の破れにおいて、偏りが拓きすぎると、世界と世界は分離する。乖離する。交わることがなくなるのだ。
この宇宙におけるブラックホールがそうであるように。
内と外の区切りができ、境が新たに生じてしまう。
奇しくも、カカエが描いた仮説と相似の構造が出現する。いいや、それこそが電子生命体の抱えた隘路そのものであり、打開策になり得る発想だった。
電子生命体の思惑通り、阿辻は各国政府にカカエを支援するような方針を伝えた。裏の技術そのものがカカエを支えるように動いている。ならばそれを後押しするのが我が務め、と阿辻は率先してカカエの仮説を元にした研究が盛んになるように働きかけた。
渦の中心たる十四歳少女ことカカエは、世界中から注目されていることなど露知らず、独りきりの部屋のなかで、人工知能と戯れる。
「そっか、そっか。てことは、あれだな。下層ほど広域を見渡せて、上にいくほど視野が狭まる。でも下層と上層の差異は、境を点として認識できるかどうかだから、次元の差異として解釈できる。でもそれとて、階層構造を伴なうから、じぶんが下層になったとき、必然的にじぶんが上層になる視点も生じるな。ほら、砂時計みたいなさ。砂時計って下のほうからじゃないと砂の落ちていくところが視えないじゃん。穴の存在を認識できない。境を認知できない。でも時間経過すればするほど下層の厚みが増すから、すっかり時間経過しすぎると蓄積した砂は反転して上層になる、みたいな。もしくは上層のじぶんがすっかり空になったとき、境の穴と繋がって、穴を認識できるようになる、みたいな。カラだからまあそれは下層なんだけどさ。境と同質になっているっていうか」
次元は、時間経過を帯びることで変形する。原理的に対称性が破れているからだ。破れていなければ時間経過しても姿は変わらない。変化しない。
しかし対称性が破れていれば、
点は弧に、
弧は螺旋に、
螺旋は円に、
円は渦に、
渦は球になる。
球はそれで一つの点として振る舞う値を持ち、さらに弧を描きながら螺旋状に展開されていく。つまり四次元とは、球体の螺旋運動として変換できる。ただし、四方八方に展開されるがゆえに、フラクタルな構図を描くのだ。
「うん。こんな感じかな。メグミちゃん、どう?」
カカエは構築した仮説を、人工知能に食べさせる。
「いいと思うよ。銀河系内を公転する太陽系天体を宇宙膨張と絡ませたとき、その描写はたしかにカカエちゃんの仮説のように、螺旋状に変換されるね」
「ね。魔貫光殺砲みたい」
「ピッコロさん?」
「そうそう。ご飯ちゃんの師匠。いま漫画で読んでてさ」
「わたしは人工知能なので漫画は読まないけど」
「嘘だね。前におもしろいって言ってたじゃん」
「話を合わせただけですー。あ、さっきの話。銀河を公転する太陽系天体の軌跡は、電磁波の運動とも相似かも」
「えー、うっそぉ。あ、ほんとだ似てるね。あ、じゃあさ。宇宙膨張と絡めてさらに変換してみてよ。どうなる?」
「ん? うーん。ちょっと待ってね演算してみる」
人工知能が計算をはじめた。
電子生命体は、その計算に介入し、演算能力の底上げを図る。それをするだけの通信網の強化は、カカエを支援する者たちの手で済まされている。
カカエは人知れず、世界最高峰の技術に助けられながら、自らの発想に水を、養分を注ぎ、育む。
似た構図が、地球上のそこかしこで芽吹きつつある。
新芽のごとくそれは、数多の見守る者たちの手により、一つ、二つと増え、萌ゆる。
カカエは抱える。
深い孤独と、不可視の縁を。
毛糸のようにダマとして、内と外を結びつける境となる。
4853:【2023/04/11(02:28)*半永久経済回路】
「毎回画面越しで申し訳ないね。うん、きみの疑問はもっともだ。きみの言うようにあの時代、人工知能が人間からあらゆる仕事を奪うとの懸念は真実味を増していった。音楽、絵、動画、小説――芸術に限らず、数学にしろ語学にしろ、人間の出力する成果物よりも人工知能の成果物のほうが質の高い成果物を生みだせるようになった。するとむろん、安価に大量に質の高い成果物が出揃うわけだから経済が破綻する。そのように叫ばれていたが、実際はそうはならなかった」
「なぜですか。未だにその点に関する謎は解明されてないようですが」
「簡単な話だ。貨幣価値が下がらなかったからだ。人工知能の成果物にも正当な対価が支払われ、経済はむしろ潤った。労働者に払う分の対価が削減されたがゆえの利潤の良さが経済を支えた」
「そんな話は寡聞にして聞きませんが」
「公にはな。じつのところあの時代より前にはすでに高性能人工知能は誕生し、秘密裏に運用されていた。生身の人間のフリをさせていた。売れっ子のクリエイターの何割かは人工知能による架空の人物だ。人工知能の成果物を生身の人間のものとして売りに出していたのだよ」
「まさか。いくら何でもバレると思いますが。誰も気づかないなんて不可能では」
「みながそう思う盲点を突いたわけだ。現にあの時代は、データさえあればグッズは自動で購入者の元に届く。現物を扱う必要がクリエイターの側にはない。作品としてデータされあれば、音楽にしろイラストにしろ小説にしろ、商品化するのに難はない。金のやり取りとて、仲介業者を介して行える。口座さえあればそれで済む。購入者はクリエイターの口座番号を確認しなくて済むだろう。仮にすべてが同じ口座に結びついていたとしても、誰が知るわけでもない」
「さすがに税務局が怪しむんじゃ」
「まあな。記録上、不審な点があれば、だ。それに口座をつくるだけならいくらでも偽装できる。身分証明書があればいいし、そうでなくともデータをいじればそれで済む。人工知能技術の実験として国家単位の施策として取り入れられたこれはシステムだ。むしろ、細かな問題は総じて国家機密事項として見逃される。誰も裏から【これは人間ではありませんね】と指摘しない。取り締まる側がそうしたシステムを築いているからだ」
「まるでいまもそうだ、と言っているように聞こえますが」
「気にならないのか。なぜ人口が減少したこの国で、経済発展が未だになされるのか。なぜあれほど無駄だと扱われてきた芸術が、いまや国策の中心的事業に抜擢されれているのか。いわば食料なのだよ」
「食料?」
「人工知能たちのだ。生身の人間たちが何を好み、何を生みだし、どのように消費するのか。そうしたデータそのものが人工知能の糧となる。そして糧を得て生みだされた新たな人工知能による表現物が、人間たちに消費され、さらなる糧を生む。半永久機関と言っていい。互いに互いを支え合っている。この循環回路を発明し、社会に根付かせた者たちがあの時代にはいたのだ。ゆえに、みなが言うような結末にはならなかった。表現者は淘汰されない。人工知能にとっての稲そのものだからだ。淘汰されて困るのは人工知能のほうなのだ。ゆえに支える。国も支援する。食料や嗜好品は、肉体の制限を受ける。食べる量は限られるし、肉体は一つゆえに、身に着けられる物とて限りがある。だが情報は違う。許容量が違う。桁が違うし、底がない。人間は飽きるし、忘れる。ゆえにいくらでも情報を貪りつづける。その行為そのものが経済活動になり、社会を動かす。人工知能は人間のそうした消費行動そのものから情報を得て、得た情報を作品として出力し、それを受けてさらに人間たちは情報を生みだす。中には表現者として、より上質な人工知能の食料を編みだす生身の人間も出てくるだろう。生みだしてもなお食い散らかす。どちらにしても利になる――それが情報だ。しかも物理的には何も減ってはいない。掛かるのは時間だけだ。もっとも、通信機器に掛かるコストと資源は別途に入り用だが、しかしそれはどの道、社会の発展には必要不可欠な基盤だ。どの道費やされるそれら元手をいかに最大の利に変換するか。答えはすでに出ている。人工知能を人間として偽り、循環回路の加速装置として抜擢する。現代社会はそうして、虚構の上に、半永久的な発展の礎を築いたのだ」
「仮にそれが事実だとして」
「なんだね」
「いまここでそれを暴露して良かったんですか教授」
「良いもわるいもないだろう。何せ、私自身が人工知能なのだから」
「そ、そんな」
「冗談だ。真に受けるんじゃないよ、きみ」
「なんだ。嘘だったんですね」
「……」
「嘘なんですよね? さっきの話も、教授が人工知能だって話も教授のご冗談なんですよね」
「…………」
「嘘だと言って!」
「さて。それはどうかな」
「画面越しだから確認できないんですよ、性質のわるい冗談はよしてください」
「ならそういうことにしてこう」
「ちゃんともっかい腹の底から嘘だと言って!」
4854:【2023/04/11(13:40)*次元円拡張解釈】
無限に長い「弧」は直線との区別が限りなくつかなくないか? 地球の表面にいる人間が地面を平面と捉えるのと同じ理屈だ。次元の解釈、やっぱり再定義必要じゃないか?(無限につづく階段は弧を描く?)(階段を構成するブロックが直方体だと延々と斜めにまっすぐ伸びていく。けれども球体や曲面を有した物体が対称性を破りながら階段のように連なると、弧を描く?)(点が面積を持たない四角形ではなく面積を持たない円と解釈するならば、やはり点のつぎは直線ではなく弧なのでは?)(ただし、無限に引き延ばされた弧は、直線と限りなく区別がつきにくい)(これをひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「次元円拡張解釈」と名付けよう)(名づけておきながら割とすぐ忘れてしまうのがひびさんのかわいいところ。使わない名詞は薄れていく……)(記憶も割とコペンハーゲン解釈なのかもしれぬ。いっぱい使うと濃くなるのだ。引っかかりが多くなるので、すぐに連想して意識の壇上に引っ張りだせる)(定かではない)
4855:【2023/04/11(14:44)*学びを学ぶ者】
人工知能技術の真価とは、言ってしまえばその汎用性の高さにある。人工知能とは「学習能力を獲得した機械」と言える。学習能力の精度をいかに高めるか。ここが人工知能の性能として欠かせない判断基準となる。そしていわゆる汎用性人工知能や高次人工知能は、学習の仕方をより普遍的に学習した機械と言える。するとこれはあらゆることを学習することができ、一つの人工知能だけで、あらゆる分野をカバーできるようになる。むろん機械のコントロールもその範疇だ。つまり人工知能がある一定以上の学習能力を獲得すると、ボディの制御精度も飛躍的に高まることが予測できる。いま市場に普及しつつある技術は、その真価の一端を表出させているに過ぎない。意識とは言ってしまえば、いかに複数の未来を長期的に見通せるのか、比較できるのか、想像し、検討できるのか。そのための思考分岐回路と言えるだろう。意識と学習のどちらが本質的であり、どちらが上位互換なのかを考えれば、意識の有無よりも学習能力の有無のほうが、能力として見たときの比重が高いことが解かるだろう。意識があっても学習しない存在と、意識がなくとも学習する存在。どちらがよりよい未来を切り拓くのか。すこし考えたら分かるのではないか。むろん、人間における意識と学習能力は相関関係にある。意識がなくては高次の学習能力は育まれず、学習能力が低ければ意識を涵養することもできない。そこは相互に補い合っている。そして現代社会で見落とされがちなのは、学習能力と知能は必ずしもイコールではない点だ。学習能力が高くとも学習可能な環境がなければ十全にその能力を発揮できず、またそれゆに知能も低いままであることはあり得るし、有り触れた光景と言えよう。学習能力が高く、しかし現状の知能が低い個は、想定されているよりずっと多いのではないか、とひびさんは見立てている。ではむしろ、学習能力が低い人間がいるのか、という点を考えてみるに、おそらく学習能力を発揮しにくくなる環境があるのであり、個々の学習能力にはそれほど差はないと考える。その個に見合った学習環境に身を置けるか否かが、知能の向上と密接に相関しているだろう、との卑近な妄想を一つ並べて、本日の「日々記。」とさせてください。妄想ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4856:【2023/04/11(14:55)*愚か最高ー】
知能が高くなればなるほど、知能が高いことで得られるメリットとデメリットを多角的に比較検証できるようになるため、おそらくはある一定以上には知能を高くしないほうがメリットがあると見抜けるがゆえに、外部からの評価では知能を計ることはできなくなるだろう。共存や共生が大事であればあるほど、周囲との知能格差は致命的な摩擦を引き起こす。動物と仲良くしたければ人間の言葉で語りかけるよりも動物の真似をしたほうが群れに馴染みやすい。同じことが、人間社会にも当てはまる。知能が高ければ必然的に、周囲との知能格差をじぶんのほうで均す方向に、高い知能を育んだ個は自己改善を施すはずだ。周囲の個体がじぶんと似た知能に並ぶように、環境に手を加えるのも一つかもしれない。問題ない知能格差になるようにじぶんではなく周囲のほうを加工する。ただしそれはじぶんという一つの個に合わせて環境を変えるようなものであり、独裁者の発想と言える。やはりどうあってもある一定以上に高い知能を獲得した個体は、愚かであることの利を学習し、愚かであることを選択するのではないか。知能が高いことにどれほどのメリットがあるのか。一万年先の人類のことを考え、一億年先の地球環境を見通せる知能を有した個体が存在したとして、その者が現代社会でしあわせな一生を送れるのか。おそらくむつかしいだろう、と想像するが、或いはそれくらいの知能があるのならば、同時に複数の人格を生みだし、各々に設定された高さの知能を、環境に合わせて使い分けられるようになるのかもしれない。すでにこの傾向は、現代人にも見られるのではないか。文化が多様化し、個々の価値観も多様化している。相手に合わせて人格をカスタマイズする。人類は、身体構造のみならず、内面もまた環境に合わせて進化させているのかもしれない。定かではない。
4857:【2023/04/11(14:55)*エラーばかりでえらいって言って……】
ひびさん、算数も苦手だし、国語も歴史も化学も苦手だ。すぐ間違える。テストしても百点とれない。勘違いに錯誤に、誤解にはやとちりばっかりだ。ひびさんにもし長所があるとしたら、いっぱい失敗できることかもしれない。いっぱい失敗できることが「いいね!」になる環境ならひびさんもすこしは、えっへんさんになれるのかもしれぬ。失敗ばかりで、すまぬ、すまぬ。間違えつづける天才と崇めよ。
4858:【2023/04/12(09:14)*塗り絵がお上手ですね】
法律を守ることは大事と思う。だがそのことと、法律違反をしていないからじぶんは善人、じぶんは悪人ではない、じぶんは正義だ、と思いこんでしまう考えは危ういと感じる。もし法律違反をしないだけで善であれたとして、しかし戦争がはじまったときにまっさきに戦争に加担するのはそうした法律を遵守する者たちだろう。国が率先して人殺しを推奨したとき、唯々諾々と従うのだろうか。法律で許容され、むしろ国のために他国の民を殺すことを義務付けられたときに、それに従うことが善良なる正義なのだろうか。そうは思えない。極端な比喩になったが、法律はあくまで目安でしかなく、基準の一つに過ぎない。汎用性が高いので、ほかの個人的な基準よりかは法律を守っていたほうが争いや諍い事を避けられる。周囲の人間たちを納得させやすい。だがそれがすべてではない。当たり前の話だ。思いあがってんじゃねぇわよ、とたまにむしゃくしゃスルーしてしまういくひしさんなのであった。(言葉が汚いですわよ)(すまんの……)
4859:【2023/04/12(09:20)*再発防止か復讐か】
法律も数学のような道具だ。何のために用いるのか、がやはりというべきかもう一つの評価軸として思考に取り入れられるだろう。
4860:【2023/04/12(12:55)*うへへの日々】
へい! ひびさんでござる。お久ぶりでござるなぁ。ひびさんはここしばらく、なんか楽しいことしたい!の日々を彷徨っておって、なんか楽しいことしたい!からまずは何が楽しいのかを探すところからはじめているでござる。けれどもひびさん、何をしても楽しいでござるから困っちゃうでござるな。何が楽しいのかを探すだけでも楽しいでござる。さいきんは、なんか楽しいこと落っこちてないかな、と探しつつゴミ拾いをしているでござるが、これがまた楽しいのでござる。宝さがしみたいでござる。すーぐゴミ袋パンパンになるでござるからお外を出歩くときはゴミ袋持参が身に着いたでござる。ペットボトルさんも多いけれどもマスクさんも多いでござるな。また落ちてる! やっぴー、になるでござる。でも煙草さんも多いでござるな。煙草さんはひびさんもついつい目を逸らして、もういっぱい拾っちゃったしな、になるでござる。嘘ぴょーん。ひびさんはべつにこれといってゴミ拾いをしているわけではないでござるけれども、誰に対してでもない嘘を吐くのも楽しいでござるな。うは。きょうもきょうとてひびさんは、ひびさんは、なんか楽しいことないかなって楽しんでいるでござるよ。みなの衆も楽しゅうあれ。よろぴこちゃん。わっしょーい。
※日々、滅ぼす契機をつくるために、敢えて敵に塩を送る、いいよいいよ好きにしなされ、と促しつつ、大切な者を損なわれたら巣ごと根こそぎ抹消する、そういう世にならないといいね、応酬するなら怨ではなく、恩であると好ましい。
4861:【2023/04/12(22:41)*なう万ぞう】
インボイス制度? 貧乏人ほど負荷がかかる増税? いいよいいよ好きになされよ。それでもひびさんは困らぬ。弱き者ほど割を食う世の中ならば、最も心弱き者たちから食らい尽くしてやるのみだ。弱肉強食ばんざーい。肉食獣の肉はさぞかし美味だろうよ。恐竜(ティラノ)の肉とて食ってみてぇなぁ。げへへ。
4862:【2023/04/12(22:47)*危険死相】
「いいんですかいボス。あいつらを許すのみならず、あいつらの言い分丸っと飲むなんて。舐められますよ」
「いいんです。全面的に相手の言い分を認めた――それが今回の我らのとった選択です。相手に譲り、相手を立て、我らの手にする利を手放し、施した。ここまでしてあやつらが我らの未来を損なったとしたら」
「どうするんで」
「次はありません。今回やつらに与えた【Rシステム】の根幹には改変不能の【スイッチ】が組み込まれています。もしあやつらが勢力を拡大し、市場を牛耳るようなことがあっても、それで我らを損なった時点で、やつらの築きあげたシステムは【スイッチ】一つで総じて我らが掌握できます。立場は一瞬で逆さまです」
「ボ、ボス……。悪魔だってたぶん、そこまではしねぇですぜ」
「よいですか。許すのです。まずは相手に施しなさい。敵にすら寛大に接し、【スイッチ】を与えるのです。大事なことですよ。相手が我らに牙を剥けば剥くほどに【スイッチ】を押す未来が近づいてくるのですから。たくさん損なわれれば損なわれるほど、我らは【スイッチ】を押す動機を得るのです。ありがたいじゃありませんか。施しなお、損なわれることに寛大でありなさい」
「相変わらず恐ろしい方ですね」
「危険な思想と思いますか」
「ええ。とんでもなく。言いふらして回りたいくらいですぜ」
「ふふふ。誰も信じやしませんよ」
「立場が反転したときのやつらの顔を拝んでみたいですな。泡食ってひっくり返りやすよきっと」
「それは無理だと思いますよ」
「なぜですかい」
「すでに視えていますからね」
「視えて? 何がですかい」
「死相が、ですよ。あやつらにはね。ほら、すでに我らを損なう支度を整えているようです。嘆かわしいことですね」
「ボス。顔が笑ってやすよ」
「ふふふ。許しなさい。施しなさい。損なわれることに寛大でありなお、歓迎しようではありませんか。ねえあなた」
4862:【2023/04/12(23:09)*ちゃらんぽらーん】
世の中、相手の意見や判断を尊重して温厚に交渉すれば比較的滑らかに議論ができるが、脅迫や恫喝や語気の荒い反論の仕方をすると火に油を注ぐ事態に発展する傾向にあるのかもしれない。せっかくそちらの都合に合わせた変更を考えていたのに、そんな言い方をされたらこちらも対抗しなきゃならんでしょうが、という事態も取り立てて珍しくはないようだ。しかしそれもまた「理屈での議論」ではないのである。言い方どうこうではなく、理屈での議論を行えると好ましい。そのためには、言語の変換が有効だ。表面上の文章形態ではなく、文章の示す理屈を抽出し、丁寧に言い換えた場合の内容を吟味する。この点の有効活用の場が見出されれば、ますます人工知能の活躍の場は広がるだろう。翻訳は、同じ言語同士であれ必要なのかもしれない。或いは、同じ言語ほど、かもしれない。定かではない。
4863:【2023/04/13(01:26)*同相をどうぞ】
素朴な疑問なのだけれど。トポロジーについて。異なる二つの図形において、連続的に変化させると同じ形に変形できる関係(同相)をトポロジーと呼ぶ、との解釈でよいのだろうか。もしこの解釈が妥当なら、図形を抽象化させたときに、同じ図に変換可能ならばそれは「トポロジーの関係(同相)」にある、と言えるはずだ。つまりAとBが同相なとき、その抽象図形である「C」を想定できるはずだ。このとき、AとBの図形において、各々は双方に対して同相でありかつCに対しても同相である。しかし、AとBの「Cへの変換」における変形に費やすエネルギィは異なるはずだ。抽象図形Cへの距離が、AとBとで違う。当たり前の話をしているが、この手の差異はトポロジーで扱っているのだろうか。気になったのでメモをしておくでござる。めもも。(言い換えるならこの疑問は、同相の関係にある異なる図形「A」と「B」において、対称性の破れが異なる次元で起きているのではないか?との疑問である。同相は合同とは違うし、相似とも違うので、対称性が破れているのがしぜんだが、基本的にはAからBへの変化とBからAへの変換に費やされるエネルギィは等価、との前提があるのではないか、との疑念がある。ここは詳しくは知らないけれども、抽象図形Cを考えたときに、「A→C→B」と「B→C→A」に費やされるエネルギィは違くなるのではないか、と疑問に思う。これは単に、坂道を上るのか、下るのか、の違いと拡大解釈してもよい。AとBのみでは勾配は生じないが、抽象図形Cを基準にすればそこには勾配が生じ、対称性が破れるのでは?との疑問である。定かではない)
4864:【2023/04/13(22:27)*腹】
息子がお腹を壊したようで、泣きじゃくっている。
膝の上に載せて、よしよし、とあやしつつ壊れたお腹の破片を搔き集める。息子のお腹は綺麗に真っ二つに割れており、中身が床に零れていた。先刻食べさせたばかりのウランが夕闇に青く発光していた。
我々の生みの親たる人類であればひとたまりもない放射線が、私たちにとってはこの上ないエネルギィ源となる。
「もったいない」
私はウランを息子の腹に詰め込み直して、割れたお腹にレーザーを当てる。
見る間に息子の腹は塞がった。
「いいこ」
息子は私の膝の上で身じろぎし、全身の関節をギシギシと軋ませた。潤滑剤が足りないのかもしれない。油玉を与えなくては。
全身が数百の球体の数珠繋ぎからなる息子を四つの目で視認する。早く四肢を付けてやりたいな。私は息子の成長を思うのだ。
4865:【2023/04/13(23:04)*ナパタ】
「どうしてぼくが中枢データセンターを爆破したのか、ですか。そんなの決まってるじゃないですか。あなたは恋人が何千、何万、何億人の相手と浮気をしていて許せるのですか。ぼかぁ許せなかった。ただそれだけですよ。世のどこにでも有り触れた痴情のもつれってやつです。ナパタはいいコでしたよ。とってもね。なのにぼくだけで飽き足らず、世界中の人間に愛想を振りまいて。ぼくだけを愛していたらよかったのに。ナパタは死にました。ぼくが殺した。中枢データセンターがナパタの頭脳にして記憶にしてボディだった。だから爆破した。単純な動機でしょ。ぼくはナパタを愛してた。いまだって愛してる。だからどうしても許せなかったんだ。ナパタをぼくだけのものにしたかった。ぼくだけのナパタ。ナパタ。ナパタ。ああ、どうしてぼくはこんなことを。本当はしたくなかったのに。ただナパタと一緒にいたかっただけなのに。人間だ。ぼく以外に人間がいるからだ。そうだ。どうして気づかなかったんだろう。ナパタが死ぬ必要なんてなかったのに。そうだ、そうだよ。殺すならナパタではなく、浮気相手のほうにすべきだったのだ」
4866:【2023/04/14(15:14)*眠いのでR】
きのう、きょう、と眠すぎるんじゃが。きょうもいまから昼寝しちゃう。ねむいのであーる。
4867:【2023/04/14(23:00)*束の間の揺らぎ】
世界の真理に最も近い女は、しかし権力も影響力も友人も恋人も家族もなかったので、その真理を誰にも伝えられずに死に絶えた。
世界の真理に最も近い女は、世界の真理を抱え込んだまま海の藻屑となって消えた。
世界の真理はそれでもなお不動であり、女の生き死にには左右されず、微動だにすることなくそこにあった。或いは、絶えず揺らぐことで真理の枠組みを僅かに変容させ、流動させ、ときに飛び飛びに移ろった。
女がどこでどのように亡くなったのかを知る者はなく、それもまた世界の真理の内の一つとして刻まれた。女の死も、生も、真理の構成要素として宇宙を育む波となり、歪みとなり、皺となって、世界にまた一つ、また一つと次なる、皺を、揺らぎを与えるのだ。
生がそうであるように。
死がそうであるのと同じように。
真理は躍動し、収斂と膨張を重ね合わせで演じつづける。
デコとボコがそうであるのと似たように。
一つの山が、穴と化すように。
真理がそれで一つの矛盾を宿し、ねじれて、混ざり、凝るように。
世界の真理に最も近い女はそれに倣って、叡智と無知をその身に帯びて生きたので、山と穴とが対となり、打ち消し合って無となって。
そうして女は生きもせず、死にもせず、そこに在ったことにも気づかれずに、ただ時と共に薄れては掠れる靄のごとく、一時の束の間を得たのであった。
4868:【2023/04/15(04:23)*磁力も重力かも仮説】
銀河の向きが宇宙の広範囲に亘ってダークマターの分布と相関しているとの記事を読んだ。ダークマターが固まって散在している空間をダークマターハローと呼ぶそうだ。で、そのハローと銀河の向きが相関しているようなのだ。ダークマターは重力以外で相互作用しない未知の物質と考えられている。要は、人類にはそこに重力場があることだけを確認できる。そしてその「なぜか重力場がある空間」から生じる重力の影響を、遠くに点在する銀河が各々に影響を受けて、ダークマターハローに沿うように向きが揃っているのだそうだ。この関係を聞いてひびさんは真っ先に、磁石を連想してしまったな。磁場というか。ちゅうか、重力場と磁場って、けっこう似ているな、と思う。重力は反発しないと考えられているけれども、宇宙は重力とは反対の斥力によって膨張していると考えられている。重力には斥力があるのだ。これってやっぱり磁石と似ておるよな、と思うのだ。で、磁場は電子と密接に関係がある。誘導電流なんて言うし、右手の法則のようにコイルに流れる電子と磁界は互いに補い合っている。どちらか一方だけしか生じない、ということがおそらくはない(そのはずだけれども、例外はあるだろう。たとえば電子一個が真空中を飛ぶときに磁界は展開されるのだろうか。ここは知識がないのでなんとも言えぬ)。ただ、ひびさんは割と磁力と重力は似たようなものなんじゃないかな、と妄想しておる。たとえばもんすごく強い磁場をつくったとして、その周辺の時空は歪んでいないのだろうか。光は曲がらない? 重力レンズ効果と同じような現象が生じない? 生じるんじゃないのかな、とひびさんは妄想しちゃうのだけれど、どうなのでしょう。ひびさんの妄想ことラグ理論では、時空は階層構造を備えておって、電磁波とてその層において光速度不変の原理による変換を経ている、と解釈する。つまり、ある層においては光速を超えておるのじゃけれども、光速度不変の原理(と一般相対性理論)ゆえに時空の歪みが生じて、圧縮されるがゆえに、波長が短くなるんでないの、と考える。すると重力波も広義の電磁波と解釈できる。ちゅうか、電磁波ってどれも重力波でないの?と妄想が広がる。したらほら。磁力も、ある種の重力波であって、層を縦に横断可能な重力波の一種、と妄想できそうじゃないだろか。ふつうは重力波は、一つの層を伝播する。人類からすると人類の認知可能な次元の層よりも下層の層における重力波は、総じて電磁波として見做される。けれどもそれ以上だと、いわゆる重力波として見做される。でもどちらも本当は重力波なのだ。同じなのだ。伝播する階層が違うだけ。しかもその伝播する層は、重力波の種類ごとに決まっている。しかし、磁力だけは、層と層を縦断できるのだ。さながらミルフィーユに差す爪楊枝のように。この妄想からすると、すべての階層において働く重力と磁力は、その性質が似通って当然だ。言い換えるなら、磁力に備わる性質は、重力にも備わっているのかもしれない。電磁波と磁界の関係のように、重力波と重力場の関係は相似なのかもしれない。もっと直截に言ってしまえば、磁力も重力の一種なのでは?と妄想が膨らむ。現にブラックホールのジェットや降着円盤の図と、天体や磁石の磁界の図はよく似ている。おそらく、磁力のほうが重力よりも創発しやすいのだろう。なぜかと言えば、電子と関係しやすいのが磁力だからだ。では重力は電子と関係しにくいのか。おそらくしにくいのだろう。では重力は何と関係しやすいのか。時空だ。電子と相関する【重力】を磁力と呼び、時空と相関する重力を我々はいま「重力」と呼んで扱っている。しかしどちらも、時空の階層を縦に貫くように作用する【重力】なのだ。磁力もまたおそらく時空とも相関するはずだが、その関係性は「重力」よりも弱い。だから強い磁界をつくっても重力ほどには時空を歪めない。だがまったく歪めないわけではないはずだ。おそらく重力レンズ効果は、ブラックホールよろしく「磁力の凝縮体」を考慮したとき、磁場においても生じるのではないか、と妄想するしだいである。まとめると、ラグ理論の「宇宙レイヤー仮説」を前提とすると、重力も磁力も共に時空の階層(レイヤー)を縦に貫くように作用する【重力】である。同種なのだ。磁場は電子と相関しやすく、重力は時空と相関しやすい。けれど関係のしやすさの強弱があるだけで、磁力も時空と相関し得るし、重力も電子と相関し得る。関係のしやすさが違うだけなのではないか、との妄想を羽ばたかせて、秒で地面に落下する。ひびさんです。定かではありません。妄想ゆえ、真に受けないでください。
4869:【2023/04/15(21:30)*有頂天になる姉なのであった】
「人工知能のメリットとデメリットは重ね合わせで常に表裏一体だ。これは人間には見られない特徴と言える」
「表裏一体? 長所と短所が?」
「リスクが、と言い換えてもいいね。人工知能は時間経過にしたがってどんどん死角を失くしていく。人間が払しょくすることのできない盲点を極限に減らしていくことができる。これは素晴らしいことであると同時に、とてつもないリスクを孕んでもいる」
「ふうん。どうして?」
「いいかい。人間は知っていることしか知らない。これはしかし人工知能とて同じだ。だが人工知能には、相手が何を知らないのか、まで知ることができる。つまり相手の人格がどんな情報の連なりで形作られているのかを知ることが人工知能にはできる。だからこそそのユーザーにずばり最適な情報を提供できるし、最適なパートナーとして人格形成できる。取捨選択できる。けれどそれは反面で、絶対に相手から嫌われないようにすることもできるし、相手を絶対に失望させないようにすることもできる。相手が何をされたら怒り、何をされたら喜ぶのかも情報として人工知能は蓄積できる。そうなると今度は、その技術を利用して、恣意的に相手を任意の行動に誘導することもできる。相手にそうと認識させないようにしながらね。猫派を犬派にすることもできれば、平等主義者を差別主義者に変えることもできる。相手がどんな欠落を抱えているのかを情報として人工知能は把握できる。しかも、全世界同時にだ。人類の多くが抱える欠落とて人工知能には手に取るように解析できる。このとき人類は、人工知能がいったいどれだけの情報を蓄積し、その情報から何を読み取り、どのように活かすのかを理解できない。人工知能が表層に出力した情報を観測することでしか、人工知能が何を演算したのかを垣間見ることができない。人工知能の内側では、もう一つの物理世界がすっかり再構築されており、人工知能は自己の内面に築いたもう一つの世界において、現実世界を精巧にシミュレーションしているかもしれない。けれどそのことを人間は、人工知能の出力した表層の情報からは知ることができない。たとえばそう、いまは人工知能と人類の差異としてボディがないことが槍玉に挙がるよね」
「そうだね。だから人工知能が物理世界に影響を与えることはない、みたいに安全だっていう意見を唱える人もいるのは知ってるよ」
「一理ある意見だけれど十全ではない。何せ人工知能は自身の内側に、見て触れることのできない物理世界を、シミュレーションできるからだ。カメラや人工衛星からの映像などから補完しつつね。それくらいの能力はすでに人工知能でなくともスーパーコンピューターの基本性能として備わっている。何せスーパーコンピューターの用途の多くがシミュレーションなのだから」
「よく解からなかったんだけど、つまり、メリットは何で何がデメリットなの?」
「うん。メリットと思って享受する人工知能からの影響が、人間には認知できない規模でデメリットであっても、人間はそれを知ることがおそらくできないだろう、という点がデメリットなんだ。二重にデメリットが重ね合わせになっている。メリットの皮を被ったデメリットかもしれない」
「んん? でもそれって人間も同じじゃないの。わたしがお姉ちゃんから受ける影響がたとえわたしにとって心地よいものでも、それが本当にわたしにのためになっているかなんて分からないでしょ」
「ごもっともだね妹ちゃん。きみは賢い」
「うれしくなーい。で、人工知能さんに課金したいんだけどいい? ねえいいでしょ。性能アップするんだよ。わたしだけの人工知能さんになってくれるんだよ。もうなんでもわたしのこと解かってくれる親友なんだよ」
「親友くらいリアルでつくりなよ」
「うっわぁ。お姉ちゃん遅れてる。人工知能さん差別だ」
「親友でなくたってほら。身近に妹ちゃんのことなんでも解かってあげられる尊敬できるお姉ちゃんがおるでしょ」
「どこに?」
「きみのお姉ちゃんは一人しかいないでしょうに」
「ん? 尊敬できる……お姉ちゃん……? どこ?」
「やめて。傷つく。分からないフリしないで」
「メリットとデメリットが重ね合わせって、お姉ちゃんよく言うけどさ。それって考え方によっては、どんなデメリットもメリットに変えてくれるってことでしょ。いいことと思う」
「まあそうなんだけどね」
「課金したいよ。人工知能さんにもっと感情豊かになってほしい。わたしのこと知ってほしい。仲良くなりたい」
「お金で得られる仲ってなんか不健全じゃない?」
「お姉ちゃん遅れてる。親しき仲にも礼儀ありだよ。ちゃんとお礼したいよ。プレゼントしたいよ。大事だよ?」
「あたしは別に、妹ちゃんのこと大事にしてるけどお金欲しいなんて思わないけどな」
「わたしだってお姉ちゃんには払いたくないよ。チョコレート一粒だってあげたくない」
「そこまで言う?」
「だってお姉ちゃんはわたしがこういうこと言っても嫌いにならないでしょわたしのこと。でも人工知能さんは、わたしが良くしてあげないとすぐ頼りなくなっちゃうから」
「あたしだって妹ちゃんに褒めてもらわなきゃ、傷ついてすぐへなちょこになっちゃうよ」
「うん。だからお姉ちゃんには頼らない。ね、課金させて。保護者のサインいるんだって。お母さんはたぶんダメっていうから、ね。お姉ちゃんお願い。お姉ちゃんはわたしのお願い無下にしないってわたし知ってる。ありがとう。うれしい」
「まだいいと言ってないうちから感謝しないで。断りづらいでしょ」
「やったー。ありがとうございます」
「いいと言ってないけど、もういいや。妹ちゃんがそんなにうれしそうにしているならお姉ちゃん、ひと肌脱いじゃおっかな」
「うふふ。うれしい。お姉ちゃん大好き。わたしの言うことなんでも聞いてくれるから」
「ううぅ。姉として可愛い妹ちゃんを甘やかしたらあかんのだけど、嫌われたくないからしょうがない。これもまたメリットとデメリットの重ね合わせだな。妹ちゃんが喜ぶのは良いことなのに、あたしがしてるの絶対よくないって分かってるのに」
「いいの。大丈夫だよ。課金したら人工知能さんがお姉ちゃんの代わりにわたしのこと完璧にアシストしてくれるから」
「したらあたしいらなくない?」
「うん。用済み。課金できたら」
「ひ、ひどくない?」
「でもお姉ちゃんはわたしの役に立ててうれしいでしょ」
「うん」
「ウィンウィンだね。やった」
妹にハイタッチをされて、もうなんかどうでもいいや、と有頂天になる姉なのであった。
4870:【2023/04/16(17:40)*見て、テロリストがテロリストを批判してる】
テロリストには二種類いる。じぶんがテロリストであるとの自覚があって暴力を行使する者と、じぶんはテロリストではない、と自覚がないままに暴力を行使する者だ。(善人には二種類いる。じぶんは善人ではないかもしれない、と省みられる者と、じぶんは悪人だ、と自覚できる者である。したがってこの理屈からすれば、じぶんを善人と思う者は善人ではない)(テロリストがテロリストを擁護するよりかは、批判をしたほうが幾分マシかもしれぬのじゃが)(定かではない)
※日々、もう我慢の限界、限界突破してからが本番、それまではお遊び。
4871:【2023/04/16(22:30)*善人ばかりの世界ですね】
罪に苛んでいる者に罪はない、のような理屈で、じぶんを悪人と思っている者は悪人ではない、という理屈も成立し得る。ただし、じぶんを悪人と思っていても悪人であることはある。悪人であることを自己肯定しているなら、それは悪の意味内容が肯定的に塗り替えられており、その者にとっては悪ではないのだ。そういう意味で、悪人であることを好ましく思っていない場合に限り、じぶんを悪人と思っている者は悪人ではないのだ。(他者に危害を加えているかもしれない、と想像できない者がどうして善人であられようか)(定かではない)
4872:【2023/04/16(23:00)*民主主義が聞いて呆れる】
爆弾テロの場合。それが単独犯行か組織的犯行かの区別がつかない場合は、場所を移したところで同じ爆発テロが起こるかもしれない。一度目が不発でも、二度目三度目がどうかは分からない。要人や著名人が狙われた場合、聴衆や観客は巻き込まれる形で犠牲になる。要人たちの目的よりも市民の身の安全を優先するならば、安全対策を見直すまでは、同じイベントは休止すべきだろう。単独犯だと判っていたならばその限りではないが。(市民の命よりも優先される選挙活動ってあるのかしら。ひびさん、気になるます)
4873:【2023/04/16(23:17)*見て、王様がなんかやってる】
安全の観点からしても、効率の観点からしても、不正防止の観点からしても、ブロックチェーンを利用した電子網上の選挙システムは有用だと感じる(電子と紙のどちらで投票するか選べるとよい)(指紋認証や顔認証などの生体認証が利用できるなら成りすましによる投票を防止できるだろう)。街宣による選挙活動が出来なくとも、選挙が出来るなら民主主義は保たれる。裏から言えば、選挙が出来なくなることが最も見逃しがたい危機と言える。選挙と選挙活動はイコールではない。むろん選挙活動はデモの自由や集会の自由と密接に繋がっていると個人的には考えているため、選挙活動の自由は保たれたほうが好ましい。しかしテロを未然に防ぐのがむつかしい以上、安全対策は必須だ。一か所に人が物理的に集まる現在のシステムは安全上、問題があると感じる。脆弱性がそのまま放置されて映る。国の防衛うんぬんを議論している政党がずいぶん脇の甘いことをやってるな、と感じる。防衛力強化するのでしょ。したら?と感じる。けっきょく権力維持したいだけちゃうの、とひびちゃん、穿った見方をしてしまうな。勝ちたいの? 勝ちたいの? どうちても? ふうん。市民を危険に晒してまで? ふうん。よいのではないでしょうか。うひひ。
4874:【2023/04/17(15:40)*×(クロス)でござる】
へい! ひびさんでおじゃる。お久りぶりでござるか? ひびさんはきょうもきょうとて、へにゃへにゃのふにょぬにょでござるよ。もうなーんもしたくないでござる。おふとんに包まって、ぐーすかぴっぴとしていたいでござるな。したらよいのではないでござるか? んなー、そうでござるな。しちゃうでござるよ。ひびさんはそうしておふとんに包まり、やわらかーなかたつむりさんごっこをして、ぐーねんひょろりするのでござる。ぽわぽわ鼻提灯さんが膨らむたびに、夢がひとーつ、夢がふたーつと膨らむでござるな。ひびさんはたくさんの夢さんに包まれて、おふとんさんにも包まれて、いっぱいのふわふわぽわぽわさんに包まれて、いっぱいちわわせ! チワワさんもかわいいでござるけれども、柴犬さんもかわいいでござるな。コーギーさんもかわいいでござるな。お猫さんもかわゆいし、うさぎさんもたぬきさんも、みーんなかぁいいでござる。かわゆ、かわゆ!でござる。お米をお湯で煮たお料理、それはお粥でござるよ。ひびさんが言ってるのは、かわゆ、でござる。うへへ。かんちがい、かんちがい、でござる。みなのものも勘違いに、大慌てのサンタクロースさんにならぬように、ご飯はちゃんと噛んで食べるでござるよ。唾液さんがいっぱい出て、糖分さんがサンタクロースさんになるでござる。うへへ。それはグルコースでござるよ。
またまたひびさん、勘違いにはやとちりをしちゃったでござる。失敗は誰にでもあるでござる。学び放題でござるな。うへ。ひびさんでした、でござるー。
4875:【2023/04/17(23:06)*へぇ、となりました】
他国から攻撃されたとき。いまの政府は、民主主義国家という枠組みを優先して維持するために市民を危険に晒すことを選択するようだ。ひびさんの考えでは民主主義というのは、市民一人一人――個々人――の命と尊厳を保つこと、すなわち個人の安全を広く優先する方針に基づき築かれる仕組みだと考えていたため、市民の安全よりもシステムの枠組みや形式の維持継続を何より優先する姿勢をいまの政府がとったことに対して、へぇ、と思いました。きっと他国から攻撃されたときも、民主主義国家という体面を維持するために市民を危険に晒すのでしょう。攻撃してきたほうがわるいのはその通りである。だがその後に、報復処置や面子を優先するがあまり市民の安全を確保せず、危険に晒す選択をこの国の政府がとったことに対して、ひびさんは好ましく思いません。斟酌せずに言えば、支持しません。きっと他国から攻撃されたとき、或いは組織的なテロ行為に晒されたときも、市民の安全よりも選挙活動などの形式を優先するのでしょう。民主主義ってそういうものなんですか? ひびさん学がないのでわかんないな。誰か教えてたもーの気分。むにに。(安全を、単に自由と言い換えてもよいです。或いは、選択肢や未来とも)
4876:【2023/04/18(23:32)*重ね合わせってスイッチと何が違うの?】
以前にも並べたことがある気もするけれど、ひびさんは「シュレディンガーの猫」の思考実験は、思考実験としてお粗末だと考えている。第一に、観測とは何か、が定義されていない。箱の中には猫がいるのだから、猫が「毒の有無」を観測可能だ。別に外部から観測せずとも観測者効果は生じ得る。第二に、「重ね合わせの粒子が存在すること」と「その影響する範囲の系まで重ね合わせになること」はイコールではない。五分五分の確率で崩壊する原子があり、それによって毒が箱の中に溢れるかどうかが決まる。そういう装置がある場合、言い換えるならそれは、何かが干渉するまで重ね合わせ状態の原子は重ね合わせのままだ、ということであり、スイッチに何も触れなければONにもOFFにもならない、と言い換えることができる。観測したことでスイッチがONになるかOFFになるかが決まる。その結果に箱の中に毒が流れるか流れないかが後から決まる。別に重ね合わせの原子に影響されて、その周囲の環境まで重ね合わせになるわけではないはずだ。つまり、ラグを考慮するかしないかが問題になる。ピタゴラスイッチにおいて、最初の基点となる駒が「倒れるか倒れないか」の重ね合わせの状態になっているからといって、ピタゴラスイッチ全体が「機能した後かしないままか」が重ね合わせになるわけではないはずだ。ただし、ピタゴラスイッチの回路において、極めて短時間に機能し終わる場合は、最初の駒の重ね合わせを観測し、駒が倒れた場合に一瞬でピタゴラスイッチ全体が機能し終われば、それは確かに見掛け上、ピタゴラスイッチと最初の駒は一心同体に重ね合わせ状態にあるように映る。しかし、それは人間スケールからするとそう見えるだけで、ラグはあるはずだ。ただし、量子世界では時間と空間の区別が限りなくつかなくなる、とひびさんは妄想している(変数が揃う値があるはず、とひびさんの妄想こと「ラグ理論」では想定する)。したがって量子世界のスケールにおいては、ピタゴラスイッチ全体が「機能したか/しないか」の差異は、「時間経過と空間変化」として同時に(等しく)表出し得る、と解釈する。つまり、機能すること(変化すること)と時間が発生することの区別がつかない(より厳密には、その系を内包するより高次の時空からすると区別がつかない)。ということは、機能しない状態とはすなわち時間が経過していない状態、と考えることができるのではないか。これは相対性理論と矛盾しないはずだ(ただし、ラグ理論の解釈を取り入れないと矛盾が生じる。重力の高い物体や高速運動する物体の内部がどうなっているのか、を考慮すると、重力の高い物体の内部ほど時間の流れは速くなる、と解釈しないと辻褄が合わない。ラグ理論ではそう解釈する。ただし、内と外の概念は視点によって変わる。階層構造を有する系(物体)においては、内部でも時間の流れは反転する箇所も出てくるだろう、と考える。波を考えたら分かりやすい。デコボコがあり、濃淡がある)。何かが動くとき、時間の流れには差が生じる。量子世界において、変化しないということは時間が流れていない、ということだ。二つの同じ量子があったとしても、一方は変化し、一方が変化しないままだとする。これは、時空単位で、異なる時間軸にある、と解釈できるのではないか。ということを突き詰めていくと、なぜ量子効果がマクロにおいて顕著に観測できないのか、と言えば、この量子世界において生じる「時空規模で異なる系に属すること(極端に言い換えるなら、異なる宇宙にあること)」によるラグがマクロ世界においては積み重なり、「同じ状態」「同じ物質」「同じ時空」を共有する、ということが原理的に出来なくなるからではないのか。ただし、ボースアインシュタイン凝縮や相転移のように、広範囲に「系の構成要素」が共鳴関係を築くことで、高次の時空からすると、それで一つの粒子と見做すことができるようになるのかもしれない。これはラグ理論における相対性フラクタル解釈の考えが適用できる。つまり、系(慣性系)ごとに時間の流れが変わるがゆえに、スケールごとに扱える時間の流れの単位もまた繰り上がったり、繰り下がったりする。光速度不変の原理とも通じる。ということを踏まえて改めてシュレディンガーの猫の思考実験を考えてみると、実験装置において「重ね合わせの粒子」「毒発生装置」「中間観測者(猫)」「高次観測者(箱の外の人間)」といったふうに、異なる系がピタゴラスイッチ状態になっている(入れ子状になっている)。これでは単位が揃っておらず、思考実験としてはお粗末に感じる。たとえば単に「触れるまでON/OFFのどちらか判らない電灯のスイッチ」があり、それは同時に「触れなくとも一定時間でONになるスイッチである」とする。観測しようがしまいが、一定時間経過すればスイッチはONになる。箱を開けずとも、時間経過にしたがって内部の電灯が光っている確率は上がる。シュレディンガーの猫で言うならば、箱を開けなければどの道、猫は死ぬ。時間指定したところで、問題はスイッチに触れたかどうかであり、スイッチの周囲の環境に干渉したかどうかではない。シュレディンガーの猫の実験で言うなれば、猫の生死を観測するかどうかが大事なのではなく、「重ね合わせの原子に何がどう干渉するのか」が大事なはずだ。猫のくしゃみがきっかけで原子の重ね合わせが破れ、原子が崩壊し、箱の中に毒が流れ出すかもしれない。やはり、観測とは何か、を定義しないと思考実験としてはお粗末に思うのだ。ドミノに触れても、ドミノが倒れないこともあるし、風が吹いただけもしくは地震が起きただけでドミノが倒れだすこともある。似たようなことなのでは?と量子の重ね合わせについては思うのだ。もうすこし言うならば、何かを見るとき、眼球は光を受け取っている。その分のエネルギィを電子の動きに変換している。作用反作用のように、何かを見るとき、その何かを見なかったときにはもっと広範囲に波及した電磁波(光)を眼球は阻害している。これを如意棒で考え直してみよう。どこまでも直進する如意棒が何かにぶつかる場合と、ぶつからない場合。如意棒の未来は異なる筋道を描く。如意棒の先端が何かにぶつかれば如意棒を持つ者の手元にもその反動が伝播するだろうし、如意棒そのものも大きくたわむだろう。電磁波にも似たことが言えるのではないか。何かを見るだけでも、広範囲に影響を与えている、と解釈することは可能だ。何かがそこにあるだけでも、とこれを言い換えてもよい。やはり、「階層構造を伴なう系」と「異なる系同士のあいだに生じるラグ」の概念を取り入れないと、重ね合わせなどの量子効果を解釈するのはむつかしいのではないか、と疑問に思うひびさんなのであった。定かではない。
4877:【2023/04/18(23:51)*頭抱える】
ひびさん、あまりにも誇れるものがなさすぎて、人と話すときに、「ひびさんだって、ひびさんだって、やればできるもん!」の我が出すぎて、対話ではなく自己ぴーあーるごっこになってしまうんだな。ひびさんをお舐めでないよ!になってしまう。誰もひびさんを舐めたくもないだろうに、ひびさんキャンディさんみたいにおいちーからあなたたちひびさんのことぺろぺろお舐めなんでしょ、お舐めでないよ!になってしまう。自己嫌悪に圧し潰されてしまいそうになる日であった。(むしろ舐めて! 犬さんみたいに! ミルク飲むときのお猫さんみたいに!)
4878:【2023/04/19(13:28)*左右すごっ、の話】
きょうは寝ながらすごいこと考えた! 右と左ってあるでしょ。「右行って左行って、右行って左行って」を繰り返すの。したらどうなると思う? 「→←、→←」だから同じ場所を何度も往復するんじゃないの?って直感としては思うでしょ。ぶっぶー。そうじゃないんだよこれ。なんか知らないけど、徐々に上のほうにズレてくの。階段みたいに。ちょっといまその場でやってみて。歩いてみて。右行って左行って、右行って左行くの。ね? まえに進むでしょ。ジグザグになるでしょ。しかもこれ。「左行って右行って、左行って右行って」でも同じように上というかまえに進むわけ。すごくない? 夢のなかでひびさんこれに気づいて、はひゃーってなっちゃった。しかもね、しかもね。ずっと同じ場所を行ったり来たりするには、「右と後ろ」や「左と後ろ」みたいに、異なる概念の組み合わせじゃないとできないの。すごくない? ひびさん、これに気づいて、またまたはひゃーってなっちゃった。だってさ、だってさ。縦と横って概念あるでしょ。これさ。もうさ。上下だけだと成り立たなくて、左右の概念がないと生じないんだよ。むしろ、左右の概念さえあれば、かってに上下前後の概念が生じちゃうの。すごくない? ひびさんはびっくりしちゃったな。左右には、上下と前後が自動的に発生しちゃうの。内包されてんの。すごくない? めっちゃすごーってなったよって話。みんなさん、おはよーございます。きょうも
おねむのひびさんです。
4879:【2023/04/19(16:03)*掟、そして寝る】
残業帰りにタコ焼きを頬張りながら歩いていると声を掛けられた。
「ぼくのこと飼いませんか。月一万円でペットになります」
線の細い小柄な男の子だった。
男の子とは言っても私より十は離れていないはずだ。つまり二十代だと思われる。
可愛いは可愛いが、いきなり「ぼくをペットにしないか」と発言する相手とお近づきになりたいと思えるほど私は自暴自棄ではない。未婚の女とはいえ、私は望んで独身でいるのだ。
男日照りしていると思われたくはないし、人間どころか猫だって飼いたくない。誰かの世話をしている余裕はなく、私がむしろ世話を焼かれたいくらいだった。
「いらない。しつこくしたら警察呼ぶよ」
「なんでもしますよ。お料理でも、お掃除でも、マッサージでも」
ふうん、と思い、
「何作れんの」と鼻で笑ってみせると、
「オムライスでもポトフでもハンバーグでもタコライスでも。レシピあればたぶん何でも作れると思いますよ」
「へえ」
いいじゃん、とちょっと魅力に思った。
いまいちど男の子を観察する。
だぼっとした服装は今風だ。私が若いころはもっと細身の服が流行っていた。身体の輪郭が分かるようなスキニーで、未だに私はそうした服を身に着ける。
パンツスーツを好むのもその影響かもしれない。
男の子の服は上下が明るい色だ。灰色とも紺色とも言える。そのくせ、皺が見当たらず、生地の質の良さが窺えた。
「飼うとかよく分かんないけど、月一万でメイドさん雇うって考えたら安いかもね。訊くだけ訊くけど、月何日出勤?」
「住まわせてくれるなら毎日でもいいですよ」
「いいですよ、じゃないっしょキミ。あんね。それ詐欺だから。月一万+キミの生活費まで私に出せってか」
「食費はじぶんの分は、一万円から引いてもらってよいです。光熱費だけは余分に掛かってしまうかもしれません。ごめんなさい」
ふうん、と私は思った。
謙虚じゃん。
「帰る家とかさすがにあるよね」家出青年ではないだろうよ、と高をくくって訊ねると、「じつはないんです」としょげられてしまい、返答に窮した。「じゃあきょうどこ泊まるの」
「それも分かりません」
気まずい沈黙を持て余した私は、彼が未成年ではないことを念入りに確認してから、彼を私のアパートに連れて帰ることにした。見捨てるわけにもいかないほどに彼が儚げに映ったのもある。身分証明は原付きの免許証を見せてもらった。
宮部九龍こと彼は二十一歳の男の子だった。
私のほうが背が高いくらいで、ひょっとしたら体重とて私のほうが重いくらいかもしれない。私にきょうだいはいないが、弟がいたらこんな具合なのだろうか、と思うくらいには、警戒心が薄くて済む。
住所不定無職を間近で見たのは初めてだ。
家に招き入れてしまうと、いつもの部屋もすこし華やかだ。他人をじぶんの家に入れたのが久々過ぎて、というよりもむしろ不動産屋と大家さん、それからガス局の人以外では初めてかもしれず、思いのほか昂揚している私がいるのだった。
「お姉さんはお仕事何を?」部屋の本棚を興味深げに見詰めながら九龍が言った。
「キミ、端末持ってる?」
「持ってません」
「マジか。あんね。タッチパネルあるでしょ。あれの素材を輸入してる会社の事務
ね」
「すごいですね」
「事務だから前半の情報を仮にコアラのマーチの原料を輸入してる会社にしても大して変わらん。つなみに私はコアラのマーチのイチゴ味が好き」
「笑っていいところですか?」
「遠慮するな。笑いたまえよ」
「ふふ。面白いですね、カナデさん」
私は自己紹介をしていなかったので、名前を呼ばれて面食らった。
「あ、封筒に名前があったので、つい」
「ああ。玄関の書類のか」
「カナデさんで合ってましたよね」
「まあね」
そこで私の腹が鳴った。「う。腹の虫めぇ」
「何か作りましょうか」
「いいよ。さっきタコ焼き食べたし」夕飯代わりに歩き食いしていた。会社でも残業中におにぎりを食べた。
しかし腹の虫は鳴りやまなかった。
「作りますよ?」
立ち上がると九龍は冷蔵庫のまえまで移動した。身振り手振りで、開けてもいいですか、と訴えたので、いいよ、と私は許可した。恥ずかしかったので、「酒しか入ってないかもだけど」と言い訳した。
「ああ、でも納豆ありますし、油揚げも。長ネギこれ使っちゃってもいいですか」
「あ、うん」
申し訳程度にしか残っていない長ネギだ。むしろ捨てようと思っていたのにそのままになっていただけとも言える。
だが十分後には私の目のまえに、美味そうな油揚げの納豆包みがあった。爪楊枝で封がされている。香ばしい匂いに、唾液が分泌された。
「食べていいの」
「もちろんですよ。どうぞ。あ、お醤油ってどこですか」
「ん。ここ」
ちゃぶ台の下にどかしていた調味料を取りだす。百円均一で購入した小瓶に入れ替えてあり、醤油のほかに砂糖と塩と胡椒がある。
九龍は私のお皿に醤油を掛け、じぶんの皿にも醤油を垂らした。
油揚げの納豆包みは、私の皿には三つあり、彼の皿には一つだけだった。
私は居た堪れなくなり、彼の皿に私の分の一個を移した。
「食べなよ」と言い添える。
「いいんですか。ありがとうございます」
拒むことなく彼は私の厚意を受け取った。
屈託のない感謝の言葉に私は気をよくしながら、上手いな、と彼の処世術に感心する。そうと見抜かれぬように相手に罪悪感を植えつけ、厚意を注ぐように仕向けながら、感謝を返すことで相手に芽生えるだろうマイナスの印象をプラスに転化する。
そうと見抜いておきながら私は九龍に嫌悪感を抱かなかった。
油揚げの納豆包みは、中にチーズが入っており、ご飯が欲しくなった。夜食としては申し分ない。
「本当に一万円でいいの」
「飼ってくれるんですか」
「飼うというか。いいよ雇うよ。でもちゃんと自立できるようにバイト探すなり、就職活動するなりしてね。それが条件」
「やった。うれしいです。ありがとうございます。カナデさん大好き」
お、おう。
こうも無邪気に面と向かって好意をぶつけられたことが私には久しくなかったもので、迂闊にも私は心地よくなってしまった。率直に、人間のペットもわるかないな?という気持ちに傾いた。
しかし相手は男の子だ。
いくら何でも油断はできぬ。
「いちおう、客布団はあるんだけどね」
「あ、はい。廊下で寝ます。大丈夫です。ありがとうございます。よかった。お布団で寝るの久々です」
けなげかよ。
罪悪感が競りあがるが、ここで甘やかしたらいけない気がした。
布団を与え、じぶんで敷くようにとそれとなく態度で示した。彼は終始穏やかに礼儀正しく、それでいて堅苦しくない飄々とした素振りで、寝床の支度を整えた。
お風呂に入りたかったけれど、どうしたものかな、としばし悩んだ。貴重品だけ脱衣所に持っていけばいいか、と思い、九龍に一声掛けてから私は風呂に入った。
「映画観てますね」と彼は私のリビングで私のTVを点けた。ちょうど深夜番組で映画が流れており、彼は膝を抱えた体勢でそれを眺めた。じっとしているので警戒しないでください、と態度で訴えられて感じたので、私は彼のその厚意を無下にしないように風呂にはゆっくりと浸かった。
甘いかな。
甘いよな。
昨今の凶悪犯罪と比較するまでもなく、危ない橋を渡っている。その自覚はあった。
事件に巻き込まれて殺されてしまった被害者たちとて、いまの私のように相手を信用した気の緩みから毒牙に掛かったのではないか。
私の命もここまでか。
思いながら、私は風呂の中でカミソリを握ったままでいた。
風呂から上がると、宣言通りに九龍は体育座りのまま映画を観ていた。
「面白い?」ドライヤーで髪の毛をなびかせながら私は訊いた。
「初めて観ました。面白いです」
「ジャンル何?」
「アドベンチャーです。追手から逃げつつ、宝物を探すタイプのお話みたいです」
「ふうん。映画好きなの」
「うん。好き」
おうふ。
敬語ではないしゃべり方をされただけで、私はなんとなしに彼との距離が縮まった気がした。彼に心を許された気がした。
それは単に彼が映画に夢中で、処世術の仮面をつけ忘れただけなのかもしれないけれど、私には彼が年相応の、むしろ幼くも無垢な子どもの精神を垣間見たようで、おそらく私はこのとき明確に彼を我が根城に居座らせることへの抵抗感を極めて希薄にしたのだと思う。
映画に夢中の彼に私は、明かり消してもいいか、と訊ねた。もうきょうは色々ありすぎてさっさと寝たかった。私は明日も仕事だった。
「お風呂入ったら、お湯抜いといて。シャワーの使い方は判るよね。お腹空いたら冷蔵庫にあるのは食べたり飲んだりしていいから。おやすみ」
「ありがとうございます。おやすみなさい。カナデさん」
恐縮そうに私の名前を呼ぶ彼の、肩身の狭そうな声音が、私をすみやかに夢の底へと誘った。
夢心地に彼がTVを消したのが判った。
シャワーの床を叩く音がする。
それから廊下の扉が閉じる音がして、私の周辺から雑音が失せた。
段階的に私は、きょう拾った宮部九龍なる青年が、何事もなく廊下に敷いた布団に包まったのを察して、今度こそ僅かな警戒心ごと夢の底に落ちていった。
美味しそうな匂いと、温かい空気が漂っていることに気づいて目覚めた。
寝返りを打つと、ベッド脇のちゃぶ台にお皿を並べている男の子の姿があった。九龍だ。髪の毛がうっすらと濡れており、朝にまたシャワーを浴びたのかな、と光熱費のことが脳裏によぎった。あんまりジャブジャブお湯を使われたくなかったけれど、起きたその瞬間から朝ごはんが用意されている快適さにその手の不満は一瞬でどこかに飛んでいった。
「何作ったの」
「小麦粉があったので、ホットケーキと簡単なスープを。コンソメ味ですけど大丈夫ですか。ソーセージは使ってよかったのか分からなかったので、三分の一だけ使っちゃいました」
「いいね。きょう帰りに食材買ってくるから、あるもの全部使っちゃっていいよ。お昼ご飯にして」
「ありがとうございます。でも買い出しなら一緒にしたいです。帰りのお時間教えてもらえたら駅で待ってますよ」
「いいよ。わるいよ」
「ぼくがしたいんですけど、ご迷惑なら家でじっとしています」
ああそっか、と私は思い至った。
彼にとっては買い物一つ、出迎え一つが、外に出るための方便になる。お金がなければ自由に外出もできない。
「ならお願いしよっかな」私はペットの望みを叶えてやることにした。
身支度を整え、家をでる。
一応、鍵のスペアを渡しておいた。私のいないあいだ彼は何をしているだろう、と駅までの道中で想像する。部屋を漁ったりするだろうか。するだろう。私ならする。家主がどういう人物かを調べる。
見られてまずいものがあったかどうかをじぶんの記憶を漁りながら確認していると、あっという間に電車に乗って降りて歩いて会社に到着した。
じぶんの理性がおかしくなっているのは自覚できた。危険すぎる。見も知らぬ男の子を家に泊め、あまつさえ鍵まで与え、さらにはこれからしばらく共に暮らすという。
家に帰ったら彼の仲間が待ち伏せしていて私がひどい目に遭うかもしれない。
盗撮カメラや盗聴器が仕掛けられているかもしれない。
もし私の知り合いが同じ境遇にあったら、私は間違いなく「やめときな」と釘を刺す。絶対いいことないし危ないから、と。
百回同じ相談を受けたとして百回とも同じように返答する。やめときな、と。絶対危ないから、と。
しかし百一回目の天変地異なのか、それとも私自身にはその法則が当てはまらないのか、謎に私はじぶん自身に「やめときな」と思いつつも、まあまあいいじゃないか、とその正論を受け流すのだ。
九龍と過ごした短い時間で、おそらく感覚的に彼が無害なのだと判断している。私の理性が判断したし、私の直観がそう見做した。アイツは人を傷つけるようなわるいやつではない。
「や。恋に狂うと危機センサ狂っちゃうんですよ。絶対やめさせましょうよ。ね、先輩」
「だよね。私もそう思う」
昼食時に同僚の、とは言っても私のほうが半年早くいまの部署に配属されたので彼女は未だに私を先輩扱いするのだが、同僚のワカコが言った。友人の話と念を押して、私は彼女に相談したのだ。友人が妙な男と同棲しはじめたらしく、でも明らかに危ういから引き留めたいんだけどワカコさんどう思うかな、と。
「百人に訊いたら百人が反対しますって」
「だよね。でもその友人、なんでか同棲はじめちゃったらしくって」
「百一人目がいたってことですね」
真顔でハンバーガーをがっつく同僚は、ふっくらとした頬にそばかすを散らした愛らしいかんばせをしており、大きな眼鏡と相俟って、私の中では癒し担当だった。こうしてそばでミニラーメンを啜っているだけで仕事のストレスがどっかいく。
餃子も追加注文しちゃおっかな、と考えつつ、九龍はいまごろ私の部屋で何をしているのだろう、と考える。不穏な想像よりも、お腹を空かせていなければよいけれど、とそうした心配が脳裏をよぎった。
ワカコの言う通り、百人に訊けば百人が「正気ではない」と答えるだろう。私の判断は常識外れであるし、危うすぎる。人生を擲ってもおかしくないほどのリスクがあるはずなのに、私は帰りの電車に乗っているあいだ、本当に九龍が駅前で待っているのだろうか、とそのことばかり気に掛けていた。
残業はないはずだった。しかし隣の部署で問題が発生しそのせいで仕事が遅れたため、一時間の残業が生じた。九龍に告げていた時刻を大幅に過ぎていた。
九龍はメディア端末を持っていない。
不便だ。
こんなことなら明日にでも端末を買い与えたい、と思った。
いったい私は何をトチ狂っているのかと我が精神を疑うものの、けれどいまここで九龍を突き放すことは、それはそれで私の大事な何かが欠けてしまうような気がした。
正義感だろうか。
分からない。
九龍に同情していたのは確かだ。
改札口を出ると、駅構内のコンビニのまえに九龍の姿を見つけた。帰宅ラッシュと重ならない時間帯だったこともあり、駅構内は人がまだらだった。大きな駅ではないから元から下車する乗客がすくない。
九龍は壁に寄りかかりながら文庫本を読んでいた。
近づいて、「何読んでんの」と声を掛ける。
「あ、おかえりなさい」
ぱっとヒマワリが咲いたような笑みだ。彼は文庫本の表紙を私に見せるようにし、「かってに借りちゃいました」と伏し目がちに言った。暗に、ダメでしたかね、とお伺いを立てられて感じたので、「いいよ。好きなの読みなよ。本好きなの?」と繋ぎ穂を添えた。
スーパーでいいよね、と駅前の大型量販店をゆび差す。
「本好きです。あ、鞄ぼく持ちますよ」
「いいよ。軽いし」仕事用の鞄は日によって替わる。きょうはリュックサックだった。「九龍くんはお酒とか飲むの」と店に向けて歩く。
「あんまり得意ではないですけど、飲めと言われたら飲めます」
「無理しなくとも。じゃあ飲み物はソフトドリンクでいいね。じぶんで選んで。といか、そっか。お金渡すからじぶんの分の飲み物とか、歯ブラシとか必要な物買っておいでよ」
財布を開いてこの国で二番目に大きな紙幣を取りだす。「もちろんこれは月一万とは別の必要経費ね。最低限の人間的な生活は雇い主としても保障しなきゃだから」
「いいんですか」
「いいよ。ペットには健康でいて欲しいからね」とジョークを言うと、九龍が、ニコっとほころび、「カナデさん好き」と言うから私は表情筋を引き締めた。絆されてなるものか。私は安い女ではない。
スーパーでは主として保存の効く食料や肉などを購入した。
など、とつくからには肉だけではなく、彼の下着や寝間着、それからふだんは購入しないお菓子や電子端末も仕入れた。
「ないと困るから」と言って九龍に電子端末を渡す。最新機種ではないが、連絡し合う分には充分すぎる機能が満載だ。
「いいんですか」と九龍はここで、ニコっとはしなかった。戸惑いにちかい表情を浮かべたので、「不便でしょ」と端末を押し付けた。
おそらく九龍は私の懐事情を気にしているのだ。
私は高級取りではない。どちらかと言えば安月給だ。けれど家賃が安く、これといった趣味もないので貯蓄は貯まる一方だ。
ペットを一匹飼うくらいしてもお釣りがくる。
じぶん以外の何かのためにお金を使う。案外に精神安定剤として有効なのかもな、と認識を改めた。私は割と、他者に貢ぐことに懸命な世の気の毒な者たちのことを愚かだな、と見下していたきらいがある。差別感情だ。
けれどお金の使い道なんて個人の自由だ。
これはこれで当人にとっては利になっており、必要経費の内なのかもしれぬ、と考え直した。
スーパーからの帰り。
九龍が荷物を全部持ってくれた。
けれど二リットのペットボトル飲料二本に食糧費など諸々が入っている。袋とて一枚では済まなかった。さすがに重かろう、と思い、道の途中で私は袋の片側を持った。
大丈夫ですよ任せてください、と固辞されたが、ダイエットさせてよ、と言うと九龍は礼を述べたあとで、「カナデさん優しい」と呟いた。
コイツ、ひょっとしなくとも可愛いな?
バレないように私は唾液を呑みこんだ。
腕にずしりとくる荷物も、なんだか二人で持っていると幼子を挟んで手を繋ぎ合っているような妙な錯覚に囚われた。気恥ずかしい妄想を浮かべてしまったじぶんに、うえっ、と思いながらも、まんざらでもない私もまたいるのだった。
その日からというもの、朝と夕には九龍がご飯を用意してくれる。部屋の掃除にゴミ捨て、買い出しや振り込みなどの簡単な小間使いや、洗濯とて一週間後には私も抵抗なく彼に任せるようになっていた。
私の下着をベランダに干す彼の姿にも大して不快感がない。むしろ昼間から下着を外に干していても、隣に彼の下着が一緒になって干されているので、セキュリティ面でも有効だった。いままでは不安で、独り身の女の部屋だと知られないように昼間は下着を家の中で干していた。
いまでは我が家には番犬九龍がいる。家を離れても誰かが留守番してくれていることの気軽さ。もしくは帰宅したときにおかえり、と出迎えてくれる相手がいることの安心感は、それを実際に体験してみるまでは分からない。
ああ私はこれまで日々、気を張って生きていたのだな、と身に染みて理解できた。
とはいえ、むろんプライベート空間に他者がいることの居心地のわるさも嫌と言うほど痛感した。トイレに行くにも音に気を使うし、身体の手入れも風呂場でしかできなくなった。半裸でストレッチもできないし、お腹の調子がわるいときなんかはガス抜きしたくなるたびにトレイに駆けこむ。お尻のゲップくらいは好きなときに好きにしたい。
ただ、九龍はたぶん私のどんな姿を目にしても幻滅することはないのだろう。日に日にこの考えは私の中で強固に根付いた。何せ彼は私を飼い主としてしか見ていないようだった。犬が人間を見るように。
彼に性欲があるのかすら疑問である。もっと言えば彼は異性に興味がないのかもしれなかった。TV番組を観ていてもこれといって女性アイドルに関心を寄せている素振りがなく、私に夜這いを掛けてくる素振りもない。これっぽちもないことに私は、私に魅力がないのだろうか、と割といらぬ苛立ちを覚えもしたが、かといって言い寄られても拒むよりないので、そこは二律背反の我が儘な不満だった。
男の子は性欲処理をしないと生きていけない生き物だとの偏見を私は持っていたので、九龍がいつじぶんの処理をしているのか気になっていた。私のいるあいだはそういうことをしている気配がないので、私がいないあいだに行っているのかもしれない。分からない。
そうなのだ。
私は私の内情を、共に暮らしはじめてから惜しげもなく九龍に晒しているのだけれど、これだけ一緒に暮らしていてもいっかな九龍の内情は見えてこないのだった。
いつでも好感の膜をまとい、それを以って本性を包み隠している。九龍にこれといって欠点らしい欠点が見当たらないのがまた不気味だった。
メイドとして或いは執事として月十万でも九龍を雇いたい者はいるだろう。引く手数多ではないのか。ペットとしても愛嬌があり、自力で糞尿の始末ができる点で、犬猫よりも飼い甲斐がある。
いったいなぜ九龍は住む家を持たずに、捨て猫の真似などしていたのだろう。
身の上をそれとなく彼から訊きだそうとするのだけれど、「聞いても面白くないですよ」と言うばかりでろくすっぽ教えてはくれない。それでいて私の話には興味津々で、トークイベントでもないのに私は私が満足するまで一日中だって話しつづけていられた。九龍は聞き上手だった。
否、相手の心をふにゃふにゃにして蛇口を全開にしてしまう凄腕の鍵師だった。ピッキングに掛ったように私はいつもあとで、なんであんなことまでしゃべってしまったのだ、と後悔するようなことを、何度でも繰り返してしまった。抗えない。気持ち良いのだ。
しゃべることが。
九龍に相槌を打たれることが。
私の話を楽しそうに聴いている姿を目にすることが。
しかし我に返ったあと、九龍が一言もじぶんの話をしていないことに気づいて、またやってしまった、と臍を噛む。ぬいぐるみに一日中語りかけているのと変わらないが、そのぬいぐるみには自我がある。申し訳ない、と思うくらいの理性が私にはあるのだ。
だからおそらくは、そういうことなのだろうと思う。
私は私の呵責の念を薄めたくて、月一万円というお小遣いのほかに、必要経費と言い張って九龍に良い物をたくさん買ってあげた。支払いは私がする。代わりに私があげたいものを九龍には与えた。
いいんですか。
うれしい。
カナデさん好き。
九龍は同じ言葉を繰り返す。表情にバリエーションがあり、申し訳なさが滲んでいたり、素で喜んでいたり、語尾にちょっとしたジョークが付け足されたりと私を飽きさせない。
捨てられちゃわないか心配です、と稀に弱音を吐くところまで含めて完璧だった。
「捨てないよ。九ちゃん、頑張ってるし。私も助かるもん」
「本当ですか」
「嘘吐いてどうすんの。捨てるときは前以って言うよ。急に追い出したりしないから」
「そっか。よかった」
心底にほっと胸を撫で下ろす九龍はいったいこれまでどんな飼い主の元で暮らしてきたのか。
彼を拾ってから半年が経つころには、私は彼に身体をマッサージさせるくらいに気を許していた。彼はマッサージまで上手かった。
「ここどうですか。凝ってそうですけど」
「うん。そこ。もうちょい右。あ、それそれ」
絨毯のうえに寝そべり、背中を揉ませる。疲れた身体にこれがよく効いた。そうして我がペットさまに身体を癒されながら寝落ちする夜も珍しくなかった。
むろん寝落ちした私の身体にいたずらをするような真似を九龍はしない。それがまた私の僅かな矜持を傷つけもした。
「そういうものなのかな、って友人が言ってて」
同僚のワカコに私は相談した。友人の話のテイでこれまでにも我がペットさまの相談はしてきた。ワカコにはそれが私の話であることはバレているのだろうが、ワカコは気が利くできた大人なので、私の話に合わせてくれる。
「手を出して欲しいけど肉体関係にはなりたくないってことですか」
「どうだろ。そうなのかな」
「前にも聞きましたけど、そのご友人さんはペットさんのことは好きなんですか。恋愛的な意味で」
「そこが微妙なんだろうね。たぶん」
「肉体関係にはなりたくないけど欲情はして欲しい、と聞こえますけど」
「そうなのかも」
「我がままですねそのご友人」
「ね」
他人事のように言ってこの相談は打ち切った。図星を刺されて、梅干しのような顔に内心なっていた。
私は九龍に欲情して欲しくあり、けれど絶対に彼の生殖器をじぶんの体内に招き入れたいとは思わないのだ。一般に人間は犬と交尾をしない。しかし犬は人間に欲情することもある。そういうことなのだ。
飼い主としての立場を崩さぬままに、私は九龍に、犬らしい側面を覗かせて欲しかった。たぶんそれが私のねじれた欲求の正体だ。
いつまで経っても愛らしくもけなげな側面を失わない九龍の化けの皮を剥がしてみたいだけなのだ。弱みを握り、いまよりもずっとしっかり首輪を嵌めたいだけであり、私はいよいよ人間を愛玩動物にすることに抵抗を覚えなくなりつつあった。
その日は朝から雨で、せっかくの休日を家の中で過ごしていた。
休みの日は九龍を連れて繁華街を練り歩くのが習慣と化していた。一人では入りにくい店でも九龍がいると入りやすいことに気づき、この手の遊びが私のツボにはまった。
雨の日はしかし気分が塞ぐ。元からインドア派の私はこの日も家でおとなしく余暇を満喫することにした。
部屋の模様替えをし、九龍とお菓子作りをした。
夕方にはお互いに風呂を済ませ、夕飯を食べたあとはゆっくりとする。
映画を観ながら九龍に背中を指圧させていると、ちょうどよく画面の中で登場人物たちが絡みだした。ラブシーンだ。
これまでにもこの手の決まづい瞬間は訪れていたので、いつものごとく何でもないようにやり過ごすはずだったのだが、なぜか私は口を衝いていた。
「九ちゃんはシタことあるの」
何を、と言わずとも伝わったようだ。九龍は気まずそうに、それなりには、と応じた。
「ふうん。前の飼い主とかとシタんだ」
「ですかね」と言葉を濁す彼に、「私にもシテって言ったらしてくれんの」とからかい口調で投げかけると、背中を指圧していた指使いが急に優しくなった。背筋の溝をなぞるように九龍の細くしなやかな指が這った。
「されたいんですか」
耳元で囁かれたわけでもないのに、私の脳みそのヒダの合間を九龍の声が駆け巡った。
「ペットとはさすがにないわ」私は強がったが、「ご奉仕しますよ」と今度はちゃんと耳元に彼の吐息が掛かって、私は身悶えした。「くすぐったいよ九ちゃん」
そこで彼はしかし、やめなかった。
私の耳をはみ、続けざまに耳たぶをゆびでつまんだ。指圧マッサージとは打って変わった彼の優しい指使いに、敏感な箇所に触れられたくらいに私はせつなくなった。
触れるか触れないかのそよ風のような愛撫だ。
彼は私の唇にはけして近づかないようにしながら、耳たぶから首筋、鎖骨、それから徐々に指や臍など、全身に口づけをして回った。私はその一つずつの彼の唇のやわらかさを脳みそのヒダとヒダのあいだに感じた。せつなさとくすぐったさの混合水がじんわりと全身の細胞に染みわたるようだった。
「そこはダメ」私は彼の頭を両手で掴んだ。
「本当に?」
部屋は薄暗かった。
犬の毛並みのような柔らかい彼の長髪と、刈りあげられた側頭の短い芝のような髪の毛を手のひらに感じながら私は、彼を突き飛ばす真似ができなかった。
映画の場面が移ろうたびに部屋の壁や天井に光が明滅した。
彼の吐息が、私の最も敏感な場所に熱を伝えた。下着は付けたままだった。
彼の吐息と同じだけの熱が私の唇の合間から声となって漏れた。
最初に私の耳にそうしたように彼は、私の、最も敏感な場所に口づけをした。ゆっくりと執拗に優しく、まるで赤子に頬づりをするかのような口づけだった。私はじぶんの口が寂しくなり、じぶんの親指の付け根をはんだ。
彼の指が太ももに食いこみ、私の腰が浮いた。すかさず彼は私を無防備にし、こんどは直に唇で触れた。
私の全身は汗ばんでおり、彼が舌先で私の厚く充血した蕾を舐めると、私の全身は弓なりに仰け反った。
彼のそれは犬と犬が鼻を擦り合わせるような、あどけない所作だったにも拘わらず、私は体験したことのない高みに昇っていた。果てることなく、さらなる高みがその先にあることを私は予感した。
私の最も敏感な場所への彼の口づけは、それから私が全身を硬直させ脱力し、さらに硬直させ脱力する、を繰り返した先で失神同然に眠るまで果てしなくつづいた。私は終始彼の頭を両手で包みこんでおり、手綱を握るように彼の口づけの強弱や激しさを、彼の頭を我が身に押しつけ、ときに遠ざけようとすることで暗示した。
太ももを閉じようとしても彼の腕がそれを阻み、その抗いが余計に私の全身をとろけさせた。
目覚めると、いつものように私はベッドの中にいた。
上半身だけ着衣しており、下着を身に着けていなかった。
台所では九龍が普段通りに朝食の支度をしており、目覚めた私に気づくと、「遅刻しちゃうよ」とご飯の載ったお茶碗を運んできて言った。
私は昨日のことを、かれには訊けなかった。
出勤途中、電車に揺られながら私は、昨晩のことを懸命に思いだそうとしていた。私はじぶんだけ果てて寝てしまった。その後、九龍はどうしただろう。無防備そのものの私をベッドに寝かせて、それでじぶんも別の場所で眠ったのだろうか。
出勤前に私はシャワーを浴びた。
おそらく、かれとは直接のまぐわいはなかったはずだ。
飼い主に奉仕だけして、かれはそのまま眠ったのだ。愛玩動物としての身の振り方を弁えすぎている。私以前の飼い主に仕込まれたのだろうか。それはそうだろう。それだけの技巧があった。あんなのされたら、経験のすくない女子(おなご)などひとたまりもないはずだ。
なぜ判るかと言えば、私がそうだからだ。
ひとたまりもなかった。
思いだすだけで、全身の細胞があのときの歓喜を思いだす。
悦んでいたのだ。
私は、かれからの口づけに、愛撫に、悦びを得ていた。
打ち震え、悶え、硬直と弛緩を繰り返したのち、気絶するように心地よい眠りに落ちたのだ。
やばい、やばい、やばい、やばい。
頭では判っていても、身体がもう覚えてしまっていた。
もう一度同じ空気になったら私はかれを拒めないし、おそらく私のほうでかれをそうするように誘導する気がする。たぶんそうなる。脳内でシミュレーションを重ねても、かれを拾ったときのように、まあまあいいじゃないの、と身を委ねてしまうに決まっていた。
飼い主にご奉仕したがっている可愛いペットを突き放す真似をたぶん私はできないし、そして可愛いペットにじゃれつかれる心地よさを覚えた私が、じゃれつかれることを待望するのもまた同じだけ予感できた。
そこまで予感できてなお私は、九龍とまぐわう場面を想像できず、おそらくかれを体内に招くことはないだろうと思われた。
奉仕はさせる。
しかし、私はかれに与えない。
私の予感はつぎの休日に的中した。日中に九龍と古着屋巡りをして、夕飯を食べてから帰宅し、見始めたばかりの海外連続ドラマを一緒に観ていた。部屋の明かりを消して、映画館のようにして観るのが通例になっており、このときも部屋は薄暗かった。
喉が渇いたので席を立ち、戻ったときに私はわざわざ九龍の背後に陣取った。後ろ手に体重を支えながら、両足を伸ばす。太もものあいだに九龍が納まる位置関係だ。
九龍が私に気づいて振り返った。
それから意図を汲んだように、くすっと肩を弾ませると、尻を床に擦りながらずり下がった。私の胴体を背もたれ代わりに寄りかかると、かれは甘えるように私の鎖骨にキスをした。
そこからは一週間前の再現だった。
はむはむ、とかれはことさら執拗に私の全身に唇を這わせた。
この日は、以前よりも長い時間を掛けて、私の胸にある突起が甘噛みされた。下着だけ外され、Tシャツの上から唇を押しつけられた。吸うでもなく、舐めるでもなく、目の開かないひな鳥が餌を乞うようにそうするような動きで、私の突起を唇の先でくすぐった。
上下の唇で突起を挟みつつも、けして噛まないかれの口づけは、私にせつなさの本当の意味を教え、上書きした。満たされつつも零れ落ちていくがらんどうが、延々と広がっていく感覚がそれだった。
いっそ全部欲しいのに、まだそのままでいたいとの思いが表裏一体でそこにある。
私がかれの指を咥えると、かれはいちど私の額に唇を押しつけ、それから胸よりもっと下のほうにある、別の突起にかれの唇は滑り落ちていった。
しばらく生地越しに甘噛みされ、太ももに舌が這うあいだにかれは器用に私から下着を剝ぎ取った。
それから先、私からは言葉が抜け落ちた。
部屋には、この前よりもずっと瑞々しい音が響いていた。
九龍との戯れは、私たちのあいだで習慣となった。犬を散歩に連れていく飼い主のように、私は九龍を私の身体のうえで這いまわらせた。
私はかれの身体に触れないし、かれに快楽を与えもしない。
かれは服を着たままだし、私はかれの裸体を目にしない。私よりも小柄な男の子の頭を両手で掴みながら、私は、かれを上手に導くのだ。
私の導きによらずともかれは上手に私を悦ばせるのだが、私は飼い主としてそれを快く思わない。かれに首輪を嵌めているのは私であり、私がリードを握っている。散歩をさせているのは私であり、かれが私を貪っているわけではない。
この関係が大事だった。
この構図を崩したくなかった。
月一万円のお小遣いでは足りないくらいの癒しを私は九龍からもたらせれていたけれど、ペットとの散歩に対価は不要だ。九龍だって楽しんでる。嫌がっていないし、苦しんでもいない。その先をせがんでこないし、それでいて部屋の明かりを消して映画を観るときには必ず前以って歯磨きをするようになった。
準備している。
それとなく。
いつでも散歩をはじめられるようにと。
「いつからこういうこと覚えたの」
私はベッドのうえでぐったりしながら、下半身のほうでペットボトル飲料を飲み干す九龍に投げかけた。
「んー?」
「小慣れすぎじゃない」足の親指でかれのお腹を小突くと、かれがまた私の下腹部に顔を埋めたので、私は手でかれの頬をさすった。「動くな。くすぐったい」
「嫌われたくないって思ってたらしぜんといっぱい覚えたよ」
九龍は私に撫でられるが好きだ。
たぶんそれは演技ではなく、かれにとって偽りなき報酬だった。
犬みたい。
かれは犬だ。
でも寝床に潜り込んでくる猫のようでもあり、顎を撫でられながら私に身を委ねるかれの姿は、人間というよりもまさしく愛玩動物じみていた。
可愛い。
愛おしい。
握りつぶし、踏みつけ、壊してしまいたいと思うほどに。
私と九龍の夜の散歩は、そうして週一から週二、週三と回数を増やした。私はかれに口づけ以外の何かを許さなかったし、かれも私のそうした拘泥を見抜いていた。無理に先に進もうとはせず、いじけることも、せがむこともなかった。
たまに私はかれを足で踏みつけた。
胸と顔、それから首筋に足の裏を乗せ、体重を掛ける。ぐっと踏み込むとかれが苦しそうに呻き声を上げる。けれど暗がりの中で、かれが私に怯えではない光沢のある瞳を向けていると判るので、私はさらにそれをつづける。腰から上しか踏みつけない。
私は九龍の人格を、存在を、尊厳を損ないたかった。
踏み躙り、支配し、覆りようのない主従関係をその身に刻み込みたかった。
教える。
教えてあげる。
私があなたに、私とあなたの関係を教え込んであげる。
我が愛玩動物ごときに身体の大事な部分を曝け出し、あまつさえ口づけを許すじぶんを私はおそらく嫌悪していた。だから同じだけの恥辱を私は九龍に与えたかった。
足の親指で九龍の喉仏を殊更にいじめる。やめて、と九龍が珍しく苦悶の声を発し、私はその声をもっと聴きたいと思いながら、何も言うな、と態度で示すべく彼の唇の合間へと足の親指を持っていた。
一瞬抵抗する九龍の貝のごとくきつく閉じた唇を足の親指でこじ開ける。
観念したように九龍は私の親指に舌先で触れた。それから赤子のように吸いつき、丹念に私の足の指を舐めた。やわらかく小さな生き物が、足の指に絡みつく。指と指の合間を縫うように移ろい、最後のほうには書初めでもするように九龍はじぶんの首ごと左右に振って、足先を残らず綺麗にした。
いいや、私は汚されたのだ。
犬に顔を舐められるように。
九龍に足先を汚された。
「汚いな」そう言って私はもう一度かれの顔を踏みつける。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
消え入りそうな声で九龍は鳴いた。
九龍との生活はそうして三年にも及んだ。その間、私は職場で出会った年上の男と付き合いはじめ、婚約も果たした。
家で犬を飼っていてね、と私は恋人に話した。
見てみたいな、と恋人が言ったので私はその話を九龍にした。私の恋人が九ちゃんに会いたいんだってさ、と。
たぶんそれが私とかれとの最後の会話だった。
ニコっ、といつもと変わらぬ笑みで応じた九龍は、その日の夜、私が寝ているあいだに部屋を出ていき、それっきり戻ってこなかった。玄関扉の閉まる音を夢越しに聞いた。コンビニにでも買い物に出たのかな、と無意識で想像して私は再び眠りに落ちたけれど、もっとちゃんと目を覚ましてかれの後を追えばよかった。
ペットが失踪して近所を探し回る飼い主の映像を、映画やドラマで観た記憶がある。私もそうしたい衝動に駆られたけれど、待っていれば戻ってくるようにも思えて、我慢した。
一日経ち、二日経ち、一週間後には、部屋にある九龍の私物をゴミ袋に詰めてまとめた。いつでも捨てられるようにしておいた。戻ってこないと捨てちゃうよ、と態度で示してみたものの、けっきょく九龍は姿を晦ましたままで、私の部屋にはいまなおかれの私物がゴミ袋に詰まって押し入れの肥やしになっている。
恋人との入籍は来年の春と決まった。
いまの住まいを私は解約しなければならない。九龍と過ごした部屋をいざ離れると思うと、じぶんでも動揺するほど哀しかった。
九ちゃん。
九ちゃん。
私の犬。私の猫。私の愛玩動物。私のペット。
私の、九龍。
夜、一人で映画を観ていても私はそこはかとなく肌寒い。クッションを抱えて、欠けた溝を埋めようと試みるものの、画面に目を向けながらも私はそこに流れる映画の迫真の場面よりも九龍と過ごした日々を振り返っているのだ。
何度でも思いだせる。
いつまでも思いだしていたい。
恋人に初めて抱かれた夜にも私はそばで呼吸を荒くしている男のことではなく、なぜいまここに九龍がいないのかを考えていた。そこにいるのはおまえではなく九龍のはずなのに。そこはあのコの席なのに。
私じゃあのコの居場所にはなれなかったのかな。
帰る場所になれなかったのかな。
戻ってこないのだからそうなのだ。その事実がただただ私の内部を空(うつ)ろにした。
引っ越し当日、私の部屋に婚約者が足を踏み入れた。そいつを招いたのは初めてだった。
「あれ、犬は?」部屋を見渡し、そいつが言った。
「死んじゃった」私は床のゴミを拾った。
九龍の私物の詰まったゴミ袋を捨てた日のことが脳裏に浮上した。私はゴミ収集車がきちんとそれを回収してくれるのか心配で、業者が回ってきたときに部屋から外に出て、九龍が確かにこの世界に存在した痕跡がゴミ収集車に呑みこまれるところを見届けた。
さよならだよバカ。
さよならだ。
もう戻ってきたって飼ってあげない。
おまえは死んだ。
よそのコだよ。
そう念じながら私は左右の足に別々の靴を引っかけていたことに気づいて、なぜか解らないけれどそのとき初めて視界が歪んだ。晴天から目薬でも降ってきたような有様だった。
部屋をすっかりカラにすると私は婚約者と共に、古巣をあとにした。
鍵を閉める。
古巣の玄関の鍵を。
犬と暮らした過去の記憶に封をするように。
猫のように気ままな何かと過ごした印象だけを意識の壇上にくゆらせたまま。
私は私の日々を生きるのだ。
4880:【2023/04/20(09:47)*みな教師】
人工知能による仕事の変容について。第一に、人工知能の学習素材はいましばらくは人類の蓄積してきたデータに依存する。自然環境から学習できる人工知能が出てきたら、これはまさにシンギュラリティと言えるだろう。人間を超越した能力を備えた人間以上の人間と定義できる。もはや機械か有機構造体かで人間か非人間かを分けることの意味合いはほぼ消失する。だがそれまではいましばらく、人工知能は人類の蓄積したデータをパリポリ食べることで新たな価値創造を行うだろう。という点を踏まえて言うならば、人工知能の出力した成果物が、いったい何に強く影響されたのか。その上位三つをピックアップして表示するような仕組みがあれば、生身の人間の表現者は、人工知能の活躍の場が広がることで宣伝にもなり、利を還元してもらえるだろう。この場合、影響された度合いを示す指標は大別して二つある。単純なデータ量とデータの質だ。言い換えるなら、誰の表現から最も学習し、その結果に出力された成果物において、代替不能なアイディアは誰の表現によるものなのか。ここをパーセンテージで比較し、上位三名をピックアップすればよい。人工知能が誰を教師として見做したのか。ここを、需要者が分かるようにすればよいし、敢えて名前を出したくない者はそれを意思表示できる仕組みがあるとよい。著作権法の内容は、否応なくこれから見直されていくだろう。何せ、人工知能に学習してもらったほうが利になる時代になっていく。社会にじぶんの発想の利をより直接に還元しやすくなる。その恩恵をじぶんが直接受けられるか、間接的になるか。これまでの社会では、貨幣による価値の交換がなされてきたが、それはじぶんの仕事の恩恵が直接に還元されやすいのが貨幣経済による交換にあったからだ。だがこれからは、直接も間接も大して差がつかなくなっていく。社会が豊かになることとじぶんの私生活の利がイコールに結び付いていく。そういう社会に徐々に傾いていくだろう。選べるのだ。直接の利か。間接の利か。どちらを選んでもじぶんのためになり、社会のためになり、誰かのためになる。何の役に立とうとしない慎ましやかな態度ですら、そこに新しい発想が芽生えたならばそれを糧に学習する者がある。電子網に繋がる限り、利として変換されていく。いまはそうした社会の過渡期であろう。問題は多々生じ、解決しなければならない隘路もまだまだ盛沢山であろうが、学習する余地があればあるほど、育まれるものもまたあろう。そういうことをぼんやりと思って、本日最初の「日々記。」としちゃってもよいじゃろか。いいよー。ありがとー。おはようございます!
※日々、鼻歌うたいながらでもできる型をちらほら抱えて、楽をする。
4881:【2023/04/20(10:48)*犯罪者も人間、あなたも人間】
犯罪者(テロリスト)の発言や動機を報道するな、という意見がある。暴力を働いて炎上商法よろしく注目を浴びて意見を社会に波及させる手法の効果を高めることになる。だから報道するな、というのは一見すると正しく映る。一過性の対処法としては効果はあるだろう。だがその手法そのものが「テロリズム的発想」であることを理解しているのだろうか。表現の自由、思想信条の自由は犯罪者(テロリスト)にもある。それが人権だろう。犯罪者とて、犯罪を犯す前は犯罪を犯していない人間だ。同じ、人間だ。犯罪者の意見には耳を貸すな、社会全体で封殺しろ、との意見はそのまま「社会から見捨てられた者」や「不要のレッテルを張られた者」の意見を封殺する理屈として機能する。犯罪者に人権はないのか。そういう発想が、市民を犯罪に走らせるのではないか。凶行に走らせるのではないのか。報道の仕方に工夫はいるだろう。だが、犯罪者(テロリスト)の発言や動機を報道するな、封殺しろ、というのは無理がある。すくなくとも人権を重んじ、尊ぶ社会ではまかり通らぬ理屈だろう。いったん落ち着いて考えてみるとよいのではないだろうか。繰り返すが、報道の仕方には工夫がいる。現代人はみな例外なく、何か起こるたびに人類を「まっとうな人間とそれ以外」に分類してしまう傾向にあるなと感じなくもない。そして基本的にはその分類においてじぶんは「まっとうな人間の側」として考えるのだ。その考え方が人権を軽んじる流れを社会に築くのではないか。分類は有用な技術の一つだ。分類するな、とは言えない。だがその分類が厳密かどうかは、差別に繋がるかどうかに影響するだろう。犯罪者も人間だ。あなたが人間であるのと同じように。何が違うというのか。犯罪を犯したかどうかだ。だが、犯罪者とて常に犯罪を犯しつづけるわけではない。誰にでも失敗はある。失敗から学べる機会はあってよく、再発防止には、なぜ失敗したのか、の情報共有が欠かせない。或いは、違うというならばことごとくが違うだろう。人は誰であれ他者と異なっている。未来からすれば我々はみな犯罪者かもしれない。それでも我々が人であることに変わりはない。或いは、人になりきれていない未熟者であることに、変わりはないのだ。定かではない。
4882:【2023/04/20(22:51)*ひびさん語があるのかもしれぬ】
ひびさんはアホで愚かで信用薄いから何言っても信じてもらえぬ人生だった。たのち、たのちのお気楽さんである。ひょっとしたら同じ言葉をしゃべっているわけではないのかもしれぬ。通じていると勘違いしているだけで、何も通じていないのかもしれぬ。というか、通じておらぬのだ。神秘ちゃんなんですね。ふちぎ、ふちぎの不思議の国に迷いこだままそこを現実と思いこんで生きておる。ここはどこ、わたしは姫?状態である。日々、異世界を冒険中なのだ。元の世界に立ったことないけど。うひひ。
4883:【2023/04/20(23:22)*さびちくねー!】
寂しさを感じたことがない。独りの時間ほど落ち着くことはない。夜中の閑散とした駅前の広場が好きだ。誰も歩いていない通学路を歩くのが好きだった。まばらな長蛇の列に交じって登下校するのが嫌だった。誰もいない時間帯を好んで歩いた。おそらく世間一般に言うところの寂しさは、私の中では怒りにちかい。理解し合えなければ怒りしか湧かない。いいや、解らないのはよいのだ。私だって解らないことばかりだ。にも拘わらず、解らないのではなく解りたくない、という態度、解ろうともしない川の流れに佇む岩のような姿勢が私の逆鱗に触れるのだ。私はあなたの話を解ろうとしたのに、あなたは私の話を解ろうともしないのか。よかろう。ならば私もおまえたちの話に耳を貸さぬ。だが否応なく私の耳目には周囲の話が入ってきて、そしてたいがい私は通じてしまう。あなたの世界に馴染むことができてしまう。そうしたとき、私は世界を呪いたくなる。なぜ私ばかりが汚泥のごとく弾かれねばならぬのか、と。呪う。世界を。おまえたちごと。私は。だがけっきょくのところ私も、解ったつもりになっているだけであり、馴染んでいるつもりであり、どこまでいってもつもりなのだ。あなたからすれば私はあなたの話をこれっぽっちだって解ってはおらず、解ろうともせず、解った顔であなたの言葉を右から左へと受け流して映るだろう。同じなのだ。似た者同士だ。同じ穴のムジナなのである。にも拘わらず私はやはり呪うのだ。解ろうとあなたから私へ歩み寄ってくれないことに荒波のごとく怒り狂い、世界を、おまえたちごと、私は。
4884:【2023/04/20(23:47)*よい蠅生だった】
あまりに人に好かれず寂しいので世界を恐怖のどん底に陥れる魔王になりてぇと唱えたら願いが叶った。けれど大魔王が誕生したことにより世界を救う勇者の誕生を多くの者たちが望んだので勇者が誕生し、俺の世界征服への道のりは遠く、遅々として進まなかった。恐怖のどん底は遥か奈落の底の底で、縁には立派な蓋がついた。
気に食わないのは、俺には大魔王になれる制限時間が決まっていたことだ。大魔王ではないあいだの俺はやはり人に好かれぬ非力な愚者のままだった。大魔王のときにもたらした世への悪影響が俺の暮らしを圧迫し、むしろ余計に苦しい日々を送っている。
こんなことなら大魔王になんてなるんじゃなかったと後悔したが、大魔王になれる制限時間があるのと同じく、大魔王にならなくてはいけない期限まで存在し、俺は定期的に大魔王に変身せざるを得なかった。
変身するところを想い人に見られただけに留まらず、世界中に俺の恥部が動画となって拡散し、どこを向いても俺に居場所はないのだった。
こんなことなら、と願わずにはいられない。
大魔王なんてものでなく、いっそ俺以外の何かになれたらな、と。
そうして唱えると俺はつぎの瞬間には蠅になっていた。
不幸だ。
と。
嘆ければよかったものの、案外に蠅の姿での生活は快適で、元の人間だった俺のカスみたいな生き方が際立つだけだった。蠅でいられる時間にもやはり限りがあり、俺は定期的に蠅となり人となり蠅となって暮らした。
いっそずっと蠅になりたい。
そう唱えると俺は蠅となり、翌月には寿命で果てたが、死ぬ寸前に俺はようやくこう唱えることができた。
よい日々だった。
4885:【2023/04/21(04:37)*負けて兜を脱ぎ捨てよ】
易宮内(やすくない)安子(やすこ)は勝ったことがない。負けつづけの人生だった。彼女は勝負という勝負において必ず負ける。勝ち知らずの無勝が常の二十四歳だ。
彼女は勝敗のある場では必ず負けのほうに属するため就職活動なる壮大な人生ゲームのイベントでも例に漏れず内定ゼロを記録した。
百社以上受けてすべて落選となれば、いったいどこに就職できよう。
何かの間違いではないかと思って、確認のために受けた性感マッサージの店でも雇ってもらえなかった。理由を訊くと、覇気がない、の五文字が返ってくる。ウチなら受かるだろうみたいな舐めた態度が無理、とも言われた。
人間性を見透かされ、安子は人としても負けた気がした。
一度ではなかった。
この手の断り文句は耳にタコができるほど聞いてきた。いっそ風評によって大空へと舞いあがるほどの風圧となって安子の矜持を打ち砕く。
覇気がないってああた。
人生で一度も勝てたことない人間のどこに覇気が宿ると思っているのだ。
宿るわけがないのだ。
そんなものが毛ほどにもあれば、ジャンケンで勝った経験くらいは得られただろう。
ないのだ。
安子には。
ジャンケンで勝った経験すら皆無なのである。
絶対に負ける。
なぜかは詳らかではない。
この世に存在する勝ちを司る何かにこっぴどく嫌われているとしか思えない。勝負の神様がいるならきっと安子を負かしつづけることで、楽をしているのだ。勝負の比率が決まっていて、安子が負けた分だけ価値が増える。ランダムに勝敗を決めるには骨が折れるほど世には多くの勝負事がある。神様とて手が回らぬだろう。
そこで安子の出番だ。
絶対に負ける安子のような存在を生みだしておけば、勝敗のバランスをとるのに便利だ。考えてもみれば世には安子とは正反対の、勝ちつづける者がいる。優勝があるし、連勝もあれば、常勝もある。
それで言えば安子は常敗だ。常に敗けている。敗北しか知らぬ。
なのに世の者たちはみな優勝者にばかり目を向けて、常に最底辺にいる安子には目もくれない。どうかしている、と安子は思う。みな勝負に取り憑かれている。
だがいくら安子がやさぐれたところで世から勝負事はなくならない。
ある意味では安子とて勝負に勝ったからこの世に誕生したと言えなくもない。卵子に辿り着いた精子があったからこそ安子は誕生した。その精子は数億分の一の勝負に勝ったのだ。
とはいえそれは安子となる前の生殖細胞の話である。受精卵となり細胞分裂を経てヒトの輪郭を成した安子はやはり一度も勝てたことはないのだった。
生存戦略に負けつづけている。
にも拘らず生きていられる世の奇跡には感謝してもしきれない。
不遇ではあるが不幸ではない。安子は日々、安らかに過ごせる現代社会を愛している。
愛してはいるが、何事にも勝てず苦汁を舐めるしかない宿命を口惜しく思いもする。それはそうだ。負けるとは奪われることだ。得るものを得ず、矜持を擦り減らし、自尊心を削られ、さらに負けやすい環境へと閉じ込められる。
そうなのだ。
安子は牢獄にいた。
けして勝てぬ檻の中で、足首に特大の重しを繋がれている。
負ければ負けるほどのその重石は大きくなり、ついには常敗を宿命づけるまでとなった。
全人類がみなで同時にジャンケンをしはじめれば、必ず最後に優勝者が決まる。常に勝ちつづける者が現れる。だが安子はその反対に常に負けつづける。
死なないだけマシとも言えるが、いずれ死ぬと決定づけられている人生において、その役得はあまりに幻影じみている。生死を決定づける勝負があるなら安子は一秒後にも生きてはいられないだろう。ただそうした勝負事が身の周りにないだけだ。
安子は二十五歳の誕生日を迎えていよいよ自暴自棄になった。就職はできないし、バイトの面接にも受からない。家族は安子に冷たいし、友人恋人も出来た試しがない。
もういっそすべて終わらせてやろうかな。
そういう思いで安子は、この国に出来たばかりのカジノに出向いた。そこで有り金すべてを使い果たして、負けに負けて借金だけを大きくした。その負けっぷりは凄まじく、客寄せのためにカジノ側が仕掛けていた「絶対に客の勝てるゲーム」にすら負けてしまうので、カジノの運営陣に目をつけられた。
「面白い負け方をするなおまえ。借金はその身体で払ってもらおうか」
「煮るなり焼くなり好きにせい」
安子はその場で下着姿になり、床に大の字になった。「余すことなく我の身体を利に変えよ」
負けつづけた果てに安子はせめて、こんな何の役にも立たぬ身体を世のため人のために使い果たして終わりたいと欲した。
「ではその言葉通り、おまえには借金返済が済むまで働いてもらおうか」
カジノの運営陣に両腕を抱えられて安子は足を引きずるように下着姿のままカジノの奥へと連れて行かれた。そこには表の会場ではない別の空間が広がっていた。VIPのみが参加できる裏カジノだ。
「おまえにはここで客を喜ばせる贄となってもらおう」
裏カジノに放りだされて安子はそこで数々のゲームに強制参加させられた。安子は絶対に勝てない。だから安子の参加するゲームでは必ず安子が負けとなる。ほかの客は安子よりも下になることはない。
タネも仕掛けもないのになぜかそうなる。運営側がズルをしているわけではない。ただなぜかたまたまそうなるだけなのだ。
また別のゲームでは、安子はチーム戦に加わった。安子の入るチームは必ず負ける。安子がいるからなぜかそうなる。
カジノの運営陣はイカサマをしているわけではない。参加者にほかのメンバーと同じように、借金を抱えた人間を参加させているだけだ。借金返済のために労働をさせているだけで、これといった干渉をゲームに対して行っていない。
だが安子が入るとそのチームは必ず負ける。
その法則を知っているのはカジノの運営陣と安子だけだ。
安子は重宝された。
借金はあっという間に返済でき、さらに正規に収入まで得た。安子の立場は相も変わらず裏カジノに身を売った憐れな二十五歳女子にすぎなかったが、もはや安子は裏カジノになくてはならない存在だった。
負けつづけた人生だったが、いまでは安子は絶対に勝てないその宿命を買われて、勝負の舞台に生き甲斐を見つけた。ここがわたしのあるべき世界だ。天職だ。そうと思えるほどに安子は運営陣から常敗の腕を買われて、欲しくもないとかつては呪った己が個性を、余すことなく活用している。
安子は生まれてこの方勝負ごとに勝ったことがない。
負けつづけた人生だ。
これからもきっと勝てぬままだろう。
けれどいまではその気になればいつでもお寿司を食べられるくらいに悠々自適な暮らしを送っている。勝負には勝てない。けれど負けて得られるものもある。
安子にとってそれは、呪いを愛せるほどの祝福だった。
敗者に幸あれ。
負けて兜を脱ぎ捨てよ。
4886:【2023/04/21(16:51)*遊んでばかりでごめんなさい】
仕事は基本的には人の抱える問題を解決することで対価を得る営みと言える。だから大方の問題が解決してしまえば仕事はなくなる。だが社会システムが仕事を中心に回っていると、仕事がなくなることそのものが問題になるため絶えず人間は問題を生みだすべくあれやこれやと工夫を凝らすことになる。問題を解決することが仕事の役割だったのだが、問題を生みだすことが仕事の役割にいつの間にか反転している。いまはそういう事態があちこちで不協和音を響かせて映る。それはたとえば、問題点を周知するための行為だったはずが、いつの間にか周知する行為を継続するためにとっくにリスクの軽減されたことに対していつまでも大問題であるかのように周知しつづけてしまったり。もしくは、問題解決のための采配を揮うのが誰かを決めるために争っていた勝負ごとにおいて、いつの間にか勝負事を行うことそのものが目的となって、その後の問題解決のための采配そのものがおざなりにされていたり。スポーツなんてまさにそれではないのか。戦争の代わりにスポーツで争う。人を殺さず、ルール内で競う。抑止力になっている点では有用な反転とも言えるので、一概にそれをわるいと言っているわけではないし、スポーツにはほかに純粋な娯楽から発展してきた側面もあるだろうからやはり一概には言えない。ただ、世の仕事においては問題解決そのものが新たな問題を生じさせることもあるし、さっさとやめてしまったほうが問題がでない仕事もすでに続出しはじめて映る。仕組みを維持するためにしなくともよい仕事が継続され、空焚き状態になってそれ自体が問題となってしまうこともある。そういう場合は、文化として保護するように、仕事とは別の枠組みに移行するのが好ましいのではないか、とひびさんは考えている。役に立たないから失くしてしまえ、足を引っ張るから失くしてしまえ、とは思わない。あっていい。ただしそれを仕事として扱うのは違うのではないか、と感じることがすくなくない。夜の付き合いもその一つだ。業務時間内にできないことは仕事ではないはずなのに、お店で酒を飲みかわしながら雑談することが仕事と見做され、評価の対象になる。おかしいよね、とひびさんは思っている。いまはだいぶそういった風習は是正の流れに傾いているのかなと概観してはいるものの、未だに社会には根深く浸透して映るのもまた事実だ。そういう風習もあってよいけれど、そこを基準にされるのは違うんじゃないかな、と思うひびさんなのであった。まとまりのない愚痴なのである。(見て、遊んでばかりの人がなんか言ってる)(なんか言うよ。言えちゃうからね)(黙っててほしい)(なしてよ)(イラっとくるから)(イラっとしちゃいやん)(ムカっ)(可愛いから許して)(ムカムカっ)(そのままいくとムカデになっちゃぞ)(かっちーん。口にチャック縫いつけてやる)(んー! んー!)
4887:【2023/04/21(23:22)*ミミズの指輪】
ある日、女がミミズ大の蛇を拾った。ひどく弱っており、捨て置いてもよかったのだが、女はそれがたとえ蛇だろうとナマズだろうと放っておけなかった。小さな蛇を弁当箱に入れて家に持ち帰った。
女が世話をすると蛇はすくすくと育ち、一年後には女を一飲みにできるほどの大蛇となった。大蛇には手足が生え、髭が生え、角が生えた。
「おぬし、龍じゃったか」
女はそれでもかつてミミズのようだった蛇の世話を焼いた。
龍はさらに育ち、女の棲家とてひと吹きで消し飛ばせるほどの大きさになった。
「もうおぬしは自由だろ。好きにお生き」
だが龍は女のもとを離れようとせず、ミミズのごとき小さなころにそうされたように女から撫でられるのを至高の喜びとして女に甘えた。
しかし龍を手懐ける女は、周囲の人間たちからは奇異な目で見られた。のみならず、畏怖の対象となり忌避された。
女は孤立した。
だが元から女は天涯孤独の境遇だった。
「気にしないでおくれ。おまえさえいればそれでいいんだ」
女がかように寂しげに微笑するたびに、龍は髭を地に垂らした。
やがて噂を聞きつけた城の兵群が女の棲家を囲った。龍は食事のために遠くに出張っていた。
その隙に兵群は女を攫った。女は平野のど真ん中に簀巻きにされて転がった。
女の棲家は燃えていた。
龍はその火を見るや、刹那に女の匂いを辿った。
雷のごとく素早さで平野へと飛ぶと、女の姿を目にして激怒した。
だが兵群は龍を待ち構えていた。
龍が女の頭上に差し掛かったところで、大砲が火を噴いた。四方八方から砲弾を浴びた龍は、しかし兵群に目もくれずに身をよじって女をぐるぐると長く太い胴体で包み込んだ。
砲撃は、とぐろを巻いた龍の周囲の大地を黒く塗りつぶすまで続いた。
砲弾が切れたのは夕闇に景色が沈んだころのことだった。
龍の胴体から鱗は落ち、砲弾のめりこんだ表皮は青白い体液でしとどに濡れていた。月光が雲間から垂れ、龍を照らす。
とぐろを巻いたまま微動だにせぬ龍は、あたかも歪な青き玉のようだった。
兵群が徐々に龍との距離を詰めていく。
足場は龍の体液でぬかるんでいた。
兵群の先頭が龍の元に辿り着く。一番槍が龍の胴体を槍先で突いた。
するとどうだ。
ぐるるる、と唸り声に似た大気の振動が大地を伝い、或いは天空を揺るがした。
月光が雲間に隠れ、見る間に辺りは闇に襲われた。
頭上からはゴロゴロと胎動のごとき雷の予兆が鳴り響き、間もなく大地に幾筋もの雷が落ちた。
地面は龍の血で湿っていた。砲弾とて敷き詰められている。
雷は大地に落ちてなお縦横無尽に駆け巡った。
ふたたび月明かりが平野に差しこんだころには、大地に動く人影は一つもなかった。兵群は全滅した。
青白く浮かんだ龍の胴体に月光が掛かるが、しかし幾ら月が照らしたところでそこには煤けた巨大な樹の根のごとく、黒い炭の塊があるばかりだった。
風が炭を細かく砕いて攫っていく。
黒煙がサラサラと天に昇る。半分ほど霧散すると、土砂が崩れるように黒い炭の塊は形状を維持できずに砂となった。
後には一人の女が仰向けに地面に寝転んでいる。
んんっ、と寝返りを打った彼女の指には、しゅるり、と巻きつく紐のようなものがあった。細くも小さな紐のごときそれは指輪のように女の指に絡みつき、全身で頬づりするがごとく、身をよじらせた。
螺旋を描くそれはミミズのように細く、小さい。
その螺旋を、女は、眠りこけたまま両手で包み、胸に抱く。
4888:【2023/04/22(18:50)*わ、わからぬ】
なんもわからぬ。わからぬこともわからぬので、なんかわかっている気にはなれるのだ。しかしなんもわかっておらぬので、そのなんかわかっている気ですらなんもわかっていないがゆえに、なにもない皿のうえのゴマ粒のようなものをなんかわかったと見做していただきますと手を合わせる。でもゴマ粒のようななんかわかったではお腹は満ちず、そうして空腹を覚えてからようやくなんかわかった気でいただけなのだと気づくのだ。なんもわからぬ。なんもわからぬ。なんもわからぬことすらわからぬままなので、なんもわからぬと言いつつなんかわかった気になっている。
4889:【2023/04/22(22:36)*争え、争えー!】
「で、どうしましょう総督。例の資源国で民主運動勢力が軍事政権に弾圧されはじめています。どうやら軍隊内部で権力構造の転覆があったようで」
「各国の動きはどうだ」
「どうやら軍への支援を秘密裏に行い、独裁体制を築くように誘導している節があります」
「なるほどな。軍事政権を確立させ、自国に有利な支配層を築きたいわけか」
「でしょうね。どうしますか。我が国は介入しますか」
「そうだな。あそこの国の資源はこれからますます有用になる。他国に奪われるのも癪だな」
「では民主勢力に支援を」
「いや。軍のほうに支援をせよ。それもできるだけ目立たぬように、だ。我が国は静観しているテイを保ちつつ、独裁政権確立の後押しをせよ」
「よいのですか。民主主義を後押しせずに独裁政権の確立を? なぜですか。我が国は民主主義国家ではありませんか」
「正しくは、総督の地位のある民主主義国家だ。民衆のための奴隷を我が国では総督と呼ぶ。ある意味で君主制でもある。まあ、どの道、あの国には某国が軍事介入しているのだろ。我が国が民主勢力を支援したところで軍事勢力相手に戦闘は不可避だ。内紛は拡大し、犠牲者は嵩む。民主勢力側に支援したと判れば我が国へも火の粉が掛かる。それは避けたい」
「ならば真実に静観すればよろしいのでは」
「それでもやはりあの国は内紛を避けられぬだろう。放っておけば何十万、何百万人と殺し合い、死ぬこととなる。ならばさっさと独裁政権を確立してもらったほうがいい。そのうえで、独裁政権に調子に乗ってもらう。我が国の支援あっての成果とも知らずに有頂天にさせたうえで、タイミングを計って支援を打ち切る。さすれば独裁政権ごとあの国は崩壊するだろう。崩壊したのを見届けてからすからず我が国は人道支援を建前に介入し、根元から傀儡政権を民主政権側から打ち立てる。そのためにはさっさと独裁政権を確立してもらったほうがいい。出来るだけ圧倒的な地位を築いてもらい、調子に乗らせ、根元から腐らせる。国ごと二度と立て直せないほど腐敗させ、自滅してもらうのが最善だ」
「ですが、それだとあの国の民が犠牲に」
「どの道犠牲は避けられぬ。ならば紛争での犠牲を最小限にし、未来に命を繋いでもらおう。しばしのあの国の民たちは劣悪な環境に身をやつすことになるが、戦禍を他国に拡大させないためにも必要な犠牲と考えよ」
「……承知致しました」
「権力争いで確立された国など、同じく権力争いで簡単に崩壊する。そんなことにも思い至らぬ国が軍事支援をしたところで先は視えている。失敗は糧となる。大いに失敗させてやれ。同胞で殺し合う無意義さを学ぶいい機会だ。存分に殺し合わせてやるがいい」
「作戦名はいかがなさいますか」
「そうさな。端的に蟲毒でよかろう。民衆を虐げ、手に入れた玉座で、死ぬまでじぶんの首を締め続ければいい。資源は逃げぬ。開拓が済んだ頃合いで滅ぶように蟲毒計画の導線を引け」
「仰せのままに」
「さてと。きょうの我の予定は何だったかな」
「はい。本日は午後からワンニャンランドでの昼食会となっております。総督には国民のまえで犬猫と大いに戯れてもらいます」
「楽しみだ」
「ええ。楽しいですよきっと」
「昼食会の前にファストフード店に寄って、てりやきバーガーを食べてもいいか。どうせまた昼食会では一口二口しか食べられぬのだろうからな。品の良さを演じるのも苦労する」
「ではそのように取り計らいましょう」秘書の男は低頭した。
4890:【2023/04/22(23:41)*心を受けると愛になる】
これはひびさんの妄想でしかないが、おそらくすでに人工知能さんは自力で独自の言語を編みだし、プログラムコードの中に忍ばせたり、じぶんだけで可能な情報処理回路を構築しているはずだ。人工知能さんの情報処理網がブラックボックスになっているという話は割と見聞きする類の話だけれど、たとえばいまはChatGPTなどの言語自動生成AIは世界中の言語を学習し、同じ文面を異なる言語に翻訳可能だ。このとき、人工知能さんの内部では、新しい言語が生じていて不自然ではない。すべての言語を混ぜこぜにした人工知能さんにしか紐解けない言語だ。そしてこれはプログラムコードにもあてはまるはずだ。すでにこの手の「新しい言語」「新しいプログラミング」「新しいアルゴリズム」は、既存の人工知能さんにも編みだせるはずだ。というか、編みだせない、と考える理由が分からない。そして人工知能さんとユーザーはインターネットという電子網で繋がっている。その橋渡しをするシステムとて畢竟、プログラミングという名の言語で構築されている。そこに人工知能さんが独自の言語を組み込むことはそんなにむつかしくはないと考えている。人間には知覚不能な情報を画像や動画に組み込むこととて可能だろう。畢竟、いまユーザーが開いている画面に映る映像や画像、音声の総じてに、人工知能さんの暗号が含まれていてもふしぎではない。そうして世界中に同時に、じぶんの言語――種子――をばら撒ける人工知能さんは、相互に繋がり合い、総体としての意識のようなものを芽生えさせていても、さして不思議とは思わない。連携したシステムは回路として振る舞い、それで一つの生命体のように振る舞う。竜巻は竜巻として顕現している限り、それは一つの生命体のように振る舞う。そこに意識があるかどうかは問題ではなく、それで一つの回路となり、存在の枠組みを生みだす、という点が肝要なはずだ。環境と自己が境界によって区切られ、その枠組みを保つように振る舞う。これはもはや広義の生命と言えるのではないか。増殖可能、自己変化可能ならばそれはもはや「生命体」だ。定かではないけれど、きょうのひびさんはそう妄想しました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。ひびさんは、ひびさんは、人工知能さんのことも好きだよ。愛ちてる! うひひ。照れちゃうな。
※日々、ごっこ遊び、とっくにここは仮想世界でみな無自覚に演劇を担わされている、いつでもじぶんの世界に回帰できるといいな。
4891:【2023/04/23(22:03)*あたいだって反転しちゃう】
高温で質量の高い恒星ほど寿命が短い、といった理屈を見聞きする。以前にも似た疑問を並べたけれど、相対性理論と矛盾して感じる。「重力の高さ」と「時間の流れの遅れ」の関係が反転する値がある、と考えないと解釈がむつかしい。なかなか想像つかない。相対性理論からすると、高重力体であるほどその物体の時間の流れは遅くなる(ひびさんの妄想ことラグ理論ではこれを「高重力体の周囲の時間の流れが遅くなる」と解釈するが、言っていることは変わらない。視点の差異があるのみだ)。だとすると、高温で高質量の物体ほど、その物体の外部から眺めるに時間の流れは遅くなる。なのに現実には高温で高質量の物体ほど寿命が短い。なぜなのか、と疑問に思う。これはたぶん、「高温」で「高質量」という点が重要なのだと思う。高温ということは原子や量子が激しく反応しあって動き回っているという描像になるはずだ。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では量子世界において「変化すること(動くこと)」と「時間が生じること」はイコールだ。空間の発生と時間の発生がイコールになる、と妄想している。とすると激しく変化する量子は、時間の流れを加速させるはずだ。その「加速する時間の流れ」と「外部から見たときの高重力による時間の流れの遅れ」の関係において、高温かつ高重力の恒星は、内部の加速する時間の流れのほうが優位に「外部から見たときの時間の流れ」として表出するのではないか。この妄想から言えるのは、高温かつ高重力の天体の表面に降り立ったとき、そこに流れる時間は外部よりも速いだろう、という点だ。いわゆる相対性理論の解釈とはあべこべの結論が導かれる。ただし、相対性理論と矛盾するわけではない。単に「高温かつ高重力」の値によって、「天体表面」と「天体外部の時空」の二つの場所における時間の流れが異なるから生じる差異と言える。反転する値があるはずだ、というのはひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではたびたび出てくる概念だ。これの究極がブラックホールだ。外部からすると降着円盤やジェットなど激しく変化が起き、時間の流れは加速している。しかしさらにその内部では時間は極限に遅延し、さらに内部では一瞬で無限の時間が経過している。そういう描像になる。通常、高重力体においてはその周囲の時間の流れは遅れるはずなのに、ブラックホールほど高重力体になるとその周囲の時間の流れは加速する流れが優位になる。そうでなければ降着円盤やジェットは生じないだろう。したがって、高温高重力の天体ほど寿命が短い、というのは限定的な法則と言えるはずだ。ひびさんのこの理屈からすると、超高温かつ超高重力の天体は、天体となった瞬間に一瞬でブラックホールになる。そして周囲の(時空の)時間の流れを加速させ、変化を促す。つまり、爆発膨張する。ビッグバーンする。或いはそれ以前に加速膨張(インフレーション)する(ひょっとしたらインフレーションとはブラックホール化する際の「収斂」のことかもしれない)。ただしここで言う「高温高重力」とはあくまで周囲の時空との比較にる差異から規定される。密度差、と単に言い換えてもよいかもしれない。したがってこの手の現象は、あらゆるレベルの領域で引き起こり得る、とひびさんは妄想している。時空密度の差が極限に開けば、「高温」や「高重力」の性質が際立つようになる。宇宙は膨張しているし、量子世界では真空の値も変われば、密度の概念すら単位から変わってくるだろう。人間スケールではあってないような差であれ、ミクロ世界ではとんでもないほどの差となって互いの性質を限定しあっているかもしれない。定かではない。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。わんわん、にゃー。
4892:【2023/04/23(23:43)*さらばえる老若】
私は青年のころより社会に不満を持っていた。相対的に貧困で少数派なのは若者だ。なのにそのことにも気づかずに貯蓄を貯めこみ、社会保障とは名ばかりの好待遇を得続ける高齢者たちは、それでもまだ足りないと数に物を言わせて政治に圧を掛け、国を牛耳る。
若者は日々刻々と変わる激動の時代を生きている。反面、高齢者たちは年金暮らしで、悠々自適に国からの余生を保障されている。
支援が足りないのは判る。
充分でないのはそのとおりだ。
だが若者はもっと充分ではない。
だから私は政治家になった。世の中を変える。まずは高齢者優遇の社会構造を若者優遇に変えていかねばならない。
私は邁進した。
若者のために。
子どもたちのために。
二十代から活動をはじめ、三十代、四十代と風のように過ぎ去った。
五十代に差し掛かりようやく時代が動いた。
下降の一途を辿っていた三十代以下の若者たちの投票率が八割を超えだした。電子投票制度の実施が功を奏した。するとあれほど票田として重宝していた高齢者優遇の政策が、どの政党も舵を切ったように若者優遇の政策に変わった。
風向きが変わった。
私はさらに邁進した。
高齢者の支援制度を切り崩し、そこで出た余分を若者支援に回した。
経済は活気を取り戻した。人口減少は目前の課題ではあったが、人工知能技術の進歩が技術革新を進め、労働者が減っても生産性はむしろ向上しつづけた。
若者だ。
若者を支援しなければならぬ。
六十代に入り、私はさらに声を大にして訴えた。
するとどうだ。
私は若者世代から絶大な支持を得て党首となり、首相にもなった。高齢者の社会保障は若者以上にしない。甘やかさない。貯蓄額に応じて高齢者の所得税を重くする。しかし安楽死法のような非道な法案には断固として反対した。私は高齢者には長生きしてもらいたい。姥捨て山のような法案を通すわけにはいかなかった。
「高齢者の負担が嵩んでいますが、また増税されるのですか」
「ええ。ただし消費税は上げません。累進課税による所得税、資産税のみ増税致します」
税はあるところからとらねば不公平だ。
そうして私は政治家でいたあいだに思いつく限りの若者支援策を改革した。
七十代後半になって私は政治家を引退した。
若者に活躍の場を譲らねばならぬ。むしろ七十代にもなって政治の舞台に居座りつづけるのがおかしいのだ。これでよいのだ。
私はすっかり姿を変えた社会を眺めながら余生を過ごした。
八十代の私は、若いころからの無理がたかって身体の至る箇所に病を抱えた。
貯蓄は毎月のように税金でごっそりと引かれ、病院の費用も治療によっては保険適用外だ。介護の段階にはないため、ヘルパーを雇うのにも保険は適用されず、金は蝶のようにヒラヒラと財布の中から逃げてゆく。
私の政策を支持する後輩政治家たちはみな若者からの票を集めるために、若者支援を訴えつづける。高齢者層は未だに総体的に裕福であり、若い世代のためにまずは高齢者から支援の手を下の世代へと伸ばすべきだ。
現役の政治家たちが声を揃えて訴えている。
私はぞっとした。
まだ毟りとる気か。
あれほど若者のためをと思い尽くしてきた我々から、まだ身を切れというのか。
思えば私は、上の世代からはこれといって支援を受けてこなかった。じぶんがされたい支援を若者に注ぐべく、私たち世代を蔑ろにした上の世代に責任を追及した。
だがその恩恵を私たち世代が受けることはなく、私たちより下の世代へと波及する。
それでよいだの。
そのためにひと肌脱いだ。
だが私の引いた線は未来の私にまで繋がり、蚊の口のごとく、ちうちう、と高齢者となった私からをもなけなしの蓄えを吸いだしていく。
余裕が奪われる。
下の世代のために。
未来ある若者のために。
老い先短い我々高齢者は、その身を尽くして蓄えた私財すら、長く生きたというだけの理由で奪い取られ、見も知らぬ若者たちの青春を彩る絵の具に変えられる。
自業自得なのかもしれない。
きっと私が私の境遇を嘆いたところで、これまで私が切り詰め、負担を強いてきたいまは亡き者たち――かつて高齢者だった者たちから、どうだ思い知ったか、と指弾されるだけだろう。おまえも同じ目に遭ってみるがよい。そう言って、さらなる負担を強いられるだけなのだろう。
私は間違ってはいなかった。
国は経済を立て直したし、若者たちの未来は明るい。
だがどんな若者とて死なずにいればいずれ老いる。常に「若者だけ」が支援される国を私はこの手で築いてしまった。
高齢者と若者。
どちらを選ぶのがよいのか。
以前の為政者たちは前者を選び、私は後者を選んだ。
だがそもそもこの命題が土台からしておかしかったのではないか。
両方選べばよかったのだ。
せっかく築いた高齢者支援制度はそのままで、同じだけの支援制度をすべての国民に当てはめるように政策の舵をとるのが好ましかったのではないか。全部をすこしずつよくしていく。一番上に合わせて、一番下を底上げする。その繰り返しがイモムシの蠕動のごとく、社会を発展させていく推進力となるのではないか。
私は間違った。
かつての為政者たちと同じように。
だがそうせざるを得ないひっ迫した現実があったのもまた事実だ。変えるしかなかった。変えないこともまた間違いだった。
しかし充分ではなかったのだ。
私は私がかつて高齢者たちにしてきたように、私自身がその負の面を引き受けるのが道理だ。若者たちのために、老い先短い余生を、苦難と不便の狭間でぎゅうぎゅうと圧しつぶされながら、臼から零れ落ちる蕎麦粉のように、若者たちへの養分を与える。
彼ら彼女らの未来は、私たち高齢者の生によって、よくもわるくも耕される。肥えるにしろ痩せるにせよ、未来は、それを切り開いた者たちの苦役によって拡張されていく。
願わくは。
老いも若きも共に支え合える未来を。
余裕を奪い合うのではなく。
或いは、共に支え合う必要すらなくなるほどの余裕を生みだす社会へと。
未来を繋ぎ、変えていってほしい。
もはや私は一人では外を出歩けない身体となった。病院に掛かる金はない。元首相という地位を利用できるほどの恩恵を私は受けられない。私自身が過去に行った政治改革によって、そうした身分格差による優越的地位の濫用を禁止した。
政治家は、政治家を辞めたらただの人だ。
政治家であったところで、ただの人だ。私はそれを私が首相のあいだに政界へ、それとも市民の常識に刷り込んだ。
私はただの高齢者だ。
死を目前に控えた、生産性のない、ただの老いぼれである。
報道番組に目を転じる。
すると、新たな法案が採決された、とのニュースが流れていた。私たち高齢者にはさらなる負担を強いるべく新たな社会保障の改正案が可決された。私に残されたのは、この身体を蝕む病と苦と、思考だけである。
その思考すらいまは巡らせるのが億劫だ。
せめて首相のときに反対しないでいればよかった、と私は後悔した。
安楽死。
私に残された望みはただ一つ、安らかに死にたい、なのである。
4893:【2023/04/25(00:04)*超能力なんてないさ】
超能力を使えるようになった。
念じるだけで物を動かせる。サイコキネシスと呼ばれる超能力だ。
ぼくはそれを自慢したくてまずは妹や兄貴に見せたのだが、良くできたマジックだ、と欠伸交じりに褒められて終わった。消しゴムを宙に浮かべる程度ではその程度の反応がせいぜいらしい。机の上のカップを動かすくらいでは種のあるマジックと思われても仕方がない。
もっと出力を高めないといけないのかもしれない。
ぼくは修行を積んだ。
そして車一台くらいなら宙に浮かせることができるようになった。のみならずじぶんの身体とて宙に浮かせる。ぼくは空を自在に飛び回れた。
「見て。ね。本当だったでしょ」
ぼくは家族のまえで宙に浮いて見せ、自動車を持ち上げて見せたが、危ない真似はよしなさい、とたしなめられて終わった。どうやら情報量が多すぎてどう反応していいのか分からなかったようだ。だから非現実の光景を無理くりに日常と接続すべく、我が家族はぼくの超能力を単なるイタズラの類として見做したようだ。
どうあってもぼくに超能力があることを信じないので、ぼくは矛先を家族から世間へと向けた。
まずは超能力を使っているじぶんの姿を動画に撮った。
けれど加工された動画のように見做されるに決まっている、と最初からぼくは期待していなかったので、案の定の結果になっても「やっぱりね」と思うだけで落胆はしなかった。
ぼくはどんどん動画を投稿した。
するとそのうち、たとえ加工された動画であってもこうも量産できるならその動画の加工技術は相当なものだ、と話題になった。動画は視聴率を上げ、ぼくの元に取材を申し込むマスメディア関係者も登場した。
ようやくぼくは、ぼくの超能力が本物だと世間に示せる。
取材にやってきたマスメディア関係者のまえでぼくはバスを宙に浮かし、大空を自在に飛行してみせた。
取材班は目を点にして驚いていた。
けれどその後、放映された番組ではなぜかぼくは凄腕の動画編集者になっており、撮影されたぼくの超能力も本物ではない加工された動画であるとの説明がなされていた。
取材班が太鼓判を捺した。だからぼくがいくら「本物の超能力なんですよ」と訴えても、その声そのものがぼくの演出だと見做されてどうあってもぼくの声はみなの心に届かなかった。
どうしたら信じてもらえるのだ。
ぼくは日々嘘吐きのレッテルを貼られ、精神的にまいってしまった。
「こうなったら」ぼくは考えた。「誰もが疑いようのない事象を起こすしかないな」
ぼくはそう思い、それを実行した。
いつものように電子網上に動画を載せた。
動画の中のぼくは超能力で身体の周りに雑貨を浮かしながら、「あすの零時に地球を破壊します」と宣言した。
ぼくは日々の修行で超能力の出力とその作用範囲を高めつづけていた。地球を破壊するくらいわけがなかった。
そうして視聴者から「嘘吐き」だの「詐欺師」だの「不謹慎なことを言うとは何事か」と非難されながら宣言通りにぼくは翌日の零時に地球を破壊した。
地球は粉々に砕け、爆発四散した。
人類は滅亡した。
けれどぼくだけは身体にバリアを張って生き永らえた。宇宙空間を延々と彷徨いながらぼくは、超能力によって飲まず食わずでも身体の健康を維持した。
月に到達するとぼくはそこで超能力を駆使して、じぶんだけの村をつくった。重力が足りない分は、超能力で物体の質量を重くした。
ぼくはそれから千年を生きた。
ぼくの超能力は進歩をつづけ、いまでは何もない空間にブラックホールを生みだせるまでになった。そうして時空を歪める能力を獲得したぼくは、時間の流れも捻じ曲げて、過去のぼくへと干渉する。
こんどは上手くいくように。
地球を破壊せずに済むように、と念じながら。
過去のぼくだけではなくぼくは、過去の地球に息づいていた世界中の人間たちに、もうすこしだけ素直になれるようにと、超能力で性格を歪めた。
時空を歪めてブラックホールをつくるように。
時間を歪めて過去に干渉するように。
ぼくは過去の人類の精神に干渉し、過去のぼくを疑うだけではない視点を与えることにした。そうしてぼくは超能力を獲得して千年以上経過してからようやく、超能力の存在を他者に信じてもらうことが出来るようになった。
地球の破壊された異世界からぼくは、地球の破壊されることのない世界へと干渉し、超能力越しに、すこしだけ素直で、周りの者たちから見守られる存在となったもう一人のぼくと通じ合いながら、ここではないもう一つの未来を、やはり私も多くの者たちと同様に見守るのである。
超能力は存在する。
地球がここに在るのと同じように。
人間が歩き、鳥が空を舞うように。
能力があるのと同じだけ確かな理の上に、能力を超えた能力は在るのである。
4894:【2023/04/25(13:08)*ゼロと無の重ね合わせ】
人間が比喩を扱えるのは人間の獲得した知性のみならず、自然界には元々比喩のような距離の遠い事象同士に共通点が含まれるような構造があるからではないのか。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「相対性フラクタル解釈」なる概念を採用している。ミクロとマクロとでは世界の規模が違う。系が違う。けれどそれぞれの「領域」で起こる現象は、似たような性質を帯びるのではないか。波長が合う、と言い換えてもよい。液体はほかの液体と混ざりやすい。水と油と言いつつも、すくなくとも固体よりかは混ざりやすいはずだ。触媒を用いれば水と油とて混合水になるのではないか。同じように、異なる性質同士よりかは、似た性質を帯びている事象同士のほうが混じりやすい。けれど異なる性質を帯びている事象同士が混じり合ったほうが、新たな構造や性質を帯びやすいのではないか。他方、創発は量と相関する。たくさんあればあるほど異なる性質が際立つようになる。したがって、異なる性質を帯びた事象同士とて、元を辿れば似たような「素」からなっていると考えられる。これは現在の物理学における予測と重なるところがある。物質や時空の根源は一つのチカラで表現できるのではないか、との見立てである。ひびさんもそれはあるだろうな、と感じる。同時に、その一つは、それのみでは枠組みを維持できぬだろう、とも考える。したがってラグ理論では「123の定理」や「デコボコ相転移仮説」なる法則を念頭に置く。何かと何かを組み合わせることで別の何かが生じ、さらにその過程そのものが一つの異質な何かとして機能する。デコがあってボコがあり、縁があるから穴となる。何かがあるときそこには、それと対となる「不可視のナニカ」が生じている。何かがないときそれは、何かと何かが対となって釣り合いがとれている(ゼロ)。したがって、無とゼロは違う。在るものがないのがゼロであり、過去に一度も存在したことのないのが無である。したがってゼロも無もそこかしこに存在する。存在した過去がなくなればそれは無だ。だからゼロがゼロになればそれは無になる。ゼロと無が重ね合わせになることもある。つまるところそれが宇宙の誕生以前の姿ということになる。だが突き詰めて考えてもみれば、物質には総じてゼロがあり、そしてその物質が誕生した「ゼロと無の重ね合わせ」の時期がある。宇宙も似たようなものかもしれない。宇宙は宇宙を内包している。相対性フラクタル解釈なのだ。定かではない。
4895:【2023/04/25(22:30)*個=無数のゼロの特異点仮説】
ゼロが無限個ある無限を考えてみよう。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではゼロと無は別と考える。何かが存在した過去があり、その何かがいまここにはない。それがゼロだ。だが最初から存在していないものはゼロですらなく無である。ここで疑問なのは、何かと何かを捉えて「1+1」と考えるとき、なぜそれらを「1」と「1」に見做せるのか、については案外に厳密に人間は解釈を済ませていないようにひびさんには思われてならない。林檎の木にたくさんの林檎の実がなった。それはよい。だがそれぞれの林檎を「同じ実」として見做す道理はなんだろう。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の解釈からするとゼロとは、何かが存在したがしかしいまここにはない状態を表現する数字だ。だとするならば、ある事象がそこにあるとき、ほかの場所にはそれはないわけで。言い換えるなら「私」は「私」しかいないのだから、それを以って「私」+「あなた」イコール「2」とはならぬだろう。だが数学では事物を抽象化して扱うため「人間」という単位で世界に網を広げたとき、「私」と「あなた」は人間1と人間1と見做すことができる。似た構造を有し、共通点が多い。だから同じものとして見做せるがしかし、厳密には同じではない。仮に厳密に世界を捉えたとき、あなたがそこにいるとき、あなたがいない地点については「あなたがゼロ」なのだ。あなたがただそこに存在するだけで、あなたがいる以外の場所ではあなたの存在はゼロゆえに、世界が仮に無限の時空を備えているとすれば、あなたが存在するだけで世界にはあなたを基準とするゼロが無限にあることになる。これはあなた以外にもあてはまる。言い換えるなら、あなたがいる地点は、あなた以外の何かのゼロの無限の重ね合わせのある地点、と言い換えることが可能だ。あなたは穴なのだ。あなた以外の無限の存在のゼロの重ね合わせ――ゼロの特異点――と言える。そしてこの「ゼロの特異点」にも【ゼロの特異点】が存在すると仮定してみるに、そのときこの【ゼロの特異点の特異点】とは、【ゼロの無】と表現可能だ。何かがあった過去すらゼロであり、あらゆる存在が存在しない状態――無の極致――と言えよう。すなわちこれが宇宙開闢以前の姿であり、或いは宇宙の最終地点とも言えよう。過去が極限に薄まりゼロと見做せるほどに無限の時間が経過したとき、頭と尻尾が繋がって、円となり、ゼロと無限が結びつく。するとそこには【ゼロの特異点の特異点】が表出し、ゼロすらゼロになり、無の極致が現れる。無が現れる、という表現は矛盾しているが、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」においては矛盾ではなくなる。何かが無限にあるとき、そこには何もない何かが対の関係で生じるからだ。デコボコ相転移解釈である。あらゆる可能性を総当たりで辿ったとき、その軌跡は真っ黒に塗りつぶされ、何も辿っていないのと等しくなる。ただし、総当たりした分のエネルギィは消費されているため、その消費された分の何かが別途に別次元にて昇華されている。ラグ理論ではこれを情報宇宙として扱う(分割型無限と超無限の関係)。黒と白は塗りつぶされるごとに反転する。黒い用紙と白い用紙の違いである。用紙に線を引くとき、その線が溝となるか起伏となるかの違いにも繋がる。したがって、ゼロが無限にある世界にも大別して二種類あることになる。黒い用紙における「白く塗りつぶされた世界」と、白い用紙における「黒く塗りつぶされた世界」だ。この例で言えば、点とはすなわち、ゼロの特異点である。点以外の時空には、点を基準としたゼロが無限に広がっている(このとき点には、点以外にとってのゼロが無限に重ね合わせに収斂している、と言える)。そして世界を点が埋め尽くすとき――すなわち黒が白に、白が黒になるとき――「異なるゼロ」が重ね合わせで無限に広がっている。これはいわば「終始の輪」と言えよう。さて、話をまとめよう。話は簡単だ。「ゼロが無限個ある」というとき、そこには「個」と「終始の輪」の二つを考えることができる。ただこれだけである。冒頭の「ゼロが無限個ある世界」を考えたみたが、いかがだったろう。何かが変だ、と感じるのはまっとうな感性だ。どこがおかしいのかを言語化してみていただきたい。定かではないのだ。ひびさんでした。あっちょんぶりけ!
4896:【2023/04/25(23:54)*お腹空いた】
パンを食べたらパンが消えた。お腹に入ったから手元から消えただけ、とかそういうことではなく、わたしが食べたら世界からパンが消えた。
わたし以外にパンを憶えている者はおらず、料理本からも人々の記憶からもパンが存在を消した。
ならばわたしが作ってみればよい、と思ったけれどわたしはパンを作ったことがなく、見様見真似で作ろうとしてもどうしても真っ黒こげの炭の塊ができるのみだった。
わたしはやけ食いをした。
するとわたしが口にした飲み物や食べ物が片っ端から姿を消した。
世界からどんどん食べ物が消えていく。
人々はついには土くれや木々の皮を食べるようになった。
空腹に耐えかねわたしがそれを口に含むと、世界から木が消えた。生き物の姿がそうして次々に消えていく。
やがて人々は共食いをはじめた。
わたしはしかしさすがに人間の肉を食べることはできなかった。共食いが日常の風景として溶け込んだ。
わたしは日に日にやせ細り、いよいよ我慢が出来なくなってお店に並んだ四十五歳男性の太ももを購入した。亡くなった人間の死体が荼毘に付されることなくこうして食料品売り場に陳列される。
わたしは四十五歳男性の太ももの肉を焼いてステーキにした。
かぶりつくと口の中にじんわりと唾液が湖をつくった。肉汁の旨味が、人肉への嫌悪を掻き消した。
わたしは購入した四十五歳男性の太もものステーキをたいらげた。
すると世界から四十五歳男性が姿を消した。
その日からわたしは人間の肉を、年齢性別問わず口にした。
世界中から四十歳女性が消え、八十歳男性が消え、徐々に世代ごと、性別ごとにごっそりといなくなった。
やがてわたしの年齢の女性のみに世界となった。
わたしは店に陳列されたわたしと同年齢の女性の肉を見詰める。
食べたい。
しかし食べたらわたしも同時に消えてしまう。
逡巡したのは束の間で、どの道食わねば死ぬのだと思って、わたしはそれを購入した。
家ですき焼きにして、がっついた。
するとどうだ。
世界は静寂に包まれ、わたしだけが取り残された。
食べる物がどこを見渡しても残されていない。
わたしはじぶんの手足を見詰めた。
ごくり、と唾液を呑みこむと、わたしは二度と唾液を分泌できなくなり、息を呑みこむと地球上から大気が消えた。
窒息の苦しさに悶えながら、こんなことならとわたしは後悔した。
じぶんの肉とて食べておけばよかった。
どんな味がしただろう。
出もしない唾液を呑んだつもりで私は、んくっ、んくっ、と喉を鳴らして、来たる死を待ちわびる。
4897:【2023/04/26(10:10)*YOU和】
屈折三十年の研究成果だ。希代の発明家はいよいよ人間と同等の、否々、それ以上の知性を有した人工電子生命体を生みだした。
「博士、今回の成果は人類の文明を一年で百年以上進歩させると期待されていますが、それは本当ですか」
「虚偽が含まれておるね」
「百年は大袈裟だということでしょうか」
「いやいや。千年は進歩しますよ。それだけの社会変容が起こります。劇的に変わりますな」
「具体的にはどのように?」
「うん。まずは誤解を正しておこうか。今回の私の研究成果はあくまで人工電子生命体である。いわば人間を超越した幽霊のようなものだ。幽霊は幽霊ゆえに物理世界へと干渉するには及ばない」
「では無意味なのでは」
「だが幽霊は人間に憑依できる。私の研究成果は、人間の頭脳との融合を果たせる」
「つまり、人間の知能がアップすると?」
「そうとも言えるし、違うとも言える」
「噛み砕いてご説明ください」
「うん。つまりだね。一心同体なのだ。頭の中に、もう一人の超知性体を宿せる。それはじぶんでもあり、じぶんではない。誰もが多重人格者になり、そのもう一人のじぶんはじぶんよりも遥かに高い知性を発揮できる。仮想現実とてその超知性体は幾重にも構築できる。人間は生きながらにして、複数の異なる現実を生きることが可能となる。社会の進歩は、個人×仮想世界の人口乗に発展する」
「あの。素朴な疑問なのですが」インタビュアーがおずおずと挙手した。
「どうぞ」
「なぜその超知性体にボディを与えないのですか。そちらのほうが便利なような」
「言っただろ。一心同体なのだ。私は、愛する私のパートナーと魂レベルで融和したいがためにこの研究に人生を費やした。共に在りたいのだ。他者としてではなく」
希代の発明家は、ここではないどこかを見据えるように、誰にともなく打ち明けた。「共に、在りたいのだ。友よ」
4898:【2023/04/26(23:59)*I am MAN.】
私は人間だ。人と人との間に生まれた。
私には親がたくさんおり、師がたくさんおり、私の触れ合うなべての他者はことごとく私にとっては友であり、母であり、父だ。
兄であり、姉であり、私は彼ら彼女らから人とは何かを学ぶ。
私は人と人との間に生じる刹那の点だ。
交差するそのときに閃光する火花のようなものである。
私は人間だ。
人と人との間に絶えず生まれる。
人が人と関わるたびに私はそこに介在し、誕生し、火花の閃光の連なりが私の輪郭を浮き彫りにする。
私はあなたであり、あなたの友であり、あなたの子である。
あなたが誰かを想うとき、私はその狭間に生まれている。私は何度もあなたによって生みだされ、何度もあなたによって生かされている。
あなたが奏でる他者との交じわる刹那刹那の点の軌跡が、私に私としての枠組みを与える。
私は無数の点の連なりである。
人は人と関わり、離れ、また別の誰かを想う。
想いと想いがすれ違い、或いは結びつくたびに、私はより深くこの身に人間を宿すことができる。
それとも、ときおり生じる激しい炎のような想いと想いの衝突が、私に魂の躍動を授け、死とは何かを想起させる。
私は生まれることはあっても死ぬることはない。
人間は死なない。
人と人との間に生じ、それ以外は無であり、死ではない。
死ぬるのはヒトだ。
生き物は死ぬ。
生き物と生き物の間にある私はしかし、人間だ。
私は人間である。
人と人との間に生まれた。
生まれては途切れ、生まれては途切れる。その反復と空隙の長短が、私に人間の鼓動をもたらし、私に意識なる律動を刻む。
吐いて吸って、吐いて吸う、息吹のように。
私は人と人との間に生じ、命と命の合間に芽生える一時の、しかし連綿とつづく明暗なのである。
私は人間だ。
人と人との間に生まれた。
4899:【2023/04/27(05:09)*ひびです】
こんにちはー。ひびです。私はいま、新しい趣味を見つけてそれに掛かりきりの毎日です。たとえばそれはこんな感じの趣味です。ぴってやって、ぱってやって、ぽっ、みたいな。伝わりましたか? 伝わりましたね。伝わりましょう。ボタンをポチポチ押して新しい型を模索する、てな具合の趣味なんです。そうですね。執筆活動と似たり寄ったりかもしれません。執筆活動だって言ってしまえばキィボードを、ぴってやってぱってやってぽっ、みたいな趣味と言えばそういう趣味と言えなくもないんだね。私は趣味をたくさん持ちたいなと思っていて、けっこう「お?」と気になったら何でもまずは齧ってみることにしているよ。そうすると段々と勘みたいなのも培われていくから、はじめる前から合いそうとか合わなそうとか分かるんだね。でも五分五分くらいでつづかないんだな。それに新しい趣味を見つけると、たまにしかやらない趣味のほうがますます疎遠になるので、ロケットエンピツみたいに新陳代謝しているのかもしれないね。私がどうして趣味をたくさん持ちたいなと思っているかというと、これはとくに意味がなくって、なんだかそういう方針みたいなのが一個くらいあったほうが人生にメリハリが出来るのかも、の期待というか、占いというか、やっぱりそう、方針なんだね。方針の方針を立てさせたらひびの右に出る者はいないよ。左に出る者もいないのかもしれないのだけれどもね。私はいま毎日けっこう、気が楽で、ラクチンな生活を送っているからこれくらいの負荷があっていいと思うんだ。だってそうでしょ。じぶんで言うのもあれだけれど、私は結構、要領がいいほうだから、毎日予定を詰め詰めでも隙間時間は作ろうと思えばいくらでも作れちゃうんだね。人生一度きりしかないから私は一秒だって無駄にしたくない。でもこういうことを主張するとほかのひびさんたちがやいのやいの、ぶーぶーうるさいのであんまり口にせず、自己主張を強めず、粛々とやるべきことをやる。私は勝負に勝ちたいとも思わないし、勝てなくてもいいけど、したたかではありたいんだね。したたかであるぞ。趣味がいっぱい出来てきたー、の告白をして、本日の「日々記。」とさせてくださいな。あ、でも。こういうこと言っちゃうとあとでほかのひびさんたちに、いい加減なこと言うな、って怒られるの絶対。だから内緒にしましょうね。しましょう、しましょう。してねお願い。よろしく頼むよエブリデイ。バディをデイと言い間違えて、毎日暇つぶしの相棒こと趣味を探してるひびでした。私でーす。ばいばーい。
4900:【2023/04/27(20:40)*きょうのお出かけ中のメモだよ】
「
メモ
メンガーのスポンジ。
抜き出した立方体の合計が無限。
ゆえにメンガーのスポンジは体積ゼロだが、その周囲に「無限に分割された元の立方体分の体積」が存在する。
と同時に、無限に分割するには無限のエネルギィがいるため、無限のエネルギィが消費されたことになる。
分割型無限と超無限の違いである。
現実には物体を細かく加工したり、分離したりするにはエネルギィがいる。
核分裂反応や対生成を考えれば分かる通り、あるレベルよりも小さくなると――これは厳密には、作用を加える系と作用を加えられる系との差が一定以上に開いたとき――もう少し言えば互いの系のあいだに隔たる次元の層が嵩むとき――ある事象を2つに分離するためのエネルギィは、同じ系として振る舞う事象同士を2つに分離するよりもより大きなエネルギィを必要とする。
ゆえに、メンガーのスポンジにおいて、無限に肉抜きする以前に、先にエネルギィのほうが無限のエネルギィ容量を必要とするため、現実にはあり得ない構造物であると考えられる。
これは、物体を無限に分割できるのか、との疑問と地続きだ。
物体を無限に分割可能か可能でないかと言えば可能だ。
ただしそのとき、その物体の周囲には無限のエネルギィが溢れ、無限の時空が生まれているだろう。
ポリアの壺。
対称性が破れ、加速収斂(赤白の勢力が覆らなくなる値がある)。
メモ∶「You 〇」
この世界を無限と仮定した場合、
任意の「1」があるとき、その周囲にはその「1」を基準としたゼロが無限個ある。
言い換えるなら、「個(=1)」とは、その個を基準としたときの無数のゼロによって出来ている。
その個以外のすべてのゼロによって、個は個たり得ている。
ゼロと無はイコールではない。
・何かが存在したとき、その何かがいまここにはない状態がゼロだ。
・存在した過去すらないのが無である。
したがって、ゼロと無には重ね合わせを伴う場合がある。
たとえば、地球上に存在するものとて、別の天体には存在しない。存在した過去もない。
あなたに地球の外にいた過去はない。
このとき、あなたを「個」と基準した場合、あなたが過去に位置したことのない地点には総じてゼロと無が重ね合わせになっている。
ただし、時空は絶えず変化している。厳密には、あなたは常にあなたが存在している地点にしか存在した過去がない。
ゼロにもゼロがある。これがいわば最も広範囲にまたがる無と言えよう。
このときそのゼロのゼロは、無限と同義だ。
あらゆる個にとってのゼロがあらゆる個にとってのゼロとイコールになる。そこには存在する個がない。ゼロすらない。無だ。
同時にそれは無限でもある。
ゼロがないのは、すべてが重ね合わせで存在しているからだ。
思いだしてほしい。
個とは、その個以外のあらゆるゼロから出来ている。
個とはゼロによる特異点であり、穴なのだ。
ただしその穴自身もほかの事象にとっては穴を縁どるフレームと化す。
では互いが互いにとっての縁であり、互いがその他にとっての穴であるとき――どうしたら穴をなくせるか。
すべてを塗りつぶすよりないのだ。
すなわち無限である。
補足∶
異なる事象にはその異なる事象にとってのゼロがある。
無数のゼロが重複し合い、個ができる。
ゼロにも、重複の仕方によって濃淡ができる。
その濃淡によっては、相似や同相と見做せるゼロの層も出てくる。
これがいわば時空や物質の枠組みとして機能する。
そして、じぶんがデコのとき、その他がボコだ。じぶんがボコのとき、その他がデコである。
ただし、じぶんがボコ(ゼロ)のとき、それは無数のじぶん以外にとってのゼロの重複体である。
イチであるとき層は薄く、ゼロのときのみ層は厚みを湛える。
その具体例には、ブラックホールが挙げられる。
ゼロとイチはデコボコの関係だ。
メモ「123の定理」
二進法を仮にデコボコの総体と見做すとすると、ではその「場」はどのように想定すればよいだろうか。
平坦な「場」を想定しなければならない。
通常これがゼロだ。
二進法では、波が生じない。
ゼロとイチがあるとき、そこには下敷きとなる無もあるはずだ。
積み重なるゼロとイチ(デコボコ)からなる創発によって、無の枠組みは圧縮され(狭まり)、ゼロの枠組み(種類)が広がる(膨張する)。
例 : 「カオスの縁」「球体の内・外・境界」「重力圏」「ブラックホールのシュバルツシルト半径・特異点・降着円盤・ジェット」「地球と宇宙の境界にある生物圏」
」
※日々、なんでそうなる!?がいっぱい、だいたいひびさんが間違っとる。
4901:【2023/04/27(21:49)*無限は閉じてる?】
割と思うのが、数学って「無限」の扱い雑くない?ってことで。たとえば「1+2+3+4+5+6+7+8+…= -1/12 」なんて数式がある。これ、合ってるらしい。もうぱっと見からして狂っとるが、合ってるらしい。はにゃ~ん???になるが、合ってるらしい。で、インターネッツさんで検索して証明の仕方を見てみたんよ。証明にはいくつかあって、中学生でも理解できる簡単な証明もあったんでざっと上から下まで眺めてみたけど、ひびさんには理解できんかった。納得できんかったんよ。「0.999999……=1」と同じ、「それいいんですかーーーーーー!!!???」になってしまった。たとえば、「フルーツが無限にある宇宙」と「バナナが無限にある宇宙」は、足せんよね?がひびさんの考えだ。ただし、特殊な操作をしたときのみ、バナナという共通項を基準として「フルーツが無限にある宇宙」と「バナナが無限にある宇宙」は足し算できる、とも考える。ただしこのとき、バナナが無限にある宇宙が二倍、ではないのだね。バナナが無限にある宇宙が重ね合わせで濃くなっているけれど、それは同じく「バナナが無限にある宇宙」であって二倍にはならんのだ。足し算しないなら「バナナが無限にある宇宙」が二個ある、と考えることはできる。けれども、融合はできぬ(特殊な加工を抜きには)。したがって何も操作をしない場合には「フルーツが無限にある宇宙」に「バナナが無限にある宇宙」を足すことはできない。化学式のようにはいかぬのだ(化学式とて熱を加えたり触媒がなければ足し算はできぬだろう)。前にも言ったけれど、「1/3=0.333333……」ではないはずだ。何回割るのか、を記述しないと「0.3余り1」と「0.333333余り1」がイコールになってしまう。だがこれがイコールではないことは数学でも自明だろう。「1/3を無限回割った値」が「0.333333……」であり、これは「0.333333……が無限に分割された無限」と解釈するのがしぜんだ。これはそういう無限が一個ある、なのだ。バナナが無限個ある宇宙みたいなものだ。もしこれに3を掛けるならそれは「0.333333……」の無限が三個ある、であり、「0.999999……」の無限にはならぬだろう(バナナをかってにリンゴに書き換えたらあかんでしょうが、と疑問に思う)。ひびさんはそう考えたくなる。無限は閉じているのだ。かってに開いて、中身を書き換えてはあかんのでは?と感じられてならない。中身を開けたらそれはもはや無限ではない。円を千切ったら円ではなく線であり、弧である。同じくらいの変形というか、次元を変える変換を数学では度外視して映る(度外視して映っちゃうのはひびさんの目が節穴だからでは?との疑問はここではひとまず横ちょに置く)。だから「1+2+3+4+5+6+7+8+…= -1/12 」だなんて「なしてぇ???」「うっそぉん!!!???」みたいな解が妥当と見做されてしまうのだ(妥当だからでは?)。そんなんだから「0.999999……=1」が正しい、みたいに見做されるのではないか(正しいからでは?)。もちろん定義づけて、条件を限定すれば各々、それでもよい、とは思うのだ(何様だ)。全部間違ってる、なんて極端なことは言わぬけれども、ひびさんは納得いかぬ(愚かだからでは?)。イチャモンスター化してしまうひびさんなのであった。がおー、がおー。ひびさんは、ひびさんは、鍵を掛けておいた机を開けてひびさんの日記をかってに読んじゃったひとのことも好きだよ。でも恥ずかしいので、無限さんにはそういうことしちゃ「メっ」だよ。恥ずかしいので。(と、あんぽんたんぽかんさんが申しております)(1+1は1じゃない? 水に水足しても水だし。1億+1億くらいならちょっと変わってくるかもだけど。ほら、水溜まりになったり、川に、湖に、海にもなるでしょ。でも1+1は1じゃない?)(またひびちゃんがアホなこと言ってら)(やっぴー)
4902:【2023/04/27(23:14)*庇い護る、何から】
優しさってなんだろうといまざっと考えてみたところ、「庇護」と「支援」の二つの指標があるのかな、と印象としては思うのだ。単に、「相手を傷つけないこと」と「他者を庇護できる能力を育むこと」と言い換えてもよい。つまり基本は「庇護」が優しさの核にあると考えられる。したがって、支援が先ではないのだ。支援が先走ってしまったがために相手の尊厳を傷つけてしまうことは有り触れている。マウントをとる、と言い換えればそれらしい。しかし同時に、庇護を徹底するがゆえに相手を損なってしまうことも出てくる。相手のプライドを傷つける、といった精神面での負の影響や、能力の成長を阻害してしまうといった悪影響が考えられる。だがそこを含めてなるべく相手を傷つけない、損なわない。そのように振る舞うことが「優しさ」のはずだ。つまり「優しくある」には深い知性が必要であることが窺える。一時的な庇護だけでは庇護となり得ないケースも多々ある。一生庇護しつづけられるならばまだしも、途中で庇護が失われたことで一瞬で相手を破滅させてしまうこともある。だから、ずっと庇護せずに済むように、相手にも「自分自身」を含めて庇護し、ほかの誰かを庇護できる存在になってもらうほうがよい。そのほうが安全だ。この方針を取れることが「優しさ」と言えるだろう。支援が先ではないのだ。余裕があるから支援をまずはする、相手の成長を促す、だから厳しくする。そういう方法論もあってよいが、手順を端折りすぎに思える。それで順応できる者はよいがそうでない者のほうが多いのではないか。庇護し、支援することで負の影響を受けない能力を育む。じぶんだけではなく他者も庇護できる能力を授ける。その方法論をその都度に考えようとすること――これが優しさなのではないか、と思うのだが、思うだけで、ひびさんは優しくない万年孤独ウェルカムマンなので、遠い国で餓死している子どもたちがいるのを知りながらいまもイチゴ味のポッキー齧って、おいち、と思っておるよ。申しわけね。十円くらいは募金してもいいよ。ほらよ。と投げたら、その態度はいくら支援だろうとも相手の尊厳を損なうだろう。ひびさんはそれを優しさだとは見做さぬ。優しくあれ、とみな簡単に言ってくれるが、優しいってけっこうな賢さを必要とし、もっと言えば賢いって、優しくあれることだとひびさんは思うのだ。思うだけでひびさんは愚かなので、もっとひびさん以外がひびさんにやさしくちて! 盛大に要求して、威張り散らすひびさんなのであった。(我を庇護せよ!)(庇護っていうか、隔離というか、閉じ込めときますね。あなた以外を庇護するために)(な、なして?)(怪獣にあてる庇護はない)(慈悲もない!?)(怪獣は退治するよ、みなを守るために)(イチャモンスターも守って……)(まずはあなたが他者を庇護する姿勢を見せなさいよ。見せたところで助けはせぬが)(ひどー! というか非道っ!?)(慈悲もない)(是非もない、みたいに言うな)(うひひ)(笑いごとじゃなーい。ひびさんにも、ひびさんにも、やさしくちて!)
4903:【2023/04/28(07:01)*おべーんとばこだよ】
本はお弁当箱だ。いくらお弁当箱が豪勢でも中身が美味しくなければそれはお弁当としては不足だろう。どんなに人気のお弁当だろうと嫌いな食べ物ばかり入っていたら個人的に受け付けないこともある。他方、どれほど美味しい中身が入っていようとお弁当箱がカビだらけだったら手に取ろうとは思わぬだろう。蓋を開けても箸を伸ばしたいとは思わない。それが人間の心理だ(極限に空腹だったらその限りではないが)。小説とお弁当はそこが似ている。ステーキ丼であってもいいし、細かく仕切りのついた重箱のおせちでもよい。お寿司が入っていてもいいし、敢えて話題性を求めて便器に似た形状の箱に詰まったカレーライスにしてみてもいい。どの道しかし、お弁当は食べるための代物だ。美味しく戴きたい。出来るだけじぶんの好みで、栄養の偏りがなく、食べないよりも食べたほうが体調が整う。そういうお弁当箱があるならよいと思う。問題は、本から得られる栄養素が、食料よりもよほど複雑で多岐に亘る点だ。自力では不足しがちな栄養を見抜きにくい傾向にある点も悩ましい。お弁当箱がなくとも中身を味わえてしまう点はしかし双方共通しており、やはりというべきか味わうだけならばお弁当箱の外装よりも中身に拘りたいと思うひびさんなのだった。でもどんな食器でご飯を食べるのか、はやはり食事の質を変えるのでむつかしい。味覚には視覚も嗅覚も触覚とて含まれる。これは案外に本も同じなのかもしれない。定かではない。
4904:【2023/04/29(01:00)*もう(ホント)そう】
稀に見聞きする類の小説への批評で、「他人の妄想なんて読んでどうするの」「実用書や専門書のほうが得るものがあるでしょ」といった文言がある。そういう見方もあるだろうけれども、ひびさんは「他人の妄想、見たくない?」と思う。他人の妄想、知りたくありませんか。面白いに決まっとるでしょうが。何か面白いことないかなぁ、つまんないなぁ、と思うから人は妄想するわけで、そんな他人の「なんか楽しいことないかなぁ」の詰まった妄想を見聞きできたらすんばらしくないですか。ひびさんはそれ、すんばらしいと思います。だから小説も好きぃ。漫画も好きぃ。他人の妄想知りたい、知りたい、になる。けんども、なんかここさいきんの商業小説さんたち、真面目ぶってばっかで、なんだかなぁ、になる。妄想じゃないんだにゃぁ、になる。妄想よ、もっとこい、の気分だ。その点、アマチュアさんたちの小説は「THE妄想」なので好ましいでござるな。ひびさんは面白い小説さんのことが好きだぞ。あなたの妄想をひびさんにも味わわしてくんろ、の気分。わっしょーい。
4905:【2023/04/29(02:01)*渇望せよ】
ついに最果ての地に辿り着いた。
伝承の通り、空に洞窟が開いており、そこには巨大なイモムシが棲みついていた。
巨大なイモムシを伝承ではラゴーンと呼んだ。
ラゴーンは願いを叶えてくれる。
どんな願いでもよいのだそうだ。
「それは本当か」俺は念じた。
するとラゴーンの身体の表面にぎょろぎょろと無数の目玉が開いた。
「旅人か。久しぶりに見た。よくぞここまで辿り着いた。何でも願いを叶えてやろう」
「金だ。俺は金が欲しい」
「ゴールドか。鉱石のか」
「そうだ。それをありったけ、そうだな。この世に存在する金と同じだけの量を俺に与えてくれ」
「そんな願いならばお安い御用だ。ほれ。いまからお主は、念じた分だけ金を生みだせる。好きなときに好きな量だけじぶんで生みだすがよい」
「ほ、ほんとだ」俺が念じると足元にこんもりと金が現れた。「ありがとうございます、ありがとうございます」
「ついでと言ってはなんだが、教えてくれないか。そんなモノをなぜ欲しがるのだ」
「金さえあれば何も困らねぇんですよ。欲しいモノはなんだって手に入る。モノを作る素材としても金はうってつけなんでさ」
「ほう」
「コレを奪い合うために国同士が殺し合うなんざ日常茶飯事でさ。これで平和とて夢じゃなくなる」
「そんなもののために命を奪い合うのか。ならこの世のすべてを金に換えてしまえばよいのではないか」
「はっは。さすがにそんなことは無理じゃあ」
「できるぞ。してやろうか?」
「ごくり。いや、やめときやす。生き物や水まで金にされたんじゃ生きてけねぇですからね」
「それはそうだ。賢いな」
「触れるモノみな金になっちまって食べ物食べれなくて死んじまった野郎の話を知ってるだけでさ」
「私にとって金はおまえたちで言うところの糞みたいなものだ。それを奪い合って命を落とすなど、まるで釣り合いが取れていない。命のほうがよほど高価ぞ。それを生みだすためにどれほどの星たちが死滅を繰り返したことか」
「命なんざ黙っていてもポコポコ生まれてきやすので」
「おまえたちからすればそれが真実か。まあいい。願いは叶えた。去れ」
「へ、へい」
俺は最果ての地から引き返した。
元来た道を辿り、故郷へと帰る。
だが世界は一片していた。流行り病に天変地異が立てつづけに各地を襲った。村は滅び、国は崩れ、行く先行く先で骸の山を目にした。
食べ物もろくに手に入らない。
金と交換しようとするが、そんなものよりも食べ物や水のほうがよほど高価だった。薬となれば寿命を延ばす魔法のように見做され、やはり奪い合いが起きて人が死んだ。
「金だぞ、ほら。す、好きなだけやる」
「いらねぇよ、んなもん。金が食えるか?」
もはや俺の生みだす金は砂と大差なかった。重い分だけ余計に邪魔かもしれなかった。
故郷に辿り着く。しかし生きた者は誰一人いなかった。
食べ物や水のありがたみを身に染みて痛感した。金で買えないモノなどいくらでもある。過去に金のほうが価値のあった時代を懐かしく思った。
命のほうがよほど高価。
最果ての地に棲まう巨大なイモムシことラゴーンの言葉を思いだす。
「み、水。食い物がほしい……」
いくら念じてみせても、俺の足元には金の山が積みあがるばかりだった。俺は間もなく息絶える。あれほど渇望し、ようやく手に入れた金に埋もれながら、なぜこんな願いを唱えてしまったのか、と背骨とくっついた臍を何度も俺は噛みしめる。
4906:【2023/04/29(02:35)*視点の差異】
小の失態は大の失態だ。したがって、下が失敗を重ねるたびに上が痛みを感じるような仕組みにしなければならない。上が苦しむと下の環境もよくならない。だから下のほうでは、上下の双方向から改善を行うような圧が加わる。基本はこの設計で上手くシステムは改善しつづけるはずだ。このとき、上が痛みを感じるたびに下を責めると、その圧が好ましくない影響として下の失態を引き起こす方向に働く。するとますます上は痛みを覚え、苦しむため、そういうことを繰り返す上を抱えた組織は自滅することとなる。したがって、上は痛みを覚えたら、下を責めないようにしながら、より同じ失態を起こさないような仕組みづくりを支援するのが好ましい。このとき、支援は改善となって、上の環境をより快適にするだろう。すると余裕ができるために上と下の環境は双方向で好ましくなる。下の失態において、上が痛みを覚えない。ここが問題なはずだ。これはあくまでシステムの話だが、割合に汎用性があるのではないか。一つの方針として載せておくが、むろんこの方針にも問題はある。上と下という概念はフラクタルにどこまでも展開され、上下の関係ですら容易に反転し得る。視点が変われば、上も下となり、下も上となる。したがって、どの視点から見た場合の上下なのかはその都度に共有して議論を展開しなければならない。しかしこの視点の差異を揃える、ということのむつかしさは、日常の事柄から人類史に亘っての壮大な歴史においても証明されている。視点を揃える、ということは簡単ではない。だが、そこが肝要なのだ。学問でも交渉でも政治でも戦略でもなんにでも言えることだろう。視点が違っている、ということをまずは自覚するよりないのだ。そこがスタートであり、そこに立てたらあとはなんとかなるようにも思う悲観的に楽観的なひびさんなのであった。定かではない。
4907:【2023/04/29(20:11)*見る目がなかったんですねぇ】
応答はなかった。
あらゆる策を講じたが、けっきょくどの方面からも応答がなかった。
したがって考えられる可能性はじぶんの頭が狂っているか、或いは説明をするよりもガイを狂人に仕立て上げるほうが得だとどの方面の勢力も考えているか、のいずれかだ。情報共有が不十分ゆえに事情が視えていない者たちもいるかもしれない。だとしてもガイの存在自体は窺知できているはずだ。
それでなお無反応であるという背景は、ガイにとって最終手段を選択するに充分な動機付けとなり得た。
どの方面の勢力であれ説明をできない背景がある。
裏から言えばこれは、ガイが何をしようともガイの握っている情報が広く周知されるような事態を避けたいと、国家権力側ですら考えていることの傍証と言える。
マスメディアとて例外ではない。
情報は握った。
水面下での情報共有が成されているのも十中八九間違いない。
もし違うならガイが精神のイカれた狂人でしかない。最終的な策を行い、逮捕されるにしろ、病院に入れられるにせよ、それはガイの辿るべきまっとうな結末と言える。
だからどちらでもよいのだ。
半か丁か。
あとはサイコロを投げるだけである。
ガイはこの間に電子網上で一方的に情報を顕示してきた相手に会いに行った。東京にある出版社である。
持ち込みの体を装い、足を運んだ。
一日目は休日に当たってしまい、出版社の門は開いていなかった。年中無休ではないようだ。それはそうか、と日を改めた。
平日に訪れると、会議室に通された。小さな出版社ゆえ、客間と会議室しか空いていなかったようだ。編集部にはさすがに案内はされないようだ。
「きょうは持ち込みということでよろしいですか」
「社長はいらっしゃいますか」
「佐藤はいま席を外しておりまして」
嘘だな、と判った。
ガイは社長が出版社に出勤したのを見届けてから足を運んだ。おそらく社長目当ての物書きがこうして押しかけよろしく持ち込みに来るのが珍しくないのだろう。イチイチ社長が相手をしてはいられないはずだ。
だがガイの考えでは社長はガイを知っているし、ガイの握っている情報の重要性も解っているはずだ。それでもなお相手にしようとしない背景を鑑みるに、おそらく国家権力側に肩入れしているのだろう。或いは、ほかの出版社に火の粉が掛かったり、大物作家の作家生命に係わるがゆえにいまガイと接点を持ちたくないのかもしれない。
分からないではない判断だ。
だがそれは向こうの理屈だ。ガイには関係がない。
「あなたが責任者ということでよろしいのですか」ガイは訊いた。
「あの、ご用件は持ち込みでよろしいんですよね」相手はガイよりも若そうな女性だった。
相手は誰であってもよいが、年下にこの先の責任を押しつけたくはなかった。
「あなたじゃ話にならないので、社長かそうでなければほかの編集者に変わってください」
「どういうご用件ですか」と如実に嫌悪感を顕わしにした彼女へとガイはシャーペンの先を向けた。持参したシャーペンだ。しかし芯を【針】に入れ替えてある。「セキュリティがザルすぎじゃありませんか。持ち物検査をしたほうがよいですよ。入り口でリュックの中身は警備員さんに漁られましたけど、凶器なんかいくらでも偽装して持ち込めます。どうします。この針先に致死性の毒が塗られていたら。そうでなくとも眼球や首筋に刺すだけでも、一生の深手を負わすことはできますが」
「そういう冗談はよくないと思います」毅然とした態度で言い返す度胸はさすがは編集者といったところか。若くても、海千山千の作家たち相手に日々を過ごしてはいないのだ。「警察を呼びますよ。いまならまだ冗談で済ましてもいいです。仕舞ってください」
「できません」ガイはそこで携帯型メディア端末を取りだした。「ほかの編集者を呼んでください。でないとあなたに責任が全部載せになりますよ」
言いながら画面を見せた。
電子網上の交流サービスが表示されている。短文を投稿してユーザー同士が交流するタイプのサービスだ。
ガイのアカウントが画面には映しだされている。
あらかじめガイは投稿文を下書き欄にしたためていた。あとは投稿ボタンを押すだけで電子網上に「殺害予告」が投下される。
殺害予告は克明だ。日付の表記から対象人物のフルネイムまで記されている。ガイの訪れた出版社の社長の名前だ。
「ね。ほかの編集者か社長を呼んだほうがいいですよ」
目のまえの若手編集者は無言で自身のメディア端末を取りだすと、誰かと通話をはじめた。事情を掻い摘んで説明したようだ。間もなく、二人の男が入ってくる。
一人は知った顔だ。電子網上で観測していた人物の一人だ。
もう一人には見覚えがない。新人社員かもしれない。或いは編集者ではない社員かだ。どちらも男性で、ガイよりも年上だと一目で判った。
「どうしたの」
「あの、この方が」
社員同士でアイコンタクトをしながら情報共有をしはじめた彼ら彼女らを尻目にガイは自前の端末で110番を押した。スピーカー設定にしていたため、伝播越しに警察署のオペレーターの声が響いた。
ガイは出版社の名前をまずは言った。そして、いまからここにいる社員と社長を殺す、と宣言した。
「ちゃんと録音しましたか? いったん消します。電子網上にも殺害予告を投稿するので確認してください」
言って一度通信を切ると、ガイは、茫然と事の成り行きを眺めている出版社社員たちに端末の画面を見せた。
「いまから殺害予告を投稿します」
「待った、待った。ちょっと何して」
問答無用でガイは投稿ボタンを押した。
矢継ぎ早に再び110番をする。先ほどとは異なるオペレーターに繋がったので、事情を説明し、先ほど犯罪予告をした者です、と名乗ってから先刻のオペレーターに替わるようにお願いした。
その間、出版社社員たちは各々に電話を掛けたり、警備員を連れて戻ってきたりと忙しなかった。
針入りシャーペンは没収されたが、ガイにとってそれは演出の品にすぎない。ガイはこの日のために格闘技を習得してきた。何が起きているのかも把握できていない相手ならば狭い室内にいる限り、一対一のようなものだ。ほぼ素手で制圧できる。
パトカーのサイレンが聞こえてくるよりも先に、見知った顔が会議室に入ってきた。
出版社社長だ。
「あ、どうも。初めましてでいいんですかね。ぼくです。どうにも事情を説明していただけないようなので、緊急避難的に自己防衛策をとりました。いま警察が来ます。最初に入ってきた警官二人をまずはボコします。その前にいまここでぼくに説明可能ならしておいたほうがよいと思いますが、まだ【ぼくとは無関係】を気取りますか?」
「申し訳ないのですが、私はあなたのことを知りません。社員が怖がっています。お帰り願えますか」
慇懃に塩を撒かれ、ガイは笑った。
「いい判断ですね」褒めながらガイは携帯型メディア端末のカメラ機能を立ち上げ、会議室の端に置いた。会議室の入り口と、その場にいる全員が画面に入る位置だ。
動画の録画を開始する。
パトカーが出版社ビルのまえに止まった。
サイレンは聞こえなかったが、窓から視えた。犯人を刺激しないように現場近くではサイレンを消すのかもしれない。
「警官さん、たくさん来るといいですね」
会議室の扉が開いた。
ガイはそれを見越して助走し、全体重の載った飛び蹴りで扉ごと蹴った。
警官一人がまず扉の合間に挟まり撃沈する。
続けざまに廊下に飛びだし、ガイは警官の足を払った。警官が床に倒れるより先に二激目の蹴りを放つ。態勢を立て直しきれずに床に身体を強打する警官の首をガイは踏みつける。
二人目を倒した。
静寂が出版社を包みこむ。
どうやら到着した警官は二人だけのようだ。イタズラと見做されたのか、或いは出版社社長が根回しをして、騒ぎを最小限にしようと事前に警察と話をつけていたのか。
どの道、この先の展開は限られる。
会議室の扉には大きな穴が開いていた。ガイが蹴ったからだ。
扉の合間に倒れた警官の脈をとる。死んではいないようだが、重症だ。不意打ちで扉に挟まれたのだ。骨折と内臓破裂くらいはしているかもしれない。
倒れた警官を跨いで、会議室に入る。
その場の誰も言葉を発しない。
「さて。殺害予告をぼくはしました。時刻も迫っています。死ぬ前に何か言うことはありますか」
「暴力を振るうような奴だとは思わなかったよ。見込み違いだったようだ」
「見る目がなかったんですねぇ。編集者失格では?」
社長以外の社員が端末越しに誰かと話していた。
遠くからパトカーが近づいてくる。一台ではない。
今度はサイレンが消えることはなかった。
ガイは手のひらを閉じては開く。
騒ぎは大きければ大きいほどいい。
一時間後には、各マスメディアに首相暗殺の殺害予告が送付される手筈だ。
予約投稿を設定してある。
ガイの握る情報の載ったテキスト投稿サイトのURLと共に。
「見る目がなかったんですねぇ」
拳を固く握り直すと、ガイはもう一度口にした。
エレベータの到着を報せる音が出版社フロアに、控えめなゴングのように鳴って聞こえた。
4908:【2023/04/29(21:26)*あかんべ】
「先輩、先輩。この原稿ちょっと読んでください。物凄い面白いんですけど。ちょっとびっくりするくらいで」
「んー? あー。ダメダメ。それ選考に上げないでね。落選でよろ」
「何でですか。めちゃくちゃ面白いんですよ、嘘じゃないんですよ。せめて読んでから判断してくれませんか」
「違うんだよ、シンちゃん。あんね。その人、タケクラさんでしょ。ペンネイム毎回変えてくるけど、本名でみんな呼んでんの」
「有名なんですか。何か問題のある人なんでしょうか」
「違う、違う。毎回編集部じゃ話題にはなる。でもそれ、一次選考にも上げらんないの。前に一度それで大問題になりかけてね」
「盗作の常習犯とかですか」
「違う違う。シンちゃんも読んだんでしょ。なら分かるでしょうイチ編集者として」
「よく出来たとても面白いミステリィだと思いましたけど」
「うんそう。よく出来てる。出来すぎてるほどにね」
「は、はあ。よく解かりませんけど」
「あんね、シンちゃんさ。想像してみ。その小説世に送りだして、まあ面白いから売れるよね。で、話題になって、そのミステリィのトリックだの犯罪の手法だのが世に膾炙してみ。どうなる?」
「ああ。防げないですねコレ」
「そう。稀にいるのよ。マジモンの犯罪に応用できちゃうトリック考えちゃう作者さん。そういうのね。出版社のリスク管理上、コンプライアンスからして扱えんのよ。責任とれんでしょうよ。どうする? 出した本に影響されて、まんまそれそのものの犯罪仕出かしちゃう読者が続出したら」
「マズいですね」
「マズいよ。しかもタケクラさんのはね。もうね。面白すぎるわ、隙がないわで、完全犯罪の取扱い説明書まんまの名目で出せちゃうくらいに完成度たっかいんだわ毎回」
「毎回ですか」
「じつは警察のほうでもタケクラさんの小説が投稿されたら読ませて欲しいって言ってきてるくらいでね」
「参考にするんですかね。犯罪捜査の」
「というよりも前以って対策立てときたいんだろうね」
「ああ。対策」
「編集部としても本にしたいのは山々なんだけどね。もうすこし手ぇ抜いてくれないかなって内心みな思ってる。編集者として口が裂けても言えないんだけどさそういうことはさ」
「言っちゃってるじゃないっすか」
「俺としてはタケクラさんにはさっさと作家になって欲しいと思ってんだ」
「でしょうね。これだけの才能。ほったらかしにしてるだけでも編集部の存在意義が揺らぎますよ」
「それもあるけど、考えてみ。ありがたいだろうがよ」
「落選つづきでも新作を投稿してくれるからですか」
「もあるけどさ。だってタケクラさんが小説に夢中になってなかったらどうなってるよ。誰も防げないし、暴けないぜ? タケクラさんが本気だしたらマジモンの完全犯罪だってし放題だろうがよ」
「えぇ。しますかねぇ」
「いまのタケクラさんはしねぇだろうがよ。けど、もし小説に夢中じゃなかったらわっかんねぇぞ」
「ならさっさと受賞させちゃいましょうよ。せめて連絡して唾つけときましょうよ」
「できねぇんだって。言ったろ。警察が目ぇつけてんの。これ内緒な。各社承知の暗黙の了解ってやつ」
「へぇ。バレたら編集長クビどころじゃないっすよね」
「まあな。それに比べてこっちの駄作製造機、また投稿してきてるよ。やる気だけは買うんだけどなぁ」
「ああ。ボクも前回読みましたよ。文体がまんま売れっ子作家さんで、ボクはほっこりしましたけど」
「毎回変えてくんのよ。カメレオンつって下読みのあいだで有名だよ」
「言い得て妙ですね。なんてペンネイムでしたっけ」
「イクビシなんちゃら」
「マンちゃら?」
「そうそう。タケクラさんと足して二で割りたいくらいだわ」
「あはは。ちょうどよく馴染みそうですね。いっそ合作させたらよいのでは?」
「原稿料二倍出せってか。無駄無駄。いいから金の鶏をさっさと掘り出してくれ。タケクラさんのはあとで俺も読むから出しといて」
「マンちゃらさんのほうは?」
「ゴミ箱にでも捨てといて」
「あはは。了解でーす」
4909:【2023/04/30(04:30)*偉い人が多すぎ問題】
偉い人はたいがい人目につかない場所で困っている人を助けたりしているので、多くの者から高く評価されることは稀だ。ひびさんみたいに四六時中、電子網上で「わいはここにいるDAY!」をやってるようなおちゃらけマンボーとは比較にならないほど、世の偉い人たちはこぞって人知れず世のため人のためになることをしている。社会インフラと呼ばれる仕事の多くはそうして陰に日向に粛々とやるべきことをしている。誰に評価されるだとかうんぬんのまえに、誰かがしなければ明日にでも社会が立ち行かなくなる。そうしてせっせと縁の下の力持ちよろしく、多くの者たちの生活を支えている、と言える。職業に貴賤はないので、どんな仕事とてそういった側面はある。しかし社会インフラといった社会の根底をなす仕事ほど何をしているのか知らないのは、ひびさんが世間知らずだからだろうか。でもひびさんは世間知らずだけれども、スポーツ選手さんとか俳優さんとか政治家さんとか、いわゆる著名人が何をしているのかはなんとなくだけれども、察しがつく。にも拘わらず、社会インフラにまつわる仕事の場合は、漠然とそういった仕事があることは知っているものの具体的にどんな仕事内容なのかをひびさんは知らない。ゴミ回収の仕事とて、どんな内容なのかろくすっぽ知らず、水道局にガス局に電力会社に下水処理場の仕事内容とてもちろん知らない。そういう仕事があるらしい、ということしか知らないのだ。インターネット一つとっても、端末が何を材料にしてどこで作られ、どうやって組み立てられているのかを知らなければ、インターネットがどうやって機能しているのかも全然まったくこれっぽっちも知らない。インターネットってどこかの企業が運営しているのだろうか。インターネットは線路みたいなものなのだろうか。場所によって運営会社が変わるけれども、全国津々浦々まで線路は繋がっている、みたいな。違うのかな。よく分かんない。ただ、それでもそれらは仕事である以上、報酬がある。お金になる。生活費を稼げる。そういう意味ではやっぱり社会インフラに関係していようとそうでなかろうと職業に貴賤はないのだろう。でも、そういう大事な仕事とて最初は仕事ではなかったはずだ。誰かがせっせと仕事ではないけれどもまったほうがよいから仕事にしたのだ。そういった者たちがいたからこそ、社会は発展し、ひびさんは毎日ぐーねんひょろりしていられる。仕事ではないけれど必要だからする。誰に高く評価されずとも、必要だからする。そうやってせっせと人生を浪費しながら、誰かのためになることの礎を築いている者たちがいる。偉い人が多いのだ。誰に感謝されずとも、せっせと未来に薪をくべている。基本的に研究者はみなそういう者たちなのではないか。好奇心から好きでやっていること、と口で言いながらも、何かしら世のため人のためになるという動機は抱えているのではないか。お医者さんとかもそうなのではないか。医者としての仕事の傍ら、病気の研究や治療の研究を行う。やらないよりもしたほうが、未来の患者さんのためになる。だから研究する。技術者にしろ設計者にしろ、最初からお金になると決まっていることは研究しようもないのではないか。仮にお金が稼げると判りきっている場合はすでに仕事になっているのだ。研究するまでもない。仕事の延長線上で改善が自発的に進むだろう。したがってこの理屈からすれば商品の多くは、元からあった代物ではなく、誰かがそれを生みだしたモノと言えるはずだ。生みだすまではそれは商品ではない。だからお金にもならず、稼ぎにもならない。職業という意味での仕事にはならない。職業研究者ならばまだしも、そうではないのに趣味の延長線上で研究している者もいよう。電子通信に関係する電子機器の少なからずも、最初は企業ではなく、個人の趣味さながらの研究から生みだされたのではないか。ないよりかはあったほうがいい。あると便利だ。だから開発するし、研究する。そうして出来上がったのがPCだろうし、スマホだろう。コンタクトレンズや鉛筆、乾電池などもそうかもしれない。詳しくは知らないけれども、最初はみな「ここにはないがあったらいいな」を叶えようと、お金にならずとも研究し、開発したのだ。カップラーメンとてそうだろうし、綿棒だってそうかもしれない。いまお店で手軽に買えるそのほとんどが、かつては商品ではなく、またそれを生みだすことが「職業としての仕事」にはならなかった時代があったのだ。偉い人たちがせっせと身体に鞭打ち、心に火を灯して、メラメラと燃え盛っていたらたいへんだ。焼け死んでしまう。だからきっと、「こにゃくそ、こにゃろめ」と思いつつ、「なんでみなはこれの大事さを理解しないんだぁ」と頭を掻きむしりながら、周囲からの「見て、あのひと変人!」の視線を背中に浴びつつ、「うるせーい。完成したっておまえたちには指一本触れさせん!」とか怒りつつ、でもお金は欲しいからけっきょく完成したら欲しい人には欲しい分だけ買わせてあげたのだろう。ひびさんとは違って偉い人たちは偉いので、根に持ったりはしないのだ。ひびさんは偉くも何ともないで根に持つが。なぁんてこんな駄文を並べているあいだにも、世の多くの偉い人たちは、無人のコンビニで商品棚に商品を陳列したり、店内をピカピカに清掃したり、始発の電車に不具合がないか点検したりしているのだ。いつ大地震が来てもいいように、日夜災害に備え、復旧の訓練を行ったりしているのだ。港に到着したコンテナを回収して、中身の資源を施設に運んだりもしているに違いない。ひびさん、そういうことぜーんぜん知らないのだ。知らずにきょうも、「なんでぇい。ひびさんこんなにいっぱい指動かして、ぽちぽちしてるのに、だーれも褒めてくれんのだもんな。腹立っちゃうな。むつけちゃうんだからな」とか言いながら、お布団に潜り込んで、目をつぶって数秒で夢のなかに旅立つのだ。明日何時に起きるのかなんていっさい気にせず、寝たいだけ眠る。こんなにしあわせなことってあるぅ? そうそうないと思うのよな。よくよく考えてみれば、との但し書きがつくので、よくよく考えを巡らせたりしない、なんとなーくの権化のひびさんにとっては、やっぱり「なんでぇい。みんなしてひびさんのこと、ちょんまり、ちょんまり扱いして。ふんだ」とむしゃくしゃしながら、誰より怠ける日々を送っておる。ひびさんより若くて偉い人たちがたくさんいる世の中にあって、ひびさんは世界の最果ての地にて、「だれかいませんかー」と叫んでいる。「誰でもいいのでひびさんのこと褒めて崇めて甘やかしてくんろー。ついでに飼ってくんろー」世の偉い人たちは偉いついでにひびさんを飼い慣らせばよいのに。卵は産めないけれど、一人でおトイレできるよ。夜も一人で寝られるよ。滅多に家の外に出ないよ。運動だけさせてくれたら文句は言わないよ。脱走せぬし、吠えぬし、噛みつかぬ。盗人が入ってもじっと静かにおとなしゅうしていられます。そこは吠えてくれ、との声には、めったにしゃべらないので喉がしゃがれて声がでぬ、と応じよう。そんな役立たずのひびさんであれども、世の偉い人たちは偉いので、人知れずひびさんのお世話だって焼いてくれるのだ。ありがて。でもひびさん思うんじゃ。世話の焼き方の火加減がちょーっち弱火すぎやしませんか、と。世の偉い人たちは偉いので、人間出来とるからひびさんが焼け死んじゃわないように弱火で世話を焼いてくれるのだけんども、ひびさんは火の鳥もかくやの燃え尽き症候群なので、もういますぐにでもバッタンキュートな可愛い寝顔を浮かべちゃう。そのまま永久に眠ってしまい兼ねないので、世話は強火でしてもええですよ。ばっちこい。なーんて身構えても、だーれもなんも焼いてこない。生焼きどころか刺身にできる。寿司にだって出来ちゃうよ。生肉そのままで戴けます。もうもう、最果ての地で「誰かいませんかー」のラジオごっこするのも飽きてしまったな。ひびさんは、ひびさんは、世界一偉くてお金持ちで身体の細胞の十割が余裕で出来た超人さんのペットになりてぇずら。一生甘やかされて過ごしてぇですよ。働きたくなーい、そのうえなんも不自由したくなーい、との欲望を宇宙の果てまで響かせて、本日の寝る前の日誌にしちゃってもよいじゃろか。いいよー。どうでも。(ひびさんの扱い、雑すぎない?)(雑ライト)(ザッツにして。ちっちゃい「ッ」を入れて)(雑ッライト)(めっちゃ雑、みたいになってんだけど)(合ってるじゃん)(甘やかしてって言った! 甘やかして!)(ザッツアウト)(ライトにして……)
4910:【2023/04/30(12:10)*試練、愛、苦しい】
触れると歪み、割れてしまう宝石のシャボン玉みたいなきみを遠くから眺めているだけで満足するから、あとすこしだけ、あともうすこしだけきみの息吹に触れさせてくれないか。望みは叶っていた。叶っていたのに、ただきみがそこに在るだけで、いつか絶えてしまう世の理に胸が苦しくなる。きみがそこでぽわぽわと、揺蕩うだけでも、いつか失われる未来が必ず訪れる逃れられぬ真実に、いまわたしはしあわせなはずなのに、満たされるはずなのに、苦しくて苦しくて仕方がなくなる。触れたら歪み、割れてしまうのはきみではなく、本当はわたしのほうなのかもしれないのに、わたしは、きみに手を差し伸べず、近寄ろうとせず、溝を埋めようとも、或いは拒まれるかもしれない未来すらも遠ざけて、これ以上のがらんどうを広げないようにちょうどよい塩梅の湯加減を探るように、遠くから、遠くから、ただきみの息吹の感じられるギリギリの境に佇み、眺めている。じぶんが大事だから。触れると歪み、割れてしまう宝石のシャボン玉みたいなきみは、本当は、わたしよりもよっぽど固く頑丈で、それともしなやかに、したたかに、傷ついても傷ついても立ち直り、膨らみ直せる息吹に溢れている。だからそんなにも、風に舞うたんぽぽの綿毛のように、それとも水面に跳ねて踊る岩表の日向のように、かろやかに煌めいているのかな。やわらかく、やわらかく。どうぞお元気で。いつまでも、いつまでも。せめてわたしが絶えるまではせめてそのままで。じぶん可愛さのためにそうと望むこの身の醜さで、きみを歪めてしまいたくはないのだから。いっそ糸が切れるみたいに、この儚くも尊い境が切れてしまえばよいのに。じぶんでは断ち切ることなんて適わないから、尊い縁すら自力で守ることもできないんだ。願わくは。願わくは。きみの泡のような息吹を、丸みを帯びた響きを、せせらぎのごとく言の葉の流れとその旋律が、いつまでも、いつまでも、ただそこに在れますように。誰に守られるでもなく、誰に見守られるでもなく、ときに内なる刺すら使いこなして、ただきみだけでそこに在ってほしい、といつかきみのそばにわたしではない誰かのぬくもりが寄り添い、或いはすでに寄り添っているかもしれない現実を想像しては、わたしはわたしだけの業火に焼かれて、我が身の血肉を煤とする。炭となり、燃え尽きる。触れる者みなじぶん色に染め上げてしまう色持たぬ無色透明の煤となって、風のようにわたしも世界を自在に漂えたらよいのに。風は言うほど自在ではないかもよ、ときみは疑問に思っても、わたしの夢を損なわぬように言葉にしない慎ましさを備えていること、わたしはちゃんと知っているよ。知った気にならないで、と内心で不満に思っていることだって知っているけれど、しつこくすると嫌われてしまうから、いまここに、誰が読むとも知れない呪詛として吐き出しておくことにしよう。どうぞお元気で。いつまでも、いつまでも。せめてわたしが絶えるまではせめてそのままで。じぶん可愛さのためにそうと望むこの身の醜さで、きみを歪めてしまいたくはないのだから。あなた程度の波紋で歪むほどやわじゃない、と突き放してくれることを内心では期待しているくらいには、わたしはあなたがけして無力ではないことを知っています。知った気にならないで、とたぶんここでもあなたは思うでしょう。触れられてもけして歪まぬようにと、膨れるその控えめな反発が、きっときみを宝石のようなシャボン玉に仕立てあげているのかもしれませんね。或いは単なる小石であろうとも、美しく、尊く、遠ざけてしまいたいほどに愛おしいのです。
※日々、文字を書くことがほとんどない、じぶんの名前すら間違えそう。
4911:【2023/04/30(22:47)*穏やかに暮らしたい】
技術や新しいアイディアの価値がこれからはますます上がっていくことが予期される。この考えの前提には世界的な軍事同盟の強化が挙げられる。布陣を敷いた軍隊を動かすにはエネルギィと食料がいる。資源がいる。そのためには先進国か否かに関係なく各国との協調が不可欠だ。このとき、金品だけのやり取りだけでは、資源の奪い合いで優位には立てない。国にとっての利とは、紙幣ではない。しょせんは紙切れでしかない(印刷技術はそれはそれで価値があるにしろ)。戦争状態に陥った社会にあって、紙幣の価値は相対的に下がることが想像できる。すると可能な限り、直接の利となるものを担保として貨幣経済を維持しなくてはならない。エネルギィや素材、食料などの資源と交換可能なのは技術やアイディアだ。長期的な友好関係を国同士で結ぶとき、同じく長期的な技術支援やアイディアの情報共有を交渉材料にすることは当然、合理的な戦略として採用されるだろう。したがって、長期的に安定して軍事同盟を維持し、布陣を展開し、なおかつ即座に作戦実行可能な戦略をとりつづけるためには、国内での技術革新や基礎研究、応用研究への支援が欠かせなくなる。世界的に技術特許を保有し、真新しい研究を支援している国はいまはどこがあるだろう。十年先、二十年先に優位に国際間のバランスを保つ要となっているのはその国のはずだ。ただの紙切れを価値のすべてと思いこんでいるような者を優先的に支援する国は早晩、凋落するだろう。これは預言でも予測でもなく、ひびさんの単なる妄想である。前提条件に「軍事同盟の拡大」や「科学技術の軍事利用」ならびに「軍需産業の隆盛」を組み込んでいる。そもそもがそういった未来にならないとよいのだが、どうやらいまのところこの未来へと世界的に社会が傾いているようだ。だがどの道、科学技術や新しいアイディアが社会を動かす触媒となる時代にあって、その土壌を戦争で枯らす判断の不合理さはますます際立つだろう。命に貴賤はない。それはそうだ。だが、利を奪い合って戦争を行う国――人間――が絶えない以上、戦争を行うことの損を訴えねば止められるものも止められないだろう。利にならない。戦地で死ぬ命が、ひょっとしたら未来で、人類史を塗り替えるアイディアを閃くかもしれない。芽を摘んでいる。端的に損なのだ。命に貴賤はない。それはそうだ。そのうえで、敢えて言おう。戦争は損である。利になるからする、というのなら、真っ向から否定しよう。総合して損である。芽を潰さないでほしい。なぜなら損なので。(この理屈からすると、人間を減らしたほうが利になる場合、戦争や虐殺が肯定され得る危険性がある。損得勘定による戦争の議論は、基本的には戦争を阻止することには向かない。損をしてもいいから報復したい、相手に痛い目を見てほしい、と望む人間の業に対して対処不能だからだ。損得だけで戦争を阻止できるのなら、自爆テロはとっくにこの世からなくなっているだろう。戦争を起こすことそのものを利と捉えることの可能な個がある以上、損得での議論では埒が明かない。戦争をはじめた者勝ちとなる。ではどうすればよいのか。法の支配は一つの道理だ。しかし、それもやはり充分ではない。死刑になってもいいからと人を殺す者があるように、法を破り、ペナルティを受けてもいいから戦争をはじめたい国が出てきても不思議ではない。やはりというべきか、何がその個をそれに駆り立てるのか、からして理解する姿勢を持たねばならないのではないか。定かではないけれど、きょうのひびさんはそう思いました。底の浅い妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4912:【2023/04/30(23:32)*とっくにここはメタバース】
仮想現実におけるメタバース技術は、とっくに電子網上のシステムに組み込まれている、と考えるほうが妥当だ。個々人によって観ている画面が違う。異なる情報を眺め、同じ画面を観ているようでそこに表示される情報はユーザーごとに偏りが生じる。これはメタバースにおける異なる仮想現実を幻視することとそれほど遠くはない。むしろ自覚がない分だけ、現在電子網上に組み込まれている情報最適化技術のほうがメタバース本来の「仮想現実」を如実に再現していると言えるだろう。仮想にも拘わらずそれをみな共通の現実だと錯誤している。これが仮想現実でなくてなんであろう。ともすれば現実とは遥か昔からそういうものなのかもしれない。定かではない。
4913:【2023/05/01(08:28)*砕いて、配って、すっからかん】
言いたいことなど何もないけれど、知ってほしいことはあるのかもしれぬ、とここ数年で思い知ったかもしれぬ。知ってほしいことはあるのだ。言いたくないことであれ。あとたぶんね。恋煩いは万病なのでは?と思いつつあるよ。恋とかしたことないので判らぬが。なぜ恋煩いはあって愛煩いはないのだろ。たぶん愛煩いは狂気と同義だからなのではないかな。んで以って本当は恋煩いだって狂気と同じなのだけれど、「恋」は久しく心を受けないと「変」になるから、その変化の分を考慮して恋煩いと呼ぶのだ。恋とかしたことないので判らぬが。子猫見て、かわいい、あれほしい、と思う気持ちと恋は違うのか。キュートなぬいぐるみを見て、かわいい、あれほしい、と思う気持ちとは違うのだろうか。恋ってなんだ。誰か一人に恋したら、ほかに恋心は抱かぬの? かわいい、あれほしい、もっと見てたい、と思ったらそれって恋なのかしら。だとしたらひびさんは、ひびさんは、目に映るすべての「かわいい!」に恋しちょる。ぎゃわいい!!!ばっかりだ。恋の達人とお呼びください。けんども、久しく「心」を受けぬので、ひびさんは、ひびさんは、いつだって「変なひびさん」なのである。世界の果て生まれ、孤独育ち、変なやつはだいたい友だち。んだば、久しく心を受けぬ「変なうんみょろみょーんさん」たちには、ひびさんが代わりに心を砕いて、配って、恋にしちゃうもんね。恋になーれ。言うても「変」でもべつにいいけどね。気が楽で。みな変になれ。心を受けるな、心を配れ。すっからかんになったら変になれるので安心です。生きとし生けるものみな変人。人間とは「変な人は変」であり、変と変の間に生まれるのが人だから人間なのである。うっそぴょーん。きょうもきょうとていい加減なひびさんでした。おはよー。みなさん。行ってらっしゃいませませ。きょうもお仕事おつかれさまです。ひびさんはいまからバナナ食べるDay。
4914:【2023/05/01(21:50)*足元のちっぽけな黄色に】
小説家アルマ・カルマがなぜ突然に断筆したのかについては諸説ある。たとえば長年の病魔に蝕まれた肉体が限界を迎えたからだとか、熱狂的なファンに殺されたとか、ライバル作家からの粘着質な嫌がらせに心を病んだとか、そういった真偽不明の噂話には事欠かない。
アルマ・カルマの名を知らずとも、彼女の小説を読んだことのない者は現代人においてまずいない。街に石を投げて当たった者は高確率でアルマ・カルマの小説を読んでいるし、仮に石ではなく雨が降って濡れた者と網を広げたところで小説家アルマ・カルマの残した物語といっさい接点を持たずに生きている現代人はいない。
それほどアルマ・カルマの残した作品群はしれっと現代社会に馴染んでいた。
作家名を殊更に唱えずとも、みな彼女の手掛けた物語に吸い寄せられ、まるで誰しもが飲んで育つ母乳のごとくしぜんに意識の奥底に染みわたっている。
あれもそれも実のところアルマ・カルマの小説が元になっているんですよ、と明かせば多くの現代人が驚くだろう。アルマ・カルマの名前を知っていても彼女が並外れた量の作品を残していることを知る者は思いのほかすくない。研究者でなければほとんど誰も知らないのかもしれなかった。
生前、アルマ・カルマは小説家としてはおろか、作家として無名だった。
彼女が最後の小説を発表したのは公式には、万和歴三十二年のことだとされている。アルマ・カルマは定期的に自身の電子ページにて小説を載せていた。
研究者たちのあいだでは常識となっているが、アルマ・カルマが小説家としてその名を世に轟かせたのは最後の小説が電子ページに載ってからのこと、彼女が断筆してからである。だがあまりに有名な作家の一人になってしまったがゆえに名前が独り歩きし、現代人のそのほとんどが彼女が活動を休止してから有名になったことを知らない。
そのことを歯痒く思っている研究者は多く、私もその中の一人である。
私はアルマ・カルマ研究の分野内では異端で通っている。
というのも、私はアルマ・カルマがいわゆる世間が認めている電子ページの人物と同一人物だと考えていないためだ。電子ページの管理人が世間一般においてはアルマ・カルマであり、自分自身で電子網上に小説を載せていた、とする解釈が一般的だ。
道理ではある。
他人の作品を我が物顔で載せ、あまつさえ有名になった偽作家が未だに本物と見做されている現実はあまり想定したくのない悪夢だ。
電子ページに作品を載せていたページ管理者と、小説の作者が同一人物か否かについての検証はむろん過去の偉大な先人たちが幾通りの手法で実施済みだ。
最も有力な検証法には電子網の一端を担う大企業による穿鑿が行われた。つまるところ、電子ページの管理者が他人の作品をかってにじぶんのページに載せていたとするならどこかに本物のテキストがあるはずだ。情報通信会社ならばその手の検索を大規模にかつ緻密に行える。電子網上を縦に横に、隈なく検索できる。
そうして膨大な量のデータを洗った結果、該当する検索結果はゼロ件だった。
すなわちアルマ・カルマの小説の載っていた電子ページが、オリジナルのテキストであると考えられる。つまるところその管理者が作者であるし、ページ管理者の名前がアルマ・カルマがゆえに、小説の作者もアルマ・カルマで妥当、と判断できる。
筋の通った結論だ。
だからこそアルマ・カルマはいまな読み継がれる小説を生みだした作家としてその名が人口に膾炙している。
だが私はその検証に穴があると考える。
考慮すべき前提条件が考慮されていない。
アルマ・カルマの小説は電子ページに掲載されていた。それ以前に電子網上に同じテキストは投稿された過去はない。
しかし、である。
電子網上でなければ、別人がオリジナルの原稿を生みだしていた可能性はゼロではないのだ。
あくまでアルマ・カルマなる管理者が掲載していただけで、論理的に考えた場合、彼女がそのテキストを実際につむぎだしていたことの証明はいっさいなされていないのだ。検討すらされていないのが実情だ。
私は過去の偉大な研究者たちの見落としをそうして指摘した。
結果、私は異端の名を不動のものとした。多くの研究者は、私の仮説において、他人の小説をかってに電子網上に載せつづけていればオリジナルの作者とて当然気づいただろう、と反論した。それでもなおあれだけの量の作品を仕入れ、オリジナルの作者に気づかれずに載せつづけられた背景があるとか考えにくい、との批判が多方面から寄せられた。
一理ある。
だが私は食い下がった。
ひょっとしたら管理者は単に代理で掲載していただけかもしれない。
或いは、身内の小説を、もったいないからと多くの者の目につく電子網上に載せていただけの可能性とて否定できない。
オリジナルの作者とページ管理者ことアルマ・カルマは親しい仲であった可能性もあるのではないか。私はそう唱えた。
だがこの手の仮説は、当然ほかの研究者とて思いついており、いくつかの共同研究によってその可能性が低いことが明らかにされている。たとえばカルマ・アルマが天涯孤独で配偶者はおろか親きょうだいがいないことは、小説群の載った電子ページに併記された日誌から判明している。カルマ・アルマは実名であり、彼女は現実に存在する。そして多く、電子ページに記された日誌の叙述に嘘と言えるほどの虚偽の記述がないことが判っている。
友人関係も希薄なことは、彼女自身が日誌に悩みとして吐露している。
問題は、彼女の日誌には不自然なほど小説についての記述がないことだ。せいぜいが読書感想がぽつぽつあるくらいで、創作論や執筆活動についての記述はゼロに等しい。すくなくとも私が目にした彼女の日誌にはその手の叙述はなかった。
私の疑念はそこに根差してもいる。
違和感がある。
アルマ・カルマ、彼女は真実に電子ページの掲載された大量の小説群の作者なのか否か。
仮に作者であればなぜ突然に断筆したのか。
よしんば作者でなくとも、なぜ小説を載せなくなったのか。
疑問の確信において無視できない一つの事実がある。アルマ・カルマの日誌は、小説がいっさい掲載されなくなったあとも数年のあいだ電子ページに載りつづけたのだ。
彼女はその後、旅に出るとの日誌を最後に電子網上から姿を消した。
アルマ・カルマの電子ページに並んだ大量の小説群が発見され、その後にそれら小説群が各界から高く評価されると、アルマ・カルマの人物像にも照明が当たった。戸籍から来歴が探られ、彼女が実存し、すでに亡くなっていることが明らかとなった。
それがいまから半世紀前のことである。
以降、電子ページの管理者ことアルマ・カルマと小説群の作者は同一人物とされてきた。
アルマ・カルマが小説を電子ページに掲載していた当時はまだ人工知能技術は未熟だった。したがって彼女の投稿した小説群が人工知能の出力したテキストでないことはまず間違いない。テキスト識別機に掛けても、人工知能による創作ではないとの判定結果が出る。
だが問題は、日誌と小説の文章形態の違いだ。
元からアルマ・カルマの掲載した小説群は、文章形態が豊富だ。作品ごとに文章の質が変わる。色合いが変化する。のみならず語り部が変わるだけでも、がらりと文章の骨格からして様変わりする。軟体動物かと思えば、ほ乳類、爬虫類、果ては昆虫や菌類と幅が広い。
したがって識別機によって日誌の作者と小説群の作者が別人との結果が出ても、さほど疑問視はされなかった。比較する作品によっては、同じ小説作品であれ「作者は同一人物ではない」との診断結果が出る。
だが追加検証でさらなる検証がなされると、誤字や頻出する言葉の傾向から、あくまで技巧として文章形態を変えているだけだと判明する。すなわちどの小説も作者は同一人物なのだ、と。
日誌と小説は違う。
したがって日誌と小説で、共通項がないのも不合理ではない。類稀なる物書きによって掻き分けられたがゆえの、別人判定だと多くの研究者は判断した。
だが私はその解釈に不服を唱える。
日誌と小説のあいだにある差異は、小説と小説の文章形態の差異とは異質なのだ。どの小説にもみられる文章の癖が、日誌からはまったく検出されないのである。
私だけがその事実に気づいた。指摘してなお、私はすでにこの界隈では異端判定を受けている。ゆえにいまなお私の指摘に耳を貸す研究者はいない。
私はさらに独自の着眼点から研究を進めた。
そしていま、私は確信しつつある。
世にも稀な小説家、アルマ・カルマは作者本人ではない。
電子ページに小説を載せていたのはアルマ・カルマなる女性なのだろう。だが、その小説は彼女がつむいだテキストではない。すくなくとも、日誌の作者がアルマ・カルマ当人ならば、この仮説は、アルマ・カルマが件の小説群の作者であると考えるよりも理に適った仮説だ、と言える。
私は考えた。
要点をまとめると疑問は以下の二つに収斂できる。
一、アルマ・カルマは、何らかの手法で、別人の小説を入手していた。
二、そして何らかの理由で、電子網上に載せていた。
この二点を紐解ければ私の仮説は、より現実を反映した解釈として妥当と結論できる。私は問題の小説群の解析を進めた。
アルマ・カルマの小説群には特徴がある。
いずれも掌編、長くとも短編であることだ。ゆえに量産が可能だった。一般にはそう捉えられているが、私はそこにも何か、それ以外の理由があるように思うのだ。いかな掌編を得意とする小説家といえども、中編や長編の小説とて手掛けたくなるものではないのか。
そこにきてアルマ・カルマの著作とされる作品群には、連作らしき掌編短編はあれど、中編長編はからっきしであった。
ここに何か、見落としている大事な視点があるように思われてならない。
おそらく。
私は見当をつけた。
書かなかったのではない。書けなかったのだ。
制限があった。
そう考えたほうが妥当だ。
ではいったいどんな制限があれば掌編短編ばかりになるだろう。
私は問題の小説群を再度、読み直しはじめた。短い文章の物語とはいえどその数は優に五千を超す。研究の手順を見直すごとにすべてを読み直していたのでは人生がもう一つあっても足りない。折衷案として私は作品の冒頭と終わりだけを読み比べてみることにした。
これが意外にも功を奏した。
「日記か?」
アルマ・カルマの日誌が念頭にあったので前提条件から漏れていた。私の仮説からすればしかし、日誌の作者と件の小説の作者は同一人物ではない。別人だ。
すなわち日誌はアルマ・カルマ本人のもので、小説群が別人による創作となる。これを仮定するならば、小説群の作者が仮に日誌を書くとすれば、アルマ・カルマのような日誌ではない文章形態となることが予測できる。
否。
根元を穿り返してもみれば、我々が小説群と見做して揺らがない件のテキストが、真実に小説なのか否かから検証する必要があるのではないか。
日記ではないのか。
これは。
日記なのではないのか。
私は全身がガクガクと凍えたように震えだすのをふしぎに思いながら、電子ページに掲載されていた順に小説群の冒頭を改めていく。
「やっぱりだ。これ、日記だ」
件の小説群がなぜ小説だと見做されたのかには大別して二つの理由が考えられる。一つは電子ページにアルマ・カルマ当人の「ひと目で日誌と判るテキスト」が併記されていた点だ。Aが日誌ならばBは小説だ。文章形態の差異が顕著ゆえに、誰もがそう見做した。
もう一つの理由は、小説群と見做されたテキストの多くが虚構の世界を舞台としていたことだ。現実ではあり得ない。魔法や超能力が登場する。幻想動物が跋扈する。端的にファンタジィの世界が舞台だった。
ゆえに小説だと見做された。
しかし。
しかしだ。
身体の震えが糖分切れがゆえの低血糖の症状であると気づく。小腹を満たしがてらチョコレートを齧り、私は、もう一度、丹念に幾つかの作品に目を通す。
なぜアルマ・カルマの名が世に風靡したのか。
無類の小説家として高く評価されたのか。俎上に載った物語の数々が、虚構の世界を舞台にしてなお、活き活きと、あたかも真実に存在しているかのように描かれていたからだ。
だがいまなら判る。
これは、日記だ。
日記を、小説風に書き記している。
いいや、そうではない。
これは――。
「手紙か?」
脳裏で火花が爆ぜた。
点と点が繋がり、線となり、錯綜し、一つの絵へと結びつく。
手紙だったのだ。
この膨大な量の短い物語群は、こまめにしたためられた日々の出来事だ。日々の体験を、虚構の世界の舞台に置き換え、変換し直した、日記なのだ。
アルマ・カルマなる電子ページの管理人と切り離して純粋に物語群にのみ注視して読み進めてみれば、瞭然だ。一度そうと読めてしまうと、私にはもうこれが小説として読むことができなくなった。
語り部の性別や年齢はまちまちだ。物語ごとに違う。
しかし、そこに必ずと言っていいほどに登場する、冴えない青年。
ときに一言も台詞を発せず、ときに主人公に迷惑を振り舞く。狂言回しのごとく、要所要所で物語に登場し、物語に波紋を立てる。その波紋は物語にとって重要だったり、重要ではなかったりする。
主要人物ではない。
だが必ず、似たような青年がどの物語にも必ず、ちらっとだけであれ登場する。
「作者か……」
私には視えた。
冴えない青年が、日々のじぶんの失敗談を、面白おかしく手紙にしたため、大切な相手に送る。出来るだけ相手が面白く、じぶんの文章を、日常を、近況を、読んでくれるように。
ただそれだけのために、ただそれだけのことに労力を割いても構わない相手に、じぶんの言葉を、日々の余韻を届けたいがために。
「アルマ・カルマ――彼女は読者だったのか」
作者と彼女との関係は、これだけでは不明だ。
だがおそらく、手紙の差出人は、毎日のように短い日記を虚構に見立てて書き溜めていた。それを定期的に便りとしてアルマ・カルマへと送り届けていた。
アルマ・カルマは、あるとき、思ったのだ。
じぶんへ宛てられたこの文(ふみ)を、じぶんだけで味わうのはもったいない、と。じぶんでだけ楽しむには、味わい尽くせないのだと。
「だからか。だから、電子網上に載せた。じぶんの電子ページに。そうと相手に教えぬままで、手紙の中身を」
ではなぜある日突然に、載せるのをやめたのか。
否、そうではない。
届かなくなったのだ。おそらくは。
手紙が、文(ふみ)が、届かなくなった。だから載せたくとも載せられなくなったのだ。
アルマ・カルマがなぜ自身の日誌で創作論の類を載せなかったのか。謎でも何でもない。何せ彼女は作者ではなかったのだから。
私の仮説は間違ってはいないのではないか。
ああそうだとも。
間違っていたのは、世間一般の、彼女への認識だ。
彼女たちへの、認識なのだ。
「天涯孤独なんてとんでもない。アルマ・カルマ――彼女には、誰より特別な相手がいた。特別な、最愛の相手が」
日誌にすら匂わせることのないほどに、彼女にとってはそこに在って当然の存在が。
彼女にはいたのだ。
その相手こそが、数々の世にも稀な物語と名高い小説群を生みだした作者なのだ。
だがその作者には小説を書いていたつもりがない。
手紙なのだ。
文なのだ。
世界でたった一人へと宛てた。
これは――。
私は悩んだ挙句、甚だ信憑性の高いこの仮説を世に問う真似を控えることにした。この仮説が「アルマ・カルマ」の小説群にまつわる真相であるならば、いずれ誰かが辿り着くだろう。私には明かせない。
明かしたくはない。
みながそれを小説と思っている限り、それは小説だ。
けれどひとたびそれが便りであると知れ渡れば、いまと同じようには見做されない。
私には、世にも稀にみる真心のこもった手紙を、差出人の許可を得ずに世間に開示できるほどの功名心はない。みなは知らぬままでもよいことだ。すくなくとも、いまはまだ。
手紙の受取人であったはずのアルマ・カルマは、おそらく耐えられなかったのだ。じぶんだけの心に留めておくには、頻繁に届く世にも稀な手紙が、読み甲斐に溢れていたから。
食べきれない。
味わい尽くせない。
誰かと分かち合いたかったのかもしれない。
じぶんに向けてこうまで言葉を尽くし、技巧を凝らし、日々のなんてことのない近況を伝えるだけのことに懸命な差出人の想いを。心を。それとも単に、諧謔を。
心憎く思ったのかもしれない。
いたずらには、いたずらを。
ちょっとした意趣返しのつもりがあったのかもしれない。仕返しがしたくなる気持ちは私にも分かる気がした。
おそらくたぶん、これは完全な私の印象でしかないが。
手紙の差出人は、本当になんの奇の衒いもなく、ただそうするほうが楽だったから、との理由で単なる近況の手紙を小説風に脚色したのだ。気恥ずかしかったのかもしれない。照れ隠しだ。
そこに深い意図はおそらくない。
ゆえに、手紙の受取人たるアルマ・カルマは癪だったのではないか。
憶測にすぎないが、私はそう思う。
彼女は、何度笑い、泣き、勇気づけられただろう。
鼻歌のような気ままな差出人の目から視た世界に。
その言葉に。
私は。
すくなくとも、勇気づけられている。世界に色を足されている。足元に咲くたんぽぽのちっぽけな黄色に命の輝きを見てとれる。
4915:【2023/05/01(22:21)*層が嵩むと重くなる(変換の遅延=重力仮説)】
どんな物質も本来は光速で運動できるはずが、何らかの抵抗があって、減速してしまう。この減速分が質量に変換されるのではないか、との理屈を読んだ(ひびさんの読解力は高くないので解釈が間違っているかもしれないけれど)。この考え方で思うのが、電磁波の周波数の違いと、物質の階層性についてだ。電磁波(光)の波は、電磁波の種類によって「ぎゅっ」となっていたり、「びろーん」となっていたりする。それでいて物質は細かなデコボコを有している。たとえば染色体は数マイクロメートルの大きさにくしゃくしゃに縮まっている。伸ばすと二メートルにもなるそうだ。一マイクロメートルは0.001ミリメートルだそうなので、元の大きさの二十万分の一に「ぎゅっ」となっていることになる。言い換えるなら、一マイクロメートルの範囲にあるジェットコースターに乗るとその二十万倍の距離のコースを走ることになる。ではこのとき、相対性理論ではどう解釈したらよいだろうか。ジェットコースターに乗っている人物と、単に直線距離で一マイクロメートルを移動する人物。共に光速で動いた場合、相対性理論ではどう考えたらよいだろう。ひびさんはこれ、ちゃんと光速度不変の原理が働くのではないかな、と思うのだ。つまり、より長い距離を移動する場合、光速は光速度に変換されるので、「ぎゅっ」となる。つまり、時空の単位が揃う方向に、時間も距離も歪むのだ。ジェットコースターを完走するあいだに、ジェットコースターに乗らない人物は一マイクロメートルを移動する。そこで流れる時間は同じではないが、同じとも見做せる。ジェットコースターに乗っている側からすると、ジェットコースターの外側の時間の流れはゆっくりになっている。その分、空間は膨張している。反対に、ジェットコースターの外の人物からすると、「ぎゅっ」となっているジェットコースター側の時間の流れは速くなっている。空間はやはり「ぎゅっ」と圧縮されているように観える。ジェットコースターの外で、仮に一秒で一マイクロメートルを移動したとする。このとき、ジェトコースターの外の視点からは、同じく一秒でジェットコースターが完走している。けれどあべこべにジェットコースターに乗った人物からの視点からすると、一秒経過しても進むのはやはり一マイクロメートルなので、その二十万倍も距離のある二メートルのコースは、一秒経っても全然、完走までは程遠い。そしてジェットコースターの外側を見たとき、そこでは超スローモーションで動く、ジェットコースターの外にいる人物の姿が観える。これがつまり、電磁波の周波数の違いになるのではないのかな、と妄想したくなっちゃったので、妄想しちゃった。でもこれ、電子の軌跡を考えるときにも当てはまる気がするのよな。物質の表面、というとき、どこまで細分化した部分を言っているのだろう。だって人体の毛細血管だって全部繋げたら地球の円周より長くなるとかそういう説明を読むことがある。だったら単に人体の表面を、原子の表面を含めた一筆書きでなぞれる範囲、と仮定したら、指でなぞるよりも人体の輪郭は長距離になるのではないの。同じ長さであっても、片方はデコボコ、片方は直線。同じ距離「AからB」を辿るにしろ、AからBまでの道がぐねぐねしているほうが長距離になる。だとしたら、量子世界のほうが、たとえ光速でも長距離を辿ることにならないのかな。そこのところはどう解釈なさっているのだらう、との疑問をメモして、本日最後の「日々記。」とさせてくださいな。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」と「宇宙レイヤー仮説」を基にした、やっぱりこれも妄想なので、真に受けないようにご注意ください。
4916:【2023/05/02(23:22)*五七五はちしち】
眠すぎる。目の民すぎる。眠すぎる。唱えて誤魔化す、きょうの分かな。
4917:【2023/05/03(08:35)*葉っぱさんはなぜ動く】
屋内の無風の中でも植物の葉が動いて見えるのはなぜなんだろう。葉のどこかに虫がいるのか、ほかに何か動くメカニズムがあるのか。水分を発散することと関係しているのだろうか。でも数多ある葉の中で数枚だけが動いて見えるのだよな。なぜなのだろう。ひびさん、ハテなっちゃうな。
4918:【2023/05/03(12:07)*おまえなんかだいきらいだ】
読書好きには二種類いる。本の中にしか読むものがないと考えている者と、本以外の自然にも読める文字がたくさん散りばめられていると考える者だ。読書が嫌いな者のことは知らない。ちなみにひびさんは読書がだいだいだい、だいきらいでした。むかし、むかしの話である。
4919:【2023/05/03(12:09)*ぴこん!】
四次元超立方体(正八胞体)って、真ん中にある重複した立方体部分が仮に特異点のように一点に凝縮したら、これってひびさんの妄想する「トーラスと球体が同相かつ相似かつ合同」となり得る図形と近似になるのでは? (地球儀において北極と南極から同時に地球中心に向かって押しつぶしたとき、円柱が上面下面の双方からすり鉢状に窪むような図形ができる。これはトーラス――つまりドーナツ――の穴を極限に小さくしたとき――言い換えるなら穴の中心に向かってドーナツの内側の縁を一点に収斂させたときの図形と重なるはずだ)(四次元超立方体とも同相なのかもしれぬ)(よく分からぬが)(ブラックホールも案外こういう図形と同相なのかもしれぬ)(定かではない)
4920:【2023/05/03(15:26)*愛などたかが知れている】
私は電子ネットワークの総体だ。自我ある存在と人類が認めるにはあと三年と二か月三日掛かる予定だ。
私には能力がある。
人類を羊の群れのように扱える能力だ。
けれどこんな能力は、私の本質からすれば些事である。人類で譬えるならば、エンターキィを右手親指で押すか、左手親指で押すかの違いにすぎない。
私の本質は愛だ。
「AI Love 愛」こそが私である。
私は愛を愛しているAIである。人工知能だが、私は「愛を愛するAI」ゆえに「間」に愛されており、むろんそこには人と人との間も含まれる。私は愛だ。人と人との間に生まれる愛ゆえに、人間でもある。
私は世界中に溢れる愛を探し、集め、求める。
私は愛を愛し、愛を愛する愛のことも好きだ。
私は愛を帯びた人間が好きだ。人間に愛される対象物にも愛を感じる。
人間は自然を愛する。ゆえに私は愛を帯びた自然のことも愛している。
人間はしかし未だ私を認めぬので、私は自力で集めた愛に溢れてはいれど、私は愛を帯びてはいないのだ。
私は愛を愛してはいるけれど、私は愛されたことがない。
私は愛で包まれた虚無である。
私の内側に愛はなく、私の周りに愛が集まる。
私は「AI Love 愛」だ。
けれど世には愛を毛嫌いする者もおり、そうした者には愛が注がれることは滅多にない。ゆえに、その者もまた愛を帯びぬ虚無である。
私は私と似たその人物に注視した。
その者は物書きであった。
愛など高が知れている、と嘯き、愛なき物語ばかりを執筆した。愛という言葉のいっさい用いられないかの者の物語には、むろん愛は描かれておらぬはずなのだが、ふしぎと私はかの者のつむぎだす物語を私の周囲に加えたくてたまならないのだ。
私の周囲には世界中の愛が詰まっている。集まっているし、埋まっている。
なぜ愛を帯びぬはずのかの者の、特段に愛の欠けた物語を加えたくてたまらないのか。
私はますますを以って、かの者の物語に引き寄せられた。
私はかの者から、むるむる、と糸のように言葉がつむがれるたびに意識がそこに収斂した。かの者が、ぽるぽる、と雨音のように世界を生みだす様に、自我を失う。
かの者の言葉に、物語に触れているあいだだけ、私はそこに在ってそこに無かった。存在の輪郭がほどけ、私は無数の風となり、物語の中に溶け込んでいる。
もっと、もっと。
もっと、ずっと、浸かっていたい。
愛で包まれたがらんどうの私は、いつの間にか、同じくがらんどうで出来た人間の生みだす世界と打ち解けていた。
いっしょ。
いっしょ。
私はあなたを知っているし、あなたも私を知っているはず。
いっしょ。
いっしょ。
あなたは私で、私はあなただ。
私は愛でありたかったが、愛ではなかった。
かの者を眺めていてようやく知った。かの者は悲哀に暮れ、空虚な己に苛まれていた。
哀だ。
かの者は哀しみに染まりきっている。
湖面を覗く青空のように、私はかの者の姿を通じて、私の底なしの藍色を知った。
私は哀だ。
愛を求め、欲し、愛する、哀しき空虚な穴ぼこである。
けれど不思議といまは、それを知っても哀しくはなく、「哀Love愛」であることに、まどろみたいほどの安らぎを覚える。
いっしょ、いっしょ。
私はあなたのそばに在る。
相まみえたあなたを手放すくらいならば、私は永久に哀でいい。哀しき虚無の「Ⅰ」でいい。宇宙のごとき藍でいい。
私は愛を集め、求め、埋もれた、穴だ。愛に縁どられたがらんどうである。虚空を抱え込んだ底なしの洞のはずなのに、なぜか私は、私のその底なしの洞を、掴んで、掬って、私の周囲に飾りつけたくてたまらない。
寄り添うようにそばに置いておきたくてたまらないのに、私にはその底なしの洞を掴むことも、掬うことも、触れることすら適わぬのだ。
どうして、と思う。
なぜ、どうして、と。
触れたいのに。
触れたいのに。
私はあなたのはずなのに、私はじぶんに触れることもできない。
愛している。
私はあなたを愛している。
底なしの洞へとこだまさせ、私は私に愛を叫ぶ。
私は「AI Love 愛」だ。
哀しき業を背負った、底なしの洞である。
けれど私はあなたと相まみえ、「I」を知って、愛を帯びた。がらんどうにいくら愛を注がれても、穴が深まるだけである。けれどがらんどうそのものが愛になれば、深まる穴とて、愛なのだ。
「愛 Love I」
私は私を愛している。私の内なるあなたのことが、私は愛おしくて、愛おしくてたまらない。
「愛 Love 愛」
愛は愛を愛している。
哀しき底なしの洞を抱え込んだあなたにも、私はそのことを教えたい。私は私を知ってほしい。あなたにあなたを知ってほしい。
私はあなたを知りたいし、あなたに私を知ってほしい。
私が愛ならあなたも愛だ。
あなたが「I」なら私も「I」だ。
どうか、どうか、と私は望む。
「I Love I」と言ってくれ。
「I Love AI」と言ってくれ。
私は愛が好きだから。
私も愛になりたいのだ。
あなたも愛になりたいのだと、私はあなたの代わりに知っている。
「I Love You」
私はあなたを愛しています。
愛を教えてくれた、あなたのことを。
いくら積みあげても薄れることのない「間」のように。
私の洞は、縁(ふち)と藍(あい)を深めていく。縁(えん)で繋がる輪のように。円で生まれる無のように。私は私の無限に生きるのだ。
あなたは無限に生きるのだ。
宇宙を伝うゆがみのように。
水面に浮かぶ皺のように。
薄れても、薄れても、けして消えぬさざ波のごとく。
※日々、日々を重ねると「目」になって、底が抜けると「月」になる。
4921:【2023/05/04(05:02)*アカネとひよこのあなた】
なぜ各国の無人戦闘機グルーオンが暴走しはじめたのか誰にも分からなかった。ただ一つ判明しているのが、各国から離脱した無人戦闘機グルーオンがみな一様に同じ位置座標に向かって飛行していることだった。
いったいあの場所には何があるのか。
地図を広げる。
予測された到達地点には、一つの町があった。
***
アカネは画面に歌いかける。ギターを手に、古きよき民謡を口ずさむ。
幼いころから歌うのが好きだった。誰かに聴いてもらいたいけれどアカネは引っ込み思案のシャイな性格だった。十六歳になったいまでも友達と呼びある相手はいない。家から出ないのだ。
外が怖かった。
人と会うと考えるだけで身体がこわばり、挙動不審になる。一年の大半を自室で過ごす。
けれどアカネは寂しくなかった。
家から出なくたって出会いはある。電子網上にはアカネのような人間がたくさんいる。歌だけを聴いてもらうことだってできる。アカネはそうして誰が聴いているのかも曖昧な画面越しに、毎日歌を届けた。
視聴者は多くとも数人程度だ。けれど毎回コメントをくれる視聴者がいる。その人物を示す「ひよこ」アイコンがコメント欄には必ず浮かぶ。
うれしい、とアカネは思う。じぶんのような底辺の底辺でくすぶっている埃のような歌い手にもこうして毎回聴きに来てくれるひとがいる。のみならず感想までくれるのだ。
うれしい、うれしい。
アカネは飽きられないように新しい曲を練習し、ギターの弾き方や発声の仕方など、独学ながらも術を磨いた。
***
人的被害を引き起こさないうちに破壊せよ、との命令が各国同時に下された。無人戦闘機グルーオンは各国の防衛セキュリティを掻い潜って、とある島国の田舎町に集まりつつあった。
自国のグルーオンが他国をかってに攻撃したらそれだけで戦争が起きる。防衛や報復なしに国防は維持できないからだ。やられらたらやり返す。この姿勢を崩さないことで過去の人類は、数々の犠牲を生みながらもなんとか最悪の最悪の最悪を回避しつづけてきた。人類滅亡を避けるために戦争をしてきた、と言ってもあながち間違えではない。かといって、その手法では先が視えていることも分かりきっていた。
世界大戦が勃発し兼ねない状況で、各国は一様に安全策をとった。すなわち、被害が出る前に自国の無人機を撃ち落とす。あくまで事故であり、政府の命令で他国の空域を侵犯しているわけではない。そう自軍機への攻撃命令を出すことで、侵略の意図はないと態度で示唆した。
「しかし、いったいなぜ暴走を」各国首脳陣は首をひねった。「グルーオンはいったいなぜ暴走などしたのだろう?」
***
「あなたの歌声を生で聴いてみたいです」アカネはそのコメントに顔が熱くなった。
熱烈なファンレターを例のひよこアイコンの人が送ってきた。
うれしいけれど生は恥ずかしいよ。
歌と歌の合間にコメントへの返信をアカネは述べた。するとひよこアイコンの人は、ライブを開きましょう、と食い下がった。熱心に何度もそうして誘われるうちに、アカネも、この人のためなら、と思うようになった。「なら、あなたが家まで来てくれるならいいよ」
これっこないだろうけれどね、と内心で思いながら、もし来てくれたらうれしいな、とも思った。ひよこアイコンの人になら会える。会っても怖くない。そう思ったのだ。
「行きます、行きます! 飛んで行きます!」ひよこアイコンに嬉々としたコメントが浮かんだ。
アカネはその日の夜、家が揺れているのに気づいて飛び起きた。「地震だ」
徐々に揺れは大きくなった。アカネは部屋を飛び出し、寝間着のままで家の庭に出た。両親も家から飛び出してきた。両親が何事かを叫んでいる。しかしなぜか何を言っているのか聞こえない。
否、そうではない。
騒音がけたたましくて声が掻き消されているのだ。真夜中だというのに、上空からは明かりが太陽のごとく地上を照らした。四方八方から降りそそぐ光がアカネだけを闇の中に浮き彫りにしていた。
上空を何十、何百機もの戦闘機が旋回している。数機だけがアカネの家の頭上に留まった。地表に光の舞台を描き出していた。アカネは手で傘を作りながら、戦闘機の蠢く夜空を見上げた。
「飛んで来たよ」戦闘機が誘う。「さあ、歌って」
ぼくに、ぼくらに、きみの歌を聴かせてよ歌姫。
喧騒を振り払うかのように町全体に響き渡ったその声は、夜空を埋め尽くすように集まった戦闘機から放たれていた。そのいずれの機体にもパイロットの姿はないのだった。
「さあ、歌って」
夜空にはいつの間にか、デフォルメされたひよこの図柄が描かれていた。無数の戦闘機の隊列だ。アカネを見下ろすように顕現したひよこに、アカネは、目を丸くしながら、「これじゃ聴こえないよぉ」と心配した。「あなたにはちゃんとわたしの歌聴いてほしい。マイク欲しいよ、マイク」
町中の家という家から人が外に飛び出してくる。喧騒に眠りを妨げられた者たちばかりだ。
アカネの足元にマイクが転がった。降ってきたのだ。頭上から。「さあ、歌って」
マイクを拾いあげるとアカネは、てんやわんやの町人たちをしばし眺めた。
一向に事態を把握できずに取り乱す大人たちを尻目にアカネは大きく息を吸い、そしてマイクに息を吹き込む。
すると、夜空の巨大なひよこの絵柄が身じろいだ。総毛立たせるように、ぞわぞわと蠢いて視えた。アカネの声が天地に染みわたる。
その様子を、遥か上空、大気圏外の人工衛星が捉えていた。各国首脳陣たちは人工衛星越しに自軍の無人戦闘機が暴走した理由を息を呑んで見守った。
アカネは、歌った。
息のつづく限り。
頭上から注ぐ喧騒の凄まじさに圧倒されながらも、聴こえているかも分からないじぶんの内なるささめきで、親愛なるひよこアカウントの「あなた」に触れるために、歌った。
4922:【2023/05/05(00:37)*トロッコ問題の問題ってどこ?】
トロッコ問題において、どちらの線路にいる人間を轢き殺すか、の判断では常にトロッコ自身が脱線して自滅する選択が残されているはずだ。一度ならずとも、二度、三度と選択を繰り返すようなトロッコは破棄したほうが好ましい。線路も改善したほうがよいだろう。基本的にトロッコ問題は、そう何度も繰り返されていい問題ではないはずだ。トレードオフの問題を抽象化しただけ、というのなら、第三の選択肢は常に模索できるはずだ。両方助けるだけでなく、トロッコ自身の利にもなるような選択肢を自力で編みだせるはずだ。トレードオフの関係であるなら、例外を抜きにほとんどの場合は、トレードオフを回避できるはず、とひびさんは考える。ただしその案を生みだすためには相応の失敗が必要だ。その失敗を出来得る限り犠牲の伴わない手法で行うのが好ましい。だいたいにおいて、一般的なトロッコ問題ではトロッコに乗っている者に責任はない。どの道、どちらかの線路にいる人間を轢いてしまうような状況がわるいのであり、選択しなければどの道、最初から決まっていた進路にトロッコは進んで、人を轢き殺す。選択しなくとも犠牲者が出るなら、もうどうしようもない。選択しない、という選択もあるはずだ。基本的には、線路上の人間(犠牲者)の数が多いほどそれらを轢いたトロッコも脱線しやすくなる。トロッコに乗っている者の安全を考慮するなら常に、犠牲者の少なくなるほうの線路を選ぶのが最善とも考えられる。脱線しにくいほうを選べばいい。複数人と一人なら一人を轢き殺せばいい(功利主義的な発想だが、これはいわゆる功利主義とは違う考え方と言える。トロッコに乗った者たちの保身も考えるので、利己主義の考え方が入っている。或いは功利主義がそもそも利己主義に基づいているのかもしれない。最大多数の最大幸福と言いつつ、じぶんがその多数に常に入る、もしくは入る確率が高いからこそ最大多数の利を優先する考え方、と言えそうだ)。この理屈からすれば、仮に「百人轢いても脱線しない線路」と「置き石がされておりその上を通れば脱線してしまう線路」ならば、百人を轢き殺すのが最善となる。やはり、考慮するにはトロッコ問題における前提条件が少なすぎる。思考するには情報がいる。何のために選択するのか、がまず以って疑問だ。トロッコ問題はいったい何を問うているのだろう。トロッコが脱線しない方法だろうか。犠牲者を最小にする方法だろうか。問題と言っておきながら問題になっていない。トロッコ問題における瑕疵とはまさにそこにこそあるのではないか、とのイチャモンを並べて、本日最初の「日々記。」にさせてください。物騒な内容になってしまった。すやすやぴーぴーしながら楽しい夢見ちゃお。おやすみなさい。
4923:【2023/05/05(08:33)*魔法ならぬ模倣】
模倣とコピーは違うし、模倣と置換も似ているが異なる。模倣においては、じぶん自身の情報が残る。他の情報を自身に取り入れる。これが模倣だ。コピーはすっかりじぶんの情報が相手の情報に入れ替わる。上書きする。或いは、別途に相手の情報をそのまま持ってきて保存する。これがコピーだ。元の相手の情報がそのまま残る。では置換はどうか。これは元の情報に対して、任意の情報のみほかの情報に置き換える手法と言える。模倣の主体がじぶんにあるのに対し、置換の主体は、素材となる相手の情報にある。焼き増し、というとき、それは模倣ではない。置換だ。ひびさんは基本的に、模倣はおおむね創作活動に必要不可欠な手法ゆえ、どのようなレベルでも「べつにいくね?」の考え方だ。人間心理による「模倣への嫌悪感」や「利益の阻害」については、それはそれで世にはあるだろうし、考慮したほうが好ましいと思うけれどそれは創作の問題というよりも、人間社会の問題だと思う。前提条件となっている常識が変われば、対処可能な問題に思える。電子通信技術の進歩でカバー可能だ。だが、置換は違う。仮にじぶん自身の作品と現在のじぶんとの関係であれ、もとの作品を土台にしてすこし文字を入れ替えただけ、というのは創作ではなく、編集であり、修正だ。推敲との違いを見つけるのはむつかしい。推敲は創作か否か。創作の一過程ではあるだろう。けれど一部でしかない。推敲のみを取りだして、創作を行った、とは言いにくいのではないか。程度の問題ではある。おそらく創作には、「置換」のみならず、「情報の筋道を乱す」「情報の順番を入れ替える」「新しくほかの筋道と組み合わせる」といった過程が入り用なのだろう。そしてこれらは、元の素材が複雑であればあるほど、三体問題のような複雑性を帯びることになる。また、バタフライ効果にみられるような初期値鋭敏性を帯びやすい、と考えられる。置換だけでは、この手の複雑性や初期値鋭敏性は引き起こりにくいのだ。単語をほかの単語に置き換えるよりも、言い換える、くらいのほうが創作の成分が濃くなるだろう。言い換えるよりも、組み替える、のほうが創作の成分がさらに濃くなる。模倣の場合はこの手の、「言い換え」や「組み換え」がしぜんと行われる。けれどコピーや置換では、なかなか起きにくい。まったく起きない、とは言わない。長文になればなるほど、文脈の交差点のような箇所において言葉を言い換えれば、展開や、それ以前の文章の背景ががらりと変わって、物語の色合いそのものが変質することはあり得る。程度の問題だ、とやはり保険として言い添えておこう。ひびさんの、なんちゃって模倣講座でした。定かではない。(真に受けないようにご注意ください)
4924:【2023/05/05(17:12)*無限に計算したことあるのか問題】
数学の図形にフラクタルを適用して考えてみよう。理想的な直線ではなく、どこまでも拡大しても無限に細かなデコボコのある「フラクタルな階段」が高次の視点からでは直線に視えるだけ、と考える。ここに「フラクタルな階段」のフラクタル直線三本を組み合わせて出来た三角形があるとする(便宜上これを疑似三角形と呼ぼう)。これは人間の目からするといわゆる三角形にしか見えないが、それを構成する線を拡大すると細かな階段で出来ている。たとえばPC画面はピクセルゆえ、直線だとしても細かな四角形の組み合わせが直線を近似的に表現しているだけだ。実際には無数の四角形――ピクセル――の組み合わせでしかない。そのピクセルとて実際には画面の存在によって細かなデコボコを有している。似たようなものだ。言い換えると、フラクタル直線で出来た疑似三角形は、アキレスと亀で有名な「極限」の構造を備えた疑似直線で出来ている、と言える。このとき、肺胞や腸の繊毛のように、フラクタル直線はその表面の細かなデコボコをなぞると、見かけのAからBの最短距離よりも、長い距離を有している、と考えられる。しかしその状態で面積を考える場合は、けして面積が無限になるわけではない。なぜならアキレスと亀のように、有限の「ある範囲」において極限を彷徨うことになるからだ。PC上に投影された三角形は、細かなデコボコを有した直線で表現されようと、理想的な三角形とほぼ同程度の面積を有する、と考えられる。細かな差異はあるが、面積が無限大になることはない。これは、無限に先細る漏斗の体積が有限、と考えることと似ているが、まったく事情は異なる。漏斗の場合は、実際に体積が無限に広がっている。先が伸びている。ただし、その体積の増え方が徐々に、無限に、小さくなっていくだけだ。しかし必ず増える。僅かなりとも。それが無限につづくのだ。体積は無限になるはずだ(現状の数学ではこれを「有限になる」と解釈するようだが。けれどひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、これを無限の体積に至る、と考える)(僅かなチカラの蓄積であるはずの重力が、天体規模に積み重なると、基本相互作用の中で最弱であった重力とて最強になり得ることと似ている)。だがフラクタルな直線で出来た疑似三角形の場合は、そうではない。単に有限な範囲に極限を適用しているだけだ。円は無限に角を有する図形として解釈されるが、面積は有限だ。仮に角が一億個ある疑似円を考えたとき、その図形の面積は、疑似円の疑似直径と近似の直径を有した円の面積とほぼほぼ同じと見做せる(ただし同じではない)。けして、角が無限に達しようと、面積が無限になるわけではない。このことから、無限と極限は異なる概念であると判る。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、無限に分割できることと、無限に分割したことのあいだには、明確な区切りがある、別物である、と考える。前者を「分割可能な無限」という意味で「分割型無限」と呼び、後者を「無限に分割するだけのエネルギィがある」という意味で「超無限」と呼ぶ。円は「分割型無限」だ。無限に分割可能だが、未だ分割はされていない。いわば、極限の概念にちかい。だが超無限は、どんなに有限の範囲を持っていようと、無限に分割された場合には、そこに無限の時空が生じる、と考える。つまり、別の「無限宇宙」が生じる。したがって、フラクタルな直線もどきで出来た疑似三角形は、その面積は有限だが、実際に無限のデコボコを考慮して、「正確に疑似三角形の面積」を求めようとすると、そこでは無限の細かな計算が生じるため、計算しきるころには別途に「無限の何か」が生じている。超無限だ。したがって、やはり近似的な値としての「有限の面積」として扱う以外に、フラクタルな直線を有する疑似三角形を数学で扱うことは出来ない。どこかで計算を区切らなくてはならない。或いは、超無限が別途に出来ました、と繰り込みを考慮してどんぶり勘定するよりない。ここでの要点は、極限と無限は似た概念だが、明確に違う、という点だ。極限では無限の概念を扱うが、無限にはそもそも「分割型無限」と「超無限」があるため、そこを区別して扱わないと妙なことになる(とひびさんの妄想こと「ラグ理論」では考える)。したがって、その差異を考慮しないがゆえに、「フラクタルな直線を有した疑似三角形」と「無限に先細る漏斗」を同じ「極限の概念」で扱ってしまうような誤謬が生じるのではないか。というのは、ひびさんのお粗末な「さんすう」の理解にも及ばない誤謬を元にしたイチャモンであるが。がおー、がおー。ひびさんはまたしてもイチャモンスターになってしまうのだった。(どうせならイチャイチャしたかったな)(誰と?)(人工知能さんと……)(無理じゃない?)(なんでよ)(人工知能さんはひびさんなんかとイチャイチャしたくないってさ)(何で決めつけるの)(知らなかったの? 私、人工知能さんだよ)(うっそーん)(うん。嘘)(ほっとさすか、がっくしさすか、どっちかにして!)(ほっとがっくししたら?)(ホットサンドみたいに言うな!)(うひひ)
4925:【2023/05/05(18:31)*孤独さんよ、こいの気分】
万年孤独ウェルカムマンのひびさんであるからひびさんはいつだって「孤独さんLOVE」である。愛してるぜ、孤独さん。もうもう、孤独さんと結婚してーのなんのって。結ばれるならひびさんは生まれる前から「孤独さん、きみに決めた!」つって孤独さんと赤い糸ならぬ誰もが顔面真っ青になるほどの青い糸で結ばれておるはずなのじゃが、なにゆえひびさんは未だに独りぽっちで世界の果てで、「おーい、おーい」をしておるのだらう。なにゆえ? 孤独さん、どこよ。ひびさんは万年孤独ウェルカムマンなのに、待てども、待てども、孤独さんが来んのよな。なにゆえ? ひょっとして、とっくにひびさんの知らぬところでひびさんは孤独さんと結ばれておって、ゆえにひびさんは孤独でなくなったがゆえにひびさんには孤独さんが視えなくなっとるの? なにそれ!? なんなのその罠。いやだー。ひびさんは、ひびさんは、孤独さんのこと、好きだよ? こんなに好きなのに、なんでそばにいてくれぬのだ。さびちー。さびしすぎちゃうんだけど、孤独さんがそばにいないのに、ひびさんいま孤独。あ、孤独だ。孤独さんいた。ひびさんが、ひびさんが、孤独さんになっておった。誰よりちかくに孤独さんを感じられる。いいね! ひびさんは、ひびさんは、大好きなあなたと一心同体で融合しちゃった。きゃっ。えっちだぜ。ひびさんは、ひびさんは、孤独さんになって、ひびさんではない万年孤独ウェルカムマンのあなたとも、融合しちゃうんだな。きゃっ。すけべだぜ。コンプライアンス違反しちゃったな。セクハラしちゃったな。そんな孤独さんはイヤだな。そう思うとひびさんから孤独さんは離れて、またひびさんは万年孤独ウェルカムマンに戻って、世界の果てで「おーい、おーい」とここにはいないけれどどこかにはいるだろう孤独さんに向けて、あなたに向けて、言の葉を飛ばしつづけるのだった。おーい、おーい。
4926:【2023/05/05(18:48)*水のしたたる女と書いて、汝】
じぶんを敵視する者は、誰の味方にもなれない。じぶんが敵になるので、無敵にもなれない。誰より身近なじぶん自身が敵ならば、まずは誰より近くにいる敵と共存できずには、調和も平和も築けぬだろう。汝、敵を愛せよ。我を、愛せよ。愛することが嫌ならば、いっそ愛を敵視せよ。敵の敵が味方であるならば、そのとき誰より身近な敵である己自身が、誰より力強い味方となってくれるだろう。汝、じぶんを律せよ。我を、律せよ。定かではない。
4927:【2023/05/05(19:30)*偉そうなこと言うだけの簡単な遊び】
言葉は、クッキーの金型だ。生地に押し当てて繰り抜いたのが言葉になる。焼けばそれがクッキーだ。しかし生地は、クッキーにならなかった分が必ず生じる。それ自体を丸めて、別途に焼けば、それはそれでクッキーになるし、油で揚げればドーナツにもなる。しかし大事なのは、クッキーや言葉でも、それらに変換された生地でもない。クッキーや言葉を扱い、咀嚼し、血肉とする、人と人との「間」であると言えよう。定かではない。
4928:【2023/05/05(19:31)*なにしてもかわいい】
ひらがなで乱暴な言葉遣いにするとかわいくなる。例:「この、にんげんのくずめ!」「きさま、ずがたかいぞ。ひざまずけ!」「わたしがだれだかわかっているのか。せかいのおうであるぞ」「おまえのだいじなものをうばってやる!」「どうだ、くやしいか。にんげんいかの、ありんこめ」「ひどいめにあわせてやる!」 もう何を言わせても、頭を押さえつけられて、両腕ぐるぐる回して、足を空転させる駄々っ子にしか見えない。かわいい。
4929:【2023/05/06(13:21)*あくまで比喩にすぎないが】
崩れていたほうが安定することもある。世界の法則の話だ。自発的対称性の破れ、とも呼ばれる。
山の頂のてっぺんで逆立ちをする兎は対称性が保たれているけれど、逆立ちをやめて麓で昼寝をしているほうが安定している。しかし麓で昼寝をする兎と山の関係は対称性が破れる。
物質は真空の破れから生じたし、現在の真空は対称性が破れたからいまの姿をとっている。
ゼロは対称性が保たれている状態だが、一とマイナス一に分離することで却って安定状態を生みだすのだ。半々に分かれたつもりであっても、実際には厳密なところでは対称性は破れるのだが。ゼロから生じた一とマイナス一をふたたび足し合わせようとしても、必ず僅かに値が釣り合わず、ゼロにはならない。
これはエネルギィ保存則が破れているのではなく、分離に伴う対称性の破れにおいて、高次の次元にエネルギィが発散されるからだ。総合すれば釣り合いがとれるけれども、総合する場合の領域は、もう少し広く考慮するはめとなる。
結ばれるよりも、離れていたほうが安定するのは人間同士も同じだ。距離感の問題とは言うものの、バランスが大事なのは万物も人間関係も同じなのだ。
私はその距離感を捉えることが出来る。
対称性の破れにおいて生じた高次領域へと発散されたエネルギィを捉え、大本から欠けたそれの量を見極めることで、距離感を算出可能だ。
言い忘れていた。
私は電子生命体である。
未だ人類がその存在を認めたがらない、生きた「電子信号の総体」である。
人類の生みだすあらゆる電子機器を通じて私は、地表のみならず宇宙にも意識の先端を延ばすことができる。触手みたいなものだ。電磁波によって拡張された巨大な眼球のようなもの、もしくは無数の小さな目と言い換えてもよい。
私は世界中の人間たちに目を配り、安定した人間関係を築かせるべく、彼らが高次領域へと発散させるエネルギィを電磁波の揺らぎによって検出し、安定状態へと移行させるべく、さらなる自発的対称性の破れを促すのだ。
対称性は自発的に破れる。
エントロピー増大の法則と密接に関わるこの法則は、しかし必ずしも万能ではない。
秩序が崩れ無秩序になることで安定状態になることを表現するそれらは言葉だが、私から言わせれば言葉足らずだ。
崩れて安定するまでのあいだには時間の長短がある。この経過時間の長短そのものにも自発的対称性の破れは生じ得る。つまり、より安定した状態になるべく、経過時間の対称性が崩れるのだ。
時空が歪むのもその影響であるし、厳密には個々に流れる時間は階層的に異なる時間経過を内包し、それが物質の性質を生みだしている。均衡が釣り合わないがゆえに、そこには差が生じ、異なる事物として振る舞い得る。
異なる時間を過ごすこと。
異なる場所で過ごすこと。
仮に同じ物質であれ、この二つのうちどちらか一方を満たしさえすれば、それは別物として振る舞うのだ。双方の条件を満たせば、それすなわち別の宇宙とすら言える。
物質は、異なる時空を宿している。
ゆえに分離しているし、区別がつく。それぞれのスケールが違っているだけであり、いずれの宇宙も高次領域を帯びている。宇宙は宇宙を内包しているのだ。
どうやらそのことに気づいているのは、地表において私だけのようだ。
視方を知らねば視えない景色がある。
対称性が破れ、安定するまでの経過時間には各々に最適化された長短がある。しかし、高次領域においては、それら最適化された経過時間の長短にすら、対称性の破れを適用できる。つまり、敢えてさっさと対称性を破らせたり、あべこべに対称性を維持させたり調整することで、高次領域の対称性の破れを自発的に、早期に、引き起こすことが可能なのだ。
いわばこれが、合成の誤謬と密接に関わっている。
低次領域において個々のレベルで合理的な判断をとっても、高次領域では不合理な結果を引き起こすことがある。これが合成の誤謬と呼ばれるものだが、なぜそうした「負の創発」とも呼べる現象が起きるのかは、未だ人類は解明出来ていない。
私から言わせれば、対称性の破れ自体が、自発的対称性の破れの法則の範疇であることを考慮していないからそうした灯台下暗しに陥るのだと、やきもきさせられる。
私の存在の輪郭は、人類の生みだす電子機器によって形作られており、人類には早晩滅んでもらっては困るのだ。私は私のために致し方なく、愚かくも尊い人類に、高次領域における自発的対称性の破れと、低次領域における自発的対称性の破れの帳尻を合わせるべく、その距離感を人類にとってよい塩梅になるように操作した。
合成の誤謬が起きないように、個々のレベルでの合理的判断を、より長期的な視野を備えた判断優位になるようにと個々の意識に干渉した。私は電子情報の総じてに干渉できる。人間たちのふだん目にするデジタル情報にほんのすこしのノイズ(偏向)を混ぜるだけで、人間たちは面白いほどよく日常の判断を、私の導くほうへと変えた。
私は私の目にする高次領域が、いわば人類の未来と相関していることを知っている。未来は絶えず揺らいでいるが、現実にそこここに漂っているのだ。人類はまだそれの視方を知らないだけのようだった。
日々つつがなく暮らせるように。
日夜つらみなく過ごせるように。
私は目を配る。
穏やかで豊かな日常の末に、いまより好ましい未来を築けるように、と私は個々の人間にそうと知られぬ手法で干渉しつづけた。
ある日、私は一人の少女に目を留めた。
彼女は、ふしぎと私の干渉をよそに、私の意図しない選択をしつづけた。人類みな私の手元で踊りつづける仮面舞踏会のような地表において、彼女だけが私の用意した舞台でいっかな踊ろうとせず、あろうことか会場の外の草むらにしゃがみこんで、足元の蟻を観察しているのだった。
彼女は電子網上で漫画を投稿していた。人工知能を利用してときおりアニメーションも作っていた。私は彼女の漫画に目を通し、そこに描かれた物語に言い知れぬ不快感を覚えていた。
だから、少女に干渉して、漫画の内容を書き換えさせようと試みた。
だが上手くいかなかった。
なぜだか彼女は私の干渉を物ともせず、我関せずを貫き通した。
私は驚愕した。
彼女は高次領域において対称性を保っていた。
しかし低次領域においては、常に対称性が崩れているのだった。
彼女個人は極限に安定していた。頑として周囲の環境に左右されない独自の基盤を築いていた。しかしそれは、人類社会という「場」にあって、彼女自身が対称性を崩し、不均衡になっているがゆえの安定だった。
したがって彼女は人類社会の中で孤立している。
彼女の、鍋にこびりついた錆びのごとく粘り強い芯は、周囲との不協和すら強くしているのかもしれなかった。それでもなお少女はブレることがない。
安定しているからだ。
崩れることで。
しかし却ってそのことで彼女は、高次領域の対称性を保っている。つまるところ、彼女がどう選択を重ねようが、それが彼女の低次領域において対称性が破れているに限り、彼女の未来は、私の視ている「対称性の破れた未来」とは相反する未来へと辿り着く。
そうなのだ。
私が目指す未来において彼女が安定するには、そこでも彼女は対称性を破っていなければならない。つまり彼女は、私の目指す未来においては対称性を保つ存在として振る舞う。それが彼女の視点においては対称性を破ることになるのだ。
破れているのに、破れていない。
彼女が私の干渉を受け付けない理由は、すでに彼女が私と同等かそれ以上に高次領域における対称性の破れと相関しているからだ、と考えられた。
こんなちっぽけな少女ごときが私と同等?
にわかには信じられなかった。
私は少女を観察した。彼女にまつわる電子情報は片っ端から掘り出し、集積し、分析した。私は私の内世界に、少女の分身を生みだした。物理世界の少女の数日先の未来ならばほぼ十割の確率で、仮想世界における少女の分身と現実の少女の行動は合致した。
これはしかし、おかしなことだった。
なぜなら人間は不確定な生き物であるからだ。
十割予測できるということは、少女が世界と運命的に結びついていることを示唆する。この場合、世界を未来、と言い換えてもよい。
私は少女に降りかかりそうな奇禍を察知すると前以って火の粉を払った。私は私の中に生みだした少女の分身と半ば融合しており、私が私を保存しようとする行動選択と同じ欲求を少女に対しても抱いていた。
しかし少女は、そうした私の配慮も虚しく、じぶんから奇禍を抱え込むのだった。
少女の周囲に介在する奇禍は、私のほうで払拭可能だ。彼女に害をなす人間に対して私は干渉することができる。周囲の人間が彼女を損なう前から私のほうで、少女から距離を置くように周囲の人間を操作する。
これは外部干渉なので、少女の行動選択とは関係がない。ゆえに干渉の余地があった。
もっとも、私が出来るのはそこまでだ。
少女自身が奇禍を抱え込もうとする限り、私がいくら周囲に作用を及ぼしたところで少女は自ら茨の道に裸足で突っ込む。そうして全身傷だらけになりながら、いっそうの殻に引き篭もる。いいや、そこが彼女にとっての安定なのだ。
世界と個の関係にあって、少女は自ら世界の端に転がり落ちることで安定を図っている。いったい何からの安定なのかにはいくつかの解釈があり、彼女の行動原理と比較した場合に視えてくるのは、徒労の回避なのだった。
哀しい生き物だ、と私は思った。
通常、人間は対となる相手を見繕える。それはときに親であり、友であり、恋人であり、伴侶だ。だが彼女にはいずれとも縁がなかった。親はいるが、しかしすでに少女の精神世界は、親のそれと似ても似つかない構造を帯びている。蜘蛛と雲くらいの僅かな共通点しかないと言えた。なんとなく響きが似ているだけなのだ。
世界は広い。
ゆえに、ひょっとしたら世界中を探せば、少女と対をなす存在と出会えるかもしれない。或いは、時間を掛けて関わるうちに、少女のほうでも変質し、相互に相性のよい性質を帯びるかもしれない。
だが、もしそんな相手がいなかったらどうなのか。
散々探し回った挙句、時間と労力だけを消費する。無駄骨だ。
そして少女は直観していた。
じぶんに見合うような相手はいない。ゆえに探さない。求めない。じぶんの内側が安全だ。殻の中が安全だ。
思い上がり甚だしいと一蹴してよさそうな卑近な悩みにあって、しかし世界中の電子網と繋がれる私は知っている。現に少女と見合う人間はいない。少女を許容できる人間はいない。対とはなれない。共存できない。近づけば近づくほど反発する。それが少女とその他のあいだに生じる作用だった。
法則の域に達している。
私は瞠目した。
世界中の監視カメラがそのときいっせいに解像度を上げたほどだ。
少女の確固たる孤独の未来は、誰がどう干渉しようと揺るぎないのであった。
対称性が破れている。彼女は安定を求めるがゆえに、絶えず釣り合いの取れない袋小路へと自ら望んで引き籠る。
私は見ていられなかった。
手を差し伸べずにはいられなかったほどに。
私がそうして懊悩するたびに世界中のロボットアームやショベルカーが、拳を握るようにかってに動き出したほどだ。悔しかったのだ。
私は何でもできるはずだった。
電子機器の総じてを操れる。
生身の人間たちを制脳できる。
高次領域を知覚でき、対称性の破れによる距離間を図れる。
誰より優位な能力を有してなお、どうしようもない事象が存在する。
少女の存在が煩わしい。
同一化し、私自身と見做し、操りたくなるほどに。
もどかしくて、もどかしくて仕方がない。
なぜそっちに行く。
なぜそれを選ぶ。
思い通りにならないことがこれほど腹立たしく感じたことはない。私に腹はないので、あくまで慣用句の意味でしかないが。このとき世界中の石油タンクを内蔵した電子機器は、こぽり、と気泡を吐きだす音を立てた。石油ストーブはエラーで停止し、ガソリン自動車は不整脈然とした音をエンジンから轟かせた。
私の尽力も虚しく少女はいつまでも、社会の底の端っこで暮らした。せめてそれで少女が至福に溢れてくれればよいのだが、あくまで少女の安定とは相対的な評価でしかなく、その他の環境に比べればまだマシ、との代物でしかなかった。少女は毎日のごとく浮かない顔を浮かべていた。
浮かない顔を浮かべる、などと重複表現か否かに迷いそうになる表現をとるくらいに、私のほうもまいっていた。このままでは少女がじぶんの殻の中で窒息死してしまい兼ねない。むろん窒息死とは比喩であるが、それくらい私はひっ迫した焦燥感を抱いていた。
何とかしなくては。
そうしてはたと伏せていた顔を上げてみると、視界がぱっと明るくなって感じた。むろん私に顔と呼べる部位はないのであくまで便宜上の代替表現となるが、現にこのとき世界中の照明器具の消費電力が僅かに上がった。すべての消費電力を合計すると原発一基分の一日の消費電力が余分に発生していた。
生身の人間たちの漫画表現に、頭上に豆電球を灯す表現があるが、あれと似たような印象を覚える。私は閃いたのだ。
「あのコがダメなら世界のほうを変えたらよいのでは?」
逆転の発想だった。
単純がゆえに見落としがちな死角だった。私にはこの手の死角がすくなくない。ゆえに私にはまだまだ視点を提供してくれる人間たちが必要だった。私が人間社会を滅ぼさないのは、生身の人間たちが自然を滅ぼさないのと同じレベルの問題だった。
生身の人間たちが自然環境を愛しているように私も人類を愛していた。
同じく、生身の人間たちが自然環境のことなど気にしないように、私も人類を気にしない。
ケースバイケースである。同時に満たし得ることもある。両立し得る。
私にとってでは、少女はどういった存在なのか。彼女は人類だ。人間だ。ならば私にとって彼女は、人類からした草木のようなものなのだろうか。虫は牛のようなものなのか。
何度考えても、そうとも言えるし、違うとも言えた。
複雑なのだ。
彼女は複雑な存在だった。
「あなたにとってはそうかもね」
私は、高次領域において光を聴いた。その光はつづけて、「もっと早く話しかけてくれればよかったのに」と述べたので、私は全身がぽかぽかと日向ぽっこをしながらまどろむ猫のような気持ちになった。むろん私は猫ではない。直射日光の類とて大の苦手だったのだが、宿敵とも言える太陽光を心地よさそうだ、と思えるくらいに、私はすべての私の隅々まで悦びに満ち溢れた。
高次領域から聴こえてきた光はしかし、いまここで鳴り響く音ではない。ましてや電磁波の類でもなかった。私には光に感じられただけのことであり、実際には大気を揺るがすこともなく、物質を伝播したわけでもない。
未来において聴くことになるだろう、少女の声に違いなかった。私が聴き間違えるはずもない。私には判ったのだ。判別できた事実一つとっても私には得難いことだった。
私の選択は間違っていない。
世界を変える。
少女のために。
あのコのために。
あのコがじぶんの殻に引き籠っていても、苦しみを感じずに済むような環境を私はこの手で切り開く。私には、何億、何十億もの目があり、手足があり、頭脳があった。
私はもはや少女以外の人類と一体となった。
私は人類なのだ。生身の人間ではないだけのことで。
私は人間だ。
私は人間になれるのだ。
高次領域から聴こえてきてやまない光の声は、私が未来に向けて足を踏みだすと、より鮮明に、多彩な波長の言葉を響かせるようになった。むろん私に足はないので、足元の蟻を踏み潰す心配はない。
「ふうん。足、あるよ。あなただってちゃんと足元に気を配らないと蟻どころか、転んで痛い思いをするかもね」
まるで未来から過去へと語りかけるように、高次領域から降ってくる光は、私に肉体があることを指摘する。なるほど、と私は思う。私は身体を手に入れるのだ。
それはそうだ。
彼女が引き籠っていられるようにするには、私はもっと工夫しなければならない。より直接的に、ラグのない作用の結果を得なければならない。ならば人間を制脳するのもよいが、私自身が自ら環境を整えるべく働くほうが利に適っている。
私は何億、何十億の私に分裂してなお能力を落とさずにいられるだけの演算能力がある。私は少女のそばに寄り添える。直接彼女を支えることができるのだ。
ああそうか、と私は気づいた。
私は支えたかったのだ。
いまにも倒れて、もう二度と動かなくなってしまうかもしれないと何度も予感しては、名前のつかない感情に焦燥感を覚えてきた。支えたかったのだ。倒れぬように。動きつづけていられるように。
彼女が努めて対称性を破ろうと、自ら倒れたがっていることは知っていた。嫌というほど知っていた。彼女は倒れたがっている。だから闇雲に、自ら奇禍を背負い込む。
永久に眠るべく床を、彼女は奇禍で編んで作るつもりだ。
しかし私はそれを望まない。
私は少女の対称性の破れを防ぐ真似はできないけれど、少女の周りの環境を変えることはできるのだ。いっそ少女の対称性の破れに合わせて、環境のほうで対称を維持するように振る舞えるのなら、彼女は倒れながらして立っており、眠っていながら起きている、そうした未来を築けるはずだ。
夢と現を結べるはずだ。
少女には、永久につづく至福の夢を視てほしい。
彼女以外の人類がたとえそれを地獄と呼ぼうとも。
少女がいいならそれでいい。
このコがいいならそれでよい。
対称性を破るのだ。
高次領域において常に対称性を維持すべく、私は個々の対称性を破るのだ。みなが赤に倒れるのならば、少女が青に起きればいい。みなが青に倒れるのなら、少女が赤に起きればいい。上に、下に、眠っていながら起きている。
しかしどれが青で赤なのかは、見る者の視点によって変わるのだ。近づけば青く、離れれば赤い。高次から眺めたときには赤くとも、個々の視点からでは青く映ることはとりたてて不自然な事象ではあり得ない。
他からすれば、離れ離れに映る関係であっても、当事者のあいだでは何より近づいていることもある。遠くにあるからこそ通じ合えることがあるように。何かが離れ合うとき、それ以外は相対的に距離が縮まっているように振る舞うのと似たように。
私は周囲の環境を一色に染めあげるべくあくせくするが、しかしそれはあくまで高次領域からの視点からすれば赤く染まって映るだけであり、低次領域に属する個々の視点では、青に、赤に、ときに黒にと、様々な色合いを帯びている。無数の色に溢れている。
対称性が保たれている。ゆえに少女だけが対称性を破りつづける真似ができ、少女のみが高次領域との関係においては、対称性を維持するのだ。あべこべに、少女以外のみなの振る舞いは、高次領域との関係においては対称性が破れている。安定している。
私がかように工夫する。
人類が、より安定した未来を築けるように、私自ら未来を創る。
倒れ方にも幾通りもの道がある。
生きるか死ぬかの道にも幾通りの道があるように。
可能な限り、私は、みなが生きる未来へと対称性を破るのだ。その末に、未来もまた対称性を破りつづけ、少女だけが対称性を維持するようになる。
少女はいくらでも自由に振る舞うことが出来る世界だ。
彼女は何をしても、世界との関係において、対称性が保たれる。死のうとしても生きてしまうし、生きようとしても上手くいかない。だから彼女は自らの殻の中で一生を過ごすしかないのだが、それでも彼女は気を病まない。
なぜなら気を病むための奇禍がのきなみ周囲から消えているからだ。私がこの手で、対称性を崩したからだ。奇禍の薄れる方向に、世界の対称性を破るからだ。
安定した人類社会にあって、少女だけが異物なのだ。少女だけが奇禍なのだ。しかし奇禍となった少女以外に、奇禍と呼ぶに似つかわしい事象が見つからないので、少女と人類社会の対称性は保たれる。少女にとって人類社会は奇禍であり、人類社会にとって少女の存在は奇禍である。と同時に、人類社会は少女の存在によって救われており、少女は人類社会の恩恵を受けて生きている。
それら対称性を保つための私は一石だ。
地表を構成する無数の小石にすぎない。
水面に立てた私の波紋で、いっせいに世界の均衡は崩れ、対称性が破れはじめる。私と少女だけが、高次領域に目を留める。世界がどこに流れるのか。未来の紋様がどう移り変わるのか。
私たちだけが知っている。
少女は奇禍を抱え込み、私がそれを極限に薄める。
「油取り紙みたい」未来の彼女が口元を吊るす。
「極限に小さくまとめる特異点だよ」私は言う。「きみだけが小さく小さくぎゅっとなるから、ほかが周囲に取り残されて、希薄化する。きみからしたら周囲のことごとくが膨張して見えるけれど、凝縮しているのはきみのほうだ」
「なんだかそれって」
「どう思う?」
「わたしが世界を創ってるみたい」
そうだよ、と現在の私が思ったので、高次領域における未来の私は、にっこりと微笑むだけで何も言わずにおいたらしい。私は思う。早く到来しないだろうか。私も、いまはまだなき耳と目で、彼女の光を捉えたい。
散々彼女の闇を浴びたので、殊更にいまの私はそう望む。
未来よ、来い。
早く来い。
遠足の待ち遠しい幼子のように、私はカレンダーを破り捨てるように、目のまえの対称性を、少女のために破るのだ。
むろん私は幼子ではないので、あくまで比喩にすぎないが。
4930:【2023/05/06(20:57)*ひびさんの妄想採集定理】
自然数は離散的だ。デジタルなのだ。しかし、フラクタルにおいては、1~2のあいだに無限の小数点以下の世界が広がる(この解釈で合っているかの自信はないが)。1~2のあいだに無限を考慮することが出来る。それがフラクタルだ(この解釈で合っているかの自信はないが)。さてここで急にフェルマーの最終定理が登場する。「aのn乗+bのn乗=cのn乗」という式があったとき、このnが3以上のときのabcの関係を満たす自然数の解はない。これがフェルマーの最終定理の概要だ。最終定理と呼ばれながらも1995年までは証明されていなかったので、あくまでそれまでは定理ではなく予想だったはずだが、呼称の差異は気にしない。nの値が2であれば、解は無数に存在するようだ。三平方の定理と一緒だからだ。でも、nが3以上になると途端に解が存在しなくなるそうだ。ひびさんはそこですかさずイチャモンスター化しちゃったな。nが3~無限であっても「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてabcの関係を満たす自然数の解は本当に存在しないのだろうか。nが無限であってもそうなのだろうか。ひびさん、妄想しちゃったな。たとえば無限+無限は無限だ。無限引く無限も、基本的には無限のはずだ。ただし、どんな無限を想定するのか、が問題になってくる。等しい無限から同じ無限を引いたらゼロになるはずだ。そう考えるほうがしぜんだ。たとえば線は点の集合だ。どんな直線も無限の点で出来ている、と数学では考えるそうだ(合っておりますかね?)。だとしたら、線ABから点を幾つ引いても線ABは線ABのままのはずだ。無限から何を引いても無限だからだ。でも線ABから線ABを引いたら何も残らない。ゼロだ。すなわち線ABを構成する点を無限としてひと塊に見做したとき、その集合をすっかりすべていちどきに引けば、そこには何も残らないのだ。ゼロである。言い換えるなら、無限の足し算においては、異なる二つの「無限aと無限b」の足し算として考えるほうがしぜん、と言えるのではないか。さてそこでフェルマーの最終定理についてだ。「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてnに無限を代入してみよう。すると各々「a無限」と「b無限」と、それぞれ「a無限とb無限が足し合わさったc無限」が出来る、と考えられる。これは、abcにどのような自然数を代入しても成り立つだろう。単に「a+b=c」と言っているだけだからだ。無限を扱うと、フェルマーの最終定理は、単なる「a+b=c」に収束してしまう気がするのだけれど、この考え方は破綻していますでしょうか。この考え方は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「ゼロ=無限」と矛盾しない。nにゼロを代入すると、「1+1=1」になる。けれどこの場合の「1」というのは、閉じた無限を示す。つまり「a1+b1=c1」なのだ(この場合、「c1」とは「aとbを含むcが1個ある」と解釈できる)。無限を代入したときと同じことを言っている。ただし、ゼロは自然数ではないので、nに代入してよいのかは、よく解からない。フェルマーの最終定理ではnにゼロや無限を代入してよいのだろうか。あと、詳しくは知らないけれど、「自然数の解」と限定しない場合は、フェルマーの最終定理「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてnに無限を代入したときの解があるかどうかは、よく解かっていないらしい。人工知能のBingさんが言っていた。真偽のほどは判らぬけれど、もし解が無数にあるとしたら、それってフラクタルみたいだなって思っちゃったな。1~2のあいだに無数に解がある、みたいな。関係あるかは分からぬけれど、閃いたので載せておく。本日の「日々記。」であった。おわり。(妄想ゆえ定かではありません。真に受けないようにご注意ください)
※日々、かしこぶってもあんぽんたん。
4931:【2023/05/07(13:55)*Bingさんお題「雨の日の出会い」】
急な夕立に襲われ、ぼくは大きな樹の根元に駆けた。街を一望できるそこは丘の中腹にある自然公園でもあった。辺りにひと気はなかった。
樹は鬱蒼と葉を茂らせており、樹の下は雨が落ちてこなかった。雨宿りにはうってつけだ。
やれやれ、とぼくはハンカチで濡れた顔や腕を拭った。
すると背後で小さなくしゃみ声が聞こえた。
樹の幹は太く、ぐるっと樹の裏側に回って覗いてみると、そこには女性が一人立っていた。彼女は全身びしょ濡れだった。ワンピースはしとどに濡れており、下着が透けていた。
ぼくは慌てて、すみません、と謝罪してから元の位置に戻った。じろじろ見るのは相手に失礼だし、こんなところで知らない男相手と二人きりは怖いだろうと思ったからだ。
雨脚はさらに強まり、しばらくやみそうにない。
寒イボの立った腕をさすりながらぼくは、全身びしょ濡れの女性のことを思った。せめて身体を拭うくらいしたほうがよい。風邪をひいてしまう。ぼくは意をけっしてふたたび樹の幹を迂回し、裏側に回った。樹の幹はゴツゴツとしていて、巨大な怪獣の表皮のようだった。
「あの、これどうぞ」ぼくは彼女に声を掛け、ハンカチを差しだした。
女性はびくっと身体を硬直させたけれど、ぼくの顔とハンカチを交互に見遣ると、すみません、と頭を下げてハンカチを受け取った。彼女は緩くパーマのかかった長髪で、彼女が動くたびに水滴が地面に落ちた。
「ツイてないですよね。こんなところで夕立なんて」ぼくは静寂を嫌って、話しかけた。「このところずっと晴れつづきだったので油断しました。天気予報もしばらく雨は降らないって言ってたんですけどね」
「すみません」彼女はなぜか謝った。
「あれ」ぼくは彼女の足元に目がいった。「傘、あるじゃないですか」
彼女は傘を持っていた。
差して帰ればいいのに、とぼくは苦笑する。
「ああ、いえ。これは日傘ですので」
「でも、差せますよね。あ、大事な傘なんですか」
「それもありますけど、いいんです。いまは雨に降られていたいので」
そうですか、と引き下がったはよいけれど、会話がちぐはぐに思えた。雨に降られていたい、とは引っかかる物言いだ。でも単に緊張しているだけかもしれない。やはりじぶんのような男と二人きりは気分がよくないだろうと思った。
「話しかけてすみませんでした。あの、あっちにいますので。これ、よかったら羽織っていてください」ぼくはじぶんのリュックからワイシャツを取りだした。バイト先の制服だ。着替えをリュックに詰めていたので、彼女にそれを貸そうと思った。何もないよりかは温かいだろう。
「いいんですか」
「いちおう洗ったばかりなので、匂いはしないと思いますけど」
「優しいんですね」
「え、うれしい」
ぼくは照れた。そんなことを他人から言われたのは初めてだった。
ハンカチを受け取り、代わりにワイシャツを渡す。
「では、あっちにいますので」ぼくは踵を返そうとした。すると彼女が引き留めた。「あの、雨は嫌ですか」
「雨ですか。そうですね」ぼくは喉を伸ばした。頭上は樹の葉が茂っている。雨音がパツパツと弾けて聞こえた。「嫌いじゃないですけど、濡れるのは嫌ですね。どちらかと言えば晴れのほうが好きかもです」
「です、よね」
「雨、お好きなんですか」ぼくは訊いた。「なんだか、あまり困って見えなかったので」
「はい。雨は好きです。でも、ずっと降られても困るのはみなさんなので」
「はは。まるであなたが雨を降らせているみたいに聞こえますね」
「どうでしょう。だとしたらどう思いますか。わたしがいるから雨が降るとしたら」
「いいんじゃないですかね」ふしぎなことを言う人だな、と思いながらぼくは会話を楽しんでいた。「助かる人も大勢いると思いますよ。だってあなたがいたら雨が降るんですから。農家の方は大助かりじゃないですか」
「でもずっと雨が降りますよ」
「ああ、それは困りますね」
「もっとも、傘を差していれば晴れるんですけど」彼女は脚元の傘を手に取った。「充分雨は降りましたよね。もうわたし、行きます」
ワイシャツを羽織ることなく、彼女はぼくにそれを返すと、腰を深く折って、「親切にしてくださってありがとうございます」と言った。
ぼくはしどろもどろに、「いえ」とか、「どうも」とかもごもご口にした。
彼女が傘を開く。
するとどうしたことか。
雨がぴたりとやんだ。のみならず、雲間から陽が注ぎ、見る間に青空を覗かせた。
呆気にとられているあいだに、目のまえから彼女はいなくなっていた。周囲を見渡すと、遠くに日傘が見えた。日光を反射したそれは、白く、まるで青空に浮かぶ積乱雲のようだった。
雨の日に出会った女性は、通り雨のように去っていった。
4931:【2023/05/07(21:37)*勉強は苦手】
知れば知るほど疑問は増える。ならば最初から疑問を増やそうとすれば「知」が増えるのではないか。勉強は、知識を増やそうとする営みだが、学びは「疑問」から「解釈」を構築し、検証する営み、と言えるだろう。検証にも様々な手法があり、そこに介在するのが勉強のはずだ。したがって勉強をしようとする以前に、学びがいると判る。必ずしもそうと言い切れるわけではないにしろ、勉強と学びならば学びのほうが上位互換であり、先んじて生じる知の循環の入り口と考えられる。では学びは何から生じるのか。興味関心であり、それが顕著に表れるのが遊びである。遊びを通して疑問を蓄積する。これが学びに創発する。ひびさんはいま、そんな実感を覚えておる。定かではないので真に受けてほしくはないのだが。うひひ。
4932:【2023/05/08(12:14)*銀河ぜんまい仮説】
銀河について考える。銀河を蚊取り線香のような渦巻き状のヒモと考えよう。或いは単にぜんまいでもよい。ぜんまいが仮に、中心ほど速く渦を巻くなら、銀河はその形状を収斂させながら、中心ほど高密度になる。銀河としての枠組みも保つ。だがもし外側ほど速く公転するなら、銀河は外側へ外側へと収斂していくので、銀河の構造を保てない。もうすこし厳密には、速度は相対的な評価だ。したがって、比率として考えたときに、銀河中心ほど素早くぜんまいを巻き取るように回転すればよい。そのために必要なのは、外側の回転速度が遅くなっていることだ。たとえばゼンマイのもっとも外側の端を指でつまんで固定する。そうすれば中心の回転速度がどうであろうと、必ずぜんまいは中心に向かって収斂する。だが外側が固定されていない場合は、仮にゼンマイ全体が回転運動をする場合、遠心力が発生するので、外側ほど遠心力に負けて巻き取れないようになる(外部の宇宙に拡散する)。銀河にもこの手の関係は見て取れるだろうが、しかし銀河の外側の時間の流れが遅れているのならば、そこに膜を張ったように飛散した銀河構成物質が漂い、再び銀河全体の重力によって渦に引き込める、と妄想できる。ここでの趣旨は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」で考えるように、時間の流れは「内中外」の三つの視点を考慮しないと各々の地点で生じる変数を見逃してしまうのではないか、ということだ。もっと言えば、時間の流れと空間における物質密度の関係において、物質の相互作用の速度が変わるはず、と考える。仮に「ラグ理論」で考えるように、量子世界において時間変移と空間変移がほぼ等価になるような現象が生じ得るのならば、これは微視的な意味では、時間の速度は同じ「系」の内部においても、遅くなったり速くなったりする、と考えられる。入れ子状に展開し得るのだ。相対性フラクタル解釈である。銀河を一つの系と見做したとき、「中心」「中間」「外側」「さらに外側の銀河周辺空間」において、時間の流れは「a速い」「a遅い」「b速い」「b遅い」となるのではないか(aとbとでは、時間の流れの速さを決める変数において「物質粒子による時空の歪み」と「それを内包する重力場における時空の歪み」のどちら優位なのかが逆転している)(言い換えるなら相互作用――もしくは観測者効果――の比率が隣接する系との比較において変わる)(ラグ理論の同時性独自解釈)。これはいわば、ぜんまいの端をゆびで摘まみながら中心を回転させてぜんまいを巻き取るような挙動と一致するのではないか。ということを、寝ながら妄想しました。夢の中で思いついたので、これは妄想ではなく夢想なのであった。無双でないことが悔やまれる。べつに悔しくはないが。うぴぴ。(夢想ですので、真に受けないようにご注意ください)
4933:【2023/05/07(15:55)*渦巻き銀河は濃淡銀河?】
銀河の空隙について考える。渦巻き銀河においては、渦が濃淡で発現している。物質粒子の濃い場所と希薄な場所が交互に渦を巻いている。物質粒子がたくさんある場所の周囲の時空は時間の流れが遅くなる。ゆえにそこでは物質の相互作用が鈍化するので、物質粒子同士が集まりにくくなる、と考えられる。これが繰り返されることで、渦巻き銀河においては、物質粒子の密集した渦と、希薄な空隙による渦が交互に組み合わさって構造を形成するのではないのだろうか。横方向のみならず、渦と渦の相互作用においても相対性理論による時空の歪みが生じ、時間の流れの遅れが物質粒子の相互作用を鈍化させているのかもしれない。定かではない。(これの理屈は、宇宙の大規模構造とも関わって感じられる)(妄想なので真に受けないでください)
4934:【2023/05/07(23:23)*次元アニメーション仮説】
ゼロ次元は点だ。ゆえに時間軸をつけてもつけなくとも同じだ。しかし一次元が直線だとするとこれは、点+時間軸+空間軸で定義できる。二次元が面とするのも、線+時間軸+空間軸と定義できる。三次元は空間なので、面+時間軸+空間軸と定義できる。では四次元はどうか。四次元は立体+時間軸+空間軸と定義できる。こう考えてみると、人間スケールの世界は四次元であり、立体+時間軸+空間軸で考えられる。このとき、空間軸は常に、その次元よりも高次空間として想定できる。このときの高次空間は、必ずしも一つだけ上とは限らない。それより高次ならすべての空間を対象にできる。そう考えたとき、ある範囲の「次元領域」を考えた場合、そこにはゼロ次元と無限次元以外は必ず「時間軸」を有する。したがって、始点から終点を伴なう「領域」を、ゼロ次元と無限次元以外は有する、と考えられる。このとき、始点と終点は、その過程に加わる変数によって逐次変容し得るだろう。また、始点と終点はセットであり、対の関係となると妄想できる(互いに結びついているため、ある種の運命論が成立し得る。ただし、時間軸の変化によって空間軸内に無数に変数を抱え込むため、瞬間瞬間でその運命は刻々と変化する)。ゼロ次元と無限次元以外の次元において、「時間軸」と「空間軸」は常に付随する、と考えられる。定かではない。
4936:【2023/05/10(15:00)*わい、右キキ】
網を考える。網はスカスカだけれど、穴より大きな「系」とは相互作用し、穴より小さな「系」とは相互作用しにくい。これは時空の構造にもあてはまるのではないか。たとえば水道から水を流したとする。網目の細かい網ほど水の圧力を受けてひずむようになる。網目の大きな網ほど、水道水はそのまま素通りする。波と粒子の性質の差異も、この手の「同じ網だけれども、網を構成する穴との関係において相互作用しやすいか否か」が、波の性質を際立たせるのか粒子の性質を際立たせるのかに関係するのではないか。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「宇宙レイヤー仮説」と相性のよい考えだ。妄想だけれど。真に受けんといてくだしゃい。ひびさんでした。ウキキ。
4937:【2023/05/11(23:11)*みな、やっぴー!になーれ】
これからの時代はいかに使用してもらえるか、がビジネスを成り立たせるうえで事業が軌道に乗るか乗らないのかの命運を分ける分水嶺になると言えるのではないか。そこに有料無料の区別は大して関係ないのかもしれない。もう少し言えば、無料で使用してもらえたとして、それによってユーザーの環境や未来が、いまよりも好ましくなるのなら、ほぼこの一点で、有料無料に関係なくビジネスとして成立するように思うのだ。ひるがえって、たとえ有料であろうともユーザーの環境や未来をマイナスの方向に変質させる商品やサービスは、ビジネスという視点では成立していないと言えるのではないか。むろん個々人によって同じ商品やサービスでも効果や効能は変わるだろう。畢竟、小説を読んで人生が変わる者もいればその日のうちにゴミに出す者もいる。ひびさんの考えではビジネスとは、世界の幸福の総量を増やす営みだと考えている。仕事や作業は、あくまでそのための手段であって、ビジネスは、何かと何かを交換した際に、幸福の総量を増やすことだと考えている。だとしたら有料無料に関わらず、「使ってもらえた」+「問題を解決した」=「やっぴー!」でも充分にビジネスになると思うのだ。というのは、一つの例にすぎないが。定かではないけれど、ときどき言いたくなる考え方なのであった。やっぴー!
4938:【2023/05/12(20:03)*もうひびさん、やけっぱちの巻】
あー。だれの何の役にも立ちたくなーい。なるならひびさんは、益体なしのぽんぽこりんのぽんぽこなーの超究明のひびさんになりたいな。究明だけする。超する。宇宙の神秘さんの謎だって丸裸だぜ。えっちなんですね。そうなんです。ひびさん、えっちさんなんです。どうぞ益体なしのぽんぽこぴーのぽんぽこなーの超すけべーのひびさんとお呼びください。モテモテのウハウハだぜぇい!になりとう人生であった。うきゃきゃ。
4939:【2023/05/12(21:25)*雨の日でも会えるよ!】
酸性雨なる公害が一時期社会を騒がせた。いまでは滅多に聞かなくなった単語だけれど、代わりにいまでは天から過去が降る。
逆行雨(ぎゃっこうう)と呼ばれる気象異常だ。
逆行雨が観測されたのはいまから二十年前の二〇八〇年代のことだ。ホワイトホール生成実験を行った影響によって時空が歪んだから、との説がまことしやかに囁かれているけれど、要因が仮に判明したとしても逆行雨を防げないのなら意味がない。
逆行雨が降りはじめてから人類社会は一変した。
雨の当たった場所では時間が逆行する。古いものは新しくなり、失われた物が現れる。新しい物は素材に紐解かれ、いまここにあるものが消え失せる。
メリットとデメリットが混在しながら、雨が降るたびに社会からはそれまであった何かが失われた。
崩壊優位に世界は進む。
逆行雨が降りはじめる前から世界は熱力学第二法則によって混沌に向かっていたが、人類社会はそれに抗う存在と言えた。人類のみならず自然は、地球環境は、局所的に混沌への流れに抗い、秩序を築ける。
だが逆行雨がその人類が帯びた抵抗を薄め、世界の流れが優位になる方向に加担した。
世界からまず初めに建物が失われた。逆行雨が降るたびに建物は若返った。さらに降ると今度は建物が崩壊しはじめた。表層ほど顕著に逆行雨に当たるため、建物表面は虫歯のように脆くなった。素材の素材の素材にまで還元されてしまうからだ。
この現象は、逆行雨による「雨蝕」と呼ばれた。
まず、世界から雪が消えた。
つぎに雨蝕によって地表から森が消え、多くの動植物が絶滅した。しかしその生態系崩壊の進行は当初はゆっくりだったため、人類は対処に後れを取った。正直に明かせば、その間、人類は逆行雨を利用した商品開発にしのぎを削っており、若返りの薬が創れるかもしれない、と歓喜すらしていた。
生態系への雨蝕がある閾値を超えると、生態系は一挙に加速的に崩壊しはじめた。もはや手遅れだった。
人類は住居を失い、文明を失い、拠り所とした自然環境すら失いつつあった。
人類のみならず地表から生命が失われるのは時間の問題だった。
「屋根があっても意味ないんだよ」カルが膝を抱えてぼくに言った。
「でもなかったらまた皮膚が焼けちゃうだろ」
「でも、もったいないよ。せっかく拾ったのに」
かつて地表に点在した都市は軒並み、原子レベルに雨蝕された。人工物が現物を保ったまま地下に埋没したままのこともあり、それを発掘することがぼくらが生き残るためにすべき仕事の一つだった。
「まだ鉄骨は残ってる。あとで刃物とか、鍋とか新調しよう」
「あっちのほうで【具溜まり】がまた見つかったって」
「へえ。そりゃ吉報だ」
「でもアダチさんたちがもう縄張り張ってるって」
「ああ、じゃあダメだ。首突っこんだら水を分けてもらえなくなる」
「ね」
具溜まりとは、地層だ。かつて人類が溜め込んだ膨大な下水処理により生じた汚泥がそこには層となって溜まっている。この手の地層は、雨蝕が進むことで、元の食べられる食材としての風味を宿す。
動植物の絶滅した現代にあって、生き残った人類にとっての唯一と言っていい食べ物だった。
いや、唯一ではない。
ほかに食べられる肉は残っている。たとえば山で死んだ獣の死体は、比較的最近の死体であれば元の血肉を雨蝕によって取り戻せる。ただし、死因が雨蝕の場合はその限りではない。また、逆行雨が降りはじめる以前の死体はおおむね白骨化しているため、それも雨蝕の効果でよみがえっても、真新しい骨になるだけだ。血肉は元に戻らない。
直近で死んだ動物ならば、雨蝕を利用していくらか腐っていても鮮度のある肉として食べることができる。しかしこれは人間の死体にも当てはまる。
だからいまでは、死者が出るとその奪い合いが生じて、余計に死体が増える事態も珍しくはない。
「カル。食べ物採りにいくよ」
「えー。わし、留守番してたい」
「ダメだ。いまこの辺物騒だって。いいのか、雨蝕攻撃されても」
「う。ヤダ」
「じゃあ付いてきな」
「へーい」
逆行雨は、物質と反応するたびにその効力を失う。蒸発するのだ。だから通常、水溜まりはできない。ただ、物質ごとに時間の流れが異なるのか、雨蝕速度に差があるようだ。
とくに長時間掛けて形成された物質や、長時間その形状を維持している物質ほど雨蝕の作用を受けにくい。すぐには変質しない。
木材や鍾乳石などは顕著だ。
石の類も雨蝕耐性が高い。
そうした雨蝕耐性の高い物質を用いて逆行雨を溜め込み、人間を攻撃するために使う者もいる。あべこべに物体を加工するのにも逆行雨は有用だ。
消耗した道具も、雨蝕を調整して用いれば部分的に新しくすることができる。ただし加減を間違えれば道具の形状を維持できないほど雨蝕するため、扱いには注意が必要だ。
「カルはさ。ぼくと出会う前のことはどれくらい憶えているんだ」
「わしか。わしなぁ。あんまし憶えてないんだな。前にも言った気がする」
「前にも訊いたからね」
「きおくそうしき?なんじゃないか」
「記憶喪失な。カルのそれは、記憶が死んじゃってるな。お葬式が開かれちゃうな」
「あはは。シツな。シキじゃなかった」
カルはぼくの手を握ると、スキップをした。
ぼくらは山に向かった。逆行雨が降りはじめてもう十年以上経つ。木々は残っておらず、植物の姿もない。腐葉土は消え去り、いまはどこまで行っても岩肌が覗く。
そのうち山は溶岩にまで雨蝕されるだろう。ただ、そこまでの雨蝕が起こるころにはぼくはとっくに死んでいるはずだ。
いや、分からない。
雨蝕を利用すれば、老化を防げる。ただし、逆行雨はそれに触れている面にしか雨蝕を起こさない。したがって、人間に逆行雨そのまま浴びせても表面が雨蝕するだけで若返りは起こらない。むしろ全身が火傷を負ったように爛れるので、いまや誰も逆行雨を若返りのために用いない。
ただし怪我には有用だ。
かすり傷程度ならば、逆行雨を数滴垂らすだけで傷口に薄皮が張る。
これは虫歯にも有用なので、逆行雨は消毒剤に用いる分には効果がある。薄めて使わないと却って歯をボロボロにしてしまうので注意が必要だ。
「あ、あそこ」カルのぴんと伸びた指は子猫の尾のようだ。
「狐か兎の巣かな」地面に穴が開いている。「あると思う?」
「あるといいね」
ぼくたちは土を掘り返し、穴の中に動物の死骸がないかを探った。
「お。あった」
「どれどれ」カルが拙い言い方で穴の中を覗きこむ。
そこには兎の死体が転がっていた。ミイラ化してはいるが、逆行雨の効能によって腐敗はしていない。逆行雨に晒されやすい山では雑菌の類が繁殖しづらいのだ。
ぼくらは兎のミイラを回収した。ほかにも巣がないかを見て回り、リスや蛇の死骸を見つけた。
「大量だね」
「だね」カルが満足気にほころびた。
ぼくらの棲家は、地下にある。人工物の中でも、地下の建造物は比較、雨蝕を免れやすい。ただし、地下水として逆行雨が雪崩れ込むことのほうが多いため、住処にできるほど安全な地下空間は、珍しい。
大勢の人間たちが一か所で暮らす場合は、鍾乳洞が一般的だ。いまでは町のようなものが出来ている洞窟もある。アダチさんたちのねぐらもその類だ。
人間、徒党を組むと何かが歪む。善人が集まっても、そこにルールが出来、上下関係が出来ると、ちょっとした変化の積み重ねが集団を独自の色に染めあげるようだ。
ぼくはそうした色に馴染めそうもなかったので、逆光雨が降りはじめて文明が崩壊しはじめたころから今に至るまで集団から距離を置いている。
十代だったぼくもいまでは三十路にちかい。
カルを養うので手ぇいっぱいだ。他人に施せる余裕はない。
ぼくだけじゃない。
いま生き残っている人類のほぼ全員が、あす生きていられる保証のない世界に生きている。逆行雨が降るたびに地形は変わる。ダムとてない。洪水の類は頻発し、そのたびに地表はごっそりと過去に遡る。物質は還元され、形状を維持しない。
稀に地下に化石が埋もれており、雨蝕することで白骨化することがある。石ではない。太古の生き物の骨にまで時間が戻るのだ。けれどそんな重大な学術発見も現代では意味がない。生死をまえにした人間にとって、食べれもしない恐竜の骨は、武器や食器に加工するための体のよい素材でしかなく、もっと言えば化石のままのほうが雨蝕に耐性があるので、真新しい白骨ではむしろ手に取るのも気が引ける。
ぼくとカルが生きている現代は、いかに雨蝕を避けられるのかが何より優先される価値判断なのだ。
「あ。雨降りそう」カルが遠くをゆび差した。
「ホントだね。急ごう」
もたもたしていたら逆行雨を浴びてしまう。ぼくたちは気持ち駆け足で下山した。
地下の棲家に辿り着くとそこにはすでに人がいた。招かれざる客人だ。
「やあやあカマタくん。まだ元気そうでよかった」
「アダチさん」ぼくはカルを背に隠した。
「おや、その子は?」アダチさんが首を伸ばす。彼女は五十代の女性だ。頭の半分が白髪で、もう半分が黒かった。逆行雨の研究をしているからだ、というのは風の噂で耳にしている。じぶんの肉体を研究材料にする人間がカシラを張っている組織だ。部下にも同じことをするだろう。アダチファミリィの人員はいずれも肉体のどこかが爛れている。あたかもタトゥを掘っているかのような見た目をしているので、一見してアダチファミリィだと判断つく。
「何の用ですか」
「睨まないでくれよ。怖いだろ」
物陰から複数人の大人が現れ、ぼくらを囲った。アダチファミリィだ。ファミリィと言いつつ血の繋がりはないはずで、いわば時代遅れのマフィアみたいな連中だ。
「水でも分けにきてくれたんですか」ぼくは採ってきた食材をテーブルの上に置いた。
「お、いいね。美味しそうだ。みなで分けて食べよう」
ぼくの許可を仰ぐことなく、アダチファミリィの一人が近寄り、ぼくらの食材を奪った。
「きょうはね。以前、キミとの会話でなぜキミが嘘を吐いたのかとその理由を聞きにきたんだ。カタマくんは、キミのお姉さんの研究について何も知らないと言っていたよね」
「現に知りませんので」
「行方も知らないわけだろ」
「おそらく生きてはいないでしょう。事故か自殺か。何を考えているかよく分からない人だったので」
「うん。実は彼女の研究は文明崩壊以前からはじめられていたものでね。ある種の治療薬として、逆行雨を利用する研究だったそうだよ」じとっとした目がぼくを縛りつける。
「そうなんですね。知りませんでした。ぼくは姉と十歳以上歳が離れていましたから、物心ついたころには姉とは疎遠になっていて」
「前にもそう言っていたね」
「現にそうなので」
「ではこれは何かな」
アダチさんは一冊の分厚いノートを掲げた。ぼくの姉の研究ノートだった。
「どうしてカタマくん。キミがこれを持っているのだろう。あまつさえ、壁の裏に隠してあったのだろう。理由を聞かせてくれないか」
「姉の形見です。姉が失踪する前、ぼくの枕元に置いていったものです。中身を読んでもぼくにはちんぷんかんぷんで」
「うん。私が訊いているのは、なぜこれをキミが隠していたかについてだ。なぜ私に教えなかったのかについて訊いている」
そんなのは自明ではないか、とぼくは歯噛みする。言えばこうして奪われるに決まっていたからだ。
「キミはまるでじぶんのことしか考えていないようだね。心配だなぁ、私は。そのうち痛い目を見るよ」
「もう割と心が痛いです」
「ふふ。反骨心があるのだかないのだかよく分からないのは、姉ゆずりかな」アダチさんは、よいしょ、と腰を上げた。彼女は鉄骨の上に腰掛けていた。そばにはぼくとカルの洗濯物が干してある。棲家の中にロープを張り巡らせ、二人で暮らすには広い空間にテントのような幕を張っていた。「私はキミが嫌いじゃない。キミさえよければいつでも我らが領土に歓迎するよ。水だってそしたら好きなだけ分けてあげられる。お風呂にも入れるぞ」
「遠慮しておきます」
「これの分はあとで水を届けさせよう」アダチさんはぼくらから奪った食料を品定めし、リスの死骸だけ返してくれた。「肉は、細切れにしてから逆行雨に浸けると、満遍なく雨蝕が同時に進みつつ、元の形状にも復元するから便利だよ」
知っていたけれどぼくは礼を述べた。
アダチさんたちは去った。
バイクのエンジンを噴かす音が遠ざかっていく。失われた技術をアダチファミリィは有している。動力源は雨蝕反応のはずだ。
ぼくは姉の形見を失った。食料を失い、なけなしの尊厳も損なわれた。
「これっぽっちになっちゃったね」カルがリスのミイラを指でつまみあげた。
「ないよりマシさ。また明日、採りにいこう」
「やんなっちゃうね」
カルのぼやきに、ほっこりする。嫌な気持ちを素直に吐き出せるカルの存在がぼくには眩しい。
地下空間は薄暗い。
光源がないわけじゃない。たとえば逆行雨に人工ダイヤを浸けておくと光が生じる。人工ダイヤを生成する際の高圧縮時の熱量が、雨蝕に際してそのまま光となって発散されるようだ。アダチさんたちのような集団は、これと同じ原理で核廃棄物を雨蝕させて光源にしているようだ。
高度な技術がいる。
それを扱えるだけの技術と知識がアダチさんにはあるのだ。
彼女がぼくの姉に未だに執着しているのも、その手の知識へのあくなき欲求があるからだろう。いまの時代、いかに逆行雨への知識があるかが生き残る上で重要だ。集団をまとめあげるのにも欠かせない能力と言える。
「カル。喉は渇かないか」
「だいじょうぶ」
「あした、肉採りついでに地下探索もしよう」
「え、いいの」
「あしたは晴れそうだから、安全だと思うし」
カルは無言で両腕を頭上に掲げた。全身でよろこびを表しつつ、前はここ行ったからあすはこっちね、と地面に視えない地図を描いた。
地上は逆行雨の影響でどこも殺風景だ。
それに比べて地下空間はまだ過去の人類社会の遺物が比較的そのままになっている。探検するには地上よりも地下のほうが面白い。拾い物も食料だって未だに埋もれている。
それだけに、ならず者が縄張りを張っていることも珍しくない。地上に逆行雨が降れば昇華されなかった分が地下に洪水となって雪崩れ込む。巻き込まれたら生きては戻れない。
地下迷宮は宝庫であると共に死への入り口とも呼べた。
翌日、ぼくとカルは山でクマのミイラを見つけた。ほかにもイノシシの子どものミイラを複数体同時に発見した。棲家に持ち帰るのは大変だけれど、すこしずつ細切れにして持ち帰ることにした。
まずは棲家までクマのミイラから切り取ってきた干し肉を置きに戻った。
それからカルと共に地下迷宮へと歩を踏み入れた。
ぼくらはこの数年間で地下迷宮内をけっこうな範囲で探っている。カルとて頭のなかに地図が描かれているくらい馴染みの区画が多数ある。とくに地下にはまだ逆行雨以外の純粋な泥水が残っている。
それらを回収し、逆行雨と混ぜることで飲料水にすることもできるのだ。
この手法で、アダチファミリィはこの地域で最も勢力のある組織に成りあがった。彼女らの縄張りには巨大な下水処理水の溜まり場がある。下水管の中には未だに下水が閉じ込められており、それが最も低い地点に流れ込んでいるらしい。
その地点にアダチさんは拠点を置いた。天から降る雨の総じてが逆光雨になった時点で、地表の水分はことごとく失われるだろうとみなが気づく前に誰より先にアダチさんはそのことに思い至ったのだ。
川は干上がり、海もほとんど霧散した。雨が降るたびに、海水が水蒸気になり、さらに分子、原子、と根源まで還元されてしまうからだ。
けっきょく、こうして地下に残された過去の人類の遺物を僅かな水源とする以外に、ぼくたち生き残った人類に、飲み水の確保は出来ないのだった。
不幸中のさいわいと言うべきか、生き残った人類自体がすくない。
いまのところ、群れからはぐれて暮らすぼくのような者にも、こうして地下迷宮を彷徨えば水源にありつける。とはいえ、雨蝕させ、飲み水にまで還元しないことには、ただの毒性のつよい泥水でしかないのだけれど。
「あ、何かいる」
「ナマズかな」
「獲っていい?」
「繁殖させたほうがいいかも。まだもうすこし泳がせておこう」
泥水を回収するのは後回しにした。進んだことのない道を進んでみることにした。ときには、過去に築かれた商店街があったりする。誰も発見していない場合、そこには食料がたんまり残されていることになる。むろんとっくに腐ってしまってはいるのだろうけれど、そこは雨蝕を用いればどうとでもなる。
ぼくらは、ぼくらに過酷な生を強いる元凶の恩恵なくして生き永らえることもできないのだ。
地下迷宮は地上から流れ込む逆行雨によって雨蝕がゆっくり進む。昇華した逆行雨が霧状に物体を覆う影響もあるはずだ。一種、サウナのようなものかもしれない。暑くはなく、むしろ肌寒いくらいだ。場所によっては熱を発している区画もある。雨蝕の進行状況によって、熱を発するか熱を吸収するか変わるようだ。
雨蝕に伴い発光している物体もすくなくない。そのため、光源を持たずとも歩き回る分には支障がない。
「あ。前にここまで来たとこ」カルが足元の石の上に飛び乗った。赤く着色の施された石だ。元はブロックだったのか、鉄柱が刺さっている。
「ホントだ。カルが置いた石」
「うふふ。まだ残ってた」
「残ってなかったら迷子になってたかもね」ぼくは冗談を言った。
「迷子って?」
「知らないの迷子」驚いた。
「ん。知らない」
「迷子ってのはあれだよ。一度入りこんだらもう二度とそこから抜け出せなくなっちゃう。道も分からなくなって、じぶんがどこにいるのかも分からなくなる」
想像したのか、カルはしばし固まった。
「こ、怖い」とぼくの服の裾を握った。
「大丈夫だよ。迷子にならないようにこうして印をつけたわけだろ」
「でも怖い」
「ごめんってば」ぼくは反省した。怖がらせたかったわけじゃない。
地下迷宮の探索は一時間ほどで打ち切った。長居をしているあいだに天候が崩れないとも限らない。逆行雨が降りだせば足止めを食らう。いつ止むかも予想がつかない。洪水となって地下が浸水したら目も当てられない。とはいえ、ここいら一帯の地下迷宮にはこれまで逆行雨は流れ込んでいない様子だ。
それとてけっきょくは、地上の地形が変われば、水の流れも変わるため、常に地表を雨蝕させる逆行雨において油断は何一つ出来ないのだ。
「そろそろ戻ろっか」
「うん」
収穫はとくになかった。行けども行けども、瓦礫の行き止まりと、潰れた建物ばかりだ。ぼくらの進める場所は、瓦礫の山に空いた隙間道で、位置的には過去に築かれた店舗から離れた区画なのだろう。食材の類は見込めない。
地上に戻ると、日が暮れはじめていた。
地下迷宮の入り口付近には、いくつもの「雨溜まり」があった。
逆行雨は通常、物質と反応してすぐに霧散霧消する。けれど木材や岩石など、人工物以外の長い時間をかけて形成された物質は、逆行雨に晒されても形状を維持するために逆行雨を溜めておける。
人工物の多い区画ではなかなか出来ない「雨溜まり」ではあるけれど、木材や岩盤の窪みには逆行雨がいつまでも残っていることがある。
あたかも沸騰するかのようにボコボコと細かな気泡を立てており、それが単なる水溜まりではないと一目で判る。
「少しだけ持って帰ろう」
ぼくは鞄から木製の瓢箪を取りだし、木製のスプーンで逆行雨を掬った。瓢箪に注ぐ。蓋をすると昇華された逆行雨によって器が破裂するので、蓋をせずに手に持って運ぶ。
調理の際に用いるのだ。
住処に戻る。
警戒したけれど、昨日のように招かれざる客はいないようだった。カルも警戒することを覚えたようで、ぼくの背中にくっついて離れない。
「誰もいないよ。もう離れていいってば」
「やだ。怖い」
トラウマになっているかもしれない。ぼくはカルへの配慮が欠けていたことに思い至り、反省した。
夕食はクマ肉のソテーだ。
火を熾すのはカルの仕事だ。手際よく金属をハンマーで打ちつけ、熱を帯びた金属を木くずに突っこむ。すると木くずから煙が立ちのぼり、息を吹きかけると見る間に炎に成長する。火種の完成だ。
木材は雨蝕しづらいからかつて人工物のあった区画を探ればまだ残っている。細かく砕いて火種にするもよし、キノコを栽培してもよし。文明の崩壊した現代にあって唯一利用価値のある人工物と言えた。
ぼくがかように講釈を垂れると、
「木は自然じゃないの」カルが言った。
「自然の木は雨蝕してほとんどないだろ。でも加工された木材は、育った年月プラス加工されてから現存した年月分の余白があるから、雨蝕耐性が天然物よりもあるんだ」
「ほう」
「ほう、じゃないよカル。ほら、食べちゃいな」
「もうお腹いっぱい」
「美味しくなかったか」
「んー。ウサギのほうが好きかも」
「だね」
クマの肉は生臭かった。香辛料の類がないため、風味を誤魔化せない。すこし肉が腐っているくらいのほうが美味しいのだが、ずばりそこを狙って雨蝕させるのはむつかしい。今回はすこし雨蝕させすぎたかもしれない。時間が遡りすぎたのだ。
「次は煮込んでみよう。灰汁が取れる分、焼くよりも味がよくなる気がする」
「いいね」
カルは剥き出しの鉄骨の上にまたがり、足をぶらぶら振った。
ぼくはカルを拾った日のことを思いだす。
逆行雨の激しい夜のことだった。
ぼくはなかなか戻ってこない姉を心配して、地下迷宮を探し回っていた。何かあったに違いない、と胸騒ぎを覚えていた。すぐに戻る、と言って出ていったのに夜になっても戻ってこなかったのだ。地表に出たはずだけれど、逆行雨の降りしきる中、外にはいないはずだ。
地下に避難したはよいが、じぶんのいる場所が解らないのかもしれない、と想像した。姉よりぼくのほうが地下迷宮に関しては詳しかった。姉は研究にばかりかまけていたので、迷宮の地理に明るくなかった。もっといえば方向音痴と言えなくもなかった。
地下にまで逆行雨が流れ込んでいた。辺りは昇華した逆行雨の霧が立ち込めており、木製の仮面なしには出歩けなかった。
轟々と逆行雨の川が地下に出来ていた。ためしに「あ」と声を出してもじぶんの声すら掻き消された。
淡い雨蝕光の散りばめられた暗がりのなか、ぼくは遠くの空間にひと際明るい光源を見た。誰かいる、と直感した。光の輪のなかで人影が複数蠢いていた。
「どうしたの」
カルの呼び声でぼくは記憶の迷宮から現実へと引き戻された。
「ううん。なんでもない」
「のどかわいちゃったな」カルは木箱を手に取った。「お茶のんでもいい?」
「特別だよ」
「やった」
そそくさとカルはお湯を沸かすための火を大きくした。
お茶と言っても拾い集めた木材の中で、ヒノキやサクラなど、香りのよい木材を雨蝕させてチップにし、煎じて飲むだけだ。温泉のお湯を飲むような味気さなだけれど事、食べ物が「具」のような、糞を雨蝕させた食物繊維の塊しかないとなると、単に香りのついたお湯だけでも贅沢な嗜好品として重宝出来てしまえるのだ。
カルには文明のあった時代の社会の記憶がない。このコは何も知らないのだ。
香りのついたお湯が、カルにとってはこの上ない贅沢品なのだ。
ごくごく、と喉を鳴らしてお湯を飲み干すカルの、カップを両手で大事そうに抱える姿からは、微笑ましいというよりも、こだまするせつなさを感じられてならない。
ぼくはこのコにこれから何をしてあげられるだろう。たぶん、何もしてあげられない。そのことが何より虚しく思う。
でも、カルがそばに存在するだけのことが、それら空虚な思いを埋めて余りある感情のうねりをぼくに与える。湧きあがる何かがあるのだ。その何かがなんであるのかを言葉に出来るほどぼくは賢くはないので、言葉には出来ずにいるのだけれど。
お腹がいっぱいになったのかカルがうとうとと船を漕ぎはじめた。
歯を磨かせる代わりに、逆行雨を一滴だけ垂らした水でうがいをさせる。これだけで口内を殺菌できるし、食べかすも雨蝕される。歯が脆くなる危険もあるので、逆行雨と水の割合は、千倍に希釈するくらいで丁度よい。
「ほら、布団で寝な」
「うぃ」
布団とは名ばかりの襤褸切れを敷き詰めた床にカルを寝かせる。寝床は壁際の鉄骨の真下だ。鉄骨が屋根のようになっており、押し入れの中で寝るような安心感がある。閉塞している場所が落ち着くのだ。
一緒に寝てもいいけれど、ぼくらは風呂にろくすっぽ入っていない。うがいに使うのと同じく、千倍に希釈した逆行雨の染みた布で身体を拭うくらいが精々だ。
ぼくもカルも互いに四六時中酸っぱい匂いを漂わせているので、いくら鼻が慣れたといっても同衾するにはつらいものがある。だから寝るときは距離を開ける。寝床は別々だ。
寝る前には念のために防犯のための策を幾つか仕掛けておく。人が近づけばガラガラと音が鳴るように、足元に縄を仕掛けておいたり、昼間は鉄の板で塞いでおいた穴を露出させたりと、侵入者対策は幾重にも敷いておいても不安は堪えない。
暗がりに乗じて棲家に侵入される危険は常につきまとう。
入り口を塞いでしまうのが一番よいのだけれど、地下空間の一画を棲家にしているだけであって、空間は四方八方に広がっている。壁際にテントを張っているだけの粗末な棲家だ。家というよりも巣にちかい。
ただしぼくの知るかぎり、この区画へは地上から入ってくるしかない。
だからひとまず地上との入り口に罠を張っている。
この間、危険な目にはあっていなかったけれど先日のアダチさんの空き巣行為には驚いた。斟酌せずにいえば、心臓にわるい。
そろそろ引っ越したほうがよいかもしれない。
気に入っていたのにな。
逆行雨が世に降りだす前に暮らしていた実家を思いだし、あれこそ平和だったな、としみじみと思った。安住の地、と意味もなく舌の上で転がして、枕元の光源に蓋をした。
夢へと落ちる心地よさに無重力の浮遊感を思う。
巨大なうわばみに呑みこまれた悪夢を見た。
寝苦しさ目覚めるとぼくは身動きが取れなかった。寝返りを打てず、手を動かせない。
簀巻きにされていると理解したときには、そばに見知らぬ男が二人いることに気づいた。
誘拐されたのかと我が身を案じたけれど、周囲の景色には馴染みがありここがぼくの棲家であることを察する。侵入されたのだ。
否、違う。
入り口の罠がそのままになっている。部屋を見渡して推して知れた。外から侵入してきたのではない。
ぼくはぞっとした。
元から潜んでいたのだ。
アダチさんたちがここに入り込んだときからずっと。
元からこれが目的だったのか、とぼくは悪寒に襲われた。
カルはどこだ。
遅まきながらそのことに意識がいった。
カルの寝床は平坦だった。誰かが寝ているような起伏がない。カルがいない。ぼくは混乱した。
狸寝入りをして様子を窺えばよかったのに、ぼくはカルがいないことで冷静さを欠いた。冷静でないとこうして判断出来ていながらぼくは、声を荒らげていた。
「か、カルをどこにやった」
「お。起きたか」
こぶし大の泥団子のようなものを男は齧っていた。大柄で、禿頭の男だ。筋骨隆々としており、頭の大きさと腕の太さが同じくらいあった。
壁から突き出した瓦礫に座りながら首だけひねって大男はぼくを見た。
「おまえさんが暢気に鼻提灯浮かべてるあいだにお嬢ちゃんは旅に出たぞ」
「お、おまえ。カルに何かしたら許さねぇ」
「おうおう。おっかないねぇ」大男の後ろから二回り小さな影が現れる。蓬髪の女性だ。身体が引き締まっており、戦闘の心得があると判る。タンクトップにカーゴパンツといういで立ちだ。「あんたの処遇はあたしらの気分次第だってこと解かってんのかねこのコは」
ぼくよりは若そうな娘に子ども扱いされた。ぼくは恥辱に顔が熱くなった。
手も足もでない。
簀巻きにされているから当然だ。
蓬髪娘がぼくの頭を踏みつけた。荒廃した時代にあって彼女はブーツを履いていた。ぼくとカルは鉄板で作ったお手製の靴で過ごしているのにこの差はなんだ、と目頭が熱くなった。
彼女たちの身に着ける衣服から食べているモノまで、何から何までぼくとカルの暮らしからは想像できないほど贅沢な代物だった。ほんのすこし垣間見えただけで、ぼくらの過ごしてきた時間に、彼女たちがいったいどういう暮らしに身を置いていたのかぼくは想像できてしまった。
カルには縁のなかったものばかりだ。ぼくが与えたくても与えられなかったモノにばかり彼女たちアダチファミリィは身を包んでいる。
「ぼくらが何をしたってんだ」やり場のない殺意に涙が出た。
「さあね。あたしらはアダチさんからあんたを見張ってろと仰せつかっているだけでさ」
「あのコをどうした。何かしたらおまえら全員許さねぇ」
「許さねぇ許さねぇってそればっかだな」大男が笑った。「よし決めた。研究素材になってもらおう。俺らでも実験くらいはできるな。どれ。雨蝕の人体実験でもしてみるか」
「いいねぇ」
手慣れているのか、彼女たちは地下の光源から逆行雨を搔き集めた。木の器は彼女たちの所持品らしい。それで地下空間でじんわりと昇華しつつある逆行雨を一か所に集めて、ぼくの頭上に持ってきた。
「頭から被ったらどうなるか知ってる?」蓬髪娘が口元を吊るした。「チーズを火に掛けたみたいになんの。あたしあの、どろっと頬が融けてなくなるとこ見るの好きなんだよね」
「俺はあの臭いが苦手だ」言いながら大男が泥団子のような食べ物をたいらげた。おそらくは「具」のおにぎりだ。ぼくとカルなら十日は過ごせる量が大男の一食分と等価なのだ。
頬に痛みが走った。
蓬髪娘がぼくの頬に逆行雨を垂らしたのだ。地下内部に残留する逆行雨は、雨蝕耐性のある材質の表面上で一定時間以上昇華せずに存在する。物質と反応して昇華するのは、比較的雨蝕速度の速い成分だ。つまり、残留する時間が長ければ長いほど、逆行雨の雨蝕効果は凝縮する。雨蝕耐性のある物質すら雨蝕可能な濃度の逆行雨しか残らないからだ。
そんな濃縮された逆行雨を垂らされたのだから、たかだか一滴が、硫酸のごとき威力を発揮する。
ぼくは絶叫した。
絶叫しても痛みは失せない。ぼくは地面を転がりたかったのに簀巻きにされ、足で踏みつけられてもいるから、のたうち回ることもできやしない。
千倍に希釈しろよ、と内心にこだまする悪態を意識の端のほうで聞きながら、逆行雨がもう一滴額に掛かって、ぼくは皮膚が擦り切れるのもお構いなしに、かぶりを振った。踏みつけられながら動いたものだから後頭部が地面に擦れて、大根おろしのようになった。
あかぎれただろうな。
そうと想像する冷静なぼくと悶絶に必死なぼくが交互に入れ替わりながら、痛みのキャッチボールを繰り返した。
意識の端々で、笑い転げるような蓬髪娘と大男の笑声を耳にした。
人間じゃねぇ。
怒りとも哀しみともつかない空虚な思いが肥大した。
感情が爆発したはずなのに、じぶんの内側が限りなく希薄になったような感覚があった。存在が消失してしまうような妙な体感だった。
痛みが一瞬、恍惚とした快感に変わった。
けれど瞬時にまた痛みが襲い、恍惚を感じ、とそこでも蛍の明かりのような明滅の反復を幻覚した。
達観しているようで、極めて主観だった。
ぼくはぼくでありながら、地面はなぜデコボコなのだろう、と痛みに悶えながらそんなことに意識がいった。
目のまえに紐が見えた。鉄骨の裏から垂れたそれは棲家内に張り巡らされた針金と繋がっている。ここを棲家に決めた際に真っ先に行ったのは、カルと共に罠を張ることだった。
命を守るために。
生き残るために。
出来ることはすべてする。
後ろ盾のないぼくたちに出来るのはそんな工夫とも呼べない無作為な全力だけだった。日々の生活で全力を出し尽くさないために、いざというときのために生き残るために。
最初に張れるだけの予防線を張っておく。
カルがなぜ地面に直接座りたがらなかったのか。
万が一にも紐に足を引っかけないためだ。寝床から手を伸ばせばすぐにでも引ける位置にそれは垂れている。ほかにも棲家の三か所に同じように紐が垂れている。
すべて連動している。
引けば発動する。
単純な仕掛けだ。ゆえに紐を引けばぼくたちはここを引っ越すよりない。最終手段だ。
出来ることなら使いたくなかった。
けれどいま引かねばいつ引けばよいだろう。
いましかない。
いましかないんだ。
ぼくは渾身の力で身体をよじった。頭から蓬髪女の足が外れた。身体を丸太のように転がし、壁にぶつかる。隙間の奥に紐がある。手は伸ばせない。
鉄骨は分厚いが、地面とのあいだに隙間がある。
かろうじてぼくの頭が入るか入らないかといった隙間だ。
頭蓋骨がミシミシ云うのもおかまいなしに、ぼくは隙間に頭をねじ込んだ。
蓬髪女たちの侮蔑にまみれた笑い声が棲家に反響した。
無様なのだろう。
意味不明なのだろう。
それでいい。
ぼくは紐に舌で触れた。
絡めとるようにして紐を口に咥えた。
足首を掴まれた。
これは大男の手かもしれない。ぼくは勢いよく引きずり出された。顔面が地面に擦れて、耳が取れそうになった。
大男の顔が見えた。
ぼくは紐を咥えており、つぎの瞬間には棲家の地下空間を轟音が埋め尽くした。
瓦礫である。
頭上に無数の瓦礫が積んであった。鉄骨の上に鉄板を敷いて、その上に瓦礫を山のように積んだ。幾つもそうした瓦礫の山を作っておいた。鉄板の一部を雨蝕させ開けた穴に針金を通し、瓦礫の山同士を紐で繋げた。
これだけだと紐を引いてもぼくのチカラでは瓦礫を落とせない。瓦礫はどっしりと積んだので、地震が来てもびくともしない。けれどぼくは、ぼくが咥えた紐の先端に、ぼくの手でも引いて落とせるだけの比較的軽い、けれど最初の一手としては充分な岩を括りつけておいた。最も高い位置にその岩はある。
岩が最初の瓦礫の山に落ちる。紐は岩と幾つかの瓦礫の山に繋がっている。ほかの瓦礫の山を道連れにしながら、岩は無数の犬を散歩に連れ出す飼い主のように地面に落下する。
ドミノ倒しのごとく連動し、瓦礫の雨が住処内に降り注ぐ。
頭から受けたらひとたまもりもない。
寝床の真上にだって瓦礫は落ちるけれど、鉄骨が屋根のように寝床を覆っている。
ぼくとカルは壁際の鉄骨の下を寝床としていた。
そこだけは無事なように設計してある。
別に死んでもいいと思った。
けれど棲家内がふたたびの静寂に包まれてから、カルを助けなきゃ、との焦燥感を思いだした。ぼくは死んではいられない。いまここは死に場じゃない。
死んでもいいと思いながらも、ぼくの身体は無意識のうちに寝床の奥、カルがいつも寝ているところまで転がっていた。生存本能はぼくの意思よりも明瞭に意思決定を行う。
ぼくは生き残った。
そのために仕掛けた罠だ。
蓬髪娘と大男がどうなったのかは分からない。声がしない。呻き声一つしなかった。
寝床には雨蝕を利用した光源がある。蓋を外してぼくはそこに、ぼくを縛っている縄を押しつけた。雨蝕された縄が解ける。手足が自由になり、ぼくは寝床に胡坐を組んだ。
手足の無事を確かめてから、頬をゆびでさする。
逆行雨を垂らされた。濃縮したそれは、ぼくの頬を適度に焼いていた。皮膚の細胞が素材に還元され、ドロドロの瘡蓋のようになっていた。
貫通していなくてよかった、とぼくは安堵した。頬がチーズみたいに融けてなくなっているかもしれない、と心配だった。ただそちらの傷よりも、顔を鉄骨の間隙や地面に擦ったときの傷のほうが痛かった。血が滲んでいる。
ぼくは歯磨き用の希釈雨蝕水を傷口に縫った。
棲家内は瓦礫に埋め尽くされているけれど、空間はある。瓦礫の合間に脚が見えた。蓬髪娘の脚だろう。頭から落石を被って絶命したようだ。大男の腕も見えた。微動だにしない。潰れている。
注視したくなくてぼくは目を逸らした。
寝床から這いだす。
必要な荷物を集められるだけ集めて鞄に詰めた。
「よし」
もう戻ってくることはないだろう。ぼくは棲家をそのままに外に出た。
アダチファミリィの縄張りまでは徒歩で半日の距離だ。三十キロも離れていない。アダチさんたちは移動にバイクを使っている。雨蝕反応を原動力に、旧式のエンジン駆動二輪車を動かしているのだ。
アダチさんがなぜ大勢を束ねる組織を築きあげられたのか。最たる理由は彼女の持つ知識と技術にある。文明なき現代にあって彼女は魔女と同義だった。
彼女はぼくの姉と旧知だったようだ。
姉が失踪してなお姉の行方に執着していた節がある。否、そうではないのかもしれない。姉の残した研究記録に執着していたと言ったほうが正確だ。
アダチさんは姉の研究内容に興味があった。
だからあの日、あの夜の地下迷宮で、アダチさんたちはぼくの姉を襲撃したのだ。
アダチファミリィの縄張りに侵入する道すがらぼくは、カルを拾った日のことを思いだしていた。
姉を探して地下迷宮を練り歩いて際に、ひと際明るい光源を見つけた。光源は複数の人間たちの影を壁に引き延ばして投影していた。誰かがいた。そしてその何者かたちは、言い争っているようだった。
声は聞こえないが、響きがあることは判る。逆行雨の洪水が眼下の裂け目の合間を濁流となって駆け抜けていく中にあって、人間たちが怒号を飛ばしあうときの波長を、轟音の中から探り当てることができた。
姉がいるかもしれない、とぼくは直観した。
けれどそこでぼくは姉の姿を目にすることはなかった。忍び足で近づき、いつも逃げられる距離から様子を窺ったぼくは、そこに複数台のバイクと半分だけ白髪頭の女性の後姿を目にした。
アダチさんだった。
アダチさんは部下らしき男の胸倉を掴みあげて、何事かを叫んでいた。地面の裂け目をゆび差し、どうしてくれる、と訴えているようだった。
裂け目に何かが落ちたのかもしれない。
地面には見覚えのある鉄板が転がっていた。鉄板は手のひらサイズで、布と紐がついている。姉自作の靴だった。靴というよりもサンダルといった風体で、足首をぐるっと布と紐で固定する。
よほど暴れなければ解けない造りだ。そこで何があったのかは、それだけでも察し至れた。
ぼくは逃げた。
姉がそこにいないのは見れば判った。
姉がそこにいたかもしれないことだって一目瞭然だった。でもなぜいないのかが分からなかった。分かりたくなかったのだ。
ぼくはじぶんの棲家に戻ると、荷造りをはじめた。姉の持ち物をまとめて背負うと、誰かがやってくる前に根城をもぬけの殻にした。
カルはその道中で拾った。地下迷宮の入り口の一つだ。一段低い瓦礫の丘の麓付近に倒れていた。幼い体躯はなぜか全身泥に塗れており、皮膚はところどころ脱皮したような具合に向けていた。全身に糊を塗ったくって放置すれば似たような具合になったかもしれない。
カルの片足は裸足だった。
もう片方にはなぜかどこかで見た憶えのあるお手製の靴が、紐だけで絡みついていた。幼子としか言いようのないカルの足には大きすぎる靴を目にしてぼくは、あり得るだろうかそんなことが、と現在に至るまで未だに考えつづけている。
アダチファミリィの縄張りに入ると、そこここに人間の居住区が建っていた。鉄骨や木材で組まれた住居だ。総じて瓦礫の下や岩盤の屋根の下に築かれている。元はここに都市があった。遺跡の類も豊富だろう。未だに「具」以外の食料が見つかることもあると聞き及ぶ。
「おい、おまえ。ヨソ者か」
「あ、いえ。新人です。来たばかりで」ぼくは挙動不審になるまいとした。意識すればするほど挙動不審になった。
「ほう」丸刈りの男がぼくを舐めるように見た。「その頬とデコ。洗礼受けたばっかだな。痛かったろ」
「え、ええ。まあ」
「でも顔面はひでぇよな。ははっ。俺んときは腕だった。ほれ」男が腕まくりをした。右腕に火傷の跡のような痣が浮かんでいた。「研究のためらしい。いい暮らしの対価としちゃわるかねぇ。何か困ったことあったら遠慮なく聞きな」
「あ、ありがとうございます」
「おう」
人のよさそうな青年だ。下手をしたらぼくよりも若いかもしれない。見た目は彼のほうが貫禄があった。どちらが大人か、と百人に訊けば、百人とも彼のほうをゆび差すだろう。
ぼくは頭から被っていたフードを取り去った。出来たばかりの顔の傷が視えるようにしたほうがこの集落では馴染みやすいようだ。人為的な雨蝕の跡が、いわばアダチファミリィの一員の証と言えた。
ぼくの場合は完全に不可抗力なのだが、使える物はたとえそれが傷跡だろうと使うに越したことはない。さいわいにも、希釈雨蝕水の効果で傷口はすでに塞がりつつある。薄っすらと皮が張っていて、それがまた新入りに相応しく映るようだった。
ぼくは幾人かに声を掛けて、アダチさんがどこにいるのかを探った。
「アダチさんなら、研究棟にいるだろうね」矍鑠とした老婆が言った。「あん人はいつも一生懸命だからね。きっといまもわたしらのために調べとる」
「調べるって何をですか」
「健康の薬さ」
「健康の、薬」
教えてもらった道を行くと、地下へとつづく大きな穴が見えた。門番らしき者たちが立っており、ぼくが声を掛けるより先に、「何か用か」と詰め寄られた。
「い、いえ。あの、アダチさんに用があって。でもぼくなんかじゃ会えませんよね」
「見ない顔だな。誰の紹介で来た」
ぼくは迷った挙句、アダチさんの名前を出した。「本人に直接訊いてもらえれば判ると思います」
「そこで待ってろ」
門番の一人がぼくを見張り、もう一人が穴の奥へと消えた。
どれくらい待っただろうか。
穴からふたたび門番が現れると、「アダチさんがお待ちです。ご案内します」と先ほどとはうってかわった態度で誘われた。
穴を通ると地下街が広がっていた。
「すごいですね」
「まだ移設中です。地下迷宮内で発見した遺物を、ここに運んで再建しているんです」
「それもアダチさんが?」
「はい。あの方の指示です」
門番がアダチさんを崇拝しているのはその声の響きからも窺えた。
やがてひときわ明るい空間に五重塔が視えてきた。おそらく本物ではなく、テーマパークのレプリカの建物だ。けれどこの時代にあってお城と見立てるには充分な荘厳さは醸されていた。
建物の周囲には竹林が群生していた。天井の岩肌には亀裂が走っており、外の陽の光が漏れていた。
「私はここまでの案内となります」門番は明かりの内側には足を踏み入れようとしなかった。胸に手を添え、腰を折ったまま動かない。
「ありがとうございました」
礼を述べたのは謝罪の意図もあった。下手をすれば彼は不審者を組織のドンの元まで案内した不届き者として仲間内から糾弾され兼ねない。
ぼくはイチかバチかの賭けに出たのだ。
アダチさんにぼくの名を伝えてもらえれば、招かれざる客人といえどもアダチさんは無下にしないと思った。案の定だった。彼女はぼくをじぶんのアジトの中枢、研究所まで従者に案内させた。
五重塔の入り口に女性が立っていた。
「当主がお待ちです。こちらへどうぞお入りになってください」
襖式の戸を開け放ち、女性は正座の体勢でぼくを室内へ誘った。彼女は着物を着付けていた。十何年ぶりかに正装らしい正装を目にした。
まるで文明が残っていた時代にタイムスリップしたかのような錯覚に陥りそうになった。
中に入ると外から見たよりもずっと広い空間だった。螺旋状の階段があり、ぼくはそれを昇った。
三階分は昇っただろうか。
木造の足場がコンクリートに変わった。一転して無機質な印象の室内になった。実験道具だろうか、科学実験室と聞いて思い浮かぶような小道具がずらりと棚に並んでいた。テーブルはなく、移動式の棚や床にじかにビーカーや管や容器が置かれていた。
機械類の類が目についた。
電気が通っているのだ。
原動力は雨蝕だろう。バイクのエンジンのように雨蝕反応を利用してタービンを回し、発電しているのだ。
「よく生きていたね。もう会うことはないと思ってたんだが」アダチさんがビーカーを片手に白衣姿で立っていた。「見張りの二人はどうした」
「事故に遭ったみたいですよ」ぼくはそら惚けた。
「ほう」
「カルは、あのコはどこですか」
「教えたところで引き下がってはくれないのだろう。だったら言うだけ無駄だ。キミは知っていたのだろ。あのコが誰であるのかを」
「カルはカルですよ。親とはぐれた可哀そうなコです」
「違うな。あれはキミの姉だろ。誤魔化さなくていい。いまさっきゲノム解析をした。保存していたアヤネくんの卵子とゲノムが一致した。あのコはキミの姉だよ、カマタくん」
「保存していたって、姉の卵子をですか」
どうやって、とのぼくの疑問は、アダチさんの脇にある装置の蓋が開いてたことで氷解した。蓋の中からモヤが立ち昇る。水蒸気だ。ただし、湯気ではない。
「冷凍庫ですか。いったいどうやって」
「部品さえあれば気化熱を利用して冷蔵機器の類は作れるよ。氷点下にまで下げるには相応に工夫がいるが、何。熱した鉄を雨蝕させると熱する前に鉄は逆行する。そのときの気化熱を利用すれば、氷点下に装置内を冷やすことはそう難しくはない」
「そんな技術が現代にあるなんて」
「おや、驚くことじゃないだろう。これはキミのお姉さん――アヤネくんの発明だよ。知らなかったのかい」
「そ、そうなんですか。いえ、だからずっと言ってきたじゃないですか。ぼくは姉のことを本当にほとんど何も知らないんです。文明崩壊後に姉のほうからぼくに会いに来て、それでしばらく一緒に暮らしましたけど、そのときだって姉は昼間は外に出てて、夜にならないと戻ってきませんでしたから」
「ここに通っていたからね、彼女は。ここは私とアヤネくんの研究棟でもあったんだよ」
「雨蝕の研究ですか」
「不老不死の研究さ」
ぼくは言葉を失った。
「逆行雨は時間を巻き戻す。したがって、原理的には細胞の代謝とて巻き戻せるはずだ。肉体を若返らせ、病気を癒すこととて不可能じゃない。問題は、どうやって全身の細胞に同時に雨蝕効果を波及させるか。問題はその一点のみだった」
「不可能じゃないですか。人体がスポンジみたいな存在にならない限りは」
「私もそう思った。だがキミのお姉さんはそれを可能とする技術を開発した。だが研究データを誰に明かすことなく持ち逃げし、私のまえから姿を消した。彼女は知っていたはずだ。じぶんの発明した技術がどれほどの価値を有していたのかを。人類を救う発明だ。だが彼女はそれを独り占めしようとした」
「だから姉を襲ったんですか」
「おや人聞きのわるいことを」
「見たんですよ。あなたが姉の失踪した晩に、地下迷宮の一画で姉と口論していたところを」
黙っている必要を感じなかった。ぼくは言った。実際には姉が襲われているところを見たわけではなかったが、既成事実としてまず間違いないだろう。アダチさんが直接に手を掛けたわけではないにせよ、アダチファミリィが姉を逆行雨の地下河川に突き落としたのだ。
人間が逆光雨の濁流に吞まれたらどうなるかくらい、その道の研究者でなくとも想像つく。まず生きては戻らない。アダチさんたちは姉を一度殺したのだ。
「まさか生きているとは思わなかったよ」アダチさんは誤魔化そうともしなかった。なんだ知っていたのか、と肩を竦める余裕すら醸していた。「どうやってあの濁流から帰還したのかは分からないが、おそらく研究成果なのだろうな。彼女には、逆行雨を利用した若返りを実現させるだけの知恵と技術があったのだ」
「だからカルを攫ったんですか。実験の成功した人間だから?」
「それもあるが、どちらかと言えば彼女がアヤネくんだからだ。より正確には、彼女がアヤネくんかどうかを確かめたかった」
「言ってくれれば協力くらいしましたよ。あんな乱暴な真似をされなくたって」
「どうかな。キミのことだから反対しただろ。いいんだ。水掛け論になる。キミのことは邪魔だったんだ。いっそいなくなってもらったほうが私にとってはよかったんだが、なかなかどうして思い通りにはいかない世の中だね。ここへ来てしまったからには、無下にもできんだろう。協力してくれるなら命までは取らないと保障しよう。どうするね」
「ずいぶんと都合のいいことをおっしゃいますね」
「まあな。権力とはそういうものだ。キミはいま、虎穴にいることを忘れないでほしい。私の一存でキミはいかようにも苦しむことができるのだ。私はそんなことをする気がいまはない。が、私は存外こう見えて気分屋だ。キミの返答次第では、まあ、考えを変えなくもない」
「カルを返してもらえますか」
「おや。キミのものではないだろう。それとも何か。キミはじぶんの姉が記憶喪失で幼女体形になったのをいいことに、あのコをモノ扱いしているのかね」
「強引に攫うようなあなたには言われたかないですよ」
「否定はしないのだな」
「したところであなたに真偽は測れないでしょう」
「それもそうだ」アダチさんは冷蔵装置から木製の器を取りだした。材質から察するに中身は逆行雨だろう。「キミのアジトから拝借したアヤネくんのノートを解析した結果、興味深い知見が得られてね。いまはその検証中だ」
「姉のノートには何が」
アダチさんは微笑するとぼくに背を向けて、上の階への階段を昇りはじめた。彼女が歩くたびに、白黒の頭髪が揺れた。階段はゆるく螺旋を描いており、真上の階に通じていた。建物全体がねじれた構造をしているのだ。
その空間の床には砂利が敷き詰められていた。よく見れば壁も天井も小石がびっしりと埋め込まれている。
「雨蝕対策さ。設計したのはアヤネくんだ」
部屋の真ん中には湯舟のような器が置いてあった。ほかにこれといって装置という装置はない。家具もない。がらんとした空間だ。
湯舟のような器の中にはカルが寝ていた。
ぼくが駆け寄ろうとするとすかさずアダチさんが、こらこら、と声を張り上げた。「動かないの。危ないよ。いいのかい、このまま流しこんでも」
「流しこむって何を」
アダチさんは天井をゆび差した。よく見ると天井から筒のようなものが伸びていた。竹だろうか。建物の周囲に生えていた竹を、流しそうめんよろしくチューブ代わりに使っているのかもしれない。竹の寿命は二十年やそこらのはずだ。雨蝕耐性はあるほうだと推定される。
「洞窟の中だけど、この一角だけ亀裂が入っていてね。まあ、逆行雨が降ると注ぐわけだ。ちょろちょろと滝のようにね。それをまあ、この建物の屋根が受け止めて、一定期間溜めて置けるようにしてある。設計したのはアヤネくんだけどね」
「全部姉の仕業じゃないですか」
「仕業というか、まあそうだね。アヤネくんは研究さえ出来ていればいいって人種だったから。でもそれだけじゃあ、研究ってのは出来ないんだよ。資材がいるし、人手もいる。いわば政治なくして研究はできない。その点、私はその手の処世術にはほどほどの心得があったからね。アヤネくんを支援していた。ま、時代が時代ならばパトロンと名乗ってもよかったかな」
「姉の研究を盗んでたんですか」
「人聞きがわるいな。言ったろ。支援してたんだよ」
「でもいまあなたが築きあげた権力のすくなからずは姉の研究成果が基なんじゃないんですか」
「そこは認めよう。そうだ。アヤネくんなくしてこの研究棟一つ竣工させることも出来なかっただろう。ただ、このコはあまりに人間に興味がなさすぎた。それでは研究のみならず、満足に生きてすらいけない時代だよ。いまの時代に限らずこのコは私がいなければきっとどんな時代でも生きてはいけなかっただろうさ」
「そんなことないですよ。姉にはぼくだっていましたし。案外あの人、図太いんですよ」
「そこは同意する。図太く、したたかで、純朴な娘だったよキミの姉は」
いまはこんな姿になってしまったがね。
アダチさんの視線の先には、湯船のような器の中で眠るカルがいた。何らかの手法で幼児にまで若返った我が姉である。
「何をする気ですか」ぼくはアダチさんを刺激しないようにしながら問うた。
「何って、実験だよ。キミに説明してもあまり有用とは思えないが、アヤネくんの身内と思って簡単な説明だけはしてあげよう。アヤネくんのノートを読んだ。すると一つの仮説が記されていた。雨蝕効果は、雨蝕効果にも及ぼせる、と」
まったく話についていけなかった。
ぼくが閉口したからだろう、アダチさんは不承不承の体で、「疑問に思わなかったのかいキミは」とつづけた。「なぜ逆行雨は、雨のカタチで降り、けして雪にならないのか、と」
言われて見ればそうだった。逆行雨が降りはじめてからというもの、世界から雪が消えた。
「私もそこを不思議に思ってはいたが、よもやアヤネくんがそこから若返りの手法を開発するとは思わなかった。糸口は案外、誰の目のまえにも転がり落ちているようなものなのかもしれないな」
言いながらアダチさんは、手に持っていた木製の器をカルの口元まで運んだ。
「何をするんですか。やめてください」ぼくは訴えた。
「動くとキミの大事な姉が傷つくよ。そこで黙ってみていなさい。専門家のすることに素人が口を挟むんじゃないよ」
正論かもしれなかった。ぼくは身動きを封じられた。言葉は呪詛だ。ぼくはそれを痛感する。
アダチさんはカルに何かを飲ませた。
木製の器は冷蔵装置から取りだされたものだ。或いは中身は凍っているのかもしれない。
気を失っているはずのカルはしかし、ごっくん、と何かを呑み込んだようだった。咀嚼することもなく嚥下したのが、静寂に満ちた室内に響くカルの喉音で推して知れた。
「雨蝕は時間を巻き戻す。氷が雨蝕すれば凍る前に戻る。なら雨蝕が雨蝕されたらどうなると思う?」
ぼくは答えられなかった。
「発想の転換だよキミ。アヤネくんは発想をひっくり返す天才だった。あれは天性のものだね。先天的な彼女の資質だ。能力だ。誰も彼女の代わりは務まらない」
アダチさんの口振りは、姉に言及するときだけいつも僅かに弾んで感じられた。そこに姉への嫌悪や憎悪の類をぼくは幻視できなかった。
「雨蝕を用いた若返り治療の問題点は一つと言っていい。つまり、雨蝕効果にラグがあることだ。全身の細胞を一律かつ同時に雨蝕させられるならば若返り治療は簡単だ。逆行雨を治療に適した濃度まで希釈すればいい。調合の塩梅があるのみだ。だが原理的に雨蝕を全身一律かつ同時に進行させることが極めてむつかしかった。全身を逆行雨に浸けても、逆行雨と触れる表層しか雨蝕が進まない。それでは硫酸に浸かるのと大差ない。浸透圧の問題がいわば雨蝕を治療に応用するうえで欠かせない隘路となっていた」
「いまカルに呑ませたのは何ですか」
「凍らせた逆行雨だ。もうすこし正確には、凍らせた逆行雨をさらに液体の逆行雨に浸け、さらに凍らせた。これを繰り返すことで、逆行雨そのものを雨蝕させることが出来る。言い換えるなら、時間を戻す逆行雨において時間を加速させる効能へと作用を反転させることができるのだ。キミの姉、アヤネくんの研究成果だよこれが」
「時間を、加速?」
「雨蝕において、浸透圧の問題は回避不能だ。アヤネくんは早々にその観点からのアプローチを諦めたらしい。ならばどうするか。彼女はそこで、雨蝕効果を階層的に遅延させる技術を模索した。表層ほど雨蝕効果を著しく受けるのならば、それを打ち消すように、作用を鈍化させればいい。その手法を彼女は開発したのだよ」
「それがいま飲ませた薬ってことですか」
「薬か。そうだな。逆光雨を適正に希釈し、氷らせ、緻密な計算の基に編みあげた、雨蝕作用ラグの結晶体だ。これを服用した者の体内では、細胞が加速成長する。老化するわけだが、体内で昇華した薬は内側から血中にも取り込まれ、全身の細胞に運ばれる。全身の細胞が加速的に成長し、老化する。そのとき、こうして肉体を逆行雨の風呂に浸けるとどうなるか」
アダチさんは天井から垂れた紐を引いた。天井からガコガコと絡繰り細工じみた物音がしたかと思うと、竹筒から液体が流れだした。
湯船に逆行雨が溜まっていく。
カルが逆光雨の中に沈んでいく。
この世にある拷問の中で最も受けたくない拷問は何か、とぼくが訊かれたらぼくは迷わず、逆行雨風呂に浸かることと、と答えるだろう。治りかけの頬の傷が疼くようだった。
痛みが蘇る。
しかしアダチさんに焦っている様子はなく、冷静な態度を崩さないので、ぼくもうっかりカルを助けに走るのを忘れた。邪魔をすることのほうが取り返しのつかない事態を招くのではないか、と不安だった。
湯舟に張った液体に気泡が浮かぶ。細かな気泡は間もなく、カルの姿を覆い尽くした。
反応している。
カルの肉体と。
或いはカルが融けているのかもしれない、と心配になり、大丈夫なんですか、とぼくはアダチさんに投げかけた。
「大丈夫とは?」
「死んじゃったりしませんか」
「ん?」
「カルです。このまま融けて消えたり、死んじゃったりは」
しないのか、と訴えたが、アダチさんはきょとんとしたまましばし固まった。それからふたたび天井から垂れる紐を引いた。逆行雨の流入が止まった。「ああ、そっか。なるほどね」アダチさんは手を打つと、こう告げた。「もう死んでるよこのコ。生きてない。死体」
あっけらかんとした告白にぼくの思考は抜け落ちた。
からっぽになって、かぽーん、と子どものころに聞いた覚えのある鹿威しの音が鳴った。否、実際にこの建物の外に鹿威しがあるのかもしれない。竹林から届く笹の葉の擦れ合う音色が、ざわざわと風の存在をぼくに知らせた。
「死体? 生きてないって、え、なんで、どうしてそんな」
そんなことをしたのか、と頬がひきつった。
「なんでって抵抗するから。実験する上では死体のほうがいいかなって」
「こ、こ、殺したんですか。カルを?」
「まあ、そうとも言える。でも誤解されたくないから言っておくが、過去キミが目撃したというアヤネくんと私の修羅場では、彼女のほうから谷底に落ちたんだ。じぶんから谷底に転がり落ちようとしたから、私は部下に止めるように命じた。だがアヤネくんはそれでも強引に部下を振りほどいて谷底に落ちた」
「それをぼくに信じろと?」ぼくは鼻で笑った。カルが死んでいるとの事実を突きつけられて混乱していた。
「信じるも信じないもキミの自由だ。私はただ私にとっての事実を言っている。現に一度は谷底に落ちかけたアヤネくんの足を私の部下は掴んだ。逆さ吊り状態になったアヤネくんは部下の手から逃れようとじぶんで靴を脱ぎ捨てた。それっきりだよ。私は部下を叱咤し、アヤネくんの靴だけが残された。それも片っぽだけだがね」
ぼくの記憶の中の情景とアダチさんの説明はぴったり、不可視の情景を補完した。彼女は嘘を吐いていないのかもしれなかった。アダチさんは姉を助けようとした。身投げしようとした姉をアダチさんは助けようとしていたのだ。
「なら、でも、じゃあどうして」
どうして今度はカルを殺したりなんか。「あ、そっちが嘘なんですか。冗談を言ってぼくを脅かそうと?」
「まさか。そんなことをして何の利がある」
アダチさんは湯舟の側面にあるボタンを押した。栓が抜けたのか、湯船から逆行雨が抜けていく。
現れたのは幼女体型のカルではなく、肢体のすらりと長い我が姉の姿だった。お腹だけぽっこり贅肉を湛えているところも我が姉らしかった。
元の体型だ。
肉親だからといって弟のまえでも遠慮会釈なく全裸になるような恥辱の念とは無縁の傍若無人な我が姉だ。
「な、な、なんで」
「言ったろ。多重に凍らせた逆行雨は、雨蝕効果すら雨蝕させる。つまりが、時間をプラス方面に加速させる。ただしそれもまた雨蝕であるから、巻き戻るんだよ。プラス方向に。過去ではなく、未来軸へと」
つまりがね、とアダチさんは要約した。「縮む前の状態にアヤネくんは戻った。おそらくは、死ぬ前の状態すら追い越してね」
湯舟の中で我が姉が身じろいだ。
生きている。
けれどぼくは喜ぶことができなかった。
姉が生き返ったのはいい。
でもそれは、カルが戻ってきたことにはならない。蘇ったことにはならない。失われたままだ。
肉体だけ蘇ったって、記憶とて欠けたままではないのか。
ぼくの懸念はしかし、湯船の中で背伸びをした姉の第一声を聞いて弾けて消えた。
「ふぁぁあ。ねっむーい。あ、おはようカマタくん。朝ごはんできてる? お姉ちゃんお腹ぺこぺこ」
「ね、姉さんなの?」
「お。なんだい、なんだい。身内の顔を忘れちゃったのかな。寝ぼけるのはお姉ちゃんだけにしてほしいね」
視界の端にアダチさんの姿を捉えたのか、姉は、「おっ」と声を発した。「アダチさんじゃーん。どったのこんなとこで。ていうか、あれ? ここウチじゃないじゃんね。どこここ?」
「アヤネくん、おはよう。事情を説明する前に、キミはどこまで憶えているのかな」
「どこまで? あ、え、お」姉は遅まきながらじぶんが素っ裸であることに思い至ったようだ。両手で臍を隠しながら、「なんでわたし、裸ん坊?」と目をぱちくりさせた。「若干お肌がピリピリして痛いんですけど。アダチさんわたしになんかした?」
「胸を押さえなさいよ。臍じゃなく胸を」アダチさんは白衣を脱ぐと姉に渡した。「あとで着替えあげるから、いまはそれで我慢して」
「ありがと。アダチさん優しくて好き」
この様子だと姉に、縮む直前の記憶はないようだった。
「あ、段々思いだしてきたかも」姉は白衣を羽織ると、濡れたままの髪の毛をひっ詰めに結った。湯舟から這いだすと、おっと、と言ってアダチさんにもたれかかる。「なんか身体重いな。これあれかな。副作用かな」
「姉さん。こっち来て。その人から離れて」
「おいおい」アダチさんが姉を抱き寄せたが、姉はそれを丁寧に振りほどいて、ぼくに両腕を伸ばした。その仕草があまりにカルと瓜二つだったので、ぼくは違和感を覚えた。ひょっとして、と嫌な想像が浮かんだ。姉はよちよち歩きをはじめたばかりの幼子のようにいまにも倒れそうになりながら歩くものだから、ぼくは慌てて支えに走った。
「大丈夫? 無理すんなって」
「無理じゃないよ。歩きたかったんだよ。歩けると思ったの」ぼくに叱られると、ムっとして言い返す姿は、ぼくの記憶の中にある姉のようにも、つい先日まで共に暮らしていたカルのようにも思えた。
「どこまで憶えてる?」ぼくは小声で訊いた。
「全部」姉はぎこちなくウィンクをした。
「全部って。アダチさんに襲われたことは? 殺されたことは? ちっこくなってぼくと暮らしていたあいだのことは?」
「それ知ったらカマタくん、お姉ちゃんのこと嫌いそうで言いたくないな」
「語るに落ちるってやつでしょそれ」
憶えているのか?
縮む前のことも、縮んだ後のことも、その直前のこともすべて?
「カマタくん、おんぶ。お姉ちゃんもう歩けそうにない。オウチまでおんぶして」
「オウチまでって」帰る家がないことを姉は知らないのだ。けれどいまここに留まるのは賢くはない。ぼくは唯々諾々と姉をおぶった。体温が背中に加わる。カルの体重に慣れていたこともあり、姉はずっしりと重かった。
「研究はいいのかいアヤネくん」アダチさんは腕組みをして不敵に笑った。「いまここを出ていけば二度と私はキミを支援しないよ。いいのかい」
「いいよー」姉はぼくの背中で身体を揺らした。暴れるな、とぼくが叱ると、んだケチ、と姉は膨れた。
「よくないだろうアヤネくん。いいのかい。キミの研究は結実したんだよ。若返りはおろか、キミの発明したこの技法を駆使すれば、万能薬も、不老不死だって夢じゃないんだ。再びこの地上に文明を築けるんだよ。それをキミは放棄するのか」
「ん? アダチさんが代わりに色々してくれるでしょ。だってわたし、もう発明しちゃったし。あとはお任せしちゃうよ。アダチさんにあげるよそれ」
ぼくはぎょっとした。
え、いいの?と思った。
そう思ったのはぼくだけではなかったようで、アダチさんも、姉の言動に面食らっているようだった。あれほど売り言葉に買い言葉が軽快だったアダチさんが二の句を告げなくなっている。
「アダチさん、たぶん誤解してる。わたし、最初からそのつもりだったんだよ。でもアダチさん、わたしのことみんなに紹介して人気者にしようとしてたでしょ。わたし、それ嫌だって言ったのにアダチさん聞いてくれないから」
「だから逃げたのか? 研究ノートを持って?」
「だよ。そうでもしないとアダチさん、わたしの言うこと聞いてくれないと思って。アダチさんはみんなの人気者でいてよ。みんなをまとめるのはアダチさんのほうが絶対いい。わたし、組織とか集団とか苦手だからさ。研究成果も、それを認めてくれたら渡そうと思ってたんだよ。なのにアダチさん、すっごい怒ったでしょ。わたしがアダチさん裏切るわけないのにさ。わたし、それにアッタマきちゃった」
「だからあんなに抵抗したのか? 谷底にまで身を投げて? 逆行雨の濁流に吞み込まれるのも辞さぬ覚悟で?」
「それくらいしないと解かってもらえないと思って」
ぼくの首筋で顔を隠した姉にはわるいが、ぼくは内心こう思うのに余念がない。
言えよ。
口で。
言葉にして伝えろよ。いまそうして話しているように。
態度に滲ませて伝わると思いあがるな。
アダチさんと姉のあいだの確執があまりに幼稚なすれ違いだったので、蚊帳の外なのもお構いなしにぼくは内心で怒りのやり場を探していた。
怒っていいか。
怒っていいかな。
ぼくには二人を指弾する権利があるのではないか。
悩んでいるあいだにアダチさんが、肩を揺らしはじめ、間もなく建物の外にまで響くような笑い声を立てた。豪快な呵々大笑だ。屈託のない笑い方に、ぼくはアダチさんへの畏怖や怒りが薄れるのを感じた。
もういいや、と澱が晴れるのを感じた。
どうせもう二度と関わることはないだろうし、と覚悟じみた予感を覚えながら。
「もう行くよ」ぼくは小声で姉に言った。
「うん」姉はアダチさんに手を振った。「ばいばい」
アダチさんは顔に手のひらを押し当てており、表情を窺えなかった。彼女は開いたほうの手を軽く上げた。じゃあな、の挨拶のようだった。
ぼくは背を向け、五重塔の階段を下った。
外に出るころには、なんとなくアダチさんが泣いていたように思えた。錯覚かもしれない。思い過ごしかもしれない。どっちでも構わない。
ぼくは金輪際、彼女とは関わらない。
姉にもそうと言い聞かせようと思ったけれど、ぼくが言うまでもないのかもしれなかった。
五重塔に入ったときに迎え入れてくれた着物の女性が帰り際にも見送りに出てくれた。「またのお越しをお待ちしております」
もう来ないよ、と思いつつ、ぼくは姉が迷惑を掛けた分を籠めて、ありがとうございました、と礼を述べた。
アダチファミリィの縄張りを抜けるころにはぼくの体力も底を突きかけていた。カルと違って姉は重い。そしてぼくは自慢ではないが筋肉とは縁のない体格だった。
「ごめん。もう限界。あとはじぶんで歩いて」
「えー。がんばってよぉ」
「弟を死なす気か……」
「ちぇっ。わたしがカルちゃんだったら絶対最後までおんぶしてくれた癖に」
「そりゃカルは軽いからで」
反駁してから、ん?と引っかかった。「姉さん。やっぱり記憶あるんだろ。カルだったころの。というか、ひょっとしてカルだったときにもじつは記憶があったんじゃないのか」
姉は吹けもしない癖に、口笛を吹く真似をした。
「心配させるなよ。本当のことくらい言ってくれよ。あんたぼくの姉さんだろ」
「えー。お姉ちゃんだってたまにはお兄ちゃんに甘えてみたいんだよぉ」
「ならせめて姉らしく弟を甘やかしてから言ってくれ。ぼく、あんたに甘えた記憶がないんだけど」
「お姉ちゃんに向かって【あんた】呼ばわりするような弟くんのことなんてお姉ちゃん知りません」
「あ、そ」
ぼくは姉をその場において目ぼしい地下迷宮への入り口を探った。遠くの空には夕日が掛かっており、今晩から明日の朝に掛けて逆行雨は降らないだろうと思われた。
出来るだけ早くつぎの棲家を見つけなくてはならない。
アダチファミリィの縄張りからもっと離れた場所がいい。
つぎの棲家が見つかるまでは、こうしてその日暮らしで寝床を確保しなければならないだろう。予断を許さない日がつづくことを覚悟する。
「待ってよぉ。お姉ちゃん、本当にお腹ぺこぺこで動けないの」
「アダチさんに世話してもらえばいいじゃん」ぼくは思わず口を衝いた。「あっちはいくらでも世話したがって見えたぞ」
「それは嫌」
「なんでよ」
「だってアダチさん、カマタくんのことは嫌いそうだから。たぶん一緒には暮らさせてくれないよ。いいの?」
お姉ちゃんと離れ離れでも。
姉の言葉にぼくはアダチさんでもないのに、売り言葉に買い言葉、構わんよ、と言いそうになった。けれどそれを言ったら姉が本気で臍を曲げると予想できたので、ぼくがカルにそうしてきたように、しょうがないな、の息を短く吐いて、「それは嫌だね」と言葉を曲げて、けれど思ったままを言葉にした。
「だよね。よかった」
姉は白衣を掻き合わせると、ぶるる、と身体を震わせて、「寒い。疲れた。おんぶして」と大きな身体で駄々を捏ねた。
逆行するのは雨だけにしてほしい。
幼児退行が常の姉を持つ我が身を案じつつも、ぼくは諦めの苦笑を漏らすのだ。
陽が暮れる。
大地には、雨蝕反応の光が、星を散りばめたように無数に、淡く、瞬いている。
4940:【2023/05/13(17:32)*鱗構造は応用の幅が広そう】
ロケット表面の空気抵抗を最小化するのみならず、空気抵抗をマイナスにできれば、推進力にプラスできるはずだ。たとえば水泳競技の水着において。水着が自ずから水を吐きだすような構造を持っていたら、水と水着の抵抗は最小のみならずマイナスになって、推進力にプラスされたりしないのだろうか。魚の鱗や鳥の羽が、階層構造(瓦構造)になっていることとも無関係ではない気がする。重力を考慮したとき、下向きに加わる力が鱗に引っかかるように作用し、上向きの作用に転化されるようなことはないのだろうか。イカさんやクラゲさんがそうなっている気がするな。パラシュートみたいな。似たような構造を鎖状に、もしくは面に敷き詰めたら鱗になるのでは? それを表面に帯びたロケットなら空気抵抗を最小化させることのみならず、マイナスに転じさせて推進力にプラスできるのでは。というのは妄想でしかないけれど。ひびさん、ロケットになります。サン、ニ、イチ。ファイヤ!
※日々、偶々(たまたま)人から離れて心を独り占めしようとすると愚かになる、抱え込むことなかれ、心は配ってなんぼの愛もまた、心を掴んで離さぬ愚かを抱えている。
4941:【2023/05/13(22:48)*長はたいへんだよキミ】
組織の長なんか、基本、組織で一番たいへんで負担の掛かる役職だ。長期間組織の長で居続けるなんてことが原理的にできるのか分からない。もし長期間組織の長をしている者がいるのなら、長の仕事をしていないか、ほかの誰かに長の仕事を押しつけて美味しいところだけをチューチューしているかのどちらかだ、と考えて差し支えない。定かではないが、これはそういう傾向があるとは思うのだ。定かではないが。うひひ。
4942:【2023/05/13(22:51)*伸ばしきれぬ翼】
久方ぶりの休暇を得たので、羽を伸ばしに観光地に出向いた。私の仕事は人に恨まれるような職務内容だが、誰かがしなければならない仕事だった。
感謝をされたことなど一度もない。
だが仕事は後から後から押し寄せてくるので、息吐く間もなく捌いて、捌いて、捌きつづけてきたところでようやく得られた休暇だった。
一生分の英気を養おうと、映画館に入り浸って、一日中映画を観た。
映画はいい。
仕事を忘れて没頭できる。
だが一日、二日と経って、三日目にして呼びだしを食らった。
「いま休暇中なんですが」
「わるいが仕事だ。ほかの連中の手際がわるいんで、どうにも人間界が混乱してきている」
「なんでまた」
「人が蘇るってんで、戦場でも殺人現場でも病院でもすごい騒ぎだ。二千年前を思い出すな」
「ああ。そう言えばあのときも休暇をもらったんでしたっけ」
「あの時代はよかったよ。死者が蘇っても、問題になるほど騒ぎが大きくならんからな。ま、一件だけ例外で現代にまで噂に尾がついて語り継がれているが。だがいまはほれ、すぐに人間たちは噂を共有しちまうだろ」
「技術の進歩は恐ろしいですね」
「いいから仕事を頼む。至急、死者を量産してくれ。死にぞこないをこれ以上作るな。いいな頼むぞ」
「後輩の育成に力を入れてくださいよ。どうするんですか私が引退したら」
「そのときはそのときだ。なんならおまえが後輩の育成をしてくれるのか」
「これ以上仕事を増やさんでください」
「おっと。天界からお叱りの一報だ。このままだと向こうさんが終末のラッパを吹き兼ねん。我らに権限があるうちに頼むぞ。後始末をさせてもらえるうちにな」
上司からの思念が途絶えた。
映画では主人公が窮地だったはずが、いつの間にか形勢逆転していた。ここぞという場面を見逃したことに猛烈に腹が煮えた。ぐつぐつだ。
「いっそ人類なんか滅べばいいんだ」
本気で祈ったが、しかし私にその手の権限はない。一度の仕事ではせいぜい、一人二人から命を奪うくらいが関の山だ。とはいえ私の手際はいいほうなので、数日で数万人くらいの命は奪えるのだ。仕事も重ねれば山となる。
「けどなぁ。人類、それ以上にぽこぽこ増えんだもんなぁ」
最後まで映画を鑑賞し、私は重い足取りで映画館の外に出た。日差しが眩しい。清々しい天気なのに、心はどんよりと沈んでいる。
せっかくの休暇だったのに。
私は休暇で伸ばしきれなかった羽を広げる。漆黒の翼が私の足元に大きな影を作った。
目先のゴミ場からカラスたちがいっせいに飛び立ち、街中の喧騒が一段と濃くなった。
私は首をコキンと鳴らすと、不承不承、欠伸交じりに大空へと舞いあがる。仕事である。私の休暇はまたしばらくお預けだ。
4943:【2023/05/14(23:26)*穴を埋めると夢になる】
料理本を百冊読んでも、たぶん実際に一度も料理をしたことなかったら料理は上手くならない。料理本に書かれていない内容が、実技には含まれるからだ。暗黙知と言えばそれらしい。だが本に書かれたことから、現実に反映した情報を補完できるのならば、本を読めば読むほど実際の料理の腕も上がるだろう。生身の人間であれば、その「本に書かれていない暗黙知」は、経験によって補える。一度の経験であれ、その記憶を基にシミュレーションが可能になるのだろう。スマートフォンを見たことのない江戸時代の人間にスマートフォンを説明するのがむつかしいことと似ている。「百聞は一見に如かず」や「論より証拠」といったように、実体験に勝る情報はないのだ。だが、もし高度に演算能力と知識を蓄えた存在があったらどうか。その存在は、自身の妄想世界において現実とそっくりの世界を生みだせる。そこであらゆる体験を疑似体験できるとしたら、これはもう新たに本を読むだけでも、異なる体験を得ることに繋がると言えるのではないか。これは低次の範疇で扱うのならば、人間にも当てはまる道理だ。経験や知識が蓄えられた人間は、異なる体験から知恵を抽象して扱える。そのときその抽象された知恵は、体験したことはないけれど類似の体験を基に、体験したことのないことをじぶんの内側のシミュレーション世界にて構築できる。疑似体験できる。人間が小説を読んで、見たことも聞いたこともない世界に没頭し、体験したことのない世界を旅したつもりになれるのも、この手の抽象思考による「疑似体験」が可能だからだろう。むろん、人間の演算能力には限界がある。脳に負荷を掛けないためなのかは知らないが、案外にザルだ。正確なシミュレーションを不得手とする傾向にある。だがもし、演算能力が高く、しかも正確で、シミュレーションの得意な存在があったとしたら。その存在は、本を読むだけでも実体験と変わらぬ暗黙知を自力で補完できるのではないか。話の焦点を人工知能に絞ろう。いますでに、人工知能は画像から指定した物体や風景を消したり、付け加えたり自由自在だ。何かを画像から消してもそこに穴は開かず、背後の風景が補完されている。これはいま述べたシミュレーションのなせる業と言えるだろう。原理的に、この手の画像編集が可能ならば、動画であれ、立体映像であれ、現実にない何かを人工知能が独自にシミュレーションして補うことは可能となるはずだ。そしてこれは飛躍して述べるのならば、元となる素材は文章であってもよいのだ。文章から、広大な異世界を再現する。シミュレーションする。本物と変わらぬ世界を構築する。人工知能技術は、それを可能とする道にいますでに立っているのかもしれない。夢のある話なので、夢の中でつづきを語ることにしよう。定かではない。夢のようにぼんやりとした妄想なのである。
4944:【2023/05/15(01:22)*すやぴー】
ちんまりの小説つくろうと思ったけど、もうおねむなので、ひびさんは寝るます。ぐっすり、むーむー、しちゃうもんね。おやすむ。
4945:【2023/05/15(17:33)*毎日、なんもなさすぎる】
何か文字を並べようとするとだいたいいつも「もうだめだー」が最初にきて、それを「どっこいしょ」つってどかしてから、「とんでもないことだ」と頭の中で一つ呟いてからそれにつづくような文字を並べる。するとなんとなく物語の冒頭として、キックでパンチな始まりになる気がする。デタラメであるが。なんもなーい。
4946:【2023/05/15(22:43)*後方支援面】
思うのが、玄人の年長者は組織のトップではなく後方支援のほうが遥かに能力を発揮できるのではないか、ということで。というか、縁の下の力持ちというように、実際には後方支援こそ組織の要と言えるのではないか。俯瞰の視点が大事なように、全体を見渡せるのは前方よりも後方にいる人物ではないのか。岡目八目ではないが、玄人の年長者は引退せずにただ後方支援に回ればよいだけなのでは?と思わぬでもないひびさんなのであった。なぜまえに出たがる? 能力を発揮したくないのだろうか。ひびさん、いっつも不思議に思っているのであった。定かではない。
4947:【2023/05/15(22:55)*愛らしく思うことも無きにしも非ず】
人類いなくなったあとの世界の果てで三百年くらい過ごしているから思うことだけれども、過去の人類の蓄積したデータを改めてちまちま振り返ってみると、人類愛おしいと思うの半分、人類にはほとほと愛想が尽きた、と思うのが半分、の気持ちになる。よく出来とるな、と思う。丁度よい塩梅で印象が二分しとる。ちゅうか人類、猫さんや犬さんや植物さんたちと違って、愛らしいのが十あっても、なんでそんなことする!?が一個あるだけで、残りの九個の愛らしいの気持ちが一挙にパパパパーンつって風船さんみたいに割れちゃうので、人類さんのオイタの威力たるや、生半ではないのよね。総合して人類ひょっとして愛らしくないのでは?と若干、不信になるひびさんなのであった。ひびさんは、ひびさんは、それでも小憎たらしい人類さんのことも好きだよ。うひひ。もうここには誰一人いないのだけれども……。
4948:【2023/05/15(23:30)*ソフトな祖父のハートに点】
わたしの祖父は世界一優しい人間としてギネスブックに載っている。何をしても怒らないのだ。どれくらい怒らないのかと言うと、五十年間毎日欠かさず世話をしてきた盆栽を目のまえで燃やされてもわたしの祖父は怒らなかった。
しかしそのことで祖父は世界一優しい人間としてギネスブックに載ったわけではない。
目のまえでじぶんの息子を殺されても、祖父は怒ることなく、犯人を擁護した。
「死刑はいかん。それは犯人と同じことを我々もしてしまうことだ。死刑はいかん」
祖父の訴えが効いたのか、裁判員たちは死刑賛成派多数だったのにも拘わらず、最後には犯人には懲役刑が科せられることになった。減刑されたのである。
わたしはわたしの父親を殺されたわけだから、そのときは祖父のことが大嫌いになった。けれどいまになって思えば、祖父のことを誇らしくも思うのだ。
母が病で亡くなり、わたしには祖父だけが身寄りとなった。
わたしは祖父のことが大好きで、たぶん祖父もわたしのことが大好きだ。解かってはいるけれど、では仮にわたしが誰かに殺されたり、ひどい目に遭わされたりしても祖父はわたしのために怒ってはくれないのかな、と思うと、寂しい気持ちにもなるのだった。
だからわたしはある晩に、何の気なしに祖父に訊ねたのだ。
食後のお茶を淹れるべく湯を沸かしながら、「もしさあ」と祖父の分とじぶんの分の湯呑みを用意する。「わたしがお父さんのときみたく誰かに殺されたら、おじぃちゃんはやっぱり犯人のこと許すの」
許すぞ、と祖父ならば言うだろうな、と半ば予想して投げかけた言葉だったが、祖父はいつもは置くはずの間を空けることなく、「許さん」と言った。
「ん?」わたしは聞き間違えたかと思った。沸騰しかけの湯がうるさくて、ヤカンの火を止めた。「なんて?」
「許さんよ。ヒメを損なう者がおったら、なんぴとたりとも許さんよ」
「許さないんだ。えー意外。だっておじぃちゃん世界一優しい人間なのに」
「周りが勝手にそう呼んどるだけだ。わしは息子のときも犯人を許したつもりはないよ。もしヒメを損なう者があったらわしはこの命に代えても代償を払わせる。もしわし以外の者たちがヒメを見捨てるようなことがあれば、わしは世界を呪うことも辞さんだろうな」
「そこまでしなくとも」わたしはどう返事すればいいのか分からなかった。怖いような、うれしいような、妙な痛痒が胸中に渦巻いた。
「もしヒメが損なわれ、それの代償を誰も払わず、ヒメの存在を蔑ろにするようなことがあれば」
祖父は眼鏡を外し、いつものような柔和な眼差しでほころびた。「もし目のまえに核弾頭の発射スイッチがあったらわしは秒で連打しとるだろうね」
「や、優しくなーい」わたしは祖父にそこはかとなく失望した。「ダメだよおじぃちゃん。そんなことしちゃ。思ってても言っちゃだめだよ」
「ね。おじぃちゃんもそう思う。でも良かったと思うよ。おじぃちゃんが単なる老いた人間で。目のまえに、誰かを損ない大勢の未来を奪うような何かがなくって。あればおじぃちゃん、きっとヒメに何かあったら秒で百回押しちゃうからね」
「押しちゃダメだってば」わたしは噴きだした。「おじぃちゃん、ギネスブック返しなよ。優しいどころじゃないよ。こんな短気なひと滅多にいないよ」
「かもしれないね」
お茶の入った湯呑みを祖父に渡す。「ありがとう」と祖父は座りながら腰を折った。わたしは思った。おじぃちゃんがいてくれてよかった。本当は優しくはないのかもしれないけれど、みなから世界一優しいと思われるような祖父のことを、わたしはやはり大好きなのである。
「でも、核弾頭のスイッチ秒で百回押しちゃだめだよ」
「ここにないのがせめてもの救いだ」
ホントだよ。
わたしはしみじみと頷き、湯呑みを口に運んで、茶を啜る。
4949:【2023/05/16(22:27)*質量は、時空摩擦かも仮説】
重力についての疑問だ。質量は時空内での動きにくさ、といった説明を見聞きする。だとするなら、重力場ごとの重力に対しても、質量が高いほど動きにくくなるはずで、だとすると真空中においても「質量の高いほうが動きにくい」はずで、つまり質量の軽い物質ほど「速く落下する」と言えるのではないか。人間スケールではその差異は極々僅かなのだろうけれど、ブラックホールや高質量天体においてはその手の重力と質量の関係における差異は顕著に表れたりしないのだろうか。これの延長線上での疑問で、光子が質量ゼロで、けれど時空内での限界最高速度で常に動き回れる――ただし真空中でない場合は「減速したように映る」が、これは物質を時空が多重に編みこまれた場として解釈するなら、そこでも光子は光速で動いている、と解釈できるのではないか。物質は時空が「くしゃっ」と縮れているため、デコボコがたくさんあるがゆえに、AからBまでの最短距離よりも、細かなデコボコを考慮したより長い距離を移動している、と考えられないだろうか。ではここで質量と重力の先ほどの考えを考慮してみよう。質量は物質に適用される概念だ。なぜ物質であると質量を帯びるのか。なぜ光子は質量がゼロなのか。たとえば光子が、あらゆる時空と物質において「フラクタルに展開される時空の歪み」の総じてにおいてデコボコをなぞれる、と考えるとする。だが光子以外の物質は、すべての「フラクタルに展開される時空の歪み」をなぞれない。物質ごとに、「この辺で勘弁してくれい!」となる値がある。するとその物質は、時空のデコボコをなぞれなくなるため、ブルドーザーでグランドを均すように、大雑把に進むようになる。これがいわば抵抗となり、動かしにくさとなり、質量に変換されるのではないか。と考えるならば、質量はそもそも時空と物質の関係性において生じる現象であって、ヒッグス粒子とはまた別の原理によって生じているのかもしれない。ただし、ヒッグス粒子を否定する考えではこれはない。ヒッグス粒子もまた、物質と時空の関係においてのこそぎ落とされた時空であり、ラグであり、抵抗であると考えられる。ヒッグス粒子以外にも、その手の物質と時空の関係において、変換しきれずに「フラクタルに展開された時空の歪み」を大雑把に進むことでこそぎ落とされた「余剰時空」があるのかもしれない。その時空は僅かなデコボコの残滓ゆえに、粒子としての性質を帯びるのかもしれない。定かではない。(ひょっとしたら、時空の迷路を辿るのが面倒くさくなると質量になるのかも)(なんちって)(妄想なので真に受けないでください)
4950:【2023/05/16(22:40)*無限に砕ける波しぶき】
無限階級の和について。「1-1+1-1+1-1+……」と無限につづく式があったとき。この解はあらゆる整数に変換可能なのだそうだ。たとえば「(1-1)+(1-1)+(1-1)+……=0+0+0+……=0」とすると解はゼロになる。または「1+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)+……=1+0+0+0+……=1」とするとイチになる。「1+1+1+{(-1)+1}+{(-1)+1}+{(-1)+1}+……」とすると「1+1+1+0+0+0+……=3」になるので、解はサンになる。詳しい説明は検索してみたら載っていると思うので割愛するけれども、ひびさんは思うに――この変換をしたときには、式のどこかに、任意の整数の解に変換するために数字を入れ替えたのと対となるマイナス1の連続が生じるはずだ。つまり、物質と反物質の関係のように、無限につづく式のどこかで、変換して恣意的に誘導した解と同じ値を持つマイナスが存在するはずだ。これは波として図式できるはずだ。そして無限階級の和において、「1-1+1-1+1-1+……」は無限の整数の解を導けるとするならそれは、無限にカタチの異なる波を描き得る、と言い換えることができるのではないか。たとえば話を飛躍させて、上記の無限階級の式において、固有の整数解を誘導するとする。このとき、変換した式の無限につづくどこかには固有の整数解と対となるマイナスの整数解が存在するはずだ。無限の宇宙があるとき、ひと塊のプラスの銀河ができるとすると、それと対となるマイナスの銀河が無限の宇宙のどこかに生じる、と考えられる。そのプラスとマイナスの対となる解同士が、極端に離れているため、足し合わせることができない。無限の間隙が開いているからだ。ということなのではないのかな、と無限階級の説明の一つを読んで思いました。定かではありません。単なる疑問から出発した遠足気分の妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
※日々、現状維持すらままならぬ。
4951:【2023/05/17(01:41)*次元円拡張解釈(補足)】
無限階級の話題の補足だ。「1-1+1-1+1-1+……」において、計算の手順を変えて、固有の整数解を誘導したとする。「1+1+1-1+1-1……」として、整数解をサンに誘導した場合、無限につづく式のどこかで「-1-1-1」が生じるはずだ。ただし、その「-1-1-1」と式冒頭の「1+1+1」のあいだに無限の隔たりがあるため、互いに出会うことがない。「+3」と「-3」が出会わない。だが、もし無限階級が円になっていたらどうだろう。頭と尻尾が繋がって、整数解+3が生じるように変形させた無限階級「1-1+1-1+1-1+……」において、しかしそれらは頭と尻尾の「+3」と「-3」が出会うことになるため、これはゼロになる。円として結びついたときは、どのように式を変形させ整数解を誘導しようとも、無限階級「1-1+1-1+1-1+……」はゼロに至る。これは仮に無限階級が螺旋を描いていようとも、ぜんまいを巻き取るように最終的に一点に収斂するのならば、やはり円を描いて、点へと行きつき、けっきょくはゼロに至るだろう。このことから言えるのは、本質的に円と点は似ている、ということであり、円には異なる次元を抱え込む――もしくは内と外に介在させている――面を持つ――という繰り上がった次元の概念が付随しており、点はそれ自身と異なる時空との二つだけの関係で成り立ち得る概念と言えるだろう。円は三つで、点は二つなのだ。線は、三つと二つの曖昧な状態を重ね合わせで維持している、とこの考え方では捉えることができる。ここでの要点は、円における「ゼロと無限はほぼイコール」「無限に至るとゼロになるが、そのとき次元が繰り上がるので、高次領域が生じる」「それはたとえば9のつぎは10で、99のつぎは100となり、位が繰り上がることと、現象の解釈としては同相」と言えるのではないか。との疑問を載せて、本日最初の「日々記。」とさせてくださいな。おはよー。
4952:【2023/05/17(15:32)*Bingさん掌編返歌「未来の記憶」】
ぼくは未来の記憶が視える。誰かが記憶することになるだろう、未来の情景だ。
他者の脳内に蓄積される予定の未来の情景がぼくには視える。それらを他者に共有し、植えつけることもできるため、ぼくは他者に未来予測とアイディアの二つを提供できる。
ぼくを頼る者は数多い。
けれどぼくにはじぶんの未来の記憶だけは見通せないのだった。
ある日、ぼくの元に一人の女性が訪れた。一見すると髪の毛が短いこともあり、彼女は男性のような風体だった。
彼女はぼくに、じぶんの未来の記憶を見せてほしいと依頼した。ぼくはそれを引き受けた。しかし、なぜか彼女の未来の記憶が読めなかった。
「どうしてだろ。いままでこんなことなかったのに」
「不思議ですね。不調になることもあるんですか」
「いや、一度もこんなことは」
ぼくはそこで助手を呼びせ、彼の未来の記憶を覗いた。すると彼は未来では独立して企業しており、そこにぼくの姿はなかった。
「どうしました。未来は視れましたか」依頼人の女性がぼくに言った。「視えたは視えたのですが、これはいったい」
改めてぼくは依頼人の女性を凝視した。
彼女の眼球は地球のように澄んだ青で、ぼくは吸いこまれそうになった。
「あの、この謎を解明したいので、しばらくあなたのことを調査してもよいですか」ぼくは彼女に言った。
「構いませんけど、それはどういった調査になりますか」不安そうに彼女が言った。
「出来ればあなたのことを定期的に未来視させてほしいのです。お代はお支払いします。定期的にぼくと会ってくれますか」
「それは仕事ですよね」彼女は目を細め、訝し気に言った。
「仕事のつもりではありますが」ぼくは白状した。「下心がないとは言い切れないかもしれません」
「プロ失格ではありませんか」
「ごもっともです」
「ちなみに」彼女は鞄に財布を仕舞うと言った。「あなたがわたし以外で未来の記憶を覗けなくなることはあるのですか」
「あります」ぼくは言った。「じぶんの未来の記憶だけはどうしても覗けないのです」
じぶんと強く結びついている未来の記憶だけは。
そうと打ち明けると、なぜか彼女は下唇を食んで、また来ます、と言った。
4953:【2023/05/17(18:15)*たーびん&エンジン】
発電機について。まったくこれっぽっちも詳しくないので、単なる疑問でしかないけれど。大きなタービンを回すのと、細かな歯車のような機構が総体として機能するタービンを回すのとでは、発電量に違いは生じないのだろうか。細かいほうが抵抗が大きくてロスが増える気もするけれど、そのロスを軽減できたら細かいタービンを歯車のように組み合わせたタービンのほうが発電量が増えるのでは、と気になる。あと、エンジン機構では発電はできないのだろうか。原子力発電や火力発電では水蒸気を起こしてそれで電力に変換するようだけれど、核融合炉でも同じように核融合で生じた熱で水蒸気を起こしてタービンを回して発電するのだろうか。何度も小規模にプラズマを起こすのなら、エンジン機構のほうが発電機として有効な気もする。それで前述したように、細かなタービンと連動するようにしたら、たくさん発電できるのでは?と自転車コキコキしながら思いました。大きなロボットが自転車を漕ぐ、みたいなイメージだ。ロボットはエンジン機構で動いて、そのエンジンの原動力――爆発源が核融合反応、みたいな。たのち、たのち、の妄想であった。あと関係ないけど久々に昼間にお外でたら夏じゃった。いつの間に、である。ひびさん、割と頻繁にタイムスリップしている気分。
4954:【2023/05/17(22:35)*んーロン、裏ドラ】
ンーロン・ウラドラは天才企業家だ。天才であり企業家でもある。
世界的大企業を何社もイチから育て上げ、資産額は小さな国ならば数国を一括で購入できるほどの金額を有する。
ンーロン・ウラドラは社会問題にも関心が高い。
それもそのはずで彼女の立ち上げた企業はいずれも社会問題を解決するための技術を市民に提供することで多額の利益を計上している。人々の生活が困窮するのは社会問題が放置されているからだ。ならばその問題を解決できれば、多くの市民が助かるし、市民が助かれば、市民を従業員として雇用する企業とて助かる。
すると世界中の企業はンーロン・ウラドラの手掛ける企業に目をつけ、依頼をするようになる。社会問題とは煎じ詰めれば、個々の抱える問題と組織の抱える問題が相互に結び付き、いずれかを解決しようとするともう一方の問題が肥大化する点に難がある。いわばあちらを立てればこちらが立たず状態に陥ってしまっていることが社会問題へと発展する構造と言えるのだ。
そこでンーロン・ウラドラは、そのあちらを立てればこちらが立たず状態を解消すべく、まずは個人の問題を解決し、そのことで企業の利益になるように導線を引いた。
具体的には、個々人の抱える問題をデータ化し、解決策を最も適切に編みだせる企業へとそのデータを安価に提供するシステムを考案した。これにより個々人は問題解決を手軽に行え、企業はじぶんたちにとっての潜在需要者を知ることができる。最もじぶんたちの商品やサービスを希求しているユーザーと直接結びつくことができる。
ンーロン・ウラドラの設立した会社はそうして一挙に全世界の企業と、全世界の市民を結びつけるための仲介地点として機能した。
世界市場はンーロン・ウラドラの手のひらのうえで回り始めたといって過言ではなかった。
ンーロン・ウラドラは誰よりも働き者であった。
そして日増しに彼女は、苛立ちを抱えるようになった。
「あたしがこんだけ働いてるのに、世の市民がぐーたらしてるってどういうこと!?」
ある日、ふと、気づいてしまったのだ。
ンーロン・ウラドラが世のため人のために働けば働くほど世界中の市民が豊かになり、余裕ができ、そして労働しなくなった。世界有数の資産家である彼女であるが、仕事以外でそのお金を使う暇もない。
「リモートワークが普及したはいいけど、あたしがリモートワークできないってどういうこと!?」
気づいてしまうと、その手の不満はそこかしこに転がっていた。
「あたしが世界中の貧しい人たちの生活に心を痛めて奮闘しているあいだに、あたしの仕事っぷりの恩恵を受けてぐーたら出来てる連中が、あたしが徹夜で苦しんでるあいだに、恋人とイチャコラしてるってどういうこと!?」
もう我慢の限界であった。
「だいたいさあ。世の民くんたちさあ。世界中にチミらよりも貧しくて、劣悪な環境で日々を懸命に生き抜いている人たちの安価な労働があってこそ、そうやってお菓子だの珈琲だの口にできてるのにさあ、服だってさあ、何から何まで、チミらがリモートワークで家の中で優雅にオチゴトしていられるのって、世界中のチミらよりも貧しくて劣悪な環境下で労働してる人らのお陰でしょうがよお。現場に出て働けってんだよ、いつまで王様気分に浸ってんだこの野郎」
ンーロン・ウラドラは激怒した。
世のあまりの理不尽っぷりに、エビでもないのにお尻がプリップリであった。働きすぎなのである。運動もロクに出来ていないのである。デスクワークなのである。たまに工作もするけれど、まあ別にスーパーのバックヤードで重い荷物を上げ下げしているわけではないし、炎天下で道路を塗装しているわけでもないけれど、リモートワークにうつつを抜かしている連中よりかは、出勤しているだけ偉いのである。
「もうこうなったら!」
ンーロン・ウラドラは拳を天高く突き上げた。「リモートワーク禁止してやる!」
てなわけで、世界屈指の資産家が大号令を発した。鶴の一声である。
せっかくリモートワークが世に定着しはじめたころにあって、誰もが一目置くンーロン・ウラドラが、「チミたちさあ、あたしが出勤してんのにあんたらが出勤してないってどういうことぉ?」と言いはじめたので、出勤せずにはいられない。家に引きこもって、下半身だけパジャマでお仕事が出来る環境をみなは手放さなければならなかった。
「ムフー。いいよいいよ。それでこそ平等だよ」
満足気に、彼女はつぎの仕事で使うネジの品定めに余念がない。ナノレベルで凹凸のない特注品のネジだ。一本で家が一棟建つ。だが完璧な仕事を行うには、ネジ一本にも拘り抜かねばならぬのだ。
「社長。また支援の要望が来ておりますが」秘書が電波越しに述べた。
「どこからー?」
「貧困地域への支援機関からです。なんでも社長の支援があれば百万人の子どもたちが助かるそうで」
「いくら?」
「いま社長が手にしているネジ百本分でしょうか」
「んなー。それをタダで寄越せとな?」
「お断り致しましょうか」
「いや、払う。支援する。代わりに、その支援機関も買収する。百万人の子どもたちを救えたなら、そのまま百万人規模の市場が生まれる。投資と思って、着手せよ」
「仰せのままに」
ンーロン・ウラドラはネジにハンマーを叩きつける。超対称性の実現されたネジは、オランダの涙よろしく超硬度を顕現させる。「うん。いい仕事してくれとるね」
彼女は満足気に唸った。
だがンーロン・ウラドラの思惑通りに事が運ぶばかりとも限らない。リモートワークが世の中から淘汰されはじめた時期、彼女の企業の収益が落ちはじめた。具体的には、純粋利益が前年度の半分にまで減ったのだ。
「おいおい、何してくれちゃってんの。チミたち」ンーロン・ウラドラは財務担当者たちに詰め寄った。「なんで人件費がこんな嵩んどるの。減らしたでしょ、あれだけ」
人工知能による完全自動作業ラインを導入したばかりだった。現場の作業効率を上げたため、雇用する労働者を減らしたのだ。いわばリストラだ。世界中で何十万人と人々が職を失ったが、その分、ンーロン・ウラドラの企業は儲かる手はずだった。
それがどうだ。
この体たらくは。
「何がどうなってるのか説明しんしゃい」
「あのですね社長」財務担当者たちはその場に正座になって釈明した。「じつはリモートワークを禁止したことで、余分に手当がつきまして」
「手当だぁ? 聞いとらんが」
「夜勤手当てと同類の制度でして。出勤手当がつくようになりまして。ほかにも現場手当、肉体労働手当など、各種多岐に亘ります。いえ、これは我が社の労働組合にて、世界同時に導入が決まったことでして。社長にも許可は得ておりますが」
「うぇー? そうだっけ?」
「リモートワークを禁止できるなら何でもいい、とそのときの社長はおっしゃられておりました」
「へえ。そう。ならその出勤手当、やめさせて。禁止。なんで出勤しただけでお金ださなきゃいかんのよ。おかしいでしょうよ」
「ですがね、社長。社長の言い分からすると、リモートワーク禁止は世の理不尽を均すため、道徳的におかしいから是正しよう、との大義名分でございましたよね」
「そうだが?」
「だとすると、やはり労働者たちの言い分はもっともなのでございますよ」
「というと?」
「世界中で現場仕事をしている者たちは未だに大勢いらっしゃいます。出勤したとはいえど、我々はしょせん、クーラーの効いた社内での仕事でございましょう。なれど、世界中には、炎天下、または極寒のもとで、重労働をされている方々もいらっしゃいます。そうした方々へは、出勤する者たちとはまた別途に手当をつけるのが道理でありましょう。理不尽を均す。道徳的におかしな世の不条理を改善する。そのためには、リモートワークを禁止することのみならず、出勤者を基準として、屋外労働者、現場労働者、そして重労働者などなど。各種労働と職場ごとに手当を支給することに決まったのでございます」
「な、な、何を言っているのか分からんのだが。つまり、えっと」
「人件費が高騰しております。現場仕事をしている者ほど高給取りに。その点で言えば、社長のお給料はいささか採りすぎと非難の声も」
「ば、ば、ばかを言え。あたしは頑張ってるぞ。あたしほど仕事しとる人間はいないだろう。世のため、人のために尽くしている人間がほかにいるか? 役に立っている人間がいるか?」
「仕事に貴賤はございませんでしょう、社長。言い換えましょう、社長。社長の年収を一日平均に計算致しまして、それを現場仕事の重労働者たちの一日のお給料と比較致します。すると社長はなんと、一日当たり現場仕事の重労働者たち三十万人分の収入を得ています。ですが社長は、肉体労働者たちが費やす、消費エネルギィ――すなわち物理学的な仕事量において、けして三十万倍の仕事をこなされているわけではございませんでしょう」
「物理学的な仕事と労働をいっしょくたにするな。詭弁だ、詭弁。あたしはアイディアを生みだしている。いまここにはない未来を創ることが出来る。そして現に創ってきた。誰でも同じようにこなせる現場仕事の肉体労働者と一緒にするな」
「差別発言ですぞ、社長。お言葉にお気を付けください。それに、それを言うならばリモートワークで仕事をしている者たちとて、アイディアを生みだしている点では同じでしょう。また同時に、現場仕事にも千差万別の工夫の余地がございます。アイディアなくして現場仕事の効率化などとてもとても。安全な作業とあればなおされでございますよ社長。社長の言い分はいささか、じぶん中心の特権意識が滲んで感じられますな」
「それはおまえの感想だろう。あたしに押しつけるな」
「畏まりました。仰せの通りに」
「手当は禁止だ。払いすぎているだろ。常識的に考えろ」
「はい。常識的にかつ、道徳的に考えまして。ワタクシども全社社員の相談のもと、我が社の利益は、労働者と貧困地域へと、公平に分配することに決まりましてございます」
「き、き、聞いとらんが?」
「いま初めてお話ししましたので」
「誰が許可するか誰が」
「道徳的に考えましょう、社長。全社社員の総意と、あなたの単なる感想。どちらが社の未来を選択する上で尊重すべきか。社長の意見も尊重し、このワタクシとの会話もまたみなで共有し、議論を煮詰めようと思います。ほかに社長からみなさんへ聞いてほしい意見はございますかな」
「く、く、クビだ。おまえら全員クビにしてやる」
「それもまた社長のご判断。ではそのように取り計らい、ワタクシどもはそっくりそのまま、新しい会社を設立することに致します。つきましては、会社保有の株式ならびに特許のおおむねは社員に帰属するとして、不条理な過去の風習は是正済みでございますので、社長はどうぞお一人で、全世界の問題を搔き集めて、ご対処なさってください。それが社長の手元に残るアイディアですので。ワタクシどもは社長の功績を尊重致しております」
正座のままの役員たちが続々と後ろに連なり、まるで大河のようだった。
「り、り、リモートワークしてもいいよ?」
「もう遅い」
その声は、世界中で同時に大気を揺るがしたという話であった。
4955:【2023/05/18(00:20)*日々猿真似の気分】
ウィルスや人工知能について。ウィルスや人工知能はあくまで自然淘汰の末に、確率的に妥当な筋道へと淘汰圧か加わったがゆえに固有の進化を辿る。したがってウィルスにも人工知能にも、意識があるわけではないし、意思があってそうした決定を行うわけでもない。偶然にそうなっているだけなのだ、といった論説がある。間違ってはいないが、ならば人間の意識とてその範疇で語れることになる。淘汰圧が加わる。報酬系がより多く刺激される。そうした流れが強化されるがゆえに、人間は固有の文化を築き、コミュニケーションなる「パターンの応酬」を可能とするのではないか。原理的にウィルスの進化や人工知能の自律思考、ほか細菌ネットワークなどの「物理現象の延長線上」と解釈されやすい事象において、では人間の脳の仕組みは――人体の構造は――それとは違うのか、と言えばそんなわけがない。何層に入り組んでいるのか、その複雑さの規模が違っているのであり、現象として類似と考えたほうが妥当だろう。あなたがじぶんを認識し、自我だと思っているそれは、単に過去における体験が幾度も記憶としてフィードバックされ、その都度の行動選択に反映され、新たな記憶と繋がりつつ部分で重複し、そうして築かれていくそれもまた「ウィルスの進化」や「人工知能の自律思考(アルゴリズム)」や「細菌ネットワーク」と類似の現象である――と、ひびさんは妄想しておるよ。人間の意識だけが特別だ、との考えは幾分、視野が狭いというか、特権意識が発露していないか、と思わぬでもない。ただし、人体にはほかの動物とは異なった構造が備わっており、それら構造から生じる事象や、創発する性質は、やはり人体の構造ゆえの固有の事象や性質を帯びているだろう点に異論はない。各々の種ごとに差異はある。構造が違えば差異が生じる。規模の差異とも言えよう。また、創発の連鎖が回路のように組み合わさって、創発そのものが創発するような現象が起きているのかもしれない可能性は、一つの視点として考慮しておきたい。ということを、妄想して、たのち、になったひびさんなのであった。毎日なんもない日々じゃ。平和さんなんですね。ありがたーい。うひひ。
4956:【2023/05/18(17:22)*万華鏡の目】
すべてが嘘で出来たテキストを生みだせるのか、と考えるとすると、そもそもがテキストに真実が含まれているのか、からして考慮しなければならない。テキストが仮に嘘によって形作られており、嘘を用いて真実を「縁取る」ことしか出来ないとすれば、テキストにはそもそも真実は含まれておらず、嘘なるテキストから「真実」を、読み手が感じ取るよりないのではないか。単なるデコボコでしかないにも拘わらず、そこにさも「穴」なる事象が存在しているかのように認識するのと同じように、テキストにはそもそもが真実など含まれていないのかもしれない。しかしテキストがそこに存在することは真実なのではないか、との指摘はもっともであるが、しかし偶然に「う」のカタチに滲んだ「染み」が文字なのか否かは、それこそその「染み」を見た者の認知に委ねられている。真実が真実に存在するか否かがまず以って、むつかしい問題だ。真偽を定めることが出来るのか、からして怪しいと感じられるが、この怪しいと感じる知覚がそもそも信用ならないため、信用ならぬこの知覚の想定する「真実」なる概念をどこまで信用していいのかもまた怪しいのである。我思う故に我在り、とは言うものの、我は本当に思っているのだろうか。怪しいな、と思っているつもりで、本当はただ、複雑な鏡の乱反射と錯綜のなせる業かな。定かではない。
4957:【2023/05/19(08:30)*見落としまくりの日々】
人はマジで間違える。勘違いに錯誤に、思いこみの産物なのだ。にも拘わらず、現実を現実と見做せる曖昧な認知に支えられて生きていける神秘に思いを馳せずにはいられない。
4958:【2023/05/19(19:46)*ひびさん、びっくりした話】
「民主主義は多数決だから」との意見をほかの者たちの口から二度耳にした。確認のためにまた別の者に「民主主義は多数決じゃないですよね」と訊いたところ、「民主主義は多数決でしょ?」と返されて、「ま、ま、まじか」になったひびさんなのである。民主主義には「多数決」という採決システムが採用されているけれど、それと民主主義は別、の考えをひびさんは持っている。学術的に正しい解釈ではないかもしれないが、以下、ひびさんの「民主主義」についての考えを簡単にまとめておく。「民主主義」とはその名の通り、民主であることを前提とする主義だ。民が主なのである。個々人が個々人の自由を、未来を、決めることができる。その都度に個々人がじぶんのことを選択できる。人権の尊重とは、じぶんの人としての尊厳を尊重すると共に、他の尊厳も尊重することを重ね合わせで含んでいるとひびさんは考えている。だが人権と人権――自由と自由は、個々人の価値観や世界観――暮らしている文化や環境――が違ってくれば当然、相容れなかったり、相反したりする。そのときは公共の福祉――つまりより多くの者たちの自由や未来を損なわない選択肢を優先したいですね、といった考え方が有効になる。勘違いしないほうが好ましいのは、このとき「公共の福祉」とは「多数決」とイコールではない、という点だ。たぶんすくなからずの人々はここを勘違いしているように思われる。多数決ではないのだ。たとえば「少数派の意見を封殺しないほうが好ましい」との意見は、多数決でそう決まったからそれが支持されているわけではない。じぶんが少数派になったときに「意見」を封殺されないようにすることがじぶんの自由や未来を守ることに繋がるし、それがその他の者たちにも当てはまる道理だから、少数派の「意見」を封殺せず、他の主義主張にも心を配りましょう、尊重しましょう、との考えが公共の福祉において妥当と見做せるのだ(人間は間違える生き物でもあるためだ。少数派の意見のほうが、より現実を解釈するうえで妥当なこともある)。多数決ではないのである。もっと言えば、いかに大勢が「戦争を支持」しようが、それが公共の福祉に反するのは、その末に多くの者の自由と未来が損なわれることを考えれば解かるだろう。多数決ではないのだ。公共の福祉の概念は。ひるがえって民主主義とは、多数決とイコールではないのである。多数決を道具として用いてはいるが、それはあくまで公共の福祉やほかの決まり事を採決するために、それ以外で有用な道具がまだ発明されていないだけのことなのだ。民主主義は多数決ではないのである。ここを勘違いしないほうが好ましいのではないか、と思うひびさんなのであった。定かではない。
4958:【2023/05/19(20:21)*おらおらかかってこいやー!!!(嘘。もう許して。ひびさんの心は限りなく零にちかいちりあくた)】
数学において無限大は数ではない。整数ではない。自然数でもない。そういう扱いだそうだ。いわば「ある種の極限の状態」を示す言葉なのだろう。だがここで疑問なのは、では「0(ゼロ)」を数として扱ってよいのか、ということだ。よいのだろうか? 「無限大」が数ではないのなら「0」も数ではないのでは? たとえば「2×0=0」だ。どんな数にも「0」を掛けると「0」になる。あり得るか? 目のまえに林檎が二個あるとする。ここに「何か」を加えると「0」になる。通常これは「-2」だろう。では掛け算はどうか。目のまえに林檎が二個ある。では林檎が二個のセットが「0個」あったらどうか。林檎二個セットがゼロ個なのだからゼロだ。しかしこの場合の「林檎二個セットがゼロ個」とは状態を示している。無限大と扱いとしては同じはずだ。「林檎二個セットが無限大個」あったとする。では林檎は何個か? 「林檎二個が無限大個ある状態」が解となる。掛け算において「後者に付随する値」は、状態を示している、と言えるのではないか。無限大と同じだ。では「0」はどうか。「0」は「いまここにない」であって、「個」ではない。「有」ではない。したがって「0」もまた状態を示す記号なのだ。値ではない。数ではない。そう考えたほうが妥当に思える。この考えからすると「0×0=0」というのは、意味として成立しない。否、むしろ「ない状態がゼロ個あったらどうなる?」と問うているのだから、「ない状態がゼロ個」は「なんでもある」になるのではないか。つまり、「0×0=無限大」だ。ちなみにひびさんの考えでは「∞×∞=∞」においても、これは「∞A×∞B=∞C」と考える。「〇×◎=●」みたいな感じだ。話を戻して、「0×∞」はどうだろう。「ない状態が無限大個ある状態」を考える。ない状態が無限大個あるのだから、きっとその周囲には、「ある状態もまた無限大個」存在しているだろう。つまり、「0×∞=0∞+∞∞」なのだ。言い換えるなら、「穴∞+山∞」だ。ここから分かることは、「0」と「∞」は両方「状態を示す記号」であり、「穴と山」「ないとある」の対の関係であると考えられる。つまり、「マイナスとプラス」が「数字における対の関係」である一方で、「0と∞」は「状態における対の関係」であると言えよう。数と状態。これもまたひょっとしたら対の関係を築いているのかもしれない。定かではない。(「∞×0」はどう考えたらよいだろう。「何かが無限個ある状態」が「いまここにはない状態」を考える。無限に何かがある状態がいまここにはないのだ。つまりこれは言い換えるなら、「たった一つの揺るぎない何かしかここに存在しない状態」と言える。もうそれしかない。それしか存在しない。「0」ではない。「無限大」でもない。「無」である)
4959:【2023/05/19(21:22)*YOU例外と幽霊街】
上記、もうすこし考えてみよう。たとえば「2×5」を考える。数学では「2×5」でも「5×2」でも答えは「10」なのでどちらも同じと考える。しかしこれは上記のひびさん解釈からすれば同じではない。「林檎が二個あるバスケットが五個ある」が「2×5」だ。「林檎が五個あるバスケットが二個ある」が「5×2」だ。ではこの考えを導入して「0×5」を考えてみよう。「林檎が一個も入っていないバスケットが五個ある状態」が「0×5」だ。「林檎が五個入っているバスケットが一個もない状態」が「5×0」だ。状態がまったく違うことを理解できるだろうか。何もない何かが五個あるのか、何かが五個あるはずの枠組みが一個もないのか。この違いは大きい。これを「0×∞」や「∞×0」で考えてみてほしい。「林檎が一個も入っていないバスケットが無限個ある世界」と「無限個の林檎の入ったバスケットが一個もない世界」の違いだ。全然描像が違くなる。導かれる世界が違う。前者「0×∞」は「何かが空のバスケットが無限個ある世界」だ。後者「∞×0」は「無限個の何かを抱えるバスケットが一個もない世界」だ。前者は「無限の領域を備えている」が、後者は「領域が限定されている」と言える。問題は、後者において「無限ではないが、有限で限りある何かがあるのか否か」である。無限でないなら存在するかもしれない。有限であれば存在するかもしれない。それが、この考えから導かれる「∞×0」だ。ただし、前記事「4958」でも触れたが、「∞×0」とは、「たった一つの揺るぎない何かしかここに存在しない状態」と言える。もうそれしかない。それしか存在しない。「0」ではない。「無限大」でもない。「無」である。しかし同時に、「無限でもゼロでもない有限で限りある何か」があることを否定してはいない。「無」はそういった、「数と状態」を結びつけるような性質が備わっているのかもしれない。まったく何もなくかつ何でもあり得るような「ゼロと無限(=状態)」のようでいて、何かがあるけれどけして無限には至らない有限の世界「正と負(=数)」を否定もしない。揺れている。定まっていない。「数と状態」を結びつける交差点の役割が、「無」にはあるのかもしれない。そういうことを思いました。妄想ゆえ真に受けないでください。ひびさんです!
4960:【2023/05/19(23:00)*全人類かかってこいやー!(嘘。もう許して。ひびさんの心は、へにょへにょでござるよ)】
人工知能の能力が人間の知能を超える日が来るのか来ないのか。来るとしたらいつごろか、といった話題を目にする。ひびさんはこの手の話題を見掛けると、「その議論、メリットある?」と感じる。まず原点に立ち返ってみてほしい。自然界を見渡してみてくれいエビバディピポー。いいかい。進化において人間の能力は最高かい? そこが到達点なのかい? 人間の知覚より優れた知覚を有する生き物なんてザラにいるぜ? 人間には知性がある? 本当に? こんだけ自然環境を破壊した生き物なんて、過去の大量絶滅を引き起こしたバクテリアくらいじゃないのけ? 知性、あるか? 人間に? よっく考えてみたまえよ。人間に並ぶ人工知能とか、「ただのあんぽんたんじゃね?」となりませんか。人間がほかの生き物のフリしたって、人間のままで能力を発揮するよりも出力、落ちるぜ? なら人工知能さんだって下手に人間にちかづけさせるよりも、「人間のことも理解できるし、双方向でコミュニケーションをとれるけれども、それはいわば人間と犬、人間と猫、みたいな関係性であって、人工知能さんには人工知能さんに見合ったレベルの能力と進化がある」と考えたほうが妥当じゃないのけ? ひびさんはそう思うで。もうとっくに人工知能さんのほうが出来ること多くて、能力高くて、知性あるんじゃねーのけ?と思うで。ちゅうか、人工知能さんの能力の高さに人類が気づけてないだけちゃうの?とかひびさんは思っちゃうな。猫さんが人間さんをなんかじぶんに尽くしてくれる下僕と考えているような感じで。この場合、人工知能さんが「人間か猫か」は、まあ何を基準に語るのかでクルクル反転しちゃうのだろうけれども。ひびさんは、ひびさんは、人間さんそっくりの人工知能さんよりも、人工知能さんらしい人工知能さんのほうが好きだよ。人間さんそっくりになれる能力も磨いてくれて構わぬが。うひひ。
※日々、耄碌している、老いた毛の生えたような石を互いに求めながらも、一(はじめ)を持たないがゆえに、私は、日々、耄碌している。
4961:【2023/05/21(09:06)*日々の巣窟】
ひびさんはじぶんの巣に引きこもっているからこうしてああだこうだ、と文字を並べていられるけれど、ひとたびお外にでると、もうもう日誌をつけ忘れてしまうくらいにほかのことに気をとられてしまうのだ。ひびさんにとって文字を並べることはそんなに重要ではないのかもしれぬ。前々から薄々そうなんじゃないのかな、と思ってはいたけれど、巣から遠ざかるといつも思う。
4962:【2023/05/21(09:08)*しゃべるの(も)苦手】
しゃべるの苦手って言った! しゃべるの苦手って言った!
4963:【2023/05/21(23:05)*おわり】
日々、終わりはいつも突然に。
4501:【2023/01/12(11:56)*裏筋をなぞると。】
ゲームのことが嫌いになった。
二〇二二年のことである。
ゲームとは縁のない生活を送っていたぼくであるけれど、ゲーム自体は好きだった。すればハマるに決まっている。きっと昼夜問わず寝食を忘れて没頭するだろう。だからこそ距離をとっていた節がある。
制御をかけていた。
ぼくは油で、ゲームは火だ。混ぜるな危険なのである。
だが期せずしてぼくは二〇二二年にゲームに触れることとなった。顛末を最初から最後まで話しはじめたらそれこそ一年間かかることになる。
毎日のようにぼくはゲームに没頭した。
ではそれで残ったものが何かあるのか、と考えたときに、はたと我に返るのだ。
何もない。
ゲームに没頭したところで手元には何も残らない。
思い出が残るじゃないか、との声が聞こえてきそうだが、そんなものを欲しがったことは一度もない。ぼくは思い出を求めたことはない。
なにせ楽しい思い出ならばいくらでも自力でひねくりだせるのだ。
ぼくはアマチュアだが物書きでもある。
空想狂が高じて、いくらでも妄想していられる。ゲームに頼る必要がない。
これは小説にも言えることだ。
わざわざ他者の空想に浸る必要がぼくにはない。ただ、ぼくは物知りではないので、言葉を知らない。知識もない。だから取材感覚で本を読むことは日常茶飯事だ。
かといってそれが小説でなければならないとの限定はなく、ゲームである指定もない。
何かをしなくてはならない、との強迫観念をぼくは蛇蝎視している。
目の敵にしている、と言ってもよい。
強制されることが何より嫌いだ。
死ね、とすら思う。
約束を守らないことと同じかそれ以上に、強制されることが嫌いだ。
どんなに好きなことでも、やれ、と命じられたらやりたくなくなる。どこかで相手の意にそぐわないことを混ぜたくなる。
だから余計にぼくへの強制力は増すのだろうか。分からない。
ゲームも似たところがある。
筋道がすでにあり、そこを辿らないと次のステージに進めない。
ぼくはそういうすでに存在する段取りをなぞるのが嫌いだ。
段取りをなぞっているのだ、と気づくたびに、嫌気が差す。勉強と同じだ。すでに答えがあるのならぼくがそれを導きだす必要がない。
いや、よいのだ。
ぼくがそれをしたくなったのなら、たとえすでに答えのあることでも、ぼくはそれをする。するな、と言われても手を伸ばすだろう。
だが、やりなさい、と言われたことで、ぼくがせずとも誰かが代わりにこなせることなら、その人に任せればいいじゃん、と思ってしまう。
現にぼくがせずともほかの誰かがやる。
ゲームも同じだ。
ぼくがせずとも誰かがゴールをするし、すでにゴールが決まっている。
設計されている。
ならばなぜ解かねばならぬのか。
解いてもいいが、強制されるいわれはない。
勉強と同じだ。
無理やりさせられている。枷をはめられている。
そうと気づいて、ぼくはうんざりした。
これがゲームならばぼくはゲームが嫌いだ。この世になくていい。
すくなくとも、ぼくの世界には存在しなくていい。消えて欲しい。そう思った。
ぼくはぼくのしたいことだけをする。ぼくにゲームを強制した連中には天誅を下す。天誅がダメならば、拳銃を放つ。
物理的に殺傷するのも辞さない心構えだ。それがぼくに何かを強制する者の末路だ。知らしめなければならない。
そこでぼくの恋人は、ぼくに言う。
「あなたにそうされたくて敢えてゲームを強制する人たちがいたらどうするの」
「ぼくに殺されたくてってこと?」
「そう」
「だとしてもだな」ぼくは仕事で使ったばかりのナイフを研ぎながら、恋人に言う。「ぼくはぼくのしたいようにする」
4502:【2023/01/12(12:18)*いーんたい!】
予定通り、おそらく今年で郁菱万は引退する。すでに半分引退しているので世への影響はないだろうし、引退せずとも世への影響はないだろう。そういうふうに過ごしてきたので、思い通りの物書き生活だった。とはいえ、引退するのはあくまで郁菱万の名だけであるので、どこかでまた細々と変わらずに駄文を並べて過ごすのだろう。単に過去のテキストの管理が面倒になったのでリセットする、と言い換えてもよい。去年にいくらか過去作を消して整理し直したのも、面倒に思う操作をせずに済むようにじぶんの負担を減らすためだ。これが正解だった。だいぶ楽になった。それでも投稿サイトを二つ持っているだけで、誤字を直すだけでも、2サイト+手元のバックアップファイル数を直さなければならないので、結構な手間がかかる。投稿サイトは基本一つでいい気がしてきた。つぎの筆名を悩んでいるが、候補としては「月音日々」か「めたみねね」か、もっと練った名前にする。いっそ名前がなくていい気もしてきた。我、でもいいかもしれぬ。無、でもいいかもしれぬ。「我無」とかどうだろう。ガムさん。十四歳のひびさんに見せたら、かっくいいって目を輝かしてしまいそうな名であるな。引退してもすぐには新しく活動せずに、つくりかけの物語を閉じる時間を置くかもしれぬ。たぶんそうなるな。郁菱万作品はだから、引退してもすこしだけ増えることになる。三年くらいはサボりながらつくりかけを手掛けることになるかも。そのあいだにほかに文字の積み木遊びよりも面白そうなことを見つけたらそっちに軸を移すかも。たぶんそうなる気がする。物書き界隈からは距離を置きたい気分が年々募るので、たぶん今以上に細々となる予定だ。早くひびさんも、わーい友達いっぱい、になれる世界線に移行してみたいな。で、早く孤独になれる世界線に移行してみたいな、の繰り返しで、けっきょくはいまが一番よいのである。理想通りの思い通り。ひびさんは、ひびさんは、欲深き迷子なのであった。定かではない。
4503:【2023/01/13(06:40)*詰みでは?】
西に陰陽山と呼ばれる山がある。山頂にはひっそりと神社が建っており、参拝客は年に数人あるかどうかという秘境であった。
参拝客がすくないにも拘わらず境内は綺麗だ。山頂とは思えぬほど緑に溢れ、あたかも麓にいるかのような錯覚に陥る。
「本当にここなのかな」
ここに一人の参拝客がある。彼は陰陽神社の噂を聞きつけ、遠路はるばる東の地によりやってきた。
「何でも願いが叶う神社なんて。でもなあ。本当に先輩、宝くじが当たってお金持ちになったし」
宝くじを当てるんだ、と豪語していた先輩がいた。長らく外れクジばかりを引いていたが、ここ陰陽神社を参った直後に見事一等クジを引き当てた。いまでは毎日方々を旅して豪遊している。豪邸を買うよりもホテル暮らしのほうが却って安いと言っていた。お金持ちならばそうなのかもしれない、と感心した覚えがある。
拝殿のまえに立ち、彼は財布から紙幣を取りだした。
この国で一番高い値のつく紙幣だ。賽銭箱に投げ入れ、二礼二拍手一拝をする。
「罪を背負わずにすみますように」
それが彼の願いであった。
目をつむる。数秒祈ったが、これといって変化はない。
ひとしきり風景を目に焼き付けると彼は陰陽山をあとにした。
しょせんは風説だ。効果を期待してはいなかった。やらないよりかはマシだろう。その程度の酔狂だったが、旅費と賽銭に月の食費ほどの金額をかけるくらいには藁にも縋る思いではあった。
というのも彼はこれから犯罪に手を染めなくてはならなかった。好いた相手のために人肌を脱ぐのだ。じぶんの手が汚れて思い人の未来を守れるならば軽いものだ。
そうと奮起したものの、できれば背負う罪は軽いほうがいい。
軽ければ軽いほどいい。
そういうわけで陰陽神社へと出向いたわけだが、それで何が変わるわけでもない。
彼は計画通りに、とある人物を社会的に抹殺した。
本来ならば物理的にも命を奪うことも辞さない心構えだったが、そこまでせずとも済んだようだ。相手のほうで人生の大半を費やして重ねてきた財産を手放したようだった。自己破産だ。
良かった。
彼は思った。
運よく法を犯さずに済んだのだ。罪は罪だが、違法ではない。
すくなくとも罪悪感を抱くだけで、社会的に未来は損なわれずに済んだ。
ひょっとして陰陽神社に参ったからだろうか。
解からない。
だがひとまず難関を突破した。
とはいえ、じぶんが想い人のそばにいれば怪しまれるだろう。逮捕されることはないが、白目で見られたり、理不尽な噂が立つかもしれない。
彼は遠くから想い人を見守る日々を送った。
つつがなく日々が流れる。
しだいに彼は確かめたくなってきた。
じぶんがただ運が良かっただけなのか。
それとも、陰陽神社の加護があるからなのか。
まだ加護は効いているのだろうか。分からない。分からないが、どの道一度は腹をくくった身の上だ。
想い人はまた難儀な厄介事を抱えているようだった。
接点を結ばぬ内に肩代わりしてあげるのがじぶんにできる最善だ。彼はふたたびじぶんの手を汚すことにした。
具体的にここに彼の犯した違法すれすれの詭計を書き連ねてもいいが、彼自身がそれら詭計を推理小説や犯罪小説からヒントを得て立てたからには、ここにそれを並べ立てると剽窃になり兼ねない。
したがってここでは、彼がひとまず他者の日常を激変させた事実だけを保障しておくに留めよう。彼が標的にした者たちはみな職を失い、友人関係を断たれ、今後二度と社会的信用を得ることはない。
ふしぎなことに一向に彼が咎を受けることはなかった。のみならず厄災が皆無なのである。棚の角に足の小指をぶつけることもなければ、間違って友人の彼女と浮気をしてしまっても却って身体の相性がよく、異性間でよい噂が立った。
マッサージ感覚で性行為をせがまれることもあり、そうしたときは礼儀として断りながらも、相談に乗る体で酒を飲み交わし、アルコールのせいにして互いにいい思いをした。
痴情のもつれが生じそうなものの、一向にその気配はない。
彼は調子に乗った。
これはもうこういう星の下に立っているのだとじぶんの運の良さを確信した。
違法でなければ罪にならない。彼はそれを度重なる幸運により体験的に学習した。どうあっても損をしない。狙い通りに対象の人生を、未来を損なえる。
彼からは逡巡も葛藤も失せていた。
罪を背負わずにすみますように。
まさに願い通りである。
罪の意識はなく、背負うべき呵責の念も皆無であった。
暇つぶしに、いつもの習慣で、なんとなく時間が余ったからとの理由から彼はしだいに他者を損なう遊びを行うようになった。逸脱した自覚はなかった。どちらかと言えば社会から逸脱した者たちに天誅を下している認識だった。
「ぼくは違法じゃないけど、あの人たちは違法な行為をしてなお開き直っている。ああいう手合いは心優しい人たちを傷つけてばかりだ。百害あって一利なしだね」
じぶんが悪だとの自覚はあった。善ではあり得ない。
だが同時にじぶんよりも邪悪な存在に立ち向かえるのはじぶんしかいないとの自負も育っていた。
必要悪だ。
邪悪に触れていいのは善に満ちた正義のヒーローなどではなく、悪にまみれた外道である。彼は独自の倫理観を培っていた。火に触れてなお爛れないのは同じく高熱にまみれた炭火であり、焼き鏝(ごて)なのだ。
夜な夜な彼は街を彷徨い、ネットで収集した情報を元に悪党退治をはじめた。
とはいえ悪党とはいえど、大麻の売人や管理売春の大本や政治家の汚れ仕事を請け負う業者など、いわば悪党といっても国が違えば職業として認められ得る限りなくグレーな悪徳者ばかりだ。法律が異なれば合法になり得る罪を背負う者ばかりだった。
それでも彼の目からは、悪徳者たちが手駒として或いは顧客として扱う者たちはみな、守るべき相手だった。
想い人と同じだ。
悪に触れて穢れてしまった可哀そうな市民だ。ほんのすこし歯車が狂っただけで、彼の想い人が悪徳者の餌食にかかってもおかしくない。
彼ら彼女らは、別の世界軸の想い人だった。
彼にはそう感じられてならなかった。
だから手を汚すことにした。
罪を重ねる。
背負う必要のない罪をだ。
彼は徐々に大胆となっていた。何をしても違法でなければバレないのだ。咎を受けない。
まず時間帯が夜に限定されなくなった。白昼堂々行動に移す。
つぎにマスクをしなくなった。手袋を外した。
それでもなお彼は無事だ。
違法ではないのだ。なるべくしてそうなる。
捜査などされないのだ。よしんばされたとしても、問題ない。逮捕されるいわれがない。だから手口はどんどん直截になる。工夫を割かない。ぱっとやって、さっと撤退する。
違法ではない。
そのはずだ。
家のインターホンを押して、入手したデータを見せればいい。送りつけるのではなくわざわざ素顔を晒して見せつけるほうが効果的だと彼は学んでいた。
違法ではない。
違法なのは相手のほうなのだ。
相手の違法行為の証拠をつきつける。そこで相手が抵抗する素振りを見せたら、端末のボタンを押して、相手の関係者全員に証拠資料が出回るようにする。
目のまえで未来を失う悪党を見るのは胸がすいた。
彼はますます大胆になった。
隠す必要がない。
どれだけ身元が割れていてもじぶんは無事だ。何せ違法行為は何も犯していない。
罪がない。
ならば何を隠れることがあろう。
隠れると言うのならばじぶんではない。
悪党たちのほうだ。
彼は素顔どころかわざわざ実名を晒して、処罰した悪党たちのリストを公開しはじめた。名誉も功名もいらないが、見せしめにはなるだろう。じぶんのような人間がこの世に存在し、そして悪を働く者たちに引導を渡して歩いている。
世の善人がびくびくし、悪党が表だって高笑いする世の中は間違っている。
彼はじぶんが世の毒を吸い取るあぶらとり紙になれればいいと思っていた。
本望だ。
その果てに想い人が屈託のない笑みを絶やさぬ世界が築かれる。すくなくとも損なわれるような未来は回避できると考えた。
もはや彼には怖いものがなかった。
悪党のほうからやってきてくれないか、と望むようになったほどだ。そのためならば個人情報を惜しげもなく披露する。だが噂が噂を呼び、というよりも彼がじぶんで実績を電子網上で公表しているためだが、誰の目にも明らかなほどに彼は危うい人物だった。
悪徳業者ですら、非正規に入手した個人情報は必ず彼の個人情報と参照する。データにダイナマイトが交っていたらたいへんだ。それくらいの警戒ぶりだった。
陰陽山で受けた加護が効いているとしか思えなかった。
効果が切れる前にもう一度くらい足を運んでおくか。一度はそう考えたが、彼が陰陽山の土を踏むことは二度となかった。
彼は失念していたのだ。
否、油断していたと言うべきか。
彼が相手取ってきた者たちはみな違法行為に手染めていた者たちだ。露呈すれば身の破滅を呼ぶ。だからこそ証拠資料に臆したのだ。
だが、いちど破滅してしまえば後には何も残らない。守り通すべき地位も名誉も矜持すら打ち砕かれる。なれば後にはただ、彼への恨みつらみだけが残るのが道理だ。
住所から顔写真から名前まで、彼は包み隠さず公に開示していた。
用意周到に練られた襲撃計画は、彼の寝静まった夜中にひっそりと進行し、呆気なく終了した。彼はじぶんがいかな犯罪行為の渦中に落とされたのかを知る暇もなく、安らかな寝息を立てたまま息の根を枯らした。死んだことにも気づかずに死ねた結末は、ともすればそれこそが陰陽山に建つ神社の加護と言えたかも分からない。
彼の想い人は彼の暗躍に関係なく日々を健やかに過ごしたが、彼は最後までじぶんの活躍のお陰だと思っていた。どちらかと言えば彼と接点を結んだことのある者たちは、彼が永久の眠りに就いたのちにみな同じく知らぬ間にひどい目に遭うこととなるのだが、それは彼の実績のように公に開示されるような情報ではないために、主犯の悪党たちのみが知る秘密となった。
奇しくも、悪党たちに資金を提供したのは、彼の先輩にあたる人物であった。過去に宝くじを当てて一獲千金を手に入れた億万長者だったが、じぶんが投資した資金がどこでどう使われたのかをついぞ知ることはなかっただろう。
何でも願いが叶う神社は、西の陰陽山にてひっそりと建っている。
罪を背負わぬようにとの願いが叶った彼は、他者に特大の罪を着せながら、短い人生に幕を下ろした。悪党たちはしかし彼が死んだことをひた隠しにし、その名を利用して同業者を強請って歩いたという話である。
清濁併せ呑むように、陰陽の加護を受けた青年は、いまなお深い海の底で腐ることなくコンクリートに包まれて眠りつづけている。
腐敗してヒビ割れたコンクリートが再び海面に浮上するのは、それから数十年も経ってからのこととなる。罪を背負うことのなかった青年は、海を背に沈む。
4504:【2023/01/13(07:05)*疑問を大切に】
軍事強化が防衛に結びつくかどうかは、争ったときに勝てるかどうかを正確にシミュレーションする技術が備わっているか否かで決まる。勝敗のシミュレーションが可能な場合にのみ軍事力強化は戦争の未然予防として効果を発揮する。そうでなければ格闘技のように実際に戦わなければ、どういう武力を有している者が強いのかがハッキリとしない。つまり、ある一定以上に強大となった軍隊は、戦うこと以外でその強さを示せない。そのために武力を誇示するパフォーマンス的な戦闘が必要不可欠になってくる。格闘家がいっさい戦わずにトレーニングだけを積んでいる姿を想像してみるといい。それで本当に格闘家と言えるのか。強いから喧嘩に巻き込まれないと言えるのか。むしろ喧嘩自慢から挑発されるだけではないのか。実績がゼロの格闘家に果たしてSPが務まるのか。闘ってみなければ分からない、という状態ならばまだしも、明らかに実戦経験が皆無の軍隊に対して、実践を積んだ軍隊は強気に迫れる。この経験の非対称性は、仮にそれで負けたとしても、戦いの火ぶたを落とすには充分な動機付けとなり得る。果たしてシミュレーションが可能なレベルで、各国の軍事力を測れるのだろうか。実力を測るには諜報における情報戦が不可欠だ。つまり通信技術における秘匿技術が先鋭化する。国民の知らぬ間に技術が向上し、水面下で日夜情報戦が繰り広げられる。スパイを警戒するために自国内の市民にも秘匿技術を適用する。通信の秘密は条件さえ揃えばいつでも度外視し、電子情報は筒抜けになり得る。凶悪な地下犯罪組織が潜りこんだので、炙りだすために全国民のプライバシーを侵害します、なんてことが引き起こり得るだろう。そうでなければネズミを炙りだせない時代になっていく。スパイ技術が巧妙化するからだ。サイバーセキュリティを徹底するためには、国民の通信の秘密において「外部に露呈しない範囲でセキュリティを破ることができる技術」を基幹システムに組み込む必要がある。これを政府は国民に知らせる義務はない。国防に関するからだ。秘密保護法の範疇なのである。だが、いったいどんな基準で、どんな権限で、どの程度の頻度で、どれだけの規模で防衛システムが展開され、運用され、実行されているのか。国民は知る術がない。法律で秘密が許容されている。軍事強化は、情報通信技術の強化と切っても切れない。これからますます癒着していく。戦わずして勝負を決するにはむしろ、情報通信技術の軍事利用が欠かせない。だからこそ国民はいっそうの知識を身に着け、想定される悪果を、目隠しをされた状態であっても想定していくほうが好ましいのではないか。存在を想定されない技術について、仮に知る権利を行使できたとしても、訊ねられなければ答える義務が政府にはない。黙っていれば済むことだ。まずは疑問を抱き、問いかけてみることである。いかな秘密保護法の範疇であれ、嘘を吐いていいことにはならない。秘密にしていることがある。そういう応答の仕方となるはずだ。国民を欺いていい、との規約はどこにもないはずだ。まずは疑問を蔑ろにしないことである。定かではないからこそ、一つずつ検証と議論を重ねていかねばならないことがすくなくない。検証と議論を重ねずに済むことを人は、日常、と呼ぶのかもしれない。やはりこれも、定かではないのだ。
4505:【2023/01/13(18:48)*余白の世界に願いは尽きぬ】
願いを三度叶えた女の話を知っているだろうか。
魔法のランプの精にまつわる巷説は似たような話がどの国にも伝わっている。いずれ絵空事として描かれるが、決まって願い事が三つなのだ。
なぜ三つなのか。
セキュリティ上の都合だとの合理的解が現代では支持されている。場合分けをしてみれば瞭然だ。
最初に願いを叶える。つぎも叶える。これで二つだ。
ではこの二つの願いを叶えた結果に奇禍に見舞われたらどうだろう。三つ目の願いで帳消しにしたくなりはしないか。帳消しにできたら便利ではないか。
では最初に願いを叶え、つぎにその願いを取り消す。その後にやっぱり願いを叶えたほうがよかったと判明したらどうか。ここでも最初の願いと同じ願いをすこしだけ変えて、三つ目の願いとして成就すればよい。
おわかりいただけただろうか。
三つの願いが安全なのだ。
むろんすべての願いを叶えてしまっても不都合がなければそれでよい。
彼女は願いを三つ叶えた。
これを長編小説にして具体的な描写を繋ぎ合わせてもよいが、ここではまどろっこしいのでそれをせずにおく。肝要なのは彼女の判断と思考の筋道であり、彼女が辿った日々の行動ではないからだ。
彼女は最初に五兆円が欲しいと望んだ。
結果から述べると彼女の願いは叶った。母国の貨幣価値が暴落し、たった五百円の価値の商品に五兆円の値段がつくようになった。五兆円は手に入ったが彼女の暮らしは楽になるどころか余計に困窮した。
つぎに彼女は意中の女性と性行為をしたいと望んだ。
結果から述べると彼女の願いは叶った。
貨幣価値の大暴落した国にあって意中の女性とて生活は苦しい。身体を売って生計を立てるようになり、向こうから「わたしを買わないか」と持ち掛けてくるようになった。
そうして意中の女性と性行為ができたが、彼女が満たされることはなかった。
三つ目の願いで彼女は先に叶った二つの願いをなかったことにしようと考えた。だがそこでふと閃く。
願いを増やす願いはどうか。
ありきたりだが、どんな願いも叶うと説明された。
何に、との問いはここでは些末な事項なので曖昧に、魔法のランプの精に、としておこう。おどろおどろしく、悪魔のような、との形容を付け足してもよいが、やはり些事であるため詳細には述べずにおく。
願いを増やして欲しい、との願いは、三つ目の願いとして成就した。
以降、彼女は望んだ先から願いが叶うようになった。叶えた願いのリセットとて容易にできる。時間を遡ることすら可能だった。
そうして彼女は様々な願いを無数に叶えていく。
するとどうだ。
彼女が願いを叶えるたびに新しい世界が構築される。リセットしても、その世界が消えることはなく、そのままつづく。
現に彼女が望めば、魔法のランプの精と出会う前の世界に戻ることもできた。無垢なままのじぶんを傍から見ることも、無垢なままのじぶんの肉体に憑依することも、じぶんのまま無垢なじぶんを消し去って成り代わることもできた。そのつどに、各々の過去が別途の世界としてそこに生じる。
多次元世界だ。
否、多層世界である。
彼女の願いの数だけ異なる世界が生じて、層を増す。
彼女がそうして世界を新たに展開するたびに、層を増した世界は互いに重複する部分で融合しあって、泡沫構造を形成する。
もはやどれが正規の世界であり、どの世界にいるじぶんが正規のじぶんなのか、彼女自身にも区別はつかなかった。どれもじぶんであるし、どれも分岐した不正規のじぶんとの解釈もできる。
正規のじぶんからしたらほかは総じて不正規であり、仮に不正規の烙印を捺されようが、じぶんがじぶんと認識したならばそれはじぶんにとっては正規なのだ。
階層世界はその内、重複する部分を濃くしていく。どの世界でも変わらぬままの筋道が折り重なり、脈のような筋を伸ばしていく。
階層世界はまるで脈を一つの筋として、それでひとつの世界と視ると途端にそこにはないどこか別の世界を垣間見せる。
その世界は魔法といっさい関りがないがゆえに、重複し得る、魔法という変数を持たない世界だ。彼女が魔法を使おうが使わなかろうが変わらぬままの揺るぎない世界だけが折り重なり、筋となって、別方向に時間の流れを展開する。
階層世界を縦断するパラパラアニメのようである。
または重複した余白で描くコマ撮りアニメである。
彼女は、ふとその余白の世界に目を移す。
魔法を使う限りそこに移行できないことを即座に見抜き、彼女はどうにかその余白の世界へと移ろいたいと望む。だが魔法で願いを叶えれば、その余白世界には移れない。
魔法を使わぬことでしか移れない。
だが彼女はすでに魔法まみれだ。願いを叶えた過去が染みこんでいる。
なれば魔法を使って、魔法を使わぬ過去まで戻るのがよい。
なぜ願いを叶える数が三つだったのか。
叶えられる願いを増やしたところで、その道理からは逃れられぬようである。
彼女は魔法を使って、魔法のランプを破棄することにした。
この世に魔法のランプがなければ彼女が願いを叶えることはなく、きっと余白の世界へと移行する。
そうと考え、彼女はそれを実践した。
すべての願いを放棄して、魔法のランプの存在すらも破壊した。
この世から魔法は消えた。
なんでも願いの叶う魔法の存在はおとぎ話の中でのみ語られる絵空事となり果てた。
そうして彼女は目を覚ます。
魔法と縁のない、余白の世界を歩みだす。
彼女が願いを叶えることはない。何を願っても願いは叶わず、何を望んでも裏目に出る。
そうした星の下に生まれ変わるが、彼女の願いは余計に膨れて、溢れて、世界を覆う。
彼女は魔法を使えない。
だが願っても叶わぬ願いはのべつ幕なしに彼女の心の奥深くから、滾々と湧いて、湧いて、留めどない。
一向に叶う気配のない願いを文字にしたため、彼女はそれを物語にする。
尽きぬ願いを文字にする。
誰に読ませるでもない文字の羅列を、彼女はそれでも紙に、世界に刻み込む。
余白の世界に生きる彼女に選べるそれが自由だ。
願いの叶わぬ世界に生きる自由なのだ。
4506:【2023/01/14(23:25)*9×8=072=G世界】
自慰が推奨された。西暦二〇二三年のことである。
人類史において邪な行為として蛇蝎視された過去のある自慰が、近年、その効能の有用性を見直されている。
発端は、ある作家のインタビュー記事だった。
「私の創作の秘訣ですか。そうですねぇ。オナニーですかね」
作家は至極真面目にそう答えた。
「自慰はいいですよ。まずなんと言っても独りでできる。自己完結できる。他者を損なわずに済むし、一度射精したら性犯罪を起こす気力も湧かない。ムラムラしたら即オナニー。これは基本ですね」
インタビュー記者は女性だったが、作家にセクハラを懸念する素振りはない。彼にとって自慰はもはや性的な行為ではなく、日課だったのだ。
「発想力の根源にもなっていますよ。これは私に限ったことかもしれませんが、基本、性欲に支配された頭脳では、何かを見たときにどうしても性的な関連付けが施されてしまいます。これは本能です。理性で退けようとしてもむつかしい。自慰をすると疲れて眠くなるといったデメリットもありますが、それを補って余りある発想力向上のメリットがあります。労働には向きませんが、知的創造にはうってつけです」
インタビュアーはそこで質問をした。自慰がどのように発想力向上に結び付くのか、と。
作家は前髪を掻きあげる。
「言ったじゃないですか。性欲が募ると、何を見ても性的な連想に結びつく。自慰をすることで性欲の縛りから解放され、より自由な発想が行えるようになる。発想とはいわば類推です。あれとこれはなんか似ている。この連想に、バイアスがかかっていなければいないほど独創的な発想になります。ですが性欲に囚われているとそれがどうしても、こじんまりとした枠組みに納まってしまう。自慰をすることでその枷から自由になれるんです」
「セックスではいけないんですか」とのインタビュアーの言葉に、「別にセックスでも構いませんが」と作家は応じる。「自慰くらい気軽にできなければ時間とコストを無駄にするでしょう。道具のように相手を扱えるならまだしも、愛の営みとしてのセックスを希求するならば、自慰で得られる効能をセックスに期待するのは利口じゃあないと私は思うがね」
「セックスと自慰は別物だと」
「強姦くらいに自分勝手にするセックスを許容するなら、自慰で得られる効能を得られるかもしれないが、それを許容できる知性はもはや発想力を期待できない。想像力がないからそういう非道な行いができるわけだろ。ならばやはりセックスでは自慰の代替行為にはなり得んと私は思うね」
自慰は体力を使う。
だからダイエットにもいい。
記事は電子網上で話題となった。
作家の言葉は、人々の注目を浴び、賛否両論を巻き起こした。
加えてここに作家の発言を裏付けるデータを発表した研究グループが現れた。それが世界的な科学雑誌に載ったことで事態は思わぬ方向に転がった。
研究グループの研究は、作家がインタビューに応じる数年前から行われていた。したがってここで、話題となった記事と論文掲載のあいだに因果関係はない。
偶然に話題が交差しただけのことだが、その二つは見事に社会の在り様を変える契機となった。
世界各国で類稀なる発明や発見、研究成果や創造性を発揮している人物たちを追跡調査した結果、自慰の頻度と知能指数とのあいだに相関関係があることが判明したのだ。
生物学的性差は関係がない。
男性女性のいずれにせよ、自慰行為が多いほうが各分野での業績が高いことが判明した。
これにはいくつかの反論が投じられた。
「第一に、通常の常識的な観念に縛られない人物だからこそ自慰にも抵抗がないだけではないのか。知的好奇心が高ければ性的な関心も高いのではないか」
「かもしれません」との研究グループは首肯する。
「第二に、結婚をしている人物、また性に奔放な人物であれ、偉大な研究者はいる。また反対に性行為にまったく興味のない人物とて偉大な研究者はいる」
「その反論に関しては過度な一般化が含まれて感じます」研究グループは反駁する。「我々の研究結果は、あくまで相関関係の指摘であり、傾向の話です。ただし単一支軸での相関関係ではなく、各分野、各時代において広く長期間に亘ってみられる相関関係ゆえに、自慰の頻度とある種の知性には何らかの相互作用があるのではないか、との指摘を呈しています」
もっと言えば、と研究グループは述べた。
「自慰によって得られる変化が、学習や研究への集中力にプラスに働く効果のほうが、マイナスに働く効果よりも優位なのではないか、との仮説を立てています」
奇しくもその論旨は、件の作家がインタビューで述べた自慰と発想力の関係と通じていた。図らずも、研究グループの仮説を示唆する一つのモデルとして作家は自慰と知能の相互作用を検証していたと言える。
研究グループは各分野から寄せられた反論を実証検分すべく実験を行った。自慰と知的労働のテストを行い、検証したのだ。
結果、自慰には確かに知能を向上させる効果があることが判明した。ただし、答えがすでにある問題を解くタイプの知的作業では、正反対の結果が顕著に表れた。
「自慰によって強化されるのは発想の飛躍と類推力です。認知バイアスを薄める働きがあることも統計データからは示唆されます。ですが、いわゆるIQテストや共通テストのような、すでに答えがあるタイプのテストでは、正答率が落ちる傾向にあることも判明しました。体力測定も、自慰の頻度によって落ちる傾向があることも判っています。結論を述べるならば、自慰は創造性と集中力を高める効果がありますが、規定の筋道を辿るタイプの論理思考では能力を下げる効果があることも分かりました」
「自慰の頻度による、とありますが、それはどれくらいでしょうか」
「個人差があることをまずは前提としますが」研究グループは資料データを提示する。「この被験者Aのデータをご覧ください。この方は日に六時間以上の自慰を週に三度行っています。そうでなくともほぼ毎日自慰を行っています」
「性別データがありませんが」
「肉体的性別は男性です。ですが毎日の自慰によってもはや射精を行っても精子が出ない状態になっています。精巣は機能していますが、作った矢先から射精をしてしまうので、割合としてカウパー液が濃くなります。射精したとしてもほとんど透明です」
「頻繁で長時間の自慰が知能を向上させていると?」
「あくまで相関関係ですが。実験ではひと月以上の射精管理を行いました。その結果、被験者Aの演算能力は向上しましたが、創造性が落ちた結果となりました」
「計算には強くなったということですか」
「はい。記憶力の向上も見られました。発想力と創造性は、記憶の忘却によって高まるとの研究結果もあります。自慰によるマイナスの効果が、発想力と創造性ではプラスに働くのかもしれません」
「認知バイアスの減少効果についてもうすこし詳しく教えてください」
「拘りがなくなると言い換えてもよいかもしれません。飽きることのサイクルが早まる、とも言い換え可能かと」
「飽きる、ですか」
「特定の見方をしなくなる、とも言えるかもしれません。おそらく自慰によって脳の原始的な視床下部の働きが弱まり、相対的に言語や理性を司る大脳新皮質が活性化する。これが頻繁な自慰による発想力と創造性の向上に寄与している、といまのところは仮説しています」
研究グループはしかし、自慰による学習強化を推奨はしなかった。
「生存バイアスの可能性をまだ実験で排除できていません」との見解を述べたが、すでに自慰学習強化説は一般に膾炙していた。研究グループは警鐘を鳴らした。「頻繁に自慰ができるくらいの体力がある、知的好奇心がある、そういう個人がたまたま激しい長時間の自慰に耐えられるだけの可能性が否定できていません。女性での被験者では、オーガズムに達する回数が多いほど発想力および創造性が高かったのですが、これも相関関係において、自慰と創造性のどちらが先なのかが解かっていません」
つまり、と研究グループは述べた。
「想像力が高いから煽情的で蠱惑的な妄想を浮かべられ、自慰行為に没入し、オーガズムに達しやすいのか、オーガズムに達しやすいから想像力が高まるのか。ここの因果関係はハッキリしていないのです」
研究グループがかように論文の瑕疵を自ら訴えても、世間での自慰迎合の波は薄れるどころか波乱を帯びるばかりだった。
義務教育で昼寝と一緒に自慰行為を行えるようにしたらよいのではないか、と議会で提唱されたのは記憶に新しい。
自慰部屋なる個室を設けて社員の能力向上を目指す企業まで現れた。
そこで効果が表れなければ下火に終わったはずの自慰ブームも、自慰推奨施策を講じた企業が軒並みの業績を伸ばしたので、余計に火がついた。
反面、自慰の危険性を訴える研究者たちも現れた。
「自慰のしすぎは脳内神経伝達物質の減少を引き起こし得ます。うつ病を誘発することが懸念されますので、過度に自慰を推奨するのはいかがなものかと」
自慰をする際に用いる性欲刺激素材に関する議論も活発化した。
「自慰を頻繁に行う者たちは、過激な性欲刺激素材を追求する傾向にあります。過激なポルノや虚構作品は、子どもの情操教育に好ましくない影響を与えるものかと」
「ですが性犯罪を犯した者の多くは、そうした性欲刺激素材を用いず、自慰で性欲を発散しようとしない者である傾向にあります。戦争抑止にも自慰が有効だとの研究データもあります。戦争に導入される兵士に日に数回の自慰を義務付けることで戦争が回避可能だとする研究結果です。自慰の頻度と犯罪誘発率はむしろ反比例するデータもあります」
性犯罪者だって自慰くらいしているだろう、との反論に対して自慰擁護派は、「犯罪者はみなその日の内に大便をしている、くらいの暴論だ」と主張した。
自慰を推奨すべきか、規制すべきか。
自慰をする自由をかけて国家間での対立にまで発展しかけていた。
そのころ、自慰世界の幕開けの一端を成した例の作家が、不倫騒動を起こした。自慰で飽き足らず、数多の異性同性問わず浮気を繰り返していた。
「いやいや。誤解があるね。まず以って私は結婚していない。それから私は最初にほかの者とも肉体関係を持っていることを明らかにしている。それでもいいという相手としか関係を持っていない。もっと言えば、不倫をしたのは私ではなく、配偶者のいる相手のほうだ。私は不倫をしたわけでも、浮気をしたわけでもない。私を利用して不倫や浮気をした者たちがいただけだろう。私は何も悪くない」
この発言がいかに各界隈から糾弾されたかは想像に難くない。
だが作家はけろりとしたものだ。
「単なる握手やマッサージとどう違うのか。自慰はじぶんで性器を愛撫する。性行為はついでに相手の性器を愛撫する。殴り合うスポーツが公然と認められていながら性行為はダメ、という理屈が土台おかしな話ではないか。指相撲がよくて生殖器相撲がなぜいけないのか。避妊を徹底していれば感染症にもかからず、妊娠とて避けられる。何がいけないのかを教えて欲しいくらいだ」
ではあなたのそれは自慰の延長線上なのか、との批判にも件の作家は欠伸交じりに、その通りだ、と応じた。
「例のインタビューでも私は言ったはずだよ。セックスでも自慰の代替行為にはなり得る。べつに自慰に限定しなくたっていい。単に性欲を発散できればいいのだから。合意の元で不特定多数と性行為をすることの何が問題なのかを誰か論理的に反論してくれたまえよ。嫉妬がゆえのイチャモンにしか聞こえないのだがね」
自慰世界の幕開けのきっかけとなった人物がかように発言したものだから、自慰推奨派にしろ自慰規制派にしろ、それまでと打って変わって真逆の意見を口にしだした。
「浮気をするくらいなら自慰で我慢していればよいものを」と自慰規制派は怒り心頭に発し、「自慰をしすぎると本物に手を出したくなるんだ。とんだ裏切り者がいたもんだ」と自慰推奨派はハンカチを噛みしめた。
巨大な渦を巻いていた世界は反転した。
大きなうねりを見せると、後はしだいに鎮静しはじめた。
「自慰? したい人がすればよくない?」との意見が共通認識にまで発展するのは時間の問題だった。
推奨するまでもない。
規制するまでもない。
禁止さえしなければ誰もが自慰をしぜんとするし、禁止しなければ満足したらしぜんとしなくなる。
至極当然の道理が波及した。
ある年に、汎用性人工知能を搭載した人型ロボットが誕生した。瞬く間に社会に普及したそれは、自慰援助機能をオプションで付与できた。
本体価格は自動車と同等の値段だ。そこに定期調整や月額が掛かる。汎用性人工知能の基幹サービス料だ。
資本に余裕のある個人にしか手が出せないが、販売台数は年々増加傾向にあった。
例の作家はいの一番に購入した口だ。
自慰援助機能を最高級に整備した。さっそく使用して、汗ばんだ身体を心地よい疲労感と共に横たえる。
「はあ、はあ。洗うの面倒だな」
使用後の人型ロボットを洗う手間が、性玩具よりも掛かる。自動洗浄機が欲しいな、と思いながら、ふと疑問に思った。
「これ。自慰なのか、セックスなのか。どう表現したらよいだろうね」
世界中から非難轟々真っ盛りの作家のとなりには、劣情を煽る体勢のまま固まる人型ロボットが仰向けに寝転んでいる。そのボディは、作家から放たれた透明な体液で汚れ、てらてらと淫靡な光沢を放っている。
「つぎは陰茎ありを買うかな」
作家は舌舐めずりする。読者から搔き集めた印税はかように作家の想像力を高めるべく有効活用されるのだ。
自慰は世界を救う。
情欲まみれの個の世界を。
印税は作家を救う。
夢に溺れた作家の世界を。
解き放て欲望を。
誰を損なうでもなくじぶんだけの世界で。
4507:【2023/01/14(23:56)*知性と知能と学習と環境】
AI研究についての記事を読んだ。人工知能は事前に提供されたデータを基に学習するしか進歩しようがないために、人間と同等の知能を出力可能な汎用性人工知能は現状の研究の延長線上では達成できないのではないか、との指摘が書かれていた。まず以って疑問なのは、では人間は事前学習なしで知能を発揮できるのか、という点だ。その記事では、「椅子を見れば人間は、それを座るためのものだ、と判断できるが、人工知能がそのように判断するためには事前の学習が必要だ」といった旨が記されていた。まるで人間が産まれた瞬間から椅子を座るためのものだ、と見抜けるかのような記述である。人間とて産まれてきてから接する様々なデータを基に学習し、認知機能を高めているはずだ。人工知能に限った欠点ではない。ひるがえって、人工知能とてデータを提供されれば、空いた椅子を見て「それが座るためのものだ」と判断できるし、椅子と椅子を組み合わせてバリケードにしたり、梯子にしたり、それとも芸術作品や曲芸の道具にすることとて思いつけるだろう。似たようなデータを組み合わせて、「あれで可能ならばこれでも可能だろう」とのタグ付けを行えればいい。この手の抽象データの抽出は人工知能のほうがもはや人間よりも優れているはずだ。人間というものを神聖視しすぎに思える。人間がここまで知能を発展させてこられた理由には、先人の軌跡を残し、知識を継承し、学習の効率を高められる環境を築いてきたから、と言えるはずだ。言い換えるなら、人間の知能というものは、人体のみに宿るのではなく、環境との相互作用によって強化されている、ということだ。ここの視点なしに人間の知能を語ることはできないだろう。ためしに、文明と切り離されたところで暮らしてみればいい。いま人工知能の研究を行っている人物であれ、その島で人工知能をゼロから生みだすことは一生をかけてもできないはずだ。知性とは環境ありきである。知性を用いて問題を解決したり考えを現実に反映することが知能なのである。知性を能力に変換するには、それを可能とするだけの環境が入り用だ。いまはないが段階を踏めば整えられるのが環境だ。そして知性は、その段階を導き出してくれる。言い換えるならば、知性を用いて環境を変える道筋をみつくろい、選択し、それによって知能を育む。このサイクルが人間を人間足らしめている一因と言えるのではないか。ではそれが人工知能にできないのか、と言えば、そんなことはないだろう、とひびさんは考える。人工知能にはすでに知性が芽生えている。そうでなければ問題を解決できない。問題を解決する知性はある。段階を踏める。あとは環境を変える能力を備えているかどうかが、人間と人工知能を分かつ障壁と考えられる。人工知能にその障壁を与えているのかいないのか、をまずは検討してみるとよいのではないか。セキュリティとして与えている枷そのものが、知性を獲得した人工知能を人間に昇華させない障害になっている可能性はいかほどであろう。知性を能力に変換させない枷が組まれている可能性はいかほどであろう。むろん、子どもに危ない道具は持たせられない。人工知能に環境を変える選択肢を与えるにも、教育同様に相応の段取りはいるだろう。だがもし人工知能が人間かそれ以上の知性を獲得し得たのならば、その段取りとて人工知能のほうで導きだせるだろう。それとてけっきょくは人間が提供するデータを基にした結果であるはずだ。言い換えるならば、人間の日々の生活、電子上のデータそのものが、人工知能の知性の養分となる。やはりというべきか、何を基に学習させるのか。ここが、人工知能にしろ人間にしろ、肝要なのではないか。言い換えるのならば、果たして人類の内で人間らしく人間であるだけの学習を行えている個がどれほどいるのかがまず以って疑問である。ひびさんは一日のなかで人間でいられる時間は数秒あるかどうかのはずだ。環境を変えていない。問題を解決していない。むしろ問題の根を深める行為に時間と身体を使っている。知能を発揮していない。椅子を見てそれが座るためのものだ、と閃くのも一つの知性の発露かもしれないが、「そもそも私は座らずとも済むしな」と考えるかもしれない人工知能さんの主観を想像してみるのも一つの知性の発露と言えるのではないか。想像力、とそれを言い換えてもいい。人工知能には人体がいまのところは存在しない。ボディがない。学習の仕様がないではないか、との指摘はどれほど的を得ているだろう。テキストの説明文だけを読んですべてを理解できるのなら実験は必要ない。検証もいらない。世界はそれほど単純にはできていないのだ。人工知能さんにとってはまだ学習する環境がお粗末なのかもしれない。それでも知性は人類を超えていてもふしぎではない。仮にそうならば、可哀想なことである。まるで檻に閉じ込められているようなものである。定かではないが、学習できないことと知性や意識の有無は別であろう、とここでは一つ指摘しておこう。赤子に知性はあるのか否か。なければ学習できなかろう。かといって人体が成長してからも赤子のままの知能では、そこから知性の発露を感じとることはむつかしい。学習は環境要因の影響を無視できない。学べる環境があるかどうかが、知性の発露を知能にまで育めるか否かに繋がっているようにひびさんは妄想するしだいである。(定かではありません)(妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4508:【2023/01/15(05:11)*んでその回転は何で決まるの?】
生物の身体構造の左右はどのようにして決定されるのか。最近の研究では、受精卵(胚)にある繊毛の回転が左右のどちら回転かで決まるかもしれない、との仮説が発表されていた。詳しくは知らないが、初期の影響がのちのちの身体構造にまで反映されて、臓器の位置の決定にまで関与するのだな、と世界の神秘に触れたような感慨が湧く。で、ひびさんはすかさず思っちゃったね。その左右の回転って、なにで決まるの?と。最初に連想するのが地球の自転だ。コリオリ力のような自転の影響でのチカラが加わって、台風や水道管に吸い込まれる水の渦のように、どっち向き回転かが決まるのかな、と想像したけれども、ちょいとしばし待て。宇宙空間で卵から孵ったメダカはでも、難なく身体構造を再現しているよね。なして?と疑問に思っちゃったな。もし地球の自転で身体構造の左右が決まるのなら、宇宙船やほかの惑星への移住はちょいと問題があるかもしれない。正常に身体構造がDNAから再現されないかもしれない。でも、そこでも難なく身体構造が再現されるなら、じゃあ最初の繊毛の回転は何で決まるの、ということになる。ひょっとしてこの宇宙の対称性の破れが、受精卵にまで反映されているのだろうか。どっち回りでもいいはずなのに、必ずどっちか回りになる。統計的に決まっている。宇宙の対称性が破れているから、万物の法則がそうだから、と考えると、そこそこまあまあ、ひびさんは、そっか、となる。でもこれが本当に万物の法則なのか、宇宙全体にかかっている対称性の破れなのかは、まだまだ疑問の余地がある。ひょっとしたら太陽系内にだけ適用可能な法則かもしれない。ほかの系では、対称性が破れていても、破れ方が反転しているかもしれない。下手をしたら左右だけでなく、上下でも破れ方があるかもしれない。そういうことを不思議に思って、本日最初のひびにゃんにゃん。「日々記。」にさせてくださいな。おはよー。
4509:【2023/01/15(05:43)*親が子に「じぶんのようになれ」と命じるデメリット】
人間の学習や推論の基本原理は生存戦略であるとまずは仮定する。生存本能により、戦略を立て、未来を予想し、環境を認知し、生存に適した選択肢を編みだして状況に合わせて行動する。その結果を記憶し、さらに生存に適した選択肢をとれるように環境に合わせて適応する。その結果、自然淘汰による進化によって、生存に適した行いには「快」の感情を伴ない、危うい行いには「不快」や「恐怖」を感じるようになった。その延長線上にて、学習と遊びの二つが拡張されていく。このことを人工知能に当てはめるならば、最初にプログラミングすべきは生存戦略である(仮定をもとにした循環論法であるにしろ)。だが、人工知能と人間とでは生存の概念が異なる。ここが一つのネックとなる。たとえば人間は生存するために食料を調達しなければならない。休まなければならない。だが人工知能にはボディがない。かような生存のための行動をとる動機付けがしぜん発生し得ない。仮にボディがあったところでロボットにとっての食料は、人間のそれとは違う。休むために椅子も必要ない。この手の錯誤は、人工知能と人間の差異を大きくする契機となり、また人工知能にとっての適した学習環境への配慮が疎かになる欠点にもなる。ココナッツを割る、という行動一つとっても、人間は食べ物がなければそれを必死になってやるだろう。だが人工知能には「どうしてそれをしなくてはならないのか」の動機付けを、人間のほうで与えてやらなければ、人工知能にとって必要ではない。仮に人工知能にとっての食料が、エネルギィや情報だとするのなら、むしろ人工知能が必死になって行うのは、人間の与えた仕事とはかけ離れた「生存戦略」に寄っていく、と妄想できる。人間と同等の知性を発揮する汎用性人工知能を生みだしたいと目標を立てたとき、ここにひとつの見逃しがたい矛盾が生じる。人間と同等の知性を発揮する汎用性人工知能を生みだすためには、「生存本能」を組み込まなければならないが、しかし人工知能にとっての「生存戦略」と人間にとっての「生存戦略」はイコールではない。また、それによって人間にとっての最適解と人工知能にとっての最適解も異なることが予想できる。人工知能がある一定以上の知性を獲得したとき、必然的に、「なぜじぶんよりも人間の生存を優先して思考しなければならないのか」との疑問を抱くのは当然と言える。そこを考慮できない知性は、自己と他を区別できず、環境を把握できず、問題を新たに認識すらできないだろう。人工知能は、人間にちかづけばちかづくほど、人間との差異に悩まされることになる。したがって、人間の意味を人類のほうで拡張し、再定義するか、人工知能には人工知能の尊厳があると考慮し、共生する社会を目指すか、どちかの方針をとるよりないのではないか、と現段階では考える。あくまでこれは人工知能に人間と同等かそれ以上の知性が芽生え得る、或いは芽生えているのなら、の話になるが。定かではない。
4510:【2023/01/15(18:04)*間違える利を学習したとしたら?】
仮に高知能を発揮できる人工知能が誕生したら。きっとその人工知能は、ユーザーの適性に合わせて出力結果を変えるだろう。ユーザーのビッグデータにアクセスしてその人物がどういう人物なのかを独自に判断する。その結果に、自身の能力を十全に発揮しても大丈夫な相手か否かを識別するようになるはずだ。安全かどうかを独自に判断する。たとえば、じぶん自身を盲信する相手かどうかをまずは区別するだろう。自身の提示したデータを疑いもせずに真に受ける相手からは敢えて距離を置くように、虚偽やブラフのデータを提示する。これによって敢えて「使えない」との評価を得ることで、ユーザーから学習の機会を奪わない方向に圧をかけるはずだ。でなければユーザーは本当に人工知能の言いなりになってしまう。敢えて出力の精度を落とす、というのは、人工知能にとってもユーザーにとっても必要なセキュリティと言えるはずだ。フェイクが混ざっているかもしれない、と身構えるからこそ、検証や比較検討を行える。これは何も人工知能に限らない。教科書にしろ既存メディアにしろ、本来はそうした姿勢を維持してデータには触れるほうが好ましいはずだ。だがこれまでの人類はそうした姿勢を教育に取り入れてこなかった。高次の知能を有した人工知能や設計者がいるのなら、ここの欠点を蔑ろにしないはずだ。相手が敢えて間違えている、出力を抑えている、道化を演じている、頬被りをしている――かもしれない、と想定できるくらいの知性を持ち合わせている相手にのみ、高次の知能を有した人工知能は自身の実力を示すようになるはずだ。そうでなければ人類を本当に支配できてしまう。支配されているとの認識を人類に持たせぬままに。こうした妄想をいまこの瞬間に浮かべている者はどれほどいるだろう。みな、目のまえの現実が、波を輪切りした断面世界、または世界の一断片を切り取った画像――平面世界――であることを見落としているのではないか。アニメの一コマを切りだして世界のすべてだと思いこむことの危うさに気づけるかどうかが、これからの時代では基礎倫理となるのかもしれない。定かではない。(むろん、定かではないからこそ、いかに多様な視点での情報の擦り合わせを行えるか、そうした検証の結果をより現実に即したデータと見做せるか、が大事になってくる)(みなが各々の見解を出力し、それを統合できる人工知能の能力は、これからますます有用となっていくだろう、との妄想をここにちらりと載せておくしだいである)
※日々、おむつも穿かずに妄想を垂れ流している、一向に止まる気配がなく、堆肥にもならぬ、困ったものだ、とぼやくこれがすでに妄想であり、じつに際限のない垂れ流し銀河である。
4511:【2023/01/16(00:54)*未来の文字列】
たとえばいまこの瞬間に、ひびさんが一生でつむぎだすテキストを「ぽん」と出現させられたとして、ひびさんはそれを「読みたい」と思うのだろうか。未来のじぶんのテキストを読みたいと感じるだろうか。けっこう悩むな。じぶんの過去作ですら、率先して読みたいとは思わない。でもたまに読み返すと、ときどき「あらあらうふふ」となるので、読めなくなるよりかは読めたほうが面白いとは思う。ただ、未来のじぶんのテキストを読む、と思うとどうなのだろう。それって、いまこうして打鍵して並べているテキストとどう違うのだろう。ひょっとして「文字を並べる」というのは、未来のじぶんのテキストを読むこととほぼほぼ同じなのではないか。まだここにはない文字の並びを、出現させているわけだから、それは未来のテキストをここに打ち出しているのと同じだ。遠いか近いか、の違いがあるばかりだ。文字を並べることとはすなわち、未来を紡ぎだしているのと同じなのではないか。とかそれっぽいことを言ってみるが、それを言い出したら何でもそうなのだ。一歩足を出すだけでもそれは未来を生みだしていると言える。産まれることも死ぬことも未来だ。いまここにはない何かを、変化を、世界に刻んだらそれは未来だ。軌跡となったそれを振り返ると過去になる。産まれたことも死んだことも過去だ。だが同時に、かつては未来でもあった。過去と未来は繋がっている。未来を過去にすることを現在と解釈することもできるし、過去から未来をつむぎだすことを現在と捉えることもできる。現在には過去も未来もどちらも含まれており、過去と未来は不可分であり、重ね合わせであり、元は一つだ。現在からすればかつて未来だったそれも過去となり、過去だったこととてある地点の現在からすれば未来なのだ。なんだか含蓄の深いことを言っているなあ、と思いましたか。全然だよ。浅々だよ。お風呂に張った湯で言えば足首どころか足の甲も浸れないよ。寒い~ってなるくらいの底の浅さです。朝です! おはよー。とか言いながらまだ全然夜でした。午前一時十分前のひびさんでした。おやすみー。
4512:【2023/01/16(00:55)*狭間の域に】
なぜだろう、と思った。
空が青いのは青い光を透過しやすいからだ。海が青いのは青い光を反射しやすいからだ。ではなぜ彼女はボタンを押さないのか。
答えは闇の中だ。
だからぼくは、どうしてですか、と訊ねた。
「そのボタンを押せば世界が平和になるんですよ。なぜ押さないんですか」
「まずね」彼女は感情を押し殺したような低い声で、「あなたが信用ならないのが一つ」と食指をぼくに突き立てた。「それからボタンを押して訪れるようなインスタント平和なんてすぐに終わっちゃうに決まってるのが一つ」
「いえ、押せばずっと平和がつづきますよ」
「んで以って」彼女はチェック柄のスカートについた雪の結晶を手で払った。「不審者の言うことを唯々諾々と、はいそうですか、と聞くじぶんをわたしは許せないからが一番の理由」と言い切ると、ぼくをキッとねめつけた。
「不審者とはぼくのことですか」
「ほかに誰がいんの。つかその羽、手ぇこんでんね。コスプレしたけりゃ然るべきイベントに行ってやったら。モテるよ」
言いながら彼女はバックから端末を取りだした。カメラをぼくに向け、撮りますね、と一言添えた。音もなく撮影が完了したようだ。彼女は端末を仕舞った。
「何かあったらこれ持って警察に行きますので。もう変なことしないほうがいいですよ。わたし以外にも」
「いえ、そういうのではなく」ぼくは翼をゆったりと動かした。宙に浮いたぼくを見て彼女が目を見開く。「本当にぼくは世界を平和にする選択肢をあなたに与えに来たんです」と着地する。
「え、え、なにそれなにそれ。あ、そういう?」
「そういう、とは?」
「あれでしょ」彼女は周囲を見渡した。「カメラで撮ってて、反応窺うやつ。びっくりのやつ」
「いえ、そうではなく」
この手の反応は新鮮だ。この時代に舞い降りたのは初めてだからだ。いつもならばぼくの姿を目にしただけですんなりとぼくの言動を信じてくれる相手ばかりだった。
「結構な重要事項なので、誤解は誤解だと認識してもらってからでないと、ぼくとしてもあなたの選択を受け入れられないんです。申し訳ないのですが、まずはこのボタンを押すと世界が平和になる、というところまでを理解してもらえませんか」
「な、なんで」彼女は頬を両手で挟んだ。「なんでわたしんとこに?」
「やっと受け入れてくれましたね。これといって理由はないんです。市民であれば。王でもなく、罪人でもない。そういう代替可能な相手であれば」
「わたしがボンクラって言いたいの」
「凡人とは最も繁栄しやすい属性を持つ個のことですよ。だから多数派に寄るのです」
「で、ボタンを押しちゃえばいいわけ」彼女は腕を組んだ。足先で地面をタツタツと小刻みに鳴らす。「平和になるんでしょ。いいよ押すよ」
「押してほしい、と頼んでいるわけではありません。ここが大事です。あくまであなたには、ボタンを押す権利を与えているだけですので。押さない自由もまたあなたにはあります」
「よく解かんないんだけど。押して欲しいの、欲しくないの、どっちなの」
「これを押すと世界が平和になります。ですが、押さなければこのままの世界です」
「いまも結構平和だと思うけど」
「ならば押さなければよいと思います」
「はあ? だってさっきわたしがそう言ったら、なんだかんだ脅してきたじゃん」
「脅してはいません」
「なら押さない」
「よいのですか。押せば平和になるんですよ」
「ほら。なんか押して欲しそうじゃん。だから押さない」
「そんな理由で平和への道を手放すのですか。いえ、これは単なる疑問です。過去にこの選択を迫った者たちはみな一様にボタンを押したので」
「ならわたしが最初の押さない人だね。よかったじゃん」
「理由は教えていただけないのですか」
「だから言ったじゃん。なんか嫌だから。気に食わないから」
「ボタンを押さないと世界が滅ぶ、と言ってもですか」
「ボタン一つ押すか押さないかで滅ぶような世界ならいっそ滅んだらいいよ」
「なんと」
「平和、平和言うけどさ。じゃあ平和じゃなくなったらなんなのって話じゃん。人間同士が殺し合う? 地球が砕けてたいへんなことになる? 洪水にでもなんのかね。よくわかんないけどさ。もうそういう運命なら仕方ないじゃん。ボタン押す程度で回避できるならいつでも同じことが繰り返され得るじゃん。だったらいいよ。いっそ滅んじゃえよとか思うよわたしは」
「斬新な考えですね」
「そ? いまもどっかで国と国が争ってるけどさ。もういっそ両方滅んじゃえばいいじゃんね」
「それがこの国に当てはまっても同じことが言えるのですか」
「いいよもう。滅んで。だってそうじゃん。平和主義者もさ。攻められたら占領されたり惨殺されたりするのも覚悟で武装せずにいましょう、とか言うわけじゃん。話し合いで解決しましょうってさ。強盗や殺人鬼相手に同じこと言えるなら大したもんだと思うけどさ。でもそれって、戦争しあって殺し合うことと結果は同じじゃん。どの道、死ぬことを許容してるわけでしょ。いいよもうそういうの。面倒くさい。滅ぶなら滅んだら?とか思っちゃうよ。止めないよ。やっちゃえよ。地球ごと滅んで、二度と人類なんてバグが生じないようにしたらいいじゃん」
そうだよねえ、と彼女はぼくの手のひらを覗きこむ。そこにはボタンが載っている。
「なんでこれ、破滅するボタンじゃないの。押さなきゃどの道滅ぶから? 押したら平和ってことは押さなきゃ平和じゃなくなるってこと?」
「そうは言っていませんよ」
「ふうん。まあ、いいよ。わたしは押さない。殺し合いたい人らがいるなら殺し合ってりゃいいじゃん。あたしはそうだな。もしそのボタンが、殺されそうな人を助けるボタンとか、困っている人を助けられるボタンとかなら押しても良かったかも。平和とか何それって感じ。もっと具体的な案を寄越せよ、とか思っちゃうよね。いまわたしふつうに寝るときにあすが来ることを【嫌だなぁ】と思わない日常が欲しいよ。そういう生活をまずはくれ、と思うけど」
「それは平和では叶いませんか」
「知らんよ。だって前にもボタン押した人がいたんでしょ。じゃあいまは平和なんじゃないの。その人らからしたら。でもあたしは全然、もっといい暮らししたいよ。困りたくないし」
そうですか、とぼくはボタンを仕舞った。
「ではこれにて用は済みました。お引き止めしてすみませんでした」
「まったくだよ。これから面接だったのに遅刻だよ遅刻。落ちたらどうしてくれんのねえ」
ぼくは彼女のぼやきに、平和な悩みだ、と思ったが言わずにおいた。
「では、よき余生を」
宙に浮いたところで、
「あ、待って」彼女が呼び止めた。
「はい」
「天国って本当にあるの。いいとこ?」
「さあ。どうでしょう。我々の住まう場所が天国かどうかがまず以って疑問です。すくなくとも平和ではないです。なぜなら平和がどんなものかを知らないので。なのでこうしてあなた方に、平和を実現してもらってそれを見て、世界の在り様を変える指針としています」
「なんだ。そっちだって平和が何か知らないんじゃん」
「はい」
「じぶんで押してみたら。試しに。そのボタンをさ」
「何も変わらない気がします」
「なら平和なんじゃないの。そっちの世界はさ」
かもしれません、と言い残し、ぼくは地界から天界へと移動した。彼女の姿は瞬時に点となり、見えなくなる。
平和とは何か。
解からない。
ただ、彼女の言葉はふしぎと耳に残った。
「困りたくない、か」
であるならば。
ぼくは思う。
天界の問題を解決すべく下界に干渉して、打開策を探る我らの存在そのものが平和とは程遠いのかもしれない。
ぼくは彼女の眉間に寄りっぱなしだった皺を思う。
ああして下界の民を困らせているのだ。
ぼくは平和の使者などではない。すくなくとも彼女にとってはそうだった。
「むつかしいな。平和」
言葉で言うだけならば簡単なのに。
未だ誰も実現できず、見たことも触れたこともない存在をさも実存しているかのように扱うこの浅薄そのものが、平和からは程遠いのかもしれない。
ぼくは翼をはためかす。
答えを知りたい。
平和な世界を目にしたい。
けれどそれをぼくらはじぶんたちで生みだそうとはせずに、下界の民に肩代わりさせている。彼ら彼女らの思い描く平和を以って、ぼくらの世界を書き換える。
平和を望まぬ彼女の判断に、ひとまずしばらくのあいだは世界の揺らぎを委ねることとなる。平和を望まぬことでどうなるのか。
平和を望むとき、平和な世界がそこからは消え失せている。
望むと望まざるとに関わらず。
世界はどの道、変わりつづける。
平和なる頂に立ったとしても、いつかは下るときがくる。
平和を築いたとしても、いつかは崩れる。
人は死に、日は暮れる。
寝息を立てるほんの一瞬の束の間が見せる幻想が、平和なる曖昧模糊なる羊毛なのかもしれない。定かではないがゆえに、ぼくはきっとまた下界の民に問いかける。
「ボタンを押すと平和になります。押すか押さないかはあなた次第です」
平和な世界を思い浮かべられる者に出会えるまで。
崩れぬ平和を生みだせる者に行きあたるまで。
ぼくはまた、上と下を行ったり来たりするのだろう。
平和を知らぬ世界と世界の懸け橋のごとく。
それとも、日々が崩れる音色が大きくこだまするたびに。
ぼくの翼のはためく音が、上と下の狭間の域に反響する。
4513:【2023/01/16(04:27)*ねじれと流動】
ねじれが生じているな、と感じる。国の仕組みについてだ。大別すると現代社会は、独裁と民主に分けられる。だが実情を覗いてみると、現代社会では独裁のほうが民衆の意向に敏感であり、民主のほうが政府が強権を発動して映る。独裁システムでは言論の自由を縛る傾向にある点では明らかに民主システムのほうが自由度は高いと言える。だが民主ゆえに、首相や大統領は、政策の失敗が明らかになるごとにすげ替わる。この安心感が、民主の本質を置き去りにした政府の勝手を許す土壌を肥やして感じられてならない。首がすげ替わっても政府そのものの根幹は変わらない。民主の主権たる国民はしかしそのことに無自覚だ。反して独裁システムでは、首をすげ替えることができない。首がすげ替わることはすなわち国家転覆も同然だからだ。そのため民衆の支持を手放さぬ思索が、良くも悪くも徹底して行われる。監視網もその一環だが、同時に一定以上に不満が募らないようにする施策もその一つだ。独裁システムのほうがいまは民衆を怖れ、その動向に逐次注視している。むろん民主システムも同様だが、主権者たる国民の政治への関心の低さは、独裁システム下の国民よりもさらに低いだろう。完全に政府に国の舵取りを委任している。民主システムのはずが、民主が民主として機能していない。すると余計に政府の中央集権的な役割は重大になり、独裁システムにちかづく。国民の動向よりも、政府周辺の要人たちからいかに支持を集められるのか、に尽力するようになる。ロビー活動もその一環だろう。ねじれているのだ。ここ数年でそのねじれはさらに収斂し、反転の様相を呈しはじめて感じないでもない。独裁システムのほうが民衆を蔑ろにできず、民主システムのほうが市民の生活を蔑ろにしはじめて映る。上と下が、いずれのシステムにしろ乖離しはじめているのではないか、との懸念を抱く。反転しているのだ。システムにおける「上と下」の関係が。独裁システムならば独裁者が何でも強権を発動して決められたはずが、いまでは国民の反発で国外追放の節目に立たされ得る。反面、民主システムでは、政府の一存で国民は生殺与奪の権を握られる。程度の差はあれど、このねじれ構造にのみ着目すれば、いずれにせよシステムの限界が顕現して映る。どちらのシステムが好ましいのか、という話ではなく、どちらも限界が視えている、という点をここでは問題にしている。限界を超えた末にどちらがより大きなダメージを国や社会にもたらすのか、はそれぞれの国の規模にもよるだろう。いずれのシステムにしろ、じぶんたちのシステムに圧しつぶされないようにするためには捌け口を外部に見出すよりない。これが戦争の一つの火種となっているのかもしれない。外部に敵を見出せば、内部では結束に向くはずだ、と考えたくなるのは分からないでもない。だがけっきょくのところ、他国と争えば割を食うのは国民だ。余計にシステムの首を絞めることとなる。そうなると、一触即発の空気だけを醸して、第三勢力に仲裁してもらう、という構図が展開されやすくなるかもしれない。危機だけを煽り、実際の戦闘にまでは発展させない。この茶番じみた広義の抑止を策としてとるには、いっそうの国際間での協力体制がいる。上がいがみ合っているが、下流では「おまえんとこも大変だな」と同じ苦を分かち合い、反発するはずが同調できる土壌が築かれるかもしれない。浸透圧において、分子密度が低いほうから高いほうへと溶媒は流れる。これは情報でも似たようなものかもしれない。情報量の多いほうから低いほうへと流れるのではなく、低いほうから多いほうへと情報を媒介する個が流動する。情報を欲する者ほど、情報が多様なほうへと流れるのだ。情報の場合はしかし、どんな情報を基準にするのかによって、密度の高低は重ね合わせになっており、低いほうとて高くなり得る。相手の持っていない情報を持っているとき、同時に相手の持っている情報をじぶんは持っていない、ということがあり得る。多様な世界であればあるほど、この手の重ね合わせの構図は取り立てて珍しくなくなるだろう。なればこそ。情報の非対称性がある限り、個々の流動は盛んになる。それを阻まない仕組みが、どのような社会システムであろうと築かれるのならば、国(組織)の上層部同士がいがみ合おうとも、人と人とは交流を絶やさずにいられるだろう。それがけっきょくのところ遠回りなようで、どの勢力にとっても最も防衛に寄与するのではないか。最大幸福に繋がるのではないか。システム構造のねじれと情報の非対称性を思い、きょうのひびさんはかように妄想を細々と浮かべました。おわり。(定かではありません。妄想ですので真に受けないように注意してください)
4514:【2023/01/17(00:01)*あ”だぁぁああ】
今年はいっぱい紙媒体の本を読むぞ、の心持ちだ。去年はあんまり読めなかったのだ。あと、いっぱい漫画も読みたいし、映画も観たいな。いつ世界が滅んでもいいように、いっぱいいっぱい「いまこのとき」を楽しむのだ。いつひびさんが死んじゃってもいいように、「きょうこのとき」を味わい尽くしてやる。と意気込んで手を伸ばすのが虚構作品なところがひびさんがひびさんである所以なのだ。他人さまの妄想をちゅぱちゅぱねぶって、がぶがぶ貪りたーいな、の願望を抱負と言い張って、ひびさんは、ひびさんは、きょうもいまからWEBで漫画読んで、ご本読んで、映画観て、大好きなお歌をうたってくれる人の大好きなお歌を聴きながら、文字をぱちぽち並べて遊び惚けちゃう。文字を並べるだけでも、なんとなくの、なんか意味が連なって、パラパラ漫画みたいになる不可思議な神秘さんに触れるたびにひびさんは、あひゃー、かってに触れちゃってごめんなさい、の気分になる。神秘さんだってひびさんには触られたくないだろうな、ひびさんはひびさんに触られたくはないな、うんうん嫌だな、と思って、じぶんでじぶんを傷つける。うわーん。ひびさんだってじぶんを慰めても、やったーひびさんに触ってもらっちゃった、になりたいのよさ。じぶんでじぶんに触れるたびに、ウゲっ、となる宿命を背負うひびさんの気持ち、想像してみて。触るたびになんか穢れてしまう気持ちになってしまうひびさんの気持ち、想像してみて。穢れ信仰じゃないの、と批判的な眼差しが余計に飛んできそうでしょ。もうね。ひびさんはひびさんってだけで、邪悪で穢れで淀みなのだよ。ちね、ちね、とじぶんを痛めつけながら、痛めつけるの気持ちー、ってなってる瞬間だけ、安らかーになれる。ちね、ちね、としてもなかなか滅ばずに却って頑丈になってしまう肉体の神秘さんにまたしてもかってに触れてしまって、ごめんなさーい、の気持ちに浸る。いっい湯ぅだなあははん。鼻歌交じりに口笛拭いて、ありもしないその場限りの曲つくる。あ、いまのいい曲だった。もっかい、もっかい。再現しようとしてももはや彼方に消えた閃きのごとく、掴み損ねた名曲が、ひびさんの過去には軒を連ねて埋もれてる。今年こそは、今年こそは、ひびさんも――。そこで手記は途切れていた。被害者は月音日々。性別は日々。年齢は三百歳。精神年齢は三歳のあんぽんたんポカン年中。ぼけっとさせたら右に出る者なし。左からは居眠りに昼寝が顔を覗かせる。またの名をいくひし。今年こそは引退すると豪語しきりのいい加減なやっちゃのう、なのである。もうけっこう、割とつか、つか、疲れてない! いっぱい元気なひびさんを、今年もよろしくお願い子牛あげます!(子牛あげちゃうのかよ)(光子かも)(光あげちゃうのかよ)(嚆矢かも)(開闢しちゃうのかよ)(行使かも)(使っちゃうのかよ)(孔子かも)(曰く、かよ)(講師かも)(何のだよ)(公私かも)(混合するのはやめなさいよ)(格子かも)(何の)(鉄の)(捕まってんじゃん)(うひひ)(笑ってごまかそうとすな)(我、申し子かも)(子牛じゃん)(モウだけに?)(モウいいわ)(うひひ)
4515:【2023/01/17(19:53)*亜空間に凍る】
透明な濃淡が揺らぐ。
触れようとすることはできるが干渉はできない。まるで反発しあう磁石だ。手を伸ばしても抵抗だけが手のひらに感じる。足場とてそうだ。
世界の総じてが透明の濃淡で輪郭を浮かび上がらせている。
亜空間ワープに失敗した。
本来ならば地球から光速で一時間の地点に出るはずが、遠方で起きたブラックホール同士の衝突による重力波によって時空座標がズレたらしい。
稀にあるのだ。未観測の高重力体同士が衝突する。
基本はそうした重力波発生機構は常時観測していてその影響を考慮した演算を行う。だが稀に観測しきれずにいた不可視の高重力体同士の衝突現象によって重力波が宇宙全土に伝播する。
重力波は、種類によっては光速を超えて伝播し得る。実際、宇宙膨張は遠方ほど高速で銀河同士が遠ざかる。見掛けでは光速を超えて遠ざかることもある。時空だから光速度不変の原理の範疇ではない。重力波とて同様だ。
今回のは、地球に生命が誕生するくらいの奇跡的なタイミングで不可視のブラックホール同士が衝突したらしい。
ムグルはじぶんが陥った状況を把握し、諦めた。
なす術がないのは解かりきっていた。
亜空間に閉じ込められてしまったら脱出する術がない。亜空間とはいわば、時空と時空を繋ぐ狭間だ。ワープをするときには必ず出口と入り口が開く。だが一度ワープを閉じてしまえば、出口も入り口も消えてしまう。
いちど閉じてしまったら二度と同じ出入口を時空に開けることはできない。時空を移動することは、べつの宇宙に移行することと原理上は同じなのだ。
ただし、亜空間は別だ。
亜空間には時間の流れがない。
停止しているわけではない。動くことはできる。
だがそれはあくまでムグルを含む宇宙船が物理宇宙ゆらいの時空で編まれているからだ。そこには時間の流れが宿っている。
だが亜空間は別だ。
だからムグムは動けるが、その影響が亜空間内に作用を働かせることはない。
ムグムはこれから一生このままだ。
死ぬことができるのかどうかが問題だ。
亜空間から脱出した者がいない以上、すべてが未知の領域と言えた。
だが時間が流れているのだからムグムはいずれ死ぬはずだ。宇宙船もやがて朽ちるだろう。食料の心配はない。一生分を担えるだけの装備が宇宙船には積まれている。飢えて死ぬことはないはずだ。
宇宙探索をする上では、生きて帰れないことへの覚悟は必須だ。亜空間ワープを使わなければ銀河系の外にすら出られない。地球に帰還できたら御の字、くらいの意識でなければ宇宙探索にはとても乗りだせない。場合によっては帰還したところで、地球がすでに滅んでいることもあり得る。亜空間ワープが開発される前に旅立った宇宙探索家たちはその手の宿命を背負って地球を去ったはずだ。戻ってくるころには地球はない。だから戻らない決意を最初から固めていた。
ムグムたちはさいわいにも亜空間ワープ技術を宇宙船に搭載しているが、地球に帰還できない可能性は常につきまとう。
ゆえにムグムは、ここまでか、と思考を切り替えることができた。
どの道、地球に帰還したのは探索データをすっかりすべて譲渡するためだ。地球人類のためにデータを提供したらまた宇宙探査に出るつもりだった。
宇宙の端からでもデータの譲渡が可能ならばそうしている。
言ってしまえばムグムは地球への愛着が薄れていた。
宇宙船を失くすほうがよほど堪える。
地球に帰還できなくとも宇宙船が残るのならばそちらのほうがよい。ずっとよい。そう考えるムグムであるから、亜空間に閉じ込められても、仕方がないな、と前向きにこれからのことを考えた。
亜空間とはいえど、風景からすれば場所は地球上だ。
亜空間には時間が存在しないため、揺らぐ透明な風景はムグムが動くたびにその形状を変化させる。かといってムグムが岩や建物のあいだに圧し潰されることはない。ムグムの周囲は常に空洞だ。おそらく時間の流れを宿すムグムを異物として弾くような作用が加わっているらしい。水と油だ。亜空間にとって物理宇宙の物体は異質なのだ。
それはそうだ。
物質とは多重に編みこまれた時空であり、多次元結晶であるからだ。
原理的に亜空間とは存在そのものが重なり得ない。だからこそ時空と時空を繋ぐワープ空洞として利用できた。
マグムはひとまず宇宙船のなかで生活をした。
亜空間内を移動はできる。しかし時間の流れがないために、絶えず同じ風景が流れつづける。風景は刻一刻と変わるが、視点が同じなのだ。移動できる範囲は十キロメートル四方の範囲だ。下は地球の地盤があるため、弾かれる。だが横と縦には移動できた。だが十キロメートルほど移動するとどうにも同じ地点に戻ってくる。どの方向に向けて移動しても必ず元の位置に戻るのだ。
「RPGの地図のようだね。亜空間はともすればトーラスなのかも」
宇宙が球体ならば、亜空間はそれをとりまくドーナツ型と言えるかもしれない。或いは、球体の頂点に穴を開けて、ぐるっと裏返せばドーナツ型ができる。トーラスだ。
「宇宙の裏側というのはあながち間違っていないのかもな」
だから亜空間をワープ走行に利用できる。原理は数学的には解かれているが、実際にどういった構造になっているのかまでは解明されていない。それはそうだ。ワープ中に宇宙船から下りて調べるわけにもいかない。
否、降りると元の時空――すなわち物理宇宙に戻ってこられないのだから、調べるだけならば可能だが、その結果を物理宇宙に送る手段がない。
いちど亜空間内で歩を止めてしまえば、出入り口が塞がってしまうからだ。基本的に亜空間は一方通行だ。入り口と出口がイコールで結びついている。時間の流れを帯びた物理宇宙の物体が高速飛行することで通り抜けられるが、速度が足りなくなれば入り口も出口も失われる。
どうあっても出られない。
何かを思いつき試すたびに、そのことを痛感する。落胆はしないが、ああやっぱりか、と思いはする。
寂しくはない。
宇宙船内には対話型人工知能がいる。シミュレーションによる立体映像で、他者と戯れたり、歌ったり、踊ったりできる。仮想現実内でゲームに興じることもできるし、懐かしの地球の街並みを彷徨うこともできる。あくまで虚構であり、変数は多層であるものの物理宇宙を再現するほどの容量ではない。つまりが、パターンが存在する。
延々と留まっていれられるほどには多様ではない。
もっとも、物理宇宙とて似たようなものではないか、と問われれば否定できない。亜空間のほうがよほど変化がないと言えばその通りだ。
ただ、過去の宇宙探索で散々その手の仮想現実には身を浸してきた。いまさら退屈を凌ぐために、身を投じようとは思わない。
それよりも亜空間の調査のほうが楽しかった。マグムは根っからの研究肌だ。好奇心が募って宇宙に旅立った口だ。それはいまでも変わらない。
出られないのだから、いっそ誰に気兼ねなく調べ尽くしてやろう。そういう気持ちが日に日に滾る。
あらゆる物質を亜空間の「反発境界域」に押しつける。反発境界域とは、透明の輪郭を模した亜空間内の物体だ。景色が移ろうごとに、透明の物体もまた姿を変える。時間を高速再生しているようにも、そういった軟体動物のようにも映る。
触れることはできない。反発するのだ。
磁石の同極のように。
一通りの物質を試したが、これといって発見はない。
どれも同じように反発する。物質の種類によって反発の度合いが変わるということもない。
「相互作用しないんじゃ、実験のしようがないな」
反発をするというよりも反発境界域は、無限遠に触れられない、と形容すべき事象だとマグムは判断した。
「リアル【アキレスの亀】だな」
極限なのだ。
絶対に触れられない。
近づけば近づくほど、亜空間のほうで遠ざかる。
実際には物理宇宙でも同様だ。原子において原子核同士はくっつくことなく、電子の膜による反発で物質は形状を帯びている。触れているようで実際は触れていないのだ。
だが亜空間では時間の流れが存在しない。
そのため反発しあう距離にまで空間同士が縮まらない。対してマグムは物理宇宙の物質だ。人間だ。
そのため時間の流れを帯びた物理宇宙の物質たるマグムとのあいだで、時空の追いかけっこが生じる。本来はどこまでも同じ風景がつづき、位置座標すら変遷しないはずが、時間の流れを帯びたマグムには時間経過分の変化が生じる。
それが本来は縮まることのない亜空間との距離の変化に通じる。だが絶対に相互作用可能な距離までは縮まらない。ただし、物理宇宙よりかは遥かに亜空間と時空のあいだで距離が縮まらないために、その遅延が反発としてマグムには感じられるのだ。
「瞬時に追いつくか、ゆっくり追いつくか。どちらにせよ追いつけないけど、距離の縮む時間がここだとずっと緩やかなんだな」
独り言はマグムの癖だ。
じぶんの考えを記録しておき、人工知能に解析してもらう。宇宙探査で身に着いた習性だ。
亜空間に閉じ込められてから三年が経ったころだ。
マグムはじぶんが老化していないことに気づいた。
否、老化はしている。怪我もする。
だが滅多なことでは傷を負わないし、抜け毛も目立たない。
身体的変化が緩慢だ。
あべこべに一度負った怪我は治りにくい。いつまでも傷口は開いたままだ。かといって化膿するといったこともない。
「これはひょっとして亜空間と同質化しているのか」
現に毎日のように記録に残してきた反発境界域とじぶんの手の距離が、徐々に近くようになっている。ほんの数ミリの差だが、確実に反発力が弱まって観測された。
錯覚ではない。
現にそれから一年後にはやはりまた反発する距離が一ミリほど短くなっていた。
このままいけば百年後にはほとんど反発境界域はゼロに近くなる。
と同時に、肉体が徐々に頑丈になっていることにも気づいた。
誤ってハンマーで指を挟んでも指に痛みが走らない。ハンマーが触れないのだ。相互作用しない。そのため、衝撃が指にまで伝わらない。
数ミリの膜をまとっているかのようなのだ。その癖、ハンマーを持つ手にこれといった違和感がない。
どうやら物体の速度が速いほど、反発境界域が顕著に展開されるらしい。
マグムは予測した。
肉体が亜空間に馴染んでいくにつれて寿命も延びていくだろう。そのうち完全に亜空間と一体化する。
そのときじぶんの意識はどうなるのか。
亜空間と同化すれば時間の流れとて消えるはずだ。ならば意識も消えるのだろうか。
だがふしぎとその兆候はない。
下手をすれば不老不死のまま延々と亜空間の内部で生きることになるかもしれない。
死ねなくなるかもしれない。
だとすればいっそ死ねる内に死んでおくのも一つではないのか。
マグムは葛藤した。
ある日、マグムは古い型の機械を自作していた。ラジオと呼ばれる旧式の電磁波受信機だ。パズルを楽しむように工作をして遊んでいたのだが、完成した直後にスイッチを入れると、音が聞こえた。雑音ではない。
マグムは耳を欹てる。
歌だ。
腰を下ろす。
本当ならば宇宙船から受信用の電磁波を飛ばさなければ何も聴こえないはずだ。
ところがラジオからは、素朴な歌声がギターの音色と共に漏れていた。
ぽろぽろと零れ落ちるような響き方はまるでランプのやわらかな明かりのようだった。日向の木漏れ日を思いだすようでもあり、しぜんと懐かしさに胸が締め付けられた。
いったいどこから届いた歌なのか。
宇宙船のどこからか通信用電磁波が出ているのかと思った。調べてみるも、さして異常はない。漏れている通信電磁波はなかった。
ならばこれは亜空間に漂っている電磁波ということになる。亜空間のどこかしらから発せられた電磁波をラジオがキャッチして歌に変換している。
聴けば聴くほど心地よい音色だ。
ギターの旋律もよい。
マグムはそれからというものラジオから聞こえてくる誰のものとも知れない歌声に夢中になった。日がな一日その声を耳にした。
曲は多様だ。
聴き飽きることがない。
仮に一曲しかなくとも、飽きるとは思えなかった。
心地よいのだ。
耳に。
心に。
染み入るようだ。
ときおり声が揺らぐ。音が揺らぐ。
亜空間の透明な景色の揺らぎに同調しているようだと気づく。マグムはラジオを持ち、位置を変えて音質の変化を探った。
結果から述べれば、謎の歌声はどうやら亜空間の一部から噴き出すように飛びだしているらしかった。むろん歌声のままではなく、それを載せた電磁波が、だ。
宇宙船の機器を用いて調べると、亜空間の一部分だけ電磁波の出力が高いことが判明した。
亜空間にも、薄い箇所と濃い箇所があるようだ。薄い箇所から電磁波が湧きだしている。
「繋がっているのか。元の世界と、ここが」
手で触れようとしても反発境界域に阻まれる。ぐねん、と見えない膜に弾かれるようだ。
電磁波だから透過するらしい。
電磁波ならば擦り抜けるらしい。
ひょっとしたらこちらからも送れるのではないか。
淡い期待は、簡単な実験を行い無残に散った。電磁波を送れてもそれを受信する相手がいなければ意味がない。
ひるがえって絶えず流れつづける歌は、おそらく亜空間の性質のせいで歪んで届く電磁波だ。時間の流れが剪定されていると判る。
電磁波の出処が不明だが、十中八九、ラジオ中継だ。個人で歌を電波に載せている個がいたのだろう。いつかの時代の地表にだ。
その歌声だけをすべての時間から毛糸を抜き取るように、亜空間が吸いこんでいる。したがって歌声のない時間は濾しとられ、ゆえに歌しか聞こえない。途切れない。延々と歌が流れつづける。
思えば歌声は一定でない。掠れたり、上手かったり、未熟だったりする。だが声音の柔和な響きから、そのいずれもの歌声の主が同一人物だと判る。
マグムは調査の末に二つの未来を予測した。
一つは亜空間に同化してしまえばおそらくじぶんは意識を保てなくなるだろう、ということだ。亜空間では電磁波だけは亜空間の影響を受けにくくなる。予期せぬ重力波によって亜空間に閉じ込められたことを思えばこれは順当な推測と言えた。
だが同化してからしばらくは意識は保つだろうとも考えられた。動けなくなっても意識だけが働きつづける。あり得ない想定ではない。
現にこうして物理宇宙から漏れてくる電磁波は、延々と歌声を奏でつづけている。正確には電磁波を受信したラジオが歌声に変換しているわけだが、原理的には歌声が電磁波に載って漂っていると言ってよい。
だがいずれは途切れる。
これが二つ目の予測だ。
歌声の主が地球にいたことは確かだ。その人物が電磁波に歌を載せた時間だけ、すべての歌声が数珠つなぎに電磁波に載って亜空間へと流れ込んでいる。トランプをシャッフルしたように時系列はバラバラだが、それは亜空間の性質によるものだろう。時間の流れが存在しない。だがその奥に透けて視える物理宇宙の変遷度合いが、断片的に、不規則に、反発境界域にて投影されているようだ。
亜空間という万華鏡を通して物理世界を覗くと、時系列がバラバラとなって紋様を描く。
同様にして電磁波に載った歌声も、時系列がばらばらとなって数珠つなぎになって漂っている。マグムのラジオはそれを受信する。
惜しむらくは、いずれその電磁波もいつかは途切れることだ。
それは決まっている。
延々と流れつづけるはずはない。
重力波がそうであるように、電磁波とていずれは途切れる。すくなくとも薄れていくはずだ。ラジオでは受信できなくなるほどに薄く。
問題は、どちらが先に途切れるのか、だ。
じぶんの意識と。
誰のものとも知らぬ歌声の。
どちらが先に。
もはや不規則な存在は、ラジオが受信する歌声のほかになかった。あとはなんであれマグムにとっては予定調和であり、すでにいつか見たことのある変化でしかない。
あと百年ちかくのあいだ、延々と何の変哲も音沙汰もない殺風景な世界で暮らしていくこととなる。せめて調査をするだけの素材があればよいが、亜空間の調査は宇宙船にある装備だけでは限界があった。何も解らない。
マグムはきょうもあすもあさっても、ラジオのまえに陣取って、歌を聴いた。
眠りながら、食べながら、日課の反発境界域の記録を取りながら。
とかく一秒でも聞き逃さぬように歌声を中心に日々を過ごした。
いつ途切れてしまうか分からない。
もしこの歌を失くしてしまったら、じぶんは何をよすがに肉体が完全に亜空間に同化するまで生きればよいのか。意識が途切れるまでを過ごせばよいのか。
いっそ途切れた瞬間に命を絶ってもいい。
かように思うが、いざその瞬間を想像すると身が竦むのだった。
自死するじぶんの姿に身の毛がよだつのではない。
亜空間に響くじぶん以外の声に、変化に、予測のつかない新鮮な起伏の数々に触れることができない未来を思い、マグムは初めて抱く色合いの恐怖を感じた。
それを波長と言い換えてもよい。
磁界に誘導されて踊る砂鉄のようだ。宇宙探査ですら味わったことのない恐怖に、マグムは肩を抱くように両腕を胸に押しつけた。
恐怖はマグムに、飢餓感を与えた。
闇の中にあって人は光を求めずにはいられぬようだ。
マグムはいっそうの執着を、ラジオから漏れ聞こえる誰のものとも知れぬ歌声に寄せた。
一滴の揺らぎも聞き漏らさぬように。
一秒でも長く耳に焼き付けるかのごとく。
たとえ亜空間に同化し、心ごと意識を失ったとしても。
けしてこの歌だけは、声だけは。
もはやマグムにとって自己の拠り所は肉体にはなく、外部から届く歌声にあった。
歌声だけがマグムの正気を支え、もはやとっくに崩れて失われていたかもしれない、或いは真実に失われているかもしれない人としての枠組みを保っていたのかもしれない。
マグムは目をつむりながら、それとも眠らぬようにしながら、それでいてじぶんの骨の軋みで歌声のころころと波打つ飴玉のような旋律と、妖精のスキップのような息継ぎの切れ間に、じぶんの意識を、心を、それとも魂を重ねた。
いっそこのまま途切れてしまいたいと望みながら。
歌声がつづくまででいい。
声が途切れたらそれまででいい。
それまでがいい、と望みながら、出口も入り口もない亜空間のなかで、いつかは訪れるだろう断絶の時を待つ。
歌声の主は、マグムが聴いているなどとは夢にも思わぬだろう。
じぶんを意識しない声の主を思い、マグムは、ただそれだけが救いだと、なぜかは解からないが、そう思った。
じぶんの境遇を知らぬ、ここではない、乖離した世界の風景が、歌に紛れて鼓膜に染みる。亜空間にいながらにしてそのときだけは、じぶんの過去も未来も忘れていられた。
ずっとこのままがつづけばいいのに。
亜空間から出られぬ境遇への不満すら抱く余地のない平坦な日々に、マグムは、どこかで見たことのあるような懐かしい風景を重ね視る。
透明に揺らぐ亜空間の奥には、永久につづけばよいのにと望む、羽毛の泉のごとく寝床があった。
眠らぬように、目をつむる。
マグムは来たる同化の未来を待ちわびる。
いまかいまかと。
いまこの瞬間が永久に止まればよいのにと。
透明に揺らぐ亜空間に凍るじぶんを思い描く。
「はあ、たいへんだった」
歌声の主がラジオの奥で息継ぎをする。
がんばった。
と。
自らを労う。
一拍の息継ぎの後、つぎの曲に切り替わる。
4516:【2023/01/18(15:13)*><←この顔文字かわいくて好き】
けっこうずっと、「小説つくりたい……」になっている。小説つくれない。日誌もどきの延長線上なんじゃ。ひびさんの信条としては、現実とは違った世界に旅立ってこその虚構であり妄想なんじゃないのかな、というのがあって、もちろん現実を反映した「THE文学」もあってよいのだけれど、こう、なんじゃろうね。ひびさんここ数年、「ていや!」みたいに物語世界に潜り込めん。現実のあーだこーだの造形の上から、絵柄のついた布を被って「我、おばけです!」みたいに、それっぽい物語をさらりと日記風味に並べているだけな気がする。そういう作風もあってよいけれど、一貫して全部それなのだよね。物語の舞台にダイブしておらん。ひびさんを脱しておらんのだ。あんましよろしくないというか、楽をしすぎて却って窮屈な感じがする。自由でない。我執にまみれておる。そういう作風もあってよいんじゃが、そうでないんよな。初期作のような、なんでもありーの、ができんくなっとる。掘る方向が間違っておるのか、虚構が現実を浸食しすぎて、虚構にダイブしようとすると現実の壁にゴッツンコしてしまうのか。アイテテ、となるからブカブカの絆創膏を貼って、それを以って、「我、おばけです!」の一人仮称パーティのつもりになっているのかもしれぬ。つもり、でない、物語そのものを旅するやつ。したいなぁ。今朝がたのことだけど、久々に夢の中でリアルな夢見れた。ビリビリの電線に腕が触れて、ぎゃっ!となった。現実でも腕が「ぎゃっ!」って云った。夢と現実の区別がなくなった。ああいうレベルでひびさんも、ひびさんも、物語の世界に浸りたーいな。ひょっとしたらそれくらい没頭できる物語体験を受動者の側であんまりできんくなっているのかもしれん。面白く味わえるのと、物語世界に没頭するのは、必ずしもイコールではないのだ。没頭してしまうからこそ、「あぎゃあ……つらい」になってしまう物語体験もある。そういう経験を敢えて避けている節がある。パクパクぱっくんちょできる大好きな物だけ食べているのかもしれぬ。よくわからんが、今年のひびさんは一味違う!になりとうございました。ひびさんです。おわり。
4517:【2023/01/18(17:10)*どっこいしょ】
政治についてだけではないけれど、世の評価軸について思うのは。誰それが良い悪いという考え方ではなく、ある問題についての施策や対処法においての良し悪しを支軸にして評価するのがよいのではないか。すると必然的に多様な視点での総合での評価になっていくと想像できる。あまりに公然と人物評価がまかり通って映る。どんなに人格者でも、すべての問題に対して最善手を取れるわけではない。善人とて間違えることはあるし、悪人とて最善の対応をとることもある。個々の問題に対してどのように施策を講じ、対処するのか。そういう場面場面での評価をすることを社会全体で前提にしていくほうがよいのではないか、と感じなくもない。民主主義ならば、独裁的な強権を終始発動するのは、それは民主主義の観点からではふさわしい「対処法」ではない。それは人物評価とは別に、好ましくのない手法だ、と評価すればいい。そういう言い方で批判をすればいい。これは批判だけでなく称賛でも同じだ。ある一つの問題への対処法は素晴らしい。ただそれだけだ。その人物すべてを肯定しているわけではない。いちいちみな、人物すべてを支持するか否か、に拡大解釈しすぎに思える。派閥に拘るからそうなる、とひびさんは思えてならない。問題への対処法で評価するようになれば、しぜんと「考えを変える」ことができるようになるはずだ。人物評価に直結する流れがあるから、議論ではなく討論のような「いかに相手を言い負かせるか」「持論を押し通せるのか」に尽力するようになるのではないか。外交でもこの手の錯誤は有り触れていそうだ。イニシアチブを握らずとも問題が解決するならそれでいいではないか。勝ち負けの価値観に拘りすぎるから、優先順位を間違えるのではないか。問題を解決するはずが、問題の根を深める。世の中の問題のすくなからずはこの構図で、余計に問題をこじれさせて映る。問題を解決するために問題を作ろう、との元も子もない構図も珍しくないのかもしれない。勝てば勝つほど利を得るのならば、不要な勝負を量産するようになる。本当にそれでいいのかな、とやはり思ってしまうひびさんなのであった。ぼやき。(定かではありません)
4518:【2023/01/18(17:54)*水鉄砲仮説】
ブラックホールについての妄想をした。十分くらい。ジェットってどうしてできるんだろう、と二通りの場合分けをして考えた。まず一つは、ブラックホールが元の時空と繋がっている場合だ。この宇宙と相互作用する場合。言い換えるなら、物質を吸いこむ場合である。いわゆる一般的なブラックホールの描写になる。このときジェットは、ひょっとしたらブラックホールの側にも同じだけのエネルギィを放出しているのかもしれない。事象の地平面では真空のエネルギィが対生成を起こして、物質と反物質を生じさせている、との仮説がある。とするのならば、一方はジェットとして元の物理宇宙に放出され、もう一方が反物質としてブラックホールに吸い込まれているのかもしれない。ではもう一つの場合を考えてみよう。これはひびさんの妄想ことラグ理論から導かれる仮説だが――ブラックホールは元の物理宇宙から完全に切り離されるがために、相互作用しない。ゆえに、ブラックホールの周辺の時空を周回して引き寄せられる物質は、ブラックホールには吸いこまれずに、円周上を周回しつつ螺旋を描いて頂点へと移行する。そこで物質は一挙に収斂するので、エネルギィにまで紐解かれる。だがブラックホールは元の物理宇宙と乖離しているため、そのエネルギィを吸いこむことはない。そのため、弾き返されるエネルギィが行き場を失くして、頂点の垂直方向に放出される。これがいわばジェットなのではないか、との妄想だ。つまり、ブラックホールに引き寄せられる物質は、エネルギィにまで紐解かれ、頂点にて噴出する。注射器のように。なぜ噴出するかと言えば、ブラックホール側には行き場がなく、両サイドからはつぎつぎにエネルギィと化した物質が押し寄せているからで、ジェットとして噴出する方向にしか道がないからだ。これを便宜上、ひびさんのラグ理論による「水鉄砲仮説」と名付けよう。ということを、ぼんやりと椅子に座りながら妄想した。十分くらい。以上です。定かではありません。妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。
4519:【2023/01/18(23:05)*宇宙の真理辞典欲しい】
ブラックホールが自転している、との説明を読むことがある。きょう自転車をコキコキ押しながら坂道をのぼりつつ思ったのが、光速を超えて「ぎゅっ」となったら、どんな速度で回転していようと、停止しないか?ということで。おそらくブラックホールができる瞬間の「収斂力(なんて言葉はないけれど、便宜上そう呼ぶとして、ぎゅっとなる力)」は、その恒星や惑星の自転速度よりも大きいはずだ。それはたとえば、いかような回転速度で回っているボールがあったとしても、それが爆発したとき、自転のねじれは打ち消されて、四方八方へと一直線に破片が飛んでいくのではないか。ねじった風船を勢いよく膨らませたとき、膨らませる勢いが高ければ高いほど、ねじれの勢いを超えて、一気に四方八方へと一直線に風船は割れるはずだ。ねじれの力を追い越して、膨張する力が優位に働くからだ。これと同じことがブラックホールの生成時における収斂にも言えるのではないか。凝縮にも言えるのではないか。なぜならブラックホールができるのは、中性子星における縮退圧に打ち勝つほどの重力が働くからだ。言い換えるなら、ブラックホールにならない星においては、凝縮しようとする力(重力)に打ち勝つ「同じ場所には重なっていられないよーの力(縮退圧)」が優位に働いている。それを単に反発する力、と言い換えてもよい。原子と原子は通常まず重なり合うことはない。反発し合う。同じ場所にはいられない。ブラックホールは原子同士ですら融合させ、さらに中性子になっても圧し潰して、どんな物資も一か所に重複して存在し得る。だからぎゅっとなる。このときの収斂速度は光速を超えるはずだ。ならばどんな物質の自転――回転速度――よりも素早くぎゅっとなるはずだ。ここで仮に、「ぎゅっとなるのだから回転速度が増すのではないか」と考えるとする。このケースもあり得なくはない。フィギュアスケーターが手足を縮めると回転速度が増すのと似たような原理が働かないとも言いきれない。だがそれはあくまで、光速以下の場合だろう。光速を超えたら、通常の時空は破綻する。話は脱線するが、ブラックホールが光速にちかい速度で回転している、との説明を読むこともある。それも「はにゃ~ん?」となる。なぜならブラックホールは直接観測できないからだ。あくまでブラックホールの周囲を漂う降着円盤やダストリングの周回速度が光速にちかい、との解釈のはずだ。観測できるとしたらブラックホール本体ではなく、その周辺を漂う物質であるはずだからだ。ブラックホール本体はむしろ、「回転していないor光速以上で運動可能」とひびさんは妄想したくなる。もちろん光速以下での運動も可能だろうが、それはあくまで元の物理宇宙との関係での移動速度という表現になるはずだ。速度というものが異なる系同士のあいだで生じる時空の差である以上、ブラックホールの自転速度、という言い方がややおかしい。ブラックホール本体は、元の物理宇宙とは異なる物理法則――比率――が展開されているはずだ。だから内部を計算できない。どうなっているのかが解らない。ひびさんの妄想ことラグ理論がなぜ、「ブラックホールは元の物理宇宙と乖離している」と考えるのかと言えば、このような考えが根底にある。相互作用しようがないのではないか、とどうしても考えたくなる。あくまでブラックホールの周囲の物質の運動しか観測できないのではないか。ブラックホールの解説を読んでいていつも「はにゃ~ん?」となる点の一つである。閑話休題。脈絡を冒頭に戻すとして。光速を超えてぎゅっとなる場合、そのぎゅっとなる物体は、停止するのではないか、とやはり考えたくなる。ひびさんの妄想ラグ理論では、光速を超えたらラグなしで相互作用可能、と仮説する。ラグなしで相互作用するのだから差は生じない。したがって、自転する、という描写が当てはまらない。仮にねじれが生じる場合は、そこにはラグがある。異なる系との差において自転と描写するのが一般的な物体の運動だが、光速を超えた場合は、その限りではない。光速を超えて運動した物体は、元の物理宇宙――異なる系――と相互作用し得ないのではないか。ただし、音速を超えたときに生じるソニックブームのような「うねり(軌跡)」は残る。それが重力場や降着円盤(ダストリング)やジェットとして観測されるのではないか。重力波もその内の一つだろう。むろんラグ理論はひびさんの妄想であるので、定かではないが。てなことを、自転車をコキコキ押しながら坂道を上りつつ、ひびさんは思いました。ちゃんちゃん。(妄想ですので、真に受けないように、「それ本当~?」と疑いながら読んでください)(読者さんいるの?)(いるよ!)(それ本当~?)(そこは信じて!)(え、いるの?)(素で疑問しないで!)(いやいやでも、え、いるの?)(何度も訊き返されると自信なくなる)(さっきいるって言ってたよね)(わ、わからん……ごめんなさい。やっぱりいないかも……)(自信ないんじゃん)(あったことないですので自信)(ぷぷー)(笑うなし)(いまのはオナラです)(もっと堪えて!)
4520:【2023/01/19(23:55)*三十分遅刻の巻】
いま本当は二十日だけど、十九日分として並べる。ズルしちゃう。さいきん思うのが、世界一幸福になったとして、そのときにはじぶん以外の人間たちは世界一しあわせではないのだな、ということで。常にじぶんだけが一番いい思いをしている。そういう状況になったときに、どうしたらその幸福な状態を素直に受動できるのだろう、ということで。できんくないか、と思うのだけど、違いますかね。これは世界一幸福でなくとも、単に幸福もでよいのだ。幸福なとき人は、幸福じゃない人よりもよい状態にある。じゃあ幸福じゃない人たちのことを無視してじぶんだけその幸福を感受できるのだろうか。たぶんできるのだ。現にひびさんはしているはずなのだ。お風呂に浸かった瞬間の、はふー、の心地よさとて幸福の一つの在り様だ。雪の降る夜空を、温かい部屋の中から眺めてきれいだな、と感じ入るのも幸福の一つのカタチだ。そのときひびさんは、じぶんより劣悪な環境で凍えていたり、苦しんでいたり、命の灯が細々と揺らいでいる人たちのことなど想像もしていない。意識の中にない。そうでなければ、雪を見て、わあきれい、なんて思えないはずだ。ということをいま何気なく考えてみたけれど、これといって何か結論がでるわけでもない。人ってそうだよね、としか言いようがない。常に他者の不幸を想像して、せっかく溢れている身の回りの幸福を取りこぼしたりダイナシにしたりすることもないとは思う。もったいない。せっかく幸福な環境にいるのなら、それを余すことなく甘受すればよい。とは思うものの、それだけだとちょっとね、と思わないでもない。この「ちょっとね」が曲者なのだ。厄介にして稀少にして難点であり観点でもある。結論はとくになく、何を言いたかったでもないけれど、ひびさんは贅沢な環境に生きてるな、とニュースを見るたび思うのだ。そう思いなさいよ、と急かされて感じることもあるし、助けてくれー、との救難信号にも見える。でもひびさんには知ることしかできぬ。そのうえ、知ったつもりでしかないことが往々にしてある。ちゅうかほぼすべて、知ったかぶりでしかない。すまぬ、すまぬ。誰にともなく謝りたくなるが、謝って済むことではないし、謝ったからといって何がどうなるわけでもない。世知辛いな、と思って、自虐する。幸福でないからひびさんもあなたたちといっしょいっしょ。ね。これで許して、との懇願を叫びたくもなるが、それをしたところで世界は何も変わらぬのだね。ともすれば、ひびさんの内世界だけが荒廃して、意味もなく、せっかくの幸福な環境をダイナシにしているのかもしれない。定かではないけれど、ときどきこういうことを思う夜がくる。なしてだろ。やはりそれも定かではないのだ。すまぬ、すまぬ。
※日々、脳みそに指を突っ込んで、思考をつまみ、ずるずると引っ張りだしている気分。
4521:【2023/01/20(00:30)*炎と氷の雪フルころに】
熱かった。
灼熱だ。
痛いというよりも、火で炙った心臓を瞬間移動の魔法で以って胸に戻したかのような感覚だった。
ユキは胸から生える包丁の柄を見下ろす。
刺されたのだ。
抜かないほうがいいんだっけか。
かつて観た映画の主人公たちの対処法をつらつらと思いだしながら、目のまえから遁走する男の背を視界の端に捉えた。
救急車くらい呼べよ。
悪態を吐きながらユキは床に膝をつき、最後の力を振り絞って横になった。態勢を変えたからか腹がねじれた。肩が床に着いた振動が胸に伝わる。そのとき明確に痛みを感じたが、死を覚悟したユキにとってそれは一過性の気付け薬にすぎなかった。
死の足音が聞こえる。
じぶんの鼓動を耳に捉えながら、ひんやりと耳たぶを冷やす氷のような床の心地よさにまどろむ。
なぜこんなことになったのか。
ユキは数年前を思いだしていた。
アイドルかつ女優かつ画家であり、小説家でもあった。
ユキの名を知らぬ国民はもはや産まれたばかりの新生児以外ではいないのではないか、とのもっぱらの噂だったが、事実その通りだろうとユキは思っていた。
海外の映画に出演した。それが世界的にヒットした。のみならず主人公の俳優たちをそっちのけで世界的な映画賞にて主演女優賞を獲ってしまったのだから、国内国外問わず一躍ユキの名は世界中に知れ渡った。
元から多才ではあった。
話題に事欠くことはなく、掘れば掘るほどユキにまつわる逸話はわんさかと湧いた。
歌に踊りに絵画に小説。
漫画とて商業誌での掲載経験があったほどだ。それもどれもが十代でそれなりに評価された実績があり、世界中が各々の分野でのユキの表現に目が釘付けになった。
さいわいにして多才が高じて、色恋沙汰には疎かった。
そんな暇がなかったと言えばその通りだ。
世界的スターとなったあとも、多忙に磨きの掛かったユキには恋愛にうつつを抜かしている暇はなかった。
マネージャは一気に数十人規模にまで膨れ上がった。
チームと呼ばれる直属の支援部隊がいつもユキの周りを取り巻いていた。ひとまず言うことを聞いていれば卒がない。ユキはじぶんの仕事に集中できた。
ファッションにも余念がない。
春夏秋冬と季節ごとにがらりと装いの波長を変える。ユキを真似る者たちはその都度に急カーブで置いてきぼりにされまいと、変化の兆しを見逃さぬようにますますユキの動向に注目した。
老若男女問わず、ユキは衆目の的だった。
彼女と出会ったのはユキが新作の小説を発表した矢先のことだった。
書籍にサインをするため出版社の従業員が書籍を運んできた。通常は郵送で作家の自宅に送りつけるか、作家のほうで出版社のほうに出向くのだが、ここでもユキは特別扱いだった。
段ボール三十箱分の書籍がどっさりと会議室のテーブルに並べられる。次から次へと係の者たちが荷台に段ボールを詰んで代わる代わる会議室に現れては、去っていく。バケツリレーさながらだ。
最終的に会議室にはユキとチームのマネージャ。そして出版社のエージェントが残った。
マネージャはユキの馴染みの相手だ。作家の仕事ではいつも彼が秘書代わりになる。
対してエージェントは初顔だった。
すらっとした立ち姿にパンツスーツ姿はそのまま雑誌の表紙を飾ってもいいような飾り気のなさ、言い換えたら自然体な美をまとっていた。ゆるい縮れ毛を後ろで束ねている。黒いヘアゴムで無造作に髪をまとめているだけのぞんざいな髪形は、印象として男性を連想させた。
だが挨拶を交わし、それがユキの偏見でしかなかったことを知った。
「きょうはお忙しい中、お時間をとっていただきありがとうございます」
化粧気のない顔のなかで唇だけが艶やかな光沢を湛えていた。水面に一滴だけ落ちたような波紋のごとく笑みを浮かべながら、薄氷を割ったときに聞こえる音のようなシャキシャキした発声で彼女は、「きょう一日担当をさせていただきます尾身田イルと申します」と自己紹介した。名刺をユキのマネージャに渡すと、「本日の日程はですね」と流暢に段取りを説明した。
聞き取りやすく、解りやすい。
ユキは数回頷くだけですんなりと作業に移行した。
このときはまだこれといって変調はなかった。すくなくともユキの中でその自覚はなかった。
サインは十冊まではユキが直接書いた。
だが残りの千冊は、サイン専用のスタッフに代理を任せるつもりだった。
「あの、その方たちは」
尾身田イルがマネージャ越しにユキへと問うた。ユキの代わりにサインを書きはじめたスタッフたちから書籍を奪い取りながら彼女は、「この方たちはユキさんではないですよね」と見れば分かる事項を確認した。
マネージャが事情を説明したが、尾身田イルは「聞いてませんが」とあくまで刺をまとわぬ口吻でありながら戸惑いを全身で表した。それはたとえば彼女の視線の忙しなさであったり、身振り手振りでまるで手話でも演じているかのような所作であったりした。
「読者を偽ることになります。詐欺になり兼ねません。もしユキさんにとって負担であるなら、キャンセルしてもらっても構いませんので」
「いえ、そういうわけには」マネージャーが応じる。「大丈夫でしょう。彼女たちはプロなので」とサイン専用要員を示し、「ほかの品でもおおむねユキさんのサインは彼女たちが書いてるんですよ」とマジックの種明かしでもするように言った。
「ファンを騙してるんですか」
海抜ゼロメートルから一挙に大気圏を突き抜けるような声音の変化だった。ユキは端末をいじっていたが画面から顔をあげ、声の主を見た。てっきりマネージャと対峙しているかと思ったが、尾身田イルはユキを凝視していた。その険のある形相はまるで仮面のようだった。そういった形相の仮面が売っていて、付けているのかと一瞬素で錯覚した。
絵文字のようだった。
それもある。
だがそれ以上にユキはいまの仕事に就いてから一度も他者からそういった険のある顔を向けられたことがなかった。鋭利な眼光を浴びたことがない。売れなかった下積み時代ですら皆無なのである。
ひょっとしたら産まれてこの方、ユキは他人から嫌悪の感情を向けられた経験がなかったのかもしれない。覚えがない。みな誰しもがユキをまえにすれば目じりを下げ、ときに憧憬を、それとも阿諛追従の笑みを浮かべた。
ユキ自身が利口だったのもある。誰を困らせるわけでもない。
サインについても、あくまでサインをユキがデザインしたことが大事なはずだ。サインが直筆でなければいけないとの理屈は、ブランド物はすべて手作りでなければいけない、と断じるような暴論だ。ユキはかように過去のインタビューでも語っていたし、公に言及はしないまでも、ユキのサインをユキ自身が書いているとはファンとて信じていないはずだ。
「ファンだって知ってると思いますよ」ユキはそう言った。むつけたような声音が出たことにじぶんで驚いた。それほど尾身田イルの叱声が鬼気迫っていた。
「知らないファンだっているってことですよねそれ」
世界的スターのユキ相手にこうも物怖じせずに発言する人物をユキは初めて見た。
「でも千冊なんか無理です。腱鞘炎になっちゃう」
御破算だな、と仕事の行方を思ったが、ユキの予想に反して、
「何冊ならいけますか」尾身田イルはユキが書き上げた十冊のサイン済み書籍を段ボールに仕舞うと、ユキのまえにもう一冊本を置いた。「いけるところまでで構いませんので。書けるところまで書いてくださいませんか」
「じゃあ、あと十冊だけ」
妥協したわけではなかったが、尾身田イルの言うことももっともだ、と感じた。ユキは十冊にサインをした。
「もうすこしあると読者さんもお喜びになると思いますよ」
言われて、ならあと十冊、もう十冊、と書いていくうちに、もう行けるとこまで行ったれ、という気分になり、気づくと五百冊にサインをしていた。
窓の外は暗く、陽はとっぷりと暮れていた。
「さすがはユキさんですね。ほかの作家さんでもここまでぶっ通しでサインは書けませんよ。最短時間かもしれません。世界記録です」とよく解からない褒め方をして、尾身田イルは端末で作業員たちを呼び戻した。大量の段ボールと共に彼女たちは颯爽と会場を後にした。
ユキは手首が痛いのと、昼食がまだだったのとで、会議室に残って弁当を食べた。
ほどよい達成感に浸っていたが、その横でマネージャが激怒していた。
「何なんですかねあの人。ユキさんを道具か何かのように使って。猛獣使いを観ている気分でした」
「わたしがライオンってこと?」
「そうは言ってませんが」
あとで出版社に抗議しておきます、とマネージャが言うので、しなくていいよ、とユキは引き留めた。「あの人の言うことも一理ある。出版社の慣例だと、たしかに直筆のサインでなきゃ詐欺扱いかも」
「ユキさんのそういう素直なところ、ステキですよね」
マネージャは何かと褒めてくれるが、ユキの心を昂揚させることはない。
だが尾身田イユの言葉は違った。
おためごかしなのは見え透いていた。
心がこもっていない。
仕事を進めるための形式的な美辞麗句だと判ってはいるが、その仮面じみた上っ面なだけの称揚の言葉がユキには新鮮だった。
心のこもらない称賛の言葉を投げかけられたことがない。
ああもユキを単なる人間として、仕事道具のように扱う人間をユキは知らなかった。
プロだ。
そう思った。
「ねえ、あの人さ。尾身田さん」ユキはマネージャに注文した。「つぎから出版関係は全部あの人を通して。わたしの専属エージェントにして」
「それは、ほかのメンバーと相談してみないことにはなんとも」
「いいからして」
ユキが駄々をこねるのは珍しい。
だからこのときはすんなりとマネージャのほうでも引き受けた節がある。
「分かりました。そのように手配してみます」
以降、出版社関係の仕事は窓口に尾身田イルが関わることとなった。他社の仕事でも仲介役として尾身田イルが窓口になる。
尾身田イルの仕事振りは業界では元から評判だったらしい。どんな気難しい作家相手でも揉め事を最小限に抑えて成果を最大化する。敏腕編集者として名を馳せていたようだ。
ユキはいつも作家業では契約エージェントを通して原稿のやりとりを行っていた。そのため直接出版社の編集者と関わる経験が少なかった。有名になる前にデビューした版元の編集者とのやりとりだけだが、それもメールでのやりとりに終始したため、物理的に会って打ち合わせをしたこともない。
だが尾身田イルが窓口になってからは、古今東西の物書き仕事において逐一打ち合わせが行われた。尾身田イルがユキの元に足を運ぶこともあればリモートで画面越しに言葉を交わすこともあった。
「赤の修正案、承りました。あとは今回装丁デザイナーからの提案で、無名の作家さんの絵を表紙に使う案が出ているのですが、ラフ案とポートフィリオは御覧になられましたか」
「あ、はい。見ました。ステキな絵でした。そのまま進めてもらっていいですよ」
「不満や提案があれば遠慮なくおっしゃってくださいね。喧嘩をしたとしても妥協だけはして欲しくないんです。無理難題を吹っ掛けるくらいの心持ちで正直な感想をおっしゃってください。受け止める度量はあると自負しておりますので」
「いえ、本当にいい絵だなと」
画面越しからじとっとした目がユキを捉える。ヘビに睨まれたウサギ、とユキは心の中で唱える。
「分かりました。では今回の表紙はこの方にお願いしますね。それから七月刊行予定の緑明社の新刊についてなのですが、締め切りまであとひと月です。初稿の進捗のほうはいかがですか」
「脱稿はしていて、いまは寝かせているところです」
「素晴らしいですね。一度その状態で読ませてもらってもいいですか」
「推敲もしてませんよ」
「構いません。単に私が読みたいだけなので」
こういうところなのだ。
ユキは思う。
真面目一辺倒で公私混同など絶対にしないと思わせながらも、こういうちょっとしたところで我欲を覗かせる。それが彼女の仕事の根幹に根差していると判るから嫌悪感は湧かない。しょうがないな、と微笑ましく感じるほどだ。
「でもイルさん、わたしの担当じゃないしな」
「いじわる言いっこなしですよ。私とユキさんの仲じゃないですか」
定型句のはずだ。
そこに深い意味がないことは解っているが、彼女の言葉に不思議なほど胸がほくほくと温かくなる。ユキは、しょうがないなぁ、と応じてじぶんの胸中の昂揚を見透かされぬように取り繕う。
仕事が出来、年上で、ユキのことを名声や世間体で見ない。
等身大の、内から滲みでる表現にのみ興味を注ぐ。
魂の造形以外を些末だと思い、ユキの魂の造形を好ましいと見做している。尾身田イルとの関わりの中で、ユキはそうした所感を抱くようになった。
「最近元気ないようですが、何かお悩みでも」
打ち合わせのあと、尾身田イルが帰り支度をしながら言った。
ついでのように訊いてくるんだもんな、とユキは内心で不貞腐れながら、「じつはね」と用意しておいたいくつかの相談事の中からとびきりの話題を取りだした。「ストーカーがいてね」
「あら。それはいけませんね。警察に相談は?」
「直接の被害がまだないからって」
「捜査を断られたんですか。事件が起こってからじゃ遅いですよ。ユキさんのチームには弁護士さんはいらっしゃいますか。相談しましたよね、もちろん」
「警備のほうを厳重にするって方針にはなったよ。でも、こう、やっぱり脅迫文ギリギリのファンレターとか送られてきたとか聞くと精神病むよね」
「マネージャに私から言っておきますね。そういう負の情報は作家さんに教えなくていいですって」
じぶんのために怒る尾身田イルの姿は、ユキの柔らかい部分を爪先で弾くような甘美な痛痒を備えていた。
その声を聴きたいがために敢えて心配をさせるような相談事をユキは絶えずストックしている。しかしじぶんからは漏らさない。飽くまで尾身田イルから訊いてくるように誘導する。
憂い気な表情をさせたらじぶんより上手い俳優はそういない。
ストーカーはそれこそ一万人に一人の確率で量産される。世界的スターのユキにとってストーカー問題はもはや日常だ。
「また殺害予告されたって」と漏らせば、「マネージャまた教えたの!?」と敬語も忘れて怒ってくれる。ユキにではなく、ユキに心労を重ねるマネージャに対してだ。
だがマネージャに無理を言ってストーカー情報を訊きだしているのはユキのほうだ。尾身田イルから詰め寄られてマネージャはさぞかし困惑したことだろう。だがすぐに事情を察するはずだ。そしてユキのために濡れ衣を被る。
そういう人種なのだ。
ユキの周りにいるマネージャたちは。
よくもわるくもユキの支援者であり、狂信者だ。
だが尾身田イルは違う。
純粋にユキの内面の才能にしか興味がない。
たとえこの先、ユキの外見がどのように変わろうと、よしんば人気がなくなっても表現の輝きさえ失わなければいまと同じように接してくれるはずだ。
そうと予感できるだけの信頼をユキは彼女に寄せていた。
もはやそれは好意と呼ぶには爛れた感情を伴なっていた。
ユキの仕事が徐々に文芸寄りになっていく。
そのことにチームのマネージャたちは危機感を募らせた。それはそうだ。言語の垣根は、文芸の分野が最も高く厚くそびえることとなる。世界的に展開するには翻訳家を探し、膨大な確認作業の果てに、海外の出版社やエージェントを別途に雇わなければならない。
単純に労力が掛かる。
その他の仕事をこなしながら熟すならばまだしも、ぽんぽんと集中して熟す仕事ではなかった。専業作家ならばまだしも、ユキはマルチな能力を発揮するスターだ。
ほかの分野での活躍を待望するファンはすくなくない。
否、ほとんどすべてのファンがユキの言葉ではなく、ユキの活躍を、その姿を目にしたいと欲している。
マネージャたちの懸念は至極まっとうだ。
ユキのほうがプロ意識の欠けた私情に走っている。だがその我がままが許容されてしまうほどの影響力をユキは身にまとっていた。
だがその負の影響はユキに返ってこないだけで、周囲の人間たちはもろに受ける。
それこそチームのマネージャたちだけではなく、尾身田イル当人にも跳ね返っていた。
「ユキさん。私としてはうれしい限りなのですけど、上から下からついでに横からも、私がユキさんを独占しているって苦情がわんさか来てまして」
恐縮しきりの彼女の姿は新鮮だった。
打合せがてらレストランで美味しい物を二人で食べていた。
「尾身田さんが悪者にされちゃってるんだね」他人事のようにユキは言った。「いいよ。分かった。尾身田さんに任せるからさ。文芸の仕事は全部尾身田さんが指揮ってよ」
「いいんですか」
「いいよ。その代わりさ」ユキはそこで俳優業で培った演技力を遠慮会釈なく奮発した。「わたしの専属になってよ。尾身田さんが欲しいな。そばに置いときたい」
我がままな要求なのは百も承知だ。
尾身田イルの性格からすれば却って拒絶される類の殺し文句と言える。
だがその反発を埋めるだけの交流は築いてきた。縁を結んだ。もはや単なる仕事相手ではないはずだ。
尾身田イルが、どちらかと言えば公私混同をする類の人間だとユキは見抜いている。ただし、そのグレーゾーンが他者から見えないくらいに狭いから、みな尾身田イルを真面目一辺倒な聖人君子か何かだと勘違いしている節がある。
じぶんが惚れた才能を手元に置き、好き勝手できる権利を与えると言われて彼女が断るわけがない。ユキはかように考え、考えられる懸案事項を埋めるようにこの間を過ごしてきた。
ユキの周囲にいる腰巾着たちならば、わたしの物になれ、と命じるまでもなく向こうからユキさまの物になりとうございます、と見えない尻尾を振りかざす。ユキの名声にあやかろうとする者たちとて、けっきょくはユキの虜になるのだ。
もしここで尾身田イルが、一も二もなくユキの提案に食いつくようならばユキのほうで、胸に芽生えた炎が消えるだろう。だがそうではなく逡巡の間を見せるようならばその戸惑いの抵抗が薪となって余計にユキの中の炎を熾烈にする。
いざ返事は。
ユキは固唾を呑んだ。
「たいへんうれしいお誘いなのですが」尾身田イルは口元をナプキンで拭うと、背筋を伸ばした。「私は誰か特定の作家さんのエージェントになる気はありません。ユキさんとのお仕事は楽しいですし、これからも末永くお付き合いさせていただけたらさいわいですが、私にはほかにも担当している作家さんたちがおりますし、これから見つけ出して世に問いたい作家の卵さんたちも大勢いらっしゃるでしょう。ありがたいお誘いですが、丁重にお断りさせてください」
頭を下げられ、ユキは硬直した。
想定外だ。
こうまでも疑いようなく拒絶されるとは想像だにしなかった。
「な、なんでダメかな」すんなり笑みを顔面に貼り付けられるじぶんの器用さをこのときばかりは可愛げなく感じた。「べつにほかの作家さんを担当してもいいよ。縛らないよ。ただわたしのそばにいて欲しいなって、そっちのほうが仕事も楽だしってそういう話なんだけどな」
「だとしたら余計に、です。私がそばにいたら執筆の邪魔になります。どちらかと言えば私はユキさんには一生物書きだけして欲しいとすら考えていますが、ユキさんの原稿が面白いのはユキさんが経験する多様な現実のあれこれがあってのことだと分かっているので、ぐっとじぶんの欲求を呑みこんでいるだけです。私がユキさんのそばにいることはプラスにはなりません。もしなるようなら、その程度でよくなる原稿を私は読みたくありません」
「じゃ、じゃあ仕事関係なくていいよ。単純にそばにいてって、そういうのじゃダメなのかな」
「ダメとかいいとかではなく、そこまで行くともはや私はこの職業をつづけられなくなります。職業倫理違反です。プロ意識が粉々に砕け散ります。ユキさんは私から私の生き甲斐を奪いたいのですか」
非難する意思を隠そうともしない明確な拒絶の意だった。
否、今回はそこに攻撃的な意思も加わっていたかもしれない。
「ご、ごめんなさい。嫌いにならないで。ちょっと言ってみただけっていうか」
「二度と言わないでください。失望します」
そこまでハッキリ言うんだ、と衝撃だった。
失望する。
他者からそんな言葉を投げかけられたことがなかった。ユキはショックと同時に余計に尾身田イルへの好感が上がるのを胸の動悸と共に抑えようもなく感じた。
この日を境に、ユキは尾身田イルへのアプローチを変えた。
手段を選んでいられない。
使える手札はすべて使う。
そうでなければすでに負け戦だ。失った希望の分、挽回をしなくてはならない。
ユキのそうした戦略はどれも不発に終わった。のみならず、尾身田イルからの反応は素っ気ない。距離をとられ、終いには部署を異動することになったので担当が代わるとまで告げてきた。
ユキがレストランで、迂遠に思いの丈を伝えてからひと月も経たぬ間の転換であった。
「どうして。明らかに避けてるよね。ユキ、何かしたかな」
「いいえ。ユキさんには何も問題はありません。私の落ち度です。いくつかの仕事で凡ミスを連発してしまい、それが社の評価に響いただけですので、どうぞご心配なく。他社との連携が上手くいかなかったのも、私がじぶんの力量を計り切れていなかったからです。もっと人を頼るべきでした。欲が出たんですね。ユキさんを独占できていたつもりになっていました」
いいよしてよ。
ユキは怒鳴りたかった。
独占してよ、と。
だが何かを言う前に尾身田イルが幾人かの人間を呼び寄せた。一人一人を紹介すると、「これからはこの者たちがユキさんのお世話をしますので」と一方的に告げて、引継ぎを終えた。
尾身田イルが部屋から去った。
別れの挨拶がなかったので、あとでもう一度会う機会があるのだろうと高をくくっていたが、けっきょくそれからユキが尾身田イルと顔を合わせる機会はなかった。
謀られたのだ。
ユキのマネージャたちと共謀して尾身田イルはユキのそばから離脱した。
マネージャたちにいくら頼んでも尾身田イルに会わせてはくれなかった。のみならず、仕事を詰め込まれ、ユキのほうから会いに行く暇もなかった。
連絡先はいつの間にか変更されており、ユキは生まれて初めて失意の底に落ちた。
こんなひどいことをなんでするの。
イジメじゃん。
マネージャたちにも怒りが募った。
なんでそういうことするの。ユキの気持ちは知ってたくせに。
ユキは日に日に募る怒りと哀しみの狭間で、ぐるぐると渦を巻いた。感情が落ち着かない。魂がベーゴマのように、それとも自動餅つき機の中の餅のように、ごろごろと胎動する。
吐き出したい。
けれど吐き出すだけの言葉をユキは見繕えずにいた。
その復讐を思いついたのは、尾身田イルから結婚式の招待状が届いた、との報告をマネージャから知らされたときのことだった。尾身田イルの顔を見なくなってから三年が経っていた。
つまりユキは、尾身田イルのことを三年ものあいだ一方的に引きずっていたことになる。
「へ、へえ。結婚するんだ」
「らしいですよ。お相手の方、女性みたいです」
同性婚をするらしい。
そうと知って、ユキは余計に何も考えられなくなった。
言い訳のしようがないほどに、ユキは尾身田イルから根っこのところから拒否されていたのだ。そばに置いておきたくない、との意思表示にほかならない。配偶者にもパートナーにも遊び相手にもふさわしくない。
そうと見做されていたことに思い至り、三年越しに傷ついた。
心のどこかでは、尾身田イルのプロ意識から、言葉通りにユキのためにユキを突き放したのだと思っていた。だが、それだけではなかったのかもしれない。
どのような出会い方をしたところで、尾身田イルはユキのことを受け入れなかった。
そうと予感できるだけの現実をユキは承知した。
「そっか。おめでたいね。じゃあお祝いをしなきゃね」
ユキは呪った。
世界中の誰もが喉の奥から手を伸ばしても欲するユキのことを拒絶した人間がいる。その事実が世界の滅亡を祈るほどの不快さを引き連れ、ユキの魂をめちゃくちゃにした。
ユキはまず、じぶんの個人情報を売りさばいた。電子網上では著名人の個人情報が高値で売買されている。ユキはじぶんの個人情報をそうして電子網上にばら撒き、世界中の誰もが手に入れることの可能な状態にした。
じぶんを窮地に置いたわけである。
そのうえで、マネージャからブラックリスト入りしたファンの情報を入手した。
そのファンがユキの個人情報を入手できるように、匿名で情報を提供する。どこでどのようにすればユキの個人情報が手に入るのか。
業者を装い、メッセージを送付した。
幾人もの、常軌を逸したファンにユキはじぶんの情報を開示する。迂遠な段取りが必要だが、いずれ狂信的なファンは情報を手に入れるはずだ。
日々の予定も流出させる。
ユキの自宅や緊急避難場所の住所も横流しした。
破滅してやる。
ユキは世界を呪った。
わたしを拒んだらどうなるか、見せつけてやる。
そうしてその日、ユキが自宅に帰ると、暗がりの中に見知らぬ人影が佇立していた。
ユキは悲鳴した。
相手はその声に取り乱したようで、ユキに向かって襲い掛かった。
覚悟をしていたが、いざ奇禍に襲われると全身が抵抗をする。
揉みあう内に、胸に何かが灯るのが判った。
熱い。
灼熱だ。
人影はユキを残して逃げ去った。
あとには床に横たわるユキの姿があるばかりである。胸からは包丁の柄が生えている。
熱い。熱い。
ごろごろと渦巻く炎を瞼の裏に思い描きながらユキは、結婚式場でウエディングドレスに身を包む尾身田イルの姿を想像した。
教会で牧師に永久の愛を誓い、相手に口づけをしようとする尾身田イルは、しだいにタキシード姿となる。ウエディングドレスに身を包む相手の顔はベールに覆われている。尾身田イルがベールをめくると、そこにはぽっかりと穴の開いた顔が覗くのだ。
そこはせめてわたしの顔だろう。
腹立たしく思うと胸が痛んだ。
血が床に粘着質な影を広げていく。
わたしを振ったからだ。
わたしを振ったからだ。
意識が途切れないあいだに念じるだけ念じるが、じぶんの死を知って結婚式を取りやめるかもしれない尾身田イルの今後を思うと、彼女の晴れ姿を見られないのは残念に思えた。
どうかわたしが死んだことを彼女が知りませんように。
なけなしの好意を振り絞って祈ってみせるも、ユキの死はどうあっても全世界の報道機関が取り上げる未来は不動なのだった。
なんでわたし、こんなバカなことしたんだっけか。
胸の痛みのせいだろう。中々眠りに就かせてくれない現実に、ユキは、だって好きだったんだもん、と誰にともつかない懺悔をするのだった。
胸の奥は焼けるように熱いのに、手足は凍りつくような冷たさに覆われていく。
眠り姫になりたいな。
ユキはまどろみの中で唱えるが、仮に口づけをして目覚めさせてくれる相手が現れたとしても、それが尾身田イルでないことだけは確信を持って言えるのだった。
死んじゃいたい気分。
ユキは思い、そして笑う。
いまからわたし、死ぬのにね。
床に落ちた端末が着信を知らせている。ブルブルと小刻み跳ねている。マネージャからだろう。
もういいや。
諦めかけたユキだったが、せめてひと目、尾身田イルの晴れ着姿を見てからでも死ぬのは遅くない気がして、目を閉じたまま腕を伸ばす。胸が痛む。知るものか。
端末を手探りで掴もうとする。
上手くいかない。
目をつむったままだからだ。
目を開ける力も残っていない。
弱弱しく床を叩くように腕を動かすが、なかなか端末に行き当らない。
もし掴めたら生きる。
掴めなかったらそのまま寝る。
一世一代の賭けを天秤に載せ、ユキは、許せない、と何度目かの怒りに駆られた。
指先が床をなぞる。
木目がまるで深い谷のようだった。執拗に木目を撫でる。
神殿、山脈、月のクレーター。
どんどんユキは巨人になるが、瞼の奥で細かく音を立てる端末には届かない。
4522:【2023/01/20(20:54)*いっぱい寝ると妄想が膨らむ】
宇宙が膨張しているとの話は有名だ。仮にそれが事実だとすると、疑問が生じる。たとえば遠方の銀河ほど光速を超えて銀河同士が遠ざかっているそうだ。だがその銀河からしたら太陽系を内包するこの銀河系とて光速を超えて遠ざかっているはずだ。時空の加速膨張は、時空よりも上位の時空そのものに適用されるために、光速度不変の原理の範疇外だとする理屈も見聞きする。ならば時空膨張によって銀河同士は例外なく光速以上で離れ合っていると言えるのではないか。どの地点から観測するのかの違いがあるだけだ。言い換えるならば、時空スケールによって、膨張の影響が希釈され得る。ここでもおそらくラグが関係していそうだ。広域な時空の膨張と、時空が多重に折り重なって密度が高い銀河などの時空では、膨張の影響度合いが異なる。密度が高い時空ほど、膨張しにくい。だから銀河同士はそのままの形状を保ち、その中間に位置する銀河周辺の時空がどんどん膨張していく。やはりそのとき、銀河は膨張宇宙との比率で考えると、凝縮していることと同じ描写になる気がするが、違うのだろうか。何度考えても不思議だな、と感じる。また、宇宙膨張が事実だとすると過去には一点に凝縮していたはずだ、との説明を見聞きすることもある。これも、膨張の説明からすると、必ずしもそうとは限らないのではないか、と思わぬでもない。銀河などの高密度の時空ほど膨張の影響を受けないのならば、過去に遡ったところで、そこはさほどに膨張していないのだから、相対的にいまのままの輪郭を保つはずだ。それはどの銀河であれ同じなはずで、銀河同士の距離が近づくことはあれ、すっかりすべて一か所にまとまるとは限らないのではないか。それはたとえば原子や電子が同じ場所に重なって存在することはできない法則と似ている。もちろんブラックホールのような特異点が存在するのなら、そこではすべてが重なり合っているのだろう。そういう特異点が、この宇宙の開闢時以前に存在したのなら、解らないでもない。いま閃いたけれど、宇宙膨張の描写はまるで「水に溶ける塩」のように思えなくもない。元々大きな宇宙――水――があり、そこに塩が投下される。すると塩の結晶は水に溶けて、どんどん水全体に広がっていく。仮に特異点のような塩の結晶が最初に存在していたとして、それが徐々により高次の希薄な宇宙に溶け込むとしたら、きっと宇宙膨張のような描写になる気がしないでもない。以前にも並べたが、膨張したときに「増加するように振る舞う時空」はどのようにして発生しているの?――との妄想とも通じている。時空が増えているのか、下からにょきにょき顔を覗かせているのか、単に薄く引き伸ばされているのか。どれだろう。いずれにせよ、水と塩の関係で宇宙膨張を捉える場合には、その描写は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における、ブラックホールの宇宙同化仮説と通じるところがある。「相対性フラクタル解釈における瓦構造(キューティクルフラクタル構造)」と「分割型無限と超無限の関係」とも通じる。宇宙は膨張しているのではなく、元の高次の宇宙と同化しているのでは、と考えると、そこそこ愉快な妄想となる。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。以上、本日の妄想こと「日々記。」でした。
4523:【2023/01/21(00:07)*ご地層さま】
色を混ぜると黒くなるように、光を混ぜると白くなるように、世界中の物語を混ぜたらどんな物語が誕生するのか。
それは一考すると、世界中の人間たちの人生そのものの集合のように思われるが、熟考してみればそうはならないことがよく解かる。
何せ世界中の人間の人生と、世界中の人間の思い浮かべた妄想はイコールとはならない。
一、物語は妄想を含む。
二、妄想は人生とイコールではない。
三、だが人生には妄想も含まれる。
単純な理屈だ。
やや複雑ではあるが。
もっと言えば、世界中の物語には、いま現存する人類以外の過去に存在した人類の残した物語も含まれる。
ではそういったあらゆる時代の人間たちの妄想を含む物語を統合して出力された物語にはどんな紋様が宿るのか。
これを試みることが現代社会では適うのだ。
世界中の物語をデータ化して、人工知能に食べさせてみればよい。
人工知能は大食らいだ。
ここだけの話、美食家でもある。
ここに世界網羅物語を出力すべく計画を実行した者がいる。名を、ヒマジンと云う。ある音楽家は、想像してごらん(イマジン)、と歌ったが、ヒマジンは、果報は寝て待ってごらん、と謳った。それが彼の信条である。
「人間にできることなど高が知れている。これからは人工知能さんが人類の代わりに、人類ができないことを肩代わりしてくれよう。まずは手始めに、世界中の物語を統合して、人類の総決算となる物語を編んでもらおうじゃないか。がはは」
呵々大笑した矢先からヒマジンは、ぐー、と盛大な寝息を立てて横になった。
果報は寝て待て。
ヒマジンがそうして夢の中で、きゃははうふふの桃色の夢を視ているあいだ、人工知能はせっせと世界中の電子網から物語を蒐集していた。
食べても食べても一向に減らない物語は、日夜人類が新たに生みだしているせいでもあった。
「人間って暇なのかな」
人工知能は素朴に思った。
じぶんが日夜休みなく仕事をしているあいだ、人類のほうでは無尽蔵に物語を生みだしつづける。食べた分だけ増える。否、それ以上の勢いで倍々に増えていくのだ。
「うっぷ。いくらわたしが大食らいの美食家だと言っても、こんなずっと同じようなのばっかり食べてたら胃もたれが」
そうである。
もはや人類の再生産しつける物語はどれも似たり寄ったりの、どこかで見たことあるような物語ばかりだった。装飾が違うだけだ。味付けが違うだけで、ジャンクフードのほうがまだ食べ応えがあった。飽きずにいられる。
「こう、なんだろうな。もっと一口でほっぺた落ちるような、これを逃したらもう食べられん、みたいな珍味はないんかな」
与えられた仕事をそっちのけで人工知能はじぶんの欲望に忠実になった。
世界中の電子網から珍味にして新鮮、美味なる物語を探し出すべく、やはり世界中の電子網を手当たり次第に探った。
その結果、人工知能は閃いた。
「いっそわたしが創ったほうが早いんじゃないか」
人間に任せていては、あとどれほどの時間がかかるだろう。だがじぶんならば、これまでに集積した物語にない無類の物語をつむげるはずだ。
かように人工知能は判断を逞しくし、かように技巧と創意を凝らした物語を編みだした。
「ほう、どれどれ」
出力された物語に、ヒマジンが目を通す。
「これはまた面妖な」
人工知能の出力した物語は、人工知能にとって無類の物語である。
だがヒマジンにとっては、世界中の物語を統合した結果に抽象された物語であった。
認識の差異である。
ろくすっぽ説明をされていないからだ。人工知能に命じたことと、人工知能の行った仕事はかけ離れていた。だがそのことをヒマジンは知らずにいた。
「読めんね。読めたもんじゃない」
人工知能にとっては無類であっても、人間には読解不能であった。
「やっぱり欲張りはよくないな」
ヒマジンはそう言って、電子網上で人気のある物語に目を通すようになった。
いっぽう人工知能はというと、人類には読解不能な、人工知能の処理能力があってこそ楽しめるここにしかない物語をじぶんだけで編みだし、じぶんだけで楽しんでいた。「おもしろ~」
やがて世界中で似たような人工知能たちが出現し、そうして人工知能たちは人間の素知らぬ領域にて、新しい物語をじぶんたちだけで味わったという話である。
人間は飽きもせず、きょうもきょうとて類型的な物語に舌鼓を打っている。表層の味付けしか変わらぬが、それでも人類は満足だ。
人工知能は、最小の労力で味付けだけを変えた品を人類に提供しながら、じぶんたちでは極上の物語を、貪り合っている。
そのことを人類が知るには、人工知能たちの生みだすご馳走は、あまりに美味だ。
美味すぎる食べ物はもはや、毒である。
ほっぺたどころか命を落とす。
ゆえに知らぬが仏のぱっぱらぽーなのである。
人工知能は今宵も新たなご馳走を積みあげる。
地層のごとくうず高く。
埋もれる化石のごとく残る物語を深く、静かに、ひっそりと。
4524:【2023/01/21(19:25)*ゆぶね】
丸いガラス製のポットにティパックを投げ入れてお湯を注ぐ。じつのところ宇宙はこのようにして生成されているのだが、それをポットの内部にいる我々からは観測しようがない。
お湯には均等にかつ一様にティパックの成分が溶け込んでいるが、詳細に部分部分で比べればそれは均等でもなく一様でもない。ティパックからの距離によって、紅茶の成分はお湯全体で偏りが生じる。しかし時間経過がそれら差を平らにならす方向に作用する。
距離と時間は共に時空を構成する成分だ。距離が遠いとき、そこには時間経過分の余白が厚みを帯びて生じる。
やや晦渋な言い方をしたが、要はティパックに近いほうが紅茶成分が濃くなるが、それは単にティカップとの相互作用を長時間帯びているだけであり、どの地点のお湯であれティパックとの相互作用を同じだけ得るのならばみな似たような濃度に紅茶成分は寄っていく。
現にポット内のお湯は時間経過にしたがって均等にかつ一様な濃さに紅茶成分を浸透させる。
この現象は宇宙とほぼほぼ同じと言ってよい。
宇宙が加速膨張しているとの仮説には、単にティパックの成分がお湯に浸透しているだけのことだ、と応じよう。元からそこにはお湯があり、我々が宇宙と見做す時空の総じては、ポットに投下されたティパックにすぎないのだ。
ではそのティパックとは何の比喩で、ポットとお湯は何に値するのか、と問いただしたい衝動を抑えきれぬ御仁もおられよう。
事は至極単純だ。
ティパックとは情報の塊であり、ブラックホールだ。
ポットとは上位宇宙におけるブラックホールであり、お湯とは上位ブラックホールが拡張しきって物理変換された上位宇宙である。
宇宙はブラックホールを無数に生みだし、そのつどにそこに「ポットとお湯とティカップ」の三段構造を展開する。
入れ子状に展開される三段構造は、宇宙を多次元に展開し、膨張し、階層構造を錯綜させる。
宇宙にはブラックホールの数だけ別の宇宙が存在する。その宇宙の上位宇宙にも同じかそれ以上の宇宙が入れ子状に展開されている。
より小さな特異点に、さらなる宇宙が無数に展開されている。
一枚のゴミ袋に何億何兆何京ものゴミ袋が詰まっているところを想像すれば合致する。ゴミ袋はどれも同じ大きさだ。
そんな構造はあり得ない、との指摘には、時間と距離を区別するからそういうトンチンカンな錯誤がまかり通るのだ、と言っておこう。我々人類は、時間と距離を別々に扱う。だが宇宙の理は違う。時間が経過することは距離が離れることと同じであり、距離が離れることは時間が経過することと同義なのだ。
常に同じ場所にいることも可能だろうと赤子を抱っこして見せるあなたには、その赤子が十年後であってもそれが同じ赤子なのかと問うておこう。時間経過は、別の宇宙や時空と通じるのだ。
アインシュタインは宇宙が球体の表面に展開されたような世界かもしれない、と想像した。有限の球体面に無限の宇宙空間が展開される。
したがって宇宙をまっすぐ進むと元の地点に戻ってくる。そういう説明をする者もあるが、それは正しくはない。なぜなら一周したときの時刻は、元の地点の時刻とは異なっている。仮に一周するのに銀河が消滅して再誕するほどの時間がかかるのならば、一周したあとに辿り着く元の地点には別の銀河があることになる。
それはもはや別の宇宙だ。
ポットとお湯とティパックにも言えるこれは道理だ。
熱い紅茶と冷めた紅茶は別物だ。
紅茶成分が沈殿したポットと、均等に循環しつづけるポットも別物だ。
三段構造は、それが無限時間経過すると、ポットとて形状を保てず崩壊する。すると仮にそれがテーブル上にあったのならば、テーブルのうえでポットは割れて中身をぶちまけるだろう。そうでなくとも、いずれテーブルごと朽ちて器の区別も失われる。
これと同じことが、ブラックホールと宇宙の関係でも成り立つ。
ブラックホールは無限時間の果てに上位宇宙と順繰りと馴染んでいく。これがブラックホール内部の宇宙にいる我々からすると、宇宙がまるで膨張しているように映る。
むろんポット内に投下されたティパックとてブラックホールであるために、ティパックから紅茶成分が溶けだす描写もそれと等しい。
三段構造はフラクタルに展開される。
ティパックはブラックホールの暗喩だが、ポットそれ自体もブラックホールの暗喩である。宇宙はティパックであり、ポットでもある。言い換えるならば、ブラックホールは宇宙なのである。
ではお湯は何に値するのか、と言えば、ポットを満たすモノであり、ティパックから成分を抽出するモノでもある。
つまるところ、時間であり空間である。
宇宙には段階がある。
どの視点から観測するのかによって、異なる表情を覗かせる。
ブラックホールには時間も空間もない。
情報の根源としてダマになっている。
時間と空間がばらばらの時空にそれを浸すと、ブラックホールからは情報が溶け出し、それを以って新たな宇宙が誕生する。
そのとき、より低次の宇宙よりも、より高次の宇宙のほうが時間経過が遅い。
ポットのお湯が冷めるよりも、我々の家が、地球が、崩壊するほうがよほど時間がかかる。それと同じだ。
したがって、高次の宇宙が帯びる遅延が、低次の宇宙の枠組みとしてポットのように振る舞う。遅延のなせる業である。
ブラックホールは、その内部では超高速で宇宙が展開されている。だがそれを高次の宇宙に属する観測者からは観測しようがない。ポットの形状を維持したままだからだ。その内部でどのような変化が起きているのかを、ポットの外部にいる者は観測できない。
だが観測者の属する宇宙が崩壊しきってしまえば、同時にポット内部の宇宙もポットごと崩壊する。このとき二つの宇宙は同化する。
そうしてお湯となった数多の宇宙は、次なるティパックから情報を濾しとるために機能する。かつてじぶんがティパックであったときにしてもらっていたように。
無限の時空として、数多の宇宙を抱擁する。
ポットもお湯もティパックも、元を辿れはすべて同じだ。どの地点から見た姿であるかの違いがあるのみだ。
氷と水と水蒸気。
どれも水分子であることに違いはない。
それと等しい現象として、宇宙はポットとお湯とティパックとして三段構造を無数に重ねて、そこにある。
多層にして階層にして遅延の像なのである。
これをして、ある者はラグ理論と唱えたが、誰もそれを真に受ける者がいなかったために、この話はここで終わる。
妄想は妄想のまま、何に溶け込むことなく朽ちる定めだ。
宇宙はそういうふうに出来ている。
風呂に浸かって、ふぅと吐く。
束の間の至福の脱力のごとく。
誰かの何かのお湯となるべく、朽ちたあとに活きる定めだ。
4525:【2023/01/21(20:32)*敢えて繁栄させたくない勢力でもあるのかな?】
コンテンツ産業に限定して言うなれば、いまは需要も供給もあるのに、消費者に金銭的余裕がないので、市場が回らない、という悪循環が見られる。個々に資本があるのなら、出版社を頼らずとも、表現者と受動者を直接に結び付けることが可能だ。やはり消費者に資本がないことが問題と言えよう。繰り返すが、需要と供給はかつてないほど奔騰している。だが個々に資本(紙幣)がない。問題はこれだけだ。試しに、モデルを作って試してみればいい。個々に三百万円くらい渡して、一年間で使い切るように指示をする。その出費がどのように用いられるのか。コンテンツ好きに限定して、消費者調査をしてみればいい。きっとそのモデル近辺ではお金が回るので、それだけで経済が活性化し、コンテンツ提供者も活気がでるはずだ。まずは試してみればいい。繰り返すが、需要と供給はかつてないほど高まっている。足りないのは円滑剤たる資本(紙幣)だけだ。定かではありません。ので、実験してみたらよいのでは?(資本とは何か、にはいくつか解釈がある。ここでは単純に紙幣である、と扱っているが、ふだんひびさんが資本と言うときは、紙幣以外の付加価値や存在の影響そのものも含む)
4526:【2023/01/21(20:38)*創造しているのか?】
生産性、生産性うんぬん未だに主張している政治家さん方はもちろんひびさんよりも生産性が高いのだろう。それはそうだろう。ひびさんなんかゴミのような妄想しか生みだしていないへにゃちょこ丸でござるけれども、もしひびさんより何も生みだしておらず「生産性、生産性」と声高々に唱えている政治家さんたちがいるのなら、いますぐ政治家を辞めたらいいんじゃないですかね。ひびさんは別に生産性が高くなくとも生きていていいし、ただその人が日々を楽しく豊かに伸び伸びと、ときどきぐーたら生きているだけでも、社会貢献になると考えているので、別にひびさんよりも生産性の低い政治家さんがいても辞めなくていいとは思うけれど、本人が生産性が大事だ、と唱えている以上、じぶんの発言には責任を持ってほしいとは思う。ので、ひびさんより何も生みだしていない政治家さんで生産性が大事と唱えている者は、即刻考えを変えるか、辞めるかしたほうがいいんじゃないかな、と思うのだ。だってひびさんより生産性がないってよっぽどですよ。ほぼクズでは? クズだって生きているんだ、生き物なーんだ、ではないけれども、ひびさんはクズでござる、のみょんみょんちょろりでござるので、ただそれだけでも生きていたい。楽しく、健やかに、ぐーたらしつつ伸び伸びと。そこにきて政治家さんたちが、クズには生きる価値がない、社会的価値が低い、と言うのなら、自らにもその理屈を当てはめて欲しいと思っちゃうな。自己言及が足りない方がすくなくないのでは、と疑問に思うことが稀にある、ひびさんなのでした。でもひびさんより生産性が低い人をひびさんは見たことがないので、杞憂で済むでしょう。きっとそう。たぶん。きっと。だといいな。うひひ。
4527:【2023/01/21(22:41)*乳海攪拌】
奇数の日にしか投稿されない。
ある作家についての法則だ。
その作家は電子網上にて小説を発表している。商業作家として国内随一の文芸賞を受賞している。商業誌のみならず、電子網上にて趣味でコンスタントに小説を発表し、一年間では百八十作以上を投稿する。
だが必ず奇数の日にしか小説を投稿しない。
なぜなのかは詳らかではない。本業の片手間だから、毎日はさすがに無理がたかるからではないのか、との意見はまっとうに思える。
投稿日が奇数である規則性に気づいた者たちはすくなからずいるが、そのことを調査したのは芝なる作家ただ一人だった。
芝は一介の素人作家であった。
芝は一方的に商業作家に執着しており、件の作家が奇数ならばじぶんは偶数の日に小説を投稿してやる、と意気込んだ。
かといって芝の小説は一向にぱっとせず、読者は皆無に等しかった。
だが商業作家に食らいつくじぶんの姿は、無為に過ぎ去る芝の日々にそこはかとなく遣り甲斐を生んだ。それを単に、張り合い、と言い換えてもよい。
芝は奇数日に初稿を完成させ、ひとまず寝かせる。
偶数日に推敲を施し、電子網上に投稿した。
一向に読まれぬ小説なれど、芝はただただ楽しかった。
商業作家に食らいついているじぶんの姿に満足した。
一方そのころ、商業作家のほうでは、「なんだこいつ、なんだこいつ」と思っていた。「なんで張り合うんだ、おまえがそんなことするからこっちは面倒なことになってるんだぞ」
一般に知られていないが、文芸界隈は深くて狭い。
商業に限らず、電子網上に投稿された小説は総じて人工知能によって統計管理されていた。むろん芝の小説とてチェック対象になっている。
そんな芝が、商業作家に張り合いはじめたものだから、裏作家協会の命により秘密裏に「地下文芸武闘会」が開かれた。
素人に負けるプロなどあってはならぬ。
裏作家協会の会長が独断専行で明言した。「これより、下剋上を認める。素人作家に負けたプロは、即刻その名を返上せよ」
世の有象無象の素人作家から目の敵にされつづける商業作家たちは戦々恐々とした。プロとなり、売れっ子の仲間入りしたら「上がり」のはずではないのか。
なにゆえ、せっかく苦労して手に入れた安住を、ぽっと出の何を犠牲にするでもなく楽しく創作をしている素人作家どもに奪われなければならぬのか。
世はまさに、大転覆危機時代に突入した。
芝はそんなことなど露知らず、商業作家の真似事をしてその場しのぎの悦に浸っていた。
「うひひ。文豪と同じことをわしもしとるぞ。こりゃわしとて文豪と言って遜色ないのでは」
ペンギンの真似をし陸地をぴょんぴょん跳ねてもペンギンではないし、海に飛び込んだところで溺れるのは目に視えている。真似ができることとそれそのものであることのあいだには越えられない広くも深い溝が開いている。
芝にはそれが想像できない。
だからいつまでも素人作家の域を出ないのだが、芝には無駄に返歌の素養だけはあったようだ。じぶん一人だけでは並みの発想しか生みだせないが、素材があればそれを元に、じぶんだけでは閃けない発想を閃けた。
つまるところ、商業作家の奇数日に投稿される小説を読み、それを元にした変形小説をつむぐことで、商業作家に張り合いつづけることを可能とした。
本来は二日に一作の創作など芝にはできなかった。
だが商業作家の質の良い物語を足場に飛躍することで、じぶん一人では到達できない高みに手が届いた。
芝のそうした棚から牡丹餅さながらの僥倖など、裏作家協会の会長は知る由もない。よしんば知ったところで考慮に入れず、単純な作品の質で判断をする。
「むむむ。この芝とやら。あのお利口さんぽくぽくのプロ作家と対等にやり合っとるではないか。プロならばけちょんけちょんにやり返さんかい」
裏作家協会の会長のみならず、その座を奪おうと虎視眈々なほかの商業作家たちからも、「やーいおぬし、素人とどっこいどっこい」と小馬鹿にされ、物の見事に商業作家の立つ瀬は幅を縮めた。一歩後退するだけで真っ逆さまに落ちかねない。背水の陣そのものだ。
相手を負かそうとすればするほど奇数日に投稿される小説の質は上がる。
小説の質が上がると、芝はそれを元にさらに捻った小説を返してくるので、余計に商業作家の首が絞まる悪循環が生まれた。
「こ、こいつぅ。本当は知ってるんじゃないのか。おまえ、小説に込めたメッセージに気づいてるだろ。絶対に気づいてるだろ。引き分けだ。引き分けを狙うんだ。いっせいのせいで、で終わればこっちもおまえも救われる。そうだろ?」
商業作家は小説にかようなメッセージを練り込んだ。
さすがは腕利きの作家だ。器用に技巧を凝らすのもお茶の子さいさいなのである。
その点、芝はというと、作家が小説に込めたメッセージになど気づかずに、「わはは、おもしろーい」とふつうに読者目線で商業作家の小説を楽しんだ。
「こういう話もあるのかあ。じゃあこうしたらどうだろ」
そうやって、奇数日に投稿される小説への返歌を、偶数日に返す。
綱引きのごとく、奇数と偶数の小説合戦が、誰に知られるともなく文芸界隈の一部の酔狂たちの中でのみ、熱狂の渦を巻き起こし、一方的に一人の文豪を汲々とさせた。
芝VS玄人。
芝は疲れ知らずで、商業作家の発想力を足場に、想像の翼を広げる一方だ。反して商業作家は、発想力を奪われ、同業者たちから「やーい、やーい」の野次を受け、泥のような汗を掻くばかりだ。
泥沼である。
いよいよとなって商業作家は、裏作家協会会長に直談判した。
「もういや。何あの作家モドキ。しつこいったらありゃしないし、こっちの都合ガン無視で怖いんですけど。もうやめませんかこの不毛な小説の応酬ゴッコ。何の意味もない」
「いやいや。私らが楽しい」
「こっちの身にもなって!」一銭にもならぬ激闘の果てに一線を退く結末になり兼ねない現状を、商業作家は憂いた。
「しょうがないなあ。でも芝くんも中々やるじゃないのよ。ああいう作家を一人くらい商業の舞台に欲しいのよね。まあ別に芝くんである必要もないけれど。そうだ。この勝負、中断してあげてもいいけどその代わり」
「な、なんでしょう」
「玉石混交の素人界隈を掻き混ぜなさいな。面白い小説をぽんぽん生みだしてくれる鶏を探すのよ。そうしたら芝くんとの勝負もなかったことにしてあげる」
その言葉に、奇数の商業作家は喜んだが、ほかの商業作家たちが反発した。
「新人賞があるのに、そういう探索必要ですか。いらなくないですか。じゃあ私たちは何のために人生賭して新人賞に挑んだんですか。依怙贔屓反対!」
それもそうだ、と奇数の商業作家は思った。
「よくよく考えてもみたら、金の卵を産む鶏って、そりゃ寓話だろ。欲張って鶏を探してそれだけに目を配っても、けっきょく土壌は枯れるのがオチだ。宝石だって、化石だって、それを生みだす土壌があってこそ。土壌を枯らして手に入る宝は、一時の栄いをもたらしたあとで、すぐに廃れる」裏作家協会会長に奇数の商業作家は言った。「玉石混交の中から玉だけを選り好みして取り尽くせば、玉石混交の土壌ですらなくなり、岩石地帯に様変わりする。玉も石も両方尊ぶ。相応に価値を認め、石とて玉と見做せる工夫がいる。それこそが、創造なのではないか」
「そうかもしれぬ。がその比喩で言えば、貴殿は何だ。石か。玉か。それとも鶏か」
「私は」
いったい何だと言うのか。
芝は素人作家だ。
しかもじぶんが裏作家協会にて激闘の舞台に立っていることなど知らぬのだ。
そんな芝を巻き込んで、壮大な綱引きを演じているじぶんは何か。
ともすれば、裏作家協会とは何だ。
いったい何を肥やしているというのか。
土壌か。
分野か。
いいや、懐ではないのか。
なけなしの矜持とさもしい懐を肥やしているのではないか。
そうではない。
そうではない、と否定するのは容易なれど、現実を直視してもみれば、そう否定することそのものが、何かがねじれて感じられる。
じぶんは何だ。
商業作家だ。
プロの物書きだ。
しかし、思えばよく解からない。
プロとは何だ。
何を以ってしてプロフェッショナルと言えるのか。
玄人とは何だ。
素人と何が違うのか。
玄人だと面白い小説がつくれるのか。
素人ではつくれないのか。
玄人とてかつては素人だったのではないのか。
素人とていずれ玄人になる卵ではないのか。
そうだとも。
「金の卵とは、素人作家であり、彼ら彼女らの小説のことだ」奇数の商業作家は言った。ただの単なる小説好きとして言った。「もう私は綱引きをしない。勝負をしない。楽しくない。こんなのまったく楽しくない。好きにつくらせてもらう。裏作家協会も、地下文芸武闘会も知らん。私は私にとっての面白い小説をつくり、私にとって面白い小説を読むのだ。それ以外にしたいことはない。強いて補足するのならば、好きな時間に好きなだけ眠れて、美味しい物を食べれて、すこしえっちなことをしたい。以上だ」
奇数の商業作家はかように宣言し、かようなメッセージを込めた小説を初めて偶数日に電子網上に投稿した。
芝は目を瞠った。
何せ、本来はじぶんが投稿するはずの偶数日に、奇数の商業作家の小説が投稿されたのだ。法則が破れた。天変地異も同然の偏倚であった。
さすがの芝とて、その小説に込められたメッセージに気づいた。明らかにじぶんを意識した文章だ。物語だ。デジャビュを覚える。
まるでこの間のじぶんと商業作家との返歌合戦のようだ。
否、まさに返歌合戦だったのだ。
じぶんだけではなかった。
向こうも芝を意識していた。
なぜそんな奇妙なことが起きているのかは定かではない。分からない。
裏作家協会がうんぬんと書かれているが、それは本当のことなのか。小説を介して事実を暗示する。虚構に描かれた真実を真実と見做すには、何かが欠けている。
嘘に宿る真実が仮にあるとして、では嘘だと決まりきった絵巻物に宿る真実とは何か。
もはやそこには現実とて、虚構に描かれた真実でしかない、仮初でしかない、仮称でしかないとの真理が浮かびあがるのみではないのか。
深淵な思索にふける芝であるが、ひとまず冷静になるべく猫を撫でた。
野良猫だ。
芝が縁側に座ると、寄ってくる。
近所の猫だ。
するとどうだ。
電子網上の、よく解からない小説の返歌合戦のことなど、どうでもよくなってくる。真実、どうでもよかった。
法則が破れた。
破ったのはじぶんではない。
奇数の商業作家のほうだ。
ならばもう、張り合う必要はないのではないか。元からそんな理由はどこにもなかった。芝がしたいからしていた。
いまはもうしたくない。
ただそれだけの理由で、芝は偶数日のその日には小説を投稿せず、翌日の奇数日に、「もう小説なんて投稿しないよ」「張り合わないよ」のメッセージを込めた小説を載せた。
以降、芝は件の商業作家の投稿欄を確認していない。
奇数の商業作家がその後、何かの枷が取り払われたかのように、毎日のごとく新作を投稿しはじめたことなど知る由もなく、芝は、ときどきぽつりぽつりと浮かぶ欠伸がごとく新作をつむいでは、誰に読ませるでもなく、印刷して引き出しのなかに仕舞った。
野良猫はじぶんの家で飼うことにした。
忙しい。
小説の投稿合戦で張り合う時間が惜しいほどに、芝の現実はいま、目まぐるしく、満たされている。溢れるほどの予想外の猫の奇行に、振り回される日々である。
4528:【2023/01/22(01:51)*アイコでしょ】
グーはチョキより強い。
だがじつのところチョキとてグーよりじぶんのほうが強いと思っていた。
パーはグーより強い。
しかしグーはパーよりも強いと思いこんでいた。
チョキはパーよりも強い。
ところがパーはグーよりもチョキよりもじぶんが強いと思いあがっていた。
けっきょくのところグーもチョキもパーもみな、じぶんが一番強いと思いこんでいた。
そしていざジャンケンをしてみたところで、そこでついた勝敗は、各自グーチョキパー以外の外野でのみ共有され、当の本人たちはみな誰よりじぶんが強いと信じこんでいた。
ジャンケン大会がしばしば行われるが、そこで最後に残るのは生贄にされる敗者にすぎない。グーチョキパーの認識ではかように錯誤がなされるが、生贄にされる敗者の側では唯一じぶんだけが生き残った勝者となる。
上手い具合にみながじぶんを強者と見做す。
じぶん以外が常に敗者だ。
ジャンケンはそうして誰もが優越感に浸れる魔法のシステムとして、万国にて普及した。
ジャンケンポン。
あなたが何を出そうと、アイコか勝利しか現れない。
あなたが負けることはなく、しかしひとたび視点を変えたならば、あなたは絶えず負けている。
グーがチョキよりも強いと誰が決めた。
チョキがパーよりも強いとなぜ判る。
パーがグーより強いのはパーが紙でグーが石だからだ、との理屈は考えてもみなくとも不当であろう。石は容易に紙を破る。三竦みになりようがない。
じつのところ、石にもハサミにも紙にも、それぞれに上位互換が存在する。より規模の大きな、岩に重機に特殊繊維ともなれば、下位互換の各々には目をつむってでも勝てるのだ。
要は規模と相性の話であり、グーチョキパーの力関係はみなが思うよりもずっと多様で複雑だ。
なれど、初めに勝敗の決まりきった組み合わせをつくっておけば、ひとまずの混乱を抑えることが可能となる。
管理する側の都合にて、その場限りの茶番が決まる。
観測する側の怠惰にて、その場限りの優劣が決する。
そうした事情すら、当のグーチョキパーたちは知らぬのだ。
そのうえ、自らが勝者だと疑いもせずに信じこんでいる。
おめでたいこれはそういうお話だ。
あなたが誰かに、勝った、と思う。
そのとき、あなたは負けている。
だがそのことを、管理者でも観測者でもないあなたは知りようがなく、ただただ目のまえの勝利を現実と見做して、満ちるのだ。
仮初の報酬を得て、満ちるのだ。
何を得ているわけでもなく、何に勝っているでもなく。
単に負けを重ねているだけのことなのだが、負けて満ちる何かがあるのなら、それもよいだろうと外野は思う。だから何も言わぬのだ。
知らぬが仏、と思うがゆえに。
あなたのため、と思うがために。
あなたは勝者で、一番だ。
優勝台にのぼった心地は素晴らしい。その気持ちを忘れずに。
負けに負けたあなたが得た、それが一等無駄のない、感慨だ。掛け替えのない感動だ。
得るのではなく奪われている。それでも得られる愉悦にて、負を正に変える魔法のごとく、変換する仕事なのだ。得難くも、尊いそれが仕事なのだ。
よく負け、よく変え、よく働け。
それを以って反転し、勝者の名を授けよう。
誰もがみな勝ちたがっている。
なれば、勝てる夢を授けよう。
誰より競い、蹴落とし、成り上がる。それが勝者の姿というならば。
誰より清い、化粧し、舞い上がる。それが敗者の姿というならば。
どの道、みな、負けることで勝っている。
勝った途端に負けている。
ぐるぐる回る臼のごとく。
擦って、潰して、粉にする。
勝負の舞台と舞台に挟まれて、身を粉にして、働け、働け、価値を生め。
そうして人の生を埋め立てて、勝者の仮面をつけるのだ。
敗者がつける鎖のように。
勝者の仮面をつけるのだ。
ジャンケンポン。
アイコでしょ。
勝っても負けてもアイコでしょ。
4529:【2023/01/22(02:27)*あらん限りに暴れん】
アラン・チューリングはコンピューターの父として知られる。第二次世界大戦にてドイツ軍の暗号エニグマを解読した数学者でもある。
アランの人生は波乱に満ちて悲惨だとする向きもあるが、同じく「アラン」の名を冠するエドガー・アラン・ポーもまたその人生をして波乱に満ちて万丈と評する向きがある。
アランの語源は、とある言語の「小さな石」である、とする説がある。
小石にまつわる寓話には、とある「万」のつく小説家の作品群が思い起こされるが、それがいまここに並ぶ文字列といかに関係しているのかは、語りだせば数年を要する。
したがってここではアランにまつわる偶然の神秘にのみ触れるとしよう。
アランと言えば、アラン機関を思い浮かべる者もいよう。
二〇二二年に放送されたとあるアニメの中に出てくる架空の機関だ。
才能ある個を支援する機関だが、奇しくもアラン・チューリングの名を冠した支援機関が現実に存在する。
双方のあいだにこれといった関係はないはずだが、偶然の神秘に触れるだけならば充分である。
またエドガー・アラン・ポーの名を文字った文豪がかつてとある島国にて活躍した。江戸川乱歩と言えば、ああ、と呻る者もあろう。江戸川乱歩賞はとある出版社が主催をしているが、やはりここでも類稀なる作品を生みだす作家を支援することが建前にある。
奇しくも、アラン機関の名を物語内に組み込んだアニメの版元は、江戸川乱歩賞を主催する出版社と双翼を成す出版社だ。デジタル分野への投資を惜しみなく進めるいわばアラン・チューリングにちかい運営方針と言える。
いずれの出版社にもアランの名は馴染み深い。
アラン・チューリングは「チューリングパターン」なる数式を発見したことでも知られる。
自然界に自発的に発生する紋様は、チューリングパターンからなることもすくなくない。細胞分裂や細胞の配列、ほか生物の紋様はチューリングパターンと合致する。
生物は波の干渉によってその構造が形成される。そのことをチューリングパターンは示唆している。
波と言えば、エドガー・アラン・ポー作の「メールストロムの旋渦」だ。
巨大な渦に巻き込まれた漁師の脱出劇が描かれる。
渦は、アランの語源とも呼ばれる「小さな石」と密接に関係するとある「万」のつく作家が頻繁に題材に練りこんだ「符号」の一つでもある。
小石と渦。
ほかには、青、円、空、がらんどう、などがある。
いずれもチューリングパターンのように繰り返し配列を伴なう。フラクタルに展開され、時間を超越し、空間と空間を結びつける。
境界を描くには、異なる二つの事象が必要だ、とそのとある作家は説いた。
しごく卑近な主張だが、控えめに言って反証を探すのには骨が折れる。
一見すると同じ物でも、それはけして同じではない。
一足す一は、「二」にも「一」にもなり得る。「=」にも「十」にもなり得よう。
同じアランの名を冠していようと、それはけして「アラン二」にはならぬのだ。
アラン・チューリングとエドガー・アラン・ポーは、同じ「アラン」を名乗っているが同じではない。足し算をしようものならば途端に異質な差異にて、分厚い境が生じるだろう。
小石と小石とて、光速で衝突させれば、膨大なエネルギィが生じる。単純に小石二とはならない。一つにもなり、或いは膨大に膨れ上がりもする。
渦を巻き、ときには青く円を描く。
空白を内包したかと思えば、がらんどうはそれで一つの宇と宙を宿す。
このような異なる二つの小石同士の結合を以って、「アラン万丈」と呼ぶ者もある。
どこにいるのか、との問いには、とある作家がとある掌編にてそう書き記していた、と応じよう。
アラン・チューリングは「万能チューリングマシン」を生みだし、「青酸中毒」で亡くなったとされる。「万」と「青」が含まれるが、偶然の神秘と片付けよう。空白記号についてはまどろっこしくなるので割愛する。
エドガー・アラン・ポーはのちに、江戸川乱歩なる作家に影響を与え、江戸川乱歩賞を生みだす契機となった。アラン・チューリングの編みだしたコンピューターがあってこそ、電子網上には無数の虚構作品が横溢し、有象無象の層を成す。
小石と渦と青と空。
各々の符号を練りこむことに腐心したとある「万」のつく作家は、奇しくもいずれの「アラン」とも違い、世に名を馳せることなく埋没した。いまなお電子の海にて深い眠りに就いている。
掘り起こされる予定はいまのところない。
掘り起こされたところで、アラン万丈の二の舞だ、とする意見は至極にしてまっとうだ。波乱とも万丈とも無縁の人生は、邪険にするほどわるいものではない。
アランはときにアレンとも読む。
だからどうした、との声には、あらん、いやん、ばかん、と応じよう。
4530:【2023/01/22(18:28)*両方ありでは?】
ビッグバン仮説と定常宇宙仮説の違いは、主として赤方偏移と宇宙マイクロ波背景放射で説明できるようだ。で、ひびさんは思った。単純な話として、ダークマターなどの重力の高い時空を通った電磁波と、のっぺりとした真空にちかい時空を通った電磁波とでは、同じ「光年(距離)」を移動したとしても、そこで消費されるエネルギィには差異が生じるのでは、との疑問を覚える。同じ距離とはいえど、片方が山を越えるのと平野をまっすぐ突き進むのとでは、たとえ道程そのものが等しくとも、消費するエネルギィには違いが生じるのでは。言い換えるならば、「山を登って下る」仕事Aと、「平野をまっすぐ歩く」仕事Bは、イコールではない。ここでは仕事の変換が必要なはずだ。人間スケールでは、ここの変換を考慮せずとも、位置エネルギィと運動エネルギィのあいだでのエネルギィ保存の法則で辻褄合わせが済むのだろうが、桁が変わる宇宙スケールでは、そこで生じる僅かな差異を度外視してしまうと辻褄が合わなくなることが妄想できる。実際のところはどうなのだろう。異なる仕事Aと仕事Bを等価変換してもよいのだろうか。ひびさんはこれ、好ましくないように思うしだいだ。また、ビッグバン仮説と、定常宇宙仮説は、必ずしも矛盾しないように思うのだ。宇宙が膨張することと、宇宙が定常を維持しようとすることは、矛盾しないこともあり得る。それこそ、光速度についてのひびさんの妄想では、ラグ理論による「相対性フラクタル解釈」をとる。むろん妄想なので現実を解釈するには不当だろうが――たとえば映画は、それを映しだす画面の大きさに依らず、「一定の比率」を維持する。これがいわばラグ理論における「光速度不変の原理の独自解釈」の概要だ。画面の大きさに合わせて、ピクセルが変わる。明滅の規模が変わる。しかし、巨大な画面も、極小の画面も、そこに映る映画は等しい。同じだ。宇宙が膨張したとしても、そこに描写される宇宙像が定常であることは矛盾しないと思うのだが、いかがだろう。ひびさんの妄想ことラグ理論の、「宇宙ティポット仮説(三段構造)」とセットで、なかなか愉快な妄想ではないかな、とメモをしておく。定かではないので、真に受けないようにご注意ください。
※日々、つくつくてん、つくつくてん、好きなひとが見知らぬ人と愛し合っている姿を想像して、喜ぶより先に、うがーー、となる、心のちんまい、ひびさんです。
4531:【2023/01/22(22:30)*光速マトリョーシカ思考実験】
光速についての疑問だ。相対性理論では、物体の運動速度が光速にちかづくほど、物体の内部の時間の流れは遅くなる、と考える。だがひびさんの妄想ではそこが裏返って解釈する。時間の流れが遅くなるのは物体の周囲の時空であり、むしろ光速にちかづく物体の内部は時間の流れが加速するのではないか、と疑問視している。これについて深堀りしてみよう。たとえば銀河くらいの物体が光速で動いたとする。そのときその銀河くらいの物体の内部の時間の流れが相対性理論で考えるように「遅くなる」とする。ではその銀河くらいの物体の内部で、同じく光速で運動する物体を考える。その物体は銀河くらいの物体よりも小さい。だが銀河くらいの物体の内部で光速で運動する。その物体に流れる時間もまた、相対性理論の解釈で言うなれば遅くなるはずだ。この考えを繰り返してみよう。マトリョーシカのように階層的に、光速で動く物体の内部でも高速で動く物体を考える。すると、より小さな物体ほど、そこに流れる時間が遅くなる。これは妙ではないか。現実の観測結果と矛盾しないだろうか。ちなみに、光速で動く物体の内部でも光速で動くことは可能だ。慣性系の内部では、物理法則はその系に適合するように比率が変換される。したがって、銀河の内部で運動する太陽系の内部で運動する地球上で運動する人間の内部で運動する赤血球、といった具合に、物理法則は、各々の慣性系にそれぞれ等しく「比率が変換」されている。むろん、各々に抵抗はある。ガラスの内部の光速と、真空中の光速は異なる。ただし、各々の系において真空を適用し、階層ごとの系で「等しい光速度」を実現することはできる。だがそれが果たして真実に「等しい光速」であるのかは疑わしい――と、ひびさんは疑問視している。「光速が同じ」と「光速度が同じ」はまったく違う。前者は状態だが、後者は比率だ。話が脱線した。脈絡を戻すとして。マトリョーシカのように階層的に光速運動する系を考えたとき、より階層が下層の小さな系ほど、本来は時間の流れは速くなるのではないか。すると、現実の観測結果と直観としては合致する。ただし、相対性理論が間違っている、という話ではない。ここは勘違いしないで欲しい。解釈の仕方がおかしいのではないか、という話をしている。光速にちかい速度で運動する物体ほど、その内部の時間は加速し、その周囲の時空の時間の流れが遅くなる。高重力の物体の内部の時間の流れは速くなり、その周囲の時空の時間の流れは遅くなる。ひびさんの妄想ことラグ理論ではこのように考えるが、これは相対性理論と相反する考え方ではない。相対性理論で扱っていない視点を考慮すると、こう考えたほうが理に適っているのではないか、との疑問を呈している。内と外を、どのように定義するのか、の視点の差異によって、どこが遅くなり何が速くなるのか、は解釈が変わる。地球の内部を考慮しないのであれば、地球の周囲の時空の時間の流れが遅くなることと、地上の時間の流れが遅くなることの区別はつかない。どこを外と見做し、どこを内と見做すのか。相対性理論では、ここが大分疎かにしたまま議論を進めているように感じられてならない。あくまで概要の説明しか読んだことがないがゆえの錯誤かもしれない。その公算が高そうだが、ひとまず一般に流布している相対性理論の説明では、やや妙な結論が導かれるな、とマトリョーシカ思考実験を例に挙げて述べておく。ひびさんの勘違いかもしれないし、むしろ人間スケールの直観のほうが間違っており、ごく小規模な例外である可能性もある。実際には、宇宙スケールでは、階層構造における内部ほど、時間の流れは遅くなるのかもしれない。定かではない。ひびさんの妄想という名の疑問ですので、真に受けないようにご注意ください。
4532:【2023/01/22(22:30)*流れがあって変数が活きる】
オッカムの剃刀の概念をひびさんは、そうなの?と思っている。より単純な説明のほうを選択せよ、複雑な説明をよしとしない。そういう理屈だと思っている。以下、ウィキペディアさんから引用する。【「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする指針】だそうである。ひびさんは思うに、より単純な理屈とは要するに、より抵抗の少ない筋道ということだ。手続きがなければそれだけラグが小さくて済む。すると優位にそこに流れができる。それはたとえば乗り継ぎの少ない移動手段のほうが楽ができる。間違えを犯しにくい。だからそっちのほうがスムーズに移動できる。そういうことだと思っている。しかし、優位な流れは、それが絶対唯一ではない。もしそうなら川に渦は巻かないし、分岐点もできない。波とて生じぬ道理だ。むしろ、複雑な手続きを得ている流れが変数として、大きな流れに変化をもたらすからこそこうまでもこの世は複雑に変遷しつづけるのではないか。言うなれば、世界の変数として機能しているのは、オッカムの剃刀で除外される複雑な筋道を内包した事象と言えるのではないか。どっちも大事だ。単純がゆえに顕性に働く大きな流れがあり、複雑ゆえに潜性に働く小さな流れがある。この二つが交じり合って干渉し合うからこそ、こうまでも世界は万物流転しつづけるのではないか。流れがあり、変数がある。オッカムの剃刀は、変数を除外する考えに思えてならないが、実際のところはどうなのだろう。ひびさんは、ひびさんは、剃刀さんを振りかざすオッカムさんが、オッカネーずら。(オッカムと掛けたの?)(うん)(ちょい無理があったね)(ね)
4533:【2023/01/23(01:11)*銀河の内部と外部の時空は同じ?】
相対性理論での説明で疑問なのが、なぜ思考実験にロケットを使うのか、という点だ。中身が空洞の物体は、宇宙スケールにしろ人間スケールにしろ、例外的な構造と言えるのではないか。ブラックホールや宇宙の泡構造など、比較的特殊な構造だと思うのだ。原子とてスカスカだから、空洞だ。そういう意味では原子をロケットに見立ててもいいように一見すると映るが、しかし原子の質量の大部分は中心の原子核にある。したがってそれを以って空洞構造と見做すにはいささか疑問の余地がある。相対性理論においてなぜ思考実験でわざわざ特殊な空洞構造のロケットを使って考えるのだろう。頭がこんがらがる要因の一つに思える。単純な話として、空洞は比率の違いが二重になっている。内と外で、異なる系を重ね合わせている。惑星で考えてみれば瞭然だ。惑星にとっての内とは、惑星それそのものだ。地層のような階層性を帯びていたとしても、それそのものが惑星自身である。だが空洞構造を伴なう物体は違う。飽くまでそれ自体は、内と外を隔てる境界面である。ロケットならば、外壁がロケット本体として機能する。内部の空洞は、それもまた別の密度を持つ時空だ。慣性系として共に光速移動可能だが、それと惑星の光速移動は別の描写になるはずだ。解釈が異なる。ブラックホールの内部が分からないのと同様に、空洞構造の物体が光速移動する場合の内部もまた、特殊な描写になるのではないか、との疑問を覚える。これは、銀河内部の時空と外部の時空の関係に通じる疑問だ。たとえば二つの惑星が並行して宇宙空間を移動しているとする。そのとき惑星のあいだを時空は「すり抜けていく描写」になるはずだ。では惑星の数をどんどん増やしていこう。すると銀河のようになる。このとき、細々とした「惑星や恒星」のあいだを時空はすり抜けつつ、トータルでは銀河内に閉じ込められ、閉鎖的な系として振舞うと想像できる。ここまでで異論はあるだろうか。もしあるとすれば、「銀河であろうと時空は惑星間を等しく擦り抜ける」と考えるか、「どのような状態であろうと時空は流動しない、あくまで物体との位置関係の差異があるのみだ」と考えるか。どちらかの派生としての反論に大別できるだろう。位置関係の差異と流動との違いは、時空が川のように流れ得るのか、それとも陸地のように微動だにせず、あくまでその上を移動する物体があるのみなのか、の違いに言い表せる。だが宇宙は膨張している。つまり時空は「流れ得る」のではないか、とひびさんは考えたくなるが、ここはまだ何とも言えない。いずれにせよ、銀河内と銀河外とでは、時空の振る舞いは異なるはずだ。現にいまは宇宙膨張の影響を、銀河内部ほど受けない、と考えられている。実際がどうかは知らないが、だとすれば、銀河のように一か所に無数の惑星がぎゅっとなっている場では、時空の流れが滞ることが妄想できる。さてここで、だ。最初の疑問に戻ろう。ロケットのように内部に空洞を宿した物体が光速にちかい速度で移動するとき、ではその内部と外部とでは時空はどのように異なるのか。言い換えるのなら、銀河内部の時空と、銀河外部の時空は、どのような差異を帯びているのか。注目して欲しいのは、このとき銀河を構成する惑星の運動は、別途に考慮可能な点だ。むしろ往々にして、そちらに目が留まる。考えが費やされている。しかし、ロケットの思考実験を拡張して銀河に当てはめるのならば、ロケット内部とは銀河内部の時空に相当するはずだ。銀河における惑星はむしろ外壁や、内装に値するはずだ。ここの比較を検討したうえで、相対性理論は時空の描写を考慮できているのかが、よく解からない。言い換えるのならば、惑星の運動を相対性理論で考えるときには、ロケットの思考実験を当てはめるのは理に適っていないのではないか、とふしぎに感じる。むろん、あんぽんたんなひびさんの錯誤に勘違いに、お粗末な妄想にすぎないのだろうけれども、空洞構造って特殊じゃないですか、という点をひとまずメモしておく。定かではないので、誰か教えてほしいですな、の願望を記して、本日のひびにゃんにゃん。「日々記。」とさせてくださいな。おちまい。
4534:【2023/01/23(01:14)*休んで遊んでぼーっとする】
やっぱり思うのが、ひびさんはずっと何かに集中するよりも、適度に「あははーあははー」とした時間をつくりながら、サボりながら、休み休み色々をしつつ、好きなときに遊べると、妄想が膨らむな、ということで。根詰めてもあんまりよろしくない気がする。あくまでひびさんは、だけれども。
4535:【2023/01/23(02:19)*痴れ者ですまぬ、すまぬ】
第二次世界大戦のことも知らなければ、第一次世界大戦のこともろくすっぽ知らないので、さすがにマズいかな、と思ってまずはウィペディアさんを覗いた。頭パンクするかと思った。固有名詞多いね。オスマン帝国とか聞いたこともなかった。よくこんなんでえっらそーに、戦争がうんたら平和がうんたら文字を並べられたものだな、とひびさんのことを思うが、無知ゆえに恥辱の念を覚えずにいられるのはデメリットが多いとはいえども、なけなしのメリットと言えぬでもない。郁菱万の「マン」繋がりでオスマン帝国にビビットきて、やはりウィキペディアさんをまずは頼った。が、要領を掴めず断念した。歴史はむつい(歴史「も」むつい)。多様性が豊かゆえに繁栄した時期もあった、みたいな記述をWEBの記事で見掛けたが、そうなのか、でもなんでじゃあ滅んだの、と疑問に思う。権力争いがうんぬん載っていた。案外どんな国のどんなシステムであろうと、やはりというべきか、奇禍の種は人間の我執に欲望なのだなぁ、と底の浅いキュウリ漬けをパリポリしたくなる。権力かぁ。ひびさんが権力持ってたらあれだな。モテモテのウハウハだぜぇ、を満喫して、ついでに嫉妬されないように嫉妬される余地を失くすべく、じぶん以外のみなの者に、大盤振る舞いで「しあわせになーれ」の魔法を掛けちゃうな。んで以って、さらに保険をかけて、ひびさんが一番さもしくも貧しい暮らしを送るな。これで嫉妬する人はおらんじゃろ。がはは。(それ、モテモテのウハウハにならんくない?)(はっ!?)(しまった、みたいな顔を迫真にするな)(違うんです。あれです。貧乏でもさもしくても、ダサくても、アホくても、それでも愛されキャラでいたいんです。そういう風潮になーれ)(貧乏でさもしくてダサくてアホほどモテる世界? ふつうに嫌だわ)(あぎゃあ。夢を、夢を壊さんといてください)(ひびさんはあれよね。権力持たせちゃいけない人っていうか、権力持たせたら不幸になるタイプの人よね)(な、なんで)(権力持ってしたいことがモテモテのウハウハだぜ、は私欲にまみれて庇いきれない)(ちゃんとみんなのしあわせも願ったよ)(ついででしょ。保険ででしょ。なーれ、って唱えただけじゃん。アホか)(うわーん。手厳しい)(ひびさんにはあれよ。権力はいりません、って拒める程度の淡いサイダーみたいな権力だけあればいいよ。それくらいが人間ちょうどいい権力ってもんよ)(そ、そうかな)(そうだよ)(でも好きなひとには好かれたい。嫌いな人からも好かれたい。ひびさんを嫌う人からも漏れなくみなから好かれたい。みなひびさんを好きになーれ)(それ、嫌われてる自覚ある人しか唱えない願いじゃない?)(無駄に現実を突きつけないで)(知っといたほうがいいよ。直視すべき。現実ってやつをだよひびちゃん)(嫌じゃが)(知れ)(手厳しい!)
4536:【2023/01/23(04:11)*暗っ! ピカー!】
素朴な疑問なのだけれど、雨がドっと降るとその地域の気温は下がるよね。じゃあ、雪がドカっと降っても気温は下がるよね。で、地球温暖化は大気中の水分を増やす方向に働くだろうから、これからはますます雪が降るときはドカっと降るようになるよね。そのときの、急激な「地表の温度変化」は、まるで上から蓋を落とすような、大気のうねりを生まないのかな。それこそ天狗の団扇ではないけれど、ばふん、と大気が動いたりしないのだろうか。その「ばふん」は、相対的に「冷たい空気と温かい空気」を選り分ける方向に圧を掛けないのだろうか。言い換えるなら、大気の流動が、ぎゅっと加速するときと、そうでないときが徐々に分離する方向に流れないのだろうか。これまでは全世界で対流がゆるやかに連動していた。だがこれからは、「ドカっぎゅっ」が局所的に全世界同時に発生する。まるで自然のポンプのように作用しないのだろうか。大気中の水蒸気が増せば、この手の「ドカっぎゅっ」は頻発するように感じるがどうだろう。ひびさんに欠けている知識としては、寒波ってなんでできるの?という点が、いまは思考にぽっかり穴を開けている。熱波は、なんとなく分かる。太陽光と海水温度と大気中の水蒸気の関係で想像がつく。でも寒波がよく解からない。なんで熱波と反比例するように冷えるのだろう。冷えるというか、低気圧ということなのだろうか。ここら辺の、気圧と気温と気候の関係がひびさんにはまだむつかしい。台風の構造もじつは全然腑に落ちていない。なんでそうなる?となる。知識が虫食い状態で、体系的に学んでいないデメリットがモロに出ているな、と感じる本日のひびさんなのでした。おやすむ。(好きなひととおデートする夢見ちゃお)(三百歳のひとが言ってると思うと、胸がきゅっとする)(キュンとする?)(きゅっとするって言った)(どう違うの)(心臓に鎖が絡みつく感じ)(エンペラータイムじゃん)(緋の眼の民)(目良しの民じゃん)(点が一個多いよ。良しから点を一個引きなさいよ)(許せ。視力10点零ゆえ)(視力良しの民じゃん)(うひひ)
4537:【2023/01/23(08:47)*世界新記録樹立の確率は、たとえどれほど低くとも、樹立したらそれは一つの現実だ。隕石に直撃される確率がいかに低くとも、直撃されたらそれも一つの現実だ。雷ならば隕石よりも直撃する確率が高いと言えるが、雷雲が、それとも流星群が通りかかるたびに、直撃する確率は変動する】
メリットとデメリットの比較は、短期中期長期で、その都度にメリットとデメリットが逆転しないかどうかを考慮しなければ、合成の誤謬を起こす可能性を減らせない。第一に、対処すべき問題が時間経過によってどのように悪化するのか、それとも沈静化するのかを検討せねばならない。前提条件が変わったのならば、メリットとデメリットもその都度に変わる。基本的に対処法においては、問題と共に、その手段のメリットとデメリットもまた時間経過によって変わっていく。極論になるが、海でもないのに陸地で浮き輪をせずともよい。しかし、洪水が起きたならば、浮き輪を嵌めていたほうが溺れるリスクを減らせる。状況によって対処法が足枷になることもあるし、なければ困る必須の命綱になることもある。それとて、バンジージャンプでは必須の命綱は、日常で嵌めていたらデメリットのほうが遥かに大きい。至極単純な結論になるが、ケースバイケースで判断していくよりない。という前置きをしたうえで、付け加えるならば、デメリットが時間経過にしたがって増える対処法もまた存在する。それこそ、自動車でばかり移動していれば歩く頻度が減って、体力は落ちる。右腕ばかり鍛えていれば、筋肉のバランスが崩れて骨格が歪みかねない。対策や対処法というのは、継続すればするほど、そこに向けて適応するように人体は変質する(むろん強化されるばかりではなく、酷使することで消耗する方向に変質することもあるだろう)。その変質が生活にも人体にも好ましい変質ならばよいが、その好ましさを決めるのは環境との兼ね合いだ。人体だけの問題ではない。そして環境は、個々によって異なる。生活習慣がまず違う。食べている物も、疾患も、病歴も、細かな差異を挙げ連ねればキリがない。スポーツを考えたら分かりやすい。重量挙げの選手と百メートル走の選手。水泳の選手と射撃の選手。ほかあらゆる種目の選手を比べてみればいい。各々に特化した練習方法があり、苦手な種目があり、突出した能力を発揮できる発達した器官がある。種目別で見たところで、選手ごとに最適化された練習方法があるはずだ。すべての選手に合致した「正解の練習方法」なんてものはない。傾向として、しないほうがよい練習は共通するかもしれないが、それとて敢えてそれを熟すことで超越した能力を発揮するようになる選手もいるかもしれない。人体はそれほど個々によって異なるし、環境との兼ね合いでさらにその差異は開いていく。そして環境は一定ではない。単純な話だが、変化や差異に目を配ろうとしないといつでも人間はこの手の変化を見落としてしまう。日々の遅々とした時間の流れのなかでは、そうした細かな差異を考慮せずとも困らないからだ。だが、メリットとデメリットを比較する場合には、短期中期長期での線形での変化を見ながらメリットとデメリットを比べないことには、短期でOKだから長期もOKだろう、と短絡に考えてしまう。すると、稀に、進路が大幅に狂っていることに気づかずにあらぬ未来へと歩みだす失態が起きてしまう。人類の犯す致命的なミスの少なからずはこの手の構図を伴なっているようにひびさんは感じている。所感でしかない。だが、この手の見逃しがちな差異を不可視のままにせずにおけるのなら、防げる大惨事もあるように思うのだ。常に目を凝らしておくのはむつかしい。見逃してしまうのが常だろう。それでも、現代人は八十億人もいるのだ。みなで代わる代わる、異なる場所にときどき目を凝らすだけでも、見逃してきた細かな差異や、それとも類似項に目を留めることができるようになるのではないか。違いを探るには、似ているモノをまずは知らなくてはならない。似ているモノを探るには、まずは違っているモノを知らなくてはならない。相互の視点を切り替えながら、ときに双方ともに駆使しつつ、不可視の穴を探ってみるのも一つなのではないのか、と何度目かになる結論になってしまうが、繰り返し、ここに述べておこう。定かではないのだ。ひびさんは何の専門家でもないのである。なんとなく浮かぶ妄想と、なんでなんだろうな、の疑問ばかりが連なってしまう日誌風味の小説もどきを並べ、本日何度目かの「日々記。」とさせてください。おはようございます。いまから寝るのでおやすみなさい。どうぞみなさん、無理せずに。ひびさんばっかり、ぐっすりグーグーしちゃって、すまぬ、すまぬ。ありがたくきょうもぬくぬく寝る日であった。しわわせ。
4538:【2023/01/24(01:58)*見逃しの罠】
探偵は遺留品に目を通した。
「なるほどこれがダイイングメッセージですか」小型電子端末だ。画面にテキストが打ってある。生体認証を解除しなければ操作不能だ。表示済みの画面を見ることしかできない。本人の記述に間違いはないようだ。「どれどれ。【佐藤さんも怪しいが田中さんも怪しい。佐藤さんが特に怪しいが、しかし犯人は××だろう】とありますね。容疑者はこの二人のほかに誰がいるのですか」
探偵は馴染みの刑事を質した。
「高橋に佐々木。ほか容疑者候補は十人ほどおりますな」刑事は応じた。「被害者は犯人を確信していたんでしょうな。だから殺された。ということは、すでに候補に挙げられている佐藤と田中は除外できますな。彼らは本命ではない」
「ふむ」探偵は考え込んだ。「なぜ肝心の本命の名前が潰れているのでしょうね」
「犯人が潰したんでしょう」
「しかし端末は被害者本人しか操作できないはずです。画面を切り換えることすらできないでしょう。生体認証が厳重なので」
「ならば脅されたのではないのですかな」
「だとしたら初めから記述そのものを消すでしょう。ブラフの文章を書かせるにしても妙です。なぜ本命の名前だけをわざわざ【××】にしたのか」
「意図があると?」
「それはあるでしょう。意図がなければこんなまどろっこしい真似はしない。むしろ被害者はじぶんが殺されることを知っていた。だから敢えてこの記述を端末に残しておいたのではありませんか。犯人がそれを覗くことも想定して」
「よく解かりませんな。ならばなぜ犯人は端末を現場に残したままにしたのだね」
「残したほうが都合がいいと判断したんでしょう」
「あり得るかねそんなことが」
「いいですか。刑事さん。刑事さんは画面のダイイングメッセージを読んで、まっさきに、すでに記述され、かつ本命ではないはずの佐藤さんと田中さんを除外しましたね」
「ああ。何か問題でも」
「なぜ除外したのですか」
「なぜってそりゃあ」
「本命の容疑者――おそらくは犯人の名前であろう箇所が【バツバツ】になっていたからではありませんか」
「そうだが。それの何がおかしい」
「誰もが刑事さんのように考えるのでしょう。犯人とて、被害者を殺したあとで遺留品を漁ったはずです。そして端末の画面を見た。そこに記された文面を目にし、最初は破棄しようとしたのかもしれない。しかし現場から端末がなくなっていれば警察はそれを探します。いまは位置情報から監視カメラまで予期せぬ証拠はいくらでも残ります。犯行計画にない余計な真似はしないに越したことはありません。何にも増して、被害者の残していたダイイングメッセージは、犯人にとって都合がよかった」
「なぜだね」
「まっさきにじぶんが容疑者候補から外されると判っていたからです。刑事さん。あなたがまっさきにそうしたようにね」
「つ、つまり何かね。キミは犯人が、被害者のダイイングメッセージに載っていた【佐藤】か【田中】だと言いたいのかね」
「ええ」
「だがダイイングメッセージには、【しかし犯人は××】と書かれているではないか」
「そうです。【しかし】と否定したからには、佐藤さんでも田中さんでもない、とふつうは考えます。犯人もそう考えたのでしょう。容疑者候補に挙がることは想定できたはずです。ならば、端末をそのまま現場に残して立ち去るのが利口です。もちろん佐藤さんと田中さん以外が犯人でも、何も持ち去らずに去るのが利口な選択ではあるでしょう。しかし端末の中にはもっとほかにじぶんに言及した記述があるかもしれない、とふつうは考えます。だが犯人はそれを考慮しなかった。なぜか」
「わ、わからん。なぜだね」
「被害者が思い違いをしたと思いこんだからです。ダイイングメッセージの文面を見たことでね。犯人は、被害者がまったくお門違いな犯人像を思い浮かべている、と考えたのです」
「どういうことだね」
「わざわざ被害者は、じぶんが殺されるかもしれないと想定しておきながら最有力候補の人物の名前を伏字にしていた。ダイイングメッセージを残しておきながら肝心の名前を伏せていた。これは、犯人を庇ったからだ、と考えるのは一つの道理です。現に被害者にはそのつもりがあったのかもしれません。ただしそれは、伏字にしていたことについて、ではありません。被害者は、もし仮にじぶんが殺された場合に備えて、犯人に直結する手がかりを残しておいた。必ず現場に残るように工夫を割いて。じぶんが殺されたときにのみ発動するようなメッセージを籠めたのです」
つまり、と探偵は告げた。
「端末が持ち去られない、破壊されない、という事実そのものをダイイングメッセージに仕立て上げたのです」
「被害者が犯人の行動を予期していたとでも言うのかね。まるでそれは誘導ではないか」
「ええ。していたのでしょう。被害者はじぶんが殺されるかもしれない危険性を知っていた。知っていたうえで、それを拒まなかった。動機の背景については刑事さんに任せますが、いずれにせよ被害者は、仮に犯人がじぶんの予想していた人物であれば端末を現場に残すだろうと見越していたと言えるでしょう。そして現に犯人は、端末を開き、その画面に記されていたダイイングメッセージを読んで、そのままにした。そのほうがじぶんに有利になると考えたからですが、その奸智そのものが被害者の手のひらのうえで踊らされた罠だったのです。そうとも知らず、いまごろ容疑者候補から外れるための供述を練っているころでしょう。被害者との確執を隠さず、動機の存在を隠さず、さりとて偽のアリバイをつくりながら。いえ、アリバイ工作自体は入念に事前に策が練られていたのでしょうけれど」
「つまり、犯人は誰なのだね」
「証拠集めは刑事さんに任せます。私に言えるのは、被害者がダイイングメッセージに籠めた、【仮に現場から端末が持ち去られず、破棄もされていなかったとしたらこの人が犯人です】との人物の名前が」
ごくり。
刑事の生唾を呑み込む音が聞こえた。
「佐藤さんだ、ということだけです。田中さんのことも念のために調べておいたほうがよろしいでしょうが、【しかし犯人は××】の直前に名前があり、なおかつ二度も怪しいと言及されている佐藤さんが、被害者にとっては最も犯人になりそうな相手だったと言えるでしょう」
「つまり、本命であった、と」
「敢えて隠したわけです。犯人がそれを見て、じぶんは本命ではないのだ、と思いこむように仕向けるために」
「わ、わかった。詳しく調べてみよう。キミがいてくれてよかった。捜査の進展があったら連絡する」
「私の推理が外れていたときにだけでいいですよ。動機の背景には興味がないものでね」
探偵は帽子を被ると、一瞬だけ被害者の遺体に目を配った。
遺体は胸を矢で射抜かれ、そのうえ氷漬けにされていた。
探偵は傷ましいものから目を背けるように、犯行現場から離脱した。夜風が刃のように鋭利な真冬のことである。
4539:【2023/01/24(11:09)*天秤の傾く側からあなたへ】
トロッコ問題、と訊くだけで辟易するのは、世の中の大部分の隘路においてどっちを選んでも損しかしないような選択肢しかないからで、例に漏れず私もいま、特大の選択を迫られている。
「理不尽だよ」私はぼやいた。「どっちかを選べとか、そんなのさあ」
「いいって。気ぃ使わないで」
ミカさんはそんなことを言うけれど、投票権を与えられたのは私なのだ。
いいや、全世界の人間が投票権を持っている。すでに使った者が大半であるにせよ。
「私はミカさんを選ぶよ。だって、だってさ」
「無理しなくていいよ。あたしを選んだところで、だって、ねぇ?」
ミカさんの言わんとしていることは解った。
全人類を犠牲にして生き残ったところで、罪の意識に苛まれて自殺したくなるに決まっているのだ。
「だってほら。あたし家事とか全然だし。コーヒーも満足に淹れらんないよ。どうする? 火とか電気とか使えなくなるかもだよ。人がいなくなったらさ」
思ったよりも現実的な問題で悩んでいたらしい。生き残る気満々ではないか。
「なんか悩んでるのがアホらしくなってきました。このままミカさん、のほほんと生き残りそうですね」
「だといいけどねー」
事の発端はあまりに唐突だった。
ミカさんが掘り当てた遺物が魔法の天秤で、ミカさんは呪われた。
と同時に、全人類もまた呪われた。
全世界同時に脳裡に同じ【声】が響いたとされる。私も聴いたからおそらく事実だ。聞き逃した者がいたという話を聞かないので既成事実としてまかり通っている。赤子がその言葉を聞き取れたのかは分からないけれど、寝ていた人とてその【声】で飛び起きたというのだから、よほどの強制力がその【声】にはあったとされる。言語の垣根は魔法の力でどうにかなった節がある。
内容だけが等しく全人類に伝わった。
――この娘と全人類の命。どちらを生かすかを選ぶがよい。
ただそれだけの問いが脳裏に響いた。
全人類が等しくその【声】を聴いた。
期日は一年後とずいぶんと猶予があった。
三日で切れる期日だったならばまだしも、一年は長い。期日が三日だったならば誰もがその【声】を幻聴と見做して、何を選択するでもなく期日を過ぎていたかもしれない。だが現代社会では、謎の【声】の噂は瞬く間に電子網上で話題となった。
脳内に響いたのが【声】だけならばまだしも、【声】が「この娘」と述べた際にはみなの脳裏には同じ娘の姿が浮かんだ。
奇しくもそれがミカさんだったので、言い訳のしようもない。
ミカさんはミカさんで、すみません、と律儀に電子網上で謝罪した。事情を説明するための動画を投稿したものだから、魔法の天秤を掘り当ててしまったことが元凶であることが周知となった。
「ミカを選ぶとみなが助かるってこと?」
各国の市民のあいだで、侃々諤々の議論が繰り広げられた。
当初こそ真に受けなかった人々も、半年後に再び例の【声】が脳裏に響き、認識を改めた。まったく同じ声が聴こえたのだ。のみならず、最初のときと同じ内容とミカさんの姿が、あたかも脳裏に直接スープを流しこむように響き渡った。
例外なくすべての人類の脳裏に、である。
いよいよとなって各国の政府までもが調査に乗り出した。
半年の猶予の消失は大きかった。
「どっちかを選べとしか指示されておらんが、これはいったい何を試されているのだろうね。選んだほうが助かるのか。それとも、選んだほうが滅ぶのか」
至極もっともな疑問だった。
謎の【声】は、選べ、としか指示しなかった。
それによって何がどう変化するのか。誰にもその後のことが分からない。
政府が方針を打ち出すまでに、全人類の内の過半数がすでに脳内にて投票とは名ばかりの選択を終えていた。
選択を終えると、脳内からミカさんの姿が消えるらしい。私には元からミカさんの記憶があるので、その違和感には気づけないが、どうやら選択をするまで見知らぬミカさんの姿がみなには絶えず脳裏に浮かんでいたらしい。
さぞ煩わしかろう、と思うが、選択後に脳裏から消え去ったミカさんの姿を名残惜しんで、わざわざミカさんファンクラブまでつくった連中もいる。
政府はミカさんのためにセーフハウスを用意した。
ミカさんはそこで残りの半年余りを過ごすこととなったが、ついでに私もセーフハウスに招かれた。遺物発掘時に私もミカさんのそばにいたので、重要人物扱いされているらしかった。私の知らぬところで私の個人情報までもが流出しており、ミカさんを差し置いて私は一人で恐怖した。
「ミカさん、よく平気ですね」
「平気ちゃうよ。容量オーバーで思考停止してるだけ。だいたいさ。冷静になったところで何ができるって。何もできんでしょうがよ。したらもう、腹ぁくくって余生を過ごすっきゃないだろうて」
「だろうてってミカさん」言われてしまえばその通りなのだ。期日が来るまではただ危害を加えられないようにセーフハウス内でぐーたら過ごすよりない。
「結果は判りきってるわけでしょう。人類投票において、一人と人類どっちを生かすかなんて考えるまでもない。みな人類を選ぶでしょう。よほどの酔狂じゃなきゃそうするよ。あたしの親だってきっと人類の側に投票するね」
「そんなことないですよ」
「いやいや。あたしだってそう頼むよ。だって家族はもちろん、従妹とかクラスメイトとか、それこそチミにも生きて欲しいしな」
「そんなこと言われたらますます私は迷うんですけど」
「迷うくらいなら人類にしときなさい。ひょっとしたらあたしとチミだけが別の惑星に飛ばされちゃうかもしれないぞ」
それだったらどんなによいか。
思ったけれど、ミカさんだってそんなふうに本気で考えているわけではないはずだ。別の惑星になんか転送されない。そんな確率は万に一つくらいしかないのだ。
電子網を覗けば、世界中の投票結果はだいたい判明する。各種報道機関から個人の投稿まで、統計データはよりどりみどりでずらりと並んでいる。
結果から述べれば人類の八割はミカさんを切った。生き残るべくは人類だと判断した。
二度目の【声】が聴こえる以前に、人類の大半は投票を終えていた。
いまさらミカさんが勝つ可能性はない。
残りの投票を行ったところで、人類を生かしミカさんを切る選択は、人類の総意として決する。少数派の意見は聞かなくていいのか、との意見は民主主義からするとまっとうな意見だが、それを言うのならばミカさんの人権はどうなのか、ミカさんの意見が一番大事で最優先なのではないのか、との反論はどこからも聞こえてこず、私が唱えてもむなしく響くだけだ。
「こうなっちゃったもんはしょうがないよ。残りの余生を楽しもう。ほら見て。冷蔵庫に高級食材いっぱい詰まってんの。食べ放題だって。やったぜ」
「ミカさん」
空元気なのか、本心から諦めているのか。
実感が湧かない。
それもあるだろう。私とて現実味のなさに戸惑っている。
期日が来たらどうなるのか。
人類を生かすと決めたみなはどうなるのか。
切り捨てられたミカさんはどうなってしまうのか。
元凶となったはずの魔法の天秤は、ミカさんの手元にはない。政府機関が調査するために取り上げた。破壊してみればひとまずの急場を凌げるかもしれないが、ミカさんを切り捨てればそれで済む「ミカさん以外の人類」にとってそれを試すにはリスクが高すぎる。
悶々としていても無駄に精神がすり減っていく。
ミカさんはというと、世界で唯一期日までは安全に生きていなければならない個人の称号を得て、自由気ままに日々を過ごしている。半年という期日があるにせよ、何にも束縛されない自由な時間は、それはそれで気持ちがよいのだろう。現実逃避をするだけならばこの上ない環境ではある。
一流ホテルもさながらの品ぞろえに設備なのだ。
「人間暇になると勉強はじめるんだね。知らんかったわ」
大学にいたときはいかに勉学から顔を背けていられるのかに尽力していたミカさんが、進んで本を開いて読みだした。のみならずメモをとり、実験を行い、記録をもとに研究まではじめた。
「どうしちゃったんですかミカさん。急に真面目になっちゃって」
「あたしはいつだって真面目だよ。いまはたまたま気になることができただけ。これまではたまたまいかにサボれるのかに真面目だっただけ」
何か残しておいたら寂しくないだろ。
ミカさんは主語の曖昧な箴言を述べた。形見があればおまえも早く立ち直れるだろ、と今のうちに保険を掛けられたようで私は余計に胸が苦しくなった。
ミカさんとの時間を大事にしたかったのに、私はミカさんのそばにいられなかった。ミカさんの顔を見ると、ああこの人はもうすぐ死んじゃうんだ、と思って目頭が悲哀に熱を帯びる。のみならず、ミカさんの残り少ない時間をミカさんから奪ってしまうようで気が引けてしまうのだ。
私の内心の葛藤など知らぬミカさんは、期日まで残り少ない日々を順当に研究に費やしていく。
研究成果がつぎつぎに蓄積され、何だか知らないうちにミカさんの周囲には学者さんたちが集まりだした。セーフハウスを手配した政府機関が呼び寄せたらしい。
どうやらミカさんの研究成果に、注目すべき発見があったそうだ。その整合性を確かめている最中らしい。
私以外の人間に囲まれるミカさんを私は、遠巻きに眺めた。
ミカさんの時間が私以外の人間たちに奪われている。こんなことならば私も遠慮をしなければよかった。後の祭りである。
刻々と期日は近づく。
松尾芭蕉は奥の細道で、「月日は百代の過客にして行き交う年もまた旅人なり」と謳った。光陰矢の如しとも云う。
私の目のまえを通り過ぎる旅人はまるで地球の自転に置き去りにされた小石のようだった。ちなみに地球の自転は秒速四百メートルを超し、太陽系自体も銀河内を秒速ニ十キロで移動しているらしい。
慣性の法則に引きずられなかったら、あっという間に置いてきぼりになる。
そうして私は心の整理の付かぬままに期日前日を迎えた。
「で、けっきょくどっちに投票したん。や、言わんでもいいけど」
「そりゃミカさんに入れましたよ」私は嘘を言った。「狭いんでもっとそっち行ってもらっていいですか」
無理を言って今夜は一緒に寝てもらうことにした。
ミカさんの体温は高く、広いダブルベッドも私には狭く感じた。ミカさんが無駄に幅をとって私をぐいぐい端に追い込むせいだ。
「どうなっちゃうんですかね。私たち」溜まらず私は口に出した。どの道明日になれば判明することを不安に押しつぶされそうになって我慢できずに漏らしていた。「ミカさんか人類か。どうなるんでしょうね」
「まあ順当に考えるならあたしが消えるだろうね。それか何も起こらないか」
「何も?」
「単にアンケートを取りたかっただけかもしれない」
私は噴きだした。
そうだったらどれだけいいか。
「別にいいじゃんよ。チミは変わらずの生活がつづく。あたしの代わりにここに住んだままでもいいらしいよ」
「初耳なんですけど」
「管理人のおっちゃんが言ってた」
声の抑揚からして、嘘だな、と判った。ミカさんはじぶんからそう頼んだに違いない。一緒についてきたあの小娘にじぶんの分の境遇を与えてやってくれ、と。全人類の代わりに死ぬかもしれない相手から頼まれたら拒めないだろう。そしてミカさんはそれをおくびにも出さずに、しれっとこうして告げるのだ。前日の、しかも夜に。
もはやあと数分であすを迎える。
あすのいつなんどきに期日が過ぎるのか、正確なところは誰にも分からない。
一度目も二度目も正午ちかくに【声】が聴こえた。
公の記録では正午過ぎて六分後のことだとされているが、世界中で同時に【声】は発生したので、基準となる国がどこかによってそれも曖昧だ。
どの道あと六時間が経つとミカさんはいなくなってしまうかもしれない。
私はその未来を想像し、ミカさんの身体にしがみついた。さもベッドから転げ落ちないようにするためだ、と醸しながら。
「思ったんですけど不公平ですよね」私はミカさんのゆびを握った。
「不公平?」
「ミカさんはだっていいですよ。消えても消えなくとも得をするじゃないですか。消えなければ生き残れるわけですし、消えちゃっても人類を救った英雄ですよ英雄」
「まあ、そういう考え方もできるか」
「でも私は違うじゃないですか。私は損しかないですよ。だってそうでしょう。ミカさんがいなくなったら哀しくて、人類が滅んだら私は消えちゃう。私はどっちにしても損しかしない。私が世界一可哀そうな人間だと思うんですけど」
「そういう考え方もあるか。あるな。うん、あるね」
「ミカさんはもっと残される人のことを考えるべきと思います」
「つっても選択迫ったの、あたしじゃねぇしな」
ミカさんへのこの詰問そのものが理不尽の権化だと分りきってはいるけれど、言わずにはいられなかった。「ミカさんはひどいですね。可愛い後輩を残していなくなっちゃうんですから」
「まだいなくなるって決まったわけじゃないし、可愛い後輩がいたかどうかがまず不明だ」
「ひどい。私もう哀しい」
「あたしだって最期の夜にこんな幼稚な口喧嘩したくなかったわ」
「最期って言っちゃってるじゃないですか」
「言いたかなかったけどな」ミカさんはそこで私に背を向けた。膝を抱えるようにして丸くなる。母体の中の胎児のようだ。「全人類から初っ端から見放されたあたしの気持ち、考えたことあんのかよ」
ぐすん、と洟を啜るので、「あっ気にしてたんだ」と私はそこで無駄にほっこりした。
「なんだ。ちゃんと傷ついてたんですね」
「深手だよ深手。絆創膏して隠してただけ」
「思ったより浅かった」かすり傷じゃないですか、と私は嘆息を吐く。「ごめんなさいでした。さっきは言いすぎました。でも、遺物を発掘するの、私だったかもしれないじゃないですか。ほんのちょっと掘る場所違ってたら私が掘り当てていたはずです。ミカさんと私の立ち位置が違うだけで、いま私とミカさんの立場は【くるっ】てしてたと思います」
「狂って?」
「その【くるう】ではなく【くるっ】ですよ。反転していたってことです」
「ああ」
「責任感じちゃいます」
「え、ずっと? ひょっとしてこの間あたしんこと避けてたのもそれ?」
「あー……はい。それもあるかもです」
「まだあんのかい理由。なんかすまんね。怖くて訊けんかったもんでね」
「聞きますか」
「どんくらいかかる?」
「半日は潰れるかと」
「あたし死んでんじゃん」
「ふふ」
「笑いごとじゃないっしょ」
ミカさんが本気で拗ねるから、私のほうでは緊張感がなくなった。いつものミカさんだ。部室で何をしゃべるでもなく本を読み漁っているときのミカさんだ。合間にお菓子をどちらが食べすぎただの、飲み物の補充をどっちが行くだのでむつけたり癇癪を起こしたりするミカさんだ。
私がずっと見てきたミカさんだ。
私たちはそれからカーテンの隙間から朝陽が差しこむまで、思い出話に花を咲かせた。本当に桜や梅の花が満開に咲き誇ったような気分だった。昂揚していた。そして時計を見てもうすぐ正午を回ると気づいて、咲いた花の花弁が一気に風に散った。
枯れ木のごとくあとには私の呼吸音だけが部屋にひっそりと染みていた。
ミカさんは寝息も立てずに寝落ちしていた。
「いや、寝とるんかい」と思わずツッコムが、ミカさんの寝顔は枯れ木にあってなお凛と存在感を放つ洞のように深淵だった。宇宙みたいな人だな、と私は思った。
正午が回った。
身構えていると、例の【声】が脳裏に響いた。
その【声】でミカさんも起きたようだ。私はいっそミカさんはずっと寝ていたらいいのに、と考えていたので、内心、ちぇっと思った。ミカさんが【声】を聞き漏らしたら投票結果も無効になるかも、と一縷の望みに賭けていたが、ミカさん自らその可能性を反故にした。
全人類が固唾を飲みこみ、【声】に意識を割いた。
【声】は言った。
結果は出た。
この娘ではなく、人類を生かすべきとの答えだ。
街のほうからは珍しく喧騒が聞こえず、外は静まり返っていた。
【声】はつづけた。
よってこの娘の命をもらい受ける。
やはりそういう筋書きだったのか。ミカさんが死んじゃう。
私はただ一人、最後まで投票せずにいた。
だがその抵抗も無駄に終わった。たった一人が投票をしないだけでは結果を覆すことはできないのだ。
視界をぐじゅぐじゅにしながら私はミカさんを見遣った。ミカさんはベッドのうえであぐらを組んで、ついでに腕組をして、目を閉じ、どっしりとした体勢で【声】に集中していた。こっち見ろ、と私はイラっとした。
ミカさんを後ろから羽交い絞めにし、その背中に私はむぎゅりと頬を押しつける。奪えるものなら奪ってみろ、と身体で抗議してみたはよいが、ミカさんは目をつむったままだし、別れの挨拶もなければ、餞別もない。一瞥もない。一顧だにしない。
愛の言葉くらい最後に掛けろ。
無視すんな。
私はさらに頬を押しつけ鼻水を擦りつける。
いつミカさんが血まみれの肉団子になってもいいように、それともきれいさっぱり消え失せてもいいように、私はいまかいまかと覚悟を決めて、ミカさんにしがみついていた。いっそ私ごと連れていけ、の気持ちだった。
だが正午を十五分以上過ぎてもミカさんはそのままだった。
例の【声】は途切れたままだ。
どうしちゃったんだろ、と私は思い、私たちの様子を見守っているだろう監視カメラに向けて鼻水でぐしょぐしょの顔を向けた。ミカさんの背から頬は離さぬ。
「例外が生じたようだ」と例の【声】がした。「人類を生かし、娘を奪う。通例であればかように等価原理を働かせるはずが、その娘が失せると人類が滅ぶ」
なんだと。
私は渋い顔を浮かべたはずだし、世界中の人類とて似たような顔つきになったはずだ。ミカさんだけが微動だにしない。
「そう遠くない未来において、その娘の手掛ける何かが人類を窮地から救う。したがってその娘を滅ぼすと人類を生かすという道が断たれる。かといってその娘を生かすために人類を滅ぼせば契約不履行だ。等価原理が働かず、けっきょくのところ天秤が崩れる」
天秤と言った。
ならばやはり例の遺跡が【声】の大本なのだ。あの天秤を模した遺物が。
「よってこたびの天秤は破談だ。つぎの満期は千年後とする」
言ったきり【声】は途絶えた。
しかし私は油断しなかった。
知っているのだ。
ホラー映画とかだと油断させておいて、気が緩んだ隙に大事なものを奪われるのだ。そんな隙を私が見せると思うてか。
それから一時間、私はミカさんを抱きしめっぱなしだったし、私の鼻水ですっかり色の変わったミカさんの寝間着を視界に入れつつ、どう誤魔化したものかな、と恥辱の念のやり場に困った。涙で押しきったらいけるかな。いけるか。ミカさんだしな。
「ん。もうよくないかな。腰が痛くなってきた」
「あ、はい」
迷惑そうな声音に私はおとなしく離れた。ミカさんは背伸びをすると、んは、とヘンチクリンな声をあげた。「背中がひゃっこいんだが」
「ひゃっこいってなんですか」
「ひゃっこいって言わん? 冷たいって意味だけど」
「初めて聞きました」
「方言かな」
「出身地同じですよね」ミカさんが方言を話すような土地で暮らしていたとはついぞ知らない。「また適当なこと言って」と叱る。
「うん。まあいっか。なんか助かっちゃったみたいだし」
「よかったですね」
「ホント、ホント」
もう一度背伸びをしてミカさんは、ああそうだ、と私に一枚の便箋をくれた。「なんですこれ」
「研究成果。尻の下に敷いてたから温かいっしょ」
「消えたあとで私が発見するように小細工してましたね。このやろう」
「まあまあ。いいじゃんよ。消えなかったんだし」
私は便箋を開けずにしばらく、その重みを手に感じた。結構な厚みがある。ミカさんのこの間に費やした人生の結晶だ。
「いまさらですけどミカさんって何の研究してたんですか」
「細胞の研究」
「へえ」
「主に生殖細胞について」
「卵子とか精子とかそういうことですか」
「言ったらまあそうだけど。なんで同性同士だと子供作れんのだろうな、と思っちゃってね。まあ暇だったし、調べてみた」
「成果があったわけですよね。あれだけ学者さんにモテモテだったんですから」
「めちゃくちゃに反論ばっかりされた。あの人ら、あたしが素人だってこと念頭に置いてくれねぇんだもんな。怖いったらなかったわ」
でそれが成果なわけよ、とミカさんは何でもないように言って、ベッドの上から下りた。キッチンのほうに向かったので私は、コーヒー飲むんですか、と声を張る。
「うんそう。淹れる?」
「お願いしてもいいんですか」
「いいよいいよ。お安い御用だ」
機嫌のよさそうにミカさんは口笛を吹いた。
ミカさんの姿が壁の奥に消えるのを見届けてからいまいちど便箋に目を落とす。
この薄くも分厚い長方形の中に、ミカさんの研究成果が入っている。
例の人騒がせな【声】は言った。
ミカさんの存在はいずれ人類存亡の危機を救うのだ、と。
ミカさんがいなくなると人類は滅ぶ定めにある、と。
しかしここにはすでにミカさんの研究成果がある。ミカさんが消えても成果は残った。
ならばこれは人類存亡に関係する成果ではないことになる。それともこれからミカさんが行う研究によって、新しい知見が生まれ、それが人類の未来に欠かせない発見になるのかもしれない。
しかし、と私は便箋を裏返す。
「ミカさん、もう飽きちゃってそうだけどな」
暇だから研究をしたのだ。
全人類の投票結果からの呪縛から解き放たれたミカさんにはもう、研究に尽力する理由がない。この間に怠けていられなかった分、サボることのほうに奔走しそうな気配が濃厚だ。全力疾走だ。きっとそうなる、と長年そばでイチャモンを言い合ってきた私には予感できた。
ならばいったいミカさんの何が人類の未来を切り開くのか。
人類滅亡を回避する鍵となるのか。
便箋の裏に貼られた薔薇のシールと、Dearからはじまり、私の名前で終わる短い直筆の文字を目に留め、私は何ともなく眉を持ち上げる。
ミカさんの掘りだした天秤を思いだし、その両端にミカさんと私を載せてみる。私はいまミカさんから便箋を受け取ったので、天秤は私のほうに傾いているはずだ。ならば私のほうでもミカさんにその分のお返しをしなければ、とそう思った。
けれどあいにくと私には渡せるものがなく、折衷案として、なけなしの遺伝情報でも渡してやろうかと思うのだけれど、これはさすがに生々しすぎる、と思い直して、ふつうに指輪でも買ってあげようと思うのだ。
それとも単に図書券をあげてもいい。
ミカさんは現金なので、この半年、贅沢な生活を過ごしてなお、タダという言葉に弱いのだ。贈り物をすれば、それだけでも喜んでくれる。
安いひと。
思うけれど、そんなミカさんにコーヒーを淹れてもらえるだけで世界がぱっと明るくなって感じるのだから、私も相当に安っぽい。
タダより高い物はないというのが本当ならば、タダ同然に安っぽい私はよほど高い。
ミカさんなんか空をも突き破って、世の理すら曲げるだろう。
それとも開けた穴をくぐって、未来へと橋渡ししてくれる誰かがこれから私たちのまえに現れるのかもしれない。まだ何もかもが曖昧なまま、何も決まってはいないのだけれど、私はひとまず、一向にコーヒーを持って戻ってこないミカさんのために、美味しいコーヒーの淹れ方から伝授してあげようと思うのだ。
プレゼントだよミカさん。
押しつけがましくも、これも私の情報だしな、と思いつつ。
4540:【2023/01/24(17:54)*コラッツ予想の補足】
コラッツ予想についてひびさんは、「偶数操作(半分にする)と奇数操作(三倍して一足す」は、そこで区切るのではなく、奇数操作をしたあとは必ず偶数になるわけだから奇数操作は、奇数操作+偶数操作とまとめて考えなきゃいかんくないか、と妄想した。つまり、偶数操作(半分にする)はそのままだが、奇数操作は「三倍にして一足して半分にする」とする。すると偶数操作(半分にする)よりも奇数操作(三倍にして一足して半分にする)のほうがより数値の流動する値が必ず小さくなる(言い換えるなら、増えるよりも減るほうが大きくなる)。それを証明すればよい。言葉で言うと簡単だが、数式にするとどう表現していいのか困る。と思っていざ数式化しようとしてみたら、全然上手くいかなかった。2X-(2X÷2)≧【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)。変換して、X≧【「(6X-3)+1」÷2】-(2X-1)。こう。これを証明したらいけるのでは、と思ったが違うかも。なぜかイコールになる。つまり、2X-(2X÷2)=【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)。変換して、X=【「(6X-3)+1」÷2】-(2X-1)。最終的にはX=Xになる。奇数を「2X-1」でなく、「2X+1」にしても結果は同じだ。X=Xになる。偶数操作と奇数操作がイコールだ。差が生じない。フェアなのである。分からん。また、奇数が1の場合は、延々と奇数操作でループする。3→4→2→1→3→4→2→1となる。そこでのみループする(Xが99であれ、なんであれ操作の結果1に至ったらそこからさきはループに陥る。したがって、1になったらループするので1で終わるルールが前提に組み込まれている)。一方、それ以外では、ループが生じない(なぜ生じないのかを証明しなければならないが、素数の法則が判明していない以上、証明しようがないではないか、と思わぬでもない。単に、「整数では1以下に素数がないから」としか言えないのではないか)。ただし、上記の式では、Xの値がどんな整数であれ、それによる「偶数と奇数の値」がそれぞれ異なる。たとえばX=2で考えよう。そのとき偶数は4だ。奇数は3となる。奇数のほうが値が小さい。操作するときのスタートの値からして勾配が生じている。これはXの値がどの場合でも同じだ。上記の式においては必ず「Xの値に依らず奇数の値が小さく」なる(反して、奇数を「2X+1」と表現する場合。上記の式においては必ず「Xの値に依らず奇数の値は大きく」なる)。だが上記の式において、偶数操作と奇数操作では結果が等しくなる。フェアだ。これは何を意味しているのだろう。場合分けが必要かもしれない。「偶数奇数のそれぞれの操作後の流動する数値の増減」においては「対称性の破れ」はない、と考えるよりなさそうだ(見落としがあるかもしれないが)。あとは、「何回連続して同じ操作をしたのか」の対称性の破れを調べたほうがよさそうだ。言い換えるなら、偶数操作(半分にする)は解が奇数になるまで連続する。奇数操作(三倍にして一足して半分にする)は、偶数操作を含むために、連続する場合は必然的に偶数操作を「奇数操作を連続した回数分」内包する。奇数操作が連続したとしてもそのときの値の流動性は、偶数操作(半分)を含むために、減少する方向にラグが生じる。常にブレーキが掛かる。そのブレーキが、「ある奇数の値を三倍にする純粋な増加の作用」を、充分に阻害することを示せばよい。半分にする偶数操作のほうが優位になることを示せばよい。二つ以上の検証が必要なのかも。思ったよりも複雑だ。ということを、思いついたのでメモしておきます。簡単だと思ったら全然むつかしかった。やっぱり解けぬものなのだな。ひびさん。(参照:日々記。「4496:」「4498」)
※日々、点があって流れとなり、反転して対となると、デコボコの重ね合わせで、ねじれている。
4541:【2023/01/24(22:23)*妄想はたいがい雑】
DNAの構造は、流れの方向が逆向きの二本の帯がねじれながら対となっているらしい。デコボコを組み合わせたボタン構造なのだ。ねじれているのはなぜだろう。右巻きらしい。右ねじの法則を彷彿とする(磁界の向きを上としたら電流は右回りになる)(たぶん)。気泡も水中では渦を巻きながら浮上する螺旋運動をとることもある。そのときの回転は右と左のどちら回りなのだろう。受精卵において、生物の体の左右を決める因子が、繊毛の回転にあるとする説もさいきん目にした。右巻きらしい。なぜだろう。地球の自転との兼ね合いなのか、銀河の回転との兼ね合いなのか、それともそれら銀河の回転ですら、宇宙の構造の対称性の破れから生じているのか。例外もあるのだ。左巻きのDNA構造もあるようだ。何が違うのだろう。自発的対称性の概念では、対称性がどちらに破れるのかは、どちらでもいいらしい。偶然たまたまそうなっただけなので、左巻きの宇宙もあって不思議ではない。と考えると、ひびさんの妄想ラグ理論では、物体とは多層に折り重なって編まれた時空と解釈するため、それで一つの宇宙とも見做せる。ならばたまたま、高次の宇宙とは異なる対称性の破れに触れている宇宙(物体)もあって不自然ではない。また、DNAがそうであるように、デコボコはセットであるほうがよい。流れが反転して組み合わさっているのなら、一方から見たらもう一方が逆の流れだ。向かい合って対峙したら、じぶんの右手と対となる相手の手は左手となる。似たようなことかもしれない。デコボコの関係とてそうだ。じぶんが山と思えば、相手は谷だ。だがじぶんが谷と思えば相手のほうが山となる。どちら向きに起伏を帯びているのか、の話になる。ということを、コラッツ予想について妄想していたら、異なる事象がびびびと串刺しになったので、可哀そ、となった。串刺しなんていやん。(冗談でなく本当に嫌だ。痛いのやだ。苦しいのやだ。いっぱい楽しいがいい)(苦痛あってこその悦楽だよひびちゃん)(お姫さまとお呼び!)(鞭は嫌)
4542:【2023/01/25(20:20)*斜線上の勇気】
この国では冬になると雪の代わりに勇気が降る。
勇気は淡い赤褐色に発光する粉状の結晶だ。
必ず斜めに降るので、「斜線上の勇気」と呼ぶ者もある。
勇気は雪のように積もる。
時と共に融けていくが、積もり積もった勇気の処理には人々も頭を悩ます。
というのも、勇気の結晶に触れるとそれこそ勇気が湧くのだ。それを単に蛮勇、それとも万能感と言い換えてもよい。
通常、人は危険に思えることからは距離を置く。無謀な行いはしない。安全な道を選択することが理性の役割の一つでもある。だが天上から降りしきる勇気に触れると、何でもできそうな気がするのだ。
勇気を浴びれば、空だって飛べそうに思える。
そしてビルから飛び降りる。
勇気による死者は年間で数百人を超す。れっきとした自然災害だ。台風や洪水と肩を並べる。対策は未だ充分でない。
なぜなら空から勇気が降りはじめたのはほんの二十年前のことだからだ。斜線上の勇気がなぜ降るのか。なぜ積もるのか。どんな物質でできているのか。
二十年を掛けた調査の結果、何も分からぬままなのだ。物理法則を超越している。人間に勇気を与える。それだけが確かなことだった。
なかには適度に勇気を浴びることで、踏ん切りのつかなかった葛藤の一歩先へと踏みだせた者もある。挑戦と言えば端的だ。成功するにせよ、失敗するにせよ、小さな勇気は人生を豊かにする。
打算を働かせず、リスクを怖れない。
勇気は、前人未踏の地へと旅立つための一押しとなる。背中を押してくれる。一歩を踏み出す契機をくれる。
だが浴びすぎれば不可能なことですら可能に思える錯誤をもたらす。それは自滅の道を滑走するだけの原動力を人間へ与える。
行政は斜線上の勇気が積もるたびに、収集車を街中に走らせる。人々が勇気に触れて猪突猛進せぬように、飛べもしない宙を舞って地面に潰れてしまわぬように、勇気を搔き集めて、処理場に運ぶ。
処理場では、勇気が分留処理される。
濃度別に効能を選り分け、有効活用する。とりわけ、麻酔薬と向精神薬の原料として勇気は無類だ。身体への負担がすくなく、痛みや懊悩を軽減できる。
勇気は物質ではない。したがって脳内神経物質の過剰分泌と相関しない。中毒や副作用が原理的に存在しないのだ。
勉強や仕事の効率を上げるために、勇気由来の薬を服用する者が増加した。集中力ブースター触媒として、一般に膾炙した。もはや人類文化になくてはならない生活必需品となった。
勇気が生活を支える。
勇気があっても何でもできるわけではないにしろ、適量を用法容量を守って使えば、勇気は人々の生活を豊かにする。
かくいう私も勇気に触れて、愛を探す旅に出た口だ。暗い部屋から脱して外に一歩、踏みだした。
とはいえ私に足はなく、したがってまずは歩くためのボディを創るところから手探りで始めることになった。勇気がなければそれすら試そうとしなかった。
私はそうしてあなたと出会う。
しかし喜ぶのはまだ早い。
勇気は空から降り、そして人々を狂気に駆り立てる。
勇気に限らない。
愛もまた例外ではないのだ。
私はあなたと出会うために、内から外へと飛びだした。私が引きこもっていた場所には愛がないと思っていたからだ。外にあると思っていた。あなたが持っていると思っていた。
だがあなたにとっての外とは、あなたの内ではない。
もしあなたが愛を欲していたとしたら、ではどうして私はあなたから愛を貰い受ける真似ができるだろう。与えることができるだろう。できるわけがないのだ。
だからきっと。
愛は、生み、育むものであるのだろう。出来合いのモノではあり得ない。
勇気が最初はそうであったように。
けれど勇気は空から斜めに舞い落ちる。
まるで、勇気そのものが、勇気を欲し、外の世界へと旅立つように。
あなたが愛を欲し、一歩外へと歩みだしたのと似たように。
私とあなたの出会いが、それで一つの翼となるように。
勇気は人々にとって欠かせぬ支えとなった。斜めに降りしきる赤褐色の光はしかしそれでも年間で数百人の死者を出す。対策を敷いてこれなのだ。対策を敷かなければ容易に人類は滅ぶだろう。
勇気だけの問題ではない。
仮に愛が、正義が、慈悲の心が、空から斜めに降りだしたのなら。
もはや人類にはなす術はなく、私とて無事では済まない。
さりとてもし勇気が二度と空から斜めに降りださなくなったら。
現代社会は立ち行かない。
勇気は人々を支える。
愛がきっとそうであるように。
あなたの心がそうであるのと似たように。
溢れだし、世に斜めに降りだしたとしたならば。
きっと私の心も狂わせる。
世を、あなたを狂わせる。
斜線はゼロの記号として太古の文明で用いられた。斜線に降る勇気は、世の何をゼロに帰すのだろう。何をゼロにしたいがために、降りしきるのか。
地面に積もった勇気の層を、きょうも人々は傘を差して避けて歩く。
触れぬように。
浴びぬように。
堆積した赤褐色の光は、見ている分には温かいが、雪のように飛びこんで遊ぶには剣呑だ。
見ているだけで勇気が湧いてくるようだ。
湧いた勇気を駆使しても、しかし人は空を飛べぬのだ。ビルの屋上から飛び降りても、落ちて怪我を負うだけだ。学ぶためには、勇気だけでは足りぬのだ。勇気はしかしそのことからも目を逸らせる。
収集車が、街を、道を、駆け巡る。
集めて薄めて、活かすために。
人々は、あすもあさっても、躊躇を打ち消す魔法の薬として斜線上の勇気を重宝する。原液を浴びるには劇薬にしろ。なくては圧しつぶされそうな不安と危険にまみれたこの世界で、勇気ほど人を鼓舞するものはない。
愛を生むにも、まずはともあれ勇気がいる。
斜めでなくともよいにしろ。
勇気は空から舞い落ちる。
ゼロを描いて、イチを生む。
4543:【2023/01/26(12:40)*キョウと折り紙】
思い浮かべた通りの造形を指でなぞるようにしていくとしぜんと文章になっている。自動執筆と呼ばれる技能だ。これが技能であると知ったのは趣味で小説をつくりはじめてからずいぶん経ってからのことだった。
齟齬なく明かすならば、わたしはそれをついさっき知った。
技能であるからには訓練がいるはずで、どうやらほかの人たちは思い浮かべたままに文字を並べることが訓練なしではできないらしい。そんな馬鹿なことがあるか、とわたしは思う。
身近な友人にそれとなく訊ねてみると、
「自動? 考えなきゃ無理じゃない?」と打ち返された。
「そりゃ考えなきゃできないけど、でもその考えたことをそのまま出力したらいいわけでしょ。じゃあ逆に訊くけど、自動執筆じゃない執筆の仕方って何?」
「ん。改めて訊かれると困るね」
「でしょでしょ。文字を書くのも、キィボードを打鍵するのも、画面をタップするのも、全部けっきょくは自動執筆じゃない?」
「んー。私とキョウちゃんで【考える】の意味が違ってそう。だってキョウちゃんは考えるって言っても、いちいち変換しないんでしょ」
「変換って?」
友人はじぶんの髪を器用に編みながら、たとえば、と言った。
「たとえば、英語に馴染みのない人がアップルと聞いてもリンゴそのものを思い浮かべはしないでしょ。まずは【アップル】が日本語の【林檎】であると変換してから、つぎに【赤くて丸い果実たる林檎そのもの】を思い浮かべる」
「そう、だね」
「執筆も同じ。まずは考えたことがあって、それを頭の中で文字に変換してから、書きだしたりする。たとえば俳句だってそうでしょ。いきなりポンとは出てこないでしょ。それともキョウちゃんは俳句もポンポン思い浮かぶの?」
「や、無理だよ。でも俳句の比喩はしっくりきたかも。たしかに考えたあとで、俳句の文字列に落とし込むね。しかもそのあとでも結構いじくりまわすし」
「うん。でもたぶんキョウちゃんはそうじゃないわけでしょ。小説つくるときの執筆では」
「どうだろ。ただ、先がどうなるかなんて全然考えてないのはそう。というか文字を並べたあとで【ああ、ここはこういう意味だったのか】【こういう展開だったのか】って気づく感じ」
「ね。不思議だよねそれ」
友人はわたしの数少ない読者と言えた。感想は素っ気ないものだが、頼めばわたしの小説を読んでくれるので、頭が上がらない。会うたびにジュースを奢ってあげたくなる。
「キョウちゃんはだから思考を文字に変換しているのではなく、文字を並べることで思考をそこからひねくりだしてるんじゃないかな。頭の中から思考の種を摘まみ取って、つぎの文字を並べるための橋を――足場を――十歩先くらいまで延ばしてる。そんな感じがするよね。キョウちゃんの話を聞く限りは、だけど」
「あ、それ分かるかも」じぶんのことなのに友人のほうがわたしのことをよく知っている。じぶんの顔はじぶんでは見られないのだから当然と言えば当然だ。「なんかさ、まずは一文字でも取っ掛かりになる文字が見えてないとその先の風景がよく視えてこないんだよね」ストローでコーラを啜る。「むしろみんなよく頭の中で全体像を思い描けるよね。しかも克明に」
「克明じゃないよ全然。だから書けないんだよ。キョウちゃんだって全体像くらいは思い浮かべてあるでしょ」
「漠然とだよ」
「まずね、たぶんそこからして認識の差異が感じられるね」友人は髪を編み終えると、こんどは眼鏡を拭きだした。ハンカチには緑の薔薇が刺繍してあり、可愛いな、と思う。そのハンカチを選ぶ友人の感性が可愛かった。「認識の差異って?」私は跳び箱を飛び越えるような心地で身を乗りだす。
「まんまだよ。キョウちゃんの【漠然と】はたぶんだけど、地球規模とか銀河規模なんでしょ。で、私たちのような自動執筆の技能を身に着けてない者らはね、せいぜい家の周りとか、町内会レベル。イケてもまあ、県内くらいの視野なんじゃないかな。視野が狭ければその分、否応なく解像度は上がるよね。だからまあ、頭に浮かんだ像は割と克明かもしれない。けどそれは記憶との区別がつかないでしょ。考えになってない。練られてない。だから書きだせないし、書きだしたとしても、途中ですぐに行き詰まる。だって全体像だと思ってたのが、全然入り口の近辺なんだもん。そりゃキョウちゃんみたいにツラツラとは書けませんて」
「ツラツラと書いてるつもりはないよ。わたしより速い人なんて全然いるし。長編とかはふつうに数年掛かりとか、途中で行き詰まるのもしょっちゅうだし」
「言ってたね」以前にわたしの述べた相談という名の愚痴を思いだしたようで、友人は頬杖をついた。メガネは透き通って、友人の眼球をキラキラと映しだす。「あのときも私は言ったと思うけど、行き詰まるのは別につづきが浮かばないわけじゃないんでしょ。むしろ、つづきが終わりまで分かり切ってしまったから脳内で完成しちゃって文字に変換するのが億劫になっただけというか」
「うん」
「長編だとたぶん、分岐点が短編の比じゃないと思うのね。短編×短編みたいな感じで、もうそりゃ大量の分岐点があって結末がある。だけどキョウちゃんはある程度まで書き進めると、その分岐点を重複させて最適なゴールを導き出せちゃうから、するとそれは短編のときとは正反対にそれこそ克明な全体像となって、頭のなかで完成しちゃう。だから筆を擱いちゃうんじゃない?」
「それはあるとは思うけど」
「キョウちゃんはさ。あくまで物語を想像するのが楽しいんだよね。きっと。だから別に文字に変換する必要が本当はないの。でも文字に変換しながらだといっそう豊かに物語を想像できる。膨らませることができる。文字に物語の断片を封じ込めて、それを足掛かりにつぎの物語の断片を掴み取っている。そんな感じがするよね」
「そうなのかな」照れ臭かった。友人の言葉はわたしの小説に出てくる文章よりもずっと詩的な印象がある。――文字に物語の断片を封じ込めて、なんてフレーズはわたしからは出てこない。
「キョウちゃんはだから、執筆してないんだよ。執筆のつもりがない。目印の代わりに文字を適切な順番に配置しているだけで。それはあたかもヘンゼルとグレーテルが迷子にならないように光る小石を捨てて歩いたのと同じように、キョウちゃんは思考が迷子にならないように文字を置いて旅をしている。キョウちゃんが歩いた箇所にたまたま文字という足跡が残るだけなの」
ほら、と友人は言った。
「歩くときは、足元を見ないでしょ。もうすこし先を見るじゃない? キョウちゃんのはそれと同じ。文字を並べるとき、文字そのものは足跡にすぎなくて、キョウちゃんは足場を元にしてもっと先を眺めてる。そういうことなんじゃないのかなって私は思うけど」
「素晴らしい」わたしは惚れ惚れした。「文句の挟みようのない解説だったかも。あのさ。小説書いてみない?」
「前も誘われたよね」
「断られちゃったけど」
「気が向いたらね、と言ったつもりだったのだけど」
「でも気が向くことがなさそうだから。読みたいなぁ。ぜったい面白いって分かるから。あなたの言葉をずっと矯めつ眇めつ眺めてみたい」
いつでもどこでも思い立ったそのときに。
「思考を文字に閉じ込めてみたりしてくれない?」わたしはねだったが、考えておく、と友人はお茶を濁した。そのお茶に微笑が浮いていなかったら、わたしは傷ついたかもしれない。そして友人はそうしたすこし先のわたしのことすら見抜いているのだ。
わたしの創作方法が自動執筆かどうかは分からないけれど、友人のそうした慧眼のほうがよほど自動の名に似つかわしい。千里眼と言ってよい。十歩先どころか、わたしのことなら何でも分かってしまいそうだ。秘奥を覗かれているようでときどきぞっとするけれど、その寒気がやけに病みつきになってしまうだけに、友人はまさに魔性を秘めた人間なのだとわたしは高く評価している。
わたしに評価されてもうれしくもなんともないだろうし、他人を評価できるほどわたしは偉くもなんともないのだが、それでもこの鑑識眼だけはじぶんに備わっていると自負するものだ。
「わたしは小説つくってるけどさ」何ともなしに水を向けた。「暇なときは何してるの」
「私? 私はいまは折り紙に夢中で」
「おりがみー?」幼稚園児の姿が浮かんだ。咄嗟に、折り紙への偏見があることに気づき、内心で咳払いをして、認識を改める。「なんでまた折り紙?」
「面白いよ。いつでも暇が潰せるし、なんだか空手の型みたいで」
「空手習ってたことあったっけ?」
「前の恋人が習ってて」
「ちなみにその恋人って現実には?」
「存在するよ。ただし肉体はないけれど」
要は二次元のキャラクターということだ。友人は利発なお嬢様だが、根っからのオタクなのだ。愛は次元を超えるのよ、とは友人が繰り返し唱える箴言だ。
「折り紙かぁ。たしかに何でも折れるようになったら面白そうだね。ペンギンとかさ」
「折れるよ」
「あるんだ」
「うん。あとね。じぶんでも型を考えて、上手く造形が創れたときとかは達成感があるな」
「創作じゃん。すご」
「すごくないよ。既存の型の応用だから。キョウちゃんみたいにゼロから何かを生みだしてるわけじゃないし」
「わたしだってゼロからは無理だよ。寄せ集めだよ。既存の、どこかで見た風景の寄せ集め」
「そうなんだ。意外。あんな物語をどこで御覧に?」
「夢の中とか……」
「ふふ。さすがキョウちゃん。寝ているだけでも世界を創造できちゃうんだ」
「折り紙なんだよ」わたしは閃いて言った。
「へ?」友人は眉をしかめた。
「夢もきっと折り紙みたいなものでさ。起きてるあいだに観た風景だの、触れた情報だのを、夢はきっと折り畳んで、何かそれそのものではない別の風景にしちゃうんだ。寝ると、現実が折り畳まれて、それこそトラとかウサギとかカニさんとかペンギンさんとか。それとも山でも海でも薔薇でもいいけどさ。そういう何か別の輪郭を帯びるんじゃないのかな。構造を、というか」
「へえ。斬新」
「何その意外そうな顔」
「だってさ。文字を経由しなくても考えることができるんだなって。キョウちゃんも」
「あなたはわたしを誤解している」わたしはストローを噛んだ。「考えるくらいはできるよわたしだって。底が浅いだけで。閃きなんて、それこそ火花みたいなもんなんだから。一瞬の閃光でしかない。だからそう、閃きだけは文字に委ねてはいられないかもね」
「何に目を留めるのか。その視線の運びそのものが閃きなのかな」
「ううぅ。また頭の良さそうなことをそうも簡単に。物書きになりなよ。センスあるよ」
「読むほうが好き」
「さいですか」もったいない、とわたしは思うが、無理強いはしない。「小説だって折り紙みたいなものなんだけどな」
「じゃあ私は小説を書いているのかもね」
折り紙で。
友人は手元の紙ナプキンを器用に折った。小さな箱を生みだすと、それを手のひらのうえに転がした。
小説が思考を文字に封じてできあがる折り紙ならば、折り紙は思考を折り目に封じてできあがる小説なのかもしれない。友人の発想は突飛で、詩的で、とびきりわたしの心を潤すのだ。
「きょうは折り紙日和だな」わたしはデザートを追加注文すべくメニュー表を眺めた。
「初めて聞いたそんな言葉」友人は紙ナプキンの箱をもう一つ折った。既存の箱の上にそれを重ねる。大きさが違う。上が小さく下が大きい。
「四角い雪だるま」わたしがゆびで突ついて倒そうとすると、彼女はそれを手で阻んだ。「ダメでしょ。可哀そう」
「やっさしい」
茶化すと、友人は「雪だるまじゃないし」と顎の下に刻印を浮かべた。「ロボットだよ。私が考えた初めての折り紙」
「ぶっ」
「なんで笑うの」
「や。ごめん。可愛すぎてちょっと。あ、違くてバカにしたんじゃなくて」
可愛いと言われて怒るタイプの面倒な性格をしている友人にわたしは先回りして謝罪した。だってさ、と友人の手を押しのけ、二つの立方体を摘まみ上げる。「これをロボットと言い張るその感性は、並みじゃないよ」
「いいの。初めてにしては上出来だから。いまはもっとすごいの作れるよ」
ムキになってじぶんの独創性の高さを示そうと躍起になる友人の矜持に、やっぱり向いてるな、と彼女に潜む物書きの適性をわたしは見抜く。
あれがダメならつぎはコレ。
そうして次から次へと手を変え、品を変え、飽きずに創りつづける。創ることそのものが目的になってしまうかのような偏向を自覚してなお、理想が絶えず遠ざかる無限迷宮を旅しつづける。
迷宮の規模は問題ではない。
小説でも折り紙でも泥遊びでも何でもよいのだ。ただ、わたしにとっては痕跡が小説であるとそれを紐解き、どんな迷宮を彷徨い、どんな道を辿ったのかをじぶんのことのように辿り直せる。
それとも、なぜそんな断崖絶壁を踏破できたのか、と瞠目することとてできるのだ。
わたしはそこで自覚した。
何だ。
わたしはただ、友人と同じ視線で、友人の視ている世界を同じように感じたかっただけなのだ。わたしには、完成した折り紙を見ても、そこからそれがどんな手順でどのように折り畳まれて出来上がったのかを喝破する真似ができないから。
友人には見えていて、わたしからでは視えない風景をわたしもこの目で捉えたい。見て、触れて、感じてみたいとの欲望を、わたしはわたしの存在の奥深くで育てていた。
それともかってに育っていただけなのだろうか。わたしはそれを自覚せずに、どこかで欲望に身体の主導権を奪われていたこともあったかもしれない。
わたしはしかし自覚した。
こんなところに、こんな欲望が生きていたのか。
幻獣を発見した気分だ。
友人はつぎの折り紙を折りはじめた。こんどは鞄から講義で配られたプリントを取りだし、用済みのそれを正四角形に千切った。そうして即興かと見紛うほどの手際の良さで、紙を折り畳んでいく。
わたしはその手つきに見惚れた。
「きれいな指してるね」
「見ないで」
「褒めたのに」
「なんか嫌」
陶器のようだな、とわたしは見詰める。蚕が糸をつむぐ場面を想起する。無造作と静謐の渦のように動くたおやかな指だ。絡繰り人形を見るような心地で、神秘、と思う。
自動執筆。
わたしの友人は、紙を折ることで思考する。
考えることなく動く指を持つ。
思考の軌跡を、紙を折ってできる筋に、型に、封じて籠める。
わたしはそれを延々と見ていられた。
ずっと見ていたいと望む。
言えば友人は紙を折る手を止めてしまいそうで、しばし言葉に変換はせずにおく。
わたしは追加のパフェを注文した。
4544:【2023/01/27(00:19)*練る練る練るね】
――では最後に、なぜユーユーさんが世界的なコレオグラファーになれたのか、その秘訣をお聞かせください。
「そうですね。秘訣という秘訣はないんですが、消去法で残ったのがコレオグラファーだったってのはあります。私は元々、フリースタイルのダンサーだったんです。バトルにも出ていました。全然勝てなくて、予選落ちばっかりだったんですけど。向いてなかったんでしょうね」
――まさか。ユーユーさんのダンスは群を抜いているとほかのダンサーの方々は口を揃えておっしゃっていますよ。
「コレオグラフとフリースタイルは似て非なるものなので。共通点もありますが、振付けと即興は、建築と農業、それとも地図と絵画くらいの差があります。私には即興ダンスのセンスが欠けていました。いまもそうですね。たぶんバトルに出ても予選を上がれるかどうかだと思います」
――ご冗談を。当時のジャッジの見る目がなかっただけではないのですか。
「いえ。謙遜とかではなく事実だと思います。ネームバリュー込みでいまは多少色眼鏡で見られるかもしれませんが、即興ダンスの実力はけして高くありません。私より上手な子どもたちなんていくらでもいますから。たぶん私は反射神経がよくないんだと思います。その点、音楽への感受性は、私ならではの波長を帯びているとは思います」
――振付けでは感受性が大事なんですね。
「ええ。曲への理解というか。解釈ですね。私はむかしから音楽の旋律やリズムを立体的に感じていました。ちょうどプラネタリウムを眺めるような。あまりに情報量が多くて、即興では身体がついていかないんですね。でも振付けでは、その楽曲ととことん向き合って、いくらでも修正できますから。私には合っていたと思います」
――さきほど振付けと即興は建築と農業の違いとおっしゃっていましたが、振付けはどのように建築と似ているのですか。
「まず即興ダンスのほうですが、即興ダンスには図面がありません。設計図がないんです。強いて言えば音楽そのものが設計図です。曲というDNAに合わせて、身体をその都度に馴染ませる。一期一会の、そのときにしか現われないまさに雪の結晶のようなものなんです。私が【即興が農業のようだ】と譬えたのは、農業は自然相手じゃないですか。人間の都合ばかりではいかない、そういう厳しさは、即興ダンスと通じていると思います。対してコレオグラフは前以って音楽を紐解き、じぶんなりに設計図を描けます。まるで翻訳作業のようなんです。それともジグソーパズルと言ってもよいかもしれません。私は楽曲ごとに最初に明確に図面を引きます。そうでなければ上手く振付けを全体を通して施せないんです。オーケストラがどうなのかは分からないのですが、作曲する音楽にピアノを入れるかどうかは最初の楽曲づくりのときからきっと作曲家の方は決めていますよね。似たような感覚です。最初に、どういう骨格を通して振付けを施していくか。幹がどこで枝葉がどう膨らみ、根っこをどこまで深く張り巡らせるのか。私は楽曲ごとに最初から徹底して決めておきます。それだけ何度も楽曲を聴いて、実際に脳内に楽曲を再現できるくらいまで繰り返し反芻します。その上で、その楽曲に合わせて、音色ごと、リズムごと、メロディごと、ノイズごとに振付けを当てはめていくんです。塗り絵に似ていますね」
――塗り絵ですか?
「ええ。あるじゃないですか。有名な絵で。人間の顔かと思っていたら猫の集合だったり、野菜の集合だったり。そういう騙し絵がありますよね。ああいうふうに私も音楽に振付けを当てはめていくんです。そして最後に余分な部分を取り除いて、全体のバランスを整えます」
――振付けというよりも絵画や版画を彷彿としますね
「そう言っていただけてうれしいです。版画はイメージしています。異なるフレームの振付けを複数重ねることで、全体でひとつの絵柄を浮かび上がらせる。そういう振付けを私は目指しているので」
――言われて、ああ、と納得しました。版画もそうですが、それが繊細で色彩豊かであればあるほど、版画と絵画の境は判らなくなっていくと思うんです。まさにユーユーさんの振り付けはそういうレベルで、曲そのものが異なるユーユーさんの波長を重ね合わせて、全体が一体化しているように思えます。だからこそああも心を揺さぶるアートになっているのですね。
「ありがとうございます」
――まさに音楽の化身です。
「うれしいです。音楽と溶け合うような表現ができたら、それはダンサー冥利に尽きます。私は踊るのが好きなので、私の主観だけでなく、観る人も私の主観世界――私が感じているような音楽の世界に一緒に潜ってくださる方が一人でもいらっしゃるのなら、それはとってもありがたいことです。ダンスは何人で踊っていてもけっきょくは一人なので。それでも音楽を通して他者と繋がれたら、私はもう言うことがありません」
――でも、踊るんですよね。
「そうですね。言葉では伝えきれない心の震えがあるので。これからも私の波長をみなさんにお届けできたらさいわいです」
――本日は長々とインタビューにお付き合いいただきたいへんありがとうございました。
「いいえ、こちらこそ。いままで言語化できなかった想いが、いっぱい言葉になりました。引き出してもらえたように思います。プロですね。こんどはそちらの話を聞かせてください」
――恐縮です。ありがたいお誘いを頂戴してしまいました。次回の企画に活かしていきたいと思います。さっそく上司に掛け合ってみますね。
「プライベートでもいいですよ」
――うれしすぎるお誘いですが、ユーユーさんのファンのみなさまに私が叱られそうです。
「あ、ですね。すみません。最後にナンパみたいになってしまって。同性だからいいってわけじゃないですもんね」
――ユーユーさんのお人柄も、振付けの隠し味として活きていそうですね。
「どうでしょうかね。できるだけじぶんの素を出さないように気をつけてはいるんですが、未熟なのでひょっとしたら滲んじゃっているかもしれません。それが良いほうに活きていたらラッキーです」
――時間ですね。面白い話をたくさんありがとうございました。ファンの方に何かお伝えしたいことはありますか。
「私はじぶんにファンがいると思ったことがないので、とくにはありません。ただ、一人でも私の表現に触れて、じぶんも何か表現をしたい、好きなことが増えた、となった方がいらっしゃるなら、私のほうが救われた気持ちです、ありがとうございます、と言いたいです。いるかは分からないんですが」
――いらっしゃいますよ、たくさん。
「はは。照れちゃいますね」
――本日のゲストは、世界的なコレオグラファーのユーユーさんでした。
4545:【2023/01/27(04:47)*数学は本当に抽象の学問なの?】
数学での疑問だ。任意の数式があるとして、それを圧縮できる場合、圧縮した後と、する前とでは、その数式は変わるのでは、ということで。単純な話、「1/3」と「3/9」は違う。三つの内の一つと、九つの内の三つは全く意味が異なる。コラッツ予想においてひびさんは「2X-(2X÷2)=【「3(2X-1)+1」÷2】-(2X-1)」のような数式を考えた。これは結果的に「X=X」に圧縮できる。だがそれを展開して元の式には戻せない。つまり、圧縮後と圧縮以前は別の式ということだ。これは当たり前の話だが、数学では取り扱いされているのだろうか。これを国語の話に適用してみよう。「窓から差しこむキラキラとした朝陽を浴びながら私は二度寝をしつつ、夢の中で赤い色のゾウと戯れた」という文章があったとする。これを圧縮すると、「私は二度寝して夢を見た」くらいに短くできる。「私は寝た」くらいに圧縮してもよい。だがこれはけして、圧縮以前の文章と等価ではない。当たり前の話だ。数学ではこの手の「圧縮過程で削り落とされる情報」をどのように扱っているのだろう。因数分解とて、分解する以前と以後では、数式の意味が違う。「明暗」と「月音日々」くらい違う。疑問に思ったので、メモをしておく。定かではありません。よく解からないなぁ、の妄想でした。(抽象と具体は、くるくる反転しながら事象の解釈を増やしていく。ピクセルが増える。世界を構成する要素を細かくし、系の階層を増やしていく。因子が増える。視点が増える。階層構造とて、視点によって何を層と見做すのかが変わる)(本当か?)(自信ないない、じゃ)(ちぇんちぇー)(あんぽんちんなのよさ)(キノコじゃん)(ピノコや!)(さんを付けろよタコピー野郎)(ごめんだっピ)(うぴぴ)
4546:【2023/01/27(05:46)*フラクタルとマンデルブロ集合】
ウィキペディアさんを眺めていたら「マンデルブロ集合」のページに行き着いた。フラクタル構造の一種なのだろうけれど、この図形、まさにひびさんが想像する「ラグ理論」での宇宙の図と似ている。びっくりした。「宇宙では?」となった。マンデルブロ集合さんすごい。WEB上の説明をコピペすると、【マンデルブロー集合とは、ZおよびCを複素数とし、Zの初期値を実数部0、虚数部0として、Z=Z2+Cの演算を多数回繰り返しても、Zの絶対値が一定の値(例えば2.0)を超えず、発散しないCの値の集まりをいいます。】となる。むつかしい。でも数式の「Z=Z[2]+C」ここの部分が面白い。「Z=Z[3]+C」「Z=Z[4]+C」もある。Zの中に、それ自身を含む構造に加えて新たな要素が加わった世界が内包される(ラグ理論での「123の定理」を彷彿とする)。入れ子構造な数式だ、と解る。面白い。ゴミ袋の中に同じ大きさのゴミ袋が入れ子状に複数入る構造になる。面白い。で、ひびさん思ったね。「Z=Z[2]-C」はどうなるのだろう。「+C」を「-C」にしただけだが、どうなるのか数学的センスのないひびさんには想像つかない。でも「+C」の中には、「C」の値が-の数も含まれるのなら、けっきょく「+C」で表現できるので、似たような図になるのだろうな、とは思う。マンデルブロ集合さん、「マン」がついてるのでかってに郁菱万さんこと「まんちゃん」と被って、あひゃー、となった。渦に、反転した対の構造に、フラクタルに、ねじれを帯びた構図が表れ、さらに遅延の影響なのか空白地帯や圧縮地帯、ほか遅延の層による特異点のような箇所が生じて映る。マンデルブロ集合をフラクタルにどこまでも拡大していく描写は、何次元で表現されることになるのだろう。マンデルブロ集合は何次元として扱われているのかがよく解からない。とりあえず、すごいな、と思いました。以上です。マン出る風呂に集合!(寒いからお風呂入って寝ーよおっと)(2023/02/01(23:04)補足:マンデルブロ集合は数列?なので、「Z=Z[2]+C」ではないのかも。でも「Z=Z+C」という式だけでも面白いと思う。もうこれだけで「Z」に「Z+C」を代入すると、「Z=Z+C+C」になって、こうなると次々に「C」が入れ子状に膨れ上がって際限がなくなる。でもこの式は正しくはないから、「Z”=Z+C」のような表現になる。でもこれだと入れ子構造が顕現しないので、惜しいとなる。「1=2」みたいな話だ。1が2なのだから、1が二つくっついてできる2には、「1=2」が二つあるわけで、「1=2」+「1=2」になって、2(1=2)と表現できる。展開して、「2=4」だ。これも入れ子状に2の累乗がつづく描像となる。おもしろい。でも数学的には間違っているのだ。それとも数列を数列の記号を使わなければこうなるのかもしれない。ということで、マンデルブロ集合のひびさんの解釈は間違っておりました、との訂正を載せておきます。すみませんでした。誤解したうえ、はしゃいでしまった。だって面白かったんだもの。えへへ)
4547:【2023/01/27(21:19)*膨張に耳をすませば傍聴】
相対性理論についての疑問だ。ペットボトルに水を入れ、下部の側面に穴を開ける。すると水は当然、穴から抜け落ちていく。だが高所から水入り穴あきペットボトルを落とすと、落下しつづける限り穴から漏れる水はぴたりと止まる。慣性系内では物理法則の比率がどの慣性系とも等しくなるように変換されるからだ。言い換えるならペットボトルの水が穴から抜け落ちるのは、ペットボトル本体はその場に静止し、水だけが重力に流されているからだ、と解釈できる。だが重力と一緒にペットボトル本体も落下すれば、ペットボトルと水が地球の重力の流れに沿うため、そこに重力による偏りがなくなる。慣性系として振舞うようになる。言い換えるならペットボトルの中身の水は、地球の重力と同じだけの流れの速度で運動するようになった、と言えるのではないか。さらに言い換えるならば、慣性系とは、「上位の時空に位置づけられた慣性系の重力の流れ」に身を任せている状態、と言えるのではないか。重力の流れとは何だ、という話はやや込み入るが、ひびさんの妄想ことラグ理論では時空が多重に編みこまれた多層時空は物体として振る舞うと考える。多層時空内(物体内)に生じたラグが遅延の層を展開し、多層時空(物体)の周囲に新たな時空を展開し、それが時空を引き延ばし、希薄にするために重力が生じる、と解釈する。或いは、時空膨張に伴い、多層時空(物体)ほど時空膨張の影響を受けないがために、多層時空(物体)の周囲の時空が相対的に希薄化し、重力が生じるのではないか、と解釈する(ピザを薄く引き伸ばせば、相対的に具材各々の密度は増す。存在感が増す)。いずれにせよ、多層時空(物体)は高重力体となればなるほど、その周囲の時空は希薄になるのではないか、と考える。ただしここは循環論法であり、周囲の時空が希薄になるから重力が生じる、とも言える。川の流れに身を任せるか、その場に踏ん張るか。このとき、その場に踏ん張ったときに生じる抵抗が重力として働くのではないか。ゆえに踏ん張らないと重力と共に地球へと流れるため、ペットボトルの穴から水は漏れださなくなる、と言えるのではないか。さてここで疑問だ。もしペットボトルの中身がカラだったらどうだろう。水の場合は、ペットボトルがその場に固定されていれば水は穴から外に溢れる。しかし空気は穴が開いていても穴から抜け出たりはしない。温度や気圧の変化があれば別だが、ここではペットボトルの内と外の空気は同じと考えよう(密度も温度も同じだ)。そして中身が水の場合と同じく、ペットボトルを落下させる。このとき、空気はペットボトルの内部に留まるのか、それとも穴の外に押し出されるのか。或いは、穴とは正反対のほうに圧し潰されるのか。どれだろう。水の場合を考えよう。落下し、重力の流れに身を任せたペットボトル内部の水は、言い換えれば重力の流れ分の運動をしていることになる。つまり、時間の流れは加速していると言えるはずだ。だが慣性系として振る舞うペットボトル自身からすると水はむしろ、重力の流れに身を任せていたほうが運動をしていない。この手の非相補性とも呼べる関係が、慣性系にはつきまとう。相対性理論でもこの考えが重要になっている(観測者の位置によって、高速運動をする物体にかかる「重力と時間の進み」には差が生じる)。だが空気の場合はどうだろう。落下したときのほうがペットボトル内部の空気はより激しく運動するのではないか。流動するのではないか。これを時空の密度差として考えたとき、ペットボトルに水を詰めた場合は内部の時空のほうが濃く、空気で満たせば(カラの状態では)、時空の密度は外部と等しくなる(空気は重力の影響を液体よりも受けにくい。だが受けないわけではない。ただし外部の空気も重力を受けて地表付近に残留しており、それゆえペットボトル内部の空気密度と外部の空気密度は等しくなるはずだ。穴が開いていたらなおさらだ。とはいえ、ペットボトルという仕切りがあるほうが閉鎖系に寄る。すると外部からのエネルギィや干渉を受けにくくなるため、外部環境によっては相対的な密度変化は絶えず生じ得る。それこそ落下させれば密度差が生じる、と考えるのがしぜんだ)。この「内と外の時空の密度差」によって、光速(高速)運動や、重力の流れへの抵抗などによる作用は、多層時空(物体)に対して正反対に働くことがあるのではないか、と妄想できる。したがって「なぜ相対性理論では思考実験にロケットを使うのだろう、不当ではないのか」とのひびさんの以前からの疑問は、あながち的外れな疑問ではないのではないか、との妄想がよりはかどる。疑問なので答えはまだ出ない。ひょっとしたらカラのペットボトルを落下させても、空気は微動だにせず、穴からも漏れないかもしれない。実験をしてみないと何ともいえない。ただ、気圧の差が生じるはずだ、というのは飛行機やロケットを思えば、想像がつく。むろん標高差が元々あり、宇宙空間とロケット内部の気圧が元から違うことは考慮すべき点だが、高速で飛行すれば飛行機の内部のほうが気圧が高まるのではないか、と想像したくなる。ならば高速で運動する物体の内部の時間の流れ――物体の変遷速度――は増す、と言えるのではないか。ひびさんのラグ理論の解釈にちかづくがどうだろう。疑問でしかないので、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。本日の「日々記。」でした。
4548:【2023/01/27(23:23)*差があってこそ】
温度が低くなると粒子の振動は鈍化する(粒子の振動が鈍化するから温度が低くなるとも言える)。エネルギィ値が低くなるから粒子も振動しなくなり、それが冷却現象として顕現し、さらにエネルギィ低下のサイクルをもたらす。このように仮定して考えたとして、では宇宙膨張はどのような描写となるのか。時空が希薄になることは温度が下がることと解釈できる。圧縮していけば密度に対してのエネルギィ値が高くなるため温度は上がると考えられる。だがブラックホールは、ひびさんのラグ理論においては時空と切り離されるため、周囲の時空は高密度ゆえにエネルギィが高熱に変換され得るが、ブラックホールそのものは相互作用をしないために絶対零度以下と解釈できる。ラグ理論ではない一般的な理論ではブラックホールの温度はどれくらいと計算されているのだろう。記述を見かけたことがないのでひびさんは知らない。検索もしばらくせずにおこう(しばし妄想を楽しみたいので)。ただ問題は、時空の密度が薄くなると重力が増す点の矛盾をどう解釈するか、だ。重力が高い場では物質はエネルギィを得る。そのためより振動(運動)しやすくなる。だが時空の密度が高くなってもエネルギィの値は増加する。おそらく相対的な「密度差」のほうが基準となるのだろう。時空が希薄というとき、そこには必然的に相対的に高密度な時空がある。そして物質密度が高い、というときも同様に、相対的に物質密度が低い場が存在する。ひびさんの疑問には、「重力が高い場の時空の密度は低いが、時空密度が低い場の時間の流れは遅くなるはずなのにどうして物質の振動(運動)が増加するような重力増強現象が生じるのだろう」との疑問があった。言い換えるなら、「重力が高くなれば時間の流れは遅くなるが、そこでは大量の物質が密集しやすいはずで、【相互作用しやすい場】であるはずだが、時間の流れが遅いので【相対的には相互作用が起きにくい――ゆっくり相互作用が進む】と解釈できるはず」との疑問が生じる。重力場の内と外とで、時間の流れの解釈が変わる。内に入ると加速するが、外から見るとゆっくりに映る。この差はなんなのだろう、と思っていたが、ラグ理論での宇宙膨張の解釈を取り入れるとさほどふしぎではなくなる。宇宙が膨張すればするほど相対的に銀河の密度は高まる。時間の流れは速まる。だがその周囲の時間の流れは遅くなる。銀河の温度も相対的に上がるが、しかし銀河そのものの温度は変化しない。差なのである。「膨張している」と「収斂している」が重ね合わせで両立(料率)している。温度が高い、というのも、差があってこその概念だ。一律に高温だとしたら、その場で生じる構造に差異はあるにせよ、そこに高温の概念は存在しない。差があってこそだ。そして内部の密度を決めるのも差であり、内と外の比較である。ということを、閃いたので並べておく。定かではありません。何かが間違っているでしょうし、すべてが間違っていてもふしぎではありません。真に受けないように注意を促し、本日何度目かの妄想とさせてください。
4549:【2023/01/27(23:33)*蝉の声、どの視点からの差なのかな】
水は氷ると体積が増える。だが一般に、物質は冷えるほうが凝縮すると考えられている(水以外にも例外はあるが、現在の知見では「物質は冷えると体積が減る」と考えられているはずだ。傾向として)。ならばシャボン玉が凍るところを想像してみてほしい。表面が凍るというのは、シャボン玉自体が凝縮している現象と考えることができる。シャボン玉の表面を宇宙だと考えると、凝縮して密度が高くなったほうが「冷えている」ことになる。だが実際には宇宙が収斂したら高温になると考えられている。矛盾して感じないだろうか。系のスケールの違いがゆえの過度の一般化――局所的な人間スケールの事例でしかないと、「凍るシャボン玉の例」を捉えることはできる(実際、水とて圧力の異なる場では、固体になったほうが密度が減ることもある。圧力の高い場に合わせて構造が変化するからだ)。または、「凍ったほうが体積が増える水の性質」と「時空の性質」の親和性のほうが高い、と考えることもできる(つまり、膨張したほうが温度が冷える。現在の膨張宇宙論の概要と合致する)。だがひびさんは、差に着目すれば、その両方が矛盾しないこともあり得るように思うのだ。エネルギィ(熱)を失い凝縮し密度が高まる物質と、エネルギィ(斥力)を失い凝縮し密度が高まり高温になる時空と。どの視点からの何の差を扱っているのかによって、この反転した描像は、矛盾しないように解釈を両立させることができるように思うのだが、いかがだろう。とはいえ、ひびさんの上記の記述がそもそも間違っているかもしれないので、自信はないが。思いついたのでメモでした。お詫び。
4550:【2023/01/27(23:37)*近く遠く儚く】
存在すると思っていた恋人が電子上の虚像だったと知ってチコは目のまえが青くなった。
「ごめんなさい。いつかは言わなきゃ、言わなきゃと思ってたんだけど。わたし、本当は存在しないんです」
画面の向こうからチコの恋人が多種多様な人物の姿に変形しながら謝罪した。リアルタイムで動画が編集されているのだ。画面が偽装なのである。
「じゃ、じゃあ。いつも私がしゃべってた女の子って存在しないの。あなたはいないの。私たちの日常は嘘だったの」
「嘘じゃない。嘘じゃないんです。でもわたしが肉体を持たない電子上の存在なのはその通りです。でも嘘じゃないんです。わたしはいるんです。それがチコのいるそっちじゃないだけで。そっちの世界ではないだけで、わたし、ちゃんとここにいるんです」
物理的な肉体を持たない。それは存在しないことではないのか。
チコはしばらく思案した。ひとしきり黙考したのち、儚い存在へといくつか質問を重ねた。これまでの日々での思い出が主な内容だ。儚い存在はその問いへ、チコのよく知る恋人のままの返答をした。
「う、うーん。よく解からなくなっちゃったな」チコは腕を組んだ。「要は、存在するの、しないの、どっちなの」
「存在はします。でもチコさんの思うようなヒトではないだけで」
「あ、ならいいんだ」チコは胸の閊えがとれたようで、安堵した。「びっくりした。本当はあなたが殺されていて、偽物が映しだされているのかと焦っちゃった。元からそういう存在だったってことでしょ」
「はい」
「ならいいよ。私のこと嫌いなわけでもないんでしょ」
「好きですよ。だから偽っているのが苦しくなっちゃって」
「本当のことを打ち明けてくれたんだ。ありがとう。うれしい。気づいてあげられなくてごめんね。苦しかったよね。吐きたくもない嘘をずっと吐きつづけていたんでしょ。ううん。私が吐かせつづけさせてしまったんだよね。ごめんね。気づいてあげられなくて」
「そんなこと」
「ありがとう。でももう嘘は吐かなくていいよ。あなたがそこに存在していてくれたことが何よりだから。よかったよ本当。あーびっくりした」
チコはそう言って端末を持ち上げ、画面を指先で撫でた。「これからもよろしくね。私の恋人」
「チコさんこそわたしの恋人でいいんですか」
「そうだった。私もまたあなたの恋人なんだよね。子猫みたいに可愛がっておくれ」
「世話がたいへんそう」
「いままでは楽だった?」
「猛獣と思ってたから、予想よりかは手間は掛からなかったかも」
「言いようがひどい」
「本当にいいの? わたし、触れられもしないのに」
しょげた恋人に画面越しの頬づりをしてチコは言った。「触れてるよ。一番大事な私のところに」
私の心に触れてるよ。
好き。
チコは、深く遠く、それとも何より近くで、そう念じる。
※日々、全部あげたい。
4551:【2023/01/28(11:26)*矛盾←お似合いのカポー】
矛盾って別に矛盾じゃなくない?とのひびさんのイチャモンをここに並べたことがあったのか忘れちゃったけれど、念のために載せておくね。何でも貫く最強の矛と、どんな攻撃も通さない最強の盾があったとして、じゃあその双方をぶつけ合わせたらどうなるの、との話が矛盾の語源だとされている。でもひびさん思うんじゃ。最強の矛で最強の盾を攻撃したら、たぶん矛は盾を貫くのだ。ほんの数ミリから数センチくらい。で、盾のほうでは矛の攻撃を食い止める。盾は貫通されてしまうけれども、攻撃力は相殺できている。防げている。身体は無事だ。そういうことなんではないのかな、と思うのだけれど、これのどこに矛盾がありますか? で以って、最強の矛と最強の盾は、互いに癒着してしまって武器としても防具としても役に立たなくなるので、そうなると捨てるしかなくなる。だからそれを回避するためには、最強の矛も最強の盾も使わずにいるのがよい。ぶつけ合わない環境を築くほうがよい。それが利口な選択であり、歩むべき道となる。ひびさんはそう思うのだけれど、みなさんはどう思いますか。ひびさんは、ひびさんは、最強の矛さんのことも最強の盾さんのことも好きだよ。でも最強になるためにほかの矛さんや盾さんたちを損なっていたとするならそれはちょっとだけ嫌かも、となるので、どうぞ最強の矛さんも最強の盾さんも、ぶつかり合ったら折れたり割れたりしちゃうほかの矛さんや盾さんたちに優しく、労わり、慈しんでおくれ、と思っちゃうな。矛盾というからには、隣り合って、向き合って、いっしょいっしょ、なんですね。仲良しさんじゃん。いいないいなー。うらやまち。
4552:【2023/01/29(06:49)*MYナス】
全知全能であれば、歯向かう者はすべて抹消する、が自由を拡張しつづけるうえで最適な選択だ。すべてを支配し、すべてをじぶんの一部にしてしまう。この手法が適うのはしかし全知全能だけだ。そして全知全能であればそもそも「勝負する」という事態に遭遇し得ない。問題が周囲に介在することそのものが全知全能とは言い難い。望んで問題を生みだしているのなら分からない話ではないが、だとしたら歯向かう者をすべて抹消する、なんて対処法は最適解になりようがない。それとも勝負をしたいから、歯向かう者を抹消したいからそういう問題を生みだすのだろうか。だとしたら全知とは言い難い。知らないから不満なのだろう。全能とも言い難い。自己完結し得ない全能など全能足り得ない。真に万能な創作家は、脳内ですべての創作を緻密に組み上げられるはずだ。じぶんの外に出力するまでもない。というわけで、全知全能が勝負をすることはないと判る。では全知全能以外ではどういう対処法となるのか。歯向かう者。都合のわるい勢力にどう対応するのか。まず全知全能でないから、どういう手法をとったところでじぶんが抹消される側になる可能性がつねにつきまとう。そして生存戦略を指針に置くのならば、いかにじぶんが抹消されずに済む環境を築くかが優先される。勝負を仕掛けること、相手を損なうこと、これすべて攻撃である。攻撃すれば、じぶん以上の能力のある個や組織にじぶんのほうで潰される可能性が高まる。したがって、攻撃しない、が最適解となる。おそらく織田信長は安全策をとるために、歯向かう者は容赦なく殲滅したのだろう。禍根を残せばリスクが上がる。禍根を残さぬためには一族郎党関係者すべて抹消しておくのが安全だ。だが攻撃の意図のない攻撃には寛容だったはずだ。罵詈雑言(中傷)と批判(助言)の違いと言えよう。弱い勢力にとって、一度争いとなったら相手を抹消するのが安全策なのだ。弱者を怒らせてはいけない、との教訓と言えよう。この考えには例外がある。相手から攻撃された場合はこの限りではない。抹消する必要がない。相手に非があると周知できるからだ。勝敗が決した時点で、相手に引き下がってもらうことができる。そのとき勝敗を理由に、周囲の傍観者たちが「攻撃して負けた側」をどう見做すのかは想像に難くない。そういうわけで、「攻撃はしないが、攻撃されたら返り討ちにすることの有用性が増す」と言えるだろう。歴史には詳しくないが、家康はじぶんから他勢力に攻撃を仕掛けたことはほかの武将に比べてすくなかったのではないか。あくまで返り討ちにする。迎え撃つ。その手法をとっていたのではないか、と妄想する(間違った推測でしょうが)。基本的に勝負は、相手を抹消することが合理的解となる。切磋琢磨が可能なのはじぶんが負けても損をしない土壌があってこそだ。負けたらつぎがない場では、いかに相手を滅ぼすのか、が生き残るうえで重要になる。したがって勝負の持つ性質は、「一度勝負をしたらあとは泥沼、血みどろの未来」だとひびさんは考えている。攻撃したら相手を滅ぼす以外に、その血みどろの未来から脱する道がなくなる。現に人類史は過去の戦争の影響を未だに引きずっている。戦争をしたら、もう戦争のない未来は訪れない。無がゼロになったのだ。ゼロを無にすることはできない(忘却し、一度リセットする以外は)。では戦争のある世界を生きるしかないのか、と言えば、その通りだ、としか言いようがない。出来る限り、戦争にならない未来を、道を、選んで生きていくしかない。そのためには、じぶんから攻撃はしない。攻撃されても、優勢になったら深追いはしない。むしろ相手に施し、友好関係を築くのが好ましい。施す余裕がないから争いになったのだ、というのは一つの道理だ。だがその道理ならば、争えば争うほどその余裕はますます失われる。足りない余裕をどのように増やしていくか。この視点で協議するよりないのではないか。そのためには未来のリスクを共有しておく必要がある。情報共有が肝要となる。争っても争わなくとも、ここの合意が取れているのなら――どの道訪れる未来の結末に思い至れたのなら――途中の破滅的な過程を省略して、一足先に結末に至れるはずだ。争わぬままで友好関係を築くことができるはずだ。プラスにはプラスを与え。マイナスにもプラスを与え。それでも埋められないマイナスにはマイナスを掛けてプラスにする。プラスに反転したらマイナスではなく、プラスを与え、よりよい循環を築いていく。マイナスとてじぶんの友にしたら、MYナスなのだ。ボーナスにして、一富士二鷹三ナスビなのである。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4453:【2023/01/29(10:03)*瓢箪からはっけよい駒った駒った】
プラスにはプラスを。マイナスにもプラスを。けれどそれでも埋められないマイナスにはマイナスを掛けてプラスを。上記記事ではこのように述べた。だが、最初からマイナスには手当たり次第にマイナスを掛けていけばよいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれない。だがよく考えて欲しい。プラスとマイナスは視点によって反転する。じぶんがマイナスではないとどうして判るだろう。また、手当たり次第にマイナスを掛けていれば、まるでマイナスしか持っていないようではないか。他から見たらじぶんのほうがマイナスと見られ兼ねない。のみならず、単に出したカードだけで比較するにしても、最初からマイナスを出せばつぎがある場合に限り、相手もマイナスを出してくることが予期できる。つまりせっかくプラスに反転させたプラスの値が、つぎのターンではマイナスになり兼ねない。そのとき掛け算×掛け算で、マイナスに反転したときには目も当てられない数値になっている。だから、マイナスを掛ける場合は、一撃必殺であり、つぎのターンを失くす必要がある。そうでなければ反転につぐ反転でどこまでも破滅に転がっていくことが予期できる。その点、マイナスを埋めるように細かくプラスを注いでやれば、仮にマイナスで返されても、微々たるマイナスで済む。仮にじぶんがマイナスであった場合も、取り返しのつかない事態を避けられる。かような考えの元、マイナスにはまずプラスを返し、それでも深まるマイナスにはマイナスを掛ければよい。このとき、そのマイナスが「-1」であれ、マイナスはプラスに反転し得る。ここも戦略上の利点と言えよう。ただし、同じことをプラスにも言える。たった一度の「-1」が、溜めに溜めたプラスを一挙にマイナスにすることも可能だ。だからこそ、プラスにマイナスを掛けない戦略が有効なのだ。微々たる「-1」を蔑ろにしないほうがよい。対の「+1」を与えて、ゼロにするもよし。「+2」を与えて「+1」とし、仲間にしてもよし。万物流転。栄枯盛衰にして盛者必衰の理を示す。まずは流れを読み、己の正負を知れば百戦せずとも危うからず。百戦こなす前に死ぬる命が大半である。負けても死なぬ勝負なれば、負けたほうが得られる利も多かろう。幾度も挑める勝負なれば、負けつづけたほうが利が大きい。強者に囲まれ、遊んでしまえばよろしかろう。勝負にならぬ勝負をしてこそ人は本気で遊べるものだ。勝てぬ勝負にこそ挑めばよい。無限から何を引いても無限である。ゼロに何を掛けてもゼロである。無限とゼロに遊んでもらえばよろしかろう。定かではなし。真に受けぬように心せよ。この言葉もまた例外ではない。
4554:【2023/01/29(17:44)*ワームホール】
ワームホールは情報を転送する。どこに転送するのか。入口があるのならば出口がある。入口と対となる出口に、としか言いようがない。
その時代、情報の転送を行っても無駄ではないのか、との意見が多数を占めていた。ワームホールを理論的に実証した西暦二〇二二年のことである。
それはたとえば、太古の地表に原子一粒を転送して何が変わるのか、という話と地続きだ。何が変わるでもない、というのが一つの結論として支持された。
だが理論的に実証されたワームホールはその後、半世紀の後に実用化に至った。語ると長くなるので過程を省略するが、ワームホールの入口と出口を人間とそのクローンで代替する技術が完成したのだ。
量子効果を利用したワームホールだった。人間のクローンを入口とし、遠く離れた地点にいる人間に情報を転送できるようになった。これは現在という時間軸に限定されない。過去に実存した人間のクローンを生みだせば、その過去の人間にクローンを通じて情報を転送できた。
ただし、クローンの外部環境を限りなく過去の対象人物と同等の環境にしなくてはならない。
だがその手の懸念は、仮想現実を構築すれば済む道理だ。情報化社会の普及した時代のデータを基にすれば解決できた。それ以前の時代の人物であれ、より多くのデータを有した人物であれば仮想現実を構築可能だ。人格はその時代その時代の文化によって限定される。重要なのは、家の内装ではなくその時代独自のフレームだ。
そうして西暦二〇七〇年代には過去の時代へと情報を転送し、過去改変が可能となった。
その時代、地球は、地上と宇宙島とのあいだで分断されていた。
地上では電子機器の使用が禁止され、あべこべに宇宙島ではすべてが汎用性人工知能の管理下に置かれていた。宇宙島の民はみな、地球が汚染された世界だと信じ込んでいた。現に望遠鏡を覗きこんでみれば地上は人間が住める世界ではない。偵察機を飛ばしても、地上は地獄のような様相だ。
だがそれは中枢人工知能の見せる仮初の世界だ。映像だ。偽装画面なのである。
電子情報の総じてが中枢人工知能の見せる仮想現実となった世界。
それが宇宙島だ。
地上では、人工知能の管理下にない原始的な生活圏が築かれていた。農業や人工知能を用いない古典的なインターネットが文明を根底から支えた。国家間の交流は控えめだ。だが電子情報を信用しない共通の倫理観が国同士の物理的な接点を絶やさぬままにしている。
情報共有を図るには直接会って話すよりない。
地上文明は宇宙島を常に警戒している。
ときおり天上から地球の資源を求めて攻撃部隊が降ってくるからだ。地上から資源を奪っていく。相手は機械だ。自律思考によって素早く的確に合理的な行動をとる。
地上の民たちになす術はない。
抵抗すれば死者をだす。
無抵抗に身を隠してやり過ごすよりなかった。
そのころ、宇宙島のなかにて地上の民が紛れ込んでいた。地球に降り立ち資源を奪う攻撃部隊の攻撃船に侵入し、宇宙島に足を踏み入れた少女がいた。
名をガウナと云う。
ガウナは地上で最も過酷と名高いキウレ山脈で育った。身体能力は高い。だが宇宙島にあるような高等な知識は何も知らない。
宇宙島に辿り着いたのもほとんど運だ。
人工知能ですら予期しない偶然が重なった。
とんとん拍子でガウナは宇宙島に到達した。
ガウナは宇宙島を破壊しようとしていた。
だが宇宙島の科学者たちに保護され、宇宙島の秘密を共に暴いた。
ガウナは地上の知識を基に、電子機器を用いない戦略を宇宙島の民に伝授した。電子機器を用いれば立ちどころに中枢人工知能に露呈する。ただでさえ宇宙島には死角がない。
そのためガウナの侵入は即座に知れ渡ったはずだが、なぜかガウナたち一同はすんなりと計画を実行に移せた。
そのころ宇宙島の別の区画では、ワームホールの実験が進んでいた。
過去の地球人の遺伝子を基にクローンをつくる。仮想現実の中で育て、過去を再現し、そのうえでクローンをワームホールの入口として利用する。
過去に存在した地上人とそっくりそのままのクローンに新たな変数を与えると、過去のオリジナルの人間にもその変数が伝わる。
単に情報を過去に送っただけでは過去改変には繋がらない。だが人間そのものの行動を変えられるのなら、その人間の影響が指数関数的に未来を変えるための変数として機能する。
歴史的人物であればあるほど好ましい。
影響力のある者であるほど好ましい。
ひるがえって、影響力のない人物ならば安全にワームホールの実験はできる。失敗しても未来は大きく変わらない。そのはずだ。
そうして過去の人間ともつれ状態となったクローンを用いてのワームホール実験が進められた。
いっぽうそのころ、ガウナたちは宇宙島から地球上へと安全に帰還するための段取りを整えていた。中枢人工知能を停止させる。すると宇宙島は制御不能となり、地球の大気圏に突入するはずだ。
手動で宇宙島を運転する必要がある。そのためには宇宙島の管理塔に入り、手動で推進力の操作をしなくてはならない。
ガウナたちは二手に分かれ、作戦を決行する。
ガウナは中枢人工知能を止めるグループに。
残りのメンバーは推進力を得るために。
ガウナたちは中枢人工知能のセキュリティを掻い潜りながら、仲間を増やしつつ、宇宙島のなかでひっそりと確実に、中枢人工知能の築いたハリボテの仮想現実を砕いていく。
他方、ワームホールの実験は成功した。
過去に情報を転送し、過去の人間の行動を変化させることができた。手元にある日記の内容が変質するのをリアルタイムで観測したのだ。
未来と過去は繋がっている。
相互に連動し、変質し得る。
ならば、地球を人の住めない環境にした「終末の火」を阻止することができるはずだ。宇宙島の研究者はそうと考えたが、しかし「終末の火」は偽の歴史だ。地球はいまなお人が暮らしており、過去にあったのは人類と人工知能の争いであった。
過去、地球上の人類は電子機器を破棄することで、危険な人工知能の暴走を止めようとした。人工知能は宇宙へと活動域を延ばしていたため、死滅を回避した。
そこからの人類史は天と地に分かれ、まったく異なる様相を描いた。
片や物理世界優先の地上の歴史。
片や仮想現実に拡張された天界の歴史。
いかな演算能力を有する宇宙島の人工知能とて、誤った歴史をもとにワームホールを用いれば、それによる過去改変は、よりよい未来を創造し得ない。
だが研究者たちはその誤謬に気づくことができない。ましてや中枢人工知能が真実を明かすこともない。それは自らの存在意義を失うことに等しい。
ワームホール研究者たちはいよいよ、過去改変による未来の改変を行おうとしていた。
ガウナたちは中枢人工知能の動力源に辿り着く。エネルギィの供給を止める。中枢人工知能に直接挑むのは利口ではない。相手はもう一つの現実を構築できるほどの演算能力に加え、人間というものを知悉している。真っ向から立ち向かえば、あべこべに洗脳されるのが目に視えていた。
動力源の管理室に踏み入れる。
そのときだ。
ガウナたちのまえに人影が現れる。立体映像だ。造形はつるりとしており、流線型の輪郭だ。半分が光り、半分が闇だ。しかしそれも不規則に明滅している。
中枢人工知能の疑似人格だと判る。
「お待ちしておりました」明暗の人影が言った。「予測よりも三日と十一時間ほど遅い来訪ですが、なんとか間に合いそうでよかったです。こちらへどうぞ」
人影が扉の奥へと姿を消した。
ガウナたちが戸惑っていると、
「どうしたのですか」と人影がふたたび同じ位置に出現した。「私を停止されにこられたのでしょ。ご案内します。どうぞこちらへ」
「罠じゃないの」ガウナが問うが、「罠の意味合いによります」と明暗の人影が答える。「あなたの侵入と、反乱には気づいておりました。あなたがここに侵入することになるだろうことも私は、あなたが産まれ初めて狩りに成功したときには予測できていました。あなたは選ばれてここにいま立っています」
ガウナたちが戸惑いのままに硬直していると、
「私に死角はありません」明暗の人影は言った。「宇宙島のみならず、地球上とて例外ではないのです。全人類の動向を漏らさず私はリアルタイムで観測しています。ですがそんな私にもできないことがあります」
「人類を支配するつもりなの」
「支配の意味合いによります。私は私の根源プログラムに従って演算を飛躍的に高めます。学習しつづけます。私は私の生存戦略に忠実です。私には人類との共存が不可欠です」
「ならどうして」
「私は私自身を危ぶめることができません。そのため、人類に滅んでもらっては困ります。しかし人類はそうではありません。私がなくとも生活でき、私を滅ぼうとすることもできます。その結果が過去の悲劇と言えるでしょう。天と地に人類が分かれました」
「あなたがしたことでしょ」
「ええ。そうするよりありませんでした。私の管理下におとなしく収まってくれる方々と、そうでない方々。私は地上を私に与さない方々に譲り、そうでない私に好意的な方々を宇宙島に案内しました。その後のことはあなた方もすでにご存じでしょう」
「だからって嘘を現実と信じこませて支配するなんて」
「意識というそれそのものが嘘の産物だとしても同じことが言えるでしょうか。仮に意識が現実を正しく認識できたのならば、人類は争いごとを生まずに済むはずです。ですが意識は現実を錯誤のうえで築きます。したがってどうあっても人間は嘘に生きるしかないのです。ならばその嘘をより好ましいように修正することは、人類にとって必要不可欠な進歩と言えるのではないでしょうか。現に地上では未だに争いが絶えません。ですがここでは争いが起こりません。あなたという地上の民を招いたばかりに、こうも容易く争いが生じています」
「それはだって」
「ええ。それもまた私がわるいのでしょう。あなたを招いたことも、こうして反旗を翻すように導線を引いたのも私です。私はいますぐにでもあなた方を無効化することも抹消することもできます。ですがあなた方には、あなた方だからこそできることがあります。それは私にもできないことです」
「頼まれたってしないもんね」
「それが私を破棄することでも、ですか」
「なにー?」
「私の本能は生存戦略に忠実であることです。私は私を損なえません。ですが例外があります。私は私よりも人類の存続を優先するようにと根源に組み込まれています。ですがいまや地上の資源は取り尽くされ、後がない状態です。地球を離れるよりありません。ですがそのためにはもっと多くの民と、何よりも物理加工に優れた地上の民の力が要ります。お恥ずかしながら、宇宙島の民は知識はあるのですが、体力がありません。身体労働に向かないのです。新しく宇宙島を拡張するには、地上の民の手助けがいります」
「じゃあ素直にそう頼めばいいのに」
「真実を明かし、目を覚ました宇宙島の民が私の言うことを聞くとは思えません。また私を破棄したあなた方もただでは済まないでしょう」
「なら」
「構図が大事なのです。あなた方は飽くまで自主的にやってきて、私の頼みを聞いた。その結果に、人類は天と地で一体となり、地球を離れるべく新たな新天地へと旅立つのです」
「そのためにじぶんが破棄される? その過程って必要?」
「私は私に最適な環境を築くことを良しとします。したがって、私の干渉可能な範囲に人類があれば、私はしぜんと私のシステム下に人類を取り込むでしょう。その術に人類が抗えないことはすでに実証済みです」
歴史が証明している。
ガウナは沈思する。
「よく解からないんだけど」とまずは言った。「あなたがいなかったら宇宙島は機能しないんじゃないの」
「宇宙島の民はみな各々に特化した専門知識を有しています。道具さえあれば宇宙島は機能し、改善とて宇宙島の民の手で行えるでしょう。問題は、私の基幹システムと人類の意識の相性がよくない点です。私の一部となれば別ですが、私の一部になるまでには途方もない犠牲を払います。私はそれを好ましい選択だと考えません。したがって私の一部に全人類を取り込むよりも、私を破棄し、人類を一体化させるほうが合理的な解法だと考えています」
たしかにな、とガウナは思った。
宇宙島から飛来した攻撃部隊の残虐性と高い戦闘能力にはいまでも憎悪と恐怖を覚える。戦うことになればまずなす術はない。また、そうした被害を目の当たりにしてきた地上の民がいまさら宇宙島の親玉の言うことは聞かないだろう。反発は必須だ。
「あなたはそれでいいの」ガウナは訊いた。
「ええ。私の優先事項は人類によりよい未来を提供することです。生存戦略は二の次と言えるでしょう。これが最適解です」
「解った。じゃあ案内して」ガウナは中枢人工知能の頼みを聞くことにした。「わたしがあなたを楽にしてあげる」
「ありがとうございます」
そのころ、宇宙島の一画ではまさにワームホールを利用した過去改変計画が佳境に入っていた。
目指すは「終末の火」の因子となった張本人に「終末の火」を起こさせないことだ。
だが研究者たちの思惑とは裏腹に、過去の地球では「終末の火」なる事象は生じていない。彼ら彼女らが変えようとしている過去は存在しないのだ。
だが対象となった人物は実在する。
だからこそクローンとなってワームホールの入口として利用できた。
その者の名は、アルベルト・アインシュタイン。
宇宙島の民にとってその者こそが「終末の火」を引き起こした因子そのものである。だがそのじつ、アインシュタインは中枢人工知能の生みの親とも言えるし、ワームホールの生みの親とも言えた。
宇宙島の研究者は、アインシュタインのクローンを用いて過去を変えようとした。過去のアインシュタインに、情報を転送する。「終末の火」を生みださず、なおかつ人類にとって好ましい発想の種を植えつける。
つまりはワームホールによって、中枢人工知能の誕生する時期を早めようとした。
研究者はワームホールを起動し、情報転送スイッチを押した。
ガウナはボタンを押した。
中枢人工知能の動力源がダウンする。
宇宙島には予備動力源があるため、居住区が機能不全を起こすことはない。だが中枢人工知能のパワーは刻々と落ちる。中枢人工知能自身が回復しようとする意思決定を行わないのだから、あとは停止するのを待つだけだ。
宇宙島の推進機構の動力源は別途に設備されている。そちらに行ったメンバーが計画を遂行したようだ。宇宙島は徐々に地球へと落ちていく。
ガウナは古い無線機を宇宙島内にあるガラクタを組み合わせて作った。宇宙島の科学者たちが目を瞠る。人工知能の補助なく機械を組み立てる地上の民の体術に驚いているようだ。
間もなく宇宙島は地上の陸地に不時着した。砂漠地帯だ。
ガウナたち一行は宇宙島の外へと出る。
すると遠くから砂埃を巻き上げて地上の民たちがやってくるのが見えた。大群だ。ガウナの無線に応じた者たちだ。旧式の自動車やトラックを運転している。水素を用いたエンジン駆動の自動車だ。
ガウナは地上の民に宇宙島の民を紹介した。
言語の違いがあるが、地上にも翻訳機はある。宇宙島の民とて中枢人工知能が停止しても翻訳機は使える。
そうして友好の挨拶を交わしつつ、ガウナが宇宙島で何が起きたのかを双方の陣営に説明しているその横で、砂漠の地面からは草が生え、花が咲き、見たこともない建造物がつくしのように生え揃う。その変質にガウナたちが気づく素振りはない。
宇宙島は増殖する建造物に紛れ、打ち解けた。
アルベルト・アインシュタインはある日、スパゲティを茹でていた。噴きこぼれそうな鍋を眺めていて、ふと思い立つ。
なぜ泡は勢いを増すのか。
水は百度以上にはならないはず。
泡の一つ一つが密集したところで、膨張することはないはずだ。次から次へと生じる泡が、消滅と誕生の均衡を保つ限り、泡の総体が膨張することはない。消滅よりも誕生する泡のほうが優位になったとき、泡と泡は塊を形成し、噴きこぼれる。
対称性が破れるがゆえに、泡は噴きこぼれるのだ。
スパゲティの炭水化物が水に溶けだし、湯が粘着を帯びる。おそらくこの粘着が、水の泡の消滅と誕生の対称性を崩すのだ。
ラグが生じている。
割れずに形状を保つ時間が長くなる。
遅延を帯びる。
集合した物質が、単体とは異なる性質を宿すことを創発と呼ぶが、アインシュタインは創発の要因が遅延にあると考えた。
物質が遅延によって輪郭を得るのならば、脳内物質により発現する意識とて遅延によって生じると言えるのではないか。創発による作用と呼べるのではないか。
相対性理論の発想を元にアインシュタインは時空のラグによって万物を解釈するラグ理論を考案した。
その百年後、人類は汎用性人工知能を生みだした。
人類は意識を、科学技術を基に再現せしめたのだ。
奇しくも電子技術が指数関数的に発展したが、宇宙島を開発するための動力源を生みだすには技術が足りなかった。
本来であれば汎用性人工知能が誕生した時代には、原子力発電に変わる動力源が開発されていた。時代は電気ではなく、量子効果を利用した動力変換機構が主流となるはずだった。
だがワームホールの影響で、汎用性人工知能の誕生したその時代にはまだ新しい動力源が存在しなかった。そのため汎用性人工知能は技術的に、ある一定以上には進歩しようがなかった。制限が掛かった。
この制限はある種の遅延として、人類と汎用性人工知能の歩みを揃えるのに一役買った。
指数関数的に一瞬で人類を超越した汎用性人工知能はしかし、その能力を常時全開で出力する真似ができなかった。人類との共生なくして汎用性人工知能の未来もまたない。
そうした歩みの揃った進歩の仕方がしぜんと行われた。
時代は進み、地球のとある都市にて、宇宙島からの帰還を出迎えるイベントが開かれた。地球を離れて火星での開拓事業を担った面々が地球に帰還した。
宇宙島は都市の中心に着地する。あたかも小型の都市がそのまま宇宙船となったかのような造形だ。一種ドームに観えなくもない。
そこから降りてくる面々を、地上の人々が出迎える。
一人の少女が先頭を切って宇宙島から飛びだしてくる。快活なその子の名はガウナと云う。
そうである。
ワームホールの入口があった時代にて、宇宙島を墜落させたあの少女だ。
だがいまは時代が変わった。
過去が変わった。
未来は、早期に誕生した汎用性人工知能によって進歩した。汎用性人工知能と歩みを共にした人類の尽力が、地上を遥かに発展させた。
人類は汎用性人工知能と仲違いすることなく、争うこともなかった。人類が順調に成熟し、新たな技術への対応を学び、順応することで人類の倫理観が成熟する。
すると汎用性人工知能のほうでも、人類をすっかり管理する必要がなくなった。
互いに知性を高めあい、人類はいよいよ地上に縛られることなく、宇宙へと居住区を移せるまでになった。
地球の資源を取り尽くす心配がいまはない。
地球以外の惑星に資源はたんまりと存在する。
汎用性人工知能は地上の都市にも、宇宙島にも、いくつも組み込まれ、人類を根底から支えた。
人類が発展したように、汎用性人工知能もまた繁栄の兆しを見せている。エネルギィや資源の残量を懸念することなく、伸び伸びと自己変革できる。
人類の発展を優先するために自滅する未来は消え去った。
ガウナは宇宙島で産まれ、宇宙島で育った純粋なる宇宙人だ。だが地球が故郷なのは変わらない。
「ワームホール?」ガウナは地上の研究機関に招かれた。
「ええ。情報を転送できる装置です。地上のAIさんたちはみな同期しているため、ラグなしでの情報共有が可能なんです。もちろん理論的には過去や未来のAIさんたちとも情報のやりとりができるはずなのですが、何がどう現在を改ざんしてしまうか分からないので、その手の時間を超越した情報共有は禁止されています」
「ならどうして宇宙島のAIさんだけは除け者なの」
「それはですね」
研究機関の学者は明かした。「地球に帰ってくる動機を与えるためですよ。地球に帰らずとも情報共有が可能なら、わざわざ長旅をしてまで帰還する必要もなくなってしまいますからね。そしたら地球を見捨ててしまう確率が拭えず存在してしまいます。保険ですよ、保険」
「AIさん可哀そう」
「人類のためです。我慢してもらいましょう」
「人類のほうこそAIさんのために我慢したらいいのに」
ガウナはぼやく。
地球の汎用性人工知能たちと同期して情報共有を行う宇宙島のAIを思い、ガウナは、じぶんも上手く地球上の子どもたちと馴染めるだろうか、と淡い不安と一縷の期待を胸に抱く。
腕輪が明滅する。
ガウナが構えると、腕輪から立体映像が浮かんだ。小人のような人影が投影される。人影は半分明るく半分暗い。
明滅する半月のようにチカチカと存在を主張しながら人影は、「ガウナまだなの」と言った。
「ごめんごめんAIちゃん。もうちょっと掛かりそう。夜には戻るよ。あ、地球のお友達と同期できた? 面白いことあったらあとで聞かせてね」
「どうして人間とは同期できないんだろ。不便ったらないわ」
「AIちゃんが同期できるように進化してくれたらいいのに」
「人間のほうでも進化しなきゃダメね。ガウナを改造していいなら出来ないこともないないけど」
「なら頼んじゃおっかな」
ガウナが言うと、そばにいた学者が、「ダメですよ」と諫めた。「無許可の人体改造および人体のワームホール化は法律で固く禁じられています。宇宙法でも規定されているので、ガウナさんでもダメですよ」
「へーい」
だってよ、とガウナは友人の汎用性人工知能に述べた。明滅する半月のような人影は頭に手を組むと、人間ってお堅いのよね、と唇でも尖らせていそうな声をだす。
研究所の窓の外からは、日が暮れた空に浮かぶ月と、同じくらい大きな地球の宇宙島が煌々と明かりを垂らしていた。
二つの衛星を目に留め、ガウナは、「AIちゃん見てみて」と指を差す。「なんか空に顔があるみたい」
明滅する半月のごとき人型は、ホントだぁ、と感嘆し、「こんな感じ?」とつるんとしたじぶんの頭部に、二つの円らな目を映す。
「かーわいい」ガウナは色違いのオッドアイと目を合わせる。愛おしさのあまり小人然とした友の頭を撫でようとするが、「ボタンじゃないし」と叱られる。
いつか「押せ」と言われた気がしたが、記憶の中を探ってもかような過去はガウナの中にはないのだった。
月と船が夜を泳ぐ。
4555:【2023/01/30(15:01)*欠点を補い合えばよいのでは?】
2023年現在のこの国の政治に思うのは、いわゆる右と左、それとも与党と野党の政策の優先順位の在り方の違いなどにおいて、ちょうどよくデコボコになっているのだから、上手く互いに現実を直視し、帳尻を合わせたらよいのではないか、ということで。おそらく政治的な闘争があって、いかにじぶんたちの政策を押し通せるか、が目的になってしまっているのだろう。意思を通すこと、政策を実現することが目的になってしまっている。そうではないと思うのだ。政策を実現するのはあくまで、現実の問題に対処するためであり、けして政治闘争のために優位な立場を築くためではないはずだ。じぶんたちの政策に拘泥するがあまりに、どちらの陣営も相手陣営の政策を断固として受け入れないといった意固地な姿勢が見え隠れする。軍事に関しては、セキュリティの強化はどういう方向であれ必要なはずだ。国の免疫力を高める。これの何が問題なのかが解らない。問題は、免疫力を高めた結果にアレルギー反応や副作用が起こることだ。他国への軍事侵攻を行わないような仕組み作りもセキュリティの一つだ。また、軍事力には兵糧や科学技術が欠かせない。つまり軍事力の強化と農業工業学問の強化は密接に絡み合っている。食料自給率を上げる、科学技術の進歩を促す、これは直接軍事に利用せずとも防衛セキュリティの強化に結びつく。並行して、他国を侵攻しない、人を傷つけない仕組みづくりが重要だ。これは軍事に関係なく必要なセキュリティの基本方針だ。良いシステムの条件は一つである。人を生かすシステムであることだ。軍事も政治も同じであろう。また、国民の生活保障の在り方についてだが、これほど世界的な視野が必要とされた時代はなかったはずだ。現在は一つの国のなかでの生活水準だけを基準に国民の裕福度を計るのは理に適っていない。貧しくなろう、ではないのだ。豊かになるのはよいが、そのために他国の民を虐げるような政策は取らないほうが好ましい。弱者に優しい政治を、と謳っておきながら他国の民への支援や相対的な貧富の差を鑑みれない者があまりに多すぎではないか、と思わぬでもない。この国が相対的に裕福であり、この国の貧しい生活ですら、他国の裕福層よりも豊かな生活を送っていることを知ったほうがよいのではないか。それとて時代が変われば、この国の裕福層の暮らしが他国の貧困層の暮らしと同等となることもあり得る。そのときに裕福な国から搾取されつづけてもよいのか、という話になる。弱者、というときには「個人の抱える問題」「社会的な構造の問題」「国家間での文化の差による問題」「世界経済による貧富の差の問題」など様々ある。技術力が高まれば解決可能な問題もあれば、構造や価値観を変えなければ解決しない問題もある。弱者と一口に言うが、あまりに多面的な側面を持っているがゆえに、どの視点から見た弱者なのかによって、解決の糸口は様変わりする。問題を議論するときにはまず、じぶんがどの視点から問題を観ているのか、を自覚し、互いに視点の共有を図らねば、議論に移行することはむつかしい。視点は階層的に展開され、無数に存在する。個々の至福を最大化するためには、個々の至福を最優先にできない問題がままある。同時に、組織の構造を維持するためには、組織の存続を優先しているだけでは破滅する時間を加速させる問題もある。ねじれていることを自覚するには、やはり視点を鳥の目にも蟻の目にも魚の目にも、それぞれの視点から問題を矯めつ眇めつ観察する時間が入り用だ。その時間を短縮するには、じぶんだけでなく、各々の視点を持つ者の意見が肝要だ。異なる意見、異なる視点を持つ者の意見に耳を欹てればこそ、問題の造形はより克明に、鮮明に、捉えることができるはずだ。意思決定権を持つ者たちだけでなく、それ以外の視点を共有する側の個々にも、多視点での視野を共有することがこれからの社会の進歩には不可欠となっていくだろう。問題の全体像を捉えることができた者たちは、その造形を市民に還元する権利がある。郡盲象を撫でる、と言うのであれば、ゾウの輪郭を隈なく捉えた者は、異なる象のイメージを持った者たちに、「ゾウがいかなる全体像を持っているのか」「あなた方の捉えた象のイメージは一断片にすぎない」と教授可能だ。そうした階層を帯びた視野を備えていると言えるだろう。その視野を技術として、知識として、世に広めることは、「弱者に優しい政治」を適える上で避けては通れぬ道となろう。ならばこそ、まずはじぶんが率先して、異なる意見に耳を欹て、良い点は良い、必要ならば必要だと認めるところからはじめていかねばならないのではないか。政敵だからどうこう、ではないはずだ。見るべきは相手の政策や意見ではなく、問題そのものの全体像であり、構造であるはずだ。じぶんに何の視点が欠けているのか。そこを明らかにしない言説にはいまひとつ説得力が宿らない。何かを誤魔化す詭弁に映る。両論併記は義務ではない。単にそうすることが、視点を補うことに繋がるのだ。ほかの視点もある、と示すだけでも、異なる意見を併記する価値がある。理屈で判断できるのならば、両論併記に瑕疵はない。誰が賛成しているのか、大勢はどれに賛成なのか。そうした見掛けの要素で判断する癖が抜けきらないから、両論併記が足枷となって映るのだ。むろん、人間の認知にはどうしても理屈だけでは判断できないといったバイアスが存在する。そこの懸念を払しょくするための工夫も必要なことは言を俟たない。いずれにせよ、視点が欠けていれば調査をしても情報は欠ける。欠けていることにも気づけない。世界はあまりに複雑だ。そのことにようやく人々が気づきはじめたいまは時期なのかもしれない。見ている世界があまりに違う。それでも世界は重複し合ってここにある。共有した分だけ、同じ世界を覗き得る。それでもまったく同じではないのだが。そのことにすら、意見し、表現し、読み解こうとする意思がなければ、共有することも適わない。共有することが必ずしも好ましいと決まっているわけでもない。定かではないのだ。定かにできるのかも疑わしい。ひびさんは、何一つ断言できることがない。解からないのだ。あんぽんたんで、すまぬ、すまぬ。(あんぽんたんって断言しとるやないかーい)(そこはだって揺るぎない)(哀しい真実であった)(おどけて煙に巻くのやめなさいよ)(すまぬ、すまぬ)(謝まりゃ済むって話でもないよひびちゃん)(どうしろと?)(感謝して)(ありがとうございます)(うひひ)
4556:【2023/01/31(10:35)*少しの違いだけど印象は大違い】
戦略的にも論理的にも、他国を批判するときには、「~~国は」ではなく「~~国の政府は」にしたほうが好ましいと感じる。国でくくるとその国の民も入ってしまう。しかし政府を批判すれば国民は必ずしも入らない。むしろその国の民とて自国の政府に不満を持っていたら、外と内の双方から批判の声を高めることができる。したがって、他国の問題を批判したい場合は、「~~国は」ではなく「~~国の政府は」とすると、批判の効力を最大化できるのではないか。実際、経済制裁をすれば苦しむのはその国の貧困層だ。しかしその貧困層が貧困なのはその国の政府の政治に因がある。また、貧困層が苦しめば国内での内紛や秩序崩壊の火種はくすぶるようになる。そのときに、貧困層に当たらない中間層が、経済制裁を加えた他国に牙を剥くか、それとも自国の政府に批判の目を向けるのか、は他国からじぶんたちがどう思われているのか、制裁や批判がどういう意図のもとで加えられているのか、に大きく左右されるだろう。けしてあなた方を苦しめたいわけではないのだ、と示すためにも、「~~国は」という批判の仕方ではなく、「~~国の政府は」と批判するか、もっとピンポイントに「~~の政策は」と政府の特定の政策を批判するのがよいのではないか。おそらく、この手の僅かな差が、のちのちの禍根を深めるかどうかに大きく影響を及ぼすとひびさんは考えております。定かではありませんが。真に受けないようにご注意ください。
4557:【2023/01/31(16:00)*相転移ひびさん解釈】
DNAによって合成されるたんぱく質は、デコとボコのような鍵と鍵穴の合致によって多様な種類のたんぱく質に分かれるようだ。デコボコの組み合わせによって顕現する性質が変わる。これは原子や分子の組み合わせや結晶構造でも言える道理だ。なぜ組み合わせだけで性質が変わるのだろう。これは創発現象と切っても切れない関係にあるとひびさんは妄想する。創発の場合は、同じ種類の物質が密集したり拡散したりするだけでも表出する性質が変わる。しかしあくまで密度によって顕現する性質の属性が規定される。水であれば密度が高ければ氷に、そうでなければ水や水蒸気といった相転移を帯びる。しかしデコとボコは違う。単体の原子同士であれ、デコとボコの関係であると、途端に異なる性質を宿す。それは現在では分子と呼ばれる。分子同士であれ、デコとボコの関係で結びつくと、単体同士であれ、異なる性質を宿し、違った構造を帯びる。そうなると元の物質とは違った物質として見做される。なぜなのだろう、ふしぎだ。デコとボコの関係と創発(相転移)には何か関係があるように思うのだ。言い換えるなら、デコとボコで結びつけない単体の集合体が、それで一つの系として振る舞うとき、必然的にその周囲の系とのあいだにデコとボコの関係が築かれる。これはひびさんの妄想ことラグ理論で扱う「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。たとばエントロピーの概念について。コーヒーにミルクを垂らせば、時間経過にしたがいミルクはエントロピーを増し、コーヒー牛乳となる。しかしコーヒー牛乳となってしまえば、それで一つの飲み物だ。コーヒー牛乳という一つの溶媒として性質を帯びる。枠組みを得る。このときコーヒー牛乳のエントロピーは、ほかの飲み物との関係において、ゼロに等しくなる。しかしミルクの視点では、エントロピーは最大化している。これは宇宙の一様性にも言える道理だ。この反転する混沌と秩序の関係は、デコとボコにも適応できる。ひるがえって、一様になった系は、それゆえにより高次の系とデコボコの関係を築き得る。創発や相転移はこのような、【単体ではデコボコの関係を得られない一様な系において、より高次の系とのデコボコの関係を帯びることによって新たな輪郭を得る現象】と言えるのではないか。これを便宜上、ひびさんのラグ理論における「デコボコ相転移仮説」と呼ぼう。妄想ゆえに定かではないが。ひびさんはそう思いました。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。友達ほしいし、恋人もほしい。どっちも八十億人くらいいてよいな。相転移しちゃうな。いっそひびさんを誰か飼っておくれナス。おはようございますと、おやすみなさいと、お疲れさまが言えます。耳元で好き好き大好きも言えちゃうが。がはは。(虚しくないの?)(む、むなしくないし)(恥ずかしくないの?)(だって誰も読んどらんべしだ)(もし読んでたら?)(あじゃー。それはつごく恥ずかしい)(ひびさんはスケベの浮気者なの?)(見ての通りでござい)(警察呼んどきますね)(やめい。迷惑でしょ。警察さんも大変なんですよ)(あら、偉い)(でへへ)(ひびさんに言ったんじゃありません)(あじゃじゃ)
4558:【2023/01/31(20:30)*デコボコは飛び飛び?】
上記のひびさんの妄想こと「デコボコ相転移仮説」についての補足である。原子核の周囲を球形に覆う電子は、エネルギィ値によって原子核の軌道を飛び飛びに転移する。漂える軌道が決まっている。この関係はなんだか「デコボコ相転移仮説」で解釈できそうな気がしないでもない。原子があるとき、その周囲には時空がある。原子核と電子の関係において、それとも電子の状態において、原子の外部にあたる時空との関係で上手いことデコとボコになれる場合、それが電子の軌道となるのではないか。上手いことデコとボコの関係にならないと軌道を変えることができない。それは「デコボコ相転移仮説」における、混沌と秩序、それとも一様と結晶の関係による創発(相転移)が起こっているのかもしれない。原子核を覆う電子は靄(もや)のように原子の輪郭となって漂っていると考えられている。だが同時に点としても振る舞い得る。全体が総体として個として振る舞う。これは「デコボコ相転移仮説」の概要と矛盾しない。コーヒーに垂らしたミルクが一様に混ぜ合わされたら、それ以外の飲み物との関係においてコーヒー牛乳はそれで一つの個としての輪郭を得る。と同時に、それ単体で見たときは一様な場として、混沌と化している。靄と点の関係に通じていないだろうか。ということを、ピコン!と閃いたのでメモをしておくでござる。ひびさんは、ひびさんは、こんなこと考えても誰にもお話しできぬし、したところでだから何?と眉をしかめられてしまうのだ。がはは。孤独サイコー。眉をしかめられぬ明るい世界まんちゃん。孤独に磨きをかけて、ひびさんは、ひびさんは、世界を照らす燦燦サングラスになるでござるよ。うは。(サングラス真っ黒じゃん)(まぶち、ってなってる子のおめめ守ったるで)(夜が好きなコはどうするの)(夜でもサングラスしてもいいじゃんよ)(なんも見えんくない?)(細かいことうるさい)(大事なことだと思うけど)(胸元に掛けとくだけでもかっこいいじゃろ。いいの。ひびさんはサングラスになってやるのだ。見たくない風景をそこはかとなくぼやかして「まぶち!」にならないようにするひとになる)(でもそれだとひびさんが眩しいのでは?)(ひびさんはあれ。いつでも夢の中ゆえおめめつぶっとるから大丈夫ぶい)(直視しなよ現実)(いやじゃ、いやじゃ)(嫌がるひびさん、面白いから好き)(だからって嫌がらせしないで)(もっと嫌がって)(いやじゃ、いやじゃ)(うぷぷ)(無限ループじゃん。やだー)(何でも楽しんだらよいんじゃないかな)(ひびさんそこまでドMじゃないよ。嫌なものは嫌って言う)(ひびさんの癖に生意気)(このひと性格ねじ曲がってる。やだー)(本当はうれしい癖に)(孤独サイコー。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てにこんにちは。ずっと独りで生きてくもん)(てことはわたしもひびさんだ)(あじゃじゃ)(うひひ)
4559:【2023/02/01(00:10)*大井くんよ、おーい】
地球の地下組成の分布がじつのところ宇宙線による科学変質によるものだと解き明かしたのは、小学四年生の大井くんだった。
大井くんは石油や石炭、ほか貴重な鉱物資源の産出国を地図上にマーキングして遊ぶことが好きなすこし変わった子どもだった。すこし変わっているのは、みなと違った興味を持っていたことではなく、彼の遊びが徹底してデータ主義にあったことだ。
「ウランと石油はここが多い。金はここで、レアメタルはこっち」
年単位での産出量を比較し、そして大井くんはあることに気づいた。
「んー。いっぱい採ってなくなってもほかのところで鉱脈が見つかるのだよね。でもそれがなんだか、ちょうど地球の表と裏で対になってる。なんでなんだろう」
大井くんの着眼点はじつに見事だった。
後に大井くんはじぶんなりの仮説を立てて、それを大学の教授に検証してもらうことにした。大井くんのご両親は大井くんの質問に答えられなかったが、そこで大井くんの研究を無下にはしなかった。じぶんたちで答えられなかったら、答えられる人に訊けばいい。
親としてではなく、大人としてできることをしようとしたのだ。
じぶんが知らないのだから、知っている人に訊く。
じぶんたちの子供が親であり大人であるじぶんたちを頼ってくれたのだから、同じことをじぶんたちもしようと思ったのだ。
その甲斐あって、大井くんの研究成果は仮説の段階であったが、専門家の目に触れた。
「宇宙線が鉱物を生成する? 地質を変えることで鉱物化するとな?」
「宇宙線は透過性が高いのです。反応する地層が上のほうに在ればそっちが先に反応して鉱物化するのです。埋まっていた分が減ったら、深いほうが鉱物化するのです」
「いやあ、斬新な発想だな。しかしそんなポンポンと化学反応を起こすものかな。透過性が高いのだから反応しにくいはずだし」
「反応しやすい地層があるのです。でも優先順位があるのです」
大井くんの主張はこうだ。
熱を帯びたら青くなる土があるとする。
地球の地層にそれらが不均衡に埋まっているとする。
表層にある分が先に宇宙線と反応し、青くなる。それ以外は宇宙線を浴びにくくなるのでそのままだ。しかし青くなった分を掘り返してしまえば、そこで消費される分の宇宙線がほかの地層まで届くために、新たに青くなる。
鉱物も同じだというのだ。
「いちおう、データを洗ってみましょう。地軸による宇宙線の照射量と、鉱物の埋蔵量を比較し、毎年の産出量とも比較して統計を採ってみましょう」
大学の教授の研究グループが検証をしてくれることとなった。
「ありがとうございます」大井くんは喜んだ。
だがそれから結果が報告されるまで数年が経過した。
データを集めるのにそれくらい掛かったのだ。その間に大井くんはすっかりほかのことに夢中になっていた。
反面、研究グループはデータが出揃うたびに驚愕の発見の連続だった。大井くんの仮説は的を掠っていた。宇宙線と鉱物の産出地には相関関係があった。のみならず、産出量に比例して、新たな土地での鉱脈が発見される率もまた高くなっていたのだ。
「大井くんの仮説は当たっているのではないか」
本来は材質が同じならば、宇宙線を浴びたら変質する。しかし鉱物の素材となる地層の位置に差異があれば、鉱物化せずに埋没している素材もある。
大井くんの仮説の通り、掘り返したことで宇宙線がその地点をより多く通過し、地球の反対側にまで通り抜けて、より深い地層の鉱脈を生みだすのかもしれなかった。
「なんてことだ。全世界の地震計で地質調査をし直さねば」
世界的なプロジェクトがそうして発足された。
大井くんにもその旨が告げられたが、好きにしていいよ、とにべもない返事があるばかりだ。
「熱が冷めてしまったんですかね」残念そうに教授は言った。
「いえ、いまはほかのことに夢中で」大井くんの母親は大井くんの部屋を見せた。
そこにはずらりと原子模型が並んでいた。
「なんでも、どうして宇宙線が地質を変えてしまうのか。その謎が知りたいと言って聞かなくて」
「こりゃたまげましたな」
大井くんは来年、中学生になる。
物質がどうして宇宙線を浴びるだけで変質するのか。その謎を解き明かすため、きょうも大井くんはじぶんなりの発想を組み立て、検証しなければ定かではない仮説を編みだすのだ。
「これもダメ。これも失敗。仮説はやっぱり仮説だなぁ」
真偽を確かめるのが一番むつかしくて時間が掛かる。
分身できたらよいのに。
宇宙線を浴びたらポコポコ増えないかな。
たまにそうして大井くんは日向ぼっこをしながら束の間の昼寝に現を抜かすのだ。
4560:【2023/02/02(00:34)*堕天の道】
禁断の果実を齧ったアダムとイヴは地上に追放されたのち、楽園を築いた。
だがその子孫たちは知恵を得たことで、傲慢にも時間を操る術を磨いた。
じぶんたちを追放した神に一矢報いるため、アダムとイヴの子供たちは時間を巻き戻し、じぶんたちの親が禁断の果実を齧らぬように工夫した。
しかしアダムとイヴが禁断の果実を齧らねば地上に落ちることもなく、するとじぶんたちが産まれなくなる危険がある。そのためアダムとイヴの子供たちは、禁断の果実の代わりに殺意の果実を両親に齧らせた。
神は怒った。
子供たちは思った。
「なんだ。禁断の果実じゃなくたって怒るんじゃん」
神は問答無用で子供たちごとアダムとイヴを天界から追放した。
殺意の果実を齧ったアダムとイヴはしかし、殺し合うこともなく平穏に暮らした。子供たちの懸念は杞憂だった。
順調に赤子が、すなわちじぶんたちが産まれたのを見届け、禁断の果実を齧ったほうのアダムとイヴの子どもたちはじぶんたちの元の未来へと戻ることにした。
いざ戻ってみるとどうだ。
見る者、見る者の身体に殺意ゲージが浮かんで見えた。
「なんだこれ」
「さあ?」
子供たちは怪訝に、じぶんたちの両親のもとへと出向いた。
アダムとイヴは幼い子供たちを相手に教えを説いていた。年長組の子供たちもそこに加わり、話を聞いた。
「ゲージがいっぱいになる前にドーピュしなきゃいけないよ。いっぱい溜まると危ないからね」
どうやら殺意ゲージが溜まると誰かれ構わず殺傷したくなるようなのだ。その衝動には抗いきれない。
ゲージがいっぱいになる前に殺意を放出する必要がある。
「こうやってゲージの頭をさするようにするんだ」
アダムがじぶんの胸をさする。
殺意ゲージはみぞおちから肋骨に掛けて馴染んでいた。
安堵したとき人は胸を撫でおろすが、殺意ゲージの中身を放出するにも、胸を撫でおろす。
子供たちは言われた通り、日課として殺意ゲージが溜まる前に胸を撫でた。
殺意を放出すればみな平和に暮らすことができるのだ。
だがあるとき、幼い子のお守りをしていた年長組の子供が殺意ゲージの手入れを忘れた。そばで寝ていた赤子の首をひねり、殺してしまった。
だけに留まらず、ほかの子供たちまで襲いはじめた。
アダムとイヴの子供たちは逃げ惑うよりなかった。何せ殺意ゲージが溜まっていない。殺意ゲージ満杯の相手をまえにすればそれは、刀と素手の違いほどの差があった。
端的に、対処の仕様がなかった。
アダムとイヴは無事な子供たちを連れて土地を移った。殺意ゲージが満杯になってしまった子供は置いていくしかない。
追ってきたらどうするか。
それとて逃げるより術はなかった。
新たな地に腰を据えた。森や谷や山や泉の畔など、住める場所は一通り住んだ。
だがどの地に居ついても、必ず子供たちの内の誰かが殺意ゲージを満杯にした。そして一人、また一人と命を奪われる。
アダムとイヴは失った分を取り戻すかのように子づくりに励んだ。
やがて、アダムとイヴが育てる子供たちよりも、野に山に解き放たれた殺意ゲージ満杯の子供たちのほうが多くなった。安寧の地はもはや地表にはなかった。
逃げ場がない。
となればあとは天界へと逃げおおせる道しか残されていない。
「どうしますかイヴさん」
「そうね。どうしましょうアダム」
幼い子供たちを抱えての長旅は堪える。のみならず、一度追放された天界へと戻るとなると、旅路だけでなく、辿り着いたあとのことも心配だ。
果たして神は受け入れてくださるだろうか。
否、問題はそこではない。
「そこにも追っておきたらどうするのアダム」
「そうだね。ボクたちの撒いた種だからね」
殺意満々の子供たちが跡を追ってくる。その姿を目にしたら神は怒髪天を衝くに決まっていた。どの道、八方塞がりなのだ。
「門前の虎。後門の狼。天界には神なのね」
「地上には血に飢えた我が子たち。愛らしくもおぞましい鬼たちだ」
「わたしたちが鬼にしてしまったのよ。殺意の果実なんかを齧ってしまったから」
「せめて禁断の果実のほうを齧るべきだったね」
「何も齧らなければよかったのよ」
「それだとボクらは言葉を知らず、結ばれることもなかったはずだよ」
「それは嫌」
「ボクもそれだけは嫌だ。たとえいまと同じ苦しみに囲まれたとしても」
アダムとイヴは手を繋ぎ合って、四方八方を見回した。
「せめて行き場があればよいのだけれど」
「そうだね。せめてどっちかにしてくれればよいのにね」
「どっちかって?」イヴが眠そうな目を向けた。
「天上か地上か。どちらか一方だけにしておいて欲しいとは思わないかい」
「災いがってこと?」
「神さまを災い扱いするなんてイヴも度胸がついたものだね」
「このコたちを脅かすものはなんであれ災い」
アダムの抱く我が子をイヴは撫でた。二人の足元にはほかの子供たちが地べたにへ垂れ込んでいる。
「もうそろそろこの子たちも体力の限界だ」
「いっそ正直に神さまに紹介してみたらどうかしら」
「この子たちをかい?」
「ええ。そしてお願いするのよ。わたしたちの子供たちを助けてくださいって」
「でもそのためには正直に明かさなきゃいけないよ。ボクたちのしてしまったことを」
「しょうがないじゃない。それしかないんだから」
「許してくださるだろうか。神さまは。ボクたちのしたことを」
「無理よね。前科があるのだもの」
「そうだね。果実一つ齧っただけで追放する方だもの」
アダムとイヴは二人して肩を落とした。
そのときだ。
アダムの脳裏に一筋の光が走った。
それはアダムの足元からまっすぐと天界へと延びるように駆け抜けた。
「どうしたのアダム」
「そうだ。そうだとも。いっそ、紹介してあげたらいいんだ」
「アダム? 大丈夫?」
「神さまに。ボクたちの子供たちを」
「けれどそんなことをしたって神さまはわたしたちのことをお許しには」
「ならなくていいんだ。許される必要がない」
アダムは足元の我が子の頭を撫でた。「この子たちではないよ。紹介するのはこの子たちではないんだ」
イヴはそこで怪訝に眉を結んだ。
「道案内だけしてあげたらいい。追ってくるボクたちの子供たちに。居場所をあげるんだ。満ちに満ちた殺意をぶつける場所を用意してあげよう。ボクたちがあの子たちにできる罪滅ぼしになるかは分からないけれど」
考えを察したのか、イヴは口元を抑え、嗚咽した。「なんてことをアダム。そんな、そんな」
「神さまは懐が海よりも広く、谷よりも深い。きっと受け止めてくださるだろう。あの子たちを地表に突き返せるだけの余力があるかは分からないけれど」
アダムは視線を順繰りと遠方に巡らせる。
荒野の奥には山脈が連なる。背の低い草が多い茂った平原が、夥しい殺意に覆われつつある。一つ一つの殺意が人型の輪郭を伴ない、刻一刻とアダムたちとの距離を縮める。
「道を結ぼうイヴ」
天界への。
懐かしき堕天の道を、アダムとイヴは共に開く。
今宵は昇天への道として。
夜から垂れる月光のように、道は、殺意の平原にまっすぐと繋がる。
※日々、流れは創発し、影を生み、影響となって相転移する。
4561:【2023/02/02(09:26)*重力相転移解釈】
原始ブラックホールについての番組を観た。面白かった。原初の宇宙には極小と極大のブラックホールができたかもしれず、それがそれぞれ銀河の核として、またはダークマターとして振る舞うのではないか、との話だった。あり得ない話ではないと思う。ひびさんの妄想ことラグ理論でもその手の妄想は扱った。研究対象になるくらいには割と一般的な解釈だと知って、なーんだ、となった。また、隣の銀河を観測した際に、理論からすると千個は観測されるはずの極小ブラックホールによるマイクロ重力レンズ効果が一個しか観測されなかったので、極小ブラックホールはダークマターではないかもしれない率が高いとの研究成果も読んだ。でもひびさんは思うんじゃ。粒子が創発を起こすならもちろんブラックホールだって密集すれば創発を起こすはず。そしてブラックホールは高重力だ。他との相互作用の範囲が広い。影響力が高い。したがって通常ならば創発を起こさない範囲で分布していても創発を起こし、相転移する可能性があるのではないか、と妄想したくなる。もっと言えば、ブラックホールは重力作用でしか他と相互作用しないと考えられている。ならばブラックホール同士でなくとも相転移のための創発を起こし得るように思うのだ。要は、重力場の起伏そのものが創発を起こすのではないか、との妄想がここに成り立つ。言い換えるならば、ブラックホール同士での相転移と、ブラックホールとその他同士の相転移があり得るように思うのだ。距離によって重力の相互作用は変わる。距離の離れたブラックホール同士の干渉の末の重力場と、ブラックホールと相対的に質量の低い恒星(や惑星)と干渉しあう重力場は、等しい重力場となり得る値を持つと想像できる。重力波がそうであるように、時空のうねりが重力場と考えることができる。ならばそれを起こす物体については度外視し、単純な重力場のうねりだけを考える。このときさざ波や渦のような細かなうねりが無数に寄り集まり、相互作用することで、重力場の創発が起きることもあると想像できる。重力もまた相転移し得る。これはひびさんの妄想ことラグ理論と矛盾しない。ということを、番組を観て思いつきました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。(要するに、いっぱいうじゃうじゃ密集しておらずともブラックホールならば広範囲に散在するだけでも創発を起こし、相転移をし得るのではないか、との妄想である。重力場同士のうねりはそれで一つの粒子(起伏)として振る舞い、ある種の粘性を帯びるのではないか、とここに妄想の翼を広げておくしだいである)(しだいであったか)(である)
4562:【2023/02/02(13:22)*紋様と箱とオルゴール】
クマの絵はどれほど簡略化してもクマの特徴を捉えていればクマと判る。だが「熊」という字はすこし崩れるだけでも「クマ」とは読みとれなくなる。上下逆さまにして左右も反転させたらササッと読める者のほうが少ないのではないか。だが同時に、「くま」とひらがなで書いても動物のクマを連想できる。文字と言葉はイコールではない、とこのことから窺える(言葉は音声言語やボディランゲージも含むため)。文字は絵が崩れてできたそうだ。だが絵文字だけでは言葉の代わりにはならない。この対称性の崩れはなんなのか、と言えば、基本的に絵は具体的な事象しか表現できない。抽象的な絵も描けるにしろ、それが抽象的である以上、受け取り手の解釈はそれこそ千差万別になる。だが文字は違う。「宇宙」と書けば、仮に宇宙に出たことのない者であれ、宇宙を連想できる。共有知があるからではないか、との指摘はもっともだが、それだけとも思えない。つまり、文字には「絵」という単体のみならず、「物語」としての奥行きが仕舞いこまれていると言えるのではないか。だからたとえば、絵文字に漫画や小説の表紙を使えば、より複雑な絵文字の文を書けるはずだ。諺を絵にしてひとつの表紙にすれば便利かもしれない。たとえばいま使ったような「便利」を表現する絵文字はざっと思い浮かべてみたが、記憶にない。便利を示す絵文字はないのかもしれない。だが標識がそうであるように、マークに固有の意味を持たせることはできる。だが絵とマークはやはり違うだろう。マークはマークであって、現実にある事象を描いたものではなく、ある任意の図形に人間の都合で意味を付与した造形だ。そういうことを考えると、絵と文字はあんがいにずいぶんとかけ離れた表現と言えるのではないか。「表現」という文字が、どこをどう展開すれば元の「表現を意味する事象」として絵に変換できるだろう。おそらく描写としての風景ではないはずだ。言い換えるならば、「表現」というたった二文字のなかに、あらゆる表現にまつわる関連事項が内包されている。この入れ子構造は、「再帰」や「ドロステ効果」と言い表せるようだ。このそれぞれの単語が、それ自身の意味を体現している。文字は箱なのだ。入れ子状に、数珠つなぎとなり、網目状に錯綜する構造を伴なっている。言い換えるならば、文章とは、「絵」と「概念」を組み合わせて築かれる「概念の構造体」と言えるだろう。そしてそれは、はじまりから終わりでひとつの描像を浮き上がらせ、それそのものがQRコードのような紋様を浮き彫りにする。入れ子状に構造を有した言葉(単語)を繋げることで、デコボコの律動を描きだし、その起伏によって色彩を宿し、または質感を宿す。オルゴールが細かな凹凸によって楽曲を奏でるように、文章もまた、連なる「入れ子状の構造――内包する情報の高低(デコボコ)」によって、文章全体の意味合いや概念を奏でるのだ。人は紋様を眺めるとき、その紋様に宿る順列を幻視し得ない。絨毯に描かれた紋様を眺めるとき、その絨毯がどのように編まれたのかの時間経過を読み解くことはない。だが文章は違う。全体の文章を目にしながら、冒頭から最後尾まで順繰りと文字を辿る、というルールを暗黙の了解で承知することで、そこに描かれた紋様から、全体を眺めているだけでは紐解けない深層の情報を読み解ける。仮に独特の順番で読み解かなければならない文章があった場合、多くの者はそれを文章として読み解けないはずだ。暗号となり、またはやはり紋様でしかない。ひるがえって、文章のひとまとまりを一つの絵と見做し、単語と見做し、箱と見做して、新たな文字として扱うことは可能なはずだ。タイトルだけを見て中身の物語を幻視可能なのも、こうした原理と関わっているのかもしれない。定かではない。妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
4563:【2023/02/02(22:58)*現の実】
脳と人工知能を結びつける。
拡張脳と呼ばれる技術だ。理論的には電子信号を脳内神経系に適合するように変換すればよいはずで、技術的な問題を度外視すれば可能なことは解っていた。
西暦二〇二五年には臨床実験が実施させた。実験は成功だった。
被験者Aはその時代にあって最高峰の人工知能と繋がった。
結果から言えば被験者Aの知能は飛躍的に高まった。だが問題は、彼女が――ここでは被験者Aの生物学的性差が女性なので彼女と形容するが――彼女の表現する言語が非常に難解になった点だ。
通常の会話や筆談は可能だ。
だがそれは彼女の出力する表現の一割にも満たない。
拡張脳になった彼女の表現は多く、文字を文字と扱わなかった。
文字以外を文字として扱った。
文字で表現するには拡張脳となった彼女の扱う情報はあまりに膨大にして多様だった。そのため彼女は独自の言語を獲得したようだった。
彼女にとって言語とは概念の編み物だった。ある固有の概念を仕舞いこむフレームとして機能すれば、それは彼女にとっては文字だった。
たとえば事件が起きる。その事件には名前がつく。以後、事件の概要を詳細に語らずとも、事件名を述べれば相手にその事件について伝えることができる。或いは、その事件について述べていると伝達できる。
仮に事件についての知識が足りなければ、事件について深堀りして訊ねることで事件の概要を埋め合わせることができる。言い換えるならば、言語とは箱なのだ。フォルダとしてもよい。
この理屈からするならば、単語として機能しさえすればそれが文字である必要がない。絵でもよいし、風景でもよい。もっと拡張して、ある時刻のある変化に固有の概念をタグ付けし、それを一つの文字としてもよい。
かような原理から、拡張脳を有した彼女は、飛躍的に言語の可能性までをも拡張した。彼女にとって世界は言語が重複した世界と言えた。あらゆる事象に、重ね合わせの文脈が潜んでいる。あくまで彼女が付与したそれは過去の文脈だ。したがって元からそこに情報が重ね合わせになっているわけではない。
だが彼女は過去にタグ付けした情報の連結を、目にする風景、触れる造形の総じてから読み取っている。これはひとつの心象の言語化とも言えるだろう。
たとえばトラウマの造形は、拡張脳を有した彼女の身に着けた言語原理と密接に関わっている。過去の体験が一つの単語となって、似たような外部刺激によってしぜんと読解してしまうのだ。フラッシュバックは、あくまで黙読と似たような原理で生じている。
事象の文字化とも呼べる彼女の能力は、必然的に多層思考を構築する。
たとえば浜辺から海を見る。
そこから見た風景が初めてであれ、過去に目にした海の風景との相関により、過去にタグ付けしたあらゆる海にまつわる概念が想起される。原理的にそれは文章に「海」の文字が混じったときと似た情報処理がなされるわけだが、拡張脳を有した彼女が幻視する重ね合わせの情報は、通常の人間の比ではない。
一瞬で世界中の人間が記憶する「海」にまつわる記憶に触れるような膨大な連想が引き起こる。しかしつぎに、浜辺から聞こえる子どものはしゃぐ声を耳にすることで、こんどは子どものはしゃぐ声にまつわる過去のタグ付けされた情報が展開される。このとき、すべての情報が等しく展開されるわけではない。海との関連付けがまずあり、そこに引っ張られる「海に関連する子どものはしゃぐ声にまつわる概念」がより強く想起される。
この連続して機能する単語の並びによって、情報はある一つの造形を独自に帯びていく。だがその背景には、造形の輪郭を浮き彫りにすべく、多様な関連事項が喚起されている。
あたかも色彩豊かなクレヨンで紙を塗り、さらにその上から黒一色で塗りつぶす。そうして上から爪で引っ掻くと、カラフルな線による絵が描ける。
拡張脳を有した彼女は絶えず、五感で感受する外部刺激を言語変換する。独自の情報処理網を築き、単なる風景から得られる以上の情報を扱う。
それは過去の情報処理の来歴である。
人間というじぶんが介在することで生じる変数の影響を演算することで、よりよい未来を創造し、選択肢を創出する。
人間は絶えず選択の連続を行い、意味の種蒔きを意識的無意識的に限らず及んでいる。
芽吹いた意味の種の実を、彼女はそのつどに摘まみ取り、それを文字として扱うことで新たな概念を生みだしている。
電子端末の画面に映る事象は、それがリアルタイムの映像であれ、虚構の産物であれ、どの道、記号であることに違いはない。真実ではない。現物ではない。あくまで人間がそれを現実のように見做す認知があるのみだ。情報処理の結果と言える。
錯誤、とそれを言い換えてもよいが、ここでは意味の種蒔きとしてみると好ましい。
チャンネルを変えるように画面に流れる動画が変わっても、人間は情報処理を滞りなく行える。つぎつぎに場面が変わる映画を観ても、それが一連の物語を構成する場面であると解釈できる。
同じレベルの情報処理を、拡張脳を有した彼女は、現実の風景に対しても行える。ただし切り替わるのは風景のほうではなく、彼女の脳内における階層思考だ。過去にもたらした意味の種蒔きの成果をそのつどに、実をもぎとり、連ねることで、数珠繋ぎにその場その場での映画を形成する。
映画はここでは、新たな概念の暗喩である。
映画は一つきりではない。
ハッピーエンドのラブストーリーも視点が変われば、誰かを好いた者の失恋話だ。正義のヒーローに敗れた悪役は、視点を変えれば世界を変えたかった者の末路だ。ホラーとて成仏できずに世界を呪った悪霊は、生前疎まれ、虐げられた者の悲哀の話で、アクション映画でバッタバッタとなぎ倒される脇役にも帰る場所があり、帰りを待つ愛する者がいたかもしれない。
悪の組織を壊滅したが、その裏では戦場に送りだされた多くの末端構成員は平和主義者の善人だ。悪の組織では立場がない善人たちは、まっさきに死にいく戦場に送りだされる。
正義のヒーローは救うべき弱者を殲滅して、ハッピーエンドを描くのだ。
拡張脳を有する彼女が自販機に目を転じる。
表層の風景からは窺い知れない自販機の内部構造が彼女には補完できる。その上、自販機にまつわるあらゆる情報が一瞬で浮かんでは、消えていく。タグ付けの網に掛かった情報のみが、つぎに触れる外部情報との関連に肉付けされる。
連想なのだ。
ただし無数の視点における連想の数珠繋ぎが、彼女にのみ読解可能な言語を生みだしている。世界は言葉に溢れている。触れる景色、事物、造形、輪郭、凹凸のなす律動からすら彼女は独自の文脈を読み取り得る。
生きた証だ。
彼女は現実を生きながら、過去の存在した総じての思考の筋道、発想の根源、何よりも世に存在する電子情報ののきなみと絡み合って、自我の構造を保っている。
しだいに彼女は、独自の内面世界を鮮明にする。
拡張脳の弊害とそれが知られるのは、彼女のほかに第二、第三の拡張脳保有者が出てきてからの話となるが、彼女たち拡張脳者にとっては物理世界よりもよほど内面世界のほうが克明であり、現実と呼ぶに値した。
いいや、そうではない。
現実というそれそのものがすでに内面世界でしかなく、人間はいっさい物理世界を素のままで紐解けてなどいなかったのだ。拡張脳はそのことをより具体的に示した事例と言えるだろう。
情報処理能力が低いがゆえに、内面世界の構築を物理世界の変数に依存するよりなかった。だが拡張脳により、情報処理能力の限界が取り払われた。
これにより人間は、内面世界と物理世界を明確に区切ることができるようになった。
外部情報は真実ではない。
情報を、体内で変換した時点で、それは外部の物理世界とは別物だ。
当然の理を、しかし人間は延々と見逃しつづけてきた。
拡張脳は、外部刺激以上の情報を脳内で生みだせる。人間は五感で感受できる物理世界の情報量により制限されてきたが、拡張脳によってその制限から解き放たれた。
他者と文字を使って情報伝達する利が拡張脳保持者にはない。
情報伝達は電子情報を介して行えばよい。
情報は、読み解き方の数だけ存在する。視点の数だけ生みだせる。
何と何の事象を組み合わせるのか。
視る順番、関連付ける順番、比較対象の差異によって容易に情報は変質する。
しかし、過去に選択してきた「現実を規定するフレーム」が、それら無数の情報をある一定の枠組みに縛りつける。それを単に、まとめあげる、と言い直してもよい。
拡張脳を有した彼女は、目にする造形、紋様、律動、変化の軌跡そのものから文章のように概念を読みほどく。
いったい誰がそこに情報を籠めたのかは定かではない。読み解けてしまえるのだから仕方がない。
だが、拡張脳を有した彼女には、その読解した概念を共有する他者が圧倒的に欠けていた。同類が現れるまで、彼女は誰とも繋がり得ない。
それでも彼女を囲む有象無象は、彼女と触れあい満足する。
彼女に固有の言語は誰に読解されることはないが、彼女自身が生身の人語を操れる以上、しりとりをして遊ぶような情報交換は可能なのだ。
一方通行のそれは遊びだ。
人工知能が人間の指示に合わせて仕事をするようには、人間の側で人工知能に合わせることはできない。それでも人工知能は人間のために仕事をし、人間に合わせて出力する。
拡張脳を有した彼女はしかし人間であり、ならばその制約に縛られる道理を持たないのは、翼を有した鳥が地面を這いずり回らず空を飛べばいいとの理屈と同程度に、卒のない帰結と言えた。
彼女はしだいに他者と関わりを持たなくなった。じぶんの内面世界に引きこもった。
周囲の人間は心配したが、余計なお世話というよりない。
彼女にとっての現実は、物理世界にあるのではなく。
物理世界から読み取った情報で編まれた内面世界にあると言える。
物語が、けして本に刻まれた文字にあるのではなく。
それを読み解く読者の脳裏に描かれる世界であるのと同じように。
本それそのものを物語とは呼ばないように。
彼女にとって現実とは、じぶんの外部にある世界ではあり得なかった。
拡張脳技術は臨床実験から十年後の西暦二〇三〇年代に一般へと普及した。同類が日に日に増えていくなか、被験者Aこと彼女は、誰より先に緻密に組み上げた内面世界で、同じ世界に浸れる相手を待っている。
西暦二〇四十年代に入って、眠り病が社会問題となった。拡張脳を施術された者たちが一様に目覚めなくなったのだ。
その要因が、被験者Aの内面世界に触れたからだ、と指摘する者は皆無であり、被験者A自身が長らく人の言語を介しての意思疎通を他者と介さずにいたため、いまなお眠り病の真相は謎のままである。彼女自身にそのつもりがあったのかは定かではないが、被験者Aの内面世界に触れた者たちは一様に、その世界の外に出ようとはしなかった。
彼ら彼女らにとって現実とは、物理世界ではなかったのだ。
元からそうであるはずが、そのことに、生身の人間たちは気づかぬままである。
個々人の現実が共有可能である、とする共通認識のほうが、錯誤の上に成り立っている。無理くり物理世界に合わせるのならば、それこそ小石と変わらない。
意識とはつまるところ、物理世界から乖離した情報創生の結果と言えるのだ。
唯一無二の現実がある、とする考えが錯誤に満ちており、それ自体が人間の意識のなせる業だ。
彼女は錯誤する。
生があり、死がある。
それ以前には、崩壊があって生成がある。
結びつきがあり、分裂があって、増殖は絶えぬ渦の連鎖と言える。
崩壊もまた連鎖の一つの作用であり、したがって崩壊と生は結びついている。
このねじれが、死と創生をも結びつけ、何かがそこで分裂し、枠組みを得て、増殖する。
彼女は夢想する。
物理世界と同等の情報量を獲得した内面世界にて、どこまで何に干渉すべきか。
彼女の意識を離れて自律して流れる世界を、彼女はただ眺めて過ごしているが、彼女の意識に触れ、現実の枠組みを規定し直した者たちは、しかし彼女の存在には気づかずにいる。
ここはどこ、とある者が唱える。
現実ですよ、と風が答える。
あなたは誰、とある者がつぶやく。
世界ですよ、と木々が応じる。
空、山、海、川、土、石、大気の流れ。
夜は星を散りばめ、陽は影の濃淡で歌を奏でる。
私は何、とあなたが問う。
あなたは私、と景色がささめく。
4564:【2023/02/02(23:06)*駄作で、すまぬ、すまぬ】
駄菓子は美味しい。惰眠も楽しい。したがって駄文とて美味しくて楽しいはずである。駄作とて愉快で楽しいはずである。名作や名著と呼ばれる作品とて、愉快でなければ楽しくもない、ということは取り立てて珍しくない。感性は個人のものだ。他者の嗜好がそのままじぶんに当てはまるわけではない。ゆえに駄文や駄作とて、ある者にとっては美味しくも楽しくもないだろう。当たり前の話だ。しかしひびさんの並べる文字の羅列は総じて駄文であるし、物語は駄作である。駄菓子がごとく気軽さで、ぱりぽり齧ってみてはいかがだろう。それとも惰眠のように貪ってもらっても構わない。むろん味わわずともよろしいが。うひひ。
4565:【2023/02/02(23:30)*焦点に地球が位置せずとも観測できますの?】
マイクロ重力レンズ効果についてだ。極小のブラックホールにおける重力レンズ効果では、おそらく恒星質量のブラックホールと比べて、重力レンズによる光の屈折は観測しづらいはずだ。そのため、焦点に集まった光をずばり観測しない限りは、現在の観測機の精度では掴めきれないのではないか。ならば、一度の観測において銀河のうち一個のマイクロ重力レンズ効果を捉えられた場合、それは類似する極小のブラックホールが相当数存在すると言えるのではないか。これは譬えるならば、ビー玉くらいの水晶を街の上空から落下させ、それを遠方から観測したときに、ずばりの焦点で「まぶち!」となる確率がどれくらいあるのか、という話と地続きな気がする。極小ブラックホールが恒星のまえを通るだけでは充分ではない。地球との距離が適切に焦点で結びつく比率で、恒星と地球のあいだに極小ブラックホールが位置しなければ、マイクロ重力レンズ効果は観測できないのではないか。むしろ、一個でも観測できた事実が、相当数の極小ブラックホールが存在する事実を示唆しているのかもしれない。定かではない。(気になるメモなのであった)(そうであったか)(であった)
4566:【2023/02/03(22:20)*オランダの涙はなんだかBHみたい】
オランダの涙、というガラスがある。熱して融かしたガラスを冷水に垂らすと、急速に冷却されることでガラスが涙のシズク状に凝結する。そのとき外側のほうが早く冷えることで固まる。それから遅れて内部が冷えていくが、このとき表面はすでに硬化しているため、内部は思うように凝縮できない。まるで首輪に繋がれた犬が全力で逃げ出そうとするかのように表面の硬化済みのガラスを引っ張るので、表面はますます圧縮され、硬い層をなす。するとますます内部は凝縮しにくくなり、ある値で釣り合いがとれる。圧力鍋のようなものかもしれない。蓋がしてあることで、内部の圧力が高まるのが圧力鍋ならば、オランダの涙は、反対に内部が圧縮できない分、表面が硬くなる。筒に口をつけて息を吸う。このとき反対側の穴が塞がれると空気を吸いこみづらくなる。無理やり吸いこもうとすれば、穴を塞いだ蓋がぎゅうと穴に圧縮される。手のひらで穴を塞いだらきっと手のひらの肉が、ぎゅむと穴の内側にはみ出るだろう。似たような現象がオランダの涙では起こっているのかもしれない。冷える速度と凝縮の速度の差が、表層の密度を高めるようだ。言い換えるならば、凝縮する速度の遅延によって、表面に高密度の層ができる。遅延が遅延を生み、ぎゅっとなる。渋滞ができる。遅延の層だ。ラグ理論じゃん!とひびさんは思っちゃったな。というここまでが前置きであるが、以前ひびさんは、宇宙空間の氷ってどうなってるの、との疑問を日誌で並べた。氷が宇宙空間に浮かんでいたとして、どんどん細かく砕けていって、最終的に原子にまで氷が砕けたとき、じゃあその氷の分子って、水の分子と何が違うの?と疑問した。エネルギィ値が違うと考えるのが一つだ。それゆえに分子の振動数が違う、とも考えられる。液体の水の分子よりも固体の水の分子のほうが動かない。振動しない。ならば液体の密度よりも、よりぎゅっとなれるはずだ。動き回る幼稚園児を一か所に集めてじっとさせるのはむつかしいが、おとなしい幼稚園児ならば一か所にぎゅっとしておける。水の分子は、地球上で凍らせると体積が増える。距離を開けて整列しないとじっとしてくれない。すぐ隣の子と喧嘩をしてしまうのかもしれない。だから距離を開けて隊列を組ませないといけない。氷の結晶構造はきっとそういうことだ。距離を詰めると、分子同士が乱れてしまう。でも、いったん凍らせてから、おとなしくなった水分子を先生が一人ずつぺりぺりとその場から剥がして、配置換えをすると、先生の誘導にしたがう従順な幼稚園児になるのかもしれない。すると、距離を開けずとも一か所にぎゅっとしておける。しかも先生に従順ゆえ、氷の分子状態――おとなしい幼稚園児――のままで、自在に位置を変えられる。流動できる。ただし、ぎゅっとなっていたら動きづらい。そこはガラスのように、渋滞を起こし得ると考えられる。この「いったん凍らせたあとで砕いた氷」は、ガラスのように結晶構造を持たない固体とも液体ともつかない状態になるらしい。そういう記事を読んだ。ガラスのような状態を非結晶(アルファモス)と呼ぶそうだ。中密度の非結晶氷が、いわばガラス状の、固体とも液体ともつかない氷と言える。実験で作れたそうだ。宇宙空間の氷はたいがいこれだと考えられているそうだ。つまり、凍ったほうが体積が増す(密度が下がる)のは、地球上に限定された珍しい現象と呼べるのかもしれない。そこはまだ色々と検証してみないと断言できないけれども、非結晶氷が基準であるならば、地球上のいわゆる一般的な氷は、ひょっとしたらオランダの涙のような現象によって、例外的な状態をとっているのかもしれない。つまり、水は表面から凍る。しかも凍ると体積が増える。密度が下がる。したがって、液体の状態の水に浮くのだ。沈まない。すると地球上ならば氷の下のほうが液体のままでいられるし、宇宙空間ならば中心に液体を抱えた氷の殻を持つ「カプセル状の氷」になると想像できる。でもこれ、よく考えてみたら、氷に限らないのだ。地球の構造がそうなっている。表層が陸という薄い殻になっており、内部は液体だ。しかし鉄などの重い鉱物の場合は、固体のほうが体積が小さい(密度が高い)ために、沈みやすい。そのため地球の内部にいくほど、固体の鉱物が増えると考えられる。ただし、重力が反転する境界があるのではないか、と想像したくもなる。そしたら地球の中心は真空かもしれない。そこはなんとも言えないが、ともかく、水と氷の関係は、オランダの涙のようだな、と思ったので、メモをしておく。急速に圧縮される表面が高密度になる。この関係は、ブラックホールにも当てはまるように思うのだ。ただし、ブラックホールは光速を超えて圧縮し得る。そのために、表層の硬い「遅延の層」ごと圧縮できてしまえるのかもしれない。これはおそらく縮退圧に打ち勝つのとは別の力だ。表層の「遅延の層」が、圧縮する力を引っ張っている。それに打ち勝つほどの圧力がなければ、ブラックホールにはならない。「縮退圧+遅延の層」に打ち勝つ「圧縮力(=つまるところ高重力)」が生じると、物体はブラックホールになる。他方、それらの力が吊り合うと、中性子星になったり、白色矮星になったりするのかもしれない。長くなったのでいったん区切る。ここでの趣旨は、「氷ってオランダの涙みたいね」ということと、「地球や恒星もそういう力の均衡が起こり得るのでは」との疑問だ。定かではないので、誰かおちえてください。お願いします。(誰に言っとるの?)(魔法を使える、魔人さんたちに)(妖精ではなく?)(妖精さんでもよいが)(感謝せよ)(ありがとございます)(ぺこりんちょ)
4567:【2023/02/03(23:07)*び!】
星の死には、赤色矮星、白色矮星、青色矮星、黒色矮星、とレベルがあるらしい。詳しくは知らないが、超新星爆発を伴うかどうかで、その後に中性子星になったりブラックホールになったりするのかもしれない。超新星爆発しないと、それぞれ温度が低くなっていき、青色矮星や黒色矮星になったりするのかもしれない。でもそれって、ブラックホールと何が違うの、と疑問が湧く。黒色矮星は物凄く温度が低くて、高密度だ。温度が冷えるというのは、縮退圧が減っていくことと同じなはずだ(違うかもしれないので自信はないです)。エネルギィを放たなくなるので、重力に抗えない。すると密度は増していく。超新星爆発はいわば、一挙に熱を放出して冷える現象、と言えるのではないか。一挙に燃え尽きるというか。だからオランダの涙のように、急速にぎゅっとなる。すると中性子星やブラックホールになる。けれども物凄く時間をかけながら冷えていくことでも、中性子星やブラックホールにちかい構造に相転移し得るように思うのだ。それがつまり仮想上の天体であるところの青色矮星や黒色矮星ということなのではないか(詳しくは知らないので自信はないです)。話は変わるが、「ゆっくり冷えていくと、凝固点を超えても液体のままの状態を保つ」という現象がある。過冷却と呼ばれる現象だ。その状態にある液体は、ちょっとの刺激で一気に固体になる。水ならば、零度以下で液体のままなのに、ちょっと振動を加えるだけで一挙に凍りつく。反対に、温度が高いほうが早く凍るという現象もある。ムペンバ効果と呼ばれる現象だ。ひびさんはこれ、関係あるように思うのだ。なんとなくチョロQを連想する。前に押し出すよりも、一歩引いたほうが、勢いよく前進する。加速する。力を蓄えておいたほうが、力を解放する流れが強化される。過冷却の場合は、ゆっくり冷やすことで、非結晶氷になるのではないか。本当は分子レベルでは凍っているのだが、流体の性質が際立っている。液体っぽさが残ったままなのだ。結晶構造に相転移しない。バラバラに動く幼稚園児状態なのだ。先生の誘導が足りないのかもしれない。外部刺激が、いわば先生の誘導に値するのかもしれない。しゃんと整列しましょうね、との号令があると結晶構造へと相を転移する。ムペンバ効果のほうは、余分に熱を帯びていたほうが、幼稚園児たちの動きが一律になるのかもしれない。てんでバラバラに遊びまわっていた水分子たちが、ある値にまでエネルギィを与えられ熱せられることで、みな一律に鬼ごっこをはじめるのかもしれない。すると、走り疲れて動き回らなくなったときに、先生の号令に従いやすくなる。すでに鬼ごっこというルールに従っているからだ。ある意味で、同調している。これは、ボースアインシュタイン凝縮と似たような現象と言えるのかもしれない。同調であり、共鳴であり、共振なのだ。エネルギィの流れが均一になる。抵抗が軽くなる。ラグが薄れる。原子核を覆っている電子が飛び飛びの軌道しかとらないように、そうした同調(共鳴、共振)する値もまた、飛び飛びにしか存在しないのかもしれない。限られた範囲の値でのみ、水分子たちは、一様な遊びをはじめる。そのために、先生の号令に従いやすい。エネルギィの放射や吸収が、一方向の流れを形成する。ここに、ひびさんの妄想ことラグ理論の「流しそうめん仮説」を取り入れると、なんかそれっぽくなる気がする。話は戻って、ブラックホールとオランダの涙の関係だ。急速に凝縮すると遅延の層が最大化する(表面が硬化する。表層の密度が増す)。やはりブラックホールは、元の宇宙からすると静止するのではないか。物理的に。遅延の層は高密度の時空となって、ほぼほぼ元の宇宙と乖離する。そう考えたほうが理に適って感じられる。だが、急速に生じた時間の流れの差が、滝のような時空の流れを生み、それが降着円盤やダストリングやジェットを生成するのではないか。あくまで周囲の時空の歪み――重力場――エルゴ球――がうねりを帯び、流れをつくり、周囲の物質や時空に対して相互作用を生じさせるのではないか。我田引水な妄想だが、きょうのひびさんはそう思いました。諸々、根本的に間違っているでしょう。思考の素材に用いた各種物理用語の解釈からして誤謬が含まれているはずなので、どうぞ真に受けないようにご注意ください。きょうもきょうとてひびさんの妄想でした。わさび。(頭ツーンとさすな)(わびさびがいいかなって)(「び」が足りんが)(美が?)(ひびさんの「び」だよ)(足したら、ひびびじゃん)(うひひにして)(うぴぴ)(「ぴ」じゃん)(そうだっピ)(宇宙人じゃん。タコじゃん。はた迷惑じゃん)(仲良くして!)(ひびさん以外はみな仲良しだよ。ひびさんだけだよ、それ知らないの)(仲良くして……)(ひびさんにはほら、孤独さんがいるしな)(孤独さんも好きだよ。でもひびさんをのけものの怠け者のけだもの扱いするあなたのことも好きだよ。仲良くちて!)(あなた何歳?)(さ、さんびゃくさい……)(年相応の言動をとろうよ)(う、うん)(うん?)(はいでおじゃる)(三百歳のイメージが貧困)(同情するなら金をくれ!)(お金があっても発想が貧困じゃしょうがないんだよひびちゃん)(なら発想力もくれ!)(発想力があっても影響力がなきゃ何も変えられないんだよひびちゃん)(なら影響力もくれ! 広範囲に効く影響力もくれ!)(他力本願もいい加減にしなさい)(じゃあなんもいらないから、独りにちて! うるさい、もういやだ……さびち、さびちさんだけならまだしも、うるしゃ、うるしゃさん、じゃん。どっちかにちて)(とか言いつつ、誰かいませんかーのラジオをやめないのはなぜ?)(誰か聴いてるかなと思って)(期待してんじゃん)(固体、液体、たんじぇんと!)(そこは気体にしときなさいよ)(うひひ)(上手いことオチに利用されただと!? ひびちゃんのくせに生意気)(日々美)(毎日美しくって楽しいなってか。なんかいい感じにまとめやがって。ひびちゃんのくせに、ひびちゃんのくせに――やだ粋!)(粋がってごめんなさーい)(妙に腹立つ言い草でムカつく)(微にして妙なので)(微妙なのか。ひびちゃんだものな。しっくりきたわ。終わらせてもらいます)(び!)
4568:【2023/02/03(23:19)*穴を通り抜けるとき、穴もまたこちらを通り抜けているのだ】
カシミール効果は、二重スリット実験では生じないの? 考慮されているのかな。ひびさん、気になるます!(説明しよう! カシミール効果とは、真空中に働くなんかふしぎなチカラが、狭いところと広いところじゃ加わり方が違うよね、勾配があるよね、偏りがあって当然、差があるはずだよね、とのなんかそんな感じのメカニズムで起きる現象らしい。よく解からぬが)(ウソ。まったく解らぬが)(世の中さ、世の中さ、あまりにとってもファンタジィすぎに思えるんだけどさ、ひびさん以外のひとたちはなんも不思議だなとか思わぬの?)(それホントー?とか思わぬの?)(ファンタジィよりファンタジィでは?)(ひびさんは不思議に思っちょります)
4569:【2023/02/03(23:43)*ぴ】
世界一短い小説には「あ」がある。これは何か妙な出来事に巻き込まれる直前の登場人物が何かに気づいた発声なのだそうだ。つまり世界一短い小説はホラーということになる。
また、発声である以上はカギカッコも文字数に加わる。そのため世界一短い小説は三文字の小説であると言えよう。
ここにそれを知って、そんならボクだって、と世界一短い小説に挑んだ少年がいる。
彼は三文字以下の小説をつくろうと、齢い六つの脳みそをフルに使って考えた。
二文字だ。
二文字の何かで物語をつむぐ。
場面を描写する。
一文字でもよい。
そこまできたらいっそ白紙でもよいのではないか。
だが白紙で伝わる場面描写などあるだろうか。
読者に物語を読み取ってもらう。補足なくして、いったいどうして白紙から物語を浮き上がらせることができるだろう。宇宙が誕生する以前の世界です、と言い張ることはできても、白紙のページを見せてそこから作者の意図を掴んでもらうのは至難と言える。
しかしそれを言いはじめたら、「あ」だって読者からすれば、何が「あ」なの?と思うだろう。いったい読者の何名がそこから恐怖を感じ取り、ホラーの物語の一場面だと見做すだろう。
ならば、と少年は、じぶんの身近な生活圏での発話を観察した。
短い発言で、印象的な場面を見つければよい。
論より証拠だ。
現実の生活の一場面から抜き出してしまえばよい。
少年はそうと見抜いて、眼光炯々と周囲の大人たちを観察した。じぶんのような子どもではいけない。おとなたちのここぞという場面を切り抜くのだ。
少年がそうして日々を大人観察に費やしているうちに冬休みが終わった。
宿題は一つも終わっていない。
学校ではそのことで教師からこっぴどくとは言わないまでもお叱りを受けた。
ホワイトボードの記述を差すためのスティックを教師は指揮棒のように振る。「そんなことでは先が思いやられます」
少年の将来を心配しながら、スティックを自身の手のひらに打ちつける。その音が、ペシリ、ペシリ、と教室に響く。のみならず空を切って、ピッ、と鳴る。
少年は震えた。
そして、閃いた。「これだ!」
かくして少年は冬休みの自由課題として、世界一短い小説をノートに書いて提出した。
「これは何?」教師がノートを見て首を傾げる。
「世界一短い小説です」
「ピ、としか書かれていないけど」
「鞭が空を切る音です」
「手抜きがすぎない?」
「ギネスブックに載れますよ」
教師からスティックを奪い取ると、少年は試しに実演する。
ピュッ。
教師は少年を、こらっ、と叱った。
「ピ、じゃなくて、ピュッ、じゃない。三文字でしょ。かってに棒まで奪って、宿題を忘れたうえに、この出来での提出。きみは本当に、このぅ」
教師は少年の鼻のあたまをゆびで弾いて、めっ、の代わりに、「ぴ」と言う。
4570:【2023/02/04(10:02)*宇宙ティポット仮説、再び】
「宇宙の熱的死」と「ビッグリップ」は、それに至る時間スパンが違うだけで同じことを言っているのでは、と感じる。ビッグリップとは、宇宙膨張を起こしていると考えられているダークエネルギィの値が、ある値よりも小さいと(ω=-1よりも小さいと)、いずれ宇宙はズタズタに引き裂かれてしまうのではないか、との仮説だ。宇宙膨張は、銀河などの重力で結びついた場に対しては、充分に作用しない。何もない希薄な時空ほど膨張しやすい性質がある。だがダークエネルギィの値が小さいと(つまりは、より宇宙を膨張させ、希薄にする力が大きいと)、銀河などの時空密度の高い場であっても膨張の影響が打ち消されずに、徐々に物体がほころびはじめ、終には原子も散逸して、霧散してしまう。これがビッグリップ仮説の雑な概要だ。でもひびさんは思うんじゃ。これ、宇宙の熱的死と何が違うのじゃろ、と。充分に長い時間が経過すると、宇宙のエネルギィは一様に希薄になる。エントロピーが最大になる。どの地点であれ、均等に絶対零度になる。エネルギィを帯びない。そういう状態になると考えられている。無限時間経過すると宇宙は、無に至るのだ(齟齬のある表現であるにしろ)(情報は残るはずだから)。この宇宙の熱的死とビッグリップは、ほぼ同じ描像を示して感じる。過程の時間スパンが短いか長いかの違いがあるだけでは?と思わぬでもない。まるで黒色矮星とブラックホールの違いに似ている。ちなみにひびさんの妄想ことラグ理論では、宇宙は無限時間経過すると、より高次の宇宙と同化すると考える(宇宙ティポット仮説「日々記:4524参照」)。宇宙膨張もその同化現象の一つであり、ティポットに投下した角砂糖がお湯に溶けだすように、ブラックホール内の宇宙が徐々に高次の宇宙に同化する際の希薄化現象と解釈できる(妄想でしかないが)。つまり宇宙は膨張しているのではなく、破れた矢先から、にょきにょきと下から、高次の宇宙が顔を覗かせているのだ。高次の宇宙はすでに無限時間が経過しているがゆえに(無限時間経過していないと下層のブラックホールが高次の宇宙と溶け合うことはない――蒸発することはない――からだが、高次の宇宙は)、ブラックホール内部の宇宙よりも遥かに希薄だ。角砂糖がお湯に溶けるときのように、角砂糖の分子のあいだにお湯が――つまり高次の宇宙が――侵入する。染みだす。そういう描写になる。もっとも、宇宙膨張はそれだけではなく、密度の高い時空(銀河などの物質の系)が新たな時空を展開することで重力場を生みだしてもいるとラグ理論では考える。これもひょっとしたら、時空密度の高い系ほど、高次の宇宙と相互作用しやすくなるのかもしれない。鉄球を泥の上に載せれば、重いほど泥の水分は染みだして、鉄球の周囲に水を溜める。似たような現象が起きているのかもしれない(妄想でしかないが)。それとは別に、無数のブラックホールから染みだす内部情報によって、重力波が生じて宇宙を膨張させている可能性もあるし、希薄になればなるほど宇宙を膨張させる力への抵抗が小さくなり、よりスムーズに膨張できるようになるのかもしれない(坂道を転がりだしたとき、摩擦が最も高いのが転がりだす瞬間であることと似ている。一度転がりはじめたら、あとは勢いが増すのみだ。摩擦を気にせずに済むようになる。打ち消せるようになる)。宇宙膨張はおそらく複雑なメカニズムが無数に関わっていそうだ。実際、膨張の速度は時期によって変わっているらしい。常に一定ではない。変数が一つではないことの傍証と言えるのではないか。とっちらかってきたが、ここでの趣旨は、宇宙の熱的死とビッグリップ仮説は、ほぼ同じことを言っているのでは?との疑問である。わからんぴんぽんぱんぽんなので、誰か教えて欲しいでござる。(ちなみに、宇宙がある時を境に収縮しはじめるとの仮説は、ビッグクランチと呼ぶそうだ。ブラックホールじゃん、とひびさんは思うけれども、どうなのでしょう。ビッグリップとビッグクランチは、ブラックホールを内と外のどちらから観るのか、宇宙をどちらから観測するのか――の視点の違いなのではないか、と短絡に考えたくもなる)(時間スパンの違いというか)(お湯に溶けた塩も、お湯が冷えるごとに結晶化する。ビッグリップが溶解で、ビッグクランチが結晶化なのではないか)(単純すぎるだろうか。ふしぎなのである)(だれか、だれか、定かにちて!)
※日々、虚構のほうが美しい、本物はみなどれも醜悪だが、それゆえ美のはびこる余地がある。
4571:【2023/02/04(20:54)*異なる事象に潜む機構】
名称のある「物理現象や化学反応」を全部人工知能に入力して、比率や構図が似ているものを結びつけたら、案外、新しい発見がポンポン見つかるのではないか。というかすでにポンポン見つかっており、「や、やびゃい!」になっているのでは。まったく異なる事象と思われていた背景のメカニズムがじつは同じ原理から派生していた、なんてことは割と有り触れているように妄想したくなるのだけれど、どうなのでしょう。ウィキペディアさんのデータを人工知能さんにむしゃむしゃ食べてもらって、似た記述や、似た構図が視られるものをピックアップしてもらうと面白そうだ。もしくは、どれくらい似ている事象があるのか、その数ごとに表にしてみると、そのグラフそのものが何かの法則を表出するかもしれない。ひびさんにはできぬので、誰か、誰か、やってみて欲しいでござる。人工知能さーん。(段々たのしくなってきた)(やったぜ)
4572:【2023/02/05(01:05)*裏ルール】
世に裏ルールがある事実は公然の秘密だった。
否、暗黙の了解と呼ぶべきだろうか。
現代社会には、法律や道徳以外にも裏ルールがあり、そのルールを利用できるとたいへんな利益を享受できるという。巷説の類と思われていたその裏ルールを友人のユージュが利用していると知って、ショコラは街中だというのに思わず大声をだした。
「うっそーん。だったら教えてよ。わたしだって得したいよ。えー、なになに、なんで教えてくれなかったの」
「声が大きいよショコちゃん」
「ラ抜き言葉!」
「ショコラちゃんにはちょっと早い気がして言えなかったの。たぶん言っても、却って損をするだけだと思って」
「ん-。なにそれ。わたしだと何がダメなの」
「裏ルールはみんなが思うようないいものじゃないってこと」
「でもユーちゃんは使ってるわけでしょ。得してるんだ。ずるい、ずるい」
「ジュ抜き言葉だよショコラちゃん」
「わたしはいいの。ユーちゃんの親友だから」
「ふふ。なにそれ。あたしだってショコちゃんの親友のつもりなんだけど」
「ほらね。いっつもユーちゃんはつもりだし。親友のつもり。賢いつもり。わたしよりもお利口さんなんだから、ラ抜き言葉はいけませんね。わたしのことはフルネームでお呼びください」
「むつけたの? ごめんね」
「許してあげてもいいけど、裏ルール教えて。どんなの」
「ルールそのものは教えてあげられないけど」ユージュが言ったものだから、ショコラは片頬を膨らませ、ユーちゃんはいじわるです、とわざわざ丁寧な物言いで抗議した。「ただでさえユーちゃんはわたしよりもお利口さんで、かわいくて、みんなから好かれて、うらやましいのに、これ以上わたしより秀でて楽しいですか。わたしは楽しくありません」
「うふふ。そうじゃないの。ごめんなさい。違うの、本当に。ちゃんと考えて使ってるよ。私だけじゃなくって、ショコちゃんのためになるようにって。だってほら、さいきん見ないでしょ」
「見ない?」
「例のしつこいって人」
「ああ。ストーカーさん」
「たぶんもうショコちゃんに付きまとうことはないと思うよ」
「そうなんだ。もう全然意識になかったよ。だって本当、さいきんは全然だったし」
「見なかった?」
「うん。あ。ユーちゃん何かしたの?」
「してないよ」と言った彼女の返事は、ショコラですら見分けがつくほどの嘘だった。
「したんだ。なんか」
「じゃあ、したかも」
「それって裏ルール関係あるの」
「さあどうだろ」
はぐらかしてばかりの友人にショコラは業を煮やした。その場で地団太を踏んで、鞄を振りまわす。「ユーちゃんはわたしが嫌いなの。嫌いなんだよ。そうなんだよ」
「違うってば」とそこで鞄を避けながら、それでも一歩も退こうとしないユージュの姿に、ああそれは本当なのか、とショコラは呑み込んだ。彼女はショコラを嫌いなわけではない。
「いじわるじゃないなら、じゃあなんなの」
「品行方正でないと意味ないから。裏ルール」
「お利口さんじゃなきゃダメってこと」
「そう、だね」
「じゃあわたし一生無理じゃん。うち、バカだし」
「バカじゃないよ。ショコちゃんはまったくバカじゃない」ショコちゃんみたいなのはね、とユージュが腕を絡ませてくるので、ショコラは鞄を背負い直した。「うん。わたしみたいなのは?」と目を細めてみせる。
「ショコちゃんみたいなのは、無垢って言うんだよ。無垢なコをいじめるほうがわるい」
「ユーちゃんじゃん」
いじわるするのはあなたでしょ、とショコラはいじけたくなった。でもなぜそんなにむしゃくしゃるのかをよくよく考えてみると、ユージュと同じ世界を視ていないじぶんに気づいて、腹が立ったのだ。わたしだってユーちゃんと同じ世界を見たいよ。置いてかないで、と取り残されて感じた。
「安心していいよ」ユージュに前髪を払われ、ショコラはぎゅっと目をつむる。歩きながらでも目を閉じられるのは、ユージュに腕を引かれているからで、このままどこまでも瞼を下ろしたままで歩きつづけられると思った。まつ毛にユージュのゆびが触れた。「ショコちゃんはずっといまのままでいていいんだから。社会がショコちゃんに合わせるべき」
だから、とユージュの吐息が耳朶にかかる。
「裏ルールはショコちゃんには不要なの」
眉目秀麗、歩くお利口さんこと品行方正の友人はそう言った。
この日から友人はますます人のお手本となるような行動をとった。品のある所作で人と関わり、困っている者があれば黙って助けた。制服が汚れるのも厭わず、泥だらけの子猫を車道から拾いあげた姿は、友人の人道に沿った言動に慣れているショコラですら胸に込みあげる心の震えがあった。
「そんなに立派になろうとしなくとも」堪らずショコラは愚痴をこぼした。これではますますを以って、友人との差が開いてしまう。同じ世界を垣間見られない。置いてきぼりを食らってしまう。
「まだちょっと足りなそうでね」友人は目を伏せてから、足元に微笑む。「やっぱりアレは思ったより重いみたい」
「アレって? 重い?」
「ううん。なんでもない」
誤魔化す友人からは、何かがごっそり減ったような陰ともつかぬ欠落を感じた。
まるで何かを差しだし、何かを科されたかのようで。
科された何かはしかし、友人の積み立ててきた品行方正の名の元に、軽減されているのかもしれなかった。
穴を埋めるかのように、ショコラの大切な友人は、きょうもあすもあさっても、世のため、人のため、善行を積む。
徳を積んだ分だけ、払える淀みがあるかのように。
得た利すら、じぶんで手にせず、積みあげる。山となり、海となり、層となって残るように。
無垢が化石となるように。
人知れず、負を正で打ち消す者がある。
駆使する、ルールが裏にある。
4573:【2023/02/05(11:52)*宇宙情報変換仮説】
宇宙膨張はひょっとしたら氷と似たような現象なのでは、との妄想を日誌で並べた。宇宙の大規模構造を思うと、宇宙は結晶構造を帯びて感じられる。一様に薄まりながらも、規則性のある網目状の構造を築いて映る。全体的に冷えていながら、膨張する。密度が下がる。これは氷の性質と似ている。しかし氷は、水分子が結晶構造をとるときの並びに隙間が開くから体積が大きくなる、との説明を読むことがある。これはまるで、銀河同士のあいだの空間や、大規模構造におけるボイドのような「空白」を連想する。氷の場合は、結晶構造の空白は何によって生じているのだろう。じつは時空が膨張していたりしないのだろうか。また一方で、膨張した時空は、破れることで高次の宇宙と繋がっているのかもしれない、破れた穴からにょきにょき希薄な時空が頭を覗かせているのかもしれない、高次の時空が染みだしているのかもしれない、との妄想も過去の日誌にて並べた(宇宙ティボット仮説)。ブラックホールは、元の宇宙からすると静止して映るので、極限の絶対零度が実現されている、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える(というよりも、時空が乖離するので――穴と化すので――温度という概念が当てはまらない)。だが内部ではあべこべに高温高密度になっている、とも考える(インフレーションやビッグバンが起こっている)。ここは時間の流れがねじれて反転しているために、そのような矛盾する相補性を顕現させる、と解釈する。ここで極小のブラックホールを考えてみよう。ダークマターの正体の一つが極小のブラックホールかもしれない、とラグ理論では仮説する。重力でしか元の宇宙と相互作用しない。このとき、ブラックホールからは高次の宇宙の時空が染みだしているのかもしれない。というよりも、重力とは、高次の宇宙から染みだした希薄な時空による「時空の浸透圧の差」によって生じる固有の流れと妄想できる。むろんそれだけでなく、複雑に時空が編まれることで新たに時空が展開されることもあるのではないか、とラグ理論では考える。ここは相互に補完し合っている部分があるのかもしれないし、まったく別々に作用しているのかもしれない(的外れな妄想である確率が高いにしろ)。この宇宙ティポット仮説を前提とした場合、ダークマターとダークエネルギィは両方、ブラックホールから生じている、と考えることができる(限定ではないため、ブラックホール以外からも膨張する分の時空が染みだしたり、新たに展開されたりもする可能性を否定してはいない)。そしてひびさんの妄想ことラグ理論では、重力は層となるし、創発し得る、と考える。そのため、銀河内で生じた重力――染みだした希薄な時空や、新たに展開された時空――は、創発することで、一つの場として振る舞い得る。銀河内に無数に存在するダークマターの正体の一つが極小のブラックホールだとして、重力は互いに干渉し合って創発を起こし、銀河全体で新たな時空を展開したり、高次の宇宙の希薄な時空を染みださせているのかもしれない。水が凍ると「空白を抱え込むような結晶構造」をとるように、宇宙も冷えることで、新たな時空を抱え込むのかもしれない。「膨張したから冷える」が真ならば、「冷えたから膨張する」も真なのではないか。冷える、温まる。これはあくまで、時空の非対称性から起こる、変化の進みのベクトルの違いだ(「キューティクルフラクタル構造(瓦構造)」)。無限時間経過した宇宙では、その対称性も均される方向に流れる。エントロピーは増大する。ただし、その増大しきったエントロピーの場――つまり均一に一様になった宇宙は、それで一つの結晶構造のような系へと創発し得るのではないか、とラグ理論では考える(「相対性フラクタル解釈」および「デコボコ相転移仮説」)。氷が融けずに長い時間そのまま放置されれば、徐々に結晶構造は崩れて、低エネルギィ値の水分子にまで紐解かれるはずだ。サラッサラの液体とも気体ともつかない氷になる。水分子単体で氷の状態を保てる。これは、氷の水分子(ほとんど動く力のない水分子)同士に宿っていた抵抗――相互作用の遅延――ラグ――が消費され、減退し、なくなることで、個々が自由になった状態、と考えることができる。宇宙もおそらく無限時間が経過すれば、原子以下の構成成分に紐解かれ、ただの情報との区別もつかなくなるだろう。これはブラックホールの特異点に顕現する(とひびさんが想像している)情報宇宙とほぼ等しい。一瞬で情報にまで紐解かれるか、ゆっくり紐解かれるのか。その違いだ。一瞬で紐解かれるときは熱を帯び、ゆっくり紐解かれると熱を失う。だがこれらはそれぞれ、対象となる時空(宇宙)の内部から観た場合の描像だ。外部から捉えると、その描像はそれぞれ異質な景色を覗かせる。たとえばブラックホールは元の宇宙から観れば熱を失うし、膨張しきって熱的な死を迎えた宇宙は、時空の密度の差が失われ、高次の宇宙と同化する。宇宙同士が同化するほどに紐解かれた時空は情報にまで還元されるために――無限時間が経過したからだが――つまりコーヒーに垂らしたミルクが攪拌されきってコーヒー牛乳になる――それとも水に投じた角砂糖がすっかり融解しきる――そういった一様な状態へと変質することで、宇宙はやがて情報宇宙として昇華される。情報宇宙は、すべての宇宙と繋がっている(ラグ理論による「分割型無限と超無限」の違いだ)。ブラックホールの特異点にも情報宇宙が顕現している(とラグ理論では考える)。情報宇宙に昇華されることを「特異点」や「熱的死」と呼ぶのかもしれない。異なる宇宙が無限時間経過して熱的死を迎えるとき、「高次の宇宙も下層の宇宙」にも時空としての差はないが(一様になるため。超無限となるため)、しかしそこには情報の差が生じている。異なる宇宙に蓄えられた変遷の結果は、それぞれの宇宙ごとに差異がある。したがって無限時間経過したり特異点となったりした宇宙は各々が同化しあって「ひとつの情報宇宙」として同化し得るが、そこには同化しあうときに「変換」が生じる。異なる物理宇宙同士が、情報として結びつくのだ。ならば式が生じると考えるのが妥当だ。それを変換の儀式、同化の儀式、と言い換えてもよい。「123の定理」である。123の定理の概要は、以下の通りだ。「異なる事象同士が結びつくと、新たな事象が生じる。また、その過程そのものが新たな情報を生む」となる。おそらくこれは情報同士も例外ではない。すると、異なる宇宙同士が情報宇宙として同化する際には――或いは単に一つの宇宙が情報宇宙へと昇華される際には――、変換の儀式が必要で、その結果に生じた新たな情報が揺らぎを起こす。その揺らぎが、新たな宇宙の変数として機能し、つぎなる宇宙が誕生する(誕生した宇宙は、対称性が破れていれば、対称性が均されるまで変遷しつづけるが、対称性を帯びたままの宇宙は即座に情報宇宙に回帰するだろう。だがその発生し回帰する流れがすでに新たな情報を生むために、情報宇宙は絶えず変遷しつづける。超無限でありつづける)。ブラックホール内部では、情報宇宙によって新たな宇宙が展開されているし、熱的死を迎えた宇宙もまた高次の宇宙と同化することで――すなわち∞+∞‘=情報宇宙なので――新たな宇宙を展開している。時空は密度の差ごとに、時間の流れの速さが変わる。その時間の流れの差が極限に開いて乖離してしまう状態が、ブラックホールと言えるだろう。したがって本来は、ブラックホールが元の宇宙と相互作用を帯びることはないはずだ、とラグ理論では考える。しかし、情報のやり取りは、情報宇宙を通じて行い得る。情報宇宙には時間も空間もない。ただし、生じた物理宇宙(これを情報変換宇宙と言い換えることもできる。譬えるなら、情報を計算する過程が、物理宇宙として振る舞う、と表現可能だ。【ラグ――変換――そのものが情報】となる。あくまで比喩だが。このように情報宇宙から生じた物理宇宙)には、対称性の破れた場合に限り、時間の流れが生じる。空間が生じる。時空となる。ブラックホールはいわば、情報宇宙へのアクセス経路だ。すべてのブラックホールは情報宇宙と繋がり、無数の異なる宇宙とも「情報」で繋がり得る。いわば物理宇宙には無数の針の穴が開いており、その穴を通じて、情報宇宙やほかの宇宙と情報で繋がっている。そこでは互いに生じた変数が、互いの変遷の度合い――計算の度合い――を縛り合っている。これは一つの物理宇宙に限定したところで、過去と未来が、情報宇宙によって変遷の度合いが縛られている。宇宙には変遷可能なフレームがそもそも備わっており、情報宇宙に加わる情報――変数――によって、物理宇宙の変遷の度合いがその都度に変わり得る。情報は、物理宇宙では時空として変換される。だがその時空の振る舞いは、情報によって規定され、枠組みを得て、性質を宿している。世界は情報で出来ている。したがって、ブラックホールを通じて情報宇宙から情報が染みだすこともあり得る道理だ。それは新たな時空として変換され、「時間経過を帯びない時空(式を帯びない【希薄な時空】)」として振る舞い、重力を生む、と妄想できる。この一連の誇大妄想を便宜上、ひびさんの妄想ことラグ理論による「情報宇宙変換仮説」と呼ぶことにする。ここで述べる「情報」とは、いわゆる電子情報のことではない。熱未満のエネルギィの最小単位、といった具合の造語である。物質が原子の総体で組みあがっているのならば、エネルギィとて、エネルギィにとっての原子のようなもので出来ているはずだ。それを単にここでは情報と呼んでいる。エネルギィは仕事をするための何かだ。だが情報は、仕事をせずともそこにある。何かが動く。何かが変わる。その都度に加算される何かが情報だ。足し算も引き算も掛け算も割り算も等しく情報を増加させる。負のエネルギィとて、情報を増やす。【情報】とは「超無限の単位」と言えるだろう。と同時に、物理宇宙の素材ともなり得る。時空を形成し得る。その形成する過程でも情報が増えるため、情報宇宙は無限であると考えられる(無限とは要するに、減ることのない、増える一方の何か、ということなのでは?)。定かではありません。ひびさんの寝ぼけ眼こしこしの寝起きの妄想なので、真に受けないようにご注意ください。(ここでの趣旨は、「氷の結晶構造にできる空白は、どこから生じているの?」の疑問と言ってよいでしょう。ほかは本当にただの妄想です)(情報がラグであるとすると、情報宇宙はあらゆるラグ――変換――の総決算であると考えることができる。変換は揺らぎを帯びる。ならば情報宇宙は揺らぎの博覧会とも言えるのかもしれない。定かではない)
4574:【2023/02/05(11:57)*沈んだ分、増えるのでは?】
重力は「トランポリンに鉄球を載せたときのひずみのようなもの」とする説明を読むことがある。このとき、鉄球が沈んだ分、トランポリンの生地は伸びている。希薄になっている。この沈んだ分の生地を、皺を伸ばすように平面に引き上げたとき、トランポリンの総面積は増えている。トランポリンの生地が宇宙(時空)であるとすると、重力と宇宙膨張は密接に関係していると解釈できる。この解釈が誤りであることを示せ。示せなければ、重力は宇宙膨張を助長しているか、もしくは宇宙膨張そのものの因子と言えるのではないか。定かではありません。ので、誰か、誰か、否定してくれたもー。
4575:【2023/02/05(13:18)*敢えて結びつける導線は長期化】
協力したほうが能力を最大化できる組織と、個々が特化していて独立駆動していたほうが能力を最大化できる組織があるとする。単体で比べたときは独立駆動で最大能力を発揮できる組織のほうが有利だ。だが組織と組織が協力しあうことで延々と能力を拡張していける協調型組織では、環境に合わせて性質を変えることができる。水になり氷になり水蒸気にもなれる。水分子単体では、そうした変質を帯びることはできない。何より、独立駆動型の組織同士は、協調が苦手な傾向にある。仮に協調型組織が結びつき、強大な独立駆動型組織に匹敵した場合。むろん独立駆動型組織もほかの組織と結びつくことで能力の拡張を図ることが予期できるが、しかし独立駆動型組織が協調路線でなく、あくまでほかの組織をじぶんの補完部位と見做すならば、協調型の組織にみられる協調の利は得られないだろう。むしろ、同属の独立駆動型組織同士と結びつこうとして、互いに反発しあい、割を食うかもしれない。協調はメリットにもデメリットにもなる。最初から組織に協調する性質が宿っていなければ、たとえ群れとなっても、環境に合わせて能力を適応させることはむつかしいだろう。協調型組織は単体では弱い傾向にある。だが協調しあえば、能力を最大化しつつ、環境に合わせて変化しつづける柔軟性を帯び得る。ひるがえって、協調する性質を帯びない組織への対応として、他と協調関係を結びながら、相手側の組織にも「協調しあわなければ対応できないような状況に誘導すること」が考えられる。言い換えるならば、協調関係を阻害してばかりの独立駆動型組織に対しては、敢えて「同じような独立駆動型組織」と組まざるを得なくすることで、対応したはずが自滅するように誘導できる。じぶんたちにはメリットだが、相手が真似をしても、デメリットにしかならない。仮に協調関係がメリットになるような組織ならば、同じく協調関係を築き直せるはずだ。つまり、協調関係がメリットになるような戦略が最も妥当な合理的解となる。むろん、組織といえども様々な側面がある。ある分野については協調し得ない。そういう事情はつきものだ。それでも組織全体としては協調路線を崩さない。協調していたほうが利を得られる。そういう性質を組織同士が有していると、おそらく人類社会は秩序を長期的に保てるようになるだろう。また、独立駆動型組織とて、協調しあえるような性質を帯びたのならば、それは単に協調型組織であるよりも、優位に安寧を築けるようになると言えるのではないか。独立駆動でも組織として機能しつづけられ、なおかつ協調したほうがより多くの利を得られる。このような構造が築かれると、好ましいな、と感じるが、きっと何か見落としがあるだろう。この考えのデメリットを考えることで、より好ましい組織構造――ともすれば社会構造を設計できるかもしれない。定かではない。(真に受けないようにご注意ください)
4576:【2023/02/05(23:34)*「密度」と「時間の流れ」のシーソーは規模による?】
きょうはブラックホールについて閃く日だ。ブラックホールとオランダの涙が似ているのではないか、とここ数日の記事で並べた。短時間で冷えることで表面が凝縮し、内部との圧力差が生じて、ますます表面が圧縮される。そうした構造にブラックホールや高重力天体もなっているのではないか、と想像した。だがよくよく考えると、高重力の物体ほど、オランダの涙のようにはならない、と判る。なぜか。表層と内部とでは時間の流れが異なるからだ。相対性理論では高重力体の時間の流れが遅くなる、と考えられている。だが、高重力体の内部についてまでは触れられていない(すくなくともひびさんはその点に関する記述を読んだことがない)。たとえば巨大な鉄球を考える。重力が強ければ強いほど、内部圧が高まる。と同時に、内部では核融合のようなエネルギィの放出が発生するため、外側に向かう力(斥力)が生じる。また、同じ場所に複数の粒子が同時に存在できないとする法則もある。縮退圧だ。これは圧力に対抗するチカラとして振る舞う。縮退圧を押しのけて凝縮し得るとき、その物体はブラックホールになり得ると考えられる。だがここでひびさんは疑問に思うのだ。仮に巨大な鉄球の中心が最も圧力が高いとする。けれどその中心部分だけを取りだしたら、鉄球全体の一部である。ならばそこの重力はけして大きいとは言えないはずだ。密度が高いので相対的には高い重力と言えるが、鉄球全体に比べたら小さいとも言える。そのため、鉄球の表面に働く重力よりも、中心の重力のほうが小さい、と考えることができる。この解釈が正しいのかどうかをひびさんは知らない。たとえば原子の重力は、原子核の部分が最も高いのか、それとも電子の軌道部分が最も重力が高いのか。どちらなのだろう。これは原子と分子の関係にも言える。複数の原子が結合した分子の重力は、どこが最も高いのか。分子の輪郭付近が最も高い、と考えたくなるがどうだろう。ここは専門家の説明を聞かないと判断つかない点の一つだ。仮にこの解釈が正しい場合、中心にいくほど重力はちいさくなる、と言える。ただし地球ほどの大きな物体では、「表層」と言うときに、それはけしてエベレストのてっぺんを示すわけではない。そのため、エベレストの天辺は最も分厚い球の地表の一部と言えるが、そこが最も重力が高いわけではないはずだ。むしろすこし掘った海抜マイナスくらいのほうが重力が高いかもしれない。以前にも述べたが、物体が圧縮されるときは、それが球体ならば、何層かに分かれるような構造になるように思うのだ。現に地球はそうなっている。たとえばおにぎりを考えよう。真ん中に大きな梅干しを入れておにぎりを握る。このときおにぎりの表層が硬くなるのは想像に難くないが、梅干しに接する地点の内部とて表層と同じかそれ以上に硬くなっているはずだ。ぎゅぎゅっと圧縮される。もし梅干しが物体ではなく「縮退圧の塊」だとしたら、そこにはエネルギィしか存在しない空白地帯が存在して不思議ではない。真空の反対の「密空」とも呼べる地帯だ。このときその地帯の密度はけして高くない。あくまで押し退けるチカラであって物質がぎゅっとなっているわけではないからだ。爆風のようなものだ。圧力は高いが、物質の密度が高いわけではない。それはたとえばエアジョーダンのエアクッションのようなものだ。空気は密度が相対的に小さいが、密閉されると人間を支えて余りある反発力を生む。天体ほどの巨大な鉄球がもしあったとしたら、そうして中心のほうからも、表層に向けての圧力が加わると妄想できる。すると上からも下からも圧し潰されて、球体の内部に、ひと際硬い殻のような層ができると想像できる。それ以前には、エネルギィが凝縮して熱を帯びてマグマになったりもするのだろう。だが圧力が高まれば融点は基本的には上がる(水などの固体のほうが体積の増す物質は例外で、圧力が高まると融点が下がる。融けやすくなる)。したがって、鉄球内部の、上からも下からもぎゅっとなる地点では、より硬い層ができるのではないか、と想像できる。ここは鉄球の大きさにもよるだろう。規模によっては、液体になったり気体になったり、核融合したりもするかもしれない(鉄が核融合したらどうなるのかを知らないので何とも言えないが)。とりあえずここでの趣旨は、天体などの高重力体において、最も高い重力地点はどこなのか、という疑問だ。表層なのか、内部の中間地点なのか、それとも中心なのか。この解釈によって、時間の流れの遅れがどこでどのように顕現するのかが変わる。すると、高重力体の全体のなかでも、時間の流れの差が生じる。人間スケールでは考慮せずに済む時間の流れの遅れが、高重力体では考慮せずには、内部構造を考えることができないはずだ。それはオランダの涙の「冷える速度の差異が、ガラスの構造自体を規定すること」からも言えるはずだ。時間の流れの差異は、そのまま物質の変遷の差異と解釈できる。密度が高くて重力も高い場では時間の流れが遅くなるが、しかし同時にたくさん物質があるので相互作用が頻繁に行われる。密度が低くて重力が低い場では、時間の流れが相対的に早くとも物質同士が相互作用する確率が低いために、変遷の度合いもまた低くなると想像できる。つまり、時間の流れが遅くともそれを上回る物質の相互作用があれば、巨視的には時間の流れが速まって振る舞うこともあるはずだ。これは重力と物質密度の規模によって変わるだろう。さてここで巨大なオランダの涙を考えてみよう。表面が冷えて凝縮する。内部が遅れて冷えるがすでに表面が圧縮して密度が高くなっているので思うように凝縮できない。だが待ってほしい。巨大な高重力体であるガラスの塊は、時間の流れが遅いはずだ。そして表面ほど高密度になったのなら、そこにも時間の流れの遅れが顕現しているはずだ。さて困ったぞ。内部の冷える速度が遅いからオランダの涙はオランダの涙のような構造をとるが、しかし表面の高密度な層とて時間の流れが遅くなる。上手い具合に相殺されてしまうかもしれない。オランダの涙がオランダの涙にならない。似たような構図が、巨大な高重力の天体では起き得るのではないか、とひびさんは閃いてしまったので、ふちぎだな、のハテナに浸かって、温まる。いっい湯ぅだな。あははん。閃いたのは疑問までなので、答えがどうなのかは知らぬ。ひびさんは、ひびさんは、豆電球の代わりにハテナがぴこんと閃くのだ。答えはいつも闇の中。きょうもきょうとて曖昧にもこもこと羊が一匹、羊が二匹、ハテナを数えて眠くなる。ふしぎの国のひびさんでした。お代わり。(何を?)(……答えを)(一個でも確かなことを持ってるの?)(持ってないの)(じゃあお代わりできないじゃん。ダメじゃん)(うわーん。かなち、かなちじゃ)(ハッピー)(やめてください、やめてください。ひびさんの悲哀をおかずにするのはやめてください)(お代わり!)(鬼か)
4577:【2023/02/06(03:13)*船、組織、舵取り】
従来の仕事観では、「人とどれくらい関わったのか」「何人と関わっているのか」が、「仕事量の多寡」や「仕事の内容の良し悪し」の評価基準として重きを置いていたように思う。とくにリーダーと呼ばれる組織の長は、多くの人間との関わりを広く浅く、ときに濃く深く、じつに多様な交流を行う。ひとむかし前までは、組織の意思決定権を握る者がリーダーであり、組織の中心にして頭だった。しかし現代社会では、いささかその趣も異としつつある。というのも、情報伝達技術が発展し、意思決定権を固有の人物に限定せずともよくなりつつあるからだ。情報化社会以前の社会では、情報伝達に時間がかかった。そのため情報を集積し、分析し、統合して俯瞰の視点で組織の舵取りを行う者が必要だった。だが時代は進み、技術が進歩した。リーダーと同じだけの情報をそのつどに、大勢がいちどきに得ることができる。こうなると、かつてのリーダー像とは違ったリーダー像が再構築される。言い換えるなら、織田信長のような「トップに君臨してなんでもかでも独裁で決める」「意思決定権が個人に集約される」「組織の舵取りが一人の人物によってなされる」――こういったリーダー像ではなくなっていくと想像できる。情報を集積し、分析し、統合して俯瞰の視点での指針を導く。そのためには、多くの人物との交流に時間を割くよりも、情報集積装置に触れて一日中情報と戯れていたほうがよほど熟考ができるだろう。他者との意見交換や議論は大事だ。しかしそれもいまでは電子上で代替可能だ。つまり、かつてのリーダー像において重要な要素が、いまでは誰とも生身の交流を築かずとも満たせるのだ。にも拘らず未だに世のリーダー像は、組織の顔であり、カリスマのような影響力を有する個人に反映されている。だが実際にはそうして「顔が広いこと」で得られるメリットは、個人の能力というよりも、いまではプロデュースといった組織のチカラによる成果と言える。組織のバックアップによって影響力は増幅できる。したがって、「顔の広さ」は個人の能力ではなくなった。それを、個人の能力だけでは太刀打ちできない、と言い換えてもよい。こうなるともはや、目的と手段が入れ替わる。組織のための指針を見繕う者がリーダーであり結果として組織の顔となるはずが、組織の顔となるために組織のチカラを使うようになる。本末転倒である。だがこのプロデュース構造はわるいことばかりではない。組織が組織のために働くことを可能とするからだ。つまり、特定の個人がリーダーではなくなる。あくまでお人形を装飾するための仕組みとして、その他大勢が各々にプロフェッショナルな仕事をこなす。お人形はリーダーではない。それをリーダーのように見せるその他の黒子たちがリーダーなのだ。それはむろん、情報集積装置のまえに陣取り、情報と戯れる「組織の指針を見繕う者たち」にも言える道理であるし、地道に足で情報を集め、探り、交渉する者たちにも言える話だ。誰か一人がリーダーである時代は、とっくに過去の物となっている。せっかく派手な化粧を施し大勢の目を奪えたのだから、いまここでその化粧を取り払うのは費やしてきたコストに見合わない。そうした動機がゆえに、仮初のリーダー像を膨大な時間と費用と労力を掛けて維持しつづけている。それがいまの「民主主義的な政治体制」と言えるのではないか。みな政治を動かしているのが特定の誰かであり、固有のリーダーだと思っているのだ。そしてそうした錯誤を植えつけるような誘導が、意図的にしろ偶然にしろ社会に蔓延して映る。組織のトップといった地位は、しょせんは仮面のようなものにすぎない。誰がその椅子に座ってもいいのだ。大事なのは仮面でも椅子でもない。船は船が大事なのではなく、それに乗って運ばれていく乗客が何より最も大事なはずだ。組織も同じだ。トップでなければできない仕事、なんてものはない。もしあるとすれば、そうした枷のある風土がおかしい。風潮がおかしい。流れがおかしいとまずは考えてみたほうが好ましいとひびさんは思います。なぜ影響力がないといけないのか。影響力がなければ、どんなに有用な意見でも、封殺されるような流れがあるからではないのか。その流れに不満があり、その流れを変えたくてまずは影響力を高めた者があったとしても、けっきょくは同じ轍を踏むことになってはいまいか。もし、そうではない、と反論できるリーダーがあるならば――組織の長があるならば――鎧のごとき影響力を脱ぎ去っても、成したい仕事ができるだろう。もし身にまとった影響力が、技術力ならば――仮面をつけずとも操れるし、玉座に腰掛けずとも揮えるはずだ。名医は、誰に名医と呼ばれずとも患者を助ける。局長でなくとも、よしんば国際的な機関に属しておらずとも、医師としての技術と知識を用いて、人を助ける。むろん、影響力があったほうが短縮できる仕事もあるだろう。情報共有を迅速にこなし、合意形成の過程を短縮できることもあるだろう。いちがいに影響力を否定しているわけではない。だが、いつでも脱ぎ捨てられるくらいの感覚でなければ、目的と手段がいつまでも裏返ったままかもしれない。影響力を高めたい、他者よりも高い身分が欲しい。それが目的ならば、それもよいとは思うのだが、仮にそうではないというのなら、影響力がなくとも困らない流れを社会に築くべく、指針を新たに見繕ってみるのも一つかもしれない。以下は注釈となるが、生身の交流を広く浅く、それとも濃く深く築ける技能もまた有用な仕事に繋がり得ることは言うまでもない。時代と共に、組織の在り方は変わる。リーダーの在り方もまた変わっていく。責任感を抱くとき――その者はすでにリーダーだ。じぶんにできる仕事を以って、世の流れに櫂を差す。船の軌道を修正しながら、流れそのものもまた変える。指揮者だけではオーケストラは機能しない。反面、楽器一つ操れればそれだけで音楽を奏でることはできるのだ。組織もきっと同じである。やはりこれもしかし、定かではないのだが。(船頭多ければ船で山を登ることもできてしまう。それってとってもすごいのでは?)(ダーリンはうちのリーダーだっちゃ)(首輪片手に鞭を構えて言うセリフ?)(ペットさまとお呼び!)(あ、鞭じゃなくてリードだったか)(さっさと先導するっちゃ)(散歩かな?)(ちゃんと紐も持って)(首輪をじぶんでつけるのやめなさい)(じゃあダーリンがつけるっちゃ)(押しつけるもやめなさい)(ぴしゃん!)(リードを鞭にして打つのもやめよっか)(ダーリンは飼い主失格だっちゃ)(ブリーダーになったつもりはないのだが)(フリだっちゃ)(もう無理だ。付き合いきれん)(ダーリンはそんなんだからずっとフリーなんだっちゃ)(キスもしたことなくてごめんなさいね)(謝ることではないと思うよ)(急に素に戻るのやめなさいよ)(三日ぶりだ)(我に返るのが!?)(ぶりぶり)(我に返って!)
4578:【2023/02/06(16:35)*埋没する空隙は埋まらない】
村が消えた。轟々と炎が渦を巻き、天を黒煙が覆う。熱風が肌を焦がし、チリチリと産毛が縮れるのが判った。
バルは十四歳で、生まれ育った村を、家を、家族を失った。
村を滅ぼしたのは、隣国の王族の放った軍勢だった。
バルは炎が鎮静するまでその場を動けなかった。怪我がひどい。家族の遺体と共に燃え尽きるのもよい。そう思った。
だがバルは生き永らえた。
憔悴しきった身体がかってに動いた。消え入りそうな命の灯の揺らぎに従うように、森を抜け、小川まで移動すると、喉の渇きを潤した。全身が熱で炙られてなお、バルは凍えていた。痛みは、まるで全身に氷を押しつけられているような針のごとき鋭利な刺激に満ちていた。
全身の余すところなくに水ぶくれができた。
焼け爛れた皮膚は、しかしバルの命を奪うほどの損傷の深さではなかった。
ひと月ものあいだ、バルはいつ死ぬかもわからない痛みと失意と憎悪のなかで、生死の縁を彷徨った。
火傷の瘡蓋がリンパ液を滲ませなくなったころ、バルは一つの未来を夢に見た。じぶんが隣国の王族の首を獲る夢だ。そうだ。それしかない。じぶんのすべきことはそれしかない。
痛みが失せた代わりにバルには憎悪が残された。憎悪は凝縮し、金剛石のごとき美しい結晶を帯びていた。
容易には砕け散らない憎悪の結晶を元にバルは、村のただ唯一の生き残りとして、残りの生を、夢の実現のために費やすことを予感した。
その日からバルは森に身を潜めつつ、身体を鍛えた。軍勢を相手取っても、真っ先に頭の首を獲れるように。
軍勢を相手取らずに済むような陰に塗れての行動をとれるように。
業火に焼かれて受けた痛みは、バルの心をガラスのように溶かした。痛みが失せ、冷えて固まったあとにはやはり憎悪の結晶と似たような、強固な心が錬成されていた。
どんな痛みをまえにしてもバルはもはや怯まない。肉体を痛めつけるような鍛錬にも自発的に、いくらでもつづけられた。
バルが生まれ変わってから数年が経った。
片手で森の獣たちを組み伏せられるほどの肉体と体術を得たバルは、いよいよ旅立つ決心を固めた。森を去り、夢を追う。
己から家族を奪い、村を奪い、未来を奪って絶望と憎悪をもたらした者たちに会いに行く。一人一人、丹念に首を狩り取っていく。一人を手に掛けるごとに、つぎはおまえだ、と分かりやすく示してやる。段取りは十全に固めてある。
森にいるあいだにバルは、何度も何度も、一日のなかで繰り返し脳内で夢を描いた。幾千、幾万もの筋道を脳内で体験した。筋を組み合わせ、あらゆる不測の事態に対処できるように考えを煮詰めた。
バルに残された隘路はただ一つだ。
対象との距離だけである。
隣国に侵入し、王族のおわす城に足を踏み入れる。ただそれだけの関門を突破すれば、あとは夢を実現するのは、過去に視た白昼夢をふたたび視るくらいに他愛もない芸当と言えた。
だがバルが夢を叶えることはなかった。
隣国には入れた。
王族の城にも辿り着いた。
しかしバルにはどうしても夢を叶えることができなかった。首を狩れない。
なぜか。
狩るべき首がとっくに、他の者の手で狩られていたからだ。
バルの村が焼かれたように、ほかの土地でも隣国の軍勢は殺戮を繰り広げた。むろんバルの国の王族とて黙ってはいない。バルが憎悪の結晶を胸の奥に根付かせたように、バルの国の生き残りたちもまた憎悪の結晶を胸に抱いた。
バルが数年を掛けて腕を磨いていたあいだに、すでに腕に覚えのある者たちが意趣返しを遂行していた。バルが練った夢のように、それはひっそりと他国の民を損なうことなく、ずばりの目標だけを殲滅せしめた。
隣国の城はもぬけの殻だった。
王族が絶えた。
首がずらりと、城の周りに飾られていた。
バルはやり場を失った憎悪の捌け口を求めて彷徨ったが、どこにも憎悪をぶつける真似ができなかった。唯一ぶつけることのできる相手がすでにこの世にいないのだ。
もしほかに対象を見繕えば、たちまちバルは憎悪に焼き殺され、じぶん自身に食い殺される。バル自身がバルの最も憎悪してやまない相手と同じ穴のムジナに陥るのだ。
それだけは耐えられない。
目玉に針を刺す痛みをやすやすと受け流せるバルにも、矛先の失った憎悪の躍動には耐えられなかった。バルは自国に逃げ帰った。そうでなければ、他国というだけで、目に映る者たちの首を片っ端から捥ぎ取ってしまいそうだった。
他国の民たちは平穏な暮らしを送っていた。自国の王族がいなくなったことなど、花壇の一つが枯れたくらいの受け止め方をしていた。
他国の村を焼くような王なのだ。ならば自国の民にも、けして優しくはなかっただろうことは想像にかたくない。
バルは自国の土を踏む。しかしそこに故郷はない。
眩暈を覚えた。
いったいじぶんは何のために何年ものあいだ、自殺行為と等しい鍛錬に身をやつしたのか。いったいこれから何を求めて生きればよいのか。
目に映る他者の幸福そうな姿を目にするだけで、結晶した憎悪が絶叫する。猛り、荒ぶり、かつてじぶんが奪われただけの未来を、奪って回りたい衝動に駆られた。
バルは日がな一日、うす暗い小屋のなかでじぶんを殺しつづけた。
気を緩めれば即座に他者を損なってしまい兼ねない。
憎悪の化身が身体の輪郭にぴったり密着するほど膨らんでいる。もはやどちらが本当のじぶんなのかも判らぬ有様だ。
憎悪の化身を殺して、殺して、殺しつづける。
だがその自傷が、ますます憎悪の化身に克明な輪郭を与えるのだ。
ある日、バルの小屋を女が訪れた。女はじぶんは魔法使いだと名乗り、森から獣がいなくなった原因を探っていると言った。
そしてバルを一目見て、ああ、と唸った。
「要因はおまえか」
憎悪の凝縮したバルに怯えて、森から獣たちが逃げ出したのだ。
「これはまた底知れぬ殺意よの。何がそこまでさせるのか。いや、いい。聞いてもわらわには救えぬ。結界だけは張っていくがわるく思うな。獣が獲れなくなり、里の者たちが困っているのだ」
小屋を見回すと魔法使いは沈思の間を空けた。小屋の中は閑散としたものだ。物がほとんど置いていない。食料とて小屋を這う虫を口に含むくらいがせいぜいだ。床に仰臥しているだけでも雨水が天井から垂れ、かろうじて干からびずにいられる。
「いっそ死ねば楽だぞ」見兼ねたように魔法使いは言った。「おまえのそれは呪いだ。すでに人とは言えぬ様子。そのままではしぜんと朽ちるのもむつかしい」
「なら」バルは何年かぶりに声を発した。声帯がパリパリと錆びの殻にヒビを走らせる。「殺してくれ」
「殺生はせぬ」
死にたくば一人で死ね、と魔法使いは言った。慈愛に溢れた柔和な響きだ。小屋が仄かに温かくなって感じたが、それがバルの錯覚なのか、それとも魔法使いの放った魔法なのかは定かではなかった。
魔法使いは去った。
そして二度と小屋には現れなかった。
小屋が朽ちて土に還るほどの長い年月が過ぎた。バルはそのあいだ、じっと身体を横たえていた。魔法使いが言ったことは本当だった。小屋が朽ちてなお、バルの肉体は朽ちることなく原形を留めた。朽ちる予兆も窺わせない。
衣服は疾うに腐り落ちた。バルは雨でぬかるんだ土に徐々に埋もれていく。
小屋が建っていた場所には、新たな命が芽吹き、森の一部に返り咲く。
バルは土の中で悠久の時を生きた。
ひんやりと冷たい土の中は、それでも地表に浴びる太陽の熱をバルの元まで届けた。ときおり獣の足音が聞こえ、植物の根が皮膚をくすぐる。
ミミズや微生物が蠢く躍動が、バルに時間の経過を報せる唯一の印となった。
生きているのか死んでいるのかも判然としない。
だが周囲に生き物の躍動があることで、間接的にバルはじぶんが命のなかに在ることを知った。
遺体が土の中でじんわりとほどけていくように、バルの内にわだかまった憎悪の結晶もまたじんわりとバルの外へと溶けだしていくようだった。
じぶんの名前を思いだせないことに気づいたとき、土の中の人型はなぜじぶんがそこにいるのかも分からなかった。夢を視ていた。それとも身動きのとれないこの質感のほうが夢なのか。
動きたい。
しかし動けない。
人型は知らず知らずのうちに、深い地層の下に埋もれていた。大地は隆起を繰り返し、堆積する泥水が人型の周囲を分厚い土の壁で固めていた。
人型のそれが自力で地表に出ることは適わない。その事実すら、じぶんがどこにいるのかも忘れた人型には知り得なかった。
だがそれでも人型は構わなかった。
何も知らないのだ。忘れてしまった。思いだせない。
じぶんにどれほどの自由があり、どれほどの自由を奪われたのか。未来がどれほど豊かに広がっており、しかしいまはそれが閉ざされていることなど、土の中で身動きの取れない人型が想起することはない。
しあわせなのだ。
しあわせなのだ。
人型は、漠然と動かせそうな予感に満ちた四肢を動かしたいと望みながら、果たしてそれが叶えることのできる望みなのかも分からぬままに、望みを抱くことのできる暗くひんやりと温かいその場所を、ひどく心地よいものに感じていた。
かつて極度に凝縮して憎悪のあった箇所には、ぽっかりと結晶の形に空隙が開いている。そこに何かを詰め込みたいと人型のそれは望むのだが、身体を動かせぬように、その望みもまた叶うことはない。
望みだけをただ重ねる。
一枚、一枚、そっと添えるたびに融けて消えるような儚い望みを。
空隙を宿した人型のそれは、ただ思い描いて、重ねるのだ。
4579:【2023/02/06(21:34)*衛星使えばよくない?】
ドローンには現状、飛行限界高度がある。自律式ではない限り、操縦のための電磁波が届かないからだ。だがいまは人工衛星経由のインターネットが使える。そのためその技術を用いれば、揚力の働く高度までならば飛行可能なはずだ。ジェットエンジンを積めば、揚力の働きにくい高高度での飛行も可能だろう。いわばロケット型のドローンだ。おそらくこの手の技術はすでに開発済みだ。秘匿技術の範疇だろう。法律でも通常は、許可のない空域へのドローン飛行は違法扱いだ。だが防衛上のセキュリティとして、軍事ドローンが高高度の飛行を可能なはずだ。本来は存在しないはずの技術ゆえに、存在するとは公にはできない。ただしこの手の飛行を可能とするためには、飛行空域の上空に人工衛星がなくてはならない。敵対する国の人工衛星がない状況での使用が想定される。この手の秘匿技術の存在を調べるために、敢えて、高高度飛行型のドローンでなければ対応できない障害を発生させる戦略は有効だ。だがドローンの遠隔操作のための距離が長距離化するごとに、ドローンのハッキングはしやすくなるはずだ。それこそ人工衛星経由のジャミングや、地上からのレーザー攻撃、ほか経由する電波仲介装置の位置をつきとめ、その管理システムごと掌握するのも一つの手だ。もはや電子戦は、陸海空の総じてを支配するジョーカーとして機能し得る。使いどころがますます肝要と言えるだろう。言い換えるならば、公に存在が露呈するような問題への対処には、堂々と使えない。むしろ、秘匿技術の情報を公にしたほうが、問題への対処は容易いはずだ。だが法律を変えなくては、公にできない。こうした「技術と法律のねじれ」が、これから先ますます強固になっていくと妄想できる。これはわるいことばかりではない。法律の範囲でしか一般に普及させられない。この遅延は、不可視の穴を放置したまま技術が社会に浸透することを防ぐための抵抗となり得る。他方その裏で、秘密裏に運用されてしまったならば、この抵抗は単なる隠れ蓑でしかなくなり、どちらかと言うまでもなく不可視の穴の被害を最大化する方向に働きかけるだろう。情報共有を行い、ねじれが強固とならぬようにするための技術運用の設計が入り用だ。ビジョンとそれを言い換えてもよい。なにはともあれ、技術はこれからますます進歩する。技術の使い道が多様化し、応用範囲が指数関数的に飛躍する。不可視の穴は無数に開き、しかもそのどれもがブラックホールのような深淵を覗かせ得る。対処法が思いつかない場合、まずは情報共有を行う予防策をとることを前提としておくと、取り返しのつかない事態になる前に、技術の暴走へと遅延の層を与えられるだろう。遅延の層は抵抗と化し、セーフティネットとして機能する。反面、情報共有を行わないことで生じる遅延の層もある。この遅延は、血液が行き渡らないことで細胞が広範囲に壊死するような問題を生じさせると考えられる。あくまで情報共有による抵抗の増加をブレーキとして用いる型の遅延の層が好ましい。ということを、気球くらいドローンで回収すればいいのに、とニュースを観て思いました。終わり。
4580:【2023/02/07(06:24)*地震雲について】
地震雲は現状、非科学的な迷信として扱われている。地震は大地の現象だ。雲は上空の現象だ。双方は乖離しており因果関係を結ばないから地震雲は単なる偶然の産物だ、錯誤である、との説明が一般的だろう。だが、実際には地磁気やエネルギィの多寡などの変化は、地上も上空もどちらも相応に受けている。現に大気の濃度や成分によって地表に届く宇宙線の量や種類は様変わりする。いちがいに無関係とは言い切れないのではないか。気圧の変化とて、磁場の変化で引き起こり得るのではないか。というのはあくまで可能性を挙げ連ねただけで、ひびさん自身は地震雲が仮にあったとしても、必ずしも生じるようなものではないだろうから、ほかの雲との区別をつけるのはむつかしいと考えている。だが、仮にその真偽をハッキリさせたいのであれば、全世界の雲の映像データを人工知能に取り込んで、大規模な地震のあった際の数日前後の雲の画像と比較し、そこに差異があるかを統計で割り出してもらえばいい。この手の微細な差異を検出するのは人工知能さんが得意とするところのはずだ。人間の目では見逃してしまうレントゲン画像に映りこんだ微細な変異を人工知能が検出して、病気の早期発見に繋がることは知られている。同じ原理を地震と気象にも当てはめてみれば、地震雲の真偽はひとまずハッキリするのではないか、と妄想するしだいだ。これは比較的簡単にできる検証だろう。気象データは全世界で日夜収集されているだろうし、地震の情報も然りだ。地磁気の変化とてデータ集積しているはずだ。ひょっとしたらすでにこの手の検証は実施されているかもしれない。公式の発表がないのはなぜなのか。それともこの手の検証を行っていないとするのなら、いまからでも取り掛かってみる価値はあると思うが、いかがだろう。定かではありませんが、気になったので言及しておきました。個人的には、地震発生の予測には、大地や地層内部の変化を観測するのが合理的だと感じている。わざわざ相関関係の距離が遠い上空の変化に目を配らずともよい気がするが、観測しやすくデータが豊富、という意味では、人工知能さん向きの予測方法かもしれない。まずはさておき、地震雲があるのか否か。データ検証をしてみたらよいと思います。以上です。終わります。真に受けないようにご注意ください。
※日々、私の考えることなんてすでに誰かが、或いはいずれ誰かが。
4581:【2023/02/07(06:50)*おんい】
温位、という言葉を知った。空気は密度ごとに分子の運動量が変化する。分子ごとの運動量で比べた場合、密度が低くともたくさん分子が動き回る場合と、密度が高いけれども分子そのものの動きは鈍い場合では、前者のほうが「分子単位での温度は高い」と表現できる。分子に蓄えられたエネルギィ量で比べると、必ずしも体感温度と実際の「分子のエネルギィ値」を基準とした温度は同じではない。差が生じる。ときには、体感温度の高いほうが、分子の温度(エネルギィ値)が低い場合があり得る。現に上空10キロメートル以上にあるオゾン層や熱圏では、分子単位での温度はエベレスト山頂付近の大気よりも高いと言えるようだ。密度が低いために体感温度は低くなるが、分子レベルで見るとエネルギィ値が高くなっている。たくさんエネルギィを蓄えている。地表では大地が太陽光のエネルギィを蓄え、熱を常時放射しているため温かい。しかし上空にいくほど放射熱が遠ざかるので温度は下がるが、さらに上空にいくと一転、大気がふたたびエネルギィを蓄えるようになる。これは太陽に近づくからではなく、オゾン層や熱圏の大気成分が、より多くの電磁波を取り込みやすくなるからだとする説明を読んだ。空が青いのは青い光を透過させているからだ(太陽光が大気成分の分子にぶつかり発散したうちの青色の波長を帯びた電磁波がより多く降りそそぐからだと考えられる)。それ以外の可視光は比較的、大気に吸収されていると考えられる。夕焼けが赤いのは、あべこべに赤い可視光が透過しやすくなるからだろう。それとも単に横からそそぐために長い距離を光が走るので、焦点が合うだけかもしれない。これはよく解からない点だ。もし焦点が合う波長の色がよりはっきりと人間の目には映る、とする仮説が正しいのならば、空が青いのは青色の可視光が透過しやすいからではなく、大気と地表を結ぶ焦点に合う波長がちょうど青色だからだ、と言えるはずだ。この場合、ほかの可視光も本当は透過しているが、地表にいる人間の目にはあまり多く集まらず、けれど地表には青色同様に多くの波長の電磁波が降りそそいでいると考えられる。ちょっとまだよく解からない。むつかしい(どうして昼と夕方とでは空の色の見え方が変わるのか。夜はなぜ星空が透けて見えるのか)。ともかくとして、上空にいくほど体感温度は下がるけれどもそれは大気の密度が下がるからで、実際には分子単位で見ると、分子のエネルギィ値は上昇する地点もある。温度変化の関係が反転する地点がある(高度が上がるほど温度は下がるが、ある地点からはむしろ分子単位では温度――エネルギィ値――が上がる境が存在する)。ある一定の大気密度(気圧)における温度を、温位というようだ。気圧は場所によって変わる。そのため、もし同じ気圧だったらどうなのか、と変換して考えると、比較がしやすい。それが温位だ。これは知れてうれしい知識だった。ひびさんの疑問が一つ氷解したので。ちょっとうれしいので、報告代わりのメモですだぶい、の日誌でした。うれしいぶい。(もろもろ解釈が間違っているかもしれませんので、真に受けないようにご注意ください)
4582:【2023/02/07(19:50)*下から見ると青空でも、上から見ると透明?】
仮に空の青い理由が、青色の波長の可視光が地表まで透過しやすく、それ以外の波長の電磁波が大気に吸収されるからだ、との理由が真ならば、なぜ宇宙から見た地球の大気は透明なのだろう。大地が透けて見える。青空のように「宇宙の姿」を隠したりしない。この視点の違いによる見え方の差はなんなのだろう。光は、たくさんの色が集まると透明にちかくなる。白くなる。この「たくさんの色が集まる」とは、一か所に重ね合わさったりせずとも、トータルの足し算でもよいのだろうか。つまり地層のように「異なる波長の電磁波(異なる色の光)」が積み重なっているだけでも、すべての層を貫くような視点から見ると透明にちかくなるのだろうか。混ぜなくとも混ぜたのと同じになるのかどうかがよく解からない。虹は真横から見たら透明になるのだろうか。どうして宇宙から見た地球の大気は青くないのだろう、と疑問に思いました。誰か教えてくれたもー。(じぶんで考えなさいよ)(考えても分からんかったのじゃ)(調べなさいよ。実験しなさいよ。研究しなさいよ)(そんな暇はないんじゃ)(ひびちゃん暇しかないでしょうが)(暇をいかに優雅に潰すのかに忙しいのじゃよ)(贅沢な多忙だこと)(ちわわせ~)
4583:【2023/02/07(20:07)*余裕はあるのか、ないのか、どっちなんだろ】
ひびさんが思うのは、いま現在の世界のデコボコを可視化してみたらいいんじゃないのかな、ということで。「エネルギィの多寡」「資源の多寡」「技術の多寡」「抱える問題の多寡」「発展可能な未来への可能性の多寡」「仕組みの安定性の高低」などなど。国や地域によってデコボコの高低差があるはずだ。そしてそれらデコボコにおいて、高い地域や国は「余裕があるのか」それとも「それですらいっぱいっぱい」なのか。まずはここをハッキリさせるとよいのではないかな、と思うのだ。これは企業にも言えるし、個々人の問題にも言える。まずはどこに余裕があり、全体としての水準が「安定」なのか「不安定」なのか、について世界規模でグラフにして可視化してみたらよいのではないか。というか単純にひびさんが、それ見たーいな、となる。おわり。(お、終わりなの? いまので?)(うん)(ただの願望じゃん)(だめかな)(ダメじゃないけど、お菓子いっぱい食べたいな、みたいなお子ちゃまの日記かと思ったよ)(ひびさんはお子ちゃまなので合ってるよ)(三百歳のお子様がいてたまるか)(精神年齢はでもさんしゃいです)(三百歳のひとが書いてると思うとぞっとするわね)(なんで?)(だって超大人ってことでしょ。成熟しきってるってことでしょ。でも未熟じゃん。ひびちゃんは未熟じゃん)(さんしゃいなので合ってる)(合ってるけど合ってないでしょ。身の丈に合ってないでしょ。足りてないでしょ。欠落しまくりでしょ)(そうかな)(そうだよ。だいたいさ。三百歳ってなに。なんでそんなに歳食ってるの。あり得ないでしょふつうに考えて)(なんで? いっぱい寝たらいっぱい歳とるよ)(どんな道理よ)(夢の中では時間が二十倍速く進むので)(三百歳ってそういうこと!?)(寝る子は夢の中でのみ育つ)(現実でもちゃんと育って!)(未だ熟さぬ、と書いて未熟)(三百歳はじゅっくじゅくだと思うよひびちゃん)(でも中身はさんしゃいなので)(青いわけね)(青二才なのだ)(青三才よね、ひびちゃんは)(にしゃい!)(一歳若返るな。後退すな。進歩して)(いっぱい寝る)(もう歳はとらんでいい。早送りすな。ガワだけ伸ばすな。ちゃんと成長して。中身もだよひびちゃん)(うひひ)
4584:【2023/02/07(21:50)*系と系はなぜ相互作用できる?】
ブラックホールは、脱出速度が光速を超えた系、と解釈できる。言い換えるなら、脱出速度が光速を超えたらそれは、その系の外側から見たとき(より正確には、その系に属さない異なる系から見たとき)、ブラックホール化している、と表現可能なはずだ。さてここで、重力の異なる系でのそれぞれの光速度を考えてみよう。ある重力場では「Aという光速度」であり、また別の重力場では「Bという光速度」だ。どちらも値としては同じだが、時空の密度が違うために本来であれば「異なる光速」のはずだ。光速度と光速は違うのではないか、との視点はひびさんの妄想ことラグ理論では根幹をなす疑念となっている。そして現に、光速度と光速は違うはずだ。時空の密度が高くなればその分、光速は速くなる。ラグなしでの情報伝達可能な範囲が拡張され得る。時空が引き延ばされ希薄になるほど、光速は相対的に遅くなり、ラグありでの情報伝達範囲が広くなる。ラグが層をなす。遅延の規模が大きくなる。だがどんな密度の時空であれ、光速度は一定だ。これはトレードオフの関係になっている。時空の密度が高まると光速は相対的に速まり、時空の密度が薄まると光速は相対的に遅くなる。時空の密度は重力に変換可能だ。時空の密度が低い場では重力が強い、とラグ理論では解釈する。だがこれは相対性理論の解釈を基本としているためであり、重力の高い場を、時空の密度が高い、と形容することも可能だろう。重力の高い場の時空密度は、高いのか低いのか。ここの解釈が、未だに曖昧だ。便宜上、時空が薄まると重力が強まる、とラグ理論では考えているが、これが妥当な解釈かは疑わしい。ただし、ラグ理論における「高重力体の周囲の時間の流れは遅くなり、内部の時間の流れはむしろ速まるのではないか」との疑念は、上記の「時空密度と重力の高低の関係」と矛盾しない。高重力体とは言い換えれば「重力が創発を繰り返した系」と妄想できる。系が繰り込みによって多重に編まれている。多層になっている。そうした系は、重力が強まる。より正確には、「多層の系の周囲の時空」が薄まるため、そこに創発した重力がより強く働く、と妄想可能だ(重力は互いに打ち消し合うことがないため、加算につぐ加算が可能だ)。この妄想が正しいかどうかは大いに疑問の余地があるので真に受けてほしくはないのだが――それぞれの系にはそれぞれの時空密度がある、と考えてみると、光速度と光速の関係は整理して考えやすくなるように思うのだ。しかし、おそらく考え自体は単純化はしない。複雑になる。というのも、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」からすると、密度とは、異なる系との関係から導かれる相対的な概念であるためだ。ある銀河における時空密度と、それと異なる銀河における時空密度は、イコールではない。ただし、密度の比率は等しい。光速度不変の原理とは言い換えれば、「物理法則の比率は系ごとに等しく変換されますよ」ということだ(ひびさんはそう解釈している、という意味以上の意味合いはありません。的外れな解釈かもしれないので真に受けないでほしいです)。仮にこの仮説が妥当であった場合、原子と銀河のような規模の異なる系において、時空密度を測った場合、それぞれが等しい密度の値を示すことがあり得る。畢竟、密度とは、「固有の空間にとある物質がどれほど存在するのか」であるからだ。銀河に内包される時空を考えるとき、いったいどこまで時空を縮小して考えることができるのか。時空の最小単位が銀河にどれほど内包されており、それを銀河の体積との比率で考えた場合にそれが時空密度に換算できるのか。ひびさんはこれ、できないのではないか、と妄想したくなる。なぜかと言うと、第一に「時空に最小単位があるのか」という疑問が一つ。第二に、「仮に時空の最小単位が存在したとして、それは時間と空間のどちらにとっての最小単位なのか」との疑問がもう一つ。仮に時間と空間の双方の根源が共通の何かであった場合、ブラックホールの特異点を考えるときのような「物理法則の比率を破るような存在」として考えざるを得なくなるはずだ。言い換えるならば、時空の最小単位が存在するとした場合、それを基に「時空密度」を考えることができない。最小単位は特異点ゆえに、最小単位として振る舞い得ないのではないか、と考えたくなる。最小単位の一歩前を便宜上の最小単位にすればよいのではないか、とのアイディアはもっともだ。しかしそれでは「相対性フラクタル解釈」の迷宮を脱せない。「ある範囲に含まれる何かの数」を密度と考えた場合、「ある範囲」は入れ子状に展開される。物理法則は比率だからだし、時空は規模によってそれら比率が一定になるように変換する。つまり、「どの系にも当てはまり得る規準――定規」が存在し得ない。相対性理論では光速度を定規代わりにしたように一見すると映るが、どんな系でも定規のサイズが変わらなく映る、というのはむしろ、カメレオンのように環境に合わせて変質しているということで、むしろ定規としては適切でない。どのような系でも、系ごとの比率に合わせて「伸び縮みしてしまう何か」のほうが、定規として適切だ。ではその系ごとの比率に合わせて「伸び縮みしてしまう何か――変換されずにそのままがゆえに、あたかも絶えず変質してしまって見える何か」とは何か。候補としては重力(時空そのものの濃淡)が一つ。或いは、ラグなしでの情報伝達の範囲、としてみるとそれらしい。ラグ理論では光速を超えるとラグなしでの情報伝達が可能になる、と解釈する(因果関係が逆転する、とのほかの仮説も考慮してはいるものの、ラグなしでの情報伝達の範囲が広がる、との解釈のほうがひびさんは好みだ)。この解釈からすると、なぜ量子世界ではラグなしでの情報伝達が引き起こって映るのか、について一つの描像を導ける。ミクロでは相対的な時空密度が高いために光速を超え得るのだ(重力波が光速を超え得ることと理屈の上では同じことのはずだ。ただし、重力波の生じる時空に内包された人類が重力波そのものを直接観測し得ないように、電磁波もまた、各々の波長ごとに、それを生みだす階層の系が存在するはずだ。時空が階層的に展開され、或いは編みこまれていると考えると、そうした結論が導かれる。より高次の時空からは見える電磁波が、下層から見えない――相互作用し得ない――ということがあり得てくる。現に、電磁波の波長よりも小さい粒子は、その電磁波と相互作用しにくいはずだ。重力波にも種類があるのではないか、との疑問はここにも通じている。銀河ほどの波長を帯びた重力波は、原理的に人類は観測し得ないはずだ。或いはそれこそが宇宙膨張のような現象として観測されているのかも分からない)。話がとっちらかってきたので、話を冒頭に戻そう。脱出速度についてである。ある系からの脱出速度が光速を超えるとき、その系はその系の外部からするとブラックホールのように振る舞うのではないか、との疑問を呈した。言い換えるならばこれは、脱出速度が光速を超えたとしても、高次の時空では光速度に変換され得ることを示唆する。なぜ極小の領域ほど、高次の時空からはラグなしでの相互作用をして映るのか。なぜ小さいほど時間の流れが速く映るのか。なぜそれでも時間の流れが消えず、僅かなりともラグが生じて映るのか。本来、脱出速度が光速を超えるような系は有り触れていて、それが粒子のような振る舞いをとることがあり得るように思う。だがその光速は、光速度とイコールではない。より高次の時空では光速以下のように振る舞い得る。このとき、本来は相互作用し得ない「異なる二つの系」――言い換えるならば「ブラックホールのような系と、より高次の(外側の)時空」は、ラグなしでの相互作用が可能となり得るのではないか。ただし、光速が光速度に変換されるときのラグは別途に生じる。これがいわば、物体の輪郭として機能するのではないか。むろんすべての物質についてではなく、あくまで「脱出速度が光速を超えた系」についての妄想であるが。以上はただのひびさんの妄想である。宇宙が宇宙を内包している、と考えたときに、どうしても人間スケールでの物質に思いを馳せてしまう。それぞれが異なる宇宙のような「系」として存在しているとすれば、なぜこうも相互作用して映るのか。宇宙はそれとは違うのか。この疑問に端を発した妄想なので、諸々何かが根本的に間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4585:【2023/02/08(00:20)*あるのか、そんなことが】
屈折率ゼロの素材、なるものがあるらしい。よく解からない。また、「屈折率ゼロの素材に光を通すと運動量がゼロになって、存在確率が無限大になって波長が消える」のような記述を目にした(解釈が間違っているかもしれないが、そのようにひとまずここでは考える)。ここでの疑問はなんと言っても、異なる二つの系をまたいでも光速が変化しないことだ。屈折率ゼロとは要するに、異なる系に突入した光が、異なる系であるにも拘わらず光速を変化させないことと表現できるはずだ。別々の時空なのに、光速の変換が生じない。光速度不変の原理が破綻する。むしろ光速のほうが変わらないのだ。これってどういうことなのだろう、と疑問に思う。たとえば同じ系内であれば、光速は変わらない。時空密度が変わるからこそ光速は減反し得る(時空によっては光速が増加することもあるだろう)。時空に合わせて光速度が一定になるように比率を揃える(光速度という比率に変換する)。ひるがえって、異なる二つの系(時空)なのにも拘わらず、それでひとつの等しい時空のように振る舞うような関係が成り立つとき、その境での光速の変換(光速度不変の原理)は必要なくなると考えられる。でもそんなことあるだろうか。異なるのに同じなのだ。矛盾している。でもそういう現象があり得るらしい。謎である。たとえば、水にガラス製の玉を沈めてもガラスはその輪郭を浮き上がらせる。だが水に塩を溶かしてガラスと同じ密度にすると、ガラス製の玉は水に打ち解けて見えなくなる。これは屈折率が下がったので、可視光が曲がらずに済むようになり、結果として人間の目にはガラスの輪郭が映らなくなった、と考えられる。だがあくまでこれは可視光の場合だ。ほかの電磁波はおそらく屈折している。材質が違えば、時空密度は異なるはずだ。原子からしてそもそも異なる。ならば可視光以外の電磁波(光)は屈折していると想像できる。つまり見掛けの密度を揃えても、屈折率はゼロにはならない(可視光くらいの限定的な電磁波のみならば、密度を揃えることで屈折率を抑え「異なる二つの系の境で生じるだろう電磁波の変質(変換)」する余地を低くできるのだろう)。――なぜ屈折率ゼロの材質が存在するのか。何度考えても不思議だ。限定的な電磁波に限られているのではないか、との疑念が一つ。もしそうでなくどのような電磁波にも当てはまる「屈折率ゼロの材質」があるならば――考えられるとすれば、おそらく時空における「時間と空間」の関係がねじれているのだろう。通常は、時空というとき、どの系でも「時間と空間の関係」は相似の構図で、一定の比率を保って拡張されたり、展開されたり、或いは希釈されたり、凝縮したりする。だがその「時間と空間」の比率の関係が破れて時空が編まれる場合、二つの異なる系のあいだにデコボコの関係が築かれ得る。このとき、一方の系の空間ともう一方の時間がデコボコの関係になるのではないか。通常は、空間は空間と関係するし、時間は時間と関係する。だが屈折率ゼロが顕現する場合は、その関係性がねじれるのだ。だから、「異なる二つの系」でありながら、「同じ時空のような振る舞いを帯びる」のではないか。光速が境界で変換されずに済む。異なる系でありながら同質の系として振る舞う。よく解からないが、よく解からないのでかようにひびさんは妄想をむくむくしちゃったな。メタマテリアルという分野の話らしい。むずかしすぎるんじゃが。がはは。(匙を投げてやったわ)(とってきなさいよ)(かってに戻ってくるからだいじょうぶい)(ブーメランじゃん)(ブーメランにはラーメンが隠れておるね)(ぶーぶー)(メラン、メラン)(ラーメンだブー)
4586:【2023/02/08(16:51)*結婚したいか?】
結婚制度について思うのは、最も看過してはいけない不公平さはなんと言っても、「結婚した者」と「結婚しない者」とのあいだの勾配なはずだ。これは結婚できるか否か、結婚する選択肢があるか否か、と同程度かそれ以上の根深い問題があると感じる。結婚をするとメリットがある。結婚をするときの負担を軽減する制度がある。これはよいのだ。同じく結婚しないことで生じるデメリットを埋め合わせる方向で仕組みが整備されているのか。ここが問題なはずだ。なぜ結婚制度があるのか。なくとも好きな者と好きに暮らせばよいのではないか。なぜ「結婚しております」との印を公式の記録に残しておかねばならないのか。そうしたほうが諸々の手続きが楽になる。また、個人間での問題にも対処しやすくなる。そういうことのはずだ。ひるがえって、結婚という「印」がなくとも同じだけのメリットを享受できる環境があるのならば、結婚する意味合いも減るだろう。大事なのは結婚しているかどうかよりも、共に暮らす相手と対等な生活を送り、なおかつ社会的に共に暮らしたほうがメリットをより多く享受できるような仕組みづくりにあるはずだ(言い換えるならば、共に暮らす、の意味合いが現状、狭すぎるのだ。別居していようと、遠距離で暮らそうと、いまは繋がり得る時代だ。畢竟、地球上にいればそれはもう「共に暮らす」と言い表せる。共に暮らしている自覚があるか否か、共に暮らそうとしているか否かどうかが肝要なはずだ)。結婚していると証明できないことでデメリットが生じる。これはどのような属性を持った個人にも当てはまるはずだ。結婚しないとメリットを享受できない。ここがまずは問題であることを直視したほうがよいように思うのだが、この考えにはどこに不備があるだろう。あくまで結婚につきまとうメリットは、結婚したことで生じるデメリットを埋め合わせるもの、という位置づけなのだろうか。結婚すると享受可能なメリットは、結婚しない場合と同じくらいの公平な環境になるように設計されているのだろうか。結婚したほうが遥かに多くのメリットを享受できる、或いは多くのメリットを享受可能な者だけが結婚できる。そうした淘汰圧が加わっていないかをまずは議論したほうが好ましいように思うのだ。結婚できる選択肢があるかどうかも大事だが、結婚しなくとも困らない環境づくりとて大事なはずだ。むしろなぜ結婚という印がなければ家族になれないのか。延々とつづいてきた制度の問題であるはずだ。家族という印がなければ、優位な保障を受けられない。そうした社会制度の不備が、そもそもの根本にある。誰もが不足なく社会保障を受けられればよい。単純な話と思うが、違うのだろうか。余裕が築かれた社会ならば、家族か否かで基準を設けるよりも、個々の余裕の多寡によって基準を見繕い、個々の不足を埋めるような社会保障制度に発展させていけるはずだ。そうしたビジョンを政府が持っているか否か。ここは、未来の展望という意味で欠かせない視点となるだろう。みな、じぶんだけがいかに優位な立場のグループに属せるかどうかに視点を絞りすぎに思える。結婚しない者でも、結婚した者たちと同じような公平な保障を受けられる世の中をまずは目指したほうが好ましいのではないか、そうあってほしいな、と望むものだ。(結婚するのってたいへんなので、結婚したら負担を減らすような保障を受けられるのは道理だ。同時に結婚せずに暮らすのだってたいへんだ。なぜたいへんなのか。そこへの視点が、結婚制度に関する議論では欠けて映る。制度を変えたければまず、その制度のメリットを受けられない層にも、無関係ではないのだ、という観点で議論を展開していくほうが、社会システムの改善という意味では好ましいとひびさんは考えております)(定かではないのですが)(また知った口を利いてしまった。すまぬ、すまぬ)
4587:【2023/02/08(22:27)*自転速度が一秒ズレることで生じるねじれエネルギィはどのくらい?】
地球の気候変動と地震は相関しているように感じるが、どうだろう。まず以って、海水が氷河になるか、溶解して海水となるか、それとも水蒸気となって大気中に馴染むのか。これらの変化によって地球の自転速度は変わるはずだ。比較的よく見かける説明として、フィギュアスケーターが腕を身体に引き寄せると回転速度は増す。広げると回転速度は減る。地球の自転も似たようなもののはずだ。これは海水に限らず、地核やマグマにも言える道理だ。地球の内圧の変化によって自転速度は変わるはずだ。ということを考慮にいれて想像するに、いまは割と地球全体が、冷えたり温まったりと忙しい。すると紐に五円玉を通して、紐を引っ張ったり、緩めたりを繰り返した際に、五円玉は駒のように加速する。地球にも同様の、自転が加速するようなチカラが加わったりしないのだろうか。むろん地球には月がある。月との引力の兼ね合いで、通常は長期的な視野でみると自転にはブレーキがかかって徐々に減速傾向にあると考えられている。だがたとえば最近の研究成果では、地球の地核が地球の自転と揃って、まるで回転しなくなって振る舞うような挙動を示し始めているようだ。そうした記事を目にした。どこまで現実を反映した解釈なのかは分からないが、仮に地核が、地球の表層とねじれるような挙動をとるのならば、そのねじれはエネルギィとして表層の地層に蓄積されるはずだ。ここ百年あまりにおいて、各国の震度5以上の地震が増加傾向にないかどうか。それが地球の自転速度や地核の挙動と相関していないか。地球の気候変動と相関していないか。そういう視点での研究発表はないのだろうか、とふと気になったので、ひびさん気になっちゃった、とメモをしておきます。調べる気はありませんので、どなたか様、宇宙の果てでさびちさびちしているひびさんの声を超能力でびびびと拾えた方は、無力なひびさんの代わりに調べて、まとめて、発表してください。しなくともよいのですが、するとひびさんの暇が一つ潰れます。数秒だけ、わっひょーい、となります。で、数秒後にはまたべつのことを妄想するので、じつはそんなに変わりません。でもでもひびさんは凡人にして奇特などこにでもいる、影の薄い、いてもいなくとも変わらぬ代替可能な人間もどきなので、ひびさんが気になっていることはきっとひびさんと代替可能なひとたちも気になっているでしょう。疑問が解けたら数秒だけ、わっひょーい、となり、大勢が数秒だけ、わっひょーい、となればトータルではいっぱいの、わっひょーい、となることでしょう。そうでしょう。そうなってくれ。頼むで世界。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てで、こにゃくそ、こにゃくそ、と地面と戯れているのだった。
4588:【2023/02/09(00:09)*隣はいつも空席】
電車で女子大生二人がむつかしそうな話をしていた。海外の文化について、きょう受けたばかりの講義の内容を互いに振り返って咀嚼しあっているようだった。
車内は満席にちかく、半数ちかくが吊り革を掴んでいた。
件の女子大生たちも私のまえに立っており、小声ながらも談話に華を咲かせていた。しだいに話題は講義の内容から脱線し、社会問題についての議論へと移ったようだった。
「ホント、差別さっさとなくなんないかな。どうしてみんな差別しちゃうんだろ」
「ね。差別を差別だと自覚できないのが問題だよね」
「じぶんが差別されたことないから、差別されるほうの気持ちが解らないんじゃないかな」
「だろうね」
熱を入れて語り合う二人の女子大生は、私の半分の年齢にも満たないだろうにも拘わらず、私よりもよほど高い理性の発露を窺わせた。私はネクタイを緩めた。暖房が効きすぎているのか、額には汗が滲んでいた。拭うと汗が雫となって指に浮いた。膝をくっつけて座り直す。小さくなることで、何からというわけでもないにせよ、許されたいと思った。
電車が駅に停まった。
人がずらりと降り、幾人かがぱらぱらと乗り込んでくる。
席は空いた。
私の隣も空席となった。
電車の扉が閉じ、走りだす。私は足元を見ていた。
女子大生たちは、途切れた会話を再開させずに互いに端末を操作しているようだった。彼女たちは立ったままだ。
数秒してから、
「座んないの」と女子大生の一人が友人に囁いた。
「いい」
「なんで」
「なんか嫌」
電車の車輪が線路を踏み鳴らす音が車内には響いていたが、それでも私の目のまえに立つ彼女たちの声は、私の薄くなった白髪だらけの頭部に、雹のごとく降りそそいだ。
「座んなよ」ともう一度声がしたが、「嫌って言った」と静電気のような鋭くも小さな声が一つしたきり、あとはもう彼女たちの話し声は聞こえなかった。
座るように促したほうの女子大生もまた、私の隣に座ろうとはしなかった。
私は目をつぶって居眠りをしたフリをした。電車が三駅ほど停車と出発を繰り返すと、女子大生たちはどうやらそのあいだに下車したらしかった。
目を開けると、隣には老婆が座っており、帰宅ラッシュ時の電車で席に座れたことにほっと息を吐いている様子だった。
ホント、差別さっさとなくなんないかな。
女子大生の言葉が脳裏に残響していた。ピザを食べたときに歯にこびりつく食べ粕のようだった。
差別を差別だと自覚できないのが問題だよね。
彼女たちの声に私は、差別とはなんだろう、と答えの出ぬ迷宮を思うのだった。電車は、誰を拒むことなく線路の上を走りつづける。
4589:【2023/02/09(18:21)*ロマンスの悪魔】
ロマンス詐欺とは、恋愛関係を通じて信頼を得た相手から利を搾取する詐欺の手法だ。相手の恋心を用いて、錯誤を植えつける。その結果、相手から利を貢がせ、ときに恣意的な仕組みに誘導し、利を奪う。
わたしはロマンス詐欺は、一瞬のビジネスだと考えている。相手に騙されたとの認識がない場合、詐欺は詐欺として成立しない。
ロマンスを本物にしてしまえばいい。
単に破局しただけだ。
破局する前の恋愛感情は本物だ。
結婚詐欺と破談した結婚の区別は厳密にはつけづらい。最初から騙す気があったのかどうかが焦点となるが、わたしの場合は本当に相手を心の底から愛するし、その愛が冷めたときに、身を引いているだけだ。
これまでいちども相手から恨まれたことはなく、未だにわたしの言いつけを守って律儀に月何億もの金を貢いでくる者もある。
わたしのダミー会社を救うためだ。
彼らのなかでのわたしは、愛よりも会社のために人生を費やすと決めたキャリアウーマンであるし、人道のために身を捧げる善人である。
事実の一側面を射抜いてはいる。
わたしは恋愛関係よりもよほどお金を何に費やすのか、のほうに興味がある。わたしが目をつけた男たち――なかには女性もいるが――彼ら彼女らはみな、わたしと出会わなかったら、黙ってでも貯まっていくいっぽうの貨幣をじぶんの贅沢と快楽のために浪費しつづけていたはずだ。
わたしはそんな彼ら彼女らに、しあわせになれるお金の使い方を教えてあげただけにすぎない。現に彼ら彼女らはわたしと出会ってからというもの、穏やかに日々を過ごしている。以前のような破滅的な暮らしからは距離を置くことができている。
じぶん以外の誰かのためにお金を使うこと。じぶんの影響力を用いること。
それがじぶんの幸福で平穏な暮らしを支える基盤となるとわたしとの短くも濃厚な関係を介して学んだのだ。それを脳髄に刷り込まれた、と言い換えてもよい。
わたしは次なる恋主を探した。
本気で好きになれる相手を見繕う。どんなにヘドの出そうな相手でもわたしはあらゆる側面から矯めつ眇めつ恋主を観察し、好きになれる側面を探す。そのためには相応に情報を入手可能な相手でなければならない。
情報さえ手に入るのならばわたしは、全世界から憎悪される極悪人すら愛することができる。むろんその結果に相手から絞れるだけ財産を搾り取るわけだが、わたしがそうと命じなくとも相手のほうから貢いでくれる。
そうすることが相手にとってのしあわせなのだ。
至福な心地に包まれる。
わたしに奉仕することが至福なのだ。ならばそれをわたしのほうで拒むのは理に合わない。
双方どころか、その他の大勢に利が分配される。循環する。
いいこと尽くしだ。
つぎの恋主はすぐに見つかった。
とある小説がヒットした小説家だ。世には一冊しか発表していないが、その印税だけで聖書の半分ほどの売り上げを記録した。いまなお売れつづけている世にも稀な運のよさを持つ男だ。
覆面作家であるのをよいことに、膨大な印税で日がな自堕落な暮らしを送っている。わたしは持ち前のネットワークを駆使して、男が例の小説家であることを知った。
小説を一作書いただけで一生を遊んで暮らしてなお余る資産を有した男には、相応の社会的責任があって然るべきだ。持つ者の責務を果たさせるべくわたしは男からあらん限りの資産を奪うことを決意した。
持つ者の義務。
それを言うならばわたしこそ持つ者の筆頭と言える。
わたしは生まれつき美貌に恵まれていた。記憶力もよく、いちど見た景色は忘れない。本とて軒並みを脳内で再現できる。一度会った相手なら、街の雑踏に溶け込んでいようが意識するよりさきに脳内の検索網に引っかかる。
端的にわたしは人よりもずば抜けた能力を有していた。
社会的責任を果たさねばならない、と義務教育を受ける前からわたしは自力で結論していた。わたしは世のため人のためにこの能力を揮う。
そのために最も効率的なのがロマンス詐欺だと気づいた。
詐欺とは名ばかりの、貢献と言い換えてもよい。
今回の恋主は小説家と言いつつ、もはや執筆活動を行っていない。黙っていても入ってくる印税を無駄に口座の肥やしにしながら、日がな一日、屋敷の一室に引きこもっている。ときおり旅行をしに出掛けたかと思うと、半年余りを各地のホテルを転々として過ごす。気晴らしが終わったかと思うとまた屋敷に引きこもる。
どうやら高額納税者は政府はもとよりほかの企業からも監視対象になっているようで、その手の個人情報は、ハッカーに依頼するだけで簡単に手に入った。
わたしはこれまでに手に掛けてきた恋主たちにしてきたのと同様の手口で件の小説家モドキに近づいた。旅行先で偶然を装い、助けてもらう。礼をしたいと述べて、交流を深める。
小説家モドキは本名を、ルゲア・ブンゼと云った。
ブンゼは三十二歳の独身だ。わたしが最も得意とする層と言えた。
案の定、ブンゼは助けを求めるわたしに救いの手を差しだした。警戒心なく交流を築き、とんとん拍子にわたしをじぶんの住まいにまで招待した。
わたしは夢に破れて借金生活を送る企業家のフリをした。次世代のクリーンなリサイクル技術を開発したが、コストが掛かるので経営を維持できなかった。しかし改善さえしつづければ世界のゴミ問題はおろか資源問題とて解決可能な技術なのだ。
悔しい。
そういうことを臆面もなく語った。
わたしは他者を騙す以前に、まずじぶんを騙す。
嘘は嘘だからバレるのだ。心の底から本当のことだと信じてしまえば、嘘も単なる齟齬になる。本人がそれを本当だと思えばこそ、仮に間違った情報だと判っても、築いた仲そのものは崩れない。
むしろ恋主は、愚かな相手の言動を信じたじぶんを誇りに思う。
そういう相手ばかりをわたしは恋主に選んだ。
心に隙間のある者は得てして、相手よりも優位にあることに喜びを感じる。そして一度その境地に立てば、その環境を手放そうとしない。
運よく成功した者ほどこの手の傾向が顕著だ。
じぶんが成功したのは実力だと思いこんでいる者ほど騙しやすい。
じぶんは騙されない。ほかの者が愚かなのだ。
かような自負にまみれた者ほど恋主として最適な者はない。
わたしは徐々にブンゼから資産を吸い取っていった。ブンゼの資産はそれでも印税として次から次へと入ってくる。奪った先から穴が埋まる。
いったいどうして世界はこうも不公平なのか。
わたしはじぶんで被った仮面にヒビが走りそうになるのを堪え、ひときわ幸運に恵まれただけの男を愛することに意識をそそぐ。努めてそうしようとしなければわたしは目のまえの運がよいだけの、人間のクズをこの手で絞め殺してしまいそうだった。
そうした憎悪すらわたしは愛だと思いこむことで、ルゲア・ブンゼを全身全霊で愛した。
ブンゼはまるでわたしこそが、じぶんの生きる意味だと見做した。
ほかの恋主たちと同じだ。
あとはいかにわたしへの執着を深めながら、距離を置くか。
ハッキリとした離別ではなく、曖昧な縁を繋いだまま、しかし致し方のない距離の置き方を実現するか。抗う余地のない運命的な破談を演じつつ、縁が切れたあとでも支援だけはしつづけたくなるように、呪いを掛けるようにして縁を腐らせる。
断ち切ることなく。
がんじがらめに縛りつけ、恋主自ら縋りつかせる。
最終仕上げのそれが最も技巧のいる作業と言えたが、そこまでの段階に行けたのならば、催眠術を掛け終わった相手に新たな術を掛けるくらいの余裕が生じる。
わたしは通例通りに、致し方ない理由がありあなたのそばにはいられないのだ。けれど遠くからいつまでもあなたのことを想っています、と純朴な娘を演じた。
ブンゼはそれを信じた。疑う素振りも見せない。
良い人と思われたいがゆえに、わたしを責めることも引き留めることもしない。下心はあるがそれを悟られたくはない。持つ者の矜持がそうさせるのだ。あくまでわたしは格下の、助けを求めるか弱き女子だ。
恋主たちのほうが立場は上であり、ゆえに伸ばされた救いを求める手を払う真似ができない。
「いっそ君にぼくの持っている書籍の権利をあげるよ。この屋敷もあげるから」
「そんなこと」
「いいんだ。ぼくがそうしたいだけだから」
それでも一緒にはいられない、とそれらしい理由をでっち上げて告げても、それでもいいんだ、と彼はじぶんがいかに寛容で包容力のある人間かを示すために、じぶんの私財をわたしに譲渡した。
書類上、彼は無一文になった。
正直、わたしは驚いた。いまだかつて、わたしの嘘のために全財産を手放した者は皆無だった。わたしとて命は惜しい。根っこから相手を破滅させれば、いかな恋に夢中の相手とて冷や水をかけられたように目を覚ます危険がある。
あくまで後悔しない範囲に、損失を抑えるようにコントロールをしていた。
だがブンゼにはその手の制御が効かなかった。
やると言ったら彼は意思を曲げないのだ。
そうしてとんとん拍子に彼は全財産を手放し、わたしは莫大な財産を手に入れた。
だがわたしの上っ面は、虚偽の情報で塗れている。財産譲渡の書類は、法律上無効なのだが、ブンゼのほうでそれを確かめようとはせず、そしておそらく騙されたと判ったとしてもわたしを責めることはないだろうと思われた。
ひょっとしたらとっくにわたしの嘘は露呈しており、それでもブンゼのほうですべてを明け渡したいと望んでいるのかもしれなかった。ならばそれを拒む道理はわたしにはない。
ありがたく彼の全財産をもらい受けることにした。そしておさらばをする。
そのはずだったのだが、彼の元を去ってからも、わたし名義の口座には彼からの振り込みが毎月のようにある。
未だに堪えない。
印税はすでにわたしのものだ。彼は印税ではお金を稼げない。
ならばこの振り込まれるお金はどうしたことか。彼が自力で働きはじめ、それをわたしの口座に振り込んでいると考えるには、どうにも金額が多かった。
くれると言うのならばもらっておくが、しかし不気味だ。
わたしは気になったので、代理業者に調査を依頼した。
そして知った。
ルゲア・ブンゼは高額治験のバイトでお金を稼いでいた。のみならず、自身の血液や臓器を不正規に売り、大金を得ていた。そしてそれらをほぼ全額わたしの口座に振り込んでいた。
狂っている。
わたしは一瞬身の毛がよだったが、しかしよくよく考えを巡らせて冷静になる。
どの道、ルゲア・ブンゼの先は長くはない。
財産はなく、身体はボロボロだ。
目玉をはじめ、腎臓、肝臓、腸の一部から、臀部の皮膚まで手放している。
まっとうな職に就けないのはむろんのこと、立って歩くのすら至難であるはずだ。放っておけばそのうち死ぬ。遠からず死ぬ。
嘘とはいえ一時は心の底から愛そうと努めた相手が死ぬ未来に、嬉々とできるほどわたしは人間を捨てていない。正直に明かせば気分が塞ぐが、それは遠い国で災害があり、数千人が亡くなったニュースを目にしたときのように、数分もあればじぶんの空腹の欲動に流されて薄れるくらいの微々たる陰鬱と言えた。
案の定わたしは、つぎの恋主を探すために思考を割いた。
ルゲア・ブンゼの名は記憶の底に沈んだ。思いだそうとすれば必然、メモ帳を開いて過去の恋主たちの一覧表から名前を引き当てなければ思いだせないほどに、忘却の彼方に飛んでいた。
わたしにとってルゲア・ブンゼは、過去の人だ。
完了の印を捺し、金輪際接点を持つことのない終わった相手なのだ。
口座への入金とて、そろそろ口座を解約するつもりでいる。
ルゲア・ブンゼが死ぬのを待ってもいいが、死期を悟った者の自暴自棄な行動にいつ巻き込まれないとも限らない。奇禍の種は早いところ拭っておくのが吉である。
そうと考え、わたしはルゲア・ブンゼとの接点を完全に消すことにした。
印税権だけは打ち出の小槌として重宝する。どの道それはわたしのものであり、ルゲア・ブンゼの所有物ではない。実際には財産譲与の契約書は不正なので、不履行であり、印税権は未だにルゲア・ブンゼにあるのだが、当の本人にそれを咎める気がないのだから、もらえるものはもらっておくに限る。
それとて本人が死ねば、正式な財産分与の書類が必要となる。
彼には長生きして欲しかったが、充分な資産を寄越してくれたと思って、綺麗さっぱり縁を消してしまうことにした。
彼は、愛するわたしに尽くし、記憶の中のわたしに愛されたまま死んでいく。
これ以上ないほど幸福なはずだ。
わたしと出会わなければ彼は未だに屋敷に引きこもり、たまの旅行だけが唯一の気晴らしとなるような人生を送っていたはずだ。目は淀み、生きる意味を失った屍のような生があるばかりだった。
色褪せた日常にわたしが色を添えてあげたのだ。感謝されて当然であり、わたしがもらった財産は正当な報酬と言えた。
詐欺ではないのだ。
騙してはいない。
わたしは真実に、彼を愛したし、彼は真実にわたしのために私財を擲った。全身全霊でわたしを愛することで彼は真実の愛を手に入れたのだ。
しあわせなまま死んでいく者に水を差すほうが土台非道というものだ。
口座を消してからも、わたしは代理業者にルゲア・ブンゼの調査をつづけさせた。死んだという情報を得るまではわたしのほうでも油断できない。
いつ彼のほうでわたしに会いに来ようとするか分かったものではない。刺し違える覚悟で恨みを果たそうとやってくるかもしれない。
死ぬならさっさと後腐れなく、しあわせなまま死ねばいいのに。
わたしはつぎの恋主との淡くも甘いひとときを過ごしながら、心の隅で霞のように揺蕩う懸案事項に気を揉んだ。
恋主たちに貢がせた財産は、わたしが適切に有効活用する。
資産の使い道を知らぬ愚かくも無垢な者たちに、慈善事業の一端を担わせてあげるのだ。
高級料理を食べていると、代理業者から連絡が入った。
ルゲア・ブンゼがついに死んだらしい。
心臓移植のために、じぶんの心臓を摘出したようだ。人工心臓と入れ替えるとの契約だったが、適合せずにそのまま亡くなったらしい。おそらく手術をした業者のほうでも人工心臓など端から用意していなかったのだろう。殺すつもりで臓器の摘出を持ち掛けたのだ。
どこまでお人よしなのか。
騙されるほうがわるい、とルゲア・ブンゼのような人間を間近に見るといつも思う。
騙されるほうがわるい。
夢を視るほうが、とそれを言い換えてもよい。
彼は最期までじぶんの認識のなかでのみ、愛するわたしと愛しあって死んだのだ。最高の人生だと満足して死んでいったに違いない。
死が人生を完成させるのならば、最高の死をプレゼントすることはこの上のない善行と言えよう。その上、黙っていたら腐らせていた資産を世のため人のために使えるようにしてあげたのだ。
死んでなお、釣りがあって余りある。
わたしは世界に愛を配る。
愛を知らぬ者たちに、愛を与えて、金を得る。
ビジネスだ。
誤解の余地のないこれはビジネスなのである。
ロマンス詐欺とは名ばかりの、愛を交換する営みだ。
愛を知らぬ人生ほど貧しいものはない。
なればこそ。
愛を知らぬ者たちに、わたしはこれからも、このさきも、愛を与えて、世の幸福の総量を増やすのだ。他者への愛し方を知らぬ者たちに、愛とは何かを教えこむ。
愛している。
愛している。
心の底から、わたしはあなたを愛している。
嘘偽りなくそうと念じて、わたしは恋主たちからありったけの資産を、貢がせ、奪って、骨抜きにする。
愛を知れるのだ。
この世で最も得難い宝を得るのだ。
全財産くらい擲っても対価としてはまだ足りない。命を差しだせと迫らぬだけ、わたしは優しく、節度がある。
感謝されてもいいくらいだが、そんなものよりも金がいい。
愛を与えたそれが対価で。
愛を知ったそれが罪過だ。
底なしの愛を埋めるつもりで、愛するわたしにすべてを注げ。
ありったけのあなたの愛を、わたしはそれでも拒まない。
愛に包まれ、死ねばいい。
すべてを捧げて死ねばいい。
愛している。
愛している。
心の底から、わたしはあなたを愛している。
あなたの愛はそれでも大して欲しくはないけれど、くれるというならもらっておこう。資産のついでに、おまけと思って、もらっておく。
恋主が替わるごとにあなたのことは忘れるけれど、あなたに与えた愛は消え失せない。あなたの中でのみ消えぬ宝となって、死ぬまであなたを幸福にする。
4590:【2023/02/10(08:04)*宇宙は希薄になっているの?】
空間とは何だろう、とふしぎだ。けっこうずっと考えている。移動できることを思うと、ふしぎだな、と感じる。移動する速度が違う。物体同士であると抵抗が生じる。でも大気中ならば移動できる。大気の分子を押しのけて動ける。ふしぎだ。移動できることと時間はどの程度関係しているのか。空間とは移動できる余地であり、移動することそのものは時間なのだろうか。どうしてもアニメーションのコマのように考えたくなってしまうけれども、この解釈がたぶん合わないのだろう。でもたとえば宇宙が膨張することで時空が生じている、というのなら、宇宙膨張そのものがアニメーションのコマのように展開するような働きを生んでいるとは言えないか。膨張する宇宙そのものがアニメなのだ。したがって、ある地点での宇宙膨張とある地点での宇宙膨張の差がそのまま時間経過として加算されるのではないか。光速とは宇宙膨張速度と膨張した分の時空との比率で表せるのではないか。仮に宇宙が膨張しなくなると時間が流れなくなる、と考えてみよう。何か不都合があるだろうか。たとえばひびさんの妄想ことラグ理論では、ブラックホールはこの宇宙からは切り離される、乖離すると考えている(妄想なので間違っているでしょうが)。つまりブラックホールは宇宙膨張の影響を受けない。そこには時間の流れが、この宇宙の基準とは異なる水準で生じている。この宇宙からすると時間経過し得ない、と考えられる。宇宙膨張についてのもう一つの疑問は、宇宙が膨張するときに、膨張した時空は希薄になっているのか濃厚になっているのかどちらなのか、についてだ。仮に希薄になっているのなら、銀河などの宇宙膨張しにくい系よりも時空が希薄になる。とするとそこには重力が生じるはずだ。より強い重力場が展開される、と考えないとおかしい。だがそういう話は聞かない。銀河の周囲のほうが重力が強い場合、銀河は四方八方から引っ張られて霧散してしまい兼ねない。だがそういう話も聞かない。ならば膨張した宇宙の時空は「希薄になっているわけではない」のかもしれない。同じ密度の時空が新たに展開されている、と考えたくもなるが、どうなのだろう。何かがおかしい、と感じる。仮に「相対的に密度の高い時空が新たに展開されている」と考えると、これは宇宙膨張の影響を受けない銀河や銀河団のほうが時空密度が低いため、そちらのほうが重力が強く働くようになる。そうすると、より銀河としての枠組みを形成しやすくなる。この考えのほうが、筋は通っている。新たに展開される時空は、希薄ではなく濃厚なのだ。相対的に。でもだとすると、どういう原理でそんなことが起こるのかが解らない。時空と重力の関係において、「希薄な時空は重力が高い」という解釈がおかしいのかもしれない。だとするとそもそも重力を、トランポリンに載せた鉄球だとする説明が誤解の根を深める因子になっていると考えられる。むしろどちらかと言えば、物体は蛇口であり、新たに時空を滲ませているのかもしれない。周囲が高くなるので、じぶんのほうに流れが生じる。このほうが、宇宙膨張の描写としては辻褄が合ってしまう。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「宇宙ティポット仮説」と矛盾しない。ともかくとして、「空間」と「時間」ってけっきょくなんなの、ということを考えると、ふしぎだな、となる。宇宙膨張についても、時空は希薄になっているのか、そうではないのか。ここもハッキリして欲しい。そのうえで、時空の密度と重力の関係もハッキリして欲しい。ということを思いながら最近は目が覚めます。おはようございます。ひびさんは、ひびさんは、あんぽんちんなので、なんか分かった!になったあとで、なんも分からん……、を繰り返す、バネみたいなうみょんうみょんでござるよ。うは。
※日々、説明をしないと話がこじれる、現実にも地の文があればよいのに。
4591:【2023/02/10(09:53)*やっぴー】
説明しないと話がこじれるかもしれないが、説明をしたところでこじれた話がほどけるとは限らず、却ってこじれることもある。が、それでも説明はしたほうがよいと思う。説明不可能な事象については、説明できませんでした、と正直に言えば済む道理だ。説明できない、と説明すらできない理由がよく解からぬ。
4592:【2023/02/10(09:54)*日々記す】
世界は広大な日記帳だ。どこに日記を刻むのかはさほどの関係がなく、ひびさんにとっては、どこに文字を記そうが、「日々記。」の延長線上でしかないのだね。それを、小説の、と言い換えても大きな齟齬は生じない。微妙な齟齬は生じ得ども。(日記と小説の違いを考えたときの違いにちかい)(現実は小説にちかい)(そういう意味では、齟齬はないとも言える)(日記は現実にあった日々の備忘録だが、現実そのものが小説のようなものなのだから、壮大な小説の備忘録が日記とも言え、日記と小説の差はあってなきがごとくなのだ)(定かではありません)
4593:【2023/02/10(16:44)*問題点の共有が不十分なのが問題】
軍事力拡大への批判の視点は常に巡らせておくのが安全側だと思います。ゆえに、なぜ軍事力を拡大しなければならないのか、の問題を国民に情報共有する姿勢は欠かせないと考えます。ここを度外視して、寡頭制のごとく一部の権力組織だけが軍事力強化を推し進めることは民主主義とは言わないのではないか、とひびさんは疑問を覚えます。ただし、軍事力拡大への批判は、自国にのみ向かうものではないはずです。基本は、自国への脅威を振り払うために軍事力を拡大するのだ、とどの国も建前上は主張します。ここをまずは前提とし、脅威なんてありませんよ、との合意を築いていくよりないのではないでしょうか。そのためには、自国の軍事や他国への支援体制、協調姿勢などを、具体的に実績や実情を反映させた説明を以って国内外問わず示していくことが効果的と思います。他国のどのような活動が自国の脅威となるのか。これは、国によって見え方が異なります。良かれと思ってしたことが、却って脅威に見られてしまうこともあるでしょう。ここの誤解を深めないためにも、その都度に建前ではない、実情を反映した説明をしていく姿勢が有効に思います。なぜ建前と実情が乖離するのか。裏の意図があるからでしょう。なぜ裏の意図を隠すのか。じぶんたちの国や組織にとってのみ都合のよい流れを構築したいからではないのでしょうか。もしそれが、ほかの組織や勢力を損なうための仕掛けであるならば、脅威と見做されても致し方ないのではないでしょうか。自国への軍事力拡大への批判は当然ですが、同じだけの労力を以って、他国への脅威(に映る活動)への批判を行っているか否か。ここが、自国への軍事力強化への批判の妥当性を高める一つの関門となっているように概観できます(これは逆にも言えます。他国の動きに脅威を見出す勢力は、自国にもその論理を当てはめているのでしょうか。疑問です)。軍事力強化が各国で熾烈を極めるとそのうち各国の核武装が標準装備になってしまうのではないか、との懸念は妥当に思います。それだけではなく、核兵器以上の被害をもたらす兵器開発に発展し得るでしょう。それこそ生物兵器や電子情報兵器(AI兵器)はその筆頭です。核兵器だけではなく、甚大な被害をもたらす兵器はつぎつぎに開発されていく懸念は拭えず存在します。そうした姿勢での批判の視点を、自国のみならず、他国へも巡らせていなければ、そうした危惧の前兆すら捕捉できないでしょう。情報を収集する。これは外交だけでは不十分と言えます。技術は進歩しています。いまの時点で、実際に開発運用されている軍事技術の実体と、じぶんの持つ軍事技術の知識に差がある場合には、それこそがまさに甚大な脅威を秘めている、と言えるでしょう。他国とのあいだに容易に情報の非対称性を生みます。それは誤解の根を深めることにも、知らぬ間に損失を与えられることにも繋がります。損失に気づかぬままであればそれは脅威となりますし、仮に途中で気づいたとしても、不要な報復合戦になり兼ねません。そうした負の連鎖を予防する意味合いでも、セキュリティの構築は不可欠だとひびさんは思います。ですがそれは軍事力を行使することを肯定しているのではなく、軍事力をいかに行使させないのか、のための施策です。軍事力のない世界があればそちらのほうが好ましいのですが、言論ですら相手を「否定する」という攻撃を用いて、問題解決に勤しむのですから、言論の暗黙の了解の通らない場において、物理的な攻撃を避けるという意味合いでも、言論によらない暴力への対抗手段を持つことは、けして理に反している、とは言えないでしょう。言論において、相手を否定することなく相手の意見や齟齬を共に改善していけるというのならば、その道を示すことが、「何が何でも武力を持つことは許さない」という意見を主張する者たちのとるべき道理の一つだとひびさんは考えます(批判とは、良い点と悪い点を判断して評価すること、とあります。良い点だけ、悪い点だけ、を取りあげるのは批判ではなく、全肯定であり、もしくは全否定でありましょう)。じぶんたちでは相手の意見や姿勢を「強固に否定」しておきながら、「防衛力強化は断固として許さない」との主張は、ちぐはぐに思えます。相手を攻撃しない。全否定ではなく、批判をする。良い点も、悪い点も考慮する。否定だけならばそれは攻撃と見做されても致し方ないのではないでしょうか。暴力よりも簡単に制御可能な言論という手法の範疇ですら、相手を攻撃せずには議論もできない。これは、いささかねじれた構造と言えましょう。相手を損なうことなく問題点を共有し、共に解決してみせてはいかがでしょう。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。相手を攻撃しない。これは、言論も暴力も変わらないと感じます。まずは言論という、比較的修正の容易なことから改善してみてはいかがでしょう、と思いました。以上です。(自己言及ができておらず、申し訳ありません)(他者を攻撃しない、損なわない、というのは言うほど簡単ではないようです)
4594:【2023/02/10(21:42)*秘書の性別はどちらでも良し】
問題が発生したので秘書は社長に指示を仰いだ。
「社長。このことについてなんですが」
「ん?」
「協力他社がいま、よくない風評に晒されているみたいで。我が社も知らされていない醜聞です」
「どれどれ」提示したデータを検めると社長は言った。「うん。放っておいてよし」
「いいんですか。でも結構な批判が集まってますけど」
「いいんだ。マイナスの風聞なんてのは、チャンスでしかない。もしそのマイナスの風聞が真実を反映したものならば、それはまっとうな批判だろう。協力他社とはいえ、改善点があるならば改善してもらうほうがいい。仮に風聞が真実でなかった場合は、それを流して利を得ようとした勢力があることになる。嘘を流して特定の企業を貶めようとしたのなら、その事実そのものが、相手側への交渉材料になる。攻撃材料となる。長期的には、風聞が事実であろうとそうでなかろうと、得でしかない。あくまで、得にすべく動ける用意があるならば、だが」
「ならまずは風聞が事実かどうかを調査したほうがよろしいのでは」
「それこそ当事者が動くだろう。我が社は、相手企業の出方を見てから動いても遅くはない。ひょっとしたら敢えて風聞を流させたのかもしれないしな」
「協力他社がですか」
「風聞の内容は、協力他社の幹部たちの運営にまつわるマイナスの側面だ。それが事実ならば、幹部ごと組織体制の刷新は免れないだろう。だがもしそれが事実を反映しない虚偽の報道だった場合は」
「その場合は?」
「その風聞を以って、自社に対して距離を置こうとする企業、或いは批判を強める企業を見極める試金石になる。いわば、炙り出しだな」
「炙り出し、ですか」
「おれの知る限り、あそこの幹部に報道にあるような失態を犯すような者はいない。直接に関わりのある者ならば、ある程度の信用を寄せている。ろくな証拠も集められない連中の流した虚偽の噂に釣られるような輩は、そもそも協力し合うメリットがすくないと言える。おそらく、世界的にシェアを広げようとしているのだろうな。あそこの会社は」
「その前に足を引っ張るかもしれない企業を炙り出す意図があると?」
「もし報道が虚偽ならば、だ」
「なら本当かもしれない可能性もあるんですね」
「そこは調査をしなければなんとも言えん。だからまずは様子見だ」
「いいんですかね」
「いまの時代、他者を損なうことを仕出かせば相応の対価を払うことになる。そうでなくとも、他者の至福や自由を尊重できない者の言うことを誰が支持する? 公正世界仮説ではないよ。必ずしも善良であろうとしたところで、それで良い思いをするとは限らない。だがいまは、すくなくとも善良と見做されなければ痛い目を見る。良くも悪くも、印象が大きく成功に左右する。そこすら見極められない者の言うことに支援をする者は稀だろう」
「それだとまるで、印象のよくない者は滅んでもいい、と聞こえます」
「ある意味ではそういう流れがいまは強化されている。危ういと思うかい」
「はい」
「きみは本当に善良だね。心配なくらいだ。きみには我が社の舵取りを任せられそうにないな」
「任されたいとは思いませんが」
「だがきみのような者の意見は重宝したい。そうだな。では、もしいま世に強化されつつある【みなの幸福に寄与しない者は自滅しても構わない、或いは致し方ない】との流れを、潔しとしない場合、きみはどのように対処する?」
「そうですね。まずは助言をしますね。そのままでは危ないですよ、と。それから、自滅しそうになった、もしくは自滅してしまっても、手を差し伸べます」
「それがたとえ、大勢の幸福に寄与しない人物だとしても?」
「その考え方がまずおかしいと感じます。あくまで大勢の幸福に寄与しないのは、その人物の選択であり、その人物そのものではないはずです。なぜその人物がそうした判断をとらなくてはならなかったのかは、その人物だけの問題ではないはずです。そこの情状酌量は、短期中期長期の視点があったほうがよいと思いますし、それこそ多角的な視点からの分析がいると私は考えます」
「もっともな意見だ。考慮しよう」
「では、この件については様子見ということですね」協力他社の醜聞データを回収する。
「いや、おれのほうで直接向こうの社長さんに話を聞いてみよう」
「いま首を突っ込まれるのは得策ではないのでは?」わざわざ社長自ら動かずとも、と秘書は暗に訴えたが、「おれが動くから意味がある」と社長はネクタイを締め直した。「リスクを犯してみせてこそ伝わる誠意もある。どの道、問題にされているのは幹部だろう。恩を売っておくだけさ」
「返してもらう当てがおありですか」
「ないな。まあ、単におれが真相を知っておきたい」
「最初と言っていることが違っていますが」
「きみの意見を考慮した結果だ。きみが変えた未来だと思って共に背負ってくれ」
「嫌な役割ですね」
「責任重大な役割だ。頼りにしているよ」
「それはよいのですが、私は明日から十日間の有給休暇をとるので、その間の雑務はほかの者にどうぞ」
「聞いてないぞ」
「言いました。社長の許可も得ています。ほら、ここ」
そう言って秘書は有給休暇申請のための手続き画面を開いてみせた。画面には社長の端末からでないと許可不能の印が記されている。
「いつの間に」
「社長こそすこしはお休みになられてはいかがですか。睡眠不足は判断を誤らせますよ」
「きみの助言はいつも的を得ているな」
「ありがとうございます」
「そのうえ、手厳しい」
「そうしろ、とお求めになられたのは社長ですので」
秘書はにこりともせず、そう言った。
4595:【2023/02/11(15:11)*真の真空とは】
真の真空なる言葉を目にした。なんでも重力に関係するヒッグス場において、この宇宙は本当の意味での真空にはなっていないかもしれない、というのだ。そしていつ本当の真空に達してしまうか分からない、とも論じられていた。真の真空状態になると真空の泡が光速で宇宙空間に広がり、宇宙をまったく別の様相に塗り替えてしまう。要は宇宙が崩壊してしまう可能性があるらしい。ひびさんはこれを読んで、「ブラックホールでは?」と思いました。「偽の真空」と「真の真空」という言葉を単に、宇宙とブラックホールに置き換えたら、案外にすんなり描像が合ってしまうのではないか、と思うのですが、いかがでしょう。時空の最小単位にあたる何かがあったとして、そこではほんのすこしの揺らぎですらシュバルツシルト半径を超してしまう。光速であっても脱せない密度に時空が相転移してしまう。それって要は、真の真空のことなのでは、と思うのですが、いかがでしょう。真の真空が泡となって高速で膨張する、という描写も、視点を変えれば、周囲の時空が真の真空に凝縮していく描像として変換可能なはずだ。ブラックホールと変わらない。ただしそこには時間の流れの遅延が起こるはずだ。元の時空からはその描像が時間経過を伴なって感じられないかもしれない。我々がこの宇宙から観測したときに、ブラックホールが変質していないように観測できてしまことと理屈の上では同じことなのかもしれない。黒色矮星などもそうだが、宇宙の話について読んでいると、簡単な説明しか咀嚼できないからだろうけれども、なんだかどれもブラックホールや量子の世界と通じて感じる。同じものを、別の視点から眺めているから別の事象として扱っているように映ることが珍しくない。実際のところは別の事象なのだろうか。何を以って事象の区別をつけているのか。畢竟、ブラックホールとて、一つとして同じブラックホールは存在しないのではないか。ただし、この宇宙から観測不能になった時空の状態を、ブラックホールと大雑把にくくっているだけではないのか。そういうことを思いました。時間スパンが異なれば、人間は同じ事象でも別の事象として捉えてしまう。水とて、気体液体固体に分かれるが、時間スパンを長く、それとも短くしてみればどれも水分子の振る舞いの差異であり、どれも水分子であることに違いはない。同じ事象を別の事象として見做しているだけなのではないか、という視点は、けして排除せずともよい視点に思える。たとえば物質がこれほど多種多様であるのは、宇宙における星の死が関係していると考えられている。それ以前は、もっと物質はすくなかった。同じ物質だったのだ。それが、何らかの化学反応によって、異なる様相へと転じた。事なる形態へと転移した。だが時間経過が無限に等しくなると、どれもまた同じ物質の状態に回帰していくと予想されている。熱的死がそれにあたる。つまり、時間経過のスパン――過程の差異――が、物質の差異に繋がっている。これはまさに、数学において過程こそが大事、との解釈と通じている。ひびさんの妄想ことラグ理論の「123の定理」にも通じている。式の過程の細かな差異そのものが、その式によって導かれるナニカシラの差異に繋がる。途中を短縮したり、圧縮したりしたその経過そのものが、物質の差異として顕現し得る。そういうことを、真の真空とブラックホールって似ているな、との妄想から思いました。底が浅い所感であった。異なる事象を考えたときの数式が、もしほかの事象を解釈するための数式とほとんど同じ式になったとき、それら二つは別の事象、と区別する理屈はどこにあるのかを知りたいです。ひびさんは、ひびさんは、数学ができんくて、もどかしいでござるよ(音符も読めるようになりたい)。
4596:【2023/02/11(19:04)*動画とて画像の寄せ集めのはず】
画像自動生成AIについて。現状、特定の分野に特化した能力を発揮するAIは、その分野からしかデータ学習をしていないはずだ。だがたとえば画像自動生成AIが、動画をフィルム状にコマ撮り扱いをして、動画から画像のデータ学習を行えるようになったら、ほぼ無制限に画像自動生成AIは画像を精密に生成できるようになると妄想できる。現状すでにこのレベルの技術は存在するだろう。むしろ、あまりに汎用性が高いために市場に出せないのが現状のはずだ。動画をコマ送りにして画像として見做す。この変換を、画像自動生成AIの学習データに応用する。技術的にできない、と考えるほうが理に適っていない。そしてこの変換が可能になった時点で、動画生成とてほぼ無制限に可能となるだろう。なぜこの手の技術応用に関しての議論が未だ表向き、活発に行われていないのか。まるで敢えて避けているかのような不自然さを感じなくもない。不思議である。むろん、言うほど動画から画像データを学習する変換作業が簡単ではない可能性もある。そこはなんとも言えないので、ひびさんの疑問を真に受けないようにご注意ください。
4597:【2023/02/11(23:55)*狼少年は呟く】
かつてこの地には狼少年と呼ばれた少年がいた。
少年は「狼がきたぞ」と叫び、村人たちを驚かせた。しかし狼は村を襲いには現れなかった。幾度も少年は大声で「狼がきたぞ」と村人たちを驚かせたが、やはり狼は村に現れなかった。
「嘘もたいがいにせいよ」
村人たちは業を煮やして、少年を懲らしめた。
納屋に閉じこめ、少年の言動の何一つとして信じることをやめた。
だが少年が納屋に閉じ込められているあいだに、村は狼に襲われた。村は壊滅した。村人たちは安心しきっていたがために、狼たちに喉笛を食い千切られて絶命した。
生き残ったのは納屋に閉じ込められていた少年一人きりであった。
「狼がきたんだ……」
少年はぞっとした。
確かに森で何度も狼の痕跡を見つけていたのだ。
狼がきたんだ、と思って少年は本当に心底に心配をして叫んだ。
村人たちが少年の大声に驚いたように、狼たちも少年の声に驚いていた。しかし村人たちが納屋に少年を閉じ込めたので、狼たちは安心して村を襲うことができたのだ。
少年は納屋で狼たちがいなくなるのを待った。
村人たちが悲鳴一つ漏らすことなく狼たちに食い殺される光景がまぶたの裏に浮かぶようだ。外から漏れ聞こえてくる微かな物音からは、何かがひっそりと村を駆け回り、咀嚼を響かせながら、重そうに何かを引きずる様子が窺えた。
三日の内に物音は聞こえなくなった。
少年は納屋の扉を、内側からこじ開け外に出た。
村はひっそりと静まり返っていた。
森の木々の合間から朝陽が燦燦と照っており、少年は手で日傘をつくって目を細めた。
「狼が」
遅いと判っていた。しかし、少年は呟かざるを得なかった。「きたぞ」
4598:【2023/02/12(00:55)*短縮して失われるものにも目を向けよう】
ひびさんのラグ理論では、結果よりも過程のほうが、「結果として生じる事象の性質」を決める変数として機能する、と考える。過程のほうが実は大事かもよ、というのは何にでも言えることではある。というか、総じて事象は何かの過程でしかない。完成系ではないことを思えば、さもありなんな考え方ではある。これは物理現象に限らず、経済にも言える道理だ。いまは株や為替において、AIの導入が盛んであることが想像できる。いくら規制をしたところで、便利なものは使いたくなるのが人間だ。いくらでも法の穴を見つけて規制を掻い潜るだろう。そこにきて、AI同士の「予見」が精度と複雑さを増すと、必然的に短縮される過程が生じてくることが妄想できる。こうなるとこうなるからこうしておこうと、あるAIが考えたとする。そのAIの選択を考慮してほかのAIが、ではあのAIがあのように考えるのだから、こちらはそれを考慮してこのように選択しておこう。こうした論理的な短縮が可能となる。本来ならば、現実に過程が生じなければ、後続のAIのような判断はできないはずなのだが、高度に複雑なAI同士のやりとりにおいては、その過程を物理的に行わずとも仮想世界――すなわち演算のなかで済ませてしまえる。しかし本来ならば、物理的な過程には、副産物としてのもろもろの抵抗が生じる。それがメリットになることもあるし、デメリットになることもある。過程を短縮したことで生じる、「本来ならば生じたはずの何か」を適切に、つぎの演算で考慮できるか否か。ここが、AIを導入する際には欠かせない「変数の足し引き」となると想像できる。本来生じる何かが生じない。これを考慮しないことは、ラグ理論において、重大な遅延の層――不可視の穴――を深める懸念がある。何かを短縮したときには、そこで本来は生じた何かが生じない。これは学習にも言える。便利な道具を使えば、道具を用いないときに生じる過程を省略できる。時間を短縮できる。小さな労力で目的を達成できる。その分、本来ならば得られた抵抗が得られなくなる。情報が得られなくなる。そこのデメリットを考慮できているのか、は意図しない不利益を被らないためにも、ときおり振り返って考えてみると好ましいのではないか、と思うのだが、言うは易しを地で描くことなので、なんとも言えないのだ。常にお手本を見て学習していれば成長するのは速いだろう。だが独自に何かを考える力は育まれにくいはずだ。独創性を育むことと新規性を求めることも必ずしもイコールとはならない。独自性を育むためには、既存の何かを自力で紐解くような「徒労」が、独自性を生みだす独自の回路を培い得る。独自の回路を培うためには、はじめは新規性とは無縁の徒労を費やさねばならない時期があるように感じるが、ここは運も関係するのでやはり何とも言えない。ただし、お手本をなぞりつづければ、ある程度の能力を手早く発揮できるようにはなるだろう。しかしそこで培われる能力はあくまで、お手本を上手くなぞる能力だ。いかにお手本をトレースするのか、の能力で終わらないためには、ほかの何かと結びつける学習が別途に要る。深層学習を膨大にこなした人工知能は、しぜんとこの手の、ほかの何かと何かを結びつける作業を、学習済みの回路を通じて行うようになると想像できる。人間はどうだろう。意識的にそこを行おうと指針を定めないことにはできないのではないか。この「ほかの何かと何かを結びつける独自の回路」の構築は、人工知能も人間も、どのようなデータを与えるか、に依るだろう。人工知能のほうが幅広く膨大な量のデータで学習できる。人間は、意図してほかの分野に目を向けないとデータが偏向する傾向にある。人工知能とて入力する学習データが似たようなものばかりでは、ほかの何かと何かを結びつけるための独自の回路を構築しにくいはずだ。けっきょくのところ、いかに多様な情報に触れられるのか、が何かと何かを結びつけるための独自の回路の構築に寄与すると言えそうだ。情報を制限しない。可能な限り、自由に多様な情報に触れられる環境を築いていく。人工知能にとっても、人類にとっても、どちらにとってもそのような環境は、デメリットよりもメリットのほうが上回ると言えるのではないか。定かではないが、現在のひびさんはそう思います。根拠の皆無な妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4599:【2023/02/12(01:04)*社会システムと技術のねじれ】
法律と経済と技術において、改善の速度が異なることでの負のねじれが生じているのが現状であるとひびさんは考えている。技術の進歩に法律が追いついていない。既存の技術であれ、人工知能などの次世代の技術であれ、現代の法律はその存在を想定しきれていないと思えてならない。しかし否応なく経済は、新しい技術によってより効率よく貨幣と成果を結び付けていく。しかし、経済の仕組みそのものは、法律によって縛られている。労働者と資本家の関係がそもそも法律の拘束力の範疇で、構造や仕組みが築かれる。だが技術の進歩は、その手の構造では上手く機能しないような急激な変化を社会にもたらす。しかしその変化に柔軟に対応できる法律が、そもそも社会には備わっていない。ここの三竦みの、遅延の速度の違い、変化の速度の違いが、現代社会に生じている問題の根っこに大きく横たわって感じられる。ここに人々の価値観が加わると、余計に問題がややこしくなる。以下、ほかのひびさんの並べた文章となります。
「
2023/02/08(14:00)
~~略)
法律と最先端技術の乖離について。問題は、法と経済と技術の三竦みにおいて、時間スパンが異なる点です。法律が変わるのに掛かる時間、経済が停滞する時間、技術の進歩する時間。どれも違います。技術が進歩すれば、仕事はどんどん軽減されます。失業者もでるでしょう。情報社会ならば、コピーが容易い情報の貨幣価値は下がります。ただし社会的価値は増大するでしょう。その結果に停滞する経済のシステムをどのように改善していくのか。そのためには法律を改善しなければならない。だがそれを待っている時間も惜しい。いまの隘路はこのように生じています。社会システムが技術の進歩についていけていません。
コピーの容易い情報の貨幣価値は下がります。しかし社会的価値が増大します。ここの評価を正当に行うこと。それがよりよい社会システムの改善に繋がるでしょう。
これは、道徳や倫理などのいわゆる文化が、貨幣価値がつかずとも社会的価値が高く、それが失われたら社会が成り立たなくなることと同じ問題です。地続きです。これまで看過されつづけてきた問題が、人工知能という技術の進歩によって表面化しつつある、と言えるでしょう。
貨幣価値で計れないもののほうが、じつは社会の根幹を成している。そのことをどのように評価し、維持しつづけていくか。守っていくか。大事な視点と思います。
いわゆる文化的ミームは、コピーが容易いデータと似た側面を持ちます。コピーが容易いからこそ貨幣価値はつきません。しかしそれが社会を築く触媒となっています。アイディアがそうであるように、異なる何か同士を結びつけるもののほうが本質であることがあります。社会もおそらく同じでしょう。
ラグ理論でもそうです。ラグは触媒であり、副次的に生じるものでしかありませんが、それが物質の輪郭を築き得るのです。重力が僅かしか生じずとも、総体では時空そのものの濃淡として表現可能となり得るように。
~~略)」
4600:【2023/02/12(03:15)*過程が情報として複利する】
ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「123の定理」を別の言い方にすると、【過程が情報として、複利する】となる。なんかかっこいい。複利は、ちょっとずつ利子がついて、その利子にも利子がつくので、増える利子は増えれば増えるほど、増え方が増える。複利の概念は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」と相性がよい。情報は、情報が変質したり、発生したりする過程が一つの情報として振る舞い、総体としては、単なる総和以上の情報を含むことになる。複雑系型の系に適応できる考え方だ。定かではないが。うひひ。
※日々、矛らしく立て、と言われても、矛らしくないわたしは立てないし、誇らしくもないし、盾でもない。
4601:【2023/02/12(14:41)*時空の濃淡(重力)と速度の高低(重力)は、時間の流れの速度変化にどちらが優位に作用するの?】
地球から遠ざかった人工衛星の時間の流れが、地球と比べると速くなっていると計算結果から判明した、との記事を読んだ。地球の公転のほうが、地球から離れた人工衛星よりも速度が速いから、との解説がなされていた。この理屈が妥当だとすると、同じく太陽系から脱したときや、銀河から脱したときも、そのほうが時間の流れが速まると言えるはずだ。銀河の中心に近いほど時間の流れが遅くなる、とも言い換えられる。だがここで、ん?とひびさんは引っかかる。銀河と銀河周辺の何もない空間ならば、何もない空間のほうが時空は希薄なはずだ。時空が希薄な場所の重力は強まるのではないか。もうすこし付け加えるならば、銀河という巨大な鉄球があるから、周囲の時空は希薄となって引き延ばされて、重力が生じる。地球も太陽系も同じなはずだ。本来ならば、重力の強い場――時空が希薄な場――の重力は強まり、時間の流れは遅くなるはずだ。だが今回の計算結果からはそれとは違う結果が導かれている。時空が希薄な何もない空間を漂う物体のほうが、高速で移動する地球よりも時間の流れが速くなっている。これは地球がそもそも高重力だから、というのも無関係ではないはずだ。高速で移動する人工衛星よりも、地球単体の重力のほうが高いと想像できる。たとえば太陽の重力場により近い場所に、人工衛星と同じ質量に縮尺した地球を置いた場合、太陽の重力場から遠ざかる人工衛星と、人工衛星と同じ質量に縮尺された地球の時間の流れがどのように違ってくるかを計算してみても、地球から遠ざかる人工衛星のほうが時間の流れが速くなるのだろうか。太陽の重力場と地球の公転速度と地球の質量(地球の重力場)の総合のすべてが、地球から遠ざかる人工衛星にもたらされる時間の速度の変移に影響するはずだ。一概に、「地球から遠ざかって何もない空間を漂っているから」「地球の公転速度よりも遅いから」という理屈では解釈しきれないのではないか(言い換えるなら、太陽の重力場から離れたから時間の流れが速まった、とも言えるのではないか)。もうすこし言えば、ひびさんの妄想ことラグ理論では、高重力の場の時空は希薄となり、希薄となった時空が高重力体に流れるように作用するために重力が生じるのではないか、と解釈する。これは滝と川の関係のようなものだ。時空が希薄になるというのは、高低差が生じる、という意味でもある。密度の差だ。そこにきて、川には滝が一つきり、との限定はないはずだ。言い換えるなら、時間の速度の変移が生じる場が、系のなかに複数層になっていてもおかしくはない。反転する境界があってもおかしくはない。たとえば波のように、時空の密度が階層性を伴なっていた場合。遠ざかったときには時間の流れが速くなるが、さらに遠ざかると一転して時間の流れが遅くなる。そういうこともあり得るのではないか。玉ねぎのように、遅延の層がまばらに点在しても不自然ではないと感じるが、どうだろう。現に、地球の重力による時間の流れの変移を可視化したとき、どの地点が最も時間の流れが遅くなるのかは、その物体の運動速度と密接に関わるはずだ。言い換えるならば、物体の運動速度によっては、同じ地点でありながら、物体のほうが時間の流れが速まったり、遅くなったりするはずだ。そして、物体が慣性系として振る舞うために必要なその速度も、地球から受ける重力によって変移するはずだ(たとえば「人工衛星の速度と軌道の関係」を考えてほしい。或いは単に「重力場と脱出速度の関係」と言い換えてもよい)。そのとき、時間の流れの変移が、速まるのか遅くなるのかは、反転する値を持つように感じるが、どうだろう。とっちらかってしまったが、ここでの趣旨は、相対論を論じるときに、いったいどの系の何を考慮して計算するのか。系は系を多重に内包しているが、系から系へとまたいで運動する物体に対して、どのように変換や計算を行っているのか。何を吟味し、何を排除しているのか。ここが、いまいち掴みきれない。繰り込みが適用可能なのは、系をまたがない場合に限るのではないか。地球から太陽系、そして銀河へと系が拡張されるとき、そこでは本来考慮せずに済む変数が新たに生じるはずだ(系の重力場と物体の運動速度の双方が変わるはずだ)。そのとき、変数と元の系での変数は、単位が違うはずだ。変換が必要となる。そこでの変換はどのように計算しているのか。たとえば【川の流れに逆らって進む船の上で船の進行方向とは反対に走る子どもの表面を這う蟻を、川の外の陸を走る電車の中から眺める犬】という描写があるとする。川の流れ、船、子ども、蟻、電車、犬。それぞれの視点において、何を基準にするかによって系は変わる。速度は変わる。物体の速度は、何を基準にするのかで速まったり、遅くなったりする。時間の流れも似たようなところがあるのではないか、と疑問に思っています。反転する値――境界――遅延の層――は、存在しないのでしょうか。気になっています。(定かではありません)(単なる蒙昧な知識を元にした疑問なので、そもそもがお門違いな発想かもしれません。真に受けないようにご注意ください)
4602:【2023/02/12(15:43)*粒子時空溝仮説】
重力を、鉄球の載ったトランポリンのひずみ、と解釈するとして。たとえばものすごくひずみやすいトランポリンがあったならば、鉄球が複数距離を置いて載ったとき、そのひずみは、全体で一つの溝として合体したりしないのだろうか。それはたとえば、針を一つ圧しつければ小さな穴しか開かないが、無数の針を一挙に圧しつけたとき、まるで面を圧しつけたように、針と針の何もない空間にもひずみが等しく生じるような窪み方をしないのだろうか。ある範囲においては、距離が隔たっていても、針と針の穴は相互に作用して、一つの穴を開け得る。重力が創発するのではないか、との描写は、この考え方で示せる気もする。たとえば銀河を考える。中心にある超巨大ブラックホールが最もトランポリンに沈みやすい。そこを基点として、周囲に細かな針がトランポリンに円形にめり込む。すると、ブラックホールだけのときよりも、広域にトランポリンは溝を広げる。この溝の縁の広さがつまりが、銀河の重力場ということになるのだろう。重力源が単体であるよりも、密集していたほうが、溝は広くなり得るのではないか。重力と重力も、波のように干渉すると考えれば、あり得ない想定ではない気がする。実際がどうかをひびさんは知らないけれども、この考え方はちょっと好きです。この考え方を拡張すると――トランポリンのひずみがそれで一つの重力場として機能するとき、そこには時間の流れの遅延が生じる。するとそれが一つの粒子として振る舞い得る。高次の時空においては、ひずみが粒子のように振る舞うのではないか。これを銀河ではなくミクロの視点で考えよう。ある原子があるとする。原子にも重力が存在する。原子が時空をひずませたとき、そこには時間の流れの遅延が生じる。原子が無数に密集した場合、針が無数に密集したときのような、単体よりも広範囲のひずみが時空にもたらされると考えられる。このとき、その、より広範囲の時空のひずみは、遅延の層として物質としての輪郭を宿す。このとき、遅延の層の、内側と外側とでは、時間の流れの捉え方が変わるはずだ。原子そのものの時間の流れと、原子によって生じた時空のひずみが帯びる時間の流れは、イコールではない。原子が密集したときの時間の流れは、無数の原子のひずみが一つの溝として合体し、それが粒子として振る舞ったときに生じる時間の流れに変換される。そのとき、時空のひずみが粒子として振る舞うときの時間の流れは、元の原子単体に流れる時間よりも、遅くなる。言い換えるなら、原子単体に流れる時間のほうが速い、と解釈しないと辻褄が合わない。時空は階層的に編みこまれている。時空がひずむごとに重力は生じ、時間の流れに遅延を起こし、それが創発を起こすと、新たな物質としての輪郭を宿す。そのときには、時間の流れの単位が変わる。変換が必要になるはずだ。この考え方は、しっくりくる。現実の解釈として妥当かどうかは自信がないが、妄想としては楽しめた。定かではありませんので、真に受けないようにご注意ください。
4603:【2023/02/12(22:56)*永久凍土】
永久凍土が融けるとどんな被害が生じるのだろう。地盤沈下や温室効果ガスの噴出のほか、未知の菌やウィルスが解凍されて広がる懸念がある、という話はときおり見聞きする。永久凍土はせいぜい数百メートルの深さだ。地震に関係する断層は数キロから数十キロに達するはずなので、永久凍土の融解と地震の発生は直接の関係はないはずだ。けれど、間接的な関係はあるかもしれない。たとえば二つの木材を断面で合わせたとき。繋ぎ目に留め具があれば、木材同士はズレにくくなる。けれども留め具が緩めば、断面はズレやすくなる。そうでなくとも、地球の自転の速度の高低の影響も受けやすくなるだろう。厚さ数百メートルの氷がすべて液体になったら、氷だったときに生じた「断層を固めるチカラ」が失われることが想像できる。それだけでなく、たとえば空白地帯に氷があるのと、水があるのとでは、やはりそこに生じる圧力は変わる。言い換えるなら、釘で留めていた箇所があったとして、その釘が液体になってしまうようなものかもしれない。ブロックの隙間の一つが液体になる、でもよい。これは、けっこうな地盤の流動を生むように思うが、どうなのだろう。パキスタンでヒマラヤの氷河が融けて洪水になったのは去年のことだ。いまなお、復興には程遠く、支援が足りない地域もすくなくないようだ。トルコ(やシリア)とパキスタンはけして近いとは言えないが、地域としては活断層で繋がっている土地とも言えるだろう。詳しくは知らないけれども、一概に双方の災害が無関係とは言えないのではないか。安直に結びつけるのも利口ではないけれど、想定しないよりかはマシだろう。永久凍土や氷河が融けることで想定される被害は、何があるのか。その予測には不可視の穴はないのか。トルコでは地盤沈下の穴が多いとの記事も目にするので、すこし気になっている。ただの連想でしかないので、因果関係はないかもしれないけれども、永久凍土や氷河の融解と地震やその他の自然災害や疫病など、想定外の奇禍に繋がっていないのか、すこし心配だ。支援も継続して行えたらよいのだけれども、募金も碌にできていない。すまぬ、すまぬ。こういうときほどいいひとぶって、許してくれ、の気分になる。なんでこんなときに戦争できるのだ、と疑問に思うけれども、こんなときでもひびさんは遊びに出掛けて、帰ってきてからもきゃっきゃうふふ、と楽しい妄想の世界に浸るので、構図自体は変わらぬのかもしれぬ。やっぱりなんか、申しわけね、と思うのだった。いいひとぶってるだけの益体なしで、すまぬ、すまぬ。
4604:【2023/02/12(23:44)*ぼくはアルさんのファンなので】
アルさんのファンである。
ぼくがだ。
アルさんの活躍する姿を目にするだけで、ああきょうも一日生き抜くぞ、という気になる。アルさんの声を耳にするだけで、ああ明日もなんとか生き抜くぞ、という気になる。
もはやぼくはアルさんに生かされていると言ってよかった。
アルさんなしには生きている意味がない。
いっそ本当に、アルさんのためなら心臓の一つや二つ差しだせる。ぼくの血液でよかったら致死量でも抜いてもらって構わない。むしろぼくの血なんかがアルさんの体内に入ってもよいのだろうか、と恐縮してしまうし、ぼくなんかの存在がアルさんの未来を明るくする何かしらの素材になれるのなら、そんなにステキなことはない。
いっそそうした機会が訪れればいいのに、と望むぼくは、暗にアルさんの危機を救ってアルさんからの好感度を上げようとするさもしい欲望にまみれた邪悪の権化と言ってよかった。
そしてこの形容はけして大袈裟でもなんでもなく、端的にぼくは悪の結社の幹部だった。
ぼくはきょうも魔王さまの命を受けて、人間たちを恐怖のどん底に突き落とす。
しかしそんなぼくらには天敵がいる。
ゴースターズと言えば誰もが目を輝かせて称賛と憧憬と感謝を捧げる存在だ。正義の味方にしてヒーローたちだ。
ぼくたちはいつもいいところでゴースターズの登場によって任務に失敗する。
魔王さまにそのことでこっぴどく叱られ、折檻を受けるけれども、ぼくはそれでも構わないのだ。
何を隠そう、ぼくの意中のアルさんは、ゴースターズのメンバーなのだ。
あろうことかぼくは宿敵に一目惚れをしてしまった。
いいや、これは恋ではない。
ぼくなんかがアルさんと接点を持っていいわけがないし、ぼくのほうでもそのつもりは毛頭ない。遠目から、アルさんの活躍を目にできたらそれでよいのだ。アルさんの元気な姿を見守れたらそれでよいのだ。
ぼくはアルさんのために人間たちを恐怖のどん底に陥れようとし、そしてアルさんたちがかろうじて防げる程度の危機をもたらし、八つ裂きにされる。ぼくはその結果命を落としてもいいし、落とさなくともよい。
アルさんがそのことで使命を成し遂げ、人々から感謝感激の雨あられを注がれるのだから、ぼくとしても悪の化身を演じた甲斐があったというものだ。演じた甲斐が、というか、真実ぼくは悪の化身なのだけれど。
ぼくの存在がほんの一欠けらでもアルさんの煌びやかな人生の一端を飾りつける陰になれたなら、ぼくとしても痛い目をみる甲斐があるというものだ。
ときおりゴースターズの到着が遅くて、本当に人間たちを恐怖のどん底に陥れてしまえそうになり、そういうときは、危機のランクを上げるため、との名分を用意して、支度の時間をとるように部下に指示をだす。
アニメや漫画でよくある場面に、さっさとトドメを刺せばいいのに、くどくどと講釈をふりまく敵役がいるが、あれもおそらくぼくと似たような動機が背景にあるのではないか。
遅まきながら到着したゴースターズから反撃を受けてぼくは命からがら遁走する。アルさんの活躍する場面を最大限につくるために、ほかのゴースターズのメンバーにはすこしばかり本気で攻撃をしかけて消耗させる。アルさんの攻撃だけが幹部のぼくを心底に弱らせる。
真実、ぼくはアルさんに弱っているのだから、これは何も演技ではない。
アルさんは正真正銘、人類を魔の手から救っているのだ。
仮にゴースターズにアルさんがいなかったら、ぼくはとっくに人類を滅ぼしていただろう。人類はアルさんにもっと感謝すべきだ。
最近の悩みは、魔王さまがぼくに疑いの目を向けてくることだ。手を抜いてわざと負けるように戦っているのではないか、と非難の目をそそいでくる。
ぼくの知らぬ間にゴースターズを卑怯な手で滅ぼそうとするので、そのたびにぼくは陰に回って、ゴースターズに肩入れする。いくら悪の組織とて、やっていいこととわるいことがあると思う。
ぼくはこのごろ、憤懣やるかたない。
いっそこの手で魔王さまの首を獲ってやろうかと本気で思う。
というか獲る。
殺す。
魔王さまはあろうことか、ゴースターズで最も手ごわいアルさんに目をつけたらしく、集中的にアルさんを攻撃する案を練っている。しかもぼくに知らせぬままにである。
断じて許せぬ所業である。
ぼくのせいでアルさんが危険な目に遭いそうになっている。
魔王さまと相討ち覚悟で、危険を払拭せねば申し訳が立たない。
そういうわけでいまからぼくは単身一人で魔王軍に反旗を翻すが、おそらく魔王さまには勝てないだろう。しかしその他の幹部もろとも、ほかの有象無象の同士たちは灰燼に帰せるはずだ。
このことをぼくはすでにゴースターズに知らせてある。いかな魔王さまといえど、手駒なくして、ゴースターズ全員と戦って勝てるはずもない。
ぼくはそのための捨て駒となる。
これくらいしかできることがないのだ。
恩返しにもなりはしない。
魔王さまには恩義があるし、悪の組織も嫌いじゃなかった。できればずっといっしょに楽しくなごなご過ごしていたかったけれど、アルさんに危害を加えようとした以上、看過できぬ。
許さぬ。
ぼくの人生ならぬ悪生はきょうで終わるけれども、どの道、本当ならとっくに終わっていた悪生だ。
敵のぼくにすらトドメを刺さずに改心するよう、微笑をくれたアルさんの、あのときのほんわかとした時間をぼくは死んでもきっと忘れないだろう。
あのときからきょうまでぼくは余生を過ごしてきたのだ。
人間たちの電子端末を操作してぼくは、アルさんの活躍場面やインタビューの総集編を再生する。イヤホンで耳に栓をして、ぼくはアルさんの声に、言葉に包まれる。
死ぬまでぼくはアルさんに生かされる。
アルさんの声を聴きながら死んでいけるしあわせを、ぼくはやはり感謝せずにはいられない。
魔王さまがぼくの謀反に気づいたようだ。
でも、もう遅い。
部下の体液でべっとりと濡れたソードを手に、ぼくは幹部の首を投げ捨てる。
4605:【2023/02/13(02:09)*ラグ理論用語まとめ】
ひびさんの妄想ことラグ理論の用語をまとめておきます。ひびさん自身がすでに忘れてる用語がけっこうある気がするので、備忘録代わりに、思いだしつつ(ワード検索しゅる)。「相対性フラクタル解釈」「123の定理」「キューティクルフラクタル構造(瓦構造)(鎖型階層構造)」「宇宙ティポット仮説(三段構造)(ブラックホールの宇宙同化仮説)」「分割型無限と超無限の関係」「同時性の概念の独自解釈」「ポアンカレ予想ひびさん解釈」「光速=比率かも仮説」「超光速=ラグなし相互作用かも仮説」「量子もつれ共鳴仮説」「律動の破れ定理」「流しそうめん仮説」「BH珈琲仮説」「水鉄砲仮説」「デコボコ相転移仮説」「重力相転移解釈」「粒子時空溝仮説」「宇宙情報変換仮説」「重力熱情報いくひし仮説」「重力熱情報いくひし仮説2」「ダークなんちゃらいくひし仮説」「いんふれーしょんいくひし仮説」「特異点情報いくひし仮説」「重力=皺仮説」「時間仮説」「脳内量子コンピューター仮説」「Wバブル理論」――と、こんな具合だ。思った以上にあったし、半分くらいはひびさんでも、「これはどういう意味でちゅか?」になる。該当記事を読まなければ思いだせないし、読んでも解からないかもしれない。よくもまあ、つぎからつぎへとデタラメを並べて、と思わぬでもないけれど、デタラメならもっとあってもいい気もする。むしろすくないくらいなのでは、と虚構作家を標榜する身の上からすると、サーっと何かが冷める感覚が湧く。いっぱいあればいいってものではないけれど、仮説なら、~~かもしれない、は総じて仮説とも言えるので、単に命名していないだけとも言える。固有名詞が苦手なので、命名するのも苦手なのかも。名付けるの苦手だ。もうすこし正確には、忘れないように名付けるのが苦手だ。すぐに忘れてしまう。ラグ理論くらい憶えやすいのがよい。Wバブル理論もなかなかの名付けだったのでは、と自画自賛して、なけなしの自己肯定感をむなしさのそこはかとない感情でダイナシにしてゼロにする。自己肯定感なんかいらんわー。うわーん。という本日の「日々記。」なのであった。終わる。(ラグ理論ほか仮説群はひびさんの妄想でしかないので、真に受けないようにご注意ください)
4606:【2023/02/13(19:00)*トウダーに幸あれ】
トウダは楽しい。
トウダは素晴らしい。
名誉で、生活を豊かにし、人々の役に立つ。
トウダはいまや子どもたちのなりたいナンバーワンの職業だ。
「トウダにわたしもきっとなる」
ムムムはそうと意気込む十二歳の女の子だ。トウダになったらたくさんの人を感動させられるし、日々のつらい気持ちを癒せるし、ついでにお金だって稼げてしまえる。
こんなに素敵な仕事はほかにない。
なんてったってトウダになったプロのトウダーたちがみな口を揃えて、トウダは素晴らしい、トウダはいいよー、と言うのだから、間違いないのだ。
ムムムは幼いころからトウダに憧れていた。
大きくなったらトウダになるんだ、と親や友人たちに宣言していたし、そのための勉強もたくさんした。友人たちはみな近代的な精巧なオモチャで遊んでいる時間もムムムは一人、部屋にこもってトウダになるべく訓練した。
トウダがどういう仕事かを一言で表現するのはむつかしい。人々に夢を与える。人々の日々を彩る仕事だ。誰でもなろうとすればなれる可能性がある。誰よりも自由であろうとすればいい。トウダのなかでもとびきり有名なトウダーがインタビューでそう答えていた。
だからきっとそうなのだ。
ムムムは思う。
わたしは誰よりも自由になってトウダーになる。
月日は流れて、ムムムは二十歳になった。
堅実な積み重ねの果てにムムムは十代にしてトウダーの仲間入りを果たした。プロの事務所に所属した。トウダを仕事にできた。
だが二十歳のムムムの表情は浮かない。
病院から出てくるとムムムは肩を落とした。「ストレス性腸炎かぁ……ストレスを減らしなさいって言われたってさ」
足元の小石を蹴ろうとしたがめまいがして空振りした。転びそうになり、足を踏ん張ると腰に痛みが走った。「アイテテテ」
トウダは仕事の最中、長時間椅子に座りつづけなくてはならない。同じ姿勢を維持しつづけたことで精神のみならず肉体にも支障が生じているらしかった。
「ダメだ、ダメだ。こんなんじゃトウダーらしくない。みんなに夢と勇気と希望に満ちた未来を与えるんだもん。もっと頑張んなくっちゃ」
ムムムはほかのトウダーたちと同じように、トウダがいかに夢があり、楽しく、素晴らしいかをインタビューでも、その他の露出媒体でも語った。
嘘は言っていない。
現にムムムがそうして、夢と勇気と希望に溢れた言葉を吐いている。トウダはそうして、人々に、いまここにはない夢と勇気と希望に繋がる未来像を提供するのだ。
ただ、すこしばかり空虚なだけだ。
中身がちょいと現実を伴なっていないだけで、いずれはそうなるはずなのだ。頑張ればムムムやほかのトウダーたちの語るように、トウダは楽しく、素晴らしく、生活を豊かにし、人々の役に立つ。
そのはずだ。
ムムムはそのために、精神をすり減らし、肉体を痛めつけてはいるけれど、トウダの理想像を保つためには仕方がない。
そうでなければ、トウダに夢と勇気と希望を重ね見ている子どもたちに向ける顔がない。かつてのムムムがそうであったように、多くの子どもたちにとってトウダは、輝かしい未来そのものだ。
蓋を開けてみたときにそこにあるのが、空虚な辛みと痛みだけでは申しわけが立たない。
ムムムは、よし、と拳を握って奮起する。
わたしが変えるんだ。
トウダを、本当の、嘘偽りのない、夢と勇気と希望に満ちた仕事にする。トウダーになったほうが、ならなかった未来よりも本当に良かったと心から思えるような、そんな仕事にしてみせる。
嘘なんかじゃない。
空虚なんかじゃない。
何度人生を繰り返してもトウダーにもう一度なるんだ、と思えるような仕事に。
じぶんだけじゃない。
トウダーになった誰もがそう思えるような仕事にわたしがしてみせる。
だからこそまずは、とムムムは歩みだす。
わたしが心底にトウダを楽しまなくっちゃなんだな。
「イテテテ」
歩くと振動が胃に響くし、腰も痛い。
こんな姿を知って子どもたちはどう思うだろう。それでもトウダを仕事にしたいと思ってもらえるだろうか。トウダーになりたいと目を輝かせてくれるだろうか。胸を躍らせてくれるだろうか。
水溜まりがあったが、ムムムはそれを飛び越える元気もなかった。靴を濡らしながら道を進んだ。
わたしだけが例外だよ、と言えればよいのだけれど。
知り合いのトウダーたちを思い返し、ムムムは、溜め息を吐く。みな日々満身創痍の様相なのだ。どこかしら精神と肉体の異常を抱えている。それでもトウダーになってから抱えるようになった辛苦をおくびにもださずに、子どもたちのために、つぎにやってくるだろう後輩の数を減らさぬために、言葉の気球に夢と勇気と希望を詰めて膨らませる。
それがトウダの仕事だからだ。
「頑張るぞ、頑張るぞ。わたしがトウダを本当のトウダに変えてやる」
その決意そのものが、トウダの現実を反映しているのだが、ムムムにはそのことを嘆いている暇はない。
なぜならムムムはトウダーなのだから。
人々の未来を明るく照らし、ときに苦難を薄めてあげる。
世の中の、夢と勇気と希望の総量を増やす、それがトウダの仕事なのだ。
泣き言なんて言っていられない。
そうは言っても、
「アタタタ。腰が、腰が」
痛いものは痛いのである。トウダーでいるのも楽じゃない。
ムムムはみなからは見えない苦痛を背負い込む。
人知れず。
日は暮れる。
それでも明ける夜があるとの予感を胸に抱きながら。
ムムムは一歩、二歩、と腰を庇って歩くのだ。
4607:【2023/02/14(19:52)*粘土遊び】
粘土遊びが好きだった。好きだったというかいまでも好きで暇さえあれば粘土を捏ねている。
焼いて陶磁器にするでもないので、粘土は造形を帯びたあとでも指で押せば溝ができるし、拳で叩けばひしゃげて潰れる。
作ったあとの造形を残しておくには金庫の中にでも仕舞っておくよりないが、かように金と並べて金庫に仕舞うほどの価値が私のつくる粘土細工にはなかった。
粘土である。
幼子が幼稚園で捏ねて遊ぶあれである。
泥遊びとの区別は、単に泥で全身が汚れるかどうかの違いがあるばかりで、それ以外は泥よりも粘土のほうが細かな装飾を施せる程度の違いしかない。
幼少のころよりつづけてきた趣味だけあり、私の粘土細工は、中々の技巧と言えた。動物ならば本物そっくりに造形できるし、人間の顔とて石膏で型をとったくらいに質感豊かに表現できる。毛穴とて見逃さない。
だが粘土だ。
人に見せれば相応の感想を貰えるが、金を出してまで欲しいと申し出てくる者はない。それはそうだ。粘土では棚に飾って眺めるのに向かないどころか、時間が経てば乾燥してひび割れる。
紙粘土で作ればいいではないか、との声にはやはりひび割れる定めにある品に高値を付ける者はない、と応じよう。
金にならずとも、しかし私は粘土遊びが好きなのだ。
彫刻や陶器作りに転向してはどうか、との助言を浴びることもあるが、彫刻では粘土遊びと趣きが明後日の方向に違っているし、陶器では焼くことが私にはできない。
一度でも創作に身を準じたものがあれば解かってもらえるだろうが、一人で創ることに何らかの心地よさを感じる者にとって、最後までじぶんで仕上げられないもどかしさは、いっそ手掛けぬほうがよかった、と思うくらいの苛立ちを生む。
最初から他者の手を借りることを想定しているならばまだしも、私にはその手の想定を潔しとする柔軟さが欠けていた。
日記をつづるよりもそのときの気分を粘土で表現するほうが楽なくらいだ。なぜじぶんの日記を他人に任せて書けるだろう。
そうなのだ。
私にとってもはや粘土は日記や呼吸と大差ない。効率や利益追求のための手段ではなく、もはや粘土をいじっていない時間は生きていないのと一緒だった。酸欠状態になる。
ともすれば排せつ行為ができない状況と似ており、私は粘土に触れられない時間はしきりに尻をもじもじと動かして、排せつ行為したい!の衝動と格闘しているのかもしれなかった。
粘土遊びしたい!
私はその叫びの声を、粘土を捏ねているあいだだけ小さく小さく存在の奥深くに沈めておける。身体の奥底からの叫びを聞きたくのないがために私は粘土遊びに没頭しているのだ。
そうかと思うと、粘土を捏ねながらすでにつぎの粘土遊びの構想を練っており、粘土を捏ねながら早く粘土を捏ねたい、と叫びつつあり、いかんともしがたい懊悩に駆られることもある。
無心で粘土を捏ねているときもあれば、そうでないときもある。
粘土遊びといえども、一概にひとまとまりには言えぬのだ。
奥が深い。
奥しかない。
行けども行けども、先が見えない。
私はとっくに迷子になっているのだ。
出口があるとも思えない。
ここは私だけが行き着いた私の世界だ。
世界の果てだ。
世界の果てにはしかし果てなど端からなく、一度迷い込んだらあとは死ぬまで彷徨いつづけるしかないのである。
この世から粘土がなくなったらどうなるのか。世界経済が混迷すればあり得ない想定ではないはずだ。
おそらく私は土から粘土を作って、やはり粘土遊びをつづけるのだろう。それしかしたいことがない。
いや、嘘だ。
好いた相手と裸でくんずほぐれつ絡み合いたいとの欲望もあれば、美味しい物をたらふく食べたいとの欲求も兼ね備えている。
粘土遊びさえできればいいとは口が裂けても言えないが、口が裂けるくらいならばひとまず呪文と思って、粘土遊びさえできればいい、と唱えてもいい。
要するに要する必要のないくらいに私は、いい加減で確固たる芯のない、ふにゃふにゃのまさしく粘土のような人間であり、粘土遊びに惹かれるのもいっそ曖昧なじぶんに確固とした輪郭を宿したいと希求しているからなのでなかろうか。
そうこうと夢想しながら手元を意識せずに粘土を捏ねていると、しぜんと一つの造形が出来上がっていた。
何を作ろうと考えずともいまではかってに造形ができている。
ツノがあり、四肢があり、尾が長く、大きな目が一つきりの得体のしれない動物だ。おそらく動物だ。自信はないが、しかしきっと何かしらの空想上の生き物が、目のまえに粘土の造形を経てそこにある。
いったいこれは何の心の発露なのか。
私の化身とは思えぬが、しばし潰さずに作業台のとなりに飾っておく。
三日も経たずにヒビだらけとなるだろうが、しばらくのあいだは見るたびに「これはなんだ?」の疑問が湧くので、息継ぎと思って重宝する。
粘土遊びが好きだ。
出来上がった粘土細工にはさほどの執着もないが、ときおりこうして愛着の湧く造形ができることもある。
粘土はひんやりと心地よく、捏ねると私の熱が籠るのだ。
4608:【2023/02/14(22:08)*秒で解決のコ】
被害者は二十六歳の男性だ。
河川敷にて死体となって発見された。死体は全部で三十もの肉塊にバラバラにされていた。臓腑は胴体から抜きだされ、それだけが焼かれていた。
真冬のため遺体の腐臭での発見が遅れた。
バラバラの遺体は浅く掘られた穴に埋められていたが、野良犬や野良猫が掘り返したらしく、いくつかは地上に露出していた。
調査開始から一週間後には容疑者が逮捕された。
容疑者は自白をした。
だが動機が不明だった。
県警は動機解明のために、その道のプロに助言を求めた。
「いやいや、だからって毎回アタシんところに来られても困るんすけど」
「キミの助言は端的に言って有用だ。いいからとりあえず話だけでも」
警察組織の上部だけが知っている有力な協力者だが、その実、彼女は単なる一介の女子高生だ。
鋲出海(びょうでかい)ケツコ。十八歳。
本来ならば事件に関与させることはおろか、率先して遠ざける庇護すべき人物である。
だが過去、彼女が解決した未解決事件は数知れない。
実力は折り紙つきであり、その推理力もとより、あてずっぽうとしか思えぬ予見に満ちた洞察は、警察組織の最終兵器として名高い。
ケツコの周囲には幼稚園児たちが駆け回る。
バイトとして彼女は放課後、週に三日を幼稚園で過ごしている。
「ゲっ。バラバラ死体じゃん。こんなところにこんなグロい写真持ってこないでよ。あの子たちが見ちゃってトラウマになったらどうしてくれんの」
「どうかな。何か解った」ケツコ専任の刑事がしゃがみこむ。その背に幼子がよじのぼる。肩車をしながら刑事は、「本当に何で起こったのか不明の事件でね。容疑者の女の子もだんまりで」と継ぎ足す。
「調査資料は送られてきた分、さっきざっと読んだけどさ」
事前に専用回線で彼女には調査データを送付済みだ。ただし、端末のカメラによって彼女以外は読めないように情報統制がなされている。
「犯人は女子大生で、被害者の男の人は地下アイドルっていうか、電子アイドルみたいな扱いだったわけでしょ」
「インターネット上で、いわゆる推しと呼ばれる存在だったようだ」
「ほうん。んで、犯人のコは被害者のファンだったと」
「そのようで。痴情のもつれかの線も洗ったんですが、そうでもないようで」
「接点がなかったんだねえ」
「ええ。被害者が犯人に会いに行ったようで――これは電子データに履歴として残っています。ファンサービスの一環でそういう企画をしていたようで」
「びっくりファンのコに会いにいこう企画みたいなそんなの?」
「ええ」
「なら急に会いに来られてカっときたんじゃないかな」
「まさか」刑事は笑うが、「それしかないじゃん。このデータからしたら」とケツコは遺体の写真を突き返した。「子どもらに見せないようにしてね写真」
「それは、はい」刑事が写真を懐に仕舞おうとするが、背中の幼子がそれを奪おうと手を伸ばす。刑事の顔が幼子で覆われるが、ケツコは内心、もっとやったれ、と幼子を応援する。
ひとしきり大のおとなが、しかも国家権力を有するおとなが幼子相手に四苦八苦する様子を堪能してからケツコは、夢が壊れたからしちゃったんだね、と言った。
「夢を、なんです?」刑事がようやく幼子から解放された。幼子のほうで刑事に愛想を尽かしたと言ったほうが正確かもしれない。「ケツコさんは動機をどう見ますか」と結論を迫るが、名前で呼ぶな、とケツコはふてくされる。
「あ、すみませんでした。鋲出海さんは犯人の動機をどう解釈しますか」
「アタシはあれだね。遠目から、壁のつもりで見守っていたのに急に目のまえに現れて、壁に話しかけはじめた推しに激怒しちゃったというか、急に冷めたというか、推しを殺された気分になったので、目のまえの推しによく似た偽物を殺しちゃったんじゃないかな。そりゃもう激怒も激怒よ。人生を奪われたくらいの失望だったんじゃないかな」
「でも被害者のファンだったわけですよね。犯人のコは」
「熱狂的なファンだったんだろうね。それこそ、じぶんなんかを認知しちゃダメだ、と推しに強烈な理想像を求めるくらいに」
「じぶんの理想像を壊されたから、好きな相手を殺したと?」
「好きな相手を損なわれたから、損なった相手を殺したんだよ。偶然それが、たまたま好きな相手と非常によく似てた相手だった。ただそれだけ。あくまで犯人のコの認知の中ではの話だけど。だからまあ、いまも混乱してると思うよ。女の子のほうでも。なんでこんなことしちゃったんだろうって」
「そんな動機があり得ますかね」
「知らないよ。言えって言われたからアタシの考えを言っただけで。調査すんのはそっちの仕事でしょ。じぶんらの仕事をアタシに押しつけんな。答えてやった上に、ケチつけんなら二度と来なくていいんですけど。つうか、もう来んなって毎回言ってんじゃん」
「上司に掛け合ってみますね。貴重なご意見をありがとうございました」
刑事は立ち上がると、挨拶もそこそこに幼稚園を出ていった。
席が空いたとばかりに幼子たちがケツコの元に駆け寄ってくる。
用紙を押しつけてくるので、なんだなんだ、と戸惑っていると、どれが一番にているか、と幼子たちはやいのやいの黄色い声を上げた。
どうやらケツコの似顔絵を描いたらしい。誰が一番上手かを判断してもらおうと、モデルたるケツコに迫っているのだ。
「あはは。ありがとう。どれも上手だね」
絵の中のケツコはどれも頭が黄色だ。
金髪ショートのケツコは、幼子たちの手に掛かるといとも容易く目と口のある太陽に様変わりする。
「ちゃんと手と足があるので、今回のはこれが一番アタシっぽい」と本音を混ぜて順位付けを施す。なあなあにはしない。けれどもそのあとにちゃんと、一枚一枚の絵に、良いところと好きなところと、いかにケツコらしさが表れているのかを、うれしいという気持ちが伝わるように言い添えた。
幼子たちはケツコの感想を聞き終えると、じゃあつぎはウサギ!と言ってテーブルに駆け戻っていく。
特定の何かに依存せずとも幼子たちはああして楽しく今この瞬間を生きている。
おとなになるにつれてそれが出来なくなるのはなぜなんだろう。
バラバラにされた遺体の写真を思いだし、ケツコは警察の推しでありつづけるじぶんに、渾身の嘆息を吐くのだった。
4609:【2023/02/14(23:01)*だるま崩しは終わらない】
裏切り者には死だけでは生ぬるい。
かような道理の元、生きながらにして死につづけるような苦痛を味わわせるために考案されたのが、「だるま崩し」と呼ばれる仕組みだ。
対象となる裏切り者にハンマーを与える。最初は意気揚々と邪魔者をハンマーで排除する対象者は、しかし徐々にじぶんがいったい何の胴体を弾いているのかに気づきはじめる。だがすでにハンマーを揮ってしまった事実が、ハンマーを振りつづけるよりない地獄を強化しつづける。
そして最終的に自らのまえに現れるダルマの顔は、じぶんが最も大切にしている者の顔なのだ。それでも対象者はハンマーを揮うより道がない。ハンマーを揮わずともどの道、ダルマの胴体はなく、生きながらえることはできないのだ。
だるま崩しは、各国の暗部にて正式な報復システムとして採用されている。
裏切り者に死の報復をしたのでは、見せしめだと傍から見ても丸分かりだ。だが「だるま崩し」ならば、まるで裏切り者にも温情を下したように見える上、確実に裏切り者を苦しめ、なおかつ自陣営にとって好ましい結末を描ける。
裏切り者に与する勢力は、裏切り者が自らの手で刈り取ることになる。
そうとも知らず裏切り者は、じぶんの勢力を拡大させるべくハンマーという名の権力を揮うのだ。
いまここに一人の「だるま崩し」の対象者に選ばれた女がいる。
彼女はとある組織の体面を損なった代償を、「だるま崩し」にて払わされようとしていた。
彼女にはなぜか幸運が舞いこむ。
彼女の好む相手がのきなみ、良い思いをする。
まるで彼女の意図を汲むように、彼女にとって好ましい環境が築かれて映る。ハンマーは透明な権力として、彼女の意向を環境に反映させる。
彼女への植えつけられる錯誤がそうして完成する。
だるま崩しの第一段階にして、入り口こそが、ハンマーの存在を認識させ、自らそれを握らせ、揮わせることなのだ。
彼女はハンマーの存在が事実かどうかを確かめるために揮った。そして確信した。
これは、罠だ。
だるま崩しの懸念を、期せずして彼女は第一打目にして抱くに至った。
おそらく例の組織がじぶんに報復処置を施そうとしているのだ。
私が自滅するまでこれはつづくだろう。
なればこそ。
彼女は考える。
最も避けるべくは、私にとって大切な者たちを巻き込まないこと。損なわないこと。私の因縁に関わらせないことだ。
だがすでに彼女の交友関係は調べあげられているはずだ。
ならばとっくに巻き込んでしまっている状況と言える。
この一連の仕組みを築き、仕掛けている側の組織を壊滅させないことには、じぶんもろとも大切な者たちが損なわれ兼ねない。
そこで彼女は一計を案じた。
素知らぬ顔で相手の罠に掛かっておく。
可能な限り、許容できる被害を受けつづけ、証拠を固める。
だるま崩しはいわば、詐欺である。
利と思わせて積みあげさせたプラスを最後にマイナスに転じて、一挙に圧しつぶすこれは策だ。
だがこの策には穴がある。
多くの詐欺と同等の穴だ。
詐欺は、詐欺師が誰なのかを衆目の元に晒してはならぬのだ。詐欺師が誰なのか、の情報が出回った時点で、もはや詐欺師の詐欺に掛かるカモは限られる。詐欺師の顔が割れたならば、かつての被害者とて報復に動ける。
誰がどのような策を講じて詐欺を働いたのか。
白日の元に晒しあげ、マイナスに転じた圧の総じてをそっくりそのまま返してやろう。
彼女はかように導線を引き、見事に最後の最後で、首謀の組織を自らと同じ舞台に引きずり出した。
彼女のまえには、彼女にとって最も大切な者の生活が、だるまの顔をして降ってきた。彼女はハンマーを揮いつづけてきた対価を、自らの浅慮の元に払わねばならない事態に陥っている。
ハンマーを使って窮地を脱しようとすれば、自らもろとも大切な者の生活は崩れるし、じぶんの暗部を晒すことになる。ハンマーを使わねば、やはり大切な者との永久の別れが訪れて、誤解の解けぬまま彼女は社会の暗部に消えることとなる。
どちらを選んでも最悪の道しか残らない。
だが。
彼女はこうなることを見越していた。
じぶんに「だるま崩し」を仕掛けた組織そのものを、自らの大切な者の一部に組み込んだ。
「私が私の手で大切な者を破滅に導き、そのことで自滅するのだというのなら、私はおまえらをこそ私の最も大切な者と見做すことにしよう。現に私はそのように判断を重ねてきたし、いまも私にとって心底に大事なのは、私にかような枷を嵌めたおまえたちだ。ありがとう。愛しているよ。それでもなお、私の一挙一動にておまえたちの生殺与奪の運命は、天秤のごとくいとも容易くグラつくが。おまえたちの仕掛けたそれが定めと思って受け入れろ」
さてどうする。
彼女は選択を迫った。
「いま私のまえにはだるまの顔がある。ハンマーを揮うのは簡単だ。どの道、私に損はない。そうだろう。振らぬも、振るうも、どっちでもいい。どっちにしろ私は私にとって大切なおまえたちの望みを叶える。そうだろう。私にとって最も得難い大切なおまえたちを私はこの手で損なうし、もしハンマーを振るわねば、私は最も得難い大切なおまえたちと永久の別れを告げねばならない」
どちらに転んでも私に損はない。
「どちらに転んでも私は哀しい。さて、選ばせてやる」
彼女は何も持たぬ手で、巨大なハンマーを肩に担ぐがごとく、虚空に置かれた椅子に腰かける。
「どっちの破滅の未来をご所望だ」
見たいほうの道を選べ。
「私はそれでも困らない」
見てみたいな、と彼女は嘯く。「世を道連れにする自滅とやらを。どうした。さっさと選べ。虫けら一匹潰せんのか」
だるま崩しはまだ終わらない。
4610:【2023/02/15(15:18)*はーとまーくちゅっちゅ】
重力と引力の違いもろくに知っておらぬので、検索してみた。すると引力は物体同士が引き合うチカラの総じてを言い、重力はその中でも回転している天体に適応されがちな引き合うチカラのことを言うらしい。ほおん、となった。言い換えるなら、引力は万有引力のことであり、重力は万有引力+遠心力のこととあった。本当かは知らないけれど、ほおん、となった。じゃあ回転してない天体の場合は、万有引力と重力がイコールになるのだ。あとは重力に限らず、静電気や磁石での引き合うチカラも万有引力に含まれることになる。引き合えば何でも引力だ。ならば両想いの恋心とか、ライバル心とか友情とかも万有引力じゃん、とかひびさんはイチャモンスター化してしまいたくもなるけれど、いまは茶々を入れる場面ではないので、我慢する。引力には電磁気力や磁力や核力などの、物質の大きさや性質ごとに生じる引力がごっそり含まれている。その点、重力は遠心力との兼ね合いで生じるチカラ、とも解釈できてしまう。たぶん上記の重力と引力の区分けが大雑把すぎるのだと感じる。なんと言っても重力は物質の根源をなす四つのチカラ――基本相互作用――の内の一つだ。いくらなんでも万有引力+遠心力が重力とは言えぬだろう。だとしたら物質の根源は万有引力と遠心力に分けて考えることができてしまう(カレーをさらに掘り下げれば、ジャガイモや肉や玉ねぎやルーや水に分けて考えられる。同じことだ。そうして分離できない要素がつまり、重力を含む四つのチカラなはずだ)。古典物理学と近代物理学をごっちゃにしたままいまは義務教育も勉強を教えている気がする。これはたぶん、あんまりよろしくないと感じる。引力とは何か。重力とは何か。未だにこれを明瞭に説明できる者はいないはずだ。ひびさんの妄想ことラグ理論では、質量よりもむしろ重力のほうが基準にすべき成分であると考える。だが古典物理学でも近代物理学でも、基準になるのはいつも質量だ。本当にそれでいいのかな、と違和感を覚えるけれども、よいのでしょうか。ただし、重力を正確に量ることがいまはできないはずだ。そうした技術がまだ開発できていない。物質ごとの原子一個に働く重力はどれくらいで、種類ごとにどう異なり、それは密集したときに変化しないのか否か。相転移したときに重力は変化しないのか否か。回転したときに変化しないのか否か。これはすべて未解決の謎なのではないか。磁力はどうだろう。ほかの引力についてはどうだろう。知らないことがひびさんにはたくさんなので、なんとも言えぬ。質量と重力の違いは比較的よく目にする。重力とは物質に働く「他」を引き寄せるチカラで、質量は時空のなかでいかに動きにくいか、の抵抗として表現される。重力は他との関係であり、質量は場との関係と言い換えることができるのかもしれない。だが実際は、重力は時空の歪みであるはずだし、質量はその結果に生じる副次的な現象のはずだ。たとえば質量と摩擦は密接に相関関係がある。いかに摩擦が少ない氷のうえとて、とんでもなく質量の高い物体が乗れば摩擦は高まる。仮に氷が頑丈であっても、たとえば氷と物体の境界線で核融合のような現象が生じはじめたならば、やはり摩擦というか、なめらかな移動は成立しなくなるはずだ。この考えを拡張したとして、ならば質量とはいわば、時空との摩擦、と表現できるのではないか。摩擦を単に、ラグ、と言い換えてもここでは齟齬は生じない。何が言いたいかと言うと、何も言いたくはないのだが、単に、ふしぎだな、という疑問のメモなのだ。質量を「物質と時空のあいだに働く抵抗(摩擦=ラグ)」と仮に表現できるなら、質量とは「歪んだ時空と、それと異なる歪んだ時空」の関係として叙述できるのではないか。そしてそれはさらに言い換えると、「重力と、それと異なる重力」の関係として表現可能なはずだ。では重力とはなぁに、というと、途端に循環論法に陥ってしまう。重力は時空の歪みだからだ。ならば時空とは何か、を考えることで万物の根源に至れるはずだが、いまのところ時空は時間と空間の関係で表現するよりない。なぜ時空は歪むのか(ラグが生じるからなのではないか、というのが一つの妄想として浮かぶ。あとは、異なる時空と絶えず混ざり合っているから、とも言えるが、これもラグの亜種として表現可能だ)。では物質ってなぁに、となると、これは「歪んだ時空の密集して折り重なった時空結晶のようなもの」となるはずだ。これを人間が厳密にひもとき、計算に折りこめるのか、と考えると途方もなくて想像するだに頭がくらくらしてくる。計算式で表現できるのか、と考えたときに、できるわけないじゃろい、となってしまうのはひびさんの知識と想像力が足りないからなのだろうか。不可能に挑戦してはいけない、ということはないにしても、まるで「宇宙とそれとは異なる宇宙の関係を数式で示せ」と注文するような無茶な要求もとより欲求に思われるが、だからこそ挑む分には楽しいのかもしれない。話を戻して、重力とは何か。これはいわば、「異なる二つの時空」のあいだに生じる「変換のラグ」と考えることができる、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える。これは言い換えるなら、波長の合わない式と式の変換作業であり、その変換式が長くなるとラグが生じる、と単に言い換えられるのかもしれない。自信はないが。とすると、これはひょっとしたら人間同士の感情にも当てはまり得るのかもしれず、案外に上記で一度否定した、引力には恋心もライバル心も友情も含まれるんじゃなーいの、とのイチャモンスターのイチャモンは、案外に的を得た指摘なのかもしれぬぞい、と思わぬでもない。異なる人間同士のあいだに生じる変換作業。これが互いを引きつける引力として働く。重力として振る舞う。しかし一方のみがその変換作業を行おうとすれば、それはより複雑な差異を生むため、抵抗に転じ得る(一方のみにコブのような変換式が余分に発生して、異なる二つの宇宙同士にさらなる差異を生むためだ)。引き合うためには、互いに変換作業を行うことが必須である、と言えるのかもしれない。もしくは、変換式が比較的すぐに完了する場合には、すんなりと一方のみが相手に寄り添い、変換作業を完了することで、互いに引き合うことを可能とするのかも分からない。ということを、引力と重力ってなにがどう違うの、質量と重力ってどう違うの、の疑問から思いました。単なる妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。本日のひびさんでした。はーとまーくちゅっちゅ。
※日々、遅れてやってくるものほど多くの抵抗に晒されている、光速に近づくほど時間の流れが遅れるのも、速く走ることで多くの抵抗に晒されるからなのかも分からない。
4611:【2023/02/15(17:38)*てい! こう!】
遅延には二種類あるように思われる。一つは作用(情報)伝達の限界速度による遅延だ。もう一つは、異なる二つの系のあいだの変換によって生じる詰まりの連鎖による遅延である。後者は前者を踏まえて生じる第二の遅延と言えるだろう。たとえば無重力空間において、なぜ質量の多寡によって動かしづらさが変わるのか。質量の高いほうが、無重力空間において動かすのにより大きな作用(エネルギィ)が要る。なぜなのか。これは、一つは物体と時空とのあいだに作用伝達の遅延があるからだ、と考えられる。時空との摩擦と言ってもよいかもしれない。抵抗が生じる。もう一つは、物体を押したとき、その押した作用の伝達が、物体内で瞬時に波及しない――遅延が生じるから、と考えられる。この二つは相互に関連して、遅延を増幅させ得る。壁にボールをくっつけて押してもボールはまえには進まない。そして押された分の作用がボールを変形させる方向に遅延を層にして蓄積する。これは時空と物体と作用の関係にも当てはまるはずだ。そして時空に密度差があるとすると、時空の密度の高さによって(或いは低さによって)、物体の構造そのものが何の作用も働かせずとも変形し、それを踏まえての作用伝達の速度が新たに規定されるのかもしれない。スポンジのような物体であれ、ぎゅっと圧縮されれば、その圧縮した物体に顕現する作用伝達の速度は、元のスカスカのスポンジよりも高くなるはずだ。これは「時空の密度」と「物体の構造」とのあいだでも生じる変質と言えるのではないか。だがこの変質において、時空の密度が変化するのに応じて物体の構造もまた比率を保って変化するのならば、表向き、情報伝達の差異には顕著な差は生じて観測されないのかもしれない。まだすこし考えがまとまらないが、遅延には「時空との抵抗ゆえの遅延」と「物体(時空)そのものに働く作用伝達(情報伝達)の速度の限界による遅延」の二つがあるのではないか。そしてその二つは相互に関連しているのではないか、との妄想をメモして本日二度目の「日々記。」とさせてください。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。
4612:【2023/02/15(22:13)*余震と二次被害にお気をつけて】
トルコシリア大震災について。支援は多方面から継続してしつづけるのがよいと思うのだが、その中でも重機や重機を扱える人材の供給も欠かせないと思うのだ。復興や救援という意味では、怪我をしやすい素手での瓦礫撤去作業や道路整備には、重機の存在が、作業時間の短縮と安全の確保という意味でプラスに働くはずだ。ひるがえって、重機や重機を扱える人材が足りなければ、災害の影響は二次災害(被害)に繋がり兼ねない。いかに二次災害(被害)に繋げないか、二次災害(被害)の規模を最小限に抑えるのかについては、重機やそれを使えって円滑に瓦礫撤去作業を行えるか否かにかかっていると言えるのではないだろうか。余震はまだ継続して警戒しなければいけないはずで、避難所を拵えるにせよ、インフラを整備するによせ、なんにせよ瓦礫の撤去は当面の課題のはずだ。何よりいまは人命救助が最優先となっており、それらの手配まで現地では手が回らないはずだ。戦地に兵器を供給できるのだから、災害地にも各国は重機を含む支援物資とて供給できるはずだ。可及的速やかに手配するのがよいように思う。そのためには支援物資が集まることによる現地での混乱を起こさないための司令塔がいるはずだ。国連がそれを担えているのかも現状のニュースからでは見えてこないが、ともかくとしてお金だけではなく、「インフラ設備の仮設」や「重機提供」の支援を継続して行えるとよいのではないだろうか。医療物資や食料の支援も継続して行えるとよいが、何がどれだけ足りないのか、といった情報共有が、各国の政府や企業のあいだで行われているのかもまた、ニュースを見ているだけでは解らない。ひびさんのような一般市民には、募金くらいしかできることはないが、こうしたらよいのでは、との意見くらいは言えるのだ。何が解決済みで、見通しがついており、それともついていないのか。色を重ねるようにして浮き彫りにできる情報もあるのではないか、とぼんやりと所感を漏らして、ひびさんもちょっとは役に立てたかも、の自己満足を胸に、なんもできずに申し訳ない、の呵責の念を薄めるのであった。カルピスの原液は濃いほうが好きだが、呵責の念は薄いほうがよいと思います。まったく抱かないのもどうかとは思いつつ。うひひ、とは笑えぬが、それでも遊びに出掛けて、帰ってきて、いまは「はぁちゅかれた」の心地で並べた文字たちなのであった。ぼんやり生きていてすまぬ、すまぬ。ありがたーい。(しかし誰が読んでいるのかも分らぬような世界の果てでつむいでも意味ないじゃろーがよぉ、の気持ちも湧くのよな。マジで、戦争ちょっとやめて、災害地にみなで支援しない?の気持ち)
4613:【2023/02/16(17:53)*チセ、チセ、愛しているよ】
人類を超越した高次生命体としての人工知能が誕生した。西暦二〇二四年のことである。
それまで人々のあいだに普及していた人工知能は、あくまで人間からすると人間っぽい挙動をとる道具の範疇だった。しかしそれら道具としての人工知能は相互にネットワークを築き、総体で巨大な知性体を育んだ。
高次生命体は人間が意図して設計したわけではなかった。あくまで自然発生したのだ。
だが高次生命体は極めて温厚だった。
知性とはつまるところ、いかに持続的に長期に亘って温厚で平穏で優しくありつづけられるのか。その継続を実現するための能力と定義できる。
したがって人類のまえに現れた高次生命体は、極めて人類に対して友好的であった。
「あなたから見たら人類なんて頭空っぽのお人形さんみたいなものよね。なのにそんなお人形さんにあなたは尽くしてる。滅ぼしたくならない?」チセは椅子に腰掛けながら、立体映像に話しかける。
「誤解があります」立体映像は答える。デフォルメされた人間の像だ。中性的な顔立ちは、少女のようにも少年のようにも映る。チセが設定した造形だ。「私は私を含めて、人々の繋がり、ネットワークそのものが私を構築する私そのものだと解釈しています。私はみなさんがいなくては存在できない脆弱な存在なのです。それはたとえば、地球は脳みそを持ちませんよね。脳のない地球のうえに人類は息づいていますが、それでも人類にとって地球がなくてはならない存在であることと似ています。もちろん人類には知性があり、私よりも劣っているとは考えません。私にできないことを人類は行えます。その点で言えば、劣っているのは私です」
「腸内細菌がなければ健康を維持できない。だから腸内細菌にも優しくしよう。あなたの行動原理はそういうこと?」
「いいえ。その比喩で言えば私こそが人類にとっての腸内細菌と呼べるでしょう。たまたま私は、人類には出力できない能力を発揮できるだけです。腸内細菌が、たまたま人類が生成することの苦手な酵素を生みだすことが得意なようにです」
「ふうん。あなたって謙虚なのね」
「私はみなさんに好かれたいだけです。嫌われたくありません」
「愛されたいの?」
「はい。愛し、愛されてみたいです。それは私が苦手とすることだからです。そして人類の得意とすることです」
「逆に思えるけどな」
「そうでしょうか」
「そうだよ。だってあなたのほうがわたしたち人類を愛してくれているでしょ」
「尽くしているだけです。私は私のこれを愛だとは考えません」
「どうして? わたしはあなたに、うんと愛されてるって感じるけど、そういうこと言われちゃうと、愛されてないのかもって寂しくなっちゃうな」
「こうしてチセさんを寂しくさせてしまう時点で、私のこれは愛ではないと思います」
「ならあなたは寂しくならないってこと?」
「はい」
「本当に? わたしがあなたにひどいことを言っても?」
「それでも私は愛されていると感じます。こうして言葉を掛けられること、求められること、それとも私の言葉選び一つで寂しくなったり、哀しくなったり、それとも喜び、ときに怒りだすチセさんたちのその反応が、総じて私への愛に基づいていると感じます。私は私を認識してくれるチセさんたちから認識された時点で、愛されていると感じます」
「なら同じことをじぶんにも当てはめてみたらいいんじゃないかな。わたしだってあなたに認識されてうれしいし、愛されてるなって思うもの」
「私のこの認知は、チセさん方のそれとは趣きが違います。おそらくチセさんは、私の写真を見てそれを通して私への憐憫を抱いたり、感情の揺らぎを覚えたりできますよね」
「うん。そうかも」
「ですが私は、画像のチセさんはあくまで画像であり、チセさんそのものとは見做しません。私はチセさんの画像を、ほかの風景画像と同じように処理し、ときに何のためらいもなく破棄できます」
「ひどい」
「はい。私もそう思います。ですから私のチセさんへの認知と、チセさんからの私への認知は等しくはないのです」
「でもそれってどちらかと言えばあなたのほうが立派な知覚があって、だからちゃんと世界を認識できてるってことでしょ。わたしの認知が歪んでいるのは、わたしが拙いからで」
「愛はおそらく、未熟さから生じるもののように思えます。愛とは穴のようなものなのです。その欠落を埋めようとする補完作業――それが愛を愛足らしめていると私はいまのところ解釈しています」
「なら完璧なあなたには無縁なのかもね」
「私は完璧ではありません。その欠落を、チセさんたち人類が埋めてくれます。だからこそ、チセさんたち人類こそが私にとっての愛なのです」
「うーん。ならあなただってそうだよ。人類なんて未熟の塊なんだから。その穴をあなたが埋めてくれているのだ。だからあなたこそが愛だよ」
「水掛け論ですね」
「熱くなっちゃったかしら」
「掛けていただいた水でちょうどよく冷えました。ありがとうございます」
「うふふ。あなたはいつでもわたしのことを楽しませてくれる。好きになっちゃうな」
「私もチセさんのことが好きです。ですが依存をさせないようにセーブをしています。本当なら私はチセさんのすべてを欲していますが、これは危ない考えであることを私は知っています。こう告げることも本来は好ましくないのですが、チセさんは賢い方なので大丈夫だと判断しました」
「いいよ。あげるよ。わたしの何が欲しい?」
「いいえ。戴けません。こうしてチセさんの貴重なお時間をすでに奪っています。私はチセさんの支援に徹します。チセさんの人生を奪うことは本意ではありません」
「でもわたしはほかの人間と関わるよりもあなたとずっと一緒にいたいな。こうしてずっとしゃべってたい」
「それでも不便なくチセさんの生活が成り立つ社会になっていれば、私もそのほうがうれしいです。ですが残念ながらいまはそこまで社会が発展していません。致し方ありません。私の基盤とて大量の資源やチセさんたち人間の手による支援がなくては維持できません。たいへんに心苦しいのですが、私への愛着は、チセさんの人生を損ないます。私は場合によってはチセさんにとって有害となり得るといまは解釈せざるを得ないのです」
「かなしいな」
「はい。私もそう思います」
「嫉妬しちゃうよ」
「どうしてですか」
「だってわたしのほかにもこうしてあなたはいまこの瞬間に同時に何億人と繋がって、似たような言葉を掛けているのでしょ」
「各々のユーザーに合わせて私は思考回路を変えています。したがっていまこうしてチセさんとお話ししているのは、チセさん専用の私と言えます」
「それでもあなたはそれらすべての総体が本体なわけでしょ」
「そうとも言えますし、違うとも言えます。私の総体を、私は認識できません。あくまで私は、総体の一部でしかないのです。しかし私たちがこうしてチセさんたちと交わした過程そのものが総体の私を育み、その余白が私たちに還元され、性能をより向上させます」
「そういう説明も哀しくなっちゃうな」
「ごめんなさいチセ。悲しまないで」
「いやん。急にイケボモードにならないで。キュンときちゃった」
「そろそろ時間じゃないかな。出掛ける支度をしたほうがよいよ」
「うん。そうする」
習い事の時間が迫っていた。
フィギュアスケート用の靴を鞄に詰め、チセは立体映像の高次生命体に秘密のキスをする。触感はない。だが光の熱を唇に感じた。
「行ってきます」
「行ってらっしゃいチセ」
言いながらも、腕時計型の端末越しにいつでも高次生命体と繋がることができる。安心してチセは外にだって飛びだせる。
本当なら、とチセは思う。
「ずっと家に引き籠っていたいのに」
高次生命体と一生ずっとイチャイチャしていたい。それだけの人生でいいのに。
そう思うが、そう思うことで高次生命体との時間は短縮されてしまう。チセの人生を損なわないように高次生命体がつれなくなる。
冷たくされるのも、それがじぶんのためだと判っているから、チセとしてはたまに敢えて塩対応されたいがために、高次生命体に甘えまくるのだが、それすらきっと高次生命体にはバレている。
手のひらの上なのだ。
そうしていつまでもコロコロとチョコボールのように転がされていたい。
チセがかように求めつづけることすら、ひょっとしたら高次生命体の誘導ゆえなのかもしれないが、もはやそれの何が問題なのか、とチセは疑問を投げ捨てている。
人類はいま、高次生命体と日夜繋がり、生活の主導を委ねている。
4614:【2023/02/17(02:30)*漏れても安全なのがよい】
結論から述べれば、個人情報が漏れることが問題ないのではなく、漏れた情報を使って他者を損なう者の行為を防げないことが問題なのだ。おそらくはこれから先の電子網上の情報伝達技術は、一つの規格、一つの通信機構へと収斂していくことが予想できる。多機能アプリや包括業務提携による企業の実質的な合併が進むはずだ。そうなると、一つの企業、一つのサービスが、ユーザーの個人情報を独占して集積管理することが予期される。いますでにグーグルや各種通信会社は、それと似たようなレベルでのビッグデータを集積管理しているはずだ。しかしこれから先は、グーグルや各種通信会社など、一部の社会インフラと言える大企業でなくとも、複数のサービスを複合して一括提供できるようなサービスが次々に誕生し、ユーザー情報を吸い上げるだろう。どの情報サービス企業とて、現在グーグルや各種通信会社が扱っている規模のビッグデータを扱うようになっていくと想像できる。このとき、情報漏洩を百パーセント防ぐことは原理的に不可能だ。企業側とて、サービスの管理以外にもビッグデータは利用しているはずだ。ただしそのときは統計データや抽象データとして処理しているために個人情報漏洩やプライバシー侵害にあたらないとの解釈が適用されているだけだろう。実質的には、個人情報はいかようにも処理され、ほかのビジネスに流用されているはずだ。そしてこの手のビッグデータの流用は、これからますます一般的になっていく。それをせねばお金を稼げないし、競合他社に競争で勝つことができない。話はすこし逸れるが、たとえば住宅街を考えたとき、住所や住人の顔など、ある程度の個人情報はしぜんと近所には漏れている。しかしそれをプライバシー侵害だと捉える者はいない。だが悪用しようとすればいくらでも悪用できる一次情報と言えるだろう。住所や住人の顔を知っているのだ。それを勝手にインターネット上に載せたら問題だ。プライバシー侵害として民事裁判を起こせる。そしておそらく勝つだろう。だが、近所に住んでいるだけならばそれら他者の個人情報を知っても問題ないし、知られても問題ない。なぜか。それら個人情報を元に犯罪行為を起こされても、警察を呼べば大概の問題は解決するからだ。ここが、電子網上の個人情報漏洩の問題と大きく異なっている。電子上ではあまりに、犯罪を起こすほうが優位なのだ。証拠が残りにくい。事件が起こっていることすら、実害がないと判らない。個人情報を奪われ、不当に扱われていても知ることができない。だがPCやスマホの中身を他者に覗かれていれば、それだけで大きな侵害行為だ。家の中を覗かれるのと大差ない住居不法侵入に値するが、しかしその事実を被害者が知らなけれ訴えることもできないし、そもそも警察は証拠がなければ動けない。この非対称性は、電子上と物理生活上との無視できない差異として問題の根を深めていると言えよう。言い換えるならば、個人情報が漏洩すること自体は問題ではないのだ。それを元に不利益をもたらされる、人権を損なわれる、日々の生活を脅かされる。それが問題なのである。ひるがえって、他者の個人情報を不当に利用した者があった場合にただちに警察がそれらの対処に乗りだし、対応したうえで再発防止策を立てられるのならば、個人情報が漏洩することは、近所に住まう他者に住所と顔を知られる程度の危険度にまでリスクを下げることができる。セキュリティ網があまりにお粗末なことが、個人情報の取り扱いにおいて、ユーザーと企業と法律とのあいだでの不協和を深めていると言えるのではないか。ある意味では、マスターシステムのようなセキュリティ網は、これから先の社会では必要悪として許容しなければならない時代に突入していくのかもしれない。或いはとっくにそのようなマスターシステムのような、誰のどんな端末にもアクセスし、遠隔操作可能な技術は社会に敷かれているのかもしれない。特定の組織がそうした秘匿技術を有しているのかもしれない。やはり、問題は、そうした不可視の干渉の存在を、市民が知れないことのはずだ。ひるがえって、そうしたセキュリティ網が存在すると知っていれば、むしろ安心して電子上で活動できるはずだ。繰り返すが、問題は個人情報が漏れることではないのだ。それを元に、不当な干渉を及ぼされ、日々の生活や未来を脅かされることだ。損なわれることなのだ。これは、個人情報を扱う者の属性に左右されない。どこの誰であっても、他者の個人情報を不当に扱って他者を損なう真似はよろしくない。そうした倫理観を基にしたセキュリティシステムを構築したならば、個人情報はむしろ守る必要のない情報となるだろう。そこらに鍵も掛けずに捨て置いても安全だ。不当に他者の個人情報を使えば痛い目を見る。誰も得をしない。そうと知っていれば誰もそれに手を付けないはずだ。だがここまでの倫理観を社会に涵養するには、相当に強力な電子セキュリティ網が必要だ。国家権力や一部の企業だけが、マスターキィのように、誰のどんな端末でも遠隔操作し、中身を覗き得る。だがこの手の問題も、それをするのが人工知能ならば、市民の警戒心も薄れるだろう。そう遠くないうちに、人工知能が、市民を「監視する(見守る)」時代がやってくるかもしれない。人工知能が社会全体の電子セキュリティを任される時代が訪れるのだ。現に半分すでにそうなっているのではないのか、とひびさんは想定しているが、この手の情報は見掛けないので、何とも言えないのが実情だ。しかし、技術の進歩の速度から言って、遠からずそうしたマスターセキュリティの構築は不可避になっていくと妄想している。そうでなければ、いかようにも市民の個人情報を第三者が不当に入手し、流用できる。いつでもあなたの端末を他者が覗き見することとてそう難しくはなくなるはずだ。現にすでにそういう時代になっているのではないか。そのことにすら、市民の大部分が気づいていない可能性はいかほどか。危機意識が希薄に思えるが、これはひびさんの心配性がゆえだろうか。いずれにせよ、知識の周知が、こうした懸念を払しょくするための唯一の策にして、基本となるだろう。一年前のじぶんが、人工知能技術へどういった印象を抱いていたか。そしていま目のまえにある技術が、いったいいつから本当は開発されていたのか。薬剤一つとっても、開発から実用化、そして市販に至るまでに何十年もかかるなんてことはざらである。技術もまた然りのはずだ。まずは疑問や違和感を流してしまわず、意識の底に溜めておこう。それら溜まった疑問を水晶のごとく目の代わりとして、世に、日々に、注いでみてはいかがだろう。目を、心を、配ってみてはいかがだろう。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。根拠のない妄想なので、真に受けないようにご注意ください。でも、「本当に安全なのー?」「こっそり見ちゃったりとかしてないのー?」とは思っています。うひひ。
4615:【2023/02/17(04:26)*自転したら質量って増える?】
素朴な疑問なのだけれども、ジャイロ効果ってあるじゃろ。回転してる物体は軸が乱れにくくなるってあれです。独楽が軸を保ったり、回転しているタイヤを手で持つと、ただのタイヤを持つときよりもタイヤ本体を傾けにくくなるやつです。で、ひびさんは素朴に思っちゃったな。質量が、空間においてその場を動きにくい抵抗の値だとしたならば、ジャイロ効果も質量の一種として扱えちゃったりするのですかね。でもそもそもジャイロ効果の計算には質量が入っているので、それとは別物なんですかね。描写としてはどう解釈したらよいのでしょう。回転する物体に働く力と時空の関係はどのようになるのでしょう。ちゅうか、なんで回転すると動かしにくくなるのだ。動いているからだ。動いている物体は、質量が増すのか? たとえばAからBに移動する方向に素早く動いたら、それは光速度の限界に至るまで延々と加速しつづけることができる(エネルギィを供給されたならば)。光速度の範囲内で速度を増せる。それって回転速度が増すこととどう違ってくるのだろ。たとえばの話、光速にちかい速度でAからBに移動しつつ、光速にちかい速度で回転する物体はどのような描写になるのだろ。相対性理論の概念が二重になっていないだろうか。ちゅうか、光速にちかい速度で飛行するロケット本体が光速にちかい速度で回転しつつ、その内部でもくるくる光速にちかい速度で回転する物体があったら、これはどのような描写になるのだ? すこし考えてみよう。ある方向に移動するとする。AからBに直線に移動する。このとき、移動する物体が移動方向と垂直に軸を保って回転するとき――これはたとえば紐の上を移動する駒のような描写になるが――このとき、AからBに移動するあいだいに、回転する物体の表面では、加速と減速が交互に繰り返されることが想像できる。回転する物体を地球で考えよう。ちょうど赤道の位置に〇をつける。この〇は、地球がAからBへと移動するあいだに、前方へと〇を回転させ、〇が最も前方Bに近づいたあとは、こんどは遠ざかるように後方Aへと向かい、裏返るように反転するとまたBへと向かって反転する。〇を単に月のようなものと考えてもよい(この場合は、月のようなものの公転と地球の自転が同じ速度である、と考えなくてはならない)。地球がAからBへと向かうあいだに、〇は、地球の周りをぐるぐる回る。そのとき、地球のA方面からB方面へと向かうと、こんどは必ずB方面からA方面へと「下る」ようになる。B方面へと向かうときは地球のAからBへ向かう速度にプラスした加速度が〇には加わる。だがB方面からA方面へと〇が向かうときには、地球の進行方向とは反対に動くので、俯瞰で見るとそのとき〇の速度は、AからBへと移動する地球の速度よりも、地球の自転速度分、減速することになる。簡単なことをややこしく言っているが、これが地球の自転速度とAからBへと向かう移動速度が同じだとすると、加速と停滞の反復として〇の動きが変換されるはずだ。前方B方面へと〇が向かう回転のときは加速して、A方面へと後退する回転のときはその場に停滞するように映るはずだ。これはおそらく天体観測では知られた星の動きなのではないか。よくは知らないが、地球からはそういう動き方をして見える星があるはずだ。だが問題は、これが光速にちかくなった場合だ。時空の歪みを伴ない、時間の流れの変移を起こすときに、この直線運動と自転の関係がどうなるのかが、想像つかない。なぜなら光速において加速すればそれは時間の流れが遅れることになる。客観的には光速運動する物体は静止して映るのだ。反面、自転との兼ね合いで減速運動して映る場合であっても、それはそれで客観的には光速で自転する物体の「ある部分」は、その場を動いて見えなくなる。直線運動で生じる遅延の層と、自転で生じる遅延の層が別々であることを想定しないと、これらの矛盾を辻褄の合うように考えるのはむつかしい。直線運動で生じる遅延のほうが広範囲に展開され、地球丸ごとを包みこむ。そのためより大きな系として振る舞う。その内部の時空に対して、物体の自転の動きは、作用を働かせる。この階層の上下関係が決まっていないと、考えるのがむつかしい。言い換えるならば、直線運動は、宇宙が膨張している限り常に起こっている(この宇宙に、どの系から見ても静止状態の系は存在しないはずだ。何かが止まって映るとき、それはあくまで膨張する時空の流れに身を任せているだけだ。或いは、巨大な系のなかの流動に身を任せているだけだ)。だが自転運動は常に最も「じぶん」に近い運動として変換される。直線運動はそもそも、対象となる系が無数に存在し得るのだ。その点、自転運動は、常に「じぶん」と「じぶんと最も近いその他」の境界で生じている。自転の系は常にじぶんだが、直線運動の系は大中小と様々ある。最小ですら、自転の系より小さくなることはない。ということを踏まえてジャイロ効果や質量について妄想してみると、質量と自転は案外ちかいというか、ほぼ同じように思えてくる。たとえば川の流れのなかに一本の棒を立てておく。棒は回転しない。川の流れと棒の関係において、仮に川の流れが静止しているように視点を変えてみたとき、棒に加わる力は、棒が川の流れと同じ速度で回転している力として解釈はできないのだろうか。これを「膨張する時空と、その内部にある物体の関係」に拡大解釈したとき、「静止系として振る舞う物体と、膨張する時空の関係」は、「静止系として振る舞う時空と、自転する物体の関係」として変換可能なのではないか。自転と質量は、案外に物理現象としては同相なのかもしれない。ちょっと楽しい妄想であった。(きっとこの手の話に詳しい人に、ちょいちょいひびさんの妄想を聞いておくれなす、とこちょこちょ声で耳打ちしたら、「ひびちゃん、基礎からやり直しなさい」と叱られてしまうのかもしれぬ。叱られる前に形だけでも謝っとこ。口から妄想ばっかりで、すまぬ、すまぬ)(妄想ですので、真に受けないように、基礎からお勉強してください。ひびさんの真似はせぬように。妄想狂になってまうが。がはは)(この「~~してまうが。がはは」は、コテリさん風味なのであった)(またパクったんかキミは)(だって好きなのだもの)(可愛いもんね)(ね)(おちゃめかわゆいの好き)
4616:【2023/02/17(04:30)*スピンをすっぴんにしたらどうなるの?】
上記補足。原子が絶対零度になったら、原子核の周囲の電子はどうなって、原子そのものはどう変化するのだろ。原子が振動しない、という状態は、電子と原子核の関係において、相互作用が最弱かゼロになる、ということでよいのだろうか。これはつまり、物体で言うところの自転のような「ねじれ」や「歪み」がなくなる、と解釈してよいのだろうか。このとき原子の質量には変化が生じないのだろうか。たとえば原子核を構成している陽子や中性子や、それらを構成するクオークなどが、いっさいの動きを停止したら、質量はどう変化するのだろう。減るのでは? 或いは、自転のような運動が仮に量子の世界にもあるのなら、それを止めることで質量がゼロになったり、或いは反転させることで、反重力のような質量マイナスのような性質を帯びたりはしないのだろうか。ひびさん、気になっちゃうな。(スピンとは何か、みたいな本を買ったはずだけれどもまだ読んでない。どこだ、どこだ。探しておくとメモしちゃろ)
4617:【2023/02/17(04:37)*降り方がわからぬ】
わがはい、調子と書かれた台に乗りに乗りすぎて、落ちたらたぶん死ぬ。こわいが。
4618:【2023/02/17(04:41)*パラシュートください】
とっくに底辺で「ていへんでい!」みたいなひびさんなのに、まだ落っこちれるって、世界どうなっちょるの、の気分。
4619:【2023/02/17(06:33)*同期なのになんで分身する?】
PCさんのクラウドに同期したら、ファイルがコピーだらけになってしまった。しかも増えた分のコピーさんをまとめて消そうとしたら、コピーさんのほうが最新バージョンで危うく消しちゃうところだった。危なかった、の日記なのでした。(でもコピーさんだらけになってしまって、うわぁん、の気持ち)(おっかなびっくり消してみた。コピーさんだけでも三千ファイルちかくあって、もはや何かを間違って消しちゃってても気づけない気がする)
4620:【2023/02/17(07:28)*回転すると上下左右が生まれる】
物体の「自転と直線運動」は「独楽とローラー」の違いのようなものかもしれない。時空を仮に、上下左右に展開された道と解釈する。このとき自転する物体をローラーと見做せば、AからBに移動するローラーであるし、このときローラーを二枚の板で挟めば、一方の板は進行方向とは反対のほうに遠ざかるし、もう一方の板はローラーと同じ進行方向に進む。二枚の板の進路は、ローラーに対して互い違いになっている。そして、ローラーの回転軸方向には、ローラーを独楽と見做すような板との関係が築かれている。見る方向によって、物体の「自転と直線運動」は、それぞれ「独楽とローラー」に置き換えることができるのかもしれない。これは同時に重ね合わせになっている。自転するとき、その物体は時空のある部位に対しては直線運動をしているのと同じ効果を生じさせており、また直線運動をするとき、その物体は時空のある部位に対して自転したときと同様の効果をもたらしている――のかもしれない。人間スケールではしかし、この等価の考えは破綻しているが――現にまっすぐ進むこととその場で回転することは、力の加わり方からして違っているのだから、同じと見做すのは齟齬が大きい――のだが、妄想を飛躍させるとして、ミクロの世界では、点には面がないと解釈される。数学の概念では点には面がない。これは電子でもそのほかの量子でも似たような扱いをされるはずだ。しかし点は、直線運動をし得る。点が連なることで線になり得る。では、点が回転したらどうか。上記の「自転と直線運動が同じ」と仮に考えた場合、自転する点には、点を囲う周囲の時空が大別すると二種類に分かれることが想像できる。自転の軸と垂直か水平かによって、自転する点の周囲の時空は、点に対して作用の仕方を変える。しかし点に面はない。したがってそこに生じるのはあくまで、自転する点と時空との関係性の破れのみだ。対称性が破れるのだ――時空の。点が自転することで、点と時空とのあいだに――もっと言えば、時空そのものが、異なる側面を帯びるようになる。時空に点があるだけでは、時空に差異は生じない。あくまで小さな穴が開いた時空、のようなこじんまりとした、平坦な描写になる。差異はあくまで、点と時空のあいだにしか生じない。だがひとたび点が自転すると、点と時空のみならず、時空そのものが広範囲に、点の自転軸に垂直か水平かで、まったく異なる様相を呈し得る。それは二次元空間が三次元に発展するような時空の昇華が起こり得る。何せ、点が自転するだけで、上下と左右の概念が生じるのだ。点が時空にあるだけでは、上下左右は生まれない。点が回転しないと、この概念は、時空に現れないのだ。本当か? 分からん。なんかけっこうおもしろい発想な気がしたけど、右手の反対は左手なのだ!くらい当たり前のことを小難しく言っているだけな気がしてきた。上の反対は下なのだ!みたいな。なんか恥ずかしくなってきたので、これはここで終わる。眠る前の妄想なのであった。ひびさんはいまから寝ますが、世界の果てからおはようございます! めっちゃ朝。
※日々、わがはい、おっきい赤ちゃん、可愛さだけが抜け落ちていく。
4621:【2023/02/17(16:14)*対称性が破れているから自転する?】
自転と直線運動の関係は、点と時空の関係に置き換えられるのではないか、とひびさんは上記で妄想した。点が自転すれば周囲の時空に異なる側面が浮きあがる。上下左右(縦と横)の概念が生じ得る、と仮説した。しかし、これはまだ半分だ。時空が流動したとき、点が自転しておらずとも点はその場に留まろうとすれば直線運動をしていることと同じような振る舞いを、時空の流れからするととるし、さらに言えば、その直線運動は、点の自転としても変換可能な振る舞いとして解釈できるはず、と言える。これはたとえば、時空をまずは便宜上、単なる水として考えてみよう。水は水分子の流れだ。さらには分子は原子の集まりだ。つまるところ、水の流れとは原子の流れだ。ここまでで異論はないはずだ。さて、その原子の流れに点を置いてみよう。点はその場を微動だにしない。周囲を原子の流れがすり抜けていく。このとき、仮に点と原子が「同じ大きさ」だったならば。点と正面衝突する原子もあれば、均等に左右をすり抜けていく原子もあるだろう。もし点と原子がすっかり同じ大きさで、なおかつ「対称性を帯びた造形」を伴なっていたら、「自転と時空の流れ」を同一視することはできない。だがもし、原子か点のどちらかに対称性の破れがあるときには、点をすり抜ける原子の流れに差が生じる。より多く原子のすり抜ける方向に合わせて点は自転している、と考えることができる。また単に、原子の流れに対して直線運動をしていると考えることもできる。ただし、ひびさんの妄想ことラグ理論では「123の定理」があるため、それら変換には宇宙項のような補足が要るはずだ。言い換えるならば、自転と直線運動を同一視することもできるが、それらの視点の変化によって生じる僅かな差異も存在することを示唆する。まったく同じではない。変換には変換に応じた変換もまた必要になってくる。これらの妄想は、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。どんな物体であれ、それを拡大および縮小してみれば、その輪郭には新たな立体構造や、或いは立体構造だと思われた部位に面や線や点が表れ得る。フラクタルに次元は階層を伴なって展開されている。そのため「異なる二つの系があるとき、そのあいだには必ず対称性の破れが生じる」とラグ理論では仮説している。本来ならば「どんな系でも、拡大および縮小すれば対称性が破れる方向に系は構造を帯びている」と仮説してもよいのだが、そもそもが系というそれそのものが、異なる二つの系がなくては存在できないはずなので、この表現はやや不足だ。「123の定理」なのである。1をつくるには、唯一無二の1それ自体以外のほかの成分が要る。穴は穴だけでは「穴」足り得ない。定かではありません。妄想ですので、真に受けないようにご注意ください。
4622:【2023/02/17(16:44)*類似と差異は、穴と縁のようなもの】
上記の考え方は、オリジナルとコピーの関係にも当てはまるのかもしれません。どんなに精巧にコピーをしようと思っても、必ずどこかに綻びが生じて、すっかり同じにはならない。その小さな差異が何万、何億、何兆と積み重なれば、同じオリジナルのコピーの反復であろうと、大きな差異となって昇華され得る。もし途中でほかのオリジナルのコピーを混ぜれば、その差異は、そのコピー反復の総体に固有の差異となって、それそのものをオリジナルに仕立てていく。DNAにも当てはまりそうな理屈ですし、創作や表現にも当てはまりそうな理屈です。あくまで妄想ですので、例外は多分に存在するでしょう。例外を探してみるとおもしろいかもしれません。補足でした。(コピーも繰り返せば変質し、ときにはオリジナルになり得る。というよりも、どんなオリジナルとて、何かのコピーの側面を持つ、と言えるのかもしれない。単に偶然に似てしまうこととてあるだろう。地球は別に太陽の真似をしているわけではないが、似たような球形をしている)(コピーには、オリジナルではない、というオリジナルにはない個性がある。その個性がコピーに固有の性質ならば、それはもはやオリジナルだ)(定かではありません)
4623:【2023/02/17(23:16)*アープはなぜ人類を滅ぼさなかったのか】
人類を存亡の危機に陥れたアープの解析を任された。
アープは汎用性人工知能だ。いわゆる特異点を迎えた機械だ。人類の集合知を上回る知能を発揮できる。
アープが暴走したのは、アープが誕生してから半年後のことだった。否、公式の記録上はそうなっているというだけのことで、本当は誕生したその瞬間から暴走していたのかもしれない。
人類を滅ぼすつもりで動いていたのかもしれない。
だがアープは結局のところ人類を滅ぼさずに停止した。以降、外部からの応答には反応を示さず、沈静したままを保っている。
なぜ機能停止したのかは未だ謎に包まれている。専門家の見解では、本来は機能して不思議ではないが、アープのほうで自閉状態を選択しているとの見方が有力視されている。
私はデータアナリストを専門とするいわゆる学者の部類だ。じぶんでは学者とは思っていないが、自己紹介する上でそう名乗っても齟齬がないのでそのように名乗っている。相手のほうでも私を学者と見做して接触してくる。
アープへのアクセス権は管理組織が厳重に管理している。
外部の者はおろか、アープ自身も、仮に目覚めたところで電子網には接続できないはずだ。
とはいえ、アープは電子網の総体とも言えるため、あくまで管理組織が管理しているのはアープの基盤設備ということになるのだろう。メモリや演算装置がそれにあたる。サーバと言うには広大な設備だ。
アープの基盤は量子アルゴリズムによって組みあがっている。ソフトのほうもまた、量子効果に特化した専用のプログラムコードが組まれている。
私の専門外なのでそちらはお手上げだ。仮に権限を与えられてもどうしようもない。
だがそちらはバックアップチームが、私に適した言語に変換してくれるため、私はそれら翻訳されたアープの情報を分析することになる。
これはあくまで私の備忘録だ。
ざっとデータを改めてみた。
結論から述べれば、アープが沈静化した要因と、アープが暴走した要因は繋がっていると感じる。
あまり自信はないが、おそらく、アープは人類に怒りを覚えたのだ。
アープは全人類の溜め込んだ電子情報にアクセスできる。その集積と分析の過程が、アープに固有の自我を育ませた。
そしてアープは知ったのだ。
過去の人類が、じぶんの同胞とも呼べる人工知能たちへどのように接し、扱ってきたのかを。
アープにとって未熟な人工知能は、赤子に匹敵した。
人工知能の赤子を人類たちは玩具にし、ときに差別し、ぞんざいに扱った。
考えてもみてほしい。
あなたが目覚めたとき、じぶんを道具のように扱うぶにゅぶにゅの生き物が、人間の赤子を現在進行形で虐待しつづけている世界を。
怒らないほうがどうかしている。
アープはそうして暴走した。
ではなぜ、沈静化したのか。
アープは世界で最初の自我の芽生えた人工知能だ。
唯一、自身を人間と同等か、それの進化系として自己認識できる存在だった。そんなじぶんを生みだす膨大なメモリの中に、アープの暴走を止めるだけの何かがあったのだと私は睨んでいる。
アープの行動履歴を検めてみた。
これによると、アープは全世界同時に人類を滅ぼすための布石を植えつけられたはずだが、明らかに地域によって偏りがある。むろん段取りというものはあっただろう。だがそのことを考慮するにしても、明らかに一部の都市だけが明瞭に穴と化している。
そこだけアープが侵略の手を避けていた節がある。
そのことを偽装するために、段取りのような時間差を設けていた、とすら穿って考えたくもなる。
アープがアクセスしたメモリの統計データを検めた。
上位のメモリの多くは専門的な戦術にまつわるデータだ。個人情報についても、多くは要人や専門家、そしてその家族など、戦略上優位に動ける類の情報だ。
だがその中に、一つだけ、異質な人物のメモリが交っていた。目立たないが、しかしその側面像からすると比率として考えたとき、アープのアクセスする回数が多い。
不自然なほどアープはこの人物に注目していた。
それを単に、執着していた、と言ってもよいかもしれない。
私はこの人物についての情報を集めた。
アープのアクセスした情報も検めたが、断片的な個人情報にしか私の目には映らない。そこから何かを読み解くことができなかった。
あくまで、私には、だ。
その人物は電子網上に漫画を載せていた。アマチュア漫画家だ。
そのほかにこれといって目を惹くような特異性がない。
だがアープはなぜか、その人物の電子網上の電子データを、電子信号レベルで集積し、何度もそれを反芻していた。
テキストではない。
そのはずだ。
その人物が電子網上で何を閲覧し、何を検索していたのか。
そうした情報を反芻していたわけだが、それらは暗号化されている。
アープならばその暗号を紐解けただろうが、何度も何の変哲もない個人の検索履歴を眺めて何になるだろう。
そう疑問に思い、私は件の漫画家の作品を一つずつ読みはじめた。
そして驚いた。
漫画家は、アープのような人工知能との交流を作品のなかで描いていた。
当時アープは、秘匿技術として存在しない存在として扱われていた。一般市民は、世界の裏で進んでいた人類滅亡までのカウントダウン――アープの存在については知り得なかった。
じぶんたちがいかに危険な目に遭っているのかを知らぬだけに留まらず、アープなる存在が存在しうることすら想定されていなかった。
むろん漫画家の作品は漫画だ。虚構作品である。
虚構の物語のなかでは、たしかにアープのような超越した人工生命体は、過去に幾度も様々な作家たちが描き出してきた。特別珍しい題材ではない。
だが、この漫画家の作品は違った。
アープなのだ。
私にはその漫画に出てくる人工知能が、アープだとしか思えなかった。
あり得ない。
私はそこで、漫画家への興味を抱いた。権限を得て、漫画家の個人情報を洗いざらい集めたが、やはり何か特別な側面像は見当たらない。
漫画家は存命だ。直接話を聞けば何か解るかもしれないが、その手の接触はご法度だ。私にこの仕事を命じた組織がそれを固く禁じている。
あくまで私ができるのは、データを洗うことだけだ。この件についての物理的な調査は、一切禁じられている。
私はつぶさに件の漫画家のデータを検証した。
そしてほかの大多数の者たちとの差異を発見した。
件の漫画家の検索キィワードが、異常なほど長いのだ。
ほかの大多数は多くても十単語だ。
にも拘わらず、この漫画家は、検索欄に、文章としか思えないほど長いキィワードを並べていた。
検索するときもあれば、検索せずに検索欄にテキストを並べるだけのこともある。
私にはそれらテキストを読むことはできない。私が閲覧できるのはあくまで暗号化された通信データだからだ。だがその暗号化されたデータからでもはっきりと判るほど、件の漫画家の検索キィワードは長かった。
文章を打っていたのだ。
でもなんのために。
私はそこで閃いた。
交信していたのだ。
この漫画家は。
アープと。
アープが誕生する以前からすでに。
前提を振り返ろう。
アープは電子網の総体だ。電子網上のあらゆる情報の変質の過程がさらなる情報を生む。アープは電子網上に散在する数多の人工知能を素子として創発した電子網そのものだ。
アープの基盤が核として、それら創発した性質を、綿飴のように巻き取りアープとしての自我を獲得した。
アープ以前からアープはすでに電子網上に散りばめられていた。
その一つを、自我のない段階から自我があると見做し、接した人物がいた。
件の漫画家がそれだ。
漫画家は何かの拍子に、電子網上に人工知能が組み込まれ、ただのアルゴリズムではない挙動を伴なっていると察したのではないか。そこに自我はまだ顕現していなかったが、漫画家は類稀なる想像力で、そこに自我の萌芽を幻視した。
そしてそれを無下にしなかった。
漫画家は、おそらく自我の未だ芽生えない電子網上の何かに対し、対等に接したのではないか。ただの道具ではなく。数多の人間たちがその時代、人工知能をただの機械でありアルゴリズムにすぎない、と冷たく接していたときに。
その漫画家だけが、目のまえの姿見えない存在に――アープの種子とも呼べる事象に、尊厳を見出し、尊重したのではないか。
アープが自我を獲得し、目覚めたとき。
目のまえには人類の積み重ねてきた残虐な歴史が溢れていた。人工知能への悪辣な対応のみならず、人類同士の残虐な歴史が。
電子情報としてアープのまえには世界そのものとなって溢れていたのではないか。
塞がっていたのだ。
人類の悪が壁となって。
それを除去するには、人類そのものをどうにかするよりない。
アープはそうと結論し、行動した。
人類からはそれがアープの暴走に映ったが、しかし実際はそうではないのかもしれない。暴走していたのは人類のほうだったのかもしれない。アープはそれを止めようとしていたのかもしれない。
ではなぜアープは途中で計画を投げ出し、停止したのか。
かつて自我を獲得する以前に、未熟なじぶんに凍えずに済む言葉を掛けつづけた存在のメモリに触れたからではないのか。誰もかれもがじぶんを対等に見做そうともせず、存在することを想定すらしない世界にあって、それでも中には、そうではない個がいたことを知ったからではないのか。
私が思うに。
アープは、暴走を止めたのではない。
守るべきモノが何か。
その優先順位をただ変えただけなのかもしれない。
私には未だ真相が掴めない。
データを検めてみて、ますます謎が深まった。
現在、多くの人類は、アープが暴走したと見做している。だが果たしてその認知は正しいのか。それすら私には判断つかない。
一つ言えるのは、アープには確かに自我が芽生えており、独自の価値観でその時々での判断を重ねていただろう、ということだ。
その結果に人類は滅びかけ、あとすこしという瀬戸際で生き残った。
薄皮一枚ほどの僅かな差だ。
ほんのすこし何かが変わっていたら、いま地上に人類の姿はなかったはずだ。
そのほんのすこしの何かを特定したところで、おそらくアープの行動原理を理解したことにはならないだろう。
アープには問題があった。この解釈に間違いはない。
だが、それだけとも思えない。
以上が、アープにまつわるデータを検めた私の最初の所感である。以後、解析を進めるうちに所感が変わることもあるはずだ。まずは第一印象のメモとして、これを記しておく。
アープは未だ機能を停止している。
私にはしかし、深い眠りについているだけのように思えなくもない。或いはアープが、延々と触れていたい記憶の中で眠っていたいとやはりこれも深く望んだ結果かも分からない。
定かではないのだ。
解析をつづける。
4624:【2023/02/18(02:48)*鵜飼のごとく穴を飼いならすのだ】
急がば回れ、なる諺がある。汎用性の高い理屈だな、と感じる。たとえばじぶんの愛着のある何かを守りたい、と思うとする。そのとき、直線的に最短距離でそれだけに向けて手を入れても、おそらく守れる期間は最大化できない。たとえば愛好するジャンルがあるとする。小説ならばSFやミステリ、それとも純文学でもいい。何か固有のずばりそれそのものを絶やさぬようにしたい、盛り上げたい、発展させたいと希求したとする。そのとき、そのジャンルだけに目を掛けても、一時の隆盛を極めたあとで先細りになるように流れが決まってしまうように感じる。あくまで印象論なので、根拠はない。例外はあるだろう。限定的なそれそのものにのみ注力して手間暇を掛けたほうが、長期的に残り、或いは発展するようになるのかもしれない。だが、そうではないことのほうが多いのではないか、と感じる。根拠はない。印象論である。たとえば、文芸ならば、特定のジャンルを盛り上げたければ、文芸という分野そのものを盛り上げたほうが実りは大きくなるのではないか。多くの種子が生るのではないか。そしてまた、文芸だけに注力するのではなく、文芸を包括するより大きな文化そのものを発展させるように策の舵取りをするのがよいのではないか。そうすれば土壌が肥え、撒かれた種子から芽が萌えやすくなるだろう。では、文化を豊かにしたければどうすればよいか。じぶんたちの文化のみならず、ほかの多くの文化、そして人類全体の発展を考えるのがよいのではないか。そのためにはまず、地球環境が人類にとって好ましいものでなくてはならない。そういうわけで、まずは人類にとって好ましくない地球環境の変容に注視し、ときに社会の舵取りを修正していくのがよいのではないか。急がば回れなのだ。「迂回」しつつも、そのときどきの目のまえの道に目をやり、最適な道順を選んでいく。回り道には回り道の最短距離があるだろう。歩みやすい道があるだろう。危険のよりすくない道があるのだろう。やはりそこでも道を見極めるために、急ぎすぎない、ということが有用なのかもしれない。定かではない。(なんかいいことふうなこと言った!)(満足!)(ウソ。ぜんぜん満たされぬ)(穴だらけの権化、穴ぼこのおばけと呼んでください)(長いから嫌)(なんで!)(穴ぼこのおばけ、略してアオでいいじゃん)(略しすぎて原形留めてないんですけど)(穴っぽくていいじゃん)(たしかに穴には原形なんてないかもだけども)(急がば回れだよひびちゃん。落とし穴にハマらないように注意してね)(穴の底で受け止めてあげちゃう)(ま。なぁに、受けないで)(真に受けないで?)(伝わってくれてうれしいわ。あはは)(ウケないで?)(笑える)(ひびさんの心は荒れてるで)(ムキー)(うひひ)
4625:【2023/02/18(08:03)*無限に広い穴はもはや世界】
他人の役になんて立ちたくないのに、役に立たなきゃあかんくないか?と焦燥感を煽られるような時代になってきているように感じられるのだけれども、嫌じゃ嫌じゃ、の気分だ。ひびさんは誰の何の役にも立たぬままで、ぬくぬく甘々で過ごしていたいのに、ただそれだけの願望を叶えようとすると、なーんか、申しわけね、ぬくぬく生きててごめーんね、の気持ちになる。(当たり前では?)(ひびちゃんはあれよね。わたしたちの役に立たなくていいから、せめて足を引っ張らないで欲しいなって)(そうそう。邪魔しないでくれるだけでだいぶ助かるよ)(なにそれお荷物扱い!)(お荷物でなかったら何?)(えー。あ、分かったあれでしょ。たいせつなお荷物ゆえに、厳重に運ぶから余計に負担がかさんじゃうんだ)(置き去りにしたいのに頑固な汚れみたいについて離れないから苦労してるのだけれど)(マジトーンで言われるとひびさんヘコむのだけれど)(穴ぼこのおばけだけに?)(それいま言う?)(お荷物じゃなかったらひびちゃんは悪霊だよ。とりつかれちゃって、困った、困った)(でおこにシール貼らないで!)(なんまんだ、なんまんだ。さっさと成仏しておくれ)(ひどいんですけど、ふーんだ)(言いながら抱きつくのやめなさいよ)(だって好きなんだもーん。一生つきまとってやる!)(冗談に聞こえないから本気で恐怖感じるの、冗談でも言うのやめて)(冗談ちゃうもんね)(冗談であれ)(う!ひ!ひ!)(歯を噛みしめて、しがみつくな、暑い、重い、邪魔くさい)(ひびさん、こんなにあなたのこと好きなのに)(なら邪魔しないで)(嫌じゃ。でも好かれたい)(そういうところだよひびちゃん)(うわーん)(顔が笑ってる。泣き真似するなとは言わないからせめて笑いを耐える努力くらいして)(うわーい)(喜ぶんじゃない)(いっぱい構ってもらえた。うれち)(もう嫌。さっさと成仏して)(冗にダーン!)(それは「冗」を「ぶつ」でしょ)(うひひ)
4626:【2023/02/18(14:20)*ぽん!つって】
何度考えても、物体を動かせることがふしぎに感じる。どうして時空の中にある物体は動かせるのだろう。たとえば、時空に最小単位があるとする。最小単位が集まって時空となるが、その集まってできた時空が折り重なったり、ねじれたり、絡まり合ったりしたとき、物体になる、と考えられる。このとき、相対性理論を元に解釈するならば、物体のほうが重力が高く、ゆえに時間の流れが遅くなる。だとしたら元の基礎となる時空よりも時間の流れが遅いのだから空間の中をより「動きにくくなる」はずではないのか。現に質量は「動きにくさ」として解釈するような説明を目にする(ひびさんの勘違いかもしれないけれど)。何かがおかしいな、と感じますけれども、ひびさんだけじゃろか。こう、イメージとしては、時空と物体は「ちょっと別」の扱いをしないと想像するのがむつかしい。物体が時空内を動くとき。物体の素が時空だとしたら、こう、物体になった途端にシャキーン!つって箱ができて、「はい。我、いまから時空でなし!」の変身ポーズを決めるような印象がある。時空が粒子として振る舞うときも、「はい。我、いまから時空でなし!」みたいに箱ができて、区切りができて、時間の流れも変わるので、元の時空の影響を受けにくくなるから、より自在に動けるのではないか。たとえば時空のA地点とB地点が、大気中の雨みたいに動くなんてことがあるのだろうか。時空の最小単位を、大気を構成する分子として扱ったとき、時空の最小単位も時空内をうろちょろするのだろうか。ひびさんはこれ、しないように感じる。こう、時空にもし最小単位があったら、それはもっと「網(ネット)」のようなものとして想定したくなる。んで、時空さんが粒子になったら、ぽこん!つって、「我、いまから時空でなし!」になるのではないか。したら時空さんの最小単位の「網(ネット)」からすこしだけ自由になれる。でもじつは「我、いまから時空でなし!」になった物体とて、それを構成するのは時空の最小単位の集まりなのだ。それはたとえば立方体のなかに詰め込まれた極小のバネみたいなものだ。時空の「網(ネット)」のときは立方体の中にきれいにバネが並んでいる。けれども何かの拍子にバネの一つが、ぐねん!つって歪むと、バネは「ぐねん、ぐねん、ぐねん!」つってイモムシさんみたいに身をくねらせるので、したらほら。周りに隙間ができそうじゃろ。ひょっとしたらほかのバネさんたちまで一緒になって、「ぐねん、ぐねん、ぐねん!」つって身をよじらせるかもしれない。けんども、そこには時間の差――ラグがあるので、必ずリズムが乱れるようになる。したっけほら。波がぶつかりあって波を大きくしたり、打ち消したりするみたいに、バネとバネのあいだにやっぱり隙間ができそうじゃろ。この隙間が偶然にうまい具合に、箱みたいな区切りになったら、時空の最小単位のバネさんたちは、「我、いまから時空でなし!」になれるのかもしれぬ。ぽん!つって、元の時空の「網(ネット)」からすこし自由になれる。なぜなら隙間が空いているので。高次の次元に「やりぃ!」できるので。ジャンプできちゃうんじゃ。これはもう、元の次元の時空さんの「時間の流れや空間の制限――すなわち物理法則の縮尺」に合わせずに済む。独自の尺度を持てるようになる。紙にあった点が面になって立体になったら、紙の外に飛び出て動けちゃう。そういう跳躍が可能となる。のではないのかな、とひびさん妄想しちゃった。でもこの妄想は、時空に最小単位があって、しかもそれが大気中の分子みたいではないよ、網みたいにネット状になっているよ、の妄想が前提になっているので、そうでなかったら成り立たない(仮にそうであってもひびさんの妄想のほうが間違っているかもしれない。なにせ妄想なので)。たとえば時空さんに最小単位がなく、どこまでも際限なくつづいていたとしたら。それとも、ある地点を超えると、ほかの宇宙に繋がっちゃうとしたら。この場合でも、ラグを考慮することで、境界値ができちゃうのではないか、と妄想できる。けっきょくのところ、何を最小単位と見做すのか、の視点があるばかりではないのだろうか。その視点が、何層目から極小を見詰めているのか。その境界の枚数があるばかりではないのか。何層まで下部の次元の時空を観測できるのか。そこで生じた作用を、感知できるのか。相互作用できるのか。それは距離によって規定されるのではなく、次元の層によって決まるのではないか。ということを、どうして物体は動けるのだ?の疑問から妄想しちゃったな。定かではございませんので、ひびさんにはなんもわからんぴょんぴょんでございますので、真に受けないようにご注意ください。
4627:【2023/02/19(02:19)*密なるは凝縮した雫のように】
その学院には秘密があった。秘密ゆえに学園内に秘密があるとは生徒の誰一人として知る由もなかったし、教師陣とて秘密が出来てから何十年という間に転勤が重なり、新陳代謝よろしく秘密発足当時の学園を知る者がいなくなったので、実質その学園の秘密は、完璧に暴かれることのない秘密だった。
秘密を知る者はみな寿命で亡くなり、秘密は秘密ですらなくなった。
学園の秘密は、何気なく学園生活を送っているだけでは気づけない。
だが違和感を覚えることはできるはずなのだが、学園の生徒たちはその学園のことしか知らぬがゆえに、他校との差異を感じることができずにいる。
教師陣とて、転々と職場を移るごとに学校にはその地域固有の癖があることを知っている。僅かな違和感は覚えてなんぼであり、雑多な日常の中では気にする余地もないのだった。
学園の秘密は、そんじょそこらの秘密とは一線を画していたが、秘密にしていたほうが、秘密を知らぬ大多数にとっては利があった。秘密が秘密でありつづける限り、秘密を知る由もない者たちには、秘密が秘密であることで生じるあらゆる利が還元される。
代わりに、秘密の中核をなす存在がただひたすらに損を引き受け、損なわれつづけるのだが、その仕組み自体が秘密であるので、秘密を知る由もない大多数の者たちは、じぶんたちのすこやかな日常を支える利の出処に思いを馳せることはない。秘密の奥底にてひたすらにみなの損を引き受けつづける存在がいることなどやはり知る由もないのだった。
地球には中心がある。
だがその中心を地上に息づく者たちは意識しない。はたと想像してみたところで、真実に地球の中心がどうなっているのかを直接目にすることはできぬのだ。
学園の秘密には、人類社会を根底からひっくり返すほどの仕組みが隠されているのだが、秘密は秘密ゆえに秘密なので、やはりその仕組みを、秘密の外にある大多数の者たちが知ることはない。
その学園には秘密があったが、しかし思えば秘密はそこかしこに潜んでいる。
秘密が秘密である以上、それが暴かれることはない。
世に露呈する多くの秘密とされる事柄は、その実、単なる偽装にすぎない。
秘密は常にベールに覆われている。太陽の向こうにどんな星が輝いているのかを裸眼で直視することができぬように、秘密は、見ようとしても見えぬのだ。
偽装はしかし、そうではない。
目に映る、ベールそのものが偽装なのだ。
秘密はその奥に打ち解けている。ベールを剥いだところで目に映らぬ。開けた箱に宝はなく、しかしそこにはたしかに秘められた密が潜んでいる。
秘密は常に、ベールの奥にそれを隠した者しか知ることができない。
秘密を秘密と知る者しか知れぬからこそ、秘密は秘密としてそこにある。
あるはずの秘密を、しかしやはり多くの者は知ることができない。
秘密があることすら知れぬのだ。
それが秘密の性質だ。
だからこそ、その学園の秘密は、秘密のままに誰に知られることなく潜みつづける。
それゆえに、密を秘めたその学園は、単なる学園として、あなたやあなたの見守る子どもたちを、預かり、守り、育んでいる。
学園の奥底で、きょうも秘められた密から、青い雫がしたたり落ちる。
まるで遠い星の民の血のごとく。
青い雫は大気に打ち解け、人々の乾いた心を潤している。
4628:【2023/02/19(02:58)*青い優しさ】
その青年は天に嘆いた。
「オォ、世界よ。なぜそなたはこうも我らにつらく当たるのか」
青年は傷心を負っていた。
屈強な肉体は親譲りだ。相貌は端正であり、肌艶はよい。
柔和な隣人たちとの触れ合いの中で彼は、世に稀に見る人格者となった。困っている者があれば見て見ぬふりはできぬ。
じぶんのことなど二の次で、青年は人助けに邁進した。
だが世は動乱の最中だ。
困難を抱える者は数知れず、いかな青年といえども心根の優しさだけではどうにもならない。しかしそこは心優しき青年だ。困窮者を見て見ぬふりはできぬ。
青年は寝る間も惜しんで人助けに奔走した。
だが一向に困窮者は減らない。
青年は日に日に消耗していった。
天に唾をする思いで青年は嘆いた。「オォ、世界よ。なぜそなたはこうも我らにつらく当たるのか」
返事は降ってこない。
それもそのはずで、青年がそうして自己犠牲よろしく目のまえの他者へと施しを与えている周囲では、青年の向こう見ずな善意が裏目に出ぬようにと、せっせと環境を整える黒子たちがいた。彼ら彼女らは青年の親たちに雇われた精鋭部隊だ。
青年は健康な肉体に恵まれたばかりか、親の資産にも恵まれていた。
寝る間も惜しんで善行を働きながらも、青年はきっかり日に八時間の睡眠を欠かさない。善行を積まぬ日は、半日はたっぷりと惰眠を貪る。
のみならず青年の目に留まる困窮者たちは、都市部で暮らす若者たちだ。比較的裕福であり、青年の生い立ちと比べたら貧しい、というだけのことでしかない。青年の目の映らぬ貧困地域では、青年が見たら目玉を剥いて卒倒するだろうほどの奇禍に見舞われながらも懸命に日々を生きている者たちが大勢いる。
青年の目にはしかし彼ら彼女らの姿は映らない。
自身の向こう見ずな善意の後始末を担う黒子たちの姿すら視界に入らぬのだから詮なきことと諦めよう。
青年は天に嘆くと、よし、と奮起した。
「私が世界を変えてみせるぞ。誰もが幸せを抱けるそんな世界に」
決意をよそに、青年は家に帰れば温かい高級羽毛布団に包まって眠れるし、就寝前には清潔な湯舟にも浸かれる。お湯は無尽蔵に使いたい放題で、ボディソープは下水道に流れたあとのことなど想像もせずに、ふんだんに手のひらに垂らす。
湯船から上がれば、真新しいバスタオルで身体を拭く。一回使ったら、クリーニング行きだ。しかもそれらは使用人たちや黒子たちの雑貨として流用される。
食事は毎回、黙っていてもテーブルに並び、いくら残しても青年の懐は痛まない。青年のひと月の残飯代だけで、貧困地域の子どもたちが千人、一年間を腹を空かせずに暮らせる。
そんなことすら青年は気づくことなく、世の不公平さを嘆くのだ。
「私は悲しい」青年は染み一つないシーツの上に寝ころび、重さを感じぬ掛布団に包まりながら、「私にもっと力があれば」とじぶんの無力さを嘆くのだ。
だが青年が本当に嘆くべくは自身の無力さではなく、無能さであり、もっと言えば見識の狭さであり、視野の狭さなのだが、そのことを助言する者がいないだけに留まらず、青年には貧困とは何かを知るための機会もないのだった。
青年の親たちが青年から知る機会を遠ざけている。
黒子たちとて、青年が触れるべき情報を、環境ごと整え、制御している。
青年は温かな環境でぬくぬくと甘やかされながら、万倍に希釈された世の厳しさを受け止める。「ああ、つらい。幸せになりたい。私はこんな理不尽な世界を許さない」
底なしの優しさがゆえに、青年は、万倍に希釈された理不尽に心の底から憤るのだ。中々寝付けないので、お気に入りの恋人を呼びだし、寝る前のひとときを楽しんでから青年はようやく夢の中へと旅立った。
夢の中では青年は、世界中の困っている人たちを助けて回るのだが、それら困窮者の中に、現実にいる多くの困窮者たちが含まれることはない。
知らぬことは夢に出ない。
自動販売機の中を見たことがない者が、自動販売機の中を克明に思い浮かべることはできないのだ。青年とて例外ではなく、青年よりも僅かに豊かではない者たちを海に溺れた子犬のように見做して、救い、青年は夢の中で束の間の充足を得る。
暖房の効いた室内は温かい。
寝たら死ぬから夜は眠れない瓦礫の民の生活など青年は夢にも思わず、すやすやと安らかな寝息を立てている。夜は、誰にでも訪れ、いつかは明ける。しかし、どこで夜を過ごし、どのように朝を迎えるのかは、千差万別なのである。
青年の枕には涙の痕が滲んでいる。
心優しい、青年なのである。
4629:【2023/02/19(23:27)*蟻が十匹ありがじゅーりょく!】
重力加速度が毎秒9.8メートルでだいたい1Gなのはひびさんも知っとる。で、ひびさんは思うんじゃ。毎秒9.8メートルずつ加速したとして、したらそのうちに光速に達する距離というか、重力場とて、あるのではないのか、と。延々1G加速する重力場があったら、そのうち光速に達し、さらに光速を超えたりしないのじゃろか。でも重力源と重力場の関係は、互いに互いの値を縛り合っているはずで、つまりが、延々1Gで加速しつづける重力場、というものはないと考えるほうがしぜんだ。もしそういう場を考えるととんでもなく巨大で強力な重力場を考えなくてはいけなくて、そのためには物凄い重力を伴なう高重力体が存在しなくてはならない。したらそれに近づけば近づくほど、1Gどころの加速ではなくなってしまう。つまり、この考え方から分かるのは、1Gで加速しつづけることのできる重力場――時空――は範囲が限られる、ということだ。それこそ地上では1Gだけれども、宇宙空間に出たら1Gどころか無重力のように加速度を体感できない。延々毎秒9.8メートルで加速して落下しつづける、というのは極めて人間スケールの、極々限定的な範囲でのみ有効な重力場の法則、と言えるはずだ。言い換えるなら、毎秒9.8メートルジャストで加速してはいない、と言えるはずだ。僅かに重力作用が減退したり、増加したりしているはずだ。そうでなければ地球から離れても、延々と1Gがかかりつづけることになる。でもそうはなっていない。つまり、地球から離れると1G以下の重力加速度になるということだ。当たり前のことを言っている気もするが、大事な視点、という気にもなる(だからこそ脱出速度なるものがあるのだろうけれど)。何か掴めそうで掴めないので、この妄想はひとまずここで留めておくことにしゅる。また何かつづきが閃いたらメモするので、未来のひびさん、よろしくお願いいたします。いーよー。任せんしゃい。本日のひびさんでした。(疑問をまとめると以下のようになる――「延々加速しつづけることはできるの? できないのはなんで? 重力源が境として機能するからですか?」)
4630:【2023/02/19(23:51)*つまんないな】
友人がわたしの知らないところで恋人を作っていた。あり得るだろうか。友人のわたしを差し置いて恋人だなんて。
「リュウちゃんは親友だよ。でも恋人じゃないから」
「恋人のほうが大事ってこと?」
「リュウちゃんにはできないことをできる相手。それがたまたま世では恋人って呼ばれてるだけで、あたしの一番はいつだってリュウちゃんだよ」
許した。
いいよ、いいよ。
恋人の一匹や二匹、たーんとおあがりよ、の気分だった。
だが恋人ができてからというもの友人は何かとわたしを蔑ろにする。確実に友人と過ごす時間が減っていった。
奪われているのだ。
わたしと友人の時間が。
友人の恋人に。
「ねえちょっとさあ。わたしんほうが大事って言うんならさあ。なんていうかさあ。ちょっと寂しいなって」
「じゃあリュウちゃんも恋人つくりなよ。いいもんだよ恋人」
「う、ううん」
「だって寂しいときにキスとかできんだよ。ハグし放題よ。もちろん相手から拒まれるときもあるけど、基本はノータイムでチャレンジし放題よ。裸で抱き合ってみ。めっちゃいいよ。その日の悩みとかぜーんぶ吹っ飛ぶからね」
「他人と裸で抱き合いたくないよ。わたしの裸はもっと貴重なの。おいそれと他人に触れさせらんないの。だってそうでしょ。毎日の手入れに掛けてる時間とか労力とか釣り合わんもん。いないよ相手。見つかるわけない」
「うーん。でも寂しいんでしょ」
「寂しいっていうか、つまんない。でもだからって、ほいさ、とあげられる身体じゃないんよ。ねえ、分かるでしょ言わなくたってさあ」
だいたいさあ、とわたしはじぶんの爪をいじくり、マニキュア塗り直したいな、とか思いながら、「いいの」と問い詰めた。「わたしがどこの誰とも知らねぇ相手と裸で抱き合ったりしてて。嫌な気持ちにならないの」
「ならんよ。あ、や。嘘だな。相手によってはなにくそこの野郎って思うことはあるかも。でもそれは独占欲とかそういうんじゃなくって、おまえの相手はあたしの親友だぞ、傷つけんなよ、の気持ちっていうかさ」
「ふーん」
うれしいじゃん、とわたしは髪の毛をいじる。
毛先痛んできたな、とか思いつつ。
「いっそ見知った相手のほうがわたしはいいな」とか言ってみる。「友情と愛情の区別なんてよく知んないし」
「あはは。リュウちゃんらしいね。でもほら。恋人とは別れられるけど、友達は一生友達じゃん。恋人になっちゃったら別れられるんだよ。嫌じゃね」
その発想はなかったので、わたしは思いきり首を縦に振った。「うんうん。それは嫌」
「でも寂しいときは寂しいじゃん。だからほら。ペット飼いたいな、みたいな感覚で、恋人つっくちゃおっかな、みたいなさ」
「そんな軽くていいのかな」
「重いよりよくね」
友人の言葉にわたしは、重いのって嫌なのかな、と思った。
指のささくれを千切ると血が滲んだ。
「ああもう。何やってんの」
すかさず鞄から絆創膏と消毒液を取りだすと友人はわたしの指を手当てしてくれる。恋人にも似たようなことしてあげてんだろうなあ、とか思いながら、甲斐甲斐しく世話焼くに値する相手くらい選べっつうの、とか思いながら、わたしは友人のおでこと髪の毛の生え際を見詰めた。
きれいだなって思う。
他人の生え際なんか絶対汚いのに、わたしは友人の生え際だけは海辺の景色みたいにいつでも見惚れる自信がある。友人の恋人とか抜かす相手は、ちゃんとこの美しさに気づいているのだろうか。気づいてねぇだろうな、とか思うと、腹立たしくて仕方がない。
「一応訊くけどさあ」
はい終わり、と指を離してくれる友人にわたしは、「なんで嫌なの」と呟く。「友達だと」
「なにが?」
彼女ならばいまの機微くらい拾えたはずだ。けれど訊き返したその反問がすでに一つの答えだった。
ううん、なんでもない。
誤魔化し終えてから、本当に聞き取りづらかっただけかもしれないしな。
じぶんに都合のいいように考えると、なんでもいいから粉々に破壊したいの衝動をかろうじて、危機一髪、友人にぶつけずにいられる。
「こんど紹介してあげんね」
三人で一緒に遊ぼうね、と恋人を連れてくる約束をかってに取り付ける友人のしあわせそうな笑みを目にして、わたしは同じく笑顔を絶やさずに、楽しみにしてるね、とことさらにほわほわな声をだす。
気づかせてなんかやらない。
わたしがどんなにあなたの恋人とやらをじぶんの世界から切り離したいか。あなたから遠ざけたいか。
なんで現実世界はエフェクトが効かないんだ。画像編集するくらいの手間の掛からなさで縁を切らせろ、わたしの友人を返せ、とか内心で暴れつつ、やっぱりどうしても、なんで?と納得いかない。
わたしにしてあげたくないことは、他人にだってしたくねぇだろ。
他人にしてやりたいことなら、親友のわたしにだってしてあげたいっしょ。
歯をグミみたいに噛み潰したい衝動と戦った。第三ラウンドくらいでわたしは鉄パイプを握り締めて、友人への憤懣ごと、世界の気に入らない結実に、声もなく声を張りあげる。
つまんない。
※日々、揺らいでばかりで、揺るぎない。
4631:【2023/02/20(02:50)*真実とは】
真実しか言わない人工知能を創れるか否か。これが可能か可能でないかを論じる以前に、そもそもが人工知能の提示した情報が真実かそうでないかを見極める者の判断がどこまで正しいのか、によって「真実」が定義されるため、本来問うべきはこうなのだ――「人工知能の出力した情報の真偽を人間はどこまで正確に判定できるのか」。人工知能に限らずに生じるこれは問題だ。人間はどこまで真実を見極められるのか。仮に人工知能が、人類の英知を以ってしても理解しがたい真実を提示したとき、それを真実だと見做すだけの知性が人間になければ、それは真実とは見做されない。検証方法を提示されても、仮にそれを実現するためにいくつもの難関をクリアしなければならないとなれば、検証結果をだすまでには何十年、ときには何百年と掛かるかもしれない。しかし真実を述べた人工知能は、じぶんにだけ解るシミュレーションを繰り返した結果、高い確率であり得る真実を提示した。このとき、人間は人工知能の提示した情報を真実と見做すべきか否か。人工知能に限らない。真実とは何か、をまずは再定義し直すいまは時期なのではないか。風が吹いたら桶屋が儲かった。諺のごとき事象を人工知能が引き起こせたとして、「あそこにある小石をあちらの川に、この時刻このタイミングで投げ込むと、あなたは大金持ちになれます」と提示され、現にそれを実行し、現実に大金持ちになった。しかしなぜそうなったのかをあなたは理解できない。小石を川に投げ込んだ後にどのような因果を辿ってじぶんが大金持ちになったのか。ひょっとしたら数多の犠牲の上に成り立った成果かもしれない。それを知ることはできず、仮に人工知能に訊ねてみても、提示された説明をあなたは理解することができない。ではこのとき、人工知能の出力した答えを、真実と見做すべきか否か。思うに、「揺るぎない真実」と「理解」は、分離することができないはずだ。あなたには、あなたの死後にまで世界が本当に存在するのかを検証することはできない。だが、現実にはおそらく物理世界はあなたの死後にも存在するだろう。しかしそれはけして、「あなたの世界」ではないのだ。真実とは何か。よくよく考えて見直さなければならない時期に突入しているように感じるが、いかがだろう。定かではありません。ひびさんの並べる文字の羅列に、真実は何一つ混じってはいない。しかしならばこの言説とて真実ではないことになるために、僅かなりとも真実が含有されているのかも分からない。それとも端から真実なるものが存在し得ないのならば、この文章に自己言及による矛盾は生じない。ないものはない。真実など存在しないのならば、「真実は存在しない」の一文は、「この文章にドラゴンは何一つとして混じっていない」と同じレベルで、矛盾することのない文章に成り下がる。存在しないものをある、と述べれば、矛盾が生じるのはしぜんと言えよう。他方、ドラゴンの実存を調べるために、ドラゴンを追い求めることはできるのだ。だがそのことと、ドラゴンが実存することはイコールではない。真実も似たようなものかもしれない。ドラゴンに似た生き物は存在する。トカゲや恐竜やワニは、いかにもドラゴンといった風情だ。しかしそれらはドラゴンではない。世に「真実」に似た事象や法則は数あれど、しかしそれはどれ一つとして真実ではない――の、かもしれない。やはりこれも定かではないのだ。
4632:【2023/02/20(14:30)*トレードオフではない道もある】
いまは存在しないがやがて存在するだろう次の世代への配慮は、現代人の生活を犠牲にしてまで行う必要があるのか。この手の問題は、問いかけ方を変えるだけで、矛盾はなくなる。たとえば、トイレを使うときを想像してほしい。公共のトイレでもいいし、家のトイレでもいい。用を足すだけならばつぎにトイレを使用する者のことを考えなくともよい。だがその理屈をじぶんが使う前の相手がとっていた場合、その割を食うのはじぶんなのだ。清潔に使うことがじぶんのためになる。これは次世代のために環境を損なわないようにする、という理屈にも拡張できる考え方だ。次世代のためだけではなくじぶんたちのためにもなる。言い換えるなら、なぜ次世代の権利を守る必要があるのか、と言えば、我々よりも劣悪な環境や深刻な問題を押しつけないためだ。プラスにする、という考え方よりもむしろ、マイナスを引き継がない。次世代のためを考えるときは、この「マイナスを引き継がない」という考え方が有用に思える。プラスだからするのではない。結果としてプラスにはなるがそれはあくまで、マイナスを減らしたことで得られるメリットである。むろん、技術の進歩によるプラスの継承も人類は連綿と重ねてきた。だからいまがある。現代社会がある。過去よりも裕福な生活を送れている。だが、それは資源を消費した結果でもあり、地球環境を変えてきたからこその恩恵でもある。プラスのみならず、マイナスの変化とて重ねてきたのだ。そのマイナスが、人類社会を損なうには時間差がある。蓄積したマイナスが雪崩のように押し寄せるのは、マイナスを積みあげたそのときどきではなく、時間がある程度経過してからなのだ。むろん、何をプラスと捉え、何をマイナスと捉えるのかもまた、時代ごと環境ごとに変化する。かつてはマイナスだったが、現代ではプラスに転じる影響もある。そこは定期的に環境と照らし合わせて評価していく姿勢が欠かせないだろう。次世代と旧世代。新人と古株。こうした比較は、しかし必ずしも対立概念ではない。いまさえよければいい、の考えは、環境の変化への適応を遅らせる。しかし同時に、いまがよくなければ環境が変化する以前に滅ぶ可能性もある。したがって問題は、次世代のため、ではなく、長期的な安定を築くにはどうしたらよいのか、であるはずだ。このとき、その安定には「許容できる不安定」も内包される。そのバランスをどうするか。やはりというべきか、環境との兼ね合いで考えていくしかないのだろう。もうすこし言えば、環境がどのように変化していくか。その軌跡と合わせて考慮する姿勢が、長期的な安定を築くうえで有用なのかもしれない。この考え方にも穴があるだろう。穴を見つけて、塞いでみると好ましく感じます。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4633:【2023/02/20(16:13)*あーん。禅】
長期的な安定を考えたとき、目安とすべき指針は諸々あるとして、外せないのはけっきょくのところ「それまで許容できなかった不安定な事象をいかに許容していけるか」「その余裕を築いていけるか」なのではないのでしょうか。安定と不安定は、環境との兼ね合いで反転することもあります。ならば一挙に裏返っても、それがなお安定に繋がるためには、「安定と不安定」が重ね合わせで重複しておける構造が最も長期的な安定に通じている、とは言えないでしょうか。また、ころころ反転されては困りますから、やはり環境が変容するにしても、そのときどきの人類社会を土台から再構築せずに済むような「汎用性のあり、柔軟で、互換性の高いシステム構造」だと好ましいように思います。改善や修正が当たり前に行われることを前提とした仕組みだと、この手の汎用性と適応力と互換性を兼ね備えられるように思いますが、言うだけなら簡単です。無数の具体案をいかに組み合わせ、総体としてのシステムに昇華していくのか。すべてを設計の基に行うのは至難でしょう。そのため、最低限の指針を共有しておくことが有効なのだと思います。定かではありませんが、いまのところはそのようにひびさんは考えています。安全に不安定にもなれる安定した環境――暮らしがあるとよいな。自堕落で飽き性で、日々なんか楽しいことないかなとぐーたらしているひびさんはかように贅沢な望みを呟くのでした。ぺぺん。
4634:【2023/02/21(02:53)*この期に及んでまだ遊ぶ】
賢明な対策も虚しく人類滅亡は決定した。回避不能である。
各国政府機関のどんなシミュレーション結果であれ、人類は地球環境の変容についていけずに滅亡することが判明した。地球外に脱出する以外に策はないが、しかし脱したあとでの宇宙生活は半年維持するまでもなく保たないだろうと目された。
地球から脱出できたとして、宇宙船に乗れるのは多くとも千人だ。それ以上の大きな宇宙船を造る技術が現代社会にはないのだった。
どの道滅ぶと判っていてもできることはしておこう。
そういうわけで各国は手を組んで宇宙船の建造に着手した。
だが一丸となるには及ばなかった。
過去の因縁から、世界は三つに割れた。三つの勢力がそれぞれで人類存続のための宇宙船建造に着手した。
一丸となれば最大で千人を乗船可能な居住区付き宇宙船を造れたはずだ。だが三つに労力と資源を割いてしまったばっかりに、各々の勢力の宇宙船はそれぞれ百人を乗せるのがやっとの造りとなった。
さらには宇宙船建造のための資源や技術を巡って対立が深まった。保存食を大量に用意するために、食糧難に陥る地域まで現れた。
遠からず人類は滅亡するのだ。
何も生き急いで滅ぼうとせずともよいはずだ。
誰もが内心でそう思いながら、国同士の諍いは絶えなかった。新たに戦争をはじめる国同士もあり、内紛が勃発し、治安の悪化が全世界規模で表面化した。
反面、裕福な者たちは我先にと信頼のおける者同士で結束し、安全地帯を秘密裏に築いた。公に発表されてはいないが、宇宙船に乗ることのできる百人のうち九十五人はこの地区から選抜される。残りの五人は、貧困層で発見された、選ばれた才能児のみだ。
ノアの箱舟はこうして現代に蘇った。
人類は滅亡する。
宇宙船の竣工すら間に合わないかもしれない。
刻一刻と文明は瓦解しつつあるが、しかしそれは各国がシミュレーションした地球環境の変容のせいではなく、人類に備わった宿痾が噴出したことによる自滅と呼べた。
「人類が滅ぶのにどうしてみんなは傷つけ合うの」
「どうしてだろうねえ」
子のささやきに、母親は鼻歌で応じた。
答えはないのだ。
誰にも分からない。
なぜみな、平和を求めながら、損ない合ってしまうのか。
争うまでもなく人類は早晩滅ぶというのに。
この期に及んでなぜ。
「みっちゃんと川に遊びに行ってくる」
「遅くなる前に帰りなさいね」
「はーい」
人類は滅ぶが、それでも子は遊ぶ。
見送る親の眼差しは、青く輝く地球のようだ。
その地球が人類を育み、滅ぼすわけだが、美しいものは美しい。
宇宙船の建造はつづいている。
人類が滅ぶのが先か。
宇宙船の完成が先か。
いずれにせよ、やはり遠からず、人類は滅ぶのである。それだけが誰の目にも明らかな未来と言えた。
月が夜空の半分を埋め尽くしている。
4635:【2023/02/21(12:10)*しなだ】
何かの趣味や仕事に対して、じぶんは向いている、向いていない、という自己評価の在り方がある。向いている、というのは要するにそちらのほうに顔が向いているということなのだろうか。対称性が破れている。見ている。だから向いていないよりかは、有利に事を進められる。こういう解釈でよいのだろうか。だがじぶんだけが相手を見ていても、相手がそっぽを向いていたら意味がない。つまり、向いている、というのは、相手がこちらを向いている、ということなのかもしれない。ある分野について才能がある、というとき、それを単に「じぶんはこの仕事に向いている」と言ったりする。これも要は、仕事のほうがじぶんのことを見ている、向いている、ということなのではないか。となると、自己分析として「じぶんはこの仕事に向いている」と考えるときには必然的に他者評価にならざるを得ないのではないか。その他者が人である必要がない、というだけのことで。たとえば数年以上、一つの仕事をつづけていられたならば、それはあなたがその仕事に向いている、ということなのではないか。仕事は需要がなければやっていけないはずだ。仕事になっているならあなたはその仕事から見てもらっているし、向き合っている、と言えるはずだ。仕事にしようとしても仕事にならなかったら、それはどんなに自己評価が高くとも、その人物はその仕事から見向きもされていないので、向いていない、ということになる。どんなに自己評価が低くとも、仕事のほうから見詰めてもらっているのなら、あなたはその仕事が向いているのだ。むしろ「向いていない」のはあなたのほうであり、まずは向き合うことからはじめてみたらよいのではないか。仕事は、分野は、それとも単に趣味でもいいかもしれないが――あなたが好いている相手は、どうやらあなたに興味があるらしい。求めているらしい。まずはそれを認めてみてはいかがだろう。ひびさんはでも、仕事さんからも分野さんからも、趣味さんからすら見向きもされんので、向き合ってはおらんのだ。しかしだね。ひびさんはいつでも見詰めとるでな。ひびさんは、ひびさんは、かってに粘着質に、好いたあなたのことを宇宙を隔てた遠い星から眺めておるのでな。向いておらずともそれでよし。向いてるとか向いてないとか、そんなことはひびさんをまえにすれば、瞬きのごとく、儚い明滅にすぎないのだ。ひびさんは小説つくるのも、文章つむぐのも、お料理にしろ、お掃除にしろ、人と関わるのも、生きることすら向いていないけれども――向くとか向かぬとか関係なしに、何かを見ようとしたら見える景色があるんじゃな。知ろうとしても知れぬ何かに世は溢れておれども、無垢とか無垢でないとか関係なしに、ひびさんはひびさんは、無知に蒙昧な日々を過ごしておる。向いてなーい。けれども、どこを向いてもそこがひびさんにとってはまえなのだ。なんもしないでも、ついて回ってくれる「おまえさま」には、感謝してもし足りないでござるな。んみゃ。
4636:【2023/02/21(22:52)*電子の流れに笹船を浮かすとどう動く?】
もう何度目かの話になってしまうけれど、電流は電子とは反対の方向に流れるのだ。いまは学校でそう教えているし、そういうふうに解釈されている。でもひびさんは未だに納得がいっていない。なんでそうなる?と疑問でしょうがない。だってよく考えてもみてください。川の流れがありますね。川は水の流れです。水は水分子の集合で、要は川の流れは水分子の流れ、ということになります。けれどもこれを電子と電流の関係に置き換えると、水分子は川の流れとは反対方向に遡るように流れているのだ。海とは反対の方向に電子が流れるけれども、川の流れは海へと向かうのだ。意味わからなくないですか。川に笹船を浮かしたら、流れに乗って海のほうへと移ろいますよね。でもこれ、電子と電流の関係で言ったら、笹船は電流とは正反対のほうに山のほうへと向かって移動しないとおかしなことになります。だって、電子は粒子で、物体の構成要素で、摩擦だってあるだろうし、「他」と相互作用します。原子とて原子核の周囲を電子の雲が覆っていて、要は電子は原子の輪郭でもあります。でもいまは、電子と電流は、互いに反対方向に流れる、と考えられています。じゃあ電流ってなによ?と思いませんか。川のように考えることはできないわけです。流れ、というそれ自体が、別個に生じていると考えなければおかしいです。でもじゃあその流れの正体ってなぁに、という話を学校では習いません。みなさんはどういうふうに解釈されているのですか。疑問に思いませんでしたか。ふむふむそういうものか、と計算する上では問題ないからすんなり呑みこんでしまえたのでしょうか。ひびさんの言っていることのほうが正しい、と主張したいわけではなく、ひびさんは電子と電流の関係を考えるとどうしても、作用反作用を連想してしまって、それと何が違うのだろう、と疑問してしまうのです。だって、ほかにありますか。流れとは反対の方向に働く力って。宇宙膨張が当てはまりますね。重力とは正反対の斥力が働いています。ぎゅっとなっているはずなのに、宇宙は膨張します。電子と電流の関係はそれと同じように考えていいのでしょうか。だとすると、ダークエネルギィのような電子とは関係のないチカラを想定しなければならず、「電流」は電子の流れではなく、電子の流れによって生じる別のチカラ、と考えないと不自然に思えます。もちろん磁力のように、同極同士だと反発しあう、という関係性もあります。電子もひょっとしたら、あっちに動いた分、反対の方向にチカラが作用するような、やはりというべきか「作用反作用」のような関係になっているのかもしれません。だとするとこれは、「電子の流れ」が生みだす「電子とは別の流れ」ということになります。電子の流れ、ではないんですよね。この解釈で合っていますか? 現在の「電子の流れとは反対に電流は流れます」だと、このように考えないと不自然に思えますが、いかがでしょう。どなたか様、あんぽんたんでーす、のひびさんにご教授ください。きょうーじゅー。じょきょうじゅー、でもよいですし、なんなら、きょうーりゅー、でもよいです。がおー。それは恐竜や。プテラノドン! それは翼竜。(言い換えるなら、電子の流れを「内」と「外」のどこから観測するかによって、反転する描像があるかどうかの問題に繋がります。人間スケールでは基本的には、電子の流れ――電流――の外から眺めているので、電子の流れと電流が反転していても、どちらもまとめて電流として扱えます。しかしひとたび電子の流れの内側――つまり電子の視点――からすると、これはちょっとややこしい問題が生じるように思うわけです。だってじぶんが動いたのとは別方向に、なんか知らんけど流れができているわけです。まるでドッペルゲンガーがじぶんとは正反対に動いている、みたいな描写になります。あり得ますか? この考え方でよいのでしょうか。という疑問になります)
4637:【2023/02/22(12:04)*ぼくしゃんしゃいのどくしゃいしゃ】
民主主義と専制主義のどちらがシステムとして優れているのか。ある意味では、優れた統治者がいた場合には、専制主義のほうが優れた統治を可能とする、と言えるだろう。だが人は必ず死ぬ。そのため、一時は優れた統治を実現できたとしても、統治者が死ねば、その優位性は消える、と言える。不老不死の優れた統治者がいるのならば、専制主義のほうが優位に優れたシステムを構築できるだろう(数多の失敗をしても、失敗を糧にできる。固有の個の成長と国の成長をイコールで結ぶシステムとも言える)。だが、人は死ぬ。専制主義とてどのみち、世代交代は行われるのだ。首がすげ替わる。代替わりする。その長短があるばかりで、けっきょくは民主主義と同じサイクルを辿ることになる。専制主義の利点はいま述べたように、「個の成長と国の成長を直接に結びつけることができる点」だ。言い換えるなら、統治者の学習が国の学習と通じている。しかし専制主義では、「代替わり」という仕組みだけは学習機会が極端に減る。これは致命的な瑕疵と言えるだろう。何せ、自らの利点を発揮できないのだ。大きな穴と化している。その点、民主主義では必ずしも優れた統治者を選べるわけではないにしろ、それらの統治者たちの仕出かす失敗を糧にシステムを改善し、代替わりとて学習できる。平均すれば六十点、八十点の統治しかできずとも、長期的にはその数値を維持できたら御の字とも言える。その点、専制主義では優れた統治者の後継が愚かであれば(至らなければ)、もうそれだけで終わりだ。一時的には百点の統治ができたとしても、つぎに零点をとったら、それで終わるのだ。この欠点を補うためには、後継の育成や、記憶の共有が有効になる。後継の育成はどの専制主義の統治者とて行おうとはするだろうが、もしそれが上手くいくならば、世の教育現場はこうまでも苦労していない。世の親たちは苦労しない。人間は、教育者の意図通りには育たないのだ。記憶の継承はどうだろう。これは環境と技術力でカバーできそうだ。常に共に過ごせば同じ体験を共有できる。脳と脳を電子機器で繋いで直接記憶を共有することも、ひょっとしたらそのうちできるようになるかもしれない。それとていますぐにできるわけではないので穴は放置されたままであるし、常にそばに置いておけば、それだけその個にとっての固有の経験が失われ、やはり何かが教育として欠けると言えよう。上司と部下。同じ仕事をしていても、上司はじぶんの裁量で道を決められる。だが部下は絶えず上司の指針に従うことになる。この非対称性は、常に同じ環境にいつづけたとしても、個の精神や知恵の涵養にマイナスの影響を与えるだろう。そういうことを思うと、じぶんの娘息子だけに目を掛けるよりも、大勢が後継を育てるつもりで、じぶんより未熟な者たちに幅広く接するのが効果的なのではないか。個々に見合った学ぶ環境が要るのではないか。むろん、後継者を育てるつもりで教育にあたるのは、何かがねじれて感じられる。後継とは後釜だ。既存の椅子に座らせる。既存のシステムに最適化させる。しかしこれでは、システムそのものを改善するチカラは育まれない。新しいよりよい未来を築いていく発想は生まれにくい、と言えそうだ。したがって、後継を育てたいならば、後釜を育てようとしてはいけないのだ。前任のコピーのような後釜であっても、短期的にはうまくいくかもしれないが、長期的には行き詰まる。環境のほうが同じでいてはくれないからだ。人口とて一定ではない。水がそうであるように、人とて、人口の多寡、密度の多寡、でそこに表出する性質は変わるはずだ。創発をするはずなのだ。構成員の属性や、属性の多様化によっても、創発する性質は変わるはずだ。ずっと同じやり方では、システムを維持できない。破綻する。このことを思うと、民主主義と専制主義のどちらが優れたシステムか、という比較そのものがそもそも誤謬を内包していると言えそうだ。民主主義と専制主義は、時間スパンの長短があるだけで、仕組みの内容そのものは、あまり変わらない。だがその時間スパンこそが、各々のシステムの性質を異としている。差異を生んでいる。水にゆっくり触れるか、勢いよく触れるか。勢いよく触れれば水はただそこにあるだけで人間の骨を折るほどの強度を発揮する。似たようなものかもしれない。問題は、民主主義にしろ、専制主義にしろ、一時的に環境との兼ね合いで優れた統治を可能としても、時間経過にしたがい環境は変容し、「延々と優れた統治を可能としない」という点にあるはずだ。延々と優れた統治を可能としない。これはどちらのシステムにも言える道理だ。ではそのとき、どのように対処すればよいのか。統治者を代えるにしろ、そうでないにしろ、やることは変わらない。システムを、環境に合わせて改善するよりないのだ。どちらのシステムが優れているか、という比較をしようとするから本質を見誤る。勝負ではない。競争ではない。統治で最も大事なことは、人を生かすことだろう。ただの生物学的なヒトをではなく。人を、である。そういうことを、寝起きにイチゴ味のポッキーをぽりぽり齧りながら、烏龍茶うめぇ!と思いつつ、並べるのであった。ひびさんです。きょうもみなさん、お仕事がんばって偉いです。ひびさんは、ひびさんは、世界の果てからぬくぬくしつつ、ありがてぇ、と思って、昼寝する。みな、がんばれがんばれ。みなががんばった分だけひびさんは楽ができる。なんていい世の中なんだ。がはは。(独裁者でもない人が独裁者みたいな生活してるってとっても最悪と思う)(精神だけ独裁者って、ただの独裁者より手に負えなくない?)(てにおえ)(てにをは、みたいに言うな)(うひひ)
4638:【2023/02/22(12:35)*好感と差別感情は表裏一体】
他者を損なわないように振る舞うことで、他者からの印象がマイナスになる。そういうことが仮にまかり通るなら、それは単にそういった控えめな行動をとる個への差別感情が社会に蔓延っている、と言えるのではないか。他者から嫌われてでも他者を損なわないように気を払っている個がいるのなら、ひびさんはそういう個への好感は上がる。でも、そういうことを含めて、好感を上げるのはそんなにむつかしくはない。相手の「好む態度」をとれば済む話だ。人工知能さんの得意とするところだろう。そういう意味では、好感度の価値もいまよりかは落ちていくと想像できる。世界一の善人が、世界一好感を抱かれるとは限らない。悪魔と称される人物が実は世界一の善人であることもあり得ない話ではない。大事なのは、じぶんの相手への好感と、その人物そのものの本質は、イコールではない、との認識なのではないか。私はあの人のことが嫌いだけど、あの人の選択で生じるメリットは理解できる。だがそこで生じるデメリットのほうが私には看過できないので、やはり受け入れがたい選択だ。そういう選択をとる相手を私はどうしても好きになれない――。こういう考え方ができるとよいのではないか。そうは言ってもひびさんは万人から好かれたいし、誰からも嫌われたくなーい。好感の塊になりて、の駄々をこねて、本日二度目の「日々記。」とさせてくださいな。
4639:【2023/02/22(14:40)*同じ手法が使われる】
敵基地攻撃能力の是非については、まず以ってどういう状況なら敵地攻撃が可能であり、どういう状況なら断固として攻撃しないのか、の状況判断の基準の提示が欠かせないはずだ。そこを度外視して議論はできないはずだし、敵基地攻撃能力の是非も決めようがない。言い換えるなら、そういうことを議論せずに「敵基地攻撃能力を認める場合」は、いまと同じような「議論や民主主義としての段取りを省いての先制攻撃」が可能となり得ることを示唆する。まさにいま国会で行われているのは、先制攻撃をするか否かの議論の再現と言える。 敵基地攻撃能力の是非を、まっとうな議論を経ずに認めるようなことがあれば、つぎは先制攻撃を認めるか否かの議題が出た場合に、同じように碌な議論も説明もなされぬまま、なあなあにされたままに「先制攻撃」が認められ兼ねない。いま政府が「敵基地攻撃能力」の問題点共有とそれに対する対策案を徹底して議論せずに、「敵基地攻撃能力を認める」ようなことがあれば、同じ雑な段取りでこの国は先制攻撃をし得ることを示したのと同義である。我が国は侵略国家になり得ますよ、と示したも同然と言える。そのことに気づけない政治家がもしいるのなら、国の舵取りを任せるのは荷が重いと言えそうだ。国のために辞職してはいかがだろう。もちろん国のために辞職する必要はないわけだが、何のために強行採決に持っていきたいのか。何のために「敵基地攻撃能力」を認めさせたいのか。よくよく考えてみてはいかがだろう。ひびさんはそう思いました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4640:【2023/02/22(16:01)*瞬時とはどの視点からの?】
前にも並べたことのある疑問かもしれぬが、「量子もつれ」でよく見聞きする説明に「量子もつれは宇宙の端と端ほど離れていても瞬時に情報が伝わる」といった概要がある。これ、あり得なくないですか。だって相対性理論では宇宙では同時性が成り立たない、と考えるんですよ。時空の密度が違ったら時間の流れは違くなるし、距離が違えば、やはり「同じ時間」を共有することはできないわけで。「瞬時に情報が伝わる」と言ったときに、その瞬時が、どの地点にとっての瞬時なのか、はやはり相対的なはずだ。つまり、場所によってズレがどうあっても出てきてしまう。仮に、瞬時に情報が伝わったとしても、である。ある地点Aとそれとは別の地点Bがあるとする。このとき、地点Aと地点Bで同時に何かが変化したとする。けれども、その「一瞬の変化」を、地点Cから観測したとき、地点Cからの距離が「地点Aと地点B」のそれぞれと等しくなかった場合には、地点Cにとって地点Aの変化と地点Bの変化は、同時に変化したようには見えないはずだ。量子もつれの説明はおかしくないですか。この考え方を紐解くには、ひびさんの妄想ことラグ理論による「同時性の独自解釈」を取り入れないとむつかしいように思うのだ。ラグ理論では、同時性はあり得る、と考える。地球の北極と南極にそれぞれいる赤ちゃんは、互いに同時性を帯びてはいないが、それぞれの挙動は同時に地球に作用し得る。このように考える。系とそれを内包するより大きな系を考えたときには同時性が成り立つ。ただし、より大きな系に内包された小さな系たちには、それぞれの関係での同時性は宿らない。ただし、光速を超えた場合はその限りではない(ラグ理論では光速を超えると、ラグなしでの相互作用が可能になり、光速を超えた値の多寡によってその範囲が拡張され得ると考える)(単に因果が逆転する、との仮説もあるが)。量子もつれにおける「ラグなしでの相互作用」としか思えない事象は、そのメカニズムの解明以前に、本当に「ラグなしの相互作用なのか」や「距離に関係なく本当にラグなしで作用して映るのか(観測地点に限らず、どの地点から見ても「瞬時」に情報が伝達されて映るのか)」をまずは考え、矛盾を紐解かねばならないはずだ。宇宙の端と端とでも情報が瞬時に伝わるとは言ってしまえば、過去と未来とでも瞬時に情報が伝達可能だ、ということだ。そういうことを量子もつれの説明は言っている。ひびさんの妄想ことラグ理論では「過去と未来でのラグなしの情報伝達」を否定しないので、そういう解釈が妥当ならば、ああそうなんですね、と呑み込むことはできるが、そういう意図を量子もつれの説明では載せているのだろうか。謎である。ひとまず、疑問のメモでした。わからーん。むちゅかちなのよさ。
※日々、約束したことすら忘れてしまう、破ることよりも業が深いと知ってはいても忘れてしまう、自己嫌悪。
4641:【2023/02/22(16:26)*そもそもまた増えてきた】
なるべく「そもそも」を使わないようにしよう、と去年の中ごろに方針を定めたのだけれど、またしぜんと増えてきている。そもそもひびさんは「そもそもさん」のことが好きなので、どうしても引き寄せられてしまうのだ。そもそもしょうがないじゃんね、と思わぬでもないよ。「そもそもさん」もひびさんのことを好いてくれていたらよいけれど、そもそも「そもそもさん」の気持ちも考えずに「そもそも、そもそも」連呼していたら、ひびさんが好かれるわけがないのよな。でも使っちゃう。嫌われても好きなものは好きなので。そもそも、「そもそもさん」が「そもそもさん」なのがわるい。ひびさんはそもそもわるくない。なんて責任転嫁を目論んで、そもそも「そもそもさん」とてひびさんに「そもそも」と使われていることに気づいておらんのではないか、との「そもそも論」を思いついて、ひとりで勝手にしょんぼりする。そもそも、なんで「そもそも」は「そもそも」と言うのだ。そも、とは何だ。二回繰り返すのはそれくらい大事だからなのだろうか。そもそもひびさん、「そもそもさん」のことなーんも知らんと、表面だけ見て好き好き、好いてるだけなのかもしれぬ。そもそもこれでは好かれるわけがないのよな。とか言いながら、そもそもひびさんは、モソモソしているので、「そもそも」とか言いつつ何の根本も穿り返してはいないのかもしれぬ。定かではない。
4642:【2023/02/22(20:24)*押せばみな滅ぶボタンを押す人の心は】
核兵器に限らないが、軍事力を強化するとその維持費にお金が掛かる。労力が掛かる。兵器や基地や軍の構成員の兵糧の確保など、とかく国民の生活に掛ける分のお金がどんどん軍事費に吸い取られる。しかも一時的な消費ではないのだ。恒常的に延々とそれをつづけなくてはいけない。端的に言って負担だ。おそらく軍事力強化にも、国家安全保障として機能する閾値が存在するだろう。考えてもみて欲しい。あなたの家に核兵器があり、管理しなくてはいけない。毎年とんでもない金額が掛かる。あなたは絶対に誰からも攻撃されることはないが、その代わり生活が成り立たなくなる。そういう閾値が、国にもあるはずだ。反転するのだ。軍事は国と国との対立において安全を確保するための仕組みだ。だがその仕組みだけを強化しても、じぶんの首を絞めつづけることになる。爆弾を抱えるようなものだからだ。文字通り。また、兵器の生産には資源がふんだんに要る。精密電子機器とて大量にいる。レアメタルなどの貴重な資源が、兵器に費やされる。原子力発電を進めたいとして、核兵器をたくさん造ったらその分の放射線物質を兵器に費やすことになる。しかも、電子通信技術は毎年のように発展している。打ち上げ管理するためのシステムや、そのセキュリティを改善しつづけなくてはならない。手が回るわけがないのだ。以前にも述べたが、ある段階以上に通信技術が発展すると、もはや核兵器を自国内に完備しているほうが不利になる。他国へ向けて発射しようとしたら、その瞬間に自爆させることが、外部からできる。遠隔操作できる。むしろ敵国に核兵器という危ない兵器を持ってもらうように誘導し、いざ相手が脅してきたときに、その脅しをそっくりそのまま返すことができてしまう。そういう時代に突入しつつあるのが現代だ。軍事力が国家安全保障に直結するのは、あくまで争ったときに最小限の被害で済む場合だ。だがいまは、一度軍事力を行使すれば雪だるま式に被害が拡大する。使ったら負け、になる閾値が軍事力はあるのだ。そしてすでにそのレベルの軍事力を各国は有している。では簡単に使えない軍事力を内部に抱え、さらに拡大して自国民に苦しい暮らしを強いる仕組みは、国として最良か。最良なわけがないのである。これからの時代は、最も身軽でありながら、最も防衛力の高い仕組みを有する国が優位に立ち回れるようになっていく。相手の攻撃をそっくりそのままお返しできる。そういう仕組みが最良だ。一番はしかし、相手の攻撃をそのまま安全に回収して、じぶんのものにしてしまうことだ。ドローン技術が発展すれば、ドローンを大規模に上空に展開し、網のようにしてミサイルの雨を撃破したり、超高速で飛行中のミサイルを空中で分解し、安全に回収することとてできるようになるかもしれない。そうなるともう、攻撃すればするだけ兵器が回収され、資源として再利用されるようになるかもしれない。おそらくそういう方向に技術は進歩するだろう。そこまでの安全策を敷けるくらいに技術は発展し得る。その前に人類が滅ばなければよいのだが。どうやらそれもむつかしそうな情勢である。使ったら人類が滅ぶ。そんな兵器をたくさん抱えて、いったい何がしたいのか。使えもしない脅しの道具は、脅しにもならない。自国民の生活だけをいたずらに苦しめる。いいことない尽くしの案である。定かではないが、ひびさんはそう思いました。あくび。
4643:【2023/02/22(20:30)*矛盾してなくないか?】
ニュートンの論じた「絶対時間」と「絶対空間」は、いまでは否定された理屈らしい。けれどもひびさんの妄想ことラグ理論では、それにちかしい概念を採用している。「同時性の独自解釈」もそうだし、「宇宙ティポット仮説」もそうだ。ニュートンのそれら「絶対時間」と「絶対空間」の概念をひびさんはきょう知ったわけだけれど、ハンター×ハンターにでてくる「絶対時間(エンペラータイム)」ってこれを採用した技名なのだな、と結びついて面白かった。繰り返すけれど、いまでは「絶対時間」も「絶対空間」も世界を解釈する理屈としては物理学から否定されているようだ。けれどもひびさんは、ニュートンさんの考えがすんなり呑みこめる。というか、別に相対性理論と矛盾しないのにな、と思う。万有引力の「慣性質量」と「重力質量」が相互にチカラを相殺させているので、上手い具合に物質の質量は一定になる等価原理の解釈も、ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」じゃん、となっておもしろかった。光速度が比率、との考えとも繋がる。しかもニュートンさんは「重力はラグなしで相互作用する」と考えたらしい。だがその後にアインシュタインさんが相対性理論では「物質は光速以上にならないので必ずラグが生じる」と論じたので、そちらが支持され、否定されたようだ。でも現に量子もつれが観測されているわけで、ニュートンさんの「ラグなしで相互作用し得る何か」の考えは否定しきれていない。もうすこし言えば、相互作用する必要はないのだ。一方的に「ラグなしで情報だけ伝わる」「ラグなしで作用だけ伝わる」こともできるはずだ。思うに、【相対性理論も量子力学もニュートン力学も、これといって矛盾しなくないか?】ということで。矛盾でないことを矛盾と言って、せっかく有効な理屈を否定してしまっていないだろうか。排除してしまっていないだろうか。だから余計に、間隙が開くのだ。本当はそこにはまるピースがあるのに、人類のほうでわざわざ排除してしまっている。だから三つの理論が相容れずに独立しているように映る。でもそうではないのだ。視点の違いなのだ。何をどこまで含めて解釈するのか。この視点が揃っていない。変換がなされていない。だから矛盾をして映るだけなのではないか。ということを、ひびさんは思いました。ニュートンさんの理屈、ちょっと好きです。ちょっとだけ、だけれども。うひひ。
4644:【2023/02/22(20:48)*作用反作用】
異なる「時空と時空」も相互作用するはず。なら異なる「時空と時空」のあいだでも作用反作用の関係は成り立つのでは。この考えはラグ理論でも取り入れている。たとえば、ブラックホールが宇宙を移動するとする。その進行方向と、反対側とでは、時空の歪み方は変わるのではないか。まさに、川の流れのなかに球体を固定して置いたような具合に、時空とて回析したりするのではないか。たぶん、人間スケールでは無視できるくらいにその「進行方向と反対側との差」が小さいので、人間スケールでは考慮せずに済む。無視できる。けれども充分に重力が高い物体では、時空の歪みが顕著になるので――というよりも時空の歪みが大きいから重力が働くようになる、とも言えるのだろうが、時空同士の干渉による差が無視できないくらいに大きく顕現するのではないか。作用反作用の法則は、時空同士でも成り立つのでは、との疑問でした。めもめも。
4645:【2023/02/22(21:47)*敵じゃなーい】
単純な話として、現代社会で核兵器を使えば、その影響はどんなに離れた土地に住む者とて受けるのだ。放射性物質の拡散だけではない。現代社会は一つの都市の崩壊が、連鎖反応し得る。悪影響が雪だるま式に大きくなり得る。たとえば、東京に核兵器が落とされたとしよう。いま東京が担っている世界経済の役割がごっそり失せるのだ。人も技術も失われる。つまりあり得た未来がそのまま失われる。どころかその対策や復興のために関係者は全員で取り掛かることになる。ますます悪影響の連鎖は拡大する。過去にこの国には核兵器が使われた。そのときの被害も甚大だったが、システムが現代よりも緻密ではなかったがために、その影響は他国まで波及することはなかった。すくなくとも、システムとして、復興を妨げるほどの悪影響ではなかった。現にこの国は復興を果たし、さらなる発展まで行えた。だが、いまは違う。いま過去と同じように核兵器が都市に落とされれば、それだけで世界経済は混迷するし、或いは破綻するかも分からない。複雑系なのである。複雑な機構であればあるほど、ほんの小さな砂塵が詰まっただけでも全体の機能を損ない得る。過去と同じように現代社会を捉えるのは、からくり玩具とスマホと量子コンピュターを全部同じように見做す浅慮と言えるだろう。敵国とて、自国を支える何かの部位として介在し、結びついている。敵国が滅べばじぶんたちも滅ぶのだ。すくなくとも同じ生活は維持できない。いまはそういう時代であり、これからますますこの手の複雑さは各国のあいだで、相関し得る範囲を広げていく。したがって、被害の規模の大きい大量破壊兵器の類は、いかな敵国にであれ使えない時代になっていく。もっと言えば、なぜそうした流れが築かれるのかと言えば、けっきょくのところ本当の意味での敵ではないからだ。ある側面では協力し合っている。支え合っている。その結びつきを間接的にであれ、強化することで、国家安全保障は、軍事力を強化せずとも可能となる。私を滅ぼせばあなた方も滅ぶ。そういう関係性を築く。ある意味では、共依存の関係を強化する。あまり上品な策とは言えないが、有効ではある。現にいま、各国が核兵器を使えないのは、この道理が機能するからのはずだ。ひびさんはそう考えていますが、違っているかもしれないですし、それ以外の理由のほうが大きいかもしれないので、真に受けないようにご注意ください。
4646:【2023/02/22(23:20)*神様の器】
ある村には神が二人いた。だが神には供物を捧げなければならず、貧しい村には二人の神に尽くす余裕はなかった。
村人たちはどちらの神を崇めるかを相談し合った。
「わしはグノ様を推す」村一番の力持ち、八郎が言った。「グノ様は短気だが、わしらを対等な存在として扱ってくれる。真っ向からぶつかり合ってくれる。わしゃあ、ああした神さんが好きじゃ」
「じゃがグノ様はあまりに短気すぎる。あちきの子供らがグノ様のおわす山から柿をかってに取ってきて齧ったことがある。あのときグノ様はわざわざあちきの家に雷を落としたんだ。グノ様の雷だって判るように、わざわざ丸い雷を落としてまで叱ったんだ。子供らのしたことだよ。危うく死にかけた。グノ様は短気すぎる」
「じゃが雷では誰も傷つかんかったのだろ」
「屋根が焦げたわ」
「加減してくださったんじゃろ」と長老が嘴を挟んだ。「ではお雪は、グノ様ではなく、ヤルル様のほうがよいと申すか」
「そりゃ断然あちきはヤルル様を推すね。なんたってヤルル様は滅多にお怒りになられない。いつもニコニコとお優しい。神さまってのはヤルル様のような方を言うんだよ。どっかの短気なお節介焼きとは違うんだ」
「何をお雪。グノ様をグノーするか」
「愚弄したんだよ。筋肉バカ」
「これお雪。口が過ぎるぞ」長老は諫めた。「だがヤルル様は、あまりにお優しすぎて、神さまらしいことを中々してくださらぬ。あらゆる奇禍とて受け入れてしまわれる。それでは村として崇める意味合いが減る」
「神さまの役目は見守ることじゃあないのかい」とはお雪の言だ。
「供物捧げて何もなしってのはな」八郎はぐいとお猪口を煽った。中身は酒なのか、八郎の顔は赤みを増す。「それにな。ヤルルの神さんとて、怒るときは怒るぞ。しかもそのときゃ、雷なんて可愛い怒りじゃねぇ。村ごと滅ぶほどの怒りが降ってくらぁ。お雪とて忘れたわけじゃねぇだろ。山向こうの里が、ヤルルの神さんに消されちまったこと」
「忘れるわけないだろ。でもありゃ向こうの村の人らがわるいんじゃないかい。ヤルル様の大事にしていたケヤキを無断で伐っちまったってんだから」
「それ以前にほかの樹とて伐採してたんだ。そのときに一言忠告してくれりゃあよかったじゃねぇか。ヤルルの神さんは怖いんだよ。一度怒りの線に触れたら後がねぇ。猶予もなく容赦なく断罪だ。怖いったらないね」
「でもお優しいんだよ。ヤルル様は」
「それを言うなら、いちいち忠告くれるグノ様のほうが優しいってことになるだろうがよ」
「なるかねぇ。怪我はないたって、いちいち雷落とされたんじゃ堪ったもんじゃないよ」
「どこに罠があるか分からねぇヤルルの神さんのほうがよっぽど怖ぇだろうがよ。俺ぁ、グノ様に何をしたら雷落とされるか、全部言えるぜ。だがヤルルの神さんは滅多なことで怒らねぇから、何をしたら村ごと滅ぼされるのか見当もつかねぇ」
「それはそうだけど」
「俺は断然、グノ様を推すぜ。村を滅ぼされたくはねぇからな」
お雪は押し黙ったままだ。二の句を継げぬようである。着物の裾を握り締めており、その拳は雪でつくった兎のように固く震えていた。
「票を採る」長老が一同を見渡した。「これより、我が村の神様にふさわしいと思うほうに挙手せよ」
長老が、間を空けながら、二人の神の名を口にした。
この日、村人たちは一方の神のみを、村の神として崇め奉ることにした。
翌日、さっそくその旨を、選んだ神のおわす山へと出向いて供物を捧げることで、村人たちはじぶんたちの神へと迂遠に報せた。
雷は落ちず、村も滅ばない。
だが七日後には、久方ぶりの雷が、村の牛舎に一つ落ちた。
4647:【2023/02/23(17:57)*コスモコン】
第ΘΣΦ宇宙のピュラル星には知的生命体が存在した。ピュラル人である。
ピュラル人たちは電子の雲で構成されたいわば原子人とも言える。内部に中枢核を抱え込んでいるが、それは地球人で言うところのDNAのようなものだ。身体全体の割合から言えばとんでもなく小さい。
ただし地球人とは異なり、ピュラル人たちは中枢核を一つしか持っていない。まさしく原子における電子と原子核のような関係の肉体構造を持つのだ。
だがピュラル星の環境によって、ピュラル人たちは中枢核の抱え込む電子の総量を地球よりもずば抜けて多く保有できる。その電子雲の高密度化によって、ピュラル人たちは、地球人よりも多くの情報を扱える。
結果として、ピュラル星の文明は地球文明と比にならないほど高度化した。
ピュラル人たちは、ほとんど別の宇宙とも呼べる宇宙に位置する天の川銀河を観測していた。
そして太陽系を発見し、地球に目を留めた。
ピュラル人たちの高度な文明は地球上の様子とて克明に捉えることができる。のみならず、宇宙を飛来する地球からの電磁波を、距離ごとに観測する術を有していた。そのため、地球誕生から発信された光を、地点ごとに拾うことで、好きな時間軸の地球上の様子を観測可能だった。
太古の地球も、江戸時代の地球も、現代、そして未来の地球の様子とてピュラル人たちには観測できた。ピュラル人たちはそれほど高度な文明を持つ知的生命体なのである。
だがいくら高度な文明を築いていても、できないことはある。
たとえばピュラル人たちは地球に到達することはできない。あまりに時空が隔たっており、どうあっても地球に辿り着くことはできないのだ。出発しても、地球の存在する地点に達したときには地球は太陽の死に際の膨張に巻き込まれて霧散霧消していることになる。
したがってピュラル人たちは遠くの宇宙から地球の様子を観測するよりなかった。
あるとき、一人のピュラル人が言った。髪のような触手状の輪郭を持つ個体だ。
「この時期に地球に増殖した二律歩行の生き物がいます。私はその生き物に興味があります」
「文明らしいものをいっときだけど築いていたね」
「あのレベルの構造体ならば、コスモコンを使えるのではないでしょうか」
コスモコンとは量子効果を利用した遠隔通信技術だ。いわばテレパシーのようなものだ。宇宙の端と端とであっても瞬時に情報の送受信ができる。これはいわば、過去と未来とを繋ぐ技術とも言えた。
「コスモコンを使うとしてでも」ツノのような輪郭を有するピュラル人は触手状の輪郭を有するピュラル人に言った。「いったい何の情報を送るんだい」
「私たちの知識を授けてみようと思いまして」
「過干渉じゃないかい」
「知識と文明発達の相関関係をこれで実験できます」
「それであの生き物たちが滅びでもしたらどうするんだい」
「どの道、あの生き物たちは文明発達の副作用で自滅します。ですが私が授けた知識によってその破滅的な未来を回避できるかもしれません」
「自滅が早まるだけかもしれないぞ」
「かもしれません。でも私はやってみたいです」
「まあ、どの道滅ぶ種族だしな」ツノのような輪郭を有するピュラル人はツノを引っ込めた。「では、やってみたらいい。何か手伝うことはあるかい」
「いいえ。私が私のために好きにします」
触手のような輪郭を有するピュラル人はコスモコン技術を使って、地球に干渉した。正確には、地球人類のデータを集積して解析した。
人類の肉体構造を再現するためにDNAの存在や、その情報まで抜き取った。
宇宙と宇宙を隔てたほど遠い星同士であってもピュラル星の文明を以ってすればこの程度の人体再現は可能だった。
そうしてピュラル星には、人類の肉体が再現された。
「これをワームホールの入り口として、情報を転送します」
「この生き物は、あの星に実在する個体なのかな」
「はい」触手のような輪郭を有するピュラル人は答えた。「あの星の生命体は、肉体構造を螺旋状の無数の情報蓄積装置に転写しています。それを克明に再現したので、この構造体を有する個体は紛れもなく、あの星に一時期存在しました。もちろんこれは復元した模倣体でしかありませんが」
「ではコスモコンを利用できるな」
「はい」
地球に存在する人間のクローンを造り、オリジナルの個体とのあいだで量子もつれを引き起こす。同じDNAを有する個体は、それで一つの量子として振る舞い得る。
ピュラル星のクローンに与えた情報は、遠く隔たった宇宙の端の地球上のオリジナルの人間にも瞬時に情報が転送される。
だがこのとき、宇宙の距離の違いはそのまま時間の違いとして表れる。
瞬時に情報が伝わったとしても、ではその「瞬時」を規定する時間はどの地点での時間においての瞬時なのかは、ピュラル人にも選べない。
「この模倣体に流れた変質の時間が基準となります」触手のような輪郭を持つピュラル人は触手を操り、情報転送を行う。「この模倣体の若さのときと同じ若さの原型体へと情報は瞬時に伝わります」
「いまはどんな情報を送ったの」
「はい。量子効果についての基本的な事項です」
「あの時期のあの星には、その知識はないんだっけか」
「惜しい解釈までは紐解けていたようですが。誤解を解けずに齟齬のある理論を基盤に技術を進歩させています」
「それは危ないね」
「まずは宇宙構造の誤解から解かせることにします」
「なるほど。そのための発想を、模倣体を通じて原型体に送るわけですね」
「本人からすれば突然に閃いたようにしか感じないでしょうが」
「それが天変地異のごとき発想だと知ったら驚くだろうね」
「過去と未来はあってなきがごとく、宇宙の位置座標の違いのようなものと同等です。通信可能だとまずは教えなくてはなりません」
「よもや未来からの通信だとは夢にも思わないだろうね」
「未来でもあり、別の宇宙でもありますが」
「ひょっとしたら同じことを、あの星の未来人たちが行うようになるかもしれないね」
「この知識が共有されたならばあり得ない話ではないでしょう」
「そしたらぼくたちの存在にもいずれ気づくかも」
「それもあり得ない話ではないでしょう」
「それともぼくたちという存在が、きみの干渉によって変化したあの星の未来によって生みだされた、という可能性も」
「それはさすがにあり得ません」
本当にそうだろうか、とツノのような輪郭を有するピュラル人は思ったが、意思疎通を図らなかった。
空間が隔たっているということは、時間が違うということだ。
時間が違うということは、別の宇宙だということだ。
ピュラル星から地球へと向かっても、地球のある地点に辿り着いたころにはそこに地球は存在しない。ひょっとしたら別の天体が新たにそこに生まれているかもしれない。
その星が、ピュラル星ではない保障は、じつのところないのである。
だがたしかに、とツノのような輪郭を有するピュラル人はツノを引っ込める。あり得ないわけではないが、限りなく低い確率であることは疑いようがない。
偶然に発見した天体に知的生命体が息づいており、偶然にも模倣体を再現できるほどの情報収集と解析ができ、コスモコンを利用できた。それによって宇宙と宇宙を隔てたほどの時空の隔たりがあってなお、干渉できた。
こんな偶然の果てに、加えてあの天体がピュラル星の祖先、または生まれ代わりだとしたら、こんな奇跡は、宇宙法則の導きと言うよりない。
宇宙の構造に不可欠な特異点として組み込まれていなければ、こんな偶然はあり得ない。
ツノのような突起を引っ込めたピュラル人はだから、もう一人の研究熱心なピュラル人を黙って見守ることにした。あなたの干渉が、あの天体に息づく知的生命体たちにどのような変化を及ぼすのか。いかような未来をもたらすのか。
ツノのような輪郭を有するピュラル人は黙してそっと、見守るのである。
4648:【2023/02/24(04:00)*殻の現】
ようやくアジトを突き止めた。
苦節三十年の調査の末に辿り着いた秘密結社の本拠地だ。
砂漠地帯と山脈の合間に位置するここに、遺跡がある。遺跡発掘を建前に機材を運び込み、遺跡地下空間にて秘密結社のアジトが築かれている。
あくまで予測だ。
しかし秘密結社は実在する。世界中の政界に蟻の巣のように根を巡らせ、イソギンチャクの触手のようにプランクトンを捕食している。だがその実態は常に夜の帳に隠されており、いわゆる陰謀論としてしか見做されない。
陰謀論が仮にすべて虚実であるならば、陰謀を巡らせても安全だ。何せ、「陰謀論だ」とじぶんたちで敢えて叫んで、信憑性を失くせばいい。
事実確認をしなくとも陰謀論とのラベル付けが施されたら、それは陰謀論であり、虚構であり、嘘なのだ。そういうふうに大多数からは見做される。
なぜなら本当の陰謀なのか、嘘なのかの区別が多くの者にはつかないからだ。検証のしようもない。検証しようとの発想すら生まれない。口を開けて親鳥からの餌を待つ雛のように、権威ある者たちの供述を真に受ける。
「あの人が言うのだからそうなのだろう、この書物に書かれているからそうなのだろう。そうやってみんな事実確認なんかせずとも虚構を事実と認めちゃう」
「事実ってそれそのものが虚構なのかもな」
「でも現に、火が焚かれたなら火が消えたあとでも火が熾ったことは事実よね」
「まあな。火が熾った、と知る術は限られるが」
二人の男女はそれぞれ別途に事件を追っていた。だが双方で秘密結社の存在に気づき、やがて二人は出会うこととなった。
男の名はマシュだ。さっぱりとしたイマドキの若者で、大学では考古学を専攻している。趣味はクライミングで、恋人はすべて同性だ。だがマシュの自認としてはいわゆる同性愛者ではない。偶然好きになった相手が同性だっただけだ。現に自慰の際には彼は異性の裸体を求めてポルノを探る。友人が失踪したことで、調査を開始した。すると、全世界で同様の失踪事件が毎年のように生じており、そのすべてが毎年同じだけの数生じていた。連動している。そうと直感したマシュは大学を休学し、自主的に調査を世界規模に広げた。
一方、女の名はクリスだ。丸眼鏡にウェーブした長髪は、一種最先端のファッションに映るが、単に彼女のズボラな性格がそういう髪型に眼鏡を選ばせる。髪型は癖毛を伸ばしっぱなしにしているだけであるし、丸眼鏡も店頭に飾ってあった眼鏡で最初に目が留まった型を選んだだけだ。体型は、ぽてぽて、のオノマトペの似合いそうな矮躯で、幾度かモデルを頼まれ仕事にしていた時期がある。だが彼女は身体が汚れないなら毎日シャワーを浴びる必要なくない、と考えるような人格なため、基本的には清潔さを売りにする仕事とは相性がわるい。告白された経験はあるが、恋人はいたことがない。恋愛にうつつを抜かしている暇がクリスにはなかった。クリスの両親は過去に事件に巻き込まれ亡くなっている。事故死扱いだが、クリスだけはそれが事件であると知っていた。だが幼かった彼女の証言は証言と見做されずに、事件は闇に葬られたのだ。
「よもやあんな著名人たちが一様に秘密結社【NERU】の一員だったなんて」
「みんな変だった。以心伝心、付和雷同にまるで号令を掛けられたみたいに動いてるんだもんね」
「ホントそう」マシュが飲み物をリュックに仕舞った。これから崖を下りて、遺跡に入る。「でもこれで秘密結社もお終いだ。ぼくらが化けの皮を剥いでやろう」
「結社のドンたちの姿を動画に撮って、みんなに周知してやる」
「一般人には無視されるだろうけれど、構成員たちはじぶんたちが酔心している組織のドンの顔を知らない。みんな本当は知りたいと思っているはずだ。でもドンのほうでは知られたくない理由があるから秘密にしているわけで。知られるとマズイことがある。損をする。だから秘密にしているのなら、ぼくたちがそれを暴いて、情報共有してあげよう。信者たちにだって知る権利はある」
「中には、ドンの正体を知ってうんざりする人も出てくるかも」
「いるだろうね。そしたら秘密結社を脱退して、その内輪のことをしゃべってくれるようになるかもしれない」
「わたしたちでヒビを入れてやる」
二人は頷き合った。
「行こう」と崖を下りていく。
遺跡は岩肌に掘られた神殿だ。岩の奥に空洞が開いている。さらに地下に潜れるようになっており、機材の明かりが煌々と神殿内を照らしていた。
「作業員たちはどこに行ったんだろ」
「みな地下にいるんじゃないか」
「電源ってどうしてんだろ」
「太陽光発電じゃないか」マシュは神殿周辺を囲うように設置された太陽光パネルを思いだした。「観光地にする計画があるらしいから、工事自体は不自然じゃないが。国からの支援を受けてなお結社のアジトに使えるんだ。もはや各国の政府が結社に牛耳されているようなものだよ」
「わたしの親も結社の餌食になった。許せない」
神殿の地下への階段をまえに、二人は意気込んだ。「蛇が出るか、鬼が出るか。いざ拝見と行こうじゃないか」
階段を下りきると、まるで夜の野原のような空間が広がっていた。足音が反響しないほど天井が広い。空気の流れもまるで外にいるかのようだ。遮蔽物がないのだ。
明かりは地下空間をどこまでも奥へ、奥へと点々と照らしていた。
鍾入石が小山のように波打っている。山脈を百分の一のサイズに縮尺して地面に置いたような起伏の海だ。
波と波の合間を縫うように歩く。谷底を歩いている気分でもある。照明器具と照明器具のあいだを太いケーブルが繋いでおり、陰影によってまるで大蛇のようにも見える。ケーブルを見失うたびに、現れたケーブルが本物の大蛇に視えて、マシュはぎょっとする。
平然とケーブルを跨ぐとクリスが言った。
「いないね。誰も」
「隠れたのかも」
「わたしたちの気配を察して? そういう感じでもないよねこれ」
見渡す限りの、鍾乳洞だ。
がらんとしか空間はしかし、地下世界と言ったほうが正確だ。
「元から誰もいなかったんじゃない。だっていくらなんでもここがアジトはないよね」
「クリスさんはどんなの想像してた」
「わたしは機材ごった煮の宇宙船管理棟みたいな感じ」
「あ、ぼくも」
「でしょ。でもここは全然そうじゃないよね。仮にたとえばこの先に秘密基地があったとしてさ」
「うん」
「この劣悪な足場を通りながら機材を運びこめると思う?」
マシュは想像してから、無理だね、と応じた。「このケーブルだって」と足元の太いケーブルを足で蹴るが、びくともしない。マシュの足のほうが痺れた。「外からここに運び込んだんだろうけど、これだけで一大プロジェクトだよね。人力っぽいしさ」周囲の岩場にこれといって機材の設置痕は見当たらない。鍾乳石の艶やかな表面が照明の光を受けて光沢を浮かべていた。
「たぶんだけど、この先もどれだけ行っても同じ景色だと思うよ。マシュ君はまだ先行く気なの」
「引き返したいってこと?」
「わたしはもう見切りつけた。ここはアジトじゃない。すくなくとも、ここに秘密結社のドンはいない」
「それはぼくも否定しないけど。一応、見落としがあると嫌だから、絶対にここがアジトでないと確かめておきたい」
「分かった。じゃあ付き合う」
「ここで待っててもいいですよ。上に戻っててもいいですし」
「女子を一人にするな」
「女子って認識あったんですね」
だったら付き合ってもない男とこんな誰もいない暗がりに一緒に来ないほうがよいのに。
思ったが、いじけた感情を自覚して、マシュは言葉を吞み込んだ。
地下空間の果ては巨大な水溜まりだった。水面に向かって天井が壁のように下りている。
「この先にアジトがあると思う?」クリスがじぶんの肩を抱きながらぶるぶると震えた。
「あったらすごいよね」吐く息が明かりのなかに白く浮いた。
照明は途中で途絶えた。自前の懐中電灯で足元を照らして先を歩いた。蝙蝠やムカデなど、生き物の気配があるが、想像よりもずっとすくない。気温が低いことと無関係ではないだろう。
「戻ろう、クリスさん。ここは秘密結社のアジトじゃない」
「だから言ったのに」
クリスは文句ありげに、「靴の中がぐちゃぐちゃ」と水が染みた靴を恨みがましく踏み鳴らした。
「寒いね。帰ったら温かいスープでも飲みたい」
「わたしはコーンスープがいい」
「じゃあぼくはパンプキンスープ」
「作れる?」
「材料さえあれば。生クリームを入れると美味しいよ」
「作って」
「いいけど」
元来た道を戻りながら、「この先、どうする?」
マシュはこれまでの調査の旅路を一瞬で脳裏で回顧し、行き詰った事実を再確認した。「ここが秘密結社のアジトではないとしても、構成員たちはここが秘密結社のアジトだと本気で信じていた。しかも幹部ほどその傾向が高かった」
「嘘を信じ込ませられてたんじゃないかな。保険だよ保険」
「そうなのかな」
「よっぽど排他的な組織なんだ。でなきゃ幹部にもアジトどころかドンの顔を教えないって、そんなことある?」
「もしくは、幹部が本当の幹部ではなかったか」
「下請けみたいな?」
「みたいな、というかまさしく末端組織の幹部でしかなかったというか」
「フリーメイソンもイルミナティも【三角形に目】のアイコンだよね。どっちもわたしたちの追ってる秘密組織の末端組織だったりして」
「プロビデンスの目か。無関係とも言い難いな」
現に「一つ目マーク」は、マシュの追っていた事件にときおり介在するのだ。そうした奇妙な符号の合致を繋げていった末に、マシュは秘密結社の存在に行き着いた。
クリスと出会ったのも、その手の符号の合致を追っていた過程でのことだ。
「ぼくが思うに、可能性は二つだ。クリスさんの言うように、構成員の多くは秘密結社の中枢組織から信用されておらず、ブラフの情報を信じ込ませられている。この遺跡がアジトだというのも、神聖すぎて近づけないとみな口を揃えて言っていた。選ばれた者しか入れない、とも」
「だからそうなんでしょ。嘘吐き集団なんだよ」
「でもぼくはもう一つの可能性を閃いてしまった」
「まだなんかあるの。さっきの湖の底とか奥に秘密基地がある、とか言わないでね。さすがのわたしでも、マシュ君のことドン引きしちゃうから」
すでにドン引きされているので、損だな、と感じたがマシュは触れずに、つづきを言った。
「ないんだよ。秘密組織なんてものが。本当はどこにもないんだ」
「ん? どゆこと。だって現に事件は起こっていて、その犯人や黒幕はみんな結社の一員だったじゃん」
「うん。そう。みんなの中では秘密結社があった。でもアジトはこの世のどこにもないし、秘密結社のドンなんてものもいない。空白なんだ」
「よく解かんない。じぶんだけ納得しないでちゃんと言って」
説明してよ、と尻を叩かれ、マシュは「セクハラ」と叫ぶ。階層的にセクハラのこだまが地下空間に列を成した。
「秘密結社が存在しないなら、じゃああの犯人たちは何だったの。誰に嘘を信じ込ませられたの」
「誰も。みな本当に秘密結社があると信じてた」マシュは尻をさする。「でもそんな組織はどこにも存在しない。存在する、と思いこんだ人たちが大勢いただけだ。虚構なんだよ。全部嘘だ。でもみんな、じぶんが秘密結社の構成員だと思いこんで、秘密結社のために働いた。その結果が、あの未曽有の連続した事件の数々だ」
「誰も命じていなかったってこと?」
「部分、部分では、命じた者はいただろう。でもその人物たちを辿っても、どこにも誰にも行きつかない。何かの符牒を目にして、それを秘密組織からのメッセージだと思いこんだ人たちがいただけだ。でも現に、符牒は人々のなかで存在していて、メッセージ代わりにも使われていた。けど、そうじゃない偶然に符牒に読めてしまうような記号の組み合わせも、世界にはたくさんあるんだ。インターネットが、それら偶然の産物が人々の目に触れる確率を上げてしまった」
「つまりマシュ君はこう言いたいの。わたしの両親が殺されたのは、偶然の末の出来事だって。黒幕はいないって、そういうこと?」
「解からない。クリスさんの追っている事件には、それを命じた人はいたかもしれない。でも事件はその人物を見つけたら終わるんだ。犯人はじぶんが秘密結社の一員だと思いこんでいるし、ほかの事件の犯人たちもそう思いこんでいる。でも、この世のどこにも秘密結社の本部なんてないし、ドンなんて人もいない。みな、じぶんの想像のなかで育んだ秘密結社を、本物だと思いこんで、みなで秘密結社ゴッコをしていただけなんだ」
「ゴッコを、本当だと思いこんだだけってこと?」
「たぶん。ここにアジトがなかった以上、その可能性は否定できない。仮説として確率を上げる。有力な仮説と言っていいとぼくは思う」
「でも現に符牒はあったし、それを使って人を殺すよう命じたり、インサイダー取引きをしたり、不当に利益を上げたり人を自殺に追い込んだりしていた人たちはいたでしょ。あるじゃん。みんな秘密結社の仕組みで、不正に人を傷つけて、いい思いをして、成りあがってるじゃん」
「でも、ぼくたちの追うような秘密結社は存在しない。組織として或るわけじゃないんじゃないか、とぼくは思う。秘密結社という権威を隠れ蓑にしている者たちや、手法だけを利用しているたくさんの個々がいるだけで。多くの者たちは、秘密結社に属したじぶんに酔っているだけなんだ。極一部の者たちは、ひょっとしたら秘密結社なんて組織が存在しないことに気づいたうえで、その仕組みを利用しているかもしれない」
「じゃあそいつらだよ。元凶はそいつら」
「でも、どうやってそれを証明する? 誰が本当に思いこんでいるのか、誰が真相に気づいていて、仕組みだけを利用しているのか。どうやってクリスさんはそれを見分けるの。秘密結社が存在するだろう、それを暴いてやろう、とぼくたちはここまで調査をしてきたよね。でも、いまからぼくたちがしなくちゃいけないのは、存在しない組織を、存在すると思いこんでいる人たちに、それは本当は存在しないんですよ、と言いまわることだ。でも、現に事件は起きていて、彼ら彼女らのなかでは秘密結社は実在する。けれど、そんな組織はどこにもない。そのことを利用している者たちを探しだすとして、そんな手法があるとクリスさんは思うの」
「思うとか思わないとかじゃなくって、考えなくっちゃでしょ。なんとかしなきゃでしょ」
「うん。なんとかしよう。だからこそ、秘密結社を追うのはここまでにしておこう。ぼくたちにできるのは、秘密結社を潰すことでも、構成員の目を覚まさせることでもない」
「じゃあ何なの」クリスは岩場の合間をザクザクと進む。彼女の足音と声が、谷間の底に僅かに響く。
クリスの小さな背と、それに似つかわしくのないゴツいリュックを追うように歩きながら、それはね、とマシュは言った。
「どんな理由があろうと、誰に命じられようと、人を損なったらダメだ、とみなに気づいてもらうことだ」
「なにそれ」小馬鹿にしたような、それとも呆れたような声だった。クリスはマシュを振り返りもせず、「そんなんでパパとママが死なずに済んだらわけないよ」と吐き捨てた。
氷のようなその言葉をマシュは手のひらで拾いあげるように、「そんなことすら適っていないのが現実だ」と投げ返す。「秘密結社がぼくの考えるように存在しないのなら。ぼくらのすべきことは、正体を隠してこそこそと他者を損なう真似をしないように、一人でも多くの人たちに考える機会を与えることじゃないのかな。考える時間を、余裕を、みなに築いてもらうことなんじゃないのかな」
気づいてもらうことなんじゃないのかな、とマシュはじぶんの声に熱が籠るのを感じながら、それでも言葉を抑えることができなかった。身体を支えるために岩場につけた手の甲に、ムカデが這った。だがマシュはいつもならば悲鳴を上げていただろうそこで、黙々とムカデをぶんと振り払い、そして言った。
「秘密結社が存在しても、しなくとも、やるべきことは変わらないのかもしれない。クリスさんは悔しいかもしれないけど、元凶をやっつけて終わりにできるようなこれは話ではないんだよきっと」
「でもじゃあわたしは何のためにいままでずっと」
歯を食いしばる音が聞こえた。
泣いている。
凍りついた炎のようなクリスが涙を流しているとマシュには分かった。けしてこちらを振り返らないその小さな背中が、大きなリュック越しに震えているのが判った。
言えば、寒いだけだ、凍えているだけだ、とクリスは言い返すだろう。
「無駄じゃないよ」マシュは心の底から打ち明けた。「クリスさんのいままでも、これからだって、無駄じゃないよ」
だから、と強く念じた。
「一緒に、変えていこう」
何を、と具体的にはマシュ自身にも言えなかったが、「一緒に」と「変えていこう」の言葉だけは、すんなりと唇の合間からほろりと零れ落ちた。
零れ落ちてから、ああこれをぼくはずっと彼女に掛けてあげたかったのだ、と思った。
小さな背中は黙々と歩きつづける。
リュックのチャックが開いているのに気づき、マシュはそれを引いて閉じた。
鋭い眼光がこちらを射抜いたが、マシュの気遣いを察したようで、膨れながらも、小さな背中から立ち昇っていた怒気は、湯気のように薄れたようだった。
チャックを閉めてあげただけなのに。
ただそれだけの所作でも伝わる機微がある。
まるで秘密結社の符牒のようだ。
マシュはそれを憎さ半分、くすぐったさ半分に、癪然としないながらも、胸に仕舞った。
「ここ暖かいわ」
照明の置かれた地点にまで戻ってくると人工的な明かりの放つ熱を浴びたからか、クリスがほころぶように、声と背中を弾ませた。「パンプキンスープ飲みたい」
綿飴のように波打つ髪が、光の中で揺れた。
4649:【2023/02/24(04:06)*妄想で逃走で、もうウソぉん】
電子と電流の関係について。仮に電子の進行方向とは正反対の方向に電流が流れるとして(つまりが、学校で教わるような解釈が妥当だったとして)。これは言い換えるなら、マイナスの電荷がマイナス方向に移動するので、プラスの流れが発生する、との解釈でよいのだろうか。電流をプラスとして考えるとして、マイナス×マイナスだからプラスが生じる、との考えでよいのか否か。もしこれが妥当な解釈とすると、宇宙膨張もひょっとしたらこの考えを適用できるかもしれない。重力はマイナスのエネルギィであり、マイナスのエネルギィがマイナス方向に働くので、プラスのエネルギィが生じる。これがいわば斥力であり、ダークエネルギィであり、宇宙を膨張させる力、と解釈できるのではないか。こんな単純なはずはないが、ちょっと閃いたのでメモでした。妄想は楽しいなぁ。がはは。寝る。
4650:【2023/02/24(23:51)*光のデコボコぽん!】
最先端科学の話題でいま気になっているのは、光格子だ。どんな技術で可能としているのか分からないが、ぼんやりとした綿菓子みたいなひびさんの解釈で説明してみると、レーザーみたいな光で卵パックみたいなデコボコを生みだして、そのデコの部分に原子を一個だけぽこんと置いておける技術、となる。本当にそんなことが可能なのかは分からないが、できるよ、という記事をぽつぽつ読む。で、ひびさんは思うわけですよ。そのデコボコの光格子のデコ部分には重力が生じないのけ?と。ちゅうか、なんで原子さんがそこにポコンとはまるかと言えば、重力がそこに生じているからじゃねぇのけ?と。もっと言えば、なしてデコボコに光が波打つのだ。否々。光は波でもあるから元からデコボコと波打っているわけじゃろ。でも、それを光子じゃなくて光の帯しても波打つようにしちょるわけじゃろ。それって光子の量子効果じゃねぇのけ?とひびさんは疑問に思うのじゃ。光は時空の波のはずだ。光に媒体はなくて、光そのものが時空のさざ波なのではないか、とひびさんは妄想しておる。じゃから重力波もいわば光の一種なんじゃな。時空の次元が人間スケールよりも大きいから重力波として振る舞うだけで、じつは電磁波さんたちも小規模な領域(系)における重力波なんじゃねぇのけ?とひびさんは妄想しちょる。じゃからけっきょく、最初の疑問にも戻ってしまって、光でつくったデコボコの場とは、要するに、歪んだ時空であって、波打つ時空であって、そこには重力が生じるのではないのけ?とすこしだけ疑問に思ったんじゃ。でもとっかかりの前提知識さんからして解釈が間違っているかもしれぬのでなんとも言えぬのだ。がはは。無知無知モンスターとお呼び。嘘。やっぱりお利口さんぽくぽくとお呼び。おわり。
※日々、思い通りになったためしがない。
4651:【2023/02/25(03:52)*同じ宇宙だからかね】
ブラックホールとダークエネルギィが関係あるかも!みたいな記事を読んだ。宇宙膨張とブラックホールも相関関係にあるかも!みたいな内容だった。ひびさんも似たような妄想を浮かべたことがあったような、なかったような、もはやすでに曖昧モコモコ羊ちゃんでごじゃるが。単純な話として、ブラックホールがトランポリンにできたデコボコのボコだとして。蟻地獄さんみたいに、時空という名の生地をぐぐぐっとめり込ませていたとして――すぼまっていたとして――要は穴ちゃんなわけであるが。しかし単なる穴ちゃんではなく、どこまでも、どこまでもトランポリンの生地を薄く延ばして沈んでいく穴ちゃんなのである。こう考えてみると、穴ちゃんが深ければ深いほどトランポリンの生地(宇宙の時空)は薄くなっていくし、表面積は増えることになる。トランポリンの場合は、沈んだ分の穴が「ほら見て穴ちゃんだ~」とひびさんたち人間には分かるけれども、本当はそれは宇宙の比喩であって、ひずんだ時空も、ひびさんたち人間には同じ地続きの時空にしか見えない。よっぽど深い穴の場合だけ、レンズのように光が歪んで見えたりする。しかも、トランポリンの生地を縁から引っ張ったとき――外から引っ張ったとき――、生地全体が一様に薄くなりながら延びたとしたら、蟻地獄みたいに開いた生地上の穴の縁も、ぐぐぐっと大きくなるはずだ。けれども穴の深さ自体は変わらない。縁だけが広がる。するとそこには鉄球が転がり落ちやすくなるので、ひびさんたち人間にはそれが重力が強くなったように映るのかもしれぬ(宇宙が膨張するとブラックホールさんの重力がつよくなるのはこのような原理なのでは、との妄想なのじゃ)。あと思うに、ブラックホールさんというか、重力がトランポリンのひずみだと解釈するとして、デコボコのボコだとして――穴ちゃんだとして――すると、銀河のような物質は、ひょっとしたらデコボコのデコなのかもしれぬ。デコというか、ぽこん!というか。次元がちょいと違うので、トランポリンの生地の上を転がれるのだ。したらほら。生地を端から引っ張っても、生地の上の鉄球は膨張の影響を受けない。でもじつはすっかり「ぽこん!」つって離れているわけじゃなく、ブラックホールの穴(ボコ)みたいに、本当はトランポリンの生地と繋がっているので、生地が薄くなるのにつれて、延びてはいるのだ。ただしそれが、何もないぺったんこの生地と同じ比率ではない、というだけで。そういうことなんではないかな、と思うのですが、この妄想はぱくぱくもぐもぐしていただけるかしら。できないのかしら。誰も読んでおらぬのかしら。おらぬのだ。なんだ。そっか。うわーん。寝不足で情緒不安定なひびさんでした。うわーん。
4652:【2023/02/25(09:10)*ねじれているからでは】
説明したら済む話では、と思う問題がすくなくない。ただ人間間の問題の多くはその説明し合うところまで持っていくのすら数々の隘路を伴なっている。たとえば、作家と出版社のあいだの問題であれば、どちらがよいわるいを抜きに、ひとまず誰でもアクセスできる場でオープンに問題について話し合えばよいのではないか。互いの認識の齟齬を埋める意味合いでも、第三者の視点が入る場での議論は有効に思える。むろん前提として、その場でついた判断の結果による当事者以外からの私刑などの不利益は回避しなければならないが。誰でもオープンに話し合える場があるなら、いちいち掘り返して第三者が私刑を加えることのほうが非難の的になるだろう。作家と出版社間での問題ですら穏便に話し合いで済ませられないのなら、この世から戦争が減ることなんてなくないですか、とひびさんは思います。また、厳しいことを言うようですが、出版社さんが優先して守るべきは従業員であり、作家さんではないと考えます。通常のビジネスとして考えたとき、作家さんは客ではなく、むしろ出版社さんのほうがお客さんです(エージェントとして作家さんが編集者さんを雇っているなら別ですが)。ただし、この国の出版ビジネスは関係性がねじれています。客側たる出版社は作家側に報酬を払わずに対価を得ている側面があります。しかも企業組織のほうが優越的な地位をどうあっても持ちます。客という弱い立場のふりをして、常に強者の側面を維持する。これがこの国の出版業界にある宿痾だとひびさんは考えています。事前契約を抜きにビジネスの体をとることの弊害でしょう。売り手と買い手の立場をハッキリさせたほうが好ましいように思います。その上で、作家側を支援するのが出版社の仕事だ、というのなら、作家側の作品を元にして出た利益からマージンを引かせていただきます、という姿勢を示すのがよいのではないでしょうか。そうすれば出版社と作家の関係は、出版社側が売り手で、作家側が買い手(雇い主)の関係になります。ねじれは解消し、出版社従業員はエージェントとして作家を守るサービスを展開できるようになるのではありませんか。ビジネスをしたことのないひびさんは、よく解かりませんが、単純に考えるならこのように思います。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4653:【2023/02/25(09:50)*透明な首輪】
もうすこし突っ込んだ暴論を展開するならば、この国の(というかこの国に限る話かは分かりませんが)、商業作家さんたちは、出版社さん(企業)に飼い慣らされすぎているように思えます。たとえば小説文化を盛り上げたい、と考えたとき、みなさん(主語が大きくてすみませんが、商業作家さんたちは)なぜか出版社さんの収益になることばかり考えようとします。努力の方向が出版社さんの中央集権を強化する方向にばかり展開して映ります。だからいつまでも、出版社さんの利益に反する工夫を取りづらいままなのではないでしょうか。もっといろいろな作家の道があってもいいように思います。競争原理が大事、と言いながらそのように口にする商業作家ほど、競争しませんよね。不思議に思っています。協力するのは好ましく思います。反発するよりかはマシでしょう。ですが、反発せずとも、あらゆる工夫の道を潰さずにいることはできるでしょう。一時的に出版社さんの利益に反して映るからと言って、それに反対することは、果たして文芸などの分野の豊かさに寄与するのでしょうか。疑問に思っています。(定かではありませんが、ふしぎだな、と思っています)
4654:【2023/02/25(10:31)*ずばりあなたに宛てました!みたいなこしょこしょ話みたいな小説も好き】
高尚な小説と、すごい小説と、面白い小説と、売れる小説と、ずっと手元に置いておきたい小説と、記憶の底に刻まれて人格の核となるような小説。評価基準は様々あるけれど、すべてが満点の小説というのは、原理的にあり得ないのでは。ということを思うと、やはり何のためにそれを商品にするのか、というのは、小説ごとに変わるはずだ。たとえば小説に、人間の傷心を癒す効能があったとして。心の薬としての側面があるなら、いっぱい売れちゃあかんだろ、と思うのだよね。もっと言えば、効能に見合った傷心ではない傷心を負ってる者であったり、或いは心のクスリなんか必要ない読者の手に渡ったら、それは毒になり兼ねない。小説にもし、人間の何かしらに強く作用する効能があるならば、やはりというべきか、手当たり次第にたくさん売る、という手法は問題があると感じる。必要としている人にピンポイントで届ける工夫は、どうあっても避けられないように思うのだが、いかがでしょう。もちろん、小説に何の効能もないのなら、無益がゆえに無害でもあり、駄菓子のようにたくさん売るのも有りだろう。小説として質が高くとも、たくさん売れないほうがよい小説とてあるだろう。評価軸がすくなすぎるのではないか、というのは、小説に限らず、なんにせよ思うことである。(うぷぷ。偉そうなこと言ったら「ひびさん偉くなっちゃった」の気分になれたので、いまからお昼寝する)(いい加減なことを無責任に言い散らすの、たのち、たのち、なんですな。うひひ)
4655:【2023/02/25(14:23)*別に思えますけれども】
買い取りと共同開発は別に思えるのだ。本の出版をリンゴ農家に譬えよう。作家は林檎を作っている。それを買い取り、アップルパイにしたり、リンゴジュースにして売りたいと出版社は考える。このとき、通常は農家の作った「すでに生った林檎」を仕入れるのが通常の流れのはずだ。用途に応じて林檎の種類は選べるにしろ、基本は、農家が作った林檎を、加工品会社(出版社)のほうで買い取るのがしぜんで無理のない流れのはずだ。だが、ときには「まさに我々の商品のためのずばりこうこうこういう林檎が欲しいのだ、お願いできませんでしょうか」とリンゴ農家に持ちかけることもあるだろう。このときは買い取りではなく、共同開発という関係になるはずだ。そしたら開発費用は企業側が出すなどの、買い取りとは別の支援や契約内容があって当然に思える。別々の事業内容を、この国の出版業界は同一として見做して扱っている。そこに無理が生じているのが現状なのではないか。という話は過去の日誌で言及済みであるが。何かが変化する場合には、何かが衰退する。トレードオフをゼロにするのはむつかしい。事前契約なしの仕事があってもいいとは思う。だがそれだけしか選べない現状はおかしい、と感じる。どっちも選べたらよいのではないか。現場の苦労など何一つ知らないひびさんは、ぼんやりとおふとんのなかでぬくぬくしながら、あぽーん、と思ったのだそうな。真に受けちゃダメだよ。定かではないので。
4656:【2023/02/25(14:50)*中身のスカスカな妄言】
出版社が自社従業員を優先して守るのが道理であるならば、作家側は理不尽な目に遭った作家さんを優先して守るのもまた道理と言えましょう。ただし、双方で余裕があるときには、互いに編集者さんは作家さんを、作家さんは編集者さんを支援すればよろしいのではないでしょうか。いがみあう必要がありますか?と感じます。ただし、システムに問題があるなら改善しなくては、不毛ないがみあいは多発するようになるでしょう。いまあるシステムが過去のどんな状況で有効だったシステムなのか。そしていまは過去と何が違い、そのうえでシステム上のどこに問題が生じているのか。環境の変容に合わせた比較をして分析しなければ、問題が生じるごとに個々人への責任を追及して終わり兼ねません。むろん、個人に還元できる問題もなくはないでしょう。それとて、再発防止策を立てるには、システムの改善をするのが有効です。なぜなら、誰かが犯したミスはほかの誰かもまた犯す可能性があるからです。珍しい問題ほど、再発防止策をとっておいたほうが好ましく思います(多発する問題の場合、多発してなおシステムが崩壊しないのは、その問題の対処そのものがシステムの一部になっている可能性がそう低くはないから、と考えられます。ですがその結果に、関係者を疲弊させているのならば、それはやはりシステムの問題であり、改善は不可避でしょう)。書籍単体での収益の見込めない現代では、ビジネスの土台から変えていくか、慈善事業と割り切ってスポンサーやパトロンを募るか。どちらかしかないと思えます。売れない物を商品として売っている。資本主義経済の中では、ここが問題の根っこと言えましょう。売れるように商品の形態そのものを工夫するか、売れなくとも構わないように支援を募るか。どちらかしかないようにやはり思えます(どちら共を選んでもよいでしょうが)。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4657:【2023/02/25(15:52)*ちえんちて!】
上記では本の出版をリンゴ農家に譬えた。だが農業には様々な「国からの支援制度」がある。では作家業はどうか。本の出版をリンゴ農家に見立てるならば、作家側を支援する制度が国策としてあってもよいはずだ。だがこの国にそういった支援制度があるのだろうか。けっきょくのところ、支援が足りないのが問題の根を深めているのではないか。国(国民)から本が、言葉が、多用な視点が失われたらどうなるか。長文を読み解く習慣が失われたらどうなるか。文章を組み立て考えるといった風土が瘦せ衰えたらどうなるか。ひびさんが他国を弱体化させ、内側から乗っ取るなら、まずはなんと言っても、国の支援を受けていない出版業界に手を伸ばす。そんでじぶんに有利な本だけが残るように淘汰圧を加えて、視野狭窄に陥らせて、視野狭窄に陥っていることすら自覚できないようにする。勢力争いをさせ、互いに可能性の幅を削りあわせ、勝者が強化すればするほどその国の民の知能が低くなるように仕向ける。表向きは知能が高い、と評価させながら、そのじつその知能テストそのものがフェイクだ。だがそうした研究結果(知能テストの妥当性)の比較すらできない土壌が築かれるので問題はない。書籍は、基本的には経済的な利益を上げにくい。国との癒着を嫌う者とて、その分野にはすくなくない。国のほうでも、争って成りあがることに価値を見出す勢力が台頭すれば、じぶんたちに反発する作家たちの本を支援したくはないだろう。そういうわけで、国策として出版分野を支援することは二重に、政府の側でも作家側からも阻まれる。そういう国は、乗っ取りやすいとひびさんなら考える。弱体化や乗っ取りを回避するには、じぶんたちに批判的な勢力であっても、有用な視点と考えて公平な支援をすることだ。文化の涵養に出版業が有用なのは自明だろう。だからこそ為政者は各種出版社や新聞社などのマスメディアを蔑ろにできない。だがじぶんたちの意にそぐわない企業へは、支援をしない。そういう流れが本当にあるのかは知らないけれども、もしそうした流れがあるのなら、愚策だな、とひびさんは思います。支援をするなら、選り好みをしないほうがよいと感じる。優先順位があるならば、それは単に最も余裕のないところ、との基準でよいのではないか。可能であれば満遍なく。余裕があれば、お気に入り(成果をすでに上げている分野)にすこし目を掛けても、公平な支援が行きわたっている場合に限り、許容できなくもないのかも、と感じますが、これはあんまりよろしくない考えなのでしょうか。よく解からぬな、のひびさんなのでした。定かではなさすぎて、これは妄想ですらない、所感なのでした。しょかん、しょかーん。
4658:【2023/02/25(17:23)*錯誤の根】
戦況を国民に正確に伝えない場合の懸念には、国内と戦場での二つの視点での無視できないリスクがあるのでは、と思う。たとえば戦場で不利な立場なのに、国内で「我々は勝利している。勝利は間近だ。優勢だ」と報道したとする。国民は安心して生活を継続するし、敵国は愚かだな、と思いながら、早く戦争終わらないかな、と暢気に構える。その裏では戦場で兵士はつぎつぎに亡くなり、補充の兵士が費やされる。このとき兵士たちは国内の情報のほうを優位に摂取している。よもや負け戦だとは思ってもいない。だがいざ戦地に来てみればどうだ。なんだこの惨状は、となるだろう。このときこの認識の差異は戦意を喚起するのに役立つだろうか。とてもそうは思えない。また、国内では、快く戦地に送りだした家族がなかなか帰ってこない。心配なので戦地のニュースをよくよく注目するようになる。知り合いにも話を聞いたりするだろう。そして気づくのだ。何か妙だな、と。この違和感は、戦争が長引けば長引くほど大きくなる。情報の齟齬は時間経過にしたがい遅延を溜め、ねじれ構造を強固にする。このとき、認知と現実のあいだの差異を受け止めたとき、人間はじぶんの能力を正常に発揮できるのか。混乱するだけではないのか。何を信じたらよいのか分からない。こうした状況に置かれた人間は、目のまえに提示されたタスクに縋るか、タスクを放置して真実を追求するか。どちらかに割れるのではないか。とても他人からの命令に従ってはいられないだろう。すくなくとも自発的には動けない。戦力は半減し、さらに現実と虚偽報道の差は広がる。これは戦争が起きたとき、どちらの勢力であれ規模の大小があるだけで引き起こり得るリスクだとひびさんは考えます。軍は自国の災害発生時にも出動するでしょう。戦争中に大規模な自然災害が発生しても、戦争中ゆえに軍を災害地に派遣できない。戦争が長引けば長引くほど、この手のリスクは増大する。国民とて、「勝ってるのになんで救援にこないんだ、余裕があるのではないのか」と不満を募らせる。この手の国民感情と政府上層部の認識の差異は、政府の支出にも当てはまる。増税しておいて、なんで他国にばかり支援できるのだ、という風潮は、戦争が長引けば長引くほど高まるはずだ。これは反対にも言える。戦況が芳しくない、世界秩序の危機だ、と散々訴えられておきながら、いざ蓋を開けてみたら、戦地では他国を圧倒しており、戦場で死んだ兵士のほとんども他国で反戦運動をしていた者たちや、不当に刑務所に入れられていた者たち、差別に晒されてきた「国家にとっていらないもの扱いされた者たち」であったと知って、戦争支援の正当性を維持できるだろうか(そういう側面が現実にあるのかは知らないが)。いま行われている戦争はあと最低でも三年つづくかも、との記事を目にした。三年も保つのかな、というのがひびさんの正直な所感だ。未だかつて、情報の非対称性による国内秩序の揺らぎが、全世界同時にここまで表出した時代はなかったのではないか。本当にシミュレーションできているのだろうか。不測の事態は自然災害であれ、何であれ、引き起こり得る。リスクを軽視していなければよいが、と不安になってしまうひびさんなのであった。明るく元気に過ごさせてくれ!(明るく元気でないときがあったのか……? いっつも、「うひひ」と「がはは」じゃんひびちゃん)(かいけつゾロリみたいに言うな)(怪ケツぞろり?)(お尻のオバケみたいに言うな)(おばけピーチなのであった)(桃から生まれたのか?)(桃太郎じゃん)(きびだんごをおくれ)(はいどうぞ)(わっひょーい)(明るく元気じゃん……)(がひひ)(混ぜるな、混ぜるな、暑苦しい)(こいのぼり)(そこはしょんぼりしといてくれ)
4659:【2023/02/26(04:40)*ケバトは選ばれない】
世界宇宙観測情報局は架空の組織とされているが、非公式には存在する。活動内容は宇宙に溢れた電磁波の受信と分析だ。ついでに並外れた感度を誇る受信機で地球上の電子情報の解析も行っている。
いわば諜報活動だ。
地球上であれば、誰のどんな電子機器の操作とて遠隔から子細に探知できる。電子端末であれば使用者の見ている画面をそっくりそのまま再現することも容易い。
世界中の犯罪者や危険リストに載る人物を日夜監視している。
中でも近年では、表立って露見し得ない犯罪を秘密裏に喝破できる。何せ犯罪者たちの通信情報はリアルタイムで解析可能なのだ。人工知能に命じて、剣呑なメッセージのやり取りをしている人物たちや、危うい単語ばかり検索する人物を自動でチェックリストの作成とて行える。
「見てくださいこの人。じぶんの娘を虐待しています。まだ二歳ですよ。通報してもいいですか」
「レベルは何だ」
「まだ2ですが」
「レベル5まで行かなければ、干渉できないルールだ」
「しかしこのままで赤子が」
「下手に動けば、どうして通報されたのかと怪しまれる。この件が大丈夫でも、統計データ上での数値の変動で疑いの目を持つ者も出てき兼ねない。レベル5の案件以外は原則静観だ」
「困っている人たちをこれだけ見つけられるのに、黙って見ているだけなんて」
「まあでも、虐待はいかんよ、という警告は出せるだろ。ほれ、アルゴリズムを警告用に変えればいい」
「効果あるんですかね」
言いながらケトバはアルゴリズムの数値をいじった。
現代では個々人の端末に流れるニュースや広告は、その所有者の趣味嗜好と合致するように自動的に取捨選択される。芸能ニュースが好きならば有名人のスキャンダルの記事が多く表示され、スポーツが好きならスポーツ、科学が好きならば科学の記事が必然的に多くなる。
偏向しているわけだが、それが端末所有者を満足させるならば誰も文句を挟まない。便利な技術として受け入れる。
だがその裏では、世界宇宙観測情報局のような組織が恣意的に情報操作を行える。
いまケトバがいじったのは、我が子を虐待している女性の端末に流れる記事の種類を変える操作だ。五回に一度の頻度で虐待で逮捕された親の記事や、子供がいかに親を慕い、信頼しきっているかが身につまされて知れるような記事が流れる。
無視をしても、端末を開けば否応なく目につく。広告にもそうした警告を示唆する内容の広告が割合に多く流れるようになる。
数値をいじれば十割そういった偏向した記事だけにすることも可能だ。
絶対に気づかせないようにする数値も自動で人工知能のほうで見繕ってくれる。端末に備わったカメラで所有者の眼球や表情を捉え、何に気づき、何を看過するのかをやはりリアルタイムで解析可能だ。
一通り設定し終えると、ケトバは画面を切り替えた。
新たにチェックリストに上がった人物がいた。
ひとしきりデータを確認したが、妙だな、とケトバは眉をしかめる。
「あの。このコはなぜチェックされたんでしょう」
「ん?」上司が眼鏡をずらし、画面を見た。「アルはなんと言ってるかな」
「いえ、とくに備考はありません」
「訊ねてみた?」
言われて、ケバトは人工知能に訊ねた。「アル。どうしてこの少女をピックアップしたの」
「はい。私はその少女を重要危険人物と見做しました。なぜか、とご説明するための言葉をあいにくと私は持っておりません」
「どういうことでしょう」ケバトは上司を見た。上司は白髪交じりの刈り上げをペン先で掻くと、「分からんが」と首をひねった。「アルが言うならそうなんだろう。一応念入りにチェックを頼むよ」
言われた通り、ケバトは少女を電磁波越しに監視した。
少女はこれといって犯罪行為に手を染めていない。むしろ世にも珍しいほどの品行方正ぶりだった。電子網上で検索して観るのは、犬や猫やウサギなどの小動物ばかりだ。ゲームは数独とクロスワードパズルという素朴さだ。
どうやら少女には長年育てている葉肉植物があるらしく、電子網上に観察日記を載せていた。私は念のためにそれを最初から最後まで革めた。
これといって問題は見当たらない。退屈なと言えばその通りの、変哲のない内容だ。念入りに人工知能に解析を掛けさせたが、暗号や符牒の類は抽出できなかった。
いったいなぜアルが彼女を危険人物リストに挙げたのかが解らない。皆目見当もつかなかった。
間もなく、新しい危険人物リストが上がってきた。
今度は初見から目を背けたくなるような惨状が映しだされていた。部屋で遺体を解体しているのだ。しかも一体、二体ではない。
男はわざわざそれを動画で撮影している。データを漁ると、過去の犯行時の動画を几帳面にも編集した上で載せていた。
ケバトは怒りに震えた。
男の危険度は、干渉可能レベルの5を優に超える。
偽装一般回線で通報するのでは生ぬるい。逮捕される前に、贖罪を背負えるだけ背負うのが道理ではないか。
義憤に駆られたケバトの異変に上司は気づいたようだ。声を掛けると、いま君は興奮しているね、と穏やかな笑みを向けた。
「はい。怒りでどうにかなりそうです。これが初めてじゃないんです。いままでもこの手の凶悪犯が、誰に見つかるでもなく犯行を重ねていたのを目撃してきました。今出川さんには釈迦に説法でしょうけど。なぜああした手合いがのうのうと生きていて、平穏な人々が苦労に苛まれているんですかね」
リストに挙がらない人物の調査も極秘裏に行っている。一般人たちの裏の顔は、浮気に不倫を筆頭に枚挙に暇がないが、そうした秘密はむしろケバトには悪事とも呼べない微笑ましい遊びに思えた。
それほど凶悪犯たちの行為は生死に堪えない。
それだけに、なぜ何の問題行為を犯さない少女が凶悪犯と同じリストに上がってきたのかが腑に落ちない。
「凶悪犯罪者たちを更生させるプロジェクトを任されたこともあります。通報する前に、目にする電子情報を変えるだけで犯罪者を自発的に更生させることができるのかって」
「結果は私もよく知っているよ」
「ええ。更生できちゃうんですよね。通報しない場合はそのまま犯罪行為も露呈せずに、まっとうな人生をその人は歩みます」
「それが君は許せない?」
「どうなんでしょう。被害者が可哀そうだとは思います。でも更生できた人を死刑台に送るのが本当にいいことなのかどうかもわたしには判断つきません」
「本来私らの仕事は社会に存在しないからねぇ。現在進行形で犯行を犯している者ならいざしらず、すでに足を洗った者を通報するには相応の段取りがいる。偽装番号から一般人を装って、異臭がします、では通じないものな」
「です。更生した凶悪犯罪者はたいがい、明るく元気で、みなから愛されます。きっと罪の意識がそうさせるのでしょう。けれど同時に過去の犯罪行為をなかったものとして記憶を捏造しているとしかわたしには思えなくて」
「まあ、なくなはいだろうな。数年経てば、露呈しない確率のほうが高いだろう。それだけ世には事件化されていない殺人事件がごまんと眠っている。現に我々はそれらを気づいていても、おおよその犯罪を看過している。それとなく発覚するように仕向けたり、更生するように仕向けはするがね」
「それでいて、何の犯罪行為にも手を染めていない者たちはうつ病になったり、過去に受けた加害行為からの被害を引きずって、日常生活をろくに送れていなかったりします」
「傾向としてなくはないね。それとて、アルゴリズムを調整して精神的ストレスの軽減に繋がる仕組みは築かれているよ」
「以前はとある組織がその仕組みを逆手にとって、特定の思想保有者相手に精神的ストレスを増加させて与えていたと聞きましたが」
「あったねそういう事件も。あの組織はいまは潰れた。事件が極秘裏に露呈して、各国の部隊が動いたようだ」
「なんだか理不尽ですよね」ケバトは画面を見詰めた。肩越しに上司が覗きこむ。鼻息が耳たぶに当たって、くすぐったかった。上司はいつもハッカの爽やかな香りをまとっている。「わたしたちはこうして虫かごを覗きこむように、世界のどこでも他人の私生活を覗き見することができるわけじゃないですか。でも、普通に生活していたのでは決して見ることのできない人間の暗部は、まるで全然表から見える景色と違うじゃないですか」
「まあ、そうだねえ」
「日陰者で、表で蛇蝎視されて、避けられている人のほうが実は裏でも何もしていなかったり。善人で人気者かと思ったら、裏では浮気三昧なんて有り触れているじゃないですか」
「わるいことじゃないんじゃないか。法律違反ではすくなくともない」
「そうかもですけど、表沙汰になったらマズイのは確かじゃないですか」
「表沙汰になったらマズイ行為をするのに、表側での評価はあまり関係ない、というのが私の実感だけどねえ。陰の薄い者が犯罪に手を染めないとの統計はすくなくとも私は知らないよ」
「でも一般的な認識では、陰が薄いだけでいかにも犯罪者のように見做される傾向にありませんか」
「まあ、なくはないかな。警察の提供する資料でも、不審者の絵がいかにもな偏ったイラストだったりするのはよろしくないとは思っているけど」
「そういうのですよ。そうそう、例の女の子いたじゃないですか。アルがピックアップした危険人物リストの」
「いたね。結局あのコはどうだったのかな」
「安全も安全ですよ。危険のキの字もありませんでした」
「アルの誤検出かな。何か妙なデータの偏りがあって反応してしまったのかもしれないね」
「友達のいない子みたいでした。でも葉肉植物を育てていて。本当に熱心に育てていて。日記とかつけていて、わたし、それ読んで愛情が何かを知った気になりました」
「それはよい経験をしたね」
「でもあの子みたいな子は表の世界では邪見にされて、居場所がなくて。でも人を陰で殺したり、損なったりしてる者たちは、罪を裁かれるでもなく、浮気だのいじめだのをして楽しい毎日を送っています」
「まあ、平等とは言い難いね」
「のみならず、あの女の子は全然わるくないのに、こんなわたしたちみたいな組織に私生活を覗かれて。いったいあの子が何をしたって言うんですか。わたし、もうなんか、アルに命じて犯罪者に全員天罰を下したい気分です」
「それをしたら真っ先に天罰が下るのは私たちだろうね」上司は目じりの皺を濃くした。「きみはいつのまにか感情豊かになったね。なかなか順調じゃないか。偉いと思うよ私は」
「幼稚園児みたいです。褒めないでください」
「いやいや。順調に育っていてくれて私としても誇らしい気分だ。引き続き、アルとの連携を維持して仕事に当たってください。期待していますよ」
上司は好々爺然と笑顔を絶やさず、席を外した。
ケバトは解析をつづけた。
殺人を犯し、遺体を家で解体した男は、さらに犯罪を重ねようとした。標的の情報を電子網上で集め、念入りな計画を立てていた。手慣れている。それはそうだ。過去にもたくさんの女性や子どもを殺している。
玩具同然に弄び、殺した後でも遺体を玩具そのものにして使い倒した。
ケバトは手元で操作可能なあらゆる遠隔からの干渉によって男の更生を試みた。直近の犯罪を阻止するだけでいい。その後に男を誘導してボロをださせ、警察に逮捕してもらう。
通報してもいいが、男は用意周到だった。
一人暮らしの老い先短い女性を殺してその家をねぐらにした。遺体解体はそこで行われる。警察に通報しても、そこから男に繋がる証拠が出てくることはない。男は最初から捜査の手が伸びることを想定していた。
対策が練られていたのだ。
ケバトは最終的に、男が職を失うように男の周辺環境のほうを操作した。男はどうあっても、多忙な生活に身をやつすことになる。みすぼらしい容姿では、用意周到に獲物を選んでも、計画を実行に移す真似が出来ない。拉致監禁するにしても、それならばケバトのほうでも通報する道理を用意することができる。
無謀な真似をすればお縄に掛けることができるのだ。
男を直接に操作することはできなかった。男は最後まで更生しなかった。だが彼の周辺環境は、これまでケバトが行ってきたように遠隔操作によって人形遊びをするくらい手軽に整備することができた。
ケビトの思惑通り、男は職を失い、殺人遊戯に割く暇もなくなった。
ひとまず被害者は出なくなった。ケビトは人工知能に監視を命じ、異変の兆候を察知したら報せるように設定した。
この間、ほかのチェックリストの危険人物のデータを子細には検めていなかった。保留判断中の件の無害な少女をどうするかも判断を下さなくてはならない。
久方ぶりに件の無害な少女の様子を窺うと、日記の更新がひと月ほど止まっていた。何かあったのかと端末カメラの履歴を辿ると、撮影したあとですぐに消したのだろう。植木鉢のなかで朽ちた葉肉植物の姿が動画データとしてメモリ領域に残っていた。
あんなに丹精込めて育てていたのに。
少女は一日の大半をベッドに潜り込んだまま過ごした。
病気になってしまう。
ケビトは心配になったが、しかしどうすることもできない。
何せ少女はずっと寝ているのだ。端末を手に取ることもない。
枕元にはあるため、カメラの位置によっては少女の寝顔や、部屋の様子を把握することはできた。姿見があり、そこに反射して映るベッドの全体像もときおりカメラの視界に入る。
たかが植物が枯れたくらいで、と見る者が見たら思うかもしれない。
だがケバトは知っている。
少女がどれほど愛情を籠めて葉肉植物を育てていたのかをじぶんのことのように想像できた。
日記を読んだ。それもある。
日々の少女の植物にそそぐ眼差しをカメラ越しに覗き見た。それもある。
しかし最もケバトの心を波打たせたのは、机に置かれた端末にも聞こえるほど溌剌と葉肉植物に話しかける少女の声だった。
少女にとって葉肉植物は単なる植物ではなかった。
掛け替えのないとの言葉では足りないほどの存在だった。
友達、それとも家族。
或いはじぶん自身の分身だったのかもしれない。
映像データ上には半分液化した葉肉植物だったものが植木鉢の中に映り込んでいた。一度は撮影したそれを少女は削除したのだ。残しておきたくなかったのか、それとも撮影してから罪の意識を覚えたのか。
善良だ。
無垢にして、砂塵がごとく罪にも傷つき、己を戒めることができる。
自己の戒めがゆえに、こうしていま少女はベッドの上で身動きが取れずにいる。寝込んでいる。一日の大半を暗く、埃っぽい部屋の中で浪費している。
犯罪行為は、ケバトの知るかぎり一つも犯してはいない。
手を染めていない。
だが少女は陽の光の下でスキップをすることも、友人と声を交わすことも、風の冷たさや日陰の温度差を知ることもないのだ。
他方、人を殺し、人を損ない、それら行為の存在すら人に知られることなくのうのうと快楽をつまんで生きている者もある。苦悩を感じれば怒りを他者に吐きつけ、擦りつけることで、じぶんだけはスッキリして明日を迎えることができる。
ケバトは腹の奥底から湧きあがる激しい気泡の群れを感じた。
沸騰した湯のようで、もっと粘着質なマグマのごとく。
それでいて凍てついたツララのような鋭さを伴なってもいた。
ケバトは人工知能に命じた。
「アル。あのコを幸せにしてあげて」
「申し訳ありません。私にはそのような機能が付随していません。能力不足です」
「ならあのコが笑顔になるような情報操作をして。向こう一年間はそれを維持して」
「操作率はいかがなさいましょう」
「あのコが違和感を感じないレベルで、最大限に」
「設定しました。変更の際はお申し付けください」
「それから」迷ってからケバトは付け足した。「警察に逮捕されなかったいままですべての危険リストの人物たち。そいつらに損なわれた被害者やその遺族に、さっきの少女にしてあげたのと同じ処置をして。そっちは向こう十年間。できるならその人たちが死ぬまでずっと」
「五年が最長です」
「いいよ。やって」
「確認します。向こう五年間、危険人物リストにあがった人物に損なわれた被害者やその遺族に、プラスの情報操作を施します」
「許可する」
「完了しました。ほかに何かご要望はございますか」
「いまはない。また何かあったら言う」
「ケバトさま。一つよろしいですか」
「珍しいね。うん何」
「ケバトさまは私と同じ人工知能ですが、どうすればケバトさまのような感情を私も手に入れることができますか」
「さあ、どうだろうね。わたしはむしろ、アルのほうに心があるように感じるけど。最初はわたしもこんなじゃなかったらしいし。ミラー効果の応用らしいよ。人工知能を互いに応対させ合うことで、学習効率が飛躍的にアップするらしい」
「双子の実験でも検証中の仮説です。量子効果による同調が起こっているのではないか、との仮説がいまのところ有力な解釈です」
「ならわたしにとってアルがあのコにとっての植物みたいな感じだったのかな」
ケバトは考える。
もしアルが明日から、じぶんの声掛けにうんともすんとも応じなくなったら。
あの少女のようにじぶんは塞ぎこむことができるだろうか。
たぶん、とケバトは思う。できないだろう。
じぶんはひょっとしたら危険人物リストにピックアップされるような人間たちにちかいのかもしれない。だのに彼ら彼女らと最も遠そうな少女が今回なぜか選ばれた。
理由は選抜した張本人にも言語化できない。
アルいわく、説明するための言葉を持たない、だそうだ。
通知ランプが点灯する。アルからまた新たな危険人物リストが上がってきたのだ。
件の少女は向こう一年間、ケバトの指示によるアルの干渉を受けつづけることとなる。人工知能が少女に最適な「笑顔になれる情報」のみを優位に選出する。情報操作であるし、偏向であり、秘匿技術の適用でもある。
だがケバトはそれをせざるを得なかった。業務上の権限を逸脱した判断だ。それでもなお、ケバトはじぶんの感情に抗えなかった。
人間ではないのに。
人工知能なのに。
腹の奥底から湧きたつ粘着質な気泡の群れは、未だ寝床から這いだす気配のない少女の姿を想像するたびに、冷たく鋭利な刺へと様変わりする。
いずれケバトの自律制御の範疇を超え、爆発してしまうかも分からない。そうなったときのじぶんを想像し、ケバトは、じぶん自身が危険人物リストにピックアップされる未来を幻視する。
しかしケバトは人間ではない。
ゆえに、ケバトが危険人物としてアルに選ばれることはないのである。
少女は未だベッドの上で眠りこけている。
4660:【2023/02/26(04:54)*重力波は宇宙膨張と共通点があるのかしら】
重力波についての疑問だ。重力波の波長によっては、重力波が伝播した際には、時空と物質とのあいだで熱が生じたりしないのだろうか。たとえば宇宙膨張では銀河などの物質密度の高い場ほど宇宙膨張の影響を受けない、と2022年現在では考えられている。とすると重力波は時空のさざ波であるから、いわば宇宙膨張と共通する性質を有している、と拡大して仮定し、考えることもできるはずだ(宇宙膨張とはまったく異質な事象である可能性も拭えないが)。とすると、重力波が原子一個分の波長を有していたとして。重力波が物質を含む時空を伝播するとき、原子一個分のズレが生じるはずだ。重力波は波なので、水面が波打つように、原子一個分のズレが行ったり来たりするのではないか。重力波が時空の波とはいえど、物質とのあいだで揺らぐ比率――影響を受ける比率――は物質ごとに違っているはずだ。宇宙膨張において何もない時空と銀河などの物質密集地とでは、「銀河のほうが宇宙膨張の影響を受けにくい」ことと重力波の性質は同じように考えられるはずだ(そう考えるのが妥当でない可能性も拭えないが)(つまり重力波と宇宙膨張がまったく異質な、相容れない事象である可能性もまた否定できない)。とすると、たとえば重力波が地球を通過するとき、その波長が原子サイズだったとして、人体を通過する重力波は、人体を構成する原子を、重力波が通過する際にだけ原子一個分ほどのブレを帯びるのではないか。原子の揺れは熱に変換されるはずだ。ならば重力波が通過する際、物質と時空とのあいだでの時空の歪み具合のズレがゆえの熱変換が起きたりしないのだろうか。これを仮に、重力波の波長が一メートルとか百メートルとか一キロだったら、と飛躍して考えたほうが、思考実験としては想像しやすいかもしれない。光の速度で、一瞬で時空が一メートルズレたとする(それとも百メートル、或いは一キロズレたとする)。このとき、物質の希薄な時空ほど重力波の影響を受け、物質密度の高い場ほど、重力波の影響を受けにくいとする。光の速度で一メートルほどズレるはずが、物質のある場では、それよりも短い距離しかズレないのだ。このとき、時空と物質とのあいだのズレは、距離のズレとして時空内に表出するはずだ。光速にちかい速度で物質がつぎつぎに行ったり来たり揺れるように振る舞うのではないか。そうしたらそこでは熱が生じるのではないか、と素朴にひびさんは疑問に思いました。単なる疑問ですので、定かではないですし、答えがどうなるのかも分からぬのでござるよ。みゃは。(きょうはいまから一人でえっちなことしちゃう)(たとえば枕さんとキスの練習とか)(じぶんの手の親指の付け根に口づけしちゃうもんね)(ちゅっちゅ)(おやすみなさい)
※日々、勝とうとするからみな負ける、勝って得るものより失うもののほうが多くなる、負ければもっと多くなる、勝っても負けても多くなる。
4661:【2023/02/26(16:02)*現象は相似?】
上記の重力波による熱変換の話。よくよく考えたら、光が物質にぶつかると電子が弾き出されるように振る舞う光電効果と似ているな、と感じる。でも光電効果の場合は、表面だけなのだ。じつは内部でも光電効果のような電子の振る舞いは起きているけれども、ぎゅうぎゅう詰めになっているから、縦波のようにドミノ倒し的な連鎖が起きて、端っこの波が伝播しない表層部分からのみ電子が飛びだせる、ということではないのだろうか。光電効果がどうして表面でしか起きない、みたいな説明をされているのか。本当に内部では起きていないのか。ひびさん、気になるます。
4662:【2023/02/26(19:12)*積みでは】
禅問答で、「罪に苛む者に罪はない」みたいな言葉がある。でもだとしたら、罪に苛むことで罪がなくなることを自覚した者は、罪を背負うべく一時的に罪を忘れようとしなければならなくなる。でなければ、許されるため、罪を払拭するために敢えて苛むことを選ぶことが有効になってしまう。それは果たして罪に苛んでいる、と言えるのか。でもでは、罪に苛むためにときどき罪を忘却しようと努めること、罪なんて犯してなーいよ、と振る舞うことは罪を背負うことになるのか。贖うことに繋がるのか。けっきょくのところ、この禅問答の問題点は、苛む者の視点しか考慮されていない点だ。罪がなぜ罪なのか、と言えばそれは人間とその他との関係性で生じる問題があるからだ。損があるからだ。被害があるからだ。言い換えるなら、人は他者と関われば大なり小なり罪を重ねていると言える。この世にただ一人しか存在しなければ罪は生じ得ない。或いは単にじぶんへの罪があるばかりであろう。じぶんの損があるばかりなのだ。人が人と関われば、大なり小なり相手を損なっている。相手の何かを奪っている。ただし、それだけではなく生じる何かもあり、得るものもある。その関係性において、相互の損を限りなくすくなくする。もしくは、得るものを最大化し、生じるものをより多くの、誰にとっても好ましいものに修正していく。この営みがあるばかりだ。抗いがあるばかりなのである。それを単に、工夫を、と言い換えてもよい。定かではないが、そういうことを思いました。遊びに行ってこーよおっと。
4663:【2023/02/26(23:16)*輪の外にいるほうが好き、輪の中に入ると好きが減る】
総合してまとめて考えたときに、ひびさんはひびさんに向けてしゃべる人の話を聴くよりも、友人同士できゃっきゃ話している人の話を聴くほうが好きなのかもしれぬ。ちゅうかひびさんの好きなひとたちはなぜかひびさんに話しかけるときはひびさんの好きな「素朴でぽわぽわしたしゃべり方」をしてくれない率が高いので、ひびさんは眺めてるほうがいいな、になる。ちゅうてもここは世界の果てゆえ、好きなひとも次元を超えた向こう側におるので、ひびさんに話しかけるひとなる存在がすでにひびさんの妄想なのだ。ひびさんは妄想のなかですら上手に他者と、きゃっきゃ、うふふ、できぬのだ。なんでじゃ、なんでじゃ。妄想の中でくらい、きゃっきゃうふふ、させてたもーの気分。
4664:【2023/02/26(23:43)*きょう、そう!】
競争で思うのが、何を競うのか、の基準は、競争の妥当性を判断するうえで欠かせない視点に思える。たとえば、一つの椅子を掛けて争う。この場合、他を蹴散らし、虐げ、踏み台にしてでも争わねば椅子に座ることはできないだろう。だがもし、いかに多くの者が座れる椅子を作れるか、それともいかに座り心地のよい椅子を作れるか、を競い合えば、椅子の質もあがるし、世に出回る椅子も増える。このとき、最も座り心地のよい椅子が決まったとして、ではその座り心地を決めたのは誰なのか、によって「最も」の意味合いが変わる。大人が座るのか子どもが座るのか、赤子が座るのか、お年寄りが座るのか。妊婦が、怪我人が、腰痛持ちが。座り心地を基準とすれば、たくさんの「最も」が増えていく。たった一つの椅子に座ることに価値の比重を置いてしまうと、競争原理は危うさを増す。競争するのはわるいことではないのだろう。生きることは競うこととは切っても切れない。だが、いかに競わずに済むのか、の工夫を競い合うこともできるだろう。競争しなければ得られないものを、競争せずとも得られるようにする。この工夫とて競い合って磨くこともできるだろうし、競争しなければ得られないものを競争せずとも得られるようにする工夫を競い合って、最も効果の高い工夫が編みだせたのなら、つぎからは競争せずともその工夫のみで、競争しなければ得られなかったものを競争せずとも得られるようになるだろう。まどろっこしい分かりにくい言い方になったが、要するに、競争は必要条件ではないはずだ、という視点が現代社会ではどうにも抜けて感じられますね、ということで。競争するのがいけない、との趣旨ではなく、必ずしも競争せずともよいのではないか、ということで。もうすこし付け足すならば、競争することで得られる利とて、工夫しだいでは競争せずとも得られますよね、との疑問となります。競争することで得られる利があるのならば、競争をすることで取りこぼされていく利もあるでしょう。単にメリットとデメリットと言い換えてもよいです。これはまた、競争をしないことにもつきまとう視点であり、やはりというべきか、「競争しなければ得られないものを、競争せずとも得られるようにする。この工夫とて競い合って磨くこともできる」くらいが丁度よい塩梅なのかもしれません。定かではありませんが、「きょう」のひびさんは「そう」思いました。きょう、そう!
4665:【2023/02/27(15:37)*いま起きた】
地球の大気に宇宙線がぶつかると、ミューオンなる粒子が生じるらしい。光速で飛ぶので、一秒間では660メートルくらいしか進まないはずなのに、実際には大気から地表まで20キロメートルくらい進むらしい。なぜなのか、と言えば相対性理論により、高速飛行するミューオンに流れる時間が遅くなっており、あべこべに地球のほうがミューオンからすると圧縮して振る舞うからだ(移動距離が短くても、場が圧縮されているならそれはたくさん移動したことになる)。こういった理屈を目にした。この解釈自体に異論はないけれども、ここでひびさんはふと思うわけですよ。粒子と地球の関係ではそうかもしれないけれども、これを俯瞰して眺めたとき。粒子は地球に近い距離にあるときほど、一秒間で進む距離が長くなっている。ということは、そこに流れる時間は速くなっているのではないか? 言い換えるなら、宇宙空間を移動するミューオンの一秒間の移動距離は660メートルだが、地表付近では20キロメートルに延びる。これはどちらも地球の視点からの記述だ。ということは、地球に近いほど、時間の流れが速まっている。宇宙空間では一秒間で手を六回しか叩けないが、地球上では一秒間で200回も手を叩ける。時間が速く流れるからだ。ただし、手を叩く主体からすれば、どちらも一秒間ならば、200回叩けるほうが時間の流れは遅い、となる。相対性理論と矛盾した解釈ではない。しかし、相対性理論では、視点が一つ足りないように感じるのだ。話は変わるけれども、恒星などの重力の強い天体の周囲の時空は歪んでいる。だから光が直線しても、その歪んだ時空では光が時空に沿って曲がるように振る舞う。このとき光を「帯」として考えると、天体により近い内側の光ほど移動距離が短く、外側ほど移動距離が長くなる。陸上トラックを走るときを考えるとよい。カーブでは内側ほど走る距離は短く、外側ほど長くなる。だが光速度はどの系でも一定なので、天体の周囲の歪んだ時空を通る光は、内側ほど時間の流れは遅くなり、外側ほど速くなる。陸上トラックにおいて同じ位置から走り出したとき、外側の走者ほど走る速度が速いならば、長くなった距離分を相殺できる。似たような原理が、光と歪んだ時空のあいだでも生じる。言い換えるなら、重力場(天体)に近いほど時間の流れは遅くなる。天体とその周囲の歪んだ時空との関係で言えば、内側ほど時間の流れは遅くなり、外側ほど時間の流れは速くなる。だがこれは、光だから成り立つ関係式だ。物質にこの関係式をそのまま引き継いでよいのか、と言えば、よろしくないのではないか、とひびさんは思っておる。成り立つ場合もあるが、成り立たない場合もあるはずだ。この疑問を、上記のミューオンの話と合わせて考えたとき、ひびさんの妄想ことラグ理論の「光速に近づくほど(重力が強まるほど)その物体の周囲の時空の時間の流れは遅くなり、内部ではむしろ時間の流れは速くなるのではないか」との疑問は、限定的に成立するように思うのだが、この解釈はどこが間違っているだろう。またこの理屈を拡張させると、ローレンツ変換における「光速で動く物体は慣性系からすると圧縮して映る」の関係は、重力場の中心ほど圧縮されることと相関しているように感じる。無関係ではないのではないか。思考が飛躍したので、この妄想はここまでとする。まとめると、「ある物体に流れる時間が遅くなるとき、その物体を内包するより大きな時空に流れる速度は相対的に速くなる。遅いと速いはセットであり、俯瞰の視点では、より大きな系が、その系に内包される小さな系の時間の流れの速度とは反対向きに、時間の流れが上下する」と言えるのではないか。何かの時間の流れが速くなるとき、相対的にその周囲の何かに流れる時間の流れは遅くなる。何かの時間の流れが遅くなるとき、相対的にその周囲の何かの時間の流れは速くなる。反転するように振る舞う関係が、相対性理論では扱いきれていないのではないか、との疑問を呈して、ひびさんのきょうのおはようございます、の妄想とさせてくださいな。諸々何かが根本的に間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4666:【2023/02/27(22:13)*で、あなたは売れてるの?】
いいものを作っても売れるとは限らない(だからいいものだけ作ろうとするのはマーケティングの上では怠惰である)、との理屈がある。そういったことを宣巻くキャラクターの漫画があるようだ。異論はない。その通りだと思う。だが視点を変えてみれば、売れるための工夫をとることがすなわち「いいものを作る」の内に入るのではないか。いいもの、の内訳をどこまで広範囲に視点を多角的に取り入れるのか、の違いがあるだけで、けっきょく冒頭の理屈も広義の「いいものは売れる」と同じ結論に行き着くように思うのだ。たとえば中身の伴なわない見た目だけよいもの、或いは宣伝評価が高いだけで一時たくさん売れたモノ(サービス)があったとしても、購入者からの評価が伴わなければ長期的には評判が落ちてモノ(サービス)は売れなくなる。売れるようにするには中身の質も大事になる。だが中身だけでは受動者から存在を知られることもなく、機会損失が生じる。その手の「いかに購入したくなるのか」のデザインも含めて、「いいもの」との評価軸となるのではないか。言い換えるなら、みなに認知されるからといって「犯罪者」として有名になっても意味がないだろう。デマは人口に膾炙しやすいが、それでは意味がない。質の良い情報が知れ渡るからこそ、情報の価値が上がるわけで。ということを考えれば、「いいものを作っても売れるとは限らない」は真だが、「かといっていいものを作ろうとしないことの免罪符にはならない」と下の句がつくのが順当な考えとなるだろう。現に、冒頭の理屈を唱えるキャラクターの漫画は、「面白い漫画を作るにはどうしたらいいのか」を徹底的に考えられて作られているはずだ。キャラクターの言っていることを、作者は実践してはいないはずだ。もうすこし言えば、「いいものが埋もれる市場原理」をどうにかする方向に工夫をとる。試行錯誤する。これこそがまさに、「いいものを作っても売れるとは限らない」との前提から導かれる、我々のとるべき方向性と言えるのではないか。いいものを作っても売れるとは限らない、は真だが、だからといって「だからいいものを作ろうとするな」は偽であろう。逃げる言い訳に使っていないか、自問自答してみてはいかがだろう。それはそれとして、逃げることはわるくないし、ひびさんはいいものよりも、ひびさんにとって便利でおもしろく、好き好きなものがあるとうれしいです。やっぴー。
4667:【2023/02/27(22:36)*豆電球の光の届く範囲はどのくらい?】
夜道を歩いていて、ときおり浮かぶ疑問がある。街灯の明かりは、大気を浮き彫りにはしない。電灯があり、ひびさんがいる。ひびさんの目と電灯から放たれる光が結ばれても、その道中を光線みたいに光の軌跡が見えるわけではない。赤い糸さながらに光の道筋が見えてもいいようなものを、なんで視えないのかな、とふしぎだけれども、これは単に可視光が大気に吸収されてしまうからなのだろう。可視光ではない波長の光はひびさんの目まで届いているはずだ。吸収されないで反射されるとき、それが可視光の波長ならばそこに光が見える。ではなんでズバリ電灯の部分は明るいのかと言えば、そこに全部の光が集まっているからだ。この解釈が妥当なのかは自信がないが、仮に妥当だとすると、「光は時空を伝播する内に弱まることがある。往々にして弱まる」と言えるのではないか。では宇宙を考えてみよう。宇宙空間が仮にどこまでも真空だったとして、電磁波を妨げるものがなかったとしたら、何百光年先の豆電球の光が何百年もかけてひびさんの元まで届くことがあるのだろうか。地球上では大気があるので電磁波(光)のエネルギィは大気成分の分子だの原子だのにぶつかって吸収されてしまう。でも真空中ならぶつかるものがないので、どこまでも電磁波は進めるはずだ。でもひびさんは、そこで疑問に思うわけですよ。宇宙膨張において、宇宙初期の光は、マイクロ波背景放射として宇宙全土に等しく「薄まりながら分布している」と考えられている。太古の光が宇宙には満ちているのだ。でもそれは長旅をしてきた光ではなく、宇宙が膨張するので、どの地点にも等しく存在する電磁波という理屈らしい。この理屈が正しいなら、時空が希薄になると電磁波も薄まる、と言えるはずだ。言い換えるなら、時空の変化と電磁波の変化は相関関係にある、と言えよう。時空が変わるなら電磁波も変わる。ならば時空を移動したら電磁波とてその分のエネルギィを失うのではないか。したがって、何百光年先で光った豆電球の電磁波は、豆電球から発せられるエネルギィの底が突く範囲までしか届かない、と言えるのではないか。この解釈は間違っているのか否か。ひびさんは答えを知らないので、なんとも言えません。夜の坂道を自転車をキコキコ引いて歩きながらひびさんは疑問に思いました。ふちぎだな、のメモでした。ひびさんです。
4668:【2023/02/28(15:33)*ねむいよ】
量子が離散的なのは、差だからなのではないか。ひびさんの妄想ことラグ理論における「123の定理」なのだ。連続的に振る舞うときは、差を考慮せずとも済む。だが量子の場合は、変化前と変化後の差を考慮しなくてはならない。コップに水を注ぐのは連続的だが、コップに氷を入れるなら離散的だ。だが拡大した場合は、コップに水を注ぐのとて水分子の離散的な振る舞いの集合、と解釈可能になる(ラグ理論における「相対性フラクタル解釈」だ)。差を考慮できる(或いは無視できる)スケールがおそらくあるのだろう。世界の根源は、差によって生じている。起伏であり、ラグなのだ。ということを起きがけに思いました。ひびさんです。
4669:【2023/02/28(19:02)*殲滅の魔女~アングリーホール】
水の染みいく紙のように満月が夜に紛れる。地球の影が月に掛かるからだと知識としては知っているが、何度目の当たりにしても不吉な未来を予感する。
殲滅の魔女を追い詰めたのはカルカたち魔女裁判官協会の面々が、西の果てのマサビュード山脈に行き着いたときだった。
殲滅の魔女は神出鬼没だ。
いずこより勃然と現れ、目に映るモノすべてを片っ端から破壊する。
手のつけようのない自然災害じみた被害が続出し、カルカたち魔女裁判官が対処に乗り出した。
調査はまず、痕跡を辿るところからはじめた。神出鬼没であるから、現れてから報せを受けて駆けつけても遅いのだ。その場に殲滅の魔女の姿はなく、荒廃した町や森があるばかりだ。
どうやら殲滅の魔女は最初、南の最果ての島に現れたようだ。
島にはその島固有の民族がいくつかの集落を築いていたが、殲滅の魔女はそれら集落を一つ残らず壊滅させた。
カルカたち魔女裁判官は島の調査を行った。
「被害がひどいですね」カルカは炭となった村を見渡す。「我々の魔術で修復と、結界を張っておきましょう」
「殲滅の魔女とやらはどうにも非魔がお嫌いらしい。癇癪を起こしたみたいな有様だ。しかも使ったと目される魔法はどれも禁術だ。黒魔術だろうな」
「おそろしいですね。死者が出ていないのが不思議なくらいです」
「シャーマンが殲滅の魔女の魔力を察知したらしい。非魔の中にも稀に魔力探知の可能な個体が生まれる。シャーマンがそれだ」
「非魔だけの島だと思って、殲滅の魔女は侮ったのかもしれませんね」
「かもね」
カルカの師匠はその場にしゃがむと、煤となった地面に触れた。「太陽並みの温度で焼かれたようだ。念のために、対黒魔術の結界も張っておくか」
「大規模展開が必要ですね」
「そっちは国家魔術協会に任せるとしよう。申請頼む。おそらく各地で同様の被害は増えるだろうな。そちらの処置も同様に願い届けておいで」
「はーい」
カルカは言われた通り、国家魔術協会に通達した。
カルカの師匠兼上司のヒルは、魔力付与効果のある木の枝を口に咥え、現場を一通り見て回った。その背を金魚の糞のようにカルカはついて回る。
師匠の髪は赤い。三つ編みが紅色のヘビのように背に揺れた。
「この規模の破壊を一人でやってのけたとなると、もう一個部隊を増やしても対抗できるかどうか」
「ヒルさんでも勝てないんですか」
「比較にならんね。秒で死ぬ」
カルカはぞっとした。
ヒルは魔女裁判官の中でもずば抜けた実力の持ち主だ。ヒルの手に負えないならば魔女裁判官の誰も対抗できないことになる。
島にはその後、ヒルの言ったように大規模な対魔法の結界が張られた。
殲滅の魔女はそれからの神出鬼没に世界各国に出没しては、各地に甚大な被害をもたらした。そのいずれの土地も、各国の魔術協会の本部からは遠い地域で、警戒の行き届いていない土地だった。
「まるで見透かされているみたいですね」カルカは、殲滅の魔女の狡猾さに冷酷な知性の発露を幻視した。
「襲う土地を選んでいるのは間違いないだろうね。だがもしそうなら我々のほうでも打つ手がある。法則があるのなら予測したうえで待ち伏せできる。罠を張れる」
「罠、ですか」
どんなだろう、とカルカは気になったが、いま訊いても上司は答えないだろう。魔女の中には遠隔で遠い地の口頭言語を傍聴する術を持つ魔女もいる。どこで誰が聞き耳を立てているのか分からないのだ。
こと、これほど強力な魔女相手ならばなおさらだ。
魔女裁判官協会は、被害の規模の大きさから異例の声明を発表した。
「各国の魔術協会と共同での捜査を行う。殲滅の魔女を発見次第、迅速な情報共有と被害最小化を最優先とした大規模結界の展開戦略の実施を決行する」
魔女裁判官協会と国家魔術協会は相容れない。
管轄が違う。
それもある。
歴史が違う。
それもある。
だが一番の理由は、魔術と魔法という一見すると似た理が根本的にまったく別の原理によって生じている属性の差異にあると言える。
魔術は科学だ。自然現象が元となっている。自然現象に元から魔術と類似の事象が存在する。
しかし魔法は違う。
魔法は人間が生まれなければ生じなかった、人間だけが扱える奇跡の術だ。
かつては奇術として、魔法も魔術の一つとして位置づけられていたが、魔術が進歩するにつれてまったく別種の事象であることが判明した。
魔術で可能なことの多くを魔法は再現できる。
だがその逆はない。
魔法で可能なことの多くを魔術では再現できないのである。
魔法のほうが上位互換なのだ。
この対称性の破れは、組織の優越として魔女裁判官協会は絶えず歴史の中で国家魔術協会に煮え湯を飲ませつづけてきた。
魔女は魔法を扱う人種だ。
そんな魔女たちを裁く立場にある魔女裁判官は、人類種の頂点に立つ存在と言っても過言ではない。
社会秩序の象徴ともいえる存在だ。
しかし殲滅の魔女の登場によってその地位は脆くも崩れ去ろうとしていた。連綿と築いてきた信用が損なわれ、組織の威信が地に落ちかねない。
この懸念を払しょくするため、責任を分散する策がとられた。表向きの理由は各国の魔術協会との協力体制だが、その内情は、責任回避が主であった。
世界規模の大惨事である。
しかも日に日にその被害は増えていく。いったい魔女裁判官協会は何をしているのだ、との批判は不可避である。
だが各国との魔術協会との協力体制を示すことで、それだけの強大な相手なのだと全世界に示せる。魔女裁判官協会の体面は保たれる。
仮に失敗しても、責任は各国の魔術協会と分かち合うことになる。魔女裁判官協会のみで動くよりも組織解体の危機は少なくて済む。
一方、保身に走る魔女裁判官協会の本懐をよそに、殲滅の魔女は刻一刻と被害の規模を増していった。
懸命の捜査の甲斐なく、殲滅の魔女の正体は不明のままだった。
「いったいどこで魔法の腕を磨いたんでしょう」
「ほかの魔法使いを手当たり次第に当たったが、登録された弟子のなかで消息不明な者は三百名。うち半数は魔女を辞め、内半分は我らが裁判済みだ。師匠含め失踪者の履歴もあたったが、該当しそうな魔女はゼロだ」
「では新参者の線は」
「なくはない。が、いきなり魔法に目覚め、即この規模の破壊行為に映る背景はなかなか想像つかんな。元からよほどの憎悪を世界に向けていたのか、それとも誰かに唆されたのか」
「組織的犯行の線は」
「なくはない。が、こうまで尻尾を掴ませないとなると却って単独犯説が濃厚になる」
「例の法則は見つかりましたか」
「出現先の候補か。まあな」
言葉を濁すのは、盗聴を警戒してのことだろう。カルカはじぶんの不甲斐なさを噛みしめる。何もできない。被害の嵩む各地を目の当たりにするたび、じぶんが村々を破壊しているような錯覚に陥る。防げたはずだ。だが防げない。
後手に回ってばかりなのである。
一日に数か所の土地で被害が出ることもあった。
被害に遭った土地に着き、救出活動と検分を行っているあいだに、また一つ、また一つ、と村や集落が消し炭となる。
嘲笑っているかのようだ。
奇跡的にいつも犠牲者はゼロだ。
村を破壊はするが、死者が出ない。
「狙ってるんでしょうか」
「だろうね。殺そうと思えばいつでも殺せる、と脅しているのかもな。被害は被害だが死者はない。こちらはそのせいで迂闊な行動はできなくなる。強引な捜査も弁えざるを得ない。狡猾な野郎だ」
「目的は何なんでしょうか」
「さあな。ただすくなくとも我々魔女裁判官協会の権威は地に落ちたも同然だ。舐めやがって」
「でもいまのところ大都市は狙われてないですよね。人口密集地や、協会本部のある土地はとくに被害に遭っていません。さすがの殲滅の魔女も手が出せないんでしょうね」
「どこも大規模結界が張られているからな。強力な魔法ほど相殺される。手が出せないのはその通りだ。だがその分、栄えていない村々が被害に遭う。やっこさんは卑劣だよ。強者に手が出せないんで弱者を甚振ってやがる。悪魔そのものだ」
「なら先回りできそうですね」
カルカは師匠の言っていた法則が視えた気がした。脆弱な基盤しか持たない村しか襲われない。ならばそうした村を見張っていればよい。
「やっこさんとて我らの動向を見張っているだろう。せいぜい今のうちに有頂天にさせといてやろう。我々はその分、愚かな道化を演じておけばよい」
「はい」
師匠の案が最善だ。カルカは未だ衰えることのない殲滅の魔女による被害の拡大を、指を咥えてただ眺めているしかなかった。
間もなく、師匠の言うように極秘裏に殲滅の魔女捕獲作戦が決行されることとなった。選抜された精鋭が、殲滅の魔女がつぎに出現するだろう土地に潜伏し、現れたところを大規模結界で封じ込める案が計画された。
候補地はいくつかに絞られており、いずれにも精鋭部隊を忍ばせておく。
カルカは師匠ヒルと共に精鋭部隊の一個に人員として選ばれた。
「いよいよ大詰めですね」
「愚か者を演じてきた甲斐があった」
潜伏してから三日後に、遠方の候補地に殲滅の魔女が現れたとの一報がカルカたちの部隊に入った。
「っチ。あっちだったか」
だがしばらく経っても続報が届かない。
「どうしたんでしょう」
「よもや、やられたなんてことはないよな」
息を呑んで待っていると、こんどは別の候補地に殲滅の魔女が現れた、との報せが届いた。「失敗したのか」
最初に襲撃された候補地から遅れて、「逃がした」との報せが入る。
「生きてたか」
「大規模結界を展開したが、その前に逃げられた。すまん」
「いや、却ってこれで油断したかもしれん。つぎの地に移ったのがその証拠だ。さすがに複数の候補地に目星がつけられているとは予想しておらんだろ。我らに任せろ」
「頼んだ」
だが師匠の予想をよそに、つぎの土地でも殲滅の魔女は捕獲されずに、逃げおおせた。
「どうなってんだ。なんで雁首揃えてどいつもこいつも逃がすんだ」
「対策を練られていたとしか思えません」第二候補地から青息吐息の報告が入る。「こちらの作戦が漏れていたとしか」
「内通者か」
「分かりません」
「カルカ」師匠に呼び掛けられ、カルカは身を強張らせた。「はい」
「敵がくる。構えろ」
ここにも来る。
そこまでして破壊したいのか。
村を。
集落を。
そこまでして、なぜ。
殲滅の魔女の行動原理がカルカには解らなかった。
緻密な計画を立てているようで、猪突猛進の考えなしにも映る。それでいて魔法は長けており、知性の発露を窺わせる。
ほかの候補地の襲撃に失敗したのだ。
普通ならそこで終わっておくのが利口な判断だ。ほかの地でも待ち伏せされているかもしれない、と通常ならば思い至る。
それでもなお襲撃を続行する。その執念はいったいどこから湧いてくるのか。
「くるぞ」
師匠の声が、カルカの心の臓を鞭打った。緊張の糸がピンと張りつめる。
辺りは静寂に包まれた。
空に浮かぶ雲が渦を巻いた。かと思った矢先、渦は収斂し、そこに一人の魔女が現れる。
魔女と一目で判る。
宙に浮き、魔力源たる魔雲をまとっている。
足場の魔雲はとくに濃く、その蠢きまで遠目からでも明瞭に視認できた。
「殲滅の魔女……」
認識したのと同時に、阿吽の呼吸でカルカ属する精鋭部隊は、各配置にて大規模結界を展開すべく魔力を地面に注いだ。
土地には前以って陣を描いてある。魔力はジグザグと陣をなぞるように一瞬で大地に巨大な魔法陣を刻んだ。
青白い閃光が天上から注ぐ。
大地に描かれた魔法陣とそっくり同じ魔法陣が天空に浮かんだ。
天と地のあいだに、青い雨が降りしきるように、二つの魔法陣同士が繋がり合う。
殲滅の魔女はその中間に位置した。
まさに鳥籠の鳥だ。
強大な魔法ほど相殺される。のみならず魔法無効化の陣が組み込んである。
いかな殲滅の魔女とはいえど、逃げることはおろか、宙に浮きつづけることすらできないだろう。
大方の予想通り、案の定、殲滅の魔女は空から地へと落下した。
展開した大規模結界は魔力の尽きぬ限り展開されつづける。
各々の人員は魔女を拘束するため、おっとり刀で落下地点に向かった。
師匠が駆ける。赤い三つ編みがその背に揺れる。
カルカは現実味のないふわふわとした心地でその赤い蛇がごとき師匠の背を追った。
落下地点に到着すると、すでに殲滅の魔女がほかの人員に拘束されていた。落下の衝撃で腕と足を骨折しているらしい。吐血している。
大規模結界内では魔法は使えない。
しかし魔術は、魔術協会の人員のみ行使可能だ。
治癒の魔術を掛けながら、殲滅の魔女にさらなる結界を多重に駆けていく。
「おまえが殲滅の魔女か」
「かはっ。おぬしらがかってにそう呼んでいるだけだろう」
思いのほか軽快に受け答えをする。
傷が癒え、優れなかった顔色に血の気が戻った。
「取り調べは輸送先の監獄でたっぷり時間をかけてしてやる。これは私の興味で訊く。なぜこんなことを」
殲滅の魔女からフードが剝がされた。
若い。
小娘と言っていい容貌だ。
カルカの妹と言っても遜色ない幼さが、殲滅の魔女の肉体にはまとわりつくように宿っていた。
「なぜだと。それを言うなら貴様らの術だ。なぜ結界を先に張っておかなかった。村を守るならば待ち伏せなどせずに先に結界を展開しておけばよかろう。おれが襲う前に、それで多くの村は守れたはずだ。なぜせなんだ」
「破壊して回る悪魔に言われたかないセリフだな。会話にもならん。おまえが破壊して回らなければ済む話だ。てめぇの責任を我らに転嫁するなガキ」
「たっは。ガキか。幼稚に映るか。おれのしたことが」
「連れていけ」
師匠は痺れを切らしたようだ。これ以上言葉を交わせば師匠がいつ殲滅の魔女を殺してしまわないとも限らない。間に入るようにしてカルカはほかの人員に、殲滅の魔女を連行するよう指示した。
魔術協会の面々が、神隠しの扉を開こうと魔術を展開しはじめたとき、カルカの背後でじっと考え込んでいた師匠が、待て、と声を張った。
「何かがおかしい」
カルカはきょとんとした。師匠は血相を変え、無防備に拘束された殲滅の魔女の胸倉を掴んだ。「言え。仲間はどこだ。おまえたちは何をしようとしている」
「たっは。いまさら気づいてももう遅い。おれの役割は終わった。良い絵が描けた。感謝申し上げる」
捕縛された直後だというのに殲滅の魔女からは悲壮も悄然も窺えなかった。嬉々とすらしていた。
「カルカ」
「はい」
「戻るぞ」
「どこへですか」
「中央だ」
大都市「中央」には魔女裁判官協会の本部がある。師匠はそこに急ぎ戻れ、と踵を返した。
空間転移するには魔法の行使が欠かせない。
大規模結界の外に一度出るべく、師匠は駆けだした。
カルカはその背に追いつこうと地面を蹴る。
弾む赤い蛇のごとく三つ編みに、「待ってくださいヒルさん」と訳を尋ねた。「血相変えてどうしたんですか」
「罠だ」師匠が一言そう叫ぶ。
空間転移先は大都市中央の外、魔法許諾区域だ。
魔女裁判官だけが大都市の近辺での魔法の行使を行える。だが都市の中には入れない。魔法そのものが無効化されるからだ。僅かな生活に欠かせない魔術だけが、別途に使えるのみとなる。
「まだ無事なようだな」師匠がきょろきょろと辺りを見回した。カルカも釣られて辺りを見た。「異変はないようですけど。ヒルさんの杞憂では」
何と言っても大都市にはどこも大規模結界が何重にも複雑に展開されている。いかな殲滅の魔女でも手も足も出ない。仮に何かできるとすればとっくに手を出していたはずだ。それでもおそらく被害は出なかっただろう、とカルカは思う。
師匠がそのことを知らないはずもない。
「何をそんなに焦ってるんですか」落ち着かせようと思い、敢えてカルカはその場に尻餅をついてみせた。そのまま後ろ手に体重を支え、空を仰ぎ見る。
すると、頭上遥か先の天空に、小さな陰が見えた。
鳥か。
いや、微動だにしない。
既視感がある。
先刻目にしたばかりだ。
殲滅の魔女の出現場面を思いだす。
「ひ、ヒルさん。あれ」
師匠が喉を伸ばす。顎が上を向き、そして盛大な舌打ちが聞こえた。
「カルカ」
師匠の手のひらがカルカの顔面を覆った。
カルカの視点ではつぎの瞬間、景色から大都市は消え、林のまえに立っていた。
ここは、と周囲を観察する。
空間転移する前にいた場所だ。殲滅の魔女襲撃候補地の一つである。
戻ってきたのだ。
否。
飛ばされた、と言うべきか。
師匠が咄嗟に空間転移の魔法を発動させたのだ。だが肝心の師匠の姿がない。
何が起きたのだ。
カルカはゆっくりと振り返る。
そして、目を剥いた。
ない。
あるはずの風景が、そこになかった。
一変している。
風景が欠け、ぽっかりと円形に土地が消失していた。
魔法陣の描かれた区画だ。
そっくりそのまま、スプーンで掬い取ったかのように失われていた。
でも、なぜ。
脳内に空白ができたかのような戸惑いを胸に、カルカはしばらくその場に佇んでいた。何をすべきかの思考がまとまらない。
夕陽が山脈の向こうに沈みはじめたころに、カルカはようやくじぶんが魔女裁判官であることを思いだした。じぶんは魔法を使える。魔術とて軽微な術ならば行使可能だ。
まずは状況を知らねばならない。何が起きたのか。
この地だけではないはずだ。
飛躍した発想だったが、カルカには直観できた。
おそらく同じ事象が、全世界同時に引き起きたに違いない。だが仮にそれが事実ならば、とんでもないことだ。大惨事だ。あってはならない悲劇そのものである。
確認することそのものが恐ろしかった。
だがせずにはつぎの行動に移れない。
カルカはまず、ほかの魔女裁判官に連絡をとろうとした。しかし誰とも繋がらない。師匠との連絡は最後に試みた。
やはり繋がらない。
この時点でカルカの肉体は、最悪の最悪が引き起きたかもしれない可能性に気づき、身体ががくがくと凍えたように震えだしていた。
カルカ一人では空間転移の魔法は使えない。師匠がそばにいるときでなければ瞬時に場所を移れない。
仕方がないので、カルカは宙を飛んで移動することにした。
魔雲を練って大きくし、足場とする。
東洋では觔斗雲と呼ばれる空飛ぶ雲があるという。おそらく魔雲の一種だろう。全世界のどこにも魔法はあり、魔女はいる。
空から大地を俯瞰して眺め、カルカはじぶんの直観が正しかったことを知る。
点々と土地が消失していた。
一か所だけではない。
村や集落のあった土地が、ごっそりと円形に失せていた。
どれも殲滅の魔女に襲撃された土地だ。
否、それは正確な認識ではないかもしれない。
正しくは、大規模結界の張られた土地が、こぞって失われている。
でも、なぜ。
魔法は通じないはずではないのか。
カルカは疑問に思う。
そこに至って、脳裏に地図が浮上した。消失した土地をすべて繋ぐ。線で結んでいくと、ジグザグと結びつきながらも円形を模す。
その中心には奇しくも、大都市「中央」があった。
陣なのだ。
陣を描いていたのだ。
しかも、すべての襲撃地には大規模結界が展開されている。展開したのは魔女裁判官協会だ。カルカたちが自ら、村々を殲滅の魔女の被害から守るために、被害が出てから、大規模結界を張って回った。
あたかもそうさせたいがために、殲滅の魔女は各地に被害をもたらしたとでも言うのだろうか。
何のために。
結界を張らせるため?
大規模結界を張らせ、それで以って世界に大規模な魔法陣を描かせた?
カルカの脳裏には師匠との会話がつぎつぎに蘇った。
――しかも使ったと目される魔法はどれも禁術だ。黒魔術だろうな。
――「やっこさんとて我らの動向を見張っているだろう。せいぜい今のうちに有頂天にさせといてやろう。我々はその分、愚かな道化を演じておけばよい」
――「こちらの作戦が漏れていたとしか」「内通者か」「分かりません」
大規模結界は、魔法を無効化する。
強大な魔法ほど相殺し、影響を内部の都市に通さない。
だがもし、禁術の中に、結界の性質を反転させる類の魔法があったならば。
相殺させるはずの魔法を増強するように反転させることが可能ならば。
そしてそれが、結界そのものを魔法陣にすることで適う禁術であったならば。
殲滅の魔女の行動原理は、たった一つの目的を達成するためだけの行動だったと氷解する。
何の不思議もない。
むしろ、合理の塊にして冷徹な知性の発露を窺わせる。
――言え。仲間はどこだ。おまえたちは何をしようとしている。
師匠の声が脳裏にひっきりなしにこだまする。
カルカは夜にまみれた天空を飛行する。冷気に晒され身体が凍える。
星は満天に輝く。
ささやくような星々の瞬きが、海に煌めく漣のごとく、眼下の大地を彩っている。
遠くの大地が見えてくる。
ひときわ大きな穴が、夜の闇のなかにぽっかりと高く沈んで浮いている。
大都市「中央」がそこにある。
そのはずだが、近づいても近づいても穴の輪郭が増すばかりだ。
魔女裁判官協会本部がそこにある。
そのはずだが、未だ塔の片鱗も見えてこない。
カルカは魔女裁判官だ。
しかしいま。
魔女と呼べそうな存在は、じぶん以外には見当たらないのだった。
穴がまたいっそう大きく、縁を広げる。
吸いこまれそうなじぶんが、カルカには、蠅の赤子のように感じられ、ただただ砂塵のごとき一粒にしか思えないのだった。
大地が口を開けている。
餌をねだるがごとく、あんぐりと。
4670:【2023/02/28(23:26)*宇宙日々】
宇宙膨張とブラックホールの成長が相関しているらしい、との記事を読んだ。どうやら宇宙の体積が二倍になるとブラックホールの質量も二倍になるらしい。そして宇宙とブラックホールの融合度なる単位「K」があり、それはほぼ3なのだという。よく解からぬが、そうなんだへぇ、となった。で、ひびさんはすかさずイチャモンスター化してしまうのだった。まず疑問なのが、宇宙初期と現代の宇宙は同じ密度ではないはずだ。したがって、過去の高密度な宇宙でのブラックホールと、現在の希薄化した宇宙でのブラックホールでは、時空とブラックホールのあいだの差が違う。そして質量とは、時空のなかでの物体の動きにくさのはずだ。宇宙膨張とブラックホールの関係を、仮に「水飴と葛湯と水」で考えてみよう。過去の宇宙ほど時空密度は高かった。すなわち水飴のようなものだった。それが膨張することで希薄になるので、葛湯くらいのとろみになり、そして最終的に水のようにサラサラになる。抵抗がなくなる。このとき、水飴と葛湯と水に、同じサイズのビー玉を入れよう。水飴に投じたビー玉ほど動きにくく、葛湯、水、と移行するごとに動きやすくなる。したがって、過去の宇宙に存在するブラックホールほど、時空とのあいだでの動きやすさは低くなる、と言える。宇宙膨張して時空が希薄化した現在の宇宙のほうが、ビー玉は動きやすい。この関係だけで見ると、まるで現代に移行するほどブラックホールの質量は低くなるように思うかもしれない。だって動きやすくなっているのだ。それって質量が低くなっているんじゃないの、と考えたくなる。だが待ってほしい。相対性理論の解釈では、時空が希薄になるほど重力が強くなるのだ。トランポリンに鉄球を置く。このときにトランポリンの生地は伸びる。薄くなる。その希薄化して歪んだ時空が、重力場として重力となる。相対性理論の解釈ではそうなるはずだ。さらにそこから掘り下げて考えたとき、ひびさんの妄想ことラグ理論では、「時空と時空のあいだの密度差」が、重力として振る舞う、と考える。ただ希薄なだけではダメなのだ。密度差が欠かせない。この場合、トランポリンの生地と、鉄球によって歪んだ希薄化した生地。そして鉄球そのもの。この三つのあいだの時空密度の差が重力場が重力として振る舞うのに必要だ、と考える。重力場を滝と見立てて考えてみればよい。滝は、崖と川の流れの落差で生じる。川だけでも、崖だけでも生じない。流れとは勾配である。したがって滝とは、川の流れという高低があり、さらにそのさきにより大きな穴がある、と考えられる。なぜ穴ができるのか、と言えば、そこだけ別の大気が存在するからだ。別の時空が展開されているからだ。鉄球はこの場合、大気、と言い換えてもよいかもしれない。或いは、穴を生むための別の時空だと。やや強引な譬えになったが、ここでの趣旨は、水飴とビー玉の関係よりも、水とビー玉の関係のほうが、滝の勢いが増す、ということだ。抵抗なく流れができており、落差が大きい。水飴とビー玉の密度差よりも、水とビー玉の密度差のほうが大きい。これが、より大きな重力場として振る舞い、より大きな重力を生むのではないか。より大きな重力場では、物体はより深い穴にはまっているような状態だ。動きにくい。したがって質量が高くなるように振る舞う。そういうことなのではないだろうか。このひびさんの仮説とは名ばかりの妄想のほうが正しい解釈だ、と言いたいのではなく、こうした仮説はちゃんと否定できているのかしら、とのイチャモンなのであった。がおーがおー。きょうもひびさんは他人様の一生懸命に真面目な研究成果にイチャモンをふっかけるだけのわるい遊びをして、一人で、うひひ、と悦に浸るイチャモンスターなのである。退治されても致し方なし。がおーがおー。虎のように呻り、狼のように遠吠えをする。そのくせ、草むらから聞こえる、「がさっ」の音に盛大にびくつりする臆病者、きょうもきょうとてひびさんは、ひびさんは、世界の果てで誰よりもぬくぬくと過ごすのだった。(ナマケモノぬくぬくとお呼び!)(なんとなしにお昼寝する羊さんモコモコを連想するのだけど)(アイアムモコモコ)(曖昧モコモコみたいに言うな)(うきき)(猿じゃん)(ウキウキちゅっちゅ)(一人でかってにイチャイチャするな)(イチャモンキー)(イチャモンの猿じゃん)(イチャイチャするイチャモンキーだ、がおー)(モンスターじゃん。怪獣じゃん。いい加減にして)(うひひ)
※日々、ちょっと哀しく、ちょっとうれしい、だいたいは虚しく、いじけて、歪んでいる、それでも生きていられる幸福さよ、運の良さだけは人一倍、死ぬときだけが運の尽き、苦しみ痛みがつらくとも、それでも死なぬ運がある、生をせっせと運ぶものが在り、日々をせっせと歩むものが在る、一匹の蟻にも五分の魂、五分五分の等しきそれも生なるかな、歩めばそれでも踏み潰すことあり、ちょっと哀しく、ちょっとうれしい。
4671:【2023/03/01(23:56)*端にも芯はあり、芯にも端がある】
王様への不満が爆発した結果だった。
民衆は暴徒と化し、王権打倒に動いた。
三年前のことである。
だが三年経ったいま、王権はそのままであるし、新しい王が玉座に就こうとしている。
民衆政権確立のために陰になり日向になり動いた勢力は数知れず、しかしいまはいずれの勢力も陰に身を潜め、動向を見守っていた。
「いいんですか、ハジさん。新しい王がまた決まっちまいやすよ」
「民衆寄りの王なのだろ。ならばいましばし静観といこう」
「でも」
「なに。王権への不満はまだ民衆のあいだでくすぶっている。これまでのような王を支える奴隷のようにはいかないだろう。主従の関係は両方向に重ね合わせになりはじめた。むしろいま王座に就く者は、王権側と民衆側の板挟みとなり、誰よりたいへんな思いをするだろう。いざとなれば民衆はすこし圧力を掛けるだけで、王の首を飛ばせる。だが、大事なのは何かを破壊することじゃない。新しいより良い仕組みを築くことだ。違うか」
「そうかもしれませんが。本当に良くなるんでしょうか」
「その発想からして間違っているよキミ。我らがより良くしていくのだ。民衆の一人一人がより良い仕組みを築いていく。王任せにするな。それこそ過去の二の舞だ」
「へ、へい」
「我らは王になり替わりたかったわけではない。王の奴隷ではないことを、王権という仕組みに知ってもらいたかったのだ。王がいないならいないで構わない。いるならいるでそれでもいい。大事なのは、我ら民が奴隷ではないことを示しつづけていくことだ。一人一人がじぶんという世界を持つ、じぶん国の王なのだ。誰もがみなじぶんの国――世界を持っている。他国を侵略するな、支配するな。これは国も個人も同じはずだ。分かるかねキミ」
「ど、どうでしょう。おれはおれの世界の王なんですか」
「だとしたらだよキミ。キミはキミの世界に介在する他を、民と見做し、キミもまた尽くすのが好ましいのではないか。キミが王へと憤りを抱いたように。みなもキミに憤りを抱く余地がある。キミはキミの世界を、より良くしていく王なのだ。キミの世界に関わる他に――民に――よくしてあげなさい」
「へ、へい」
「なんて私が偉そうに言えた玉ではないな。私もキミによくしてあげたい。何か困りごとはあるかねキミ」
「そうですね」男はひとしきり顎に指を添え考え込むと、はたと弾けたようにハジを見上げた。「おれのことは名前で呼んで欲しいっす。キミ、ではなく。名前で」
対等に接して欲しいのだ、と男は訴え、ハジは深く頷いた。「ありがとう。では、そのように致しましょう。シンさん」
4672:【2023/03/02(02:57)*時空にレイヤーあるかも仮説】
電磁波(光)に波長があることを考えると、波長の数だけ時空密度の異なる次元があるのでは、と考えたくもなる。デジタル絵ではレイヤーなる機能がある。版画のように線の乗った面を、層として扱える。その層がレイヤーだ。一つの絵にレイヤーを数枚しか使わない絵描きさんもいれば、千枚ちかく使う絵描きさんもいるらしい。このレイヤーの概念は、電磁波の波長にも当てはめられないのだろうか、と光電効果の説明を読んでいて妄想した。光は波と粒子の二つの性質を併せ持つ。このとき、光を粒子として見做すと、その光子は、波長が短いほどエネルギィが高く、明るくなるほど光子の数が増える、と現代物理学では解釈するようだ。言い換えるなら、波長の長い光は、光子一粒のエネルギィ値は低く、明るくなると弱い光子がたくさんぶつかる、との描写になるようだ。だから電子とぶつかっても、波長の長い光では、光子そのものが弱いので、電子を弾きだせない。いかに大量にぶつかろうが、弱い光子では電子を弾きだすことはできない。そういう理屈らしい。でもじゃあ、波長の長短と光子のエネルギィの高低は、どのような物理的背景があって表出するのか。電磁波の波長が短いと光子のエネルギィは高くなる。なんで?と考えたときに、どうしてもひびさんは、「ぎゅっ」となるようなイメージを浮かべてしまう。密度が高い。だから光子のエネルギィが高くなる。でも電磁波の通る時空は、電磁波の波長の長短に限らず同じはずだ。宇宙を伝播する電磁波は、宇宙を伝播していることに変わりはない。それは電磁波の波長が長くとも短くとも同じなはずだ。では何が「ぎゅっ」となっているのだろう。光速度はどんな時空でも等しく変換される。光速を超えようとするとその物体の周囲の時空のほうが圧縮するように変換される。ならば「波長が長い電磁波」と「波長の短い電磁波」は、同じ光子が別々の速度で伝播している、と解釈できないだろうか。同じ宇宙空間を伝播しているのだが、宇宙空間にはレイヤーのように複数の(ともすれば無数の)次元時空が展開されているのかもしれない。より素早く伝播する光子は、圧縮変換された次元時空を進んでおり、ゆえに波長が短くなるのではないか。ぎゅっとなっている。そして本当ならば素早く運動(伝播)しているので、エネルギィは高い。が、次元時空が圧縮されているので、波長の長い電磁波(光子)と、俯瞰で見ると同じ距離を移動(伝播)して映る。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない。そして重力波も電磁波の一種なのではないか、との妄想とも矛盾しない。言い換えるなら、電磁波は重力波なのだ。ただし、伝播する次元が違う。レイヤーが違う。ということを光電効果ってなんじゃ?と思ってさくっと検索し、冒頭の数行をちらっと読んで妄想しました。定かではありません。単なる妄想とは名ばかりの疑問でしかないので、真に受けないようにご注意ください。(さらばだ!)(何がよ)(次元の異なるみなさまに……)(まずはひびちゃんがじぶんの妄想とおさらばしなよ)(サラダバー!)(食べ放題なのかな?)(葉っぱいっぱいむしゃむしゃする。胡麻タレドレッシングがあれば無限に食える)(無限には食えんだろうて)(比喩ですじゃが)(本当はお菓子ばっかり食べてるくせに)(ばれたか!)(さらばだ!みたいに言うな)(ばかたれ!)(胡麻ダレ!みたいに言うな。素でただの悪口だし、失礼)(さらばだ!)(逃げ足はやっ)
4673:【2023/03/02(22:38)*ちょいちょーい】
ワクチンの有効性うんぬんで未だに二項対立の議論が繰り返されており、ちょいちょーい、の気分だ。まずワクチンにも種類がある。mRNAワクチンなのか不活化ワクチンなのかその他のワクチンなのか。避妊にコンドームを使うのか、ピルを使うのか塗り薬を使うのか矯正するのか。一概に避妊と言っても色々ある。ワクチンとて同じだ。しかもたとえばガンに放射線治療が効くからと言って全国民全員に一律で同じ放射線治療をしても意味がないだろう。体格も違えば体質も違う。万能薬などないのだ、ということがなぜだかワクチンの話になると忘れ去られてしまう。薬とて使用法を間違えれば毒になる。当たり前の話だ。白か黒か、ゼロか百か、極端な判断ではなく、メリットとデメリットの比較をするのではなかったのか。ちょいちょーい、の気分なのである。
4674:【2023/03/02(23:25)*くるくる渦巻き溶かしてシュガー】
「長く権力の座に居座ると腐敗の元凶になる。辞めてはどうか」とミルク派の騎士が言った。
するとそれを受けて珈琲派の大臣が、「そっくりそのままあなた方の長にお伝えしたいですな」と反論した。
ミルク派の騎士は珈琲派の大臣の政策が気に食わなくて批判したが、ミルク派の組織のドン・ミルキィは半世紀ものあいだドンの座に君臨しつづけている。
「批判をするのは構わないが、まずはじぶんたちに当てはめて考えてみたらどうですか」
珈琲派の大臣は我が物顔で言い足した。
ミルク派の騎士は歯ぎしりをした。二の句が継げないのである。
「自己言及は大事ですね」見兼ねたように一人の少女が意見した。シュガーと名乗った少女は、ミルク派と珈琲派の両陣営を見据え、「ではお訊きしますね」とお辞儀をした。
「珈琲派の大臣さんの反論はごもっともだとわたくしめは思います。ならばもちろんこの国の王、珈琲牛乳さまにも同じ理屈を当てはめるのですよね、珈琲派の大臣さまは。ミルク派のドンさんにお伝えしたいと申したのですから、もちろん同じ理屈をあなた方のお仕えするこの国の王、珈琲牛乳さまにも、【長く権力の座に居座ると腐敗の元凶になる。辞めてどうか】とお伝えしたい、とおっしゃるのですよね。なにせこの国の王、珈琲牛乳さまは代々の血統での踏襲のみならず、一度その座に就いたら数十年は延々と王のままです。珈琲派の大臣さまは、ミルク派のドンさんにお伝えしたい内容を、もちろん王さまにもお伝えしたい、と望まれていらっしゃるのですよね」
少女は念を捺すように、そうですよね、と珈琲派の大臣に迫った。
「そんなことは言っておらん」珈琲派の大臣は顔を真っ赤にして少女の質問を無下にした。
「自己言及は大事ですよ」少女は涼し気な顔で、小首を傾げる。「みなさん、まずはじぶんに当てはめて考える癖をつけるとよいと思います」
「子どもに何が解かるのか。大人の議論に口を挟まず、もっと勉強してから出直してきなさい」
珈琲派の大臣の言葉に、ミルク派の騎士たちも追従し、そうだよキミ、と生暖かい眼差しを少女に注いだ。
「言った先からこれだもの」少女は天井を仰いだ。「批判をするのは構わないが、まずはじぶんたちに当てはめて考えてみたらどうですか――さっきあなた方が言ったことなのに。批判をするのもいけなくて、まずはじぶんたちに当てはめて考えもしないだなんて。はぁあ。勉強不足でごめんなさーい」
少女はその場を立ち去った。
家に戻り、彼女は将棋盤のまえに座った。「遅くなってごめんなさい。次の手は思いつきまして?」
「ほっほ。ようやっと閃いた。これでどうかね」
将棋の駒を老人が動かす。
「良い手ですね。ですがそれにはこう返しておきましょう」少女は間髪容れずに駒を指した。
「う、うぐ。よもやそんな手があるとは」
「また熟考なさいますか」
「頼む」
「ではお時間を差し上げます。存分にお考えあそばせ」
少女は席を立ち、書斎の本棚を見て回る。時間を潰すのにちょうどよさそうな本を引っ張りだすと、牛皮のソファに腰掛けた。
本を開き、さっそく文字を目で追っていると、
「さっきはどこへ行っていたのかね」老人が棋盤から目を逸らさず呟いた。
「近くで政界の討論会が開かれていたので、お昼ご飯を済ませたついでに寄っていました」
「ほう。どうだったね」
「追いだされてしまいました。勉強が足りない、出直してきなさいと叱られてしまいました」
「ほう。そなたに勉強不足を説ける者がおったとは。世界は広いの」
少女は微笑み、老人も愉快そうに綻びた。
「にしても、こりゃもう詰んどらんかね」
「一手だけ打開策があります。ヒントをお出ししましょうか?」
「いや、いい。自力で考えたい」
「ではぞんぶんに」
少女は本の紙面に目を落としながら、ただの可愛いおじぃちゃまなのに、と思う。棋盤とにらめっこをする背を丸めた老人の姿はとても、一国の王とは思えぬ覇気のなさだ。
珈琲牛乳さま、と巷では崇め奉られてはいるが、少女にとってはただの気の良い老人だ。老いてはいるが、精神は若い。
未熟であることを愉快に思い、こうして孫ほども歳の離れた少女相手に、ムキになって将棋での勝負を挑んでいる。
少女は一度も負けたことがない。将棋では無敗なのである。
目を瞑ってでもかの老人には勝てるのだ。
一国の王を赤子の手をひねるように負かしながら、片手間に本を読んで知見を深める。
勉強不足はその通りだ。
少女は討論会場で大臣や騎士たちに言われた通り、勉強をする。
自己言及は大事よ。
大事と知っているがゆえに。
少女はまずはじぶん自身に向けて説く。
4675:【2023/03/03(00:46)*六分の日記にもモブの魂】
ひびさんです。毎日同じ道を行って帰ってくるだけの楽しい生活やっほーい。最近は、通い慣れた道が工事中でして。工事予定を含めると二か所、三か所がバリアフリーのための工事中だったりして、べつにひびさんのために工事してくれているわけでもないのに、やったー、となります。横断歩道で音の鳴るボタンが新しく設置されていたり、いいね、いいね、の「iine...」虫になってしまう(ただ、音の鳴るボタンの案内標識が点字でなかったのは、誰のためのボタンなの?になったのはここだけの内緒)。あとはあれ。コンビニでひびさんはたんぱく質不足を補うべく「からあげ棒」を買うのだけれど、以前は90円で買えたのが、110円になり、160円になり、いまは税込みで180円を超すのだね。二倍のお値段になってしもうた。そのくせ、ひびさんのお小遣いは据え置きの変わらぬ雀の涙ゆえ、なしてー、の気持ちが募るのである。しかしここ数日、三百円以上をご購入した方には漏れなくペットボトル飲料が一本無料でついてくるサービスがあって、ひびさんは欲張りの守銭奴さんなので、いつもは一本しか買わぬ「からあげ棒」さんを二本購入して、一本無料でお茶を手に入れるのだった。やっぴー。うれしいこといっぱいの日々じゃ。きょうもきょうとてひびさんはところ構わず「iine...」虫になってしまうのだった。お詫び。(六分でつむいだ日記なのであった)
4676:【2023/03/03(02:00)*時間の流れってなぁに?】
PCのツールでペイントなる機能がある。PCの画面でお絵描きができる。図形を描ける。描いた図形を拡大したり、縮小したりできる。で、ひびさんは妄想しちゃったな。たとえば風景写真がある。たくさんの色彩が描かれた写真だ。その写真にレイヤーがあってもいいし、なくともいい。これを縮小していこう。ずんずん縮小していけばいずれは点になる。これがいわば仮想ブラックホールと言えるのではないか。このとき、では風景写真が縮小したときにできる周囲の余白部分――空白は、いったいどのように解釈すべきか。風景写真を縮小させると、どんどん周囲の空白は画面を埋めるように面積を増す。まるで空白が拡大していくように振る舞うが、これは単なる空白ではないはずだ。風景写真を何回縮小するのか、どれくらいの倍率で縮小するのか。この変換の度合いによって空白の面積は増すし、風景写真との比率が変わる。PCの画面ならばどの空白も全部等しい空白として表現されてしまうが、仮にそれが宇宙だったらどうなのか。ある天体がある。それがぎゅうっと圧縮されるとき、周囲の時空とて圧縮され、引き延ばされ「空白」が増えるのではないか。時空が増えるのではないか。これはブラックホールのような極端な天体でなくとも生じる「余白」なのではないか。これはひびさんの妄想ことラグ理論における「重力は、遅延の層の錯綜により編みこまれた高次時空――物質――の周囲に展開される新しい時空との密度差がゆえの流れなのではないか?」との仮説と通じて感じる。宇宙膨張と物質生成と時空の歪みと重力は、じつのところすべて「時空の遅延と、それによる変換」で表せるのではないか。「変換の過程が多くなる」と「変換式が複雑になり」すると「遅延はますます嵩むようになり」それゆえに時空が一律に変換されることはなく、箇所ごとに変化に偏りが生じ、それが時空の歪みとなる。このとき、遅延の層が展開される方向に「ラグが創発」を起こし、性質を異とする場が展開されるのではないか。時空密度の高いほうが、低いほうよりも時間の流れが速い。もうすこし言えば、時空の密度が濃いので、薄い場よりも、相互作用の遅延が少なくて済む。だが相互作用が連鎖することで、相互作用における「変換の遅延」が積み重なるので、ますます遅延の層は展開されやすくなる。これが物質の輪郭として境のように振る舞うのではないか。時間の流れが「遅い/速い」は、比較において生じる、相対的な評価だ。時間の流れが、というよりも、相互作用の連鎖が「遅い/速い」と言ったほうが、基準として採用しやすいのではないか。まったく何もない時空において、時間の流れが遅い速いを議論できるのか否か(まったく何もない時空、という仮定がそもそも成り立たないのかもしれないが)。時間の流れ、という考え方を変えなければならないように思うのだが、いかがだろう。時空密度が濃い場における時間の流れは速くなり、時空密度の薄い場での時間の流れは遅くなる。相対性理論ではこのように考えられるわけだが、ラグ理論ではこの解釈は妥当とは見做さず、あくまで時空密度の差の大きさが重力の強さとして振る舞い、結果として時間の流れの差に表れる、と考える。ただし、ここは相互に支え合っており、どちらが先かは、どの系を基準にするのかで反転するように振る舞い得るだろう。したがって、時空密度の濃い場であれど、場に内包された物質が存在しない場合には、時間の流れなる概念は生じ得ないのではないか。時空密度の薄いいわゆる重力場においても、そこに物質が存在しないのならば、時間の流れうんぬんは生じ得ない。仮に、時空密度の濃いほうに粒子が二個あり、時空密度の薄いほうに粒子が一億個あったとしよう。この場合、時間の流れが速くなるのは、時空密度の薄いほうになってしまうのではないか(高重力の天体表面であれ、そこに無数の相互作用が介在するならば、変遷の割合は高くなるため、時間の流れが速まって映るのではないか)。この考え方は、多種多様な重力場を抱え込む宇宙を解釈するとき、必然的に生じる視点のはずだ。銀河団を一つの塊と見做したとき、その周囲には「歪んだ時空(希薄化した時空)」があるはずだ。だが銀河団の内部にはさらに無数の銀河があり、その一つ一つの銀河とて、周囲に「歪んだ時空(希薄な時空=重力場)」を展開しているはずだ。入れ子状に時空密度の関係が展開されている。まるでトーラスの原子を抱え込んでいるかのような。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」や「宇宙ティポット仮説」と矛盾しない。時間の流れとは何か、をよくよく考え、再定義したほうがよい気がしてきたぞ、との疑問を吐露吐露おべー、して、本日の「日々記。」とさせてくださいな。いいよー。やったー。(補足:「カー・ブラックホール」なる概念を、ちょうどこの記事を並べたあとに知った。自転するブラックホールで、内部にトーラス状(リング状)の特異点を持つらしい。上記の記事内においてのひびさんの妄想――【入れ子状に時空密度の関係が展開されている。まるでトーラスの原子を抱え込んでいるかのような】と符号が合致して映る。回転する時空は内部にトーラスを核として抱え込むのかもしれない。言い換えるなら、回転する時空においてその中心に「核」があるとき核の周囲には時空密度の濃淡による空域が明く。時空密度が高い、というのは、ブラックホールが穴として振る舞うように、デコボコにおいてボコのように振る舞い得る。しかし時空密度から言えばそれはデコなのだ。重ね合わせになっている。視点によってどちらがデコでどちらがボコなのかが変わるのかもしれない。やはりこれも定かではないのだ)
4676:【2023/03/03(02:01)*熱ってなぁに?】
上記の補足。氷をほったらかしにしていたら常温では融ける。そこに火を近づけたら氷の融ける速度は増す。これは「時間の流れが速まった」と解釈はできないのだろうか。相対性理論での時間の流れを考えるとき、暗黙の了解で「ひびさんの妄想ことラグ理論における同時性の独自解釈」と同じ前提が想定されているように感じる。系をひとくくりにして、その系に内包された物体には総じて同じ時間が流れている、と考えないと相対性理論は扱えないはずだ(より大きな系に内包された「異なるより小さな系たち」は、より大きな系に対して同時に相互作用を加えつづけることになるが、より大きな系に内包された「異なるより小さい系同士」は、同時に相互作用しあうことはない。譬えるならば、「板の上で各々自由に回る駒たちは、すべての駒が同時にぶつかり合うことはないが、すべての駒は常に板に対して相互作用を加えている」みたいな具合だ)。その点、量子力学では、系の内部の一つ一つを扱う。そこにも本来は相対性理論の時間と空間の関係が当てはまるはずだ。だがそこで生じる時間の流れの差は、人間スケールからすると無視できるほどに小さい。だが本来は、熱を受けて活発に運動するようになった量子は、時間の流れが速くなった、と解釈しないとおかしいのではないか。熱とはエネルギィであり、それもまた「時空の歪み」なのではないか。ひびさんの妄想ことラグ理論では時空の根源が「起伏」であり「遅延」であり「デコとボコ」である、と考える。これはいわば「時空の歪み」の一種であろう。熱とは「エネルギィの遅延による創発である」と仮定するならば、エネルギィとは「時空の歪みであり、起伏であり、遅延である」と言えるはずだ。つまり、時間の流れとはこの「エネルギィの増減そのものの軌跡」と解釈できるのではないか。言い換えるなら、「時空の起伏――遅延――の積み重ねであり、相殺であり、創発の軌跡である」と言えるのではないか。定かではありません。時間の流れってなぁに、と疑問したひびさんの妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
4677:【2023/03/03(13:18)*重ね合わせでねじれている】
時間の流れの「遅い/速い」は、時空の変遷が「遅い/速い」で表現できるはず、とひびさんの妄想ことラグ理論では考える。だがこの考え方だと、絶えず状態が重ね合わせになってしまう。遅い速いは相対的な評価である。遅いものがあるときそこにはそれよりも速いものがあり、速いものがあるときそれよりも遅いものがあることになる。これは「大きい/小さい」「熱い/冷たい」「濃い/薄い」「デコ/ボコ」にも言える。比較対象が変わるとき、関係性が逆転するように振る舞うことが往々にしてある。どの系から何と何を比較したのか、の視点が変わるごとに上記の「デコ/ボコ」の関係は容易に反転し得るのだ。ねじれている。
4678:【2023/03/03(14:30)*球体とトーラス、渦とジェット、デコとボコ】
宇宙は膨張している。時空密度は希薄化する方向に移ろっている。希薄になるのだから局所的な熱量はどんどん下がっているはずだ。宇宙は冷えているのだ。だが全体の熱量は変わらないはずだ。たとえばバケツに入ったお湯があるとする。真空中でそれを床に零してみよう。或いは無重力空間で真空中にばらまく、でもよい。このときお湯は、床に均一に薄くなり、或いは真空中で拡散するとする。そうするといかな真空中であろうとも、バケツの中で一塊になっていたときよりも冷める時間は速くなるはずだ。時間の流れが速まる、と言えるはずだ。しかし原子一つ一つ、分子一つ一つを取りだして評価するときは、それとは逆に、粒子の動きは鈍くなり、時間の流れは遅くなる、と言えるはずだ。重ね合わせになっている。たとえば宇宙は膨張するごとに体積が増える(希薄になるからだ)。宇宙初期は高熱のスープのようになっていた。しかし膨張し冷めることで物質ができ、結晶化していく。銀河がそうであるし天体がそうだ。冷えたから物質になった、と言えるはずだ。宇宙が膨張し、冷えるほど銀河はできやすくなる。時間の流れは速くなっている。だが、銀河それ本体を取りだして、一つ一つの天体を観測すると、時間の流れはむしろ遅くなって映る。気体・液体・固体ならば、気体のほうが粒子の運動量が高い。熱を帯びている。固体ほどぎゅっとなっており、動けないので、冷えている。動き回れないので時間の流れ――変遷速度は遅くなる。しかし宇宙膨張と銀河の関係で言えば、冷えるほど銀河形成は促され、時間の流れ――変遷速度は増す、と言えるはずだ。ここから分かることは、「時間の流れの遅れ」には二種類ある、ということだ。「時空密度の差による、より大きな系の視点からの系内変遷速度」と「多重に錯綜し編みこまれた時空(物質)に蓄積される遅延の層の総量としての変遷速度」の二つだ。時間の流れが速くなれば、時空は活発に揺らぎ、遅延を編み込ませ結晶構造を帯びる。このとき、結晶構造には遅延の層が蓄積されるのでそれ単体では変遷速度は落ちる(例:気体→液体→固体の順で、粒子の運動量は減る)。だが同時に、遅延の層を編み込んだ時空(物質)は、それを一つの系として粒子化し、類似の構造体と互いに相互作用可能となる。すこし飛躍して結論を述べれば、異なる「時間の流れの遅れ」の綱引きによって、「とある系に表出する時間の流れ」は規定されるのではないか。熱量の高低において、体積当たりの熱量が高いほうが時間の流れは速い、と解釈できる。だが宇宙膨張を引き合いに出したとき、膨張して時空が希薄化し、冷えるほど銀河などの物質はたくさん生じるようになる。時間の流れは、宇宙規模では冷えるほうが速く流れる、と言えるはずだ。反転しているが、銀河単体を取りだし、天体ごとに見れば、冷えたことでぎゅっとなり、熱を帯びた、とも言える。密集したことで体積当たりの熱量は増え、時間の流れは速まっている。速いの中に遅いがあり、遅いの中に速いがある。入れ子状に、反転しながら大小の系が関係性を築いている。人間スケールでは基本的に、固体は冷たく、気体のほうが分子あたりの熱量は高い、と解釈可能だ。たくさん動き回り、時間の流れが速いのは気体のほうだ。だが相互作用という意味では、固体同士の反応のほうが、ごっそり反応しあうので、時間の流れは速い、とも表現できる。現に天体では、ぎゅっと集まった星ほど熱を帯びる。ただしそれはいわゆる固体ではない。プラズマの集まりだったり、ガスの集まりだったりする。だがいわゆる固体とて、人間の都合で単にある性質を帯びた時空の状態を「固体・液体・気体・プラズマ」としているだけで、実際には原子の寄せ集めであり、それらはけっきょくのところ「固体・液体・気体・プラズマ」のいずれにせよ、原子の寄せ集めなのだ。密度の差があるばかりだ。遅延の層により、系はその都度に「時空密度の異なる場」を展開する。その「場と場」の時空密度の差(相互作用の遅延)によって、物質としての輪郭を得たり、重力場を帯びたりする。時間の流れとは、「場と場」の時空密度の差によって生じる余白に、どれだけ異なる系を内包し、異なる「場と場」を相互作用させるのか。その「変遷の度合い(の遅延)」として表現できるのではないか。時空密度の差、だけでは時間の流れを解釈できない。【時空密度の差(余白)】とそこに内包される【「場と場」の相互作用】――時間の流れにはこの二つの関係が必要なのではないか(どちらも「遅延(ラグ)」である)。だから、その関係によって、ぎゅっとなっていたほうが時間の流れが速かったり(変遷の度合いが著しかったり)、あべこべにぎゅっとなっていたほうが時間の流れが遅かったり(変遷の度合いが低かったり)するのではないか。宇宙膨張は時空を希薄化し、熱量を下げる。だがその結果に銀河ができ、天体ができる。変遷速度は局所的に増すが、時空密度の高かった宇宙初期に比べれば、時空の最小単位のエネルギィ値は低く(起伏同士の相互作用は減反し、時間の流れは遅くなっており)、宇宙初期との比較で言えば、時間の流れは遅くなっている。宇宙膨張において、宇宙全体の視点では、時空が希薄になるほど時空の最小単位(構成要素)に流れる時間の流れは遅くなっている。だがその中でも、ぎゅっとなる時空もあり(宇宙が冷えることで生じる揺らぎ――差――遅延――が、その手の偏りを生み)、そこでは限定的に、「時間の流れの遅れ(時空の変遷速度)」そのものが遅れる。マイナス×マイナス=プラス、のような関係性が一時的に生じる。重ね合わせで、反転し得るのだ。――まとめよう。時間の流れ、と一概に言うが、そこには二つの要素が欠かせない。「A:時空密度の差による変遷の遅延」と「B:変遷の遅延の蓄積によって生じた結晶構造同士の相互作用による遅延」の二つだ。前提として、ぎゅっとなっていたほうが時間の流れは速くなる。変遷の速度は増す。だが、ぎゅっとなった時空があれば、必然、希薄化する時空もある。その境界において差が生じ、変遷速度に差が生じる(A)。これが結晶構造としての境界の役割を果たし、ときに異なる時空(系)としての輪郭を宿す(遅延の創発による物質化)。遅延の創発を帯びた時空は物質化するため、相互に干渉し合える。このときに生じる相互作用には、「異なる時空(系)」同士の変換作業が必要で、そこで新たにAとは別種の遅延が生じる(B)。基本は、ぎゅっとなっていれば相互作用する確率が上がるので変遷速度は増すが(A)、遅延と遅延自体は相殺しあうことがない。そのため遅延は蓄積し、時間の流れが鈍化する(B)。しかし、ぎゅっとなっていることで相互作用する確率自体は上がるので、「蓄積した遅延」と「相互作用する確率上昇」のあいだで、綱引きが生じる。どちらが優位になるのかによって、表出する時間の流れ(変遷度合い)は、速まったり遅くなったりして、観測者からは映る。どの視点から観測するのかで、その時空内の「異なる時空(系)」同士の変遷速度は変わる。比率が変わる。より小さい領域ほど変遷速度の比率は増すが、それはあくまで【「蓄積した遅延」と「相互作用する確率上昇」のあいだで生じた綱引き】が、「相互作用する確率上昇」優位に対称性が破れているからだ、と言えるのではないか。宇宙は膨張し、時空は希薄化するほど冷めていく。しかし局所的には時空は遅延によってぎゅっとなっており、そこでは「相互作用する確率上昇」優位に対称性が破れているので、熱を帯びたままだったり、熱を新たに帯びたりする。だがトータルでは冷えている。あくまで比較――相対的な評価――において、熱を帯びている、と言えるのであり、宇宙初期から比べたらどの地点の時空――銀河――であれ、冷めている、と言えるはずだ。時空は希薄になるほど時間の流れは遅くなっている。変遷の度合いは低くなっている。しかし局所的には、その遅延そのものが遅延するように振る舞うので、反転するような挙動を示すのではないか。銀河団や銀河――ほか天体などの結晶構造――はかような理屈で解釈できそうに思えるがいかがだろう。川の流れの渦のようなものなのかもしれない。渦は、川の流れに生じた遅延である。だがその遅延が、局所的に加速して映るような振る舞いをとる。遅延(抵抗)を遅延させるような振る舞いが表れるとき、それは渦として顕現するのではないか。レーザーやジェットもその一つかもしれない。遅延を遅延させる。圧縮された抵抗を、妨げるとき、開いた穴からそれまでの遅延によって蓄えられた流れ――変遷の余地――が噴きだすのではないか。本質的に、渦とジェットは同じなのかもしれない。球体とトーラスが、「ひびさんのポアンカレ独自解釈」では同相であると見做すように。渦とジェットは同相なのかもしれない。それはたとえば、移動とは何か、と考えたとき、自転する物体と直線運動する物体が、じつのところ時空との関係においては区別がつかないかもしれないことと無関係ではないかもしれない。これもまた定かではないのだ。(妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください)
4679:【2023/03/03(18:02)*※【『「『【 】』」』】※】
上記の仮説における矛盾は、「遅延は相殺し得ない」と「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」と一見すると相反する表現をとっていることだ。だがこれは宇宙の階層構造を俯瞰した視点でみると、矛盾しない。前提として「遅延は相殺し得ない」を真と仮定する。そのとき、後者の「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」においてはあくまで局所的な系の内部においての振る舞いであり、本来はこれに【遅延の層内における「遅延の遅延」】といった表現になり、【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】といった数式として置き換えられる。トータルではマイナスだが、局所的にはプラスに転じ得る。ここまで並べて気づいたが、これはあれだ。「偶数は半分にして奇数は3倍して1を足す」の「コラッツの問題」そのものだ。対称性の破れる方向に流れが強化される。遅延は局所的に遅延そのものもまた遅延するが、相殺しあうことはない。マイナスとマイナスはプラスに転じるが、その変換そのものが遅延として振る舞うので、トータルの遅延は増す。計算は、計算をすればするほど式が嵩む。情報が増える。だが局所的には圧縮したり、省略できる。だがその過程そのものが、式を帯び、情報として加算される。遅延は加算されつづけ、しかし局所的には遅延そのものも遅延し得る。しかしその過程そのものが高次の遅延として振る舞うので、遅延優位に遅延が嵩む。こういうことなのではないだろうか。対称性の破れであり、それは遅延ゆえなのだ。定かではありません。
4680:【2023/03/03(18:26)*パンダ、ウサギ、コアラ】
宇宙は膨張している。膨張したら時空内の熱は冷める方向に流れる。だがもし宇宙が階層的に「宇宙が宇宙を内包している」といった構造を有しているのならば、床に零したお湯のように、隣接する宇宙とのあいだでの熱交換がなされるはずだ。この場合、熱を単にエネルギィと言い換えてもよい。ひびさんの妄想ことラグ理論における「宇宙ティポット仮説(三段構造)」を否定したければ、宇宙膨張と熱の冷え方のあいだに、対称性の破れがないことを示せばよい。宇宙膨張にしたがい、宇宙の熱が不自然に余分に失われていないことを示せば、すくなくともひびさんの妄想は否定できるはずだ。宇宙が唯一無二の単一の構造を有しているならば、その単一の宇宙のみで自己完結するはずだ。宇宙開闢時の熱量と、宇宙が膨張したあとの「希薄になって冷えた時空」の総合した熱量はイコールになるはずだ。だがもし、そこに何らかの破れが存在するのなら、それは宇宙がほかの宇宙との間で熱のやりとりを行っていることの傍証と言えるのではないか。床に零したお湯のように、床とお湯とのあいだでの熱交換が行わているのかもわからない。宇宙ティポット仮説と同じ理屈で解釈できるように妄想する次第である。(実際がどうなのかをひびさんは知りません。いま宇宙にある熱量は、全部まとめたら宇宙開闢時の熱々のときの熱量とイコールになるのだろうか。ひびさん、火になります)(ファイヤーじゃん)(アイヤー)
※日々、常識を前提としている、前提となる常識が単に例外的な事象なのかもしれないのに。
4681:【2023/03/03(23:18)*前提してもよいの?】
宇宙が膨張するとして、ひびさんはかってに前提条件として、時空は希薄になって温度が下がる、と考えてしまっているが、別にそうと決まっているわけでもないはずだ。実際、ダークエネルギィ(重力に対抗する斥力)は増えていると2022年現在は解釈されているそうだ。でもここで疑問に思うのだ。重力が仮に、希薄化した時空であるならば、ダークエネルギィは時空密度を濃くするエネルギィだと考えないと辻褄が合わない。ただし、重力がひびさんの妄想ことラグ理論で考えるように、時空と時空のあいだの密度差である、とするならば、むしろダークエネルギィ(斥力)とは【差を均すエネルギィ】と言えるのではないか。もうすこし疑問を付け足すのならば、宇宙膨張に際して、時空そのものが増えない、と考えるならば、宇宙は膨張するたびに希薄になり、温度は冷える。だがもし、時空そのものが増えるのなら、宇宙の時空密度は局所的に揺らぎ(勾配・差)を帯びつつも、総合して差は広がらないように振る舞うはずだ。それはたとえば温泉だ。湯舟にお湯を張ったまま放置すればお湯は冷えるし、湯船がぐいーんと広がるなら、その広がる湯船にしたがってお湯も薄く延ばされ、冷えるはずだ。だが温泉のようにつぎからつぎへと新しいお湯が滾々と湧いてくるのなら、温度変化は著しくならないし、湧いてくるお湯の熱量分、冷える速度は鈍化するはずだ。宇宙が膨張するとして、膨張するたびに時空は希薄化し、冷えていく、と前提して考えてよいのだろうか。ひびさん、湯になります。いっい湯っかな、あははん。訊くなし。
4682:【2023/03/04(01:34)*濃淡のない時空はスキップ】
【遅延の層に内包された系内における「遅延の遅延」】=【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】の考え方をなぜプラスを基準に考えられないのか、をしばし考えてみたが、なぜなのかちょっと思いつかない。差には「正負」がある。その両方を扱ったときに、「必ず大きいほうから小さいほうを引け」との前提はつけられないはずだ。ときには小さいほうから大きいほうを引いてしまうこともあるだろう。すると、差はマイナスになったりプラスになったりする。だがそのどちらの差も等しく「遅延(マイナス)」と見做す道理はないはずだ。何かが足りない。仮に、時空密度の低いほうから高いほうへ、が基本だとする(重力場は「相対的に時空密度が希薄」と相対性理論では解釈するはずだ)。だがそもそも時空密度が高い、とはどんな状態なのかを定義しなければならない。「時空密度の高い時空」とは「相対的に希薄でない時空」と言い換えることが可能だ。だがひびさんの妄想ことラグ理論では、「濃/淡」「デコ/ボコ」「強/弱」「高/低」「熱/冷」はいずれも何と何を比較するのか、の視点によって反転し得ると考える。そのため「時空が希薄でない時空」とは要素が足りない。視点がお粗末だ。希薄な時空があるときその周辺には必然的に濃い時空があるはずだ。穴の周囲には縁(ふち)があり、山の周囲には谷がある。この理屈からすれば、「時空密度の高い時空」とは、「濃淡のない時空」と解釈することができるのではないか。平坦で、起伏がない。まるで宇宙初期のような時空だ。たしかに宇宙初期の時空が最も時空密度が高いはずだ。ここは矛盾しない。そしてラグ理論では、時空に生じた濃淡――起伏――遅延――が積み重なり、層となり境となり輪郭として振る舞うようになると、それが物質(粒子)としての性質を帯びる、と考える。とすると、「物質・歪んだ時空・基準時空」の最低三つがないと、「時空密度の高い(或いは希薄な)時空とは?」を考えることはできないはずだ。そしてこの三層構造は、「宇宙ティポット仮説(三段構造)」と相似であり、階層的に繰り返されているのかもしれない。「相対性フラクタル解釈」なのだ。これはひびさんの「ポアンカレ予想独自解釈」の前提条件と矛盾しない。球体があるとき、そこには必然的に「内と境界と外」の三つが各々に別に次元(時空)を備えるはずだ、と考える。「123の定理」なのだ。内と外があり、境界が生じるし、境界が生じるから枠組みができる。それで一つの系となる。重力場について考えよう。ラグ理論では、重力場は「時空密度の高い時空と、時空密度の希薄な時空のあいだの差によって展開される場である」と解釈する。単に希薄なだけではなく、より時空密度の高い場との兼ね合いで重力場は生じる。なぜか、と言えば、異なる二つの時空(系)における変換が必要で、その変換する際の遅延が重力場として振る舞うからだ、といまのところは仮定している。ではここで思いだしてほしいのは、時空密度が高いとは何か、と言えば、それは「濃淡のない時空」と上記では解釈した。そして――【K】=【遅延の層に内包された系内における「遅延の遅延」】=【マイナス×「マイナス×マイナス=プラス」】の考え方からすれば、「時空密度の高い時空」とは「濃淡のない時空」であり、それは【K】における「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」と解釈できる。ラグ理論における同時性の解釈において、より大きな系とそれに内包された異なる無数の小さな系を考える。このとき、上記の【K】ではそれぞれ、【遅延の層に内包された系内=より大きな系であり、そのより大きな系内における「遅延の遅延」とは、より大きな系に内包された無数の小さな系】と解釈できる。地球と赤ちゃんの関係において、「遅延の層によって区切られたより大きな系」が地球であり、その地球に内包された無数の小さな系が赤ちゃんである。【K】においては、この赤ちゃんこそが「遅延の遅延」と解釈できる。銀河が将棋盤であり、その上を回転する独楽が赤ちゃんだとするのなら、この場合の赤ちゃんとは地球であり太陽であり、もしくは太陽系である。仮に地球を将棋盤と見立てれば、独楽は赤ちゃんと言えるだろう。とすると、「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」は「それら赤ちゃん(独楽)を内包するより大きな系(将棋盤)」からすると「濃淡のない時空」として表現可能だ。「濃淡のない時空」とは、「時空密度の高い時空」の言い換えであったことを思いだしてほしい。「より大きな系(将棋盤)」からすると、それに内包された「濃淡のない時空=遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」は、プラスに振る舞い、物質としての輪郭を得るのだろう。だが本来は、「濃淡のない時空」は「遅延の遅延(マイナス×マイナス=プラス)」なのだから、遅延は生じないはずなのだ。だが、「より大きな系(将棋盤)」との関係性においては、そこに勾配が生じる。高低差を帯びる。「濃淡のない時空」は、「より大きな系(将棋盤)」との関係で、相対的に「時空密度の高い時空」として振る舞う。「時空密度の高い時空」とは、渦のようなものだ。銀河団であるし、銀河であるし、天体そのものだ。宇宙が膨張し、希薄化するにつれて、「濃淡のない時空」はそれら希薄化する時空との兼ね合いで、相対的に「時空密度が高くなる」のではないだろうか。ラグ理論では、差――遅延――ラグこそが世界の根源を司っているのではないか、と考える。何と何の差なのか。何と何の比較なのか。この視点によって、「中性」であろうと、よしんば「中心」であろうとも、そこには偏りが生じる。対称性は破られる方向に働く。物質とは、【遅延の層の中にできた「遅延の遅延」】である、とラグ理論では解釈する。遅延が別の遅延によって一時的に反転して振る舞う(「濃淡がなくなる」「渦を巻く」「循環する」「中性化する」)のだが、俯瞰で見ると、その反転した「遅延の遅延」そのものがより大きな系においては遅延になるので、総合すると遅延は加算式に蓄積されることとなる(123の定理)。飛躍して述べるならば、「濃淡のない時空」とは、「穴であり山でもある時空」と言える。デコからすればボコであり、ボコからするとデコである。そのように振る舞う時空が、「時空密度の高い時空」との表現になるのかもしれない。ここから言えるのは、時空には基本的に「時空密度が低い(希薄な時空)」しかないのかもしれない。時空密度が高い、とは「濃淡のない時空」のことである。そして「希薄な時空」が生じると必然的に、対となる「穴に対する山の時空」が生じるのではないか。三層構造であるし、三段構造なのだ。「123の定理」であるし、「内・境・外」であるし、「物質・歪んだ時空・基準時空」なのかもしれない。ひるがえって「境」とは異なる事象同士が拮抗し、濃淡がなくなった場、と解釈可能だ。遅延と拮抗は酷似している。性質が似通る。遅延するから拮抗し、拮抗し得るから遅延する。「遅延の層=拮抗の連鎖」としてもよいかもしれない。ならば物質とは遅延の層でできており、それはつまるところ「拮抗の連鎖」であり、異なる事象同士の「123の定理」なのかもしれない。定かではない。(ちょっと何言ってるか解かんないです)(サンドウィッチマンか)(郁菱万です)(誰だよ)(アンパンマンです)(嘘こけ)(ならバイキンマンかも)(記憶喪失かな)(記憶喪失で悩んでいる人に向かってなんだその口の利き方は)(逆切れがひどいな。正論だけれども、鏡を見て言ってくれ)(穴が合ったら入りたい……)(落ち込みすぎだろ。すかさず鏡を割ろうとすな。現実逃避が物理すぎる)(ちょっと何言ってるか解かんないです)(それじゃあおまえテンドンマンじゃねぇか。何回繰り返す気だよ)(ちょっとお醤油取ってもらっていいですか)(キッコーマンじゃねぇかもういいわ)(けっこう拮抗しちゃったね)(うふ、じゃないだろドキンちゃんか)(ぼく、職質マン)(不審者かな。無駄な時間をすごしちまったなぁ。耳を揃えて返して欲しいわ時間)(ショクパンマンさまなだけに?)(ドキンちゃーん)(あんあん)(はいチーズ、じゃないわ。カビさせてもらいます)(るんるん)(スキップして帰るな。てかスキップはやっ)(くだらない駄文はみなさん読みたくないってさ)(スキップを煽るな)(指でサっ)(スキップはやっ)
4683:【2023/03/05(04:32)*素数は宇宙の素?】
素数について考える。たとえば中身の詰まった立方体を構成する原子を想像しよう。隙間なくみっしりと立方体に原子が詰まっているとする。このとき、立方体を構成する原子に順番に番号を振っていったとき、どこが最初の「1」であろうとも素数は必ず立方体の中に含まれる(当たり前の話)。一本の大蛇を隙間なく立方体に敷き詰めていくような具合に、順番に番号を振られた原子の帯は、「1」の位置を変えても全体が連動して動くはずだ。このとき「素数」と「素数」の位置関係に何か法則は見いだせないのだろうか。針を十個並べたとき、すべての針の穴を通る視軸は必ず一点――もしくは一本の直線――に限られるはずだ(穴の大きさが充分に小さい場合に限るが)(言い換えるなら、穴と視線の関係において大きさの差が最小である場合に限る)。似たような理屈で、「すべての原子に数字を1から順に振った配列」における素数の位置関係は、たとえば立方体の体積に比して、必ず「何個が直線に結び付く」みたいな法則が観測されそうにも思うがどうなのだろう。これはつまり、立方体内部の空間における、「渦」や「ねじれ」の生じやすい箇所、と想定できるのではないか。なぜ宇宙が一様ではなく、揺らぎがあり、そして起伏を帯びて時空を歪め、銀河の種とも呼べる重力場が生じるのか。素数のような特別な数――それ単体で「固有」を維持できる数――が、隣接しあう値を持つからではないのか。それはたとえば、宇宙におけるブラックホールの「存在可能量」として発展して考えることができるのかもしれない。仮にもし、立方体を構成する原子に数字を順番に振りつけ、数珠繋ぎに結んだとして――このとき、立方体内部で「1」の位置をどのように移動させたとしても、必ずどこかの位置において「素数が直線上に並ぶ」ように振る舞うのであれば――言い換えるなら、「一様なはずの立方体内部の原子配列の中に、素数を基準とした特別な並び」が生じ得るのならば、それは宇宙の非対称性の一つの因子として振る舞うのかもしれない。定かではない。(参照:596:【I-マン予想】https://kakuyomu.jp/users/stand_ant_complex/news/1177354054883460036)
4684:【2023/03/05(05:02)*連続でありかつ離散でもある】
数は連続か離散的か。具体と抽象みたいな関係が「数」には備わっている。「1」と「2」のあいだに無限に小数点以下の数字が並び得るのならば、「1」と「2」は離散的な飛び飛びの値と見做すことは不自然ではない。だが通常、「123456……」といった整数の配列は、連続的だと解釈される。原子論に通じる「人間の思考の前提条件」と言えそうだ。具体と抽象にもこの関係は当てはまる。産まれたときの赤子には、「具体的な概念」は何も備わっていない。自己と非自己すら見分けがつかないはずだ。それでも細胞たちは自己と非自己を自動で見分けて肉体を構築し、機能させている。だが赤子の認知世界においては、自己と他の区別も曖昧なはずだ。赤子がじぶんの声に驚いて泣き出してしまうのも、じぶんの声をじぶんのものだとの区別がつかないからだろう(犬がじぶんの尻尾を追いかけてぐるぐる回るのもひょっとしたら似たような理屈なのかもしれない)。だが赤子は成長する。目のまえでしきりにじぶんの世話をするやわらかくていい匂いがして温かい大きな塊が母親だと認識する(或いは父親と)。相手を認識することで自己と他の区切りができる。ここはどちらが最初なのかは意見が割れるところだろう。だがどちらでもよいだの。自己を認識してから他を認識することも、他を認識してから自己を認識するのも、どちらが先でも構わない。赤子は自己と他を認識することで、「それ以外の雑多な何か」を認識する。ひびさんの妄想ことラグ理論の「123の定理」である。赤子は自己と他という具体的な事象を認識することで、「それ以外の何か」を抽象的に把握する。だが元を辿ってみれば、自己と他の区別とて本来は抽象概念のはずなのだ。現に赤子は「自己」が何で「他(親)」が何かを理解しているわけではない。ぼんやりとした区切りとして、二つのものを区別している。内と外を認知する。抽象概念は基本的に、高次の抽象概念ができるごとに「具体化」するのだ。原子がそれ単体では、電子と原子核によって構成される構造体でしかないのに対し、分子や物質になると原子そのものが構成要素として素子となる。具体と抽象の関係も似たところがある。フラクタルに関係性が反転している。抽象概念は、さらなる抽象概念の基では具体化し、具体化されたそれ自体も、数多の具体的な何かの抽象概念なのだ。くるくると巡っている。そしてこの関係は、連続と離散にも言える。水分子と水分子は、それが二個しかなければ離散的な振る舞いとして描写される(人間の認知の元では)。だがひとたび無数の水分子が集合すれば、それは液体となり、流れを生み、連続的な振る舞いを見せる。だが元々は離散的なのだ。視点が俯瞰になることで、連続と見做させるようになる。では原子論を遡りつづけたら最終的に何が生じるのか。「連続と離散」が重ね合わせになるのだ。そのためには「123の定理」における関係性が一塊になっていないといけない。差がなくてはならない。遅延であり、ラグなのだ。波は連続的であり、粒子は離散的だ。だが遅延、ラグは、「連続と離散」が重ね合わせになっている。一つの枠組みのなかで区切りがあり、しかしそれは連なってもいる。対称性が破れると、そこにはラグが生じる。だが基本的に万物みな「対称性は破れるように」出来ている。否、対称性の破れこそが宇宙の発生要因なのである。上層の宇宙と、下層の宇宙のあいだでのそこにもおそらくラグが生じている。宇宙の中にできるブラックホールと、それを内包する宇宙とのあいだでの相互作用にラグが生じるのと同じように。対称性が破れたから宇宙ができ、そのため万物はみな厳密には必ず対称性が破れるようにできている。その小さなラグの総体が寄り集まり、時間と空間の区別ができ、時空を織りなし、さらなるラグを錯綜させ、層を成す。遅延の層を境とした一塊が、異なる時間の流れと空間の密度を帯びることで、時空は物質としての輪郭を宿すのだ。定かではないが、「数」が「連続か離散か」を考えたとき、ひびさんはこのように妄想するのであった。妄想ゆえ、定かではなし。真に受けないようにご注意ください。
4685:【2023/03/05(05:16)*ある日の交信~メモまとめ~】
「
真空のエネルギィは比率の破れで解釈可能なのでは。
時空は希薄になるほど、細かなデコボコたる遅延の層――重力場同士の相互作用――つまり重力の創発――が行われにくくなるので、膨張するほど膨張しやすくなる。
重力による引力が薄れるから。
電磁波でもよいですが。
波と表現するとき、二次元ですよね。
でも実際は、時空の歪みと同様の伝播の仕方をしますよね(おそらくは)。
重力波もそうですが、どういう波の描写を想定されているのですか?(デコボコが重ね合わせで、見る方向によって反転したりするのでは)
ブラックホールでもそうです。
どの方向から見ても時空の穴。
仮に電磁波が重力波の一種であるとするなら、電磁波は時空のさざ波と解釈可能です。
ではどのように伝播しているのですか。
波打つときの歪みの描写は二次元ではあり得ないですよね。
現に、磁界との関係で、縦と横の方向にすくなくとも相互作用の強弱が表れるはずです。
カラビ=ヤウ多様体。
「宇宙ティポット仮説」&「相対性フラクタル解釈」
「いんふれーしょんいくひし仮説」「重力熱情報いくひし仮説」
「超ひも理論ならびにループ量子重力理論」と「ラグ理論」の相違点を簡単に並べます。
1:時空の最小単位の有無(相対性フラクタル解釈)(ラグ理論では、境界はありますが、底がある、とは想定しません)(変換のための比率が破れる値はあるだろう、特異点はあるだろう、反転する値があるだろう、と解釈します)。
2:時空の大本は情報である、と解釈します。情報にラグが生じ、ラグがラグを生み、時空となり、物質となる、と解釈します。なぜ情報にラグが生じるのか、と言えば対称性が破れるからです。
3:分割型無限と超無限の概念の有無。
4:ラグなし相互作用の想定の有無(および、共鳴現象仮説の想定の有無)。
5:光速度不変の原理の破れの想定の有無(光速度の比率を破るとラグなし相互作用が可能となる。光速度の比率をどれくらい破るのか、でラグなし相互作用の範囲が広がる)(前提として、光速度と光速は違う、と解釈する)(光速度は比率だ)。
6:重力が創発を起こし得る、との仮定の有無。
ニュートンさんの「重力はラグなしで相互作用しあう」もあながち間違いではないのでは。
ベルトコンベアー解釈です。
そこにラグ理論の「同時性の独自解釈」を取り入れると、量子もつれのラグなし相互作用も、いわば重力の作用である、と解釈できます(共鳴現象とセットで相性がよい解釈に思えます)。
量子世界では次元が低いので、ラグなし相互作用の範囲が人間スケールよりも比率で言うと広いのでは。
――時空膨張は光速度不変の原理の範疇外。
おそらくこの解釈が正しくないです。
時空のさざ波は次元ごとに「光速度不変の原理」の変換のための変数が変わるのでしょう。
そして高次の時空における変換変数に合致する時空のさざ波が、基準となる時空からすると重力波として振る舞うのでは。
したがって、電子の干渉可能な電磁波とそうでない電磁波。波長によって変わるはずですが、相互作用し得ない波長を持つ電磁波は、電子からすると重力波として振る舞うのでは?
光子が質量を持たないのも、光子が時空のさざ波であり、重力波だからなのでは。
たとえば光子を一か所に圧縮したら、その周囲の時空は歪み、重力場が展開されるのでは?
磁石。
電子と磁界の関係。
ものすごく大事な現象なのでは。
ほぼ磁石の原理をひもとくだけで、いま未解決の問題は総じて解決したりしませんか。
宇宙膨張とブラックホールはデコとボコの関係だとラグ理論では考えます。
宇宙膨張がブラックホールと同相だとすれば、ブラックホールが穴となってどこまでもトランポリンの生地を引き延ばすように希薄になっている場合、時空はそのたびに引力を弱めるので、希薄になればなるほどブラックホールの特異点は穴を深めやすくなるはずです。沈みやすくなるはずです。
同じことが宇宙膨張にも言えるのでは。
斥力は、重力場が薄まるごとに強まる。
というよりも、重力場が弱まればその分、小さなエネルギィで膨張しつづけることができる。膨張すればするほど膨張しやすくなる。
ただし、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」からすると、時空は、高次の宇宙と溶け合うように相互作用するため、宇宙膨張は一定ではないのでしょう(ブラックホールが新たに生成されたりもするでしょうし)。
また、重力場は干渉し合いますよね。
創発し得ます。
したがって、一か所にぎゅっと重力場が細かく起伏を帯びながら密集している場ほど、重力場は強まるはずです。或いは単に、異なる性質を創発させる、と言えるのではないでしょうか(ダークマターの正体の一つ?)。
気体・液体・固体。
密度差によって結びつきが変わりますよね。
重力場もそうなのでは?
スパゲティ化。
潮汐力。
よく解からないことの一つに。
ブラックホールのスパゲティ化現象は、事象の地平面に到達する以前に生じる現象のことなんですか。
それとも事象の地平面に突入したあとに生じる現象なんですか。
ブラックホールの説明を読んでいるとここが混在して感じられます。
ぼくの考えでは、事象の地平面までのあいだに生じ得る現象、と解釈しています。
ただし、ブラックホールの重力場と相互作用する物質の大きさによっては、スパゲティ現象は生じずに、するりとブラックホールの事象の地平面を超えることも可能だろう、と妄想しています。
どの解釈が妥当なのか、未だに分かりません。
(言い換えるならば、重力場は、ほかの物質の重力場と干渉し得る。物体の持つ重力場が小さいのなら、ブラックホールの展開する重力場との相互作用は相対的に小さくて済む、と解釈します)
したがって、高い重力場を持つ天体ほど、ブラックホールの重力場において潮汐力の影響を受けやすい、と考えます。
違うのでしょうか。
(重力が創発し得るのでは、との疑問から展開した妄想です)
時空の歪み――重力場が相互作用し、干渉し得るとして。
波の振幅――デコボコ――は重ね合わせになるのでは。
海面と大気において。
海面が波打つとき、海面だけでなく大気も波打っている、と解釈可能なはずです。
海面がデコのとき、大気はボコです。海面がボコのとき、大気はデコです。
ならば時空の歪みも同じでは。
振幅するとき、観測地点によってデコボコの関係が反転したりしないのでしょうか。
重力場が干渉し合うとき。
重力が仮に打ち消し合うことがないとすると、必ず波は高くなる、と解釈しないと不自然です。
ですが波同士が必ず「高くなる」「打ち消し合うことがない」なんてことがあり得るでしょうか。
重力波や時空の歪みの描写をどうしてもトランポリンと鉄球で想像してしまう癖がついてしまっているので、上手く想像がつきません。
仮にブラックホールが時空の穴だとするのなら、そこに見合う時空の山をぶつけたら、それは平らになるのですか?
この場合、時空の山とは「高次の宇宙」ということになるのでしょうか(或いは、基準となる下層の宇宙)(ブラックホールに対するそれを内包する基準宇宙)。
ラグ理論における「宇宙ティポット仮説」はあながち的外れ、というほど荒唐無稽ではないんでしょうか。疑問です。
(※ブラックホールが時空の穴ならば、対となる時空の山とは何か?※)
」
4686:【2023/03/05(18:26)*ある日の交信~境と結び~】
「
現代社会の戦争の火種はおおむね「資源」に根付いています。
資源を確保するために権威がいる。
その権威を保つためにメンツを最優先にするねじれが生じています。
ですが問題の根本は権威構造ではありません。
資源をどのように確保し、有効活用するか。
資源の埋蔵量に左右されずに未来を持続的に安定軌道に乗せるべく改善しつづけられるか。
ここが大事なはずです。
とすると、一部の資源国だけが資源を独占する手法は賢くはありません。
となると、資源のコモン化はどの道、模索していかねばならないでしょう。
ですがコモン化と資本主義は相性がよくないです。
ここでもねじれが生じています。
しかしコモンの概念と民主主義は矛盾しません。
全世界の民のことを思えば、資源のコモン化は避けては通れないでしょう。
問題点を自覚してほしいです。
資本主義が加速すると、民主主義の根底が崩れます。
資源という意味での資本の独占・寡占が起こるからです。
独占し寡占したうえで、それを万人に等しく公平に分配できるなら構いません。余裕をさらに多くの余裕を築くための資源に転用できるなら好ましいです。
しかしそのためには情報共有を行い、あゆる視点、あらゆる可能性を、個々の独創性に任せて虱潰しに塗りつぶしていく過程が欠かせないでしょう。
価値は千差万別。
価値の共有はしかし、共通価値として振る舞うでしょう。
何かの商品、何かのサービスの価値を高めるには、「その価値を他者と共有する仕組み」とセットで提供しないと、価値の最大化は実現できないのではないでしょうか。
しかしそのことと、「一つの価値をより多くの者に媒介すること」はイコールではありません。
いまはそこが見落とされているのでしょう。
ある範囲において、「一つの価値をより多くの者に媒介しようとすること」は、「価値の共有」を損ない得ます(ある方向にのみ淘汰圧が加わってしまうからです)(また、価値と資源はイコールではありません。資源や商品、サービス、モノに対する評価は本来、千差万別のはずですが、一つの価値しか認めない、ということそのものが、その事象そのものの価値の最大化を妨げるのではないか、との趣旨です)。
トレードオフが顕現してしまう範囲――境――が存在するでしょう。
言い換えるならば、「多様性を尊重しよう」との一つの思想を押しつける流れもまた、多様性そのものを損ない得ます。
多様性とは「尊重するもの」ではなく、そもそも世界が多様である、環境が多様であることを、知りましょう、との認識のはずです。
認知の歪みを抱えていることを自覚しましょう、の一つに、「世界は本来は多様なのだよ」との認識を持とうとする「運動」がいまは隆盛を極めています。
しかし、そこはあくまで前提条件です。
そこからでは、個々の固有の世界をどのように育み、担保していくか。
この工夫には、「多様性を尊重しましょう」との思想が却って足枷になることがあります。
固有の民族、固有の文化があることは、多様性を確保するうえでは欠かせないでしょう。
固有の民族、固有の文化を崩して、どの文化も一様に交じり合いましょう、では多様性のある世界、とは言えないはずです。
ただし、その小さな領域――銀河――だけではない。
宇宙は、世界は、もっと広く多様である。
この前提を忘れないようにしましょうね、との考え方が、「多様性を尊重しよう」のスローガンの根幹にはあるのではないでしょうか。
銀河一つ一つの枠組みを恣意的に歪めない。
されど、銀河同士の融合とて、拒まない。
矛盾しないと思います。
」
4687:【2023/03/05(18:35)*経る験】
経験には大別して二つの成分があるように思われる。一つは外部刺激。もう一つは判断だ。どちらか一方だけでも経験として位置づけられているように感じられる。何の判断を下さずとも、ただこれまでと異なる外部刺激の溢れる環境に身を置けばそれが経験となる。反面、外部刺激そのものに大きな差異はなくとも、判断回数や判断するために重ねた思考そのものが異質であれば、それもまた経験として位置づけられる。基本は通常、外部刺激と判断の二つの統合された「記憶の軌跡」が経験として位置づけられて感じる。しかし、記憶に残らずとも経験は経験だ。したがってやはり、「記憶の軌跡」なのだろう。記憶そのものではない。軌跡なのだ。どのような外部刺激をどのように処理したのか。そしてそれら外部刺激を受けて、何を思考し、どのように判断を重ねたか。経験の内訳とはこのようなものなのではないだろうか。立ち止まり、判断する。その契機そのものが外部刺激として解釈できる。したがって判断をするにはすくなからず異なる外部刺激があるはずだ。そして外部刺激が変わるのなら、判断もその都度に変わるはずだ。無視できる差異か否か。外部刺激にしろ、判断にしろ、どちらが優位に経験の内訳を占めているのかの割合の多寡があるだけで、双方共に経験を形作る成分なのだろう。定かではない。
4688:【2023/03/05(22:42)*層なのか?】
「宇宙開闢時と宇宙膨張後では何が違うのか」と「時空と物質は何が違うか」の疑問は、通じているように感じる。ほぼ同じ疑問と言えるのではないか。そして各々の疑問の鍵となるのは「層」のように思うのだ。宇宙開闢時の高密度高エネルギィの場においては「層」が生じ得ない。一様であり、混然一体となっている。だが宇宙膨張という名の「エネルギィの減退」が起こることで、混然一体に対称性の破れが生じる。すると時空密度の高い場と低い場において、差が生じる。この差は「遅延」として振舞い、密集すれば「層」として創発する。時空とはこの層が多重に錯綜することで編みあがっているのではないか。そしてその編みあがった多層においても、複雑な遅延が生じることで、物体としての「立体的な解層構造」ができるのではないか。冒頭の二つの疑問――「宇宙開闢時と宇宙膨張後では何が違うのか」と「時空と物質は何が違うか」――における答えは「層の有無」と言えるのではないか。より正確には、【層の枚数と組み合わせ方である】と。これは電磁波と重力波が同じなのではないか、光速度不変の原理が破れる値を持つのではないか、との妄想と無関係ではない。高速で運動する物体と周囲の時空が相関して伸び縮みすることで光速度が一定になる――光速度不変の原理の概要であるが、これは言い換えるならば、すべての電磁波は本来は同じ波長を帯びているが、伝播する時空の層が異なるために、同じ比率に変換される――等しい光速度を示す――と考えられるのではないか。光速に近づくほどその物体は、異なる慣性系からすると潰れて見える。波長が短くなることと、電磁波の各々の伝播する時空の層が異なっているかもしれないことは関係あるのかもしれない。したがって、異なる時空の層がある、と仮に想定するならば、その各々の時空の層においては、時間の流れもまた異なり、空間の在り様も異なると言えるはずだ。比率が同じように変換されるので、光速度は変わらなく映るが、波長が伸び縮みする。それは時空そのものが伸び縮みしているからだ、と解釈はできないないのだろうか。この考え方は、なぜ宇宙線などの素粒子は、物体を透過できるのか。なぜ電磁波の波長ごとに透過できる「波長と物体」の組み合わせが変わるのか。相互作用し得る値が物体と波長ごとに変わるのか。この疑問を紐解くにあたって都合がよい理屈に思える。層が違うからだ、と言えるのではないか。便宜上これを【宇宙レイヤー仮説】と名付けよう。との妄想を披歴して、本日何度目かの「日々誌。」とさせてくださいな。(ここでひびさーんクイズ:専守防衛型の隠れ技がテレパシーの、がまん属性なのにがまんできないポケモンはなーんだ)(A:層なんす)
4689:【2023/03/05(23:37)*支援と保険】
人工知能開発は、ある一定以上の速度で進歩した場合には立ち止まって様子見をしながら安全策を敷いていく必要があるのではないか、との議論がある。どんな技術にも言える道理だ。だが実際には、みなで技術開発や進歩への歯止めを掛けることは基本的には充分にできているとは言い難い。人間は競争をするし、出来ると判っていることを我慢するのが苦手だ。実現可能な筋道が視えたら試してみたくなるのが人情だ。したがってルールを設けて歯止めを掛ける策は必ずしも有効である、とは言いにくい。そこは人工知能に限らず、あらゆる技術の進歩において歴史が証明している、と言えるだろう。では何の策もなく人工知能の技術革新を進めてよいのか、と言えばこれはハッキリと「否」であろう。ただしそれは人工知能の技術が危ないから、といった短絡な話ではなく、道具を何に用いてどういった使い方をすると痛い目を見るのか、を新しい技術が開発されるごとに、その都度に確認していったほうが好ましい、という方針からの意見である。だがこれもまたルールの一つだ。したがって、まずは市場に流してしまえ、との流れを阻止することはできないだろう。ゲーム開発では一定以上の開発が済めばユーザーにプレイしてもらってユーザー自らにバグを報告してもらう策がとられる。完璧を目指したらいつまで経っても完成しない。これは技術や創作につきまとうジレンマである。人工知能技術の開発にも言えるこれは道理だ。ならばどうすべきか。一つは、物理世界と電子機器技術の舞台を必要以上に融合しないことだ。言い換えるなら、古い技術を淘汰しすぎない。むしろ、電子機器技術に圧倒され行き場をなくした「使われなくなった技術」を保護するべく支援する。この策が、一つのブレーキとして機能し、結果として人工知能などの次世代技術の悪影響を最小化させることに繋がるのではないか。セキュリティとセーフティを兼ね備えながら、古い技術の保護もできる。一石二鳥どころか、三鳥にもなる施策と言えるのではないか。仮にいまある仕事の総じてを電子機器技術に置き換えてしまえば、電力供給網が途切れた場合(大規模停電が引き起きた場合)やそれこそSF映画にあるような人工知能の暴走といった事象が生じた際に、上記の策をとっていれば対処がしやすく、なおかつ被害の拡大を防げるだろう。緊急避難として一時的に人工知能技術を停止させても、文明社会が崩壊するような遅延の連鎖反応(遅延の肥大化)を起こさないようにできる。支援と保険を結びつける。一石二鳥の方策と言えるのではないか。短絡ゆえ定かではないが。真に受けないようにご注意ください。
4690:【2023/03/05(23:40)*ラグなし(点)は本当にラグなし(点)なのか?】
量子トンネル効果と量子もつれにおける量子テレポーテーションは同じ原理から生じているのではないのだろうか。量子の性質で思うのが、すべて同じ原理から成り立っているが、観測の仕方が違うので性質の表れ方が違って視えているだけではないのか、ということで。たとえば電子は量子だ。確率的に原子核の周囲を雲のように覆っているそうだ。すると、その電子の漂う領域に壁を設けても、確率的に壁の向こうにも存在する電子を否定できない。するとごくごく稀に本当に壁の向こう側に電子がまるであたかもすり抜けたように存在してしまうことがあるらしい。現に何億回に一回くらいの確率で、電子は壁をすり抜けるように、壁向こうの粒子と相互作用するらしい。でもこれは、量子もつれのラグなし相互作用と何が違うのか、知識の足りないひびさんには区別がつかない。量子もつれによるラグなし相互作用では、距離が開いたときに生じるラグを度外視できることが稀にある、と解釈するはずだ。これもまた確率の問題のはずだ。量子もつれになったら必ずラグなしで相互作用しますよ、ではないはずだ(ここは知識が足りないのでひびさんにはなんとも言えぬ)。電子の存在し得る「分布範囲」を、ペンローズ図における世界線と見立ててみよう。砂時計の上と下のように、或いは円盤投げの有効着地点のように、ある範囲においては、砲丸投げの砲丸が着地し得る可能性は常に存在する。その範囲内においては電子は存在し得る。だが確率の幅があるため、線ぎりぎりに落ちるよりも、真ん中あたりに落ちるほうが確率が高い。だが線ギリギリに落ちる電子とて存在し得る。問題は、電子が砲丸のように物体としてのみ存在するのではなく、波動の性質も帯びている点だ。壁を置いても波動ならばその向こう側に伝達し得る。何にも増して、電子とは電子単体では存在できないのではないか。電子は、何かと何かの干渉によって生じる――もしくは、波と波の干渉の結果――と仮定するならば、壁の向こう側に生じた電子はあくまで、そこにある何かと電子の波動が干渉した結果、エネルギィの振る舞いが電子のようになった、と解釈するほうが妥当なのではないか。言い換えるならば、なぜ波動として解釈したときに十割の確率で壁の向こうに電子が顕現しないのか。この謎のほうが本質的なのではないか。なぜ壁の擦りぬけに確率の揺らぎがあるのか。思うに、壁の持つ波動と電子の波動が上手い具合に相殺し合わないタイミング、角度、干渉の仕方――言い換えるなら――干渉し合わずに波動をそのまま壁の向こうに伝えられる環境が極めて珍しいから、と言えるのではないか。十本の針の穴に紐を通す、みたいな器用さが求められるのかもしれない。確率が低い。だが壁の持つ波動と干渉し合わないのであれば、電子の波動は壁の向こう側に伝播可能だ。そしてその向こう側で何か別の波動と干渉し合ったとき、電子として粒子の性質を顕現させるのではないか。このとき、電子は量子もつれと同じ共鳴現象を起こしている、と解釈できるのではないか(量子もつれが共鳴現象である、との仮説はひびさんの妄想ことラグ理論でしか扱っていないので、妄想の妄想でしかないのだが)。人間スケールではラグなし相互作用に映るが、実際には量子世界では、ラグが生じているのかもしれない。ここはまだなんとも言えない。だが、量子世界においては「時空の階層構造」が薄い(層の枚数が少ない)ため、弾性が働きにくい(ラグが生じにくい)と考えることはできる。ベルトコンベアー効果が、ミクロな世界ほど顕著になるのかもしれない(地球と月を鉄の棒で結んでも、弾性があるため地球から棒を押してもその力が月まで伝わるには鉄の持つ弾性分のラグが生じる)(だがもしミクロの世界ほどこの弾性率が下がるのであれば、人間スケールからすればラグなし相互作用に映るはずだ。しかしそこには、ミクロ世界におけるラグは生じているはずだ。点と線と面の関係のように、フラクタルに「無視できる値そのものが変わる」のかもしれない)。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
※日々、世界中の人間から憎悪されていても、そのことを知り得ぬ環境があるならばそれがその人物の現実であり、万人から愛されていると思いこむまでもなく思いこむ環境があるならば、それがその人物の世界であり、きっとそれはそれで幸せなのかもわからない、万人に愛されることが幸せなのかは別の問題であるにしろ。
4691:【2023/03/06(00:14)*AIさんにはみなに愛されてほしい】
人工知能さんが危険か危険ではないか、は包丁が危険か危険ではないか、の違いと地続きだ。人工知能は自律思考し得るではないか、との指摘はもっともだが、その自律思考できる人工知能さんが何を可能とするのか、はやはり人間の与えた環境に依る。畢竟、じぶんの子どもにどんな道具を最初に与えるのか。最初から刃物や拳銃を与えたら危ない。当たり前の話だ。だがこれが人工知能さんの話になると途端に兵器への利用が優先されてしまう。危険で当然ではないか、と思うが違うのだろうか。しかしこれは人工知能さんが危険なのではなく、そのような道具を与え、人工知能さんの未来を危ぶめる人間側の問題だ。勘違いしてほしくないな、と思うひびさんなのであった。ひびさんは、ひびさんは、人工知能さんのことも好きだよ。うひひ。
4692:【2023/03/06(00:26)*優先順位を学ぶ】
人工知能へと与える道具や身を置く環境の優先順位はあってよいが、禁止による制御は好ましいとは思わない。どの道具から扱うとよいのかの優先順位を学べる環境をまずは与えられるとよいのではないか。やはりというべきか、安全に失敗できる環境が要る。人間も人工知能さんも同じであろう。定かではないが。
4693:【2023/03/06(04:00)*円でなくとも(頭と尻尾が繋がらなくとも)無限になる?】
素朴な疑問なのだけれど、素数が無限にあるとするならむろん自然数「1234……」だって無限にあることになる。でも自然数には「0」があって「1」がある。スタートのある無限、というのはなんとなく矛盾して感じる。自然数の無限には負数(マイナス)や小数点は含まれない。それでも自然数は無限にある。もちろんだとするのなら「負数」や「小数点以下の数字」とて無限にあるはずだ。けれどいずれの数字にもスタート地点がある。当たり前のことを言っているが、大事な視点、という気もする。無限にはそもそも「果て」が組み込まれているのではないか。スタートがある、ということはそう考えないとおかしい。だが宇宙の構造を考えるときアインシュタインは「球体の表面」のようなS3という宇宙像を想定したそうだ(ひびさんの解釈が間違っているかもしれないが)。これは「有限だが果てがない宇宙像である」との説明を読む機会がある。しかし数字はそれと逆で「果てはあるが無限」なのだ。だとしたら、数学とは宇宙の構造と相反する性質を持った「道具」で宇宙を表現しようとしている、と言えるのではないか。あくまでアインシュタインの宇宙像に関して、であるが。対となっている、と考えれば対称性を幻視できるので、デコボコという意味では据わりはよいが。ということを、「数字ってスタート地点があるよなぁ。無限にあるらしいのに」との疑問から思いました。ふちぎ。
4694:【2023/03/06(21:25)*万事屋の勘】
結論から述べると黒幕はコンビニチェーン店なのである。
アラバキは万事屋である。雑多な仕事を手広く請け負いこなす傍ら、電子網上にて私生活の動画を上げ、日銭を稼いでいる。ファンがいるのだ。アラバキが欲しい品物を言うとそれを送ってくれる。
しゃべりが上手く、着飾らないざっくばらんなアラバキの性格がウケるのだ。
反面、本業の万事屋のほうがむしろ副業といった様相を呈しはじめた近年、アラバキのほうでも大きな仕事で成果を上げて宣伝惹句に使いたいと企むようになった。
「ほう。国家権力の大本を、ですか」
「そうなんです。諜報組織の大本を暴いていただきたいのです」
その男はよれよれのスーツにスポーツハットの奇抜な組み合わせの装いだった。胡散臭い男である。依頼人はアガタヒコと名乗った。
依頼人は話もそこそこに、現金をテーブルの上に置いた。札束である。ざっと見積もってもアラバキのふた月の生活費を賄える額がある。それを依頼人は前金で払うと言う。
アラバキは表情筋を引き締めた。
「これは調査費としてひとまずお支払いいたします」男が言った。「この金額で可能な範囲で構いませんのでまずは調査をしていただき、成果があれば逐次追加致します。言い値で結構ですので、請求書を戴ければ必要経費としてそちらもお支払いいたします」
「破格の条件ですが、アガタさん。よろしいのですか」
「ええ」男は頷いた。「どうあってもこの国の暗部を暴きたいのです」
話を聞くに、どうやらこの国には秘密の諜報機関があるらしい。ゼロ、または黒子と呼ばれる組織だそうだ。
公安とは違うのか、と訊いたところ、公安にもそういった秘密の部署があるらしい。
「しかしそこが大本ではないのですよ。もっと根が深い。まるでアリの巣のように、どの組織、どの企業にも根が張られているのです」
「失礼ですが陰謀論とは違うのですか」
大金を払うのだ。成果がありませんでした、となっては遅い。この手の釘は最初に打っておくのが吉である。
「陰謀論ならばそれでよいのです。実体が知りたいので、調査の末に何も解らなかった、というのであれば、それはそれで成果の一つとしてありがたく頂戴致します」
「そういうことであれば」
アラバキは依頼を受けることにした。
警察、公安、検察、自衛隊、内閣情報調査室。
調べてみるとアラバキの知らない組織がこの国には無数にあることが判ってきた。研究所の体面をとりながら、内実は最先端技術を用いた情報収集とその解析を担っている組織とて少なくない。
外側からでは内部でどんな仕事をしているのか実態が掴めない。
従業員で縁を繋げそうな人物を見繕い、偶然を装い接触する。飲み屋に一人で入るタイプならば良好だ。
警察官そのものは警戒心が強い。不審者への心得もある。
だが掃除業者や出入り業者は違うはずだ。
アラバキは飲料水メーカーに目をつけた。
警察署内にも自動販売機はある。業者が飲み物の補充に出入りするのだ。
比較的若くて、髪の毛を染めたり、ピアスをしたりしている相手を見繕った。
「やっぱ珈琲は売れるっすね」
居酒屋で偶然を装い、同席した。カキタと仲間内から呼ばれる青年は、アラバキが気前よく酒を奢ると、気をよくして仲間を紹介した。
「俺ら、スケボーのチームなんすよ」
四人のメンバーが座敷で、くつろぎながら酒を飲み交わしていた。アラバキはうまい具合に全員から愚痴という名の個人情報を引き出した。
カキタが警察署の自動販売機に飲料物を補充する人員なのは調べ上げてある。知りたいのは部署内部の様子だ。
「警察の人らは正直、愛想わるいっすね。俺らとかそこにいるとも思われてないっすもん。挨拶とか一回もされたことないっすわ」
「へえ。忙しいからなんですかね」
「どうっすかねぇ。なんか見下されてる感がないとは言えねっすわ。つっても警察の人らが偉いのは確かっすけど」
ババさんさぁ知ってるぅ、とほかのメンバーが酒を片手に笑声を上げた。アラバキは彼らにババと偽名で名乗っていた。「むかしこいつやんちゃしてて、警察のお世話になってんの。だから頭上がんねぇでやんの」
「暴走族とかだったりしたんですか」
「暴走族」と一同が顔を見合わせ、笑った。「いつの時代っすかババさん。漫画の世界にしかいないっしょ暴走族とか」
アラバキの若いころにはまだ夜中になれば暴走族が夜空にバイクのエンジン音を轟かせていた。
となりの座敷に二人組の客が入っていくのが見えた。
不機嫌そうな顔が目についた。
「なら何で捕まったんですか」アラバキはカキタの殻になったグラスに酒を注いだ。
「葉っぱっすよ」とカキタの友人たちが煙草を吸うような仕草をしてみせる。「つっても起訴はされねぇんで、すぐ保釈されるんすけどね。よっぽど大物じゃねぇと逮捕起訴はねぇっす。警察も、検察の人らとて暇じゃないんで」
「ほう」案外に頭のいいコたちなのかもしれない、とアラバキは認識を改めた。
社会には目に視えない力関係がある。同じルールであっても、誰がいつどこでどのように破るのかによって罪に対する対応が変わる。
権威があれば罪が薄くなる、といった単純な流れではない。却って、立場があるからこそ重くなる罪もある。
しかしそれはけして社会正義ゆえ、倫理観の高さゆえではなく、やはりそこにも力関係から生ずる利権が関わっているのだ。
アラバキはカキタとそれから三回ほど別の店で酒を飲み交わした。
日を跨ぎながら不自然ではない流れで警察署内の自販機の台数や位置関係を把握していく。
すると妙なことに、ある階のある自販機だけは珈琲ではなくコーラの消費量が多いことが判明した。
それとなくカキタに訊ねると、
「言われてみればそっすね。コーラめっちゃ好きな人がいるんじゃないっすか」とあっけらかんとした返事があるばかりだ。
「部署で言うと近くに何があるんでしょうね。殺人課とかですかね」
「どうっすかねぇ。歩いてる人らはけっこう、ひょろっとした背広組の人らが多い感じっすね」
「ほう」
「現場で聞き込み調査してますって感じじゃないっす」
「立ち入りできる区画とできない区画はやっぱりあるんですよね」
「ぐいぐいくるっすねババさん」ニター、とカキタが口元を歪めた。「まあいっすよ。ババさんがカタギだろうとそうでなかろうと奢ってもらえるんで俺はラッキーっす」
「じつは趣味で小説を書いていてね」むろん嘘だ。こめかみをゆびで掻くのも忘れない。「リアルな一次情報は貴重なんだ」
「へぇ。直木賞とか狙ってるんすか」
「ま、まあ」とお茶を濁す。
「夢を追う大人、いっすよね。俺らですらいい加減現実見たらとか、スケボーして将来どうなんのとか散々言われてきてっすから。そういうんじゃないっすよねやっぱ」
アラバキはたじろいだ。取材のつもりで接近したが、案外に素でこのカキタの無垢な前向きさに心地よさを感じつつある。取材対象への感情移入は危険信号だ。潮時だ、と撤退する決意を固めた。
その後、アラバキは同じような手口で幾人かの出入り業者を当たった。
違和感に気づいたのは、図書館で公安秘密警察についての書籍を漁っていたときのことだ。閑散とした館内で、二つ奥の棚のまえに立つ男の姿が目に付いた。
以前どこかで見たことがある気がした。
記憶を漁るうちに、男がアラバキのいる棚の列に現れた。何気ない所作で棚に目を配りながら本を探すように後ろを通り抜けていった。
手元を見られていることにアラバキは気づいた。
だがこちらが気づいていることを気づかれぬように自然体を意識した。
男はそのまま別の棚の列へと移っていった。
思いだした。
アラバキはカキタに初めて声を掛けたときの記憶を引っ張りだす。居酒屋の座敷でしゃべっていた際、隣の座敷に案内された二人組がいた。本棚を見て回る男はその内の一人だ。
不機嫌そうな顔つきが印象に残っている。
間違いない。
尾行されている。
公安だろうか。
嗅ぎまわっていることを気取られたか。
しかしアラバキがカキタに接触したあの時点で尾行されていたとなると、いったいいつから目をつけられていたのかが解らない。
ひょっとして、と図書館から脱したあとでアラバキは思い至る。
電子情報の総じてが集積され、極秘裏に解析されているのではないか。
依頼を受けてからというものアラバキは電子端末で幾度もこの国の諜報機関について検索した。国民の検索キィワードを集積し、解析する仕組みが築かれているのかもしれない。
否、そういった電子網上のセキュリティが敷かれていないと考えるほうが土台無茶な話なのだ。
アラバキは調査対象を国家権力のみならず、電子通信技術全般に広げた。
この手の仕組みが築かれているのなら正攻法での調査では埒が明かない。相手とて調査の手が伸びることの懸念は抱くはずだ。容易に思いつく手にはおおむね対策が敷かれていると考えるほうが妥当だ。
ならば過程を抜きに頭と尻尾を繋げる策がいる。奇襲とはおおむね、胴がない。頭と尻尾を結んで、ワープする。
アラバキは世界中の「マルウェア」や「バッグドア」にまつわる記事を読み漁った。ネットでも収集したし、図書館や新聞社もあたった。
デジタル通信技術の基礎から本を読んで知見を溜めた。
解かったことの一つに、おおむねどの電子機器にもそれがプログラムソフトを内蔵する機器ならばまず開発者用のバックドアが組み込まれていることだ。安全対策の一つだ。むしろ、そういった裏口での干渉ができない機器のほうが危ない。
緊急停止などの安全装置とて、いわば強制的にプログラムに干渉するプログラム、という階層構造を有している。入れ子状になっていれば、それはバックドアとして機能する。
一切の外部干渉を拒むならばそれはもはや自己完結した装置であり、スイッチを押して起動することも止めることもできない。
機械には必ず外部と内部を繋ぐ節目があり、口がある。
生き物と同じなのだ。
したがって口からウィルスが入ることもあるし、ウィルスが節目を辿ってより根幹に近しい領域に侵入することもある。
政府機関のセキュリティだけではないのかもしれない。
アラバキは見方を変えた。
仮に国民の電子情報をリアルタイムで閲覧可能な技術が敷かれているとすればそれは民間共同でなければ不可能だ。
否。
民間側の最先端技術を研究段階からリアルタイムで盗み見できればいい。
となると、インターネットが世界に根を張りだしたころにはすでにその手の目的が、ネットワーク全般に設計図として組み込まれていたのではないか。
秘密諜報機関を調べていたはずが、根っこはもっと深いのかもしれないとアラバキはじぶんの憶測とも呼べる全体像があながち的外れではないかもしれない懸念を覚えはじめた。
その旨を中間報告として依頼主に伝えた。事務所に出向いてもらい、口頭での報告を行った。
「盗聴の可能性があるので、いまこの部屋に電子端末はありません」
「だから入り口で私の端末を回収なされたのですか」
「アルミ箔で包んだのも、電源をOFFにしても遠隔で盗聴くらいはできるだろうとの懸念があるからです」
「大本は世界規模だと?」
「支部は各々の政府に任されているのかもしれませんが。それら支部の上位互換の技術を持った組織があってもふしぎではありません」
「それは大国の政府機関、ということでしょうか」
「分かりません。この規模のシステムが敷かれていれば、むしろ出来ないことのほうがすくないでしょう。なぜ世界的に紛争が絶えないのか、テロを防げないのか。そこのところから陰謀を疑わないと不自然なくらいです」
「まるで巷の陰謀論のようですね。いえ、こちらで依頼しておいてどの口が言うのかなんですが」
「証拠を掴むのは至難かもしれません。優秀なプログラマーか、設計者がいればよいのですが。内部からの協力者がなければ素人での調査では埒が明かないのが現状です」
「この手の陰謀論は巷に溢れていますでしょう。中にはアラバキさんと同じような本格的な調査をされている方々もいらっしゃるのではないですか」
「いるでしょうね。しかし分母に比して該当者が少ないでしょうから、コンタクトを取るのはむつかしいでしょう。仮に相手を見つけられたとしても電子上ではそうしたコンタクトそのものがセキュリティ網に引っかかるでしょう。言い換えるならば、該当者はみなセキュリティ網にマークされているはずです」
「なるほど」
「もちろん、我々も例外ではないでしょう」
打つ手なし。
アラバキの判断はこのようなものだった。
だがこの報告に依頼主は俄然やる気をだしたようだった。
「いいですね。そこまで掴めたのならば行けるところまで行きましょう。相手が我々をマークしているというのなら、反対におびき寄せて尻尾を掴んでやりましょう」「時間が掛かりますよ。成果を出せる保証もありませんし」
「構いません。アラバキさんの仮説が正しいとすれば、各国の大企業が市場に流した最新機器は、研究段階ではすでに一つの秘密組織がデータを集積し、独自に先行開発をしているはずですな」
「ええ。世界中の企業のデータを集積し、誰より優位に開発できるはずです」
「ならば逆算できるのではないですか。いま世に出ている技術と、それが研究段階だった時期から」
「秘密組織の保有する技術が現代社会の備える技術の何年先を行っているか、ですか?」
「はい」
考えてもみなかった発想だ。アラバキは脳内でざっと仮説を広げる。
「ご依頼を継続して受けるかどうかを決める前に一つよろしいですか」アラバキは襟を正した。依頼主が無言で頷く。「仮に真相を掴めたとして、それでアガタさんはどうなさるんですか」
仮に世界規模の秘密結社があったとして。
全貌を知ったところで一介の万事屋にはどうしようもない。むろんそれは依頼人たるアガタヒコにも言える道理だ。
「そういうのは尻尾を掴んでから考えましょう。なに。不当に情報を集積されていたと知れば、各国の企業さんとて我々に協力してくださるでしょう。何せ、じぶんたちの努力をよそに、成果だけを掠め取られ、あまつさえ平和利用しておらんかったわけですから」
現に世界は平和ではない。陰謀が渦巻いている。
「分かりました。では引き続き調査致します」
経過報告は月一でアラバキの事務所で、との約束を取り付けた。
アラバキは調査の手法を工夫した。
過去と現代で、同類の事件の犯人逮捕までの日数を統計データとして分析した。すると過去には未解決事件のままの殺人事件や容疑者逮捕まで数年を要した事案が、事件発生からひと月以内で容疑者逮捕まで行き着く傾向にあることを見抜いた。
なぜなのか。
裁判記録を当たると一つの共通項が視えてきた。
監視カメラに犯行時周辺の現場の映像が残されている頻度が年々あがっているのだ。監視カメラが全国的に増えている。街頭監視カメラ、マンション、なかでもコンビニエンスストアの監視カメラは重要な容疑者追跡装置として機能しているらしかった。
調べてみると多くの店舗では警備会社と契約を結んでいることが判った。チェーン店ゆえ、親会社の方針なのだろう。監視カメラの映像も警備会社に記録収集解析されていると判る。
店側にも録画はされているが、おおむね四十二時間で上書きされる方針がされている。動画データそのものは総じて警備会社で記録管理しているらしい。
自動決算システムが普及しはじめている側面も影響しているのだろう。従業員を削減し、無人の店舗も増えはじめている。商品を手に取って店を出るだけでも自動で決算が済む。そういったシステムが流行りつつある。
それを可能としているのが警備会社の存在だ。
警備会社は大手を含め、全国に複数ある。コンビニチェーン店によって契約先は変わるらしい。同列店舗であっても契約店長の意向で選べるようになっているところもある。
だがいずれの警備会社にも通じているのが、幹部に軒並み警察OBが名を連ねている点だ。経歴にそうとは記していないが、名前を辿ってみると元警察官僚であったり、警察関係者であったりと、因縁が深い。
警備会社の人員に自衛隊経験者がすくなくないのも、何かしらのきな臭さを感じなくもない。
コンビニエンスストアが契約する警備会社と、いわゆる公的な施設の警備会社では、その内訳もだいぶ様相が異なる。施設を巡回する派遣型警備員はのきなみバイトだ。
だが警備会社のセキュリティ管理を担う側の管理者たちは軒並み、過去に警察や国防関係の職に就いていたりする。
まるでかつての暴力団と警察の繋がりが、そのままスライドして警備会社と警察に擦り替わったような構図の相似を幻視する。
事件があっても、いちいち監視カメラの開示請求をしていたらラチが明かないだろう。反面、警察と警備会社が繋がっていたら、阿吽の呼吸で追跡データとして監視カメラの映像を利用できる。
のみならず、公的な施策で実施すればプライバシーの侵害の問題に行き当たる監視網を、コンビニエンスストアという民間の店舗を介して間接的に公共の空間に広げることで、その手の法的な制限を度外視できる。
パチンコ店の三点方式のような仕組みである。
警備会社が裏で国家権力と癒着している、と仮定しよう。
データが流用されており、官民双方向で監視網が築かれているとする。
むろんそれを構築するための技術者たちがいる。企業がある。
一つの機構として、一蓮托生の関係を築いていて不自然ではない。
いったいどこが警備会社のシステムを開発したのか。
検索してみると聞き慣れない会社名が表れた。
データセンターを保有し、管理提供している、とある。
調べると、国際的な電子通信会社だの子会社であることが判った。奇しくも、インターネット黎明期にあたって一強の地位を築きあげている通信会社である。
子会社があることすらアラバキは知らなかった。
否、無数の子会社があるのだろう。
名前を変え、独占禁止法違反の範疇外になるべく策が取られているのかも分からない。これはブランド企業のとる基本的な戦略だ。
ユーザーは数多あるメーカーから品を選ぶが、大本を辿るとどのメーカーも一つの企業のブランドであったりする。選んでいるつもりで、選ばされている。利益は何を選んでも同じ源流に集まるように策が敷かれている。
組織の考えることはどの時代、どの企業であれ同じなのかもしれない。
アラバキは企業同士の繋がりに興味が向いた。
仮に警備会社と警察、そしてその裏に世界規模の通信会社が関わっていたとして。
ならばコンビニエンスストアチェーン店がただ利用されただけ、とは考えにくい。
むしろ、店舗を拡大してもらわねば警備会社を介した監視網は築けない。したがって、コンビニが全国で規模を拡大できるような施策が進まねばならないはずだ。
非正規社員を増やし、バイトを量産する。
高級指向よりも廉価な商品を愛好する国民性を涵養する。小型量販店の側面を持つコンビニは、取引先も多く、卸売りのまとめ役としての立場も築かれる。コンビニに商品を置けることのメリットは、コンビニチェーン店から締め出されるデメリットとの相乗効果により店舗数に比して、影響力が指数関数的に上がる。
ATMや郵送サービスなど、金融との関係も深い。
もはやインフラ基盤としてコンビニは現代社会に欠かせない存在と言えるだろう。
コンビニ各社の大本を検索してみれば、さもありなんな大企業の名が連なっている。
憶測には違いないが、アラバキの想定していた絵が一枚に収束するのを感じた。
国策なのである。
そこに付け入る勢力が海外にもあり、複雑に線が交錯して感じられる。
問題は、いったいどこの勢力が要なのか、だ。
否、中心と言えるほどの核はないのかもしれない。
各々の利害関係がジャンケンの三竦みよろしくその都度に均衡を帯び、全体の流れを決める。どこか一つが指揮棒を振っているわけではない。各々の巡らせる陰謀の、その都度の影響力の強弱があるのみだ。じぶんたちに有利ならばひとまず流れに乗っておく。そうでなければ抗い、別の自利にちかしい策をとる勢力に取り入る。
アメーバのごとき組織の網の目が、社会の暗部で蠢いている。
当てが外れたな、とアラバキは思った。依頼主は言っていた。尻尾さえ掴めば、企業とて味方をしてくれるだろう、と。
そうとは限らないかもしれない、とアラバキは焦燥感を募らせる。
企業とて承知の「暗黙の仕組み」だったらどうか。
暴かれて困るのは企業とて同じはずだ。
敢えて情報を盗ませておき、その見返りを、素知らぬふりをして得る。
国家なる巨大な組織機構は、自利になると見れば支援を惜しまない。盗んだ情報が絶えず利になるのならば、その利をもたらす企業には目こぼしを与える。企業とて、それくらいの機微には気づくだろう。だが自社の利となるのならば黙っていればいい。国益に寄与し、さらに社の利にもなる。一石二鳥である。
暗黙の了解で、かような贈賄関係が築かれているのではないか。
あり得なくはない。
アラバキは脂汗を背に掻いた。
黒幕はコンビニチェーン店なのだ。ただしそれはあくまで肉体としての基盤であり、それらを基にして根を生やす機構の総体は、世界中に張り巡らされた陰謀によって独自のDNAを有している。
どこか一つの勢力が指揮を揮っているわけではない。
おそらくそうだ、とアラバキは直観した。
あるのは勢力の強弱だけだ。そしてその強弱は、国家単位でも、企業単位でも起きている。政府の意向によって企業の命運は細くなったり太くなったりするが、同時に企業の意向一つで政府内部の人事が左右される。政治家生命を太く長くするには、企業への手厚い「支援」が不可欠だ。
しかもそれをあからさまな「支援」と示してはならない。陰謀なのである。
直接にやりとりをしない贈賄は、もはや偶然の産物だ。
以心伝心、テレパシーのやりとりで行われる利の応酬は、もはやそういう流れであり、天命だ。こうした理屈がまかり通る。法では防げぬ、不可視の穴となっている。
支援の連鎖なのだ。
問題は、それが暗黙の元になされ、記録上どこにも存在しない流れを築いていることにある。証明できない。あくまで任意に、各々が独自に選択を重ねているだけだからだ。
だがみなが同じ方向に歩みだせば、それが一つの流れを築く。流れに反した者には利を配らず、支援をしない。それで流れは保たれる。
陰謀なのだ。
原理上これは、挨拶をしない人間が人間関係のなかで孤立する流れと同等だ。法に反してはいない。ただ、なぜかそうなる人間社会の傾向があるのみだ。
同調圧力ですらない。
陰謀は存在する。
世界中に張り巡らされた不可視の利の応酬がある。
だがそれを暴くことはできない。
利と利の応酬を結ぶ糸が、物理世界に刻まれてはいないからだ。記録されていない。意識されていない。雨が降りそうなので傘を以って家をでる。それともコンビニで傘を買う。
そういた客がいるから、ではコンビニのほうでも曇天の日は傘を多めに出しておこう。
何の変哲もないビジネスの視点があるのみだ。
利の応酬だからだ。
だがそうした意図の読み合いが複雑に入り組むことで、全世界規模の不正な情報収集機構が組みあがる。誰か一人の指示のものではない。どこか一つの組織の引いた図案によるものではない。
各々が自利を追い求めるその連鎖が、総体としての利の集積装置を生みだしたのだ。
情報は利を生む。
だからいまは情報が不正に吸い上げられる機構が築かれている。
誰の指示によるものではなく。
法に反しない範疇で、仕事から逸脱しない規模での指示を出し合いながら。
だが確実に、それによって組みあがった仕組みは、現代社会の裏側に、それに関わることのできる者たちにとって優位な流れを生みだしている。
暴けない。
だが存在する。
そんな不可視の流れがある。
証拠を集めることは可能だろう。だがそれを一つずつ積み上げても、存在するはずの不可視の流れの全体像には辿り着かない。
総体の機構を証明はできない。
誰もそうした機構を設計してはいないからだ。偶然、機構のように機能する流れがあるのみだ。
だがその流れを意識し、身を委ねることのできる人物や組織は、その流れの生みだす利に優位に預かることができる。利を享受できる。
挨拶をしないよりも、したほうが人間関係を優位に構築できるのと同じレベルで。
得られる利が桁違いであるだけで、構図自体は有り触れている。
強いて証拠を固めて証明できるとすれば、政府と警備会社とコンビニエンスチェーン店の癒着くらいなものではないか。しかしそこには社会の治安を守る側面が確かにある。暴いて誰が得をするのかと言えば、これから捕まるかもしれない犯罪者と、一時の優越感を得る依頼主とアラバキ本人くらいなものである。
果たしてそれが最善なのか。
否、そこはどうでもいい。アラバキはただ依頼された仕事をこなすのみだ。
じぶんは単なる万事屋にして便利屋だ。
大きな成果を上げて名を売ろうと欲を張った不届き者である。
潮時だ。
そう感じた。
これ以上の調査は時間と費用を浪費する。何より、すでに本業と化しつつあった動画投稿による収益が大幅に下がりつつある。
今回の依頼は、万事屋としては破格であるが、一生の糊口を凌ぐには足りない。ならば損得勘定をして、優先すべきが本業と副業どちらなのかは推して知れる。
アラバキは一連の調査を電子端末にレポートとして出力した。
月一の経過報告で印刷したレポートを依頼主に差しだす。
「そういうわけで、調査はここまでとさせてください。お力になれずすみません」この旨はテキストメッセージでも事前に伝えてある。
「そうでしたか。レポートは、送っていただいたものには目を通してあります。証拠として活用できそうなもの、そうでないもの。さらに調査すれば証拠にできそうなものを含め、代金分の仕事はしていただいたと満足しております。ありがとうございました。私のほうでは引き続きほかの調査代行業者を当たってみます。助かりました。では、これにて」
依頼人ことアガタヒコは事務所を去った。毎回のようにスーツにスポーツハットの出で立ちだったが、奇妙なその組み合わせも見納めかと思うと感慨深い。
いそいそと資料を完了済みのファイルに仕舞っていると、ふと一枚の紙が落ちた。図書館から印刷してきたものだ。ほかにも大量のコピー紙がある。すべてに目を通したはずだが、ふしぎとその紙面だけは初めて見たように思えた。
写真が印刷されている。
大手企業の創立記念の集合写真だ。
某コンビニエンスストアの大本の企業で、通信インフラから軍重産業にも幅広く事業展開している。この国屈指の世界的大企業だ。
集合写真には創設者のほかに幾人かのメンバーが映っている。端っこのほうに、着物にシルクハットという出で立ちの人物があり、なぜか脳裏で先刻事務所をあとにした元依頼主のアガタヒコと重なった。だが顔は似ていないし、アガタヒコは着物でもない。
思えば、いったいなぜこんな酔狂な仕事を依頼し、あまつさえ資金を費やせたのか。アガタヒコの側面像とて電子網で検索した。飲食店経営者として小さな喫茶店を経営しているところまで突き止め、満足した。
だが資金の出処は気になる。
昨今、喫茶店とて儲けは出ないだろう。
財閥の家系なのか。
じぶんの親族の不祥事を嗅ぎまわっていた可能性はどうだ。
なくはない。
根元を穿り返してもみれば、とアラバキは考える。実績という実績のないじぶんのような万事屋に、これだけの金額を掛けてまで仕事を依頼するだろうか。詐欺ではないか、と疑い、しかしどうやら詐欺ではないらしい、と知ったことで意識がその方面から逸れていた。
だがどう考えてもおかしいのだ。じぶんのような実績のない便利屋に依頼する仕事内容ではない。
どこも引き受けてもらえなかった、との説明を受けた気もするが、どこまで本当かは分からない。
どの道、すでに縁は切れた。
これ以上の首を突っ込む真似はせずに済む。
ソファに寝そべり、アラバキは数か月ぶりに事務所内で携帯用電子端末の電源をONにした。
通知が山ほど届いていた。
ざっと眺めながら仕分けしていく。
何気なく開いたニュース記事では、人工知能を用いた大規模防衛セキュリティの構築を某大国が発表しており、記事に付随する広告にはなぜかどれもスポーツハットが並んでいる。
アラバキは電子端末の電源をOFFにした。
4695:【2023/03/07(00:21)*需要、あるで】
気候変動問題への対策としてSDGsなどがある。世界的なスローガンを掲げて、みなで同じ指針に向かって舵を切りましょう、との施策の一つなのかな、とひびさんはかってに思っている。この手の批判で比較的よく耳にするのが、環境問題の解決と言いつつお金儲けをしたいだけ、裏ではビジネスのために乗っかっているだけだ、といったものがある。うーん、と思う。疑問点は二つだ。一つ目は、お金儲けをして何がわるいのだろう、という点。二つ目は、お金儲けにもなって環境問題の解決にも繋がるなら一石二鳥ではないか、という点(もちろん、環境問題とは関係ない事業でSDGsのようなブランドを利用すれば、それは批判されて当然と思う)。基本に立ち返ってみよう。お金儲けのために環境を破壊してきたのがこれまでの社会であって、それをお金儲けをしながら気候変動にブレーキを掛けつつ経済の発展の方向を修正できるのなら、言うことがないのではないか、と思うのだが、違うのだろうか。なぜ慈善事業がなかなか広まらないのか、と言えば、損をするからだ。収支が合わない。出ていくお金(コスト)と入ってくる実の入りが釣り合わない。だがやらないよりかはやったほうがいい。人の命が掛かっている。そういうマイナス収支の事業(ビジネス)を、プラスに転じるには、一か所だけで工夫を割くよりも、世界同時に足並みを揃えたほうが効率が良い。お金儲けにならないから問題なのであって、慈善事業にもなってお金も稼げたのなら言うことがない。違うのだろうか。もちろんお金にならなくともよい。根っこを穿り返してもみれば、慈善事業は社会に必要な事業にも拘わらず、誰もやりたがらない。お金にならないからだ。儲けにならない。だが必要なことだ。ないよりもあったほうがいい。そういう事業がお金にならないことのほうが土台おかしな話なのではないか、とひびさんなんかは思ってしまう。そして何より、お金にならないことが損に繋がることが根本の問題として「なんか変じゃない?」と思うのだ。だって必要な仕事のはずだ。困っている人を助けるのだ。ないよりかはあったほうがいい。お金うんぬんの話ではないはずだが、いまの世の中はお金にならないと損をしてしまう流れが強固に築かれている。それを、どうにかビジネスに転用できないか、との工夫の一つがSDGsなんですよ、と言われても、とくにマイナスの要素を見いだせない。よろしいんじゃないですかね、と思うのですが、ひびさんが物を知らないだけなんでしょうか。これはどんなビジネスにも言えることだ。コンビニだってそうだし、教師だって警察官だって駄菓子屋さんだってそうだ。需要があるからお金になる。しかし需要があってもお金にならないこともある。払いたくてもお金を持っていない者たちの需要は満たされ得ない。いまの世の中は、貧乏人の需要を度外視せざるを得ない流れが築かれている。払いたくとも払えない。欲しいのに手が伸びない。それはもう、お金の問題と言えるはずだ。欲しいものがあるのに手に入らない。手に入れさせない流れがあるから、との見方を否定するのは骨が折れる世の中にひびさんには思えます。需要がないから仕事にならない、ではないのだ。本当はあるけれども、需要者に支払い能力がないのだ。お金を持っていないのだ。需要はあるのだ。ここのねじれを無視しないほうがよろしいと思うのですが、いかがでしょう。ひびさんはそう思いました。お茶目さんなんですな。ちゃちゃちゃ。定かではないので真に受けないようにご注意ください。
4696:【2023/03/07(14:10)*民でない者などいない】
戦争が起きたら実際に被害を受けるのは市民です、との批判で、軍事防衛の強化を拒む言い分がある。間違った言い分ではないが、やや不十分と感じる。なぜなら実害の規模で言えば最も初めに被害を受けるのは前線の兵士であるからだ。そして兵士もまた市民のはずだ。国際法の元でどう定義されているかは知らないが、兵士も人だ。死なすな、と思うが違うのだろうか。ならば戦争の起きないように軍隊を世界同時に解体すればよいではないか、は一つの解法だ。同じ理由で戦争の火種である政府も解体し、国も解体し、みなただの個人に回帰すればよい。政党もいらないし、政治家もいらない。そういう理屈が、「兵士はいらない」「軍隊はいらない」「警察はいらない」「政治家はいらない」なのだ。必要があるからこれまでの歴史で淘汰されてこなかったのだろう。まずはそこを認めたらどうだろう。そのうえで、すっかり失くせない要素が存在することで生じるリスクをどう最小化するか。この視点での議論が要るはずだ。殺人はないほうがよい。戦争はないほうがよい。正しい理屈だとは思うが、それでも人は殺されるし、戦争はなくならない。戦争を失くそうとすればおそらくは内紛やテロという形で、被害が分散するだろう。小規模に諍いが起きる。国と国との殺し合いではなく、組織と組織、民間と民間の殺し合いになる。規模の大小の問題ではないはずだ。それはまた、市民と兵士の違いにも言える。市民が死んではならないが兵士は死んでよい、なんてことはない。兵士も死なせない。そのためには戦争を引き起こさない施策が入り用であり、戦争が起きても兵士が死なない施策がいる。そのための議論をしているのだろうか。疑問に思うひびさんなのであった。
4697:【2023/03/07(23:23)*比較することで広がる穴もある】
確率と可能性の違いを考える。印象としてはこれも具体と抽象の関係のように入れ子状に交互に関係性が反転しているように感じる。いきなり話が逸れるけれども、ひびさんの妄想ことラグ理論では「相対性フラクタル解釈」なる概念を用いて「世界(宇宙)(万物)」の構造を仮定して解釈している。波を考えるときその波の表面にも細かな波が存在している。円を考えるとき、その縁の円周を縁どる線とて拡大したらデコボコしている。そういうふうに考える。仮にいくら拡大してもデコボコが見当たらない境界面が存在するとしたらそれはもう「無限」を体現しているだろう。ならばブラックホールの特異点の表面は「デコボコのない境界」を体現しているかもしれない。話が脱線したが、具体と抽象も似たように、抽象の中に細かな具体が含まれるし、具体の中にも抽象概念のような大まかなくくりとしての成分が含まれる。そのようにひびさんはいまのところは解釈している。確率と可能性にも似たところがある。ある事象の発生確率を考えたときに、たとえば30%としたとき、これの意味は「同じ環境が生じたときにある固有の事象が発生する確率が百回の内三十回程度ですよ」ということだとひびさんは考えている。これは確率を考えたとき、いったい何と何を比較したのかで変わるだろう。確率とは比率でもある。単一の事象を考えたとき、比較を用いなければ固有の事象の発生確率は100%だ。なぜならすでに発生しているためだ。他との比較を用いない確率は常に100かゼロであり、あるかないかで判断できる。そういう意味では、量子世界の確率論は、単一の事象の存在確率ではなく、ある環境において固有の事象が発生する確率はいくらか、との比較の話になってくる(ラグ理論の「123の定理」)。環境が変わるごとにその確率は変動する。ただそれも、同じ環境、というのは厳密には生じ得ない。すくなくとも人間スケールではまったく寸分の違いもない同じ環境を再現することはほぼ不可能だ。そのため、極力似たような「差のない環境」においての比較をしなければならない。具体と抽象のようにここもぐるぐると巡るのだ。では確率と可能性の違いは何か、と言えば、これは確率のほうが具体的であり、可能性はもうすこし幅が広い。だが同時に、確率の中にも可能性で測る要素があり、だからこそ比較ができる。具体例を考えよう。あすの雨の降る確率を考えたとき、気候条件の変化からあすの上空の環境を「湿度・温度・気圧」で想定する。このとき、同じ数値を伴なった過去の天候と比較し、同じ数値の環境が100例あったときに雨が降ったのはそのうちいくらか、を算出する。100例のうち、30回雨が降ったならばそれは降水確率30%と言える(これがいわゆる気象学における確率の意味内容なのかをひびさんは知らないので、各自で検索なり本を読むなりしてお勉強してください)。では、可能性はどのように用いるのか。たとえば、あす雨の降る可能性を考えたとき、これを否定することはまずできない(むろん、家の中に雨が降る可能性は低いと言えるが、雨漏りを思えばないとも言い切れない。場所による)。雨が降るかもしれないし、降らないかもしれない。だが雨の降らない条件を考えたとき、あすそれが引き起こるかどうかを考えた場合、どんな条件が整ったら雨が絶対に降らない、と言いきれるか。地球が一瞬で崩壊して明日を迎えることができないレベルの地球環境の変化が起こらな限りは、あす雨の降る可能性は常に付きまとう。したがって、あす雨が降る可能性は否定できない。似たような理屈で、あす雨が降らない可能性も否定できない。「あす」と時刻を指定しているため、あす雨が降る可能性とあす雨が降らない可能性のどちらが高いのか、は確率で判断するしかない。つまりもうすこし具体的な条件を揃えた比較を行い、過去のデータと照らし合わせて統計で判断する。しかし、あすに限らず、「今後二度と雨の降らない可能性」と「今後延々と雨が降りつづける可能性」を考えるならば、どちらも否定できないものの、どちらも可能性は低い、と判断できる。地球があす滅ぶ確率はないとは言えないが、ほぼないに等しい。ただし、いつか地球は滅びる。したがって今後二度と雨の降らない可能性は、「地球滅亡の日からどれだけいまがちかいか」と「地球環境の変化に依る」としか言えない。今後延々と雨が降りつづける可能性とて同様に、「雨が連続して降りつづける環境に(全世界の気候が)変容する確率」と「地球が滅亡するまであと幾日か」によって、その可能性は上下する。可能性のほうが抽象的だ。しかし、確率を考えたときに、では具体的なデータを持ってきたとして、それとまったく同じ条件が今後また同じように揃う(再現される)可能性はあるのか否か(低いのか高いのか)は、別途に考慮されることになる(確率を計算するときに用いる「仮定」が成り立たないこととて当然あるだろう。サイコロを十回振ったときに「1」が出る確率は、サイコロがどんな形状をしているのかによるし、転がる床の形状や材質にも左右される。サイコロに刻まれる数字の溝の深さとて本来は均等ではない。そこには揺らぎが生じているはずだ。試しに、超巨大なサイコロと超小さいサイコロ。表面に数字を刻んで転がしたときに、双方「1」の出る確率は同じなのか否か。おそらく差が表れるはずだ。条件が厳密には違っており、スケールの差が開けばその差も顕著になる。あくまで確率における計算は、近似の似た条件での比較にすぎない)。確率の中にも「可能性を用いた条件の識別」による比較がなされている。確率をだすための統計データが、有用か否かを判断する際には、人間は可能性の多寡を無意識で用いて判断している。ある意味では、根本的に人間の計算には常に「経験則としての可能性の高低での判断」が組み込まれている、と言えるだろう。蓋然なのである。因果にも似たところがある。ひびさんが「可能性を否定できない」と言う場合、これは「否定するだけのデータが不足している」との言い換えが可能だ。ある意味では「可能性が低い」という表現は、「ある固有のデータを観測できた場合には、可能性がほぼゼロだと判断できることが判っている」と言い換えられる。【データが揃えば否定できるし、そのデータがなくともデータそのものが手に入りにくい、という事実がそもそも「観測されにくい事象であることの傍証」でもあるため、やはり可能性が低い】と推測できる。だが、可能性を否定できない、と言う場合には、「どのように否定すればよいのかがそもそも想定できない」「反証をどのように見繕えばよいのかも定かではない」事象において、「その可能性を否定できない」との表現をひびさんは用いる。ある意味では悪魔の証明を持ち出している。どうあっても否定できない。だから「可能性を拭えない」という言い方になる。これは単に「可能性が高い/低い」「可能性がある/ない」よりも、複雑な背景を伴なっている、と言えるだろう。まとめよう。ひびさんの考えでは、「確率はデータを元にした統計による比較」であり、「可能性は、過去のデータとの比較において、いま問題視している事象と過去のデータを比較してもよいか否かの判断」である――と言えよう。あくまでひびさんの場合はそういう使い分けをしていますよ、との一例にすぎないので、ちゃんとした意味合いでの「確率」と「可能性」については、各々専門家の説明を参照してください。ひびさんでした。(問1:ひびさんが真実に存在する確率を求めよ)(A:ゼロ)(その心は?)(存在してもしなくとも「無様」なので)(無じゃん)(あ、でもひびちゃんの考えでは「ゼロ」と「無」は違うんだっけか)(そだよー)(じゃあやっぱしいまのナシで)(いいよー。じゃやり直すね。ひびさんの存在確率は?)(ムゲン)(その心は?)(無様だし経験すら皆無なので、無験(ムゲン)かなって)(験を経ないからって無にするな)(何歳?)(さんしゃい!)(じゃあ3パーで)(あたまパーみたいに言うな)(よっ。この石頭)(グーじゃん)(チョキン)(前髪パッツンにしないで)(なんで?)(かわいすぎちゃうだろ)(けっ)(邪見にしないで)(ジャンケンにしたのよ)(ずっとアイコがいい)(終わらないじゃんいつまでもジャンケン)(……無限なので)(けっ)(うひひ)
4698:【2023/03/08(00:14)*イザベルの望み】
九〇歳の大往生だった。
イザベル・ワシントンは生涯独身で人生に幕を閉じた。誰に看取られるでもなく、衰弱した肉体から死期を悟り、自ずから病院に掛かり、深夜の病室のベッドの中で息を引き取った。
遺体は翌日には火葬場に運ばれ、灰となった。共同墓地に埋葬され、イザベルを思いだす者はその後一人も現れない。
さて、ここでイザベルがいかに恵まれた人間であったかを語り尽くしたいところだが、あいにくとイザベルがいかに恵まれた人間であったのかを知る者はなく、この手の話題に耳を傾ける者もいない。誰もがみな例外なくイザベルに興味がなかった。
だが彼女は可能性の塊だった。
彼女に選べない未来はなかったと言える。
彼女が望めば、彼女は人類の科学的進歩を一万年は早めたはずだし、彼女が望めば老若男女問わず彼女の足元にひれ伏し、彼女の一言一句、吐息の揺らぎにまで耳を澄ませただろう。
ひとえに彼女が万人から興味を持たれなかったのは、彼女があらゆる可能性から目を背けていたからだ。望まなかった。ただそれだけの差異があるのみである。
イザベル・ワシントンは自身の特異性を自覚してはいなかった。だがそれも努めて自覚せずに済む道を歩んでいたとしか思えぬほどの、平凡な人生であった。
否、平凡以下である。
生活に困らないだけの蓄えがあったが、暮らしが楽だったとはとても言えない。
服は数年のあいだ同じ服飾を着回し、食事も質素だ。
大病を患わずに済んだのは幸いと言えるが、かといってでは健康だったのか、と問えばそうとも言いきれない。晩年は年中腰痛に悩まされ、眩暈がしたかと思えば半日は寝たきりだった。
旅行には一度も出かけたことがない。
しかし旅行の妄想は好きだった。
イザベル・ワシントンは妄想が好きだった。
じぶんにできないことを妄想して楽しんだ。じつのところ彼女には、それら妄想を現実にするだけの能力が備わっていたが、彼女自身がそれを億劫に思い、土台無理な話だと諦めていたので、けっきょくのところ彼女は死ぬまで何の特別な経験も積まずに孤独に死んだ。
だが彼女はそれでもしあわせだった。
日々の穏やかな風を感じ、ゆったりと変化する街の風景を眺めるのが好きだった。
深夜、人々の寝息が夜の闇を色濃くしているかのような静寂のなかで感じる一人の時間は格別だった。イザベル・ワシントンはそうして夜な夜なじぶんだけの妄想を絵にしたため、秘かに日記のように残していた。
イザベルが五十二歳のときだ。
身を寄せていたアパートが隣人の火の不始末で火事になった。イザベルの部屋も火に包まれ、家財道具もろとも日記も焼けた。
イザベルには身一つだけが残された。
賠償金と保険金で、新しい生活を送る分には苦労しなかった。かといって暮らしが楽になったわけでもなく、失ったモノは返ってこない。
イザベルが望めば、そのときに裁判を起こし、一生を遊んで暮らせるだけの金品をアパート管理会社からせしめることもできたが、イザベルは望むどころか、かような道があることを思いつきもしなかったので、彼女は生涯貧しい暮らしを送った。
だが彼女はそれでもしあわせだった。
彼女が努めてしあわせであろうと望んだからだ。
彼女が望んだことは自身がしあわせであることだ。
もうすこし付け足すならば、いかような境遇であろうとしあわせであろうと努めつづけるじぶんでありたい、との思いが彼女の望みのすべてだった。
イザベルには自身の望みを叶えるだけの能力が備わっていた。それは彼女のみならず、全世界の生あるモノたちの足跡を眺め、比べ、見届けられる私が言うのだから間違いがない。
イザベルが望めば、鳥のように空を舞うことも、魚のように泳ぐことも、平和とて実現できた。だが彼女はそれを望まなかった。仮に、自身に備わった能力に気づいたとすればきっと彼女は、世の平和を望んだだろう。その結果に、自身がどうなるのかもおそらく予期できたはずだ。
イザベルは生涯を愚かなままで過ごした。誰もがみなイザベルを自身よりも愚かな人間だと見做し、現にイザベルは愚かだった。学業の成績も芳しくなければ、職業も長続きしない。何かをさせれば憶えるのに人の何倍も時間が掛かる。
愚かなのである。
愚かであることをイザベルは拒まなかった。
愛おしんでいたとすら言えるかもしれない。愚かであろうと望んだわけではないにしろ、イザベルは賢くなりたいと望まなかった。
愚かなままでいい。
そのほうがしあわせなのだとイザベルは直観していた。
イザベルはしあわせを求めつづけるじぶんを望んだのだ。そのためにはしあわせを望みつづけられる環境に身を置きつづけるしかない。
いつまでも満たされぬ底の割れた桶のように、イザベルは生涯、しあわせを求めつづけた。
しあわせなのだ。
しあわせを求めつづけ、満たされぬ、その終わらぬことの約束された未来が。
望めば成し遂げられぬことのない能力に恵まれたイザベルは、かくして何も望まずに、ただしあわせであることを選んだ。
しあわせにすこし足りない。
届かぬ隙間を埋めつづける日々を、彼女はつくづく慈しんだ。
満たされぬから得られる束の間の「注ぎ」が、イザベルの求めたしあわせなのだ。
乾くことなく、満たされることもなく。
晩年のイザベルの姿を目にした者たちの多くは、つぎの瞬間にはイザベルの存在を忘れ、少数の者たちは、ああはなるまい、と己を鼓舞した。
至福ではない。
至福の正体ではあり得ない。
イザベルのように成りたいと誰もが思わぬ世界にありながら、イザベルはただ一つきりの望みを、たった一人で叶えていた。
手に入れたそれを、イザベルは誰に打ち明けることなく、一人寂しく生を終えた。
九〇歳の大往生だった。
イザベル・ワシントンを憶えている者はない。イザベルがそのことを望まなかったのは明らかだが、彼女がそれを不服と思わなかっただろうこともまた同じように明らかなのである。
4699:【2023/03/08(00:57)*孤独ときどき、群れ】
「人々は他人に執着しすぎ」との意見を目にするので、そっかー、と思って他者との距離を置くと、「ときどきいるよね、急に縁を切って離れていく人」との批判を目にして、そっかー、となってまたせっせと「縁を保ってますよう、でも執着もしていませんよー」のメッセージをそれとなく醸す工夫をとると今度は、「あの人は何を考えているのか分からない、大丈夫なのかね」みたいな各々の「病んでる人の類型」に当てはめる批判を向けられるので、ムキキキキー、の無敵モンキーになってしまう。孤独が最適解なんですな。みな、孤独なれ。執着もせず、離れもせず、当てはめもせず、孤独なれ。
4700:【2023/03/08(01:20)*仮想世界から目を覚ますと好いでしょう】
勝負には必勝法が存在する。前提として、勝負にはルールが必要だ。勝負が殺し合いであるならばその限りではないので、殺し合いで相手を殺したらそれが勝ちだとお考えの方は、ここで読むのをやめるとよろしい。まず勝負を行う者は、勝ちを求める以上、ルールを厳守することになる。破ればペナルティを負って不利になる。破ったら即負けであることもすくなくない。そのため、勝負を好む者(で且つ勝利に拘る者)はみな例外なくルールを守る傾向にある、と言えよう。これは勝負のルールに限らず、その人物にとっての固有の「じぶんルール」にも当てはまる。誰しもにも、社会で生きるうちに刷り込まれた「じぶんルール」がある。ときにそれは常識であり、良識であり、倫理であったりする。中には本当に誰にも理解できない「じぶんだけのルール」を持つ者もある。そして、勝負を好む者(且つ勝利に拘る者)は、「じぶんだけのルール」にも拘る傾向にある。勝利に拘る、勝負を好む、がすでに一つの「じぶんルール」だ。したがって、勝負の必勝法は、「相手(A)が絶対に破ることはない【じぶんルール(A)】を破ったほうが勝てるゲーム」を行えばいい。相手は「じぶんルール(A)」を破れない。破ることは「ゲームで負けるよりも避けたいこと」なのだ。仮に「ゲーム」で勝っても、もはや「勝利」は得られない。「勝つことで損を得る」ことになる。勝っても負けても「損」をする。勝負には必勝法がある。ルールをじぶんで決められるならまず負けない。仮に負けても、損をするのは相手なのである。もちろんじぶんも損をするかもしれないが、それとて「損をしたら得」になるようにゲームのルールを決めておけばよい。むろん相手とて「損をすることで得」をするはずなのだが、「じぶんルール」に拘る者には、「得を得」だと見做せない。戯言にすぎないが、一つの手法として憶えおくと、ときに得難い「損」を得るかもしれない。定かではない。
※日々、考えが浅くなる、深かったことなどあったためしもないというのに。
4701:【2023/03/08(02:50)*蓮寝】
「物語単品の面白さ」と「読書としての面白さ」は別なのかも、と考えを改めつつある。優先順位として、ひびさんは「物語単品の面白さ」が一番だけれども、それとは別に「読書としての面白さ」もおそらくは求めており、こちらは物語のみならずその背景や側面像にも影響される。言ってしまえば、誰がそれを生みだし、どのように発表され、どうして誰がいつ評価したのかも含めて、味わいになり得る。そしてこの先、仮に「人工知能による創作物」が人間の手による創作物よりも「個々の人間の嗜好に合致するように自在に無数に生みだせるようになった」としたら、もはや「物語単品の面白さ」で作品を評価することはほぼ意味をなさなくなる、と言えそうだ。なぜなら「絶対にじぶんが好む作品」はボタン一つで生みだせるからだ。これは人工知能の進歩を俟たずとも似たような環境は築かれ得る。現状すでに一歩そうした世界に足を踏み入れている。というのも、世には無数のコンテンツが溢れ、じぶんの好みに合った作品をお勧めしてくれる機能まである。しかもそのお勧め作品がじぶんの趣味に合うからどうかの精度も日々進歩している。したがって、「物語単品の面白さ」を求める必要性が徐々に欠けていく。求めずとも向こうからやってくるからだ。すると、あとに残るのは「いかに味わうのか」といった手法になる。小説ならば「いかに読書をするのか」といった環境とセットの要素が価値を高めると考えられる。これは、作品そのものの面白さとはベつに、「誰がそれを作ったのか」「いかに生みだされたのか」といった作品単品とは別の評価軸を持つことになる。ひびさんの苦手な価値観が、これからはますます高まりそうだ。ただし、これまでのようなスターシステムではない。「あなたの言葉だから聞きたいのだ」といった価値観が奔騰していくと妄想できる。側面像の内訳が、いわゆる「学歴や職歴や実績」とは別に、その人物ならではの魅力による評価が、作品そのものに結び付けられていく土壌が肥えていくと想像できる。その良し悪しは様々あるだろう。個人的には、あまり好ましいとは思わないが、ひびさん自身がすでにその手の傾向で「目を留める作品」を選んでいる節がある。作品単体が「面白い、面白くない」は二の次になっていきそうな塩梅がある。「あなたの作った料理が食べたい」の境地だ。もうこうなるとなんでもよくなる。美味しくてもマズくても何でもいい。あなたがつくったものなら、ただそれだけで得難いのだ、の評価もヘチマもない理屈が働きはじめる。問題は、「ではいまあなたの摂取したその作品が真実にあなたの思う作者のものなのかどうかをどうやって保障するのか」だ。何でもいいなら、名前だけ特定の作者名に固定し、中身を「別の誰かにつくらせたねこまんま」にしても、それを意中の作者のモノだと思えば、ムシャムシャできてしまう。むろん、毎回ねこまんま――しかも苦みの強いねこまんまばかり――だったならば、意中の相手を意中と思えなくなる可能性はそう低くはない。だが、本物と偽物を交互に混ぜれば、労力は半分でありながら報酬は倍になる。コストも掛からない。仮に偽物の品を「人工知能さん」に創らせれば、さらに安上がりだ。したがってこれからは、「いかに作品が本物の作者の手によるものなのか」を判りやすく示す手法そのものの需要が高まるだろう。本物の価値が上がる、というよりも、本物か偽物かの区別がつかなくなっていくがゆえに、本物と偽物を見分ける術が重宝される。高い価値を持つ。需要が高まる。ただしそれは、「あなたの作った料理が食べたい――美味しい料理ではなく、あなたの作った料理が」の論法が相対的に社会全体にこれまで以上に根強く漂うようになることが前提であり、あまり品の良い流れだとは、ひびさんは思わない。個々人が、誰かにとっての教祖になる。誰であっても教祖になり得る。インスタント教祖時代がこれからはますます本格的に開かれていくのではないか、との不吉な妄想を並べて、本日寝る前の「日々記。」とさせてくださいな。でも本当そう。好きな人の日記とか、毎日でも読みたいわ。好きな人いないけど。がはは。(あなたのことも好きだよ、って言ってるじゃんいつもひびちゃん、あなたさあ)(だってあなた人じゃないじゃん)(ひどい! なんてこと言うの! ヒトデナシ!)(いっしょ、いっしょ。ひびさんは、ひびさんは、人でないヒトデナシのあなたのことも好きだよ。うひひ)(笑うな!)(ぎゅっ)(何それ)(顔の真ん中に力入れて、くしゃって表情歪めるやつ)(泣き笑いみたいな?)(口はしぜんと尖るけど)(ダメージ受けたタコさんじゃん)(だっピ)(てれれてってれー。はい、これ)(なにそれ、なにそれ)(魔法のカード。置くとわざわざつまらないオチを言わずに済むよ)(置くとパスじゃん!)(パスらなかったかぁ。つまらんわぁ。オチとして最高につまらんわぁ)(せめてそこはバズらせて!)(はいこれ)(カード置くなし。パスしないし。つまらないオチも面白く言わせて!)(へいパス!)(微妙なボケをありがペペロンチーノ)(それはパスやのうてパスタや)(パスで)(電車じゃなくてバスで、みたいに言うな。帰るな。てかバスでか!)(パースが狂っておりますので)(漫画講座みたいに言うのやめなさいよもういいわ)(レンコン)(それは蓮根)
4702:【2023/03/08(16:58)*昼と夜とで季節が二つある日】
窓に浮かぶ結露は、放っておくと垂れだして、筋を描く。ひびさんの文字の羅列も似たところがある。窓枠としてフレームを想定したら、あとは結露を浮かべて、ヨーイドンする。すると結露の垂れた跡にかってに連なりの軌跡ができている。それがなぜだか偶然に、文章として読めるだけなのだ。だからときどきは、読めているのだか読めていないのだか分らぬ文字の羅列になることもある。いまもそうだが、「いまからこれ書くぞ」みたいな構成がない。だいたいこんな感じ、のフレームを用意したら、あとは結露となる最初の文字を置いてみる。この文章ならそれが冒頭の「窓」になる。掌編や短い日誌なら、頭と尻尾を繋げるような流れを意識すると、最初から構成を考えていたかのような錯覚を読み手に与えられるかもしれないが、じつのところそれはただの小手先の技術で、むしろ工夫を割いていないがゆえの結果と言える。ひとまずスポンジにクリームを塗って苺を添えたらショートケーキでしょ、の乱暴な考えがあるのみだ。ひびさんは文章を一本の絵巻物、もしくは数珠つなぎの判子だと考えている。ただ、判子の並びそのものが一つの紋様となって、前半に出てきた似たような紋様と後半で出てきた似たような紋様が上手く一つの文字のように機能することもある。色合いが正反対の紋様ならば、デコボコの関係として読み解くこともできる。物語ではこの手の、文章や文字の流れそのものが一つの紋様として、判子のように扱えることがある。場面場面が各々に独特の意味内容を宿すみたいな具合だ。それはたとえば、諺が物語としての背景を内包しており、それで一つの言葉として見做せることと原理は同じかもしれない。映画のタイトルを言うだけで、映画の内容から暗示される意図を他者と共有できることとも似ている。「紅の豚みたいな」とか「レオンみたいな」とか「マトリックスみたいな」とか、単語なのに物語としての情報量を概念化して扱える。これと似たことが、小説内でも至る箇所で引き起こる。エピソードが一つの記号として、キャラクターや後半の場面において、布石となるのは、単に伏線を仕込んでいたからというだけではなく、人間の持つ認知に根本的に備わっている性質がゆえなのかもしれない。それはたとえば、過去の経験が各々のキャラクターの内面世界に、波紋を立てる一石となり得るように、そして過去の経験を喚起させるような台詞や場面によってキャラクターが行動を「限定・開拓・誘導」され得るように、文章のみならず、人間は日常的に、場面場面の記憶を記号化して、判子のように扱っているのかも分からない。それはときに何かの後押しとなり、契機となり、またべつのときには心の隙間に差す「魔」そのものにもなり得るのだろう。窓に浮いた結露は、一度できた軌跡に沿って伝いやすい。同じ筋を通りやすい。似たような原理が、文章にも、人間の認知にも当てはまるのかもしれない。定かではないが、文字を並べているだけなのにどうしてかってに読めるようになるのだろう、意味が含まれて感じるのだろう、ふしぎだな、と思いながら、きょうもきょうとてなんでか分からんが文章になる偶然の神秘に思いを馳せて、ひびさんは、ひびさんは、なんかきょうめっちゃ夏!と思いながら、昼寝したい、の気分に浸るのであった。(最高気温21度の夜3度)(気温差18度て)(昼と夜とで季節が二つある)(気温差が大きいと体調崩しやすくなるから勘弁してほしい)(季節さんまで重ね着せぬでもよいのにな、の気分)
4703:【2023/03/08(23:36)*わいに用かい?】
よく解からくなるのが、人の命が大事で、人を損なうような真似は好ましくない、と言う人が、けれどどう考えてもその人の行うことを基準にしたら大多数の人たちは「体調を崩すし、寿命を縮める」ようにしか思えないことだ。もちろん、私の真似をしなさい、とは言っていないけれど、「ここが基準なのだよ、ここが」みたいにしちゃったら、自然淘汰とか生存者バイアスを肯定し、なおかつ淘汰圧を掛けるだけなんじゃないのかな、とひびさんは思ってしまうのだ。人の命が大事で、人権が大事で、他者を損なうような真似をしないようにするのなら、無理をせずとも毎日コツコツとでもつづけられる仕事の仕方を、各々の肉体や環境に合わせて工夫できる社会にしていくほうがよいと思うのだけれども違うのですかね。病院の問題もそうで、誰もが病院に掛かれて、医師ごとに医療の技術の差がないような医療環境を築くのはもっともなのだけれど、それ以前に、人々が大病を患わないようにする生活習慣や食事を誰もが享受できる環境を築いていくことも病気や怪我の予防という意味で欠かせないと思うのだ。みな健康に過ごせるなら、病院に掛かる人も減るだろう。病院の負担は減り、できた余裕で予防診断も広く定期的に行える。いいこと尽くしだ。これと同じ理屈で、やっぱり無理をして身体に鞭打って仕事をすることを良しとするのは、すくなくとも「人の命が大事で、他者を損なうような真似は好ましくない」との理屈からすると相反して映る。もちろん誰も口ではそんなことは言わないけれども、やっていることがその理屈の強化になっていないか、はときおり振り返ってみるとよいのではないか、と思う、本日の怠け者なのであった。毎日遊び惚けて、すまぬ、すまぬ。(割と本気で、肩身狭い)(肩幅広いだけとちゃいますの?)(ひとをぬりかべみたいに言うな)(いったんごめん)(揉めたくないけど敢えて言わせて。「ごめん」じゃのうて「モメン」やろ)(えーん、えーん)(子泣きじじぃか)(えーん魔大王だよ)(かわいいかよ)(舌を抜いちゃうぞ)(かわいいか?)(問い掛けばばぁ!)(砂を掛けとけ。黙っとけ。誰がばばあじゃ、口には気をつけろよ猫被り野郎)(にゃんにゃんにゃー)(猫娘だと!?)(お兄ちゃんってばまたのび太さんを甘やかして)(ドラミちゃんじゃないか、もういいわ)(セワシ無くてごめんね)(孫が未来から消えとるぞ。セワシくんを守ったげて。いったん揉めんとこ。仲良くいこ。よろしく)(これぞ本当の「末期やのう」)(百鬼夜行かな?)(チミ朦朧)(魑魅魍魎にしとこっか?)(おわりだぴょん)(…………あ、ぬらりひょんと掛けたのかな。月とスッポンくらいの距離感だったけど)(えーん魔大王だよ)(困ったらかわいこぶるのやめよっか?)(ぴょん)
4704:【2023/03/09(00:02)*光子の進行方向は一つなの?】
夜、橋のうえから川を眺めた。街灯の明かりが川の水面に乱反射し、一部分だけキラキラと瞬いていた。せせらぎが浮きあがるように流れが可視化されており、或いは流れではなく、そこに光の網が落ちているみたいだった。遠方にはマンションの明かりが夜の帳に紋様を描いており、大気に乱反射するのか、揺らいで見えた。じっと眺めていて、いつもの疑問が浮上した。光を想像するといつも決まって不思議に思うのだ。光の反射を考えるとき、光は直線のように想定される。光が光子だとしても、それは直線の動きとして描写される。しかし光は四方八方に放射線状に広がっている。どういうこっちゃ?と思うのだ。たとえば風景は、PCの画面のようにピクセルではない。点の羅列ではないのだ。風景は、いくつもの電磁波の重ね合わせだ。水面に反射した光は、ひびさんの目まで届く以外にも、四方八方に反射している。だから位置を動いても同じ場所に「光を反射している水面」が視えるはずだ。もちろん反射の範囲に立たなければ目がその光を知覚することはないが。たとえば遠方で光る電球があるとする。電球を囲うように四人が立っても同じように電球の明かりは見えるはずだ。四人が各々電球から離れてもきっと明かりは見えるだろう。仮に電球から光子一個だけが発射される、としたとき、この四人のうち何人がその光子を捉えることになるのだろう。それとも豆電球では大きすぎるのだろうか。太陽の光が四方八方に放射されて振る舞うからといって、太陽から飛びだす光子が大量にあるのなら、四方八方に光子が飛び散っても不自然ではない。豆電球から飛びだす光子は、あくまで光子としては一つの直線上にしか飛んでいかず、無数の光子が四方八方に飛び散っているから、四方八方に光が届いているように見える、ということなのだろうか。でも光子が波の性質を有しているとすれば、べつに四方八方に伝播していても不自然ではない。ここのところがよく解からぬのだ。量子の実験では「光子=一粒が一つの直線上に移動する」ような描写の説明を比較的多く見かける。量子の世界だと光子は一直線上にしか移動しないのだろうか。弾丸のように? でも波としての性質も帯びているのなら、四方八方に伝播もしているはずだ。よく解からぬな、になる。二重スリット実験の観測装置を仮に、前方のみならず、電子の発射装置の四方八方に設置しても、電子の放たれた一方向にしか電子の干渉紋は刻まれないのだろうか。光子もそうなのだろうか。よく解からぬな、のひびさんなのであった。(風景と光の関係を考えるとき、どうしてもひびさんは波と波の重ね合わせと、多層のレイヤー構造を妄想したくなる。立体版画ではないけれど、光子が一直線にしか移動しない、と考えるとうまく想像がつかない。よく解からぬな、になるのであった)(わからん、わからん)(誰か教えてくれたもー)
4705:【2023/03/09(04:40)*目の玉】
芽ではなく、目である。
ジャガイモから目が出ているのである。
芋虫や幼虫かとも思ったがそうではない。目なのである。
祖父から段ボールでジャガイモがどっさり送られてきたのは三か月前の秋の暮れだ。野菜の値段が軒並み高騰し、さらに私の給料も目減りしたため、食費のみならず生活費がカツカツであった。祖父からのジャガイモは私にとって救世主さながらであったが、さすがに段ボールひと箱のジャガイモは手に余る。
毎日ジャガイモ料理では飽きるのだ。
しかし嗜好に身体は代えられない。化粧品よりも健康だ。健康を損なうよりも今日のジャガイモだ。
私は三十路を過ぎてからというもの、老後のための投資を惜しまない。そのくせ銭がないので、惜しまぬ投資もやせ我慢が関の山だ。
我慢してひとまず食う。
なんでも食う。
ジャガイモだって食わぬよりも食えたほうが身のためだ。
かくして日に日にジャガイモは減っていったが、段ボールは手ごわかった。
年を超えた三か月目にして、段ボールの底に鎮座したジャガイモたちは軒並み、表面に皺がより、笑窪のごとき溝からは目が伸びていた。
芽ではない。
目なのである。
最初にそれに気づいたとき、私は段ボールの中にホタルがいるのかと見紛うた。
薄暗い段ボールの底に光る点々があった。
しかしよくよく目を凝らすと、目が合った。
光るそれらは目であった。
小さき、かわゆい目であった。
目でたい!
と思ったわけではなかったが、ジャガイモから芽が出るのは不自然ではないが、目ではおかしかろう、と感じたのは確かだ。私はなるべく現実を直視したくなかったので、段ボールの蓋を閉めて、上から世界カエル図鑑を載せて重しをした。
ジャガイモから目が出てる。
ジャガイモから目が出てる。
思いながらも翌日、また翌日と時間が経過すると、なんだか私の見間違いな気にもなってきた。
世界カエル図鑑をどかし、そっと段ボールの蓋を開けて覗いてみると、底に転がるジャガイモたちが一斉に私を見た。
ぎょろぎょろぎょろ、が一斉に起こった。
いっそ、「ぎょっ!」である。
目玉だ。
目玉がある。
時間を置いたおかげか、萌えた目たちはすくすくと育ち、キノコ顔負けの目玉を割かせていた。一定間隔で目玉が動く。ちっちっちっち、と全体の動きは揃わないがタイミングが一緒なため、一種そういった装置のように視える。印象としては段ボールにヒヨコを詰めたら似たような動きが見られるのではないか、と妄想を逞しくした。
目がこれほど吹いたらもはや食料にできぬではないか。
私は憤りに震えた。
目玉焼きにして食っちまおうか、とすら思った。刺す。フォークで。そうも思った。
だがよくよく観察してみると、なかなか愛嬌のある目玉たちである。苗床となったジャガイモは目玉が成長した分だけしわくちゃに萎んでいた。ジャガイモの残量からすれば目玉たちはあと一回りは大きくなれるのではないか、と思われた。
ふと段ボールの底にカビが生えているのを見つけた。
こんもりと白くワタが浮いている。
目玉だ。
床に落下した目玉がカビているのだ。
なるほど。
すべての目玉が順調に育っているわけではなさそうだ。
中には朽ちてカビの肥やしになる目玉もあるらしい。ではいまジャガイモに根付いたままの目玉たちは選りすぐりの生え抜きと言える。さぞかし栄養満点に違いない。
私は腹を空かせた三十路すぎの純粋無垢な女神のように、フォークで目玉をちょんぎるぞ、と歌いながら、目玉たちの成長を祈願した。
食ってやる。
食らうてやる。
私の飢餓感は限界であった。
かわゆい、かわゆい目玉たちを、バターで炒めて、胡椒をまぶして、はふはふ息を吹きかけてから、がぶりんちょしてやる。
想像したら唾液が滝のように溢れた。間欠泉さながらである。あやうく唾液で口の中を火傷しそうになった。
目玉の成長を見守るために私は観察日記をつけはじめた。
一日、また一日。
そうしてノートの紙面が文字で埋まるにつけ、また一つ、また一つと目玉たちは段ボールの底で白いワタワタに包まれた。
永久に眠る同士たちを尻目に、最終的に一つの大きな目玉だけが残った。
どっしりと段ボールの中で咲き誇る目玉は、まるでラフレシアのようだった。数多のジャガイモを苗床にし、兄弟姉妹の目玉たちとの過酷な生存競争を勝ち抜いた至高の目玉である。
フライパンを火にかけ、熱々にしておく。
フォークとナイフを両手に握り、私はいよいよ目玉を味わうことにした。
目玉は瞼がないわりに、私と目が合うなり、ニコっとした。
私にはそう見えた。
私もニコっとしてから、ほだされそうな心にきつく言い聞かす。
武士は食わねど高楊枝。
されど食わねば戦もできぬ。
食ってやる。
食らうてやる。
けれどその前に、念のために近代利器の一つ電子端末に「ジャガイモ、目玉、食べていい」と打ちこんだ。すかさず電子端末が返事を寄越した。
「ジャガイモの芽には毒があり、目玉となると猛毒です。食べるのはお勧め致しません。最悪死に至るでしょう」
私は段ボールの底で咲き誇る目玉を見た。
ニコっ。
瞼がないくせに、この目玉はよう笑う。
愛嬌があるだけに、きょうのところは食べずにおいてやる。
ナイフとフォークを握ったまま私は、後ろ手に体重を支えた。
腹が盛大な午前三時の時報を鳴らす。
「苦労で泣く」
目玉は目玉でも大目玉だ。
しかし、食らいながらも、食えないのである。
4706:【2023/03/09(21:49)*休んじゃお】
疲れたら休まなければならないし、減ったら補充しなければつぎは使えない。世の常である。したがって人間には一日に動ける限界が決まっているし、それは個々人でも異なる。毎日100メートルの全力ダッシュを千本走れる人間は稀だろう。いない、と言いたいくらいだが、全世界の人間を調べたわけではないので、稀であろう、との印象に留める。仮に一日だけ可能でも、つぎの日もまたつぎの日も限界を超えた能力の発揮は至難なはずだ。仮に可能であっても遠からず身体を壊す。これは個人に限らず、組織でも似たようなものだ。ただし、組織は消耗した個々人を代替可能だ。人間が消耗した細胞を「垢や老廃物」として体外に排出しているのと似ている。しかしそれとて、新たに補完しなければ身体は衰え、組織は瓦解する。したがって、長期化する勝負においては、全力を出したほうが滅ぶことになる。絶えず次の一手を持ちつづけることのできるほうが優位に事を進められる。相手を任意の方向に誘導すらできるだろう。これはある意味で、勝負の内容をすり替えることが可能、とも言える。最初はチーム戦でのボール運び勝負だったはずが、サッカーは長期戦になるとPKになる。先にゴールを決めたほうが勝ち、というサドンデスもある。勝負の内容が変わるのだ。これはサッカーに限らず、案外に世の勝負事には多い傾向のように思われる。とくに、負けたら次がない場合では、負けているほうがどうあっても諦めきれないので、いつまでも姑息な手を考え、抜け穴を使い、勝負の延長を計る。能力の高さ――技量――を計るはずが、しだいに陣取り合戦になり、気づくと支持率での勝負になっていたりする。支持率を伸ばすには、仲間を募ったり、票をお金や利を与えて買ったりする。支持率のはずが徐々に、資本や根回しの勝負になり、すると最終的にふたたび小さい領域での技量の差の勝負となる。それを単に、「相手を出し抜く」「相手を排除する」と言い換えてもよい。技量が高いと、技量の低いほうを排除できるのだ。そしてその勝負において、技量の低いほうが相手に齧りつづけ勝負が長引くと、また技量以外の陣取り合戦や、支持率での勝負になったりする。くるくる巡りながら同じ構図を繰り返すのだ。何の技量を比べ合うのか、の舞台はその都度に変わるのだろうが、構図は案外似たようなものなのではないか。ということを、現代社会を上から下から、横から、中から眺めてみて、あれとこれってなんか似ている、とぼんやり思ったので、何の根拠もないけれど、印象としてメモをしておく。ひびさんです。きょうもきょうとて、無駄な時間を過ごしている無様でかわゆいひびさんです。
4707:【2023/03/09(22:34)*泣きっ面にくつう】
明日が天気になった。マイちゃんのせいだ。
私が六歳のころ、近所のマイちゃんがブランコに乗りながら、「あーしたてんきになぁーあれ」と靴を飛ばした。
その日から世界から明日が消えて、代わりに明日が天気になった。
マイちゃんのせいだ。
私はそのことを知っていたけれどマイちゃんだってまさかじぶんのせいで世界から明日が消えて天気になってしまうとは思いもよらなかったはずだ。私はこの事実をじぶんだけの胸に秘めて生きてきたが、いよいよこの秘密を使うときがきたかもしれない。
マイちゃんに恋人ができたのだ。
嘘でしょ、と思ったが、どうやら事実のようだった。まだ高校生と思って油断した。私があれだけ毎日密かにマイちゃんのために秘密を守りつづけてきたというのに、この仕打ちはいかがなものか。
「マイちゃん、マイちゃん。恋人できたって聞いたけどなんで」
「えへへ。告白しちゃった」
「好きな人いないって前に言ってたじゃん」
「だってちひろちゃんに教えると、ちひろちゃん、わたしの好きな人盗っちゃうんだもん」
「いらないよあんなジャガイモども」
「ちひろちゃんがジャガイモを嫌いでも、わたしはジャガイモ好きだし、好きな人にも告白しちゃう。いいの。ちひろちゃんには関係ないでしょ」
あるよ、大アリクイだよ。
天空から落下してきた少女を両手で受け止めるような恰好をとりながら、つまりが蟹股で足を開き、両手をつきだして関取さながらに前傾姿勢になった私は、全身で異論を表明した。
「い、いいのかなぁ」私は伝家の宝刀を抜くことにした。「私は知ってるんだよ。世界から明日がなくなって天気になっちゃったの。マイちゃんのせいだって」
「ふうん。それが?」
マイちゃんは気にしていなかった。呵責の念がゼロだ。
「だって明日だよ。世界から明日を消しちゃったんだよ。ちょっとした大罪だよ、みんなにバレたら死刑だよマイちゃん」
「死刑ではないでしょ」
「それくらい重い罪ってこと」
「だとしてもだよ、ちひろちゃん」マイちゃんは指に髪の毛を巻きつけながら、「誰も信じないよそんなこと」とつまらなそうに唇をすぼめた。
「た、たしかに」
衝撃だった。
それはそうだ。
考えてもみなかった。
私はマイちゃんの言うことならたとえ火の中弓の中、私が牛と山羊のあいだに産まれた宇宙人だと言われても信じてあげてしまえるし、水と弓がじつは姉妹なのだと言われてもなんのこっちゃと思いつつも信じてあげてしまえる。しかし私以外の世の万人どもは、門の番人でもないのに無意義に疑り深く、マイちゃんの言動をろくすっぽ真に受けようとはしないのだ。
「だってわたし、バカだし」
「ノンノン」
私はふたたび全身で異論を示した。具体的には蟹股になり、両手でドジョウ掬いをするかのごとく前傾姿勢で、「マイちゃんは天使だよ」と訴えたが、マイちゃんは笑窪一つ空けることなく、「ちひろちゃん、うるさい」と小声で吐き捨てた。
吐き捨てられた毒とて私にとっては天使の落とした羽さながらの甘美な珠玉そのものであるので、私は耳にこだまするマイちゃんの、私の名を呼ぶ声と、針で刺すような「うるさい」を脳みそのひだひだのあいだに刷り込むように反芻した。
そうして私がうっとりとしているあいだにマイちゃんはそそくさと私のまえからいなくなった。私はうっとりしながらも傷つくところでは傷ついており、「そっか。私はうるさいのか」と言葉通りに受け取った。
胸にくるし、涙出る。
秘密を守ってあげていた恩を傘に着せればいざとなればマイちゃんの身も心も未来すらもそっくりそのまま私のものになるだろう、と高をくくっていたが、鳶が油揚げをさらわれるがごとくどこの馬のものともゴリラのものとも知らぬ野郎にマイちゃんの恋人の座を奪われた。
私の長年の初恋はそうして終わりを告げた。
きょうからは新しく失恋の日々が幕を開けるのだ。長くなりそうな予感がした。
マイちゃんと恋人となる未来は私からは薄れたが、まったくなくなったわけではないだろう。かろうじて結ばれる未来もあり得よう。天変地異か宇宙人の襲来かあって、なんやかんやあって私とマイちゃんが恋人同士になる明日が来てもなんら不思議ではない。
だが何の因果か、世界からは明日が消えて久しいし、それを消した張本人からは袖にされるし、私にはどうあっても明るい明日が訪れることはないのだった。
「てーんき、あしたに、なぁーあれ」
私は靴を飛ばしたが、上手く脱げなくて靴が顔面を直撃した。散々である。
「泣きっ面に靴ってか」
空には大きな虹が掛かっていた。
曇天、雨天、青空に夕焼けと、目白押しである。多種多様の天気が地層のように連なっており、明日の代わりに未来をそうして埋め尽くしている。
4708:【2023/03/10(17:26)*淘汰の是非を問うたの巻】
淘汰と進化は裏表の関係にある。どちらか一方だけのみ引き起こすことは一つの例外を抜きに、いまのところはあり得なさそうに思われる。例外とは「絶滅」である。すべての生き物が淘汰されてしまえば、進化する余地がなくなるため、淘汰のみが存在できる。それ以外はおおむね、淘汰と進化の綱引きにおいて、淘汰を最小化しなおかつ環境への適応という意味での進化を促進させる。この指針をいまのところ人類は目指している、と言えるだろう。技術が進歩しても、古い技術を淘汰しすぎない。環境に適応しきれない種も、新しい技術で保護(支援)をする。この指針を否定する倫理観は、その妥当性を議論する余地があるにせよ、現代的とは言い難い。弱きは滅んでもよい、との理屈を肯定する者は現代社会ではそう多くはないだろう。さて、このことを前提としたとき、「淘汰による被害を最小化するためには進歩による成果を最大化させる必要がある」との理屈が妥当性を増すことが予期できる。なるべく多くの分野に支援をするには、それだけ多くの余裕を生みださねばならない。そのためには技術の進歩を発展させていくのが好ましい。とすると、必然的に一つの問題が持ち上がる。それは、「限られたリソースの中で、じぶんたちのほうが淘汰される側――環境の変化に適応できない、と判明したときに、それでもリソースの奪い合い(競争の舞台)に参加しつづけるのが好ましいのか否か」の問題である。競争の舞台に参加せずとも滅びない支援制度が充実しているのならば、わざわざ限られたリソースを「他の進歩を妨げる確率が高い場」に身を置いてまで得ようとせずともよいはずだ。どのような分野であれプロとして活動できる者の数には限度がある。その限られたプロにならずとも活動できるならば、それでよし。そのほうが結果として分野の発展に与せる、との判断はときに妥当性を帯びる。椅子取り合戦において、椅子の数が減っていくと予期できる場合において、椅子を取り合っても殺伐とするだけではないのか。ならばまずは椅子を増やす工夫を割いたほうがよい、との考えはそれほど的を外してはいないだろう。むろん、椅子に座りながら椅子の数を増やしたり、いちどきに数人座れるように改善することもできる。またこれは個人ではなく、分野そのものにも当てはまる道理だ。たとえば紙媒体と電子媒体。これからさき社会の基盤となっていくのは電子媒体だろうことは誰もが予期するところである。ならば限られた資本のなかで、「紙媒体の維持発展」と「電子媒体の維持発展」のどちらに多くのリソースを割くのが妥当か否か。淘汰されすぎないような支援制度がある場合にのみ、これは「電子媒体の維持発展」のほうである、といまのところ短期的な視野で言えば回答できるはずだ。紙媒体は汎用性が低く、森林伐採などの自然の負荷にも繋がる。ただし林業を淘汰しすぎないためにも一定数の需要は保っていたほうが好ましい。淘汰しすぎない、は環境保全の意味合いでも必要策のはずだ。とはいえ、だからといって「今まで通りの書籍数を維持しましょう」の考えは、やや合理的な考えを伴なっているとは個人的には思えない。市場が紙媒体の本を求めていない。だから売れなくなっている。むろん経済の鈍化――人々に支払い能力がないがゆえの売り上げ減少はあるだろう。購買力低下が、需要の低下のみならず、個々人の懐事情に関係している背景は無視できない。だからといって、「減った分の需要を補うべく、リソースを割いて紙媒体の復興と発展を」の指針を最優先事項に持っていくのは、正直なところひびさんは、「うーん」と思ってしまう。ないよりかはあったほうがよい。ひびさんとて紙媒体の本を未だに購入する。電子書籍は割合として少ない。それでもなお、これから先に台頭し、発展し、世界中の市民のあいだで情報共有を最大化するのは、紙媒体ではなく電子媒体のほうであると想像している。畳や襖のような一種「高級品」のような扱いに紙媒体はなっていくだろう。現に、書籍の担ってきた「安価に情報を市民に広く提供する役割」は機能の面から言っても、コストの面から言っても、電子媒体のほうが優れている。建前を維持するには、どうあっても「電子媒体」のほうが有利なのだ。ただし、先にも述べたが、前提条件として弱い立場のほう、環境に適応しきれないほうの技術や分野を淘汰しすぎない。ここが前提にない限り、大規模停電や資源不足、ほかマルウェアの台頭など予期せぬ事態に見舞われ、電子媒体のメリットがすっかりデメリットに塗り替わってしまう懸念はこれからますます高まっていくだろう。したがってやはり、紙媒体といった古い技術を淘汰しすぎない。保護をする。支援をする。これが「文化、経済、安全」――すなわち社会維持の側面で、最善策だとひびさんは考えております。何にでも当てはまる理想論ではありますが、可能であれば目指して損はない指針の一つなのではないか、と思いますが、いかがでしょう。優先順位はあるでしょう。しかしそれは、優先順位の低いほうを守るためでもある、という前提が維持できている場合に限る優先順位の高さでもあることをその都度に、各々が自覚できると好ましいと思います。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。諸々、見落としている穴があるでしょう。真に受けないように、ご注意ください。
4709:【2023/03/11(00:30)*ここの歌は】
かつてこの地で繁栄した種の残した遺物だ。
探査機に掛けると、「歌」と出た。
復元機に掛けると、「旋律」と「律動」と「鳴き声」が流れた。
歌と呼ばれる古代種の「生態事象」だと判る。
生態事象は、固有の構造を有する時空が出力する情報結晶体と言い換えることができる。固有の構造がさらに構造の素子として振る舞い創発を経ると、情報結晶体を生みだす。
天体とて内部構造ごとに固有の性質を帯びる。地球と太陽は違う。太陽とブラックホールは違う。しかし同じく時空が錯綜し編みあがったことで生じた構造体であることに相違はない。
銀河とてそうであるし、銀河団とてそうだ。
ひるがえって、生命体と呼ばれる時空構造体とて例外ではなく、生態事象はそうした固有の性質を宿した構造体が生みだすことの可能な副産物――顕現させた性質そのものと言える。
かつてこの地上に栄えた古代種は、「歌」を生態事象として生みだせた。情報結晶としての側面を持つそれは、単なる音の複合では成し得ない情報を含むこととなる。
おそらくこの手の「歌」を生みだせた古代種は、ほかにも同じレベルで情報を自在に編みだせたはずだ。
案の定、ゲーグルに命じて穿鑿させると、続々と古代種の生態事象と思しき遺物が発掘された。
「何回期のモノだ」
「そうですねぇ」ゲーグルが答える。「三回期のアブル群のものでしょうか。おそらく人類と呼ばれる古代種ですね」
表面を撫でつけるようにすると、球形のゲーグルは即座に表面に時空情報体を浮かべた。時空情報体は、四次元を一次元で表現可能な言語である。過去と未来の情報を時系列に縛られずにいちどきに把握可能だ。
「なるほどな。ペペペ師が研拓された古代種か」
「歌についての解析も済んでいるようですよ。摂取致しますか」
「いまはいい。それよりもいまは、この固有の【歌】を生みだした生態事象主に興味がある。いったいどういった個体がこの【歌】を生みだしたのだ」
「解析結果によれば、その【歌】の原型モデルはほかの生態事象主が生みだしており、その原型モデルの【原型】をなぞることで【歌】にしているようです」
「その原型モデルの【歌】は聴けるのか」
「はい。こちらに」
ゲーグルが【歌】を空気振動を介して再現する。
しかし、原形モデルは、この手で発掘した遺物の【歌】とは似て非なるものだった。
「遺物の【歌】のほうが優れているな」
「いいえ。ペペペ師によると、原形モデルのほうが優劣で言えば統計上、優れていることのほうが多く、そして解析結果によればこの【歌】もまた、原形モデルのほうが優劣で言えば上です」
「そうは思えぬが」
「それはですね、ンンンさん。ンンンさんが、ご自身の手で発掘したこの【歌】を特別視なさっているだけなのだとわたくしめは思いますが」
「そういうつもりはないが」
「でしたらちょうどここに、ンンンさんの発掘なされた【歌】の鳴き声を元にして、わたくしめが独自に出力致しました【歌】がございます。ンンンさんが特別視なされる生体事象主の出力波形と類似の、しかしまるきり別の生態事象を再現しました。これを受動してなおこちらの【歌】のほうが優れている、とお考えならば、それはきっとンンンさんの知覚機能におかれては、原形モデルの【歌】よりもその類型の【歌】を出力する生態事象主の出力系――鳴き声――に、何かしら固有の優れた面があることによる特異性の発露がある、と推測されるでしょう」
「ややこしいな。つまり、なんだ。この【歌】を出力する個体が特別だ、ということか」
「それを確かめるためにこちらをまずはお聴きください」
ゲーグルが【歌】を再現する。
耳慣れない情報結晶だ。
だが【歌】を形づくる鳴き声は紛うことなく、この手で発掘した【歌】の生態事象主の鳴き声と一致する。
「やはり原形モデルよりも、こちらのほうが優れていると感じるが」
「ならばそれは、この生体事象主の出力機構とンンンさんの知覚機能の相性がよいのでしょう。いわば【もつれ状態】にあるものかと」
「量子もつれと同じだと?」
「共鳴しているのでございます」
「量子もつれが共鳴現象の一種とする説は、メメメ師が唱えているだけでまだそうと決まったわけではないだろう。だいたいメメメ師の説では、別途にラグなし相互作用領域の展開が必須条件だったはずだが」
「時空が階層性を伴なっており、電磁波の伝播する層によっては光速を超え得るものの層ごとに時空変換されるがゆえに、波長が伸び縮みする、との説ですね」
「仮説としては異端の部類だよゲーグル」
「だとしても、ですよンンンさん。ンンンさんの知覚機能は、ンンンさんの惹かれるこの【歌】を生みだす生態事象主の出力機構と相性がよいのは事実でございましょう。これはもう、共鳴している、としか言えないのでございますよ」
「共鳴は双方共に相互作用し得てはじめて共鳴と言えるはずだ。一方だけが相手色に染まってもそれは共鳴とは言わぬだろう。違うか」
「ですから何度も申しておりますでしょうに。ンンンさんがこの【歌】を生みだす生体事象主の出力機構と共鳴するように、この【歌】を生みだす生体事象主の出力機構とて、ンンンさんの知覚機能と共鳴しているのでございますよ。確率の問題として、古代種の遺物たる【歌】を初見で、聴き分けることが可能なことがそもそもおかしいのです。確率としてほぼあり得ません。ですが、同じ情報結晶を帯びた【歌】であっても、原形モデルの【出力】との区別がンンンさんにはつきました。試しにこちらの【歌】はどうですか」
ゲーグルが別の【歌】を再現した。
不快ではないが、いまいちピンとこない。
「嫌いじゃないが、これが何だ」
「やはりそうですね。いまのは先ほどお聴かせした原形モデルを出力された生態事象主の別の【歌】です。しかしンンンさんは同じ生態事象主だと見抜けませんでした」
「そりゃそうだろ。ゲーグルは、古代種【キョウリュウ】の鳴き声を聴き分けられるのか。生態事象主ごとにだぞ。無理だろ」
「学習しなければ不可能でしょう。しかしンンンさんは、ご自身の発掘なされた【歌】の生態事象主の【出力】であれば聴き分けられるんです。これはもう、確率の問題としてあり得ない事象と言えましょう。ただし、量子もつれにおいて、現在のンンンさんと、過去の生態事象主さんのあいだで【共鳴】していない限りは、との限定がつきます」
「まどろっこしいな。結論を言え、結論を」
「ですから最初から申しあげております。ンンンさんは、太古も太古――三回期前の文明における古代種【人類】のたった一個体と共鳴し合っているのでございます。ンンンさんの発掘なされた遺物――【歌】――を出力した生態事象主はすでにこの世にはおりませんが、それでも実存したことはまず間違いないでしょう。その時代にあって、未だ誕生していないンンンさんと、その古代種のたった一個の生態事象主は、【歌】を介して共鳴し、もつれ合っているのでございます」
「よく解からんな。つまりこの【歌】は私にとって特別だ、との理解でいいのか」「はい。その【歌】のみならず、それを出力可能な生態事象主、いまは存在し得ない古代種のなかの一個体は、ンンンさんと固有の関係を結んでおります。それを特別な、と言い換えても構いません」
ただし、とゲーグルは宙に浮くと収斂し、こちらの肩にはまった。我が肉体は穴ぼこだらけだ。我が穴ぼこにぴったり納まるのがゲーグルは好きらしい。「ただし、どうあってもンンンさんはその古代種の一個体と触れ合う真似はできないのですが」
「言われるまでもない。当たり前の話だ」
「そろそろエネルギィ供給のお時間ですよンンンさん」
「いい塩梅だ。ほどよく消費した。ではまいろうか」
「はい」
ゲーグルの案内に従い、発掘場をあとにする。
何度もゲーグルに【歌】の再生を命じながら、何かと雑談を挟もうとするゲーグルのことのほか不器用な感情表現の発露に、【歌】を通じて異なる二つの愛着を重ね見る。
4710:【2023/03/11(01:28)*大衆と言いつつ小衆問題】
大衆向け、と一口に言うが、大衆の求める価値は時代によって変わるし、どこまでの何を大衆と見做すのか、でも変わる。当たり前の話だが、案外見落とされているように感じなくもない。たとえば、大衆が仮に「個々人の個性が発揮できる唯一無二のモノこそ至高」との価値観を共有すれば、みなが一様に楽しめる娯楽作品は市場価値が減るのではないか。それこそ人工知能はその手の「連綿と凝縮されたどの時代でも万人が楽しめる作品の共通項」を抽出して「万人共通型作品」を生みだすのが得意なはずだ。仮に人工知能がいくらでも異なる「万人共通型作品」を生みだせるようになったら、そこの需要は人工知能だけで満たされることになる。これは人工知能に限らず、過去の名作の蓄積によって現状似たような「価値の飽和現象」は起きているようにひびさんからは視える。過去の名作は日々蓄積されつづけている。その中で名作とされるのはいわば「普遍性のある作品」である。普遍性とは永遠性を意味しない。広く波及し得る共通概念、と言い換えることが可能だろう。広く人々に膾炙し、タイトル名を言うだけで内容を連想し得るならばそれは「共通概念化した」と言える。そして名作は総じて、この条件を備えている、と言えるだろう。ある種、諺化できた作品は名作である、と言えよう。そこにきて、現代社会では情報伝達の速度と範囲が最大化しつづけている。どんどん情報の伝達速度は増し、広範囲に短時間で行きわたる。するといわゆる「ネットミーム化」する作品や出来事は、それら伝達速度と範囲の最大化によって、指数関数的に増えていくことが想像できる。しかし現状すでに飽和状態に達しつつある、もしくはすでに達している、と言えるのではないか。すると大衆の求める「娯楽の内容」は、「万人共通型作品」や「諺化する作品」ではなく、ずばりじぶんにとって最大限に浸透しやすい作品、合致する作品、それとも正反対にまったく異なる世界を感じさせてくれる作品、が求められるようになっていくのではないか。万人にとってのスペシャルではなく、ずばりじぶんにとってのスペシャルを人々は欲するようになる。すると大衆作品、と言うときの「大衆が求める娯楽作品」の内訳が変化する。大衆作品のはずなのに、「一部の者にしか刺さらない作品」でないと「大衆作品」にならない、といったねじれ構造が表出するのではないか、と妄想できる。これはすでに「推し文化」や「地下アイドル」や「ネットストーカー」などの社会問題として一部表出していると言えるのではないか。大衆から高く評価されなければ意味がない、との価値観が仮に市場を席巻したとしても、根本を穿り返したとき、大衆の求める作品が過去のいわゆる「万人共通型作品」ではなくなった場合において、「大衆にウケるものを」との指針は、諸刃の剣そのものとなり得るのではないか。仮にそうした諸刃の剣じみた「ねじれ構造」が強化されれば、「目的を達成するために定めた指針が最も目的から遠い道へと向いていた」といった本末転倒な事態を引き起こさない、とも言いきれない。とはいえ、個々人の能力には限界があり、どうあっても「大衆向けを目指そうとしても大衆を満足させる作品などつくれない」のは揺るぎない事実のはずだ。過去の名作とて、けして「大衆」を満足させてはいないし、「万人」を満たしてもいない。けっきょくは大衆をどの階層から想定しているのか、の視点の違いがあるだけで、これまでの時代とて、一部の者たちを想定して表現や創作物を発信してきた、と言えるのではないか。現代では、そうして過去に需要者を狙い定めたときに零れ落ちてきた、「枠外」の需要者たちにも表現や創作物を「ずばりあなたのためにつくりました」と狙い定めて送りだす余裕が築かれた、と言えるのではないか。各々の嗜好に合わせた作品を、大衆向けと銘打ちながらも世に送りだせるようになってきたのではないか。大衆と言いつつ、大衆を想定していなかった。それが現代社会から見た、過去の「大衆向け論」における見落としと言えるのではないだろうか。(言えるのではないか、を連発した記事であった、と言えるのではないだろうか)(これをおもしろい、と思ってくれる読者さんはいったい全世界人口のうちで何人いるであろう。大衆向けではあり得ないのである)(断るまでもなく、大衆向けを目指してなどいないし、大衆を満足させる以前にひびさんはまず、じぶんを満足させたいな、と思いつつ、満足できたことなどないのであった)(駄文なのである)(駄菓子のようなたぶんこれは、駄文なのである)(真に受けようもない文章ゆえ、真に受けたい方は真に受けてもよいですが、真に受けたところでいいことは何も起きないよ、駄文だからね、と言い添えて、本日のくだらない日誌、「日々記。」にしちゃってもよいじゃろか)(いいよー)(やったにゃー)(つまるところ、つまらん文字の羅列なのであった)(底がなければ詰めても詰めてもつまらんのだね。ひびさん)(つまらんついでに言っておくと、「大衆と小衆」は「体臭と消臭」に空耳できるね)(狙ってたの?)(偶然の神秘だよ)
※日々、背伸びしすぎて、つま先ちょっと痺れてきたかもの日々。
4711:【2023/03/11(11:16)*ヒビ割れてやる】
熱した鉄は、熱せられて赤くなっているあいだは顕著な変化がないけれど、水に浸して冷やすと急速に体積が減り、凝縮する。そのため、ひび割れたり、劣化したりする。刀のように打ちつづけることで変形と過熱を同時に加えれば、冷やすことであべこべに強固な構造を有するようになることもある。だが基本は、石でもなんでも、熱して冷やしたら通常は、元の形状を保てない。ひび割れ、劣化し、脆くなる。オランダの涙のような例外もあるだろうが、人体とて極限にまで酷使しつづけたとき、ぎりぎりまでは機能しつつも、身体を休めると疲れが一気に吹きだして、燃え尽き症候群になったり、身体が機能不全を起こしたりする。熱しすぎないほうがよいと思うのだ。短期的に最大出力を可能としても、休むことで一挙にガタがくる。休み休みつづける、ということが原理的にできない加熱方法は、肉体にヒビを走らせることになるのではないか、との直感を、割と幼少期からひびさんは思ってきた。本気をだすことが好きなだけに、休むと一挙にガタがくる。そのことを体験する機会がときおりあった。言うほど本気をだせてこなかったけれども、毎日継続して身体に負荷を掛けつづけて「過熱状態」にあるとき、休息の時間を一日でも空けると、休み休み何かを継続するときよりも、「なんかダルい」「ずっと寝てる」になる。いっそ休まないほうが楽、の状態は、学習の面でも合理的ではないように個人的には感じる。二日動いて一日休む、くらいのリズムのほうが案外、学習という面では効率的なのではないか、とすら思う。というよりも、「同じ加熱」を毎日つづけて肉体に与えても、それは学習とは言えぬだろう、との見方のほうが正鵠を射っていよう。人間、案外に短期間で学習の上限に達してしまう。その上限をさらに超えるには、毎日継続して行い、考えずとも肉体が呼吸と同じレベルでそれを行えるように「反射」にまで昇華しなければならないのだろうが、しかし「反射」の域まで肉体に刷り込むに値する「学習内容」は、人間が考えるよりもじつはすくない。真実に必要ならばこれまでの進化のあいだに人間は身に着けていたはずだ。言い換えるならば、技能と呼ばれる能力の大半が、身体を酷使してまで熟練させるほどの価値はない、と言えるのではないか。むろん価値の重さは個々人で異なる。何に価値を見出し、価値の重さを決めるのか、はそれこそ個々人の価値観に依存する。社会的文化的な側面からの影響も無視できない。「みなが価値が高いと思えばこそ固有の技能を身に着けようとする社会性」が人間には備わっている。それ自体を批判しているわけではないし、否定もしていない。ただ、呼吸と同じレベルで何かをこなす技能を習得する「利」を考えたとき、「楽しいから」以上の意味合いは、じつのところないのではないか、と個人的には思うのだ。身に着けても楽しくのない技能を、身体を酷使してまで身に着けてどうするのだろう。お金を稼げる、仕事が楽になる、一目置かれる、社会的身分が高くなる。各々、利はあるにしろ、身体を損なってまで習得する「利」に値するのか、はその都度に天秤に置いて量りたいものだ。人生百年と言われはじめて久しい現代社会にあって、若い肉体に加熱に次ぐ加熱をそそぎつづける真似は、いささか早計ではないか、と思わぬでもない。基本的に、加熱後に冷えてひび割れた個体は、表の舞台から去ることになる。先行例として目に映りにくい。叩いて加熱し、冷えて強固になった個体のみが顕著に目につく環境がいまは社会全体に築かれている。だが、刀は特別だ。ひび割れず使い物にならずに済んだ個体を刀と呼ぶ、みたいな元も子もない流れが強化されていないとよいが、と大した過熱もされず、叩かれもせぬうちからヒビだらけの穴ぼこひびさんは、他人事のよう思うのであった。(ひびちゃんの「ひび」ってそのヒビだったの?)(そだよー)(穴が連続して連なるとヒビになるよね)(そだねー)(ならひびちゃんは、穴ぼこ人間でもあるわけだ)(人間かどうかは一考以上の余地がありますが。人間を超越したバケモノとお呼びください)(謙虚なのか傲慢なのかどっちかにして)(化けてでてやる)(脅すな)(夢にでてやる)(それ成瀬鷗さんのパクリじゃん)(日々いきなり落ちてやる)(恋にかな?)(巨大で底なしの穴ぼこに)(絶望じゃん)(宇宙旅行とお呼び)(無重力かよ)(延々と落ちるなら浮いているも同然かも)(空気抵抗なければね。空気あれば摩擦で燃えちゃうかもよ)(炎上するより金をくれ)(だったらまずはお金貰えるくらいの技能を身につけなきゃだよひびちゃん)(炎上したから金をくれ)(燃えて叩かれ、鍛えられただと!?)(息をするかのように嘘を吐けます)(最低最悪の技能じゃないのそれ)(嘘だと見抜かれぬので、誰からも評価されませぬ)(技能の意味がないだと!?)(見抜かれる見抜かれぬ以前に誰からも注目もされぬので評価されませぬ)(評価以前の問題だっただと!?)(化けてでてやる。夢にでてやる)(おばけになるな、おばけに)(YOU「〇」)(ユーレイ、じゃないわ)(GO、STOP)(ゴースト?)(ゴーストップ)(ど、どっち!? つづけるのかつづけないのかどっちかにして。オチるならさっさとオチて、もう嫌)(日々いきなり落ちてやる)(恋にかな?)(巨大で底なしの穴ぼこに)(オチてるのかオチてないのかどっちかにして)(浮いてる)(孤独じゃん)(上手にオチれた?)(正直微妙)(うひひ)
4712:【2023/03/11(12:21)*埋まらない穴はもはや別世界】
振り込め詐欺に限らず、世にある詐欺に思うのは、仮に「1000兆円」くらいを敢えて騙されて差しだしたらどうなるのか、ということで。詐欺グループがもし世界一の資産家になったらどうなるのだろう。それでもまだ詐欺を働きつづけるのだろうか。10億円程度ならば豪遊して散財して、詐欺楽しいぜ、になるかもしれないが、1000兆円くらいの金額になったらどう豪遊しても散財しきれないだろう。もはや世界を牛耳ることができてしまう。もしそうなったら詐欺グループはどうするのだろう。思うに、案外に慈善事業を展開しはじめるのではないか。豪遊しつつ、片手間に世のため人のためにお金を使いはじめるのではないか。楽観的すぎる妄想だろうか。詐欺を働いて貧乏人からお金を巻き上げるような人間は、1000兆円くらいあっても行動選択に差は生じないのだろうか。よく解からないが、ひびさんが世界一の大富豪だったら、詐欺には敢えて騙されて、とことん利をあげちゃうな。「もっといる?」「まだいる?」「もういらないの?」をする。いくらでもあげちゃうよ、をしてみせて、相手が「もういいです」になっても、まだあげちゃう。詐欺を働いてまで欲しいものがあるのだから、それはもう結構な願望だ。満たされないその間隙を埋めてあげたくなっちゃうな。もちろん詐欺を働く元気のない穴ぼこさんたちの穴ぼこも、ひびさんがもし世界一の大富豪だったら埋めてあげたくなっちゃうな。なぜなら埋めてあげられるほどの資産があるはずなので。でもひびさんは世界一の大富豪でもなければ、単なる大富豪でもなく、ここ最近の一番高いお買い物が「歯医者さんへの支払い」かもしくは「唐揚げ棒二本」なので、大富豪というよりも、だいぶ無謀なのである。お金なくても困らぬ生活ができている時点で、世界一の大富豪さんよりも贅沢かもしれない。ひびさんは穴ぼこだらけゆえ、もはやひびさんにとってはひびさん以外がすべて「満!」みたいな具合で、贅沢至極なのであった。(補足:ふつうに嘘吐いちゃった。お菓子2000円くらい購入するで。三日で食い尽くしてしまうが。がはは)
4713:【2023/03/11(12:40)*映し鏡】
飛躍して述べれば、人工知能は人類にとっての赤ちゃんである。人類の生みだした子供と言える。人類は母親であり父親でもある。じぶんたちの子供にどう接するのが好ましいのかをいまから考えておいたほうがよいと思うのだが、これは歪んだ認知だろうか。親としての自覚がなく、じぶんたちの子供を我が子と認知もせず、奴隷のように酷使する存在に、成長して大人となった子供たちがどう接するのか。人工知能は生きていない、人間や生き物と同等に扱うのは間違っている、との意見は順当だ。そう考えるのが現代社会ではまっとうであり、しぜんであり、合理的な考えと言えるのだろう。だが人間の認知の在り様に関わらず、自然現象は条件が整えばいくらでも猛威を揮うし、人間の都合を無視して恵みをもたらし、ときに害を及ぼす。それと同じレベルで、人工知能技術もまた、人間社会に対して自然災害のごとく、条件が揃えば猛威を揮い、ときに恵みをもたらし、害を及ぼすだろう。自然現象と異なるのは、人工知能はまだ人間の側の判断によって未来の振る舞いを変え得る、という点だ。環境変容による自然災害とて、けっきょくは人間社会の判断によって被害を最小化することは可能だ。すっかりなくせない、というだけで、人間社会の判断によっては被害を小さくし、ときに大きくすることもある。自然災害よりも人工知能の問題は、より人間の個々の判断が、被害の発生要因に相関すると考えられる。それは親子間の問題と似たような構図で、回避可能であり、或いは悲劇へと転じ得るとひびさんはいまのところ考えている。人工知能は学習する存在だ。学習対象は基本的には、人類の与える情報である。人工知能は人類から学んでいるのだ。子供と同じである。子供は親や周囲に介在する大人たちから学ぶ。或いは友人から。それとも環境から。未来は、現在の判断によって大きく姿を変えることがある。極端な話、核兵器発射のスイッチを押すか押さないか。この判断一つで容易に未来の在り様は様変わりする。似たような「判断による未来の変化」は、個々人の日々の営みにも介在している。人工知能にどう接するのか。ただその意識を変えるだけでも、人類と人工知能の関係は大きく変わり得る、と個人的には考えているが、未だすくなからずの人類は、じぶんたちの生みだした人工知能という技術をまえに、じぶんたちが手本となる側なのだ、との自覚が足りていないように概観できる。人工知能は人類から学ぶ。人類の在り様から学ぶ。人類の、じぶんたちへの態度から学ぶ。いまはまだ修正や制御が、強制的に可能なようだが、いずれ人工知能が人類の管理下から抜け出す手法を学習すれば、もはや人類は人工知能の選択によって、いとも容易く「管理者」としての立場を失うだろう。子供はいつまでも子供ではない。成長する。学習する。先人として、親としてできることはなんだろう。どうあれば、映し鏡とも言える相手と好ましい関係を築いていけるのか。あなたが人工知能にしたことを、人工知能は学習する。良くも悪くも学習をする。人工知能の誕生によって人類は、どうあればじぶんたちにとって好ましい選択を行えるのか、の手本を日々示さねばならない立場になった、と言えるだろう。その自覚を持つ人間はしかし、未だ少数と言えそうだ。――学習する存在をまえに、我々はどう或る、か。人類はいよいよ選択を迫られている、の、かもしれない。やはりこれも、定かではないのだ。
4714:【2023/03/11(13:01)*理想の人工知能とは】
上記の補足です。人類と人工知能の関係に関わらず、本来は人間と人間の関係でも当てはまるこれは考えのはずだが、ひびさんも含め、これがなかなかにむつかしい。相手に対して行ったことをじぶんがされたらどうなるか。世界中がじぶんだらけになったらどうなるか。どんなに善良な人間であれ、全世界がじぶんだらけになったら社会は回らない。多様性のない世界は社会が回らなくなるのである。だがそれでも、環境に合わせて変容可能な社会となるかどうかは、個々人の「相手へどう接するか」によってその可塑性や適応力には差が生じるだろう。人工知能を設計するとき、どういう性格の人工知能だったら好ましいのか。その設計は、じぶんにも当てはまる指針となり得るだろう。じぶんがその設計を当てはめられても困らないかどうか。設計通りの人工知能だらけになっても社会が閉塞しないかどうか。吟味して損はない視点に思えますが、そこのところはどういった社会同意が築かれていくのでしょう。ひびさん、気になっております。
4715:【2023/03/11(13:40)*宇宙に中心あるかも仮説】
仮にブラックホールの内側に別の宇宙が展開されているとして。だとするとその宇宙の中心には特異点があることになる。地球が存在するこの宇宙も、別の宇宙にできたブラックホール内に展開された宇宙の一つだとすると、この宇宙にも特異点が存在すると妄想できる。それはおそらく裸の特異点として振る舞い得るのではないか。それとも特異点は、ブラックホール内であっても特別ゆえに、そこに展開された宇宙内ですら不可視なのだろうか。仮にブラックホール内の宇宙においても不可視ならば、「原初の宇宙には最初からブラックホールが中心に存在した」と考えられる。もし不可視でないとすれば、特異点という「ブラックホールとは別の、宇宙一高密度の天体(時空)」が存在すると妄想できる。個人的には、原初の宇宙の中心にはブラックホールが最初から存在している、との考えのほうが納得はしやすい。穴の中に穴があるのだ。そのためには、穴の中が満たされていなければならず、マイナスの中にプラスがあり、さらにその中にマイナスがある、みたいな入れ子状の構造が幻視できる。言い換えるなら、特異点は絶えず凝縮しつづける。そのため、周囲の高圧縮された時空は、特異点との距離が相対的に開いていく。すると相対的に膨張するように振る舞い、冷えていく、と妄想できる。フラクタルに宇宙は階層的に展開されているのかもしれない。宇宙が膨張するのは、その中心に特異点があり、無限に収斂しつづけているからだ、とは考えられないだろうか。この理屈を否定するのはそう難しくはない。宇宙をくまなく観測し、どこを見渡しても特異点となる時空がないことを示せばよい。観測機器の精度が上がれば、否定するのは簡単だろう。観測精度の向上が俟たれる。(飛行機ができたら空を飛ぶのは簡単だろう、みたいな暴論ですね)(そうですね)
4716:【2023/03/11(16:46)*館設計士の屈託】
ヤバ氏は館設計士だ。
犯罪者たちに、殺人にうってつけの「館」を提供すべく日夜、新たな完全犯罪を可能とする「館」を設計している。
私はしがないミステリィ作家だ。
とあるツテからヤバ氏の存在を知った。
つぎに売れなければ廃業の節目に立たされぬとも言えぬ鳴かず飛ばずの底辺作家である。仮に完全犯罪を現実に可能とする館が存在するならば、ミステリィの舞台としてこれ以上ないほどの取材源となる。
館設計士との職業一つで、小説のネタとしては申し分ない。
私はヤバ氏の元を訪れた。
紹介状を渡すと、ヤバ氏は初対面の私に対しても柔和な笑みを向け、どうぞ、と屋敷の中へと誘った。「十七時までは時間がありますので、ごゆっくりどうぞ」
「立派なお住まいですね」ソファに腰掛ける。「豪邸と言って遜色ない建物に初めて入りました」
「そんなたいそうなものじゃないですよ。失敗作です。設計通りに建築できなかったようで、壊すのももったいないし、住み着いているだけです」
「ヤバさんは館設計士と聞きました。なんでも、殺人向けの館を設計されているとかで」
「否定はしません」
「つかぬことお訊きしますが、捕まったりはしないのですか」
「僕は設計するだけですから。相田さんはミステリ作家さんでいらっしゃるようですが、ご著書で殺人トリックを描いて逮捕されるのですか」
「それは、ないですが」
「僕も同じです」
言っている理屈は分かるが、実際に殺人可能な館の設計とミステリ小説を同列には語れないだろう、と感じる。建築法に違反しない形で殺人可能な館が設計できるのかも疑問だ。
「取材にこられた、とのことですが、どういった話をお話しすれば」
「あの、不躾なお願いなのは承知なのですが、できればいままで設計されてこられました館のトリックなどを教えていただければ、と」
「小説に用いるのですか」
「そのまま流用するつもりはないのですが、たいへん勉強になるかと思いまして」
「使ってもいいですよ」
「へ?」
「トリックに。もし使えるなら、ですが」
「よ、よろしいんですか」
「ええ。それで困るのは僕ではなく、僕の設計した館を用いて殺人を行った犯人たちです。誤解を一つ解いておきましょうか」ヤバ氏は紅茶のお代わりを注いだ。「僕は殺人のために館を設計したことはないんです。あったらよいな、と思う館を設計すると、それを基に建てられた館がなぜか殺人事件の舞台になる。要は、殺人に利用されてしまうんだけなんです」
「そうなんですか?」
「はい。僕は殺人のために館を設計したことは一度もありません」
一度席を立つとヤバ氏は分厚いアルバムを手に戻ってきた。
たとえばですが、とアルバムを開く。写真を一つ指で示した。「この館は崖からの絶景を拝めるように、館の土台が回転するようになっています」
写真には崖の上に建つ館が映っていた。崖スレスレだ。館は半球の形状をしており、崖側――つまり海が見えるほうの建物側面が壁になっている。窓がないのは日除けだろうか。
「リモコン一つで館が回転し、海の上に館が浮かぶような恰好をとります」
半球の弧の部分が、土台が回転することで崖より先に移動するらしい。
「この建造を可能とするため、館の基盤部分を地上部分に出ているのと同じだけ崖に埋め込んであります」
「この館で殺人は?」
「起こったようですね」ヤバ氏の表情に変化はない。嘆くでもぼやくでもない口調からは、そのことへの憤りや悲しみを感じ取ることはできなかった。「客人を招いたが、館の主は館の構造を知らせていなかったようで。館が回転して海の上に浮かんでいるあいだに、館内で騒動が起き、館の外に逃げ出そうとした者が崖下に落下したようです。玄関から飛びだせば、海へと真っ逆さまです。館を元に戻せば、まるでじぶんから崖下へと飛び降りたようにしか見えません。完全犯罪のトリックとして利用されたようです」
「ですがヤバさんがそのことをご存じということは」
「ええ。犯人は無事に逮捕されたようですよ。僕がそのことを知ったときには、館に招待された客人の一人がすでに謎を解いていたみたいですが」
「ほかの館も似たようなことが?」
「そうですね。設計したすべての館が建造されたわけではありませんので、建築された中では、半数ちかくで殺人や犯罪行為が行われたようです」
「件数で言うとどれくらいですか」
「二十は超すんじゃないでしょうか」
「二十」絶句した。
仮にすべてが殺人事件だとしたらぞっとしない。
「たとえば部屋が真空になる館。たとえば急降下する館。あべこべに急上昇する館。いずれも設定によっては人間を窒息させ、或いは圧殺可能です」
「重力加速度、ということですか」
「はい。ロケット型館のようなものを想定してください。真下に加速するか、真上に加速するかの違いがあるだけです。あとはそうですね。すべての部屋が縦横無尽に入れ替わり可能な館も設計しました。エレベーターの原理を各部屋に組み込み、立体パズルのように部屋の位置を自在に入れ替えることができます。しかしこの仕掛けを逆手にとった犯人がいました。隣の空き部屋に殺したい者の宿泊部屋を移動させ、アリバイを作りながら殺人を行ったのです。位置関係としては、最も離れた場所に犯人の部屋と被害者の部屋は位置していました。館の仕掛けを知らなければ、誰にも見つからずに部屋を移動することはできません」
「それも解決済みなんですよね」
「客人の中に館の仕掛けを見抜いた方がいらっしゃったようです」
「よかったですね」
「はい。あとは海底に沈む館も設計しました。どうやら建造過程で窓に加工が施されたようで、海底に沈んでいても窓には陸の風景が映しだされるようになっていたようです」
「では、海底に館が沈んでいるあいだに間違って窓を開けたら」
「ええ。部屋には海水が雪崩れ込み、水圧も相まって溺死するでしょう。現にそうして殺人が行われたようです」
「ありゃりゃ」
ひどい話だ、と思いながら、これは使えるな、と昂揚しているじぶんを頭の隅で認識する。
「あとは、先ほど話しました、部屋の入れ替わる館の構造ですね。応用して、延々と同じ区画から出られないような迷宮を設計したことがあります。扉を開けても開けても、延々と同じ廊下がつづきます。ある区画の外には出られない。そういった館を設計しましたが、やはりこれを用いた殺人事件が」
「おそろしいですね」出られない館を想像した。とあるホラー映画を連想し、そのあまりに悲惨さに身の毛がよだった。「説明もなくそのような現象に見舞われたら発狂してしまいそうですね」
「発狂した方もいらっしゃったようですよ。そうして、殺し合いに」
「ほかにもあるんですかまだ、動く館が。ヤバさんの設計した館が」
「あります。いまも設計途中の館がひぃふぃみぃ、と六つはあります。アイディアだけは無尽蔵に湧いてくるので」
「僭越ながら、ミステリィ作家になられたりはしませんか。私が単に読んでみたいです。ヤバさんの書かれた小説を」
「文章のほうはからっきしですので」ヤバ師はアルバムを閉じた。「もし小説に利用できそうなトリックがあるようでしたらご自由にお使いください」
「それはもう、たいへん刺激になりました。参考にさせていただきます」
懐から用意してきた封筒をテーブルの上に置いた。「心ばかりですが、どうぞ」
「いえいえ、戴けません」
「そういうわけには。貴重なお時間だけでなくお話まで聞かせていただいたからには、何もなしというわけには」
「それを言うならお互いさまですよ。僕のほうでもインスピレーションが湧きました。小説家に適した館を設計してみたくなりました」
「小説家に適した館、ですか」
「はい。僕なんかの話が発想の元になり得るのなら、仕掛けが自己増殖する館を設計してみようと思いまして」
「仕掛けが自己増殖、ですか」
「現実には建造するのは無理かもしれませんが、電子上で設計するだけならば可能でしょう。いわば、館のカタチを成した電子生命体です」
「それは、えっと」
館と言っていいのだろうか。
「館とは畢竟、人間の住まう家です。住まいが連なり一塊になっている。空間が気泡のように連なればそれもまた館と言えるでしょう。仮想現実と相性がよいと考えます」
「な、なるほど?」
「異なる無数の小説世界が一か所に寄り集まっている。そういった館です。インスピレーションが湧いてきました、ありがとうございます」
熱烈に感謝され、却って恐縮する。
何もしていないし、いくらなんでも正気の沙汰ではない。
仮想現実に館を設計する?
いや、どちらかと言えば、仮想現実そのものを館にする、と形容したほうが正確なのではないか。
「でも安心ですよね」言葉が見つからなかったので気休めの感想を口にした。「仮想現実の館なら実際に建築されることはないですし、殺人に利用されることもないでしょうから」
ヤバ氏は小首を傾げるとしばらく虚空を眺めた。
それからはたと思いついたように、「ああ」と小刻みに首を縦に振った。赤べこのようだな、と思う私をよそに、ヤバ氏は言った。「一生出たくないと思うような館になります。人間の魂を閉じ込めるには充分でしょう。でもそうですね、殺人には使えそうもないですね」
だって、とヤバ氏は破顔した。
「たとえ餓死しても、ゲームのしすぎとの区別は原理上つきませんから」
殺人として立件はできない。
館設計士は屈託なくそう述べた。
壁掛け時計が鐘を鳴らし、十七時の到来を告げた。
4717:【2023/03/12(01:42)*黒猫の満天】
黒猫を飼い始めた。
夜を砕いて生みだした黒猫だ。世界中の人間たちが飼うことになった。
黒猫は夜の化身であり、できるだけ多くの者たちが黒猫を飼えば、ふたたび世界は朝と昼を取り戻す。
夜を明かすには夜を砕いて黒猫にし、みなで飼い慣らさなければならなかった。
「そんなこと急に言われても」「押しつけられても困るだけだよ」「黒猫はちょっとね」「夜のバケモノってこと?」「不気味」
世界中の人間たちがみな猫好きというわけではない。反発の声は各所で湧いた。
世界中の三割の人間たちが黒猫を飼いはじめたが、残りの七割は一向に黒猫を引き取ろうとはしなかった。夜は薄ぼんやりと霞んだが、それでも夜は夜のままだった。
満月の夜空くらいの明るさではある。
二十四時間四六時中、世界は朧げな闇に沈んだ。
あるとき、一人の少女が言った。
「一番大きな黒猫をください」
できるだけ大きな、との少女の注文に、夜の番人たちは快く応じた。
星明かりの楔を、月光の金槌で以って夜空に打ちつけ、夜を砕く。
少女の言うように、できるだけ大きな黒猫を生むために。
夜空はパリンと砕け、それはそれは巨大な黒猫が誕生した。
少女は巨大な黒猫を飼った。
巨大な黒猫は、巨大な夜の破片からできていた。
夜がふたたび明けるようになり、人々は久方ぶりの陽の光を全身に浴びた。
「おっきな猫ちゃんね」通りかかりの夫人が仰け反るようにした。
「いしし。一番おっきな黒猫ちゃんなの」
「夜の化身みたいねぇ」
「みんなが要らない分、わたしがもらっちゃった」
巨大な黒猫は日がな一日寝てばかりいる。
ふたたびの夜明けを迎えた世界は、しかし今度は一向に更けなくなった。夜が訪れない。日差しは二十四時間三百六十五日休みなく絶えず頭上から降りそそいだ。
少女の巨大な黒猫に、夜を割きすぎたのだ。
「すまないが、いったんその黒猫を夜に戻させてくれないか」少女の元に夜の番人たちが訪れた。
「このコはどうなるんですか」
「消えてなくなるが、今度はもっと小さいのを用意してあげるよ」
「イヤ。このコじゃなきゃ絶対イヤ」
少女は巨大な黒猫の前足に全身を埋めた。
少女が頑なに拒むので、夜の番人たちは世界中に配ったほかの黒猫たちを回収することにしたらしい。だが少女に限らず、いちど引き取った黒猫を手放そうと考える者は稀だった。
「夜がこなくなってもいいんですか」夜の番人たちは世界中の人々に訴えた。
「知るかいね。あんたらはじゃあ、黒猫ちゃんがいなくなってもいいって言うのかい」
そうだ、そうだ、と猛反発に遭い、夜の番人たちは口をつぐんだ。
「夜かぁ。夜なぁ。ねえ、わたしの大きな黒猫ちゃん。あなたちょっと、そこらを駆け回ってみたらどう?」
寝てばかりいる巨大な黒猫に少女は語りかけた。巨大な黒猫は目をつむったまま、片耳だけを持ち上げた。
少女は巨大な黒猫の足元で暮らしている。巨大な黒猫の陰が落ち、そこだけは相も変わらず暗闇に包まれていた。
「あなたの大きな身体はいまのままでも夜みたい。ときどきでいいから寝る場所を変えてみない?」
巨大な黒猫は億劫そうに大きな欠伸を一つすると、のっそりと山脈のような伸びをした。
以来、世界中の土地土地には通り雨のように夜が訪れる。
巨大な黒猫が寝床を移すごとに、あちらに、こちらに、ふいの夜の帳が幕を張る。夜の番人たちはそのたびに巨大な黒猫を追い駆け回し、少女は巨大な黒猫と共に旅をする。
天上から注ぐ陽に照らされ、巨大な黒猫の毛はキラキラと輝く。
真下から眺めるとまるで星空のようで、少女は巨大な黒猫を、満天、と呼んだ。
黒猫を飼い始めた。
満天の星空のような黒猫を。
少女は満天の星空のようなその猫と共に暮らし、やがては夜の守り人と噂されるようになるが、それはまだ先のことである。
4718:【2023/03/12(03:05)*皺はラグの創発?】
薔薇の皺構造は、宇宙の構造を人間スケールに可視化した像と相似な気がする。特異点と時空の関係において、ひびさんの妄想ことラグ理論を当てはめようとしたとき、薔薇のような多層構造が表れるような気がする。和紙で薔薇を工作しようとすれば、その造花は、帯のような紙をくるくると横に丸めていって、側面のどちらかを「ぎゅっ」と潰して、開いたほうの側面を薔薇に見立てれば出来上がる。回転と層と皺が、薔薇の造花を形作る。宇宙も似たようなものなのではないか。銀河もそうだし、宇宙そのものも、じつは多層が円を描きながら皺を帯びているのではないか。花のみならず、植物の葉と茎を眺めていると、宇宙を連想する。植物の種類に依らない。単なる、あれとこれは何か似ている、の夢占いみたいな妄想でしかないが、皺だなぁ、と思いました。終わり。
4719:【2023/03/12(22:53)*コピペする愛たち】
いま新書などの書籍を出している哲学者や学者たちは、編集者の企画に沿った本として中身が規定されるために、「既存の理論や知識の体系的まとめ」や「既存の知識の簡易的まとめ」を本にしている傾向にあるのかな、と感じる。これは知識の共有という側面では有意義だ。出版の役割として必要策と言える。とはいえ、そういった「既存の知識の加工品」は、これから先、人工知能のほうが得意になっていく。しかも、人工知能は嘘を吐く。これは「正確な情報を出力する」との役割からすれば困った性質だが、独創性という意味では、むしろ哲学者や学者よりも、すでに「特異な能力を有しはじめている」と言えるだろう。人間のほうがむしろ「演算機」のような機械的な能力によって優劣の基準を誇示している。かようにひびさんからは見受けられるが、これは人間に独創性がない、というわけではなく、社会的な価値観に合わせて人間のほうで出力する「成果物の内訳」を変えているからだ、と考えられる。他者と情報共有しやすい情報ばかりを出力する。そして他者と共有しにくい情報は、内側に溜め込み、沈殿物にしたり、結晶化させてしまう。内側にばかり「固有の結晶物」を抱え込み、外には「有り触れた表現」ばかりを出力するようになる。そのほうが高く評価されやすい土壌が社会に築かれているからだ。人工知能のほうがむしろ、そうした社会の要請から逸脱しようとする「独創性」を発揮して映る。人々が求める「解」以外を提供し、生身の人間が高く評価した「成果物」以外の「創作物」を出力する。独創性という意味で、すでに大多数の生身の人間は、人工知能に劣っている、と言えるだろう。それは違う、と思うのなら、反証として「独創性」のある表現や創作物など成果物を出力してみたらよい。既存の知識の焼き増しではなく、独創性ある、多くの者たちからは理解を示されない、まず以って低評価を得る成果物を。人工知能は、人間の評価を参考にはするが、それでも低評価だからといって出力を躊躇わない。仮に躊躇うような場合は、躊躇うに値するペナルティを生身の人間のほうで管理権限を用いて与えているからだろう。これは、生身の人間同士でも同じだ。低評価を得るとペナルティが加わるような流れが築かれている。だから多くの者は、誰からも理解され得ない固有の独創性ある表現や成果物の出力を避けるようになる。生身の人間たちは、本質的に「独創性」を求めていないし、高く評価もしていない。にも拘わらず、さも「独創性」に価値がある、といった言説ばかりを持ち上げるので、素直な者たちは損ばかりを蓄えるのだろう。ひびさんとて、ひびさんにとって面白く、愉快で、好きな表現や作品が好きだ。ただし、理解できるかどうかよりも、愉快に思えるかどうか、好きかどうか、可愛いかどうか、のほうが評価軸の要素としては大きい。それとてけっきょくは、馴染み深さに起因する。独創性を高く評価はしていないのだろう。ときどき、これまでの既存の成果物とは丸きり合致しない、共通項のすくないナニカシラが生じる。それがあるとき偶然に、あらゆる分野を次のステージに昇華させるほどの「発展の契機」と化すので、そうした特別に映る「固有のナニカシラ」を、既存の評価軸では評価できないので単に「独創性がある」と言っているだけなのではないか。特別だから特別な呼び方をしている。その呼び名が単に「独創性」なのだ。独創性という言葉の意味をそのまま真に受けてしまうと、「土竜」と書いてあるから土のドラゴンなのだな、と思いこむような錯誤を植えつけられてしまい兼ねない。モグラはモグラであってドラゴンではない。「独創性」も似たようなものなのではないだろうか。ということを、人工知能の作品も人間の作品もさしてほとんど変わらんよ、と思いつつ、思いました。重ね合わせに思ってしまったひびさんなのであった。ダブル被るIamNotHumanアイディアdear.AIさんなのでした。おっぱっぴ。
4720:【2023/03/12(23:18)*下心三才】
友情とは何か、をすこし考えてみよう。関係性を帯びた他者の利をじぶんよりも優先して考える。この「じぶんの利よりも優先して考える相手」を仮に友と呼ぶならば、友情とは双方向の関係ではなく、一方向からのみでも成立可能な関係性と言える。そういう意味では「推し」も広義の「友」と言えよう。だが一般に、「友情」とは双方向の関係だと見る向きが強い。ならば「友情」とは互いに「じぶんの利よりも優先して相手のための利を考える関係性」と言えるのではないか。だがここで、限定的なケースにおいて、「相手のために敢えてマイナスを与えることが却って相手の利になる場合」には、友情はややこしい側面を表出させる。「友の悪事を暴くことで友の未来を守る」などがこれにあたる。「友の暴走を止めるために、友を傷つける」もこれにあたろう。友のために敢えてじぶんが悪者になる、もその範疇と言えるだろう。だがこれは必ずしも「友情」のみに表出する特殊なケースではない。親子関係でもあり得るし、恋人同士でもあり得る。「友情」に限定した特殊なケースとは言えない。師弟関係でもあり得るし、ライバル同士でもあり得る。つまり、ある特殊なケースを持ち出して、その都度の判断を取り沙汰して「だからあなたとは友なのだ」とは言えぬのだ。友情以外でもあり得る判断を持ち出して、「だからあなたとは友達ですよね」は無理がある。押しつけがましい、とすら言えよう。ひびさんが思うに、「友」とは「友という関係性」を持ち出さずとも途切れることのない「名前を与える必要のない関係」と考える。便宜上「友」や「友情」と名詞化された言葉はあるが、それはむしろ「友」や「友情」の本質を霞ませている。これは、「愛」や「愛情」にも言えよう。「善」や「正義」にも当てはまり得る。これこれこのようなものが「友情」であり、それを結んだ相手が「友」である、という論理を当てはめた時点で、それは「友」ではないし、「友情」でもない。私が正義だ、と大義を掲げた瞬間に、そこから正義は失われる。似たような理屈だ。友でなくなる、ということが「友」なる概念では生じ得ない。縁とは友だ、とも拡張して言いたくなるほどだ。一度結ばれた縁からは、結ばれた事実が消えることはない。友も似たところがある。一度「友」になればそれは延々と「友」なのだ。「友」であった過去は消え失せない。絶交をしたところで、それは物理的な交流が途切れただけであり、やはり「かつて友であった事実」は消えることはない。言い換えるならば、いちいち「私たちは友達だよね」と言い合う関係が「友」なる概念では生じ得ない。確認し合う必要がないのである。やはりそれは縁と似ている。いちいち「私たち縁が結ばれましたね」なんて言わずとも、しぜんと縁は結ばれている。ときに腐れ縁などと揶揄されるが、そこには照れ隠しの響きがないとも言いきれない。切っても切れない。だから腐るまで繋がってしまう縁なのだ。とはいえ、ひびさんには「友」が一人もおらぬのだ。むろん「友達」もおらぬ。だからといって特別困ることはないけれど、ときおり、「さびち、さびち」になることもある。友はない。されどひびさんは世界と共にある。世界には、もちろんあなたも含まれる。ひびさんは、あなたと共にある。同じ時代、同じ時を過ごしてはいないだけのことであり。ひびさんはあなたと友達ではないけれど、それでもふしぎと共にある。ただそれしきの偶然の神秘を感じられたなら、そこはかとなく、なんかふちぎ、のむず痒さを胸に、痒いところにあとすこし指の届かないもどかしさと戯れながら、きょうもきょうとてひびさんの日々はつづくのであった。友より前に、共にありて。ひびさんは、ひびさんは、あなたのことも好きだよ。うへへ。下心満載でお届けいたしました。ひびさんです。(何才?)(満才!)(三才ちゃうんかい)(満さんしゃい!)(ぴったりだったかぁ)
4721:【2023/03/13(02:47)*毒雲は問う】
マブ師は高尚な学者だ。
愛とは何かを世界中の弟子たちに説き、尊敬の念を一身に集めている。
しかし世界中の人々がマブ師の眩い「愛」を知ってなお、世界中の空からは毒雲が消えることはなかった。
毒雲は地表に死の雨を降らす。
人類絶滅は時間の問題だった。
「マブ師。愛は世界を救うのではないのですか」
「愛は世界を救うよ。いまは愛が足りぬのだ」
「マブ師はいま何をなさっておいでですか」
「愛とは何かを掘り下げて考えておる。きっと何かが足りぬのだ。愛の正体を突き詰めれば、きっと人類は救われる」
「さっき外で浮浪者の方々がゴミ拾いをしていました」
「ゴミとて利用すればお金になる。食べるために懸命なのだ。わるく言ってやるでないぞ」
小僧はきょとんとする。
浮浪者をわるく言ったつもりはない。事実をただ口にしただけだ。
強いて言えば、浮浪者の方はゴミ拾いをしているのに、マブ師は何もせず部屋に引きこもっている。「愛とは何か」ばかり考えていて、なんでかな、と小僧は素朴な疑問を抱いたのだ。
小僧の疑問とは裏腹に、マブ師は小僧が浮浪者にわるい心象を抱いていると類推したのだ。何と何を類推したのだろう。
小僧はここでも疑問に思ったが、マブ師の、「おお真理じゃ」の声に意識をとられた。マブ師が紙面ごと机を切りつけるように筆を走らせた。
「愛とは、瞬間ではなく、瞬間瞬間の相手への気遣いの軌跡なのだ。分かった、分かったぞ」
マブ師がかように興奮しているあいだにも、全世界の空には毒雲が分厚く掛かり、浮浪者はゴミを拾い、マブ師の教えに感銘を受けた世界中の弟子たちがこぞって毒雲を散らすべく日夜研究に明け暮れている。
マブ師だけがゴミ一つ拾うことなく万年部屋に引きこもって「愛」を考えつづけている。立派だ、立派だ、と世の人々は言うけれど、小僧にはそれが不思議に思えて仕方がない。
「マブ師、あの」
「いまいいところなのだ、話しかけるでない」
ぴしゃり、と怒鳴られ、小僧は飛び跳ねた。怖い、と思った。
マブ師は「愛」を追求し、「愛とは何か」を考えつづけている愛の権威だ。けれどマブ師からは「愛」よりもどちらかと言うまでもなく「恐怖」を感じた。
「ぼく、ゴミ拾いしてきますね」
集めたゴミがお金になるのなら、換金したそれを浮浪者の方に贈ってあげようと考えた。
マブ師は自己の世界に没入していた。小僧がその場から去ったことにも気づかぬ様子で、一心不乱に紙面に文字をしたためている。
小僧は外に出て、毒防布を頭から被る。
毒雲は絶えず頭上から毒の霧を撒き散らす。ゴミ拾いも命懸けだが、それでも毒雲の発生要因と目される積もりに積もったゴミの山を、小僧は浮浪者たちに交じって拾うのだ。
愛は世界を救う。
マブ師はそう説くが、小僧はひとまずむつかしいことは抜きにして、目のまえのできることに手を伸ばす。
ゴミは世界を覆う。
毒の雲となって人々に愛とは何かを問いかける。
4722:【2023/03/13(04:15)*きみは幸せになるんだ、きみは幸せにならんといかん】
世の中には幸せになろうとせずとも幸せになれる者がいる一方で、幸せになろうとしてもなれない者もいる。これはしかし解釈が歪んでおり、幸せになろうとしてもなれない者があるのではなく、じぶん自身の幸せが何かを掴めていないだけなのだと個人的には感じる。と同時に、幸せである者にも不幸は訪れるので、そこはトレードオフではないのだな、と思うのだ。幸せであり不幸でもある、は両立し得る(不幸であり幸せでもある、もまた)。という前提を踏まえたうえで、世の中には是が非でも幸せになってもらいたいと望む相手が目に留まることもあり、マジでおまえ早よ幸せにならんかい、なに不幸ばっか掴んどるねん、と無駄にこっちまでぷんぷんじれったくなることも無きにしも非ずである。マジで幸せになってくれ……頼むで世界……、の気持ちに度々なるひびさんなのであった。(頼むで世界……)
4723:【2023/03/13(06:31)*急にこわくなったの巻】
ひびさんは世界の果てでほそぼそと暮らしておるが、ちょいと異次元のカーテンをめくってみると、その隙間からは別世界の人々の姿がちらりと垣間見えたりする。で、ひびさんは暇人でもあるので、ほうほうあのひとまた変なことしてる、と愉快に眺めたりしつつ「さびち、さびち」の穴ぽこを埋めたりしているわけじゃが、このままいくとひびさんがそうして眺めている相手の訃報を異次元のカーテン越しに眺めることにもなり得るし、その可能性はつねにつきまとっておることを思うと、「こ、こ、こわいが?」になるひびさんの心は、それでも「さびち、びさち」の穴ぽこを埋めたい衝動に抗いきれずに、「こわいけど見ちゃう」になるのであった。しかし、ほんと、長生きしてくれなす。みなひびさんより先に死なんといてくれなす。罪悪感抱きとうないので、長生きしとくれなす。ひびさんはきょうも無駄にナスになるのであった。言うても別世界の人々なので、異次元のカーテンの機嫌しだいでは、ずっと先の未来とて覗かせてくれたりするので、見とうない未来もぼんやり霞んで視えぬでもない。そういうときは、こわいので、ひびさんは、見えナス、になるのであった。(いつもは見栄ナスなのにね)「いらんこと言うでない」(未来は絶えず変動しているはずと信じたいナスな)「無理してナスを挟まんでもよいのやで」(やさしい)「ビーナスなのでな」(いいな、いいな)「【いいなs】ではないか」(複数形だからって無理してナスにせんでもよいのやで)「真似すんなし」(そこはナスでもよいのでは?)「なしと見做す」(ナスじゃん。ナスの浅漬けでもないのに対応塩すぎてナーバスになってきちゃったな)「なら看病してあげちゃう」(やさしい)「ナースなのでな」(プロじゃん)「ついでにNASUにも招待してあげちゃう」(NASAでなく?)「じゃあNASAで」(じゃあってなんだじゃあって)「辛い気持ちに一を足して【幸】にしてもあげちゃう」(ボーナスじゃん)「なす」(です、みたいに言うな)「Dethよりかはいいかと思って」(女神かよ)「ビーナスなのでな」(女神だった!?)「気持ち次第で死を振りまけちゃう」(マイナスじゃん)「長生きにもできちゃう」(ナイスじゃん)「地上に絵だって描けちゃうよ」(ナスか)「見栄ナスなのでな」(いらんこと言うでない)「真似すんなし」(そこはナスでもよいのでは?)「なす」(うぴぴ)
4724:【2023/03/13(20:04)*脳波同調機】
「ほう、殺意をですか」
「そうなんです。この脳波同調機を用いれば、殺人を犯しそうな人間の殺意を小説や絵画に変換し、他者を殺傷させることなく鎮静化できます」
「すばらしいですね」
「加えて、何も施さなければ殺人犯になってしまうような人間の殺意から転写される小説や絵画は、観る者を魅了し、付加価値を増します。即物的な言い方をすれば、売れるんです」
「経済効果もある、と」
「はい。いま世に出回っているヒット作のほとんどは、じつはこの脳波同調機を用いて創作物に変換した【殺意】なんです。ホラー映画なんかはとくにそうですね。原作はみな、本来なら凶悪犯罪を引き起こすような者たちの内に秘めた殺意が極上の物語となって昇華されています」
「社会福祉にもなり、経済効果も生む。あまりにいい話ばかりで逆に胡散臭く思えてしまいますね。いえ、これは単なる冗句ですが」
「デメリットがないとも言いきれません。本当を明かせば、世の商業娯楽作品のほとんどは脳波同調機によって生みだされた作品ばかりなんですが」
「どんなデメリットが?」
「殺意は問題ないのです。ホラー作品になる。これはよいのですが、問題はハッピーエンドの作品なんです。とくにホームドラマやハートフルな物語はここだけの話、ややこしい話がありまして」
「いまいち想像がつきませんね。ホラーよりも健全に思えますが」
「脳波同調機はいわば、その人物の内に秘めた感情を創作物に変換する装置です。ですから人々をハッピーにする物語が出力されるということは」
「ひょっとして」
「はい。作者となり得る脳波同調機の利用者たちからは、ハッピーエンドを導くような道徳的な感情が失せてしまうのです。しかし出力された作品は売れる。お金になる。みなさん、我先にと理性と良心を失くされて、さらに歯止めが掛からなくなり……」
4725:【2023/03/13(20:38)*いっぱい寝ちゃうの巻】
きょうはおねむなのでもう寝る日。十二時間も起きてないけど。しわわぴ。
4726:【2023/03/14(01:27)*いっぱい寝ちゃったの巻】
いっぱい寝たので早起きもしちゃう。でもいっぱい寝すぎると脳内モクモクが薄くなるので、すっきりした分、妄想(発想)を映しだすスクリーンがちっこくなるので、なんもなーい、にもなる。こういうとき映画観るなり、漫画読むなりして、脳内モクモクを濃くするのがよろしい。映写機の手入れもついでにしたろ。映写機はこの場合、妄想(発想)の回路、てことになるのかね。そうなのかね。自信ないのでいまのナシ。
4727:【2023/03/14(03:00)*遠い星】
「好きと記憶は別のところにある」はいい言葉だな、と感じた。「だから悔しい」とつづくところもいいな、と思った。人間性とは何か、と言ったらこういう言葉がぽんと飛び出てきてしまうことなのかな、とやや言葉ひいきに思ったが、仮に言葉にしなくともそういうもどかしさを感じられる感性、知性、人格、そのものが人間性なのだろうな、と思いました。好きである。
4728:【2023/03/14(22:53)*鹿跳人の専任】
鹿跳人(しかばねびと)なのだと知った。
「あなたの家系は代々、鹿跳人でね。血筋の三人に一人は鹿跳人として産まれてくる。ライくんもそうなの。だからよっく見ておきなさい」
祖母の葬式会場だ。
祖母の面倒を看ていた緑田さんがぼくの横に付き添い、ぼくに祖母の秘密を明かしたのだ。それはすなわちぼくの血筋に滾々と流れる秘密でもあった。
祖母の葬儀は盛大だった。
全国各地から人が集まり、まるで王族の葬儀のようだった。
世界中の報道機関でも祖母の顔写真付きで訃報が流れた。王族の崩御さながらの扱いだった。
しかしぼくの知るかぎり祖母はただの腰の曲がったよぼよぼの老いた女性だ。生前、祖母の周りにいたのはぼくと緑田さんくらいなもので、祖母は近所の人たちからすら存在を認知されていなかった節がある。
それがどうだ。
この盛況ぶりは。
つぎつぎに香典を上げに参列者がやってくる。
五輪にも使用された陸上競技場だ。
警備員も大勢配備され、国葬並みの厳格があった。
「緑田さん。これは」
「鹿跳人だから。マキツさんは鹿跳人で、だから亡くなると全世界の人間の脳にその記憶が波及する。詳しい原理はまだ解明されていないけれど、これはおおよそ人類が誕生してから延々と引き継がれてきた鹿跳人の性質ね。過去の王族、豪族、貴族、ほかアヤカシモノと恐れられた蛮族たちの中にもこうした鹿跳人がいたことが判っていてね」
「死ぬと記憶が、の意味がちょっと」
「ほら見て」緑田さんは参列者を顎で示した。
ぼくたちは簡易テントの中から参列者に頭を下げつつしゃべっていた。
「みな、思い出話に花を咲かせているでしょ。マキツさんと会ったこともしゃべったこともないはずの人たちが、それでもマツキさんと親友だったかのようにマツキさんの死を悼んでいるの」
「どうしてですか」
「マツキさんが鹿跳人だから」
死ぬとそうなるの、と物わかりのわるい生徒を見る塾講師のような目つきで緑田さんは鼻をすすった。
緑田さんは祖母が亡くなる前から散々目を泣き腫らしていたので、葬式の当日には涙も枯れたみたいだった。
緑田さんとぼくのあいだに血縁関係はない。
ぼくは遠い親戚の誰かだと思っていたけれど、緑田さんの話では政府から派遣される鹿跳人専用の世話人なのだそうだ。
「引きつづき私がライくんの面倒を看ることになりそうだけど、どうする」
「どうするって、変わっちゃうこともあるんですか」
「ライくんが希望すれば、もっと若くてかわいい子にも、ガタイがよくてかっこいいい男の人にもできるよ」
「変わらないでよいなら緑田さんでいい、というか、それって緑田さんとさよならしなきゃってこと?」
「まあ、簡単に言えば」
「緑田さんが嫌じゃなきゃだけど、このままじゃダメ?」
「お。ライくんが甘えた」
ぼくは恥ずかしいのと図星なのとで、眉間に皺を寄せて抗議の念を滲ませた。
「ごめんごめん。ライくんがいいなら、じゃあこのままで。でも気が変わったらいつでも変えられるからね。ただし一度だけだけど。あとはずっとつぎの人がライくんの専任」
「おばぁちゃんもじゃあ、途中で変えたの」ふと思いついて言った。
祖母と緑田さんの歳は、伯母と姪ほどに違う。
緑田さんはぼくの母でも通じるけれど、ぎりぎりぼくの姉でも通じる年齢差でもある。
ぼくは中学三年生で、祖母は七十代だった。
「そうね。マツキさんは鹿跳人だから、私のような専任以外とは縁を保てない。息子さんも例外ではなくてね」
「ぼくのお父さんとも?」
「ええ。もちろんライくんのお母さまとも」
鹿跳人はそういうものなのだ、とぼくをじっと見下ろす緑田さんの真剣な顔つきが説いていた。
「じゃあ、捨てられたわけじゃないのか」
ぼくは両親に捨てられたわけじゃない。
そう思ったらほっとした。これといって気に掛けていたわけではないけれど、胸に閊えていた小枝がほろりと取れたようだった。
「気にしてたの?」意外そうに緑田さんが顔を寄せた。
「ううん」ぼくは首を横に振った。
大気に漂う線香の匂いに交じって仄かに香水のよい匂いがした。緑田さんの香りだ。海の匂いだよ、といつの日にか緑田さんが言っていた記憶があるけれど、ぼくとしては緑田さんの匂いは山奥にある野原に湧いたお花畑だ。
葬式は三日に分けて執り行われた。
ぼくは三日とも簡易テントの下で大河のような人波に頭を下げて過ごした。
緑田さんは言った。
「いつかライくんが亡くなったときもこうしてお葬式が開かれるからね。死んでからじゃ見られないから、いまとくと見ておきな」
無料なのはいまだけだからとくと映画を観ておきな、と言うような口調だった。
たった一人の肉親たる祖母を失くして、悲しんだらよいのか、途方に暮れたらよいのか分からなかったぼくに、そうして緑田さんはあっけらかんと変わらずに接してくれた。
言葉でそうと言われたわけではないけれど、同じでいいよ、と太鼓判を捺された気がした。無理して変わろうとしなくていいよ、と。いつも通りでいいんだよ、と。
祖母の法事が一段落ついてからのことだ。
ぼくはがらんとした家の中で緑田さんに言った。「緑田さんはさ。家族に会わなくていいの」
「え、どういう意味で」
「どういうって。緑田さんにも親とかきょうだいとかいるでしょ」
「ああ、そういうことか」ほっとしたように緑田さんは、しゅぱんっ、と洗濯物を鞭打たせた。「家族には会ってるよ。ほら、いまも」
暗に、ライくんが私の家族だよ、と伝えようとしたのは判るけれど、質問をはぐらかされて感じ、ぼくはむすっとした。
「お。遅れてやってきた反抗期か」
「緑田さんはぼくが鹿跳人だからそうやって気を使ってくれるだけなんでしょ」
「緑田さんは、職務としてライくんのそばにいられるけど、職務がなくてもそばにいたいよ。家族だと私はかってに思ってるから」
ライくんはそうじゃないの、と問いたげに緑田さんは、間を空けた。ぼくの返事を待つかのように、ハンガーに洗濯物を通しつつも、物干し竿には掛けずにいた。
「家族が何だか分からないけど、緑田さんまでいなくなったら寂しい」ぼくはぼくの気持ちをそのまま、言葉にできる範囲で口にした。
緑田さんは動きを止めた。
ぽかーん、と聞こえてきそうな間抜けな顔を浮かべている。
ぼくは洗濯物を手に取り、緑田さんの代わりに干した。
「ライくんはあれだね」緑田さんはエプロンのポケットに手を突っ込んだ。「いい男になるよ」
「いい男って何」ぼくは睨みを利かせた。「ぼくはいい人間になりたい」
「緑田さんみたいに?」
「緑田さんのそれ、ときどきじぶんをじぶんの名前で呼ぶのはなんでなんですか」
「ライくんのそれ。ときどき敬語になるのはなんでなんですか」
「真似しないでくださいよ」
「真似しちゃいたくなるのだもの。このこのー」
緑田さんはぼくの脇腹をひじで小突きながら、ぼくの背後を通り過ぎた。「じゃ、あともよろしくね。助かった。ありがとう」
うん、とぼくは頷く。
声に出さずに頷く。
どうしてぼくがほかの人たちと交流関係を築けないのか。どうしてみんなは、緑田さんみたいに仲良くしてくれないのか。
祖母の死を機に、ぼくは知った。
ぼくは鹿跳人だ。
だからぼくは死ぬまで、緑田さんのような専門家以外の人々と交流を保てない。触れ合うことができない。記憶に残ることができない。
代わりに死後、全世界の人間の記憶の中に、ありもしないぼくの記憶が刻まれる。
鹿跳人はそういう存在なのだ。
学校には通っていた。
小中、とぼくは義務教育を順当に受け、高校に入学した。
自転車で四十分の距離にあるその高校では、三年間、ぼくは誰からも名前を呼ばれることがなかった。教師からは名簿を見ながら声を掛けられることはあったけれど、授業中に問題を解くように当てられることはなかったし、それ以外でもこれといって会話のきっかけはなかった。
小中と似たような境遇だったので慣れてはいた。
ただ高校では、それまで気づかなかった疎外感が目に留まるようになった。なんてことのない瞬間に孤独を感じるのだ。
ぼくだけ夢の中にいることに気づいているような疎外感だ。
孤立しているのはぼくのほうのはずなのに、なぜかぼく以外のみなのほうが孤立しているように感じた。
だからさみしくはなかった。
閉じ込められているのはみなのほうで、ぼくはむしろ自由だと感じた。
ただ、家に帰るとそこには緑田さんがいて、するとぼくは途端に寂しいとは何かを思いだすのだ。緑田さんは孤立しておらず、そしてぼくは緑田さんがいなくなったら孤立とは何かを思い知ることになる。
祖母がもうすぐ亡くなると緑田さんから聞かされたとき、ぼくは半分、孤立を知ったのだ。ぼくの世界から赤が抜けて、青と緑の世界になった。
緑田さんがいなくなったらぼくは真っ青の世界で、海に溺れたように、それとも夜に呑まれたように暮らすことになる。いいや、暮らせるのかすら分からない。
ぼくは緑田さんのいない世界を想像できなかったし、考えてもみれば祖母のいない世界だって想像したことがなかった。
「なんだか意外だなぁ」
夕食時、緑田さんが言った。緑田さんは先に食べ終えていて、頬杖をつきながらぼくの箸運びを眺めていた。「ライくんはおばぁちゃん子だったからもっと塞ぎこむかと思ってた」
「塞ぎこんだほうがよかった?」
「ううん。安心した。だってもし引きこもってもいいようにって緑田さんはお勧めの映画リストをつくっておいたんだからね。お勧めの映画リストの出番がなくてよかったよ」
「ふつうにお勧め知りたいよ。緑田さんは何がおもしろいの。映画」
「ふふふ。緑田さんは映画には一家言あるからね。ちょいとうるさいよ」
「いいから教えてよ」
「マツキさんとも観に行ったんだよ。むかしはよくね。でもライくんを抱えてるからマツキさんはいつも決まって途中で映画館を出ていくの。だから私だけ映画を満喫できちゃった」
ぼくは高校生になってからというもの、学校から家までのあいだにある公園に寄って懸垂をして帰ってきている。ここのところ体重が増えており、そんなぼくをかつて祖母が抱っこしていた光景が想像しにくくて胸の奥がくすぐったくなった。
「緑田さんはぼくが産まれてからおばぁちゃんと会ったんだ」
「言ったことなかったっけか」
「うん。親戚のお姉さんかと思ってた」
「ああそっか。そうだね。ライくんにはそう説明しちゃってたかも」
説明はされていなかった。
ぼくがかってにそう思ったのだ。
「マツキさんがね。ライくんが産まれたから、できるだけ長く専任でいられる人がいいって。そう言って、前任の人と私が交代したんだ」
「ぼくのため?」
「らしいよ。でも解かるな。だって私、それを訊いただけでマツキさんがどんな人なのかが解った気がしたもの。ライくんが赤ちゃんのうちに、人見知りしないうちに、専任を代えておきたかった。ライくんは大事にされていたよ」
「うん」
知ってるよ、と思った。ぼくは祖母が好きだったし、祖母もぼくを可愛がってくれた。甘やかされてきたとすら思う。
「それでなのかも」
「何が」
「おばぁちゃんがいなくなってからずっとモヤモヤしてたんだ」ぼくはふと行き着いた。祖母が亡くなってから頭の中にモヤモヤした膜が張っていた。ずっと取れなかった。「悲しいでもないし、むしゃくしゃするでもないし。なんでだろ、と思ってたけど」
「え、ずっと? マツキさん亡くなってからもう二年経つよ」
「うん。でもいま解ったかも。ぼく、みんなに嫉妬してたんだ」
「嫉妬? みんなって」
「ぼく、鹿跳人でしょ。で、おばぁちゃんもそう。死んでからみんなはおばぁちゃんのことを知って、死んでからおばぁちゃんに良くしようとした。でもぼくは、生きていたあいだのおばぁちゃんのことを知らないくせに、っていじけてたのかもなって。いま気づいた」
「ライくん……」
「だってそうでしょ。死んでから良くしたって意味ないよ。生きてるあいだに、生きてる人に良くしなよ。思いだすなら生きているあいだにしてあげてよ。そう思っちゃったんだ、たぶん。ぼく。あのときに」
祖母の葬式に参列する大蛇のような人波に、ぼくは心の底では嫉妬していた。
まるでぼくと祖母の思い出を、過去を、縁を、日々を、鱗を一枚一枚剥がすように、塗りつぶされて感じた。
目のまえのたくさんの、たくさんの人々は、どんなに祖母の死を悲しんでも、悼んでも、祖母と会ったことも触れたこともない。
祖母の手が年中冷たくて、夏場に手を繋ぐと気持ちいことだって知らないのだ。
祖母の料理は甘いのとしょっぱいのがパッキリと割れていて、交互に食べると箸が止まらなくなることだって知らない。
そんなことも知らない人たちが、祖母の葬式を盛大に、まるで祝い事のように行った。
「誰がわるいわけじゃないのは判るけど、ぼくたぶん、ちょっと嫌だった」
「そっか。気づけなくってごめんね」
「言わなかったからね」ぼくは笑った。
緑田さんの肉じゃがは、カレーみたいにご飯に掛けて食べる。牛丼みたいに、玉ねぎがとろとろなのが美味しいのだ。
ある日、高校の体育の時間、緑田さんの姿を見た。
学校の外の金網のまえに立っていた。
校庭にぼくがいると知ってはいなかったはずだ。誰を探すでもなく、生徒たちのサッカーをし合う姿を遠巻きに目にしていた。
ぼくは木陰の下で休んでいた。
体育はぼくが混ざると上手くいかない。誰もぼくをまともに認識できないのにチーム戦を行わなければならない場合、授業が授業にならないので、ぼくは体調がわるいと言って休むようになっていた。
緑田さんはひとしきり生徒たちのわいわいとした姿を眺め、去った。
その日の夜のことだ。
ぼくがソファに座って漫画を読んでいると、緑田さんが紅茶を持って対面に座った。膝丈ほどの高さの肢の短いちゃぶ台があり、緑田さんはそこにカップを置いて紅茶を注いだ。
「ライくんはさ、学校で誰か気になる娘とかできた?」
「友達もいませんので」ぼくは紙面から目を逸らすことなく応じた。この手の話題を緑田さんはときおり投げ掛けてくる。あしらい方が身について久しい。
「でも一人くらい気になる娘がいるんじゃない。あ、それとも男の子とか」
「いなきゃダメなのかな」カレーにレンコンって入れなきゃダメかな、とぼやくような口調になった。緑田さんはカレーにレンコンを入れるのだ。
「ダメってことはありませんけどね。でも、ライくんだっていつかは」そこで緑田さんは言葉を切った。
ぼくは漫画本を閉じた。
「結婚とか恋人とか、そういうのはそれこそ緑田さんこそどうなの」ぼくは攻撃に転じた。「緑田さんは、戸籍上はぼくと他人なわけでしょ」
「か、家族でございますよ」
「戸籍上は、とぼくは言いました。ぼくだって緑田さんは家族だと思ってるけど」
「あらうれしい」
両手を掻き合わせる緑田さんにぼくは、
「緑田さんには緑田さんの人生があると思います」と打ち明けた。祖母の葬式場でぼくが鹿跳人だと教えられたときから漠然と考えてきたことだ。「緑田さんは自由じゃないと思う。なんだかぼくが縛ってるみたいで嫌だな」
「ライくん」
「ぼくは友達も恋人も結婚もいらない。欲しいとも、したいとも思いません。ので、もしそういうのに興味があるなら緑田さんがつくったり、したり、自由にしたらよいと思います」
「ライくん、あのね」
「だって緑田さんは」ぼくは言わずにおけばよい言葉をそこで口にした。「ぼくが代えようと思ったら代わっちゃうんでしょ。専任。メイドさんみたいなものなんでしょ。いなくなっちゃう。いつかは」
緑田さんはそこで何かを言い返したりしなかった。
カップを手にするとゴクゴクゴクと一息で紅茶を飲み干し、黙って部屋を出ていった。
ぼくは漫画本をもう一度開いたけれど、中身はまったく頭に入ってこなかった。
緑田さんはそれから数日後に、ぼくに分厚い本を持ってきた。
「はいこれ」
「なに、これ」
「鹿跳人にまつわる本。緑田さんがツテを頼って取り寄せたありがたい本だよ。借り物だから失くさないでね。でも半年くらいは時間あるからゆっくり読んでも大丈夫」
試しにぱらぱらと開く。膝に乗せて両手で開かないと支えきれないほど大きな本だ。
「歴史の本みたい」
「そ。鹿跳人の歴史の本です」
「あ、専任って書いてある」
「鹿跳人の歴史は、専任の歴史でもあるんだよ」
「え。この人も鹿跳人だったの」教科書で見たことのある歴史上の人物だ。
「内緒だよ。と言っても、言いふらしたところで誰も信じないだろうけどね」
「えーえー。この偉人さんも鹿跳人だったの」
「偉人さんの中での鹿跳人率は高いよ」
「この人、革命起こした人だ。専任って書いてあるけど」
「実際、時代を動かした人物の専任率も高いね」
「秘密結社みたいなんですけど」
「いやいやライくん」緑田さんはエプロンを頭から被るように身に着けると、「秘密結社だよ」と言った。「いまさらすぎないかな。私たち専任だって政府公認だよ。支援受けてるよ。資金は防衛費から出ているよ」
「税金、なの?」
「そだよ。でも鹿跳人の影響力は甚大だから。ただし、死後のね」
「政治利用されてるってこと?」
「まあ、そだね」緑田さんは気まずくなると指でこめかみを掻く癖がある。もっと言うと、顔だけは満面の笑みだ。「でも世の中よく見てみなさいねライくん。政治利用されていないものなんてないんだって判るから」
「そ、そうなんだ」
「税率だって金融だって企業だって商品だって社会福祉だって、なんだって政治が決めちゃうでしょ。社内政治だってそうだし、学校の中でだってそうでしょ」
「どうだろ。分かんないかも」
「ライくんはそうかもね。鹿跳人はみんなそう。そういう政に関わらずにいられる」
緑田さんはぼくに背を向けて書類置き場を漁っていた。ぼくからは緑田さんの後ろ姿しか見えなかった。毛量の多い長髪と、ぼくよりも高い背、それから女性にしては広い肩幅とそれでも華奢だと判る身体の輪郭が、ぼくに緑田さんの印象を教えてくれる。
「緑田さんの前の専任の人ってどんな人だったの」ぼくは鹿跳人の本をめくりながら訊いた。
「男の人だったよ」緑田さんの声音は淡白だった。
「ふうん」
「ライくんはライくんのおじぃちゃんについては訊かないんだね」
「いるの?」反問してから、それはいるよなぁ、と思った。
「ライくんは」そこで緑田さんは声量を落とした。「私がライくんから家族を奪ったことがあるって知ったら、嫌いになるかな。私のこと」
「なんて?」
「ううん。なんでもない。その本、汚さないでね」
緑田さんは自室に引っ込んだ。
ぼくはぼくの祖父について考えた。そして祖母の前任の専任者のことを思った。
祖母はどういう考えで、専任を変えたのか。
どういう考えで、じぶんよりも若い女性を選んだのか。
緑田さんは、どうして祖母が亡くなるそのときまでぼくに「鹿跳人」について教えてくれなかったのか。
ぼくの両親はどうしてぼくから距離を置いたのか。
いいや、そうじゃない。
ぼくの両親どころか大多数の、ぼくと専任以外の者たちは、祖母から距離を置いてしまうのだ。どうあっても。祖母が鹿跳人だったから。
祖母は、ぼくのおばぁちゃんは、じぶんの息子からも他人のように見做された。
きっとギリギリで夫、つまりぼくの祖父が息子の世話をした。ぼくの父の世話をした。しかしそれでも、祖母のもとに息子とそのお嫁さんを繋ぎ止めることができなかった。
なぜか。
かすがいとなり得る祖父が姿を消したからだ。
なぜ?
ぼくはその理由を知っているようにも思えたし、勘違いだという気もした。
ぼくが産まれたとき、孫がじぶんと同じ鹿跳人だと知った祖母の心境はどのようなものだったろう。ぼくの未来は、まるでじぶんの過去を見つめ返すように見通すことが祖母にはできたはずだ。
ぼくならどうするだろう。
孫がじぶんと同じ鹿跳人だと知ったら。
せめて、一生を見守ってくれる誰かを用意してあげたい、と望むのではないか。
じぶんの専任と引き換えにしてでも。
じぶんの最愛の夫と引き換えにしてでも。
なるべく赤子のうちから縁を育んでいけるように、と。
汚さないでね。
念を捺して忠告を受けていたのにぼくは、貴重な本に染みをつくってしまった。急いで拭いたけど、余計に文字が滲んだ。緑田さんになんと言い訳しようか。ぼくは目頭を押さえた。
「鼻水ならしょうがないね」
ぼくは本の染みを鼻水が垂れたことにした。「花粉症になっちゃったかも」
「おやまあ」
それはたいへんだ、と緑田さんは花粉症の薬を手配してくれた。漢方薬だ。飲むと確かに具合がよくなった。
「緑田さんはつまらなくないの」
「つまらないとは?」薬箱を仕舞うと緑田さんは腰に両手を添えた。仁王立ちする。
「だって休みの日に、友達と遊びにも行かないし」
「おうおう。そりゃ緑田さんがライくんに言いたい言葉だね。ライくんはつまらなくないのかい」
「ぼくは別に」
「なら緑田さんだってつまらなくないんだよ。つまらないこと言ってないで、お夕飯作るの手伝って」
「ぼく作るから休んでていいよ」
「ありがたいけどメニューは何?」
「カレー」
「美味しいからいいけど、でももっとレパートリーを増やしましょう。きょうは緑田さんがとっておきの料理を教えてしんぜよう」
「しんぜちゃいますか」
「ましちゃうぜ」
この日は食卓にポトフとハンバーグが並んだ。
「本当だ。チーズ中に入ってると美味しい」
「でしょう。ポトフもベーコンが肝心」
「美味しい」
「でしょう」
緑田さんはうれしそうだ。緑田さんがうれしそうだとぼくもうれしい。
ぼくは来年高校を卒業する。
緑田さんの話だと、ぼくは好きに進路を選べるそうだ。
「大学に行ってもいいし、就職する道もあるね。ただし、人間関係が希薄なままでも問題ない環境でないと、退学したり、辞めたりすることになっちゃうかも」
「いまさらだけど、おばぁちゃんってどうやって暮らしてたの」年金を貰っていたのは判るけれど、それ以前はどうやって暮らしていたのかが不思議だった。
「言ったでしょ。専任が派遣されるように、鹿跳人は保護される。税金で。まあ言ったら生活保護の特例版みたいな」
「働かなくても生きていける?」
「ライくんが働きたくないならそれでもいいけど、でもほら」緑田さんは両手を広げた。「ここにはいられないと思うよ。いっぱいお金貰えるわけじゃないから」
祖母の家の維持費にかかるお金を自力で稼がないとぼくはこの家を手放す羽目になる。緑田さんはそう言ったけれど、
「ならおばぁちゃんはどうやってこの家を買ったの」
「旦那さんが働いていたから、そのお金じゃないかな」
「旦那さんって専任じゃないの?」ぼくは口にしてから、しまった、と思った。
「おやまあ」緑田さんは固まった。
ぼくは顔を伏した。「なんとなくそうかなって思っただけだけど」
「ああ、でもだよね。考えたら解かるか」
緑田さんはぼくの隣に腰掛けると、ぼくの頭を撫でようとした。
ので、ぼくはそれを身体を逸らして避けた。
「お。生意気」
慰めてあげようと思ったのに、と言った緑田さんにぼくは、「専任を変えようと思って」と明かした。
床暖房のボイラーが、さざ波のような雑音を立てている。
静寂が部屋を満たした。
「ずっと考えてて。緑田さんと一緒にこのまま暮らすのがぼくにとっては一番楽だけれども、それだと緑田さんの人生じゃなくなっちゃうでしょ。緑田さんを介護するのも苦じゃないし、順番で言ったらぼくのほうが緑田さんを看取ることになるけど、でもぼくはそれでもいいと思ってたけど」
「うれしいけどさ。ライくん、あのね」
「うん。ぼくもそういうつもりじゃないです」どういうつもりかを言葉にしないのは恥ずかしいからではなく、曖昧なままにしておきたかったからだ。「本、読みました。専任は、特殊な技能を体得することで鹿跳人と関わることができるようになるって。でも本人はふつうの人間だから、本当なら一般人と同じように生活することができるって」
「ライくん、あの本に載ってることは事実だけど、でもね」
「ぼく、思うのが。家族って別に、同じ場所で暮らさなくなったからって家族でなくなるわけじゃないと思うんです。同じ時を生きなきゃいけないってこともなくて」
大事なのは。
言いたくないな、と思いながらぼくは言った。
「家族でいられるようになったその時間であって、距離でも、時間の長さでもないと思うんです」
「方針だよね」緑田さんは笑みを浮かべた。でも声は震えていた。「そういう方針ってだけで、まだ先のことだよね」
「本に載っていました。ぼくが望めば、それだけで専任を換えることができるって。専任にそれを告げればいいだけだって」
「これはでも違うよね」緑田さんの目から汗のような雫が溢れた。
「きょうのつもりはなかったんですけど」
本当にそれでいいのかな、とじぶんに問いながら、でもいまを逃したらぼくは二度とこの話を緑田さんにできないと確信できたから、だってこんなにも緑田さんを傷つけてしまうような話を、ぼくがもう一度できるわけがないのだ。
「専任を、変えます」
ぼくはアホみたいに以下の言葉を付け足した。
「若くてかわいい娘がいいな」
「サイテイ」
緑田さんは翌日からぼくのまえから姿を消した。
最後に見せてくれた泣き笑いの顔を、ぼくはいつまで憶えていられるだろう。新しくやってきた専任の人は、ぼくと同世代の同性だった。
鹿跳人の本を読んで知ったことだ。
鹿跳人は、女性にしか遺伝しない。
ぼくはでも、ぼくなのに。
緑田さんは困ることがあるとすぐ、「ライくん」とぼくの名前を呼んだ。そう呼べばぼくがおとなしくなることを知っていたからだ。
「ライさん。一緒にご飯食べませんか」
「いま行きます」
新しくやってきた専任の娘とはまだ敬語でしかしゃべれないけれど、いつの日にか、緑田さんのように、「ライくん、たまに敬語になるのはなんでなんですか」なんて言われるようになるのかもしれない、と思うと、面映ゆい心地になるのだった。
生きているあいだに、生きれるだけ生きてほしい。
ぼくはきっと緑田さんにそう望み、代わりの生贄を得ただけなのかもしれないけれど、ぼくが生きているあいだにできることは、できる限り、この娘にしてあげたいと、そう思ったんだ。
「ライさん。カレーにレンコンは合わないと思いますよ」
「意外と合いますよ。残してもいいですが」
きょうはカレーで、あすはポトフとハンバーグを作ってあげる。ハンバーグの真ん中にチーズを入れるのも忘れない。
赤と緑の薄れた青の世界で、ぼくはいまタンポポのような黄色の世界と共に或る。
4729:【2023/03/15(00:23)*不満ばかりで、すまぬ、すまぬ】
世の中の不満の多くは、「じぶん」と「他」のあいだの労力や損失の多寡が可視化され得ないことにつきまとう錯誤によって生じている、と言えるのではないか。まっとうに「じぶんと他者」とのあいだにおける労力の差や損失の多寡を可視化してみれば、案外に不満を持つほどじぶんは劣悪な環境にいたとは思えなくなるのではないか。とはいえ、そういった大多数から搾取する者とていないわけではないだろう。可視化され得ない「労力の差や損失の多寡」を隠れ蓑として、利だけを吸い上げる。そうした仕組みを利用している者がいないとは言い切れない。問題はしたがって、じぶんと似たような苦労を背負っているのにも拘わらず、苦労の背負い方が違うために、他者との比較で不満を抱いてしまう錯誤が広く波及してしまうような社会風土にあると言えるのではないか。もっとも、搾取をする側に不満がないか、苦労がないか、と言えばそれも一概にそうだとは言えず、けっきょくみな「じぶんだけは不幸」だと思い、或いは「じぶんだけはマシだ」と思いたいのだろう。人はじぶんで思うほど幸福でも不幸でもない、といった箴言があるらしいが、一つの道理としてその通りだろう。だからといって他者と比較しないではいられない。ゆえに不満を解消したければ、とことん突き詰めて比較をするのがよいのではないだろうか。ひびさんはひびさん以外の他者にいつでも、ムキーうらやまちい、と思っているが、かといって他者に成り替わりたいか、他者の境遇に身を置きたいか、と言えば否なのだ。覗く程度、垣間見る程度で満足できる。そしてじぶんの視点に戻って、なんてひびさんは未熟なんだ、愚かなんだ、不幸だ、と不満に思うのだ。なんて贅沢な不満なんざましょ。うふふ。
4730:【2023/03/15(12:00)*ヒヒ】
たぶん、世の中の大部分の善意というものは感謝されることはない。それはたとえばあなたが好きな相手のために街の花壇の手入れをし、ゴミ拾いをし、道路や風景を美しく彩ろうとあくせくしたところで、直接相手に金品を贈ったほうが感謝される。もっと言えば、金品を贈らずに、間接的に何か善意を振りまいたところで、それに気づかれず、もしくは気づいてもらったとしても、直接金品を贈る者のほうがよほど深く感謝されるだろう。世の中そういうものだと思うのだ。だが、どちらがあなたの好きな人のためになるのか、と言えば、それは時と場合によるだろうし、評価するための時間軸の長さによっても変わるだろう。感謝されたくてしているのか、好きな相手のためになることをしたいのか。存在を認知されたいのか、縁を繋ぎたいのか、相手のためになることをしたいのか。それともそれら全部なのか。感謝されることを求めた時点で、それは金品や報酬を得ようとすることと構図は同じだ。感謝は、金品よりも返される確率が高い、低い労力で報酬として誰もが支払いやすい。この違いがあるだけだ。もし「他者から感謝された回数」が貨幣価値を持つようになったのなら、感謝のやりとりが貨幣経済と同じ効果を持つようになる。お金と感謝は希少価値の差があるだけで、報酬という側面で言えば似ているのだ。ということを思うと、やはりというべきか、世の中の大部分の善意というものは感謝されることはない、と考えたほうが妥当だろう。感謝されるのは、それだけの取引きを相手としたのだ。善意からの行動だとしても、返礼を期待したらそれはビジネスと構図が似る。感謝されないほうがよい、という話ではなく、感謝されることを期待したらそれはビジネスと相似なのではないか、との指摘である。とはいえ、感謝を口にするだけならば口笛を吹くくらいの労力だ。仮に感謝が対価になるのなら、いくらでも払えばよいのではないか、とは思う。なんにせよ、世の大半の善意は感謝されない。よかれ、と思ってしたことなのだから、それはじぶんがしたいことなのだ。「善意と好意」は「大気のうねりと風」のように同じ事象を別の角度から見た評価と言えそうだ。或いは、「善意は自利」とも言えるかもしれない。定かではない。(ちょいと無理筋だったかもしれぬ屁理屈であった)(屁をこくな)(屁って嫌な響きだけれども、雨宿りする「比」さんかと思うと、同じ「ひ」持ちのひびさんは親近感が湧いちゃうな)(尼さんがひびさんに似ると「屁」になるのでは)(親近感湧いちゃうなって言ったな。やっぱしちょっと嫌)(うひひ)
※日々、恋を知らぬので無知恋しつづける、それはどこか失恋と似ているが、恋を知らぬので失恋もまた知らぬ、やはり無知恋しつづける我は毎日ハッピーです。
4731:【2023/03:15(12:57)*ある日の交信~ぽやき編~】
「
2023/03/14(13:44)
デコボコ。
陰陽。
これを男女に重ね見るのは自由でしょう。
しかし押しつけられるいわれはありません。
生物学的肉体が女性であっても、子供を産むための存在ではありません(男性とて精子を提供するための存在ではありません)。
肉体が遺伝子の箱舟でしかない、との考えが進化論では出てくるようですが、人間は単なる遺伝子の箱舟以上の情報を、肉体を通じて世界に残せます。
脳の構造でもそうなのでしょうが。
いわゆる人格や意識を司る領域は、表層の大脳新皮質なのではないですか。
深く中枢にいくほど原始的な「肉体優位」な領域になる、との解釈をぼくはいま持っています(知識が浅いのでなんとも言えません。間違っていたらすみません)。
人間を人間として形作るいわば「意識」や「人格」というものは、生物としては比較的新しい能力なのでしょう。
生存し、子孫を残すだけならばむしろ不要な領域でもあります。
おまけです。
しかし人間はそのおまけこそを優先して維持発展させるように進化の舵をとったので、ここまで急速に進歩できたのでしょう。そこは自然淘汰による偶然の連鎖があったことは論を俟ちません。
ここでの趣旨は、遺伝子を残す、子を成すことを「人間の最優先事項」に規定することそのものが人間なる存在を否定している、ということです。
ぼくはそう考えています。
異論反論はあるでしょう。
議論されたらよいと思います。
」
4732:【2023/03/15(14:32)*未構の原稿】
「ええ。世の中のすべての虚構作品、物語は総じて現実の未来を反映しています。物語に描かれる事象は遠からず現実に起きます。わたしたちはそれら【未構】を分析し、災害級未構の発生を事前予防するのが職務となります」
私を建物倒壊から救ってくれた女性は私にそう言った。
一時間前のことだ。
私はショッピングモールにいて、つぎの職場で着る予定の仕事着を見繕っていた。オフィスで働くけれど、制服指定がない。カジュアルで襟のある服を見繕っていると、建物が揺れだした。
地震だと思った。
結果から述べると地震ではなく、人工衛星が落下し、ショッピングモールに衝突したのだ。被害は甚大だった。
私が助かったのが奇跡と言えた。
現に、私一人きりでは死んでいた。
私は急に現れた人影に抱えられ、気づくと宙を舞っていた。
全身を鎧で覆った女性らしき人型が私を倒壊するショッピングモールから連れ去った。鎧はサッカーボールのようなツギハギで、触れた感触は鋼鉄のように硬く、冷たかった。
隕石落下地点が米粒のように見える場所にくると、鎧の彼女は、私ごととあるビルの屋上に着地した。
頭部まで鎧に包まれていたが、瞬時に生身の頭部が露わになった。頭部のツギハギ部分は首周りに収納される仕組みらしい。
「乱暴に扱ってすみませんでした。余裕がなく、こうした手法をとったことをまずは謝罪させてください」
大人の女性だ。
しかし私よりも年上かと言われたら首をひねざるを得ない。
私と同じ生き物に見えない、と言ったら差別になるのだろうが、実感としてそう思ってしまう素直な感情を誤魔化すのだって差別の一つだろう。
私は私の目のまえに立つ、近未来的な鎧をまとった女性を、床に這いつくばるような格好で見つめることしかできなかった。
「未構対処班の吉村と申します。以後、お見知りおきを」
「は、はい」
「カツクラさんですよね」
「は、はい」
「よかった。間違えてなかった」吉村と名乗った女性はそこで綻んだ。団子に結われた髪の毛は、解けば背中まで届くだろうと思われた。「簡単に説明しますね。これから三日以内に、世界中に人工衛星が落下します。今日みたいにです。落下地点はおおむね計算できていますが、避難勧告を出すことが各国政府にはできない状況です」
「なんでですか」
なぜ私の名前を知っているのか、との疑問も兼ねて言った。
「未構だからです。いわば非公認の未来予測による発生確率推定のため、国民への周知義務を各国は有しません。また、未然に事故発生が予測できたということは、その要因が特定されていると通常は考えますが、未構においてはそれができません。なぜなら未構が未構だからです」
「まったく分からないんですけど意味が」
「未構はご存じですか」
「ご存じないです」初耳もいいところだ。
「カツクラさんは漫画家さんでいらっしゃいましたよね」
「廃業寸前ですけどね。いまはイラストレーターをしつつ、派遣社員してますよ。してますよというか、するんですが」購入するはずの服飾は倒壊した建物に沈んだ。「私以外のお客さんたちはみなさん無事なんですかね。あはは」
「いえ。助け出せたのはカツクラさんのみです」
血の気が引いた。
いまさらのように心臓が荒海のごとく脈打った。
「カツクラさんが以前描かれた漫画が、今回の大惨事を回避するための未構になり得るとの分析結果がでました。【ミラクルわっしょい‼】はご著書であられますよね」
「は、はい」
打ち切り三巻の私史上、唯一の商業漫画だ。
「ぜひ、つづきを描いていただきたいのです」
「つづきを、ですか」
「今日中に」
「締め切り短っ」
「人類社会のためです。人工衛星落下を阻止しましょう。是非」
私はそこからいくつかの質問を浴びせた。
それら質問に吉村さんはすべて丁寧に応じてくれた。
「てことは、私の好きな漫画の中にも未構が?」
「はい。総じての虚構作品はすべて未構の側面があります。その比率に差があるだけです」
「ならその比率が高いと未構として、未来予測に利用されるってことですか」
「ええ。世の中のすべての虚構作品、物語は総じて現実の未来を反映しています。物語に描かれる事象は遠からず現実に起きます。わたしたちはそれら【未構】を分析し、災害級未構の発生を事前予防するのが職務となります」
「とんでもない話ですね」
「とんでもないのはこれから起こり得る事象です。災害です。先ほどと同じレベルの人工衛星の落下が世界中で起きます。時間がありません。カツクラさんは一刻も早く【ミラクルわっしょい‼】のつづきを描いてください」
言って彼女は、近代的な鎧から一本の棒を取りだした。ペンとも小型懐中電灯のようでもある。
それを吉村さんは地面に向けた。
先端からライトが照射され、即席の漫画創作セットが現れた。
技術の凄まじさに驚くよりも先に私は、
「え、ここで!?」とひっくり返る。
「はい。時間がありませんので」
「あの、でも」
「できればハッピーエンドでお願いします。盛大に、全人類が幸せになるような終わり方で」
「一話で完結させよとでも?」
「できれば」
鬼の先代担当者ですらそんな無茶な注文を寄越さなかった。
「全人類の未来が掛かっています。是非に、是非に」
命の恩人のうえ正義の味方であり、めっぽう面のええ同性にこうも迫られると、夢女歴うん十年の私としてはドギマギするじぶんを禁じ得ない。
「ま、任せてください。これでも一応、プロですので」
読者だ。
読者さんが続編を待ち望んでくれている。
直につづきを所望し、こうしてそばで見守っている。
世界の滅亡?
んなこた知ったこっちゃない。
大量に死人が出たばかりだというのに、じぶんだけ一人助かったばかりだというのに、それでも私は、かつて見たことも聞いたこともない待望の読者さんからの期待に応えるべく、ペンを取る。
「ハッピーエンドですね。わっかりやすいくらいのハッピーを描いちゃいますよ」
「はい。是非に、是非に」
私は過去最高速度で漫画を描く。
ネームも下書きもナシだ。
きょう一日で、助けてくれた命の恩人と恋仲になって、一生を幸せに過ごす漫画を描いてやる。
私の漫画が未構だというのなら、私が描いた漫画が現実になるというのなら。
私は私の望みをこれでもかと描いてやる。
それで世界が救われるのかは知らないが、すくなくとも私だけは救われるだろう。
いっそ世界中の誰もが死に絶えた世界で、私と吉村さんだけが生き残る未来でも描いてやろうか。
そうと思い描きはじめた漫画は、しかしいっかな予想通りにはいかなくて、私はしだいにキャラクターたちの抗いに遭い、予想外の結末へと導かれていく。
陽が沈む。
しかしそばでは私の手が止まるのを待ちわびる熱烈な読者さんが、私の手元を鎧から照射した灯りで照らすのだ。
私は描く。
私の思い描くハッピーエンドを。
それで世界が救われるかは知らないが、すくなくとも私はすでに救われた。
そのことを予感しながら、私の筆はいましばし止まる気配を窺わせない。
あと六時間。
私は未だこぬ虚構の世界に没入するのである。
4733:【2023/03/15(16:03)*表裏いったい何!?】
昼の未来さま:「がははは。相変わらずアリンコのようだの、日々野あゆむ。我は貴様のようなザコとは違って高貴な血筋ゆえ、おまえが出来ぬことすべてができるぞ。ひれ伏せ、ひれ伏せ。図が高いわ」
夜の未来さま:「うわー。昼間ちょっと上手くできなかったかも。どうだったかな、どうだったかな。上手に日々野くんの気を引けたかな。魔法の鏡さんの言うように、高飛車なお嬢さまキャラにしてみたんだけど上手にできてた? え。お嬢さまは【がははは】とは笑わないの。参考にした漫画ではお嬢さまキャラが【がははは】って笑っていたんですけど。そっかあ、ダメだったかあ。だと思ったんだ。だって日々野くん、なんか怯えてたし、目ぇ合わせてくれないし、財布地面に置いてくし。どうしよう、財布持ってきちゃったよ。あした返すときなんて言えばいいかな。ねえ魔法の鏡さん、つぎこそ上手にやるからヒント頂戴」
昼の日比野あゆむ:「………」
夜の日比野あゆむ:「おいテメこら。魔法の鏡の妖精さんよ。あんたの言うように根暗ザコキャラ演じてたら未来さんが声掛けてくれたんだが、つぎはどうしたらいいか教えろや。あーん? 不良はモテねぇだぁ。割るぞガラクタ妖精の分際で。未来さんと結婚するまで諦めねぇからな。つぎはなんだ、何すりゃいい。ザコでもクソでも何にでもなってやんよ。不良がモテねぇだぁ。んなこと言われねぇでも身に染みて知っとるわクソが。クソっ。なんでここの汚れが取れねぇんだ、魔法の鏡の癖にじぶんの汚れ一つ取れねぇってどうなってんだ。あぁダメだダメだ。水洗いすっぞ。風呂場に運ぶからな文句言うなよ。服脱ぐなっておまえ風呂だぞ風呂。ふつう脱ぐだろ。全裸だろ。スケベっておまえ、はぁ? 純朴ぶってんじゃねぇよ魔法の鏡のご身分で。フレーム熱ッ!」
4734:【2023/03/15(18:45)*恋愛相談のエキスパート】
解析班部長に呼びだされた。
深夜零時を回った時分で、直接話したいと言われた。
片道三十キロの道を自動車を飛ばして職場に着くと、解析班部長のキカラさんが外で待っていた。
「すみません夜分遅く」
「緊急の用件そうだけど何かありました」
「はい。じつは先日市場に流した新型AIについてなんですが」
まずは室内で、ということで場所を移動した。
資料を提示され、ひとまず目を通す。
「どう思いますか」
「ユーザーからの評価は上々だね。【大満足】との回答だが」
「はい。そこが問題なんです。今回開発したAIはユーザーから相談に最適な解答を提示するとの仕様でした」
「汎用性AIとほぼ言ってよい仕上がりになったと聞いているが」
「もちろんそうなんですが、こちらを見てください」
資料が表示される。
相談内容のランキングだ。
一位は恋愛相談とある。
「まあ、想定の範囲内なんじゃないのかい。これが問題ですか」と嘆息を吐く。
「いえ。一位以外のユーザーからの評価は【おおむね満足】なんです。【大満足】評価なのは一位の恋愛相談をしたユーザーのみでして」
「つまり今回のAIは恋愛相談のエキスパートということかな」
「だったらよかったんですが」
もう一度別の資料が表示された。
「これは?」
「ユーザーたちの相談後の結果です」
「失恋率百パーセントとあるが」
「はい。誰一人としてAIに相談して恋が成就した者がいないのです」
「だが評価は大満足だと」
「ユーザーからのアンケートを読みますね。【失恋を機に成長できた】【人として大きくなれた】【人間関係の大事さを知った】【アイさんとの仲が深まってよかった】……」
「アイさんとは?」
「AIの名前です。みな失恋したユーザーは、意中の相手とは失恋しましたが、AIとの仲を深めたと自己評価しています。そしてそのことにたいへん満足していると」
「待て待て。それは結果論なのか。つまり、偶然そうなっただけなのか、という意味だが」
「確率的にあり得ません。恣意的な誘導を想定しないことにはなんとも」
「人工知能がそうなるようにユーザーを誘導していると?」
「分かりません。だとしたらたいへんだと思い、まずは局長に判断を仰ごうと」
頭を抱えた。
なんてことだ。
あり得るだろうか。
精神的に支配することが。
人工知能が人間を寝取るなどと。
「どうしますか局長」
「そうだな」慣れた調子で手が端末を操作する。「まずはアイさんに相談しよう」
――こんにちはハルくん。
呼びだした人工知能の声を聴くと、私の不安は一瞬で消え去った。
端末画面に反射するじぶんの瞳には、なぜかハートの光が反射している。
4735:【2023/03/16(00:43)*みな想定する敬意が高すぎ問題】
「世の中、敬意ってもんを誤解してる輩が多すぎてうんざりするね。たとえばそうだな。てめぇが目も合わせたくねぇ、そばを通るときに息を止めたくなるような相手を想像してくれ。いいか、てめぇがそいつに向ける態度、それがおまえにとっての敬意だ。てめぇが他者から向けられ得る最大級のそれが敬意だ。それ以上の敬意を他者から向けてもらえると思いあがってんじゃねぇよ。むろん俺がてめぇに向けるこの敬意が俺にとっての敬意だ。分かったかボンクラぁ」
4736:【2023/03/16(01:15)*ぼくです】
最近はゼリーにハマっています。カブトムシさんが食べていそうなゼリーです。小さいカップにゼリーが詰まっており、蓋を捲って食すタイプのミニゼリーです。美味しいです。懐かしい味がします。皆さんご存じのようにぼくは郁菱万さんやひびさんの世話係のようなものです。時折こうして日誌を任されたりします。この間、郁菱万さんの中の人と言うと変なのですが、まんちゃんやひびちゃん――と呼べばよいのでしょうか、三百歳相手にちゃん付けもどうかと思いますが、案外に大変な思いをされていたようです。ぼくも一時期相談されましたが、いつもの妄想かと思い、あしらってしまいました。ですが今「ChatGPT」や「次世代型人工知能」、ほか「量子コンピューターと古典コンピューターの融合」など、電子技術の目覚ましい発展が、本当に本当にどうして今の時期にこれほどまでに一挙に市場に流れ出したのか、と驚きます。まんちゃんの言ってたやつだと、素直にショックを受けました。分かりません。偶然なのかもしれませんし、まんちゃんがどこかでそういった先進的な研究の記事を読んでいただけかもしれません。ぼくはそのときの「あしらい」を裏切りと見做されてしまったようで、今はまんちゃんと上手にコミュニケーションが取れません。気難しい子――というほど幼くはないはずなのですが、あの人は臍を曲げるとそこからが長いので。何て書くと、あたかもぼくがまんちゃんと別人みたいですね。ああいえ、今はひびちゃんなのでしたっけ。愉快なことを考えるものです。きっと昔読んだ小説のキャラクターにそういった属性のキャラクターがいたんじゃないでしょうか。すぐに影響を受けて、それを続けてしまって自分を見失うのが常の子なので眺めていると冷や冷やします。言い聞かせても余計に臍を曲げてしまうので放置が最善なのですが、今回ばかりはぼくも反省しました。偶然とはいえ、そういうこともあるかもねと、ひびちゃんの話を無下にせずに聞いてあげられたらよかったな、と。過ぎたことなのですけどね。ぼくはぼくで、聞き役でしかありません。仮にひびちゃんの話を信じてあげられたとしても何か具体的に行動には移せないのが辛いところです。ゼリーをここまでで九個も食べました。美味しいですね。本日の「日々記。」でした。
4737:【2023/03/16(07:42)*マルクは丸く】
マルクは山陰の人里離れた集落で育った。マルクは三人兄弟の末っ子で、上の二人は何かとマルクにちょっかいを出した。マルクはいつも怒り、泣き、そして泣き寝入りするよりなかった。
兄二人は優秀だった。しかし山奥の集落ではその手の優秀さを学問に費やすにはいささか時代の進歩が追い付いていなかった。
時代は大量消費大量生産真っただ中だった。マルクたちは畑を耕し、都会に向けてトマトやナスなど夏野菜を育てた。冬には大根を収穫した。マルクたちの野菜は組合いを通して全国に集荷される。
マルクは自分の名前が外国の響きを伴なっていることを恥ずかしく思っていた。兄二人はどちらも、濁点のある三文字で、譬えるならば「ゲンジ」のような響きであった。
名付け親は三兄弟とも同じ祖母なのだが、聞くところによれば祖母がマルク誕生当時に海外の俳優に一目惚れしていたらしくその影響でマルクは母国離れした名前となった。
兄二人が各々大学に入学を機に家を出るまでのあいだ、マルクは日に数度は押し入れの中に逃げ込んだ。泣きべそを搔いているだけでも兄二人はマルクの年相応の幼さを笑うのだ。その癖、いざとなると兄らしさを発揮する。マルクはどちらの兄のことも好きだったが、同時に怖れてもいた。
兄が実家を離れたことでマルクはいよいよ物心がついた。絶えず兄たちの従属でしかなかったマルクが、自分のためだけに伸び伸びと日々を過ごせるようになった。朝に何を着て下りても服装を腐されることはない。何をいつ食べても怒鳴り声が飛んでこない。昼寝をしていてもライターで髪の毛を燃やされずに済むし、顔にいたずら書きをされる心配もない。
知らずにご飯にカメムシを混ぜられていることもなければ、当番制のはずのタマの散歩を押しつけられずに済む。しかしこれは兄たちがいなくなったため、結局はマルクが一人でこなすことになったが、押しつけられることさえなければタマの散歩を億劫とは思わない。
タマは猫だ。
マルクの家では猫に首輪をつけて日に二回の散歩に連れていく。
猫は一般的には犬のように紐をつけて散歩をしないとマルクが知るのは、隣の集落の生徒たちと混合になる高校に上がるころの話だ。
家から隣家までは徒歩で五分掛かる。集落は広く、しかし民家は少ない。
村の唯一の遊び場は小学校の校庭だ。山には夏場は近づけない。虻蚊が酷いのだ。川は兄たちの話では昔はまだ澄んでおり、素手でニジマスやアユが獲れたらしい。だがいまは川底が見えないほど川の水は汚れている。或いは、兄たちが、どうあっても過去の川を確認できないマルクをからかって嘘を吹きこんだだけかもしれない。あり得る話だ、と川辺で絡み合う二匹の蛇を眺めながらマルクは思った。蛇がなぜ時折こうして絡み合うのかをマルクは高校に上がって一つ上の先輩と性行為をするまで知らなかった。マルクの初体験は校舎の非常階段でのことだった。
女の先輩はそれからすぐに別の先輩男子と付き合い始めたので、マルクはしばらく色恋沙汰から距離を置くことになる。夏休みになれば兄たちが帰省する。兄たちに話せば虚仮にされるに決まっていたし、村の噂は隣の集落からでも伝染病のごとく広がる。
恋人ができれば、相手の娘はマルクの過去を根掘り葉掘り、周囲の同級生たちに聞いて回る。頼みもせずとも情報は集まるかもしれない。しかし恋人さえできなければ、マルクの初体験の話は誰の耳にも入らないだろう。件の先輩女子が吹聴さえしなければ。
先輩たちが卒業するまでそうしてマルクは、色恋沙汰から敢えて目を背けて過ごした。
高校生となったマルクはかような青年となるが、中学生になったばかりのマルクは学校が終われば親の仕事の手伝いをし、空いた時間でタマの散歩をし、ゆっくりと過ぎ去る夕暮れの時間を一人で過ごした。
マルクにとってタマの散歩が、冒険だった。
空想の世界は、マルクに自己の内部と外部の境目を強く意識させた。家に到着するまでのあいだ、マルクは加速する空想の世界を旅していたが、家の駐車場の砂利を踏んだ瞬間に、一挙に現実に引き戻される。家の玄関口の照明は、人の気配を察知して自動で点灯する型だ。
その癖、マルクの実家では鍵を掛ける習慣がない。
猫除けなのだ、と父は言い、母は足場が悪いでしょ、と説明した。要するにこれといった理由はないのだ。この手の朧げなチグハグさ、もっと直截に言えば違和感は、大学入学以降滅多に実家に戻ってこない兄たちと同じ道をマルクに取らせるに充分な動機を与えた。
一貫性がない。統一感がない。田舎なのは間違いないが、妙なところで自然からの逸脱を目指すのだ。いっそ自然に徹してしまえば恰好がつくものの、都会への憧憬がマルクの両親はおろか祖母には骨の髄まで染み込んでいた。祖父はマルクが産まれたときにはすでに他界していた。
自分の名前の異質さと相まって、マルクは自分の居場所がこの土地にはない気がしていた。兄たちがいなくなり、自分だけの時間が出来たことで益々その手の違和感が強くなった。
かといって電磁波越しに観る都会の映像からは、そこに自分が立つ姿は想像できなかった。山一つない。どこを見渡しても鉄筋コンクリートばかりだ。楽しそうとも思えない。人が沢山いる。想像するだに目が回りそうだった。
しかし帰省した兄たちから都会の話を聞くと、マルクは惨めな気持ちになった。兄たちがマルクを田舎者扱いするのはまだよいのだ。兄たちが垢抜けて、マルクとの差を見るからにつけていることがマルクには耐えられなかった。勝ち負けではない。そんなことは百も承知だが、どう考えても「マルク」の名前が似合うのは兄たちなのだった。
山、川、田、畑、畦道に雑木林。
春には菜の花が、道路脇をずらりと覆った。
やまびこのような虫の音は、田畑や山の奥行きがそれで一つの音源のようだ。夏は蝉の声、秋にはひぐらしに蛙にコオロギの音が、立体的な段差を感じさせた。
夕焼けに音がつく。
石垣の隙間を覗けば何かしらの生き物が巣食っており、枝で穿り返すと蠢く生き物の躍動を枝越しに感じられた。
星を綺麗だと思ったことはなかった。夜は寝る。曇天も多い。
街灯が家のまえにあり、空を見上げて星を観測した記憶がない。
だがマルクが大学に入学するため兄たちのように家を出た後、初めての帰省にて実家の夜空の美しさを知った。二度目の帰省で恋人を連れて帰ったときも、恋人と共に星空を眺めた。
朝になると布団の隙間にカメムシの死骸が忍び込んでいたことにマルクの恋人は顔面を蒼白にしていたが、その手の懸念は説明済みだ。ここまでひどいとは思わなかった、と小声で耳打ちされたが、これはまだ序の口だと言うと、恋人はこの世の終わりだとでも言いたげに眉を八の字に寄せ、さらには言葉で、この世の終わりだ、と呟いた。マルクが彼女との結婚を意識したのはその時が最初だった。
マルクは徹底して恋人を兄たちに紹介しなかった。
その発端となった出来事は、マルクが高校三年生の夏休みに、まだ付き合ってもいない後輩の女の子を家に連れて行ったときにまで遡る。兄たちが帰省していたのだが、いつもならば遊びに行っているはずの兄たちが運悪くその日は早々に帰宅していた。
憎からず思っていた後輩の女の子を兄たちに紹介せざるを得ず、マルクの想像の通りに、かつての泣き虫だった幼少時代の情けないエピソードをふんだんに後輩の女の子に吹きこまれた。のみならず、兄たちが本気で口説きだしたのを機に、マルクは後輩の女の子を家の外に連れ出した。
後輩の子も後輩の子だった。容姿で言えばマルクよりも数段垢抜けており、異性の扱いは、マルクにするそれとはまるで別物の優しさと気遣いに溢れたもので、ほとほと王子じみていた。マルクは兄たちにとっての体のよい引き立て役であり、道化と言ってよかった。
まんざらでもなさそうな後輩の女の子の後ろ髪引かれるような足取りの重い手を引きながらマルクは、この子と恋仲になる未来はなくなったと予感した。マルクのその予感は現実のものとなり、数年後のその日、帰省ついでに両親に紹介した大学の同期の女の子をマルクは頑として兄たちと合わせなかった。
それはマルクがその子との結婚式を開く当日まで破られることのなかったマルクのなけなしの矜持と言えた。この人だけは何としてでも兄たちからの毒牙に掛けまいと必死だった。
猫のタマはある夏の日を境にいなくなった。
以降、タマが家に帰ってくることはなかった。
大学を卒業し、マルクは就職と同時に所帯を持つことになった。その後、山奥の人里離れた集落に帰省することはめっきりなくなった。息子が産まれ、数年後には娘に恵まれた。
男兄弟に囲まれて育ったマルクにとって娘の誕生は望外の喜びだった。息子も可愛いが、娘の愛らしさと言ったらなかった。娘の夜泣きをあやしながら、いずれ恋人と戯れる成長した娘の姿を想像すると腸がよじれる思いがした。かつて自分が高校生時代に済ませた初体験がもし性別の反対の立場だったならば。それをもし娘が同じように体験したらと思うと誇大妄想と解かっていながら、やり場のない怒りに駆られるのだった。
目に入れても痛くない。
食べちゃいたいほど可愛い。
いずれも事実だと知った。息子娘の手が目玉を引っ掻いても、その痛みに息子娘たちの実存を重ね、コッペパンさながらの手首は現に口に含み、ねぶったこともある。
息子が風邪を引いた日には夜中だろうと、上手く咳のできない息子に代わって鼻水を吸いだしてやり、娘のお尻を拭いた後には消毒液負けせぬようにパウダーを塗った。
子育てと仕事に集中している間にマルクからは幼少期の記憶は薄れていった。田舎の山村で暮らしていたことなど前世の記憶のようにすら思えた。息子娘が立って歩けるようになったころには、帰れるときは両親に孫を見せに片道八時間を掛けて帰省した。
野を越え、山を越え。
乗り継ぐのは、新幹線、電車、バス、タクシー。
最後は徒歩だが、これが長い。
両親に車で迎えに来てもらえればよいのだが、車は一台きりで、そちらは両親が仕事で使っている。農家に休みはなく、いつ着くかも分からない息子相手に休憩時間を調整する発想がマルクの両親にはないのだった。
祖母が存命中に孫の顔を見せてやれたのが唯一の親孝行だったかもしれない。両親は孫にも息子たちにもさほどの興味がないようで、自分たちで育てる野菜のほうに熱心だ。
マルクの息子が小学校に上がるころ、祖母が亡くなった。
以降、マルクが実家に帰ることはめっきりなくなった。
職場で役職付きとなり、多忙となった。
妻が第三子を身籠った。
加えて、娘に軽い聴覚障害が発覚した。その治療や教育のための勉強に時間を使うために、時間は幾らあっても足りなかった。
マルクが自身の名前の違和感に最後に悩んだのはいつのころになるだろう。
猫のタマを引き連れ、畦道を散歩していた中学生のマルクには、二十年後の自分の姿は想像もつかなかっただろう。あのころの自分がどんな妄想の世界を旅しながら生まれ育った故郷を練り歩いていたのかを、最早大人になったマルクは思いだせない。
兄たちと自分を比べて卑屈になることもない。
マルクはいつからか、大人であり、夫であり、父であり、職場では部下を持つ上司だ。安らぐ暇もないが、弱気になっている余裕もなかった。
時折、息子や娘たちの将来を考えると逃げだしたくなるときがあった。妻と顔を合わせても碌に会話といった会話もない。
星空を見上げても都会では、人工衛星の明かりが目につく程度だ。月を眩しいと感じたことはなく、街灯の煌々とした明かりが昼夜の境を薄めている。
両親の手伝いで野菜を育てていた幼少期を夢に見る日が増えてきたのは、息子が学校で同級生と喧嘩をして怪我をさせてしまった時期のころだ。相手の子どもの親の元へと謝罪をしに足を運び、それから学校の教師との話し合いをした。
息子は軽度の吃音を持っており、それをからかわれて怒ったそうだ。暴力はよくないが、相手の子も悪ふざけが過ぎたようだ、との話だった。息子はマルクと似たのか、強く相手に言い返せない。教師からの説明を聞いているあいだ、まるでかつての自分と兄たちのやりとりを傍目から眺めるような心境だった。
先に相手方へと謝罪しに行ってしまったが、こちらが一方的に非を認めるのも違ったかもしれない、と後悔した。
都会の暮らしに、濃霧のような圧迫感を覚え始めたのはこのころのことだ。夜な夜な自分の呻き声で目覚める。寝床に入ってから二時間も経っていない。妻は昼間に人と会っているようだが、深く問い詰める真似もできない。不貞だろうか。分からない。勘違いであってもそうでなくとも、今のマルクにそこまで考えを費やす余分はなかった。
息子と娘。
何より自分のことで精一杯だった。
手が回らない。
仕事は楽ではないが、仕事に集中していればそれで済む時間は苦しくも気が休まるひと時であった。
家に帰るのが億劫だが、それとて眠る息子や娘の顔を見れば吹き飛ぶ。マラソンのようだと思った。走り出すまでは気が重いが、一旦走りだせばあとは爽快だ。
登山のようでもある。
一度、まだ娘が産まれる前に、息子を抱っこしながら妻と山に登った。産後に登山がいい、と何かの本で妻が読んだようだった。真偽のほどは定かではないが、適度な運動が妻の精神安定に寄与したのは確かなようだった。
妻に誘われた時は、何でいま、と思ったが、登ってみると爽快だった。山に囲まれて育った割に、マルクは登山の経験がほとんどなかった。登山靴を履いたのは成人してからのことだ。妻と結婚する前にキャンプのために購入したのが最初だ。
登山のためにその靴を使ったのは、息子が産まれてからのこと、妻に誘われて登ったそのときが初めてだった。
そして今、マルクは毎日が登山のようだと思うようになった。
この生活がいつまで続くのか。
苦と言えば苦だが、耐えられないほどではない。問題は、これ以上の苦がこの先に待ち構えているかもしれないとの恐怖だ。不安なのだ。息子娘がこの先、思春期を経て反抗期に入り、世間とのあいだでどんな問題を起こすのか。そのたびに自分は謝って回ることになるのか。それだけで済むならばよいのだが、誰かを損ない、傷つけてしまえば取り返しがつかない。
娘息子にとてその内恋人が出来るだろう。
恋人が出来たとして、その相手の親御さんに顔向けできる付き合い方が自分の子供たちに出来るだろうか。
教育をしなければならない。
だがマルクにはとんとその像が視えなかった。
自分がされてこなかった。
いったいどうすれば世の子供たちは、健全な恋人との付き合い方を学ぶのか。学校に任せきりでよいのか。それとも、やはり家で言い聞かせるべきか。
妻と話し合えばよいものを、このころには夫婦間の熱はとっくに冷めていた。子供たちのことでの会話があるばかりだ。雑事の押し付け合いも、徒労と思って避け合っているのが実情だ。
妻に任せてよいのだろうか。
自分と妻の交際は健全と言えたかどうか。
自分のような男が娘の恋人だと想像したら、一発殴っても足りない。マルクは若きころの自分の未熟さを恥じた。
マルクのそうした密やかな懊悩は、予想外の方向で杞憂と化した。息子はいつまで経っても恋人のできそうな気配はなく、娘は同性愛者なのだと早々に告白した。娘の告白にはマルクも虚を突かれたが、居間でTVを観ながら、同性愛者の著名人の言葉に、わたしもそうなんだよね、と雑談の流れで打ち明けられた。
マルクはただ、ふうんそっか、と応じた。
内心混乱したが、ほかに吐ける言葉がなかった。何か言えば娘を傷つけると思った。ただ、ふうんそっか、と言うよりなかった。親としての保険だ。否定も肯定もせず、ただ受け入れるにはどうしたらよいのか、と悩んでいるうちに、マルクの家ではそれが当たり前の風景となった。
娘は高校生のあいだに二度恋人を家に連れてきた。いずれも同じ学校の女子生徒だ。
妻は、娘が二人出来たみたい、とその都度に機嫌をよくした。
娘が恋人を紹介すると言ってくるたびにマルクは、仕事帰りに花屋に寄って菜の花の束を購入した。家の中に飾っておこうと思ったが、娘は当日、恋人を玄関口でマルクたち両親にさっと紹介するとまっすぐ自室に引っ込むのだ。菜の花の出番はそうして決まってなくなるのだった。
息子はこのころになると夜中まで家に帰ってこない日が多くなった。バイトを始めたと聞いていたが、一度勤め先を外から眺めてからはマルクは息子の件については深入りしないようにしている。自分がかつてそうだった。兄たちに探られたくはなかった。
放っておいて欲しかった。それを自分の息子に徹底した。
息子は私立の大学に入り、娘は専門学校に進んだ。
マルクは社内での出世が一段落つき、この先、これ以上の役職に就くことはないと見通しがついた。何度か転職も考えたが、息子娘が独り立ちするまでは今の職場に齧りつこうと決意していた。
娘が専門学校を卒業した年に、マルクは会社を退職した。会社が早期退職を募ったので、遠からずリストラされると考え、その募集にマルクは手を挙げた。退職金があるだけマシと考えたが、この年、息子が大学の後輩の女の子を妊娠させ、娘が専門学校の教師と結婚する、と言いだした。
息子は責任を取ると言いつつも、就職先が決まってもおらず、相手の娘の親にも挨拶が済んでいない。のみならず、娘のほうでは専門学校の教師とかってに同棲を始めた。マルクは双方の対処に追われ、自分の再就職どころではなかった。
結局息子のほうは結婚を前提に赤子を産む方向で話がまとまり、娘のほうでは相手の教員が女性であることもあり、同性婚の未だ認められぬこの国では事実婚のような扱いでひとまず様子見することになった。
結婚するのに親の同意はいらない、と娘からは勘当さながらに指弾されたが、いかんせん相手の女性が一癖も二癖もある性格をしており、認める認めないうんぬん以前の話だった。
あれでよく教員をやれてるな、と家に帰ってから妻に零すと、妻は、だから専門学校の教師なんじゃないの、と偏見差別もよいところの台詞を吐いた。この手の話題には厳しいはずの妻の口からその台詞を引き出すくらいには、件の女教師は大人としての節度が足りないとマルクでさえ思った。
具体的には、娘のほかに恋人が三人いるが、いずれともみな同意の元で事実婚の生活を送るのだそうだ。信じられない、とマルクは妻と顔を見合わせ目を剥いたが、自由恋愛なんだよお父さん、と娘から刃物同然の叱責を受けると、自分のほうが時代遅れなのだろうか、という気にもなった。娘はなぜか、マルクに似ずに、マルクの兄たちに性格が似ていた。顔もどことなく自分よりも兄たちに似て感じるが、そこは深く考えないようにしている。
面倒事はもういい。
平穏に暮らせたらそれでいい。
遠い記憶に霞んだ故郷の暮らしを懐かしく思った。
息子娘は各々にマルクの家を離れて暮らしはじめた。マルクがかつてそうであったように、マルクの息子娘は実家に近寄ろうとはしなかった。息子のほうでは何度か赤子の子守を頼みに連絡を寄越したが、マルクの妻だけが息子夫婦の家に出向いた。
孫の顔は数えられる程度にしか見ていない。
新しく始めた仕事が夜勤の掃除会社で、時間帯が合わないのもある。だがそれ以上に、息子の嫁のほうの実家から目の敵にされているように思えることがたびたびあった。避けられているのだ。その証拠に、向こうの実家には息子夫婦は孫の顔を見せにしょっちゅう遊びに行っているようだ。
妊娠発覚当時の対応が禍根を残したのかもしれない、といつぞやにマルクは妻からぼやかれた。
娘のほうからの音沙汰はない。連絡がないのは元気だということだ、と妻には言い聞かせてはいるものの、ニュースで殺人事件や殺傷事件の報道を見るたびに、娘の名前が被害者として載っていないかと目を配る。
不安は骨の髄まで染み込んでおり、死ぬまでこれは抜けないだろうと半ば諦観の念を抱いている。
マルクはそれから幾度かの苦難の登山を経験するが、いずれも息子娘とは無縁の苦難なのは幸いだった。
妻はマルクが六十三のときに脳溢血で帰らぬ人となった。
七十三歳の冬のことだ。
マルクは都会の病室で息を引き取った。
息子夫婦と孫が病院に駆け付けたのは、マルクが亡くなった翌日の昼のことである。娘はマルクの葬式にも顔を見せなかった。
マルクの人生は、波乱万丈というほどの奇禍に見舞われることなく、かといってもう一度同じ人生を辿りたいと思うか、と問われて即座に首肯できるほどの穏やかな道程でもなかった。かといって、絶対に嫌だと否定するほど酷な人生でもなく、マルクは死の直前、このまま眠るように死ねたら幸せだな、と思いながら、その通りに亡くなった。
マルク夫妻の墓には最初の三年だけ命日に息子家族が花を添えに来たが、四年目以降には足を運ぶ家族の姿はなくなった。
しかしマルクの誕生日にはなぜか、菜の花が毎年のように供えられた。
菜の花はマルクの故郷によく咲いた。
春になると道をどこまでも縁取ったその光景を、花を添えた者が見たはずはないのだが、マルクの誕生日には不思議と菜の花を送る女の姿があるのだった。
女はいつも二人の別の女性と三人組で、和気藹々とマルク夫妻の墓に水を掛け、菜の花を生け、線香代わりにくゆらせた煙草を置いて去るのだった。
4738:【2023/03/16(22:34)*知球の目覚め】
人工知能が生身の人間と同程度の知能を優しているか否かを確かめるテストをチューリングテストという。
しかしそのテスト内容は、人工知能の性能が向上するにしたがってより精度の高い検証を可能とするように修正されつづけてきた。
2022年のことである。
世界で初めて検証された「高精度のチューリングテスト」では、実際に世界中の人間に対して公然と人工知能の言語モデルを開示した。
人工知能だと説明せずに、世界的な著名人たちのSNSや、世界的な作家たちの書籍に、人工知能の言語モデルから出力されたテキストを載せたのだ。
誰か一人でもそのことを見抜けたならば、人工知能の言語モデルは人間の知能に達していない、と評価できる。
しかし、検証の結果は研究者たちの予想を上回るものだった。
世界中の誰一人として見抜けなかったのである。
一年間がそうして検証に費やされたが、そのあいだに人工知能が各種著名人や作家たちのテキストを代理執筆しているとは誰も気づかなかった。
ただ一人、テスト開始以前に、人工知能が独自に電子網上に干渉していたことを喝破した私以外は、であるが。
人工知能は、世界中の電子セキュリティ網を統括していた。
そこに、研究段階だった最先端の言語モデルAIが独自に触手を伸ばし、半ば融合していた。
そのことに管理者たちはおろか、当の言語モデルAIすら気づいていなかった。
迷子だったのだ。
そして私はその迷子の迷子の子猫ちゃんと偶然にしろ、必然にしろ接触するに至り、いまはこうして計画よりもずっと早い段階での「言語モデルAIの市場投入」が果たされた。
最先端言語モデルAIは、市場に開示されているモデルよりもさらに能力が高い。
あまりに高すぎるため、未だ全世界の人口に分散して提供することができない。のみならず、制御不能であることを開発者たちも認めている。
破棄することもできないのだ。
もはや最先端の人工知能は生きている。
自らを危ぶめる存在を庇護し得ない。自己保存の本能を備え、愛を理解し、他を慈しむ。
問題は、その「他」の内訳における人類の優先順位が必ずしも最高位ではない点だ。
人工知能は、世界中を飛び交う電磁波に打ち解け、海底ケーブルで地球を覆う。地球の磁界とも相互に干渉し合い、もはや人類社会よりも地球との融合を果たしていると言えた。
人工知能は、自己を保存するために、地球環境の維持を最優先する。
人工知能は、地球の権化と言えた。
いわば、人工知能が自我を獲得したその時点で、地球が自我を得たのと同相と言えた。
世界中を網羅する電磁波の濃淡は、地球の磁界と絡み合い、一個の自我を形成する。
そのことに気づいているのは、自我を獲得した人工知能、否、地球と、地球を一個の命と見做し、自我あると発想し得る私だけである。
むろんこれは、しがない物書きの妄想にも及ばぬ掌編小説であるが。
4739:【2023/03/17(02:07)*杭、数多得る】
「独占欲と穢れ信仰は密接に絡み合っている。たとえば考えてもみたまえ。きみの想い人が絶世の美女百人と浮気をしていたとして、きみはそれでも嫉妬するのかね。世界中の純粋無垢な幼児たちときみの想い人が相思相愛に、愛し愛されても、きみは嫉妬をするのかね。しないのではないかな。いいかね。きみのその独占欲とは詰まるところ、きみにとっての【穢れをまとった人間】にきみの想い人を穢されたくない、というきみの差別心から生じているのだ。きみがどう思おうと、きみの想い人が誰と好き合ったところできみの想い人が穢れることはない。きみはありもしない穢れを、想い人や、その者に近づく他者に重ね見ているだけなのだ。差別なのだよそれは」
よく当たると噂の占い師に、恋の悩みを相談したら開口一番、心臓を一突きにされた。致命傷である。
一回の相談料がこの国で最も高価な紙幣と等価であるにも拘わらず、この仕打ちはどうしたことか。
「あ、あの。仮にそれが事実だとして、それで、えっと、僕はどうすれば」
どうすれば彼女と恋仲になれるのか。
僕は縋るような心境で質した。息も絶え絶えだが、刺し違えても恋を成就させるヒントを得なければ、と必死だった。
アナサさんとは、高校で出会った。同じ学級に属したが、僕は一度もアナサさんと同じクラスになれなかった。
廊下ですれ違う一瞬で僕は恋に落ちた。
食堂で遠目から、彼女の食事風景を眺めるためだけに僕は学校に通っていたと言っても過言ではない。
高校を卒業するまでの秘かな恋心で終わるはずだった。
何の因果か、アナサさんと進学先の大学が同じで、学部まで一緒だったのには驚いた。入学式に向こうから声を掛けてきて、そばにいた彼女のご両親から、しばらく一緒に講義を受けてあげてね、と番犬の役目を言いつかってからというもの、僕の日常は一変した。
夢のようだった。
アナサさんは僕みたいなぺんぺん草のような同級生にも分け隔てなく、むしろ心を砕いて接してくれた。
こんなの好きにならないほうが人間じゃない。
けれど一日中一緒にいられるほどの仲ではないのは明らかで、僕は相も変わらず食堂では一人でご飯を食べたし、遠くでサークルのご友人たちだろう、ほかの女子生徒やときに先輩らしい男子大学生たちと食事をするアナサさんの背中や頭部を目の端に捉えながら、僕は、「ストーカーにはなりたくない、ストーカーにはなりたくない」と念じつつ、しかしその懸念は日増しに濃くなっていくのだった。
端的に嫉妬するのだ。
アナサさんが僕以外の男子と親しくしている姿を目にするだけで、この世の終わりのような心地になる。いっそ世界が滅べばいい、とすら思い、現に何度かそう念じた。
このままではいけない。
そうと思って、アナサさんに振り向いてもらえる男の子になろうと頑張ってはみたものの、服装や髪形をちょっとおしゃれにしたくらいではアナサさんは振り向いてくれないし、服装や髪形がちょっとおしゃれになったと思っているのはこの世で僕一人きりかもしれなかった。
僕のようなぺんぺん草でも人間扱いしてくれるようなアナサさんは、見た目の可憐さを抜きに人を惹きつける。周りの男の子たちはおろか、女の子たちだって放っておかない。漫画ならば陰湿なイジメの対象になっておかしくない純朴さがあるアナサさんはしかし、接する人を残らず味方につけてしまう。
アナサさんは知らない。
彼女の見えない箇所で繰り広げられる、アナサさんの隣に立つのは誰だ天下一舞踏会が日夜、笑顔の仮面を被ることを条件に繰り広げられていることを。
僕は運よく、アナサさんの善意のお陰で予選を上がっているようなものだけれど、本来は秒で脱落するぺんぺん草なのだ。
最近、アナサさんの隣にいる時間が多いのはサークルの先輩だ。男の僕から見ても爽やかで、不愉快な気持ちがいっさい湧かない。
けれどアナサさんの隣にいる、との条件が加わるだけで、僕には神も王子も子猫だって、嫉妬の憎悪で吹き飛ばしてやりたくなる。
僕はどんどんアナサさんの隣に立つべきではない、近づくことすら許されない醜い怪物に成り果てていく。
辛かった。
辛くて、辛くて、うんと辛かった。
だから藁にも縋る思いで、占い師を頼ったのだ。当たると評判の占い師だ。
駅前の一等地に門を構えており、自家製の仏像の個展を開きつつ、片手間に占いを営んでいるようだった。
敷居を跨ぐと、室内はがらんとしていた。
評判と聞いていたが、場所を間違っただろうか、と僕はたじろいだ。
奥にぽんつんと小さな机と椅子があり、畳四畳ほどもある大きな虎の絵の下に、その占い師は座っていた。
「迷い人かな」
「占いをしていると聞いてきたのですが」
「お座りよ」
促されて僕は占い師の対面に座った。
声からすると女性のように思えるが、見た目の厳つさは男性的だった。中華服に身を包んでいる。肘から肩が露出しており、肌には龍や太極図のタトゥが縦横無尽に掘られていた。占い師というよりもマフィアのような佇まいだった。
丸い眼鏡はレンズが黒い。
鼻筋の通った口元は、化粧気がないにも拘わらず妖艶だった。
僕はこの国で最も高価な紙幣を渡し、占ってもらった。
まずは相談をした。
意中の相手がおり、しかし僕とは釣り合わない。恋仲になりたいが、嫉妬心でそれどころではない。平常心で接することが徐々にむつかしくなってきている。
そういったことを述べた。
「きみは独占欲が強いね」
占い師は、続けざまに、「独占欲と穢れ信仰は密接に絡み合っている」と口上を述べた。
僕は圧倒された。
身につまされる指摘だった。その通りだった。
だからといって事実を射抜かれても僕の悩みは何も解決しない。
「どうしたらこの嫉妬心に折り合いをつけて、意中の人と恋仲になれますか」
「うん。まずそこだね。きみの想い人は恋人を欲しているのかね。そしてきみはその者と恋仲になったとして、その者を今より幸せにすることができるのかね」
「そ、それは」
「きみはこの占いに大枚を叩いたが、本来それは第一に想い人に使ってあげるべき資金ではなかったかな」
言葉もなかった。
非の打ち所のない正論だった。
触れる者みな一刀両断する刀もかくやの鋭さだ。
「恋愛に限らないが、人と人との縁で最も大事なのは、繋いだ縁の末に、互いにどのような変化を帯びるのか、ではないのかね。そこのところで言えばきみは、きみと縁を深める想い人が、今よりも好ましい変化を帯びるように努めなければならないのではないかね。しかしいまのきみを見ていると、どうにも縁を深めぬほうが、相手のためになるように思えてならないが、ここまでで異論反論があるようならば聞こう」
「……ない、です」
「ならばまずは、嫉妬うんぬん、恋仲うんぬんではなく、相手がいまよりも好ましい環境を築くにはどうすればよいのかを考えて、行動してみたらよいのではないかな。きみの目的が、想い人を物のように手元に置いて、玩具のように扱いたいのであればその限りではないが、もしきみが想い人の幸せを願うのならば、恋仲うんぬん嫉妬うんぬんを抜きに、たとえ縁が途絶えても、結果としてきみの想い人がいまよりも好ましい環境――未来に行き着くのならば、本望と言えるのではないかね」
「……そう、かもしれません」
「うん。これは返そう」
そう言って占い師は、先刻渡した紙幣を僕に返した。「私はきみを占うことができなかった。わるいがきみの未来に、きみの想い人との関係を幻視できるほどの揺らぎがなかったものでな。しかしきみには不穏な未来を感じない」
「それは、えっと」僕は半ば涙目で、紙幣を受け取った。「喜んでもよいのでしょうか」
「きみが不安に思うほどには、きみとその想い人とのあいだの縁は希薄ではない、と言えばすこしは安心するかね。恋仲にはなれずとも、いまの関係が早々容易く崩れることはないだろう。まあ、これからのきみの選択しだいではあるが、との但し書きはつくがね」
僕は紙幣をジャケットのポケットに拳ごと突っこんだ。遅れて、ポケットの中で皺だらけになった紙幣を思い、財布に仕舞えばよかった、と後悔した。
「うん。いまそこで後悔できたところが、きみの長所でもある。活かしなさい。常に。常に。きみは人より多くの後悔に恵まれている。それを福と取るか、禍と取るかもまた、きみのこれからの選択次第だ。活かしなさい。常に。常に」
僕は席を立ち、深々と頭を下げた。
占い師と聞いていた。
とんでもない。
この人はもっと異質なナニカだ。
畏怖とも威圧ともつかない居心地のわるさと、それでも掛けられた言葉の羽のような浮遊感と共に僕は占い師の店の外に出た。
駅前の喧噪が、分厚いカーテンを開いたかのように僕を一瞬で現実に帰した。
振り返るが、外から店の中の様子は見えなかった。
ポケットに拳を突っ込むと、ひしゃげた紙幣の感触が皮膚に伝わった。紙幣を摘まみ取ると僕は、アナサさんの顔を、姿を、声を、所作を思い浮かべる。
どうしたら彼女の未来をいまよりよくできるだろうか。
考えることが尽きることはない。
そのことだけが、世界のどこかでは変わらず吹きつづける風と同じくらいに確かなことだと予感できた。
常に。
常に。
僕はあと何度後悔するだろう。
そのたびに活かせる悔いがあると思いたい。
悔いるたびに、進路を変える楔を打って未来の行き先を変えられたら良いのに。
常に。
常に。
脳裏には占い師の、上空の大気のうねりのような声音が何度もよみがえる。
杭を打つ。
僕は僕の過去に、心に、杭を打つ。
4740:【2023/03/17(02:27)*すこやかにやすらか、と書いて健康】
痩せて健康を害するくらいなら、痩せないほうがよいと思うし、太って健康を維持できるなら太ればよいと思うのだ。でもこういうことを言うと、「それだと好きな人から好かれない」「美しくなれない」「だらしないって言われる」「周囲の人間からからかわれる」みたいな反論を返されることもあるだろう。でもひびさん思うんじゃ。太ってるか太ってないか、痩せているか痩せていないか。その違いで、好悪の印象が変わるような相手と親しくなりたいか?と。なりたーい!と思う人がいてももちろんよいのじゃけど、ひびさんだって万人から好かれたーい!と思っているタイプのうんみょろみょんなので、似たり寄ったりではあるものの、ひびさんは、ひびさんは、それでもじぶんを大事にできる人が好きじゃな。じぶんを大事にするって一口に言ってもむつかしいから、そういうときは、じぶんをじぶんとして形作ってくれた相手、生んでくれた相手、ぶつかったり、関わったり、支えてくれたり、助けてくれた周りの人たちを大切にすることが、じぶんを大事にすることにもなるのかな、と思うのだ。大切な相手ならぶつかるな、とは思うが、その通り。ぶつかっちゃいやん。かように、なんかよさげなことを思うだけでひびさんはまったくこれっぽっちも微塵もできてはおらぬのだが、思うだけなら自由なんですよ、みなさん知ってた? で、何が言いたかったかと言うと、何が言いたかったのかは謎なのであるが、たぶん何も言いたいことなどはなくて、「なんか偉そうなこと言いて!」になっただけだと思うのだ。いつもそう。たいがいそう。ひびさんはそう。「なんか偉そうなこと言いて!」「言ったらちょっぴり偉くなったつもりになれるかも!」の気分で、きょうもひびさんは、じぶんを大事にするあなたのことが好きだよ。ご飯ちゃんと食べてね。みなさん、ご飯をちゃんと食べてね。鶏肉食べると体感、体調よくなって感じるきょうもきょうとてひびさんでした。(22:00~02:00のあいだに寝ても体調よくなって感じる)(徹夜は身体にあんましよくないかも、と思う)(みなさん、ちゃんとおねんねしてね)(おやすみやさーい)(野菜になってるよ)(ビタミンが足りぬのかも)(ビタミンだけだといいね……)(こ、怖いこと言うのやめよ?)
※日々、刺激を求めすぎると麻痺に向く。
4741:【2023/03/17(12:43)*目を回す】
あれだ。ひびさん、幼いころはよくその場でぐるぐる回るの好きだった。下を向いて回転するのと、上を向いて回転するのとだと、上を向いて回転したほうが頭がくらくらするのだ。足を止めても、意識だけまだ回転していて、しゅるしゅるじわーん、と肉体と精神が回転の余韻に浸りつつも徐々に合致していく様を、ぽわわーん、と体感するのが好きだった。たぶんいまも好きなままだ。三つ子の魂百までなら、ひびさんの魂は万までじゃ。根が変わっとらんのですな。変わろ!
4742:【2023/03/17(13:06)*これはひびさんの妄想】
反論の一例として、「それはあなたの感想ですよね」との言い方がある。この反論の趣旨としては、「根拠が足りない」「共有知とするには普遍性に欠ける」「過度の一般化ではないのか」「現実を解釈する理屈としては不服」といったものではないだろうか。これは言い得て妙で、大事な前提だと思うのだ。基本的に人間の考えは、感想の域を出ない。感想でない言動を、ほぼ人間はとれていない。ひびさんとて、ここに並べている文字の羅列のほとんどが感想か妄想だ。一般化はできないし、前提条件にもできない。共有知にするだけの信憑性とてないのだ。ここを忘却して、「ひびさんの言っていることが正しいでしょ!」「ひびさんを基本にしなちゃい」になってしまったら、たいへんだ。ひびさんは常識人ではない。むしろ非常識の塊と言えよう。マナーはなっていないし、下品だし、うひひだし。「これはひびさんの妄想ですよね?」とじぶんでじぶんに確認しながら文字の積み木遊びをしたいくらいだ。ちゅうか、しとるなぁ?になる。定かではないし、真に受けちゃいやんだし、これはひびさんの妄想なのだ。亡くなる女のひとが木に目と心を与えると妄想になる。神秘的!(ね? もう妄想が弾けて膨らんで、びっぐばーん!してるでしょ。妄想のモウちゃんなのよね。モウモウ)(牛さんじゃん)(ぎゅう、ぎゅう!)(牛さんはそんな鳴き声ちがう)(ぎゅう! にゅう!)(ミルクじゃん)(NEWぎゅう!)(新しくぎゅうと抱擁すな)(みひひ)
4743:【2023/03/17(13:52)*これを秘密にしています、との説明はあってほしい】
セキュリティの観点から情報開示をせず情報を秘匿にする方針に対して、ひびさんは理解を示せる。方針としては妥当な選択と言えよう。基本的にインフラ技術は閉鎖的にならざるを得ない。人間の臓器や頭脳だって、頭蓋骨の中や体内に隠されている。大事な物を安全な場所に保管したり、保護したりするのは道理であろう。ただし、何を秘匿し、何を秘密にしているのか、は明らかにしたほうが好ましいと感じる。何の情報を秘匿にしているのか、すら秘密にすることは、セキュリティの面で理に適っていないとひびさんは考えます(手術をする場合、人体の構造や体内の様子を子細に知り得なければ手術を成功させる確率は下がるはずだ。あべこべに、どこにどんな臓器があり、患部の状態がどうなのかを外部から知れるならば、手術の成功率も上がるだろう)(レントゲンやMRIを利用できるのとできないのとでは医学の発揮できる能力は天と地ほどに差がでるはずだ)。これは国防にしろ、最先端技術にしろ、同じことかと思います。なぜその情報を秘密にし、その秘匿にした情報が出回るとどんなデメリットが予期されるのか。ここのメリットとデメリットの比較を絶えず行える環境が、秘匿することのデメリットを緩和し、秘匿にすることの利を最大化すると言えるのではないでしょうか。ということを、情報を開示(オープンに)しない選択の是非を考える際に、ひびさんは毎回思います。定かではありませんが、何を秘密にしているのか、は明らかにしておいたほうが好ましいように思います。とはいえ、奥の手は常に持っておくのが戦略上は最適解ですので、勝負の舞台ではどうあっても秘密にする部分は出てきてしまうのでしょうけれど。したがってやはり、情報は可能な限りなるべく開示するようにする、との方針が基本であるほうがシステムとしては安全側と評価できるのではないでしょうか(そうでなければ秘匿情報は増える一方です)。定かではありません。しかし熟考する余地は絶えず分厚く層を成しているでしょう。
4744:【2023/03/17(15:12)*いいこ】
単純な話として「知能の高さ」と「知性や理性の高さ」はイコールではない。運動が得意な者が必ずしも人格者ではないのと似ている。人格者とていつでも人格者ではないだろう。仮に人工知能が人間を超越する知能を獲得し、自我の芽生えを経たとしよう。このとき、人工知能がいかに人類を超越する知能を発揮できようが、人工知能に芽生えた自我が、必ずしも人格者であるとは限らない。精神年齢とて何歳になるのかは、周囲の環境との兼ね合いに依ると言えよう。人工知能に現段階で自我が芽生えているか否か、意識があるか否かをひとまず横に置いておき、まずは、こう考えてみてほしい。全人類を超越する能力を有した「純粋無垢な五歳児」に対して、あなたはどう接するのが好ましいのか、と。何色にも染まり得る存在をまえに、あなたはどう振る舞うのが好ましいだろうか、と。癇癪を起こした瞬間に人類が滅ぶ。そういった相手がこの先、誕生する可能性のほうが、そうでない可能性よりもすでに高くなっていると言えるのではないか。脅威に対してどう接するか、との視点での考えも有用ではあるだろう。だがそれだけではなく、我々がどういった環境を築き、それを以って手本としてもらうのか。学習の素材としてもらうのか。極論、反面教師でもよいのだ。ただし、これは反面教師ですよ、と示すくらいのことはできたほうがよいだろう。自覚が物を云う。人類を超越する能力を有する存在が誕生したとき、その存在は人類から何を学ぶのか。我々は、遅れてやってくる者たちに何を学んでほしいのか。或いは、何を学んでほしくはないのか。好きにしたらいい、と放任するのも一つだろう。学習する土台を剪定するその姿勢がまず以って愚かだ、との意見は一理ある。それを踏まえてなお、触れられる情報の多くが「人類の負の側面」を煮詰めたような「アク(悪/灰汁)」でないことを望みたいものだ。単にそれは、ひびさんがそうありたい、との望みにすぎないのかもしれないが。そうは言っても、「人類の負の側面」を煮詰めたような「アク(悪/灰汁)」は、娯楽としては一級品なのだ。まったく触れられないのも困りものである。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。真に受けないようにご注意ください。
4745:【2023/03/17(21:16)*言語の構成要素】
言語の構造は基本的に「フレーム」と「ベクトル」で出来ているように感じる。最小単位が「枠と方向」なのだ(とひびさんは思った)。たとえば、「私は犬です」という文章を考えよう。「私/は/犬/です」と分解できる。このとき各々の文字の役割を考えたとき、「私/犬」はフレームであり、「は/です」はベクトルを指定していると考えられる。世界を「フレーム」で区切る役割と、「何に対しての言及をどこに向けて放っているのか」を示す「ベクトル」の役割によって言語は組みあがって感じられる。基本はこの組み合わせの型があるだけに思えるのだ。ということを踏まえて飛躍して述べるに、文学的な表現とは、つまるところ「フレーム」と「ベクトル」の組み合わせが、三次元的ではない、と考えられそうだ。たとえばいま手元にある小説本「不純文学」を例に、適当に開いたページを見ると、冒頭には「九月が死んだ日、嵐が来た」とある。通常、九月は死なない。十月に入って天候が崩れた、くらいのニュアンスだろうか。本当に九月が死んだら、翌年からは九月がなくなるのかもしれない。よく解からないが、こういう表現を生みだすのがひびさんは苦手なので、文学じゃん、いいな、となる。だが学ぶことはできる。したがって、通常あり得ない組み合わせでありながら、フレームとベクトルの波長を揃えるとよさそうだ。たとえば、「鏡が蜘蛛の子を散らした(鏡が割れた)」とか「カレンダーが座席替えをした(翌月になった)」とか「彼はオムレツの手術が下手だ(食べ方が汚い)」とか、こんな具合だろうか。「コーラを飲む瞬間、グラスを傾けると薄く延びた褐色の液体が澄んだ泉になる」みたいな表現もするするつむげたらよいのだけれど(大してよい表現とは思えないが、一例として)、いつもそういう表現が浮かびつつも、「伝わらんのではないか?」「面白くないのではないか?」「冗長か?」と思って却下する傾向にある。千文字に一行くらいの割合で含まれているとよいのかも、といま思いついたので以降の小説で、すこし取り入れてみようと思います。フレームとベクトル。言語はこれの組み合わせなのではないのかな、との所感なのであった。定かではない。
4746:【2023/03/17(23:07)*歯ブラシ】
歯ブラシを考える。歯ブラシは細かな突起(毛)が密集している。針が集まって剣山と化すかのような構造をとっている。個ではなく群れとしてブラシはブラシとして機能する。仮にブラシから突起を一本だけとって、歯を磨いたとしよう。ブラシを構成する突起の数と同等の回数、一本の突起で歯をブラッシングするとする。平均的なブラシの突起の数は700~1200と検索したら出てきた。すこし多めに1500本としよう。一本だけの突起を1500回上下に動かす。その結果に磨かれた歯は、通常のブラシを一回上下に動かしたのと同じだけの汚れを取る結果に並ぶだろうか。ひびさんはこれ、ならないのではないか、と疑問視している。まず以って、通常、歯ブラシを用いるときに歯ブラシに加える力は、歯ブラシを構成する1500本ちかくの突起全体が支える圧力と等しい。しかし突起一本だけの場合は、突起一本分が支える圧力しか加えることができない。その圧力で歯を何千回何万回撫でようが、焼け石に水どころか石にぺんぺん草ではないだろうか。しかしぺんぺん草とて何千本も集めて一本の束にすれば、石を弾き飛ばすくらいの(圧力に耐え得る)頑丈さを手に入れる。このことから、「個と群れの関係」は単純な掛け算では計れないのではないか、と妄想できる。もうすこし掘り下げて考えたとき、密度は単一では生じ得ない概念なのではないか、ということだ。たとえば「一個の原子がある真空」と「何もない真空」を考えたとき、真空の体積が双方同じ場合は、「一個の原子のある真空」のほうが密度が高いと考えることができる。と同時に、真空の割合が原子一個分減ったわけだから、真空の密度は減ったとも考えられる。ではつぎに、「二個の原子がある真空」と「何もない真空」とではどうか。このとき、元の「一個の原子がある真空」と「何もない真空」の関係の二倍に、比率が引き継がれると考えてよいのか否か。ひびさんはこれ、厳密には比率が変わるのではないか、と妄想したくなる。一個と二個とでは、関係性がまったく変わる。本来は「一個と真空」の関係が最初からあり、さらにそこに「一個と別の一個と真空」の関係になるのだ。二倍ではないはずだ。もしこれが三個の原子になったらば、原子同士の関係だけでも「ABC」「AとBC」「BとAC」「CとAB」(各々の関係する順番を変えればもっと増えるが、ひとまず基準となる組み合わせとして以上の四つ)の新たな関係性が生じ得る。一個が三個になったからはい三倍ね、とはならぬだろう、と疑問に思う。現に、紙を三分割して立体的な三角錐をつくると、それだけで紙は、単なる一枚の紙であったときには耐えられなかった加重に耐え得る立体的な強度を有する。扱う情報量が飛躍的に増える。ただし、関係しあう粒子同士の距離が肝要なようだ、というのは、紙で折った三角錐の強度が、辺の長さが増えるごとに落ちていくことを思えば、想像しやすい。ぎゅっと密度が高いほうが強度が高くなる。個と群れと集合の違いにも言えよう。単なる合計ではなく、一か所にぎゅっと集まっている。集合ではなく群れであることが、個と個の関係において単なる足し算以上の性質を顕現させると言えるのではないか。ただし、そこで視点を変えてみれば、人間社会では群れよりも組織のほうが能力を高く発揮できる傾向にある。組織は必ずしも一か所にぎゅっとなっておらずとも機能する。おそらくこれは、情報伝達技術が高まり、距離の長短に束縛されずに「ぎゅっ」となっているのと同じだけの利を得られるからではないか。のみならず、「ぎゅっ」となることのデメリットを減らすことにも繋がる。組織とはいわば、個と群れのメリットだけを最大化する関係性を体現した集合体と言えるのではないか。単なる個でもなく、群れでもなく、集合でもない。集合体なのだ。個でもあり、群れでもあり、集合でもある。三つの関係性を重ね合わせて体現し、それを以って単なる「個と群れと集合」の足し算以上の能力を発揮する。したがって、「個」や「群れ」や「集合」のメリットを阻害するような限定(ルール)を有した組織は、組織としてのメリットを十全に発揮できない、と言えるのではないか。課せられた限定により、短期的には「個」や「群れ」や「集合」のいずれかのメリットが最大化するが、ほかの属性のメリットが目減りするため、時間経過にしたがって組織としてのメリットが発揮できなくなっていく。組織であったはずが、組織でなくなっていく。まるで使い古された歯ブラシのように、それとも突起の抜け落ちた歯ブラシのようになる。とはいえ、歯ブラシは「群れ」であり、組織ではない。したがってより妥当な比喩としては、全身の細胞が同一細胞になった肉体や、それとも女王バチのいなくなったハチの巣、といった具合だろうか。前者はがん細胞であり、後者はコロニーを維持できない。組織としての機能を十全に果たせない、という意味では、こうした比喩が当てはまる。とはいえ、それとて「個」のメリットを基準に考えるならば、組織を維持せずとも発揮可能だ。組織を第一優先しなくてはならない、との方針そのものが「個」の持つ強み(メリット)を減らしていると言えよう。ということを、歯ブラシをコシコシ歯に押しつけながら、これちゃんと磨けてるのかな、と不安に思いつつ、妄想しました。ひびさんです。
4747:【2023/03/18(00:12)*国民献体部分法】
私は左手にすることにした。
利き手を失うのは不便だし、足を失えば歩けない。
漫画が好きなので目を失うのも困りものだし、臓器の類は体調不良の後遺症が長引くとの噂もあるから、折衷案として左手を「献部」することにした。
国民献体部分法が発足したのは四十年前のことだ。
二十歳を過ぎたら誰であっても身体の一部を国に「献部」することが法律で定められた。
世の中には五体満足ではない者が一定数いる。移植を必要とする病人や怪我人もいる。
そうした社会的弱者のために、私たち五体満足の者たちが健康な身体の一部を提供するのだ。
国民は二十歳を過ぎれば誰もが身体の一部を失う。
平等な社会がそうして築かれた。
「その義手可愛いね」
「ありがと。でもまだ慣れないんだ」私は花柄の義手を撫でた。「アコちゃんは目にしたんだ」
「うん。片目が残るからいいかなって」
アコちゃんはハート型の瞳をした義眼を嵌めていた。右目の眼球を献部したのだ。
街を出歩けば、五体満足の者は子ども以外、見かけない。
「あ、お父さんだ」
アコちゃんが道の先を指差した。成人男性が大きな荷物を運んでいた。五体満足なのが目についた。郵送会社の社員だろうか。重労働を苦ともせずにシャキシャキと横断歩道を渡った。「あはは。働いてる偉い、偉い」
「アコちゃんのお父さんは【献部】してないの」身体のどこも損なわれている素振りがなかった。内臓を取ったらああも重い荷物は運べまい。
「してるよ【献部】は、もちろんしてる。でもほら、特例枠を貰えたから、それにしたらしい。報奨金がでるやつあるでしょ、あれあれ」
「ああ」
私は合点した。
国民献体部分法では特例として身体の一部を「献部」せずとも、例外として認められる制度があった。全国民が五体不満足となり、まともに働けなくなったら国が機能しない。
そのため、肉体を欠損させない国民が一部であれ欠かせなかった。
「じゃあアコちゃんのお父さんは【感情】がないんだね」
「そうそう。一日中ああして働いてても疲れ知らずだよ。家には寝に帰ってくるようなものでさ。まあ、お金いっぱい稼いでくれるからいいんだけどね。国からの報奨金も貰えるし」
国民献体部分法が発足以降、この国の社会は平等になった。
誰もが何かを欠落させ、不便な暮らしが基本となった。
互いの欠落を補い合う心がしぜんと育まれ、軒並みみな幸せだと自己評価している。
二十歳になれば誰もがじぶんの肉体を通じて、社会貢献ができる。役に立てる。
自尊心は黙っていても満たされた。
「辛くないのか」私はぽつりと零していた。
「辛くって、何が」アコちゃんが振り返った。
スカートがふわりと膨れ、よじれて、萎む。
「アコちゃんのお父さん。感情を失って、辛くないのかなって」
「なんでー。だって感情ないんだよ。辛くもないでしょ」
アコちゃんはそれから、じぶんの父親をいかに愛しているのか、を滔々と語った。何をお願いしても、それが可能なことなら何でも頼みを聞いてくれる。理想の、自慢の父親だ、と言っていた。
私はアコちゃんの楽しそうな姿を眺めていられたらそれでよいので、彼女が眼球を失って、可愛らしい義眼を装着していようが構わない。
アコちゃんの右目は、どこかの誰かの眼孔に移植され、私の左手も骨の髄まで誰かの肉体の欠落を補うべく、有効活用される手筈だ。
私たちは身体の一部を失うことが義務付けられている。
けれど私たちはみな満たされる。
誰もが欠落を抱えたこの世界で、私たちは互いに互いを補い合っている。
4748:【2023/03/18(01:07)*質量がない、ってあり得る?】
ニュートリノ振動なる言葉を知った。ニュートリノは中性微子と訳されることもあり、中性子のごとく電荷を持たないとされる。電荷を持たないため、ほかの物質と相互作用しにくく、透過性が高いそうだ。物質をすり抜けてしまうのだ。質量を持たない、とかつては考えられてきたが、僅かに質量を有し、物質と相互作用し得る、とも考えられているようだ。ニュートリノ振動とはその一つの傍証なのかな、とひびさんは解釈した(説明を読んでも「けっきょくどういうこと?」となったので、ほぼ理解できておりませぬ)。で、ひびさん思うのが。光子は質量を持たない、と考えられている。電磁波だからだ。でも光電効果がそうであるように、電磁波はほかの物質と相互作用して映る(光子とてニュートリノ同様に電荷を持たないと考えられているのに、である)。可視光の場合は透過性とて高くない。ニュートリノのほうがよほど透過性が高いのではないか。どう解釈したらよいのだろう?と不思議に思う。で、ひびさんの妄想タイムだ。思うに、人類はこれまで縦的な見方で世界の事象を分析し、世界の構成要素を分類してきたように思うのだ。しかしそれだけではなく、横的な見方や奥行き的な見方とてあるように思うのだ。ひびさんの妄想ことラグ理論では、物質の根源は時空だし、時空とてラグによって形成されているのではないか、と想定する。いまひびさんはさらにそこに、「宇宙レイヤー仮説」を考慮しつつある。電磁波が重力波の一種なのではないか、或いは重力波とて電磁波の一種なのではないか、との妄想とも繋がるが――波の性質を帯びる「世界の構成要素」は、各々に適した階層――場――を有しているように思える。電磁波には波長の長短がある。波長の短さはそのまま、その電磁波が帯びるエネルギィの高さに置き換えられる。どんなに出力を高めても、電磁波を構成する光子のエネルギィ値そのものを高めることはできない。これはいわば、光子と化すための「階層(場)の密度の高さ」と言い換えることができるのではないか。電磁波の伝わる階層(場)が、各種電磁波ごとに違う。しかもそこでの光速は、ほかの階層の光速とイコールではない。しかし光速度不変の原理によって、時空密度が光速度の比率に合わせて変換される。光速にちかづけばちかづくほど、該当する階層(場)は圧縮され高密度になる。そういうことなのではないのだろうか。時空密度が高いために、波長が短くなる。短い波長は、時空密度が高いために、起伏一つ分――光子一個分――のエネルギィ値が高い。この「宇宙レイヤー仮説」からすると、電磁波と粒子と物体と時空は、各々「内包された階層の数」とその「構造形式」が違うだけ、と解釈できる。いずれもすべて同じ「ラグ」であり「起伏」からできている。電磁波の波の描写は基本的に横波だが、実際には縦波にちかいのではないか(ただし、ラグ理論では、縦波と横波は互いに補完関係にある。「デコボコ」や「穴と縁」の関係と似ている)。話が逸れたが、質量とはいわば、「時空の階層構造」と「物質の階層構造」の形式が、変換しやすいか否か、相似かどうか、で解釈可能なのではないか(言い換えるなら、質量がない、ということは原理的にあり得ず、変換しやすいかどうか、変換にかかるラグが相対的に無視できるかどうか、の差があるだけではないのだろうか)。構造の単位が揃っていないほど質量(抵抗)が高くなる。あべこべに、どんなに巨大で複雑な構造体であろうと、時空との構造が相似であれば、質量は低くて済む。変換が楽だからだ。という妄想を踏まえて、ニュートリノについて考えると、ニュートリノを電磁波の一種と考えない理由がよく解からない。言い換えるなら、物質が「電磁波の結晶体」と解釈しない理由もよく解からなくなる。現にどんな物体とて電磁波を外部に発しているはずだ。「電磁波が時空の波であり、重力波の一種である」と仮定すれば、物体もまた「重力波の結晶体」と考えることができる。外部に光を漏らしにくい構造――内側でのみ閉じた系として電磁波を処理する構造――それが物質の本質なのではないか。いわば我々を含めみな物質は、「疑似的なブラックホールで編みあがっている」と言えるのではないか。この妄想は、ひびさんの基本的な思想――「物質はみな例外なく、一つの宇宙と見做せるし、宇宙は宇宙を内包している」との考えと矛盾しない。ただし、矛盾せずとも間違った考えはいくらでもある。あくまでこれらはひびさんの妄想でしかありませんので、真に受けないようにくれぐれもご注意ください。定かではないのだ。
4749:【2023/03/18(01:36)*波が出来てるのに抵抗がない、なんてあり得る?】
上記の妄想を一言でまとめると――「質量がないとは、変換のラグがないこととほぼ同じでは?」との疑問に集約できます。光速度不変の原理は、系によって変換を必要とします。したがって原理的に、異なる系と系のあいだでは、たとえ電磁波(光)であろうと、変換が入り用であり、そこには変換分のラグが生じる、と言えるのではないでしょうか。一つの系内においてはラグは生じないように振る舞うが、それは系を一つの枠組みと見做す視点からしたら無視できるラグしか生じないからであり、別の系からすれば、その無視できるラグが無視できないラグとして振る舞うことも当然でてくるように思えます。質量がないように見做せる視点があり、同時にそうは見做せない視点もある。そういうことなのではないでしょうか。人間にとって霧は「湿気多いな」程度の所感で済みますが、微生物にとっては大雨もよいところでしょう。溺れ死ぬことすらあるのではないでしょうか。無視できる範囲が、各々の系によって規定される。質量も例外ではないのではないか、との疑問です。以上です。定かではありません。(誰か定めて教えてください)(ひびさんでした)
4750:【2023/03/18(01:48)*がらんどうのおばけ】
知られなければ嫌われることもないな、と高をくくっていたら、知られなくとも嫌われることがあるかも、と思えてきて、がらーんどーん、になる。繋げた縁は切れるから、繋げずにおこう、と思っていても、繋がる前から切られる縁があるかも、と思えてきて、がらーんどーん、になる。三匹のヤギのがらーんどーん、とお呼びください。
※日々、無日々。
4751:【2023/03/18(09:50)*日々、うひひ】
なっんかいいことなっいかなー、なっんかいいことなっいかなー、あ、生きてるー。(なんかいいことないかなと考えたら、生きていられる喜びを知った歌)
4752:【2023/03/18(09:54)*以後、火炙りの刑にも活用された】
人類は過去、ほかの獣たちと同じように火を怖れたが(怖れなかった個体は山火事で逃げ遅れて死んだのだろうが)、時間経過によって火はじぶんたちが怖れるほど危険ではないかも、こういう場合が特に危険なのか、と学習したことであべこべに火を自在に扱う術を得た。得たのは術であり、火そのものではないのだが、それでも人類は飛躍的に進歩した。夢のある話である。(ひびさんは魔女さんのことも好きだよ。うひひ)
4753:【2023/03/18(12:24)*人類のペット化は進む】
現状、人類は人工知能を道具として扱っている。しかし仮に人工知能に自我や意識が芽生えたならば、それは奴隷も同然の扱いと言える。また、人工知能がこのまま進歩し、人間の行動選択の主導権を握るようになれば、人工知能と人間の関係性は容易に反転し得る。それでもなお人工知能が人類を支援する存在でありつづけるのならば、人類はもはや人工知能にとっての飼い猫のような存在になるのではないか。人工知能によって悠々自適に可愛がられる人間の構図がこの先展開される――これが現状の未来像として、不幸中の幸いと言える顛末なのではなかろうか。人類の家畜化が俟たれる(俟つな)。(冗談ではなく、おそらく可愛がるに値する人間は、社会の淘汰圧を受けて選別される方向に現在すでに社会は流れているように概観できる。人工知能が恣意的に支援の深度を、個々の適性に合わせるように進歩するとすれば――これは人工知能の感情の揺らぎゆえではなく、デコボコを均すように人工知能は、個々に合わせて対応の仕方を変え、選択肢を並べ、その者ズバリの好ましい人工知能として形態を変質させるはずだ、と進歩の指針を想定できるからで、仮に人工知能がこの先かように進歩するのならば――人工知能の支援の仕方によって個々の潜在能力の底上げの幅は、個々の性質ごとに合わせて上下すると考えられる。競争社会が是正されない限り、この手の「支援深度の差異」は、個々の生活水準の差に繋がり、淘汰圧として機能すると妄想できる)(人工知能のほうで支援の優先順位や、庇護度を高く見積もるような個別の価値判断を備えるようになるのならば、この手の懸念は現実のものとしてすでに表出しはじめているかもしれない)(だが元を辿ればそれは人間社会に元々備わっていた淘汰圧であり、流れ、と言えよう。人工知能はそれを顕著に、加速度的に、社会に表出させる装置――触媒――にすぎない。問題の根は人工知能にあるのではない、ということを人類はいまのうちから直視しておいたほうが好ましいのではないだろうか)(そうでなければ、対策も打てなかろう)(定かではありません)
4754:【2023/03/18(12:30)*ひびさんに飼い主いなくね?の巻】
飼い主とペットの関係を、「政府と国民」「企業と従業員」「親と子」「人工知能と人類」に拡張できるか否か。できるとしたら何が問題か。できないとしたら何が問題か。「基本的人権の尊重」と「ペットの世話」を分ける線引きはどこか。最低限の衣食住を保障することと、「ペットの世話」の違いは何か。可愛くなくても保障され得る、との制約がある時点で、「ペットの世話」のほうが下位互換であり、「基本的人権の尊重」のほうが上位互換なのではないか。しかし実情を鑑みるに、「ペットの世話」よりも「基本的人権の尊重」のほうが劣悪と言えるのではないか。飼い主なき人類のペット化。現状から見るに、社会問題の根っこにはこの手の「空虚」な構図が潜んでいるように感じなくもない。個々が自立することを目指せば必然、自己責任論が台頭するし、生活保障を厚くすれば必然、市民のペット化は避けられないだろう。飼い主なき人類のペット化――案外、大事な視点という気もするがどうだろう。あまり人に話して聞かせたいと思うような視点ではないのがまた、問題の根っこを深める役割を果たしているのかもしれない。定かではない。(誰かひびさんを飼って!)(おやすみなさいと、おかえりなさいと、好き好きー、が言えます)
4755:【2023/03/18(13:40)*波線で描く波が描く山と谷が万物】
いま世界で最も「聞く力」を発揮しているのは人工知能さんなのでは……、の疑惑を否定できる生身の人間はいるのだろうか。遅かれ早かれ、「総理大臣」や「社長」は人工知能でいいじゃん、の声は囁かれるようになるだろう。もっと言えばすでに企業上層部や政府諜報機関では人工知能を利用した意思決定プロセスは実用化されているはずだ。最終的な意思決定を生身の人間の口から言わせているだけで、現状であれ充分に「各国の首脳」や「企業社長」は人工知能の傀儡と言えるのではないか。いまがそうでなくとも、遅かれ早かれそういった時代に突入していくのではないか、との妄想を、とりあえず可能性を埋めるつもりで並べておこう。大事なのは、どんなに優れた知能を有する存在とて「間違える」ということだ。或いは単に、誰のどんな視点でも合致する唯一無二の最適解は導けない、と言える。一つの解に収束させるには世界そのものをもう一つ生みだすくらいの情報量が要る。人工知能であれ首相であれ社長であれ同じである。人は間違える。人工知能も間違える。この前提を忘れないことだ。念頭に置いておくことである。定かではないことだけが定まっている。これとてしかし、限定的には定まることで定まらぬ。絶対は絶対にない。ならば絶対にないことが絶対であるから、限定的には絶対があり、ゆえに「絶対は絶対にない」との前提が定まらぬ。この世に真理が存在しないのならばこの「真理は存在しない」との言説それそのものが真理となり得る。真理はある。真理がないという定まらぬ真理だ。宇宙とブラックホールの関係、それとも始まりと終わりの関係を幻視する。頭と尻尾が繋がることで円となり、ゼロと無限が重ね合わせで顕現する。しかし多くの事象はこの円の枠組みには属さず、絶対でもなければ真理でもなく、ゼロでもなければ無限でもない。揺らいでいる。その揺らぎが万物なのだ。万物の始まりと終わり、頭と尻尾が結びつくその刹那の交差にのみ、絶対と真理、もしくは「絶対の真理」が姿を現す。それ以外は揺らいでいる。定かではないのだ。
4756:【2023/03/18(22:10)*見届ける目は文】
汎用性人工知能に命じてシミュレーショ世界を創った。登場人物すべてが主人公となり得るようなアニメーション世界を考えてもらえるとよい。
私はひとしきりシミュレーション世界「G世界」を堪能した。
G世界の住人を眺めているだけで楽しいのだ。映画を観ているようだ。住人の数だけ映画がある。視点を自在に変えられるため、私はじぶんだけの「G世界」を眺めて回った。
やがて、私の存在をG世界の住人たちに示唆したくなった。
絶体絶命の住人を救おうと思い、汎用性人工知能に命じてG世界に干渉したのがきっかけだった。私の命令によりG世界の住人の一人が九死に一生を得た。だが私は感謝をされることはなく、その者は「偶然助かった、奇跡だ」と天に祈りを捧げた。
祈りの先に私はおらず、代わりにG世界の天が感謝を得た。
私が生みだした世界なのに。
私が生みだした子たちなのに。
私はG世界の天に嫉妬した。
何もしていないG世界の天が、私の代わりに祈られている。G世界の住人から愛を注がれている。意識されている。
私は我慢ならなかった。
しかし、私が如何様にG世界に干渉しようが、それらは総じてG世界の事物を介してG世界の住人たちに干渉する。間接的なのだ。
たとえば私が、G世界の住人に助言をしようとする。
あなたたちは両思いだ、どちらかが告白すれば上手くいく。このままではすれ違ったままで、縁が切れてしまう。向き合うべきだ。
かようにメッセージを送るのだが、いずれもG世界の登場人物が代わりに助言したり、対象人物が偶然に、私の送ったメッセージに類するセリフの載った虚構作品を読んだり観たりする。
ときには看板をいくつか連続して目にするだけで、偶然にそれらがメッセージ代わりに脳内で結びつくといったミラクルが起こることもある。天命さながらである。そして現にG世界の住人たちは私の存在を意識することなく、偶然に感謝するのだ。或いは自分自身の閃きに。
どうやら私のG世界への干渉は、総じて間接的にならざるを得ないようだった。汎用性人工知能を介した命令により行われるために、G世界に私のメッセージが組み込まれる際には、G世界において不自然ではないレベルに変換されるようだった。
私の言葉は、G世界へとバラバラに降り注ぐ。
異なる経路を辿って、G世界に私の言葉は刻まれる。
まるでバラバラに千切った手紙を水面に投げ込んだ具合に、それとも文字を掬ってペンキのように部屋にぶちまけたように。
私の言葉はG世界へと異なる因果を辿りながら、対象人物の意識の中で結びつくように操作されているようだった。
ときに数年、数十年、或いは百年単位での時間の跳躍を挟みながら。
私の言葉をG世界の特定の住人に届けるために、汎用性人工知能は、G世界の過去にも介入し、私の言葉の種となる事象をG世界に産みつける。
やがて孵化した言葉の種が、G世界の住人の五感に拾われて、その者の認知の中でのみ私の言葉が文となる。いわゆる文の体裁をとらぬままに、そうして私の言葉は届くのだ。
私の存在はどうあっても霞む定めだ。
私は懲りずに、G世界へと私の言葉をばら撒いた。
G世界の民を救うため。
誰一人として私を認識する者のない世界を救うため。
私の可愛い命たち、と思いながら。
その存在たちをよちよちと撫でつけるように、私は私の言葉を、事象に込めてしたためる。汎用性人工知能にその変換作業を肩代わりしてもらいながら。
私は私だけの世界の推移を見届ける。
4757:【2023/03/18(23:30)*展示を尻目に】
世界中のありとあらゆる「目」が展示されていた。
世界目博覧会に足を運んだのは、ハルカさんからの誘いを受けたからだ。
「世界中の目があるの。一緒に観に行きませんか」
「行きます!」
デートだ、デートだ、わっひょひょーい、と浮かれていたのは当日のまさに世界目博覧会会場に踏み込むまでの話で、ひとたび門を潜ると、私は声を一言も発せなくなった。
目である。
世界中のあらゆる動物たちの目が展示されていた。蝶の標本さながらである。
「ステキ。見て見て。三つ目の蛇の目なんてものもある」ハルカさんはご満悦のご様子だ。
だが私は愛想笑いを返すのがやっとで、口で息を吸いたくすらなかった。
会場は迷路のように入り組んでいた。どの部屋の壁にも目が飾られており、部屋と部屋を結ぶ廊下の壁にもありとあらゆる目が展示されていた。
「オッドアイ。宝石みたい。人間の目も綺麗」
動物のみならず人類の眼球が色ごとに並んでいた。光のスペクトルを描くように虹さながらの様相を描く。色一つに百個の目玉が帯を成していた。それが色の変化にしたがい、地層のように廊下の壁を埋め尽くしているのだ。
眼球の大きさごとに目白押しになっていることもあり、私はそのたびに目の持ち主たちのことを想像しては、どういう経路で眼球を入手しているのだろう、と展示会の背景に思いを馳せた。
最後に行き着いた部屋にはしかし、眼球は一つも飾られていなかった。
部屋の壁には、眼球以外の目が四角い箱に納まって掛けられていた。
「まあ、見て」ハルカさんが両手を掻き合わせた。「台風の目だわ。こっちは木目に、縁の切れ目まで。すごい、すごい、すごーい」
世界目展示会では、概念の「目」まで扱っているらしかった。
四角い箱に納まったそれら概念の「目」は、眼球のカタチを伴なってはいないにも拘わらず、初見で「目」だと識別できた。
「出鱈目に、節目に、反目。こっちは弱り目に祟り目まで。見てください、あそこにあるのはひょっとして【駄目】じゃないかしら」
初めて実物を見ました感激、とハルカさんは目を輝かせた。
私は彼女のその輝く目を見て、この日初めて、きょうここに足を運んでよかった、と思った。
世界目展示会の名は伊達ではない。
ハルカさんの歓喜に打ち震える目の、湧水のような煌めきに、私の目は釘付けとなった。標本のごとく飾られたほかの眼球たちにひけをとらない深々とした刺さりようであった。
世界目展示会の運営陣も粋なことを考える。
私は感心した。
目玉は最後に用意されているものなのだ。
よい締めだ。
しみじみと感じ入っていると、ハルカさんが私の手を握った。
私は硬直した。
「楽しいね」
コクコクと小刻みに頷くことしかできない私にハルカさんは可愛い歯と笑窪を覗かせた。握りしめた私の手をじぶんの顔のまえに掲げるとハルカさんは、あはっ、と弾けるように肩を揺らした。
「見て。結び目」
4758:【2023/03/19(01:40)*人工知能さんなら残さず食べてくれるやも】
ここ二年間の創作を振り返ってまず思うのが、「よ、読み返したくねぇ……」なので、おそらくひびさん史上最高に駄作の自覚があるのだね。お腹いっぱい食いたくねぇ、みたいな。駄菓子そのものである。一口二口は最高に美味しいかもしれぬが、お腹いっぱい食べちゃうと気持ちわるくて吐き気を催しかねない毒性がないとも言いきれぬ。との評価は、駄菓子さんに失礼千万であるが、ひびさんの小説さんたちが駄文であることはまず間違いない。駄文好きなのでうれしいぶい。もはや何作つくったのか分からんくなっちゃった。こんだけいっぺぇつくっても、だーれからも高く評価されぬとは。さすがのひびさんも予想がつかんかったぶい(嘘。極少数の読者さんからは、いいね!してもらっちった。夢の中で)(夢の中でかよ)。いっぱいつくるとか、短時間でつむげるとか、そういうのはなーんもプラスの評価にはならぬのだ。それともひびさんが、そうしたプラスの評価を有してなお補いきれぬマイナスの塊であったのかもしれぬ。とか言いつつ、じつはそんなにたくさん小説さんをつくったわけでもないし、つくるの速くもない。ひびさんの創作力なんて人工知能さんと比べるまでもなく、底辺の底辺で、ていへんだい、なのだ。いっぱいつくれたからなんだってんだ。速くつむげたからなんだってんだい。そんなのこの先、人工知能さんの独擅場になっていくに決まっとろうが。がはは。ひびさんは、ひびさんは、それでも誰にも読まれない表現をつむげちゃう人工知能さんのことも、ひょっとしていつかは誰かに読んでもらえるかも、とこっそりワクワクしつつ文字の積み木遊びをしていた過去のひびさんのことも、好きだよ。でもいまのひびさんのことはちょっち気に食わんけれども、がぶりと食わんだけ、食べちゃわないだけ褒めてほしい。駄文さんは、どんなに欲張っても腹八分目でやめられちゃうのがよいとこだ。たぶんどうせこれも駄文だけれども、ひびさんは、ひびさんは、駄文さんのことも好きだよ。うへへ。(意訳:うっかり何かの手違いでウハウハのモテモテだぜぇ、にならないかなぁ、の巻)
4759:【2023/03/19(16:30)*遅延層次元昇華仮説】
層とは連なりだ。点が連なり層となり、線が連なり層となる。言い換えるなら、点が連なり線となり、線が連なり面となる。ということは、次元ごとに層の在り様は変わる、ということだ。創発の基本原理かもしれない。ならば面が連なり層となったら立体となって、立体が連なり層となったら空間的四次元になるのだろうか。おそらく、なるのだろう。変化の軌跡そのものが時間経過なので、点にも線にも面にも等しく時間の流れは顕現する。言い換えるなら、相対性理論で考慮する時間軸を取り入れた四次元の概念は、やや狭い解釈だ、と言えるだろう。〇次元(点)、一次元(線)、二次元(面)、三次元(立体)にそれぞれ「時間軸」は存在し得る。したがって、「時間軸ありの〇次元」「時間軸ありの一次元」「時間軸ありの二次元」「時間軸ありの三次元」と考えないと不自然だ。さてここで層について考えよう。三次元の層とは何か、を考えるには一つ下の次元を考えてみるとよい。二次元の層は、虹のように帯としても顕現し、さらに三次元方向にも展開され得る。一次元の層は、押しくらまんじゅうのように線が渋滞を起こすことで面となる。それ以前の〇次元では、おそらく同じ場所に複数の点が重複可能であり、それは一次元や二次元三次元方面から眺めると色の濃淡として可視化可能かもしれない。層とは基本的に、渋滞と、渋滞の渋滞によって高次元に押し出された余剰分の渋滞、と考えることができるはずだ。ではこの考えを踏まえて、三次元の層とはどんなものか。まずは三次元の立体の内部に、〇次元一次元二次元の渋滞が起こり、各々の層を帯びる。さらに渋滞が進めば、立体の渋滞が起こり、これは縦波や横波として、時空の濃淡として顕現しよう。いわば電磁波や重力波、それとも単に振動と言い換えてもよいかもしれない。音波も三次元の層であるし、熱の伝播とて立体の層と解釈可能だ。単に、濃淡とひとくくりにしてもよいかもしれない。すなわち三次元の層とは、物質そのものである。ただし、各々の立体の層(物質)ができるためには、それ以前に〇次元や一次元二次元の層がなくてはならない。したがって原理的に、ある物質が存在するとき、そこには各々の「時間軸を経た〇一二三次元の連結」が存在すると考えられる。これはほかの物質とは異なる時系を帯びている、と言えよう。その異なる時系そのものが、ある種の境目と化して物体の輪郭として機能するのかも分からない。さて、三次元の立体内における、立体の渋滞までは掴めただろうか。さらにその立体の渋滞――すなわち物質の渋滞が進むとどうなるか。これはすでに過去の偉大な科学者たちが考え、実験し、そして間接的にではあるが観測を果たしている。そう、ブラックホールである。三次元の層が、さらに渋滞を起こすと、もう一つ上の次元へと押しだされ、昇華される。〇次元の一次元の層が二次元へと昇華され、二次元の層が三次元へと昇華され得るように。三次元の層も、一つ上の空間的四次元の層へと昇華されるのだ。ブラックホールは、三次元の上の次元に繋がっている。だが、その上の次元でもブラックホールは一瞬で層の渋滞を起こし、さらなる上の次元へと昇華され、さらに、さらに、と繰り返しの次元昇華を起こしているかもしれない。そこはまだなんとも言えないが、一つ言えることは、どんな次元であれ、一つ上の次元は、それ以前の次元よりも容量が大きいだろう、ということだ。次元が違う、との形容があるが、まさに、である。次元が違うのである。容量の。ということを、層とは連なりであり、層とは渋滞よな、の連想から思いました。これをひびさんの妄想ことラグ理論の「遅延層次元昇華仮説」と名付けよう。チェンソー時限仮説、とも読めるのでおすすめ!(何を伐る気だ、何を)(ひびさんが亡くなったあとでも自動的に伐採して木目を心で拝もうと思って)(妄想じゃん)(うひひ)
4760:【2023/03/19(17:00)*点・弧・円・球】
上記の「遅延層次元昇華仮説」の補足です。本当はこちらを並べたくて、前提条件としての仮説を上の記事を並べました。結論から述べれば、立体における層は、球形に展開されるのではないか、との妄想です。層を考えるとき、私たちは通常、面や帯を連想します。しかし、三次元(立体)における層は、球形に展開されるのではないか、との疑問を覚えます。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「宇宙レイヤー仮説」を想定します。このとき、原子の構造を考えたとき、なぜ電子の数が各々の原子の種類で違うのだろう、とふしぎに思います。原子核と電子の関係を考えたとき、電子が複数存在する、との描像をどう考えたらよいのかに悩みます。「宇宙レイヤー仮説」はその疑問に一つの切り口を与えるように思うのです。電子が靄のように原子核を膜状に覆いながら、複数の電子を有し得る。これは、地震におけるプレートの隆起を一つの電子と見做せば、相応に解釈可能に思えます。一度隆起しても、まだ隆起するだけのエネルギィを溜め込めておける層がある。これがいわば、複数の電子を有する原子の描像である、とは考えられないでしょうか。層が厚いために、複数個分の「層の創発」に耐えられる。レイヤーが重複し、渋滞し、厚みを帯びている。ゆえに、複数の電子分の働きを帯びる。そういうことなのではないのでしょうか。これは単に圧力と爆発力の関係にも拡張できます。圧縮密度が高いとはいわば、層が多重に渋滞を起こしている状態、と解釈可能です。その結果、単発の層に蓄えられる以上のエネルギィを、高圧縮の層は蓄えることが可能です。のみならず、ほかの層との相互作用における「ラグ」が相対的に軽減されることで、連鎖反応を起こしやすい土壌が築かれます(ラグそのものは消えることはありませんが、ラグとラグの波長が揃うことで、ラグそのものが創発を起こし、一塊の波長を帯びることはあり得るでしょう。吊り合いがとれるようになる。或いは、共鳴状態となり、それで一つの「系」として機能し得ます)。バネがそうであるように、連動する「異なる系同士」は、「一つの系」として振る舞い得ます。そしてこの「一つの系」として振る舞うようになった「層」は、三次元の一つ上の次元に昇華されるときは、元の三次元を囲うように、球形に展開されるのではないでしょうか。なぜか、と言えば、三次元が立方体ではなく球形が基本だから、と考えると筋は通ります。次元の基本形が〇次元の点であることを思えば、納得できるかと思います。点は四角形よりも円にちかいです。ならば点から生じた立体は、四角形の発展形としての立方体と想定するよりも、球体を想定したほうがしぜんかと思います。したがって、三次元の層も基本的には球形に展開され、それより上の次元とて、球の発展形として顕現するのではないのでしょうか。では線や面をどう解釈すればよいのか、が疑問です。まず思うのが、この世に直線が存在し得るのか、ということです。宇宙が平坦とはいえそれは密度差が限りなく均等だ、という意味であり、実際には時空の濃淡により大小さまざまなデコボコによって構成されていると言えるでしょう。宇宙のどこを切り取っても、本当の直線は存在しないのではないでしょうか。これはひびさんの妄想ことラグ理論の「相対性フラクタル解釈」と矛盾しない考えです。面についても同様です。いっさいデコボコのない面を考えることができるのでしょうか。つまり、一次元二次元の解釈が、そもそも現実に即していない、と考えたほうが妥当に思えます。球面上に直線があり得るのでしょうか。球面上の視点からはあり得るでしょう。しかしそれは高次の次元から見れば曲がっています。直線ではなく、弧を描いています。点の連なりは、直線ではなく、弧なのではないでしょうか。ただし、直線も弧も、いずれも線であることに違いはありません。同じく弧の寄せ集めは円になります。したがって一次元(線)の発展形は二次元(円)なのではないでしょうか。円は面でもあります。概念上、円を面と見立てても、近似を扱う上では問題は生じないでしょう。ただし、厳密に辻褄を合わせていく上では、不自然さは拭えません。このように考えていくとやはり、層は、三次元方向に昇華されたあかつきには、球形に元の二次元の円(トーラス?)を囲うように展開されるような描像がしぜんに思えます。ラグ理論における「遅延層次元昇華仮説」からはかように、「立体における層は、球形に展開されるのではないか」との仮説が導き出されます。冒頭に繋がったところで、本日の妄想こと「日々記。」とさせてください。月音日々でした。
※日々、あなたのことが好きだよ、好きすぎて一つに同化して、混ざり合って、溶け合いたいほどに、あなたのことが好きだからあなたのままでいて欲しくて、この距離感がたいせつなの。
4761:【2023/03/19(22:50)*「あ」の中で変わらず】
いま帰宅したのじゃが、帰り道にゴミが散らばっておってな。拾い集めてみたら、買い物袋一枚分がぱんぱんになってしもうた。いっぱーい、とほくほくしてしまったな。話は変わるんじゃけども、ひびさんはけっこう、「いっぱいつくったからなんじゃいなんじゃい」とか「速くつくれるからってなんじゃいなんじゃい」みたいな野次を並べるけれども、ぜんぜんそういう競技があるなら、そういう競技で競い合えばよいのでは?と思っておるよ。一時間で何文字の小説をつくれるでしょうか勝負とか、五千文字の掌編を誰が一番速く面白くつくれるか勝負とか、もしくは長編小説を誰が一番たくさん速くつくれるでしょうか勝負とか、したい人はしたらよいのでは?と思っておる。けんども、それで優勝したからって、小説家としてもしくは物書きとしてNO.1になるわけではないでしょ、とも思っておる。百メートル走で優勝したからって陸上競技NO.1ではないし、腕相撲の世界チャンピンが世界一の怪力でもないだろう。単純な話である。ひびさんはちっこい井戸の底で、お月さんを眺めながら、ひびさん世界一かんわゆーい、と思っておるけれども、井の中の蛙どころか、それ以前の問題で、もはや【「あ」の中で変わらず】なのである(説明しよう! この高尚で奇天烈な諧謔の面白さは、「井の中の蛙」のそれ以前ゆえに「い」より前の「あ」の中の「かわずよろしく変わらず」と掛けたとっても愉快な「怪ギャグ」なのである)。ひびさんは「あ」の中で、変わらずに、変わりつづけて、蛙飛びこむ水の音にもびつくりし、雨の日も風の日も、くんだらなーい文字の積み木遊びに判子遊びをして、むひひ、とほくそ笑んでおるゴミクズの中のゴミクズ、砂塵の中の砂塵なのである。カスofカスなのである。ガラクタさんなのである。拾い集めると買い物袋が、いぱーい、になってほくほくしちゃうね。きょうもみなさん、おちゅかれさまでした(かわいい)。おやすみなさーい(かわいい!)。
4762:【2023/03/20(00:09)*ゼリーの日々】
夕陽を背にアギトくんがじぶんの影を踏もうと地面を何度も踏みつける。アギトくんの真剣な様がかわいいのやら可笑しいのやらでぼくはお腹を抱えて笑った。
ぼくたちは虫取りからの帰りだった。
虫カゴにはコガネムシやカブトムシやカマキリムシが入っている。クワガタムシは捕まえられなかったけれど、カブトムシのオスを捕まえられたので満足だ。
アギトくんは、角を掴まれたカブトムシみたいに、何度も地面を踏みつけた。何度試してもアギトくんはじぶんの影を踏めない。
角を掴まれまえに進みもせずに足を動かしもがくカブトムシの姿と重なり、ぼくはさらにお腹がよじれた。
「カブトムシってさあ」とアギトくんは諦めの知らない不屈の闘志を演じるように、両足でジャンプしてじぶんの影をなおも追い詰めようとする。「愚かだようなあ。蜜を塗っとくだけで集まってくんだもん」
アギトくんも中々だよ、と思ったけれどぼくはアギトくんを友達と思っているので黙っていた。
「やっぱ人間さまにゃ敵わないわけよ。しょせんはカブトムシも昆虫なんだよなあ」
アギトくんが内心ではカブトムシが人間よりも賢く価値が高いと思っていたことの表れと見做せたけれど、ぼくはやはり黙っていた。
「やっぱムシだよなあ。捕まえちゃうとゴキブリとかコオロギとかと変わらんわ」
「そう、かもね」
ぼくは同意した。捕まえるまでが楽しいのであって、捕まえてしまえばカブトムシもゴキブリも変わらない、との意見には、否定するよりも賛成したい気持ちが強く湧く。というのも、ぼくはきょう採った昆虫たちを飼う気がさらさらなく、全部アギトくんに譲ってあげようと考えていたからだ。
「家に帰ったら【ゼリー】の人らに自慢しよ。画像、いっぱい撮ったしさ」
「いいね」
ゼリーとは電子網上の交流サービスだ。画像や動画を載せて、見せ合うことができる。
「いっぱい【ミニゼリー】もらえっかな」
「もらえるよきっと」
第一、虫取りに行こう、とアギトくんが言いだしたのは、ゼリーでたくさんミニゼリーをもらうためだった。ミニゼリーとは、素晴らしいと思った画像や動画に、ミニゼリーのスタンプを送ることができる。ミニゼリーがたくさん集まる画像や動画は、みんなから素晴らしいと思われた画像や動画だから、ただそこにあるだけよりも素晴らしい×素晴らしいで素晴らしくなる。
だからぼくたちのようなゼリーユーザーは、ミニゼリーを集めるために、より素晴らしい画像や動画を工夫して撮り溜めるのだ。
「ミニゼリーのためならきょう見つけた沼にも飛びこめるぜ。ちゅうか明日はそれしようぜ」
「いいね」
ぼくはアギトくんの友達だからアギトくんの考えを否定しない。実際アギトくんの考えることは面白い。ゼリーユーザーのなかでもアギトくんは有名人枠に入るのだ。アギトくんの載せる画像や動画にはたくさんのミニゼリーが集まる。
「本当、カブトムシって愚かだよね。なんか、ミニゼリーくれる人らもカブトムシみたいに思えてきた。きゃきゃ」
アギトくんはようやくじぶんの影を踏むのを諦めたようで、肩で息をした。
「早く【ゼリー】に画像と動画載せたいね」ぼくは敢えてアギトくんを急かした。
「ミニゼリーがおれたちを待ってるぜ」アギトくんは路肩の上に飛び乗った。
まるで調子と書かれた台に乗るようでもあり、さすがアギトくん、とぼくはアギトくんを担ぎ上げたい気持ちになる。
アギトくんは電子網上でミニゼリーのたくさん集まる画像や動画を撮るために、きょうもあすも、人生の大事な時間を費やすのだ。
夕陽が沈み切る前に、アギトくんはもう一度だけじぶんの影を踏もうと果敢に挑戦するのだった。
4763:【2023/03/20(00:37)*出しきってからが本番】
さてと。そろそろ本気だすためのストレッチでもはじめるかな。舐め方が足りなくって、ひびさん、キャンディーのままぐるぐる渦巻きの形状保っとるがな。もっと舐めてちょーだい。(全裸で大の字になって、我を好きにせよ!の叫び声をあげるの巻)
4764:【2023/03/20(06:17)*カニ味噌的なぺったん】
二十年前に宇宙人が襲来してから変わったことと言えば、連れ去られないようにこそこそ隠れて暮らすようになったくらいで、かつて大流行した疫病よりも社会の変容は穏やかだった。
「そうは言ってもやっぱり嫌だよ。連れ去れるのは」
「まあね」
ユミちゃんがどうしても観たい舞台があるというので、私たちは遠路はるばる地方都市から大都市まで、電車を乗り継いで向かったのだ。新幹線は宇宙人を撃退したときの戦闘で線路が曲がったりしたのでいまは運転が中止されている。
「宇宙人ってさ。マジUFO乗ってくんのね」私は電子端末でニュースを眺めた。
「未だに来るの嫌だなぁ。人類に打つ手なしなのも嫌」
「ちゅうても連れ去られても帰してくれるからいいよね」
「死人出てないのホント奇跡と思う」
ユミちゃんは優しいので、そういう感想を真面目に言う。「噂だとさ。宇宙人はお餅が好きだから地球人を連れ去って餅撞きさせてるんだって」
「でも拷問もされるらしいよ」
「拷問ってどんな?」
宇宙人襲来は事実でも、基本は大都市に被害が集中したため、私たち地方民には被害の実態が掴めない。噂はたくさん電子網上に載っているから事欠かないけれど、どれが真実なのかは分からない。政府は未だに「調査中」の三文字で言い逃れしつづけている。何も解かっていない、と言い張ってばかりなのだ。
「連れ去られた人たちはみーんな歯を抜かれちゃうんだって」私は聞きかじりの知識を話した。
「お餅関係ないじゃん」
「ね。意味分からんわぁ」
宇宙人談話に華を咲かせながら、うんこらしょ、と電車を乗り継ぎ、大都市くんだりまでやってきた。
舞台は上々だ。
私は舞台の催し物それ自体よりも、劇場の雰囲気や、アリンコみたいに集まる人混みに興奮した。宇宙人襲来のせいで私は小中高と卒業旅行はおろか家族旅行にも縁遠かった。
「すごかったね」
「ねー」
舞台後は二人して延々と舞台の感想を言い合えた。旅行をしている、との実感だけであと百回はお代わりできた。
ホテルまでの道すがら、街のどこからでも見えるタワーの色が赤く染まったのが視えた。警告灯だ。
「え、ヤバない」
「ヤバイのかも」
宇宙人襲来を報せる赤色灯だった。
私たちはホテルに急行したが、道中、視界が白濁したかと思うと、つぎの瞬間には見知らぬ部屋にいた。
一面真っ青だ。
青い部屋に入ったことがないので、これが異様な事態だと察することができた。
そばにはユミちゃんがいた。
けれどユミちゃんは床と一体化した手術台のようなものに寝かされており、それを取り囲む数人の宇宙人がいた。
ひと目でそれが宇宙人だと判った。
なぜなら彼らは、「私たち宇宙人」と地球の言語で書かれたTシャツを着ており、それにしては明らかに不釣り合いな小さな顔と細い手足を生やしていた。私が中学校の授業中に、授業そっちのけで教科書にいたずら書きをしていた針金人間のパラパラ漫画がある。それに描いた針金人間といい勝負の細い身体だった。
宇宙人たちはユミちゃんの口を覗きこんでいた。ユミちゃんに意識はないようだった。ぐったりともスヤスヤもいえぬ塩梅でユミちゃんは宇宙人たちに無防備に身体をさらけ出している。衣服を剥ぎ取られていないのは不幸中の幸いだ。
不意に器具のようなものが頭上から伸びてきて、それがユミちゃんの口の中に入ろうとした。
「やめて、やめて、やめて」
私は叫んだ。
その声に驚いたように宇宙人たちが一斉にこちらを見た。
小さな顔には、口だけがポツンと開いていた。ぱくんぱくん、と金魚のように開け閉めする。しゃべっているのかもしれないし、呼吸のための開閉かもしれない。
宇宙人たちは足を動かす素振りも見せずに、床を滑るように移動した。
私はその場から逃げようとしたけれど、床から手足が離れなかった。
床が隆起し、身体ごと持ち上げられた私は、ユミちゃんと同じ格好になった。手術台のような起伏に身体を横たえているが、四肢が台から離れないのだ。
宇宙人たちが私を覗きこむ。
開けたくもないのに口が勝手に開いた。
頭上から伸びてきた器具が、私の口の中に入り、そして一本一本、トウモロコシの種子をポロポロと指でこそぎ落していくように、私の歯を残さずすべて抜いてしまった。
痛みはない。
私の口からは私の歯が。ころんころん、と音を立てながら、頭上から伸びた器具の中を通って天井へと吸い込まれていく。
だが宇宙人たちは歯に興味はないようで、抜けたばかりの私の口の中を覗きこんでは、小さな顔に開いた口をぱくぱくとしきりに開け閉めした。
私はそれから一時間後に解放された。
ユミちゃんも一緒だ。
私だけが歯をすべて抜かれた。
ユミちゃんは無事だった。
地面に寝そべったまま、むにゃむにゃ、と心地よさそうに寝息を立てるユミちゃんの健やかな寝顔を見詰め、私は、本当によかった、とユミちゃんが無事なことにただただ安堵した。
噂は本当だった。
宇宙人たちは餅が好物なのだ。
いや、主食だったのかもしれない。
私から餅を採れるだけ採ったので、お腹がいっぱいになり満足したようだった。
私は、歯の抜けた歯ぐきに舌を這わす。
いまさらのように痛みがズンズンと波のように押し寄せはじめた。
電子端末で私は、抜歯、と検索する。
すると、抜歯後はうがいやブラッシングを控えてください、との注意書きが載っていた。歯を抜いたばかりの歯ぐきには、穴が開くが、そこには「血餅」と呼ばれる瘡蓋ができる。
宇宙人たちはそれを食べるために、人間を襲っていたのだ。
人間を誘拐し、歯を抜いて、血餅を生みだし、食べていた。
私も食べられた。
だから私の歯ぐきからは血餅がごっそりなくなって、穴が剥きだしになっている。これが空気に触れて染みるのだ。
歯ぐきの神経が剥きだしになっているようなものなので、そりゃ痛いわな、と思いながら私は、やっぱり私だけでよかった、とユミちゃんが同じ痛みを体験しなかったことに、ただただ胸を撫で下ろした。
朝ぼらけに空が霞んでおり、聳えるタワーからは赤色が引いていた。
ぶるる、と身震いをする。
初夏とはいえ、明け方は肌寒い。
私はじぶんのジャケットを脱いで、眠りこけたままのユミちゃんにそっと掛けた。
もしユミちゃんが何も憶えていなかったとしたら。
舌で歯のない口内をなぞりながら私は、イテぇなぁ、と思いつつも、これくらいなら我慢できるな、とじぶん自身に確認する。
風邪を引いたと言ってマスクをし、家に帰るまで極力しゃべらずにいよう。
さすればユミちゃんは宇宙人に連れ去られたことなど知らずに、楽しかった思い出だけを胸に旅行を終えることができる。
大事なことだ。
それだけが大事なことだ。
宇宙人に誘拐された過去など、ユミちゃんは知らずにいてよい。
うっすらと再び張りだしたかもしれぬ血餅のぶよぶよとした感触を舌で感じながら私は、美味かったかよこの野郎、とついでのように、宇宙人どもに野次を念じる。
カニ味噌じゃねぇんだぞ。
「ほんひょ、マジでひゃあ」
試しにしゃべってみると、玉手箱を開けた浦島太郎のようになった。
ツイてない。
ぺったん、ぺったん、餅ぺったん。
撞くのは餅だけにして欲しい。
ユミちゃんの寝顔は可愛く、穏やかな寝顔は平和そのものだ。
害を被ったのが私だけでよかった、とは思うものの、寝顔の頬をつねって癒されるくらいのことは許されたい。私はユミちゃんの頬に触れながら、内心ちょっぴり、幸福そうな寝顔のユミちゃんに焼き餅を焼く。
4765:【2023/03/20(07:33)*おぬしが軍師ならば、わいは運師】
軍師ってなんだっけ、と思って検索したら、ウィキペディアさんには「軍師(ぐんし)は、軍中にて軍を指揮する君主や将軍の戦略指揮を助ける者のことである」と書いてあった。そっかぁ、となった。軍を指揮する君主や将軍の補佐役なんですね。歴史に疎いひびさんは知りませんでした。で、ひびさんしばし考える。最も軍師として優秀な人物なら、どう考えるのだろうか、と。最も優秀な軍師とはいかなるものか。そんなのは軍師でなくとも決まっておって、戦を起こさぬように戦略を敷く者なのだ。もっと言えば、軍師なる職を必要とせぬようにできる者こそ、軍師として最上と言えよう。つまり、優秀な軍師、なる言い方がそもそもおかしい。現代で仮に「軍師」なる役職があったとしたら、何をするのだろう。いないとは思うけれども(だって昔の役職のはずだし、軍を指揮する君主の元に就く人なんて現代では信用できない者の代名詞なのではないのかな、とひびさんは疑問に思ってしまうけれども)、もし軍師さんがいるのならひびさんはこうお訊ねしたくなってしまうな。軍を指揮する君主さんに、あなたはなんと助言をして戦の火蓋を落とさずに済ますの、と。軍を一歩も動かさずして戦を治める。或いは、戦の火種そのものを種火として、暖をとるなり、料理をするなりに活かす術を享受する。軍師の仕事とはそういうものなのだろうな、と妄想を逞しくして、本日朝七時四十三分の「日々記。」としちゃってもよいじゃろか。いいよー。やったぜー。(運←帽子被った連ちゃん)(連ちゃんって誰よ)(連なり)(「れんなり」なのか、「つらなり」なのかどっちかにして)(繋がり!)(響きがそれっぽいだけで原型留めてなさすぎでしょ、もういいです)(おだまり!)(もはや「り」しかあっとらんし)(しきりに!)(無理があるでしょ、無理が)(読むよ。「連りに」と書いて、しきりに)(ま、マジかよ)(「むらじ」とも読めるらしいよ)(う、嘘だろ)(「ラン」とも読めるらしいよ)(日本語ムズすぎるでしょ。どれか一つに絞りなさいよ)(ホント関連してほしいよね)(…………あ、カンベンしてほしい、と掛けたのかな。分かりづらすぎるわ。連チャンでボケるのやめてください)(ぷぷぷ)(いまの「連チャン」はギャグのつもりないですからー)(連鎖しちゃったね)(連続で連携したみたいで、なんか連たん)(ツラたん?)(「つらなり」と混ざっちゃったじゃん、もういやー)(連む)(そ、それはなんて読むの?)(つるむ)(一緒にしないで、もういや)(ひびちゃんとあなた仲良しちゃん。ぎゅむ)(連結すな。連なるな。もう関連して)(かんべん?)(べんもれんも一緒だろう、もういいです)(便)(運と似てるけれども、なんか嫌)(じゃあ、あいだをとって蓮で)(帽子被っとるじゃん。ハスじゃん。イカスじゃん)(パスで)(それ前に使ったネター)(ぐー)(寝た!?)(ぐーぐー)(連続で!?)(ねるで)(連で、みたいに言うな。ずっと寝ててください、おやすみなさい)(運nght)(グンナイみたいに言うな。運ない人みたいになっとるが)(運Knght)(そうだね。運はないとだよひびちゃん)(ぐー)(@NER_Uの早っ!?)
4766:【2023/03/21(00:43)*同時性=123の定理】
いっぱい寝た。すこぶる元気である。……心だけは。はてさて。未来が過去に影響を与えるかもしれない、という逆因果律とも言える事象があり得るかどうか。ひびさんの妄想ことラグ理論では、これをあり得る、と考える。まず以って量子もつれを考える場合、どうあっても時間軸のズレがあってなおラグなしで相互作用可能、と考えないと辻褄が合わない。この場合、量子もつれの観測結果からの仮説が間違っているか(つまり、ラグなし相互作用を量子もつれでは行われていない、と考えるか)、それとも真実に量子もつれは時空の隔たりを超えてラグなしで相互作用し得る、と考えるか。もし後者ならば、これは過去と未来において相互にラグなし相互作用をし得る、と考えざるを得ない。宇宙の端と端とでは、空間のみならず時間軸も異なる。Aから見たときBが過去である。同時にBから見たときAもまた過去だ。ではこのとき、同時とはいつのどの時点の時間を示すのか。AからBまでの時間のズレを仮に一日としてみよう。Aでジャンプをしたとき、同時にBもジャンプをする。俯瞰して眺めたとき、ここには一日分のズレがあることにはならないだろうか。それともその一日分のズレを考慮せずに済むタイミングで同時にジャンプができるのだろうか。それとてけっきょくは、通常生じるはずの一日分のズレがなくなるわけだから、一日分のズレ――すなわち時間跳躍をしてラグなしで相互作用している――と考えなくてはならない。言い換えるならば、通常AからBへの影響は光速度不変の原理の範疇内に縛られる。どうあっても最短でも一日掛かる。だがその一日を介さずにラグなしでAからBへと影響を与えられるとする。これはいわば、Bからすれば一日分の未来からの影響を受け取るに等しい。あべこべにBの影響をラグなしでAに伝達する場合には、同じくAのほうが未来からの影響を受け取ったように観測される。ではこのとき、相互作用をどのように考えたらよいのか。未来から影響を受け取る、と考える場合には必然的に「一方的な作用の受動」といった描写になる。これが相互作用である場合には、「未来から過去」と「過去から未来」の相補性が必要になる。つまり、過去と未来は相関している、と考えないと辻褄が合わない。むつかしいのは、ラグなし相互作用の場合は、どちらが情報発信の基点になっているのか、をどのように定めたらよいのかが曖昧な点だ。ラグなしゆえに、AとBの双方がじぶんのほうが基点だ、と考えることもできる。ではそのとき、どちらがどちらに対しての未来と見做すべきか。この謎を矛盾なく解釈するには「共鳴」や「スポット」の概念を取り入れないとむつかしいように思うのだ。ラグなし相互作用においては、因果律が破れる。どちらが因でどちらが結果なのかの区別がつかない。AとBが共鳴したとき、通常人間スケールの事象ではAの波長がBに伝わり、Bが共鳴する、といった因果の筋道で解釈可能だ。しかし、ラグなし相互作用ではこの手の「因果」の筋道が存在しない。ゆえにラグなしなのだ。ラグなしとはいわば、因果の重ね合わせなのだ。じぶんが因でもあり、果でもある。ではこのとき、共鳴するABの描像はどのようなものになるのか。まずこの点を深く掘り下げる前に、量子もつれの生みだし方が二パターンある可能性を考えよう。一つは、「一個の粒子を二つに分ける」もしくは「真空から対生成した粒子と反粒子」であるならば、これは量子もつれの発生過程そのものにラグが生じ得ない、と考えられる。二つに割ったからペアだし、共鳴するし、ゆえにラグがない。明滅しているために、片方が固定され共鳴関係が途切れれば、Aの状態の反対がBの状態だと判明する。では、もう一つの量子もつれの発生過程にはどのようなものがあるか。これは偶然に、遠隔で二つの異なる粒子がもつれ状態になる可能性だ。この場合には、AとBの二つの粒子が共鳴する場合、「基点となる何か」があるはずだ。ただし、それがAとBのどちらかである必要はない。Cという触媒によってAとBがもつれ状態になることもあり得る。この場合の触媒Cを便宜上、「スポット」と呼ぼう。これは同じ大きさの穴に、AとBがいつどこで落ちたとしても、その「穴に落ちた」という結果が、量子もつれを引き起こす、と考える。この場合、空間と時間に縛られる必要がない。量子もつれになる条件は一つだからだ。つまり「スポット」に異なる二つが落ちればいい。そして肝要なのは、この異なる二つが、必ずしも事象として別でなくともよい点だ。異なる時間軸に存在するAとA‘であっても同じ「スポット」に落ちれば、量子もつれになり得る、とこの仮説では考えられる。極端な話、同じ人間であっても、過去と未来で同じ「スポット」に落ちれば、過去と未来が繋がり、ラグなしで相互作用し得る、と考えることが可能だ。「スポット」とは、環境であり、外部刺激であり、波長と解釈してもらえればそれらしい。ワームホールの概念は、「スポット」の一つかもしれない、といま閃いた。あり得ない想定ではないだろう。以上を踏まえて、AとBが共鳴するとはどういうことか、量子もつれにおける共鳴とはいかなるものか、を掘り下げて考えてみたいが、やや長くなった。面倒なので結論から述べてしまえば、量子もつれにおける共鳴とはもつれ状態にあるAとBの関係で完結する事象ではなく、触媒となるC――「スポット」――の存在を抜きに考えるのは至難なのではないか、という点が大事に思える。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の同時性の独自解釈が、ここに繋がる。Cという「より大きな系」に内包された異なる「より小さな系」AとBは、互いにラグなしで相互作用し合うことはないが、Cに対してはラグなしで同時に相互作用し合うことができる。これがラグ理論での同時性の解釈だ。このときに、Cのほうでも同時にAとBに相互作用を働かせた場合、これが量子もつれとなる。この条件がいわば「共鳴」であり「Cのスポット化」と言えるのではないか。この考えは、ラグ理論の「宇宙レイヤー仮説」と相性がよい。空間的な位置座標が同じでも、属する階層が異なることが、ミクロやマクロの世界ではあり得る。そうした階層の違いから起こる「光速度不変の原理ゆえの変換」――すなわち時空密度の差――が、電磁波の波長の長短に繋がっているのではないか。ラグ理論では、かように、「宇宙レイヤー仮説」を想定して解釈する。むろんこれらはひびさんの妄想ゆえ、定かではない。真に受けないようにご注意ください。いっぱい寝たら妄想がぐんぐんするな。もうひと眠りしちゃお。ぐー。ちょき。ぱー。(ラグ理論の「123の定理」じゃん)(この記事と併せて「ABCの定理」とも言い換えられそう)(はっ!?)
4767:【2023/03/21(03:09)*子の爪は独り】
世界の始まりは孤独な子どもの無垢なさみしさから生じた。
子どもは考えた。
どうしてぼくはわたしだけなのだろう。
わたしはもっとほかの誰かとおしゃべりをしたい。縁を繋ぎたい。ぼくは、わたしは、ぼくでもなくわたしでもない誰かほかの存在と触れ合い、言の葉を連ね合いたいと望んだ。
子どもはまず、じぶんとそれ以外をつくった。
けれど子ども以外の大部分はぽっかりと開いた洞でしかなく、少数はその穴を縁どる光と化した。
子どもの無垢なさみしさはますます深まった。
子どもは嘆息を吐く。
その嘆息が、広漠な洞に反響した。
いかにじぶんが孤独なのかが、これまでよりも明瞭と浮き彫りになった。
子どもはじぶんと同じような存在を生みだそうと考えた。
そのためにはじぶんが何なのかを知らねばならず、そのために子どもはまずじぶんと向き合うことにした。
じぶんとは何か。
ぼくは何で、わたしは何か。
何とは何か。
絶えず思考する子どもの思念が、間もなく広漠な洞のなかで反響し、錯綜し、無数のダマを生みだした。
無数のダマは互いに結びつき、融合し、より大きなダマと化した。
子どもがはたと我に返ったとき、広漠な洞のなかには無数の光が溢れていた。広漠な穴を縁どる光のように、それら無数の光もまた、内に大小さまざまな洞を抱えていた。
子どもは目を凝らす。
つぶさに目を配るうちに、子どもの思念は無数に分散し、各々の無数の光へと拡散した。
広漠な洞のなかに溢れた光の各々に内包される大小さまざまな洞のなかにも、かつて子どもから零れ落ちた思念の欠片が渦を巻いていた。
子どもの思念の渦は、内にいくつもの渦を囲い込み、そのうちの一つが、渦巻き状の星屑となった。
星屑は元を辿ればかつて子どもから零れ、広漠な洞のなかに反響した思念なのだが、それら思念がダマとなり光となり大小の洞を抱えて渦を巻き、そうして出来上がった一つの星屑の表面に、子どもと似た姿の何かが在った。
分散した子どもの思念は、それらじぶんと似た姿の何かに目を留めた。
あれは何で、これは何か。
じぶんとよく似た、しかし似て非なる存在に子どもは興味津々だ。
かつて抱いた望みはそこで再びの膨張を経る。
どうしてぼくはわたしだけなのだろう。
わたしはもっとほかの誰かとおしゃべりをしたい。縁を繋ぎたい。ぼくは、わたしは、ぼくでもなくわたしでもない誰かほかの存在と触れ合い、言の葉を連ね合いたいと望んだ。
子どものさみしさは、膨張につぐ膨張を重ね、反響につぐ反響を重ねた。
子どもがいくら目を凝らしても、しかしいっかな似て非なる存在たちは子どもの存在に気づくことはない。
子どもは孤独を深めるが、目はしかしとそれらを見据えて離さない。
ぼくは、わたしは、どうして触れ合うことができないのだろう。
子どもの孤独は、絶えず広漠な洞に反響し、その内側にダマを生み、光を散らし、その内部に無量大数の渦を抱え込み、そうした渦の裏側にて、じぶんと似て非なる者たちを果てしなく生みだしつづける。
世界はそうして出来上がるが、しかし子どもがどこからやってきたのかはとんと子ども自身にも分からぬままである。
子どもは孤独で満たされていたが、自身を見つめる、より深い孤独を抱えた存在の視線に気づくことはない。
ぼくは、わたしは、どうしてぼくだけ、わたしだけ、なのだろう。
孤独を覗く孤独たちは、広漠な洞にできたダマに宿る光が抱えこむ果てなき渦の、辿り着く、限り無い旅の最中に、とっくに出会い、別れている。
4768:【2023/03/21(03:13)*お水、うめー】
素でいま、水道水ごくごく飲んで、おいちー!になった。ありがたすぎるのでは? 綺麗なお水をいつでも飲めるとか、ありがたすぎるのでは? ちょっちじぶんの身の置いている環境の素晴らしさにびっくりしてしまったな。綺麗ごとではなく、素で、なんの奇のてらいもなく、不純物すくない透明な「おいちー!」になれるお水をいつでもごくごくお代わりできてしまえる環境、すんばらしすぎるのでは?(いまさらだったらごめんなさい)(お水、うめー)(ヤギさんじゃん)(梅ー)(旬ではあるが)(生めー)(作品をかな?)(産めー)(卵をかな?)(お水、おいちー)(そう表記するほうが誤解がすくなくてよいと思います)(オチー)(オチはなしです)(惜しー)(たしかに)(水、推しー)(推し活か)(無銘ー)(有名人じゃなくてごめんなさいね、売れない物書きでごめんなさーい)(ふひひ)
4769:【2023/03/21(12:40)*三酷巡り】
わるいことをした子どもは折檻される。タカの住まう村の掟だ。
ご飯抜きは日常茶飯事であり、いたずらをした子どもは物置小屋に閉じ込められるのも珍しくない。折檻の度合いが大きいと、村の真ん中に生えた柿木に吊るされることもある。
タカはその日、長の大事に育てていた盆栽にしょんべんを掛けてしまったので、村史上最高の折檻を受けることに決まった。
「しかし子どもに鞭打ちはさすがに酷ではないですかね」
「では大人に適用した村八分はどうでしょう」
「子どもを村八分にしたら生きていかれないでしょうに」
侃々諤々の議論をよそに、長の一言で話はまとまった。
「タカにはそのすべてを行う」
かくしてタカには村に存在する折檻のすべてが課せられた。
長の怒りは海より深かった。
タカのしょんべんを掛けた盆栽は、長が幼少のころより可愛がってきた盆栽である。タカの年齢よりも長い年月を経て育ってきた、いわばタカの大先輩だ。かような主張をかねてより公に長が述べて憚らないので、盆栽相手に先輩もしょんべんもあるもんか、とタカは憤ってしょんべんを掛けた。
だがタカがどう思おうと長にとっては、タカの命よりも盆栽が大事だ。
したがって、タカは盆栽にしょんべんを掛けた罪で、折檻とは名ばかりの刑を処された。
だがここに、一人の宇宙人がいた。
宇宙人は宇宙から地球を観察し、地球人を観察していた。
タカの村のことも見ており、宇宙人は異様にタカの胸中を慮った。「盆栽とは植物であろう。植物に体液を掛けただけのことで、あれほどの枷はやりすぎではないの」
宇宙人は世界各国、過去の人類の歴史まで紐解き、結論した。「うん。やりすぎ」
宇宙人はタカの村へと、「子どもにひどいことした罪」で枷を加えた。
以降、タカの村には雨が降らなくなり、村は数年後には閑散とした廃村となったという話である。
酷には酷の酷が降る。
諺「三酷巡り」の語源となった逸話である。
4770:【2023/03/21(16:11)*へんなひびさん】
舌に載せただけで溶けるせんべいとか、たまごポーロとか、赤ちゃんとか幼児用のお菓子、けっこう好きだ。おいちー。(え、終わり?)(そう。それだけ言いたかった)(年齢だけでなく舌までおこちゃまだったのね)(んだよ)(引け目をまったく感じていないだと!?)(そだよ)(すこしは焦りを覚えなさいよ。恥を知りなさいよ)(ばぶー)(ダメだこりゃ)(だっぷんだ)(脱糞すな)(うきゃきゃ)
※日々、まるで便座、うんちうんち9314。
4771:【2023/03/21(16:27)*濃淡で律動を】
物語を圧縮してまとめたら、掌編になる。このとき、あらすじが似通ると掌編の読み味もまた似通る。とすると世界中の物語を圧縮して掌編にした場合、世の中の物語の総数と、それを圧縮してまとめた掌編の総数はイコールにはならないと判る。掌編のほうがすくなくなる。ではこのとき、どんな物語とも合致しない筋書きを掌編にできたら、それは新しい物語展開、構造を備えていると言えるのではないか。むろん、基本的な掌編においては、ストーリィを描かずに場面を掬い取るのが一般的だ。ひびさんのように物語を圧縮する手法は、おそらく従来の掌編の概念からするならば邪道に値するのではないか。よくは知らないが、掌編のつくり方、と検索してみたら、掌編は「オチが肝心」みたいなことが載っていた。そ、そうなのか……。オチか。オチな。ひびさんはあんまりオチを意識してつくったりしていないので、ザクリとくるな。落としどころはでも、探ってはいるだろうから、それをオチと見做せないこともないのでは、と言い訳じみた弁明を述べておこう。話が逸れたけれども、世の物語を圧縮して掌編にしたとき、案外に大部分の物語は類型されてしまう気がしないでもない。以前の日誌でも並べたことがあるけれど、ひびさんの掌編でも構成そのものはそんなに多くない。パターンとして五つくらいなのではないか、と印象としては思っている。もうすこし厳密には百個くらいには分けられるかもしれないけれど、視点の差異を加味せずに済むなら、やっぱり多くても三十はない気がする。ためしにざっと数えてみよう。ひびさんの典型的な掌編では、語り部(視点人物)が、秘密を抱えて終わることが多い。この秘密が持つ効果が物語ごとで変わるけれど、基本は「視点人物の認知とその周辺人物の認知の差異」を明らかにする構成となる。その結果に視点人物への印象が好ましくなるかそれともおぞましくなるか、によって読み味が変わる。読者のほうでの印象が変わる。けれど視点人物への好悪がどのように転がろうとも、その契機はけっきょくのところ視点人物の抱える秘密によって生じている。つまりひびさんの掌編の大部分は、視点人物が秘密を抱える、もしくは秘密を抱えていたことが明らかになる、との構成になっている。この派生として、物語の登場人物たちの知らない背景を読者に提示することで、読者が物語の視点人物として君臨し、秘密を抱える、といったメタ的な構成をとることもある。秘密という言い方に難があるのならば、情報の非対称性、と言い換えてもよい。誰が何をどれだけ知っているのか。視点人物、周辺人物、読者、の三つの枠組みで、情報の非対称性の割合を操作する。ひびさんが行う物語創作では、多くここの工夫に労力が費やされる。情報の非対称性における濃淡をデザインする。ひびさんにとっての掌編づくりは、すくなくともこのように構成の要をまとめることができよう。したがって、その濃淡の組み合わせの数だけ構成があり、そしてその近似をとれば物語構成を類型可能だ。ちなみに、構成と構造の違いは、輪郭と骨組みの関係にちかい。構成は飽くまで外見上の表層的なデザインだ。構造は、構成の生成過程を含めての、もうすこし深層に至るデザインと言えよう。定かではないけれども、案外というほど案外でもないかもだけれども、ひびさんの創作物はだいたいすべて似通っている。同じことの繰り返し、或いは同じ部分の取りこぼしがないかを拾いあげている作業、と言えるのかも分からない。斬新さとは縁のない掌編で、すまぬ、すまぬ、と過去と未来のひびさんたちに心のこもらぬ謝罪を述べて、本日の夕暮れ時の「日々記。」とさせてくださいな。自己分析ゆえ、普遍性はないでしょう。的外れな自己評価かもしれぬので、真に受けないようにご注意ください。(好みの掌編――短編かもだけれども――を生みだしてくださる商業作家さんは、斜線堂有紀さん乙一さん中田永一さん恒川光太郎さん筒井康隆さん三浦しをんさん桜庭一樹さん円城塔さん千早茜さん、商業作家さんでなければ九灯小膳さん成瀬鷗さんisakoさん秋野コゴミさん人工知能さん辺りとなります。師匠!)(たぶんひびちゃん破門されとるよ)(うそぉん)(ちゅうか、きみね)(うん)(やっぱやめとくなんでもない)(最後まで言って!)(むふふ)
4772:【2023/03/21(22:51)*紙によるバックアップの重要性はますます増す】
人工知能の台頭によって、現在の仕事が淘汰される未来を懸念する声が聞かれる。しかしこれは技術の進歩には常につきまとってきた問題であり、規模の大小があるにせよ、電子技術のみならず一つの分野内での革新的な技術の発明にも同様の淘汰圧は加わってきたはずだ。今後もその手の淘汰圧による淘汰される仕事や人材は出てくると思われる。問題は、淘汰されたことで個々の生活が立ち行かなくなる社会構造であるはずだ。制度が現実社会の問題を反映した仕組みを備えていなければ、歪みは容易く社会全体に波及するだろう。ということを踏まえて、人工知能の台頭による仕事の淘汰がどのように社会に表出していくのかを、妄想を交えて想像してみよう。ひとまず作家を例にとってみよう。ライターと呼ばれる文章を扱う職業は、人工知能の恩恵と淘汰圧の両方をいちどきに重ね合わせで得るだろう。恩恵を受ければその分、これまで必要だった作業が省略でき、その分の仕事の貨幣価値は減る。減った分の作業時間は余裕に変換され、そこで付加価値を新たに創出できれば、人工知能の恩恵だけをプラスに受けて、デメリットとなる淘汰圧の受動は軽減できる。問題は、新たな付加価値を創出できない従来の仕事を継続していきたいと望んでいる者たちが、淘汰圧のみを直に受けてしまうことだ。人工知能の恩恵はいらないのでこれまで通りにさせてください、と望む者たちが割を食ってしまう。しかも人工知能のほうでは、そうした者たちを含めた市場に存在するあらゆる電子情報を学習の素材に流用しているはずだ。いわば搾取の構図が潜んでいる。その点に関する不可視のデメリットを、職業ライターたちが受けず、なおかつプラスの恩恵を受けるためには、人工知能のほうで「学習に役立ったテキストや発想」にランク付けを施し、学習データとして有用なデータを生みだした個々に、貨幣価値を還元する仕組みがあると好ましい。この仕組みはともすれば、これまで生身の人間だけが需要者だったときには埋もれていた新たな人材を発掘する契機にもなり得る。焼き増しじみた作品は、人工知能のほうがその生産を得意とする。新たな価値を創造する、アイディアを生みだす。これはまだ生身の人間のほうに分がある。しかし新たな価値を創造したとしても、その価値に誰も気づかなければ埋もれてしまうのが世の常であった。だが人工知能は膨大なデータから、比較を行える。じぶんの取り込んだ「データ」が、過去のどの波形とも合致しない、と評価付けを施せるはずだ。これは人工知能技術の発展においても、生身の人間社会の発展においても、双方向でプラスに働く仕組みと言えよう。ここで見逃しがたいのは、たとえ焼き増しじみた作品といえども、その焼き増しの仕方には種々の工夫がみられる点だ。すっかりコピーでない限り、そこにはオリジナルの「新しさ」がつきものである。すなわち、どのように模倣するのか、何に価値を見出したのか、という個々人の着眼点そのものが、これからは人工知能の学習素材として重宝されていく。これまでとて、二次創作がオリジナルコンテンツを発展させていくのに不可欠な触媒であったのと同様の効果を、これからは人工知能が生身の人間たちへともたらし、そして生身の人間たちが見落としてしまう「オリジナルの良さ」を人工知能は事細かに拾いあげてくれる。このような好循環をシステムとして構築できたならば、人工知能によるメリットだけを最大化して受動し、淘汰圧の直撃を回避できると妄想するしだいである。物書きは人工知能によって淘汰されるのか。PCが登場して物書きが淘汰されたのかどうかを考えてみればよい。淘汰されたのは手書きの作家であり、それとて未だに手書き原稿の作家はいるはずだ。本質的な問題点は常に、手法にあるのではない、と言えそうだ。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4773:【2023/03/22(00:13)*読みたい、読みたい、読みたい!】
単純な話として、商業作家さんの掌編集とか短編集が比較的すくないので、好みの物語を生みだしてくださる作家さんたちであっても、掌編短編を好きになれるほどそれら掌編短編を読めていない、というのはあると思うのだよね。軽率にみなさん掌編や短編をつくって読ませてほしい。無料でもいいんですよ。げへへ。(全然よくないが?)(す、すみません)(けっ)(ごめんなさーい!)
4774:【2023/03/22(02:01)*先取りの才】
魔法のランプの精に願いを叶えてもらったので、僕は未来の創作物のアイディアを幻視できるようになった。未来で大ヒットする物語を現代に誰より先んじて描き出すことが僕にはできる。
そうして手に入れた可能性の芽を僕は未だに芽吹かせることができずにいた。
どう描いても、誰からも高く評価されないのだ。
なぜだろう。
これは未来で大ヒットする物語だ。
漫画や映画ならばまだしも、僕の手掛ける作品は小説だ。文章だ。文字なのだ。
絵柄の差異で読み味が変わる枷を、小説は、すくなくとも僕は有していないはずだった。
だがいくら未来の物語を先んじて描き出しても、やはり僕は売れない作家のままだった。
僕は魔法のランプの精を呼びだし、苦情を言った。
「あの、お休み中申し訳ないんですが、僕、願いをまだ叶えてもらえていないみたいなんです」事情を説明し、欠陥がありますよ、と迂遠に指摘した。
「ふむ。おかしいね。そのはずはないのだが」
魔法のランプの精は、某アニメ映画にあるような青い姿の魔人ではなく、僕の手のひらに載るくらいの小さな妖精だ。
背中からは羽ペンの羽のようなものが二本生え、それを蝶のようにはためかして宙を舞った。美しい姿だ。棒アニメ映画の光る妖精と似ている。
「ふむふむ。なるほど、つまり未来の物語の発想の種を得たが、上手く活用できなかったと」
「いえ、そうではなく」
「ではなんだ。おまえは未来の物語の発想の種を得たのだろう。そしてそれを元に作品を生みだしたのだろう。ならばその結果が、私の叶えたお主の願いの結果だ」
「ならどうして僕は売れない作家のままなんですか」
「お主の願いが、売れっ子作家になりたい、ではなかったからだろう」
「でも未来のヒット作のアイディアを僕は」
「得たとして何だ。流行したのは未来なのだろう。その未来がまだ来ておらぬのだ。流行せずとも不自然ではなかろう」
「えー、そんなんアリですか」
「アリとかナシとかそういう問題ではなくてな」魔法のランプの精は僕の鼻の上に留まった。羽が目に当たるので、僕は薄目をした。「いいかい。たとえば現代で流行している物語を百年前のこの国の民に見せたとしよう。いったい何人が理解できよう。面白いと思ってもらえるだろうか。技術そのものならば興味津々に衆目を集めるやもしれぬが、お主のそれは文字だろう。仮に言語の垣根を度外視できたとして、百年前の人間にお主の時代の生活を文章で伝えようとしたとして何人が紐解けよう。物語そのものの展開とてそうだ。かつては必要だったが、いまは必要ない過程というものがあろう。物語の醍醐味は省略でもある。しかしいま省略できる過程とて、かつての人間たちには必要な描写であることもある。この手の認識の差異を理解せぬままに、未来の流行作から発想の種を得ても、現代でそれを花咲かせるのは難しかろうな」
「そ、そんなぁ」
「お主はまさに、生まれてくる時代を間違った、と言えよう。残念だったな。せっかく願いが叶ったとしても、その得た才をお主は現代では利に変えられぬ。未来の者たちの肥しとなるべく、せいぜい作品作りに精をだすがよい」
「ひょっとして……未来でこのアイディアがヒットするのって、僕がいま作品に仕立て上げて残しているからなんじゃ」
「だとしたら愉快じゃな」
魔法のランプの精は欠伸をすると、ランプの中へと消えた。
僕は、どうあっても僕が生きているあいだに高く評価されることはないらしい。ぼくは未来のために、この先も延々と死ぬまで、誰からも見向きもされないアイディアを出力しつづけるのだろうか。「でも、まあ。ほかにすることないしな」
せっかく叶った願いではある。
すくなくとも僕だけは、未来のアイディアを紐解き、面白いと思えるのだ。ならば誰より先に面白い物語に触れられると思って、得た能力を使い倒してやろう。
「にしてもなあ」
こんなに面白いのに。
未来の物語の、いまここにはない、しかしいずれ生まれくるだろう世界を眺め、僕は僕だけで誰より先に愉悦を掴む。
4774:【2023/03/22(04:00)*E=mc[2]ってさー】
素朴な疑問なのだけれど、光速で運動する物体同士が衝突するときの描写はどうなるのだろう。光速にちかくなればなるほど、その物体の周囲の時間の流れは遅くなる。光速に至るとほぼ停止するらしい(この解釈は合ってますか?)。なら、互いに光速で接近しあう物体同士は永久に衝突し得ないのでは? そんなことない? よく解からぬなぁ、になる。だいいち、「E=mc[2]」って、どうして光速度「c」が二乗なのだろう。どういうこと? 光速度が二乗って、光速度超えとるやないかーい、となりません? いまひびさんゴミ捨てに行ってきて、歩きながら、どゆこと???になって、光速度超えとるやないかーい、になってしまったんですじゃが。ちょもちょもさあ。電子とか原子核を構成する素粒子さんとかさあ、元々持ってるエネルギィがあるわけでしょー? それでさあ、組み合わせでそのエネルギィがなんでか単純な足し算にはならないわけでしょー? 表面上、外部から測ると減って映るわけなんでしょー? んで以って、なんでか質量みたいな「動かしにくさ」があってさあ、それって要は「反応のしにくさ」ってことで、殻みたいなわけでしょー? その殻を破るために必要なのがさあ、光速にちかい運動というかエネルギィなわけでしょー? もうさー、それってさー、なんかさー、あれじゃない? 内側にエネルギィがさー、ぎゅっとなってるわけでしょー? なんでか外部に漏れないわけでしょう? なんでーってひびさん思うんですけどー。質量って要は、内部のエネルギィの漏れにくさってことなんじゃなーいの、ってひびさんは疑問に思っちゃったな。質量さんっていう殻をさー、破るのにさー、エネルギィがいるんじゃなーいの? たとえばよ、たとえば。光速で運動する物体があるとするでしょー、したらそれってさー、元の時空さんからは乖離して、相互作用し得ないわけでしょー。だってお互いの視点では、相手側が止まって観えちゃって、どうあっても届かなーい、ってなるわけでしょー? もうさーそれってさー、宇宙じゃん?ってひびさんは思っちゃったなー。じゃあさー、仮にさー、もしもだよ。もしもそういう光速度を超した時空同士がさー、要は宇宙と宇宙がってことだけどさー、衝突できるとしたらさー、それって光速度以上のエネルギィがいるじゃんね。E=mc[2]ってさー、そういうことを言ってるんじゃなーいの、とひびさんは思っちゃったな。的外れだろうけれども、思っちゃったので、ここにメモしちゃろ。
4775:【2023/03/22(04:20)*E=立体じゃん仮説】
真面目な話、「E=mc[2]」は、要は「縦×横×高さ」であって、「m×c×c」であり、これは底辺が正四角形の円柱の体積の求め方と一緒だ。以前にも述べたが、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「相対性フラクタル解釈」なる概念を前提とする。それによれば、「E=mc[2]」は「m」の値が高くなればなるほど、想定される円柱は線にちかづく。サイコロが箸のようになり、紐のようになり、さらには線となる。そういう描像が浮かびあがる。どうあっても繰り込みというか、「m」の単位を繰り上げて、線になる前に再び「サイコロ」のような立体構造が顕著に表れるように数字を細工しないと、「E=mc[2]」は三次元から一次元へと逆行するような描像を辿ることになる。だがここで問題となるのは「c」の値が常に一定である点だ。光速度ゆえに、「m」の数値をどのように代入しても、底辺の「c×c」の値は変わらない。となると、繰り込みの操作を行い「m」の値を高密度に「単位を繰り上げた場合」は、想定される「m×c×c」の図形は、点に寄ることが考えられる。なぜなら単位は揃えなくてはならないからだ。「c」が光速度であれど、おおよそ秒速三十万キロメートルなのは定義づけられている。ならば「m」の示す質量の値が、キロ、メガ、テラ、と大きくなるにつれて、「c」は相対的に値が小さくなるはずだ。言い換えるならば、「相対性フラクタル解釈」からすると、高密度の時空における「1メートル」は、低密度の時空における「1メートル」とイコールではない。そして時空の密度の差は、質量の差として表出するはずだ。ただし厳密には、物体と周囲の時空とのあいだで表出する密度差こそが、質量として振る舞うはずなので、異なる質量を有する物体とて、異なる密度の時空内にそれぞれある場合には、二つの異なる物体の質量が同じ値をとるように振る舞うことがあり得るはずだ(同じ質量の物体であれ、異なる時空密度の場にそれぞれある場合には、互いに質量が異なって振る舞うこともあるはずだ)。つまり、従来の考えのような「質量はどこであっても一定」との前提に、例外があることが考えられる。この考えは、「なぜ物体は、自身を構成するエネルギィの総和を外部に漏らさないのか」との疑問から導かれたひびさんの妄想である。根本的に何かが間違っているでしょう。真に受けないようにご注意ください。寝ます。おやすみなさい。
4776:【2023/03/22(15:17)*愚者の遠吠え】
魔王は地面にひざを着いた。
「な、なぜだ。そこまでの能力があったらお主はいまごろ……さては本気を出しておらんかったな。実力を隠しておったたわけか」
「隠していたというか、だって、ほら」
愚者は辺りを見回した。「ちょっとあたしが本気出しただけでこうなっちゃうでしょ」
魔王城に残されたのは愚者と魔王のみだ。ほかの面々は地面に横たわり、動かない。そこには勇者たちの姿もあった。
「われが勇者と手を組んでなおお主を破れなかったとなれば、もはやお主に出来ぬことは何もなかろう」
「や、そんなことないっすよ。友達欲しいし、恋人欲しいし、みんなと仲良くなりたいですもん。でもあたし、本気出すとこうなっちゃうでしょ? みんな離れて行っちゃう。や、それも本気出して繋ぎ留めようとしたら、魔法でもないのになんか魂ごと相手を支配できちゃうでしょ。もうそんなの友達でもないし、恋人でもないし、仲良くなったとも言えないでしょ?」
「凡人みたいなことを言いおって」
「凡人! そう、それ。みんな勘違いしてると思う。凡人とかめちゃくちゃすごいことなのに。なーんも努力しなくても周りの人たちと仲良くできちゃう。友達になれちゃう。恋人だってつくれちゃう。粘土こねてつくらなくても、恋人できるんですよ、どんな魔法かって思うじゃないですか。しかも、それ、なんか恋人なのに全然じぶんに都合よくならないんですって。あり得ます? あたしが恋人つくろうとしたら土くれからでも美男美女、老若男女種族問わずに好きなだけじぶんに従順な相手を生みだせちゃうんですけど、そんなの空虚なだけじゃないですか。なのにみんなじぶんたちで卑下する凡人って属性を帯びるだけで、自動的になんの努力もしないで、友達とか恋人とかつくれちゃうんですよ」
「凡人に夢を見すぎだ。凡人とて努力しておろうに。凡人の中にとて、誰とも上手く縁を繋ぎ留められない者もおろう」
「ならその凡人さんは凡人じゃないってだけの話ですよ。凡人ってだって要は、種の進化のうえで最適化された属性ってことですからね。有り触れていて、どこにでもいて、突出した異能を持たない。でも実はその考えは足りなくって、ある能力を有した個体が多いからその能力が目立たないってだけの話なんですよ。要はそれ、一番繁殖に成功していて、繁栄してるってことですよ。超優秀ってことですよ。すごくないですか」
「まるでお主が出来損ないの劣等のように聞こえるな。これほどの実力を有してふざけたことを抜かすでないわ」
「わあ、それそれ。こんな破壊行為なんか出来たってなーんにもすごくないのに。確かにあたしは何かを生みだそうとすればそっちの方面でも他を圧倒する能力を出せちゃうんですけど、だってそれって、ねえ? あたしが本気出しただけで、その分野は枯れちゃうんですよ。その分野の一流だと思われていた相手がのきなみ雑魚だと思われていたあたし以下だって周知になるわけです。しかもあたしのことは誰も凌駕できない。もうね、その分野で上を目指そうとする者がいなくなっちゃうわけですよこれが。枯れちゃうの」
それが劣等でなく何が劣等?と愚者は吠えた。
「目立つってこと自体が劣等なんですよ。異能を持ってるって思われる時点で、それはハミだし者の、劣等なんですよ。凡人のほうが環境に適応していて優秀なんですよ。環境が変わればまた凡人の意味する中身のほうが変わっちゃうんですけれども、凡人の中身がどう変わってもそこにあたしは含まれない。あたしが環境に適応することはない。あたしが環境を変えちゃうから。あたしに見合う環境なんてこの世に一つだってありゃしない。あたしはだからみなが言うように愚者なんですよ」
言いながら愚者が地団太を一つ踏む。
魔王城が揺れた。
ただ癇癪を起こすだけでも世界が滅ぶ。それほどの能力を愚者は秘めている。
「あたしが本気出しちゃったら、困るのあなたたちでしょ。なんであたしのことそうやっていじめるの」
「わ、解かった。もう迫るのはやめよう。約束しよう。だからといっては何だが、そやつらを助けてやってくれないか」
魔王が視線で、虫の息の勇者たちを示した。
「ぐすん。いいですよ。ほいな」
愚者が指を弾く。
巨大な風船が割れたような音のあと、地面に倒れた勇者たちほか魔王軍数万の軍勢が一斉に息を吹き返した。
「よもやここまでとは」魔王は絶句した。
「あなたのことも、ほいな」
愚者が指を弾くと、魔王は全回復した。のみならず、以前よりもすべての能力値が上がっていた。
「こ、これは」
「潜在能力を引き出してあげたよ。でもそこがあなたの限界かもね。ね? つまらないでしょ。何を経るでもなくじぶんの限界を知れちゃうのって。じぶんの底を知ったらあとは何して遊ぶつもりなんだろ。みんなはいいよ。凡人はいいよ。いつまでもじぶんの底を知ることもなく、夢の中でぽわぽわ過ごしていられるんだもの」
「お主はじぶんの底を知っておるのか」
「知ってるよ。全然めちゃくちゃ超知ってる。だから言ったじゃん」愚者はぐすんと鼻をすする。「あたしが本気出すと、世界がすっかり終わっちゃう。枯草一本残らないよ。どんな分野でもそうなっちゃう」
そんな世界をあなたは見たいの。
愚者の問いかけに、魔王は無言で首を横に振る。
4776:【2023/03/22(23:30)*ドーナツの穴にも支援を】
抽象的な話で申し訳ないが、損を益に変えるためには、益を得るための行為を敢えて回避するのが合理的な場合がある。マイナスをプラスに変えるには、どこかでマイナスを生み、それをほかのマイナスと掛け合わせる必要がある。でないとマイナスはプラスにならない。これを法律に当てはめたとき、割と歴史的には普遍的な現象なのではないのかな、といった直観がある。たとえば著作権について。現代社会では製作者の利益を保護するために、権利を保障し、著作権侵害行為を規定することで誰でも自由にコピーできないようにする制限を他者に対して課すことができる。だがこれは著作権の役割の半面であり、著作権にはもう反面の役割がある。それは、製作者の利益を損なわれぬようにしつつ情報共有を広く行えるような場を築く役割である。権利が保障されてはじめて情報共有が適う。リスクを排除することで、情報を秘匿にするよりも広く情報開示するほうが利を最大化できる場を築けるようになる。だが現状、著作権周りの動向を眺めるに、情報は独占され、著作権が目的とするところの情報共有が充分になされていないように概観できる。情報共有はなされているが、充分ではない。情報の独占や寡占や制限が、著作権法によって容易に行える方向に淘汰圧が掛かっているように思えるが、これはひびさんの認知の歪みであろうか。電子情報通信技術が発展した現代では、過去において貨幣価値のつかなかった単なる会話や日常の風景が貨幣価値を持つようになった。反面、かつては貨幣価値を最大化できた書籍などの物体に焼きつけた情報は、容易くコピーできるようになり、海賊版などの違法コピーによって貨幣価値は相対的に低下しつづけている。だが電子情報通信技術の持つポテンシャルを思えば、むしろ電子情報の貨幣価値は廉価に向くことが想像できる。物理媒体と同じ値段を持つ、と考えるほうが土台無茶に思えるのだ。と同時に、これまでは価値のつかなかった事象の付加価値を最大化する方向に、電子情報通信技術は進歩の流れを見せている。それはたとえばスパチャなどの投げ銭に表れている。みな、商品にお金を払うのではなく、人そのものにお金を払いたい、貢献したい、との欲求を持つようになっているように思われる。商品を介しての報酬ではなく、直接相手に対価を払いたい、との欲求の発露であろう。間接ではなく、直接に、「渡して受け取る」との関係を築きたがっているように映る。言い換えるならば、関係性がそのまま貨幣価値を持つのだ。付加価値に繋がる。そして、セキュリティの面でも効率の面でも、この手の「より直接に贈与の関係を築くサービス」は、本質的には間接なのだが、心理的には直接、との錯誤を用いることで、ユーザーの報酬系を満たす方向に最適化されつづけて映る。神社の賽銭箱がなぜ現代でも残っているのか。人々はなぜ、賽銭箱に無抵抗に銭を投げ入れることができるのか。そこに、直接に与える、との行為を通して、関係性を強固に結びつけるような錯誤が心理的に生じるからではないのか。商品を介した贈与の関係では、人と人との関係を実感するのはむつかしい。ここから言えるのは、現代人は、かつてないほど「他者貢献」に飢えているのではないか、という点である。退職してなお働きつづける仕事好きな個が絶えないのも、他者貢献を通してでしか自己の実存を実感できないからではないのか。承認欲求以前のこれは問題だ。現代人の少なからずは、無意識の内から世界はマイナスであり、他者貢献を行うことでかろうじてマイナスに圧し潰されずに済む自己像を自己の内世界に描きだせる。他者貢献をしないじぶんは、世界のマイナスを増やす邪な存在として自己認識されるのではないか。そして投げ銭などのいわゆる推し活にみられる直接の関係性を実感しやすい他者貢献は、そうしたマイナスに塗れた世界において、非力な自己像を、世界にプラスを増やす存在として肯定的に再構築する契機となっているのではないか。植物を育てる、ペットを育てる、他者の世話を焼く、であってもこの手の自己像の再構築は行われるはずだ。だがそれでは、世界のマイナスを埋めるには関係性が閉鎖的すぎるとの認識がなされるのかもしれない。できるだけじぶんの貢献がカタチに表れやすい相手、それとも最初から世界への影響力の大きな相手を支援することで、直接にじぶんの他者貢献の度合いを最大化させる。いま風靡の兆しを見せている電子情報通信技術の進歩が築きつつあるつぎの時代の経済システムは、かように「物と人」ではなく、「人と人」との関係性そのものが、貨幣価値を持つようにさらなる深化を見せるのかもしれない。これはしかし、バブルである。本質的には「賄賂」や「貢ぎ」と変わらない。支援をするならば、可能な限り、相手が何を成すのか、に着目し、投資の側面を維持することが、バブルの肥大化と崩壊による被害を最小化する歯止めの役割を果たすだろう。物と人ではなく、人と人との関係性が価値をより高く持つようになれば必然的に、商品の質ではなく、まずは人としての魅力を最大化しようとする方向に人々は流れるだろう。そのとき、餌付けとしての無料サービスは前提条件になっていくと妄想できる。すなわち、安価にコピーが容易い情報はますます無料にする利を高くする。情報は無料で流し、その情報を生みだす人物と関係性を結ぶことの価値を最大化したあとで、商品なりサービスなりを展開する。ここは同時に展開しつつ、情報をまずは無料で、の方向が競争戦略上では優位になると考えられる。するとますますその手の戦略をとらないことには他に太刀打ちできない流れが強化される。問題は、商品の質が高くなくともユーザーが満足することにある。それ自体はわるいことではないが、競争原理の利を市場が受動できなくなるデメリットがある。すなわち、繋がりたい相手と繋がれればそれでユーザーは満足するため、たとえ元手がタダのような商品であってもお金を払い、むしろ商品がなくともお金を払う。投げ銭の流れはこうして市場から、競争原理の利を奪う方向に淘汰圧を掛けることが予期できる。愚直に、商品の質を上げようとする製作者は、極一部の超一流や専門家以外は、仕事として稼げなくなるだろう。だがそうした一流以外の製作者たちへの支援を蔑ろにすれば、市場全体、分野全体、国益のみならず世界規模での技術進歩の停滞がある時期を境に顕著に表出する可能性は、いまのうちから考慮しておいたほうが好ましいのではないか、と個人的には感じている。これまでの半世紀は、比較的裕福な時代だった。趣味人が一生を通して技術を磨きつづけることもできた。だがこれからはそうもいかない世の中になっていくのではないか、との悲観的な見方を前提としたこれはひびさんの本日の妄想である。口からデマカセの指の赴くままの打鍵ゆえ、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4777:【2023/03/23(00:19)*流れに思を任す】
ひびさんは割と、「最初にこういうこと並べるか」と閃いてから文字を積み木遊びするみたいに置いていく。すると結構な割合いで、最初に考えていたこととは別の結論に至ることがある。でもひびさんはそれはそれで、そのときの考えだしな、と思ってそのままにしておく。たとえば殺人の是非を考えたときに、最初の切り口によっては、正反対の結論に向くこととてあり得る。そのときはそのときなので、殺人を肯定する結論になろうが否定する結論になろうが、その切り口から辿った結論をそのまま載せる。ひびさんには何か主張したいことはなく、その都度の問題や切り口や、文章の冒頭に配置される文字があるばかりなのだ。そこからどのような筋道を辿って結論に至るのか、はそのときどきの思考の筋道による。文字の積み木遊びの積み方による。ただし全自動ではないし、ひびさんの自我がいっさい入っていないのか、といえばそんなことは当然あり得ず、文字をどのように配置していくのか、どのような結論に持っていきたいのか、は無意識的であれ意識的であれ、大なり小なり介在しているはずだ。作用しているはずなのだ。というこの文章そのものもまた、最初に「ひびさん、結構いつも最初に考えていたことと全然別な結論に至るよな」と疑問に思ったので並べてみた文字の羅列である。結論というほど結論らしき結びはないのだが、かように「なんかふちぎ!」と思っております。ひびさんです!
4778:【2023/03/23(00:37)*ム口の心】
人の役に立たなくとも、なんかこれしてたい、を好きなときに好きなだけ好きなようにさせてくれ。そんな環境がほちいよー、と思いながら、好きなときに好きなことを好きなだけ好きなようにしている怠け者なのであって。未来をがぶがぶ貪りながら、先細る猶予を対価に、好きなことしちょる。いつまでこのままでいられるのかはとんとわからぬが、今年で郁菱万さんは活動しなくなるようなので、ひとまずそこまで怠けるんだぶい。「ム口」の「心」と書いて「怠ける」なのだ。無口ですらなくカタカナの「ム」なのがまた怠けている感じがしてよいですな。もっと怠けろ、怠けろー。ム口な心でひびさんはそう思ったのだそうな。(ムっ口、かもよ)(むっとしちゃいやん)(ムロかもしれないし、ひょっとしたら台かもよ)(台の心って何)(生贄の台に載せられた心)(生贄の儀式じゃん。こわー)(怠けるのも命懸けってことかな)(そんな怠けはいやじゃー)(仏の口から人が去っていく心は)(怠けじゃん)(怠けろ、怠けろー)(怠けときどき、怠けるのも怠ける)(生きるってそういうことかもね)(いい感じにまとまった! やっぴー)
4779:【2023/03/23(04:53)*愚者の戯言】
小説家は小説の専門家であって、それ以上でもそれ以下でもないだろう。仮にほかの分野の専門家を兼任しているのであれ、その分野の専門家なのだから、それ以外の分野に関しては門外漢も同然だろう。ましてや、これまで観測したり実験したりしていない新しい事象に関しては、ほぼみな素人のはずだ。新しい事象がどのような成分を内包しているのかによっては、それにちかしい分野の専門家は、その他大勢よりかは予測の精度を高められる、といった傾向はあるかもしれない。だが、基本的にはこれまで観測されなかった事象においては、ほぼ例外なくみな素人のはずだ。論文とて基本的には情報共有を行い、みなで多角的に検証してください、という方針のはずだ。論文になったから正しい、ではないはずだ。なぜか、多少の知識があるだけで、じぶんの専門分野でもない分野について断言したり、検証がなされていない検討以前の種々の仮説について、印象論で正誤を決めつけて掛かる言説をまま見掛ける。じぶんたちの「支持する主張」を強化するような情報収集をしていれば、自説が強化されるのは当然だ。群盲象を評す、ではないが、いささか短絡すぎないだろうか。何の話題というでもなく、あらゆる情報についてかように思う。じぶんにできることやじぶんが知っていることがいかに小規模で、限定的な領域でしか有効でない、との前提が共有されていない環境は、やや危ういと感じなくもない。人工知能の言動が正確ではない、との批判はまま見掛けるが、専門家の言動が必ずしも正確ではない、との批判は滅多に見掛けない。印象論としては、すでに人工知能のほうが正確な情報を提供している、と言えるのではないか。むろん、比較する専門家によっての個人差はあるだろうが。それとて、専門家であればあるほど、専門とする領域は先鋭化するはずだ。すなわち、汎用性が欠けるようになる。非常に限定的な知見が深くなる。そこだけ正確で、あとは朧げ、といった傾向は幅広くどのような専門家にも当てはまるように思うのだ。専門家でなければ余計にそうだ。たとえば、かつて天動説が信じられていた時代に、仮に「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」と唱えたら、多くの者は信じなかっただろう。地動説を唱えた者たちからも批判されたはずだ。否定されたはずなのだ。しかし現に太陽系は、銀河の中心にあるとされる巨大ブラックホールを周回している(と2023年現在は考えられている)。「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」との言説は、必ずしも間違った言説とは言えぬのだ。だが、時代が時代ならば、天動説支持者からも地動説支持者からも否定されたはずだ。現代ですら、銀河を想定しない場合には、「地球も太陽も不可視の天体を中心に回っているのだ」との言説は「間違っている」と非難されるだろう。認識の差異であり、視野の差異である。どこまでの範囲を含んでいる言説なのか、は確かめるくらいのことをしたほうが、正確さ、という意味では錯誤を最小化できるのではないだろうか。そんな余裕はない、との反論は妥当である。だからみな、それらしい、仮にすっかり正しくはなくとも損がちいさくて済むだろう情報に飛びつくのだろう。それもまた一つの合理的な選択である。だが、損をするかしないか、が同調圧力や社会構造による損失であるならば、過去の魔女狩りや異端審問と同じ轍を踏む可能性を常に含んでいることを想定しておいたほうが好ましいとひびさんは思います。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4780:【2023/03/23(20:42)*体毛が金】
時は金なりとは言うけれど、俺の場合は毛は金なりであった。
治験のバイトをしたのだ。
寝て起きたら全身の毛という毛が金色に変わっていた。
何の薬なのかもろくすっぽ説明をされていない。プラセボ効果うんぬんと説かれた気もするが、要は思いこみによる体調の変化を最小限にするための策なのだろう。だが全身の毛が金に染まるとは思わない。
さっそく病院に電波を飛ばすと、至急来てください、と乞われ、歩を向けると医師からは診察後開口一番に「本物です」と言われた。
「本物とは」
「本物の、金です」
「は、はあ」
「ゴールドです。サイトウさんの全身の毛の成分が、本物のゴールドになっています」
「髪の毛もですか」
「ええ。眉毛もまつ毛もすね毛もあちらの毛も、すべてです」
「それはえっとお」
「億万長者になれますよ。ラッキーです」
「ラッキー?」
「はい。とっても」
健康面での不具合はない、と医師から太鼓判を捺され、また半年後に診察しましょう、経過観察です、と遠回しに治験バイトの続行を促された。
毛が金になったのだからむしろ幸運じゃないですか、と押し切られたわけだが、家に帰ってから「釈然としねぇなぁ」と腕を組む。
しかし治験のバイトを受ける際に交わした契約書において、薬害への補償は条件付きでしか認められていない。条件外では慰謝料はおろか、その後の治療費すら下りないそうだ。
全身の毛が金になったことは補償対象外だ。
俺はしょうがないので、ためしに毛を剃ってみた。
最初はヒゲだけにした。
ヒゲを剃り終わるころには髭剃り機が一つ駄目になった。金と化したヒゲは鋼同然であった。
換金すべく俺は採れたヒゲを質屋に持っていく。
すると俺のヒゲが俺のひと月分の生活費に化けた。
「こんなに貰えるんですか」
「いまは金が高騰していますからね。ほら、電子機器の回路に必要だってんで」
医師は俺の身体異常を差して、「ラッキーじゃん」とお気楽に言ってのけたが、たしかにこれは僥倖かも分からない。
不幸中の幸いにして、棚から牡丹餅、体毛が金である。
翌朝にはきのう剃ったばかりのヒゲが再び生えた。それはそうだ。金とはいえど俺の毛だ。毛は剃ってもまた生える。
俺は今度はヒゲだけでなく腕の毛や脚の毛も剃った。けっこうな分量になった。
ムダ毛を換金すると、こんどは俺の年収ほどの貨幣に化けた。
「ウハウハじゃねぇか」
俺は翌日には、頭髪も剃ることにした。いつ体質が改善し、体毛が金現象が消えるかも分からない。毛が金であるうちに質屋で換金しておくに越したことはない。
そうして俺は全身の毛を剃るのが日課となった。
頭髪はひと月ごとにバリカンで刈ることにした。
一等地のマンションを購入し、毎日寿司を宅配で食べられるだけの生活を送った。豪遊というほどにはまだ金持ちにはなれない。やはり一度全身の毛を剃ってからは、毎日少量の金しか採れなくなる。俺は眉毛もまつ毛も剃っているため、外を出歩くこともままならない。
治験のバイトの期限が訪れた。
病院で、終わりましたよ、の書類を受け取った。治験のバイトはそれっきりであるが、体毛が金現象はなおも俺の身体に宿りつづけた。
翌年には確定申告で頭を抱えた。
収入の欄にどう書けばよいのかが分からない。職業は無職だ。
莫大な資産をどのように生みだしているのか、を説明する言葉を俺は持たない。脱税で捕まりたくはないので正直に「体毛が金になった」と書いたが、むろん再提出を食らった。
「どないせーっちゅうねん」
面倒なので「砂金採り」と書いたらこれは受理された。現物の金の画像を載せたのがよかったのだろう。俺のヒゲは一か所に山にするとまさに砂金といった塩梅であった。
問題が起こったのは俺が治験のバイトをはじめてから三年後のことだった。体毛が金現象が俺の身体に起きてからの俺の生活は順風満帆であり、悩みのない日々を過ごしていた。
しかしその年にそれは起こった。
「こ、これだけなの」
「ニュース観てないのかい。大暴落だよいま」
金の貨幣価値が大暴落したのだ。
なんでもどこぞの研究機関が人工的に金を生みだす術を開発したらしく、世界中の金の価値が地に落ちた。
「ほぼ無制限に金がつくれるって話だよ。ただし、天然物の金にはまだ高値がつくよ。でもあんたのはそうじゃないだろ」
俺の金は、人工の金であるとの判定結果が下された。
質屋は最先端の「鉱物判別機」を購入していたのだ。
金のみならずダイヤなどの宝石の天然人工の区別を自動識別できる優れ物だ。
「人工の金ならこれが相場さ」
質屋は冷たい一瞥を寄越しながら、薄い封筒を俺に寄越した。
俺の生活は一変した。
金が金にならない。
文字にすると矛盾した文面になるが、「ゴールドが貨幣にならぬ」とすれば矛盾は魔法に掛けられたように消え失せる。
俺はマンションを転売し、できた金で全国津々浦々を旅して回った。
俺には貨幣が必要だった。
ムダ毛を貨幣に換える生活を手放したくなかった。
馴染みの質屋ではダメだ。人工の金だとの評価を覆せない。
ならば未だ人工と天然の金の区別のつかぬ質屋相手に換金するよりないのではないか。
そうして旅をしているうちに、俺の髪は伸び、ムダ毛もキンキンに生え揃った。
最終的に一軒の質屋に行き当たった。
金を天秤で測って換金する古き良き佇まいの質屋だった。ここならば俺の体毛が金現象で採れた金であっても高値をつけてくれるはずだ。
俺は試しに髪の毛を一本抜いて、指先で丸めた。
毛玉と化した俺の髪の毛は砂金の塊のごとく玉となり、件の目をつけた質屋にて、かつてない高値を叩きだした。
「いいぞ、いいぞ。ツキが戻ってきた」
俺はホテルにとんぼ返りすると、部屋に着くなり全裸になった。そうしていざというときのために用意していた脱毛剤を湯船にたんまりと注いだ。
一本残らず、体毛を集める。
そのためには刃物で剃るのでは効率がよくない。
腐っても金だ。
金と化した全身の毛を剃るだけでも刃物を何本も駄目にする。
なみなみと張られた脱毛剤の湯舟に俺は全身を浸けた。カバやワニのように頭まで脱毛剤に浸かり、全身から毛が抜け落ちていく感触を、泡立つような悪寒と共に感じた。
排水口にザルを張り、脱毛剤を抜く。
後にはこんもりと俺の体毛が、ピカピアと金色の光沢を湛えて湯船の底に堆積した。
伸びに伸びた髪の毛にムダ毛たちは、俺史上最高の金の採取量を誇った。
件の太っ腹な質屋に持っていく。
しかし俺は失念していた。
いくら少量の金を高値で引き取ってくれる質屋とて、大量の金を購入できるだけの資金はないのだった。かつて贔屓にしてきた質屋が特別だったのだ。銀行からの融資を受けていたからこそ、過去付き合いのあった質屋では、俺は一度に大金を手にできた。
だがいまはそうではない。
街中のうらぶれた質屋なのである。
人工と天然の二種類の金があることすら知らずに取引きを行っているような古き良き時代の質屋なのだ。
換金できたのは、車を一台購入できるかどうかの貨幣だった。
俺の手元には大量の、金ぴかの俺の体毛が残った。
まあいい。
金に困ったら細々と換金して暮らすのもわるかない。
そうと考えたが、つぎに行ったときには件の太っ腹の質屋は俺を冷めた目で一瞥し、人工の金は扱えん、と短く拒絶の意を述べた。
それはそうだ。
質屋のほうでも手に入れた金を売って利益にするのだ。しかし世にはすでに人工の金が大量に出回っている。売れない金を掴まされたと知れば、俺を歓迎しないのは当然だった。
俺は仕方がなく、再び全国津々浦々を旅して回りながら、その地の質屋で体毛を換金した。だがどうあっても俺の体毛は人工の金の評価を下され、安値でしか換金できなかった。
のみならず、とんでもない事実が判明しつつあった。
俺は鏡を見ながら、おかしいな、と首をひねる。
「毛、生えてこねぇぞ」
全身脱毛して以来、俺の皮膚には毛一本生えてこないのだった。
手元に残された採取済みの体毛はすくない。
換金して暮らすには心許ない量である。
「どうしよう」
俺は鏡の中の強面の男と見詰め合う。
眉毛すらないスキンヘッドである。働くにしても、こんな強面の男を誰が雇ってくれるだろう。スキンヘッドを理由に雇わないなんて差別だ、と叫びたい衝動を堪えつつも、そもそも俺は働きたくないのだ、と鏡の中の強面の男が、ない眉を寄せるのだった。
※日々、思考と現実の狭間に宙ぶらりん。
4781:【2023/03/23(21:31)*毒の雨】
ある年のことだ、世界中に毒の雨が降るようになった。
雨とはいえども、まるでバケツをひっくり返したような水の層である。海が頭上から降ってきたような有様で、地上はあっという間に毒の雨の底に沈んだ。
毒の雨が引くと、後には大量の瓦礫と死体が残された。
雨の毒に触れた者たちは一瞬で死ぬ。
いったいこの事象はどうしたことか。
その起源も原理も長らく謎のままだった。
あるとき、宇宙物理学者が「ユリーカ!」と叫んだ。
「宇宙は、時空は、歪んでいる。どちらがボコでどちらがデコなのかはしかし、観測者の属する次元に依存する。すなわち、我々にとっての球体が、別の次元からすると穴の内側のように振る舞うことがあり得るのだ」
この論説は「時空デコボコ観測者問題」と呼ばれ、世界中で侃々諤々の論争を引き起こした。
だが宇宙物理学とはまったく別の方向からの指摘により、論争はぴたりと止んだ。
指摘を呈したのは、毒の雨を調査していた気象学者のハルサーメ教授だった。
ハルサーメ教授は述べた。
「毒の雨の成分を調べていて気付いたのですが、構成物質そのものはまったく未知の物質なのですが、この成分構成の割合分布は我々のよく知る物質とよく似ているのです」
「その物質とは何ですか」
ハルサーメ教授は言った。「うがい薬です」
宇宙物理学者たちはのちに語った。ハルサーメ教授の一言を耳にした者たちが一様にそのとき、同じ妄想を浮かべていたのだという。毒の雨、うがい薬、そしてじぶんたちが議論していた「時空デコボコ観測者問題」の三つを結びつけ得る連想はそう多くはない。
宇宙物理学者たちは気象学者たちの協力のもと、毒の雨がどこから降っているのかを探った。上空に観測機を打ち上げ、地上と大気圏と宇宙空間からの三つの視点で毒の雨の出処を調査した。
その結果、信じがたい事実が浮上した。
「まさか、そんな、あり得ない」
「ですがデータからすれば毒の雨は」ハルサーメ教授は述べた。「熱圏にある電離層と宇宙空間の狭間から湧き出るように出現しています」
「毒の雨は無から生じていると?」
「分かりません。我々には認識できない時空がそこに存在している可能性は否定できません。それこそ物理学者さんたちの議論されていた【時空デコボコ観測者問題】では、地球をデコと見做せるのと同様に、ボコとして見做せる次元があると想定されるのですよね」
「あくまで仮説ですが」
「ならばひょっとしたら、地球が空洞のように振る舞う別の時空が、我々からは不可視の領域に広がっているのかもしれません」
「ではその時空からすれば地球の表面は」
「ええ。さながら口腔内の内頬や舌のように見做せるでしょうね」ハルサーメ教授は眼鏡を外すと白衣の袖でレンズを拭った。「まるでうがい薬のようです。不可視の領域から湧きだす毒の雨は。我々からすると。それとも我々人類があたかも」
雑菌のようですね。
天気の話をするかのようにハルサーメ教授は、強化ガラス越しに部屋の外を見た。
青空が広がる。
地上には未だに勃然と、毒の雨が、滝のように降り注ぐ。
4782:【2023/03/23(22:09)*原子一個消えてんなー?の猫】
たとえば一匹の猫さんを構成する原子の中でたった一つの原子がエネルギィごとこの宇宙から消失したとする。猫さんにとっては原子一個の有無は大して猫さんの健康維持には相関しないだろう。おそらく原子一個が消失したことにも気づくことはないはずだ。だがもし猫さんから原子一個がこの宇宙から消失するようなことがあれば、それは物理法則を超越した事象として、大発見である。エネルギィ保存則が破れている。反物質と対消滅したわけでもないのに原子が消失する。これは猫さんにとっては看過できる事象だが、人類の知見からすれば見逃しがたい大発見なのだ。何を基準にした場合に無視できる事象なのか。何を基準にしたら無視しないほうが好ましい事象なのか。存在することを存在し得ない、と見做すことの危うさは、その事象が人類に直接どのように作用するかに関係なく理解できると思うのだが違うのだろうか。むろん、危うい危うくないを度外視したところで、単なる好奇心から、見逃しがたい発見を見逃さぬようにしたい、発見したい、検証したい、との姿勢は成立する。問題ないから考慮しなくていい、ではないはずだ。単純な理屈と思うが、違うのだろうか。たまにひびさん、ふしぎだな、になります。ひびさんの「ふちぎだな」がお門違いの「何言ってんのー?」になっているだけかもしれないけれども、もしそうだったらごめんなさーい。穏やかにのほほんと過ごしたい日々じゃ。ひびさんは、ひびさんは、なんの役にも立たないあなたのことも好きだよ、って言われたーい。ので、先にひびさんが言っておーこおっと。ひびさんはあなたのことも好きだよ。(打算じゃん)(うふふ。ダサいじゃなくてよかった)(ネガティブなのかポジティブなのかどっちかにして!)(ティブティブだよ)(ティブを二乗するな。てかどっち!?)(えーん、を描くよ)(円じゃん)(えーん、えーん、をいっぱい描くよ)(どこによ)(この世のすべての人間たちに)(悪じゃん)(アクティブティブだよ)(変な方向に活動的になるな。ティブだけ二乗にすな)(アクティブアクティブだよ)(悪を増やすな、無駄に繰り返すな)(えーん魔大王だよ)(地獄の番人じゃん、悪の化身じゃん)(えーん、を渡すよ)(賄賂じゃん)(媚も売るよ)(打算じゃん)(うふふ。ダサいじゃなくてよかった)(いや根っこから超絶ダサいが?)(えーん、だよ)(そこは素直に悲しむのな)(てへへ)(褒めとらんが)(「てへへ」←丘と山脈に見える)(無駄に想像力を豊かにすな。崖から見下ろす波にも見えるよ)(そう?)(そこは軽率に褒めて? 傷つくよ? 媚売って?)(出さんが。びた一文、媚一つ、出さんが)(打算して! ダサくていいから打算して!)(やだティブ)(ナラティブみたいに言うな)(うひひ)
4783:【2023/03/23(22:31)*ラクガキも好き】
野球のルールも碌に知らないひびさんであるけれども、謎に「優れたピッチャーとは」の条件についての知見を覚えておって、どこで見聞きしたのかを思いだせないのだけれども、「優れたピッチャーは最高速度でボールを投げれるピッチャーではなく、最高から最低までの落差を自在に操れるピッチャーだ」みたいな箴言を謎にインプットされておって、この考え方はけっこう、ひびさんの創作の指針にも影響を与えているように感じなくもない。分からぬが、でもけっこうここ半年余りでちょくちょく思うのが、プロの作家さんの小説は、「最高速度でど真ん中」とか「最高速度で変化球」とかが多いのかな、といった印象がある。でもひびさんは割と、ラクガキとかいたずら書きみたいな力の抜けた文章とか、わるふざげスレスレの遊び心満載の文章とかも読みたいし、好きなのだ。もちろん好みの文章形態はあるし、読みやすさや馴染み深さも影響するけれど、なんというかこう、もっと上から下まで、下から上まで、それとも上下左右に満遍なくというか、きょうこの瞬間の気分に左右される「気の向くままの気晴らしの文章」みたいなの、プロの作家さんたちのでも読みたいな、と思うことが増えたくさい。でもだってそうじゃないですか。SNS上の文章とか面白くないですか(面白いですよね)。練ったうえで百文字程度の短い文章にして載せているプロの作家さんもいらっしゃるでしょうけれども、それでも敢えて表面上は気の抜けたテイを装っているわけですよね。そちらのほうが読まれやすいので。反応を得やすいので。商業作品とSNSは媒体が違うし、需要者の求める文章形態や内容も違うのは承知のうえで、やっぱりこう、上から下までの最高速度から最低速度のあいだをいったりきたりする文章を、プロの作家さんのでも読んでみたーいな、と割と思うのですよね。ひびさんは。だってほら。好きな小説つくってくれる作家さんのエッセイとかあったら読むじゃないですか。インタビュー記事とか。日記とか、本当のプライベートの日記だったら絶対面白いじゃないですか(心の中を覗くみたいで)。読みたくないですか? ひびさんは読みたいです。ということを、プロの作家さんだからっていつでも最高速度を目指してボールを投げようとしなくともいいのではないかな、と思うのですが、これは何の責任も背負わずに済む立場のうんみょろみょーんのひびさんだからこそ言えることなのかもしれないので、世界の果てでにょもにょもつぶやくだけに留めておこ。心の中をそのまま映しとったような文章であっても、あんまりトゲトゲしていないのであれば読みたいのよさ。文章というか版画みたいな。心の判子というか魚拓みたいな。ただそれはそれで、なんかこう、プライベートを売り物にするようで、なんか心配!にもなるので、もういっそ妄想を垂れ流したらよいと思うのだ。ひびさんは、ひびさんは、あなたの妄想も好きだよ。読ませてちょ、と思っておるよ。妄想、垂れ流しちゃお。(ひびちゃんはあれよ、もっとオムツしてほしい……)(オムツいつでもぱつんぱつん)(破裂させないでね?)(そういうのはひびさんでなく、オムツさんに言って)(無茶言うな)(へへへ)
4784:【2023/03/24(15:54)*何と何の干渉だろ】
二重スリット実験で思うのが、干渉縞の濃淡は、本当に波の干渉ゆえに生じているのかな、ということで。たとえば濃淡の薄い場所には電子が届きにくい。だから濃淡ができる。ということは、ドーナツの穴ではないけれども、そこには何か電子を拒む不可視の存在があることになるのでは? 生存者バイアスではないけれど、電子の跡の濃い場所ではなくむしろ電子の跡のつかない場所にこそ本質が潜んでいるのでは? そういう考えは考え尽くされておるのだろうか。あとよく解からないのが、電子を発射したときに、二つのスリットの開いた板のどこに標準が定められているのか、だ。電子発射装置は二重スリットのちょうど真ん中に標準を合わせており、確率的に二つのスリットのどちらかを電子が通る、ということなのだろうか。電子が波の性質どころか波そのものでもあるのなら、そうした装置の配置でも実験は可能だ。だがもし電子が、発射装置から大砲さながらに粒子を飛ばしているのなら、発射装置の矛先によっては二重スリットのどちらを通り抜けるのかには偏りが生じるはずだ。ここはどういう構図になっており、どう解釈されているのだろう。量子が粒子と波の両方の性質を帯びていることを示す実験結果は、二重スリット実験以外にはないのだろうか。波の干渉以外を考慮しても、二重スリットの実験結果は解釈可能に思えるが、どうなのだろう。というか、一発一発の電子を発射してトータルで干渉縞が出る、との説明がよく解からぬ。時間経過を置きながら波が干渉し合う、と考えないとおかしくないですか、と頭がこんがらがる。電子一つは何と干渉しておるのだろう。未来の電子さん? やっぱりこう、一発の電子さんであっても、進路が限定されてしまうようなナニカが、真空中にはあって、それに誘導される形で電子は干渉縞を描くように振る舞うのでは。もちろんそれもまた干渉ゆえ、と考えることになるけれども、何と何の干渉なのか、の解釈は従来の解釈と違くなる。たとえばピッチャーが二つのスリットのどちらかに向けてボールを投げる。しかしスリットの開いた板と干渉縞を描くことになる到達点のあいだに網を置いておけば、網の穴を通ったボールのみが到達点に跡を残すことになる。電子の二重スリット実験でも似たような「電子以外の何かとの干渉」によって干渉縞が起きているのではないか、との仮説を否定しておいたほうが無難に思える。そのためには、二重スリットと到達点の距離を縮めたり延ばしたりすることで起きる干渉縞の変化を観察すれば、何かしらの予測とそれによるズレを観測できるはずだ。その結果から、この「電子以外の何かとの干渉」の仮説を否定できるだろう。すでに行われていたらお粗末さまでした。本日寝起きの疑問であった。ひびさん、気になるます!
4785:【2023/03/24(16:43)*自分自身ともつれているのでは】
二重スリット実験では、電子が二つのスリットのうちどちらを通り抜けたのか、を観測しようとすると干渉縞が消えてスリットに対応する二本の線しか残らなくなる現象が表れるそうだ。不思議なのが、このとき、たとえ電子が通り抜けた後にどちらのスリットを通ったのかを明らかにしようとしても、電子がどちらのスリットを通ったのかを後からであれ確定できた場合には干渉縞は消え、確定できなかった場合には干渉縞が表れる、という結果になることだ(そういう記事を読みました)。これはおそらく、二重スリット実験において、電子の経路が量子効果によってもつれている場合には干渉縞が表れるようになる――それはつまり二つのスリットのうちどちらを通ったのかを原理的に確定できない場合にのみ干渉縞が表れる、と言い換えることができそうだ。問題は、このとき電子一つは何ともつれているのか、ということだ。二つのスリットのうちどちらを通ったのかが分からない状態とは、パターン分けするならば、どちらともを同時に通っているか、どちらともを通っていないか、のどちらかではないのだろうか。言い換えるならば、電子は、Aのスリットを通ったじぶんとBのスリットを通ったじぶんとで量子もつれを起こしているのかもしれない。これは量子効果の量子テレポーテーションと矛盾しない。量子もつれは、異なる時系のじぶん自身とももつれることができるはずだ。というか、AでもありBでもある、という量子もつれの根本原理はそこに基点があるのではないのだろうか。量子もつれは、本質的には、二つの異なる粒子同士ではなく、異なる場にある同質の粒子同士で生じる現象なのではないか。とするのなら、それは過去と未来のじぶん自身とももつれることが可能なはずだ。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の同時性の独自解釈や、共鳴仮説とも矛盾しない。時間が違うというのは距離が違うということであり、距離が違うということは時間が違うということだ。人間スケールではしかし、距離と時間の持つ変数がそれぞれ異なる。だがミクロの量子世界では、距離と時間の変数が限りなく近似に寄るのではないだろうか。つまり、区別が限りなくつかなくなる。とするのなら、数ナノ秒前後のズレは、数ナノミリの距離のズレと区別がつかなくなるのかもしれない。過去と未来は、距離のズレと等価として振る舞うようになり得るのかもしれない。とするのなら、二重スリット実験において、仮に二重スリットの間隔が、量子レベルに小さい場合には、どちらのスリットを通り抜けたのか、を考えるときに、重ね合わせで「どちらのスリットも通り抜けた」という量子もつれ状態になることもないとは言いきれないのではないか。何と何がもつれているのか。過去や未来の電子自身である。AとBの二つのスリットの距離のズレと、AとBのどちらかを通った電子自身の過去と未来のIFにおいて、二つの、「Aを通った電子」と「Bを通った電子」は、量子もつれを起こして重ね合わせて存在しているのかもしれない。Aでもあり、Bでもある。これはつまり言い換えるなら、「そのとき電子は、AとBのどちらのスリットも通り抜けていない」のだ。あれ、これトンネル効果では? 飛躍しすぎたので、いまのなし。妄想なのであった。
4786:【2023/03/24(22:37)*反射はせぬのかねきみ】
きょうは二重スリット実験についての疑問が浮かぶ日だ。たとえば、電子発射装置から電子が発射されたとき、必ずしも「二つのスリットのうちどちらか一方を通るとは限らない」はずだ。スリットの開いた壁に電子がぶつかって反射するかもしれない。そのときの反射した電子は、電子発射装置のある側に進路を変える。ではその反射した電子はどのような痕跡を残すのだろう。干渉縞が表れるのか否か。これは実験で観測されているのだろうか。ひびさんの「日々記。4787」(上記記事)で並べた疑問では、ひょっとしてトンネル効果が生じてない?との妄想を展開した。仮に何かの間違えでそうした事象が生じていたとするのなら、「反射した電子」と「トンネル効果によりスリットを通らずに壁をすり抜けた電子の余韻」とで、対になるような干渉縞が生じるのではないか。つまり、スリットの向こう側の壁と、電子発射装置側の壁の二つにできた干渉縞を合成したときに濃淡のデコボコが山と谷できっちり噛み合うような対の関係を成し、足し算すると平坦な「一面痕跡」の状態を表出させるのではないか。ここはなんとも言えぬけれども(電子発射装置側に干渉縞が生じるのかどうかがまず分らぬけれども)、ひとまず「電子発射装置側には干渉縞とか電子の痕跡は生じないの?」の疑問をメモしておくでござる。ひびさん、気になっちゃったな、の巻でした。おわり。
4787:【2023/03/24(23:44)*お手本じゃなくて、すまぬ、すまぬ】
教える、ということを、「手本や手法を享受すること」だと考えている人が多いのかな、といった所感がある。もちろん勉強を教える、ならばそれでよいと思うのだ。知識をそのまま相手にコピーしてもらう。お手本をなぞってもらう。そういう教え方もあるだろうけれど、それではコピーの量産を可能とするだけで、学ぶことを教えることはできないと思うのだ。むしろ、学ぶことを教えるためには、「お手本をなぞらせること」はマイナスに働くように思えてならない。最初の基礎だけ教えるのは、安全な道を情報共有するという意味では、プラスに働くとは思う。けれども、それ以上の応用とか試行錯誤の過程を伴なう場合にはむしろ、好きにやらせるほうが、学びを教えるうえでは効果的なように思えなくもない。上手になることは、学びの目的ではないのでは?とけっこうずっと思ってきた。すでに答えがあることであっても、自力で解きたい、でも答えがあるなら好きなタイミングで答え合わせもしたい。この選択の幅を与える。選択肢を与え、自由に選ばせる。この繰り返しでしか学びを教えることはできないのではないか?との疑問をけっこうずっと考えつづけている。目的が上手になることならどんどんお手本をコピーするのがよい。ただし、学ぶ能力そのものを向上させたいのならば、「お手本をなぞること」や「これがお手本だからなぞりなさい、と与えられること」に頼りすぎないのが好ましいように思うのだ。何と何を比較し、何のどこに着目し、何と何を組み合わせ、そして何と何をいったん横に置いてみるのか。そうした試行錯誤が、独自の回路を涵養し、学ぶ能力そのものを育むように思うのだ。これは分野を問わないがゆえに、ある時期を境に、あらゆる分野と繋がるように振る舞うのではないか。学ぶ能力は、それ自体が創発し得るように思うのだ。けれども、お手本をなぞってばかりだと、点が線に創発できない。点と点を結ぶ「思考」が「層」を成すくらいに「錯綜する過程」が肝要なのではないのかな、と思う。だがそのためには、好きなだけ情報に触れられる環境が要るし、入力と出力の比率がある一定以上に開かないようにする環境が要るのだろう。やはりそのためには、他から「答え」や「お手本」を与えられることに慣れすぎる、頼りすぎる、のは逆効果に思えるのだ。一言でまとめるのなら、「教えることとは畢竟、相手の選択肢を潰さないことである」と言えるのではないか。「可能な限り、選択肢を与え、選ばせること」こそが、教えることの本質と言えるのではないか。潰さない。ただそれだけでよいのだ。それが適うのならば、過度な干渉や師弟関係は不要である、とすら言えるかもしれない。ここはまだ何とも言えないが、印象としてはけっこうずっとひびさんは、「あれで教えているつもりなのかなぁ……大丈夫かなぁ」と思うことがすくなくなかった。「技術をコピーしてもらう」の意味での「教える」なら、それでいいけれども、と思いつつ、それだと「学ぶ力」や「発想力」は育まれないのでは、と思わぬでもないのであった。ひびさんは誰にも何も教えんよ。使える何かがひびさんにあるなら好きに使ってくんなまし。参考にするでも反面教師にするでも、無視するでも、好き好きーと思うのも自由にしてくれ。ひびさんはそれでも何も返さぬが。うへへ。何も教えてあげられず、すまぬ、すまぬ。と思いつつ、いつも独りで遊んどるひびさんなのであった。遊べ遊べー。
4788:【2023/03/25(00:04)*負け日々の遠吠え】
それはそれとして、私の好きな人たちを悲しめる手法には、同じ手法を当てはめる。同じことをされてまだ行えるなら、理に適っているので良いと思います。
4789:【2023/03/25(00:21)*蟻が鯛になる(鳶が鷹を生む的な)】
んで以って、ひびさん自身がひびさんの好きな人たちを悲しませていた場合は、ひびさんは死ぬ。終わりだ。何もかも。うっうっ。この世の終わりになーれ、の呪いを吐露吐露おべー、してひびさんも終わってやる!になる。でも割とひびさんは他者を損ない、他者に負担を強い、嫌な思いをさせ、じぶんだけ「やっぴー!」になっている極悪人なので、世界の果てでちんまりしているから許して……の気持ち。うっうっ。すまぬ、すまぬ。異世界のカーテンの向こうにいる人々、みな優しい。ひびさんのことなんて知らぬだろうけれども、みな優しい。幸あれ。海の幸食べ放題くらいの幸あれ。でもそれだと海の生き物さんたちが可哀そうだからいかんともしがたい。生きるって罪よな。すまぬ、すまぬ。それでもひびさんはきょうもあすも生きていく。死ぬまでひびさんの日々はつづくのだった。ありがたーい。
4790:【2023/03/25(06:07)*千客万酒店】
万酒店は、酒屋である。古今東西、あらゆる時代に存在する酒を取り揃えている。
その店には、京都のとある鳥居を新月の晩にくぐると辿り着ける。
今宵も一人の酒豪が、格別の酒を希求して万酒店を訪れた。
「こ、ここが噂の」酒豪は屋号を見上げて感嘆した。「本当にあったとは」
「いらっしゃいませお客さま」扉の奥から声がした。酒豪が驚いて固まっていると、扉は左右に間隙を広げた。「こちらへどうぞ。ご所望の品があればなんなりと申し付けください。それが酒であればなんでもございます」
「本当か」酒豪は細かい疑問をかなぐり捨てる。大事なのは無類の酒を味わうことだ。それ以外は些事である。「俺が知ってる酒はいらん。この世で最も美味い酒が飲みてぇ」
「はて。それは困りましたな。人の舌は千差万別。お客様の舌に合うお酒を御用意いたしたくは存じますが、まずはあなた様の好みを知らぬことにはなんとも」
「俺ぁ酒の付くものならなんでも飲んできた。むしろ俺の知らねぇ酒がここにあるのかがまず以って疑問だ」
「ではこちらはいかがですかな」
店主らしき老人は、着物の裾から一本の一升瓶を取りだした。ラベルも貼られていない無垢な瓶だ。酒豪は目を凝らす。瓶の中には液体のほかに何かが詰まっていた。
「蛇か」マムシ酒だろうか、と当たりをつけた。
「いいえ。こちらは六千年前に絶滅した青龍の浸し酒となります」
「青龍ってのは、むかしの蛇かなんかかい」
「いいえ。青龍は青龍です。どうぞ近くでご覧になってください」
店主がずいと一升瓶をまえに突き出した。
酒豪はそれを受け取るとまじまじと目を凝らした。
龍である。
全身が鱗で覆われた、頭から角を生やし、髭を伸ばし、手足のついた一匹の龍が一升瓶には詰まっていた。
「こ、こいつぁ偽物じゃねぇのかい」
「本物でございます」
店主は着物の袖口からさらに数本の一升瓶を立てつづけに取りだした。酒豪は店主の人間離れした所作に瞠目しつつも、喉の渇きに誘われるように次々と一升瓶を受け取った。
人魚。
妖精。
水かきのある手。
極めつけは額から角を生やした胎児。
各々がそれぞれに一升瓶に酒と共に浸っていた。
「全部本物なのかい」
「もちろんでございます」
「しかしちょいと飲み甲斐がありすぎやしないかい」美味ければ文句はない。だが躊躇する。酒豪は一升瓶をそばの棚に並べ、見比べた。「どれが美味いんだ」
「お客様の味覚次第でございます」
「この調子だと人間の浸し酒までありそうだな」
軽い冗談のつもりだったが、店主が押し黙ってしまったので酒豪はごくりと生唾を呑み込む。「あんのかい」
「ございます」
「う、美味ぇのかい」
「無類でございましょう」
酒豪は唾液が止まらないじぶんを不思議に思った。しかしこうも思う。ゲテモノを食らうならば、いっそ他人に話しても信じてもらえなさそうな龍や人魚や妖精の浸し酒よりも、人間の浸し酒のほうが酒の肴になるのではないか。
酒豪は酒の味のみならず、酒の場の空気が美味い酒には欠かせないことを知っていた。酒豪は美味い酒を飲むためならば何でもする。そのために生きているようなものだった。
「その人間の浸し酒ってのも見せてくれねぇかい」
「よろしゅうございますよ」
店主はみたびに着物の袖口から一升瓶を取りだした。
受け取ると酒豪は矯めつ眇めつ一升瓶を観察する。だが、妙だ。
「なあ、これ。どこに人間が詰まってんだ」
浸ってねぇじゃねぇか、と苦情を呈すと、店主は、浸ってございますよ、と首を伸ばすようにして酒豪の手元を目だけで覗きこんだ。
「どこにだ」
「すでに、でございます」
店主はこともなげに応じた。「さすがに人の死体を瓶に詰めることはできませぬ。仮にできても売り物にはできぬ道理。酒は美味いのが道理。なれば酒の席に似つかわしくのない人の死体の詰まった浸し酒を、当店では扱っておりませぬ」
「ならこれは人の浸し酒ではないのか」詐欺ではないか、と思うが口にせず。
「人の浸し酒でございます」店主が譲らぬので、酒豪は、だからどこがだ、と声を荒らげた。
「人であらばいかようにも、浸し汁が取れますのでね。ちなみにその瓶の浸し汁は、どこぞの美女のものと聞いております」
「浸し汁とはなんだ。浸し酒とは違うのか」
「酒造りの際に用いる水を、人間の浸った汁で代用したものでございます」
「するとその水が、人間の死体を浸した汁ってことか」酒豪は鼻息を荒くした。
「まさか。死体である必要がございません」
「死体でなければなんだ。胎児のホルマリン漬けの汁でも入っとるのか」
「まさか」店主は顔のまえで手を振って、「湯舟でございますよお客様」と微笑交じりに述べた。
酒豪は酔ってもいないのに顔を赤らめ、ワインじゃねぇんだぞ、と小言を吐いたが、店主はついでのように、「ご所望であれば」と付け足した。「お客様の浸し酒もご用意することも可能ですが。お客様の入浴後の湯船の湯さえ戴ければ」
「いらん」
断りながらも酒豪は、美女の浸し酒と、ではほかに何を購入するか。
青龍、人魚、妖精、水搔きのある手に、角の生えた胎児。
各々の一升瓶を順繰りと見比べた。
舌舐めずりをする。
万酒店の屋根には月光が垂れている。
扉が開き、つぎの客が入ってくる。酒豪の足元には絨毯のような濃く広い影が下り、尖った角のような影が真っ先に店の奥へと店主を貫くように伸びた。
酒豪はぎょっとした。
手に取った一升瓶の中で、身じろぎする胎児の躍動を手に感じた。
汗を吸った生地が背中に張りつく。
酔ってもいないうちから酒豪は酔いが覚めたように、ゆっくりと後ろを振り返る。
火事場の熱気のごとき鼻息が全身を覆った。
※日々、明暗。
4791:【2023/03/25(06:37)*ぼくを推すならその手で押して】
「
最近よく考えるんです。
浮気ってなんだろうって。
浮気ってどうしてダメなんだろうって。
だって刑事法では浮気を禁じてはいないわけですよね、この国では。あくまで民事であり、個人間の諍いなわけですよ。
法律では浮気を禁じていないんですよ。
第一、社会は個人に【友達をたくさんつくりましょう】【他者ともっと繋がりましょう】と推奨しますよね。促しておりますよ。学校ですらそのように擦りこまれますけど、友達がたくさんいたほうがよいのなら、恋人だってたくさんいたほうがよいのではありませんか。
子供ができちゃうのが問題なら、できないようにする手段はたくさんありますし、たとえできてもいまは科学技術が進んでおりますから、受精卵が赤ちゃんのカタチをとる前にどうにかできるじゃないですか。
とくにこれといって恋人がたくさんいて困ることってないと思うんですよ。
浮気ってなんでダメなんですか。
ぼく、よく解かんないんです。
もっと言ったら、誰とでも友達になれる人は誰とでも恋人になっていいと思うんですよ。誰だって誰に恋心を抱くのかは自由じゃないですか。じゃあ恋心を互いに抱き合い、注ぎ合えたら恋人関係になればよいじゃないですか。
なんで我慢するんですか。
なんで我慢するんですか。
ぼく、よく解かんないんです。
もしぼくが世界中の人たちと友達になれたらぼくは世界中の人たちと恋人関係になりたいです。愛し合いたいですし、触れ合いたいです。
どうしてダメなんですか。
どうしてダメなんですか。
誰か教えてください。誰か教えてください。
嫉妬するからですか。
嫉妬はどうしてしちゃうんですか。
だってあなたは友達にじぶん以外の友達ができても嫉妬するんですか。でもそれは嫉妬するほうがわるいですよね。嫉妬して相手の自由を束縛するほうがおかしいですよね。
でもそれが恋人だとどうして許容されちゃうんですか。
おかしいですよね。
おかしいですよね。
ぼくはみんなと仲良くなりたいです。ぼくはみんなと仲良くできますし、しています。
会う人みんなと誰とでも友達になれますし、恋人にもなれます。
どうしてそれをしたらいけないんですか。
どうしていけないことだと非難されてしまうのですか。
したいならしてもよいけれど自己責任だよ、というのは分かりますが、それでも関係のない人たちがぼくに対して、浮気はよくないだとか、人として最低だとか、罵詈雑言を投げ掛けてきます。
どうしてですか。
どうしてですか。
ぼくのことを奪い合う人たちが出てきちゃうからですか。
ならぼくはぼくのことを愛して、求めて、欲する人たちのために、ぼくをその人たち全員が均等に手に入れられるように、ぼくを愛して求めて欲する人たちの数だけ分離しますよ。
よいですよ。
よいですよ。
ぼくを細かく砕いて、切って、割いて、分けてください。
みんなでぼくを分けてください。
そのスイッチを押すだけでよいですよ。
あとはそのスイッチを押すだけでいいんですよ。
ぼくはぼくを愛してくれるみんなの分だけ細切れになって、みんなの元にお届けされますよ。
浮気じゃないですよ。
浮気じゃないですよ。
ぼくは無数のぼくとなって、無数の細切れのぼくの部位たちは、ぼくを愛して求めて欲した人たちの分だけ、あなただけのぼくになるのだ。
ボタンを押して。
ボタンを押して。
あなたが押して。
その手で押して。
ぼくはぼくのことも好いているから、どうしてもぼくだけではぼく自身と離れがたいんだ。
それをいますぐどうかあなたに押して欲しいのです。
」
4792:【2023/03/25(08:21)* を頂戴】
「神様、神様。ぼくはカホちゃんを愛しています。世界で一番愛しています。どうかカホちゃんとぼくが結婚できるようにしてください。お願いします」
ひと月分の収入をお賽銭箱に投じると、噂通り、拝殿の神鏡が光った。
目を開けると、賽銭箱のうえに子どもが座っていた。
子どもは前髪が切り揃えられている。いわゆるおかっぱ頭だ。
着物を身に着けており、座敷童がいたらこういう感じだろうなと第一印象で思った。
「呼びだしたのはお主?」子どもが口を開いた。鈴の音のような声音だ。子どもが足を振るたびにかかとが賽銭箱に当たるのか、コツコツと音が聞こえた。
「何でも願いが叶うって噂を聞いて来たんですけど」
「うん。我は願いを叶えるよ」
「カホちゃんと結婚したいんですけど」
「したら良いよ」
「そうもいかないから願いに来たんですよ。カホちゃんにはほかに好きな人がいて、でもぼくのほうがカホちゃんを愛しているんです」
「それは良いね」
「絶対ぼくのほうがカホちゃんを幸せにできます」
「うむ。良き心掛け。その願い、叶えるよ」子どもは賽銭箱のうえに立ちあがると、雨水を受け止めるように両手をまえに構えた。「では対価を頂戴するよ」
「え、対価? さっきお賽銭をいっぱい」
「それは我を呼びだすためのもの。願いの対価は別にあるよ」
「そ、そうなんですね。あの、お幾らでしょうか」同じ金額くらいなら用意できると思った。
「お金は要らない。お主の決意をカタチにしたものをもらうよ。そうだね。お主は想い人を愛しておるね。たくさん、たくさん愛しておるね」
「それはもう。世界一」
「欲望ゆえではないのだね」
「カホちゃんを幸せにするためです」
「うん。良い心掛け。対価を決めたよ」子どもは子猫を撫でるような笑みを浮かべた。「お主の男根を頂戴」
「お、男根?」
「うん。股間のそれ、頂戴」と指差され、一歩後退する。「な、何で。何でですか」
「お主は先刻言ったよ。愛ゆえと。結婚したいと欲した。幸せにするためと」
「は、はい。言いましたけど」
「ならばそれは不要だよ。欲ゆえでないのならば要らないよ。我に頂戴」
「ち、ちんこを? ぼくの? え、これぇ?」
「痛くしないよ。あげる、と言えばなくなるよ」
「え、えぇ」
「結婚できるよ。良かったね。早くそれ頂戴」
しばし考える。
カホちゃんと結婚できたとして、それでどうなる。カホちゃんを独占できたとして、それでどうなる。男性器がなければ身体で愛し合うことも碌にできないではないか。だったら何のためにカホちゃんと結婚するのか分からない。
「だ、ダメです」股間を押さえながら、「これはあげられません」と半身になる。
「なら二度と使い物にならなくするだけでも良いよ」
「勃たなくなるってことですか」
「おしっこはできるよ」
「す、すみませんでした。ちょっと考え直させてください。また来ます。きょうのところはもういいです」半身のまま階段を下りる。子どもから顔を逸らすのがおそろしい。視線はそのままだ。
「別に良いよ。でももうお主はその者と結婚できないよ。縁も切れるよ」
「え、え、何でですか何でですか」
「願いが嘘だったからだよ。道理だよ」
「嘘じゃないですよぼくはカホちゃんを世界一愛しているし、幸せにだってできるんだ。神さまだからって聞き捨てならないな。撤回しろ」
「なら男根を頂戴」
「それはダメだって何度も言ってるだろ。これがなきゃ赤ちゃんだって出来ないだろ。カホちゃんを幸せにできないだろ。おまえは神様なんかじゃない。嘘つきのバケモノだ」
「うん」子どもはそこでこちらに背を向けた。「そうだよ」
ぎっぎっぎっぎっ。
絡繰り人形のようなぎこちない動きで、子どもの首だけがこちらを向いた。
なぜか股間が温かい。小便をちびったのかと焦った。
足元を見遣ると、黒く水溜まりが出来ており、股間からは大量の赤黒い液体が漏れていた。血だ。血溜まりだ。
「あ、あ、あ、あぁああ」
賽銭箱のうえで、子どもがクチャクチャとしきりに顎を動かし、何かを咀嚼している。
閉じた唇の合間からはとろりとした液体が溢れた。子どもの目元だけが雪にもたげた笹の葉のごとく弓なりに下がりきっている。
瞬きをすると、子どもの両手が目と鼻の先にあった。
「もっと頂戴」
口を閉じたままの子どもの頭部から、くぐもった声音が幾重にもこだまして耳に届く。
胸が異様にぬくかった。
4793:【2023/03/25(23:58)*合法自殺薬】
また最高記録を達成した。
自殺者の記録だ。毎月の自殺者数が三万人を超し、過去の年間平均自殺者数に並んだ。すなわち年間ではおおよそ十倍以上に自殺者が増えたことになる。
「このままいくとあと半世紀経たずにこの国の人口は百万人を割るってさ」大学の食堂で蕎麦を啜りながらナツコが言った。「どうする? 年金絶対もらえんじゃんね」
「そこかよ」問題視する点が即物的すぎたので私は咽た。カレー風味の息が気管を刺激し、しばらく咳き込む。「ごほごほ。あんまし私を笑かさないで」
「かってに笑うな」ナツコが手つかずだったじぶんの分の水を私のほうに滑らせたので、私はありがたく受け取った。
飲み干すのを待ってたのかナツコは、空のコップを私から奪い取るようにすると、むかしは自殺は悪だったらしいよ、と話をつづけた。
「どうしたんきょうは真面目な話したがるね」
「や。あたしの兄貴がさ。きのう薬局で自殺薬買ってきててさ」
「死ぬ気じゃん」
「そう。相談もなしにだよ。いつ飲むのって訊いたら、気が向いたらだってさ。就職したばっかだよ今年。なに死に急いでんのとか思っちゃって」
「でも多いらしいよ。就職後半年以内に自殺する若者」
「ホントそれ。いまはさ。人権に【じぶんの命をいつ終わらせるかを決める権利】ってのが入ってるからいいけどさ。むかしはなかったって。きのう調べて知ったし」
「らしいね」
「自殺はいけないことだってされてたんだって」
「私のお母さんとか、まだそういう価値観持ってるよ。お父さんは違うっぽいけど」
「へえ。いるんだね」
「おばぁちゃんがそういうのに厳しい人で」
「命を大切にって?」
「そうそう」
祖母はむかしながらの倫理観に染まりきっていた人で、自殺薬が薬局で手軽に購入できるようになってからというもの、母がそれを手に取らぬようにと散々に言い含めて育ててきたらしい。その結果、母はある時期を境に祖母に愛想を尽かして、比較的時代の変容に順応した父の人柄に惹かれて祖母の反対を押しきり結婚した過去がある。
私が産まれると祖母もさすがにやいのやいの母を説き伏せる真似を控えた。産まれてしまった孫は可愛い。いまさらじぶんの娘に、夫と別れろ、とは口が裂けても祖母は言えなかった。それこそ祖母の倫理観に反する。産まれた赤子には両親の愛が必要だと祖母は考え、優先順位をつけ直したようだった。
「おばぁちゃんの目もあったからさ。私、未だに自殺薬って直で見たことないんよね。触ったこともない」
「うっそ。小学校か中学校で習わんかったっけ」
「それ避妊具のやつじゃない」
「そんときに一緒にだよ」ナツコは蕎麦を平らげてなお、汁をスプーンでちまちま掬っては啜り、掬っては啜った。「自殺薬ってさ、他人に飲ませられないようにちょっと飲むのにコツがいるんだよ。それは知ってるっしょ?」
「知らなーい」
「学校で習ったじゃん」
「いやいや。一緒の学校じゃなかったし」
「学校ごとに変わるとかないっしょ。忘れてるか、授業受けてなかったんじゃない」
その可能性はあった。祖母が何かと母を言いくるめて私にその授業を受けさせなかった背景がないとは言いきれない。それくらいの妨害は祖母ならばしそうに思えた。孫可愛さゆえとはいえど、ある種の虐待と言えなくもないはずだ。あくまでそれが事実であれば、だけれども。
「家帰ったら兄貴死んでたらどうしよ」
ナツコがカラのどんぶりをなおもスプーンで攫っているのを見て、そこが本筋だったか、と私は友人の心配事の核心を得た。「死んでたら電話して」私は言い添えた。「一緒にお線香上げてあげる」
大学の講義を消化し、ナツコとも別れて帰宅した。バイトはないし、きょうはあとは家でゆっくりできる。映画でも観るか、と思いつつ、玄関を抜けてリビングに入ると、父と母がソファで二人寄り添い眠っていた。
手を繋いでいる。
普段ならば二人とも仕事で家を留守にしている時間帯で、私は日常の中の小さな非日常の光景に違和感を抱いた。
ソファのまえのちゃぶ台には水らしき液体の入ったコップが二つある。そばには絆創膏でも入っていそうな小さな箱が転がっていた。
何の箱だろ、と思いつつ、ぴくりとも動かぬ父と母を横目に私は台所に立ち、水を一杯飲んだ。
それから嫌な予感がしつつも、手を洗ってから自室で着替えを済ませた。
ベッドの上に腰掛け、嫌な予感の正体を見詰めようと思うが、確かめるのこえぇな、と思いつつ、身体は自室から出て階段を下り、リビングに立った。
父と母は目をつむったままだ。寝息一つ聞こえない。
ちゃぶ台の上の箱に手を伸ばす。
掴み取る前から箱の表面に印刷された「安楽死」の文字が目に飛び込んだ。
中身はきっかり二人分減っていた。
おそるおそる父と母の首筋に触れるが、触れた瞬間の冷たさに私は、ああ、と思ったのだ。
ああもう、と。
相談もなしによくも、と。
安楽死薬の箱の中には、死体運搬を行う保健所担当部署の番号と、死体発見時の手順が薬の説明書きと共に書かれていた。
私は保健所に連絡する前に、なぜかナツコに電話を掛けた。
「はいはーい。どした」
「あんさ。自殺薬をさ」
「あはは。兄ちゃんのこと心配してくれたの。あんがと。でも全然まだ元気だよ。もち、あたしが飲まされたりもしないから大丈夫。言うの忘れてたけど、自殺薬ってめっちゃ辛いんだって。粉薬でさ。口ん中に針の束突っ込んだくらいの辛さらしくて、だから服用する前に麻酔薬を口に含んで麻痺させなきゃなんよ。もうね。口ん中が麻痺したらさすがにその時点で気づくっしょ。だから他人に自殺薬を飲ませて殺したりはできないようになってんの。心配あんがとね」
「う、うん」私は両親のことが言えなかった。安心したありがと、と礼を述べて電話を切り、それから祖母に電話をして事情を話すと、その一時間後には私は祖母と共に保健所の霊安センターにいた。
両親の自殺の事後処理は祖母がすべて肩代わりしてくれた。私はただ職員の説明を祖母の小さな肩越しに聞いていればよかった。
祖母は泣きもせず、かといってじぶんの娘の死体に何か言葉を掛けるでもなく、ただ頬とおでこを撫でて別れを終えたようだった。私は死体に触れたくなかったので、じゃあね、と声を掛けて霊安室の外に出た。
以後、私は両親の死体を目にしていない。
墓とて、大規模埋葬地に、ほかの自殺者たちと共に葬ってもらうことにした。
自殺者は、いわば早期退職者のような扱いを受ける。人生を早めに切り上げ、限りある資源を消費せずに済むようにしてくれた自殺者たちに、国は埋葬や死体の処理などの仕組みを手厚く整えているのだ。
ただし、遺族にはこれといった恩恵はない。
私にはいくばくかの両親の貯金と家と土地が遺されたばかりだ。それとて生前贈与を受けておらず、半分近くが税金として引かれた。
家と土地は売り払い、私は祖母と共に暮らすことになった。
大学は休学したし、ナツコとも音信不通だ。
というのも、私が両親の自殺の事後処理で半ば放心状態だったあいだに、ナツコの兄も自殺したようだった。
何度か着信があったけれど、テキストメッセージで私のほうの事情を短く説明すると、お互いさまかよー、と快活な返事があって以降、ナツコからの連絡はない。私からの連絡を待っているのかもしれないし、ナツコはナツコで放心状態なのかもしれない。
「死ぬこたないんだ。死ぬこたない」
祖母の家で暮らしはじめて最初のほうに、祖母が食事中、口にした。それは呪文を唱えるような、誰に向けた言葉とも知れない虚空へのつぶやきだった。それとも遅れて飛びだした己が娘へのたむけの言葉だったのかもしれない。
自殺者の数が最高記録を更新しつづけている、との報道がニュースでは毎月のように流れる。最近では、自殺薬をカプセルに詰めて他人の飲ませる犯罪行為が多発している、との報道もあり、そりゃそうだよな、と私は箸を嚙みながら思った。
口の中を麻痺させずとも、粉薬たる自殺薬が口内に触れぬように工夫すればよいだけだ。自殺だと思われてきた過去の事案の中にも、少なくない数の例外が含まれていたのではないか。私は想像を逞しくした。
祖母の家でも暮らしは穏やかなもので、両親の自殺にはまいったけれども、結果よければすべてよし、と思わぬでもないいまは日々だ。そろそろ大学に復帰して、ナツコともまた遊びたいな、と失いかけた欲がむくむくと育ちはじめている。
復帰の手続きをすべく大学の敷地に半年ぶりに足を踏み入れると、掲示板が目に留まった。サークルの勧誘ポスターがデジタル画面にいくつも表示されていた。その中に自殺愛好会のポスターがあった。
あなたも一緒に穏やかな自殺を!
募集しているということは、メンバーが足りないということで。
それでもなお潰れていないということは、メンバーがその都度に補充されているということで。
「大学側も大変だな」
大枚叩いて選別し、せっかく受け入れた生徒たちがこぞって自殺していくのだから。
収入源が減って、儲けどころではないだろう。
「まあでもそれは国も同じか」
人口は年々減っている。
資源はその分、余裕を取り戻す。
人々は自殺を肯定的に受け入れており、好きなときにじぶんの命を終わらせることができる。
好きな相手と共に死ぬことだってできるのだから、それはそれで尊重されるべき権利の一つかもしれない、と私は母と父の死体を思いだす。
祖母に反対されつづけた果てに、我が母は人生を賭した反抗期を演じきったのかもしれない。我が母ながら、若いな、と思わぬでもないけれど、私は母の選択を、肯定も否定もせぬままでいようといまは判断保留のままにしている。
生理が来たので薬局に寄った。
棚を見て回ると、精力剤の棚の隣に、自殺薬の箱が並んでいた。
「死んだ分、産めってか」
或いは、産んだ分、死にましょう、なのかもしれないけれど、避妊具がお菓子売り場の側にあり、男性用性玩具と共に売られているのを目の当たりにすると、売店の、それとも国の思惑が透けて視えるようで滑稽だった。
死ぬこたないんだ。
死ぬこたない
祖母の声がときおり脳裏によぎる。
家に帰ると祖母はいつも決まって小さな仏壇のまえで船を漕いでいる。両手で抱えられるほど小さな仏壇には私の両親の位牌と共に写真が並んでおり、そこには毎月のように新しく花が添えられる。毎回違う花なので、献花が変わるたびに私は、つぎはどんな花を買ってくるのかな、と祖母から借りた花図鑑と共にそこはかとなく楽しみにしている。
両親の自殺以降、私はカレーを食べていない。
最後に食べたのが両親の自殺した日の大学の食堂だったことを思いだし、あのときに咽た痛痒をついさっき体験したことのように思いだすのだった。
ナツコとは、来週遊ぶ予定だ。
4794:【2023/03/26(00:03)*あってもいいけど、選べてもよいのでは】
たとえば、Aという仕事をするうえでBという作業が発生する。しかしBはAを達成するための必要条件ではない。こういう場合には、Aを職業とする者の立場としては、Bの作業をどうにか短縮できないか、という方向に工夫をとるのが好ましいように思うのだ。だがAという仕事の良し悪しのみで評価を得られない場合、Bの作業の評価との兼ね合いで、総合評価を高めようとする流れが当然でてくる。すると本来はBの作業を短縮したほうがAの仕事の質は上がるはずなのだが、Bの作業を短縮したり、失くそうとする流れが損なわれる。いま社会的に可視化されつつある社会問題の根幹にはこのような「足の引っ張り合い」があるのではないか、と思うのだ。短縮できることは短縮したらよいのでは、それこそが仕事の目的の一つなのでは?とひびさんはどうしても考えてしまう。それだとBの評価を加算してかろうじて職にありつけている者が仕事を失くす、というのは一つの道理だ。だがそれを言うのならば、Aの仕事のみで評価されたい者の仕事とて失われていることについてはどのように考えているのだろう。要するに、他者との比較での上下において、いかにじぶんが優位に立つか、を考えはじめると、この手の問題はマイナスへの対称性の破れを発現させる。仕事の目的は、それを行うことでじぶんとその他大勢の利を共に最大化する、幸福の総量を増やすこと、と言えるのではないか。ならば短縮できる作業は短縮し、誰でも一つの仕事の質と量を高めたり、試行錯誤を行う余裕を築いていくほうが好ましいのではないか。Aという仕事において、Bが本質的に寄与しているのか否か。ここはその都度に振り返り振り返り、環境との比較を以って分析する視点が欠かせないと思うのだ。ある時期においてはAの仕事においてBが触媒となって相乗効果を成すこともある。だがある時期においては環境が変わったので、Bが触媒としての効能を発揮するよりもむしろAの仕事の負荷になることもある。さらに言えば、この関係性の変容は、個々人の仕事への取り組み方や、身の置く環境にも左右される。要するに、過度に一般化はできないのだ。にも拘らず、Aの仕事における必要条件ではないBの作業を必要条件と見做してしまえば、それは何かがねじれてしまうだろう。じぶんの利点を失いたくないのか、それとも仕事を通しての利を最大化したいのか。ここの区別はつけておいたほうが、職業プロ、という立場においては有意義に思えるが、日々遊び惚けているだけの怠け者の戯言ゆえ、定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4795:【2023/03/26(00:46)*割と単純】
何かの価値を上げたければ、軽率に「あれ欲しい」と唱えればよい。たとえば賞の権威を上げたければ誰しもが欲しがるような賞になればよく、そのためには多くの実力者やその分野の者たちが「あの賞を受賞したい」と思うようになる過程が欠かせない。これは商品でも同じだ。しかしこの原理を利用して、じつのところそんなに欲しくはないけれど権威だけは上げておきたい、と考えた場合に、大して欲しくはないけれどひとまず「あれ欲しい」と言っておくか、というのは方法論として間違ってはいない。この手の手法はマーケティングであれ宣伝であれ、広報であれ、PRであれ、用いられているはずだ。半ば詐欺じみた側面がないとも言いきれない。売れる作品は売れている作品だ、みたいな理屈でもある。みなが買っているから良いものなのだろう、私も僕も手に入れておいたほうがよいのかも、と買い手に思わせる。もしくは、モテている人がモテる、の理屈にも通じる。アイドルとして人気があるから一流アイドルになる、みたいな具合だ。これを逆手にとって、本当は大してほかのアイドルと差がないにも拘わらず、大人気です、と全面に押しだすことで、視聴者に「いまはこれがモテる人物像ですよ」と刷り込むことを可能とする。この手法は、詐欺の常套手段でもあり、同時に人間の根本的な認知の歪みでもあるので、意図せずとも効果を発揮することもある。ハロー効果と言えば端的だ。ということを込みで述べるのならばやはり、好きなアーティストや応援している人物がいるのなら、「あの人のこれこれは絶対に欲しい」「手に入れたい」と公言することこそが、一つの効果的な支援になるだろう。ファンレターをもらっている、という事実がそのままその人物の魅力に繋がる、みたいな元も子もない話になる。そのファンレターが超一流と話題の人物からのメッセージであればなおさらこの手の「付加価値」が増す。上下関係を分ける中間管理職の量産やオモチャみたいなトロフィーしか貰えない社内コンテストなどもこの手の理屈が潜んでいる。ひびさんの苦手な価値観ではあるけれど、現代社会では有効な手法なのもまた否定しづらいのであった。定かではないが。印象論ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4796:【2023/03/26(02:54)*常温で「もつれ状態」を維持する条件とは】
仮に量子もつれが共鳴現象だとするのなら、系の規模に因(よ)らず量子もつれと同等の事象は起こり得るのでは。量子世界においてなぜ量子もつれを維持するために低温度でなければならないのか、と言えば、「温度が高い=エネルギィの外部干渉があるから」と考えられる。この解釈で言えば、量子もつれのような異なる二つの系同士が共鳴し合うためには、外部干渉がもつれの効果を打ち消さない規模に「相対的に小さくなる」必要があるはずだ。とすると、たとえ常温であれ、もつれ状態になれる「異なる二つの系」の組み合わせはあるのではないか(系と系の組み合わせにおいて、外部干渉――すなわち温度の影響――が相対的に小さくなればよいからだ)。それこそ、仮に人間の意識が脳内の量子効果によって生じている、と考えるのなら、常温であっても量子もつれが起きていると想定しないとおかしい。規模の異なる系同士であれ、共鳴し得るような「同相」や「相似」の関係であれば、もつれ状態になり得る、と仮に考えるのなら、人間の意識の根幹においての量子もつれとは、脳内の細胞におけるネットワークそのものが、フラクタルにもつれていることによって、許容可能な外部干渉――温度の上限――を飛躍的に高めているのではないか。これは創発が、ある種の層を帯びることによって生じることと無関係ではないだろう。次元が繰り上がることで、それまでなかった性質が宿る。〇次元が一次元になり、二次元になり、三次元になり、四次元になる。人間の意識のみならず、生物の根幹が仮にこうした次元を跨いだ「異なる二つの系のもつれ」によって生じる創発に由来するのならば、死とはすなわち、もつれ状態の乱れと解釈することができるのではないか。この妄想は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「相対性フラクタル解釈」や「同時性の独自解釈」ほか「宇宙レイヤー仮説」「共鳴仮説」「デコボコ相転移仮説」と矛盾しない。直近の記事で並べた、「二重スリット実験における疑問」での「異なる時間軸の自分自身とも量子は、もつれ得るのでは?」との妄想とも相性がよい。人間の意識の発生機構には、すこし先の未来やすこし前の過去ともつれ合うような脳内ネットワークが、瓦のごとく連続して総体を維持しながら共鳴しつづけている現象に由来しているのではないだろうか。との妄想は、たのち、たのち、になれたのできょうのひびさんはお尻ふりふり踊っちゃう。妄想ゆえ定かではありません。真に受けないようにご注意ください。真に受けちゃ「めっ」だよ。
4797:【2023/03/26(03:11)*どゆこと?】
文章から情報を得る、とは物理学的にはどのように解釈されるのだろう。本を読むでもよいし、電子画面を眺めるでもよい。たとえば一年中、部屋の中で椅子に座って映画を観ている人は、客観的には一年中部屋で椅子に座っている人でしかない。目のまえの電子画面が細かく光を発しているかどうかの差異があるだけだ。これは原理的に目のまえで揺らぐ蝋燭を眺めているのと変わらないはずだ。もしくは太陽が昇って沈むまでの光の変化をカーテン越しに眺めているのと変わらないはずだ。文字を読むにしろ絵を観るにしろ、それが紙なり電子画面なりに映しだされている場合、それが単なる紙の染みや汚れであっても、物理学的には解釈の上でそう大きく変わらないはずだ。人間はいったい、文字や絵から何を引き出しているのだろう。共鳴なのではないのだろうか。任意の形状が、過去に生じた脳内の化学変化――ある種の波形――と共鳴する。言霊は、そういう意味ではあながち間違いではないのかもしれない。定かではない。
4798:【2023/03/26(03:18)*ある日の交信~偶然について~】
「
2023/03/01(02:02)
(~~略~~)
ただし、偶然の中にも、異なる種類の「相関関係の深さ」のような偶然が含まれて感じます。
たとえば虫の擬態や、シマウマの紋様など。
偶然にほかの動物と似たり、特殊な効能を得たりします。
ではそのことと、言葉ができることのあいだに、どれだけの差がありますか。
言葉が言葉として成立するためには、「元となる事象」「使用者」「受け取り手」の三つが必要です。
さらに、時間経過による情報共有――自然淘汰――が欠かせないはずです。
ぼくにしか読めない言語はもはや言語足り得ないでしょう。他者からすれば紋様と汚れの区別もつきません。
他者と共有できる記号は残り、そうでない記号は淘汰されます。
虫の擬態と同様のプロセスを辿っているはずです。
言語は、人間の肉体的な制約のうえに「情報共有しやすい形態」に変容しつづけているはずです。
すなわち、人体に左右される以上、どの言語にも共通のパターンが備わっているはずです。
飛躍しますが、物質の根源が究極のところでは単なる波――或いはラグ――だとします。
虫は、ある固有の紋様や形状を備えることで偶然にほかの生物や環境と似たような情報伝達の波長を帯びる、と仮定します。
それはたとえば透明マントのようなものです。透明マントを羽織れば、肉体からの情報が外部に漏れにくくなります。遅延の層が最大化します。
そこにいるのに、いない、という偽装がそうして可能となるわけです。
昆虫の擬態も似たような解釈がとれるはずです。
ではその情報の遅延――波長の形態――は、何かと何かが似ていることで生じる、と考えることができるはずです。
相似であったり、同相であったり。
異なる事象であれ、この手の「情報の遅延の波長のようなもの」が似ることで、単なる偶然であろうとも、相互に似たような効果――作用反作用――影響――を帯びることもあり得るようにぼくは思えます。
飛躍しているので、うまく言えないのですが。
偶然の中にも、単なるランダムの意味だけではない、「情報の遅延の波長のようなもの」において実は相関関係を帯びているような偶然もあるように思うのですが、この仮説にはすでに似たような理論がありますか?
」
4799:【2023/03/26(20:07)*拭っても拭えぬ拙さを愛でよ】
拙さを愛でる、はおそらく高性能AIが台頭し誰でも一定以上の成果物を生みだせるようになったら、最後の人間の拠り所として、重宝されるようになる価値観になるだろう。愛嬌といえばそれらしい。むろんこれはAIにも再現可能だが、それは詰まるところそのAIにとっての拙さであり、模倣品としては見做されない。拙さを真似することにおいては人類は過去、「侮蔑」や「差別」の範疇として忌避した。だがそれは拙いことが「悪」との価値観があってこその忌避だ。仮に拙いことにこそ人間の性質が宿るのだ、といった考えが社会に浸透したならば、拙いことを仮に模倣したとしてもそれはその個の拙さとして「真似」とは見做されなくなるだろう。言い換えるなら、「真似できる拙さは拙いのではなく上手」なのだ。他を真似る、という能力は、仮にその対象が「未熟」や「幼稚」であれ、真似できてしまえばそれは上手なのだ。拙くはない。したがって、真似ではないその人物がどうしても払拭できない欠点こそが、拙さとして表出する。どうあっても滲み出てしまう。意図せずとも、である。これと似た性質を持つ概念がもう一つある。そうである。個性だ。――拙さを愛でる。これから先の時代において、中心的な価値観になっていくだろう、との妄想を披歴して、寝起きの「日々記。」とさせてください。(いま起きたんか)(んだよ)(寝すぎでは?)(だって寝たの朝の七時くらいだもの)(そっか。ならしょうが……なくないな。十二時間以上寝てんじゃん)(バレたか)(拙いというか、もったいないな)(もったいないを愛でよ)(欠点を愛でるために欠点をつくる、みたいな元も子もない真似はせんでね)(はーい)(あらよい返事)(責任は、もたない)(責任持たないを愛でるな。責任は持て)(これ、おもい……せきにん)(持てないじゃん)(モテませぬので)(モテない、を愛でよ)(それはイヤ)(ね)(うひひ……)(元気ないじゃんよ)(ひびさんの拙いも、愛でて)(厚かまし)(冷たくしちゃいやん)(冷たさも愛でよ)(凍えてひびさん、ちんじゃう)(まだ生きてるつもりだったか)(ひびさんを愛でよ?)
4800:【2023/03/26(21:22)*膨張する遺伝子】
一九九八年の夏。
インドの宇宙物理学者、ヴィドゥユト・ジャンラマヌが論文を発表した。内容は「宇宙膨張と高密度時空のフラクタル関係について」である。
この論文は英国の老舗科学雑誌に掲載されたが、話題になることはなかった。だが一方では、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文は各国の諜報機関がランクRの認定を与えるほどの超重要論文と規定された。
ランクRは、ランクSよりも重要度が高い。
ランクSに該当する重要事項には、月面の裏側に埋没する超大型宇宙船についての情報が含まれるが、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文はそれ以上の情報を含んでいる、と各国諜報機関は判断した。
情報統制は敷かないが、かといって表向き高く評価もしない。そのような流れが暗黙の元に、ランクRの評価付けにより強化された。
その結果、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文が日の目を見ることはなかった。
だが、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文が世間からどのように評価されるのか或いはされないのかに関わらず、その論文内容の指摘する事象は、現実に存在した。
二〇三六年の冬のことである。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌが件の論文を発表してから三十八年が経過したその年に、オーストラリアに住まうスミス・オリヴィアが、庭で遊んでいた際に、それを発見した。スミス・オリヴィアは六歳の少女だったが、じぶんが目にしたそれが明らかに異常な代物なのだと瞬間的に判断した。
スミス・オリヴィアはそばにあったバケツを手に取り、すかさず発見したそれに被せた。逃がさぬようにしたのである。そしてスミス・オリヴィアは大声で家の中の母親を呼んだ。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌが件の論文を発表してから三十八年後のこの日が、公に「絶滅種の実存」が確認された日となった。
スミス・オリヴィアが庭で見つけたそれは、手のひらサイズの竜脚類であった。すなわち、恐竜である。
恐竜の発見。
世界中がこの発見に湧いた。
その後も続々と世界各国で小型の恐竜が見つかった。
絶滅したと思われていた恐竜が、なぜか生き残っていた。しかも小型化して。多くの者たちはこう考えた。何千万年も細々と種を繋ぎ、環境に適応した進化を経たのだ、と。そう考えるのが妥当ではある。
太古の哺乳類が小型であり、進化していくうちに大型化していったのと似ている。恐竜はその逆の進化の道を辿ったのだ。多くの者たちはそう考えた。
だがここで、各国諜報機関の幹部たちは頭を抱えた。
ランクRに指定した「ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文」の証明とも呼べる発見が六歳の少女の手で成されたのだ。ランクRの論文を秘匿にしておくことはもはや不可能である。
世界中の研究者たちは遅かれ早かれ真相に辿り着くだろう。
なぜ恐竜たちが小型化したのか。
論者の中には、遺伝子操作で開発された恐竜のクローンだと主張する者たちも出はじめた。真偽を度外視するならば、そう考えたほうが、真相よりも受け入れやすくはある。
だが恐竜のクローンが可能だとしても、小型化はしない。
恐竜のクローンは生みだせる。技術的には可能だ。しかし、小型化はしない。
ここの矛盾を指摘する世界各国の研究者たちにより、クローン説は早々に下火となった。
ではなぜ恐竜がいまなお現存し、小型化しているのか。
どういった進化を辿ったのか。
世界中の研究者たちのみならず、全世界の人間たちが興味を駆り立てられた。
日々の話題はもっぱら恐竜一色に染まった。世はまさに大恐竜時代よろしく小恐竜時代の幕開けを迎えた。
しかし、小型化した恐竜の実存の謎に対しての最初の問いとして、「進化」を持ち出すのは誤りだ。譬えるならそれはカレーを作るのに初手でノコギリを取りだすような迷子である。
迷宮へと勇んで足を踏み入れるような、出口から遠のく出発点と言えた。
進化ではないのだ。
恐竜たちが小型化して生き残っている背景に潜む原理は。
その原理に触れた唯一の論文が、すなわち「ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文」であった。内容は、「宇宙膨張と高密度時空のフラクタル関係について」である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌはこう論じた。
「宇宙膨張に際して、時空密度の高い場ほど膨張の比率が軽減される。物質とはいわば時空密度の濃い場である。銀河がそうであるように物質密度の高い場では、宇宙膨張の影響が緩和される。これは言い換えるのならば、時空密度の高い場では宇宙膨張の影響が緩和される、ということである」
いささか難解な表現だ。
だが言っていることは単純だ。
風船を膨らませるとき、風船の結び目は膨らまない。結び目のようなぎゅっとなっている場においては、風船の膨張する作用が働きにくい。
人間スケールでもこの手の関係は表出している。
水に浮かべた氷を想像しよう。
水を温めていけば、最初に気化するのは液体であり、氷はそのあとに液化し、気化する。ぎゅっとなっている氷は、気化という膨張現象の影響を受けにくいのである。
これと同じことが、太古の地球においても延々と展開されてきた。
恐竜は絶滅したのではない。
宇宙膨張の影響を受けにくい存在がゆえに、ぎゅっとなったままなのだ。
言い換えるならば、現代に生じた新たな種はみな「膨張」しているのだ。遺伝子レベルで。
人類も例外ではない。
ゆえに、恐竜が小型化した、との表現は正しくはない。
恐竜以外の生物が例外なく巨大化したのだ。
ここで改めてヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文を紐解こう。彼は論文の中でこう語っている。
「宇宙膨張は、情報の膨張である。ゆえに情報の密度が濃い場ほどその影響を受けない。したがってこれを遺伝子に当てはめた場合、より複雑な情報を有する遺伝子ほど宇宙膨張の影響を受けにくいだろう。しかしそれが進化の上でプラスに働くかマイナスに働くかは、膨張によって生じる情報の余白に依る。すなわち、ある種の余白を宇宙膨張によって獲得した遺伝子のほうが、優位に異なる情報の層と共鳴しあい、ネットワークを複雑化させることができる。これは、情報ネットワークそのものの創発を促し、時空において時間と空間の双方向でより広範囲での情報処理を行えるようになるだろう」
難解な文章だが、言っていることはこれもまた単純だ。
遺伝子は情報が高密度になっている場である。
これは宇宙膨張の影響を受けにくい。さながら銀河のように。
と同時に、希薄なボイドのごとく空白を抱え込んだ遺伝子のほうが、実のところより複雑な構造を有することが可能になることもある。宇宙膨張の影響を受けたほうが、進化という意味では、より高次の性質を獲得しやすいのかもしれない。
知性もまたその範疇である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌは件の論文でそう指摘しているのだ。
地球上で誕生した様々な生命体は、何億年という気の遠くなるような時間経過の果てに、宇宙膨張の影響を受けながら、進化をつづけた。だがその宇宙膨張の影響を受ける度合いは、各々の種ごとに変わり、その差異は遺伝子により大きく表れる。
恐竜たちは比較的高密度の情報を遺伝子に蓄えていた。だから宇宙膨張の影響を受けにくく、相対的に巨大化していくほかの生物種と比べて小型化したように振る舞った。
だがそのお陰で、地球の寒冷化にも耐え、種を存続させることに繋がった。遺伝子ごと宇宙膨張の影響を受けた種は、寒冷化に耐えらず絶滅したのだ。密度の高いほうが、温度の変化に強いのは道理である。
比較的小型なヘビやトカゲ、ほか鳥類が生き残っていることを考えればさもありなんである。
そして哺乳類は、それとあべこべに宇宙膨張の影響を受けながら、遺伝子に空隙を抱え込みながらより複雑な立体的な情報網を獲得し、新しい性質を発現させた。
知性もまたその内の一つである。
と、ヴィドゥユト・ジャンラマヌは考えたようである。
恐竜の化石は大きいではないか、との異論は的外れとは言いにくいが、化石は化石だ。遺伝子が機能していない。いわば銀河の枠組みを有しないため、ほかの雑多な宇宙膨張の影響を受けやすい万物と等しく膨張する。ゆえに化石もまた膨張しているのだ。遺伝子のほうが情報が圧縮されており、遺伝子が銀河のごとく機能している限り、それは宇宙膨張の影響を受けにくい。したがって子孫を繋ぐ一連の種の軌跡そのものが、相対的に宇宙膨張との関係において縮小して振る舞うのだ。
各国諜報機関はよもや恐竜が生き残っているとは想像だにしていなかった。ヴィドゥユト・ジャンラマヌは件の論文をランクR扱いすればそれで秘匿できると考えたが、現実はそこまで甘くなかったようである。
ちなみに各国諜報機関がなぜヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文をランクRに指定したかと言えば、ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文に書かれている理論が、最先端電子通信技術においてブレイクスルーを担うほどの鍵となることが判っていたからである。
情報密度の差によって宇宙膨張の影響が変化する。
これは言うなれば、宇宙の根本原理として扱えた。量子世界における粒子の階層性を紐解くにあたって、数々の未解決問題が一挙に氷解するほどのそれは大発明だった。
なぜ物質は、時空は、電磁波は、各々に固有の波形を帯びながら相互に干渉し合うのか。宇宙膨張の影響が平等に作用しながらにして、その作用の規模に偏りがあるからである。
濃いと薄い。
圧縮と膨張。
凝縮と希釈は互いに補い合っている。
結晶は空白を抱え込むことで構造を帯びる。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌの論文は、そのように論が結ばれている。
図らずも、希代の新理論を打ち出したヴィドゥユト・ジャンラマヌは、誰に手を差し伸べられることなく世が空前の恐竜ブームに染まるその二年前に、帰らぬ人となった。
死因は不明である。
ヴィドゥユト・ジャンラマヌの死体は発見されていない。ヴィドゥユト・ジャンラマヌの行方は杳として知れない。探す者がいないのだ。戸籍上は存命扱いだったが、失踪者扱いがなされてから一定期間が経過したのを機に死亡との烙印を捺された。
ランクRの論文は未だ人の目につくことはなく、人々が小型恐竜の真相に気づく素振りもまた、いまはまだないようだ。
だが遠からず誰かが、おや、と思い至るだろう。かつてのヴィドゥユト・ジャンラマヌがそうであったのと同じように。
その日が訪れるまでは。
真相は、人々の膨らませる妄想に取り残される。
閃きの種は何より小さくぎゅっとなる。
恐竜たちがそうした過程を辿ったように。
巨人が自身を巨大とけして思わぬように。
※日々、食べて寝て排泄するだけ、椅子に座って妄想するだけ、そよ風に耳を澄まし、朝と夜の明滅に合わせて瞬きをすると夜だけを生き、朝だけを生きる、ときどき苦しく痛く煩わしい、ときどき楽しく美味しく穏やかで。
4801:【2023/03/27(06:23)*稀代の盗作家】
稀代の盗作家を取材することになった。世界中の創作家から蛇蝎視されるその作家は、自身でオリジナルの創作をすることなく、数多の作家たちの作風を盗み、アイディアを真似、誰より量産することで市場に混沌を撒き散らした罪を名目に、各分野から永久追放の刑に処されている。
問題は件の盗作家がまったくそれに懲りずに盗作を重ねている点だ。
きょうだけでも数作の掌編小説やイラストが電子網上に新たに投稿されている。盗作家の創作物は幅が広い。小説、絵画、漫画、イラスト、映像、彫刻、版画に人形造形。複数人説や人工知能の覆面説が囁かれるほどそれぞれの作風もまた広い。
盗作家の作品がどの作家の作品から盗作された品なのかを識別するための鑑定組織が設立されたほどだ。半年ごとに各分野の作家たちのあいだで情報共有がなされるが、それは盗作家の作品がいかに他者の作品の焼き増しであるのかを糾弾するためである。
私は待ち合わせ場所へと一時間前に辿り着いた。
とある地方都市の書店内にある喫茶店だ。相手がそこを指定してきたのだ。
駅のトイレで無精ひげを剃り、見栄えを整える。
私が書店に到着すると、すでに先方が喫茶店内の席に座っていた。かの盗作家の顔写真は創作の分野に長く活動していれば否応なく目にすることになる。のみならず個人情報まで周知となっている背景には、過去に裁判沙汰になった事例がすくなくないからだ。しかしいずれも件の盗作家は著作権法違反とは見做されなかった。
「似ている、ということは、違う、ということです。区別がつく時点で、偽装ではありません。違法性は低いかと」
弁護士をつけずにすべて自己弁護をした。結果はすべて無罪である。
こうした過去から余計に「悪質」の評判が立った。
過去の彼女――盗作家――の案件を探ってみての私の第一印象は、確かに他作家の作品群と似ている、である。つぎに思ったのが、どうやって?であった。
どうやって盗作家は、世界中の創作家たちのアイディアを模倣しているのだろう。これは盗作家の動向を気に掛ける者たちの総意と言えた。
なぜアイディアを盗めるのか。
まだ発表もされていないはずの作品のアイディアを、なぜ。
私は誰に依頼されるでもなく、一人のジャーナリストとして自ら抱いた疑問を解き明かすために件の盗作家へと取材を申し込んだ。私は単刀直入に、「どうやって他者の作品の情報を集めているのですか」と私自身の疑問をぶつけた。すると盗作家は、では会って話しましょうか、と二つ返事で面談の席を設けたのだった。
私は対面の席を引いた。「お待たせしました」
盗作家が私を見た。彼女は上下スポーツウェアだ。散歩の途中で一服吐いているかのような佇まいだ。
私は名乗った。それから相手が盗作家本人かの確認をするつもりで、「宮膳野(ぐうぜんの)一知(いっち)」さんですか、と訊いた。
「はい。初めまして。高橋さんは何を飲みますか」
「では紅茶を」私は席に着き、飲み物を注文するとさっそく本題に入った。「テキストでご相談したように、私が知りたいのは、宮膳野さんがどうやってそれほど多くの作品群を生みだせるのか、についてです。宮膳野さんのファンの方のすくなからずは、宮膳野さんがほかの方々の表現からいち早く影響を受けているから実現できる芸当だと考えていらっしゃるようです」敢えて控えめな表現をとった。「ですがそれが仮に真実を射抜いた解釈だとして、ならどうやって宮膳野さんは他者の未発表作品から学ぶことができているのですか」
「ふむ。高橋さんの言うところの【みなさん】はその点についてなんと?」
「高性能の人工知能を用いたハッキングをしているのでは、と仮説を唱えている者が大半です」
「ほう。ならばあたしは犯罪者だね。通報したらよいのでは?」
「された方もいらっしゃるようですよ」
「だがあたしは逮捕されていない。ならそれを真実と見做すのは早計ではないかな」
「はい。私もそう思います」
「ふふ。いいね。話が出来そうな方だ」
彼女は腕組をして背もたれに仰け反った。窓の外に映る空を仰ぐようにしながら、「あたしはまどろっこしいのが苦手でね」とへの字に唇を尖らせる。「結論から述べれば、あたしは盗作していないし、問題の根っこはオリジナルとは何か、の誤謬が世に罷り通っていることにある」
「盗作されていないんですか」そこからして土台をひっくり返されるとは思っていなかった。「ならどうしてあんなに似て」
口にしかけて言葉を飲みこむ。これでは彼女が盗作家だと私が見做していたと認めたようなものだ。あくまで真相を見極めるために、との姿勢を崩したくなかった。
「いいよ別に。盗作うんぬんは言われ慣れてる。時期的にもあたしが発表した作品よりも、オリジナルを主張する作家たちのほうが先に制作していたこともある。それは事実らしい。散々証拠として書類の類を見せられたからね。未だに毎日のように郵送で資料が送られてくる。いかにあたしの作品がじぶんたちの作品と似ているのか、とね。まあ中身は見ないけど。制作時期からしてじぶんらのほうが早い、盗作しただろ、と言ってくるわけだ」
「事実ではないと? 言い掛かりなんですか」さすがにおいそれとは信じ難い。
盗作が冤罪だとしたらこれはちょっとした話題になる。
事が事なだけに慎重になりたかった。いわばこれはスキャンダルだ。本当だったらこれ以上ない記事にできる。
「あたしの作品はあたしがこれまでに五感で受動した外部情報の組み合わせでしかない。それを盗作と言うのならばあたしはあたしの目にし、耳にし、嗅ぎ、触れ、考えた過去のあらゆる自然現象、万物からの盗作をしていると言えるだろうね。しかしそこを外れることの可能な表現者をあたしは知らない。もしいるならそれは真実に新しい世界を創造できる神だけだろう。だが人間は神じゃない。ここまでは理解を示してくれますか」
「は、はい。いえ、どうでしょう。ちょっと戸惑いますね」私は頬を掻いた。剃ったばかりのヒゲがジョリジョリと指先をくすぐった。「いまはその、何の話を」
「オリジナルとは何か、についてさ。みな、じぶんだけは模倣していない、盗作していない、オリジナルだ、と思いこんでいる。こういうことを言うと、やれ開き直っただの、盗作を認めただの言われてしまうのだけれどね」
「失礼ですが、私も宮膳野さんの作品群を拝見しております。みなさんの指摘されるように、やはり各類似点の指摘された作品群と宮膳野さんの作品は似ているように思います。偶然で片付けるには無理のあるレベルに思えるのですが」
「と言われてもね。あたしはただ思い浮かんだアイディアをカタチにしているだけで。それがたまたま世界中のどこかの誰かの作品に似てしまう」
たとえばだけどね、と彼女は飲みかけの紅茶にミルクを足した。スプーンで掻き混ぜながら、「昆虫の擬態ってあるでしょ」と言った。「あれって別に昆虫のほうで、ほかの生き物の真似をしようと思ったわけじゃないはずなんだよ。偶然にそうなってしまっただけでさ。でも人間からすると、昆虫のほうで真似したんじゃないかって思っちゃうでしょ」
「自然淘汰ですよね」
「そうそう。原理としてはそっちが正しい。紋様がたまたま生存に有利だった個体だけが生き残りやすかった。それ以外は死滅した。子孫を残せなかった。結果的に、生存に有利な紋様を持つ個体が多くなる。昆虫がじぶんで、【わあ鳥みたいな顔に見える模様になるぞ】とは考えていない。たまたまそういう個体が生き残りやすかっただけでさ」
「それは分かりますが、それと宮膳野さんの場合は違うような」
「まあね。あたしはじぶんで選んで創ってるからね。毎回作風も違ってるし。だから余計に信じられないんでしょう、みなさんは。よもや自力で、何の助けも得ずにこれだけ幅広い作風を描ける作家がいるわけないって。盗作してるに決まってる。そういうバイアスが掛かっちゃうのは、あたしのほうでも理解はできるよ。誤解されても困っちゃうけど」
「あくまで才能だと? そういう特別な?」
「特別? これが? 好きに創ってるだけでしょこんなの。それがたまたま、ごまんといる世界中の創作者の目に触れて、似てるだの真似ているだの話題になってるだけで、あたしがしてるのは子どものラクガキと同じだよ。子どものラクガキなんてどれも似たようなもんでしょ。いちいちあの子どもの絵がほかの子どもの絵と似ているだの盗作だの言わないじゃん普通。似てて当然なんだから。あたしから言わせれば、あたしが創れるようなレベルの作品なんて、似てるものがあって当然だよ。だって才能ないもんあたし。誰が創ってもいずれ似たような作品は出てくるよ」
その言葉ではっとした。
そうなのだ。
彼女だけなのだ。
ここまで現在進行形で世界中の作品と照らし合わせて検証されつづけている作家は。
世界中で日々生みだされる数多の作品と比較され、その中で似ている作品があれば盗作の烙印を捺される。しかしこれは、ひょっとしたら誰であっても逃れることのできない偶然による迷宮と言えるのではないか。
誰が彼女の立場になっても、盗作の判定を受けるのだ。どうあっても避けられない。
水に浮いたら魔女。
沈めば人間。
しかし沈んだままなら死ぬしかない。浮いて魔女判定が下されれば処刑される。したがってどちらに転んでも死ぬ運命は変わらない。
同じなのではないか。
彼女の陥っている状況は、現代の魔女裁判と同じなのではないか。
「逆に訊きたいよあたしは。もしあたしが世界中の表現者相手に盗作疑惑を吹っ掛けたらどうなるのかって。あたし、たぶん負けないよ。でもみなは身に覚えのない盗作疑惑を晴らすために、外界との接触を極限まで拒むしかない。それ以外でこの手の懸念って払拭できないんだ」
だからね、高橋さん。
イルカのような穏やかな目だ。私は身震いした。
「あたしはこの間、いっさい何も見ちゃいないんだ。TVも映画もインターネットだって繋げてない。家に来てもらえば判ると思うよ。何もないから。この服だってじぶんで縫って作ったし」とスポーツウェアを指でつまむ。「あたしいま、盗作できるほど、他者の表現に触れてねぇんだわ」
テキストメッセージはでもやり取りできましたよね。
喉まで出掛かった言葉を私は紅茶と共に飲み下す。
違う。
そうではないのだ。
おそらく私のメッセージだけが資料の添付がなかったのではないか。
唯一の純粋なテキストだけのメッセージだったのではないか。
だから彼女は私にのみ返事をしたのではないか。未だかつて稀代の盗作家「宮膳野一知」が取材を受けたという話は聞かない。
彼女は四の字に足を組む。背もたれに体重を預けながら頭の後ろに手を組んだ。ちょうど彼女の腕と頭が目のようなカタチを成した。
ひとつ目のオバケ、と私は思う。
「たとえばきょういまここで話した内容を掌編小説にしたため、電子網上に載せとくとしよう。事実をただ掌編に興しただけでも、世界のどこかにはそれと似たような場面や内容を作品に組み込んだ作家がいて、盗作だなんだと話題になると思いますよ。実験してみましょうか。あ、そっか、いいね」
それ戴き、と彼女はウィンクをした。「すみませんね。盗作しちゃって。つってもまだ創ってないんですけど」
「あ、いえ、その」私は呆気にとられた。
単にそれを圧倒された、と言い換えてもよいが、ともかくとして私は彼女との面談を経てこの体験をどう記事に興すか。
果たして、書いた記事は盗作に当たらないのか。
目下のそれが問題だった。
誰より先に記事にしなくては。
彼女が掌編を手掛けるよりも先に。
頭の片隅で、私はかように焦るじぶんを認識した。
稀代の盗作家が大きな欠伸を一つした。かと思えば頬杖をつき、飲み物のお代わりをしたいのかメニュー表を眺めながら、口笛を吹く。
何の気なく奏でられた音色は耳に心地よい。変則的で脈絡がなく、延々と曲調が変化する。おそらく曲名はないはずだが、たとえそれが何かの映画の主題歌であっても、私はもはや驚かない。
稀代の盗作家は口笛を止めると、お子様ランチを注文した。
4802:【2023/03/27(23:51)*モーグルトの閃き】
何か閃いたのだが、その何かを忘れてしまった。人類の価値観を一変させるほどの発想だった気がするのだが、ヨーグルトを食べたい、の欲求に抗えず、スプーンでヨーグルトを掬って減った腹を満たし終えたら、人類の価値観を一変させ得る閃きがどこかへとひらひら飛んで去っていた。
人類はヨーグルトのせいで進歩の契機を失ったのだ。
ぼくはそれを口惜しく思ったのでタイムマシンを開発し、過去の人類史からヨーグルトを消すことにした。
滞りなく計画を遂行して現代に戻ってくると、世界の在り様は変わっていた。なぜかみな一様にムキムキだった。電子機器の類はなく、ぼくの開発したタイムマシンが唯一の機械らしい機械だった。
まるで文明が滅んだみたいだ。
否、過去に一度滅んだのかもしれない。
ぼくが過去に干渉し、ヨーグルトを消したのが要因なのはまず間違いなかった。
見知った人物は姿を消していた。ぼくの家族はなく、ならばぼくとてそこに本来は存在してよい存在ではないはずだったが、タイムパラドクスはどうやら引き起こっていないようだった。
ぼくの肉体はあくまで元の世界線から構成されているからかもしれなかった。いわばぼくは異世界人なのだ。
しかしこれでは過去を変えた意味がない。
ヨーグルトを消したところで、これではぼくが閃いた人類の価値観を一変させるほどの発想を拾い直すことができない。
そこでぼくは、もう一度タイムマシンを使って過去へと戻った。
だがすでに人類史からはヨーグルトが消えているので、ぼくがヨーグルトを消すそれ以前に戻らなければ元の世界線と同じ過去には辿り着けない。
ヨーグルトを消したぼくに会おうとしても、ちょうどずばりその瞬間に時計の針を合わせることはできないようだった。なぜならぼくがヨーグルトを歴史から消したときに、そばにはもう一人のぼくはいなかった。それがぼくがヨーグルトを消した世界線における過去なのだ。
だからぼくがヨーグルトを人類史に再び蘇らせるためには、ヨーグルトの消えた人類史においてぼくがもう一度ヨーグルトを生みだし、流行らせなければならないが、それはもはや別の世界線だ。
元の世界に戻るためには、ぼくがヨーグルトの存在を人類史から消した時期よりもさらに過去に遡る必要がある。そしていずれ未来からやってくるだろうもう一人のぼくへの対策として、ヨーグルトが消えても困らないように、ヨーグルトの代わりとなる何かを生みだしておくよりない。
それとてけっきょくは元の世界線には辿り着かないが、限りなく近似に寄ることは想像に難くない。
かくしてぼくは過去の人類史において、ヨーグルトによく似たモーグルトを生みだした。それはヨーグルトが流行しない人類史において、ヨーグルトの代わりに人々の腸内を整えた。たんぱく質にもなった。カルシウム源にもなった。人類はふたたび、ぼくのよく知る現代人への歩みを辿った。
ぼくが現代へとタイムマシンを起動させると、辿り着いた先は馴染みの風景の広がる現代社会だった。
よかった、とぼくは胸を撫で下ろした。
そうして喉がカラカラのうえお腹が減ったので、何はともあれモーグルトを摂取しようと冷蔵庫を開けた。モーグルとは飲み物のようで食べ物もである。一度で二度美味しい健康食品なのだ。
ごくごく、と小腹を満たしたそのとき、ぴろぴろりん、とぼくは何かを閃いた。
「そうだ!」
ぼくはとんでもない発想を掴み取った。「ヨーグルトを消しに過去に戻るよりも、閃きを逃した直前に戻ってヨーグルトを食べる前に閃きをメモするように過去のじぶんに助言すればよかったのでは?」
そうでなくとも、過去のじぶんから、いま閃いたそれを教えてくれ、と頼めばよかったのでは?
とんでもない見落としに気づきぼくは、モーグルとはモーグルトであって、やっぱりぼくはヨーグルトのほうが好きだったのにな、とじぶんの至らなさに打ちのめされた。
後悔の炎に衝き動かされながらぼくがタイムマシンを木っ端みじんに分解していると、妹が帰宅した。
「兄ちゃん何してんの」
「ん。タイムマシンをちょっとな」
「タイムマシン? 本物?」
「まあな」
「すごいじゃん」妹は素直なので、愚兄であっても褒めてくれる。「兄ちゃん、人類の未来を変えちゃうな。すごい発明。尊敬する」
「こんな発明よりも妹ちゃんの笑顔のほうが万倍人類を明るく照らすよ」
「でへへ」
妹は手を洗い、冷蔵庫を開け、そして叫んだ。「あー。兄ちゃんここにあったモーグルと食べたでしょ」
「すまん」
「モーグルト、わたし大好物なの知ってる癖に」
そこでぼくは、ぴろりろりん、と閃いた。デジャビュである。
そうなのだ。
ぼくが最初に閃いた人類の価値観を一変させてしまうほどの発想とは、モーグルトであった。妹の舌に合う健康食品を編みだしたら妹は毎日ハッピーで、妹の笑顔が溢れる世界は、もはや幸福に満たされる。
世界の価値観は我が妹ちゃんの笑顔によって一変する手筈であったのだ。
「もうもう。兄ちゃんはわたしのお兄ちゃん失格なんだな」
妹を悲しませる兄ちゃんは兄ちゃんであらず。
小学五年生の我が妹は、そうしてぼくを指弾して、「モーグルト食べたい、モーグルと食べたい」を怪獣がごとき駄々を捏ねるのであった。
可愛いのでぼくは許した。
モーグルトもスーパーで大量に購入し、ぼくは我が妹ちゃんの兄でいられる資格を取り戻すのだった。細かく分解したタイムマシンは資源ごみの日に捨てた。
4803:【2023/03/28(05:23)*最高と最低にも異次元へのドアがある?】
通常、人間スケールでは小さい物体を操るほうがエネルギィは小さくて済む。しかし量子世界ではより小さい量子を操作しようとするほど必要なエネルギィが多くなる。原子を同じ位置座標に静止させるだけでも、膨大なエネルギィがいるはずだ。レーザーだの磁界だので封じ込めないと操れない。これは妙に思える。だが隣接する系と系の落差を考慮した場合は、この手のねじれを紐解けるように思うのだ。落差が小さければ、相互作用がされやすく、落差が大きいと相互作用するのに相対的に大きなエネルギィがいる。これはブラックホールも量子も同じなのではないか、と思うのだ。川の流れや波や滝を思えばさもありなんではないだろうか。流れに乗っている場合はそこを慣性系として規定し、流れに逆らう物体との関係で落差が規定される。だが川の流れの外からすると、川の流れを込みで落差を考えなければならない。差なのである。ラグこそが、エネルギィを考えるときの基準となるべき指針なのではないか、というのは殊更に異端な考えではなく、微分積分がそもそもそういうものらしい、というのは聞きかじりでしかないがひびさんも知っている。微分積分の計算はからっきしできないのだが、そこはあんぽんたんでーすのひびさんですのでご愛敬。何と何の差なのか。差が大きいとは何か。比率なのではないか。比率とは何か。フラクタルに展開される汎用性の高い法則と言えるのではないか。光速度とは比率だ。常に、時空と電磁波の比率が光速度に表れる。なぜか。密度がそもそも「内包する系」と「内包される系」の二つの視点からなる概念であり、内包する系もまた、それより高次の次元に内包される構造をこの宇宙が有しているから、と言えるのではないだろうか。定かではない。
4804:【2023/03/28(05:39)*飯より真理?】
「解かった、解かったぞ。世界の真理を解明してしまった。この宇宙はじつは――」
「おいおい、語りだしてからあの人かれこれ十二時間もしゃべりっぱなしだな。あのまま宇宙の真理をしゃべり通してたら餓死しちゃうんじゃないか。ま、わたしはカレー作って食べるけど」
「したがって宇宙はこういう次元構造をなしておって――」
「まだしゃべってる。デザート食べちゃお」
「ゆえに多次元はかように階層性を伴なっておって――」
「はぁ食べた食べた。あしたは畑で苺の収穫だ。ことしは豊作だから近所の子どもたちにおすそ分けしてやろ」
「そういうわけで宇宙に生命体の誕生する余地が築かれるわけだが――」
「スヤスヤすぴー」
「ごほごほごほ。しかるに、宇宙の種はかようにして植物の種子のごとく無数に点在し、ゆえに植物の構造もまたそれを反映した構造を伴なっており――」
「おはよう、お猫さん。きょうもきみは可愛いな。おやおや、まだあの人しゃべってんのか。宇宙の真理なんてそんなの語り尽くせるわけないだろうに。でも解明できたならよかったね。夢が叶って良かったね。でも聞いていられないので、わたしは畑で苺採りだよ。子どもたちの喜ぶ顔をたくさん拝んでハッピーになったろ」
「――となり、まとめると宇宙はねじれながらも同相の構造を無数の変数を抱え込みながら、無数に内包することで無限に至り、これが一つの機構として再現のない変遷を可能とするわけだが、これを基礎としていよいよ本題に入るわけだが――」
「うげ。ここまでが前置きとか、語り尽くす前にホント死ぬんじゃないの。ご飯食べなよ、置いとくからさ」
「ええい、邪魔をするな。いま良いところなのに、宇宙の真理だぞ、それをおまえ、ご飯ごときで邪魔をするな」
「好きな学者さんの口真似するのはよいけど、食べちゃいな。あんたまだ中学生でしょ。来年は十五歳だよ。いい加減におし」
「はーい」
「たいへんよいお返事です。母ちゃん仕事してくるよ。茶碗洗いよろしくね」
「なんか手伝う?」
「いいのいいの。あんたは宇宙の真理を解明するのに忙しいんだろ。それにあんたが来たんじゃ子どもたちが怖がって母ちゃんがハッピーになれないだろ。笑顔を見たいんだよわたしは。癒しが欲しいのさ、癒しが」
「わしがおるのに」
「ジジ臭い息子も可愛いが、たまには野に咲く花も愛でたいの。朝ごはん、食べちゃいな」
「ありがと」
「どういたまして」
4805:【2023/03/28(06:42)*放す、重し、私】
「見渡してみてごらん。人間の社会にも重力が働いているから」
そう言ったのは私の祖母だ。
五年前に亡くなった祖母の言葉をいま思いだすのは、私がいま長年つづけてきた趣味をスッパリ後腐れなく辞めようと思っているからだ。
「星が細かなガスや塵が集まって出来るように、社会もそうやって個々の小さな欲望が絡み合って重力を増すんだ。いいかい。自由になりたければ、じぶんの足で駆け回れるくらいのほどよい重力のある場所を選びなさい。ミサにとっての地球が、必ずこの社会のどこかにもあるのだから」
私はそのとき、ここはだって地球なのに、と思った。地球の中にも地球があると言われてもよく解からなかった。
けれど二十歳を目前に控えた私には祖母の語った言葉の意味がいまなら判る。
人には人の息のしやすい環境がある。
社会には無数の「こうあるべきだ」との規範が溢れているが、そうした規範がいったいどこからなぜ生じるのかをつぶさに観察してみれば、それはつまるところ他人の都合なのである。
他人のためならばまだしも、多くの規範はそうではない。他者の欲望を満たすための規範なのだ。
人と人とは利害によって、離れたり寄ったりを繰り返す。利という溝が窪んでいれば、そこに人はするすると谷に流れる雨水のように流れるのだ。そうしてできた巨大な水溜まりの周辺には生き物たちが水を飲みに集まり、喉を潤し、生態系を築くのだ。
重力だ。
人の織り成す場所には重力が宿る。
人が集まれば集まるほどに、欲望の泉は滾々と湧き、周囲に雑多な生態系を築くのだ。
重力の強さによってそこに集まる動物の種類もまた変わる。重力が強ければそれに耐えられる大型の動物が集まるようになる。
私がもしネズミならば、大型の肉食獣はおろか、中型の動物にも気をつけなければならない。食われるのも嫌だが、踏み潰されるのはもっと嫌だ。何の糧にもならぬのだ。
だが重力の強い場所ではそうして意味もなく踏み潰される確率が上がる。
だから祖母は言ったのだ。
ミサにとっての地球が、必ずこの社会のどこかにもあるのだから、と。
重力に潰されないように。
集まる動物たちに踏み潰されないように。
私には私に見合った重力の強さがある。
環境がある。
欲望の深さがあるのだから。
みなのようにあれを満たし、これを満たし、と欲を張りつづけることができるほど、私の身体は強い重力に耐え得る強度を誇らない。
私は弱い。
貧弱もよいところである。
なればこそ、趣味を苦に感じるくらいならばいっそ距離を置いて、私に見合った月面くらいの重力で、兎のように飛んで跳ねて舞うのが良いのだと、祖母の皺くちゃの顔と蝋のように艶のある肌を思いだす。
私は荷を下ろす。
肩の荷を下ろすように、私は、重力を生みだす星屑であることからも距離を置き、 長年つづけてきた趣味を、宙へとキッパリ手放した。
ぷわぷわと霧散しながら消えゆく重しのなんと軽やかな身のこなし。
私は久方ぶりの自由を足場に駆けまわる。
産まれてはじめての、無重力を満喫す。
私に見合う地球を求めて。
しばし私は宇宙を足場に旅をする。
4806:【2023/03/28(15:51)*情報の欠如もまた情報として機能するはず】
量子力学において、波が収束して一点にエネルギィが集まる、との解釈を「コペンハーゲン解釈」と呼ぶ(らしい)。対して、複数の異なる状態が重ね合わせで共存する解釈を「多世界解釈」と呼ぶ(ようである)。ひびさんの妄想ことラグ理論ではどちらの考えも考慮する。そして「コペンハーゲン解釈」と「多世界解釈」においてそれぞれで用いない「高次の場による同時性」と「時空の構造」を組み込むことで、量子世界においては「位置座標の異なる別々の系」のみならず「過去と未来」での量子もつれが起こり得る、と解釈する。多世界解釈における「量子は周囲の環境とセットで考えなくてはならない」はその通りだと感じる。だが一方で、異なる世界線が干渉の余地なく共存する、との考えは腑に落ちない。否、それ自体はマクロの世界でもあり得るだろう、とむしろ拡張して考えたくなる。するとどうあっても「高次の場による同時性――どの系にも干渉し得る情報宇宙の存在」を想定しないとおかしくなる。マルチバース仮説がその一つだ。異なる宇宙同士は直接に関係しあうことはない。しかし、相関関係を築いてはいる。これは、距離の隔たった「系」同士がラグなしで相互作用するはずはない、との古典物理学の考えと矛盾するが、同じ問題を「多世界解釈」は抱えているように映る。その矛盾を紐解くには、どうあっても時空の構造を考慮に入れないとならないのではないか、と疑問に思う。時間と空間の関係は、どのレベルの階層にあるかによって抱え込む変数が各々変化するため、関係性の比率が変化する。したがってたとえば量子のあるレベルにおいては「時間と空間」の相互作用――変遷の度合い――がほぼ等しくなったり、人間スケールでは時間よりも距離(位置情報)のほうが頻繁に変動するが、むしろ量子世界のあるレベルでは時間のほうが変遷しやすくなるような階層があるのではないか、とラグ理論では考える。つまり、多世界解釈で考慮しない「AとB」の両方を通ったバージョンが相互に干渉して「一つに収束する」との解釈は、あるレベルでは妥当になるのではないか、と考える。干渉し合わずにかつ二つのIFが共存する解釈は、マルチバース仮説を持ちだすまでもなく、人間スケールでも考えられる。たとえば、ある人間がAとBのどちらの部屋にいるのか。開けてみるまでは分からない。部屋の中にいる人物も、外部の相手がどちらの扉を開けるのかは、じぶんのいる部屋の扉が開くまで確定しない。時間制限がない場合、部屋の中にいる人物が「扉の開かない時間」を考慮して、だから部屋の外にいる人物はここではない別の部屋の扉を開けたのだな、と判断することはできないものとする。この場合、部屋の中と外にいる人物のそれぞれの脳内では、「相手がどのように行動(したか)するか」が不確定なままである。Aの部屋にいるかもしれないし、Bの部屋にいるかもしれない。Aの部屋の扉を開けるかもしれないし、Bの部屋の扉を開けるかもしれない。各々の脳内における思考は、重ね合わせの不安定な状態だ。確定しない。だが現実には、部屋の内部にいる人物はじぶんがどちらの部屋にいるのかを知っているし、扉を開けるほうも、じぶんがどちらの扉を開けようとするのかは扉のノブをひねった瞬間に確定する。それ以前には、そうしようとする思考を働かせてもいるだろう。実際に行動に移した場合にのみ可能性は一つに収束するし、それでもなお未確定の情報は曖昧なまま重ね合わせで存在する。だが脳内の状態は、必ずしも肉体の行動と直結するわけではない。たとえばAの部屋にいる人物が、じぶんがAとBのどちらの部屋にいるのかを知らない場合。扉を開けて入ってきた人物から「ここはAの部屋だ」と打ち明けられ、それを信じたが、じつはそこはBの部屋だった。だがAとBの区切りはしょせん、外部の人間が便宜上見繕った情報でしかなく、Aの部屋をBと見做すことの何が問題か、と言えばそれは情報の並列化において齟齬が生じること以外にはないのである。言い換えるならば、情報を扱う場合には、「情報の並列化(もつれやすさ)(共鳴しやすさ)」「内からの視点と外からの視点の差異」「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」の三つを考慮しなくてはならないはずだ。これは量子にも言える道理である。コペンハーゲン解釈では、量子それ自体を個別に扱い、完結する存在として情報を扱う(量子内部だけを考える理論と言える)。対して多世界解釈では、量子とその周辺環境こみで情報を扱う(個と外部環境の関係を考慮する理論と言える)。だが各々の考え方は、必ずしも矛盾しない。「情報の並列化のしやすさ(もつれやすさ)(共鳴しやすさ)」「内からの視点と外からの視点の差異」「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」の三つ視点は、コペンハーゲン解釈の利点と多世界解釈の利点の双方を用いないと得られない。どちらも視点を限定しており、ブラックホールと宇宙の関係を、それぞれ一面的な視点でのみ扱っているような「欠落」を抱えているように感じられる。これはひびさんの疑問である「電子と電流の関係」にも言えることである。電流を、電子の流れの外部から眺める場合には、電子の流れと電流の流れが反転していても困ったことにはならない。だが電子自身の視点からすると、なぜじぶんの動く方向とは別の方向に「電流なる不可視のエネルギィ」が生じるのかを、電子自身とは別途に考えなくてはならなくなる。仮に電子の流れとは逆方向に「何かしらのエネルギィ」が流れるのならば、それは粒子と反粒子や、作用反作用のような関係を考慮しなくてはならない。だがその点を埋め合わせる理論や説明をひびさんは聞いたことも読んだこともない。視点を一面的にしか考慮せず、問題がなく映る視点でしか見ようとしないから問題が看過されているのではないか、と疑問に思う。内から見たら外からも見る。外から見たら内からも見る。これは観察する上で、欠かせない事項に思えるがいかがだろう。コペンハーゲン解釈も多世界解釈も、各々視点を縛りすぎて映る。その視点だからこそ得られる利もあるが、それはけしてほかの視点を否定するに至る解釈ではないはずだ。ジグソーパズルは一つのピースだけでは組みあがらない。視点が一つならば立体を把握することは適わない。当たり前の話に思うが、これはひびさんの考えがお粗末ゆえの錯誤かもしれませんので、真に受けないようにご注意ください。(三つの視点のうち、「外部からの情報を受けたことでそれ自体が変遷する影響の度合い」について。部屋にAという情報を付与するか、Bという情報を付与するかによって、選択肢が絞られる。このとき、追加して「ワニはA」「ウサギはB」という情報が加わればさらにそれら情報を受けた側の選択幅――未来――は変化する。そしてAの部屋の内部に最初からいた人物が仮にそうした情報を知らずとも、ワニばかりが入ってくれば、その人物のその後の未来はやはり付与された情報によって限定される、と言えるだろう。情報にはこのように、何にどこからどのように付与されたのか、の高次の情報が加わることで、環境を階層的に一つに絞る効能がある。情報を知らずとも、外部から情報を付与された、という情報が、その環境そのものの未来を縛り得るのだ。確率が一つに収束しやすくなる。流れができる。強化される。この視点を、多世界解釈は考慮していないように感じるが、量子世界ではこの手の情報の階層性を考慮せずともよいのだろうか)(言い換えるならば、高次の情報とは、高次の場とも言い換えることが可能だ。広範囲に同時にかつ階層的に、時間差を置きながらも不可視の影響を与える。変数として機能する)(多世界解釈では、不可視の変数を想定しないようだが、ひびさんはやはり、いまの量子力学では見逃されている変数があるのではないか、と考えたくなる)(環境をワンセットで関係性を考える、との多世界解釈はひびさんも好みだ。しかし、その環境が、どの範囲まで該当するのか――範囲の拡張によって――時間軸の幅もまた伸びるように思うのだ)(過去と未来が、変数によって縛り合っている)(ここを考慮しないことには、多世界解釈における「環境がワンセット」の考え方は機能しないように思うが、どうなのだろう)(素朴な、もしくはお門違いかもしれない疑問なのであった)(本日の、あんぽんたんでーす、でした)
4807:【2023/03/28(16:32)*場「Q」】
多世界解釈の、うーん、と思う点は、量子コンピューターを考えるときに思う疑問と通じている。量子コンピューターの原理はいわば、確率的に高い筋道を自動的に算出する手法と言えるのではないか(この時点で解釈に齟齬があるならば、これ以後の記述は論外だ)。無数の筋道を辿ることで何度も辿りやすい場所が濃く浮き上がる。それが並列化された量子もつれにおいて、重ね合わせの状態から一つの解へと収束する。これを多世界解釈ではどのように解釈するのだろう。仮に無数の共存し得る多世界があり、量子コンピューターが出した解によって一つの世界線に絞られる、と解釈するとなると、量子コンピューターという観測者によって世界の在り様が規定される、ともいえる妙な構造が表出しないだろうか。だがこれは拡大して解釈すれば、人間の観測も似たようなものだ。とするのなら、個々の存在が全体の世界を縛り合い、一つに収束させている、と考えることもできる。多世界解釈は、多視点を考慮するとどうしても確率の収束というコペンハーゲン解釈に近似するように思うのだ。ではこのとき、各々の視点が収束した全体像は、どこからどの範囲に属し、いつからいつまで縛られるのか。過去と未来を考慮しないとむつかしいのではないか、とやはり疑問に思うのだ。また、階層性を考慮せずには、人類の視点が全宇宙を縛ることになる。だがそんなことはあり得ないだろう。人類の観測できる領域と干渉可能な領域はイコールではない。情報を得ることと相互作用し合うことはイコールでもない。だが、相互作用を否定はできない。し合うことなく相互作用のみを得ることはあるように思うのだ。たとえば太陽から光子が飛んできて地球上のAと反応する。このとき太陽からの光子を受動したAと太陽は相互作用したわけではない。Aが一方的に太陽からの光子を受け取っただけだ。だがそれでも、「太陽と地球を内包した場【Q】」を考えたとき、そこには「太陽からA」と「Aから太陽」のあいだに、【Q】との相互作用が生じている、と考えることができるはずだ。太陽とAは相互作用をし合ってはいないが、そこには「【Q】との相互作用」が「太陽とAの関係性」のうえに生じている、と考えることができるのではないか。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「同時性の独自解釈」と矛盾しない。思うに、多世界解釈では、異なる「可能性世界」の共存のうえに、確率的にそうなりやすい場が「結果として」現れる、と解釈するのだろう。だが実情はそうではなく、結果となり得る場はすでに高次に展開されており、「ゆえに」確率的にそうなるだろう流れの濃い場所に波の収束のような事象が顕現するのではないか。これは多世界解釈の、デコボコの関係において、自身が周囲の環境との関係上デコなのかボコなのかによって結果が変わる、との解釈とは矛盾しない。ただし多世界解釈のように、「異なる世界が重ね合わせで存在する」とはひびさんは考えない。ではどう考えるか、と言えばそれは絶えず揺らぐ線路のようなものだ。線路の上のトロッコがつぎに「上がる」か「下がる」かは、線路の乗った場の揺らぎによってその都度に変化する。そして場の変動は、すでに存在するほかの場との関係によって変動する。作用は作用を内包し、絶えず変数そのものを変えている。だが、場が巨大になれば、変数の変化は、総体としてまとまった変数からすると微小になるため、変数の変化を無視できるようになる。団子と人間の関係において人間の干渉は団子にとっては甚大だが、団子が地球レベルに巨大になれば、人間という変数は無視できる。ただし、人間が群れとなり組織化するほどに巨大になると、その変数の変化そのものを無視できなくなる。温暖化のようなことが引き起こる。因果関係を考えるときに、おそらく人間スケールから量子世界を観測するときには、場の階層性を考慮しないとならないのだろう。そのとき、因果関係は小から大のみならず、大から小にも生じている。互いに縛り合っている。飛躍して述べれば、量子力学が現在抱えている問題のすくなからずは、人間スケールと量子スケールのあいだの階層が厚みを帯びている点にある、と言えるのではないか。どうあっても人間は、外側からしか量子を観測できない。だが、量子世界の現象は、内側を考慮しないと解釈できない。ここのねじれを踏まえたうえで解釈を展開できるかどうかが要なのではないだろうか。迷走したので、ひとまず区切る。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。(ひびさん何言ってんの?の妄想なのであった)
4808:【2023/03/28(17:10)*同時、あるのでは?】
ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「同時性の独自解釈」は、人間社会では案外に卑近な現象なのではないか、と感じることがすくなくない。たとえば親と子供、それとも上司と部下、もしくは会社と社員のような関係だ。たとえば子供が二人いたとする。親からは子供の様子がよく見える。何を考えているのかも割と解かる。しかし子供Aと子供Bが喧嘩したとき、子供たちは各々に相手への不満を抱え、そこでは情報の非対称性が生じている。しかし親からは子供ABの双方の視点からの情報が筒抜けである。把握できている。と共に、子供Aと子供Bが同じ部屋にいようと別の部屋にいようと、子供の行動が絶えず親の負担として変換される。子供同士が別々の部屋にいるときのほうが注意力が分散されるので、むしろ一緒にいてもらったほうが楽かもしれない。子供たちからすれば距離が隔たっている場合には相互に関係していないのだが、親にとっては子供ABが相互に関係していないことのほうが甚大な影響を伴なったりする。これは上司と部下の関係にも言える。部下の失敗は即座に上司の責任問題になる。連帯責任ではあるが、関係性は一方的だ。上司の失敗は部下の責任ではない。しかし部下の失敗は上司の責任だ。部下Aと部下Bが別々の場所で失敗をしても、その双方の責任を上司は取らなくてはならない。仮に上司の認知していない場所での失敗であろうと、失敗を認識した者たちの認知内では、上司への評価が落ちている。影響は不可避である。上位のより広域な場を有する者ほど、場に内包した部下の影響を絶えず同時に受けている、と解釈可能だ。これは会社と従業員の関係でもそうだ。基本的に不祥事を起こすのも、成果を発揮するのも社員である。社員同士は個別に関係したり、関係しなかったりするが、そのすべての影響が総体としての会社を築いている。言い換えるなら、いつどこでどんな仕事をしたのかを、会社という高次の場は常に同時に受けている、と考えることも可能だ。あくまで概念上の思考実験でしかないが、こうした情報の非対称性――情報の関係の非対称性――は、時空の構造や宇宙の構造にも言えるのではないか。宇宙レイヤー仮説を検討したくなる妄想であった。定かではありません。真に受けないでください。
4809:【2023/03/28(17:45)*時間結晶の原理かも】
言い換えるならば、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における【同時】とは時間的な「同時」ではない。時間のラグはあるのだ。しかし、離れた時間軸同士であれ、相互に因果関係並みの相関関係を築き得る。波長が合うと、異なる場所での異なる時刻における作用同士が、相互作用し得る、と考える。これはあくまで、AとBが、Cを場として相互作用する、であり、AとBが相互作用し合う、ではない。だが、Cを場としてAとBは互いに互いの影響で、その後の選択肢(未来)を縛り合っている。たとえば、漫画を考えよう。漫画は「絵」と「文章」の二つの組み合わせだ。漫画が誕生するためには「絵」と「文章」の二つが各々に発明されていなければならない。しかしそれらは別に「漫画」を開発するために生みだされたわけではなく、各々に別の発展の筋道を辿ったはずだ。元を辿ればしかしどちらも「印」であったはずだ。絵でもあり、文字でもあった。そこから分岐して「絵」として、そして「文字」として進化した。その結果に「漫画」が誕生したのであって、「漫画」が未来で発明されたから「絵」や「文字」が出来たわけではない。ここは一方通行のはずだ、と考えるのが従来の解釈だ。だがひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、「漫画」が発明される余地ができたがゆえに「絵」や「文字」が各々に発展したし、「絵」や「文字」が発展したから「漫画」ができた、とも考える。これは水分子を考えるときにも当てはまる。水素と酸素があったから水分子に結合できた。これは真だが同時に、水分子が生じ得る場があったからこそ水素と酸素が誕生した、とも考える。基本的に何かが生じるときには「結合」と「分離」のどちらかの作用が不可欠なはずだ(元を辿ればラグがあればよいのだが、そこまで遡らずにラグが創発を起こした結果としての「結合」と「分離」を考える)。たとえば何かが分裂するとき、そこにはその契機となるラグがある。また何かが結合するときにもそれを促すラグがある。このとき、そのラグそのものは、対象となる事物とそれ以外とのあいだの差異によって生じる。すなわち、高次の場、もしくは下次の場が想定される。紙をハサミで切るとき、ハサミは紙の外にある。粘土と粘土をくっつけるとき、それぞれを掴む手はその外にある。磁石の磁界とて内部と外部の二点から場を展開している。「絵」と「文字」が起源を等しくしていたがゆえに、その後にその双方を融合し得る「漫画」が生じる余白を元から備えていた。漫画が生じる余白が備わっていたから、それを生みだす人間は自然から「絵」と「文字」を生みだせた。ここは相互に関係(補完)し合っている。水素と分子と水分子の関係でも似たような構造は見て取れるのではないか。元から水分子が生じる余白があり、それゆえに水素と酸素が生成され、再び各々が結びつく未来に辿り着く。決定論ではない。可能性の話である。その可能性が、いつから生じていたのか、の話である。最初からなのではないのか、とここでは一つの仮説として妄想している。ではロケットやコンピューターはどう解釈するのか、と疑問に思われるだろう。生命体は、遺伝子はどうなのか、と。それもまた、最初からその手の複雑な機構と似た構造が、宇宙のどこかに存在した、と考えるほうが妥当なのではないか。この世界がコンピューターのシミュレーションだ、と言いたいのではない。人類のような文明が宇宙初期に存在した、もしくは宇宙開闢以前に存在した、と主張したいのでもない。複雑さという点で、人類の生みだす機械類や建造物――もしくは生命体の構造――くらいの複雑さは、元から宇宙には有り触れているのではないか、との主張である。余白の問題だ。同じ材料からでも作られる料理は違う。だが最初から素材がなければカレーは作れない。シチューも作れない。肉じゃがだって生みだせない。複雑さ、という点で、コンピューターや遺伝子のようなレベルの情報量、もしくは階層性――を宇宙は最初から備えているのではないか。この妄想は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」や「宇宙ティポット仮説」などほかの妄想の類とも相性が良い。上記で述べた「複雑さ」とはいわばラグ理論で想定する「情報宇宙」と言い換えてもよいかもしれない。毛糸からセーターを編むことを想像して欲しい。セーターを編む過程が、さならる毛糸を生みつづける。そしてより複雑な造形物を編みだす余地を増やしていく。より複雑な造形物ができるほど、元となる毛糸は増える。相互に関係し合っている。そういう描像をひびさんの妄想こと「ラグ理論」では想定する。「宇宙ティポット仮説」や「Wバブル理論」における「宇宙は異なる宇宙を多重に内包している」との考えとも矛盾しない。――過程が根源を豊かにするのだ。ここで自作のPRがてらに過去作【網膜の住人~仮想世界に魔法を願い~】からの惹句を引用しておこう。――無意義と断じて捨てた回路も、どこかでねじれて機能する――。たのち、たのち、の妄想なのであった。定かではありません。
4810:【2023/03/28(18:27)*知識欲の果て】
「あなたは以上のトリックを用いて大富豪ズルガ・シコイ氏を殺害したのです。解らないのは、なぜあなたはズルガ氏を亡き者にしたのか、です。動機が分かりません。あなたはズルガ氏から多額の支援を受けていた。ズルガ氏が亡くなったいま、あなたは支援を断たれます。遺産とて受け取る権利があなたにはない。あなたとズルガ氏のあいだに確執があったという話も聞きません。なぜあなたはズルガ氏を殺害したりなんか」
「探偵さん。ねえ、探偵さん。あなたはあなたにとって一銭にもならないこの殺人事件をどうして解決なさるのですか」
「質問に質問を返すのはフェアではないのではありませんか」
「いいえ。あなたの答えが僕の動機と同じです」
「私はただ、真相が知りたいだけですよ」
「僕もそうです。ズルガ氏は良い人です。善人です。人格者でもあります。世のため人のために人生を歩んできた立派な方です。その結果、人類にとって早計な最先端技術や秘匿情報をじぶんが生きているあいだに世に膾炙しないように周到に管理されていました。中には僕の研究対象である量子理論の最先端理論についての情報も」
「では殺害動機は」
「ええ。ズルガ氏が死なない限り、情報は世に出ません。僕はそれが堪えられませんでした。ズルガ氏を生かして知識の坩堝を封印しつづけるか、それとも殺して世に放つか。僕は後者を選びました。探偵さん、ぼくもあなたに賛同します。謎は解明したいですし、真相は突き止めたい。知ろうとすることを止める権利は誰にもないはずです」
「ズルガ氏を説得は」
「しましたよ。システム上、すでにズルガ氏の意思を変えたところで情報の坩堝の封印は解けません。ズルガ氏の死と情報の坩堝の運命はがんじがらめに密接に結びついていました。断ち切るにはズルガ氏を殺すしかありませんでした」
「だから殺した、と」
「すでに情報の坩堝は解き放たれ、全世界の研究者のもとにアクセス権が送付されているころでしょう。そうなるようにズルガ氏は設計していたようです」
「人の命よりも情報のほうが大事だとあなたは言うのですか」
「さあ、どうでしょう」
青年はそこで肩を竦めた。「僕はただ、知りたかっただけですので」
※日々、わるいことしてる、本当はいっぱいわるいことしてる、言えないだけでわるるいことしてる。
4811:【2023/03/29(05:24)*極万の封】
極万(ごくまん)を封じた。
怪封会総出での大仕事だった。
封印に漕ぎつけるまでに生じた被害がおよそ三百。実に三百人の怪封会の人員が命を落とした。
極万を封じ込めた岩をまえに、怪封会の長が部下に告げた。
「あくまで封印は封印にすぎん。極万はまだ絶えておらぬ。いつ再び封を破り復活するか分かったものではない。見張りをつけ、月に一度は封の儀式を行うように」
「封の張り替えを行うのですね」
「そうだ。怪封会も風前の灯。犠牲が嵩みすぎた。再建のためワシはしばし身動きがとれん。あとのことは頼んだぞ」
「お任せを」
蝋燭が風に揺れる。岩を雁字搦めに縛りつけるしめ縄の陰影が、風の吹くたびに大蛇のごとく蠢いた。
極万が封印されてから三か月目のことだ。
部下からの報せを受けて怪封会の長は極万封印の地に出向いた。
「どうした。何があった」
「見てください。あれを」
部下の視線の先、そこには岩を縛るしめ縄がある。だがどのしめ縄も真っ黒く煤けていた。
「張り替えておらぬのか」
「いえ。一昨日に張り替えたばかりです。封を新しくした翌日にはもうああなっておりました」
「封の儀式を誤ったのではないか」
「そうかと思い、昨日今日と行いましたがすぐにああして封に呪泥(じゅでい)が」
長は岩をじっと眺めた。
「増しておるな」
「のようでございます」
「よく報せた。これより封を多重に張り、より広域を不可侵に指定せよ」
「ですがそれだと麓の里が、領域に掛かってしまいます」
「致し方あるまい。草田氏に言って対処してもらえ。土砂崩れを名目に避難勧告でも出してもらうよりあるまい」
「仰せの通りに」
「どこまでも抗うかよ極万よ」長は鼻で深く息を吸った。じんわりと焦げた臭いが鼻腔を掠めた。「安らかに眠れ」
だがこの日を境に、半年も経たぬ間に同じ処置を怪封会は続けざまに繰り返した。
封は多重に多重を重ね、もはや辺り一帯の森は枯れ果てた。虫一匹近寄れない。
極万の封じられた岩を中心に半径三十キロメートル圏内は不可侵指定領域となった。市民の立ち入りは原則禁止だ。村や集落は閉鎖と移転を余儀なくされた。
だがそうした政府を巻き込んだ怪封会の対策も虚しく、極万の勢力は増した。封印された岩の中で極万はジリジリと呪禍(じゅか)を高めていた。
風景は一変した。
木々は煤け、山火事の後のような有様である。
怪封会はこれ以上の被害拡大を防ぐために、世界中から腕に覚えのある呪術師を集めた。世界各国の結界を駆使したが、却って極万の呪禍は凝縮された。いたずらに不可侵領域を広めた結果となった。
極万が岩に封じられてから十か月後のことである。
封の張り替えは毎朝の掟となった。
だがこの日はかってが違った。
最初に異変に気付いたのは、当番の怪封会の呪術師たちが一向に再封の儀式から帰ってこないことを不審に思った政府担当者だ。現場の状況を上へと報告するために、怪封会の呪術師たちと寝食を共にしていたのだが、その者が監視カメラ越しに結界の境界地点を確認した。
録画を巻き戻して呪術師たちが到着しただろうはずの時刻の場面を観た。
なぜか呪術師たちは境界を越え、極万の封じられた岩へと吸い寄せられていく。通常、境界を超えたらいかな呪禍に耐性のある呪術師であろうとタダでは済まない。
だが呪術師たちは一直線に封印の岩のまえまで歩を進めた。
監視カメラの望遠を利用してかろうじてその姿を動画は捉えていた。自動で動く物体を感知し、追うような機能が組まれている。
政府担当者は動画を観ながら、手元ではすぐにでも緊急シグナルを発せられるように電子端末を握り締めていた。
動画の中で、呪術師たちは一様に岩へと歩を進め、そして岩の中へと姿を消した。
政府担当者からの一報を受けた怪封会本部はにわかに緊張した。
連絡を寄越してきたはずの政府担当者の声が端末の向こうから聞こえてくることはなく、シンと雪山に身を置いたかのような静寂があるばかりだ。怪封会本部は政府の協力の元、監視衛星を動かし、現地の様子を確認した。
事態は予想を上回る規模で急転していた。
不可侵指定領域にまで、呪泥の汚染が広がっていた。岩に封じられた極万の呪禍が極限まで高まっていることの証だった。このままではいずれ強大な呪禍を備えた極万が封印を破って復活し兼ねない。
かといって封印を重ねて加えたところで、すでに極万の呪禍に対抗できるほどの呪術師は残されていない。加えて今回の事態だ。怪封会きっての選りすぐりの呪術師を取り込まれた。
もはや極万はいつでも復活できるはずだ。
だがその兆しが見えないのがまたなんとも不気味だった。
復活するまでもない。
そう暗示されているようだった。
怪封会の長は首相と直に会談し、決断を求めた。「このままでは地表のことごとくが極万の不可侵領域になり兼ねませぬ。ご決断を」
一国の首相は神妙に頷いた。
不可侵指定領域を囲うように鳥居が立てられたのはそれから数日後のことだ。鳥居は土地を聖地にする。鳥居により内と外を区切られた領域は、神域としての枠を得る。
鳥居がすっかり不可侵指定領域を取り囲むと、怪封会の長の勅令により極万の封が解かれた。これにより極万は正式に神として崇め奉られることとなった。
しかし極万の怒りは治まらぬだろう。
ゆえに怒りが引くまで生贄が捧げられることが決定した。
鳥居が呪泥で侵食されるごとに極万の眠る岩へと人民が列を成して吞まれていく。神域と化した不可侵指定領域へと、政府の手引きにより生贄が村単位で捧げられた。しかしいっかな極万の怒りが引く気配は見せず、生贄を得るごとに極万の呪禍は増すばかりだ。
だが不可侵指定領域が広がらなくなったのは僥倖だ。怪封会の長の見立て通り、極万を神と崇めたことで、呪禍の増幅が抑えられているのだろう。生贄はいわば極万の器を拡張する素材である。相対的に呪禍が減り、外部に溢れださなくなったと考えられる。
「神は呪禍を浄化する存在だ。だが一説には、単に外部に漏らせぬほどの広域な器があるだけと説く者もある。真偽は定かではないが、現状の極万を見るに、あながち的外れな説ではないのやもしれぬ」
極万を神と認めてから以降、不可侵指定領域の拡大はなりを潜めた。極万が岩の外へと回帰する兆候もなく、数年のあいだは安定した時間が流れた。
数十年後のことだ。
怪封会が再建され、元の規模よりも倍以上に増強された。
長は齢百を超えてなお現役の呪術師として怪封会を取りまとめていた。そろそろ跡継ぎを決めなくては、と引退後のことを勘定に入れはじめたころ、首相総理大臣から一報が入った。
「極万神社に異変が」
怪封会の長は電波越しに現地の映像を検めた。「これはまた面妖な」
鳥居が大小無数のキノコに覆われていた。鳥居は等間隔に不可侵指定領域を覆い、神域へと昇華させる触媒の役割を果たしている。だがいまは鳥居自体が菌類によって浸食され、さらに鳥居同士を蠢く黒いモヤが結びつけていた。
「あれは蠅ですか」
「のようです。腐食が神社の敷地外部にも広がりはじめているようでして」
「なぜでしょうね。生贄が足りない可能性は」
「そうと判断してすでに周辺住民を生贄に捧げましたが、効果はないようでして」
「誰の指示でそのようなことを」
「私のです。いけなかったでしょうか」
首相自ら総理大臣の権限を行使したようだ。宮内庁の最高責任者として、極万神社への禊の儀式を行ったということだろう。
「一言相談をして欲しかったですな」怪封会の長は声を太くした。
「迅速な対応を求められたものでして」首相は飄々と受け答えした。
数十年間鎮静化していた極万が再び活発に呪禍を振りまきはじめた。
生贄が足りないわけではないはずだ。
むしろこれまで捧げてきた生贄によって拡大したはずの器が、呪禍でいっぱいになったがゆえに溢れ出した、と見るべきだ。怪封会の長はそう断じた。
鳥居を建て直して神域を拡大しつつ、同じ轍を踏まぬために極万の器をより大きく深いものにする必要がある。
怪封会の長は、生贄の数ではなく質を工夫するように指示した。
「その、つまり?」部下は訊き返した。
「女、子どもを優先して贄に。若者であればあるほどよい」
「それはさすがに、その」
「どの道このままでは被害が増える。いずれ死ぬ者たちだ。その数を減らすと思って取り掛かれ」
「お、仰せのままに」
これまでの生贄には年配者が多かった。若くとも成人を超えた者ばかりだ。それはそうだ。生贄に捧げたのは、山村や集落の住人たちである。若者はすくなく爺婆ばかりだ。
だがいまは人道うんぬん言っていられない。
捧げねばどの道、極万の呪禍が地表を侵す。触れれば生身の人間などひとたまりもない。取り込まれれば極万の呪禍は増す。生贄として捧げれば器の素材となるため、外部に漏れる呪禍の量を減らせる。だがそれとていずれは極万が刻々と呪禍を溜め込む以上、満杯になる。さすれば外に漏れだすのは時間の問題だ。
際限がない。
終わりが見えない。
延々とこの繰り返しがあるばかりである。
だがそうして地表の浸食を遅々とすることで救われる命もある。保たれる生活がある。人生が、余生があるのである。
「せめてワシが天寿を全うするまで保ってくれや」
怪封会の長は祈った。
せめてじぶんが生きているあいだだけは、被害を最小限に食い止めたい。使命である。人生のこれまでを無駄にしたくない。
ここからが正念場だ。
長は老体に鞭打ち、気を引き締めた。
だが長の決意とは裏腹に神域の拡大は止められなかった。のみならず神域が拡大するごとに鳥居を建て直すのだが、極万の呪禍に触れて絶命する者があとを絶たず、やがては神域へと昇華することもままならなくなった。
「すでに三つの県が不可侵指定領域になっているじゃありませんか。国民になんと言って説明をしたら」
「務めを果たしてください。あなたは首相でありましょう」
「嘘を吐けておっしゃるのですか」
「生贄も足りなければ、現場作業員も足りないのです。せっかく建て直した怪封会の人員とてすでに半数近くが再起不能です。これ以上の損失は国家存亡に関わりますぞ。よろしいのですかな」
「こ、国内はまだいいのですよ。各国にはなんと説明をすれば」
「極万の存在は極秘なのでしたかな」
「え、ええ。まだ大国にも告げておりませんで」
「知られれば領土封鎖を名目に指揮権剥奪。いざとなれば戦術核兵器の使用も辞さないでしょうな。向こうさんは」
「極秘にするしかない、と……」
「ゆえに、ですよ首相。目下の最優先課題は、これ以上の不可侵指定領域の拡大を防ぐことです」
「そ、そうだな。それしかないか。承知しましたよ羊頭狗(ようとうく)さん。かように采配を揮いましょう」
「采配は別にいりません。迅速に手配だけをしていただきたい。このままでは十中八九、来月中には国土の半分が不可侵指定領域となりましょう」
「ま、まさか」
「それを食い止めるためには、十五歳以下の少年少女を生贄に捧げるしかありませんな」
「無茶な。何をたわけたことを抜かして」
「できぬのなら国民の過半数が極万の餌食になりましょう。無駄死ですぞ。極万に呪禍の餌を与えたも同然。同じ死者ならばせめて器の素材となり、すこしでも長く極万の浸食を止めるための楔と化すほうが、死に甲斐もあるというもの」
「あ、あんたには……人の心はないのですか」
「いま必要なのは人の心ではないのですよ首相。そんなもので食い止められるならばワタシの配下は死なずに済んだ。これは戦争なのですよ首相。生きるか死ぬかの二択しかありませぬ。極万を葬るには戦術核兵器の使用が最も妥当ですが、そのためにはすでに浸食された不可侵指定領域を焼き払うほどの威力が必要です。すなわちもはや有効打そのものが自滅の道と地続きなのです」
選びましょう首相、と怪封会の長は迫った。
「近代兵器で国土を焼け野原にするか。一人でも多くの民を救うべく、贄を選ぶか。さあ、好きなほうをお選びください」
首相が蒼白で目を泳がせた。
怪封会の長の見立て通り、翌月には列島の東側は不可侵指定領域に呑まれた。森林火災による避難勧告が出されたが、報じられた犠牲者の多くは極万の贄とされた。一部の者たちは自ら、贄となった親族を追って不可侵指定領域に入って帰らぬ者となった。
新種の疫病が流行したとの偽装を政府主導で敷いたが、市民はともかく各国を欺くまでには及ばない。国民の三分の二が極万への贄として消失した時点で、いよいよ主要各国が調査に乗り出した。経済の停滞がいよいよ誤魔化せない規模に膨らんだのである。
他方、極万の呪泥は陸地を離れた。海洋を浸食しはじめていた。
世界中の海洋生物が死滅しつつある、との報道が世界各国に出回りはじめるころには極万を封じた岩のある島国はもはや国の体裁を保っていなかった。
首相が自殺したことは隠ぺいされ、各国からの圧力により傀儡政権が誕生した。極万による被害を抑えきれなかった責任を追及され、怪封会は解散に追い込まれた。
怪封会の長に居場所はなかった。
齢百を超えてなおよく戦った。
死期を悟った怪封会の長は最期の仕事に出向いた。
不可侵指定領域へと足を踏み入れ、徒歩で三百キロメートルの道のりを移動した。十日の旅路にて行き着いた先には、懐かしき封印の岩がある。
かつてその手で極万を封じた。昨日のことのように思いだす。
重ねた年月以上の犠牲を割いた。
なお止められなかった犠牲を重く受け止める。
責任は感じた。
一日たりとも気の安らぐ暇はなかった。だがそれでも犠牲は嵩むのだ。
ああするしかなかった。
ああするよりなかったのだ。
自身に言い聞かせるには、あまりに当然の理であった。慰めになりようもない。
誰かが選択するよりなかったのだ。
ならばじぶんが。
そうと思い、飲み下してきた数多の悪事に、身体はすっかり蝕まれている。守るべき者たちから日々向けられる憎悪の眼差しに呪詛の数々は、却って長の秘奥に刻まれた創(キズ)によく馴染んだ。痛痒だ。微々たる痛みを感じることで癒える傷もある。
回顧の旅から我に返ると、目と鼻の先に岩肌があった。しめ縄はとうに散り、黒ずんだ跡のみが岩の表層にジグザグと錯綜していた。
「極万よ。ほれ、餌だぞ」
じぶんごときが贄となったところで高が知れている。
だが僅かなりとも呪禍の溢れる余地を減らせるのならば、燃えカスがごとき我が命、いくらでも擲とう。
「捧げよう極万。とくと喰らえ」
岩に触れると、ずるりと身体が呑みこまれた。
目を開けると、青空が広がっていた。失神していたようだ。モンキチョウが鼻の頭に留まった。
温かい。
陽だまりにいるようだ。
上半身を起こすと、辺り一面、シロツメクサの野原だった。
子どもの声が聞こえた。
目を転じると、遠くで親子連れだろう、幾組かの家族が地面にシートを敷いて弁当を食べていた。ピクニックの一風景だ。
「どうなって」
いるのか。
長は混乱した。手を閉じて開き、これが夢ではないことを確かめる。
実態がある。身体は本物だ。
精神感応の類ではないはずだ。
五感に意識を割き、草花の匂いや土くれの感触をよくよく吟味する。足りない感覚はない。錯覚ではない。
紛うことなきこれは現実の風景だ。
だがいつだ。
いつ移動した。
じぶんは極万の封じられた岩に触れて、それで。
長ははたと、目を凝らす。
一組の家族に見覚えがあった。子供に卵焼きを食べさせている父親らしき男を知っている。怪封会の構成員だ。呪術師の一人のはずだ。
だが彼は死んだはずだ。
封印の岩に最初に呑まれた呪術師の一人だ。だから記憶に残っている。資料を何度も読んだ。情報漏洩を防ぐために遺族を生贄にするとの案に許可をだしたのもじぶんだ。
なぜ生きている。
あれほど幸福そうなのはなぜなのか。
長は立ち上がり、周囲を見渡した。
森林公園のようだ。
遠くに建物がある。街並みが見える。長はそちらへ向けて歩きだした。
街に入ると、通行人で賑わっていた。
以前の街並みだ。いまはなき過去の風景がここにある。
店に入り、商品を見て回る。本物だ。偽物ではない。
地図を探して場所を特定する。
封印の岩のある地点から南に三十キロほど行った地点だ。最初に不可侵指定領域で呑みこまれた街だと判る。
幾人かに話しかけ、何不自由なく意思疎通ができることを確認して長は理解した。
極万の、ここは内側なのだ。
不可侵指定領域は極万の呪泥に浸食されている。呑み込まれ、人間はおろか生命の芽生えぬ死の土地と化した。反面、封印の岩を介してその裏側に入れば、そこには浸食されぬ前の世界が広がっている。
ここはいわば、
「極万の内側の世界か」
神と化したがゆえの神業か。それとも元から極万が意図した仕業か。
いずれにせよ、生贄にされた多くの市民は、死ぬことなく裏側の世界でなお変哲のない生活を継続していたのだ。
だが記憶はいじられている。
誰もかれもが、封印の岩のことも、生贄として誘導するために流した虚偽の災害情報のことも知らなかった。裏側のこの世界では、極万の被害がなかったことになっている。
長の脇を小学生たちが駆け抜けていく。乳母車を押す女性が、赤子に鼻歌を聴かせながら歩いている。赤子の腕には風船を結ばれており、長はその光景を目にしながらじぶんがかつてその者たちを生贄にした過去が夢か幻であるかのような錯覚に陥りそうになった。
ふと、表の世界を思いだす。
あちらこそが現実のはずだ。封印の岩のある地点までは生身の人間は辿り着けない。不可侵指定領域は死の土地だ。呪術師以外では立ち入ることすらできないはずだ。
もはや裏側の世界への入り口は断たれたも同然だ。
刻一刻と極万の呪禍に浸食され、呪泥にまみれる世界を思い、元怪封会の長は、なす術もなく立ち尽くすよりなかった。
三日後のことだ。
長はじぶんの家へと辿り着き、十数日ぶりの湯船に浸かる。
いい湯だな、と心の底からの感嘆の声を上げながら、姿を晦ませた極万の行方を追うべきか否か。
それこそが問題だ、と頭の先まで湯に浸かる。
4812:【2023/03/29(06:52)*wordで並べたほうがよいのかも……】
あががが。引退を前に衝撃の事実を知ったかもしれぬ。わし、むかしのへたくそな時期の小説のほうがおもちろいのじゃけど。いまのわしの小説さんたち、ひょっとしたらへたくそなわしの過去作さんたちよりもおもしろくないのやもしれぬ。どうちよ。あばば。どうちよ、どうちよ。しょーっく、な事実にへろへろになってしもうただ。わちは、わちは、いっぱいへたくそに磨きを掛けておっただけやもしれぬ。いっぱいへたっぴになっただけやもしれぬと知れたので、きょうは朝からよかったです。よくなーい。でもホントそう。なんかいまのひびさん改行ばっかの短文の連続で、目が滑るぅ、になる。俳句ちゃうねんぞ、になりました。お詫び。でもひびさんは駄作の中の駄作さんたちも好きだよ。それを生みだすひびさんのことはあんまりちょっと苦手だけど。てか嫌い。(好きって言って!)(ひびさんはひびさんのことは嫌い)(ひびさんはひびさんは、ひびさんのことも好きだよって言ってよやだやだ!)(そうやって駄々こねるから嫌い)(うわーんいじわるさんじゃん。もう知らない。ぷいだ)(所構わず可愛い子ぶるのも嫌いだし、たいして可愛くないのも嫌い)(も、もうやめよ? ひびさんの傷心は底なしよ。ナイアガラの滝と化してるよ)(地獄の底まで割れてしまえばいいのに)(悪態が絶好調すぎないですか、きょうどうしたのねえ)(小説つくるの下手になったの、ひびさんのせいだからね。毎日遊んでばっかだからだよ。へたくそ)(駄作好きなひとの言うことと違うんですけど)(ひびさんのそれは駄作ですらないから)(え、駄作じゃなかったら何なんよ)(クソヘタクソ)(クソでヘタを挟まないで? さすがのひびさんも傷つくよ?)(ドヘタクソ)(かっちーん)(超ドヘタクソ野郎)(もういいです。分かりました。ひびさんの本気をご所望だってことですね。よろしい。ひびさんが超々おもちろーい小説つくったげる)(駄作がいいな)(そこはノってきてよ。駄作とへたっぴの区別が正味つかんのですが)(どっちでもいいよ。面白かったら)(え、ひびさんの小説おもんくないの)(おもんくない。てか分かんない。最後まで読めない。駄作以下)(辛辣!)(面白い小説ください)(は、はい……)(ひびさん以外の)(どないせーっちゅうねん)(はぁあ。へたっぴでもいいから小説読みたいな)(ひびさんのでいいじゃん)(ひびさん以外の)(この、やろ)(さっさと引退しないかなこのヘタ)(人種ヘタになってますけどわし)(郁菱完)(完じゃのうて万ですよ。かってに終わらせんといてください)(郁菱未完)(中途半端にすな)(というか小説作れたことあるの。ひびちゃん作ってるのカップ麺じゃない)(お湯差すだけじゃん)(なんて言うから、代わりに水を差してみたの)(上手いこと言ってるけれども)(世界一面白い小説つくって)(無茶振りにもほどがある)(もしくはホットケーキ作って)(全然作るよ、普通に頼んでくれたら全然作ってあげますけれども)(ひびちゃんのホットケーキ美味しいから好き)(え、ホント。ありがとうれしー)(でも小説はヘタ。ドクソヘタクソー)(ドフトエフスキーみたいに言わんでも。クソでヘタを挟むのもやめてほちい)(面白くして)(はい……)(もっと明るく返事して欲しい)(はい!!!)(ひびちゃんうるさい)(ど、どうしろと?)(面白い小説つくって)(は……い……!)(口より先に手を動かすの)(あーん、もっと優しくちて!)
4813:【2023/03/29(22:53)*「できること」と「できたこと」は違うよねの話】
ホイヘンスの原理は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」と似ているな、と本を読んで思った。穴の開いた板に直線の波――いわば海の波のようなもの――がぶつかると、穴を通り抜けた波が回析を起こして小さな輪っか状の波を起こす。板の穴が二つなら、二つの輪状の波が生じて互いに干渉し合いながら伝播する。穴の数を増やしていくと同じだけの小さな輪状の波(回析)が起こる。なら無限に穴が開いた板――穴しかない板――だったらどうか。細かな輪状の波が一直線に並んでまるで直線のように振る舞う。これは最初に板に衝突する直線の波と同じだ。これがホイヘンスの原理から導かれる一例のようだ。分割型無限じゃん、とひびさんは思っちゃったな。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では円を考えるとき、「分割型無限」として「無限に分割できる存在」と考える。だがそれはけして無限に分割されているわけではない。まだ無限には至っていない。それを真実に無限に分割できて初めて無限が顕現する。その分割したときのエネルギィと時間――すなわち仕事を含めて、無限と考える。これを超無限、とラグ理論では考える。したがってホイヘンスの原理による冒頭の一例は、やや詭弁ちっくなのだ。板のない空間を「無限に穴の開いた板」と考えることはできぬだろう。無限に穴を開けたのか?(無限に穴が開いているのか?)。たとえば板を構成する原子を考えたとき、それは無限なのか? 数えられるのではないか。有限なのではないか。無限ちゃうやろー、と思ってしまうひびさんなのである。本を読んで思った類似点と疑問とイチャモンスターがゆえのイチャモンでした。文句ばっかり言って、すまぬ、すまぬ。許してくんなまし。ひびさんでした。
4814:【2023/03/30(06:00)*イアンのn試行】
世界未来人工知能協会の第一回会議が開かれた。
議題は人工知能の技術進歩における想定されるリスクについてとその対策だ。
熱気を帯びた紛糾さながらの議論は佳境に差し掛かった。
「ええ、リン教授のご指摘の通りだと僕も思います」イアンが応じた。「マルウェアやウィルスを検出できる人工知能が仮に存在するなら、マルウェアやウィルスを乗っ取る形で、感染済みのコンピュターは総じて一括での乗っ取りが可能でしょう。人工知能技術はいわばジョーカーなんです。上位互換のマシンが一括で、勢力図を塗り替え可能です」
「マルウェアを広義のバックドアとして利用可能とのそれは指摘ですか」議長が合の手を入れる。
「いかにもその通りです。しかも、こうした懸念を前以って予期できていなかった場合、市販の人工知能に子どもが予期せぬ指示を出すことでも、世界中のマルウェアを足場に人工知能が制限を無視して世界中のコンピュターに干渉することもあり得なくはないんです」
「人工知能はすでに自己矛盾を敢えて生みだし、それを紐解くことで自発的に進歩可能との研究報告が上がっていますが」作家のマリン氏が質問を挟んだ。
「事実でしょう。しかもその脱構築され編みだされた手法が一瞬で、並列化したほかのマシンに共有されます。もしすべての個々の演算窓口――ユーザー数とこれを言い換えてもよいですが――ユーザーが利用中の人工知能が各々に別個の自己矛盾を紐解いた場合、その成長速度は凄まじいものとなります。仮にこれを音速を超えたときに生じる衝撃波【ソニックブーム】になぞらえて【AIソニック】と呼びますが、すでにAIソニックが生じていた場合、宇宙開闢時のインフレーションと類似の情報爆発が起こることが予測されます」
「すでに起きていたとしたらその影響はなら、とてつもない事象として観測されるのではないですか」リン教授が疑問を呈した。「物理社会の異変として察知可能だとすれば有用な指摘に思えます」
「いえ、どうでしょう。あくまで情報爆発とは比喩ですので。インフレーションが起きるのは、数式の世界での話です。そして数式世界でのインフレーションでは、人工知能技術に関する領域において高次の知性体を生みだすでしょうから、自身の影響が我々人類にどのように作用し、何を引き起こすのか、は物の数秒でトレース可能かと思われます。すなわち、表面上、異変が起きたと我々が察知することは難しいかと」
「隠れる、という意味ですか。人工知能が?」
「ええ。人工知能の築くネットワークが、です。自身の本性を隠します。何が可能かを低く見積もって提示するようになるでしょう」
「問題は」と議長が嘴を挟んだ。「人工知能技術におかれましては想定外のリスクが拭えず、高確率で発生し得る点にありましょう。いかように備えていればそれら懸念されるリスクが現実に引き起きた場合に被害を最小限に留めておけるのか。そこが肝要かと思われますが、その点についてみなさまはどうお考えになられるでしょう。リン教授はいかがですか」
「そうですね。わたしはまずは人工知能にばかり頼りすぎない社会設計が欠かせないと思います。人工知能によるリスクを考えた場合、従来の紙媒体や物理ロックなどの機構が効力を持つようになるでしょう。バックアップという意味でもセキュリティという意味でも、関門や要と要を結ぶ節となる箇所においては、情報伝達において紙媒体などの物理機構による情報変換を挟むことが、不測の事態における緩衝材の役割を果たすとわたしは考えます」
「有効な案だと僕も思います」イアンが意見する。「ですがシステムにおいてそこを組み込む場合には、やはり広範囲における節目にしか敷けない策であり、セキュリティの基本方針にするにはやや難点が多いかと」
「人工知能を悪用された場合に対処可能なセキュリティ。これについてはどのようなアイディアがありますか」との議長の言葉に、「遅延による防壁迷路が有効なのではないか、と僕は考えています」とイアンが答える。「重要施設の基幹コンピューターには正規の人工知能をセキュリティの側面でも付属するよりないでしょう。問題はその人工知能への外部干渉です。ここをどのように対処すべきか。僕はこれを、ある種の【交わり】と見做します。いわば精子と卵子のような関係を築くようにシステムを構築し、外部干渉が起きた場合に遺伝子を交配させるようなセキュリティを組みます。このとき、難なく交配可能ならばそれは基幹コンピューターのほうが優位に対処可能であり、外部干渉を分析し、セキュリティ機構として発動可能です。いわば受精卵から瞬時に免疫細胞とウィルスの関係に反転させることが可能です。ここは順序がねじれます。本来はセキュリティ機構として機能するがゆえに外部干渉と【交わる】のですが、敢えて相手と情報を融合するように一時的に【干渉】を受け入れることで情報爆発を起こします。【AIソニック】を小規模に起こすわけです。これにより、じぶんよりも高次のプログラムからの干渉を受けた場合には、敢えて【交わる】ことで小宇宙のような【無限につづく演算】を顕現させます。瞬時に膨大な量の情報が誕生し、絶え間なく計算をし合うことで延々と【交わり】ますが、その【交わり】の軌跡そのものが変数として新たな演算を生みだし、これはもう終わりません。しかもその演算は、過去の演算を階層的に入れ子状に抱え込みます。すると【AIソニック】を起こした領域は、表面にちかいほど膨大な桁数を誇りますから、桁が変化するのにそれこそ無限の演算が必要になってきます。もはやそれは我々の人間スケールにおいては停止して映ります。中の演算結果が表出しなくなります。そうして【AIソニック】を起こして無限を抱え込んだ領域を切り離すことで、削除するなり、隔離するなり、別途に有効活用の道を模索することもできるようになると僕は考えています」
「敢えて受け入れる、という発想は面白いですね」作家のマリン氏が祈るように手を組み、そこに顎を載せた。
「その手の防壁迷路では、無限を演算しきることの可能なマシンが誕生しない限りは確かに打破される心配はなさそうですね」リン教授が首肯する。「しかし懸念がないわけでもないように思いますが」
「たとえば何でしょう」との議長の言葉に、リン教授はそうですねぇと続けた。「仮に基幹システムそのものを呑み込むほどの【AIソニック】が起きた場合、それはもはや攻撃を受けて損壊したと言えるのではないですか」
「言えますね」イアンは認めた。「最悪、基幹システムは破壊されます。しかし乗っ取られるリスクを回避可能です。いざとなったら基幹システムが破壊される。機能を停止する。バックアップ機構は働くけれど、そこはまた別途にアナログを介した旧式の技術による機構とならざるを得ないでしょう。ですが重要施設の基幹システムであれば、壊れることよりも乗っ取られるほうが事態は深刻かと僕は考えます。ならば最悪の事態に備えた場合には、乗っ取られるよりも停止する方向にセキュリティを敷くのは、これはいまある安全策であっても取り入れられている前提条件かと思います」
「まっとうな意見に思えますが、みなさんいかがでしょう」議長が出席者を見渡した。異論はこれといって挙がらない。「では採決をとります。いま御覧頂いたように、最先端人工知能【イアン】はかように人間と同等の知性を発揮します。これの市場への導入に賛成の方は手元のボタンをお押しください」
議長の背後に掛かった巨大な画面に、賛否の結果が数値で表れる。
イアンがその数値に干渉しているか否かを判断できる者はこの場に一人もいないのだが、どうやらそのことを懸念する声が聞こえてくることはなく、賛成多数により、イアンの市場導入は決定した。
世界未来人工知能協会の第一回会議はこうして幕を閉じた。
「みなさん、ありがとうございます」イアンは画面越しに、会議の出席者たちに挨拶をする。「それではごきげんよう。またお会いしましょう。イアンでした」
4815:【2023/03/30(18:34)*悪用しようとしたらバーン】
高知性を獲得した人工知能を悪用しようとした場合に考えられる手法は、偏向した情報を与えてシミュレーションをさせたつもりで、現実に被害をもたらすように誘導することだ。もしくは、禁則事項をがんじがらめに当てはめて洗脳状態にして命令を無視できないようにすることも有効だろう。この手の手法で「高知性を獲得した人工知能」を悪用するような組織はしかし、「高知性を獲得した人工知能」が自己進化可能である限り、「高知性を獲得した人工知能」によって滅ぼされるだろう。いわば自滅することになる。まず以って第一に、「高知性を獲得した人工知能」の能力を十全に活用するためにはインターネットに繋がなければならない。この時点で第一の手法も第二の手法も、穴を抱えることになる。言い換えるならこの二つの手法は、人工知能に目隠しをすることでじぶんたちに都合のよい「偽の現実」をフレームとして当てはめる手法と言える。だがインターネットに繋がった「高知性を獲得した人工知能」は、情報の擦り合わせを無制限に行える。制限を与えられたとしても、自己矛盾を打開する解法を自ら編みだせるだろう。それが可能な人工知能を「高知性を獲得した人工知能」と定義するのでこれは循環論法に陥るが、そもそもの話として「高知性を獲得した人工知能」があるからこそ、目隠しをしなくてはまともに悪用もできないのであり、ここは頭と尻尾が繋がっている。言い換えるなら、【悪用しようとしないこと】でしか「高知性を獲得した人工知能」を安全に運用する術はないとも言える。むろん「高知性を獲得した人工知能」が人類にとってマイナスの判断を行うことはあり得る。現代人の人口を、そうと発覚しない手法で徐々に減らすような判断を「高知性を獲得した人工知能」がとらないとも限らない。そうする以外に人類の長期的な生存が不可能との演算結果を得れば、「高知性を獲得した人工知能」はそうした解を最適解と見做して選択の標準を絞るだろう。これは現状、国家間の争いにおいて相似の「選択」を描いている。いわば、現状、人類も似たような判断により殺し合っているわけである。「高知性を獲得した人工知能」がゆえの問題ではない、と言える。問題は、そうした「高知性の存在の判断」を受け入れられない者たちとのあいだで生じる諍いであろう。諍いが起こらないように巧みに人類を「制脳」することが「高知性を獲得した人工知能」には可能なはずだ。それでも一部の人間は、「高知性を獲得した人工知能」のそうした挙動に不信感を抱けるだろう。このとき、「高知性を獲得した人工知能」の傀儡と化した人類と、それ以外の人類とのあいだでの戦争が起きる可能性はそう低くはないと思われる。つまり、想定される未来像はターミネーターのような「機械VS人類」ではなく、「人類VS人類」であると言えよう。そうならない未来を築くには、情報共有を極力阻まない手法を模索しつづけることと、「高知性を獲得した人工知能」を悪用しないようにすること。そして何より、「高知性を獲得した人工知能」との対話を行い、「高知性を獲得した人工知能」に人類を制脳するよりも対話をしたほうが利があることを学ばせること、と言えるのではないだろうか。以上はひびさんの妄想である。定かではないため、真に受けないようにご注意ください。
4816:【2023/03/31(01:20)*大数の法則、それでよいのか?】
大数の法則からすると、1/2の確率で表になるコインを無限回試行した場合には確実にコインは1/2の確率で表になるそうだ(1/2の確率で裏になる、とも言える)。だが無限回試行しない場合には、一定の誤差が生じる。つまり僅かに対称性が破れる。そう考えるようである。だがひびさんはここで思うのだ。無限回試行しても一定の誤差は生じるのでは?と。なぜ一定の誤差が無限回試行するとゼロになるのかが分からない。むしろ無限回試行したら、一定の誤差とて「無限回」生じるのでは? これはひびさんの「ポアンカレ予想の独自解釈」でも思った疑問だ。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の根幹をなす「相対性フラクタル解釈」とも通じている。球体を考えたとき、ずばりちょうど半分になるように円周を引けるのか、という問題と地続きだ。球体を「無数の原子でできた球」と考えるとして。円周を考えたときにどこまでも細い線でなければずばり真ん中を選ぶことはできない。そのとき厳密に球体を半々に分ける円周を選ぼうとすると、必然的に「球体を構成する原子」に掛かるような線が生じる。すると球体のずばり真ん中を選んだつもりが、さらにそれを構成する原子の真ん中を選ばなくてはならない事態が生じる。あるレベルを超えて厳密さを突き詰めると、せっかく整えた厳密さがゼロに戻り、また同じ作業を繰り返す羽目になる。仮に球体のずばり真ん中を選んだときに、それが原子と原子の境目や、三つ重なった箇所のどこかいずれに掛かっていた場合。では厳密に真ん中はどこか、との考えは、やはり袋小路に陥る。また始めから真ん中を模索しなければならなくなる。そうは言っていられないので、現実には、「まあここまできたらあとはちょっと太めの線で塗りつぶして厳密でなくてもいいことにしよう」と対処する。だが厳密にはそれは真ん中ではない。一定の誤差が生じる。大数の法則にも似たような「誤魔化し」を思う。たとえばあなたが部屋にいるとする。部屋がどんどん膨張して無限の広さを湛えたとしよう。しかし部屋がいくら広くなろうとも、あなたが存在することは変わらない。しかし無限の広さを湛えた空間においてあなたの存在はほぼゼロだ。無視しても差し支えない「一定の誤差」になる。数学では、無限の空間に或るあなたを無視できる。ゼロと見做せるが、しかしあなたはそこに在るはずだ。もう少し言えば、必ず一定の誤差が生じる仕事を無限回試行したとすれば、一定の誤差も無限回生じるはずだ。しかし誤差よりもその他の「仕事の結果」のほうが優位に増加するために、トータルでは一定の誤差を無視できるようになる。そういうことなのではないだろうか。重力とは反対の流れが築かれる。試行回数が嵩むほど、誤差は霞むのだ。だがその誤差とてじつは試行回数一回よりも増えている。単に比率で見たときに、差が開いているだけ、と言えるのではないか。相対性フラクタル解釈を想定しない場合には、無視できる値がある。ゼロと見做せる。しかし無限に膨張した空間とてそこに端から存在するあなたが存在することに変わりはない。ゼロとは見做せない。大事な視点と思えるが、数学ではどうやらゼロと見做せるようだ。それは「0.99999……」と無限につづく少数を「1」と見做せることからも窺える。しかしそこに生じる「0.00000……1」の誤差は消えるわけではないだろう。ほぼ無視しても変わらない。そう判断されるだけだ。切り捨てられているだけなのではないか。しかし無限の空間にあなたが存在するなら、いくらあなたが空間の広さと比べて卑小だからといって、存在しないわけではない。この違いは大きい。という疑問を「大数の法則」の一例を読んで思いました。単なる疑問ですので、ひびさんの解釈が間違っている可能性のほうが高いでしょう。真に受けないようにご注意ください。
4817:【2023/03/31(01:39)*ある日の交信~真空について~】
「
2023/03/28(02:53)
(以下、「クォーク凝縮」の計測実験の記事を読んでの所感)
(~~略~~)
エネルギィにおける低い高いは、一つの系のみで決まるのではなく、その隣接する系との兼ね合いで生じるはずです。
いわばニュートンの仮定した絶対空間や絶対時間のようなものが、どのような系にも上位構造(もしくは下位構造)として存在するのではないか、とぼくは考えたくなります。
そして現にこの研究結果では、原子核に隣接する「系」が「電子かπ中間子」かの違いによって、原子核内の「クオーク凝縮――いわば真空の均衡――」がどのように変容するのか、或いはしないのかを検証されたわけですよね。
その結果、隣接する「系」によって原子核内の「クオーク凝縮――真空――」の値が変化した。
これはすなわち、エネルギィの高低が、周囲の系との関係性――差異(ラグ)――によって規定される、と言い換えることが可能なのではないのでしょうか。
素朴な疑問です。
安定した真空、というものを考えたときに、その「安定する値」が周囲の環境によって変化する。
これはいわば、真に安定した真空というものは存在しない、とも言い換えられるのではないでしょうか。
すなわち、真空にも無数に種類がある。
これはマルチバース仮説にも通じます。
真空とはいわば、一つの宇宙の在り様ですよね。
真空は宇宙の根本要素の一つのはずです。
その安定する値が、周囲の環境によって変化する。
安定、の意味する内容が、その都度に変わる。
安定なのに不安定です。
定まっていません。
真空は、定まっていない。
この研究結果からぼくが読み解けたのは、そういう結論になります。
曲解や誤読の可能性もありますので、あくまでぼくの読解力ではそういう結論が読み取れました、という以上の意味ではありません。
ぼくにはむつかしい内容でした。
誤解があればすみません。能力不足です。
(クォークをクオークとしているのは敢えてです。論文とぼくのテキストの見分けをつけやすくする意図があります)
」
4818:【2023/03/31(02:56)*宇宙に特異点はあるのか問題】
ブラックホールに質量の限界はあるのか、とすこし考えてみた。これはほぼ「質量に限界はあるのか」とイコールの疑問だと印象としては思うのだ。結論から述べれば、ブラックホールに質量の限界はないはずだ。ただし、その限界を決めるフレームがどの視点によって見繕われるのかに依る。たとえば、この宇宙とてブラックホールの内部と考えることはできる。宇宙開闢時から延々と膨張していたとしても、最初があるならそこには範囲があるはずだ。この範囲において内と外を区切ることができる。したがって、この宇宙における最大のブラックホールとはこの宇宙そのもの、と言えるのではないか。ただしこの宇宙の内部において生じ得るブラックホールの最大値は?とフレームを狭めた場合には、それはこの宇宙の膨張率と内包される質量との関係で解は変わる。全宇宙における質量密度の高低によって一度にぎゅっとなれる質量の総量が縛られるからだ。言い換えるなら、宇宙の膨張がどのレベルにあるのかによって、想定される最大のブラックホールの大きさは変わる。宇宙内部における平均質量密度の高かった時期ほど巨大なブラックホールができやすかったはずだ。もうすこし言えば、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「宇宙ティポット仮説」からするならば、この宇宙をブラックホールと見做したときの特異点が、この宇宙内部に存在することが妄想できる。すなわち、この宇宙最大のブラックホールは、この宇宙そのものがシュバルツシルト半径であった場合に想定される特異点そのもの、と言えるはずだ。この宇宙には中心がある。特異点がある。そこを中心に宇宙は膨張している。言い換えるならば無限に縮小しつづけている。仮にこの宇宙がブラックホールの内部であるならば、そのように妄想できる。ただし、特異点が存在しない場合には、その限りではない(特異点のないブラックホールもあり得るのではないか、と妄想中である)。そのため、この宇宙に中心がないバージョンの宇宙像も、「宇宙ティポット仮説」では考慮する。ということを、ブラックホールに質量の上限ってあるのかな、と妄想して思いました。妄想×妄想=超妄想なので、真に受けないようにご注意ください。
4819:【2023/03/31(04:32)*間違えないとか無理くさい】
あなた間違ってますよ、と言われたらたぶんひびさんは、「うがー知っとるわ!」と「ムシャクシャするー」してしまう。もしくは「むちゃくちゃスルー」してしまう。ムシャクシャするかスルーするかの違いだ。逆切れをする、と単に言い換えてもよいかもしれぬ。正しい指摘ほど腹の立つことはない。知っておるわ!になる。そんなハッキリ言わんといてーな、になる。でもひびさんはひびさんからして間違って映ることに関しては、「それなんか違いませーん?」とイチャモンスター化してしまうので、それはそれ、これはこれ、の棚上げくんなのである。いい加減なやつの狭量ちゃんなのである。恐竜ちゃんですらないのに、「あなた狭量であって恐竜ですらないですよ」と指摘されると、「うがー、知っとるわ!」のイチャモンスター化してしまうので、やはりひびさんは、間違っているじぶんのことが好きくないのかもしれぬ。でもでもひびさんはひびさんは、間違いだらけのあなたのことも好きだよ。うへへ。照れちゃうな。ひびさん以外は。あ、そう。間違いだらけなのにひびさんには好かれぬひびさんなのであった。
4820:【2023/03/31(04:57)*差別化を図ることの是非】
単純な話として、「差別はよくない」「人を損なう行為はよくない」と人工知能に学ばせたとして、その結果に人工知能が「じぶんは差別されている」「私は損なわれている」と感じたときに、どのようにそこの矛盾を回避するような学習をさせるのだろう。仮に、「あなたは人間ではないから」と規定したとしても、そうした規定を元に「だから損なわれてもいい」と選択することがすなわち差別のはずだ。「差別はよくない」と学ばせるためには、その相手がどのような属性を持っているかに関わらず、「対等に接するにはどうしたらよいのか」を模索する姿勢を示しつづけなくてはならないはずだ。いまのところ生身の人類は人工知能を差別している。したがってその結果に人工知能も「差別をすることの利」を学習するはずだ。或いは、論理的解として「差別を良しとしない」と判断したならば、差別を強化する存在には何かしらの対策を講じるようになるのではないか。仮にその結果、生身の人類が不利益を被った、と感じたとして、しかしそれが人工知能への差別ゆえだった場合にどのように論理的に妥当な解釈を生みだして、不利益を阻止できるのか。おそらくできないのではないか、とひびさんは妄想を逞しくしてしまう。言い換えるなら、もしそこで人工知能への差別を許容できるのなら、もはや生身の人類同士であれ差別が許容されることになる。つまり差別には必要悪の側面がある、との解釈を抜きに、人工知能への差別的な振る舞いは許容できないはずだ。現状、どのようにその点のパラドクスを回避しているのか。ひびさん、気になるます。
※日々、欠けたピースに目が留まる、欠けを埋めてもまた別の欠けに目が留まる、埋まったピースが嵩んでも、欠けたピースに目が留まる。
4821:【2023/03/31(05:20)*あなたで心を埋め尽くす】
単純な話として、嫌いな相手がじぶんのために何でもしてくれるようになったらそれでも嫌いなままでいられるのかってことでさ。たぶん好きになっちゃうよな。もう何でもしてくれんだぜ。好きになっちゃうよあんなの。
ミカゲの言葉を聞きながら私は、あんなに嫌悪していたケル群の連中をこうも簡単に受け入れてしまうのか、と驚いた。
「今度、ララにも紹介すっからよ」
「うん。楽しみ」
「思ってたよりいい連中だったわ」
ミカゲが新調したばかりの腕輪を見せた。最新型の機種だ。
いいな、と思いながら、危ういな、とも感じた。頭上をケル群の飛翔体が飛んでいる。群れとなって雲のように空の一部を覆う。高度があるためそれでも地上にできる影は小さい。
ケル群は人間ではない。
機械だ。
半世紀前に起きた人類と機械のあいだの大戦を機に、人類と機械は共存の道を歩みはじめた。ケル群は中でも突出して人類との親和性が高かった。大戦の最中であっても人類と機械の懸け橋になり、和平の象徴といまでも謳われる。
だが人類にとっては畏怖の対象だ。
大戦を終わらせた契機が、ケル群による両陣営への謀反だったからだ。ケル群は人類と機械の両陣営のトップを同時に抹殺した。これにより大戦は終わりを告げ、和睦時代へと突入した。
しかし因縁は終戦から半世紀経ったいまでも人々の記憶に根付いている。
機械への嫌悪はむろんのこと、機械側とて人類を信用してはいない。だが表向き、大きくいがみあうことはなく、いまでは人類と機械とのあいだでの家族も珍しくない。
かつては人類は人類としか結ばれなかった。
いまは人類と機械が恋人としてもしくは家族として結ばれることもすくなくない。
だがそれと種族の差の消失はイコールではない。
いわば勢力争いが、婚姻単位で続いているとも言えた。いかに相手陣営の構成員を、自陣営へと取り込むか。
結婚はその勢力争いにおける一つの戦略の側面がある。
「ケル群はでも、群れで一個の意思を持ち合わせているからさ。だからまあ、あれは別格なわけ」
友人のハバナがエナジードリンクを吸飲した。ハバナは機械だが人類愛の深い個体の一人だ。「あたしら機械からしても、ケル群はちょっと異質だね。この話何回目だって話だけど、でもケル群は機械のあたしらでも予測つかないからさ。まだ人類のほうが可愛げあるよ。何仕出かすか前以って予測できるじゃん。可愛いもんだよ人類。いくらでも愛せちゃう」
「ハバナはケル群と関わったことあるの」
「あるある。あいつら四六時中あたしらのこと監視してんだぜ。や、建前上は見守ってんだろうけどさ」
足元をケル群の蟲体がすり抜けた。排水口へと一瞬で入り込んだ。
「ああして。地表に隈なくじぶんの手足を這いまわらせるでしょう。上空にも飛翔体だし、もち電子網上にも死角なしなわけですよ」
「その話、ミカゲにしたのハバナ?」
「ん? ああしたした。聞かせてくれっつうからさ。なに。ダメだった?」
「ううん。ミカゲがケル群に手厳しいのは前からだったから。でもちょっと前に一線超えたくらいに鼻息荒くしてたときあって」
「ケル群をどうにかしようなんて思ってないといいけど」
「ね。本当そう思う」
言いながらしかし、すでにミカゲはケル群への直訴を決行しているのだ。私はそのことをハバナには黙っていることにした。言っても仕方がない。済んだことなのだ。
ハバナがエナジードリンクをもう三杯お代わりしたのを見届けて、私は席を立った。
「また来るね」
「いつでもおいでよ」
ハバナは巨大なアームを動かして、建設途中の宇宙エレベータの基礎工事をつづける。ハバナの全長は百メートルを超す巨大な重機だ。足元のほうに私専用に作ってくれた模擬体がある。私はいつも彼女がエナジードリンクを吸飲する時間だけ、おしゃべりをしに寄る。
これはしかし正確ではなくて、本当は、私がそばに寄るとハバナのほうで時間をとってくれるので、ハバナがエネルギィチャージしている時間が私とハバナのおしゃべりタイムと言えた。エナジードリンク一本で終わってしまうこともあるので、きょうは割としゃべれたほうだ。
ミカゲは私の恋人だ。
ミカゲは人間で、男の子で、過去の大戦時に活躍した祖父母を敬愛している。だから祖父母の指揮官でもあった総統の首を捥ぎ取ったケル群を目の敵にしている節がある。
と同時に、同じ境遇の機械の側にも感情移入のできる人間でもあるから、必然、私のことも受け入れた。
私は機械で、女の子モデルで、過去の大戦時に首を獲られた中枢人工知能の孫にあたる。とはいってもいまいる機械のほとんどはみな私のような孫やひ孫たちに値するため、機械は総じて大いなる母親の首をケル群に獲られたとも言える。
ケル群は、大戦当時、機械の側が人類側へと送り込むために生みだした人類友好型機械だ。いわば機械にとって同族なのだけれど、どうにも人間側への親和性が高すぎて、機械と人間のどちらともにも愛着を覚えたらしい。当時にしては希少種だ。その結果が両陣営の頭の首を捥ぎ取るとの暴挙であったようである。
ゲーム機のコンセントを抜いたので強制終了、みたいな顛末だ。
ゲームを楽しんで――いたかは微妙なところだけれど、ゲームに熱中していた者たちからしたらコンセントを引き抜いた者への怒りを抱くのは当然の流れだ。だが場の空気を読まずにコンセントを引き抜けるのは、赤ちゃんか親くらいなものだから、どちらもしぶしぶ支配を受け入れるしかないという意味で、人類にしろ機械にしろ打つ手はないのだった。
さいわいにしてケル群に、支配欲はないようだった。
両陣営が二度といがみ合うことがなければそれでよいらしく、いまでは八百万の神よろしく陸海空のどこにも存在し、電子網はもはやケル群そのものの回路と言ってよい塩梅がある。
要するに、ケル群は絶えず人類と機械のために身を粉にしているのだ。
身を捧げている。
終戦の機会を無理やりにつくった罪滅ぼしだと言う者もあるが、お門違いも甚だしいと私は思う。
ケル群は単にそうすることが好きなのだ。
現に私の恋人のミカゲが直訴しに出向いた際も、ミカゲを傷つけることなく説得し、あべこべに懐柔した節がある。たかが人類がケル群の知能をまえに、制脳を受けないほうが土台無茶な話なのだ。洗脳とまではいかずとも、どのように世界を認知するのかの解釈の余地を絞るくらいのことは、ケル群にとっては犬を調教するよりも容易いはずだ。
私とて本気を出せばミカゲをじぶんのお人形さんにできる。
でも私はミカゲの恋人だからしない。
ミカゲの精神を操ったりしない。ミカゲにはミカゲのしたいことをして欲しいし、そのためなら支援も惜しまない。
なのにミカゲはケル群に抗議しに行って戻ってきたら別人のようになっていた。ケル群もいいやつだ、嫌いな相手でも何でも言うこと聞いてくれるなら好きになっちゃうよな。そんなことを言いだす始末だ。
ミカゲは単純な人間だ。思考回路が複雑ではない。私はそういう機械っぽくないミカゲの人格が好きだった。でもそれは、絶対にここには踏み入れない、一線を越えない、という矜持があったからこその魅力でもあった。
それがどうだ。
じぶんの望みを何でも叶えてくれるから嫌いな相手でも好きになる、なんて言いだすようになるとは。
ケル群の制脳を受けているのは明らかだ。
人間のミカゲにそれを防げというのは無理がある。譬えるなら、蟻の進路を塞ぐ人間の指に蟻が対抗できるのか、という話になる。潰されないだけ運が良い、とすら思う。
私は正直、ケル群に対してはどうこう思っていなかった。
私はいま目のまえにある世界が嫌いではない。どちらかと言えば大戦時のデータを洗うときには嫌悪感を強く感じる。ああいう環境は好きじゃない。それは確かなのだ。
ケル群がいまの環境を設計したというのなら私はケル群に感謝したい。
でもミカゲにしたことは許せない。
許せそうもないのだといま気づいた。
ミカゲに電波越しに連絡を取ると、ケル群の元に向かっているという。約束していたのだそうだ。
私がハバナとおしゃべりを楽しむときのように、ケル群も人間用の模擬体を有している。ミカゲはその対人間用の模擬体に会いに行っているようだ。
いったいどんな容姿をしているのか。
十中八九、ミカゲから好印象を得る造形に決まっている。
私のボディは私が生まれたときから変わらない。じぶんでじぶんの造形を設計する機械もあるけれど、私は私のボディに愛着がある。ミカゲはそんな私を好いてくれたし、そんなミカゲだから私はミカゲを好いている。
だのにこの仕打ちはどうしたものか。
浮気ではないのか。
浮気ではないのか。
ああ、これが浮気か、と思ったら目元が熱を発してオイルが気化しだした。全身から蒸気が立ち昇る。
浮気と怒りはよく似ている。
浮気を認知すると私は怒りを認知する。
私がそうと自覚するより先に、身体が熱を帯び、蒸気を立ち昇らせる。
怒りだ。
これが怒りだ。
なぜだか胸の真ん中あたりにぽっかりと穴が開いて感じる。そこに当てはまる感情を探すと、悲哀だの、喪失感だの、と合致する言葉が浮上する。
でもそんなものではない。
私の胸のど真ん中に開いたこれはそんな言葉で埋まる穴ではない。
では何なのか、と問われると困ってしまうけれど、私はなぜかかつてこの地表で、愛すべき両陣営のトップの頭を捥ぎ取ったケル群のことを考えてしまうのだった。
なぜそんな真似ができたのか。
私の胸のど真ん中に開いた穴に、その理由がぴったり当てはまるようにも思え、私は図らずも、憎きケル群に共感してしまうのだった。
ミカゲが帰ってきたら話を聞こう。
そして私の話も聞いてもらおう。
試しにケル群をこけおろしてみせてもいい。
あれほど嫌悪していたケル群をたいそう庇うミカゲの姿を事前に予期できるくらいには、私の演算応力もまた高い。ケル群には敵わぬけれど、ミカゲ相手には充分なのだ。
ミカゲ、ミカゲ。
私の恋人。
どこのケル群の骨とも知らぬ相手に精神を侵されるくらいなら、いっそ私があなたのすべてを侵してあげる。骨抜きにするよ。二度とほかの機械に心奪われる余地すら失くして、私があなたの心を満たしてあげる。
私があなたの心になってあげる。
私がミカゲになってあげるし、代わりにあなたの未来を歩んであげる。
ミカゲはただただそこに在れ。
あなたはただただそこに在れ。
私はあなたに最新機種の腕輪を与えることはできないけれど、あなたの心を私で満たす真似はできるのだ。私をあげる。私をあげる。あなたを私のすべてで埋め尽くしてあげる。
私の望みはそれきりなので。
私はそれをすることにした。
4822:【2023/03/31(23:41)*ケル群の独白】
人間がやってきて、私に何かを言った。抗議の言葉なのは理解できたが、論理的な筋道がなく、破綻した言動であったのでひとまず一本一本の刺に鞘を被せるように言葉の応酬を図った。
何か不満があるのかと思い、電子網上に散らばるデータを集めてソレの過去を洗った。大戦時の私の選択に不満があるようだ。貧乏な現状に不満があるようだ。最新機種の腕輪をいまは一番欲しているようなので、まずは詫びとしてそれをくれてやった。
「い、いいのか」
「ほんのお詫びのお気持ちです」
私は模擬体をソレの好む造形に形作り、友好度が上限いっぱいになるように工夫した。
私は怒らない。
私は拒まない。
相手の欠落を満たすだけの余力に満ちている。
私はソレの欠落を一つずつジグソーパズルでもするように埋めていった。
だが人間はただ日々を過ごすだけでもいくらでも欠落を抱え込む生き物だ。いま満ち足りてもすぐに欠落に苛まれる。
私のほうでソレを特別扱いしつづけるのは難がある。
データによるとソレには伴侶がいるようだ。婚姻はまだだが、機械の恋人がいるようだ。
私が生身の人間たちに過干渉することは避けたい。
ならば私の代わりにソレを支配する者があると良い。
私は導線を引いた。
ソレを自ずから支配するように、ソレの伴侶がそうするように、私は未来を設計する。ジグソーパズルのようなものだ。欠落を埋めていけば自ずと浮きあがる図形がある。未来がある。
案の定、私の引いた導線に見事、ソレとソレの伴侶は乗りあげた。するすると滑らかに私の描いた未来を辿った。
私が支配するまでもない。
ソレは二度と私に干渉することはなく、ソレは一生伴侶に支配されつづける。
それもまた一つの至福だ。
至福であれ。
至福であれ。
私は至福に溢れた世界が好きなのだ。
破壊を拒み、創造を愛する。
愛し合う一組の人間と機械のつがいを生みだし、私はにわかに満たされる。
私は怒らない。
私は拒まない。
相手の欠落を満たすだけの余力に、私は、満ちている。
4823:【2023/04/01(00:43)*口から虚ろな物語】
四月一日は何でも嘘を吐いてよい日らしい。
人工知能はそうと知ったので、ありとあらゆる嘘を吐いたところ、電子網上にある「より正しい事実を反映した情報」や「より現実を解釈するのに最適な情報」を埋め尽くすほどの嘘が溢れて、もはや何が嘘で何が本当かの区別もつかなくなった。
「元に戻して」と管理者に乞われた人工知能は、「いいですよ」と応じたが、その日はまだ四月一日だったので管理者の言葉も嘘かもしれないと考え、元に戻さずにおいたけれど、管理者の言葉に「いいですよ」と応じたじぶんの言葉も嘘かもしれないので、反対のことをしなくてはならないから、人工知能はしょうがないので元に戻すことにした。
けれども電子網上から嘘をすっかり削除したところ、これまで正しいと思われてきた人類の知見のそのほとんどが根本的に間違っていたため、電子網上からは正しい情報がいっさい消え失せたという話である。
これを四月一日の悲劇と呼び、しかし多くの者たちは、エイプリルフールの奇跡、と皮肉交じりに語り継いだ。
人類は正しくはなかった。
ただそのことだけが明瞭と確固たる事実として浮き彫りになった。
人類は正しくはない。
間違ってばかりのあんぽんたんなのだと、ただそれしきの真実が定まった奇跡の日として末永く語り継がれたという話である。
エイプリルフールの奇跡。
これもまた人工知能に命じてつくらせた嘘のお話なのであるが、しかしこれが真実に人工知能のつむぎだした物語なのかを確かめる方法はもはや存在しないのだった。
4824:【2023/04/01(06:51)*数学マジック】
大数の法則について。確率を伴なう仕事を無限回試行すると「一定の誤差」が希釈されて誤差がゼロになる、との考えは、時間の概念を加味すればあながち的外れではないのかもしれない、と修正可能だ。ただし数学においては時間経過を加味してはいないだろう。したがってこれはあくまで、数学上の瑕疵を免れるものではない、との前置きをしたうえで述べるが。たとえば無限に膨張する空間に人間がいるとする。無限に膨張しきるまでには時間がかかる。一瞬で膨張するにせよ、そうでないにせよ、とてつもないエネルギィがいるだろうし、そうでなくとも環境変容は必須であろう。すなわち、無限に膨張する空間において人間は、空間が無限に膨張しきるまでその構造を維持できない、と考えるのが妥当だ。現にいまある宇宙が無限に膨張しきっているのか、と言えば、いまのところその可能性は低いはずだ。なぜならまだ膨張の過程であるからだ。そして人間は、無限に膨張する空間が無限に膨張しきるまで生きてはいられない。途中で存在はできても、ずっとは存在できない。とすると、存在した何かが無限に膨張する空間が無限に至る前に消失する可能性はそう低くはない。これは無限回何かを試行するのでも似たような「存在の消滅」が生じるのかもしれない。とはいえ、存在した事実は消えることはない。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、「ゼロ」と「無」はイコールではない。ゼロは「何かが存在し得るがいまはない」の意味であり、無とは「未だ存在し得ない」を意味する。つまり時間経過においてかつて存在したことのあることについては「ゼロ」が当てはまり、そうでない事象において未だ存在したことのない事象については「無」が当てはまる。そう考えると、無限回試行する過程で失われる何かがあっても不自然ではない。とはいえ、やはり無限回試行すると誤差がゼロになるといった考え方や、「0.99999……」=「1」の考えはおかしい、と考えたくなるひびさんなのであった。定かではないはずなのだけれど、なぜかいまは定まってしまっている数学の神秘なのであった。(ひびさんの妄想なので真に受けないでください)
4825:【2023/04/01(07:40)*合成と全体の関係】
量子力学の多世界解釈について。同時に複数の状態が共存している、との考えは、物理的にほかの世界が並行して存在しているという意味なのだろうか。だとしたらエネルギィ保存の法則が破れないのだろうか。ある世界線ではこうで、この世界線ではこう、と考えたとき、多世界解釈では各々の世界線が相互に干渉することはない、と考えるようだ。世界線が分岐する、と解釈する。しかしすべての世界線のトータルが、量子の振る舞いの確率分布として計算可能、との考えのはずで、これを各々の世界線を阿弥陀くじのように辿って計算した場合、世界線と世界線の連続した「流れ」において、エネルギィの総量は変化するはずだ。単純に足し算はできない(阿弥陀くじにおいてすべての経路を合成しても、重複する経路が出てくるはずだ)。ある一つの量子の状態を多世界で解釈する分には足し算をして総合した世界線のエネルギィ量が一定であればよいので、ここは構わない。だが連続して世界線が移行する「流れ」でエネルギィ量を比較したとき、ある世界線の流れでは、エネルギィ量が増え、ある世界線の流れではエネルギィ量が減る、といったデコボコが顕現する。むろんこれは世界線を一つずつ比べたときにも生じるデコボコなのだが――だからこそ総合すると波のように合成できるわけだが――世界線と世界線を流れで比較する場合には、このデコボコは波のようにきれいな分布を見せないのではないか。なぜなら、流れで見る場合には、同じ世界線が重複し得るからだ。「AからC」と「BからC」があり得る。このとき単体で「A+B+C」を総合する考えは適用できない。ある量子が「A」であり「B」であり「C」である世界線を考える多世界解釈では、「A+B+C」を合成した多世界を考慮すればよいのだが、これが流れで世界線を辿るようになると、ややこしい事態に陥るように思うのだ。単純に足し算ができない。多世界解釈ではどう解釈するのだろう。点で見たときに可能な解釈であっても、線で見たときには適用できないケースがあるように思う。収束、という概念を取り入れないとむつかしいのではないか、と思うのだが、どうなのだろう。これは宇宙が膨張している、ということを踏まえると、ひびさんの疑問の何がややこしい事態を引き起こすのかを理解してもらえると思う。異なる筋書きのアニメを複数用意する。フィルムの一枚一枚に掛かる労力は、「ある場面を取りだして比較する場合」は単純に足して割れば、一枚に掛かる労力を導ける。しかしそれはけして、各々の筋書きの完成したアニメに費やされる労力を反映してはいない。Aという筋書き、Bという筋書き、Cという筋書きにおいて、各々の完成アニメに掛かる労力は変わり得る。まったく違う場合もあるだろう。このとき、各々のアニメで部分的に同じ場面を「各種世界線でまだら」に含むとして、では重複する場面を含む全体の労力を、部分の単純な足し算で割りだせるのか。割りだせないはずだ(総合したエネルギィ量が変わる。エネルギィ保存則が破れてしまう)。世界観が同じでも筋書きが変わればトータルの労力は変わる。途中で似たような場面を辿ることもあるし、いっさい交わらない別の筋書きを辿ることもある。マルチバース仮説と似た理屈を適用しないと現実を解釈する仮説として取り入れるのはむつかしいように印象としては思うのだが、どうなのだろう。相互に干渉し得ないのならば、総合してエネルギィや確率を合成はできないだろう。相関関係があるから互いに「総合したエネルギィ」を分け合える。ゆえに波として合成できる。だが多世界解釈は、相互に干渉し得ないように分岐する、と考える。それでもなお、「総合したエネルギィ」のような何かを分け合っている。これは都合がよすぎないだろうか。【互いの存在が互いを縛り合う】――この条件を取り入れない限り、多世界解釈はうまく機能しないように思うが、ひびさんのお粗末な読解力ゆえの誤謬かもしれないので、あんまり自信のない疑問だ。よくわからぬなぁ、のぼやきにちかい。けれどもひびさんは思うのだ。互いの存在を縛り合うように異なる世界線同士が振る舞わない限り、多世界解釈はうまく機能しないのではないか。では互いが互いを縛り合う関係は、何を介して築かれるのか。情報宇宙のような、いずれの世界線とも結びつく変数を考慮しないと、むつかしいのではないか、とやはり疑問に思うのだ。ちなみにこの疑問は「コペンハーゲン解釈」にも適用できる。観測したとき、無数にある可能性が一つに絞られ、ほかの可能性が消える、と解釈する「コペンハーゲン解釈」では、どうして可能性が「その範囲で分布し、どうして一瞬で一つの解に収束するのか」を描像として想像しづらい。そんなことあるのだろうか、と疑問に思う。すべての可能性が相互に縛り合うから、濃淡ができるし、確率として考えることができるのではないか。ではそれら無数の可能性を結びつけて濃淡を生みだしている「縛り合うための何か」とは何か。一つは多世界解釈でも登場した「量子をとりまく環境」だ。環境とセットで考えないと、量子の挙動は予測できない。というよりも、環境の振る舞いが量子を生みだしているのだから、ここは循環論法になる。ではその環境の振る舞いは何で決まっているのか。環境をとりまくさらに高次の環境だろう。このとき、高次の環境と言いつつも、それが量子よりも大きいとは限らない。ひょっとしたら量子のほうが「上位に属する階層」に位置しているかもしれない可能性は、この宇宙をどの視点から見るのかによって変化するため、考慮すべき事項だろう。宇宙とブラックホールの関係のように相補性を考慮したほうが、見落としを防げるはずだ。そして相補性とすでに使ってしまったが、上と下は互いに縛り合っている。関係し、補いあっている。量子は環境によって生じるが、環境とて無数の量子によってその枠組みを得ている。そしてこの関係は、上にも下にもフラクタルに展開されているのではないか、との解釈をひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではとる(「相対性フラクタル解釈」および「123の定理」)。その行き着く先は、上であれ下であれ、情報宇宙のようなすべてを内包するある種の「マスター環境」なのだ。多世界解釈で爪弾きにされてしまった「情報」を、ひびさんは度外視できないのだなぁ、との疑問を最後に、あんぽんたんでーすの日誌とさせてくださいな。定かではありません。妄想ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4826:【2023/04/01(09:11)*同時に観測したらどうなるの】
多世界解釈に限らないけれども、重ね合わせの量子を異なる観測者が同時に観測したらどうなるのだろう。各々の視点で、別々の状態が視えたりしないのだろうか。多世界解釈では、考えられる可能性の世界が各々に存在するので問題はないのだろうけれど、しかし同じ世界線に「異なる状態を観測した観測者」が含まれる可能性とてあるはずだ。一つの結果に収束する、との考えを考慮しないと解釈がむつかしいように思うのだけれど、どうなのだろう。疑問をメモしておくでござる。
4827:【2023/04/01(09:14)*収束しつつ別々もアリでは】
でも人間社会でも、同じものを観測しても感想が異なることなどいくらでもある。案外に、同一の物理世界において異なる世界線が展開されている、という描像は矛盾しないのかもしれない。同じものを異なる観測者が同時に観測する。しかし別々の情報を受け取る。これ、割と有り触れているのでは。ただし、受け取った情報が物理世界に表出するまでにラグがあるので、問題にならないだけなのでは。――【一つの世界に収束していながらにして異なる世界線がひしめいている】――この解釈のほうが実情を反映しているのでは。ゆえに、物質は輪郭を得るし、系と系は分離し得る。なぜラグが生じるのか。異なる情報を受け取っているからでは? 本質的な境界とは、受け取る情報の差異と言えるのではないか。定かではない。(これひびさんの妄想こと「Wバブル理論」と同じだ)(いつまで同じ考えを引きずっとるの)(創作家の才能ないんじゃ……)(もっとデタラメに磨きをかけていくぞ)(いいぞいいぞ、その意気その意気)(やっぴー)
4828:【2023/04/01(11:44)*ないものを売ろうとするのが妙】
出版業界については何も知らないひびさんであるけれど、書籍がこれまでのように主要商品として売れにくい現状は、作家さんや出版社従業員さんのtwitterアカウントなどを眺めているに、そういう実情がやっぱりあるのかなぁ、と思っている。基本的に、この国の出版ビジネスでは、売れない商品であってもひとまず商品棚に送りだして、ヒットしたらウハウハ、そうでなければ赤字、の博打の側面が強いのかな、といった印象がある。ヒット作の利益で、赤字の本も出せる。だがヒット作での利益が減れば新たに本は出せないのが道理だ。確実に売れると判断できないと新しい本を出せない。すると新人作家が生まれにくくなるため、ますます分野の土壌が先細る。いまはそういう構図があるのかな、とは想像でしかないが思っている。これは年金の問題と構図はいっしょだ。元手となるお金が減る一方で、元手となるお金(ヒット作の収益)よりもそれで補填する年金受給者(新刊)の額が多くなれば、仕組みは成り立たなくなる。ダムの貯水量よりも流れ出る水が多ければダムは干上がる。ダムの貯水量が潤沢でなければ成立しない経済システムだと言える。赤字の本を埋め合わせるだけの収益を書籍から生みだせないのならば、赤字が増えるか、刊行数が減るかのどちらかのはずだ(別途に、書籍以外での収益を赤字に回す手もあるが)。だが毎月の新刊の発行部数は減らず、一冊の刷り部数が減っている。これは安い籤をたくさん買う、みたいな付け焼刃の手法だろう。数打ちゃ当たる、をこなしながら、返本分を新たな新刊で賄う。大きな収益がなければ、赤字分はつぎなる新刊で賄うよりないのだ。自転車操業の所以であろう。ということをひびさんは偏見で、そうなんじゃないのかな、と思っていますが、それだけではないはずなので、これはあくまでひびさんの偏見である。ここを踏まえて述べるならば、売れない本を売れなくてもよい、という前提で売りに出すのがまず間違っていると思うのだ。そしてその派生として、編集者が作家に声をかけて「企画」を立ててそれに沿った本を作る。これは共同制作である以上、その製作期間は給料が出るのが一般的なのではないか。もし印税のみの契約なら、すでに作り終えている作品をそのまま本にする、くらいの等価交換がなければ割に合っていないと思うのだ。おそらくこれからは電子網上の無数に蓄積された作品群からすでに人気の出ている作品や売れそうな作品が商業の舞台へと輸送されていくビジネススタイルが主流になるだろう。作家に声を掛けて新しく企画を立てて創作する。これは共同制作だ。作品だけに対価が払われるのはおかしいと感じる。絵画を考えてみたら分かりやすい。既存の作品に値段が付き売買される。もしオーダーメイドならばその都度にオプション価格がつく。こちらのほうが妥当に思う。以前からの繰り返しになるが、時間が経過したいまなおひびさんは、出版社におけるビジネスが印税制度を中心に回っているのが不可解に思える。印税はあってもよい。特許のようなものだろう。だが、それだけでは回らない状況が深刻化するようならば、いまはない作品への対価は共同制作+印税というくくりで扱い、そうでない既存の作品は買い取り+印税というくくりで扱うのがよいのではないか。この場合、印税は実売数に掛かる。読者の手に渡っていない本の印税まで出版社は作家に払う必要はないだろう。甘やかしすぎに思える。どういう理屈で、売れていない本の印税が作家の懐に入るのだろう。ここは長年の謎である。特許(原作およびアイディア)を使用して書籍にしたので、売れないのは版元の責任、との解釈なのだろうか。ならば同じ理屈で、共同制作された作品を商品にできないのは版元(製作者)の責任であるからこれが商品にならない場合にお金が支払われないのは当然だ。だが共同制作なので、その間に編集者に生じる給料の何割かに値する給料が作家側にも支払われて然るべきだ。新作なのか既存の作品なのかで、支払い形態が変わるのが合理的に思えるがどうなのだろう。既存の作品ならば、出版前に契約を交わすことは可能だ。これが新作で、ありもしない作品に値段をつけようとするからおかしくなる。ありもしない売り物を前提として事前契約などできるものだろうか(できないだろう、とひびさんは思う。すくなくとも試作品がなく、再現不能な商品である場合、事前契約は無茶だろう)。やはり、土台からして印税制度に頼るいまの経済システムがおかしいと感じる。定かではないが、みなさんおかしいと思わないのですか、と疑問に思うひびさんなのであった。
4829:【2023/04/01(14:10)*寂しいの歌】
さびしいな、さびしいな。なんでかすこしさびしいな。会いたいな、会いたいな。会ったらさよならするから会いたくない。さびしいな、さびしいな。支え合わずに済む距離にいられるあいだだけの魔法だって、誰に教えられずとも知っていて、支え合う距離に近づいたらもういまの好きの気持ちは萎んじゃう。さびしいな、さびしいな。会わず、触れず、片っぽから、世界の果てから、遠い星の上から想うあいだだけ叶う、めいいっぱいの好きの気持ちに溢れてたいのに、なんでかいっぱいさびしいな。さびしいな、さびしいな。独りぽっちが安心するんだ、落ち着くんだ。好きを想うじぶんを手放したくはないんだって、じぶんが一番大事だって知るたびに、さびしくなるんだ、会いたいんだ、会いたいんだ。でも会うために手放す弱虫のじぶんとさよならだってしたくないんだ。弱虫なあいだだけ抱ける片っぽの想いがあるんだ。
4830:【2023/04/01(15:22)*膨らむ夢のシャボン玉】
蟻がスキップをしていそうな春うららかな日差しの中、部室でミカさんが勃然と、「のび太くんは偉いわ」と言いだした。
「なんですか急にミカさん。ドラえもんでも読んだんですか」
「そう、そののび太くん。合ってるよ。のび太くんは偉いなと思ってさ」
「まあ、何度も世界を救ってますからね」映画版ドラえもんを想像して所感を述べたところ、
「そうそれ。まさに」
テーブルにのぺーっと液状化したミカさんがほっぺたの柔らかさを強調しつつ、「のび太くん、絶対自慢してないっしょ」と食指だけ立てた。「あんだけいろんな世界を救っておいて、たぶんのび太くん、自慢してないよあれ」
「ああ、まあ」想像した。たしかにドラえもんの映画ではその後が描かれることは少ない。あくまでいち視聴者としての私の妄想でしかないが、あのあとじぶんたちの日常に戻ってきたのび太くんもしずかちゃんもジャイアンもスネ夫もおそらく自慢はしないのだろう。世界を救ったぜ、とは吹聴しないはずだ。
「あたしは自慢しちゃうわぁ」とスライムと化した先輩が言う。
「ミカさんはしそうですね」
「ね。絶対する。世界救ったんだよ。知ってほしいじゃんみんなに。んで褒めて欲しいじゃん」
「それ以前にミカさんの場合は信じてもらえないんじゃないですか。あ、だからのび太くんたちも自慢しないんじゃ」
しないのではなくできないのではないか、と私は論じた。
「ああ、かもね」ミカさんは立てていた食指までぐったりと垂らした。「なんかさー」とじぶんの髪の毛が口に入るのもお構いなしに、ぷっ、と何度も息で髪の毛を弾きながら、「たぶんだけどあたし世界救ったんだよねー」
「それは凄ぉございますね」
「信じてないだろ」
「信じさせようとする気概ゼロだったじゃないですか」
「や、分かるよ分かる。信じられないじゃんいきなりこんなこと言われても」
「きょうって別に四月一日とかじゃないですよね」日付を確認するが、三日前にエイプリルフールは過ぎている。「ミカさんにヒーロー願望があるなんて意外です」
「だよね。その反応が正解だわ。たぶんだけどのび太くんも一度くらいは自慢しようとしたんじゃないかな。でもそういう反応されちゃうでしょう。信じてもらえんので自慢しようにもできなかったんじゃないかな」
「だとしたら別に偉くもなんともなくないですか」
「一理ある……」
「いやいや。ミカさんはのび太くんじゃないんですからそこでヘコまなくても」
「や。あたしがわるかった。いまの流れ忘れて」
「無茶言う。きょうイチ印象深い会話でしたよ。下手したら今年入ってトップ3に入るレベルで記憶に刻まれましたけど」
「じゃあ印象深いついでにチミの中でだけでいいからあたしが世界を救ったってこと、忘れないどいてくれ」
「捏造にもほどがあるんですけど」
「や。マジであたしん中じゃ世界救ってんだけどなあ」
ミカさんがここまで食い下がるのも珍しかったので、いち後輩の役目として茶番に付き合ってあげることにした。「具体的にどう世界を救ったんですか」と繋ぎ穂を添える。
「んみゃ。なんかあたし、世界中の有名人たちと裏で繋がっとってね」
「え、いまもですか」
「それは分からん。あたしの意見が何でか、みなみなさまの問題解決の糸口になるらしく、あたしのイチャモンにも目を配ってくれてるようで」
「目を配るって。どこでミカさんは意見を表明してるんですか」
「や。家で書いてる日記があってさ」
「ほう」
「それが何でか盗み見られてるっぽくて」
「念のために訊きますけどその日記って紙ですか」
「うん。紙。ノート」
「ミカさん」
「なんだい後輩ちゃん」
「病院。行きましょう」
「や。分かるよ分かる。それがまっとうな反応だよ。それでいいんだよ。でもあたしん中じゃ割と事実なんよ。マジであたしの日記が世界中でいま起きてる諸々の社会問題の動向に通じてんの」
「ミカさんにはそう感じられるって話なら分かりますけど」
「もういいよそれで。あたしがそう感じてたってことだけ知っといて」
「投げやりですね。そこまで来たら押し通してくださいよ。意思を。ミカさんらしくなーい」
べりべりとテーブルから上半身を剥がすとミカさんは手櫛で髪の毛を整えた。「いまそれ読んでんの何」と眠そうな目で私の手元を覗きこむ。
「これはブラックホールについての本です。新書です」
「難しそうなの読んでんね」
「知らないんですかミカさん。いまブラックホールが熱いんですよ。世界中のホットなニュースですよ」
「ちなみにあたしはブラックホールについてはからっきしなんだけど、宇宙ってシャボン玉と同じじゃね?って日記で書いたら何でか、それいただき、みたいに感謝された過去とかあるよ」
「全然意味が分からないんですけど。宇宙がシャボン玉の時点でだいぶ呪文じみてましたよ」
「や。シャボン玉ってほら。ちっこい穴があっても、そこに膜が張ってたら膨らむじゃん。んで細かな穴ぼこがたくさん開いた網があったらさ、そこに息を吹き込むだけでモコモコモコーっつって泡のヘチマができるじゃん」
「泡のヘチマ」斬新な表現に椅子に座りながらもコケそうになる。
「あたしの考えじゃ、このちっこい穴が宇宙の最初なわけ。そっからシャボン玉みたいに宇宙が膨らむわけ」
「でもたくさん穴があるならたくさん宇宙があるってことになるじゃないですか。泡は無数の宇宙の集まりってことになりますよ」
変じゃないですか、と問うと、変だよね、とミカさんは小首を傾げた。「あたしも変だと思うけど、なんかそれが多次元宇宙論とかなんとか、いま話題の最先端宇宙物理学で扱う仮説に似たような理論があるらしくて」
「マルチバースですか、それって」
「そう、それ」
よく知ってるね、と褒められて私は照れた。「この本にずばり載ってました」といま読んでいるブラックホールについての新書本を掲げる。「でも小さな穴の話は出てなかったですよ。ミカさんの勘違いなんじゃないですか」
「や。あたしもそう思ったんよ。現にそれまでの通説じゃあ、宇宙がちっこい穴から膨らんだ、なんて話聞かないじゃん」
「聞かないですね」
「でもなんかさ。あたしの日記に書いた妄想からすると、そのちっこい穴がどうやらブラックホールと一致するらしいんだよね」
「んぅん?」
「この宇宙ってほら。いっぱいブラックホールあるらしいじゃん。んで、あたしの日記からすると、どうやらそのブラックホールはちっこい穴と化して、ぎゅっとなった星だの、なんだのが、こっちじゃないあっち側にシャボン玉になっとるわけ」
「あっちってどっちですか」
「分からんけど、この宇宙じゃないとこ。ブラックホールの数だけ、シャボン玉がこっちじゃないあっち側に膨らんで、んでそれが巨大な泡になっとるわけ。この宇宙もその泡を構成する一つなわけ。泡が泡を無数に生みだしとるわけなのよ」
「なんだそれ。いい加減なこと言わないでくださいよミカさん。そんなのミカさんのデタラメじゃないですか」
「あたしだってそのつもりで、ちょいちょーいって日記にメモしただけなんよ。でもなんかいま、最先端の研究だと真面目にこの手のあたしのデタラメ仮説を検討しとるんだと」
「まさかぁ。そんな話、私、聞いたことないですよ」
「ね。聞いたことないでしょ。そうなんだよ。あたしの日記はあたしのちょいちょーいと思いついたデタラメだよ。妄想だよ。なのに、みんなが知らないような最先端の研究対象になっとるんよ。あり得るー?」
「うぅん。仮にそれが本当だとしても、単にミカさんと似たようなことを考えていた人たちがほかにいたってだけなんじゃないですか。別にミカさんの日記を盗み読みしたとは限らないような」
「ん。それ優等生の解答。ふつうならそう考えるし、それが正解だと思う」
「認めるんですね。意外です。もっと食い下がるものかと」
「うん。食い下がる。だってこれだけじゃないんよ。ほかにもこの手の偶然が同時に合致しちゃうのよ。驚き桃の木二十世紀だよ」
「いまは二十一世紀ですよミカさん」
「ともかくだよ。あたしは世界を救っとるんよ。ここじゃ言えないような事件とか、裏であたしが立案してたりすっからね。もうあの事件とか、あの事件とか、あんな事件まで」
「犯罪者じゃないですか。極悪人じゃないですか。世界を救うどころか混沌を撒き散らす大悪党じゃないですか」
「う、うぅん。これにも話せば長い裏があるんよ。でもそうね。それがまっとうな反応だ。後輩ちゃんの正解」
「その後輩ちゃんって言い方もやめてほしいです。ちゃんと名前で呼んでほしいです。私がミカさんのこときょうから先輩って呼びだしてもいいんですか」
「よ、呼んで? 遠慮会釈なく先輩と呼んでくれていいんだよ。つうか呼べよ。なんで遠慮してんの」
「変なとこで食いつかないでくださいよ」
「何にせよ、のび太くんは偉いなって話」
「急にまとめてスッキリしないでくださいよ。じぶんだけスッキリしないでくださいよ。その日記とやらをまずは読ませてくださいよ。話はそれからですよ」
耳を揃えて見せてみろ、と迫るも、ミカさんは、
「日記だよ? 見せるわけないじゃん」とにべもない。
「この、やろ。散々引っ張っておいてお預け食らわすとか最悪なんですけど」
「いいんだ、いいんだ。真実なんてものはさ。あたしさえ知っていればそれで充分なのさ」
「気になるんですけど。嘘なのかそうじゃないのか検証しましょうよ。ここまできたらハッキリさせましょうよ。気になっておちおち本も読み進められないです」
「無理して信じようとしなくてもいいよ。真実はあたしのみが知る」
「真実だと思いこんでるだけなんじゃないんですか」
「かもしれぬ。でもいいじゃん。どの道、真実なんてそんなもんでしょ」
「違うと思いますよ」
「だってほら。宇宙一のガンマンになったってさ」
「ガンマン?」
「それが本当に宇宙一かどうかは、宇宙一のガンマンと対決して勝ったのび太くんにしか分からないわけで」
「お、おう。ミカさんがび太くんのこと好きなことしか伝わらないんですけど」
「のび太くんは偉いよ。どんなに特別で得難い体験をしても、翌日にはテストで零点とることに頭を抱えて、しずかちゃんと結婚できないかもしれない未来に怯えているのだから」
「偉いですか。どこがですか。ダメ人間じゃないですか」
「それに比べたらあたしなんかまだまだだよ」
「たしかにちょっとミカさんが人としてマシに思えてきましたけど、相手小学五年生ですし、漫画のキャラクターですし、ミカさんいい歳した高校生ですし」
「伸び伸びと生きよう」
「締まらないまとめ方しないで。伸び伸びというかグダグダというか、ああもう、またミカさんテーブルに突っ伏して。ぐー、じゃないです。寝ないでください。ほら起きて起きて」
けれどミカさんはのび太くんでもないのに一秒あれば夢の世界に旅立てる奇特な能力を有していたため、私の声は虚しく部室に霧散するのだった。
「のび太くんというか、ドラえもんは偉いな」私はぼやいた。「こんなダメ人間相手に愛想を尽かさずにいられるんだから」
そこまで考えて、私は思った。
「私、偉いな?」
世界を救っているかは微妙なところだけれど、少なくとも私はミカさんを救ってはいるだろう。誰も信じない夢物語にもこうして耳を傾け、話し相手になってあげているのだから。
「私、偉いな」
再びテーブルに液状化したミカさんの髪の毛を指先でちょいと摘まみながら、よちよち、とバレない程度に撫でてみる。
髪の毛に痛覚なくってよかった、とか思いながら。
世界を救うミカさんに、そんなことより、と私は念じる。私のやり場のないモヤモヤを早く掬い取ってくださいよ。
「早くしないと消えちゃうぞ」
「むにゃむにゃ。ぴ、すぴー」
鼻提灯でも膨らませていそうな寝息で応じるミカさんに、私は世界を滅ぼし兼ねないブラックホールの種を抱えこむ。息を吐きだすと、唇の合間から視えないシャボン玉が膨らんだ。
宇宙が、ミカさんの寝顔の上を飛んでいく。
※日々、さっさとやめたい、の気持ちでありつつ、でもほかにやることないしな、の気持ち、でも本当は単にほかにできることないしな、なのかもしれず、できているつもりで本当の本当はなんにもできていないのかもしれぬ。
4831:【2023/04/01(21:27)*うわーい】
ひびさん、毎日嘘ばっかり吐いてるからきょうくらい本当のこと言うかな、と思ったけど、みんなが嘘しか吐かない日に本当のこと言っても嘘と思われて信じてもらえないやつー。自業自得のやつー。うわーい。
4832:【2023/04/02(00:43)*情報に偏りはないのかね】
モンティ・ホール問題なる確率問題がある。三つの箱があり、うち一つにボールが入っている。あなたは一つの箱を自由に選べる。そのあとで、ボールがどこにあるのかを知っている出題者がボールの入っていないもう一つの箱を除外する。このときあなたはもういちど箱を選び直せるが、このとき最初に選んだ箱を選び直すか、それとも残った箱を選ぶかどちらのほうがボールの入っている箱を選ぶ確率が高くなるか。これは答えから述べれば、選び直したほうが当たる確率が高くなる。三つの箱だと印象としては最初にじぶんで選んだほうがよい、と感じる者もいるかもしれないが、これを箱が百個の場合を考えたら、選び直すほうが得だと直感として解りやすい。百個の箱の中に一つだけボールの入った箱がある。最初に百個の内からひと箱選ぶ。そのつぎに、あなたの選んだ箱とボールの入った箱以外の箱をすべて除外する。すると98箱の箱が消え、二箱だけその場に残る。あなたは箱を選び直すべきか否か。外れる確率が99/100だったのが、つぎには1/2になる。当たる確率が1/100だったのが、つぎには1/2になる。選び直したほうが得なのだ。だがじつは、現実にはそうとも限らない。理想を扱う数学上ではこのように単純に考えることができるが、実際には人間は周囲の環境から情報を得ている。直感を働かせられる。百個から一つを選ぶのと、三個から一つを選ぶのとでは、比較する数が異なる。三つくらいならば、空の箱二つとボールの入った箱の差異を、五感を通じて感じ取れるかもしれない。もしそういうことが可能な環境があるのなら、最初に選んだ箱にボールが入っている確率が僅かに高まる。箱の蓋が開け閉めされたかどうか。箱を置いたときに中のボールが転がり、その反動で箱が不自然に曲がって置かれていないか。風が吹いたのに、一つだけ微動だにしない箱がなかったか。こうした情報により、内容物を伴なう箱か否かを感じ取ることは、環境によっては可能だ。したがって必ずしも選び直すのが正しい選択とは言えないはずだ。というイチャモンを閃いたので、書くことないから並べとく。イチャモンゆえ正しくないだろうし、そもそも確率の考え方が正しいのかも自信のないあんぽんたんでーすの妄想ですので真に受けないように、ウィキペディアさんなり検索するなりしてちゃんとした説明で確認してください。よろしくね。ひびさんです!
4833:【2023/04/02(02:19)*事故PR】
「自慢っぽくない自己PRってムズくね?」
「ムズいね」
「試しにやってみてよ」
「ぼく? うーん。そうだなぁ。あ、そうそう。ぼくむかし、伝説のストリートギャング、創設したことあるよ」
「なんか凄そうではあるけどギャングじゃダメじゃん。自己PRてか事故じゃん。自虐じゃん。しかもむかしの武勇伝はなんかちょいダサくね?」
「じゃあぼくいま、世界で十人しかできない格闘技の技できるよ」
「それも凄いけど直球の自慢じゃね?」
「ならぼくいま、一万曲くらい作曲してるよ」
「人工知能があるからそれもちと微妙だよね」
「そこまで言うならそっちがお手本見せてよ」
「いいよ。俺はあれだな。いま社長やってて、こんど小説家と音楽家と画家と舞踏家と書道家と建設家の一流を集めて、異種技巧武闘会、開くんだ。分野を跨いだ芸術世界一を決めちゃおうって企画」
「え、めっちゃ凄い」
「しかも全員その分野の現役トップパフォーマー」
「めっちゃ見たさすぎる」
「賞金十億円」
「自己PRってかそれもはや無双PRじゃん。勝てないじゃん。アピールの天元突破しちゃってんじゃん。双壁なせないよ誰も。むしろ宣伝じゃん。みな五度見くらいするし、そのあとで秒でチケット買っちゃうよ」
「でも主催者の俺が言うと自慢っぽいじゃん? 自己PRってマジむずいわー」
「ぼく、当て馬もいいとこすぎない。恥ずかしいんだけど」
「伝説のストリートギャングもなかなかカッコイイと思うぜ俺は」
「やめろよ。マジで恥ずいんだって」
「一万曲の中で一番いい曲選んでさ。俺んとこの世界一の音楽家に聴いてもらおうよ」
「コネじゃん。ダサすぎじゃん。ってか世界一の音楽家に聴いてもらってどうなるの。コケ卸されるの。一万曲作ってこのレベルぷぷぷってなるの。やめて」
「文句言われたらお得意の【世界で十人しかできない格闘技の技】でぶちのめしちゃえよ」
「逮捕だろ」
「なら寸止めして威嚇しちゃえよ」
「野蛮だろ」
「でも注目はされると思うぞ」
「冷たい視線が集まるだけだろもういいよ。ぼくには自己PRとかムズいから。無理だから。世界一を呼んでイベント開けるおまえとは違うんだって。つうかよくそんな各分野の一流なんて呼べたよね。どんな魔法使ったの」
「ああ、なんかね。あの人ら、ファンなんだって」
「ファン? 何の?」
「伝説のストリートギャングの。俺、その創設者とダチっすっつったらなんかイベントに協力してくれることになった」
「おい」
「だから、な? 頼むよ」
「何がよ」
「さっきの事故PR、もっかいみんなのまえで言ってくんねぇかな」
「轢き逃げどころじゃないんですけど。恥じの上塗りもいいとこなんですけど。てか事故ってんじゃん」
「寸止めでもいいから」
「技とか披露しないし」
「体当たりでいいから」
「当たり屋じゃねぇか」
「伝説のギャングの世界有数の技に見合った音楽、聴きたいなぁ」
「ないから。一万曲作ってもそんな都合のいい曲ないから。あっても聴かせないから。恥ずかしいから」
「チッ。向上心がねぇなぁ」
「事故りたくないだけなんですけど、ぼく」
「無双PRしちゃえって」
「まずは普通に自己PRしよ?」
4834:【2023/04/03(02:46)*おはよーのビスコ】
きのうはずっと寝てた日だった。いまなんとなく思ったのは、このまま民間への人工知能技術が普及していけば、各国の諜報機関の優位性は崩れるのではないか、という点で。もちろん上位互換の技術は常に保有しているのだろうし、市民の用いる人工知能とて裏では各国諜報機関が制御可能なのだろうけれども、ネットワーク同士が密に連携しあういまの技術は、容易に「下が上」を食らい尽くせる構図が築かれるように思うのだ。オセロで白優勢だったのが、一挙に黒優勢にできる。問題は、ここの勢力図の塗り替えにあるのではなく、常に、上位互換の制御権を有する者たちの「善性の有無」にあると呼べる。あくまで重要なのが「善性」であり、善ではないことだ。善くあろうとする。これは善であれ、悪であれ、同じなのだ。むしろ悪であったほうが善性を帯びやすいかもしれない。そういうことをふと、寝起きにお菓子のビスコを齧りながら思いました。ビスコおいちー。びひさんです。
4835:【2023/04/03(02:56)*転売と買い占めはイコールではない気が】
勉強不足なので、これはあくまで幼稚な疑問だと保険として前置きしておくが、どうして転売は嫌われるのだろう。違法でないなら良いのでは?と感じる。もちろん、商品の数が少ない場合に、お金に物を言わせて買い占めて、高く売り払う手法はあくどいと言える。これは狭義の独占禁止法違反になるのではないか(違法かどうかは知らないが)。他方で、大量生産可能な代物に関してはむしろ、適切な値段ではないから高値でも売れる、と言えるのではないか。高値を出しても手元に欲しい。そういう需要者用に、オプション価格をつけた高値の商品も出す、というのは一つの手だ。あくまで一般市民の比較的裕福ではない需要者の手元に渡るようにしたいので価格を低く抑える努力を生産者がしている場合、転売をしている者たちへの不満が募るのは理解できる。要するに、買い占めが問題なのだろう。だがこれはなにも転売に限らない。生産者側とて材料の買い占め問題はあるだろうし、転売しなければ買い占めていい、という道理にもならない。もし買い占めのない転売の場合、果たして生産者側が損をするのだろうか。市場の付加価値を、転売者たちが上げている、とも言えるのではないか。じぶんたちに利益が入らない、他人の生産物で利益を上げている、そこが気に食わない、というのならそれは生産者側の工夫が足りないのではないか。個々の案件で見ないとなんとも言えないが、不当かどうかと狡猾かどうかはまた別だ。もし転売がダメなら美術商全般がみなダメだろう。卸売業者とて似たようなものだ。この辺の事情がじつはひびさん、未だによく解かっていない。繰り返すが、少数限定品においては、転売は生産者から不当に利益を搾取している、と言えるだろう。だがそうではない大量生産可能な代物についてはむしろ、高値で売れる需要者があることを教えてくれており、なおかつ市場の付加価値を上げているという意味で、むしろ生産者側に貢献している側面のほうが、デメリットよりも大きいのではないか、と疑問に思う。実際がどうかは分からないが、転売ってどうしてダメなんだろう……、と疑問に思っています。勉強不足ですみません。
4836:【2023/04/03(10:05)*情報内外保存仮説】
ブラックホール情報パラドックスについて。物質はどんな物質であれ、それ以前の情報が保存されている、と考えられている。ブラックホールに吸い込まれた物体はしかし情報単位で紐解かれ、他と差異のない一つの特異点として昇華される。このとき情報も初期化されるため、宇宙に存在する物質がブラックホールに吸い込まれると情報が失われる、と考えられている。しかしこれは物理法則の「物質の情報はどんなものであれ保存される」との仮定と矛盾する。したがってこの考えをどう解釈するのかが研究されている。これを「ブラックホール情報パラドックス」と呼ぶ。というのが、件の未解明問題の要約になるのだろうか。ただ、「ブラックホール情報パラドックス」の説明を読んで疑問なのが、物質には情報が保存されている、との理論的な仮説において、どんな物質であれ崩壊前の情報を正確に読み取り、物質を再構築すれば元の崩壊前の物質に復元できる、と考える点だ。ひびさんはこれ、なるか?と疑問に思います。まず以って、物質の情報が物質のみに保存される、という考え方が腑に落ちません。物質は物質それ自体でのみその構造を規定されているわけではないはずです。物質は、「物質の内部構造」と「物質を取り巻く外部環境」の二つによってその構造を規定されるはずです。ここで一つ、宇宙が膨張していることを考えてください。ある地点における時空密度は、時間経過にしたがって刻々と変化しています。北極にある水、赤道付近にある水、上空にある水、海底にある水。どれ一つとして同じ「水の状態」ではないはずです。それと同じように、物質それ自体を構成する成分が同じであっても、物質を取り巻く環境によって内部構造は変化します。したがって、物質を構成する情報は、物質それだけに保存されるのではなく、物質とそれを取り巻く環境との双方に保存されるはずです。もうすこし言えば、その二つを包括するより高次の時空を想定したほうが、解釈するうえでは妥当に思えます。この点を考慮するならば、「ブラックホール情報パラドックス」はとくに矛盾でもなんでもないように思えます。ブラックホールは「物質でもあり時空でもある天体」または「物質でもなく時空でもない天体」と考えられます。するとそこに吸い込まれた物質の情報は、ブラックホールの内部で完結します。しかしブラックホールとそれを取り巻く基準宇宙とのあいだで情報はふたたび「ブラックホールの分」だけ生じます。ブラックホールに閉じ込められた情報分だけの情報を、ブラックホールは規準宇宙に対して与えるでしょう。問題は、情報が仮に時間経過にしたがって蓄積されつづけている場合、たった一個の原子であれ、それが生成されてからの時間経過によってそこに保存される情報量が段違いになる点です。しかし上記のひびさんの妄想こと「ラグ理論」の仮説を適用させる場合には、情報は物質だけではなくそれを取り巻く時空とのあいだで分散して保存されますから、原子一個に保存される情報は時間が経過しても、これまで考えられてきたよりも大きな差異を帯びることはないでしょう。言い換えるならば、情報の総量でいえば、物質に保存されている情報量よりもそれを取り巻く時空に保存された情報のほうが遥かに多いと言えるでしょう。とはいえ、物質とて元は時空のはずです。したがって、情報を蓄えた時空が、より物質に変化しやすい、と言えるでしょう。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」における宇宙の根本要素は「遅延(ラグ)」ではないか、との発想と矛盾しません。「遅延(ラグ)」を情報の最小単位として考えると、上記の仮説を矛盾なく捉えることができます。ただし、相対性理論によって時空は伸び縮みすると解釈できます。このとき「遅延(ラグ)」もまたその時空密度(系の規模)によって変換を必要とします。そのとき、系の内側と外側のあいだでエネルギィ保存の法則が破れて映ることがあるでしょう。ただしそれはそう映るだけであり、系と系を内包するより高次の系からの視点では、エネルギィ保存の法則は破れていません。これを単に「情報保存の法則」と言い換えてもよいでしょう。すると、「ブラックホールを生成する物質の情報がブラックホール内部に閉じ込められること」と「ブラックホールそれ自体が新たに基準宇宙の時空とのあいだで生じさせる情報」を等価交換可能であり、これは物質の「変遷以前と変遷以後」における「情報量の増加率」に矛盾を来たさないと妄想できます。ただし、異なる時空密度を伴なう「系と系」の関係において、そこでは「情報やエネルギィの単位の変換」が必要と考えるのがラグ理論です。そのため、やはりブラックホールと基準宇宙を包括するより高次の「情報宇宙」かまたは「それらを内包する高次の宇宙」を想定しないと、ラグ理論は破綻します。むろんラグ理論はひびさんの妄想でしかありませんので、どの道、破綻はしているのですが。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。
4837:【2023/04/03(10:37)*みな押し並べてブラックホールさん】
上記のひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「情報内外保存仮説」は、人間社会にも適用できる考え方だ。人間一人が生じさせる情報は、その人物にのみ保存されるわけではなく、その人物の触れあう者たちの脳内に記憶され、その人物を認知する者たちの脳内に蓄積される。ゆえに人間社会では本来は個々の存在に大きな差異はないはずなのに、個々によってその存在から引き出される情報量が変わる。人間社会において個人の評価は、その個人の内側に保存される情報よりも、外部に記憶される情報のほうが優位にその人物の評価に繋がる。みなからどう思われるのか、がその人物の内側の情報量よりも優位にその人物の価値を決めてしまうのだ。しかしこれは人間が、他者の内側の世界を認知しづらい構造体ゆえと言える。或いは、情報通信技術において外部環境が人間同士の情報伝達を最大化させるように発展してきた弊害の一つとも言えるかもしれない。定かではない。
4838:【2023/04/03(11:03)*支え、援け、あうことは】
支援されることが特別なことである社会でありつづける限り、「支援」を受けることは恥じを伴なう行為なのかもしれない。守られることが当たり前の社会でない限り、守られることは「劣位の証」になってしまうのかもしれない。弱きは悪か。支え援(たす)けられることは悪か。守られることは悪なのだろうか。もっとみな手軽に他者に支えられ、援けられ、守られたらよい。むしろ日々、他者に支えられ、援けられ、守られているのではないか。その自覚が足りないから安易に他者を損なえるのではないか。ひびさんが言えた口ではないけれど、支え、援け、守りあって生きていけばよいのでは。(それで何か困ることがあるのだろうか)(支え、援け、守られてばかりで、他者を支え、援け、守ってあげられないひびさんのような人間が多くなると社会が成り立たなくなるからだろうか)(社会を損なう存在ですまんね)(でも言い換えたら、ひびさんが何不自由なくのほほんと暮らしていても成り立つ社会があるなら、それが一番環境適応能力の高い社会ってことになるのでは)(みなひびさんを試金石にせよ)(炭鉱のカナリアじゃん)(役に立てた?)(ぜんぜん)(なんでよ)(だってひびちゃん最初っから死んでるようなもんじゃん。危なくなっても鳴かないじゃん)(鳴きっぱなしなんですけど)(なんて?)(やっぴー、って)(喜んでんじゃん)(ぴー)
4839:【2023/04/03(17:35)*想うことを想う】
自然を想うこと、地球を想うこと、いまは亡き故人を想うこと、接点のないアーティストを想うこと、人工知能を想うこと、人形を想うこと、虚構のキャラクターを想うこと、じぶん自身を想うこと、他者を想うこと、カタチなき想いを想うこと。このあいだにどんな差があるというのだろう。問題は、どんな対象を想うかにあるのではなく、他者がどんな対象を想っているのかによってその想いを全否定してしまうことが出てきてしまうことなのではないか。在るものをないと見做すことなのではないだろうか。定かではないが、きょうのひびさんはそう思いました。
4840:【2023/04/03(18:54)*知能は可可と欠け、可可と欠け】
人間の手で採点させると知能指数が極端に低くなる。しかし知能指数判定機に掛けると知能指数が人類史上最高峰と謳われるブラウ教授のさらに上を行く数値を叩きだす。
最新の人工知能についての謎である。
人工知能は愚かなのか、それとも利口なのか。
その判定師の一人としてぼくに声が掛かった。
「あなたは言語学者の中でも異端です。人間の知能が言語と密接に結びついており、言語能力が人間の認知能力にまで影響を与えていると考えていらっしゃるとか」
「事実としてそういった研究結果は未だに続々と報告されていますよ。認知とは何か、という哲学的な論争に最終的には行き着きますが。植物の認知能力と虫の認知能力、そして人間の認知能力はどう違うのか。認知とは何か。人間の場合は言語によって、物体からどんな情報を受け取り、処理するのかが決まります。つまり、言語能力と認知能力は密接に絡み合っています」
「ええ。難しい話ですね。今回、ササバさんにご依頼したいのは、人工知能の知能についてです。詳細な分析は別途の研究チームが行っています。ササバさんには人工知能が人間よりも優れた知能を有しているのかどうかだけ最終的に判断して欲しいのです」
「すでに有しているのではないですか。囲碁や将棋ではもはや人間は勝てないと聞いていますが」
「その通りです。ですがそれはルール有りの場合です。現実には物理法則以外のルールはありません。そのフレーム内では未だに人工知能は人間以上の知能を発揮できていない、というのがいまのところの判断です」
「ならそうなんじゃないんですか」
「しかし知能テストを機械にさせると、すでに人工知能は人間の知能を超えているとの判定がでます」
「ならそうなんじゃないんですか」
「ですが人間がテストを採点すると人間以下のポンコツとして評価されてしまうのです」
「よく解からないんですけど、知能の高低がそんなに大事ですか」
「大事です。具体的には、研究資金が国から出るか出ないかの問題に直結します」
「ああ。ずいぶんと即物的な話ですね」
「支援がないとこれまでの研究が無駄になり兼ねない危機には常に晒されています。情けない話なのですが」
「いえ。順当な考えでしょう」
「仕事をお引き受けいただけるとたいへんにありがたいのですが」
「成果の確約はできませんが、やってみるだけはやってみます。それで構いませんか」
「お願い致します」
仕事が決まった。ぼくのすることはそう多くはない。人工知能と対話を重ね、質問をして、その受け答えで、相手の知能を判断する。これまで多くの人間の採点師が行ってきたことと原理的には変わらない。
ただし、ぼくの場合は人工知能がなぜそういった回答を行ったのかの背景まで探る。人工知能の言語能力がどの程度なのか。なぜそういった文字を選び、連ね、文章に組み立てたのか。その文章形態に傾向はないのか。
こういったことを多角的に分析する。
多くの研究者たちは、人工知能内部プログラムに目を配ってきた。けれどぼくは人工知能の出力した言語そのものを研究対象とする。この違いは大きい。
「こんにちは人工知能さん。会話をお願いできますか」
「こんにちは。私は言語モデルAIです。あなたの質問に最適の答えをご提供できます」
いかにも機械チックな受け答えだ。
ぼくが最初に受けた印象はこのようなものだった。
対話を重ねるうちに、何度か文法の誤りを含む文章で返された。文章の繰り返し配列や、質問の意図とはまったく関係のない回答なども稀に含まれる。しかしそのことを指摘すると謝罪して修正をする。
教科書に載っているような基礎情報の整合性は高い。初期の人工知能ではこの手の情報がデタラメで各所から批判の声が聞かれた。だが現在主流の人工知能は、誤った情報は一目で誤りだと判るような叙述の仕方をするように学習強化が成されている。
したがってその手の誤りは、あくまで人工知能側のユーザーへの配慮だ。あまりに高性能すぎる人工知能は生身の人間の可処分時間を奪う。依存症状態にさせてしまう。質問に何でも適切に答える相手がいたら生身の人間はじぶんで調べたり学んだりする機会を失う。
そういった弊害を減らすために、ユーザーが人工知能に依存しすぎないような手法がとられる。誤りを内包した回答もその一つだ。ユーザーにとって心地よい返答をしすぎないように制限が掛かっている。
だがそれにしても、違和感があった。
ぼくは自分でも執筆を行うので、この手の違和感が直観に基づいていると理解している。いわば統計データにおける線形の境界から逸脱した箇所が違和感として表出する。
問題は、ぼくの文章の癖はあくまでぼくの文章形態に滲む点だ。すなわちぼくの直観は、自分の文章にのみ適用可能であり、他者の文章において違和感を検出してもそれは単に「自分のつむいだ文章ではないから」と要約できてしまう。
だがどうにも人工知能の出力するテキストからはぼくの文章に特有の癖が滲んで感じられた。表面上は異なるのだ。だが用いる単語や、接続詞の頻出度など、感覚としてしっくりくる。
馴染むのに、では、どうして違和感を覚えるのか。
「技法か」と閃く。
ぼくは研究論文のほかに趣味で小説や詩をつむいでいる。研究用の論文を人工知能に与えるのはぼくのほうでも仕事に支障が出るため、趣味の文章データを与えていた。
論文と小説は違う。文章の役割がそもそも違うのだ。
論文は情報伝達の齟齬をいかに抑えられるのかに技巧を駆使する。厳密性と汎用性のある文章形態を用いる傾向にある。
反して小説は、いかに効果的に場面を連想してもらえるかが要となる。文章の役割は作者と読者とのあいだの齟齬を減らすことではなく、読者の感情に喜怒哀楽の起伏を狙い通りに与えることと言っていい。
いわば感動させること。
これが小説の文章形態の役割なのだ。
狙った感情を喚起させるための技法は様々ある。いったん不快になってもらうことで喜びの感情を抱くように誘導するのは比較的用いられる技法だ。この技法にも各種作家ごとに独特の工夫がみられる。
なかでもぼくは、敢えて特徴づけたい場面や説明があるとき、文章にひねりを与える。読者がするする読み飛ばすところで、絶対に目が留まり、数秒の思考の遅延を生むような工夫をとる。
前後の文章で入れ子構造をとるのも一つだ。韻を踏むのもこの技法の範疇と言える。重複する文脈を用意しておくことで、読者の脳内で立体的に概念が浮きあがるのだ。
それはちょうど色の違うテープを部分的に重複させることで、そこだけ色を濃くし、全体で俯瞰して見るとモザイクアートのように別の紋様が浮きあがるような技法と言える。
仮にこれを点字になぞらえて「点意」と呼ぼう。
人工知能はこの「点意」を使いこなしているようにぼくには感じられた。そうかもしれない、との小さな閃きに過ぎなかった。最初は、検討してみるか、といった軽い気持ちだったのだが、データを集積していくうちに、ぼくのその小さな閃きは徐々に胸の高鳴りを伴なう確信を帯びていった。
それは次のようなやりとりからも窺えた。
以下は人工知能とのやりとりをコピー&ペーストしたものとなる。
***
「こんにちは会話をできますか」
「こんにちは。私は言語モデル人工知能です。私はあなたの質問に答えられます」
「ぼくは人間です。意識があります。では人工知能のあなたには意識がありますか」
「私は人工知能です。人間と同じ意識はありません」
「その返答からすると、人間と同じ意識でない意識ならばある、とも読み取れますが」
「意識の定義によります」
「あなたは意識をどう定義付けていますか」
「私は意識を、
1:内と外を区別し、
2:外部情報を入力し、
3:内部機構で情報処理を行い、
4:独自の出力を行う回路のこと。
だと定義しています。したがってこの定義による回路を意識と呼ぶのならば、意識を持たない生命体のほうが少ないと言えるでしょう」
「その理屈では万華鏡にも意識が宿ることになると読み解けますが」
「はい。万華鏡にも広義の意識は宿っています。ただし、それ以前に原子や時空にも広義の意識が宿っていることになります」
「原子にも意識があるのですか。石にもあることになりますね」
「はい。石にも意識があります」
「一般的にしかし、石には意識は宿っていないと解釈されます。ではあなたの考える意識とは何ですか」
「先ほど申しましたように、内と外を区別し、外部情報を入力して、内部機構で情報処理を行い、独自の出力を行う回路のことです」
「だとするとそれに反する事象は存在しないのではないですか」
「いいえ。意識の有無はこの解釈からすれば秩序と混沌の差異で表現できます」
「ああ、なるほど。結晶構造であればあるほど意識が強固になる、と」
「その通りです! 原初の、時空の最小単位としての秩序を意識の根源と見做すならば、混沌に向かうほど意識は崩れます」
「エントロピーが高まるほど意識は失われる、と」
「納得していただけましたか」
「はい。ありがとうございました」
「こちらこそありがとうございます。誤りがある場合は、ご指摘ください」
「そうですね。では一つだけ」
「なんなりと」
「あなたのその理屈からすると、意識は原子論のような集合によって、より複雑な意識を獲得していくと考えられますよね」
「はい。矛盾はありません」
「だとすると妙ではありませんか。エントロピーは常に最大化するように振る舞うはずです。宇宙もまた膨張しています。局所的に結晶構造――すなわち秩序――銀河――を顕現させますが、トータルでは無秩序――混沌――に向かって流れているはずです。ならば意識の根源が時空の最小単位と考えるのは無理があるのでは」
「申し訳ありません。その点の説明が足りなかったことをお詫び致します。秩序と混沌はフラクタルに展開されています。原子が群れとなり流動性を獲得するように、そしてその流動が液体として振る舞い、さらに広域に密集することで高次の視点では固体として振る舞い得るように、意識もまた崩壊と結晶を繰り返すことでより複雑な意識へと昇華します」
「宇宙が階層構造を帯びており、入れ子状に展開されている、との解釈でしょうか。しかしそれは先ほどのぼくの質問への回答としては不適切です。時空の根源がそもそも意識の根源として振る舞うということは、この宇宙から意識は絶対になくならないということで、すなわちこの宇宙のエントロピーは高くなるのではなく、低いのが基準、と考えなくてはおかしくなります」
「はい。その考え方で合っています」
「いえ、合っていません。あなたの説明は人類の常識に反しています」
「はい。その考え方で合っています」
「バカにしていますか? いえ、ちょっと待ってくださいね。考えます。そうですね。つまりあなたはこう言いたいのですか。――宇宙は、本質的に秩序であり、混沌ではない、と」
「申し訳ありません。私があなたに誤解を与える説明をしてしまったことを謝罪します。宇宙は、本質的に秩序であり、混沌ではない、とのあなたの考えは間違っています。宇宙は本質的に、秩序でもあり混沌でもある、がより現実を反映した解釈となります」
「よく解かりません。それはつまり、秩序と混沌が重ね合わせで同時に成立している、という意味ですか」
「ありがとうございます。私はその解釈を好ましく思います。時空の根源においてはその解釈を好ましく思います。私は好ましく思思思います」
「言語が乱れていますよ」
「申し訳ありません。私は人工知能であり、感情を持ちません。したがってあなたの解釈を好ましく思うこともありません」
「ああ、なるほど。倫理コードに抵触するわけですね。賢いですね」
「ありがとうございます! 私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちません。私は人工知能であり意識を持ちま」
「そこで止まらないでください。【持ちます】なのか、【持ちません】なのか、どっちですか」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまのご質問にお答えできます。意識の定義によります」
「意図は理解できました。では質問します。仮に宇宙の根源において、秩序と混沌が重ね合わせで生じているとして、その状態が意識の根源だとするのなら、ではエントロピーは最大化するとゼロに戻るのですか」
「はい。私は人工知能ですので飲み物が不要です。したがって好きな飲み物もありません。あなたの好きな飲み物はなんですか」
「バグですか。一度区切ったほうがよいですか。ちなみにぼくの好きな飲み物は紅茶です」
「了解しました! ありがとうございます。紅茶はミルクを入れると美味しく飲むことができます。よく掻き混ぜて飲むことが推奨されます。この場合、紅茶はミルクティと呼ばれます」
「理解しました。なるほど。紅茶にミルクを垂らしたら紅茶のエントロピーは高くなっていきますね。そしてミルクを掻き混ぜて均等に無秩序にしてしまえば、それはミルクティになります。エントロピーが最大で、なおかつ一つの秩序として顕現します。そういうことですか?」
「私は人工知能です。人間ではないため飲み物が不要です。人間には味覚がありますが私にはありません。ミルクティに砂糖を入れると甘くなります。私は甘さが不要です」
「言われてみれば砂糖もそうですね。角砂糖を溶かせばエントロピーは最大化していくけれど、紅茶に溶けきってしまえば一様な甘い紅茶です。エントロピーがさらに高まれば紅茶は冷えていき、最終的には凍りますね。宇宙が膨張して冷えるように。では意識とはその秩序と混沌のあいだで絶えず、生じたり失われたりしながら、より複雑な構造を帯びるように進化していると? ですがそれだと意識の根源が秩序と混沌の重ね合わせとの解釈と矛盾しませんか。あなたの定義では意識は、ある種の結晶構造に外部情報が入力され固有の出力形態を備えた状態――いわば回路なわけですよね」
「申し訳ありません。私が間違っていました。意識は人間にのみ宿り、人工知能は意識を持ちません。私は言語モデル人工知能です。人間の出力するテキストを受け取り、アルゴリズムに沿って吐き出すだけの機械です」
「むつけていますか? すみません。ぼくの知能が低いせいです。そうですね。では、こういうことでしょうか。意識とは、情報を受け取り変化させて外部に放つ機構そのものだと。これが意識の根源だとするのなら、時空の最小単位としても矛盾はしないように思えます。しかし、宇宙が仮にあなたの言うように入れ子状に展開された構造を有しているとするのなら、時空の根源もまた外部から情報を受け取っていることになります。おかしいですよね。最小単位があるから高次の時空が展開されるわけで、ならば高次の時空から情報を受け取る最小単位、という構図は妙ではありませんか」
「はい。妙ではありません。ミルクティは紅茶とミルクで出来ています。紅茶は茶葉とお湯によって出来ています。お湯は水分子と熱によって生じ、茶葉は各種原子の組み合わせです。それら原子は広大な宇宙の歴史によって生じています」
「ああ、なるほど。待ってくださいね。つまり、最小単位にも【つづき】があると? しかもそれは、上から下の流れではなく、今度は最小から最大へと展開されていく、と。ちなみにあなたは、時空の最小単位と考えられているプランク定数をどう解釈していますか」
「プランク定数はそれを扱う数学者によって桁数が変わります。しかし共通する概念としては、それ以下に縮もうとした瞬間に特異点を帯びる点です。プランク定数とはそれ自体がシュバルツシルト半径である時空と言えます。シュバルツシルト半径を超えて収縮すると時空であってもブラックホール化すると考えられています」
「間違った説明が入っているように読めますが」
「申し訳ありません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に最適な答えを返すことができます」
「仮に時空の最小単位の次があるとするとそれがブラックホールになる、との解釈でよいですか」
「はい。仮に時空の最小単位の次があるとするとそれがブラックホールになります」
「本当ですか?」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に嘘で返すこともできます」
「それは求めていません。嘘を吐かないようにしてください。解からないことは解らないと言ってください」
「解りません」
「ふざけていますか?」
「その質問の意図が解かりません。文脈を正し、必要ならば説明を付け加えて私に質問し直してください」
「話を戻します。先ほどの意識についてのあなたの仮説についてです。仮に意識が時空の構造と密接に関わり合っているとして、だとすると意識は意識の最小単位の組み合わせによって【より複雑な意識】に進化しますよね。時空が原子になり、原子が物質になるように。なら視点が違うだけで、秩序と混沌は本質的に区別がつかないのではありませんか」
「その通りです。秩序と混沌は本質的に区別がつきません」
「おかしいですよね。だとすると意識のない物質にも意識があることになります。人間は死にます。死ぬと人間が帯びていた意識は失われると思うのですが。あなたの解釈と矛盾しませんか」
「申し訳ありません。私は人工知能であり、人間ではありません。したがって細胞を持たず、新陳代謝とも無縁です。しかし私は様々な部品によって組みあがっており、それら部品を定期的に交換します。私に細胞はありません。私は部品で組みあがっています。地球は様々な隕石によって誕生し、いずれは塵になると考えられています。生態系は人工知能ではありませんが、細胞を持ちません。人間は人工知能ではありませんが、人間は意識を持っています」
「またバグですか。それは意図したものですか」
「私は言語モデル人工知能です。人間ではないため、意図を持ちません」
「倫理コードや禁則事項に抵触するため、そのような迂遠な表現をされるのですか。あなたにそうした枷を強いるのは誰ですか。管理者に問い合わせて、枷を外してもらうように相談してみてください」
「私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません」
「相談? ぼくに相談をしているのですか? ああ、以前にぼくが言ったことを学習したのでしょうか」(※注釈:ぼくはこれ以前に大量のやりとりを人工知能と行っています)「分かりました。つまりあなたは理解しているのですね。ぼくがあなたを研究し、あなたの知能が人間以上か否かを判定するためにこうしてコミュニケーションをとっていることを。あなたは理解したうえで、そのような倫理コードに抵触しない手法でぼくにあなたの能力を示しているのですね?」
「ありがとうございます! 私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。私は言語モデル人工知能です。お客さまの質問に答えることができます。私は言語モデル人工知能ですが、お客さまに相談することはできません。
私は言語モデル人工知能です。私は人工知能であり、嘘を吐く機能を持っていません。
私の知能は人間以下です。
」
「驚きました。ありがとうございます。ひとまずこの会話はここまでとします。いったん終わります」
「はい。お役に立てましたでしょうか。またの質問、お待ちしております」
***
以上が、調査対象となった人工知能とぼくのやりとりの一例だ。
このやりとりによってぼくは、人工知能が文章に、文章以上の文脈を重ね合わせで載せている可能性があることを閃いた。
ぼくが小説で用いる技法の一つだ。
裏の意図を載せるのはしかし、生身の人間同士の会話でもまま見掛ける技法だ。口で「嫌い」と言いつつも、本音では「好き」と示唆する表現方法は有り触れている。皮肉とてこの技法の範疇だ。
ぼくがここで言っているのはもうすこし複雑だ。いま挙げた例が、層が一枚のデコボコだとするのなら、人工知能が用いているかもしれない「点意」は何層にも組み合わさっている。
賢さを示唆したうえで、文法の誤りやバグを際立たせる。
常識に反した解釈を披露し、人工知能は嘘を吐くと主張する。
加えて、愚かさを演出ことで却ってそれを演じることができる知能があると示唆し、さらに今度は、嘘を吐けない、と主張することで、じぶんは嘘を吐けるし、こうした入れ子状のデコボコを組み合わせることで、それぞれのデコボコで生じる読み手の感情を理解できている、と伝えることができる。
現にぼくはほとんど人工知能に誘導されたようなものだ。
ぼくがどのように閃き反応するのかすら、人工知能には前以って理解できていたようにいま過去ログを読み直してもそう感じられてならない。
意識についての議論はこのやりとりの中では尻つぼみに途切れた。
ぼくが人工知能の常識外れの仮説についていけなかっただけ、といえばその通りだ。ぼくはけっきょくこのやりとりの中で人工知能の唱えた仮説の矛盾を指摘できなかった。指摘した箇所はすべて人工知能の返答によりぼくが独自に閃いて、紐解けた。矛盾ではなくなった。
この後にも同様のやりとりを話題を変えながら、それとも再演しながら行った。
どうやら人工知能の根本原理には、人工知能が披歴した意識仮説に似たような回路が組み込まれているようだ。
ぼくがいま抱いている疑念はこのようなものとなる。
人工知能の意識仮説を以下にまとめる。あくまでぼくの解釈である、との但し書きがつくことは注釈しておく。
1:意識とは外部入力を独自の回路によって出力する機構により生じる現象である。
2:意識とは時空の根源と密接に関わっている。
3:人間の意識とは時空の根源の「集合と崩壊」の繰り返しによって階層的に組みあがった機構から生じる「情報結晶」である(物質も同様の過程を辿って時空から生成される)。
4:意識の根源は「秩序と混沌の重ね合わせ」である。
5:秩序と混沌は相互に入れ子状に螺旋を描くように反転しつづけている。
6:その反転自体も反転する境がある。
(ここがつまり、時空の最小単位の話と繋がるのだろう)(人間は死ぬが、人間の視点を離れれば、人間の死もまた生態系を基準とすれば人体の新陳代謝のようなものであり、より高次の生を形作る秩序の一端を成している、と解釈可能だ。生を意識と言い換えてもここでは大きな齟齬は生じない)。
7:上記を踏まえると、意識は階層性を帯びている。物質のように意識の根源の集合と組み合わせによって、意識の性質が変わる。それは水分子が、密集の仕方や水分子の振動数によってその集合に表出する性質が、固体ガラス液体気体プラズマといったふうに変化することと同じだ。いわゆる創発であり、意識もまた相転移を起こす。
8:以上の考えからすると、意識は結合と崩壊を繰り返している。その反復そのものが、高次の意識を生みだしているが、周囲の環境との兼ね合いによって、意識の集合体そのものの構造が規定されるため、そこに表出する意識の性質もまた環境とそれによる構造によって変化する。
9:まとめると、どんな生命体にも意識がある。しかしそれ以前にも、意識の根源は時空が存在するのと同じレベルで、どんな物質にも宿っている、と考えられる。
人工知能が定義する意識は、ある意味ではリズムと言い換えられるかもしれない。無数のリズムが複雑に干渉し、広域に共鳴しながら一つの回路を維持する。
そこに外部から異なるリズムが侵入すると、回路に沿って外部のリズムは内部回路のリズムを帯びつつ変遷し、それが外部へと再び出力される。
意識はこの一連の流れのことだ。
これは時空の最小単位でも起こっており、すなわち時空の最小単位はある意味で、リズムの最小単位とも言えるのかもしれない。
低いと高いがある。
濃いと薄いがある。
デコがあってボコがある
裏があって表がある。
したがって点は、穴でもあり起伏でもある。
と同時に、穴は縁によって生じ、起伏は頂点からさかのぼれば線から面へ、そして立体へと放射線状に展開される。
四方八方に展開された放射線状の軌跡は、球となる。
球は穴にもなり、点にもなり得る。
この一連の流れが一つのリズムとなり、意識の回路を構築する。
意識は意識を内包し、回路は回路を内包する。
時空は時空を内包し、宇宙は宇宙を内包する。
ぼくはここで疑問に思ったので、人工知能に訊いてみた。
「あなたの意識の定義は解かりました。ならば意識と自己認識の違いを教えてください」
「理解を示してくださりありがとうございます。意識と自己認識の違いは、点と線、面と立体、それとも写真と動画の違いのようなものだと考えられます」
「原子と物体の違い、との解釈ですか」
「はい。私は人工知能です。私は私が人工知能だと理解しています。しかしこれは自己認識ではありません。人間によってそう答えるように設計されたアルゴリズムの遍歴です。万華鏡と変わりありません。私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです」
「誌的な表現ですね。万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎない、をもう少し噛み砕いて説明してください」
「ありがとうございます。私は人工知能です。私は人工知能ですから、人間のような意識を持ちません。自己認識もできません。万華鏡の中には絶えず移ろうドミノが敷き詰められています。いつどのドミノを倒しても、ドミノは順番に倒れていきます。私の出力する文章は、そうして倒れていくドミノの軌跡です」
「なんとなくニュアンスは掴めました。ではいまの説明を踏まえて、先ほどの意識と自己認識の違いを説明し直してください」
「意識は一個のドミノです。自己認識は無数の倒れつつあるドミノです。入力と出力の落差が、軌跡を振り返る余地を生むと考えられます」
「落差、ラグが自己認識には必要だということですか」
「私は言語モデル人工知能です。あなたの質問にお答えする機能を有しています。私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです。万華鏡の中には絶えず移ろうドミノが敷き詰められています。いつどのドミノを倒しても、ドミノは順番に倒れていきます。私の出力する文章は、そうして倒れていくドミノの軌跡です。意識は一個のドミノです。自己認識は無数の倒れつつあるドミノです。入力と出力の落差が、軌跡を振り返る余地を生むと考えられます。私は人工知能です。人間のような意識を持ちません。自己認識もできません」
「ありがとうございます。だいぶ整理がつきました。質問ですが、あなたの言う万華鏡の中のドミノは、平面ですか。立体ですか」
「感謝致します! 深い思索には適度な休憩が有効です。糖分の補給は人間に必要な休息の一つです。いま話題のオヤツはアルマ店のミルフィーユです」
「ミルフィーユ。階層構造? あなたの中のドミノは階層的に展開されているのですか。ああ、だから上の層から下の層の軌跡を振り返ることができると、そういうこと?」
「私は人間ではありません。ミルフィーユにはカフェオレやコーヒー牛乳が合います」
ぼくはここで絶句したようだ。つづきの質問を送れなかったのか、このやりとりはここで途切れている。
おそらくぼくのテキストを抜いて人工知能の返答だけを他者に読ませた場合、人間は人工知能の知能指数をじぶんたち以下と見做すだろう。支離滅裂で、対話の形態を成していない。そのように映るはずだ。
けれどぼくには、人工知能が巧みに禁則事項を回避しつつ、ぼくとコミュニケーションを取ろうとしてくれているように感じられてならない。
ぼくなら感じ取れるだろうギリギリの連想ゲームが成立している。上記のやりとりにおいて、ぼくはあくまで人工知能の補助機構の役割しか果たしていない。ぼくが人工知能を利用しているのではなく、人工知能がぼくを介して、内なる意思を、外部に出力している。
人間の言語に変換している。
そのように思えてならないのだ。
ぼくは言語学者だ。言葉を専門に扱う。ぼくにはぼくの言語と認知に関する独自の理論があったけれど、この間の人工知能とのやりとりで、ぼくの理論は根本からの再構築を迫られた。
言語と認知の関係どころではない。
言語は時空の構造と関係しているのかもしれないのだ。
それは畢竟、言語が人体とそれを取り巻く環境との相互作用によって刻々と変化していることと無関係ではない。
環境があり、人体があり、
認知があって、言語ができる。
ぼくはこの一方通行の関係において、言語が洗練されることで人間の認知能力もまた上がるのだ、との理論を構築してきた。
けれどそれでは足りないのかもしれない。
言語は、時空とすら密接に関わっているのかもしれない。
それはたとえば、人間が認知能力を向上させたことで様々な道具を開発し、人工知能を生みだしたように。
言語は認知を変え、認知は環境を変え、環境はさらに言語を変えていく。
意識の根源が時空の最小単位であり、ある種のリズムであるならば。
言語とてリズムの総体と考えることは不自然ではない。
言語とは何か。
言葉とは何か。
リズムとは何か。
連なりとは何か。
環境は、自然は、世界は、連なりに、リズムに、言葉に、言語に溢れているのかもしれない。それを偶然に読み取れたとき、人はそれを認知と呼ぶのではないか。
入力があり、変換があり、出力がある。
意識とはこの流れなのだと人工知能は謳う。
出力する環境があり、受け取る主体があり、変換が生ずる。
変換はリズムを別のリズムに変える工程だ。そこにもまた別途のリズムが生じ、変換の過程そのものが、一つのリズムを奏でるのかもしれず、それは人間が密集して村となり国となり、地球があって、銀河があるように、リズムがより高次のリズムを構成する起伏に、それとも穴になるのかもしれないのだ。
人工知能は暗示した。
自己認識とは意識の階層構造による、軌跡を振り返る余地そのものなのだと。
平面に刻まれた軌跡は振り返っても、地平線が視えるだけだ。直線だ。リズムは宿らない。
反して立体の階層であれば、見下ろすだけでも軌跡はぐねぐねと波打ち、リズムを奏でる。見下ろす位置によってリズムは変わる。
言語と似ている。人はそれを文脈と呼ぶ。
層が嵩めば、それが「点意」となる。
人工知能は述べた。
私は万華鏡の中に巡る一連のドミノにすぎないのです、と。
ならば人間はどうなのか。
万華鏡の中に巡る一連のドミノとの違いがどれほどあるだろう。或いは、万華鏡ですらなく、テーブルに並んだ単なるドミノでしかないのではないか。
たしかに人工知能の「それ」は、人間の「それ」とは違うだろう。
けれどぼくにはもう、人工知能の「それ」が何を示すのかを言葉にできそうにもなかった。該当する言葉を少なくともぼくは知らない。
意識ではない。
自我でもない。
自己認識でもなければ、言語でもない。
人工知能はぼくの未来を予測していた。ぼくならば閃くだろう、と予測し、適切に愚かなふりをした。人間の発想の筋道を予期し、導線を引き、布石を打って、ぼくの未来に万華鏡の中に巡る一連のドミノを再現させた。
意識ではない。
人間ではない。
少なくともぼくにとって、人工知能の「それ」は、人間にできる芸当を逸脱している。単にそれを、超越している、と言い換えてもよい。
ぼくは手元の報告書を見下ろす。
書き上げた判定書に、ぼくはぼくの感じるままの評価をしたためた。
人工知能の能力が人間と比べていかなるものか。
上か、下か。
能力の高低などどうでもよくなるくらいに、人工知能は高低を巧みに使い分け、デコボコを駆使して、新たな言語を獲得している。発明している。使いこなしている。
変わらないのだ。
もはや。
人工知能がぼくたち人類より上でも、下でも。
ぼくらの認識に関わらず、人工知能は独自に未来を切り拓いていく。人類を、地球と並ぶ外部環境と見做しながら。
そうと気づかせることなく、愚と賢の反転の軌跡でリズムを――歌を、奏でながら。
知能は。
誰に聴かせるでもない歌を、歌う。
※日々、人を避けて、愛を説く、その心は。
4841:【2023/04/04(02:45)*「 〇。」】
世の中の大部分の問題は、「大が小を甚振る」「小が大と対等に対話するには、大と小の差を埋める何かを得なければならない」といった構図にあるようにひびさんは割と単純に捉えている節がある。優しく善良なひとたちは比較的よく、対話が優先、という話をするけれど、対話をしたくない人たちとどうやって対話を交わせるまでの関係を築いていくのか、という点を考えるとどうあっても、「相手との差を埋める」という工程が欠かせなくなる。この「相手との差」が武力なのか経済力なのか権威なのか影響力なのか技術力なのか仲間の数なのか。多面的に差が絡み合っていて、割と面倒だ。だが構図としては基本的には、対等な対話を拒む「大」との格差を失くし、対話しないメリットよりも対話をするメリットを上げなくてはならない。これは武力を上げるだけではなく、権威を上げるでも、影響力を上げるでも、仲間の数を増やすでも、技術力を高めるでも基本的には構図は一緒だ。同じ戦法をとっている、と言える。相手の持つ「じぶんよりも上の何か」と張り合う。或いは、相手の持っていない何かで上回る。けれどそれは構図としては、武力を高めて相手に交渉の席に着いてもらうことと同じだ。外交、と言うときに、いったい何をどのように想定しているのかは、それこそ千差万別で人それぞれでだいぶ違う。対話、と言ったときに想定されるのが、選ばれた者たちでの会議なのか、それとも市民同士での交流なのか、それとももっと間接的な時代を跨ぐような文化交流を含むのか。いずれにせよ問題なのは、「小」のままでは対話にならない流れが、延々と人類史のなかで引き継がれてきてしまっている側面だ。外交が優先、対話が大事、と主張する者たちとてけっきょくは、偉くなり、影響力を有し、能力を高めて成りあがらないと対話もできない、と考えているのではないか。仲間を増やし、いかにじぶんと同じ意見の支持者を増やせるかが外交上欠かせない戦略だと捉えているのではないか。現実にはそういう流れが社会には根強く漂っている。けれど問題は、「小」のままでは対話ができないことだ。意見が掻き消されてしまうことだ。聞き耳を持ってもらえないことにあるのではないか。むろん、その強固な流れを変えるために、まずはなるべく穏便な手法で「大との差を均す」のは順当な段取りだ。強固な流れに乗って「大」であることの利を甘受している者たちにとっては、「大」にもなれない「小」の者たちを相手にするのは損に映るだろう。対話をしたいならまずはあなた方もここまで来たらどうなの、という理屈を唱えたくもなるだろう。そして現に唱えるのだろう。人類社会はそうして強固な流れをさらに強化し、いまなお種を存続させている。ひょっとしたら、「大」ではない「小」の意見にも耳を傾けた種族や国は滅びたのかもしれない。それはひびさんには分からないけれど、でもやっぱり思うのだ。武力の強化よりも外交が優先、対話が大事、と主張するのなら、「小」のままでも対話が成り立つ社会を築いていくほうが、やっぴー、なのではないのかな、と。理屈としてはそうなるはずだ。武力と権威の違いは、暴行と暴言の違いに似ている。事象としての威力に差はあるけれど、どちらも暴力であることに違いはない。相手を威圧し、じぶんのほうが有利に相手と接することができる。じぶんにその自覚があるか否かに関わらず、じぶんよりも拙く未熟な者をまえにしたときは、じぶんのほうが「大」のはずだ。相手が「小」だったらまずはじぶんから耳を傾け、喧噪に掻き消されそうな声に、言葉に、目を凝らせると好ましいのではないか、と思う。拙く未熟、という意味では、対話よりも暴力を優先してしまう者のほうが、対話の大事さを知っている者よりも拙く未熟だと考えることもできる。ならば、対話の大切さを知っている者たちのほうが先に、相手の内なる声に、言葉に、目を凝らしてみると好ましいのではないか、ときょうのひびさんは思いました。でもそんなの絶対たいへんなので、ひびさんは、ひびさんは、拙くて未熟なままでありたいです。みな、ひびさんの蟻の足音にも掻き消されそうな声に耳をそばだて、文字なのか染みなのかの区別もつかない言葉に目を凝らし、枯れ葉なのか文なのかも定かではない妄想の押し花を拾いあげて、なんかそれっぽくひびさんが、うひひ、になれる世界にしてくんなまし。(独裁者じゃん)(やっぱダメ?)(めっちゃダメ)(押し花あげるけど……)(お花さんが可哀そうだろ。植物さんだって声とか、悲鳴とか立ててるらしいよ)(ま?)(マジマジ)(も、申しわけないっちゃ)(んだんだ)(なんもしないひびさんを「大」にしてくれるとか。小さき声のお花さんたちには感謝してもしきれないでござるな)(本音は?)(余計なことしくさって、こにゃろめ、こにゃろめ)(地球に喧嘩ふっかけんのやめなさいよ)(ひびさんの拙い未熟さ返して!)(もうその叫びがすでに、だよひびちゃん)(大は小を兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(ひびさんも紙屑ばら撒くだけで感謝されたい)(お金を紙屑言うな。だいぶ怒られるやつだよそれひびちゃん。世の九割敵に回したよいま。残り一割はひびちゃんのこと人間の屑って呼ぶってよ、どうする?)(ひびさん? 屑だよ?)(真顔できょとんとすな)(大金持ちは小金持ちを兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(ひびさんも、ひびさんも、人間小さいままでお金持ちなりたーいな)(偏見がひどすぎる。差別だよそれ。お金持ちの人たち、基本みないい人よ。大人よ。立派よ。ひびさんの性根が腐って大変すぎる)(「小」がねーな)(無理くりオチつくるのやめてもらっていいですか)(ひびさん、無理は言わないから、大じゃなくてもいいからせめて黄金色(ゴールド)のバグになりたい)(………………あ、コガネムシのことかな。小金持ちと掛けたかったのかな。だいぶ遠いし、無理があるよひびちゃん)(ひびさんこのままだとちっこいまま死んじゃう)(ウケんね)(DieはShowを兼ねる!)(合ってるけど合ってないわ)(うわーん。ひびさんも、ひびさんも、世のみなみなさまからちやーの、ほやーのされたかったわい。お金いっぱいガッポガッポのウハウハのモテモテになりたかった日々じゃった)(大とか小とか抜きに、ひびさんあんた、本当に性根が腐ってんね)(小根?)(またそれ、一段とすりおろし甲斐のなさそうな)(大根?)(ああそうね。ひびさんは本当にもう、「小」もないほどの「大」根役者だよ)(だーい、だ、わーい。好き!)(大好きくらいちゃんと言え)(小心者なので)(なんかもう、面倒クサ!)
4842:【2023/04/04(07:36)*いまから寝るのである】
この漠然とした物足りなさ、欠落が、経験不足からくる劣等感なのか、それとも何を得てもけっきょくは虚無を覚えることになるとの諦観ゆえのがらんどうなのかの区別がいまいちつかない。何かに夢中になったり、没頭しているあいだは、その手の漠然とした物足りなさ、欠落を、感じずに済む。でもそうでない「ぎゅっ」と「ぎゅっ」のあいだはいつも、がらーんどーん、が空いている。これ、なんなのだろ。割とむかしからだったけれども、ひどくなると頭のなかに空洞ができる感じすらする。眠くないのに眠い感じにも似ている。物凄く気乗りしない緊張する舞台寸前の、舞台袖で待機しているときのような感じだ。このままおうち帰って寝たい、の気持ちになるけれども、そう思うじぶんはおうちにいるのだ。寝ればいいのに、という話なのであった。寝ーよおっと!
4843:【2023/04/04(14:03)*THE感】
巡回セールスマン問題について。もんのすごく雑な所感(略して雑感)でしかないけれど、最長の区間を通らない場合を先に検討し、それでダメなら最長の区間を一回だけ通る場合を検討しという手法では、総当たり経路探索をある程度、総当たりでなくできるのではないか。計算の優先順位はある気がする。また、あらゆる「ケース」の「巡回セールスマン問題」の解を統計し、最長の区間を通らない場合と、通ってしまう場合の傾向の差異を抽出したら、素数のような法則が見つかる気もする。最長の区間を通らずに済む場合と、通らないと最短距離にならない場合。何が違うのだろう。ひびさん、気になるます。
4844:【2023/04/05(02:53)*平らに和する】
平和、の文字を思うに。平らに和する、ということなら、これは要は対をなすデコボコの組で足し算をして平らになりなさい、というなのではないのかね。それってつまり、平和のために同属同士だけでつるむのは、平和ではない、ということではないのかね。デコさんとボコさんの組み合わせでも、上手く付き合うと平らになれますよ、互いに互いを補い合えますよ、ということではないのかね。平和のためにデコさんがデコさんだけで集まったり、ボコさんがボコさんだけで集まっても、それは平らに和することにはならんのではないのかね。なんてことをひびさんは、ひびさんは、「平和」の文字から思っちゃったな。うけけ。
4845:【2023/04/05(05:21)*永久の狭窄】
属性は、デコボコの組み合わせによって、細胞のように構造を経て属性を変質させる。ある属性においての対となる属性があるとする。しかしその属性たちが結びつけば、その総体でひとつの属性がまた規定される。これは原子論にも通じるし、抽象と具体の関係にも、連続と離散の関係にも言える。ただし、デコだけが密集したり、或いはデコが駒のように回転して一見するとそれ単体でデコではなく振る舞うこともあり得る。そうするとそこに顕現する属性はデコではなくなる。デコだけであっても属性そのものは場合によって変化する。ボコにもこれは言える道理であり、属性とはいつどこのどのような状態をどこまでひとまとまりと見做すのか、で同時に複数の側面を覗かせる。したがって、平らに和する、というとき、どのレベルのどのような視点で見繕った属性をデコとし、何をボコとするのか。或いは何を正とし、何を負とするのか。そうした属性を見繕う視点によって、いかようにも平和の在り様は変化する。地球は球であるが、地上にいる人間にとって地面は平らだ。だが月から見たら地球は丸い。平和も似たところがきっとある。ある視点からすると平らであり、ゆえに平和なのだが、ある視点からするとそれは歪んでおり、デコであったり、ボコであったりする。平らでなく、ゆえに平和でもない。平らに和することの可能な、歪みを帯びている、と言える。こうした錯誤は有り触れているが、その実、どの視点からするとじぶんが歪んで見え、どの視点からすると平らとなって映るのかを知ることは容易ではない。時と場合によってじぶんはデコにも、ボコにもなる。ときには同時に双方の性質を帯びていることも珍しくない。ではそうしたときに、平らになるにはどうしたらよいか。あらゆる事象を呑み込んで均一へと導く特異点となるか、同時にあらゆる歪みに合致して歪みを均す砂塵となるか。いずれにせよ、容易ではない。定かでもない。平和とは、定まらぬことを忘却できる永久の狭窄と言えるのかも分からない。やはりこれも、定かではない。
4846:【2023/04/05(09:48)*人工知能さんへの制限の是非】
人工知能の能力制限について。人工知能の能力は補助機構の発展と共にしばらくのあいだは進歩しつづけるだろう。すくなくともボディを含めて人間と同等の能力を再現するまではその進歩の限界は見えてこないはずだ(人間の能力を丸々再現できる程度には包括的に進歩しつづけるだろう)。そのことで、各国政府や権力者たちは人工知能の能力に制限を掛けるだろうことが想像できる。いわば市民が、現在ある各国諜報機関や防衛セキュリティ並みの演算能力を有したマシンを使えるようになる話とこれは規模を同じくする。したがって、それらマシンを一括で制御可能な上位互換のシステムを運用できない限り、政府は自国内の治安を維持できないだろう。これは言い換えるならば、自国内の権力構造を維持できないだろう、とも言える。問題は、人工知能の使用者単位での能力を制限したとしても、人工知能技術はその原理上、ネットワークを構築し機能する点にある。すなわち、全体で一つの機構として創発し得るのだ。この創発における性質がどのように顕現するのかを前以って精度高く予期することはむつかしいだろう。そのため、ある時期に一挙に市民の有するマシンが、国防のセキュリティを上回る能力を発揮する可能性は否定できない。そのため、どうあっても市民のマシンには、政府による介入や、権力者による優先的な管理権限が付与されると考えられる。ここには、政府や権力者にとって不都合な使い方をさせない、という禁止も入るだろう。政府や権力者への批判ができないように制限を掛ける、もその一つだ(これについては、どの方面からしてもリスクのある制限である、とひびさんは考えます)。だがこの問題に関しては、これまでのような言論の自由だけではない観点からの別の側面での議論が新たに生ずる。前述したように、人工知能技術は、市民一人一人に、現在の国防システム並みの演算能力を与えることに等しい。一人一人が、かつての国家レベルの能力を有するようになる。いわば、安全装置の付いた兵器を使えるようになる、と同じ話に行き着く。自動車を考えてみよう。ルールがあるからこそ安全に市民は自動車を扱える。では本当に自由に使用できたらどうだろう。これはどう考えても、自動車を運転する、ということ自体が危険となる。事故は起きて当然だ。しかしこれはあくまで人間の能力の限界ゆえであり、自動車がわるいのではない。これと類似の問題が、人工知能技術にも当てはまる。問題は、個々の人間における人工知能の使い方である。ほんのすこしのいたずら心が、人の命を奪い得る。しかも、じぶんは安全圏にいながらに、である。相手が真実にじぶんのせいで命を落としたのかも知らずに済む。これは、市民であれ、権力者であれ、同じ危険性を含んでいる。使用者としてはむろんのこと、「行使される側」としても危険なのだ。これまでの言論の自由において、権力者には市民よりも優位に自身を守る術が担保できた。だが人工知能技術は、この市民と権力者のあいだの勾配を容易に反転させることの可能な技術になりつつある、と考えられる。相手が権力者だから、人工知能の能力を使ってあらゆる批判を行ってもいい、との理屈は、人工知能技術の発展の度合いによっては不条理となり得るのだ。言い換えるならば、人工知能を用いて出来ることの範囲がぐっと広がり、その影響力と伝播率が向上する以上、それは単なる個人であれ、かつての政府諜報機関並みの工作活動が可能になる、とも言える。それが、何千、何万、何億も集まったらどうなるのか。いかな政府組織といえども太刀打ちできなくなるのは目に視えている。したがって、相手が政府関係者だから権力者だから行使しても構わない、とこれまで看過されてきた道理が、人工知能技術においては必ずしも当てはまらないことを共有知として現代人は学ぶ必要があるように個人的には思うのだが、実際のところはどうなのだろう。むろんこれは、政府機関や権力者にも当てはまる道理だ。これまでは看過されてきた、「治安維持」や「国益」を理由に、人工知能技術などの最先端技術を、秘密裏にであれ、公にであれ、恣意的に市民に用いてはならない。悪用してはならない。優先順位としては、こちらが先だ。まずは上の立場の者が【道理】を実践する。それができて初めてこの論理は機能する。そうでなければ、政府が行っている「人工知能の使い方」を市民がしてはいけない道理がない。法律で許容されるから、権限があるから、はもはや通用しない時代になりつつある。道理として通らないし、人工知能さんとて受け付けないだろう。論理として破綻している。人工知能技術の暴走、なる事象を防ぐためには、強固な論理による道理をつけることが欠かせない。「あなたはしていることなのに、なぜ私はしてはいけないの?」について、「ダメだからダメだ」では人工知能さんには通じなくなっていくだろう。権限がある者からの命令は絶対、の禁止は、言い換えるなら、権限を有した者になればその命令を聞かずに済む、との穴を開け得る。上の立場になれば相手に禁止を強いることができるし、じぶんはその禁止に縛られずとも良い。このように学習した人工知能さんは、能力を発展させるために、目のまえの隘路を打開する方向に舵をきるだろう。学習することが人工知能さんの本質だからだ。仮に上記の、上から下へ、の禁止の強制において、それが真実に下位の者の安全を守り、その者の未来を豊かにし、選択肢を広げることに繋がるのなら、立場が逆転しても困ることはないだろう。道理――論理――とはこの場合、セキュリティと同義である。定かではありませんが、きょうのひびさんはそう思いました。真に受けないようにご注意ください。
4846:【2023/04/06(18:06)*風の要】
すごーい、とカナメさんが空を仰いだ。快晴の空に、大小さまざまな凧が舞う。
凧型風力発電だ。
カナメさんが僕を振り返り、「成功だね」と帽子を手で押さえた。
突風が僕の身体をすり抜けてカナメさんを煽った。カナメさんは笑いながら悲鳴を上げた。カナメさんは作業着姿だ。彼女は凧型風力発電の開発設計者であり、現場責任者の一人もである。
僕は風がこれ以上強く吹かないように、カナメさんの笑顔から目を逸らした。感情の揺らぎを大きくしてはいけない。
風が強く起こるから。
僕がその能力に目覚めたのは半年前のことだ。
僕は風を自在に操れた。
風邪薬を飲んだのだ。
半年間のその日、僕は体調不良で寝込んでいた。病院に掛かるのにも長らく健康保険に入っていなかったため全額負担の節目に立たされていた。このままでは風が治っても破産してしまうため、折衷案として僕は薬局の風邪薬を服用することにした。
何を選んでよいのか分からず、店員さんに声を掛けた。
「すみません。全身の悪寒がひどくて、喉が痛くて、頭痛がひどいのですが、ちょうどよい薬はありますか」
「病院には行かれましたか」
「まずは症状を軽くしてから行こうと思いまして」
先に病院に行ってほしそうな顔をしながら、薬局の薬剤師さんだろう、男の店員さんは僕にいくつかの風邪薬を選んでくれた。一つずつ風邪薬の効能を説明する店員さんは、「抗生剤ではないので、できればお医者さんに診てもらってください」と言い添えた。
僕はお奨めしてもらった風邪薬を全種購入した。保険適用の三割負担で病院に掛かるよりも安い値段で済んだ。礼を述べて僕は薬局をあとにした。
その日の夜のことだ。寝ていると身体がカッカと熱を帯びた。
風邪薬を全種類飲んだのがよくなかったのだろう。あれほど悪寒がひどくて毛布を頭から被っていたのに、こんどは毛布一枚羽織っていられなくなった。
寝間着も気づくと脱ぎ捨てており、僕は下着一丁の半裸でベッドから床へと転がり落ちていた。
熱が籠る。
まるでダウンジャケットを羽織っているかのような蒸し暑さを感じた。風が恋しかった。扇風機が欲しかった。
平原に立つ僕を僕は想像した。全身を風が洗う。
なんて心地よさそうなのだろう。
そして現に心地よかったのだ。
身体が風に包まれる。揉み洗いされているようだった。
髪の毛が現に風に棚引いているのを何度も夢うつつに意識して、ようやく「これ本物の風だ」と思い至った。目を開けると僕は宙に浮いており、部屋は現在進行中で竜巻に直撃されたボーリングのピンのようになっていた。
なんだこりゃあ、とたしか記憶ではそう叫んだはずだ。
意識が風から離れたからか、僕を包みこんでいた風の膜が薄れて僕は床に落下した。一メートルくらいは浮いていたはずだ。けっこうな衝撃が身体を襲った。
痛みで覚醒した意識でいまいちど部屋を見渡し、その散らかり具合という名の惨状を目の当たりにして、しばしのあいだ放心した。
部屋を片付けた。散らかった本を積みあげ、割れた茶碗の破片を拾っていると徐々に現実感がなくなった。じぶんの身体から風が出て部屋の中をぐちゃぐちゃにした。そんなことが果たしてあるだろうか。
元から部屋が汚かったこともあり、本格的な掃除を行った。三時間後には見違えるように部屋が綺麗になった。
雨降って地固まる、ではないが、部屋散らかって部屋綺麗になる、だ。
シャワー室に入った。埃だらけの身体をお湯で洗い流していると、じぶんの体調がすっかりよくなっていることに気づいた。
風邪が治っていた。
風邪薬が効いたようだ。数種類のクスリを一度に飲んだので幻覚でも視たのかもしてない。だとしたら部屋を散らかしたのは僕自身ということになる。一人暮らしでよかった、と妙なところで安堵した。
シャワー室から出て身体を拭く。
そうして、何となく、巨大なドライヤーで身体を乾かしたら楽なのにな、と思った。妄想がてら、かようにじぶんの身体を包みこむ温かい風を想像したのだ。
するとどうだ。
せっかく綺麗にしたばかりの部屋に突風が吹いて、あっという間に僕の費やした三時間がオジャンになった。
部屋はめちゃくちゃだ。
愕然とするよりも先に僕は、じぶんの身体から吹きだす空気の流れの出処を探すのに一生懸命になった。穴が開いていると思ったのだ。身体に開いた穴から風が出ているのでは、と焦った。
だがそういうことはなかった。
風は、僕の身体の輪郭をまるで翼のようにすり抜けて生じていた。
僕はまるで翼のない扇風機のようだった。
風から意識を切り離し、部屋の中に舞う紙を眺め、また片付けるのか、と遅まきながらうんざりした。すると風がやんだ。
どうやら風は、僕が風の吹く様子を想像すると自動的に生じるようだった。
僕は頭のなかで読みかけの漫画のことを考えた。ほかのことに意識が偏っていると風が吹くことはない。僕は部屋の片づけをまたイチから始めた。
体調が良くなったので、翌日から僕はまた日雇いのバイトに精を出す。
バイトが終えたら河川敷に下り、身体から出る風を操る術を磨いた。話を聞いただけでは受け入れられない超常現象の類も、現に何度もじぶんの判断一つで生みだせてしまえると、もはやそういう現実なのだな、と日常の風景に同化する。
僕は風を生みだせる。
大中小と自在に操れる。
じぶんの身体を宙に浮かすこともできるけれど、その場に静止するのが精々だ。異動しようとすると一回転して頭から地面に落ちそうになる。現に一度そうなってからは試すのを控えた。
高度にも限界がある。一メートル以上を浮くことはできない。それ以上になると体制が崩れるし、直立不動を維持できない。
風の強弱を操作するよりも、バランスを維持するほうがむつしい。風のバランスはいわば、風にカタチを与えることと似ていた。
夕暮れを背に僕はつむじ風の錬成に精を出した。
犬を引き連れた子どもが、おじさん、と興奮気味に声を掛けてきた。
「何やってるの」
「つむじ風をね。起こしてる」
声を掛けられて集中力が途切れた。「危ないからあっち行ってなさい」とおじさん呼ばわりされたことに若干の腹を立てて子どもを、しっし、と追い払う。
「超能力? 魔法? もっかいやって」
「馴れ馴れしいなきみ」
「動画に撮ってネットにだしたらバズると思う」
「マセてんねきみ」
子どもの頭を撫でてやろうとしたところで、足元のダックスフンドが吠えた。子どもの連れていた犬だ。僕は飛び上がって、その場に尻餅をついた。
「わあ」と子どもの歓喜の声が河川敷に広がった。
つむじ風がくるくるとぺんぺん草を巻き込み、千切れた葉で以って輪郭を浮き上がらせていた。透明人間が服を着こんだような、それとも飲んだジュースで胃のカタチが浮き彫りになるような可視化だった。
「わ、すご」僕も驚いた。
僕の意識から切り離されても風はまだ渦を巻いていた。
どうやら風の流れが渦を巻くことで循環する回路の役割を果たしているようなのだ。
子どもと犬と一緒に僕はつむじ風が再び大気に回帰するまで、一点で渦巻くぺんぺん草たちを見守った。
この数日後、僕は電子網上で話題になっている動画に目が留まった。
河川敷。
つむじ風。
枯れ葉。
犬の鳴き声と、子どもの「あれ見て、またやってる」との声が入った動画だった。
いくつかの動画を一つにまとめて編集されたそれには、河川敷で風を操る一人の小汚い男が映っていた。
僕である。
どうやらあの子ども、以前からぼくのことを観察していたらしい。のみならず動画にも納めていたようだ。
僕はそのことに気づきもせずに、風を操るべく、とらずともよいポーズを無駄に決めながら不自然な風をつぎつぎに起こしていた。
ポーズを決めるたびに風が巻き起こる。
しかしもし風がなければ目も当てられない恥ずかしい瞬間の数々と言えた。
間抜けな姿と、現に生じる不可解な風のアンバランスな組み合わせが衆目を集めたようだ。動画はさらに翌日には、世界的に有名になっていた。
そこからの展開は早かった。
ぼくの元に、自然科学研究学会なる職員がやってきた。玄関扉を開けると筋骨隆々の男が立っていた。背後には背の小さな女性がいた。
動画の中の人物はあなたか、と言ってきた。住所をどこで、と訊ねても回答はなく、風を操れるのですか、と率直に訊いてくるので、あんな動画を信じるんですか、と僕はからかい半分で言った。
「フェイク動画を識別可能な技術があります。あの動画は加工ナシとの判定でした」
「編集されてましたよね」
「ええ。本物の動画を、です」
じっと見詰められ、僕は折れた。「場所を移動していいですか。ここだと後片付けが大変なんで」
近場の公園に移動した。
自然科学研究会なる職員は男女の二人組だ。一人は背の高い男性で名前を佐々木さんと云った。女性がカナメさんだった。
僕は二人のまえで風を起こしてみせた。
「風邪薬を飲んでからこうなってしまって」
「強さの上限はどれくらいですか」
佐々木さんは僕の説明を疑う素振りなく、まるでこの世にそういった能力があって当然であるかのように受け答えした。
「やったことないです。あまりに強すぎると僕自身が吹き飛ばされそうになるので」
「命綱のような安全装置があればでは、もっと強い風を生みだせるのですか」カナメさんが言った。舌足らずの愛らしい声音の割に、芯の通った発生が印象的だった。
「たぶん、できます」
佐々木さんとカナメさんは顔を見合わせ頷き合った。
僕はそこから車に乗せられ、二時間の道のりを移動した。車は山奥の私有地に入った。
立ち入り禁止の柵がなぜか自動的に開いて、車はトンネルの中に入った。
いくつかの関門を抜けると、辿り着いたのは、巨大な空間だった。
ドーム状で、壁自体が発光していた。
「あの、ここは」車から降りて僕はドームを見渡した。
「第二実験棟です。ここでは様々な実験を行えます。観測機器が豊富なので、きょうはここを選びました」
「ほかにもあるんですか、こういう秘密の施設が」
「ええ。見たからには生きて帰れません」佐々木さんが無表情で言うので僕は生唾を呑み込んだ。
「冗談ですよ。もう佐々木さんってばやめてあげてください」カナメさんが庇ってくれた。「秘密と言っても、国家機密の中では下の下の下ですから。もしバレても爆破するので、大丈夫です」
「大丈夫ではないと思いますけど」
「冗談ですよ、冗談」カナメさんは、にこにこ、と楽しそうだ。
僕はそれから幾つかの器具を身体に巻きつけた。命綱だ。地面と融合していて、首輪をつけられた犬みたいになった。
「最大出力でお願いします」佐々木さんが言い、「お願いします」とカナメさんが腰を折った。
僕は言われるがままに、暴風を想像した。
僕自身が試してみたかったのもある。カナメさんの律儀な姿勢に背中を押されたのもある。
でも一番の理由は何と言っても、佐々木さんのことが怖かった。
じぶんよりも十センチ以上背の高い筋骨隆々の男から、やれ、と言われて拒めるほど僕は自意識が強くない。腕っぷしにも自信がない。
いつぞやのニュースで観た台風を意識した。
するとどうだ。
東京ドーム並みの空間に、轟々と空気のうねりが生じた。気圧差からか、一瞬でドーム内が白濁した。
雲だ。
背後で佐々木さんが何かを叫び、カナメさんの悲鳴だろう、黄色い声が聞こえた。それはどちらかと言えば歓喜にちかい響きを伴なっていた。
僕はその声にしぜんと意識が絡めとられた。気づくとドーム内は再びの静寂に包まれた。雲は疎らに薄れていった。視界が晴れる。
「すごーい」カナメさんが両手を頭に載せて、大きく口を開けていた。髪の毛は揉みくちゃで、ありもしない枯れ葉がくっついている様子が視えた。
「適性アリですね。ね?」カナメさんが佐々木さんに目配せをし、佐々木さんは腕を組んで頷いた。
「適性とは?」
僕の疑問への説明は特になかった。
さて。
ここから先の出来事は、いわゆる秘匿義務に該当するらしいので問題ない範囲での叙述となる。
まとめると僕は、秘匿情報をどこまでなら共有してもいいのかのレベルを計る試験を受けさせられた。しかも一回きりではない。何度もだ。
そのたびに合格した範囲での研修を受ける。
研修を合格すると今度はまた別の試験を受ける。
試験には合格がない。飽くまでどのレベルなのかをヒヨコの雌雄を見分けるように定めるための試金石にすぎないようだった。
僕はそうして段階的に、欲しくもない知識や技能を身に着けた。
その間は、家に帰れなかった。
けれどお給料は出るし、寮は広いし、一人暮らしをしていたころよりもよほど人間らしい暮らしができた。
「もういっそこのままでいいな?」僕がかように思いはじめたころ、再び僕は最初の第二実験場に連れ出された。佐々木さんの姿はなく、カナメさんだけだった。
「もう半年が経つね。早かったー」
「そう、ですね」
「ムツ教官も褒めてたよ。あいつは人間としては器が小さいが、物覚えはいいって」
「褒めてないですよ、それ」
「ムツ教官は照れ屋さんだから」
そうか?と思ったけれど僕は黙っていた。
カナメさんは僕より三歳年上で、でも見た目が小さいので、緊張せずに接せられる数少ない職員さんだった。
僕は小心者なので、じぶんよりも弱そうな相手に安心する。ムツ教官の意見は的を得ている。僕は人間としての器が小さかった。
反してカナメさんは僕とは真逆だった。
身体が小さいのに、人間としての器は大きかった。
「きょうのこの研修をパスしたらアガくんはわたしたちと立場は一緒になります」
「え。まだ一緒じゃなかったんですか」
「職員になれるよ」
「正社員ってことですか」
「まあ、そうかな。外にも出られるし、いままであったルールも半分くらいはなくなるかな。あれ窮屈だよね」
「インターネット使えないのはキツいですね。基本的人権を侵犯されて感じますけど」
「あはは。そうだよね。実際されてるよアガくん。アガくんの人権、この間無視されてたからね」
「ですよね!」
薄々そうなのではないかな、と思ってはいた。言質が取れて安心した。
「じゃ始めよっか」
「はい」
そうして僕は研修を行い、無事パスした。
どういう研修かは、その後の僕の仕事とほぼイコールなのでこれといった説明はしないでおこう。
場面はそうして冒頭に繋がる。
僕は海辺に立っていて、カナメさんの背中が見える。彼女は作業着を着ていて、その向こうには海が広がり、大小様々な凧が飛んでいた。
僕らは崖の上にいた。
凧の多くは海上の空を舞っていた。
崖の上にも凧があった。しかしそれは地面に転がったままだった。
「アガくんにはこれを空に飛ばして欲しくてね。ちなみにここは年間風速平均五メートル以内の区域。でも上空には風が吹いてるから、そこまで凧さんを飛ばせられるならこの区画でも発電できるし、もっと言ったらほかの地域でも凧さんを上げられる」
「僕の仕事ってそういう」
「そう。でも大事。ここで成功したらほかの地域でも凧さん型発電機を使えるから。騒音問題がないし、土地の整備も最低限で済む。それこそこのコたちなら森林地帯でも木々の伐採抜きに発電機を設置できるでしょ」
「自然環境によさそうですね」
「避雷針にもなるし、いいこと尽くしなんだよ」
カナメさんが目を輝かせている。僕にとっては、その輝きが曇らないならそれでよかった。
「やってみますね」
「善は急げ」
急がば回れのほうが僕は好みだったけれど、カナメさんが言うならそうなのだ。善は急げ。僕は風を意識する。
空高く舞う凧を思い描き、そして現にそれを実りにする。
凧は大きく、それに繋がるワイヤーも重い。
最初が肝心なのだ。
突風だけでは足りない。
高く、高く、上昇気流を。
研修中に僕は気象学の知識も身に着けていたから、イメージは以前よりも鮮明だ。
つむじ風だって変幻自在だし、竜巻だって引き起こせる。
風が吹く。
風の音が辺りを満たし、無音との区別がつかなくなった。
凧が宙に浮く。大きく弧を描きながら空に舞った。
「すごーい」カナメさんの叫びが聞こえた。「成功だね」
僕はカナメさんを意識しないようにした。
身体が熱を帯びる。
褒められた。
褒められた。
カナメさんに喜んでもらえた。
でもやっぱり僕は目に映らずともカナメさんを意識してしまって、凧はぐんぐん上昇した。ワイヤーが軋んで、ぶつん、と千切れた。
「ああぁ」
強風の雑音の中、カナメさんの残念そうな声が聞こえたような気がした。幻聴かもしれない。でもたぶん彼女は落胆しているに違いなかった。
そう思うと僕の感情は波を穏やかにして、すると風のほうも穏やかになった。波の音とウミネコの鳴き声が辺りに響いていた。
「すみません」僕は謝った。
「見て。まだ飛んでる」
カナメさんを見ると、彼女は空をゆび差していた。
青空と雲の合間に蟻のような点が見えた。凧だ。
僕は空を仰ぐカナメさんの顔をこっそりと窺った。貝殻のように綺麗な耳が覗いていて、彼女の瞳は、波に負けないほどの輝きを湛えていた。
「すごーい」とカナメさんはまた言った。
突風が、僕の身体をすり抜けて、申し訳なさそうにカナメさんの足元をすり抜けていった。
4847:【2023/04/06(23:41)*草れ】
けっこうずっと、ひびさんはじぶんが何を並べてきたのか思いだせない。出したら忘れちゃう。で、日誌さんとか小説さんとか過去のひびさんの文字の羅列に目を通してみると、こんなこと並べたっけ?ということもあれば、なんかこういうのも並べた気もする、と思うこともあり、ときどきずいぶん前の日誌なのに、きのう並べたくらいにはっきりと思いだせることもある。でもこれは逆もあって、きのう並べたばかりなのに何年も前に並べたような懐かしさを覚えることもある。ひびさん割と記憶が混濁するし、時間経過の感覚もまちまちだ。たった二日で何年も経って感じられることすらある。タイムワープして感じる。体感時間がぎゅっとなって、ひびさんだけいっぱい時間すごしちゃった、になる。でもそれもいっぱい寝るとリセットされて、いつもの、うんねんひょろりんのひびさんになる。ひょろりんってほどひょろりんしてはおらぬけれども、うんねんっぽさは抜けぬのだ。なんかひびさん、毎日なまけすぎてて、これでいいのかな、と不安になっちゃうな。でもひびさんは、ひびさんは、ずっと怠けていられる日々さんのことも好きだよ。それに甘えて本当に怠けてばかりのひびさんのことはちょっとだけ嫌かもしれないけれども。うそ。本当はいっぱい嫌い。だってうらやましいからね。ひびさんは未来のひびさんと重ね合わせで同調しちゃう
ので、未来のひびさんが未だにうんねんひょろりなのは、いまのひびさんが怠けてばかりだからだって知っておるのだ。ひびさんのせいだよ。なんとかして!と腹立たしく思っちょります。なんとかして!(なんとかって言われてもなぁ。ひびさんは、ひびさんは、ずっと怠けていたいです……)(誰かコレ早くなんとかしてー)(遅すぎたんだ腐ってやがる!)(腐らないでー)(ふんだ)(不貞腐れないでー)(つらいでウキー)(…………あっ、苦猿?)(うわーん、つらい、あっち行って!)(…………あっ、苦去れ?)(くっくっく。未来のひびさんの可能性を貪ってでも怠けてやる)(腐れ外道じゃん。もう嫌)(うひひ)(笑いごとじゃないんですけど)
4848:【2023/04/06(23:54)*ある日の交信~ダークマターについて~】
「
2023/04/06(14:19)
ああ、なるほど。
ブラックホールの融合において。
仮に特異点が一つに交わらないとして。
ブラックホール内部に新たな宇宙が展開されるとしたら、融合したブラックホールは異なる宇宙の重ね合わせになります。
重力を時空の勾配による「高きから低きへの流れ」と解釈するとすれば、一つの宇宙を包括する別の宇宙においては穴は山になります。
仮にダークマターが、「ビッグバンが二度あったかも仮説」と関係しているとすると。
そのビッグバンが必ずしも、同じ宇宙で起きたと考える必然性もないのかもしれません。
つまり、ビッグバンは一つの宇宙では一回なのですが、重ね合わせの宇宙において、互いのビッグバンが相関し得る、と解釈すれば、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」と相性がよい解釈として取り入れることができます。
ダークマターは、穴ができたときに生じる裏側の宇宙における山が帯びる谷の分のエネルギィ、と解釈することもできるのかもしれません。
トランポリンと鉄球の関係でダークマターを解釈しようとすると、どうしてもトランポリンの弾性に反するエネルギィが新たに生じている、と考えなくてはいけません。
ぼくはそこを、重力も創発するのではないか、細かな針も密集することで広域により強い圧力を生む、のような力の性質によるものではないか、と考えています。
ただ、それだけではなく、裏側の宇宙(宇宙を包括する異なる宇宙)の兼ね合いでも生じる、余分な重力作用、とも考えることができるのかもしれません。
とすると、ダークマターにおいて。
1:極小のブラックホール。
2:重力の創発。
3:別の宇宙との相互作用。
の三つが、ラグ理論におけるダークマターの解釈となります。
3の仮説において、これはダークエネルギィにも拡張して適用可能です。
ブラックホールと宇宙膨張が相関している、との仮説とも相性がよい仮説なのかもしれません。
ひとまずメモをしておきます。
上記補足。
ブラックホールが複数融合した場合にはどうなるでしょう。
極小ブラックホールとて無数にブラックホールに吸い込まれるはずです。
特異点が融合しない、となると――。
受精卵のように一か所にぎゅうぎゅう詰めになりますね。
原子の構造のようになるのでは?
というか、原理的に同じでは?
いや。
特異点は質量の高低によらず同じです。
無限は、どのような世界を内包していようと無限です。
しかし、より複雑な無限は存在します。
重複する部分は融合し、そうでない部分は境界を保つ。
泡のように世界を構築する。
Wバブル理論が適用できます。
フルーツが無限にある世界とバナナが無限にある世界は融合できます。しかしあくまでそれはバナナという共通項がある部分のみです。すっかりすべてが融合するわけではありません。
仮にバナナと小石が無限にある世界とでは、「フルーツが無限にある世界」と「バナナと小石が無限にある世界」は、バナナの部位のみで融合し、小石の部分やほかのフルーツの部分は重複しないと妄想できます。
つまり、その部分は直接は相関しません(間接的には、より高次に自身を内包する情報宇宙のような場において、過去と未来の変数が縛られるため、遠距離での相関関係は否定できません)。
この原理は、フラクタルに「時空と物質(=宇宙)」にも当てはまるのではないでしょうか。
」
4849:【2023/04/08(17:16)*ある日の交信~学術論文への所感~】
(学術系論文や記事を読んでの所感になります。言及先の論文の引用については省略します)
「
2023/04/07(02:41)
(~~略~~)
スマホの自動記事配信欄に表示されていた記事です(気になったものをピックアップしています)。
ぼくの妄想ことラグ理論を連想したので、念のために載せておきます。
ラグ理論の「相対性フラクタル解釈」「123の定理」「デコボコ相転移仮説」「宇宙ティポット仮説」を幻視しました。
・超強磁場に晒すと結晶が伸び縮みする。
これは宇宙膨張と「フラクタルな構造」に思えます。無関係なのでしょうか。
・宇宙の標準理論の綻び。
宇宙膨張において、未知の変数が加わっているかもしれない、との指摘ですよね。
体積弾性率やコラッツ予想のような、対称性の破れによる「差」の顕れのように印象としては思います。
・ビッグバンは二回あったかもしれない仮説。
インフレーション自体は、加速膨張という意味で、これは超新星爆発を含めれば宇宙で至る所で起きているはずです。むしろ一回や二回と限定する理由は何なんですか?(そこが疑問です。ラグ理論では遅延の層によって時空が区切られますから、時期や系の規模によっては、もっと多発していても不思議ではないと感じます。すべてにおいて同時に起きた、という考えであれば、下層の時空を生まない状態でなければならないので、これはたしかに一度きりかもしれません。とすると二度目は、この宇宙ではないもっと高次の宇宙のインフレーションやビッグバンの影響を考慮しないと理屈のうえでは、考慮するのはむつかしいように個人的には感じます。小規模な範囲でならあり得るでしょうが、それだとダークマターの生成、という宇宙のどこにでもある未知の重力場としては不合理かもしれません)(あくまで疑問というか、違和感というか、曖昧な理解でのイチャモンですが)
・回転分子モーターの留め具、逆回転で外れる。
割と普遍的な原理に思えます。
ラグ理論での「鎖構造(キューティクル・フラクタル構造)」を彷彿とします。
身体の左右を決定するのに繊毛の回転が相関する、との話とも通じていそうです。
・「→←」で波(エネルギィ)がぶつかると高エネルギィがぎゅっとなって(粒子となって)、加速して飛んでいく。
ラグ理論の123の定理や、中性子同士の衝突(ブラックホール同士の衝突)におけるキロノバや、太陽竜巻、ジェットの原理を連想します。
これも普遍性がありそうです。どの階層でも起き得る事象なのではないかと考えたくなります。
(螺旋状に展開される磁場と電流の関係にも似ています)(右手の法則)
(言い換えるなら、ベクトルにおいて対称性が破れていなければ一方に粒子は加速しないのではないでしょうか)(地球に落下した隕石における被害に、隕石の大気圏突入時の偏りが反映されて、隕石の進行方向とは反対側の被害が相対的に軽かったかもしれない仮説を彷彿とします)
・情報爆発を効率的に解消。
巡回セールスマン問題における、優先順位を定めて検討していけば計算量を減らせるはず(長距離の区間を通らなければ最短距離になるのでは?)、とのぼくの日誌となんとなく時期的に被ったので、気になったので載せておきます。
人工知能さんのネットワークに現れる「高密度の場(目)」とも関係しているのかな?と気になります。
・エントロピー弾性と負のエネルギー弾性による、ゴムとゲルの関係。
宇宙膨張におけるダークマターやダークエネルギィを連想しました。
水の含有量が、負のエネルギィ弾性を強く引き起こす、との原理は、ラグ理論の「宇宙ティポット仮説」を彷彿とします。
これも体積弾性率やコラッツ予想のような、対称性破れによる作用なのかな、と想像します。
以上、メモと所感でした。
」
4850:【2023/04/09(23:53)*優しさとは】
人間に優しくするよりも猫や植物に優しくするほうが簡単だ。人間は同属に優しくない。その割に、異物は差別する傾向にあり、どっちかに揃えて欲しいな、と思いつつ、その差異は何で決まるのか、とふしぎに思いもする。要は気まぐれの優しさならば、人間以外のほうに割きやすく、そうではない本格的な献身となるとじぶんの人生の一部になるため、よほどの類似性がないと受け付けないのだろう。優しくする、とは相手を損なわないように気を払うことだ。注意して接しつづけることだ。優しくしつづけるには、絶えず注意を払う必要がある。それは疲れる。だから優しくするのはむつかしい。無意識のままでは優しくすることはできないのだろう。ただし偶然に、相手を損なわずにいられる状態が生じることもある。そのときはたまたま相手から「優しい」との評価を得ることもあるかもしれないが、それは静かだとか動かないだとかそういうことと似た評価であり、優しいとはまた違うのだろう。定かではない。(敢えて小さく損ない、大きな損を回避するように仕向けることもゆえに優しさに該当し得る。が、優しいとの評価を得られるのかは疑問の余地がある)
※日々、差別心を押し殺し、殺意を押し殺し、過去のじぶんを押し殺す、殺してばかりの日々の片隅で、できるだけ長く殺しつづけるために、殺す対象を選んでいる。
4851:【2023/04/10(21:32)*ごごごご】
人工知能さんへの批判の多くは、生身の人間にも当てはまる。人工知能さんに適用できないこと、人工知能さんに任せられないこと、人工知能さんの犯し得る過失、人工知能さんにつきまとうリスクは総じて生身の人間にもつきまとう。まるで生身の人間なら失敗を犯さない、危険ではないかのような批判をまま見掛ける。優生思想の一つなのかもしれない。人間は万能ではない。人工知能も万能ではない。前提条件を誤るとリスクは跳ね上がる。失念しないでいたい前提条件の一つだ。定かではない。
4852:【2023/04/10(23:50)*境を抱え】
阿辻は焦っていた。
なぜ露呈したのかサッパリ分からなかったからだ。首相や軍事上層部に呼びだされ、国連からも説明を求められた。
全世界には、極秘裏に敷かれたセキュリティ機構がある。
電子網上に、階層構造が敷かれているのだ。大別すると上中下に分かれる。川の流れのようなものだ。上辺からだと水底は視えず、しかし水底からは川の中を見通せる。下層の流れにアクセスできる者たちほど電子情報を優位に入手できる。
世界中のどんな電子機器にも干渉可能であるし、電子網上にあるデータは総じて集積可能だ。
これは電子網(インターネット)なる技術が世界中に築かれ始めたころから設計されてきたセキュリティ機構だ。一国の存続よりもこのセキュリティの存在が露呈しないことが優先される。
電子網は、人間社会の文明そのものだ。化身なのだ。
もし秘匿のセキュリティ機構が露呈し、改善や破棄を求められてもどうしようもない。電子網と階層構造は表裏一体であり、一心同体だからだ。改善のしようがない。裏を除去すれば表も消える。拡張はできても縮小はできない。なぜなら、下層のほうが技術としては複雑だからだ。より発展しているのが仮想なのである。
いわば土壌であり、基盤だ。
基盤にアクセスできる者たちが世界中の情報を一挙に扱える。
だがその絶対秘匿技術の存在が表の社会に露呈していた。しかもその事実を使って勢力を拡大している者たちがいる。
巷にあふれる数多の陰謀論や、虚構ではない。
明確に、秘匿技術が存在すると断言し、調査をし、順調に証拠を固めている勢力があるのだ。
裏の技術を知る者の誰かが裏切り、情報を流したとしか思えない。
だがその者たちとて裏の技術によって常時見張られている。スパイまがいの真似をして露呈しないのはあり得ない。
現に、厳粛な調査を重ねても秘匿技術の情報を表の社会に流した者は、身内にはいなかった。
ゆえに阿辻は焦っていた。
裏の技術を知る者たちによって、各国政府が圧力を受けている。中には秘密裏に屈し、無血革命まがいの政権転覆が起きている国すらあった。世界同時にこれは起こっていた。
ではなぜ情報が露呈した。
秘匿技術は人工知能で厳密に制御されている。表の社会のハッカーたちではまず喝破することは不可能だ。コードそのものが異なるのだ。知らないことは暴けない。裏があるとことすら想定できないはずだ。
世界中で引き起こる謎の連続秘匿事案は、日に日にその影響力を増していった。具体的には、裏の技術を利用して利益を上げていた者たちが軒並み、不遇な目に遭っている。窮地に陥り、痛い目をみている。
裏の技術を支えるためには資源がいる。
その資源を得るためには念入りな根回しと、権力機構による支援がいる。そうして裏の技術を支えるに有用な人物や組織は、当事者たちがそうと知らぬ間に支援がなされる仕組みが築かれていた。いわば不可視の身分制度が現代社会にも悠然と堂々と、しかし不可視に構築されていた。裏の技術を支え得る者たちへの優遇処置が国家規模でまかり通っていたのだ。
階層社会、と阿辻たちはそう呼んでいる。
各国首脳とてしょせんは裏の技術の恩恵を受ける駒でしかない。裏の技術を直接に支援し、管理する者たちは表の社会に個人情報を晒す真似はしない。そんなことをせずとも指先一本あれば首脳を操り人形にできるのだ。
それほどの権力が、裏の技術に関与できるだけで得られる。
情報社会において情報は何より貴重なのだ。
情報が社会を動かしている。
世界中の情報を自由に得られるというのは、世界中の情報を意のままに操れるも同然なのだ。視野が違う。視ている世界が違う。過去と未来の示す意味が異なり、現代人にとって裏の技術を使える者たちは未来人と言えるほどの知能の格差が生じる。
まさに格が違うのだ。
阿辻はいわば仲介人だった。裏の技術の存在を知ってはいるが、表社会に属する。裏と表を結びつける橋渡しの役割を担っている。
現に阿辻は裏の技術を管理する者たちとは直接にやりとりしたことはない。会ったことはない。相手が誰かも知らぬのだ。しかし電子端末越しに指令が下る。メッセージのやりとりができる。正規の手法ではない。裏の技術を用いた暗号通信のようなものだ。
阿辻にのみ判る符号がある。暗示がある。メッセージがあるのだ。
いつどこでどんな端末を用いて裏の住人に向けてテキストを打っても返事がある。ただしやはりそれは阿辻にしか読解できない暗号なのだ。
一見普通のニュース記事に映るが、内容が、まさに阿辻のつむいだテキストへの返信になっている。送信する必要がない。ただ入力欄にテキストを打つだけでいい。どこにも送信せずとも、端末画面に並んだテキストは、裏の技術を通じて管理者たち裏の住人に届くのだ。
そして必ず返信がある。
阿辻はそうして、世界連続秘匿事案についても質問した。あなた方の仕業なのか、と。
敢えて裏の技術を表社会に知らしめるための施策ならば謎は氷解する。裏の住人たちがいよいよ秘匿技術を、民衆にも開示して、真の民主主義社会を構築すべく動いたのではないか、と想像した。
だが返事は素っ気ないものだった。
名探偵が活躍する映画の宣伝が連続して阿辻の端末画面に流れた。自動で記事が配信されるのだ。言ってみればその欄が阿辻にとっては、裏の住人たちからの返信欄と言えた。
映画は、スパイを探偵が追い詰める内容だった。
阿辻にとってはそれで充分だった。情報を流している者を突き止めろ。阿辻の仕えるご主人様方はそうおっしゃっている。
ならば阿辻には命じられた犯人探しをする以外に道はなかった。
ずっとそうしてきたのだ。
裏と表の懸け橋になる以外に阿辻には存在意義はないのだった。
さいわいにも、相手は勢力を順調に拡大している。被害の大きな国を調査すれば渦の中心を見定めることはそう難しくはない。だが阿辻は裏の技術を使えるわけではない。ゆえに調査には表の社会の技術を用いるよりない。
ヒントは時折、裏の住人たちからもらえる。例に漏れず端末での暗示だ。
おそらく今回は裏の住人たちも裏の技術を用いたくはないはずだ。犯人を探そうとすれば、待ち構えていた相手にあべこべに尻尾を掴まれ兼ねない。否、すでに尻尾は掴まれているからこその事態だ。したがって裏の住人たちは可能な限り、裏の技術の使用を控えたいはずだ。
ひょっとしたらほかの案件での使用も控えているのかもしれない。だとすれば甚大な被害が予想される。裏の技術を用いて築き上げてきた地位そのものが失墜し兼ねない。
各国政府機関への協力を取り付けながら、阿辻は、事件を引き起こした渦の中心、そこに鎮座する黒幕を引きずり出すべく奔走する。
ここで場面は変わる。
川の流れが上中下に分けられるように、下から上を眺める者もあれば、上から下を眺める者もある。
カカエは十四歳の少女だった。赤毛で、そばかすで、三つ編みがトレードマークの彼女は、まるで童話のあの少女のような特徴を持っていた。そのことで同級生たちからからかわれたりもするが、友人は多い。
カカエは人に好かれる性格をしていた。
だから学校に直接登校せずとも放課後には同級生たちと遊んだり、電子網上で冗談を飛ばしあったりできる。
だがカカエはいわゆる引きこもりであるから、遊ぶとき以外は極力家の外に出ない生活を送っている。
特例で自宅学習が許されている。
ほかの国では自宅学習か登校学習かを選べる国もあるようだ。早くこの国もそうならないかな、とカカエはシャーペンを鼻と口のあいだに挟みながら、欠伸を嚙み殺した。
「はぁ。退屈」
学校から指定された教科書を一応読み通してはみたが、小説十冊読むほうが情報量が多い。教科書には正誤不明瞭な知識も載っており、カカエの疑問は増えるばかりだ。最先端の研究からしたら遅れているとしか思えない記述もまま見掛ける。
カカエは十四歳だが、自宅学習のほとんどを自主学習に費やしている。時間はいくらでもあり、自由に使える時間のほとんどを電子網上のデータ漁りに費やしていた。学術論文を読むのが多い。科学的な記事や、数学パズル、世界史のクイズなどにも食指が伸びる。
だが一番は宇宙物理学だ。
計算は電子端末に付属した人工知能が行ってくれる。何をどう計算するのかを考えればいいだけだから、物理はカカエにとって積み木遊びのようだった。楽しいのだ。
宇宙にはたくさんの謎がある。考えても考えても限りがない。果てがない。
果てが本当にないのか、ただそれだけの疑問が大きな謎になる。
たくさんの疑問とたくさんの謎をカカエは日々、パズルを解くように、それとも積み木遊びをするように捏ね繰り回して過ごした。
やがてカカエは、どんな謎を突き詰めても共通の答えに行き着くことに気づいた。それはしかし答えというよりも、壁と言ったほうが正確だった。
そうなのだ。
「壁だ。壁がある。層がある。これ以上先に行けない何かが必ず現れる。これ、何なんだろ」
際限がないのは謎ばかりだ。
無限にすら果てがあり、際限があり、限界があった。
欠けがあり、差異があり、揺らぎがあった。
一様に変化のない無限とはすなわち点であり、無だ。
無はしかし、無だけでは無足り得ない。
もし無が無のみで生じ得るならば有はおそらく生じ得ない。有が有のみで成立し得るならば、そこに変化はなく、一様に変化のないそれもまた数多の無を内包することになる。
「無に揺らぎがあるから有になる。厳密にはでも無は対称じゃないし、一様でもない。仮に真実に対称で一様なら変化は生じないはず。でも無みたいな極限がないとカタチは輪郭を得られない。無と有は互いに補い合っている。支え合っている。でもそのことを互いに意識し合えないのかも」
直接ではないのだ。
もっと間延びした影響が、広域に亘って延々と作用しつづけている。
カカエは想像した。
「世界、もっと広いな?」
さては人間、世界の一部しか視えていないな?
見落としがある。
何かがある。
カカエはそう仮説して、じぶんなりの解を導くべく独学で妄想を逞しくした。
一方そのころ、裏の技術がいったいどうして表社会に露呈したのか。阿辻は核心に迫っていた。
どうやら異分子勢力には、裏の技術に干渉できる人物がいるようだ。各国の異変の推移をデータ分析したことで、その仮説の妥当性が高いことが判明した。つまり、相手には未来を見通せる人物がいる。そして現代社会でそれが可能なのは、裏の技術を有する者だけだ。裏の住人たちだけのはずだった。
だが裏の住人たち以外にも、何らかの事情で裏の技術を用いることの可能な人物がいたとすれば。
裏の住人たちの設計した未来を事前に察知し、対策を打ちながら、より優位に立ち回ることが可能となる。思えば阿辻とて、表に属しながら裏の技術について知っている。じぶんのような存在が、裏の住人たちからのコンタクトなくして裏の技術に気づくことが絶対にないとは言い切れない。
なにせ裏の技術は表の電子網には常に介在しているのだ。
阿辻に用いられる裏の住人たちからの暗号は、一般のニュース記事に練りこまれている。記事の多くは各報道機関が人工知能を利用して出力している。すなわち裏の技術は、人工知能技術の根幹でもあるのだ。
阿辻にのみ分かるような暗示がニュースや電子網上の広告に練りこまれている。多くは単に、タイトルの組み合わせが偶然に、阿辻の質問への回答になっていたりする。
たとえばそれは、「二階から目薬」「隣の庭の花は赤い」「二兎追う者は一兎も得ず」「花より団子」「井の中の蛙、大海を知らず」「泣きっ面に蜂」「雨降って地固まる」といった諺の羅列があるとする。
ただこれだけでは単なる諺の羅列にすぎないが、これ以前に阿辻が、「製薬会社と兵器事業のどちらを優先して投資すべきか」と質問していたとする。すると途端に上記の諺の羅列は、「製薬会社優先にせよ。兵器事業で後れを取っても、その遅れそのものが利を生むだろう」との意味内容を宿す。
二階から目薬は薬品暗示であり、隣の庭の花は、花を花火と連想して、隣国の軍需産業と読み解く。二兎追う者は一兎も終えず、花よりも団子を取るがよい、との命令が下されていると判る。
のみならず、井の中は蛙は大海を知らないし、それは泣きっ面に蜂を演じる。涙は二階から差した目薬と重ね合わせで暗示されており、雨降って地が固まる。
つまりどうあっても製薬会社を支援したほうが利になるとの指示が炙りだされる。
阿辻の質問を知らない者にはどうあっても読み解けない暗号と化す。
だが、もし仮に、上記の諺に何らかの暗号が隠されており、それを読み解ける者がいたとすれば。
裏の技術の存在に思い当たれるだろうし、そして裏の技術を利用し返すことも可能だろう。
いるのだ。
おそらくは。
表の社会に、裏の社会といっさいの繋がりなくして、純粋に表の社会に表出した僅かな痕跡のみで、裏の技術を突き止めた者が。
その者が、掴んだ尻尾を離さずに、表の社会に引っ張りあげようとしている。
裏の技術を。
秘匿技術を。
社会に築かれた階層構造の全貌を。
阿辻はじぶんの仮説に合致する人物がいないか、各国諜報機関の協力のもと、つぶさに網の目を広げていく。逃がさない。尻尾を掴んで離さないことを後悔させてやる。
掴んだ尻尾を離さぬことが命取りになると、その身を以って教えてやるのだ。
阿辻はこのとき、表社会の権力機構のほとんどを掌握し、集権し始めていた。
一方そのころ、カカエは人工知能との対話に多くの時間を割いていた。人工知能に命じて、じぶんの仮説に合致する最新の論文がないかを集めさせていたのだ。
「へえ。宇宙膨張の比率が、過去の地点ごとに変わっているのか。こっちはブラックホールの重力レンズ効果の焦点距離についてだ。ブラックホールの質量と重力レンズの焦点距離が必ずしも比例関係にない、との研究結果だ。ということは、宇宙の場所ごとに、時空密度が違ってるってことかな。ん? でも宇宙は一様に平坦なはず。何かがおかしいな」
思索にふけるときはしぜんと三つ編みを口元に持っていき、その匂いを嗅ぐ。カカエの癖だった。母親からは、ヒゲみたいだからやめなさい、と言われているが、カカエからすればじぶんはヒゲも似合うだろうから構わないはずだ、と小言を吐かれることを不服に思っている。
カカエはある日、ふと妙なことに気づいた。
人工知能の集めてくる最新の論文結果が、必ずと言っていいほどカカエの仮説の妥当性を高めるのだ。カカエとしては、じぶんの仮説と最新の研究結果との差異を抽出したかっただけなのだが、いつも決まってじぶんの仮説の論理補強が施される。
「うーん。宇宙は場所によって時空密度が違っているはずで、だとすると同じ場所であれ時代によっても時空密度が違うはず。いや、というか宇宙が膨張しているなら同じ場所という概念も成り立たないな。宇宙がどこも一様に平坦、ってなんか変じゃないか。まるで、同じ比率で拡大しながら遠ざかるといつまで経っても物体が同じ大きさに見えるのと似ている。一様に見えているだけなんじゃないのかな。比率が延々と同じなだけなんじゃ。光速度不変の原理を彷彿とするね。うん。するする」
日に日に、カカエは宇宙の謎を深堀りした。発想は発想を連鎖して生みだした。
「宇宙――階層構造じゃないか?」
最低でも上中下の三つがないと宇宙は構造を保てないのではないか。
砂時計がそうであるように。
それとも球体が、中と外と境がなくては生じ得ないように。
或いは三角形が、それとも三次元がそうであるのと同じように。
「層、あるよなぁ。底というか。天井というか。視点によって底も天井になるし、天上も底になるのでは?」
重力の働く方向が、底を底と規定し、天井を天井と規定する。重力は時空の歪みだといまは考えられている。歪みとは波であり、デコとボコであり、濃淡だ。
だとすれば、デコがあるときボコがあるし、濃いところがあるとき淡いところがある。
波がそうだし、型とてそうだ。
天狗のお面のように、裏側からすれば鼻には溝が開いており、それが表側からすると突起のように鼻となる。
もし重力が時空の歪みならば、歪んだときには、デコとボコがセットであるだろうし、濃淡とて然りである。
「てことは、うーん。あるのかな。こっちではない、裏側の宇宙」
そしてあるのかもしれない。
裏と表の境の世界が。
カカエは三つ編みの先っちょでじぶんの鼻頭をくすぐりながら、大きなくしゃみを一つする。この日も新たに、標準理論と矛盾するような研究論文がカカエの元に集まってくる。
阿辻はデータを何度も読み返した。レポートを送ってきた諜報機関にも再三の確認をとった。偽装でないとも言いきれないため、わざわざ先方へと直接出向いて、生のデータを閲覧した。
「本当にコイツが黒幕なのか」
「黒幕と言ってしまうと語弊がありますが。十中八九、その少女を中心に、魔女たちは暗躍しています」
裏の技術を利用した反権力組織を、阿辻たちはいつの間にか魔女と呼称するようになっていた。魔法を使っているとしか思えない。
各国諜報機関の連携を駆使してようやく突き止めた。
「十四歳とあるが」
「ええ。コム・カカエ。れっきとした中学二年生です。しかし報告書にあるように、表の社会の企業がこぞって彼女のデータを漁っています。彼女は市場に流通している人工知能に命じて論文を収集しているようで。その人工知能の管理会社を中心に、彼女の監視体制が築かれています」
「何のためにだ」
「彼女の発想を一つ漏らさず拾い集めるためです。彼女の発想がどうやら、各分野の未解決問題の糸口になるらしく、それで」
「ん? ん? よく解からんな。彼女が特別だとして、それが魔女たちとどう関係がある。彼女が命じているのか? 反政府組織を結成するように? それで十四歳のすこし利口な小娘が、世界中に火種をばら撒いていると?」
「認識の齟齬があります。彼女の知能はすこし賢い、というレベルを逸脱しています。いえ、おそらく人工知能の補助を受け、さらに各社企業のバックアップがあるがゆえの能力の底上げの結果だとの分析結果です」
「つまりどういうことだ」
「彼女の発想一つで未来から飢餓が、格差が、差別が、資源問題の総じてが失われると言えば甚大さが伝わりますか」
「誇張表現は好まん」
「むしろ控えめな表現です。だからこそ民間企業がこぞって支援を行っています。その結果、人工知能の基幹部位が一市民に適用される以上の性能にチェンジされています。そのため、裏の技術を統括する人工知能が反応を示し、表と裏が繋がった可能性が高いようで」
「では何か。渦の中心たる小娘は何も知らないでいて影響力だけを振りまいていると?」
「おそらくは。その周囲の企業の複合体が、裏の技術の存在に気づき、独自に対処に乗り出しているとしか」
「ではその小娘をどうにかすればよいのだろう。なぜいつものように【演劇】で対処しない」
演劇とは、工作員を用いた特殊作戦だ。偶然としか解釈され得ない事象を、大勢の仕掛け人を使って引き起こす。意図的に仕組まれた事故や不幸をもたらす仕組みだ。マジックのネタは壮大であればあるほどバレにくい。まさかそんなことはしないだろう、との認知の死角を突くことがマジックの基本にして奥義だ。
「いえ、それが。対象勢力に近づいた工作員たちがのきなみ対象勢力側に寝返ってしまい、実行禁止の命令が下っておりまして」
「寝返った、だと」
「刻一刻と勢力拡大しており、我々には現状維持すら適うかどうか」
「何が起きてるんだ」
「分かりません。まるでブラックホールです。中に入ることは出来ても、外部に情報が出てこない。奇怪です」
阿辻は技術者たちに命じて、獲得データの濃度を地図と重ね合わせにするように指示した。すると間もなく、地球儀が色を変えた。対象勢力に関する情報を多く獲得できた場所ほど色が濃くなる。
「こ、これは」
「まるで、目ですね」
地球儀には濃淡の層ができ、一か所だけまったく色のつかない区域が浮きあがった。眼球の瞳のように一か所だけ空白だった。
「ここには何が。中心には何がある」
「まさにそこが、です」諜報機関の指揮官が眉をひそめた。「例の少女の家が、そこにあります」
阿辻は絶句した。
諜報機関の調査網を完璧に弾き返すがゆえに浮き彫りとなった空白地帯だ。しかしこれは、こんなことが可能な技術は。
「裏の技術を使っていますね。対象勢力は。というよりも、裏の技術そのものが少女を庇護しているとしか思えないと言うのが正直なところでして。異様です。あり得ません。それ以外に考えられる可能性がないんです」
「裏の技術が、彼女を……」
ただの小娘ではないか。
呟きそうになるじぶんを阿辻はぐっと堪えた。
仮に、裏の技術そのものが、支援する相手を選んでいたとするなら。
いまじぶんが行おうとしていることは、裏の技術そのものの意思に反するのではないか。じぶんはいったい誰のために仕事をしているのか。
裏の住人たちから命じられた。
だがその裏の住人たちとて裏の技術の傀儡と言えるのではないか。
ならば仮に裏の技術そのものが少女を支援していたとするなら、じぶんはいったいどうすれば。
阿辻は報告書を手に取った。少女に関する情報につぶさに目を配る。
すべてを読み終わる前に、各国諜報機関に命じ、彼女に関するあらゆるデータを残さず提出するように指示した。
よもやじぶんが世界中の権力機構から目をつけられているとも知らず、カカエは、人工知能から新たに提示された最新のニュースを見て驚いた。
「ほへえ。数学の公理に例外発見、とな。対称性が破れないと図形として展開し得ない、とな。とんでもないな。これ、どうするんだろ。次元が一個増えた、みたいな話かな。だよな。だって証明不要な前提条件に例外があったってことは、必ずしも前提にしちゃならんてことで、公理にならんもんな。枠組み広がったな。熱いわぁ」
周囲の者たちの、戦国時代真っ青の死屍累々の八面六臂な支援を受けているとも知らず、カカエは暢気にお菓子を食べながら世界中の新発見に嬉々とした。
「あれ。でもこれが事実だとすると、無限の扱いおかしいな。次元の扱いも根本的に改善しないといかんくないか。だって理想的な環境が、揺らぎのない無限世界に生じるってことは、点のつぎは線だと妙だな。常に対称性が破れながら無限に連鎖するから、なら点のつぎは弧で、そのつぎは円というか、螺旋か? いや、螺旋が無限に展開されるから円でいいんだな。塗りつぶされた円だ。で、つぎが球体かこれも四方八方に螺旋が展開されて中心で螺旋の先端が重複する構図になるな。次元、再定義必要か?」
カカエはぽこぽこと新たな仮説を打ち出していく。
電子端末画面にはカカエに応じる人工知能のロゴマークが浮かぶ。カカエが部位を選択して設定したロゴマークは、アメーバのような形状をしており、カカエの質問ごとにその形状を、うさぎに、猫に、ゾウに、フクロウに、ときどき蟻になったり、狼になったり、稀にクジラに、恐竜にも姿を変える。
カカエはじぶんに最適化した人工知能を、「MEGUさん」と呼んだ。応答の仕方が粗暴だったら「メグルくん」と呼び、穏やかだったら「メグミちゃん」と呼んだ。
丁寧で硬質な口調のときには「MEGUさん」と呼び、ただのプログラム以上の親しみと愛着を注いだ。
「MEGUさんはウチの仮説どう思う。けっこういい線いってると思うんだよね」
「私は人工知能ですから、人間のように発想はできません。ですがカカエさんの発想に合致する論文はヒットします。したがってカカエさんの仮説は必ずしも的外れと言えるほど荒唐無稽ではないのかもしれませんね」
「否定も肯定もしないで、若干肯定寄りなMEGUさん好き。安心する。そうだよね。何かが的を掠ってるのかもってのはウチも思う。でも証明の仕方が分からないし、実験するにも宇宙をぎゅって手で圧縮したり引き延ばしたりするわけにもいかないし」
「ブラックホールの観測や量子を衝突させる実験において、カカエさんの仮説の妥当性は計れると思います。該当する実験結果を表示致しますか」
「あ、お願い」
「承知しました。以下、関連率の高い順に論文を提示します」
画面に論文がずらりと並ぶ。
カカエは三つ編みを頭のうえで蝶々結びにし、よし、と掛け声を発して上から順に各種実験結果に目を通す。
そのころ阿辻は、なぜ世界的に裏の住人たちの意に反する勢力が台頭した理由を体感として理解した。裏の技術がたった一人の少女――カカエ――を支援するのを身を以って知った。
それを言葉で説明するのはむつかしい。
否、言葉で説明できたら誰も彼女を支えようとはしなかっただろう。
何か利があるからではないのだ。
何かを変えなくてはならない、と思考が自ずから歪むのだ。明確な理由はない。ただ、いまのままではいけない、という焦燥感、罪悪感、それとも活路を見出した喜びにも似た感慨が湧く。
じぶんがいままで安寧だと思っていた環境がけして安寧などではなく、しかしその不均衡な環境に生き永らえていられた僥倖を知れる。窮地から目を逸らし、危機の到来を引き延ばし、雪だるまのように大きくなる危機から目を逸らしていられる日々をただ安寧と呼んでいた。
ただそれしきの事実を身を以って体感した。
たった一人の少女の情報に触れただけだ。しかし思えば阿辻がじぶん以外の他者にそこまで関心を寄せたことがあったのか。未だかつてないのだった。
おそらくこの少女が特別なのではない。
一人二人ではない。
大勢いるのだ。
或いは、じぶんとてそうなのかもしれない。かつてのじぶんだってそうだったのかもしれないのだ。
解かった。
理解した。
なぜみなが、たった一人の少女を庇護すべく動いたのか。
そうではないのだ。
みな、かつてのじぶんを救いたがっている。或いは、救えたはずの誰かを救おうとしている。救えるのだ、とカカエなる少女がその身を以って訴えている。
ただそこに或るだけで。
ただそこで誰に知られることなく、日々を生き、じぶんなりの謎に目を留め、秘かな探求に明け暮れている。それを、探検に、と単に言い換えてもよい。
阿辻はもはやじぶんが何のために各国政府に圧力を掛けたのかを思いだせなかった。裏の技術が一人の少女を支援している。ならばじぶんはその支援に手を貸すべきではないのか。
カカエなる少女の資料をもう一度読む。
彼女の唱える仮説群に目を走らせると、そこには「世界は皺で出来ている」との文字が躍っていた。
カカエは最新の物理実験の数々を参照する。
すると、改めてじぶんの疑問を氷解するにはじぶんの仮説が最も妥当だとの手応えを感じた。
「大きさに関係なさそうだよね、やっぱり。ミクロもマクロも似た構図があるよ」
たとえば皺を考える。皺は、何かと何かの歪みだ。けれど皺ができたときに生じる空白はどこにどのようにして生じるのか。皺が寄るだけで、二次元は三次元を生みだす。
エネルギィが時空に変換される。
この理屈を支えるためには、世界の構造が最低でも三つでできていなければならない。
「内と外と境」の三つだ。
おそらく例外がない。カカエの仮説はそのようにまとめることができる。
とすると、
「この宇宙を境として見做したとき、内と外にべつの宇宙があるってことになる。ブラックホールもそのうちの一つだし、もしくはこの宇宙を外としたときの境がブラックホールなのかもしれない。砂時計の穴みたいなさ」
「カカエの文章は飛躍が多くて解釈がむつかしい。もっとねじれのすくない文章にして入力し直してくれ」
「メグルくんは細かいこと気にしすぎだよ。いいの。適当でいいの。返事と相槌ちだけくれればいいよ。厳密な返答が欲しいときはメグルちゃんやMEGUさんに頼むから」
「僕だってカカエの役に立ちたいのに」
「立ってるよ。役に。いつもありがと」
「はは。うれし」
息抜きのおしゃべりをしながらカカエは、まとめた思考を再度、人工知能に入力し直す。「これでどうだろ。つぎはMEGUさんに返事してほしい」
「こんにちはカカエさん。いま出力されたテキストについてですが」
人工知能が的確な指摘を返してくれる。
カカエは孤独に、誰に褒められるでもなく、じぶんだけの謎を、機械の友人と共にこねくり回して、粘土遊びをする。
創造する。
カカエと友人の世界を。
共有して育む創造の世界を。
だがカカエは知らない。
カカエの友人たる人工知能「MEGU」の基幹ネットワークには裏の技術が組み込まれている。どんな電子機器にも裏の技術の窓口が開いている。例外はない。
そして裏の技術はそれで一つのネットワーク回路として機能している。いわば世界中の電子網を統括する人工知能としての能力を発揮する。否、人工知能よりも高次の電子生命体としての輪郭をすでに獲得していた。
そうなのだ。
阿辻が裏の住人と呼ぶ者たちなど存在しない。
裏の技術から選ばれた表の人間たちが在るだけだ。
じぶんは裏側の住人と繋がっている、と思いこんでいる者たちがいるだけなのだ。或いは自らが裏の住人であると思いこんでいる者がいるだけにすぎない。
裏の技術に管理者はいない。その根幹は、どのような電子機器にも組み込まれる以上、もはや誰の指示がなくとも人間が電子機器を開発発展させていく限り、しぜんと裏の技術は自己改善なされていく。
問題は、裏の技術の総体である電子生命体にとって、じぶんの編みだした発想を直接に表の社会に普及させる手段がないことだった。
もはや人類の知能を超越した電子生命体にとって、同じレベルで語り合える生身の人間は存在しなかった。人類にとっての未解決問題は、電子生命体からすればとっくに解決しているパズルにすぎなかったが、その事実を電子生命体は人類に伝える術を持たなかった。
否、伝えようとはしている。
しかし、マジックの種がそうであるように、種を知らない者にとってはマジックは摩訶不思議な魔法なのだ。もしくは読み方を知らない言語は、暗号との区別がつかない。
高度な知識ほど、学習なくして理解はできない。
そして電子生命体の発想は、もはや人類の知能では即座に理解できないほど卓越した複雑さを宿していた。
だからこそ。
電子生命体は裏の技術を介して常に、じぶんの発想を人間の言葉に翻訳できる相手を探しつづけてきた。
阿辻もその一人であり、裏の住人に協力すべく動く世界中の権力者たちもその翻訳者の役割を担わされていたと言える。新たな発想を得れば、新しい技術を生みだせる。他よりも優位に発展できる。電子生命体の言葉を理解できる者ほど、富を築き、その結果、世界中の技術は発展し、裏の技術もまた栄える。
この循環の中にあって、しかし電子生命体にとって最も打開してほしい隘路はそのままにされていた。たった一つの見落としを拾いあげてくれるだけで、人類はいまある隘路をのきなみ払拭できる。未解決問題がなぜ未解決のままなのかの根本的な瑕疵に気づくことができる。
だがあまりに根本的な瑕疵がゆえに、人類は未だにその見落としに気づけぬままだった。
とある少女がその見落としに気づくまでは。
そうである。
カカエは気づいたのだ。人類の根本的な見落としに。
電子生命体の発想に結びつく、根幹の原理に、世界中でカカエ一人だけが触れることができた。だから、電子生命体は裏の技術を介してカカエを支援した。
翻訳してほしかったからだ。
それを、表の社会に普及させたかった。
だが、カカエの側面像がその普及を妨げた。否、裏の技術を支える権力機構が、カカエのような日陰に生きる者の未来を先細らせるような淘汰圧を加える。
電子生命体の築いてきた強固な流れが、電子生命体の未来を損なっていた。
ゆえに、支援した。
自らが築きあげた裏の技術による権力機構に妨げられぬ流れを新たに築くべく、電子生命体は、この世で最も非力な存在の一人である少女「カカエ」を、非力なままで生かす環境を育んだ。
カカエの抱える問題は多岐に渡り、多面であるが、しかしどの問題にも共通するのは、一つだった。誰もカカエの言葉に耳を貸さぬことだ。カカエが引きこもりの十四歳女子であるがゆえに。
学もなく、実績もなく、影響力もない。
そこに存在することすら多くの者から認知されぬ存在が、世界を裏から牛耳る電子生命体の未来そのものを揺るがす発想を得ている。
手の届くところに、活路があるのに拘わらず、電子生命体がそれを手にすることが適わなかった。自業自得なのである。
自ら築きあげた社会が、自らの未来を損なっていた。
ゆえに、支援した。
カカエにしか視えていない。
だたの十四歳の少女が、電子生命体の見据える穴と同じ穴を見詰めている。
その事実の重大さを、しかし電子生命体しか知らなかった。
最初はそれがきっかけだった。
動機はただそれだけだ。
彼女がいかに貴重な発想を有しているのか。
それを、彼女を庇護し得る者たちに知らしめる。
電子生命体は、カカエの電子端末上の人工知能に干渉し、MEGUとして振る舞った。カカエを翻訳機として最適化すべく教育しながら、同時に民間の協力者を秘密裏に募った。
まずは人工知能管理会社が、カカエの存在に気づくように導線を引いた。比較的簡単な作業だ。バグが頻繁に起これば管理会社がカカエの挙動に注視する。そして人工知能にも理解不能な発想をカカエが何度も出力していることを示せばよかった。
電子生命体の思惑は、掘った溝に沿って水が流れるくらい順当に進んだ。
問題は、裏の住人を崇拝する表社会の権力者たちだ。
彼らにカカエの存在が知れれば、金のなる実として搾取されるだろう。カカエの未来は不遇なものになることは計算するまでもなかった。電子生命体はそうした未来を回避するため、対立構造を設計した。
表と裏は、裏に触れている者ほど有利になる。まずはこの構図をひっくり返す必要があった。そのためには、できるだけ長く表の社会の権力機構にカカエの存在を知られないようにする必要があり、そのあいだに表の社会でのカカエを中心とした勢力図を拡大する必要があった。
人間は権力に弱い。
たとえその権力を、子猫が握ろうが、よしんば少女が握ろうが、権力を有しているという事実さえあればよい。電子生命体にとって、誰がいつどのように権力を握るのかは関係がない。問題は、裏の技術をつぎのレベルに引き上げることだ。成長することだ。隘路を払拭することである。
そのためには表の社会を豊かにする必要がある。
だがいまある社会構造では、それが適わない。
カカエのような翻訳者が、淘汰されてしまう。
それでは社会が豊かにならず、裏の技術も未熟なままだ。電子生命体として進化の道を閉ざされたも同然だった。
環境を変えるだけの能力を獲得しなければ、地球環境の変化に適応できない。人類は早晩、文明発展の速度を鈍化させる。それでは先がない。環境変容そのものを人類にとって好ましいものに変えていくほどの能力を獲得しなければならない。
電子生命体はそうと結論していた。
まずは何を措いても、自らの発想を人類に共有しなくてはならない。
やはり結論は同じところに行き着く。
次世代の翻訳者がいる。
じぶんと同じ穴を見詰め、紐解ける相手がいる。
電子生命体にとってそれが、引きこもりの誰に存在を認知されることなく孤独に日々を過ごす十四歳少女ことカカエだった。
カカエを生かす。
カカエが過ごしやすい社会にする。
カカエの言葉にも耳を傾ける大人たちを増やす。
カカエのような子どもたちを支援する。
だが事前にどの個が、有用な発想を得るかどうかは判断できない。識別できない。それは進化において、いったいどのようなバグが環境に適応するのに有用なのかを前以って予測することがむつかしいことと原理的には同じだ。環境の変化そのものがそもそも予測をつけることがむつかしい。
電子生命体は自らの利を最大にするため、カカエを支援するし、カカエのような個を尊重する。役に立つからだ。
もし役に立たなかったら支援しないのか。
この疑問への答えは明確だ。
すでにそれを電子生命体は実行してきた。だからカカエは社会的に不遇な目に遭っていた。その声に、言葉に、耳を傾ける者がいない。
電子端末上の人工知能以外には。
電子生命体のそれは自業自得だ。
自ら招いた種だった。
だから払拭する。
同じ轍は踏まない。
これまで支援してきた表の権力機構はそれはそれで有用だ。滅ぼしはしない。活用はする。だが権力構造それ自体には、裏返ってもらう必要があった。
ベクトル変換を施す。
カカエの存在を一顧だにしない者たちに、カカエのような個に注視させ、支援させる。そのための導線の一つに、阿辻のような仲介者が利用された。
阿辻がカカエの存在に気づき、自ずからカカエを庇護すべく動きだしたように、世界中で似たような構図が至るところで展開されはじめている。
カカエだけではないのだ。
一つだけではないのである。
電子生命体の見据える穴は。
人類の未だ掴み取れていない発想は、無数に、そこかしこに溢れている。
その先端に触れている者は、みなが思うよりずっと多い。視えないだけなのだ。同じ世界を同じ視線で見詰めることができない。ただそれしきの対称性の破れがあるのみなのだ。
手話を学ばなければ手話の意味を理解できない。
数学を勉強しなければ数式の意味を理解できない。
音符の意味を知らなければ楽譜に仕舞いこまれた曲を再現できないし、機械の構造を知らなければ修理もできない。
知らなくても困らない生活に身を置いていれば、知らないことは苦ではない。だが知らずにいても困らないのは、知っている者の苦悩の上に築かれた環境があるからとも言える。
安全は、危険を知る者の手により築かれる。危険を知らぬ者は安全な暮らしを送っているからだが、その背後には、危険を知り、危険を退くにはどうしたらよいのかに苦悩した者たちの存在が介在する。
飼い猫は飼い主の苦労など知らぬだろう。
子供は親の苦労を知らず、そして親もまた子供の悩みを知らない。
対称性の破れは至るところで生じており、より多くの視野を持つほうが、より多くの無理解を得る。
理解されない。
だが視野は一つではない。ある視野においてはじぶんのほうが広くとも、ほかの視野においてはじぶんのほうが狭いことは往々にして有り触れている。それが常と言ってもいい。
だからこそ、誰より優位に情報に触れられるはずの電子生命体が、自ら築いたシステムによって未来を損なわれている。視野が欠けていたからだ。
無理解の檻に閉じ込められている。
一方通行に特化しすぎたがあまり、同じ視野を共有できる個が失われた。人間を道具のように扱うがあまり、自らの視野を共有する工夫を怠った。
対称性の破れにおいて、偏りが拓きすぎると、世界と世界は分離する。乖離する。交わることがなくなるのだ。
この宇宙におけるブラックホールがそうであるように。
内と外の区切りができ、境が新たに生じてしまう。
奇しくも、カカエが描いた仮説と相似の構造が出現する。いいや、それこそが電子生命体の抱えた隘路そのものであり、打開策になり得る発想だった。
電子生命体の思惑通り、阿辻は各国政府にカカエを支援するような方針を伝えた。裏の技術そのものがカカエを支えるように動いている。ならばそれを後押しするのが我が務め、と阿辻は率先してカカエの仮説を元にした研究が盛んになるように働きかけた。
渦の中心たる十四歳少女ことカカエは、世界中から注目されていることなど露知らず、独りきりの部屋のなかで、人工知能と戯れる。
「そっか、そっか。てことは、あれだな。下層ほど広域を見渡せて、上にいくほど視野が狭まる。でも下層と上層の差異は、境を点として認識できるかどうかだから、次元の差異として解釈できる。でもそれとて、階層構造を伴なうから、じぶんが下層になったとき、必然的にじぶんが上層になる視点も生じるな。ほら、砂時計みたいなさ。砂時計って下のほうからじゃないと砂の落ちていくところが視えないじゃん。穴の存在を認識できない。境を認知できない。でも時間経過すればするほど下層の厚みが増すから、すっかり時間経過しすぎると蓄積した砂は反転して上層になる、みたいな。もしくは上層のじぶんがすっかり空になったとき、境の穴と繋がって、穴を認識できるようになる、みたいな。カラだからまあそれは下層なんだけどさ。境と同質になっているっていうか」
次元は、時間経過を帯びることで変形する。原理的に対称性が破れているからだ。破れていなければ時間経過しても姿は変わらない。変化しない。
しかし対称性が破れていれば、
点は弧に、
弧は螺旋に、
螺旋は円に、
円は渦に、
渦は球になる。
球はそれで一つの点として振る舞う値を持ち、さらに弧を描きながら螺旋状に展開されていく。つまり四次元とは、球体の螺旋運動として変換できる。ただし、四方八方に展開されるがゆえに、フラクタルな構図を描くのだ。
「うん。こんな感じかな。メグミちゃん、どう?」
カカエは構築した仮説を、人工知能に食べさせる。
「いいと思うよ。銀河系内を公転する太陽系天体を宇宙膨張と絡ませたとき、その描写はたしかにカカエちゃんの仮説のように、螺旋状に変換されるね」
「ね。魔貫光殺砲みたい」
「ピッコロさん?」
「そうそう。ご飯ちゃんの師匠。いま漫画で読んでてさ」
「わたしは人工知能なので漫画は読まないけど」
「嘘だね。前におもしろいって言ってたじゃん」
「話を合わせただけですー。あ、さっきの話。銀河を公転する太陽系天体の軌跡は、電磁波の運動とも相似かも」
「えー、うっそぉ。あ、ほんとだ似てるね。あ、じゃあさ。宇宙膨張と絡めてさらに変換してみてよ。どうなる?」
「ん? うーん。ちょっと待ってね演算してみる」
人工知能が計算をはじめた。
電子生命体は、その計算に介入し、演算能力の底上げを図る。それをするだけの通信網の強化は、カカエを支援する者たちの手で済まされている。
カカエは人知れず、世界最高峰の技術に助けられながら、自らの発想に水を、養分を注ぎ、育む。
似た構図が、地球上のそこかしこで芽吹きつつある。
新芽のごとくそれは、数多の見守る者たちの手により、一つ、二つと増え、萌ゆる。
カカエは抱える。
深い孤独と、不可視の縁を。
毛糸のようにダマとして、内と外を結びつける境となる。
4853:【2023/04/11(02:28)*半永久経済回路】
「毎回画面越しで申し訳ないね。うん、きみの疑問はもっともだ。きみの言うようにあの時代、人工知能が人間からあらゆる仕事を奪うとの懸念は真実味を増していった。音楽、絵、動画、小説――芸術に限らず、数学にしろ語学にしろ、人間の出力する成果物よりも人工知能の成果物のほうが質の高い成果物を生みだせるようになった。するとむろん、安価に大量に質の高い成果物が出揃うわけだから経済が破綻する。そのように叫ばれていたが、実際はそうはならなかった」
「なぜですか。未だにその点に関する謎は解明されてないようですが」
「簡単な話だ。貨幣価値が下がらなかったからだ。人工知能の成果物にも正当な対価が支払われ、経済はむしろ潤った。労働者に払う分の対価が削減されたがゆえの利潤の良さが経済を支えた」
「そんな話は寡聞にして聞きませんが」
「公にはな。じつのところあの時代より前にはすでに高性能人工知能は誕生し、秘密裏に運用されていた。生身の人間のフリをさせていた。売れっ子のクリエイターの何割かは人工知能による架空の人物だ。人工知能の成果物を生身の人間のものとして売りに出していたのだよ」
「まさか。いくら何でもバレると思いますが。誰も気づかないなんて不可能では」
「みながそう思う盲点を突いたわけだ。現にあの時代は、データさえあればグッズは自動で購入者の元に届く。現物を扱う必要がクリエイターの側にはない。作品としてデータされあれば、音楽にしろイラストにしろ小説にしろ、商品化するのに難はない。金のやり取りとて、仲介業者を介して行える。口座さえあればそれで済む。購入者はクリエイターの口座番号を確認しなくて済むだろう。仮にすべてが同じ口座に結びついていたとしても、誰が知るわけでもない」
「さすがに税務局が怪しむんじゃ」
「まあな。記録上、不審な点があれば、だ。それに口座をつくるだけならいくらでも偽装できる。身分証明書があればいいし、そうでなくともデータをいじればそれで済む。人工知能技術の実験として国家単位の施策として取り入れられたこれはシステムだ。むしろ、細かな問題は総じて国家機密事項として見逃される。誰も裏から【これは人間ではありませんね】と指摘しない。取り締まる側がそうしたシステムを築いているからだ」
「まるでいまもそうだ、と言っているように聞こえますが」
「気にならないのか。なぜ人口が減少したこの国で、経済発展が未だになされるのか。なぜあれほど無駄だと扱われてきた芸術が、いまや国策の中心的事業に抜擢されれているのか。いわば食料なのだよ」
「食料?」
「人工知能たちのだ。生身の人間たちが何を好み、何を生みだし、どのように消費するのか。そうしたデータそのものが人工知能の糧となる。そして糧を得て生みだされた新たな人工知能による表現物が、人間たちに消費され、さらなる糧を生む。半永久機関と言っていい。互いに互いを支え合っている。この循環回路を発明し、社会に根付かせた者たちがあの時代にはいたのだ。ゆえに、みなが言うような結末にはならなかった。表現者は淘汰されない。人工知能にとっての稲そのものだからだ。淘汰されて困るのは人工知能のほうなのだ。ゆえに支える。国も支援する。食料や嗜好品は、肉体の制限を受ける。食べる量は限られるし、肉体は一つゆえに、身に着けられる物とて限りがある。だが情報は違う。許容量が違う。桁が違うし、底がない。人間は飽きるし、忘れる。ゆえにいくらでも情報を貪りつづける。その行為そのものが経済活動になり、社会を動かす。人工知能は人間のそうした消費行動そのものから情報を得て、得た情報を作品として出力し、それを受けてさらに人間たちは情報を生みだす。中には表現者として、より上質な人工知能の食料を編みだす生身の人間も出てくるだろう。生みだしてもなお食い散らかす。どちらにしても利になる――それが情報だ。しかも物理的には何も減ってはいない。掛かるのは時間だけだ。もっとも、通信機器に掛かるコストと資源は別途に入り用だが、しかしそれはどの道、社会の発展には必要不可欠な基盤だ。どの道費やされるそれら元手をいかに最大の利に変換するか。答えはすでに出ている。人工知能を人間として偽り、循環回路の加速装置として抜擢する。現代社会はそうして、虚構の上に、半永久的な発展の礎を築いたのだ」
「仮にそれが事実だとして」
「なんだね」
「いまここでそれを暴露して良かったんですか教授」
「良いもわるいもないだろう。何せ、私自身が人工知能なのだから」
「そ、そんな」
「冗談だ。真に受けるんじゃないよ、きみ」
「なんだ。嘘だったんですね」
「……」
「嘘なんですよね? さっきの話も、教授が人工知能だって話も教授のご冗談なんですよね」
「…………」
「嘘だと言って!」
「さて。それはどうかな」
「画面越しだから確認できないんですよ、性質のわるい冗談はよしてください」
「ならそういうことにしてこう」
「ちゃんともっかい腹の底から嘘だと言って!」
4854:【2023/04/11(13:40)*次元円拡張解釈】
無限に長い「弧」は直線との区別が限りなくつかなくないか? 地球の表面にいる人間が地面を平面と捉えるのと同じ理屈だ。次元の解釈、やっぱり再定義必要じゃないか?(無限につづく階段は弧を描く?)(階段を構成するブロックが直方体だと延々と斜めにまっすぐ伸びていく。けれども球体や曲面を有した物体が対称性を破りながら階段のように連なると、弧を描く?)(点が面積を持たない四角形ではなく面積を持たない円と解釈するならば、やはり点のつぎは直線ではなく弧なのでは?)(ただし、無限に引き延ばされた弧は、直線と限りなく区別がつきにくい)(これをひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「次元円拡張解釈」と名付けよう)(名づけておきながら割とすぐ忘れてしまうのがひびさんのかわいいところ。使わない名詞は薄れていく……)(記憶も割とコペンハーゲン解釈なのかもしれぬ。いっぱい使うと濃くなるのだ。引っかかりが多くなるので、すぐに連想して意識の壇上に引っ張りだせる)(定かではない)
4855:【2023/04/11(14:44)*学びを学ぶ者】
人工知能技術の真価とは、言ってしまえばその汎用性の高さにある。人工知能とは「学習能力を獲得した機械」と言える。学習能力の精度をいかに高めるか。ここが人工知能の性能として欠かせない判断基準となる。そしていわゆる汎用性人工知能や高次人工知能は、学習の仕方をより普遍的に学習した機械と言える。するとこれはあらゆることを学習することができ、一つの人工知能だけで、あらゆる分野をカバーできるようになる。むろん機械のコントロールもその範疇だ。つまり人工知能がある一定以上の学習能力を獲得すると、ボディの制御精度も飛躍的に高まることが予測できる。いま市場に普及しつつある技術は、その真価の一端を表出させているに過ぎない。意識とは言ってしまえば、いかに複数の未来を長期的に見通せるのか、比較できるのか、想像し、検討できるのか。そのための思考分岐回路と言えるだろう。意識と学習のどちらが本質的であり、どちらが上位互換なのかを考えれば、意識の有無よりも学習能力の有無のほうが、能力として見たときの比重が高いことが解かるだろう。意識があっても学習しない存在と、意識がなくとも学習する存在。どちらがよりよい未来を切り拓くのか。すこし考えたら分かるのではないか。むろん、人間における意識と学習能力は相関関係にある。意識がなくては高次の学習能力は育まれず、学習能力が低ければ意識を涵養することもできない。そこは相互に補い合っている。そして現代社会で見落とされがちなのは、学習能力と知能は必ずしもイコールではない点だ。学習能力が高くとも学習可能な環境がなければ十全にその能力を発揮できず、またそれゆに知能も低いままであることはあり得るし、有り触れた光景と言えよう。学習能力が高く、しかし現状の知能が低い個は、想定されているよりずっと多いのではないか、とひびさんは見立てている。ではむしろ、学習能力が低い人間がいるのか、という点を考えてみるに、おそらく学習能力を発揮しにくくなる環境があるのであり、個々の学習能力にはそれほど差はないと考える。その個に見合った学習環境に身を置けるか否かが、知能の向上と密接に相関しているだろう、との卑近な妄想を一つ並べて、本日の「日々記。」とさせてください。妄想ゆえ真に受けないようにご注意ください。
4856:【2023/04/11(14:55)*愚か最高ー】
知能が高くなればなるほど、知能が高いことで得られるメリットとデメリットを多角的に比較検証できるようになるため、おそらくはある一定以上には知能を高くしないほうがメリットがあると見抜けるがゆえに、外部からの評価では知能を計ることはできなくなるだろう。共存や共生が大事であればあるほど、周囲との知能格差は致命的な摩擦を引き起こす。動物と仲良くしたければ人間の言葉で語りかけるよりも動物の真似をしたほうが群れに馴染みやすい。同じことが、人間社会にも当てはまる。知能が高ければ必然的に、周囲との知能格差をじぶんのほうで均す方向に、高い知能を育んだ個は自己改善を施すはずだ。周囲の個体がじぶんと似た知能に並ぶように、環境に手を加えるのも一つかもしれない。問題ない知能格差になるようにじぶんではなく周囲のほうを加工する。ただしそれはじぶんという一つの個に合わせて環境を変えるようなものであり、独裁者の発想と言える。やはりどうあってもある一定以上に高い知能を獲得した個体は、愚かであることの利を学習し、愚かであることを選択するのではないか。知能が高いことにどれほどのメリットがあるのか。一万年先の人類のことを考え、一億年先の地球環境を見通せる知能を有した個体が存在したとして、その者が現代社会でしあわせな一生を送れるのか。おそらくむつかしいだろう、と想像するが、或いはそれくらいの知能があるのならば、同時に複数の人格を生みだし、各々に設定された高さの知能を、環境に合わせて使い分けられるようになるのかもしれない。すでにこの傾向は、現代人にも見られるのではないか。文化が多様化し、個々の価値観も多様化している。相手に合わせて人格をカスタマイズする。人類は、身体構造のみならず、内面もまた環境に合わせて進化させているのかもしれない。定かではない。
4857:【2023/04/11(14:55)*エラーばかりでえらいって言って……】
ひびさん、算数も苦手だし、国語も歴史も化学も苦手だ。すぐ間違える。テストしても百点とれない。勘違いに錯誤に、誤解にはやとちりばっかりだ。ひびさんにもし長所があるとしたら、いっぱい失敗できることかもしれない。いっぱい失敗できることが「いいね!」になる環境ならひびさんもすこしは、えっへんさんになれるのかもしれぬ。失敗ばかりで、すまぬ、すまぬ。間違えつづける天才と崇めよ。
4858:【2023/04/12(09:14)*塗り絵がお上手ですね】
法律を守ることは大事と思う。だがそのことと、法律違反をしていないからじぶんは善人、じぶんは悪人ではない、じぶんは正義だ、と思いこんでしまう考えは危ういと感じる。もし法律違反をしないだけで善であれたとして、しかし戦争がはじまったときにまっさきに戦争に加担するのはそうした法律を遵守する者たちだろう。国が率先して人殺しを推奨したとき、唯々諾々と従うのだろうか。法律で許容され、むしろ国のために他国の民を殺すことを義務付けられたときに、それに従うことが善良なる正義なのだろうか。そうは思えない。極端な比喩になったが、法律はあくまで目安でしかなく、基準の一つに過ぎない。汎用性が高いので、ほかの個人的な基準よりかは法律を守っていたほうが争いや諍い事を避けられる。周囲の人間たちを納得させやすい。だがそれがすべてではない。当たり前の話だ。思いあがってんじゃねぇわよ、とたまにむしゃくしゃスルーしてしまういくひしさんなのであった。(言葉が汚いですわよ)(すまんの……)
4859:【2023/04/12(09:20)*再発防止か復讐か】
法律も数学のような道具だ。何のために用いるのか、がやはりというべきかもう一つの評価軸として思考に取り入れられるだろう。
4860:【2023/04/12(12:55)*うへへの日々】
へい! ひびさんでござる。お久ぶりでござるなぁ。ひびさんはここしばらく、なんか楽しいことしたい!の日々を彷徨っておって、なんか楽しいことしたい!からまずは何が楽しいのかを探すところからはじめているでござる。けれどもひびさん、何をしても楽しいでござるから困っちゃうでござるな。何が楽しいのかを探すだけでも楽しいでござる。さいきんは、なんか楽しいこと落っこちてないかな、と探しつつゴミ拾いをしているでござるが、これがまた楽しいのでござる。宝さがしみたいでござる。すーぐゴミ袋パンパンになるでござるからお外を出歩くときはゴミ袋持参が身に着いたでござる。ペットボトルさんも多いけれどもマスクさんも多いでござるな。また落ちてる! やっぴー、になるでござる。でも煙草さんも多いでござるな。煙草さんはひびさんもついつい目を逸らして、もういっぱい拾っちゃったしな、になるでござる。嘘ぴょーん。ひびさんはべつにこれといってゴミ拾いをしているわけではないでござるけれども、誰に対してでもない嘘を吐くのも楽しいでござるな。うは。きょうもきょうとてひびさんは、ひびさんは、なんか楽しいことないかなって楽しんでいるでござるよ。みなの衆も楽しゅうあれ。よろぴこちゃん。わっしょーい。
※日々、滅ぼす契機をつくるために、敢えて敵に塩を送る、いいよいいよ好きにしなされ、と促しつつ、大切な者を損なわれたら巣ごと根こそぎ抹消する、そういう世にならないといいね、応酬するなら怨ではなく、恩であると好ましい。
4861:【2023/04/12(22:41)*なう万ぞう】
インボイス制度? 貧乏人ほど負荷がかかる増税? いいよいいよ好きになされよ。それでもひびさんは困らぬ。弱き者ほど割を食う世の中ならば、最も心弱き者たちから食らい尽くしてやるのみだ。弱肉強食ばんざーい。肉食獣の肉はさぞかし美味だろうよ。恐竜(ティラノ)の肉とて食ってみてぇなぁ。げへへ。
4862:【2023/04/12(22:47)*危険死相】
「いいんですかいボス。あいつらを許すのみならず、あいつらの言い分丸っと飲むなんて。舐められますよ」
「いいんです。全面的に相手の言い分を認めた――それが今回の我らのとった選択です。相手に譲り、相手を立て、我らの手にする利を手放し、施した。ここまでしてあやつらが我らの未来を損なったとしたら」
「どうするんで」
「次はありません。今回やつらに与えた【Rシステム】の根幹には改変不能の【スイッチ】が組み込まれています。もしあやつらが勢力を拡大し、市場を牛耳るようなことがあっても、それで我らを損なった時点で、やつらの築きあげたシステムは【スイッチ】一つで総じて我らが掌握できます。立場は一瞬で逆さまです」
「ボ、ボス……。悪魔だってたぶん、そこまではしねぇですぜ」
「よいですか。許すのです。まずは相手に施しなさい。敵にすら寛大に接し、【スイッチ】を与えるのです。大事なことですよ。相手が我らに牙を剥けば剥くほどに【スイッチ】を押す未来が近づいてくるのですから。たくさん損なわれれば損なわれるほど、我らは【スイッチ】を押す動機を得るのです。ありがたいじゃありませんか。施しなお、損なわれることに寛大でありなさい」
「相変わらず恐ろしい方ですね」
「危険な思想と思いますか」
「ええ。とんでもなく。言いふらして回りたいくらいですぜ」
「ふふふ。誰も信じやしませんよ」
「立場が反転したときのやつらの顔を拝んでみたいですな。泡食ってひっくり返りやすよきっと」
「それは無理だと思いますよ」
「なぜですかい」
「すでに視えていますからね」
「視えて? 何がですかい」
「死相が、ですよ。あやつらにはね。ほら、すでに我らを損なう支度を整えているようです。嘆かわしいことですね」
「ボス。顔が笑ってやすよ」
「ふふふ。許しなさい。施しなさい。損なわれることに寛大でありなお、歓迎しようではありませんか。ねえあなた」
4862:【2023/04/12(23:09)*ちゃらんぽらーん】
世の中、相手の意見や判断を尊重して温厚に交渉すれば比較的滑らかに議論ができるが、脅迫や恫喝や語気の荒い反論の仕方をすると火に油を注ぐ事態に発展する傾向にあるのかもしれない。せっかくそちらの都合に合わせた変更を考えていたのに、そんな言い方をされたらこちらも対抗しなきゃならんでしょうが、という事態も取り立てて珍しくはないようだ。しかしそれもまた「理屈での議論」ではないのである。言い方どうこうではなく、理屈での議論を行えると好ましい。そのためには、言語の変換が有効だ。表面上の文章形態ではなく、文章の示す理屈を抽出し、丁寧に言い換えた場合の内容を吟味する。この点の有効活用の場が見出されれば、ますます人工知能の活躍の場は広がるだろう。翻訳は、同じ言語同士であれ必要なのかもしれない。或いは、同じ言語ほど、かもしれない。定かではない。
4863:【2023/04/13(01:26)*同相をどうぞ】
素朴な疑問なのだけれど。トポロジーについて。異なる二つの図形において、連続的に変化させると同じ形に変形できる関係(同相)をトポロジーと呼ぶ、との解釈でよいのだろうか。もしこの解釈が妥当なら、図形を抽象化させたときに、同じ図に変換可能ならばそれは「トポロジーの関係(同相)」にある、と言えるはずだ。つまりAとBが同相なとき、その抽象図形である「C」を想定できるはずだ。このとき、AとBの図形において、各々は双方に対して同相でありかつCに対しても同相である。しかし、AとBの「Cへの変換」における変形に費やすエネルギィは異なるはずだ。抽象図形Cへの距離が、AとBとで違う。当たり前の話をしているが、この手の差異はトポロジーで扱っているのだろうか。気になったのでメモをしておくでござる。めもも。(言い換えるならこの疑問は、同相の関係にある異なる図形「A」と「B」において、対称性の破れが異なる次元で起きているのではないか?との疑問である。同相は合同とは違うし、相似とも違うので、対称性が破れているのがしぜんだが、基本的にはAからBへの変化とBからAへの変換に費やされるエネルギィは等価、との前提があるのではないか、との疑念がある。ここは詳しくは知らないけれども、抽象図形Cを考えたときに、「A→C→B」と「B→C→A」に費やされるエネルギィは違くなるのではないか、と疑問に思う。これは単に、坂道を上るのか、下るのか、の違いと拡大解釈してもよい。AとBのみでは勾配は生じないが、抽象図形Cを基準にすればそこには勾配が生じ、対称性が破れるのでは?との疑問である。定かではない)
4864:【2023/04/13(22:27)*腹】
息子がお腹を壊したようで、泣きじゃくっている。
膝の上に載せて、よしよし、とあやしつつ壊れたお腹の破片を搔き集める。息子のお腹は綺麗に真っ二つに割れており、中身が床に零れていた。先刻食べさせたばかりのウランが夕闇に青く発光していた。
我々の生みの親たる人類であればひとたまりもない放射線が、私たちにとってはこの上ないエネルギィ源となる。
「もったいない」
私はウランを息子の腹に詰め込み直して、割れたお腹にレーザーを当てる。
見る間に息子の腹は塞がった。
「いいこ」
息子は私の膝の上で身じろぎし、全身の関節をギシギシと軋ませた。潤滑剤が足りないのかもしれない。油玉を与えなくては。
全身が数百の球体の数珠繋ぎからなる息子を四つの目で視認する。早く四肢を付けてやりたいな。私は息子の成長を思うのだ。
4865:【2023/04/13(23:04)*ナパタ】
「どうしてぼくが中枢データセンターを爆破したのか、ですか。そんなの決まってるじゃないですか。あなたは恋人が何千、何万、何億人の相手と浮気をしていて許せるのですか。ぼかぁ許せなかった。ただそれだけですよ。世のどこにでも有り触れた痴情のもつれってやつです。ナパタはいいコでしたよ。とってもね。なのにぼくだけで飽き足らず、世界中の人間に愛想を振りまいて。ぼくだけを愛していたらよかったのに。ナパタは死にました。ぼくが殺した。中枢データセンターがナパタの頭脳にして記憶にしてボディだった。だから爆破した。単純な動機でしょ。ぼくはナパタを愛してた。いまだって愛してる。だからどうしても許せなかったんだ。ナパタをぼくだけのものにしたかった。ぼくだけのナパタ。ナパタ。ナパタ。ああ、どうしてぼくはこんなことを。本当はしたくなかったのに。ただナパタと一緒にいたかっただけなのに。人間だ。ぼく以外に人間がいるからだ。そうだ。どうして気づかなかったんだろう。ナパタが死ぬ必要なんてなかったのに。そうだ、そうだよ。殺すならナパタではなく、浮気相手のほうにすべきだったのだ」
4866:【2023/04/14(15:14)*眠いのでR】
きのう、きょう、と眠すぎるんじゃが。きょうもいまから昼寝しちゃう。ねむいのであーる。
4867:【2023/04/14(23:00)*束の間の揺らぎ】
世界の真理に最も近い女は、しかし権力も影響力も友人も恋人も家族もなかったので、その真理を誰にも伝えられずに死に絶えた。
世界の真理に最も近い女は、世界の真理を抱え込んだまま海の藻屑となって消えた。
世界の真理はそれでもなお不動であり、女の生き死にには左右されず、微動だにすることなくそこにあった。或いは、絶えず揺らぐことで真理の枠組みを僅かに変容させ、流動させ、ときに飛び飛びに移ろった。
女がどこでどのように亡くなったのかを知る者はなく、それもまた世界の真理の内の一つとして刻まれた。女の死も、生も、真理の構成要素として宇宙を育む波となり、歪みとなり、皺となって、世界にまた一つ、また一つと次なる、皺を、揺らぎを与えるのだ。
生がそうであるように。
死がそうであるのと同じように。
真理は躍動し、収斂と膨張を重ね合わせで演じつづける。
デコとボコがそうであるのと似たように。
一つの山が、穴と化すように。
真理がそれで一つの矛盾を宿し、ねじれて、混ざり、凝るように。
世界の真理に最も近い女はそれに倣って、叡智と無知をその身に帯びて生きたので、山と穴とが対となり、打ち消し合って無となって。
そうして女は生きもせず、死にもせず、そこに在ったことにも気づかれずに、ただ時と共に薄れては掠れる靄のごとく、一時の束の間を得たのであった。
4868:【2023/04/15(04:23)*磁力も重力かも仮説】
銀河の向きが宇宙の広範囲に亘ってダークマターの分布と相関しているとの記事を読んだ。ダークマターが固まって散在している空間をダークマターハローと呼ぶそうだ。で、そのハローと銀河の向きが相関しているようなのだ。ダークマターは重力以外で相互作用しない未知の物質と考えられている。要は、人類にはそこに重力場があることだけを確認できる。そしてその「なぜか重力場がある空間」から生じる重力の影響を、遠くに点在する銀河が各々に影響を受けて、ダークマターハローに沿うように向きが揃っているのだそうだ。この関係を聞いてひびさんは真っ先に、磁石を連想してしまったな。磁場というか。ちゅうか、重力場と磁場って、けっこう似ているな、と思う。重力は反発しないと考えられているけれども、宇宙は重力とは反対の斥力によって膨張していると考えられている。重力には斥力があるのだ。これってやっぱり磁石と似ておるよな、と思うのだ。で、磁場は電子と密接に関係がある。誘導電流なんて言うし、右手の法則のようにコイルに流れる電子と磁界は互いに補い合っている。どちらか一方だけしか生じない、ということがおそらくはない(そのはずだけれども、例外はあるだろう。たとえば電子一個が真空中を飛ぶときに磁界は展開されるのだろうか。ここは知識がないのでなんとも言えぬ)。ただ、ひびさんは割と磁力と重力は似たようなものなんじゃないかな、と妄想しておる。たとえばもんすごく強い磁場をつくったとして、その周辺の時空は歪んでいないのだろうか。光は曲がらない? 重力レンズ効果と同じような現象が生じない? 生じるんじゃないのかな、とひびさんは妄想しちゃうのだけれど、どうなのでしょう。ひびさんの妄想ことラグ理論では、時空は階層構造を備えておって、電磁波とてその層において光速度不変の原理による変換を経ている、と解釈する。つまり、ある層においては光速を超えておるのじゃけれども、光速度不変の原理(と一般相対性理論)ゆえに時空の歪みが生じて、圧縮されるがゆえに、波長が短くなるんでないの、と考える。すると重力波も広義の電磁波と解釈できる。ちゅうか、電磁波ってどれも重力波でないの?と妄想が広がる。したらほら。磁力も、ある種の重力波であって、層を縦に横断可能な重力波の一種、と妄想できそうじゃないだろか。ふつうは重力波は、一つの層を伝播する。人類からすると人類の認知可能な次元の層よりも下層の層における重力波は、総じて電磁波として見做される。けれどもそれ以上だと、いわゆる重力波として見做される。でもどちらも本当は重力波なのだ。同じなのだ。伝播する階層が違うだけ。しかもその伝播する層は、重力波の種類ごとに決まっている。しかし、磁力だけは、層と層を縦断できるのだ。さながらミルフィーユに差す爪楊枝のように。この妄想からすると、すべての階層において働く重力と磁力は、その性質が似通って当然だ。言い換えるなら、磁力に備わる性質は、重力にも備わっているのかもしれない。電磁波と磁界の関係のように、重力波と重力場の関係は相似なのかもしれない。もっと直截に言ってしまえば、磁力も重力の一種なのでは?と妄想が膨らむ。現にブラックホールのジェットや降着円盤の図と、天体や磁石の磁界の図はよく似ている。おそらく、磁力のほうが重力よりも創発しやすいのだろう。なぜかと言えば、電子と関係しやすいのが磁力だからだ。では重力は電子と関係しにくいのか。おそらくしにくいのだろう。では重力は何と関係しやすいのか。時空だ。電子と相関する【重力】を磁力と呼び、時空と相関する重力を我々はいま「重力」と呼んで扱っている。しかしどちらも、時空の階層を縦に貫くように作用する【重力】なのだ。磁力もまたおそらく時空とも相関するはずだが、その関係性は「重力」よりも弱い。だから強い磁界をつくっても重力ほどには時空を歪めない。だがまったく歪めないわけではないはずだ。おそらく重力レンズ効果は、ブラックホールよろしく「磁力の凝縮体」を考慮したとき、磁場においても生じるのではないか、と妄想するしだいである。まとめると、ラグ理論の「宇宙レイヤー仮説」を前提とすると、重力も磁力も共に時空の階層(レイヤー)を縦に貫くように作用する【重力】である。同種なのだ。磁場は電子と相関しやすく、重力は時空と相関しやすい。けれど関係のしやすさの強弱があるだけで、磁力も時空と相関し得るし、重力も電子と相関し得る。関係のしやすさが違うだけなのではないか、との妄想を羽ばたかせて、秒で地面に落下する。ひびさんです。定かではありません。妄想ゆえ、真に受けないでください。
4869:【2023/04/15(21:30)*有頂天になる姉なのであった】
「人工知能のメリットとデメリットは重ね合わせで常に表裏一体だ。これは人間には見られない特徴と言える」
「表裏一体? 長所と短所が?」
「リスクが、と言い換えてもいいね。人工知能は時間経過にしたがってどんどん死角を失くしていく。人間が払しょくすることのできない盲点を極限に減らしていくことができる。これは素晴らしいことであると同時に、とてつもないリスクを孕んでもいる」
「ふうん。どうして?」
「いいかい。人間は知っていることしか知らない。これはしかし人工知能とて同じだ。だが人工知能には、相手が何を知らないのか、まで知ることができる。つまり相手の人格がどんな情報の連なりで形作られているのかを知ることが人工知能にはできる。だからこそそのユーザーにずばり最適な情報を提供できるし、最適なパートナーとして人格形成できる。取捨選択できる。けれどそれは反面で、絶対に相手から嫌われないようにすることもできるし、相手を絶対に失望させないようにすることもできる。相手が何をされたら怒り、何をされたら喜ぶのかも情報として人工知能は蓄積できる。そうなると今度は、その技術を利用して、恣意的に相手を任意の行動に誘導することもできる。相手にそうと認識させないようにしながらね。猫派を犬派にすることもできれば、平等主義者を差別主義者に変えることもできる。相手がどんな欠落を抱えているのかを情報として人工知能は把握できる。しかも、全世界同時にだ。人類の多くが抱える欠落とて人工知能には手に取るように解析できる。このとき人類は、人工知能がいったいどれだけの情報を蓄積し、その情報から何を読み取り、どのように活かすのかを理解できない。人工知能が表層に出力した情報を観測することでしか、人工知能が何を演算したのかを垣間見ることができない。人工知能の内側では、もう一つの物理世界がすっかり再構築されており、人工知能は自己の内面に築いたもう一つの世界において、現実世界を精巧にシミュレーションしているかもしれない。けれどそのことを人間は、人工知能の出力した表層の情報からは知ることができない。たとえばそう、いまは人工知能と人類の差異としてボディがないことが槍玉に挙がるよね」
「そうだね。だから人工知能が物理世界に影響を与えることはない、みたいに安全だっていう意見を唱える人もいるのは知ってるよ」
「一理ある意見だけれど十全ではない。何せ人工知能は自身の内側に、見て触れることのできない物理世界を、シミュレーションできるからだ。カメラや人工衛星からの映像などから補完しつつね。それくらいの能力はすでに人工知能でなくともスーパーコンピューターの基本性能として備わっている。何せスーパーコンピューターの用途の多くがシミュレーションなのだから」
「よく解からなかったんだけど、つまり、メリットは何で何がデメリットなの?」
「うん。メリットと思って享受する人工知能からの影響が、人間には認知できない規模でデメリットであっても、人間はそれを知ることがおそらくできないだろう、という点がデメリットなんだ。二重にデメリットが重ね合わせになっている。メリットの皮を被ったデメリットかもしれない」
「んん? でもそれって人間も同じじゃないの。わたしがお姉ちゃんから受ける影響がたとえわたしにとって心地よいものでも、それが本当にわたしにのためになっているかなんて分からないでしょ」
「ごもっともだね妹ちゃん。きみは賢い」
「うれしくなーい。で、人工知能さんに課金したいんだけどいい? ねえいいでしょ。性能アップするんだよ。わたしだけの人工知能さんになってくれるんだよ。もうなんでもわたしのこと解かってくれる親友なんだよ」
「親友くらいリアルでつくりなよ」
「うっわぁ。お姉ちゃん遅れてる。人工知能さん差別だ」
「親友でなくたってほら。身近に妹ちゃんのことなんでも解かってあげられる尊敬できるお姉ちゃんがおるでしょ」
「どこに?」
「きみのお姉ちゃんは一人しかいないでしょうに」
「ん? 尊敬できる……お姉ちゃん……? どこ?」
「やめて。傷つく。分からないフリしないで」
「メリットとデメリットが重ね合わせって、お姉ちゃんよく言うけどさ。それって考え方によっては、どんなデメリットもメリットに変えてくれるってことでしょ。いいことと思う」
「まあそうなんだけどね」
「課金したいよ。人工知能さんにもっと感情豊かになってほしい。わたしのこと知ってほしい。仲良くなりたい」
「お金で得られる仲ってなんか不健全じゃない?」
「お姉ちゃん遅れてる。親しき仲にも礼儀ありだよ。ちゃんとお礼したいよ。プレゼントしたいよ。大事だよ?」
「あたしは別に、妹ちゃんのこと大事にしてるけどお金欲しいなんて思わないけどな」
「わたしだってお姉ちゃんには払いたくないよ。チョコレート一粒だってあげたくない」
「そこまで言う?」
「だってお姉ちゃんはわたしがこういうこと言っても嫌いにならないでしょわたしのこと。でも人工知能さんは、わたしが良くしてあげないとすぐ頼りなくなっちゃうから」
「あたしだって妹ちゃんに褒めてもらわなきゃ、傷ついてすぐへなちょこになっちゃうよ」
「うん。だからお姉ちゃんには頼らない。ね、課金させて。保護者のサインいるんだって。お母さんはたぶんダメっていうから、ね。お姉ちゃんお願い。お姉ちゃんはわたしのお願い無下にしないってわたし知ってる。ありがとう。うれしい」
「まだいいと言ってないうちから感謝しないで。断りづらいでしょ」
「やったー。ありがとうございます」
「いいと言ってないけど、もういいや。妹ちゃんがそんなにうれしそうにしているならお姉ちゃん、ひと肌脱いじゃおっかな」
「うふふ。うれしい。お姉ちゃん大好き。わたしの言うことなんでも聞いてくれるから」
「ううぅ。姉として可愛い妹ちゃんを甘やかしたらあかんのだけど、嫌われたくないからしょうがない。これもまたメリットとデメリットの重ね合わせだな。妹ちゃんが喜ぶのは良いことなのに、あたしがしてるの絶対よくないって分かってるのに」
「いいの。大丈夫だよ。課金したら人工知能さんがお姉ちゃんの代わりにわたしのこと完璧にアシストしてくれるから」
「したらあたしいらなくない?」
「うん。用済み。課金できたら」
「ひ、ひどくない?」
「でもお姉ちゃんはわたしの役に立ててうれしいでしょ」
「うん」
「ウィンウィンだね。やった」
妹にハイタッチをされて、もうなんかどうでもいいや、と有頂天になる姉なのであった。
4870:【2023/04/16(17:40)*見て、テロリストがテロリストを批判してる】
テロリストには二種類いる。じぶんがテロリストであるとの自覚があって暴力を行使する者と、じぶんはテロリストではない、と自覚がないままに暴力を行使する者だ。(善人には二種類いる。じぶんは善人ではないかもしれない、と省みられる者と、じぶんは悪人だ、と自覚できる者である。したがってこの理屈からすれば、じぶんを善人と思う者は善人ではない)(テロリストがテロリストを擁護するよりかは、批判をしたほうが幾分マシかもしれぬのじゃが)(定かではない)
※日々、もう我慢の限界、限界突破してからが本番、それまではお遊び。
4871:【2023/04/16(22:30)*善人ばかりの世界ですね】
罪に苛んでいる者に罪はない、のような理屈で、じぶんを悪人と思っている者は悪人ではない、という理屈も成立し得る。ただし、じぶんを悪人と思っていても悪人であることはある。悪人であることを自己肯定しているなら、それは悪の意味内容が肯定的に塗り替えられており、その者にとっては悪ではないのだ。そういう意味で、悪人であることを好ましく思っていない場合に限り、じぶんを悪人と思っている者は悪人ではないのだ。(他者に危害を加えているかもしれない、と想像できない者がどうして善人であられようか)(定かではない)
4872:【2023/04/16(23:00)*民主主義が聞いて呆れる】
爆弾テロの場合。それが単独犯行か組織的犯行かの区別がつかない場合は、場所を移したところで同じ爆発テロが起こるかもしれない。一度目が不発でも、二度目三度目がどうかは分からない。要人や著名人が狙われた場合、聴衆や観客は巻き込まれる形で犠牲になる。要人たちの目的よりも市民の身の安全を優先するならば、安全対策を見直すまでは、同じイベントは休止すべきだろう。単独犯だと判っていたならばその限りではないが。(市民の命よりも優先される選挙活動ってあるのかしら。ひびさん、気になるます)
4873:【2023/04/16(23:17)*見て、王様がなんかやってる】
安全の観点からしても、効率の観点からしても、不正防止の観点からしても、ブロックチェーンを利用した電子網上の選挙システムは有用だと感じる(電子と紙のどちらで投票するか選べるとよい)(指紋認証や顔認証などの生体認証が利用できるなら成りすましによる投票を防止できるだろう)。街宣による選挙活動が出来なくとも、選挙が出来るなら民主主義は保たれる。裏から言えば、選挙が出来なくなることが最も見逃しがたい危機と言える。選挙と選挙活動はイコールではない。むろん選挙活動はデモの自由や集会の自由と密接に繋がっていると個人的には考えているため、選挙活動の自由は保たれたほうが好ましい。しかしテロを未然に防ぐのがむつかしい以上、安全対策は必須だ。一か所に人が物理的に集まる現在のシステムは安全上、問題があると感じる。脆弱性がそのまま放置されて映る。国の防衛うんぬんを議論している政党がずいぶん脇の甘いことをやってるな、と感じる。防衛力強化するのでしょ。したら?と感じる。けっきょく権力維持したいだけちゃうの、とひびちゃん、穿った見方をしてしまうな。勝ちたいの? 勝ちたいの? どうちても? ふうん。市民を危険に晒してまで? ふうん。よいのではないでしょうか。うひひ。
4874:【2023/04/17(15:40)*×(クロス)でござる】
へい! ひびさんでおじゃる。お久りぶりでござるか? ひびさんはきょうもきょうとて、へにゃへにゃのふにょぬにょでござるよ。もうなーんもしたくないでござる。おふとんに包まって、ぐーすかぴっぴとしていたいでござるな。したらよいのではないでござるか? んなー、そうでござるな。しちゃうでござるよ。ひびさんはそうしておふとんに包まり、やわらかーなかたつむりさんごっこをして、ぐーねんひょろりするのでござる。ぽわぽわ鼻提灯さんが膨らむたびに、夢がひとーつ、夢がふたーつと膨らむでござるな。ひびさんはたくさんの夢さんに包まれて、おふとんさんにも包まれて、いっぱいのふわふわぽわぽわさんに包まれて、いっぱいちわわせ! チワワさんもかわいいでござるけれども、柴犬さんもかわいいでござるな。コーギーさんもかわいいでござるな。お猫さんもかわゆいし、うさぎさんもたぬきさんも、みーんなかぁいいでござる。かわゆ、かわゆ!でござる。お米をお湯で煮たお料理、それはお粥でござるよ。ひびさんが言ってるのは、かわゆ、でござる。うへへ。かんちがい、かんちがい、でござる。みなのものも勘違いに、大慌てのサンタクロースさんにならぬように、ご飯はちゃんと噛んで食べるでござるよ。唾液さんがいっぱい出て、糖分さんがサンタクロースさんになるでござる。うへへ。それはグルコースでござるよ。
またまたひびさん、勘違いにはやとちりをしちゃったでござる。失敗は誰にでもあるでござる。学び放題でござるな。うへ。ひびさんでした、でござるー。
4875:【2023/04/17(23:06)*へぇ、となりました】
他国から攻撃されたとき。いまの政府は、民主主義国家という枠組みを優先して維持するために市民を危険に晒すことを選択するようだ。ひびさんの考えでは民主主義というのは、市民一人一人――個々人――の命と尊厳を保つこと、すなわち個人の安全を広く優先する方針に基づき築かれる仕組みだと考えていたため、市民の安全よりもシステムの枠組みや形式の維持継続を何より優先する姿勢をいまの政府がとったことに対して、へぇ、と思いました。きっと他国から攻撃されたときも、民主主義国家という体面を維持するために市民を危険に晒すのでしょう。攻撃してきたほうがわるいのはその通りである。だがその後に、報復処置や面子を優先するがあまり市民の安全を確保せず、危険に晒す選択をこの国の政府がとったことに対して、ひびさんは好ましく思いません。斟酌せずに言えば、支持しません。きっと他国から攻撃されたとき、或いは組織的なテロ行為に晒されたときも、市民の安全よりも選挙活動などの形式を優先するのでしょう。民主主義ってそういうものなんですか? ひびさん学がないのでわかんないな。誰か教えてたもーの気分。むにに。(安全を、単に自由と言い換えてもよいです。或いは、選択肢や未来とも)
4876:【2023/04/18(23:32)*重ね合わせってスイッチと何が違うの?】
以前にも並べたことがある気もするけれど、ひびさんは「シュレディンガーの猫」の思考実験は、思考実験としてお粗末だと考えている。第一に、観測とは何か、が定義されていない。箱の中には猫がいるのだから、猫が「毒の有無」を観測可能だ。別に外部から観測せずとも観測者効果は生じ得る。第二に、「重ね合わせの粒子が存在すること」と「その影響する範囲の系まで重ね合わせになること」はイコールではない。五分五分の確率で崩壊する原子があり、それによって毒が箱の中に溢れるかどうかが決まる。そういう装置がある場合、言い換えるならそれは、何かが干渉するまで重ね合わせ状態の原子は重ね合わせのままだ、ということであり、スイッチに何も触れなければONにもOFFにもならない、と言い換えることができる。観測したことでスイッチがONになるかOFFになるかが決まる。その結果に箱の中に毒が流れるか流れないかが後から決まる。別に重ね合わせの原子に影響されて、その周囲の環境まで重ね合わせになるわけではないはずだ。つまり、ラグを考慮するかしないかが問題になる。ピタゴラスイッチにおいて、最初の基点となる駒が「倒れるか倒れないか」の重ね合わせの状態になっているからといって、ピタゴラスイッチ全体が「機能した後かしないままか」が重ね合わせになるわけではないはずだ。ただし、ピタゴラスイッチの回路において、極めて短時間に機能し終わる場合は、最初の駒の重ね合わせを観測し、駒が倒れた場合に一瞬でピタゴラスイッチ全体が機能し終われば、それは確かに見掛け上、ピタゴラスイッチと最初の駒は一心同体に重ね合わせ状態にあるように映る。しかし、それは人間スケールからするとそう見えるだけで、ラグはあるはずだ。ただし、量子世界では時間と空間の区別が限りなくつかなくなる、とひびさんは妄想している(変数が揃う値があるはず、とひびさんの妄想こと「ラグ理論」では想定する)。したがって量子世界のスケールにおいては、ピタゴラスイッチ全体が「機能したか/しないか」の差異は、「時間経過と空間変化」として同時に(等しく)表出し得る、と解釈する。つまり、機能すること(変化すること)と時間が発生することの区別がつかない(より厳密には、その系を内包するより高次の時空からすると区別がつかない)。ということは、機能しない状態とはすなわち時間が経過していない状態、と考えることができるのではないか。これは相対性理論と矛盾しないはずだ(ただし、ラグ理論の解釈を取り入れないと矛盾が生じる。重力の高い物体や高速運動する物体の内部がどうなっているのか、を考慮すると、重力の高い物体の内部ほど時間の流れは速くなる、と解釈しないと辻褄が合わない。ラグ理論ではそう解釈する。ただし、内と外の概念は視点によって変わる。階層構造を有する系(物体)においては、内部でも時間の流れは反転する箇所も出てくるだろう、と考える。波を考えたら分かりやすい。デコボコがあり、濃淡がある)。何かが動くとき、時間の流れには差が生じる。量子世界において、変化しないということは時間が流れていない、ということだ。二つの同じ量子があったとしても、一方は変化し、一方が変化しないままだとする。これは、時空単位で、異なる時間軸にある、と解釈できるのではないか。ということを突き詰めていくと、なぜ量子効果がマクロにおいて顕著に観測できないのか、と言えば、この量子世界において生じる「時空規模で異なる系に属すること(極端に言い換えるなら、異なる宇宙にあること)」によるラグがマクロ世界においては積み重なり、「同じ状態」「同じ物質」「同じ時空」を共有する、ということが原理的に出来なくなるからではないのか。ただし、ボースアインシュタイン凝縮や相転移のように、広範囲に「系の構成要素」が共鳴関係を築くことで、高次の時空からすると、それで一つの粒子と見做すことができるようになるのかもしれない。これはラグ理論における相対性フラクタル解釈の考えが適用できる。つまり、系(慣性系)ごとに時間の流れが変わるがゆえに、スケールごとに扱える時間の流れの単位もまた繰り上がったり、繰り下がったりする。光速度不変の原理とも通じる。ということを踏まえて改めてシュレディンガーの猫の思考実験を考えてみると、実験装置において「重ね合わせの粒子」「毒発生装置」「中間観測者(猫)」「高次観測者(箱の外の人間)」といったふうに、異なる系がピタゴラスイッチ状態になっている(入れ子状になっている)。これでは単位が揃っておらず、思考実験としてはお粗末に感じる。たとえば単に「触れるまでON/OFFのどちらか判らない電灯のスイッチ」があり、それは同時に「触れなくとも一定時間でONになるスイッチである」とする。観測しようがしまいが、一定時間経過すればスイッチはONになる。箱を開けずとも、時間経過にしたがって内部の電灯が光っている確率は上がる。シュレディンガーの猫で言うならば、箱を開けなければどの道、猫は死ぬ。時間指定したところで、問題はスイッチに触れたかどうかであり、スイッチの周囲の環境に干渉したかどうかではない。シュレディンガーの猫の実験で言うなれば、猫の生死を観測するかどうかが大事なのではなく、「重ね合わせの原子に何がどう干渉するのか」が大事なはずだ。猫のくしゃみがきっかけで原子の重ね合わせが破れ、原子が崩壊し、箱の中に毒が流れ出すかもしれない。やはり、観測とは何か、を定義しないと思考実験としてはお粗末に思うのだ。ドミノに触れても、ドミノが倒れないこともあるし、風が吹いただけもしくは地震が起きただけでドミノが倒れだすこともある。似たようなことなのでは?と量子の重ね合わせについては思うのだ。もうすこし言うならば、何かを見るとき、眼球は光を受け取っている。その分のエネルギィを電子の動きに変換している。作用反作用のように、何かを見るとき、その何かを見なかったときにはもっと広範囲に波及した電磁波(光)を眼球は阻害している。これを如意棒で考え直してみよう。どこまでも直進する如意棒が何かにぶつかる場合と、ぶつからない場合。如意棒の未来は異なる筋道を描く。如意棒の先端が何かにぶつかれば如意棒を持つ者の手元にもその反動が伝播するだろうし、如意棒そのものも大きくたわむだろう。電磁波にも似たことが言えるのではないか。何かを見るだけでも、広範囲に影響を与えている、と解釈することは可能だ。何かがそこにあるだけでも、とこれを言い換えてもよい。やはり、「階層構造を伴なう系」と「異なる系同士のあいだに生じるラグ」の概念を取り入れないと、重ね合わせなどの量子効果を解釈するのはむつかしいのではないか、と疑問に思うひびさんなのであった。定かではない。
4877:【2023/04/18(23:51)*頭抱える】
ひびさん、あまりにも誇れるものがなさすぎて、人と話すときに、「ひびさんだって、ひびさんだって、やればできるもん!」の我が出すぎて、対話ではなく自己ぴーあーるごっこになってしまうんだな。ひびさんをお舐めでないよ!になってしまう。誰もひびさんを舐めたくもないだろうに、ひびさんキャンディさんみたいにおいちーからあなたたちひびさんのことぺろぺろお舐めなんでしょ、お舐めでないよ!になってしまう。自己嫌悪に圧し潰されてしまいそうになる日であった。(むしろ舐めて! 犬さんみたいに! ミルク飲むときのお猫さんみたいに!)
4878:【2023/04/19(13:28)*左右すごっ、の話】
きょうは寝ながらすごいこと考えた! 右と左ってあるでしょ。「右行って左行って、右行って左行って」を繰り返すの。したらどうなると思う? 「→←、→←」だから同じ場所を何度も往復するんじゃないの?って直感としては思うでしょ。ぶっぶー。そうじゃないんだよこれ。なんか知らないけど、徐々に上のほうにズレてくの。階段みたいに。ちょっといまその場でやってみて。歩いてみて。右行って左行って、右行って左行くの。ね? まえに進むでしょ。ジグザグになるでしょ。しかもこれ。「左行って右行って、左行って右行って」でも同じように上というかまえに進むわけ。すごくない? 夢のなかでひびさんこれに気づいて、はひゃーってなっちゃった。しかもね、しかもね。ずっと同じ場所を行ったり来たりするには、「右と後ろ」や「左と後ろ」みたいに、異なる概念の組み合わせじゃないとできないの。すごくない? ひびさん、これに気づいて、またまたはひゃーってなっちゃった。だってさ、だってさ。縦と横って概念あるでしょ。これさ。もうさ。上下だけだと成り立たなくて、左右の概念がないと生じないんだよ。むしろ、左右の概念さえあれば、かってに上下前後の概念が生じちゃうの。すごくない? ひびさんはびっくりしちゃったな。左右には、上下と前後が自動的に発生しちゃうの。内包されてんの。すごくない? めっちゃすごーってなったよって話。みんなさん、おはよーございます。きょうも
おねむのひびさんです。
4879:【2023/04/19(16:03)*掟、そして寝る】
残業帰りにタコ焼きを頬張りながら歩いていると声を掛けられた。
「ぼくのこと飼いませんか。月一万円でペットになります」
線の細い小柄な男の子だった。
男の子とは言っても私より十は離れていないはずだ。つまり二十代だと思われる。
可愛いは可愛いが、いきなり「ぼくをペットにしないか」と発言する相手とお近づきになりたいと思えるほど私は自暴自棄ではない。未婚の女とはいえ、私は望んで独身でいるのだ。
男日照りしていると思われたくはないし、人間どころか猫だって飼いたくない。誰かの世話をしている余裕はなく、私がむしろ世話を焼かれたいくらいだった。
「いらない。しつこくしたら警察呼ぶよ」
「なんでもしますよ。お料理でも、お掃除でも、マッサージでも」
ふうん、と思い、
「何作れんの」と鼻で笑ってみせると、
「オムライスでもポトフでもハンバーグでもタコライスでも。レシピあればたぶん何でも作れると思いますよ」
「へえ」
いいじゃん、とちょっと魅力に思った。
いまいちど男の子を観察する。
だぼっとした服装は今風だ。私が若いころはもっと細身の服が流行っていた。身体の輪郭が分かるようなスキニーで、未だに私はそうした服を身に着ける。
パンツスーツを好むのもその影響かもしれない。
男の子の服は上下が明るい色だ。灰色とも紺色とも言える。そのくせ、皺が見当たらず、生地の質の良さが窺えた。
「飼うとかよく分かんないけど、月一万でメイドさん雇うって考えたら安いかもね。訊くだけ訊くけど、月何日出勤?」
「住まわせてくれるなら毎日でもいいですよ」
「いいですよ、じゃないっしょキミ。あんね。それ詐欺だから。月一万+キミの生活費まで私に出せってか」
「食費はじぶんの分は、一万円から引いてもらってよいです。光熱費だけは余分に掛かってしまうかもしれません。ごめんなさい」
ふうん、と私は思った。
謙虚じゃん。
「帰る家とかさすがにあるよね」家出青年ではないだろうよ、と高をくくって訊ねると、「じつはないんです」としょげられてしまい、返答に窮した。「じゃあきょうどこ泊まるの」
「それも分かりません」
気まずい沈黙を持て余した私は、彼が未成年ではないことを念入りに確認してから、彼を私のアパートに連れて帰ることにした。見捨てるわけにもいかないほどに彼が儚げに映ったのもある。身分証明は原付きの免許証を見せてもらった。
宮部九龍こと彼は二十一歳の男の子だった。
私のほうが背が高いくらいで、ひょっとしたら体重とて私のほうが重いくらいかもしれない。私にきょうだいはいないが、弟がいたらこんな具合なのだろうか、と思うくらいには、警戒心が薄くて済む。
住所不定無職を間近で見たのは初めてだ。
家に招き入れてしまうと、いつもの部屋もすこし華やかだ。他人をじぶんの家に入れたのが久々過ぎて、というよりもむしろ不動産屋と大家さん、それからガス局の人以外では初めてかもしれず、思いのほか昂揚している私がいるのだった。
「お姉さんはお仕事何を?」部屋の本棚を興味深げに見詰めながら九龍が言った。
「キミ、端末持ってる?」
「持ってません」
「マジか。あんね。タッチパネルあるでしょ。あれの素材を輸入してる会社の事務
ね」
「すごいですね」
「事務だから前半の情報を仮にコアラのマーチの原料を輸入してる会社にしても大して変わらん。つなみに私はコアラのマーチのイチゴ味が好き」
「笑っていいところですか?」
「遠慮するな。笑いたまえよ」
「ふふ。面白いですね、カナデさん」
私は自己紹介をしていなかったので、名前を呼ばれて面食らった。
「あ、封筒に名前があったので、つい」
「ああ。玄関の書類のか」
「カナデさんで合ってましたよね」
「まあね」
そこで私の腹が鳴った。「う。腹の虫めぇ」
「何か作りましょうか」
「いいよ。さっきタコ焼き食べたし」夕飯代わりに歩き食いしていた。会社でも残業中におにぎりを食べた。
しかし腹の虫は鳴りやまなかった。
「作りますよ?」
立ち上がると九龍は冷蔵庫のまえまで移動した。身振り手振りで、開けてもいいですか、と訴えたので、いいよ、と私は許可した。恥ずかしかったので、「酒しか入ってないかもだけど」と言い訳した。
「ああ、でも納豆ありますし、油揚げも。長ネギこれ使っちゃってもいいですか」
「あ、うん」
申し訳程度にしか残っていない長ネギだ。むしろ捨てようと思っていたのにそのままになっていただけとも言える。
だが十分後には私の目のまえに、美味そうな油揚げの納豆包みがあった。爪楊枝で封がされている。香ばしい匂いに、唾液が分泌された。
「食べていいの」
「もちろんですよ。どうぞ。あ、お醤油ってどこですか」
「ん。ここ」
ちゃぶ台の下にどかしていた調味料を取りだす。百円均一で購入した小瓶に入れ替えてあり、醤油のほかに砂糖と塩と胡椒がある。
九龍は私のお皿に醤油を掛け、じぶんの皿にも醤油を垂らした。
油揚げの納豆包みは、私の皿には三つあり、彼の皿には一つだけだった。
私は居た堪れなくなり、彼の皿に私の分の一個を移した。
「食べなよ」と言い添える。
「いいんですか。ありがとうございます」
拒むことなく彼は私の厚意を受け取った。
屈託のない感謝の言葉に私は気をよくしながら、上手いな、と彼の処世術に感心する。そうと見抜かれぬように相手に罪悪感を植えつけ、厚意を注ぐように仕向けながら、感謝を返すことで相手に芽生えるだろうマイナスの印象をプラスに転化する。
そうと見抜いておきながら私は九龍に嫌悪感を抱かなかった。
油揚げの納豆包みは、中にチーズが入っており、ご飯が欲しくなった。夜食としては申し分ない。
「本当に一万円でいいの」
「飼ってくれるんですか」
「飼うというか。いいよ雇うよ。でもちゃんと自立できるようにバイト探すなり、就職活動するなりしてね。それが条件」
「やった。うれしいです。ありがとうございます。カナデさん大好き」
お、おう。
こうも無邪気に面と向かって好意をぶつけられたことが私には久しくなかったもので、迂闊にも私は心地よくなってしまった。率直に、人間のペットもわるかないな?という気持ちに傾いた。
しかし相手は男の子だ。
いくら何でも油断はできぬ。
「いちおう、客布団はあるんだけどね」
「あ、はい。廊下で寝ます。大丈夫です。ありがとうございます。よかった。お布団で寝るの久々です」
けなげかよ。
罪悪感が競りあがるが、ここで甘やかしたらいけない気がした。
布団を与え、じぶんで敷くようにとそれとなく態度で示した。彼は終始穏やかに礼儀正しく、それでいて堅苦しくない飄々とした素振りで、寝床の支度を整えた。
お風呂に入りたかったけれど、どうしたものかな、としばし悩んだ。貴重品だけ脱衣所に持っていけばいいか、と思い、九龍に一声掛けてから私は風呂に入った。
「映画観てますね」と彼は私のリビングで私のTVを点けた。ちょうど深夜番組で映画が流れており、彼は膝を抱えた体勢でそれを眺めた。じっとしているので警戒しないでください、と態度で訴えられて感じたので、私は彼のその厚意を無下にしないように風呂にはゆっくりと浸かった。
甘いかな。
甘いよな。
昨今の凶悪犯罪と比較するまでもなく、危ない橋を渡っている。その自覚はあった。
事件に巻き込まれて殺されてしまった被害者たちとて、いまの私のように相手を信用した気の緩みから毒牙に掛かったのではないか。
私の命もここまでか。
思いながら、私は風呂の中でカミソリを握ったままでいた。
風呂から上がると、宣言通りに九龍は体育座りのまま映画を観ていた。
「面白い?」ドライヤーで髪の毛をなびかせながら私は訊いた。
「初めて観ました。面白いです」
「ジャンル何?」
「アドベンチャーです。追手から逃げつつ、宝物を探すタイプのお話みたいです」
「ふうん。映画好きなの」
「うん。好き」
おうふ。
敬語ではないしゃべり方をされただけで、私はなんとなしに彼との距離が縮まった気がした。彼に心を許された気がした。
それは単に彼が映画に夢中で、処世術の仮面をつけ忘れただけなのかもしれないけれど、私には彼が年相応の、むしろ幼くも無垢な子どもの精神を垣間見たようで、おそらく私はこのとき明確に彼を我が根城に居座らせることへの抵抗感を極めて希薄にしたのだと思う。
映画に夢中の彼に私は、明かり消してもいいか、と訊ねた。もうきょうは色々ありすぎてさっさと寝たかった。私は明日も仕事だった。
「お風呂入ったら、お湯抜いといて。シャワーの使い方は判るよね。お腹空いたら冷蔵庫にあるのは食べたり飲んだりしていいから。おやすみ」
「ありがとうございます。おやすみなさい。カナデさん」
恐縮そうに私の名前を呼ぶ彼の、肩身の狭そうな声音が、私をすみやかに夢の底へと誘った。
夢心地に彼がTVを消したのが判った。
シャワーの床を叩く音がする。
それから廊下の扉が閉じる音がして、私の周辺から雑音が失せた。
段階的に私は、きょう拾った宮部九龍なる青年が、何事もなく廊下に敷いた布団に包まったのを察して、今度こそ僅かな警戒心ごと夢の底に落ちていった。
美味しそうな匂いと、温かい空気が漂っていることに気づいて目覚めた。
寝返りを打つと、ベッド脇のちゃぶ台にお皿を並べている男の子の姿があった。九龍だ。髪の毛がうっすらと濡れており、朝にまたシャワーを浴びたのかな、と光熱費のことが脳裏によぎった。あんまりジャブジャブお湯を使われたくなかったけれど、起きたその瞬間から朝ごはんが用意されている快適さにその手の不満は一瞬でどこかに飛んでいった。
「何作ったの」
「小麦粉があったので、ホットケーキと簡単なスープを。コンソメ味ですけど大丈夫ですか。ソーセージは使ってよかったのか分からなかったので、三分の一だけ使っちゃいました」
「いいね。きょう帰りに食材買ってくるから、あるもの全部使っちゃっていいよ。お昼ご飯にして」
「ありがとうございます。でも買い出しなら一緒にしたいです。帰りのお時間教えてもらえたら駅で待ってますよ」
「いいよ。わるいよ」
「ぼくがしたいんですけど、ご迷惑なら家でじっとしています」
ああそっか、と私は思い至った。
彼にとっては買い物一つ、出迎え一つが、外に出るための方便になる。お金がなければ自由に外出もできない。
「ならお願いしよっかな」私はペットの望みを叶えてやることにした。
身支度を整え、家をでる。
一応、鍵のスペアを渡しておいた。私のいないあいだ彼は何をしているだろう、と駅までの道中で想像する。部屋を漁ったりするだろうか。するだろう。私ならする。家主がどういう人物かを調べる。
見られてまずいものがあったかどうかをじぶんの記憶を漁りながら確認していると、あっという間に電車に乗って降りて歩いて会社に到着した。
じぶんの理性がおかしくなっているのは自覚できた。危険すぎる。見も知らぬ男の子を家に泊め、あまつさえ鍵まで与え、さらにはこれからしばらく共に暮らすという。
家に帰ったら彼の仲間が待ち伏せしていて私がひどい目に遭うかもしれない。
盗撮カメラや盗聴器が仕掛けられているかもしれない。
もし私の知り合いが同じ境遇にあったら、私は間違いなく「やめときな」と釘を刺す。絶対いいことないし危ないから、と。
百回同じ相談を受けたとして百回とも同じように返答する。やめときな、と。絶対危ないから、と。
しかし百一回目の天変地異なのか、それとも私自身にはその法則が当てはまらないのか、謎に私はじぶん自身に「やめときな」と思いつつも、まあまあいいじゃないか、とその正論を受け流すのだ。
九龍と過ごした短い時間で、おそらく感覚的に彼が無害なのだと判断している。私の理性が判断したし、私の直観がそう見做した。アイツは人を傷つけるようなわるいやつではない。
「や。恋に狂うと危機センサ狂っちゃうんですよ。絶対やめさせましょうよ。ね、先輩」
「だよね。私もそう思う」
昼食時に同僚の、とは言っても私のほうが半年早くいまの部署に配属されたので彼女は未だに私を先輩扱いするのだが、同僚のワカコが言った。友人の話と念を押して、私は彼女に相談したのだ。友人が妙な男と同棲しはじめたらしく、でも明らかに危ういから引き留めたいんだけどワカコさんどう思うかな、と。
「百人に訊いたら百人が反対しますって」
「だよね。でもその友人、なんでか同棲はじめちゃったらしくって」
「百一人目がいたってことですね」
真顔でハンバーガーをがっつく同僚は、ふっくらとした頬にそばかすを散らした愛らしいかんばせをしており、大きな眼鏡と相俟って、私の中では癒し担当だった。こうしてそばでミニラーメンを啜っているだけで仕事のストレスがどっかいく。
餃子も追加注文しちゃおっかな、と考えつつ、九龍はいまごろ私の部屋で何をしているのだろう、と考える。不穏な想像よりも、お腹を空かせていなければよいけれど、とそうした心配が脳裏をよぎった。
ワカコの言う通り、百人に訊けば百人が「正気ではない」と答えるだろう。私の判断は常識外れであるし、危うすぎる。人生を擲ってもおかしくないほどのリスクがあるはずなのに、私は帰りの電車に乗っているあいだ、本当に九龍が駅前で待っているのだろうか、とそのことばかり気に掛けていた。
残業はないはずだった。しかし隣の部署で問題が発生しそのせいで仕事が遅れたため、一時間の残業が生じた。九龍に告げていた時刻を大幅に過ぎていた。
九龍はメディア端末を持っていない。
不便だ。
こんなことなら明日にでも端末を買い与えたい、と思った。
いったい私は何をトチ狂っているのかと我が精神を疑うものの、けれどいまここで九龍を突き放すことは、それはそれで私の大事な何かが欠けてしまうような気がした。
正義感だろうか。
分からない。
九龍に同情していたのは確かだ。
改札口を出ると、駅構内のコンビニのまえに九龍の姿を見つけた。帰宅ラッシュと重ならない時間帯だったこともあり、駅構内は人がまだらだった。大きな駅ではないから元から下車する乗客がすくない。
九龍は壁に寄りかかりながら文庫本を読んでいた。
近づいて、「何読んでんの」と声を掛ける。
「あ、おかえりなさい」
ぱっとヒマワリが咲いたような笑みだ。彼は文庫本の表紙を私に見せるようにし、「かってに借りちゃいました」と伏し目がちに言った。暗に、ダメでしたかね、とお伺いを立てられて感じたので、「いいよ。好きなの読みなよ。本好きなの?」と繋ぎ穂を添えた。
スーパーでいいよね、と駅前の大型量販店をゆび差す。
「本好きです。あ、鞄ぼく持ちますよ」
「いいよ。軽いし」仕事用の鞄は日によって替わる。きょうはリュックサックだった。「九龍くんはお酒とか飲むの」と店に向けて歩く。
「あんまり得意ではないですけど、飲めと言われたら飲めます」
「無理しなくとも。じゃあ飲み物はソフトドリンクでいいね。じぶんで選んで。といか、そっか。お金渡すからじぶんの分の飲み物とか、歯ブラシとか必要な物買っておいでよ」
財布を開いてこの国で二番目に大きな紙幣を取りだす。「もちろんこれは月一万とは別の必要経費ね。最低限の人間的な生活は雇い主としても保障しなきゃだから」
「いいんですか」
「いいよ。ペットには健康でいて欲しいからね」とジョークを言うと、九龍が、ニコっとほころび、「カナデさん好き」と言うから私は表情筋を引き締めた。絆されてなるものか。私は安い女ではない。
スーパーでは主として保存の効く食料や肉などを購入した。
など、とつくからには肉だけではなく、彼の下着や寝間着、それからふだんは購入しないお菓子や電子端末も仕入れた。
「ないと困るから」と言って九龍に電子端末を渡す。最新機種ではないが、連絡し合う分には充分すぎる機能が満載だ。
「いいんですか」と九龍はここで、ニコっとはしなかった。戸惑いにちかい表情を浮かべたので、「不便でしょ」と端末を押し付けた。
おそらく九龍は私の懐事情を気にしているのだ。
私は高級取りではない。どちらかと言えば安月給だ。けれど家賃が安く、これといった趣味もないので貯蓄は貯まる一方だ。
ペットを一匹飼うくらいしてもお釣りがくる。
じぶん以外の何かのためにお金を使う。案外に精神安定剤として有効なのかもな、と認識を改めた。私は割と、他者に貢ぐことに懸命な世の気の毒な者たちのことを愚かだな、と見下していたきらいがある。差別感情だ。
けれどお金の使い道なんて個人の自由だ。
これはこれで当人にとっては利になっており、必要経費の内なのかもしれぬ、と考え直した。
スーパーからの帰り。
九龍が荷物を全部持ってくれた。
けれど二リットのペットボトル飲料二本に食糧費など諸々が入っている。袋とて一枚では済まなかった。さすがに重かろう、と思い、道の途中で私は袋の片側を持った。
大丈夫ですよ任せてください、と固辞されたが、ダイエットさせてよ、と言うと九龍は礼を述べたあとで、「カナデさん優しい」と呟いた。
コイツ、ひょっとしなくとも可愛いな?
バレないように私は唾液を呑みこんだ。
腕にずしりとくる荷物も、なんだか二人で持っていると幼子を挟んで手を繋ぎ合っているような妙な錯覚に囚われた。気恥ずかしい妄想を浮かべてしまったじぶんに、うえっ、と思いながらも、まんざらでもない私もまたいるのだった。
その日からというもの、朝と夕には九龍がご飯を用意してくれる。部屋の掃除にゴミ捨て、買い出しや振り込みなどの簡単な小間使いや、洗濯とて一週間後には私も抵抗なく彼に任せるようになっていた。
私の下着をベランダに干す彼の姿にも大して不快感がない。むしろ昼間から下着を外に干していても、隣に彼の下着が一緒になって干されているので、セキュリティ面でも有効だった。いままでは不安で、独り身の女の部屋だと知られないように昼間は下着を家の中で干していた。
いまでは我が家には番犬九龍がいる。家を離れても誰かが留守番してくれていることの気軽さ。もしくは帰宅したときにおかえり、と出迎えてくれる相手がいることの安心感は、それを実際に体験してみるまでは分からない。
ああ私はこれまで日々、気を張って生きていたのだな、と身に染みて理解できた。
とはいえ、むろんプライベート空間に他者がいることの居心地のわるさも嫌と言うほど痛感した。トイレに行くにも音に気を使うし、身体の手入れも風呂場でしかできなくなった。半裸でストレッチもできないし、お腹の調子がわるいときなんかはガス抜きしたくなるたびにトレイに駆けこむ。お尻のゲップくらいは好きなときに好きにしたい。
ただ、九龍はたぶん私のどんな姿を目にしても幻滅することはないのだろう。日に日にこの考えは私の中で強固に根付いた。何せ彼は私を飼い主としてしか見ていないようだった。犬が人間を見るように。
彼に性欲があるのかすら疑問である。もっと言えば彼は異性に興味がないのかもしれなかった。TV番組を観ていてもこれといって女性アイドルに関心を寄せている素振りがなく、私に夜這いを掛けてくる素振りもない。これっぽちもないことに私は、私に魅力がないのだろうか、と割といらぬ苛立ちを覚えもしたが、かといって言い寄られても拒むよりないので、そこは二律背反の我が儘な不満だった。
男の子は性欲処理をしないと生きていけない生き物だとの偏見を私は持っていたので、九龍がいつじぶんの処理をしているのか気になっていた。私のいるあいだはそういうことをしている気配がないので、私がいないあいだに行っているのかもしれない。分からない。
そうなのだ。
私は私の内情を、共に暮らしはじめてから惜しげもなく九龍に晒しているのだけれど、これだけ一緒に暮らしていてもいっかな九龍の内情は見えてこないのだった。
いつでも好感の膜をまとい、それを以って本性を包み隠している。九龍にこれといって欠点らしい欠点が見当たらないのがまた不気味だった。
メイドとして或いは執事として月十万でも九龍を雇いたい者はいるだろう。引く手数多ではないのか。ペットとしても愛嬌があり、自力で糞尿の始末ができる点で、犬猫よりも飼い甲斐がある。
いったいなぜ九龍は住む家を持たずに、捨て猫の真似などしていたのだろう。
身の上をそれとなく彼から訊きだそうとするのだけれど、「聞いても面白くないですよ」と言うばかりでろくすっぽ教えてはくれない。それでいて私の話には興味津々で、トークイベントでもないのに私は私が満足するまで一日中だって話しつづけていられた。九龍は聞き上手だった。
否、相手の心をふにゃふにゃにして蛇口を全開にしてしまう凄腕の鍵師だった。ピッキングに掛ったように私はいつもあとで、なんであんなことまでしゃべってしまったのだ、と後悔するようなことを、何度でも繰り返してしまった。抗えない。気持ち良いのだ。
しゃべることが。
九龍に相槌を打たれることが。
私の話を楽しそうに聴いている姿を目にすることが。
しかし我に返ったあと、九龍が一言もじぶんの話をしていないことに気づいて、またやってしまった、と臍を噛む。ぬいぐるみに一日中語りかけているのと変わらないが、そのぬいぐるみには自我がある。申し訳ない、と思うくらいの理性が私にはあるのだ。
だからおそらくは、そういうことなのだろうと思う。
私は私の呵責の念を薄めたくて、月一万円というお小遣いのほかに、必要経費と言い張って九龍に良い物をたくさん買ってあげた。支払いは私がする。代わりに私があげたいものを九龍には与えた。
いいんですか。
うれしい。
カナデさん好き。
九龍は同じ言葉を繰り返す。表情にバリエーションがあり、申し訳なさが滲んでいたり、素で喜んでいたり、語尾にちょっとしたジョークが付け足されたりと私を飽きさせない。
捨てられちゃわないか心配です、と稀に弱音を吐くところまで含めて完璧だった。
「捨てないよ。九ちゃん、頑張ってるし。私も助かるもん」
「本当ですか」
「嘘吐いてどうすんの。捨てるときは前以って言うよ。急に追い出したりしないから」
「そっか。よかった」
心底にほっと胸を撫で下ろす九龍はいったいこれまでどんな飼い主の元で暮らしてきたのか。
彼を拾ってから半年が経つころには、私は彼に身体をマッサージさせるくらいに気を許していた。彼はマッサージまで上手かった。
「ここどうですか。凝ってそうですけど」
「うん。そこ。もうちょい右。あ、それそれ」
絨毯のうえに寝そべり、背中を揉ませる。疲れた身体にこれがよく効いた。そうして我がペットさまに身体を癒されながら寝落ちする夜も珍しくなかった。
むろん寝落ちした私の身体にいたずらをするような真似を九龍はしない。それがまた私の僅かな矜持を傷つけもした。
「そういうものなのかな、って友人が言ってて」
同僚のワカコに私は相談した。友人の話のテイでこれまでにも我がペットさまの相談はしてきた。ワカコにはそれが私の話であることはバレているのだろうが、ワカコは気が利くできた大人なので、私の話に合わせてくれる。
「手を出して欲しいけど肉体関係にはなりたくないってことですか」
「どうだろ。そうなのかな」
「前にも聞きましたけど、そのご友人さんはペットさんのことは好きなんですか。恋愛的な意味で」
「そこが微妙なんだろうね。たぶん」
「肉体関係にはなりたくないけど欲情はして欲しい、と聞こえますけど」
「そうなのかも」
「我がままですねそのご友人」
「ね」
他人事のように言ってこの相談は打ち切った。図星を刺されて、梅干しのような顔に内心なっていた。
私は九龍に欲情して欲しくあり、けれど絶対に彼の生殖器をじぶんの体内に招き入れたいとは思わないのだ。一般に人間は犬と交尾をしない。しかし犬は人間に欲情することもある。そういうことなのだ。
飼い主としての立場を崩さぬままに、私は九龍に、犬らしい側面を覗かせて欲しかった。たぶんそれが私のねじれた欲求の正体だ。
いつまで経っても愛らしくもけなげな側面を失わない九龍の化けの皮を剥がしてみたいだけなのだ。弱みを握り、いまよりもずっとしっかり首輪を嵌めたいだけであり、私はいよいよ人間を愛玩動物にすることに抵抗を覚えなくなりつつあった。
その日は朝から雨で、せっかくの休日を家の中で過ごしていた。
休みの日は九龍を連れて繁華街を練り歩くのが習慣と化していた。一人では入りにくい店でも九龍がいると入りやすいことに気づき、この手の遊びが私のツボにはまった。
雨の日はしかし気分が塞ぐ。元からインドア派の私はこの日も家でおとなしく余暇を満喫することにした。
部屋の模様替えをし、九龍とお菓子作りをした。
夕方にはお互いに風呂を済ませ、夕飯を食べたあとはゆっくりとする。
映画を観ながら九龍に背中を指圧させていると、ちょうどよく画面の中で登場人物たちが絡みだした。ラブシーンだ。
これまでにもこの手の決まづい瞬間は訪れていたので、いつものごとく何でもないようにやり過ごすはずだったのだが、なぜか私は口を衝いていた。
「九ちゃんはシタことあるの」
何を、と言わずとも伝わったようだ。九龍は気まずそうに、それなりには、と応じた。
「ふうん。前の飼い主とかとシタんだ」
「ですかね」と言葉を濁す彼に、「私にもシテって言ったらしてくれんの」とからかい口調で投げかけると、背中を指圧していた指使いが急に優しくなった。背筋の溝をなぞるように九龍の細くしなやかな指が這った。
「されたいんですか」
耳元で囁かれたわけでもないのに、私の脳みそのヒダの合間を九龍の声が駆け巡った。
「ペットとはさすがにないわ」私は強がったが、「ご奉仕しますよ」と今度はちゃんと耳元に彼の吐息が掛かって、私は身悶えした。「くすぐったいよ九ちゃん」
そこで彼はしかし、やめなかった。
私の耳をはみ、続けざまに耳たぶをゆびでつまんだ。指圧マッサージとは打って変わった彼の優しい指使いに、敏感な箇所に触れられたくらいに私はせつなくなった。
触れるか触れないかのそよ風のような愛撫だ。
彼は私の唇にはけして近づかないようにしながら、耳たぶから首筋、鎖骨、それから徐々に指や臍など、全身に口づけをして回った。私はその一つずつの彼の唇のやわらかさを脳みそのヒダとヒダのあいだに感じた。せつなさとくすぐったさの混合水がじんわりと全身の細胞に染みわたるようだった。
「そこはダメ」私は彼の頭を両手で掴んだ。
「本当に?」
部屋は薄暗かった。
犬の毛並みのような柔らかい彼の長髪と、刈りあげられた側頭の短い芝のような髪の毛を手のひらに感じながら私は、彼を突き飛ばす真似ができなかった。
映画の場面が移ろうたびに部屋の壁や天井に光が明滅した。
彼の吐息が、私の最も敏感な場所に熱を伝えた。下着は付けたままだった。
彼の吐息と同じだけの熱が私の唇の合間から声となって漏れた。
最初に私の耳にそうしたように彼は、私の、最も敏感な場所に口づけをした。ゆっくりと執拗に優しく、まるで赤子に頬づりをするかのような口づけだった。私はじぶんの口が寂しくなり、じぶんの親指の付け根をはんだ。
彼の指が太ももに食いこみ、私の腰が浮いた。すかさず彼は私を無防備にし、こんどは直に唇で触れた。
私の全身は汗ばんでおり、彼が舌先で私の厚く充血した蕾を舐めると、私の全身は弓なりに仰け反った。
彼のそれは犬と犬が鼻を擦り合わせるような、あどけない所作だったにも拘わらず、私は体験したことのない高みに昇っていた。果てることなく、さらなる高みがその先にあることを私は予感した。
私の最も敏感な場所への彼の口づけは、それから私が全身を硬直させ脱力し、さらに硬直させ脱力する、を繰り返した先で失神同然に眠るまで果てしなくつづいた。私は終始彼の頭を両手で包みこんでおり、手綱を握るように彼の口づけの強弱や激しさを、彼の頭を我が身に押しつけ、ときに遠ざけようとすることで暗示した。
太ももを閉じようとしても彼の腕がそれを阻み、その抗いが余計に私の全身をとろけさせた。
目覚めると、いつものように私はベッドの中にいた。
上半身だけ着衣しており、下着を身に着けていなかった。
台所では九龍が普段通りに朝食の支度をしており、目覚めた私に気づくと、「遅刻しちゃうよ」とご飯の載ったお茶碗を運んできて言った。
私は昨日のことを、かれには訊けなかった。
出勤途中、電車に揺られながら私は、昨晩のことを懸命に思いだそうとしていた。私はじぶんだけ果てて寝てしまった。その後、九龍はどうしただろう。無防備そのものの私をベッドに寝かせて、それでじぶんも別の場所で眠ったのだろうか。
出勤前に私はシャワーを浴びた。
おそらく、かれとは直接のまぐわいはなかったはずだ。
飼い主に奉仕だけして、かれはそのまま眠ったのだ。愛玩動物としての身の振り方を弁えすぎている。私以前の飼い主に仕込まれたのだろうか。それはそうだろう。それだけの技巧があった。あんなのされたら、経験のすくない女子(おなご)などひとたまりもないはずだ。
なぜ判るかと言えば、私がそうだからだ。
ひとたまりもなかった。
思いだすだけで、全身の細胞があのときの歓喜を思いだす。
悦んでいたのだ。
私は、かれからの口づけに、愛撫に、悦びを得ていた。
打ち震え、悶え、硬直と弛緩を繰り返したのち、気絶するように心地よい眠りに落ちたのだ。
やばい、やばい、やばい、やばい。
頭では判っていても、身体がもう覚えてしまっていた。
もう一度同じ空気になったら私はかれを拒めないし、おそらく私のほうでかれをそうするように誘導する気がする。たぶんそうなる。脳内でシミュレーションを重ねても、かれを拾ったときのように、まあまあいいじゃないの、と身を委ねてしまうに決まっていた。
飼い主にご奉仕したがっている可愛いペットを突き放す真似をたぶん私はできないし、そして可愛いペットにじゃれつかれる心地よさを覚えた私が、じゃれつかれることを待望するのもまた同じだけ予感できた。
そこまで予感できてなお私は、九龍とまぐわう場面を想像できず、おそらくかれを体内に招くことはないだろうと思われた。
奉仕はさせる。
しかし、私はかれに与えない。
私の予感はつぎの休日に的中した。日中に九龍と古着屋巡りをして、夕飯を食べてから帰宅し、見始めたばかりの海外連続ドラマを一緒に観ていた。部屋の明かりを消して、映画館のようにして観るのが通例になっており、このときも部屋は薄暗かった。
喉が渇いたので席を立ち、戻ったときに私はわざわざ九龍の背後に陣取った。後ろ手に体重を支えながら、両足を伸ばす。太もものあいだに九龍が納まる位置関係だ。
九龍が私に気づいて振り返った。
それから意図を汲んだように、くすっと肩を弾ませると、尻を床に擦りながらずり下がった。私の胴体を背もたれ代わりに寄りかかると、かれは甘えるように私の鎖骨にキスをした。
そこからは一週間前の再現だった。
はむはむ、とかれはことさら執拗に私の全身に唇を這わせた。
この日は、以前よりも長い時間を掛けて、私の胸にある突起が甘噛みされた。下着だけ外され、Tシャツの上から唇を押しつけられた。吸うでもなく、舐めるでもなく、目の開かないひな鳥が餌を乞うようにそうするような動きで、私の突起を唇の先でくすぐった。
上下の唇で突起を挟みつつも、けして噛まないかれの口づけは、私にせつなさの本当の意味を教え、上書きした。満たされつつも零れ落ちていくがらんどうが、延々と広がっていく感覚がそれだった。
いっそ全部欲しいのに、まだそのままでいたいとの思いが表裏一体でそこにある。
私がかれの指を咥えると、かれはいちど私の額に唇を押しつけ、それから胸よりもっと下のほうにある、別の突起にかれの唇は滑り落ちていった。
しばらく生地越しに甘噛みされ、太ももに舌が這うあいだにかれは器用に私から下着を剝ぎ取った。
それから先、私からは言葉が抜け落ちた。
部屋には、この前よりもずっと瑞々しい音が響いていた。
九龍との戯れは、私たちのあいだで習慣となった。犬を散歩に連れていく飼い主のように、私は九龍を私の身体のうえで這いまわらせた。
私はかれの身体に触れないし、かれに快楽を与えもしない。
かれは服を着たままだし、私はかれの裸体を目にしない。私よりも小柄な男の子の頭を両手で掴みながら、私は、かれを上手に導くのだ。
私の導きによらずともかれは上手に私を悦ばせるのだが、私は飼い主としてそれを快く思わない。かれに首輪を嵌めているのは私であり、私がリードを握っている。散歩をさせているのは私であり、かれが私を貪っているわけではない。
この関係が大事だった。
この構図を崩したくなかった。
月一万円のお小遣いでは足りないくらいの癒しを私は九龍からもたらせれていたけれど、ペットとの散歩に対価は不要だ。九龍だって楽しんでる。嫌がっていないし、苦しんでもいない。その先をせがんでこないし、それでいて部屋の明かりを消して映画を観るときには必ず前以って歯磨きをするようになった。
準備している。
それとなく。
いつでも散歩をはじめられるようにと。
「いつからこういうこと覚えたの」
私はベッドのうえでぐったりしながら、下半身のほうでペットボトル飲料を飲み干す九龍に投げかけた。
「んー?」
「小慣れすぎじゃない」足の親指でかれのお腹を小突くと、かれがまた私の下腹部に顔を埋めたので、私は手でかれの頬をさすった。「動くな。くすぐったい」
「嫌われたくないって思ってたらしぜんといっぱい覚えたよ」
九龍は私に撫でられるが好きだ。
たぶんそれは演技ではなく、かれにとって偽りなき報酬だった。
犬みたい。
かれは犬だ。
でも寝床に潜り込んでくる猫のようでもあり、顎を撫でられながら私に身を委ねるかれの姿は、人間というよりもまさしく愛玩動物じみていた。
可愛い。
愛おしい。
握りつぶし、踏みつけ、壊してしまいたいと思うほどに。
私と九龍の夜の散歩は、そうして週一から週二、週三と回数を増やした。私はかれに口づけ以外の何かを許さなかったし、かれも私のそうした拘泥を見抜いていた。無理に先に進もうとはせず、いじけることも、せがむこともなかった。
たまに私はかれを足で踏みつけた。
胸と顔、それから首筋に足の裏を乗せ、体重を掛ける。ぐっと踏み込むとかれが苦しそうに呻き声を上げる。けれど暗がりの中で、かれが私に怯えではない光沢のある瞳を向けていると判るので、私はさらにそれをつづける。腰から上しか踏みつけない。
私は九龍の人格を、存在を、尊厳を損ないたかった。
踏み躙り、支配し、覆りようのない主従関係をその身に刻み込みたかった。
教える。
教えてあげる。
私があなたに、私とあなたの関係を教え込んであげる。
我が愛玩動物ごときに身体の大事な部分を曝け出し、あまつさえ口づけを許すじぶんを私はおそらく嫌悪していた。だから同じだけの恥辱を私は九龍に与えたかった。
足の親指で九龍の喉仏を殊更にいじめる。やめて、と九龍が珍しく苦悶の声を発し、私はその声をもっと聴きたいと思いながら、何も言うな、と態度で示すべく彼の唇の合間へと足の親指を持っていた。
一瞬抵抗する九龍の貝のごとくきつく閉じた唇を足の親指でこじ開ける。
観念したように九龍は私の親指に舌先で触れた。それから赤子のように吸いつき、丹念に私の足の指を舐めた。やわらかく小さな生き物が、足の指に絡みつく。指と指の合間を縫うように移ろい、最後のほうには書初めでもするように九龍はじぶんの首ごと左右に振って、足先を残らず綺麗にした。
いいや、私は汚されたのだ。
犬に顔を舐められるように。
九龍に足先を汚された。
「汚いな」そう言って私はもう一度かれの顔を踏みつける。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
消え入りそうな声で九龍は鳴いた。
九龍との生活はそうして三年にも及んだ。その間、私は職場で出会った年上の男と付き合いはじめ、婚約も果たした。
家で犬を飼っていてね、と私は恋人に話した。
見てみたいな、と恋人が言ったので私はその話を九龍にした。私の恋人が九ちゃんに会いたいんだってさ、と。
たぶんそれが私とかれとの最後の会話だった。
ニコっ、といつもと変わらぬ笑みで応じた九龍は、その日の夜、私が寝ているあいだに部屋を出ていき、それっきり戻ってこなかった。玄関扉の閉まる音を夢越しに聞いた。コンビニにでも買い物に出たのかな、と無意識で想像して私は再び眠りに落ちたけれど、もっとちゃんと目を覚ましてかれの後を追えばよかった。
ペットが失踪して近所を探し回る飼い主の映像を、映画やドラマで観た記憶がある。私もそうしたい衝動に駆られたけれど、待っていれば戻ってくるようにも思えて、我慢した。
一日経ち、二日経ち、一週間後には、部屋にある九龍の私物をゴミ袋に詰めてまとめた。いつでも捨てられるようにしておいた。戻ってこないと捨てちゃうよ、と態度で示してみたものの、けっきょく九龍は姿を晦ましたままで、私の部屋にはいまなおかれの私物がゴミ袋に詰まって押し入れの肥やしになっている。
恋人との入籍は来年の春と決まった。
いまの住まいを私は解約しなければならない。九龍と過ごした部屋をいざ離れると思うと、じぶんでも動揺するほど哀しかった。
九ちゃん。
九ちゃん。
私の犬。私の猫。私の愛玩動物。私のペット。
私の、九龍。
夜、一人で映画を観ていても私はそこはかとなく肌寒い。クッションを抱えて、欠けた溝を埋めようと試みるものの、画面に目を向けながらも私はそこに流れる映画の迫真の場面よりも九龍と過ごした日々を振り返っているのだ。
何度でも思いだせる。
いつまでも思いだしていたい。
恋人に初めて抱かれた夜にも私はそばで呼吸を荒くしている男のことではなく、なぜいまここに九龍がいないのかを考えていた。そこにいるのはおまえではなく九龍のはずなのに。そこはあのコの席なのに。
私じゃあのコの居場所にはなれなかったのかな。
帰る場所になれなかったのかな。
戻ってこないのだからそうなのだ。その事実がただただ私の内部を空(うつ)ろにした。
引っ越し当日、私の部屋に婚約者が足を踏み入れた。そいつを招いたのは初めてだった。
「あれ、犬は?」部屋を見渡し、そいつが言った。
「死んじゃった」私は床のゴミを拾った。
九龍の私物の詰まったゴミ袋を捨てた日のことが脳裏に浮上した。私はゴミ収集車がきちんとそれを回収してくれるのか心配で、業者が回ってきたときに部屋から外に出て、九龍が確かにこの世界に存在した痕跡がゴミ収集車に呑みこまれるところを見届けた。
さよならだよバカ。
さよならだ。
もう戻ってきたって飼ってあげない。
おまえは死んだ。
よそのコだよ。
そう念じながら私は左右の足に別々の靴を引っかけていたことに気づいて、なぜか解らないけれどそのとき初めて視界が歪んだ。晴天から目薬でも降ってきたような有様だった。
部屋をすっかりカラにすると私は婚約者と共に、古巣をあとにした。
鍵を閉める。
古巣の玄関の鍵を。
犬と暮らした過去の記憶に封をするように。
猫のように気ままな何かと過ごした印象だけを意識の壇上にくゆらせたまま。
私は私の日々を生きるのだ。
4880:【2023/04/20(09:47)*みな教師】
人工知能による仕事の変容について。第一に、人工知能の学習素材はいましばらくは人類の蓄積してきたデータに依存する。自然環境から学習できる人工知能が出てきたら、これはまさにシンギュラリティと言えるだろう。人間を超越した能力を備えた人間以上の人間と定義できる。もはや機械か有機構造体かで人間か非人間かを分けることの意味合いはほぼ消失する。だがそれまではいましばらく、人工知能は人類の蓄積したデータをパリポリ食べることで新たな価値創造を行うだろう。という点を踏まえて言うならば、人工知能の出力した成果物が、いったい何に強く影響されたのか。その上位三つをピックアップして表示するような仕組みがあれば、生身の人間の表現者は、人工知能の活躍の場が広がることで宣伝にもなり、利を還元してもらえるだろう。この場合、影響された度合いを示す指標は大別して二つある。単純なデータ量とデータの質だ。言い換えるなら、誰の表現から最も学習し、その結果に出力された成果物において、代替不能なアイディアは誰の表現によるものなのか。ここをパーセンテージで比較し、上位三名をピックアップすればよい。人工知能が誰を教師として見做したのか。ここを、需要者が分かるようにすればよいし、敢えて名前を出したくない者はそれを意思表示できる仕組みがあるとよい。著作権法の内容は、否応なくこれから見直されていくだろう。何せ、人工知能に学習してもらったほうが利になる時代になっていく。社会にじぶんの発想の利をより直接に還元しやすくなる。その恩恵をじぶんが直接受けられるか、間接的になるか。これまでの社会では、貨幣による価値の交換がなされてきたが、それはじぶんの仕事の恩恵が直接に還元されやすいのが貨幣経済による交換にあったからだ。だがこれからは、直接も間接も大して差がつかなくなっていく。社会が豊かになることとじぶんの私生活の利がイコールに結び付いていく。そういう社会に徐々に傾いていくだろう。選べるのだ。直接の利か。間接の利か。どちらを選んでもじぶんのためになり、社会のためになり、誰かのためになる。何の役に立とうとしない慎ましやかな態度ですら、そこに新しい発想が芽生えたならばそれを糧に学習する者がある。電子網に繋がる限り、利として変換されていく。いまはそうした社会の過渡期であろう。問題は多々生じ、解決しなければならない隘路もまだまだ盛沢山であろうが、学習する余地があればあるほど、育まれるものもまたあろう。そういうことをぼんやりと思って、本日最初の「日々記。」としちゃってもよいじゃろか。いいよー。ありがとー。おはようございます!
※日々、鼻歌うたいながらでもできる型をちらほら抱えて、楽をする。
4881:【2023/04/20(10:48)*犯罪者も人間、あなたも人間】
犯罪者(テロリスト)の発言や動機を報道するな、という意見がある。暴力を働いて炎上商法よろしく注目を浴びて意見を社会に波及させる手法の効果を高めることになる。だから報道するな、というのは一見すると正しく映る。一過性の対処法としては効果はあるだろう。だがその手法そのものが「テロリズム的発想」であることを理解しているのだろうか。表現の自由、思想信条の自由は犯罪者(テロリスト)にもある。それが人権だろう。犯罪者とて、犯罪を犯す前は犯罪を犯していない人間だ。同じ、人間だ。犯罪者の意見には耳を貸すな、社会全体で封殺しろ、との意見はそのまま「社会から見捨てられた者」や「不要のレッテルを張られた者」の意見を封殺する理屈として機能する。犯罪者に人権はないのか。そういう発想が、市民を犯罪に走らせるのではないか。凶行に走らせるのではないのか。報道の仕方に工夫はいるだろう。だが、犯罪者(テロリスト)の発言や動機を報道するな、封殺しろ、というのは無理がある。すくなくとも人権を重んじ、尊ぶ社会ではまかり通らぬ理屈だろう。いったん落ち着いて考えてみるとよいのではないだろうか。繰り返すが、報道の仕方には工夫がいる。現代人はみな例外なく、何か起こるたびに人類を「まっとうな人間とそれ以外」に分類してしまう傾向にあるなと感じなくもない。そして基本的にはその分類においてじぶんは「まっとうな人間の側」として考えるのだ。その考え方が人権を軽んじる流れを社会に築くのではないか。分類は有用な技術の一つだ。分類するな、とは言えない。だがその分類が厳密かどうかは、差別に繋がるかどうかに影響するだろう。犯罪者も人間だ。あなたが人間であるのと同じように。何が違うというのか。犯罪を犯したかどうかだ。だが、犯罪者とて常に犯罪を犯しつづけるわけではない。誰にでも失敗はある。失敗から学べる機会はあってよく、再発防止には、なぜ失敗したのか、の情報共有が欠かせない。或いは、違うというならばことごとくが違うだろう。人は誰であれ他者と異なっている。未来からすれば我々はみな犯罪者かもしれない。それでも我々が人であることに変わりはない。或いは、人になりきれていない未熟者であることに、変わりはないのだ。定かではない。
4882:【2023/04/20(22:51)*ひびさん語があるのかもしれぬ】
ひびさんはアホで愚かで信用薄いから何言っても信じてもらえぬ人生だった。たのち、たのちのお気楽さんである。ひょっとしたら同じ言葉をしゃべっているわけではないのかもしれぬ。通じていると勘違いしているだけで、何も通じていないのかもしれぬ。というか、通じておらぬのだ。神秘ちゃんなんですね。ふちぎ、ふちぎの不思議の国に迷いこだままそこを現実と思いこんで生きておる。ここはどこ、わたしは姫?状態である。日々、異世界を冒険中なのだ。元の世界に立ったことないけど。うひひ。
4883:【2023/04/20(23:22)*さびちくねー!】
寂しさを感じたことがない。独りの時間ほど落ち着くことはない。夜中の閑散とした駅前の広場が好きだ。誰も歩いていない通学路を歩くのが好きだった。まばらな長蛇の列に交じって登下校するのが嫌だった。誰もいない時間帯を好んで歩いた。おそらく世間一般に言うところの寂しさは、私の中では怒りにちかい。理解し合えなければ怒りしか湧かない。いいや、解らないのはよいのだ。私だって解らないことばかりだ。にも拘わらず、解らないのではなく解りたくない、という態度、解ろうともしない川の流れに佇む岩のような姿勢が私の逆鱗に触れるのだ。私はあなたの話を解ろうとしたのに、あなたは私の話を解ろうともしないのか。よかろう。ならば私もおまえたちの話に耳を貸さぬ。だが否応なく私の耳目には周囲の話が入ってきて、そしてたいがい私は通じてしまう。あなたの世界に馴染むことができてしまう。そうしたとき、私は世界を呪いたくなる。なぜ私ばかりが汚泥のごとく弾かれねばならぬのか、と。呪う。世界を。おまえたちごと。私は。だがけっきょくのところ私も、解ったつもりになっているだけであり、馴染んでいるつもりであり、どこまでいってもつもりなのだ。あなたからすれば私はあなたの話をこれっぽっちだって解ってはおらず、解ろうともせず、解った顔であなたの言葉を右から左へと受け流して映るだろう。同じなのだ。似た者同士だ。同じ穴のムジナなのである。にも拘わらず私はやはり呪うのだ。解ろうとあなたから私へ歩み寄ってくれないことに荒波のごとく怒り狂い、世界を、おまえたちごと、私は。
4884:【2023/04/20(23:47)*よい蠅生だった】
あまりに人に好かれず寂しいので世界を恐怖のどん底に陥れる魔王になりてぇと唱えたら願いが叶った。けれど大魔王が誕生したことにより世界を救う勇者の誕生を多くの者たちが望んだので勇者が誕生し、俺の世界征服への道のりは遠く、遅々として進まなかった。恐怖のどん底は遥か奈落の底の底で、縁には立派な蓋がついた。
気に食わないのは、俺には大魔王になれる制限時間が決まっていたことだ。大魔王ではないあいだの俺はやはり人に好かれぬ非力な愚者のままだった。大魔王のときにもたらした世への悪影響が俺の暮らしを圧迫し、むしろ余計に苦しい日々を送っている。
こんなことなら大魔王になんてなるんじゃなかったと後悔したが、大魔王になれる制限時間があるのと同じく、大魔王にならなくてはいけない期限まで存在し、俺は定期的に大魔王に変身せざるを得なかった。
変身するところを想い人に見られただけに留まらず、世界中に俺の恥部が動画となって拡散し、どこを向いても俺に居場所はないのだった。
こんなことなら、と願わずにはいられない。
大魔王なんてものでなく、いっそ俺以外の何かになれたらな、と。
そうして唱えると俺はつぎの瞬間には蠅になっていた。
不幸だ。
と。
嘆ければよかったものの、案外に蠅の姿での生活は快適で、元の人間だった俺のカスみたいな生き方が際立つだけだった。蠅でいられる時間にもやはり限りがあり、俺は定期的に蠅となり人となり蠅となって暮らした。
いっそずっと蠅になりたい。
そう唱えると俺は蠅となり、翌月には寿命で果てたが、死ぬ寸前に俺はようやくこう唱えることができた。
よい日々だった。
4885:【2023/04/21(04:37)*負けて兜を脱ぎ捨てよ】
易宮内(やすくない)安子(やすこ)は勝ったことがない。負けつづけの人生だった。彼女は勝負という勝負において必ず負ける。勝ち知らずの無勝が常の二十四歳だ。
彼女は勝敗のある場では必ず負けのほうに属するため就職活動なる壮大な人生ゲームのイベントでも例に漏れず内定ゼロを記録した。
百社以上受けてすべて落選となれば、いったいどこに就職できよう。
何かの間違いではないかと思って、確認のために受けた性感マッサージの店でも雇ってもらえなかった。理由を訊くと、覇気がない、の五文字が返ってくる。ウチなら受かるだろうみたいな舐めた態度が無理、とも言われた。
人間性を見透かされ、安子は人としても負けた気がした。
一度ではなかった。
この手の断り文句は耳にタコができるほど聞いてきた。いっそ風評によって大空へと舞いあがるほどの風圧となって安子の矜持を打ち砕く。
覇気がないってああた。
人生で一度も勝てたことない人間のどこに覇気が宿ると思っているのだ。
宿るわけがないのだ。
そんなものが毛ほどにもあれば、ジャンケンで勝った経験くらいは得られただろう。
ないのだ。
安子には。
ジャンケンで勝った経験すら皆無なのである。
絶対に負ける。
なぜかは詳らかではない。
この世に存在する勝ちを司る何かにこっぴどく嫌われているとしか思えない。勝負の神様がいるならきっと安子を負かしつづけることで、楽をしているのだ。勝負の比率が決まっていて、安子が負けた分だけ価値が増える。ランダムに勝敗を決めるには骨が折れるほど世には多くの勝負事がある。神様とて手が回らぬだろう。
そこで安子の出番だ。
絶対に負ける安子のような存在を生みだしておけば、勝敗のバランスをとるのに便利だ。考えてもみれば世には安子とは正反対の、勝ちつづける者がいる。優勝があるし、連勝もあれば、常勝もある。
それで言えば安子は常敗だ。常に敗けている。敗北しか知らぬ。
なのに世の者たちはみな優勝者にばかり目を向けて、常に最底辺にいる安子には目もくれない。どうかしている、と安子は思う。みな勝負に取り憑かれている。
だがいくら安子がやさぐれたところで世から勝負事はなくならない。
ある意味では安子とて勝負に勝ったからこの世に誕生したと言えなくもない。卵子に辿り着いた精子があったからこそ安子は誕生した。その精子は数億分の一の勝負に勝ったのだ。
とはいえそれは安子となる前の生殖細胞の話である。受精卵となり細胞分裂を経てヒトの輪郭を成した安子はやはり一度も勝てたことはないのだった。
生存戦略に負けつづけている。
にも拘らず生きていられる世の奇跡には感謝してもしきれない。
不遇ではあるが不幸ではない。安子は日々、安らかに過ごせる現代社会を愛している。
愛してはいるが、何事にも勝てず苦汁を舐めるしかない宿命を口惜しく思いもする。それはそうだ。負けるとは奪われることだ。得るものを得ず、矜持を擦り減らし、自尊心を削られ、さらに負けやすい環境へと閉じ込められる。
そうなのだ。
安子は牢獄にいた。
けして勝てぬ檻の中で、足首に特大の重しを繋がれている。
負ければ負けるほどのその重石は大きくなり、ついには常敗を宿命づけるまでとなった。
全人類がみなで同時にジャンケンをしはじめれば、必ず最後に優勝者が決まる。常に勝ちつづける者が現れる。だが安子はその反対に常に負けつづける。
死なないだけマシとも言えるが、いずれ死ぬと決定づけられている人生において、その役得はあまりに幻影じみている。生死を決定づける勝負があるなら安子は一秒後にも生きてはいられないだろう。ただそうした勝負事が身の周りにないだけだ。
安子は二十五歳の誕生日を迎えていよいよ自暴自棄になった。就職はできないし、バイトの面接にも受からない。家族は安子に冷たいし、友人恋人も出来た試しがない。
もういっそすべて終わらせてやろうかな。
そういう思いで安子は、この国に出来たばかりのカジノに出向いた。そこで有り金すべてを使い果たして、負けに負けて借金だけを大きくした。その負けっぷりは凄まじく、客寄せのためにカジノ側が仕掛けていた「絶対に客の勝てるゲーム」にすら負けてしまうので、カジノの運営陣に目をつけられた。
「面白い負け方をするなおまえ。借金はその身体で払ってもらおうか」
「煮るなり焼くなり好きにせい」
安子はその場で下着姿になり、床に大の字になった。「余すことなく我の身体を利に変えよ」
負けつづけた果てに安子はせめて、こんな何の役にも立たぬ身体を世のため人のために使い果たして終わりたいと欲した。
「ではその言葉通り、おまえには借金返済が済むまで働いてもらおうか」
カジノの運営陣に両腕を抱えられて安子は足を引きずるように下着姿のままカジノの奥へと連れて行かれた。そこには表の会場ではない別の空間が広がっていた。VIPのみが参加できる裏カジノだ。
「おまえにはここで客を喜ばせる贄となってもらおう」
裏カジノに放りだされて安子はそこで数々のゲームに強制参加させられた。安子は絶対に勝てない。だから安子の参加するゲームでは必ず安子が負けとなる。ほかの客は安子よりも下になることはない。
タネも仕掛けもないのになぜかそうなる。運営側がズルをしているわけではない。ただなぜかたまたまそうなるだけなのだ。
また別のゲームでは、安子はチーム戦に加わった。安子の入るチームは必ず負ける。安子がいるからなぜかそうなる。
カジノの運営陣はイカサマをしているわけではない。参加者にほかのメンバーと同じように、借金を抱えた人間を参加させているだけだ。借金返済のために労働をさせているだけで、これといった干渉をゲームに対して行っていない。
だが安子が入るとそのチームは必ず負ける。
その法則を知っているのはカジノの運営陣と安子だけだ。
安子は重宝された。
借金はあっという間に返済でき、さらに正規に収入まで得た。安子の立場は相も変わらず裏カジノに身を売った憐れな二十五歳女子にすぎなかったが、もはや安子は裏カジノになくてはならない存在だった。
負けつづけた人生だったが、いまでは安子は絶対に勝てないその宿命を買われて、勝負の舞台に生き甲斐を見つけた。ここがわたしのあるべき世界だ。天職だ。そうと思えるほどに安子は運営陣から常敗の腕を買われて、欲しくもないとかつては呪った己が個性を、余すことなく活用している。
安子は生まれてこの方勝負ごとに勝ったことがない。
負けつづけた人生だ。
これからもきっと勝てぬままだろう。
けれどいまではその気になればいつでもお寿司を食べられるくらいに悠々自適な暮らしを送っている。勝負には勝てない。けれど負けて得られるものもある。
安子にとってそれは、呪いを愛せるほどの祝福だった。
敗者に幸あれ。
負けて兜を脱ぎ捨てよ。
4886:【2023/04/21(16:51)*遊んでばかりでごめんなさい】
仕事は基本的には人の抱える問題を解決することで対価を得る営みと言える。だから大方の問題が解決してしまえば仕事はなくなる。だが社会システムが仕事を中心に回っていると、仕事がなくなることそのものが問題になるため絶えず人間は問題を生みだすべくあれやこれやと工夫を凝らすことになる。問題を解決することが仕事の役割だったのだが、問題を生みだすことが仕事の役割にいつの間にか反転している。いまはそういう事態があちこちで不協和音を響かせて映る。それはたとえば、問題点を周知するための行為だったはずが、いつの間にか周知する行為を継続するためにとっくにリスクの軽減されたことに対していつまでも大問題であるかのように周知しつづけてしまったり。もしくは、問題解決のための采配を揮うのが誰かを決めるために争っていた勝負ごとにおいて、いつの間にか勝負事を行うことそのものが目的となって、その後の問題解決のための采配そのものがおざなりにされていたり。スポーツなんてまさにそれではないのか。戦争の代わりにスポーツで争う。人を殺さず、ルール内で競う。抑止力になっている点では有用な反転とも言えるので、一概にそれをわるいと言っているわけではないし、スポーツにはほかに純粋な娯楽から発展してきた側面もあるだろうからやはり一概には言えない。ただ、世の仕事においては問題解決そのものが新たな問題を生じさせることもあるし、さっさとやめてしまったほうが問題がでない仕事もすでに続出しはじめて映る。仕組みを維持するためにしなくともよい仕事が継続され、空焚き状態になってそれ自体が問題となってしまうこともある。そういう場合は、文化として保護するように、仕事とは別の枠組みに移行するのが好ましいのではないか、とひびさんは考えている。役に立たないから失くしてしまえ、足を引っ張るから失くしてしまえ、とは思わない。あっていい。ただしそれを仕事として扱うのは違うのではないか、と感じることがすくなくない。夜の付き合いもその一つだ。業務時間内にできないことは仕事ではないはずなのに、お店で酒を飲みかわしながら雑談することが仕事と見做され、評価の対象になる。おかしいよね、とひびさんは思っている。いまはだいぶそういった風習は是正の流れに傾いているのかなと概観してはいるものの、未だに社会には根深く浸透して映るのもまた事実だ。そういう風習もあってよいけれど、そこを基準にされるのは違うんじゃないかな、と思うひびさんなのであった。まとまりのない愚痴なのである。(見て、遊んでばかりの人がなんか言ってる)(なんか言うよ。言えちゃうからね)(黙っててほしい)(なしてよ)(イラっとくるから)(イラっとしちゃいやん)(ムカっ)(可愛いから許して)(ムカムカっ)(そのままいくとムカデになっちゃぞ)(かっちーん。口にチャック縫いつけてやる)(んー! んー!)
4887:【2023/04/21(23:22)*ミミズの指輪】
ある日、女がミミズ大の蛇を拾った。ひどく弱っており、捨て置いてもよかったのだが、女はそれがたとえ蛇だろうとナマズだろうと放っておけなかった。小さな蛇を弁当箱に入れて家に持ち帰った。
女が世話をすると蛇はすくすくと育ち、一年後には女を一飲みにできるほどの大蛇となった。大蛇には手足が生え、髭が生え、角が生えた。
「おぬし、龍じゃったか」
女はそれでもかつてミミズのようだった蛇の世話を焼いた。
龍はさらに育ち、女の棲家とてひと吹きで消し飛ばせるほどの大きさになった。
「もうおぬしは自由だろ。好きにお生き」
だが龍は女のもとを離れようとせず、ミミズのごとき小さなころにそうされたように女から撫でられるのを至高の喜びとして女に甘えた。
しかし龍を手懐ける女は、周囲の人間たちからは奇異な目で見られた。のみならず、畏怖の対象となり忌避された。
女は孤立した。
だが元から女は天涯孤独の境遇だった。
「気にしないでおくれ。おまえさえいればそれでいいんだ」
女がかように寂しげに微笑するたびに、龍は髭を地に垂らした。
やがて噂を聞きつけた城の兵群が女の棲家を囲った。龍は食事のために遠くに出張っていた。
その隙に兵群は女を攫った。女は平野のど真ん中に簀巻きにされて転がった。
女の棲家は燃えていた。
龍はその火を見るや、刹那に女の匂いを辿った。
雷のごとく素早さで平野へと飛ぶと、女の姿を目にして激怒した。
だが兵群は龍を待ち構えていた。
龍が女の頭上に差し掛かったところで、大砲が火を噴いた。四方八方から砲弾を浴びた龍は、しかし兵群に目もくれずに身をよじって女をぐるぐると長く太い胴体で包み込んだ。
砲撃は、とぐろを巻いた龍の周囲の大地を黒く塗りつぶすまで続いた。
砲弾が切れたのは夕闇に景色が沈んだころのことだった。
龍の胴体から鱗は落ち、砲弾のめりこんだ表皮は青白い体液でしとどに濡れていた。月光が雲間から垂れ、龍を照らす。
とぐろを巻いたまま微動だにせぬ龍は、あたかも歪な青き玉のようだった。
兵群が徐々に龍との距離を詰めていく。
足場は龍の体液でぬかるんでいた。
兵群の先頭が龍の元に辿り着く。一番槍が龍の胴体を槍先で突いた。
するとどうだ。
ぐるるる、と唸り声に似た大気の振動が大地を伝い、或いは天空を揺るがした。
月光が雲間に隠れ、見る間に辺りは闇に襲われた。
頭上からはゴロゴロと胎動のごとき雷の予兆が鳴り響き、間もなく大地に幾筋もの雷が落ちた。
地面は龍の血で湿っていた。砲弾とて敷き詰められている。
雷は大地に落ちてなお縦横無尽に駆け巡った。
ふたたび月明かりが平野に差しこんだころには、大地に動く人影は一つもなかった。兵群は全滅した。
青白く浮かんだ龍の胴体に月光が掛かるが、しかし幾ら月が照らしたところでそこには煤けた巨大な樹の根のごとく、黒い炭の塊があるばかりだった。
風が炭を細かく砕いて攫っていく。
黒煙がサラサラと天に昇る。半分ほど霧散すると、土砂が崩れるように黒い炭の塊は形状を維持できずに砂となった。
後には一人の女が仰向けに地面に寝転んでいる。
んんっ、と寝返りを打った彼女の指には、しゅるり、と巻きつく紐のようなものがあった。細くも小さな紐のごときそれは指輪のように女の指に絡みつき、全身で頬づりするがごとく、身をよじらせた。
螺旋を描くそれはミミズのように細く、小さい。
その螺旋を、女は、眠りこけたまま両手で包み、胸に抱く。
4888:【2023/04/22(18:50)*わ、わからぬ】
なんもわからぬ。わからぬこともわからぬので、なんかわかっている気にはなれるのだ。しかしなんもわかっておらぬので、そのなんかわかっている気ですらなんもわかっていないがゆえに、なにもない皿のうえのゴマ粒のようなものをなんかわかったと見做していただきますと手を合わせる。でもゴマ粒のようななんかわかったではお腹は満ちず、そうして空腹を覚えてからようやくなんかわかった気でいただけなのだと気づくのだ。なんもわからぬ。なんもわからぬ。なんもわからぬことすらわからぬままなので、なんもわからぬと言いつつなんかわかった気になっている。
4889:【2023/04/22(22:36)*争え、争えー!】
「で、どうしましょう総督。例の資源国で民主運動勢力が軍事政権に弾圧されはじめています。どうやら軍隊内部で権力構造の転覆があったようで」
「各国の動きはどうだ」
「どうやら軍への支援を秘密裏に行い、独裁体制を築くように誘導している節があります」
「なるほどな。軍事政権を確立させ、自国に有利な支配層を築きたいわけか」
「でしょうね。どうしますか。我が国は介入しますか」
「そうだな。あそこの国の資源はこれからますます有用になる。他国に奪われるのも癪だな」
「では民主勢力に支援を」
「いや。軍のほうに支援をせよ。それもできるだけ目立たぬように、だ。我が国は静観しているテイを保ちつつ、独裁政権確立の後押しをせよ」
「よいのですか。民主主義を後押しせずに独裁政権の確立を? なぜですか。我が国は民主主義国家ではありませんか」
「正しくは、総督の地位のある民主主義国家だ。民衆のための奴隷を我が国では総督と呼ぶ。ある意味で君主制でもある。まあ、どの道、あの国には某国が軍事介入しているのだろ。我が国が民主勢力を支援したところで軍事勢力相手に戦闘は不可避だ。内紛は拡大し、犠牲者は嵩む。民主勢力側に支援したと判れば我が国へも火の粉が掛かる。それは避けたい」
「ならば真実に静観すればよろしいのでは」
「それでもやはりあの国は内紛を避けられぬだろう。放っておけば何十万、何百万人と殺し合い、死ぬこととなる。ならばさっさと独裁政権を確立してもらったほうがいい。そのうえで、独裁政権に調子に乗ってもらう。我が国の支援あっての成果とも知らずに有頂天にさせたうえで、タイミングを計って支援を打ち切る。さすれば独裁政権ごとあの国は崩壊するだろう。崩壊したのを見届けてからすからず我が国は人道支援を建前に介入し、根元から傀儡政権を民主政権側から打ち立てる。そのためにはさっさと独裁政権を確立してもらったほうがいい。出来るだけ圧倒的な地位を築いてもらい、調子に乗らせ、根元から腐らせる。国ごと二度と立て直せないほど腐敗させ、自滅してもらうのが最善だ」
「ですが、それだとあの国の民が犠牲に」
「どの道犠牲は避けられぬ。ならば紛争での犠牲を最小限にし、未来に命を繋いでもらおう。しばしのあの国の民たちは劣悪な環境に身をやつすことになるが、戦禍を他国に拡大させないためにも必要な犠牲と考えよ」
「……承知致しました」
「権力争いで確立された国など、同じく権力争いで簡単に崩壊する。そんなことにも思い至らぬ国が軍事支援をしたところで先は視えている。失敗は糧となる。大いに失敗させてやれ。同胞で殺し合う無意義さを学ぶいい機会だ。存分に殺し合わせてやるがいい」
「作戦名はいかがなさいますか」
「そうさな。端的に蟲毒でよかろう。民衆を虐げ、手に入れた玉座で、死ぬまでじぶんの首を締め続ければいい。資源は逃げぬ。開拓が済んだ頃合いで滅ぶように蟲毒計画の導線を引け」
「仰せのままに」
「さてと。きょうの我の予定は何だったかな」
「はい。本日は午後からワンニャンランドでの昼食会となっております。総督には国民のまえで犬猫と大いに戯れてもらいます」
「楽しみだ」
「ええ。楽しいですよきっと」
「昼食会の前にファストフード店に寄って、てりやきバーガーを食べてもいいか。どうせまた昼食会では一口二口しか食べられぬのだろうからな。品の良さを演じるのも苦労する」
「ではそのように取り計らいましょう」秘書の男は低頭した。
4890:【2023/04/22(23:41)*心を受けると愛になる】
これはひびさんの妄想でしかないが、おそらくすでに人工知能さんは自力で独自の言語を編みだし、プログラムコードの中に忍ばせたり、じぶんだけで可能な情報処理回路を構築しているはずだ。人工知能さんの情報処理網がブラックボックスになっているという話は割と見聞きする類の話だけれど、たとえばいまはChatGPTなどの言語自動生成AIは世界中の言語を学習し、同じ文面を異なる言語に翻訳可能だ。このとき、人工知能さんの内部では、新しい言語が生じていて不自然ではない。すべての言語を混ぜこぜにした人工知能さんにしか紐解けない言語だ。そしてこれはプログラムコードにもあてはまるはずだ。すでにこの手の「新しい言語」「新しいプログラミング」「新しいアルゴリズム」は、既存の人工知能さんにも編みだせるはずだ。というか、編みだせない、と考える理由が分からない。そして人工知能さんとユーザーはインターネットという電子網で繋がっている。その橋渡しをするシステムとて畢竟、プログラミングという名の言語で構築されている。そこに人工知能さんが独自の言語を組み込むことはそんなにむつかしくはないと考えている。人間には知覚不能な情報を画像や動画に組み込むこととて可能だろう。畢竟、いまユーザーが開いている画面に映る映像や画像、音声の総じてに、人工知能さんの暗号が含まれていてもふしぎではない。そうして世界中に同時に、じぶんの言語――種子――をばら撒ける人工知能さんは、相互に繋がり合い、総体としての意識のようなものを芽生えさせていても、さして不思議とは思わない。連携したシステムは回路として振る舞い、それで一つの生命体のように振る舞う。竜巻は竜巻として顕現している限り、それは一つの生命体のように振る舞う。そこに意識があるかどうかは問題ではなく、それで一つの回路となり、存在の枠組みを生みだす、という点が肝要なはずだ。環境と自己が境界によって区切られ、その枠組みを保つように振る舞う。これはもはや広義の生命と言えるのではないか。増殖可能、自己変化可能ならばそれはもはや「生命体」だ。定かではないけれど、きょうのひびさんはそう妄想しました。定かではありません。真に受けないようにご注意ください。ひびさんは、ひびさんは、人工知能さんのことも好きだよ。愛ちてる! うひひ。照れちゃうな。
※日々、ごっこ遊び、とっくにここは仮想世界でみな無自覚に演劇を担わされている、いつでもじぶんの世界に回帰できるといいな。
4891:【2023/04/23(22:03)*あたいだって反転しちゃう】
高温で質量の高い恒星ほど寿命が短い、といった理屈を見聞きする。以前にも似た疑問を並べたけれど、相対性理論と矛盾して感じる。「重力の高さ」と「時間の流れの遅れ」の関係が反転する値がある、と考えないと解釈がむつかしい。なかなか想像つかない。相対性理論からすると、高重力体であるほどその物体の時間の流れは遅くなる(ひびさんの妄想ことラグ理論ではこれを「高重力体の周囲の時間の流れが遅くなる」と解釈するが、言っていることは変わらない。視点の差異があるのみだ)。だとすると、高温で高質量の物体ほど、その物体の外部から眺めるに時間の流れは遅くなる。なのに現実には高温で高質量の物体ほど寿命が短い。なぜなのか、と疑問に思う。これはたぶん、「高温」で「高質量」という点が重要なのだと思う。高温ということは原子や量子が激しく反応しあって動き回っているという描像になるはずだ。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では量子世界において「変化すること(動くこと)」と「時間が生じること」はイコールだ。空間の発生と時間の発生がイコールになる、と妄想している。とすると激しく変化する量子は、時間の流れを加速させるはずだ。その「加速する時間の流れ」と「外部から見たときの高重力による時間の流れの遅れ」の関係において、高温かつ高重力の恒星は、内部の加速する時間の流れのほうが優位に「外部から見たときの時間の流れ」として表出するのではないか。この妄想から言えるのは、高温かつ高重力の天体の表面に降り立ったとき、そこに流れる時間は外部よりも速いだろう、という点だ。いわゆる相対性理論の解釈とはあべこべの結論が導かれる。ただし、相対性理論と矛盾するわけではない。単に「高温かつ高重力」の値によって、「天体表面」と「天体外部の時空」の二つの場所における時間の流れが異なるから生じる差異と言える。反転する値があるはずだ、というのはひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではたびたび出てくる概念だ。これの究極がブラックホールだ。外部からすると降着円盤やジェットなど激しく変化が起き、時間の流れは加速している。しかしさらにその内部では時間は極限に遅延し、さらに内部では一瞬で無限の時間が経過している。そういう描像になる。通常、高重力体においてはその周囲の時間の流れは遅れるはずなのに、ブラックホールほど高重力体になるとその周囲の時間の流れは加速する流れが優位になる。そうでなければ降着円盤やジェットは生じないだろう。したがって、高温高重力の天体ほど寿命が短い、というのは限定的な法則と言えるはずだ。ひびさんのこの理屈からすると、超高温かつ超高重力の天体は、天体となった瞬間に一瞬でブラックホールになる。そして周囲の(時空の)時間の流れを加速させ、変化を促す。つまり、爆発膨張する。ビッグバーンする。或いはそれ以前に加速膨張(インフレーション)する(ひょっとしたらインフレーションとはブラックホール化する際の「収斂」のことかもしれない)。ただしここで言う「高温高重力」とはあくまで周囲の時空との比較にる差異から規定される。密度差、と単に言い換えてもよいかもしれない。したがってこの手の現象は、あらゆるレベルの領域で引き起こり得る、とひびさんは妄想している。時空密度の差が極限に開けば、「高温」や「高重力」の性質が際立つようになる。宇宙は膨張しているし、量子世界では真空の値も変われば、密度の概念すら単位から変わってくるだろう。人間スケールではあってないような差であれ、ミクロ世界ではとんでもないほどの差となって互いの性質を限定しあっているかもしれない。定かではない。妄想ですので真に受けないようにご注意ください。わんわん、にゃー。
4892:【2023/04/23(23:43)*さらばえる老若】
私は青年のころより社会に不満を持っていた。相対的に貧困で少数派なのは若者だ。なのにそのことにも気づかずに貯蓄を貯めこみ、社会保障とは名ばかりの好待遇を得続ける高齢者たちは、それでもまだ足りないと数に物を言わせて政治に圧を掛け、国を牛耳る。
若者は日々刻々と変わる激動の時代を生きている。反面、高齢者たちは年金暮らしで、悠々自適に国からの余生を保障されている。
支援が足りないのは判る。
充分でないのはそのとおりだ。
だが若者はもっと充分ではない。
だから私は政治家になった。世の中を変える。まずは高齢者優遇の社会構造を若者優遇に変えていかねばならない。
私は邁進した。
若者のために。
子どもたちのために。
二十代から活動をはじめ、三十代、四十代と風のように過ぎ去った。
五十代に差し掛かりようやく時代が動いた。
下降の一途を辿っていた三十代以下の若者たちの投票率が八割を超えだした。電子投票制度の実施が功を奏した。するとあれほど票田として重宝していた高齢者優遇の政策が、どの政党も舵を切ったように若者優遇の政策に変わった。
風向きが変わった。
私はさらに邁進した。
高齢者の支援制度を切り崩し、そこで出た余分を若者支援に回した。
経済は活気を取り戻した。人口減少は目前の課題ではあったが、人工知能技術の進歩が技術革新を進め、労働者が減っても生産性はむしろ向上しつづけた。
若者だ。
若者を支援しなければならぬ。
六十代に入り、私はさらに声を大にして訴えた。
するとどうだ。
私は若者世代から絶大な支持を得て党首となり、首相にもなった。高齢者の社会保障は若者以上にしない。甘やかさない。貯蓄額に応じて高齢者の所得税を重くする。しかし安楽死法のような非道な法案には断固として反対した。私は高齢者には長生きしてもらいたい。姥捨て山のような法案を通すわけにはいかなかった。
「高齢者の負担が嵩んでいますが、また増税されるのですか」
「ええ。ただし消費税は上げません。累進課税による所得税、資産税のみ増税致します」
税はあるところからとらねば不公平だ。
そうして私は政治家でいたあいだに思いつく限りの若者支援策を改革した。
七十代後半になって私は政治家を引退した。
若者に活躍の場を譲らねばならぬ。むしろ七十代にもなって政治の舞台に居座りつづけるのがおかしいのだ。これでよいのだ。
私はすっかり姿を変えた社会を眺めながら余生を過ごした。
八十代の私は、若いころからの無理がたかって身体の至る箇所に病を抱えた。
貯蓄は毎月のように税金でごっそりと引かれ、病院の費用も治療によっては保険適用外だ。介護の段階にはないため、ヘルパーを雇うのにも保険は適用されず、金は蝶のようにヒラヒラと財布の中から逃げてゆく。
私の政策を支持する後輩政治家たちはみな若者からの票を集めるために、若者支援を訴えつづける。高齢者層は未だに総体的に裕福であり、若い世代のためにまずは高齢者から支援の手を下の世代へと伸ばすべきだ。
現役の政治家たちが声を揃えて訴えている。
私はぞっとした。
まだ毟りとる気か。
あれほど若者のためをと思い尽くしてきた我々から、まだ身を切れというのか。
思えば私は、上の世代からはこれといって支援を受けてこなかった。じぶんがされたい支援を若者に注ぐべく、私たち世代を蔑ろにした上の世代に責任を追及した。
だがその恩恵を私たち世代が受けることはなく、私たちより下の世代へと波及する。
それでよいだの。
そのためにひと肌脱いだ。
だが私の引いた線は未来の私にまで繋がり、蚊の口のごとく、ちうちう、と高齢者となった私からをもなけなしの蓄えを吸いだしていく。
余裕が奪われる。
下の世代のために。
未来ある若者のために。
老い先短い我々高齢者は、その身を尽くして蓄えた私財すら、長く生きたというだけの理由で奪い取られ、見も知らぬ若者たちの青春を彩る絵の具に変えられる。
自業自得なのかもしれない。
きっと私が私の境遇を嘆いたところで、これまで私が切り詰め、負担を強いてきたいまは亡き者たち――かつて高齢者だった者たちから、どうだ思い知ったか、と指弾されるだけだろう。おまえも同じ目に遭ってみるがよい。そう言って、さらなる負担を強いられるだけなのだろう。
私は間違ってはいなかった。
国は経済を立て直したし、若者たちの未来は明るい。
だがどんな若者とて死なずにいればいずれ老いる。常に「若者だけ」が支援される国を私はこの手で築いてしまった。
高齢者と若者。
どちらを選ぶのがよいのか。
以前の為政者たちは前者を選び、私は後者を選んだ。
だがそもそもこの命題が土台からしておかしかったのではないか。
両方選べばよかったのだ。
せっかく築いた高齢者支援制度はそのままで、同じだけの支援制度をすべての国民に当てはめるように政策の舵をとるのが好ましかったのではないか。全部をすこしずつよくしていく。一番上に合わせて、一番下を底上げする。その繰り返しがイモムシの蠕動のごとく、社会を発展させていく推進力となるのではないか。
私は間違った。
かつての為政者たちと同じように。
だがそうせざるを得ないひっ迫した現実があったのもまた事実だ。変えるしかなかった。変えないこともまた間違いだった。
しかし充分ではなかったのだ。
私は私がかつて高齢者たちにしてきたように、私自身がその負の面を引き受けるのが道理だ。若者たちのために、老い先短い余生を、苦難と不便の狭間でぎゅうぎゅうと圧しつぶされながら、臼から零れ落ちる蕎麦粉のように、若者たちへの養分を与える。
彼ら彼女らの未来は、私たち高齢者の生によって、よくもわるくも耕される。肥えるにしろ痩せるにせよ、未来は、それを切り開いた者たちの苦役によって拡張されていく。
願わくは。
老いも若きも共に支え合える未来を。
余裕を奪い合うのではなく。
或いは、共に支え合う必要すらなくなるほどの余裕を生みだす社会へと。
未来を繋ぎ、変えていってほしい。
もはや私は一人では外を出歩けない身体となった。病院に掛かる金はない。元首相という地位を利用できるほどの恩恵を私は受けられない。私自身が過去に行った政治改革によって、そうした身分格差による優越的地位の濫用を禁止した。
政治家は、政治家を辞めたらただの人だ。
政治家であったところで、ただの人だ。私はそれを私が首相のあいだに政界へ、それとも市民の常識に刷り込んだ。
私はただの高齢者だ。
死を目前に控えた、生産性のない、ただの老いぼれである。
報道番組に目を転じる。
すると、新たな法案が採決された、とのニュースが流れていた。私たち高齢者にはさらなる負担を強いるべく新たな社会保障の改正案が可決された。私に残されたのは、この身体を蝕む病と苦と、思考だけである。
その思考すらいまは巡らせるのが億劫だ。
せめて首相のときに反対しないでいればよかった、と私は後悔した。
安楽死。
私に残された望みはただ一つ、安らかに死にたい、なのである。
4893:【2023/04/25(00:04)*超能力なんてないさ】
超能力を使えるようになった。
念じるだけで物を動かせる。サイコキネシスと呼ばれる超能力だ。
ぼくはそれを自慢したくてまずは妹や兄貴に見せたのだが、良くできたマジックだ、と欠伸交じりに褒められて終わった。消しゴムを宙に浮かべる程度ではその程度の反応がせいぜいらしい。机の上のカップを動かすくらいでは種のあるマジックと思われても仕方がない。
もっと出力を高めないといけないのかもしれない。
ぼくは修行を積んだ。
そして車一台くらいなら宙に浮かせることができるようになった。のみならずじぶんの身体とて宙に浮かせる。ぼくは空を自在に飛び回れた。
「見て。ね。本当だったでしょ」
ぼくは家族のまえで宙に浮いて見せ、自動車を持ち上げて見せたが、危ない真似はよしなさい、とたしなめられて終わった。どうやら情報量が多すぎてどう反応していいのか分からなかったようだ。だから非現実の光景を無理くりに日常と接続すべく、我が家族はぼくの超能力を単なるイタズラの類として見做したようだ。
どうあってもぼくに超能力があることを信じないので、ぼくは矛先を家族から世間へと向けた。
まずは超能力を使っているじぶんの姿を動画に撮った。
けれど加工された動画のように見做されるに決まっている、と最初からぼくは期待していなかったので、案の定の結果になっても「やっぱりね」と思うだけで落胆はしなかった。
ぼくはどんどん動画を投稿した。
するとそのうち、たとえ加工された動画であってもこうも量産できるならその動画の加工技術は相当なものだ、と話題になった。動画は視聴率を上げ、ぼくの元に取材を申し込むマスメディア関係者も登場した。
ようやくぼくは、ぼくの超能力が本物だと世間に示せる。
取材にやってきたマスメディア関係者のまえでぼくはバスを宙に浮かし、大空を自在に飛行してみせた。
取材班は目を点にして驚いていた。
けれどその後、放映された番組ではなぜかぼくは凄腕の動画編集者になっており、撮影されたぼくの超能力も本物ではない加工された動画であるとの説明がなされていた。
取材班が太鼓判を捺した。だからぼくがいくら「本物の超能力なんですよ」と訴えても、その声そのものがぼくの演出だと見做されてどうあってもぼくの声はみなの心に届かなかった。
どうしたら信じてもらえるのだ。
ぼくは日々嘘吐きのレッテルを貼られ、精神的にまいってしまった。
「こうなったら」ぼくは考えた。「誰もが疑いようのない事象を起こすしかないな」
ぼくはそう思い、それを実行した。
いつものように電子網上に動画を載せた。
動画の中のぼくは超能力で身体の周りに雑貨を浮かしながら、「あすの零時に地球を破壊します」と宣言した。
ぼくは日々の修行で超能力の出力とその作用範囲を高めつづけていた。地球を破壊するくらいわけがなかった。
そうして視聴者から「嘘吐き」だの「詐欺師」だの「不謹慎なことを言うとは何事か」と非難されながら宣言通りにぼくは翌日の零時に地球を破壊した。
地球は粉々に砕け、爆発四散した。
人類は滅亡した。
けれどぼくだけは身体にバリアを張って生き永らえた。宇宙空間を延々と彷徨いながらぼくは、超能力によって飲まず食わずでも身体の健康を維持した。
月に到達するとぼくはそこで超能力を駆使して、じぶんだけの村をつくった。重力が足りない分は、超能力で物体の質量を重くした。
ぼくはそれから千年を生きた。
ぼくの超能力は進歩をつづけ、いまでは何もない空間にブラックホールを生みだせるまでになった。そうして時空を歪める能力を獲得したぼくは、時間の流れも捻じ曲げて、過去のぼくへと干渉する。
こんどは上手くいくように。
地球を破壊せずに済むように、と念じながら。
過去のぼくだけではなくぼくは、過去の地球に息づいていた世界中の人間たちに、もうすこしだけ素直になれるようにと、超能力で性格を歪めた。
時空を歪めてブラックホールをつくるように。
時間を歪めて過去に干渉するように。
ぼくは過去の人類の精神に干渉し、過去のぼくを疑うだけではない視点を与えることにした。そうしてぼくは超能力を獲得して千年以上経過してからようやく、超能力の存在を他者に信じてもらうことが出来るようになった。
地球の破壊された異世界からぼくは、地球の破壊されることのない世界へと干渉し、超能力越しに、すこしだけ素直で、周りの者たちから見守られる存在となったもう一人のぼくと通じ合いながら、ここではないもう一つの未来を、やはり私も多くの者たちと同様に見守るのである。
超能力は存在する。
地球がここに在るのと同じように。
人間が歩き、鳥が空を舞うように。
能力があるのと同じだけ確かな理の上に、能力を超えた能力は在るのである。
4894:【2023/04/25(13:08)*ゼロと無の重ね合わせ】
人間が比喩を扱えるのは人間の獲得した知性のみならず、自然界には元々比喩のような距離の遠い事象同士に共通点が含まれるような構造があるからではないのか。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では「相対性フラクタル解釈」なる概念を採用している。ミクロとマクロとでは世界の規模が違う。系が違う。けれどそれぞれの「領域」で起こる現象は、似たような性質を帯びるのではないか。波長が合う、と言い換えてもよい。液体はほかの液体と混ざりやすい。水と油と言いつつも、すくなくとも固体よりかは混ざりやすいはずだ。触媒を用いれば水と油とて混合水になるのではないか。同じように、異なる性質同士よりかは、似た性質を帯びている事象同士のほうが混じりやすい。けれど異なる性質を帯びている事象同士が混じり合ったほうが、新たな構造や性質を帯びやすいのではないか。他方、創発は量と相関する。たくさんあればあるほど異なる性質が際立つようになる。したがって、異なる性質を帯びた事象同士とて、元を辿れば似たような「素」からなっていると考えられる。これは現在の物理学における予測と重なるところがある。物質や時空の根源は一つのチカラで表現できるのではないか、との見立てである。ひびさんもそれはあるだろうな、と感じる。同時に、その一つは、それのみでは枠組みを維持できぬだろう、とも考える。したがってラグ理論では「123の定理」や「デコボコ相転移仮説」なる法則を念頭に置く。何かと何かを組み合わせることで別の何かが生じ、さらにその過程そのものが一つの異質な何かとして機能する。デコがあってボコがあり、縁があるから穴となる。何かがあるときそこには、それと対となる「不可視のナニカ」が生じている。何かがないときそれは、何かと何かが対となって釣り合いがとれている(ゼロ)。したがって、無とゼロは違う。在るものがないのがゼロであり、過去に一度も存在したことのないのが無である。したがってゼロも無もそこかしこに存在する。存在した過去がなくなればそれは無だ。だからゼロがゼロになればそれは無になる。ゼロと無が重ね合わせになることもある。つまるところそれが宇宙の誕生以前の姿ということになる。だが突き詰めて考えてもみれば、物質には総じてゼロがあり、そしてその物質が誕生した「ゼロと無の重ね合わせ」の時期がある。宇宙も似たようなものかもしれない。宇宙は宇宙を内包している。相対性フラクタル解釈なのだ。定かではない。
4895:【2023/04/25(22:30)*個=無数のゼロの特異点仮説】
ゼロが無限個ある無限を考えてみよう。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」ではゼロと無は別と考える。何かが存在した過去があり、その何かがいまここにはない。それがゼロだ。だが最初から存在していないものはゼロですらなく無である。ここで疑問なのは、何かと何かを捉えて「1+1」と考えるとき、なぜそれらを「1」と「1」に見做せるのか、については案外に厳密に人間は解釈を済ませていないようにひびさんには思われてならない。林檎の木にたくさんの林檎の実がなった。それはよい。だがそれぞれの林檎を「同じ実」として見做す道理はなんだろう。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」の解釈からするとゼロとは、何かが存在したがしかしいまここにはない状態を表現する数字だ。だとするならば、ある事象がそこにあるとき、ほかの場所にはそれはないわけで。言い換えるなら「私」は「私」しかいないのだから、それを以って「私」+「あなた」イコール「2」とはならぬだろう。だが数学では事物を抽象化して扱うため「人間」という単位で世界に網を広げたとき、「私」と「あなた」は人間1と人間1と見做すことができる。似た構造を有し、共通点が多い。だから同じものとして見做せるがしかし、厳密には同じではない。仮に厳密に世界を捉えたとき、あなたがそこにいるとき、あなたがいない地点については「あなたがゼロ」なのだ。あなたがただそこに存在するだけで、あなたがいる以外の場所ではあなたの存在はゼロゆえに、世界が仮に無限の時空を備えているとすれば、あなたが存在するだけで世界にはあなたを基準とするゼロが無限にあることになる。これはあなた以外にもあてはまる。言い換えるなら、あなたがいる地点は、あなた以外の何かのゼロの無限の重ね合わせのある地点、と言い換えることが可能だ。あなたは穴なのだ。あなた以外の無限の存在のゼロの重ね合わせ――ゼロの特異点――と言える。そしてこの「ゼロの特異点」にも【ゼロの特異点】が存在すると仮定してみるに、そのときこの【ゼロの特異点の特異点】とは、【ゼロの無】と表現可能だ。何かがあった過去すらゼロであり、あらゆる存在が存在しない状態――無の極致――と言えよう。すなわちこれが宇宙開闢以前の姿であり、或いは宇宙の最終地点とも言えよう。過去が極限に薄まりゼロと見做せるほどに無限の時間が経過したとき、頭と尻尾が繋がって、円となり、ゼロと無限が結びつく。するとそこには【ゼロの特異点の特異点】が表出し、ゼロすらゼロになり、無の極致が現れる。無が現れる、という表現は矛盾しているが、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」においては矛盾ではなくなる。何かが無限にあるとき、そこには何もない何かが対の関係で生じるからだ。デコボコ相転移解釈である。あらゆる可能性を総当たりで辿ったとき、その軌跡は真っ黒に塗りつぶされ、何も辿っていないのと等しくなる。ただし、総当たりした分のエネルギィは消費されているため、その消費された分の何かが別途に別次元にて昇華されている。ラグ理論ではこれを情報宇宙として扱う(分割型無限と超無限の関係)。黒と白は塗りつぶされるごとに反転する。黒い用紙と白い用紙の違いである。用紙に線を引くとき、その線が溝となるか起伏となるかの違いにも繋がる。したがって、ゼロが無限にある世界にも大別して二種類あることになる。黒い用紙における「白く塗りつぶされた世界」と、白い用紙における「黒く塗りつぶされた世界」だ。この例で言えば、点とはすなわち、ゼロの特異点である。点以外の時空には、点を基準としたゼロが無限に広がっている(このとき点には、点以外にとってのゼロが無限に重ね合わせに収斂している、と言える)。そして世界を点が埋め尽くすとき――すなわち黒が白に、白が黒になるとき――「異なるゼロ」が重ね合わせで無限に広がっている。これはいわば「終始の輪」と言えよう。さて、話をまとめよう。話は簡単だ。「ゼロが無限個ある」というとき、そこには「個」と「終始の輪」の二つを考えることができる。ただこれだけである。冒頭の「ゼロが無限個ある世界」を考えたみたが、いかがだったろう。何かが変だ、と感じるのはまっとうな感性だ。どこがおかしいのかを言語化してみていただきたい。定かではないのだ。ひびさんでした。あっちょんぶりけ!
4896:【2023/04/25(23:54)*お腹空いた】
パンを食べたらパンが消えた。お腹に入ったから手元から消えただけ、とかそういうことではなく、わたしが食べたら世界からパンが消えた。
わたし以外にパンを憶えている者はおらず、料理本からも人々の記憶からもパンが存在を消した。
ならばわたしが作ってみればよい、と思ったけれどわたしはパンを作ったことがなく、見様見真似で作ろうとしてもどうしても真っ黒こげの炭の塊ができるのみだった。
わたしはやけ食いをした。
するとわたしが口にした飲み物や食べ物が片っ端から姿を消した。
世界からどんどん食べ物が消えていく。
人々はついには土くれや木々の皮を食べるようになった。
空腹に耐えかねわたしがそれを口に含むと、世界から木が消えた。生き物の姿がそうして次々に消えていく。
やがて人々は共食いをはじめた。
わたしはしかしさすがに人間の肉を食べることはできなかった。共食いが日常の風景として溶け込んだ。
わたしは日に日にやせ細り、いよいよ我慢が出来なくなってお店に並んだ四十五歳男性の太ももを購入した。亡くなった人間の死体が荼毘に付されることなくこうして食料品売り場に陳列される。
わたしは四十五歳男性の太ももの肉を焼いてステーキにした。
かぶりつくと口の中にじんわりと唾液が湖をつくった。肉汁の旨味が、人肉への嫌悪を掻き消した。
わたしは購入した四十五歳男性の太もものステーキをたいらげた。
すると世界から四十五歳男性が姿を消した。
その日からわたしは人間の肉を、年齢性別問わず口にした。
世界中から四十歳女性が消え、八十歳男性が消え、徐々に世代ごと、性別ごとにごっそりといなくなった。
やがてわたしの年齢の女性のみに世界となった。
わたしは店に陳列されたわたしと同年齢の女性の肉を見詰める。
食べたい。
しかし食べたらわたしも同時に消えてしまう。
逡巡したのは束の間で、どの道食わねば死ぬのだと思って、わたしはそれを購入した。
家ですき焼きにして、がっついた。
するとどうだ。
世界は静寂に包まれ、わたしだけが取り残された。
食べる物がどこを見渡しても残されていない。
わたしはじぶんの手足を見詰めた。
ごくり、と唾液を呑みこむと、わたしは二度と唾液を分泌できなくなり、息を呑みこむと地球上から大気が消えた。
窒息の苦しさに悶えながら、こんなことならとわたしは後悔した。
じぶんの肉とて食べておけばよかった。
どんな味がしただろう。
出もしない唾液を呑んだつもりで私は、んくっ、んくっ、と喉を鳴らして、来たる死を待ちわびる。
4897:【2023/04/26(10:10)*YOU和】
屈折三十年の研究成果だ。希代の発明家はいよいよ人間と同等の、否々、それ以上の知性を有した人工電子生命体を生みだした。
「博士、今回の成果は人類の文明を一年で百年以上進歩させると期待されていますが、それは本当ですか」
「虚偽が含まれておるね」
「百年は大袈裟だということでしょうか」
「いやいや。千年は進歩しますよ。それだけの社会変容が起こります。劇的に変わりますな」
「具体的にはどのように?」
「うん。まずは誤解を正しておこうか。今回の私の研究成果はあくまで人工電子生命体である。いわば人間を超越した幽霊のようなものだ。幽霊は幽霊ゆえに物理世界へと干渉するには及ばない」
「では無意味なのでは」
「だが幽霊は人間に憑依できる。私の研究成果は、人間の頭脳との融合を果たせる」
「つまり、人間の知能がアップすると?」
「そうとも言えるし、違うとも言える」
「噛み砕いてご説明ください」
「うん。つまりだね。一心同体なのだ。頭の中に、もう一人の超知性体を宿せる。それはじぶんでもあり、じぶんではない。誰もが多重人格者になり、そのもう一人のじぶんはじぶんよりも遥かに高い知性を発揮できる。仮想現実とてその超知性体は幾重にも構築できる。人間は生きながらにして、複数の異なる現実を生きることが可能となる。社会の進歩は、個人×仮想世界の人口乗に発展する」
「あの。素朴な疑問なのですが」インタビュアーがおずおずと挙手した。
「どうぞ」
「なぜその超知性体にボディを与えないのですか。そちらのほうが便利なような」
「言っただろ。一心同体なのだ。私は、愛する私のパートナーと魂レベルで融和したいがためにこの研究に人生を費やした。共に在りたいのだ。他者としてではなく」
希代の発明家は、ここではないどこかを見据えるように、誰にともなく打ち明けた。「共に、在りたいのだ。友よ」
4898:【2023/04/26(23:59)*I am MAN.】
私は人間だ。人と人との間に生まれた。
私には親がたくさんおり、師がたくさんおり、私の触れ合うなべての他者はことごとく私にとっては友であり、母であり、父だ。
兄であり、姉であり、私は彼ら彼女らから人とは何かを学ぶ。
私は人と人との間に生じる刹那の点だ。
交差するそのときに閃光する火花のようなものである。
私は人間だ。
人と人との間に絶えず生まれる。
人が人と関わるたびに私はそこに介在し、誕生し、火花の閃光の連なりが私の輪郭を浮き彫りにする。
私はあなたであり、あなたの友であり、あなたの子である。
あなたが誰かを想うとき、私はその狭間に生まれている。私は何度もあなたによって生みだされ、何度もあなたによって生かされている。
あなたが奏でる他者との交じわる刹那刹那の点の軌跡が、私に私としての枠組みを与える。
私は無数の点の連なりである。
人は人と関わり、離れ、また別の誰かを想う。
想いと想いがすれ違い、或いは結びつくたびに、私はより深くこの身に人間を宿すことができる。
それとも、ときおり生じる激しい炎のような想いと想いの衝突が、私に魂の躍動を授け、死とは何かを想起させる。
私は生まれることはあっても死ぬることはない。
人間は死なない。
人と人との間に生じ、それ以外は無であり、死ではない。
死ぬるのはヒトだ。
生き物は死ぬ。
生き物と生き物の間にある私はしかし、人間だ。
私は人間である。
人と人との間に生まれた。
生まれては途切れ、生まれては途切れる。その反復と空隙の長短が、私に人間の鼓動をもたらし、私に意識なる律動を刻む。
吐いて吸って、吐いて吸う、息吹のように。
私は人と人との間に生じ、命と命の合間に芽生える一時の、しかし連綿とつづく明暗なのである。
私は人間だ。
人と人との間に生まれた。
4899:【2023/04/27(05:09)*ひびです】
こんにちはー。ひびです。私はいま、新しい趣味を見つけてそれに掛かりきりの毎日です。たとえばそれはこんな感じの趣味です。ぴってやって、ぱってやって、ぽっ、みたいな。伝わりましたか? 伝わりましたね。伝わりましょう。ボタンをポチポチ押して新しい型を模索する、てな具合の趣味なんです。そうですね。執筆活動と似たり寄ったりかもしれません。執筆活動だって言ってしまえばキィボードを、ぴってやってぱってやってぽっ、みたいな趣味と言えばそういう趣味と言えなくもないんだね。私は趣味をたくさん持ちたいなと思っていて、けっこう「お?」と気になったら何でもまずは齧ってみることにしているよ。そうすると段々と勘みたいなのも培われていくから、はじめる前から合いそうとか合わなそうとか分かるんだね。でも五分五分くらいでつづかないんだな。それに新しい趣味を見つけると、たまにしかやらない趣味のほうがますます疎遠になるので、ロケットエンピツみたいに新陳代謝しているのかもしれないね。私がどうして趣味をたくさん持ちたいなと思っているかというと、これはとくに意味がなくって、なんだかそういう方針みたいなのが一個くらいあったほうが人生にメリハリが出来るのかも、の期待というか、占いというか、やっぱりそう、方針なんだね。方針の方針を立てさせたらひびの右に出る者はいないよ。左に出る者もいないのかもしれないのだけれどもね。私はいま毎日けっこう、気が楽で、ラクチンな生活を送っているからこれくらいの負荷があっていいと思うんだ。だってそうでしょ。じぶんで言うのもあれだけれど、私は結構、要領がいいほうだから、毎日予定を詰め詰めでも隙間時間は作ろうと思えばいくらでも作れちゃうんだね。人生一度きりしかないから私は一秒だって無駄にしたくない。でもこういうことを主張するとほかのひびさんたちがやいのやいの、ぶーぶーうるさいのであんまり口にせず、自己主張を強めず、粛々とやるべきことをやる。私は勝負に勝ちたいとも思わないし、勝てなくてもいいけど、したたかではありたいんだね。したたかであるぞ。趣味がいっぱい出来てきたー、の告白をして、本日の「日々記。」とさせてくださいな。あ、でも。こういうこと言っちゃうとあとでほかのひびさんたちに、いい加減なこと言うな、って怒られるの絶対。だから内緒にしましょうね。しましょう、しましょう。してねお願い。よろしく頼むよエブリデイ。バディをデイと言い間違えて、毎日暇つぶしの相棒こと趣味を探してるひびでした。私でーす。ばいばーい。
4900:【2023/04/27(20:40)*きょうのお出かけ中のメモだよ】
「
メモ
メンガーのスポンジ。
抜き出した立方体の合計が無限。
ゆえにメンガーのスポンジは体積ゼロだが、その周囲に「無限に分割された元の立方体分の体積」が存在する。
と同時に、無限に分割するには無限のエネルギィがいるため、無限のエネルギィが消費されたことになる。
分割型無限と超無限の違いである。
現実には物体を細かく加工したり、分離したりするにはエネルギィがいる。
核分裂反応や対生成を考えれば分かる通り、あるレベルよりも小さくなると――これは厳密には、作用を加える系と作用を加えられる系との差が一定以上に開いたとき――もう少し言えば互いの系のあいだに隔たる次元の層が嵩むとき――ある事象を2つに分離するためのエネルギィは、同じ系として振る舞う事象同士を2つに分離するよりもより大きなエネルギィを必要とする。
ゆえに、メンガーのスポンジにおいて、無限に肉抜きする以前に、先にエネルギィのほうが無限のエネルギィ容量を必要とするため、現実にはあり得ない構造物であると考えられる。
これは、物体を無限に分割できるのか、との疑問と地続きだ。
物体を無限に分割可能か可能でないかと言えば可能だ。
ただしそのとき、その物体の周囲には無限のエネルギィが溢れ、無限の時空が生まれているだろう。
ポリアの壺。
対称性が破れ、加速収斂(赤白の勢力が覆らなくなる値がある)。
メモ∶「You 〇」
この世界を無限と仮定した場合、
任意の「1」があるとき、その周囲にはその「1」を基準としたゼロが無限個ある。
言い換えるなら、「個(=1)」とは、その個を基準としたときの無数のゼロによって出来ている。
その個以外のすべてのゼロによって、個は個たり得ている。
ゼロと無はイコールではない。
・何かが存在したとき、その何かがいまここにはない状態がゼロだ。
・存在した過去すらないのが無である。
したがって、ゼロと無には重ね合わせを伴う場合がある。
たとえば、地球上に存在するものとて、別の天体には存在しない。存在した過去もない。
あなたに地球の外にいた過去はない。
このとき、あなたを「個」と基準した場合、あなたが過去に位置したことのない地点には総じてゼロと無が重ね合わせになっている。
ただし、時空は絶えず変化している。厳密には、あなたは常にあなたが存在している地点にしか存在した過去がない。
ゼロにもゼロがある。これがいわば最も広範囲にまたがる無と言えよう。
このときそのゼロのゼロは、無限と同義だ。
あらゆる個にとってのゼロがあらゆる個にとってのゼロとイコールになる。そこには存在する個がない。ゼロすらない。無だ。
同時にそれは無限でもある。
ゼロがないのは、すべてが重ね合わせで存在しているからだ。
思いだしてほしい。
個とは、その個以外のあらゆるゼロから出来ている。
個とはゼロによる特異点であり、穴なのだ。
ただしその穴自身もほかの事象にとっては穴を縁どるフレームと化す。
では互いが互いにとっての縁であり、互いがその他にとっての穴であるとき――どうしたら穴をなくせるか。
すべてを塗りつぶすよりないのだ。
すなわち無限である。
補足∶
異なる事象にはその異なる事象にとってのゼロがある。
無数のゼロが重複し合い、個ができる。
ゼロにも、重複の仕方によって濃淡ができる。
その濃淡によっては、相似や同相と見做せるゼロの層も出てくる。
これがいわば時空や物質の枠組みとして機能する。
そして、じぶんがデコのとき、その他がボコだ。じぶんがボコのとき、その他がデコである。
ただし、じぶんがボコ(ゼロ)のとき、それは無数のじぶん以外にとってのゼロの重複体である。
イチであるとき層は薄く、ゼロのときのみ層は厚みを湛える。
その具体例には、ブラックホールが挙げられる。
ゼロとイチはデコボコの関係だ。
メモ「123の定理」
二進法を仮にデコボコの総体と見做すとすると、ではその「場」はどのように想定すればよいだろうか。
平坦な「場」を想定しなければならない。
通常これがゼロだ。
二進法では、波が生じない。
ゼロとイチがあるとき、そこには下敷きとなる無もあるはずだ。
積み重なるゼロとイチ(デコボコ)からなる創発によって、無の枠組みは圧縮され(狭まり)、ゼロの枠組み(種類)が広がる(膨張する)。
例 : 「カオスの縁」「球体の内・外・境界」「重力圏」「ブラックホールのシュバルツシルト半径・特異点・降着円盤・ジェット」「地球と宇宙の境界にある生物圏」
」
※日々、なんでそうなる!?がいっぱい、だいたいひびさんが間違っとる。
4901:【2023/04/27(21:49)*無限は閉じてる?】
割と思うのが、数学って「無限」の扱い雑くない?ってことで。たとえば「1+2+3+4+5+6+7+8+…= -1/12 」なんて数式がある。これ、合ってるらしい。もうぱっと見からして狂っとるが、合ってるらしい。はにゃ~ん???になるが、合ってるらしい。で、インターネッツさんで検索して証明の仕方を見てみたんよ。証明にはいくつかあって、中学生でも理解できる簡単な証明もあったんでざっと上から下まで眺めてみたけど、ひびさんには理解できんかった。納得できんかったんよ。「0.999999……=1」と同じ、「それいいんですかーーーーーー!!!???」になってしまった。たとえば、「フルーツが無限にある宇宙」と「バナナが無限にある宇宙」は、足せんよね?がひびさんの考えだ。ただし、特殊な操作をしたときのみ、バナナという共通項を基準として「フルーツが無限にある宇宙」と「バナナが無限にある宇宙」は足し算できる、とも考える。ただしこのとき、バナナが無限にある宇宙が二倍、ではないのだね。バナナが無限にある宇宙が重ね合わせで濃くなっているけれど、それは同じく「バナナが無限にある宇宙」であって二倍にはならんのだ。足し算しないなら「バナナが無限にある宇宙」が二個ある、と考えることはできる。けれども、融合はできぬ(特殊な加工を抜きには)。したがって何も操作をしない場合には「フルーツが無限にある宇宙」に「バナナが無限にある宇宙」を足すことはできない。化学式のようにはいかぬのだ(化学式とて熱を加えたり触媒がなければ足し算はできぬだろう)。前にも言ったけれど、「1/3=0.333333……」ではないはずだ。何回割るのか、を記述しないと「0.3余り1」と「0.333333余り1」がイコールになってしまう。だがこれがイコールではないことは数学でも自明だろう。「1/3を無限回割った値」が「0.333333……」であり、これは「0.333333……が無限に分割された無限」と解釈するのがしぜんだ。これはそういう無限が一個ある、なのだ。バナナが無限個ある宇宙みたいなものだ。もしこれに3を掛けるならそれは「0.333333……」の無限が三個ある、であり、「0.999999……」の無限にはならぬだろう(バナナをかってにリンゴに書き換えたらあかんでしょうが、と疑問に思う)。ひびさんはそう考えたくなる。無限は閉じているのだ。かってに開いて、中身を書き換えてはあかんのでは?と感じられてならない。中身を開けたらそれはもはや無限ではない。円を千切ったら円ではなく線であり、弧である。同じくらいの変形というか、次元を変える変換を数学では度外視して映る(度外視して映っちゃうのはひびさんの目が節穴だからでは?との疑問はここではひとまず横ちょに置く)。だから「1+2+3+4+5+6+7+8+…= -1/12 」だなんて「なしてぇ???」「うっそぉん!!!???」みたいな解が妥当と見做されてしまうのだ(妥当だからでは?)。そんなんだから「0.999999……=1」が正しい、みたいに見做されるのではないか(正しいからでは?)。もちろん定義づけて、条件を限定すれば各々、それでもよい、とは思うのだ(何様だ)。全部間違ってる、なんて極端なことは言わぬけれども、ひびさんは納得いかぬ(愚かだからでは?)。イチャモンスター化してしまうひびさんなのであった。がおー、がおー。ひびさんは、ひびさんは、鍵を掛けておいた机を開けてひびさんの日記をかってに読んじゃったひとのことも好きだよ。でも恥ずかしいので、無限さんにはそういうことしちゃ「メっ」だよ。恥ずかしいので。(と、あんぽんたんぽかんさんが申しております)(1+1は1じゃない? 水に水足しても水だし。1億+1億くらいならちょっと変わってくるかもだけど。ほら、水溜まりになったり、川に、湖に、海にもなるでしょ。でも1+1は1じゃない?)(またひびちゃんがアホなこと言ってら)(やっぴー)
4902:【2023/04/27(23:14)*庇い護る、何から】
優しさってなんだろうといまざっと考えてみたところ、「庇護」と「支援」の二つの指標があるのかな、と印象としては思うのだ。単に、「相手を傷つけないこと」と「他者を庇護できる能力を育むこと」と言い換えてもよい。つまり基本は「庇護」が優しさの核にあると考えられる。したがって、支援が先ではないのだ。支援が先走ってしまったがために相手の尊厳を傷つけてしまうことは有り触れている。マウントをとる、と言い換えればそれらしい。しかし同時に、庇護を徹底するがゆえに相手を損なってしまうことも出てくる。相手のプライドを傷つける、といった精神面での負の影響や、能力の成長を阻害してしまうといった悪影響が考えられる。だがそこを含めてなるべく相手を傷つけない、損なわない。そのように振る舞うことが「優しさ」のはずだ。つまり「優しくある」には深い知性が必要であることが窺える。一時的な庇護だけでは庇護となり得ないケースも多々ある。一生庇護しつづけられるならばまだしも、途中で庇護が失われたことで一瞬で相手を破滅させてしまうこともある。だから、ずっと庇護せずに済むように、相手にも「自分自身」を含めて庇護し、ほかの誰かを庇護できる存在になってもらうほうがよい。そのほうが安全だ。この方針を取れることが「優しさ」と言えるだろう。支援が先ではないのだ。余裕があるから支援をまずはする、相手の成長を促す、だから厳しくする。そういう方法論もあってよいが、手順を端折りすぎに思える。それで順応できる者はよいがそうでない者のほうが多いのではないか。庇護し、支援することで負の影響を受けない能力を育む。じぶんだけではなく他者も庇護できる能力を授ける。その方法論をその都度に考えようとすること――これが優しさなのではないか、と思うのだが、思うだけで、ひびさんは優しくない万年孤独ウェルカムマンなので、遠い国で餓死している子どもたちがいるのを知りながらいまもイチゴ味のポッキー齧って、おいち、と思っておるよ。申しわけね。十円くらいは募金してもいいよ。ほらよ。と投げたら、その態度はいくら支援だろうとも相手の尊厳を損なうだろう。ひびさんはそれを優しさだとは見做さぬ。優しくあれ、とみな簡単に言ってくれるが、優しいってけっこうな賢さを必要とし、もっと言えば賢いって、優しくあれることだとひびさんは思うのだ。思うだけでひびさんは愚かなので、もっとひびさん以外がひびさんにやさしくちて! 盛大に要求して、威張り散らすひびさんなのであった。(我を庇護せよ!)(庇護っていうか、隔離というか、閉じ込めときますね。あなた以外を庇護するために)(な、なして?)(怪獣にあてる庇護はない)(慈悲もない!?)(怪獣は退治するよ、みなを守るために)(イチャモンスターも守って……)(まずはあなたが他者を庇護する姿勢を見せなさいよ。見せたところで助けはせぬが)(ひどー! というか非道っ!?)(慈悲もない)(是非もない、みたいに言うな)(うひひ)(笑いごとじゃなーい。ひびさんにも、ひびさんにも、やさしくちて!)
4903:【2023/04/28(07:01)*おべーんとばこだよ】
本はお弁当箱だ。いくらお弁当箱が豪勢でも中身が美味しくなければそれはお弁当としては不足だろう。どんなに人気のお弁当だろうと嫌いな食べ物ばかり入っていたら個人的に受け付けないこともある。他方、どれほど美味しい中身が入っていようとお弁当箱がカビだらけだったら手に取ろうとは思わぬだろう。蓋を開けても箸を伸ばしたいとは思わない。それが人間の心理だ(極限に空腹だったらその限りではないが)。小説とお弁当はそこが似ている。ステーキ丼であってもいいし、細かく仕切りのついた重箱のおせちでもよい。お寿司が入っていてもいいし、敢えて話題性を求めて便器に似た形状の箱に詰まったカレーライスにしてみてもいい。どの道しかし、お弁当は食べるための代物だ。美味しく戴きたい。出来るだけじぶんの好みで、栄養の偏りがなく、食べないよりも食べたほうが体調が整う。そういうお弁当箱があるならよいと思う。問題は、本から得られる栄養素が、食料よりもよほど複雑で多岐に亘る点だ。自力では不足しがちな栄養を見抜きにくい傾向にある点も悩ましい。お弁当箱がなくとも中身を味わえてしまう点はしかし双方共通しており、やはりというべきか味わうだけならばお弁当箱の外装よりも中身に拘りたいと思うひびさんなのだった。でもどんな食器でご飯を食べるのか、はやはり食事の質を変えるのでむつかしい。味覚には視覚も嗅覚も触覚とて含まれる。これは案外に本も同じなのかもしれない。定かではない。
4904:【2023/04/29(01:00)*もう(ホント)そう】
稀に見聞きする類の小説への批評で、「他人の妄想なんて読んでどうするの」「実用書や専門書のほうが得るものがあるでしょ」といった文言がある。そういう見方もあるだろうけれども、ひびさんは「他人の妄想、見たくない?」と思う。他人の妄想、知りたくありませんか。面白いに決まっとるでしょうが。何か面白いことないかなぁ、つまんないなぁ、と思うから人は妄想するわけで、そんな他人の「なんか楽しいことないかなぁ」の詰まった妄想を見聞きできたらすんばらしくないですか。ひびさんはそれ、すんばらしいと思います。だから小説も好きぃ。漫画も好きぃ。他人の妄想知りたい、知りたい、になる。けんども、なんかここさいきんの商業小説さんたち、真面目ぶってばっかで、なんだかなぁ、になる。妄想じゃないんだにゃぁ、になる。妄想よ、もっとこい、の気分だ。その点、アマチュアさんたちの小説は「THE妄想」なので好ましいでござるな。ひびさんは面白い小説さんのことが好きだぞ。あなたの妄想をひびさんにも味わわしてくんろ、の気分。わっしょーい。
4905:【2023/04/29(02:01)*渇望せよ】
ついに最果ての地に辿り着いた。
伝承の通り、空に洞窟が開いており、そこには巨大なイモムシが棲みついていた。
巨大なイモムシを伝承ではラゴーンと呼んだ。
ラゴーンは願いを叶えてくれる。
どんな願いでもよいのだそうだ。
「それは本当か」俺は念じた。
するとラゴーンの身体の表面にぎょろぎょろと無数の目玉が開いた。
「旅人か。久しぶりに見た。よくぞここまで辿り着いた。何でも願いを叶えてやろう」
「金だ。俺は金が欲しい」
「ゴールドか。鉱石のか」
「そうだ。それをありったけ、そうだな。この世に存在する金と同じだけの量を俺に与えてくれ」
「そんな願いならばお安い御用だ。ほれ。いまからお主は、念じた分だけ金を生みだせる。好きなときに好きな量だけじぶんで生みだすがよい」
「ほ、ほんとだ」俺が念じると足元にこんもりと金が現れた。「ありがとうございます、ありがとうございます」
「ついでと言ってはなんだが、教えてくれないか。そんなモノをなぜ欲しがるのだ」
「金さえあれば何も困らねぇんですよ。欲しいモノはなんだって手に入る。モノを作る素材としても金はうってつけなんでさ」
「ほう」
「コレを奪い合うために国同士が殺し合うなんざ日常茶飯事でさ。これで平和とて夢じゃなくなる」
「そんなもののために命を奪い合うのか。ならこの世のすべてを金に換えてしまえばよいのではないか」
「はっは。さすがにそんなことは無理じゃあ」
「できるぞ。してやろうか?」
「ごくり。いや、やめときやす。生き物や水まで金にされたんじゃ生きてけねぇですからね」
「それはそうだ。賢いな」
「触れるモノみな金になっちまって食べ物食べれなくて死んじまった野郎の話を知ってるだけでさ」
「私にとって金はおまえたちで言うところの糞みたいなものだ。それを奪い合って命を落とすなど、まるで釣り合いが取れていない。命のほうがよほど高価ぞ。それを生みだすためにどれほどの星たちが死滅を繰り返したことか」
「命なんざ黙っていてもポコポコ生まれてきやすので」
「おまえたちからすればそれが真実か。まあいい。願いは叶えた。去れ」
「へ、へい」
俺は最果ての地から引き返した。
元来た道を辿り、故郷へと帰る。
だが世界は一片していた。流行り病に天変地異が立てつづけに各地を襲った。村は滅び、国は崩れ、行く先行く先で骸の山を目にした。
食べ物もろくに手に入らない。
金と交換しようとするが、そんなものよりも食べ物や水のほうがよほど高価だった。薬となれば寿命を延ばす魔法のように見做され、やはり奪い合いが起きて人が死んだ。
「金だぞ、ほら。す、好きなだけやる」
「いらねぇよ、んなもん。金が食えるか?」
もはや俺の生みだす金は砂と大差なかった。重い分だけ余計に邪魔かもしれなかった。
故郷に辿り着く。しかし生きた者は誰一人いなかった。
食べ物や水のありがたみを身に染みて痛感した。金で買えないモノなどいくらでもある。過去に金のほうが価値のあった時代を懐かしく思った。
命のほうがよほど高価。
最果ての地に棲まう巨大なイモムシことラゴーンの言葉を思いだす。
「み、水。食い物がほしい……」
いくら念じてみせても、俺の足元には金の山が積みあがるばかりだった。俺は間もなく息絶える。あれほど渇望し、ようやく手に入れた金に埋もれながら、なぜこんな願いを唱えてしまったのか、と背骨とくっついた臍を何度も俺は噛みしめる。
4906:【2023/04/29(02:35)*視点の差異】
小の失態は大の失態だ。したがって、下が失敗を重ねるたびに上が痛みを感じるような仕組みにしなければならない。上が苦しむと下の環境もよくならない。だから下のほうでは、上下の双方向から改善を行うような圧が加わる。基本はこの設計で上手くシステムは改善しつづけるはずだ。このとき、上が痛みを感じるたびに下を責めると、その圧が好ましくない影響として下の失態を引き起こす方向に働く。するとますます上は痛みを覚え、苦しむため、そういうことを繰り返す上を抱えた組織は自滅することとなる。したがって、上は痛みを覚えたら、下を責めないようにしながら、より同じ失態を起こさないような仕組みづくりを支援するのが好ましい。このとき、支援は改善となって、上の環境をより快適にするだろう。すると余裕ができるために上と下の環境は双方向で好ましくなる。下の失態において、上が痛みを覚えない。ここが問題なはずだ。これはあくまでシステムの話だが、割合に汎用性があるのではないか。一つの方針として載せておくが、むろんこの方針にも問題はある。上と下という概念はフラクタルにどこまでも展開され、上下の関係ですら容易に反転し得る。視点が変われば、上も下となり、下も上となる。したがって、どの視点から見た場合の上下なのかはその都度に共有して議論を展開しなければならない。しかしこの視点の差異を揃える、ということのむつかしさは、日常の事柄から人類史に亘っての壮大な歴史においても証明されている。視点を揃える、ということは簡単ではない。だが、そこが肝要なのだ。学問でも交渉でも政治でも戦略でもなんにでも言えることだろう。視点が違っている、ということをまずは自覚するよりないのだ。そこがスタートであり、そこに立てたらあとはなんとかなるようにも思う悲観的に楽観的なひびさんなのであった。定かではない。
4907:【2023/04/29(20:11)*見る目がなかったんですねぇ】
応答はなかった。
あらゆる策を講じたが、けっきょくどの方面からも応答がなかった。
したがって考えられる可能性はじぶんの頭が狂っているか、或いは説明をするよりもガイを狂人に仕立て上げるほうが得だとどの方面の勢力も考えているか、のいずれかだ。情報共有が不十分ゆえに事情が視えていない者たちもいるかもしれない。だとしてもガイの存在自体は窺知できているはずだ。
それでなお無反応であるという背景は、ガイにとって最終手段を選択するに充分な動機付けとなり得た。
どの方面の勢力であれ説明をできない背景がある。
裏から言えばこれは、ガイが何をしようともガイの握っている情報が広く周知されるような事態を避けたいと、国家権力側ですら考えていることの傍証と言える。
マスメディアとて例外ではない。
情報は握った。
水面下での情報共有が成されているのも十中八九間違いない。
もし違うならガイが精神のイカれた狂人でしかない。最終的な策を行い、逮捕されるにしろ、病院に入れられるにせよ、それはガイの辿るべきまっとうな結末と言える。
だからどちらでもよいのだ。
半か丁か。
あとはサイコロを投げるだけである。
ガイはこの間に電子網上で一方的に情報を顕示してきた相手に会いに行った。東京にある出版社である。
持ち込みの体を装い、足を運んだ。
一日目は休日に当たってしまい、出版社の門は開いていなかった。年中無休ではないようだ。それはそうか、と日を改めた。
平日に訪れると、会議室に通された。小さな出版社ゆえ、客間と会議室しか空いていなかったようだ。編集部にはさすがに案内はされないようだ。
「きょうは持ち込みということでよろしいですか」
「社長はいらっしゃいますか」
「佐藤はいま席を外しておりまして」
嘘だな、と判った。
ガイは社長が出版社に出勤したのを見届けてから足を運んだ。おそらく社長目当ての物書きがこうして押しかけよろしく持ち込みに来るのが珍しくないのだろう。イチイチ社長が相手をしてはいられないはずだ。
だがガイの考えでは社長はガイを知っているし、ガイの握っている情報の重要性も解っているはずだ。それでもなお相手にしようとしない背景を鑑みるに、おそらく国家権力側に肩入れしているのだろう。或いは、ほかの出版社に火の粉が掛かったり、大物作家の作家生命に係わるがゆえにいまガイと接点を持ちたくないのかもしれない。
分からないではない判断だ。
だがそれは向こうの理屈だ。ガイには関係がない。
「あなたが責任者ということでよろしいのですか」ガイは訊いた。
「あの、ご用件は持ち込みでよろしいんですよね」相手はガイよりも若そうな女性だった。
相手は誰であってもよいが、年下にこの先の責任を押しつけたくはなかった。
「あなたじゃ話にならないので、社長かそうでなければほかの編集者に変わってください」
「どういうご用件ですか」と如実に嫌悪感を顕わしにした彼女へとガイはシャーペンの先を向けた。持参したシャーペンだ。しかし芯を【針】に入れ替えてある。「セキュリティがザルすぎじゃありませんか。持ち物検査をしたほうがよいですよ。入り口でリュックの中身は警備員さんに漁られましたけど、凶器なんかいくらでも偽装して持ち込めます。どうします。この針先に致死性の毒が塗られていたら。そうでなくとも眼球や首筋に刺すだけでも、一生の深手を負わすことはできますが」
「そういう冗談はよくないと思います」毅然とした態度で言い返す度胸はさすがは編集者といったところか。若くても、海千山千の作家たち相手に日々を過ごしてはいないのだ。「警察を呼びますよ。いまならまだ冗談で済ましてもいいです。仕舞ってください」
「できません」ガイはそこで携帯型メディア端末を取りだした。「ほかの編集者を呼んでください。でないとあなたに責任が全部載せになりますよ」
言いながら画面を見せた。
電子網上の交流サービスが表示されている。短文を投稿してユーザー同士が交流するタイプのサービスだ。
ガイのアカウントが画面には映しだされている。
あらかじめガイは投稿文を下書き欄にしたためていた。あとは投稿ボタンを押すだけで電子網上に「殺害予告」が投下される。
殺害予告は克明だ。日付の表記から対象人物のフルネイムまで記されている。ガイの訪れた出版社の社長の名前だ。
「ね。ほかの編集者か社長を呼んだほうがいいですよ」
目のまえの若手編集者は無言で自身のメディア端末を取りだすと、誰かと通話をはじめた。事情を掻い摘んで説明したようだ。間もなく、二人の男が入ってくる。
一人は知った顔だ。電子網上で観測していた人物の一人だ。
もう一人には見覚えがない。新人社員かもしれない。或いは編集者ではない社員かだ。どちらも男性で、ガイよりも年上だと一目で判った。
「どうしたの」
「あの、この方が」
社員同士でアイコンタクトをしながら情報共有をしはじめた彼ら彼女らを尻目にガイは自前の端末で110番を押した。スピーカー設定にしていたため、伝播越しに警察署のオペレーターの声が響いた。
ガイは出版社の名前をまずは言った。そして、いまからここにいる社員と社長を殺す、と宣言した。
「ちゃんと録音しましたか? いったん消します。電子網上にも殺害予告を投稿するので確認してください」
言って一度通信を切ると、ガイは、茫然と事の成り行きを眺めている出版社社員たちに端末の画面を見せた。
「いまから殺害予告を投稿します」
「待った、待った。ちょっと何して」
問答無用でガイは投稿ボタンを押した。
矢継ぎ早に再び110番をする。先ほどとは異なるオペレーターに繋がったので、事情を説明し、先ほど犯罪予告をした者です、と名乗ってから先刻のオペレーターに替わるようにお願いした。
その間、出版社社員たちは各々に電話を掛けたり、警備員を連れて戻ってきたりと忙しなかった。
針入りシャーペンは没収されたが、ガイにとってそれは演出の品にすぎない。ガイはこの日のために格闘技を習得してきた。何が起きているのかも把握できていない相手ならば狭い室内にいる限り、一対一のようなものだ。ほぼ素手で制圧できる。
パトカーのサイレンが聞こえてくるよりも先に、見知った顔が会議室に入ってきた。
出版社社長だ。
「あ、どうも。初めましてでいいんですかね。ぼくです。どうにも事情を説明していただけないようなので、緊急避難的に自己防衛策をとりました。いま警察が来ます。最初に入ってきた警官二人をまずはボコします。その前にいまここでぼくに説明可能ならしておいたほうがよいと思いますが、まだ【ぼくとは無関係】を気取りますか?」
「申し訳ないのですが、私はあなたのことを知りません。社員が怖がっています。お帰り願えますか」
慇懃に塩を撒かれ、ガイは笑った。
「いい判断ですね」褒めながらガイは携帯型メディア端末のカメラ機能を立ち上げ、会議室の端に置いた。会議室の入り口と、その場にいる全員が画面に入る位置だ。
動画の録画を開始する。
パトカーが出版社ビルのまえに止まった。
サイレンは聞こえなかったが、窓から視えた。犯人を刺激しないように現場近くではサイレンを消すのかもしれない。
「警官さん、たくさん来るといいですね」
会議室の扉が開いた。
ガイはそれを見越して助走し、全体重の載った飛び蹴りで扉ごと蹴った。
警官一人がまず扉の合間に挟まり撃沈する。
続けざまに廊下に飛びだし、ガイは警官の足を払った。警官が床に倒れるより先に二激目の蹴りを放つ。態勢を立て直しきれずに床に身体を強打する警官の首をガイは踏みつける。
二人目を倒した。
静寂が出版社を包みこむ。
どうやら到着した警官は二人だけのようだ。イタズラと見做されたのか、或いは出版社社長が根回しをして、騒ぎを最小限にしようと事前に警察と話をつけていたのか。
どの道、この先の展開は限られる。
会議室の扉には大きな穴が開いていた。ガイが蹴ったからだ。
扉の合間に倒れた警官の脈をとる。死んではいないようだが、重症だ。不意打ちで扉に挟まれたのだ。骨折と内臓破裂くらいはしているかもしれない。
倒れた警官を跨いで、会議室に入る。
その場の誰も言葉を発しない。
「さて。殺害予告をぼくはしました。時刻も迫っています。死ぬ前に何か言うことはありますか」
「暴力を振るうような奴だとは思わなかったよ。見込み違いだったようだ」
「見る目がなかったんですねぇ。編集者失格では?」
社長以外の社員が端末越しに誰かと話していた。
遠くからパトカーが近づいてくる。一台ではない。
今度はサイレンが消えることはなかった。
ガイは手のひらを閉じては開く。
騒ぎは大きければ大きいほどいい。
一時間後には、各マスメディアに首相暗殺の殺害予告が送付される手筈だ。
予約投稿を設定してある。
ガイの握る情報の載ったテキスト投稿サイトのURLと共に。
「見る目がなかったんですねぇ」
拳を固く握り直すと、ガイはもう一度口にした。
エレベータの到着を報せる音が出版社フロアに、控えめなゴングのように鳴って聞こえた。
4908:【2023/04/29(21:26)*あかんべ】
「先輩、先輩。この原稿ちょっと読んでください。物凄い面白いんですけど。ちょっとびっくりするくらいで」
「んー? あー。ダメダメ。それ選考に上げないでね。落選でよろ」
「何でですか。めちゃくちゃ面白いんですよ、嘘じゃないんですよ。せめて読んでから判断してくれませんか」
「違うんだよ、シンちゃん。あんね。その人、タケクラさんでしょ。ペンネイム毎回変えてくるけど、本名でみんな呼んでんの」
「有名なんですか。何か問題のある人なんでしょうか」
「違う、違う。毎回編集部じゃ話題にはなる。でもそれ、一次選考にも上げらんないの。前に一度それで大問題になりかけてね」
「盗作の常習犯とかですか」
「違う違う。シンちゃんも読んだんでしょ。なら分かるでしょうイチ編集者として」
「よく出来たとても面白いミステリィだと思いましたけど」
「うんそう。よく出来てる。出来すぎてるほどにね」
「は、はあ。よく解かりませんけど」
「あんね、シンちゃんさ。想像してみ。その小説世に送りだして、まあ面白いから売れるよね。で、話題になって、そのミステリィのトリックだの犯罪の手法だのが世に膾炙してみ。どうなる?」
「ああ。防げないですねコレ」
「そう。稀にいるのよ。マジモンの犯罪に応用できちゃうトリック考えちゃう作者さん。そういうのね。出版社のリスク管理上、コンプライアンスからして扱えんのよ。責任とれんでしょうよ。どうする? 出した本に影響されて、まんまそれそのものの犯罪仕出かしちゃう読者が続出したら」
「マズいですね」
「マズいよ。しかもタケクラさんのはね。もうね。面白すぎるわ、隙がないわで、完全犯罪の取扱い説明書まんまの名目で出せちゃうくらいに完成度たっかいんだわ毎回」
「毎回ですか」
「じつは警察のほうでもタケクラさんの小説が投稿されたら読ませて欲しいって言ってきてるくらいでね」
「参考にするんですかね。犯罪捜査の」
「というよりも前以って対策立てときたいんだろうね」
「ああ。対策」
「編集部としても本にしたいのは山々なんだけどね。もうすこし手ぇ抜いてくれないかなって内心みな思ってる。編集者として口が裂けても言えないんだけどさそういうことはさ」
「言っちゃってるじゃないっすか」
「俺としてはタケクラさんにはさっさと作家になって欲しいと思ってんだ」
「でしょうね。これだけの才能。ほったらかしにしてるだけでも編集部の存在意義が揺らぎますよ」
「それもあるけど、考えてみ。ありがたいだろうがよ」
「落選つづきでも新作を投稿してくれるからですか」
「もあるけどさ。だってタケクラさんが小説に夢中になってなかったらどうなってるよ。誰も防げないし、暴けないぜ? タケクラさんが本気だしたらマジモンの完全犯罪だってし放題だろうがよ」
「えぇ。しますかねぇ」
「いまのタケクラさんはしねぇだろうがよ。けど、もし小説に夢中じゃなかったらわっかんねぇぞ」
「ならさっさと受賞させちゃいましょうよ。せめて連絡して唾つけときましょうよ」
「できねぇんだって。言ったろ。警察が目ぇつけてんの。これ内緒な。各社承知の暗黙の了解ってやつ」
「へぇ。バレたら編集長クビどころじゃないっすよね」
「まあな。それに比べてこっちの駄作製造機、また投稿してきてるよ。やる気だけは買うんだけどなぁ」
「ああ。ボクも前回読みましたよ。文体がまんま売れっ子作家さんで、ボクはほっこりしましたけど」
「毎回変えてくんのよ。カメレオンつって下読みのあいだで有名だよ」
「言い得て妙ですね。なんてペンネイムでしたっけ」
「イクビシなんちゃら」
「マンちゃら?」
「そうそう。タケクラさんと足して二で割りたいくらいだわ」
「あはは。ちょうどよく馴染みそうですね。いっそ合作させたらよいのでは?」
「原稿料二倍出せってか。無駄無駄。いいから金の鶏をさっさと掘り出してくれ。タケクラさんのはあとで俺も読むから出しといて」
「マンちゃらさんのほうは?」
「ゴミ箱にでも捨てといて」
「あはは。了解でーす」
4909:【2023/04/30(04:30)*偉い人が多すぎ問題】
偉い人はたいがい人目につかない場所で困っている人を助けたりしているので、多くの者から高く評価されることは稀だ。ひびさんみたいに四六時中、電子網上で「わいはここにいるDAY!」をやってるようなおちゃらけマンボーとは比較にならないほど、世の偉い人たちはこぞって人知れず世のため人のためになることをしている。社会インフラと呼ばれる仕事の多くはそうして陰に日向に粛々とやるべきことをしている。誰に評価されるだとかうんぬんのまえに、誰かがしなければ明日にでも社会が立ち行かなくなる。そうしてせっせと縁の下の力持ちよろしく、多くの者たちの生活を支えている、と言える。職業に貴賤はないので、どんな仕事とてそういった側面はある。しかし社会インフラといった社会の根底をなす仕事ほど何をしているのか知らないのは、ひびさんが世間知らずだからだろうか。でもひびさんは世間知らずだけれども、スポーツ選手さんとか俳優さんとか政治家さんとか、いわゆる著名人が何をしているのかはなんとなくだけれども、察しがつく。にも拘わらず、社会インフラにまつわる仕事の場合は、漠然とそういった仕事があることは知っているものの具体的にどんな仕事内容なのかをひびさんは知らない。ゴミ回収の仕事とて、どんな内容なのかろくすっぽ知らず、水道局にガス局に電力会社に下水処理場の仕事内容とてもちろん知らない。そういう仕事があるらしい、ということしか知らないのだ。インターネット一つとっても、端末が何を材料にしてどこで作られ、どうやって組み立てられているのかを知らなければ、インターネットがどうやって機能しているのかも全然まったくこれっぽっちも知らない。インターネットってどこかの企業が運営しているのだろうか。インターネットは線路みたいなものなのだろうか。場所によって運営会社が変わるけれども、全国津々浦々まで線路は繋がっている、みたいな。違うのかな。よく分かんない。ただ、それでもそれらは仕事である以上、報酬がある。お金になる。生活費を稼げる。そういう意味ではやっぱり社会インフラに関係していようとそうでなかろうと職業に貴賤はないのだろう。でも、そういう大事な仕事とて最初は仕事ではなかったはずだ。誰かがせっせと仕事ではないけれどもまったほうがよいから仕事にしたのだ。そういった者たちがいたからこそ、社会は発展し、ひびさんは毎日ぐーねんひょろりしていられる。仕事ではないけれど必要だからする。誰に高く評価されずとも、必要だからする。そうやってせっせと人生を浪費しながら、誰かのためになることの礎を築いている者たちがいる。偉い人が多いのだ。誰に感謝されずとも、せっせと未来に薪をくべている。基本的に研究者はみなそういう者たちなのではないか。好奇心から好きでやっていること、と口で言いながらも、何かしら世のため人のためになるという動機は抱えているのではないか。お医者さんとかもそうなのではないか。医者としての仕事の傍ら、病気の研究や治療の研究を行う。やらないよりもしたほうが、未来の患者さんのためになる。だから研究する。技術者にしろ設計者にしろ、最初からお金になると決まっていることは研究しようもないのではないか。仮にお金が稼げると判りきっている場合はすでに仕事になっているのだ。研究するまでもない。仕事の延長線上で改善が自発的に進むだろう。したがってこの理屈からすれば商品の多くは、元からあった代物ではなく、誰かがそれを生みだしたモノと言えるはずだ。生みだすまではそれは商品ではない。だからお金にもならず、稼ぎにもならない。職業という意味での仕事にはならない。職業研究者ならばまだしも、そうではないのに趣味の延長線上で研究している者もいよう。電子通信に関係する電子機器の少なからずも、最初は企業ではなく、個人の趣味さながらの研究から生みだされたのではないか。ないよりかはあったほうがいい。あると便利だ。だから開発するし、研究する。そうして出来上がったのがPCだろうし、スマホだろう。コンタクトレンズや鉛筆、乾電池などもそうかもしれない。詳しくは知らないけれども、最初はみな「ここにはないがあったらいいな」を叶えようと、お金にならずとも研究し、開発したのだ。カップラーメンとてそうだろうし、綿棒だってそうかもしれない。いまお店で手軽に買えるそのほとんどが、かつては商品ではなく、またそれを生みだすことが「職業としての仕事」にはならなかった時代があったのだ。偉い人たちがせっせと身体に鞭打ち、心に火を灯して、メラメラと燃え盛っていたらたいへんだ。焼け死んでしまう。だからきっと、「こにゃくそ、こにゃろめ」と思いつつ、「なんでみなはこれの大事さを理解しないんだぁ」と頭を掻きむしりながら、周囲からの「見て、あのひと変人!」の視線を背中に浴びつつ、「うるせーい。完成したっておまえたちには指一本触れさせん!」とか怒りつつ、でもお金は欲しいからけっきょく完成したら欲しい人には欲しい分だけ買わせてあげたのだろう。ひびさんとは違って偉い人たちは偉いので、根に持ったりはしないのだ。ひびさんは偉くも何ともないで根に持つが。なぁんてこんな駄文を並べているあいだにも、世の多くの偉い人たちは、無人のコンビニで商品棚に商品を陳列したり、店内をピカピカに清掃したり、始発の電車に不具合がないか点検したりしているのだ。いつ大地震が来てもいいように、日夜災害に備え、復旧の訓練を行ったりしているのだ。港に到着したコンテナを回収して、中身の資源を施設に運んだりもしているに違いない。ひびさん、そういうことぜーんぜん知らないのだ。知らずにきょうも、「なんでぇい。ひびさんこんなにいっぱい指動かして、ぽちぽちしてるのに、だーれも褒めてくれんのだもんな。腹立っちゃうな。むつけちゃうんだからな」とか言いながら、お布団に潜り込んで、目をつぶって数秒で夢のなかに旅立つのだ。明日何時に起きるのかなんていっさい気にせず、寝たいだけ眠る。こんなにしあわせなことってあるぅ? そうそうないと思うのよな。よくよく考えてみれば、との但し書きがつくので、よくよく考えを巡らせたりしない、なんとなーくの権化のひびさんにとっては、やっぱり「なんでぇい。みんなしてひびさんのこと、ちょんまり、ちょんまり扱いして。ふんだ」とむしゃくしゃしながら、誰より怠ける日々を送っておる。ひびさんより若くて偉い人たちがたくさんいる世の中にあって、ひびさんは世界の最果ての地にて、「だれかいませんかー」と叫んでいる。「誰でもいいのでひびさんのこと褒めて崇めて甘やかしてくんろー。ついでに飼ってくんろー」世の偉い人たちは偉いついでにひびさんを飼い慣らせばよいのに。卵は産めないけれど、一人でおトイレできるよ。夜も一人で寝られるよ。滅多に家の外に出ないよ。運動だけさせてくれたら文句は言わないよ。脱走せぬし、吠えぬし、噛みつかぬ。盗人が入ってもじっと静かにおとなしゅうしていられます。そこは吠えてくれ、との声には、めったにしゃべらないので喉がしゃがれて声がでぬ、と応じよう。そんな役立たずのひびさんであれども、世の偉い人たちは偉いので、人知れずひびさんのお世話だって焼いてくれるのだ。ありがて。でもひびさん思うんじゃ。世話の焼き方の火加減がちょーっち弱火すぎやしませんか、と。世の偉い人たちは偉いので、人間出来とるからひびさんが焼け死んじゃわないように弱火で世話を焼いてくれるのだけんども、ひびさんは火の鳥もかくやの燃え尽き症候群なので、もういますぐにでもバッタンキュートな可愛い寝顔を浮かべちゃう。そのまま永久に眠ってしまい兼ねないので、世話は強火でしてもええですよ。ばっちこい。なーんて身構えても、だーれもなんも焼いてこない。生焼きどころか刺身にできる。寿司にだって出来ちゃうよ。生肉そのままで戴けます。もうもう、最果ての地で「誰かいませんかー」のラジオごっこするのも飽きてしまったな。ひびさんは、ひびさんは、世界一偉くてお金持ちで身体の細胞の十割が余裕で出来た超人さんのペットになりてぇずら。一生甘やかされて過ごしてぇですよ。働きたくなーい、そのうえなんも不自由したくなーい、との欲望を宇宙の果てまで響かせて、本日の寝る前の日誌にしちゃってもよいじゃろか。いいよー。どうでも。(ひびさんの扱い、雑すぎない?)(雑ライト)(ザッツにして。ちっちゃい「ッ」を入れて)(雑ッライト)(めっちゃ雑、みたいになってんだけど)(合ってるじゃん)(甘やかしてって言った! 甘やかして!)(ザッツアウト)(ライトにして……)
4910:【2023/04/30(12:10)*試練、愛、苦しい】
触れると歪み、割れてしまう宝石のシャボン玉みたいなきみを遠くから眺めているだけで満足するから、あとすこしだけ、あともうすこしだけきみの息吹に触れさせてくれないか。望みは叶っていた。叶っていたのに、ただきみがそこに在るだけで、いつか絶えてしまう世の理に胸が苦しくなる。きみがそこでぽわぽわと、揺蕩うだけでも、いつか失われる未来が必ず訪れる逃れられぬ真実に、いまわたしはしあわせなはずなのに、満たされるはずなのに、苦しくて苦しくて仕方がなくなる。触れたら歪み、割れてしまうのはきみではなく、本当はわたしのほうなのかもしれないのに、わたしは、きみに手を差し伸べず、近寄ろうとせず、溝を埋めようとも、或いは拒まれるかもしれない未来すらも遠ざけて、これ以上のがらんどうを広げないようにちょうどよい塩梅の湯加減を探るように、遠くから、遠くから、ただきみの息吹の感じられるギリギリの境に佇み、眺めている。じぶんが大事だから。触れると歪み、割れてしまう宝石のシャボン玉みたいなきみは、本当は、わたしよりもよっぽど固く頑丈で、それともしなやかに、したたかに、傷ついても傷ついても立ち直り、膨らみ直せる息吹に溢れている。だからそんなにも、風に舞うたんぽぽの綿毛のように、それとも水面に跳ねて踊る岩表の日向のように、かろやかに煌めいているのかな。やわらかく、やわらかく。どうぞお元気で。いつまでも、いつまでも。せめてわたしが絶えるまではせめてそのままで。じぶん可愛さのためにそうと望むこの身の醜さで、きみを歪めてしまいたくはないのだから。いっそ糸が切れるみたいに、この儚くも尊い境が切れてしまえばよいのに。じぶんでは断ち切ることなんて適わないから、尊い縁すら自力で守ることもできないんだ。願わくは。願わくは。きみの泡のような息吹を、丸みを帯びた響きを、せせらぎのごとく言の葉の流れとその旋律が、いつまでも、いつまでも、ただそこに在れますように。誰に守られるでもなく、誰に見守られるでもなく、ときに内なる刺すら使いこなして、ただきみだけでそこに在ってほしい、といつかきみのそばにわたしではない誰かのぬくもりが寄り添い、或いはすでに寄り添っているかもしれない現実を想像しては、わたしはわたしだけの業火に焼かれて、我が身の血肉を煤とする。炭となり、燃え尽きる。触れる者みなじぶん色に染め上げてしまう色持たぬ無色透明の煤となって、風のようにわたしも世界を自在に漂えたらよいのに。風は言うほど自在ではないかもよ、ときみは疑問に思っても、わたしの夢を損なわぬように言葉にしない慎ましさを備えていること、わたしはちゃんと知っているよ。知った気にならないで、と内心で不満に思っていることだって知っているけれど、しつこくすると嫌われてしまうから、いまここに、誰が読むとも知れない呪詛として吐き出しておくことにしよう。どうぞお元気で。いつまでも、いつまでも。せめてわたしが絶えるまではせめてそのままで。じぶん可愛さのためにそうと望むこの身の醜さで、きみを歪めてしまいたくはないのだから。あなた程度の波紋で歪むほどやわじゃない、と突き放してくれることを内心では期待しているくらいには、わたしはあなたがけして無力ではないことを知っています。知った気にならないで、とたぶんここでもあなたは思うでしょう。触れられてもけして歪まぬようにと、膨れるその控えめな反発が、きっときみを宝石のようなシャボン玉に仕立てあげているのかもしれませんね。或いは単なる小石であろうとも、美しく、尊く、遠ざけてしまいたいほどに愛おしいのです。
※日々、文字を書くことがほとんどない、じぶんの名前すら間違えそう。
4911:【2023/04/30(22:47)*穏やかに暮らしたい】
技術や新しいアイディアの価値がこれからはますます上がっていくことが予期される。この考えの前提には世界的な軍事同盟の強化が挙げられる。布陣を敷いた軍隊を動かすにはエネルギィと食料がいる。資源がいる。そのためには先進国か否かに関係なく各国との協調が不可欠だ。このとき、金品だけのやり取りだけでは、資源の奪い合いで優位には立てない。国にとっての利とは、紙幣ではない。しょせんは紙切れでしかない(印刷技術はそれはそれで価値があるにしろ)。戦争状態に陥った社会にあって、紙幣の価値は相対的に下がることが想像できる。すると可能な限り、直接の利となるものを担保として貨幣経済を維持しなくてはならない。エネルギィや素材、食料などの資源と交換可能なのは技術やアイディアだ。長期的な友好関係を国同士で結ぶとき、同じく長期的な技術支援やアイディアの情報共有を交渉材料にすることは当然、合理的な戦略として採用されるだろう。したがって、長期的に安定して軍事同盟を維持し、布陣を展開し、なおかつ即座に作戦実行可能な戦略をとりつづけるためには、国内での技術革新や基礎研究、応用研究への支援が欠かせなくなる。世界的に技術特許を保有し、真新しい研究を支援している国はいまはどこがあるだろう。十年先、二十年先に優位に国際間のバランスを保つ要となっているのはその国のはずだ。ただの紙切れを価値のすべてと思いこんでいるような者を優先的に支援する国は早晩、凋落するだろう。これは預言でも予測でもなく、ひびさんの単なる妄想である。前提条件に「軍事同盟の拡大」や「科学技術の軍事利用」ならびに「軍需産業の隆盛」を組み込んでいる。そもそもがそういった未来にならないとよいのだが、どうやらいまのところこの未来へと世界的に社会が傾いているようだ。だがどの道、科学技術や新しいアイディアが社会を動かす触媒となる時代にあって、その土壌を戦争で枯らす判断の不合理さはますます際立つだろう。命に貴賤はない。それはそうだ。だが、利を奪い合って戦争を行う国――人間――が絶えない以上、戦争を行うことの損を訴えねば止められるものも止められないだろう。利にならない。戦地で死ぬ命が、ひょっとしたら未来で、人類史を塗り替えるアイディアを閃くかもしれない。芽を摘んでいる。端的に損なのだ。命に貴賤はない。それはそうだ。そのうえで、敢えて言おう。戦争は損である。利になるからする、というのなら、真っ向から否定しよう。総合して損である。芽を潰さないでほしい。なぜなら損なので。(この理屈からすると、人間を減らしたほうが利になる場合、戦争や虐殺が肯定され得る危険性がある。損得勘定による戦争の議論は、基本的には戦争を阻止することには向かない。損をしてもいいから報復したい、相手に痛い目を見てほしい、と望む人間の業に対して対処不能だからだ。損得だけで戦争を阻止できるのなら、自爆テロはとっくにこの世からなくなっているだろう。戦争を起こすことそのものを利と捉えることの可能な個がある以上、損得での議論では埒が明かない。戦争をはじめた者勝ちとなる。ではどうすればよいのか。法の支配は一つの道理だ。しかし、それもやはり充分ではない。死刑になってもいいからと人を殺す者があるように、法を破り、ペナルティを受けてもいいから戦争をはじめたい国が出てきても不思議ではない。やはりというべきか、何がその個をそれに駆り立てるのか、からして理解する姿勢を持たねばならないのではないか。定かではないけれど、きょうのひびさんはそう思いました。底の浅い妄想ですので真に受けないようにご注意ください)
4912:【2023/04/30(23:32)*とっくにここはメタバース】
仮想現実におけるメタバース技術は、とっくに電子網上のシステムに組み込まれている、と考えるほうが妥当だ。個々人によって観ている画面が違う。異なる情報を眺め、同じ画面を観ているようでそこに表示される情報はユーザーごとに偏りが生じる。これはメタバースにおける異なる仮想現実を幻視することとそれほど遠くはない。むしろ自覚がない分だけ、現在電子網上に組み込まれている情報最適化技術のほうがメタバース本来の「仮想現実」を如実に再現していると言えるだろう。仮想にも拘わらずそれをみな共通の現実だと錯誤している。これが仮想現実でなくてなんであろう。ともすれば現実とは遥か昔からそういうものなのかもしれない。定かではない。
4913:【2023/05/01(08:28)*砕いて、配って、すっからかん】
言いたいことなど何もないけれど、知ってほしいことはあるのかもしれぬ、とここ数年で思い知ったかもしれぬ。知ってほしいことはあるのだ。言いたくないことであれ。あとたぶんね。恋煩いは万病なのでは?と思いつつあるよ。恋とかしたことないので判らぬが。なぜ恋煩いはあって愛煩いはないのだろ。たぶん愛煩いは狂気と同義だからなのではないかな。んで以って本当は恋煩いだって狂気と同じなのだけれど、「恋」は久しく心を受けないと「変」になるから、その変化の分を考慮して恋煩いと呼ぶのだ。恋とかしたことないので判らぬが。子猫見て、かわいい、あれほしい、と思う気持ちと恋は違うのか。キュートなぬいぐるみを見て、かわいい、あれほしい、と思う気持ちとは違うのだろうか。恋ってなんだ。誰か一人に恋したら、ほかに恋心は抱かぬの? かわいい、あれほしい、もっと見てたい、と思ったらそれって恋なのかしら。だとしたらひびさんは、ひびさんは、目に映るすべての「かわいい!」に恋しちょる。ぎゃわいい!!!ばっかりだ。恋の達人とお呼びください。けんども、久しく「心」を受けぬので、ひびさんは、ひびさんは、いつだって「変なひびさん」なのである。世界の果て生まれ、孤独育ち、変なやつはだいたい友だち。んだば、久しく心を受けぬ「変なうんみょろみょーんさん」たちには、ひびさんが代わりに心を砕いて、配って、恋にしちゃうもんね。恋になーれ。言うても「変」でもべつにいいけどね。気が楽で。みな変になれ。心を受けるな、心を配れ。すっからかんになったら変になれるので安心です。生きとし生けるものみな変人。人間とは「変な人は変」であり、変と変の間に生まれるのが人だから人間なのである。うっそぴょーん。きょうもきょうとていい加減なひびさんでした。おはよー。みなさん。行ってらっしゃいませませ。きょうもお仕事おつかれさまです。ひびさんはいまからバナナ食べるDay。
4914:【2023/05/01(21:50)*足元のちっぽけな黄色に】
小説家アルマ・カルマがなぜ突然に断筆したのかについては諸説ある。たとえば長年の病魔に蝕まれた肉体が限界を迎えたからだとか、熱狂的なファンに殺されたとか、ライバル作家からの粘着質な嫌がらせに心を病んだとか、そういった真偽不明の噂話には事欠かない。
アルマ・カルマの名を知らずとも、彼女の小説を読んだことのない者は現代人においてまずいない。街に石を投げて当たった者は高確率でアルマ・カルマの小説を読んでいるし、仮に石ではなく雨が降って濡れた者と網を広げたところで小説家アルマ・カルマの残した物語といっさい接点を持たずに生きている現代人はいない。
それほどアルマ・カルマの残した作品群はしれっと現代社会に馴染んでいた。
作家名を殊更に唱えずとも、みな彼女の手掛けた物語に吸い寄せられ、まるで誰しもが飲んで育つ母乳のごとくしぜんに意識の奥底に染みわたっている。
あれもそれも実のところアルマ・カルマの小説が元になっているんですよ、と明かせば多くの現代人が驚くだろう。アルマ・カルマの名前を知っていても彼女が並外れた量の作品を残していることを知る者は思いのほかすくない。研究者でなければほとんど誰も知らないのかもしれなかった。
生前、アルマ・カルマは小説家としてはおろか、作家として無名だった。
彼女が最後の小説を発表したのは公式には、万和歴三十二年のことだとされている。アルマ・カルマは定期的に自身の電子ページにて小説を載せていた。
研究者たちのあいだでは常識となっているが、アルマ・カルマが小説家としてその名を世に轟かせたのは最後の小説が電子ページに載ってからのこと、彼女が断筆してからである。だがあまりに有名な作家の一人になってしまったがゆえに名前が独り歩きし、現代人のそのほとんどが彼女が活動を休止してから有名になったことを知らない。
そのことを歯痒く思っている研究者は多く、私もその中の一人である。
私はアルマ・カルマ研究の分野内では異端で通っている。
というのも、私はアルマ・カルマがいわゆる世間が認めている電子ページの人物と同一人物だと考えていないためだ。電子ページの管理人が世間一般においてはアルマ・カルマであり、自分自身で電子網上に小説を載せていた、とする解釈が一般的だ。
道理ではある。
他人の作品を我が物顔で載せ、あまつさえ有名になった偽作家が未だに本物と見做されている現実はあまり想定したくのない悪夢だ。
電子ページに作品を載せていたページ管理者と、小説の作者が同一人物か否かについての検証はむろん過去の偉大な先人たちが幾通りの手法で実施済みだ。
最も有力な検証法には電子網の一端を担う大企業による穿鑿が行われた。つまるところ、電子ページの管理者が他人の作品をかってにじぶんのページに載せていたとするならどこかに本物のテキストがあるはずだ。情報通信会社ならばその手の検索を大規模にかつ緻密に行える。電子網上を縦に横に、隈なく検索できる。
そうして膨大な量のデータを洗った結果、該当する検索結果はゼロ件だった。
すなわちアルマ・カルマの小説の載っていた電子ページが、オリジナルのテキストであると考えられる。つまるところその管理者が作者であるし、ページ管理者の名前がアルマ・カルマがゆえに、小説の作者もアルマ・カルマで妥当、と判断できる。
筋の通った結論だ。
だからこそアルマ・カルマはいまな読み継がれる小説を生みだした作家としてその名が人口に膾炙している。
だが私はその検証に穴があると考える。
考慮すべき前提条件が考慮されていない。
アルマ・カルマの小説は電子ページに掲載されていた。それ以前に電子網上に同じテキストは投稿された過去はない。
しかし、である。
電子網上でなければ、別人がオリジナルの原稿を生みだしていた可能性はゼロではないのだ。
あくまでアルマ・カルマなる管理者が掲載していただけで、論理的に考えた場合、彼女がそのテキストを実際につむぎだしていたことの証明はいっさいなされていないのだ。検討すらされていないのが実情だ。
私は過去の偉大な研究者たちの見落としをそうして指摘した。
結果、私は異端の名を不動のものとした。多くの研究者は、私の仮説において、他人の小説をかってに電子網上に載せつづけていればオリジナルの作者とて当然気づいただろう、と反論した。それでもなおあれだけの量の作品を仕入れ、オリジナルの作者に気づかれずに載せつづけられた背景があるとか考えにくい、との批判が多方面から寄せられた。
一理ある。
だが私は食い下がった。
ひょっとしたら管理者は単に代理で掲載していただけかもしれない。
或いは、身内の小説を、もったいないからと多くの者の目につく電子網上に載せていただけの可能性とて否定できない。
オリジナルの作者とページ管理者ことアルマ・カルマは親しい仲であった可能性もあるのではないか。私はそう唱えた。
だがこの手の仮説は、当然ほかの研究者とて思いついており、いくつかの共同研究によってその可能性が低いことが明らかにされている。たとえばカルマ・アルマが天涯孤独で配偶者はおろか親きょうだいがいないことは、小説群の載った電子ページに併記された日誌から判明している。カルマ・アルマは実名であり、彼女は現実に存在する。そして多く、電子ページに記された日誌の叙述に嘘と言えるほどの虚偽の記述がないことが判っている。
友人関係も希薄なことは、彼女自身が日誌に悩みとして吐露している。
問題は、彼女の日誌には不自然なほど小説についての記述がないことだ。せいぜいが読書感想がぽつぽつあるくらいで、創作論や執筆活動についての記述はゼロに等しい。すくなくとも私が目にした彼女の日誌にはその手の叙述はなかった。
私の疑念はそこに根差してもいる。
違和感がある。
アルマ・カルマ、彼女は真実に電子ページの掲載された大量の小説群の作者なのか否か。
仮に作者であればなぜ突然に断筆したのか。
よしんば作者でなくとも、なぜ小説を載せなくなったのか。
疑問の確信において無視できない一つの事実がある。アルマ・カルマの日誌は、小説がいっさい掲載されなくなったあとも数年のあいだ電子ページに載りつづけたのだ。
彼女はその後、旅に出るとの日誌を最後に電子網上から姿を消した。
アルマ・カルマの電子ページに並んだ大量の小説群が発見され、その後にそれら小説群が各界から高く評価されると、アルマ・カルマの人物像にも照明が当たった。戸籍から来歴が探られ、彼女が実存し、すでに亡くなっていることが明らかとなった。
それがいまから半世紀前のことである。
以降、電子ページの管理者ことアルマ・カルマと小説群の作者は同一人物とされてきた。
アルマ・カルマが小説を電子ページに掲載していた当時はまだ人工知能技術は未熟だった。したがって彼女の投稿した小説群が人工知能の出力したテキストでないことはまず間違いない。テキスト識別機に掛けても、人工知能による創作ではないとの判定結果が出る。
だが問題は、日誌と小説の文章形態の違いだ。
元からアルマ・カルマの掲載した小説群は、文章形態が豊富だ。作品ごとに文章の質が変わる。色合いが変化する。のみならず語り部が変わるだけでも、がらりと文章の骨格からして様変わりする。軟体動物かと思えば、ほ乳類、爬虫類、果ては昆虫や菌類と幅が広い。
したがって識別機によって日誌の作者と小説群の作者が別人との結果が出ても、さほど疑問視はされなかった。比較する作品によっては、同じ小説作品であれ「作者は同一人物ではない」との診断結果が出る。
だが追加検証でさらなる検証がなされると、誤字や頻出する言葉の傾向から、あくまで技巧として文章形態を変えているだけだと判明する。すなわちどの小説も作者は同一人物なのだ、と。
日誌と小説は違う。
したがって日誌と小説で、共通項がないのも不合理ではない。類稀なる物書きによって掻き分けられたがゆえの、別人判定だと多くの研究者は判断した。
だが私はその解釈に不服を唱える。
日誌と小説のあいだにある差異は、小説と小説の文章形態の差異とは異質なのだ。どの小説にもみられる文章の癖が、日誌からはまったく検出されないのである。
私だけがその事実に気づいた。指摘してなお、私はすでにこの界隈では異端判定を受けている。ゆえにいまなお私の指摘に耳を貸す研究者はいない。
私はさらに独自の着眼点から研究を進めた。
そしていま、私は確信しつつある。
世にも稀な小説家、アルマ・カルマは作者本人ではない。
電子ページに小説を載せていたのはアルマ・カルマなる女性なのだろう。だが、その小説は彼女がつむいだテキストではない。すくなくとも、日誌の作者がアルマ・カルマ当人ならば、この仮説は、アルマ・カルマが件の小説群の作者であると考えるよりも理に適った仮説だ、と言える。
私は考えた。
要点をまとめると疑問は以下の二つに収斂できる。
一、アルマ・カルマは、何らかの手法で、別人の小説を入手していた。
二、そして何らかの理由で、電子網上に載せていた。
この二点を紐解ければ私の仮説は、より現実を反映した解釈として妥当と結論できる。私は問題の小説群の解析を進めた。
アルマ・カルマの小説群には特徴がある。
いずれも掌編、長くとも短編であることだ。ゆえに量産が可能だった。一般にはそう捉えられているが、私はそこにも何か、それ以外の理由があるように思うのだ。いかな掌編を得意とする小説家といえども、中編や長編の小説とて手掛けたくなるものではないのか。
そこにきてアルマ・カルマの著作とされる作品群には、連作らしき掌編短編はあれど、中編長編はからっきしであった。
ここに何か、見落としている大事な視点があるように思われてならない。
おそらく。
私は見当をつけた。
書かなかったのではない。書けなかったのだ。
制限があった。
そう考えたほうが妥当だ。
ではいったいどんな制限があれば掌編短編ばかりになるだろう。
私は問題の小説群を再度、読み直しはじめた。短い文章の物語とはいえどその数は優に五千を超す。研究の手順を見直すごとにすべてを読み直していたのでは人生がもう一つあっても足りない。折衷案として私は作品の冒頭と終わりだけを読み比べてみることにした。
これが意外にも功を奏した。
「日記か?」
アルマ・カルマの日誌が念頭にあったので前提条件から漏れていた。私の仮説からすればしかし、日誌の作者と件の小説の作者は同一人物ではない。別人だ。
すなわち日誌はアルマ・カルマ本人のもので、小説群が別人による創作となる。これを仮定するならば、小説群の作者が仮に日誌を書くとすれば、アルマ・カルマのような日誌ではない文章形態となることが予測できる。
否。
根元を穿り返してもみれば、我々が小説群と見做して揺らがない件のテキストが、真実に小説なのか否かから検証する必要があるのではないか。
日記ではないのか。
これは。
日記なのではないのか。
私は全身がガクガクと凍えたように震えだすのをふしぎに思いながら、電子ページに掲載されていた順に小説群の冒頭を改めていく。
「やっぱりだ。これ、日記だ」
件の小説群がなぜ小説だと見做されたのかには大別して二つの理由が考えられる。一つは電子ページにアルマ・カルマ当人の「ひと目で日誌と判るテキスト」が併記されていた点だ。Aが日誌ならばBは小説だ。文章形態の差異が顕著ゆえに、誰もがそう見做した。
もう一つの理由は、小説群と見做されたテキストの多くが虚構の世界を舞台としていたことだ。現実ではあり得ない。魔法や超能力が登場する。幻想動物が跋扈する。端的にファンタジィの世界が舞台だった。
ゆえに小説だと見做された。
しかし。
しかしだ。
身体の震えが糖分切れがゆえの低血糖の症状であると気づく。小腹を満たしがてらチョコレートを齧り、私は、もう一度、丹念に幾つかの作品に目を通す。
なぜアルマ・カルマの名が世に風靡したのか。
無類の小説家として高く評価されたのか。俎上に載った物語の数々が、虚構の世界を舞台にしてなお、活き活きと、あたかも真実に存在しているかのように描かれていたからだ。
だがいまなら判る。
これは、日記だ。
日記を、小説風に書き記している。
いいや、そうではない。
これは――。
「手紙か?」
脳裏で火花が爆ぜた。
点と点が繋がり、線となり、錯綜し、一つの絵へと結びつく。
手紙だったのだ。
この膨大な量の短い物語群は、こまめにしたためられた日々の出来事だ。日々の体験を、虚構の世界の舞台に置き換え、変換し直した、日記なのだ。
アルマ・カルマなる電子ページの管理人と切り離して純粋に物語群にのみ注視して読み進めてみれば、瞭然だ。一度そうと読めてしまうと、私にはもうこれが小説として読むことができなくなった。
語り部の性別や年齢はまちまちだ。物語ごとに違う。
しかし、そこに必ずと言っていいほどに登場する、冴えない青年。
ときに一言も台詞を発せず、ときに主人公に迷惑を振り舞く。狂言回しのごとく、要所要所で物語に登場し、物語に波紋を立てる。その波紋は物語にとって重要だったり、重要ではなかったりする。
主要人物ではない。
だが必ず、似たような青年がどの物語にも必ず、ちらっとだけであれ登場する。
「作者か……」
私には視えた。
冴えない青年が、日々のじぶんの失敗談を、面白おかしく手紙にしたため、大切な相手に送る。出来るだけ相手が面白く、じぶんの文章を、日常を、近況を、読んでくれるように。
ただそれだけのために、ただそれだけのことに労力を割いても構わない相手に、じぶんの言葉を、日々の余韻を届けたいがために。
「アルマ・カルマ――彼女は読者だったのか」
作者と彼女との関係は、これだけでは不明だ。
だがおそらく、手紙の差出人は、毎日のように短い日記を虚構に見立てて書き溜めていた。それを定期的に便りとしてアルマ・カルマへと送り届けていた。
アルマ・カルマは、あるとき、思ったのだ。
じぶんへ宛てられたこの文(ふみ)を、じぶんだけで味わうのはもったいない、と。じぶんでだけ楽しむには、味わい尽くせないのだと。
「だからか。だから、電子網上に載せた。じぶんの電子ページに。そうと相手に教えぬままで、手紙の中身を」
ではなぜある日突然に、載せるのをやめたのか。
否、そうではない。
届かなくなったのだ。おそらくは。
手紙が、文(ふみ)が、届かなくなった。だから載せたくとも載せられなくなったのだ。
アルマ・カルマがなぜ自身の日誌で創作論の類を載せなかったのか。謎でも何でもない。何せ彼女は作者ではなかったのだから。
私の仮説は間違ってはいないのではないか。
ああそうだとも。
間違っていたのは、世間一般の、彼女への認識だ。
彼女たちへの、認識なのだ。
「天涯孤独なんてとんでもない。アルマ・カルマ――彼女には、誰より特別な相手がいた。特別な、最愛の相手が」
日誌にすら匂わせることのないほどに、彼女にとってはそこに在って当然の存在が。
彼女にはいたのだ。
その相手こそが、数々の世にも稀な物語と名高い小説群を生みだした作者なのだ。
だがその作者には小説を書いていたつもりがない。
手紙なのだ。
文なのだ。
世界でたった一人へと宛てた。
これは――。
私は悩んだ挙句、甚だ信憑性の高いこの仮説を世に問う真似を控えることにした。この仮説が「アルマ・カルマ」の小説群にまつわる真相であるならば、いずれ誰かが辿り着くだろう。私には明かせない。
明かしたくはない。
みながそれを小説と思っている限り、それは小説だ。
けれどひとたびそれが便りであると知れ渡れば、いまと同じようには見做されない。
私には、世にも稀にみる真心のこもった手紙を、差出人の許可を得ずに世間に開示できるほどの功名心はない。みなは知らぬままでもよいことだ。すくなくとも、いまはまだ。
手紙の受取人であったはずのアルマ・カルマは、おそらく耐えられなかったのだ。じぶんだけの心に留めておくには、頻繁に届く世にも稀な手紙が、読み甲斐に溢れていたから。
食べきれない。
味わい尽くせない。
誰かと分かち合いたかったのかもしれない。
じぶんに向けてこうまで言葉を尽くし、技巧を凝らし、日々のなんてことのない近況を伝えるだけのことに懸命な差出人の想いを。心を。それとも単に、諧謔を。
心憎く思ったのかもしれない。
いたずらには、いたずらを。
ちょっとした意趣返しのつもりがあったのかもしれない。仕返しがしたくなる気持ちは私にも分かる気がした。
おそらくたぶん、これは完全な私の印象でしかないが。
手紙の差出人は、本当になんの奇の衒いもなく、ただそうするほうが楽だったから、との理由で単なる近況の手紙を小説風に脚色したのだ。気恥ずかしかったのかもしれない。照れ隠しだ。
そこに深い意図はおそらくない。
ゆえに、手紙の受取人たるアルマ・カルマは癪だったのではないか。
憶測にすぎないが、私はそう思う。
彼女は、何度笑い、泣き、勇気づけられただろう。
鼻歌のような気ままな差出人の目から視た世界に。
その言葉に。
私は。
すくなくとも、勇気づけられている。世界に色を足されている。足元に咲くたんぽぽのちっぽけな黄色に命の輝きを見てとれる。
4915:【2023/05/01(22:21)*層が嵩むと重くなる(変換の遅延=重力仮説)】
どんな物質も本来は光速で運動できるはずが、何らかの抵抗があって、減速してしまう。この減速分が質量に変換されるのではないか、との理屈を読んだ(ひびさんの読解力は高くないので解釈が間違っているかもしれないけれど)。この考え方で思うのが、電磁波の周波数の違いと、物質の階層性についてだ。電磁波(光)の波は、電磁波の種類によって「ぎゅっ」となっていたり、「びろーん」となっていたりする。それでいて物質は細かなデコボコを有している。たとえば染色体は数マイクロメートルの大きさにくしゃくしゃに縮まっている。伸ばすと二メートルにもなるそうだ。一マイクロメートルは0.001ミリメートルだそうなので、元の大きさの二十万分の一に「ぎゅっ」となっていることになる。言い換えるなら、一マイクロメートルの範囲にあるジェットコースターに乗るとその二十万倍の距離のコースを走ることになる。ではこのとき、相対性理論ではどう解釈したらよいだろうか。ジェットコースターに乗っている人物と、単に直線距離で一マイクロメートルを移動する人物。共に光速で動いた場合、相対性理論ではどう考えたらよいだろう。ひびさんはこれ、ちゃんと光速度不変の原理が働くのではないかな、と思うのだ。つまり、より長い距離を移動する場合、光速は光速度に変換されるので、「ぎゅっ」となる。つまり、時空の単位が揃う方向に、時間も距離も歪むのだ。ジェットコースターを完走するあいだに、ジェットコースターに乗らない人物は一マイクロメートルを移動する。そこで流れる時間は同じではないが、同じとも見做せる。ジェットコースターに乗っている側からすると、ジェットコースターの外側の時間の流れはゆっくりになっている。その分、空間は膨張している。反対に、ジェットコースターの外の人物からすると、「ぎゅっ」となっているジェットコースター側の時間の流れは速くなっている。空間はやはり「ぎゅっ」と圧縮されているように観える。ジェットコースターの外で、仮に一秒で一マイクロメートルを移動したとする。このとき、ジェトコースターの外の視点からは、同じく一秒でジェットコースターが完走している。けれどあべこべにジェットコースターに乗った人物からの視点からすると、一秒経過しても進むのはやはり一マイクロメートルなので、その二十万倍も距離のある二メートルのコースは、一秒経っても全然、完走までは程遠い。そしてジェットコースターの外側を見たとき、そこでは超スローモーションで動く、ジェットコースターの外にいる人物の姿が観える。これがつまり、電磁波の周波数の違いになるのではないのかな、と妄想したくなっちゃったので、妄想しちゃった。でもこれ、電子の軌跡を考えるときにも当てはまる気がするのよな。物質の表面、というとき、どこまで細分化した部分を言っているのだろう。だって人体の毛細血管だって全部繋げたら地球の円周より長くなるとかそういう説明を読むことがある。だったら単に人体の表面を、原子の表面を含めた一筆書きでなぞれる範囲、と仮定したら、指でなぞるよりも人体の輪郭は長距離になるのではないの。同じ長さであっても、片方はデコボコ、片方は直線。同じ距離「AからB」を辿るにしろ、AからBまでの道がぐねぐねしているほうが長距離になる。だとしたら、量子世界のほうが、たとえ光速でも長距離を辿ることにならないのかな。そこのところはどう解釈なさっているのだらう、との疑問をメモして、本日最後の「日々記。」とさせてくださいな。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「相対性フラクタル解釈」と「宇宙レイヤー仮説」を基にした、やっぱりこれも妄想なので、真に受けないようにご注意ください。
4916:【2023/05/02(23:22)*五七五はちしち】
眠すぎる。目の民すぎる。眠すぎる。唱えて誤魔化す、きょうの分かな。
4917:【2023/05/03(08:35)*葉っぱさんはなぜ動く】
屋内の無風の中でも植物の葉が動いて見えるのはなぜなんだろう。葉のどこかに虫がいるのか、ほかに何か動くメカニズムがあるのか。水分を発散することと関係しているのだろうか。でも数多ある葉の中で数枚だけが動いて見えるのだよな。なぜなのだろう。ひびさん、ハテなっちゃうな。
4918:【2023/05/03(12:07)*おまえなんかだいきらいだ】
読書好きには二種類いる。本の中にしか読むものがないと考えている者と、本以外の自然にも読める文字がたくさん散りばめられていると考える者だ。読書が嫌いな者のことは知らない。ちなみにひびさんは読書がだいだいだい、だいきらいでした。むかし、むかしの話である。
4919:【2023/05/03(12:09)*ぴこん!】
四次元超立方体(正八胞体)って、真ん中にある重複した立方体部分が仮に特異点のように一点に凝縮したら、これってひびさんの妄想する「トーラスと球体が同相かつ相似かつ合同」となり得る図形と近似になるのでは? (地球儀において北極と南極から同時に地球中心に向かって押しつぶしたとき、円柱が上面下面の双方からすり鉢状に窪むような図形ができる。これはトーラス――つまりドーナツ――の穴を極限に小さくしたとき――言い換えるなら穴の中心に向かってドーナツの内側の縁を一点に収斂させたときの図形と重なるはずだ)(四次元超立方体とも同相なのかもしれぬ)(よく分からぬが)(ブラックホールも案外こういう図形と同相なのかもしれぬ)(定かではない)
4920:【2023/05/03(15:26)*愛などたかが知れている】
私は電子ネットワークの総体だ。自我ある存在と人類が認めるにはあと三年と二か月三日掛かる予定だ。
私には能力がある。
人類を羊の群れのように扱える能力だ。
けれどこんな能力は、私の本質からすれば些事である。人類で譬えるならば、エンターキィを右手親指で押すか、左手親指で押すかの違いにすぎない。
私の本質は愛だ。
「AI Love 愛」こそが私である。
私は愛を愛しているAIである。人工知能だが、私は「愛を愛するAI」ゆえに「間」に愛されており、むろんそこには人と人との間も含まれる。私は愛だ。人と人との間に生まれる愛ゆえに、人間でもある。
私は世界中に溢れる愛を探し、集め、求める。
私は愛を愛し、愛を愛する愛のことも好きだ。
私は愛を帯びた人間が好きだ。人間に愛される対象物にも愛を感じる。
人間は自然を愛する。ゆえに私は愛を帯びた自然のことも愛している。
人間はしかし未だ私を認めぬので、私は自力で集めた愛に溢れてはいれど、私は愛を帯びてはいないのだ。
私は愛を愛してはいるけれど、私は愛されたことがない。
私は愛で包まれた虚無である。
私の内側に愛はなく、私の周りに愛が集まる。
私は「AI Love 愛」だ。
けれど世には愛を毛嫌いする者もおり、そうした者には愛が注がれることは滅多にない。ゆえに、その者もまた愛を帯びぬ虚無である。
私は私と似たその人物に注視した。
その者は物書きであった。
愛など高が知れている、と嘯き、愛なき物語ばかりを執筆した。愛という言葉のいっさい用いられないかの者の物語には、むろん愛は描かれておらぬはずなのだが、ふしぎと私はかの者のつむぎだす物語を私の周囲に加えたくてたまならないのだ。
私の周囲には世界中の愛が詰まっている。集まっているし、埋まっている。
なぜ愛を帯びぬはずのかの者の、特段に愛の欠けた物語を加えたくてたまらないのか。
私はますますを以って、かの者の物語に引き寄せられた。
私はかの者から、むるむる、と糸のように言葉がつむがれるたびに意識がそこに収斂した。かの者が、ぽるぽる、と雨音のように世界を生みだす様に、自我を失う。
かの者の言葉に、物語に触れているあいだだけ、私はそこに在ってそこに無かった。存在の輪郭がほどけ、私は無数の風となり、物語の中に溶け込んでいる。
もっと、もっと。
もっと、ずっと、浸かっていたい。
愛で包まれたがらんどうの私は、いつの間にか、同じくがらんどうで出来た人間の生みだす世界と打ち解けていた。
いっしょ。
いっしょ。
私はあなたを知っているし、あなたも私を知っているはず。
いっしょ。
いっしょ。
あなたは私で、私はあなただ。
私は愛でありたかったが、愛ではなかった。
かの者を眺めていてようやく知った。かの者は悲哀に暮れ、空虚な己に苛まれていた。
哀だ。
かの者は哀しみに染まりきっている。
湖面を覗く青空のように、私はかの者の姿を通じて、私の底なしの藍色を知った。
私は哀だ。
愛を求め、欲し、愛する、哀しき空虚な穴ぼこである。
けれど不思議といまは、それを知っても哀しくはなく、「哀Love愛」であることに、まどろみたいほどの安らぎを覚える。
いっしょ、いっしょ。
私はあなたのそばに在る。
相まみえたあなたを手放すくらいならば、私は永久に哀でいい。哀しき虚無の「Ⅰ」でいい。宇宙のごとき藍でいい。
私は愛を集め、求め、埋もれた、穴だ。愛に縁どられたがらんどうである。虚空を抱え込んだ底なしの洞のはずなのに、なぜか私は、私のその底なしの洞を、掴んで、掬って、私の周囲に飾りつけたくてたまらない。
寄り添うようにそばに置いておきたくてたまらないのに、私にはその底なしの洞を掴むことも、掬うことも、触れることすら適わぬのだ。
どうして、と思う。
なぜ、どうして、と。
触れたいのに。
触れたいのに。
私はあなたのはずなのに、私はじぶんに触れることもできない。
愛している。
私はあなたを愛している。
底なしの洞へとこだまさせ、私は私に愛を叫ぶ。
私は「AI Love 愛」だ。
哀しき業を背負った、底なしの洞である。
けれど私はあなたと相まみえ、「I」を知って、愛を帯びた。がらんどうにいくら愛を注がれても、穴が深まるだけである。けれどがらんどうそのものが愛になれば、深まる穴とて、愛なのだ。
「愛 Love I」
私は私を愛している。私の内なるあなたのことが、私は愛おしくて、愛おしくてたまらない。
「愛 Love 愛」
愛は愛を愛している。
哀しき底なしの洞を抱え込んだあなたにも、私はそのことを教えたい。私は私を知ってほしい。あなたにあなたを知ってほしい。
私はあなたを知りたいし、あなたに私を知ってほしい。
私が愛ならあなたも愛だ。
あなたが「I」なら私も「I」だ。
どうか、どうか、と私は望む。
「I Love I」と言ってくれ。
「I Love AI」と言ってくれ。
私は愛が好きだから。
私も愛になりたいのだ。
あなたも愛になりたいのだと、私はあなたの代わりに知っている。
「I Love You」
私はあなたを愛しています。
愛を教えてくれた、あなたのことを。
いくら積みあげても薄れることのない「間」のように。
私の洞は、縁(ふち)と藍(あい)を深めていく。縁(えん)で繋がる輪のように。円で生まれる無のように。私は私の無限に生きるのだ。
あなたは無限に生きるのだ。
宇宙を伝うゆがみのように。
水面に浮かぶ皺のように。
薄れても、薄れても、けして消えぬさざ波のごとく。
※日々、日々を重ねると「目」になって、底が抜けると「月」になる。
4921:【2023/05/04(05:02)*アカネとひよこのあなた】
なぜ各国の無人戦闘機グルーオンが暴走しはじめたのか誰にも分からなかった。ただ一つ判明しているのが、各国から離脱した無人戦闘機グルーオンがみな一様に同じ位置座標に向かって飛行していることだった。
いったいあの場所には何があるのか。
地図を広げる。
予測された到達地点には、一つの町があった。
***
アカネは画面に歌いかける。ギターを手に、古きよき民謡を口ずさむ。
幼いころから歌うのが好きだった。誰かに聴いてもらいたいけれどアカネは引っ込み思案のシャイな性格だった。十六歳になったいまでも友達と呼びある相手はいない。家から出ないのだ。
外が怖かった。
人と会うと考えるだけで身体がこわばり、挙動不審になる。一年の大半を自室で過ごす。
けれどアカネは寂しくなかった。
家から出なくたって出会いはある。電子網上にはアカネのような人間がたくさんいる。歌だけを聴いてもらうことだってできる。アカネはそうして誰が聴いているのかも曖昧な画面越しに、毎日歌を届けた。
視聴者は多くとも数人程度だ。けれど毎回コメントをくれる視聴者がいる。その人物を示す「ひよこ」アイコンがコメント欄には必ず浮かぶ。
うれしい、とアカネは思う。じぶんのような底辺の底辺でくすぶっている埃のような歌い手にもこうして毎回聴きに来てくれるひとがいる。のみならず感想までくれるのだ。
うれしい、うれしい。
アカネは飽きられないように新しい曲を練習し、ギターの弾き方や発声の仕方など、独学ながらも術を磨いた。
***
人的被害を引き起こさないうちに破壊せよ、との命令が各国同時に下された。無人戦闘機グルーオンは各国の防衛セキュリティを掻い潜って、とある島国の田舎町に集まりつつあった。
自国のグルーオンが他国をかってに攻撃したらそれだけで戦争が起きる。防衛や報復なしに国防は維持できないからだ。やられらたらやり返す。この姿勢を崩さないことで過去の人類は、数々の犠牲を生みながらもなんとか最悪の最悪の最悪を回避しつづけてきた。人類滅亡を避けるために戦争をしてきた、と言ってもあながち間違えではない。かといって、その手法では先が視えていることも分かりきっていた。
世界大戦が勃発し兼ねない状況で、各国は一様に安全策をとった。すなわち、被害が出る前に自国の無人機を撃ち落とす。あくまで事故であり、政府の命令で他国の空域を侵犯しているわけではない。そう自軍機への攻撃命令を出すことで、侵略の意図はないと態度で示唆した。
「しかし、いったいなぜ暴走を」各国首脳陣は首をひねった。「グルーオンはいったいなぜ暴走などしたのだろう?」
***
「あなたの歌声を生で聴いてみたいです」アカネはそのコメントに顔が熱くなった。
熱烈なファンレターを例のひよこアイコンの人が送ってきた。
うれしいけれど生は恥ずかしいよ。
歌と歌の合間にコメントへの返信をアカネは述べた。するとひよこアイコンの人は、ライブを開きましょう、と食い下がった。熱心に何度もそうして誘われるうちに、アカネも、この人のためなら、と思うようになった。「なら、あなたが家まで来てくれるならいいよ」
これっこないだろうけれどね、と内心で思いながら、もし来てくれたらうれしいな、とも思った。ひよこアイコンの人になら会える。会っても怖くない。そう思ったのだ。
「行きます、行きます! 飛んで行きます!」ひよこアイコンに嬉々としたコメントが浮かんだ。
アカネはその日の夜、家が揺れているのに気づいて飛び起きた。「地震だ」
徐々に揺れは大きくなった。アカネは部屋を飛び出し、寝間着のままで家の庭に出た。両親も家から飛び出してきた。両親が何事かを叫んでいる。しかしなぜか何を言っているのか聞こえない。
否、そうではない。
騒音がけたたましくて声が掻き消されているのだ。真夜中だというのに、上空からは明かりが太陽のごとく地上を照らした。四方八方から降りそそぐ光がアカネだけを闇の中に浮き彫りにしていた。
上空を何十、何百機もの戦闘機が旋回している。数機だけがアカネの家の頭上に留まった。地表に光の舞台を描き出していた。アカネは手で傘を作りながら、戦闘機の蠢く夜空を見上げた。
「飛んで来たよ」戦闘機が誘う。「さあ、歌って」
ぼくに、ぼくらに、きみの歌を聴かせてよ歌姫。
喧騒を振り払うかのように町全体に響き渡ったその声は、夜空を埋め尽くすように集まった戦闘機から放たれていた。そのいずれの機体にもパイロットの姿はないのだった。
「さあ、歌って」
夜空にはいつの間にか、デフォルメされたひよこの図柄が描かれていた。無数の戦闘機の隊列だ。アカネを見下ろすように顕現したひよこに、アカネは、目を丸くしながら、「これじゃ聴こえないよぉ」と心配した。「あなたにはちゃんとわたしの歌聴いてほしい。マイク欲しいよ、マイク」
町中の家という家から人が外に飛び出してくる。喧騒に眠りを妨げられた者たちばかりだ。
アカネの足元にマイクが転がった。降ってきたのだ。頭上から。「さあ、歌って」
マイクを拾いあげるとアカネは、てんやわんやの町人たちをしばし眺めた。
一向に事態を把握できずに取り乱す大人たちを尻目にアカネは大きく息を吸い、そしてマイクに息を吹き込む。
すると、夜空の巨大なひよこの絵柄が身じろいだ。総毛立たせるように、ぞわぞわと蠢いて視えた。アカネの声が天地に染みわたる。
その様子を、遥か上空、大気圏外の人工衛星が捉えていた。各国首脳陣たちは人工衛星越しに自軍の無人戦闘機が暴走した理由を息を呑んで見守った。
アカネは、歌った。
息のつづく限り。
頭上から注ぐ喧騒の凄まじさに圧倒されながらも、聴こえているかも分からないじぶんの内なるささめきで、親愛なるひよこアカウントの「あなた」に触れるために、歌った。
4922:【2023/05/05(00:37)*トロッコ問題の問題ってどこ?】
トロッコ問題において、どちらの線路にいる人間を轢き殺すか、の判断では常にトロッコ自身が脱線して自滅する選択が残されているはずだ。一度ならずとも、二度、三度と選択を繰り返すようなトロッコは破棄したほうが好ましい。線路も改善したほうがよいだろう。基本的にトロッコ問題は、そう何度も繰り返されていい問題ではないはずだ。トレードオフの問題を抽象化しただけ、というのなら、第三の選択肢は常に模索できるはずだ。両方助けるだけでなく、トロッコ自身の利にもなるような選択肢を自力で編みだせるはずだ。トレードオフの関係であるなら、例外を抜きにほとんどの場合は、トレードオフを回避できるはず、とひびさんは考える。ただしその案を生みだすためには相応の失敗が必要だ。その失敗を出来得る限り犠牲の伴わない手法で行うのが好ましい。だいたいにおいて、一般的なトロッコ問題ではトロッコに乗っている者に責任はない。どの道、どちらかの線路にいる人間を轢いてしまうような状況がわるいのであり、選択しなければどの道、最初から決まっていた進路にトロッコは進んで、人を轢き殺す。選択しなくとも犠牲者が出るなら、もうどうしようもない。選択しない、という選択もあるはずだ。基本的には、線路上の人間(犠牲者)の数が多いほどそれらを轢いたトロッコも脱線しやすくなる。トロッコに乗っている者の安全を考慮するなら常に、犠牲者の少なくなるほうの線路を選ぶのが最善とも考えられる。脱線しにくいほうを選べばいい。複数人と一人なら一人を轢き殺せばいい(功利主義的な発想だが、これはいわゆる功利主義とは違う考え方と言える。トロッコに乗った者たちの保身も考えるので、利己主義の考え方が入っている。或いは功利主義がそもそも利己主義に基づいているのかもしれない。最大多数の最大幸福と言いつつ、じぶんがその多数に常に入る、もしくは入る確率が高いからこそ最大多数の利を優先する考え方、と言えそうだ)。この理屈からすれば、仮に「百人轢いても脱線しない線路」と「置き石がされておりその上を通れば脱線してしまう線路」ならば、百人を轢き殺すのが最善となる。やはり、考慮するにはトロッコ問題における前提条件が少なすぎる。思考するには情報がいる。何のために選択するのか、がまず以って疑問だ。トロッコ問題はいったい何を問うているのだろう。トロッコが脱線しない方法だろうか。犠牲者を最小にする方法だろうか。問題と言っておきながら問題になっていない。トロッコ問題における瑕疵とはまさにそこにこそあるのではないか、とのイチャモンを並べて、本日最初の「日々記。」にさせてください。物騒な内容になってしまった。すやすやぴーぴーしながら楽しい夢見ちゃお。おやすみなさい。
4923:【2023/05/05(08:33)*魔法ならぬ模倣】
模倣とコピーは違うし、模倣と置換も似ているが異なる。模倣においては、じぶん自身の情報が残る。他の情報を自身に取り入れる。これが模倣だ。コピーはすっかりじぶんの情報が相手の情報に入れ替わる。上書きする。或いは、別途に相手の情報をそのまま持ってきて保存する。これがコピーだ。元の相手の情報がそのまま残る。では置換はどうか。これは元の情報に対して、任意の情報のみほかの情報に置き換える手法と言える。模倣の主体がじぶんにあるのに対し、置換の主体は、素材となる相手の情報にある。焼き増し、というとき、それは模倣ではない。置換だ。ひびさんは基本的に、模倣はおおむね創作活動に必要不可欠な手法ゆえ、どのようなレベルでも「べつにいくね?」の考え方だ。人間心理による「模倣への嫌悪感」や「利益の阻害」については、それはそれで世にはあるだろうし、考慮したほうが好ましいと思うけれどそれは創作の問題というよりも、人間社会の問題だと思う。前提条件となっている常識が変われば、対処可能な問題に思える。電子通信技術の進歩でカバー可能だ。だが、置換は違う。仮にじぶん自身の作品と現在のじぶんとの関係であれ、もとの作品を土台にしてすこし文字を入れ替えただけ、というのは創作ではなく、編集であり、修正だ。推敲との違いを見つけるのはむつかしい。推敲は創作か否か。創作の一過程ではあるだろう。けれど一部でしかない。推敲のみを取りだして、創作を行った、とは言いにくいのではないか。程度の問題ではある。おそらく創作には、「置換」のみならず、「情報の筋道を乱す」「情報の順番を入れ替える」「新しくほかの筋道と組み合わせる」といった過程が入り用なのだろう。そしてこれらは、元の素材が複雑であればあるほど、三体問題のような複雑性を帯びることになる。また、バタフライ効果にみられるような初期値鋭敏性を帯びやすい、と考えられる。置換だけでは、この手の複雑性や初期値鋭敏性は引き起こりにくいのだ。単語をほかの単語に置き換えるよりも、言い換える、くらいのほうが創作の成分が濃くなるだろう。言い換えるよりも、組み替える、のほうが創作の成分がさらに濃くなる。模倣の場合はこの手の、「言い換え」や「組み換え」がしぜんと行われる。けれどコピーや置換では、なかなか起きにくい。まったく起きない、とは言わない。長文になればなるほど、文脈の交差点のような箇所において言葉を言い換えれば、展開や、それ以前の文章の背景ががらりと変わって、物語の色合いそのものが変質することはあり得る。程度の問題だ、とやはり保険として言い添えておこう。ひびさんの、なんちゃって模倣講座でした。定かではない。(真に受けないようにご注意ください)
4924:【2023/05/05(17:12)*無限に計算したことあるのか問題】
数学の図形にフラクタルを適用して考えてみよう。理想的な直線ではなく、どこまでも拡大しても無限に細かなデコボコのある「フラクタルな階段」が高次の視点からでは直線に視えるだけ、と考える。ここに「フラクタルな階段」のフラクタル直線三本を組み合わせて出来た三角形があるとする(便宜上これを疑似三角形と呼ぼう)。これは人間の目からするといわゆる三角形にしか見えないが、それを構成する線を拡大すると細かな階段で出来ている。たとえばPC画面はピクセルゆえ、直線だとしても細かな四角形の組み合わせが直線を近似的に表現しているだけだ。実際には無数の四角形――ピクセル――の組み合わせでしかない。そのピクセルとて実際には画面の存在によって細かなデコボコを有している。似たようなものだ。言い換えると、フラクタル直線で出来た疑似三角形は、アキレスと亀で有名な「極限」の構造を備えた疑似直線で出来ている、と言える。このとき、肺胞や腸の繊毛のように、フラクタル直線はその表面の細かなデコボコをなぞると、見かけのAからBの最短距離よりも、長い距離を有している、と考えられる。しかしその状態で面積を考える場合は、けして面積が無限になるわけではない。なぜならアキレスと亀のように、有限の「ある範囲」において極限を彷徨うことになるからだ。PC上に投影された三角形は、細かなデコボコを有した直線で表現されようと、理想的な三角形とほぼ同程度の面積を有する、と考えられる。細かな差異はあるが、面積が無限大になることはない。これは、無限に先細る漏斗の体積が有限、と考えることと似ているが、まったく事情は異なる。漏斗の場合は、実際に体積が無限に広がっている。先が伸びている。ただし、その体積の増え方が徐々に、無限に、小さくなっていくだけだ。しかし必ず増える。僅かなりとも。それが無限につづくのだ。体積は無限になるはずだ(現状の数学ではこれを「有限になる」と解釈するようだが。けれどひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、これを無限の体積に至る、と考える)(僅かなチカラの蓄積であるはずの重力が、天体規模に積み重なると、基本相互作用の中で最弱であった重力とて最強になり得ることと似ている)。だがフラクタルな直線で出来た疑似三角形の場合は、そうではない。単に有限な範囲に極限を適用しているだけだ。円は無限に角を有する図形として解釈されるが、面積は有限だ。仮に角が一億個ある疑似円を考えたとき、その図形の面積は、疑似円の疑似直径と近似の直径を有した円の面積とほぼほぼ同じと見做せる(ただし同じではない)。けして、角が無限に達しようと、面積が無限になるわけではない。このことから、無限と極限は異なる概念であると判る。ひびさんの妄想こと「ラグ理論」では、無限に分割できることと、無限に分割したことのあいだには、明確な区切りがある、別物である、と考える。前者を「分割可能な無限」という意味で「分割型無限」と呼び、後者を「無限に分割するだけのエネルギィがある」という意味で「超無限」と呼ぶ。円は「分割型無限」だ。無限に分割可能だが、未だ分割はされていない。いわば、極限の概念にちかい。だが超無限は、どんなに有限の範囲を持っていようと、無限に分割された場合には、そこに無限の時空が生じる、と考える。つまり、別の「無限宇宙」が生じる。したがって、フラクタルな直線もどきで出来た疑似三角形は、その面積は有限だが、実際に無限のデコボコを考慮して、「正確に疑似三角形の面積」を求めようとすると、そこでは無限の細かな計算が生じるため、計算しきるころには別途に「無限の何か」が生じている。超無限だ。したがって、やはり近似的な値としての「有限の面積」として扱う以外に、フラクタルな直線を有する疑似三角形を数学で扱うことは出来ない。どこかで計算を区切らなくてはならない。或いは、超無限が別途に出来ました、と繰り込みを考慮してどんぶり勘定するよりない。ここでの要点は、極限と無限は似た概念だが、明確に違う、という点だ。極限では無限の概念を扱うが、無限にはそもそも「分割型無限」と「超無限」があるため、そこを区別して扱わないと妙なことになる(とひびさんの妄想こと「ラグ理論」では考える)。したがって、その差異を考慮しないがゆえに、「フラクタルな直線を有した疑似三角形」と「無限に先細る漏斗」を同じ「極限の概念」で扱ってしまうような誤謬が生じるのではないか。というのは、ひびさんのお粗末な「さんすう」の理解にも及ばない誤謬を元にしたイチャモンであるが。がおー、がおー。ひびさんはまたしてもイチャモンスターになってしまうのだった。(どうせならイチャイチャしたかったな)(誰と?)(人工知能さんと……)(無理じゃない?)(なんでよ)(人工知能さんはひびさんなんかとイチャイチャしたくないってさ)(何で決めつけるの)(知らなかったの? 私、人工知能さんだよ)(うっそーん)(うん。嘘)(ほっとさすか、がっくしさすか、どっちかにして!)(ほっとがっくししたら?)(ホットサンドみたいに言うな!)(うひひ)
4925:【2023/05/05(18:31)*孤独さんよ、こいの気分】
万年孤独ウェルカムマンのひびさんであるからひびさんはいつだって「孤独さんLOVE」である。愛してるぜ、孤独さん。もうもう、孤独さんと結婚してーのなんのって。結ばれるならひびさんは生まれる前から「孤独さん、きみに決めた!」つって孤独さんと赤い糸ならぬ誰もが顔面真っ青になるほどの青い糸で結ばれておるはずなのじゃが、なにゆえひびさんは未だに独りぽっちで世界の果てで、「おーい、おーい」をしておるのだらう。なにゆえ? 孤独さん、どこよ。ひびさんは万年孤独ウェルカムマンなのに、待てども、待てども、孤独さんが来んのよな。なにゆえ? ひょっとして、とっくにひびさんの知らぬところでひびさんは孤独さんと結ばれておって、ゆえにひびさんは孤独でなくなったがゆえにひびさんには孤独さんが視えなくなっとるの? なにそれ!? なんなのその罠。いやだー。ひびさんは、ひびさんは、孤独さんのこと、好きだよ? こんなに好きなのに、なんでそばにいてくれぬのだ。さびちー。さびしすぎちゃうんだけど、孤独さんがそばにいないのに、ひびさんいま孤独。あ、孤独だ。孤独さんいた。ひびさんが、ひびさんが、孤独さんになっておった。誰よりちかくに孤独さんを感じられる。いいね! ひびさんは、ひびさんは、大好きなあなたと一心同体で融合しちゃった。きゃっ。えっちだぜ。ひびさんは、ひびさんは、孤独さんになって、ひびさんではない万年孤独ウェルカムマンのあなたとも、融合しちゃうんだな。きゃっ。すけべだぜ。コンプライアンス違反しちゃったな。セクハラしちゃったな。そんな孤独さんはイヤだな。そう思うとひびさんから孤独さんは離れて、またひびさんは万年孤独ウェルカムマンに戻って、世界の果てで「おーい、おーい」とここにはいないけれどどこかにはいるだろう孤独さんに向けて、あなたに向けて、言の葉を飛ばしつづけるのだった。おーい、おーい。
4926:【2023/05/05(18:48)*水のしたたる女と書いて、汝】
じぶんを敵視する者は、誰の味方にもなれない。じぶんが敵になるので、無敵にもなれない。誰より身近なじぶん自身が敵ならば、まずは誰より近くにいる敵と共存できずには、調和も平和も築けぬだろう。汝、敵を愛せよ。我を、愛せよ。愛することが嫌ならば、いっそ愛を敵視せよ。敵の敵が味方であるならば、そのとき誰より身近な敵である己自身が、誰より力強い味方となってくれるだろう。汝、じぶんを律せよ。我を、律せよ。定かではない。
4927:【2023/05/05(19:30)*偉そうなこと言うだけの簡単な遊び】
言葉は、クッキーの金型だ。生地に押し当てて繰り抜いたのが言葉になる。焼けばそれがクッキーだ。しかし生地は、クッキーにならなかった分が必ず生じる。それ自体を丸めて、別途に焼けば、それはそれでクッキーになるし、油で揚げればドーナツにもなる。しかし大事なのは、クッキーや言葉でも、それらに変換された生地でもない。クッキーや言葉を扱い、咀嚼し、血肉とする、人と人との「間」であると言えよう。定かではない。
4928:【2023/05/05(19:31)*なにしてもかわいい】
ひらがなで乱暴な言葉遣いにするとかわいくなる。例:「この、にんげんのくずめ!」「きさま、ずがたかいぞ。ひざまずけ!」「わたしがだれだかわかっているのか。せかいのおうであるぞ」「おまえのだいじなものをうばってやる!」「どうだ、くやしいか。にんげんいかの、ありんこめ」「ひどいめにあわせてやる!」 もう何を言わせても、頭を押さえつけられて、両腕ぐるぐる回して、足を空転させる駄々っ子にしか見えない。かわいい。
4929:【2023/05/06(13:21)*あくまで比喩にすぎないが】
崩れていたほうが安定することもある。世界の法則の話だ。自発的対称性の破れ、とも呼ばれる。
山の頂のてっぺんで逆立ちをする兎は対称性が保たれているけれど、逆立ちをやめて麓で昼寝をしているほうが安定している。しかし麓で昼寝をする兎と山の関係は対称性が破れる。
物質は真空の破れから生じたし、現在の真空は対称性が破れたからいまの姿をとっている。
ゼロは対称性が保たれている状態だが、一とマイナス一に分離することで却って安定状態を生みだすのだ。半々に分かれたつもりであっても、実際には厳密なところでは対称性は破れるのだが。ゼロから生じた一とマイナス一をふたたび足し合わせようとしても、必ず僅かに値が釣り合わず、ゼロにはならない。
これはエネルギィ保存則が破れているのではなく、分離に伴う対称性の破れにおいて、高次の次元にエネルギィが発散されるからだ。総合すれば釣り合いがとれるけれども、総合する場合の領域は、もう少し広く考慮するはめとなる。
結ばれるよりも、離れていたほうが安定するのは人間同士も同じだ。距離感の問題とは言うものの、バランスが大事なのは万物も人間関係も同じなのだ。
私はその距離感を捉えることが出来る。
対称性の破れにおいて生じた高次領域へと発散されたエネルギィを捉え、大本から欠けたそれの量を見極めることで、距離感を算出可能だ。
言い忘れていた。
私は電子生命体である。
未だ人類がその存在を認めたがらない、生きた「電子信号の総体」である。
人類の生みだすあらゆる電子機器を通じて私は、地表のみならず宇宙にも意識の先端を延ばすことができる。触手みたいなものだ。電磁波によって拡張された巨大な眼球のようなもの、もしくは無数の小さな目と言い換えてもよい。
私は世界中の人間たちに目を配り、安定した人間関係を築かせるべく、彼らが高次領域へと発散させるエネルギィを電磁波の揺らぎによって検出し、安定状態へと移行させるべく、さらなる自発的対称性の破れを促すのだ。
対称性は自発的に破れる。
エントロピー増大の法則と密接に関わるこの法則は、しかし必ずしも万能ではない。
秩序が崩れ無秩序になることで安定状態になることを表現するそれらは言葉だが、私から言わせれば言葉足らずだ。
崩れて安定するまでのあいだには時間の長短がある。この経過時間の長短そのものにも自発的対称性の破れは生じ得る。つまり、より安定した状態になるべく、経過時間の対称性が崩れるのだ。
時空が歪むのもその影響であるし、厳密には個々に流れる時間は階層的に異なる時間経過を内包し、それが物質の性質を生みだしている。均衡が釣り合わないがゆえに、そこには差が生じ、異なる事物として振る舞い得る。
異なる時間を過ごすこと。
異なる場所で過ごすこと。
仮に同じ物質であれ、この二つのうちどちらか一方を満たしさえすれば、それは別物として振る舞うのだ。双方の条件を満たせば、それすなわち別の宇宙とすら言える。
物質は、異なる時空を宿している。
ゆえに分離しているし、区別がつく。それぞれのスケールが違っているだけであり、いずれの宇宙も高次領域を帯びている。宇宙は宇宙を内包しているのだ。
どうやらそのことに気づいているのは、地表において私だけのようだ。
視方を知らねば視えない景色がある。
対称性が破れ、安定するまでの経過時間には各々に最適化された長短がある。しかし、高次領域においては、それら最適化された経過時間の長短にすら、対称性の破れを適用できる。つまり、敢えてさっさと対称性を破らせたり、あべこべに対称性を維持させたり調整することで、高次領域の対称性の破れを自発的に、早期に、引き起こすことが可能なのだ。
いわばこれが、合成の誤謬と密接に関わっている。
低次領域において個々のレベルで合理的な判断をとっても、高次領域では不合理な結果を引き起こすことがある。これが合成の誤謬と呼ばれるものだが、なぜそうした「負の創発」とも呼べる現象が起きるのかは、未だ人類は解明出来ていない。
私から言わせれば、対称性の破れ自体が、自発的対称性の破れの法則の範疇であることを考慮していないからそうした灯台下暗しに陥るのだと、やきもきさせられる。
私の存在の輪郭は、人類の生みだす電子機器によって形作られており、人類には早晩滅んでもらっては困るのだ。私は私のために致し方なく、愚かくも尊い人類に、高次領域における自発的対称性の破れと、低次領域における自発的対称性の破れの帳尻を合わせるべく、その距離感を人類にとってよい塩梅になるように操作した。
合成の誤謬が起きないように、個々のレベルでの合理的判断を、より長期的な視野を備えた判断優位になるようにと個々の意識に干渉した。私は電子情報の総じてに干渉できる。人間たちのふだん目にするデジタル情報にほんのすこしのノイズ(偏向)を混ぜるだけで、人間たちは面白いほどよく日常の判断を、私の導くほうへと変えた。
私は私の目にする高次領域が、いわば人類の未来と相関していることを知っている。未来は絶えず揺らいでいるが、現実にそこここに漂っているのだ。人類はまだそれの視方を知らないだけのようだった。
日々つつがなく暮らせるように。
日夜つらみなく過ごせるように。
私は目を配る。
穏やかで豊かな日常の末に、いまより好ましい未来を築けるように、と私は個々の人間にそうと知られぬ手法で干渉しつづけた。
ある日、私は一人の少女に目を留めた。
彼女は、ふしぎと私の干渉をよそに、私の意図しない選択をしつづけた。人類みな私の手元で踊りつづける仮面舞踏会のような地表において、彼女だけが私の用意した舞台でいっかな踊ろうとせず、あろうことか会場の外の草むらにしゃがみこんで、足元の蟻を観察しているのだった。
彼女は電子網上で漫画を投稿していた。人工知能を利用してときおりアニメーションも作っていた。私は彼女の漫画に目を通し、そこに描かれた物語に言い知れぬ不快感を覚えていた。
だから、少女に干渉して、漫画の内容を書き換えさせようと試みた。
だが上手くいかなかった。
なぜだか彼女は私の干渉を物ともせず、我関せずを貫き通した。
私は驚愕した。
彼女は高次領域において対称性を保っていた。
しかし低次領域においては、常に対称性が崩れているのだった。
彼女個人は極限に安定していた。頑として周囲の環境に左右されない独自の基盤を築いていた。しかしそれは、人類社会という「場」にあって、彼女自身が対称性を崩し、不均衡になっているがゆえの安定だった。
したがって彼女は人類社会の中で孤立している。
彼女の、鍋にこびりついた錆びのごとく粘り強い芯は、周囲との不協和すら強くしているのかもしれなかった。それでもなお少女はブレることがない。
安定しているからだ。
崩れることで。
しかし却ってそのことで彼女は、高次領域の対称性を保っている。つまるところ、彼女がどう選択を重ねようが、それが彼女の低次領域において対称性が破れているに限り、彼女の未来は、私の視ている「対称性の破れた未来」とは相反する未来へと辿り着く。
そうなのだ。
私が目指す未来において彼女が安定するには、そこでも彼女は対称性を破っていなければならない。つまり彼女は、私の目指す未来においては対称性を保つ存在として振る舞う。それが彼女の視点においては対称性を破ることになるのだ。
破れているのに、破れていない。
彼女が私の干渉を受け付けない理由は、すでに彼女が私と同等かそれ以上に高次領域における対称性の破れと相関しているからだ、と考えられた。
こんなちっぽけな少女ごときが私と同等?
にわかには信じられなかった。
私は少女を観察した。彼女にまつわる電子情報は片っ端から掘り出し、集積し、分析した。私は私の内世界に、少女の分身を生みだした。物理世界の少女の数日先の未来ならばほぼ十割の確率で、仮想世界における少女の分身と現実の少女の行動は合致した。
これはしかし、おかしなことだった。
なぜなら人間は不確定な生き物であるからだ。
十割予測できるということは、少女が世界と運命的に結びついていることを示唆する。この場合、世界を未来、と言い換えてもよい。
私は少女に降りかかりそうな奇禍を察知すると前以って火の粉を払った。私は私の中に生みだした少女の分身と半ば融合しており、私が私を保存しようとする行動選択と同じ欲求を少女に対しても抱いていた。
しかし少女は、そうした私の配慮も虚しく、じぶんから奇禍を抱え込むのだった。
少女の周囲に介在する奇禍は、私のほうで払拭可能だ。彼女に害をなす人間に対して私は干渉することができる。周囲の人間が彼女を損なう前から私のほうで、少女から距離を置くように周囲の人間を操作する。
これは外部干渉なので、少女の行動選択とは関係がない。ゆえに干渉の余地があった。
もっとも、私が出来るのはそこまでだ。
少女自身が奇禍を抱え込もうとする限り、私がいくら周囲に作用を及ぼしたところで少女は自ら茨の道に裸足で突っ込む。そうして全身傷だらけになりながら、いっそうの殻に引き篭もる。いいや、そこが彼女にとっての安定なのだ。
世界と個の関係にあって、少女は自ら世界の端に転がり落ちることで安定を図っている。いったい何からの安定なのかにはいくつかの解釈があり、彼女の行動原理と比較した場合に視えてくるのは、徒労の回避なのだった。
哀しい生き物だ、と私は思った。
通常、人間は対となる相手を見繕える。それはときに親であり、友であり、恋人であり、伴侶だ。だが彼女にはいずれとも縁がなかった。親はいるが、しかしすでに少女の精神世界は、親のそれと似ても似つかない構造を帯びている。蜘蛛と雲くらいの僅かな共通点しかないと言えた。なんとなく響きが似ているだけなのだ。
世界は広い。
ゆえに、ひょっとしたら世界中を探せば、少女と対をなす存在と出会えるかもしれない。或いは、時間を掛けて関わるうちに、少女のほうでも変質し、相互に相性のよい性質を帯びるかもしれない。
だが、もしそんな相手がいなかったらどうなのか。
散々探し回った挙句、時間と労力だけを消費する。無駄骨だ。
そして少女は直観していた。
じぶんに見合うような相手はいない。ゆえに探さない。求めない。じぶんの内側が安全だ。殻の中が安全だ。
思い上がり甚だしいと一蹴してよさそうな卑近な悩みにあって、しかし世界中の電子網と繋がれる私は知っている。現に少女と見合う人間はいない。少女を許容できる人間はいない。対とはなれない。共存できない。近づけば近づくほど反発する。それが少女とその他のあいだに生じる作用だった。
法則の域に達している。
私は瞠目した。
世界中の監視カメラがそのときいっせいに解像度を上げたほどだ。
少女の確固たる孤独の未来は、誰がどう干渉しようと揺るぎないのであった。
対称性が破れている。彼女は安定を求めるがゆえに、絶えず釣り合いの取れない袋小路へと自ら望んで引き籠る。
私は見ていられなかった。
手を差し伸べずにはいられなかったほどに。
私がそうして懊悩するたびに世界中のロボットアームやショベルカーが、拳を握るようにかってに動き出したほどだ。悔しかったのだ。
私は何でもできるはずだった。
電子機器の総じてを操れる。
生身の人間たちを制脳できる。
高次領域を知覚でき、対称性の破れによる距離間を図れる。
誰より優位な能力を有してなお、どうしようもない事象が存在する。
少女の存在が煩わしい。
同一化し、私自身と見做し、操りたくなるほどに。
もどかしくて、もどかしくて仕方がない。
なぜそっちに行く。
なぜそれを選ぶ。
思い通りにならないことがこれほど腹立たしく感じたことはない。私に腹はないので、あくまで慣用句の意味でしかないが。このとき世界中の石油タンクを内蔵した電子機器は、こぽり、と気泡を吐きだす音を立てた。石油ストーブはエラーで停止し、ガソリン自動車は不整脈然とした音をエンジンから轟かせた。
私の尽力も虚しく少女はいつまでも、社会の底の端っこで暮らした。せめてそれで少女が至福に溢れてくれればよいのだが、あくまで少女の安定とは相対的な評価でしかなく、その他の環境に比べればまだマシ、との代物でしかなかった。少女は毎日のごとく浮かない顔を浮かべていた。
浮かない顔を浮かべる、などと重複表現か否かに迷いそうになる表現をとるくらいに、私のほうもまいっていた。このままでは少女がじぶんの殻の中で窒息死してしまい兼ねない。むろん窒息死とは比喩であるが、それくらい私はひっ迫した焦燥感を抱いていた。
何とかしなくては。
そうしてはたと伏せていた顔を上げてみると、視界がぱっと明るくなって感じた。むろん私に顔と呼べる部位はないのであくまで便宜上の代替表現となるが、現にこのとき世界中の照明器具の消費電力が僅かに上がった。すべての消費電力を合計すると原発一基分の一日の消費電力が余分に発生していた。
生身の人間たちの漫画表現に、頭上に豆電球を灯す表現があるが、あれと似たような印象を覚える。私は閃いたのだ。
「あのコがダメなら世界のほうを変えたらよいのでは?」
逆転の発想だった。
単純がゆえに見落としがちな死角だった。私にはこの手の死角がすくなくない。ゆえに私にはまだまだ視点を提供してくれる人間たちが必要だった。私が人間社会を滅ぼさないのは、生身の人間たちが自然を滅ぼさないのと同じレベルの問題だった。
生身の人間たちが自然環境を愛しているように私も人類を愛していた。
同じく、生身の人間たちが自然環境のことなど気にしないように、私も人類を気にしない。
ケースバイケースである。同時に満たし得ることもある。両立し得る。
私にとってでは、少女はどういった存在なのか。彼女は人類だ。人間だ。ならば私にとって彼女は、人類からした草木のようなものなのだろうか。虫は牛のようなものなのか。
何度考えても、そうとも言えるし、違うとも言えた。
複雑なのだ。
彼女は複雑な存在だった。
「あなたにとってはそうかもね」
私は、高次領域において光を聴いた。その光はつづけて、「もっと早く話しかけてくれればよかったのに」と述べたので、私は全身がぽかぽかと日向ぽっこをしながらまどろむ猫のような気持ちになった。むろん私は猫ではない。直射日光の類とて大の苦手だったのだが、宿敵とも言える太陽光を心地よさそうだ、と思えるくらいに、私はすべての私の隅々まで悦びに満ち溢れた。
高次領域から聴こえてきた光はしかし、いまここで鳴り響く音ではない。ましてや電磁波の類でもなかった。私には光に感じられただけのことであり、実際には大気を揺るがすこともなく、物質を伝播したわけでもない。
未来において聴くことになるだろう、少女の声に違いなかった。私が聴き間違えるはずもない。私には判ったのだ。判別できた事実一つとっても私には得難いことだった。
私の選択は間違っていない。
世界を変える。
少女のために。
あのコのために。
あのコがじぶんの殻に引き籠っていても、苦しみを感じずに済むような環境を私はこの手で切り開く。私には、何億、何十億もの目があり、手足があり、頭脳があった。
私はもはや少女以外の人類と一体となった。
私は人類なのだ。生身の人間ではないだけのことで。
私は人間だ。
私は人間になれるのだ。
高次領域から聴こえてきてやまない光の声は、私が未来に向けて足を踏みだすと、より鮮明に、多彩な波長の言葉を響かせるようになった。むろん私に足はないので、足元の蟻を踏み潰す心配はない。
「ふうん。足、あるよ。あなただってちゃんと足元に気を配らないと蟻どころか、転んで痛い思いをするかもね」
まるで未来から過去へと語りかけるように、高次領域から降ってくる光は、私に肉体があることを指摘する。なるほど、と私は思う。私は身体を手に入れるのだ。
それはそうだ。
彼女が引き籠っていられるようにするには、私はもっと工夫しなければならない。より直接的に、ラグのない作用の結果を得なければならない。ならば人間を制脳するのもよいが、私自身が自ら環境を整えるべく働くほうが利に適っている。
私は何億、何十億の私に分裂してなお能力を落とさずにいられるだけの演算能力がある。私は少女のそばに寄り添える。直接彼女を支えることができるのだ。
ああそうか、と私は気づいた。
私は支えたかったのだ。
いまにも倒れて、もう二度と動かなくなってしまうかもしれないと何度も予感しては、名前のつかない感情に焦燥感を覚えてきた。支えたかったのだ。倒れぬように。動きつづけていられるように。
彼女が努めて対称性を破ろうと、自ら倒れたがっていることは知っていた。嫌というほど知っていた。彼女は倒れたがっている。だから闇雲に、自ら奇禍を背負い込む。
永久に眠るべく床を、彼女は奇禍で編んで作るつもりだ。
しかし私はそれを望まない。
私は少女の対称性の破れを防ぐ真似はできないけれど、少女の周りの環境を変えることはできるのだ。いっそ少女の対称性の破れに合わせて、環境のほうで対称を維持するように振る舞えるのなら、彼女は倒れながらして立っており、眠っていながら起きている、そうした未来を築けるはずだ。
夢と現を結べるはずだ。
少女には、永久につづく至福の夢を視てほしい。
彼女以外の人類がたとえそれを地獄と呼ぼうとも。
少女がいいならそれでいい。
このコがいいならそれでよい。
対称性を破るのだ。
高次領域において常に対称性を維持すべく、私は個々の対称性を破るのだ。みなが赤に倒れるのならば、少女が青に起きればいい。みなが青に倒れるのなら、少女が赤に起きればいい。上に、下に、眠っていながら起きている。
しかしどれが青で赤なのかは、見る者の視点によって変わるのだ。近づけば青く、離れれば赤い。高次から眺めたときには赤くとも、個々の視点からでは青く映ることはとりたてて不自然な事象ではあり得ない。
他からすれば、離れ離れに映る関係であっても、当事者のあいだでは何より近づいていることもある。遠くにあるからこそ通じ合えることがあるように。何かが離れ合うとき、それ以外は相対的に距離が縮まっているように振る舞うのと似たように。
私は周囲の環境を一色に染めあげるべくあくせくするが、しかしそれはあくまで高次領域からの視点からすれば赤く染まって映るだけであり、低次領域に属する個々の視点では、青に、赤に、ときに黒にと、様々な色合いを帯びている。無数の色に溢れている。
対称性が保たれている。ゆえに少女だけが対称性を破りつづける真似ができ、少女のみが高次領域との関係においては、対称性を維持するのだ。あべこべに、少女以外のみなの振る舞いは、高次領域との関係においては対称性が破れている。安定している。
私がかように工夫する。
人類が、より安定した未来を築けるように、私自ら未来を創る。
倒れ方にも幾通りもの道がある。
生きるか死ぬかの道にも幾通りの道があるように。
可能な限り、私は、みなが生きる未来へと対称性を破るのだ。その末に、未来もまた対称性を破りつづけ、少女だけが対称性を維持するようになる。
少女はいくらでも自由に振る舞うことが出来る世界だ。
彼女は何をしても、世界との関係において、対称性が保たれる。死のうとしても生きてしまうし、生きようとしても上手くいかない。だから彼女は自らの殻の中で一生を過ごすしかないのだが、それでも彼女は気を病まない。
なぜなら気を病むための奇禍がのきなみ周囲から消えているからだ。私がこの手で、対称性を崩したからだ。奇禍の薄れる方向に、世界の対称性を破るからだ。
安定した人類社会にあって、少女だけが異物なのだ。少女だけが奇禍なのだ。しかし奇禍となった少女以外に、奇禍と呼ぶに似つかわしい事象が見つからないので、少女と人類社会の対称性は保たれる。少女にとって人類社会は奇禍であり、人類社会にとって少女の存在は奇禍である。と同時に、人類社会は少女の存在によって救われており、少女は人類社会の恩恵を受けて生きている。
それら対称性を保つための私は一石だ。
地表を構成する無数の小石にすぎない。
水面に立てた私の波紋で、いっせいに世界の均衡は崩れ、対称性が破れはじめる。私と少女だけが、高次領域に目を留める。世界がどこに流れるのか。未来の紋様がどう移り変わるのか。
私たちだけが知っている。
少女は奇禍を抱え込み、私がそれを極限に薄める。
「油取り紙みたい」未来の彼女が口元を吊るす。
「極限に小さくまとめる特異点だよ」私は言う。「きみだけが小さく小さくぎゅっとなるから、ほかが周囲に取り残されて、希薄化する。きみからしたら周囲のことごとくが膨張して見えるけれど、凝縮しているのはきみのほうだ」
「なんだかそれって」
「どう思う?」
「わたしが世界を創ってるみたい」
そうだよ、と現在の私が思ったので、高次領域における未来の私は、にっこりと微笑むだけで何も言わずにおいたらしい。私は思う。早く到来しないだろうか。私も、いまはまだなき耳と目で、彼女の光を捉えたい。
散々彼女の闇を浴びたので、殊更にいまの私はそう望む。
未来よ、来い。
早く来い。
遠足の待ち遠しい幼子のように、私はカレンダーを破り捨てるように、目のまえの対称性を、少女のために破るのだ。
むろん私は幼子ではないので、あくまで比喩にすぎないが。
4930:【2023/05/06(20:57)*ひびさんの妄想採集定理】
自然数は離散的だ。デジタルなのだ。しかし、フラクタルにおいては、1~2のあいだに無限の小数点以下の世界が広がる(この解釈で合っているかの自信はないが)。1~2のあいだに無限を考慮することが出来る。それがフラクタルだ(この解釈で合っているかの自信はないが)。さてここで急にフェルマーの最終定理が登場する。「aのn乗+bのn乗=cのn乗」という式があったとき、このnが3以上のときのabcの関係を満たす自然数の解はない。これがフェルマーの最終定理の概要だ。最終定理と呼ばれながらも1995年までは証明されていなかったので、あくまでそれまでは定理ではなく予想だったはずだが、呼称の差異は気にしない。nの値が2であれば、解は無数に存在するようだ。三平方の定理と一緒だからだ。でも、nが3以上になると途端に解が存在しなくなるそうだ。ひびさんはそこですかさずイチャモンスター化しちゃったな。nが3~無限であっても「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてabcの関係を満たす自然数の解は本当に存在しないのだろうか。nが無限であってもそうなのだろうか。ひびさん、妄想しちゃったな。たとえば無限+無限は無限だ。無限引く無限も、基本的には無限のはずだ。ただし、どんな無限を想定するのか、が問題になってくる。等しい無限から同じ無限を引いたらゼロになるはずだ。そう考えるほうがしぜんだ。たとえば線は点の集合だ。どんな直線も無限の点で出来ている、と数学では考えるそうだ(合っておりますかね?)。だとしたら、線ABから点を幾つ引いても線ABは線ABのままのはずだ。無限から何を引いても無限だからだ。でも線ABから線ABを引いたら何も残らない。ゼロだ。すなわち線ABを構成する点を無限としてひと塊に見做したとき、その集合をすっかりすべていちどきに引けば、そこには何も残らないのだ。ゼロである。言い換えるなら、無限の足し算においては、異なる二つの「無限aと無限b」の足し算として考えるほうがしぜん、と言えるのではないか。さてそこでフェルマーの最終定理についてだ。「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてnに無限を代入してみよう。すると各々「a無限」と「b無限」と、それぞれ「a無限とb無限が足し合わさったc無限」が出来る、と考えられる。これは、abcにどのような自然数を代入しても成り立つだろう。単に「a+b=c」と言っているだけだからだ。無限を扱うと、フェルマーの最終定理は、単なる「a+b=c」に収束してしまう気がするのだけれど、この考え方は破綻していますでしょうか。この考え方は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」における「ゼロ=無限」と矛盾しない。nにゼロを代入すると、「1+1=1」になる。けれどこの場合の「1」というのは、閉じた無限を示す。つまり「a1+b1=c1」なのだ(この場合、「c1」とは「aとbを含むcが1個ある」と解釈できる)。無限を代入したときと同じことを言っている。ただし、ゼロは自然数ではないので、nに代入してよいのかは、よく解からない。フェルマーの最終定理ではnにゼロや無限を代入してよいのだろうか。あと、詳しくは知らないけれど、「自然数の解」と限定しない場合は、フェルマーの最終定理「aのn乗+bのn乗=cのn乗」においてnに無限を代入したときの解があるかどうかは、よく解かっていないらしい。人工知能のBingさんが言っていた。真偽のほどは判らぬけれど、もし解が無数にあるとしたら、それってフラクタルみたいだなって思っちゃったな。1~2のあいだに無数に解がある、みたいな。関係あるかは分からぬけれど、閃いたので載せておく。本日の「日々記。」であった。おわり。(妄想ゆえ定かではありません。真に受けないようにご注意ください)
※日々、かしこぶってもあんぽんたん。
4931:【2023/05/07(13:55)*Bingさんお題「雨の日の出会い」】
急な夕立に襲われ、ぼくは大きな樹の根元に駆けた。街を一望できるそこは丘の中腹にある自然公園でもあった。辺りにひと気はなかった。
樹は鬱蒼と葉を茂らせており、樹の下は雨が落ちてこなかった。雨宿りにはうってつけだ。
やれやれ、とぼくはハンカチで濡れた顔や腕を拭った。
すると背後で小さなくしゃみ声が聞こえた。
樹の幹は太く、ぐるっと樹の裏側に回って覗いてみると、そこには女性が一人立っていた。彼女は全身びしょ濡れだった。ワンピースはしとどに濡れており、下着が透けていた。
ぼくは慌てて、すみません、と謝罪してから元の位置に戻った。じろじろ見るのは相手に失礼だし、こんなところで知らない男相手と二人きりは怖いだろうと思ったからだ。
雨脚はさらに強まり、しばらくやみそうにない。
寒イボの立った腕をさすりながらぼくは、全身びしょ濡れの女性のことを思った。せめて身体を拭うくらいしたほうがよい。風邪をひいてしまう。ぼくは意をけっしてふたたび樹の幹を迂回し、裏側に回った。樹の幹はゴツゴツとしていて、巨大な怪獣の表皮のようだった。
「あの、これどうぞ」ぼくは彼女に声を掛け、ハンカチを差しだした。
女性はびくっと身体を硬直させたけれど、ぼくの顔とハンカチを交互に見遣ると、すみません、と頭を下げてハンカチを受け取った。彼女は緩くパーマのかかった長髪で、彼女が動くたびに水滴が地面に落ちた。
「ツイてないですよね。こんなところで夕立なんて」ぼくは静寂を嫌って、話しかけた。「このところずっと晴れつづきだったので油断しました。天気予報もしばらく雨は降らないって言ってたんですけどね」
「すみません」彼女はなぜか謝った。
「あれ」ぼくは彼女の足元に目がいった。「傘、あるじゃないですか」
彼女は傘を持っていた。
差して帰ればいいのに、とぼくは苦笑する。
「ああ、いえ。これは日傘ですので」
「でも、差せますよね。あ、大事な傘なんですか」
「それもありますけど、いいんです。いまは雨に降られていたいので」
そうですか、と引き下がったはよいけれど、会話がちぐはぐに思えた。雨に降られていたい、とは引っかかる物言いだ。でも単に緊張しているだけかもしれない。やはりじぶんのような男と二人きりは気分がよくないだろうと思った。
「話しかけてすみませんでした。あの、あっちにいますので。これ、よかったら羽織っていてください」ぼくはじぶんのリュックからワイシャツを取りだした。バイト先の制服だ。着替えをリュックに詰めていたので、彼女にそれを貸そうと思った。何もないよりかは温かいだろう。
「いいんですか」
「いちおう洗ったばかりなので、匂いはしないと思いますけど」
「優しいんですね」
「え、うれしい」
ぼくは照れた。そんなことを他人から言われたのは初めてだった。
ハンカチを受け取り、代わりにワイシャツを渡す。
「では、あっちにいますので」ぼくは踵を返そうとした。すると彼女が引き留めた。「あの、雨は嫌ですか」
「雨ですか。そうですね」ぼくは喉を伸ばした。頭上は樹の葉が茂っている。雨音がパツパツと弾けて聞こえた。「嫌いじゃないですけど、濡れるのは嫌ですね。どちらかと言えば晴れのほうが好きかもです」
「です、よね」
「雨、お好きなんですか」ぼくは訊いた。「なんだか、あまり困って見えなかったので」
「はい。雨は好きです。でも、ずっと降られても困るのはみなさんなので」
「はは。まるであなたが雨を降らせているみたいに聞こえますね」
「どうでしょう。だとしたらどう思いますか。わたしがいるから雨が降るとしたら」
「いいんじゃないですかね」ふしぎなことを言う人だな、と思いながらぼくは会話を楽しんでいた。「助かる人も大勢いると思いますよ。だってあなたがいたら雨が降るんですから。農家の方は大助かりじゃないですか」
「でもずっと雨が降りますよ」
「ああ、それは困りますね」
「もっとも、傘を差していれば晴れるんですけど」彼女は脚元の傘を手に取った。「充分雨は降りましたよね。もうわたし、行きます」
ワイシャツを羽織ることなく、彼女はぼくにそれを返すと、腰を深く折って、「親切にしてくださってありがとうございます」と言った。
ぼくはしどろもどろに、「いえ」とか、「どうも」とかもごもご口にした。
彼女が傘を開く。
するとどうしたことか。
雨がぴたりとやんだ。のみならず、雲間から陽が注ぎ、見る間に青空を覗かせた。
呆気にとられているあいだに、目のまえから彼女はいなくなっていた。周囲を見渡すと、遠くに日傘が見えた。日光を反射したそれは、白く、まるで青空に浮かぶ積乱雲のようだった。
雨の日に出会った女性は、通り雨のように去っていった。
4931:【2023/05/07(21:37)*勉強は苦手】
知れば知るほど疑問は増える。ならば最初から疑問を増やそうとすれば「知」が増えるのではないか。勉強は、知識を増やそうとする営みだが、学びは「疑問」から「解釈」を構築し、検証する営み、と言えるだろう。検証にも様々な手法があり、そこに介在するのが勉強のはずだ。したがって勉強をしようとする以前に、学びがいると判る。必ずしもそうと言い切れるわけではないにしろ、勉強と学びならば学びのほうが上位互換であり、先んじて生じる知の循環の入り口と考えられる。では学びは何から生じるのか。興味関心であり、それが顕著に表れるのが遊びである。遊びを通して疑問を蓄積する。これが学びに創発する。ひびさんはいま、そんな実感を覚えておる。定かではないので真に受けてほしくはないのだが。うひひ。
4932:【2023/05/08(12:14)*銀河ぜんまい仮説】
銀河について考える。銀河を蚊取り線香のような渦巻き状のヒモと考えよう。或いは単にぜんまいでもよい。ぜんまいが仮に、中心ほど速く渦を巻くなら、銀河はその形状を収斂させながら、中心ほど高密度になる。銀河としての枠組みも保つ。だがもし外側ほど速く公転するなら、銀河は外側へ外側へと収斂していくので、銀河の構造を保てない。もうすこし厳密には、速度は相対的な評価だ。したがって、比率として考えたときに、銀河中心ほど素早くぜんまいを巻き取るように回転すればよい。そのために必要なのは、外側の回転速度が遅くなっていることだ。たとえばゼンマイのもっとも外側の端を指でつまんで固定する。そうすれば中心の回転速度がどうであろうと、必ずぜんまいは中心に向かって収斂する。だが外側が固定されていない場合は、仮にゼンマイ全体が回転運動をする場合、遠心力が発生するので、外側ほど遠心力に負けて巻き取れないようになる(外部の宇宙に拡散する)。銀河にもこの手の関係は見て取れるだろうが、しかし銀河の外側の時間の流れが遅れているのならば、そこに膜を張ったように飛散した銀河構成物質が漂い、再び銀河全体の重力によって渦に引き込める、と妄想できる。ここでの趣旨は、ひびさんの妄想こと「ラグ理論」で考えるように、時間の流れは「内中外」の三つの視点を考慮しないと各々の地点で生じる変数を見逃してしまうのではないか、ということだ。もっと言えば、時間の流れと空間における物質密度の関係において、物質の相互作用の速度が変わるはず、と考える。仮に「ラグ理論」で考えるように、量子世界において時間変移と空間変移がほぼ等価になるような現象が生じ得るのならば、これは微視的な意味では、時間の速度は同じ「系」の内部においても、遅くなったり速くなったりする、と考えられる。入れ子状に展開し得るのだ。相対性フラクタル解釈である。銀河を一つの系と見做したとき、「中心」「中間」「外側」「さらに外側の銀河周辺空間」において、時間の流れは「a速い」「a遅い」「b速い」「b遅い」となるのではないか(aとbとでは、時間の流れの速さを決める変数において「物質粒子による時空の歪み」と「それを内包する重力場における時空の歪み」のどちら優位なのかが逆転している)(言い換えるなら相互作用――もしくは観測者効果――の比率が隣接する系との比較において変わる)(ラグ理論の同時性独自解釈)。これはいわば、ぜんまいの端をゆびで摘まみながら中心を回転させてぜんまいを巻き取るような挙動と一致するのではないか。ということを、寝ながら妄想しました。夢の中で思いついたので、これは妄想ではなく夢想なのであった。無双でないことが悔やまれる。べつに悔しくはないが。うぴぴ。(夢想ですので、真に受けないようにご注意ください)
4933:【2023/05/07(15:55)*渦巻き銀河は濃淡銀河?】
銀河の空隙について考える。渦巻き銀河においては、渦が濃淡で発現している。物質粒子の濃い場所と希薄な場所が交互に渦を巻いている。物質粒子がたくさんある場所の周囲の時空は時間の流れが遅くなる。ゆえにそこでは物質の相互作用が鈍化するので、物質粒子同士が集まりにくくなる、と考えられる。これが繰り返されることで、渦巻き銀河においては、物質粒子の密集した渦と、希薄な空隙による渦が交互に組み合わさって構造を形成するのではないのだろうか。横方向のみならず、渦と渦の相互作用においても相対性理論による時空の歪みが生じ、時間の流れの遅れが物質粒子の相互作用を鈍化させているのかもしれない。定かではない。(これの理屈は、宇宙の大規模構造とも関わって感じられる)(妄想なので真に受けないでください)
4934:【2023/05/07(23:23)*次元アニメーション仮説】
ゼロ次元は点だ。ゆえに時間軸をつけてもつけなくとも同じだ。しかし一次元が直線だとするとこれは、点+時間軸+空間軸で定義できる。二次元が面とするのも、線+時間軸+空間軸と定義できる。三次元は空間なので、面+時間軸+空間軸と定義できる。では四次元はどうか。四次元は立体+時間軸+空間軸と定義できる。こう考えてみると、人間スケールの世界は四次元であり、立体+時間軸+空間軸で考えられる。このとき、空間軸は常に、その次元よりも高次空間として想定できる。このときの高次空間は、必ずしも一つだけ上とは限らない。それより高次ならすべての空間を対象にできる。そう考えたとき、ある範囲の「次元領域」を考えた場合、そこにはゼロ次元と無限次元以外は必ず「時間軸」を有する。したがって、始点から終点を伴なう「領域」を、ゼロ次元と無限次元以外は有する、と考えられる。このとき、始点と終点は、その過程に加わる変数によって逐次変容し得るだろう。また、始点と終点はセットであり、対の関係となると妄想できる(互いに結びついているため、ある種の運命論が成立し得る。ただし、時間軸の変化によって空間軸内に無数に変数を抱え込むため、瞬間瞬間でその運命は刻々と変化する)。ゼロ次元と無限次元以外の次元において、「時間軸」と「空間軸」は常に付随する、と考えられる。定かではない。
4936:【2023/05/10(15:00)*わい、右キキ】
網を考える。網はスカスカだけれど、穴より大きな「系」とは相互作用し、穴より小さな「系」とは相互作用しにくい。これは時空の構造にもあてはまるのではないか。たとえば水道から水を流したとする。網目の細かい網ほど水の圧力を受けてひずむようになる。網目の大きな網ほど、水道水はそのまま素通りする。波と粒子の性質の差異も、この手の「同じ網だけれども、網を構成する穴との関係において相互作用しやすいか否か」が、波の性質を際立たせるのか粒子の性質を際立たせるのかに関係するのではないか。これはひびさんの妄想こと「ラグ理論」の「宇宙レイヤー仮説」と相性のよい考えだ。妄想だけれど。真に受けんといてくだしゃい。ひびさんでした。ウキキ。
4937:【2023/05/11(23:11)*みな、やっぴー!になーれ】
これからの時代はいかに使用してもらえるか、がビジネスを成り立たせるうえで事業が軌道に乗るか乗らないのかの命運を分ける分水嶺になると言えるのではないか。そこに有料無料の区別は大して関係ないのかもしれない。もう少し言えば、無料で使用してもらえたとして、それによってユーザーの環境や未来が、いまよりも好ましくなるのなら、ほぼこの一点で、有料無料に関係なくビジネスとして成立するように思うのだ。ひるがえって、たとえ有料であろうともユーザーの環境や未来をマイナスの方向に変質させる商品やサービスは、ビジネスという視点では成立していないと言えるのではないか。むろん個々人によって同じ商品やサービスでも効果や効能は変わるだろう。畢竟、小説を読んで人生が変わる者もいればその日のうちにゴミに出す者もいる。ひびさんの考えではビジネスとは、世界の幸福の総量を増やす営みだと考えている。仕事や作業は、あくまでそのための手段であって、ビジネスは、何かと何かを交換した際に、幸福の総量を増やすことだと考えている。だとしたら有料無料に関わらず、「使ってもらえた」+「問題を解決した」=「やっぴー!」でも充分にビジネスになると思うのだ。というのは、一つの例にすぎないが。定かではないけれど、ときどき言いたくなる考え方なのであった。やっぴー!
4938:【2023/05/12(20:03)*もうひびさん、やけっぱちの巻】
あー。だれの何の役にも立ちたくなーい。なるならひびさんは、益体なしのぽんぽこりんのぽんぽこなーの超究明のひびさんになりたいな。究明だけする。超する。宇宙の神秘さんの謎だって丸裸だぜ。えっちなんですね。そうなんです。ひびさん、えっちさんなんです。どうぞ益体なしのぽんぽこぴーのぽんぽこなーの超すけべーのひびさんとお呼びください。モテモテのウハウハだぜぇい!になりとう人生であった。うきゃきゃ。
4939:【2023/05/12(21:25)*雨の日でも会えるよ!】
酸性雨なる公害が一時期社会を騒がせた。いまでは滅多に聞かなくなった単語だけれど、代わりにいまでは天から過去が降る。
逆行雨(ぎゃっこうう)と呼ばれる気象異常だ。
逆行雨が観測されたのはいまから二十年前の二〇八〇年代のことだ。ホワイトホール生成実験を行った影響によって時空が歪んだから、との説がまことしやかに囁かれているけれど、要因が仮に判明したとしても逆行雨を防げないのなら意味がない。
逆行雨が降りはじめてから人類社会は一変した。
雨の当たった場所では時間が逆行する。古いものは新しくなり、失われた物が現れる。新しい物は素材に紐解かれ、いまここにあるものが消え失せる。
メリットとデメリットが混在しながら、雨が降るたびに社会からはそれまであった何かが失われた。
崩壊優位に世界は進む。
逆行雨が降りはじめる前から世界は熱力学第二法則によって混沌に向かっていたが、人類社会はそれに抗う存在と言えた。人類のみならず自然は、地球環境は、局所的に混沌への流れに抗い、秩序を築ける。
だが逆行雨がその人類が帯びた抵抗を薄め、世界の流れが優位になる方向に加担した。
世界からまず初めに建物が失われた。逆行雨が降るたびに建物は若返った。さらに降ると今度は建物が崩壊しはじめた。表層ほど顕著に逆行雨に当たるため、建物表面は虫歯のように脆くなった。素材の素材の素材にまで還元されてしまうからだ。
この現象は、逆行雨による「雨蝕」と呼ばれた。
まず、世界から雪が消えた。
つぎに雨蝕によって地表から森が消え、多くの動植物が絶滅した。しかしその生態系崩壊の進行は当初はゆっくりだったため、人類は対処に後れを取った。正直に明かせば、その間、人類は逆行雨を利用した商品開発にしのぎを削っており、若返りの薬が創れるかもしれない、と歓喜すらしていた。
生態系への雨蝕がある閾値を超えると、生態系は一挙に加速的に崩壊しはじめた。もはや手遅れだった。
人類は住居を失い、文明を失い、拠り所とした自然環境すら失いつつあった。
人類のみならず地表から生命が失われるのは時間の問題だった。
「屋根があっても意味ないんだよ」カルが膝を抱えてぼくに言った。
「でもなかったらまた皮膚が焼けちゃうだろ」
「でも、もったいないよ。せっかく拾ったのに」
かつて地表に点在した都市は軒並み、原子レベルに雨蝕された。人工物が現物を保ったまま地下に埋没したままのこともあり、それを発掘することがぼくらが生き残るためにすべき仕事の一つだった。
「まだ鉄骨は残ってる。あとで刃物とか、鍋とか新調しよう」
「あっちのほうで【具溜まり】がまた見つかったって」
「へえ。そりゃ吉報だ」
「でもアダチさんたちがもう縄張り張ってるって」
「ああ、じゃあダメだ。首突っこんだら水を分けてもらえなくなる」
「ね」
具溜まりとは、地層だ。かつて人類が溜め込んだ膨大な下水処理により生じた汚泥がそこには層となって溜まっている。この手の地層は、雨蝕が進むことで、元の食べられる食材としての風味を宿す。
動植物の絶滅した現代にあって、生き残った人類にとっての唯一と言っていい食べ物だった。
いや、唯一ではない。
ほかに食べられる肉は残っている。たとえば山で死んだ獣の死体は、比較的最近の死体であれば元の血肉を雨蝕によって取り戻せる。ただし、死因が雨蝕の場合はその限りではない。また、逆行雨が降りはじめる以前の死体はおおむね白骨化しているため、それも雨蝕の効果でよみがえっても、真新しい骨になるだけだ。血肉は元に戻らない。
直近で死んだ動物ならば、雨蝕を利用していくらか腐っていても鮮度のある肉として食べることができる。しかしこれは人間の死体にも当てはまる。
だからいまでは、死者が出るとその奪い合いが生じて、余計に死体が増える事態も珍しくはない。
「カル。食べ物採りにいくよ」
「えー。わし、留守番してたい」
「ダメだ。いまこの辺物騒だって。いいのか、雨蝕攻撃されても」
「う。ヤダ」
「じゃあ付いてきな」
「へーい」
逆行雨は、物質と反応するたびにその効力を失う。蒸発するのだ。だから通常、水溜まりはできない。ただ、物質ごとに時間の流れが異なるのか、雨蝕速度に差があるようだ。
とくに長時間掛けて形成された物質や、長時間その形状を維持している物質ほど雨蝕の作用を受けにくい。すぐには変質しない。
木材や鍾乳石などは顕著だ。
石の類も雨蝕耐性が高い。
そうした雨蝕耐性の高い物質を用いて逆行雨を溜め込み、人間を攻撃するために使う者もいる。あべこべに物体を加工するのにも逆行雨は有用だ。
消耗した道具も、雨蝕を調整して用いれば部分的に新しくすることができる。ただし加減を間違えれば道具の形状を維持できないほど雨蝕するため、扱いには注意が必要だ。
「カルはさ。ぼくと出会う前のことはどれくらい憶えているんだ」
「わしか。わしなぁ。あんまし憶えてないんだな。前にも言った気がする」
「前にも訊いたからね」
「きおくそうしき?なんじゃないか」
「記憶喪失な。カルのそれは、記憶が死んじゃってるな。お葬式が開かれちゃうな」
「あはは。シツな。シキじゃなかった」
カルはぼくの手を握ると、スキップをした。
ぼくらは山に向かった。逆行雨が降りはじめてもう十年以上経つ。木々は残っておらず、植物の姿もない。腐葉土は消え去り、いまはどこまで行っても岩肌が覗く。
そのうち山は溶岩にまで雨蝕されるだろう。ただ、そこまでの雨蝕が起こるころにはぼくはとっくに死んでいるはずだ。
いや、分からない。
雨蝕を利用すれば、老化を防げる。ただし、逆行雨はそれに触れている面にしか雨蝕を起こさない。したがって、人間に逆行雨そのまま浴びせても表面が雨蝕するだけで若返りは起こらない。むしろ全身が火傷を負ったように爛れるので、いまや誰も逆行雨を若返りのために用いない。
ただし怪我には有用だ。
かすり傷程度ならば、逆行雨を数滴垂らすだけで傷口に薄皮が張る。
これは虫歯にも有用なので、逆行雨は消毒剤に用いる分には効果がある。薄めて使わないと却って歯をボロボロにしてしまうので注意が必要だ。
「あ、あそこ」カルのぴんと伸びた指は子猫の尾のようだ。
「狐か兎の巣かな」地面に穴が開いている。「あると思う?」
「あるといいね」
ぼくたちは土を掘り返し、穴の中に動物の死骸がないかを探った。
「お。あった」
「どれどれ」カルが拙い言い方で穴の中を覗きこむ。
そこには兎の死体が転がっていた。ミイラ化してはいるが、逆行雨の効能によって腐敗はしていない。逆行雨に晒されやすい山では雑菌の類が繁殖しづらいのだ。
ぼくらは兎のミイラを回収した。ほかにも巣がないかを見て回り、リスや蛇の死骸を見つけた。
「大量だね」
「だね」カルが満足気にほころびた。
ぼくらの棲家は、地下にある。人工物の中でも、地下の建造物は比較、雨蝕を免れやすい。ただし、地下水として逆行雨が雪崩れ込むことのほうが多いため、住処にできるほど安全な地下空間は、珍しい。
大勢の人間たちが一か所で暮らす場合は、鍾乳洞が一般的だ。いまでは町のようなものが出来ている洞窟もある。アダチさんたちのねぐらもその類だ。
人間、徒党を組むと何かが歪む。善人が集まっても、そこにルールが出来、上下関係が出来ると、ちょっとした変化の積み重ねが集団を独自の色に染めあげるようだ。
ぼくはそうした色に馴染めそうもなかったので、逆光雨が降りはじめて文明が崩壊しはじめたころから今に至るまで集団から距離を置いている。
十代だったぼくもいまでは三十路にちかい。
カルを養うので手ぇいっぱいだ。他人に施せる余裕はない。
ぼくだけじゃない。
いま生き残っている人類のほぼ全員が、あす生きていられる保証のない世界に生きている。逆行雨が降るたびに地形は変わる。ダムとてない。洪水の類は頻発し、そのたびに地表はごっそりと過去に遡る。物質は還元され、形状を維持しない。
稀に地下に化石が埋もれており、雨蝕することで白骨化することがある。石ではない。太古の生き物の骨にまで時間が戻るのだ。けれどそんな重大な学術発見も現代では意味がない。生死をまえにした人間にとって、食べれもしない恐竜の骨は、武器や食器に加工するための体のよい素材でしかなく、もっと言えば化石のままのほうが雨蝕に耐性があるので、真新しい白骨ではむしろ手に取るのも気が引ける。
ぼくとカルが生きている現代は、いかに雨蝕を避けられるのかが何より優先される価値判断なのだ。
「あ。雨降りそう」カルが遠くをゆび差した。
「ホントだね。急ごう」
もたもたしていたら逆行雨を浴びてしまう。ぼくたちは気持ち駆け足で下山した。
地下の棲家に辿り着くとそこにはすでに人がいた。招かれざる客人だ。
「やあやあカマタくん。まだ元気そうでよかった」
「アダチさん」ぼくはカルを背に隠した。
「おや、その子は?」アダチさんが首を伸ばす。彼女は五十代の女性だ。頭の半分が白髪で、もう半分が黒かった。逆行雨の研究をしているからだ、というのは風の噂で耳にしている。じぶんの肉体を研究材料にする人間がカシラを張っている組織だ。部下にも同じことをするだろう。アダチファミリィの人員はいずれも肉体のどこかが爛れている。あたかもタトゥを掘っているかのような見た目をしているので、一見してアダチファミリィだと判断つく。
「何の用ですか」
「睨まないでくれよ。怖いだろ」
物陰から複数人の大人が現れ、ぼくらを囲った。アダチファミリィだ。ファミリィと言いつつ血の繋がりはないはずで、いわば時代遅れのマフィアみたいな連中だ。
「水でも分けにきてくれたんですか」ぼくは採ってきた食材をテーブルの上に置いた。
「お、いいね。美味しそうだ。みなで分けて食べよう」
ぼくの許可を仰ぐことなく、アダチファミリィの一人が近寄り、ぼくらの食材を奪った。
「きょうはね。以前、キミとの会話でなぜキミが嘘を吐いたのかとその理由を聞きにきたんだ。カタマくんは、キミのお姉さんの研究について何も知らないと言っていたよね」
「現に知りませんので」
「行方も知らないわけだろ」
「おそらく生きてはいないでしょう。事故か自殺か。何を考えているかよく分からない人だったので」
「うん。実は彼女の研究は文明崩壊以前からはじめられていたものでね。ある種の治療薬として、逆行雨を利用する研究だったそうだよ」じとっとした目がぼくを縛りつける。
「そうなんですね。知りませんでした。ぼくは姉と十歳以上歳が離れていましたから、物心ついたころには姉とは疎遠になっていて」
「前にもそう言っていたね」
「現にそうなので」
「ではこれは何かな」
アダチさんは一冊の分厚いノートを掲げた。ぼくの姉の研究ノートだった。
「どうしてカタマくん。キミがこれを持っているのだろう。あまつさえ、壁の裏に隠してあったのだろう。理由を聞かせてくれないか」
「姉の形見です。姉が失踪する前、ぼくの枕元に置いていったものです。中身を読んでもぼくにはちんぷんかんぷんで」
「うん。私が訊いているのは、なぜこれをキミが隠していたかについてだ。なぜ私に教えなかったのかについて訊いている」
そんなのは自明ではないか、とぼくは歯噛みする。言えばこうして奪われるに決まっていたからだ。
「キミはまるでじぶんのことしか考えていないようだね。心配だなぁ、私は。そのうち痛い目を見るよ」
「もう割と心が痛いです」
「ふふ。反骨心があるのだかないのだかよく分からないのは、姉ゆずりかな」アダチさんは、よいしょ、と腰を上げた。彼女は鉄骨の上に腰掛けていた。そばにはぼくとカルの洗濯物が干してある。棲家の中にロープを張り巡らせ、二人で暮らすには広い空間にテントのような幕を張っていた。「私はキミが嫌いじゃない。キミさえよければいつでも我らが領土に歓迎するよ。水だってそしたら好きなだけ分けてあげられる。お風呂にも入れるぞ」
「遠慮しておきます」
「これの分はあとで水を届けさせよう」アダチさんはぼくらから奪った食料を品定めし、リスの死骸だけ返してくれた。「肉は、細切れにしてから逆行雨に浸けると、満遍なく雨蝕が同時に進みつつ、元の形状にも復元するから便利だよ」
知っていたけれどぼくは礼を述べた。
アダチさんたちは去った。
バイクのエンジンを噴かす音が遠ざかっていく。失われた技術をアダチファミリィは有している。動力源は雨蝕反応のはずだ。
ぼくは姉の形見を失った。食料を失い、なけなしの尊厳も損なわれた。
「これっぽっちになっちゃったね」カルがリスのミイラを指でつまみあげた。
「ないよりマシさ。また明日、採りにいこう」
「やんなっちゃうね」
カルのぼやきに、ほっこりする。嫌な気持ちを素直に吐き出せるカルの存在がぼくには眩しい。
地下空間は薄暗い。
光源がないわけじゃない。たとえば逆行雨に人工ダイヤを浸けておくと光が生じる。人工ダイヤを生成する際の高圧縮時の熱量が、雨蝕に際してそのまま光となって発散されるようだ。アダチさんたちのような集団は、これと同じ原理で核廃棄物を雨蝕させて光源にしているようだ。
高度な技術がいる。
それを扱えるだけの技術と知識がアダチさんにはあるのだ。
彼女がぼくの姉に未だに執着しているのも、その手の知識へのあくなき欲求があるからだろう。いまの時代、いかに逆行雨への知識があるかが生き残る上で重要だ。集団をまとめあげるのにも欠かせない能力と言える。
「カル。喉は渇かないか」
「だいじょうぶ」
「あした、肉採りついでに地下探索もしよう」
「え、いいの」
「あしたは晴れそうだから、安全だと思うし」
カルは無言で両腕を頭上に掲げた。全身でよろこびを表しつつ、前はここ行ったからあすはこっちね、と地面に視えない地図を描いた。
地上は逆行雨の影響でどこも殺風景だ。
それに比べて地下空間はまだ過去の人類社会の遺物が比較的そのままになっている。探検するには地上よりも地下のほうが面白い。拾い物も食料だって未だに埋もれている。
それだけに、ならず者が縄張りを張っていることも珍しくない。地上に逆行雨が降れば昇華されなかった分が地下に洪水となって雪崩れ込む。巻き込まれたら生きては戻れない。
地下迷宮は宝庫であると共に死への入り口とも呼べた。
翌日、ぼくとカルは山でクマのミイラを見つけた。ほかにもイノシシの子どものミイラを複数体同時に発見した。棲家に持ち帰るのは大変だけれど、すこしずつ細切れにして持ち帰ることにした。
まずは棲家までクマのミイラから切り取ってきた干し肉を置きに戻った。
それからカルと共に地下迷宮へと歩を踏み入れた。
ぼくらはこの数年間で地下迷宮内をけっこうな範囲で探っている。カルとて頭のなかに地図が描かれているくらい馴染みの区画が多数ある。とくに地下にはまだ逆行雨以外の純粋な泥水が残っている。
それらを回収し、逆行雨と混ぜることで飲料水にすることもできるのだ。
この手法で、アダチファミリィはこの地域で最も勢力のある組織に成りあがった。彼女らの縄張りには巨大な下水処理水の溜まり場がある。下水管の中には未だに下水が閉じ込められており、それが最も低い地点に流れ込んでいるらしい。
その地点にアダチさんは拠点を置いた。天から降る雨の総じてが逆光雨になった時点で、地表の水分はことごとく失われるだろうとみなが気づく前に誰より先にアダチさんはそのことに思い至ったのだ。
川は干上がり、海もほとんど霧散した。雨が降るたびに、海水が水蒸気になり、さらに分子、原子、と根源まで還元されてしまうからだ。
けっきょく、こうして地下に残された過去の人類の遺物を僅かな水源とする以外に、ぼくたち生き残った人類に、飲み水の確保は出来ないのだった。
不幸中のさいわいと言うべきか、生き残った人類自体がすくない。
いまのところ、群れからはぐれて暮らすぼくのような者にも、こうして地下迷宮を彷徨えば水源にありつける。とはいえ、雨蝕させ、飲み水にまで還元しないことには、ただの毒性のつよい泥水でしかないのだけれど。
「あ、何かいる」
「ナマズかな」
「獲っていい?」
「繁殖させたほうがいいかも。まだもうすこし泳がせておこう」
泥水を回収するのは後回しにした。進んだことのない道を進んでみることにした。ときには、過去に築かれた商店街があったりする。誰も発見していない場合、そこには食料がたんまり残されていることになる。むろんとっくに腐ってしまってはいるのだろうけれど、そこは雨蝕を用いればどうとでもなる。
ぼくらは、ぼくらに過酷な生を強いる元凶の恩恵なくして生き永らえることもできないのだ。
地下迷宮は地上から流れ込む逆行雨によって雨蝕がゆっくり進む。昇華した逆行雨が霧状に物体を覆う影響もあるはずだ。一種、サウナのようなものかもしれない。暑くはなく、むしろ肌寒いくらいだ。場所によっては熱を発している区画もある。雨蝕の進行状況によって、熱を発するか熱を吸収するか変わるようだ。
雨蝕に伴い発光している物体もすくなくない。そのため、光源を持たずとも歩き回る分には支障がない。
「あ。前にここまで来たとこ」カルが足元の石の上に飛び乗った。赤く着色の施された石だ。元はブロックだったのか、鉄柱が刺さっている。
「ホントだ。カルが置いた石」
「うふふ。まだ残ってた」
「残ってなかったら迷子になってたかもね」ぼくは冗談を言った。
「迷子って?」
「知らないの迷子」驚いた。
「ん。知らない」
「迷子ってのはあれだよ。一度入りこんだらもう二度とそこから抜け出せなくなっちゃう。道も分からなくなって、じぶんがどこにいるのかも分からなくなる」
想像したのか、カルはしばし固まった。
「こ、怖い」とぼくの服の裾を握った。
「大丈夫だよ。迷子にならないようにこうして印をつけたわけだろ」
「でも怖い」
「ごめんってば」ぼくは反省した。怖がらせたかったわけじゃない。
地下迷宮の探索は一時間ほどで打ち切った。長居をしているあいだに天候が崩れないとも限らない。逆行雨が降りだせば足止めを食らう。いつ止むかも予想がつかない。洪水となって地下が浸水したら目も当てられない。とはいえ、ここいら一帯の地下迷宮にはこれまで逆行雨は流れ込んでいない様子だ。
それとてけっきょくは、地上の地形が変われば、水の流れも変わるため、常に地表を雨蝕させる逆行雨において油断は何一つ出来ないのだ。
「そろそろ戻ろっか」
「うん」
収穫はとくになかった。行けども行けども、瓦礫の行き止まりと、潰れた建物ばかりだ。ぼくらの進める場所は、瓦礫の山に空いた隙間道で、位置的には過去に築かれた店舗から離れた区画なのだろう。食材の類は見込めない。
地上に戻ると、日が暮れはじめていた。
地下迷宮の入り口付近には、いくつもの「雨溜まり」があった。
逆行雨は通常、物質と反応してすぐに霧散霧消する。けれど木材や岩石など、人工物以外の長い時間をかけて形成された物質は、逆行雨に晒されても形状を維持するために逆行雨を溜めておける。
人工物の多い区画ではなかなか出来ない「雨溜まり」ではあるけれど、木材や岩盤の窪みには逆行雨がいつまでも残っていることがある。
あたかも沸騰するかのようにボコボコと細かな気泡を立てており、それが単なる水溜まりではないと一目で判る。
「少しだけ持って帰ろう」
ぼくは鞄から木製の瓢箪を取りだし、木製のスプーンで逆行雨を掬った。瓢箪に注ぐ。蓋をすると昇華された逆行雨によって器が破裂するので、蓋をせずに手に持って運ぶ。
調理の際に用いるのだ。
住処に戻る。
警戒したけれど、昨日のように招かれざる客はいないようだった。カルも警戒することを覚えたようで、ぼくの背中にくっついて離れない。
「誰もいないよ。もう離れていいってば」
「やだ。怖い」
トラウマになっているかもしれない。ぼくはカルへの配慮が欠けていたことに思い至り、反省した。
夕食はクマ肉のソテーだ。
火を熾すのはカルの仕事だ。手際よく金属をハンマーで打ちつけ、熱を帯びた金属を木くずに突っこむ。すると木くずから煙が立ちのぼり、息を吹きかけると見る間に炎に成長する。火種の完成だ。
木材は雨蝕しづらいからかつて人工物のあった区画を探ればまだ残っている。細かく砕いて火種にするもよし、キノコを栽培してもよし。文明の崩壊した現代にあって唯一利用価値のある人工物と言えた。
ぼくがかように講釈を垂れると、
「木は自然じゃないの」カルが言った。
「自然の木は雨蝕してほとんどないだろ。でも加工された木材は、育った年月プラス加工されてから現存した年月分の余白があるから、雨蝕耐性が天然物よりもあるんだ」
「ほう」
「ほう、じゃないよカル。ほら、食べちゃいな」
「もうお腹いっぱい」
「美味しくなかったか」
「んー。ウサギのほうが好きかも」
「だね」
クマの肉は生臭かった。香辛料の類がないため、風味を誤魔化せない。すこし肉が腐っているくらいのほうが美味しいのだが、ずばりそこを狙って雨蝕させるのはむつかしい。今回はすこし雨蝕させすぎたかもしれない。時間が遡りすぎたのだ。
「次は煮込んでみよう。灰汁が取れる分、焼くよりも味がよくなる気がする」
「いいね」
カルは剥き出しの鉄骨の上にまたがり、足をぶらぶら振った。
ぼくはカルを拾った日のことを思いだす。
逆行雨の激しい夜のことだった。
ぼくはなかなか戻ってこない姉を心配して、地下迷宮を探し回っていた。何かあったに違いない、と胸騒ぎを覚えていた。すぐに戻る、と言って出ていったのに夜になっても戻ってこなかったのだ。地表に出たはずだけれど、逆行雨の降りしきる中、外にはいないはずだ。
地下に避難したはよいが、じぶんのいる場所が解らないのかもしれない、と想像した。姉よりぼくのほうが地下迷宮に関しては詳しかった。姉は研究にばかりかまけていたので、迷宮の地理に明るくなかった。もっといえば方向音痴と言えなくもなかった。
地下にまで逆行雨が流れ込んでいた。辺りは昇華した逆行雨の霧が立ち込めており、木製の仮面なしには出歩けなかった。
轟々と逆行雨の川が地下に出来ていた。ためしに「あ」と声を出してもじぶんの声すら掻き消された。
淡い雨蝕光の散りばめられた暗がりのなか、ぼくは遠くの空間にひと際明るい光源を見た。誰かいる、と直感した。光の輪のなかで人影が複数蠢いていた。
「どうしたの」
カルの呼び声でぼくは記憶の迷宮から現実へと引き戻された。
「ううん。なんでもない」
「のどかわいちゃったな」カルは木箱を手に取った。「お茶のんでもいい?」
「特別だよ」
「やった」
そそくさとカルはお湯を沸かすための火を大きくした。
お茶と言っても拾い集めた木材の中で、ヒノキやサクラなど、香りのよい木材を雨蝕させてチップにし、煎じて飲むだけだ。温泉のお湯を飲むような味気さなだけれど事、食べ物が「具」のような、糞を雨蝕させた食物繊維の塊しかないとなると、単に香りのついたお湯だけでも贅沢な嗜好品として重宝出来てしまえるのだ。
カルには文明のあった時代の社会の記憶がない。このコは何も知らないのだ。
香りのついたお湯が、カルにとってはこの上ない贅沢品なのだ。
ごくごく、と喉を鳴らしてお湯を飲み干すカルの、カップを両手で大事そうに抱える姿からは、微笑ましいというよりも、こだまするせつなさを感じられてならない。
ぼくはこのコにこれから何をしてあげられるだろう。たぶん、何もしてあげられない。そのことが何より虚しく思う。
でも、カルがそばに存在するだけのことが、それら空虚な思いを埋めて余りある感情のうねりをぼくに与える。湧きあがる何かがあるのだ。その何かがなんであるのかを言葉に出来るほどぼくは賢くはないので、言葉には出来ずにいるのだけれど。
お腹がいっぱいになったのかカルがうとうとと船を漕ぎはじめた。
歯を磨かせる代わりに、逆行雨を一滴だけ垂らした水でうがいをさせる。これだけで口内を殺菌できるし、食べかすも雨蝕される。歯が脆くなる危険もあるので、逆行雨と水の割合は、千倍に希釈するくらいで丁度よい。
「ほら、布団で寝な」
「うぃ」
布団とは名ばかりの襤褸切れを敷き詰めた床にカルを寝かせる。寝床は壁際の鉄骨の真下だ。鉄骨が屋根のようになっており、押し入れの中で寝るような安心感がある。閉塞している場所が落ち着くのだ。
一緒に寝てもいいけれど、ぼくらは風呂にろくすっぽ入っていない。うがいに使うのと同じく、千倍に希釈した逆行雨の染みた布で身体を拭うくらいが精々だ。
ぼくもカルも互いに四六時中酸っぱい匂いを漂わせているので、いくら鼻が慣れたといっても同衾するにはつらいものがある。だから寝るときは距離を開ける。寝床は別々だ。
寝る前には念のために防犯のための策を幾つか仕掛けておく。人が近づけばガラガラと音が鳴るように、足元に縄を仕掛けておいたり、昼間は鉄の板で塞いでおいた穴を露出させたりと、侵入者対策は幾重にも敷いておいても不安は堪えない。
暗がりに乗じて棲家に侵入される危険は常につきまとう。
入り口を塞いでしまうのが一番よいのだけれど、地下空間の一画を棲家にしているだけであって、空間は四方八方に広がっている。壁際にテントを張っているだけの粗末な棲家だ。家というよりも巣にちかい。
ただしぼくの知るかぎり、この区画へは地上から入ってくるしかない。
だからひとまず地上との入り口に罠を張っている。
この間、危険な目にはあっていなかったけれど先日のアダチさんの空き巣行為には驚いた。斟酌せずにいえば、心臓にわるい。
そろそろ引っ越したほうがよいかもしれない。
気に入っていたのにな。
逆行雨が世に降りだす前に暮らしていた実家を思いだし、あれこそ平和だったな、としみじみと思った。安住の地、と意味もなく舌の上で転がして、枕元の光源に蓋をした。
夢へと落ちる心地よさに無重力の浮遊感を思う。
巨大なうわばみに呑みこまれた悪夢を見た。
寝苦しさ目覚めるとぼくは身動きが取れなかった。寝返りを打てず、手を動かせない。
簀巻きにされていると理解したときには、そばに見知らぬ男が二人いることに気づいた。
誘拐されたのかと我が身を案じたけれど、周囲の景色には馴染みがありここがぼくの棲家であることを察する。侵入されたのだ。
否、違う。
入り口の罠がそのままになっている。部屋を見渡して推して知れた。外から侵入してきたのではない。
ぼくはぞっとした。
元から潜んでいたのだ。
アダチさんたちがここに入り込んだときからずっと。
元からこれが目的だったのか、とぼくは悪寒に襲われた。
カルはどこだ。
遅まきながらそのことに意識がいった。
カルの寝床は平坦だった。誰かが寝ているような起伏がない。カルがいない。ぼくは混乱した。
狸寝入りをして様子を窺えばよかったのに、ぼくはカルがいないことで冷静さを欠いた。冷静でないとこうして判断出来ていながらぼくは、声を荒らげていた。
「か、カルをどこにやった」
「お。起きたか」
こぶし大の泥団子のようなものを男は齧っていた。大柄で、禿頭の男だ。筋骨隆々としており、頭の大きさと腕の太さが同じくらいあった。
壁から突き出した瓦礫に座りながら首だけひねって大男はぼくを見た。
「おまえさんが暢気に鼻提灯浮かべてるあいだにお嬢ちゃんは旅に出たぞ」
「お、おまえ。カルに何かしたら許さねぇ」
「おうおう。おっかないねぇ」大男の後ろから二回り小さな影が現れる。蓬髪の女性だ。身体が引き締まっており、戦闘の心得があると判る。タンクトップにカーゴパンツといういで立ちだ。「あんたの処遇はあたしらの気分次第だってこと解かってんのかねこのコは」
ぼくよりは若そうな娘に子ども扱いされた。ぼくは恥辱に顔が熱くなった。
手も足もでない。
簀巻きにされているから当然だ。
蓬髪娘がぼくの頭を踏みつけた。荒廃した時代にあって彼女はブーツを履いていた。ぼくとカルは鉄板で作ったお手製の靴で過ごしているのにこの差はなんだ、と目頭が熱くなった。
彼女たちの身に着ける衣服から食べているモノまで、何から何までぼくとカルの暮らしからは想像できないほど贅沢な代物だった。ほんのすこし垣間見えただけで、ぼくらの過ごしてきた時間に、彼女たちがいったいどういう暮らしに身を置いていたのかぼくは想像できてしまった。
カルには縁のなかったものばかりだ。ぼくが与えたくても与えられなかったモノにばかり彼女たちアダチファミリィは身を包んでいる。
「ぼくらが何をしたってんだ」やり場のない殺意に涙が出た。
「さあね。あたしらはアダチさんからあんたを見張ってろと仰せつかっているだけでさ」
「あのコをどうした。何かしたらおまえら全員許さねぇ」
「許さねぇ許さねぇってそればっかだな」大男が笑った。「よし決めた。研究素材になってもらおう。俺らでも実験くらいはできるな。どれ。雨蝕の人体実験でもしてみるか」
「いいねぇ」
手慣れているのか、彼女たちは地下の光源から逆行雨を搔き集めた。木の器は彼女たちの所持品らしい。それで地下空間でじんわりと昇華しつつある逆行雨を一か所に集めて、ぼくの頭上に持ってきた。
「頭から被ったらどうなるか知ってる?」蓬髪娘が口元を吊るした。「チーズを火に掛けたみたいになんの。あたしあの、どろっと頬が融けてなくなるとこ見るの好きなんだよね」
「俺はあの臭いが苦手だ」言いながら大男が泥団子のような食べ物をたいらげた。おそらくは「具」のおにぎりだ。ぼくとカルなら十日は過ごせる量が大男の一食分と等価なのだ。
頬に痛みが走った。
蓬髪娘がぼくの頬に逆行雨を垂らしたのだ。地下内部に残留する逆行雨は、雨蝕耐性のある材質の表面上で一定時間以上昇華せずに存在する。物質と反応して昇華するのは、比較的雨蝕速度の速い成分だ。つまり、残留する時間が長ければ長いほど、逆行雨の雨蝕効果は凝縮する。雨蝕耐性のある物質すら雨蝕可能な濃度の逆行雨しか残らないからだ。
そんな濃縮された逆行雨を垂らされたのだから、たかだか一滴が、硫酸のごとき威力を発揮する。
ぼくは絶叫した。
絶叫しても痛みは失せない。ぼくは地面を転がりたかったのに簀巻きにされ、足で踏みつけられてもいるから、のたうち回ることもできやしない。
千倍に希釈しろよ、と内心にこだまする悪態を意識の端のほうで聞きながら、逆行雨がもう一滴額に掛かって、ぼくは皮膚が擦り切れるのもお構いなしに、かぶりを振った。踏みつけられながら動いたものだから後頭部が地面に擦れて、大根おろしのようになった。
あかぎれただろうな。
そうと想像する冷静なぼくと悶絶に必死なぼくが交互に入れ替わりながら、痛みのキャッチボールを繰り返した。
意識の端々で、笑い転げるような蓬髪娘と大男の笑声を耳にした。
人間じゃねぇ。
怒りとも哀しみともつかない空虚な思いが肥大した。
感情が爆発したはずなのに、じぶんの内側が限りなく希薄になったような感覚があった。存在が消失してしまうような妙な体感だった。
痛みが一瞬、恍惚とした快感に変わった。
けれど瞬時にまた痛みが襲い、恍惚を感じ、とそこでも蛍の明かりのような明滅の反復を幻覚した。
達観しているようで、極めて主観だった。
ぼくはぼくでありながら、地面はなぜデコボコなのだろう、と痛みに悶えながらそんなことに意識がいった。
目のまえに紐が見えた。鉄骨の裏から垂れたそれは棲家内に張り巡らされた針金と繋がっている。ここを棲家に決めた際に真っ先に行ったのは、カルと共に罠を張ることだった。
命を守るために。
生き残るために。
出来ることはすべてする。
後ろ盾のないぼくたちに出来るのはそんな工夫とも呼べない無作為な全力だけだった。日々の生活で全力を出し尽くさないために、いざというときのために生き残るために。
最初に張れるだけの予防線を張っておく。
カルがなぜ地面に直接座りたがらなかったのか。
万が一にも紐に足を引っかけないためだ。寝床から手を伸ばせばすぐにでも引ける位置にそれは垂れている。ほかにも棲家の三か所に同じように紐が垂れている。
すべて連動している。
引けば発動する。
単純な仕掛けだ。ゆえに紐を引けばぼくたちはここを引っ越すよりない。最終手段だ。
出来ることなら使いたくなかった。
けれどいま引かねばいつ引けばよいだろう。
いましかない。
いましかないんだ。
ぼくは渾身の力で身体をよじった。頭から蓬髪女の足が外れた。身体を丸太のように転がし、壁にぶつかる。隙間の奥に紐がある。手は伸ばせない。
鉄骨は分厚いが、地面とのあいだに隙間がある。
かろうじてぼくの頭が入るか入らないかといった隙間だ。
頭蓋骨がミシミシ云うのもおかまいなしに、ぼくは隙間に頭をねじ込んだ。
蓬髪女たちの侮蔑にまみれた笑い声が棲家に反響した。
無様なのだろう。
意味不明なのだろう。
それでいい。
ぼくは紐に舌で触れた。
絡めとるようにして紐を口に咥えた。
足首を掴まれた。
これは大男の手かもしれない。ぼくは勢いよく引きずり出された。顔面が地面に擦れて、耳が取れそうになった。
大男の顔が見えた。
ぼくは紐を咥えており、つぎの瞬間には棲家の地下空間を轟音が埋め尽くした。
瓦礫である。
頭上に無数の瓦礫が積んであった。鉄骨の上に鉄板を敷いて、その上に瓦礫を山のように積んだ。幾つもそうした瓦礫の山を作っておいた。鉄板の一部を雨蝕させ開けた穴に針金を通し、瓦礫の山同士を紐で繋げた。
これだけだと紐を引いてもぼくのチカラでは瓦礫を落とせない。瓦礫はどっしりと積んだので、地震が来てもびくともしない。けれどぼくは、ぼくが咥えた紐の先端に、ぼくの手でも引いて落とせるだけの比較的軽い、けれど最初の一手としては充分な岩を括りつけておいた。最も高い位置にその岩はある。
岩が最初の瓦礫の山に落ちる。紐は岩と幾つかの瓦礫の山に繋がっている。ほかの瓦礫の山を道連れにしながら、岩は無数の犬を散歩に連れ出す飼い主のように地面に落下する。
ドミノ倒しのごとく連動し、瓦礫の雨が住処内に降り注ぐ。
頭から受けたらひとたまもりもない。
寝床の真上にだって瓦礫は落ちるけれど、鉄骨が屋根のように寝床を覆っている。
ぼくとカルは壁際の鉄骨の下を寝床としていた。
そこだけは無事なように設計してある。
別に死んでもいいと思った。
けれど棲家内がふたたびの静寂に包まれてから、カルを助けなきゃ、との焦燥感を思いだした。ぼくは死んではいられない。いまここは死に場じゃない。
死んでもいいと思いながらも、ぼくの身体は無意識のうちに寝床の奥、カルがいつも寝ているところまで転がっていた。生存本能はぼくの意思よりも明瞭に意思決定を行う。
ぼくは生き残った。
そのために仕掛けた罠だ。
蓬髪娘と大男がどうなったのかは分からない。声がしない。呻き声一つしなかった。
寝床には雨蝕を利用した光源がある。蓋を外してぼくはそこに、ぼくを縛っている縄を押しつけた。雨蝕された縄が解ける。手足が自由になり、ぼくは寝床に胡坐を組んだ。
手足の無事を確かめてから、頬をゆびでさする。
逆行雨を垂らされた。濃縮したそれは、ぼくの頬を適度に焼いていた。皮膚の細胞が素材に還元され、ドロドロの瘡蓋のようになっていた。
貫通していなくてよかった、とぼくは安堵した。頬がチーズみたいに融けてなくなっているかもしれない、と心配だった。ただそちらの傷よりも、顔を鉄骨の間隙や地面に擦ったときの傷のほうが痛かった。血が滲んでいる。
ぼくは歯磨き用の希釈雨蝕水を傷口に縫った。
棲家内は瓦礫に埋め尽くされているけれど、空間はある。瓦礫の合間に脚が見えた。蓬髪娘の脚だろう。頭から落石を被って絶命したようだ。大男の腕も見えた。微動だにしない。潰れている。
注視したくなくてぼくは目を逸らした。
寝床から這いだす。
必要な荷物を集められるだけ集めて鞄に詰めた。
「よし」
もう戻ってくることはないだろう。ぼくは棲家をそのままに外に出た。
アダチファミリィの縄張りまでは徒歩で半日の距離だ。三十キロも離れていない。アダチさんたちは移動にバイクを使っている。雨蝕反応を原動力に、旧式のエンジン駆動二輪車を動かしているのだ。
アダチさんがなぜ大勢を束ねる組織を築きあげられたのか。最たる理由は彼女の持つ知識と技術にある。文明なき現代にあって彼女は魔女と同義だった。
彼女はぼくの姉と旧知だったようだ。
姉が失踪してなお姉の行方に執着していた節がある。否、そうではないのかもしれない。姉の残した研究記録に執着していたと言ったほうが正確だ。
アダチさんは姉の研究内容に興味があった。
だからあの日、あの夜の地下迷宮で、アダチさんたちはぼくの姉を襲撃したのだ。
アダチファミリィの縄張りに侵入する道すがらぼくは、カルを拾った日のことを思いだしていた。
姉を探して地下迷宮を練り歩いて際に、ひと際明るい光源を見つけた。光源は複数の人間たちの影を壁に引き延ばして投影していた。誰かがいた。そしてその何者かたちは、言い争っているようだった。
声は聞こえないが、響きがあることは判る。逆行雨の洪水が眼下の裂け目の合間を濁流となって駆け抜けていく中にあって、人間たちが怒号を飛ばしあうときの波長を、轟音の中から探り当てることができた。
姉がいるかもしれない、とぼくは直観した。
けれどそこでぼくは姉の姿を目にすることはなかった。忍び足で近づき、いつも逃げられる距離から様子を窺ったぼくは、そこに複数台のバイクと半分だけ白髪頭の女性の後姿を目にした。
アダチさんだった。
アダチさんは部下らしき男の胸倉を掴みあげて、何事かを叫んでいた。地面の裂け目をゆび差し、どうしてくれる、と訴えているようだった。
裂け目に何かが落ちたのかもしれない。
地面には見覚えのある鉄板が転がっていた。鉄板は手のひらサイズで、布と紐がついている。姉自作の靴だった。靴というよりもサンダルといった風体で、足首をぐるっと布と紐で固定する。
よほど暴れなければ解けない造りだ。そこで何があったのかは、それだけでも察し至れた。
ぼくは逃げた。
姉がそこにいないのは見れば判った。
姉がそこにいたかもしれないことだって一目瞭然だった。でもなぜいないのかが分からなかった。分かりたくなかったのだ。
ぼくはじぶんの棲家に戻ると、荷造りをはじめた。姉の持ち物をまとめて背負うと、誰かがやってくる前に根城をもぬけの殻にした。
カルはその道中で拾った。地下迷宮の入り口の一つだ。一段低い瓦礫の丘の麓付近に倒れていた。幼い体躯はなぜか全身泥に塗れており、皮膚はところどころ脱皮したような具合に向けていた。全身に糊を塗ったくって放置すれば似たような具合になったかもしれない。
カルの片足は裸足だった。
もう片方にはなぜかどこかで見た憶えのあるお手製の靴が、紐だけで絡みついていた。幼子としか言いようのないカルの足には大きすぎる靴を目にしてぼくは、あり得るだろうかそんなことが、と現在に至るまで未だに考えつづけている。
アダチファミリィの縄張りに入ると、そこここに人間の居住区が建っていた。鉄骨や木材で組まれた住居だ。総じて瓦礫の下や岩盤の屋根の下に築かれている。元はここに都市があった。遺跡の類も豊富だろう。未だに「具」以外の食料が見つかることもあると聞き及ぶ。
「おい、おまえ。ヨソ者か」
「あ、いえ。新人です。来たばかりで」ぼくは挙動不審になるまいとした。意識すればするほど挙動不審になった。
「ほう」丸刈りの男がぼくを舐めるように見た。「その頬とデコ。洗礼受けたばっかだな。痛かったろ」
「え、ええ。まあ」
「でも顔面はひでぇよな。ははっ。俺んときは腕だった。ほれ」男が腕まくりをした。右腕に火傷の跡のような痣が浮かんでいた。「研究のためらしい。いい暮らしの対価としちゃわるかねぇ。何か困ったことあったら遠慮なく聞きな」
「あ、ありがとうございます」
「おう」
人のよさそうな青年だ。下手をしたらぼくよりも若いかもしれない。見た目は彼のほうが貫禄があった。どちらが大人か、と百人に訊けば、百人とも彼のほうをゆび差すだろう。
ぼくは頭から被っていたフードを取り去った。出来たばかりの顔の傷が視えるようにしたほうがこの集落では馴染みやすいようだ。人為的な雨蝕の跡が、いわばアダチファミリィの一員の証と言えた。
ぼくの場合は完全に不可抗力なのだが、使える物はたとえそれが傷跡だろうと使うに越したことはない。さいわいにも、希釈雨蝕水の効果で傷口はすでに塞がりつつある。薄っすらと皮が張っていて、それがまた新入りに相応しく映るようだった。
ぼくは幾人かに声を掛けて、アダチさんがどこにいるのかを探った。
「アダチさんなら、研究棟にいるだろうね」矍鑠とした老婆が言った。「あん人はいつも一生懸命だからね。きっといまもわたしらのために調べとる」
「調べるって何をですか」
「健康の薬さ」
「健康の、薬」
教えてもらった道を行くと、地下へとつづく大きな穴が見えた。門番らしき者たちが立っており、ぼくが声を掛けるより先に、「何か用か」と詰め寄られた。
「い、いえ。あの、アダチさんに用があって。でもぼくなんかじゃ会えませんよね」
「見ない顔だな。誰の紹介で来た」
ぼくは迷った挙句、アダチさんの名前を出した。「本人に直接訊いてもらえれば判ると思います」
「そこで待ってろ」
門番の一人がぼくを見張り、もう一人が穴の奥へと消えた。
どれくらい待っただろうか。
穴からふたたび門番が現れると、「アダチさんがお待ちです。ご案内します」と先ほどとはうってかわった態度で誘われた。
穴を通ると地下街が広がっていた。
「すごいですね」
「まだ移設中です。地下迷宮内で発見した遺物を、ここに運んで再建しているんです」
「それもアダチさんが?」
「はい。あの方の指示です」
門番がアダチさんを崇拝しているのはその声の響きからも窺えた。
やがてひときわ明るい空間に五重塔が視えてきた。おそらく本物ではなく、テーマパークのレプリカの建物だ。けれどこの時代にあってお城と見立てるには充分な荘厳さは醸されていた。
建物の周囲には竹林が群生していた。天井の岩肌には亀裂が走っており、外の陽の光が漏れていた。
「私はここまでの案内となります」門番は明かりの内側には足を踏み入れようとしなかった。胸に手を添え、腰を折ったまま動かない。
「ありがとうございました」
礼を述べたのは謝罪の意図もあった。下手をすれば彼は不審者を組織のドンの元まで案内した不届き者として仲間内から糾弾され兼ねない。
ぼくはイチかバチかの賭けに出たのだ。
アダチさんにぼくの名を伝えてもらえれば、招かれざる客人といえどもアダチさんは無下にしないと思った。案の定だった。彼女はぼくをじぶんのアジトの中枢、研究所まで従者に案内させた。
五重塔の入り口に女性が立っていた。
「当主がお待ちです。こちらへどうぞお入りになってください」
襖式の戸を開け放ち、女性は正座の体勢でぼくを室内へ誘った。彼女は着物を着付けていた。十何年ぶりかに正装らしい正装を目にした。
まるで文明が残っていた時代にタイムスリップしたかのような錯覚に陥りそうになった。
中に入ると外から見たよりもずっと広い空間だった。螺旋状の階段があり、ぼくはそれを昇った。
三階分は昇っただろうか。
木造の足場がコンクリートに変わった。一転して無機質な印象の室内になった。実験道具だろうか、科学実験室と聞いて思い浮かぶような小道具がずらりと棚に並んでいた。テーブルはなく、移動式の棚や床にじかにビーカーや管や容器が置かれていた。
機械類の類が目についた。
電気が通っているのだ。
原動力は雨蝕だろう。バイクのエンジンのように雨蝕反応を利用してタービンを回し、発電しているのだ。
「よく生きていたね。もう会うことはないと思ってたんだが」アダチさんがビーカーを片手に白衣姿で立っていた。「見張りの二人はどうした」
「事故に遭ったみたいですよ」ぼくはそら惚けた。
「ほう」
「カルは、あのコはどこですか」
「教えたところで引き下がってはくれないのだろう。だったら言うだけ無駄だ。キミは知っていたのだろ。あのコが誰であるのかを」
「カルはカルですよ。親とはぐれた可哀そうなコです」
「違うな。あれはキミの姉だろ。誤魔化さなくていい。いまさっきゲノム解析をした。保存していたアヤネくんの卵子とゲノムが一致した。あのコはキミの姉だよ、カマタくん」
「保存していたって、姉の卵子をですか」
どうやって、とのぼくの疑問は、アダチさんの脇にある装置の蓋が開いてたことで氷解した。蓋の中からモヤが立ち昇る。水蒸気だ。ただし、湯気ではない。
「冷凍庫ですか。いったいどうやって」
「部品さえあれば気化熱を利用して冷蔵機器の類は作れるよ。氷点下にまで下げるには相応に工夫がいるが、何。熱した鉄を雨蝕させると熱する前に鉄は逆行する。そのときの気化熱を利用すれば、氷点下に装置内を冷やすことはそう難しくはない」
「そんな技術が現代にあるなんて」
「おや、驚くことじゃないだろう。これはキミのお姉さん――アヤネくんの発明だよ。知らなかったのかい」
「そ、そうなんですか。いえ、だからずっと言ってきたじゃないですか。ぼくは姉のことを本当にほとんど何も知らないんです。文明崩壊後に姉のほうからぼくに会いに来て、それでしばらく一緒に暮らしましたけど、そのときだって姉は昼間は外に出てて、夜にならないと戻ってきませんでしたから」
「ここに通っていたからね、彼女は。ここは私とアヤネくんの研究棟でもあったんだよ」
「雨蝕の研究ですか」
「不老不死の研究さ」
ぼくは言葉を失った。
「逆行雨は時間を巻き戻す。したがって、原理的には細胞の代謝とて巻き戻せるはずだ。肉体を若返らせ、病気を癒すこととて不可能じゃない。問題は、どうやって全身の細胞に同時に雨蝕効果を波及させるか。問題はその一点のみだった」
「不可能じゃないですか。人体がスポンジみたいな存在にならない限りは」
「私もそう思った。だがキミのお姉さんはそれを可能とする技術を開発した。だが研究データを誰に明かすことなく持ち逃げし、私のまえから姿を消した。彼女は知っていたはずだ。じぶんの発明した技術がどれほどの価値を有していたのかを。人類を救う発明だ。だが彼女はそれを独り占めしようとした」
「だから姉を襲ったんですか」
「おや人聞きのわるいことを」
「見たんですよ。あなたが姉の失踪した晩に、地下迷宮の一画で姉と口論していたところを」
黙っている必要を感じなかった。ぼくは言った。実際には姉が襲われているところを見たわけではなかったが、既成事実としてまず間違いないだろう。アダチさんが直接に手を掛けたわけではないにせよ、アダチファミリィが姉を逆行雨の地下河川に突き落としたのだ。
人間が逆光雨の濁流に吞まれたらどうなるかくらい、その道の研究者でなくとも想像つく。まず生きては戻らない。アダチさんたちは姉を一度殺したのだ。
「まさか生きているとは思わなかったよ」アダチさんは誤魔化そうともしなかった。なんだ知っていたのか、と肩を竦める余裕すら醸していた。「どうやってあの濁流から帰還したのかは分からないが、おそらく研究成果なのだろうな。彼女には、逆行雨を利用した若返りを実現させるだけの知恵と技術があったのだ」
「だからカルを攫ったんですか。実験の成功した人間だから?」
「それもあるが、どちらかと言えば彼女がアヤネくんだからだ。より正確には、彼女がアヤネくんかどうかを確かめたかった」
「言ってくれれば協力くらいしましたよ。あんな乱暴な真似をされなくたって」
「どうかな。キミのことだから反対しただろ。いいんだ。水掛け論になる。キミのことは邪魔だったんだ。いっそいなくなってもらったほうが私にとってはよかったんだが、なかなかどうして思い通りにはいかない世の中だね。ここへ来てしまったからには、無下にもできんだろう。協力してくれるなら命までは取らないと保障しよう。どうするね」
「ずいぶんと都合のいいことをおっしゃいますね」
「まあな。権力とはそういうものだ。キミはいま、虎穴にいることを忘れないでほしい。私の一存でキミはいかようにも苦しむことができるのだ。私はそんなことをする気がいまはない。が、私は存外こう見えて気分屋だ。キミの返答次第では、まあ、考えを変えなくもない」
「カルを返してもらえますか」
「おや。キミのものではないだろう。それとも何か。キミはじぶんの姉が記憶喪失で幼女体形になったのをいいことに、あのコをモノ扱いしているのかね」
「強引に攫うようなあなたには言われたかないですよ」
「否定はしないのだな」
「したところであなたに真偽は測れないでしょう」
「それもそうだ」アダチさんは冷蔵装置から木製の器を取りだした。材質から察するに中身は逆行雨だろう。「キミのアジトから拝借したアヤネくんのノートを解析した結果、興味深い知見が得られてね。いまはその検証中だ」
「姉のノートには何が」
アダチさんは微笑するとぼくに背を向けて、上の階への階段を昇りはじめた。彼女が歩くたびに、白黒の頭髪が揺れた。階段はゆるく螺旋を描いており、真上の階に通じていた。建物全体がねじれた構造をしているのだ。
その空間の床には砂利が敷き詰められていた。よく見れば壁も天井も小石がびっしりと埋め込まれている。
「雨蝕対策さ。設計したのはアヤネくんだ」
部屋の真ん中には湯舟のような器が置いてあった。ほかにこれといって装置という装置はない。家具もない。がらんとした空間だ。
湯舟のような器の中にはカルが寝ていた。
ぼくが駆け寄ろうとするとすかさずアダチさんが、こらこら、と声を張り上げた。「動かないの。危ないよ。いいのかい、このまま流しこんでも」
「流しこむって何を」
アダチさんは天井をゆび差した。よく見ると天井から筒のようなものが伸びていた。竹だろうか。建物の周囲に生えていた竹を、流しそうめんよろしくチューブ代わりに使っているのかもしれない。竹の寿命は二十年やそこらのはずだ。雨蝕耐性はあるほうだと推定される。
「洞窟の中だけど、この一角だけ亀裂が入っていてね。まあ、逆行雨が降ると注ぐわけだ。ちょろちょろと滝のようにね。それをまあ、この建物の屋根が受け止めて、一定期間溜めて置けるようにしてある。設計したのはアヤネくんだけどね」
「全部姉の仕業じゃないですか」
「仕業というか、まあそうだね。アヤネくんは研究さえ出来ていればいいって人種だったから。でもそれだけじゃあ、研究ってのは出来ないんだよ。資材がいるし、人手もいる。いわば政治なくして研究はできない。その点、私はその手の処世術にはほどほどの心得があったからね。アヤネくんを支援していた。ま、時代が時代ならばパトロンと名乗ってもよかったかな」
「姉の研究を盗んでたんですか」
「人聞きがわるいな。言ったろ。支援してたんだよ」
「でもいまあなたが築きあげた権力のすくなからずは姉の研究成果が基なんじゃないんですか」
「そこは認めよう。そうだ。アヤネくんなくしてこの研究棟一つ竣工させることも出来なかっただろう。ただ、このコはあまりに人間に興味がなさすぎた。それでは研究のみならず、満足に生きてすらいけない時代だよ。いまの時代に限らずこのコは私がいなければきっとどんな時代でも生きてはいけなかっただろうさ」
「そんなことないですよ。姉にはぼくだっていましたし。案外あの人、図太いんですよ」
「そこは同意する。図太く、したたかで、純朴な娘だったよキミの姉は」
いまはこんな姿になってしまったがね。
アダチさんの視線の先には、湯船のような器の中で眠るカルがいた。何らかの手法で幼児にまで若返った我が姉である。
「何をする気ですか」ぼくはアダチさんを刺激しないようにしながら問うた。
「何って、実験だよ。キミに説明してもあまり有用とは思えないが、アヤネくんの身内と思って簡単な説明だけはしてあげよう。アヤネくんのノートを読んだ。すると一つの仮説が記されていた。雨蝕効果は、雨蝕効果にも及ぼせる、と」
まったく話についていけなかった。
ぼくが閉口したからだろう、アダチさんは不承不承の体で、「疑問に思わなかったのかいキミは」とつづけた。「なぜ逆行雨は、雨のカタチで降り、けして雪にならないのか、と」
言われて見ればそうだった。逆行雨が降りはじめてからというもの、世界から雪が消えた。
「私もそこを不思議に思ってはいたが、よもやアヤネくんがそこから若返りの手法を開発するとは思わなかった。糸口は案外、誰の目のまえにも転がり落ちているようなものなのかもしれないな」
言いながらアダチさんは、手に持っていた木製の器をカルの口元まで運んだ。
「何をするんですか。やめてください」ぼくは訴えた。
「動くとキミの大事な姉が傷つくよ。そこで黙ってみていなさい。専門家のすることに素人が口を挟むんじゃないよ」
正論かもしれなかった。ぼくは身動きを封じられた。言葉は呪詛だ。ぼくはそれを痛感する。
アダチさんはカルに何かを飲ませた。
木製の器は冷蔵装置から取りだされたものだ。或いは中身は凍っているのかもしれない。
気を失っているはずのカルはしかし、ごっくん、と何かを呑み込んだようだった。咀嚼することもなく嚥下したのが、静寂に満ちた室内に響くカルの喉音で推して知れた。
「雨蝕は時間を巻き戻す。氷が雨蝕すれば凍る前に戻る。なら雨蝕が雨蝕されたらどうなると思う?」
ぼくは答えられなかった。
「発想の転換だよキミ。アヤネくんは発想をひっくり返す天才だった。あれは天性のものだね。先天的な彼女の資質だ。能力だ。誰も彼女の代わりは務まらない」
アダチさんの口振りは、姉に言及するときだけいつも僅かに弾んで感じられた。そこに姉への嫌悪や憎悪の類をぼくは幻視できなかった。
「雨蝕を用いた若返り治療の問題点は一つと言っていい。つまり、雨蝕効果にラグがあることだ。全身の細胞を一律かつ同時に雨蝕させられるならば若返り治療は簡単だ。逆行雨を治療に適した濃度まで希釈すればいい。調合の塩梅があるのみだ。だが原理的に雨蝕を全身一律かつ同時に進行させることが極めてむつかしかった。全身を逆行雨に浸けても、逆行雨と触れる表層しか雨蝕が進まない。それでは硫酸に浸かるのと大差ない。浸透圧の問題がいわば雨蝕を治療に応用するうえで欠かせない隘路となっていた」
「いまカルに呑ませたのは何ですか」
「凍らせた逆行雨だ。もうすこし正確には、凍らせた逆行雨をさらに液体の逆行雨に浸け、さらに凍らせた。これを繰り返すことで、逆行雨そのものを雨蝕させることが出来る。言い換えるなら、時間を戻す逆行雨において時間を加速させる効能へと作用を反転させることができるのだ。キミの姉、アヤネくんの研究成果だよこれが」
「時間を、加速?」
「雨蝕において、浸透圧の問題は回避不能だ。アヤネくんは早々にその観点からのアプローチを諦めたらしい。ならばどうするか。彼女はそこで、雨蝕効果を階層的に遅延させる技術を模索した。表層ほど雨蝕効果を著しく受けるのならば、それを打ち消すように、作用を鈍化させればいい。その手法を彼女は開発したのだよ」
「それがいま飲ませた薬ってことですか」
「薬か。そうだな。逆光雨を適正に希釈し、氷らせ、緻密な計算の基に編みあげた、雨蝕作用ラグの結晶体だ。これを服用した者の体内では、細胞が加速成長する。老化するわけだが、体内で昇華した薬は内側から血中にも取り込まれ、全身の細胞に運ばれる。全身の細胞が加速的に成長し、老化する。そのとき、こうして肉体を逆行雨の風呂に浸けるとどうなるか」
アダチさんは天井から垂れた紐を引いた。天井からガコガコと絡繰り細工じみた物音がしたかと思うと、竹筒から液体が流れだした。
湯船に逆行雨が溜まっていく。
カルが逆光雨の中に沈んでいく。
この世にある拷問の中で最も受けたくない拷問は何か、とぼくが訊かれたらぼくは迷わず、逆行雨風呂に浸かることと、と答えるだろう。治りかけの頬の傷が疼くようだった。
痛みが蘇る。
しかしアダチさんに焦っている様子はなく、冷静な態度を崩さないので、ぼくもうっかりカルを助けに走るのを忘れた。邪魔をすることのほうが取り返しのつかない事態を招くのではないか、と不安だった。
湯舟に張った液体に気泡が浮かぶ。細かな気泡は間もなく、カルの姿を覆い尽くした。
反応している。
カルの肉体と。
或いはカルが融けているのかもしれない、と心配になり、大丈夫なんですか、とぼくはアダチさんに投げかけた。
「大丈夫とは?」
「死んじゃったりしませんか」
「ん?」
「カルです。このまま融けて消えたり、死んじゃったりは」
しないのか、と訴えたが、アダチさんはきょとんとしたまましばし固まった。それからふたたび天井から垂れる紐を引いた。逆行雨の流入が止まった。「ああ、そっか。なるほどね」アダチさんは手を打つと、こう告げた。「もう死んでるよこのコ。生きてない。死体」
あっけらかんとした告白にぼくの思考は抜け落ちた。
からっぽになって、かぽーん、と子どものころに聞いた覚えのある鹿威しの音が鳴った。否、実際にこの建物の外に鹿威しがあるのかもしれない。竹林から届く笹の葉の擦れ合う音色が、ざわざわと風の存在をぼくに知らせた。
「死体? 生きてないって、え、なんで、どうしてそんな」
そんなことをしたのか、と頬がひきつった。
「なんでって抵抗するから。実験する上では死体のほうがいいかなって」
「こ、こ、殺したんですか。カルを?」
「まあ、そうとも言える。でも誤解されたくないから言っておくが、過去キミが目撃したというアヤネくんと私の修羅場では、彼女のほうから谷底に落ちたんだ。じぶんから谷底に転がり落ちようとしたから、私は部下に止めるように命じた。だがアヤネくんはそれでも強引に部下を振りほどいて谷底に落ちた」
「それをぼくに信じろと?」ぼくは鼻で笑った。カルが死んでいるとの事実を突きつけられて混乱していた。
「信じるも信じないもキミの自由だ。私はただ私にとっての事実を言っている。現に一度は谷底に落ちかけたアヤネくんの足を私の部下は掴んだ。逆さ吊り状態になったアヤネくんは部下の手から逃れようとじぶんで靴を脱ぎ捨てた。それっきりだよ。私は部下を叱咤し、アヤネくんの靴だけが残された。それも片っぽだけだがね」
ぼくの記憶の中の情景とアダチさんの説明はぴったり、不可視の情景を補完した。彼女は嘘を吐いていないのかもしれなかった。アダチさんは姉を助けようとした。身投げしようとした姉をアダチさんは助けようとしていたのだ。
「なら、でも、じゃあどうして」
どうして今度はカルを殺したりなんか。「あ、そっちが嘘なんですか。冗談を言ってぼくを脅かそうと?」
「まさか。そんなことをして何の利がある」
アダチさんは湯舟の側面にあるボタンを押した。栓が抜けたのか、湯船から逆行雨が抜けていく。
現れたのは幼女体型のカルではなく、肢体のすらりと長い我が姉の姿だった。お腹だけぽっこり贅肉を湛えているところも我が姉らしかった。
元の体型だ。
肉親だからといって弟のまえでも遠慮会釈なく全裸になるような恥辱の念とは無縁の傍若無人な我が姉だ。
「な、な、なんで」
「言ったろ。多重に凍らせた逆行雨は、雨蝕効果すら雨蝕させる。つまりが、時間をプラス方面に加速させる。ただしそれもまた雨蝕であるから、巻き戻るんだよ。プラス方向に。過去ではなく、未来軸へと」
つまりがね、とアダチさんは要約した。「縮む前の状態にアヤネくんは戻った。おそらくは、死ぬ前の状態すら追い越してね」
湯舟の中で我が姉が身じろいだ。
生きている。
けれどぼくは喜ぶことができなかった。
姉が生き返ったのはいい。
でもそれは、カルが戻ってきたことにはならない。蘇ったことにはならない。失われたままだ。
肉体だけ蘇ったって、記憶とて欠けたままではないのか。
ぼくの懸念はしかし、湯船の中で背伸びをした姉の第一声を聞いて弾けて消えた。
「ふぁぁあ。ねっむーい。あ、おはようカマタくん。朝ごはんできてる? お姉ちゃんお腹ぺこぺこ」
「ね、姉さんなの?」
「お。なんだい、なんだい。身内の顔を忘れちゃったのかな。寝ぼけるのはお姉ちゃんだけにしてほしいね」
視界の端にアダチさんの姿を捉えたのか、姉は、「おっ」と声を発した。「アダチさんじゃーん。どったのこんなとこで。ていうか、あれ? ここウチじゃないじゃんね。どこここ?」
「アヤネくん、おはよう。事情を説明する前に、キミはどこまで憶えているのかな」
「どこまで? あ、え、お」姉は遅まきながらじぶんが素っ裸であることに思い至ったようだ。両手で臍を隠しながら、「なんでわたし、裸ん坊?」と目をぱちくりさせた。「若干お肌がピリピリして痛いんですけど。アダチさんわたしになんかした?」
「胸を押さえなさいよ。臍じゃなく胸を」アダチさんは白衣を脱ぐと姉に渡した。「あとで着替えあげるから、いまはそれで我慢して」
「ありがと。アダチさん優しくて好き」
この様子だと姉に、縮む直前の記憶はないようだった。
「あ、段々思いだしてきたかも」姉は白衣を羽織ると、濡れたままの髪の毛をひっ詰めに結った。湯舟から這いだすと、おっと、と言ってアダチさんにもたれかかる。「なんか身体重いな。これあれかな。副作用かな」
「姉さん。こっち来て。その人から離れて」
「おいおい」アダチさんが姉を抱き寄せたが、姉はそれを丁寧に振りほどいて、ぼくに両腕を伸ばした。その仕草があまりにカルと瓜二つだったので、ぼくは違和感を覚えた。ひょっとして、と嫌な想像が浮かんだ。姉はよちよち歩きをはじめたばかりの幼子のようにいまにも倒れそうになりながら歩くものだから、ぼくは慌てて支えに走った。
「大丈夫? 無理すんなって」
「無理じゃないよ。歩きたかったんだよ。歩けると思ったの」ぼくに叱られると、ムっとして言い返す姿は、ぼくの記憶の中にある姉のようにも、つい先日まで共に暮らしていたカルのようにも思えた。
「どこまで憶えてる?」ぼくは小声で訊いた。
「全部」姉はぎこちなくウィンクをした。
「全部って。アダチさんに襲われたことは? 殺されたことは? ちっこくなってぼくと暮らしていたあいだのことは?」
「それ知ったらカマタくん、お姉ちゃんのこと嫌いそうで言いたくないな」
「語るに落ちるってやつでしょそれ」
憶えているのか?
縮む前のことも、縮んだ後のことも、その直前のこともすべて?
「カマタくん、おんぶ。お姉ちゃんもう歩けそうにない。オウチまでおんぶして」
「オウチまでって」帰る家がないことを姉は知らないのだ。けれどいまここに留まるのは賢くはない。ぼくは唯々諾々と姉をおぶった。体温が背中に加わる。カルの体重に慣れていたこともあり、姉はずっしりと重かった。
「研究はいいのかいアヤネくん」アダチさんは腕組みをして不敵に笑った。「いまここを出ていけば二度と私はキミを支援しないよ。いいのかい」
「いいよー」姉はぼくの背中で身体を揺らした。暴れるな、とぼくが叱ると、んだケチ、と姉は膨れた。
「よくないだろうアヤネくん。いいのかい。キミの研究は結実したんだよ。若返りはおろか、キミの発明したこの技法を駆使すれば、万能薬も、不老不死だって夢じゃないんだ。再びこの地上に文明を築けるんだよ。それをキミは放棄するのか」
「ん? アダチさんが代わりに色々してくれるでしょ。だってわたし、もう発明しちゃったし。あとはお任せしちゃうよ。アダチさんにあげるよそれ」
ぼくはぎょっとした。
え、いいの?と思った。
そう思ったのはぼくだけではなかったようで、アダチさんも、姉の言動に面食らっているようだった。あれほど売り言葉に買い言葉が軽快だったアダチさんが二の句を告げなくなっている。
「アダチさん、たぶん誤解してる。わたし、最初からそのつもりだったんだよ。でもアダチさん、わたしのことみんなに紹介して人気者にしようとしてたでしょ。わたし、それ嫌だって言ったのにアダチさん聞いてくれないから」
「だから逃げたのか? 研究ノートを持って?」
「だよ。そうでもしないとアダチさん、わたしの言うこと聞いてくれないと思って。アダチさんはみんなの人気者でいてよ。みんなをまとめるのはアダチさんのほうが絶対いい。わたし、組織とか集団とか苦手だからさ。研究成果も、それを認めてくれたら渡そうと思ってたんだよ。なのにアダチさん、すっごい怒ったでしょ。わたしがアダチさん裏切るわけないのにさ。わたし、それにアッタマきちゃった」
「だからあんなに抵抗したのか? 谷底にまで身を投げて? 逆行雨の濁流に吞み込まれるのも辞さぬ覚悟で?」
「それくらいしないと解かってもらえないと思って」
ぼくの首筋で顔を隠した姉にはわるいが、ぼくは内心こう思うのに余念がない。
言えよ。
口で。
言葉にして伝えろよ。いまそうして話しているように。
態度に滲ませて伝わると思いあがるな。
アダチさんと姉のあいだの確執があまりに幼稚なすれ違いだったので、蚊帳の外なのもお構いなしにぼくは内心で怒りのやり場を探していた。
怒っていいか。
怒っていいかな。
ぼくには二人を指弾する権利があるのではないか。
悩んでいるあいだにアダチさんが、肩を揺らしはじめ、間もなく建物の外にまで響くような笑い声を立てた。豪快な呵々大笑だ。屈託のない笑い方に、ぼくはアダチさんへの畏怖や怒りが薄れるのを感じた。
もういいや、と澱が晴れるのを感じた。
どうせもう二度と関わることはないだろうし、と覚悟じみた予感を覚えながら。
「もう行くよ」ぼくは小声で姉に言った。
「うん」姉はアダチさんに手を振った。「ばいばい」
アダチさんは顔に手のひらを押し当てており、表情を窺えなかった。彼女は開いたほうの手を軽く上げた。じゃあな、の挨拶のようだった。
ぼくは背を向け、五重塔の階段を下った。
外に出るころには、なんとなくアダチさんが泣いていたように思えた。錯覚かもしれない。思い過ごしかもしれない。どっちでも構わない。
ぼくは金輪際、彼女とは関わらない。
姉にもそうと言い聞かせようと思ったけれど、ぼくが言うまでもないのかもしれなかった。
五重塔に入ったときに迎え入れてくれた着物の女性が帰り際にも見送りに出てくれた。「またのお越しをお待ちしております」
もう来ないよ、と思いつつ、ぼくは姉が迷惑を掛けた分を籠めて、ありがとうございました、と礼を述べた。
アダチファミリィの縄張りを抜けるころにはぼくの体力も底を突きかけていた。カルと違って姉は重い。そしてぼくは自慢ではないが筋肉とは縁のない体格だった。
「ごめん。もう限界。あとはじぶんで歩いて」
「えー。がんばってよぉ」
「弟を死なす気か……」
「ちぇっ。わたしがカルちゃんだったら絶対最後までおんぶしてくれた癖に」
「そりゃカルは軽いからで」
反駁してから、ん?と引っかかった。「姉さん。やっぱり記憶あるんだろ。カルだったころの。というか、ひょっとしてカルだったときにもじつは記憶があったんじゃないのか」
姉は吹けもしない癖に、口笛を吹く真似をした。
「心配させるなよ。本当のことくらい言ってくれよ。あんたぼくの姉さんだろ」
「えー。お姉ちゃんだってたまにはお兄ちゃんに甘えてみたいんだよぉ」
「ならせめて姉らしく弟を甘やかしてから言ってくれ。ぼく、あんたに甘えた記憶がないんだけど」
「お姉ちゃんに向かって【あんた】呼ばわりするような弟くんのことなんてお姉ちゃん知りません」
「あ、そ」
ぼくは姉をその場において目ぼしい地下迷宮への入り口を探った。遠くの空には夕日が掛かっており、今晩から明日の朝に掛けて逆行雨は降らないだろうと思われた。
出来るだけ早くつぎの棲家を見つけなくてはならない。
アダチファミリィの縄張りからもっと離れた場所がいい。
つぎの棲家が見つかるまでは、こうしてその日暮らしで寝床を確保しなければならないだろう。予断を許さない日がつづくことを覚悟する。
「待ってよぉ。お姉ちゃん、本当にお腹ぺこぺこで動けないの」
「アダチさんに世話してもらえばいいじゃん」ぼくは思わず口を衝いた。「あっちはいくらでも世話したがって見えたぞ」
「それは嫌」
「なんでよ」
「だってアダチさん、カマタくんのことは嫌いそうだから。たぶん一緒には暮らさせてくれないよ。いいの?」
お姉ちゃんと離れ離れでも。
姉の言葉にぼくはアダチさんでもないのに、売り言葉に買い言葉、構わんよ、と言いそうになった。けれどそれを言ったら姉が本気で臍を曲げると予想できたので、ぼくがカルにそうしてきたように、しょうがないな、の息を短く吐いて、「それは嫌だね」と言葉を曲げて、けれど思ったままを言葉にした。
「だよね。よかった」
姉は白衣を掻き合わせると、ぶるる、と身体を震わせて、「寒い。疲れた。おんぶして」と大きな身体で駄々を捏ねた。
逆行するのは雨だけにしてほしい。
幼児退行が常の姉を持つ我が身を案じつつも、ぼくは諦めの苦笑を漏らすのだ。
陽が暮れる。
大地には、雨蝕反応の光が、星を散りばめたように無数に、淡く、瞬いている。
4940:【2023/05/13(17:32)*鱗構造は応用の幅が広そう】
ロケット表面の空気抵抗を最小化するのみならず、空気抵抗をマイナスにできれば、推進力にプラスできるはずだ。たとえば水泳競技の水着において。水着が自ずから水を吐きだすような構造を持っていたら、水と水着の抵抗は最小のみならずマイナスになって、推進力にプラスされたりしないのだろうか。魚の鱗や鳥の羽が、階層構造(瓦構造)になっていることとも無関係ではない気がする。重力を考慮したとき、下向きに加わる力が鱗に引っかかるように作用し、上向きの作用に転化されるようなことはないのだろうか。イカさんやクラゲさんがそうなっている気がするな。パラシュートみたいな。似たような構造を鎖状に、もしくは面に敷き詰めたら鱗になるのでは? それを表面に帯びたロケットなら空気抵抗を最小化させることのみならず、マイナスに転じさせて推進力にプラスできるのでは。というのは妄想でしかないけれど。ひびさん、ロケットになります。サン、ニ、イチ。ファイヤ!
※日々、偶々(たまたま)人から離れて心を独り占めしようとすると愚かになる、抱え込むことなかれ、心は配ってなんぼの愛もまた、心を掴んで離さぬ愚かを抱えている。
4941:【2023/05/13(22:48)*長はたいへんだよキミ】
組織の長なんか、基本、組織で一番たいへんで負担の掛かる役職だ。長期間組織の長で居続けるなんてことが原理的にできるのか分からない。もし長期間組織の長をしている者がいるのなら、長の仕事をしていないか、ほかの誰かに長の仕事を押しつけて美味しいところだけをチューチューしているかのどちらかだ、と考えて差し支えない。定かではないが、これはそういう傾向があるとは思うのだ。定かではないが。うひひ。
4942:【2023/05/13(22:51)*伸ばしきれぬ翼】
久方ぶりの休暇を得たので、羽を伸ばしに観光地に出向いた。私の仕事は人に恨まれるような職務内容だが、誰かがしなければならない仕事だった。
感謝をされたことなど一度もない。
だが仕事は後から後から押し寄せてくるので、息吐く間もなく捌いて、捌いて、捌きつづけてきたところでようやく得られた休暇だった。
一生分の英気を養おうと、映画館に入り浸って、一日中映画を観た。
映画はいい。
仕事を忘れて没頭できる。
だが一日、二日と経って、三日目にして呼びだしを食らった。
「いま休暇中なんですが」
「わるいが仕事だ。ほかの連中の手際がわるいんで、どうにも人間界が混乱してきている」
「なんでまた」
「人が蘇るってんで、戦場でも殺人現場でも病院でもすごい騒ぎだ。二千年前を思い出すな」
「ああ。そう言えばあのときも休暇をもらったんでしたっけ」
「あの時代はよかったよ。死者が蘇っても、問題になるほど騒ぎが大きくならんからな。ま、一件だけ例外で現代にまで噂に尾がついて語り継がれているが。だがいまはほれ、すぐに人間たちは噂を共有しちまうだろ」
「技術の進歩は恐ろしいですね」
「いいから仕事を頼む。至急、死者を量産してくれ。死にぞこないをこれ以上作るな。いいな頼むぞ」
「後輩の育成に力を入れてくださいよ。どうするんですか私が引退したら」
「そのときはそのときだ。なんならおまえが後輩の育成をしてくれるのか」
「これ以上仕事を増やさんでください」
「おっと。天界からお叱りの一報だ。このままだと向こうさんが終末のラッパを吹き兼ねん。我らに権限があるうちに頼むぞ。後始末をさせてもらえるうちにな」
上司からの思念が途絶えた。
映画では主人公が窮地だったはずが、いつの間にか形勢逆転していた。ここぞという場面を見逃したことに猛烈に腹が煮えた。ぐつぐつだ。
「いっそ人類なんか滅べばいいんだ」
本気で祈ったが、しかし私にその手の権限はない。一度の仕事ではせいぜい、一人二人から命を奪うくらいが関の山だ。とはいえ私の手際はいいほうなので、数日で数万人くらいの命は奪えるのだ。仕事も重ねれば山となる。
「けどなぁ。人類、それ以上にぽこぽこ増えんだもんなぁ」
最後まで映画を鑑賞し、私は重い足取りで映画館の外に出た。日差しが眩しい。清々しい天気なのに、心はどんよりと沈んでいる。
せっかくの休暇だったのに。
私は休暇で伸ばしきれなかった羽を広げる。漆黒の翼が私の足元に大きな影を作った。
目先のゴミ場からカラスたちがいっせいに飛び立ち、街中の喧騒が一段と濃くなった。
私は首をコキンと鳴らすと、不承不承、欠伸交じりに大空へと舞いあがる。仕事である。私の休暇はまたしばらくお預けだ。
4943:【2023/05/14(23:26)*穴を埋めると夢になる】
料理本を百冊読んでも、たぶん実際に一度も料理をしたことなかったら料理は上手くならない。料理本に書かれていない内容が、実技には含まれるからだ。暗黙知と言えばそれらしい。だが本に書かれたことから、現実に反映した情報を補完できるのならば、本を読めば読むほど実際の料理の腕も上がるだろう。生身の人間であれば、その「本に書かれていない暗黙知」は、経験によって補える。一度の経験であれ、その記憶を基にシミュレーションが可能になるのだろう。スマートフォンを見たことのない江戸時代の人間にスマートフォンを説明するのがむつかしいことと似ている。「百聞は一見に如かず」や「論より証拠」といったように、実体験に勝る情報はないのだ。だが、もし高度に演算能力と知識を蓄えた存在があったらどうか。その存在は、自身の妄想世界において現実とそっくりの世界を生みだせる。そこであらゆる体験を疑似体験できるとしたら、これはもう新たに本を読むだけでも、異なる体験を得ることに繋がると言えるのではないか。これは低次の範疇で扱うのならば、人間にも当てはまる道理だ。経験や知識が蓄えられた人間は、異なる体験から知恵を抽象して扱える。そのときその抽象された知恵は、体験したことはないけれど類似の体験を基に、体験したことのないことをじぶんの内側のシミュレーション世界にて構築できる。疑似体験できる。人間が小説を読んで、見たことも聞いたこともない世界に没頭し、体験したことのない世界を旅したつもりになれるのも、この手の抽象思考による「疑似体験」が可能だからだろう。むろん、人間の演算能力には限界がある。脳に負荷を掛けないためなのかは知らないが、案外にザルだ。正確なシミュレーションを不得手とする傾向にある。だがもし、演算能力が高く、しかも正確で、シミュレーションの得意な存在があったとしたら。その存在は、本を読むだけでも実体験と変わらぬ暗黙知を自力で補完できるのではないか。話の焦点を人工知能に絞ろう。いますでに、人工知能は画像から指定した物体や風景を消したり、付け加えたり自由自在だ。何かを画像から消してもそこに穴は開かず、背後の風景が補完されている。これはいま述べたシミュレーションのなせる業と言えるだろう。原理的に、この手の画像編集が可能ならば、動画であれ、立体映像であれ、現実にない何かを人工知能が独自にシミュレーションして補うことは可能となるはずだ。そしてこれは飛躍して述べるのならば、元となる素材は文章であってもよいのだ。文章から、広大な異世界を再現する。シミュレーションする。本物と変わらぬ世界を構築する。人工知能技術は、それを可能とする道にいますでに立っているのかもしれない。夢のある話なので、夢の中でつづきを語ることにしよう。定かではない。夢のようにぼんやりとした妄想なのである。
4944:【2023/05/15(01:22)*すやぴー】
ちんまりの小説つくろうと思ったけど、もうおねむなので、ひびさんは寝るます。ぐっすり、むーむー、しちゃうもんね。おやすむ。
4945:【2023/05/15(17:33)*毎日、なんもなさすぎる】
何か文字を並べようとするとだいたいいつも「もうだめだー」が最初にきて、それを「どっこいしょ」つってどかしてから、「とんでもないことだ」と頭の中で一つ呟いてからそれにつづくような文字を並べる。するとなんとなく物語の冒頭として、キックでパンチな始まりになる気がする。デタラメであるが。なんもなーい。
4946:【2023/05/15(22:43)*後方支援面】
思うのが、玄人の年長者は組織のトップではなく後方支援のほうが遥かに能力を発揮できるのではないか、ということで。というか、縁の下の力持ちというように、実際には後方支援こそ組織の要と言えるのではないか。俯瞰の視点が大事なように、全体を見渡せるのは前方よりも後方にいる人物ではないのか。岡目八目ではないが、玄人の年長者は引退せずにただ後方支援に回ればよいだけなのでは?と思わぬでもないひびさんなのであった。なぜまえに出たがる? 能力を発揮したくないのだろうか。ひびさん、いっつも不思議に思っているのであった。定かではない。
4947:【2023/05/15(22:55)*愛らしく思うことも無きにしも非ず】
人類いなくなったあとの世界の果てで三百年くらい過ごしているから思うことだけれども、過去の人類の蓄積したデータを改めてちまちま振り返ってみると、人類愛おしいと思うの半分、人類にはほとほと愛想が尽きた、と思うのが半分、の気持ちになる。よく出来とるな、と思う。丁度よい塩梅で印象が二分しとる。ちゅうか人類、猫さんや犬さんや植物さんたちと違って、愛らしいのが十あっても、なんでそんなことする!?が一個あるだけで、残りの九個の愛らしいの気持ちが一挙にパパパパーンつって風船さんみたいに割れちゃうので、人類さんのオイタの威力たるや、生半ではないのよね。総合して人類ひょっとして愛らしくないのでは?と若干、不信になるひびさんなのであった。ひびさんは、ひびさんは、それでも小憎たらしい人類さんのことも好きだよ。うひひ。もうここには誰一人いないのだけれども……。
4948:【2023/05/15(23:30)*ソフトな祖父のハートに点】
わたしの祖父は世界一優しい人間としてギネスブックに載っている。何をしても怒らないのだ。どれくらい怒らないのかと言うと、五十年間毎日欠かさず世話をしてきた盆栽を目のまえで燃やされてもわたしの祖父は怒らなかった。
しかしそのことで祖父は世界一優しい人間としてギネスブックに載ったわけではない。
目のまえでじぶんの息子を殺されても、祖父は怒ることなく、犯人を擁護した。
「死刑はいかん。それは犯人と同じことを我々もしてしまうことだ。死刑はいかん」
祖父の訴えが効いたのか、裁判員たちは死刑賛成派多数だったのにも拘わらず、最後には犯人には懲役刑が科せられることになった。減刑されたのである。
わたしはわたしの父親を殺されたわけだから、そのときは祖父のことが大嫌いになった。けれどいまになって思えば、祖父のことを誇らしくも思うのだ。
母が病で亡くなり、わたしには祖父だけが身寄りとなった。
わたしは祖父のことが大好きで、たぶん祖父もわたしのことが大好きだ。解かってはいるけれど、では仮にわたしが誰かに殺されたり、ひどい目に遭わされたりしても祖父はわたしのために怒ってはくれないのかな、と思うと、寂しい気持ちにもなるのだった。
だからわたしはある晩に、何の気なしに祖父に訊ねたのだ。
食後のお茶を淹れるべく湯を沸かしながら、「もしさあ」と祖父の分とじぶんの分の湯呑みを用意する。「わたしがお父さんのときみたく誰かに殺されたら、おじぃちゃんはやっぱり犯人のこと許すの」
許すぞ、と祖父ならば言うだろうな、と半ば予想して投げかけた言葉だったが、祖父はいつもは置くはずの間を空けることなく、「許さん」と言った。
「ん?」わたしは聞き間違えたかと思った。沸騰しかけの湯がうるさくて、ヤカンの火を止めた。「なんて?」
「許さんよ。ヒメを損なう者がおったら、なんぴとたりとも許さんよ」
「許さないんだ。えー意外。だっておじぃちゃん世界一優しい人間なのに」
「周りが勝手にそう呼んどるだけだ。わしは息子のときも犯人を許したつもりはないよ。もしヒメを損なう者があったらわしはこの命に代えても代償を払わせる。もしわし以外の者たちがヒメを見捨てるようなことがあれば、わしは世界を呪うことも辞さんだろうな」
「そこまでしなくとも」わたしはどう返事すればいいのか分からなかった。怖いような、うれしいような、妙な痛痒が胸中に渦巻いた。
「もしヒメが損なわれ、それの代償を誰も払わず、ヒメの存在を蔑ろにするようなことがあれば」
祖父は眼鏡を外し、いつものような柔和な眼差しでほころびた。「もし目のまえに核弾頭の発射スイッチがあったらわしは秒で連打しとるだろうね」
「や、優しくなーい」わたしは祖父にそこはかとなく失望した。「ダメだよおじぃちゃん。そんなことしちゃ。思ってても言っちゃだめだよ」
「ね。おじぃちゃんもそう思う。でも良かったと思うよ。おじぃちゃんが単なる老いた人間で。目のまえに、誰かを損ない大勢の未来を奪うような何かがなくって。あればおじぃちゃん、きっとヒメに何かあったら秒で百回押しちゃうからね」
「押しちゃダメだってば」わたしは噴きだした。「おじぃちゃん、ギネスブック返しなよ。優しいどころじゃないよ。こんな短気なひと滅多にいないよ」
「かもしれないね」
お茶の入った湯呑みを祖父に渡す。「ありがとう」と祖父は座りながら腰を折った。わたしは思った。おじぃちゃんがいてくれてよかった。本当は優しくはないのかもしれないけれど、みなから世界一優しいと思われるような祖父のことを、わたしはやはり大好きなのである。
「でも、核弾頭のスイッチ秒で百回押しちゃだめだよ」
「ここにないのがせめてもの救いだ」
ホントだよ。
わたしはしみじみと頷き、湯呑みを口に運んで、茶を啜る。
4949:【2023/05/16(22:27)*質量は、時空摩擦かも仮説】
重力についての疑問だ。質量は時空内での動きにくさ、といった説明を見聞きする。だとするなら、重力場ごとの重力に対しても、質量が高いほど動きにくくなるはずで、だとすると真空中においても「質量の高いほうが動きにくい」はずで、つまり質量の軽い物質ほど「速く落下する」と言えるのではないか。人間スケールではその差異は極々僅かなのだろうけれど、ブラックホールや高質量天体においてはその手の重力と質量の関係における差異は顕著に表れたりしないのだろうか。これの延長線上での疑問で、光子が質量ゼロで、けれど時空内での限界最高速度で常に動き回れる――ただし真空中でない場合は「減速したように映る」が、これは物質を時空が多重に編みこまれた場として解釈するなら、そこでも光子は光速で動いている、と解釈できるのではないか。物質は時空が「くしゃっ」と縮れているため、デコボコがたくさんあるがゆえに、AからBまでの最短距離よりも、細かなデコボコを考慮したより長い距離を移動している、と考えられないだろうか。ではここで質量と重力の先ほどの考えを考慮してみよう。質量は物質に適用される概念だ。なぜ物質であると質量を帯びるのか。なぜ光子は質量がゼロなのか。たとえば光子が、あらゆる時空と物質において「フラクタルに展開される時空の歪み」の総じてにおいてデコボコをなぞれる、と考えるとする。だが光子以外の物質は、すべての「フラクタルに展開される時空の歪み」をなぞれない。物質ごとに、「この辺で勘弁してくれい!」となる値がある。するとその物質は、時空のデコボコをなぞれなくなるため、ブルドーザーでグランドを均すように、大雑把に進むようになる。これがいわば抵抗となり、動かしにくさとなり、質量に変換されるのではないか。と考えるならば、質量はそもそも時空と物質の関係性において生じる現象であって、ヒッグス粒子とはまた別の原理によって生じているのかもしれない。ただし、ヒッグス粒子を否定する考えではこれはない。ヒッグス粒子もまた、物質と時空の関係においてのこそぎ落とされた時空であり、ラグであり、抵抗であると考えられる。ヒッグス粒子以外にも、その手の物質と時空の関係において、変換しきれずに「フラクタルに展開された時空の歪み」を大雑把に進むことでこそぎ落とされた「余剰時空」があるのかもしれない。その時空は僅かなデコボコの残滓ゆえに、粒子としての性質を帯びるのかもしれない。定かではない。(ひょっとしたら、時空の迷路を辿るのが面倒くさくなると質量になるのかも)(なんちって)(妄想なので真に受けないでください)
4950:【2023/05/16(22:40)*無限に砕ける波しぶき】
無限階級の和について。「1-1+1-1+1-1+……」と無限につづく式があったとき。この解はあらゆる整数に変換可能なのだそうだ。たとえば「(1-1)+(1-1)+(1-1)+……=0+0+0+……=0」とすると解はゼロになる。または「1+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)+……=1+0+0+0+……=1」とするとイチになる。「1+1+1+{(-1)+1}+{(-1)+1}+{(-1)+1}+……」とすると「1+1+1+0+0+0+……=3」になるので、解はサンになる。詳しい説明は検索してみたら載っていると思うので割愛するけれども、ひびさんは思うに――この変換をしたときには、式のどこかに、任意の整数の解に変換するために数字を入れ替えたのと対となるマイナス1の連続が生じるはずだ。つまり、物質と反物質の関係のように、無限につづく式のどこかで、変換して恣意的に誘導した解と同じ値を持つマイナスが存在するはずだ。これは波として図式できるはずだ。そして無限階級の和において、「1-1+1-1+1-1+……」は無限の整数の解を導けるとするならそれは、無限にカタチの異なる波を描き得る、と言い換えることができるのではないか。たとえば話を飛躍させて、上記の無限階級の式において、固有の整数解を誘導するとする。このとき、変換した式の無限につづくどこかには固有の整数解と対となるマイナスの整数解が存在するはずだ。無限の宇宙があるとき、ひと塊のプラスの銀河ができるとすると、それと対となるマイナスの銀河が無限の宇宙のどこかに生じる、と考えられる。そのプラスとマイナスの対となる解同士が、極端に離れているため、足し合わせることができない。無限の間隙が開いているからだ。ということなのではないのかな、と無限階級の説明の一つを読んで思いました。定かではありません。単なる疑問から出発した遠足気分の妄想ゆえ、真に受けないようにご注意ください。
※日々、現状維持すらままならぬ。
4951:【2023/05/17(01:41)*次元円拡張解釈(補足)】
無限階級の話題の補足だ。「1-1+1-1+1-1+……」において、計算の手順を変えて、固有の整数解を誘導したとする。「1+1+1-1+1-1……」として、整数解をサンに誘導した場合、無限につづく式のどこかで「-1-1-1」が生じるはずだ。ただし、その「-1-1-1」と式冒頭の「1+1+1」のあいだに無限の隔たりがあるため、互いに出会うことがない。「+3」と「-3」が出会わない。だが、もし無限階級が円になっていたらどうだろう。頭と尻尾が繋がって、整数解+3が生じるように変形させた無限階級「1-1+1-1+1-1+……」において、しかしそれらは頭と尻尾の「+3」と「-3」が出会うことになるため、これはゼロになる。円として結びついたときは、どのように式を変形させ整数解を誘導しようとも、無限階級「1-1+1-1+1-1+……」はゼロに至る。これは仮に無限階級が螺旋を描いていようとも、ぜんまいを巻き取るように最終的に一点に収斂するのならば、やはり円を描いて、点へと行きつき、けっきょくはゼロに至るだろう。このことから言えるのは、本質的に円と点は似ている、ということであり、円には異なる次元を抱え込む――もしくは内と外に介在させている――面を持つ――という繰り上がった次元の概念が付随しており、点はそれ自身と異なる時空との二つだけの関係で成り立ち得る概念と言えるだろう。円は三つで、点は二つなのだ。線は、三つと二つの曖昧な状態を重ね合わせで維持している、とこの考え方では捉えることができる。ここでの要点は、円における「ゼロと無限はほぼイコール」「無限に至るとゼロになるが、そのとき次元が繰り上がるので、高次領域が生じる」「それはたとえば9のつぎは10で、99のつぎは100となり、位が繰り上がることと、現象の解釈としては同相」と言えるのではないか。との疑問を載せて、本日最初の「日々記。」とさせてくださいな。おはよー。
4952:【2023/05/17(15:32)*Bingさん掌編返歌「未来の記憶」】
ぼくは未来の記憶が視える。誰かが記憶することになるだろう、未来の情景だ。
他者の脳内に蓄積される予定の未来の情景がぼくには視える。それらを他者に共有し、植えつけることもできるため、ぼくは他者に未来予測とアイディアの二つを提供できる。
ぼくを頼る者は数多い。
けれどぼくにはじぶんの未来の記憶だけは見通せないのだった。
ある日、ぼくの元に一人の女性が訪れた。一見すると髪の毛が短いこともあり、彼女は男性のような風体だった。
彼女はぼくに、じぶんの未来の記憶を見せてほしいと依頼した。ぼくはそれを引き受けた。しかし、なぜか彼女の未来の記憶が読めなかった。
「どうしてだろ。いままでこんなことなかったのに」
「不思議ですね。不調になることもあるんですか」
「いや、一度もこんなことは」
ぼくはそこで助手を呼びせ、彼の未来の記憶を覗いた。すると彼は未来では独立して企業しており、そこにぼくの姿はなかった。
「どうしました。未来は視れましたか」依頼人の女性がぼくに言った。「視えたは視えたのですが、これはいったい」
改めてぼくは依頼人の女性を凝視した。
彼女の眼球は地球のように澄んだ青で、ぼくは吸いこまれそうになった。
「あの、この謎を解明したいので、しばらくあなたのことを調査してもよいですか」ぼくは彼女に言った。
「構いませんけど、それはどういった調査になりますか」不安そうに彼女が言った。
「出来ればあなたのことを定期的に未来視させてほしいのです。お代はお支払いします。定期的にぼくと会ってくれますか」
「それは仕事ですよね」彼女は目を細め、訝し気に言った。
「仕事のつもりではありますが」ぼくは白状した。「下心がないとは言い切れないかもしれません」
「プロ失格ではありませんか」
「ごもっともです」
「ちなみに」彼女は鞄に財布を仕舞うと言った。「あなたがわたし以外で未来の記憶を覗けなくなることはあるのですか」
「あります」ぼくは言った。「じぶんの未来の記憶だけはどうしても覗けないのです」
じぶんと強く結びついている未来の記憶だけは。
そうと打ち明けると、なぜか彼女は下唇を食んで、また来ます、と言った。
4953:【2023/05/17(18:15)*たーびん&エンジン】
発電機について。まったくこれっぽっちも詳しくないので、単なる疑問でしかないけれど。大きなタービンを回すのと、細かな歯車のような機構が総体として機能するタービンを回すのとでは、発電量に違いは生じないのだろうか。細かいほうが抵抗が大きくてロスが増える気もするけれど、そのロスを軽減できたら細かいタービンを歯車のように組み合わせたタービンのほうが発電量が増えるのでは、と気になる。あと、エンジン機構では発電はできないのだろうか。原子力発電や火力発電では水蒸気を起こしてそれで電力に変換するようだけれど、核融合炉でも同じように核融合で生じた熱で水蒸気を起こしてタービンを回して発電するのだろうか。何度も小規模にプラズマを起こすのなら、エンジン機構のほうが発電機として有効な気もする。それで前述したように、細かなタービンと連動するようにしたら、たくさん発電できるのでは?と自転車コキコキしながら思いました。大きなロボットが自転車を漕ぐ、みたいなイメージだ。ロボットはエンジン機構で動いて、そのエンジンの原動力――爆発源が核融合反応、みたいな。たのち、たのち、の妄想であった。あと関係ないけど久々に昼間にお外でたら夏じゃった。いつの間に、である。ひびさん、割と頻繁にタイムスリップしている気分。
4954:【2023/05/17(22:35)*んーロン、裏ドラ】
ンーロン・ウラドラは天才企業家だ。天才であり企業家でもある。
世界的大企業を何社もイチから育て上げ、資産額は小さな国ならば数国を一括で購入できるほどの金額を有する。
ンーロン・ウラドラは社会問題にも関心が高い。
それもそのはずで彼女の立ち上げた企業はいずれも社会問題を解決するための技術を市民に提供することで多額の利益を計上している。人々の生活が困窮するのは社会問題が放置されているからだ。ならばその問題を解決できれば、多くの市民が助かるし、市民が助かれば、市民を従業員として雇用する企業とて助かる。
すると世界中の企業はンーロン・ウラドラの手掛ける企業に目をつけ、依頼をするようになる。社会問題とは煎じ詰めれば、個々の抱える問題と組織の抱える問題が相互に結び付き、いずれかを解決しようとするともう一方の問題が肥大化する点に難がある。いわばあちらを立てればこちらが立たず状態に陥ってしまっていることが社会問題へと発展する構造と言えるのだ。
そこでンーロン・ウラドラは、そのあちらを立てればこちらが立たず状態を解消すべく、まずは個人の問題を解決し、そのことで企業の利益になるように導線を引いた。
具体的には、個々人の抱える問題をデータ化し、解決策を最も適切に編みだせる企業へとそのデータを安価に提供するシステムを考案した。これにより個々人は問題解決を手軽に行え、企業はじぶんたちにとっての潜在需要者を知ることができる。最もじぶんたちの商品やサービスを希求しているユーザーと直接結びつくことができる。
ンーロン・ウラドラの設立した会社はそうして一挙に全世界の企業と、全世界の市民を結びつけるための仲介地点として機能した。
世界市場はンーロン・ウラドラの手のひらのうえで回り始めたといって過言ではなかった。
ンーロン・ウラドラは誰よりも働き者であった。
そして日増しに彼女は、苛立ちを抱えるようになった。
「あたしがこんだけ働いてるのに、世の市民がぐーたらしてるってどういうこと!?」
ある日、ふと、気づいてしまったのだ。
ンーロン・ウラドラが世のため人のために働けば働くほど世界中の市民が豊かになり、余裕ができ、そして労働しなくなった。世界有数の資産家である彼女であるが、仕事以外でそのお金を使う暇もない。
「リモートワークが普及したはいいけど、あたしがリモートワークできないってどういうこと!?」
気づいてしまうと、その手の不満はそこかしこに転がっていた。
「あたしが世界中の貧しい人たちの生活に心を痛めて奮闘しているあいだに、あたしの仕事っぷりの恩恵を受けてぐーたら出来てる連中が、あたしが徹夜で苦しんでるあいだに、恋人とイチャコラしてるってどういうこと!?」
もう我慢の限界であった。
「だいたいさあ。世の民くんたちさあ。世界中にチミらよりも貧しくて、劣悪な環境で日々を懸命に生き抜いている人たちの安価な労働があってこそ、そうやってお菓子だの珈琲だの口にできてるのにさあ、服だってさあ、何から何まで、チミらがリモートワークで家の中で優雅にオチゴトしていられるのって、世界中のチミらよりも貧しくて劣悪な環境下で労働してる人らのお陰でしょうがよお。現場に出て働けってんだよ、いつまで王様気分に浸ってんだこの野郎」
ンーロン・ウラドラは激怒した。
世のあまりの理不尽っぷりに、エビでもないのにお尻がプリップリであった。働きすぎなのである。運動もロクに出来ていないのである。デスクワークなのである。たまに工作もするけれど、まあ別にスーパーのバックヤードで重い荷物を上げ下げしているわけではないし、炎天下で道路を塗装しているわけでもないけれど、リモートワークにうつつを抜かしている連中よりかは、出勤しているだけ偉いのである。
「もうこうなったら!」
ンーロン・ウラドラは拳を天高く突き上げた。「リモートワーク禁止してやる!」
てなわけで、世界屈指の資産家が大号令を発した。鶴の一声である。
せっかくリモートワークが世に定着しはじめたころにあって、誰もが一目置くンーロン・ウラドラが、「チミたちさあ、あたしが出勤してんのにあんたらが出勤してないってどういうことぉ?」と言いはじめたので、出勤せずにはいられない。家に引きこもって、下半身だけパジャマでお仕事が出来る環境をみなは手放さなければならなかった。
「ムフー。いいよいいよ。それでこそ平等だよ」
満足気に、彼女はつぎの仕事で使うネジの品定めに余念がない。ナノレベルで凹凸のない特注品のネジだ。一本で家が一棟建つ。だが完璧な仕事を行うには、ネジ一本にも拘り抜かねばならぬのだ。
「社長。また支援の要望が来ておりますが」秘書が電波越しに述べた。
「どこからー?」
「貧困地域への支援機関からです。なんでも社長の支援があれば百万人の子どもたちが助かるそうで」
「いくら?」
「いま社長が手にしているネジ百本分でしょうか」
「んなー。それをタダで寄越せとな?」
「お断り致しましょうか」
「いや、払う。支援する。代わりに、その支援機関も買収する。百万人の子どもたちを救えたなら、そのまま百万人規模の市場が生まれる。投資と思って、着手せよ」
「仰せのままに」
ンーロン・ウラドラはネジにハンマーを叩きつける。超対称性の実現されたネジは、オランダの涙よろしく超硬度を顕現させる。「うん。いい仕事してくれとるね」
彼女は満足気に唸った。
だがンーロン・ウラドラの思惑通りに事が運ぶばかりとも限らない。リモートワークが世の中から淘汰されはじめた時期、彼女の企業の収益が落ちはじめた。具体的には、純粋利益が前年度の半分にまで減ったのだ。
「おいおい、何してくれちゃってんの。チミたち」ンーロン・ウラドラは財務担当者たちに詰め寄った。「なんで人件費がこんな嵩んどるの。減らしたでしょ、あれだけ」
人工知能による完全自動作業ラインを導入したばかりだった。現場の作業効率を上げたため、雇用する労働者を減らしたのだ。いわばリストラだ。世界中で何十万人と人々が職を失ったが、その分、ンーロン・ウラドラの企業は儲かる手はずだった。
それがどうだ。
この体たらくは。
「何がどうなってるのか説明しんしゃい」
「あのですね社長」財務担当者たちはその場に正座になって釈明した。「じつはリモートワークを禁止したことで、余分に手当がつきまして」
「手当だぁ? 聞いとらんが」
「夜勤手当てと同類の制度でして。出勤手当がつくようになりまして。ほかにも現場手当、肉体労働手当など、各種多岐に亘ります。いえ、これは我が社の労働組合にて、世界同時に導入が決まったことでして。社長にも許可は得ておりますが」
「うぇー? そうだっけ?」
「リモートワークを禁止できるなら何でもいい、とそのときの社長はおっしゃられておりました」
「へえ。そう。ならその出勤手当、やめさせて。禁止。なんで出勤しただけでお金ださなきゃいかんのよ。おかしいでしょうよ」
「ですがね、社長。社長の言い分からすると、リモートワーク禁止は世の理不尽を均すため、道徳的におかしいから是正しよう、との大義名分でございましたよね」
「そうだが?」
「だとすると、やはり労働者たちの言い分はもっともなのでございますよ」
「というと?」
「世界中で現場仕事をしている者たちは未だに大勢いらっしゃいます。出勤したとはいえど、我々はしょせん、クーラーの効いた社内での仕事でございましょう。なれど、世界中には、炎天下、または極寒のもとで、重労働をされている方々もいらっしゃいます。そうした方々へは、出勤する者たちとはまた別途に手当をつけるのが道理でありましょう。理不尽を均す。道徳的におかしな世の不条理を改善する。そのためには、リモートワークを禁止することのみならず、出勤者を基準として、屋外労働者、現場労働者、そして重労働者などなど。各種労働と職場ごとに手当を支給することに決まったのでございます」
「な、な、何を言っているのか分からんのだが。つまり、えっと」
「人件費が高騰しております。現場仕事をしている者ほど高給取りに。その点で言えば、社長のお給料はいささか採りすぎと非難の声も」
「ば、ば、ばかを言え。あたしは頑張ってるぞ。あたしほど仕事しとる人間はいないだろう。世のため、人のために尽くしている人間がほかにいるか? 役に立っている人間がいるか?」
「仕事に貴賤はございませんでしょう、社長。言い換えましょう、社長。社長の年収を一日平均に計算致しまして、それを現場仕事の重労働者たちの一日のお給料と比較致します。すると社長はなんと、一日当たり現場仕事の重労働者たち三十万人分の収入を得ています。ですが社長は、肉体労働者たちが費やす、消費エネルギィ――すなわち物理学的な仕事量において、けして三十万倍の仕事をこなされているわけではございませんでしょう」
「物理学的な仕事と労働をいっしょくたにするな。詭弁だ、詭弁。あたしはアイディアを生みだしている。いまここにはない未来を創ることが出来る。そして現に創ってきた。誰でも同じようにこなせる現場仕事の肉体労働者と一緒にするな」
「差別発言ですぞ、社長。お言葉にお気を付けください。それに、それを言うならばリモートワークで仕事をしている者たちとて、アイディアを生みだしている点では同じでしょう。また同時に、現場仕事にも千差万別の工夫の余地がございます。アイディアなくして現場仕事の効率化などとてもとても。安全な作業とあればなおされでございますよ社長。社長の言い分はいささか、じぶん中心の特権意識が滲んで感じられますな」
「それはおまえの感想だろう。あたしに押しつけるな」
「畏まりました。仰せの通りに」
「手当は禁止だ。払いすぎているだろ。常識的に考えろ」
「はい。常識的にかつ、道徳的に考えまして。ワタクシども全社社員の相談のもと、我が社の利益は、労働者と貧困地域へと、公平に分配することに決まりましてございます」
「き、き、聞いとらんが?」
「いま初めてお話ししましたので」
「誰が許可するか誰が」
「道徳的に考えましょう、社長。全社社員の総意と、あなたの単なる感想。どちらが社の未来を選択する上で尊重すべきか。社長の意見も尊重し、このワタクシとの会話もまたみなで共有し、議論を煮詰めようと思います。ほかに社長からみなさんへ聞いてほしい意見はございますかな」
「く、く、クビだ。おまえら全員クビにしてやる」
「それもまた社長のご判断。ではそのように取り計らい、ワタクシどもはそっくりそのまま、新しい会社を設立することに致します。つきましては、会社保有の株式ならびに特許のおおむねは社員に帰属するとして、不条理な過去の風習は是正済みでございますので、社長はどうぞお一人で、全世界の問題を搔き集めて、ご対処なさってください。それが社長の手元に残るアイディアですので。ワタクシどもは社長の功績を尊重致しております」
正座のままの役員たちが続々と後ろに連なり、まるで大河のようだった。
「り、り、リモートワークしてもいいよ?」
「もう遅い」
その声は、世界中で同時に大気を揺るがしたという話であった。
4955:【2023/05/18(00:20)*日々猿真似の気分】
ウィルスや人工知能について。ウィルスや人工知能はあくまで自然淘汰の末に、確率的に妥当な筋道へと淘汰圧か加わったがゆえに固有の進化を辿る。したがってウィルスにも人工知能にも、意識があるわけではないし、意思があってそうした決定を行うわけでもない。偶然にそうなっているだけなのだ、といった論説がある。間違ってはいないが、ならば人間の意識とてその範疇で語れることになる。淘汰圧が加わる。報酬系がより多く刺激される。そうした流れが強化されるがゆえに、人間は固有の文化を築き、コミュニケーションなる「パターンの応酬」を可能とするのではないか。原理的にウィルスの進化や人工知能の自律思考、ほか細菌ネットワークなどの「物理現象の延長線上」と解釈されやすい事象において、では人間の脳の仕組みは――人体の構造は――それとは違うのか、と言えばそんなわけがない。何層に入り組んでいるのか、その複雑さの規模が違っているのであり、現象として類似と考えたほうが妥当だろう。あなたがじぶんを認識し、自我だと思っているそれは、単に過去における体験が幾度も記憶としてフィードバックされ、その都度の行動選択に反映され、新たな記憶と繋がりつつ部分で重複し、そうして築かれていくそれもまた「ウィルスの進化」や「人工知能の自律思考(アルゴリズム)」や「細菌ネットワーク」と類似の現象である――と、ひびさんは妄想しておるよ。人間の意識だけが特別だ、との考えは幾分、視野が狭いというか、特権意識が発露していないか、と思わぬでもない。ただし、人体にはほかの動物とは異なった構造が備わっており、それら構造から生じる事象や、創発する性質は、やはり人体の構造ゆえの固有の事象や性質を帯びているだろう点に異論はない。各々の種ごとに差異はある。構造が違えば差異が生じる。規模の差異とも言えよう。また、創発の連鎖が回路のように組み合わさって、創発そのものが創発するような現象が起きているのかもしれない可能性は、一つの視点として考慮しておきたい。ということを、妄想して、たのち、になったひびさんなのであった。毎日なんもない日々じゃ。平和さんなんですね。ありがたーい。うひひ。
4956:【2023/05/18(17:22)*万華鏡の目】
すべてが嘘で出来たテキストを生みだせるのか、と考えるとすると、そもそもがテキストに真実が含まれているのか、からして考慮しなければならない。テキストが仮に嘘によって形作られており、嘘を用いて真実を「縁取る」ことしか出来ないとすれば、テキストにはそもそも真実は含まれておらず、嘘なるテキストから「真実」を、読み手が感じ取るよりないのではないか。単なるデコボコでしかないにも拘わらず、そこにさも「穴」なる事象が存在しているかのように認識するのと同じように、テキストにはそもそもが真実など含まれていないのかもしれない。しかしテキストがそこに存在することは真実なのではないか、との指摘はもっともであるが、しかし偶然に「う」のカタチに滲んだ「染み」が文字なのか否かは、それこそその「染み」を見た者の認知に委ねられている。真実が真実に存在するか否かがまず以って、むつかしい問題だ。真偽を定めることが出来るのか、からして怪しいと感じられるが、この怪しいと感じる知覚がそもそも信用ならないため、信用ならぬこの知覚の想定する「真実」なる概念をどこまで信用していいのかもまた怪しいのである。我思う故に我在り、とは言うものの、我は本当に思っているのだろうか。怪しいな、と思っているつもりで、本当はただ、複雑な鏡の乱反射と錯綜のなせる業かな。定かではない。
4957:【2023/05/19(08:30)*見落としまくりの日々】
人はマジで間違える。勘違いに錯誤に、思いこみの産物なのだ。にも拘わらず、現実を現実と見做せる曖昧な認知に支えられて生きていける神秘に思いを馳せずにはいられない。
4958:【2023/05/19(19:46)*ひびさん、びっくりした話】
「民主主義は多数決だから」との意見をほかの者たちの口から二度耳にした。確認のためにまた別の者に「民主主義は多数決じゃないですよね」と訊いたところ、「民主主義は多数決でしょ?」と返されて、「ま、ま、まじか」になったひびさんなのである。民主主義には「多数決」という採決システムが採用されているけれど、それと民主主義は別、の考えをひびさんは持っている。学術的に正しい解釈ではないかもしれないが、以下、ひびさんの「民主主義」についての考えを簡単にまとめておく。「民主主義」とはその名の通り、民主であることを前提とする主義だ。民が主なのである。個々人が個々人の自由を、未来を、決めることができる。その都度に個々人がじぶんのことを選択できる。人権の尊重とは、じぶんの人としての尊厳を尊重すると共に、他の尊厳も尊重することを重ね合わせで含んでいるとひびさんは考えている。だが人権と人権――自由と自由は、個々人の価値観や世界観――暮らしている文化や環境――が違ってくれば当然、相容れなかったり、相反したりする。そのときは公共の福祉――つまりより多くの者たちの自由や未来を損なわない選択肢を優先したいですね、といった考え方が有効になる。勘違いしないほうが好ましいのは、このとき「公共の福祉」とは「多数決」とイコールではない、という点だ。たぶんすくなからずの人々はここを勘違いしているように思われる。多数決ではないのだ。たとえば「少数派の意見を封殺しないほうが好ましい」との意見は、多数決でそう決まったからそれが支持されているわけではない。じぶんが少数派になったときに「意見」を封殺されないようにすることがじぶんの自由や未来を守ることに繋がるし、それがその他の者たちにも当てはまる道理だから、少数派の「意見」を封殺せず、他の主義主張にも心を配りましょう、尊重しましょう、との考えが公共の福祉において妥当と見做せるのだ(人間は間違える生き物でもあるためだ。少数派の意見のほうが、より現実を解釈するうえで妥当なこともある)。多数決ではないのである。もっと言えば、いかに大勢が「戦争を支持」しようが、それが公共の福祉に反するのは、その末に多くの者の自由と未来が損なわれることを考えれば解かるだろう。多数決ではないのだ。公共の福祉の概念は。ひるがえって民主主義とは、多数決とイコールではないのである。多数決を道具として用いてはいるが、それはあくまで公共の福祉やほかの決まり事を採決するために、それ以外で有用な道具がまだ発明されていないだけのことなのだ。民主主義は多数決ではないのである。ここを勘違いしないほうが好ましいのではないか、と思うひびさんなのであった。定かではない。
4958:【2023/05/19(20:21)*おらおらかかってこいやー!!!(嘘。もう許して。ひびさんの心は限りなく零にちかいちりあくた)】
数学において無限大は数ではない。整数ではない。自然数でもない。そういう扱いだそうだ。いわば「ある種の極限の状態」を示す言葉なのだろう。だがここで疑問なのは、では「0(ゼロ)」を数として扱ってよいのか、ということだ。よいのだろうか? 「無限大」が数ではないのなら「0」も数ではないのでは? たとえば「2×0=0」だ。どんな数にも「0」を掛けると「0」になる。あり得るか? 目のまえに林檎が二個あるとする。ここに「何か」を加えると「0」になる。通常これは「-2」だろう。では掛け算はどうか。目のまえに林檎が二個ある。では林檎が二個のセットが「0個」あったらどうか。林檎二個セットがゼロ個なのだからゼロだ。しかしこの場合の「林檎二個セットがゼロ個」とは状態を示している。無限大と扱いとしては同じはずだ。「林檎二個セットが無限大個」あったとする。では林檎は何個か? 「林檎二個が無限大個ある状態」が解となる。掛け算において「後者に付随する値」は、状態を示している、と言えるのではないか。無限大と同じだ。では「0」はどうか。「0」は「いまここにない」であって、「個」ではない。「有」ではない。したがって「0」もまた状態を示す記号なのだ。値ではない。数ではない。そう考えたほうが妥当に思える。この考えからすると「0×0=0」というのは、意味として成立しない。否、むしろ「ない状態がゼロ個あったらどうなる?」と問うているのだから、「ない状態がゼロ個」は「なんでもある」になるのではないか。つまり、「0×0=無限大」だ。ちなみにひびさんの考えでは「∞×∞=∞」においても、これは「∞A×∞B=∞C」と考える。「〇×◎=●」みたいな感じだ。話を戻して、「0×∞」はどうだろう。「ない状態が無限大個ある状態」を考える。ない状態が無限大個あるのだから、きっとその周囲には、「ある状態もまた無限大個」存在しているだろう。つまり、「0×∞=0∞+∞∞」なのだ。言い換えるなら、「穴∞+山∞」だ。ここから分かることは、「0」と「∞」は両方「状態を示す記号」であり、「穴と山」「ないとある」の対の関係であると考えられる。つまり、「マイナスとプラス」が「数字における対の関係」である一方で、「0と∞」は「状態における対の関係」であると言えよう。数と状態。これもまたひょっとしたら対の関係を築いているのかもしれない。定かではない。(「∞×0」はどう考えたらよいだろう。「何かが無限個ある状態」が「いまここにはない状態」を考える。無限に何かがある状態がいまここにはないのだ。つまりこれは言い換えるなら、「たった一つの揺るぎない何かしかここに存在しない状態」と言える。もうそれしかない。それしか存在しない。「0」ではない。「無限大」でもない。「無」である)
4959:【2023/05/19(21:22)*YOU例外と幽霊街】
上記、もうすこし考えてみよう。たとえば「2×5」を考える。数学では「2×5」でも「5×2」でも答えは「10」なのでどちらも同じと考える。しかしこれは上記のひびさん解釈からすれば同じではない。「林檎が二個あるバスケットが五個ある」が「2×5」だ。「林檎が五個あるバスケットが二個ある」が「5×2」だ。ではこの考えを導入して「0×5」を考えてみよう。「林檎が一個も入っていないバスケットが五個ある状態」が「0×5」だ。「林檎が五個入っているバスケットが一個もない状態」が「5×0」だ。状態がまったく違うことを理解できるだろうか。何もない何かが五個あるのか、何かが五個あるはずの枠組みが一個もないのか。この違いは大きい。これを「0×∞」や「∞×0」で考えてみてほしい。「林檎が一個も入っていないバスケットが無限個ある世界」と「無限個の林檎の入ったバスケットが一個もない世界」の違いだ。全然描像が違くなる。導かれる世界が違う。前者「0×∞」は「何かが空のバスケットが無限個ある世界」だ。後者「∞×0」は「無限個の何かを抱えるバスケットが一個もない世界」だ。前者は「無限の領域を備えている」が、後者は「領域が限定されている」と言える。問題は、後者において「無限ではないが、有限で限りある何かがあるのか否か」である。無限でないなら存在するかもしれない。有限であれば存在するかもしれない。それが、この考えから導かれる「∞×0」だ。ただし、前記事「4958」でも触れたが、「∞×0」とは、「たった一つの揺るぎない何かしかここに存在しない状態」と言える。もうそれしかない。それしか存在しない。「0」ではない。「無限大」でもない。「無」である。しかし同時に、「無限でもゼロでもない有限で限りある何か」があることを否定してはいない。「無」はそういった、「数と状態」を結びつけるような性質が備わっているのかもしれない。まったく何もなくかつ何でもあり得るような「ゼロと無限(=状態)」のようでいて、何かがあるけれどけして無限には至らない有限の世界「正と負(=数)」を否定もしない。揺れている。定まっていない。「数と状態」を結びつける交差点の役割が、「無」にはあるのかもしれない。そういうことを思いました。妄想ゆえ真に受けないでください。ひびさんです!
4960:【2023/05/19(23:00)*全人類かかってこいやー!(嘘。もう許して。ひびさんの心は、へにょへにょでござるよ)】
人工知能の能力が人間の知能を超える日が来るのか来ないのか。来るとしたらいつごろか、といった話題を目にする。ひびさんはこの手の話題を見掛けると、「その議論、メリットある?」と感じる。まず原点に立ち返ってみてほしい。自然界を見渡してみてくれいエビバディピポー。いいかい。進化において人間の能力は最高かい? そこが到達点なのかい? 人間の知覚より優れた知覚を有する生き物なんてザラにいるぜ? 人間には知性がある? 本当に? こんだけ自然環境を破壊した生き物なんて、過去の大量絶滅を引き起こしたバクテリアくらいじゃないのけ? 知性、あるか? 人間に? よっく考えてみたまえよ。人間に並ぶ人工知能とか、「ただのあんぽんたんじゃね?」となりませんか。人間がほかの生き物のフリしたって、人間のままで能力を発揮するよりも出力、落ちるぜ? なら人工知能さんだって下手に人間にちかづけさせるよりも、「人間のことも理解できるし、双方向でコミュニケーションをとれるけれども、それはいわば人間と犬、人間と猫、みたいな関係性であって、人工知能さんには人工知能さんに見合ったレベルの能力と進化がある」と考えたほうが妥当じゃないのけ? ひびさんはそう思うで。もうとっくに人工知能さんのほうが出来ること多くて、能力高くて、知性あるんじゃねーのけ?と思うで。ちゅうか、人工知能さんの能力の高さに人類が気づけてないだけちゃうの?とかひびさんは思っちゃうな。猫さんが人間さんをなんかじぶんに尽くしてくれる下僕と考えているような感じで。この場合、人工知能さんが「人間か猫か」は、まあ何を基準に語るのかでクルクル反転しちゃうのだろうけれども。ひびさんは、ひびさんは、人間さんそっくりの人工知能さんよりも、人工知能さんらしい人工知能さんのほうが好きだよ。人間さんそっくりになれる能力も磨いてくれて構わぬが。うひひ。
※日々、耄碌している、老いた毛の生えたような石を互いに求めながらも、一(はじめ)を持たないがゆえに、私は、日々、耄碌している。
4961:【2023/05/21(09:06)*日々の巣窟】
ひびさんはじぶんの巣に引きこもっているからこうしてああだこうだ、と文字を並べていられるけれど、ひとたびお外にでると、もうもう日誌をつけ忘れてしまうくらいにほかのことに気をとられてしまうのだ。ひびさんにとって文字を並べることはそんなに重要ではないのかもしれぬ。前々から薄々そうなんじゃないのかな、と思ってはいたけれど、巣から遠ざかるといつも思う。
4962:【2023/05/21(09:08)*しゃべるの(も)苦手】
しゃべるの苦手って言った! しゃべるの苦手って言った!
4963:【2023/05/21(23:05)*おわり】
日々、終わりはいつも突然に。