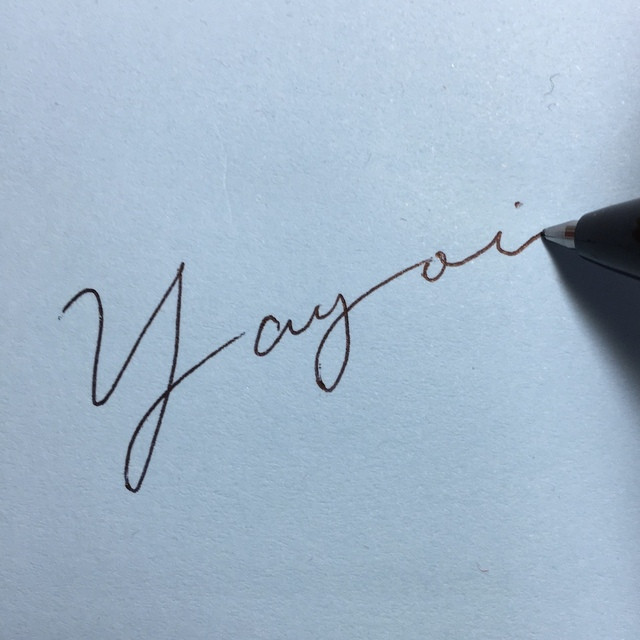前編
文字数 1,781文字
「また、在庫が一つ減っているんです。今度はフィリックスガムが」
そう言って、少女は、笑った目のまま、眉根を寄せた。
「不思議だねえ。今度も、防犯ゲートは鳴らなかったのかい?」
ココアシガレットの箱をレジにかざしながら、レジの横に座っている少女に、真由美は話しかける。
「ええ。それに、あの子たちを疑いたくありませんし。やっぱり私がポンコツなのかも」
少女は苦笑しながら、少し首をすくめてみせた。
「そんなことないよ。あまり自嘲しなさんな」
そう慰めながら、自嘲するなんて、まるでこの子、人間のようだ、と真由美は思う。
真由美の住んでいるマンションは、すっかり寂れた商店街の通り沿いにある。
商店街を、大通りに向かって歩き、横断歩道を渡って向かいの、トランクルームと酒屋さんの間を入っていくと、右手に、この駄菓子屋さんかくかんがある。真由美が物心ついた時からずっと。つまり、少なくとも七十年ほどは。
なぜ、さんかくかんかというと、お店の形が三角形だからだ。敷地自体が1対2対√3の直角三角形だから、お店もこういう形になったのだろう。それだけは、真由美が子どもの頃から変わらない。でもお店としては、かつてとは全く別物になっている。直角三角形だと底辺にあたる壁に備えられた入り口は自動ドア。入ると両側にそびえる防犯ゲート。斜辺にあたる壁沿いに、駄菓子の入った箱やビンがずらりと並び、その右奥には、おもちゃ類がぶら下がっている。直角三角形の対辺であるところの右側の壁中央あたりには、備え付けられた無人レジ。レジの右側に置かれた簡易な木製の椅子。その椅子に座っている、十代後半くらいの少女にみえるロボット。
二十一世紀になって、かつてのように、おばあちゃんが店番をして、十円玉や五円玉を握りしめた子どもたちが放課後に集まってくる駄菓子屋が存続するはずもない。コンビニのようになるのは当然だろう。だからといって、ロボットに店番させなくても、と、いまや自らもおばあちゃんとなった真由美は当初思った。でも、気がつくと、子どもたちがまだ姿を見せることのない午前中、買い物のたびに立ち寄るようになっていた。
ロボットの姿が、出会ったばかりの頃の未希子に似ているから。
真由美にも十代の時はあったのだ。周囲の娘たちがかっこいい男子たちに夢中になるなか、真由美が心奪われたのは、バイト先の喫茶店で知り合った未希子だった。腰のあたりまでとどく髪をラフに束ね、針金のような細い身体で店中を飛び回りながら笑顔を振りまいていて、お客さんたちからの評判も上々だった。愛想の悪い店員と陰口を叩かれる真由美とは大違いだった。
いきなり同性に思いを告げるような度胸もない。けれどもいつのまにか一緒に帰ることが多くなり、一緒に遊びに行くようになり、やがて二人とも高校を出て、働くようになった。
仕事帰りに待ち合わせて、駅近くの、戦前から続いているのかと思うような傾いた居酒屋が密集している谷のような場所で、あるいは駅向こうに立ち並ぶ雑居ビルに入っているチェーンの居酒屋で、二人は飲むようになった。
最初のうちはよかった。働き始めたばかりの若い二人の前には、無限の明るい道が開けているように思えた。けれども、若い真由美や未希子が会社から望まれていることは、真由美たちがしたいと思っていることとは全くかけ離れていた。
やがて、真由美は酔いにまかせて、仕事の鬱憤を未希子にぶつけるようになった。
「あたしたちってさ、結局、数年だけいる腰掛けだと思われてんだよね」
「自分が、しょせん女だろ、って馬鹿にされてるのがわかっちゃうのよ」
未希子はじっと耳を傾けてくれた。でも、次第に真由美は、言わなくてもいいことまで言うようになってしまっていた。
「未希子はいいわよ。顔も可愛いし、愛想もいいし、バイトしてた頃からお客さん受け良かったもんね。いざとなったら結婚できるじゃない。でもあたしみたいなのは、どうせ貰い手もないでしょ? いやんなっちゃう」
真由美は、未希子が困っているのはわかっていた。そして、未希子が決して怒ったりしないこともわかっていたのだ。少し顔をしかめながらも笑みをたやさない未希子の表情に、真由美は見とれていた。
未希子は、たしかに、最後まで怒ることはなかった。ただ、静かに真由美のもとを離れていった。
そう言って、少女は、笑った目のまま、眉根を寄せた。
「不思議だねえ。今度も、防犯ゲートは鳴らなかったのかい?」
ココアシガレットの箱をレジにかざしながら、レジの横に座っている少女に、真由美は話しかける。
「ええ。それに、あの子たちを疑いたくありませんし。やっぱり私がポンコツなのかも」
少女は苦笑しながら、少し首をすくめてみせた。
「そんなことないよ。あまり自嘲しなさんな」
そう慰めながら、自嘲するなんて、まるでこの子、人間のようだ、と真由美は思う。
真由美の住んでいるマンションは、すっかり寂れた商店街の通り沿いにある。
商店街を、大通りに向かって歩き、横断歩道を渡って向かいの、トランクルームと酒屋さんの間を入っていくと、右手に、この駄菓子屋さんかくかんがある。真由美が物心ついた時からずっと。つまり、少なくとも七十年ほどは。
なぜ、さんかくかんかというと、お店の形が三角形だからだ。敷地自体が1対2対√3の直角三角形だから、お店もこういう形になったのだろう。それだけは、真由美が子どもの頃から変わらない。でもお店としては、かつてとは全く別物になっている。直角三角形だと底辺にあたる壁に備えられた入り口は自動ドア。入ると両側にそびえる防犯ゲート。斜辺にあたる壁沿いに、駄菓子の入った箱やビンがずらりと並び、その右奥には、おもちゃ類がぶら下がっている。直角三角形の対辺であるところの右側の壁中央あたりには、備え付けられた無人レジ。レジの右側に置かれた簡易な木製の椅子。その椅子に座っている、十代後半くらいの少女にみえるロボット。
二十一世紀になって、かつてのように、おばあちゃんが店番をして、十円玉や五円玉を握りしめた子どもたちが放課後に集まってくる駄菓子屋が存続するはずもない。コンビニのようになるのは当然だろう。だからといって、ロボットに店番させなくても、と、いまや自らもおばあちゃんとなった真由美は当初思った。でも、気がつくと、子どもたちがまだ姿を見せることのない午前中、買い物のたびに立ち寄るようになっていた。
ロボットの姿が、出会ったばかりの頃の未希子に似ているから。
真由美にも十代の時はあったのだ。周囲の娘たちがかっこいい男子たちに夢中になるなか、真由美が心奪われたのは、バイト先の喫茶店で知り合った未希子だった。腰のあたりまでとどく髪をラフに束ね、針金のような細い身体で店中を飛び回りながら笑顔を振りまいていて、お客さんたちからの評判も上々だった。愛想の悪い店員と陰口を叩かれる真由美とは大違いだった。
いきなり同性に思いを告げるような度胸もない。けれどもいつのまにか一緒に帰ることが多くなり、一緒に遊びに行くようになり、やがて二人とも高校を出て、働くようになった。
仕事帰りに待ち合わせて、駅近くの、戦前から続いているのかと思うような傾いた居酒屋が密集している谷のような場所で、あるいは駅向こうに立ち並ぶ雑居ビルに入っているチェーンの居酒屋で、二人は飲むようになった。
最初のうちはよかった。働き始めたばかりの若い二人の前には、無限の明るい道が開けているように思えた。けれども、若い真由美や未希子が会社から望まれていることは、真由美たちがしたいと思っていることとは全くかけ離れていた。
やがて、真由美は酔いにまかせて、仕事の鬱憤を未希子にぶつけるようになった。
「あたしたちってさ、結局、数年だけいる腰掛けだと思われてんだよね」
「自分が、しょせん女だろ、って馬鹿にされてるのがわかっちゃうのよ」
未希子はじっと耳を傾けてくれた。でも、次第に真由美は、言わなくてもいいことまで言うようになってしまっていた。
「未希子はいいわよ。顔も可愛いし、愛想もいいし、バイトしてた頃からお客さん受け良かったもんね。いざとなったら結婚できるじゃない。でもあたしみたいなのは、どうせ貰い手もないでしょ? いやんなっちゃう」
真由美は、未希子が困っているのはわかっていた。そして、未希子が決して怒ったりしないこともわかっていたのだ。少し顔をしかめながらも笑みをたやさない未希子の表情に、真由美は見とれていた。
未希子は、たしかに、最後まで怒ることはなかった。ただ、静かに真由美のもとを離れていった。
ワンクリックで応援できます。
(ログインが必要です)
(ログインが必要です)