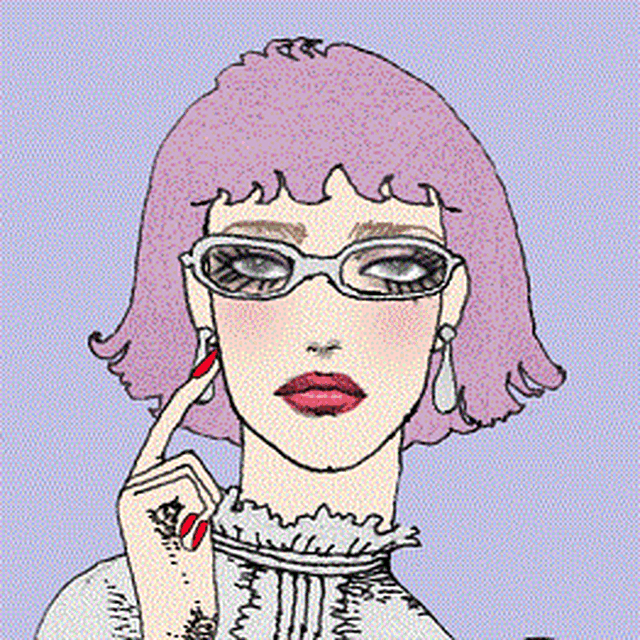第3話
文字数 3,126文字
平家が壇ノ浦に沈んだとき、完子の姿もその場にあった。
ひと月後には、姉の建礼門院徳子たちと共に都へ移送されたが、いよいよ上洛というそのときに、都に残っていた夫の噂が届いた。
平家の都落ちに同行しなかった基通は、新帝(後鳥羽)の摂政として、そして法皇の寵愛も深い側近として、いまも変わらず宮中にいる。
その基通が、数日前に行われた賀茂祭に際して、その前日に慣行として賀茂詣を行ったというのだ。
賀茂詣と言えば、その行列を見ようと見物人も出るほどに盛大な行事で、摂関家の権威を象徴する神祇儀礼でもある。
しかし、平家が滅亡してまだ間もないこの時に、一門の恩顧を永く蒙ってきたはずの彼が美しく着飾り、行列の主となって都大路を往く姿には、さすがに眉をひそめる者が多くいたという。
けれど、完子はいっさいの感情を見せることなく、静かにその話を聞いた。
そもそも、完子が都落ちに同行することになったのは、夫である基通が幼帝(安徳)を補佐する摂政として、平家と行動を共にするはずだったからだ。
それなのに、基通は落ち延びてゆく一行から抜け出し、再三の説得も聞き入れずにゆかりの寺へ籠った。
正妻である完子にはなにも言わず、たったひとりで。
夫の姿がないことに気づいた完子は、顔色をなくす女房たちを横目に、じわじわとこみ上げる笑いを隠すために両手で顔を覆った。
(あの方は、とうとう平家をお見捨てになったのね。わたしにはひと言もなく、ご自分だけ逃げておしまいになったわ)
周囲の動揺に反して、完子は夫の翻意を歓迎していた。
基通が平家を見捨てたということは、姉への気持ちよりも、自らの保身を優先したということだ。かねてから、法皇とは男色の噂があることも知っている。
(基通さまは、姉上のこともお見捨てになったのよ。やっと姉上からお目覚めになったのね。──ああ、なんて気分がいいのかしら)
笑いをこらえて肩を震わせる完子の姿は、夫の裏切りに泣く気の毒な妻に見えたことだろう。
けれどあの日、一行に悲壮な空気がただよう中で、彼女だけが喝采をあげていた。
そしていま、基通が平然と賀茂詣を行ったという事実も、完子にとっては平家への不義理ではなく、姉への再度の裏切りとしか感じなかった。
(やはり、あの方にとって姉上は、もうその程度の存在なのよ)
完子は口もとに添えた袖の陰で笑みをもらした。
いまさら、基通が自分を顧みてくれるとは思っていない。すでに完子以外の三人の女から、それぞれに男子が誕生している。しかしそのことすら、姉が過去の人となった証拠とばかりに、完子はよろこんだ。
それに、完子と基通は離婚したわけではない。完子は依然として基通の正室であり、都入りのあとは夫が所有する邸のひとつへ落ちついた。
翌日には夫の代理と称して、冷泉局という女房が挨拶にやってきた。聞けば、もともとは姉に仕えていた女房だという。彼女は大仰に目もとを押さえながら言った。
「こうして北政所さまとお話をさせていただいておりますと、白河殿が思い出されて涙がこぼれてまいります。きっと、よく似ておいでなのでしょうね」
姉は生前、その住まいから「白河殿」と呼ばれていた。その名は知っていても、一度も会ったことがないのだから、似ているかどうかなど知らない。
もっとも、夫からは「ぜんぜん、似てない」とのお墨付きをもらっているし、この女房にしてもそれくらいは知っていて、わざと言っているのではないかと思った。
(──なんだか、感じの悪い人ね)
完子はきわめて短い言葉で、淡々と返答を続けた。
けれど、完子がいくら素っ気なく対応しようとも、彼女の言葉を伝える女房が無難にやり取りをしてしまう。冷泉局はいつまでも帰る気配を見せず、宮中や都の様子を完子に話して聞かせた。
「賀茂祭での大殿のお姿は、いかにも艶やかで、お見事でしたよ。法皇さまも、桟敷から直々にご覧になったようでございます。わたくしも、大殿を法皇さまへお繋ぎした甲斐がございました」
「……あなたが?」
冷泉局の姉妹には、二代の后として有名な皇后多子や、法皇の中宮忻子がいる。その伝手を使ったのか、平家寄りだった基通を、反平家の頭目とも言える法皇と引き合わせるために奔走し、首尾よくそれは実現した。
「ええ、ええ。法皇さまは、大殿をひと目でお気に召されたようです」
「どうして、そんなことを──」
いったい、この女房になんの利益があるというのだろう。仮に基通が平家と命運を共にしていたところで、彼女は勤め先を変えてしまえば済んだことだ。
御簾のむこう側に座る冷泉局は、完子の問いが意外だったのかわずかに目を見ひらいた。そして、納得したようにゆっくりと笑顔をつくって答えた。
「近衛家がつつがなく続いてゆくことは、白河殿のご遺志でしたから」
「……」
「晩年は、お二人のあいだではそのようなお話ばかりでございました。よくよく近衛家をお守りするようにと、白河殿は口が酸っぱくおなりになるほど、大殿へくりかえしておいででした」
懐かしむように、しみじみと冷泉局は言った。
当時、ふたりの会話を取り次いでいたのは彼女なのだろう。そのやわらかな表情を見れば、夫と姉のあいだに流れていた空気も手に取るようにわかる。
呆然とする完子の背中を、ひやりとしたものが撫でつけた。
(基通さまは、姉上との約束を守るために──平家を、わたしを……あっさりとお見捨てになったというの?)
思ってもいなかった事実に、完子は視線を落ちつかなくさせた。ひどい耳鳴りがして、頭の中を引っ掻くようにかき回す。冷たくなった指先は、小さく震えていた。
(そんな、そんなこと……うそよ)
それからの会話はまったく記憶になく、冷泉局が退出したことにも気づかなかった。
やがて日が傾くと、完子は庭先で薄闇の中に咲く牡丹の花へ目を留めた。
(手折った花は、枯れてゆくだけ──でも、触れることのできない花ならば、いつまでもそこにありつづける……)
そうして、いまも夫の心には姉が生きつづけているのだ。触れることが叶わないまま、これまでも、これからも、ずっと。
(あの方にとって、わたしは挿頭 の花でしかなかったのかもしれない。はじめからずっと、わたしは基通さまの飾りのために造られた花でしかなかったんだわ)
平家が摂関家との繋がりを保つために、また、その莫大な財産を管理するために、清盛は娘たちを嫁がせた。完子の人生も、そのようにして定められたということだ。
(わたしは……何ために生きているの?)
ぽとりと、完子の手に涙が落ちた。それは花びらがこぼれるようにすべり落ち、乾く間もなく新たな雫がはらはらと落ちてくる。
ひとひら、ふたひら──
西国の海へひとり、またひとりと沈んでいった光景がよみがえる。
彼女たちはなにを思いながら波間に消えたのだろう。どうして自分は生かされたのだろう。
ただひとつの恋さえも手に入らず、なにひとつ思うままにならない人生で、このさきも与えられた生を全うすることに意味はあるのか。
(わからない……生まれてきた意味も、死んでいく理由も。わたしには、なにもわからない──!)
握った手の甲に、震える袖口に、いくつもの花が降りしきる。
すべての感情という感情を涙の花びらに変えて流し尽くすと、完子は真っすぐに牡丹の花を見据え、空っぽになった心へ明りを灯すようにつぶやいた。
「それでもわたしは、生きてきた。そして、これからも生きていく。それだけよ」
◇ ◇ ◇
都入りから数日後、建礼門院徳子が出家した。完子もおそらく出家したものと思われるが、都へ戻ってからの動向については、没年も含めて明らかではない。
了
ひと月後には、姉の建礼門院徳子たちと共に都へ移送されたが、いよいよ上洛というそのときに、都に残っていた夫の噂が届いた。
平家の都落ちに同行しなかった基通は、新帝(後鳥羽)の摂政として、そして法皇の寵愛も深い側近として、いまも変わらず宮中にいる。
その基通が、数日前に行われた賀茂祭に際して、その前日に慣行として賀茂詣を行ったというのだ。
賀茂詣と言えば、その行列を見ようと見物人も出るほどに盛大な行事で、摂関家の権威を象徴する神祇儀礼でもある。
しかし、平家が滅亡してまだ間もないこの時に、一門の恩顧を永く蒙ってきたはずの彼が美しく着飾り、行列の主となって都大路を往く姿には、さすがに眉をひそめる者が多くいたという。
けれど、完子はいっさいの感情を見せることなく、静かにその話を聞いた。
そもそも、完子が都落ちに同行することになったのは、夫である基通が幼帝(安徳)を補佐する摂政として、平家と行動を共にするはずだったからだ。
それなのに、基通は落ち延びてゆく一行から抜け出し、再三の説得も聞き入れずにゆかりの寺へ籠った。
正妻である完子にはなにも言わず、たったひとりで。
夫の姿がないことに気づいた完子は、顔色をなくす女房たちを横目に、じわじわとこみ上げる笑いを隠すために両手で顔を覆った。
(あの方は、とうとう平家をお見捨てになったのね。わたしにはひと言もなく、ご自分だけ逃げておしまいになったわ)
周囲の動揺に反して、完子は夫の翻意を歓迎していた。
基通が平家を見捨てたということは、姉への気持ちよりも、自らの保身を優先したということだ。かねてから、法皇とは男色の噂があることも知っている。
(基通さまは、姉上のこともお見捨てになったのよ。やっと姉上からお目覚めになったのね。──ああ、なんて気分がいいのかしら)
笑いをこらえて肩を震わせる完子の姿は、夫の裏切りに泣く気の毒な妻に見えたことだろう。
けれどあの日、一行に悲壮な空気がただよう中で、彼女だけが喝采をあげていた。
そしていま、基通が平然と賀茂詣を行ったという事実も、完子にとっては平家への不義理ではなく、姉への再度の裏切りとしか感じなかった。
(やはり、あの方にとって姉上は、もうその程度の存在なのよ)
完子は口もとに添えた袖の陰で笑みをもらした。
いまさら、基通が自分を顧みてくれるとは思っていない。すでに完子以外の三人の女から、それぞれに男子が誕生している。しかしそのことすら、姉が過去の人となった証拠とばかりに、完子はよろこんだ。
それに、完子と基通は離婚したわけではない。完子は依然として基通の正室であり、都入りのあとは夫が所有する邸のひとつへ落ちついた。
翌日には夫の代理と称して、冷泉局という女房が挨拶にやってきた。聞けば、もともとは姉に仕えていた女房だという。彼女は大仰に目もとを押さえながら言った。
「こうして北政所さまとお話をさせていただいておりますと、白河殿が思い出されて涙がこぼれてまいります。きっと、よく似ておいでなのでしょうね」
姉は生前、その住まいから「白河殿」と呼ばれていた。その名は知っていても、一度も会ったことがないのだから、似ているかどうかなど知らない。
もっとも、夫からは「ぜんぜん、似てない」とのお墨付きをもらっているし、この女房にしてもそれくらいは知っていて、わざと言っているのではないかと思った。
(──なんだか、感じの悪い人ね)
完子はきわめて短い言葉で、淡々と返答を続けた。
けれど、完子がいくら素っ気なく対応しようとも、彼女の言葉を伝える女房が無難にやり取りをしてしまう。冷泉局はいつまでも帰る気配を見せず、宮中や都の様子を完子に話して聞かせた。
「賀茂祭での大殿のお姿は、いかにも艶やかで、お見事でしたよ。法皇さまも、桟敷から直々にご覧になったようでございます。わたくしも、大殿を法皇さまへお繋ぎした甲斐がございました」
「……あなたが?」
冷泉局の姉妹には、二代の后として有名な皇后多子や、法皇の中宮忻子がいる。その伝手を使ったのか、平家寄りだった基通を、反平家の頭目とも言える法皇と引き合わせるために奔走し、首尾よくそれは実現した。
「ええ、ええ。法皇さまは、大殿をひと目でお気に召されたようです」
「どうして、そんなことを──」
いったい、この女房になんの利益があるというのだろう。仮に基通が平家と命運を共にしていたところで、彼女は勤め先を変えてしまえば済んだことだ。
御簾のむこう側に座る冷泉局は、完子の問いが意外だったのかわずかに目を見ひらいた。そして、納得したようにゆっくりと笑顔をつくって答えた。
「近衛家がつつがなく続いてゆくことは、白河殿のご遺志でしたから」
「……」
「晩年は、お二人のあいだではそのようなお話ばかりでございました。よくよく近衛家をお守りするようにと、白河殿は口が酸っぱくおなりになるほど、大殿へくりかえしておいででした」
懐かしむように、しみじみと冷泉局は言った。
当時、ふたりの会話を取り次いでいたのは彼女なのだろう。そのやわらかな表情を見れば、夫と姉のあいだに流れていた空気も手に取るようにわかる。
呆然とする完子の背中を、ひやりとしたものが撫でつけた。
(基通さまは、姉上との約束を守るために──平家を、わたしを……あっさりとお見捨てになったというの?)
思ってもいなかった事実に、完子は視線を落ちつかなくさせた。ひどい耳鳴りがして、頭の中を引っ掻くようにかき回す。冷たくなった指先は、小さく震えていた。
(そんな、そんなこと……うそよ)
それからの会話はまったく記憶になく、冷泉局が退出したことにも気づかなかった。
やがて日が傾くと、完子は庭先で薄闇の中に咲く牡丹の花へ目を留めた。
(手折った花は、枯れてゆくだけ──でも、触れることのできない花ならば、いつまでもそこにありつづける……)
そうして、いまも夫の心には姉が生きつづけているのだ。触れることが叶わないまま、これまでも、これからも、ずっと。
(あの方にとって、わたしは
平家が摂関家との繋がりを保つために、また、その莫大な財産を管理するために、清盛は娘たちを嫁がせた。完子の人生も、そのようにして定められたということだ。
(わたしは……何ために生きているの?)
ぽとりと、完子の手に涙が落ちた。それは花びらがこぼれるようにすべり落ち、乾く間もなく新たな雫がはらはらと落ちてくる。
ひとひら、ふたひら──
西国の海へひとり、またひとりと沈んでいった光景がよみがえる。
彼女たちはなにを思いながら波間に消えたのだろう。どうして自分は生かされたのだろう。
ただひとつの恋さえも手に入らず、なにひとつ思うままにならない人生で、このさきも与えられた生を全うすることに意味はあるのか。
(わからない……生まれてきた意味も、死んでいく理由も。わたしには、なにもわからない──!)
握った手の甲に、震える袖口に、いくつもの花が降りしきる。
すべての感情という感情を涙の花びらに変えて流し尽くすと、完子は真っすぐに牡丹の花を見据え、空っぽになった心へ明りを灯すようにつぶやいた。
「それでもわたしは、生きてきた。そして、これからも生きていく。それだけよ」
◇ ◇ ◇
都入りから数日後、建礼門院徳子が出家した。完子もおそらく出家したものと思われるが、都へ戻ってからの動向については、没年も含めて明らかではない。
了